�A�C�X�u���[�̂ЂƂ育�Ɓ@�@2006�N9���`2015�N8��
2015/08/19 (��) ���~�x�݂��I�����
2015/08/02 (��) ���̎��݂ƎG����
2015/06/21 (��) �쎡����
2015/06/10 (��) �� �p���A�����ė����I�����
2015/04/025 (�y) �p���ɂ�
2015/04/04 (�y) �O�b�o�C�I �앧
2015/03/18 (��) �앧�h���C�u�I�s�̎O����
2015/03/04 (��) �앧�h���C�u�I�s�̓����
2015/02/28 (�y) �앧�h���C�u�I�s�̈����
2014/04/20 (��) ���a�̓��X���v���o��
2013/12/25 (��) �q���E���̔ޏ�
2013/12/14 (�y) ����Ƀ]�E����������
2013/12/08 (��) �^�[�L�[
2013/12/04 (��) ���z�@�̒���
2013/08/27 (��) ����
2013/08/16 (��) �h���[���K�[���Y
2013/08/06 (��) ���~
2013/07/18 (��) �S�y�H
2013/07/14 (��) �Ⴋ���ɐG�ꂽ�D������
2013/07/10 (��) �����Ă�����ė���
2013/04/13 (�y) ���M
2012/10/20 (�y) �ʂ��Ђ�
2012/09/11 (��) �S�c��
2012/06/20 (��) ���V�O�ɂ�
2012/06/02 (�y) �a�̌���b
2012/05/13 (��) �ڔ����i
2012/04/28 (�y) �w�ԍ��Q�S
2012/04/17 (��) �ق����炩���̓�
2012/04/08 (��) ���O
2012/02/22 (��) �S��ڂ̂ЂƂ育��
2011/11/02 (��) �U�E�K�[�h�}��
2011/10/16 (��) �a������
2011/09/21 (��) ���N
2011/07/31 (��) �@�؉���
2011/07/10 (��) �\�b
2011/06/19 (��) ���[���ɃC���^�[�l�b�g
2011/06/12 (��) ���Ȏ�
2011/05/27 (��) �K��
2011/05/25 (��) ���ꂩ��
2011/01/11 (��) �~�̗�
2010/12/15 (��) �v���o����
2010/12/08 (��) �����X�J�C�c���[
2010/11/28 (��) ������
2010/10/18 (��) �T�E�i
2010/09/27 (��) �������̈�i
2010/09/14 (��) �����n����
2010/07/31 (�y) �����̖�
2010/07/20 (��) ���w�����b�g
2010/05/19 (��) �J�̓�
2010/05/08 (�y) ���炱
2010/05/01 (�y) ������
2010/02/18 (��) �m���Ȃ���
2009/12/28 (��) �v���[���g
2009/11/30 (��) �e�q�̊W
2009/10/17 (�y) �H�̊C�ނ�
2009/09/30 (��) �ςݏd��
2009/08/08 (�y) ����Ɏv������
2009/07/22 (��) �Q�{�̉f��
2009/06/17 (��) �w�A�X�v���C
2009/06/10 (��) �d�v�ۑ�
2009/06/09 (��) �k�o
2009/05/12 (��) �S�Ɏc�邾��
2009/04/23 (��) �Z�\�����
2009/04/20 (��) �������猾����
2009/04/18 (�y) �����ƈႤ��
2009/02/23 (��) ���Y
2009/02/11 (��) ����G�߂�����ė���
2009/02/02 (��) �[���ΐF�̃Z�[�^�[
2009/01/28 (��) ��Ȃ��H���Ӓn
2009/01/27 (��) �Ƃ����ɐl�̐���
2009/01/10 (�y) �]�m���w��
2008/12/24 (��) ���R
2008/12/15 (��) ���ꂪ��߂���
2008/12/01 (��) ���N�A���̃i���o�[�E����
2008/11/29 (��) �ꔑ���s
2008/11/16 (��) �����A������
2008/11/07 (��) ���̘b
2008/09/26 (��) �����L�[�E�X�^�W�A��
2008/09/02 (��) �V�ԍ╗��
2008/08/24 (��) �Q�O�O�W�N�A�Ă̏I����
2008/08/11 (��) �O����͉�������
2008/07/23 (��) �`�����ƈ⎸��
2008/07/20 (��) �قǂقǂƂ����b
2008/07/11 (��) �Ė����
2008/07/08 (��) �S�N��̓���
2008/06/09 (��) ���W�I�h���}
2008/05/29 (��) �R�[���Ɩ�̗V���n
2008/05/22 (��) ���o�̐V����
2008/05/08 (��) �j�̕�����
2008/04/26 (�y) �閧�̏ꏊ
2008/04/22 (��) �h����X����
2008/04/01 (��) �Ԑ���
2008/03/31 (��) �������̃n���C
2008/03/24 (��) �ŋ߂̎Ԏ���
2008/01/25 (��) �t�̎U�����a��
2007/12/28 (��) �V�˃A�X���[�g�ƐS���܂�b
2007/12/04 (��) ���낢��Ȕs�҂���
2007/11/15 (��) �o��̕s�v�c�i�p�[�g�U�j
2007/11/11 (��) �o��̕s�v�c
2007/11/10 (�y) �X�|�[�c�̋K��ɋ^�╄
2007/09/09 (��) �V���Ɖ���̗r��
2007/09/07 (��) ��������̑�
2007/09/01 (�y) �Ă̏I���̃n�[���j�[
2007/08/31 (��) �ɓ��̗�
2007/08/13 (��) ���t��
2007/07/19 (��) �A���F�E���F�����E�R���v�X
2007/06/28 (��) ���̉Ă̓����E����
2007/06/27 (��) �����Q�x�y����
2007/06/14 (��) �Ă̑z���o�E�吣��
2007/06/09 (�y) ���̗L���l
2007/06/08 (��) ���̂Ƃ����y����
2007/05/29 (��) �\��H�������H �������\�I
2007/05/20 (��) �告�o�ϐ�L
2007/05/15 (��) �P���ӊO��
2007/05/02 (��) �����ȎԂ̘b
2007/04/15 (��) �S�Ɏc�閼��ʂƂ�
2007/03/20 (��) ���E�ӂꂠ���X����
2007/03/18 (��) �����ō�
2006/11/26 (��) �N���͍]�ˋC��
2006/11/19 (��) �ߗ��Ɖ��F�����[���X
2006/11/01 (��) �Y����Ȃ����H
2006/10/29 (��) ��y���l�܂�
2006/10/28 (�y) ���H��Ɏv��
2006/10/18 (��) �X�܂ł�55����
2006/10/17 (��) ������Ȃʼn�ɂ䂭
2006/10/08 (��) 17�̉Ă�
2006/10/02 (��) 9��28���ߑO11��
2006/09/17 (��) �_�ے��̃^�b�Z���E�X���b�v�H��
2006/09/10 (��) �u�D�_�����v�ƃR�[�g�_�W���[��
2015/08/02 (��) ���̎��݂ƎG����
2015/06/21 (��) �쎡����
2015/06/10 (��) �� �p���A�����ė����I�����
2015/04/025 (�y) �p���ɂ�
2015/04/04 (�y) �O�b�o�C�I �앧
2015/03/18 (��) �앧�h���C�u�I�s�̎O����
2015/03/04 (��) �앧�h���C�u�I�s�̓����
2015/02/28 (�y) �앧�h���C�u�I�s�̈����
2014/04/20 (��) ���a�̓��X���v���o��
2013/12/25 (��) �q���E���̔ޏ�
2013/12/14 (�y) ����Ƀ]�E����������
2013/12/08 (��) �^�[�L�[
2013/12/04 (��) ���z�@�̒���
2013/08/27 (��) ����
2013/08/16 (��) �h���[���K�[���Y
2013/08/06 (��) ���~
2013/07/18 (��) �S�y�H
2013/07/14 (��) �Ⴋ���ɐG�ꂽ�D������
2013/07/10 (��) �����Ă�����ė���
2013/04/13 (�y) ���M
2012/10/20 (�y) �ʂ��Ђ�
2012/09/11 (��) �S�c��
2012/06/20 (��) ���V�O�ɂ�
2012/06/02 (�y) �a�̌���b
2012/05/13 (��) �ڔ����i
2012/04/28 (�y) �w�ԍ��Q�S
2012/04/17 (��) �ق����炩���̓�
2012/04/08 (��) ���O
2012/02/22 (��) �S��ڂ̂ЂƂ育��
2011/11/02 (��) �U�E�K�[�h�}��
2011/10/16 (��) �a������
2011/09/21 (��) ���N
2011/07/31 (��) �@�؉���
2011/07/10 (��) �\�b
2011/06/19 (��) ���[���ɃC���^�[�l�b�g
2011/06/12 (��) ���Ȏ�
2011/05/27 (��) �K��
2011/05/25 (��) ���ꂩ��
2011/01/11 (��) �~�̗�
2010/12/15 (��) �v���o����
2010/12/08 (��) �����X�J�C�c���[
2010/11/28 (��) ������
2010/10/18 (��) �T�E�i
2010/09/27 (��) �������̈�i
2010/09/14 (��) �����n����
2010/07/31 (�y) �����̖�
2010/07/20 (��) ���w�����b�g
2010/05/19 (��) �J�̓�
2010/05/08 (�y) ���炱
2010/05/01 (�y) ������
2010/02/18 (��) �m���Ȃ���
2009/12/28 (��) �v���[���g
2009/11/30 (��) �e�q�̊W
2009/10/17 (�y) �H�̊C�ނ�
2009/09/30 (��) �ςݏd��
2009/08/08 (�y) ����Ɏv������
2009/07/22 (��) �Q�{�̉f��
2009/06/17 (��) �w�A�X�v���C
2009/06/10 (��) �d�v�ۑ�
2009/06/09 (��) �k�o
2009/05/12 (��) �S�Ɏc�邾��
2009/04/23 (��) �Z�\�����
2009/04/20 (��) �������猾����
2009/04/18 (�y) �����ƈႤ��
2009/02/23 (��) ���Y
2009/02/11 (��) ����G�߂�����ė���
2009/02/02 (��) �[���ΐF�̃Z�[�^�[
2009/01/28 (��) ��Ȃ��H���Ӓn
2009/01/27 (��) �Ƃ����ɐl�̐���
2009/01/10 (�y) �]�m���w��
2008/12/24 (��) ���R
2008/12/15 (��) ���ꂪ��߂���
2008/12/01 (��) ���N�A���̃i���o�[�E����
2008/11/29 (��) �ꔑ���s
2008/11/16 (��) �����A������
2008/11/07 (��) ���̘b
2008/09/26 (��) �����L�[�E�X�^�W�A��
2008/09/02 (��) �V�ԍ╗��
2008/08/24 (��) �Q�O�O�W�N�A�Ă̏I����
2008/08/11 (��) �O����͉�������
2008/07/23 (��) �`�����ƈ⎸��
2008/07/20 (��) �قǂقǂƂ����b
2008/07/11 (��) �Ė����
2008/07/08 (��) �S�N��̓���
2008/06/09 (��) ���W�I�h���}
2008/05/29 (��) �R�[���Ɩ�̗V���n
2008/05/22 (��) ���o�̐V����
2008/05/08 (��) �j�̕�����
2008/04/26 (�y) �閧�̏ꏊ
2008/04/22 (��) �h����X����
2008/04/01 (��) �Ԑ���
2008/03/31 (��) �������̃n���C
2008/03/24 (��) �ŋ߂̎Ԏ���
2008/01/25 (��) �t�̎U�����a��
2007/12/28 (��) �V�˃A�X���[�g�ƐS���܂�b
2007/12/04 (��) ���낢��Ȕs�҂���
2007/11/15 (��) �o��̕s�v�c�i�p�[�g�U�j
2007/11/11 (��) �o��̕s�v�c
2007/11/10 (�y) �X�|�[�c�̋K��ɋ^�╄
2007/09/09 (��) �V���Ɖ���̗r��
2007/09/07 (��) ��������̑�
2007/09/01 (�y) �Ă̏I���̃n�[���j�[
2007/08/31 (��) �ɓ��̗�
2007/08/13 (��) ���t��
2007/07/19 (��) �A���F�E���F�����E�R���v�X
2007/06/28 (��) ���̉Ă̓����E����
2007/06/27 (��) �����Q�x�y����
2007/06/14 (��) �Ă̑z���o�E�吣��
2007/06/09 (�y) ���̗L���l
2007/06/08 (��) ���̂Ƃ����y����
2007/05/29 (��) �\��H�������H �������\�I
2007/05/20 (��) �告�o�ϐ�L
2007/05/15 (��) �P���ӊO��
2007/05/02 (��) �����ȎԂ̘b
2007/04/15 (��) �S�Ɏc�閼��ʂƂ�
2007/03/20 (��) ���E�ӂꂠ���X����
2007/03/18 (��) �����ō�
2006/11/26 (��) �N���͍]�ˋC��
2006/11/19 (��) �ߗ��Ɖ��F�����[���X
2006/11/01 (��) �Y����Ȃ����H
2006/10/29 (��) ��y���l�܂�
2006/10/28 (�y) ���H��Ɏv��
2006/10/18 (��) �X�܂ł�55����
2006/10/17 (��) ������Ȃʼn�ɂ䂭
2006/10/08 (��) 17�̉Ă�
2006/10/02 (��) 9��28���ߑO11��
2006/09/17 (��) �_�ے��̃^�b�Z���E�X���b�v�H��
2006/09/10 (��) �u�D�_�����v�ƃR�[�g�_�W���[��
2015.08.19 (��) ���~�x�݂��I�����
�~�J�����Ƌ��ɏƂ���鑾�z�ɂ�����悤�ȏ����A�����č��A�悤�₭�����Ȃ���~���̏H���������邱�̋G�߂ɂȂ�Ƃ����v����������B���ꂼ��̌̋��A��A���߂��Ă��邨�~�x�݂̎����B���̊ԁA���N���O�܂œ������K���K���ɂȂ���݁A���ƂȂ����������ԗl����藣���ꂽ�悤�ȁA�����͂��ƂȂ��������悤�Ȏ₵���l�ȕs�v�c�ȋC���ɂȂ��Ă����B�������܂������Ƃ���͐̂̒n���Ō����Γ����̕����搅�����Q�Ԓn�A���Ō����t���ƌĂ�Ă���Ƃ��낾�B���ꂱ���傫�ȎR�Ⓑ�Ղȓc��ڂ͖��������B����̑���ɐ_�c�삪����A�傫�ȐX��R�̑���ɏ��X�ɋn������A���X�������o�����̒��ɓ�����y���̒뉀�⏬�ΐ�A�������������B���ꂪ���ɂƂ��Ă̌̋��ł���B�Ƃ̗��ɂ̓j���g�������������āA�����ɂ����j���g���͌䑽���ɘR�ꂸ����������ƃR�P�R�b�R�[�I�Ɣh��ɂ���Ă����B���t���O�̐V����D���ɂ��āA���̋G�߂��Ƃɑc����{�点�Ă����`�����̏���������A�ꎞ���ɂ͓V�䗠���^����Ɗ��Ⴂ����l�Y�~�B�������B�Q���ɓ�������A����Z�Ɓg�����͉����ɂȂ��撣���Ă���ˁI�h���ƌ����Ȃ���������p���Ȃ���̃`���[�`���[�Ƃ���������g�R�g�R����܂�鉹�����B�ޓ����A��̉^������~�߂đ�l�����Ȃ�ƁA���܂��Ē�̖��ԉʂ���̖ɃV�}�w�r��A�I�_�C�V���E�Ȃ�Ă����傫�Ȏւ��o�v����B����Ȃ��鎞�A�������̓c�ɂ̌Â��Ƃ̓V�䂪�����A�ւ������ė����Ȃ�Č����b�����̂ŁA�l�Y�~�B�̉^����̓ˑR�̒��~�ƁA�ւ���ɏo�鑊�֊W��^���ɍl���Ă����������������B���v���ƂĂ��z�����������厩�R�̐H���A����f�i�Ƃ�����o�����������B
�H�ׂ���Ȃ��������̎����n���]�����l�ȊÎ_���ς������������ė�����ƁA�����҂��\���Ă������n���i�q�I�h�V�`���E�j���I�����W�F�̉H���q���q�������ĕ����A�傫�ȓ��悯�̗l�ȑ��I����A�Ԃ牺����悤�Ɏ��������Z�i�w�`�}�j������Ă͊������A����Ă���ő̂��S�V�S�V������B���Y����̎��́A�N�}���o�`�A�~�c�o�`�A�A�V�i�K�o�`�Ƃ����A�X�Y���o�`�ȊO�̖I�ɂ͈�ʂ�h����ċ������B���̒ɂ��͕M��ɐs�����������A�h���ꂽ�Ƃ���͎��Ԃ��o�ɂ�傫����ꂠ����A���S�����瑞���I�̐j���|�����Əo�ė������̂������B�����Ă��̒�ɂ͖���̐e�F�ł���G�팢�̃G�X����������҂��Ă����B�ނ����A���̎����e�F���Ǝv���Ă����炵���A�ɂȓ�l�H�͂����ꏏ�������B

�ނ͉��������Ȃ鎞�����ɗD���������B���钩�ǂ����Ă��ꏏ�ɍs���I�Ǝ����痣��Ȃ��B��������ł��J����Ƌ����ɕ@���˂�����ŊO�֏o�Ă��܂��B���x����Ă������������̂Œ��߁A������A�q�ɂȂ��Ă����ʉَq���܂ōj�������ɂ��ė��Ă��܂��������������B���R�A�����̂�����Ɏ��ƃG�X���{��ꂽ�B���ɂƂ��Ă͐e�F�Ȃ̂����A���̂�����ɂƂ��āA�G�X�͂����Ȃ薳�����ɓX�ɓ����ė��������̉������ł���B���v���A������������̂Ђ�ɂP�O�~�ʂ����肵�߁A�قƂ�ǖ�������Ă��邨���ӗl�������̂ł��̎�������������������������ƋL�����Ă���B���̑ʉَq���̖��͈ȑO���̂ЂƂ育�Ƃɂ��������g���X�h�ł���B���̎ʐ^�͒�ɂ���������̃G�X�Ǝ��ł���B
�����o����������Ə��w���ɂȂ������A�G�X�����B�N�����c������D����������Ă��ꂽ�e�F�Ƃ̐h���ʂ�Ɋ������ꂸ�܂����ڂꗎ�����B���̗l�q�����Ă����c�ꂪ������g�܂̕ʂ�h�ƌĂ�ł����B�����̎��ɂƂ��Ă��̌��t�����ɒp�����炵���悤�Œ��y�����������̂������B���ꂪ�؋��ɍ������̂悤�ɂ��̃V�[����Y��Ȃ��ł���B���ꂩ��V�F�p�[�h���̃x�A���瑱���̋��̌������̗��j�͂U����������B
�����Ă̏I��肪�߂Â����̎��߂ɂȂ�Ƃ��̍����v���o���B���܂��ɒ����j�q�Z������������Ȑt�̒W�����S�Ȃ�Ă����̂��Ȃ������ɂȂ��đh��B�N�ɂł��獷���ʁA�����ȓy�n�ɂ����Ȏv���o�̌̋�������B���̗��e�͂������ɖS���Ȃ������A���͂��̒�ƉƂɌZ�Ƃ��̉Ƒ��������Z��ł���B��̊̂���ł��̉Ƃ̓}���V�����ɂȂ�A��͓����̎O���̈ꂩ�S���̈�ɂȂ��Ă��܂����B�����͎��̏Z��ł��邱�����玩�]�Ԃł�����葖���Ă��������R�O���قǂ̋����ł���B����߂��ĉ����̋��̎v���o�́A���F���烂�m�N���[���ɂȂ�A���̍����炩�Z�s�A�F�ɕς�����B���N�͉����������̌̋��̒�̕Ћ��ɂł������Ă݂�̂��ꋻ���Ǝv���n�߂Ă���B�a�f�l�ɐ�̐^�ŁA�c�N�c�N�{�E�V�ł����Ă����Έ�w������������オ��̂�������Ȃ��B
 �ǐL�F
�ǐL�F����A���N�P�ቻ�����l�ɂ��ז����Ă����Ў���̐�y�̍L��Ȃ鐛���̕ʑ��֍s���Ă����B���̊Ԃɐ{��A���R�A�R�c�����Ċ}���x����u�ꍂ���A���c�����������B���悢�擌���A�鎞�Ɍ�납��B�e���Ă��ꂽ�ʐ^�ŁA��Ԃ��Ă���͎̂����܂ߘV�����H�R�l�̃I���W�B���B�s����͂��ꂼ��̉Ƃł͂Ȃ��A�܂�ł��̐��Ɍ������Ă���悤���I���܂�ɂ��h���s�V���Ȏʐ^�Ȃ̂Ōf�ڂ����Ă����������B
2015.08.02 (��) ���̎��݂ƎG����
���N�̂S������~�͋����ɒʂ��n�߂��B���̃u���O�̒��Ԃł���ǂ���y�ł���g�W���Y�ƃ~�X�e���[�h�̒S���҂���A�Ƃ��Ƃ��͒W�̋��n���I�Ƃ��A�ŋ߁A���������܂ꂽ齉��̋��I�̎傩��́A�S�R������Ȃ��I�ȂǂƂ����Ȏ��������Ă���B��l�Â��ɂ��̏����Ȑ��E�Ɉ������܂��ƁA�������琶�܂�L�����z�▲��ʔ������Ă���B�����O�̒����̓V���l��ɁA�؍��̒m���h�ŕ����������߂�����J�i�C�E�I���������j���E�g�k�ݎu���̓��{�l�h�̒��҂ł�����ނ��A�����ɂ����������Ă������ɓ��{�����̓����������Ă���̂��ʔ����B��̗�ł͂��̖~�͂Ɉꐡ�@�t�A�o��A�g�����W�X�^�E�E�E�B�����A���ɂƂ��Ă��̂ǂ�����ƂĂ��D���Ȃ��̂��B����Ƀ~�j�J�[��S���͌^�A�W�I���}���X��������肪�Ȃ��B�����ȃQ���}�j�E�����W�I�������ō��A����Ɖ����o�����̊����͖Y�ꂪ�������̂ɂȂ��Ă���B�����Ȃ��̂ɍׂ����H���{����Ă��镨�Ȃǂɂ��䂩���B�c��������m���ɏ������������m���D���������B ���̖~�͋����ł͕��ɖ�o���Ɍܗt�̏��Ȃǂɒ��킵���B�c�O�Ȃ��珼�͌͂炵�Ă��܂����̂����A�����ő�{�̖~�͑��܂ōs�������Ă������Ȃǂ��܂߂�ƍ���Z���قǂɂȂ��Ă���B���\�N����ďグ���|�p�̈�ɒB�������̂��ς�ƁA���̐l���㔼�Ɏ������N��炵�āA���A�茳�ɂ��镨����͂����炭����Ȃɉ��l���镨�ɂ͈炽�Ȃ����낤�B�~�͋����̐搶���g���̕c���P�T�N���o�ĂΗ��h�ɂȂ�܂��h�Ƃ̎��A������Ă������Ɠ��N��Ǝv�����l�����g����܂Ő����Ă����邩�ȁ`�I�h�ƊF���킹���̂����A�g���̒ʂ�I�h�Ǝ��������ɑ��Ƃ�ł����B�l���ꂼ��̊y���ݕ�������A�i�F�~�͂ɑΛ�����ƁA�����Ȏv���o���h��Ђ�����ƐS���₩�ɂȂ鎞�Ԃ�����Ă���B���̎��ɂƂ��Ă͂��ꂾ���ŏ\�����Ǝv���Ă���B
���̖~�͋����ł͕��ɖ�o���Ɍܗt�̏��Ȃǂɒ��킵���B�c�O�Ȃ��珼�͌͂炵�Ă��܂����̂����A�����ő�{�̖~�͑��܂ōs�������Ă������Ȃǂ��܂߂�ƍ���Z���قǂɂȂ��Ă���B���\�N����ďグ���|�p�̈�ɒB�������̂��ς�ƁA���̐l���㔼�Ɏ������N��炵�āA���A�茳�ɂ��镨����͂����炭����Ȃɉ��l���镨�ɂ͈炽�Ȃ����낤�B�~�͋����̐搶���g���̕c���P�T�N���o�ĂΗ��h�ɂȂ�܂��h�Ƃ̎��A������Ă������Ɠ��N��Ǝv�����l�����g����܂Ő����Ă����邩�ȁ`�I�h�ƊF���킹���̂����A�g���̒ʂ�I�h�Ǝ��������ɑ��Ƃ�ł����B�l���ꂼ��̊y���ݕ�������A�i�F�~�͂ɑΛ�����ƁA�����Ȏv���o���h��Ђ�����ƐS���₩�ɂȂ鎞�Ԃ�����Ă���B���̎��ɂƂ��Ă͂��ꂾ���ŏ\�����Ǝv���Ă���B ���̖~�͂Ƌ��Ɏn�߂��̂��~���g�͔̍|�ł���B�~���g�ɂ̓X�y�A�~���g�A�N�[���~���g�A�u���b�N�~���g�Ȃǂ�����A���ꂼ�ꂪ�����Â�������h��������ŁA�����Ȗ��⍁��̈Ⴂ������B���́A�n�[�u�͔|�Ȃǂ����̂��́A������ݕ������������Ŏn�߂Č����B����̓��q�[�g�Ƃ��������x�[�X�̑u�₩�Ȍ�������̃J�N�e���ł���B���낢��ȃo�[�ň���ł݂��̂����A��͂茈�ߎ�̓~���g�̗t���V�N�ł����������Ղ�Ɠ����Ă�����̂��|���Ƃ������_�Ɏ������B������̒�Ă�����A����Ȃ�ǂ��ɂ������Ȃ��|�����q�[�g���Ƃō�낤�I�Ƃ����̂��A�����������̃~���g�͔|�̂��������ł���B���q�ɏ���Ă����S��قǁ����q�[�g�E�p�[�e�B�[���Ȃ���̂��䂪�ƂŊJ�Â����̂����A�t���ς̐������ǂ��t�������͏��x�~�Ƃ��������ł���B
���̖~�͂Ƌ��Ɏn�߂��̂��~���g�͔̍|�ł���B�~���g�ɂ̓X�y�A�~���g�A�N�[���~���g�A�u���b�N�~���g�Ȃǂ�����A���ꂼ�ꂪ�����Â�������h��������ŁA�����Ȗ��⍁��̈Ⴂ������B���́A�n�[�u�͔|�Ȃǂ����̂��́A������ݕ������������Ŏn�߂Č����B����̓��q�[�g�Ƃ��������x�[�X�̑u�₩�Ȍ�������̃J�N�e���ł���B���낢��ȃo�[�ň���ł݂��̂����A��͂茈�ߎ�̓~���g�̗t���V�N�ł����������Ղ�Ɠ����Ă�����̂��|���Ƃ������_�Ɏ������B������̒�Ă�����A����Ȃ�ǂ��ɂ������Ȃ��|�����q�[�g���Ƃō�낤�I�Ƃ����̂��A�����������̃~���g�͔|�̂��������ł���B���q�ɏ���Ă����S��قǁ����q�[�g�E�p�[�e�B�[���Ȃ���̂��䂪�ƂŊJ�Â����̂����A�t���ς̐������ǂ��t�������͏��x�~�Ƃ��������ł���B�p�[�e�B�[�̃����o�[�͏�ɗ����I�ŁA�ߏ��ɂ��錤���M�S�ŋÂ����|���������܂���A����܂�齉��̏�����G�i���J�S�q��_�O�̂s�t�i�h�E�a�`�q�̃I�[�i�[�A�ނ͎����o�����Z�̌�y�Ƃ����������ł��̃p�[�e�B�[�ɎQ������悤�ɂȂ����B���ɂ͖������̉�Ђ̓����Ȃǂł���B���C�����i�肻���ɂ����Ղ�ڂ̃~���g�̗t�A�����ł͐h�߂��D���Ȑl�ɂ̓u���b�N�~���g�𑽂߂ɁA�X�^���_�[�h�ȊÂ����D�݂̐l�̓X�y�A�~���g�Ƃ�����ł���B����Ƀu���E���V���K�[���V���b�v�����X�A�����Ƀ��W���[�E�J�b�v����z���C�g���������A�ǂ�����܂���悤�y�X�g���ƌĂ��_�ʼn����B���ꂩ��X�A�����čŌ�ɒY�_�������A�o�[�E�X�v�[���Ōy���D���������ďo���オ��B�������č�郂�q�[�g�̂Ȃ��Ȃ��̖��Ɏ����������I�a�f�l�͂�͂�W���Y�����e���n�̕���I��ł���B
�G��
���N�͏t���珉�Ăɂ����āA�̂���̗F�l�����Ƃ̐S�̂���Ⴂ�𑱂��ĂQ�x�قnjo�������B�����������|���s���Ƃ͌���Ȃ��̂��l���B����͕S�����m�̃W�W�C�ɂȂ�A�����Ď����������������Ƃ͎v��Ȃ��펯�͐g�ɂ����͂��Ȃ̂ɁA�����キ�Ȃ�l���������e�͈͂����܂����Ǝv���Ȃ����Ȃ��B����Ȗ�����l�ɂȂ肫��Ȃ��������₵����Ȃ��̂����A���ʃX�b�L���E�n�b�L�������̎v�����B���Ȃ��A�F�D�Ȑl�ԊW��ۂׂ̂����Ɖ䖝�I���匙���Ȏ����������C�������̂ł���B���낢��Ȏ����v���Ȃ��獡�N�������Ă͉߂��Ă䂭�B
2015.06.21 (��) �쎡����
�~�J����O�̐���A���Z���ォ��̗F�l�̂m�N�Ɛ쎡����ɍs���Ă����B�ނ͑̂��Ĉȗ����͈��߂Ȃ��B�����l���̊y���݂Ƃ��Đ����Ă��鎄�Ɖ���́A�K�R�I�ɂ��݂����C���˂����������ł���悤�ɉ��قɈꔑ���鎖�ɂȂ�B���݂ɑO��͋��y���̂�◷�ق������B�쎡����P�Q�L���قǎ�O�̋S�{��ɂ͍s�����L��������̂����A�����炭�����͐l�����̉���n�ł���B���̗��͕K���h���C�u�����˂����̂Ȃ̂ŁA����͎��̃����Z�f�X�d�̃J�u���I���ōs�����ƂɂȂ����B�̂̃����Z�f�X�́g�őP�������h�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�̂��ƁA�l�W��{�Ɏ���܂Ŋ�����S���������i��m����̂Ƃ��āA�ߔN�͔R�������l�����y�ʉ��ƃR�X�g�_�E���ŏ��X������Ȃ������ۂ��Ȃ����Ɗ����Ă���B�ɂ������ȁA���ꂪ������O�ɐ��E�̒����ɂȂ�����������B ��N�̂P�P���ɔ[�Ԃ���Ă���A���s�����������Q��L�������Ɗ��炵�^�]����I���Ȃ����B�Ԃ����点�ăi���{�̕��A�M���Ŏ~�܂�G���W���X�g�b�v�͂������̎��A�o�b�N�̎��͌��̉f�����i�r�̉�ʂɉf��A�{�P�i�X�B�̐���������̏Փ˖h�~���u����A�㑱�̎Ԃ����Ă���̂ɃE�C���J�[���o���ƁA�x���������ăh�A�~���[���Ԃ��_�ł���B�������ԉ^�]����Ƌx�݂܂��傤�ƂȂ�B���傭���傭�ԂɎ����{���Ă���C���ɂȂ�B����͎ԂɌ��炸���݂̐��̌X���̂悤���B�V�����䂪�Ƃ̃g�C�����֍����痧���オ��A�l�����Ȃǂ����Ă̂�т�p���c���グ�Ă���Ɓg���^���^����Ȃ�I�h�Ƃ���A����ɕ֊킪�W���[�b�I�Ɛ��𗬂��Ă��܂��B�����āg�������������C�������܂��h����g���āA�ł߂̐��т��J�n�������܂��h���ꂩ�炢�������g���}�ȉ����o������@�B�����ȃ��m�����y�⏗���̐��ł���ׂ�܂���B�������������S�ƋC�z��A�o�ϐ�����Ƃ��l���Ă̗L���i�Z�p���낤���A���X�@�B���R�E���T�C���Ƃ̂悤�Ɏv���鍡�����̍����B
��N�̂P�P���ɔ[�Ԃ���Ă���A���s�����������Q��L�������Ɗ��炵�^�]����I���Ȃ����B�Ԃ����点�ăi���{�̕��A�M���Ŏ~�܂�G���W���X�g�b�v�͂������̎��A�o�b�N�̎��͌��̉f�����i�r�̉�ʂɉf��A�{�P�i�X�B�̐���������̏Փ˖h�~���u����A�㑱�̎Ԃ����Ă���̂ɃE�C���J�[���o���ƁA�x���������ăh�A�~���[���Ԃ��_�ł���B�������ԉ^�]����Ƌx�݂܂��傤�ƂȂ�B���傭���傭�ԂɎ����{���Ă���C���ɂȂ�B����͎ԂɌ��炸���݂̐��̌X���̂悤���B�V�����䂪�Ƃ̃g�C�����֍����痧���オ��A�l�����Ȃǂ����Ă̂�т�p���c���グ�Ă���Ɓg���^���^����Ȃ�I�h�Ƃ���A����ɕ֊킪�W���[�b�I�Ɛ��𗬂��Ă��܂��B�����āg�������������C�������܂��h����g���āA�ł߂̐��т��J�n�������܂��h���ꂩ�炢�������g���}�ȉ����o������@�B�����ȃ��m�����y�⏗���̐��ł���ׂ�܂���B�������������S�ƋC�z��A�o�ϐ�����Ƃ��l���Ă̗L���i�Z�p���낤���A���X�@�B���R�E���T�C���Ƃ̂悤�Ɏv���鍡�����̍����B���炵�^�]�����˂��Ԃœ��k�����F�s�{�܂ōs���A�����F�s�{���H�ɓ���̂����A�����̂��ƂȂ���z�e���̃`�F�b�N�C�����Ԃɂ͑����̂ŁA�ړI�n�ߕӂ̔��p�قɊ�蓹������̂���X�̏퓅��i�ł���B����͉F�s�{���p�قɍs�����ƂɂȂ����B�F�s�{�C���^�[�ō~��A�~�J���蒼�O�̂���₩�ȋG�߂Ȃ̂ŎԂ��I�[�v���ɂ��Ă������Ɨ����B���p�ق̖T�܂ŗ���ƊX�̗l�����ς��B�o�u���̍��̐�t���Ƀ`�o���[�q���Y�Ȃ���̂��o�����̂����A�܂��ɂ���̓Ȗ،��łł���B���h�ȏZ��������сA�����������E�Ƃ͈�����悵����C�ɂȂ�B�f�G�ȊX���݂ɏ��Ă̐S�n�悢���敗�����������A���̎�����͕����̗J����Y���B
�F�s�{�̒��S������T�L���قǖk�֍s�������ɂ��̔��p�ق͂���A�L��ȐX�ƎŐ����L����̋�Ԃ̒��ɂЂ�����ƘȂ�ł���B�����̒n�����p�ق������ł���悤�ɁA�����������ȋߑ㌚�z���B��J�̍̌@������ȑ�J���߂��̂ŁA���̐Ƒ傫�ȃK���X�����ɂ��܂��R���{�����A��莩�R�����I�݂Ɏ�����č�i�̖��͂��ۗ������Ă���B�����i�̒��ɂ̓V���K�[���A�p�E���E�N���[�A���c���P�A��䒉�A�����S�i�ˁj�Ȃǂ̊G���W������Ă���B�����S�͉������ɉ��炵�����_���ȃA�g���G���c����Ă��āA�n���ł͂Ȃ��݂̂����Ƃł���B�]�k�ɂȂ邪�����V�h���̒���w�ō~��Ă���A���������ƐX���q�̕��Q�L�ł�����݂̗ѕ����q�̉Ƃ�����B�ޏ�������͒����N���������Ă���ƒT�����Ă����C�ɓ���̍���Ɉʒu����y�n�ŁA���̕������{�Ɖ��͈ꌩ�̉��l������B���ꂩ��R��ʂ��n���ď��a�̌Â��ǂ�����������鍲���S�O�̃A�g���G�A�����Ă��̒����S�̃A�g���G�ŏI���Ƃ������C�y�U���������߂ł���B��͗₽���r�[���ƍs�������Ƃ��낾�B
�b�͓Ȗɖ߂�A�F�s�{���p�ق̃��X�g�����Œ��H���I�ƍl���Ă����̂����A�G���C���݂悤�łR�O�`�S�O���قǑ҂����ꂻ���Ȃ̂ō����͑��X�ގU�Ƃ������ɂȂ�B�C���^�[�ɖ߂�����F�s�{���H������A���s�C���^�[�ō~���B���낻�남��������A�h�̗[�т̎��Ԃ��l����Ƃ����炠����ŐH�ׂĂ����Ȃ��ƁA���y�R�����������ς��Ńz�e���̐H���Ƃ����Ԕ����ȃI���W�ɂȂ肻���ł܂����B�C���^�[�����E��Ɍ����ė����̂��������̂��������Ђ��A���s�C���^�[�X���Ƃ������\�h��ȊŔ̓X�\���B�����Ŏ�ł�����T�邱�Ƃɂ���B���͌��q�V�n���̃Z�C���𗊂B�b���҂��ė����̂͑傫���u�����Ƃ��������������q�V���B����������͍r���������Ƃ�����ł��ł���B�ꎞ���A�k�������ŏC�Ƃ�ς�ł��ΐE�l��ڎw�������������̂�����ԈႢ�Ȃ��B�i���F���ǂ����̋����ł��̎�ŏI���I�j���̒��H�̑I���͑吳���������B
 ���ꂩ�玩�����K���o�[�ɂȂ�A���E���̖������Ղ�������C�������\�y�����������[���h�E�X�N�F�A�Ȃǂ��E��ɂ݂āA��z�e�������ԋS�{�쉷��X���Ďb������ƁA�쎡����̍����̏h�ł���E�쎡�ɓ�������B�k�͖k�C�������͉���܂őS���ɂQ�S�قǎP���ɒu���A���A��Ԓ��𗎂Ƃ������̐��̃��]�[�g�̈�ł���B�Ԃ̃i�r�ɂ͏h���`���Ƃ������ŏo�ė���̂ŁA���������Ă܂��Ԃ��Ȃ��悤���B���c��ΔȂɌ����Ă������h�ȔL���z�e�������̎P���ɓ������炵���B�`���b�g�̘̂b�ɂȂ邪�A���`�Ő���̃��X�g�����Ǝ�������Ɍ��߂Ă��镟�Ֆ傪�A����ȓc�ɂ̃z�e���i����I�j�̒��ɓ����Ă����̂ɂ͋��������̂������B���{���o�u�����̏I�����}���邱�낾�����Ǝv���B�Ƃ肠�����H���܂łɂ͂����ԂԂ�����̂łm�N�ƎU�����Ă�X�ɏo�Ă݂��B�ȑO�̔ɉh���Â��鐔�������݉����A�قƂ�ǂ̗��ق�z�e�����߂��l�q�Ől�C���Ȃ��B
���ꂩ�玩�����K���o�[�ɂȂ�A���E���̖������Ղ�������C�������\�y�����������[���h�E�X�N�F�A�Ȃǂ��E��ɂ݂āA��z�e�������ԋS�{�쉷��X���Ďb������ƁA�쎡����̍����̏h�ł���E�쎡�ɓ�������B�k�͖k�C�������͉���܂őS���ɂQ�S�قǎP���ɒu���A���A��Ԓ��𗎂Ƃ������̐��̃��]�[�g�̈�ł���B�Ԃ̃i�r�ɂ͏h���`���Ƃ������ŏo�ė���̂ŁA���������Ă܂��Ԃ��Ȃ��悤���B���c��ΔȂɌ����Ă������h�ȔL���z�e�������̎P���ɓ������炵���B�`���b�g�̘̂b�ɂȂ邪�A���`�Ő���̃��X�g�����Ǝ�������Ɍ��߂Ă��镟�Ֆ傪�A����ȓc�ɂ̃z�e���i����I�j�̒��ɓ����Ă����̂ɂ͋��������̂������B���{���o�u�����̏I�����}���邱�낾�����Ǝv���B�Ƃ肠�����H���܂łɂ͂����ԂԂ�����̂łm�N�ƎU�����Ă�X�ɏo�Ă݂��B�ȑO�̔ɉh���Â��鐔�������݉����A�قƂ�ǂ̗��ق�z�e�����߂��l�q�Ől�C���Ȃ��B �͂��ɂQ���قǂ̃z�e�����J���Ă��邾�����B�����������܂�z�e��������ȏŐ��̃��]�[�g�ɔ���n�����̂�������Ȃ��Ɛ��@����B�z�e���ɖ߂��āA���r�[�ɍL����̑�p�m���}�A����Ɠ����R�߂Ȃ���̘I�V���C���ǂ��������A�H���̃s�J�s�J�ɋP�����Ă��ƂĂ��������������B�ȑO��m��Ȃ��̂ł����܂ł��z�������A�S�̂̊O�ǂ≃���̕��䂾�����Ǝv�����̊����ȂǁA���X�O�̏h�̖ʉe���c���Ă��܂��̂����A�悭�������܂Ŏa�V�ɐ��܂�ς�������̂��Ɗ��S����B
�͂��ɂQ���قǂ̃z�e�����J���Ă��邾�����B�����������܂�z�e��������ȏŐ��̃��]�[�g�ɔ���n�����̂�������Ȃ��Ɛ��@����B�z�e���ɖ߂��āA���r�[�ɍL����̑�p�m���}�A����Ɠ����R�߂Ȃ���̘I�V���C���ǂ��������A�H���̃s�J�s�J�ɋP�����Ă��ƂĂ��������������B�ȑO��m��Ȃ��̂ł����܂ł��z�������A�S�̂̊O�ǂ≃���̕��䂾�����Ǝv�����̊����ȂǁA���X�O�̏h�̖ʉe���c���Ă��܂��̂����A�悭�������܂Ŏa�V�ɐ��܂�ς�������̂��Ɗ��S����B���̒��ɂ͕ς��Ȃ���Α���������Ȃ����m�ƁA�l�̉��������v������Ƃ��ĕς���ė~�����Ȃ����m�Ƃ�����B��ɋL�����Ԃ�Ɠd�A�����Ă��̗��ق�z�e���Ƃ͂܂��ɑO�҂ŁA���Ɍ������o�c�𔗂��鎞�������x������̂��낤�B���C��Ń^�I������芷���ɗ����]�ƈ��̕��ɕ������b�ł́A���̐쎡�Ƃ������n�A��͂�k�ЈȌ�̌����̉e�����傫�������������B��������͐�������������̂ɁI�Ƃ̎��������B�E�쎡�͂��̒n�̊�]�̐���������Ȃ��B�Ƃ�����Ύ���ɕ�����ė������ڂ�C�Ȑl�X�̐S�𑨂��A�����������p�����݂ȕω��ŏ����ƂȂ��B���̒��ŁA���a�̖Y��`���̎����{�[���ƐV�̎R�̗y����A������܂��ς�邱�Ƃ��Ȃ������ȁA�������Ƃ����g���r�̋V�j�߂Ă���B
2015.06.10 (��) �� �p���A�����ė����I�����
���������Ă���~�J���}���������ɂ���ΐ����̂̎��̂悤�����A�S�����O�̃t�����X���s�L�̒��߂�����Ƃ��Ă̂ЂƂ育�ƁB�R���ڂ̃p���̓z�e����������Ă����T�́A�n�ɏ�����W�����k�_���N�̉������̉�����o�����A�o�X�łT�O���قǍx�O�̃A�E�g���b�g�ɍs���Ă݂��B���ƂȂ��Ă͂���ƌ����ė~�������͖̂����̂����A�ʂ����ă��[���b�p�̂���͂ǂ�Ȃ��̂��낤���ƉƑ��ɕt�������Ă݂��B�w�Ǔ��{�Ɠ����`�ԂŁA�㊥�o�X���Ă���X���Ⴄ���ȁH�Ƃ������Ƃ��낾�������A�Ⴂ���ɗ��s�����X�|�[�c�p�i�������Ă����}�N���K�[���������B���������Ɨ��̎v���o�ɖȂ̃T�}�[�Z�[�^�[���ꖇ�����B ���ꂩ��z�e���ɖ߂�A�삯���ő��q�Ɠ�l�ŕَ��Ԑ��O�̃I���Z�[���p�قւ��s���Ă݂��B�ق̓�����ɂ͊Z��Z�����l�ȁA�傫���Ă����ɂ��������ȃC���h�T�C�̓������h�h�[���Ə����Ă���B�t�����X�l�͉��̂����̃C���h�T�C���D���Ȃ悤�ŁA���s���Ɋ��x������Ɠ����悤�ȃ��m�������B�ٓ��ɂ̓~���[�́g����Ђ낢�h�A�������ނ̍�i�ŏ��w�Z����ɂ��̐���ߒ���ǂ�Őe���݂̂���g�ӏ��h�A�h�K�́g�_���X�����h�A���̂��������������ł���s�v�c�ȊG�ł���}�l�́g����̒��H�h�A�����ۗ��S�b�z�́g���摜�h���𑫑��Ɍ���B�G���������悤�ɕǂ̐F���ւ���ꂽ�ƕ����Ă������A�[�݂�������ɂ����F�������B
���ꂩ��z�e���ɖ߂�A�삯���ő��q�Ɠ�l�ŕَ��Ԑ��O�̃I���Z�[���p�قւ��s���Ă݂��B�ق̓�����ɂ͊Z��Z�����l�ȁA�傫���Ă����ɂ��������ȃC���h�T�C�̓������h�h�[���Ə����Ă���B�t�����X�l�͉��̂����̃C���h�T�C���D���Ȃ悤�ŁA���s���Ɋ��x������Ɠ����悤�ȃ��m�������B�ٓ��ɂ̓~���[�́g����Ђ낢�h�A�������ނ̍�i�ŏ��w�Z����ɂ��̐���ߒ���ǂ�Őe���݂̂���g�ӏ��h�A�h�K�́g�_���X�����h�A���̂��������������ł���s�v�c�ȊG�ł���}�l�́g����̒��H�h�A�����ۗ��S�b�z�́g���摜�h���𑫑��Ɍ���B�G���������悤�ɕǂ̐F���ւ���ꂽ�ƕ����Ă������A�[�݂�������ɂ����F�������B ����͂�������Či�F�����ɏW�������l�P�S���[���̑D��I�B�ǂ�����n�������Ȃ̂����A��͂�܂����͗₽���B�D�̏ォ�璭�߂�I���Z�[�Ƀ��[�u�����p�فA�p���̋����������A�G�b�t�F�����̉���U�^�[���B�Z�[�k���璭�߂�ߌ�̌��ɏƂ炳�ꂽ�p���͂����ƈႤ�����B�����ł͐��ȗ��l���C����Ă̂₹�䖝�I������Ў�Ɋʃr�[���B�ǂ��̍����痈���̂��H���m��ʋq�ƁA�C�����̂�������̓��̍K�^���j���B
����͂�������Či�F�����ɏW�������l�P�S���[���̑D��I�B�ǂ�����n�������Ȃ̂����A��͂�܂����͗₽���B�D�̏ォ�璭�߂�I���Z�[�Ƀ��[�u�����p�فA�p���̋����������A�G�b�t�F�����̉���U�^�[���B�Z�[�k���璭�߂�ߌ�̌��ɏƂ炳�ꂽ�p���͂����ƈႤ�����B�����ł͐��ȗ��l���C����Ă̂₹�䖝�I������Ў�Ɋʃr�[���B�ǂ��̍����痈���̂��H���m��ʋq�ƁA�C�����̂�������̓��̍K�^���j���B����ӂ��V���D���̌��𖡂������ɁA�O�邩��C�ɂȂ��Ă����t�����X���\����J�W���A���E�V���[�Y�̃p���u�[�c���X�ɍs���Ă݂��B�����ŃC���N�u���[�̃v���[���g�D�����B���̉�Ђ̒�ԏ��i�Ƀ`�����A���E�V���[�Y������B���̒��ł��A�U���V�̖ё��̒Z���炪�A�C�̍b�ɒ����Ă��郂�m�������ƈȑO����~���������̂����A��������c�̂���̋��������Ő������~��]�V�Ȃ�����Ă����B���͐^�����ȃE�T�M�̃v���v���̖є炪�t���Ă��郂�m�ɕς���Ă���B����𗚂��Ă݂��̂����A�ǂ�����Ă��ς��҂ɂ��������Ȃ��̂Œ��߂邱�Ƃɂ����B�~��C���J�A�����Ă����ł̓A�U���V�ɑ�\����铮������c�̖̂��Ȏv������̗��_�͖����ɗ����ł��Ȃ��ł���B���̖�̓I�y�����̂������̃r�X�g���ŁA�O���Ɉ��������������X�e�[�L��H�ׂĂ݂��B�������N�A�܂������ł͍D��ŃX�e�[�L�ނ͐H�ׂȂ��̂����A������͂����Ղ�Ɗ|�����\�[�X�������ڂ�肳���ς肵�Ă��Ď_���ƊÂ݂��������B�Ă������쐫�I�ŊO���͍������ł��ڂ����A��Ɠ��͐Ԃ��W���[�V�[�Ȃ̂ŋv���U��ɔ��������Ɗ�����B���ꂩ��z�e�������C�g�E�`�F�b�N�A�E�g���Đ[��̃t���C�g�ŋA���̓r�ɏA�����B
�܂��܂����Ă݂������Ƃ͈�t����̂��Ƃ��Â��v���B��������R�ʂ肪�����������ȓX��X�[�p�[�ŁA�����ɍ����ō����Ă���l�X�̐����Ŋ����邱�Ƃ��y���������B�v�X�g�߂ɂȂ����C�O���s�ł��A���߂ĕ������̊X�̓����₻���ŏo��l�X�����グ�Ă���ٕ����́A�����ɂȂ��Ă��V�N���B�����Ė{��ʐ^�Ō��m���Ă����������ۂɖڂ̑O�Ɍ��ꂽ�����Ȃǂ������y����ł���B�������݂̎����Ƃ��āA�t�����X�̗����͂�������Ƃ������ƍ��肪����A���̗�����H�ׂĂ���Ɠ��{����Ē��Ȃǂł͂Ȃ��A�B�ꃏ�C�����������݂����Ȃ�B���ׂĂ̓��C�������ވׂɍ���Ă��闿�����Ƃ��������������B�H��ʂ��Ă����������L���I���������͉̂䂪���{���Ɖ��߂Ďv���B���������ǂ�Ȃɕ֗��Ő����ȍ��ɐ����Ă���̂��A���A�����ۂ��Ȏ������O���猩�ߒ����������������B���낢��Ȗ�������Ȃ�����A����ς肱�̓��{�Ƃ����������͍D�����B
 �����čŌ�ɓ앧�̃J�[���g���z�e���ɔ��܂�邱�Ƃ��ł��Ė{���ɗǂ������Ǝv���Ă���B�ȑO�̂ЂƂ育�Ƃł��G�ꂽ�������g�D�_�����h�Ƃ����f��̒��ŁA�O���[�X�E�P���[������A�����J���܂�̑f�G�ȏ������A�z�e���̕����܂ő����Ă��ꂽ�ȑO�̓J���X�}�I��ΓD�_�������P�[���[�E�O�����g�ɁA�����Ȃ�L�X�����邠�̃V�[�����ς��j�����́A���Ȃ炸�Ƃ��N��������S������u�Ԃ��Ɗm�M���Ă���B���ꂩ��U�O�N�Ƃ�������������A�������̖ʉe���c���B�e����ɍs�������ƂɊ��ӂł���B����Ɠ����悤�ȑ̌����R�N�O�ɂ��������B�����ƂQ�l�ōs�������[�}�ŁA�ǂ����Ă��s���Ă݂��������f��������ɉ˂���T���^���W�F����̋��̏�ɗ������B�����͉f��g������ȁh�ŁA���ɔY�ރX�U���k�E�v���V�F�b�g�ƁA�}�Z���e�B�ɏ�肱�Ȃ��A�a����l�̃v���C�{�[�C�����������b�T�i�E�u���b�c�C�����ɂ��ė@���A��荇�����f�G�ȏ����B���A���̋��̂������́g���[�}�̋x���h�ʼn����̃I�[�h���[���A�����̌�q�c��ɁA�D��p�[�e�B�[�ő嗧�����������ꏊ���B�������̐S�ɟ��݂����̃V�[�������n���̂悤�ɑh��B����ȓ���ɏo�������A�����̓����T���Ă݂悤�Ǝv���B
�����čŌ�ɓ앧�̃J�[���g���z�e���ɔ��܂�邱�Ƃ��ł��Ė{���ɗǂ������Ǝv���Ă���B�ȑO�̂ЂƂ育�Ƃł��G�ꂽ�������g�D�_�����h�Ƃ����f��̒��ŁA�O���[�X�E�P���[������A�����J���܂�̑f�G�ȏ������A�z�e���̕����܂ő����Ă��ꂽ�ȑO�̓J���X�}�I��ΓD�_�������P�[���[�E�O�����g�ɁA�����Ȃ�L�X�����邠�̃V�[�����ς��j�����́A���Ȃ炸�Ƃ��N��������S������u�Ԃ��Ɗm�M���Ă���B���ꂩ��U�O�N�Ƃ�������������A�������̖ʉe���c���B�e����ɍs�������ƂɊ��ӂł���B����Ɠ����悤�ȑ̌����R�N�O�ɂ��������B�����ƂQ�l�ōs�������[�}�ŁA�ǂ����Ă��s���Ă݂��������f��������ɉ˂���T���^���W�F����̋��̏�ɗ������B�����͉f��g������ȁh�ŁA���ɔY�ރX�U���k�E�v���V�F�b�g�ƁA�}�Z���e�B�ɏ�肱�Ȃ��A�a����l�̃v���C�{�[�C�����������b�T�i�E�u���b�c�C�����ɂ��ė@���A��荇�����f�G�ȏ����B���A���̋��̂������́g���[�}�̋x���h�ʼn����̃I�[�h���[���A�����̌�q�c��ɁA�D��p�[�e�B�[�ő嗧�����������ꏊ���B�������̐S�ɟ��݂����̃V�[�������n���̂悤�ɑh��B����ȓ���ɏo�������A�����̓����T���Ă݂悤�Ǝv���B
2015.04.25 (�y) �p���ɂ�
�ߌ�̂Q�����ɉ����̃j�[�X��`����ǂ���܂����p���֓����B���̒n��l�X�ɍ��ꍞ��ł��Ȃ��̂����A�P�Ȃ鐬��s���łS�x�ڂ̃p���ł���B�傫�ȉו��ƉƑ��T�l�̈ړ��͂ǂ����Ă��^�N�V�[�Q��̈ړ��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�������ړ����l����ƁA�o�ϓI�Ŗ��ʂ̂Ȃ��V�`�W�l�͏����^�̃~�j�o�������炩���ߗ���ł����B���R���{������\�\�ŁA��������`�̓������r�[�Ńv���J�[�h�������ďo�}���Ă����B�A����z�e���̃��r�[�܂ŗ��Ă����̂ň��S�ŕ֗����B�z�e���̓p���̒��S�n�̃`���C�����[�뉀�̂قڒ����ɖʂ����T���E�W�F�[���X�E�A���o�j�[�B�����͍��ɍs�������ׂ����[�u�����p�فA���̃`���C�����[�뉀��^�������ɉ����āA�Z�[�k��ɉ˂��郍���C��������n��ƃI���Z�[���p�فB�E�ɍs���R���R���h�L�ꂩ��䑶�m�V�����[���[��ʂ�Ɍq����B�����ăR���R���h�L����E�ɋȂ�M���V���������̃}�h���[�k����B���̓r���ɂ̓G�����X��O�b�`���A�u�����h�D���ɂ͂��܂�Ȃ��X�����ԃt�H�[�u���E�T���E�g�m���ʂ肪����B�n���S�̉w�͖ڂ̑O�ɂ���A�I�y�����܂ŋ�����������Ă�����D���n�ȃz�e�����B���̂S���Ԃ̖����A�ڂ̑O�̃`�F�C�����[�뉀���o�Γr���̃p���W����������ڂɁA���{�ł�����Ă��錒�N�ێ��̂��߂ɂP���ԂقǕ������B�̂͋{�a�Ɨאڂ̃C�^���A���뉀�����������������A���͏��X�Ƀ|�c���Ƃ���C�Ȃ��u���ꂽ�����⑽���̃J�����������W�܂��̒r�A�������傫�����ĂȂ��Ȃ����ꂾ�Ɖ���Ȃ����ؓ�������̂����A���Ƃ����̂������L���ɂ͋������肾�B�p���������x�݂��Ă���A�ȑO�ɂ͂Ȃ������傫�Ȋϗ��Ԃ��s�J�s�J�ƌ��肾�����R���R���h�L��܂ōs���A�����B�e�^�C���ƂȂ�B�����ł͂S�S�N�O�Ɏ������߂ăp���ɗ������̎v���o�����X�Ƒh��B�t�����X�v���u����ɃM���`�����ݒu����A���C�P�U���A���̍Ȃ̃}���[�E�A���g���l�b�g�ق��P�R�S�R�l�̖��������ɏ������Ƃ����B���̏ꏊ�ŃK�C�h������}���[�E�A���g���l�b�g�����Y����鎞�ɁA�����̌����ڗ����ʂ悤�ɐ^���Ԃȃh���X�𒅂Ă����Ƃ����Ȃ����߂����b�����ꂽ�B
 ���ɍs�����̎��܂ŁA�ޏ��̔��ւ̂������Ɋ��������Ⴋ���������Y��Ȃ��ł���B�v���L��Ƃ��Ăꂽ���̍L��́A���h��ꂽ���j�������Âԏ��ł�����B�������瑱���[���̃V�����[���[��ʂ������B�ŋ߂̓����͉����֍s���Ă��O���l�̑����ɂ͖{���ɋ����̂����A�t�����X�͂���܂ōs���Ă����ɂ߂̈ږ������A���[���b�p�̊e���ɒn�����Ƃ�����������A���̔�r�ɂ͂Ȃ�Ȃ��l��̚��Ăł���B�M����Ɍ������č����ɂ���A���⒆���l�̓X���ɒ����l�̂��q���w�ǂƂ������C���B�g���̖{�X�����ɐ܂�āA�t�߂肷��悤�Ɏb�������ƁA�f�B�i�[���V���ɗ\�����X�g�����g�V�F�E�A���h���h�ɒ����B
���ɍs�����̎��܂ŁA�ޏ��̔��ւ̂������Ɋ��������Ⴋ���������Y��Ȃ��ł���B�v���L��Ƃ��Ăꂽ���̍L��́A���h��ꂽ���j�������Âԏ��ł�����B�������瑱���[���̃V�����[���[��ʂ������B�ŋ߂̓����͉����֍s���Ă��O���l�̑����ɂ͖{���ɋ����̂����A�t�����X�͂���܂ōs���Ă����ɂ߂̈ږ������A���[���b�p�̊e���ɒn�����Ƃ�����������A���̔�r�ɂ͂Ȃ�Ȃ��l��̚��Ăł���B�M����Ɍ������č����ɂ���A���⒆���l�̓X���ɒ����l�̂��q���w�ǂƂ������C���B�g���̖{�X�����ɐ܂�āA�t�߂肷��悤�Ɏb�������ƁA�f�B�i�[���V���ɗ\�����X�g�����g�V�F�E�A���h���h�ɒ����B �����͒����̉�Ђ̃p���x�X�̂������ŁA�����œ����Ă�����y�����̂��E�߂̃r�X�g���̈���������B����̃p���̃z�e�����ޓ��̏Љ�����B�Ȃ�قǂ��C�y�Ȋ����Œ��͍L�����n���̐l�����łقږ��Ȃœ�����Ă���B�ꌩ���ĊO���l�͎������Ƒ������������B�H���̃��j���[�����Ȃ���A�܂��͔����C���Ɖ��y�𒍕����鎖�ɂ����B���y�̒l�i�͘Z�łP�W�C�Q�O�A�Q�Q���[���ƂR�i�K����B���̓X�̃��[���A����E�F�C�^�[�̂������g����̓x�X�g���I�h�ƑE�߂���܂܂Ɏv�����ĂQ�Q���[���̕��ɂ����B
�����͒����̉�Ђ̃p���x�X�̂������ŁA�����œ����Ă�����y�����̂��E�߂̃r�X�g���̈���������B����̃p���̃z�e�����ޓ��̏Љ�����B�Ȃ�قǂ��C�y�Ȋ����Œ��͍L�����n���̐l�����łقږ��Ȃœ�����Ă���B�ꌩ���ĊO���l�͎������Ƒ������������B�H���̃��j���[�����Ȃ���A�܂��͔����C���Ɖ��y�𒍕����鎖�ɂ����B���y�̒l�i�͘Z�łP�W�C�Q�O�A�Q�Q���[���ƂR�i�K����B���̓X�̃��[���A����E�F�C�^�[�̂������g����̓x�X�g���I�h�ƑE�߂���܂܂Ɏv�����ĂQ�Q���[���̕��ɂ����B �j���[���[�N�̃O�����h�Z���g�����E�X�e�[�V�����ɂ���I�C�X�^�[�o�[�Ɠ����H�ו��ŁA�g�̒��ɒ��悭�c�����C���̉����𗘗p���āA�����Ɍy�����������Q�C�R�H�i�邾���ŁA���y�{���̎|�����V���v���ɋ��邨����݂̐H�ו����B����͖{���ɔ����������B���ɂ͐㕽�ڂɃ`�L���A���[�W�����ŐH�ׂ����̔���������ł݂��B�������ɕ]���ʂ�A�ǂ̗����������I�ŋC�����Ȃ��A���ꂾ�������̋q�Ɉ�����闝�R���������B�������Ĕ��������p���̈���ڂ̖�͍X����B
�j���[���[�N�̃O�����h�Z���g�����E�X�e�[�V�����ɂ���I�C�X�^�[�o�[�Ɠ����H�ו��ŁA�g�̒��ɒ��悭�c�����C���̉����𗘗p���āA�����Ɍy�����������Q�C�R�H�i�邾���ŁA���y�{���̎|�����V���v���ɋ��邨����݂̐H�ו����B����͖{���ɔ����������B���ɂ͐㕽�ڂɃ`�L���A���[�W�����ŐH�ׂ����̔���������ł݂��B�������ɕ]���ʂ�A�ǂ̗����������I�ŋC�����Ȃ��A���ꂾ�������̋q�Ɉ�����闝�R���������B�������Ĕ��������p���̈���ڂ̖�͍X����B�Q���ځA�Ƒ��̒��ōȂ����̃��[�u�����p�ٕK���g�ƁA����͂��������g�Ƃ̂Q�g�ɕ������B���������g�̎��ƒ����͂Ђ�����p����������Ƃɂ����B�z�e�����o�����Ă���A�I�y�����̑O�ōŏ��ɏo���킵���̂��W�v�V�[�炵���s�Ǐ����B�ŁA�O��������N�̓��{�l�v�w�ɂT�`�U�l�Ŗ������`���V�������t���Ȃ���A�W�c�ŃX�������Ƃ������m�������B�Ȃ�Ƃ�����̐l��������`���Ė������������A�����ς炩��l�ڂ��͂��炸��_�Ȏ���������̂ł���B���x�͂�����̕S�ݓX�A�M�������[�E���t�@�C�G�b�g�̑O�ŁA�A���P�[�g�����U������đ҂��\����ʂ̃X���W�c�炵�������B������B�������͊����ɖ������т��B�ǂ��������͔ޏ������̉҂����̗l���B����̃e���ɑ��āA�t�����X�͍��������Ă̖h�q�̐��ɓ����Ă��邽�߁A�t�ɂ��̏����B�̃`���P�Ȉ��s�ɂ܂Ŏ肪���Ȃ��Ƃ��������炵���B�m���ɓ앧�ł��|���X�͂������̎��A���ʕ��Ɏ������e���\�����������悭���������B�ނ�͂��ł����C�ł����ԂȂ̂ŁA�T�ɗ�����Ɗ�Ȃ��Ј���������B
���ꂩ��p���̖k�̍⓹�����X�Ƒ��������}���g���̋u��o��A�e���g���L��ɏo�ĉ�Ƃ����̊G���ӏ܂���B��͂荡������̍D���ȃ^�b�`�̊G�ɂ͏o��Ȃ��B�����ł͎��摜��`���Ă�����Ƃ�����Ƃ������A���Ԃ��Ȃ�����Ɏ��M���Ȃ����Œf��̂ɕ�����B�ׂ̃T�N���N�[�����@����p���̑S�i�߂Ȃ���A�X�ɍ~��č����ʂ�����Ă݂��B�Ԃ��܂������B���O�X�g�k�ʂ�Ƃ��������Ō����Ȃ�A���闢�̐��n�≮�X�̃p���łƂ������X�ɂȂ�B�ٖD�����鏗���Ȃ���Ɋy�������ȁA�����t�����X�̐��n�⏬���̓X�������Ă���B���̖≮�X���I��肻�̂܂ܓ��^�������������B���x�͒��ߓ����v�킹��x���[�_���X�̈ߑ��̗l�Ȃ��̂��V���[�E�C���h�[�ɏ����A�����������ȕ��͋C���ӂ��ʂɕY���X�ɂȂ�B�����Ȃ�ʐ��E�ɗ����悤�ł��Ȃ�ʔ����̂����A���鏊�Ɍ��̕�������A���f���Ă悻���Ȃǂ��Ă���ƔߎS�Ȃ��ƂɂȂ�B�g�����͖{���ɂ��̓���̃p������I�h�ȂǂƖ��ɘb�������Ȃ���A�悤�₭�ڎw���Ă����n���S�̃V���g�[���[�W���w�ɒ����B��������Z�[�k��̉��������A��芷���Ȃ��łP�R�Ԗڂ̉w�ł���T���E�W�F���}���E�f�E�v���������B��荞�ԗ��̒��͎��B���܂߁A���̂��L�F�l�킾���Ƃ������������i�������B
�~�肽���̊X�͎��ɂƂ��Ă����炭���߂ė���ꏊ�ł���B�T���E�W�F���}���E�f�E�v������̐��ʂ̃J�t�F�g�t���[���h�ŁA�����ƃ��[�u�����p�ق֍s�����Ȃ�����҂��ɂ����B���̍��ł͐V�������������N�z�̒j������l�ł������y����ł���p���悭��������B���ꂪ�Ȃ��Ȃ��a���B���̐Ȃ��狳��̕������Ă���ƁA���N�̗��l�Ǝv�����J�b�v����A���邩��ɒ��̗ǂ�����悭�����ꖺ�̗��l�Ȃǂ��O��ʂ�B���A�b������Ƃ������Ȃ̂��낤���A�ÁX�Ɛi�ފ��̌�ɁA�⑰�炵���l�X������̒��֓����Ă������B����Ȉٍ��̐l���͗l���ڂ��蒭�߂��肵�Ă�����ɁA�p���̎��Ԃ͂������Ɖ߂��Ă䂭�B�悤�₭�Ƒ��������A�T���E�W�F���}����ʂ����k�ʂ���E�C���h�[�V���b�s���O�Ŋy���B�����̓\���{���k��w�Ȃǂ�����A�t�����X���\����m�I�Ő������ꂽ�G���A���������B�C���E�V�����Ƃ����t�����X�̉̎肪���̒n���ނɉ̂����g�J���`�F���^���̌ǓƁh�Ƃ������������A���o�����v���o���Ă����B���̍��͂܂��D�����������郌�R�[�h�S���̎��ゾ�����B�����Ă����Ȃ�S�S�N�O�ɖ߂����A��̃R���R���h�L��ɂ��鎞�������������̂����A���̒n�֍s���čĂёh�鉓�����̎v���o�́A��������S�̗��ƍ������ɂ��錻������������ƂĂ������u�ԂɂȂ�B�����������p���̓���ڂ��悤�₭�I���B
2015.04.04 (�y) �O�b�o�C�I �앧
 �����A�����̃��i�R�ɑ����u�˂��ق�̂薾�邭�Ȃ��Ă����悤�����A���̃J���k���ʂ͂܂����̒ʂ茎���o�Ă���B�����u���[�ł����ނ��̐F�������n�߂���̉��A�܂��j�[�X�̒��͖����Ă���悤���B�����ł��̓앧�Ƃ����ʂ�A���B�Ƒ��T�l�Ɠ~�̗��̏d���ו�������킸�ɏ悹�悭�����Ă��ꂽ�ԂƂ����ʂꂾ�B���ɂ͕K�R�I�ȑ��̊Ԃ̏o�������ʂꂪ����B�l���͊��x������������O�^�C���ŌJ��Ԃ��킯�����A�l���D��ōs�����Ƃ������̒Z�����Ԃɂ��ꂪ�Ïk����Ă���B
�����A�����̃��i�R�ɑ����u�˂��ق�̂薾�邭�Ȃ��Ă����悤�����A���̃J���k���ʂ͂܂����̒ʂ茎���o�Ă���B�����u���[�ł����ނ��̐F�������n�߂���̉��A�܂��j�[�X�̒��͖����Ă���悤���B�����ł��̓앧�Ƃ����ʂ�A���B�Ƒ��T�l�Ɠ~�̗��̏d���ו�������킸�ɏ悹�悭�����Ă��ꂽ�ԂƂ����ʂꂾ�B���ɂ͕K�R�I�ȑ��̊Ԃ̏o�������ʂꂪ����B�l���͊��x������������O�^�C���ŌJ��Ԃ��킯�����A�l���D��ōs�����Ƃ������̒Z�����Ԃɂ��ꂪ�Ïk����Ă���B �����ł̊ό��q�̒N�����s���}�e�B�X���p�ق�V���K�[�����p�ٌ��w�͔�s�@�̏o�����Ԃ̊W�ł��̍ۃJ�b�g����B�����Ă��傤�Ǎ����͓��j���A���T���̊X�ʼnԂ̒��s���J����Ă���̂ő��X�s���Ă݂鎖�ɂ����B���l�̖{���������A�j�[�X�ň�Ԋy�����̂����̒��s�ł���B�z�e������قNj߂��}�Z�i�L��ɏo��B�����������[���b�p�̂R��J�[�j�o���ƌĂ��Ղ肪���̃j�[�X�ŊJ�����B���N���E��������ɑ����̊ό��q���K���Ƃ����B���̊ϋq�ň�t�ɂȂ�傫�Ȋϗ��Ȃ����C�����H������ŗ����ɏo���Ă����B���̓K�����Ƃ��Ă��邪�A��������ɂ����ɏW�܂�吨�̐l�X�̓��킢��p�Ӗ��[�A���͂����Â��ɑ҂��Ă���Ƃ�������ł���B�������炵�炭���ɐi��ł���C�ݕ��ʂɍs���ƁA�ԑ����������l�����Ƃ���Ⴄ�B
�����ł̊ό��q�̒N�����s���}�e�B�X���p�ق�V���K�[�����p�ٌ��w�͔�s�@�̏o�����Ԃ̊W�ł��̍ۃJ�b�g����B�����Ă��傤�Ǎ����͓��j���A���T���̊X�ʼnԂ̒��s���J����Ă���̂ő��X�s���Ă݂鎖�ɂ����B���l�̖{���������A�j�[�X�ň�Ԋy�����̂����̒��s�ł���B�z�e������قNj߂��}�Z�i�L��ɏo��B�����������[���b�p�̂R��J�[�j�o���ƌĂ��Ղ肪���̃j�[�X�ŊJ�����B���N���E��������ɑ����̊ό��q���K���Ƃ����B���̊ϋq�ň�t�ɂȂ�傫�Ȋϗ��Ȃ����C�����H������ŗ����ɏo���Ă����B���̓K�����Ƃ��Ă��邪�A��������ɂ����ɏW�܂�吨�̐l�X�̓��킢��p�Ӗ��[�A���͂����Â��ɑ҂��Ă���Ƃ�������ł���B�������炵�炭���ɐi��ł���C�ݕ��ʂɍs���ƁA�ԑ����������l�����Ƃ���Ⴄ�B ��͂蒩�s�i�}���V�F�j�͑O�ɗ����ꏊ�Ɠ����Ƃ��낾�����B
��͂蒩�s�i�}���V�F�j�͑O�ɗ����ꏊ�Ɠ����Ƃ��낾�����B���z�̒��Ŋς�Ԃ̐F��ῂ����قǑN�₩���B���̎��ɍ��킹�č炫�ւ邻��͂܂��Ƀj�[�X�̊�ł���B�s��̉��ł͍K�^�ɂ��N���V�b�N�J�[�̃C�x���g������Ă����B�Ԃ����[�K����I�[�X�`���q�[���[���A�������w�⍂�Z����̍��ɓ��ꂽ���������Ԃ��������Q�����Ă����B
 ������������āA���̓��{�𑖂�Ԃł͂Ȃ��Ȃ��k���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A���̃K�\��������������������r�C�̓����I���ꂪ�G���W���̗E�܂������ɍ������ĕY���Ă���B�s��œ����Ă��錳�C�Ȃ�������₨����B�͊F�傫�Ȑ��ŗǂ������B�����֗���Ɛl�͂��Ƃ�蔄���Ă��鏤�i�܂ł����C������A�����S���e��ł��ĉ��ƂȂ��������Ȃ�B�������̉Ԃ̑��ɂ͐V�N�ȉʕ����A���x���_�[��o�j���ɕς���ł�
������������āA���̓��{�𑖂�Ԃł͂Ȃ��Ȃ��k���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A���̃K�\��������������������r�C�̓����I���ꂪ�G���W���̗E�܂������ɍ������ĕY���Ă���B�s��œ����Ă��錳�C�Ȃ�������₨����B�͊F�傫�Ȑ��ŗǂ������B�����֗���Ɛl�͂��Ƃ�蔄���Ă��鏤�i�܂ł����C������A�����S���e��ł��ĉ��ƂȂ��������Ȃ�B�������̉Ԃ̑��ɂ͐V�N�ȉʕ����A���x���_�[��o�j���ɕς���ł� �`���R���[�g�̍��肪����J���t���ȐΌ��A����͂قƂ�ǐF�������Ȃ̂Ŏv�킸�����肽���Ȃ�B���̑��ɂ͂����Ȏ�ނ̃I���[�u�I�C���A�܂����ɂȂ��Ă��Ȃ����̂܂܂̍��h���Ƀj�[�X�y�Y�̉��������ށA���̐�֍s���ƔM�X�̃g�}�g�ƃI�j�I���̃s�U�����������������Ă���B�������̃g�}�g���̂������̃s�U��H�ׂȂ��疔����B
�`���R���[�g�̍��肪����J���t���ȐΌ��A����͂قƂ�ǐF�������Ȃ̂Ŏv�킸�����肽���Ȃ�B���̑��ɂ͂����Ȏ�ނ̃I���[�u�I�C���A�܂����ɂȂ��Ă��Ȃ����̂܂܂̍��h���Ƀj�[�X�y�Y�̉��������ށA���̐�֍s���ƔM�X�̃g�}�g�ƃI�j�I���̃s�U�����������������Ă���B�������̃g�}�g���̂������̃s�U��H�ׂȂ��疔����B�z�e���ɖ߂�`�F�b�N�A�E�g���ς܂��Ă��悢��j�[�X��`�ցB�������قǗǂ�����n�����R�[�g�_�W���[���̊C�ݐ��𑖂肢�悢���`���߂��Ȃ�B�����I�T���o�ł���B���{���t�����X���肽�Ԃ^���ɂ��ĕԂ��Ƃ������ꂾ���͓������܂莖�炵���A
 �s����ȃK�\�����X�^���h�ʼn��Ƃ��Z���t�Ōy���^���ɂ����B��`���̃����^�J�[��Ђւ��̎��Ԃł���ߑO�P�P���W���X�g�ɎԂ��ɕԋp����B�����Ŏv�������A���̎��A���{�ł͈��S�ŕ��a�Ŏ��ɋN���̂Ȃ����X���J��Ԃ��Ă���B����Γw�͂Ɍ��������������A���h�͒��炸�����������̐��_�ł���B��������̓앧�Œ��N�̏����Ȗ]�݂��������Ƃ����[�����́A�{���ɋv���Ԃ�ɖ��키���������o�������B���̊Ԃɂ������ł������قǂ̔N��ɂȂ�A�`���S�̃J�P���Ȃǔ��o���Ȃ��Ȃ����ƒ��߂Ă����B����ł��l�Ԃ͊�ɂȂ��Ă��A�����đ����̊댯��X�N��w�����Ăł��A���ݏo�����S�O����S���������ׂ̒���͕K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����I�ƂӂƎv���B�p���s���̌ߌ�ւ̒��A�䂪�g�ɉ�����悤�Ɂg���x�͉�����炩�������ȁH�h�ƐS�̒��ł̂ЂƂ育�ƁB�������Y��Ă������̋C���I����͎��ɂƂ��Ă��̗��̍ő�̎��n�������̂�������Ȃ��B
�s����ȃK�\�����X�^���h�ʼn��Ƃ��Z���t�Ōy���^���ɂ����B��`���̃����^�J�[��Ђւ��̎��Ԃł���ߑO�P�P���W���X�g�ɎԂ��ɕԋp����B�����Ŏv�������A���̎��A���{�ł͈��S�ŕ��a�Ŏ��ɋN���̂Ȃ����X���J��Ԃ��Ă���B����Γw�͂Ɍ��������������A���h�͒��炸�����������̐��_�ł���B��������̓앧�Œ��N�̏����Ȗ]�݂��������Ƃ����[�����́A�{���ɋv���Ԃ�ɖ��키���������o�������B���̊Ԃɂ������ł������قǂ̔N��ɂȂ�A�`���S�̃J�P���Ȃǔ��o���Ȃ��Ȃ����ƒ��߂Ă����B����ł��l�Ԃ͊�ɂȂ��Ă��A�����đ����̊댯��X�N��w�����Ăł��A���ݏo�����S�O����S���������ׂ̒���͕K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����I�ƂӂƎv���B�p���s���̌ߌ�ւ̒��A�䂪�g�ɉ�����悤�Ɂg���x�͉�����炩�������ȁH�h�ƐS�̒��ł̂ЂƂ育�ƁB�������Y��Ă������̋C���I����͎��ɂƂ��Ă��̗��̍ő�̎��n�������̂�������Ȃ��B
2015.03.18 (��) �앧�h���C�u�I�s�̎O����
 ���ꂪ�{���̃V���f�����X�g�[���[�Ȃǂƌ����Ĉ��Z���Z�[�V�����������N�������B����܂ł̑�X�^�[�ł���}�������E�������[�ɏے������A�����ăZ�N�V�[�Ȕ������Ƃ͑ΏƓI�ȁA�N�[���r���[�e�B�[�ƌĂꂽ�C�i�ƗD�낳���Y���O���[�X�E�P���[�B�����e�J�����Ƃ������E�ł��L���ȍ����n�������i�R�ƃN�[���r���[�e�B�[�̌����ȃR���{�̑�����ʂ͑f���炵���A���ꂩ�牢�Ă͂��Ƃ��A���E�e�n���瑽���̊ό��q���W�߂邱�Ƃɂ��Ȃ����ƕ����B
���ꂪ�{���̃V���f�����X�g�[���[�Ȃǂƌ����Ĉ��Z���Z�[�V�����������N�������B����܂ł̑�X�^�[�ł���}�������E�������[�ɏے������A�����ăZ�N�V�[�Ȕ������Ƃ͑ΏƓI�ȁA�N�[���r���[�e�B�[�ƌĂꂽ�C�i�ƗD�낳���Y���O���[�X�E�P���[�B�����e�J�����Ƃ������E�ł��L���ȍ����n�������i�R�ƃN�[���r���[�e�B�[�̌����ȃR���{�̑�����ʂ͑f���炵���A���ꂩ�牢�Ă͂��Ƃ��A���E�e�n���瑽���̊ό��q���W�߂邱�Ƃɂ��Ȃ����ƕ����B �R�[�g�_�W���[���𐼂��瓌�փh���C�u���鍡���́A����̗��ł͈�Ԓ������̂�ł���B�C�����̂����C�ӂ𑖂肽���̂����A���Ԃ̊W�ł��������炭�͍������H�𑖂�B�悤�₭��ʓ��ɏo��ƁA�\��ʂ�n���C���E�Ɍ���u�̏�ŏ����a�����B����ł��ӊO�Ƒ������i�R�̒����ɓ������B�����͂��̃��i�R�ɔ��܂邩�A����Ƃ��T���E�W�����E�J�b�v�E�t�F���Ƃ������̕ʑ��n�ɂ��邩�A�����֍s���ɂ����S�̃j�[�X�ɂ��邩�ŎU�X�������������A�ŏI�I�ɒn�̗��������j�[�X�ɂȂ����B�P�O�N�O�ɂ͊X���ɓd�Ԃ𑖂点��ׂ̍H���ŏa���Ă������A���ǂ�ȕ��ɕς�����̂����m���߂������̗v�]�������Ă̌��肾�����B���̃��i�R�̋��s�X�ɓ���ƁA�X�̌����̎��鏊����i�ȃp�X�e���J���[�ɓh���Ă��ĂƂĂ��₢���C���ɂȂ�B���b�p�������ɏh�����Ȃ��������Ƃ������������B
�R�[�g�_�W���[���𐼂��瓌�փh���C�u���鍡���́A����̗��ł͈�Ԓ������̂�ł���B�C�����̂����C�ӂ𑖂肽���̂����A���Ԃ̊W�ł��������炭�͍������H�𑖂�B�悤�₭��ʓ��ɏo��ƁA�\��ʂ�n���C���E�Ɍ���u�̏�ŏ����a�����B����ł��ӊO�Ƒ������i�R�̒����ɓ������B�����͂��̃��i�R�ɔ��܂邩�A����Ƃ��T���E�W�����E�J�b�v�E�t�F���Ƃ������̕ʑ��n�ɂ��邩�A�����֍s���ɂ����S�̃j�[�X�ɂ��邩�ŎU�X�������������A�ŏI�I�ɒn�̗��������j�[�X�ɂȂ����B�P�O�N�O�ɂ͊X���ɓd�Ԃ𑖂点��ׂ̍H���ŏa���Ă������A���ǂ�ȕ��ɕς�����̂����m���߂������̗v�]�������Ă̌��肾�����B���̃��i�R�̋��s�X�ɓ���ƁA�X�̌����̎��鏊����i�ȃp�X�e���J���[�ɓh���Ă��ĂƂĂ��₢���C���ɂȂ�B���b�p�������ɏh�����Ȃ��������Ƃ������������B ���i�R�ōł������ȃz�e���E�h�E�p����G���~�^�[�W���A�J�W�m�E�h�E�����e�J���������W�܂�A�����e�J�����n��̍�̓r���̒n�����ԏ�ɎԂ����Ēʂ�ɏo��B���x�͑O���Z���K�v�ȗ������̊m�F�������B���̌��������ɓn���ă��i�R�̘p�������낷�ƁA������݂̕��i�ɂȂ��Ă���x�������̏��L����傫�ȃN���[�U�[�����z���~�܂��Ă���B�D�̐��E�͎Ԃƈ���đS�Ă̗D���̑傫���Ō��܂�Ƃ����Ă���B�j���[���[�N�̃A�b�p�[�C�[�X�g�ɏZ��ł���������B���A���Ɨp�@�ŃR�[�g�_�W���[����`�ɒ����A�e�P�O�����v���̓��ɂ̓O���X�Ў�ɂ��̑D�ŊC����̂e�P�ϐ�I�Ȃ�ď���ȑz�������Ă݂�B�ȂƖ������͗�ɂ���Ĕ������œX��`�������Ƃ̃��N�G�X�g�B���Ƒ��q�͏��X��������A�L���ȃJ�t�F�E�h�E�p���ł����ƌy�����H���Ƃ邱�Ƃɂ���B�����͈ꗬ�̃t�@�b�V������g�ɂ܂Ƃ����l�X�ƍŐ�[�̍����ԒB���}�����J�[�E�E�H�b�`���O����̂ɂ͂����Ă����̃J�t�F���B��Ԃ̓����ȂƂȂ铹�H�ۂ̐Ȃɍ���B�ߑO�̌��ł���w�l��Ԃ������P���Č�����B
���i�R�ōł������ȃz�e���E�h�E�p����G���~�^�[�W���A�J�W�m�E�h�E�����e�J���������W�܂�A�����e�J�����n��̍�̓r���̒n�����ԏ�ɎԂ����Ēʂ�ɏo��B���x�͑O���Z���K�v�ȗ������̊m�F�������B���̌��������ɓn���ă��i�R�̘p�������낷�ƁA������݂̕��i�ɂȂ��Ă���x�������̏��L����傫�ȃN���[�U�[�����z���~�܂��Ă���B�D�̐��E�͎Ԃƈ���đS�Ă̗D���̑傫���Ō��܂�Ƃ����Ă���B�j���[���[�N�̃A�b�p�[�C�[�X�g�ɏZ��ł���������B���A���Ɨp�@�ŃR�[�g�_�W���[����`�ɒ����A�e�P�O�����v���̓��ɂ̓O���X�Ў�ɂ��̑D�ŊC����̂e�P�ϐ�I�Ȃ�ď���ȑz�������Ă݂�B�ȂƖ������͗�ɂ���Ĕ������œX��`�������Ƃ̃��N�G�X�g�B���Ƒ��q�͏��X��������A�L���ȃJ�t�F�E�h�E�p���ł����ƌy�����H���Ƃ邱�Ƃɂ���B�����͈ꗬ�̃t�@�b�V������g�ɂ܂Ƃ����l�X�ƍŐ�[�̍����ԒB���}�����J�[�E�E�H�b�`���O����̂ɂ͂����Ă����̃J�t�F���B��Ԃ̓����ȂƂȂ铹�H�ۂ̐Ȃɍ���B�ߑO�̌��ł���w�l��Ԃ������P���Č�����B �����Ŏ��̓J�t�F�I���ɃT�[�����ƃ`�[�Y�A���q�̓N���u�n�E�X�̃T���h�C�b�`�����ꂼ��������B�T���h�C�b�`���Q�O���[���Ƃ��Ȃ荂���B�b���҂��Ď��̏��ɗ����T�[�����E�`�[�Y�T���h�����ăr�b�N���B�������̂S�ꂵ���Ȃ��A�������ƂĂ��������B�g������Ɓ[�I�J�[���g���z�e���̃f�b�J�C���̃I�����c�����K����I�h�ƈ�l�ԂԂ����Ȃ���A����܂�ł݂�Ɖ��߂��Ă��āA���g�̋�ƃp�������Ɉ��k���ꂽ�H�������܂�Ȃ��|���I�����Ȉ��}���V�O�O�~�̒������ȃT���h�C�b�`�𑧎q���H�ׂ��B�ނɂƂ��Ă����炭�Y����Ȃ��v���o�̃T���h�C�b�`�ɂȂ邾�낤�B�����Ėڂ̑O���u�����h�̔��𑩂˂��J�b�R�C�C�������A��F�ɓh��ꂽ�ŐV�̃t�F���[���S�T�W�C�^���A�ł��������������Ȃ��瑖���Ă����B���ɗ����͍̂����̏�������锒���}�Z���[�e�B�[�f�s�A���̂��C�^���A�ԂƏ����肾���A�܂�ʼnf��̃����V�[�����ςĂ���悤�������B�ǂ���炱�̃J�t�F�A���̂������̎Ԃ����̌����т炩���̔q�ϗ����܂߂��l�i�̂悤���B
�����Ŏ��̓J�t�F�I���ɃT�[�����ƃ`�[�Y�A���q�̓N���u�n�E�X�̃T���h�C�b�`�����ꂼ��������B�T���h�C�b�`���Q�O���[���Ƃ��Ȃ荂���B�b���҂��Ď��̏��ɗ����T�[�����E�`�[�Y�T���h�����ăr�b�N���B�������̂S�ꂵ���Ȃ��A�������ƂĂ��������B�g������Ɓ[�I�J�[���g���z�e���̃f�b�J�C���̃I�����c�����K����I�h�ƈ�l�ԂԂ����Ȃ���A����܂�ł݂�Ɖ��߂��Ă��āA���g�̋�ƃp�������Ɉ��k���ꂽ�H�������܂�Ȃ��|���I�����Ȉ��}���V�O�O�~�̒������ȃT���h�C�b�`�𑧎q���H�ׂ��B�ނɂƂ��Ă����炭�Y����Ȃ��v���o�̃T���h�C�b�`�ɂȂ邾�낤�B�����Ėڂ̑O���u�����h�̔��𑩂˂��J�b�R�C�C�������A��F�ɓh��ꂽ�ŐV�̃t�F���[���S�T�W�C�^���A�ł��������������Ȃ��瑖���Ă����B���ɗ����͍̂����̏�������锒���}�Z���[�e�B�[�f�s�A���̂��C�^���A�ԂƏ����肾���A�܂�ʼnf��̃����V�[�����ςĂ���悤�������B�ǂ���炱�̃J�t�F�A���̂������̎Ԃ����̌����т炩���̔q�ϗ����܂߂��l�i�̂悤���B �����Ă�������e�P�̃��i�R�E�O�����v���Ő��E��L���ɂȂ����w�A�s���J�[�u�ɍs���Ă݂�B���[�Y�w�A�s���ƌĂ�A���[�X���������ς����̃|�C���g�Ɍ��z�e���A�t�F�A�����g�E�����e�J�����͂��̎����͏�ɗ\��ł����ς����ƕ����B���ꂩ�玄�B�̓j�[�X�Ɍ������̂����A�r���A�������ɑ�l�T�l�ő傫�ȃg�����N���S���ς��̃V�g���G���͒x���炵���A�W���`�[�̎ԂɃN���N�V�����܂Ŗ炳��Đ�����B��͂艽���̍��ɂ��g����ȓz�͕K��������̂����A
�����Ă�������e�P�̃��i�R�E�O�����v���Ő��E��L���ɂȂ����w�A�s���J�[�u�ɍs���Ă݂�B���[�Y�w�A�s���ƌĂ�A���[�X���������ς����̃|�C���g�Ɍ��z�e���A�t�F�A�����g�E�����e�J�����͂��̎����͏�ɗ\��ł����ς����ƕ����B���ꂩ�玄�B�̓j�[�X�Ɍ������̂����A�r���A�������ɑ�l�T�l�ő傫�ȃg�����N���S���ς��̃V�g���G���͒x���炵���A�W���`�[�̎ԂɃN���N�V�����܂Ŗ炳��Đ�����B��͂艽���̍��ɂ��g����ȓz�͕K��������̂����A �ǎ����鑽���̓��{�l�͂����܂ł͂��Ȃ��B�����ċ��R�ʂ肩�������A������h�̑����Ƃ��ėL���ȃG�Y�Ɋ�����B�����̃z�e���̃V���g�[�E�G�U�ł͂������ƒn���C�����n���Ȃ���H�����ł���B�O�ɗ������ɍs���Ȃ�������ԍ������ɂ���G�Y�뉀�܂œo���Ă݂�B�T�{�e�����炯�̂܂�Ȃ���œ������͈�l�U���[�����B�����A�Â���Ղ������G�Y�̓V�ӂł��鍟������̒��߂́A�����n���C�̐��������ʂ�`���A�n���̊ۂ�����������ɗY��Ȍi�F�������B
�ǎ����鑽���̓��{�l�͂����܂ł͂��Ȃ��B�����ċ��R�ʂ肩�������A������h�̑����Ƃ��ėL���ȃG�Y�Ɋ�����B�����̃z�e���̃V���g�[�E�G�U�ł͂������ƒn���C�����n���Ȃ���H�����ł���B�O�ɗ������ɍs���Ȃ�������ԍ������ɂ���G�Y�뉀�܂œo���Ă݂�B�T�{�e�����炯�̂܂�Ȃ���œ������͈�l�U���[�����B�����A�Â���Ղ������G�Y�̓V�ӂł��鍟������̒��߂́A�����n���C�̐��������ʂ�`���A�n���̊ۂ�����������ɗY��Ȍi�F�������B ���ꂩ����C���L����`���A���B���t�����V���E�V�������[����A�h�̌��ɋ��������T���E�W�����E�J�b�v�E�t�F���Ȃǂɗ������Ȃ���j�[�X�ɓ������B�j�[�X�̂قڒ��S�ɂ���{�X�R���Ƃ����C�^���A�n�̃z�e���������̏h�B���r�[����S�Ĕ�����ɂȂ��Ă���B�����̂ǐ^�ɃJ�[�e���������Ȃ��S�ʃK���X����̕��C������A�J���I�ł��������������A���̗l�ȐT�ݐ[���H���{�l�͏��X�ʐH�炤�B���ꂩ��ό��q��n���̐l�œ��키�[���̃j�[�X�̒��ɏo�Ă݂��B�y���݂ɂ��Ă����d�Ԃ͎��̑z�������͂邩�ɑ傫���A�Q���Ґ��Ŋό��Ƃ��������s���̒ʋ�ʊw�̑��Ƃ�������������B���̓T���t�����V�X�R�̃P�[�u���J�[�̗l�ȕ���S�ɕ`���Ă����̂����A�C���[�W�������̂Ƃ͂��炭����Ă����B�Ƃ肠���������������ŗǂ������ˁI�ƃz�e���̌}���̃��X�g�����Ŋ��t�B
���ꂩ����C���L����`���A���B���t�����V���E�V�������[����A�h�̌��ɋ��������T���E�W�����E�J�b�v�E�t�F���Ȃǂɗ������Ȃ���j�[�X�ɓ������B�j�[�X�̂قڒ��S�ɂ���{�X�R���Ƃ����C�^���A�n�̃z�e���������̏h�B���r�[����S�Ĕ�����ɂȂ��Ă���B�����̂ǐ^�ɃJ�[�e���������Ȃ��S�ʃK���X����̕��C������A�J���I�ł��������������A���̗l�ȐT�ݐ[���H���{�l�͏��X�ʐH�炤�B���ꂩ��ό��q��n���̐l�œ��키�[���̃j�[�X�̒��ɏo�Ă݂��B�y���݂ɂ��Ă����d�Ԃ͎��̑z�������͂邩�ɑ傫���A�Q���Ґ��Ŋό��Ƃ��������s���̒ʋ�ʊw�̑��Ƃ�������������B���̓T���t�����V�X�R�̃P�[�u���J�[�̗l�ȕ���S�ɕ`���Ă����̂����A�C���[�W�������̂Ƃ͂��炭����Ă����B�Ƃ肠���������������ŗǂ������ˁI�ƃz�e���̌}���̃��X�g�����Ŋ��t�B
2015.03.04 (��) �앧�h���C�u�I�s�̓����
 �����̂��ƂȂ���O���ɂ���Ǝ����łȂ��Ȃ��悭����Ȃ��B�����Ȕg�̉��Ɉ�������悤�ɁA�܂��^���Âȑ����̕�������ʂ��`���B����Ɛ��|�Ԃ��Q�x�����Ē���|�����Ă���B��x�ڂ̓S�~������Ȑ����Ő�������A�Q�x�ڂ͐�������ꂽ�����E���Ă䂭�B��������Ă��鎄�������ɂł���܂����A���������E�̃��]�[�g�n�ł���B�앧�̓���ڂ̓J���k�̃J�[���g���z�e���̃r���b�t�F����n�܂�B�f��g�D�_�����h�ł悭�o�ė����L���ɑ嗝�̒��������Ă��郌�X�g�����ł���B���̃z�e���̎��鏊�ɎB�e�����̃O���[�X�E�P���[�ƃP�C���[�E�O�����g�̎ʐ^�������Ă���B
�����̂��ƂȂ���O���ɂ���Ǝ����łȂ��Ȃ��悭����Ȃ��B�����Ȕg�̉��Ɉ�������悤�ɁA�܂��^���Âȑ����̕�������ʂ��`���B����Ɛ��|�Ԃ��Q�x�����Ē���|�����Ă���B��x�ڂ̓S�~������Ȑ����Ő�������A�Q�x�ڂ͐�������ꂽ�����E���Ă䂭�B��������Ă��鎄�������ɂł���܂����A���������E�̃��]�[�g�n�ł���B�앧�̓���ڂ̓J���k�̃J�[���g���z�e���̃r���b�t�F����n�܂�B�f��g�D�_�����h�ł悭�o�ė����L���ɑ嗝�̒��������Ă��郌�X�g�����ł���B���̃z�e���̎��鏊�ɎB�e�����̃O���[�X�E�P���[�ƃP�C���[�E�O�����g�̎ʐ^�������Ă���B �������̉�Ђ̃R���x���V�������������炵�����Ȃ荬��ł���B���̃h�T�N�T�Ŏ������̓X�B�[�g���[���ɓ��ꂽ�̂�������Ȃ��Ɛ��@����B���{����y���݂ɂ��Ă��������̒��H�͂�͂�V�N�Ŕ��������B�G�X�v���b�\�R�[�q�[�̃~���N�̖A�ɂ͂��̃z�e���̃}�[�N��������ł����B�H�����㔼�ɂȂ��āA�~�������̂ɖ����������z�̂����E�G�C�g���X�Ɋ��߂���܂܂ɃI�����c�𗊂B���ꂪ��l�̌C���炢�f�J�C�I����H�ׂ�ƃo�^�[�̉��Ƃ������Ȃ��������������ς��ɍL����̂����A���������̓p���p�����B���X�����Ȃ��ɃJ���k�̒��֏o��B
�������̉�Ђ̃R���x���V�������������炵�����Ȃ荬��ł���B���̃h�T�N�T�Ŏ������̓X�B�[�g���[���ɓ��ꂽ�̂�������Ȃ��Ɛ��@����B���{����y���݂ɂ��Ă��������̒��H�͂�͂�V�N�Ŕ��������B�G�X�v���b�\�R�[�q�[�̃~���N�̖A�ɂ͂��̃z�e���̃}�[�N��������ł����B�H�����㔼�ɂȂ��āA�~�������̂ɖ����������z�̂����E�G�C�g���X�Ɋ��߂���܂܂ɃI�����c�𗊂B���ꂪ��l�̌C���炢�f�J�C�I����H�ׂ�ƃo�^�[�̉��Ƃ������Ȃ��������������ς��ɍL����̂����A���������̓p���p�����B���X�����Ȃ��ɃJ���k�̒��֏o��B���N�T���ɊJ�����J���k�f��ՂŗL���ȏ����������āA�z�e���̑O�̃N�����[�b�g��ʂ���E��ɏ��������ƁA�J�オ��̌����̎��鏊�Ƀp�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A���A�X�^�[�E�H�[�Y�A�`���[���[�Y�E�G���W�F���Ȃǂ̉f����e�[�}�ɂ������������ς�����B���ꂼ��Ɏ剉�����X�^�[�B�̊Ŕ̊�̕��������蔲����Ă���̂ŁA������������ϊ���o���Ă̎B�e��ƂȂ�B��������������̂悤�ɉ����ŃJ�������������Ă���B���ꂩ�班���s���ƃp���E�f�E�t�F�X�e�C�o���E�G�E�f�E�R���O���ɂ͐��E�̃X�^�[�B�������A��̗L���ȃ��b�h�J�[�y�b�g�̊K�i������B�����ނ�ɂ����ɗ����A�T�N�Z�X�X�g�[���[�̎�l����낵���j�b�R�����Ď�������Ă݂�B����ƂЂ��߂������J�����̃t���b�V���Ɣ���̗��B���̕Ў��̊y������z�͂����̓�������̖ϑz���낤���E�E�B�ӂƉ�ɋA��A�ڂ̑O���o�Γr���̐l�X����Ђ�R���x���V�������Ɍ������đ����ɕ����Ă���B���ꂪ�����ł���B���ɂ͂������ɓy�Y���Ɖf��ق����������B
��딯���Ђ����悤�ɃJ���k����ɂ��āA�����͐�����h�̑����̒��ł��ł��������ƌ�����T���|�[���E�h�E���@���X�Ɍ������B����������ĐM���̂Ȃ����[�^���[�����B�t�����X�̍x�O�ɂ͂قƂ�ǐM���͂Ȃ��B
 ���̓Ɠ��ȃN�����Ǝ��v���̌����_�ɂ��Ȃ����B���ɒ�������Ǝv���Ă������̓K���\�͂͂܂����Ƃ��c���Ă����炵���B�ړI�n�ɋ߂��Ȃ�A�ׂ��čd���Ώ�̓c�ɓ����s���B�̂���t�����X�Ԃ̏��S�n���ǂ��̂́A���̃S�c�S�c�Ƃ����̓��H�����y�ɑ��j����ׂ��B�����Ă��悢�揬�����u�ɔ����ۂ��Ƃ���d�ɂ��d�Ȃ������قȕ��i�̑��A�T���|�[�����E���Ɍ����Ă���B�����͈ȑO�ɂ������̂����A�Ƒ��ɂ����̑��̑f���炵���������悤�ƍĂіK�˂Ă݂��B
���̓Ɠ��ȃN�����Ǝ��v���̌����_�ɂ��Ȃ����B���ɒ�������Ǝv���Ă������̓K���\�͂͂܂����Ƃ��c���Ă����炵���B�ړI�n�ɋ߂��Ȃ�A�ׂ��čd���Ώ�̓c�ɓ����s���B�̂���t�����X�Ԃ̏��S�n���ǂ��̂́A���̃S�c�S�c�Ƃ����̓��H�����y�ɑ��j����ׂ��B�����Ă��悢�揬�����u�ɔ����ۂ��Ƃ���d�ɂ��d�Ȃ������قȕ��i�̑��A�T���|�[�����E���Ɍ����Ă���B�����͈ȑO�ɂ������̂����A�Ƒ��ɂ����̑��̑f���炵���������悤�ƍĂіK�˂Ă݂��B �܂�ł����̍��ɗ����悤�ȕs�v�c�Ȋ��o�𖡂키�����o����B���̓�����ɂ͗�ɂ���āi�O����S���������i�j�j�������y�^���O�Ƃ����S�̋��𓊂��ėV�ԃQ�[���ɋ����Ă���B���ɓ���Ƌ��R�A�C�u�E�����^���ƃV���[�j���E�V�j���������������������Ƃ�������̏�����B��������ł������邱�̓��͑��̃V���{���ł���B�Ό��⍁���A�u���ɊG��₨�َq�̐��X���X�A���炵�����X����������Ď���Y��Ă��܂��B�����ł͎��Ԃ����R�Ɏg����l���s�̋��݂ŁA�����ɃT���|�[�����̊y�����𖡂�����B
�܂�ł����̍��ɗ����悤�ȕs�v�c�Ȋ��o�𖡂키�����o����B���̓�����ɂ͗�ɂ���āi�O����S���������i�j�j�������y�^���O�Ƃ����S�̋��𓊂��ėV�ԃQ�[���ɋ����Ă���B���ɓ���Ƌ��R�A�C�u�E�����^���ƃV���[�j���E�V�j���������������������Ƃ�������̏�����B��������ł������邱�̓��͑��̃V���{���ł���B�Ό��⍁���A�u���ɊG��₨�َq�̐��X���X�A���炵�����X����������Ď���Y��Ă��܂��B�����ł͎��Ԃ����R�Ɏg����l���s�̋��݂ŁA�����ɃT���|�[�����̊y�����𖡂�����B�����Ē��ԏꂩ��Ԃ��o�����Ƃ����̂����A�������ł��������悤�Ƃ��Ă��ǂ��ɂ�����鏊�������B���R�o�[�͍~�肽�܂܂ŎԂ͗��������ƂȂ�B�����t�����X�ł͒��ԏ���̉������Ő�ɐ��Z���ς܂��A�Ō�ɂ̓J�[�h�����邾���̑O�������Z�ƂȂ�B
 �����ł܂���������B���ꂩ�獡���̏h�ł��郋�E�}�E�J���f�B�[�������郀�[�W������ڎw���B�����̓O�����ƌ|�p�̑��Ƃ������A�T���E���[������f�C�I�[���A�|�\�E�ł̓J�g���[�k�E�h�k�[�u��G�f�B�b�g�E�s�A�t�A�����Ă��̃s�J�\�����Z���Ƃ��Ă��m���Ă���B�����̃J���k��������ɂق�̂P�O�L���قǂ̏��ɂ���Â��ȑ������A���̍���Ɉʒu���钭�]�ƕ֗����䂦�ɒ����l����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���͂S�O���������ΑS�̂����ĉ���قǏ������̂����A�����Ƀi���g���\���قǃ��X�g����������B
�����ł܂���������B���ꂩ�獡���̏h�ł��郋�E�}�E�J���f�B�[�������郀�[�W������ڎw���B�����̓O�����ƌ|�p�̑��Ƃ������A�T���E���[������f�C�I�[���A�|�\�E�ł̓J�g���[�k�E�h�k�[�u��G�f�B�b�g�E�s�A�t�A�����Ă��̃s�J�\�����Z���Ƃ��Ă��m���Ă���B�����̃J���k��������ɂق�̂P�O�L���قǂ̏��ɂ���Â��ȑ������A���̍���Ɉʒu���钭�]�ƕ֗����䂦�ɒ����l����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B���͂S�O���������ΑS�̂����ĉ���قǏ������̂����A�����Ƀi���g���\���قǃ��X�g����������B ����̃f�B�i�[�͎����������܂�z�e���̃��X�g�����A�����E�G�E�V���g�[�Ɍ��肵���B
����̃f�B�i�[�͎����������܂�z�e���̃��X�g�����A�����E�G�E�V���g�[�Ɍ��肵���B�����̃J�[���g���z�e���̃r���b�t�F�������Ă��܂��Ė����ɂ������Ȃ��B�P�X���S�T���Ƃ����x�߂̗[�H��\�A���̑O�ɂ₽��ƍL���~�n�����z�e���̃X�p���Y��ȃv�[���A�[���̑������肷��B�H���̓R�[�X�����𗊂݁A���C���͔��ƌ㔼�̓��[�B�O�̐l�Q�̗₽���X�[�v����n�܂�A
 �O���[���F�̃V���[�x�b�h�̏�ɂق�̂�Â������S������ɂ��ꂽ�@�ׂȃT���_�A���͂������̃\�[�X�ɂق�̏������������������A���C���̓������͔Z���ȃu���E���\�[�X�������������B�Ō�̃`�[�Y�������y�����m�ɂ��Ă����悤�ɗ����A�i���g�I�f�U�[�g���O��ނ����Ă��܂��A�����H���C���ɂȂ�B���ɃO�������̃��[�W�������\���郌�X�g�����łǂ������Ă݂Ă��{���ɔ������������B�~�����������������̂������Ă���ō��������B���H�̑傫�ȃI�����c�͖�܂�
�O���[���F�̃V���[�x�b�h�̏�ɂق�̂�Â������S������ɂ��ꂽ�@�ׂȃT���_�A���͂������̃\�[�X�ɂق�̏������������������A���C���̓������͔Z���ȃu���E���\�[�X�������������B�Ō�̃`�[�Y�������y�����m�ɂ��Ă����悤�ɗ����A�i���g�I�f�U�[�g���O��ނ����Ă��܂��A�����H���C���ɂȂ�B���ɃO�������̃��[�W�������\���郌�X�g�����łǂ������Ă݂Ă��{���ɔ������������B�~�����������������̂������Ă���ō��������B���H�̑傫�ȃI�����c�͖�܂� �����������B
�����������B���̗��̂R���ځi���m�ɂ͂S���ڂ����j�ɂ����鑁���ɁA�������{�ł���Ă���l�Ɉ�l�Ń��[�W���������U���B���̋G�߁A������ł͒���������o���̂͂W�������O�ɂȂ�B���̔����ɐ������ꂽ�q�B�̎v�������̂܂ܖ��郌�X�g�������������сA�����ɂ͉��������ȗ����̎c�荁�Ɖ��̌�ɕK������ė���̂������Â��ɕY���Ă����B�������Ԃ߂�l�Ƀ��[�W���������I�����W�F�ɐ��ߏグ�钩�Ă��́A��߂��S�ɋv���Ԃ�̊������Ăъo�܂��Ă��ꂽ�B
2015.02.28 (�y) �앧�h���C�u�I�s�̈����
�v���U��̂ЂƂ育�ƁB��N�̂U�����{�ɂP�T�N�̊ԁA�����ʂ�Q�H�����ɂ��������̃s�m��S�����Ă��牽���������ς��Ă��܂����B���ł����̉��������ʉe�₱�̎�Ɏc�鏬���ȑ̂̊��G���h��A�ˑR�܂��鎖�������ʼn��Ƃ���Ȃ������ł���B���ꂩ����ɐS�@��]�̂���ŁA�Ƒ��p�̉������S�������Z�f�X�̂d�N���X�E�J�u���I���ƌĂ��V�����Ԃɑւ��A���Ƃ��C����ς��悤�Ǝ��݂��̂���������܂܂Ȃ炸�A�Ƒ�������������̂̕K�R�I�ȕʂ�Ƃ��������̝|�ɉ��������Ȃ��v���ł����B�N��������������A�w���ł��钷�j�͂������̎��A�Љ�l�ł��钷���Ǝ������x�ɂ�����ĉƑ����S���Q���̗��ɏo�Ă݂悤�Ƃ������ɂȂ����B���肵�����͎������낤�ɂ��̐�����Ɏ����̂������t�����X�ł���̂����Ƃ��䂪�Ƒ��炵���̂ł��邪�B���ɂƂ��ĂP�O�N�Ԃ�̓앧�ł���A�Q�N�O�̖k�C�^���A�ȗ��̃��[���b�p�B���x�͒��N�̖�����������̃R�[�g�_�W���[�����A���Ɏ����̉^�]�ŏ���h���C�u���s�����Ă݂悤�Ƃ������ɂȂ����B����ɂ͎����������N�ɂȂ��āA�������Ȃ��������ŏI��邩������Ȃ��Ƃ����₵�����Ƃ��ؔ������v�����A���܂ł��ς���Ȃ��ł��������㉟�������̂������B�ǂ����Ă�����Ă����������ƁA��ɓ���Ă݂����������̂����̔N�ɂȂ�Ɣ����͂����肵�ė���B����͎������g�̑̂̐����i���̍����炩���삪�����Ȃ蓮�̎��͂������A�s���Ȃ邪�䂦�Ɏ��X�Ɉ��S��S������悤�ɂȂ�j��������悤�ɂȂ����҂ɂ�������Ȃ����̂ł���B�O���̎��̎ԍD���l���Ɉ�x�͏���Ă݂��������I�[�v���J�[��������A�����܂ł����ŏI��点�Ȃ����ɂ����֗��Ĉꐶ�����ł���B
���āA���s�����̏o���ԍۂɂȂ��āA�����ƒ��j�̃p�X�|�[�g���R���Ŋ������}����Ƃ������ɋC���t���A��������R�����ȓ��Ɋ�������郂�m�̓t�����X�ł͗��s��������Ȃ������ƌ����O�Ⴊ����������m��B���Ăǂ����悤�I�p���������A�����������ɒ����j�[�X�ł͕������h���ꂽ�Ȃǂƌ������ȃj���[�X�B
2014.04.20 (��) ���a�̓��X���v���o��
�����͂�����x�J�����i�݁A�����͂��悢�悱�ꂩ��Ƃ����a�J�̉w�O���[�^���[�ł̎��������B�^�N�V�[�ɏ�荞��Łg�����̌����_�܂ł��˂������܂��h�ƌ�������^�]�肳��̕Ԏ����Ȃ��B���܂�ɋ߂��̂œ{�����̂��ȁH�Ǝv���Ă���ƁA�b�����āg�����z�̌����_�ł�낵���̂ł��傤���H�h�Ƃ̕Ԏ��ɂ������I���̒����͍���ʗp���Ȃ��Ȃ����̂��B���A�����Ă��邯�lj����̔��q�ŏo�Ă���̂̌��t�B���₻�̖����c���̂͐�c���Y�́g��������h���炢���낤�B���b�h�V���[�Y���A�}���h���A�������Ȕy���閈�W�����t�H�b�N�X�o�[���E�����͂Ȃ��B����͈ڂ�A�c�����͈̂�t���݉��̕l�̉ƂƏē��X�̏\�X�⏖�X�������肾�낤���B�������ɓ��X����N���̒��ԓ����Ɋ�����B ���������Ύq���̍��A���̐_�c���n���̎��B�͍]�ː�ƌĂ�ł����B�ܘ_�������̏���̐�𗬂�A�����Ɛ�t���Ă���]�ː���[���m���Ă̂�����̍]�ː�A������̍]�ː�ƌ������Ƃ��낾�����B���ꂪ�����q�b�g����������P�́g�_�c��h�Œn���̒N�������������悤�ɂȂ����B�̗w�Ȃ̃p���[�Ƃł������̂��낤���A���̐̂Ȃ���̃��[�J���ȌĂі���B��c���̂́A�L�y�����̔ѓc���ƌ썑���̊Ԃ̉w�ł���]�ː싴�ł���B
���������Ύq���̍��A���̐_�c���n���̎��B�͍]�ː�ƌĂ�ł����B�ܘ_�������̏���̐�𗬂�A�����Ɛ�t���Ă���]�ː���[���m���Ă̂�����̍]�ː�A������̍]�ː�ƌ������Ƃ��낾�����B���ꂪ�����q�b�g����������P�́g�_�c��h�Œn���̒N�������������悤�ɂȂ����B�̗w�Ȃ̃p���[�Ƃł������̂��낤���A���̐̂Ȃ���̃��[�J���ȌĂі���B��c���̂́A�L�y�����̔ѓc���ƌ썑���̊Ԃ̉w�ł���]�ː싴�ł���B����e���Ăі��⒬���͉��������A�����������ė������a�����̊Ԃɂ���������X�������̒��ɂ���B����͂���Ӗ��A�����̐l�����m�肵�����Ƃ����Ȃ���]���痈��̂�������Ȃ��B�����ċߔN�A���̎����w�i�ɂ����f��⏬���̃q�b�g�ȗ��A���a���₽��ƃN���[�Y�A�b�v�����悤�ɂȂ����B��T�s�����L�y���w�̃K�[�h���ɂ��A���̎���̃|�X�^�[���O�ǂɓ\��t���Ă�����݉��͂Ȃ��Ȃ��̔ɐ��Ԃ�ł���B
�ʂ����Ď������܂ꂽ���̏��a�͂���Ȃɗǂ������̂��H�Ɨ�ÂɐU��Ԃ�B���̎�����͕s�ւ��̏�Ȃ��������A���ɂƂ��Ă��̎���͂��Ȃ�L�������Ƃ����L��������B�����Ƀo�L���[���J�[��������A�����@���������c�����́A�s��ɂ��̎p���������r�[�v�������葧���z�����݁A���̉���S���͂ő��蔲���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B����ł����̏Z��ł���������ł͔�r�I���������ɉ����̍H�����s���A���w�Z�̒����ɂ̓g�C���͐���ɕς�����Ƃ����L��������B���Z���w����ɓ����āA�����␙����ɏZ��ł����F�l�����̉Ƃɍs���ƁA�i�V�тɍs�����Ē����Ȃ��玸��ɂ܂�Ȃ��̂����j�܂����������Ă��Ȃ��āA�Ƃɓ���Ɛ^����ɗ�̏L�����܂����߂ɕ@��˂����̂��o���Ă���B���A�����̋����ɂ��K�����ߐF�̃n�G��莆���Ԃ牺����A�����R�����i�ł��鋛�����̏�����b�N���Ɖ���Ă����B�v����Ƀn�G�������͊m���ɑ����Č��C�������B���������ăn�G�̔��ł��Ȃ��Y��ȏ��a�̉f��g�O���ڂ̗[���h�̓`���b�g�Ⴄ���I�ɂȂ�B
����͗]�k�ɂȂ邪�A�����ׂ̗̓X�ɂ͂����T�~�ʂ����ɓ���Ă��锪�S���̃I���W�������B�˂��蔫�����������ނ̖V�哪�͂��������݂ɗh��Ă����B�ǂ����ĂT�~�������̂��A�v���Ɉ�~�ł̓`���P�����A�P�O�~�ł͑傫�����ĕ��ʂ��≹���Ւf�����̂ł���B�ƂɋA��ƁA���ł��^�������鎄���g�������đ̌������̂�����{���ł���B�����Ă��ꂩ�牽�\�N���o���ċC�t�����̂����A���q�l�Ƃ����i�T�~�j������܂��l�ɁI�ƁA���̃I���W����Ȃ�̟����������̂��Ƃ��v����B
��������ΎԂ����Ƃ��������������݂����A���鏊�Ɍ��̕��������Ă����B���싅�ł����Â��Ă��܂������Ƃ���x���x�ł͂Ȃ������B���ɏ_�炩�ȌC��Ŋ����邠�̊��G�ɂ͖����ɕ��������A�����Ő��̒����I�������Ƃ��v�����B���ɂȂ��Ă��_�炩�����m��Â���ƃh�L���I�Ƃ���B����͂����Ƃ��̎���̃g���E�}�Ȃ̂��낤�B��J��䕗������ƁA��̐_�c��͊ȒP�ɔ×����Đ��̓D������̉ƁX���������B����炪�����Ƃ��ɔ�����L�����܂��������B���悻���̊�ɕ@�̌��Ƃ������m���J���Ĉȗ��̈��L�ŁA���������������̉Ƃ̎q��������A�Œ�ł���T�Ԃ͉Əo�������Ƃ��̓x�Ɏv���Ă����B���̉ẴS�~���W�Ԃ����炷�t�̖̂ҏL��焈ՂƂ���B���a�̏L���̎v���o�ł���B�����ď��a�̂��ꂳ��͖Z�����A���̗l�Ɋw�Z�̐搶�ɂ��������t����ɐl���F���ŁA�ق����炩���ŐQ�����Ă��肢���Ԃ�V�ɂ͐�Ǔ������������B�m���ɐl�͍����M���P���ŁA�K���ɂȂ낤�Ƃ������ɐ^���Ɍ��������Ă����B�����͑�������͕n�����A�֗��Ƃ͒�������Ԃ̂����鎞�ゾ�����B
�����č��͕����ɂȂ�Q�U�N�ڂ��}���Ă���B����A�X�}�t�H�����߂Ȃ���فX�ƕ����Ă䂭�l�X�߂Ă����B�����Ȃ���̕��i�ł���B�ނ�̓���ɂ͐^���ȋL����A�u�₩�ȕ��ɔ��g�F�̉Ԑ��Ⴊ�����Ă����B����ȑf�G�Ȍ��i�����グ�邱�Ƃ��Ȃ��B���͘V�l���肾�������ɂȂ�A�����͎��ɕ֗��ŕK�v�ȃ��m������A�قƂ�ǘJ�������Ȃ���ɂ��đ����Ɏ�ɓ���B�����F��������ɂȂ�Q�[���̑S�Ă��X�}�t�H�̂ق�̏����ȉ�ʂ̒��ɂ���B�C���t�H���ʼn��E���V���b�g�A�E�g�I�Q�߂����A���ς����т��ʋΓd�Ԃ̒���N�͂��邱�ƂȂ����ʏ���H��ɕς�点��B�ǂ�Ȑ���������l�[���ŃI�[�P�[�A���邳�������l�����Ȃ��Ȃ����B
���̎�����A���a�͍D���̂��H���Ȃ̂��H�����͂��ꂼ��̊����┻�f�Ɉς˂邱�Ƃɂ��悤�B�Ō�ɁA���̏��a�ɂ͐��ԑ̂Ȃ���̂��������B���ɂ���͔ς킵�����R�ւ̑��g�ɂ��Ȃ���m�������B�e����q�ցA�q���瑷�ւƉƑ����l�����ł��q����l�i��l�̓��Ȃ���̂��p�������B����Ȃ�̏펯���ێ�����̂ɐ��ԑ̂��܂���ʂ������a�B���i�ɂ�����݁A���h�Ɍւ�A���߉�Ȃ��̖ڒB��ࣁX�ƋP���Ă�������B����͂���Ŗʔ��������̂��������ł���B
2013.12.25 (��) �q���E���̔ޏ�
�N�̂����Ȃ̂��A���~�������ʼn����̍����炩�~�������̂��啪���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B����ł��������K�������đ����I�ɔ�����������ƈĂ̒莸�s����B�����O����̂��B����Ȃ�ɏn�l����̂ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂����A��肷����ƒN���ɐ���z����Ĕ��������Ă��܂������������B�ł͂ǂ�����̂��A���̔N�ɂȂ�Ƃ���Ȃ�̔����N�w�Ȃ�Ă��̂��o���Ă���B����͂�����Ԃ����߂Ă��猋�_���������ƁB�Z�����͂��̕ӂ��������Ă���̌��肩�A��ӂ悭�l���Ă݂�B�傫�Ȕ������̎��ɂ͈ꂩ�����Ԃ�u�����Ƃ�����B�����Ă��ꂪ�ǂ����Ă��K�v�A�~�����ƂȂ�Δ����ɍs���B����������Ă��܂��Ă����ꍇ�ɂ͉����Ȃ������̂��Ƃ����ς�ƒ��߂�B���̒��߂��̐S���B����ł����ʂɂ����A�������]�v�Ȃ��̂�w�������܂��ɍς̂��Ǝ����ɔ[��������B�����Ȃ̂��낤���A�ӊO�ɑ������߂���B������O�̎��������Ă���悤�����A��ɂ����O���ɒu���Ȃ��ƌ�����鎖�ɂȂ�B����Ǝ��ɂ͎������D���ȕ��͋C�̓X�A�X�p��ʂ�ɍs���ƕK����͗ǂ����m������̂��ƌ��ߍ��ވ����Ȃ�����B�́A�Z�{����������l�̊X���������̃��A�r���̂ȂȂߌ}���A���h���L�������Ă��邠����ɁgIN��OUT�h�Ƃ����n���ɓ���j�����̏����ȗm�������������B�����������������Ă��Ȃ��A����ŋ����ɍׂ����M���U�[�������Ă���̂ɃJ�W���A���ɒ�����V���c��A���n�F�ł܂Ƃ߂�ꂽ�p�b�`���[�N�̃T�}�[�W���P�b�g�Ȃǂ����莄����D���ȓX�������B�Ɛg�ŋC�܂܂Ȃ��Ƃ�����A�����֍s���ƈ�͕K���������̂��ƌ��߂Ă������Ƃ��������B
�b���͂���ȓX���Ȃ��Ȃ藎�������Ă����̂����A���͂������N�z�e���E�j���[�I�[�^�j�Ńf�B�i�[�V���[�̃C�x���g�N�Q���ɂ���Ă���B���������̂ŕK�R�I�Ɏ��Ԃ�S�ɗ]�T���ł��Ă���B���͂����̂S�K�̃��r�[�t���A�ƁA�n���Q�K�̃V���b�s���O�E�A�[�P�[�h������̂��y���݂ɂȂ��Ă���B���̃V�[�Y���͉������ŕK���Z�[��������Ă���B����܂ʼn������炨�C�ɓ���������Ă������A���N�����̒n���̃A�[�P�[�h�ʼn��C�Ȃ��`�������m�̒��ɁA�ƂĂ��C�ɂȂ�l�`���������B���̎��A���̊��o�͈ȑO�ɉ������ő̌������悤�ȕs�v�c�ȋC�����ɂȂ����B���̉����g�͏�k�̂悤�ɍ��Ƒ��������傫���A�L��������̌^�͂ǂ������b�`�Ō|�p�̍�������Ă����̂��o���Ă���B�͂ĉ����ł���Ȋ��o�𖡂�����̂��낤�H�Ƃ��������~�܂��Đl�`���ɂ߂����������̂����A�Ƃ��Ƃ��v�������邱�Ƃ��Ȃ������𗧂��������B
 ���ꂩ���T�Ԃقnjo�������鎞�A���s�G�����L���Ă����炠���I���ꂾ�����Ɛ��Ɏv���o�����B�W�N�O�ɍs�����앧�̃j�[�X�ɂ���l�O���X�R�E�z�e���ł̎��������B���̃z�e�����E�߂̃s���N�V�����p�����t�����g���̃o�[�����˂��x�e���ň��݁A�ق됌�������Ń��r�[�ɏo��ƁA�g�̏�S���[�g�������낤���Ƃ����O���}���X�ȏ����̃I�u�W�F�ɏo������B���̈��|�I�ȑ��݊��͏������������R�P�e�B�b�V���ȖL�����ƁA�������炩��Ƃ������[���A�����R�ƂȂ��ĕ\������Ă����B���ɂ��̕��͋C�Ɠ������̂������ȗ�̐l�`�ɗ���Ă����̂��B
���ꂩ���T�Ԃقnjo�������鎞�A���s�G�����L���Ă����炠���I���ꂾ�����Ɛ��Ɏv���o�����B�W�N�O�ɍs�����앧�̃j�[�X�ɂ���l�O���X�R�E�z�e���ł̎��������B���̃z�e�����E�߂̃s���N�V�����p�����t�����g���̃o�[�����˂��x�e���ň��݁A�ق됌�������Ń��r�[�ɏo��ƁA�g�̏�S���[�g�������낤���Ƃ����O���}���X�ȏ����̃I�u�W�F�ɏo������B���̈��|�I�ȑ��݊��͏������������R�P�e�B�b�V���ȖL�����ƁA�������炩��Ƃ������[���A�����R�ƂȂ��ĕ\������Ă����B���ɂ��̕��͋C�Ɠ������̂������ȗ�̐l�`�ɗ���Ă����̂��B ���ꂩ��ꂩ�����o�����B�j���[�I�[�^�j�̂������̐ԍ�ɍs�����ƂɂȂ������́A���łɂ�������Ă��܂��Ă��Ȃ���������Ȃ��q���E���̃h���X�̗�̐l�`�ɉ�ɍs�����Ƃɂ����B�C���͓앧�̊������ĂсI�ł���B���̓�����҂��Ă������̂悤�ɔޏ��͑��ۂɂ����B���Ԃ������Ԃ�o���m���͒Ⴉ�����̂����A�������������炱��������̉����Ɣ������Ɍ��߂Ă����B���ɂ����X�̏����Ɉ�u�̊Ԃ������āg������������h�ƌ������B����ď��߂Ĕ����l�`�͒������g�O���}�[�I���ƂȂ��ϑԃI���W�̂悤�ŔN�b����Ȃ��p���������B���ݖ����Ɋ�����ς܂���ƁA���x�͂��X�̎�l�炵�������܂ł��o�Ă��Ă����J�ɂ�������I�ł���B�����������肽���̂ɁA����Ȏ��Ɍ����Ď����C�𝆂�ő҂a�Q�ւ̃G���x�[�^�[�͂Ȃ��Ȃ��~��ė��Ȃ��B�܂�����̂��ȁH�Ƃ��X�̕��ɖڂ����ƁA�Q�l�̏����͂ɂ��₩�ɔ��݂Ȃ��炶���Ƃ���������Ă���B�̒����J�b�ƔM���Ȃ�A��⊾���e�̉���z�ɕ����o���Ă���B�s���|�[���ƃh�A���J���āA�[�X�Ƃ����V�����Ă���Ă��鏗�������Ƃ���ƕʂ�邱�Ƃ��ł����B�h�A���܂�N�����Ȃ��̂��m�F���g����`�Q�����ȁI�h�Ƒ傫�Ȃ��ߑ�������̓Ƃ茾�B
���ꂩ��ꂩ�����o�����B�j���[�I�[�^�j�̂������̐ԍ�ɍs�����ƂɂȂ������́A���łɂ�������Ă��܂��Ă��Ȃ���������Ȃ��q���E���̃h���X�̗�̐l�`�ɉ�ɍs�����Ƃɂ����B�C���͓앧�̊������ĂсI�ł���B���̓�����҂��Ă������̂悤�ɔޏ��͑��ۂɂ����B���Ԃ������Ԃ�o���m���͒Ⴉ�����̂����A�������������炱��������̉����Ɣ������Ɍ��߂Ă����B���ɂ����X�̏����Ɉ�u�̊Ԃ������āg������������h�ƌ������B����ď��߂Ĕ����l�`�͒������g�O���}�[�I���ƂȂ��ϑԃI���W�̂悤�ŔN�b����Ȃ��p���������B���ݖ����Ɋ�����ς܂���ƁA���x�͂��X�̎�l�炵�������܂ł��o�Ă��Ă����J�ɂ�������I�ł���B�����������肽���̂ɁA����Ȏ��Ɍ����Ď����C�𝆂�ő҂a�Q�ւ̃G���x�[�^�[�͂Ȃ��Ȃ��~��ė��Ȃ��B�܂�����̂��ȁH�Ƃ��X�̕��ɖڂ����ƁA�Q�l�̏����͂ɂ��₩�ɔ��݂Ȃ��炶���Ƃ���������Ă���B�̒����J�b�ƔM���Ȃ�A��⊾���e�̉���z�ɕ����o���Ă���B�s���|�[���ƃh�A���J���āA�[�X�Ƃ����V�����Ă���Ă��鏗�������Ƃ���ƕʂ�邱�Ƃ��ł����B�h�A���܂�N�����Ȃ��̂��m�F���g����`�Q�����ȁI�h�Ƒ傫�Ȃ��ߑ�������̓Ƃ茾�B���̘b�A���Ȃ�f�G�ȏꏊ�ƃ��m���肾�B�j�[�X�̃l�O���X�R�E�z�e���ɋI���䒬�̃z�e���E�j���[�I�[�^�j�A���łɂق�̂芹�k�n�̍��肪�����������s���N�V�����p���B�����Ă���������Ă���̂́A���b�`�ŃJ�b�R�ǂ��������̎��̃A�����E�h�����Ȃ�ʕ��т̏オ��Ȃ��A�����ėa�����Ȃ����{�̃I���W�I�܂莄�Ȃ̂��B�����ɂ��̘b�̗��Ƃ��ǂ��낪����B���ɂ����A���o�����X�Ƃ͂���Ȏ��Ɏg���ł��I�m�Ȍ��t���B�ȗ��A��⊾���������b�オ����H�l�`�ł���ޏ��͎��X�Ƒ��ɂ͓����Ŏ��̑�������Ă����B���R�A�����Ȃ������̂��������Ȃ̂�BGM���K�v�ƂȂ�B�Ȃ͒����݂䂫�́g�����h���ǂ��������A��͂�t�����X��ő�C����Y���悤�ɗ��S�̂����g�J���v�\�h�Ȃǂ��������Ă���B�̎�͂��̖��䂩�����t�����X�E�M�������B
�N���̂ЂƂ育�ƂS�A��A�܂����N������Ȃ��n���Ȃ��Ƃ���t�����܂��l�ɁI���̃l�^�ɂȂ�Ԕ����ȏo�����ɏo��܂��l�ɁI�Ɗ肤�N�̐��͒W�X�Ɨ�����Ă䂭�B
2013.12.14 (�y) ����Ƀ]�E����������
�N�����l���̒��ň���A�s�m���ȋL���Ƃ������̂����̒��̉������ɑ��݂���Ǝv���B���������ւ��ĉv�X���̋L���̐��m�����������Ȃ��Ă����B�������悤�Ȗ��������悤�Ȃ���͖��A����Ƃ����������̂��Ƃ��v����B�Ⴆ�A�������Ȃ��ЂȂт��w�̃z�[���̋x�e���ŁA��Ɖ����ȃX�g�[�u�̑O�ʼn߂������[��ꎞ�̎��B�r���X�̂܂����Â������Ɉ��O���[���F�̃X�[�v�i���v���O�����s�[�X���낤�j�̏�ʂȂǂ��A����܂Ŋ��x�ƂȂ��h��̂����A����������������肠�̉f���������������̂��ۂ��͂킩��Ȃ��B����Ɠ����悤�Ȏ������A�q���̂���ɕ����Ă����䂪��l�ɂȂ�܂Ŗ������̂܂܂ł��鎖���ԁX����B����Ȃ��Ƃ͐l����H�邤���ʼn���d�v�ł��Ȃ��A�m��Ȃ��ł��������Ƃ��w�ǂł��邱�Ƃ��������B�������A�����I�ȏ���o���Ă��炻�̓䂪���������Č����A�ق�̂�Ƃ��������������̂ŏ������߂邱�Ƃɂ����B��N�̂X���A���̂ЂƂ育�ƂɁg�S�c��h�Ƃ����^�C�g���œ��{���E�������̉���ł̏o�������������B�傫�ȏۂɋC������ď�ꂸ�ɋ������c�����A���̑���ɂR�Ώ�̌Z�����̏ۂɏ���������������̂����A���̎��ɕ����Ă����^��́A�ǂ�����Ă���Ȃɑ傫�ȓ���������ɏオ���Ă����̂��A�i���̓䂾�Ƃ�������
 �����B
�����B�P�P���̏��{�̒��A�����̂悤�ɉ��C�Ȃ����������Ă�����A
�@�@�@�@�@����Ƀ]�E����������@�@�^�C������{���������֖��͍��q
�Ƃ����ƂĂ��C�ɂȂ�^�C�g���̋L���B��͂�A������O�̖ʑO�ő勃�����Ă��܂������̓��̒p���������v���o���̂܂܂̃C�x���g�̎ʐ^���ڂ��Ă���B�����Ď������������ہA�i����A����Ɏ����������̂ŏۂɂ͂Ȃ�̍߂�����܂���j�̂��Ƃ��ڂ���������Ă����B���͌��債�č������̍����Ƃ��č��q�A���a�Q�S�N�Ƀ^�C�̓암�ɐ��܂�A���Q�T�N�ɐ���W�����ʼn��ւɉ^��A���ꂩ�瓌���̍������̉���Ŏ���ꂽ�Ƃ����B�������A���U��A���b�p�����ƌ|�B�҂������炵���B�q����������Ԃ��̎p���ڂɕ����ԁB�₪�ĂT�O�O�L������P,�T�g���ɂȂ������q�͏�쓮�����Ɉڂ�A���ꂩ�畽���Q�N�ɑ������������Ŏ��Ƃ����B�����ǂ�ł��邤���ɖړ����M���Ȃ��Ă����B�W�W�C���L�̗܂��낳�ł���B
���悢�捡���̖{��B�ǂ�����đ傫�ȏۂ�����ɏオ�����̂��ƌ����A�N���[���Œn�ォ���C�ɉ���ɒ݂�グ���Ƃ����B��{�I�ɂ͌���̋Z�p�ƕς��Ȃ��A�A�o�E�g�U�O�N�ڂ̐^���ƌ����Α�U�����낤���H�����̎ʐ^�ł��Ȃ�ڂ₯�Ă���̂����A�ۂ̍��q���݂�グ���Ă���ʐ^���f�ڂ���Ă����B���C�Ɉ���ł���B�������������낤�ɁI�Ɖv�X�ړ����M���Ȃ��Ă����B
���̏ۂɉ��x�����i���̖��_�ׂ̈ɕt�����������Ă��������A��͂莄���Q�ΔN��̂��̐l���ŏ��͕|���ƌ����ċ����ď��Ȃ������������j���̎v���o���g�f�p�[�g�̂����̂��������h�Ƃ����^�C�g���ŊG�{���o�����r��Î}����Ƃ�����������B�Q�O���N�O�A�r�䂳�{�l���������������ŁA���̏ۂɐ��\�N�Ԃ�ɍĉ���������B�v�킸�g�������h�Ƒ吺�ŌĂ�U��Ԃ��Ă�����֕����Ă����������B�����������������b�ɂ͂߂��ۂ��キ�A���Ɉ�Ȃ݂���������B�����ł���B
����Ŏ��̖}�������I�ɋy�Ԃ��킢�Ȃ��䂪�������Ƃ����b�B���̊G�{���ɍs�������ȁH�ƂӂƎv���B�q������ɏ�ꂸ�ɋ����āA���̐V���L���ŋ����āA���x�͊G�{���B���̏ۂ̍��q�ɐl����ʂ��ĂR�x�����������̂͂ǂ�Ȃ��̂��낤�B����䂭�v���C�h�͋����̂����E�E�E�A��͂�~�߂Ă������B
2013.12.08 (��) �^�[�L�[
�g���V�I���̃^�[�L�[�̖��O�̗R�������������m���߂Ă݂悤�h�ƌ��S�������͎v�����Ă��̓X�ɓ������B�c�t�������炢�̏����Ȏq���A��̏����ƁA���܂��ɏo�����ĂƂ������[�������`���[�n����H�ׂĂ��钆�N�̒j���������B�b���T�����̂����A�X�̃��j���[���ǂ��ɏ����Ă���̂�����Ȃ��B�~�[�̒��̂ނ���Ƃ����I���W�����ɂ���́H�Ƃ���ɓ˂������Ď��������ƌ��Ă���B���͏����ł��Ďv�킸�g���[�������������h�ƌ����Ă݂��B�܂��͎����葁���ԈႢ�̂Ȃ������ł���B���ꂩ�痎�������ėǂ����n���ƁA�J�E���^�[�̑O�ɂa�T�قǂ̖�������ʼn��F���Ȃ��������\���Ă������B�����ɏ�����Ă���̂��X�̃��j���[���ƋC�Â����B����ȉB�ꂽ���ɁI����ᖳ�������I
���̃I���W����A��������̂��������͈�É��t���̘V�l�z�[���ɓ������Ƃ��A���ߏ��̃��[�J���Șb����q�A��̂��ꂳ��Ƙb���Ă���B�C����I���W�ł͂Ȃ��������B�b�����ĊF���o�Ă䂫�A���̑O�ɂ͐̂Ȃ���̃��[�������o�ė����B�˂͎㊥���߂ŃX�[�v�̐F�͔Z�������͂����ς�n���B�`���[�V���[���������A������ނƏ_�炩�Ŗ��Ɏ|���B
���ɂ��̃I���W����Ǝ������ɂȂ����B�`�����X�����ł���I�g�ǂ����ă^�[�L�[�Ƃ����̂ł����H�h�ƃC�L�i������Ă݂��B����ƃI�E���Ԃ��Ɂg���ʒ��h�Ƃ��������B���ʒ��������̂��I�Ǝ��B���ꂩ��͂��̃I���W����̌��オ�n�܂�B�ނ͐��܂���炿���V�h�̋����ŁA�́A�V�h�Ɏ��ʒ��Ƃ������O�̔����������[�������������������ȁB�����X���𖼏��̂��ʔ����Ȃ��Ƃ�����p��ɂ��Ă݂��B���b���܂��o���Ȃ��Ԃ����܂ł�����������^�[�L�[�I�p�p�A�}�}�A���������獡�x�̓^�[�L�[�I�Ə���ɔ��f�B�����������Ή��Ń^�[�L�[�Ƃ͉��ƂȂ������Ă��Ėʔ����B�p�\�R���Œ��ׂ���m�H���ł͂P�O�X�قǂ��邻�������A�����Ή��ł͂����ꌬ���������B����Ⴒ�����Ƃ��B
���͂��̖��ŘA�z�����̂͐��̍]��q����ł����Ƃ����ƁA�I���W����͂�����ڂ����B���̐l���g����X�^�[���������A�f��̃v���a���[�T�[�ŐΌ��T���Y�Ȃǂ̃X�^�[�@�����Ƃ��b���Ă�����A���̊Ԃɂ��^�[�L�[�͔ޕ��֔��ōs���Ă��܂��A���[�������x�߂��ƌĂ�A���̒l�i�͂R�O�~����������ɂ����̂ڂ�B�V�h�̓���̗V�Z��ŗV�b�A�₪�ăI���W�B�̉�b�͓͗��R���V���[�v�Z������`���b�v�ł������A���a�̐^�������̎���ɂ܂Ń^�C���X���b�v����L�l�B
�悤�₭���̋q�����āA�܂����x��点�Ē����܂��ƓX���o���B���̘b���������ɂȂ�g���ł����܂��傤�h�g�V���{���ʃz���f�[�h�g�X�`�����J�Ј��h���X���a�̃q�b�g�ԑg���v���o���A�̂̃e���r�͖{���ɖʔ������̂������ς��������Ɖ������ށB�����Ȃ���A�ӂƐ���̃e���r�̓������v���o�����B���N��肽���͉ߋ������A��҂����͖����̖�������遄�A�i�E���T�[�̂����Ƃ��炵�����������������ł������B������Ƒ҂āI�ߋ��̂Ȃ���҂�����I������ɂ�R�قljߋ�������B����ȓ����ɂ́A���͓��c�܂��ƕ�����g�ĂȂ����O�x�}�h�̂����̎����Y�ɂȂ�B�g���̌�����肥�`�˂�����ʼn����K�^�K�^���킵���납�h�ƐS�Ɏc�閼�[���t�H���v���o�����B���̏����ȏ��a�̙ꂫ�́A�͗t�����_�炩�Ȍߌ�̓������̒��ɏ����Ă������B
2013.12.04 (��) ���z�@�̒���
�Èł̖����ŁA���\�ȉ��ʂœd�b�����Ă���B���V���V���ƌ����������̊�����т��l�ȃ_�~���Ɍ˘f���B ���炩�ɍ���̎��̂������B
���炩�ɍ���̎��̂������B�g���͂悤�������܂��I�t�����g�ł������܂��B�����͂ƂĂ��₦���݂܂����̂ŁA�K�^�ɂ��������o�܂����I�h�Ƃ����u�₩�Ȓj���̐��B�����������̗[�H�̎��ɂ��́g�T�̈�ʑ��h�̒����c�@�[�Ȃ���̂ɒ������\�����̂������B�����͑啪���A���z�@�B���N�\�ꌎ�̉������A���������z�@�̒��S�̂������ۂ�ƕ�ݍ���ł��܂����������ۂ��N���邻�����B�����R�z�x�̒������猩���낷�Ƃ����A���̗��قȂ�ł͂̃T�[�r�X�E�c�@�[�ł���B
���X�����ɑς�����g�x�x�𐮂��ăt�����g�Ɍ������B���h��̎ԂŁA�����Ȃ����\�ȃX�s�[�h�ŎR����o���čs���Ȃ���^�]�莁�H���A�g���q�l�͂ƂĂ����b�L�[�ł��B���̎����ł������͓��R���邱�Ƃ͂ł��܂��A�N�Ԃł��\�l���قǂ��������͏o�܂���̂Łh�Ƃ̂��ƁB�h�ׂ̗ɂ���ƌĂԂɂ͂��܂�ɂ����������،ɂ͉����ꍞ��ł���B���̒��S�̂ɗN���o�鉷��̉��������Y���Ă��鏊�ɁA���̎������L�̗�C���R����~��Ă���ƁA���̊��g�̍��Ŗ����������邻�����B�ォ�猩���낷�Ɠ��z�@�̒����w�ǔ����_�ɕ����Ă���B�V�ƒn���t�ɂȂ����l���ŁA���ɂ͗R�z�x���A���̌��ɍg�t�Ő��܂����Ԓ��̒������P�����Ă���B����Ȗʔ����i�F��Q�ڂ���Ŋ��\����B
 ���̂R�N�ԁA���͔ӏH����ɂȂ�Ɨ��ɏo�Ă���B�ʂɂ��̎�����_���ė��ɏo�Ă���킯�ł��Ȃ��̂����A���̂��s�v�c�ɂ����Ȃ��Ă���B���N�͖k�C�^���A�A���N�͂��̂ЂƂ育�Ƃɂ����������܂Ȃ݊C����n��A���|�̋{������R�����������\�ȓ��̂�����Ȃ����������B���N�͖��B�Ɖ��\�N���Ԃ�̋�B�̈��h���瓒�z�@����闷�ɂȂ����B�����Ɠ�l�ő啪��`�܂ōs���A�����ׂŃ����^�J�[����A�ʕ{�Œx���ċx�݂̋x�ɂʼn�X�Ƃ͕ʃ��[�g�ŋ�B�ɗ��Ă��������Ƃ��������A��d�ɂ�����{��̒��������苴�ŗ�Ԃ≩�F�̍g�t���y���B
���̂R�N�ԁA���͔ӏH����ɂȂ�Ɨ��ɏo�Ă���B�ʂɂ��̎�����_���ė��ɏo�Ă���킯�ł��Ȃ��̂����A���̂��s�v�c�ɂ����Ȃ��Ă���B���N�͖k�C�^���A�A���N�͂��̂ЂƂ育�Ƃɂ����������܂Ȃ݊C����n��A���|�̋{������R�����������\�ȓ��̂�����Ȃ����������B���N�͖��B�Ɖ��\�N���Ԃ�̋�B�̈��h���瓒�z�@����闷�ɂȂ����B�����Ɠ�l�ő啪��`�܂ōs���A�����ׂŃ����^�J�[����A�ʕ{�Œx���ċx�݂̋x�ɂʼn�X�Ƃ͕ʃ��[�g�ŋ�B�ɗ��Ă��������Ƃ��������A��d�ɂ�����{��̒��������苴�ŗ�Ԃ≩�F�̍g�t���y���B�ŏ��̏h�A�v�Z�̃X�p�E�O���l�X�Ƃ����ꌬ�Ƃ̃R�e�[�W�ɔ��܂�B�ܓ��O�ɃI�[�v�������Ƃ�������̃C�^���A�E���X�g�����ł́A�ǂ������̐�Ŋ뜜��̎R�r�̃`�[�Y���́A���Ƃ��n���̐����Ȃ����Ƃ��A�����������ɒ������H�ނ̃I���p���[�h�Ɏv�킸�z���g����I�ƐS�̒��Ō����Ă݂�B�����Ў����Â�悤�Ɋy���ޗ��G�̐g�Ȃ̂ŁA�^�킵���͔������̋C���ł���B�r�ƃZ���X�̂����V�F�t������炵�����͂Ȃ��Ȃ��̂��̂������B���̓��͈��h�̃J���f���܂Łg��܂Ȃ݃n�C�E�G�C�h�ōs���̂����A�ǂ��܂ōs���Ă����̓X�X�L����ʂɍL�����Ă��āA�ǂ��������������{�̏H�̌���I�ȕ��i���Ȃ��S��h���Ԃ�B�����ĖړI�̑�ϕ�ɓ����B���̈��h�̃J���f���̗Y��Ȍi�F�͊������̂������B
�v�����N�̍����A�~���m�̃X�J�����̑O�Ő��܂�ď��߂ăX���ɂ������B�܂�������������ȂɃg���}�������Ƃ̓K�b�N���ł���B�c�@�R���̂�����A����̓v�����̃v���̎d�Ƃ��ƁA�Ԕ����Ȃ��q�ł��鎄���ꐶ�����Ԃ߂Ă��ꂽ�B�����ăx�j�X��t�B�����c�F�ŏo���킷�����l�ό��q�̖T�ᖳ�l���ɂ���������B������z�e���̃r���b�t�F�ŃR�[�q�[��W���[�X�����������������Ă������@�r�ɋl�߁A��������ɂ��Ă��܂��B����̉ʂĂ̓W������o�^�[�܂ł��I�J���������ǂ���Ȃ��Ƃ͂��̂��Ƃ��B����Ɩܘ_�A���[���b�p�ɂ͑f���炵���G�⒤���ɗ��j���錚����������B�������E�̖���ƌĂ�Ă���A�r�[�i�X�a���A�t�̂߂��߁A��ٍ��m�A�V�n�n�����X�A�@���Ƃ����̂ł����グ�̕��������ł����I�ƌ���������ƁA�M�Ƃ������̂ɂ͉������A�܂��ăL���X�g���ł��Ȃ����ɂ͊����H���C���ɂȂ�B
����Ȉ�N�O�̗����v���o���Ă���ƁA����ς���{�͂��������Ƃ��Â��v���B���ɂƂ��Ă̊C�O���s�Ƃ����̂́A���{�l�Ƃ��̍��̗ǂ����ĔF������ׂ̗��ł�����B��ʋ@�ւ̐��m���́A���̍��Ŕ|�����ΕׂƂ������t�ɗ��ł����ꂽ���Ȉ��S��������B�����đS���ɎU���ꗬ�ƌ����闷�ق̃T�[�r�X�́A��X���{�l�������Đ��E�Ɍւ����̂��Ǝv���B�������C����嗁��͏�ɐ����ŋC�z�肪�s���͂��Ă��邵�A�n�ő����E�H�̑V�ȂǏ����ꂽ���������M�̕����Ȍ����\�Ȃǂ́A�����֗����O���l�q�Ȃǂɂ͂ƂĂ������y�Y�ɂȂ邾�낤�B�O����n�܂�A�����͈�̗����������Ȃ鍠�Ɏ����玟�ւƉ��������̂��₵�����̂��^��Ă���B�▭�ȍ������͂܂�ʼn������ŎM�̒���`���Ă��̂悤�������B
�ߔN�A��ɐF�X�Ȗ���Y�݂�����Ă��āA�����������ΐ肪�Ȃ����ł���B����ł��������{�l�ɐ��܂�Ă��ėǂ������A�Ǝ����ł���̂͂���ȗ��̂ЂƎ��ł���B
2013.08.27 (��) ����
�������͏�ɑ傫�Ȃ��̂Ɏv����y���邱�Ƃ��D���Ȃ悤���B�ŋ߂ł͐[�C�̃_�C�I�E�C�J�Ȃǂ͂��̍ł�����̂ŁA���A�����قœW������Ă��锍���ł��Ȃ�������̖͌^�ł��l�C���Ă�ł���炵���B�����Ƃ������NHK�X�y�V�����ŁA���E���̐����Ă���M�d�ȉf�������f���ꂽ�̂����������������B����܂ł͂����܂ł������z���̐��E�ŁA�}�b�R�E�N�W���Ƃ̐[�C�ɂ�����H�����H���邩�̍U�h���L���ŁA���̑��݂͍L���m���Ă����B���������ۂɂǂ�ȏꏊ�łǂ�ȓ��������Đ������Ă���̂��͖��m�̐��E�������B ���̐����Ă���f���́A�ȑO���f���ꂽ�V�[���J���X�ɑ����ďՌ��I�������B�H���齉��ŐH�ׂĂ��邠�̃C�J�̓������Ԃ��T���[�g���Ƃ��V���[�g���Ƃ�����ƕ����A�[�C�ւ̋����͂��₪�����ɂ������Ă���B���ꂼ���m�Ȃ�傫�ȃ��m�ւ̃��}���ł���B�q���̂���Ƀ}�����X�͏ۂ̉��{���傫���̂��낤�Ə���ɑz�����Ă����̂����A���ۂɂ͈ӊO�Ə����������ƒm�炳��Ă������肵���̂��o���Ă���B���̂S���̏��{�̒����̓V���l��ɂ���Ƃ͋t�ɁA���������m�̘b���ڂ��Ă����B�A�C�������h���܂�̍�ƃX�E�B�t�g�̎��Ł@���m�~�ɂ�����m�~�������@�m�~�̃m�~�ɂ�����m�~�������@����ł͂ǂ��܂ł����Ă����肪�Ȃ����@����̓~�N���̐��E�ŁA�����A�����ŗ��s���Ă������C���t���G���U�̃E�C���X��̘b�ɂ����Ă䂭�̂����A�ۂ�哤���Ƃ���A�E�C���X�̑傫���͖����q�̈ꗱ�قǂ炵���B�l�Ԃ����������d�q�������Ȃ���̂ł��̑��݂����炩�ɂȂ����Ƃ����B�����̉B���̎���@���A�Ō�͂��̏������ċ��ЂȂ���҂�n���l�����͂������Č��ނ��悤�Ƃ����A�A�����J�f��̑�ނɂȂ�悤�Ȏ�|�Œ��߂�����B���̐��E�ɂ���X�̕������ł͑��肫��Ȃ������Ƃ����Ə����Ȑ�����������Ƃ���A�~�N���̐��E���܂������ɍL�����Ă䂭�B
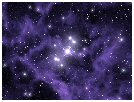 ���ĒN������D���ȃX�P�[���̑傫�Șb�ɖ߂��āA�m���ɉ������N�̉F���̉ʂĂɉ������낤�Ƃ��A����͉�X�������Ă��錻���̘g�̊O�̂��Ƃł���B����ł��Ȃ��A�z����₷�鉓���Ƃ���̐V��������T���Ė������߂��������҂����邾�낤���A�����܂߁A����ɖ���ʂĂȂ��z�����������Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B���グ��A�������̏�ɂ͏�ɂ��̋�ƈ�̂ɂȂ��Ă���F��������B�Ⴆ�Γ����h�[���ʼn����c�̖����Ă��������≹���������́A�_�{����̋�ɏ����䂭���̂ق����S�n�������A���R�̕��ɐ�����Ĉ��ރr�[���́A�������ꂽ�����t���̉��ň��ނ��̂������{�|���Ɗ�����B
���ĒN������D���ȃX�P�[���̑傫�Șb�ɖ߂��āA�m���ɉ������N�̉F���̉ʂĂɉ������낤�Ƃ��A����͉�X�������Ă��錻���̘g�̊O�̂��Ƃł���B����ł��Ȃ��A�z����₷�鉓���Ƃ���̐V��������T���Ė������߂��������҂����邾�낤���A�����܂߁A����ɖ���ʂĂȂ��z�����������Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B���グ��A�������̏�ɂ͏�ɂ��̋�ƈ�̂ɂȂ��Ă���F��������B�Ⴆ�Γ����h�[���ʼn����c�̖����Ă��������≹���������́A�_�{����̋�ɏ����䂭���̂ق����S�n�������A���R�̕��ɐ�����Ĉ��ރr�[���́A�������ꂽ�����t���̉��ň��ނ��̂������{�|���Ɗ�����B�F�����猩��A�E�C���X�̖����̈�����������ł��낤�������́A���̐������Ȑ��œ��X�{����������苃�����肵�Ă���B���܂��Ɏ��ɑ���Ȃ����łЂ��肢������������Ă���B���i�����l�����Ɉꐶ���������Ă���킯�����A���߂Ă�����ǂɍ\���Ă݂�ƁA�����̂��܂�̏������ɗ�߂����������ݏグ�Ă���B�����Ď������̈ꐶ�͉F���̏u���ɂ��y�Ȃ��قǒZ���ƂȂ�A�����͂قږ����Ƃ��������t�����ɁA���X�����Ƃ��y�������߂��������Ȃ��Ƃ��v���Ă���̂����ǂ����낤�B
�ɏ��̐��E��ƂĂ��Ȃ��傫�Ȑ��E���_�Ԍ��Ă��A���F�͍���������A�����̊�]��s��������Ȃ���A�����Ă��铙�g��̎����������ɂ���B���߂ĎO���Ɉ�x�͑������߁A���₩�ɂ����Ă����炩�ɁA�����ۂ��Ȏ��������Ȃ��琶���Ă����������̂ł���B
2013.08.16 (��) �h���[���K�[���Y
�A���̍����ɂ���Ƃ���B�Ƃ̃h�A���J����ƃ��b�Ƃ��鏋���ő����l�܂�悤���B���Ă̓����́A�܂�Ŗ�����������ԓ������̃V���K�|�[���̂悤���B���̂�����悤�ȏ���������ɋv���U��̊������������B����10���ɂ��˂Ă���y���݂ɂ��Ă����u���[�h�E�F�C�E�~���[�W�J���́g�h���[���K�[���Y�h�𖺒B�Ɗςė����B�ꏊ�͉��x���l�ׂ̈Ƀ`�P�b�g���ɍs���̂����A��x�����������Ƃ��Ȃ������a�J�̓��}�V�A�^�[�I�[�u�B�a�J�̐V�����q�J���G�̒��ɂ���B ���̃~���[�W�J����1981�N�Ƀj���[���[�N�̃u���[�h�E�G�C�ŏ�������A�g�j�[�܂�6����Ŏ�܂����Ƃ����B���̓����̂��Ƃ͂��܂�m��Ȃ������̂����A�W�F�C�~�[�E�t�H�b�N�X�A�r�����Z�A�G�f�C�[�E�}�[�t�B�[�����o�����Ă����f�扻�ł����m�����B����ɔ���2010�N�ɗ����������������Ƃ����B�X�g�[���[��60�N��̔�Ԓ��𗎂Ƃ��������������[�^�E���E���R�[�h�̋������B���l�����g���I�g�V���[�v���[���X�h�̃T�N�Z�X�X�g�[���[���B�h���ƍ��܂ƗF��A�����Đ����n�̖ڂ��V���[�r�Y�̐��E�̗�����Z�����Ԃ̒��ōI���ɉs���`���Ă���B�������̃��R�[�h�ƊE�Ɏl�����I�̊Ԑg��u���Ă����̂ŁA�Ȃ�����ʔ������邱�Ƃ��ł����B
���̃~���[�W�J����1981�N�Ƀj���[���[�N�̃u���[�h�E�G�C�ŏ�������A�g�j�[�܂�6����Ŏ�܂����Ƃ����B���̓����̂��Ƃ͂��܂�m��Ȃ������̂����A�W�F�C�~�[�E�t�H�b�N�X�A�r�����Z�A�G�f�C�[�E�}�[�t�B�[�����o�����Ă����f�扻�ł����m�����B����ɔ���2010�N�ɗ����������������Ƃ����B�X�g�[���[��60�N��̔�Ԓ��𗎂Ƃ��������������[�^�E���E���R�[�h�̋������B���l�����g���I�g�V���[�v���[���X�h�̃T�N�Z�X�X�g�[���[���B�h���ƍ��܂ƗF��A�����Đ����n�̖ڂ��V���[�r�Y�̐��E�̗�����Z�����Ԃ̒��ōI���ɉs���`���Ă���B�������̃��R�[�h�ƊE�Ɏl�����I�̊Ԑg��u���Ă����̂ŁA�Ȃ�����ʔ������邱�Ƃ��ł����B�ȑO�A���̂ЂƂ育�Ƃŏ����Ă����̂����A�V���[�v���[���X�ɍݐЂ��Ă����_�C�A�i�E���X�������̃~���[�W�J���̎�l���̈�l�ł���B�ޏ��ɂ͖Y����Ȃ��v���o������B�����܂�20��̍��A���X�x�K�X����A���Ă������e���H�c�Ɍ}���ɍs�����Ԃ̒��ŁA�ꂪ���Ɂg���X�x�K�X�̃V�[�U�[�X�p���X�ŁA�ƂĂ��̂̂��܂����l�����̎�Ɉ�������Ă��炢�A���̐l�̃��R�[�h�܂Ŗ�����̂�h�ƌ����Ă����B�ƂA���Ă��̃��R�[�h��������A�������Ƃɂ��̉̎�̓_�C�A�i�E���X�ŁA���܂��ɃW���P�b�g�ɔޏ��̃T�C���܂ł��Ă������B�ޏ��̓A�����J���\���鏗�����H�[�J������I�ƌ�������ڂ��ۂ����Ċ������Ă����B�����Ĉꌾ�g�ْ����Ă����炵���A��͗₽��������h�Ƃ������t���A���ł��_�C�A�i�E���X������Ǝ��̐S�̒��őh��B
���ۂ̎���́A�V�J�S���疺3�l�ŃI�[�f�B�V�������Ƀj���[���[�N�ɂ���ė������̃��[�h���H�[�J���ŁA�`���C���ڂ̃G�t�B���B�j�ɗ����A����ł������ĂƏ��̃v���C�h�����Ȃ���̂Ă����̉́A�����ē�l�̃q���C��������܂ł̂킾���܂���Ԃ��ĐS�������������̉́B���̔M���͂����N�������I���W�̖j�ɂ������̗܂���ꗎ���邱�Ƃ��Y�ꂳ���Ă��܂��B�n�̒ꂩ��N���オ���ēV�ӂɎ����Ă䂭�܂ł̂�ǂ݂Ȃ��L���ȉ̐��Ɣ��^�̊���\���́A�����ɂ������ׂĂ̊ϋq�̐S��h�Â��݂ɂ���B���̏��߂ẴV�A�^�[�I�[�u�̌��z�v���V���������ɁA���≹���ɂ��Տꊴ���{��̃u���[�h�E�G�C���������Ă����B
�o���҂̂قƂ�ǂ����l�ł��̉̏��Ɨx��̑f���炵���ɂ���������̂����A60�N��̉����������R�[�h�̎���ƌ���Z���X�̍I�݂ȗZ���́A�h��ȐU��t����o�b�N�̌��̑����Ȃǂɂ���Ĉ�i�Ɛ���オ��B�����ăV���[�v���[���X��������o���҂��������߂��悤�Ȉߑ����A�����玟�֑��ς�肵�Ă����l�͖��̂悤�B�p�ꂪ���Ȏ��ɂƂ��Ă����䍶�E�Ɍ��₷�������̃X�[�p�[������A�b���������ɍ��������͉��ڂł������������B
�{��֍s���Δ�s�@��12���Ԃ�������A�z�e����͈ꔑ5���`7���~�ƍ����B����������p�قɐ��E�����[�h����ŐV���s�̓X�������L�[�X������B����͂ƂĂ����͂����A�����ł͖O���邱�Ƃ̂Ȃ��ʐ��E��2����30��������B���̎��Ԃ����͏a�J���u���[�h�E�G�C�ɕς��y�����ЂƎ��ł���B���C�y�ɐS�N�����~���[�W�J���I�߂��̂����珋���͉̂䖝�A���܂ɂ͑����̂����������āA�����ƈႤ������l�̎����ɉ����Ă݂�B
2013.08.06 (��) ���~
���ɂ��̍K���̍��ɐ��ς��N�����Ƃ����B�����O�̂��ƁA����݂ł���V�h�̏��a���g���Y�����X�g�����ŁA�����̒��ԂƐl�̍K���ɂ��Č�������Ƃ��������B�����Ő��E�ň�ԍK���Ȑl���Z��ł���Ƃ����u�[�^�������̘b�ɂȂ����B���A�������̍��ɍs���čK���ɂȂ�邩�Ƃ��������𗧂ĂĂ݂��̂����A�ɂׂ��Ȃ�����͏��F�����Șb���Ƃ������_�Ɏ������B���������̐��̒��ɐ��܂�炿�A���̍��̐l�X�̂悤�ɐl�Ɛl�Ƃ̘a�������Ƃ��A�ǂ��������肤�_�ւ̐M�ɓ��X���i���邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�܂��Ă₳�܂��܂ȕ֗��ȕ��Ɉ͂܂ꂽ�����Ɋ���e���g�ɁA����Ȃ��T�܂��������J�����@���Ƃ̂悤�ȋ��n�Ɏ���܂łɂ́A����������قǂ̏C�s���l���ς��ς��悤�ȑ̌������Ȃ�����́A�����ɓ͂��������Ȃ��Ƃ��������B����ȍ��A���̃u�[�^���ɂ��������ς�鎞�������炵���B����܂Œ��ڂ���Ă��Ȃ������C���h�ƒ����ɋ��܂ꂽ�鋫�Ƃ�������y�n���ɁA�����̐l�E���E�����̗����ŁA�����ɂ��O���[�o���Ȕg�������Ȃ�Ƃ��������̂��Ƃ��v����B�ǂ����C���h�y���Œ������C�V���̗^�}�����삵���炵���B��͂�l�Ԃ������Ȃ�Ƃ������I�L������m�邱�Ƃ́A�H�~�����A���̂̏d�J������������A���ԒZ�k�̋Z��m��A�₪�Č���ɖ������邱�ƂȂ��A��ɂ����W�Ԃ���^���ɂȂ��Ă����̂��낤�B���̐��ς����A�u�[�^�������̌��݂̖{�����������Ă���悤�ȋC������B
���āA���������̖Y��`���̂悤�Ȏ����B���̍��ɐ����Ă��鑽���̐l��������������Ȃ����A���͎����̍��̐����ɉ����K�v������ɍl���Ă���B�����l���邱�Ƃ͐l���̈ꕔ�ɂȂ����B�U��Ԃ�A�����ł��]�T���ł���Ə�ɉ�����~������X���ɂ���B����ł����̔N�ɂȂ��Ă悤�₭�~�������̂����Ȃ��Ȃ��Ă����B����͎�ɓ��ꂽ���̊���������Ă��Ă��邱�ƁA�����Ĕ߂������ɓ���̏��Օi�ȊO�͂��܂�K�v���������Ȃ��Ȃ��ė��Ă���B
���~���N�X������鎄�̒��ŁA�~��������ǂ܂��܂����̎��i���Ȃ��Ǝ��������ߎ肪�o���Ȃ��ł��郂�m�A����������Ύ�ɓ��邩������Ȃ����A���̐S���ɓ��B�ł��Ȃ��܂܉��\�N���o���Ă��܂��Ă��郂�m��T���Ă݂��B
�P. �^�q�`�̃{���{�����̐���R�e�[�W����A�����̒��H�̗]��̃x�[�R�����p�����a�ɂ��Ēގ��𐂂炵�Ă݂�A����͒��N�̖��ł���B�����炭�l���͑N�₩�ȃR�o���g�F��O���[���F�̃x���̒��Ԃ��ނ�邾�낤�Ɨ\�z���Ă���B
�Q. �ꎞ�͌C���t�@�b�V�����̌��_�Ƃ܂ōl���Ă������Ƃ����������ɂƂ��āA�C�̉��l�I���݂ł���W�������u�̃X�g���[�g�`�b�v���~�����Ǝv���Ă�����ɂQ�O�N�̍Ό������ꂽ�B���̍������l�i���啪�オ���Ă��܂��Ă���B
�R. �������N�ł̓p�e�b�N�t�B���b�v�̃J���g���o�Ƃ����A�ƂĂ��V���v���Ŕ��������v��r�ɂ͂߂�̂��Ă���B
�ȏ�͍s���Ă݂����A��ɓ��ꂽ�����ǂ��ɂ�������ݏo���Ȃ��܂ܒ��N�̖��ƂȂ���郂�m�������B��������炨���͌����Ē��߂���̂ł͂Ȃ��A�y���ވׂɂ�����̂��Ɗ�ȂɐM���ė����B����ł��^�q�`���W�������u���p�e�b�N���A�ꐶ�̖��ŏI���̂�������Ȃ��B�l�Ԃ̑��l�����Ζ��͎�������Ɩ��łȂ��Ȃ鎖���w�B�͂������œ͂��Ȃ����ǂ����������������悤�ɂȂ��Ă����B����o�鐔�X�̊y�����~�]�Ƃ̊����́A�c��l�����Ă䂭�ׂ̗ƂƂ��v����B���ʎ��{��`�Ƀh�b�v���Z���������~�̐\���q�́g�u�[�^�������ɐ��܂�Ȃ��Ŗ{���ɗǂ������h�Ƌ����Ȃł��낷�}���Ƒ�����B
2013.07.18 (��) �S�y�H
�̎�����n���Ƃ������t������B�q���̂��납��S�y�H���D���������̂����A���̏ꍇ�͏����A����傢�ɂ��̌��t����z���ł���|�p���Ƃ��������̂ɂ͒��������̂��������B���������ΔS�y�V�тł���B���v���Ώ��̎q�����l�`����V�тł��̐��E�ɓ��荞�ނ̂Ɠ����悤�Ȃ��̂ŁA����̒j�q�ł������悤�ȋC������B�����ŗV�S�y�͌ł��Ȃ�Ȃ����S�y�ŁA���̍��̃v�����X���[�����l������ẮA�e�[�u���Ő�킹��̂ł���B����Βj�̎q�̂��l�`�������ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B��������J�n����Ō�̏��s��������܂ł̊����X�g�[���[�́A��҂ł��鎄���S���������Ă���B���̓��̋C���Ō���̖��A���̉��������l���������オ��Ȃ��قǂ̃_���[�W����������B����Ȏ��͎��������̈�l�V�тɖO���ė������ŁA�S�y�ō��ꂽ�v�����X���[�̏���������܂ŁA���炭�̊Ԃ��̋��s�͂��x�݂ƂȂ�B���̃��X�����O�������͗c�t���̔N�����珬�w�Z�܂ŁA���Ȃ蒷���������Ƃ����L��������B
����ɏo���������M�����[�w�́A�͓��R���牓���K�g�A�L�o�i�g���m�{���j��т��炯�̃}�����X��A�͓��R���u���W������A��Ă��������̃A���g�j�I���ɁA�A�����J�ŕ��ҏC�s�����āA�₽��Ƌ����Ȃ��ċA���Ă����Ⴋ�W���C�A���g�n��B�����Ď����ŏ��̉����Ԃ��͈А��̂�����l�A�g��������ςȃ^�C�c�i�G�Ƀp�b�`�̂悤�ȃ��m���t���Ă����j�̖F�̗��ȂǂŁA�����ɊO���̈������X���[�������T�ւ��ŏo������B���Z�t�E�g���R�≫�����i�I�L�V�L�i�j�ȂǂƂ����A�����̓x�ɃV���c��j��ꂽ��A�O�l���X���[�̔����ɒm��Ȃ��U��������肷�郌�t�F���[�����̎d��������̉���́A����ɐ�킹�Ă��鉽�ł����̎��̎d���������B�r���A���܂�̔M��ɉ��Y��Đ����傫���Ȃ�B����𒃂̊Ԃ̉~��ł����̂�����A�K�R�I�ɑc���������A�����̎��̂���������킯���B
�g���`���I�������߂ł��I�u���b�V�[�̊��݂��ɗ͓��R�@�����オ��܂���I�h�ȂǂƗǂ���Ɏ��̌��^��������Ă��炩��ꂽ���̂������B�N�����̏]���������n�I���̉ƂɗV�тɗ��Ă������̂�����A���̖��S�y�͐e�ʂ̊Ԃł��L���ɂȂ��Ă����B�m�ق��ƂĂ����ӂȏ]���Ȃǂ́A�͂��g���T�Z���`�قǂ̔S�y�̃��X���[�������O�ɒ��Ă���ԕ��̃K�E���Ȃǂ�����Ă��ꂽ�B����͖{���ɏ������K�E���������B�U��Ԃ�ƁA���̎�����͑z�������Ȃ��قnjb�܂ꂽ�K�L�������Ƃ������B
�䑶�m�̂Ƃ���͓��͑z����̐������ł���B�������̓`���͖{���Ɍ����Ƃ��A�~�C���ɂȂ����肪�ǂ������̎��ɂ���Ȃǂƕ��������Ƃ��������̂ŁA�S�̒��ł͗B����݂̉\�����͂��Ɏc���Ă���d���Ƃ��Ẵ��}�����������B�̂ɐ��Ղ̎��_�Ƃ��Ă���ȏ�̓K�C�҂͂��Ȃ��Ƃ������_�ɂ��������B�q��������v���o���Ȃ���A�}�����쎞�ԂS���Ԃ������ďo���オ�����̂����͓̉������A�B�e�̂��߂ɐ��Ղ��牮��ɘA��o���Ă݂��B���ɑf�l�������đ�G�c�ł͂��邪�A�������Ƃɍ���Ă���Ƃ��������Ă䂫�A����|�p�Ƃ̐S���ɂȂ��Ă䂭�B�ҏ��̋����������ŁA���̕ӂ�̐F���ς���Ă��Ă��܂����̂����A����������g�B�C�̂������낤���H���̂����̍��ɍ���Ă����S�y���X���[�̖ʉe�������Ă��܂��B�g�O�q�̍��S�܂Łh�Ƃ͗ǂ����������̂ł���B
2013.07.14 (��) �Ⴋ���ɐG�ꂽ�D������
���Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��̂����A�ŋ߉v�X�V�����e���r���ʔ����Ȃ��B�܂��Đ����Ȃǂ͂��̍ł�����̂ŁANHK�ŎQ�c�@�̗����҂̊炪�o�Ă���Ə������A�`�����l����ς��Ă��܂��B�N�����Ɣ��ɂȂ�̂����߂̋��n�ɂȂ�̂��Ǝv���̂����A��ʓI�ɂ͔N�����قǑI�������オ��ƕ����B���̕����ƁA���{�̂��N��肽������D���Ȏ��������|�I�ȏ����������߂āA�����`�̌`�����낤���Ď���Ă����l�W���������������ł���B����Ȃ�����A�����ǂ݂Ƃ����`�œ����V�����䂪�Ƃ̃|�X�g�ɓ����Ă����B���̎����ǂ݂͉�����Ă�����Ă���̂����A�}���l���̒����Ɖ���������܂Ō_�Ă��܂��Ă���̂ŁA�Ȃ��Ȃ��v�����ĕς���C�ɂȂ�Ȃ��ł���B���ɂȂ��V�N�ȋC�����ł��̐V�����L���Ă݂�ƁA�Љ�ʂɃj�b�|�������̃A�i�E���T�[����������ܘY����̉��������Ί�̎ʐ^���ڂ��Ă����B�g���cDJ�̈ꖜ�������قցh�@�Ƃ����^�C�g�������Ă��āA�ނ̎��W�������R�[�h���k�C���̐V�����̉��y�~���[�W�A���Ɋ����Ƃ̂��Ƃ������B
�S���Ȃ��Ă���Q�X�N���o�����ŁA���߂đO�́g�ЂƂ育�Ɓh�ɑ������̗���̑�����������B�L���̒��ŁA���݂W�U�ɂȂ�ꂽ�Ƃ����A�ƂĂ����������������l�͍��������C�Ȃ悤�ŁA�����̌䎩��̓]���ƂƂ��Ɏ��W�i�̃��R�[�h�̐������@��e�ʂ̕��ɂ��肢���ꂽ�Ƃ̂��Ƃ������B���x�����ז��������䂳��̌䎩��͍L���̍ŏ�K�̃}���V�����ŁA�O�����ʂ��Ղސ�����ʂ����ׂčL�����ɂȂ��Ă����B����ɂ������Ă���u���C���h����C�Ɏ����ŊJ���Ă䂭�l�́A�܂��Ɍ���̖����J���悤�ős�ς������B���̉��ɂ͑傫�Ȑ��E�n�}���\���Ă���A����܂ł��v�w���s���ꂽ�Ƃ�����A���������Y��ȃs���Ŏ~�߂��Ă����B���̋L���œ]���ƕ����Ă��̎��̉���������i���v���o���B
���R�[�h��Ђň��`�}���̎�m���������́A�j�b�|�������̑��R�Ƃ�������̑啔���� �낭�ɘb�������Ă���Ȃ������ǂ̃f�B���N�^�[�B��ɁA�������₵���v�������Ă������̂����A���̒��ɂ��������䂳��̃f�X�N�͎��ɂƂ��ẴI�A�V�X�������B���䂳��̂Ƃ���֍s���ƕK���ׂ̐Ȃ��Ă���A�t�قȎ��̃v�����[�V�����b�Ɏ����X���Ă��ꂽ�B�����ɍ���Ƃ������p�̃��N�_�̊G���`���ꂽ�p�b�P�[�W�̉����A�L�����������Ɋ��߂Ă��ꂽ�B�����̂��납�炩�A���̈ꕞ���y���݂Ńj�b�|�������֍s���悤�ɂȂ��Ă����B���R�[�h�e�ЂƂ̋����ɂ��������Ď����Ɏ��M���������A����Ȃ��肰�Ȃ��D�������S�ɟ��݂��̂�����̂��Ƃ̂悤�Ɋo���Ă���B
���炭���Ď��̓��R�[�h�̐�`�̎d������Ґ��Ɉڂ�A�\�E�����͂��߂Ƃ���u���b�N�E�~���[�W�b�N�S�ʂ�S�����邱�ƂɂȂ����B������RCA�́g�}�C�P���E���C�R�t�h�Ƃ������l�A�[�`�X�g����{�Ŕ������邱�ƂɂȂ����B�����Ƃ��Ắi���͍������Ă��j��l���ۂ��������ȃT�E���h�ŁA�S���҂̎������ꍞ�ꖇ�������B���䂳��͂��̃A�[�`�X�g�̉���������������Ă�������A�����ɏ����ꂽ���͂́A���̃~���[�W�V�����̓�����I�m�ɂƂ炦�����ɐS�̂��������f���炵������������B�����炭���̃��R�[�h���V�����̂��̃~���[�W�A���̒��̈ꖇ�Ƃ��Ċ����̂��낤�B����͂����Ŏ��䂳��̐���������悤�ɂȂ�炵���B���̓����t�̃J�P�����E���ɍs���Ă݂������̂ł���B
����̒��ŁA�ӂƂ�������ȃj���[�X�őh��̓��̔M���S�B���̋��������Ⴋ���Ɏ����C�Ȃ��D�����A�����S�̒��Ŗ����ɐ��������Ă���̂��Ǝ�������
2013.07.10 (��) �����Ă�����ė���
���X�Ȃ��玞���o�̂͑������̂ł���B�͂����肵�Ȃ��~�J���I���A�����͎��[�ō��N�������߂��Ă��܂����B���̕����Ɩҏ��̉Ă��߂��Ă����̂������Ƃ����Ԃ����H�ȂǂƎv���̂��������͂����Ȃ��B�����������̂ق�̂ЂƎ��͗D�����̂����A���ꂩ�炪�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���N���Q�ꂵ����Ƃ̑ΐ���ǂ�����Ă��̂��̂��A������Â��C�����ł���B���ς�炸���N���l���ĕ������Ƃ���ۂɂ��Ă��鍡���A�G�i���J�̋S�q��_�̎Q���������Ă���ƁA�����傫�Ȓ������ł����B���ꂪ�Ȃ�ƃJ���X�A�Q�n�������B�A�Q�n����������傫���H�����z���ɓ�����ƁA���n�ɑN�₩�ȗΐF���L���L���ƋP�����ɔ��������ł���B�Q�N�قǑO�ɍ]�Óc�̐X�����ł������������Ƃ�����B�q������ɉƂ̒�ŏ��߂Č����̂������̏��Ζʂ������B�ȗ����Z����ɓߐ{�����łQ�x�ڂ̍ĉ�Ƃ����̌������Ȃ������̂����A���ꂪ���\�N���o�������̓s��ɂ��肰�Ȃ��G�X�Ɣ��ł���B���Ƃ��������ΐF�̉H�����q���q���ƕ����̂Ɍ��Ƃ�āA�v�킸�R�O���[�g���قǒǂ������Ă݂��B�������ȑ����������ˑR�̃I���W�̏o���ɁA�����Ɍ����Ă���Ƃ̃V�[�Y�[�ƃ��[�N�V���[�̏�������C�̌����A�Q�K�̃x�����_����ڂ����ς�����o���Ėi�����Ă�̂ł���܂ŁI�ƒf�O����B�������߂ĉ����Ɏ����ꂽ�l�Ƀt���t���Ƃ��܂悤�I���W�I�m���ɉ������ɈႢ�Ȃ��B
�~�J���I���ƊԂ��Ȃ��ċx�݂ɂȂ�B���N����ɒ����y���������ċx�݂��I����ĂQ�w�����n�܂���A�v���Ԃ�ɉ�F�B�ɉ��ƂȂ��C�p���������v���������̂����������B���̎��͐����ƒ��������o�����Ɗ����Ă����̂����A����S�O����T�O���U��̉�H��ĉ�Ȃǂ́A����������������肶��Ȃ����A�ȂǂƊ����Ă��܂��B�ǂ�ǂ�X�s�[�h���グ�Ă䂭���Ԃɔۉ��Ȃ��悹���Ă���g�ɂ́A���̑�����h��������N��ɂȂ��Ă����B
��T���A�������Ƒ��S�����������[�H���ɂ���Ȏ��Ԃ̘b���Ƒ��Ƃ��Ă�����A��N��l���̌ܕ��̈��\���̈���Ă���q���ƁA�\���̈��Z�\���̈���Ă���l�Ԃł́A���̗���͑S���Ⴄ������������̂��낤�Ƒ��q�►�����������Ă����B�l�����߂����Ă����l�ԁA�܂莄�̂��Ƃ����A��N�͂���܂Ő����Ă����l���̋͂��Z�\�̈�Ƃ������ɂȂ�B�������Ă��鎞�Ԃ͓���Ȃ̂����A���N�B�Ƃ͂��̈�N�Ƃ������Ԃ̑傫���ɑ���ʂ⎿�����o�I�Ɉ���Ă���B�����Ă����N��Ƃ���ƁA�N���ɂƂ��Ă̈�N�͓��R�ق�̏����ȕ��q�ɂȂ��Ă䂭�킯�ł���B
�Ƃ肠�������͌o���A���̉Ă����X�߂��Ă䂭�B���̒���̐F�Ƀg���{�ɒ��ɐ�̐��A�X�C�J�̐L���ɉ������A�g�ł��ۂ̊y�������ȏ����A�����ɏo��Ɖ߂����肵���������Ă̏u�Ԃ����X�Ŋ���o���B�����Ŋ����I�ȉĂ̏I���܂Ŏv���o���̂́A��ǂ݂���ɂ͑�������B���̗������������Ɗ̂ɐ����A�������[�����Ă̂��ƂȂ炢���̂����A�������g���q�ϓI�Ɍ���ƁA�ڑO�̏o���������ǂ�������A���傤�Ǎ����̃J���X�A�Q�n��ǂ��Ă������̐S���Ȃ������Ŏ��������Ă���̂ł́H�E�E����ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��̂����A������܂���̐l���ƊJ������B
2013.04.13 (�y) ���M
������ƑO�̘b�ɂȂ邪�A���M�̍L�����V���̈�ʂɍڂ��Ă����B����͏��w���p�̎q���T�C�Y�̉��M������o���ꂽ�Ƃ̂��Ƃ������B�����ē��R�̂悤�������܂ł͖��������悤�ł���B����܂ł̂��̂Ɣ�ׂ�ƂP�Z���`���قǒZ�����̂��������B��������ď��w�Z�ɏオ��Ƃ��ɁA��ɉ��M���Ă�������̂��v���o�����B�����̖��O�����̂Ђ炪�ȕ����ō���Ă�����̂ŁA���v������͂ƂĂ��ւ炵���A��ȕ̂悤�Ɏv���Ă������Ƃ��h��B������g���Ĉꐶ�������ɗ�݁A���ꂩ��n�܂�w�Z�����ɖ����]�������ς��ɂ����悤�Ƃ���e�S�B���̎��͕���A���̎��ɑ����Ȃ�Ƃ����҂��Ă���Ă����悤�������B�e�Ƃ������̂͗L����̂ŁA���m�Ȃ�q���̖����ɂ͖{�l���]�܂Ȃ��A����I����y�Ȃ������l���v��W�X�ƐS�ɕ`���Ă�����̂Ȃ̂��B�����̐l�X�Ɍ�����̂́A�ŏ�����Ƃ��ɒ��߂��悤�ȃ_���o���́A�q���v���e�S�̒��ɂ͔��o���Ȃ��B
���N�̂Q���ɓ����Ď����ݐЂ��Ă������R�[�h��Ђ̉��������l�����Ɖ�@��������B ���̈��݉�̏������ꂽ�ȂŒN�����M���������H�Ƃ����悤�ȁA���ɂƂ��Đ��ɒ��y���W�J�̘b���������Ă����B���W�I�A�e���r�ǂ̓d�g�}�̂̐�`�}�������������A�m�y�f�B���N�^�[�ɐ������Ă��ꂽ�A�����f���B�b�g�E�{�E�C��v���X���[�Ȃǂ�S�����Ă��������ے��̍��������A�ˑR���̖��O���Ă�ł��̎��̎��I�Ȃǂƌ����ăv�b�I�ƕ��o�����B��̐▽�I���ɔ��������b��̂ǐ^�Ɏ������o��H�ڂɂȂ����B�l�͂���Ȏ����s���`�Ƃ������̂��낤�B�����A���̂悤�ȕ֗��ȃp�\�R���̕��y���Ȃ��A�Ă��ʼn�c�̎��������M�ō���Ă������ゾ�����B���R���̈��M�͉�c�ɏo�Ȃ̑S���̖ڂɔ����ꂽ��ł���B����ł��l�ԍ��Ƃ�ƁA�����Ȃ��ǂ���������������g�ɕt���Ă��āA�̂̏��b�Ƃ��Ď�����Ƃ��g�ɕt���Ă���B�K�����̐�������`���āA�������̘b��͑��Ɉڂ��Ă��ꂽ�B�����������Ď��̈��M�͓����Ɠ��l�ς��Ȃ��B��ɍŏ��̓w�͂ōő�̌��ʂ�_���g�ɂƂ��āA���ʁA�B�M�ɂȂ�邱�Ƃ͓��R�]�ނׂ����ł͂Ȃ��B
�����ċG�߂͍��A��y�����ɂ������Ԃ����Ƃ̕ʂ�A���̌�A��p�����Ɋ��҂ƕs�������R�Ƃ���o�����x�ɂ���Ă���t���}���Ă���B�w�O�ŕ����ƘA�ꗧ���ē����A���w�Ɍ������q������������ɂ��A���̓��̕�ɓn���ꂽ�����̖��O����̉��M���ڂɕ�����ł���B���ꂩ��ǂ�ȏo����҂��Ă���̂��낤�A���҂����s���̂ق��������Ă����ƋL�����Ă���B���������F�B���ł���Ǝv���̂́A�{�l����ł͂Ȃ��e�����l�̋C�����ł���B�Ȃ��������G�߂��B���̈��M��V�ɂ����ɘl�тȂ���A�ߖځA�ߖڂŌ����Ă��ꂽ�e�̈�����v���o���B����ǂ����Ƃɉ������Ȃ����������̒��Ŗڂ����ƁA���܂݂�̎����̑��݉��l���A�v���U��ɖ�����L�ւƕς���Ă����B
2012.10.20 (�y) �ʂ��Ђ�
����Ɨ������Ȃ����Ǝv�����獡�x�͔������B���X�Ƒ������c�����炢���Ȃ�H�����ď��~�̊�������B����ȍ������N����Ƃ����̋V�����n�܂�B�܂��͏��ւ̗��܂����������}���ŎU���ɘA��čs���A���ꂪ�I���ƌ��։��̂U���قǂ̕n���ȑ��Ԃɐ������A�Ǝ�ȓ��{�̐����E�o�ς̑̎��ƍs���l�܂���̗l�ɒm�点��V�����L����B�ŋ߂����Ńk�J�~�\��s�˂�Ƃ����V��Ƃ���������B����܂ł̐l���ɂ͍l�����Ȃ��������ŁA��������Ă����̎p���h�鎖��������ɐV�N�Ȏv���ł���Ă���B�������݉��Œ��Ղ��炠����ɂ����ė��ނʂ��Ђ��ŁA�|�����̂ɓ�����Ƃ����S�s���܂ŐH�ׂ��������Ƃ���������������N�����Ă����B�ȑO�͉Ƃł�����Ă����̂������̊Ԃɂ��I����Ă��܂��A���O�̂ʂ��Ђ��͉ߋ��̉����o�����ɂȂ�������B���̉āA��������炽���Ղ�Ƃ����k�J�~�\�̒��ɍD���̐��֎q�����������̂����B���̂܂܃k�J�~�\���̂Ă�ɂ͂��������Ȃ��ƁA�������ɂʂ��Ђ������N���Ԃ�ɉ䂪�ƂōĔR�����B���Q�l�܂łɂ��̐��֎q�̎����͏I��������A���ŐH���Ă����̔炪�ʕ��ɂ��������肪������Ɏ|���B���̍ہA�������X�t����ƊÖ��������B
�ʂ����Ă߂鈤�H �Y�ꂩ�����̓��̓��{�̐S�����ދC���ƌ��������̂��낤���B�������n�߂�����ŒЂ��肷������A�܂�����������i���Ƃ����ڂ��Ȃ��̂ł͂��邪�A����͂���Ŕ��W�r��̎����Ɋ��҂���I���V����������B�d���݂̃k�J�������������A�ǂ�ȕ��ɐ邩�Ŗ��̟��݂��ݕ����Ⴄ�B�Ō�Ƀy�^�y�^�Ǝ�̕��Ōy���@���č��x�͑҂�Ƃł���B���̓��̉��x�A�u���ꏊ�A�Ђ��鎞�ԂŔ����ɖ����ω�����B���y�Ƃ����������̂悤�Ȃ��̂ƕt���������́A�҂�ƂƂ��Ă̊y����������B
�l�͂����ɕn�����Ƃ��T���ł��A�����čs�����߂ɂ͐��܂�Ă��玀�ʂ܂ŐH�ב�����B�j���[���[�N�̃A�b�p�[�C�[�X�g�ɏZ��ł��悤���ꍑ�̑哝�̂ł��낤�Ƃ��A���������ۂ��Ȉ݂ɍ����ȐH�ނ��M���E�M���E�ɋl�ߍ����������������̔\�͂��B���F�l�Ԃ͏����Ȉ݂���������ĂȂ��B����͍��̐��ł͂��肦�Ȃ��������Ȏ��ł���B
����ł������ɗ~�������A�����ł����Ɍ������y�����Ƃ������̂łȂ��A�������̔�����������H�ׂ悤�Ɠw�͂��邱�Ƃ͎��̖{�]���B�́A����ȉ̂��̂��ƃk�J�~�\������Ƃ悭�������B�������Ǝ��ɒǂ��A���т��݂邱�Ƃ��k�J�~�\�L���Ȃ�Ƃ�����ꂽ�B���̂ق����~�߂̗����Ȃ��k�J�ɓB�Ƃ��A�����ăJ�b�R�C�C���t�̌`�e�ɂ͎g���Ȃ��k�J�~�\�Ȃ̂����A���̎|���ݏo�����p�͐�傾�B
�j�Ƃ��āA���Ƃ��Ă̐��ԑ́A��ʓI�Ȓ�`��펯�Ƃ͕ЈӒn�������l�ԎЉ�����ɖ����̐��̏����ō��グ�����́B����͖����`�̍����ł���B�����h�邪�����́A���w�Z�ŊF�ƈႤ��������ƈْ[�Ƃ��Ĕ����ڂŌ���ꂽ�A���ɗǂ����Ă���B���낻�낱��܂ň�l�Ƃ��Ĕ|���Ă����������Ő����Ă݂悤�Ǝv���B���̎�Ɏc��k�J�~�\�̍��������b���͑��������ł���B�Љ�a��H�k�J�~�\�L����l�̃I���W���A�ւ荂����������{�j�������̊T�O�Ƃ���G�ɉĂ̌��Q�I �H����̒��Ƀp���p���b�Ɗ��ށB�K���Ƃ͐g�߂Ȃ��̂����C�Ȃ��E���W�߁A�����₩�Ɋ�������̂Ǝv���邨�N���B�͂�Ă����G�߂ɁA�ȑO��菭�X�͂�Ă����������d�ˍ��킹�Ă݂�B
2012.09.11 (��) �S�c��
����܂ł̐l���ōł��d��ŖZ���Ȃ��Ƃ̔�����A���݂Ƃ��������������Q�N�قǑ����Ă����B����ƈꑧ��������A�v���Ԃ�ɓ��{���̍������ɍs�����B�ǂ����Ă��Z��ł���n��̗�������r�܁A�V�h���ʂɍs�����������A���{���͂Ȃ��Ȃ��i���������đf�G�ȊX���B�ړI�͂��̕S�ݓX�ɏo�X���Ă���Ē��E�ɐ��A�̉����˂������B���ݒ��߂�ƁA��ƐV�N�ȓ��Ɖ��̎|�݂������ƌ����ɍL����A�����Y�ŏĂ��グ�����̂������肪�@�o��S�n�悭�ʂ蔲����B���ԑтŎ��ɂ͏��i������ۂɂȂ�̂����A�������̋����{�X�̏Ă��オ���҂ĂΕ�[�����B�������̂ЂƂ育�Ƃɏ������ƂĂ������g���炱�h�����n���̖��X���W�܂��̏ꏊ�ł���B�ɐ��O�̒����_���Ő�s�I�Ȓn���H�i�������ʔ������A��͂肱���̉������ɏ��a�̖��c�Ɛ������������Ă�����C�͘a�ށB��K�̃G���x�[�^�[�̉��̐Ε��̒��ɂ̓I�E���K�C�ނ̉������C�Ȃ��U�������̂����̃f�p�[�g�̗��j�������鏊�ł���B���Ȃ₩�ŗ�V�������G���x�[�^�[�K�[���ɓ�����A�����̍s���͂������F�̊i�q�̃G���x�[�^�[�ɏ�荞�ށB�����Ő́A�p�����������S�c��ȏo���������������Ƃ��ӂƎv���o�����B���{�ɂ͐S�c��Ƃ����A�����ɂ���딯�������悤�ȑf�G�Ȍ��t������B����܂Ő����Ă������ł�������x�Ƃ��o�����Ă����̂����A���̓x�ɑ召���܂��܂Ȃ��ߑ������Ă������t���B�N�����c�����ɂ͕s�N���Ȏv���o����������Ă�����̂����A���̂���͗c���Ȃ����ΓI�Ȏ����Ƃ��āA���̍������̍��Ƃ��������������̔]���ɂ�������ƍ���Ă���B
�����̍����͒肩�ł͂Ȃ����A�q������ɐl�O�ŗ܂������邱�Ƃ͐�ɒp���Ɗ����Ă��������������B�ŏ��Ɏ����Ă����G�X�Ƃ������O�̌��������A�m�炸�m�炸�Ɏ��̖ڂ���嗱�̗܂����ڂꗎ�����B�����c�ꂪ���āg���ƃG�X�Ƃ̗܂̕ʂ�h�ƕ\�����Ă����B���̎��͋������̃��b�e����\���Ă��܂����Ƃ����A���N�̖��ɏ��C�ȋL���������c�����B�ȗ��A�s���Ŗ��l�Ȍ��܂̎��ł����A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����܂𗬂����ɐ����ė����B���̐���̉ʂĂ̍��̎����A���h�����ςĂ��āA�����Ō��Ă���P���ȓz���������邼�I�Ƃ�����҂̎v�f�ʂ�A�܂�܂ƃn�}�b�e���������Ă��܂��Ƃ����w���e�R�Ȃ��₶�ɂȂ�̂�����A�l���͂킩��Ȃ��B
 �܂������Ȃ��Ō����ɐ����Ă����lj��̂��̓��A�������̉���Ŏq���������ۂɏ悹��Ƃ������C�x���g���������B�������ۂ͗���ɐ�������̂ł͍ő�̐����ł���B�����ł����ĉ𖾂͂��Ȃ��̂����A�ǂ�����Ă��̑傫�ȓz������ɏグ���̂��́A���̂Ƃ��Ă����̉i���̓�ł���B���̃C�x���g�ɂ����Ɛe���\�����̂��낤�A�吨�̐l������钆�Ŏ��ƌZ�����̏ۂɏ�鏇�Ԃ�����ė����B���͂ǂ����Ă����̑��̔w���ɏ�邱�Ƃ��o���Ȃ������B���낤�����I���O�������ʑO�ŁA�|���ƌ����đ勃���������̂ł���B���C��{�����������A�ǂ����Ă���ȋC�����ɂȂ����̂��͂��܂��ɂ킩��Ȃ��ł���̂����A�����炭�A���̑��̔w�̑傫���ƌ����q�̑����Ɉ��|���ꂽ�̂��Ǝv���B
�܂������Ȃ��Ō����ɐ����Ă����lj��̂��̓��A�������̉���Ŏq���������ۂɏ悹��Ƃ������C�x���g���������B�������ۂ͗���ɐ�������̂ł͍ő�̐����ł���B�����ł����ĉ𖾂͂��Ȃ��̂����A�ǂ�����Ă��̑傫�ȓz������ɏグ���̂��́A���̂Ƃ��Ă����̉i���̓�ł���B���̃C�x���g�ɂ����Ɛe���\�����̂��낤�A�吨�̐l������钆�Ŏ��ƌZ�����̏ۂɏ�鏇�Ԃ�����ė����B���͂ǂ����Ă����̑��̔w���ɏ�邱�Ƃ��o���Ȃ������B���낤�����I���O�������ʑO�ŁA�|���ƌ����đ勃���������̂ł���B���C��{�����������A�ǂ����Ă���ȋC�����ɂȂ����̂��͂��܂��ɂ킩��Ȃ��ł���̂����A�����炭�A���̑��̔w�̑傫���ƌ����q�̑����Ɉ��|���ꂽ�̂��Ǝv���B�ꐶ�Ɉ�x�̌��ł��邩�ۂ��̗L������߉�Ȑe�S�B���̎������̏�ɂ�����A�q�������ɂ����Ƃ����������ɈႢ�Ȃ��B����Ȏ��͎�����������Ă��A�Ȃ��߂��Ă��K���Ƃ��Ă��̏ۂɏ��Ȃ������B�ۂ̔w�̕z�ɕ`���ꂽ�A�������̍��Ƃ������ő傫�Ȉꕶ�����܂ş��B�����ċ����Ă��邵�傤����������u���āA�������Ȃ��Z���Ƃ�ŏۂɏ�����B�����炭���̌Z�̔N�����琄������ƁA���͂R���S�̍��̎��ł���B
���ł��S�c��Ƃ������t������قǎ�������ʂɂ͂��������o����͖����B�������ł�������Ηǂ������A����������ǂ��Ȃ������낤���H�Ƃ����Y�ޓ��X�̌J��Ԃ����l���ł���B����͍ł��g�߂ȃ��C�o���������Z�Ƃ������N�ɁA�剉�j�D�܂��������c�����̂��Ƃł���B
2012.06.20 (��) ���V�O�ɂ�
 �����Ė��邢�ȂǂƂ͌����Ȃ����̎Љ�A���܂ɂ͔n���ɂȂ�Ȃ��Ƃ܂�Ȃ��Ǝv���Ă���B���͂����n���Ȃ̂����A�O�ɉƂ���X�J�C�c���[�����Ă����烈�V�b�I�������̉��܂ōs���Ă݂悤�Ƃ������ɂȂ����B����͈�N���قǑO�̂��̂ЂƂ育�Ƃɏ������̂����A�����́A�����z���Ă����䂪�Ƃ̕����������˂����ォ��A�r�܃T���V���C�������Ă���ƁA����̃��V�b�I���o���B�����炩���������̂�����A�����炩���������������͂����Ə�X�v���Ă����B�Ƃɂ�����x�͂������ɏ���āA�V��̂悤�ȏ����玩���̉Ƃ�T���Ă݂��������B���傤�Ǘׂ̓��}�n���Y�ɁA�C�̓����ɓ\��v��T���ɍs�����Ǝv���Ă������Ƃ�����A�v�����������g���A���s�Ɉڂ����ɂ����B
�����Ė��邢�ȂǂƂ͌����Ȃ����̎Љ�A���܂ɂ͔n���ɂȂ�Ȃ��Ƃ܂�Ȃ��Ǝv���Ă���B���͂����n���Ȃ̂����A�O�ɉƂ���X�J�C�c���[�����Ă����烈�V�b�I�������̉��܂ōs���Ă݂悤�Ƃ������ɂȂ����B����͈�N���قǑO�̂��̂ЂƂ育�Ƃɏ������̂����A�����́A�����z���Ă����䂪�Ƃ̕����������˂����ォ��A�r�܃T���V���C�������Ă���ƁA����̃��V�b�I���o���B�����炩���������̂�����A�����炩���������������͂����Ə�X�v���Ă����B�Ƃɂ�����x�͂������ɏ���āA�V��̂悤�ȏ����玩���̉Ƃ�T���Ă݂��������B���傤�Ǘׂ̓��}�n���Y�ɁA�C�̓����ɓ\��v��T���ɍs�����Ǝv���Ă������Ƃ�����A�v�����������g���A���s�Ɉڂ����ɂ����B�����̑������Ŗ�Q�O�����A�v�������ӊO�ɑ����T���V���C���r���ɓ����B��K�̎�q����ɓW�]��͂���܂����H�ƕ����Ă݂��B�n����K����G���x�[�^�[�ŏオ��܂��Ƃ̎��B����ɑ��������͂�����܂����H�ƕ�����"���R�ł�"�Ɨ₽���ꌾ�B���������Ⴄ�����������邾�낤�ɂƋC���œ���B�Ƃɂ����A�n������G���x�[�^�[�ň�C�ɂU�O�K�̓W�]��܂ŏオ���ė����͂U�Q�O�~�B�C���͂Q�T�P���[�g�����������B�������ɒr�ܐ���̍������ւ��Ă���̂ŁA�ߕӂɂ͂���ɓK���������Ȃ����X���Ă���B
�U�O�K�ɒ����Ǝ���l�ŋ����قǃV���ƐÂ܂�Ԃ��Ă���B"���܂␢�E�Ɍւ�X�J�C�c���[������A����ȏ��ł�����z�̓I�����炢���I"�ƙꂭ�B�Ƃ肠����������k�A�r�������肷�鎖�ɂ����B����Ɛl�̎���G�������ς��������Ă���ꏊ�ɂ���Ă����B�����Ƀ|�c���ƃv���̎���G�t�炵���l�������݂Ȃ��ɍ����Ă����B�ǂ���玄��l�̂U�O�K�ł͂Ȃ������悤�ŁA���S�����N���Ă����B
����G�͉����́A���ɘA���ꂽ���{���̃f�p�[�g�ŊG�M�ɕ`���Ă���������Ƃ�����B�c�����͐l��{�p�����������łƂĂ����������̂����A���͂��ɂȂ��M�S�Ɋ��߂��B������N���A����A�H���ōD���̃`���R���[�g�p�t�F�������ɏ������Ă��܂����̂����A�������f���H�ɂȂ�ƁA�ʂ肷����̑����̐l�B�������~�߁A���̊�ƊG�`���̃L�����o�X�Ȃ�ʊG�M�����݂Ɍ��Ĕ[����ŋ����čs���B�����͍��̃f�p�[�g�̏��Ȃ��Ƃ��T�{�͋q���������ł���B����͕����ʂ�炩����o��v���������B����ȉ����������p�������������v���o���A����Ȗ��V�O�̃e�b�y���őh��B
��������Ăѕ����o���A���悢��r���̓쐼�̉䂪�Ƃ̕��p�ɍ����|����B��͂萊���Ă�������ł͂悭�����Ȃ��B�����t���̑o�ዾ������A���̉��ɏ�����Ă�����������̎菇�ɏ]���B���Ɏ��t���Ă��銊�Ԃ̂悤�ȕ����Q�O�����ʼnƏ����Ă���B���Ɍ������Ɣ��d�������ꂪ�v���̂ق��d���A���ꂩ��P�O�O�~������B�Ȃ�ł���ȑP�ǂȎs���H�������ɔ��d�����̂ɋ����v��̂��낤���A����͌����̃{�b�^�N�����B�Ƃ̕��p�Ɍ��������Ĕ`���Ă݂�ƁA�ŋ߃I�[�v�������ڔ��w�O�ɂ���a�َq���̊��i���̊Ŕ��傫���f��B��������������Ƃ̕��ɂ��炵�čs���ƌ������I�����Ȕ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����̉Ƃł���B
�����̃��C�u�f���Ȃ̂ŁA�v�킸�g�тʼn䂪�Ƃɓd�b�����Ă݂��B����ƁA�N���Ă���̂����Ȃ��̂��A�閾���̃K�X����A�z������Ȃ̐��A�f�������������ĉ���ɏo�Ă��炤�B�₪�ăR�[�h���X�t�H���Ў�ɉƂ̊K�i���オ��ޏ��̎p���f���Ă����B�����T���V���C���̑傫�ȃr���̒��̉����ɂ���̂��S�R�������Ȃ��悤�����A������͑S�Ă����ʂ��B"���A������グ�Ă��邾��"�ȂǂƏ����ւ����悤�ɋ������Ă���ׂ鎄�́A���@�̖]�����������A�V��t���牺�E�������낵�Ă���悤�Ȃ����C���ł���B���炭���̌i�F���y����A���x�͂��̐�Ŏ����̐��܂ꂽ���̐V�����R�s�[�ŏo�Ă���ƌ������̋@�ɏo���킷�B�q���̐���"�ʔ������I"�ƌJ��Ԃ��@�B���Ăт�����̂ŁA������o���Ă��܂��B�����ǂ�ȓ��ɐ��܂ꂽ�̂���m��̂ɂS�O�O�~���������B
 ����A���̎���G���`���ꂽ�G�M�������Ƃ��̂܂܂ɂȂ��Ă����_���{�[������T���o�����B�Ȃ�Ƃ��Â����^�̏��N�ŁA���ɂ͏��a�R�S�N�P�P���R���ƌ������t�Ǝ��̖��O��������Ă����B�����A�������܂ꂽ���̐V���ɂ́A�����{�͖��卑�ƌQ�֕��A�A�g���[�}���哝�̈�ʋ������\�A���Y��`�\�A�̉A�d���Ȃǂƌ������A�����J�ւ̌X�|�ƂQ�卑�̗�펞��̎n�܂肪�F�Z���o�Ă���B�{���I�ɃA�����J�ւ̏]���́A���Ƃ��܂�ς���Ă͂��Ȃ��悤���B
����A���̎���G���`���ꂽ�G�M�������Ƃ��̂܂܂ɂȂ��Ă����_���{�[������T���o�����B�Ȃ�Ƃ��Â����^�̏��N�ŁA���ɂ͏��a�R�S�N�P�P���R���ƌ������t�Ǝ��̖��O��������Ă����B�����A�������܂ꂽ���̐V���ɂ́A�����{�͖��卑�ƌQ�֕��A�A�g���[�}���哝�̈�ʋ������\�A���Y��`�\�A�̉A�d���Ȃǂƌ������A�����J�ւ̌X�|�ƂQ�卑�̗�펞��̎n�܂肪�F�Z���o�Ă���B�{���I�ɃA�����J�ւ̏]���́A���Ƃ��܂�ς���Ă͂��Ȃ��悤���B���̉Ƃ���Ăт��̃T���V���C�������Ă���ƁA���̓��̓W�]��̈ʒu���킩��B�������������͂������ɉ������ɍs�����̂��A�ŏ��̖ړI��v���Ȃǂ͉����_�̂悤�ɏ��������Ă���B���F�䂪�l���͋C�܂���ɐ������̃I���V�������{�ŁA���̌{�͍��X�Ɖ߂��Ă䂭�A���ԂƂ������̌����č~��鎖���o���Ȃ���Ԃɏ悹���Ă���B�E�����������]�Ȑ܁A�������������Ė��m�Ȃ鐬��s���̒����Ă���B
2012.06.02 (�y) �a�̌���b
"���ނقǂɐ����قǂɏ��̗ւ��L����"���������X�E�F�[�f�����痈���A���g�̃N���V�b�N�E���H�[�J���X�g�A�}���A�E�t�H�V���X�g���[���̃R���T�[�g�֍s�����̂��n�܂肾�����B�a�̌��͏a�J����c���s�s���ő�������z���ē�w�قǂ̏��ɂ���B���ɂƂ��ď��߂č~�肽�w�������B�����͋����قǐl�������A�g�ˎ��◧��Ƃ������ł�����悤�ȑ�^�̉w�Ɠ����悤�ȕ�������B������������ĂU���قǂɐ����w�����y��w������A���̍u���ł̃R���T�[�g�������B�j���s�A�j�X�g�̃}�b�e�B�Ɠ�l�����̃R���T�[�g�����A���̔��������ƕ\���̖͂L���������\�����B
���̋A��ɂ�����K����ƃI���W��l�ň���ł����̂����A���̌�S�l�̏����w�������A���R�ɂ��F���߂Ă������͖�����Ђ̓�����Ƃ����`�ɂȂ����B�K�R�I�ɋL����b��͂��̍��Ƀt���b�V���o�b�N����B����ȏꍇ�A�������̃l�^�͂�͂肠�̐l�͍��H�I�Șb�ɂ͂Ȃ�̂����A����͂���Ŗʔ����B�����듯�����̔т�H�����̂ɍ��͑S�����M�s�ʂɂȂ��Ă��܂��Ă���̂����A���̌�̈ӊO�Ȑl���W�J�ɋ�������鎖������B�Ⴆ�Ύ��̕����������l���Z�{�Ń��[������������Ă���Ƃ��A���A����l�͗������ĉ������̓��ɓn���l�Ŕ_�Ƃ�����Ă���Ƃ��A����Șb�Ō��\����オ�����B
����[���Ȃ�ƁA�d���A��̋q�����荡�܂ł�����Ă����X���}�ɐÂ��ɂȂ�B���悢��b�͉����ɓ���A��l�̃X�^�[�H����R�r���𗁂т鎖�ɂȂ����B���R��l�͎��̍����ł����ɂ͂��Ȃ��B��l�̓i���g�����Ă�W���ł���B���܂��܂��̖�́A�ނ̎��ꕗ�ς������ɘb�肪�W�������B�a�J����{�v����オ�����R�ʂ�̍����ɁA�u�ꍩ���Ƃ����V�܂�����B�����͂�������̏W�ɕK�p�ȖԂ⒍�ˊ�A���̑��O�b�Y�����邱�ƂȂ���A���ۂɒ����������̕W�{�������Ă���B
���鎞�A������W�����ƂĂ��Ȃ��傫�ȃo�b�^�̕W�{���Ă����ƁA��Ђő呛���ɂȂ����B�p�^�p�^�Ƌ���т܂�����肷���̃o�b�^�ł���B�Ȃɂ���ΐF�ő̒��P�O�Z���`�z���̋H�Ɍ���啨�������Ƃ����B�܂����̏��_�Ԍ��Ă��܂����̂�TA���������BW���ɂƂ��ĉ����ł�����݂���Ȃ��A�������낤�ɕ����X�s�[�J�[�ƈٖ�������TA���Ɍ���ꂽ�̂ł���B�����ɂ��C�����������ɑ吺�Ō��̂ŁA�b�͒n���̗����ɂ܂œ͂������Ȑ����ōL�܂����B
�����̎��͂��̎��M���^�ŕ����Ă����̂����A���̖�̇T��̘b�ɂ��ƁA���̘b�ɔ��Ђ��w�т�܂ŕt���Ă����B�u�ꍩ���̂��X�̐l���V���������W�{������ƁA�܂��X���ɕ��ԑO��W����߂܂���"�V���m�̐����̂�����܂�����"�ƃj�R�j�R��ŕ���Ƃ����̂��B������Ƃ��Ă����̓��ӗl�ւ̃T�[�r�X�ł���B����ɂ͑S��������ɂȂ����B��Ђł͂����̕ς��ҁi����I�j���u�ꍩ���X�ł�VIP�A�Ƃ�����̊�����j�Ƃ����킯�ł���B�����ēs���ߍx�ɂ���P�[�u���J�[�ŏ㉺����X�𗘗p�����}���V�����ɏZ�݁A��ɑS�g���s���߂̈ߑ��B���瓖�Ԃ̎��́A���܂��čŌ�ɖ�̂킩��Ȃ����P�₱�Ƃ킴���p��Ō����Ă̂����B����W���A���܂ł��l���y���܂�����O�ꂽ�\�͂����j�ł���B
���̓��̂�����l�̃X�^�[��TS���ł���B����𑲋Ƃ��A�L���ȑ啨�����Ƃ̉ƌn�ɐ��܂ꂽ�l�����́A��X�̂������R�[�h�ƊE�Ȃǂɗ����̂��낤�Ƃ����^�₪�A���ꂩ�牽�\�N���o�������̖�ɍĔR�����B����������Ɣނ͑��l�̂悤�ȏ㏸�u���͂Ȃ��A�㗬�K���ɂ��肪���ȁA�����ĉ��~���D�����l�������̂ł́H�ȂǂƂ����A�傫�Ȃ����b�ȉ������A�r�[���̖A�Ƌ��ɕ����яオ��B��{�I�ɖ����Ȑl���������A�����ɂ���M��H���A"�ނ̖{���̗D�����Ɉ�ꂽ�ꌾ���A���ł��S�Ɏc���Ă���"�Ƃ����B
���̎��A�����ނ̗D��������������o�������v���o�����B��ЂŒ��H�ٓ̕����J����Ɣ��������Ă��Ȃ������B���̂悤�ɃR���r�j���ٓ������Ȃ�����ł���B�������ꏊ�͋C��������h�̃s�A�U�r���B�ǂ����悤�Ɠr���ɂ���Ă���ƁA���̗l�q�����������ł����ƌ��Ă���TS�����킴�킴���̏��ɂ���ė��āA�C�L�i�������̊��蔢�̈�{���ɐ܂�"������g���Ȃ���"�Ɠn���Ă��ꂽ�B
 ���݂��ɂ��炭�Z�����ŕٓ���H�ׂ��̂����A���̎��̗L��͐��U�Y��鎖�͂Ȃ��B�ꌩ�l�Ԍ����̂悤�Ɍ����Ă��܂��s��p��TS���B�����͂��̐l�́A���̎��̗D�����ɂT�t�ڂ̊��t�I�ƂȂ�B
���݂��ɂ��炭�Z�����ŕٓ���H�ׂ��̂����A���̎��̗L��͐��U�Y��鎖�͂Ȃ��B�ꌩ�l�Ԍ����̂悤�Ɍ����Ă��܂��s��p��TS���B�����͂��̐l�́A���̎��̗D�����ɂT�t�ڂ̊��t�I�ƂȂ�B�C���t���ƏI�d�߂��ŁA�X�̋q���قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B���̋A�蓹�A�����߂��̏��a���g���Y���X�̑O�ő����~�߂��ق됌�������̂U�l�́A���������̃z�������Ă��̂ǂ��������������ɕ�܂ꂽ�B�߂����肵���X�A������ʂ����D���������j�[�N�Ȑl�����Ɏv����y�����ЂƎ��B�a�̌��̊y����������ꂽ����l�Ɋ��ӁB
2012.05.13 (��) �ڔ����i
�ꌩ�͂ꂽ�悤�ȍ��̎}�ɂۂ��ۂ����Q�����A���ꂪ���̊Ԃɂ��c���ł��̐�[�ɔ��F���`���Ă���B���ꂪ�ق�̂���F�ɂȂ��Ă��瑁�炫�A�x�炫�̎}�����Ȃ��珙�X�ɖ��J���}���A�Ԑ��ᕑ������������̂͐�����̂悤���B�Ԃ��Ȃ��Y��ȐԐF����[�̉��ΐF�̗t���A���͂ƂĂ��N�₩�ȗɕς���Ă���B�����ڔ��ɉz���ė��ĂQ�������܂�o�����B�Ƃ������o���Ă��܂����Ƃ����ق����I�m�����m��Ȃ��B�ו��̐����ɏI������X�A���̌o�̂͑������̂ł���B�N���낤���H�ȑO���撣��C�͂��N���Ȃ��B ����ł����������̓y�n������ӎ���킩���Ă����B���̉Ƃ̑O���E�Ɏb���s���ƁA�Ԃ��Ȃ������r�ܐ��̓��ɂȂ�B�����n��ƍ��̏d�v�������ɂȂ��Ă��鎩�R�w���̖����ق�����B�����Ȑl�����������Ŋw�炵���B�t�����N�E���C�h�E���C�g�v�ɂ�邱�̌����́A���̌��z�ł͏o���Ȃ��Ȃ��������B�ނ͓���J�̒鍑�z�e���̐v�ł��L���ł͂��邪�A���Ƃ����Ă��č��s�b�c�o�[�O�̃G�h�K�[�E�J�E�t�}���@�̗����������E�I�ɒm���Ă���B��ʏZ��ɂ����Ă����͂������ɖڂ��s���B�ؘg�ŏ��X�Âڂ������̂ł��A���̎���̂悤�ɉ��I�Ȃ��͖̂����A�吳�A���a�̎���̃i���Ƃ������ʋ��D�ɂ��������o���h��B���̎��ォ�獡���Ɏ���܂ŁA�N���ǂ�Ȏv���ŊO�߁A�܂�������̘R��镔���ɂ͂ǂ�Ȑl�ԃh���}���������̂��낤�A�ȂǂƎv����y���Ă݂�B���������s���ƌ�������W��̓��ɂԂ����Ă��܂��A�����ɒ��ɂ͓����Ă��Ȃ��̂����A���x�͋Ă������ȕ����ɂł����������݂ɍs�����Ǝv���Ă���B
����ł����������̓y�n������ӎ���킩���Ă����B���̉Ƃ̑O���E�Ɏb���s���ƁA�Ԃ��Ȃ������r�ܐ��̓��ɂȂ�B�����n��ƍ��̏d�v�������ɂȂ��Ă��鎩�R�w���̖����ق�����B�����Ȑl�����������Ŋw�炵���B�t�����N�E���C�h�E���C�g�v�ɂ�邱�̌����́A���̌��z�ł͏o���Ȃ��Ȃ��������B�ނ͓���J�̒鍑�z�e���̐v�ł��L���ł͂��邪�A���Ƃ����Ă��č��s�b�c�o�[�O�̃G�h�K�[�E�J�E�t�}���@�̗����������E�I�ɒm���Ă���B��ʏZ��ɂ����Ă����͂������ɖڂ��s���B�ؘg�ŏ��X�Âڂ������̂ł��A���̎���̂悤�ɉ��I�Ȃ��͖̂����A�吳�A���a�̎���̃i���Ƃ������ʋ��D�ɂ��������o���h��B���̎��ォ�獡���Ɏ���܂ŁA�N���ǂ�Ȏv���ŊO�߁A�܂�������̘R��镔���ɂ͂ǂ�Ȑl�ԃh���}���������̂��낤�A�ȂǂƎv����y���Ă݂�B���������s���ƌ�������W��̓��ɂԂ����Ă��܂��A�����ɒ��ɂ͓����Ă��Ȃ��̂����A���x�͋Ă������ȕ����ɂł����������݂ɍs�����Ǝv���Ă���B��������Ƃɖ߂�r���ɖڔ��뉀�Ƃ������{�뉀������A���������w�⒃��ȂǂŖK���l�����Ȃ��Ȃ��B���j�͂��������͂Ȃ��悤�����A�����̑��Ǝ��̓��͂��ߏ��ł���y�Ȏ�������A�L�O�ɂ����Ŏʐ^���B�����B�w�Z���������Ƃ������Ŕޏ����F�l�������ĂсA���̖������̎B�e�܂ł��鎖�ɂȂ��Ă��܂��A���J�����}���͗�⊾��~�����B������ꐶ�Ɉ�x�̐���p�A�����Ȃ���̂��������ȋC�����ł͎B��Ȃ��B���ꂼ�ꖳ���ɎЉ�l�ɂȂꂽ�Ƃ̂��Ƃň���S�����̂����A10���قǑO�ɂ��̎B�e����ɂȂ����ڔ��뉀�ŃJ���K���̃q�i���z�����ƕ������B
 �����A�Ăі��J�����}���ɐ��肷�܂��B�e���Ă݂��B���̐e�q�����A�������낻��r����ł͂Ȃ����ɂ������Ĉ��ɂȂ��ĕ����o���悤�ł���B�����������Ƃ�����ꐶ������ĂĂ���꒹�̎p�ɂق��ƈꑧ���B�m�������̑��Ƃ̓��A���̊�̏�ɂ͋T�������b�����������Ă����̂����A�J���K���e�q�̈���ɉ��������̂��A����Ƃ����̒�����D��������������Ă���̂��낤���A���������̌e���̏�ł�����Ў��ł������Ă���Ă���B����ȏ���ȓ����X�g�[���[��S�̒��ɕ`���Ă݂�B�����̌o�ς����ׂƂ͂����A�������̓����������̂��̂��Ǝ咣�������l�Ԃ������߂����v����B���̃J���K���̕�͎����̔��œ��A�����A�����Ŏq��������l�ڂⒼ�˓����������Ă��鎖�����邻�����B
�����A�Ăі��J�����}���ɐ��肷�܂��B�e���Ă݂��B���̐e�q�����A�������낻��r����ł͂Ȃ����ɂ������Ĉ��ɂȂ��ĕ����o���悤�ł���B�����������Ƃ�����ꐶ������ĂĂ���꒹�̎p�ɂق��ƈꑧ���B�m�������̑��Ƃ̓��A���̊�̏�ɂ͋T�������b�����������Ă����̂����A�J���K���e�q�̈���ɉ��������̂��A����Ƃ����̒�����D��������������Ă���̂��낤���A���������̌e���̏�ł�����Ў��ł������Ă���Ă���B����ȏ���ȓ����X�g�[���[��S�̒��ɕ`���Ă݂�B�����̌o�ς����ׂƂ͂����A�������̓����������̂��̂��Ǝ咣�������l�Ԃ������߂����v����B���̃J���K���̕�͎����̔��œ��A�����A�����Ŏq��������l�ڂⒼ�˓����������Ă��鎖�����邻�����B�����͕�̓��B���̕ꂪ�S���Ȃ��Ă���20�N�ɂ��Ȃ�̂����A�������ĐS�̒��ł��̑��݂�����鎖�͂Ȃ��B���j�̍ȂƂ��ĉ����Ɛe�ʒ����W�܂鎖�����������䂪�Ƃ́A��̎���̗������l���ŐH�ׂ鎖�������ŁA���̋�J�͍��v���Α�ς������Ǝv���B���̎d������`���āA��X���܂Ń^�C�v���C�^�[��ł��Ă������̉����Y��鎖�͂Ȃ��B������Ƒ傫�ڂ���������A���̗m���Ȃǂ͑���Z�����ꂪ����Ă��ꂽ�B���̍��A�܂����{�ɂ̓{�^���_�E���̃V���c�����i�Ƃ��đ��݂��Ă��Ȃ���������A�f��̒��̃g���C�E�h�i�q���[�����Ă����{�^���_�E���̃V���c���~�����āA�݂̐�Ƀ{�^����t���Ă�����������������B���ӋC�ȏ��w���̃j�Z�̃{�^���_�E���E�V���c�ł���B���̈���͈̑�ł��葼�ɑ������̂������B�����ǂ�ʼn������Ă��邨��l���������̑A�܂������Z�����ɂ́A�o�������̐e�F�s�������߂������ł���B
2012.04.28 (�y) �w�ԍ��Q�S
�v���싅���J�����������ꌎ���܂肪�o�߂����B��͂莄�͍ŋ߂̃T�b�J�[���ʔ����Ƃ͎v���̂����A���N���ォ�炸���Ƒ��싅�Ŋ���e��������̕������g�߂Ɋ�����B�q���̍��A�������Ȃ�ƉƂ̗��̌����ςŕ��ƃL���b�`�{�[�����������̂������B�����̏ꍇ�A�����L���b�`���[���������̂����A�������������̓�����{�[���͈ӊO�ɑ����A���̃V���[���ƚX�鉹�͍��ł����̉������Ɏc���Ă���B����Ȗ싅���N���������ɖY����Ȃ������������B ���S���C�I���Y�i���E�������C�I���Y�j�̍��̒�h���A��y�����ꂩ������ĂT���قǂ̏t�����ɂ���������̎��B���i�͓����ɂ���Ă����w�������̏C�w���s�̏h�ɂɂ��Ȃ��Ă��āA���̖��͑单���Ƃ������B���a�����z�̂Ȃ��Ȃ���̂��闷�ق������ƋL�����Ă���B���{�V���[�Y�Ő��S���C�I���Y���D�������P�X�T�W�N�̂��Ƃ������B���S�����l�ɂR�A�s������ɂS�A���ŗD�������A���ł����p�����M��V���[�Y�ł���B�D���ē�"�O���}�W�b�N"�Ƃ������t���{���ɐZ�������N�ł�����B�ނ͕��Ƒ�w����̓����ŁA�K�R�I�ɂ킪�Ƃ͎O������������`�[�����������鎖�ɂȂ��Ă����B���������̔N�A�`�[���ɂ�"�_�l�A���l�A����l"�ƌ���ꂽ�^�t�ȓS�r����܂ł����B�}�W�V�����̊ēƐ_�l�ƌĂꂽ����A�܂��ɋS�ɋ��_�̃R���{�ł���B��Ղ͋N����ׂ����ċN�������̂�������Ȃ��B
���S���C�I���Y�i���E�������C�I���Y�j�̍��̒�h���A��y�����ꂩ������ĂT���قǂ̏t�����ɂ���������̎��B���i�͓����ɂ���Ă����w�������̏C�w���s�̏h�ɂɂ��Ȃ��Ă��āA���̖��͑单���Ƃ������B���a�����z�̂Ȃ��Ȃ���̂��闷�ق������ƋL�����Ă���B���{�V���[�Y�Ő��S���C�I���Y���D�������P�X�T�W�N�̂��Ƃ������B���S�����l�ɂR�A�s������ɂS�A���ŗD�������A���ł����p�����M��V���[�Y�ł���B�D���ē�"�O���}�W�b�N"�Ƃ������t���{���ɐZ�������N�ł�����B�ނ͕��Ƒ�w����̓����ŁA�K�R�I�ɂ킪�Ƃ͎O������������`�[�����������鎖�ɂȂ��Ă����B���������̔N�A�`�[���ɂ�"�_�l�A���l�A����l"�ƌ���ꂽ�^�t�ȓS�r����܂ł����B�}�W�V�����̊ēƐ_�l�ƌĂꂽ����A�܂��ɋS�ɋ��_�̃R���{�ł���B��Ղ͋N����ׂ����ċN�������̂�������Ȃ��B���鎞�A�����N�ゾ�����ߏ��̎q�������ƁA���̏h�ɂ֑I�肽���̃T�C����Ⴂ�ɍs�����Ƃ����b���ɂȂ����B�������w�Z�̂Q�N�����������́A�{���ɂ���Ȏ����Ƃ̋߂��Ŏ�������̂��̂��A�T�C���������e�ɔ��M���^�Ŕޓ��ɕt���čs�����̂������B���̓��̒��A�单���̌��։��ɑI�肽���̃w�����b�g��������ɒu����Ă����B����̑I�肽��������Ă���w�����b�g�I�ǂ�����Ƃ����Ԃ��t���Ă��āA����Ȃ��Y��Ȃ��̂ł͂Ȃ������̂����A�v�킸��ŐG��Ă݂��B�W�[���Ɗ��������ݓn��B�����"�R���I�R���I�R���`�b�ƁI"�Ƒ傫�Ȑ�������ɋ������B�r�b�N�����Ă��̐��̕�������ƁA�Q�����p�ŕЎ�Ƀo�i�i���������A���̖L�c������肪�����Ƃ�������ɂ�ł����B�����o�i�i�͎��ɂƂ��ăA�C�h���̂悤�Ȃ��̂ŁA�����Ȕ��������ʕ��������B�a�C�̎��ɂ͕ꂪ���z�Ɏv�����̂��H�o�i�i���H�ׂ�ꂽ�B�w�Z�͋x�߂邵�A�D���͂��邵�ł܂�a�C�ɂȂ�̂������ł͂Ȃ������B����������Ŏ҂̃X�^�[�I��ɓ{��ꂽ�V���b�N�͑����Ȃ��̂������B
�ӋC�������Ă���Ԃ��Ȃ��A���x�͔w�L�p�̎O���ē�����Ă����B�N�����}�ɗ����炵���̂����}���ł���炵���A�O�ő҂��Ă���Ɨ��ق̐l�ɓ`���Ă����B���̑҂��l�ł���A��Ɋē̒����ƌ��������������I�肪���R�Ɠo�ꂵ���B������O�����ނ̃g���[�h�}�[�N�̉������̃w�����b�g�͔���Ă��Ȃ��B���C���璼�ڏo�Ă����炵���A�^�I�������Ɍ��������܂܁A��͑f���Ƀ��C�V���c�ꖇ�Ƃ��������̎p�������B����Ɠd���Ή̑��Ƃ��H�������t�����ɃY�o�Y�o�b�ƁI�傫�ȉ������ĂȂ���Y�{��������āA�ē̌��ǂ��悤�ɔ�яo���čs�����B���Ɍ����m�[�p���ł���B���X�F�͈Ⴄ���A�ނ͍��Ō������C�I���Y�̃I�J�����N�E�����I��̂悤�ȑ��݂������B�����I�肪���a�䋅��̑�f�i���E��t���b�e�}���[���Y�j��ŕ���������̃z�[�������́A�j��Œ��Ƃ����`���ɂ��Ȃ��Ă���B���ꂩ��V�l�ł܂��p�����������ɂ��Ă�����ˑI��ɂ��T�C���������B�卑���̌���͂܂��ɐ��S���C�I���Y�̐l�ԃh���}���f���Ă����B
���̌�A��ۃI�[������I�肪�L���̉��Ɍ������B�����A���{���̃}�X�R�~�����̐l�Ə̂���������肾�����B�N�������������̂��낤���A���i�ł����g�̂���ׂ��Ⴊ��w�ׂ�������B�̂͂ǂ̑I������傫���A���Ƀ��C�I���Y�̃��j�t�H�[���𒅂Ă����B���̈�����肪�q���̒��ň�ԏ����Ȏ��������A"�V��`���b�g�I"�Ǝ菵�������Ă���B���͖������Ă���悤�ɑO�ɍs���ƁA�ނ͌��ւ̏オ��y�i���܂��j�ɍ������B����Ɣނ̑傫�ȑ��̂ܐ悪�A���������Ɏ��̗����Ă���C�̏�ɏ�����B�V�����^�����ȌC���������B���̐}�͍��v���Ă������Ȃ�B������召�̓�l�A�����Ȏq���������Ă��āA�ƂĂ��傫�Ȓj���������܂܂ŁA���̎q���̏����ȉ^���C�̏�ɂܐ���悹�Ă���̂ł���B�����Ă��̎q�ׂ̈Ɉꐶ�����ɃT�C���������Ă���B���[���A����A�����J�����A�z������B����̐l�͎��R�ŏ���Ȃ��哊�肾�����B�b������ƁA���̑��ɔނ̉����肪�`����ė����B
���ꂩ�甼���I�Ƃ��������߂����B���N����ɉ��x���s���l�܂藎�������A���̍b�Ɏc�������̎v���o�ŋ~��ꂽ����������B�卑���͑卑�r���Ƃ����͂��ɖ��O�������c��݂��r���ɂȂ�A���̔w�ԍ��Q�S����������a�v������Q�O�O�V�N�ɑ��E�����B�ȗ��ӂ�"�Q�S"�Ƃ��������ɏo��ƁA���̉��������D�����u�Ԃ��h��B
2012.04.17 (��) �ق����炩���̓�
�G���ɂ��̗Y��ł̂�т肵���ʐ^���ڂ��Ă����B���������ԓ��̐l�C�̓��A��̓��Ƃ��Ă�����ʂɌN�Ղ��Ă���A���̖����Y�o��"�ق����炩���̓�"�Ƃ����̂�����B�V������Ȃ��炽���Ղ蓒�ɐZ����B�ȑO�����x�͍s���Ă݂����Ǝv���Ă����B
�F�l����z�e���E�`�F�[���̏h������������Ă����̂����A�����ŋ߂̈��z���Ȃǂł��܂ł��s�����A���悢��D�Ҋ��Ԃ���Ă��܂��̂ŏł��ďh��T�����̂����A���������t�������B���߂������Ō�ɁA�R�����̃t���[�c�p�[�N�x�m���z�e�����������Ƃ��\��ꂽ�B�t�x�݂��I�鐡�O�̑��q�Ƃ̓�l���ƂȂ����B�������܂�܂ʼn����Ɩ��ȉ䂪�Ƃł͂���̂����A���܂�l�����ɂ������_���o��������j��l�A���Ȃ肨�C�y�ŃV���v���ȗ��ƂȂ����B
����ȍs��������o�b�^���̗��͌��\�ȏE�����������Ėʔ������ɂȂ�B���̋��R�̏E�����Ƃ́A��̎��������s���Ă݂�������"�ق����炩���̓�"�����̃z�e���̂����T�ɂ��邱�Ƃ������B�������Ɉꔑ���s�ł��邽�߁A�s���������͑�l�����z�e���̓��ɐZ���肻�̋ߕӂ̎{�݂Ȃǂ����w���鎖�ɂ����B����ɂ��Ă������ɂ���t���[�c�p�[�N�͂����炭�R���������͂������Ď��g�Ǝv���邨���̂��������{�݂ł���B���̉w���炢����X�����ɂ͂��傤�ǂ����̂����A�������l���������x����c���J��Ԃ����������m�ŁA�w�p�߂������p�̒����Ƃ��������̃p�^�[���ł���B
�z�e�����R�̒����ɂ���A�������ŏ�K�ł���וK�R�I�Ɍ����炵�̂��������������B�H���͘a�E�m�E�����璆�ؗ�����I�B�G���x�[�^�[�͍~���l�����l���D��Ƃ����A�����������q��������A�H�ׂĂ��鉡���������Ŏq�������蔲������ŁA�ٕ����̉����������������[�J���F���`����Ă���B����͒n����ߌ�����̋q�����������ŁA�i�ʂ����Ƃ��ۂ������]�ƈ��ɂ͂���J����Ɛ������������Ȃ�B
 �A����̑����A���悢��"�ق����炩���̓�"�֏o���ł���B�o���Ƃ͌����Ă��Ԃłق�̐����R�����オ�邾���Ȃ̂ł���B���̓��͎Ԃ�����~�܂��Ă��邾���ŁA���b�L�[�ɂ��Ă����B��������Ƃ������̓��A�������̓��Ɠ��ɕ�����Ă���B
�A����̑����A���悢��"�ق����炩���̓�"�֏o���ł���B�o���Ƃ͌����Ă��Ԃłق�̐����R�����オ�邾���Ȃ̂ł���B���̓��͎Ԃ�����~�܂��Ă��邾���ŁA���b�L�[�ɂ��Ă����B��������Ƃ������̓��A�������̓��Ɠ��ɕ�����Ă���B�������̂����A�������̓��Ƃ����̂����ƂȂ����̎��̋C���������B�n���̂܂�܂Ƃ�����t�̃I�W�T���ɂV�O�O�~�x�����ē���B���b�J�[�t���̒E�ߏ�͂��邵�A�h���C���[�܂Ŋ����B�����"�ق����炩��"�Ƃ͂悭���������̂ł��邪�A�Ȃ��Ȃ��ǂ����ď[���ȃT�[�r�X�ł���B
���悢��I�V���C�ł���B��̎G����C���^�[�l�b�g�Ō����������ʌ��i���ڂ̑O�ɍL����B�Ⴄ�̂͂Ȃ�Ƃ��S�n�̂������������Ă��āA�D�������̌����������ʂɍ~�蒍���ł��邱�ƁB���ɐZ����Ȃ���A����̍K������ɓ��ꂽ�������A�������Ⴄ���ɍs���Ă��܂��̂�������Ȃ��ƕs���ɂȂ�A���x���ڂ�����J����B���̓s�x���z�̌��ň�u�Â��Ȃ�̂����A�ቺ�ɂ͗Y��Ő����ލb�{�~�n���L�����Ă���B������͂ގR�X�A�E�艜�ɂ͐^�����ȕx�m�������яオ��悤�ɘȂ݁A������^������悤�ɓ~�̖��c�̌͂�X�X�L���h��Ă���B����܂ł����ȕ��ɐ�����Ă������A�����̕��͊i�ʂł���B���ʼnΏƂ��Ă������u�₩�ɁA�����悤�ɐ����ʂ��Ă䂭�B�t�̖K���͂��钹�̐����Ȃ��A�Â܂�Ԃ��Ă���̂����ł���B
�j�̗��͔N�ƂƂ��ɉ����ɍs�������A�����ʼn���H�ׂ������H�ȂǂƂ������Ƃɂ͂��܂苻���������������Ȃ��Ă���B�����ł͂ǂ�ȕ��ɐ����ꂽ���A�ǂ�Ȍ��ɕ�܂ꂽ����������ׂɑ�Ȃ菬�Ȃ�A�`���b�Ƃ������X�N�܂Ŕw�����ė���������̂ł���B
�������Ɨ���鎞�́A�ʓ|�Ȍ������ߋ����������Ȃ��B�����S�̒��ɂ���A���̂悤�Ȑ��ʂɍהg�������L�����Ă䂭�B����Ȉ�u�����߂Ẵ{���E���H���[�W�����ƁI�܁`����ȋ�ł���B
2012.04.08 (��) ���O
����Ət������ė��Ă���B�������N�Ԃ͕ʂ�̑��Ǝ��ɍ炭�����A���N�͊��������������o��̓��Ў��E���w���ɔ����炫�̂ƂĂ������ɂȂ��Ă���B�x���낤�������낤�����̍炩�Ȃ��t�͖����A�K�����̎��͂���ė���B���̋G�߂̈ڂ낢�̒��ł�������������t�͂Ȃ����A���Ƃč�N�Ɠ����ł͂Ȃ��A���̍����������l�������菭������̏d���y���A����N���Ƃ��������������ɂ���B����Ƃ��̈��z���őz���o�̕i�X�Ƃ��ʂꂽ�B����܂Ŏ̂Đ�Ȃ������d���Œm�荇�������������l�����̖��h�A���\�N�ɂ��n��X�P�W���[�����B����͎����̋�̓I�ȋL�^�ł���A����ł����l�����̂��̂̂悤�Ȃ��̂ł���Ɗ����Ă����B���ꂪ�����ɗ��āA�����ċ���t���Ă݂��B���X�A�����Ɍ����Đ�����I�ȂǂƂ����ӋC���݂����o����C�͂��Ȃ��̂����A�V�Аl�ЁA���������m�h�����̒������X�ς���čs���̂�����A�ߋ����������݁A�����~�܂��Ă��邱�Ƃ��D���ł��鎩���������Ɋ��������ʂł���B
���̈�A�̓����̒��ŗB��ς��Ȃ��̂������̖��O�ł���B�傫���Ȃ艽�����������Ȃ����Ă��A�Ԃ�V�̎����炸���Ɠ����ŌÂ����V�������Ȃ�Ȃ��̂����̖��O�B�����͌����◣���Ő����ς��Ƃ����̂�����ł͂���̂����A������߂������A�v�w�ʐ��Ƃ������̂ɂȂ�̂�������Ȃ��B�傢�Ɍ��\�Ȏ��ł���A�{����������ׂ����Ƃ��Ǝv���B
�����̖��O�A���������͂��̏H����i�i�A�L�o�@�R�E�W�j���Ă��ƁA�ƂĂ��p���������C�����Ă����B�J�b�R�����Ƃ����v���Ă����B�ߔN�A�H�t�����A�L�o�Ƃ�������������O�ɂȂ�A�������獡���Ƃ��߂��A�C�h�����o�������B���̐́A�s�d�̂P�R�Ԍn���͐��V�{����H�t���A��������ʂ��ĐV�h�̊p���ӂ�܂ł�����ő����Ă����B�����ʂ������w�E���Z�����̓r���ɂ���A�ԏ����悭"�A�L�o�s���܂���I"���ƌ����Ă����B���̓x�Ɏ����̖��O���Ăт��ɂ��ꂽ�C�ɂȂ��āA"�Ⴄ����A�L�n�o���Ƃ����ƌ�����"�ƂU�N�Ԃ��̒����ɓn���Ďv���Ă������̂��B���ꂪ���ꂱ��S�O�N�ȏ���O�̘b�ɂȂ�̂����A�������ɂ��̎����獡���̌X�������������ɂȂ�B
����͎c�O�Ȃ���ߋ���U��Ԃ����b�ł���B�O�r�̂Ƃ��薭�Ɏ����̖��O��p���������Ǝv���Ă������w�Z�̂R�N�̍��������B�������N�ɂ������Ȃ��Ƃꉮ�ň��Y�D�����������͍��ł��͂�����o���Ă���B���鎞�A�Z��ŗV��ł���ƃc�J�c�J���ƈႤ�N���X�̏��̎q�R�l�����̑O�ɗ������B�����Ă����Ȃ�"�����O�͉��Ă����̂ł���"�ƌ���ꂽ�B�v���t�i���p�ł���B�ˑR�̎��A�p�����������B�����Ƃ�����t�Ő^�ʖڂɓ����鎖�͂ł��Ȃ��B��l�Ɍ������ďo���̂�"�o�L�A"�������B�g���R�̌i���n�̂悤�ł��邪�A���̂��Ƃ͂Ȃ������̖��O���t���ɂ��������́A���Ō����ƊE�p��ł���B
�����Ă���������̎q�����̔����͉��x�����x�������Ԃ��A���̓x��"�o�L�A"�Ɠ������B�S�R�[���������Ȃ��Ƃ�������ŋ����čs�����̂����A���͂��ꂩ�炪���̎����̎n�܂肾�����B���̋旧�̏��w�Z�A�������N���X�ւ��Ƃ������̂��S���Ȃ��w�Z�������B���������Ă��̎O�l�̏��̎q�������Z�N�̑��Ƃ܂ŁA���Ƃ͎��ۂɘb���@��͂قƂ�ǂƌ����Ă����قǂȂ������B�������A�x�ݎ��Ԃ̍Z��A�^����A�����Ƒ��N���X�ƍ����œ�����������킯�ŁA���̓x�ɔޏ������ɏo���킷���ɂȂ�B
�ȗ��A���"�A�b�I�o�L�A�N���I"�ƃL���b�L���Ə��������B�^�ʖڂɓ����Ȃ������d�ł���������Ȃ��B�����̂��傫���A�����f�J�C�ޏ������R�̂��ƂȂ��玩�R�Ɣ�����悤�ɂȂ����B������Ɩ��Ȏ��ɂȂ����Ǝv�������A���X�Ȃ���̒�����ӂ��������ւ̂��l�т��j���p��ƁA��r�ȉ䖝�ł������B
���w�N�ɂȂ�����w���̗ǂ����ꂽ���A�Q�V�ő啝�ɒx�����������������B�ꎞ�Ԗڂ̎��Ƃ��n�܂肻���Ȏ��ԑтɁA���̖���"�x���̉���"�ƌĂꂽ���̓g�{�g�{�ƍZ�������Ă����B����ƓˑR��̂ق�����"�x�����I�o�L�A�N�`���I"�Ɨ�̂R�l���̉��F���������Â��ȍZ�ɂɋ����n�����B��������A�w�Z���̂��낢��ȋ�������炪�o�Ă���B������̏�������N���X������B�N���X�̗F�l�����͂���Ȏ��̕ʖ���m�锤���Ȃ������B���̌��ǂ�������悤�ɁA�L��~�b�I�Ƃ����g�����^���ȋ�̉ʂĂ܂ŐL�тĂ������B�Z��̂ǐ^�ʼn����ɂ�������̂Ȃ����ɂƂ��āA����͂܂��ɓˑR�̏P���������B
���̘b�A�ꐶ�t�����������̖��O�͑�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������B�����Đl�A���ɏ����ɑ��Đ����ɑΉ����Ȃ���A�����ؕԂ��͕K������Ƃ������̎q������ɂ�������y�����P�ł���B
�]�k�ɂȂ邪�A����A�����R�ΔN��̌Z�B�̊w�N�ł����y�������A���\�N�U�肩�ŃN���X��������������B���̒��̈�l�����j�̖k���N��̕�ゾ�����������B���R�����ɂ����l��������傫�Ȋ������オ�����Ƃ����B�c����݂́���������E�i���o�[�����̃X�C�}�[�݁A��Ă��ƕ����A�����ɂ����F���������������������낤�B�ߏ��̂��ĉ�����̖��������Ƃ������̐l�ƁA�R�N�Ԃقǂ���"�o�L�A�N"���������w�Z�ɒʂ��Ă������ɂȂ�B
2012.02.22 (��) �S��ڂ̂ЂƂ育��
����ƓV�̌b�݂̉J�Ƃ���Ƃ������Ȃ����̂��~���Ă����Ǝv������A�����V�������Ă���B���N�̊����͈�i�ƌ����������Ă����̂����A����͂Ȃɂ����̔N�̂��������ł͂Ȃ��A��N�ɂȂ����g�����Ă����悤���B����n������ƈ�̂ƂȂ����₽����C���A�ΏƂ����x�ɓ���̂��S�n�����Ɗ�����B���̒��̐X�̒��𑁕����ňꎞ�Ԕ��A���A�a�o�łׂ̈̈�l�̉^���͖������₩�ɁA���₩�ɑ����Ă���B��N�̔ӏH������ɂ����ẮA�����ȖX���Ԃ≩�F�ɐ��܂�^���ȋ�Ɉ�ۑN�₩�������B����������Ƃ����ԂɔN���z���A�͂�ߕ����I���Ă��܂����B�����ł͑����̔N�y�̐l�X���A�ꗧ���Ęa�₩�ɕ����Ă���̂����A���ɂƂ��ėB��̑��_�̓E�H�[�N�}���ɓ����Ă����D���ȋȂ����ł���B����Ƃ��̏�v�ȑ́H������Δ������J�����������̗F�������Ȃ��B���^�E�N�[���b�W��W���j�X�E�C�A���̗D�����̐����A��������f���Ȃ�����فX�ƕ���������B���������N�ɂȂ�̂��Ƃ��������ӎu�ƁA�����܂��Ă���Ă���I�Ɗ��Ⴂ�����Ă���邱�̏������H�[�J���̖ʁX�B���悻�S�O�N�O�ɂȂ鐬�l���̓��A�����斯�̃K�[���t�����h�Ƃӂ��������ɕ�������i���V�r�b�N�Z���^�[�j�֍s���Ă݂悤�Ƃ������ɂȂ�A���̉ƂŔޏ���҂ԁA�ޏ��̎o�����R�[�h�Œ������Ă��ꂽ�f�B�I���k��"�����Ȋ肢"�ȂǁA�������̋Ȃɂ͎��Ȃ�̉��������z���o���]�����߂���B ���ɂ���ċ�Ɖ_�͂����\���ς��ĖO�������鎖�͂Ȃ��B�j��@�ɐ������镗�͂߂��ۂ��₽���̂����A�����͂��������Ă�������������ɋ����Ă����B���̐X�ł́A����X���܂ő�U��̃v���^�i�X�̌͗t�����ɕ����Ȃ���U�藎���Ă��Ă������A�����Ȃ��݂����̗t�̒��ɂ̓N���N���ƁA�܂�Ńw���R�v�^�[�̉H�̂悤�ɕ����Ȃ���ĕ����������J��Ԃ��Ȃ���t�B�i�[�������郂�m������B�䂪�l���𓊉e�����A����ȎU����������ȁI�ȂǂƔ[�����Ă��鎩���Ɏv�킸�n�b�ƂȂ�B
���̃A�C�X�u���[�̂ЂƂ育�Ƃ������n�߂Ă��獡��ł��傤�ǕS��ڂɂȂ�B�������O���₷�����ɂƂ��āA�ǂ������������̂ł���B�����܂������X�Ԃ��Ă��܂����̂́A��N�̉Ă��猚�z���������ڔ��̉Ƃ����T����Ɗ������A����܂ł͂��Ɩ����A���̓J�[�e�����A����͂ǂ�����H�����̕ǎ��̑I�����ƖZ���Ȃ��A�v���Ԃ��Ȃ����z���̏����ɒǂ��Ă���B�n�R�������̐��܂Ő��ݍ���ł�����̂�����A���\�N�̒~�ς̏�Ɏ̂Ă鎖���o���Ȃ������c��ȉו��̐����͋�ɈȊO�̉����̂ł��Ȃ��B����Ƃ���Ȏ���ł���A�i�j���������̐S�z������B
�����B��A�ώG�Ȑ������̊y���݂͎v�������Ȃ����̏o���ł���B�ĉ�Ƃ������ق��������̂�������Ȃ��B�����Ƃ����ɉ������Ŏ������Ă��܂����悤�Ȏʐ^�╞�A�z���o�̕i�Ȃǂ����C�Ȃ����R�Əo�Ă���B���w�Z����̂����h�ȁH�ʐM��Ȃǂ͂����ɔj��̂Ă����̂����A�搶�̎��ɓI�m�ŗ��₩�Ȍ��t�ƁA���傤���Ȃ��䂪�q�ł��鎄�Ɋ��҂�q���A������̕����B�v�킸�ړ����M���Ȃ�B���X�Ȃ��疳���̈��Ɋ��ӂł���B���̒��̈�ŁA������\�N�ȏ�����Ă��Ȃ��������ƕ�ƂR�l�ōs������p���s�̎ʐ^���Ђ������Əo�Ă���̂����炽�܂�Ȃ��B�m���A"�t�@�[�X�g�N���X�ōs����p����̗�"�ȂǂƂ���
 �X�����^�C�g���̗��������B
�X�����^�C�g���̗��������B���̑c���͓��{�̓�������ɐ�䂩���p�̏��w�Z�ɓn��A�����ōZ�������Ă����ƕ����Ă����B��������c�����̎v���o�̑唼�͂����ɂ������B�����c�����A����̉ʕ��ł���A�������{�ł͒����������p�p�C�A��}���S�[���ǂ��䂪�Ƃ̐H��ɏオ�����̂��A�����̂��Â�ł��鎖�Ɨ������Ă����B���̓r���A�c�@�[�̈�s�ƕʂ�A�R�l�ʼnË`���̑�щw�Ƃ��������炻�̑z���o�̏��w�Z�ɍs���Ƃ��̎������������A���ɂƂ��Ă��̗��s�̃n�C���C�g�������Ǝv���B�����H��̌Âڂ����D�F�̑q�ɂ���o�Ă����g���b�N���A�傫�����ɌX���Ȃ���썑�̕��ؓ��𑖂肷���čs�������i���A�ǂ����Ă��Y����Ȃ��S�̕��i�ł���B����ȒʐM���ʐ^���o�Ă����肷����̂�����A����ɐ�������d�����i�܂Ȃ��B�ʐM��͖{���Ɏc�O�Ȃ���H��̎���������鎖�ɂ���B�����Ďʐ^�͎����čs���邪�A��匈�S�ō���͑z���o���������ݕt�������╨�����Ƃ��ʂ�悤�Ǝv���B
����Ƃ����Ƃ����ɒ��߂Ă������̈���������������B���Ȃ�Ă��̂͂����܂ł����̖��ŁA
 �����ł͂Ȃ��Ƃ����v�����������N�Ԃ̎��̎����������B����"�A�C�X�u���[�̂ЂƂ育��"�̃A�C�X�u���[�Ƃ����̂́A���̏��ɗ��Ă��炱�̂R���ŁA���傤�ǂQ�O�N�ڂ��}����|���V�F�̐F�̂��Ƃł���B���˂Ă��玄�̊肢�������̂́A�Ƃ̒��̐�����Ԃ��炱�̎Ԃ߂�Ƃ������Ƃ������B����ȎԍD���̂����₩�Ȗ�����������B���N�t�������ė����F�B�̗l�ȎԂ�����Ɠ��̖ڂ�����Ƃ����S���ł���B�ЂƂ育�Ƃ̕S��ڂɖƂ��āA���̎��Ȗ����̋ɂ݂Ƃ�������ʐ^���f�ڂ����Ă������������B
�����ł͂Ȃ��Ƃ����v�����������N�Ԃ̎��̎����������B����"�A�C�X�u���[�̂ЂƂ育��"�̃A�C�X�u���[�Ƃ����̂́A���̏��ɗ��Ă��炱�̂R���ŁA���傤�ǂQ�O�N�ڂ��}����|���V�F�̐F�̂��Ƃł���B���˂Ă��玄�̊肢�������̂́A�Ƃ̒��̐�����Ԃ��炱�̎Ԃ߂�Ƃ������Ƃ������B����ȎԍD���̂����₩�Ȗ�����������B���N�t�������ė����F�B�̗l�ȎԂ�����Ɠ��̖ڂ�����Ƃ����S���ł���B�ЂƂ育�Ƃ̕S��ڂɖƂ��āA���̎��Ȗ����̋ɂ݂Ƃ�������ʐ^���f�ڂ����Ă������������B���̐l���ɂ����̂������R�L���قǂ̈ڏZ�ŁA�܂��V���Ȑߖڂ����悤�Ƃ��Ă���̂�������Ȃ��B����ł���̂��l���A�͂�ė����̂��A�����������A���h�������B�M���厖�Ȃ��̂������̂����ꖔ�l���Ɗ�����B�]����s�����̒��A���X�������ɉ����Ă���ς킵���Ƃ����d�ׂƋ��ɁA�V�������ł̐V�N�ȋ����┭���𑽏��Ƃ����҂��������̂ł���B
2011.11.02 (��) �U�E�K�[�h�}��
�X�ł͂���"�N���̈��������܂�"�ȂǂƂ����L��������o����Ă���B�܂���N���������I�Ղɍ����|�������Ƃ������Ƃ��낤���A�Ă��璷�ՂȏH�������Ȃ�A�����Ȃ�~���}����S���Ƃ��������̂��낤���A������͈���ɂ��̋C�ɂȂ�Ȃ��B����ł����낻��Ε�̎����ɂȂ�̂��낤�A�S�ݓX���炻��炵�������ڂ��Ă��鏬���q���͂����B���̎����̂P�O�x������銦�����ɂ́A�ӂƎႢ���̃A���o�C�g���v���o����������B�����Ȃ�Ɍ��\�ʔ����o�C�g���o�����Ă����ƈ�l���_���Ă���B�l�Ƃ��̘b�������"�������Ȃ������̂́A�l�E���Ƌ������炢���ȁH"�Ƃ܂�Ȃ��W���[�N�������̂����̏�Ȃ��D���������B���ꂪ���ɔ����̂Ȃ��W���[�N�������B���ʂ̐l�́A�����̃W���[�N���Ȃ��������Ȃǂ́A���̔�������C��p���������Ƃ��đ�����炵�����A���̏ꍇ�A�Ⴆ�C�l�܂�ȕ��͋C���K��悤�Ƃ��A�Ȃ����������̂��ƂĂ������A��u�̒��ق̌�̂Ȃ�Ƃ������Ȃ����ꂽ������Ă���ƁA�v�X�����ɂȂ�Ƃ����}�X�����������Ă���B�v����ɑ��l�ւ̎_���ł͂Ȃ��A��l�x�ɂ���ǓƂȃW���[�N�ł���B�R�����ߔN�ł͊����Ƃ������炵�����A���������W���[�N�Ƀn�}���ƁA����͏����~�܂�Ȃ��Ȃ鎖������B�����m���͂��Ȃ�Ⴂ�B
���̃A���o�C�g�ł��邪�A���C�ӓ��ł͍Ε�i�̋q�̏Z���s���ɂ��ԕi�W�Ϗ�ł̎d�����B���鎞�͔��߂𒅂������g�Q���̃G�Z��t�A�����鎞�͎�Ɏ�@���������ăg���b�N�ő�����A�Q���쏜�̉^�]��B���������A���o�C�g�ł́A�����ȃ`���R���[�g��H�ׂĂ��̊��z���������ꂽ���Ƃ��������B�c�O�Ȃ��炱�̃o�C�g�͂���������ŏI��B���̃`���R�̗l�ɐ��̒������Â��͂Ȃ��B�����ċɂ߂��͋��ցA���n��̃K�[�h�}���������B����͂����Ƃ���Ȓ��x�̂��̂ł���B���\�F�l�̉Ƃ����̉ƋƂŁA�͂���R�̓��킢�ŁA�}��̏����l�Ƃ��Ă�鎖���������ƋL�����Ă���B
���̒��ō��ł�����̂��K�[�h�}���������B���������������̂ŁA�قƂ�NJX�Ō������鍮�F�̌x�@���Ɠ����悤�ȕ��𒅂�����o�C�g�������B���ɂ����Z�̗F�l�ł����l�����̃A���o�C�g�ɎQ�������B�W���ꏊ�͌x���ۏ��Ђ̗F�l��ł��邪�A�����ŏ��ɓ������A�����ƖX�q�܂Ŕ���ďo����҂��Ă����B�����x��Ă����F�l�����́A���̎p������Ȃ�A�|���悤�ɂ��ď��o�����B���̏��������I��̂��Ǝv������A���x�͑����o���Ȃ��Ə��ɔ��������Ă܂ŏ��Ă���B�Ȃ�Ƃ�����Șb�ł��邪�A�m���ɋ��Ɏʂ�䂪�p�A�`���`���̔����X�q�̉����疟��̂悤�ɂ͂ݏo�Ă���B�����艽���������ŁA�������̏d�T�O�L�����������̏����Ɨ��Ă���B�x���̂悤�ȕ��͎������킯�������̂ł��邪�A�ڍׂ����Ɉ������ȏ�A�����Ŏ��߂ċA��킯�ɂ͂����Ȃ��B�������������̂ł͂Ȃ��A�F�l�����̃K�[�h�}���p�������������肾�����̂����A���X�����ł͐G��܂��B
 �����Ē��������͗���̋��֏ꂾ�����B�����Q�O�l�قǂ̃K�[�h�}���̐���n�܂����B�����֗���܂ł̓����A�{���̗\��⒍�ӎ����Ȃǂ�D��������Ă����A�����炵��������K�[�h�}������X�̑O�֏o�Ă����B����܂łƂ͑ł��ĕς���ĕ|����ɂȂ��Ă���B������"�C��t���I�h��I"�Ɗ�������̑吺�œ{�����B�����Ȃ�̕^�ϐU��ɋ��������̂��H����܂Ŏ��̎p���U�X���Ă����F�l�̈��v�ÌN�̃u�J�u�J�̐������A�ڂ̑O�Ők���Ă���B��������Ďv�킸�����o�������ɂȂ�̂����A�����͉䖝�ł���B���l���^���̐��U�ŏ��ōŌ�̂��ڂ��Ȃ��h��������B���̃W�L���ƃn�C�h���̌P���̌�ɑ����ċ������̂́A���q�̓��ꂾ�����B�J��Ɠ����ɑS�����A����Ƀ`�P�b�g�����֑S���͂œ˂�����B�䓙�K�[�h�}����"����Ȃ��ł��������I"�ȂǂƋ���ł����ƂȂ��������A���ł͂Ȃ��B����Ɠ����悤�Ȍ��i�͉������̐_�Ђ���̃e���r���p�Ō��������������B����͍�������̐Ȃ̕߂荇���炵���A�N�������ɕ������������B�]��܂������肷��҂܂ł���B���̂����܂ňꐶ�����ɂȂ��̂����킩��Ȃ��B
�����Ē��������͗���̋��֏ꂾ�����B�����Q�O�l�قǂ̃K�[�h�}���̐���n�܂����B�����֗���܂ł̓����A�{���̗\��⒍�ӎ����Ȃǂ�D��������Ă����A�����炵��������K�[�h�}������X�̑O�֏o�Ă����B����܂łƂ͑ł��ĕς���ĕ|����ɂȂ��Ă���B������"�C��t���I�h��I"�Ɗ�������̑吺�œ{�����B�����Ȃ�̕^�ϐU��ɋ��������̂��H����܂Ŏ��̎p���U�X���Ă����F�l�̈��v�ÌN�̃u�J�u�J�̐������A�ڂ̑O�Ők���Ă���B��������Ďv�킸�����o�������ɂȂ�̂����A�����͉䖝�ł���B���l���^���̐��U�ŏ��ōŌ�̂��ڂ��Ȃ��h��������B���̃W�L���ƃn�C�h���̌P���̌�ɑ����ċ������̂́A���q�̓��ꂾ�����B�J��Ɠ����ɑS�����A����Ƀ`�P�b�g�����֑S���͂œ˂�����B�䓙�K�[�h�}����"����Ȃ��ł��������I"�ȂǂƋ���ł����ƂȂ��������A���ł͂Ȃ��B����Ɠ����悤�Ȍ��i�͉������̐_�Ђ���̃e���r���p�Ō��������������B����͍�������̐Ȃ̕߂荇���炵���A�N�������ɕ������������B�]��܂������肷��҂܂ł���B���̂����܂ňꐶ�����ɂȂ��̂����킩��Ȃ��B�b�����Ă���A���̍����̎d����ł���ꏊ�ɘA��čs�����B�����x����S�����鏊�́A�l�̉����̌������K�i�̗x��ꂾ�����B�ߌ�ɂȂ�~�̓������������ɌX�����A���̑O�ɗ����͂����錩�m��ʂ����������B������͎b���m��ʂӂ�����Ă����̂����A���܂�ɂ����X�Ɏ������Ă���̂ŁA�d���������̂�������̊�������B����ƈꌾ"�U�E�K�[�h�}���I"�ƌ����āA�U����������������Ă������B�t���t�����������̌�p�́A�Ⴍ�z�X�����H���̖ڂɏĂ������B
�����A�F�s�䌒�ⓡ���������o���̃e���r�h���}��"�U�E�K�[�h�}��"�́A�N�Ԃ�ʂ��ĂQ�x���ō����������ւ钴�l�C�ԑg�������B���̋��֏�̂�������́A����ȃW���[�N�������������ׂɁA�����Ǝ��̑O�ő҂��Ă����̂��B���v�����̃W���[�N�A���l�ւ̎_���ł͂Ȃ��A��l�x�ɂ��鎄�Ɠ���̃W���[�N�������Ƃ�������B��͂�ƌ����Ή������A�l���ꂼ��̊炪����悤�ɁA�l���ꂼ��̃��[���A������B�����Ă��̎v���o�ɂ�����҂�ق�ꂳ��������̂́A�x�@���̗l�ȕ����A���ɂ͑S��������Ȃ��������B�����āA���ł��V����e���r����킹�Ă���x����Ђ��������ł���B���̌�В��ɂȂ����F�l�͂V�N�قǑO�ɑ������Ă���B
2011.10.16 (��) �a������
�S�n�悢�H���������ʂ���_�Ђ̑O��ʂ肩����ƁA����s���N�y�̏�������炵�Ēʂ�߂��čs�����B����₩�ȏ�i�������B�����Ŏv�����̂����A���͐_�ЂŔq�ގ��A��ɂ��ΑK����肱�܂Ȃ���Ί肢������Ȃ��悤�ȋC�ɂȂ�B�^�_�Ŕq�ނƉ��ƂȂ��Y���������悤�Ȍ��߂����C�����ɂȂ�B����ł��P�`�Ȏ��͂����`�����̂T�~���P�O�~�A���܂ɕ������ĂP�O�O�~�Ƃ��������H���s�Ȃ��B����͑Ó��ȋ��z���Ǝv���P�O�~���Ȃ��Ƃ��ł���B���܂�Ă��炨�D����ꂽ���Ƃ͖����A�����R���R���A�`�������I�ł���B���̉��ɐ_�l���C�t����"�n�C�킩��܂���"�ƌ����Ă����l�ȋC�ɂȂ�B�����肤�����̎��X�̎�������ȃj�[�Y�����A���悻������`���I�ɍs�Ȃ��B�A���ɂȂ�ƁA�l�C�̐_�ЂɍՂ��Ă���_�͑�Z���ŐQ��ɂ��������낤�B�ӔC���̋����_�Ȃǂ́A��x�ɐ����l�̊肢�����Ă��˂Ȃ�Ȃ��B�܂��ɐ_�Z�Ɏ����_�Z�̘A���ł���B�l�鏊�A�l�͊肢�����������������ȂɌ����������A���S����ׂɂ��ΑK������̂��Ǝv���Ă���B���̓��̗[���A���������ɗF�l�̂��a������ɂ��Ăꂵ���B���������Ή��ƂȂ����N�̂悤�ʼn����̂����A���͔ނ͂U�Q�ŌĂꂽ�������N�U�O�ɂȂ��Ă���B�������{�l�������ŁA���R���u�ɂ��闧���H�����ĕ�̐��X������Ă̒a������ł���B�Ȃ��Ȃ��������Ȃ��Ƃ�����Ǝv���Ȃ�����A����͂������Ɏ�Ԃ�ł��ז�����킯�ɂ��s���Ȃ��B��Ȃ���_�Ђ̂��ΑK�ƗF�l�̒a�����v���[���g���S�`�������ɂ���C�͖����̂����A������͂��悻���̒m��Ȃ��l�X�̐_�Љ^�c��ɂȂ�A������͗ǂ��F�l�ł���ׂ̗F�D�p����ƂȂ�B���z�̍���������A�ǂ��炪�L�v���Ƃ����Ό����܂ł������B
����ʼn����v���[���g�������Ƃ����A�����t���[�����̃p�[�v���E�J���[�̉����̃p���c�ł���B���ʁA���������̃p���c�͂��悻���̖ڂ����邱�Ƃ������B�قƂ�Ljꐶ���A�ҁA������A���ł���B�����������ܖ������ȃI�i���ڐ�����������B���ƂȂ��Ă͂ǂ����̗d���Ȕ�������A��������̒���"����A�����p���c�I"�ȂǂƖJ�߂��鎖���܂��Ȃ��B����ł��킸���ɓ��̖ڂ�����Ƃ���A���Ƃ��ĕ������ɉ˂��鎞���炢�̂��̂ł���B�̂ɁA���܂������Ŋ撣���Ă���ꈬ��̃`���C���I���W�ӊO�́A�����������̂Ɉ�����������Ȃ��B������Ƃ����Ή������A�����ȃp���c���͂��ċC���̍��g��d��B����ȃ`���b�Ƃ��������S�ő����������y�����̂ł���B
�a������ɓ�������ƁA�����ɂ͉��������ʁX����𑵂��Ă����B�j�b�|�������A�iwave�A�g�[�L���[FM�ANHK�Ȃǂ̔ԑg����X�^�b�t�⎄�Ɠ������R�[�h�ƊE�������l�X�ł���B���ꂼ���Ԃ�ł͖��������l�Ȃ̂ň���S�A���Ƃ������Ȗʖڂ�ۂ����悤���B �����A�̘b�ɉԂ��炭�B�Y�p�̔ޕ��ɂ������o�����́A���̐l�̊������Ȃ�N���ɑh�邩��s�v�c���B�Ⴆ�ΐ̂̕��}�ЁA���̃}�K�W���n�E�X���̃p���`�E�p���`�E�p���`�Ƃ����ԑg���j�b�|�������ɂ������B�����ɕy�c�M����Ƃ����V���Z�T�C�U�[�t�҂̑��l�҂��N�C�Y���o�����ɂȂ����B
 �������R�[�h�����ɂȂ����ނ̂U��ڂ̃A���o��"�o�~���[�_�E�g���C�A���O��"�̃T�E���h�̒��ɉ~�Ղ��o�ꂷ��B�����A���̃��R�[�h�̌��͂T�`�����l���̉��Ő��삳�ꂽ�B�������ʂ̂Q�`�����l���E�X�e���I�Ƀg���b�N�_�E�����Ĕ����ƂȂ����̂����A��̔ԑg�����`���̌ܓ��ԂłP�T���̑т������B�y�c���H���A�T�`�����l�������`���ň���P�`�����l�������𗬂��A�~�Ղ��ǂ̂悤�ɕ������삯����̂�������Ƃ����B�����͑O���̉E�̃X�s�[�J�[�A�����͓V����Ăȋ�ł���B
�������R�[�h�����ɂȂ����ނ̂U��ڂ̃A���o��"�o�~���[�_�E�g���C�A���O��"�̃T�E���h�̒��ɉ~�Ղ��o�ꂷ��B�����A���̃��R�[�h�̌��͂T�`�����l���̉��Ő��삳�ꂽ�B�������ʂ̂Q�`�����l���E�X�e���I�Ƀg���b�N�_�E�����Ĕ����ƂȂ����̂����A��̔ԑg�����`���̌ܓ��ԂłP�T���̑т������B�y�c���H���A�T�`�����l�������`���ň���P�`�����l�������𗬂��A�~�Ղ��ǂ̂悤�ɕ������삯����̂�������Ƃ����B�����͑O���̉E�̃X�s�[�J�[�A�����͓V����Ăȋ�ł���B���̃A�C�f�A�Ɉꓯ�傢�ɐ���オ�����̂����A�����ő傫�Ȗ�肪���鎖�ɋC���t�����B�T�`�����l�����ɕ����ƂȂ�ƃ��W�J�Z�͂T����K�v�ɂȂ邵�A������ɉ����l���T�l�K�v�ƂȂ�B�������P�`�����l���ɂ������������Ă���킯�������A�P�T�b���Q�O�b���̋̃`�����l��������B�_���Ă���̂ɉ����o�Ȃ��Ȃ����I�Ȃǂƌ����āA���W�I�̌̏Ⴉ�������̂Ɗ��Ⴂ����l���o�Ă���B�����������A�Ⴉ�����S���̋{�{�f�B���N�^�[�͋ǂ̏�i�Ɋ|�������A���̓�����N�C�Y�ԑg�����������Ă��܂����B
�������ē���N�C�Y�ɉ��債������҂̐l�����͂V�O���ɂ��y�B���Ȃ݂ɉ~�Ղ́A�����ɐ��Ȃ���^��̏��ɏ�����B�Ƃ����̂��N�C�Y�̐����������B���̌�A�^�ʖڂȕy�c�M���̓N�C�Y�ɉ��債�����N�����ɂ�������������A��l��l�Ɏ��M��"������I�ǂ��撣��܂���"�Ƃ����t���𑗂����̂ł������B���̐��E�̕y�c���A����Ȃ����{���������A�s��ȉF���̃��}���ɖ�������A�ǂ��炩�Ƃ����Δh��ȃA�[�`�X�g�Ƃ������́A�����ȋZ�p���ŏ����ȐS���������f�G�Ȑl�ł���B�����ɗ��Ă����j�b�|�������̋{�{�����Ƃ���ȉ��������o�������y����������B
�����ł͖{���ɋv���Ԃ�̏o����������B�ꏏ�ɔԑg����������Ƃ�����O�؎�����AFM�ԑg�̑I�Ȃ̎d���������鎖�ɂȂ����B�ς�����l�A�����Ƒ̌n�����^���S�R�ς�炸�A���̎��̂܂܂Ƃ��������炵���l������B���͂Ƃ�����̂̒��Ԃɉ���Ƃ́A�����S�͂��̎���ɋA�邱�Ƃ��o����B���ĕ�ƃG�X�j�b�N�ȃr�[�������������������A���ɂ͂���Ȏ��A����Ȏ�����荇���A�����ĉ���肻���ɂ͉��������Ί炪���邱�Ƃ��ō��̂��y���������B�����Ă���͂����܂ł����߉�ɂ܂�Ȃ����������A�����炭���A���ɂȂ肻���ȃp���c�ꖇ�̂������ŁA����ȂɊy���l�̒a����������߂Ăł���B
2011.09.21 (��) ���N
�b�͍�N�̂T���̎��������B�l�ԃh�b�N���I���A�Ō�ɗ�̌��ʔ��\�ƂȂ��҂Ƃ̖ʒk�̍�"���Ȃ��͗��h�ȓ��A�a�ł�"�Ƃɂׂ���������ꂽ�̂͂�����̎��̂悤���B�l�ԉ������ɉߐM���Ă��鏊������B���͂��Ȃ��v�ȑ̂̎�����ł���Ǝv���Ă����̂����A���̈ꌾ�ł��ꂪ���낭�����ꋎ�����B���ꂩ�瑁��N���߂��A�Q�x�ڂ̉����ɔY�܂���Ȃ������9���B���N�̂S���A�N���ɒɂ݂�����悤�ɂȂ�Ăш�҂ɂ��������B���낢��Ȍ����̌��ʁA�����炭���A���痈�Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ̎��B���̍ۂɉh�{�m�܂Ŗʉ�����A�{�i�I�ɑ̏d�����炵�A�K�R�I�Ɍ��ʂ��o���悤�ȕ������ɂȂ��Ă����B�ڎw���I�̏d�U�T�L���ƁA�N�n�߂̐����𗧂ĂĂ���Y���Y���Ǝ��s�o���ʂ܂܂ɁA���Ȃ��Ƃ��V�N�͉߂����Ǝv���B�c�����͉�����H���ׂ��A�`�r�ő������ۂ��ȏ��N�������B�����Ă��̔������A�Љ�l�ɂȂ��Ă���̖\���\�H�A���ɓƐg����̎��́A�Z�{�⌴�h�A�a�J�𒆐S�ɖ���̂��Ƃ��ǂ��̂������đς����ƁA���ɂł͂Ȃ��ݑ܂Ɗ̑��ɉ��Ƃ��h�_�܂���������C���ł���B���ꂩ�猋�����Ďl�����I�A�ɕ��̔���Ɛt�����Ɍ�����ꂽ�̂��Q�x�R�x�B�����A���⏟��ɑ����������ƖO�H�̒~�ς��A�䂪�ƌn�ł͑O�㖢���́A���A�a���҂̏o���ƂȂ�����ł���B�^�ʖڂɐ����Ă��āA��������V�I�ȓ��A�a�̕��ɂ͐\����Ȃ��̂����A���̏ꍇ�͗~�]�����������ɏ����A�ӑĂƂ킪�܂܂����������ʂƂ������ɂȂ�̂��낤�B
 ���̍ۖ{�i�I�ɐS�����ւ��鎖�ɂ����B���傤�ǂV�N�O�ɋ։������č��Ɏ����Ă��鋭�����ӂ��v���o�����B�^���̏�Ƃ��ď��X�O���Ă����N�w�������ߕӂɕʂ�������āA���x�͂��鎞�ɋ��R�������A���������L��Ȗʐς��ւ�]�Óc�̐X�����ɁA���Ɠ��A�a�̌���̏���ڂ����ɂ����B�Ƃ��炻���ւ��ǂ蒅���܂łQ�O���A�`�����͂�߂ĕ����Ă���B���[�ɍ炢�Ă��闕�F�̒���Ɏb�������~�߁A�������̉Ă̒��Ɏv����y������A�ʂ肩�������Ƃ̖��X�`�̍���ɉ��̂��ق��Ƃ�����A����Ȓ��̑��������n�߂ĂS�������܂�ɂȂ�B�傫�Ȗ������邱���͂�����Ƃ����X�ł���B�����͌��C�ȘV�l�������A�C�̉���Ԃ����ƃy�`���N�`������ׂ�Ȃ���U�����y���݁A�����Ɍ��N����ɓ����Ƃ�����Γ̗���ƁH���̂悤�ɌJ��Ԃ��Ă���B�W�����炢����͎�҂����Ȃ�̃n�C�y�[�X�ŃW���M���O�ɗ��ł���Ƃ�����ł���B
���̍ۖ{�i�I�ɐS�����ւ��鎖�ɂ����B���傤�ǂV�N�O�ɋ։������č��Ɏ����Ă��鋭�����ӂ��v���o�����B�^���̏�Ƃ��ď��X�O���Ă����N�w�������ߕӂɕʂ�������āA���x�͂��鎞�ɋ��R�������A���������L��Ȗʐς��ւ�]�Óc�̐X�����ɁA���Ɠ��A�a�̌���̏���ڂ����ɂ����B�Ƃ��炻���ւ��ǂ蒅���܂łQ�O���A�`�����͂�߂ĕ����Ă���B���[�ɍ炢�Ă��闕�F�̒���Ɏb�������~�߁A�������̉Ă̒��Ɏv����y������A�ʂ肩�������Ƃ̖��X�`�̍���ɉ��̂��ق��Ƃ�����A����Ȓ��̑��������n�߂ĂS�������܂�ɂȂ�B�傫�Ȗ������邱���͂�����Ƃ����X�ł���B�����͌��C�ȘV�l�������A�C�̉���Ԃ����ƃy�`���N�`������ׂ�Ȃ���U�����y���݁A�����Ɍ��N����ɓ����Ƃ�����Γ̗���ƁH���̂悤�ɌJ��Ԃ��Ă���B�W�����炢����͎�҂����Ȃ�̃n�C�y�[�X�ŃW���M���O�ɗ��ł���Ƃ�����ł���B�����ɂ��ƁA�����͍]�ˎ��ォ�珫�R�����Ɏg���Ă��������ŁA���̌�A�����s�ɂȂ茋�j�̗×{���ɂȂ����Ƃ����B���̗��j�̏d�݂���Ă��̂��낤���A���̓����ɂ͒��������h�ȑ�������B�����̐X�͂ǂ�ȏ������ł����X�����ċC�����������B�����Đ����̑O�܂ł́A���A�Q�n��A�Q�n�͓�����O�A���{�ł͂܂����邱�Ƃ��H�ȁA�O���[���F�ɋP���J���X�A�Q�n�����ł���̂ɂ͊������m�ł���B���ʂɖ쐶�̃J�u�g���̃I�X�ƃ��X���A�n�O��������t���z���Ă���̂ɂ���������ł���B�����č��͂W���ɂ͑S�����ւ��Ă����A�u����A�~���~���䂪���Ȃ��Ȃ�A�Ă̏I���̃c�N�c�N�z�E�V���킸���ɖ��Ă���B�����炭�����̂��̋���ȑ䕗�ŁA��������͐�̖��Ȃ��X���҂��Ă���̂�������Ȃ��B
�ȗ����̐H���͖�ؒ��S�ɐ�ւ��A��͋ɗ͒Y���������T����B���͍d����ǂ����݁A���̑����ł̂P����~�Q���Ԃ��������^���̌��ʂ���A���ʁA�̏d�͔O��̂U�T�L���قǂɂȂ����B����������V�L�����ł���B�Ƃ肠�����ڕW�B���B��������ɂ��Ă��̂��y���Ȃ����Ɗ����邵�A���邳���ȑO�ɔ�ׂ�ƈ��|�I�ɏ��Ȃ��Ȃ����B����ɂ��Ă��s�v�c�Ɋ����͂Ȃ��B
�����āA�����̏��߂ɍĂь������������B���ς�炸�a�@�͍���ł��āA�҂����Ԃ������Ղ肠��̂ŕK�R�I�ɐl�ԃE�H�b�`���O�ɂȂ�B���������Ȃ��ꂳ��t�ŝ��߂Ă���B����Ƃ����炩��A�����̑傫�ȔD�w����B�����ɕ���ōs�i���ė����B�݂�Ȑ^�ʖڂɕa�@�{�݂̐������Ȃ���̍s�i�A���̂������������ݏグ�ė���B�݂�ȑ����ĊO�҂ŁA�������̂����E�ɗh�炵�ĕ����Ă���B����Ȃ���A�܂�ŏ��^�̖����͎m�����̓y�U����̕���ł���B���̐l�������₪�ĕ�ɂȂ�A������Ղ�̎q��ĂɎ��g�̔����̂قƂ�ǂ�������悤�ɂȂ�B�ǂ��������ɏ�v�Ȏq���Y��ł��������ƐS�̒��ŋF��B���̕a�@�ŕꂪ�Z���Y�ƕ����Ă���B�����A���̑c��ɂ�����Ƃ����̒������@�ɕ����A�܂��������Z���c���ꂽ��ʓ|�ƁA��Ԗڂ̎��͎���Ő���ł���ƌ������ɂȂ����炵���B�����ł��Y�k������Ă�ł̍ݑ�o�Y�Ŏ��͐��ɏo���炵���B���O�ꂩ�牽�x�����̘b�����B���v���A����͕�̋�s�������Ƃ��v����B
�҂����悻�S0���B�₪�ĉh�{�m�Ƃ�4�x�ڂ̖ʒk���n�܂����B�ʂɉ��S������킯�ł��Ȃ����A4�x������Ă�����̐l�̖��O���o���悤�ƁA�ӂƂ��̋����ɕt���Ă��閼�D�������B���x�ڂ��Â炵�Ă��A�����ɂ�"�F��"�Ə����Ă���BSIKIMA�Ɠǂݕ��������ł���B�ޏ��͉̂���Ⴂ�����ł���B�Ɛg�Ȃ瑁���������ĈႤ���O�ɂȂ����ق����A�ȂǂƂ����傫�Ȃ����b�Ȏ����l���Ȃ���A�ꐶ�����Ȕޏ��̘b��_���Ȋ�ŕ������B�������Ă݂�Ɗ������l���W�܂�^���Ōł��a�@���A���X�ǂ����ď��̎�͓]�����Ă���B�����āA��҂�����w�͂̌��ʂ̍D���l�ɂ��J�߂̂����t����������B
�������Ď��́A���N�ɑ��ď��߂Đ^���Ɏ��g��ł݂��B�S���Q�P������S�x�ڂ�HbA1c�A�Ƃ���������Ȃ��L���ł���w���O���r���̐��l�͕s�\���A�܂��s�\���A�����ėǂ���D�ցB�w������ɂȂ��Ȃ����Ȃ������D���A���̓��A�a�A�g�蒠�̒��ɂ���B���N�Ƃ������t�̓��͐����Ă��鎖�̗L����т̌��A�܂�S�Ăł���B���X�Ȃ��猒�N�I�^�N�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���A�l���݂Ɏ����̑̂ɋC���g�����ւ̑�1�����A���Ȃ�ɓ��ݏo�����̂�������Ȃ��B
������k��
�h�{�m����̖��O�̌��ŗF�l��������v�������Ȃ��������������B����͐F���i�V�J�}�j���낤�A����F���̖��͖����̖����낤�A�Ȃǂƒ����V���Ȃǂ̎���Ő���オ�����B���x���������m�F�����Ǝ����ł��v���Ă����̂����A����ł��s���ɂȂ��Ă����B������m���߂�`�����X�����R�ɂ���������Ă����B���Ȃ̈�t�̑O�ɁA�K�^�ɂ��H�h�{�m�Ƃ̖ʒk���s�Ȃ��Ă��������ƌ���ꂽ�B�����ɓ���A���鋰��ޏ��̋����̏����ȕ����𓐂�����ƁA�Ȃ�Ɩ��ł͂Ȃ����ł������B�ǂݕ��̓V�L�}�ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��̂����A��ώ���Ȍ��ԈႦ�B�����̌y���Ŗ��ȑ����_��[�����l�т���B
2011.07.31 (��) �@�؉���
�����Ă�����O�������B�r�܂̃W�����N���ł��̖{����ɓ���A���̂܂܂ɂȂ��Ă����푺�G�O���́u�]�˓�������z���p�j�L�v�Ƃ������̂�ǂ�ł݂��B�I�O�\�قǂ̓����̊X��舕����A���̊X�̂��ڂ�b��A�Â���������`��鋻���[�������Ȃǂ��Љ�Ă���B���҂͂����̐l�ƂȂ��Ă���̂����A�Ǐ��ƂŔ��w�����邱�ƂȂ���A���̑O�����Ő��ȒT���S�Ɋ�������B���ł��ŏ��̍��ɂ���蕶�J�̘@�؉����Ƃ������̂����͌l�I�ɋC�ɓ����Ă���B����Ȃ�����A���}�������̓s����w�O�ɁA�ȑO���̋߂Ă������R�[�h��Ђ̐ꑮ�̎肾�����O�쐴���̎�����������A�����֗��t�̃C�x���g�̑ł����킹�ōs�����ɂȂ����B�m�����̖{�ɏ����ꂽ�����͈��O�̊w�|��w�O�������̂��v���o���A�d���̌�̂��y���݂Ƃ��āA�ڍ��ߕӂ̎U�����X�K�˂Ă݂鎖�ɂ����B
 �܂��͊`�̖؍���X�^�[�g���A���Z���i����䂤���j�Ƃ����@�؉����̕���ɂȂ����Ƃ�������ڎw���B�s����̉w���ʂɖڍ��ʂ��n��A�ՐÂȏZ��X���b���k�Ɍ����Ɗ��ɏo��B�r���A"���̂��h"�Ƃ��������ɂ��Ă͒��������h�Ȓ|�т̌���������B���������a�����ɂ͒|�̎q�̓��Y�n�Ƃ��Ēm��ꂽ�_���n�������Ƃ����B���̒|�тƓc�����L�����Ă����蕶�J�����A�������J�ʌ�A�����Z��n�ɕς�������j���ÂтA�b�������̋x�e���Ƃ�B�����͗��"�����̂͂��炳��A�̂��ɗh�ꂽ"�Ƃ��������������[�̉S���A�ӂƌ������ďo�镗��ł���B
�܂��͊`�̖؍���X�^�[�g���A���Z���i����䂤���j�Ƃ����@�؉����̕���ɂȂ����Ƃ�������ڎw���B�s����̉w���ʂɖڍ��ʂ��n��A�ՐÂȏZ��X���b���k�Ɍ����Ɗ��ɏo��B�r���A"���̂��h"�Ƃ��������ɂ��Ă͒��������h�Ȓ|�т̌���������B���������a�����ɂ͒|�̎q�̓��Y�n�Ƃ��Ēm��ꂽ�_���n�������Ƃ����B���̒|�тƓc�����L�����Ă����蕶�J�����A�������J�ʌ�A�����Z��n�ɕς�������j���ÂтA�b�������̋x�e���Ƃ�B�����͗��"�����̂͂��炳��A�̂��ɗh�ꂽ"�Ƃ��������������[�̉S���A�ӂƌ������ďo�镗��ł���B���ꂩ��P�T���قǕ����Ėڎw�����ɓ����B���Z�������@�@�@�؎��Ƃ��ĉh�����]�ˊ��i�N�ԁA�R���V��]�̎���ɂP�W�̖V�ɂ�i���A�����͂V�T�𐔂����ƌ����B�����ɂ͖ؑ��̋����͎m�����ɂ݂����閼���̐m���傪����B�������Ďb���s���ƁA�������㏉���̌����Ƃ����āA�������铌���s����A�ŌÂ̎��@���z�ł���߉ޓ�������B���R�̂��Ƃ����A���l�̎����������������̂́A����������ʂ̒m���l�I�ȗ��j�⌚�����ł͂Ȃ��B���̎��ōs��ꂽ�ƌ�����@�؉����Ƃ����������ȏ@���A�g���N�V�����̎����B
�������猴���̂܂ܕ\�L����B�@�؉����Ƃ͉����B�M�҂ɑ��g�������肤���̂�����Ƃ��悤�B�܂���]�҂����������ŁA���̐l�Ɍo��q�i�����т�j�𒅂��A�����i���炩�ˁj�̔��t�̘@�̑�ɍ��点�ĉԂ����B�V��ǂ����@�ؑ���͂�Ŗ؋���ށi���ˁj���W�����W�����������A����W�������ɓnjo�̐���������B�ƁA���̂����ɘ@�ؑ�̉��ɂ����肱���߂̒j���A�]���҂����𑄐�i�Ă��Δ��Ƃ��j�ŃG�C���b�Ƃ���h���т��̂ł���B�M���A�M���b�[�ƒf�����̋��т����̂������B�Ǝv������A�njo�̍����ɂ���������Ď��͂���芪���M�҂����̎��ɂ͓͂��Ȃ��B�₪�Ę@�̉Ԃ������ނ�ɊJ���ƁA���������M�҂������Ƃ�ƈ��炩�Ȏ��Ɋ���ׂĂ���Ƃ������@�B���肪����B���ꂼ�@�؉����A�Ɋy�����B���݂���M�҂����̓R�����Ƃ܂����āA���Y�������������i���Ă��܂��B�ȏ㌴���̂܂܂ł���B���������͈�l�Ƃ������A��̂ɂ��S�������S���B�v���ɘ@�؉����҂��ɏ����~�܂�Ȃ����������낤�B
 ���̏����A�n�߂��̂͊�������̏Z�E�̓����ł͂Ȃ��A���ꂩ��S�N�������̂ڂ錳�\����̓����������Ƃ������Ƃ��B����ɂ��Ă����̎���ɁA�@�̉ԕق��@�B�d�|���ŕ�����J�����肷�鎖���l���t�������Z�E�������Ȃ��̂������Ǝv����B����A�ǂ������̒��Ɏd�|��������炵���Ƃ̉\�����ԂɍL�܂�A����̎肪�L�тĐ��Ɉ����I���B���ꂼ��̎���̓�l�̏Z�E�́A�����悤�Ɏ��߂ɂ͂Ȃ炸���������ɂȂ����B�ƌ������Ƃ͕S�N�̎����o�ĂQ�x�������悤�ȏ@���A�g���N�V�������J���ꂽ���ɂȂ�B�����A�����̐��ʂ邳�ɕ��S����������������Ƃ����B���̌�A�@�؎��͓��@�@����V��@�ɏ@�|�ւ����A���̖������Z���Ɖ��߂č����Ɏ����Ă���B
���̏����A�n�߂��̂͊�������̏Z�E�̓����ł͂Ȃ��A���ꂩ��S�N�������̂ڂ錳�\����̓����������Ƃ������Ƃ��B����ɂ��Ă����̎���ɁA�@�̉ԕق��@�B�d�|���ŕ�����J�����肷�鎖���l���t�������Z�E�������Ȃ��̂������Ǝv����B����A�ǂ������̒��Ɏd�|��������炵���Ƃ̉\�����ԂɍL�܂�A����̎肪�L�тĐ��Ɉ����I���B���ꂼ��̎���̓�l�̏Z�E�́A�����悤�Ɏ��߂ɂ͂Ȃ炸���������ɂȂ����B�ƌ������Ƃ͕S�N�̎����o�ĂQ�x�������悤�ȏ@���A�g���N�V�������J���ꂽ���ɂȂ�B�����A�����̐��ʂ邳�ɕ��S����������������Ƃ����B���̌�A�@�؎��͓��@�@����V��@�ɏ@�|�ւ����A���̖������Z���Ɖ��߂č����Ɏ����Ă���B����Ȏ����v���Ȃ��炱�̎�������B���̖{�̕t�^�ɂ�������Ă���̂����A����ȐÂ��Ȏ��ł����ɂ���Ȃ��@���C�x���g���Ȃ��ꂽ�Ƃ͂ǂ����M���������B���̘b�̗��ɂ͓��ǂ������A����Ƃ��Ђ��݂̉�ƂȂ������@�����������ɂ߂�@�؎���ׂ��ׂ́A���]��Q�𗬂����ƌ����Ƃ���ł͂���܂����B���ꂪ���̏����s�̊��z�ł���B�����A���悻�吳����A���̎ʐ^�̐m����̉����M���@��N�����ƁA�Ă����l���̒ق���������Ȃ��قǏo�������ł���B�i�ڍ����M"�ЂȂ��ڂ���"���j���ꂪ�@�؉����̋]���҂��ǂ����͒m��悵���Ȃ��B
�����֗���܂Ŗ�ꎞ�Ԕ��A���X������ꂽ�̂ɊՎU�Ƃ������̐Â��������ݍ���ł����B���̕Ћ��ɍ���A�y�������Ɏv�����߂��点��ƁA�����ꂱ�̘b���{���ɂ������Ȃ�A�@�̉ԕق��܂�A�V�傽���̓njo�̒��A�J�����ɂ͓��l�͋Ɋy�ɍs���Ă���Ƃ������ɂȂ�B���̐��ŕn����a�Ȃ�ŋꂵ�ސM�ҒB�́A�m�������ގv���ł��̍��\�C�x���g�ɖ���y�����ɈႢ�Ȃ��B
���̒m�����A�Ƃ����@���͉Ȋw�I�A�����I�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�L���X�g�̕ꂪ�����Ŕނ��Y�݁A�߉ނ͐��܂�ĊԂ��Ȃ��X�^�X�^�����A�V��V���B��Ƒ��Ƃ̎������Ƃ����B �ߔN�ł͍������܂ܒ��ɕ����������z�������B�����`���Ƃ������̂͏�ɂ��s����`�̋����A�r�F���t�����ł���A���̂悤�ɉ�X�̒m�肤��̐l�A���l�A�Ɉ��l���R������Ȃ�ƌ������Ƃ���ł���B�����������A�����������A���̑S�Ă͐l�̐S���������A�n�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv��������B�D���������ł�����A�キ���|��������l�̐S�B����Ȑl�Ԃ̐^���v���Ă̌ߌゾ�����B
2011.07.10 (��) �\�b
���N���{�i�I�ȉĂ�����ė����悤���B�悤�₭�k�ЃV���b�N���痧���オ��S�\�����o�����̂��낤���A���C�����ȂǂƏ̂��Đl�Ɖ�@��������Ȃ��Ă����B�J�ɂ͐₦�邱�ƂȂ������ȉ\������Ă��āA�N���ƒN������ƕK������ɂȂ�B���̒��ł���l������\�b�ƁA�q���ǂ����̉\�b�Ƃ͒��g�͂�������A�Ӗ��������قȂ��ė���B�O�҂͂Ƃ����e���r�̃��C�h�V���[�I�Ȃ��߉�Șb���������A����������͒������I�Ŗ��̃J�P�����猩������Ȃ��B�����֍s���Ǝq�������̉\�̂قƂ�ǂ͐��������Ȃ����̂��唼���������A�R���ۂ����ɃA�b�P���J���Ƃ�������}���������������������B���̉\�b�͎��̏��w�Z����܂ş�鎖�ɂȂ�B�����ɂ�����Ƃ���ɖ쌴��X�A�R���_�݂��Ă������ゾ�����B�Ƃ�������ĊԂ��Ȃ����ɁA�R�ɐX���������Ԃ������悤�ȏ�������A���̓r��������ɖ��ȉ��˂炵�����̂��������B���[�J���łƂĂ��Â��b�͂��ꂩ��{�ɓ���B
���鎞������ʂ肩����ƁA���낤�����A���˂��狰�낵�������������ė��āA���̌�Ƀt�����Ɖ����オ�����ƌ����|���\���������q���̊ԂɍL�܂�����������B�����A�������傱���傢�Ƃ������t���A���̂܂ܒj�̎q�ɂȂ��Ă��܂����l�ȘA���ɂ���āA������m���߂�ׂ̒T�������Ґ����ꂽ�B�����R�l�A���̒��S�l���͑��Ȃ�ʎ��������B���R�́A�\�̌��ꂩ��Ƃ���ԋ߂��Ƃ����������������B���Ԃ̂Ȃ����|���Ƃ��Ȃ����̎�̉\�͂ƂĂ���肾�����B����s���ɗ����ꂽ�Ƃ������͍��Ɠ����ł���B
�ꉞ�����N�����Ă������悤�ɖ̎}�ō�������܂����̖_�ƃ��[�v�������A�p�Ӗ��[�A�E�҂Ȃ�T�����͔��������B�R�����Ȃ���������B�r���J�}�L���̗��̂�����A���̎��[�������ς��̒w偂̑��Ȃǂ�~�������Ȃ���A��̌���ɓ��������B�ቺ�̌������͏��ΐ��y���̐X���T���ƍL�����Ă����B���A���ׂ̗͓����h�[�������A�����͍ŏI��m�点����̉��ɗN���オ�銽���A����ȍr��C����O�ɂ����ڂꗎ���鋣�֏ꂾ�����B���̉\�̉��˂́A�f�Ă��ň�����قǂ̓y�ǂ��n���Ɏh�������悤�ȏ�ԂŁA���傤�ǎq���̍����炢�̍����������B��ɂ͋����Ă��Ԃ̂悤�Ȃ��̂�����Ă����B
�ӂ�͐Â܂�Ԃ��Ă���B�\�̕|���������Ă��Ȃ��������Ȃ��B���ȒT�����̃v���C�h���㉟�����̂��낤�A���X�Ȃ��璆��`������ł݂��B�����͐^���Âʼn��������Ȃ��B��˂ł͂Ȃ��炵������Ɍ��鐅�������A���������Èł��L�����Ă����B��u�A�����ٗl�ȋ�C�������オ�����C�����ă]�N���Ƃ��邪�A��͂肻���ɂ͙z�Ƃ����Ïl�����邾���������B�b�����ĉ������i�������j���Ȃ��Ƃ킩��A���q�ɏ��̂͂�����������B������"�A�b"�Ƒ傫�Ȑ����o���Ă݂��B���ꂪ�G�R�[���������l�ɔ������ƂĂ��ǂ��������B���ꂩ��͎q�����L�̊y�����Ɖ��x�ł��J��Ԃ��A��̕Ȃ��o���B
�A�b�A�b�Ƃ����升���I�|���\�𐋂ɐ����I�����ւ����悤�ɖ����ɂȂ肩�������������B"���邹�[���I���̃����[�I"�Ƃ����剹�����A�^���ÂȒn���̒ꂩ�狿���n�����B�����Ȃ肾�����B����͂����r�b�N���V�Ȃ�Ă��̂ł͂Ȃ������B���̏�Ŕ�ђ��˂���ɐK�݂����҂����đS�����b�������Ȃ������B�C����蒼���A��ڎU�ɊR���삯�o�����B����Ƃ̎v���œ����������V�_�l�̋����ŁA�����ňÉ_�������߂�ً}��c���s�Ȃ�ꂽ�B�c��͂������A�����̂͂��������i���������̂��I���Ƃ������̂������B�������ɂ��Ă͐����傫�����邵�A���t�����\������B���������Ă����_���o�Ȃ����A����قǂ̃V���b�N�ɂ��߂����������Ă����B�c�O�Ȃ���T�����͂���ɂĉ��U�Ƃ������_�Ɏ������B������[�ł����鍠�A�|�������v�������ꂼ��̋��ɉƘH�ɂ����B
�[�H�̎��A�R�ΔN��̌Z�ɍ����̋��|�̏o������������B����ƁA"�n�����ȁ`���O�����́A�������̉��ɂ͏��q����Ƃ�����Ƃ��Z��ł��āA����́i�\�̉��˂̎��j�ƂɊO�C���������̂Ɏg���Ă���̂��낤"�Ƃ����b�������B���̎���A�������R�ł��������ʂɍ����������B�|���\�△�ʂɏI�����`���S�A�������������ꂽ�����̒n������̑吺�A���̂��ׂĂ̓䂪�������Ȃ���������邾�����B�c�����̂͋��ƈ��S�����荬���������G�Ȏv�������������B
���悻���N����̏o�����͊Ă͕Ԃ��g�̂悤�ŁA�����玟�ɂ���ė��Ă͉����c���������čs�����B�����ْ��A�y�V�A�n���ƁA�O�b�̊��o���ꏏ�ɂȂ��Ă���ė������̃V�[���͍����S�Ɏc���Ă���B�q���B�̉\�b�̖{���Ƃ͏��F����Ȃ��̂������Ɖ�z����B ���������ł���悤�ɁA��l�ɂȂ����j�̑����́A�������Ă��܂����`���S�����ʂĂʖ��̂悤�ɂ����S�̂ǂ����ɒT���Ă���B�������߂������o���Ȃ����C�ȐS������������ł���B���ꂩ�����A���͂���Ȃ����₩�Ȏv���o�����܂ł��Y��Ȃ��ł��邾�낤�B
2011.06.19 (��) ���[���ɃC���^�[�l�b�g
����A�ꐡ�����������������B���낻�날���邱�Ƃ��o�������Ɗ��Ⴂ���Ă��邱�̔N��ɂȂ�ƁA���ӋC�ɂ�������Ƃ₻���Ƃ̂��Ƃł͊�Ȃ����A�������������ɂ߂��荇���������Ȃ��Ȃ��Ă���B����ȓ���ɗ�����Ă��鎄�ɂƂ��āA��͂肻��͊��������������B���������ʂɓo�ꂵ���A�[�J�̊��B�T�R����̓d�b�������B����"�A�C�X�u���[�̂ЂƂ育�Ƃ����ĐH���ɗ��܂���"�Ƃ������q�����ĉ��������Ƃ̂��ƁB���ɂ��������R�Ŗ₢���킹���������Ƃ����B�������̂́A����������Ă��鎄�̒m�荇���ł͂Ȃ��Ƃ������������B�S�������m�炸�̕�������ȂЂƂ育�Ƃ�ǂ�ł���āA�������[�J�܂ł킴�킴�����^��ł������������ɁA�����͂��ƂȂ��������o�����B
 �I�[�v�����ĖN�B�T�R���̗����l�Ƃ��Ă̓O�ꂵ�����ւ̂������ƁA�����̂��낻��80�N�Ɏ肪�͂������Ȗ��ƂƂ̃R���{�����܂��@�\���āA���ł͒��X�\���h���B��ƓI�ȗ������ɂȂ��Ă���炵���B����Ȑ܂ɁA���̃C���^�[�l�b�g����Ŗc��Ȑ��̒��̈�ł����Ȃ��A���̃u���O�ɖڂ𗯂߂Ă����l�������B�悭�悭�l����ΐ���������}�������̂��Ǝv���B�q���̍����玚�������̂������ŁA�ċx�݂̏h��̓��L�����J���Ă��������A����������"�ЂƂ育��"�Ȃ郂�m���p�����Ă���B���̐̂�m��l�B�ɂ͓���M�����Ȃ������낤�B
�I�[�v�����ĖN�B�T�R���̗����l�Ƃ��Ă̓O�ꂵ�����ւ̂������ƁA�����̂��낻��80�N�Ɏ肪�͂������Ȗ��ƂƂ̃R���{�����܂��@�\���āA���ł͒��X�\���h���B��ƓI�ȗ������ɂȂ��Ă���炵���B����Ȑ܂ɁA���̃C���^�[�l�b�g����Ŗc��Ȑ��̒��̈�ł����Ȃ��A���̃u���O�ɖڂ𗯂߂Ă����l�������B�悭�悭�l����ΐ���������}�������̂��Ǝv���B�q���̍����玚�������̂������ŁA�ċx�݂̏h��̓��L�����J���Ă��������A����������"�ЂƂ育��"�Ȃ郂�m���p�����Ă���B���̐̂�m��l�B�ɂ͓���M�����Ȃ������낤�B����܂Ŏl�����I�ɂ��y�ԃT�����[�}�������ł��]�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ炸�A���������ĉ����̒n�ɂ���炳�����̓����ɐ��܂�A�Z�ݑ����Ă���Ƃ������ɂȂ�B
���̂ЂƂ育�Ƃ̕���͕K�R�I�ɓ����ł���A���͏��a�ɍs������A�܂����̕����ɖ߂���������R�ɏo���Ă��܂��B����Ζ�����Ԃ��J��Ԃ�����̗��l�ƌ����������낤�B�m���ɎႢ���Ƃ͈Ⴂ�A�ׂ��Ȃ����L���̎�����J��̂ɂ͎��Ԃ�������B����ł��A�v�������Ȃ��̓��̏�i�́A���͖S���Ⴉ�肵����̂��̎��X�̕\��⌾�t�A�c������t����^������̒��Ԃ��������R�ƌ������������ЂƎ��ł���B���̈���ł͉����܂ɂ��ꂽ����A�߂����������������B����Ȏv���̉����������A��̐��₱�����ȂǂƂ������̂���X��������A���̎��̒��̈ꕔ���ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��悤���B
 ���݂͉����ɂ��Ă��g�т�炳��`�F�b�N������B���l���m�����݂��ӎ��̓��ɔ��肠���A�F�l��d�����Ԃ�����A���̕Ԏ����Ȃ��ƃT�{���̃��b�e�����\���Ă��܂����ゾ�B�閧���ԈႦ��A���[���ꔭ�ől�Z�̂��Ƃ������A���\���̐l�ɒm���Ă��܂��B��̑告�o���g�у��[�������Ȃ�������A���o�Ƃ������j���n�܂��Ĉȗ��s�Ȃ�ꂽ�A��Ɋ����鏟���̐��E���A���S���Ƃ��Đ��̒��̂�������鎖�͂Ȃ��������낤�B
���݂͉����ɂ��Ă��g�т�炳��`�F�b�N������B���l���m�����݂��ӎ��̓��ɔ��肠���A�F�l��d�����Ԃ�����A���̕Ԏ����Ȃ��ƃT�{���̃��b�e�����\���Ă��܂����ゾ�B�閧���ԈႦ��A���[���ꔭ�ől�Z�̂��Ƃ������A���\���̐l�ɒm���Ă��܂��B��̑告�o���g�у��[�������Ȃ�������A���o�Ƃ������j���n�܂��Ĉȗ��s�Ȃ�ꂽ�A��Ɋ����鏟���̐��E���A���S���Ƃ��Đ��̒��̂�������鎖�͂Ȃ��������낤�B�����m���ɐS��I�ɂ��������������̂��炠�������A����̗\�z�𗠐銽��̈ӊO�����������B��l���q��������ȃv���̐��E�̉������ƌ��������A�Ɠ��̕��y�Ƃ��đ����ė����B���ꂪ��X��O�Ɗp�E�̈Öق̗����������B���ꂪ�����ȏ؋�����돂�ɁA�{���A�\���������m�̃n�Y�̃}�X�R�~������ďW���Ĉ����I���S�����I�Ƒ����܂���B�Q�O�̈��ȂŁA�������ۂƂȂ��Ă�鎖���̂����S�����B�^����`����`���͔F�߂�B�����������ɂ��Ă������{�l�Ƃ��Ă̐ߓx�Ƃ������̂��A�Ȃ�ł��H���Ă͓f���o���}�X�R�~�ɂ͕K�p�ƍl����B
���̐̂ƌ����Ă����捠�̂悤�����A���ډ���Ă��̐l�̖ڂ����Ęb���A�S�ʂ킹�����ゾ�����B�҂����킹�ꏊ�ɒx��Ă��邠�̐l�́A�ǂ̕ӂ�ɂ���̂��낤�ƃC���C�����Ȃ�����S�z���A�Ƒ������͂��̎��Ԃɂ��ꂼ�ꉽ�����Ă���̂��낤�H�ȂǂƎv����y�����������ƂȂ��Ă͉��������B�X�s�[�h�ƌ����̂����Ȃ��Nj���焈ՂƂ��A�V��������Ȃ邪�̂ɐ��܂�o������ɒ��ʂ��邱�Ƃ��������B����ł����͂��̎���ɐ����Ă���B���N���Ă��̋C�ɂȂ�A���\�l�̒m�荇���Ƃł���x�ɏ����������ł���B���A���Ȃ���ɂ��ċ��̐U�荞�݂�A�ߑO�ɒ����������̍��d�����Ă��A���̓��̗[���ɂ͎���ɓ͂��B�w���{�A����͉��Ƃ����Ă��֗��Ȏ���ɓ˓����Ă���B�����Ă���"�ЂƂ育��"�ɂ���āA���m��ʐl�ƐS���q�����Ă����肷�邱�ƂɁA�ق̂ڂ̂Ƃ����K���������ł���B
�����ɔw�������A�ӌŒn�Ȍł��k�ɕ������肽���������l�̎������A���X�S�̒��ɂЂ������Ƃ���ė���B�ł������� "����ւ̊���"�ƌ������e������A���N�l�Ԃ������Đg�ɕt�����A�͂��Ȓm�b�𗊂�Ɋy������͍����Ȃ��琶����B����ȍm�肪�ق�̂����₩�ȍK�������ĂъĂ����Ȃ�A���͂���ŏ[�����Ǝv���B"�S�J���K�����I"�Ȃ�Č������̃��^�N�V�B�����Ƃ��炵�������J��������i�G�Z�j�V��ɂȂ��Ă��܂����悤�����A�l�鏊�A�����G���W���C����B�����ꂾ���̎����B
2011.06.12 (��) ���Ȏ�
���̒��ɂ͗����ɋꂵ�ގ���A���Ȏ�������������ɓ]�����Ă���B�����Ƃ߂��Ȃ�ƂĂ��ʔ����Ǝv���̂����A�������̏����ɂȂ��ĖY��Ă��܂��B���|�c���A�|�c���Ǝv���o���Ă���̂����A����ł��O�قǕ�����ł����B���I�J�}�ƃI�i�x��
����̓I�J�}�S������̒P�Ȃ�^��ł���B�s�u��_����ƕK���������ŃI�J�}���f���Ă���B�ȑO�͂��̑��݂����ł������A�������y���y���ǂ�����ׂ�҂���i���̒m�����A��̖����͂��Ȃ��悤���j�t�@�b�V������|�\�ɂ��邳���̂����S�������B�ŋ߂͉��Ƃ����Ă��₽��ƃf�J�C�̂���A���e�̐��Ƃɑ�E����荬�������y�ƁA�x��̐U�t�t�Ƀ}�b�T�[�W�������ӂ̂��A��������\�͂������Ă������Ȏ҂܂ŁA������W�������Ŋ���I�J�}�B���s�u�ƊE���x���Ă���B���̃z���̂킸���Ȍo���ł͂��邪�A���Ƃ��Ƃ͐V�h�̂Q���ڂ�S�[���f���X�A�����z������Ŗ锼����[��ɏo�v���Ă����l�X�������ƋL�����Ă���B���ꂪTBS�̃��W�I�ɏo�����Ă����������ƃs�[�q�����肩��A���W���[�E�f�r���[�ƂȂ����Ǝv����B�z���͂��₾���I�J�}�͖ʔ����Ƃ����A����������Ő���������̂��͖����ɂ킩��Ȃ��B�C���[�W�Ƃ��ăz���͈Â��ăI�J�}�͖��邭�ʔ����Ƃ������Ȃ̂��낤���B������}�X�R�~�̘A�������܂����グ�āA���݂̃I�J�}��������グ���̂�������Ȃ��B
����ɔ�ׂď����̃I�i�x�͂ǂ����Đ��ɏo�Ȃ��̂��낤�H�Ǝv���B���̂����܂��ɓ��A�҂������ɂȂ��Ă���B�j���ۂ����A�����ۂ��j�A�l�Ԃ���Ȑl�X�͐g�߂ɐ����Ă��S�}���Ƃ���B���̂��j���ۂ����͋������Ƃ��ĕʂ̓������ł���B���̐́A���鏗���̎肪�A����ƒm���Č|�\�E����p�������������������B�������珗�Ə��̓W���[�N�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�I�J�}�ƃI�i�x�A�����牷�߂�Ƃ����ǂ���������悤�ȋ@�\�Ɨp�r�Ȃ̂����A�ǂ����s�u�ƊE�œ����I���W�ǂ��́A�`���z�������̂��������炵���A�j�̗v��Ȃ����̃I�i�x�����A�j���j�����C�V������I�J�}�̂ق����D���炵���B���A�L���ɂȂ肽����A�I�J�}�ɂȂ��ăe���r�ɏo��̂���Ԃ̑�����������Ȃ��B���͐�Ɍ������B
���^�ʖڂɂ��恄
 ���̈�厖�����߂���t�s�M�C�Ă̍���p�������B�}�A�Ȃ�Ƃ��Ђǂ������Ƃ���Ȃ̂��낤�Ǝv���̂����A�ŋ߂͓��ɖڂɗ]����̂�����B�ڂɂ͍����̊F�l�ׁ̈I�ƌ����Ă���i���g�J�Ȃ�Ǝv���Ă���炵���A�^��}���藐��Ĉٌ������̘A�ĂƂȂ��Ă���B����ȑ�ςȎ��߂ł��A����������ׂȂ牽�ł�����B�{���͍����ׂ̈ȂǂƎv���Ă����Ȃ����ȂǁA�����͕S�����m���B����ɂ��Ă�����p�Ƃ����������A�c�������͔@���ɂ����Ŋ撣���Ă���̂����A�����Ɍ������ʂł���B��\���قȂǂ��Ă���҂́A�������Ɏ������Ȃ���ǂ݊ԈႦ�Ă͑�ςƋْ���������̂����A������c���������J�������f���ƁA�O�l�Ɉ�l�A����Ȃ̌���ɍs���Γ�l�Ɉ�l�͋����肵�Ă���B
�O���̗����ł̎����c���Ă��܂����̂��낤���A�{�i�I�ɐQ�Ă��ăC�r�L�܂ŕ������Ă��������B
���̈�厖�����߂���t�s�M�C�Ă̍���p�������B�}�A�Ȃ�Ƃ��Ђǂ������Ƃ���Ȃ̂��낤�Ǝv���̂����A�ŋ߂͓��ɖڂɗ]����̂�����B�ڂɂ͍����̊F�l�ׁ̈I�ƌ����Ă���i���g�J�Ȃ�Ǝv���Ă���炵���A�^��}���藐��Ĉٌ������̘A�ĂƂȂ��Ă���B����ȑ�ςȎ��߂ł��A����������ׂȂ牽�ł�����B�{���͍����ׂ̈ȂǂƎv���Ă����Ȃ����ȂǁA�����͕S�����m���B����ɂ��Ă�����p�Ƃ����������A�c�������͔@���ɂ����Ŋ撣���Ă���̂����A�����Ɍ������ʂł���B��\���قȂǂ��Ă���҂́A�������Ɏ������Ȃ���ǂ݊ԈႦ�Ă͑�ςƋْ���������̂����A������c���������J�������f���ƁA�O�l�Ɉ�l�A����Ȃ̌���ɍs���Γ�l�Ɉ�l�͋����肵�Ă���B
�O���̗����ł̎����c���Ă��܂����̂��낤���A�{�i�I�ɐQ�Ă��ăC�r�L�܂ŕ������Ă��������B�̎�ł����Ȃ�A�g���ɐ��o�����Ă���悤�Ȑ���̏�ł���B�e���r�͑S���ÁX�Y�X�̍��������Ă���B�����ō����ׂ̈̋c������Ă���̂ɁA�ǂ����Ă���Ȃɑ���҂�ɋ����肪�o����̂��낤�B�ꎖ�������ł���B��c���͋�����h�~�̌��������A�������̎��̖V���������A�����Ă���W�W�C�����̓��̈�ł����邩�A�q��ł���w����_�Ńr�V�r�V���ƒ@�����c���K�p�ł���B�����A�V����̉��߂͈Ӗ��������قȂ�̂����A����Ȏ��͂��̍ۂǂ��ł������A���{�͂��߂Ă���ʂ͐��ӂ������ė~�������̂ł���B�������f���鍡�̓��{�ɂ́A�e���r�ʂ肳���S���C�ɂ��Ȃ��Ȃ����A���������̐}�X�����z��Ɏx�������ł́A��~����Ƃ��Ȃ��͂����B
�����[��
�����r���v�u�[���ɂȂ��ĉ��N�ɂȂ�̂��낤�B���̗��s�͎��ɒ����A�����̔N���������Ă���Ǝv����̂����A�������N�̌X���Ƃ��đ傫���d�����̂����Ă͂₳��Ă���l���B�r�ɂ͂߂�ƈُ�ɑ傫�������h�ŁA���R�ɂǂ��ɂȂ��Ă������Œp���������Ȃ�B�m���̓A�o�N���̓X����낵���A���̔����ւ�ׂ��L�`�L�`�ŏ������Ȃ��Ă��āA�r���v���肪����Ƃ͋t�ȌX���ɂ���悤���B���̋@�\�͂���Ƃ����郂�m���t���Ă���炵���A���ꂪ�����ő傫���Ȃ�̂��Ƃ��v����̂����A����ȋ@�\�̈�Ő̂���傢�ɋ^��Ɏv���Ă������Ƃ�����B����͐��[�Ə�����Ă���\���Ȃ̂����A���镨�ł͐��P�O�O���[�g���A�ˏo�����̂͂P�O�O�O���[�g���Ƃ��Q�O�O�O���[�g���Ə�����Ă���̂����A���������N������Ȃɐ����̂��낤�H�Ƃ����^��ł���B����ɒ��킵���ڂ�ʂ���яo�Ă���i����ȑz���ł͂��邪�j�[�C���̂悤�ȓz�ɁA��x�ł������炨�ڂɂ����肽�����̂ł���B
2011.05.27 (��) �K��
���N�̏����Ɏ��͂����Ȃ�җ���}�����B���̂����Ȃ�Ƃ����\�������̐S�����ԓI�m�ɕ\�����Ă���Ǝv���B���߂čs�������B�T�R�ŐH�����������̎��A�i���g�I�Ƒ�����Ԃ��`�����`�����R���Ă��Ȃ胀�b�ƂȂ����B����ȓ��{�̌Â����ȕ��K���䂪�Ƃɂ܂���ʂ�Ƃ͎v���Ă��݂Ȃ������B���̔N�ɂȂ�Ə����ł��Ⴍ���肽���Ƃ�����]������B�l�ԑ厖�Ȃ��̂̓Z���X�ł���B���ہA�����ƋC�̂��������̔N�̃v���[���g�����҂��Ă����̂�������Ȃ��B�������A���ꂩ��f��͐�~�A���Ă����肩��N�����Ⴆ��Ƃ̂��ƁB�����ďꏊ�ɂ���Ă܂��܂��炵�����A�V�h�悩��͖���4��܂ŁA����Ȃ牽���̑K���ɂł��^�_�œ����`�P�b�g�������Ă����B���͔F�߂Ȃ��������F�߂邨�ꂳ��Ƃ����Ƃ���ł��낤���B�������ۂɁANHK���h����"�Ă��ς�"�ɑ������^����"���Ђ���" ��A�����̈����͂邩��"JIN"�����Ă͖���܂���ł��܂����ȂǁA�������h�ɔN���̓����ɗ������悤�ł���B
 ����Ȗ�ŋv���Ԃ�ɑK���ɍs���Ă݂��B�Ȃɂ���^�_�Ƃ������͓̂��������C���ɐZ���B���鎞�ɕ��C���̃I�o�����ɉ��Ƃ����Ă��������炸�A���˂�"�j��l"�ƌ����Ă݂��B������ƊԂ�u����"���̂͂����ˁI"�Ə��Ă���B���̌�ɍ��z�c�����܂��I�ƌ��������ȕ��͋C�������B�l����Ύ����I�o�T���⏭�N�����Ɍ�����킯�͂Ȃ��B����ȃg���}�ȋq���y�����Ȃ����̐l�ɁA���𗬂�閭������̐��Ȑ앗�������ʂ����l���B
����Ȗ�ŋv���Ԃ�ɑK���ɍs���Ă݂��B�Ȃɂ���^�_�Ƃ������͓̂��������C���ɐZ���B���鎞�ɕ��C���̃I�o�����ɉ��Ƃ����Ă��������炸�A���˂�"�j��l"�ƌ����Ă݂��B������ƊԂ�u����"���̂͂����ˁI"�Ə��Ă���B���̌�ɍ��z�c�����܂��I�ƌ��������ȕ��͋C�������B�l����Ύ����I�o�T���⏭�N�����Ɍ�����킯�͂Ȃ��B����ȃg���}�ȋq���y�����Ȃ����̐l�ɁA���𗬂�閭������̐��Ȑ앗�������ʂ����l���B�Ƃ肠�����A���̃m�[�g�ɂ����V�[�����ꖇ�͂����Ƃ���ŃI�[�P�[�B
�E�ߗp���b�J�[�̌������A���ɓ����ĂӂƋL�����h��B�q���̍��̑K���́A�E�������͑傫�Ȋۂ��|�Ăɓ��ꂽ���̂������B�E�ߏ��͒|�U���炯�ŁA����C���̏]�ƈ��ł��邨�o�������d���Ă��āA�������q�̒��t���܂ł���`���Ă����B���R���w�Z�̗F�l�Ȃ����R�����ŏo���킷���ɂȂ�B�����A�Ƃ̕��C������̂ɕ����K���D���ŁA�c������A��Ă悭�ʂ������̂ł���B
�����A�����ł������Ȃ��ׂ̗�q����������ɘA����A���̑K���ɂ���ė����B���͂���������オ���ė������������̂����A�ޏ��Ɩڂ��������Ƃ���"�₾�����I"�Ƃ�����q����̉��F�����B"�����������I�����͒j������"�ƌ��������C���ł���B
����ȗ��A�ǂ����ޏ��̓������C�ɂȂ�A���낻������������낤�ƌ���ƁA���������ɔ����E�����p���c�Ɏ���������܂܁A�����W�b�ƌ��߂ē˂������Ă���B���Ō���"�n���P�c���"�ł���B�b�����Ă悹�����̂ɁA�܂����Ă��܂��B����ƃL���I�ȂǂƂ����Ă��������E���������p���c���A�������Ă��܂��B�����̒p�炢���A�E���ɒE���Ȃ����̈Ӓn�Ƃ������Ƃ��낾�����̂��A���̋C�����A���ƂȂ����N�̎��ɂ��킩��悤�ȋC�������B
2�l�̕��e�������A�Ƃ��Ƃ������ʼn����N���Ă���̂����C�t���ď��Ă���B�����������N�Ƃ������b�e����\��ꂽ�C���ŗ��������Ȃ��B�܂��܂��������o���Ă���̂ɁA���������Ɛe�q��l�ł��̕��C������ގU�����̂��v���o�����B���ɂƂ��āA���̎�������ۂlj��������̂��낤�A���炭���̏o�������y�������ɉƑ���e�ʂɌ���Ă����B�����ł̗�q����́A���̃K�[���t�����h�Ƃ����֒��������������t���Ă����B
�K���ɂ����̕��C���̎��̓��A�����łǂ�ȋC�����Ŕޏ��ɍĉ���̂��͋L�����Ȃ��B�t�ł͂Ȃ��c�t�̂P�y�[�W�ł���B
�v�X�̓��ɐZ����ƌ��\�M���B���ꂪ�]�˂��q�̐S�ӋC�Ȃ̂��낤���H�Ƃ̕��C��T�E�i�A���h�̉��@���ɂ₳�������x�Ȃ̂����킩��B�قƂ�ǂ̐l������҂Ő̂قǂ̊��C�͂Ȃ��̂����A�����ł��܂��v���o���h��B
���鎞�A�F�l�̌��N�ƏҊ����̓��ɑK���ɍs�����B��X�͏��w�Z��w�N�̈��Y����ł���B��ԕ��C�̂�����Ƃ���ɏҊ����T����Ă��āA����𑖂�Ȃ���E���W�߂�̂������������B�����Đ험�i�̏Ҋ������ɒu���A��l�ő̂����Ă���ƁA�ڂ̑O�̋��ɂ₽��ƃf�J�C�j�̃C�`���c���f���Ă����B����͂������t���������炢�̑傫���������B�v�킸��l�͐U��Ԃ����̂����A���̌��グ����ɂ����̂́A�����N���X�̊C�V��N�̂��Z�������B���A��������A�܂������ɔނ͎������ׂ̗ɍ����Ă��܂����B
�ǂ����Ă��C�ɂȂ�A���R�Ɩڂ͗�̃��m�ɍs���B�ǂ����Ȃ����ς����Ă��A�������̃`���P�ȃC�`���c�̂T�{�͂���B���̏u�Ԃ���C�V��N�̂��Z����̃C�`���c�`�����n�܂����B����͌��N�ƈ��K�L���������̓�l�ɂ����킩��Ȃ�"�r�b�N����"�Ƃ����A�閧�̓`���ł���B���C���̋A��A���̉S�܂ō��قǂ̋C�̓���悤�������B
�������ċv�X�̑K���́A�����ԕ����Ă����������ᔠ���A�����̔��q�ɂЂ�����Ԃ����悤�Ȃ��̂������B�ǂ���E�������Ă��A���̈����Y�ꂩ���Ă������������v���o�B�Ō�܂Ńp���c��E���Ȃ�������q���������60�B���̂��Z����̑傫�ȃC�`���c�̍����́H�ȂǂƂ����A�����ӂ̔n���Ȏ��Ɏv�����点�Ă���ƁA�A�`���Ƒ傫�Ȃ��ߑ��B���̌�ɂ̓t�t�b�I�Ƃ����܂ݏ����A������铒�C�̒��ɏ����Ă������B
2011.05.25 (��) ���ꂩ��
���X�T�{�肷�����ȁH�Ǝv���Ă�������"�ЂƂ育��"�B���̂R�D�P�P���N���钼�O�Ɏv���Ă������ł���B���N�̏��߂ɁA�ˑR�~���ĕ������悤�Ȗڔ��̓y�n�w���̘b�������̎��ƂȂ�A��s��s���Y�W�ҒB�ƂʼnE���������Ă���^�Œ��ɁA���̂Ƃ�ł��Ȃ��h��ł���B����܂ł͑�n�k�ɂ��Љ�̕ω��ƁA�l���̈�匈�S������悤�Ȏ������d�Ȃ��āA�p�\�R���̃L�[��@���S�̗]�T�ȂǂȂ������B���Ԃ������Ƃ����Ԃɉ߂������A�ʂ����Ă��̑傫�ȏo�����͉��������̂��낤�ƁA����ȗ��A�ӂƋC�t���ƍ������Ă��鎖��A���̂��ƂȂǂ�܂ɐG��l����悤�ɂȂ����B�ǂ��l�͐S���炩�ɐ����A����������ɂȂ�܂��悤�ɂƁA�r���^�₾�炯�̍��̃��[�_�[��V�����œ�����t�̖�l��������@����K�����A���X�Ȃ��������肵�Ȃ��琶���Ă����B���A���h�ɒl�����l��A�����鏊�Ő_�╧�̓�������@���Ƃ����̌��t�ɂ�������A�����S�̉������ŐM���A��܂����Ő��_�̒���z���Ă����悤�ɂ��v���B��������A�c������n�߂Ƃ��邻�ꂼ��̐�c�B�ǂ���炱�ꂪ��Ԃ̐S�̎x���ł�����̂����A����Ȃ��g�߂Ȑl�X�ɂ�����Đ����Ă���Ƃ��v���Ă����B����������ȗ��A���̂��ׂĂ̂��̂������̒��Ŗ��[���o�ɐ������ł��܂����l���B
�T�N�O�A�{�Â̍`����ꎞ�Ԉȏォ���ď�y���l�܂ŕ��������A�����ł̓�������o������A���₩�ŗD���������l�X�͂����炭���炩�̌`�Ŕ�Ў҂ɂȂ��Ă���̂��낤�B���k�̐l�������A�Ȃ�����ȉߍ��Ȗڂɉ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A��قǂ̉R�����U�P�҂łȂ�����A�N�������̓�����m��Ȃ��B�����Ă����T���Ȃ�A�펞���R�Ő��藧���Ă��鎩�R�Ƃ������̂��A�W�X�ƋN��������o�����Ȃ̂�������Ȃ��Ƃ��������B
�����鎄�����ɂƂ��āA�l���ɂ͊��x���Y����Ȃ������N����B�[���ꐶ�S�ɍ��ݍ��܂ꂽ����̏o�����B�����ɂ͖��炩�ɓV�ЂƂ͌�����������܂�ł���B
����L���ŁA���������w�ɗ������w�����A�{�݂̐��������Ă��鏗���ɁA"���ꂪ���߂�������ǂ�����́H" "����͂������ĉ������܂�" "���ꂪ���߂�������ǂ�����́H" ��������J��Ԃ������ɁA"����Ȏ��͐�ɂ���܂���I"�ŏI�����Ƃ����B�������A���ۂɂ͂���Ȏ��͐�ɂ������B
�厩�R������z��̒��ɖ�����艟�����݁A���������ǂ����l�Ԃ�遂肩������Ȃ��B����܂ł̕��i��A���▢����ł��ӂ��A�����̎E���Ƃ������E�������c���Ă���B�Q�����ȏソ�������ł����̐[���ȏ͕ς�炸�A�����̂悤�ɈÂ��j���[�X���肪����Ă���B����ł��l�͖��̌��萶���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���Ԃ̌o�߂Ƃ������̂́A�����͐l�𗧂����点��Ƃ����s�v�c�ȗ͂������Ă���B�����A�w�Ԏ��͂Ȃ��ƍ��������Ă����l�Ԃ́A����̎��ő�R�̉ۑ��˂�����ꂽ�B�����Ė������A������5����ɉ����N���邩�킩��Ȃ�������Ɋ��������B�����F���{���ɏ����������̂��A�S��ɂ��đ҂Ƃ��Ǝv���B
2011.01.11 (��) �~�̗�
���̎����A���܂ɂ͟����ŎR�����ɉ͓�H�ׂɍs�����Ƃ�����k���A�ǂ��������Ƃ��{���̎��ɂȂ��Ă��܂����BJAL�̃}�C���[�W�̃|�C���g�����܂�A�����Ő\�����܂Ȃ��Ə���ȏ�͐�̂ĂɂȂ�Ƃ����A���������Ȃ�����ɂ����B�����o�[�͍Ȃƒ��������O�r�[�̕������x�݂̒��j�Ƃ�"�Č��s�\�g���I"�ł̒������ɂȂ����B���ꂩ��R�z�����ԓ��ōL�������قډ��f���A�����W�N�ɐ��E��Y�ɓo�^���ꂽ�����_�Ђ̂�����|�̋{�������B���{�O�i�ŗL���������̔N�ɂȂ�܂ň�x���s���������Ȃ��A�����@��Ȃ̂ł����ɔ��܂鎖�ɂ����B���낻��[�ł��߂Â��ė����̂ŁA�����^�J�[�̃v���E�X�̃A�N�Z����[�����ݍ��B���ꂪ�ǂ�����Ïl�ȏ�ɋ��Z�����ǂ��A�������R���v�̐j���قƂ�Ǔ����Ȃ��B���̐��E�Ɍւ�鍑�Y�Ԃ̎��͂ɂ͖ڂ���Ƃ��������������B
�ȑO���炻�̕����Ȗ��O�������ŋ��������������āB���̊��Ȃǂ����w�������ƃz�e���ɑ��k���Ă݂�ƁA���̓��ł͗L���ȏ\�l��E�V����k�Ƃ����������Љ�ɂ����������B����̓G���C���ɂȂ��Ă��܂����ƐS�����₩�ł͂Ȃ��B�����딋�ĊE�ł͒m��Ȃ��l���Ȃ��قǂ̐l�ŁA����ȏ��ւЂ₩��������ɂ͍s���Ȃ��B"�r�[���⒃�����ނ̂Ɉ���炢�͗~�����Ǝv���������ŁA�|�p�̈�ɒB���Ă�����̂͋C��������"�ƌ����ƁA�h�̔��l�����"�搶�͑�ς������Ŕ��킸�Ƃ������C�ɂ��Ȃ��đ��v�A���Ō��w�����Ă���܂�"�Ƒ��۔��������Ă��ꂽ�B
���ꂩ�甋�������A�X�̐��X�Ő搶�̒W���F�������f�G�ȓ����ݒ��q���L�O�ɔ������B�n���q�œ��키�V�[�}�[�g�ł͊C�Y��������ł��āA�V�R�̌`�̂����Չ͓��P���W��~�A���������̃R�[�X�ɂ͂Ȃ��������h�Ȕ��q���t���Ă���B�f��E������тƂŎR��w���|�����ɐH�ׂĂ������c�ł���B�ƂĂ��C�ɂȂ�̂����A�������ɍ���̍����ł͔���������悤�ȋC�ɂȂ��āA�Q�x�R�x�ʂ�߂��Ă͗����ڂ������邾���ɗ��߂Ă������B
���悢��A��̋�`�Ɍ����A�����^�J�[��Ԃ��Ē荏�ǂ���ɔ�s�@�͔�є������B�₪�č���ɖ�̐��˓��C�������Ă���B����A�����Ƃ����I�����W�F�̃C���~�l�[�V�����ɏ���ꂽ���{�n�}���̂܂܂ɁA�������������܂Ȃ݊C���A�W�H���Ɛ_�˂����Ԗ��ΊC���勴����̂����܂ɂ�������ƌ����Ă���B�₪�āA�ቺ�ɍL������̑傫�Ȍ͑�ゾ�B�������j�������̎ւ̂悤�ȗ��삪���p�ɒ����ł���̂������Ă����B���V�Ƃ����K�^�ɂ��b�܂ꂽ���̏I��ɂ́A�v���������f�G�ȃ��X�g�V���[���҂��Ă����B
�����ɋA�������̓��̉䂪�Ƃ̗[�H�́A������"���ł�"�������B���낢��ȋ�̒��Ŏ�����ɋC�ɂȂ�̂�"��ŗ�"�ł���B�������̔���悪�C�ɂȂ�ڂŒǂ��Ă��܂��B ������"��ŗ�"�A�������ɕ��i�͋C�ɂ����߂��Ȃ����m�B�����A����"��ŗ�"�����A�䂪�l���̓��킻�̂��̂ŁA���ꂪ���Ƃ�������"���ł�"�ɐZ����ƁA���̋�͉�R�P�������Ė��킢�[�����̂ɂȂ�B���ŏo������̐l�X��o�����́A�V���Ȃ鉽����S�̒��ɐ���ł����l���B���l�̓��̏_�炩�ȓ~�̓������̒��ŁA����ȉ��Ȕ�g�����Ǝv�������ׂȂ��炻�̗]�C�ɐZ��B
2010.12.15 (��) �v���o����
�g�t�̐Ԃ≩�F���犌�F�ɕς���Ă��܂��������t�݂Ȃ�������ƁA�������ƃJ�T�J�T�Ɗ����������S�n�悢�B�k�̒n����͐�̕ւ肪�͂��悤�ɂȂ�A�����������悤�₭�^�~����������悤�ɂȂ��ė����B����ȋG�߂ɂȂ��Ă���V�����B�[�E�o���^���̋L����������A�W���j�[�E�A���f�B��"�₽���J�Ɍ��āA�̏e�e��"�Ƃ����A���Q���m�̏a���A�N�V�����f���������A�ŋ߂ł̓J�g���[�k�E�h�k�[���̗��N���X���J�̉f��"�����킹�̉J�P"�̍��m��������ŁA���������l�����̊�����y����ł���B"�V�F���u�[���̉J�P"����h�k�[���͉J�P�ɉ�������悤�����A����������A�z��������i�Ȃ̂�������Ȃ��B���̐́A���̎O�l���W�����ԍ�̗����Ɏ�ސw���W�߂���������B���̋߂郌�R�[�h��Ђ̏����A�[�e�B�X�g�������V�����B�[�́A�v�X�̂P�O�����q�b�g�ƂȂ���"�f�C�X�R�E�N�B�[��"�Ƃ����ȂŃv�����[�V�����������Ă����B�ޏ��̕v�ł�����ʌ��ŗ������������W���j�[�E�A���f�B�̒a�������A������܂����R�ɉf��̎d���ŗ������̃J�g���[�k�E�h�k�[���ƍȂ̃V�����B�[�̓�l���j���Ƃ����A�b����ׂ̈̃n�v�j���O�C�x���g�ŁA�q�b�g�̏�悹��_�����ɂ��D�s���Ȋ�悾�����B
�X�|�[�c���͈�Ђɍi�荞��ŗ~�����Ƃ��������������̂ŁA���������Ɛ��b�ɂȂ������������X�|�[�c�̊O���L�҂�����Y����Ɏ�ނ𗊂B�ؑ����z�̗������̂Q�K�L�Ԃő҂����悻�R�O���A���悢��X�^�[�����̂��o��ł���B������l�͗D��ȊO���ɂ�������炸�A�ӊO�ɂ��h�X�̗������Ⴂ���Řb���Ȃ�������Ă����B���ɐ��̍L���������邢�F�̑f�G�ȃh���X�𒅂��Ȃ��Ă���B��ɍ���Ƃ����K�����Ȃ��ޏ��B�́A�������D��ɓ��{�I����ō��邱�Ɠ��͋������Ă��Ȃ��B���̎��A�h�k�[�����h�b�R�C�V���I�Ƃ����_�ɂ����G�������̂ŁA���R�̂��ƂȂ���X�J�[�g�̒����ی����ɂȂ��Ă��܂����B��u�A�ڂ̑O���^�����H�ɂȂ�قǁI�h�L�h�L�����̂��o���Ă���B�����x��Ă��̓��̎���A�w�������A�Ԃ��łӂ���Ƃ������[�[���g�̃W���j�[�E�A���f�B���o��B�X�[�c�𒅂Ă���̂����C���͂��Ȃ��t�����`�E���b�N�����[���[�́A���ɏオ�����͓��̂��Ƃ����݂Ȃ��ŊG�ɂȂ�Ȃ��B�₪�ăr�b�O�X�^�[�̂R�l���t�������Ċ��t�I�t���b�V�����p�p���ƌ������Ɠ����ɂ����S�����̉�X�́A��ސw�ƂƂ��ɂ��̏ꂩ��ޏ�ƂȂ����B
���̓��A���X�ɓ��������X�|�[�c�̋L���̐蔲������Ɏ��A��i������K���������ł��鎄�̎d�����`�F�b�N�����B����ƓˑR"�I�C�A�ǂ��Ȃ��Ă���I�����̋Ȃ̍��m���ڂ��ĂȂ����I"�Ƃ����̑吺�ł�߂��U�炷�̂������B�������̋L�������ďł�B���x�͗�̋L�҂�Y����Ɏ����{��̓d�b���B���ꂪ�P�זE�l�Ԃ̓{��̘A���Ƃ��������H
�����Y����͔��q��������"�ڂ��Ă��܂���A��������ǂ����Ă��������I"�Ƃ̓����B�Ăђ��ׂ����ʂ͉��̂��Ƃ͂Ȃ��A���̐蔲���������䂪�Ђ� �h ����Ƃ����I�W�T�����A��ԏd�v�ȃ��R�[�h�̍��m���O���Đ蔲���Ă��܂����̂������B���ꂪ���������獡�x�� I �����̏�i�ł���K���ɂ܂��܂��傫�Ȑ��œ{��ꂽ�B�h ��������̋L���̐蔲����e�ؐS�ł�����̂ɁA�A�x�R�x�ɓ{����Ƃ����A�i���Ƃ����z�Ȍ����ɂȂ��Ă��܂����B
��������b�̓t�����X�̂R��X�^�[����A�䂪�Ђ̐蔲���S�����H�̇T����Ɉڂ�B�ނ͍�������^�ʖڂȐl���������A�ǂ��������������l�Ԃ������M�y��`���ɏ������Ă����B�����͉̎�S�����Ƃ������̂�����A�ނ�"����݂ǂ�"�Ƃ����V�l�̏����̎�̒S���ɂȂ����B���̉̎�ɂ܂��ƊE����̖₢���킹�ȂǁA���ׂĂ̑������T����ɂȂ�B���鎞�A���R�[�h��Ђ���v���_�N�V�����A�����ǂ̃f�C���N�^�[���W�܂鎋����������B�̎�f�r���[��������݂ǂ�����ɗ������A�䂪�Ђ̑�\�Ƃ��ĎQ�������T����A�ӋC�g�X�Ƃ��Ă̑�ꐺ��"�݂ǂ�̑����̇T�ł������܂�"�������B��u�Ԃ�u���ăh�b�g���̏ꂪ���ɕ�܂ꂽ�������B�{�l�͊F���i���̎��ŏ����̂��킩�炸�ɃL���g���Ƃ��Ă����B���̇T����̂Ƃڂ����炪�Ăя����ĂƂ����b�B�b���ƊE��`�}���̊Ԃł͌�葐�ɂȂ����B
���ꂩ��b�����āA�T����͐l���ٓ��ő������ɂȂ����B���x���������ނ̓N�\�����قǐ^�ʖڂȂ����l�ł���B�䂪�Ђł���N�̎n�܂�͉����ɂȂ��Y��ȉԂ�A�N�l�N�l�Ȃ��������F�̖Ȃǂ������āA�����ȋC���Ŏn�Ǝ��̖����J���B���̎��̎i��i�s���́A����������̂��̇T����ł���B�В��̌P���⏉�t�̈��A�̑O�ɂ͕K���ނ̌��t��������B�ނ��������܂���������Ă݂�Ȃ̍����O���ɗ��B
�������N����I����ȗ\��������̂��낤���A�����ꂾ���Ŋ��l���̏����Ј�����N�X�N�X�Ɗ��҂̏������������Ă���B�l�O�ɗ������ŏ����Ƃ��|�l�́A��������ɂ�����̂ł͂Ȃ��B�܂��Ĕނ͕��ʂ̃I�W�T���ł���B�����Ă���ׂ�n�߂Ă���K�����g�`���A���ȊP�����A���t�ɋl�܂�Ԃ����肷��x�ɐV�N�̉��͘a�₩�ȏ��ɕ�܂��B�����Ȃ�Ǝ��̎В��̘b�͂ǂ��ł��ǂ��Ȃ�B�����ނ̎��̏o�Ԃ�S�Ј����҂���т�B���̏u�ԁA�ނ̓A�C�h���Ƃ����̈�ɒB���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
�l���̈�R�}���y���������Ă��ꂽ�S�̉��l�T����A����܂łɂ͉��x���v���o�������������Ă����B�����l���킹�悤�ȂǂƎv�������Ƃ͂Ȃ��̂��낤�B���������ꂪ�v�Z�Â��Ȃ�A�ނ͏��̐_�ł���BTV�ɏo�����ς�̂����|�l�����Ȃǂ́A�ނ������o�����R�̂̉����ɂ͂ǂ�����Ă����Ȃ�Ȃ��B�T������G�X�Ƃ��ĉ��C�Ȃ��e�ɂ����x���G�ꂽ��������B�����������ĔN�̎n�߂��߂Â����ɂȂ�ƁA���͌��܂��Ĕނ��v���o���B
2010.12.08 (��) �����X�J�C�c���[
 ���N���������N���ʂ܂t������ƂȂ�A�Y�N��Ə̂������Ɛl�ɉ�@������Ȃ��Ă����Ǝv���Ԃ��Ȃ��A�N�z���Ƃ������ɂȂ肻�����B����̂��ƁA�����Ȃ����̌����������Ă���ƁA���܂łȂ����������������Ɍ����Ă����B���b��̃X�J�C�c���[���Ɗm�F�ł����u�ԁA�b���Y��Ă��������������ݏグ�Ă����B���䉺�Â��A��͂�{���ɍ��������ƍĔF��������ꂽ�B����܂ł͏��������炵�����������炾�ƁA�K�������^���[��T�������̂����A���Ȃ铌���̌i�F�̊�̓R���ɕς��̂�������Ȃ��B�n���̏��X�X�ł����̃c���[�i�C�Ɋ��҂��c���ł���炵���B
���N���������N���ʂ܂t������ƂȂ�A�Y�N��Ə̂������Ɛl�ɉ�@������Ȃ��Ă����Ǝv���Ԃ��Ȃ��A�N�z���Ƃ������ɂȂ肻�����B����̂��ƁA�����Ȃ����̌����������Ă���ƁA���܂łȂ����������������Ɍ����Ă����B���b��̃X�J�C�c���[���Ɗm�F�ł����u�ԁA�b���Y��Ă��������������ݏグ�Ă����B���䉺�Â��A��͂�{���ɍ��������ƍĔF��������ꂽ�B����܂ł͏��������炵�����������炾�ƁA�K�������^���[��T�������̂����A���Ȃ铌���̌i�F�̊�̓R���ɕς��̂�������Ȃ��B�n���̏��X�X�ł����̃c���[�i�C�Ɋ��҂��c���ł���炵���B����Ȕ�тʂ������݂͒N�����y���ߐS�a�ނ��̂����A���͍��w�r����������Ƃ���Ɍ������E���ǂ��ł���B�ł���ΐ��V�h�A�ۂ̓��A�����Ȃǂ̈ꕔ�̏������Ɍł߂ė~�����Ǝv���̂����A���������ŋ��Ō��Ă��s���Ȃǂ����p�̍������ւ��Ă���̂�����A���ɏ���K���Ȃǂ͏o����킯���Ȃ��B����獂�w�r���̂��������̎n�܂�͂P�X�U�W�N�Ɋ������������փr���������ƋL�����Ă���B�ȗ��A�l�����̐��E�f�ՃZ���^�[����A�����v���U�A�Z�F�A�O��ƂV�O�N��ɐ��V�h�ɓ��{��������������r�����W�����Č��Ă�ꂽ�B���ɒr�܂̃T���V���C���A�s���A�X�R�N�̉��l�̃����h�}�[�N�^���[�ō��̂Ƃ��덂���̋����͏I���Ă���悤���B�������A�܂��܂����w�r���̌��z�͂��������ő����Ă��āA���܂Ō����Ă������̂��ˑR�����Ȃ��Ȃ�Ƃ����A�ߗׂ̐l�X�Ɉُ�ȕNJ���^�������Ă���B
���̎q������ɂ͉Ƃ̒납��x�m�R�������Ă����B�ׂ̋��V�_�i�k��_�Ёj�ɏオ��Ηy����������騋�����^�D��ʂ��ׁA�n�̎��ɂȂ��ďオ��̂��������B�Ă̖�ɂ͉ԉ��������̂����A���ꂪ�����Ƃ��߂������Ȃ̂��͍��ƂȂ��Ă͒肩�ł͂Ȃ��B�x�m�R�͂Ƃ������A��騋��◼���͓d�Ԃ�Ԃł͉����̂����A�n�}�Ō������������̐_�Ђ��璼���ɂ��ĂT�L�����Ȃ̂ŁA��͂��C������Ő��ꂽ���ɂ͏[���ɉ\�Ȏ��E�������Ǝv����B�����Ղ镨���Ȃ������Ȃ�A�ǂ�ȂɊy�����������̂����������Ƃ��낤�ƍ��X�Ȃ��犴���Ă���B
 �C�����悭���ꂽ�T���̓��j���B���������炠�̓��ȗ��C�ɂȂ�X�J�C�c���[�����Ă��邤���ɁA���V�I�������܂ōs���Ă݂悤�ƁA�܂�Ŗ`���D���̎q���̂悤�ɃJ�����������ĎԂɏ�����B�ڔ��ʂ�̋�ǂ͗���قƂ�lj��F���Ȃ�A�����̌��ɉv�X�N�₩�ɉf���Ă���B�����͐l�ł������Ԃ��Ă�����͗��̑O�̐Â�����낵���A���̂����邢��C�̒��ŊՎU�Ƃ��Ă���B���߂���ӂ肩��A�r���̊Ԃ��猩���B�ꂷ��X�J�C�c���[�������傫���Ȃ��ĐS���e�ށB�i���n�H�炵���ƕ����O�ƌ����o�X��̂��ɎԂ��~�߂��B���ɉƑ������A�V�l�̃O���[�v�⑽���̐l�����Ă���A���Ȃ�̓��킢�������Ă���B
�C�����悭���ꂽ�T���̓��j���B���������炠�̓��ȗ��C�ɂȂ�X�J�C�c���[�����Ă��邤���ɁA���V�I�������܂ōs���Ă݂悤�ƁA�܂�Ŗ`���D���̎q���̂悤�ɃJ�����������ĎԂɏ�����B�ڔ��ʂ�̋�ǂ͗���قƂ�lj��F���Ȃ�A�����̌��ɉv�X�N�₩�ɉf���Ă���B�����͐l�ł������Ԃ��Ă�����͗��̑O�̐Â�����낵���A���̂����邢��C�̒��ŊՎU�Ƃ��Ă���B���߂���ӂ肩��A�r���̊Ԃ��猩���B�ꂷ��X�J�C�c���[�������傫���Ȃ��ĐS���e�ށB�i���n�H�炵���ƕ����O�ƌ����o�X��̂��ɎԂ��~�߂��B���ɉƑ������A�V�l�̃O���[�v�⑽���̐l�����Ă���A���Ȃ�̓��킢�������Ă���B���悢�悻�̏ꏊ�ɗ������B���������猩������ƁA��F�̈Зe���ւ鋐��ȃX�J�C�c���[���A�^���ȋ�ɒ��݂�����悤�Ɍ����Ă���B�������Ɍ����l�����Ȃ��Ȃ��悤�����A���ꂽ���ɂ͍����֗���̂��ꋻ�ł͂Ȃ����낤���B�삪�������𗬂�A�L���L���P����ʂ����Ȃ��畗�ɐ�����Ă̎U���B�y�n���A���s��B���O������H���̂��������A���A�������������l��ɂ��o��邩������Ȃ��B�X�̉�������ł�������X�J�C�c���[���A�����̖����Ƃ����V������������Ɍ����Ă���Ă���B�����ɂ͐V���̎����ӑR�ƍ����荇�������Ղ�I�Ȗ��邳���Y���Ă���B���܂ł́A�قƂ�Ǔ���݂̂Ȃ���������Ƃ��������Ƀj���b�L���ƕ\�ꂽ�������́A���ƂP�O�O���[�g���قǗ͋����L�т邻�����B���̌��グ���ɂ͗D�����Ɗ�]�����Ă��邱�Ƃ��肤�N�̐��ł���B
2010.11.28 (��) ������
��ʌ��̐[�J�w����k���V���Ƃ������ɁA���{�Ɖ��̍Ȃ̑c�ꂪ�Z��ł����Ƃ�����B�c��͒����ԕa�@�ɓ��@���Ă����̂����R�N�O�ɖS���Ȃ�A���ꂱ��P�O�N�͋Ƃ̏�Ԃ������Ă����B�ȗ��A�����𑊑������Ȃ⎄�ɂƂ���"���Ƃ����p���Ȃ����"�Ƃ����ӔC���ƂƂ��ɁA�C�̏d���s���Y�ƂȂ��Ă����B�P�W�O�ɋy�ԉƂ́A�T�قǂ̒r�₢�낢��Ȏ�ނ̖X�A�ق�̏����ȋu�ɑ傫�߂ȓ��U�Ȃǂ����������A�Ȃ��Ȃ���̂���ƂȂ̂����A�Ȃɂ��Â��Ȃ�A�l���܂Ƃ��ɏZ�����Ƃ���Ȃ�Ί�b���炩�Ȃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ԃ������B ���̎���͌��z�̍��������i�݁A�܂��p�\�R���̒��ʼnƂ����āA���̃f�[�^����ޗ����E���B����C�ɑg���Ă��@����̂̂悤���B�̂���̓`���I�Z�p���Ȃ��Ȃ���錻��ł́A���̉Ƃ̘L���̏�ɓn���Ă���W���[�g���ɂ��y�Ԓ����ۂ�����A���ׂĂ̎V�̊p������Ă���ጩ�̏�q�A�ׂ����i�q�̗��ԂȂǂ�E�l���قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�A������x�Ɠ����悤�ȉƂ鎖���o���Ȃ����낤�ƁA���̉Ƃɗǂ��o���肵�Ă���m�l���牽�x����������Ă����B�ׂ��ɂ͐ɂ����A�������h�f�l�̎�����荞��ŋ������ł���낤���A���ⓙ�������Ń}���V���������������ԏ�ɁI�Ȃǂƍl�������Ȃ���A�������肪���ʂɗ���Ă������B
���̎���͌��z�̍��������i�݁A�܂��p�\�R���̒��ʼnƂ����āA���̃f�[�^����ޗ����E���B����C�ɑg���Ă��@����̂̂悤���B�̂���̓`���I�Z�p���Ȃ��Ȃ���錻��ł́A���̉Ƃ̘L���̏�ɓn���Ă���W���[�g���ɂ��y�Ԓ����ۂ�����A���ׂĂ̎V�̊p������Ă���ጩ�̏�q�A�ׂ����i�q�̗��ԂȂǂ�E�l���قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�A������x�Ɠ����悤�ȉƂ鎖���o���Ȃ����낤�ƁA���̉Ƃɗǂ��o���肵�Ă���m�l���牽�x����������Ă����B�ׂ��ɂ͐ɂ����A�������h�f�l�̎�����荞��ŋ������ł���낤���A���ⓙ�������Ń}���V���������������ԏ�ɁI�Ȃǂƍl�������Ȃ���A�������肪���ʂɗ���Ă������B���N�̋L�^�I�ҏ��̉Ă��n�܂낤�Ƃ��Ă�������Ȃ�����A�́A�V�h�ŗ��������o�c���Ă����`��i�Q�Q�N�O�ɑ��E�j�ɐ��b�ɂȂ����Ƃ����A�T�R���K�����牽�\�N���U��ōȂɓd�b���������B���܂�̋��̐[�J�ň���グ�����ƁA�������ɂȂ�ׂ�������T���Ă������A���̍\�z�ɂ҂�����̉Ƃ�����A���̉Ƃ̎����傪���R�ɂ��Ⴂ���ɏC�s��ς������̖��������Ƃ����A���R���d�Ȃ��Ă̏o����������B
���B�ɂƂ��Ă��A���̉Ƃ��Đ�������Y��ȉ��Η������ɂȂ鎖�͊�����芐������ł���B�o���ɂƂ��Ă܂��ƂȂ����v�����̒��_�Ȃ���A���X�ɍH���̉^�тƂȂ����B�������A���\�N���̊Ԉ�x����������邱�ƂȂ����܂�ɗ��܂����c��ȉו��̐����́A�z�����͂邩�ɒ������ςȂ��̂ɂȂ����B�����L�^�����߂̏����ĂɁA�֓��ōł������n��ƂȂ�[�J�ł̗͎d���ł���B��������ł��������ɂȂ��Ă��܂��A�܂������A�������B�ӑĂȐ����œ݂����̂ɂ͏��X�h�������̂������ł���B�K���ɂ��āA���Ԃ��������M���ǂȂǂƂ������낵�����ɂ��Ȃ炸�A���Ƃ������ɏI���邱�Ƃ��o�����B
 ����ȉ����̓��X���R�̂悤�Ȕ������G�߂ɂȂ�A���̉Ƃ͉��T�R�Ƃ������̗������ɂȂ��Ė����ɂ��̂P�P���P�X���ɃI�[�v�������B�I�[�i�[�V�F�t�ɂȂ����T�R���́A�`��̗������ł�����"�ނ���"���X�^�[�g�ɁA�������ځA���҂�"������"�̗������Ƃ��Ęr���A�Z�����C���u���W���p���̗����ږ�A���{����������t�͂Ȃǂŕ��L������Ă����B����A���i�o��鎖���Ȃ��ݖ��Ȃǂ̒��������g���A�����܂ł��V�R�ɂ�����茵�I���ꂽ�f�ނ̖���A�ق̂ڂ̂Ƃ������肪�������{�i�I�Ȕނ̉��Η��������\�����B����e���Ƃ��A���N�Ŋ��B�������Ƃ������̂Ɍ����ɕϐg����Ƃ����ڂ̓�����ɂ��āA����l���ɂ�����l�Ƃ̂Ȃ����A���Ԃ��D�萬�����R�̖����𖡂���Ă���B
����ȉ����̓��X���R�̂悤�Ȕ������G�߂ɂȂ�A���̉Ƃ͉��T�R�Ƃ������̗������ɂȂ��Ė����ɂ��̂P�P���P�X���ɃI�[�v�������B�I�[�i�[�V�F�t�ɂȂ����T�R���́A�`��̗������ł�����"�ނ���"���X�^�[�g�ɁA�������ځA���҂�"������"�̗������Ƃ��Ęr���A�Z�����C���u���W���p���̗����ږ�A���{����������t�͂Ȃǂŕ��L������Ă����B����A���i�o��鎖���Ȃ��ݖ��Ȃǂ̒��������g���A�����܂ł��V�R�ɂ�����茵�I���ꂽ�f�ނ̖���A�ق̂ڂ̂Ƃ������肪�������{�i�I�Ȕނ̉��Η��������\�����B����e���Ƃ��A���N�Ŋ��B�������Ƃ������̂Ɍ����ɕϐg����Ƃ����ڂ̓�����ɂ��āA����l���ɂ�����l�Ƃ̂Ȃ����A���Ԃ��D�萬�����R�̖����𖡂���Ă���B���Ԃł́A�����Ƃ��Ö��ƕ��ɑ���ꂽ�����̃��X�g�������A�����ȑn�엿���Ƃ̈ӊO�Ȑܒ��̖ʔ����ŋq���䂫���Ă���B����ȏɁA�����̐l�����낻��O���Ă������������ł���B���̉Ƃ͂W�O�N�O�Ɍ��Ă��o�������̂̂܂܂��c�����A�Â��ǂ����a�̎���������Ɏc���Ă���B�������Ɩ��키���Η����ɁA�Â��Q�������X���������̐����ɁA���A�Y�ꂪ���ȉ����������{�̐S�������ė~�����Ǝv���B�ӂƋC�t���ƁA����Ȏ�O���X�̘V�k�S�ɂȂ��Ă��鏊�Ȃǂ͐ɂ������������������B
�v���I�[�v���ł̕]�����悩�����̂��A�y�E���͂��Ȃ�\�����Ă��Ă���Ƃ̎��B���̃����`�͂P�T�O�O�~����p�ӂł��邻�������A�����ǂ�ʼn������Ă���F�l�ɁA���A��̏����s��h���C�u�̂ЂƎ��ɁA�����x�����^��ł��������鎖���肤����ł���B
| ���@�T�R |
| ��ʌ��[�J�s�������P���ڂT�|�P�T |
| �d�b�@�O�S�W�|�T�X�W�|�T�S�O�O |
| �c�Ǝ��ԁ@���@�ߑO�P�P���R�O�`�ߌ�Q�� �@�@�@�@�@ ��@�ߌ�T���R�O�`�ߌ�X�� |
| ��x���@�ؗj�� |
2010.10.18 (��) �T�E�i
���͖��ނ̃T�E�i�D���������B�̎����ς�����̂��A���͈ȑO�قǕp�ɂɂ͍s���Ȃ��Ȃ����B�ΏƂ����̂ŗ₽�������C�ɓ��������̂��̑u���������������Ȃ������B�K���������Ȃ��Ă䂭����Ƌ��ɁA�����̃T�E�i�����Ȃ萔�����Ȃ��Ȃ��Ă����悤���B����ȁA���͂Ȃ��T�E�i�̎v���o�����v�������ׂĂ݂��B�Ƃ̂��ɂ������n�C���o�[�h�Ƃ����T�E�i���A�P���R�[�Ƃ��������Y�̉�Ђɕς���Ă��܂����B��ʃ��J�ɂ������O���T�E�i�������Ȃ��Ă��琏�������o�B�����œ����Ă����C����̐l�́A�ŏ��̓L�r�L�r�������ɂ�����������A���N�ʂ������ɁA�S�}�����̑���������������̗l�Ȃ�������ɂȂ��Ă��܂����B�ނ͂������ɐ���������̂����A���̓x�ɓc������I�Ǝ����ĂԁB�ǂ��łǂ������c���ɂȂ����̂����A�S���������t���Ȃ��B�ŏ��̂����͈Ⴄ��I�ƌJ��Ԃ������Ă����̂����A��x�C���v�b�g���ꂽ��Ō�܂ŕς��Ȃ��]�̎�����炵���A�d�����ɂ͎���������߂āA���̃T�E�i�ł͓c������ƌ������Œʂ����ɂȂ����B
�ʔ������ɁA�����̔�r�I�ՐÂȏꏊ�ɂ������̂����A�C���Y�~�A�\�͒c�͂��f�肵�܂��Ƃ�����Ƃ���ɏ����Ă���̂ɂ�������炸�A�q�͖��ɖ\�͒c�W�҂������A��ł́A��铪�����S���݂���Œ���Ă���A�̒��C���Y�~�̑������_���i��������A�X�ł̓��N���g�̃T�[�r�X������A�P�{�܂łł��Ə����Ă���ɂ�������炸����ɊJ���ĂT�{������ł��܂����N�U��������A�����鎞��A���̖\�͒c�R���������p�ɂɋN���������Ȃǂ́A�������肻�̋C�ɂȂ��āA�Z�M���炵���l�����T�E�i�������Ɏ���܂ŁA�ꐶ�����Ɍ�q���Ă���Ԕ����ȃ`���s����������Ō��\�y���߂��B���̌����ȃ`���s���ɁA���������N���H���̂��߂ɁH����ȓ����ŁA�������f�����ŕ��a�ȃT�E�i�܂ōU�߂ė���̂��H���Е������������̂����A�G��ʔn���ɂ�����Ȃ��ł���A�|���̂ł�߂��B��̍C����̂��ɂ������́A����Ȃ��q�Ƃ����\���܂�����Ă����悤�ŁA�Ō�܂ŗ��h�ɋߏグ���ƁA���ł��c�Ƃ��Ă����̏ē���ʼn\�����B
 �r�܁E�����̃r���̂W�K�ɂ��T�E�i���������B���Ȃ茩���炵���ǂ��A�o�����������Y�킾�����̂��낤�B�ߔN�ł͂��Ȃ�V�������i��œX��߂鎖�ɂȂ����炵���B�����̓T�E�i������o�Ă������ɐ����ݏꂪ����B���Ńy�_���ނƐ����o��Ƃ����A�̂��牽���ɂł��������^�C�v�̂��̂������B���鎞�A�N���������������Ƃ������A�����Q���[�g���������オ�����B���̌�N������Ă������������Ő����オ��B�F���ꂼ��ɋ����̌��̍��͂���̂����A���Ă���ƖO���Ȃ��B���̊Ԃɂ����̓h�b�L���J�����̎d�|���l�̋C���ɂȂ��Ă��āA���̐���ɃJ���̒N��������̂��y���݂ɂȂ��Ă����B
�r�܁E�����̃r���̂W�K�ɂ��T�E�i���������B���Ȃ茩���炵���ǂ��A�o�����������Y�킾�����̂��낤�B�ߔN�ł͂��Ȃ�V�������i��œX��߂鎖�ɂȂ����炵���B�����̓T�E�i������o�Ă������ɐ����ݏꂪ����B���Ńy�_���ނƐ����o��Ƃ����A�̂��牽���ɂł��������^�C�v�̂��̂������B���鎞�A�N���������������Ƃ������A�����Q���[�g���������オ�����B���̌�N������Ă������������Ő����オ��B�F���ꂼ��ɋ����̌��̍��͂���̂����A���Ă���ƖO���Ȃ��B���̊Ԃɂ����̓h�b�L���J�����̎d�|���l�̋C���ɂȂ��Ă��āA���̐���ɃJ���̒N��������̂��y���݂ɂȂ��Ă����B����Ȏ���@�ł�������Ă��邤���ɂ��ꂱ��S�O���A���낻�뎄���{���ɐ����~�����Ȃ��Ă����B�������݂����Ǝv���Ύv���قlj䖝���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�F�Ɠ����悤�Ƀr���[���Ɛ����オ��̂��ȁH�Ǝv�����A�������͂���ȃh�W�͓��܂Ȃ������ƁA�����̘����ȐS��������������B����ɑ̒��̊�����t�o�������A�̊����ɂ͏��ĂȂ��B�P�P�O�x�̔M���T�E�i�����o�āA��ڎU�ɗ�̐��̂ݏ�ցI
����ƁA�����ׂɂ͍��܂ŒN�����Ȃ������͂��Ȃ̂ɁA�N�����������Ă���B�����܂������I�Ǝv���Ȃ�����������Ȃт�����A�ܐ�ł����ƃy�_����ł݂��B ��͂�ł���B�X�̂悤�ɗ₽�����́A�����Ԃ̂��Ƃ������オ���Ďv��������@�ɓ��荞�݁A�c�[���ƑO���t��Ⴢꂳ�����܂ܑ����ł��Ȃ��B�v�킸����������߂��̂͂������A���X�Ɛ����オ�������̐��A���x�ׂ͗ňꐶ�����ɓ������Ă����A�������̃I���W����̔w�����A�^�ォ��o�V���o�V���ƒ������Ă���B�v�킸�S�̒��ł����~�߂Ă���I�Ɛ��ɋ����A�V���b�L���O�ȏ�ʂ̓X���[���[�V�����̗l�ɑ����Ă���B�����m�炸�ɓ������Ă����̂����A�ٕςɋC���t�����I���W����A��قNj������̂��낤�B�c�b�c�b�c���e�`�I�Ə��̂悤�Ȕߖ������Ȃ���ׂ̎������グ���B
����Ă��܂������͕��S��ԂŃI���W����̊�����߂Ă����B�i���g�A���̃I���W����͋����̂��܂�ڂ�����Ă���I�ƍŏ��͎v�����̂����A��ł悭�悭�l����A���i���炻�̖ڂ͊���Ă���ɂ������Ȃ��B���g�̂��邻�̊�ɁA�v�킸�������ݏグ��B�b�����Ă���ƌ������ꂵ����̃S�����i�T�C�I�@�������{���ɐ\����Ȃ��Ƃ����S�ł����ς��Ȃ̂����A�����������ς��I�@���U�ł���Ȃɋꂵ���ĕςȃS�����i�T�C�͂���������̂ł͂Ȃ��B���̂ݏ�̃g���}�Ȑl�B�����Ă��������A���x�͐l�ɑ�ςȖ��f�������ăh�W�ȏ��҂ɂȂ�B�܂�ŃC�\�b�v���b�̂悤�ȏo�����������B �l�Ɛl�Ƃ̕����ʂ�̔ߊ삱�������̗��̐G�ꍇ���B���͂����Ƃ����Ƃ����Ȏ����������̂����A�����͂��̈ʂł��J���ɂ��悤�B
2010.09.27 (��) �������̈�i
�p�\�R���̃}�C�h�L�������g����t�ɂȂ�A�T���̂ɑ�ςȘJ�͂�v����悤�ɂȂ��Ă��܂����B��������ɐ������鎖�ɂ����̂����A���̒��ňȑO"�ЂƂ育��"�p�ɂƏ��������̂��A�����Ēu�����̂����������������B���̂܂܃S�~���ɓ����ɂ͔E�тȂ��A���X��������Ă̌f�ڂɂȂ����B���ɂƂ��Ă̕��~�Ƃ͑����̐l���~��������́A�݂�Ȃ��������̂������悤�ȋC������B���ꂪ���̂��납�炩�A�����Ȃ�̂������Ƃ������̂��悤�₭�萶���A���ꂪ���Ȗ����Ƃ����A�N�����ݍ��ނ��Ƃ̂ł��Ȃ��B�ꖳ��̉��l�ςɂȂ����B
�ґ�i�Ƃ������̂́A��{�͕K���i�ł͂Ȃ����́B�ꎞ��ɗ������ɂ߂邪�����ɂ͂��Ȃ����Y�����́A����Ȉ�ߐ����ґ�̋ɂ݂ƌ�������̂ƁA�`���Ɉ�܂�A����ҁA���҂��݂��̉��l�ς��i���I�ɋ�����������̂ƂɂQ�������Ǝv���Ă���B���R�P�`�Ȏ��͌�҂̗ϗ��I���ґ�Ƃ����A�����錾�t�̕��т̕��Ɏ䂩���B
�ʔ������ɂ��̘b�A�������̂���~�����������ł��Ȃ��A���Ƃ����Ĉ����ł��Ȃ��A���̂Ƃ��Ă����̉��l�ςƂ͕ʂ̏��ɂ��������́B�l�֑�����̂������ɂƂ��Ċ|�ւ��̂Ȃ��l���̎v���o��A�������̈�i�ɂȂ����Ƃ����b�B
�y�s�A�X�z
�j���[���[�N�̌ܔԊX�̃e�B�t�@�j�[�B�w�b�v�o�[���̉f��ɂ��Ȃ������̓X�ŁA�����ȃs�A�X�̔����������������������B���̎��̓X�ɕY����i�ȕ��͋C�ƁA�u�����h�w�A�̒j���������X���́A���������Łi�Ƃ肠���������������j�A�������ꂽ�����͈ꗬ�ŁA�T�X�K�I�Ǝv�킹����̂������B
�悭���{�ł̗L���u�����h�V���b�v�ł́A�����Ŕ����Ă��鏤�i������ŁA��������Ă���q�͍��q�ł��I�Ȃ�ĕ��͋C�̓X������̂����A�����ł͏��i�ł͂Ȃ��A�q�������܂ł�����ł���A���̐S�������܂ł����d����p�����O�ꂳ��Ă����B�X�̂��̃A�b�p�[�C�[�X�g�ɂ́A�A�����J���\����悤�ȉ������҂����������̂悤�ɁA���̕ӂ��舕����Ă���B����ȋq���玄�̂悤�Ȓʂ肷����̏��������̋q�܂ŁA�����ĂȂ��̑ԓx�͐������Ȃ��悤�Ɏv�����B�������͓y�Y�p�̔��������������A���ł����F�̃p�b�P�[�W�̐��ȍL��������ɂ��A���̎��̏Ί��X���o�鎞�̖������肽�v�����h��B
�y���v�z
�����炨�悻�R�X�N�O�̂��ƁA���߂Ă̊C�O���s�ɍs�������̂��Ƃ������B���̍��͂܂��A����Ȃɕp�ɂɊC�O���s���g�߂Ȃ��̂ł͂Ȃ������悤�Ȏ��ゾ�����B�܂��܂��C�O����̓y�Y�͕̂悤�Ɏv���������A������������Ȃ������A�������r���v���Ă��Ă���Ǝ��ɗ��B�w�����������͂������Ȃ��A�����̊C�O���s�͂ƂĂ������ŁA���v���Ώ�Ȃ��b�����A���s�ォ�珬�����̂قƂ�ǂ��o���Ă��ꂽ�B����Ȍ��߂���������A���ł��̏d�ӂ��������B
 ���̏I�����߂��Ȃ���������B�W���l�[�u�ł���ƌ��������ړ��Ă̎��v���X�ŁA�����̏�i�Ȃ����炢���Ȏ��v�������Ă�������B�v������菬���Ȃ��̓X�́A�V���[�E�B���h�D�[�Ƃ������̂͂Ȃ��A���v�͂������������r���[�h������ꂽ�ؘg�̔ɉ��{���ڂ����A�����ɂ���Ă���B���̂��w�l���猩��A���m�l�̎��͎Ⴍ�����A���̂悤�ȔN���Ɏʂ����̂��낤�B�����z���C�g�S�[���h�͂ǂ����낤�Ȃǂƌ����ƁA���Ԃɂ������"Very�@Expensive�I"�Ƃ����ꌾ�Ńs�V�����I�܂�Ő搶�����k�������Ă���l�������B���̂�Very������傫����������B�ǂ���ɂ��Ă��ǂ�������ŁA���̗���̏������ł͑���Ȃ������悤���B�����āA�ŏI�I�Ɋ��߂��Č��߂��̂��A���̒��ł͔�r�I�����ŁA�ł��I�[�\�h�b�N�X�Ȓ�Ԃł�����"�f�C�g�W���X�g"�Ƃ����^�C�v�̎��v�������B
���̏I�����߂��Ȃ���������B�W���l�[�u�ł���ƌ��������ړ��Ă̎��v���X�ŁA�����̏�i�Ȃ����炢���Ȏ��v�������Ă�������B�v������菬���Ȃ��̓X�́A�V���[�E�B���h�D�[�Ƃ������̂͂Ȃ��A���v�͂������������r���[�h������ꂽ�ؘg�̔ɉ��{���ڂ����A�����ɂ���Ă���B���̂��w�l���猩��A���m�l�̎��͎Ⴍ�����A���̂悤�ȔN���Ɏʂ����̂��낤�B�����z���C�g�S�[���h�͂ǂ����낤�Ȃǂƌ����ƁA���Ԃɂ������"Very�@Expensive�I"�Ƃ����ꌾ�Ńs�V�����I�܂�Ő搶�����k�������Ă���l�������B���̂�Very������傫����������B�ǂ���ɂ��Ă��ǂ�������ŁA���̗���̏������ł͑���Ȃ������悤���B�����āA�ŏI�I�Ɋ��߂��Č��߂��̂��A���̒��ł͔�r�I�����ŁA�ł��I�[�\�h�b�N�X�Ȓ�Ԃł�����"�f�C�g�W���X�g"�Ƃ����^�C�v�̎��v�������B���J���~�郌�}���̂قƂ�̏����ȃz�e���ɋA���āA������x���̎��v�߂�"�{���ɂ���ł悩�����̂��낤���H"�ȂǂƂ����s���������悬��B���̎��A���W�I���痬��Ă����̂̓T�C�������K�[�t�@���N����"�{�N�T�["�������B���̂����̋ȂɗE�C�t����ꂽ�̂��o���Ă���B�����Ă��̎��v�������A�������{�ł́A�W���l�[�u�Ŕ��������̂R�{�ȏ�̊��������i���t���Ă����ƋL�����Ă���B
���̓y�Y�͐S������ł��ꂽ�B���ꂩ��ӔN�Ɏ���܂ő厖�Ɉ��p���Ă��ꂽ�B ���̎��̘r���v�͍��A���̃p�\�R����@���Ă��鎄�̎��Ɋ�����Ă���B�����Ă��炸���ƕς��ʎ������ݑ����āA���N�͂S�O�N�ڂ��}����B�����̂��镨�����A��������̓�����l�ɂȂ������q�ɓn�����ƌ��߂Ă���B��������̂��ׂĂ��ꕪ�A��b�������ɘV���Ă䂭�A���̎��m�ɒm�点�A�K��������ׂɐl�����o�������́B�z���o�����r���v�A���͐�������p���Ƃ����A�V���Ȏ������ݎn�߂��悤���B
2010.09.14 (��) �����n����
������̏���������āA�k�y���A����������Ă����B���������͑��q�̃��O�r�[���h�ɁA�e�o�J���̈���Ƃ��ĎQ���������������������������B���̂����߂��ɂ���A��N�O�ɂ��ז�����������̍L��ȕʑ����v���o���A�����ɋA���Ă���ނɃ��[�������Ƃ���A�܂����̉ė��Ȃ����Ƃ̊��������U���B�ނƂ��e���̂���ԍ�̏Ă�����"�Ă��Ă�"�Ŗ�������ł��钇�ԂƋ��ɁA�Ăєނ̕ʑ��ɂ��ז����鎖�ɂȂ����B����"�Ă��Ă�����"�̈�l�ł���ވ䂳�A���x�͖ڐ��ς��āA�����̖k�y���̕ʑ��ɗ��Ȃ����Ƃ����B�ł͂�����ɍs�����ƁA�����̕t�a�����U���������Ȃ���������B���n�ɂ��������Ƃ͐����Ɩk�y���̒��Ԃɂ��镗�C���ő҂����킹�鎖�ɂȂ����B�y�������̎n�܂�ł���B
�Ă��Ă������o�[�̐쓈����A�ވ䂳��Ƒ҂����킹�A�S�@��]�A�����P�Q�N�Ԃ�ɎԂ�ς��Ĉ�H�A�k�y���ցB�����Ă����̗l�ɁA�������H�̈�ԉE���̒ǂ��z���Ԑ������𑖂�B���̈��Ȃ́A�ꂪ�Ƌ����Ƃ��ĊԂ�
 �Ȃ����ɁA�����鏭�N�̎������悹�āA�����S�O�L���قǂ̃X�s�[�h�Ŏ�s�����𑖂����̂������ƁA���Ȑf�f���Ă���B�ǂ��z���Ă䂭�Ԃ̑S���ƌ����Ă����قǁA�x����Ƃ̎Ԃ�}���悤�ȖڂŁA�i���ɂ͖{���ɏ��Ă���y�������j�U��Ԃ��čs�����̂��ڂɏĂ����Ă���B
�Ȃ����ɁA�����鏭�N�̎������悹�āA�����S�O�L���قǂ̃X�s�[�h�Ŏ�s�����𑖂����̂������ƁA���Ȑf�f���Ă���B�ǂ��z���Ă䂭�Ԃ̑S���ƌ����Ă����قǁA�x����Ƃ̎Ԃ�}���悤�ȖڂŁA�i���ɂ͖{���ɏ��Ă���y�������j�U��Ԃ��čs�����̂��ڂɏĂ����Ă���B���̎�"�����l���Ƌ����������A��ɑ����Ԃɏ��A�������H�ɂ���S���̎Ԃ������Ă�낤"�ƐS�ɐ������B����������������̂͂Q�T�N�O�������B�����̈��ԁA�|���V�F�X�Q�W�̃A�N�Z�������܂œ��ݍ��u�ԁA�O�𑖂��Ă����ԌQ���A�u���Ԃɗy������ɐ������ōs���S�n�悳�𖡂�����B�N��Ƌ��ɑ啪���܂����Ƃ͂����A���܂ɂ��̏��N����̐����H�̕З��h��B�n�C�u���b�g����{�b�N�X�E�J�[�����X�ƘA�Ȃ鍂�����H���A���Ȃ�̃n�C�y�[�X��ۂ��Čy���ɓ��������B
���y���̉w�O�̋�����"�������Ƃ�"�ŁA����`�Ƃ��鋼���̃Z�b�g�i�P�P�O�O�~�j��H�ׂāA�Q�N�Ԃ�̐�����ƕ��C���ŗ��������B�n���̃X�[�p�[�ŁA����̐H�����Ă���k�y���̌ވ䑑�ցB���������t�H�[�������Ƃ��Ŕ����������Y��ȕʑ��B�X�̒��̂��₶�B�́A���J�����Ǝ��ʼnH�ڂ��͂��������ɂȂ�B��X���܂ő傫�Ȑ��ŁA�b�͎Љ�l�^���瓾�ӂ��Βk�ւƈڍs����B���܂��ܗ��Ă�����ߏ��̐l�ɁA"�����傫���ł���"�Ɖ��\�N���U��ł����������炤�B��������̃x�����_�ŁA�����ڂ肷��I���W�����̎p�����z�������������B��������ȕ��i�������낤�ƁA�����܂ݏ����o��B
 ���̓��͂�͂�H�S���ɂȂ̂ŁA�����ꔑ���悤�ƌ������ɂȂ����B���x�͐����̐����ցB���̑O�ɁA�v���Ԃ�̌y��w�ƂȂ����B�܂��͑�߂���B���~�߂̑ꂩ������Ă����̐�ԑ��A���̓�̑�͏��߂Ă������B�L�x�Ȑ��ʂɈ��|����A���̗������Ɋ����A�ܔM�̓����������Y�ꂳ���Ă����ЂƎ��������B�O�ڂ̑�́A�n������N���o�鐅���l�C�̔����̑�B���x���s�����A��Ԗq�ꂩ��̃n�C�L���O�̏I���_�ŁA�M���Ȃ������������ŗ�₵�����̂������B�����Ē��쌧�ƌQ�n���ɂ܂�����O�X�������炵��������B�������z���o�̏ꏊ�ŁA�L�����v���̃��[�X�z�X�e����^�钆�ɏo�����A�����܂œo���Č䗈���������B���傤�ǖ��`�R�̍�����ʂ���I�����W�F�̑��z������o�����̂��A���͎����������^�ȐS�Ō��߂����̂������B���̍��Ɠ����悤�ɁA����������߂��́A�����������ʂ��铻�̒����ŗ͖݂�H�ׂ��B����݂�S�}�A�A���R�ƐF�X���邪�A��͂�卪���낵�̖݂���Ԃ������B�̌n�͑傫���ɂݕω����Ă��A��̊��o�͐̂������ς��Ȃ��悤�ł���B���ꂩ�狌�y���̊X�։���A�����̎U���B�V�����X���o�X���ẮA�����ɕς���Ă��܂����y�̊X�B�������͋C�͕ς���Ă��܂������A���������Ö����"������"�A��◷�فA������X�A�y���ʐ^�قȂǂ͖����Ɍ��C�ɓX���J���Ă����B
���̓��͂�͂�H�S���ɂȂ̂ŁA�����ꔑ���悤�ƌ������ɂȂ����B���x�͐����̐����ցB���̑O�ɁA�v���Ԃ�̌y��w�ƂȂ����B�܂��͑�߂���B���~�߂̑ꂩ������Ă����̐�ԑ��A���̓�̑�͏��߂Ă������B�L�x�Ȑ��ʂɈ��|����A���̗������Ɋ����A�ܔM�̓����������Y�ꂳ���Ă����ЂƎ��������B�O�ڂ̑�́A�n������N���o�鐅���l�C�̔����̑�B���x���s�����A��Ԗq�ꂩ��̃n�C�L���O�̏I���_�ŁA�M���Ȃ������������ŗ�₵�����̂������B�����Ē��쌧�ƌQ�n���ɂ܂�����O�X�������炵��������B�������z���o�̏ꏊ�ŁA�L�����v���̃��[�X�z�X�e����^�钆�ɏo�����A�����܂œo���Č䗈���������B���傤�ǖ��`�R�̍�����ʂ���I�����W�F�̑��z������o�����̂��A���͎����������^�ȐS�Ō��߂����̂������B���̍��Ɠ����悤�ɁA����������߂��́A�����������ʂ��铻�̒����ŗ͖݂�H�ׂ��B����݂�S�}�A�A���R�ƐF�X���邪�A��͂�卪���낵�̖݂���Ԃ������B�̌n�͑傫���ɂݕω����Ă��A��̊��o�͐̂������ς��Ȃ��悤�ł���B���ꂩ�狌�y���̊X�։���A�����̎U���B�V�����X���o�X���ẮA�����ɕς���Ă��܂����y�̊X�B�������͋C�͕ς���Ă��܂������A���������Ö����"������"�A��◷�فA������X�A�y���ʐ^�قȂǂ͖����Ɍ��C�ɓX���J���Ă����B �y��琛���̐����������B�����͍��x����i�ƍ����A�������B�L����̕~�n�ɂ͌F����{�J���V�J���o�v���A���鎞�̓��}�l������Ƃ��ŁA�厩�R�Ƌ������Ă���Ƃ����������킢�Ă���B���̖�͍K���ɂ��ČF���o���A�����t�̃G���L�s�A�m�ŃW���Y���y���B���͂�����o�b�N�O���E���h�E�~���[�W�b�N�ɁA���O�E�n�E�X�̒��̐���ɁA�t�WTV�̃r�[�g�|�b�v�X�̐��X���y�̂悤�Ɂi�Â����āA�����N���m��Ȃ����낤�j���y�ɂ��킹�Ȃ�������t�E���E�̊��`�����B�������A���̊G���������̚q�f�Ɍ�����ƁA�S�����쎟�����ł����B�����N�A���x�͑f�ʂł��ז����āA�����A�ǂ����Ă��t�N���E�Ɍ����Ȃ�������A�ēx�A���킳���Ă����������Ǝv���Ă���B
�y��琛���̐����������B�����͍��x����i�ƍ����A�������B�L����̕~�n�ɂ͌F����{�J���V�J���o�v���A���鎞�̓��}�l������Ƃ��ŁA�厩�R�Ƌ������Ă���Ƃ����������킢�Ă���B���̖�͍K���ɂ��ČF���o���A�����t�̃G���L�s�A�m�ŃW���Y���y���B���͂�����o�b�N�O���E���h�E�~���[�W�b�N�ɁA���O�E�n�E�X�̒��̐���ɁA�t�WTV�̃r�[�g�|�b�v�X�̐��X���y�̂悤�Ɂi�Â����āA�����N���m��Ȃ����낤�j���y�ɂ��킹�Ȃ�������t�E���E�̊��`�����B�������A���̊G���������̚q�f�Ɍ�����ƁA�S�����쎟�����ł����B�����N�A���x�͑f�ʂł��ז����āA�����A�ǂ����Ă��t�N���E�Ɍ����Ȃ�������A�ēx�A���킳���Ă����������Ǝv���Ă���B������ɂ��Ă��A���̓�ӂ͓����̏�����Y���A�u�₩�Ő����Y��Ȗ邾�����B���i�A���R��O��I�ɔr�������i�F�̒��ŁA�g�̉��̎���A���̎��Ȃ����܂��܂ƍl���Ȃ���A�R���N���[�g�̓�������܂���Ă���B�r���̒��̋������ŁA�̐S�Ȏ��ɐG��Ȃ��A���������ȃ}�X�R�~�ɃI�_�������A�y�ŕ֗��ŁA���������ȋ@�B�B�Ɉ͂܂�Ȃ��琶���Ă���B����Ȑl�H�������������A���́A����ȑ厩�R�̐ۗ��̕Ћ��ɐ��܂ꂽ�̂��Ƃ��������A�v�X�Ɏ��������B���ׂĂ̂�����݂͏����A���������ꂽ�S�́A�ق�̈�u�Ȃ��琯��V�����B��C���S�n�����Ă̏I���̗��������B
2010.07.31 (�y) �����̖�
�ߍ��̏����ɂ͂قƂقƎQ��B���ɍ��N�͗�N�ɂȂ��h���ĂɂȂ��Ă���B�����������Ȃ����A�l����̂������ɂȂ�قǂ̏������B�ߓ��A�v�킸�q������ɗǂ������������C�������Ă݂��B�b���Z�����Ă�����A�W�����O���ŏ������̂������Ă���Ղ̋C���ɂȂ����B�R�����ǓƊ������ݏグ�ė��Ĉꋻ�Ȃ̂����A���̂�����ȏ����Ă̎v���o�́A�O����"���w�����b�g"�ɑ����q�����オ�����B���̎q���̎��ɂ́A�N�ł���l�ɂȂ����牽�ɂȂ肽�����H�Ƃ����G���������ꂽ��A���킳�ꂽ����o������悤�ł���B�������A�̕���Ȃǂɑ�\�����`���|�\��A���̓��̉ƌ��A�c���̂Q���R�������͐��ꗎ�������̓�����A������K���h�W�ޓz�ł��A���P�ɂ�鏫�����������Ă���B��ʂł͋ɋH�ɁA���̖�����킸�w�͂Ɖ^�Ŏ���������̂��̂�����B��͂�ƌ����Ă͉������A�c�����̎����̏ꍇ�͐S�Ɍ��߂������Ȃ��A������肪�������킯�ł��Ȃ��A�������ʂɐ����Ă����悤���B���w�Z�̕��W�Ȃǂɖ������A���̏ꂵ�̂���"�����̖�"���������o���͂���̂����A���R�̂��ƂȂ���A���̓��e�Ɋւ��Ă͑S���L�����Ȃ��B�������Ɍ������̂Ȃ��q�ł͂Ȃ��A�肦�ΕK�����Ȃ��I���ȁA���̍������Ȃ��_������I�Ȋ��o��M���Ă����悤�ł�����B
���̏ꍇ�A���ɏ����̖��Ƃ������̌��]�[���ɂ����ẮA�p���������v���o������B������w�Z�ɏオ��Ƃ肠�����l�̖ڂ��ӎ������A�J�b�R�C�C�F����s�m���́A�搶�ɃP�[�L������A�싅�I�肾�̂ƒN�����m�^�}�����̂����A����ȑO�̖��h���ȗc������ɁA���͏���ɕꂩ�炻�̎d�����s�b�^�����ƌ���ꂽ�E�Ƃ�����B
���̎���ł́A���̊Ŕ��猩���Ȃ��Ȃ����̂����A���̎���A���ɋC�ɂȂ�"�����݃}�b�T�[�W"�Ƃ����Ŕ��������B���̎��͓`�ʉ@�̎�O�̘H�n�̓����ɁA���n�ɐ^�����ȕ����ŏ�����Ă����B�܂������ɖ����ʂ����c�t���̒ʉ��H�ł���B
�����A�������������̏A�E��͂��ꂪ�����I�ƕꂪ�������B�����炭������̒x�������A���炩�������A��k�����̂��肾�����̂��낤�B�b�������āA�q�������܂�A���̏o��������ׂ̈ɂ���E�Ƃƕ������悤�����A�����ɂ�����m���߂��킯�ł��Ȃ��B
������D���ȃI�b�p�C�����������ł��������炦��Ȃ�A������ǂ��Ǝv�������Ƃ��o���Ă���̂����A����������͕�̓��������D���Ȃ����Łi���̍��͂����I�j�A�ǂ��̒N��������Ȃ��A�������ςȊ�������I�o�T���̃I�b�p�C�𝆂ނƂȂ�ƁA����̓��_�ƌ������̂��L�����Ă���B���̎��ɕ��o������̏Ί�́A�����Ɏ��̐S�̒��ɂ���B
�ȗ��A���̐E�ƂƎ��̊W���A�ꂪ�y�������ɑc���ɑc��A����Z�ɘb���̂��炩��̏o��v���ŕ��������̂������B���ꂪ�ŏ��̎��̂Ȃ肽���I�ł͂Ȃ��A�����Ă���ƈ���I�Ɋ��߂�ꂽ�E��"�����݃}�b�T�[�W"�ł���B
���o�ɖڊo�ߎn�߂����w�Z�ɏオ�������A�R�������̐S����̊�]�ł͂Ȃ��A���x�̓S�����̎���W�Ƃ������ɂȂ����B���Ƃ��Ɠ����D���ŁA�����Ƃɂ͌��A��A�J�G���A�C���R�A���A���X�V����삯��l�Y�~�A��ɂ͂�������X�o�v����ւ�g�J�Q�Ȃǂ������B����������������A���������ɊW�����d�����������Ə�X�v���Ă����B���ƃS�����̂��������̊W�́A�q������̎��͏������đ��������Ă����B�A�t���J�ɂ���R���S�̃}�E���e���E�S�����̋������ȃI�X�́A�D�ɂQ�T�O�L��������̂������B����ȏ����Ȏ����A�傫���E�܂����S�����ɓ��ꂽ�͕̂K�R�������Ƃ�������B
���傤�ǂ��̎���ɁA���̓������Ƀ��u���ƃU�[�N�ƃu���u���Ƃ���3���̐����[�����h�E�S�����̎q��������ė����B�ނ�����ɁA������s�d�ŏ��ɒʂ��Ă��邤���ɁA�����̖��́A���̊Ԃɂ��ޓ��̎���W�ɂ������Ă����B�������̎d�Ƃ������C������B���̖����A��͂�Ƃ������I�����̐e�ʉ��҂����ɍL�������B���N�̓˔�Ȃ閲�A�S�����̎���W�Ƃ�����������l�����́A�ŏ��́A�w�[�b�I�ƈӊO�����Ȋ�����Ă���A���̌�ꉞ�ɏ����B���x�����̏��a�܂����悤���B�����A���̓����}�ӂ́A���w�Z�̋��ȏ��̉��\�{����Ȃ��̂������B�S�����ɂ�����炸�A�����W�̎d��������̂����̂����������v���o�ɂȂ��Ă���B
�������āA�������ۂɑ�l�ɂȂ��ĉ��ɂȂ������Ƃ����ƁA���R�[�h��Ђ̃T�����[�}���������B�����݂��A�͂��܂��S�����̎���W�A�����ă��R�[�h��Ђ̎Ј��B�ʂ����Ă��̂����̂ǂꂪ�ǂ������̂��́A���̂��߉ޗl�ł��킩��Ȃ��B����A�S���Ȃ������w�҂̐X�B����"�\��ʂ�̐l���Ȃ�āA������������Ȃ���"�ƌ����Ă����B�m���ɃR���܂ł̐l���͗\��O���炯���B�����āA�N����������"�l���A�ꐡ��͈ł�"�Ƃ����i���́A���̃j���A���X�Ƃ͏��X�قɂ���B�q������̎��̏ꍇ�́A�ꐡ�O�̉��ɂȂ邩�����ŁA���ɂ��������E�Ƃ����ɉ����B����������"�l���A�ꐡ�O�͊��m��"�����̍��̎��ɂ́A�ƂĂ����������̌��t�̂悤���B
2010.07.20 (��) ���w�����b�g
�ߑO���̑僊�[�O���p�����Ă���ƁA�A�����J�e�n�̗V�ѐS���鋅�ꕗ�i���f���o����Ċy�����B����A�V�J�S�E�J�u�X�̕����I��̑N�₩�Ȑ��w�����b�g�����Ă��āA"�������̐F�́I"�ƁA�q���̍��̉��������o�������v���o�����B���̎q������́A�L���H�n�ōs�Ȃ������R�Ƀr�[�ʁA���ŋ��ɊʏR��Ɩ������Z���������B�q���������A�悭����Ƃ������Œώςɂ���قǁI�Ȃǂƌ������A�x�ݎ��Ԃ̏��w�Z�̍Z��͂܂��ɂ���ȋ�������B�ߏ��Ƃ̂Ȃ���́A�����������Ɛe���Ȏ��ゾ�����ƋL�����Ă���B
�����A�Ƃ��o�č������Ə������āA�����̏��ꂳ��͂��̋G�߁A�X�̑O�����܂݂�̎����ʂ肩����ƁA�K���Ăю~�߂āA�₽���Ĕ���������ː������܂��Ă��ꂽ�B�����ł͂�����̏������A���J���̎����璼�ڐ������Ɋ܂݁A�^�V������Ƀu���[�b�ƁA����ɂȂ�������f���o�����i���������Ă����B����͂܂�Ŗ��@�̂悤�ŁA�ƂA���Ă���A���X��������̐^���������̂����A���x����Ă����Ƃ͒������A���܂��ĕ���C���т���G��ɂȂ邾���������̂��v���o���B
�̂����ׂ̐��{���ł́A���ꂳ������˒[��c��낵���A�������Ԙb�ɉԂ��炩���Ă���B�傫�߂ȕ������̂悤�Ȃ��̂ŏ��C�������������ĂȂ���A��������Ǝ���܂��Ă����B�����ܑ傫�Ȑ��ŏ��Ȃ���A�ǂ���ꕔ�̋������Ȃ��܂��Ă䂭�B���̉ƂŁA���w���łɒ����͂�܂ł��y���ɂȂ��������������B���R���ƈ���āA����Œp����������₾�������́A�Ȃ��Ȃ����������A�����̃I�o�T���Ǝb���ɂ߂����ɂȂ����̂����������B���̂��т́A���ł͋M�d�Ȕ��т������B�v���Β��̂�����Ƃ���ɐl��╗�����A��l�����l�̎q����������A�a�₩�Ȏ��ゾ�����Ƃ�������B
���̍��̎��́A����Ȃ��ߏ��G�ꍇ���̗����A�e�ɓ����Ŗ����̂悤�ɌJ��Ԃ��Ă����悤�ł���B���̒��ł���ԍD���ȏꏊ�͊Ŕ��ŁA�����̏��������̎d���U�������̂��������y���݂������B�����֗���Ƃ����@�Ƀc���Ɨ���A���������̓h���̓����������B
���������̒�Ԃ������d���́A����̑哹��̓h���A���Ɍ�����V���n�ɂ������ؐ��̃x���`�����F�ɓh��A�����Ɣ��n�ɍ��̊p�����������ŏ����ꂽ"�X�i�L��������"�̓S���A�w�ɕt������������B���̂��ׂĂ̍�Ƃ��E�l�̎�ōs�Ȃ��Ă����B�ԉ��M�ŏ����ꂽ���n�̐��̏���A��~�����͂ݏo�����ɕM�������̂��A���������E���Č�������B
��y��������߂��A�K�R�I�ɖ싅���N���������́A���ɔ����Ă�������w�����b�g����������Ă����B���̎���A�q���̖싅�p�w�����b�g�Ȃǂ͋M�d�ŁA�̂悤�ɑ厖�ɂ��Ă����̂����A���̃w�����b�g�ɂ͗B��̌��_���������B�����̃v���싅�I��̃w�����b�g�݂͂�ȍ��F�Ȃ̂ɁA���̂����̃w�����b�g�̐F�͔��������B���̎������ɂƂ��Ďc�O�łȂ�Ȃ��A���������F�͎�C��y�ɂ܂݂ꂢ�����l�Y�~�F�ɕϐF���Ă����B
��̊Ŕ��ɂ͂������C�ȏ����������B�������͊O�āi�K�C�}�C�j�ƌ����A�ǂ����Ă��̂��������t�����̂��͒m��Ȃ����A�܂��A�ނ̖{�����m��Ȃ������B
�����ŏ_�炩���Ȃ����A�X�t�@���g�͌C�Ղ��c���A������ɗz������������悤�Ȍߌゾ�����B���͂����̔����w�����b�g����Ŕ��̈�K�ɂ����B����ƊK�i�̏ォ��K�C�}�C���q���C�Ɗ��`����"�I�C�A������Ɠ�K�ɏオ���ė�����"�ƌ������B
�����オ���Ă䂭�ƁA�ނ͓�K�̑��ӂɊ�肩����A"���̃w�����b�g�A���ł͂�Ȃ�I"�Ə��Ă���B�ˑR�A�{�S�����ꂽ���͐����o�����ɖق����������B�K�C�}�C�����"���V�b"�ƌ����ăR�o���g�u���[�̑N�₩�ȐF�̃y���L��I���牺�낵�A"�����Ȃ�I"�ƌ����A����������܂܂̃w�����b�g�ɐF��h�肾�����B
�T�b�T�b�T�Ǝ�ۂ悭�A�������M���w�����b�g�̏������悤�ɓ������̂��킩��B
���悢��A����ƔO��̐F�ɂȂ�w�����b�g�B�ł��A�]��ɂ����̎������˂ɂ���Ă��āA�厖�ȃw�����b�g�͎��̓��̏�ŁA�ǂ�Ȏ��ɂȂ��Ă���̂��낤���ƕs���ł��������B
�܂��Ȃ��傫�Ȑ���"�o�������I"�ƌ����Ē��Ӑ[���A���̓�����w�����b�g��������B�Ă̓��������A���ׂ����M�Ղ̒��ŁA���炫���ῂ����x���Ă����B�����ꂽ�����w�����b�g�̓s�J�s�J�Ɍ���A�N�₩�Ȑw���ɕϐg���Ă����B�����������I�{���ɂ����Ƃ����Ԃ̌����ȐE�l�Z�������B����ȗ��A�K�C�}�C����͎��̉��l�ɂȂ����B
���v���A�����͍����n���������Ȃ����ゾ�����B���Y���m������O�ɏo��ƁA�|���J�~�i���I���W�ɔN��̂����߂��q�A�K����������ʂ钋�Ԃ̐��������ɁA�������Ӓn��������������B�����ĉ������S�Ɏc��A�������̗D�����ɂ��o������B�����ɐ����鎖���A�݂�Ȃ����Y���̂Ŏ~�߂����ゾ�����B���̂����鏊�ŁA�q�������Ƒ�l�������ӑR�ƍ����荇���Đ����Ă�������Ƃ�������B
�V�J�S�̕����I��̐^���ȃw�����b�g�́A���̉����������̎��̏o�������A���R�Ƒh�点�Ă������̂������B
2010.05.19 (��) �J�̓�
�����ւ��Ē������ǂ��V�C�������Ă������A�����͉J�B�v�����̏t�͂���ȉJ�������A���g�̍�������A��������~�̃R�[�g����ւ��Œ��������������B����ƐS�n�悢�����������������ł�����A��n���ŗh��Ă��鉫��ł́A���Ɉꕔ�~�J����Ƃ̂��ƁB��͂肱�̋G�߁A�����͐��̍��ɐ����Ă���̂��Ƃ����v��������B���̉J�̕������c���獪�t�������{�ɂ́A�����ȉJ�̌Ăі��������B�t�ƌĂ�ł����捠�܂ł́A�t�J�i�͂邳�߁j���~���Ă����B���Ă��߂��������̉J�́A�܌��J�i���݂���j�Ƃ����f�G�ȌĂі��������Ă���B���̎����A���J�i�������j�Ƃ����t�ɍ~�肩����J��A�ΉJ�i��傭���j�Ƃ����V�̍��ɍ~��J�̌Ăі�������炵���B����ȉJ�̌Ăі����ƁA�����Ƃ�Ƃ�������������A�������ɂ����̐��ɂ܂Ŏv����y���Ă��܂��B�J���A�܁A���v���A����Ȍ��t���ǂ��������J�̓��B
�̂̐��E�ł��A�J���^�C�g���ɂ�����i�̃q�b�g�������A��������ɂ����ʼnJ���̎��Ɏg�������Ȃ͐��m��Ȃ��B�J�ɗ��ٍ��̋Ȃ������A�Â���"�߂����J��""�J�̓��ƌ��j����""�J����������"�ȂǂȂǁA�J�Ɋ�v���͖������ʂƂ������Ƃ��납������Ȃ��B���A�Ẵ~���[�W�J���f��"�J�ɉ̂���"�̗L���ȃ����V�[���ɁA�ꔲ���ɖ��邭�͂��Ⴎ�W�[���E�P���[������B�J���傢�Ɋy�������Ƃ����A���Đl�̋C����V�ѐS��傢�Ɋ��������鏊�ł͂���B�}�����{�ɂ́A����X�̎ւ̖ڎP�A�I�c��_�Е��t�̌Òr�Ȃǂɂ��������́A�Î�ȉJ���悭�~��悤���B
���̖L�x�ȓ��{�ɏZ��ł��鎄�����ɂ́A�����Ђ˂�ƖL�x�ɏo�Ă��鐅��������O�����A�C�̌������ł͎������Ă���B��̑O�A�^�N�V�[�̉^�]�肳�畷�����Y����Ȃ��b������B���ߓ��̌�̂������{�ɗ����ہA"�厖�Ȉ��ݐ����A�g�C���ŗ������Ɏg���Ƃ͂��������"�ƌ��{�����������B�ٍ��ɂ̓R�b�v��t�̐��ŁA�g�̑S�̂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l��A�������L��������܂ŕ����āA���̓��ɕK�v�Ȑ������݂ɍs��������q������������B�������{�ɐ��܂ꂽ���́A����������Ƃ��đ����鎖�͓���B ���ɉJ�͉͐��×������A�R��R������đ�ςȍЊQ�������炷���Ƃ�����̂����A�����̐l�������̂悤�ɕ��C���g���A���ꂽ���ɂ͐�������Ȃ���A�S�n�悭�߂�������ɐ����Ă���B�U��Ԃ�A�J�Ƃ������������V�Ɋ��ӂ��A�b�܂�Ă��邱�Ƃ���ɔc�����ׂ��Ȃ̂��낤�B
���̉J�̍��ɐ��܂ꂽ���ɂ��P�̑z���o������B�w�Z�A��ɁA�������\��ʂ�̂ɂ킩�J�ɂ��������̎��B����悭�P�������Ēʂ肪�����������̖̑O�A�����ɘȂ�ł��鏗�i�ЂƁj�Ǝb���ڂ��������B��������N��̃V���[�g�w�A�̑f�G�ȂЂƂŁA�ˑR�̉J�ɓr���ɂ���Ă���悤�������B�Ⴓ�ƏƂꂭ����������A�ǂ����Ă�"�ǂ���"�̈ꌾ���������A�P�������|�����Ȃ��������̎��A��딯���䂩���v���ŗ��������Ă��܂����B�b�����āA�_�c���n������_�ŐM���҂������Ă�����A����������\����Ȃ������ɂ��Ă����̔ޏ��ƁA�g�̂̊ۂ��������̃I���W�i�܂�ō��̎��̂悤�ȁI�j���A�A�C�A�C�P�ł������ɂ���ė���̂��������B���͓�����悤�ɉƘH���}�����B���g�ƌ�������荬����A���ꂢ�J�̑z���o�ł���B�������A���̏��i�ЂƁj�������̍D�݂̃^�C�v�łȂ�������A�ʂ����āA����Ȏv���o�ɂȂ����̂��낤���H�ƌ����̂��A���̋U�炴��ЂƂ育�Ƃł���̂����E�E�B
���ɉJ�́A�l��D��������͂�����B�[�ŕY���J�̒��A�P�������čs���Ȃ������l���Ƒ�����l�����R�̂悤�ɉw�Ɍ}���ɍs�������オ�������B�d�Ԃ������A���D���o��l���݂̒��ɂ��̐l��T���B���m�N���[���̗₽���J�͍~�葱���邯��ǁA�A��g���A�҂g���ق�̂�S�͉������B����ȃV�[�������x���ڂɂ������Ƃ�����B���ꂩ��n�܂�~�J���ɁA����ȏ��a�̖Y��`���̂悤�Ȍi�F���A���Ăь��Ă݂����Ƃ��v���B�͂����Ă��̐S���q�����P�A���̓R���r�j��w�̍\���ȂǁA�ǂ��ł��ȒP�Ɏ�ɓ���B�����◘���̂��ƁA�l�̎{��ɂ���Đ��܂ꂽ�֗������A�c�O�Ȃ���l�̉�������J����A����Ə����Ă䂭����ɂȂ��Ă��܂����̂�������Ȃ��B
2010.05.08 (�y) ���炱
�S�[���f���E�C�[�N���I���Ԃ̏a�������A�V���������G�߂ɂȂ����B���̊��ԁA�ߍx�̃A�E�g���b�g��|�����̒T���̃f�p�n���ł��߂������ƌ��߂�������̂��ƁB�܂�����Ă��܂����Ƃ����o�������������B
�s�͂�݂̖��ȁA"��サ����"�̂Q�Ԃ̉̎��ɏo�Ă��铰���B�D���ȉ̂Ȃ̂Ŏ��ɂ͓���݂̂���n�������A�����炭���̏ꏊ�ō���Ă���̂��낤�B�������[���Ƃ����T�b�p���n�ʼn��C�ɔ����������[���P�[�L�ƁA�����̈ɐ��A���o�X���Ă���A���̂��ˁi���Ă��Ɍ���j��ړ��ĂɁA�ɂɔC���ē��{���̓�̃f�p�n�����n�V�S�������̂��ƁB
�����̂悤�ɁA�����ȐH�ނ����Ȃ���{�P�b�ƕ����Ă����̂����A�����Ȃ�j���[�b�ƃT�[�����s���N���Y��Ȃ��炱���@��ɏo�������B���̂��Ƃ͖����A�|�����߂����Ȃ������A����Ă͂����Ȃ����H�̎n�܂�ł���B�А��̂������Z����A���̓��͋q�����Ȃ��A�n���ʂ����ĕ����ė��������J�����A�����[�g���O����_���Ă����悤�ł���B
�v�킸��Ɏ���Ă��܂�����H�ׂ邵���Ȃ��B���ɉ^�ԂƁA���ꂪ�Ȃ�Ƃ��É��ŗ��̍d�������傤�Ǘǂ��B������"���炱"�����A���̔����ɂ�����Ɗ����B
"�X�[�p�[�����ɏo��Ȃ����炱����"�Ȃ�ĎE��������ꗬ�H�ŁA�H���Ӓn�̒��������̋Ր��ɐG��邱�Ƃ������B�������܂�ł���B
"�悵�A�������i�A�C�E�E�B���E�e�C�N�E�f�B�X�H�j"�B����ɂ��Ă��悭�悭����A�傫�����h�Ȃ��炱�ł���B"�傫������̂ň�{�ł�����"�ƌ����ƁA��{�ň�ɂȂ��Ă��āA�����ɗ����ƕ���Ă��܂��Ƃ̎��B���傤���Ȃ��̂łЂƂ͂甃���B�����̂��Z����̌������킯�ł͂Ȃ����A�]��A���~���ɂł����ŗⓀ�Ƃ����������B�����āA��Ɏ�������炱�̒l�D���݂āA�������瓮�h�ւƎ��̐S�͕^�ς���B���Ƃ��炱�ЂƂ͂�ŎO�玵�S�~���z���Ă���B�������悤�����A���r����Ȃ��A������"���炱"�ł���B
�A��̎Ԃ̒��ł͎��R�Ɩ����ɂȂ��Ă��鎩���ɋC���t���B���̎�`�Ƃ����傰���Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂����A�Ƃ肠�����̔������ł��A���̉ߒ����y�����Ȃ���Ηǂ��������Ƃ͌����������B�����Ƃ��̒��O�܂ŔY���������A�����Ă��̓X�̋�C��X���̑ԓx�i�ܔԊX�̃e�B�t�@�j�[���܂ł͋��߂͂��Ȃ��j�Ȃǂ��A���̒l�i�Ɋ܂܂�Ă�����̂��Ƃ����l�������ɂ͂���B���ʁA�����̐����Ŕ����Ƃ����A��ψ����Ȃ�����B���ɋ��Ȏ��H�Ƃ����������邪�A����͐�Ɉ����Ȃ��o���Ƃ��������悤���Ȃ��B
����́A���s�����܂ł��c��ߗނȂǂɔ�ׂ�ƁA�H�ׂ����Y��T�b�p�������������I���A���܂ɂ͂����������������ǂ����낤�Ɗ�����Ďv�����ɂ����B�����āA����Ȃ��Ƃł����Y��ł��鎩�����A����Ɏv���Ă����B
�[�H���̎q�������i���ɑ�l�����j��"���܂ŐH�ׂ����ŁA��Ԕ����������炱���ė�����"�Ƒ傰���Ɍ����Ă݂��B�S�̒ꂩ��̋��тł���A�H�ׂ�O�̈��̐��]�ł���B����ƁA�S�����{���ɔ��������ƌ����āA���q�͂��т��R�t������肵�A���̎��̓����݂�ȂŃ\�����y���B���ꂩ��A�������o�����������A���̗]�������炱�͑厖�ɗⓀ�ɂɎd�����Ă���B���������āA��ϗǂ��������������̂�������Ȃ��ƁA���͖����Ɏv�������Ă���B
�V�������Ă�TV�����Ă��A�}�X�R�~�̓G�R���I�����Ă悢�i�I�|���X�I�ƃo�����[�t�H�[�}�l�[�����肷��قNj���ł���B�����鎞�ɁA�݂�Ȃ��݂�ȃ��j�N����}�b�N��x�m���ł͖ʔ����Ȃ��B����Ȃɍ��z���̋L���Ɏc�邽�炱�͂����͂���܂��B
�����s�͐����̌����ł͖����A���s���킩��Ȃ������͎��s�Ƃ͌��킸�A���s�������ƌ��_�������܂łɂ́A���ꑊ���̎��Ԃ�������Ƃ������B����������Ƃ��̂��炱�A���ɂƂ���"�Y�ꂦ�ʃo�����[�t�H�[�}�l�["�������̂�������Ȃ��B
2010.05.01(�y) ������
"�ЂƂ育��"���������ɂR�����A�������T�{���a�ł���B���傤���Ȃ��̂œk�R�Ƀp�\�R���̃L�[��@�����ɂ����B�����������́A���w�Z�̉ċx�݂̏h��ȗ��A�p���I�Ɏ����̏o�������L�^����Ƃ����ߑ��������̂�������Ȃ��B���̏t�ɂ́A�����̐��l���A�����̑�w���w�A���j�̍��Z�Ɠ��w�B���ꂼ��̎q�������̐ߖڂ�����A�g�߂ɉ����ƃC�x���g�������Ă����̂����A������l�^�ɏ����ƂȂ�ƁA"���}�Ȏ��̍K��"�Ƃ������A���������ǂނق����A���ɖʔ����Ȃ����ɂȂ�B�K�R�I�ɉv�X�M���i�܂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
����ȍQ�������X�̒��ŁA����A���̒��w�E���Z�̓�����Ȃ���̂��������B������v�悵���̂́A�ȑO"�ꔑ���s"�Ƃ����ЂƂ育�Ƃ����������̃����o�[�ł���B���̍��A�^�ʖڂ��s�ǂ̓�ґ���ƂȂ�ƁA�ǂ��Â����Ă��A�ԈႢ�Ȃ���҂ɓ�����ʁX�ł���B �j�q�Z���������̓�����ɏW�܂����̂́A��ɍZ���ɂȂ�������l�A����ɑ̈�A���y�A�����A����A���w���e���̐搶���ƁA��U�O���̐��k�����B���k�����́A���̊w�N����ԏ�ŁA���̓���̊w�N�܂ł̎O�w�N�������B�Ƃ͂����A�������낻��U�O�ɓ͂����Ƃ����N��Ȃ̂ŁA�����I���W�B����ł���B���ɂ͐搶��������y�Ɍ�����y������������B
 ��͐��߂̎��ԂɎn�܂�A���̍ŏ��̐���オ��́A��{�搶�̏Љ�̎��������B�p��̋��t�������ޏ��́A�������ɁA���w����������X�̃N���X�A�S�V�l�̈�l��l�ɉp�ꂪ���g�߂ɂȂ�悤�ɂƁA���Đl�̖��O��t�����̂��B���������k�ɂƂ��ẮA�|�\�E����Ō����A�|���⌹�����������悤�Ȃ��̂ŁA�����ӂ����ẮA���̖��O���Ăэ����Ă͊��ł����L��������B�����āA�����ɏW�܂�����l��l���A���̍��̖��O�𗧂��Č������ɂȂ����B�T���A���B���Z���g�A�n���X�A�G���b�N�A�����Ă��悢�掄�̔ԂɂȂ�A"�r��"�Ƒ吺�Ō������B���̃N���X�̎Q���͂Q�O�l�قǂ��������A�S���������̌������H���o���Ă��āA���̓s�x����ɂȂ����B�����������O���Ă��邤���ɁA�܂�Œ��w�̉p��̎��ƂɃ^�C���X���b�v�����悤���B�������A���ꂼ��̖���t������{�搶�̂��w�͂����邱�ƂȂ���A�S�O���N�O�̖��O���o���Ă����A��X���k�̋L���͂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��ƁA���掩�^�̏��̉Q�ɂȂ����B����������Ƃ���ɂ��ƁA�搶�͉�X�̋L���ɁA�������������ꂽ�������B
��͐��߂̎��ԂɎn�܂�A���̍ŏ��̐���オ��́A��{�搶�̏Љ�̎��������B�p��̋��t�������ޏ��́A�������ɁA���w����������X�̃N���X�A�S�V�l�̈�l��l�ɉp�ꂪ���g�߂ɂȂ�悤�ɂƁA���Đl�̖��O��t�����̂��B���������k�ɂƂ��ẮA�|�\�E����Ō����A�|���⌹�����������悤�Ȃ��̂ŁA�����ӂ����ẮA���̖��O���Ăэ����Ă͊��ł����L��������B�����āA�����ɏW�܂�����l��l���A���̍��̖��O�𗧂��Č������ɂȂ����B�T���A���B���Z���g�A�n���X�A�G���b�N�A�����Ă��悢�掄�̔ԂɂȂ�A"�r��"�Ƒ吺�Ō������B���̃N���X�̎Q���͂Q�O�l�قǂ��������A�S���������̌������H���o���Ă��āA���̓s�x����ɂȂ����B�����������O���Ă��邤���ɁA�܂�Œ��w�̉p��̎��ƂɃ^�C���X���b�v�����悤���B�������A���ꂼ��̖���t������{�搶�̂��w�͂����邱�ƂȂ���A�S�O���N�O�̖��O���o���Ă����A��X���k�̋L���͂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��ƁA���掩�^�̏��̉Q�ɂȂ����B����������Ƃ���ɂ��ƁA�搶�͉�X�̋L���ɁA�������������ꂽ�������B�����ĉ��y�̒����搶��"�I�[�E�\���E�~�[�I"�̓��X�̓Ə��́A�����̉��y���Ɠ��̕��͋C���h��B�₪�āA���k�������e�Ő搶��w�Z�W�҂ɕt���Ă����A�������̍����^�C���ɂȂ����B���N�U�̂悤�ȕ��e�̒J���搶��"�^�j��"�A���^�ʖڈ�{�̕l���搶��"�n�}�`���["�ƂȂ�A�������w���ɁA�������܍��̗p��������ɂ�"�R�{���i�V�����w�[�j"�ȂǁA�������猾����H�����������A���ɂ܂�Ȃ�����������яo���Ă����B�搶���̒��ɂ́A�S�����₩�Ȃ�ʕ��������͂����B
�����ł͂��邪�A�N��ǂ����ƂɁA�������܂������Ԃ̌o�߂������Ɗ�����N��ɂȂ����B�c�����c�钆�w����̎ʐ^���A������̃e�[�u���ɒu���Ă������B�N�����P���Ă������̍��B���B�̂���܂ł̐l���ɂ́A���x���̍��܂ƁA���x���̉����܂ɕ�ꂽ�����������͂����B����Ȏv����Ƃɍĉ�̊�тɐZ�������B�搶���͂V�O�ォ��W�O��̔N��ɂȂ�B�W�܂����l�̒��ɂ́A�����炭��������Ƃ��Ȃ��l�����鎖���낤�B�o��ƕʂ���J��Ԃ����X�̒��A���̏t�A�������S�n�悭���ꂽ�y�j�̒������肾�����B���̂ЂƎ������ł��A���̍��ɖ߂ꂽ����������݂̂�Ȃ̏Ί�B�I���W�B�̐t�̃J�P���͂ӂ�ӂ�ƁA�r���̂����Ԃ̕��ɏ��A�Ȃ��P���S���̐�ɕY�����I�E�E�悤�Ɍ������B
��L�F ����̖锼����~�葱���₽���t�̒��J�A�J�_�̐�Ԃ��甖�����������R��Ă���B����߂Ȃ���A�S�̒��łԂ₢�Ă݂�@"���̓��͊m���ɂ�����������"�ƁB
2010.02.18(��) �m���Ȃ���
����ȔN�ɂȂ��āA���X�Ȃ���l�̗���̈Ⴂ�ɁA���X�v�������ʎ���m��B�ǂ��q���̍��ɐ搶��e����"�l�̗���ɂ����čl���s������悤��"�ƌ���ꂽ�̂��A�F������o�����ꂽ�����낤�B����͐l�̗���ł͂Ȃ��A�����̗��ꂪ�S�z�ȈׂɋN���邱�Ƃł͂���̂����A���͐̂���f�p�n����n�����Y�W�Ȃǂŗǂ���������A�����H�Ȃ���̂��A�o������������l�ɂ��Ă���B��������Ă��܂��ƁA���A����Ȃ�������Ȃ��悤�ȋC�ɂȂ�̂��B"���y���l"�ƌ����āA���肰�Ȃ�����������̂����ł���B�ǂ����ɐH�������Ƃ����߂̈ӎ��������Ă���̂�������Ȃ��B�����Ė{���ɔ����ӎ������鎞�����͎��H���Ă݂�B������X������ɂƂ��Ď��́A�ƂĂ������̂�����q�ƌ����邾�낤�B�����A���̂悤�ȗ��V�ȋq�͂����H�炵������m�����B����́A����̃o�����^�C���f�[�ɂȂ�܂ł̂Q�T�Ԃ���A�����Ŗ炷�f�p�n���ŁA�`���R���[�g����̃A���o�C�g�����Ă��������畷�������b�ł���B�Q�C�R���ŁA�L���`���R���[�g�E���[�J�[�̔�����S�����A�Ί���₳���A�������邭�����b�g�[�ɁA�����炩�ɔ��邻���ł���B���̎��A�K�����H�^�C���Ȃ郂�m������̂����A���̎��̔ޏ����̋ɔ�̉̂����邻�����B"�|�b�|�b�|�A���|�b�|�A�����~�����������邼�`" �������q�ɂ͐�ɕ������Ȃ��悤�ɁA�����Ȑ��ʼn̂���B�����ĊԂ��Ȃ��o���ꂽ�A��M�ɏ������R�̎��H�p�`���R���[�g�́A���܂ʼn����ɂ����̂��낤�Ƃ������炢�A�����̏������������b�ƏW�܂��ė��ẮA�ЂƂ�������c�����ƂȂ��A�u���Ԃɖ����Ȃ邻���ł���B���̌��i�́A�܂�Ő_�Ђ�����ɎT���ꂽ�A�a�ɌQ���锵�̂悤���Ƃ����B���̉̂��A���̏��C�x���g���s�Ȃ���O�̂Ƃ��āA�▭�Ɏ����������ł���B���R�̂��ƂȂ���H�ׂ��q�̑����́A����A�قƂ�ǂ̋q�͉��H��ʁH��ŗ��������Ă��܂��������B�`���R�̖���������l�i�j�j�ׂ̈ɁA�^���ɋᖡ���鏗���q�i���̂��I�o�T���������������j�̗���͋����B�ق�̐��p�[�Z���g�̊m���ł̔����s��B���̋����y����k�Ŏ����A���ׂ̈ɂ͊i�D�̉̂Ȃ̂��������B
���̘b���āA���̗���ɗ����Ȃ���킩��Ȃ����ƁA���̗��ɂ͂��낢��̊肢��v�f��������̂��ƁA���܈�x�čl�����̂������B���̐́A�͎d���̘J���ɂ́A�S�������̓��̂ɐV���ȗ͂��Ăэ��ވׁA��ۂƂȂ��ĉ̂�ꂽ"�悢�Ƃ܂��̉�"��A�A�����J�ł͓z�ꐧ�x�ɂ��A�h���J�������"���l���"���������B����Ȑ[���ȐS�̋��тƂ��v���闧�h�Ȏu�Ƃ́A�啪��������Ă͂�����̂́A�܂ꂻ���ȐS���x���悤�ƁA���C�ɂȂ��S�̉́B��ΓI�Ɉ̂�����ɂ���q�ɁA����閧�̋t�P�̂Ƃ��āA���C���ǂ�������̂�����B
���̃o�����^�C���f�[�ɂ͂������Ȏv���o������B�������̎Ј����������̂��ƁA��Ђ̏�i�ŁA���̓��ɂȂ�ƁA�`���`���R��������̏�ɐςݏグ��j�������B�N���ǂ����Ă����̐l�ԂɁA�S����`���R���[�g�������鏗���Ȃǂ���킯���Ȃ��̂ɁA�K�����̎����ɂȂ�ƁA���肸�ɖ��N���������Ă����B�����̓��e���j���Ƃ����A�����ɂ͐Ȃ����Ȏ咣�̗��ꂪ�����āA�����鏗���ɂ��d����̋`���ƁA��l�������c����܂��Ƃ����d���̗��ꂪ����B�����Ă��̏���₩�Ɍ��߂�Ⴉ�������B�B���ꂼ��̎v�f��肢�̂��ׂĂ��A�K���X�̔��̒��g�̂悤�Ɋی����ɂȂ��Ă����B
���邭���C����f�p�n���̔�߂�ꂽ�̂̈ӊO���ƁA�A�b�s�[���������j�̊쌀�I�K�R���B���N�̃o�����^�C���͓��j���������B�ʓ|�ȋ`���Ƒ����̏o���~��ꂽ����������A�Ⴆ�邩�Ⴆ�Ȃ����A���\�s�����������̒j�����ɂ��A����Ӗ��~����������������Ȃ��B���َq��Ђ��d�|�����A�o�����^�C���Ƃ������̃w���e�R�ȕ��K�ɂ́A�ߊ삱�������̐S�̗��ʂ肪����B����������l�Ԗ͗l�Ɉ��D�Y������������B
2009.12.28(��) �v���[���g
 �������̂ō��N���c�肠�Ƃ킸���ɂȂ����B�����֗��Đ���܂ł̊����܂��A�D���������������₩�ȓ��������Ă���B�������܂ł́A�X�ɂ̓N���X�}�X�̏�������Ȃ���A��̉̂�����Ă����B�N�̐��̋�C�́A�Q�����̒��ɉ���������������āA�C���~�l�[�V�����̌��̒��ŐS���e�ށB�q���̍��A���̎����ɂȂ�ƃv���[���g�₨�N�ʂ̂��Ƃœ�����t�ɂȂ��āA���������l�Z�����l���Ă����悤�ȋL��������B���Ƀf�p�[�g�ɘA��čs���Ă��炢�A�D���������`���R���[�g�p�t�F��H�ׁA�ړI�̃v���[���g���Ă���������̓��̂��Ƃ��h��B
�������̂ō��N���c�肠�Ƃ킸���ɂȂ����B�����֗��Đ���܂ł̊����܂��A�D���������������₩�ȓ��������Ă���B�������܂ł́A�X�ɂ̓N���X�}�X�̏�������Ȃ���A��̉̂�����Ă����B�N�̐��̋�C�́A�Q�����̒��ɉ���������������āA�C���~�l�[�V�����̌��̒��ŐS���e�ށB�q���̍��A���̎����ɂȂ�ƃv���[���g�₨�N�ʂ̂��Ƃœ�����t�ɂȂ��āA���������l�Z�����l���Ă����悤�ȋL��������B���Ƀf�p�[�g�ɘA��čs���Ă��炢�A�D���������`���R���[�g�p�t�F��H�ׁA�ړI�̃v���[���g���Ă���������̓��̂��Ƃ��h��B���͎Ⴂ���������S���Ȃ�ꂽ�A�X�ɂ���̎В��V���[�Y����D���������B�ނ̕�����n�߂Ċς��̂̓~���[�W�J��"�����̏�̃��@�C�I�����e��"�ŁA���̌�A���{�̃f�B�X�N�W���b�L�[�̑������I���݂ŁA���R�[�h��Ђ̋삯�o����`�}���ł����������A�悭�L���̂�����ɂ܂ŏ��҂��ĉ��������A�����ܘY����̏o�ŋL�O�̃p�[�e�C�[�ł����Ƃ�����Ă���B�A�i�E���T�[�Ƃ��Đ�y�ƌ�y�̊W�������ƁA���̎��ɏ��߂Ēm�����B
��T�̎��A�₵������������"������ׂ�В�"�Ƃ����X�ɂ���̃V���[�Y�̈�{���������̎��������B���̉f��A���{�����x�����̎�����}���A�C�܂܂ȃ����y���������y����ł���Ƃ����̔ނ��A�ȑO�ɋ߂Ă����ߋ�[�J�[�̑㗝�В����A�R�����Ԃ������܂�A�Ǝ��̃J���[��ł��o���Ȃ��犈��Ƃ����X�g�[���[�������B
���̃I�[�v�j���O�̉f���ɁA�i���g�I�����c�����ɃN���X�}�X�E�v���[���g�Ŗ�����S�����̂������Ⴊ�o�Ă����B���̎��͂��̙��߂��v���o���A�v�킸�W�[���ƂȂ��ĉ�ʂɓB�t���ɂȂ����B���R�̂��ƂȂ���A����Ȏ��ł����^���C�Ȏq�����オ����A�T���^�N���[�X���{���ɂ�����̂��ƐM���Ă�����������B
���̃v���[���g�́A����܂Ŗ�����ǂ̃v���[���g������ۂ��[���A�������ꂽ�T���^�N���[�X�ƌ��ʂ������̂��̂������B
�̓��̎t���ɓ��������鎞�A�ꂪ�f�p�[�g�̂������ᔄ���ŁA���̃S�����̂������Ⴊ�ʔ����ƁA���Ɏ��X�Ɍ����������������B�����炭�ꎩ�g���A�ȑO���炱�̂���������C�ɓ����Ă����悤�ł���B�ǂ�Ȃ��̂��ƌ����ƁA�����Ȃǂł��悭��������A�R���N�e�̃s�X�g���ŁA�g�̏�Q�T�Z���`���̃u���L�̃S�����̐l�`��_���B�����āA�e�����̊ۂ��ӏ��ɓ�����ƁA�ڂ��Ԃ��s�J�s�J�ƌ��肾���A"�E�@�[�b"�Ɠ{�����悤�ɐ����o���Ȃ���A�o���U�C������悤�ɗ����������Ƃ����㕨�������B���̎���ł��A���̖ʔ����͏[���ʗp���邾�낤�Ǝv����B���̍��A�ߏ��̌�y���V���n�ɏo�����Ă͂悭�V�A�싅�I��̊G�ɓ�̃{�[���𓊂��āA�^�̕����o���ӏ��ɓ�����ƁA����̃T�C�����Ɠ����悤�ȑ傫�ȉ�����o���Q�[���ƁA�����͓����������悤�������B
�����āA�悤�₭����Ă����N���X�}�X�C�u�̖�A�����炭���̃S�����̂���������T���^������鎖�ɂȂ��Ă���̂��ƁA���ȗ\���͂��Ă����̂����A���̖�͂��ɂȂ��Ă��Q�t���ꂸ�ɂ����B���̂����ɉ���������"�E�@�[�b"�Ƃ����@�B�I�Ȑ��Ƌ��ɁA�����̏������������Ă����B���v���ɁA���ւ̃v���[���g��n���O�ɁA�S�����̎����쓮�H�����Ă������̂��Ǝv����B����Ȑ����������Ă���ƁA�����̂��܂�v�X����Ȃ��B
���ꂩ��b�����āA�ꂪ���̖����ɂ���ė���"�����A�܂��N���Ă���"�Ǝ����Ś����Ȃ���A��̃v���[���g��u���Ă������̂��o���Ă���B�e�q�̒��Ƃ͂����A����͐m�`�ɔ����鎖�ƁA���͈ꐶ�����Q���ӂ�͂����̂����A���F�͎O�����ҁH�̎q���̉��Z�A��ɂ͉��ł������ʂ��������悤���B�ȗ��A��͂�T���^�͗��e���������Ƃ��A�m���ɂȂ������̖�̎���Y�ꂸ�ɁA�����Ɏ����Ă���B
 �V�����Ղ̔N�����������n�܂�B�����ł������̎q�������ɗD�����T���^�����Ă���Ă��܂��悤�ɁB�����đ����ɂ�����炸�A�Ί�ł��N�ʂ��Ⴆ�܂��悤�ɂƊ肤�B
�V�����Ղ̔N�����������n�܂�B�����ł������̎q�������ɗD�����T���^�����Ă���Ă��܂��悤�ɁB�����đ����ɂ�����炸�A�Ί�ł��N�ʂ��Ⴆ�܂��悤�ɂƊ肤�B����͎��̋��̕Ћ��ɂ���A�lj��̏o�����ł���B����܂ł͑z�����炵�Ȃ������A���{��`�̋Ȃ���p�ɗ��Ă��܂����A�����̐h�������̔N�̐��Ɏv�����B
�e����q�ցA�����Ă��̎q���瑷�ցA����Ȃق̂ڂ̂Ƃ����z���o�̌J��Ԃ����A�D�������܂ł��l�̐��ɑ����ė~�����Ɗ肤�B
2009.11.30(��) �e�q�̊W
���~���}����������A�����̑|�������˂Ė{�̐��������Ă����܁A"��l"�Ƃ�����N�̏t�ɔ�������Ă����G������ɂƂ��Ă݂��B�����Ƃ��߂���Ƃ����̐S�Ɏc�����A�l���ς�ς�������������Ă��鋻���[�����̂������B�吨�̑I�l�Ō��߂鉽�X�܂Ȃ���̂ɂ́A�S�R�������킩�Ȃ��̂����A���𐬂�����Ƃ��ƒf�ƕΌ��őI��i�ɂ́A���Ȃ苻������������B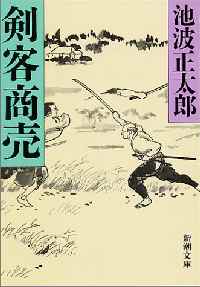 ���̒��ŎR�{��͎������㌀�����̌���Ƃ��ċ����Ă������̂�"���q����"���������B���͒m��Ȃ������̂����A�s�u�ł��l�C�������悤�ł���B���܂��ܐ���A�����̊w���Ղ��L���Ă݂��ہA����X�O�~�Ƃ��������������ŁA���̌Ö{�𐔍���ɓ��ꂽ�B��҂Ɏ��b�قǂ���e�[�}���A���̓s�x�b���������Ă����̂ŁA��������ł������Ă����ēǂ݂₷���B�������A��J�ɂ��鎄�̕��A����ݐ[�������̒������������ɏo�Ă��āA���̕`�ʂ����ɐ��m�Ȃ̂ɂ͋����B������Ƃ����]�ˎU���̋C���ɂȂ��̂��A���̃V���[�Y�̖��͂ł�����B��҂ł���r�g�����Y���́A�����炭�]�˂̌Òn�}�Ў�ɁA�Ȗ��Ɍ���̓�������������̂Ǝ@������B���A�ނ͍L���H�ʂŒm���邾���ɁA���C�Ȃ������ɏ�����Ă�����̍�⋼���̘b�́A���D���̎����y���܂��Ă����B���̕���͕��Ƒ��q�̋����J���S�҂ɗ���Ă���B���̓�l�̐▭�ȊW�����݂����x���A��������߂�����̍��ɐ����Ă��鎄�ɂ́A���ꂪ�V�N�ŐS���a�ށB
���̒��ŎR�{��͎������㌀�����̌���Ƃ��ċ����Ă������̂�"���q����"���������B���͒m��Ȃ������̂����A�s�u�ł��l�C�������悤�ł���B���܂��ܐ���A�����̊w���Ղ��L���Ă݂��ہA����X�O�~�Ƃ��������������ŁA���̌Ö{�𐔍���ɓ��ꂽ�B��҂Ɏ��b�قǂ���e�[�}���A���̓s�x�b���������Ă����̂ŁA��������ł������Ă����ēǂ݂₷���B�������A��J�ɂ��鎄�̕��A����ݐ[�������̒������������ɏo�Ă��āA���̕`�ʂ����ɐ��m�Ȃ̂ɂ͋����B������Ƃ����]�ˎU���̋C���ɂȂ��̂��A���̃V���[�Y�̖��͂ł�����B��҂ł���r�g�����Y���́A�����炭�]�˂̌Òn�}�Ў�ɁA�Ȗ��Ɍ���̓�������������̂Ǝ@������B���A�ނ͍L���H�ʂŒm���邾���ɁA���C�Ȃ������ɏ�����Ă�����̍�⋼���̘b�́A���D���̎����y���܂��Ă����B���̕���͕��Ƒ��q�̋����J���S�҂ɗ���Ă���B���̓�l�̐▭�ȊW�����݂����x���A��������߂�����̍��ɐ����Ă��鎄�ɂ́A���ꂪ�V�N�ŐS���a�ށB������܂ŏ�f����Ă���"�K���̓V�����\�j�A���ꂩ��"�Ƃ����t�����X�f������R�ɂ��A���Ƒ��q�̈������̃e�[�}�ɂ������B�P�X�R�U�N�̃p���̉����B���E�s���̉e�����A�s�i�C�Œׂꂻ���ȃp���̃~���[�W�b�N�E�z�[�������̕���ɂȂ�B�x�z�l�œ�����l�����W�F���[���E�W���j�����D�����Ă���B�v�X�̉̂�����l���D�̃m���E�A���l�[�f�[���̑��݂��傫���A���̉f��ɉԂ�Y���Ă���B�P�X�Ƃ����Ⴓ�����邱�ƂȂ���A�ޏ��̔��e�Ɣ����͂��̎��̍�i��傢�Ɋ��҂�����B
 ���s������̎x�z�l�Ƃ��ċ�킵�Ă��镃���A�����ł������悤�Ƒ��q���̃}�N�T���X�E�y�������A�X�ŃA�R�[�f�C�I���e�������邪�A���N�ׂ̈ɕ⓱����Ă��܂��B
�����͂̂Ȃ�������A���q�͕ʂ̒j�ƌ��������ʂꂽ�ȂɈ�������A�ꏏ�ɕ�炵�������Ƒ��q�͗��ꗣ��̐h�������𑗂鎖�ɂȂ�B�����ԑ��q�ɉ�Ȃ��������́A����̒��ԒB�Ɏx�����Ȃ���A���Ȃ̏��֗y�X���q�Ɉ����ɗ���B�ʂ��ꂽ�q�������ŁA�����ɂ��Ȃ����q�̃V���c�̓�����k���Ȃ���A���炦���ꂸ�ɋ����V�[���͂����Ɨ��閼��ʂ������B�W���E�L�����[�̃}�W�F�X�e�B�b�N���霂Ƃ�����X�g�[���[�A�㔼�̕���̂������ȐF�ʂɊ������A�t�����X�f��ɂ͒������n�b�s�[�G���h�ɋ����Ȃł��낷�B
���s������̎x�z�l�Ƃ��ċ�킵�Ă��镃���A�����ł������悤�Ƒ��q���̃}�N�T���X�E�y�������A�X�ŃA�R�[�f�C�I���e�������邪�A���N�ׂ̈ɕ⓱����Ă��܂��B
�����͂̂Ȃ�������A���q�͕ʂ̒j�ƌ��������ʂꂽ�ȂɈ�������A�ꏏ�ɕ�炵�������Ƒ��q�͗��ꗣ��̐h�������𑗂鎖�ɂȂ�B�����ԑ��q�ɉ�Ȃ��������́A����̒��ԒB�Ɏx�����Ȃ���A���Ȃ̏��֗y�X���q�Ɉ����ɗ���B�ʂ��ꂽ�q�������ŁA�����ɂ��Ȃ����q�̃V���c�̓�����k���Ȃ���A���炦���ꂸ�ɋ����V�[���͂����Ɨ��閼��ʂ������B�W���E�L�����[�̃}�W�F�X�e�B�b�N���霂Ƃ�����X�g�[���[�A�㔼�̕���̂������ȐF�ʂɊ������A�t�����X�f��ɂ͒������n�b�s�[�G���h�ɋ����Ȃł��낷�B����"���q����""�K���̓V�����\�j�A���ꂩ��"�͌��l�D�݂̕��Ɍ��킹��Ȃ�A�ǂ�����y�����̌�y��i�ƌ����Ă��܂���������Ȃ��B�����A���̏����ł͎����]�ˎ���̐��E�ɉ��̈�a�����Ȃ��A���R�Ɠ���Ă���鎩�R��������B�܂�����̃t�����X�f��ł́A�m�X�^���W�b�N�ȃp���̉�����A�����������Ȃ������Ȍ���̊y���̎G���ɁA�Q�������S���e�ށB���F�͑����̌o�����A�܂��đ��l�ɐ�����邱�Ƃ����Ȃ�Ȃ����Ԑ������̐l���ł���B���͂���ȂɒP���Ńn�b�s�[�ł����鎞�Ԃ��D�����B
 �����̓�̕���̖{��́A�ǂ���ɂ��Ă����Ƒ��q�̈����J�����C���ł���B���͂ǂ��炩�Ƃ����A�ٍ��ł��錀��̎x�z�l�̕��������ł��鑶�݂��B���̓��{�ł͉����֍s���Ă��A�Ƃ����e���͉��������̂Ǝv��ꂪ���ł���B�ꂪ�{���I�Ɏq������̈����Ƃ��߂ɂ��Ă��܂��̂������悤�Ɏv���Ă��܂��B�e�q�̉������āA����Ȏ��������Ɉ�ĂĂ��ꂽ���ɂ͑�ώ��炾���A�����̎q������̑̌�������ȏ��ł͂Ȃ����낤���B
�����̓�̕���̖{��́A�ǂ���ɂ��Ă����Ƒ��q�̈����J�����C���ł���B���͂ǂ��炩�Ƃ����A�ٍ��ł��錀��̎x�z�l�̕��������ł��鑶�݂��B���̓��{�ł͉����֍s���Ă��A�Ƃ����e���͉��������̂Ǝv��ꂪ���ł���B�ꂪ�{���I�Ɏq������̈����Ƃ��߂ɂ��Ă��܂��̂������悤�Ɏv���Ă��܂��B�e�q�̉������āA����Ȏ��������Ɉ�ĂĂ��ꂽ���ɂ͑�ώ��炾���A�����̎q������̑̌�������ȏ��ł͂Ȃ����낤���B�����ŋH�Șb�A���̒m�荇���̒���"���E�ň�ԑ��h����͕̂��ł�"�Ȃ�Ă̂��܂����q�����ڂ̑O�ɂ������Ƃ�����B����������Ɛ��Ԃɂ͗ǂ����錾�t�Ȃ̂�������Ȃ��B����͓������Ƃ������݂Ƃ��Ă����܂�������ł͂���̂����A���ʁA�ł��Ǝ�ŗ���Ȃ����t�̈�����h�ł�����B�܂��Ă�A�M�ɂ��������h�Ƃ�����₱�������̂Ɍ����ẮA���̊��҂𗠐������̔����͌v��m��Ȃ����̂�����B�͂����������܂ŁA���h�ȕ��͉����Ă����Ȃ��̂��A�����̍J�̒j�����̖{���ł͂Ȃ��낤���B
���Ɍ���s�K�ɂ��āH�����̑��q�����̌��t���g�����Ƃ́A�����̈�̉\�����Ȃ��̂�����A�ЂƂ܂��͌��ׂ̉Ȃ��ɁA�n�������Ȃ���C�y�ɐ����Ă������ł���B �F�B�A�v�w�̊W�ƈႤ�̂́A��̓I�ɂ͐��Ă���Ȃ����Ōq�����Ă��鎖�B�������e���琶�܂ꂽ�Z��Ƃ����ǂ��A���̐e�q�W�ɂ͍��ق�����B�N�����e���琶�܂�A�l�̐��Ɠ������������̊W�����݂���B��ʂŗǂ������A���Ĕ�Ȃ���́B��킭�͂��̂��ׂĂ�"������̊W"�ł����ė~�������̂ł���B
2009.10.17(�y) �H�̊C�ނ�
�悭���ꂽ�H�̈���A�v���Ԃ�ɊC�ɏo�Ă݂��B�Â�����̒m�荇���̏�쎁�ɗU���A���l�̈�q����ނ�D�ɏ��A�����{�̃A�W��_�����ɂȂ����B�C�ނ�Ƃ����Β��������̂��펯�����A�V�т܂őӂ��҂̎��ɂƂ��ėL������̂́A�����̂P�Q���R�O���ɏo�q�Ƃ����y�ȃX�P�W���[���������B�ނ�D�ɂ͉��ƂQ�O�N�Ԃ�̏�D�ł���B ��l�̒j�U��~�i�����ƒ��w���܂ł͂R��~�j�̏�D���ɂT�S�~�݂̑��ƁA�a�Ȃǂ��p�ӂ���Ă���̂ŁA��͒��ւ��ƒނ������������A��N�[���[�{�b�N�X������Α��v�B�����̏����܂肢���V�C�Ɍb�܂�Ȃ��������Ƃ�����A���₩�ȓ������ƒ��̍��̊C�����������B�D�͌��\�ȃX�s�[�h�Ŕg���Ԃ����グ��B���ʂɒ��˂���S���̌��Ɖ�������_�ސ���ʂ̌i�F�����Ă��邤���ɁA�Q�O�����ŖړI�̒ނ��ɂ���ė���B
��l�̒j�U��~�i�����ƒ��w���܂ł͂R��~�j�̏�D���ɂT�S�~�݂̑��ƁA�a�Ȃǂ��p�ӂ���Ă���̂ŁA��͒��ւ��ƒނ������������A��N�[���[�{�b�N�X������Α��v�B�����̏����܂肢���V�C�Ɍb�܂�Ȃ��������Ƃ�����A���₩�ȓ������ƒ��̍��̊C�����������B�D�͌��\�ȃX�s�[�h�Ŕg���Ԃ����グ��B���ʂɒ��˂���S���̌��Ɖ�������_�ސ���ʂ̌i�F�����Ă��邤���ɁA�Q�O�����ŖړI�̒ނ��ɂ���ė���B�ނ�j�ɃC�\�������āA�����ȓS���Ăɂ܂��a������I�[�P�[�B�d�肪�C�̒�ɒB������A�Q,�R���[�g�����炢���[���������グ�ăN�C���Ƃ��Ⴍ��B������J��Ԃ������A�ƂɃr�r���Ƃ����肪�����烊�[���������Ĉ����グ��B�悭�ނ�̖��l�B�������Ȋ��o�ō��킹��Ƃ������A����ȃe�N�j�b�N�͂���Ȃ��B�����肪�����犪���グ�邾�����B�D�͋��e�T�m�@��ς�ł���̂ŁA���S�҂ł����Ȃ�̊m���Œނ��Ǝv���Ă������낤�B
���Ԃ͂����Ղ�̂S���ԂR�O���Ȃ̂����A���Ȃ�Z�����Ă������H���ȂǂƂ�ɂ��Ȃ��B
 ����Ȏ��ɍŏ��̂����肪�����̂̓C�V���`�������B����������ƒ͂�L���[���Ƌ����A�ꐡ���z�ɂȂ邪�����͐S���S�ɂ��Đj���O���B���炭�W�����Ȃ������������Ă����̂����A���̎�����͎���Y��Ēނ�ɑł����ށB�Q���Ԃقǂł悤�₭����Ă���ƁA�D�̎���ɂ��鉫�̃J�����Ȃɖڂ����Ȃ���A���̓������҂悤�ɂȂ�B����܂ł͎��������グ�����đ傫�߂ȏd����R�c���Ɠ��ɓ��Ă���A���������������܂��ƁA�h���b�ŐK�݂�������ŁA���Ō����D���̚}��̏������������Ă����B�������Ďb���s�{�ӂȏX�Ԃ����炯�o���Ă����̂����A�������܂ł��p���炵�̓S�����ł���B�v���Ԃ�ɂނ��ނ��ƗN���オ��v���C�h���A�Ƃ��ɖY��Ă����Ђ��ނ��ȐS��h�点��B
����Ȏ��ɍŏ��̂����肪�����̂̓C�V���`�������B����������ƒ͂�L���[���Ƌ����A�ꐡ���z�ɂȂ邪�����͐S���S�ɂ��Đj���O���B���炭�W�����Ȃ������������Ă����̂����A���̎�����͎���Y��Ēނ�ɑł����ށB�Q���Ԃقǂł悤�₭����Ă���ƁA�D�̎���ɂ��鉫�̃J�����Ȃɖڂ����Ȃ���A���̓������҂悤�ɂȂ�B����܂ł͎��������グ�����đ傫�߂ȏd����R�c���Ɠ��ɓ��Ă���A���������������܂��ƁA�h���b�ŐK�݂�������ŁA���Ō����D���̚}��̏������������Ă����B�������Ďb���s�{�ӂȏX�Ԃ����炯�o���Ă����̂����A�������܂ł��p���炵�̓S�����ł���B�v���Ԃ�ɂނ��ނ��ƗN���オ��v���C�h���A�Ƃ��ɖY��Ă����Ђ��ނ��ȐS��h�点��B �₪�ē����X�����A�C���t���Ό��\�ȖL���������B�A�W�ɃC�V���`�A�T�o�ɃJ�c�I�ƁA�����ƂQ�O���قǂ������̎��̓w�͂̌����������B�H�̂Ђ���Ƃ������̒��łق��Ƃ���ЂƎ��A�A��̑D�̃G���W����g�̉��Ȃɂ܂����"�����͂ʂ�߂����������A��͂��Ԃ����C�J�ł����A���͖����Ȑl������"�Ȃ�āA������������������͍Ȃɖ������A���̎���ɂ͉�����T���Ă����Ȃ��A�����ȏ���"�M��"���������ށB
�₪�ē����X�����A�C���t���Ό��\�ȖL���������B�A�W�ɃC�V���`�A�T�o�ɃJ�c�I�ƁA�����ƂQ�O���قǂ������̎��̓w�͂̌����������B�H�̂Ђ���Ƃ������̒��łق��Ƃ���ЂƎ��A�A��̑D�̃G���W����g�̉��Ȃɂ܂����"�����͂ʂ�߂����������A��͂��Ԃ����C�J�ł����A���͖����Ȑl������"�Ȃ�āA������������������͍Ȃɖ������A���̎���ɂ͉�����T���Ă����Ȃ��A�����ȏ���"�M��"���������ށB��͂肱�̏�ł͉��R�Y�O�͉̂�Ȃ��B�ނ̎��́A�F���I�K�͂̎��M�Ɉ��Ă��Ė������Ȃ��B�������N�A�����∣�D�̉̐S�Ɏ䂩��鎄�̐S��Ƃ́A�@���ɂ��������ꂷ���Ă���B�K���ɂ����̔N�ɂȂ��Ă���Ɛ����ɂȂ�A�����Ɏ�����Ȃ����Ƃ͔�����悤�ɂȂ��ė����B
 �ӂƓ����Y�ꂽ�T���Ԃ��܂�A�v���قƂ�Ǘ������ςȂ��ł����悤���B���g���ƐS�n�悢��J�����J���_�S�̂ɍL�����Ă����B���ꂩ��g�t���ɃS���t�ɂƐ�D�̍s�y�V�[�Y�����B����ȏ�������I�ŁA�C�y�ɒނ���y���ފC�̈���������߂ł���B�Ȃɂ���A���Ă���A�����̈ꗬ�������ɂ������Ȃ��V�N�Ŏ|���A�W��J�c�I�̂������ƁA�C�V���`�̉��Ă��ł̈�t���҂��Ă���B�ނ�y���݂ƐH�ׂ�y���݂̈�ΓB���܂ł����Ă���J���������ɕʂ�������āA���X�ƘH�ɒ������B
�ӂƓ����Y�ꂽ�T���Ԃ��܂�A�v���قƂ�Ǘ������ςȂ��ł����悤���B���g���ƐS�n�悢��J�����J���_�S�̂ɍL�����Ă����B���ꂩ��g�t���ɃS���t�ɂƐ�D�̍s�y�V�[�Y�����B����ȏ�������I�ŁA�C�y�ɒނ���y���ފC�̈���������߂ł���B�Ȃɂ���A���Ă���A�����̈ꗬ�������ɂ������Ȃ��V�N�Ŏ|���A�W��J�c�I�̂������ƁA�C�V���`�̉��Ă��ł̈�t���҂��Ă���B�ނ�y���݂ƐH�ׂ�y���݂̈�ΓB���܂ł����Ă���J���������ɕʂ�������āA���X�ƘH�ɒ������B
2009.09.30(��) �ςݏd��
�������N�A�䂪�ܑB�͊ɂ݂��ςȂ��ŁA�j�̈Ӓn���ւ�����������Ă���B����Ȃ��鎞�A�ԂŒ����Ă������W�I�ŒN���������Ă���"�l���͂ǂ̈ʑ����̗܂𗬂������ŁA���̐l�̍K���x���킩��"�ƌ����Ă����B�ŏ�����͈قȗ��_�ł���Ǝv�������A���̐S�́A�߂����ɂ��������ɂ��A�S����������Ɠ��������ƁB�܂芴��̓����ł���l�ԂƂ��āA�ǂ��������Ƃ������炵���B�C�������ĂȂ��Ȃ��܂𗬂��Ȃ��q�������������A���l���Ă��牽�\�N���o�������A��Ȃ��قǗ܂��낭�Ȃ��Ďv���ɁA���̃��W�I�̖����H�����̍K���͑����̗܂��Ƃ����A�ق��Ƃ���悤�Ȍ��t�̂ǂ����ɋ~���Ă���悤�ł���B
���āA�V���̓w�͂̒B�l���炱��������Ă��鎄���Ɩ}�l�́A����܂łǂ�Ȏ���ςݏd�˂Ă����낤�ƂӂƎv���B������U��Ԃ�ƕK�����Ȃ����A�K�������Ȃ�B���܂�Ă�����X���ꂾ���͐ςݏd�ˁA�H�ׂ��ʂƐQ�����Ԃ͎��ȐV�L�^���X�V���ł���B
����A�ڂɗ��܂������͂ɁA���{�l�̐H�����͖ڊo�������サ�A������������E�ꉄ�тāA�l���W�O�N����ɂȂ����Ƃ����B�ł́A���{�l�͈ꐶ�̊Ԃɂǂ�ʐH�ׂ�̂��B
���q�h�{��w�̌ܖ������Ƃ����l���͂����o���������ɂ��ƁA�Ă�6�g���i����11���t���̗ʁj�A���b���ނ�2,2�g���A����͂��悻��6�����B����2,6�g���A�����3�g���A��1,3�g���i37,000�j�A���7,5�g���A���̑��̐H�������Z����ƁA���悻50�g���̗ʂ��A�ꐶ�̓��ɐg�̂�ʉ߂��邻�����B
���̏ꍇ�A����ɕʕ��������͗J�����炵�H�ׂ̈̎������Z�����B���Ȃ����ς����Ă�����R�T�Occ�̃r�[�����R�O�N�Ԉ��ݑ����Ă����Ƃ���ƁA����܂ł��悻�S�烊�b�^�[��������ɂȂ�BCC�Ō����ƂS�O�O��CC�B���ꂩ������ݑ����āA���C�ŕ��ώ�����S������V��`�W�烊�b�^�[�̎�ނ��݂ɕ��荞�ގ��ɂȂ�B���ɂƂ��Ă��̐����͂��Ȃ�T���߂Ȑ����ł���B�l�ɂ���ĉ��˂Ǝ����݁A��H���Ə��H�̈Ⴂ�͂��邩������Ȃ����A�����ςݏd�˂Ă����Ƃ��Ȃ藧�h�Ȑ����ɂȂ�B
�p���͗͂Ȃ�A�x�X�g�Z���[��胍���O�Z���[�ɂ�����������B�V�˂œw�͉Ƃ̃C�`���[�̐��E�I�L�^�Ƃ͔�ׂ���̂ł͂Ȃ����A�}�l�Ƃ��Ă��ꂾ���̈̋ƁH��i�s���ł���B�܂�A�R����J����̋N���̐l�������Ƃ����Ȃ��Ă���Ƃ������B����͂���Ӗ��A�V�Ɋ��ӂ��Ă��������̂ł͂Ȃ����낤���B
�����āA��̗܂̘b�ɖ߂��āA�������ɂ��A�߂����ɂ��l�Ƃ��Đ����Ă���Ƃ��āA��͂肱�ꂩ����傢�ɗ܂𗬂��������̂ł���B�����A���ƂP���b�^�[�ʂ͗����������̂ł���B���̗܁A�����܂⊴���̗܂��肾�Ƃ����̂����E�E�E�B
2009.08.08(�y) ����Ɏv������
 ���ς�炸���̃X���[�W���M���O�𑱂��Ă���B���掩�^�ł͂Ȃ����A������߂邱��܂ł̎��ɂ��Ă݂�A���Ȃ�撣���Ă������������Ȃ��B���낻���f�������߂��Ă��܂������N�f�f���悤�Ǝv���Ă���B���������Ƃ��������̎����A�܂��ɐ䎞�J�̋G�߂ł���B�͂��悢��Z���[���A�s���ȋC��ɂ��߂����A���R�͏�ɐ��Ƃ����������̘g�̒��ŁA�Ȃ܂łɐ���t�̉c�݂𑱂��Ă���B���N�͓��Ƀ~���~���[�~�̓�����N�ŁA�ȑO�͊��l�ł��������̖����́A���J������̓܂��̉��A�����܂ł����̍s����ɂ͂��̐����������Ă���B�����̎��R���܂��̂Ă����̂ł��Ȃ��炵���B
���ς�炸���̃X���[�W���M���O�𑱂��Ă���B���掩�^�ł͂Ȃ����A������߂邱��܂ł̎��ɂ��Ă݂�A���Ȃ�撣���Ă������������Ȃ��B���낻���f�������߂��Ă��܂������N�f�f���悤�Ǝv���Ă���B���������Ƃ��������̎����A�܂��ɐ䎞�J�̋G�߂ł���B�͂��悢��Z���[���A�s���ȋC��ɂ��߂����A���R�͏�ɐ��Ƃ����������̘g�̒��ŁA�Ȃ܂łɐ���t�̉c�݂𑱂��Ă���B���N�͓��Ƀ~���~���[�~�̓�����N�ŁA�ȑO�͊��l�ł��������̖����́A���J������̓܂��̉��A�����܂ł����̍s����ɂ͂��̐����������Ă���B�����̎��R���܂��̂Ă����̂ł��Ȃ��炵���B����ȓ��Ǝ��Ԃ��ٗ�ɒZ�����̉ĂɁA�F�����H����A���x�͉F����s�m�̎�c����̋A�҂ƉF���t�����b�肪�������B���̒m�l�������̕ƒn�܂ŁA���̊F�����H�Ȃ���̂����ɍs���Ƃ����Ă����̂����A�ʂ����Ă��̌�ǂ��Ȃ������Ƃ��B�n����̖��̍����ł���傢�Ȃ鑾�z���B�����A���̌��ɂ܂�郍�}���̘b�͐s���Ȃ��B�l�ނ͖�ɔ������P�����̐����A�F���̂ǂ̐������g�߂Ɋ����A���₩�Ȋ肢���Ȃǂ����Ă����̂��낤�B
���ł����A����Ȏ�������ƒ�͖����Ȃ��Ă��܂����̂��낤���A���������\�����������q���̍��̏\�ܖ�̎��A�����ɂ̓E�T�M���f�邩������Ȃ��ƁA�����o�ዾ������Ȃ����������B���v���Ȃ�ĕ����Ȏq�����ゾ�낤�Ɖ��������v���B
����Ȑl�ނ̃��}���▲���������ɁA�����炿�傤�ǂS�O�N�O�̂V���ɁA�A�|���P�P���͂����֍s���ċA���ė��Ă��܂��Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��|��������Ă̂����B���̍��A�l�ނ̖������Ɏ����I�ȂǂƐ��E�������삵�Ă��̉f���Ɍ����������̂ł���B���ꂩ�瓖�R�A�Ȋw�Z�p���������i���A�Ȃ��s�����肫���肵�Ȃ��̂��A�l�ލő�̉�������A�S���E���\�����j��ŋ��̃g���b�N�Ȃ̂ł́A�ȂǂƂ��������ȋ^�������悤���B
 ���̃A�|���P�P���̃A�[���X�g�����O�D�����������̂́A�L��ȃp�E�_�[��̍��̊C�������悤���B�����ɂ͎c�O�Ȃ���A�݂��������E�T�M���A�܂Ȃ���ɂ����ɋA���čs�����A������P�̎q�����A���̐��̎g�҂ł��錎�����ʂ̐e�ʂ����Ȃ������B���ꂪ�����ł���B��펞�̑卑�̈АM�Ƃ��Ȋw�̐i���́A�l�ނ̊�]�����������悤�ŁA�Ñ����ɂ��Ă����M�▲��D���Ă��܂������Ƃ������ł���B���ǂ̂Ƃ��떲��}���́A���m�Ȃ���́A�z���̒��ɂ������l������Ƃ������Ȃ̂��낤�B
���̃A�|���P�P���̃A�[���X�g�����O�D�����������̂́A�L��ȃp�E�_�[��̍��̊C�������悤���B�����ɂ͎c�O�Ȃ���A�݂��������E�T�M���A�܂Ȃ���ɂ����ɋA���čs�����A������P�̎q�����A���̐��̎g�҂ł��錎�����ʂ̐e�ʂ����Ȃ������B���ꂪ�����ł���B��펞�̑卑�̈АM�Ƃ��Ȋw�̐i���́A�l�ނ̊�]�����������悤�ŁA�Ñ����ɂ��Ă����M�▲��D���Ă��܂������Ƃ������ł���B���ǂ̂Ƃ��떲��}���́A���m�Ȃ���́A�z���̒��ɂ������l������Ƃ������Ȃ̂��낤�B���̌��ɐl���s�����f��ŖY����Ȃ����̂�����B�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�̊ēE�剉��"�X�y�[�X�E�J�E�{�[�C"�̃��X�g�V�[���ł���B���̉f��̃X�g�[���[�́A�F����s�m�����������o�[����������A�F���ɍs������NASA����̎w�߂Œf����Ă��܂��B�S�������ނ����V��ɁA�Ăяd��ȔC���ł��Ăт�������A�N�������������Ă��������o�[�̃g�~�[���[�E�W���[���Y������E�C���A�����A�]�����������Ȃ��a�������A�����̖��ƈ��������ɁA�l�ނ̊�@���~���ׂɁA��l�Ō��Ɍ������ē˂�����ł䂭�B�F�����𒅂��܂܁A�����錎�Ŏ��j�̃J�b�R�悳���A�r�b�O�o���h���o�b�N�ɒꔲ���ɖ��邭�̂��A�V�i�g����"�t���C�E�~�[�E�g�E�[�E�U�E���[��"������グ��B
���̎����玄�̒��ŁA�������ɂ̕�ł���Ƃ����v���͕ς��Ȃ��B�����������߂��������A���グ��Ή�X��D�������ŕ�ݍ���ł����B�傫�ȌÕ����s���~�b�h���A�吹����^�W�E�}�n�[�����ɂ������ȁA���̐��w�������s�傳�ɂ͋y�Ȃ��B�{���͍��̈АM�ł͂Ȃ��A�l���l�ׂ̈ɂ��Ȋw�Z�p��F���J���ł���B���������̂��̓����A���ɂ���Ȃ�Ď��オ����̂�������Ȃ��B�J�オ��̌��̌����Y��Ȗ�ɁA���܂ɂ͂���ȁA�O��Ĕ�v�������点�Č���B
2009.07.22(��) �Q�{�̉f��
�u���X���[�v�@�~�b�L�[�E���[�N���{���ɋv���Ԃ�ɋ▋�̐��E�ɋA���ė����Ƃ����b�萫�������āA�ʂ����Ăǂ�Ȃ��̂��Ƃ������҂ƕs���̓��荬�������Ϗ܂������B����͉ߋ��̋P�������h����w���������X���[���A�V���ƌǓƂ��������l���̊�H�ɂ��B�����āA����܂ŐU����������Ȃ��������g�̖�����l�ɐS�̋~�������߂�Ƃ��������̂ł���B���Ȃ莎���ł̂������V�[�������邪�A���[�J���ȃA�����J�̃v�����X�E�̓��������Ȃǂ����������m���B
�@���̉f��̎剉�ł��郌�X���[���������Ă���̂��~�b�L�[�E���[�N�B���N�Ԃ��ǂ�ꎞ��𖡂�����ނ̎��̐l���ƁA���ǂ����Ă��d�Ȃ荇���ė���B�ēł���_�[�����E�A���m�t�X�L�[�́A���̖����ǂ����Ă����[�N�ɂƁA�L���X�^�[�𐄑E����X�^�W�I�Ɛ���������ƕ������B���v���ɔވȊO�ɂ��̖��͕����Ȃ��قǁA���ɓK���������Ǝv���B�����A�ނ�����Ƃ̎v���ŁA���N�Ԃ������Ă��������Ƙb������V�[���͎��ɔ������B�C�ӂ̂���ꏊ�Ȃ̂����A�G�ߊO��̒N�����Ȃ��C�ӂ̔����F�̕��i���A���̐e�q�ɗǂ��������B��̂���₵�������A���̂���l�̐S�����̂܂�i�ɉf���o���ꂽ�悤�������B��������ȊC�ӂɍs���Ă݂����Ǝv�킹��悤�ȁA�Y����Ȃ���ʂƂȂ����B
�@���̉f��A�j�̃��}������ꏊ���e�[�}�̂悤�ł���B�h������x��ɂ����j�̂������A�������A�����͔N���̌o�߂Ƌ��ɂ��܂ł����̂܂܂ɂ��Ă����Ă͂���Ȃ��B�����ʼnߋ��ւ̎v���₱������������邩���l����f�悾�����B����͏��Ȃ��炸���������Ă���l�Ԃ̒j���o��������̂ł���A�d�������҂̉i���̉ۑ�ł�����B����s���C���A�o���Ƃ������Ƃ������̂悤�Ȑ��i�̎�l���B���X�g�V�[���ł́A�ނ̂킾���܂���̂Ă����S�������I�ɉf���o�����B���ꂩ�猩����ɐ\����Ȃ��̂ł��ꂮ�炢�ɂ��Ă������A�G���f�C���O���[���ŁA�u���[�X�E�X�v�����O�X�e�B�[���̉̂ƃA�R�[�X�e�B�b�N�ȃM�^�[�̉��F���S�ɐ��݂�B���̉f��̂��߂����ɍ��ꂽ���̋Ȃ�����Ă���ƁA�S�n�悳�ƈꖕ�̎₵�������ݏグ�Ă���B
�u�����������l�v
�@�ȂɎ��ɕʂꂽ��w�������剉�̘b�ł���B�W�X�Ƃ�������ɐ������������߂Ȃ���A������Ȃ��ƌǓƂ�����Ă������Ȃɐ����Ă���B�����Ɉږ��̃W�����x�Ƃ������ۂ̑t�҂ł���N�Ƃ̏Ռ��I�ȏo�������B
�@�O�P�N�̂X�E�P�P�ȗ��A�j���[���[�N�ł͓��ɃC�X���������ւ̒��ߕt�����������Ȃ�B���̃V���A�o�g�̉��y�������A���a����D���Ȉږ��̃n�[�Y�E�X���C�}��������N���A�s�@�؍݂��猵�����Ώ����鎖�ɂȂ�B�m���ɂX�E�P�P�͐l���╶�����u������ɂ���悤�ȁA���܂�ɂ��傫�ȏo�����ł͂������B����ł��A��ɍ��ێЉ�̒��ő��̎҂������������ȉ��ēƓ��̒��S��`�A�ߑ�I�[�ւ̂��������ƕΌ������̉f��ɂ͂�������Ɛ��荞�܂�Ă���B
�@���̕���̃j���[���[�N�̉��C�Ȃ��X�̕`�ʂ����ɂ����B�Z���g�����p�[�N��o�b�e���[�E�p�[�N����o�����ăX�^�e�����������A�����t�F���[���璭�߂�}���n�b�^���B�O���j�b�W�E���B���b�W�炵�������݁A�n���S�Ƃ����Ŏd��������T�u�E�F�C�E�~���[�W�V�����B�j���[���[�N������ɂȂ����f���"���u�\���O���o����܂�""�v���_�𒅂�����""�e�B�t�@�j�[�Œ��H��""�X�p�C�_�[�}���R"�ȂǁA�����������̂����A���̒��ł�����͂��Ȃ荂���_�����������i�`�ʂ̐��E�ł���B�����Ď剉�̋������̃��`���[�h�E�W�F���L���X���f���炵���B������~�b�L�[�E���[�N���l�A�ވȊO�ɂ��̖��͍l�����Ȃ��قǂ͂܂��Ă���B�����Ă��ꂼ��̏����̖��҂��������ɖ{���L���āA�{���ɂ��̐E�Ƃ̐l���������̂܂܉f��ɏo�Ă��Ă��܂����悤�ȍ��o�Ɋׂ�B���̉f��̌����"�r�W�^�["�ł���B���ꂪ���{�̃^�C�g����"�����������l"���B����ȃL���b�`�[�Ȍ�����A�����Ă��̑薼�ɂ������t���e�ɐS���甏��肽���I
�@���̉f���[���S���爤�����l�Ȃ̂��낤�B���̃W�F���L���X�������w�����A�Ō�̃V�[���̐S�̒��ɂ��̔��̈Ӗ�������B��������S�Ɏc�閼�^�C�g���ɏo����B
�@�����̉f����ϏI���Ďv�����ƁB���ς�炸���̓��{�ł́A�W����A���X�g������z�e���̃����`�A�X�|�[�c�{�݂≷��Ɖ����֍s���Ă������̂������ꂳ������ł���B�����������{�̏��������͉����ɏ����Ă��܂����̂��낤���Ə�Ɏv���B
�@�����͂���������Ă��鎄�̂悤�ɁA�������̋������ʼnߋ��̎v���o����ɌQ��Ă͎U����X���߂����Ă���̂�������Ȃ��B���̉f���̒��̏��������̐l���A����炵�������l�𖣂��Ă����B�����ō��X�A�j�̈��D�Ȃ���̂��q�ׂ����͂Ȃ����A��͂肱��������������Ƃ������̂�����ꂽ�����͂܂�Ȃ��B�������N�Ԃ�"���Ȃ����`"�Ƃ������̒������ɂ������Ă��鎄�ł��A���ʂ�o��A���_�ɒ���╱�N�A����ȋN���̂���l���������ȁI�@�Ǝv�킹�Ă����悤�ȋv���Ԃ�̖��悽���������B
2009.06.17(��) �w�A�X�v���C
�@�U���P�Q���̒����ɁA���̉��������~���[�W�J���A�E�G�X�g�T�C�h�E�X�g�[���[�̓��{���������肵���ƌ����L���L�����ڂ��Ă����B�u���[�h�E�F�C�ōĉ������肵�����Ƃ̓C���^�[�l�b�g�Œm���Ă����̂����A����Ȃɑ������{�ɂ���Ă���Ƃ͎v��Ȃ������B�f��ł���q�b�g�ƂȂ�A�j���[���[�N�̏��w�̖鉹�𗊂�ɁA�n��ɃJ�������~��Ă䂭�����I�ȃI�[�v�j���O�E�V�[���A�V���[�N�c�̃i���o�[�Q�Ǝv�����^�b�J�[�E�X�~�X���̂�"�N�[��"�̏�ʂ��D���������B�Ȃ�Ƃ��̖���͂P�X�T�V�N�̂X���Ƀu���[�h�E�F�C�Ŗ����J�����������B�@��Ƃł͍��T�A�~���[�W�J���̘b�ő傢�ɐ���オ���Ă���B����̂P�O���A�V�h�̌����N����قł���Ă����A"�w�A�X�v���C"�Ƃ����u���[�h�E�F�C�E�~���[�W�J�������Ă������肾�����B���܂��ɂ��̓��̃V���[���I��A���R�O�ɏo�ė������҂����ƁA�b�������ň���������肢������Ɏʐ^���������ŁA���̋��������܂���߂�炸�Ƃ��������ł���B���������́A��N�s�����j���[���[�N�̃j�[���E�T�C��������ŁA���ƒ�����"�w�A�X�v���C"�̑�t�@���ɂȂ����B�����Ă��̂U���A�܂����̓��{�̍ĉ�����̃j���[�X�Ɋ�B�Ƒ��̒N�����l�����y����ł���Ɗ��Ⴂ���Ă��鎄�́A�Ƒ���D�悳����̂��l�̓��ƍl���A���^�����q�{������ĊԂ��Ȃ��a�ݏオ��̈����ƁA���ǂ�������Ԃ̖��������Ăł��B
 �@���̕���͉�X���{�l�ɂƂ��āA�A�����J���ł��P���Č������P�X�U�O�N�㏉���A�암�̃{���`���A������ł���B�Q�O�O�R�N�̃g�j�[�܂̃~���[�W�J������ŁA�W����̉h�_�ɋP�����n�`�����`���ɒe�����y������i���B�Q�O�O�V�N�̂Q�x�ڂ̉f�扻�ł���q�b�g���Ă���B���߂̎�l�����A�܂��R���قǃf�J�C���ꂳ����́A��ɒj�D�ƌ��܂��Ă���悤�����A���̖��ɂȂ肫�����W�����E�g���{���^�̉����Ԃ�����Ȃ�̐��݂��������B�Â��悫����̃t�@�b�V�����́A�܂��ɍ��N�A���a�T�O�N���}�����o�[�r�[�l�`�̐��E�ŁA���̃m�X�^���W�b�N�őN�₩�ȐF�g���┯�^�́A��������������̐��E�Ƀ^�C���X���b�v�����悤�ł���B���y���܂��ɂ��̍��ŁA�A���T�E�t�����N������V���[�v���[���X�A�R�j�[�E�t�����V�X�Ȃǂ̃X�^�[�B��Ǒz����t���[�Y��A�L�����N�^�[�������ɏo�Ă���B�X�g�[���[�͐l�C�e���r�ԑg"�R�[�j�[�E�R�����Y�E�V���["�����S�ɂȂ�B
�@���̕���͉�X���{�l�ɂƂ��āA�A�����J���ł��P���Č������P�X�U�O�N�㏉���A�암�̃{���`���A������ł���B�Q�O�O�R�N�̃g�j�[�܂̃~���[�W�J������ŁA�W����̉h�_�ɋP�����n�`�����`���ɒe�����y������i���B�Q�O�O�V�N�̂Q�x�ڂ̉f�扻�ł���q�b�g���Ă���B���߂̎�l�����A�܂��R���قǃf�J�C���ꂳ����́A��ɒj�D�ƌ��܂��Ă���悤�����A���̖��ɂȂ肫�����W�����E�g���{���^�̉����Ԃ�����Ȃ�̐��݂��������B�Â��悫����̃t�@�b�V�����́A�܂��ɍ��N�A���a�T�O�N���}�����o�[�r�[�l�`�̐��E�ŁA���̃m�X�^���W�b�N�őN�₩�ȐF�g���┯�^�́A��������������̐��E�Ƀ^�C���X���b�v�����悤�ł���B���y���܂��ɂ��̍��ŁA�A���T�E�t�����N������V���[�v���[���X�A�R�j�[�E�t�����V�X�Ȃǂ̃X�^�[�B��Ǒz����t���[�Y��A�L�����N�^�[�������ɏo�Ă���B�X�g�[���[�͐l�C�e���r�ԑg"�R�[�j�[�E�R�����Y�E�V���["�����S�ɂȂ�B�@����͐́A���{�̃t�W�e���r���A�������ԑт̓y�j�̌ߌ�ɂ���Ă���"�r�[�g�E�|�b�v�X"���霂Ƃ�����B���̃R�����Y�E�V���[�̃��M�����[�ɂȂ邱�Ƃ���A�g���C�V�[�Ƃ������ڂŏ��^���C�ȏ��̎q����l���ŁA�ޏ��̑O�����ňꐶ�����Ȏp�́A�����̐l�ɗE�C�Ɗ�]��^�������Ƃ��낤�B"���ڂ̓X�^�[�ɂȂȂ�Ȃ���"�ƈÂɔے肷��A���̃��C�o���ł���ׂ����������̎q�ƁA���̔ԑg�v���f���[�T�[�ł��鐫���ȕ�e�B���A�����ɂ͍��l�Љ�ւ̍��ʂ��A��������Ƒg�ݍ��܂�Ă���B�Â��{���`���A������ł͂��邪�A�Ȃɂ����̘b�̖{���̓A�����J�Ɍ��������̂ł͂Ȃ��l�ɂ��v����B�ǂ�Ȑl�Ԃł��������ɉB�����G�S�⍷�ʂ��A���̃X�g�[���[�̍���ɗ���Ă���B����Ȃ����ۂ��ȕΌ����������������Ȃ����I������Ė����������I�Ƃ����ꔲ���ɖ��邭�J���t���ȃ��b�Z�[�W���A��X�ϋq�Ƀp���[�⌳�C�������B
�@�����u���[�h�E�F�C�ŏ��߂Ċς��~���[�W�J���́A�P�X�R�O�N��̃j���[���[�N�������"�N���C�W�[�E�t�H�[�E���["�������B���̎��̊��������ł��N���Ɋo���Ă���B�L���X�g�B�ɂ́A���E������W�܂鑽���̋��͂ȃ��C�o�������Ƃ̐킢�����������āA����̃u���[�h�E�F�C�̕���ɗ������Ƃ����A�v���C�h�Ɗ�т�����B��Ɏ����Ƃ��킢�A�����ɉ̂��x��ނ�̑f���炵���p�t�H�[�}���X�A����̒N�����P���Ă����B
�@�킪���ɂ͐��P�ƌ����Â��̎����������P���A���{�������\������I�ȓ`���|�\������B���̐��藧���̈Ⴂ��Ɋ�����B�ߔN�A�A�����J�̂��ƌ|�̃x�[�X�{�[�����A���{�̖싅���ł��������悤�Ȏ���ɂȂ����B�������A���̃~���[�W�J���̐��E�����́A�������̂���������悤�Ɏv����̂́A��������������������ł͂Ȃ����낤�B
�@���x�̓u���[�h�E�F�C���̂��̂�����ł���"�R�[���X���C��"�̓��{���������܂����炵���B�܂�����Ɗϋq�͈�ɂȂ�̂��낤�B�����Ƃ������G�߂ɁA���܂肢���j���[�X���������Ă��Ȃ����A����ȗJ�����炵�ό��͎��ɃX�J�b�Ƃ��邾�낤�B
�@���̃j���[���[�N�̌���ł́A�������������F���Ȃɂ��Ă��悢�斋���J�����̎��A�����Ƃ��߂����閺���������B"����̃����L�[�X�̎����Ƃ��̃~���[�W�J���A�ǂ������ʔ������ȁH"�����S�O�Ȃ�������"�����A�ܘ_����������"�ƁB
2009.06.10(��) �d�v�ۑ�
�@�Ƃ肠����"�}���ƃr�[��"�̋G�߂�����Ă����B���������G�߂ł����邱�̍��A���̈ꎞ�Ԃ�X�̒��ʼn߂����Ă���B���������ƕ������͂����̂����A���͂������ɘR�ꂸ���^�{��̈�ŁA���̂悤�Ȕ�펖�ԂɂȂ����B���N�R���ɋ�̌��f�������A��ł͂��邪���A�̐��l���o���ƌ���ꂽ�B���l�̎Ⴂ���ォ�痬���ȓ��{��ŕ�������A���܂�̓ˑR�Ȍ��t�ɜ��R�ƂȂ��ĕ����Ԃ����B�ޏ��̌��̋C�̂Ȃ������O����o�錾�t�́A�W�X��"�����o��"�ƌ����������J��Ԃ������������B�Q�T�Ԍ�̂�������̈�҂ł̐����������ʂƌ��_�́A�܂�����g�킸�̏d�����炷���Ƃ������B�����ւ����Ă��Đ挎�̔�����̍��ɁB�V���ɂ��������O�Ȉ�̌��_�́A����܂������̏d�����炷���ƁA���̍��ɂ�����d�ʂ��y�������S�����炷�A����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��Ƃ����B�@�H�������Ƒ����̉^���B�܂��͂��̉^���A���X�A�ȑO�ɒʂ����X�|�[�c�N���u�ŁA�ׂɗ���N�����C�Â����Ȃ���A�n�c�J�l�Y�~�̂悤�ɃJ���J���ƃE�H�[�L���O�̃��[���[���C�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�y�_���������̂�������A���ł���Ȍi�F���ς�炸�A��C����ǂ�ł��鑛�X�����ꏊ�Ŋ��𗬂��̂��낤�H���ꂱ���X�g���X�����܂�B
�@����Ȏ��A�̂���T�E�i�œǂ��p���v���o�����B�P�X�Q�O�N��ɋ����_�����X���l���������E�������̗���I��A�t�B�������h�̉p�Y�̃k���~��������"�T�E�i�͂Ȃ�ċC�����������̂��낤�B�܂�ŐX�̒������L�������������̂悤�ȑu������"�Ƃ������t�������B�ȗ����̌��t���C�ɂȂ��āA��x�͂��̐X�̒��̐S�n�悳��̌����������̂��Ǝv���Ă����B�����łƂ肠�����A���ߏ��̓N�w���̐X�̒����A�}���\���Ȃ�ʑ������Ŋ��𗬂��悤�ɂȂ����B���W���ɂ͖傪�J���B�����ؘ̖R������˂��Ђ���Ƃ����X�̒��͑u���ł���B�����đ傫�Ȍ����ł͂Ȃ�������̐Ώ�̊K�i��Ȃ��炩�ȃX���[�v�A����ȍ�����s�������邤���Ɋ������o���Ă���B���͒r�̎���̃A���������J�ŁA���F�A�Ԏ��A�����Ǝ����Y�킾�B�����̖X�̓������l�X�ŁA�����K�v�ȏ�ɔx�ɓ���Ă��B���̂������������Ȃ�����x���`�ɃS�����Ɖ��ɂȂ�A����̍����X�����グ��B�₪�čL����Ԃɂ�������l�ł���A���̊Ԃ̃l�C�`���[���[���h������ė���B�����t��h�炵�A���̎C��鉹��쒹�����̐����A�������X�ւ̋��D��U���B�\�F�̗l�X�ȗΐF�ɂ������Ƃ�A���̗t�悩�牽�{���̌��̎������炫��ƋP���A���ɂȂт��Ă���B���L���Ă݂�Ƃ���͒w偂̎��������B�㉺�Ɍ������g�ł��i���ɂȂ��Ă���ɂ�������炸�A���Ȃ�̌��݂�����j�ƁA�߂����܂łɐV�����_�f��~������䂪�@�o�ƌ��B���������Ă��邤���ɁA�����o��̂������Ȃ��Ă���̂ɋC�t���B
�@���N�̏K���ł��铒�オ��́A�Ƃ肠�����̗₦���r�[���Ǝ}���B䥂ŗ��Ă̓��ɁA���肫����������P�̖����������W���Ȃ���A�≖���ӂ�|����B���X�M�����A���X�Ɍ��̒��Ƀv�`�v�`�b�Ɠ����B�L���铤�̊Â��Ɖ����炳�A�����Ɋ����I�ȗ₽���r�[���𗬂�����ł䂭�B�J���b�g����L���ȎႢ�J���A���͂����ς��̐l�M�Ɏ��h�A���I�┖��̃j���j�N���̂����������܂��B�ق됌��������i���܂�����Ԃ����邪�j�Ɏd�グ�̔тƂ���ɍ����������B����Ȃ�肽�����肪�J��Ԃ��ꂽ�閈�ɁA���̎��Ԃ��̂��Ȃ��悤�ȑ̂��o���Ă��܂����悤���B��������^���ɐߓx�������ėՂ܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������N������I�ȉ^�������Ă��Ȃ��ӑĂȐ����A���R�̋A���Ƃ������Ȃ̂��낤�B�����͂�낤�A���Ȃ��Ă͂ƐS�ɐ����̂����A���扄���ɂ��Ă����̂��A���˂Ζ����͂Ȃ��悤�ȐS�����ɂȂ����B�S�N�O�A�C������ꂽ�։����A�v���̂ق��X���[�Y�ɏo�����̂�����A����Ȃ��ƈʂ͏o���Ȃ��͂��͂Ȃ��B�q���̎����獪�������͒N�ɂ������Ȃ��Ǝ������Ă����̂����A����ȍ��������b���������Ɠ����ɏ�����������������B���h�b�R�C�V���ƌ��킹�邱�̑́A�X�̃K���X�ɉf��ǂ����̃f�u�A���ꂪ�������ƋC�t����������ǂ̈ʂ̎����o���Ă��܂����̂��낤�B���g���Ă��܂����^�{�ȂǂƂ����A�ŋ߂̗��s��͑傢�ɋC�ɐH��Ȃ��B����lj䂪�̂������A���ɂ��Ƒi���Ă������A�����̖�f�܂łɂ͂��ƂQ�L���A���N�̏H�ɂ͂��ƂT�L���A���x�������g�܂˂Ȃ�Ȃ��d�v�ȉۑ�ɂȂ����B�����̂ɒu���Ă���"�g�y��"�ɂ�����x�����Ă݂����ƐɎv���B"�����Ƃ���"�܂���"�`�F�W�E�ƃN�H���T���E"�̂悤�ɁA���������ň����Ȃ�����Ⴂ�����͔��������S��ł���B�l����x���炢�͐^�ʖڂɂȂ낤�B"�f�u�͈���ɂ��Đ��炸�A���Z������ɂ��Đ��炸"���ꂪ���̖{���̊i���ł���A�{���̂ЂƂ育�Ƃł���B
2009.06.09(��) �k�o
�@�����Ɛl�Ԃ̐S���܂�G�ꍇ�����ނɂ����f���h���}�͑��ς�炸�����A�ŋ߂ł�TV�̃S�[���f���^�C���̃o���G�e�B�[�ԑg�ł����������グ����̂������B�����Ɠ����͂⎋�����ň��肵�Ă���̂��낤���A�����l�Ɠ������e�[�}�̂��̂͂��܂��傤�����I�ȃX�g�[���[�������A�����D���̎��ɂƂ��āA�킩�肫���Ă��Ă��K������Ă��܂��{���ɋ��ȃW�������ł���B�����N�������j�̋�����Ȃǂ𑼐l�Ɍ����Ȃ����߂ɁA�����Ɛl�Ԃ̗����̂���f���̉f��قɂ́A�������\�N�������^��ł��Ȃ��B���̘b�͓����̎��\�͂��A�g�߂Ȍ��Ōo�����������������߂��A�܂��炸��"�ЂƂ育��"�ł���B�@�����Ă̓��̒��̏o�����������B�����Ă����V�F�p�[�h���̃x�A�����Ȃ��Ȃ����B��͒�ɕ��������ɂ��Ă����̂����A���R�̂��ƂȂ��炢���̂悤�ɒ��ɂȂ�A�ꂪ�����ɓ���悤�ƃx�A���Ă�ł��ނ͉����֍s�������p�`���Ȃ��B�����K�������̑O�ŕ��҂��Ă����̂ɂ���Ȃ��Ƃ͏��߂Ă������B���̌��͉̂��D���ŁA�n�[���j�J��J�Ȃǂ�ނ̑O�Ő����ƕK���̂��Ă��ꂽ�B���w�Z�̗F�l��������������������ׂɌ��w�ɗ��Ă����B���v���A����͎q�����������̈�l���_�������炵���A���̐��͂��Ȃ���̔߂����A�T��R���[�e�����i��������Ƃ��̖쐶��A�z��������̂������B���̌㎔�����A�t�K���E�n�E���h������Ɠ����ŁA�ޏ������T�C�̎q�����������h�Ԃ�~�}�Ԃ̃T�C�������������Ă���ƁA�F�ŗւɂȂ��ē����悤�ɒ����@����Ɍ����A���������ɉ��i�����n�߂��̂������B
�@���̉̂̎|���H�x�A�����Ȃ��Ȃ��ĂR�T�Ԃقnjo�����B�ی������̑���T���Ă����������ɂ炿�������Ȃ��B�Ƒ������낻�날����߂����Ă�������Ȃ�����̂��ƁA���̖��ł���f�ꂪ����ė����B�ޏ��͕�����̏������Ƃ����Ƃ���ɏZ��ł��āA��y���ɂقNj߂��A���Ƃł��鎄�̉ƂɌ��ɓ�A�O�x�͗V�тɗ��Ă����B�����̂悤�ɁA�����ɂ��Ȃ��e�ʂ̘A����b�̃l�^�ɂ��ẮA�����炩�ɏ��Ă����̂����A�A��ۂɂȂ���"���A�����������̉Ƃł����������n�߂��̂�A�����������̉ƂƓ����傫�ȃV�F�p�[�h�Ȃ̂�"�Ƃ����B�x�A�����Ȃ��Ȃ��č��x�͏f��̉Ƃœ����V�F�p�[�h���������Ƃ����A���������R���ȂƋ������B�s�v�c�Ɏv���Ȃ���A���炭�f��̌��̎����b���Ă����B���ɍ������������悤�ȖѐF�A�f�ꂪ���������ƁA�䂪�Ƃ̌��̖��O���v���o��"�x�A"�ƌĂԂƔ��ł���Ƃ����B������̑����A���̏f��̖��ł���A���ɂƂ��Ă͏]�o�����ʂ����W�I�̑��ɂ��̌���A��čs�����������B�����ɂ��������̎q�������� ���X��"�T�������I"�Ƌ��яo���A�V�n���Ђ�����Ԃ�悤�ȑ呛���ɂȂ����������B�m���ɉƂ̃x�A���T�Ɏ��Ă����B�����Ă��̌��͂�����f��̉Ƃɗ����̂���u�˂�ƁA�R�T�ԈʑO�̒��ɁA���ւ̑O�ɂ��ƂȂ��������Ă����ƌ����B�傫�Ȍ��̂����Ȃ�̏o���ɁA���ւ��J�����f��͖{���ɋ������������B�܂��Ƀx�A�����Ȃ��Ȃ������ł���B
�@����͉������Ǝv�����̂����A����ɂ��Ă��x�A�͏f��̉ƂɈ�x���s�������Ƃ͂Ȃ��B�������A���i�S���f��ƃx�A�͐ڐG���Ȃ��A���݂����قƂ�ǒm��Ȃ��B�܂��Đ^�钆�ɏf��̉Ƃ֍s�����͂��肦�Ȃ��Ɖv�X�^��͕�����B����������͊m���߂邵���Ȃ����낤�A�Ƃ������ɂȂ����B�f������X�c�O���������A���ꂪ�ǂ��Ɣ[���̂��l�q�B�����ꏏ�ɂ������ɂȂ�A�s���Ƌ������o���Ȃ���f��̉ƂɌ��������B���̍���X�^�[��������싴����ȂǂƂ����傫�ȉƕ��݂�ʂ��āA���悢��f��̉Ƃɒ������B���鋹�A�₪�ăh�A���J���ƁA�����ɂ͈����̃x�A��������������K����U���Ď����o�}�����B�x�A�͊ԈႢ�Ȃ���Ƃ��瑱���f��̓����𗊂�ɔޏ��K�˂��̂������B
�@�ދ��Ȗ����ɐV�V�n�����߂ė��ɏo���̂��A����Ƃ��^�̎��R�����߂����ۂ��͔ށA�x�A�݂̂��m��B�{��������������A�����Ƃ������b���܂������グ�����낤�B�ȗ��A�l�Ԃł͒m�肦�Ȃ��_��Ƃ������铮���̔\�͂�M���A���̗��������Ɉ،h�̔O����������悤�ɂȂ����B����ɂ��Ă��A�l�Ԃ̎��Ƃ��ۂ��Ɠ����̉s���k�o���ۗ������o�����������B
2009.05.12(��) �S�Ɏc�邾��
�@����̕�����X���Ƃ������̂������Ƃ����炵�����A�l�ނ̗��j���n�܂��Ĉȗ��N���~�߂��Ȃ��������ԂƓ����ŁA�Ⴆ�l�דI�Ȃ��̂ł����Ă��N������ɐg��C�����ɂ͂����Ȃ��B��ԋ��ۂ̗����Ȃ��A�������r�����Ԃ̂����Ȃ���Ԃ̂悤�ɐ��܂ꗎ�������̓����狭���I�ɂ���ɏ悹���Ă���B���E�I��s�������邱�ƂȂ���A���q���̉e��������Ƃ����������������N���ǂ������̂́A�����̏o�g�Z�����p���Ȃǂŏ��ł��Ă��܂����ȂǂƂ����b�B���̏ꍇ�K���ɂ��āA��S�s���ɕw�ɗ�H�c�t������n�܂�w�юɂ��p�Z�ɂȂ����Ƃ����\�͕����Ă��Ȃ��B�����A�q���̍��ɗǂ��V�ꏊ�Ȃǂ́A���̂قƂ�ǂ��Ռ`���Ȃ������Ă���B�����͉ߋ��̑z���o�ƌ����`�̂Ȃ����m�ɕς��A�����m��N���Ɖ����ڂ����Č�荇���A�]�זE�̂ǂ����ɉB�����ł䂭���̂Ȃ̂�������Ȃ��B�@�挎�A�ȑO���̋߂Ă������R�[�h��Ђ����U�����B���낢��ȉ�ЂƋz���������J��Ԃ����������ė����̂����A����ȉh�͐����̗��j�ɖ������肽�B���̃��R�[�h��Ђɂ��悻�l�����I�Ƃ��������ɓn�肨���b�ɂȂ�A���ق�̂ЂƎ������b�������B�U��Ԃ�����ɎႢ��M�̌���������݁A����ɂ܂�鐔����Ȃ��قǑ����̊y�������������h��B�����������̐h���܂����邪�A���̂悤�Ɍ����D��Ő���������ǂ������邾���Ƃ����E���Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�����ɂ̓��}���▲�����邨�悻�������ゾ�����B�������g���Ⴍ�v�������茳�C����������ɁA���y�ƌ����f���炵�����̂��d���ɏo�������Ɋ��ӂ��Ă���B
�@���w���ォ���ł����W�߂����R�[�h�B�������Ȃ������̂ŃV���O���Ղɂ͎v�����ꂪ�����A�ŏ��ɔ������̂̓��b�L�[�E�l���\����"�n���[�E�����[�E���["��"�g���x�����E�}��"�̃J�b�v�����O�̃V���O���ŁA�ނ̃n���T���ȃ��m�N���̎ʐ^���u���[�ɔ��]�����W���P�b�g�������B���ł��ŏ��͑N��ȃC���p�N�g������B�����ĉ�Ђɓ���A�ŏ��ɏo������L���l�͓����ꐢ���r�����V�����B�[�E�o���^���������B�ޏ��͎��̒��w���ォ��̓���ŁA"�A�C�h����T��"�Ƃ����̂���D���ŃV���O���Ղ��قƂ�ǖ����̂悤�ɒ������B�Ȗ����^�C�g���ɂȂ����f��A�V�������E�A�Y�i�u�[����A��ɔޏ��̒U�߂���ɂȂ����W���j�[�E�A���f�C���o�����Ă������̂��A�F�l�����Ɖf��قɊςɍs�����̂����������B�R�̃r�N�^�[�X�^�W�I�ŁA���{�Ŋ�悵���A���o���̃��R�[�f�C���O���ɐ�y�̃f�B���N�^�[����ޏ����Љ�ꂽ�B�X�^�W�I�̕������d����F�̃h�A���J���ƁA�ǂ��ƈ��o�����M�C�Ƒ剹�ʂɂ������|�����B�����ɐ^���ԂȃW�����v�X�[�c�ł���"�A�C�h����T��"���̂����o���^�����u�����h�̔��������グ�Ȃ���o�ꂵ���B�f���TV�ł������Ȃ������{�������̖ڂ̑O�ɗ����A�ɂ��₩�Ɉ��肵�Ă��ꂽ�����̈�u��Y��Ȃ��B
�@���ꂩ��͗m�E�M��킸�A�{���̗L���A�����̉̎肽���Ƃ̏o��̐l�����n�܂�̂����A��̋L�q�̂悤�ɉ��ł��ŏ��͂ƂĂ���ۂ��c��B��Ђł͌��Ɉ�x�̊��A�Ґ����ꂼ��̉�c������A3������Ƀ��R�[�h�V���b�v�ɕ��є��������}���郌�R�[�h�ACD�����肷��B����c�ł͊e�f�B���N�^�[���m�y�ł͊C�O���[�x������A�M�y�ł͑O�����č�������̂�v���_�N�V�����Ȃǂ��玝�����܂ꂽ�y�ȓ����v���[�����āA�����ɋ����ԏo�Ȏ҂̍��ӂ�������Δ��������肷��B�Ґ���c�͔����̍Ċm�F�ƋȂ̃^�C�g���Ȃǂ����肷��B�O�����e���݂₷�����{��ɕς���Ȃ̃^�C�g���Ȃǂ͌l�̊����̖�肾���A�������̊����������Đ�킪�W�J�����c���ڍ�����B��̃g���u�����N����������(�����ł͎q�����݂��Ƃ͌����܂�)�f�B���N�^�[�͂������܂��Ă��āA�������c�̊y���݂̈�������B����ȉ��y���������l�X���W������ЁA���v���A�[�`�X�g�����S���ӁA����ΐl���������č�������y���A����Ȃ��A�ǂ��̈����̂ƌ����Ă������̍��B�����̂����ł��������ȏ����������Ǝv�����ʁA�����ɂ͕����ǂ����߂Ƃ���}�X�R�~�̏�������āA�q�b�g������Ƃ����f���炵���ړI�Ɗ�т��������B�S���̃��R�[�h�X�ł̔���グ���W�v�����A���X�̏o�ז����Ɉ���J���Ă������̍��A�������̒��S�ɂ���ꂽ���Ƃ͍K�^�������B
�@���̕����ł������l�����͂��̉��U���܂ʼn��l�������B���̋ƊE�Ɍ��炸�{���Ɍ���������ɂȂ��Ă��܂������A���̐l�����̐V���Ɏn�܂�l���ɃG�[���𑗂肽���B���̍�������������A�y����������̓��X���߂��������Ԃ����B���̓����A���������������̉��������̂�������������āA���������݂����ȃ��R�[�h�E�R���T�[�g����悵�悤�B�S�ɐ��ݕt�����z���o�̋Ȃ̐��X�B���ɂ܂萌���ċ������n���ȓz���o�邩������Ȃ��B���ꂪ���łȂ���悢�̂����B
2009.04.23(��) �Z�\�����
�@���͐l�̉������s�k�Ƃ������̂��̂��ǂނ̂����������D�����B�����͂��ƂȂ��l�Ԗ��Ɉ��S���A���̑��݂����̓��ނƂ��āA���g�߂Ɋ������邩�炾�Ǝv���B�l�͖Y�ꕨ�Ȃǂ��܂߂�ƈ�N�̓��ő召�ǂ̂��炢���s����̂��낤�B�����Ɍ����Ď��͂��Ȃ�̉Ńh�W�ށB�������h�W�𐔂���Ȃ��قǓ��ނƁA���̂܂ܓ��݂��ςȂ��ł͖{���ɉ������Ȃ�B������J��Ԃ������ɂ����ł͓]�Ȃ��A�����ł͋N���Ȃ��Ȃ�B�ƌ������͓]��œ˂�����̋߂��ɂ������ł��A���ł���������E���ė����オ��悤�ɂȂ�B���ꂪ�����������獡���́I�Ǝ��X�v���������̍��ł���B�@�ǂ������ȍ��A�����߂����q������������߂��q�ɓˑR�ϐg����悤�ɁA�ǂ��h�W��ŋ����Ă����l�Ԃ��A�h�W����݂Ŕ�яo���A�Z�\��������ɑ{���悤�ɂȂ�B�����čŌ�͂��̃h�W���炱������Ȍo�����߂��A����Ȑ������������ȂǂƖ�̂킩��Ȃ��m��_�������o�����肷��B�����l��葽���h�W�������ŁA�����͐l���݂̋�J�l���������Ă���B�Ⴂ�����ɋ�J�͔����Ăł�����Ƃ������A�߂������ȎႭ���Ȃ����ł��A�h�W�̂������ŏ����ȋ�J�͎~�܂Ȃ��B
�@����̂��Ƃ������A����͋ߔN�H�Ɍ���ʔ����h�W�������B���q�Ǝ����ɗU����܂܂ɐ�������ɐ������b�e������ɍs�������̎��B�����J�n���Ԃ͂P�S���A�Ƃ��o���̂͂P�R���R�O���A����Ԃɍ���Ȃ����A�Ƃ肠�����r������̊ϐ�ł��Əo���B�d�Ԃ̏��p���������A���Ȃ��d�Ԃ��C���C�����Ȃ������ƒ������̂͂P�S���S�O���B�����������킪�X�^�[�g���ĊԂ��Ȃ��̂ɁA��������O�Ƃ����w�͊ՎU�Ƃ��āA�ق�̐����邮�炢�̐l�������Ȃ��B�����S�z�ɂȂ�Ȃ�����`�P�b�g�����ɋ}�����ōs���A"���A�����͉��炢�ł��傤��"�ƌ��������A"���낻��T�����ڂ��I�鏊�ł�"�Ɩ�̂킩��Ȃ��������Ԃ��Ă����B�e�q�R�l�ŃL���g���Ƃ��Ă���ƁA���̂��Ƃ͂Ȃ����̓��͊֓��n��̏��N�싅���Ƃ̂��ƁA��X�����ɗ����͂��̎����́A������t�̃}�����X�^�W�A���ōs�Ȃ��Ă����̂������B���̃h�W�����q�⎟���ɂ��`�����Ă��܂����̂�������Ȃ��B�܂����Ⴂ���q����������ȊԈႢ�͂Ȃ����낤�ƁA�m���߂������Ƀm�R�m�R�t���ė������B�R�l�ŏ������ƌ������̂����A����ȋC�͂������Ă���B
�@���傤���Ȃ��������������̂�����A���̊�WBC�̓����h�[���Ő����m���قlj��������A�����I�肽���̃z�[����������ċA�낤�ƁA�Ƃ肠�������ɓ����Ă݂��B����͖싅���N�����ƁA���̐e��R�[�`�̊W�҂ł��Ȃ�ɂ�����Ă����B�ǂ̑I����������āA�����̓C�`���[��_���r�b�V���ɂƁA���낤���Ă܂�����������N��ŁA�������オ�邽�тɁA�e���q���ɑ��������]���J�����̂��鋅��̕��ƂȂ��ċ삯�����Ă����B�����ă`�P�b�g�����̂��Z���Ō�Ɍ�����"�����͑��œ�R�I��̎���������Ă��܂���I"�Ƌ����Ă��ꂽ���t�𗊂�ɁA���̊��҂������ɍs���Ă݂��B���ꂪ�����̕Z�\���������B����������A�h�W�œ]�сA��������ɂ�����ɂ͎v�������Ȃ��������l�܂��Ă����B
�@���ƌ����Ă��N�ł�����āA�������ϋq�Ȃ�����킯�ł��Ȃ��B�o�b�N�l�b�g���łق�̐��\�l����������A�y��ɍ����Ċϐ킵�Ă����B���������������̒��ɉ�������B���̓��e�͈�R�Ə������ς��Ȃ��B�Ƃɂ����������Ō����铊���A�ŋ����������A�y���������ɏ�����傫�ȂQ�{�̃z�[������������ꂽ�B�{���ɖڂ̑O�Ńv�����v�����������Ă���B���ہA��R�Ɠ�R�͉�X�f�l�ڂł͉��炻�̎��͍��͕ς��Ȃ��B���܂��ܑ��q�������Ă������ׂẴv���I�肪�ڂ��Ă���{�����ɗ����A�w�ԍ��ł����������̖���m���Ă���I�������B�����͈�R�łƂ����Ⴂ�I��A���܂��܉���ȂǂŒ��q��������x�e�����A�����͈�̒ʉߓ_�Ƃ����ӎ����A�ǂ̑I������̒b����ꂽ�g�̂��甭�U���Ă����B���̊F�̃X�}�[�g���A�J�b�R�悳�ɂ͋����B
�@�������I���B�w�Ɍ������A�蓹�A�܂��q�������̂��鋅�ꂩ�犽�����オ�����B���̏��N������������L���I�肽���A�����Ă����|���͂�������R�ŕK���Ɋ撣�鑽���̑I�肽���B�ނ�Ƃčb�q���Ȃǂ��o�������싅�̐��E�ł̓G���[�g�X���𑖂��Ă����l�X�ł���B�ޓ��̂Ђ��ނ��ɐ�����p���������āA�v�X�ɂ������������C�����𖡂�����B�K�����Ƃ����A��̐������ɏ��Ȃ���ӂƎv���B���A�����̃h�W���m�肷�錾���o���Ă��܂����悤���ƁB�����Ė{���ɍ��������ɕꂪ�ǂ�������"���v�A���Ƃ��Ȃ邩��"�Ƃ������t���v���o���Ă����B
2009.04.20(��) �������猾����
�@�������J���~��Ȃ����������A�����������Ԃ̊����̂����ŏZ������̎R�Ύ��̋L�����ڂ��Ă����B���������ΐ́A�Ύ��͂����ƕp�ɂł������g�߂ɋN�����Ă����Ƃ����L��������B����Ȓ��̈�A�^���͉��\�N���o�������ł��K���ɂ��Ĉł̒��B�������炱���ʔ����������A�����ł͂ƂĂ����O�ł��Ȃ�����������Ɗ�Ȃ��b���v���o�����B�@�������͌Z��œ���������т̊w�Z�ɒʂ��Ă����B�Z�̊w�N�͍��Ō����c��̐���̖����ɓ�����A�ƂĂ��l���̑����w�N�������B���̒��ɌZ�̗F�l��K����Ƃ������������ڂŁA�ǂ��炩�ƌ����ƕs�ǂ��ۂ����ƂĂ��C�̂�����y�������B�����ǂ��m���y�ŁA�����ʊw�ɗ��p�����������s�d�̒��ʼn�ƁA�l�ڂ��͂��炸�傫�Ȑ��Ŏ��ɘb�������Ă���B���钩�A�^�����H�܂��ꏏ�̓d�Ԃɏ�荇�킹�Ă��܂��A�w�Z�ɕt���܂ʼn��X�Ɣނ̎����b���ۖ����y���Ȃ�قǂ̑吺�ŕ������ꂽ�B���ꂩ��b��������������A�w�Z���Ύ��ɂȂ����B
�@���Ȃ�̉ΐ��Ńe�j�X�R�[�g���́A�Â��ؑ����z�����o���o���Ƒ傫�ȉ��𗧂ĂĔR�����B�����낻�̓��̂s�u�̃j���[�X�ɁA��̉f���ʼnΎ��̖͗l���f���o�����قǂ̑厖�������B�ǂ̐V���ł��ʐ^���ŔR����䂪��Z���ڂ��Ă����B���x���x�݂ŁA�₪�ĂT���Ԗڂ��}���悤�Ƃ��Ă������������̂Ŏ�������������茩���H���o�����B �������炱�̘b�͉����ɓ���B�Z�̘b�ɂ��A���Z�̘L���̑�����g�����o���A�N�����傫�Ȑ��ő����ł����̂͗��K�������Ƃ����B�T�C������炵������̑傫�ȏ��h�Ԃ��Z���ɓ����ď��h�m�������Q���������o�������A�ނ̋���ł��錾�t����"�݂�ȁI�������ɉ��̃I���W���n�b�X�����Ċ撣���Ă��邼�I"�ł������Ƃ����B�����B�����ނ̕���͂����̊NJ��̏��h���̏����������B
�@�������A�����ɂƂ�ł��Ȃ����̉Ύ��̗��b������B�Z�����������ɂ́A���̉Ύ����N������̌ߑO���ɁA����K�����̉Ύ�����ʼnB��ă^�o�R���z���Ă����Ƃ����M�ߐ��̍����\���������Ƃ����B�Ύ��ɂȂ�܂ł̈ꕔ�n�I��N�����Ă����킯�ł͂Ȃ��̂Œf���m��͏o���Ȃ��̂����A���̃^�o�R�̉̕s�n���̉\���͑傫�������炵���B �̂Ȃ����ɉ��͗����Ȃ��A����ł͑��q�������Đe�������̉������ɗ����B�ꌩ�f���炵���e�q���̂��b�ł͂���̂����A�^�o�R�D���̕s�Ǒ��q�Ə��h�m�̕��̂��܂�ɂ��ӂ������������R�̏o�����ł���B�ǂ��^�����g��L���l�̑��q���@�ɐG���߂ŕ߂܂�A�e�������}�X�R�~�̑O�ŁA�܂Ȃ���ɂ��̍߂𐢂ɘl�т邱�ƂƂ͑ɂɂ���B�d���̌�������������q�̊w�Z�ʼnΏ����̕����劈��A�����ƈႤ�z�X�����J�b�R�C�C���̎p���������q�͉��Y��Ă͂��Ⴂ�ł���B���̍����̎����͈ł���łɁB
�@���̒��ɂ���ȉB�ꂽ���b�͐��̐��قǂ���̂�������Ȃ��B�����\�ʓI�Ȍ��t�����𗊂炴��Ȃ��̂����̏�ł���B���̌�K����͉������Ȃ��������̂悤�w�ɗ�݁A�������Z�𑲋Ƃ���w�ɂ������B�������ނ̏��h�m�̕���́A�����m�炸�ɒ��N�ɓn��d����S���������Ƃ��낤�B�m���ɉΎ����̂��̂͐[���ȏo�������������A����l���o�Ȃ����������K�����āA���̗��̂Ƃ�ł��Ȃ��\�b�͍��ɂȂ��Ă������B�^���Ƃ͈ĊO����Ȃ��̂ŁA�l�͑召���܂��܂ȏo�����̒��ŁA�\�����̈�厖�ɂȂ�̂��A����Ƃ�����Șb�̂悤�ɐ��Ԃɂ͒m��ꂸ�A�����������̐e�ɂ��m���Ȃ��ꕔ�̏��b�ŏI��̂��A���̐l�̎��^�������ő�G�c�ɓ����悤�ł���B���l�̎v���o�̒��ł�����͋ɒ[�Ȉ�Ⴞ�����B
�@������������܂łɁA����d�̗l�X�ȕ�����ڂ������ɂ��������悤�ȋC�����ė����B���߂��苃�������J��Ԃ��l���̓��X�A����ȓn���Ɋ��m�������ށB�����߂�Ȃ����̍��A�ق���Ă��̉��������o���������̎�����J��ƁA���������ɂ͔��������҂��Ă���B
2009.04.18(�y) �����ƈႤ��
�@�p�\�R���̌̏�╔���̈��z���Ƃ���ɂ܂��H���ȂǁA�����ꃖ���Ԃ̓p�\�R���Ƃ͉������Ȃ��Ă����B�����@������̂ł���܂ŕ`�������ŁA���N�Ԃ������Ă���30���قǂ̊G�����������Ă݂��B�傫�ȊG�����Ɋz���傫���A���̕��o��������Ă��܂������A�����C�����肾���������ɉ��ƂȂ������ɂ����߂������悤�ȁA�d�ׂ��������悤�ȁA�������ɂ͋v�X�ɂ���₩�ȋC�����ɂȂ����B���̊ԋG�߂͈ڂ�A��D�̍s�y���a�������Ă�������I��ŁA�����̗F�lN���Ɖ��{����p�قɍs���Ă����B�����ւ��Č|�p�ɖڊo�߂��킯�ł͂Ȃ����A���傤�ǎ��̃h�f�l�͂����̊G�̊����ƁA�|�p�Ƃł���N���̏��ŊJ���ꂽ�s���W�ւ̑��̏o�i���I��A��i���ƂȂ����Ƃ��낾�����B�������N�����A��ł�����p�ق�K�˂Ă���B�����ōs�Ȃ�����Ԍ���̉��Ƃ��W�̐l�̑�����焈Ղ��Ă�����ɂ͂��̒��ՂȔ��p�ق߂���͂����߂ł���B�@�ǂ݂����̒P�s�{��Ў�ɂ̂�т�d�Ԃɏ����悵�A����S�J�ɂ��ăy���[�E�R���ł������Ȃ���Ԃł������Ɨ������悵�A�ǂ���ɂ��Ă����͂��������D�̋G�߂ł���B��t���̍��q�ɂ���쑺���p�قȂǂ̓����u�����g�����߁A�s�J�\�A�S�b�z�A���l�A�V���K�[���A�}�e�B�X�A���R��ςȂNj����قǑ��ʂȖ���ɂ��ڂɂ������B���A�����̔��p�ق����͂ޑf���炵�����ɂ��S�a�ށB��s���ߍx�̔��p�ق͓��ɂ����ɒu����Ă����i���d�v�����A�������s�����˂��V�ъ��o�̎��ɂƂ��ẮA���������̊��A��A���X�g�����̎��������Ȃ�d�v�ł���B���������͂��邪�A���̊}�ԓ������p�ق����������m���[���̒����A�h�K�A�E�H�[�z���A�ݓc�����Ȃǂ�������Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���B
�@����s�����A���{����p�ق͂����̏����i�Ɋւ��Ă͈�ʂɗǂ��m���Ă�����̂͂���قǂł��Ȃ��̂����A���̌����Ǝ���̊��ɂ͈ꌩ�̉��l������B���͈�ԋC�ɓ������̂������̃��X�g�����������B�O�̃e���X�ɍ���ƁA���傤�ǎO�Y�����牓���x�ÁA�َR�����肪���ʂɂȂ�[�������������y���ɒ��߂��A�����p�ɖʂ��Ă��鉡�l�`��A���[�̐�t���ʂɏo���肷��傫�ȃ^���J�[���珬���Ȍl�̃N���[�U�[�܂ŁA���܂��܂ȑD���s�������̂��A�_�炩�ȏt�̕��ɐ�����Ȃ���̂�т�ƒ��߂邱�Ƃ��o����B�O�m�ɏo��ɂ͕K��������ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŕK�R�I�ɑD�̍s�������ʂ͑����̂����A��������͉̂��������𑖂�Ԃ̉��Ƃ���₩�ȕ��̉������A���l�̎R�肪����̃��[�~���̉̂̐��E�������ƕ������ꂵ�����o�ɂȂ��B����ꂪ���̂͂Q�W�O�O�~�̃����`�E�R�[�X�������B�������߂Ȑݒ肾���A�o�Ă�����̂͒n���Ŏ�ꂽ����g�����I�[�h�u���A���̑f�ނ̐V�N���ɍŏ������d�ۂ����B�p���ƃp�X�^�Ɨ����ɊW�Ȃ��I�ׂ�D���Ȉ��ݕ��A���̂ق��Q��ނ̃f�U�[�g�Ɖ������S�ɔ����������̌i�F�A���Ȃ�Z�ʂ̗����]�ƈ������̃T�[�r�X�ɂ͏[���ɖ�����������B�O���猩����ߑ�I�Ȍ����͈ꌩ�������Ȃ̂����A���ɐ[���@���Ă��āA�����ǂƑ����Ɏg��ꂽ�����O���[���F�̃K���X����Ɍv�Z���ꂽ�v�́A�n��̊C�ӂ̌������ɂ��܂�������Ă���̂Ŗ��邭�J���I���B���������R���Ȃ̂ō�i�̐F�������I���Y�킾�B�ȑO�A���R�[�f�B���O�̃X�^�W�I���������̂ŏh���������̂��鋞�}�ω���z�e���̏�����ŁA���l���{�ꓹ�H�ŐV�����J�ʂ����n�x�C�݃C���^�[���o��z���̐������x�Œ����B
�@�����I���A�ԕ������낻��[�܂����B�S�����ς�TV�ǂ̔ԑg�ɖڂ�ʂ��Ă݂Ă��A�V�����L���Ă݂Ă��A�}���l���Ɨ^�}�����̉��S�������Č����郁�f�B�A�ɕNJ�����������肾�B�X�|�[�c��|�p�A�S�����������������߂ē����Ă݂�B���S���t���n�߂����ɁA�w�Z�̔��p�̐搶����|�p�͈�u�̂Ђ�߂��Ɗ����̍Č����Ƌ������Ă��瑽���̎��Ԃ����ꂽ�B�D�����ȕ��̐������A���E�I�Ȍ|�p�Ƃ����̎c���Ă��ꂽ��M�⊴����Â��Ɏ~�߂�B���܂ɂ͂���������������̒��ɒT���ɍs���̂������Ǝv���B���ꂱ�������ƈႤ�V�N�ŎG�O�̂Ȃ����Ԃɏo���B
2009.02.23(��) ���Y
�@�N�ł�����܂ł̐l���ɂ�����Ƃ������Y�������Ȃ�Ă��Ƃ����邾�낤���A��������͐l�ɂ���Ĉ��Y���A�����łȂ��̂����̉��߂��傢�ɈقȂ�ꍇ������B���̏ꍇ�A�Ȃ�ł��Ȃ����̐���s���������āA��l��F�l���爫�Y�ƕ]������邱�Ƃ����������B����l�͐̂̎��Ƃ��ĐG���̂������肠���ĕ��Ă��܂�����A������l�͑厖�ɐS�Ɏd�����A���܂ł��ʔ����l�Ɍ������A��������Y�p�ӂƂ���s���̂����]�����l�ȂǂƂ��낢��ł���B�ǂ����ԓ��Ő̂̏o�����∫�Y�b������ƁA����Ă������{�l��"����Ȏ������������H"�Ȃǂƌ����ĊF�𔒂�������B�L���ƌ������̂ɂ͂��Ȃ�̌l��������悤���B�����ɂ��Љ��̂́A�K�^�ɂ����ɂȂ�Ȃ��������̏��N����̂��鎞���A����W�ɏ������Ă������̈��Y�b�ł���B�@���b�͎������w�Z�̎���W�ɂȂ��Ďb�����āA�`���{��j���g���̒��ɓ�H�̌R�{�i�V�����j������̂ɋC���t�����B�肰�ɕʁX�̏����ɓ����Ă����̂����A���̓�H�͂ǂ����Ă����܂ŗL���ȌR�{�ł���B�ʂ����Ăǂ��Ȃ�̂��A�l������͂܂��͎��s�ƁA���̓�H�������ɓ���A�������F�l�ƈ�H�������Ċ���߂Â��Ă�������Ă݂��B����Ƃ����܂���̎���̒��߂̖т��O�b�Ƌt�������B�G��ʐ^�Ō������{�̃X�^�C���ł���B�����A���Ԃ̓y�b�^���R������̂��o�����ɂȂ�ƃ��b�Ɛ���オ��A�������̃A�p�[�g�ɂ������o����̔��^�Ɠ����ł���B����܂ł��ƂȂ����������Ƃ͎v���Ȃ��A�܂�Œ����ς�����悤�ł���B�����ƌ������������ق��ɂݍ����A��̂ǂ��������ň��������Ă��邩�̂悤�ɁA�����悤�ȃ^�C�~���O�œ�̓����㉺���n�߂��B���ꂩ�炪��ςł���B�^�C�~���O�����v������悤�ɁA�����Ȃ蓯���ɔ�яオ���Ă̏R�肠���A�˂����������n�܂����B�܂������Ȃ����낤�ƍ����������Ă����̂����A�{���Ɏn�܂��Ă��܂������{�̔��͂ɋ������B
�@���ꂩ��͊撣��I�������I�ȂǂƉ��Y��Ă̑勻���B�w�F�̒N�������܂�����Ɖ��̂��S���W�̂Ȃ��O��̓z���n�C�ɂȂ邻��ł���B���̒��͖{���ɓ����S�������A���ꂩ��ǂ̂��炢�o�߂����̂��A�g�T�J�Ɍ����o��̂ł͂Ȃ��A�g�T�J���猌���o�Ă����̂ł������Ɏ~�߂������B�ق����Ă����Ύ��ʂ܂ł�肻���ȍ����������Ă����B���ꂩ����������ی�ɂȂ�Ƃ��̃G�L�T�C�e�B���O�ȃC�x���g���ĊJ���ꂽ�B�q��̂��J���̂悤�ɁA���̏����ɂ͌��̌������ȗF�l��������������A���͓��ӂɂȂ��ă����O�A�i�E���T�[�̐^�������āA���������Ȓ��̃����O�l�[����ǂݏグ��B�o�ꂷ��R�{�͓�H�������Ȃ��̂ŁA�K�R�I�ɂ��������ΐ푊��̖����ĂԎ��ɂȂ�B�����炭���̏��w�Z���n�܂��Ĉȗ��A�B��̋M�d�Ȏ��������Ă͗F�l���������������̂��o���Ă���B���v���A���ɂȂ�Ȃ��R�{�̃}�l�[�W���[�����s�t�̂悤�ł������B
�@���b�́A�`���{�Ƃ����j���g������܂��قǏ������A�j���g���Ɠ������Ԃ̍����������̘b�ɂȂ�B������A���E�ň�Ԑg����Ȏ���������W�̃~�[�e�B���O�́A���̘A���i�`���{�j�����ŁA���������h�ȉH�������ׂȂ����Ƃ͂Ȃ����낤�ƌ������_�ɂȂ����B�Ăэl������܂��͎��s�Ƃ����A�ǂ������������Ă��܂����悤�Ȏq�����������ƗF�l�́A�ŏ��̓��͍Z��̒���䂩��P���[�g���قǍ����A�P���I�ȂǂƏ���Ȏ�������ł͗���Œ��ɓ����Ĕ���Ă����B�`���{���������̂܂ܗ�������ɂ��̂ŕK���ɉH�����Ē��n����B���������|�����n����̂Ŏ��M���t���Ă����B����͊̐S�ȃ`���{�ɂł͂Ȃ��A�������Ɏ��M�������Ƃ������ׂ��ׂȘb�Ȃ̂����A�`���{�ɂƂ��Ă͑�ւ���f�Șb�������ɈႢ�Ȃ��B�_����т̑I�肪���킷��悤�ɁA�����グ�鍂���͂Q���[�g������R���[�g���ƒi�X�����Ȃ��Ă������B���̂������q�Â������͒����v���������ɓ����グ�Ă݂��B����ƒ��ɍ��X�Ə��A��ɂ���ĕK���Ƀo�^�o�^�ƉH�������B���̏u�ԁA�`���{�͖��@�ɂ�����R�E�������J���X�ɂł��ϐg���Ă��܂������̂悤�ɍ��������オ�����B���ꂩ�炻�̂܂܂̍�����ۂ����܂܁A�Z��̃u�����R�╻�̗y�����I�X�Ɣ��ōs���A�P�O�O���[�g������̂����̌������ɏ����Ă��܂����B
�@���̎��͂������Ɏ����F�l�������A�������������N�������̂��낤��䩑R�����A���t���������B���̂����ɂ͕|����������B�����̒��̂���Ƃ���̊Ԃ�������Ă����R�E�����Ȃ�ʃ`���{�������A����Ƃ̎v���Ŗ����A��߂����̂����A���v���Δ�ׂȂ����̃M�l�X�L�^��������������Ȃ��B�������A����Ȏ�������������w�Z��搶�����ڋʂ�H�炤���낤�Ɩ{���ɐS�z�ɂȂ����B����܂ł����q�ɏ�肷���čŌ�͕K���{����Ƃ����̂����̓��ӂ̃p�^�[���������B���̋��`���{�����ōs���V�[�����ڂɏĂ����Ăǂ����ڊo�߂������B�ȗ��A�s�^���ƌR�{�̋S�C����j�P�O�����v�����`���{�̃~���N���ȋV�j���Ȃ��Ȃ����B�`���{�̕K���̔�s�́A���ƌ������N���X���H������̂ɏ[���ȏo�����������B�����āA���ɂ̓N���X�݂̂�Ȃ��狋�H�̎c�蕨�̃p�������炢�W�߁A���z�������`���{��R�{�A�j���g����A�q���̉a�ɂ����肵�āA���͖{���̗D�����H����W�̏��N�ɕԂ�炢���B
�@����܂ł͂����N���X�̒��ň��Y�������N����Ə�ɋ^���鑤�̈�l�������B�������A���������đ�l�ɂȂ�v���Ԃ��������ނȂ��A�ǂ����̍��̈������L�ȂǂƂ������̏����̑f�ނɂł��Ȃ肻���ł���B�����Ă��̈��Y���m�肷��킯�ł͂Ȃ����A���������ȃj���g�������̒Ⴂ�ڐ��̌i�F�������Ă��Ȃ������`���{�B���̒��͖{���g�ɂ��Ă�����ԂƂ����{�\��̌������B��c��X����Ƃ��ɖY��Ă��܂��Ă�����������̋C���A������C�������悩�����낤�Ǝv���̂��A���̍��̋U�炴�鎄�̐S���ł���B
2009.02.11(��) ����G�߂�����ė���
�@���͐F���Ȃ��A������Ȃ��G�߂̐^�����Ƃ������������A�������ɓ����L�тĂ��邱�Ƃ͎�������B�₪�ĉ�������Ƃ��Ȃ��������̒��ɔ~�̍��肪�������G�߂ɂȂ邾�낤�B�@�����o�ׂ̍Ő����ɓ��������̍ł��D���ȃq���V���X�A���̍����k���Ɨc�t���̑��ӂɂ�������������˂��o���N�₩�Ȑ��̐F�A�搶�̒e���A��ɂǂ����ŋ�C�������Ă���悤�ȏ�Ȃ��I���K���̉��Ȃǂ��h��B���̔~���I��肵�炭����ƒ����ԁA������D���ȍ���ŁA���Ŗ��J�ɂȂ������̖̑O�Ő[�ċz�����Ȃ��炢�܂ł������Ă����B�����ȉԂ��������W���Ă��邻�̒��Ŏ��͏����Ȓ��ɂȂ�A��������̂���ԁX���ƂɌ����ĂāA�ǂ̉ƂɏZ�������ȂǂƂ����y������z���߂��炵���������������B�f�B�I�[���̍����̃f�B�I���b�V���͂��̉Ԃ̍���ɗǂ����Ă����B
�@�ڂ⎨�Ŋo���Ă��邱�Ƃ͊m���ɑ�R����A�f��A�{�A�ʐ^��CD�A�Ԃ̃G���W������l�̐��ȂǂƂ�����̓I�Ȃ��̂ŕ��i����G�����̂����A���ƍ���͎��ԂƂ��Ă��ݏ����Ȃ��B���̏o��͊X��c�ɂ̂ӂƂ������ŁA�O�G����Ȃ������Ȃ�@�̒��ɓ����Ă���B�������ꎞ�����ĉƁX�ɖ����肪���鍠�A������ɗ[�H�̂����������Ă���������Y���B����̂��̉Ƃ̂������Ȃǂ�z�����Ȃ�������Ɗy�����B�ƂɋA���Ă��ߏ��̔ӌ�т̂������ӊ�Ŕ��\���Ă݂�Ƃ��������a�₩�ɏ���B�������������́A���̎���₻�̏�i�̒��Ɏ��������߂��B����͔]�̂ق�̕Ћ��Ŗ����Ă����זE�������ɂ���Ėڊo�߂Ă��܂����̂悤���B�����Ď��ɂ͉��������Ɠ������Ă���Ȃ��ȂǂƂ����Z���`�ȓz�܂ł����S�̉�������ݏo�Ă���B����������Γ����͎��̂̂Ȃ��S�̌̋��ł��邩������Ȃ��B
�@2�N�قǑO�A�F�l�Ɩ@�t����ɍs�������̒��̐d�i�܂��j��R�₷���̓����ɁA�ߏ��Ŕт�d�ł����Ƃ��������c�������̂��h��B�����A�Ƃ̂��ɕ��X�Ƒ�a���Ƃ�����̑ʉَq�����������B�قƂ�ǖ����̂悤��10�~�ʂ����肵�߂Ă����Ɍ��������������������́A�������ɂƂ��āA�ƂĂ������Ȃ����ӂ������̂��낤�ƍ����v���B ���X�͌C���̐V�����S���Ɣ�̓����A��a���͏����ȕ��[��X�̍��������S���Ǝ��̓����A�Y����Ȃ��������������ł���B�ǂ�������p�̏����ŁA�ʉَq�������ł͎q���������������̎���ł������������悤�ł���B
�@�����Ė����ɓ������̓��C�̒��̑哤�̓����ɁA�h�����ʂɐς܂ꂽ�������Ⴂ�Ɍ������̓����v���o�����肷��B���w�Z����Ɏ��͎���W�Ŗ����̂悤�Ƀo�P�c�Ў�ɃE�T�M�̉a��Ⴂ�ɂ��������̎��ł���B���A���q�̂ق���L���w�����ɂ��̍��̏��C�����������v���o����A�e�ɖ��f��S�z������������̏o�������h��B
�@���̂悤�ɓ����̎v���o�͐s���Ȃ��̂����A��͂肱�ꂩ��}����Ԃ̋G�߂���N�̒��ň�Ԋy���݂ł���B�O�r�̂悤�ɍ��͉Ԃ̍����J�オ��̓����A����Ȑ܁X�̎��R�������邱�ƂɊ�т������Ă���B�܂�Ō͂ꂽ�����l���C����Ă���悤�����A�����̊Ԃ܂ł́A�����̐��̃V�����v�[�̍��肪���̐��ň�Ԃ��Ǝv���Ă����B���̂����̊Ԃ͉����ߋ��̂悤���ɂ����ɕ���ꂽ�܂܂ł���B�l�ԔN���d�˂�Ɗy�Ȃق��ɐg���S���i��ł䂭���̂炵���B
�@���R�̂��ƂȂ���Ԃ͐l�������ׂɂ���̂ł͂Ȃ��A�K���ɂȂ��Ē��������Ă�Ŏ�҂��A�q���ɉh������Ă���B�����ɗ]�v�Ȑl�Ԃ��J��������������@���߂Â����肵�Ă���B����ł��Ԃ͉ǖقŒN�ɂł���g�ɔ���ł����B���Ȃ��Ȃ��̎p�͎����̒Z������m��ʂ��̂悤�ȁA��r�ŐT�܂��₩�ȘȂ܂�������B
�@����ɑ��A���̒��̗D�����ȃV�����v�[�̍�����v���ƁA�ǖقƂ͐����̎��������B�Ԃ̉���{���̐����͂������Ȃ₩���Ƌ���������A�Ƃ��Ă���ؓ�ł͂����Ȃ��B ���������̍���ɂ͉��������ߊ삱�������̑z�������܂�Ă���B���ׂĂ����܂��Ɉ��������Ă���̂��A���̉�����̂���z���̈���A�K�ѕt�������ɖY��Ă�������̂悤�ɁA�S�̒��Ŕ����ɖ�Ƃ�������B
2009.02.02(��) �[���ΐF�̃Z�[�^�[
�@���͋���Ƃ����X���D�����B���̑����ŏI�鎕��̂���������ƁA������������l�̐��E���v�������ׂ�B�O����a���A�O�z�A���Y�̂��ꂼ�ꂪ�p�ɂ���S���ڂ̐�̎����������_�A�~���L�ʂ�Ɍq���邻�ꂼ��̓��̏������������������������B������肱�����y�������Ƃ����l�������Ă���]�T��S�ӋC�����悭���̊X�̕��ɗn������ł���̂��낤�B�����܂����w���̍��A���̊X�̌Â����j���猩��ق�̕Ў��̗��s�ł����Ȃ������A�C�r�[�ɐg���ł߂��A�~���L���ƌĂ���҂��������̊X��舕����Ă����B�@���������������̂��A���ɂ����鎩���̕����ւ̂�����肪�萶�����̂����̍��������Ǝv���B�W���P�b�g�A�Z�[�^�[�A�l�N�^�C�ȊO�͐F�����F���g��Ȃ��A�����ƕ�������{�I�ɑg�ݍ��킹�Ȃ��B�����̑嗬�s�̕����̃V���c�ɕ����̏㒅���d�˂�Ƃ������Ƃ͎��̊o�����t�@�b�V�����̊�{�ɂ͂Ȃ������B������ɐ��O�̒j�̐V�قɍs�����Ƃ��A�V�����u�����h�̌C������ł����B�S���m��Ȃ��V�����͂̃��[�J�[�̒�ɂ͎��̗����������B�O���[�⍕�̃X�[�c�ɖ��邢���̌C�����킹��Ȃ�Ă��Ƃ��Ȃ��������A�����̒�������������Ȏ�҂����͂�����|���������Ȃ��Ă���B�����Ⴂ���������ɏo�������炢�͊y�������ƁA����Ȃ�ɒ�����̂ɂ͋C���g���悤�ɂ��Ă���B�����ɂ͑S���ȑO�̊X�������Ă��܂����悤�ȘZ�{�ȂǂƂ͈Ⴄ�A�ǂ�ȂɊC�O�̍����u�����h���i�o���Ă��Ă��A�̂Ȃ���̖ʉe���c���Ă�����S���Ƌ��D�̂悤�ȑz�������̊X�ɂ͂���B���������_����a���Ɍ����������Ƀe�C�W���E�����Y�V���b�v�⍡�����ɂ͌����Ȃ����g�L�Ƃ����j�����S�̗m���X�A�S�����s�@�Ȃǂ̖͌^�������V�ܓ��Ȃǂ�����B
�@�����w�������������̂��ƁA���ƎO�}��قŐH���������A��ɂ��܂��ܒʂ肩���������g�L�ɓ����������������B���͐̂������̌ł��l�Ԃ��������A�l�N�^�C��}�t���[�Ȃǂ͑傫�Ȕ�����t�ɂȂ�قǎ����Ă��āA�Ăɂ͔����W���P�b�g�Ȃ����肰�Ȃ�����A���̎���̒j�ɂ��Ă͂��Ȃ肨�����Ȑl�������Ƃ����L��������B���͂��̃��g�L�̒��łƂĂ��C�ɂȂ�Z�[�^�[���������B�[���ΐF���������w�A�[�̇X�݂������B�������낢�뎩���̕������Ă����悤�����A���̎�ɂ��Ă���Z�[�^�[�����炭������`������ł����B"����͂ƂĂ������F�̃Z�[�^�[���ȁA�C�ɓ������̂�"�Ǝ��ɕ������B���̎��A���͖{���ɗ~���������̂����A���̂��f���ɃE���ƌ������ɍ��x�ɂ����ƌ����ċA�����B
�@���ꂩ�琔�����o�����B�O�o����A���ė����������������C���Ȃ��₵�����Ȋ炵�āA "���̎��A���O���~�������Ă������g�L�̂��̃Z�[�^�[�A����ȗ��C�ɂȂ��č����̌ߌ�ɔ����ɍs���Ă݂���A���x�A��قǗ���ꂽ�Ⴂ���������Ă�����܂����ƌ����Ă��܂��A���̍ɂ͂Ȃ��̂��ƐH���������Ă��Ō�̈ꖇ�������炵���A�c�O��������" ����������͜��R�Ƃ����B���i�͖��S���Ă��镃�͎��̖{�S���������茩�����Ă����B���̂₳�����ɕ��Ȃ��������A�����ĉ��������̉^���Ƃ������ׂ��A���̍ň��̃^�C�~���O�̈����A���Ƃ������ʋC�܂����B����ňꐶ���ɓ����オ��Ȃ��Ƃ��v�����B
�@���g�L�̓X�̐l�����Ɍ������A�Z�[�^�[���čs���Ă��܂����Ⴂ���͎��������B ���ꂩ��ЂƂ�����A���̃Z�[�^�[�𒅂邽�тɉ�Ƃł͂��̘b��Ő���オ�����B ���ꂩ�琔�\�N�Ƃ��������̎������ꂽ�B�s�v�c�Ȏ��ɁA���̓��̕��̌��t��\��𒀈�o���Ă���̂����A��������ɍs���Ăǂ̂悤�ɂ��ăZ�[�^�[�����̂��A���̂����̃V�[�������|�b�J�������������l�ɋL�����Ȃ��B���N�͂��̒����������Ă��ꂽ���̂V������}����B�����ăO���[�̕\���̌Â��A���o�����v�������悤�ɊJ���ƁA���̃Z�[�^�[�𒅂Ċ��������ɏ��Ă���A�ƂĂ��Ⴉ������������B
2009.01.28(��) ��Ȃ��H���Ӓn
�@�l�Ԃ̑̂Ƃ͖{���Ɏ����ł���A���s�v�c�ʼn����[���Ƃ����v���B�����H�ו��ł�����������������������Ԕ����������邵�A�𑽂̂������������ɂ�����Ȃ�ɂ������͐H�~�������B���ۂɂ͔]�̎w�߂ɂ���Ă��ׂĂ��Ǘ�����Ă���̂��낤���A�v����ɑ̂��~���Ă��鎞����Ԃ̂��y���ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤���B�������ׂŐQ����ň��߂Ȃ�����������A�v�X�Ɉ��ގ��ܑ͌��Z�D�ɐ��ݓn�芴���̈�t�ƂȂ�B���ꂪ���������A�������^���s�����d�Ȃ�Ɣ��������������������Ĕ������Ƃ͊����Ȃ��Ȃ�B�@���j��L���Ȕ��H�Ƃł������ƌ����鐼���@�́A�������鎞�ɂ͉��\�l���̗����l�������A�ꂽ�������B�����v���ɗ����������������y���̘A���A�������z������ɉ^���s���ł��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��ޏ��A�{���ɔ��������H����������̂��͋^�₪�c��B����Ƃ͋t�ɓ����̐��E�ł͕s�K�ɂ��i�A���ɂƂ��Ă͑傫�Ȃ����b��������Ȃ����j���ނ̂��̂����H�ׂȂ��Ƃ������̂����āA���̑�\�I�Ȃ̂̓p���_�̍��A�R�A���̃��[�J���̗t�ł��낤�B��X�^�[�̃p���_�͂Ƃ������A�R�A���͂����{�[�b�Ƃ��Ă���B���[�J���̗t��������ƃ~���g�̂悤�Ȃ���₩�ȍ��肪����A���ꂪ����̂悤�Ȍ��\�����邻�����B����ŃR�A���͂����{�[�b�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����ʔ����b�������Ƃ�����B
�@�����܂ł������ł͎G�H�ŁA���������ꂪ�����������̘b�ɂȂ邪�A����H�ׂ��C�J�̒��i���^�j�Ǝv�������łǂ������Ȃ������낵���Ȃ��B����͖���H�ׂ�Ƃ����Ȃ�B�����Ă��ďݖ��Ƃ݂���悭�C�J���ɟ��݂Ă��āA���ɓ����ƈ�̍���ƂƂ��Ƀt���b�Ɖ����Ă䂭���̊��G���~�߂��Ȃ��B�����ɐh���̓��{���������������ɗ������ށB����͎����̃`�F�C�T�[�ł���B���̖����o�����̂͏a�J�̕S���X�ɂ������n���Ƃ����������������B�ŋ߂ł͊�Ȃ��݂̋����̃I���W���h���g���ƁA���X�I�}�P�ɕt���Ă����B���܂�ɔ����Ȃ̂ŐH�߂���B����Ɍ��炸�A���Ɏ��̏ꍇ�����ł�߂�Ύ��̓����y���������Ă��Ƃ͐��m�ꂸ�B�v�͂��Ȃ�H���Ӓn�E���݈Ӓn�������Ă���ƌ������ƂȂ̂��낤�B�����Ɩ��m�ɕ\������A�Ӓn�����Ƃ������炵���B
�@���̒��ɂ͊�Ȃ��ƒm��Ȃ��������H���l������B�L���Ȃ͉͓̂ł���B���̊�Ȃ��́i��ɗ����Ɗ̑����L���j�̕������V�ɂ�����悤�ɔ��������������A�{���ɓV�ɏ����Ă��܂������l���̂��牽�l������B���͕ς��X�P�[���͏������Ȃ邪�A���ɂ��ȑO����Ȏ����������B
�@�I�͐|�ł��߂ĂȂ����͎~�߂Ƃ��ƌ���ꂽ�̂ɁA���������ɐ����锧�̗U�f�ƈА��̂����������̒���Ɋ��߂���܂܂ɐ��ŐH�ׂ��̂����A���̖�A�M���[���ƈ݂��������ނ悤�ɒɂ��Ȃ����B�b������Ə����āA�܂��C�V�`�ɂȂ�قǐ����ɂ݂�����ė���B���̌J��Ԃ������ɒ��܂ő������̂ŁA�ߏ��̈ݒ��Ȉ�@�ɋ삯���B��͂�ɂ݂͎��܂炸�A�ߌ��Ԃɂ߂ł����݃J�����B�e�Ƒ��������B�݂̒��ɃJ����������b������ƁA��҂��A���܂����I���܂����I�Ƃ܂�Œ��b�ł��������悤�ɋ���ł���B�����̌���������ȖڂŃ��j�^�[�����߂�ƁA���̔������H�s���N�F�݂̈̕ǂɁA�����������̂悤�Ȓ����H������ł���B��҂͂�����N�p�ɃJ�������g���ĎO���̃n�T�~�̂悤�ȕ��ł܂ݏグ���B���̒����H�����Ă������̉������Ȉ݂ɂ͐Ԃ������Ȍ����J�����B ���̒����̓A�j�T�L�X�Ƃ������̂ŁA���ɎI��C�J�̑̂̒��ő����������Ă���ƌ����B �݂���o�Ă��������������r�[�J�[�̐��̒��ɕ����ƁA���ꂪ�܂�Ō��C�ȉV�̂悤�Ɋ��������Ɖj��������̂������B���̒��͐l�Ԃ̑̂̒��ł��R�C�S��������������Ɏ��ʂ��������A���̊Ԏ��]���|�ł͂��܂������̂ł͂Ȃ��B����ȃ��c�����̒��ɂ���Ɛg�������Ēm�����̂͂P�O�N���炢�O�̂��Ƃ������B�ȗ��A�I�ƃC�J�͕��X�ɂȂ�܂ŗǂ�����ŐH�ׂ�悤�ɂȂ����B�l�ԁA�~�����Ε��قǔ����������́A��Ȃ����̂ɂ��������H���o�Ă��܂����̂炵���B
�@�����Ȃ���́A�Y��Ȃ��̂ɂ͓łɂ͂�����Ƃ͗ǂ����������̂ł���B�����悤�ɒN���������� "���������i�ЂƁj�ɂ͓ł�����"�Ƃ����B���̓ł��u�X�Ƃ��ǂށB��͔��������S�̓u�X�A�܂�ŒN������̂悤�Ȓ����Ȃ钠�K�ƌ������ɁA����ƂȂ����Ɏʂ��Ă������̊�́A�Ԃ̔������Ί�ɂȂ��Ă����B
2009.01.27(��) �Ƃ����ɐl�̐���
�@��邩��~�葱�����݂��ꍬ����̂��ʂ��J����݁A�_�Ԃ��牷���Ȍ����˂��Ă���B�v���Ε�ꂩ��b�����V�����������N�ŏ��̉J�������Ǝv���B�[�������z�����ނƁA�₽�����������̋�C���x�����ς��ɐS�n�悭�L�����Ă����B�@���̋�ɂ͐����A������ł��锒���_�͉��̂悤�ɐ����ǂ���ɗ�����Ă䂫�A����Əd�Ȃ肷��Ⴄ�_�͂��Ȃ荂�����ɂ���悤�ŁA�������������~�܂����G�̂悤�ɂ����Ƃ��ē����Ȃ��B����̂ӂƂ�������Ȏ��A��������ɂ��邱�̎��R�́A�C��R�����ω��ɕx�\����y���܂��Ă���Ă���̂��ƋC�t���B�ƁX�̒���v���Ԃ�̉J�ɑ��𐁂��Ԃ����悤�ŁA��Ύ������ɋP���Ă���B
�@���ɂ͖����ɏ��X�����肪����A������N�p�ɂ悯�Ȃ����Ƃ̌��������ŕ����Ă䂭�B����͋��ȉJ�ŕ\�ɏo���Ȃ��������̕��A�ޏ��͂��̎���������2�{�y����ł���悤���B�������A�������N���}�[�L���O�Ƃ����Ď����̐w�n���̗l�ɁA���ւ�������Ƃ���Ɉ��������ĕ����悤�ɂȂ��Ă��܂����̂ɂ͕����Ă���B���C���A�D���Ȃ悤�ɕ�������������̐ӔC�͖����Ȃ̂����A���̂������������������̂��͖����ɂ킩��Ȃ��ł���B�����s�V�̌��������̕i�]��Ȃ���̂ɂł�A�ޏ��͂����炭�ʼn��ʂɂȂ邾�낤�B
�@�����܂��P�O��O���̍��A�ǂ��łǂ��Ԉ�����̂��A�����Ă����{�N�T�[���ł���ɒ��킵�����Ƃ�����B����͂܂��̓_�]����ɂ����R���������̂Ƃ���ɂ���Ă��āA�ڕ@�⎨�̌`�A�O���܂��肠���Ă̎����т̃`�F�b�N�A�т̐F���A�̌^���獜�i�ɂ�����ׂ����̓_���Ȃ����B�Ō�ɂ͑傫�ȉ~�̊O����������Ƌ��ɉ��A�����肩�畁�ʂɕ����̂����x���J��Ԃ��B���̏ꍇ������Ƒ��������Ă��鎖�A���������Čy�₩�ɕ����Ă��邩�Ȃǂ��̓_�̏d�v�|�C���g�ƂȂ�B�ŏ��͊O���ł������ɂ����̂����A���ꂢ�₢��������̑ԓx�i�ǂ����͎�����Ɏ���Ƃ����j�ɐR�����̌������̓_���������̂��v���o���B�ǂ����킪�ƌn�͓`���I�Ɍ��ɂ������Â��A�������Ǝ��ɂ͋C�̌����܂܁A�{�\�������܂܂̎��炪�������悤���B
�@�ȗ��A�q����������ɂ��s�����A�܂��ău���[�_�[�ł��Ȃ���Ƃł́A�i�]���h�b�O�V���[�͖����̑��݂ɂȂ����B�ȑO�ɂ����������A���̎������ɗv�����邱�Ƃ́A�܂��͋A���Ă�������ŏo�}���邱�ƁB�x������Ƒ呛���͗]�v�����A������x�̖h�ƂɊ�^���邱�ƁA���𓐂�ŐH�ׂʂ��ƂȂǂŁA�}�[�L���O�ɖڂ��ނ�Δޏ��͐��Ԉ�ʂł����D�G�Ȍ��Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�A�����]�ޖ�ڂ��[���ʂ����Ă���B�����Ŗ����̉��l�Ȃ���̂���������̂ł��邩���l����ƁA����͒P�ɐl�����̃j�[�Y�ɍ��킹�Ă�������ł���A���̃j�[�Y���Ȃ���Ή��̉��l�����o���Ȃ����ɂȂ�B
�@�ꉭ�l�̐l�Ԃ�����Ƃ���A���R�ꉭ�l�����ꂼ��̌�������B�����Ɍ��d����_��ȉ��l����Ƃ������̂��l���̑I�����ɂ���A�����Ȏ��ɒ��킷��l����葽���o�����邾�낤�B�c�O�Ȃ���ߋ������݂��A�����Ă��ꂩ����A���̂�����˔\��u���ǂ�ȂɖL���Ȑl�������Ă��A������ƁA�l�̈��S�ƗD�z������邨�������܂Ȃ�����A���悻���Ԃ͂�����K���Ƃ͌��킸�A���đO�ł͂Ȃ��{���̕]���������̂����̏킾�낤�B�����ĉ��X�ɂ��Ă��̐l�̍s�Ȃ����d���▼�O���F�߂���̂́A���̐��������Ă��牽�Ă��Ƃ���������B
�@����Ȏ��A���� "�Ƃ����ɐl�̐��͏Z�݂ɂ���"�Ƃ������̑����̈�����v���o���B�l�̐��ɂ������N���������Ǝ��Ԃɒǂ��Đ����Ă䂭�B�����Đl�̐��͐_��S����������̂ł͂Ȃ��A�������O�����ׂɂ��炿�炵�Ă��邽���̐l�����������̂ł��邱�Ƃ��m���ł���B�l�̂��߂ɔ߂��݁A�ꂵ�݁A�l�̂��߂Ɋ�т��J��Ԃ����F�͊F�����̐l�B���ꂪ�U�O��ڂ̂ЂƂ育�ƁA�v�X���m�h���Ȃ��Ă䂭�Ɗ����鍡�̐��ŁA���߂Ă����Ǝ��Ԃ͗L���ɁA�ێq��K�̂����d���̐l�X�͂��Ēu���āA���ԓ��ł͋K����ȂǂƂ������������́A�ɂ₩�ɂ����炩�ɍs���������̂ł���B
2009.01.10(�y) �]�m���w��
�@�����̂������N���̍s���́A���ߏ��̘@�؎��ɏ���̏���˂��ɍs���̂ƍ]�m���w�ł������Ă���B���̂��Ƃ͂Ȃ��I���W�B���]�m���ɍs���ĐV�N�̗[�������Ȃ���������ނ����Ȃ̂����A���ꂪ�Ȃ��Ɖ��ƂȂ��₵���N�̏��߂ɂȂ�悤�ŎQ�����ĂT�N�ڂɂȂ�B �]�m���ւ̍s���������܂��܂ŁA�]�m�d�A���m���[�����p�A���c�}���}���X�J�[�A�}�s��̂�т�e�w�Ɗy�����B���N�͐V�h�w����v���X600�~�������ă��b�`�ȋC���̃��}���X�J�[�ɂ��Ă݂��B�@�����̉��₩�ȓ��ɕ�܂ꂽ�����݂����Ȃ����ꎞ�Ԃœ����A���̎����͗��ɉJ�ɍ~��ꂽ���Ƃ��Ȃ��S�n�悢�B�_�炩�ȊC���ɐ�����Ȃ��璷�������l�̗���ɐg���܂����A���ɐ��q�A�E�Ɋ�������ʂ����Ȃ���������Ƌ���n��B��̏�ɍՂ�ꂽ����̐_�X�ɂ��Q������Ȃ��瓇�̓˒[�̂����̓X�ɓ���B���j���[�͖��N�S�������C�J�̊ۏĂ��A�A�W�̂������A���ł�A�L��h���g������ꂽ�]�m���T���_�A���̗F�͑��ɂȂ��̂ł�������Ɏ�藯�߂̂Ȃ��b�����Ȃ�����v��҂B
�@������12���̑҂����킹�Œ��ɕK���x���s�͂��ҁi���N�͎��j���o��̂����A�x���Ƃ��ߌ�1���ɂ͈��݉�̃X�^�[�g���̂ŁA���Ȃ��Ƃ�4���Ԃ͂����Ղ���݂��ςȂ��A����ׂ���ςȂ��ƂȂ�B�]�m���̓˒[�̍���Ɉʒu���邱�̓X�̃x�����_�ɂ́A�J�b�v����Ƒ��A�ꂪ��O�ɍL����C�����Ȃ���H���̏o����A�P�ɔ����ׂ��ג����e�[�u��������B�y�����ʂɑ哇�A���̂��E�ɕx�m�R���]�߁A������O�ɂ͊C�����̓����y���ގԂ�����A��������������ɓ������ɑ�����i�����\�ł���B������������グ��A��N������݂̃g���r���s�[�q�������Ƃ������ʼn̂��Ă���B
�@���ݎn�߂͒��H���Əd�Ȃ��Ă��Ȃ荬�ݍ����Ă���̂����A2���Ԃ�����Ƌq���܂�ɂȂ��Đ�D�̓D���^�C��������ė���B��X�̘b���ŏ��͂܂Ƃ��ȉ��y�A�f��A�����A�����Ƒ���ɓn���Ęb���i��ł䂭�̂����A��������낻��̒��ɐ�������鍠�ɂȂ�ƁA�l�ɉ������L�c�l��K�������f���ĐK�����o���悤�ɁA��ʏ펯�l�Ȃ���ɂ��Ȃ����t�̐��X���A���R�[���ɂ܂݂ꂽ�������яo���悤�ɂȂ�B�ق��50�Z���`�l���̏����ȃe�[�u���Řb�������鐺�́A�X�̗y������ԃg���r�ɂ܂ŕ����������ȂقǑ傫�Ȑ��ƂȂ��ďÓ�̊C���ƌ����B���ɐ�قǂ܂ŐX�ƈ��D���̂��Ă����g���r�̖������A���̊Ԃɂ��I���W�B�����n���ɂ����悤�ȏ����ɕ������Ă���B
�@�ЂƂ������Βk�Ŏv���̂���������Ă���A��������������J�ɂ����̂��A����ׂ葱���ē��̒�������ۂɂȂ������̂��͒肩�ł͂Ȃ����A���̊Ԃ̐Ïl���K��Ă���A���x�͑��̊O���{���̐�i�^�C���ɂȂ�B��������X�����������̂�O�ɂ������̎�����͐^�ʖڂȖʎ����ɂȂ�A�S�͏������������N����ɋA��B��قǂ܂ŋP���Ă������z���A���̊Ԃɂ����̋�̈��_�ɂ����ۂ�ƉB��A�s������������I�����W�F�̌��͐^���̊C�ɑ��̑��z�܂ꂳ�����B���̉��ɂ��c�ɂ��L�������[�����z�́A��u��ῂ��P���ڂ���������̊C�ɉf�������B�����Ă��悢��_�ƎR���݂̌��Ԃ���{���̑傫�ȗ[�z������o���B�����ɂ������Ȃ����̊ԁA�����O�����������C���N�u���[�̋�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�n��̂��ׂĂ̖X�⌚���A�����Đ����Ă��I���W�B�̊�̂��ׂĂ��I�����W�F�ɐ��ߏグ�Ȃ���A�厩�R�̈������߂�����A���i���������j�̃X�e�[�W�̖��͍~���B
�@���̂悤�Ȋ�����Â��Ɏア�l�Ԃ͏����̏o�₲���������邱�Ƃ͋H�����A����ȑf���炵���T���Z�b�g�͓���̒��ł������o���킷���Ƃ��o����B�q���̍��A�Ƃ̂��̊R�̏ォ�璾�݂䂭����ȗ[�������Ă����̂��v���o�����B
�@���͗���A�����̍��ƌ����Ă��܂����a�Ƃ������オ�I��葁20�N�ȏオ�߂����B������2009�N�̃X�^�[�g�͐��A�����A���W������Z�s��̍����Ɛl�Ԍy���̌o�ς����������ł���B�₪�ē��{�̐������傫�Ȑߖڂ��}���A�A�����J���V�������[�_�[�Ɋ��҂��鎞�オ�n�܂�B���Ƃ��ƐM�S�̔���������߂����g�̏ゾ���A��N�Ɉ�x�͂���Ȕ��������R�Ɋ�������鎖�������Ǝv���B�����Ă��Ȃ�������Ƃ����̂������͂Ƃ�����N�̏��߁A���ׂĂ̐l�������Ȃ�����O�����ɑ̂ƐS�̃o�����X���Ƃ�Ȃ���A�D�����ȗz�����˂�������N�ł����ė~�����Ɗ肤�B
2008.12.25(��) ���R
�@���̐����f���Ă�����Ƃ��C�̂������A��N���X���Â��ʼn��ƂȂ�����オ��Ȃ��Y�N������悤�Ɋ�����B����A�����^���[���T�O���}�������������A�\�Q���ɂ͖��N���邽�тɃ��}���`�b�N�ȋC�����ɂ�����ꂽ�A���̃C���~�l�[�V�������Ȃ��B�@����A����̏Ă�����ł����₩�Ȉ��݉�������B�킴�킴���R���炻�ׂ̈ɏo�Ă���T���Ƃ̎�藯�߂̂Ȃ��b�̒��ŁA�������������x�������ǂ�ł݂����Ƃ����b�Ő���オ�����B���̕NJ��ɒǂ������������郁�f�B�A�̎l�Z�����̕s�i�C�A�āA�����͂��̂����ƈȑO���炻��Ȏ��ɋC�t���Ă���B���̃`�O�n�O�ŎE���Ƃ�������A�����ł����{�l�̐S�̌̋��A�D�����C�����ɐG��Ă݂������̂ł���B����܂ł̖c��ȍ�i�̒��ŁA�ق�̑�\�삵���ǂ�ł��Ȃ����������T���ɃW�����N���ɍs�����B
�@�I�{�͎l�̘b����Ȃ��Ă���A���̒��ŋ����b�̒��Ɉ������܂ꂽ�̂�"�|���~���̏t��"�������B�c��������̏����m�̃��C�o���̘b�ŁA�q���C���̓c�߂͂��Ȃ�̌��̎g����ł���A���ɗ����v�̏o���������Ȃ���b�͐i�ށB���C�o���̎O��́A�c�߂̕v�̂���܂����C�o���W�ɂ��鎩���̕v�̏o����������ށB�����Ȏv�f�������ʁA���̐l�����I�����ŗ����Ƒ�����B
�@�����ǂݏI�������A���C�Ȃ�TV�����Ă���ƂX������NHK�̎��㌀�X�y�V�������n�܂����B���Ɠ�������̌���Ƃ���B���ɂ���ēǂ��̓��̂��ƁA����������̉��Ɠ��R���鎖�ɂ����B�Ԃ̌ւ�`�Ƃ����^�C�g���Ő��˒������剉�̃h���}���n�܂�A�r������A���b�ƂȂ����B�ޏ��������Ă���͕̂�����Ȃ���قǓǂݏI����������"�|���~���̏t��"��l���̓c�߂������B���̖����̈�̋��R�ɋ������肾�����B�����A���˂̌�C�̋��������̒��̓c�߂̃C���[�W�Ƃ͈قȂ������A�����̋r�{�Ƃ̒��J�ȍ��́A�������̓I�ȕ\���������Ă킩��₷�������B
�@���̋��R�����ł��̖{��������x�J���A���C�Ȃ��u�b�N�J�o�[���͂����Ă݂�ƒP�Ȃ鎄�̕s���ӂł��������ƂɋC���t�����B�^�X�L�ɂ͂�������Ɠc�ߖ��̐��˒������f���Ă��āANHK�̓����̕����\����܂Ŗ��L����Ă����B���ꂳ�����Ȃ���Q�O�O�W�N����߂����鎄�̐�ڈ���̏o�����Ƃ��Ĉꐶ�S�Ɏc����̂������ɈႢ�Ȃ��B
�@���̂悤�ɐ��̒��ɂ͌��Ȃ���Ηǂ������B�����Ȃ���Ηǂ��������Ď������̐��قǂ���B����͊O�I�v�f�������A�����I�Ȃ̂͌���Ȃ���ǂ������ł��낤�B�������Ƌ{�̂R�C�̉��݂����Șb�ɂȂ邪�A���̕�ꂩ��N�n�ɂ����Đl���W�܂邱�Ƃ������A���ߕ��A��˒[��c�̂悤�Ȑl�̉\�b������܂ňȏ�ɑ����Ȃ肻���ł���B����̕����܂܁A�v�������y�X�������ɏo�������Ȃ́A���̍ېT�݂����B���v�ٍl�A���N�͉N�̔N�A������ǂ����ݍӂ��A�ȑO�ɍQ�������ݍ���ł��܂����o������������x���ݒ����Ă݂�̂��������낤�B��������Ƃ��Ȃ����ł���n�G��A�u����������Ɣ��Œ@���A�������Ƃ������m���ɑO�i���闈�N�ł��肽���Ɗ肤�N�̐��ł���B
2008.12.15(��) ���ꂪ��߂���
�@�@ �@�Q�����N�̐��̒����Ɍ���PRAYBOY���̔p���̋L�����ڂ��Ă����B���ɂR�R�N�̗��j�ɖ������肽�Ƃ������Ƃ��B���ۂɂ͎��͂��̖{�̈��ǎ҂ł��Ȃ�ł��Ȃ��̂����A�A�����J�����ւ̓���̏I���Ƃ������S�[�����̂������悬�����B�T�ԃv���C�{�[�C�̌㔭�ƂȂ�A�A�����J�{���̎o�����Ƃ��ăX�^�[�g�����L��������B���̍��A�����J�Ŗ{���Ɍf�ڂ��ꂽ�����̑̂̈��|�I�{�����[���ɋ�������A�������ȃ}���K�̑}�G�ɓ���̕����������A�R�}�[�V�����̃y�[�W�ɂ����̐������ꂽ�C���p�N�g���V�N�������B���̓����ł���A����ł��鏗���̃k�[�h�͂��̂܂܂ɁA���{�Ǝ��̓W�J�ł��̎��X�̎���̃h�L�������g��ǂ��āA�Љ����������ƑO�ʂɑł��o���Ă������Ƃ����̎��̖��͂ł������Ǝv���B���x���������悢��~�n�����}�������A�����̃G���[�g�E�T�����[�}���ƁA�����ł���Ɗ��Ⴂ�����j�S����������v���C�{�[�C�N���u�Ȃ���̂��Z�{�̃��A�r���̒��ɏo�����B�Q�O�㔼�̎������Ѓ}���̐�y�ł�����X�ɘA��čs���ꂽ�̂��o���Ă���B�����ɂ͖ԃ^�C�c�̃o�j�[�t�@�b�V�����ɐg�����������������ƁA�����ł��Ȃ������������D��������Ŏ������̎��Ȃǂ��^��ł��ꂽ���ƂȂǂ��v���������B�����Ă��̃E�T�M�̃��S�}�[�N�̕t�����Z�[�^�[��|���V���c�̗��s�Ȃǂ����v���Ή��������B�@�A�����J���̂��̂̃C���[�W���F�Z���c�邻�̖��O"�v���C�{�[�C"�B���ƂȂ��Ă͂��̋����ɉ��������������Ă��܂��B�����Ō����Ȃ�C�P�����Ƀ`���C�������悤�Ȃ��̂��낤���H �ȑO�A"�R�[���Ɩ�̗V���n"�Ƃ����ЂƂ育�Ƃł��G�ꂽ�A�A�����J�ւ̓����S�ɐt���߂��������̐���B���ꂩ�璷���N�����o�ăO���[�o�������i�ޒ��A�A�����J�͏�ɉ�X�̓���ɓ��荞�݁A���{�l�͒��ڂ��̕������Ɛ��_���̂��̂ɐG���悤�ɂȂ�B���ł̓��W���[�E���[�O���玖���A���̗̂ނ܂ŁA���C�u�f���ŃA�����J�̌��������{�̒��̊Ԃɓ����Ă���悤�ɂȂ�A�O�L�̗l�ȓ���⋻�������ꂽ���Ƃ��A�����PRAYBOY���̔p���ɂȂ����������������Ȃ��B
�@�T�u�v���C���E���[���ɒ[�������Z��@�A�ď،����̃��[�}���E�u���U�[�X�͎����j���[���[�N�ɒ����������ɔj�]���A�������̖��̃r���̑O��ʂ����B�ꓙ�n�ł���^�C���Y�E�X�N�G�A���ɉ��鍶���Ɍ����A�F���K���X�����菄�炳�ꂽ���̊O�ς́A�}�l�[�Q�[���ɖ�����ꂽ�ʂẴA�����J���{��`�̎c�[������悤�������B�����Ɖ����ăE�H�[���X�ɍs���A�傫�ȕč��̊��̉��A�����TV�ǂ��������p�����Ă��đ�ւ�ȑ����ɂȂ��Ă����B�����č��A���̎Ԃ̃r�b�O�X���[���o�c�j�]�̊�@�ƂȂ��Đ��{�Ɏx�������߂Ă���B�ŏI�I�ɂ͂P�P���~�ɂ����x�������K�v�ɂȂ�Ƃ����B����܂ł̕����o�c�̕t���������̐ŋ��ł܂��Ȃ��Ƃ͂��������Ƃ������_�A�����̗[���ł͕ċc��A�~�ϋ��c����Ƃ���B�o�u���������̓��{�̋�s�~�ςւ̖��ӂƗǂ����Ă���̂����A���s�c�菑�ɑ�\�����u�b�V�������̃G�l���M�[�����ɔw���������p��������A���̏����ւ̊Â��Ƙ��������A���̂܂܃A�����J��Ƃ��\����o�c�ɂ����f�������̂悤�Ȍ����������B�ꂷ��B�o�ςŌq���ꂽ�ꍑ���P������A�����ɂ͒n�̉ʂĂ̍��܂ł������ׂ������A���A���^�C���ʼn����������ׂĂ̏�s���������̒��ɂȂ萢�E�͋����Ȃ����B�킩��Ȃ����A�`���Ȃ������������������v���鍡�����̍��ł���B
�@�����̓ˑR�̗Ⴆ�ŋ��k�����A"���l�͎O���ŖO���邪�A�u�X�͎O�����o�ĂΊ����"�Ƃ����A���l�ƌ���Ȃ������吨�̒j�������Ԃ߂�悤�ȁA�����Ƃ��炵���W���[�N������B�������A���{�l�̃A�����J���Ɠ��l�A�ǂ���ɂ��Ă�����鎖�ł̍D���Ⓑ���t�������قǍ���Ă����Ȃ�Ď��͋H�ŁA�ꏏ�ɂ����"������������"��������"�����͂���"�������Ƃ����^����m�鎞������B��������e�ŕ�ݍ��߂邩���ꐶ�̔����A���N�̗F�ł��邱�Ƃ̕ʂ�ڂ̂悤���B�X�ł���Ⴄ���l��ǂ����Œm�荇�������Ζʂِ̈��ɋ����Ƃ��߂��������Ƃ����x�������낤���Ɖ������ށB�������A�ǂ��ώ@���Ă݂��炻���ł��Ȃ������Ȃ�Ă����o���͂Ȃ����낤���H���̕�������o���킪�g���Ȃ݂��A���������x���Ă���Ă���Ƒ����Ȃ݂��̌����������肾���A���̊F�ܖ��������t���A���{�̎���Ȃ������ꂪ�����قǒZ���Ȃ��Ă��鎞�オ���������B�����ł����͗�߂�Ƃ��������̃e�[�}�A���ꂾ���ł͐��̒��͙R���߂�������B�t���܂��^�Ȃ�A���Ă̑f���炵�������A�����J�f��̐��X�A�����P��������u���[�h�E�F�C�E�~���[�W�J���̂悤�Ɋ��߂Ί��ނقǖ����o��A�m��Βm��قǍD���ɂȂ�`�i���̏ܖ��������ւ邻�̉��������߂ā`���T�u�^�C�g���ɒu���Ă݂��B
2008.12.01(��) ���N�A���̃i���o�[�E����
�@�@�������炢�悢��t���ɓ������B�������ǂݕ��ŁA���̐��̒��͂炢���ɖڂ��������A�y�����y�ȕ����ɐi��ł��鎖�������グ�Ă��肢��Ǝw�E���Ă����B�܂��Ɏ��̂��̂ЂƂ育�Ƃ��w���Ă���悤�������B���ہA���̂ق��������Ă��Ă��y�������炾�Ƃ������Ƃ�����̂����A���̐��ɐ���������ɂ͗��s�s�A�߈��ɂ��K���o��A�����ďI�ǂ̎��Ƃ����N������щz���邱�Ƃ̏o���Ȃ������ɂ���������˂Ȃ�Ȃ��B�@�@�������Ȃ莞�Ԃ͌o���Ă��܂����̂����A���{�f��ŋv�X�̃����O�����𑱂��Ă���"������т�"���P�O���Ɍ����B���͂��̉f��Ƃ̏o��͍��N�̏t�悾�����B�m�l�����i��ق̒n���ɂ��郌�X�g�����œn���ꂽ��{�ŁA�������̂���\���ɔ�����"������т�"�Ə����ꂽ�Ђ炪�ȕ����A�������ɂ��̎����獡�g���Ă��郍�S�����肳��Ă����B "�Ƃ肠�����ǂ�Ŋ��z�����Ă�"���ނ̌��t�ŁA�Ƃ肠�����ǂ�ł݂��B�ē͑�c�m��Y�A�L���X�g�ɖ{�؉�O�A�L�����q�A�R��w�Ƃ��������A�Ȃ��đ�̂̕��͋C�����݂Ȃ���̓ǂݎn�߂������B�����ēǂݏI����ċC�����Ɨ܂��j��`����Ă����B
�@�@�d����s�u�̔ԑg�̑�{�Ȃǂ͗ǂ��ڂ�ʂ����̂����A�������ĉf��̑�{��^�ʖڂɓǂ̂����߂Ă��������A��{�ŋ������̂����߂Ă̌o���������B�����Ă��̑�{�̉ǂ݂����̎��̒��ԓ��Ŏn�܂����B���ꂼ��̊��z�𒀈ꕷ�����킯�ł͂Ȃ��̂����A���̘b���U�肩��z������ɁA�����ꏭ�Ȃ���F���Ɠ����悤�ȏɊׂ����͗l�ł���B��{��ǂS�l���A���̉f�����������Ɍ��ɍs�����Ɗy���݂ɂ��Ă������؊Ԃ����ɂȂ��āA���̍�i�������g���I�[���̐��E�f��ՂŃO�����v������܂����ƕ������B����Ȋ��Ɏア���{�l�̂��ƁA�����吨�������邾�낤�Ə����Ԃ�u���Ă̊Ϗ܉�ƂȂ����B
�@�@���ۂɌ��I����Ă���̊��z�́A�܂��Ɏ��ƒ��ڌ����������f�悾�����B�O���ł����Ƃ����������ʂ̎����e�[�}�A������ǂ����镨��̈�����҂̈�l�̎���ǂ��̂ł͂Ȃ��A�����̎���W�X�ƒԂ��Ă䂭�A���ꂪ���ɐS�ɋ����A���̐g�߂ɂ���������܂ł̎��������Ɏv���o�����A�����̊��o�Ɉ����߂��ꂽ�B����͎c���ꂽ�҂̐S�̕`�ʂ����ł��錾�t��\��ɂ���ĕ����яオ�点��f���̏����ł���B�������͗ǂ�����"��{�ɂ͂Ȃ��������t"�ł͂Ȃ�"��{�ɂ͂Ȃ������f��"�ł���B�R�`����������̏���I���i�A���̋G�߂̈ڂ낢�̒��ŕ���͐i��ōs���B�N�����}���鎀�A�N�������̒��O�܂Ō��C�ł������Ɗ肢�A�����ĒN�������̉f��̂悤�Ɏ����ɂ͏o���邱�ƂȂ��Y��ł��肽���Ɗ肤���낤�B����͂���܂ł̐l���̃t�B�i�[���������Ȏ��̂悤�ȋC�ɂ�����ꂽ�B
�@�@�����܂ޑ����̓��{�l�͂��Ƃ��Ɩ{���I�ɖ��@���ł���A�������ɂ̓L���X�g���ɂȂ�����_���ɂȂ�����A�e���̑��V��@���ɂ͂����Ȃ蕧���ɂȂ����肷��̂�������O�ŁA���{�l�͂����������̐��ɂ͉������҂��Ă���̂��낤���Ƃ��v���B���������̐�������̂����A���ׂĂ̐l�͍s�������Ƃ��Ȃ��̂ł킩�炸���܂����B���̋��|�Əd�ꂵ���C����������ׂɐ��܂ꂽ�̂��@���ł���A�L���X�g��߉ށA�A���[�₻�̑��̐_�X�ɐ�����҂̐S�̋~���Ƃ��ĊF��������킹��B�ǂ���̏@����I�Ԃ��͂��ꂼ��̌l�����D���Ȃ悤�ɂ�������̂����A "������т�"�ł͂���ȏ@���S�Ȃ���̂�ǂ������鎖���Ȃ��A�����I�Ȃ��Ƃڌ����Ċ��������Ă��܂��͂�������B���ۂɐ_�ɋF��̂ł͂Ȃ��A�g�߂ŖS���Ȃ������̐l�Ɍ�肩����悤�Ɏ�����킹��l�������Ǝ��͐M���Ă���B
�@�@�e�[�}���e�[�}�����ɈÂ��h�����̂�A�z�����������A���Ȃ�R�~�J���ȉf��Ȃ�ł͂̌�y�I�v�f���܂܂��Ă���B�L���̉�����Ȃ��v�̎d���̓��e�ɂ�����ʂĕʋ�����̂����A�v�̂��ƂɋA���Ă��鏊�ɉf������Ă���j�����N�ւ̋~��������A���C���̂����݂���ɕ�����g�s�a�q�������A����̖{���q���̍��ɕ��C���ŗ��e�̗�����Y�݁A�N�ɂ������Ȃ��悤�Ɉ�l�ŋ����Ă����Ƃ������t�Ɏv�킸�ق���Ƃ������A���̉f��̍Ō�̌�����A��{�ł������������ꂽ�����ł��镃�Ǝq�̈�����p���S���A����ꂽ�ۂ��ɑ����Ă���Ƃ���͑�z�����W�J�������B���ۂɎ��Ƃ������̂͋ł͂��Ȃ��ĂƂĂ��߂����B�������̉f��̂悤��"�S"��B�ꎟ����Ɍq���c���鉷���ȍ��Y�Ƃ��ĕ\�����A����ɔ����Ƒ����J�����X�ł��肰�Ȃ��`�������S�������o�́A���܂ł��l�X�̐S�Ɏc��A�ߔN�̖���ƂȂ肦��̂ł͂Ȃ����낤���B
2008.11.29 (��) �ꔑ���s
�@�@�}�X�R�~�������g���̏o��҂����܂�A���悢�捡�N�����Ƃ킸���B�����I��A�����ˁI�Ƃ��ꂪ���܂��čJ�̈��A�ɂȂ��Ă���B�N�X�����o�̂������Ȃ�Ɗ����Ă���̂́A�l�ދ��ʂ̊��o�̂悤���B�����܂łɂ����V�����̑r���t�����Ă���B���肠������A�l���ɂ�����ߋ��̓h���h���傫���c���ł䂭���A�����̓h���h�����ꏬ�����Ȃ��Ă���B���R�Ȃ��炻��͐��܂ꂽ������n�܂��Ă������ƂȂ̂����A�l�������z����������A�����Ɖߋ��̑傫�����t�]���������肩��g�ɟ��݂Ă����������悤�ɂȂ�B�@�@���ۂɂ��ꂩ�炱��Ȃ��Ƃ����Ă�낤�A����Ȃ��Ƃ����Ă�낤���Ǝv���Ă���S���h�炮���Ƃ������ŁA����ł������B������ׂ̓w�͂ƐS�ӋC�����͗����܂��ƁA����ӂ��S�Ƃ̐킢�͑����Ă���B����A���̖c��ɖc��オ�����v���o�̔��̒��ɁA�G�R�Ɠ]�����Ă���ߋ��̐������E���グ�A���w����̋��F�����Ə��߂Ẳ��s�ɍs���Ă����B�j�q�Z�������ׁA���s�u��t����ƈ��ʂ̐l�̒��ɁA�K����l�͓o�ꂵ�Ă���悤�ȃI�J�}�ɂȂ�Ȃ���������A���R�ނ������I���W�B����ł���B�������ʔ������ɁA���\���K�L�Ŗ���y�����U�l���������B���ꂼ�ꎝ���Ă���Ԃɕ֏�͎~�߂āA���̃����{�b�N�X�̃����^�J�[�ɑS������荞�݁A���Ƃ܂݂�����ł����M�C�֏o���Ƃ����Ȃ����B
�@�@���A�X���𑖂����Ă���Ƒ��v���̕��������Ă�܂Ȃ������{�b�N�X�J�[�A���Z�E��w�����ʂ��ă��O�r�[���������啿�ȂR�l�Ə��X�H���߂Ȏ��ƒ����N�A���̍��ؚ̉��ȑ̂𖢂��Ɉێ����Ă���̂́A�^�]�����Ă��ꂽ�X�c�N�����������B����ȃI���W�������������]�T�ň��ݍ���ł��܂����̎��͂ƕ֗����́A��͂�Ԃ̕i�i�ȂǂƂ��������Ȏ����ɂ͂��܂��Ă͂����Ȃ���Ԃ�����B���̎Ԃ̒�����C���͊��ɁA�F���w���̂��̍��ɋA���Ă���B���R�A�v���o�̏o�������b��̒��S�ɂȂ�̂����A����͔N�̌��A�b�͔��Ђꂩ��w�т�A���т�������ۂɂ��������Ƃ��A���̊Ԃɂ����{�傰���ȏ��b�ɐ������čs���B�����Ȃ�ƕ��i�T�ς𗭂ߍ��I���W�B�̐S�́A��ɕ����ꂽ��̂��Ƃ��A�����A���������オ����E�̎�������������Ȃ��Ȃ�B�x���̑�a���Ȃ�̂��́A��C�����C���ł����Ƃ����ԂɔM�C�ɓ����A���̂܂ܖ�܂ŏ�k�Ƃ��{�C�Ƃ����Ȃ���b�Ə��͑������B���������ɁH�F���Q�Â܂����N�O���A�N�����Q���œ����̍Z�̂�M���Ƃ����I�}�P�܂ł����B�i���g�Q���ōZ�́I���̖�S�R�N�Ԃ�̍Z�̂��A���܂�̉��������Ɋ����A���܂Ŗ���Ȃ������Ƃ����y�܂ŏo��n�����B�������Ď��̓��̒��́A��͂�ƌ�������܂łȂ̂����A���ƐQ�s���Ŏw�ʼn����A���R�[���������o�������Ȃނ���̕i�]��B���ʂ�̓��A���X�����Ɏ˂����̌������t���́A�f���炵���n���T�������̎B�e��ƂȂ�B
�@�@�����č��A���̎ʐ^�����Ă��鎄�A��������z�������悤�Ɉ�l�������ݏグ�Ă���B�t�̓�����łȂ�ł��V�N���������̍��A���ɉ߂������������Ԃ������Ǝv���B���R�̂��ƂȂ��瑽���̐l�������A����ȑz���o�𗼎肩�炱�ڂ��قǎ����Ă���̂��낤�B��x�A���������傫���Ȃ��Ă䂭�ߋ�����A�����y���ވׂ̍ޗ����E���W�߂Ă͂ǂ����낤�B�����I�Ԃ͎̂������g�A�N�ɋC���g���ł��Ȃ��A���̓��̋C���ōD������ɍs�Ȃ������B����Ȏ���҂��Ă���l���c��ȉߋ��̔��̒��ɂ͑�R����悤�ȋC�����邵�A���̖ʔ����ɋC�t�����ɉ߂����Ă����̂͐ɂ����C������B����������Ƃ��̋ʎ蔠�ɂ́A���ꂩ��̐l����ς��Ă��܂��悤�Ȗʔ������ƁA�V�����W�J�̌����]�����Ă���̂�������Ȃ��B
2008.11.16 (��) �����A������
�@���ԑg��TV�����ċC�ɂȂ邻�̏ꏊ��n�}�ŒT���Ă݂�ƁA���N�̉Ăɍs�������������̎������o�Ă����B��Ђ̐�y������������̍L��ȕ~�n�Ɍ����O�n�E�X�̕ʑ����A��͂蓯����В��Ԃ������ވ䂳��ƖK�˂����̂��Ƃ��v���o���ꂽ�B�@�ڗ��̃p�m���}���C�����h���C�u���Ă���ƁA�Ȃ��炩�ȌX�ɗΑN�₩�ȍ����̔����L�����Ă����B���n�����}�����L���x�c��������d�ɂ����R�ƕ��сA���������点���ƂĂ��Ȃ��傫�ȕǂ��A�܂�Ō��������ɓ|��|�������悤�Ȍ`��ł���A�������̐�͔Z�W�̂���ΐF�̒n�����ɂȂ��Ă����B������͍����A�����ɍ��R�Ɨ����オ���������_�����̌i�ςɂ��悢�攗�͂�Y���āA�Y��Ȃ���ʂ̉Ă�搉̂��Ă����B
�@�^���I�肽�������h�ŗǂ��g���X�|�[�c�Z���^�[�ɍs���A���|�I�ɋ����t�����X�̍��Z��\�̃��O�r�[�E�`�[���Ɠ��{�ł͏폟�̖���Z���W�܂����֓���\�Ƃ̌𗬐�����邱�Ƃ��o�����B�c�O�Ȃ�����{�͑卷�ŕ������B���̃X�|�[�c�قNj��R���̏��Ȃ����͂ǂ���̃X�|�[�c�͂Ȃ��B���{�l�����ӂƂ���`�[�����[�N�ɂ�����A�g��W�U�A�v��������̂����^�b�N���A���̂��ׂĂ������ɍs�Ȃ��Ă����ڂԂ��荇���̗͂ƃX�s�[�h�ŏ�����̂���������B�ⓚ���p�̒j�̃X�|�[�c�ł���B���̖�A�����������߂̒Y�ΏĂ̐싛�������Ŗ�����������̎����ɋ��ݍ��܂�Ă����B�⋛�̍����ő��������Ă͂������A�g�C���ɒ����Ă��������̎������C�Ȃ��ڂɗ��܂����B�����ēǂݏI�����"�ʔ��������g�C���ɒ����Ă���܂��ˁI"�Ƃ����ƓX�̂�������̎��̃R�s�[�����ꂽ���̂������B�����ɗ���q����J�߂���Ɗ��Ŕz���Ă���悤�Ȃ��̎��͍�Җ����薼���Ȃ��A�����Ȃ肱���n�܂��Ă����B
�@"���O�͂��O�Œ��x�悢�@����̂����O���������O�ɂ���͒��x�悢�@���������O�̐l���͈������Ȃ���Ηǂ����Ȃ��@���O�ɂƂ��Ē��x�悢"����Ȓ��q��"���x�悢"�������B�����Ď��͍Ō��"�������v���Ȃ��ډ�����v���Ȃ��@����Ȃ���Ή����Ȃ��@���ʓ������������x�悢"�ŏI���Ă���B�N���r�̂��m��Ȃ����A���������Ȏ��Ŗʔ����Ǝv�����B�����܂܂̐l���̂��ׂĂ��m�肵�A�Ƃ荇�_�Ȍ����J���Ă���B���R�̂��ƂȂ���l�͂��ꂼ��̐l���ς������Ă���B��҂̂��ׂĂ���߂��悤�ȒB�ϐU����_�Ԍ�����B���߂Ď����̐l���̌�p�����߂āA���̒��Ŕ|�������l�ςƂ͂Ȃ낤�Ǝv�����A�������̂��܂�ɂ��t�قŒP���ȕn�����ɋ�����R���B
�@���̎��͂��I���������邩������ʖ����̂ǂ�Ȏ��ł�����悤�Ƃ��A�����癋�߂ɕς���čs���ǂ����悤���Ȃ������ʌ����̉ߋ����^���Ɏ���邱�ƁB����͂܂��A�K�����肤�l�X�ɒ��悢���炬�̐��E����Ă��邩�̂悤���B���A���̏ꍇ�͔Y�݂����邵����������B�����Č���̏���܂������A�����鎞�͂��̎��̂悤�ɒ��x�ǂ��Ƃ��A���\�K�^�̐l���Ƃ�������B���̃g���C�A���O���̒��ɂ����������A���ʂ̏o�Ȃ����ʂ�"���ɂ͒��x�����l��"�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
2008.11.07 (��) ���̘b
����̒����V���̓V���l��̒��ŁA���ɂ��ĂƂĂ������[�����Ƃ�������Ă����B ���̂���܂ł̐l���ɂ͊������ՂɎn�܂�A��s�������������Ԃ�v���Ԃ�Ɉ������F�Ƃ̐ȂȂǁA�������̃e�[�u���̒��S�ɂ������͎̂��������B�����������ł̖ʔ�������s���Ȃǂ����x�������낤�Ƃ��v���Ԃ��B�c�O�Ȃ��玄�̏ꍇ�́A���Ȃ�����̎��s�k���唼���߂�̂����A����ł����͎��̐l���ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ł���B�����ŏ�����Ă���̂�"�Ќ��̎��͔����ɂȂ�B���̏�ł͂����Ƀu���S�[�j����㓙�̃X�R�b�`�Ȃǂ̍����Ȏ�������ł��A����͉�b��e�܂��邽�߂̏�����ɑނ�"�Ƃ���B�U��Ԃ�d����ǂ����Ă���肢���������A����₱����̈���I�ȓs���Ŏӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�܂��A�d������X�̏o���ł�������������A����Ȏ��ɂ��K�������������B���̎��̎����������v���o���Ă����̖��͋L���̂��Ȃ��ɏ����Ă���B
�t�ɗ��Q�W�̂Ȃ��l�ɂӂƗU��ꂽ�_�c�w�̃K�[�h���̎��A�V�h�̗��ʂ�ň��v�������Ȃ������ȓX�̎������ɉ��������A���̖��o���v���o�����Ƃ�����B�����ł͖����̈ꗬ�����X���獂���z�e���̃o�[�̂͂����̂��Ƃɂ��G��Ă����B��ɖ����̔����ׂ̈̏��������W�߂Ă���̂��낤���A�����E�̎��͎Ќ��ł���Ƃ����B�����ł��鎄���o�������A���t�K�ɂ܂ŋC���g���Ќ��̎��͔���B�ꍑ���\����̎��̏ꏊ���ǂ��̂����̂Ƒ������Ă�}�X�R�~�ɂ�焈Ղ��邪�A�I����"���܂ɂ͓Ƃ���̃O���X�Ɏ������f���Ă݂܂���"�ƌ���ł���B���ꂪ�����̖{��ł���B
�ʐ��E�̘b���͂��Ă����A���̏ꍇ�������N�A���ނƂ���͋���������Ȃ̂����A���������Ɏ��̐ȂɌĂ�A�Ăꂽ��ɂ͎������Ȃ��B���Ă��Ă���́A�|���������ނƂ�����|�Ƃ��Ȃ��Ⴊ�����A�ꂪ����オ�����琺��グ�čŋ߂̏o�����ɑ���ӌ����k��������A�������ꂽ��̌J��Ԃ��ɏI�n���Ă���B���ɂ͖���A�̂̓����o�������J��Ԃ������l�Ԃ܂ŏo�n�߂��B����Ȏ��͎|���Ƃ��܂����Ƃ��̔��e�ł͂Ȃ��A���̏�Ŋy��������オ�葁�������ׂ̎��ł���A���R�����������̕i�X�����������������ׂ����̂��̂ɂȂ�B����͂���ł������̂����A���ꂪ�����܂ł������Ǝv���o���͍̂��̂����E�B�X�L�[�Ő����قǂɖ����ɑz�������A���R�̂Ȃ��ЂƂ���ł���B�{���Ɏ����|�������鎞�͌܊��S�̂��g���Ă���𖡂킢�����B�I�m�ȕ\���͏o���Ȃ����A��������݂�Ƒ̂ɟ��݂Ă���悤�ȁA���͂��̎��قǔ����������͂Ȃ��Ǝv���Ă���B
�����قǂɂ��������̗̂��S�Ȃ��Ăі߂������@��ł���A�����ɂ͂��̍��̂܂܂̉��������H�������������o�̓��荬��������z�̒��ɓo�ꂳ���Ă͖��z����B����ȏ�̎��̍�͂Ȃ��A���R���V���n�߂��킪�S�͏������������̍��ɍs������A��������J��Ԃ��B�����Ȃ�ƌ��̒��ɍL����E�B�X�L�[�̍��͍ō����ɒB���Ă䂭�B����Ȃ��Ƃ�z�����������߂ɁA��Ƃ̊J������"��l�ŕ����ɂ��ꂱ�߂ĉ����Ɉ��ގ��̉x�y"���c���Ă���B"�c�x�R�x������������A�`���z��������������A�ǂɗh��߂������̉e�Ɖ�z������ɂ��Ă���ނ�Ă���ƁA���ꂭ�炢���������͂Ȃ�"�Ə�����Ă����B��ɖ�ɂȂ�Ɠ��R�̂��Ƃ�����ł���ӎނ̃}���l�����~�߂āA�̒��𐮂��Ă���̂ЂƂ���ɐZ�肽���Ǝv�����B�������炭�炵�Ă����V���O�������g�̃E�B�X�L�[���ɍs���B���Ƃ͐����ɔC���ĕ���CD�𐔖��p�ӂ�����������̂��ƁB�ߔN�A���̗��ꂪ��i�Ƒ����Ȃ����Ɗ����鎄���炷��A���捠�܂ł̏�����ɂ͍l�����y���A���t�ɂ��ꂩ�炷���K���ł��낤�����~�̖�́A�������{�[�b�Ƃ���܂Œg�߂邱�ƂȂǔς킵�����Ƃ������Ȃ�B
�ł������G�߂��K�ꂽ���A�p�Ӗ��[���̋C�ɂȂ��ĂЂƂ���̖��҂��ɂ���B�����Ő����Ă��܂�����A�t���Ă������̍��Ƀ^�C���X���b�v���Ă��܂����M���S�����ɁA�]�̐c�܂Ŋo������悤�ȃL�[���Ɨ₦����C�Ɗۂ�����ɁA�ӂ�ӂ�ƔӏH�̖�𖧂��Ɋy����Ō��������̂ł���B
2008.09.26 (��) �����L�[�E�X�^�W�A��
����̂P�V�����j���̖�A���{���Ԃł͂P�W���̒��A���͂��˂Ă���̖������������L�[�E�X�^�W�A���̒��ɂ����B�����̎����ڂ��ŁA���{���Ɏ����͓���Ă������̏ꏊ�ɂ���̂��Ƃ������M���^�̋C�����ɏP���Ȃ���A�ڂɉf��͔̂Z���s���N�F���Y��ȗ[�Ă��̋�ɔ�s�D����сA���ɏƖ��������炫��ƋP���Ă���B�X�^�W�A���̃t�@�C�i���̃��S��������T�V���c�A��̃����L�[�X�̖X�q�����Ԃ����n���̃t�@������C������ʼnE���������Ă���B��̑O�A���{�ɂ����l�R�̖X�q�����Ԃ����q����������R�����B���͂قƂ�nj������Ȃ��Ȃ������A�����j���[���[�N�ł͊X��������Ƃ���ŁA�q�������l�܂ő����̃����L�[�X�X����������B�����ē��{�̋���ɂ���������̎q�����̔���q�Ƃ͑ɂɂ���A������������B���r�b�N������قǑ傫�Ȑ��Ńr�[����s�[�i�b�c���Ă���B���ɗ��Ă����Ȃ�{��̂ʼn��x����яオ�����B�ȑO�����L�[�E�X�^�W�A���̃z�b�g�h�b�O�͊i�ʂɎ|���ƕ����Ă����B���ۂɂ̓}�X�^�[�h�ƃP�`���b�v�����̃V���v���Ȗ��t�����̂ŁA���߂̂��Ȃ肵����ς��\�[�Z�[�W�������B���ꂪ�₽���r�[���ɂ͂������ł������݂����Ă��܂��BTV�ł������Ȃ������X�[�p�[�E�X�^�[�̃f���N�E�W�[�^�[��A�E���b�h�̖{�������̂R�O���[�g���قǐ�ɂ���B���ɃL���v�e���̃W�[�^�[�̓j���[���[�N���q�̓��炵���N������������������ԁB
�����������̗��̓}�C���[�W�̃`�P�b�g�����܂����̂ŁA��N�̕��Ɍ��߂Ă������������B�僊�[�O�̎���������̂͏��߂Ă������B�^�̂������Ƀz�[���x�[�X��菭���O�ۑ��̃l�b�g���ɒ��߂��A�O����P�P�ԖڂƂ����A���̎����ł͊�ՓI�ȃ`�P�b�g����ɓ���邱�Ƃ��o�����B���{�ł̃C���^�[�l�b�g�̔����ł́A�v���~�A���t���āA�ǂ�Ȃ͂���̐Ȃł��Q�T�O�h���ł������Ȃ���������Ȃ��ƌ���ꂽ�̂ɁA���n�j���[���[�N�̃~�b�h�^�E���ɂ���N���u�E�n�E�X�̃V���b�v�ňꖇ�P�W�O�h���A��Q���~��Ŏ�ɓ���邱�Ƃ��ł����B�m���ɍ����ł͂��邪�A��������j�I�X�^�W�A�����܂�ŏI���̃{���`���A��̃l�b�g���̃`�P�b�g�́A�v���~�A�����ĂU���h���i�U�S���~�j�Ƃ����\���o�Ă����B
���̋���͂P�X�Q�R�N�̂S���P�W���ɃX�^�[�g������B����Ȃɑ傫�Ȃ��̂��킸���Q�W�S���ԂŌ��݂���A�J����ɂ͖�V���S��l�������A�Q���l�����ɓ���Ȃ������Ƃ����B�ʏ̃��[�X�����Ă��ƂƌĂꂽ�������B���̓`���̎���ł���x�C�u�E���[�X���͂��߁A�W���[�E�f�B�}�W�I�A�~�b�L�[�E�}���g���̂T�O�O���z�[�������A���[���h�E�V���[�Y�ł�MR�I�N�g�[�o�[�A���W�[�E�W���N�\���̂R�A���z�[�������A�f�r�b�h�E�E�B���A���X�A�f�r�b�h�E�R�[���̊��S�����A�C�`���[���������ꂽ�o�[�j�[�E�E�B���A���X�̊���A����G���̃f�r���[��̖��ۃz�[�������ȂǁA���X�̗��j�Ɖh���������Ő��܂ꂽ�B���̃X�^�W�A���̂W�U�N�̗��j�ɖ������t�@�C�i���J�E���g�_�E�������Ɏn�܂�A�j���[���[�N�͂��Ƃ��A�����J�̖�����̎���̖������낻���Ƃ��Ă����B����Ō��[�߁A�Ō�̓����T����̓��j���ɔ����Ă����B���s������w���̒����ƁA���̂Q�����̃`�P�b�g����S�O�͉������֔��ōs�����B
��Γ��肪�C��n��A�P�X�W�X�N����NHK���僊�[�O���p���n�߂Ă���́A���{�ł��僊�[�O�͂����̖�������g�߂ȑ��݂ɂȂ����B�؍݂��Ă���~�b�h�^�E������n���S�ɏ���ăA�b�v�^�E�����ʁA�u�����N�X�̃����L�[�E�X�^�W�A����ڎw�����B�r������O�ɏo�Ēn����P�O���[�g���قǍ������˂𑖂�ƊԂ��Ȃ������B����ۂ͎v���Ă��������Âڂ��Ă��ď��X���������B�~�b�h�^�E������������Đi�s�����̉E���A�����L�[�X�E�O�b�Y�̂��y�Y���������ƕ���ł���B���ɓn��ƉE���ɂ͊��Ƀx�[�W���̗��h�ȐV�X�^�W�A�����Q�O�O�X�N�̃I�[�v����҂��Ă���B���{�ł���̑O�ɂ����A�_�t�����̉������ȘA�������Ԃƒk���Ȃ��炽�ނ낵�Ă���B�����u�ĂĂ��悢��X�^�W�A���̒��ɁB������ł̓����L�[�X�̃��j�t�H�[���𒅂������X�k�[�s�[�̂ʂ�����݂��A�C�O�ǂ��N�ɂł��z����B�����������������L�[�X���B
�����̓V�J�S�̃P���E�O���t�B�[JR�̂���z���C�g�E�\�b�N�X��ŁA���r���\���E�J�m�[�A�W���j�[�E�f�[�����AA�E���b�h�i�ނ͂���܂ł͖}�łɎO�U�A�ނ̋��E����̔N�_�ւ̗e�͂Ȃ��쎟����сA�����L�[�X�̃t�@���͉\�ǂ��茵�����j�̂R�l�̃z�[�������A�����ӂ̈ꔭ�U���̂T�P�Ń����L�[�X���������B����I��͕G�̋�����S�ł͂Ȃ��c�O�Ȃ��炨�x�݂��������A�����O�̃Z�����j�[�Ŏ��P�c�̂���̉ԑ������������ɖ���Ă����B�T�I��Ɨ�̃O�����h�����ŁA���B���b�W�E�s�[�v�����̂�������݂�"YMCA"�A�V��ɂ�"�S�b�h�u���X�E�A�����J"����"����싅�ɂ�Ă���"���F�ő升���A�����I����ɃV�i�g���̃j���[���[�N�A�j���[���[�N���傫�ȉ��ŗ���n�߂�B�A��̒n���S��������������A�^�N�V�[�Ə����Ă��鎆���L���ĉ��l���̔��^�N���҂���B�������ɖc��オ�����n���S�̉w�̃z�[���A�����Ă����d�Ԃ̃h�A���Ȃ��Ȃ��J���Ȃ��B������~�����I�[�o�[�����炵����߂�A�z�[���ɂ����S���Ńu�[�C���O�I���̎��݂̂�Ȃ̊y�������ȏΊ�A���{�ł͂ƂĂ����킦�Ȃ�����������������̊��B���̃j���[���[�N�ɖ����Č������Ǝv�킹��u�Ԃ������B
���{�ɋA���ĉ��ē̎��C���傫������Ă����B��ΓI�Ȏ��͂Ɛl�C���ւ���ON������{���̏I�����������B�����āA�����L�[�E�X�^�W�A���̍ŏI������̂Q�P���ɏI��A�������̃X�^�W�A���ł̎��������邱�Ƃ͂Ȃ��B���Ă̖��Ɖh���ɒԂ�ꂽ���X�A����ȃA���o�������Â��ɕ���ꂽ�������������B
2008.09.02 (��) �V�ԍ╗��
����A�d���̊W�Őԍ�R���̓��}�_�Ђ̗���ɂ��鎖������q�˂��B���̊Ԃɂ��S���Ⴄ�������������сA�Y�����Y��Ԃ̎��͂��̌��i�ɂ���䩑R�Ƃ��ė����s�����Ă����B���}�_�Ђ̗���̒��ԏ�ɗ��ƁA����������낷�悤�Ɍ����Ă��門�V�O�̂悤�ȃr���ɂ́A���ăr�[�g���Y���͂��߈ꐢ���r�����A�[�`�X�g�𔑂߂��L���s�^�����}�z�e�����������͂��A�̖̂ʉe���������ł���B��������_�Ђ�������Ɖ���ʂ��TBS���ʂ֓n��B��c�ؒʂ肩��Z�{�̃~�b�h�^�E���܂ł̌i�ς́A�ߔN�̓����ōł��ς�����n��̂ЂƂ��낤�B�B��A���̖ʉe�╵�͋C���c���̂͐ԍⓌ�}�̂Q�K�̃V���b�s���O�A�[�P�[�h�ƃx���r�[�ԍ₮�炢�ŁA��͂قƂ�ǂ��ׂĂ��ʐ��E�ɂȂ��Ă���B"�lj��̊X����""�s�d������������"�Ȃljߋ��̊X�̎ʐ^�W����������ƁA��������o���Ă��܂������ȁB��������܂�ɕς���Ă��܂������݂��ǂ��ɂ����ċL���̕Ћ��Ɏc���Ă��������A����Ȏv�������̒��ɂ���B
���̑z���o�̈�ɁA�ԍ�ŏ��߂čs�����f�B�X�R�̃}�m�X�Ƃ����X������B�m�����Z�Q�N�̂Q�w�����n�܂钼�O�������B�G�߂͒��x�����̂��ƁA��ŕ������b�ł́A���������͕s�NJO�l�̗��܂��Ɖ\����Ă����Ƃ����B���Q����r�u���X�Ƃ����L���Ȃ��̂��������̂����A�؏�̎�U�߂Ƃ����������̗F�l�ɗU����܂܂ɍs�����̂��}�m�X�������B�h�A���J����Ƃ܂����̑傫���Ɉ��|�����B�����A����̃t�B���s���E�o���h���t�H�[�N�\���O�̃������c���[���_���X�~���[�W�b�N���Ɏ��Ɏ|���A�����W���ĉ��t���Ă����̂����A����ɂ͑����̈�a���͎c�����B�ۂ���ɏ���ėx���Ă���u�����h�̏��̎q���A�Ⴂ�����������Ĕ������������Ȃ���A���炩�������ŕЖڂ��Ԃ�B���ƍ����̓��荬��������l�̓����A�����̃X�|�b�g���C�g�̓^�o�R�̉��𗬍s���_�̂悤�ɑN���ɕ����オ�点���B���炭���āA���肪�N����悤�Ȍ������瓦���悤�ɊO�ɏo��ƁA���������������Ԃɂ͑z�����炵�Ȃ������A�G�߂�������H�̖镗����C�����j��S�n�悭��܂��Ă��ꂽ�̂��o���Ă���B
��������z���o�͈��Â鎮�ɂȂ�B���̌������ɂ͒n���̃j���[���e���N�H�[�^�[�ł̗͓��R�̎E��������Ύ��ŗL���ɂȂ����z�e���E�j���[�W���p���B���̕��т𗭒r�Ɍ������ƎR���z�e���Ƃ����A�A�����J�̍����𗧂Ă������O�ς̒n���Ȍ������������B�����͕ČR�̎d���ɏ]������W�҂������W�܂�A���ʂ̓��{�l�ł͓���Â炢���O�@���I�Ȗ�����̃z�e���ł������B���鎞�A�F�l�̃X�e�������̎R���z�e���֒��H�ɗU���Ă��ꂽ���Ƃ��������B�ޏ��̕��̓C�^���A�n�̃A�����J�R�l�ŕ�͓��{�l�A���̊W�Ŕޏ��͂�����p�ɂɗ��p���Ă����炵���B���̎��A���͂��̓��̃����`�̃��U�j�A�𗊂̂����A���ꂪ�܂��傫���������A�t�������̃|�e�g���R�̂悤�Ŏc�����H�ׂ�̂Ɉ��J�����B�܂��ɃA�����J�{�y�̗������̂܂܂̗ʂ������B���̐H���͔����~���g�O���[���̕ǁA�������ݍ����A�^�����ȃe�[�u���N���X�ɂ͈�ւ̉Ԃ������A�傫�߂ȃm�X�^���W�b�N�ȑ��ɂ́A�Â߂������ԕ��̃J�[�e�����h��Ă����B���͂��ׂăA�����J�̔��l�ŏ����ȏݖ���͂킽����l�����i�X�e���̓n�[�t�����������猩�Ă��O�l�������j�A�������z���̐��E�����T�O�N��̌Â��ǂ�����̃A�����J�ɂ��邪���Ƃ��A�ƂĂ������������̐ԍ�Ƃ͎v���Ȃ��s�v�c�Ȋ��o�𖡂�����B���̐H�����ɖƐł̃^�o�R����A�����Ēj���G���̃v���C�E�{�[�C��y���g�n�E�X�̖��C���̖{�������Ŕ�����Ƃ����A���ɂƂ��Ċ���Ă��Ȃ�����ޏ��������Ă��ꂽ�B
���̎��㓖����O�̂��Ƃ������ł͑�ςȂ��Ƃ������B�ޏ��͎����S���N���̃n�C�e�B�[���A�����̍w�����ɂ͊W�҂̃J�[�h���Ȃ���Γ���Ȃ��B������͊O����̌��w�ɂȂ�B�J�[�h�����đ̂ʼn����ƃN���b�Ɖ�鑾���^�J�̖_�A�����ɂ����ꂽ�����Ŕޏ������ɓ����čs�����B���O�҂̎����O����F��悤�ȋC�����Ō���钆�A�ޏ��͎��������׃^�o�R�̃Z�[�����̃����J�[�g���ƒj�����A���x�������������C���̃y���g�n�E�X�R�Ɣ���̂�����ɍ����o�����B�ዾ���������┯�ŁA�����ɂ����C�̂悳�����ȃA�����J�l�̂�����́A���̔������ƃX�e���̊�����炭���݂Ɍ���ׁA���ꂩ�牽�b�Ԃ������Ɣޏ����ɂB�ޏ��͊��^���Ԃɂ��Đ�ɂ�����̖ڂ����Ȃ��B���ɂƂ��Ă��̉��b�Ԃ����i���ɏI��Ȃ��C�������B�悤�₭������͗������s�N���Əグ�A������L���Ă����ꂽ�Ƃ������ӂ̃|�[�Y�B�������Ǝ��܂ɖړI�̃��m�����Ă��ꂽ�B�X�e���͎��̏��Ƀj�b�R���Ə��Ȃ���s�[�X�T�C���Ŗ����o���H����҂��Ă����B�ޏ��̖��C�ȏΊ炪�A�ق�̐���s���Ƃ͂����A�C�܂����v���������Ă��܂����Ƃ����N��̎��̌��߂�����Y�ꂳ�����B���̖�A�Z�{�̈��݉��ł��̑厖�Ȗ{�𐌂��ĖY�ꂽ�ꐶ�̕s�o�́A���ł����X�v���o���B���ꂩ�牽�N����ɁA�ޏ��̓A�����J�쓌���o�g�̎Ⴂ�j�ƌ��������ĊC��n�����̂����A�����I�ȎЉ�ŋ�J���Ă���ƕ��̉\�ŕ������B�����K���ł��Ă��������Ǝv���B
����Ȏ���̈ꂱ�܂��y���܂��Ă��ꂽ�X�A�ԍ�B���̊X�ł̑z���o�̐��X�A����͎��̐S�̒��ł͌����ĐF�邱�ƂȂ���d�ɂ��ςݏd�Ȃ��Ă���B�����o�����̎��̃}�m�X���R���z�e�������̂悤�ɏ������B����Ⴄ�������E���Ă���悤�Ȑl�̌Q��A�����ɂ͂��̍���m��A���̍����啪�Â��Ȃ��č����Ă��鎄�ƁA���̍��������ɏ������ԍ�ƌ������́A�Ў����ω����~�߂Ȃ����m��ʊX�������������ɋP���Ă����B
2008.08.24 (��) �Q�O�O�W�N�A�Ă̏I����
���̎����ɂȂ�ƁA�l�͂��̉Ă̏������������ꂽ���g�ƁA�������ȕ��������������ɑ����̎₵����������B�ȑO�A���̂ЂƂ育�Ƃ�"�N���͍]�ˋC��"���������B��̒��b���̋O�Ղ����ǂ�b�Ȃ̂����A�����ɓ��{�l����D���ȋw���������グ�Ă����B�ς��ɑς��A���ǂ͍Ō�Ɋ���������Ċ����܂��͏��������ށB���{�l�������Ă�܂Ȃ������p�^�[���B�͓��R�����Ԃ��Ȃ����̓��{�ŁA�V���[�v�Z���t���b�h�E�u���b�V�[�����߂Ƃ���O���l���X���[�̔����Z�ɑς��ɑς��A�Ō�͓��{�×��̋Z�ł�����`���b�v�ŊO���l���X���[���������Ƃ����A�I��̏��̖����Ȃ��r���{�l�̐S�ɂ��̏�Ȃ����M�Ɗ������������Ă��ꂽ�؏����̂���h���}�́A���܂���������Ə����̋L���ɍ��܂�Ă���B�\�z�������܂�ɂ��������{�l�̔M���Ԃ�ɁA�폟���ł���č��̃}�C���h�R���g���[�����傫���h�炢���ƕ����B�̘b�̂���I����A���������R���疈�T����Ă���TV�̕K�E�V���[�Y�␅�ˉ�������߂Ƃ��鎞�㌀������A���{�l�̐S�̒��ɂ́A����I�ɂ���čŌ�ɏ������銮���̔������؏���������̒�ԂɂȂ��Ă���B
����A�I�����s�b�N�ŏ��q�\�t�g���ߊ�̋����_�����l�������B���|�I�ȃp���[�ŏ�ɏ����̍���Ƃ��߂ɂ��Ă����č��`�[���B�č��ٌ̕c�̂悤�ȃL���b�`���[���m�������ɂȂ�ƁA���{�̃o�b�^�[�͂��̑̂̔����ɂ��������Ȃ��B���̗͍̑����܂��܂��ƌ����t�����Ă̏������B�č��͂��̋��Z���̗p���ꂽ96�N�A�g�����^����3�A�e���̃`�����s�I���A�������{�̌��������o�����撣��ɁA�Ō�͕K�������ӂ������������ǁB���̒��ŁA��Ɍ��𗎂Ƃ������{�I��̉��ŕ��������Ċ�ԑ傫�ȊO���l�I�肽���̎p�́A���̊Ԃɂ����ꂪ�����܂�̉������ŏI�V�[���Ƃ����قɏĂ����Ă����B
���ꂪ����3�x�ڂ̐����A�S�r��삪�ς��ĂS�P�R���I�Ƃ����V���̌��o���B��͂���{�l����D���ȁA�ς��ĂƂ������t�����鏟���B����Ŏ��̃����h���ł͖싅���l�A���Z����͂���鎖�ɂȂ����\�t�g�̗L�I�̔��A�{���ɗ܂��o���B�����Ėk���I������߂Ƃ�����{�I�肽���̊���B�싅�Ɍ����ẮA�N�������҂������{���E�̐��A�_���r�b�V��������Ȃ�����������߂�d�v�Ȉ��ɓo�����Ȃ������̂��A�S�_���łقڕ��������肵���R�ʌ����̂X��ɓo�������̂͂Ȃ����낤�Ƃ����A����єz�Ɋ���̋^�₪�c�����B
���ǂ�����ق��͏���ł���A�����͈ꏏ�Ɋ�ъ��x��������鏟���̉f���ɁA���x���������ĂыN�����B������Ƃ��̉������������Y��悤�ƐS������B�������A���̕����ɂ͂ǂ�قǂ̓w�͂����߂��Ă��邩�Ƃ������Ƃ��ڂ݂��ɂ��鎩���ɁA���X����鎖������B�\�I�Ŕs�ނ����l�A�Ō�̍Ō�ŏ��������l�A���ꂼ��̐l�����Ƀ��_����������l�������l�̔���𑗂肽���B���̎����قǎ��������{�l�ł��邱�Ƃ��ӎ����邱�Ƃ͂Ȃ��B��ɊO���̌����Ȃ�ŁA�v�������������Ƃ��������Ȃ��ېg�Ƃ�T���̓��{�O���ɔ�ׂ�A�����4�N�Ɉ�x�A���X�Ɠn�荇�����̂����Ă̐킢�ł���B
����Ȏ��A����ʔ����L�����������B�������d�Ȃ荡�܂蒍�ڂ���Ȃ��������Z�싅�ɂ��āA���̎��������Ă��Ċy���Ƃ����l�������B�Ȃ��Ȃ�Ύ����̌̋���\�������Ă�����͓������{�l�A���̉������������ȉ����Ƃ����B������f���ȐS�ƌ��������Ȃ̂����A������ɂ��Ă����̎����̃i�V���i���Y���̍��g�͂��₪�����ɂ�����オ��B���j�A�_���E���X�����O�̃��_����������I�肪���������t�̒��ň�ۂɎc�����̂́A�Z��A�e����̈���ɑ��銴�ӂƉƑ��̋����J���Ӗ����錾�t�B�����ă��_���͎����ЂƂ�̂��̂ł͂Ȃ��x���������Ă��ꂽ�l�X�̂��̂ł��Ƃ��������̃R�����g�������ꂽ�B���̐��_�̓X�|�[�c�}���Ȃ炸�Ƃ��A�l�Ƃ��ĎЉ�������ƂĂ���Ȍ��t�ł���B
���X�̊����A�˂��グ�����A���������p�A��т̗܁A�����܁A�����Ēj�q�̗͂̏_���A�X�s�[�h�E�}���\���ɑ�\����鐢�E�̖���B����u�Ԃ̂�������A��R����R�Ƃ�������B����ȑ����̉����Ƒ傫�Ȋ����̐��X���c�����X�|�[�c�E�h���}�A�Q�O�O�W�N�k���I�����s�b�N�͍����ŕ��A�Ђ���Ƌ��D��������H���������A�����ɕ��������������̐��ł��̉Ă��I��B
2008.08.11 (��) �O����͉�������
�l�Ԃ̕����������炷�n�����g���ɂ���āA�����̐�����������ł̊�@�ɕm���Ă���ƌ����Ă���v�����B���ꂱ�����P�O���Ɉ��ނ��A���̒n���ォ�炻�̓��A���킪�����Ă���ƌ����B���ʁA���{�̂���Ƃ���ł͓Ŏ֑�̂͂��������}���O�[�X�A���m�ł����ނ�Ƃ��Ɉ����������Ėʔ����Ƃ������R�ŕ����ꂽ�u���b�N�o�X�A�������Z����ɗ��s�����Y��ȐF�������~�h���T�i�~�V�V�b�s�[�E�A�J�~�~�K���j�A���̂ق��A���C�O�}�C���M�Ȃǂ��ɐB���A���{�̍ݗ��킪�����̊�@�ɕm������A���̓y�n�̐��Ԍn�����ꂽ��Ƃ����L����j���[�X���ڂɂ���B���Ƃ͐l�Ԃ������ȖړI�������Ă����ɘA��Ă������̂����A���̖ړI���O�ꂽ�芮�������肷��ƁA�����̖��҂Ƃ��Ă��̑��݂�a��悤�ɂȂ�B��Ԑg����Ȃ̂͐l�Ԃł���A�����ɐ����Ă��铮���ɂ͂Ȃ�̍߂��Ȃ��B����Ȏ������Ǝv�������ׂĂ���ƁA���̐̂ƂO���킪���̐g�߂Ɍ��ꂽ�����������̂��v���o�����B��������قǔN��̏]�o���A�͂��A�t���J�̃^���U�j�A����C�O�N���͑��̎d�����I���A�Q�N�Ԃ�ɋA���Ă������̘b�B���ƈႢ�ޏ��̓l�C�e�B�u�ȉp��͂������̂��ƁA���n�ŗm�ق������Ȃ���A���̂Q�N�ԂŃ^���U�j�A�̌��t�ł���X���q����܂Ŋ����ɘb����悤�ɂȂ��ċA���Ă����B���̉��N����ɂ̓^���U�j�A�̑哝�̂����������ہA�������Ƃɂ��̓����ʖ�Ƃ���NHK��TV�Ƀ��C�u�o��������͂�����Ă����B���̏]�o�����{�ɋA���������ɂ��ꂽ���|�i�̓y�Y�̒��ɁA�悭��̎��Ɍ��Z�������悤�Ȗє�̏����������B���̏������炭���Ė��������N�������ƂɂȂ�B
���̍����炩�A�Ƃ̒��Ɍ������Ƃ��Ȃ��悤�ȃx�[�W���̉H�����T�~���قǂ̉邪��Ԃ悤�ɂȂ����B�ŏ��͉�Ȃǂ悭���鎞�ゾ�����̂ŋC�ɂ������ɂ����̂����A�Ȃ����O��������Ă���l�q���Ȃ����ߐ�̋q�ԂŔ�сA�������������ɑ����Ȃ�̂����������Ƃ������ɂȂ����B����Ȃ�����A��Ƃɗ���������"�����������̃A�t���J�y�Y�̏������ǁA�������珬���ȉ邪�v�[���Ɣ��ł�"�ƌ����B���āA������Ĉꓯ�r�b�N���ł���ς�I�Ƃ������ƂɂȂ����B���̏������߂ďڂ������ׂ����A�v����Ɋv�̂Ȃ߂��������Ă��炸�A�����Ɍ��n�̃^���U�j�A�ŎY�ݕt����ꂽ��̗����A�͂����{�ɗ��Ă���z�������Ƃ������������B�^���U�j�A�Y�Ō��u�Ȃ��̒��A���ł���B
�������āA�O���킪������`�œ��{�ɂ���Ă��邱�Ƃ̈����A���͐g�������Ēm�邱�ƂɂȂ����B�����Č��݁A���{�͌��L�̃y�b�g�͂������A���̑��̖쐶�����̗A���卑�ł���Ƃ����b������L���Œm�����B�m���ɐ̂����ׂ�ƃ}�j�A�b�N�ȃy�b�g�V���b�v�������A�����ȃ��X���A�{�A�Ȃǂƌ�����Ă̑傫�Ȏւ⍻���ɏZ�ޑ傫�Ȏ������L�c�l��̃t�F�l�b�N�ȂǁA����܂œ�������f���ł������Ȃ������������������X�̃y�b�g�V���b�v�Ŕ����Ă���̂�����ɂ��A����������������ł���B�T�Ȃ͔N�Ԃɉ��P�O���Ƃ������ŗA������Ă��邻�����B
���A���̐�ł̊�@�̂قƂ�ǂ́A�s�{�ӂɂ��l�Ԃ������J��L����n�����g���̌����Ƃ��Ȃ�X�т̔��̂⍻�����A�����̈ړ��͏���ȃj�[�Y��l�I����قƂ�ǂł���A�����o�������^���U�j�A�̉��ߔN�ł͗A���؍ނȂǂɍ������ē��荞�ފQ���Ȃǂ̖]�܂Ȃ����R�������ƕ����B�ŋ߁A�N���d�ˏ@���ƂɂȂ낤�Ƃ����킯�ł��Ȃ����A�Ƃɖ�������ł��������Ȓ�����̂Ђ�ɏ悹�A�ł��邾�������瓦�����悤�ɂ��Ă���B������������Ȃ��ł��锒���⍕�����A�l�Ԃ͑��ʔ����Ƃ������R�����ʼn���E���B������U�������Ă�������S�����̃`���������A�����Ȃ�j�ɏR���đ��������Ƃ����j���[�X�������B�N�ł��悩�����ƌ����Đl���l���E���M�����Ȃ����Ƃ��p�ɂɋN���鍡�A�̂Ă�ꂽ��E���ꂽ�肷�铮������������ɂ��A���̒��O�܂Ő����邱�ƂɂЂ��ނ��Ȃ��̕\���������삪�߂�����������������B�n����̉c�݂��炷��A�ق�̈�u�Ƃ�������������F�Ƃ��āA�l�͂����ƗD�����Ȃ�Ȃ����̂��낤���B
�����Ĉ����A���悢��l�ނ̕��a�̍ՓT�ł���k���I�����s�b�N���f���炵���J��Ŏn�܂����B�����̒����Ɏc�O�����ȉ��̒J���q�I��̗��ɓ����Ă���̂́A���V�A�̖C�e�ɂ��e�ނ̖S�[����������Ă���O���W�A�̒j�̎ʐ^�B�i�v�ɐ킢���~�߂��Ȃ��A�����Ȑ������Ƃ��Ă̐l�Ԃ̕\���������ɉf���o����Ă���B
2008.07.23 (��) �`�����ƈ⎸��
�V���P�T���̉Ηj���A�������ŐV�h���痧����ʂɌ������Ă���Ɖ��\�H�Ƃ��������Q��𐬂��Ĕ��ł����B�����Ă��锵�͈ꎅ����ʕґ���g�ނ̂ł���Ɖ���B�����ɂ���Ȃɔ��������Ă���l������̂��Ɖ��������A����z���o���h�����B���̏��N����A�����������Ƃ��嗬�s�����B���������グ��Ƃ�����Ƃ���ő召�̔�������������ꂽ���ゾ�����B�������̗��s�ɏ��A���ɖ����ɂȂ������N�̈�l�������B�w�Z�֍s���Ă���H��H�̔��̂��Ƃ��肪���ɕ�����ŗ���Ȃ������B���͐��܂ꂽ�Ƃ��͉��F���Y�тŕ����Ă���B�����Ă��͂ǂ̒��ނ����������A�₪�Ė_��̍d�����̂������Ė��l�ɂȂ�A���̍d���_�̐悩��{���̉H�т�H���k��j��悤�ɏo�Ă���ƁA�₪�đ�l�Ɠ����悤�ȎႢ���ɂȂ�B���̖_�̂悤�ȉH��������Ƒ̂��傫���Ȃ�A���ӋC�Ɏ�Ȃǂ��o���ƌ����ł��Ȃ��R����悤�ɂȂ�B���̎��ɂȂ�Ɠ`�����ł��鎖�̏؋��ł��鑫�ǂƂ����A�]���莆�����鎞�̃A���~���̈ꐶ���m�𑫂ɂ͂߂�B���̔��������̔��ɂ̔��ł��邩���������̂ł��������B�����A���ɔ��Ɏ莆������ȂǂƂ��������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�����ς爤�߂ׂ̈Ɏ����l���قƂ�ǂ������B���ɂ͂P�O�O�L���`�P�O�O�O�L���ɋy�ԋ�����@���ɑ��������̔��ɂɋA���Ă��Ă����������[�X������A���ׂ̈Ɏ������I�Ȑl�������B�ǂ��N���b�V�b�N�Ȃǂŏ����������D�G�ȋ����n�́A�e�n�̎�t���������z�Ȃ��ƂŒm���邪�A���͂��̓`�������S�������ŁA���e�Ƃ������[�X�ŗD�G�Ȑ��т��Ƃ�͂�D�G�Ȏq�����܂��B���̎����Ă������ň�ԗD�G�ȉ��Ǝ��̔��̃c�K�C�̎q����āA���̔��Ő��˂��瓌���܂ł��ԂP�O�O�L�����[�X�ɒ��킵����������B�����������̌��̂��Ƃ������B�O�̔ӂɓ`����������ق��Ăɓ��ꂽ���̔���a���ɍs���B�����͑�l����̐��E�ŏ��w���͎���l�������B�����������S�H�ƏW�܂肾�����R�Ƃ��Ă��钆�ŁA"�撣���A�K���A���ė�����"�ƌ����Ă��̔��̓����Ȃłĕʂꂽ�B���̎��A�N���������Ă������W�I����A�R�j�[�E�t�����V�X�����{��ʼn̂���"���̃f�C�g"���G���̍�����傫�ȉ��ŗ���Ă����B���̒��ŗF�B�̗��l��������߂Ă��܂��Ƃ����̂������B����̋A�蓹�A���̐Ȃ��̎����₯�ɐS�ɟ��݂��B
���̓��͑������炸���Ƌ�����߂Ă����B���ɂȂ��Ă��A���Ă��Ȃ��A�ꂪ�������ĂԂ̂ł������Ȃ��x���Ȃ������H���}���ŐH�ׂĂ܂���ɏo��ƁA�Ȃ�Ɨ�̔����A���ė��Ă����B�����̏�ɂ��������Ԃ������ɂ����ƌ��������ɁA��������߂ĐQ�Ă��镗��B���̎��̊����͐��U�Y����Ȃ��B�����ďł�Ώł�قǁA�Ȃ��Ȃ����ɂɓ����Ă���Ȃ������A���J�Ɖa�Œނ��Ă���Ɠ��ꂽ�B���̓��̗[���A�����ɓ`��������Ń��[�X�̌��ʔ��\�ƕ\�������������B�c�O�Ȃ�����҂������҂̒��Ɏ��̖��O�Ɣ��̔ԍ��͂Ȃ������B�������A���̖����悹���P�O�O�L���̓��̂���A�ꐶ�����ɉ䂪�Ƃ�ڎw���Ĕ��ł��ꂽ�������������B����ȏ�̒������ɂȂ�ƃn���u�T�Ȃǂ̖ҋחނ�S�����n���^�[�̎U�e�ɏP���A���ė����Ȃ����������A�ŏ��ōŌ�̑��ɂ��������ɂȂ����B���܂ւ̊肢�͓͂��Ȃ��������A���̈�H�͏��N����̑f���炵�����������ɂ��ꂽ�B�����������������ɗ[�ɋ���삯�����̌Q��B�h���d�Ԃł������Q�ł������̂��낤���A���͂��̊Ԃɂ��D�����H���𗧂ĂďW�܂������������������̒��ɂ����B
�₪�ēd�Ԃ��w�ɒ����A�����̐l�̋C�z�Ŗڂ��o�߂ĂӂƎv���B���̓��A�[��ɂ��̔��ƈꏏ�ɔ��ł�����r�ȔM���S�A���͂����������ɒu���Ă��Ă��܂����̂��낤�B���ƂȂ��Ă͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ������Ă̓��̈⎸���B�܂����̓����K����ɓ��ꂽ�����̂ł���B
2008.07.20 (��) �قǂقǂƂ����b
�قǂقǂƂ����b�Â����炱�̓��{�ɂ�"�قǂق�"�Ƃ����������t������B�����ɂ��ƁA���ɉ����邳�܁A�K�x�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�B�����悤�ȈӖ��������t�Ƃ��ĉp��̃��f���[�V����������B ���ɗD��������������"�قǂق�"�͒������b��A�_�l���C�ɂȂ肾����������A���̑�Ȍ��t�ɂȂ��Ă���B�H�ɂ��Ă�"�قǂق�"�Ƃ����b�B
�ʂ̑������[������
�ǂ����Ō�������s��̂ł��郉�[�������A���̓��͂��قǂ̍s������Ă��Ȃ��̂ŋ����ÁX�ŕ���ł݂邱�Ƃɂ����B�����Ă݂�Əo����Ă���ǂ̊�������吷��ɂȂ��Ă���̂ň����\���������̂����A�Ƃ肠�����Ȃɍ����Ă��̃��[������҂��ƂT���A���̑O�ɏo�Ă������̗ʂ͂�͂�F�Ɠ����吷�肾�����B�v����ɕ��ʂ��吷��ɂȂ��Ă���A���ꂪ���̓X�̐l�C���x���Ă��邱�Ƃ��Ƃ킩�����B�������������̖{�X�̑n�Ǝ҂́A�w����Ⴂ�J���҂���������ׂɁA�����ĕ�����t�ɂȂ�悤�ɂƕ�d�̐��_���܂߂Ă̊J�Ƃ������炵���B����ɂ��Ă������B���̒��ɂ͑�H���̐l���@���ɑ�R���邩��m�����B�������܂����H�ׂĂ��A�H�ׂĂ�����Ȃ��A�t�ɂǂ�ǂ�N���ė���悤�Ȗ˂ɂ͎���"�قǂق�"���ʂ��Ȃ��炵���B
�В��͘A���̍��f�C�i�[
�܂��ǂ̋ƊE���i�C�̂悩�������A������ɂȂ���I���͂��鎞�A��i�ł���В��ɘA����ċ���̍��������X�֍s�����������B�o�Ă�����̂��ׂĂ��A�A���r�A���ɁA��g���A���̎q�Ƃ����������Ȃ��̂��肾�����B���̎В����������ɞH���A"�˂��T�N�A�l�݂����ɎВ��ɂȂ�����A��������Ȃ��̂��H�ׂ���悤�ɂȂ�̂���B�撣���"�B���̘b�������A�E���U�������ƂƂ��Ɍ����悤�̂Ȃ��̂������������B������������ȐH������������A�������b�A�A�_�l�ߑ��łP�O�����҂��Ȃ��œ��@���邱�ƂɂȂ邾�낤�B���t�������ő����邵���Ȃ��̂Ȃ�A������L��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂȂ�B�����������̂͂��ꂼ��̉��߂����낤�A����ɂ��Ă��u�����h�Ɏn�܂邽�������Ȃ��̂�����ǂ����߂邱�̎�̐l�̐^�ӂ��킩��Ȃ��B�C�����Ƒ͕̂ʂł���B���̎В��̈ݑ܂Ɖ��l�ςɂ�"�قǂق�"���Ȃ��炵���B
�h�{�̃o�����X
��������ǂ̎Ј��H���ł̂��ƁA�ꎞ�������l�C���ւ��Ă����j���̎��v�Ɏ��L�����D���A���ׂ̗̃e�[�u���ɗ����B���̎��̔ޏ��̃e�[�u���̏�ɕ������̎�ނɋ������B�䂤�ɂU�C�V��ނ͂������Ǝv���B���̒��ɂ͋�����J���[�Ƃ������h�ɂ��������ł��H�����������Ă��܂����܂ł���B���̂₹���l�����ł���ȂɐH����̂��ƕs�v�c�Ɏv���A���Č��ʂӂ�����Ȃ���M���Ă���ƁA���ꂼ��̗������ق�̓�����O�������H�ׂȂ��łقƂ�ǂ��c���Ă��܂����B�Ȃ�Ƃ����_�����������̓��̐l�ɘb���ƁA"����͏��D�̕����ǂ����H�ו��ŁA�ł��邾�������̂��������������H�h�{�̃o�����X���Ƃ�A���̐��E�ł͓�����܂��̂悤�ɍs���Ă��邱�Ƃł�"�Ƃ����B��������������ǂ̎Ј��H���Ƃ͂����A���̓��ӂ̌��t"���������Ȃ�"���������ďo�Ă����B�h�{�̃o�����X��"�قǂق�"�������Ǝv���̂����B
�O���[�o���ȐS
"�������a�A���p�S"�Ƃ����W���N���[���E�r�Z�b�g�����o���̉f��B�f���炵���r�����L���ȃR�b�N�������A���X�ɎE����Ă䂭�~�X�e���[�ƃR�~�b�N�����킹���l�ȉf�悾�����B�N���C�}�b�N�X�ŁA���̐^�Ɛl�͗L���R�b�N�B����闿��������Ȃ�������j�i�}�b�N�X�j�̔鏑�̔ƍs���Ƃ킩��B���̎E�l���R���U����Ă���B����ȏ�H�ׂđ�������}�b�N�X�̖����낤���Ȃ�B��ނȂ����̔���������������闿���l�������ÎE����A�g�̉�肩������������̂��Ȃ��Ȃ�A�}�b�N�X�̎��������т�Ƃ����E�l�����Ȃ̂��B�����Ȃ�Ό��N�ێ��ׂ̖̈��R�b�N�Ɣ����̃��X�g���ł���B���̐g���肳�͑z����₷����̂�����A�����܂ŗ���Η��h�ȃW���[�N�Ƃ��Đ�������B���鎖�ւ̖��ɂ́A�O��I�Ȍ����Nj��̉ʂĂ̐ӔC�]�ŁB�ꕔ���������Ɛ�I���͂ɂ��c�݁B��ɉE���オ��ŁA���Ƃ����ꂪ���\�ł��ړI��B�����A���ׂ̈Ȃ���@���I�Ȃ��Ƃ����O���[�o�����ȂǂŒm���ƃG�S�B���̐��_���_�Ԍ���悤�Ȃ��̐��m�f��́A�c�O�Ȃ��玄�̎ړx�ł���"�قǂق�"�Ƃ����D���Ȍ��t�̂��������������Ȃ������B
2008.07.11 (��) �Ė����
���̓��͂ƂĂ��������ɂȂ����B����܂ł̓n�b�L�����Ȃ��~�J�̂������A��N�̂��̍��Ɣ�ׂĂ���r�I�߂����₷�����������Ă����B���闢��JR���狞�����ɏ�芷���āA����̉͂�n���Ē����������w�B�Ė���������ʂɍs���ׂ̏�芷���̉w�Ȃ̂����A�������璭�߂�i�F�͈�C�ɉ����̈�̑O�ɖ������C���ɂȂ�B�z�[�����猩����X�̖��O�������Ǝ��̋Ր��ɐG��Ă���B�̂��鋏�������ԁA�������ӂ݁A�����ăj���[�O�b�s�[�Ə��a�̉��̂����̂܂ܓX�ɉ���������ł���B�������������̏Ί炪�f�G�ȃ}�}����Ȃ�z�����A�C���͂�������Ђ����Ԃŋ����s���̈�ڂ̎Ė��ō~�肽�B�����ő҂��Ă���Ă����̂͌Â�����̗F�l�̑��삳��Ƌv������B�C���b�ƉE����グ�Ă����ӂ̈��A�B������l�̑҂��l����������j�̃h�^�L������3�l�͏��X������������͔N�̌��A�߂����ɎĖ��c�A�[�̎n�܂�Ƒ��������B�����A�w�O�ɏo���Ă���Ђ���̓����ŋL�O�B�e�B�����Ēc�q����݂₰���̓X�����ԎQ���ł����c�q��H���ƁA��X�̃c�A�[�̑�{�ɂ͂Ȃ��Ă����̂��������̂ŕX�ɕύX�B�����ł͒��̕��͋C��厖�ɂ��������������������낤�ƌ������ɂȂ����B����Ă����X�������͐^�����ȕX����ʼn��ɂ����ɂ��������������Ȃ��A�S�z���Ȃ���X�v�[���Ō@�肳���Ă䂭�Ƃ���܂����A�^�ɊÂ��������̂����܂�A���ꂼ�I�Ė��}�W�b�N�ȂǂƔn���������Ȃ����ߓV�����ցB�f��Ō����ꂽ�����V��������苫���ɓ���Ƃ��Ȃ�L���A�q�����̌�����Ђ���A��O�l�̎p���h��B�����ł͌��w�����āA�ꖇ�̑傫�ȕ���������@��N�������Ƃ����A�{�a�̊O�ǂ̒����̐��X�������邱�Ƃ������߂���B����͌����Ȃ��̂ł���B�����ċ��L�̃`�P�b�g�ŃI�[�P�[�ȗאڂ��Ă����������Ȃǂ����w�B��ߓV�ɂ���ȑf���炵�����̂�����Ƃ͐V�����ł������B
�����āA�Ђ���̉f��ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��V�[���������쌴�̗̓y�������Ė�̓n���ցB�����͏������ɂ�������炸�A���̂��䂦����������������B�]�ː�̐앗���S�n�悭�A��̉̂����R�ƌ������ďo�Ă���B�n���̑D�ɏ��A"����ς�I���W�i���̂������̉̂������A����q�b�g�����א�̉̂������A�Ȃ���l�͓������̂��A���ł͐e�ɔw�����Ƃ͌����Ă��邪�A���͋g�������肩��̑������������̂ł�"�ȂǂƘb���Ă��邤���ɁA���ˁA�s�쑤�̐�������ɒ����A�����Ȃ��̂Ŗ������߂��ė���B�قƂ�ǐ܂�Ԃ���D�ł���B������"�Ђ���L�O��"�ŃV���[�Y�̑z���o�������炢����B�����ł͎Ė��̗��j�ɂ��G�����B���ׂ͗̎R�{�@�ցA���a�����Ɍ��Ă�ꂽ���ƉƂ̉ƂŁA�����̗ΖL���Șa���뉀�����Ȃ���A���@����̘a���ł����Ƃ����ґ�������B��X�ɂ͂��̌�ɗ₽���r�[�����҂��Ă���̂ł��������Ă��܂����̂����A������������߂ł���B
���悢��A�����̑ł��グ�͎Q���ɂ��ʂ��Ă���싛�����ŘV�܂̐�牮����B�Â��ȕ����ɒʂ����ƎQ���̓��킢���R�̂悤�ȕʐ��E�ɂȂ�B��̐A����Ȃǂɐ�ۂ�ł��A��������ŎĖ��̖��͂��قڊ��\�ł��������c�A�R���̑��삳��Ɋ��ӂ��A�ق됌�������ŋA��̋����d�Ԃɏ�����B���c�֍s���X�J�C���C�i�[�ɏ���Ă��܂��ƋC�t���Ȃ��A���Ԓ����A�x�؏Ҋ����ȂǂƂ����Ȃ�Ƃ������̂����w������B�����������[���Ȃ葋���猩����͍̂����́A���̂��ɂ͑傫�ȃ}���V����������Ȃ������Ă���B �͂��z���Ă��炭�s���Ă��}���V�����͑����Ă���B�ǂ�قǂ̐��Ȃ̂��낤���A���ɏc�Ɍ������R�ƕ���ł���B�y�������܂Ō����邻�ꂼ��̌��̒��ɂ́A���R���ꂼ��̐l��������B�����ɂ���ǂꂾ���̐l�����̓Ђ����m���Ă���̂��낤���A���a�Ƃ���������I��葁�Q�O�N�B���̍��̐l�̗D�����A�ꐶ�����Ȃ邪�̂̋������A����Ȏv������t�l�܂����Ė����s���ƂĂ���������������B�l�̐S�̕Ћ��ɁA�����������ܕ��������ʂ��镽���̍��A�N������e���܂�A�l����邠��ȃV���[�Y�����̓��������܂�Ȃ����̂��낤���B����Ȏv�����悹�ēd�Ԃ͖�X���̉����𑖂蔲���Ă������B
2008.07.08 (��) �S�N��̓���
�������w���̍��A�}�H����p�̎��Ԃ�����̂��y���݂ɂ��Ă����B�G��`���Ƃ����s�ׂ́A�b�����Ƃ╶�͂��������Ƃ��ƂĂ���肾�������ɂƂ��āA�v�������莩����\���ł����ł�����A���̎��Ԃ��ƂĂ��Z����������B��̎��Ƃ������̂��o���Ă���B���͑債�ċ������Ȃ��A���������̈�̎��Ԃ��A�傢�ɑ̂����邵�J����������Ƃ������R�ŁA����ɏ����邭�炢�������B���̍ł��D���Ȕ��p�̎��Ƃ̒��ł��Y����Ȃ������������B����͒S���̐搶����A"�S�N��̓���"�ƌ����e�[�}�ŊG��`���Ȃ����ƌ���ꂽ���������B���w�Z��6�N�Ԃł��̃e�[�}��3��قǂ��������Ǝv���B�ǂ�Ȗ�������z�����邱�Ǝ��̂��S�Ƃ��߂����̂������B���̎���A�Â��Ȃ�܂ő��싅�₩�����ڂɖ�������q�������ɂƂ��āA�����͉��ł����肾�����B�����r�������R�ƌ����A���ꂼ������ԘL���⋴���������Ă���B���ɂ͋�n��X�g���[�^�̓��H���Ԃ�����A�Ȃǂ͈�{�������Ă��Ȃ��R���N���[�g�̊X�������B
����̌ߌ�ɂ��܂��ܗp�������āA�����̍ĊJ���n�������Ă��鎞�̂��ƁA����ȊG��`���Ă����̂�ˑR�v���o�����B�܂��ɂ��̍��̋�z�ł����Ȃ������S�N��̓����������ɂ������B���̐������ꂽ�r���Q�͗y���V�ӂ̂ق��܂Ő����ɋP���A�v�Z���ꂽ��i�ȐF�ʊ��o�A�r���ƃr���̂��ꂼ�ꂪ�咣���A���a�����J�b�R�悳�ɂ������Ƃ�Ă����B���̓����Ƃ����s��͖ʔ����A����E�V�h�E�a�J�Ȃǂ̖{���̒��S�X�ɂ͓y�n�̒l�i���Ȃǂɂ���āA���̂悤�Ȗ����s�s�̌i�ς͂Ȃ��B���������q���Y��~�b�h�^�E���̂���Z�{�̈ꕔ������炵�����͋C�������o���Ă���B�����͂��ꂽ���V�h�A�����A�V���F�A��t�̖����Ȃǂɂ����A����Ȗ��������������Ă����̂��Ǝ������鎞������B
���������q���̍��ɕ`�������́A�S�N��҂����A�����̔N���ł��̖���i�ς����������悤�Ƃ��Ă���B���_�����̂܂܊C�O�Ɉڂ��A���ĉ����W�߂Ă����c��ȋ����A���܂��ɗ��ꍞ��ł���Y�����Ɏ����ẮA�l���z�����炵�Ȃ��������̂悤�Ȗ����s�s�������̑O�܂ł͍�����C�������h�o�C�Ȃǂɏo�����Ă���B����ȃh�o�C�ł��A�������{�ł����̌��݂Ɍg���ׂɏo�҂��ŗ����A�������̉������œ����l����������B�i���͉����ɂł�����Ȃ��L�������B���ǂ̊X�ł��ڂɂ����J�[�h���Ԃ牺���A�p�\�R����������������A�}�j���A���ł��������Ȃ��Ȃ����T�����[�}������������ɂ��A���������ȊǗ��̉��A���̈��S�Ƃ������̂��Ƃɖ{�l���m�F���Ȃ���ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ����Љ�̐S�̈ł������B�ꂵ�Ă���B���̍��A�q���S�ɂ����̊G�̒��ɐ�����l�Ԃ͂ǂꂾ���̍K������ɓ����̂��낤���ƁA���N���N���Ȃ���`���Ă����̂��v���o���B����ǂ��Ă������̎���A�z�����炵�Ȃ������i���Ə��Ƃ����s�K�������ɂ͂���B
���̎�������̋A�蓹�A����J�o�R�Œʂ����ЂƋC�̂Ȃ�����c�����B���߂Ă��̑������Ɉ��|���ꂽ�B���������͏��w�Z�̎Љ�Ȍ��w�ŖK�ꂽ���ƑS���������B�S�N����������Ĉ̗e���������Č���������̂��낤���B������܂ŁA���̒��ł͐�����n�ʊm�ۂׁ̈A����ς������Ȃ������ƂƁA�L���Ȍ���ێ��ׁ̈A����ς�点�Ȃ��Ƃ������������������̌��ł����߂Ă����߂��Ă����B
���̂����T�ł͍ĊJ�����s�Ȃ��A�X�͍��X�ƕϖe�𐋂��A�����̍����͏d�ł╟���̐؎̂āA�������̍�����N�����ɚb���ł���B�z�������悤�ȔM���Â���7��5���̓y�j�̌ߌ�A�Ђ�����ƐÂ܂�Ԃ��������́A���X�Ƃ����Ќ��Ƃ͗����ɁA���̒��g�������s������̘O�t�Ƃ��ċ����Ă���悤�������B�������������B��^�����Ă��鐭���ւ̌����A����ׂ��I���ɂ͐S�����߂��F��̈�[�𓊂��悤�Ǝv���B����������q���������S�N��̖������v���A���̂���G��`����悤�ɂƁB
2008.06.09 (��) ���W�I�h���}
����̓��j���̗[���A������葁�߂̕��C�ɓ���A���̒��ł�����������̃��W�I�Ńh���}�����B�v���Ԃ�ƌ����������\�N�Ԃ�̂��Ƃ��낤�B�`�����l���͋������Ƃɗm�y�u����DJ����������J-WAVE�ł���B�m���X�s���b�g�E�I�u�E�A�W�A�̃����R�[�i�[���������A�v�������Ȃ����Ƃ������̂łƂĂ����������������B���̐́A�g�[�L���[FM�̐[��ɂ���Ă������W�I�h���}�A"������"�Ƃ����ԑg���D���ŁA���̎��Ԃ�����̂��y���݂ɂ��Ă����������������B�h���}�ƌ������͒Z�ҏ����̂悤�ȍ��ŁA�b�����̓s�x�������Ă���̂����A��l����"������"�́A��ɗ�Ò����ň��|�I�ɋ����A�閧�g�D�̃M�����O�Ⓦ�̍��̃X�p�C�����Ƃ̐킢�͒ɉ��������B�����Ĕԑg�̍Ō�ɗ����Ȃ́A�������ꂽ�u���b�N�E�~���[�W�b�N�n�Ƃ������܂肪�����āA���̂��тɍ��x�͒N�̉̂������̂����y���݂̈�������B�n�����h�E�����r���ƃu���[�m�[�c��"��l���J"�Ƃ������Ȃɏo�������̂����̔ԑg�������B�o���͔o�D�̓������j���A�ނ̒m�I�Ȑ��ƃX�������O�Ȍ�����ۓI�ŁA�ԑg�̍ő�̖��͂ɂȂ��Ă����B
�������̋ƊE�ɏA�E���Ă��炵�炭���āA"������"�̔ԑg�𐧍삵�Ă���f�B���N�^�[�̉F�y�����畷�������ł́A����w�i�₠�̗�Âȋ����́u�S���S�P�R�v���q���g�ɂ��Ă���Ƃ̂��Ƃ������B�����A���ł��ǂ�������R�̖��Ȃ��������܂ꂽ����ŁA���傤�ljf��E�ł́A�����j�̃X�^���[����V�������c�F�l�b�K�[���f�r���[���������ł��������B���W�I�h���}���A�~�X�e���[�����̎�l�����A�����܂ł������̒��őz��������̂ł����āA��l���̊���A���R�Ƃ����C���[�W�ŐS�̒��ɕ`���Ƃ�������͂ɂȂ��Ă���B
���̂S������ANHK�͕ۊǂ��Ă���S�O�O�O�{�̃��W�I�h���}�̒����珺�a�S�O�N��̂��̂𒆐S�ɑI�яo���A���W�I���Ŗ����̑�S���j���A�[��̃����R�[�i�[�ŏЉ�Ă���B����A���܂��܋��R���낤���A�����̌������҈�Ö��ŁA�Ăыr���𗁂т鎖�ɂȂ������t�A�W�̂ĎR����ނ�"��܂��"������Ă����B���W�I�h���}�͒B�҂ȏo���҂����̌��t�����邱�ƂȂ���A�����Ɏg���Ă�����ʉ���Ў��̒��قɁA�����ɕY���o���҂����̔����ȐS�̓����������Ɏʂ��o�����B���̓����A���͕K�����W�I���Ă����B
���͋N�����TV�����Ă��܂��}���l�������낻��~�߂āA������������Ă��邳��₩�Ȓ���������������Ȃ��Ǝv���n�߂Ă���B�O�����߂č�Ƃ����M����������h���}�̐��E�A�ޓ����S�̒��ŕ`�����E���A�������������邱�ƂɁA���߂Ă��̖��͂������Ă���B�傫�Ȗ{����CD�V���b�v�Ō�������A���j�Ɏc�閼�������≉�Z�̎|���o�D�������N�ǂ���CD�ɂ́A�������ǂ�ł���Ƃ��Ƃ͖��Ⴄ�A���킢�[�����̂�����B
�����E�ł͎�����f�����q�b�g�������I�ɏo�Ă���B���W�I�ƊE���ǂ��ł������Q�X�g�̋ߋ���ADJ���j���[�\���O���Љ����ՂȔԑg����ł͂Ȃ��A�ߋ��ɗD�ꂽ������Ƃ���ĂĂ������т�w�i�ɁA���z���▲���c�ނ悤�Ȑ��E������Ă݂Ă͂ǂ����낤�B �������N�A��ɎԂɏ���Ă��鎞�ɂ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������W�I�̐��E�ɁA�S�҂�����悤�Ȗ��h���}�▼�ԑg���o�����邱�Ƃ��肤�̂́A�P�Ȃ鎄�̏��a�m�X�^���W�A�Ȃ̂�������Ȃ��B�������A���W�I�͌܊��̒��œ�ȏ�g�����Ƃ������Ȃ������̎���A���̈�������W�������镶���A������ł������Ȃ��z���̕����������Ă���B
�J�����Â��ɑ���@������ȋG�߂ɁA����̍������镔���ł��҂����˂̃��W�I������Ă���A����Ȃق̂ڂ̂Ƃ����V���W�I���オ���邱�Ƃ����҂��Ă݂����B
2008.05.29 (��) �R�[���Ɩ�̗V���n
�l�͐��܂�ď��߂Č��ɂ���͕̂���A�������͂���ɍł��߂��ނ̂��̂��낤�B�c�O�Ȃ��炻�̐_���ȋL�O���ׂ��s���́A���ꗎ�������ׂĂ̐l�X�̋L���Ɏc��Ȃ��B���ꂩ��͏��߂Đs�����̐l�����X�^�[�g���Ă����B�l�X�ȏ��̌��A�����A���d���A���ł�����H�ׂ���́A���E�̉ʂĂ̗�������Q�e���m�A�V�����J�����ꂽ�V���i�Ɏ���܂ŁA���܂鏊��m��Ȃ��B�����ꐶ�|���Ă��I��Ȃ��̂��낤�B�����Ɍ���ł����|�s�����[�ɂȂ�A�N��������ł�����̂ŖY����Ȃ��z���o������B���̒��w����A�܂�܂Ɖ�Ђ̐헪�ɏ悹���A�R�[�������ނ��Ƃ͂��̎���̐�[��������悤�ȁA�ƂĂ��������������s�ׂƂ��ĎƂ߂Ă����̂��o���Ă���B���ł��A�����J�i�C�Y����Ă��邱�Ƃ��J�b�R�悭�A���{�I�Ȃ��̂͌ÏL���ă_�T�C�Ƃ����������������B��ォ��X�^�[�g�����卑�̃}�C���h�R���g���[�����A����Ƃ���X���{�l������ɂ�����Ɍ��������̂��͒肩�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�Ȃ�Ƃ��U�E���X�̔w���̌���قǃe�[���ɂ����l�ȁA�傫�ȃA���Ԃ̃R���o�[�e�B�u���A���̃h�A���J���Ƌ��̂悭�ʂ������̐N���~�藧���A�ԂɌ��������܂܂��D�u�ƉƂ̒��ցA�����Đl�̔w�����傫�ȗ①�ɂ̔����J����B���o�����̂͂P���b�^�[�قǂ̊ۂ��đ傫�ȋ����r���A�W���J������S�O�Ȃ����̂܂܃��b�p���݁B���̉f���͎��ɂƂ����ґ�̋ɂ݂������B���ɂ��ƒ�ɂ���ꂽ�A�A�����J�̃t�@�~���[�E�h���}��t�f�������ɂ��A�����̍��������̖L�����ɓ�����������B
�����A�����͋����ł͂Ȃ��R�[���̘b�B����͂��̒��w�����肳��ɂU�N�قǑk��B�������w�Z�ɏオ�邩�オ��Ȃ����̍��������B�����ɕ��Ǝ����A�Ȃ���̕����Ԃ��������܂�����y���V���n�ɁA��������l�����ł����̂��͂킩��Ȃ��B�Ƃ̖T�Ƃ䂤�����������̂��낤�B�����A���̃g�[�L���[�E�h�[���̏ꏊ�͋��֏ꂾ��������̂��Ƃł���B���ւ��J�Â������́A�ԉ��M�����ɋ��݁A�������Ԑ��������ꂽ�V�����A�K�̃|�P�b�g�ɓ˂����I�b�T���B�Ŋۂ̓����͈�t�ɂȂ����B�����������y���ɓn��ƁA���ɂ͂T�O���[�g���̖�O�v�[���A�E�ɂ̓��[���[�E�X�P�[�g�ꂪ����A�V���n�̖ʐς͍��̎O�{�͂��������̂��Ƃł���B�����łR�C�S�l��������Ă��Ȃ��A�ۂ��Ƃڂ����炪�^�ɂ���I�N�g�p�X���A�����̏����ȓd�������ꂼ��̑��ɕt���āA�N���N���Ɖ���Ă����B�₵���ŁA�D�������Ԃ������V���n�̖邾�����B�镗������������K�����Ƃ����I�[�v���̌y�H���X�g�����B�F�������r�j�[�����������Ă���A�p�C�v�֎q�ɍ����������A�����ɂȂ��D���������̂��o���Ă���B
"���ł���������D���Ȃ��̂�I��ł��Ȃ���"�Ǝw�����������ɂ́A���Ă����ĉ���ł��܂����Ȃ��A�A�̂ӂ�����ď���Ă���r�[����A�z�R���ō�����ł���n���E�T���h�̃C�~�e�[�V���������ԃV���[�P�[�X���������B���͗E��ő�D���ȃ`���R���[�g�p�t�F��I�тɍs�����̂����A�f�p�[�g�̐H���̂悤�Ȃ킯�ɂ͂������A�c�O�Ȃ���ړI�̂��̂͂Ȃ������B���낢��v���Y����A�I�̂̓o�����[�X�E�I�����W�̂悤�ȃr���ɓ������`���R���[�g�F�̉t�̂������B�����Ĉ������ł݂�ƁA�ٗl�Ȗ��Ƃɂ����Ɏv�킸�f���o���Ă��܂����B���ꂪ�R�[���Ǝ��́A�����킹�̂悤�ȏo��ł���B
���̍��A���܂����y���Ă��Ȃ��Ƃ���R�������B���̃g�C���̏��L�܂�A�z����ɂ���������B�D���̃`���R���[�g�̐F�ɂ悭���Ă������Ƃ�����A���̖����v���`���Ă����B�悭�����Ǝv���Ĉ����Ɏ���������A���|�������肵�ċV���鎞�̃A���ł���B�������̍s���ɋ������炵���A"�ǂ������H���v��"�Ƃ����ĐS�z�����Ɏ��̊��`������ł����B����"�u�̌�"���Â��ɗ���A���Ɏc������L�����ݕ��̂ɂ������A������x�@�̒���ʂ�߂����B���ꂩ����N�Ƃ����������߂��A�悤�₭�R�[���Ƃ������ݕ�����ʓI�ɐ��ɏo�������B�ȗ��A���̌��̑̂��炭�H�͂��Ă����A���̓R�[������{�l�̒��ł��Ȃ葁�����q���Ƃ��āA�ւ�������Đ����邱�Ƃɂ����B�����čŏ��Ɉ����z��"�g�C���̏��L��"�Ƃ������t�́A�ȗ����̋��̒��ɐ[�����܂�Ă���B
����Ȗ�̃R�[���Ƃ̏o�������I�A���̒Y�_�����Ƃ̒����t�������́A�ǂ����镅�ꉏ�̗F�l�̂悤�ɁA���������Ă���B
2008.05.22 (��) ���o�̐V����
��N�̂T���ꏊ�̑告�o�ϐ�L�ł��G��A���N�̂P���ꏊ�ɍĂь���Ŏv�����̂����A���Z�قɂ���O���l�t�@�����������Ă���Ɗ������B���̂T���ꏊ�͋Չ��F�̊���ɉ����A�����ɂP�U�l���̊O���l�͎m������B�\�������킹��ƂQ�Q�l�ɂ��Ȃ邻�����B���̒��ł��ɂ߂��̓����S�����̖��i���B�����ɂW���A�\���ɂU���A�����X���A�R�i�X���A�ȏ�A���ɂR�Q���̃����S���͎m���告�o�E�ɂ���B���ɏ�ʂ̓�l�̉��j�����߂Ƃ��開���͎m�����̋����Ƒ����͍ۗ����Ă���B�ꐢ���r�����n���C���͉����������̂��낤�Ǝv���Ă�����A���Z�ق̐���ő傫�ȕ����ېe���������Ȕ��̒��ł����ς��ɂȂ��āA�ؕ��̂���������Ă����ʂ͔��܂��������B�i���Z�ɏo��m�b�N�A�E�g���ꑱ���Ă��������l�ƈႢ�A�ɂ��v���������吳���ł���B��N�A�������ސT���Ė��y�U�ɏオ�鎞�A�������Ȃ������悤�ɗD������̂ł͂ƁA�{���Ɏv���Ă����l�������B���K�����Ȃ��Ă��A�������������ɂ�ł��Ă��A���{�l�͎m������V�I�ɋ����A����͂����Đ��܂ꂽ�����A�܂�œ��H�b�Ƒ��H�b�̂悤�ɈႤ���炾�Ƃ����ɒ[�Ȉӌ����������B�ŋ߂̑��o���p�����ĉ��ƂȂ��[�����Ă��܂��_������̂����A�����͎v�������Ȃ��̂��A����܂ő告�o���y����ł������������{�l�̖{���ł���B�ł͉����ɔނ烂���S���l�͎m�ƁA���{�l�͎m�̈Ⴂ������̂��낤�ƍl����B
���Ƃ��ƗV�q�����ł���A��H�͎�ɗr���A��ɂ���ď��������ɂ���邪�A�ނ�ɂƂ��đ��͉ƒ{���H�ׂ���́A���͖����h����R�̗��������Ă���̂ŎE�����Ƃ�����k�Ƃ��{�C�Ƃ��Ƃ��b�����B����������A���̃T���_�͂Ƃ������A�^���R�␔�̎q�A�C�N���̋����ނ���D���Ȏ��́A�ǂꂾ�������̖������ɕ��荞�̂��낤���ƁA�S�����₩�ł͂Ȃ������B�ƒ{�ƂƂ��ɐV�����y�n�����߁A��ɒn�����ٖ̈M�l���Z���Ȃǂ̊댯�ƑΛ����A�����̗͂ƒm�b�����𗊂�ɐ����Ă����������B�`���M�X�E�n�[�������߂Ƃ����X�̃��[�_�[�B�́A�N��̍��A�g���A�G�����A�ٖM�l�Ȃǂɂ�����炸�A�����B�ɂȂ����̂�ٕ�������荞��ł䂭���������������Ƃ����Ă���B�������玩�R�ł���A���ׂĂ͗͂����`�ŁA���̗͂̑O�ł͂��ׂĂ������ł���Ƃ������ƁB���A���{�ɂ��郂���S���͎m�����͂��̎v�z���p���q�������ł���B�����̍s���Ȃǂ��A��c����`���͂����`�Ƃ����v�z���痈�Ă�����̂��Ƃ���A�����镔���������Ă���B
���{�l�͂��Ƃ��Ɣ_�k��Z�̖����ł���A�y�n���k���A�Ă���H�ɁA�Â��Ȃ�ƁA���������ɔ����ĐQ��B�g���A�㉺�̎�]�W�A�k�퐧�x�Ȃǂ̓O��ɂ���ė��j������ł����B�����������ł���ׁA����ɂ����ĊO������̕�����v�z�̗�����댯�����Ȃ��A�m�_�H������n�܂�A���X�ƍ����c����̕���̐��E�ɑ������P�̂悤�ɁA���ꗎ���������炻�̐g���Ɏ���A�����ʂł������ʂł�������p�����Ă����B����Ȏq�����A�������ƍ��̓��{�l�͎m�����ł���B
���{�̑��o�̏ꍇ�A���ʍ��E�ɐ^�����ȉ����u���ꂽ�ۂ��y�U�A���i�j�A�鐝�i�ԁj�A���Ձi���j�A�����i���j�̋G�߂ƕ��p��\���A�l�F�̖[��������V�䂪����A�`���ɗ��ł����ꂽ����d��_���Ȑ킢�̏�ł�����B�����S�����o�͉ʂĂ��Ȃ�������n�̂��ׂĂ��y�U�ł���A��ɂȂ�Ɩ��_�̐���ɂȂ�F�������̓V��ł���B�����ɂ͎��R�ƂƂ��ɐ����閯���̃X�P�[���̑傫����������B���̗��j�͂͂邩�I���O����s�Ȃ��A�i�[�_���̍Ղ�ł͂���ɋ|�ƋR�n�̋��������������B�����͉ƒ{�̐��b����q��āA�H���̗p�ӁA���̂��ׂĂ����Ȃ��A��������ɂȂ����ߔN�ł́A�w���͒j�q�����D�悷��Ƃ����B���̓�l�̉��j�A���Q�A�����̂��ꂼ��̕�e�͋��ɍ�����w�̏o�g���B����Ȃ������������ł��m���Ă����ƁA�����Ă��郂���S�����痈���͎m�������A���g�߂Ɋ������A�e���݂��킫�A���o�ϐ�����y�����Ȃ��Ă���B
������ɂ���厩�R�̒��ň炿�A��c����p���ꂽ�v�z�̈Ⴄ�͎m�������A�b����ꂽ�����ȑ̂Ƀ}���V����߁A��������餂������ő��ǂ������B���{�������A����d����{�̑��o�E�ňꐶ��������Ă���B�ނ̒n�ɂ́A���{�ɗ��邱�Ƃ���L�]�ȎႢ�͎m����R����ƕ����B���{�l�̓����]�҂����������A���{���o����̓��̒ɂ��Ƃ���ł�����B�����A�ނ烂���S���͎m�̗D�ʂ͗h�邬�������Ȃ��B����͏����̏��b�ɂȂ�̂��A�����ɂȂ�̂��͒肩�ł͂Ȃ����Ƃ��b�B�ق�̈ꈬ��ɂȂ��Ă��܂������{�l�͎m���A�͂邩�����S���̂���ꏊ����A�q�����p�����Ȃ���A�ٍ��ɂ��鎄�B���������鎞�オ����̂�������Ȃ��B����͂���ŁA���̑僊�[�O�ɍs�������{�l�I�����������悤�ɁA���{���瑗��o�����H���̗���Տ��e�̂悤�Ȋ��҂̗͎m���A�����ȃ����S���͎m�̒��ŁA�@���Ɋ��邩���l����ƁA�����ۛ�����D���ȓ��{�l�́A�����A���������ƔR���邾�낤�B
�����Ƃ����`�o�A���{���瓦��ċ���ȃ����S���𗦂���`���M�X�E�n�[���ɂȂ����Ƃ������̂悤�Șb�́A���̏�������l����Ɛ�ɂ��肦�Ȃ��A�P�Ȃ閲�������ƍ����ɐ鐾����B�t�ɐ��Ԃ��Ȃ��]��g�v���m�ɂ���ď�����ꂽ"�R�n�����͓��{�𐪕�������"�Ƃ����Y��Ń��}����������A���̒��ł���ɑ傫���^������ттĂ��Ă���B
2008.05.08 (��) �j�̕�����
��N�ōł�����₩�ȐV�̋G�߂�����Ă����B�X�ł͏��X���������V�Љ�l�炵���l�B���A���������̂���\��ɕς��n�߂Ă���B�悭���Ԃł́A�l���ōł��K���Ȃ��Ƃ́A�E�Ƃ������̎�ƈ�v���Ă��邱�Ƃ��ƌ����l������B�������̒ʂ�ɂȂ��āA�s���Ȃ�����Ȃ�̐������x���A�܂��Ă�l���݈ȏ�̐��������Ă���l�́A�ق�̈ꈬ��̐l�B���낤�B���̍��Z����A�Ȋw�̋��ܐ搶�Ƃ����N�z�̐搶�������B�����ؚ��ȑ̂ɔ��߂𒅂āA�L�яk�݂���ׂ��������̖_�������Ă����B�搶�͓�����w��D�G�Ȑ��тő��Ƃ���A���ڂ��{�l����ł͂Ȃ����A�����v�܂ő���ꂽ�Ƃ����P�������O��������������B���C����Ȓj�q�Z�͂������������A�����ɓ����Ă���Ə�ɗ�̋����_��V��Ɍ������č����A���Ԃɂ������"�Â��ɂ��ā`�I"���搶�̑�ꐺ�������B���U��Ԃ�ƁA�{���ɂ��������f���肩���Ă����B
���鎞�A�搶���ዾ��@�̐�[�܂ʼn��낵�A��ڂ������ɉ�X��l�A��l�����Ȃ���A���݂��݂ƌ����������������B�����ꂩ��b�����͉Ȋw�ł͂Ȃ��l���̎������A�F�悭�����Ȃ����B�j�Ƃ������͈̂ꐶ�̂����ŁA�O�̑傫�Ȏd�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̑��́A������w�ɓ��葲�Ƃ��邱�ƁB���́A�ꐶ�����ɂȂ��A�����d���ɏA�����ƁB��O�́A�����ЂƁi�����j�������Č��������邱�ƁB������|�����Α�T�̒j�͍K���Ȉꐶ�𑗂��B�l�̏ꍇ�A���܂ł͂��܂��������̂����A���A��O�Ŏ��s���Ă��܂����I�@���▢���̂���N�����͊撣��Ȃ�����
���̎��A�����܂ߑ����̐��k����A�m��Ȃ����ŏ���Ȏ��������Ă���搶�̉��l�̖��O����z���A���ȏ����R�ꂽ�̂����A�Ȃ������̌�A�����S�̂����v���ɂӂ������悤�ɐÂ��ɂȂ����B�������ɁA���̂���������u���A�����w�Z�́A���A��O�𐬌�������ׂ��z���Ղ̂悤�Ȃ��̂��B�t�ɑ��A��O�͓���ɉ��X�Ƒ����A�l�����̂��̂Ƃ����Ă��������̂ł���B�ق�̈��ɉ߂��Ȃ��搶�̐l�����P�͖Y����Ȃ����t�Ƃ��č����N���Ɋo���Ă���B
�d���ƌ����͂��܂��܉��������āA���̉�ЂȂ�A���̌���������������I�сA�I��A���X�𑗂邤���ɁA���|�ւ��̂Ȃ����̂ɂȂ鎖�����z�ƌ����邩������Ȃ��B�����ƌ����Ύd���⌋����������̒��ɁA�D���Ȃ��̂���葽����������\�͂�|�����Ƃ��A�������K���Ǝv����l�����̒��ԓ��肪�o���鎖�Ȃ̂�������Ȃ��B�{���A�K���Ƃ͎�����m�鑼�l��Љ���l��q�Ϙ_�Ō��߂���̂ł��Ȃ��A�������g���܂��A���R�Ɋ�������܂œw�͂��鎖���ƐM���Ă���B���̎��A�搶���b���I�������A�ӂƌ������V�l�̂���������ۂ����݂����͌������Ă͂��Ȃ��B�搶�̖{�����A����������k�Ȃ̂��A���\�N�����������킩��Ȃ��B����ł����̎��́A�ꐶ�����E����I���̑���������A�搶�����g�̐l���̈�����B�ς��A����������悤�ȋC������B
�������ė�����邪�܂ܐ����Ă��鎄�̐l����U��Ԃ�A�������I���ł��镪����̉E�������A���ꂪ�K�����������A�s�K���������̔��f�́A����܂Ő����Ă��������ɂ�������炸�A�����ɉ��������������Ă���B�������ꂩ������̉��ɋ~���Đ�����̂��낤�B�������Ă��鍡���A���ɉߋ��ɂȂ�ߋ��ɐ�ł�������A��������J��Ԃ������̐l���ɁA���������̔t���グ�鎖�ɂȂ肻�����B
2008.04.26 (�y) �閧�̏ꏊ
���̔N��ɂȂ��Ė��Șb�����A���ɂ͐S���������閧�̏ꏊ������B�H�̓��̂Ƃ�����j���̌ߌ�A���R�ʂ肩�����������̗���Ɍ������ܒؒ��̂�����܂肵���n�ŁA�X�g���b�`�Ȃ���̂��n�߂��B����Ɖ������̐�������B�l�̏����������ł������ɕ�������悤�ȐÂ��ȏ��������B���̂���������グ��ƁA�������ɓ�V�̎����^���Ԃɏn���Ă��āA������q���h���B���y�����ɂ���ł����B���ΐF�̔������t�̐F�ƏH��̐����A�Ԃ����Ƃ̐▭�ȐF�̒��a�������Ă���A�܂�œ썑�̊y���ɂ���悤�������B ���̔��������i�̒��ŁA�C�����Ǝ����g�����ɂȂ����悤�ȋC���ɂȂ��Ă����B�ȗ��A�Ă���H�ɂ����āA�ЂƋC�̂Ȃ��̂��m�F���Ă���A�����ɗ���̂��y���݂ɂ��Ă���B ���ʁA������N���ƈꏏ�ɋ��L�������Ǝv�����̂����A���R�ŐS�n�̂������Ԃ������A�Ƃ�ł������s�v�c�ȏꏊ�ł���B�����Ŗڂ����ƁA�q���̍��ɂ��閧�̏ꏊ���������̂��v���o���B�����A�Ƃ̗���͍L���쌴�ɂȂ��Ă��āA�������瑱���Ă���R�̏�ɂ܂��y�n���L����A�^�Ɉ�{�̑傫�Ȗ��������B�Ă̐��ꂽ���A�����s���Ă����̖ɂ́A��D���ȃA�I�X�W�A�Q�n�������o�}����悤�ɔ��ł����B�H�Ƀu���[�E�O���[�����Y��ȋ����鏬�U��ȃA�Q�n���̒��ԂŁA�̏�ɍ炢�������ۂ��ʂ̂悤�ȉԂ̏���A�Q����Ȃ��Ĕ��ł��邱�Ƃ��������B���̔閧�̏ꏊ�ɂ́A�s�K�ɂ����̓y�n����鋰�낵�������k���Z��ł����B�������̂悤�ȏ�i�Ɍ��Ƃ�Ă���ƁA�ˑR����Ă͖_��|�̂ق����ŁA���^�ł��������Ȏ�(�H)��ǂ������܂��̂������B�ޏ��͏o�n����������Ȃ����A��Ƀg���[�h�E�}�[�N�̃^�X�L�����̘a���p�ł���̂ŁA�ߏ��̈��������̊Ԃł́A���}���o�i��̐F�͓����悤�����A�ȑO�A�a�J�̃Z���^�[�X�ɂ����̂Ƃ́A�������ꂽ�{���t�@�b�V�����j�Ƃ��������������Ă����B�������̖_�����������}���o�ƃg���R�ΐF�̃A�I�X�W�A�Q�n����ԃV�[���͖Y��Ȃ��B
����������A���̐V������l��(�H)�閧�̏ꏊ�́A�Ԃ����ƒ�����������̈��炬�̏ꏊ�ƂȂ��Ă���B�����������Ă���̂����A����͐����֗̕����ƈ��������ɁA�l���̔×��ɂ�銱�ȂǁA��R�̔ς킵�����������B�قƂ�ǂ̐l�������ɂ��Ă����[����g�т�炳��`�F�b�N������B���N���̔N���E��Ô�V�����̖��A�Ԃ̃V�[�g�x���g�����Ȃ���"�������M�̈��S�����Ȃ��l�́A�������d�u�����܂�"�Ƃ����肳�由�_���o�Ă��܂��A�S�n�悭�����ĉ̂��J���I�P�ɂ܂ŁA�̂ɓ_�������邨�߉�ȋ@�B���o�ꂵ�Ă��܂��悤�ȁA�傫�Ȃ����b�̎��ゾ�B���R�A�閧�Ƃ������͎̂Љ�⑼�l����m���邱�Ƃ��Ȃ��B�܂��Ă⏊�F���\�ł��Ȃ��~�ɗ��l�ԒB�������]���Ȃǂ́A�v��������ᒠ�̊O�܂ŏR�����B�����̊��������ɂЂ��炩���}�C�E�u�[���Ƃ͑ɂɂ�����́B�����Ǝ��������̖z���Ȑ��E�ɐS�n�悭�Z�鎖�ƍl����B������������␔���Ől���܂ł������܂肩�˂Ȃ����̐��ɁA���ׂ��y���݂̗ƂƂ��āA�S�Ƃ��߂��悤�Ȕ閧�����Ƃ߂��舧���čs���������̂ł���B
2008.04.22 (��) �h����X����
���z�������������z�Ԃ̉Ԃ��炭���ɂȂ�B���̉Ԃ��炭�ƕK�����钩�̏o�������v���o���B���鎞�A��ɍ炢�����z�Ԃ�ꂪ���āA���̗��肪��t�ɂȂ�قǂ̑傫�ȉԑ��ɂ��āA�c�t���Ɏ����čs���������Ƃ��������B�������Ȃ�����j�炵�����ӎ����āA�Ԃ����Ƃ������Ƃ͎��̊����ɂ͂Ȃ������̂����A�Q�����ˑR�̒��̏o�����������̂ŁA���̐���s���ɏ悹���Ă��܂����ƌ����̂��{���ł������B�����ő�ςȒp�����������Ƃ����A���̎���m��l����͂ƂĂ��z�����ł��Ȃ��A�����ȍ��̎��́A�ق��Đ搶�ɉԑ��������o�����Ƃ�������ςȃv���b�V���[�������邱�Ƃ������B����Ȏ���N�����������Ă����̂���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂����A���v���Ɏ���b����ׂ��A�����q�����c�t���ł悭�v����ׂ������̂��A��������Ȏv���������̂��낤�B�����̎��]�Ԃŕ��̒�̔�������ɑ����A���^���ԁi���������������ɈႢ�Ȃ��j�ɂ��Ă��̉ԑ���搶�ɓn�����B����ƁA���̐搶�̔������܂������Ȃ������B�ڂ��ۂ����đ吺��"�܂��I�Y��"�ȂǂƊ��Q�̐����グ�n�߂Ă���B���Ƃ��Ɩ����Ȃ̂Ŏ~�߂Ă��������Ƃ������Ȃ��B�����ŗF�B�͏W�܂�́A�����������̃N���X�̐搶�܂ł���������ŁA�呛���ɂȂ��Ă��܂����B�p���������̂��܂�A���̓�����A�قƂ�NJ���グ���ɉ߂������̂��o���Ă���B�J�ɔG�ꂽ���A�Ԏ��̑傫�Ȕ������Ԃ��炭�ƁA���̓��̒����h��B
���[�����X�N
�F�B���A��n�߂�������̌ߌ�A�Ƃ̓s���ŋ��c�邱�ƂɂȂ����̂��낤���A���ƂȂ��Ă͒肩�ł͂Ȃ����A���͑�����X�������e�𗎂Ƃ��u���Ɉ�l�����B�����������ɂ���ƍ��郏�b�N�X�̓������D���������B�����̍s���͂����Z�����F��������̏����A�ߌ�̌��˂���ῂ��������Ă����B����Ƃ����̏I��̍��}�ł���Ȃ��ˑR�傫�ȉ��ŗ���n�߂��B�o�C�I�����̋|�ƌ����킸���Ɉڍs���鎞�ɎC��鉹�܂ł����̋Ȃ̈ꕔ�Ƃ��Ċ����I�ɒ��������B�������C�Ȃ����Ă����I��̍��}�ł����Ȃ��Ȃ́A�ˑR���̏�ɑi���閼�ȂɂȂ����B�����Ă����̍D���ȃ��b�N�X�̍��肪�A���ɐȂ��o�C�I�����̉��̒��ɗn������ł������B�����o���A�傫���Ȃ��Ă��疳�����s�����ꂽ���y��ŁA�Ăт��̋Ȃ����ɂ���@������đ薼��m�����B"���[�����X�N"�B�y�����邢�^�b�`����A���X�ɐȂ��A�₪�Ċ��\�I�ɍ��܂��čs���A�܂��A�������Ȃ������悤�ɂ͂��߂̃t���[�Y�ɖ߂�B�ȗ����̋Ȃ͎��ɂƂ��ĂƂĂ��Ȃ��Â��Ȃł���B�����A���\�N���o�̂ɁA����"���[�����X�N"�����тɁA�K�������˂��u���̃V�[���Ƃ��̉����������b�N�X�̓������h��B
��̎�
����c����O�m�ւ܂ŁA���̓����ł͗B��ɂȂ��Ă��܂����s�d�������Ă���B�����q���̍��A�s�d�͖Ԃ̖ڂ̂悤�ɓ������𑖂�܂���Ă����B�����A�����̏f�ꂽ������A������l�ɂȂ�܂Ō���ꑱ�������Ƃ�����B�܂��A���̋L�����m���ł͂Ȃ��قǏ����Ȏ��A�f��̗ǂ��m�閺���A�q����łɎ���A��ďo�������̂����������A���̖�����Ǝ������ׂȂ��ƂŃg���u���ɂȂ����Ƃ̎��B�����Ď����L�����H�̐^�A�����������𑖂�s�d�̐��H�ɁA��̎��ɐQ�Ă��܂����Ƃ����B��̂悤�ɓ����Ȃ��Ȃ��������A�����ɂ������l���̐l�ɏ����Ă��炢�A���[�܂ňړ����ĉ��Ƃ����̏�����̂����ƌ����b�������B�����āA�ނ����鎄���A�Ƃ܂œ͂��Ă��ꂽ������H���A"�����ȑ����̎q�������Ă��܂������A����Ȉ����q�͏��߂Ăł�"�Ƃ����ς�Əf�ꂪ����ꂽ�Ƃ����B�ȗ��A�e�ʁi�]�Z�킽���������A��ɑ�l���������j���W�܂�ƁA�K���傫�Ȑ��ł��̘̐b���n�܂�̂������B���̒��̏�ŁA����ɕ֏悵�āA�����炱��Ȏ������ꂽ�A����Ȉ������������ȂǂƂ����b���o�Ă���B�����͊��܂ꂽ���c�܂Ō�����n�����B���`�ł͂Ȃ����`�E��������̔��\��ɂȂ�̂������̗����������B���ɂȂ��Ă��s�d�̎ʐ^��͌^�A�܂��Ă����������ƁA�f�ꂽ���̍����t�ł��������̑�̎��`�����h��B
2008.04.01 (��) �Ԑ���
����̌ߌ�͈�������~�葱�����J���~�݁A����C�Ƒ����̊������c��A���ܓ����˂����Ȃ�C�����̂����ߌ�ɂȂ����B���������炢�������₽���J�ɂ���ĎU��}�����̂�������Ȃ��Ǝv���A���X�ɂ��ߏ��̍��̖����ł���N�w���ɍs���Ă݂��B���J���玞�Ԃ��o���Ă��Ȃ������̂��K�����Ă��A�܂��܂������낾�����̂ň���S�B�܂��ɂ��ꂩ��U���Ă䂭���Ȃ̂��낤�A���������Ɛ�ɉԂт炪�����Ďv�킸�����~�܂�A�����ƃs���N�̃R���g���X�g�Ɍ��Ƃ�Ă��܂����B���̏ꍇ�������̎����ɂȂ�ƌ������މ̂�����B����͂������Ȃ��݂�"�Ԑ���"�ƌ����̂ł���B���̋Ȃ͊w�����ォ��M�^�[�̒e�����ʼn̂��Ă����B�������̉��D���ŁA���̐����Ȃ����p�[�g���[�̈�ł���B���������ޏ��ɂ��Ă݂�A������������Ɖ̂��i���o�[�ŁA���ӂ��Ȃ��Ƃ������Ȃ��݂ƋC�t�����ɕ��������Ă��܂��B����ȏ��ɔޏ��̉̏��͂̉��[����������B���̓��e�́A�w���̏����Ȃ��X�̃}�}�ł����l���������Ȋw���Ɨ�������B�₪�Ă��̊w���͑��Ƃ̊����}���̋��ɋA���Ă䂭�B����܂ł̑z���o�����ɁA�Ԑ��Ⴊ���ɗx�钆�Ŏ������܂��A���܂ꂽ���ɖ߂錈�S������Ƃ������̂ł���B�������̐��ƐȂ����C�ɓ����Ă��̎����ɂ͕K���������ނ��ƂɂȂ��Ă��܂����B
�l���Ă݂�A�ŋ߂̍�����݂̃r�b�O�q�b�g�Ȃ̑����ɂ͋������肾�B���͓��{�̏ے��ł���A���{�l�̐S�ɋ����i����Ԃł��邱�Ƃ͏O�ڂ̈�v���鏊�ł���B�p�b�ƍ炢�ăp�b�ƎU�邻��Ȍ��������Ԃ��A�l���̒��ōł����̋�������̐ߖڂ̎����ɖ��J���}����B�Ȃ�Ɠ��{�l�̋Ր��ɑi��������ԂȂ̂��낤�B�����ĎЉ�l�ɂȂ��ĉ��N������ƁA���̊��������āA�߂����d�����ԂƁA���̉Ԃ̉��ŗJ�����炵�̂悤�Ɏ�������Ő��������B����ł��S�̕Ћ��ɂ͂��̊Î_���ς��悤�Ȑ̓��̎v���͎c��A�Ȃ��������Ȃ��琌�����ڂŗ����Ă䂭�Ԃт��ǂ��B����A�f�ʂ̎��͂��̎U��ۂ̍�����������ƌ��߂Ă݂��B���ɂ������ꐶ�����Ɉ�ւ̉Ԃ͕����܂��Ɨh���̂����A����ɑς����˂Ă��̒��̈ꖇ�̉Ԃт炪�����Ă䂭�A�����ł͂��낢��Ȋ��S�����邾�낤�B�����V���ȗ������Ƃ��Č��C�Ɍ����邱�Ƃ��悵�A�����̂̒��Ԃ�����U��Ԃ���悵�A�܂��A����҂́i���͎��̂��Ƃł��邪�j�ڌ��肵�Ă�����s�̗a���ʒ����v�������ׁA����҂͎����̐l�����̂��̂𓊉e������B
������ɂ���A�����̓��{�l�ł���w����Љ�l�ɂƂ��āA���̍��͐V���������}�S��V���ɂ���B�����ɊG�ɏ������悤�ȍ����ڈ�t�ɍ炫�ւ�B�����Ă���BGM�ɂ͖ړ���M�����鐔�����̖��Ȃ����܂�Ă���B�ߔN�A�Ԍ��ɖK���O���l�̑����ɂ͋�������ł���B�ނ�ɂ́A���t�̐�����`�����̉Ԃ̂͂��Ȃ���@�ׂ��A����ɂ܂�镨��Ȃǂ́A�����͈̔͂ɋy�Ԃ�������Ȃ��B����Nj��ɋ����A�傢�ɏ��A�傢�ɔY�t�A���̐ɕʂ̎��ɍ炢�Ă������ɑ��鈤�ɂ̏�̒��ɂ܂ŁA�O���[�o�����̕��͂ǂ����Ă����荞�ނ��Ƃ��o���Ȃ��B�����炫�U���Ă䂭�A���̂��ׂĂ̎����͖��₩�ȐS�̕����A���{�l�ɂ���đn��ꂽ���{�l���������L����Z���`�����g�Ȃ̂�������Ȃ��B
2008.03.31 (��) �������̃n���C
����A���̐�"�Ă�Ƃ����̃T���o"�̃q�b�g�ŗL���������`�F���b�V�����A�v�w�Ńn���C�̃R���h�~�j�A���ɏZ��ʼnp��̕�������Ƃ����ԑg������Ă����B�X�[�p�[�œ����n���̐l�Ƃ̂����ȂǁA���ۂɗǂ��g�������ɖ��������p��Ȃ̂łƂĂ��ʔ��������B��������āA37�N�O�̂��ƁA�n���C�̃q���g���E�n���C�A���E���B���b�W�̒��ɂ������_�C�A�����h�w�b�h�E�A�p�[�g�����g�i���̓^���[�ƂȂ��Ă���j��20���Ԃقlj߂����������v���o�����B�������������邱�Ƃň����グ�悤�Ƃ����̂����A��������̂悤�Ȃ������Ɖ��܂�d�C�R�����Ȃǂ�����߂��A���ǃn���o�[�K�[���̃W���b�N�E�C���E�U�E�{�b�N�X�̏�A�q�ɂȂ����B�}�J�n�E���@�[���C�ɂ���������{�̓���C�L�L����n�i�E�}�E�x�C�ւ̃T�C�N�����O�A�A�p�[�g�����g�̉��ɂ���Ă����ړ��V���n���A����Ȃ��Ƃ��v�������Ă��邤���ɖ����ɐ̂̃n���C�����������Ȃ�A���̍����������G�����B�X�́u�u���[�E�n���C�v��DVD���ܗǂ��o�[�Q���E�v���C�X�ɂȂ��Ă����̂Ŕ����Ă݂��B
����������Ə�����������ł��낤���A�{���ɋv�X�Ɍ���u�u���[�E�n���C�v�͂���ł����ƌ����قǐ��X�̃q�b�g�Ȗ��ڂŁA���Ă��Ċy�����B���̉f������������ɃG�����B�X�͑��̉���������}����B�f��̒��̗��l�}�C��������Ă���^���Ԃ�MG�EA���_�C�A�����h�w�b�h������J���J�E�A��ʂ���A�����A�i�Ɍ����đ���B���̓r���ɕ����s������Ă���̂����A���̍��͐��傫�ȋL�����Ă���B�܂����[�J���F���ڂ̃z�m������`�A�����������鐶�Ԃ̃��C�������Ă���������Ȃǂ��h��B
�ނ̉f��炵���A��ɂ���ăX�g�[���[�Ȃǂ͂ǂ��ł��悭�A��ɃG�����B�X�̑f�G�ȉ̂��肫�̐t�f��ł���B�l�ӂ𑖂�Ԃʼn̂�"�I�[�����X�g�E�I�[���E�G�C�Y�E�g���["��₩�ȃI�[�v���J�[�ŏ��w�������Ɖ̂�"���e�̏�"�A�����ł��D���ȃV�[���́A�}�C���̂��k����̒a�����ɔނ��I���S�[�����v���[���g�����ʂ��B���k���W���J����ƁA����"�D���ɂȂ炸�ɂ����Ȃ�"�̃C���g�����I���S�[���̉��ŗ���n�߁A�G�����B�X���̂������Ƃ����S�������o�B�g���J�E�t���E�x�C�r�[�h������A�g�A���n�E�I�G�h������A���ꂼ��̋Ȃ������ɃJ�b�R�悭�����������邩�̔��Q�̉��o�͂́A�����F�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�ŋ߂̎��͋L���Ɏ��M���Ȃ����Ă��āA���X�v���Ă����̂Ƃ͈Ⴄ�W�J�ɋ������Ƃ�����B����Ɠ����Ɏv��ʔ���������B��e���̃A���W�F���E�����Y�x���[��TV��"�W�F�V�J������̎�����"�̃W�F�V�J��������A���̎��ɂ͋C�ɂ����߂Ă��Ȃ������X�p��o�D�����Ă��镞�A�Ԃ�X�≻�ϕi�̗ނ܂ŁA���̎���ɂȂ��ĉ��������Ȃ������̂��|�c���Ǝʂ��Ă����肷��Ɗ������Ȃ�B
�ߔNCG�̖ڊo�����i���ŁA��������Ă����ȂȂ���l���������A�ˋ���W�F�b�g�퓬�@���X�̒���F��������肷��悤�Ȃ��ƂȂǂ͗e�Ղ��o����B������f���Ɋւ��Ă͕s�\�ƌ������t�����Ă͂܂�Ȃ�������}�����B�ŐV�Z�p������ł����Ǝ��X�ɋ������A�ς�҂������̘A���ň��|����B����ȉf��ɖO���Ă����͎̂������ł͂Ȃ����낤�B���̌Â��ǂ�������v�킹��f���́A���̎��̐l�⒬�⏍�����邪�܂܂̎p�ł���B�����ɂ͑f�̔��������E������A�D�������₩�Ȑl�X�̐S���h��Ă����B�����Č���҂��ׂĂ̐S�̑��ɑ��̊Ԃ̖����E���f�������Ă���B
2008.03.24 (��) �ŋ߂̎Ԏ���
���ɍ��Y�Ԏj��ŋ��Ƃ�������Y��GTR���X�𑖂�n�߂��B���N�O�܂ł͍��Y�Ԃ̔n�͂͂Q�W�O�n�͂�����Ƃ���Ă����̂����A�z���_����ɔn�͂̏���������Ȃ����B����GTR�͂Ȃ�ƂS�W�O�n�͂Ƃ��������X�^�[���݂̃p���[���ւ�B�[�������A�܂�O�`�S�O�O���[�g���ɗv���鎞�Ԃ͂������̂P�P�b�U�Ƃ����������ł���B����͂ǂꂾ���������ƌ����ƁA�����𑖂邱�Ƃ��Ȃ����[�V���O�E�J�[���̑����Ȃ̂��B���������̒l�i�͂V�O�O���~��Ƃ����B��ʓI�ɂ͍����ł͂��邪�A�����̐��\��L����ԂƂ����ŐV�̃|���V�F�X�P�P�^�[�{�Ƃ��A�t�F���[���̍ō���N���X�ɂȂ�B���̃N���X�͂��̔{�̋����x�����Ă����ꔃ���Ȃ��A�v�����GTR�͂ƂĂ������������\�ԂƂ������ƂɂȂ�B���̎Ԃ̔����͐��E�I�ɂ��Z���Z�[�V���i�����B�ȑO�g���^�̃Z���V�I���������ꂽ�Ƃ��́A���̐Â����Ő��E���A���ƌ��킹���B�h�C�c�̍����ԃ��[�J�[���������������グ�A�o���o���ɂ��Ă��̐Â����̔閧��T�����Ƃ����B���A���[�^�[�ƃG���W�������������n�C�u���b�h�̃v���E�X�����̊v�V�ƌo�ϐ��Ő��E�����������B�����ŎԎY�Ƃ̏����̖������������̂ł���B�����č���A�h�C�c���ɂǂ����Ă����Ȃ�Ȃ��������������\�̃W�������Ő��E�ɖ������グ���B�������ē��{�̎����ԎY�Ƃ͈����ď�v�ʼn��Ȃ��Ԃ���A������㏞�Ƃ��鍂���\�ʂł����E�̃g�b�v���x���Ƃ��ČN�Ղ���ɂ��������킯�����A�ԍD���̓��{�j�q�̈�l�Ƃ��Ăǂ����Ă��~�������̂����������B����͉₩�ȗ��j���ւ郈�[���b�p���ɑ���u�����h�͂ł���B
�g���^���K���ɂȂ��ă��N�T�X�������u�����h�Ƃ��Ĕ���o���Ă���BJAL�̏㓙�ȋq�����p��������E���W�̂悤�ȃV���[���[���A�����ł̓I�[�i�[�����̌e���̏�A�҂����킹�̏�Ƃ��Ă����p�ł���B�����č��̃X�[�c�ɐg����ŏ�i�ȕ����������]�ƈ����҂���B���鎞����Ȃ��Ƃ��������B���钬�̃V���[���[���ł��̃L�����Ƃ����]�ƈ�����������ɐ[�X�Ɠ��������Ă���V�[����ڂɂ����B���͂��̂��q�ł��鏬������̃t�@�b�V�����ł���B�T���_�������ŁA���ƂȂ�̉ƂɎ}���ł��͂��ɍs���悤�ȗl�q�ł������B���ꂪ���̍��̈�̕����ł��茻��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂����A�����ň�̒�Ăł���B����������Ƒ����őP�̓w�͂����č������ŋq�����̋C�ɂ����Ċy���܂��悤�Ƃ��Ă���B����Ȃ�q�������ꂽ�V�ѐS��傢�ɔ������āA���̕���Ŏ���ɂȂ��Ă͂ǂ����낤���B���N�T�X�̎Ԃ����͂�����̂Ȃ�v�C�̈ꑫ�������Ă��邾�낤�A�������邩��A�q������ǂ�Ȋi�D�ł��ԓx�ł����܂�Ȃ��ł́A���{�̃I���W�B�̕i�i���オ��Ȃ��B
���������A�u�����h�͂�������L������g�����肷��q���n���Ă���̂ł���B�G�����X�̃P���[�E�o�b�O������A����n�ʂ̐l��m���l����������p���Ă��邱�Ƃ��u�����h�ɂȂ�Ⴊ�܂܂���B�܂��͎����葁���ATPO�̊�{�ł���g�����Ȃ݂ƃ}�i�[���疁�����B�������{�ł́A�`�����d�鐢�E�̃u�����h�ł��A������g�p����y�����i�ȗ����U�镑���œx�X�䖳���ɂ��Ă��܂����Ƃ�����̂��������B���{�̊�Ɠw�͂������܂ŗ���A��͋q�����̂ق�̂����₩�Ȏ��o�ł���B���E�ɖ������郈�[���b�p�ԃu�����h�ւ̊y���݂ȓ��{�̒���́A�����ŐV���ȓW�J�������͂��߂Ă���B
2008.01.25 (��) �t�̎U�����a��
�Ėڟ��̍�i�ɁA��g���ɂ̓ǎғ��[�i���o�[�����ɋP����"������"�ƁA�قړ����ꏊ�𒆐S�ɕ��ꂪ�i�s����"�O�l�Y"������B�i�n�ɑ��Y�̖{���E�G�ł�������݂̂Ƃ��낾���A�̂ǂ��ȏt�̓��̈����I��ŁA�ēc�B�O�N��"�Ԃ��e�@�t"�A"������"�ɏo�Ă���搶��"�O�l�Y"�ɂȂ�ς���Ă��̘b�̕�����U��̂͂ǂ����낤�B���̒n���Ȃ邪�䂦�A���낢��X�^�[�g�n�_�Ŗ������̂����A�܂��͒n���S��y���ō~��邱�Ƃɂ��Ă݂��B���D���ł��獶�Ɍ������I����������ďt���ʂ�ɏo��B��������ɏオ��B�O�㓿��ƌ��̓���E�t���ǂ̓����ɔq��A�₪�ē`�ʉ@�����_���E�ɓ���B�������炷����̍����ɉi��ו������܂��������x���A�����̌|�\�l���Z�݁A�����ߑ�I�Ŋi�������������Řb��ɂȂ�����������Y�̐���}���V����������B�ׂɂ͍����E�O��Ƃ̑傫�ȉ��~������B���ʂ̓`�ʉ@�ʼnƍN�̕�ł��鉗��̕��̕��A����ƈ��̕���Q�q�A�ǂ�����h�Ȃ̂ł��Ȃ葑���ȋC�����ɂ�������B���̂ق����l�E��Ƃ̍����t�v�A�ēc�B�O�Y�A�i��ו��A���{��Ƃ̋��{�����Ȃǂ̕悪����B
�����̂�������Ɏ����ʂ����c�t��������B����̓S�̔��������A��������ɂ����̗R�����邨��Q�̉����A�v�������葖�蔲���ċߓ������邱�Ƃ����̒ʉ��̓��ۂ������B�����̂Ƃ����������A���̖�̑O��"�\���̐l�ɏ\���̕ꂠ��ނ��A�䂪��ɂ܂���ꂠ��Ȃނ�"�Ƃ������t��������Ă����B�����Ő��肵���������҂��Ă����ꏊ�ł�����A���݂Ȃ�������Ă����̖ʉe������̂��Ƃ̗l�Ɏv���o���ꂽ�����������B�����m�̒ʂ�A�`�ʉ@�Ƃ͉���̕��̉����ł���A���̉��ɉ��X�Ə\�ꕶ���������B����o���炷�����ɉ���B�₪�č]�ː}�ɂ��o�Ă���L���Ȍ͂ꂽ���N�̑�������Ă���B�E�ɓ��{�̗��������Ƃ̑���ł������Ԗx�Ƃ�����B
���̐����[�g����ɂ�"�Ԃ��e�@�t"�ɂ��o�Ă�������i��ׁi�������������Ȃ�j����@������B�`�ʉ@�̊o�R��l�����ʍ�i���̑P������Ǝv����j�ŏo��������ڏG��A�ˊo��}�̎�m�̑����i�̕����ւ̓�����������B�ނ͉@�ł̏C�s�̍ۂɐ����ɕ����Čς̐��������A������y�m�Ɍ�������B�b�g�Ȃ��畧�����u�������Ƃ��ӂ��������֒��d���Ă��܂����Ƃ����b�B�����̐Δ�ɂ͌ς������Ɗi������������Ă��āA���̈Ⴂ���ʔ����B��l�͂��̐S�����������K�i�ق���j�𗧂āA����A�����Ƃ����B���ꂪ���̑����i��ׂ��B���ׂ̗ɍK�c�I���╶�A���������ɋ{�����Z��ł����B�ׂ̑P�����̖�Ȃǂ͍��������̐��Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ���V�N���B
����"������"�ɏo�Ă���搶�̈ꐶ�����E���邱�ƂɂȂ������h��́A���N�̖Ət���ʂ�̂��傤�ǒ��Ԃ�����ɂȂ�B���݂̒n���͏��ΐ�ڂƂȂ�B���ꂩ��搶�����h�ɋA�鎞�ɂ����ʂ�������ɂႭ���i���o���j�́A��̉��̒ʂ���E�ɍs���Ƃ���B���̖��̗R���́A���l�ɖڂ��������V�k���F��ɗ������A�s���Ɏv��������̉E�ڂ�^�����B�V�k�͂���Ɏ����̍D���̂���ɂႭ���������Ƃ������Ƃł��̖��������Ƃ����B�������قLj��Ղ����A���̖����ʔ����̂Ł��Ƃ��Ă������B�搶�͕\�傩�珬���ȗ���֔������Ǝv���邪�A���͗��傪������Ă���B����܂ł̂Ƃ���͟����n�߁A�i��ו��A�e�r���A�����t�A�ΐ��ؓ��̕��l�������D��ŕ��������Ƃ���Ă���B
����ɂႭ�����łĂ܂������i�ݔ��R�ʂ��n���č��ɍs���Ɣ����t�̔肪����B���ꂩ�牽�ł������Ă���f�B�X�J�E���g�E�V���b�v�̃I�����s�b�N���z���ĉE�ɓ���Ƒ傫���Ȃ����ċ}��ɂȂ�B����炵�Ȃ��瑴����o�肫��Ɛ��В��ɂȂ�B��t�͂������̖{���ɔ�����e��ɂ��Z��ł������A�����ɉz���Ď��M����������B���̎O�l�Y�Ɣ��H�q���n�߂ĉ�b�����L�c�搶�̎؉Ƃ�����A���������_�ɘb�����B���̒n�͟��Ύ��g�������v������̂������Ǝv���A��ʖɑ���������ł̓�Ԗڂ̋���ɂ��Ȃ����ՐÂȏZ��X�ł���B����̊w�҂������Z��ł������Ƃ�����A�w�ҊX�Ƃ��Ăꂽ�������B���������̐Â��Ȍ����ŕ��w�̋�C���z���ċx�e�A���炭�s���ƌ���ʂ���܂������ɂł�̂ł���������B����ʂ���オ��{���ʂ���E�ɍs���A�O�l�N���ʂ��������m�A����E�O�c�Ƃ̓���̐Ԗ�Ȃǂ�����B
�{���O���ڌ����_�ɂłč��Ɂi�E�ɍs���ΐ^�����̐搶�̉ƂɂȂ�j�B�Ԃ�"�w�i����ȁj�n�}"�̐V�h�̎ŋ��ŁA������ł������̌|�҂��ӂ��Ăяo���A�̂ɂ��Ȃ��������V�_������B���͎��B�̐Ȃ�肢�̊G�n�ň�t�ł���B����������t���ʂ�����ɁA�܂��s���ĂȂ����͊��@�����w�B�O�H�̑n�n�ҁA���푾�Y�̉��~�ł���B"��y�͔L�ł���"�̈�߂ɑ�������̊��j�݂̂悤�Ȋ�]�X�Ƃ�������Ă���܂��ɂ��̐l���̉Ƃł���B�v�͐_�c�̃j�R���C����v�����p���l�̃W���T�C�A�E�R���h���Ŗ�������Ɍ��Ă�ꂽ�B���Ɍ����ȗm�ٌ��z�ŊK�i�̎肷��A���̎O�A�A�[�`�A�O�ǂ̒����A���F�Ƌ��̋��Ԃ̗R������ǎ��ɂ�����܂ł��ׂĂ��f���炵���A�{�����e�B�A�̏f�������J�ɐ������Ă����̂��������B�܂��ɂ��̎���̉h���Â��B
���ꂩ��r�V�[������āA�s�E�r�ɕ����ԕٓV���ɎĘB�̉e�@�t�̈��r�Ȃ��߂��v���o���Ȃ���A���̎R��o��O�l�Y��F�l�̗^���Y�������H�����y���A���Ȃ��݂̐��{���ŁA�[�������Ȃ��獡�N�̂����₩�Ȋ�]�ƌ��ӂ���ɁA�����ƔM���Ŕ���������̎U���̑ł��グ�͂ǂ����낤���B
2007.12.28 (��) �V�˃A�X���[�g�ƐS���܂�b
���N��N��U��Ԃ�A���́u�ЂƂ育�Ɓv�ł͂̂Ȃ��Ƃ��������������A�����ł͋ߔN�܂�Ɍ����ςȈ�N�������B���N�����͂����N�ɂȂ�܂��悤�ɂƊ肤�������̍��A���킽�������N�̐��ɓ���[���̌��t�Ƃق��Ƃ���b��B�ݕĂ̏����S���t�E�W���[�i���X�g���A�����V���Ƀ^�C�K�[�E�E�b�Y�̂��Ƃ�"�V�˂䂦�̒m���̐[��"�Ƃ����^�C�g���ŏ����Ă����B�����ǂ�łȂ�قǂ������Ă��܂����B���A�S�Ă�h�邪���g�p�̘b��A�ނ̏����ȍ��̎��A�ăc�A�[�̏o�����ȂǁA�E�b�Y���������I�m�Ȑ[���m���������Ă��邩�炱���̌��t��s�����Ԃ��Ă���B���̍Ō�̏͂ɁA"�E�b�Y�͐��܂ꂽ�Ƃ����獋�ł�łĂ��킯����Ȃ��B�ǂꂾ���������d�ˁA�m���𑝂₹�邩�B�ǂꂾ���b�B�Ɠw�͂𑱂����邩�B���̔\�͂������Ă��邩�炱���A�l���G�ł邱�Ƃ��o����B�V�˃A�X���[�g�̖{���́A������\�͂��V�˓I�ł��邱�ƁB���҂����҂���䂦��"�B�ƌ���ł���B������������莄�ɒu��������Ȃ�A�}�l�̖{���͎�����Â₩���\�͂��V�˓I�ł���Ƃ������ƁB�����ď�ɍŏ��̓w�͂ōő�̌��ʂ�_���A���R�Ȃ��炻�̐��ʂɂ������]����B���ꂪ�}�l�̖}�l����䂦�A�ƂȂ��Ă��܂��B
���ꑽ�����A�������̃W���[�i���X�g�̏͂Ɉꌾ������Ȃ�A�b�܂ꂽ�̗͂��ێ����A����ꂽ���Ԃ̒��ł����ɗL���ȓw�͂����邩�Ƃ������t�肽���B�������\�͂̒��Ɋ܂܂�錤���ƒm���A�w�͂̌p���B�Ȃ����}���i�[�Y�̃C�`���[�I�肪���ɕ�����ł���̂́A�ނ�����ɍł��߂����{�l�A�X���[�g�̈�l�Ȃ̂��낤�B�E�b�Y�ƃC�`���[�ǂ�����V�˃A�X���[�g�ł��邪�A���̓�l�ɂ͒N�ɂ������Ȃ���Ȃ��̂���������邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͓�l�̃S���t�Ɩ싅�ɒ������ꂼ��̈���A���Δ������ꋉ�i�ł���Ƃ������Ƃ��낤�B
�A���̂���Ȏ����⎖�́A����̈���ٔF���P���l�B�̐g����ȓV�����ڑҒЂ��B�l���݂�����d�Ԃɏ��ƁA�ȑO���Ί炪���Ȃ����ƂɋC�t���B�i���g��ň�ԑ傫���Ȃ����͍̂��ƍ����̍��ł͂Ȃ����낤���B�����ł���ׂ��V���̐e�ʂ�����A�ƍِ����i���ׂ̘̈A���\�z�B�ނ͉ߋ��Ɉ�Ԃ����Ԃ܂Ŏl�ԃo�b�^�[��~���W�߂������s�����B�����A�����A������Y�n�U���̊�Ƃ�����ł����ƒ@�������A����Ǘ��E�w���̊Â����̐ӔC�͖��Ȃ��}�X�R�~�B�ǂ��ł����������X�|�[�c�}����|�\�l�l�^��ǂ������A����J��L���閯��TV�̂����܂����K�L�����ԑg�̗���B��`�O���܂��ɑ呛�������^�f�̌o�c�A�̒��̘b�����s�^���ƌ����ɖ����Ȃ�B����ȗ����̍��̕���͉����x�𑝂��Ă���B
����ȓ��X�̒��ň�������̐S���܂�o�������������B�ꏊ�͐V�ڔ��ʂ�̍��ˋ�����s�d�ƕ��s���đ��铹�ł̂��ƁA���͂����̂悤�ɎԂō]�ː싴���ʂɌ������đ����Ă����B����ƑO���痈�鎩�]�Ԃɏ�����x�@�����A�}�u���[�L�������Ď��̎Ԃ������ƌ��Ă���B����Ⴂ���܂������̂ŋC�ɂ͂Ȃ������A�ʂɍ��}������ł��Ȃ��̂ł��̂܂ܑ��苎�����B���炭���ăo�b�N�~���[�œ_�̂悤�ɏ������Ȃ����ނ�`���ƁA���������ƂɁA�ԑ̂����E�ɗh�炵�Ȃ��炸���ƑS���͂Ŏ���ǂ��ė��Ă���B���傤�ǎO�ڂ̐M�����ԂɂȂ荶�ɊĎ~�܂����B����Ɣނ��ǂ����n�[�b�n�[�Ƒ���炵�Ȃ���A"�V���I �V�����t�����g�O�����ɒ���t���Ă��܂��B�I�[�o�[�q�[�g�̌����ɂȂ�܂��̂�"�Ƃ킴�킴���S���[�g����S���͂ő����Ēm�点�Ă��ꂽ�B�ނ̈�r�Ȗڂ����āA�܂��܂����̒��̂Ă����̂���Ȃ��Ƃق��ƐS�~����v���������B�����������Ȃ��A�����Ȃ����Ȏ�`�Ƃ��������������������鍡�̐��ɁA����Ȑl�����܂ł��K���ł��ė~�����Ɗ肤�B�˒ˈ꒚�ڌ�Ԃ̎Ⴂ���܂�肳��Ɋ��ӁB
2007.12.04 (��) ���낢��Ȕs�҂���
����A����}���قŘZ�N�O�ɏ����ꂽ�V���l��W��ǂB���̒��̈��"���낢��Ȕs�҂���"�Ƃ����^�C�g���ŁA�����̃{�N�V���O�̂��Ƃ�������Ă���B��A�t���J�ōs�Ȃ�ꂽ�����ŁA�Ⓒ���ɂ���A������͂����Ȃ��Ƃ���ꂽ�p���̃`�����s�I���A���m�b�N�X�E���C�X���܂�����K�O�������i�����Ƃ����b�B����ƂƂ���74�N�ɍs�Ȃ�ꂽ�������p����`���ɂȂ������n���b�h�E�A���ƃW���[�W�E�t�H�A�}���̎����̂��ƂɐG��Ă���B���̐S�ɍ���̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o����鎎���ł���B�����A�t���J�嗤�̃U�C�[���E�L���V���T�ōs�Ȃ��A����܂��Ⓒ���ɂ������`�����s�I���̃t�H�A�}���͂S�O�햳�s�A���ۂɔނ̎�����TV�Ō��Ă������͐����j���o�Ă����ȂƎv���Ă����B�ۂ����|���Ƃ���ꂽ�ނ̃p���`�̈З͂͂����܂����A������˂��グ�����Ԃ��͑O�`�����s�I���������W���[�E�t���C�W���[�̑̂�e�����S���l�`�̂悤�ɕ����オ�点���B�����炭���̌�Ɍ��ꂽ��b�̂悤�ȃ}�C�N�E�^�C�\�������̎��̃t�H�A�}���ɂ͕��������낤�Ə���Ɋm�M���Ă���B�����⒥�������ۂ��A�`�����s�I���E�x���g�D����A�T�N���̃u�����N��]�V�Ȃ�����Đ�����߂����A���B�N�����t�H�A�}���̈��|�I�ȏ������^��Ȃ������B�����Ď������n�܂胍�[�v��w�ɋ���ȃp���`���������V�Y�A�����W��A�����Ƒ̂����ւ������c�[�Ńt�H�A�}����|�����B���ꂪ"�L���V���T�̊��"�Ƃ��Č��`������B�A���̈ꌂ�̓t�H�A�}���̐l�������ł��ӂ����B"�{���ɋ��낾�����B�^�C�g���������������ł͂Ȃ��B�l�ԂƂ��Ẳ����ؖ�������̂܂Ŏ������̂�"�Ɣނ͎��`�̒��ʼn�z���Ă���B
�����āA���̓`���̎������ӎ����ăA�t���J����]���AKO���ꂽ���C�X�͋���Ȗڂ� "���������A�����N�����̂�"�Ƃ����������Ƃ����B����ɔ���Ȃ��Ƃ͓��̃t�H�A�}�������̎����̉���҂ł��������ƂŁA���C�X��"���S�A���M�ߏ肾����"�Ɛ��Ď̂Ă��B���͓����̂��Ƃ��v���o���Ă����B�Ȃ��A�A�t���J�̂ւ��ƌ�����L���V���T�Ȃ̂��A����͎j��ŋ��̓�l�̍��l�{�N�T�[�̗y���Ȍ̋��ł���A���̃w�\�i���S�j��I���Ƃɂ��̎����̈Ӗ����������̂ł͂Ȃ����낤���A����͓�l�����̐킢�ł͂Ȃ������Ǝ��R�����E���Ă����A�����J�̗��j�Ƃ̐킢�ł��������Ƃ������Ƃ��B�����āA���̂Q�O�N��ɖ{���̊�Ղ��N����B�s�҂ł������t�H�A�}���͎��M�r���̌��ʁA���]�Ȑ܂����Ėq�t���o������̂����A�L���V���T����Q�O�N�o�����P�X�X�S�N�Ƀ}�C�P���E���[���[�ɏ����A�Ăуw�r�[���̃`�����s�I���E�x���g�������Ƃ͒N���\�z�ł������낤�B
�����i���S�T�Ƃ�������`�����s�I���̓t�H�A�}���������Ȃ����낤�B�����ĂP�X�X�V�N�P�P���Q�Q���V���m���E�u���b�N�X�ɔ��蕉���ŁA�Ăєs�҂ƂȂ��Ĉ��ނ���B�h��������܂̂Q�O�N�ԁA�Ȃɂ��ނ�����܂œ˂����������̂��낤�A���̃L���V���T�̔s��̎��A�t�H�A�}���͂����������Ă���A"�����̒��̐c���A�����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����悤�ȋC������"�B�t�H�A�}���ɂƂ��Ă��̎����̒��̐c��T���������Q�O�N�������̂�������Ȃ��B����ȑz�����߂��炵�Ȃ���Â��ɖ{������B�����Ď��̓��ATV�̃��C�h�V���[�ɍ��x�͓��{�̔s�҂��f���Ă����B
�ǂ����Ĕ������s�Ȃ����̂��H "���܂�v���o���Ȃ��A�ْ����Ă���ł��傤"�B�������I������܂��̂��̂ł����H "�����A�̍D���₵��"�B����ȃ��x���̔s�҂��A�߂������ȁA�ǂ̃`�����l�����Ă��f���Ă����B�܂��ɂ��낢��Ȕs�҂����ł���B
2007.11.15 (��) �o��̕s�v�c�i�p�[�g�U�j
���Ԃł͂悭�l�̉^���͍ŏ����猈�߂��Ă���ƌ����邪�A����͌��ʘ_�ł���A���͐l�̏o���o�����͂��̏u�Ԃ̋��R���s������n�܂��Ă���ƍl���Ă���B���̐́A�����Z�Ə��߂ă��X�x�K�X�ɍs�������̖Y����Ȃ��o�����ł���B��s�@�͑�؍q�����B�V�[�g�x���g�̋���ɂ��̈ꐢ���r�����p���A�����J���q��̃}�[�N������Ă����B�悭�悭�����Ă݂�Ƒ�؍q�p���i���@�̒��Â�����Ďg�p���Ă����̂������B�r���n���C�œ����葱�������āA�L��Ȍ��̊C�̂悤�Ȗ�̃��X�ō������ɏ��p�����B�����܂ł������^���Âȍ����ɍ��R�ƐԂ���Y��Ȍ��̌ł܂肪�͂邩�ޕ��Ɍ����Ă����B�^�钆�ɕs���̃��X�x�K�X�ɓ����B
�����������X�x�K�X�̓t�[�o�[�E�_�����݂ɂ���������H���W�҂̈Ԉ��ׂ̈ɑ���ꂽ���̂������B�����ōŌẪz�e���ł���t���~���S�E�q���g���ɒ������̂͌ߑO�R���A�C�����Ԃ��Ė���ɂ����ꂸ�A���鋰��J�W�m��`���Ă݂邱�Ƃɂ����B��͂肱���͐^�钆�ɂ�������炸���Ȃ�̓��킢�������Ă����B����߂��̒��A�_�����I�������炵���傫�Ȑ����グ��j��A�w���̑傫���J���������O�E�h���X�𒅂����������̉₩���A�ԃ^�C�c�łɂ��₩�ɂ�����^�o�R��z��Z�N�V�[�E�K�[���A������̂��ׂĂ��ڐV���������̘A������������Ȓ��A�^�����ȃT�}�[�W���P�b�g�𒅂āA��l�|�c���ƃu�����h�̏����f�C�[���[����Ƀ|�[�J�[�����Ă��鏭�N�̂悤�ȓ��{�l�炵���j�������B�O���X�Ў�ɂ��Ȃ肻�̕��͋C�Ɋ���Ă���l�Ȕނ͂����Ǝ��̊�����߂Ă���B�����Ă����Ȃ萺�������Ă����B���˂��N�I ���̎��m��Ȃ��H���ł���B
�^�钆�A���X�x�K�X�̃J�W�m�Ƃ������߂Ă̏ꏊ�ł��Ȃ�C��ꂵ�Ă����\�̎��́A�����ƌx���Ő����o���̂�����Ƃ������B�d�����Ȕނ̊���܂��܂��ƌ��߂��̂������o�����Ȃ��B������A�m��Ȃ����Ɠ�����ƁA�ނ͏�݊|����悤�Ɋw�Z�͉����A���̑O�́I�ƕK�v�ɐH��������A�Ƃ��Ƃ����̏o�g���w�܂ł����̂ڂ��ĕ����B�������ǂ����Ă��ړ_���Ȃ��炵���A����ł��ނ́�����A���͐�ɌN�ƈȑO�A�������ʼn���Ă��遄�ƌ������B���ꂩ��͔ނ̔��͂ɏ������������͋C�ɂȂ�A���͍����߂ăA�����J�̖{�y�ɗ������ƂȂǂ������ĕʂꂽ�B����ȃC���p�N�g�̂���̌������āA�z�e���̒���ɏo��Ƃ������̌��������Ă����B
�����āA���̓���ɕ��ƕ�̓�l�œ������X�x�K�X�ɍs�����B�Ȃ�����Șb������ƃM�����u���D���̂ǂ����悤���Ȃ���Ƃ̂悤�����A���܂��ܕ������X�x�K�X�E�c�A�[���̃S���t����ɂȂ�A�����z�e���ɂ܂Ƃ܂������������a����Ίi���ȗ��s�̓��T�����Ă����̂������B�����ēq���������Ȃ����e�̓V�[�U�[�X�E�p���X�̃_�C�A�i�E���X��MGM�̃V���[�Ȃǂ��y���i�]�k�����_�C�A�i��m��Ȃ���͈����T�C���܂ŖႢ�A���̊��z��"�������̂̎|���₽����̐l������"�j�B�����ē�����ԑ傫���������X�x�K�X�E�q���g���̃x�j�n�i�̃��X�g�����ŐH�������Ă����̂����A�ڂ̑O�œ��{�l�R�b�N���J��L���郊�Y�~�b�N�ȃV���[�̂悤�ȕ�ق��Ɋ������A����܂ł��ĈӋC�����B���낢��Șb�Ő���オ��A�R�b�N����̏o�g�n�Ɏ���܂Řb���y�炵���A����Ɠ����̉�Ƃ̗ג��̏��ΐ�Ƃ̂��ƁA���͖��Ƃ������w�Z�͎��Ɠ������x���w�Z�̈�N��ŁA����m���Ă��鏬�ΐ�X�ǂׂ̗̃��E�{�[�O���e�@�̖����q�������B�A���Ă���Ȃ�ꂪ���̈ꕔ�n�I��ʔ������������ɘb���ĕ��������B���̎��A���̓]�N���Ɛg�k�����Ȃ��烉�X�x�K�X�ɒ��������ɏo����������W���P�b�g�̒j�̎���N���Ɏv���o���Ă����B
�����̐l�͐F�����āA�����Ŕ��ɃE�G�[�u���������Ă���ڂ̑傫�Ȑl����Ȃ��H�� �Ǝ��������ƕꂪ�ڂ��ۂ����Đ^��ł��̒ʂ肾�Ƃ����B���̓^���ƕ�ɕ�������Ɠ�l�͊m�M�������ĊԈႦ�Ȃ����̐l���R�b�N�̖�쎁���Ƃ����B����ɂ��Ă��A�ނ����w�Z�܂ł����̂ڂ��ĕ����ď��w�Z�܂ł��ƈ���������Ƃ́I �����A�q����������w�N���S�N���X���T�N���X�����鎞��A�悭���ނ͈�N���̎��̏��w�Z����̊���o���Ă������̂��Ɗ��S����ƂƂ��ɁA����Ԃ��Ύ��̊O���͂��̍�����S�R�ς���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���ꂵ��������A��Ȃ�������̐S���������B�����Ă��̗����ɍĂю��̓��X�x�K�X�Ɍ������ӋC�g�X�Ɣނ�K�˂��B�ꂩ���쎁�ւ̎莆���x�j�n�i�̃{�[�C����ɗa���đ҂��ƂQ�O���I�ނ͐~�[���甒���X�q�����Ԃ葁�����̃K���}���̂悤�ɍ��ɕ��n�T�~�������A�܂�ŃX�^�[�̂悤���D�u�Ɠo��I ���������ď����ւ����悤�Ȕނ̈ꌾ�́A������ς�I ���̎v�����ʂ肾�����B���`���A�������肵���I���B ���̌�A���̏o�����͂��炭��Ƃ̌�葐�ɂȂ����B
2007.11.11 (��) �o��̕s�v�c
����̕ς��ʒ����t�������̒��ŁA�ߋ��ɋ��R�����ꏊ�ɂ�����A���ʂ̗F�l��m���Ă�����A�Ȃ�Ă����o�����������͂Ȃ����낤���A�ˑR����Ȃ��Ƃ�����ƁA�����傰���ɐl����^���̕s�v�c�Ȃ���������_���Ă��܂��B�Ȃ������͂��̉��Ƃ������t�Ɏア�A�l�����Ȃ��l�̌��т��͂Ȃ��Ə�X���������A�������R�ɉ^���������Ă��܂��B���̓T�^�I�Șb�̈�Ƃ��Đ���A�ԑg�����Ђ��o�c���Ă�������������В��ޔC�̒m�点���͂����B�Ⴂ�l�ɍ��̎��Ƃ�����A��艹�y�v���f���[�X�̎d���ɗ͂�����Ƃ̂��ƁB�v���ΔނƂ͕s�v�c�ȉ��Ō���Ă���B����͎����P�U�ŋG�߂͂��傤�Ǎ����������Ǝv���A�����A�a�J�̃��L�X�|�[�c�E�p���X���v�ۂ̎O����قȂǂŁA������Ƀ_���X�E�p�[�e�B�[���s�Ȃ��Ă������A�ȑO����ɏ��������w���ォ��̗F�lM�N���ƐX�c�N�i�{�l��������OK�Ƃ̎��j�����鎞�A���i�T�O�O�~�O�オ����̃p�[�e�C�[���̂R�{�̂P�T�O�O�~�Ƃ����ƂĂ��Ȃ����������y���痊�܂�Ď����Ă����B�l�J��"�t�����N�X"�Ƃ������{�Ђׂ̗ɂ������{�i�X�e�[�L�E�n�E�X���X���A���̏ꏊ�ōs�Ȃ�ꂽ�p�[�e�B�[�������B�Ȃ�ł�����"�t�����N�X"�́A���̐Ό��T���Y���햱�����Ă����Ƃ��ŁA�Ő����ɂ͉f���|�\�W�҂ł����ɂ�����Ă����Ƃ����B���̃p�[�e�B�[�͎q���i���̎�����݂āj�̂����ɑS�����_�[�N�X�[�c�Ő��o���h�A���t�Ȃ́u�t���C�E�~�[�g�E�E�U�E���[���v�Ȃǂ��{�T�m�o�̃A�����W�Ō��߂Ă���B�����̍��Z�����{�T�m�o���t�ł���B���v�������ԂӋC�ȃp�[�e�C�[�������B���͏����傫�߂̌Z�̈�{�^���̍��̃A���R���̃X�[�c�����U�`�b�v�̌C�A���F�̃P�[���[�E�O�����g���D���n�̃^�C�Ƃ����S�Ď蕨�̂��ł����ŎQ�������B���ݕ��͂ǂ�ɂ��A���R�[���������Ă����B�R�[���Ǝv���Ĉ����̂��S���Ⴄ���̍���̂悤�ȃn�C�J���Ȗ�������B��ŕ������ꂪ�W���R�[�N�Ƃ��A�e�̖ڂ𓐂�ň����Ƃ͑S���Ⴄ���̂ŁA���̒��ɂ���ȟ��������ݕ�������̂��Ƌ��������̂������B���͉\�ǂ���C���������ŁA�傫�ȃK���X�˂̊O�͍L���e���X�ɂȂ��Ă��āA�s���J���璷�������肫���������u�Ă����������ɂ́A�l�J�̍����т��L�����Ă����B�p�[�e�B�[�ł͐������j���ۃe�[�u�������邭��ƉA���X�ƒ����ꂽ�O���X�̎������̉��S�͂Ŏl���ɔ�юU��A����₷���Ȃ������ŗx���Ă������o����B���]�肵�āA���炢�����ɂȂ��Ă����B
��ɂ���đO�u���������Ȃ��Ă��܂������A����ȑz���o�̃p�[�e�B�[�ş������{�T�m�o�̃M�^�[���t�����Ă����̂���̍������ł������B���鎞�������Ƃ����̂悤�Ɏ�������ł��ĎႢ���̘b�ɂȂ����B�w������̑z���o�b�����Ă��邤���ɓ�l���Q���������̃p�[�e�B�[�ɍs���������Ƃ����킯�ł���B���̎��̓�l�͂܂��ɑ吺���グ�ċ�����ԂɂȂ����̂͂����܂ł��Ȃ��A���̌��т������ǂ�ƃp�[�e�B�[����Â������̍��Z�̐�y�i�]�k�������̐�y�̊������͗��悵�A���̌㓯�����ɂȂ莄�̐^���̐Ȃɍ��邱�ƂɂȂ�j�ƍ��������F�l�W�Ńo���h���t�𗊂܂ꂽ�Ƃ̂��ƁA�K�R�I�ɓ�l�͌��т��Ă���̂����A�m�荇���Ă��牽�\�N���o���Ă��炻��ɋC�t�����Ƃ����Ȋ������ĂсA�������R��傢�Ɋ�Ƃ�����ł���B�ȗ��A�V�����o�������ƁA�����̐l�Ǝ��Ƃ̉ߋ��̌��т��⋤�ʂ̒m�荇���͂��Ȃ����ƁA���ӎ��̂����ɒT���Ă��鎩���ɋC�Â����Ƃ�����B
2007.11.10 (�y) �X�|�[�c�̋K��ɋ^�╄
����̒��ؗ������ł̐���オ��́A���ɂ̃X�|�[�c�͂Ȃ낤�Ƃ����b����n�܂����B�ŋ߂̊i���Z�₢���Ȃ��̂��o�����A�ŏI�I�ɂ���͂P�O�O���[�g���������Ƃ����b�ɂȂ����B�Ȃ��Ȃ�Γ����I�����s�b�N�̗\�I�A�ǂ����ŋL�^�ɂȂ�Ȃ������{�u�E�w�C�Y�Ƃ�����j�����㋣�Z��ɂ��鎄�̖ڂ̑O�ŏo�����X�D�X�b�A�A������S�R�N�Ƃ�������������A�ȗ��l�ނ��ǂ�ȂɊ撣���Ă��O�R���}�R�b���k�߂��Ȃ��ł���A���ꂱ���l�Ԃ̌��E��m�鋆�ɂ̃X�|�[�c�Ȃ̂��Ƃ������ƂɂȂ����B���ꂩ��b��͐�̐��E����ɂ����̂ڂ�A���q�}���\���̓y���̍Ō�̔S�ɔ���I���̂ق����{�I��̊撣��ɂ�������炸�A���̍��Ă̏����ɂ���z����̏�A���̐��тɂ͈ꖕ�̎₵���𖡂�����͎̂��B�������͂ł͂Ȃ����낤�B�����⎼�C�����̂Ƃ����Ȃ����E���x���̋����͖{���ŁA���҂Ȃ���̂����������̂��Ɖ��߂ċ�����ꂽ�B����ɂ��Ă����������茞��A�i��̐D�c�̓��ɕX���悹�ė�₵�Ă���TBS�̂܂Ƃ��ȏ]�ƈ��͂��Ȃ��̂��낤���B
���̘b��ň�C�Ɏ����i��ł��܂����̂����A�F����͋C�t�������낤���A���Z��̃��[������g���Ȃ������̂��A�����͂W���[���ō���͂X���[���������B�����͂����W�l�ōs�Ȃ��A��ԓ����̂P���[���͏�ɋ����B���������Ǝv���邩������Ȃ����A�Ȃ�̂��߂ɂ���Ȃ��ƂɂȂ����̂��A����͑��̒����O���l�I��ɂƂ��ăR�[�i�[�̂����P���[���͕s���ɂȂ鎖�ł����Ȃ����̂��ƁA�ꏏ�Ɉ���ł������̗��㋣�Z�]�_�Ƃł������N���������B��X��ʐl�ɂƂ��āA���̊Ԃɂ����[�����ς���Ă����Ƃ����킪�X�|�[�c���Z�̋K��ł͂�����̂́A����͂����������{�I�肪���ӂƂ��邫���R�[�i�[���Ȃ�����͎̂ߑR�Ƃ��Ȃ��B���ʘ_�����A���ꂪ�Ȃ���Γ��{�j�q�̃����[�̓��_���Ɏ肪�͂�����������Ȃ��B�Ԃ�F1�Ńz���_���Z�i�ƃv���X�g��i���ď폟���������^�[�{���K�����A�X�L�[�E�W�����v�œ��{�I�肪���̊ۂ������Ă��������̒�����ς��A���j�̗�ؑ�n�̃o�T���j�@�ŏ������������A���A���������肻��Ȍア�Ƃ��ȒP�ɋK�����ς��Ă��܂��B�ߔN�A��э��炷���I��T�O���[�g���ȂǁA�ʼn_�ɑ����Ă������j���Z�̎�ڂ��C�ɂȂ�̂����i���̐́A�A�����J�̃}�[�N�E�X�s�b�c�I�肪�����_�����V����Ԃ牺���Ă����B����Ȕn���������Z�͑��ɂȂ��j�A�ŋ߂ł͍��Z�̏_���܂ł���{�����̌�ɋZ��������悤�Ȕڗ�ȍs�ׂ��܂���ʂ鎞�ゾ�B���ꂼ��̈ψ��̏�w���̊O�l���L�̃|�[�Y���Ƃ�Ȃ���܂������Ă錚�đO�͂�������A�N�������Ȃ�ׂ̈ɋK���ς���̂����̖{���̖{����m�肽�����̂ł���B
��������E����Ƃ͖�����ŁA�A�����J�͂��̖����ȓz�ꐧ�x�̗��j�ł킩��̂����A�t�����X�A�C�M���X���͂��߂Ƃ��郈�[���b�p�l�͔��l�ł͂Ȃ������̂��낤���Ƃ����P���ȋ^��ł���B������Z�E���E�������𑖂��Ă��郈�[���b�p�e���̑I��͂قƂ�ǃA�t���J�n���[���b�p�l�ł������B����͋ɒ[�ȗႦ�ɂȂ邪�A�Ñ�̃R���b�Z�I�ƌĂ�铬�Z��Ŏ����B�̉Ɩ��n��̊���̂ɕt�������A�ٍ������Ă����z���s�c�������𑖂点�����킹���肵�āA��������Ďs����M���������M�����Ă������[�}����̍Č��̂悤�Ȏ�ł���B�^�ŕ��𓊂�����A��蒵�˂��肵�Ă��锒�l�₲���ꕔ�̉��F�l����Ȃ��āA���̎���𑖂��Ă���̂͌��E���A�t���J�l���قƂ�ǂŁA���������Z�̏�ʂ�Ɛ肷��B���ƃg���b�N���Z�ɂ����č��l�I��̉^�����ԂɂȂ��Ă���B��������̂��̔w�i�ɂ͈ږ���e�ՂɎ���A���ꂼ��̍�����x�̈Ⴂ�𗝉����Ă̘b�Ȃ̂����A��͂�P���Ɍ��ĕςȌ��i�ł���B���̏����Ȉ��݉�̍Ō�ɁA�ߎS�ȕ���������A�R�����o�ϗ͂⑽���̏����ɔY�ރA�t���J�̍��X�Ɏv����y���A����ȃA�t���J�嗤�ň�x����������Ƃ̂Ȃ��I�����s�b�N�␢�E������J�Â��A�撣���Ă��鑽���̍��l�I�肽���̌̋��ɂ��̓����т����点�����Ƃ����z���Ƌ��ɁA�卑���i���̈ӎ����g�ׂ̈����ɂ���A���A�n�r����������X�|�[�c���Z�̋K����L�������Ȃ��̂ɂ���肢���������l�̌��_�ƂȂ����B�����Ă����̃V���̑�p���[�������ڂ̑O�ɉ^�ꂽ�̂������B
2007.09.09 (��) �V���Ɖ���̗r��
���������̎��̎n�܂�͒����̗�����ł���B�ȑO�A�k�����琼���Ɍ��������ɒ����E�������̐����q��ɏ�����Ƃ��̎��A�����̋q���斱���̖��͂ɋ��������Ƃ�����B���������ǂ��m��n�[�t�̐l�̔������ł͂Ȃ��A���߂Č���������Ȃ̂ł���B���̓u�����h�ɋ߂��A�ڂ̐F�͓����ʂ�l�Ȗ��邢�ΐF�ɃN���[���F�̔��A�痧���͒����̓��m�n�B����܂ŎႢ������̎d���ɉ������Ċ����̔��l�͌��Ă������肾�������A���̂悤�Ȕ��`�͏��߂Ă������B�ޏ��ɂ͓������m�̌�������Ă͂���̂��낤���A�A���O���T�N�\���n���������l��Ɏv�����B����ɂ��n���Č����������ċ����I�ɔ����`���������A�Ǎ��ŃG�L�]�`�b�N�Ȗ��͂�n��Ƃ�������B�ޏ��͂܂��ɂ��̓T�^�I�Ȑl�������B�����͍L������֍s��������A���u�n��g���R�n�܂ŁA�����̐l�킪����Ƃ킩���Ă����̂����A���̂�������l�̋�ŏo����������ɍL��Ȓ��������������m�邱�ƂɂȂ����B�����̘b��́A���̗��̂Ƃ��ɐ��S���[�g���ɂ��y��ʼn��䂪�W�܂��Ă��钆�̈ꌬ�ŐH�ׂ��r���̂��Ƃł���B�����܂ł��X���������̌����ȏ�i�́A���܂Ŗڂɂ������Ƃ��Ȃ��������A�Ȃ������D��U�����̂������B�ג����S�̋��ɂ��邭��Ɗ��������r����H��ɒu���ꂽ����̖ؔ��̒��̍��h�����~�肩���ĐH�ׂ�B�n���̋q�͂ǂ�����āA�c��Ȑ��̓����悤�ȓX�̒������̓X��I��ł���̂��l���Ă݂��B���ꂼ��̓X�̐e�����~�肩���鍁�h���̔����Ȗ��̈Ⴂ����̏Ă����ŁA�q�͓X��I��ł���炵���B����܂Ŏ��ɂƂ��ă}�g���Ƃ����W���M�X�J���ŁA�D�y���͂��ߒn���̍����ʼn��x�����킵������ǁA���̓��͂����̂������̓��܂ŕ@�̉��Ɏc���������肾�����B���ꂪ�����ł͖{���ɔ��������H�ׂ��A�����܂��H�ׂĂ݂����Ɩ{�C�Ŏv���Ă����B
���̋��Ă��r���ɓ��{�̑�v�ۂōĉ�邱�Ƃ��o�����B�������E��v�ۉw�ƎR�̎���E�V��v�ۉw�̊Ԃɂ���痢���Ƃ����X�A�����ł͗r���������������������{�����E�Ɍւ�I���G���^���E�^�E���̑�v�ہA�r�͂������̃��c����J���r�Ȃǂ�����������Ɏh���Ėڂ̑O�̒Y�ŏĂ��ĐH�ׂ�B�������M�ɓ������O��ނ̍��h�����w�ł܂�ŐU�肩���ďĂ��A�������̖�����邱�Ƃ��y�����B�ߔN�A�ǂ�Ȃɔ��������ē��ł������}���l�������Ă����Ƃ���A���̍ĉ�̖��͐V�������C�ɓ��������Ă��ꂽ�B
���E���ŏ������̒ʂ��������̖��͂������{�ŊȒP�Ɋy���߂�悤�ɂȂ����B���������[�J���̌��̋��������́A�܂��܂������ł������̖ڂ����Ă��Ȃ��悤���B�����o�����܊��̊����𗊂�ɁA���̑z���o�̖������̓��{�ŋC���ɒT���o�����͎��̊y���݂̈�ɂȂ��Ă���B���N�����邩�킩��Ȃ����܂��T���Ă��闿�����R����B�������悱���ł��Љ���Ă����������Ǝv���B
�嗤�̂Q���̓����銦��̉��A���ɕ�܂�Ȃ���H�ׂ����̗r���A��ŏo������ٍ�����ӂ��}�h���i�܂ŁA�������������h���v�ۂ̖邾�����B
2007.09.07 (��) ��������̑�
�X���S���A�������N���]�������ƂS�����ɂȂ��Ă��܂����B�Ǝ҂̎萔�������܂�ɍ����A�����ɂ��ċv�X�ɓ��̘J���������B�A�p�[�g�̎肷��̃y���L�h���ǂ̕�C�A�u�����̎�ւ��A�����̎��̌����A�ʂĂ͕֊�̊W�̎�ւ��Ȃǂ����ɂ܂݂�Ă���Ă��Ď��Ԃ�Y�ꂽ��������A�x�����H�̃~�b�N�X�T���h����n��̍���̋i���X�ő��̊O�����Ȃ���E��ł����B���傤�ǖڂ̑O�̑傫�ȃ^�C������̃}���V�����̂悤�Ȉꌬ�Ƃ́A�S�N�O�ɖS���Ȃ������w���ォ��̗F�l�̑���N�̉Ƃł���B�S���Ȃ�T���ԂقǑO�ɁA�ނƉ���Ă��Ď�藯�߂̂Ȃ��l���R�b�ɉԂ��炢���B�W���̏I���ō��x��̂͂X���ɓ����Ă��炾�Ȃƌ����ĕʂꂽ�B���̖�A�ƂŐH�������Ă��鎞�ɑ���N������������������������Ƃ̓ˑR���]��̓d�b���|�����Ă����B�������܂Ŏ��ƌ��C�ɏ�k�����Ă����j�ł���B�����̓������w����̋��ʂ̗F�l�̋��q�N���o�c���Ă��闿�����œ|��A�]�쌌�ł��̂܂ܐ����Ă��܂����B���̎��̋����͕M��ɐs�����������A�܂����̎��قǐl���̂͂��Ȃ���ɐɊ��������͂Ȃ������B���Ƒ���N�͒��w���ォ���̗m�y�|�b�v�X���D���ŁA���̍����Ȃ��ނ̃R���N�V�����̃V���O���E���R�[�h���A�����ł����܂�Ƃ��ꂼ��̋Ȃ�ނ�D.J�ɂȂ肫���ēd�b�ŕ������Ă��ꂽ�B��l�œ����̐t�f��A�u�p�[���X�v�����O�X�̏T���v��u�A�C�h����T���v�A�u�|�b�v�E�M�A�v�Ȃǂ����ɍs�����̂����������z���o���B��l�ɂȂ��Ă���͉f��ł͂Ȃ��A�����ς����A�n���̒r�܂̃t�B���s���E�p�u�֍s���̂����ɂȂ��Ă��܂����B�ނ̈�Ƃ͒r�ܓ������o�Ėڂ̑O�́A���̌|�p���ꉡ�̔��K���Ẵr�W�l�X�E�z�e�����o�c���Ă����B
�����������Ԃ�Ԃ��Ă������A����Ȕނ̉Ƃ̉������グ��ƁA�d���ɕ����Ȃ������Ɛ��ꂽ���䏤�X�X�̊��ɉ��������o���̂���G���`����Ă���B��ɏ��������n��Ɨ��U�O���N�Ə�����A���ɂ͑傫�����֓`�Ə�����Ă���B���w�Z�̍u���ɏW�܂��ĊF�Ō����A�j���̉f��ł���B����Ȏ��̎��͓d�C�������ĈÂ��Ȃ�ƁA����������������Ȃ���C�����܂Ȃ������ŁA�Ȃ�ׂ�����ɍ��菀���X�����|�P�b�g�ɋl�߂������ȍ������A���i�����Ƃ��������搶�Ɍ������郄�c�̓��߂����ē������B�������ō����ɐ���オ���đS�����f��ɏW�����Ă��鎞����Ȃ��ƃo�����̂ŁA�܂Ƃ��ɉf������Ă���]�T�͂قƂ�ǂȂ������B����Ȏ��ł����̔��֓`�����͂��������B�A�j���Ƃ����f�B�Y�j�[�f��S���̎��ゾ�����B���{�f��ł���Ȃ��ꂢ�ȃA�j���͍��܂Ō������Ƃ��Ȃ������B�b�͒����̐��b�����ƂŁA���ւ��c�����A�������Ă��ꂽ��҂̂Ƃ���֎Ⴂ���ɕϐg���ĕ\��ē�l�͗��ɗ�����B���ւȂ邪�䂦�d���Ƃ݂Ȃ����l�͋��̓�����ނƂ����؏����B��l�ƒ��ǂ��̃��b�T�[�E�p���_��W���C�A���g�E�p���_�Ȃǂ̒������L�̓������������ɂ����A�X�̋�A���ł���傫�ȓƃp���_�̌��܂̃V�[���Ȃǂ͍��̎q�������ɂ��傢�Ɏ�ɈႢ�Ȃ��B���̉f��͊C�O�ł��R�A�����ł͂V���̏܂��l�����Ă���B���݂̓��{�����E�Ɍւ�A�j���f��̂��������ɂȂ�����\��ƌ�������̂��B ���D�w���X�ɋv��A�{��܂�q�A���̍��V�l�̍��v�ԗǎq�ȂǍ��ŁA�����̓��f�Ƃ��Ă͕��X�Ȃ�ʗ͂̓������M�����B
���āA�T���h�C�b�`�̎M���A�C�X�E�R�[�q�[����ɂȂ����B���̊O�̑���N�̕�オ�������̉ƂɌy����߂��A���������ėh��n�߂����֓`�̊��ɏ������Ă���A�܂��܂���������̒��̋�C���z���ɊO�ɏo�邱�Ƃɂ����B
2007.09.01 (�y) �Ă̏I���̃n�[���j�[
�����ޏ����䂪�Ƃɗ��ĂW�N�ɂȂ�B�s�m�Ƃ�������8�̃{�X�g���E�e���A�ŁA�{�ŒT���u���[�_�[���甃�������̂��Ƃł���B40�N�قǑO�ɂȂ邾�낤���A�����������S�Ȏ��T�̃G���T�C�N���y�f�B�A�ɍڂ��Ă�������ŁA���̎ʐ^�Ɉ�ڍ��ꂵ�Ăǂ����Ă���x�͎����Č��������������B�������c���Ƃ�����قƂ�ǖ����̂悤�Ɍ������������ƌ��������A����ɍ��������Ă̂��Ƃ������̂����A���͐l�Ԃ��Z���Ŗ{���ɔ߂����ʂ���o������Ƃ����Ă��A���̌������Ă��Ȃ��q���ɂ͂킩�邷�ׂ��Ȃ��A��匈�S�����Ă̂��Ƃ������B�����������͎q���̎����牽��ɂ��n�肸���ƌ��������Â����ƒ�Ɉ�����ׁA���̌��߂������������̂�������Ȃ��B�ǂ��������Ȃ玄�̖]�݂̈�����Ȃ��Ă��ǂ����낤�Ƃ̌���I�т������B���̐́A��[�N���������Ă��āA�ނ̋b�Ƃ��������ɂ��o�Ă���B�ڂ͑傫�߂Ŏ��������A�Z�т̍��Ɣ��ŕ@���Z���A�U�����Ă���Ƃ悭�t�����`�E�u���h�b�O�ɊԈႦ���邪�A��������ȑO���������Ƃ̂���{�N�T�[��ɂ��߂��A������R���قǏ����������悤�Ȃ��̂��B�V�F�p�[�h��A�t�K���E�n�E���h�Ƃ����@�̒������Ƃ������������A��x�ł����̕@�y�`�����o������Ƃ���Ɍ����Ƀn�}���̂ł���B�����ŗV�эD���Ń{�[����n������Ō�A�����܂ł��V�т������ށB�ǂ����Ԃł͌��h���L�h���Ɩ���邪�A���͐�Ɍ��h���Ǝv���B�L�h�̕��ɂ͎��Ƃ͉������Ⴄ���͋C������B���̐l�͔L���D���������ȂƎv���Ƒ�̂��̊��͂�����B�ǂ����͐l�ɂ��L�͉Ƃɂ��Ƃ����A���̌��t�ǂ���L�͌��قǐl�ɛZ�тȂ��A�v���C�h�������̂т̂т��������ǂ��ƔL�h�̐l���畷�������̂����A���Ƃ��Ă͋A���Ă���Ɩ{���Ɋ�т�̈�t�ɕ\�����錢�������Ă��܂�Ȃ��B���̎������ɂ͑傫�������ē�ʂ肠���āA�����Ŏ������ƊO�Ŏ������ɕ������B�������傫�Ȓ�Ŏv�������莩�R�ɑ��点�����Ƃ��낾���A��Ƃɂ͎c�O�Ȃ��炻��Ȓ�͂Ȃ��A�K�R�I�ɉƂ̒��Ől�Ԃƌ������荬�����Ă̐����ɂȂ�B����Ɩʔ������ƂɌ����l�̘b�⌾�t�𑽏��Ȃ�Ƃ���������悤�ɂȂ�B���̒P�Ȃ�v�����݂�������Ȃ����A�ꐶ�������E�Ɋ���X���č��Ȃɂ������Ă���̂������悤�ɂȂ�B�����̂��ꂩ��u������l�̐S��c�����悤�Ƃ��Ă���悤�Ɏv����B�Ƒ����ł悭��邢���̌��܂ł��A�N����Ƃ��̊Ԃɂ��E�҂̂悤�ɂǂ����ɏ����Ă���B�����悤�ɂ����C�Ƃ��V�����v�[�Ƃ������Ȍ��t���Ɖ������֏����悤�Ǝ��݂�B�������A�D���Ȍ��t���ƈ�u�ɂ��Ď��𗧂Ėڂ��P�������B��̃{�[����U���Ȃǂ����ɂ��Ă��܂����Ƃ�����A��������炽���܂���������B�ȊO�Ȃ̂́A�ǂ̌������ȏb�コ���A���̖��O���Ɛ��������Ƃ��Ă���B��قǏb�コ��Ɣn�����H�������炵���A�ߑO�̈�҂߂��肪��D���Ȃǂ����̍��̂�������̗l�ł���B
���͂Ƃ�����A�ŏ��Ɏq�������Ǝ������Ɍł����������Ɩ��2��̎U���͌����ɗ����A���̊Ԃɂ����̒S���ƂȂ����B��������͎��̃x�b�h�ł����Q�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����Đ�T�̌ߌ�A���k�������|�����n�̘O���Ƃ����X�ōȂ������ɂ́A���ƌ��̃s�m���▭�̃n�[���j�[�Ŗ��邢�т��̋��������Ă���Ƃ����B����͂܂��Ɉ��z���Ƌʒu�_��ŁA���݂Ɏ|���̂��Ă���Ǝv���ƁA�ǂ��炩���x��C���ɂȂ�����ǂ�������A���̉��₩�Ȑ��̗z�����̃C�r�L���A�A�e���܂�Ńn�X�L�[�ȋʒu�_����̃s�m�̃C�r�L�������Ȃ�\���ɂȂ�����i����͒P�Ɏ������X�Ȃ閳�ċz�nj�Q�ɂȂ��Ă��鎞�̂��ƂȂ̂����j�A�Q�l�H���ڈ�t����オ���đ傢�Ƀn����T�r�̏��́A�v�킸�����̂Ƀ^�I���P�b�g����A���܂��Ɏ����ǂ��炵���B����J�Ȃ��Ƃł���B�����A�Ȗ���"�Ă̏I���̃n�[���j�["���������B�������̂��Ă��鎄�B�ɂƂ��Ă͐Q���ɐ��̘b�Ȃ̂����A���낻��������Ȃ�̂ŁA�Ȗڂ����E���[�����͗t�ɕς��ė~�����ƓˑR�̃��N�G�X�g�B�����Ƃ͌��������̂́A���ꂩ����������낤����}�ȃC�r�L�E���C�g�E�V���[�Ɍ����āA���Ǝ��̌��������b�X���H�����̒��Ŏn�܂�B
2007.08.31 (��) �ɓ��̗�
�ȑO����o�ŎЂ̕����畷�����b�ŁA�ڂ̑O�̊C���P�W�O�x���n���Ȃ������I�V���C������A���̗Y�傳�Ɋ��������Ƃ����Ă����̂��v���o���A����A�q�������̉ċx�݂��I�Ղɍ����|����A���̉Ă̑z���o�ɂƖk�쉷��ɂ����Ă����B���܂Ŗk��͉��c���ɓ��ɍs���Ƃ��ɍ����ɐ������z�e���Q�����Ȃ���ʂ�߂��邾���������B�Ȃ�قǁA�����P�R�T����w�ɊC�̍ۂɍ��ꂽ�����镗�C�ŁA�����P�W�O�x�̊ۂ������������Ȃ��瓒�ɐZ����B���c�ŋߕӂ̃z�e���q�͑������A�ʂ肷����̈�ʂ̋q�����U�O�O�~���x�����Γ����\���B�����̂ڂ�����A�����Q�O���[�g���قǓn���Ă������̊C�ő̂��₵�Ă܂���������A�l����������̂ɂ������߂ł���B�����㍬���Ȃ̂����A�����̓o�X�^�I���������ē����B�������V��̒j����Ȃ̂ŁA���Ȃ�̌��ӂ�����B��̂V���`�X���͏�����p�ɂȂ邻�������A���̎��ԑтł͗Y��Ȑ������Ȃǂ͈Â��Č����Ȃ��B�����Ȃ�o����Ύ��B�Ƒ������܂����z�e���]���ŁA�嗁��łȂ���ꎞ�Ԃ݂̑�����I�V���C�������߂���B���������̐H���O�A���ق��Ă���\�K�v�����A����Ă����炩�Ȃ蓌�m�I�ȃ��b�`�ȋC���𖡂킦��B���̖]���́A���ւ���������������̌����ň�ԍ����W�K�̊C��]�̃��r�[�ɂȂ��Ă���B��ƒ��̊C�̍K�����肾������ȍ��ȐH���Ƃ����A���C�D���ŐH���y�̐l�ɂ͂��Ȃ�̖����̂����h���낤�B��N�̂T���ɂ͂��̐�̉��c�̘@�䎛����̐������ɍs�����̂����A������̓t�F�j�b�N�X�����N������鉷��v�[���Ɛ̓��̎���錚���A�L���ɂ���x�e����o�[�Ɍ����鏺�a��吳�̎���ɐ��m�l�����|�������ꂽ�A�a�̊i��������̗��قł���B�J�[�^�[�O�哝�̂�������������Ƃł��m���Ă���悤���B
���̈ɓ��̗��Ɍ��������Ƃ̏o���Ȃ����̂����߂̊C�݂����Љ��B�������̕��͋C���_�̃o�[��C����Ă���T�[�t�@�[�̏�쎁�������Ă��ꂽ�ꏊ�ŁA�������Y��Ȑ��C���L������c�l�Ƃ������{�ɂ��Ȃ���C�O�C���𖡂킦��l���B�����͈ɓ��̊C���D���ȕ��Ȃ�ǂ������m���Ǝv�����A���傤�ǃn���C�E�I�A�t���̖k���ɂ���J�C���A�̃r�[�`�����Ȃ菬���������悤�ȏ����B���̃J�C���A�܂ŗ���Ɗό��q���قƂ�ǂ��Ȃ��B�n���̐l�������{���̃n���C�̔������r�[�`�����\�ł���B���c�l�͂���ȉB�ꏈ�̕��͋C������A�������炱�̕l�ɏo��̂ł������ȊŔƋ������������Ƃ��Ă��܂������ɂȂ�B�Ă��߂����ꂩ��H���[�܂鎞���A�ǂ����ꂽ���ɊC���ɐ�����Ă̂�т�₽�����ݕ��ƍD������ꂽ�ٓ��ł������Ă����ō��̋C���𖡂킦�邾�낤�B
������ƌÂ߂̃��W�J�Z��P�EP�EM��"���ɐ������"�Ȃ𐁂�����Ŏ����Ă䂭�Ƃ�����������Ȃ��B�M�^�[�������Ă����ĉ̂��̂͂����Ƃ�����������Ȃ��B���̂ق����X�˕l�A���l��l�Ȃǂ�����B���ЁA�ɓ��ɍs�����牺�c�܂ő���L���Ă��̕l�֍s�����悤�����߂���B���Љ����̏h�A��ʂ̏h���炷��Α������߂̗����ݒ肾���A�ɓ��̒��ł͂��Ȃ薞�����𖡂킦��h�Ƃ��Ă����E�����Ă��������B���R�Ȃ��痷�̉����������ɉz�������Ƃ͂���܂��A���鐰�ꂽ���ɂӂ���ƕ��ɔC���ė�����̂��̂Ă��������A�N�X�����x�����܂�N�ɂȂ��Ă��������Ő\����Ȃ��̂����A������������̂ɂ͂���Ȃ�ɐM���̏��A���z�Ȃ犴���̏��Ȃ����ɂQ��s���̂����ɂ��āA�{���ɏ[�������S�Ɏc�鎞�Ԃ���������Ɏv����悤�ɂȂ��Ă����B�G���̂ЂƂ育�ƂƂ��ĎQ�l�ɂ��Ă���������K���ł���B
�@
2007.08.13 (��) ���t��
�y����ژ^�B�k�����H�̗��t���Ƃ�����������A���߂ĐG�ꂽ�̂͐t����^�����̉Ă̏I���̍��A�������̌l�I�ȕ��W�̊����Ɏg���Ă������̂������B���̎��ɉf���o���ꂽ���i�ɂ����̈��ɂ̔O�������A�����̋��ɂ��̊G�����ݍ��܂܂����ƍ��Ɏ����Ă���B�����m�̂Ƃ��蔒�H�͉̂̐��E�ł����Ȃ̍쎌���肪�������̐l�ɒm���Ă���B���̓��A���R�A���炽���̉ԁA�郖���̉J�A���̂ق��w�Z�̍Z�̂ȂǑ����̍�i���c���Ă���B���̗��t���͔ނ��R�x�ڂ̌����������吳�P�O�N�A�M�B�ɂ���Ƃ��ɍ��ꂽ�B�S���Ŕ��͂���Ȃ���̂��̎��́A���X�Ɨ��t���̗т��s�����̂ŁA���̓�������S�̕`�ʂ�����Ă���B����͂܂��ɐl�����̂��̂ł���A��҂͂��Ƃ��ǂގ҂̂��ꂼ��ɐ����Ă���������X�ƐU��Ԃ点��B���t���̓��͓��X�̌o�߂����ǂ邪���Ƃ������B���t���ɂ�����J�A�����ʂ��镗�ɏo�����𓊉e������B���͂̒��̂�������ӏ��ɐ�ԎR�̉��ō����������ł��邩��m�炵�߂Ă���B�����ɐl���̐���₩�Ȏ����f���o���Ă���B����G�ꂽ���̐S�̒��̊G�́A���������[�����闎�t���̗т���]�ސ�ԎR�ł���B�N���]���Ɋ����������閼���͍ŏI�͂ɓ����镔���ŁA�l���ւ̒B�ρA�����ĐG�ꍇ�������̂ւ̎����݂ƗD�������r�������ɂ������Ă���B�����ł͂ق�̂����̎O�͂����Љ���Ă��������B����܂̗т��߂���
����܂�����
����܂͂��т����肯��
���т䂭�͂��т����肯��
����܂̗т��o�ł�
����܂̗тɓ����
����܂̗тɓ�����
�܂��ׂ����͂Â���
����܂̗т̉���
�킪�ʂ铹�͂��肯��
���J�̂����铹�Ȃ�
�R���̂���ӓ��Ȃ�
2007.07.19 (��) �A���F�E���F�����E�R���v�X
�V�����{�̖�A�����̂悤�Ɏ�������łڂ����Ƃ���TV�����Ă���ƁA�ǂ����Ō����悤�ȉƂ��o�Ă����B�ŏ��͗ǂ�����f�W�������ȂƎv���Ă���ƈႤ�̂ł���B�ǂ����Ă����o��������A������肩���ɓ��������Ƃ�����ƂȂ̂��B���̂����Ɏ�l�炵���l�������̉Ƃ̂��Ƃ��ڍׂɐ������n�߂��B�����ɐ�����ꂽ�g�F��L�X�ƌʂ�`���悤�ɕ����A�J�������������ʂ��Ă䂭�Ǝ��ɂ���̂�������ł����B�A���F�E���F�����E�R���v�X�B���̉Ƃł��̒g�F���͂�ł݂�Ȃʼn̂����Ȃ������B�����܂��\��̍��ŁA���������ϗL���Ȍ��z�Ƃ̃��[�����h���̕ʑ��ɂ��ז������Ƃ��̂��ƁATV�i�ԑg����NHK�̃v���~�A���P�O�j�ɉf���Ă���̂͂܂��ɂ��̉Ƃł���B������[�����h�������g�Őv���ꂽ�Ƃ�������́A�����猩����X���R�U�O�x�̃p�m���}�Ɍ��n���A�W�W�ƌ�������P�Q�p�`�������傫�ȃ��r���O�A���傤�ǐ^�ɉ~���`�̒g�F���������B�������z�ɂ͉��̋������Ȃ������������̓Ƒn�I�Ȏa�V���ɋ������������B���̓`�F�R�ɐ��܂ꂽ�A�����J�l�Ŋ����̂��������̘V�l�������B�����҂�������������Ɏ��������o�����Ă̎]���̃A���F�E���F�����E�R���v�X���̂����̂������B���̓A�����J�ŖS���Ȃ�A���݂͎t��̕������̉Ƃ��p���ł���Ƃ̎��B
���͕߂Ă��܂����y��[�X�E�z�X�e�������A���N�Ă̂T���Ԃ����s��ꂽ�y���~���[�W�b�N�E�L�����v�B��̂͐��N���y����Ƃ����A���̈�Ƃ��Ď��̐l���̎t�ł�����i�́j�R�{�����������S�ƂȂ��āA���y��ʂ��Č��S�Ȃ���N�̈琬��ړI�Ɏn�߂�ꂽ�L�����v�ł���B�Ȃ��A�s�ǂ̎������̃A�J�f�~�b�N�ȃL�����v�ɎQ�������̂��́A�����Ȃ�̂ŏȗ������Ă��������B��{�͉��y�����S�̃L�����v�ŁA���Ԓ��ɂ͂��܂��܂ȃ��N���G�[�V����������A���̒��̈�ɋ��y�̒����烌�C�N�E�j���[�^�E���܂ł̃T�C�N�����O���������B�r���Ƀ��[�����h���̂��̕ʑ�������A�R�{���̂��m�荇���Ƃ������ƂŃL�����v�ɎQ�����Ă��鎄�B�������҂ɂ����������̂������B�L�����v���ɂ͉���̌��y�l�d�t�̕��X�����Ă������A�T�C�N�����O�̓r���Ƃ����Ă��̎�����̓A�J�y���ɂȂ����B
�܂����y�̒����ߔN�̂悤�ɂ₽��ƓX��l�������Ȃ��A�^�Ăł��������̂�т�Ƃ��Ă��āA���Ȃ�����x��������������̂��Ƃł���B�ڔ��ɂ��邱�̎��㟭�����X�i�b�N�̈�p��S���Ă���"����"��A���̌�A���N���x��ĘZ�{�̃J���[����"�f���["�����y�̒��ɏo�X���Ă������ゾ�����B���͉����̃X�[�p�[�ł���ɓ��鍟���̃J�V�~�[���E�J���[�͓������甼�[�Ȑh���ł͂Ȃ������B�X�q�̎�������i�ȘV�w�l���悹�����[���X�E���C�X�̃V�����@�[�E�N���E�h�����ނ悤�ɐi�݁A�����������s���A�����������Ԃł��A�^�Ă̗т̒��͂���ƐÂ܂�Ԃ�A���̉��x�͂Q�x�قlj�����B�傫�Ȗ���l���ɎU���Ȃ��痎���Ă䂭�ؘR����́A���Â������������ƏƂ炵�A���̗y����Ő������́A������̗t�e�������Q�̏�ŗx�点���B���v���Α����̔g������Ă���ȑO�̌Â��ǂ�����A���̖ʉe���c���Ō�̌y������̂�������Ȃ��B
TV�����Ȃ���ӂƁA���̐l���̒��ŕs�ލ����Ȃ��̂��������Ƃ�����̎^���̂̃A���F�E���F�����E�R���v�X���낤�Ǝv�����B�^���̂Ƃ������̂����܂ł̎��̐l���ς�M���Ɉ�x����Ƃ�����鏊���Ȃ��A�q���̎�����_�Ђ₨���Ŏ�����킹��悤�Ȃ��Ƃ��A�����䂭��肾�����B�܂��Đ��m�̏@���̂Ƃ��Ă͂Ȃ�����ł���B�������ɔF�߂�s�������̍ł����荇�킹�������̂��Ǝv���B���̕s�������ɂ܂�Ȃ����̂��A�ǂ����Ă��̂悤�ɂ͂�����ƋL���̒��ɐ����Ă���̂��낤�B���܂�ɈႤ���̂ւ̎v���A����͎����ɂȂ����̂����l�Ɏ䂩�ꂽ��A�ʂ̎Љ�ɏ����������ݓ��ꂽ�肷�邱�Ƃɂ��������̖�������A����Ȑl�̐^���������Ă���̂������Ȃ��B�ɂڂ���Ɏh��������A�v�X�ɉ���������ʂ�l�B���v���N�������Ă����ԑg�������B
2007.06.28 (��) ���̉Ă̓����E����
�U���̓��j���̒��A�T���ɋN���ċm�����Ɍ������A�����̊��̓K���K���Ŗ̎��Ԃ��Q�O�������������Ă��܂����̂����AM�N�̓�l���̃I�[�v���̃����Z�f�X���A�����ɃV���o�[�̎ԑ̂����点�Ď���҂��Ă����B�����̓I�[�v���̔ނ̎Ԃōs�����Ƃ����܂��Ă����B��������Ă����Ԃ𒓎ԏ�ɓ���Ă���ނ̎Ԃŏo�������B�ނ͂Ȃ�ƂS���ɋN���Ă��܂����X�ƃX�^���o�C���Ă����悤���B�U���Ƃ͂����~�J�̋��Ԃ̉����A���S�ȃI�[�v���ɂ��đ���ɂ͒��̂U���͔������A���̍��̒��w����̎v���o�����ǂ闷�͑����̎Ⴓ�ƍs���́A�₹�䖝���K�v���B�������w��N�̗ՊC�w�Z�Ŏʂ��Ă���̂̎��B�Q�l�����ꂩ�牽�\�N���o�������A�����ꏊ�A�����i�D�Ŏʐ^���B�낤�Ƃ����m�[�V�C�Ȋ��ł���B���������̂ɂ͎����m�����������ł͂Ȃ��̂����A���̒m�����M�N���q���̂Ƃ�����m���̂������ŁA���ꂪ�����܂ł����Ƒ����Ă���l�ł���B�ނƂ͍��Z����̎u�ꍂ���̃X�L�[�ȗ��̌l���s�ƂȂ�͂����B���َR���犊�����N�����Ȃ��ъԃR�[�X�͖{���ɂ����v���o�ɂȂ��Ă���B�ǂ����ꂽ���A��������̂̓X�L�[�̃G�b�W����ƎC��鉹�Ǝ��������̓f�����̉������A�]��Ő�̒��ŋ����ɂȂ�ƁA������͉̂����܂ł����ݓn��������Ɗ炪���������ꂽ����̐��E�A��͉����������Ȃ��B�����ł��ق�̎����܍~���ŊX���Â��ɂȂ�A���������ꂾ�������Ƃ����َ͈̂����̐��E�ɂȂ�B�����ł͔���������X�ɍ~�蒍�����ɂ����������ȑ��g����������悤�ȕs�v�c�Ȋ��o��̌������B
�����č��A�����i�F��̘b���y���݂Ȃ��瓌�����P�O�O�L����Ő^�̎Ԑ���������藬���Ă���B�E�̒ǂ��z���Ԑ�����͓��R�Ȃ̂����A�E�����J���Ă���̂ɂ킴�킴�����甲���ɗ��邯�������y������A�l���͂��낢��ł���B�Ԃ͏��ÃC���^�[�ʼn���A�����̂P�V����ڎw���B�x�[�W���n�̖��邢�z�F�̒W���z�e�����E�̊C�Ɍ��āA�O�ÃV�[�p���_�C�X��ʂ�z���A���悢��C�ݐ��̃��[�J���ȓ��ɂȂ��Ă���B���N���͎O���̓��A���j���̒��Ȃ̂ɎԂ͉����܂ł��������X���[�Y�ɑ���A�W���ɂ͖ړI�̑吣��ɓ��������B�����̊ቺ�ɉ����������������Ă���Ƃ�͂苹���������B�������ŏ��N����̉Ă��S�x���߂������Ǝv���Ɗ��S���ЂƂ������B�Ԃ��߂Ă��炨���b�ɂȂ����ؑ��̌Â��h�������吣�ق�K�˂Ă݂��B�����͂�������ߑ�I�ɂȂ�A�Ó�ɗǂ������������ȃv�`�z�e���̕��͋C���Y���Ă����B�����A�ԃt���h�V�ŏ����̑������l�̓X�L���[�o�E�_�C�r���O�p�̑�R�̃{���x��K�l�Ȃǂ��u����Ă��Đ̖̂ʉe�͂Ȃ��B�������͓��{�ł��L���̃_�C�r���O�̃��b�J�ɂȂ����炵���A���ꂩ��吨����ė���ł��낤�A�_�C�o�[�q�ׂ̈̏����ɒǂ��Ă���l�X�������B
���悢��J�����������đz���o�̏ꏊ�ł��閦�Ɍ������B���������ł��������|���v���������吣�_�Ђ̎Q���炵���ׂ������Ă����ƁA�ۂ��傫�Ȑ���d�ɂ��]�����Ă���ʐ^�̂��̏ꏊ�ɏo���B�����̏u�Ԃł���B���ꂢ�ȓ����ʂ������A�ł���g�͈ȑO�ɂ��܂��ėD�����A���������͐̂̂܂܉���ς���Ă��Ȃ��B�����ĕς���������グ��ƁA�����ɉ���Ō�������Õ��ʂ̌����������Ȃ������ƁA�����V���̏I���̗ՊC�w�Z�ŕx�m�͉ĕx�m�ŁA�S�̂��W���������A���͂��̒��ɑ����̐Ⴊ�c���Ă��邮�炢�̈Ⴂ�ł���B�����A�̂̎ʐ^�����Ȃ��炻�̏ꏊ��T���B����������M�N���x�m���͂���ŗ����Ă���ꏊ�A�Ȃ�ƂȂ��������낤�Ɠ�l�̘b�������̂����A�܂������Ƃ����ĒN���J�����̃V���b�^�[�������Ă����l�����Ȃ��B�����ʼn����l����T���Ă���_�C�o�[�����邾�����B���傤�ǂ�����̏�ɓK���ȃJ�����ʒu�����߂āA�����V���b�^�[�ɐ�ւ��B�e���J�n�����B�V���b�^�[�������ĂR���[�g����܂ŏ�����Ń|�[�Y���Ƃ�A�₪�ăt���b�V��������u�Ԃ܂ʼn��b�Ԃ������̂��낤���B���̎��A���̍��Ɠ����������������̕����������B
���ꂩ���\���̉Ă��߂��A�����Ă��̎v���o�Ɛ�����Ȃ��قǂ̔M���v�����点���B�����ꂻ�̂��ׂĂ̎����͂����ɍL������C�Ƒ傫�ȋ�̒��ɖ���Ƃ����������ď����Ă䂭�B���̐S�̒��ɂ���Ț����������c���A���̕��͖�����C�ւƐ��������Ă������B
2007.06.27 (��) �����Q�x�y����
�Ԃ̐��E�R�僌�[�X�Ƃ����C���f�C�[�T�O�O�A���}���Q�S���ԁA������F1���i�R�E�O�����v���ƂȂ�B�挎��27���钆��TV�Ń��i�R�E�O�����v���������B�����m�̒ʂ萢�E���̋��������W�܂�ꏊ���B���̐��E��2�Ԗڂɏ����ȍ��̐l���͕��i32�A000�l�𐔂��邻�������A���̂Ƃ�����͂��̖�10�{�߂��̐l���ɂȂ�炵���B�܂��Ɉ�N�Ɉ�x�̍��������Ă̑�C�x���g�Ȃ̂��B�����ŗD�����邱�Ƃ̓h���C�o�[�ɂƂ��đ�ςȖ��_�ƂȂ�B����͎Ԃ̐��\�����h���C�o�[�̋Z�p���D�悳����R�[�X�ŁA�ׂ�����̂����R�[�i�[������A�O�𑖂�Ԃ��̂ɂ��אS�̒��ӂƍō��̋Z�p��K�v�Ƃ��邩�炾�B�e�R�[�i�[�ɂ͂��̏ꏊ�ɂ��Ȃ��O�����Ă���A�ł��L���Ȃ̂̓��[�Y�E�R�[�i�[�Ń��i�R�̃w�A�s���E�J�[�u�Ƃ��Đ��E�ň�Ԓm���Ă���J�[�u�ł���B���̃w�A�s���E�J�[�u��^���ʂŌ�����z�e�����z�e���E���[�Y�E�����e�J�����ł��̖��O�������B���̓����e�J�����E�O�����h�E�z�e���Ɍo�c���ς���ăR�[�i�[�̖��O���O�����h�E�R�[�i�[�ƂȂ����B���̃��[�X���s�Ȃ��鎞���ɂ��̃z�e����\��͎̂���̋Ƃʼn��N���O������ʗ\����Ă���Ƃ����A���E�ōł�����Ƃ�����R�[�i�[���A���ō��̋Z�p�����I�є����ꂽ�h���C�o�[���A��Ƃ̓��]�����W���������E�ꑁ���Ԃő���B�����ڑO�Ɍ���̂����瓖�R���̉��l�͏オ��̂��낤�B�������N��2���ɂ����̃O�����h�E�R�[�i�[�ɍs�����Ƃ��̎��B �j�[�X����̔����̃c�@�[�ŁA�����ɂ��Ȃ��ŐH���������ɋA��Ƃ����B�����������i�R�ɗ����̂ɂ��������Ȃ��ŋA���Ă͈ꐶ����ނƎv���Ďc�邱�Ƃɂ����B�c�@�[�̃o�X�ɕʂ�������Ă���A�F�l��N����K���v�Ȃ�4�l�ł��̃R�[�i�[�Ɋ����ɐZ��Ȃ���30�����������낤�B���ăZ�i��v���X�g�A���V���[�}�b�n�i��N���ށj���������蔲�����R�[�i�[�͂̂ǂ��Ȍߌ�̒n���C�̌��ɕ�܂�āA���i�R�p�̐^���ȊC���O�����h�E�z�e���̓��ɍL�����Ă����B�������牺��ƁA���̃��[�X�ł͍ł��X�s�[�h���o��Ƃ����g���l���̓����������A���̂������̊C�ӂ̃��X�g�����A�[�u���E�X�N�G�A�iK���l���{�Œ��ׂ������E�̃��X�g�����j�łS�l�Œ��H���y���B���̓I���[�u�I�C�����u�߂��O��̋����A���ꂼ��Ⴄ�����悹�����̂ƃr�[���ƃ��[�E���C���𗊂B�����`�����}�b�g���͂��߁A���ׂĂ̕����[�u���̃V�}�E�}�͗l���{����A�傫�ȑ��̊O�͕����ʂ�̃R�[�g�_�W���[���̌i�F�A�������������Ɗy������b�ŖY����Ȃ����H�ɂȂ����B���̌�AK���v�ȂƂ��ʂꂵ�ĕ������O�����E�J�W�m�̑O�ł́A���R�����e�J�����E�����[�̃N���V�b�N�E�t�F�X�e�B�o�����J�Â���Ă����B�n���̘V�v�w������Ă����P�X�T�O�N��ɐ��삳�ꂽ�v�W���[�Q�O�R�ɏ悹�Ē�������A�O�����E�J�W�m���̃J�t�F�E�h�E�p���Ń\�[�_������A�����̃��i�R���y���B�L��̏�̃o�[�N���C��s�O�̒◯�������S���[���̒������H���o�X�ŋA�H�ɒ������B���ɒn���C�A�E�ɑ傫�Ȋ₪�������Ă���}�ȎR��������A���̐����ɂ͊�d�ɂ��܂�d�Ȃ�悤�ɓ��H�������Ă���B�O���[�X�E�P���[����ʎ��̂ŖS���Ȃ����������̎R�̒����̓��������Ƃ����A���O���[�X���܂̕�̓��i�R�吹���̒��ɂ���B����ȊC�ݐ����ꎞ�ԂقǗh���Ȃ���j�[�X�ɖ߂����B
���ꂩ��Q�N�S�����A��T�A�R���̍b�{��K���v�Ȃƍĉ���ʂ������B���Œm�荇�����l�ƌ��ł͖�������܂��傤���ƌ����ĕʂ�邪���������ׂ����Ȃ��A�C�O���s���ł̍ĉ�͎n�߂Ă̌o���ł���B���܂����̃��[���E�A�h���X���ς�����̂Ō�A���������A�b���Ƃ�Ƃq�ɉ^�т��̍ĉ�ƂȂ����B���E�ŗF�l��N�����悹�āA���������̏����ł���l�ƍĉ�A��������͌��Ε��ʂɖ�T�O���������B�ǂ�����c�ɂ̈ꌬ�Ƃ����̂܂��������Ă���Ƃ������ׂĂ��Z���t�̂��ǂ�X�A�̂����o�Ă��Ȃ����ʂ̉ƂɌC��E���ŏオ��B���i�R�ȗ��̂S�l�̒��H��̖��͒n���Œm���Ă��遃�g�c�̂��ǂƂ�����ł��őf�p�Ȃ��̂������B���~�蒍���n���C�ł͂Ȃ��A�����̂��X�̐l�̉Ƒ��ʐ^������ꂽ�ǂ����Ȃ���A�f���ǂ�Ƃ͕ʂɂ�ł��L���x�c�����ĐH�ׂ�Ƃ����{���ɃV���v���Ȃ̂����A���̉Ɓi�X�H�j�̕��͋C�����ɐV�N���B���̎��������A�������~�̏`�̖��A���炭����Ɩ��H�ׂĂ݂����Ȃ�悤�Ȗ��͂�����̂������B�����R�O�O�~�Ƃ����l�i�ɂ��������ꂽ�B���Ȃ݂Ƀ��i�R�ł��v�w�����~�l�����E�E�H�[�^�[�̒l�i�͂P�W�O�O�~�������������B�Θa����ɓ������āA���̎��̃A���o����r�f�I�Ȃǂ���������Ďv���o�b�ɉԂ��炢���B����l���\�Ă���������"�z�e����܂Ȃ�"�́A�����悵�A���C�悵�A�����悵�̎O���q�������喞���̏h�������B���͕s�v�c�Ȃ��̂��A�����ƈႤ�����ɂȂ��Ă��鎖�ɋC�Â���������B��_�ɂȂ��Ă�����A���鎞�͑f���Ŋ����I�ɂȂ��Ă�����ŕ��i�̐�������J������鎞�����A�{���̑f�̎���������o���悤�Ɏv����B��Ђł͏㉺�W��C�o���W�A���Ƃ��w�Z�ł����Ԉӎ��Ƃ����F�l�̂�����݂͂���B����Ɉ����������̗F�͉��̗��Q�W���Ȃ��A���݂��ɑf�̂܂܂̎������I�ԁA�f�̂܂܂̗F�Ƃ�������̂��낤�B�ʐ^��r�f�I�����đz���o�����ǂ鎞�̊F�̏Ί�A�����čs�����앧�̃A���o�������A���݂Ɖ�����𑝂����悤���B
2007.06.14 (��) �Ă̑z���o�E�吣��
�ŋ�TV��ނȂǂŒm���Ă���ˉz����Ƃ������{�ł��L���̒������X�X���i��ɂ���B�u���b�N�E�~���[�W�b�N�̕]�_�ƂƂ��Ē�����S�����A�����s���Ă������R���u���炱���Ɉ��݉���ڂ����ƂɂȂ����̂łQ�x�قǖK�˂Ă݂��B���������Ă��傫�ȃX�[�p�[�����𗘂����鍡�̐��ŁA���������͌X�̏��X�����ꂼ��̌����o���Ċ撣���Ă���B�Ȃ�ł����{�ň�ԏ��߂ɉ��X����Ɩ���������������ŁA�吳����ɋ���̃����K��Ⴂ���̂����O�̏��ȂɂȂ����Ƃ��A�K�͂��傫����l���܂����łP,�U�L���ɂ��y�Ԓ������BS���̎d���������A���w���ォ��̗F�l��M�N�������ɏZ��ł���B���̍��w�Z���Ő␢�̔�����搂�ꂽ�ނ̕�Ƀq���}���Ƃ����ԂʼnH�c��`�܂ő����Ă��炢�A���߂ă��m���[���ɏ悹�Ė�����̂��o���Ă���B�Ƃ͑S���t���[�����O�ɂȂ��Ă��ēy���ł��̂܂オ��A���ւ̖ؔ��ɓ������R�[���͈��ݕ���A�A�����J��TV�h���}�����̂܂ܓ��{�ɗ����悤�ȃJ���`���[�E�V���b�N�����B���݁A�ނ͌ˉz����Ŏ��Ȉ���c��ł���B����Ȏ���ɂ������ˉz����͒ʂ��Ă͂�����̂́A���A���߂Ă��̑傫���ɋ����Ă���B���݉�̑O�ɂ��������Ȃ̂�M�N�̂Ƃ���֊���o���̂����A����A���o�������Ă�������R�ɂ��ނƂQ�l�Ŏʂ��Ă��钆�w����̗ՊC�w�Z�̎ʐ^���o�Ă����̂ŁA�����ɉ������̉Ă̑z���o������Љ���Ē����A�ꏊ�͑吣��Ƃ����ď��Í`����D�łR�O���قǓn�����Ƃ���ł���B���傤�ǐ��ɓ��̏�ɓ����鏊�ŏ��т̖��̐�ɕx�m�R��]�ނƂ����f���炵���i�F�����߂�ꂽ�B
�i�F�͗ǂ��̂�����X�ɂƂ��đ傫�Ȗ�肪��������B����͊w�Z�̓`���̐����A�^���ԂȂU�ڃt���h�V�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł������B�ǂ�Ȃɕ����o���Ă��A�ǂ�Ȃɕs�ǂł����K�ۏo���̐ԃt���ł���B�ň��Ȃ̂����ɓ���O�̏����̑��̎��ł���B �������������̑����n�߂�ƁA���̊Ԃɂ��N��̎Ⴂ�����B�����Ȃ�����������Ǝ��͂�ł���B�ǂ̗F�l�����i���ɏĂ������Ƃ̂Ȃ��^�����ȐK���ق�̂蓍�F�ɏĂ��Ă��ĉ��������A���̂����������������Ă���悤�łP�R�`�S�̏��N�ɂ͍��ȏ�ʂ������B�ϋq�H�������ׁA���Ƀ^�I�������������c���A�Ⴍ�ăo���o���̑̈狳�t��T�搶�ɁA�v�������肨�K���R��ꂽ�̂ł�����o���Ȃ��B�܂�ŏ��N�X�g���b�p�[�ł���B �F�l�̐^�ʖڂŐ��`���̂���O�N�́A��O�ɍL������C�����߂Ȃ���"�ߌ�����"�ƈꌾ��������܂��̂������B���w���ア���Ă�����Ɣ߂����Ȃ�̂͂��ׂ̈������B�����ɍ��Z�P�N�܂ł̂S�N�Ԓʂ����B�Ō�̔N�͉�X�̐��k��������̎��ɁA�ԃt���p�~������ɓ��ꂽ�̂ŁA���k�̑S�����ނɓ��[���Ċw�Z�n�݈ȗ��̒��������ԃt���̎���ɖ����~�肽�B���ł��U�ڃt���h�V�Ȃ�R�O�b�ȓ��ɂ�������ƒ��߂邱�Ƃ��o����̂����A�������ꂪ�ǂ������H�ƌ�����̂ŒN�ɂ�����Ȃ����Ƃɂ��Ă���B
�ˉz��M�N�͑�ς������Ȏq�������B�{���̋������D���ŁA�݂䂫�ʂ�œ����l�C�̃W�����A���i�����ȓX���́u�Ԃƍ��v�̎�l���̂܂�܂�"�W�����A���E�\����"�ƌ������j�Ƃ����i���X���D���������B���̓X�ɓ���A�QF�֏オ�錄�Ԃ��炯�̗����K�i���������o���čs���ƁA�����b�����f����̂������B���������̗ՊC�w�Z�̑吣�ł̓I�V�������N�\���Ȃ��A���̐ԃt���E���K���N�ł���B
����ȑz���o�����ՊC�w�Z�̎ʐ^�͔ނƎʂ��Ă��邱�̈ꖇ�����Ȃ��B�Ăт��̑吣��ɍs���Č��悤�Ǝv���B�吣��̓˒[�ɋ߂����ł̎ʐ^�A�ނ������Ď��������ĂQ�l�̐^�ɉ����x�m�R�������Ă���B�ނ͂Ƃ��������̕ς��悤�͂����܂����A�������̍��̑̏d�͍��̂��悻�����ʂ��낤�B�N���Ǝ����ؚ��Ȏ��̊���̂��Q�{�ɖc�ꂳ���Ă��܂����B���Г�l�ł��̏ꏊ�ɗ����ē����l�Ȏʐ^���B�肽���Ǝv���B�㔼�g���ʼn��͔��̃g���p���ŁA�R�N�ԓr�₦�Ă��܂����N���X��̈ē���ɂQ�l�̎g�p�O�A�g�p��̂悤�ȐV���Q���̎ʐ^���ڂ����Ȃ�A���F�B�ɐ�ɃE�P�����ƊԈႢ�Ȃ����낤�B�����āA���o���̕���́A���W�܂�I�吣�̓��K���N�B��I���Ō��܂肾�B
��l�Ǝq���̋��Ԃ̒��ŏ��Ȓj�S���h�ꓮ���A�����悤�ȁA�߂����悤�ȉĂ̑z���o�ł���B
2007.06.09 (�y) ���̗L���l
�����܂��c�����A�ג��ɂ݂�Ȃɐe���܂ꂽ�m�I��Q�̐N�������B�ނ̂������͈Ɣn�V��Ƃ������B�Ȃ����̂������������̂��͒m�炸�ɁA�����Ȏ����ނ��ĂԂƂ��ɂ͂����Ɣn�V��ƌĂт��ɂ��Ă����B�g�̏�͎��̓�{�߂��������̂ɔނ��D�����ē{��Ȃ��̂��������ɁA���K�L�̎��������ԂӋC�Ȃ��Ƃ��������B���ɂȂ��Ă����Ȃ�����ł���B�ނ͕K�������̒��̃C�x���g�̎��ɓo�ꂵ�ė��Ă͎d��̂ł���B�������̂悤�Ɍ���ẮA�����̌�ʐ�����ӔC�҂Ƀp�b�Ƒ����肷��B�Ղ��~�x��Ɏn�܂�A�����A�Q���쏜�A�����⎖�́A�ʂĂ͕ĉ��̌�p�����A�����⎖�̂̂Ƃ��͌x���̉��Ŏ蒠�܂ŏo���ď����^���܂ł���O�̂���悤���B�ʂ肷����̖쎟�n�Ȃ͂�������W�҂��Ǝv���A�ނɎ�ނ���n���ł���B���̓o��͕S�p�[�Z���g�Ƃ����Ă������낤�B�ނ��ǂ����Ă��̏���f�����d����ēo�ꂷ��̂��́A�������璬�̎��s�v�c�̈�ɂȂ��Č��p���ꂽ�B�����o���A���a�V�c���A�S���Ȃ�ꂽ�䒷���̂���Q��Ɏ��̉Ƃ̑O�̈������ʂ��邱�ƂɂȂ����B
�x�@�����吨�o�Čx���ɂ������Ă����A���炭���Ă����̔ނ����Ȃ��̂ɋC�������̂͊F�����т����đ啪�o���Ă̎��������B�������낻��A�V�c�̏��ꂽ���Ԃ������鍠�ł���A"�������ɍ����́A�Ɣn�V��͏o�ė��Ȃ���"�ƌ��ɂ�����Ɍ������B����Ɖ��̂ق�����傫�ȉ��ʂ̉����������Ă����B�J�b�J�b�J�b�J���ƁA����傫���Ȃ�B�����Đ���"�݂Ȃ�~��I�����܂�����O�ɏo�Ȃ��ł������`���I"�Ƃ����̗ǂ��ʂ�b�������A�����̂悤�ɍL����̃h�^������ɋ삯�オ���Ă䂭�J���J���̖V�哪�́A������Ȃ����̈Ɣn�V��ł���B
�x�������������ŏ��Ă��Ē�߂悤�Ƃ����Ȃ��B�吨�̐l��ڂ̑O�ɂ��Ă������e���V�������オ���Ă����B�����Č��̕��"����ς�o���ˁI"�Ƃ����ē�l�Ŕ��B�Ԃ��Ȃ����o�C������ăG���W�F�̑傫�ȎԂɏ��ꂽ�É�����X�Ɏ��U��Ȃ���s���ꂽ�B�Ɣn�V�炪��w����Č�납�痈�锒�o�C�̘I����������`�ɂȂ����B���̌�A�������������̂������̗R�����l���Č���Ƃ��鎖�ɋC�t�����B����͉f��ɏo�Ă��闒���\�Y�̈Ɣn�V��́A����Ђ�̐����P�ǂȎs�������l�ɂ����ꂻ���ɂȂ�ƕK���o�ꂷ��B������̈Ɣn�V��͒��̃C�x���g�ɕK���o�ꂷ��B�_�o�S�v�A�o�邼�I�o�邼�I�ŕK���o��I�ǂ�����݂�Ȃ̃q�[���[�A������f��A���Ȃ����̈Ɣn�V��Ƃ������Ƃ������B
���ꂩ��Ԃ��Ȃ����Ĕ߂����o�������������B�����p�ɂɉΎ������������ゾ�����B���̏��w�Z�ł���N���ƎO�N���̎��A�����̑����玩���̉Ƃ��R���Ă���̂����C�u�Ŗڌ����铯���̎q����l����������ł������B�����Ă��낤�����A�ށE�Ɣn�V��̉Ƃ��Ύ��ɂ����đS�Ă��Ă��܂����̂��B�����l�̂��Ƃő呛�����Ă����ނ��A���x�͂Ȃ�Ǝ����̉Ƃ��R���Ă��܂����̂������ςł���B����ɑ������̂��낤�A�s����������͂��̎O����̗[���A�������̗����w�ŕی삳�ꂽ�Ƃ����B�ѓc�����痼���͂��Ȃ�̋������B�O���O�ӂ����������ǂ�����đ������̂��͖����ɔނ����킩��Ȃ��l�ނ̓�ł���B
����ȗ��ނ̎p�͌������Ȃ��Ȃ����B���N���o���āA�����ψ������Ă��ċߏ��̂��Ƃ͉��ł��m���Ă����ɂ��A�ނ͎{�݂Ō��C�����ɂ��Ă���"���̂��Ɗo���Ă���H"�ƕꂪ������������"�E��"���������������B���ꂾ�������Ɛ̂̓��{�f��̗��l���m�̉�b�̂悤�ł���B
���̉Ύ��̂Ƃ����璬�̃C�x���g�͕��i�Ɠ����悤�ɑ����Ă�����̂́A����������Ȃ��Ȃ����B���������ɂ��ď��グ���Ɣn�V�炪���Ȃ��B���x�����o�ꂵ�Ȃ����낤�Ƃ������ɂ��Ō�ɂ͓o�ꂵ�Ă��ꂽ�Ɣn�V��́A�Ⴆ��Ί����̏܂����Ă����ŋ����Ăƃt�@�����S�̒��ŋ��ԂƂ��A�K�������Ă���鏼�c���q�̗܂Ɠ������B���O�ɂƂ��Đ��q�̗܂ƈƔn�V��͐l�̊��҂𗠐邱�Ƃ�m��Ȃ����ʂȑ��݂������B�����Ăǂ������������ʖڗ����������Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ��B���̕���͒�����o���L���l�̋L�^���A�l�X�̋L���̕Ћ��A�]��Ɏc��l�̘b�ł���B
2007.06.08 (��) ���̂Ƃ����y����
���N�̏t���NHK�̒��̃��W�I�ԑg�ŁA������ɃQ�X�g���J�߂Ă����~�l�\�^�������"�����̋u"�Ƃ���������ǂ�ł݂��B�����͎��������Ȃ��A�����J���s�ōs�������ʼn�����������`���Ă̓Ǐ��������B���҂̓E�C���A���EK�E�N���[�K�[�ŁA��l���̌��ۈ����R�[�N�E�I�R�[�i�[�́A�G��ȃ~�X�e���[�����̃n���[�E�{�b�V����X�y���T�[�E�V���[�Y�̃X�y���T�[�ɔ�ׂ���Ȃɋ������Ȃ��A��邱�Ƃ������Ă������悭���Ȃ����A���R�������A�Ƒ��������e�ߊ����N�����ʐl�ł���B�܂��A�n�搫���ǂ���������Ă���A�~�l�\�^�����m�邱�Ƃ��o�����B�������ꂾ���ł͏����ɂȂ炸�A��ɂ���Ă����Ȏ��������玟�ւƋN����A�ǂ�ł��ĖO���邱�Ƃ͂Ȃ������B�����̂ڂ��ēǂO���"������S��"�̕������͖ʔ����������B���̓�A���ǂݏI����Ă���A�~�l�\�^�̗��s�����������v���o����A���̎G�����������Ƃɂ����B1994�N��2���Ƀ~�l�\�^�̃~�l�A�|���X�ōs�Ȃ�ꂽNBA�v���E�o�X�P�b�g�{�[���̃I�[���X�^�[��̊ϐ�ɍs�����Ƃ��̎��B�����͉ĂƂĂ������A�~�͂Ƃ��Ƃ��Ƃ����T�^�I�ȑ嗤���C��ŁA���̍s���������O�Ƀo�X��ō����ׁ̈A�l���������Ƃ����|���b�����B���̔��܂����z�e����400���[�g���قǂ̌����ɃA�����J�ň�ԑ傫���Ƃ�����V���b�s���O�E�Z���^�[�̃��[���E�I�u�E�A�����J������A����ȋ߂��ł����܂�̊����ׂ̈ɃV���g���E�o�X�𗘗p�����̂��o���Ă���B�����͓X�̐��̑��������邱�ƂȂ���A�������̃��[���̒��Ƀ��[���[�E�R�[�X�^�[��������A�ϗ��ԁA����5�`6���[�g���͂��낤���Ƃ����X�k�[�s�[���u���Ă���傫�ȗV���n��a�@������̂ɂ͋������B�Z�[�����̈ߕ��≻�ϕi�͏B�@�Œ�߂�ꖳ�łƂȂ��Ă���A�������D���̐l�Ȃ炱�̃��[���̒��Ɉ�T�Ԃ��Ă��ދ����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B��ɂ���đO�u���������Ȃ��Ă��܂�����"���̎����y����"�Ƃ����e�[�}�͂��̎��� �I�[���X�^�[��̂��Ƃł���B
�ϋq�ł��鎄�̎���ɂ͂Ȃ����A�o�X�P�b�g�{�[���W�҂̑傫�ȍ��l���肾�����B�����ȏ��ň����n�O�����킳��Ă���B�L���I�肾�����Ǝv�����l��吨�̐l�����͂�ł�����A�����`�[���������̂��낤���A�O���[�v�̗ւ��o���Ă�����ő�ςȓ��킢�������B�������A�^�~�ō����̃~�l�A�|���X�Ƃ����āA�����̃c���c�����̑�j�������ǂ���������̖є�̃����O�E�R�[�g���͂���i�Ƃɂ����g�̏�Q���[�g���߂��̒j�B�̖є�ł���B�����������C�̓������������𗎂Ƃ����̂��낤�Ɨ]�v�Ȏ����l����j�F�������̂悤�ɋ��̃s�A�X��u���X���b�g�A�_�C������̎w�ւ����Ă���B�����Ɍ����ē��R�Ɛ��R�ɕ�����A�V���L�[���E�I�j�[�����n�߂Ƃ���X�[�p�[�E�X�^�[�B���ꐶ�����������Ă��鎎�������A������̋x�e���Ԃ̋q�̕������Ă��ĖO���Ȃ��B�Ȃ���A���̑�j�����̓�����ɕ��ꍞ�悤�ȍ��o�Ɋׂ�B
���̓��̂��߂Ɉ꒣���𒅂āA���̂ǂ̊���{���Ɋy�������ŁA���̎����ԑ҂��]��ł����Ƃ�����тŕ������悤�ȕ��͋C�ɕ�܂�Ă����B���̕��i�͍��ł��[���S�ɏĂ��t���Ă���B�ȑO�e���r�Ō������I�̃J�[�j�o���ɏo���Ⴂ�x��q�̃R�����g��"���̈�N�ԁA���ׂ̈ɐ����A�����撣���Ă����̂�I"�ƌ������^���Ȃ܂Ȃ������v���o���B
�l���̐ߖڂ₻�̐l�ɂƂ��Ă͑傫�Ȋ�т̎��A�������₩�Ȋy���݂̎��ł��A�����傢�Ɋy���ނ��߂̓w�͂ɂ͌����Ď���Ȃ��A�������[�A���̂Ă���ܐ�܂Ŏv�������肨���������āA�y���������������ׂ��S�O�Ȃ��ϋɓI�ɐl�Ɛڂ���B���Ƃ����̓w�͂����ʂɂȂ��Ă��A�I���Ă���̋��ɂ����Ȃ܂�Ă��őP��s�����B�߂������Ƃ�����Ēʂ肽�����Ƃ���t���鐢�̒��ŁA�l�͂���Ȃ��̎������邩�炱���������Ƃ����������Ă���̂��Ǝv���B���������̎��A���T�̎��A���C�Ȃ�����̊y���݂ɂ��Ă��鎖��ߖڂ̓���T���Ă���A����Ȓ���Ȃ������Ƀt�b�Ə������ݏグ�Ă���B
2007.05.29 (��) �\��H�������H �������\�I
��T�A�v���Ԃ�ɐ_�y��ɏo�������B������TV�h���}�̕���ɂȂ������ƂŁA���A�����̐l���W�܂�悤�ɂȂ��Ă���B�E�C�[�N�E�f�C�̗[��5���߂����炢����A�l�N�^�C����߂��T�����[�}�����ѓc�����ʂ���s��̗l�ɑ��X�Ɛ_�y���o���Ă���B�q���̍������������J����A������y���݂ɕ��Ɏ���Ђ���_�c���n���ėV�тɗ��������ł��Ȃ��݂̏ꏊ�ł���B�Â�����Ԗ��E�̓y�n���A�����͗Ⴆ�����ł��A����t�ɗ����̕����H�ׂ��̉��͏��X���߂̐ݒ�̓X�������A�����ɐΏ�Ƃ��������ȕ��͋C���ׂ������ɕY���Ă����B����͔ѓc��������߂��A���Ȃ�����̂�����̋������ɏW���Ƃ������Ƃʼn�����������`���Ă킴�킴���������ĕ����Ă݂��B���̐ԏ�_�Ђŋ{�i�����Ă���F�l��K���ɉ���Ă����v�ےʂ��n���A�c�����Ƃ��������Ȑ��m���X�g������������V�̖T�ɂ������̂����A���͖����Ȃ��Ă��܂����̂��������Ȃ������B�m���ѓc���̉w�O�ɂ��o���X������A������͍����ȉʕ��Ƃ�����g�����p�t�F�����o���Ă����B���̂����ׂ̌\��Ƃ����Ö����͌��݂������B���͂��̓X�ɂ͉��������v���o������B���Z����ɊÂ����̂���D���ȗF�l���ג��̒}�y�������ɏZ��ł����B�Q�l�Ŕѓc���߂��̋I�̑V�̂��`����H�ׂ���A���o���Č\���ʂ肩�������Ƃ���A�ˑR�I�ނ��疳����肱�̓X�ɉ������܂ꂽ�̂������o���Ă���B���i�Â��ő������j�̉����ɂ���Șr�͂��������̂��낤���A������Ȃ�ł��Ö����̃n�V�S�͊��قł���B�X�̒��ʼn����ⓚ���Ă��邤���ɂ��o�������������ė��Ă��܂������x���A������R�Ƃ��Ă���Ԃɏ����������������Ă��܂����B���X�̐l���q���A�㊄���������Ȃ̂Ɋw�����𒅂��j�̎q��2�l����͒����������̂��낤�A���낢��ƋC�������Ă��ꂽ�̂��o���Ă���B�t�������̎��h�̎���E�݁A���N���̂悤�ɂ�����������A�ނɂԂԂ���������Ȃ��牽�Ƃ��H�I�����̂������B���̘b�ɂ͂��̕����Ƃ��Ă���Șb������B
���̓��̌ߑO�̎��A�����̎��ƂŌ��c�搶�Ƃ����N�z�̐搶���A���w����̕��K�Ƃ��ĉ����ɂȂ��M����������Ƃɒ[���Ă���B����͐搶���w�����������A�̊Ö�����"���`�����\��t�H�ׂ�����ɂ��܂�"�Ƃ����傫�Ȓ��莆���������Ƃ����A�搶�B�͎Ⴓ����`���A�悵�I���킵�悤�Ƃ������ƂɂȂ����B6�t�܂ł͂Ȃ�Ƃ��������̂����A�댯���@�m�����X�̐e�������ꂩ��͕K���̌`���ŁA�����̗ʂ������̉��{�ɂ����đ~��������B�i���̎��̔��߂𒅂����c�搶���A�ڂ��Ԃ�v���������������������B�̏���U�����j�V�t�ڂ���́A�قƂ�ǂ��̉�̗l�Ȃ��`�����o���Ă����Ƃ����A�ǂ�����Ӓn�̒��荇�����������̂����A���������Ă��ɂȂ����搶�B�����ɔ������������Ƃ����B�������ɓX�̐e�����Ⴂ�w������ɐH�������̑S�z���x�����Ƃ͌��킸�A�����������Ă��ꂽ���������A���̎��̖ⓚ�������A"12�H�������H �������\�I"�Ɖ�����J��Ԃ��Č����A�قƂ�Ǘ����ԂɂȂ��Ă���B
�������^�ʖڂŏ�k������Ȃ��搶���A�����ɏオ�������Ƃ̏d���̂悤�ł���B���͂���A�̂̏����튯�̏��ԂɁA�\��w���A�A�A�Ӓ��A�����A���A�̂��Ƃ������B������i�\����H�ӌ���I�����イ�ɂ��������H�������������I�j�������ɂ���Ȗʔ����b�H�ŁA�o���������̂������B�������Őe��������������������܂ŋL���Ɏc���Ă���Ƃ͐搶�̑_���ʂ肾�B
���c�搶�̂��̎��̖��u�`�ŁA���ƗF�l�̗��R���r�̓��̒��Ɉ�Ԉ�ۂɎc�����̂͂������"���`��"�ł���B������2�l���J��o�����̂͊Ö����̂���_�y��Ƃ������Ƃ������B�����͔ѓc���̈��z�̂������l�}�}������I�J�m�Ƃ����i���X�Ɋ�蓹���鏊�����A���̎�����͐搶��"���`��"���������B�I�̑V�ƌ\��̃n�V�S�ł���B���̂Q�X�܂͍������C�ł���B
���̊E�G����������ς��A�߂��ɂ͍��w�}���V�����������A�t�@�~���X��R���r�j�A���̋������`�F�[�����������o�X���ė��Ă���B�������C�Ȃ������Ă����̂ɁA����ȉ��������������Â邵���Ɏv���o�������̂͐V��������̔g�������āA��z�̔O���N�����̂�������Ȃ��B���̎�������ĉ����֘A��ė��Ă��ꂽ�����A���c�搶���A�����ĎႭ���Đ������Â����D���̗F�l���������Ȃ��A�ǂ�ȂɊX���ς���Ă��A�������ꂩ������ɂƂ��Ă����_�y��́A���邽�тɂ��̍����v���o�������̏ꏊ�ł���B
2007.05.20 (��) �告�o�ϐ�L
�告�o5���ꏊ6���ځB��N9���ꏊ�ȗ��A8�����Ԃ�ɍ��Z�ق�`���Ă݂��B���ӂ̗��Z���g��2100�~�̓��ʎ��R�Ȃ����������悤�Ƃ����̂��������Ɏ��s�A�ߑO11���ɂ͔����ŏ��X�����ȐȂɒ������ƂɂȂ����B�����ŋߎv�����Ƃ͂����O�l�q�̑����ł���B���E�e���̐l�킪�����̍��Z�قɏW�܂��Ă���B���Ȃ���I�����s�b�N���̂悤�ł���B���R�Ȃ���͎m�������ȍ��������Ă��Ă���B�܂��ɓ��{�Ǝ��̍��Z����A���E�̃v���X�|�[�c�ւƕϑJ�𐋂�����������B���ꏊ�A���̂Ђ����Ȋ�]�̐��A�L�m���������Ɍm�Ò��Ƀv�����X�܂����̋Z���������E�Ђ��ƉE�Ђ���ɂ߂�5�A�s���A�������Տ��e�ɗ��r�����߂�ꕉ���Ă��܂����B168�Z���`�Ƃ��������Ȃ���啿�ȗ͎m�����]�����郏�U�͖{���ɑ告�o�̑�햡�𖡂��킹�Ă����͎m�ł���B�͂₭�ǂ��Ȃ��ė~�����ƐS����v���B�����āA�����������Ă���y�ʂ̈��n�����Q�ɒ��킵�����A�˂������C��������������̑P��ނȂ����s�ꂽ�B���Q�̋����Ɨ��������͊��ɉ��j�̕��i������Ă���B���n�Ƃ����͎m�͏����ւ̂������ƂƂ��ɁA�q���ǂ�ȑ��o���������̂���S���Ă���B����ɗ��\�̂Ȃ��ꐶ���������`��鐔���Ȃ��͎m���B���̑��o�E�̕�ł���B�H���̗��A�L�^���Ɠ��{�l�͎m�̊��҂̐�������Ă��邪�ȓ������ނ������A�Ƃɂ�������2�l�̓��{�̐��A��������Ȃ��悤�ɏ����ɂ����ė~�������̂��B
���o�͂����m�̂悤�ɑ̏d�ʃN���X�������Ȃ��A���������Ăǂ�Ȃɑ̏d���̂��鋐��ȑ���ɂł��A���̓y�U�ŗ���сA�܂킵��{�Ő��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Â��͓ȋтƑ���R�A���M�m�Ԃƍ����R�A���̊C�Ə��A�ŋ߂ł͖L�m���ƋՉ��B�A"���悭��𐧂��A"�̌��t�ǂ���A�S�R�̊i�̈Ⴄ���̂��y�U�̏�Ő��X���X�Ɛ킢�n���f�����y�ʂ̂��̂ł����A����͋`�o�A�����̎�������{�l�̍���ɗ���锻���т����̐S�����₪�����ɂ�����オ���Ԃł͂Ȃ����낤���A�V���̑o�t�R������A���a��30�N�㏉�����痧�h�ȑ̊i�����������Ȃ��̑傫�������A�S�r�̐��̎R�A���j�͎m�̋g�t�R�A�˂�����Ƌ��т̒����Ƃ����啿�͎m���㓙���Ă�������A�ȋтƎ�T�ԂƂ�����l�̏����͎m�̊���́A���̍��̐��̏��������ʑ����̓��{�l�̐S���ǂꂾ���E�C�t�������Ƃ��낤�B���Ȃ݂ɂ��̓�l�A�ȋт������A��T�Ԃ��O���M���̏��ΐ�̎��̑̏d�͂Ȃ��85�L����83�L���A����s�����H�t�����ӂɂ́A������͂邩�ɑ̂̑傫���d�����ȃI�^�N�����낲�낵�Ă���B���̏\���E�����̗͎m�B�̂��悻���������Ȃ������B���݂̗͎m�̋����ׂ��̏d���ł���B�̂��傫����Ή��ł��������瑦�E���o���I�̓��̔��z�́A����������Ă���̂��낤���B
���̔��ˁE�_�̑�Q�A�ǂ��������ʃ��C�o�����j�A���炵���قNj����k�̌ΑΉ����̍��̗֓��A���̒����̂悤�Ɉ�l�V���̈�C�T�A�E���t�̐��̕x�m�A����ȃn���C���Ύ�M�Z��A���������ĊO�����Έ��������{�̌Z��A���̎���w�i�����邱�ƂȂ����Ɉ����Ɛ��`�A�ǂ�������͂��鋭�҂̃��C�o���A�F��������Ɠ����ӌ����Ǝv�����A������ɂ���D�������̂����ɓ��{�l�͎m�����ė~�����Ǝv���B
�僊�[�O�̓��{�l�I��̊���ɋ����Ȃł��낷���������Ȃ��Ă������A���{�ɂ��Ȃ��猾����������̊O���l��i�̗��v�ׂ̈ɓ����Ă���T�����[�}����卑�̊�F���f���Ȃ��琶���Ă��鐭���Ƃ⊯���̑������̐��ŁA���߂ĐS�Z�́A���{�̐S�̌̋��ł��鑊�o�ɖ���y���������̂ł���B������"�ǂ���"��H�ׂɗ���������������c��A����o�X���ቺ��ʂ�A�[�Ŕ���X�����Ԃ�Ԃ�Ɠn��Ȃ���̂ЂƂ茾�B
2007.05.15 (��) �P���ӊO��
�ŋߖ��ACD��ǂ������悤�ɂȂ����B�������Ă��鎞�ɂ������悤�ɐS�����Ă���B���Ԃ�V��ɂ���ĂȂ�ƂȂ����̕��͋C�ɉ���y��T���Č���ƁA���̈ӊO���Ɍ˘f�����Ƃ�����B�J�̓��̒��Ƀn���C�A�����ƐS���a�ށA���{�f���"�t���K�[��"�̓���BGM�Ɏg���Ă����i���I��P�A���[�E���C�V�F���Ȃǂ̂��Ȃ�|�b�v�ł�OK�ł���B�X���b�N�E�L�[�E�M�^�[�̖{�i�h��j���O���[�v�Ȃ��C�C�A�����J�������̉J�̓����Ȃɂ��ǂ��������A�܂�ŃV�����[�̌�̃I�A�t���̊O��ɂ���C���ɂȂ�B
������Ɗ撣���ăV���O���E�����g�̂P�Q�N�`�P�T�N���̂Ȃ����b�N�ł��Ȃ���A ��X���ɕ����̂͑�l�̏������H�[�J���Ɍ���B�����͉����̒N��I�ڂ����Ȃ�Ďv���Ȃ���CD�̔w�\����T���Ă���ƁA�I���茩���̑剜�̓a�l�ɂȂ����C���ł���B�����A�I��Ȃ����������̎�ɉ��̋C���˂����Ȃ��ł�����̂��������A���̓_�ł����a�l���z���Ă���S���ł���B�r���[�E�z���f�C�A�T���E���H�[���A�T���i�E�W���[���Y�A�i�^���[�E�R�[���A�j�[�i�E�V�����A�ŋ߂̃m���E�W���[���Y�A��������肪�Ȃ����A���̒��ł����̎��ɂƂ��ăW�����[�E�����h���������A�ޏ��̑傫�����̊J�������m�N���̎ʐ^���p�[�v���ɔ��]���������̃W���P�b�g�A�V���O���E���R�[�h��"�z���o�̃T���t�����V�X�R"���q���̎�����厖�ɂ��Ă����̂����A�A���o�����Ă���Ȃɂ����̎�ł��邱�Ƃ͑�l�ɂȂ�܂Œm��Ȃ������B����܂ł̓����f�B�E�N���t�H�[�h�ƃW���[�E�T���v���̍�N�̍�i�A"�t�B�[�����O�E�O�b�h"�ɂ͂܂��Ă����B���̑O�͍ň��̃h���C�u�̗F�ł�������n�̃_�C�A�i�E�N���[���A���܂��W�����[�̉̐����Ă���B�ޏ��̒�߂̊��������ƃr�u���[�g�A�̐S�̂��ׂĂ������B���ɂƂ��Ẳ��y�́A�������̎��̐S�̕����܂܍D���Ȃ��̂��A���Ɩ�X���ƃW�����[�E�����h���ł���B���̂R���������Ȃ�C�C��ɂȂ�B ������ŋ��k�����A�r�[�������������G�߂ɂȂ��Ă����B���͌����ăA�����ł͂Ȃ����A�ʃr�[����Ў�ɒ�������̋x���ɂ̓g�D�[�c�E�V�[���}���̃n�[���j�J�����E�߂���B ���������Ă����C���邢�ߌ�ɁA�܂Ƃ�蒅���悤�ɗD���������̂ɟ��ݍ���ł���B �S�͓앗�ɐ�����Ȃ���n�����b�N�ŗh��Ă���悤�ł���B�l�������ǂ��ɂł��Ȃ��A�Ƃ����������ȐS�����Ɣς킵�������Ȏ����C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B�������̂����₩�Ȍo����A��X���ɂ���A�x���̌ߌ�ɂ���A�m��������ł̈��݂����ɂ͗v���ӂł���B
���āA������������̉��y�I�тɂȂ��Ă��܂������A�����̃e�[�}�̓o�b�h�ł͂Ȃ��A�O�b�h�ȈӖ��ł̈ӊO���ł���B�J�~��̒��̃n���C�A���A��X���̃��H�[�J���A�ߌ�̃n�[���j�J�A�펯��T�O�����ł͐l���͑ދ��Ȃ������B�ƂĂ�������Ȃ��Ǝv���Ă��鎖��l�Ԃ��A�����Ȃ艽���̂Ƃ��ɑf���炵�����a��˔\�������Ă����B����ȑf���炵���ӊO�������͑�D�����B�Ⴆ�A�Z�����F�ɉ��F�����킹�邩�A���ʂ̓x�[�W���Ȃǂ̒g�F�n�Ŗ���ɂ܂Ƃ߂����������A�����ɑN�₩�Ȑ��F�����킹��ƒ����_���Ȓ��a���������肷��B��������͐l�ɂ��Ă̈ӊO���ɂȂ�B�������ʂ̒j�����鎖�Ő����D������ʂ���������A���A���i���y�̂��̎����Ȃ��l�Ԃ��A�s�A�m�̒u���Ă���o�[�œˑR�����t���I������A�������Ɠ������x�����߂̐l�Ԃ��A�N���u�ł����Ȃ�f���炵���_���T�[�ɕϐg������A����ȈȊO�����邽�тɋ����ƐV�N�Ȋ������o���Ă����B
�l���͈ӊO�������邩��y�����A�������ꂪ�Ȃ���Ή��Ƃ܂�Ȃ����̒����낤�Ǝv���B�ӊO���͎����̒��Ɉ������������邱�ƁA���͂����Đ��܂ꂽ���ɒ[�ȓ�ʐ��̂ǂ��炩���ۗ������낤�B�����ȒP�ɐl������������O�b�h�ȈӊO���͎�ɓ���Ȃ��A������ɍ�낤�Ƃ���Ɩ��l�Ƃ��������������B�ꂷ��B�{���A����͐S�ɔ|���Â��ɔ�߂Ă�����́A�d�v�Ȃ̂͂����Ƃ��\���̂ł͂Ȃ���߂Ă��鎖�A���ꂪ�������\����ɗ��������A�����܂��Ė��͓I�ɋP���𑝂����̂��B
2007.05.02 (��) �����ȎԂ̘b
����ǂ{�ɁA���h�C�c�Ɛ��h�C�c��������Ă�������̘b���������B�����̓����Z�f�X��BMW�A�A�E�f�C�����A�E�g�o�[���œr���������X�s�[�h�ő������Ă��鍠�A�����ł͍ō�����100�L������������600CC�ɂ������Ȃ����G���W�����悹���A�g���o���g601�Ƃ����Ԃ������Ԃ̂悤�ɑ���܂���Ă����Ƃ����B����Șb��ǂ�Ŏv���o�����̂����A�O�ɂ��L�����u�_�y�X�g�ɍs�������̎��A�j���[�g���E�t�@�~���[�Ƃ����o���h�̏������H�[�J���A�`�F�v���M�E�G�[���@�����L���Ă����Ԃ��܂��ɂ��̎Ԃ������B�y�X�g�X�ɂ��������R�[�f�B���O�E�X�^�W�I���玄�̔��܂��Ă���z�e���i�h�i�E��̒��̓��ɂ��鋌���e���}���E�z�e���j�܂ł��̎Ԃő����Ă��ꂽ�̂����A�p�^�p�^�ƂȂ�Ƃ�����Ȃ��G���W�������Ȃ���ꐶ���������Ă��������Ԃ������B���{�̃X�Y�L�����Ԃ�1955�N���瑢���Ă����X�Y���C�g�i�y�����ԃt�����e�̑O�g�j�Ƃ����Ԃ��霂Ƃ����鏬���ȎԂŁA�܂�Ńu���L�̂������Ⴊ���̂܂ܑ傫���Ȃ����悤�Ȃ��̂������B�����Ă���Ƃ����ȏ�����M�V�M�V�Ƃ����މ����ԓ��ɏ[�����A���~�܂��Ă��܂��̂��n���n�������B���̓��A���̃o���h�E�����o�[���炠�̎Ԃɏ���ėǂ��������ɍ������}����ꂽ���̂��ƁA��k�Ƃ��{�C�Ƃ����Ȃ��悤�Ȏ��������ď�ꂽ�̂��o���Ă���B���̍��n���K���[�͐����Ƃ͂����Љ��`�̍��ł���A���h�C�c�Ƃ̌𗬂�f�Ղ͓��R�̂��Ƃ��s�Ȃ��Ă����̂��낤�B�����A�����o�[�̒��ɂ͎��Ƃ��������̏����ƌ��������_�X�e�C���E�z�t�}�����ŁA�h�����X�S���̃W�����E�o���h�[�c�B�́A���Ȃ�̏d�łɂ�������炸�����Z�f�X�̃��S���ɏ���Ă����B���̌�g���o���g601�̔����A�`�F�v���M�̓O���[�v�̃M�^�[�S���̃A�_���E�x�O���@�[���ƂQ�l�ŗ������āA1983�N�̃��}�n���E�̗w�ՂɎQ���A"���̂䂭��"�Ƃ����ȂŃO�����v�����l�����A�܋��ł���10,000�h�����o���h�̊W�҂ƎR���������B
�����āA������̏����ȎԂ̎v���o�Ƀ��b�T�[�V���~�b�g�Ƃ����Ԃ�����B���̐́A�܂��y���֍s���̂ɂ��˂��˂Ɗ�d�ɂ��Ȃ���O�X�������Ȃ����̂��Ƃł���B���̍�VAN�W���P�b�g�̃A�C�r�[�E���b�N�ɐg���݁A4711�̊��k�n�R�������D��������4�N��y��T�����A���̃��b�T�[�V���~�b�g�ł͂�铌������O�X����o���Ď��B�����N�s�Ȃ��Ă����y���̃L�����v�ւ���Ă������Ƃ��������B���ꂱ������Ƃ��ǂ蒅�����Ƃ����\�����҂�����ŁA�����ɓ�����������{���Ɋ��ł����B���̎Ԃ͂Ȃ�ƂR�ւŁA�O�ƌ��A�c��2�l�����d�l�ɂȂ��Ă���B�킸��200CC���炢�̏����ȃG���W����ς�ł��āA��l2�l���悹���R�ȓ��𑖂�̂���ς��낤�ɁA���v�����̉O�X����o�������Ƃɂ���������������ł���B����T���A�����v���^�[�Y�̃I�����[�E���[���A�J�y���Ō����ɉ̂��Ă͎��������킹���B
����Ȏ��ォ�獡���܂ŁA�����̎Ԃ̓��f���`�F���W�̓x�ɔ�剻���A���{�̊X��w�̍����傫��SUV����{�b�N�X���p�ɂɍs�������̂�����ɂ��A���̍��̎Ԃ͂Ȃ�Ə������ؚ��������̂��낤���Ǝv���B�Ԃ̐��\�⓹�H�̔��B�ƂƂ��ɁA�傫�����S�ł������Â��ŃX�s�[�h���o��Ԃ�������O�ɂȂ����B�̏�ׁ̈A���[�ɎԂ��߂ă{���l�b�g���J���Ă���l���قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����B�Ԃ̑I������������ł�����A������j�[�Y�̂��ׂĂ���������Ă��܂����A����f�B�[���[�̏C���S���҂́A�قƂ�ǂ̕��i�̓R���s���[�^�[����œ����Ă���̂ŁA�����Ȃ���̕������̂ł͂Ȃ��A�������肻�̕��i��������d���ɂȂ����Ƃ����B�ԎЉ���W�r�ゾ�������̍��́A����̉����肪��������悤�ȎԂ��K���[�W�Ɏd�������݁A�{��Ў�ɁA�����Ǝ����Ń����e�i���X��X�g�A�Ȃǂ���鎖���Ă��܂��A�������̂˂���̂��̍��ł���B
2007.04.15 (��) �S�Ɏc�閼��ʂƂ�
�Â��f��̗\���҂����ҏW���āADVD�Ŕ���o�����Ƃ��Ă���l�����̒m�荇���ɂ���B�v�����ł͂ƂĂ������Ǝv���̂����A�ʂ����Ă��ꂪ����グ�Ɍ��т��Ă����̂��͑����s�����c��B�m���ɉf��̈�ԃL���ƂȂ�V�[���������W�߂Đ���ҁA�f���ЂȂǂ��C�������č����̂�����A���̉f��̑S�̂̎�|�₩�����悳�Ȃǂ�Z���ԂŊ_�Ԍ��邱�Ƃ��o����B���������̗\���҂͏o���@���ŋq�̓��������܂肩�˂Ȃ��d�v�Ȃ��̂��B�]�k�ɂȂ邪�f��̐����A�s�����͏����̋q�̓����łقƂ�nj��������Ƃ����A���Ȃ�M�����u�������������̂��Ƃ������Ƃ��f���Ђ̐�`�}�����畷�������Ƃ�����B���͂Ƃ����ꂱ�̊��A�f��D���̋L�^�p�Ƃ��Ă͂ƂĂ������A�C�e���ɂ͂Ȃ邾�낤�B������������������Č����킯�ł͂Ȃ��̂����牽�Ƃ������܂ł̘b�ɂȂ��Ă��܂��̂����A������q���g�Ɏ������g�����܂Ō����f��̒��ŁA�ǂ̃V�[����\���҂ɂ���̂����v�����点�Č���Ɩʔ������ɋC�t���A�ӊO�Ȃ͎̂��ɂƂ��ăI�[�v�j���O�̃V�[���������ɏd�v�ł��鎖�����킩�����B�Ⴆ�A�����E�h�������Y������"���X�{�����}"�ł͗[�ł��܂锖�Â��C�ӂ̒��ɉJ���~���Ă���B�Ԃ̃��C�p�[���Ђ�����Ȃ��Ƀt�����g�E�E�B���h�[��@���Ă���B���̊C�ӂ̒��͐V�������ȃA�p�[�g����������ł��Ă����ɂ��O��̐V���Z��n�̕��͋C�������Ă����̂ł���B"�h���̃��}��"�ł̓t�����X�̐Â��ȓc�ɒ��̃��}��������B���̊X�͈�N�Ɉ�x�A�����ԃ��[�X�̊��Ԃ������E������l���W�܂�TV���p�ȂǂŒ��ڂ����B���̐Â��ȃ��}�������G���W���Ɠ��̊����������������č����i���[�E�|���V�F�i911�̏����^�j�ł����𑖂�V�[���Ŏn�܂�B�h���C�o�[�͂��̃X�e�B�[�u�E�}�b�N�B�[���A���[�X���Ɏ������N�����Ă��܂������̌���ŎԂ��߂ĉ�z����V�[���܂ŁA�܂��ɔނ����o���Ȃ��������悳�ł���B���A�I�[�h���[�������̃j���[���[�N5�ԊX�ɂ���e�B�t�@�j�[�̑O�ŕ�����Ȃ���p����E��ł���B�f��^�C�g�����̂��̂��I�[�v�j���O�̃V�[���ɂȂ���"�e�B�t�@�j�[�Œ��H��"�B������"�E�G�X�g�E�T�C�h�E�X�g�[���["�ł̓j���[���[�N�̏���B���s�Ȃ���B�Z���g�����E�p�[�N����_�E���E�^�E���։������炩���J�ƃR���K�̉��A�����Ɏw��e�������������Ă���B�o�X�P�b�g�E�{�[���̃R�[�g�ɂȂ��Ă���n�̏�ɂ���������Ƃ��̎w�̖���ɃJ�����͉���Ă䂭�B�����ʼn��̌��ł����l���̃W�F�b�g�c�������B�����悤�Ȏ�@�̂��̂ł�"�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N"�̋�B���f���炵���B�ŏ��͂̂ǂ��ȏ��Ȃ�����A�ϋq�̉�X�͉_�̒�����ł���̂����A�₪�Ė�������ėy���ɎR���������Ă���B���̒��̉����ĕė��̂悤�ɏ����ȃW�����[�E�A���h�����[�X�ɃJ���������X�ɋ߂Â��Ă䂭�V�[���B�����ď��Ȃ��炢�悢��Ȃ͐���オ��ޏ��̉̂��n�܂�Ɠ����ɃJ�����͒n��ɍ~���B�ォ�畷�����b�ł͂��̃V�[���͎B�e�����o���҂���ςȋ�J���������Ƃ����B����Ƃ������̂͌��܂��đf���炵���V�[���������Ă���B���������������I�[�v�j���O�E�V�[���͗\���҂ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����낤�B����ƌ����Ȃ��Ƃ������ɂƂ��đf���炵���V�[��������A����͂��ꂼ��̐S�ɏĂ����A�����܂ł��Y����Ȃ��f��ƂȂ�B�������ɒu���Y��Ă��܂����̂�������Ȃ����A�ӂƎ����g�̐l���̒��Ŗ���ʂ͉��������̂��낤���ƈꐶ�����v�����点�T���Č����B���R�ƌ����Ă��܂�����܂łȂ̂����A�F���ł���B�c�O�Ȃ���p���������V�[���͎����玟�ւƔ]���ɕ�����ł��Ă͗��܂鏊��m��Ȃ��B
���āA�S�ł���ʂƂ�50�N�A����100�N����l�X�Ɉ����ꑱ����A�r�{�Ƃ�V���̖��ēA���D���������̈�u�ׂ̈ɑ����̎��ԂƐS���𒍂������ƃ��}���̌����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�Ō�ɂ������"���[�}�̋x��"�̃��X�g�V�[���ŁA�N�����Ȃ��Ȃ����L�҉��ɐÂ��ɋ����R�c�A�R�c�A�Ƃ��������B�萶�������͂��݂��̐g���̈Ⴂ�Œ������Ȃ��A���̈��䂦�ɐ��I�̓��_�l���Y��Ȏv���o�ɑւ����j�̗D�����A�O���S���[�E�y�b�N�̈��D�����鑫���Ŗ{���̖������낷���Ƃɂ���B
2007.03.20 (��) ���E�ӂꂠ���X����
�s�u���܂�Ȃ��Ɗ�����悤�ɂȂ��ĉ��N���̂��낤�B�����̓����悤�Ȋ�Ԃ�̏o���҂����̔n��������CM���ʂ̑傫���A��̌��ʂ��o��܂ł���ł����Ɠ���CM����������B����ȏ��������A�ŋ߂�����Ɩʔ����ԑg���������BNHK�̑����ł͖ؗj���̐[��A�n�C�r�W�����Ȃ炩�Ȃ�p�ɂɌ��邱�Ƃ��o����"���E�ӂꂠ���X����"�Ƃ����ԑg�ł���B���͂��Ȃ藷�D���ł����ȏ��֍s���̂���D���Ȃ̂����A���̔ԑg������Ƃ�͂萢�E�͍L���A�����ɍs���ĂȂ����������ɑ������Ƃ����킩��B����Ȃ�̌���ꂽ�\�Z�Ŕԑg������Ă���悤���B�n���̈ē��l���J�����}���Ɛ��l�Ŏ�ނ̊X����������B�J�����͐l�̖ڂ̍����Ȃ̂ł܂�Ŏ����������ŗ��l�ɂȂ��Ă���悤�ȋC���ɂ�������B�s������̂��̒��̐l�̎��R�����J�����Ɏʂ�B�Ƃ������̎�̔ԑg�͎��R�����Ȃ��烄���Z���o���o���ȏꍇ���������̂����A����Ɋւ��Ă͌��m��ʗ��l���i��̒n���̈ē��l�j�ɂ����ł̐������y����ł���l�����߂Đ����������Ă��邱�Ƃ��f�l�ڂɂ��킩��A�������⍑�����A�y�n���Ȃǂ���������B
����A���̔ԑg�Ńn���K���[�̃u�_�y�X�g������Ă����̂����A20���N�O�A�������R�[�f�B���O�̎d���ł��̊X�֍s�����Ƃ��̎Љ��`���F�Z���c���C�Ƃ͂����Ԃ����Ă����B���m�g�[���������X���݂����Ȃ�₢�ł��Ď��̗��������������B���̐́A�u�_�y�X�g�̓p����E�B�[���ƕ��ԃ��[���b�p���\����ؗ�ȓs�Ƃ��Ė���y���Ă����B���̐^���h�i�E�삪����A�u�_�X�ƃy�X�g�X�ɕ�����Ă���B�y�X�g�X�ɂ͊�����N���o�Ă���B�}�W���[�����b���A���̔����͔��ɓ��{��ɋ߂��A�������������A���[���b�p���ł͒������A���܂��q���̐K�ɖÔ��������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�܂��A���Ɩ������{�Ɠ����ŁA������Ŗ�����ɗ���B�����Ɛe���݂������邨�������B�������A�����s�������͎s�������������ƃ\�A�̕�����p�ɂɌ������A56�N�̃n���K���[�����̉e���F�Z���c���Ă����̂��o���Ă���B���̎v���o�������Ԃ�Ό��e�p��15���ȏ�ɋy�Ԃ��ƂɂȂ�̂ŁA����܂łɂ��Ă������A�{���ɋv���Ԃ�ɂ��̃}�W���[������A����̉��œ������X���̉���v�[�����f���o���ꂽ�B�J�����I�����l�X���W�܂�A�傫�Ȑ��̃}�W���[���ꂪ��ь����r���E�z�[���ŁA�����ɕ��ŐH�ׂ��A�d���������h���������Ղ�������n���o�[�O�̖��Ȃǂ���݂�����A���������܂��Ăэs���Ă݂����Ȃ����B
�ŋ߂̎��͒N���ǂ�ȉƂɏZ�������A��������A�H�ׂ��肵�悤�����܂�S�͂Ȃ��̂����A���A���Ɍ����Ă͕ʂł���B���Ɍ��m��ʂЂȂт��C�ӂ̊X��s��Ȃ������A�l�̐���G���̉����A���̋�C���z���Ă��邱�Ƃ������ɑA�܂����Ȃ鎖������B�l�͗�������Ƃ������Ƃɐl���𓊉e�����A����l�͖��������Ă����B���O�A������D���ŎႩ�������̗��������Ԃ����Ă��ꂽ�B���̑f���炵���������Ă��ꂽ���Ƃ��������Ċ��ӂ��Ă���B�ǂ����Ԃ͐S�̍��Y�A�����������֏����Ă��܂�������ÂтĂ��܂����ƈႢ�A�����ɂȂ��Ă��D���ȂƂ��ɐS�Ɉ����o����f���炵�����̂��Ǝv���B���̔ԑg�����܂ő������Ƃ��낤�A����撣���Ăق������̂ł���B���Ȃ���ɂ��Č��m��ʊX���s���A�����ł����݂Ȃ���ق��ƈꑧ���ɂ͂ƂĂ��ǂ����Ԃ��B
2007.03.18 (��) �����ō�
�������܂��������ō��A�ʔ����b�Ő���オ���Ă���B��y����ѓc�����������10���قǂ̏��Ȃ̂����A�ĊJ���œ��H���g�����ꂽ����̊�Ƃ��ڂ��Ă�����ŁA���͂�l���Â��ɏZ�ނƂ���ł͂Ȃ��A�ʋŒʂ��I�t�B�X�X�ɕϖe������B�̖̂ʉe�͍������Ƃ�����Ȃ̂����A����ȏ��ɍŋ߁A���낤���Ƃ���Ȗ�Ȃ��鐶�������o������Ƃ����̂��B���ɐ���A���̌Z�����̉\�̐������ɏo���킵���̂��������B�[�ł����܂钆�A�L�ɂ��Ă͑傫���������Ⴄ���̂��ڂ̏�̍����̓y��ɂ����Ƃ����A����Ɩڂ��������炭���l�ߍ����Ă����̂����A����͊ԈႢ�Ȃ��K�Ȃ̂��������B�旧���w�̓쓌�̓y��A�܂莄�̎��Ƃ̉��ɂP�O�O�قǂ̓y�肪����B���̒��̌��ɂł�����ł���̂ł͂Ƃ����b�Ȃ̂����A���ߏ��ł�����������l�����āA���̎��͂Q�C�ł����Ƃ����b���B�ւ�O���A�l�̂������Ȃ�b�͂킩�邪�A���������̐^�łȂ�ƒK�ł���B�y�b�g�Ƃ��Ď����Ă����̂��A�w�Z�Ŏ���ꂽ���̂Ȃ̂��A����Ƃ��������炩�������тĂ������̂Ȃ̂��A�^�₪�^����Ă�ł���B�����A�}���V�����X�Ńy�b�g�Ƃ��ĒK���������Ƃ́A�܂��Ȃ����낤�A�������ǂ�ȕ��D���ȃy�b�g�E�V���b�v�ł��قƂ�ǒK�͔����Ă��Ȃ��B�w�Z�ł�����Ƃ��Ă͂�قǂ̂��Ƃ��Ȃ����莔���\���͒Ⴂ���낤�B�ł͌�y���������ė����̂��A��y���͗V���n��g�[�L���[�E�h�[���ȂǂŗL�������A�{���A�����͐��ˌ����̕ʓ@�ŁA���������ȍ����琅�˗l�ƌĂ�ł悭�V�тɂ����������B�m���ɒK��C�^�`�̗ނ��������Ă��Ă����������͖������̐X���傫�ȂQ�̒r�A�Ҋ��c��~�т�����B�����������̗т̒��ɓ���Ɩ��ȓ����L�����������Ƃ��������B����ƍl������͖̂k�Ɉʒu���鏬�ΐ�A���������A����ɂ͑傫�ȏt���ʂ���Βʂ�����z���āA����ƍN�̕ꂪ����`�ʉ@�Ƃ�����������u���z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͒K�ɂƂ��Ă��Ȃ�V���h�C���Ȃ̂ŁA���̏���y�������L�͂��B�����ATV�ǂ��Ƃт������Ȃ��̓��_�l�b���ƂŎ������ɘb�������Ƃ���A���B�͑S�R������"���B�̊w�Z�ɂ͒K���o�邵�A�n�N�r�V���܂ŏo��̂�"�Ƃ̎��A����ɂ͓�x�r�b�N���ł���B���B�̊w�Z�͍��c�n�ꂩ�瑁��c���ʂɕ�����15���قǂ̏��q�Z�Ȃ̂����A����ȓs��ɂ��Ƃ�ł��Ȃ��쐶���������Ă����B�W���R�E�l�R�Ȃ̂��̃n�N�r�V���ł���B�������ɂ���������Ƃ��͕a���ۂ̊W�Ŋw�Z�ɕ����Ȃ���s���Ȃ����ƂɂȂ��Ă���Ƃ̎����B��������Șb�����Ă��邤���Ɋy�����Ȃ��Ă��āA�����O�̂��Ƃ��v���o�����B�m����N�A�H����̂���₩�Ȓ��Ɍ��ƎU�����Ă���ƁA�ُ�Ȓ������̐�������̂ŏ������グ����A1�H�̃J���X��7�H���炢������������Ă����B�������傫�ȃJ���X�߂����ėE���ɂ����x�Ɩ������Ԃ�����Ȃ���ˌ�������̂ł���B�J���X���d���ɂƂ܂��Ă��U���̎���ɂ߂Ȃ��A���炭���Ă��Ă킩�����͔̂����̒��ɂЂƂ���̂̏����ȃq�i�����邱�Ƃ��킩�����B������J���X���_�����̑����ɂȂ����̂������B�����J���X�͑ގU�A�e����2�H�������Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���̒��Ԃ��������Ńq�i����邱�Ƃ�ڂ̓�����ɂ��ċ����M���Ȃ����B�����Ă�����̂����Č��ʐU������Ēʂ肷���鉽�����̐������Ƃ͂��炢�Ⴂ�ł���B����Ȏ����v���o���Ȃ���l�����B�r���̒��ł͑����̐l�Ԃ�����������߂ē����Ȉ���p�\�R���Ɍ������d�������Ă���B�O�ɂ̓o�C�N��Ԃ��r�C�K�X���T���U�炵�Ȃ��瑖����A�����d�Ԃ̒��ł͌g�ѕЎ�ɉ��������Ȃ��疈�����炵�Ă���B����ȓ����̃h�^�Ől���v�������Ȃ������⎩�R���������ɂ��āA�ق�̏����Ȍ��Ԃ��ꐶ�������������Ă���B�Ȃ�Ƃ����܂����E�C�t������b�ł͂Ȃ����낤���B
2006.11.26 (��) �N���͍]�ˋC��
����A�F�l�̂m���ƍc�����䉑�ɍs���Ă����B�F����͍]�ˏ�̓V��t�ՂƂ��A���b�����[�̎������N�������̘L���Փ������w�ł���̂������m���낤���A�p�������Ȃ��玄�͂�������3�w�̂Ƃ���ɐ��܂�炿�Ȃ���A�c���̒��Ō��d�Ȍx���̂��ƁA�s�����Ƃ����邱�Ƃ��o���Ȃ����̂��Ǝv���Ă����B����Ȃ��Ƃ��m��Ȃ��̂��Ƃ������������邾�낤���A�g�߂ȃ��T�[�`�̌��ʁA�ӊO�ƒm���Ă��Ȃ��Ǝv�������ɂ��Љ��B�������̒|���ō~��Ă���A���x�ʂ��n���ĕ���傩��������B���Ȃ�ɍs�������v���X�`�b�N�̎D��Ⴄ�A���ꂪ�������ƂȂ�A�o��Ƃ��ɂ�������o���ċA��B���̑��o������͖k�j����Ƒ��傪����B������̖�ł�����ۂɎD��Ⴂ�����̖�ł��o����B���j�Ƌ��j���x�݂��������B�܂������āA�s��̃h�^�ɂ���ȂɐÂ��ōL��������肵���ꏊ�����鎖�ɋ����B���a�c�@�̊җ���L�O���Č������ꂽ���������؊y�������Ɍ��Ȃ�������ƍ]�ˏ�V��t�Ղɂł�A����18���[�g���̐Ί_�����̂��̂����A���̏��5�w�̓V��t�������Ă����Ƃ����B�Ί_�̏ォ��͓쐼�ɑ�蒬�����J�̑傫�ȃr���X�����ʂ���B���̌i�F�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂��B���̑��L���䉑�ɂ͋��S�l�ԏ����Y��Ȓ�X��L���Ő�������A�Â��Ȏ��Ԃ���������B�����ɒr������̂͌�Ńq���������Ƃ����ʔ��������j���ł���B��Ղ̓쐼�ɏ��̘L���Ղ̔肪�����Ă���B�������獡���̖{��ɓ���B1701�N�i���\14�N�j��3���A�g�Ǐ���Ɛ��������̓����������N�������ꏊ���Ǝv���ƂȂ��s�v�c�ȋC�����ɂȂ�B���̎����A�c���������ɂ��Ɛ����̂����߂��q�Ɛ����̒Z�C�Ƃ�����l�Ȃ̂����A���������ɂ܂ŋy���e�͂��܂��ɓ�߂��Ă���B�w����̋g�ǂ����̕t���͂������Ȃ��A���𗧂č��ʂ������Ƃ�����������B���̖L���Ȗ�l�B�ƈႢ�A���̎���͓o�邷����A������鑤�����Ȃ茵���������������Ƃ����B�����ł́A���������ƃX�g���[�g�ɐ�����Ƃ������Ƃɐ^���������̂��낤�B�Ƃɂ������]�Ȑ܁A���̘b�������炩���{��3��w�����̑�\�i�ƂȂ�A�ߑ���{�̔N���̃}�X�R�~�p�ڋʏ��i�ƂȂ������͂����܂ł��Ȃ��B���ʓ��{�l�͋w�������̂���D���ɂȂ����B�����œˑR�����v�������A�t���̒��b���c�A�[����悵�Ă݂��B�܂��O���̖�A�r�f�I�ʼnf��̒��b��������B�Ȃ�ׂ��Љ���b�������J���v�̎���A�S�������ċєV���܂łƂ���B�����Ď��̓��A�c�����䉑�̏��̘L���Ձi���������Ă��邾���Ȃ̂����j�����w�A���傩��o�āA�s�c�����g���O�c�抷���Ő�x���ցA�l�\���m�̕�Q��̌�͎����قœ�������̍ۂɎ��ێg��ꂽ���̂Ȃǂ����w�A�����͋t�ɂȂ邪�������疔�A�s�c���ɏ����抷���ŗ����ցA�{�����⒬�̋g�Ǔ@�i�{�����⒬�����̈ꕔ�j�����w�A���Ƃ��Ƌg�Ǔ@�͌������ɂ������̂����A���̎����ȗ��A�����ԕ�Q�m�̋w�����Ȃǂō]�˂̐^�ő������N������ʓ|�ƁA�܂��V���Z��n�ł��������̒n�ɓ@���ڂ��ꂽ�����ł���B����Șb���Ɩ��{�͋w������\�����Ă����̂��Ƃ������ƂɂȂ�B���̏����O�ɖ{���[��ŏ����m�Ԃ��ǂ�i�H�[���ׂ͂Ȃɂ�����l���j�Ɖr�������炢�Â�����̉����ƈႢ�A�����͗ߏ��̕t�������͂Ȃ������悤���B����䂦�ɓ�������͐��������Ƃ����Ă���B���̌�A���Ԃ�����Η����k���̍]�˓��������قŎ���w�i�Ȃǂ����w�A�[�H�͂������炷���̉X����n���ĕ����Ă�������A�^�N�V�[�Ȃ烏�����[�^�[��"����ǂ���"�ŁA���N�̎����s�\���ۂ����������Ȃ���A�M���ƍ��݃l�M�������莩�R�̂ǂ��傤������B���̌�A�C�������Ε����Đ̐_�J�o�[�ŁA���Ȃ��F���b���Œ��߂�Ƃ����̂͂ǂ����낤�B
2006.11.19 (��) �ߗ��Ɖ��F�����[���X
�f�恃���F�����[���X�E���C�X�����P�O�N�Ԃ�Ō����B�����m�̂Ƃ��胍�[���X�E���C�X�͎Ԃ̉��l�I���݂Ń��[�J�[�����̃v���C�h�䂦�ɐ��܂ꂽ���X�̈�b�ݏo���Ă����B���̒��ł�����Ȗʔ����b������B����Ƃ��A�A���v�X�̎R�̒��Ń��[���X�E���C�X���̏Ⴕ���B�����傪�����ă��[���X�Ђɓd�b����ꂽ�Ƃ���A��������Ƃ��Ȃ��w���R�v�^�[������āA���̎Ԃ��Ĕ�ы����Ă������Ƃ����B���ꂩ�牽�����o���A���̎��̋��̎x�����̌��ŘA���������A�ꌾ"���[���X�E���C�X�͌̏Ⴂ�����܂���"�Ƃ����������Ȃ��Ԏ����Ԃ��Ă����Ƃ����B�̂���ԍD���̊Ԃł͌��p���ꂽ��b�ł���B���̉f��͈��̉��F�����[���X�E���C�X�𒆐S�ɁA���ꂼ��̐l���͗l���R����̃I���j�o�X�ŒԂ��Ă���B���b�͐V�Ԃ̃��[���X���y�����ă����h���̒����s���V�[������n�܂�B���b�N�X�E�n���\��������O����b�����݂��A���x��̌����L�O���ɍȖ��̃W�����k�E�����[�ւ��̎Ԃ�B�������A���̍Ȃ͎Ⴋ�O�����Ƃ̓��Ȃ�ʗ��ɂ���Ƃ����ݒ�B���b�N�X�E�n���\���Ƃ����u�}�C�E�t�F�A�E���f�B�v�̃q�M���Y������h���g���搶�Ȃǂ̉p���a�m�̎�{�̂悤�Ȗ��蒅���Ă���B�Ԃ̃V���[�E���[���ł̘V�Z�[���X�E�}���Ǝԓ��̓d�b�̈ʒu��f�J���^�̌`�̂����́A���Ă�����܂Ń��b�`�ȋC���ɂ����Ă����B�����A�e�̂���m�I�Ȗ̑����W�����k�E�����[�͍���̖��Ɍ���A�����̑Ë����������Ƃ����Ă������낤�B���b�͂��̉f��̃��C�����B����̓C�^���A�A���b�̉��F�����[���X���M�����O�ɕ�����W���[�W�E�b�E�X�R�b�g���ό��p�Ɏg���B��w���̃V���[���[�E�}�N���[���̍D�����f���炵���B�u�`�����X�v������A�u�A�p�[�g�̌��݂��܂��v������A�����Ƃڂ�����������������������ޏ��ɂ��Ȃ����D�͂��Ȃ��B����ɗ��ފό��n�œ����A�i���p�Ȏʐ^�t���̃A�����E�h���������邭�Čy�����B�ނ��o�������u���삳����炩�Ɂv�̃L�����N�^�[�ƃ_�u���̂����A���̎�̃v���C�E�{�[�C������点�Ă����ꗬ�ł���B�A�����J�֍s�����X�R�b�g�̗��璆�ɂ��̓�l�͗��ɗ�����B�M�����O�̏�w�䂦�ɗ��l�̖�����Ȃ��Ȃ邱�ƂŁA�h�����Ƃ̗�����߂�B��J���Ȃ���������ȐS���������������������{���̗���m��A��W�ȏ����ĕʂ��������V�[���͎v�킸�ق���Ƃ�������B���̑��b�����Ɏg������̂�"�t�H�Q�b�g�E�h�}�[�j"������A�h�������J�t�F�ł��̋Ȃ̃����E�t���[�Y���̂��B����"���A"�̍쎌�ł��m���Ă���m�[�}���E�j���[�E�F���̋ȂŁA�쉢�̕����^��ł����B��O�b�̓C���O���b�h�E�o�[�O�}���ƃI�}�[�E�V�����t�A����͓����̃��[�S�B�푈�Ƃ����d���e�[�}�ɂȂ�̂����A�u�J�T�u�����J�v����18�N�o���A�ј\�Ǝ��M�Ɉ��A���D�Ƃ��Ẳ~�n���ɓ������o�[�O�}�����č��̋C��ȋM�w�l����M�����Ă���B�u�A���r�A�̃������X�v�Ŕ��͂���x�h�E�B�����̎�̖��������I�}�[�E�V�����t�́A���x�͉���R�̎�̂������A�Ԃƃo�[�O�}���ɏ�������B���̂悤�ɂ����ȃI�[�i�[�Ƃ̏o�������o���������F�����[���X�E���C�X�́A�C��n��o�[�O�}��������M�w�l�̌̋��A�A�����J�ɓ����������Ŗ��������B������ɂ���A���̕���̑S�O�b�͂��ׂĔߗ��ł���B
��b�ł͍ȂƎႫ�O�����̕s�ς̗��͎���Ȃ��B��b�ł͕|���M�����O�̏�w�䂦�A���l�̖�����Ȃ��Ȃ�̂ŕʂ��]�V�Ȃ������B�O�b�ł͐푈�Ƃ������̂��ƂɁA���݂��̗����펞���̏Ō���Ȃ��B���������i�̒����A���Ɖ��F�̃c�[�g���E�J���[�̃��[���X�E���C�X�Ƃ�������̉ؗ�Ȃ������A���ꂼ��̔ߗ����Ԃ߂Ă���B���ۂɈ�����͂���Ȑ����A����A����Ⴂ�ȂǂŐ��A����Ȃ��ꍇ���������̂��B�Ȃ��S������Ȃ��琶���čs���A���ꂪ�l����������Ȃ��B�ǂ����ꂽ���A�N���[���ɒ݂邳�ꂽ���̉��F�����[���X�E���C�X���A����܂ł̎v���o����t�l�ߍ���Ńj���[���[�N�̔g�~��ɉ��낳���B�Ў��̃I�[�i�[�������l�X�A���ꂼ��̐l����v���̂���������ł������̂悤�ɁA�������ԑ̂����̂��ׂĂ�����Ă���B���Ƃ����S�̂��郉�X�g�E�V�[���������B
2006.11.01 (��) �Y����Ȃ����H
��茧�p�[�g�U�ł���B�{�ÂƓ�����茧�̐����s��K�ꂽ�Ƃ��̎��A�����Ƃ����ΖY����Ȃ�����Ȏv���o������B�d�����I������A��䂩��킴�킴���̏o���ɂ��t�����������Ă��ꂽ���k�c�Ə��̂l�N��2�l�A�\�̂�����ɒ��킵�悤�Ƃ������ƂɂȂ����B������͂�����H�ׂĂ����������ŁA�̎�ނ̑����Œl�i�����߂��Ă���B���̍��ގ��ԑт��͂���Ă����Ƃ������Ƃ�����A����Ȃ�Ȃɂ����B�Ԃ��Ȃ����̂�����̋V���H���n�܂����B���R�ƌ����ׂ�ꂽ�l�p�����~���y�X�ƕЎ�Ŏx���A�Ԃ������������̎o����i���͂�����Ƃ������A�����ł͎o����ƌĂԂ��Ƃɂ���j���A���킵�Ȃ��n���̖��w�炵�����ɍ��킹�A����őO��Ɍ����h����Ă���B���̓��̉��Ȃ̂ŁA�����H�ׂȂ����Ƃ�������Ă���悤�ŗ��������Ȃ��B�ޏ��̌���͎���������H�I������u�ԁA�d���Ή̂��Ƃ��Ђ�����Ԃ�A�C�����Ǝ��̌���ɐV���������������Ă���B�������ցA�S����S�ցA�������Ȃ��H���Ӓn�ƁA�����U�̘A�g�v���C�ł���B�Ȃ�Ƃ�30�t���炢�܂ł͐H�I���邱�Ƃ��o�����B��������������𖡂킢�������A������ȗ]�T���^���Ă���Ȃ��B33�t�ڂ����肩��}�ɂ����Ȃ��Ă����B�y�[�X�������Ă���ƃW�����E�W�����ƌ����Ďo�����j��������B���ꂩ�琔�t�撣���Ă݂͂����A���Ɍ��E�������čŌ�Ɍ���ɊW�����邱�Ƃɂ����B�F����͂����m���낤���A������͍Ō�Ɏ����̌���i���̎��͐H�I���ċ�ɂȂ��Ă��鎖�������j�Ɏ��g�ŊW��߂Ă��珉�߂ďI������Ƃ����������邱�Ƃ��B�������A���̏ꍇ�I��Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�H�I���Ă����}���ŊW��߂�O�Ɏo����̑����U�ŋ����������Ă��܂��̂��B������}���ł��W������O�ɋ����������Ă��܂��B�ŏ��͂��̂��Ƃ��V�N�ŏ��Ă����̂����A��������x�ƂȂ��J��Ԃ����ɂقƂ�ǃ��P�ɂȂ��Ă����B����͏펯�I�ɂǂ��l���Ă��������Șb�ŁA���������Ȃ�q��������H���ΐH���قǓX�͑�������킯�ŁA���ꂪ��������Ȃ��Ƃ킩���Ă��āA�ǂ����Ė�����莄�̌���ɋ�������荞�ނ̂������ɋꂵ�ށB�l�N�Ƃ���������킹�đ�����Ă����̂�������^��ɂȂ��Ă����B���̂܂܂ł͈݂̃p���N�ł���B���̎��A�ꂵ����̑f���炵�������v�������̂ł����Ɍ��I����B����͎o����������荞�Ɠ����ɁA���₭�����̌���ɊW�����邱�Ƃ��B�����āA�ق�̏��������W�����炵�������Ɍ������A��������v�������苼�����X�X���̂��B����ł͎o����͋�������荞�߂Ȃ��A�����đ傫�Ȑ��ŏI���Ƌ��ԁB���Ɏo����̐_���U�����߂��B�ꂵ����Ƃ͂�����Ȃ��炢���A�C�f�A���v���������̂��Ǝ��掩�^�B���ǎ���43�t�ŏI�����B�������15�t�ł���������l�O���炢�̗ʂƂ̎��A�����X�ɂ���Č덷�͂��邾�낤���A�����̕ǂɓ\��ꂽ�L�^��300�t���鉡�j������A������Ƌ����قǑ����̋�����H�ׂ��l�����̖�������ł���B���Ȃ݂Ɍ��݂̍ō��͂��̌��96�N��21�̎R�����̒j�����H�ׂ�559�t�I���������B�M�����Ȃ��I
�X���o�āA�k�֍s���l�N�Ƃ���������ĕʂꂽ�B����ɂ��Ă��A�Ă���q��l�ɓV���̑����U��������]�ƈ�����l�t���A�ŏ�����Ō�܂ŕt������Ő��b������d�g�݂͂������{�ł����E�ł��������̂ł͂Ȃ����낤���B�����H�ނ�荂���l�����ɂ��݂Ȃ��g���Z���u�ȃ����`�Ƌv���Ԃ�ɑ�������Ă��ꂽ�o����B�Ɋ��ӁI�ƋA��̓o��d�ԂłP�l���������ׂȂ���A�E��ł��܂��Ƀp���p���ȕ��ӎ��ɂ������Ă��鎩���ɋC�Â��A�v�킸�h�L�b�Ƃ��Ď�������n�����B
���Ƃ����F�Â��b�ŋL�����s�N���ȂƂ���⑽���ӂ������\�������邪�A�����֍s�����Ȃ�A���Њy����������ɒ��킷�邱�Ƃ������߂���B�����뗷�ƕ����d�݂𑝂��̂��B
2006.10.29 (��) ��y���l�܂�
����10��15���A���j���ɖ{�B�œ��[�̒��A�{�Âɂ���Ă����B���̋{�ÂƂ����Ƃ���͊�茧�̎O���C�݂̂��傤�ǒ��ԂɈʒu���A�L���ȊC�ƎR�̎��R�Ɍb�܂ꂽ�A�������ݒn�̐������瑾���m�ɂ܂��������Ɍ����������Ɉʒu����`���ł���B�X�i��̍`���u���[�X�ɂ��o�Ă��鏊���B�����͂��̋{�Øp�̕u������{�Ð���̌i���n�A��y���l�܂ŕ����Ă݂邱�Ƃɂ����B�ߑO9��30���A���悢��X�^�[�g�B�u�������������10���A�R�����o���ꂽ��R�̍ޖ������ɏ���Ă���������^��ł���B���̖��낤���y���̐X�̒��Ɠ����ɂ���������B���̍ޖؒu����̍L���͋�������ł���B����Ȃɐ��đ��v���낤���A�ȂǂƗv��ʐS�z�����Ȃ�������Ă䂭�ƁA�傫�����ɋȂ����č����ɏo��B���j���Ƃ������Ƃ�����A���ՂȒ����݂͐l���قƂ�Ǖ����Ă��Ȃ��A�s�y�n�┃�����Ɍ������ł��낤�Ԃ�����2�Ԑ����s�����藈���肵�Ă���B���Ȃ�ɂ��炭�s���ƒ��Ȃ��{�Ñ勴�ɏo���B�ׂɂ�����{�����ȋ������s�ɓn���Ă���B�l���ɐ�����Ȃ���勴���������n���ĉE�����ցA���炭�s���ƉE���ɏ����Ȓނ�D�����z�����܂��Ă��鏊�ɁA�x���̌��𗁂тȂ���ނ���y����ł���l�����������Ă����B�h�g��ɋ�ꂽ�����ȃg���l���̂悤�Ȗ��������ƎԂ̌���������u�₳��A�Â��Ɏ�������ł���ʐ��E�ƂȂ�B�ނ�l�̃o�P�c�̒��̎�����l����`���Č���ƁA�N�`�{�\���傫���ĐF�����������R�O�C�قljj���ł���B�f�������"����͂Ȃ�Ƃ������ł���"�ƕ����ƁA"�`�k��"�Ɠ�����B�L�k�Ƃ�����������������ɂ��Ă��A�`�k�ƌ����̂͊m�����₾�����̂ł͂Ǝv���Ȃ�����A����Ƃ͎��Ă������Ȃ��n���̋��Ƃ��āA����܂Ŏ��̒m���Ă��鐔���Ȃ����ނ̐V��Ƃ��Ď~�߂Ȃ���Ȃ�܂��B"�����ł����`�k�ł���"�Ƃ����Ƃ��̋������Ă���ƁA���̒ނ�l�̏f������A�����������Ɏv�����̂��A"�̃��J�T�M�Ɠ���������"�ƌ������B���������A���̓V�Ղ�ɂ��郏�J�T�M�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��Ɣ[���B"�����͔��������V�Ղ�ł���"�Ƃ����Əf������͂ɂ���������B����Ȓނ�l��Ƒ����ꂪ�W���g�~��ׂ̗̗ՊC�ʂ�ɕʂ�������āA�v������������������Ă���A�p�[�g�炵���ؑ������Ɍ��Ȃ���A�����オ���Ă䂭�Ɩ��V�����p���o�������B��������́A���[�J���F������w�����Ȃ�B�s�������l�Ɩڂ���A���Ɉ��A�����Ă����B�Ȃ��̂ɖ߂����l�ŁA���������ĂƂ��Ă��D�����C�����ɂȂ�B���炭�i�ނƌÂт�����̂���S�̌����̑O�ɂ���Ă����B��̑�������Ă��鏊�܂ŊG�ɂȂ��Ă���B���������X�e�����X�Ő^�V�������̉��ŁA�J�ɂ��炳��F����������O�̃|�X�^�[�����܂��ɓ\���A"���v���~�߂��"�Ə����ꂽ���������������ނȂ�����������B�������琔���[�g����̏����ȊŔɋ{�ÑN�������g���E�Ⓚ�q�ɂƏ�����Ă����B�f��̃��P�Ŏg�������ȃV�u�C�q�ɂ��B�Â��Șp���E�Ɍ��Ȃ��炵�炭�����Ă䂭�ƁA���̍�����i�Ƌ����Ȃ艽�z���̏��D���R���N���[�g�̗��ɏグ���Ă���B���̉��ł������̔��F�̋����I�����W�F�̊ۂ��u�C�����Ɍ����Ă���B�����ł͋��t���̓T�^�I�i�F���W�J���Ă���B�Ō�̍���オ��Ə�y���l���B���傤�ǂ��̍�́A���������Ƃ������鏬�����u�̉A�ɂȂ��Ă��ċ�C���}�ɗ₽���Ȃ�B�C����2,3�x�Ⴄ�̂��낤�A���������������Ă��Ă����ƕ��������ĔM���Ȃ����̂ɐS�n�����B
���Ȃ蒷�������オ�肫��Ə�y���l�̒��ԏ��A���X�g�������o�Ă���B���̐悪�V�����ō��x�͒����������~�肫��ƁA�����Ȃ��Y��Ȑ������������p�A���ړ��Ă̏�y���l�ɏo���B�Ȃ�قǁA�����͑f���炵���i�F�ŁA���ɗV�ԃ{�[�g����Ɗ�̊Ԃɉ��z��������ł���B�Ȃ�ł�300�]�N�O�A�싾�a���Ƃ����l��������K�ꂽ�Ƃ��Ɂu���Ȃ���Ɋy��y�̂悤���v�Ɗ��Q�����Ƃ��A���̌��t�ɂ���Ă��̏�y���l�Ƃ������O�����������ł���B�C�����Ɏ肷��̂����ׂ������ɐi�ނƔ����ΊD��̂悤�Ȋ₪�A�Ȃ��āA�̊C�̐F�Ƃ̌����Ȓ��a�ɖڂ�D����B��������̃J�����B������A����グ��Ɖ��������̂��Ɗ���Ă��Č��\�X�������y���߂�B�����Ɍ������̏�����������Ă���B��ԋ߂��傫�Ȕ�����́A��ƃZ�U���k������Ȃ������A���̊G�������������c�����v���o���X�̐ΊD��̔����R�A�T���E�r�N�g���[���R���̂��̂��C�ɕ����Ă���悤�Ɍ�����B���̏�y���l�̊�͐Ήp�e�ʊ�Ƃ����čz�������������Ă�����̂炵���B���炭�́A�����߂Ɣ�����Ɛ������܂ł����Q�̊C�̒��߂��y���B
�����܂ŕ����Ă��Ė{���ɂ悩�����Ǝv���B�Ԃ�o�X�ł͈�u�Œʂ�߂��Ă��܂������݂�`�ɂ́A���Ɠ������Ƃ����������L���Ă��錩�m��ʐl����������B�����ȏ�������Ŕ�����Ă�����Ă��鏭�N�̉�������A�����b���Ă���N�z�̋��t�̊y�����Ȏp�A�ޖ̍���⋭�����̍���A������������Ђ���Ƃ������A�n�߂Ă��������`���ŏo��l�╗�i����R�}�P�ʂ̊G�ƂȂ��ĐS�ɟ��݂���ł���B���R�̒��̃g���b�L���O���f���炵���Ǝv�����A����Ȍ��m��ʒ��Ŏv�����̂悤�ȎU���̗��������Ǝv���B�C���^�[�l�b�g��L�x�ȏ�ڂ������s�G���ȂǂŁA�O�����Ă��̋������蓹����Ƃ���ׂ邱�Ƃ����₷�����鍡�A���C�Ȃ��o��≽�C�Ȃ��������������낢�B�����肤�ꂵ�������́A�����̒��̂߂����ɋN���Ȃ��`���S���ڂ��o�܂����Ƃ��B
2006.10.28 (�y) ���H��Ɏv��
55���Ԃ̋�̗����I���ĐX��`�Ń����^�J�[�����A�_�ЂƂȂ��H����ōō��̃h���C�u���a�ɂȂ����B�܂��́A�����̖ړI�ǂ��蔪�b�c�R��ڎw�����Ƃɂ����B���傤�ǁA�@�����猩�Ă����̂ł킩���Ă�����肾�������A�������ɍ~��Ă݂�Ɨl�q���Ⴂ�������킩��Ȃ��Ȃ�B�����ŕ����̗���J�[�E�i�r�o��ł��C���̃h���C�u�ƂȂ�B�����炵�̂����������E�̕��p��30���قǑ���Ƒ����̓o��ɂȂ��Ă���B��������ƎR��ڎw���Ă���B���b�c�R�Ƃ͘A��̑��̂�10�]�𐔂���R�X����\������Ă���B�~��t�ɂ̓X�L�[�A�Ăɂ͍��R�A���A�H�̍g�t�ƈ�N��ʂ��Ċy���߂�Ƃ����B�r���ŏ��h�m�����q����A�z������j�̒c�̂��o�[�x�L���[���y����ł��銞�썂����ʂ��āA���悢�攪�b�c���[�v�E�F�[�ɂ����B�s�y�V�[�Y���̓y�j���Ƃ����ĎԂ̒�߂鏊�����J�A����ƒ�߂Ă��烍�[�v�E�F�[��҂���40���Ə����Ă���B�����ł������l�̒c�̂���t����B����͌�a��̃A�E�g���b�g�A���N�̓p���̃��[�u���A�����ւ����Ă����C�̂��������l�ň�t�A�܂������b�c�܂ł����̏��Ƌ�������ł���B�l��13���Ƃ�14���Ƃ�������p���[�͂��̂܂ɂ����E���ɎU����Ă���B�Ђƍ��A���E���ǂ������Ă����{�l������Ɨǂ����������̂����A���A�����֍s���Ă������l���A�������c�̂ł���̂��B���Ȃ݂ɁA���[�u���ł͓��{��̉���͂Ȃ��Ȃ�A������Ɏ���ĕς���Ă���̂ɂ͈ꖕ�̎₵�����������B�҂���35���A�����ꂾ������ь��������̃��[�v�E�F�[�̒��A���|�I�����̓��{�l�̎��́A�فX�Ɛԉ��ɐ��܂����R�����J�����Ɏ��߂��B���̃��[�v�E�F�[�A������Ȃ���101���Ȃ̂ł���B���ł���Ȕ��[�Ȑ����Ȃ̂��낤�A�����A�傫�Ȃ����o����Ə����ȗc�t��������l�Ȃ炱�̔��[�͕ςȂ��ƂɂȂ�B����Ȃ炫������100���ł��C�C����Ȃ����Ǝv������ɒ����B
�����͂���₩�ȕ��������A�����p����X�`�A����ɑ����s���A���Α��ɂ͐X�ň�ԍ������R�Ȃǂ���]�ł���B��ꏊ�A���Z�قŌ����l��{�傫���������R�͂��̕ӂ�̏o�g�Ȃ̂��낤�B�V��������������ƉE���ɍ��̖݁A�����ɐ������}�̂Ȃ��͂ꂽ�����A���̌��Ɍ�����R�X�Ɣ��Q�̒��a�������Ă���B��t�����̎��R�����X���R�ɑ��錩���Ȍi�ς́A����l�Ԃ̍��o�����̂Ɣ�ׂ邱�Ƃ��o���Ȃ��D�ꂽ���̂ɂȂ�B���������肫��Ǝ���������A���̂قƂ�ɂ͒���肻�̌������̎R���ʂ��o���A�����̃J�������������l�X�̊i�D�̎B�e�ꏊ�ɂȂ��Ă����B���R�A���������A����ΓV��̒뉀�̂悤���B�R���~�荡�x�͎s���Ɍ������r���̂˂Ԃ��̗��Ɋ���Ă݂�B�Ղ�Ŏg��ꂽ�{���̂˂Ԃ����Â��傫�ȑq�ɂ̂悤�ȏ���10����u����A���������Y��ɏƖ�����Ă��āA���̑傫���Ɣ��͂ɋ����B���c�M���Ə㐙���M�A�`�o�Ȃǎ��㕨�������A�������͎̂s���܂≽�炩�̏܂���������̂��肾���A�Ղ�̌セ�̑��̏܂����˂Ԃ��͑傫���Ďn���ɍ���̂����������A�����������ꂽ���̂Ȃ̂ʼn��Ƃ����p�ł��Ȃ����̂��n���ł͓��ɂ̎킾�������B���������Ƃ��X�|���T�[�ɕt���Ă��Ȃ���Γ���Ƃ̂��ƁB����͂��̖邨������A�n���̗�����ɏڂ����Ìy�O�����̖���̎R�㎁���炨���������b�B
��������A�����V���o�C�p�X�Ŏs����ʂ�z���āA�O���ێR��ՂɌ������B�������E�ɐ܂�ĊԂ��Ȃ��A�ߑ�I�Ȍ����̓ꕶ���R�ق�����A�����œ���邱�Ƃɂ܂������B�������4000�`5500�N�O�A�����ɓꕶ��550���ɂ��y�ԏW�����������Ƃ����B����̂͂邩�̂Ƃ������Ƃ́A���{�̗��j�Ƃ������̂̋L�q���Ȃ�����B�����ŋ����̂́A���̐l�����̐H���̍��Ղł���B�u���A�J���C�A�A�T���Ȃǂ̊C�Y���A�I�A�`���͂��߂Ƃ���̎���ʎ��A���A�������Ȃǂ̓����A�����A�o�����X�̂Ƃꂽ�H�����Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃɋ����B�������h���܂�����̂͊F���ł���B�ق��o��ƐÂ��ȕ��n���L�����Ă��Ă����ɒG�����Z����A�x���������Ȃǂ��������z�蕜������Ă���B���̏Z�����Ɏq���̕�Ƒ�l�̕悪���ꂢ�ɂQ��ɒ�������ł����Ƃ����B�q���̈�͓̂y��̒��ɖ�������A���̑����̓y��̒��ɂ͂��Ԃ���̐������Ă����Ƃ����B�����͋F��ׂ̈Ȃ̂������ȉ������ĂԂ��A���ۂǂ�ȈӖ�������̂��͂킩���Ă��Ȃ��B������̂悤�ɐ�i��Â��Ȃ���ΐV����Ȃ�����A���̎���̕��ώ�����30�㔼�Ƃ����Ă���B�����ɎR�X�����ď������u�ɂ��������Q�����Ă���̂ǂ��Ȍi�F�̒��ɁA��l�B�̒Z�����Ȃ�������a�Ȑ������Â��B�����ƁA�q���v���e�S�A�Ƒ����J�Ȃǂ͂��̎��ォ�牄�X�Ǝ������݈��ł����̂��낤�B����ɂ��Ă��A�������������Ă��鍡���v���ɁA���C�Œn���������A�������~�ׂ̈ɍ��ʂ⏟�������ɂ������A�푈��e���Ƃ������̂��ƂɎE�C�̈����S����������l�́A���̌Ñォ�獡���܂ł�5000�N�Ƃ����������₵�āA�������������w��ł����̂��낤�B�ӂƁA����Ȃ��Ƃ��v�킹��[�f���̐��H�����B
2006.10.18 (��) �X�܂ł�55����
��s�@�œ��{�̖k�֍s���͍̂����ł��ʔ����������B�������ꂪ�����Ȃ�����̓��ŁA���������ۂȂ炢�����Ȃ��ł���B���͐�T�̓y�j���A10��14���̌ߑO7��35���H�c���A�X�s��1201�ւł��̏��������ׂĖ��������Ƃ��o�����B�Ȃ��k���������ƌ����ΊC�֊O��邱�ƂȂ��A�{�B�̂قڐ^�̋N���ɕx���n����ł���邩�炾�B�@�����̏I���̕��̕łɂ�����{�n�}�ƌ���ׂȂ���s���Ǝ��ɖʔ����B�܂��A�㏸���Ƀf�B�Y�j�[�����h�������ɁA�����Ɛ�Ƀg�[�L���[�E�h�[���̉�����������B�猩��ƃr�b�O�E�G�b�O�̃j�b�N�l�[���̗R�����킩��B�����n��Ō��Ă���g�߂Ȃ��̂��A�v�������Ȃ������F�l�̂悤�ɉ�������������B���̋�C�͂����܂ł�����ł���悤���B��ʁE�Q�n�E�Ȗƌ��������Ă䂭�A�܂������Ă��邩�ȂƁA���ߌ���̕x�m�R��U��Ԃ�Ɨ֊s���₯�ɑ傫��������B�����āA�ቺ�̎R�X�͂��낻�뒸��ߕӂ��Ԃ��Ȃ��Ă���̂������ė���B�k�֔�ԂقǐԂ������Ȃ�A�̕����͂��ɐN�H����čs���A�܂��ɍg�t�O����ǂ��Ď��ԍ��̂Ȃ����݂̌����ƂȂ�B���ꂪ�C�O�ƂȂ�Ƃ����͂����Ȃ��A�����܂ōs���Ă��C��c���h���Ɖ_�A���������ɂԂ���100������1�̊m����UFO�T�����炢�ł���B�������ďォ�猩�Ă䂭�ƁA���{�͂����ɏ��Ȃ����n��L�����p���Ă��邩���킩��B�c���Ɛl�Ƃ̏W�܂肪�������Ɋ��Y���悤�Ɍ�����A�삪�J�̐^�����˂�悤�ɗ���Ă�����A�R�Ԃɖ��X�Ɛ����������������������肵�Ă���B
��N�A�앧�ɗ����������̂��ƁA�h�̑����Ƃ����������u��R�̏�ɖ��Ƃ�y�Y���⋦��A�z�e���Ȃǂ��W�܂��Ă��鑺���������B���ꂪ���鏊�ɂ���A���̐̂������D���ŏW�܂��Ƃ⎑�Y�Ƃ����������Ƃ����B���ł͂��̂��ׂĂ̑����ό������ꑽ���̗��s�҂��W�߂Ă���B�m���Ɍi�F���ǂ������̖ʂł��O�������ވ��S�������邪�A���Ƃ��Ƃ͂����閯������̍U����N����h���ׂɁA���̒n�̗��ɕK�R�I�ɍ��ꂽ�v�ǂ̗l�Ȃ��̂������̂��Ǝv���B�������{�����h���ŕ��a�ȓ����łȂ�������A���̓앧�̗l�ɐl�X�͋u��R�̏�ɏZ�̂��낤���A�����Ȃ��Ă����獡�̉��{���̌����炵�̂������Z�悪�ł����̂����Ƃ����t�قȋ�z�����Ă݂��B�������A���{�̊��q���{�̊J�݂ɂ�����A�����Ȃǂ͊C�ƎR�Ɉ͂܂�Ă��邩�炱�����S�ȕ��n��I�Ƃ����Ă���B���̎���̕����⍑���̏K��������A��T�ɂ��̈Ⴂ�����ߕt����킯�ɂ͂����Ȃ����A�ʔ������������̋�z�b���G�X�J���[�g�����Č����B�u�ɏZ�ގҁi�����낷���ɏZ�݂����ҁj�E���n�ɏZ�ގҁi���グ�鏊�ɏZ�݂����ҁj�A�O������̐N�������ҁE����Ȃ��̂��Ȃ�������Ȃ��ҁA��ɂȂ�ƌ��C�ɂȂ������E��ɂȂ�ƐQ��_�k�����A�A���O���T�N�\���ł���Ƃ���̔��l�Ɖ�X���A�W�A�̉��F�l��ɂ����閯����l��̑Δ�ɂ܂ŋy��ŁA�͂ƗY�قȌ��t�œ`���Ă䂭�ҁE�����ȓw�͂œ`���Ă䂭�ҁA�����܂ōs���Ƃ��肪�Ȃ��B�Ƃ肠�������͂��̋�̉��Ő��܂�炿�A���̋G�߂ɐԂ����܂�s�����{���D���Ȃ̂��낤�B
����Ȏ����v���Ă���Ƃ��̊Ԃɂ����ɊC�������Ă���B���{�C�ɓ˂��o���傫�Ȕ����������Ɍ�����A���ꂪ�j���������낤�B���炭���{�C�̑�����ł������������ɖ߂�B����������Ȃ�ƂȂ��@�̂��O�ɌX���������ȂƎv���Ă���ƁA�������V���̋@���A�i�E���X�B"�F�l�A���@�͊Ԃ��Ȃ������Ԑ��ɓ���܂��B�V�[�g�x���g���`�A��g�p�ɂȂ��܂����e�[�u���́`�B"���ׂ̗ɂ͂��̋@����l��17�����҂������ꌩ�Z���u���Ƃ����t�@�b�V�������D���ȁA�����̂����M�����������Ă���B"���A���̋@���x��܂�������[�����l�ѐ\���グ�܂�"�Ɨ������ƒ�������2�x�ɓn���ăM�����Ƀv���b�V���[�������鏬���������ȃX�b�`�[���Ƌ@���斱���̌��t�B�����ȃM�����͉v�X�������Ȃ��āA�ׂŐQ���ӂ�����ߍ���ł���B���͂���Ȃɑ�_�ł͂Ȃ��������B�ŏ��͖��_�o�ŃY�{���Ȃ���Ǝv���Ă������A�������l�Ƃ������E�ӎ����킭�̂��A�i�X�������Ɏv���Ă��邩��s�v�c���B�����Ɍ����Ă������b�c�R�̏�����ɁA�@�̂����ɑ傫���X���Ă��珬��������]������ƁA�����Ȕ�s�ꂪ�����Ɛ�Ɍ����Ă����B��������55���Ԃ����A�����Ȃ��Ƃ��l���A�����ȃh���}���N���Ă���B��������Ă܂߂ɕM�ɂ���ƕn�����]�������Ɋ������Ă���̂����A���߂Ă킩���Ă����炵���B�������I���悢�揉�߂Ă̐X���B
2006.10.17 (��) ������Ȃʼn�ɂ䂭
���A���X�Â��b�ɂȂ邪�A�g���C�E�h�i�q���[�ƃX�U���k�E�v���V�F�b�g�剉�E������"�������"�Ƃ����f��̘b�B�X�g�[���[�͒P���������̂��̂ň�x����Ɖ��N���͌��Ȃ����Ƃɂ��Ă���B���ؗ������炵�炭���āA�ѓc���̑�����_�ׂ̗ɂ����������ȉf��فA�N��������ł���������B���̐�̐_�y��ɏオ�鏭����O�̑����Y��œ��ꗿ��30�~�قǍ�������������ł͂Ȃ��Ƃ���ɂ��̘b�̃}�C�i�[��������B���ɂƂ��Đt����ɓ���2�`3����O�̉f�悾�����Ǝv���B�߂܂��邵���ς�鎞�ケ���̉f��ق́A���͂����Ȃ��B�o�D���X�g�[���[���A�����J�f�悻�̂��̂Ȃ̂����A����̓C�^���A�̑f���炵���ό��n�A���y�������������܂��C�^���A�A���̃C�^���A���f��̏d�v�ȃL���ɂȂ��Ă��Ă�������ȏo���҂������Ԃ�Y���Đ��藧���Ă���B
�܂��X�g�[���[�́A��w�̐}���قɋ߂�v���[�f���X�i�X�U���k�E�v���V�F�b�g�j���ΎG�Ȗ{�i���l�����̃��b�X���j�k�ɑ݂��o���āA��̂����̐搶���ɌĂяo����Ē��ӂ����B�ޏ��͗���m��Ȃ��܂�Ȃ��l���Ȃ�����̎��R�ȃC�^���A�ɕ��ɍs���ƁA�V��������Ď��\���o�������炱�̉f��͎n�܂�B1962�N�̃A�����J�ł܂��D���Ƃ��������ӊO�����A�C�^���A�s���̑D�Œm�荇�����C�^���A�l�̒��N�j�����x���g�i���b�T�m�E�u���b�c�B�j�Ƀ��[�}�ő؍݂���A�p�[�g���Љ�Ă��炤�̂����A���e�܂ő���ɗ��Ă����厖�Ȗ��̒����؍^�̂��h�A�I�C�I�C�܂����܂��Ă��Ȃ������̂���Ƃ������ɂ����������B���̃A�p�[�g�ɏZ��ł����A�����J�l�̎�҂̃h���i�g���C�E�h�i�q���[�j�ƒm�荇���A�v���[�f���X���{���ɏA�E�����܂������A�ꏏ�ɏj�����h���Ƃ̗����n�܂�B���ꂩ��̓C�^���A�ό����s�̂悤�ȗ����n�܂�B���̌�A�����̐S�̍s���Ⴂ�͂�����̂̍Ō�͏o�������Ō��Ă��鎄���p���������Ȃ�قǂ̃n�b�s�[�E�G���h�B
�f��̃I�[�v�j���O���痬���T���g����"���[�}�E�A�h�x���`���["�Ƃ����C���X�g�D�������^���́A�������ŏ��̃����t���[�Y���琷��オ��̃T�r������B���ꂪ�I���W�i���̉f��^�C�g���ɂȂ��Ă��āA���������[���b�p�̒����ׂ݂̈ɂ���ꂽ�悤�Ȗ��ȁA���R�[�h��b�c�ł͋���̏��̉����ŏ��ɓ���B�����āA������Ȃ͂��̋ȂȂ����Ă��̉f��͐��藧���Ȃ��Ƃ���1961�N�̃T���������y�Ղł̗D����"�A���f�B��"�ł���B����𐢊E�I�ȃq�b�g�ɂ������G�~���I�E�y���R���{�l���o�����ĉ̂��Ƃ����ґ�Ȃ��Ƃ�����Ă���B�������A���̃T���g��2�Ȃ͌��������ȏ�ʂŎ��Ɍ��ʓI�ɃA�����W��ς��Ďg���Ă���̂��B�䂦�ɁA�������ꖇ�̃V���O����A/B�ʂQ�Ȃŗ��h�ȃT���g���ՂɂȂ�B�h�������Ԃ��X�N�[�^�[��"���[�}�̋x��"���v���o��������̂ŃC�^���A�̑�\�I�Ȗ��ԁB�剉��2�l�Ƃ����̎����ł��{�ŁA���ɃX�U���k�E�v���V�F�b�g�͔ޏ����o�������ǂ̉f��������̎�����Ԕ������B�g���C�E�h�i�q���[�͂��Ƃ���TV�X�^�[�Ƃ��ē��{�ł�������݂��������A"�����n�̏o����"�A"�����h��"�i�X�U���k�Ƌ����j�A"�p�[���X�v�����O�X�̏T��"�ȂǁA�����p���c�ɐ^���ԂȃZ�[�^�[���ǂ��������A�����J�t�f��̑㖼���I���݂������B��ɂ���2�l�͎������ł������������A�������ɘR�ꂸ�����͑����Ȃ������B
�����w���܂��V�u�C�B�D�����C�^���A�l�Ńv���[�f���X�̃A�p�[�g�𐢘b���A�Ԓ��̃}�Z���e�B�E�R�����@�[�`�u���ɏ����̎w����̃��b�T�m�E�u���b�c�B�́A����Ƃ����"����"�A�~���[�W�J���f��"�쑾���m"�Ȃǂւ̏o���ŗL���B����"���f�̏���"�̂��Ă��鎞�̔ނ͖{���ɑf���炵�������B�h���̔N��i�����j�ŁA���ޏ����̃A���W�[�E�f�B�b�L���\���͐�������"���I�E�u���{�["�ŃW�����E�E�G�C���̗��l���ŏo�����A���X�^�[�ɂȂ����l�B�ޏ����W�����E�E�G�C���Ɂu����Ȕ����o�������͒���ȁv�i�f��̗��ꂩ������̃v���|�[�Y�j�̗l�Ȃ��Ƃ������āA�����{�f�B�X�[�c���ȕ����Q�K�̑�����O�ɒE���̂Ă�ƁA���傤�ǂ��̉���ʂ肩�������E�H���^�[�E�u���i��������Ђ傤����ꂳ��̏�ɗ����Ă���B�킯���킩��Ȃ��u���i�����q�[�q�[���Ȃ��短���Ń\������Ɋ|���ċ����Ă䂭�Ƃ����L���ȃ��X�g�V�[���͉��Ƃ����������B���Ȃ�h�h��ȃh���p�`�̍Ō�ɐF�C�Œ��߂�Ƃ͐S�������o�ł���B�����ʼn̂���f�B�[���E�}�[�`���ƃ��b�L�[�E�l���\���̃f���I��"���C�t���ƈ��n"�͂������Ă����̃J�b�R�悳�ɒ��������B�������ł̌����̂ł̓}�������E�������[��"�A�炴���"�Ƒo���ł͂Ȃ��낤���B
�啝�ɒE�����Ă��܂������A���̂悤��"�������"�͂��Ȃ�̎��͂��������o�D�������������Ă���B�ē̓w�����[�E�t�H���_�A���[�����E�I�n���o����"�X�y���T�[�̎R"�A"��\�̉ΗV��"�������̃g���C�E�h�i�q���[�o���̍�i�Œm����f���}�[�E�f�C�r�X��1962�N�̍�i�B�f��̓X�g�[���[�����ׂĂƂ����l�������낤�A�������A���������l���͂ǂ����낤�B�C�^���A�ό��nj䐄�E�I�ȃ��[�}�s�X����ɁA�t�B�����c�F�A�s�T�A�}�W�����A�C�^���A�E�A���v�X����c�̗��s�̃o�X�K�C�h���n�߂Ƃ���o���ҒB�̐��̉������ōs���P���ԂQ�O���قǂ̃C�^���A�̗��B���s����͔̂w�������u�����h�������������g���C�E�h�i�q���[�ƍ����ŒN�ɂ������Ȃ��������ڂ������X�U���k�E�v���V�F�b�g�B�Q�l�̗��̉��Z����̃T�[�r�X������A�������ς킵���@�B����⎨�Ƀw�b�h�t�H���������ɁABGM�̑f���炵���ȒB�������P�ԂƂ������ɕ������Ă���B����Ȍ��̗͂����f��̊y���ݕ����ꋻ�ł͂Ȃ��낤���B�Ƃ����悤�ɂ����Ȍ�����͍�����Ă��鎄�̖{���́A���̏����̍��A�ł������������������g�ɉ�ɍs���S�̗������Ă���̂��Ǝv���B�����āA�����N�������皺�̔�����r�f�I�E���C�u�����[�̒I���炻���ƈ����o���Ă݂�B���ɂƂ��Ă��������̂Ȃ��f�悪����"�������"�ł���B
2006.10.08 (��) 17�̉Ă�
�̓��ɓ����𗷂������̎��A3�ΔN��̌Z�̗F�l�ł����y�����A���傤�Lj��g�x��̂��鎞���Ɏ��Ƃ̓����Z�����҂��Ă��ꂽ�̂��������A�ꂪ��������̎���A��čs�����A�������Ȃ�����̗��s�͋����Ȃ��Ƃ܂Ō����A�d���Ȃ��Z�͑���܂Ƃ��Ȓ�̎���A��čs�����̂������B���v���A�����l�c����Q�l�c���������J�̖����ƌZ�̂��ڕt�����̈ꋓ�����������̂��낤�B�H�c���̎n�߂ď���s�@�ő��ցA���傤�ǃW���C�A���g�n�ꎁ��������s�@�ł�������ɂȂ�A���܂�̑傫���ɋ������������̂��o���Ă���B�Ȃɂ��A�ނ����ƕ��ʂ̎G�����蒠�Ɍ�����̂ł���B���ꂩ��D�œ����ցA�Ă̓����͂���3����ɂ��܂������g�x��̍Ղ�ׂ̈̏����ōQ���������C������A���S�̂������q�̉��Ɉ��Ă����B���̊p�X�ɂ͔����ɈႤ�����q������A�������ɂ��Ɗe�O���[�v���Ƃɂ��ꂼ��̃��Y���������Ă���Ƃ̎��ŁA���l���̗x��肽�������̔��q�ɂ��킹��悤�Ɋy�������Ɏ�ŊԂ��Ƃ��Ă����B�ǂ̊�����ꂩ��\�z�����₩�ȓW�J�̂Ȃ��ŁA��u�̍��g��҂M���S���`���A���ꂪ���ɂ͂ƂĂ��V�N�������B�����āA�Ղ�̖�A�ނ��Ԃ�悤�Ȑl������ƌ����̒��A���Ԃ������邢���̒��ŕ�R�Ɗϗ��Ȃ̒��Ɏ��͂����B���������̂����q�Ɉꎅ����ʓ����������閺�����B��O�̋�C�����C���ǂ���悤�Ȏ�̓����A�����ʂ̐�͂����܂ł��O�ɌX���y�₩�ɐi�ށA���������j�A�^�g�̍g�������������J�����O�A���̋����锒�����Ȃ��A�}�̉����玞�X�`�������̓��B�j�x��̒j�����͂������荘�𗎂Ƃ��A���ǂ��������̒��Ɉ�u������^�������̌����������B���̉��Ő�[�ɒ����������Ƃ��v��������˂��グ�Ă͉��낷�����܂�����҂̘r�A�N�Ɉ�x�J��L������썑�̍Ղ�͉����܂ł��M�������I�������B�����̌ߌ�A�Z�̗F�l�B�Ɩ�C�������̕l�ӂ���]�Ƃ��A�g�ƗV�Ԓ��Ԃ̏������r��r��ɕ������Ă����B�l�ɍ���ڂ���Ĉ�V�M�̐��Ɏ��܂��Ă���ƕ��Ɣg�̉�����������������悤�ɏd�Ȃ�B�l�̋C�z�łӂƖڂ��J����ƁA���̏�ɒ����e����������l�̏������̑O�ɗ����Ă����B�����S�ΔN��̔ޏ��̖��O�͐^�Ղ���Ƃ����A�Z�B�̗F�l�̈�l�őΊ݂Ɍ�����W�H�����痈���l�������B�T�[�����s���N�̃����s�[�X�����F�̗[���ɉf���A�����������h��Ă����B���̔������������݂Ȃ��炶���Ǝ������Ă��邱�ƂɋC�����A�v�킸���������Ă��܂����E�u�Ȏ������������̋��̒��ɂ���B�������̒��ł��܂ł��S�Ɏc���u������B
���ꂪ�A�����̂��łɊ����Ȍ`�őh��Ƃ�������B�O��́i9��28���ߑO11���j�̒��ŋL��������̑D���ŁA����17���������̎��ȗ��̉��������W�H�����������ƂŁA���̏�i�̐��X�����n���̂悤�Ɏ��̐S�̒��ʼn�����B�N���d�˂ė����������A�ߋ��̂����₩�Ȏv���o�̈�Y�����ܐH���ׂ��Ă���悤�ɂ��v���鍡�����̍��B���Ďv���ɁA����A�����A�����Ƃ������X����������ŁA�V�����l�̏o���o�����̒��ɉߋ��v�����鎖���l���Ȃ�A�߂����肵���X��U��Ԃ�A�U��Ԃ芚�ݒ��߂Ȃ�����ނ̂��l���B �o������̒��f���܂������i�݂������̂ł���B
2006.10.02 (��) 9��28���ߑO11��
9��28���ߑO11���A���A�S��9368���[�g���Ƃ��������̓��{���ւ鐣�ˑ勴�̉�����2���Ԕ��ɂȂ�B���ɉ��₩�Ȑ��˓��C�̏�ɂ���B���z���炱�ڂꗎ�����������́A���g�̏���ς��ς��Ɩ����ɂ͂������сA�����ɍs���s���قǁA����͏��X�ɏ������ׂ��ȗ��ƂȂ��Đ��ʂɌ���Ă͏����Ă䂭�B���̐�̉����������̏�͔��������݁A凋C�O�̂悤�ɑ����̓��X��Â��ɕ����яオ�点�Ă���B���l��������4���ځA����͐������̐��˓c�Ɋ�`�A���̑O�̔ӂɍ��A��D���Ă��邱�̑D�p�V�t�B�b�N�E�r�[�i�X�ł��m�荇���ɂȂ������R��v�攌�̒킳��ł��镽�R���������ْ����߂��Ă��镽�R��v���p�ق�K�˂Ă݂��B����萔���ԑ������D�Ȃ��ꂽ���͎��������}���Ă��ꂽ�B���͈�v�攌��12�ΔN���̓������x�̎���ōł���v�攌��m����̈�l�ł���B���{���\������{��ƁA���R��v���͐��E������ނ�e�P�A�e�n�̕�����Y�ی�̂��߂ɗ������ꂲ����Ă���B�܂��A���p�ق̖��������ƉE��̒���́A���˓��C���k���������̂ɂȂ��Ă��ĖX�̗����Y����B�ٓ��̓o�[�~�A���̑�Ε��A�A���R�[�����b�g�A�V���N���[�h�A������˂̕��i���A�f���炵����i�Ō������ڂł��邪�A���̒��ł��攌���q�ǂ��̍��ɕ`�����G���L����f�`�ɂ�����܂ł��ۑ��W������Ă��鎖�ɂ͋����A���̎���A���a�������猻��Ɏ���܂ł̓���̂��̂��c����Ă��鎖�́A���{�l�̍�i�ɑ���v������͂��Ƃ��A����l���͂��߂Ƃ������Ƒ��������ɗc���̍����A���̗ނ܂�Ȃ�˔\�����������ł��������v���̂ł���B�����č��A���������Ă��邱�̐��˂̌��ƕ��́A�攌�̉s�������Ə�M��|�킹���̂悤�Ɏv����B�D�͉E�ɒW�H�������Ȃ���A���ꂩ�炵�炭���ĉ�����蔲����ł��낤�Ǝv���閾�ΊC���勴������������ł���B����Ɗu�₵���D�ゾ���̐��E�ɕ����𗣂ꂽ�J����������B����ɂ͂܂闷�s�o���L���ȔN�z�҂������Ƃ����B
�̂�т�Ɠ��X�����Ȃ���A���ɐ�����Ċ���̋���������ʂ��Ă����n�߂Ă̑D���B�r����q����e�n�ɂ��ꂼ��̎v�����l�ߍ���ōs�����A�Ȃ�ƂȂ��������̂ł���B
2006.09.17 (��) �_�ے��̃^�b�Z���E�X���b�v�H��
����ATV�ʼn����������}�p���`�̓��W�����܂����B���傤�ǒc��̐t�^������̍��A���̕��}�p���`���S�����}�����悤�ł��B�勴������̗V�ѐS��t�̃C���X�g�̕\���A�A�C�r�[�E�t�@�b�V�����ɐg���N�����̓��킪�`����Ă��܂����B����͂����܂��̂Ŗ��T�ǂ�ȃe�[�}�ɂȂ�̂��A���̖����Ȋy���݂ł�����܂����B���̕\����1964�N�̃S�[���f���E�C�[�N����1971�N��12���܂łȂ��390���ɂ��y�Ԃ����ł��B�p���`�Ƌ��ɁA�����Y�E�N���u��j�q��ȂȂǂ́A�܂������Ƃ��Ă͒������j���t�@�b�V���������������ɂ߂Ă��܂����B���̔ԑg�����Ă��ĂӂƂ��̎���̋L�����h��܂����B��͂�1964�`65�N���炢�̎��������Ǝv���܂��B���̃����Y�E�N���u�Ƀz�[���E�p�[�e�B�[�̎ʐ^���ڂ��Ă��āA���̒��̈�l�̒j�����f���������Ă����b�̒��S�Ƀ��{���̕t�����X���b�v�H�����ǂ����Ă��C�ɂ�����܂����B�Ȃ��A�j�̌C�Ƀ��{���H�i������30�N�ʑO�ɑ嗬�s���A���̎��A�傫�ȌC�X�ł͕K���u���Ă������^�b�Z���E�X���b�v�H���̂��Ƃł��B�j6�`7�l���̃��f�����ʂ��Ă��钆�̂�������l�̖{���ɏ����ȌC�̕����ł����A���x���Ă����ꂾ�����C�ɂȂ�܂��B�����ŁA���̕ł̌�ɍڂ��Ă����ދ��͓X�̒�����V���[�Y����ŕ��a���C�X�̖��O�������܂����B
�ǂ��ɂ����̂��Ƃ����������痣�ꂸ�A�����̔ѓc���ɐ��܂��������͂��̒n�̗����������A���N�ʂŒ��߂�������������߁A�������グ�����̓X��K�˂Ă݂܂����B�_�c�E�_�ے��̌����_��������ʂ��{�c�����ʂɌ������A�Ό��T���Y�∰�삢���݂̊Ŕ̏o�Ă���A�_�c�����Ƃ����f��فi���A�ϗt�A���Ȃǂ��Ă���傫�ȓX�j�����ɁA�ߌ}���̎O�ȓ����E�Ɍ��Ă��炭���Ȃ�ɐi�A�[�P�[�h���r�ꂽ���̊p�A�_�c���쒬�i������܂��Ɠǂށj�ɕ��a���͂���܂����B�n�Ƃ͑吳12�N�Ƃ������j������̂ŁA�V�����̒��Ɋi���������镵�͋C�̂���X�ł����B�����āA���̃V���[�E�C���h�[�̕Ћ��ɂ��ړ��Ă̂��̌C�͂���܂����B
�����̂�����8000�~�����Ǝv���܂��B���w���̎��ɂƂ��Ă͂���������ł���������ƌ�����������A�����ł��̂܂܋A�����̂��ƁA�G�C�b�I�Ƃ���ɐ����̕��䂩���э~���o��Ŕ������̂��o���Ă��܂��B�������̓��A�������Ɋw�Z�ɗ����Ă����A�������Ƃ��Ȃ��C��O�ɃN���X���[�g�̊Ԃł͑�ςȘb��ɂȂ�܂����B���̌C��ꂪ�C����܂ŗ����āA�����܂ł����ɓ���đ厖�ɂ��܂����B�������悻40�N���O�̎��ł����A�����A�����Ƀ^�b�Z���E�X���b�v�I�����ŏ��ɗ��������{�l�̒j�q���w���͎����ƐM���Ă��܂��B���ꂪ�ǂ������ƌ�������܂łȂ̂ł����A�����ŎG���̕Ћ�����C�ɓ���������������A�����1�l�ő{�����ĂĎ�ɓ��ꂽ���Ƃ��������w���̎��ɂƂ��ĂƂĂ������������̂ł��B����ȗ��A���͕��a���̃t�@���ɂȂ�A�X�̃I���W�i���Ő�̊ۂ��S����̌y���ė����S�n�̂����C�ɂ͂܂�A�Q���������Ԃ����̂��o���Ă��܂��B
��������b�͏������߂̍ŏI�͂ɓ���܂��B����A�v���Ԃ�ɐ_�ے��̃X�|�[�c�p�i�X�ɂق������̂�����A�s���ƕK����镽�a����`���Č���ƁA�Ȃ�ƁA�N�����m���Ă�����̒j�������X�ɕς���Ă���̂ł��B���炭�������݁A�V�����X�̓X������ɕ����A���N��3���̖��ɓX��߂��Ƃ̎��B�܂���A���̐����Ȃ��t�̏��_�ے��̊X��������Ă��܂��܂����B�v���o�ƌ������̂͂�������ƐS�ɍ���ł����Ƌ��ɂ��܂����ނ��̂Ƃ͌������A�S�z�ɂȂ��Ă��̐�̍����M�^�[�̘V�܁A�J���Z�y��ɍs���Ă݂�Ƃ�������c�ƒ��ł����B����S���āA������C�ɂȂ�X�A���̂܂ܑO���i�ݑ傫�Ȍ����_���E�ɐ܂�A�����E���̖V�哪�̒j�����`���ꂽ�A�傫�ȊŔ��L����Y�V���c������܂ōs���Ă݂܂����B��������������撣���Ă��āA�V��̏f������̊G������z�b�Ƃ��܂����B�q���̍��A�����ɘA������{�����ʂ������s�d����A�K�����̏f������̊Ŕ����Ă͂��낻��ړI�n���߂��Ȃ��������m�F���Ċ��ł������̂ł��B
�������肵����A���S������ŕ�������H�������������1���̑�D���ȋ����̂܂�i�ŋ߁A������肾�Ƃ��Ō`����̃L�U�ȋ������������Ȃ��Ă����̂ł����A�n��100�N����Ƃ������̓X�́A���s���Ă����肰�Ȃ��D�����}���Ă���܂��B�j�ň�t���Ȃ���l���܂����B�����������ς�邱�̐��̒��ł��ꂪ�킾�Ƃ킩���Ă��Ă��A�ς���ė~�����Ȃ���Ȃ��́A�����܂ł������ɂ��ė~�������́A����ȑ��݂������Ƃ����l�Ԃɒu�������āA�����g������ȑ��݂ɂȂꂽ�炢���ȁ`�B�i�A�`���`���b�e�I�傻�ꂽ�A�ЂƂ育�ƁA�ЂƂ育�ƁB
2006.09.10 (��) �u�D�_�����v�ƃR�[�g�_�W���[��
�����Ȃ蓂�˂ŋ��k�ł����A�ԍD���A�������ŗ��D���̐l�ցA�����ƃA�C�X�u���[�̂����߂̉f���"�D�_����"�ł��B1954�N�̃A���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N�̍�i�B�q�b�`�R�b�N�{���̎�Ɋ�����T�X�y���X�����ׂ�Ə��X��ʂ邢���ȂƂ͎v���܂����A���̕���͓앧�R�[�g�_�W���[���A�o�Ă���o�D�͍ł��q�b�`�R�b�N�̂��C�ɓ��肾�����P�[���[�E�O�����g�A�O���[�X�E�P���[�Ƃ����␢�̔��j�����A���E�I�ɂ��L���Ȕ������i�F�A�Q�l�̔o�D�̑f���炵���ߑ��Ƃ��̒����Ȃ��́A�܂��ɋZ����ł��B����ɂȂ����z�e���A�J���k�ɂ���J�[���g���E�C���^�[�R���`�l���^���̐��A�R�����@�[�e�B�u���̎Ԃ̐F�A���̂ǂ���Ƃ��Ă����Ă��邾���Ŗ��̂悤�ȋC���ɂ������܂��B����ƂƂ��ɁA�������̐���ҁA�o���҂����͂قƂ�ǂ��̐��������Ă��܂��Ă��鎖���痈�Ă���̂ł��傤���A������v�킹��t�B�����̐F�ȂɈꖕ�̈��D�������܂��B�O���[�X�͂��̈�N��ɃJ���k�f��ՂōĂт��̒n��K��A���i�R�̃��[�j�G����ƒm�荇���A���̈�N��Ɍ���܂��B���ԓI�Ɍ����A����͂܂��ɃV���f�����E�X�g�[���[���̂��̂ł����B�����Ă��̉f��̒��ŃP�[���[�E�O�����g�ƃs�N�j�b�N��h���C�u���y���u�̓��ŁA1982�N9��14���Ɍ�ʎ��̂ő��E���܂��B�����̓j�[�X����G�U���A�E��ɒn���C�����Ȃ��烂�i�R�֍����|�������������u�̒���������ɂȂ������ł��B�i���Ƀ��i�R�吹���ɖ���O���[�X���܂̉^�������̉f��ɋ��������܂��B
����"�D�_����"�̒��ŁA2�̖Y����Ȃ����̑�D���ȃV�[��������܂��B1�͎n�߂ďo��������ɃO���[�X���z�e���̕����̑O�ŁA���x�݂��������r�[���̃P�[���[�E�O�����g�ɂ����Ȃ�L�X������V�[���B���M�ɖ�������������ƃ��C�g�E�u���[�̃h���X���N�₩�ł����B2�ڂ͐�ɂ��q�ׂ��A�u�̏�ł̃����`�̎��Ԃł��B�Z���C���N�u���[�̃R�����@�[�e�B�u���ɏ���āA�R�[�g�_�W���[���̊C���ቺ�Ɍ��Ȃ���A2�l�����F�̏��r�̃r�[���炵�����ݕ������݂Ȃ���A�`�L����H�ׂ�V�[���ł��B�������ȑ�l�̃n�C�L���O�Ƃ������܂������������đf�G�ł����B
���͂��Ȃ�̎ԍD���Ȃ̂ł����A����2�l�����L���Ă����ԁA�P�[���[�̂̓G���W�A�O���[�X�͔̂Z���C���N�u���[�A���̗��ԂƂ����܂��ɎԎ킪�킩��܂���B�s�j���t�@���[�i��M�A�Ȃǂ̃J�[�E�f�U�C�i�[�ɂ���Č��萔��Ƃ����`�ō��ꂽ�A���Ȃ�I�[�_�[�E���C�h�F�̋����ԂȂ̂ł��傤���A50�N�ȏ���O�̍������[���b�p�Ԃ͑����f�l�ɂƂ��Ĕ���ɂ������������ł����A���ꂪ�������ᛂ̎�ł��B�܂��A����͂悵�Ƃ��āA�Ƃɂ�����ΓD�_�Ƃ����e�[�}�̌y�����A���邢�^�b�`�Ɨ����̂���₩���A���ȃt�@�b�V�����A�Ɉ��̈��l�͏o���J�b�g�A���ł͉����̕��؊قł����邱�Ƃ��ł��Ȃ�����Ȍy�����ƂĂ��S�n�����̂ł��B
���`���ЂƂ育�ƂɂȂ�܂����I