�N���V�b�N ���m�Ƃ̑����@�@2008�N5���`2024�N4��
2024/04/15 (��) �t�̃N���V�b�N�y�Ȃ̂�Ԃɂ�ݓI�l�@
2024/03/11 (��) �����݂䂫�R���T�[�g�u�̉�VOL.1�v�`�����I���|�[�g
2024/02/15 (��) �uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ƃ����{
2024/01/17 (��) �V�N�����`���T�C�A�o����Җ]����
2023/12/10 (��) 12�� �G���`�Ⴊ���N�̊����́u���v
2023/11/15 (��) �����O�bCD�����̓^��
2023/10/12 (��) �c���\��Y����A���炩��
2023/09/10 (��) �n�������̉ĂɃE�N���C�i��z��
2023/08/16 (��) ��叫�E���R�Y�O�́u���y�݂͂�ȂƂ������v�`�������̊y�ȃA�E���E�J�E���E�g
2023/07/13 (��) ������ƕρI�H ���s�̂̉̎����낢��
2023/06/14 (��) ���n�l���A���Ɖe
2023/05/10 (��) �����I��{����ρ`�u���ԁv�Ɋ�
2023/04/05 (��) �tࣖ��`WBC�A�����Ē����݂䂫
2023/03/15 (��) ���ΐ�]�_��3�e�`�������ȕ]�_���ꂱ��
2023/02/15 (��) ���ΐ�]�_��2�e�`�u�����X�e���I�^�C�v�I��]�p
2023/01/11 (��) 2022�^2023�N�܂������y���]
2022/12/14 (��) �H�̐M�B�`�R���T�[�g2�A��
2022/11/15 (��) ���ΐ�̉��]�_����ǂ���
2022/10/12 (��) �x�[�g�[���F���A���̊y�Ȃ��Ă߂��v��
2022/09/18 (��) �x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v���l�@����
�`���R���t�b�̑�31�ԂɐG�������
2022/08/16 (��) ���R���t�b �Ռ��̃N���b�V�F���h
2022/07/26 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g2
�`�����h�q�Ƃ����d���s�A�j�X�g
2022/06/20 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g�P
�`���q�b�q�Ɠc�����q
2022/05/20 (��) �v�[�`���̃E�N���C�i�N�U�ƃV���X�^�R�[���B�`�̌�����
2022/04/23 (�y) �t�Ȃ̂ɁE�E�E�E�E
2022/03/15 (��) ���D�J���XVS�V�g�e�o���f�B
2022/02/25 (��) �k���~�G�I�����s�b�N�`�����Ƌ\�Ԃ̍ՓT
2022/01/25 (��) DIVA�}���A�E�J���X�̃I�y���̎�l��
�`�M���V���A�A�����J�A�C�^���A�A�����āu�m���}�v
2021/12/18 (�y) Come Come Everybody ���烋�C�E�A�[���X�g�����O���v��
2021/11/11 (��) MLB�A�����đ�J�ĕ��ɂ��Ďv������
2021/10/20 (��) �H�Ɏ₵������
2021/09/25 (��) �q�[ ���c�r��搶�`���� �W�i1964�N���w�ETp�j
2021/08/25 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�j�Z��KV626�`���̕�M�������߂�����
���c�r�� 1954�N���w Va �i�ꋿNo.21�f�ځj
2021/07/20 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������
���� �W 1964�N���w Tp�i�ꋿNO.20�f�ځj
2021/06/20 (��) ��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ��u���S���v�Ɓu4�̊K��v�̂��b
2021/05/20 (��) �F����F�搶�̂���
2021/04/15 (��) �}�X�^�[�Y2021 ���R�p���̏����e���l����
2021/03/20 (�y) �����炢�Ȃ� ���炪�t
2021/02/10 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������
2021/01/15 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������
2020/12/05 (�y) �`���[���[�E�p�[�J�[�`�L�u�o�[�h�v��ǂ��
2020/11/12 (��) 2020�đ哝�̑I���N�����m�I����
2020/10/10 (�y) �哝�̑I������s�v�c�̍��A�����J��T��
2020/09/05 (�y) ���{������7�N8��������� with Ray�����
2020/08/16 (��) �����A���̂��Ƃ��烏�[�O�i�[�Ɩ��t�W�ɑz����y����
2020/07/13 (��) 7���G��
�`�Ȃ����m���E�F�[�A�����ăG�����g������x�[�g�[���F���o�R�����F���܂�
2020/06/26 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X10
�`PORTRAIT OF SIDNEY BECHET�ɂ�����G�����g���̑I��
2020/05/20 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X9
�`�ēx�A����搶�Ƃ̂����A����
2020/04/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X8
�`��͂�v���R�[�v�A�����Đ��쏹�v�搶
2020/03/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X7�`����̓W���j�[�E�z�b�W�X
2020/02/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X6�`����̓V�h�j�[�E�x�V�F
2020/01/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X5
�`�삯�o�����D�Ƃ́uELLINGTON UPTOWN�v����
2019/12/15 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X4
�`�K�[�V���C���u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\��
2019/11/05 (��) �Ǔ� ���瑐�O����
2019/10/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X3
�`�A���h���E�v�����B���A�I�����[����
2019/09/22 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X2
�`�W���Y�̖��� ���[�c�@���g�����t���� �̊�
2019/08/16 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X1
�`�W���Y�̖���̓N���V�b�N�̖��Ȃ��ǂ������������H
2019/07/13 (�y) ���@��9�������}�����Ă��Ԃ��ׂ�
2019/06/25 (��) �����x���̃��c���N�A�����āA�V���������ł̒�
2019/05/25 (�y) ���z�`���O��5����
2019/04/25 (��) ���̃I�[�f�B�I�j
2019/03/31 (��) ����v���搶�̎v���o
2019/02/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ ���
2019/02/01 (��) �N�C�[���u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v���|�[�g
2019/01/20 (��) �N���N�n�G���E���y�с`�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�Ə���
2018/12/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ �O��
2018/11/25 (��) �W�l�b�g�E�k���[�^�`�H��̓V�˃��@�C�I���j�X�g���Â�
2018/10/27 (��) �X�g���f�B���@���E�X�l�@�`��ՁA���̐^��
2018/09/30 (��) �����FM���ǂ���
2018/08/31 (��) �킪����Â��
2018/05/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l2�`�G�~�[���E�x�����i�[
2018/04/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l1�`�j�R���E�e�X��
2018/03/05 (��) �����ܗ� ��l�̒��쌧�l���_���X�g�̖��ƈ�
2018/02/15 (��) �������`�j�ϓV�ڂ��烂�[�c�@���g�u�A�f���C�[�h���t�ȁv���l�@����
2018/01/15 (��) 2018�N�n�G���`�A���Q���b�`�AABC�\�z�Ȃ�
2017/12/10 (��) �ꋴ��w�I�[�P�X�g��47�N�Ԃ�̓�����
2017/11/16 (��) �J�Y�I�E�C�V�O������FM���ǂ���20���N�A�����āA���߂łƂ��ޗǂ���I
2017/10/25 (��) ���r�S���q�̎��s�`��]�����]��
2017/10/04 (��) ���r�S���q�K���̃T�v���C�Y�`�Ō�̈��̓~�X�^�[X�̏o�n��
2017/09/29 (��) ���ς�8�N�����ł���Ă���I�H�`���r�S���q�́u���̐�͏��Ă�I�v�Ɠ���
2017/09/20 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`��ҁu��F���������v
2017/09/05 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`�O�ҁu�N�����m�v�L�q�͕s���m
2017/08/15 (��) �^�Ă̖�̖��`�V�F�C�N�X�s�A ���ꂱ��
2017/07/25 (��) �ẴN���V�b�N���y�`�u�����N���V�b�N�v����
2017/07/15 (�y) �h�L�������g�`�V���[���h���E���F�[�O��K137���𖾂���
2017/06/26 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� ��ҁ`4�l�ڂ̃��i���U�͒N�H
2017/06/20 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� �O�ҁ`�B��Ă����W���R���_
2017/05/25 (��) ���{�ƃg�����v�A���߂�̂͂ǂ����H
2017/05/15 (��) �G���K�[�u���̈��A�v�ƃh���}�u���_�v�ɓZ���ʔ��b
2017/03/25 (�y) �u���Ȃ����g���v��� ����
2017/03/15 (��) 3���́u���N���v�́u����VS�N���V�b�N�v�̏t�Ό�
2017/02/25 (�y) �Ǔ� �D���O�`�̂͐S�ł���������
2017/02/15 (��) ��156�؏�܍�u���I�Ɖ����v�͂Ȃ��Ȃ��̌��삾
2017/01/25 (��) 2017�N���G���u�X�|�[�c�v�ҁ`with Ray�����
2017/01/15 (��) 2017�N���G���u���O��v�ҁ`with Ray�����
2016/12/25 (��) �{�u�E�f�B������蒆���݂䂫
2016/12/10 (�y) �ێR�O����Ǔ����t��
2016/12/05 (��) ��������̂��ƂȂǁ`with Ray�����
2016/11/15 (��) �����̃��[�O�i�[�̌�
2016/10/25 (��) �{�u�E�f�B�����̃m�[�x����܂�P��
2016/10/15 (�y) FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v
2016/09/26 (��) ��Ղ̖�`�g���E�n���N�X�Ƒ����̓^��
2016/09/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 4 �`�{���g �Z������4 �}���J�i���̊���
2016/09/07 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 3 �`�_���Ƌ��j ���ƌ|�����I�H
2016/08/31 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 2 �`���P�b�g���Z ��Ղ�5�A���|�C���g
2016/08/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 1 �`�g�c�ƈɒ������ē����ƃx���j���G�t
2016/08/10 (��) �X�R�b�`�E�E�C�X�L�[�ɂ܂��G�g�Z�g��
2016/07/25 (��) �b����`�s�m���I�A���z���̃g�̓g���`���J���̃g
2016/07/05 (��) �u�b�V���~���Y����u�_�j�[�E�{�[�C�v����������
2016/06/19 (��) �b����`�u�}�X�]�G�̓t�H�[�N���v���c�T��
2016/05/30 (��) �t�������Y �g�ēx�h�Ⴂ���炯�̉��y�u��
2016/05/15 (��) ���̒� ���L������Ă����悤�ŁI�H with Ray�����
2016/04/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�7�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����C
�Ñ��̎����Ȃ�������u���˂̉ԉŁv�͒a�����Ȃ������I�H
2016/04/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�6�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����B�t�̒u���y�Y
2016/03/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�5�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����A�Ñ��A��̂����̊ԁI
2016/03/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�4�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����@�Ñ����Ƃ����j
2016/02/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�3�`�l���ɔV���̃��j���[�A�����
2016/02/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�2�`�u�܂��������܂Łv�͈��v�I���g�̃p���f�B
2016/01/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊ԂɂP�`����Ђ�u�߂������v�͓�Ԑ���
2016/01/10 (��) ���ƃZ���X�̊��S��`�҃u�[���[�Y�̎��𓉂�
2015/12/28 (��) 2015�N�����k with Ray�����
2015/12/10 (��) �e���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂��H
2015/11/25 (��) ���E�싅�v���~�A12 ���ؐ�̔s��
2015/11/10 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 ���
2015/10/25 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 �O��
2015/10/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞�� �ŏI��`�u�����B���Łv�̌��_�Ɖ����ł̒�
2015/09/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��11�`�u�����B���Łv���܂�3�̔ł��l�@����
2015/09/10 (��) ���70�N�Ɋāi��ҁj�`��㕜���A������Jiiji�̒�
2015/08/25 (��) ���70�N�Ɋāi�O�ҁj�`���{�͂Ȃ��������̂��H
2015/08/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��10�`���[���_�[�ł͖�肠��I
2015/07/25 (�y) ���c���N�Ɏa�荞��9�`�����ς������o�C���[��
2015/07/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��8�`���ׂĂ̓��[�c�@���g�̎w��
2015/06/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��7�`�W���X�}�C���[�̎��s�͂Ȃ��N���Ă��܂����̂��H
2015/06/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��6�`�W���X�}�C���[�ő�̎��s
2015/05/25 (��) ����ł����̂� ���{�I�Iwith Ray�����
2015/05/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��5�`�u�T���N�g�D�X�vSanctus�́u�ǎ��@�~�T�v�̈��p
2015/04/29 (��) ���c���N�Ɏa�荞��4�`�u�܂̓��vLacrimosa�ɂ����郂�[�c�@���g�̎w��
2015/04/12 (��) ���c���N�Ɏa�荞��3�`�R���X�^���c�F ���̌����ȍٗ�
2015/04/01 (��) ������ƕς������̒��� with Ray �����
2015/03/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��2�`��ȎO�p�W
2015/03/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��1�`���z�ȃW���X�}�C���[
2015/02/25 (��) �A�����J���u���c���N�v�ŔƂ�����
2015/02/10 (��) �����Ƀ��N�C�G����
2015/01/25 (��) �f��u�o���N�[�o�[�̒����v�Ƒh��
2015/01/13 (��) �V�N�Ɋ� with Ray�����
2014/12/25 (��) 2014�����_����� with Ray�����
2014/12/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���11�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�b�n��3�̕s���s�u�o�b�n�̓��[�~���̐擱�t�v
2014/11/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���10�`�o�b�n��2�̕s���s�u���ϗ��v
2014/11/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���9�`�o�b�n�s���s����1�u�Έʖ@�v
2014/10/25 (�y) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���8�`�u���ɕa��Łv�̐[��
2014/10/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���7�`�ʂĂ��Ȃ��s���s
2014/09/025 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���6�`�u�����̂ق����v�Ɂu�s���s�v��T��
2014/09/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���5�`�m�Ԃɂ�����u�s���s�v�̊T�O
2014/08/05 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�������Y �ԈႢ���炯�̉��y�u��
2014/07/25 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g �ԊO�ҁ`�o���I�@���d�F�̂Ƃ�ł��Ȃ��_�]
2014/07/20 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g6 �` �h�C�c�D���Ƒ���
2014/07/13 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g5 �` �Ō�ɒ]�t�@���n�[���єz
2014/07/11 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g4 �` ��Ƃ̓_�r�h���C�X
2014/07/08 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g3 �` �x�X�g4�o����
2014/06/30 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g2 �` �O���[�v���[�O�Ɉٕ�
2014/06/26 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g1 �` ���{�I���Jiiji�̒�
2014/06/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���4�`�u�����̂ق����v�Ɍ���Βu Contraposition �̖�
2014/06/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���3�`J.S.�o�b�n �V�����g���[�̈ӎ�
2014/05/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���2�`�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�Ɍ���F����
2014/05/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���1�`�m�Ԃ̉F����
2014/04/15 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����7�`�����ȉƂ̘_�]
2014/04/01 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����6�`�q�[ �_�R�T�m�l
2014/03/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�Ȃ̂�
2014/03/11 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����5�`�t�B�N�T�[X�̑���
2014/03/01 (�y) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����u�ŏI��v�`���ؐ��i�͂Ƃ�ł��Ȃ�
2014/02/25 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����3�`�����r�̑O�㖢���̐�����
2014/02/20 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����2�`�{���ɒm��Ȃ������̂��H
2014/02/16 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����P�`��O���̎���
2014/02/10 (��) Jiiiji�̂Ԃ₫�`�t�ĂԃN���V�b�N
2014/01/25 (�y) �N���E�f�B�I�E�A�o�h�Ǔ�
2014/01/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�G���^����
2014/01/10 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�X�|�[�c��
2013/12/15 (��) �b����`Global�N���X�}�XSongs
2013/12/05 (��) �ӏH�f�́`���N�̏H�͉�A���e�[�}
2013/11/20 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊��2�`�u�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I���Y�v
2013/11/10 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊�ՂP�`����́u�X�C�[�g��L�������C���v����n�܂���
2013/10/31 (��) �b����`�V��S�g����
2013/10/25 (��) �b����`�u�x�[�g�[���F���ƃx�[�g�z�[�t�F���v
2013/10/10 (��) ���I�u���R�����_�v�ŏI��`����ɎE���ꂽ���R�葥
2013/09/15 (��) �b����`�ˑR�̑������
2013/09/02 (��) �b����`�u�������ʁv���ς�
2013/08/25 (��) ���I�u���R�����_�v5�`���������̏
2013/08/10 (�y) ���I�u���R�����_�v4�`����̘b ���
2013/07/22 (��) �b����`�f��u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�v������
2013/07/20 (�y) �b����`�T�v���C�Y�A���̃R���T�[�g
2013/07/17 (��) �b����`�\�����G���蕱���L
2013/07/10 (��) ���I�u���R�����_�v3�`����̘b �O��
2013/06/25 (��) ���I�u���R�����_�v2�`�Ɛl�̍s����ǂ�
2013/06/10 (��) ���I�u���R�����_�v1�`�����̖{���Ƃ���܂�
2013/05/25 (��) �b����`���O��G�߂�
2013/05/15 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��12�`���{�����u���[�c�@���g�̔��y�v��ǂ��
2013/04/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��11�`���R�E�߂́u���J�v�̒��ɐ����Ă���
2013/04/15 (��) �b����`���N�̃}�X�^�[�Y�͓����15�ԃ^�C�K�[�̑�3�łŏI�����
2013/04/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��10�`���[�c�@���g�ɍ��R�E�߂��~�ՁI
2013/03/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��9�`�E�B�[���ł̍ĉ�Ɓu���J�v�ւ̒���
2013/03/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��8�`�t���[���C�\���ւ̓���
2013/02/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��7�`�l���ő�̓]�@
2013/02/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��6�`�~�����w������E�B�[����
2013/01/31 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��5�`�V�J�l�[�_�[�Ƃ����j
2013/01/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��4�`���[�c�@���g�ƃE�R���h�m�̐ړ_
2012/12/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��3�`�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�Ƃ����@����
2012/12/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��2�`���[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h��
2012/11/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��1�`�^�~�[�m�͍��R�E�߂��H
2012/11/05 (��) ���G���Ō�̑䎌�Ɍ����܂����킯
2012/10/25 (��) ���A���Y����胊���V�Y���`�u���Ȃ��ցv���ςēǂ��
2012/10/20 (�y) ����t���Ɛ�t���ƃm�[�x���܂� �����āA�R������
2012/10/05 (��) ��t���̐^���`����͓c���p�h�̕s�p�ӂȔ�������n�܂���
2012/09/05 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�E
2012/08/25 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�D
2012/08/15 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�C
2012/08/13 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�B
2012/08/10 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�A
2012/08/07 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�@
2012/07/25 (��) ���̒��̒����݂䂫5�|�����݂䂫�́g���́h�ł���4
2012/07/10 (��) ���̒��̒����݂䂫4�|�����݂䂫��"����"�ł���3
2012/06/27 (��) �b����`�g���X�s�[�J�[�Ȃ�
2012/05/31 (��) �b����`���O��G�߂̒���
2012/05/20 (��) ���̒��̒����݂䂫3�|�����݂䂫��"����"�ł���2
2012/05/10 (��) ���̒��̒����݂䂫2�|�����݂䂫��"����"�ł���1
2012/04/20 (��) ���̒��̒����݂䂫�P�`���I�ꌳ�I�����݂䂫�_
2012/04/05 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��D �L�҉�����̐^��
2012/03/20 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��C ��ƂƂ��Ă̐Ό��T���Y
2012/03/10 (�y) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��B�u���v��ǂ��
2012/03/01 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��A�u�|�g�X���C���̏M�vVS�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v
2012/02/20 (��) �T��Łu�����̋L�v
2012/02/15 (��) �ً}�Ք��I������̊H��܍�i���l����
2012/02/10 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��@�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�̖ʔ���
2012/02/05 (��) FM����
2012/01/25 (��) ���V���� ���{�̕�
2012/01/10 (��) �b����`2012�V�N�G��
2011/12/25 (��) �b����`2011���N�����s��
2011/12/05 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����31�|40
2011/11/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����21�|30
2011/11/15 (��) �b����`�����E�����̃V���[�x���g���V�˘_
2011/10/31 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����11�|20
2011/10/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����1�|10
2011/10/13 (��) �u���Ɂv���Ɋ���
2011/09/30 (��) �u���[�����C�v�́u�t�̖��v���琶�܂ꂽ
2011/09/20 (��) �u�����̉́v����
2011/09/11 (��) �u�~�̗��v����
2011/08/31 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�2
2011/08/25 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�1
2011/08/15 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`���a���̊�
2011/07/31 (��) �b����`�Ƃ�ł��Ȃ��T�b�J�[�_
2011/07/25 (��) �b����`�u�Ȃł����W���p���v�N�����m�I����
2011/07/10 (��) �b����`�u�V�F�G���U�[�h�v�ɂ܂��G�g�Z�g��
2011/06/30 (��) ��k�Вf�́m9�n �����̒��� ��
2011/06/20 (��) ��k�Вf�́m8�n�͂��I���y�̗́`�C�O�A�[�e�B�X�g��
2011/06/05 (��) ��k�Вf�́m7�n�Ԏq�̓����ŗx�������
2011/05/25 (��) ��k�Вf�́m6�n�����}��A���Ɍ�����؍����͂Ȃ�
2011/05/20 (��) ��k�Вf�́m5�n�����l��Ղ��s�K
2011/05/12 (��) ��k�Вf�́m�ԊO�ҁn ���k�ɕ�����A�_�[�W��
2011/05/09 (��) ��k�Вf�́m4�n �G�l���M�[����̐����������
2011/04/30 (�y) ��k�Вf�́m3�n �������ǂ�����
2011/04/25 (��) ��k�Вf�́m2�n �������̂͐l��
2011/04/20 (��) ��k�Вf�́m�P�n �z��O�͒p
�@2011/03/23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X��21 �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v14
2024/03/11 (��) �����݂䂫�R���T�[�g�u�̉�VOL.1�v�`�����I���|�[�g
2024/02/15 (��) �uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ƃ����{
2024/01/17 (��) �V�N�����`���T�C�A�o����Җ]����
2023/12/10 (��) 12�� �G���`�Ⴊ���N�̊����́u���v
2023/11/15 (��) �����O�bCD�����̓^��
2023/10/12 (��) �c���\��Y����A���炩��
2023/09/10 (��) �n�������̉ĂɃE�N���C�i��z��
2023/08/16 (��) ��叫�E���R�Y�O�́u���y�݂͂�ȂƂ������v�`�������̊y�ȃA�E���E�J�E���E�g
2023/07/13 (��) ������ƕρI�H ���s�̂̉̎����낢��
2023/06/14 (��) ���n�l���A���Ɖe
2023/05/10 (��) �����I��{����ρ`�u���ԁv�Ɋ�
2023/04/05 (��) �tࣖ��`WBC�A�����Ē����݂䂫
2023/03/15 (��) ���ΐ�]�_��3�e�`�������ȕ]�_���ꂱ��
2023/02/15 (��) ���ΐ�]�_��2�e�`�u�����X�e���I�^�C�v�I��]�p
2023/01/11 (��) 2022�^2023�N�܂������y���]
2022/12/14 (��) �H�̐M�B�`�R���T�[�g2�A��
2022/11/15 (��) ���ΐ�̉��]�_����ǂ���
2022/10/12 (��) �x�[�g�[���F���A���̊y�Ȃ��Ă߂��v��
2022/09/18 (��) �x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v���l�@����
�`���R���t�b�̑�31�ԂɐG�������
2022/08/16 (��) ���R���t�b �Ռ��̃N���b�V�F���h
2022/07/26 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g2
�`�����h�q�Ƃ����d���s�A�j�X�g
2022/06/20 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g�P
�`���q�b�q�Ɠc�����q
2022/05/20 (��) �v�[�`���̃E�N���C�i�N�U�ƃV���X�^�R�[���B�`�̌�����
2022/04/23 (�y) �t�Ȃ̂ɁE�E�E�E�E
2022/03/15 (��) ���D�J���XVS�V�g�e�o���f�B
2022/02/25 (��) �k���~�G�I�����s�b�N�`�����Ƌ\�Ԃ̍ՓT
2022/01/25 (��) DIVA�}���A�E�J���X�̃I�y���̎�l��
�`�M���V���A�A�����J�A�C�^���A�A�����āu�m���}�v
2021/12/18 (�y) Come Come Everybody ���烋�C�E�A�[���X�g�����O���v��
2021/11/11 (��) MLB�A�����đ�J�ĕ��ɂ��Ďv������
2021/10/20 (��) �H�Ɏ₵������
2021/09/25 (��) �q�[ ���c�r��搶�`���� �W�i1964�N���w�ETp�j
2021/08/25 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�j�Z��KV626�`���̕�M�������߂�����
���c�r�� 1954�N���w Va �i�ꋿNo.21�f�ځj
2021/07/20 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������
���� �W 1964�N���w Tp�i�ꋿNO.20�f�ځj
2021/06/20 (��) ��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ��u���S���v�Ɓu4�̊K��v�̂��b
2021/05/20 (��) �F����F�搶�̂���
2021/04/15 (��) �}�X�^�[�Y2021 ���R�p���̏����e���l����
2021/03/20 (�y) �����炢�Ȃ� ���炪�t
2021/02/10 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������
2021/01/15 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������
2020/12/05 (�y) �`���[���[�E�p�[�J�[�`�L�u�o�[�h�v��ǂ��
2020/11/12 (��) 2020�đ哝�̑I���N�����m�I����
2020/10/10 (�y) �哝�̑I������s�v�c�̍��A�����J��T��
2020/09/05 (�y) ���{������7�N8��������� with Ray�����
2020/08/16 (��) �����A���̂��Ƃ��烏�[�O�i�[�Ɩ��t�W�ɑz����y����
2020/07/13 (��) 7���G��
�`�Ȃ����m���E�F�[�A�����ăG�����g������x�[�g�[���F���o�R�����F���܂�
2020/06/26 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X10
�`PORTRAIT OF SIDNEY BECHET�ɂ�����G�����g���̑I��
2020/05/20 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X9
�`�ēx�A����搶�Ƃ̂����A����
2020/04/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X8
�`��͂�v���R�[�v�A�����Đ��쏹�v�搶
2020/03/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X7�`����̓W���j�[�E�z�b�W�X
2020/02/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X6�`����̓V�h�j�[�E�x�V�F
2020/01/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X5
�`�삯�o�����D�Ƃ́uELLINGTON UPTOWN�v����
2019/12/15 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X4
�`�K�[�V���C���u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\��
2019/11/05 (��) �Ǔ� ���瑐�O����
2019/10/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X3
�`�A���h���E�v�����B���A�I�����[����
2019/09/22 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X2
�`�W���Y�̖��� ���[�c�@���g�����t���� �̊�
2019/08/16 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X1
�`�W���Y�̖���̓N���V�b�N�̖��Ȃ��ǂ������������H
2019/07/13 (�y) ���@��9�������}�����Ă��Ԃ��ׂ�
2019/06/25 (��) �����x���̃��c���N�A�����āA�V���������ł̒�
2019/05/25 (�y) ���z�`���O��5����
2019/04/25 (��) ���̃I�[�f�B�I�j
2019/03/31 (��) ����v���搶�̎v���o
2019/02/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ ���
2019/02/01 (��) �N�C�[���u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v���|�[�g
2019/01/20 (��) �N���N�n�G���E���y�с`�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�Ə���
2018/12/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ �O��
2018/11/25 (��) �W�l�b�g�E�k���[�^�`�H��̓V�˃��@�C�I���j�X�g���Â�
2018/10/27 (��) �X�g���f�B���@���E�X�l�@�`��ՁA���̐^��
2018/09/30 (��) �����FM���ǂ���
2018/08/31 (��) �킪����Â��
2018/05/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l2�`�G�~�[���E�x�����i�[
2018/04/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l1�`�j�R���E�e�X��
2018/03/05 (��) �����ܗ� ��l�̒��쌧�l���_���X�g�̖��ƈ�
2018/02/15 (��) �������`�j�ϓV�ڂ��烂�[�c�@���g�u�A�f���C�[�h���t�ȁv���l�@����
2018/01/15 (��) 2018�N�n�G���`�A���Q���b�`�AABC�\�z�Ȃ�
2017/12/10 (��) �ꋴ��w�I�[�P�X�g��47�N�Ԃ�̓�����
2017/11/16 (��) �J�Y�I�E�C�V�O������FM���ǂ���20���N�A�����āA���߂łƂ��ޗǂ���I
2017/10/25 (��) ���r�S���q�̎��s�`��]�����]��
2017/10/04 (��) ���r�S���q�K���̃T�v���C�Y�`�Ō�̈��̓~�X�^�[X�̏o�n��
2017/09/29 (��) ���ς�8�N�����ł���Ă���I�H�`���r�S���q�́u���̐�͏��Ă�I�v�Ɠ���
2017/09/20 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`��ҁu��F���������v
2017/09/05 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`�O�ҁu�N�����m�v�L�q�͕s���m
2017/08/15 (��) �^�Ă̖�̖��`�V�F�C�N�X�s�A ���ꂱ��
2017/07/25 (��) �ẴN���V�b�N���y�`�u�����N���V�b�N�v����
2017/07/15 (�y) �h�L�������g�`�V���[���h���E���F�[�O��K137���𖾂���
2017/06/26 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� ��ҁ`4�l�ڂ̃��i���U�͒N�H
2017/06/20 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� �O�ҁ`�B��Ă����W���R���_
2017/05/25 (��) ���{�ƃg�����v�A���߂�̂͂ǂ����H
2017/05/15 (��) �G���K�[�u���̈��A�v�ƃh���}�u���_�v�ɓZ���ʔ��b
2017/03/25 (�y) �u���Ȃ����g���v��� ����
2017/03/15 (��) 3���́u���N���v�́u����VS�N���V�b�N�v�̏t�Ό�
2017/02/25 (�y) �Ǔ� �D���O�`�̂͐S�ł���������
2017/02/15 (��) ��156�؏�܍�u���I�Ɖ����v�͂Ȃ��Ȃ��̌��삾
2017/01/25 (��) 2017�N���G���u�X�|�[�c�v�ҁ`with Ray�����
2017/01/15 (��) 2017�N���G���u���O��v�ҁ`with Ray�����
2016/12/25 (��) �{�u�E�f�B������蒆���݂䂫
2016/12/10 (�y) �ێR�O����Ǔ����t��
2016/12/05 (��) ��������̂��ƂȂǁ`with Ray�����
2016/11/15 (��) �����̃��[�O�i�[�̌�
2016/10/25 (��) �{�u�E�f�B�����̃m�[�x����܂�P��
2016/10/15 (�y) FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v
2016/09/26 (��) ��Ղ̖�`�g���E�n���N�X�Ƒ����̓^��
2016/09/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 4 �`�{���g �Z������4 �}���J�i���̊���
2016/09/07 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 3 �`�_���Ƌ��j ���ƌ|�����I�H
2016/08/31 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 2 �`���P�b�g���Z ��Ղ�5�A���|�C���g
2016/08/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 1 �`�g�c�ƈɒ������ē����ƃx���j���G�t
2016/08/10 (��) �X�R�b�`�E�E�C�X�L�[�ɂ܂��G�g�Z�g��
2016/07/25 (��) �b����`�s�m���I�A���z���̃g�̓g���`���J���̃g
2016/07/05 (��) �u�b�V���~���Y����u�_�j�[�E�{�[�C�v����������
2016/06/19 (��) �b����`�u�}�X�]�G�̓t�H�[�N���v���c�T��
2016/05/30 (��) �t�������Y �g�ēx�h�Ⴂ���炯�̉��y�u��
2016/05/15 (��) ���̒� ���L������Ă����悤�ŁI�H with Ray�����
2016/04/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�7�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����C
�Ñ��̎����Ȃ�������u���˂̉ԉŁv�͒a�����Ȃ������I�H
2016/04/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�6�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����B�t�̒u���y�Y
2016/03/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�5�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����A�Ñ��A��̂����̊ԁI
2016/03/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�4�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����@�Ñ����Ƃ����j
2016/02/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�3�`�l���ɔV���̃��j���[�A�����
2016/02/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�2�`�u�܂��������܂Łv�͈��v�I���g�̃p���f�B
2016/01/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊ԂɂP�`����Ђ�u�߂������v�͓�Ԑ���
2016/01/10 (��) ���ƃZ���X�̊��S��`�҃u�[���[�Y�̎��𓉂�
2015/12/28 (��) 2015�N�����k with Ray�����
2015/12/10 (��) �e���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂��H
2015/11/25 (��) ���E�싅�v���~�A12 ���ؐ�̔s��
2015/11/10 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 ���
2015/10/25 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 �O��
2015/10/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞�� �ŏI��`�u�����B���Łv�̌��_�Ɖ����ł̒�
2015/09/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��11�`�u�����B���Łv���܂�3�̔ł��l�@����
2015/09/10 (��) ���70�N�Ɋāi��ҁj�`��㕜���A������Jiiji�̒�
2015/08/25 (��) ���70�N�Ɋāi�O�ҁj�`���{�͂Ȃ��������̂��H
2015/08/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��10�`���[���_�[�ł͖�肠��I
2015/07/25 (�y) ���c���N�Ɏa�荞��9�`�����ς������o�C���[��
2015/07/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��8�`���ׂĂ̓��[�c�@���g�̎w��
2015/06/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��7�`�W���X�}�C���[�̎��s�͂Ȃ��N���Ă��܂����̂��H
2015/06/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��6�`�W���X�}�C���[�ő�̎��s
2015/05/25 (��) ����ł����̂� ���{�I�Iwith Ray�����
2015/05/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��5�`�u�T���N�g�D�X�vSanctus�́u�ǎ��@�~�T�v�̈��p
2015/04/29 (��) ���c���N�Ɏa�荞��4�`�u�܂̓��vLacrimosa�ɂ����郂�[�c�@���g�̎w��
2015/04/12 (��) ���c���N�Ɏa�荞��3�`�R���X�^���c�F ���̌����ȍٗ�
2015/04/01 (��) ������ƕς������̒��� with Ray �����
2015/03/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��2�`��ȎO�p�W
2015/03/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��1�`���z�ȃW���X�}�C���[
2015/02/25 (��) �A�����J���u���c���N�v�ŔƂ�����
2015/02/10 (��) �����Ƀ��N�C�G����
2015/01/25 (��) �f��u�o���N�[�o�[�̒����v�Ƒh��
2015/01/13 (��) �V�N�Ɋ� with Ray�����
2014/12/25 (��) 2014�����_����� with Ray�����
2014/12/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���11�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�b�n��3�̕s���s�u�o�b�n�̓��[�~���̐擱�t�v
2014/11/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���10�`�o�b�n��2�̕s���s�u���ϗ��v
2014/11/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���9�`�o�b�n�s���s����1�u�Έʖ@�v
2014/10/25 (�y) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���8�`�u���ɕa��Łv�̐[��
2014/10/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���7�`�ʂĂ��Ȃ��s���s
2014/09/025 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���6�`�u�����̂ق����v�Ɂu�s���s�v��T��
2014/09/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���5�`�m�Ԃɂ�����u�s���s�v�̊T�O
2014/08/05 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�������Y �ԈႢ���炯�̉��y�u��
2014/07/25 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g �ԊO�ҁ`�o���I�@���d�F�̂Ƃ�ł��Ȃ��_�]
2014/07/20 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g6 �` �h�C�c�D���Ƒ���
2014/07/13 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g5 �` �Ō�ɒ]�t�@���n�[���єz
2014/07/11 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g4 �` ��Ƃ̓_�r�h���C�X
2014/07/08 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g3 �` �x�X�g4�o����
2014/06/30 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g2 �` �O���[�v���[�O�Ɉٕ�
2014/06/26 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g1 �` ���{�I���Jiiji�̒�
2014/06/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���4�`�u�����̂ق����v�Ɍ���Βu Contraposition �̖�
2014/06/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���3�`J.S.�o�b�n �V�����g���[�̈ӎ�
2014/05/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���2�`�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�Ɍ���F����
2014/05/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���1�`�m�Ԃ̉F����
2014/04/15 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����7�`�����ȉƂ̘_�]
2014/04/01 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����6�`�q�[ �_�R�T�m�l
2014/03/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�Ȃ̂�
2014/03/11 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����5�`�t�B�N�T�[X�̑���
2014/03/01 (�y) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����u�ŏI��v�`���ؐ��i�͂Ƃ�ł��Ȃ�
2014/02/25 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����3�`�����r�̑O�㖢���̐�����
2014/02/20 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����2�`�{���ɒm��Ȃ������̂��H
2014/02/16 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����P�`��O���̎���
2014/02/10 (��) Jiiiji�̂Ԃ₫�`�t�ĂԃN���V�b�N
2014/01/25 (�y) �N���E�f�B�I�E�A�o�h�Ǔ�
2014/01/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�G���^����
2014/01/10 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�X�|�[�c��
2013/12/15 (��) �b����`Global�N���X�}�XSongs
2013/12/05 (��) �ӏH�f�́`���N�̏H�͉�A���e�[�}
2013/11/20 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊��2�`�u�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I���Y�v
2013/11/10 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊�ՂP�`����́u�X�C�[�g��L�������C���v����n�܂���
2013/10/31 (��) �b����`�V��S�g����
2013/10/25 (��) �b����`�u�x�[�g�[���F���ƃx�[�g�z�[�t�F���v
2013/10/10 (��) ���I�u���R�����_�v�ŏI��`����ɎE���ꂽ���R�葥
2013/09/15 (��) �b����`�ˑR�̑������
2013/09/02 (��) �b����`�u�������ʁv���ς�
2013/08/25 (��) ���I�u���R�����_�v5�`���������̏
2013/08/10 (�y) ���I�u���R�����_�v4�`����̘b ���
2013/07/22 (��) �b����`�f��u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�v������
2013/07/20 (�y) �b����`�T�v���C�Y�A���̃R���T�[�g
2013/07/17 (��) �b����`�\�����G���蕱���L
2013/07/10 (��) ���I�u���R�����_�v3�`����̘b �O��
2013/06/25 (��) ���I�u���R�����_�v2�`�Ɛl�̍s����ǂ�
2013/06/10 (��) ���I�u���R�����_�v1�`�����̖{���Ƃ���܂�
2013/05/25 (��) �b����`���O��G�߂�
2013/05/15 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��12�`���{�����u���[�c�@���g�̔��y�v��ǂ��
2013/04/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��11�`���R�E�߂́u���J�v�̒��ɐ����Ă���
2013/04/15 (��) �b����`���N�̃}�X�^�[�Y�͓����15�ԃ^�C�K�[�̑�3�łŏI�����
2013/04/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��10�`���[�c�@���g�ɍ��R�E�߂��~�ՁI
2013/03/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��9�`�E�B�[���ł̍ĉ�Ɓu���J�v�ւ̒���
2013/03/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��8�`�t���[���C�\���ւ̓���
2013/02/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��7�`�l���ő�̓]�@
2013/02/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��6�`�~�����w������E�B�[����
2013/01/31 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��5�`�V�J�l�[�_�[�Ƃ����j
2013/01/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��4�`���[�c�@���g�ƃE�R���h�m�̐ړ_
2012/12/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��3�`�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�Ƃ����@����
2012/12/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��2�`���[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h��
2012/11/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��1�`�^�~�[�m�͍��R�E�߂��H
2012/11/05 (��) ���G���Ō�̑䎌�Ɍ����܂����킯
2012/10/25 (��) ���A���Y����胊���V�Y���`�u���Ȃ��ցv���ςēǂ��
2012/10/20 (�y) ����t���Ɛ�t���ƃm�[�x���܂� �����āA�R������
2012/10/05 (��) ��t���̐^���`����͓c���p�h�̕s�p�ӂȔ�������n�܂���
2012/09/05 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�E
2012/08/25 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�D
2012/08/15 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�C
2012/08/13 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�B
2012/08/10 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�A
2012/08/07 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�@
2012/07/25 (��) ���̒��̒����݂䂫5�|�����݂䂫�́g���́h�ł���4
2012/07/10 (��) ���̒��̒����݂䂫4�|�����݂䂫��"����"�ł���3
2012/06/27 (��) �b����`�g���X�s�[�J�[�Ȃ�
2012/05/31 (��) �b����`���O��G�߂̒���
2012/05/20 (��) ���̒��̒����݂䂫3�|�����݂䂫��"����"�ł���2
2012/05/10 (��) ���̒��̒����݂䂫2�|�����݂䂫��"����"�ł���1
2012/04/20 (��) ���̒��̒����݂䂫�P�`���I�ꌳ�I�����݂䂫�_
2012/04/05 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��D �L�҉�����̐^��
2012/03/20 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��C ��ƂƂ��Ă̐Ό��T���Y
2012/03/10 (�y) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��B�u���v��ǂ��
2012/03/01 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��A�u�|�g�X���C���̏M�vVS�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v
2012/02/20 (��) �T��Łu�����̋L�v
2012/02/15 (��) �ً}�Ք��I������̊H��܍�i���l����
2012/02/10 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��@�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�̖ʔ���
2012/02/05 (��) FM����
2012/01/25 (��) ���V���� ���{�̕�
2012/01/10 (��) �b����`2012�V�N�G��
2011/12/25 (��) �b����`2011���N�����s��
2011/12/05 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����31�|40
2011/11/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����21�|30
2011/11/15 (��) �b����`�����E�����̃V���[�x���g���V�˘_
2011/10/31 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����11�|20
2011/10/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����1�|10
2011/10/13 (��) �u���Ɂv���Ɋ���
2011/09/30 (��) �u���[�����C�v�́u�t�̖��v���琶�܂ꂽ
2011/09/20 (��) �u�����̉́v����
2011/09/11 (��) �u�~�̗��v����
2011/08/31 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�2
2011/08/25 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�1
2011/08/15 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`���a���̊�
2011/07/31 (��) �b����`�Ƃ�ł��Ȃ��T�b�J�[�_
2011/07/25 (��) �b����`�u�Ȃł����W���p���v�N�����m�I����
2011/07/10 (��) �b����`�u�V�F�G���U�[�h�v�ɂ܂��G�g�Z�g��
2011/06/30 (��) ��k�Вf�́m9�n �����̒��� ��
2011/06/20 (��) ��k�Вf�́m8�n�͂��I���y�̗́`�C�O�A�[�e�B�X�g��
2011/06/05 (��) ��k�Вf�́m7�n�Ԏq�̓����ŗx�������
2011/05/25 (��) ��k�Вf�́m6�n�����}��A���Ɍ�����؍����͂Ȃ�
2011/05/20 (��) ��k�Вf�́m5�n�����l��Ղ��s�K
2011/05/12 (��) ��k�Вf�́m�ԊO�ҁn ���k�ɕ�����A�_�[�W��
2011/05/09 (��) ��k�Вf�́m4�n �G�l���M�[����̐����������
2011/04/30 (�y) ��k�Вf�́m3�n �������ǂ�����
2011/04/25 (��) ��k�Вf�́m2�n �������̂͐l��
2011/04/20 (��) ��k�Вf�́m�P�n �z��O�͒p
���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@�ŏI��
�@2011/03/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևS �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v13
���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����4��
�@2011/02/25 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևR �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v12
���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����3��
�@2011/02/15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևQ �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v11
���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����2��
�@2011/02/05 (�y) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևP �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v10
���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����1��
2011/01/20 (��) �b����\�\�n�f�W���̌��p
2011/01/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևO �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v9���������Ȃ��̂����̖{�́I��
�@2010/12/25 (�y) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևN �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v8
2011/01/20 (��) �b����\�\�n�f�W���̌��p
2011/01/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևO �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v9���������Ȃ��̂����̖{�́I��
���u�Ō�̈�t�v�́u�Ō�̊�]�v���ׁ[�X�@�̍�����
2010/12/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևM �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v7 ���V���[�x���g�ƃI�[�E�w�����[��
2010/11/29 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևL �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v6 ���u�~�̗��v�͖l�̕��g��
2010/11/19 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևK�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v5 ������ł��ׂĂ��ǂ߂��I��
2010/11/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևJ�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v4 ���V���|�x���g�˘f����
2010/10/28 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևI�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v3 ���~�����[���Ԍ���̐^����
2010/10/18 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևH�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v 2���u�E�C�v�ɂ�����~�����[�̎��
2010/10/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևG�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v�P���ȏ��̓䁄
2010/09/22 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևF�@�����̃����E�����6�u�����Ɍ��ЂɂȂ�Ȃ��ŁI�v
2010/09/03 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևE�@�����̃����E�����5�u�ّ��͋֕��v
2010/08/23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևD�@�����̃����E�����4�u���v�͓݊��H
2010/08/09 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևC�`�t�F���V�e�B�E���b�g
2010/07/26 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևB�`�@�����̃����E�����3�u�ЂƂ܂� 3��̋ȏW�ȊO�ցv
2010/07/15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևA�`�@�����̃����E�����2�u�܂̉J�v
2010/07/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�և@�`�@�����̃����E�����P�u�O��̋ȏW�v
2010/06/24 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ց`�v�����[�O
2010/06/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��19�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�A
2010/05/30 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��18�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�@
2010/05/10 (��) �V���p�����a200�N �ƒf�ƕΌ��ɂ�鋆�ɂ̃R���s���[�V����
2010/04/22 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��17�`�u�����f���ƃ|���[�j3
2010/04/14 (��) �f��u�h���E�W�����@���j�v�`�V�ˌ���Ƃƃ��[�c�@���g�̏o� ���ς�
2010/04/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��16�`�u�����f���ƃ|���[�j2
2010/03/31 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��15�`�u�����f���ƃ|���[�j1
2010/03/21 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��14�`���c���q�̐����V���[�x���g2
2010/03/11 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��13�`���c���q�̐����V���[�x���g1
2010/02/24 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��12�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�C
2010/02/15 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��11�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�B
2010/01/29 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��10�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�A
2010/01/20 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��9�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�@
2010/01/11 (��) �i�����ƃ��q�e��
2009/12/25 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��8�`�~�T�ȑ�6��
2009/12/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂV�`���͂Ȃ��
2009/11/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��6�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�E
2009/11/16 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��5�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�D
2009/11/06 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��4�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�C
2009/10/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��3�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�B
2009/10/17 (�y) �V���[�x���g1828�N�̊��2�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�A
2009/10/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂP�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�@
2009/09/29 (��) Romance�ւ̗U���G�u�u���[���X�̓����c���D���H�v
2009/09/21 (��) Romance�ւ̗U���F�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����5
2009/09/16 (��) Romance�ւ̗U���E�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����4
2009/08/31 (��) Romance�ւ̗U���D�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����3
2009/08/24 (��) Romance�ւ̗U���C�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����2
2009/08/17 (��) Romance�ւ̗U���B�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v���̂P
2009/08/03 (��) Romance�ւ̗U���A�u�h���j�R�E�X�J�����b�e�B��J�DS�D�o�b�n�͓����̍��v
2009/07/20 (��) Romance�ւ̗U���@�u�Z�U�[���E�t�����N��̊�v
2009/06/29 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�R
2009/06/22 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�Q
2009/06/15 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�P
2009/06/01 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�ŏI��
2009/05/25 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�W
2009/05/18 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�V
2009/05/11 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�U
2009/04/27 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�T
2009/04/13 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�S
2009/04/06 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�R
2009/03/30 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�Q
2009/03/21 (�y) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�P
2009/03/09 (��) �b����\�\�`���C5
2009/03/02 (��) �b����\�\�u�t�B�K���̌����v�^���̎p ����k
2009/02/23 (��) �b����\�\������x�g�c�G�a���a��
2009/02/09 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�ŏI��
2009/02/02 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�V
2009/01/26 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�U
2009/01/19 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�T
2009/01/12 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�S
2008/12/29 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�R
2008/12/22 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�Q
2008/12/15 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�P
2008/12/01 (��) �P�l�f�B�Ǔ� ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɓZ���Έ�G�ƌܖ��N�S
2008/11/17 (��) �Έ�G�̂��̈ꖇ���I
2008/11/10 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�V���G�s���[�O
2008/10/27 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�U
2008/10/13 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�T
2008/10/06 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�S
2008/09/29 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�R
2008/09/22 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�Q
2008/09/15 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�P
2008/09/01 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�Q
2008/08/25 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�P
2008/08/11 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\�G�s���[�O
2008/08/04 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂Q
2008/07/29 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂P
2008/07/14 (��) ���E�n�C�t�F�b�c�̍ė�
2008/07/07 (��) �n�C�t�F�b�c�̍ė�
2008/06/30 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�ŏI��
2008/06/23 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�U
2008/06/16 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�T
2008/06/09 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�S
2008/06/02 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�R
2008/05/26 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�Q
2008/05/21 (��) �u�t�B�K���̌����v�`3�l�̕��_�����Y��Ղ̌���
2008/05/19 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�P
2008/05/12 (��) �N���V�b�N ���m�Ƃ̑����\�\�v�����[�O
2010/12/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևM �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v7 ���V���[�x���g�ƃI�[�E�w�����[��
2010/11/29 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևL �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v6 ���u�~�̗��v�͖l�̕��g��
2010/11/19 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևK�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v5 ������ł��ׂĂ��ǂ߂��I��
2010/11/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևJ�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v4 ���V���|�x���g�˘f����
2010/10/28 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևI�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v3 ���~�����[���Ԍ���̐^����
2010/10/18 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևH�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v 2���u�E�C�v�ɂ�����~�����[�̎��
2010/10/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևG�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v�P���ȏ��̓䁄
2010/09/22 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևF�@�����̃����E�����6�u�����Ɍ��ЂɂȂ�Ȃ��ŁI�v
2010/09/03 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևE�@�����̃����E�����5�u�ّ��͋֕��v
2010/08/23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևD�@�����̃����E�����4�u���v�͓݊��H
2010/08/09 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևC�`�t�F���V�e�B�E���b�g
2010/07/26 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևB�`�@�����̃����E�����3�u�ЂƂ܂� 3��̋ȏW�ȊO�ցv
2010/07/15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևA�`�@�����̃����E�����2�u�܂̉J�v
2010/07/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�և@�`�@�����̃����E�����P�u�O��̋ȏW�v
2010/06/24 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ց`�v�����[�O
2010/06/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��19�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�A
2010/05/30 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��18�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�@
2010/05/10 (��) �V���p�����a200�N �ƒf�ƕΌ��ɂ�鋆�ɂ̃R���s���[�V����
2010/04/22 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��17�`�u�����f���ƃ|���[�j3
2010/04/14 (��) �f��u�h���E�W�����@���j�v�`�V�ˌ���Ƃƃ��[�c�@���g�̏o� ���ς�
2010/04/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��16�`�u�����f���ƃ|���[�j2
2010/03/31 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��15�`�u�����f���ƃ|���[�j1
2010/03/21 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��14�`���c���q�̐����V���[�x���g2
2010/03/11 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��13�`���c���q�̐����V���[�x���g1
2010/02/24 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��12�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�C
2010/02/15 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��11�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�B
2010/01/29 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��10�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�A
2010/01/20 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��9�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�@
2010/01/11 (��) �i�����ƃ��q�e��
2009/12/25 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��8�`�~�T�ȑ�6��
2009/12/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂV�`���͂Ȃ��
2009/11/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��6�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�E
2009/11/16 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��5�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�D
2009/11/06 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��4�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�C
2009/10/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��3�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�B
2009/10/17 (�y) �V���[�x���g1828�N�̊��2�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�A
2009/10/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂP�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�@
2009/09/29 (��) Romance�ւ̗U���G�u�u���[���X�̓����c���D���H�v
2009/09/21 (��) Romance�ւ̗U���F�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����5
2009/09/16 (��) Romance�ւ̗U���E�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����4
2009/08/31 (��) Romance�ւ̗U���D�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����3
2009/08/24 (��) Romance�ւ̗U���C�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����2
2009/08/17 (��) Romance�ւ̗U���B�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v���̂P
2009/08/03 (��) Romance�ւ̗U���A�u�h���j�R�E�X�J�����b�e�B��J�DS�D�o�b�n�͓����̍��v
2009/07/20 (��) Romance�ւ̗U���@�u�Z�U�[���E�t�����N��̊�v
2009/06/29 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�R
2009/06/22 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�Q
2009/06/15 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�P
2009/06/01 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�ŏI��
2009/05/25 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�W
2009/05/18 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�V
2009/05/11 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�U
2009/04/27 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�T
2009/04/13 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�S
2009/04/06 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�R
2009/03/30 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�Q
2009/03/21 (�y) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�P
2009/03/09 (��) �b����\�\�`���C5
2009/03/02 (��) �b����\�\�u�t�B�K���̌����v�^���̎p ����k
2009/02/23 (��) �b����\�\������x�g�c�G�a���a��
2009/02/09 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�ŏI��
2009/02/02 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�V
2009/01/26 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�U
2009/01/19 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�T
2009/01/12 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�S
2008/12/29 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�R
2008/12/22 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�Q
2008/12/15 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�P
2008/12/01 (��) �P�l�f�B�Ǔ� ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɓZ���Έ�G�ƌܖ��N�S
2008/11/17 (��) �Έ�G�̂��̈ꖇ���I
2008/11/10 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�V���G�s���[�O
2008/10/27 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�U
2008/10/13 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�T
2008/10/06 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�S
2008/09/29 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�R
2008/09/22 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�Q
2008/09/15 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�P
2008/09/01 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�Q
2008/08/25 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�P
2008/08/11 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\�G�s���[�O
2008/08/04 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂Q
2008/07/29 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂P
2008/07/14 (��) ���E�n�C�t�F�b�c�̍ė�
2008/07/07 (��) �n�C�t�F�b�c�̍ė�
2008/06/30 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�ŏI��
2008/06/23 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�U
2008/06/16 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�T
2008/06/09 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�S
2008/06/02 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�R
2008/05/26 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�Q
2008/05/21 (��) �u�t�B�K���̌����v�`3�l�̕��_�����Y��Ղ̌���
2008/05/19 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�P
2008/05/12 (��) �N���V�b�N ���m�Ƃ̑����\�\�v�����[�O
2024.04.15 (��) �t�̃N���V�b�N�y�Ȃ̂�Ԃɂ�ݓI�l�@
 �@���N�̍��͑������āA���������o�������O�O���p�ق��t���ɂȂ��Ă���c�O�Ȏv�����������̂ł����A���N�͕��ʂɖ߂�܂����B��͂�A���̉��ł̓��w���A���ԏ܂͂������̂ł��B������MLB�ANPB�̊J���A�}�X�^�[�Y�J�ÂƂ�͂�t�����̓E�L�E�L���܂��B
�@���N�̍��͑������āA���������o�������O�O���p�ق��t���ɂȂ��Ă���c�O�Ȏv�����������̂ł����A���N�͕��ʂɖ߂�܂����B��͂�A���̉��ł̓��w���A���ԏ܂͂������̂ł��B������MLB�ANPB�̊J���A�}�X�^�[�Y�J�ÂƂ�͂�t�����̓E�L�E�L���܂��B�@���̏t�É_���ꍞ�߂������ꕽ���̈�@�q�������A4��11���A�ĘA�M���@���u�������̑�����24��5000���~�ɏ��A���\�e�^�ői�ǂ����B��J�I�肪�֗^���Ă������Ƃ������؋��͂Ȃ��A�ނ͔�Q�҂Ƃ݂���v�Ƃ̌����\���܂����B�z�̔��傳�Ɉ��R�Ƃ������̂́A��J�I��̌����͏ؖ����ꂽ�킯�ŁA�܂��͈���S�B���Ƃ̓h�W���[�X�̃��[���h�E�V���[�Y���e�Ɍ����ē˂��i��łق������̂ł��B
�@����́A�t�Ɉ��y�Ȃ��N�����m�I�Ύ��I�p�x����l�@���Ă݂܂��傤�B
�i�P�j�u�t�̐��v�`���n���E�V���g���E�X2��
�@�����c�u�t�̐��v�B���̋Ȃ̒a���͎��Ƀ��j�[�N�B�s�A�m�̖��p�t �t�����c�E���X�g���W���Ă����ł��ˁB1883�N�A���n���E�V���g���E�X2�����I�y���b�^�u�����Ȑ푈�v�̏����̂��߃u�_�y�X�g�ɑ؍݂��Ă����܁A���m�̊ԕ��̃��X�g�ƃp�[�e�B�[���J���A�����Ō݂�������C�܂܂ɉ��t�������Đ��܂ꂽ�̂��u�t�̐��v�ł����B���̔N�̕�A�̎��������ăE�B�[���ŏ����B�劅�т𗁂т܂����B�₩�ȃT������3�x�ڂ̌������T�����V���g���E�X�̍K���������f���āA���邭�������ɖ����A�܂��ɏt�������v�킹��y�Ȃł��B
�@���̐S���y�Ȃ͉f��u�j�͂炢��v�ɂ����x���o�ꂵ�܂��B��8��u�Ў��Y���́v�ł́A�}�h���i�r���~�q�����関�S�l�M�q����̈�l���q�w���A�]�Z��Ԃ��Ȃ����ߗF�B���ł��Ȃ��̂������˂��Ђ��A�]�ː�̐쌴�ňꏏ�ɗV��ł���ėF�B���Ɉ���B����ȏ�ʂŗ���Ă��܂����B�䂪�q�ɗF�B���ł��Ċ�Ԓr������̎��R�ȉ��Z���ƂĂ���ۓI�ł����B�����ł��A�e�Ƃ������́A�q���ɗF�B���ł��邱�Ƃ����������ꂵ���̂ł��B�V���[�Y�u�j�͂炢��v�͖{��ŏ��߂�100���l�������ʂ����A��1972�N����͖~���N2����J���蒅���܂��B
�@�u�t�̐��v�͂��̌�A��9��u�Ė����v�A��30��u�Ԃ������Ў��Y�v�A��41��u�Ў��Y�S�̗��H�v�ɂ��o��B���v4����g���Ă��܂��B����̓V���[�Y48�쒆�ő�̕p�x�B�R�c�ē�Ԃ̂��C�ɓ���ȂƂ�����ł��傤�B����ɑ����Ắu�g���C�����C�v(�V���[�}�����)��3��ƂȂ��Ă��܂��B
 �@�����P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�ł�1987�N�̉��t�������ł����B�w���̓w���x���g�E�t�H���E�J�������B�l�C�㏸���̃\�v���m�̎�L���X���[���E�o�g�����\���X�g�ɓo�p�A�u�t�̐��v�{���̎p�ʼn��t����܂����B���J�������A���ʂ����G���^�[�e�C�������g�ł����B���̋L���ł́A�j���[�C���[�̉̎�̃Q�X�g�o���͂��ꂪ�ŏ��ōŌォ�Ǝv���܂��B�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�ł͂���ȍ~�A�w���҂����N����ւ��̂��P��ƂȂ�܂��B
�@�����P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�ł�1987�N�̉��t�������ł����B�w���̓w���x���g�E�t�H���E�J�������B�l�C�㏸���̃\�v���m�̎�L���X���[���E�o�g�����\���X�g�ɓo�p�A�u�t�̐��v�{���̎p�ʼn��t����܂����B���J�������A���ʂ����G���^�[�e�C�������g�ł����B���̋L���ł́A�j���[�C���[�̉̎�̃Q�X�g�o���͂��ꂪ�ŏ��ōŌォ�Ǝv���܂��B�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�ł͂���ȍ~�A�w���҂����N����ւ��̂��P��ƂȂ�܂��B�@���{�̍����I�f��u�j�͂炢��v�Ɛ��E�̃N���V�b�N�t�@�������̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�B����2��s���̍P�ቻ�Ɂu�t�̐��v���֗^�i�H�j���Ă����͖̂ʔ������R�Ƃ����邩������܂���B
�@���݂ɁA�L���X���[���E�o�g���͋Z�ʁ^�e�p���˔��������Q�̃X�^�[���̎�����B�n����掞��A�ޏ����̂��j�b�J�E�E�B�X�L�[��CM�u�I���u���E�}�C�E�t�v���t�B�[�`���[����LD�uDIVA�v�������[�X�B�����Ԃ��Ȃ��V��Ђ̔���グ�ɑ傢�Ɋ�^���܂����B��������������v���o�ł��B
�i2�j�h�r���b�V�[�́u�t�̃����h�v
 �@�u�t�̃����h�v�̓h�r���b�V�[�u�nj��y�̂��߂̉f���v�̏I�ȁB�X�R�b�g�����h���́u�W�[�O�v�A�X�y�C�����́u�C�x���A�v�ɑ�����3�Ȃ��t�����X���́u�t�̃����h�v�Ƃ����킯�ł��B�u�����h�v�́u�֕��ȁv�Ɩ�A���̖��̒ʂ胁�C���̐��������x�������舒B�ȕ��ȕ��y�Ȍ`���ŁA�x�[�g�[���F����`���C�R�t�X�L�[�̃R���`�F���g�̏I�y�͂��₩�ɏ����Ă��܂��B���A����ȃC���[�W�ł��̃h�r���b�V�[�u�t�̃����h�v���ƌ���������H�炤���ƂɂȂ�܂��B�܂��A��v��肪�t�����X�̓��w�u�����X�ւ͍s���Ȃ��v�Ɋ�Â������Ȃ̂ł����A���ꂪ�F�ڒ͂߂Ȃ��B�����h�Ȃ̂ʼn��x���o�Ă���͂��ł����A���ɕs���āB������ꂽ�h�C�c�I�����h�Ƃ͎��Ă������ʁA���ɕ����Ă���悤�Ȋ��o�Ȃ̂ł��B�h�C�c�n���y�Ɋ��炳�ꂽ���̂悤�Ȃ��̂̓t�����X�I�e�C�X�g�ɓ���߂Ȃ��̂�������܂���ˁB�A���}�E�}�[���[���u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�ɂ��A1910�N�A�����ȑ�2�ԁu�����v�̃p�������ɎQ���h�r���b�V�[�͑�2�y�͂̓r���ŐȂ𗧂��Ă��������������ł��B�u�}�[���[�̌����Ȃ͂��܂�Ɉٍ��I�ŃX�����I���v�B������t�����X�I�ƃh�C�c�I�̑��e��Ȃ��̕\�ۂȂ̂ł��傤���B
�@�u�t�̃����h�v�̓h�r���b�V�[�u�nj��y�̂��߂̉f���v�̏I�ȁB�X�R�b�g�����h���́u�W�[�O�v�A�X�y�C�����́u�C�x���A�v�ɑ�����3�Ȃ��t�����X���́u�t�̃����h�v�Ƃ����킯�ł��B�u�����h�v�́u�֕��ȁv�Ɩ�A���̖��̒ʂ胁�C���̐��������x�������舒B�ȕ��ȕ��y�Ȍ`���ŁA�x�[�g�[���F����`���C�R�t�X�L�[�̃R���`�F���g�̏I�y�͂��₩�ɏ����Ă��܂��B���A����ȃC���[�W�ł��̃h�r���b�V�[�u�t�̃����h�v���ƌ���������H�炤���ƂɂȂ�܂��B�܂��A��v��肪�t�����X�̓��w�u�����X�ւ͍s���Ȃ��v�Ɋ�Â������Ȃ̂ł����A���ꂪ�F�ڒ͂߂Ȃ��B�����h�Ȃ̂ʼn��x���o�Ă���͂��ł����A���ɕs���āB������ꂽ�h�C�c�I�����h�Ƃ͎��Ă������ʁA���ɕ����Ă���悤�Ȋ��o�Ȃ̂ł��B�h�C�c�n���y�Ɋ��炳�ꂽ���̂悤�Ȃ��̂̓t�����X�I�e�C�X�g�ɓ���߂Ȃ��̂�������܂���ˁB�A���}�E�}�[���[���u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�ɂ��A1910�N�A�����ȑ�2�ԁu�����v�̃p�������ɎQ���h�r���b�V�[�͑�2�y�͂̓r���ŐȂ𗧂��Ă��������������ł��B�u�}�[���[�̌����Ȃ͂��܂�Ɉٍ��I�ŃX�����I���v�B������t�����X�I�ƃh�C�c�I�̑��e��Ȃ��̕\�ۂȂ̂ł��傤���B�@�h�r���b�V�[�̉��y�ɂ́A�`���I�s���Ă��͂�����̂́A�����́g�������h�͓Ɠ��ł��B��ƁE�������H���u�Ăɒ������y�̓h�r���b�V�[����ԁv�Ƃ����̂������ł��܂��B
�@���̏ꍇ�A�u�����h�v�ƕ����Ă������ɕ����Ԃ̂́A���[�c�@���g�̃g���R�s�i�Ȃł��B����̓s�A�m�E�\�i�^K331�̑�3�y�͂Ȃ̂ł����A�`���̓����h�A�\�L�� Alla Turca Allegretto�i�g���R���A���O���b�g�j�ƂȂ��Ă��܂��B�`���I�ɂ͂��Ȃ莩�R�ŁA������u�t�����X�������h�v�Ƃ�������������܂��B�܂��A�s�i�ȂƂ����\�L�͂���܂��A���肪���ރ��Y�����g���R�R�̍s�i��\�킵�Ă���Ƃ������ƂŐ̂���u�g���R�s�i�ȁv���ʂ葊��ƂȂ��Ă��܂��B
�@�����͂܂������Ƃ��āA�����[���̂�Allegretto�Ƃ������x�\�L�ł��B����́AAllegro�i�����Ɂj���A1���ԂɎl��������120�`152���ޑ��x�Ȃ̂ɑ��AAllegretto�i�������Ɂj��96�`120�Ȃ̂ł��B
�@�����ŁA����A���[�c�@���g�u�g���R�s�i�ȁv��My�R���N�V��������10����CD��I��ő��x���Z�o���邱�Ƃɂ��܂����B�܂��A�y������u�g���R�s�i�ȁv�̏��ߐ��𐔂���B�����2�{���Ďl�������̐����Z�o����`448�B����Ɗe�X�̃s�A�j�X�g�̉��t���Ԃ��瑬�x������o���A�x�����ɕ��ׂĂ݂܂����B(�@) �������͘^���N�B

 �E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�i1968�j ♩��107
�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�i1968�j ♩��107�O�����E�O�[���h�i1970�j ♩��109
�����^�[�E�M�[�[�L���O�i1954�j ♩��121
�{�q�i1983�j ♩��125
���c�^�� �i2021�j ♩��126
���c���q�i1983�j ♩��127
�A���h���[�V���E�V�t�i1980�j ♩=129
�����[�E�N���E�X�i1956�j ♩=130
�t���[�h���q�E�O���_�i1977�j ♩=132
�E�B���w�����E�o�b�N�n�E�X�i1955�j ♩=141
�@�ȏ�AAllegretto�̑��x�i♩��96�`120�j�Ɏ��܂��Ă���̂́A�z�����B�b�c�ƃO�[���h�̓�l�����Ƃ������Ƃ��������܂����B���Ƃ͂��ׂ�Allegro�̑��x�ƂȂ��Ă���A�����炭���݂͂��̌X���������Ǝv���܂��B���݂ɒ����ȍs�i�Ȃ̑��x�A�Ⴆ�A�X�[�U�́u��������i���Ȃ�v��116�A���F���f�B�̉̌��u�A�C�[�_�v��s�i�Ȃ�101�Ƃ�������Allegretto�̘g���Ɏ��܂��Ă��܂��B��͂�s�i�Ȃ�Allegretto���X�^���_�[�h�Ƃ������Ƃł��傤���B���[�c�@���g���s�i�ȂƂ����Ӗ���������Allegretto�Ƃ����̂Ȃ�A�z�����B�b�c�ƃO�[���h���ł���Ȏ҂̈Ӑ}�ɒ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB�܂��A10�l���̍ŌÎQ�o�b�N�n�E�X���ő��������͈̂ӊO�ł����B
�@�u�����h�v�����Ƀh�r���b�V�[���烂�[�c�@���g�ɒ���ł݂܂������A��Ȏ҂̈Ӑ}������Ȋp�x����l�@����̂��y�������̂ł��B
�i3�j���[�O�i�[�u�~�̗��͋���āv
 �@�u�~�̗��͋���āv�̓��[�O�i�[�̊y���u�j�[�x�����O�̎w�v��1���u�����L���[���v�̑�1���ŃW�[�N�����g���̂��A���A�B�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�́A����u���C���̉����v�A��1��u�����L���[���v�A��2��u�W�[�N�t���[�g�v�A��3��u�_�X�̉����v��4��16���Ԃɂ킽���ČJ��L�����郏�[�O�i�[�L���̑��I�y���ł��B�_�X�^�l�ԑ��^�n�ꑰ�����͂̏ے��u�w�v�������đ����A�₪�ĉ��������E���Ƃ�������B���[�O�i�[�͂�������ɂ�����A�Q���}���̉p�Y�������u�j�[�x�����Q���̉́v�A�k���_�b�u�G�b�_�v�A�A�C�X�L�����X�̃M���V���ߌ��u�I���X�e�C�A�v�����Q�l�ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�u�j�[�x�����Q���̉́v�͂Ȃ�Ɩ����f�悪����悤�ŁA�����Brownie K�����炨�肷�邱�ƂɂȂ��Ă��āA������ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@�u�~�̗��͋���āv�̓��[�O�i�[�̊y���u�j�[�x�����O�̎w�v��1���u�����L���[���v�̑�1���ŃW�[�N�����g���̂��A���A�B�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�́A����u���C���̉����v�A��1��u�����L���[���v�A��2��u�W�[�N�t���[�g�v�A��3��u�_�X�̉����v��4��16���Ԃɂ킽���ČJ��L�����郏�[�O�i�[�L���̑��I�y���ł��B�_�X�^�l�ԑ��^�n�ꑰ�����͂̏ے��u�w�v�������đ����A�₪�ĉ��������E���Ƃ�������B���[�O�i�[�͂�������ɂ�����A�Q���}���̉p�Y�������u�j�[�x�����Q���̉́v�A�k���_�b�u�G�b�_�v�A�A�C�X�L�����X�̃M���V���ߌ��u�I���X�e�C�A�v�����Q�l�ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�u�j�[�x�����Q���̉́v�͂Ȃ�Ɩ����f�悪����悤�ŁA�����Brownie K�����炨�肷�邱�ƂɂȂ��Ă��āA������ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B�@�u�~�̗��͋���āv�͑�2���ڂ����l���Ƃ��ēo�ꂷ��W�[�N�t���[�g�̕��W�[�N�����g���A��ƂȂ閅�W�[�N�����f�Ƃ߂��舧���A�u���������t�v�ƈ���v����f�I����A���[�O�i�[�炵����ʁi�H�j�����E�������f�B�A�X�ȃA���A�ł��B�u�~�̗��͋�������G�߂ƂȂ����@�_�炩�Ȍ��ɕ�܂�t�͋P���Ă���v�Ɖ̂��n�߂�̂ł����A�tLenz�Ƃ����P�ꂪ�㖼�����܂�13����o�Ă��܂��B�̂��I������W�[�N�����g�Ɍ������ăW�[�N�����f�́u�����ł� ���Ȃ��������t�Ȃ̂ł��v�Ɗ��܂̌��t�𓊂���B������ fanatic & paranoid �ȃ��[�O�i�[�̔Z�����ł��B
�@���̐́u�w�v�����߂Ē������Ƃ��A�Z���̌����`�Ȃ�Ė��ȁA�Ƃ���������ق̔O�ɑł���܂������A�䂪���̓V�c�Ƃ̗��j��H��ߐe���͂����Ē��������Ƃł͂Ȃ��A�ߍ��ł͏��X�Ɉ�a�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B
�@�ȏ�A�t�̃N���V�b�N3�Ȃ����グ�Ă݂܂������A�t�y�Ȃ͏�L�̑��ɂ��A���B���@���f�B�u�l�G�v�`�u�t�v�A���[�c�@���g�u�t�ւ̓���v�A�x�[�g�[���F���u�X�v�����O�E�\�i�^�v�A�����f���X�]�[���u�t�̉́v�A�V���[�}���F�����ȑ�1�ԁu�t�v�A�}�[���[�u��n�̉́v�`�u�t�ɐ�����ҁv�A�X�g�����B���X�L�[�u�t�̍ՓT�v�A�R�[�v�����h�u�A�p���`�A�̏t�v���A��������܂��B�܂������A�����̋Ȃɂ��Ă��l���Ă݂����Ǝv���܂��B�ł͍����͂��̕ӂŁB
���Q�l������>
�ŐV���ȉ���S�W(���y�V�F��)
�V���[�c�@���g�S�W�i�x�[�������C�^�[�Łj
�f��u�j�͂炢���8��`�Ў��Y���́v�i1971�N12�����J�jDVD
CD�u�Ђ���N���V�b�N�v�i�������ꐧ��BMG�r�N�^�[�j
�u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�i�A���}�E�}�[���[���A�Έ�G�� �������Ɂj
CD�u�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g1987�v
�@�@�w���x���g�E�t�H���E�J�������w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c
�@�@�L���X���[���E�o�g���i�\�v���m�j
CD���[�O�i�[�F�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�`�u�����L���[����1���v
�@�@�n���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c
�@�@�Z�b�g�E�X���@���z�����i�e�m�[���j�A�L���X�e���E�t���O�X�^�[�g�i�\�v���m�j1957�^��
2024.03.11 (��) �����݂䂫�R���T�[�g�u�̉�VOL.1�v�`�����I���|�[�g
 �@2��22���A�������ۃt�H�[���� �z�[��A�B�҂��ɑ҂��������݂䂫�R���T�[�g�ɍs���Ă��܂����B�݂䂫���C�u�͂����ꏏ��N.Y�����ŁB�O��́u2020���X�g�E�c�A�[�`���ʃI�[���C�v���A�R���i�ɂ��C�x���g���l�v���ɂ��A2��26���A���t�F�X�e�B�o���E�z�[�������I����ɒ��f�A�����4�N�Ԃ�̊J�Âł����BN.Y.����͑O��s���Ă��܂����A�ꏏ�ɍs���\�肾������͒��f�ゾ�����̂ŁA���ɂƂ��Ă�2018�N�̖��ȗ�6�N�Ԃ�̂��ڒʂ�ƂȂ�܂��B����^�C�g���͕ς���āu�̉�VOL.1
�@2��22���A�������ۃt�H�[���� �z�[��A�B�҂��ɑ҂��������݂䂫�R���T�[�g�ɍs���Ă��܂����B�݂䂫���C�u�͂����ꏏ��N.Y�����ŁB�O��́u2020���X�g�E�c�A�[�`���ʃI�[���C�v���A�R���i�ɂ��C�x���g���l�v���ɂ��A2��26���A���t�F�X�e�B�o���E�z�[�������I����ɒ��f�A�����4�N�Ԃ�̊J�Âł����BN.Y.����͑O��s���Ă��܂����A�ꏏ�ɍs���\�肾������͒��f�ゾ�����̂ŁA���ɂƂ��Ă�2018�N�̖��ȗ�6�N�Ԃ�̂��ڒʂ�ƂȂ�܂��B����^�C�g���͕ς���āu�̉�VOL.1�v�B�O��g���X�g�E�c�A�[�h�Ɩ��ł����̂́u�S���ɏo�����g�c�A�[�h�Ƃ��Ă̓��X�g�v�Ƃ����Ӗ��������ŁA�P���̃R���T�[�g�͍���������邻���ł��B�gVOL.1�h�����̂ˁB�Ȃ̂ŁA�����A�݂䂫����ɂ͂��ڂɂ����邱�Ƃ��ł������Ŋy���݂ł��B
�@�O��́A�u�A�U�~��̃����o�C�v�u�����v�u���D�v�u�Ō�̏��_�v�u���̉S�v�u���v�u���v�ȂǁA�q�b�g�ȁA�^�C�A�b�v�Ȃ����������сA�u���X�g�E�c�A�[�v�ɑ����������e�ƂȂ��Ă��܂����B�����ւ䂭�ƍ���́A19�Ȓ�15�Ȃ�2000�N�ȍ~�̊y�ȂŁA�ŐV�V���O���u�S���v������A���̉̎��̂悤�Ɂg�����ցh�������݂䂫����̈ӗ~���q�V�q�V�Ɠ`����Ă���\���ł����B
�@�X�^�[�g���u�͂��߂܂��āv�́A���f�����O��c�A�[�̃��X�g�ȁB����́A���̎��̑����ł��� �Ƃ������b�Z�[�W�ł��傤�B��������������A�o�ꂵ���݂䂫����A�Ȃ�Ɗዾ�������Ă����̂ɂ̓r�b�N���B�S�z�����̂͐��ł������A�o�����͂����芴�Ɍ��������̂́A�i�ނɂ�Ē��肠�鐺���r���r���o�Ă��āA�S�z�͑S���̞X�J�ɏI���܂����B
�@2�Ȗ��u�̂����Ƃ�������Ȃ���v��2020�N�̃A���o���uCONTRALTO�v����B�u�J��Ԃ����킢�̓��X ���t�͕����߂��Ă䂭�v�Ƃ�������������܂����A���̎��_�ł̓��V�A�̃E�N���C�i�N�U�͂܂��B���V�A�̌��_�����ƃR���i�ɂ�郉�C�u���l��\�����Ă��邩�̂悤�ł��B�݂䂫����̓����͂ł��傤���B
 �@����ɑ����u��ÎO����v�͑O���̈����B�u�ŋ߂̕����Ă���ƕa�@�̉f�����ƂĂ��p�ɂɏo�Ă���悤�ȋC�����܂��B����܂ł���Ȃ��Ƃ��������ł��傤���v�ƑO�u�����āA�h���}�uPICU�����W�����Î��v���́u��Ɂv�iAL�u���E������Č�������v���^�j�`�u�a�@���v�iAL�u���W�v���^�j�`�h���}�uDr.�R�g�[�f�Ï��v���́u��̗��̔w�ɏ���āv�̎O�A���B
�@����ɑ����u��ÎO����v�͑O���̈����B�u�ŋ߂̕����Ă���ƕa�@�̉f�����ƂĂ��p�ɂɏo�Ă���悤�ȋC�����܂��B����܂ł���Ȃ��Ƃ��������ł��傤���v�ƑO�u�����āA�h���}�uPICU�����W�����Î��v���́u��Ɂv�iAL�u���E������Č�������v���^�j�`�u�a�@���v�iAL�u���W�v���^�j�`�h���}�uDr.�R�g�[�f�Ï��v���́u��̗��̔w�ɏ���āv�̎O�A���B�@�u��Ɂv�̓X�P�[���傫�ȋȑz�̒��ɃO�b�Ɣ���̎������������܂��B�u���O�̓����Ƃ��Ă� ������܂ł�������Ɠ_���Ă������v�B���̌��t�ǂ����ŕ��������Ƃ�����ȁ@�Ǝv������H�g�q�q����ł����B�u���Ƃ�̂͋t�炦�Ȃ��B������A���̂��Ƃ��ǂ������l���Ă��d�����Ȃ��B��Ȃ̂͂��̓����̓�����������Ɛ����邱�Ɓv�B������������80��B�̑�ȓ�l�̏����A�[�e�B�X�g�̌��t���g�ɟ��݂܂��B�u�a�@���v�͍��~��炵�̕a�@�ŁB���z�����j�[�N�ł��B�u�a�@�͐�ꂾ �a�@�͊O���� ���ʂ̕\�ʂ肩�� ���قlj����Ȃ��v�B����ȕa�@�̓��i��炵�j�ɂȂ肽���Ƃ݂䂫����͉̂��B���~��炵���Z�ݒ������Ƃ͍��𐬂��Ƃ����Ă���B�a�@���͏o��������҂���Ɂu�����Ǝ����Ă� �����Ə��ċA���Ăˁv�ƌĂт�����B�K�^�̗d���Ȃ̂ł��B
�@�ҋȂ̐�����O���͂��̋Ȃɂ��Ă����q�ׂĂ��܂��E�E�E�E�E��������ƍŏ������w���E�^�b�`�Ŏd���Ă܂������A�݂䂫����_���o����H�炢�܂����B�u�g���h�Ȃ�������Ƌْ������o���āv�ƁB�����ŁA�u����ER�ɂ����Ⴄ���v�ƃ��b�N�ɂ�����C�ɓ����Ă��炦�܂����ˁB�݂䂫�������R���r��38�N�B���Ă���Ȃ��p�[�g�i�[�ł��B��������͂܂������݂䂫�ɂ��Ă�������Ă��܂��B
�����݂䂫�����グ�Ă�����̂́A�}�N���`�~�N���A���ʓI�Ȃ��́`���ՓI�Ȃ��̂ƃI�[���}�C�e�B�݂����ɂƂĂ��Ȃ����L���B����C�Â��Ȃ��悤�ȐS�����ɂ��邳������݂����Ȃ��̂����C�Ȃ����Ă���B���ɂ͏��ɉ�������܂����A�����������̂��܂߂���ő傫�Ȉ�������B�����Č��̂ĂȂ���ނ悤�Ȉ��ł����ˁB������Ō�ɂ͖������B�l�A���Ȃ��Ƃ����Ƃ���̑Λ��̎d�������Ă���̂ŁA�����������l�Ɉ�ԋ����̂��Ǝv���܂��B�ޏ��ɂ͂܂��l�ɂ͌����ĂȂ����������Ǝv���̂ł��݂����ݐi�s�`�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�܂��܂�������i���o�Ă���Ǝv���܂��B�@�ׂ̓�l�A�ꏗ���̈�l���u�݂䂫����̉̂͑S�����Ɍ�肩���Ă���Ă�悤�ȋC������v�ƒ����Ă����̂��A�����������ƂȂ̂ł��傤�B
�@�u��̗��̔w�ɏ���āv�́A��͂�Q����t���u�����͗��̔w�ɏ���� ���̍����� �J�_�̉Q���^��ōs�����v�Ɖ̂��B��͂Ȃ痴�̗͂��������B��Ȃ̂͐l�̖����~�����ƁB�{����������Ȃ��݂䂫����̎��_�ł��B
�@�uLADY JANE�v�͂Ƃ���JAZZ�i���̈�R�}���̂��Ă��܂��B���݂���݂䂫���C�ɓ���̓X�������ł��B2015�N�̃A���o���u�g�ȁv�Ɏ��^�B�����Ńs�A�m��e���Ă��鏬�ѐM�Ⴓ��݂͂䂫�o���h�̃o���}�X�ł������A2022�N�A�A��ʐl�ɂȂ��Ă��܂��܂����B62�̎Ⴓ�ł����B���̓��A�u�ԑt�̃s�A�m�E�p�[�g�͏��т��₵���\���E�e�C�N�����܂��v�Ƃ݂䂫����B���̕����ŁA�s�A�m�Ɋ��Y���������F��悤�Ȃ݂䂫����̎p���ƂĂ���ۓI�ł����B
�@�����́u���v�ŁA�t�@���N���u�u�Ȃ݂ӂ��v����ł�����N.Y.���`�P�b�g���Q�b�g�ł��Ȃ������܁A�������т���̃}�l�[�W���[������Ă����J�I����ƕy�����D����Ɋl���Ă���������Ƃ�����܂����B���т���A���̐߂͂��肪�Ƃ��������܂����B�ނ�ł����������F�肵�܂��B
�@�O���̍Ō�͍P��́u�������R�[�i�[�v�ł��B�����œo�ꂵ���̂�����v���B���̓`���I���W�I�ԑg�u�����݂䂫�̃I�[���i�C�g�j�b�|���v�̂������������\����S�������q�r������Ƃł��B���X�i�[����̕ւ��I�肷�����Ă݂䂫����ɓn���̂��ނ̖�ځB����Ȓ����琶�܂ꂽ�̂�1983�N�̖��ȁu�t�@�C�g�I�v�ł����B
�@2023�J�^�[���E���[���h�J�b�v�\�I���[�O��2��A�R�X�^���J��B�I���ԍۂɋg�c���炪�N���A�E�~�X��Ƃ��ɍ��̔s����i���Ă��܂��܂��B���̃X�y�C����͏������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ᔻ�W���A�L���v�e���Ƃ��Ă̐ӔC���Ƃ����܂��āA�g�c�͋ɓx�ɗ������ށB����ȂƂ����ɂ����̂������݂䂫�́u�t�@�C�g�I�v�������B�u�₽�����̒��� �ӂ邦�Ȃ���̂ڂ��Ă䂯�v�B���̃t���[�Y�Ɂu��������ł�ꍇ����Ȃ��A��邵���Ȃ��v�Ɖ�ɕԂ�B���{�͋����X�y�C�������j�B�O���[�v�X�e�[�W��˔j���邱�Ƃ��ł��܂����B�u���̉̂̂��A�Ő����Ԃ�܂����v�Ƌg�c�B���{�������삵�����̐킢�̉A�ɂ͒����݂䂫�́u�t�@�C�g�I�v���������B
�@���������������R���r�͎芵�ꂽ�����ʼn���グ�܂����B��ԑ��������������́u�����͒a�����B���߂łƂ��������܂��v�Ƃ������́B�����ł��A�݂䂫����͎��̓��A2��23���Ŗ�72�ƂȂ�̂ł��B���������x�͒C�A�N���ł��ˁB�����āA�x�e�ɁE�E�E�E�E�B
�@���̐́A���Ȃ̋x�e���ԂɁA�^���W�����Ǝʐ^�Ƃ̓c���m���ƃo�b�^���o��������Ƃ�����܂����B�����̂悤��N.Y.�����ŁB���̂Ƃ��^���W������u�����A�����������Ɓv�Ɣ������̂ł��ˁB�g�����������Ɓh�Ƃ͂ǂ��������ƁH�@�����ɂ��^���W������炵���t�@�W�[�ȕ\���ł����B�^���W������́A�݂䂫����̃t�H�g�E���[�N���A���o����2��u�݂�ȋ����Ă��܂����v����S�����Ă���̂ŁA���낻�딼���I�ɒB���钷���t�������B�݂䂫����ɂƂ��Ĉ�ԋC�̒u���Ȃ��X�^�b�t�̈�l�Ƃ����Ă��܂��B
�@��6��u�����Ă��Ă������ł����v(1980)�́A���̏�O��˂��l�߂āA�����A�u�����݂䂫�͈Â��v�Ƃ̒��������Â����A���o���B���̒��ɁA�����ɃI�A�V�X�I�ȐS���܂�y�Ȃ����݂��܂��B�u�������v�B���̑�D���ȋȂł��B

�@�@���E��������������̂��z�Ɏv���Ă���
�@�@�܂�Ŏ����ЂƂ肾��������Ȃ��悤�ȋC�����鎞
�@�@�ˑR���܂�����d�b������@���̂��A���ł��H��Ȃ������Ă�
�@�@�����̎��s�b�ɂ��炯����Ę��ɂ��܂�Ȃ���A���܂�
�@�@���̂ˁA�킩��Ȃ��z�����邳���ā@����܂�ˑR�]������@���������Ȃ��
�@�݂䂫����A��������ł�� �Ɗ����āu���ł��H��Ȃ����v�ƗU���A�������Ȃ��b�����Ȃ���ӂƁu�킩��Ȃ��z�����邳�v�ƌ��t��������B����A�^���W������̂��ƂƂ����Ă��܂��B�u�����������Ɓv�^�u�킩��Ȃ��z�����邳�v�B���������e�C�X�g�ɕ������܂��B
�@�����A�x�e�̂��ƁA�݂䂫����̐��͂܂��܂��͋�����X�����|���܂��B�X�^�[�g�́u���v�y��5�A���B1989�N����n�܂��������݂䂫�̌��t�̎�������u���v����~���[�W���E�z�e���`�S��Ԗڂ̏���̏��`�g���́`���̃����[�`���g���E�g�[�L���[���Ԓf�Ȃ��̂��A���������ւ��A�f�����ܕω��ʼn�X�̖ڂ��y���܂��Ă���܂����B
�@���ł��u���̃����[�v�������B���̍ɂȂ�Ɓu���̈ꐶ�����ł͒H�蒅���Ȃ��Ƃ��Ă� ���̃o�g���͂�Ŋ肢�������p���ł䂯�v�̃t���[�Y���S�Ɏh����܂��B�����͂����������𑧎q�⑷�����Ɉ����p���ł���̂��낤�����ĂˁB
�u���v�͑q�{���������낵��TV�h���}�u�₷�炬�̋��v�i2017�j�̎��́B
�����}�����̂��ǂ��ɂ������̂��낤 ������ɂ��ĉ����}�����̂��낤�@����܂��A�S�ɟ��݂܂��B�l�͒N��������D�悵�������NJ���Ȃ����Ƃ�����B�藣���Ă͂Ȃ�ʔ��̉������������Ȃ낤����ǂ��A������ɂ��Č��������̂ł��B���̃h���}�ɂ�BMG����ɍ�����ACD�u�����̂Ȃ݂��v�ŘN�ǂ����肢�������瑐�O���o�����Ă��܂����B�W���P�b�g�ʐ^�̓^���W������B2003�N�̗ǂ��v���o�ł��B
�Â��Ă͂����Ȃ� ���ɏ�͂Ȃ� �藣���Ă͂Ȃ�ʔ��̉������ԈႦ���
 �@�u�̉��v�́u����ȂɊ�Ȃ����̒��� �����Ă邾���Ŋ�Ղł��傤 �̉������邾���ŏE������ł��傤�v�Ɖ̂��A�����J���E�|�b�v�X���̌y���ȃi���o�[�BAL�u���E������Č�������v�i2023�j�Ɏ��^����Ă���A�g�c��Y���T�C�h�E�M�^�[��e���Ă��܂��B�����낤�Ƃ����A2006�N�A�ܗ��ł́u�i���̉R�����Ă���v�̃p�t�H�[�}���X���Y����܂���B�����낤�̉̂��o���̂��ƁA�ˑR�A�W�[���Y�ɔ��������O�E�X���[�u�̒����݂䂫���X�e�[�W�Ɍ���܂��ĂˁB�\�z�O�̃n�v�j���O�ɉ��͋����̚��ĂƉ����܂����B
�@�u�̉��v�́u����ȂɊ�Ȃ����̒��� �����Ă邾���Ŋ�Ղł��傤 �̉������邾���ŏE������ł��傤�v�Ɖ̂��A�����J���E�|�b�v�X���̌y���ȃi���o�[�BAL�u���E������Č�������v�i2023�j�Ɏ��^����Ă���A�g�c��Y���T�C�h�E�M�^�[��e���Ă��܂��B�����낤�Ƃ����A2006�N�A�ܗ��ł́u�i���̉R�����Ă���v�̃p�t�H�[�}���X���Y����܂���B�����낤�̉̂��o���̂��ƁA�ˑR�A�W�[���Y�ɔ��������O�E�X���[�u�̒����݂䂫���X�e�[�W�Ɍ���܂��ĂˁB�\�z�O�̃n�v�j���O�ɉ��͋����̚��ĂƉ����܂����B�@�u�i���̉R�����Ă���v�́A1995�N�A�����݂䂫���g�c��Y�ɒ����y�ȁB���Ɍ������Ȃ���ʂ�����Ȃ��j���u�܂��܂��A���ꂩ��v�Ƌ������Ă���B����Ȓj�Ɂu���܂ł����˂����������Ȃ��ł���v�Ɖi���̉R��������������B���҂̐S��̈������w�I�Ɍĉ�����B�����낤�̉̂�{�l�����h���s�V���ɕ`�����Ⴄ�i�H�j �݂䂫����͐����Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�݂������X�y�N�g�����{�̉��y�V�[�����D�u�ƌ������Ă�����l���D��Ȃ������̃X�e�[�W�ł����B���͂������特�������o���āA����CD�u�����݂䂫Supreme�x�X�g�v�ɓ���Ă���܂��B
�@���̂��ƁA�E�N���C�i��f�i�Ƃ������u�Ђ܂��SUNWARD�v�A���̃A�j�������u�S���v�A�A���R�[�����u�삤�����̂悤�Ɂv�A�u�n��̐��v�ŃX�e�[�W�͏I���܂����B
�@�݂䂫����A71��364���̋L�O���ׂ��X�e�[�W�B���_�~�Ղ̉��ł����B�A��͍P��̊��z��B�����݂䂫�̃X�e�[�W��40�N�A150��ȏ���������Ă���N.Y.������u�����͎̂�̊O�悩�����v�Ƃ̌��B���̂��Ɓu�N�����m�v�������ɂ������ĉ��x�����[���̂��������܂����BN.Y.����A���肪�Ƃ��A�܂���낵���ˁB
���Q�l������
NHK-BS�u�����݂䂫�X�y�V�����v1994 O.A.
BS�t�W�u�P�������钆���݂䂫�v2021.3.7 O.A.
NHK-BS�uSONGS �����݂䂫�v2022.1.27 O.A.
TBS-BS�u�S�Ɏh����O�b�ƃt���[�Y�v2022.12.29 O.A.
2024.02.15 (��) �uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ƃ����{
 �@�N�������X�A���FIceblue�������d�b������B�uZEN����{�l���������Ƃ����{�������Ă��܂����B���R��������ɂ������Ă܂���ˁv�B�u����A���ĂȂ��ȁB�ǂ�Ȗ{�H�v�Ǝ��B�u�����̉�Ў���̑̌��k�Ƃ������Ƃ���ł����ˁB�����Ƃ��냌�M�����[�̏o�Ŗ{�ł͂Ȃ��āA����o�ł݂����ł��v�Ƃ̂��Ƃł����B
�@�N�������X�A���FIceblue�������d�b������B�uZEN����{�l���������Ƃ����{�������Ă��܂����B���R��������ɂ������Ă܂���ˁv�B�u����A���ĂȂ��ȁB�ǂ�Ȗ{�H�v�Ǝ��B�u�����̉�Ў���̑̌��k�Ƃ������Ƃ���ł����ˁB�����Ƃ��냌�M�����[�̏o�Ŗ{�ł͂Ȃ��āA����o�ł݂����ł��v�Ƃ̂��Ƃł����B�@ZEN����Ƃ͓n���S�����B����RCA���R�[�h�`�n����掞��̏�i�ł���A�i�`�̏�Łj���炴��l���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B������u���R�����Ă܂���ˁv�Ƃ����̂́A�u�����ɑ����Ă����̂�����A����ȏ�ɐ[���Ȃ���̂��鉪������ɂ͓��R�����Ă���͂��v�Ƃ����Ӗ������ł��B
�@�܂��A���̂����͂����낤�Ƃ��܂�C�ɂ��������ɂ��܂������A�ꂩ�������Ă����ׂ����B���̊ԁA�u�����Ă������lj�������ɂ͓��R�����Ă��ˁv�Ƃ��u��������ǂ�ł݂����NJ̐t�̋Ȗ����Ԉ���Ă���v�Ƃ��u�Ȃɂ����ĂȂ��̂Ɏ�����������悤�ɏ����Ă���v�Ƃ��A�u�����J�����ɃS�~���Ɏ̂Ă��v�Ƃ��A���ɓ���͂������������̃I���p���[�h�B�����Ȃ�Ɠǂ�ł݂����Ȃ�̂��l��ł��B�����������Ɂu�����݂��Ăق����v�Ƒ����Ă��炢�܂����B�^�C�g���́uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�B�����ǂ�ł݂܂������A���ɖʔ����B�����Ƃ����A���̓��e�ł͂Ȃ��A��������m�Ō������Ⴂ�܂����A�펯�����ӗ͂��^�킴��Ȃ��앶�͂̂��Ƃł��B����́A����̃e�[�}�Ƃ��Ă�������Ə������Ă��������܂����A���̑O�Ɉꌾ�B
�@ZEN����͉|�{���iJOE�j����Ƃ̋����o�c���SVAC�̔j�Y������Ȃ̂ł��B���̉�ЁA�n�����̏o�ʼn�ЂȂ̂ł����A�{�̂��\�t�g���삩��P�ނ�����AZEN���В��ʼnf���S���AJOE���������CD�S���Ƃ��āA����SVAC�Ń\�t�g����̔����Ƃs���Ă��܂����B
�@�Ƃ��낪�A���N�O����Ɛт����X�Ɉ����A�������̈ێ�������ƂȂ�A���ɂ�JOE����̎���}���V�����Ɏ��������ڂ��čׁX�ƋƖ����p���BJOE����Ɍp���̈ӎv�͂�����̂́AZEN����ɂ��̋C�͂Ȃ��Ȃ�A��N����A��Дj�Y�Ɍ����ē����o�����킯�ł��B���������҂Ƃ�߂����ҁB��l�̍a�����܂�Ȃ��܂܁AZEN����͉�Дj�Y�ɓ˂��i�݂܂��BJOE����́u�j�Y������͎̂d���Ȃ��Ƃ��āA�Ȃ���߂Ă�����̌������͎c���Ăق����B�Ⴆ���R�[�h��ЂɌl�Ŏx�������ۏ؋���A����������Ɏg�����}���V�����̉ƒ��̈ꕔ�����v��ZEN����ɐ��肷����u�ٌ�m�̉��A�j�Y�葱���͐i��ł���B�\�����Ă�����Ȃ�ٌ�m�Ɍ����Ă���v�Ƃ̕ԓ��������Ƃ��B���ꂪ�A����܂Ő��\�N���R���r�ł���Ă����p�[�g�i�[�ւ̌����l�ł��傤���B���̊m���E����������������A��N�H�AJOE����͔]�[�ǂǂ��Ă��܂��܂����B
�@����Ȃ킯�ŁA���\�q�𐢂ɏo�����q�r�f�B���N�^�[�Ƃ��āA�ƊE�ɂ��̖����������Ă���JOE����ł����A����A�̒��͂����ꂸ�A�����������Ċy�ł͂Ȃ��悤�ł��B�p�[�g�i�[�������Ă��鎞�ɁAZEN����A����Ŗ{���o���Ă��������ɔz��܂���Ƃ́A��̂ǂ������_�o�����Ă���̂ł����B����ȋ�������̂Ȃ�A���߂�JOE����ɕ����ׂ����̂��Ă�����̂��Ƃ������̂���Ȃ��ł����B�l�I���݂�݂͂Ȃ����̂́A�m�`���d�鎄�Ƃ��ẮA�uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ȃ�{��O��I�ɒ@���Ă�낤�Ǝv���킯�ł���܂��B
�@�܂��w�E�������̂́A�ԈႢ���炯�̋L�q�ł��iP�����̓~�X�̃y�[�W�j�B
�@�@�@�@�@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@���@ZEN����͉�Ў���A��X���������Ă��܂����B�u�Ȃ����O�A���͂���������ԋC�����Ȃ��Ă͂����Ȃ����ƒm���Ƃ邩�B����͂ȁA�ŗL�����͐�ɊԈႦ���炢����[���Ƃ�B����������ȁB�悭�o���Ƃ��v�B�����ZEN���ŗL���������ꂾ���Ԉ���Ă��܂��B�̂��猾�s�s��v�̐l�ł����i�j�B�ł͌ʂɃc�b�R�~�����Ă����܂��傤�B
�t�H�[�N�E�N���Z�[�_�X P5�@�@�@�@ �U�E�t�H�[�N�E�N���Z�_�[�Y
�v�w�D P22�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�w�M
�G���r�X P29�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�����B�X
�A�����J���E�|�b�v�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����J���E�|�b�v�X
���c�M�q P30�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�c�M�q
�u�����` P52�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����`
�ˑ� P58�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ّ�
���̉߂��䂭�܂܂� P109�@�@�@�@�@ ���̉߂��䂭�܂�
�Z�o P113�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �N�U
�W�����E�o�G�Y P117�@�@�@�@�@�@ �@�W���[���E�o�G�Y
�M��̔��� P120�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �M�y�̔���
�ςݍ��� P128�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��ݍ���
������ P132�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �傢��
�j�D�剉�� P138�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�剉�j�D��
�N�[���t�@�C�u P144�@�@�@�@�@�@�@ �N�[���E�t�@�C�u
���� P152�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �n��
���u�U�E�t�H�[�N�E�N���Z�_�[�Y�v���u�t�H�[�N�E�N���Z�[�_�X�v�̓C�J���ł��ȁB�u�U�v�����͂܂������Ƃ��āA�������Ƒ������}�`�}�`�Ȃ̂͂��������܂���B��_�u�^�C�K�[�X�v���A�u�^�C�[�K�Y�v�Ə����悤�Ȃ��́B��_�t�@���Ƀh������܂����I
��ZEN����͎O�}�D�q�����]���Ă��������Ă��܂����B�u�O�}�D�q�Ƃ����̂͐����̎肾�B�̂ɕ��ꂪ����B��͂�Q�Ȃ�����Ă����l�͈Ⴄ�ȁv�B����قnjh������O�}�D�q����ő�̃q�b�g�ȁu�v�w�M�v���u�v�w�D�v�Ə�������܂����ł��傤�B�q�D����Ȃ�����B
���u�G���r�X�v�ł͂Ȃ��u�G�����B�X�v�Ə����܂��傤�BRCA���R�[�h�̉��䍜��S�����̑�ȃA�[�e�B�X�g�̕\�L�Ⴂ�͍߂ł��B����͂܂��u�N�[���t�@�C�u�v�ł͂Ȃ��u�N�[���E�t�@�C�u�v���������ƁB�g�i�J�O���h�Ȃ�������Ȃ����ƌ����Ȃ���B�������RCA�M�y�̑b��z�����̑�ȃA�[�e�B�X�g�Ȃ̂ł�����B
�����R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�u�́u����͍������J�������v�̍쎌�҂́u���c�M�q�v�ł͂Ȃ��u�i�c�M�q�v�ł��BZEN����{���ŁA�����̂悤�Ȗ��O�ł������̕��͒j�Œ���u��n�ԁv�̎x�z�l�E�E�E�E�ȂǂƉ��X�Ɛ������Ă���̂ł����疼�O���ԈႦ���Ⴂ���܂���ˁB
���u�A�����J���E�|�b�v�v�A�u�u�����`�v�A�u�ˑ��v�A�u�ςݍ��ށv�A�u�����Ɂv�A�u�����v������́A�P�A���X�E�~�X���펯���@�̂Ȃ���ƁBZEN����͐����ς炤�Ƃ悭�A�u���O�A�������邩�v�Ƌ��Ă��܂������A�悭�悭������m��Ȃ��l�̂悤�ł�(��)�B�匾�s��͋C��t���܂��傤�B
���f��u�J�T�u�����J�v�̑}���̂́u���̉߂��䂭�܂܁v�ł��ˁB�u���̉߂��䂭�܂܂Ɂv�͑�c����B
���i�`�X�E�h�C�c�u�Z�o�v���ĂȂɁH�m���Ɂu�Z�o�v�Ƃ������t�͂���܂����A�R���A�����n���o���Ƃ����Ӗ��B����͎��̑z���ł����AZEN����A�i�`�X�E�h�C�c�́u�V���V���c�v��P/C���������̂ł��傤�B�����Ɂu�Z�o�v�Ƃ����������o�Ă����̂ō̗p�����B�����́u�N�U�v�ł��傤�ˁB�j���[�X�����Ă�悭�o�Ă��镶���ł��B
���u�W�����E�o�G�Y�v����Ȃ��u�W���[���E�o�G�Y�v�ł��B���c��b�́u�����|�E����v�Ɂu�����z�E�ł��v�Ƃ��������������@�u�c���ł������AZEN����A�����̓t�H�[�N�̏��_�ɓ{���܂����B�u�W���[���ł��B�W�����͒j�̖��O��v���āB
���u�M�y�̔��ہv���u�M��̔��ہv�͂Ȃ��ł��傤�BRCA�͉�L�o�c�̉�Ђ���Ȃ���ł�����B
���A�J�f�~�[�܂ɂ����ẮA�̂���u�剉�j�D�܁v���ʂ葊��Łu�j�D�剉�܁v�Ƃ͌����܂���B�u�Ђ�����Ԃ��Ă��邾������Ȃ����A�ڂ����痧�Ă�Ȃ�v�Ȃ�Č���Ȃ��ł��������ȁB�����ɂ�����悤�ȁA�Ⴆ�A�u�A�[�l�X�g�E�{�[�O�i�C���͉f��w�}�[�e�B�x�ɏo�������v�́u�o���v���Ђ�����Ԃ��u���o�v�����ɂȂ����Ⴂ�܂��B�j�D�{�[�O�i�C�����ēɂȂ����Ⴄ�̂������Ⴂ�ł��傤�B�R���A�������I�H
�@�ȏ�A����͈�ڗđR�A����₷���~�X�e�[�N���w�E�����Ă��������܂����B����͕��͍͗\���͓����e�ɂ��Č��y���Ă݂����Ǝv���܂��B�܂��A�w�E��ꂵ�Ă��Ȃ���̘b�ł����B
2024.01.17 (��) �V�N�����`���T�C�A�o����Җ]����
�@�N�������X�A1���ɂ͔\�o�����n�k���A2���ɂ͊C��ۈ����@�Ɠ��q�@�̏Փˎ��̂��A���đ����ɋN����Ƃ����ň��̃X�^�[�g��������{�ł����B��Ђ��ꂽ�F�l�ɂ͈�����������킪�K��܂��悤���F�肢�����܂��B�@����ȏ��A�u�̋��ƂȂ��āv�͊|��������A�{�C�x�[���̉䂪��������b�̌��t�͑S���S�ɋ����܂���B�����I�O�ɋg�c��Y���u���̍��Ƃ�����q������̂ȂǂȂ����v�Ƌ������z�i���F���{�����݁j�̐��E���疳�i����Ԃނ���މ��r���������{�ł��B���E������A�E�N���C�iVS���V�A�A�p���X�`�iVS�C�X���G���̐푈���p�����B�n�������B���E��s����͐��E�o��3�N�A�������̌��ʂ������o�B�܂��ɍ��Í�����^���Â̐��̒��ł��B
 �@�����̂�������ĐV�N�P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g��1��6���ɉ����B��͂�C�����o�܂���B�w���̃N���X�e�B�A���E�e�B�[���}���i1959-�j��5�N�Ԃ�2�x�ڂ̓o��B���o���2019�N�́A������X�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����̊��тł������A�����ɂƂ��ẮA�O�N�ɕ��S���������߂ł��傤�A�҂����C�����Ŋς��̂�z���o���܂��B���ꂩ�瑁5�N�B���N�͕�̎�����̖@�v�ł��B
�@�����̂�������ĐV�N�P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g��1��6���ɉ����B��͂�C�����o�܂���B�w���̃N���X�e�B�A���E�e�B�[���}���i1959-�j��5�N�Ԃ�2�x�ڂ̓o��B���o���2019�N�́A������X�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����̊��тł������A�����ɂƂ��ẮA�O�N�ɕ��S���������߂ł��傤�A�҂����C�����Ŋς��̂�z���o���܂��B���ꂩ�瑁5�N�B���N�͕�̎�����̖@�v�ł��B�@�ԑg�Q�X�g�͍�ȉƁE�w���҂̋v�Ώ����B���Œ����̂͏��߂Ă��Ƃ��B���̊��z�͂Ƃ����u�v�����ȏ�Ɋy���������v�ł����B�u�v�����ȏ�Ɂv���Ăǂ��v���Ă������B����ɂ́u�e�B�[���}������͓��̂����g�ݕ������Ă��܂��ˁv�Ɨ����B�u���̂����v�͉��y�Ƃɑ���_�ߌ��t���蓾�Ȃ��B�܂��E�B�[���t�B���ɑ��Ắu�o�����X�������v�̈ꌾ�B���F�I�����≉�t���̂��̂ɑ��錾�y�͂قƂ�ǂȂ��B�܂��A���ꂪ���̉��y�Ǝ��̊����Ȃ̂ł��傤�B���̂������̕��A���y�̖{��E�B�[���ōs����`������C���F���g�ɑ��A�ǂ����ォ��ڐ��̉]���l�Ȃ�ł��ˁB��������ȉƁE�s�A�j�X�g�E�w���҂Ȃt���Ă��܂������ׂĂ��O���I�H ���ꗬ�̃C���F���g�ɑ��ĎO�����y�Ƃ����ق����A�����ƌ����ɒ����̂����I�ƌ��������Ȃ�܂��B
�@��2���ł̓u���b�N�i�[�i1824-96�j�́u�J�h���[���v�����t����܂����B�����2024�N���u���b�N�i�[���a200�N�̃������A���E�C���[������B�����ڎw���āA�e�B�[���}�����E�B�[���t�B���̓u���b�N�i�[�̌����ȑS�W�����������Ă��܂��B��������������܂����A���ݑ傢�ɖ����Ă���Ƃ���B�ǂ���݂ȓ����悤�ɕ�������u���b�N�i�[�̌����Ȃ͍Ō��3�Ȃ���������悤�ȁB7�Ԃ̓n�C�e�B���N�A8�Ԃ̓N�i�b�p�[�c�u�b�V���A9�Ԃ̓N�����y���[�ŏ\�����Ǝv���Ă���܂��B���h�I
�@�c�B�[���[�́u�E�B�[���̎s���v�̓��n���E�V���g���E�X�U�́u�E�B�[���C���v�ƕ��ԃE�B�[���l��`�������i�B�E�B�[���̉��y�ƁA�Ⴆ�V���[�x���g��s���g�̃A�E�O�X�e�B���Ȃǂ���A�E�B�[���l�̋C���̓��}���e�B�X�g���y�V�ƂƊ����Ă��܂����B�u�E�B�[���C���v�̓��}���e�B�X�g�A�u�E�B�[���̎s���v�͊y�V�ƓI���ʂ��e�X�ے����Ă���悤�Ɏv���܂��B���̓��́u�E�B�[���̎s���v�ɂ�����e�B�[���}���̃_�C�i�~�b�N�ȕ\���́A�䂪���C�ɓ���̃A���o���u�E�B�[���̋x���^�N�i�b�p�[�c�u�b�V���v�̋��l�t�@�t�i�[�̕��݂̂悤�Ȑ�����������Ǝv���o�����Ă���܂����B
�@���NHK�j���[�C���[�E�I�y���R���T�[�g�͗�N�ʂ�1��3����O.A.����܂����B���N�A�Ō����߂�����͉̂̌��u�֕P�v�́u���t�̉́v���̌��u��������v�́u�Ԃǂ����̔R���闬��Ɂv�Ȃǒꔲ���ɖ��邢�ȂƑ��ꂪ���܂��Ă����̂ł����A���N�̓w���f���i1685-1759�j�̃I���g���I�u���T�C�A�v����u�n�������E�R�[���X�v�ł����B��������̂Ƃ���̐����f���Ă���̂ł��傤���B
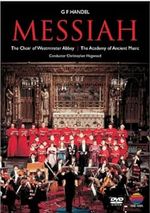 �@�I���g���I�u���T�C�A�v�́A�C�G�X�E�L���X�g�̍~�a�`��Y�`���`�܍߁`�����Ƃ�������̒��ɁA�l�ނ̋~����Ƃ��ẴL���X�g�̑��݂��^���Ƒ����̔O���Ȃ��ĕ`���o���܂��B�X�^���_�[�h�ȃe�L�X�g���@���ȂƂ��Ă͒������p��Ȃ̂̓w���f�����C�M���X�ɋA����������ł��傤�B�ނ̓E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɖ����Ă���̂ł��B�S�Ȃ̒������ۓI�ȉ̎��𒊏o�����
�@�I���g���I�u���T�C�A�v�́A�C�G�X�E�L���X�g�̍~�a�`��Y�`���`�܍߁`�����Ƃ�������̒��ɁA�l�ނ̋~����Ƃ��ẴL���X�g�̑��݂��^���Ƒ����̔O���Ȃ��ĕ`���o���܂��B�X�^���_�[�h�ȃe�L�X�g���@���ȂƂ��Ă͒������p��Ȃ̂̓w���f�����C�M���X�ɋA����������ł��傤�B�ނ̓E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɖ����Ă���̂ł��B�S�Ȃ̒������ۓI�ȉ̎��𒊏o�����
��͓V�ƒn�����ĊC�Ɨ� ���ׂĂ̍���h�蓮�����@�u���T�C�A�v�Ƃ́u���𒍂��ꂽ��ҁv�����u�_����I�ꂵ�x�z�ҁv�̈Ӗ��B�܂��Ɂu�~����v�̂��ƁB�u�n�������E�R�[���X�v�́h�n�������g�Ƃ͐_���̂���^���̌��t�B�O�ʈ�̐�����_����C�G�X�E�L���X�g�ł��邩�炵�ăL���X�g�^���̌��t�ł�����킯�ł��B
�����Ă��ׂĂ̖����]�ނƂ���������炷
�l�X���Â��łɕ����Ă��鍡
�傱�����ׂĂ̖��ɕ��a�������炷�������~����
���ׂĂ̖��̐S�Ɉ��炬�������炷�~����
�@�A�����J�̒�����Ѓ��[���V�A�O���[�v���u���N�̐��E���X�N�v�\���܂����B���̃x�X�g5�������Ă݂܂��傤�B
1 �g�����v�̑哝�̕��A
2 ���ˍۂɗ�����
3 �E�N���C�i�̕���
4 AI�̃K�o�i���X���@
5 �Ȃ炸�ҍ��Ƃ̐���
�@6�Ԗڂɉ䂪���{�̃��X�N��t��������Ƃ���A���ӂ��炩�����ꂽ�D�_�s�f�ȃ��[�_�[�̉��A��u�������������ېg�ɑ��邾���̂����������� �Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
�@��L�g6�僊�X�N�h������A�g����ȗ����ŕs���𐳓�����AI�����p���R�Ōł߂����`��U�肩�������͎҂��肪���s����u�^�̃��[�_�[�s�݂̕��f�Ɗi���̐��E�v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�ނ�͂܂����g���������炷�ُ�C�ۂɂ����S�B�����炱���A���ɕ��a�������炵�l�Ɉ��炬�������炷���T�C�A���~����̏o����҂����Ȃ��B�o�ł惁�T�C�A�I�ƋF��I���g���I�u���T�C�A�v�Ɏ����X���鍡�����̂���Ȃ̂ł���܂��B
�@��N�́A�V���h�~�̂��߂ɗ��������ۈËL�����������s���Ă��܂����B�_�[�r�[�n90���A�L�n�L�O�n68������ɁA�����{�̑�����b37�l�A�A�����J�哝��14�l�A�C�M���X��19�l�A�����̍��Ǝ��6�l�A�\�A�`���V�A�̎E�哝��11�l�A���j35�l�A�u�~�̗��v24�ȁA�u�䂪�c���v6�ȁA�u�W����̊G�v10�ȁA�u���[�}�O����v12�ȁA���q�R�A���s�R etc�B
�@����䍂����1�`2���͖Y��Ă��܂��ˁB�ʖڂȂ�(��)�B�ł��Y�ꂽ�甽������B���̌J��Ԃ��łȂ�Ƃ����ɍ��荞�܂����̂Ȃ�ł��B �ŁA���N�͎�n�߂ɖ����@�A�����A���E���E���E���E�E�E�E�E�Ȃǂ̒����吔���̕\������S���o���悤���Ǝv�������܂����B�ł͋��̎����牺�L�A�i�@�j���͂O�̐��B
���i20�j𥝱�i24�j���i28�j�a�i32�j���i36�j���i40�j�ځi44�j�Ɂi48�j�@����Ȑ��A�ǂ��Ŏg���Ⴂ�I �ł́A����͂���ł��J���Ƃ������܂��傤�B
�P�͍��i53�j���m�_�i56�j�ߗR���i60�j�s�v�c�i64�j���ʑ吔�i68�j
�@2024�N���ǂ��N�ł���܂��悤�ɁI
���Q�l������
�ŐV���ȉ���S�W21���y�ȂP�i���y�V�F�Ёj
�w���f����ȁF�I���g���I�u���T�C�A�v DVD �i���[�i�[�E�~���[�W�b�N�E�W���p���j
�@�@�@�z�O�E�b�h�w���F�A�J�f�~�[�E�I�u�E�G���V�F���g�E�~���[�W�b�N
�@�@�@�E�F�X�g�~���X�^�[�吹��1982�N���^
��CD��
�E�B�[���̋x���^�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c1957
�u���b�N�i�[��ȁF�����ȑ�7��
�@�@�@�n�C�e�B���N�w���F���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c1978
�u���b�N�i�[��ȁF�����ȑ�8��
�@�@�@�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�~�����w���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c1963
�u���b�N�i�[��ȁF�����ȑ�9��
�@�@�@�N�����y���[�w���F�t�B���n�[���j�A�nj��y�c1970
2023.12.10 (��) 12�� �G���`�Ⴊ���N�̊����́u���v
 �@���������12���̂����肪����͂��߁@�Q���������x��X��N�����D���ɂȂ�`B'z�u�����̃����[�N���X�}�X�v�̈�߂��S�ɋ����G�߂ɂȂ�܂����B
�@���������12���̂����肪����͂��߁@�Q���������x��X��N�����D���ɂȂ�`B'z�u�����̃����[�N���X�}�X�v�̈�߂��S�ɋ����G�߂ɂȂ�܂����B�@����Ȑ܁A�{�N�̗��s���܂����\����܂����`�u�A���v�B��_�^�C�K�[�X���c���z�V�ē��A�u�D���v�����̌��t�ɒu�������ăV�[�Y����˂�����A�I���b�N�X�Ƃ̒��㌈��ɂ��������ē��{����������܂����B�����Ɓu�A���v�u�A���v�ƕ�������ĂȂ�R���� �Ǝv���Ă��܂������A���ʂ悯����ׂĂ悵�B���������͒��ԂƍP��̓��{�V���[�Y�E�g�g�J���`���Ɂu��_��4��3�s�v�Ɠ���Č����I���B����͂�������̂��悤������܂���B���c�ē�Thank you very much !!�ł��B
�@��_�̓��{���1985�N�ȗ�38�N�Ԃ�B�����Ԃ�̘̂b�ł��B���̔N�ɗ��s�����̂ɓV���悵�݂́u���ږx�l��v������܂��āA���ꂪ����܂Ŗ�������������V���A�N���̃q�b�g�ȂɂȂ�����ł��ˁB���ꂼ�Q�Ԃ̃h�����ƕ]���ɂȂ�܂������A���͂��̉̂��Ă����͊����܂���ł����B�ł�1�Ԃ̉̎������L�B
�ӂ�ꂽ���炢�ŋ����̂͂��ق��@���̉́u�����������łȂ�Ƃ��撣�������Ǖ����Ă��܂��āA�Ȃ�����������Q�ԂŐ����Ă䂱���v�Ƃ����A�����Ă݂�Ε������̉̂Ȃ�ł��ˁB������Ȃ�ł��̉̂��Q�Ԑl�̉����̂ɂȂ�̂��킩��Ȃ��B�ł��܂������͂悵�܂��傤�B����œV���悵�݂̏o���̂��������ɂȂ�A���̔N��_�^�C�K�[�X�����̓��{��ɂȂ����̂ł�����B
�ۂ�ŖY���@�J�̖��
�������炠����@�������炠����œ�����
��ƂȂ��@�₳�����X�⓹�ږx��
�����̂Ă���@�����߂�����
�����ς肫�傤����@�Q�Ԃɐ�����̂�
 �@�C�̌������ł͑�J�ĕ��I�肪���{�l����MLB�z�[�����������l��A2�x�ڂ̖��[MVP�ɋP���܂����B���[MVP2���MLB�j�㏉�̉����������ł����A����͂܂��I�}�P�B�Ȃ�Ƃ����Ă��z�[���������͐����I���̏���G����Ȃ����Ȃ��������Ƃ��A�����������Ă�10���Ɠ��Ő����������Ⴄ�B����͂����������̉����ł��B
�@�C�̌������ł͑�J�ĕ��I�肪���{�l����MLB�z�[�����������l��A2�x�ڂ̖��[MVP�ɋP���܂����B���[MVP2���MLB�j�㏉�̉����������ł����A����͂܂��I�}�P�B�Ȃ�Ƃ����Ă��z�[���������͐����I���̏���G����Ȃ����Ȃ��������Ƃ��A�����������Ă�10���Ɠ��Ő����������Ⴄ�B����͂����������̉����ł��B�@���āAFA�̑�J�I��͂ǂ��ւ䂭�B�ނ̖]�݂̓|�X�g�V�[�Y�������ă��[���h�V���[�Y�𐧂��邱�ƁB�Ȃ�A�h�W���[�X���A�W���C�A���c���A�u���[�W�F�C�Y���A�J�u�X���A���Ԃ͎��Ɍ������B���̗\�z�̓G���[���X�c���ł��B���R�͍��N�̃|�X�g�V�[�Y���̓^���ł��B�|�X�g�V�[�Y����A�̋����u���[�u�X���h�W���[�X�������ɔs�ށA���[���h�V���[�Y�𑈂����̂́A���V�[�Y�� �G���[���X��艺�ʁA�n��4�ʂ����������W���[�Y�Ɠ��������V�[�Y���n��4�ʂ������_�C�������h�o�b�N�X�ł����B���̑��A�Ⴆ�A���[�O���n������Ă��A�����L�[�X��b�h�\�b�N�X�Ƃ������V�܋����`�[���ɑ����ăI���I�[���Y�A���C�Y�A�u���[�W�F�C�Y�ȂǐV�����͂��䓪�����B�����̂��Ƃ����J����A�������`�[���K���������[���h�E�`�����s�I�����炸�A�`�[����肱���������`�[������� �Ɛg�������Ċ������͂��B���c������Ɩ{�������Ď��т��郍���E���V���g���ē�2�N�_������킵���B�Ȃ���c�̂��C�ɓq���ē��ʂ����Ŋ撣�낤�B�_��ɂ̓I�v�g�A�E�g�i�_����Ԓ��ł̉����j��t��������B�u�����`�[���ɍs���v���� ���ƈ�������G���[���X���u�����`�[���ɂ���v�B���ꂪ��J�ĕ��̑I���ł͂Ȃ����B�ނ̐��i���l����Ƃ����m�M������܂���E�E�E�E�E�Ƃ����܂ŏ������Ƃ���Łu��J�A�h�W���[�X��10�N7���h���i1,015���~�j�ō��Ӂv�̃j���[�X����э���ł��܂����B���̗\�z�͌����ɊO��I��͂�ނقǂ̑I��ɂȂ�Ǝ����l�X�Ȏv�f�����ނ̂ł��傤�B�ނ̖{�ӂ�m�肽�����̂ł��B
�@�����X�|�[�c�E�ɂ����ē��{�l�B�����Ă������Ƃ�3����܂����B��̓S���t�̃}�X�^�[�Y�D���B�������MLB�̃z�[���������B�����ăT�b�J�[ ���[���h�J�b�v�̗D���ł��B����܂łɑO��҂͐��A�B���Ƃ̓��[���h�J�b�v�̗D���ł��B�Ȃ�Ƃ����ʂ܂łɌ��������́B�K���o���X�ۃW���p���I�I
�@�T�b�J�[J���[�O�ł͓������F���f�B16�N�Ԃ��J1���A�����܂�܂����B���F���f�B�Ƃ����L���O�E�J�Y����X�ڈ̂��i����J���[�O���������A�폟�̖���`�[���B���ꂪ2008�NJ2�ɍ~�i�����܂܂��̒n�ʂɊÂĂ����B�W�҂̊�т͂������肩�Ƒz�����܂��B
�@�Ƃ���ŁA���̌��I�o�������N�����̂́AJ���[�O�����G����J1��2�`�[�����₷���Ƃɂ�������ł��BJ���[�O�͌���3���[�O���B����N����ւ��Ȃ��犈������}���Ă���B1993�N�̔����ȗ��o�܂ʉ��v�ɂ���Č`�����Ă������n�̋@�\�Ȃ̂ł��B����Ɉ�������1936�N�ɒa�������V�ܓI���݂̓��{�v���싅�@�\NPB�̂Ȃ�ێ�̎��B��Ԃ̖��̓|�X�g�V�[�Y���̃V�X�e���ł��B6�`�[�������M�����[�V�[�Y�������ă��[�O�`�����s�I�������܂�B���̂��ƁA���������Ă���͂��̏��3�`�[����������G��ōēx���{�V���[�Y�̏o�ꌠ�𑈂��Ƃ������́B�����烊�[�O�`�����s�I������Ȃ��`�[�������{��ɂȂ�Ȃ�Ă��Ƃ��N����B�g�N���C�}�b�N�X�E�V���[�Y�h�Ȃ�đ�Ȗ��O�������Ă��܂����A���Ƀw���e�R�ȃV�X�e���Ȃ�ł��ˁB
�@�����Œ�Ăł��B�Z�p�����[�O�Ɋe2�`�[�����������āA1���[�O8�`�[�����Ƃ���B8�`�[���𓌐�4�`�[�����ɕ����A�����n��D���`�[�����m�Ń��[�O�D�������߂�B�����ă��[�O�`�����s�I���E�`�[�����m�����{��𑈂��B����ŗ��ɓK�����܂Ƃ��ȃV�X�e�����ł���B�V����4�`�[���𑝂₷�̂͑�ς����āH ����Ȃ���A���C�ɂȂ�����ɂ��ł��܂���B���ݓ��{�ɂ͓Ɨ����[�O���Ă̂������Ė�20�`�[�������݂��Ă���B��������I������4�`�[�������B���͓������ē���ւ����ɂ���B���f���̓A�����J�A���f��J���[�O�B��������K���ׂ��ł��B�ł��Â��̎���NPB���ᖳ���ł��傤�ˁB�����i�x�c�l����̎����������������Ăق������̂ł��B
�@����ANHK-BS�����Ă�������������l�����o�ꂵ�܂����B�^�c�t������BBMG JAPAN�ňꏏ�Ɏd�����������Ƃ�����܂��B���͔ށA�̗w�ȁ`J-POP�̔�����q�쎌�Ƌ��{�~�i1939-�j����̌�q���B�ԑg�́A���{�����F���������i1940-2020�j����̈������炪���������đh�点�悤�Ƃ�����B�̂���͕��R�݂��B�肵�āu�U�E�q���[�}�� ����ΗF��v�B�^�c����͂��̃v���W�F�N�g�̃f�B���N�^�[�Ƃ��ēo�ꂵ�܂����B�e������̂��w���������̂ł��傤�ˁB
�@�Ƃ��낪���̐e�q�A�n�i������܂��������ݍ����܂���B���q�͂��������܂��B
�̂��肪���R�݂�����Ƃ������_�ōw���w�͂��Ȃ苷���Ȃ�B�����������������Ȃ�����Ȃ��ƃ_�����Ǝv���B�@����ɑ��ĕ��e��
�ǂ̐���ɍ��킹�邩�Ȃ͂ǂ��ł������B���O����̘b���Ă���ƃ��A���Ȍ����_����B������Ėʔ����Ȃ���B�N�͎Љ�ɍ��킹�Ă���B���͍��킹�����ƂȂȂ��B�q�b�g�Ȃ͎Z�p�����Ƃ��납��o�Ă���B�@�������A�H��̃q�b�g���[�J�[���{�~�B�����ɏd�݂�����܂��B�����ċ��{���A���q���N�r�ɂ��ĐV���ȃf�B���N�^�[�𗧂ĂĂ��܂��܂����B�m���ɗ^�c����͉�Ў�����u�R���Z�v�g�v���u����v���u�^�[�Q�b�g���v�Ɛ헪�I���������������B�ł��A���R�[�h��Ђ̃f�B���N�^�[�͂܂�����Ȃ��̂Ȃ�ł��B�����MISIA�������Ă��Ĕ������̂�����A�ނ͗D�G�Ȏd���l�������Ƃ������Ƃł��B�����Ŏ��͍l���܂����B��L�̔����͂ǂ��Ȃ̂��B���̃v���W�F�N�g�ł���Ȕ��������邩�Ȃ��ƁB�����₱��A�o�����[�X����点 �ł́H NHK�ł͍ŋ߁A�o�ƍ��\���������u�N���[�Y�A�b�v����v�ł�点�^�f�����Ă��邵�B�^�c�����m����̂Ƃ��ĂȂ���ȋC������̂ł���܂��B���������Η^�c����A�̌N�ɐi�悵���p�����X�s�[�J�[Rogers PM410�͌��݂��ȁB
 �@12��6���A�T���g���[�z�[���AN����1999���������ɉƓ������ōs���Ă��܂����B�n�C���C�g�̓A���X�E�їǁE�I�b�g�̃s�A�m�ɂ�郊�X�g�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁA�w���̓t�@�r�I�E���C�[�W�B
�@12��6���A�T���g���[�z�[���AN����1999���������ɉƓ������ōs���Ă��܂����B�n�C���C�g�̓A���X�E�їǁE�I�b�g�̃s�A�m�ɂ�郊�X�g�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁA�w���̓t�@�r�I�E���C�[�W�B�@�^���Ԃȃh���X���D�u�Ɠo�ꂵ���A���X�B���l�͂܂�ŗd���̕��B���ꂾ���ł����ꕝ�̊G��̎�B���t���n�܂�B�������ǂ������A���X���������A�����Ǝ㉹�̑Δ�̈��A���������ӂ�铮��A���łŗ���锯�A�t���[�Y�I���̎�̓����A��̕\��B�܂��ɑS�g���ꉹ�y�B�����Ƒ@�ׂ��������X�g�̌��싦�t�Ȃ̖��͂�]���Ƃ���Ȃ������o�������ȃp�t�H�[�}���X�ł����B�e���I����āA�u�������Ȃ̂��Ƃ̓\�t�g�ȋȂ����͂����܂��v�ƃT�e�B�̃O�m�V�F���k�����t�B�S�[�W���X�ȃ��C���f�B�b�V���������ƕ�ݍ��ނ悤�ȑu�₩�ȊÂ��̃f�U�[�g�B����ȃA���R�[���ł����B
�@�ޏ��A���͑������d���ǂ������Ă��܂��B���̕a�A���̓V�˃`�F���X�g �W���N���[�k�E�f���E�v���i1945-1987�j�̉��t�Ɛ�����D������a�ł��B���P���Ă��邩�킩��Ȃ��������Ԃ݂A���X�̓p�t�H�[�}���X�̈�u��u�ɖ��������Ă���B�ǂ������i���ł�����蒷���������Ăق����B�_�ɋF�����ł��B
�@���͂��̃R���T�[�g�A�c����̗F�lM.F.������̃v���[���g�ł����B�N���V�b�N�D���ŕx�T�w�̔ނ�N���ƐV��������I�y��������N�Ԃŗ}���Ă���A����炪�o�b�e�B���O�A���l�Ɂu�N���Ȃ̂Ŋ�̌��w��������x�ɂ��܂��傤�v�ƌ����A����N��������Ă����Ƃ�������B�_�̔z�܂Ɋ��ӂł��B�A���X�����̃X�e�[�W�ɂ���̃��[����ł����Ƃ��� (>_<)�}�[�N���Ԃ��Ă��܂����B�����Ŏ���(^_^)�}�[�N��ԐM���܂����BM.F.����A�{����N���ɍs�����������̂��ȁH
�@�ł́A�Ⴊ���N�̊����ꕶ�����B����́u���v�B���̐S�́A�߂�����4�l�������Ă��܂������ƁB2��3����T.M.����A8��21����K.T.����A9��26����J.S.����A������11��14���ɂ�T.F.���������čs���Ă��܂��܂����B���ꂼ�ꂪ�e������ȕ��X�ł����B�҂������c�O�Ȏv���ł����ς��ł��B�ނ�ł����������F�肵�܂��B�܂��������܂� ���炩�ɁI
2023.11.15 (��) �����O�bCD�����̓^��
 �@�H�Ƃ����Ă�����ق�ē��������ُ�C�ۂ�11���A�u16���A�z�e���j���[�I�[�^�j�̃g�D�[���E�_���W�����ɗ��Ă��������B�f�B�i�[�����ꏏ���܂��傤�v�Ƃ̂��U��������܂����B�A���̎�͐Έ�G�搶�B�������̏t���炨��`�����Ă����u�����O�b���T�C�^���v��CD�����������������j���� �Ƃ̂��Ƃł��B�����O�b����͐Έ�搶�̉��l�ɂ��ėD�G�ȃs�A�j�X�g�����t�̕��B����CD�͎O�b���₳�ꂽ�B�ꖳ��̘^���ł��B
�@�H�Ƃ����Ă�����ق�ē��������ُ�C�ۂ�11���A�u16���A�z�e���j���[�I�[�^�j�̃g�D�[���E�_���W�����ɗ��Ă��������B�f�B�i�[�����ꏏ���܂��傤�v�Ƃ̂��U��������܂����B�A���̎�͐Έ�G�搶�B�������̏t���炨��`�����Ă����u�����O�b���T�C�^���v��CD�����������������j���� �Ƃ̂��Ƃł��B�����O�b����͐Έ�搶�̉��l�ɂ��ėD�G�ȃs�A�j�X�g�����t�̕��B����CD�͎O�b���₳�ꂽ�B�ꖳ��̘^���ł��B�@���A�Έ�搶�Ƃ��t�����������Ă��������ď\���N�A���݉�/�H����͐��m�ꂸ �Ȃ̂ł����A�n��1582�N�A���E�̉���M�����W���Z�[�k�͔Ȃ̘V�܃��X�g�����̐��E�B��̎x�X�Ȃ͖��_���A�]�O�̏o�����ł��B���ꏏ����͓̂�CD�̕����ɒ��ڌg����Ă������������m�����̉c�Ɩ{�����c���m�����B�搶����u�����̋łɂ�3�l�ł��j��������܂��傤�v�ƕ����Ă͂������̂́A�܂������̂悤�Ȓ��h���̃��X�g������ �Ƃ͎v���Ă��݂܂���ł����B�搶�A���̊�������قǂ��ꂵ�������̂ł��傤�ˁB����͂��̓^�����L�����Ă��������܂��B
4��15���i�y�j �Έ�搶����̎莆
�O�b���S���Ȃ������N2016�N7��20���ɔ������ꂽ�u�����O�b���T�C�^���v��CD���A��ԋM�d�i�Ƃ��č��l�Ŏ������Ă��邻���ł��B�艿3000�~��CD���Ȃ��10,000�~���̒l�i�����Ă���Ƃ̂��ƁB�l�b�g��ł͍Ĕ����̗v�]�����܂��Ă���Ƃ��B����CD�͏���500���A�Ĕ�250���B���̐����̔������ɂ���Ă����������[�[�����y�o�ł̎����G���͍�N�S���Ȃ��Ă��܂��A�ăv���X�̎藧�Ă��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�����ŁA���R�[�h��Џo�g�̋M�Z�ɂ���CD�́u�����̔��v�Ƀg���C���Ă������������A���肢���鎟��ł��B�������}�X�^�[�e�[�v���t���i�̍��ł��s���m�ꂸ�ɂ��A�f�ނ͊���CD�ƂȂ�܂��B
 �@CD�u�����O�b���T�C�^���v�͔����シ���ɐΈ�搶���璮�����Ă��������܂����B1986�N12��5���̘^���ŁA���^�Ȃ́A�V���[�}���u�N���C�X�����A�[�i�v��i16�A�V���p���u���z�ȁv��i49�A�u�o���[�h ��3�ԁv��i47�A���X�g�u�n���K���A�����ȑ�12�ԁv��4�Ȃł��B1�Ȗڂ́u�N���C�X�����A�[�i�v���特������o�����u�ԁA���̃s�A�j�Y���ɑ���ۂ݂܂����B�͋����P�������^�b�`�A�M�C���郍�}���̍���B�z�����B�b�c��A���Q���b�`�ɂ��C�G�����ꋉ�̃s�A�m���t�ł��B���̗D�����Ί�̉��l������Ȑ��܂������t������Ȃ�āI ���O�̎p��m��҂ɂƂ��āA����͋��Q�̈ꌂ�ł����B
�@CD�u�����O�b���T�C�^���v�͔����シ���ɐΈ�搶���璮�����Ă��������܂����B1986�N12��5���̘^���ŁA���^�Ȃ́A�V���[�}���u�N���C�X�����A�[�i�v��i16�A�V���p���u���z�ȁv��i49�A�u�o���[�h ��3�ԁv��i47�A���X�g�u�n���K���A�����ȑ�12�ԁv��4�Ȃł��B1�Ȗڂ́u�N���C�X�����A�[�i�v���特������o�����u�ԁA���̃s�A�j�Y���ɑ���ۂ݂܂����B�͋����P�������^�b�`�A�M�C���郍�}���̍���B�z�����B�b�c��A���Q���b�`�ɂ��C�G�����ꋉ�̃s�A�m���t�ł��B���̗D�����Ί�̉��l������Ȑ��܂������t������Ȃ�āI ���O�̎p��m��҂ɂƂ��āA����͋��Q�̈ꌂ�ł����B�@�������̓��������ŁA���R�[�h�|�p�̓��I�ՂɋP���A�Y�o�V���A�ǔ��V���ł́A�����O�b�u���h���Ԃ�s�A�j�X�g�v�u�C���̐l ���̃s�A�j�X�g�v���� �v�̐Έ�G����CD���@�ȂǂƐ�^�̋L�����f�ڂ���܂����B
�@�t���̐Έ�搶�������낵�ɂ��u�b�N���b�g�͐��\�łɋy�ԑ��B�O�b����Ƃ̏o����烄�}�n�̃s�A�m�̑ݗ^�A���{���y�R���N�[��1�ʊl���i2�ʂ̓t�W�R�E�w�~���O�j�A�p�����w�A�����Č����Ɏ���܂ł̓��̂肪�����ɕ`���ꂽ�Ӑg�̃��C�i�[�m�[�c�ł��B���̂悤�ȍ�i�𐢂̒��Ɉ₷���Ƃ͑傢�ɈӋ`���邱�ƁB�Ȃ�Ƃ��Ă������ɑ������悤�ƌ��ӂ��V���ɖ���CD�����̃X�^�[�g���܂����B
5��12��(��) K�ЂƉ
�@�����݂̂Ȃ炸�̔����Ƃ������ƂȂ̂ŁA��͂�����̃��R�[�h��ЂɈ˗����邵������܂���B�ƊE�������ď\�]�N�A��������̒m�荇���͂قƂ�ǂ����^�C�A�B�ǂ��������̂��Ǝv�Ă��Ă�����A���T�C�g�̎�ɎҐ쓈����K�ЂƂ̈ϑ��Ɩ����p�����Ƃ������ƂɋC�Â��܂����B�܂��ɓ��䉺�Â��B
�@���R�[�h�ƊE�ACD�̔���グ�͋}�~���B���ɃN���V�b�N�́A���̎w�j�I�X�^���_�[�h�������u���R�[�h�|�p�v���p���ɂȂ�ȂǁA���ނ̈�r�����ǂ��Ă��܂��B�����̒��ŁA�N���V�b�N���D�҂̎���ɍ��v���ēK���ȃ����[�X�𑱂��Ă���K�Ђ������ł��M���ł����Ђł��� �ƍl���Ă��܂����B�쓈���Ɏ掟�����˗�����ƁA�����ɕԎ������܂����BGW��A�����{���ň��݂Ȃ���b�� �Ƃ������ƂɁB
�@����͕��������O���A�N���V�b�N����S����M���A�W���Y�S����H����3���B���A���Q����������n���Đ�������ƁAM�����u�Έ�搶�Ƃ͐̍��ӂɂ��t�����������Ă��������܂����B���_����CD�͑����グ�Ă���A��ϋM�d�ȉ����ł��邱�Ƃ����m���Ă��܂��B����O�����Ɏ��g�܂��Ă������������v�Ƃ̌��B����CD�̉��l�𗝉����Ă�����Ă��邵�A�搶�Ƃ����m�A����͂��܂��������ƊԈႢ�Ȃ� �̊��G�ł����B
�@�]�k�ł���H���͌̓c������ƒm�荇���ŁA�g���E�n���N�X�̃c�C�b�^�[�����Ă���A�l���R�b�ɉԂ��炫�܂����B
�@�����A�搶�ɂ́uK�Ђ���͂ƂĂ��D�ӓI�Ŏ���悭�^�ԂƎv���܂��v�Ƃ̗t���𑗂�܂����B�Έ�搶�͌�N92�B�����A���̋�̊W�ŁA�d�b�͎g���Ă��炸�A���FAX�Ȃ̂ł����A����͎����s�����B�Ȃ̂ŁA�ʐM��i�͗X�ւ̂݁A���Ƃ�Ɉ�T�Ԃ͂�����܂��BIT�̎���ɂ���܂��I���Șb�Ȃ̂ł��B
�@5��16���i�j�AM������A�u���݂̎s��̏���A����CD�͋����ł��邽�߁A�V���b�v����̃I�[�_�[�͓��x�i100���ȉ��j�Ǝv���܂��B���������āA�����[�X����������ɂ͔���肪�K�v�ƂȂ�܂��v�Ƃ̃��[���B���������Ă�`�I�ł��B�u��̓I�ɂǂ̂��炢�ł��傤���v�Ǝ���B�u�P��1500�~�Ƃ���200���v�Ƃ̕Ԏ��B�M�����物�F���_�ŁB�ł������̏��炻��Ȃ��낤�Ɨ������A�搶�ɂ͂��̎|���������܂����B����ɑ��Đ搶����u�����͂�Ԃ����ł͂Ȃ����A�v������Ȃ琔���I�����������Ă�����ׂ��v�ƕԓ�����B��������R�̂��Ƃł��B�݂��̎v�f���A�����ԂɁA�X�����܂�ł���肷��̂���ςȘJ�́A���Ԃ̘Q��A�X�g���X�r��B�Ȃ̂ŁA�Έ�搶��K�Ђ̊獇�킹�𑁋}�ɂ��܂��傤 �Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�g���}�h�Ƃ����Ă�1�����]��ƂȂ����̂́A�X����݃R�~���j�P�[�V�����`�Ԃɂ����̂ł��i�j�B
6��30���i���j �Έ�搶��őł����킹
�@�ꓰ�ɉ���̂́AK��M���A���m����������Љc�Ɩ{�����c���m�����A�Έ�搶�A�����Ď���4���B
�@�܂��c�������琻����̐������B�����f�ނ͊���CD�̂݁A�������u�b�N���b�g�����\�łɋy�ԑ啨�Ȃ̂ŁA���ς����1,040,564�~(300��)�ɂȂ� �Ƃ������́B����ɑ��搶�́A�u�킩��܂����B���x�����̏����́H�v�B�u�O���ƂȂ�܂��v�Ɠc�����B�u���m���܂����v�Ɛ搶�B����ɂ͎����т����肵�܂����B�Έ�搶��100���~�Ȃ�o���C�ł���B�����̊������ŗD��Ŏs�̃��[�g�\�z�͓�̎��B���̂�����ɁA�搶�̂���CD�ɑ���v�����݂̐[�������߂Ċ����܂����B
�@�搶��M���Ɂu�̔��͂ǂ̂悤�ɂȂ�܂����v�Ɛq�˂܂��BM���u���Ђ�����̔��𐿂������ɂ͂��̐�����ł͓���B�ϑ��̔����ʓr�g�c��ʂ��˂Ȃ炸�A�����͒v�����˂܂��v�ƕԓ��B����͂�A�����̐������R�̂悤�ȏ��ɂ��B�Έ�搶�A���q�����̑́B�����A����ȏ�͓˂����܂��A�b�͐�����̌y���Ɉڂ�܂��B
�@�������8���̓u�b�N���b�g����߂Ă��܂��B���ł��Ȃ����Ƃ��������������Ă���킯�ŁA����p�̃f�[�^������Δ�p�͑啝�ɍ팸�ł���͂��B�Ȃ�A�����������ш���Ђɖ₢���킹�悤 �Ƃ������ƂŎU��܂����B
7��24���i���j ���m��������V���Ȍ��ς��肪
�@���炭���ēc��������N��э���ł��܂����B�u��ш���Ђɖ₢���킹����f�[�^���ۑ�����Ă���g�p���\�Ƃ̂��Ƃł��v�B�{�����ׂ�K�Ђɑ����đŐf���������ʂł����B�V���ɏo�Ă������ς����67���~�B�Ȃ��37���~�̌y���ł��B��C�Ɏ��ԍD�]�B�c�����̂��s�͂ɂ͊��ӂ���̂݁B�����܂ŗ������K�Ђ̐����̔����\�ɂȂ�̂ł́H K�Ђւ̐�����v��A�����������ǂ���������g�c���ʂ邩���l���܂����B
�@�������z�́A5��16���̂���肩��A1500�~�~200����30���~�B���쐻����͒艿��30�����ڈ��Ȃ̂ŁA�P��900�~�~300����27���~���v��B����Ȃ��K�Ђ��g�c�͒ʂ�͂��ł��B
�@����A�Έ�搶�̕��S���z�́A�����30���~�B�������U67���~-27���~��40���~�B���v70���~�B����͗p�ӂ��������Ă���100���~���͂邩�ɉ����܂��B����őo���ۂ����܂�̂ł͂Ȃ����B���̈Ă�������K�Ђɏo�������Ƃɂ��܂����B
8��10���i�j K�ЂƉ
�@�����O����M���B���A������������O������o���܂����B�u�O��Ƃ��Đ����͐Έ䎁�ɂ��肢�������B����CD�Ђ��P��1000�~��50����������ăX�^�[�g���A�lj��I�[�_�[�͏����s�����Ƃł������ł��傤���v
�E�E�E�E�E���R�I�I�艿3000�~�̏��i��1000�~�Ƃ͂Ȃ���l���ς���B���̗]�n�Ȃ��B�����̒�Ă��o���܂ł�����܂���B���̍ŏ��̔M�C�͂����������������̂��I�ł������K�Љ]�X�Ƃ��������A�N���V�b�N�ƊE�̋}���Ȓn�Ւ����̂����Ȃ̂��낤�ƔF�m������܂���ł����B�u�����炭�����Έ�搶���ۂނ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�̔��ɂ��Ă͕ʓr�l���邱�Ƃɂ������܂��B���X�����b�ɂȂ�܂����v��K�Ђ���ɂ��܂����B
�@�Έ�搶�ɂ͑��莆�ŕB�uK�Ђ͂���Ȃ��̂ł��傤�B�Ƃ������邱�Ƃ͐i�߂܂��傤�B�c�����ƍŏI�ł����킹���������̂ŁA���������߂Ă��������v�Ƃ̂��Ԏ������܂����B
9��12���i�j�Έ�搶��őł����킹
�@���m�����c��������300�������̍ŏI��p�A�[�i���A�N���W�b�g��Ⓟ�\���A�x�����������̒���������A�Έ�搶�͂���𗹏��B�����Ɋւ���ł����킹�͒Z���ԂŏI�����܂����B
�@���̂��ƁA�c��������̔��c�[���̒�Ă�����܂����B���m�����̓A�i���O�Ղ̔̔����[�g��Ǝ��ŗL���Ă���A�^���[���R�[�h�ł̔̔��͉\�Ƃ������Ƃł��B����͍����̃A�i���OLP�̍D�����̂Ȃ���Ƃł��傤���B����ɁA�C���^�[�l�b�g�ʔ̂ɏ悹�邱�Ƃ��\ �Ƃ������Ƃł����B�Έ�搶���u�����낵���v�Ƃ������ƂɁB��������̂���q����֘A�ł͂��łɑ����̍w����]�����Ă���A���̗���Ȃ�A300���̕����͓K���������Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B
10��4���i���j �Έ�搶����t����
�����C�ł����@���m�����c�������10��27���i���j�Ɋ��[������ɓ͂������ł��B��ʎs�̃��[�g�̓^���[���R�[�h�������Ă���邻���ł��B���낢�낲����������܂������A����ňꊪ�̏I���A���肪�Ƃ��������܂����B���s�͂Ɋ��ӂ��܂��B�@�˗��l����́u�ꊪ�̏I���v�錾�ɂق��ƈ��g�̋����Ȃł��낵�܂����B�����̊y�ς����_�ɕς�������ƁA�Ƃɂ������ɂ������̖ړr�������āA�Ō�͔̔����[�g���\�z�B�n�������̖ҏ������ߊ삱�������̔��N�Ԃ��I���܂����B����K�ЂƂ͉����Ȃ��������ƂɂȂ�܂����A����́A�O�ɂ��q�ׂ܂������A�S���҂̂����ł͂Ȃ��ACD�s�ꂪ�z���ȏ�ɗ�������ł��邱�Ƃ������ł��傤�B����Ȓ��ŁAK�Ђ����m�����̓c�����ƈ������킹�Ă��ꂽ���Ƃ������̍ő���ƂȂ�܂����B���̈Ӗ��ł�K��M���̌��т͑�Ƃ����ׂ��ł��B�����āA�c�����̐^���ɂ��Đ��ӂ���Ή��ɂ͊��ӂ���݂̂ł��B
�@�Έ�搶�́A���l�̖����t�Ǝ��g�̎�ɂȂ�Ӑg�̃u�b�N���b�g�����̂���CD�̊��S�������������āA�傢�ɖ�������Ă���Ǝv���܂��B
�@����̃v���W�F�N�g�ɂ����ẮA�Έ�搶���������쓈����K�Ё����m�����c�����̃����[�������ɓ��������ƂɂȂ�܂��B�W�̊F�l�ɑ傢�Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B
�@�ł͖����A�l�N�^�C���p�A�ْ����܂���Ȃ���A���E�L���̃��X�g�����ɍs���Ă܂���܂��B
2023.10.12 (��) �c���\��Y����A���炩��
�@8��21���A������悤�ȏ����̒��A�c���\��Y����l�ŗ������Ă����Ă��܂��܂����B���{�r�N�^�[��2�N��y�̔ނƂ́A�o����Ă���53�N�ԁA�ƂĂ��ƂĂ��e�����t�������Ă��܂����B���̕���A���ꂪ��������l���ł͂Ȃ��������߁A�܂��͋����A���ɂ́A�Ȃ��Ƃ����^�₪���X�ƗN������B�ł������͎����B �^����𖾂����Ƃ���Ŕނ͊҂��Ă��Ȃ��̂�����A�����͂������炩�Ȑ������F�邵���Ȃ��̂ł��傤�B
�^����𖾂����Ƃ���Ŕނ͊҂��Ă��Ȃ��̂�����A�����͂������炩�Ȑ������F�邵���Ȃ��̂ł��傤�B�@�N�ɊŎ���邱�ƂȂ��A��l�҂����������c������i�ȉ�K.T.����j�ɂ͉��y�ő����Ă��̂����������Ǝv���A�r��ł���ނ̂��Z�����CD������Ă��͂����܂����B�^�C�g�����u�G���[�E�A�������N�{ For K.T.�v�Ƃ��܂����B�A�������N�i1933-�j�͔ނ���D���������I�����_�l�\�v���m�̎�B���̐��ݐ��������͔ނ̎�̗ǂ����`���܂��B�ޏ��̉̂�15�ȁB�{�́A���C�ɓ���̃C���X�g��2�Ȃ��v���X�������ƁB�ނ̋C�����ɂȂ��đI�Ȃ��܂����B���̋Ȗڂ����L�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G���[�E�A�������N�{ For K.T.
�@�@���[�c�@���g
�@�@�@�@1 ���݂�@2 �[�ׂ̑z���@3 �N���[�G�Ɂ@4 �t�ւ̂�������@5 (�p���̋�̉�)
�@�@J.S.�o�b�n
�@�@�@�@6�u�R�[�q�[�E�J���^�[�^�v���A���A
�@�@�V���[�x���g
�@�@�@�@7 ���@8 ���̏�ʼn̂��@9 �K���@10 (�C�p�l�}�̖�)�@11 ���y�Ɋ�
�@�@�@�@12 �A���F�E�}���A�@13 �q��́@14 (�\�t�B�X�e�B�P�C�e�b�h�E���f�B)
�@�@�t�H�[��
�@�@�@�@15�u���N�C�G���v���u�����A�C�G�Y�X��v
�@�@�h���H���U�[�N
�@�@�@�@16 �������X�N
�@�@�p�b�w���x��
�@�@�@�@17 �J�m��
�@�@�@�@�G���[�E�A�������N�i�\�v���m�j1-15
�@�@�@�@�@�@�C�G���N�E�f���X(P) 1-4�@���C�X�E���@���E�f�B�W�b�N(P) 5,10,14
�@�@�@�@�@�@�R���M�E���E�A�E���E�����t�c 6�@���h���t�E�����Z��(P) 7-9,11-13
�@�@�@�@�@�@�W�����E�t���l�F���b�e���_���E�t�B���n�[���j�[ 15
�@�@�@�@�@�@���[�t�E�X�[�N(Vn) 16�@�p�C���[�������nj��y�c17
�@�݂�K476 �̓��[�c�@���g�̉̋Ȃ̒��ł����Ƃ��|�s�����[�Ȋy�Ȃł��傤���B�����ɓE�ݎ���邱�Ƃ��肢�Ȃ���A���݂����Ă��܂����݂�̂͂��Ȃ����O�����̂��܂��B�u���킢�����Ȃ��݂�@����͖{���ɂ��킢�����݂ꂾ�����v�B���[�c�@���g���������B��̃Q�[�e�̋ȁB
�@T.K.����ɌK���뒼����Ƃ����e�F�����āA�c�����z�̂��V�����B���͂��̉��R�����Ŏi�@��U�����������@��w�̌��ЌK���������m�B�o�̂��݂ꂳ��͔��q�q��c�ܓa���Ƃ���F�̂���n�[�s�X�g�B���q�q�܂��ՐȂ̉��t���T.K.����ƈꏏ�ɍs�������Ƃ��v���o���܂��B���o����̖��O�͂�����̃��[�c�@���g�̉̋ȂɗR�����Ă��܂��B
�@���[�ׂ̑z���� ���炩�Ōh�i�ȉ̋ȁB��N3���AT.K.����Ƃ��m�荇���̊��R�I���S���Ȃ����Ƃ��A���̋Ȃ����CD������Č��悵�܂����B�u�₩�ŗD���������ޏ��ɂ҂����肾�Ǝv��������ł��B�C�i����A�������N�̉̏��͂��̋Ȃɑ����������̂ł��B
�@��t�ւ̂�������K596�͂��ׂĂ��P���t5����҂���т�ȁB���[�c�@���g�Ō�̃s�A�m���t�� ��27��K595�̑�3�y�͂̎��Ɏ���t�������́BT.K.���C�ɓ���̊y�Ȃł��B
�@J.S.�o�b�n�́�R�[�q�[�E�J���^�[�^����A���A�����܂������A����K.T.���R�[�q�[�D������������ł͂Ȃ���ł��B�ނ́A�ߔN�A�i���X�ł͌��܂��ă~���N�E�e�B�[�B���N�O�A���ɃZ���~�b�N�̃R�[�q�[�E�h���b�p�[��E�߂Ă��ꂽ��ł����ˁB�Ȃɂ��̉����ŃR�[�q�[���ꂵ��������̂��ȁB����͂����i���̓�ƂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�V���[�x���g�ł́����̏�ʼn̂����o�F�B������������ƌ��邳���g��f�i�Ƃ�����s�A�m�Ƃ̑Δ�̖��B���̗���̙R�����A�������N�͐[���A�e�������ĉ̂��グ�܂��B1998�N�̓��{�f��u�̗��v�ł͂��̃A�������N�̉̏����g���āA�V���A�X�Ȍ��ʂ������Ă��܂����B
�@���N8��8���̈��݉�AK.T.����́u����Ȃ̂��o�Ă������炠����v�ƌ����āA�V���[�x���g�̎O��̋ȏW�̃A�i���OLP 3���g�i�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���W�F�����h�E���[�A EMI 1962�N�^���j�������Ă��Ă���܂����B�I�[�f�B�I�E�}�j�A�������ނ��ŋ߂̓A�i���OLP���Ȃ��Ȃ��Ă����̂��ȁB���ł��������܂������A���ꂪ�`���ɂȂ��Ă��܂��Ƃ� ���̎��͎v���Ă��݂܂���ł����B�O��̋Ȃ̈�u�~�̗��v�͐�]���Ď��Ɣw�����킹�̗��������҂̘b�B�ł��Ō�͎�I���K���e���̘V�l�ɏo��A�Ƃɂ��������悤�Ƃ���B��]�����Ă��Ȃ�����K.T.����B�ǂ����āA���͎���ł��܂������I
�@�i�@�j�t���ő}�������̂́A�A�������N�̃A���o���uSentimental Me�v����̑I�ȁB����̓s�A�m���x�[�X�̃V���v���ȕҐ��ŁA�X�^���_�[�h�Ȗ��Ȃ��W���W�[�ɉ̂��ِF��B�A�������N�̕ʂ̊炪�y���߂܂��B��\�t�B�X�e�B�P�C�e�b�h�E���f�B�̓f���[�N�E�G�����g���̖��ȁB�䂪�G�����g���̎t�E���쌛�F���A�����A�u�����͗F�B�����Ȃ�����Ǔc������͐����Ȃ��C�̒u���Ȃ��F�l�̂ЂƂ�v�ƌ���Ă��܂����B�䂪���������^�C�v�̒��삭��ɂ������킹��K.T.����͂�͂�݂�ȂɈ�����Ă����ˁB
�@�N���V�b�N�D��������K.T.����Ƃ́A���x���R���T�[�g�����ꏏ�������̂ł��B�L�^�ɂ�����̂������_���ɗ�L���Ă݂܂��傤�B
2009.11.14 �C�V���݂� �s�A�m���T�C�^�� (����������ُ��z�[��)
2014.10.24 N�� ��1791��@������t�� �i�w���F�T�[�E���W���[�E�m�[�����g���@NHK�z�[���j
2014.11.26 N�� ��1795�� ������t�� �i�w���F�l�����E�T���e�B�@�T���g���[�z�[���j
2017.10.20 N�� ��1868�� ������t�� �i�w���F�N���X�g�t�E�G�b�V�F���o�b�n�@NHK�z�[���j
2022.12.6 �x�Ă䂸�q ���@�����[�E�A�t�@�i�V�G�t�@���T�C�^�� �i�T���g���[�z�[���j
2023. 6.11 �O��Z�F�C��nj��y�c��41�������t�� (�����|�p����)
 �@�����͂ق�̈ꕔ�ł����A��ۂɎc���Ă���̂͂�͂蒼��2023�N6��11���̉��t��ł��傤���B�Z�F�C��nj��y�c�͎��̏]���̒��j�����������ƃI�[�P�X�g���B���͒r�܂̓����|�p����B�}篂̗U���ɁA�u�u��1�͑�D��������s����v�Ɖ����삯���Ă���܂����B�ނ͎��̒���̎��Ƃ���c�̕ʑ��ɂ��V�тɗ��Ă���A�]���Ƃ���Ȃ��݁B���삩�痈���]���Ƃ͊��k�̉Ԃ��炫�v�X�̋��������߂Ă��܂����B���̒���AK.T.����͏]���ɃN���V�b�N�̃R���T�[�g���k�C���̎��R����DVD�𑗂��Ă��ꂽ�����ŁA������ɂ��ނ̗D����������Ă��܂��B9���A�]���ɔނ��]����������Ƃ���A�u�M�����Ȃ��B���N2���́w���z�����ȁx�A�����ł܂� ���Č����Ă����̂ɁE�E�E�E�E�v�Ɛ�傷�邾���ł����B
�@�����͂ق�̈ꕔ�ł����A��ۂɎc���Ă���̂͂�͂蒼��2023�N6��11���̉��t��ł��傤���B�Z�F�C��nj��y�c�͎��̏]���̒��j�����������ƃI�[�P�X�g���B���͒r�܂̓����|�p����B�}篂̗U���ɁA�u�u��1�͑�D��������s����v�Ɖ����삯���Ă���܂����B�ނ͎��̒���̎��Ƃ���c�̕ʑ��ɂ��V�тɗ��Ă���A�]���Ƃ���Ȃ��݁B���삩�痈���]���Ƃ͊��k�̉Ԃ��炫�v�X�̋��������߂Ă��܂����B���̒���AK.T.����͏]���ɃN���V�b�N�̃R���T�[�g���k�C���̎��R����DVD�𑗂��Ă��ꂽ�����ŁA������ɂ��ނ̗D����������Ă��܂��B9���A�]���ɔނ��]����������Ƃ���A�u�M�����Ȃ��B���N2���́w���z�����ȁx�A�����ł܂� ���Č����Ă����̂ɁE�E�E�E�E�v�Ɛ�傷�邾���ł����B �@�n���E�b�h�̑�X�^�[ �g���E�n���N�X�Ƃ̑������Y����Ȃ��v���o�ł��B2016�N9��16���AK.T.����܂މ�X�F�l4�l���_�c�̋������u�܂�v�ň���ł�����A�g���E�n���N�X��s���ׂ̃e�[�u���ɍ������̂ł��B�܂��ɗ\�����ʏo�����BK.T.����̓g���E�n���N�X�̑�t�@���B�x����ԁA�₨��ނɁA�u���Ȃ��̉f��͑S�����Ă��܂��B��ԍD���Ȃ̂́w�O���[���}�C���x�ł��v�Ɖp��Řb�������܂����B���ꂩ��Ƃ������́A�n���N�X��s�Ɖ�X����̃O���[�v�Ɖ����A�a�C�\�X�u�����ɉ˂��鋴�v��u��������ĕ������v�̑升���ƂȂ�Ȃǂ܂��ɓ��đ剃��ƂȂ�܂����B�n���N�X�������B�肵�����̎ʐ^�͗����c�C�b�^�[�ɂ������āA�u�g���E�n���N�X�ƃW���p�j�[�Y�E���b�p���C�v�ƃc�C�[�g����A���E�����삯����܂����B���̑厖���̂���������������̂�K.T.�N�̗E�C����s���������Ƃ����킯�ł��B
�@�n���E�b�h�̑�X�^�[ �g���E�n���N�X�Ƃ̑������Y����Ȃ��v���o�ł��B2016�N9��16���AK.T.����܂މ�X�F�l4�l���_�c�̋������u�܂�v�ň���ł�����A�g���E�n���N�X��s���ׂ̃e�[�u���ɍ������̂ł��B�܂��ɗ\�����ʏo�����BK.T.����̓g���E�n���N�X�̑�t�@���B�x����ԁA�₨��ނɁA�u���Ȃ��̉f��͑S�����Ă��܂��B��ԍD���Ȃ̂́w�O���[���}�C���x�ł��v�Ɖp��Řb�������܂����B���ꂩ��Ƃ������́A�n���N�X��s�Ɖ�X����̃O���[�v�Ɖ����A�a�C�\�X�u�����ɉ˂��鋴�v��u��������ĕ������v�̑升���ƂȂ�Ȃǂ܂��ɓ��đ剃��ƂȂ�܂����B�n���N�X�������B�肵�����̎ʐ^�͗����c�C�b�^�[�ɂ������āA�u�g���E�n���N�X�ƃW���p�j�[�Y�E���b�p���C�v�ƃc�C�[�g����A���E�����삯����܂����B���̑厖���̂���������������̂�K.T.�N�̗E�C����s���������Ƃ����킯�ł��B�@�I�[�f�B�I�E�}�j�A������K.T.����B�ŏI���C���E�A�b�v�́ATHORENS�̃v���C���[TD125mk�U�`Mark Levinson�̃R���g���[���A���vML-1L�`Quad�̃p���[�A���v405�`JBL�̃X�s�[�J�[4343 �Ƃ������h���̑g�ݍ��킹�B���h����I�[�f�B�I�]�_�ƁE����~�����̎w��ɂ����̂ł����B
�@�I�[�f�B�I����i��������A���e�B�[�N�E�J�����ɋ����������ALeica�ANikon�Ȃǂ̖��@��В[�����甃���W�߁A�Ȃ��3000���~�قǂ̎����𓊓������Ƃ��B�Ȃ�Ƃ����Â萫�I
�@�c���\��Y����̎��͂��܂�ɓˑR�ŏՌ��I�Ȃ��̂ł����B����������Ȃ�����������Č��t�ɂ���E�E�E�E�����`�ɍ��`���O�`���Ɂ`�Ǖ�`�⛋�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
�@��ɐ����A�F��Ɍ����A���₩�ŒN������D���ꂽK.T.����B�������ł������ƁA�D���ȉ��y���A�������i�F���B�e���A�y�����߂����Ă���낤�ˁB���C�ł��Ă����B�܂��������܂ŁB
2023.09.10 (��) �n�������̉ĂɃE�N���C�i��z��
 �@�����e�͂Ȃ����A�u�_�y�X�g�ŊJ�Â��ꂽ���E����B���X�g��t�]�����ŁA���{�̏��q�t�B�[���h���Z�ɏ��̋����_���������炵����蓊���̖k���Y�ԁA���q4�~400m�����[�Ń��x���W�̉����������I�����_�E�`�[���̋t�]�����_���ɍv�������{���ȂǁA��ۓI�A�X���[�g�͐�������ǁA�����ł����������̂͏��q���荂���т̃E�N���C�i �����X�����E�}�t�`�N�I��ŁA����p�͂܂�ňꕝ�̊G��̂悤�ȗD�낳�ł����B
�@�����e�͂Ȃ����A�u�_�y�X�g�ŊJ�Â��ꂽ���E����B���X�g��t�]�����ŁA���{�̏��q�t�B�[���h���Z�ɏ��̋����_���������炵����蓊���̖k���Y�ԁA���q4�~400m�����[�Ń��x���W�̉����������I�����_�E�`�[���̋t�]�����_���ɍv�������{���ȂǁA��ۓI�A�X���[�g�͐�������ǁA�����ł����������̂͏��q���荂���т̃E�N���C�i �����X�����E�}�t�`�N�I��ŁA����p�͂܂�ňꕝ�̊G��̂悤�ȗD�낳�ł����B�@��N2���A�v�������Ȃ����V�A�̐N�U�ɁA�}�t�`�N�͑��A���O�ɓ��S�B�Ȍ�A���E�e�n��n��������̌��r��ς�Ō}�������E����̕���B�u���̒��c���̗͂ɂȂ�v�ƐM���Ĕޏ��͒��B���ʁA���X�̋����_���B�c���Ɋ�]�̌�������܂����B����͂���ȃE�N���C�i�ɑ���ꕶ�ł��B
(1)�`���C�R�t�X�L�[�̌����ȁu�����V�A�v
�@�`���C�R�t�X�L�[�Ɍ����� ��2�ԁu�����V�A�v�Ƃ����Ȃ�����܂��B�u�����V�A�v�̓E�N���C�i�̕ʖ��B���V�A�Ƃ͈Ⴄ����ƕ����������Ȃ��獑�������Ƃ������ꂸ�A�����܂Ń��V�A�鍑�̈ꕔ�Ƃ��ē�������Ă��܂����B
�@�`���C�R�t�X�L�[�͖����Z�ރE�N���C�i�ʼnĂ��߂����̂��D���ł����B�����ʼn߂������K���ȋC�������ƂɃE�N���C�i���w��������č�����̂������� ��2�� �n�Z���u�����V�A�v�ł��B������1871�N1���B1879�N�ɑ啝�ȉ������{���Ă��܂��B
�@��1�y�͂ł̓E�N���C�i���w�u��Ȃ郔�H���K������āv���A��4�y�͂ł͓������u�߁v�̃����f�B�[�����Ƃ��Ďg���Ă��܂��B���ɑ�4�y�́u�߁v�̎��̓��\���O�X�L�[�u�W����̊G�v�̏I�ȁu�L�G�t�̑��v�̃R���[���ɒʂ�����̂�����܂��B�ȑz�͂����Ȃׂă`���C�R�t�X�L�[�Ɠ��̝R��Ƒs�킳�ɖ����Ă��܂����A����ɂ͂ǂ������̔߂������Y���Ă��܂��B�n�����������y�Ȃɂ͂��̓y�n�̕��y�I���肪�������̂ł����A�����ɗ��j��z�N��������̂�����܂��B�����f���X�]�[���̌����ȑ�3�ԁu�X�R�b�g�����h�v��������ł��B�`���C�R�t�X�L�[���E�N���C�i�Ƃ����y�n�̗��j�I�߈��ƁA�����������炻�̌�~�肩����ߌ���\�����Ă����̂�������܂���B
(2)�V���X�^�R�[���B�`�̌����ȁu�o�r�E���[���v
 �@�V���X�^�R�[���B�`�Ɍ����� ��13�ԁu�o�r�E���[���v�Ƃ����y�Ȃ�����܂��B�u�o�r�E���[���v�̓L�[�E�ɂ���k�J�̂��ƁB��2�����E���̒��A���V�A�ɐi�U�����h�C�c�R���A�E�N���C�i�̃��_���l���ʋs�E�A���̌�A����Ԃ������V�A�R���A���x�̓i�`�X�E�h�C�c�ɋ��͂����E�N���C�i�l�����Y����ȂǁA10���l����l�X�̖���D�����������܂킵���ꏊ�ł����B�E�N���C�i�͓ƃ\��̐��ƂȂ�o���̓ʼn�ɎN���ꂽ�ߌ��̓y�n�������̂ł��B
�@�V���X�^�R�[���B�`�Ɍ����� ��13�ԁu�o�r�E���[���v�Ƃ����y�Ȃ�����܂��B�u�o�r�E���[���v�̓L�[�E�ɂ���k�J�̂��ƁB��2�����E���̒��A���V�A�ɐi�U�����h�C�c�R���A�E�N���C�i�̃��_���l���ʋs�E�A���̌�A����Ԃ������V�A�R���A���x�̓i�`�X�E�h�C�c�ɋ��͂����E�N���C�i�l�����Y����ȂǁA10���l����l�X�̖���D�����������܂킵���ꏊ�ł����B�E�N���C�i�͓ƃ\��̐��ƂȂ�o���̓ʼn�ɎN���ꂽ�ߌ��̓y�n�������̂ł��B�@�����ȑ�13�ԁu�o�r�E���[���v��1962�N�̍�i�B�O�N�A�Ⴋ���l�G�t�Q�j�[�E�G�t�g�D�V�F���R�̔����_����`�ᔻ�̎��u�o�r�E���[���v�Ɋ��������V���X�^�R�[���B�`�́A���̎��Ɋ�Â�����������ȁB���̌�A����W������5�y�͂���Ȃ�����Ȃ����������܂����B���̓X�^�[�����̎���9�N�B�V���Ȍ��͎҃t���V���t�́u������v�Ƃ����镶�������ł��o���Ă��܂����B�����ȁu�o�r�E���[���v�a���ɂ͂���Ȕw�i���������̂ł��B�Ƃ͂����K�������S�ɊO�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A����������̉�����]�V�Ȃ�����Ă��܂��B
�@�Ґ��̓o�X�Ə��ƒj�������ƃI�[�P�X�g���B�S�̂ɉA�T�ȋ������[�����钆�A���V�A�̕��̗��j�A���͂ւ̔��R�Ƃ��Ẵ��[���A�A�����ւ̎^���A���|�̕ω��ƈӖ��A�^�̏o���Ƃ́H �Ȃǂ��₢�������܂��B�ł́A�^�C�g���ɂȂ�����1�y�́u�o�r�E���[���v�̉̎��̗v������L�B
�o�r�E���[���ɋL�O��͂Ȃ��@�肽�R�͍r�ꂭ�ꂽ���̂悤���@���l�G�t�g�D�V�F���R�́A���_���l�Ƃ��������ŃX�p�C�̌��^���������l�߂ɏ����ꂽ�t�����X�̌R�l�h���t���X��u�A���l�̓��L�v�̃A���l�E�t�����N�ɂȂ肫���āA�ނ�̔ߌ���搂��Ă��܂��B�����āA�i�`�X�E�h�C�c�̃��_���l�s�E�ƕ����āA�u�|�O�����v�Ƃ������t�ɏے�����郍�V�A�̔����_����`�ɂ����X�����܂��B�ŏ��Ɂu���̓��_���l�v�ƌ����Ȃ���u���̓��V�A�l�v�ƌ����Č��Ԃ̂͂��̌���ł��傤�B�u�C���^�[�i�V���i���v�Ƃ̓��V�A�v����1917�N����1944�܂ʼn̂�ꂽ�\���B�G�g�A�M�̍��́B�����ɂ��\�A�Ƃ������Ƃւ̔���Ɣᔻ���������Ă��܂��B
���܂킽���͎v���@���̓��_���l���Ɓ@ �h���t���X ���ꂪ�킽���ł���悤�ȋC������
�킽���͓S�i�q�̒��ɂ���@�킽����㩂ɂ͂܂���
�킽���͎v���@�킽���͂��̃A���l�E�t�����N���Ɓ@�l���̎�t�̂悤�� �����Ƃ���A���l
�o�r�E���[���ɂ��߂���̑��@�ٔ������Ȃ��狺�����悤�Ɍ����낷�X
�����ł݂͂Ȃ������̋��т�������
�킽���͂����ŏe�E���ꂽ�V�l�̂ЂƂ肾�@�킽���͂����ŏe�E���ꂽ�q���̂ЂƂ肾
�u�C���^�[�i�V���i���v��Ƃǂ낯
��n����Ō�̔����_����`�҂��i���ɑ��苎����Ƃ���
�킽���̌��Ƀ��_���̌��͗���Ă��Ȃ��@����ǂ킽���̓��_���l�̂��Ƃ����܂��
�r�ꂭ�ꂽ�G�ӂ� ���ׂĂ̔����_����`�҂ǂ����
�����炱�� �킽���͂܂��Ƃ̃��V�A�l�Ȃ̂�
�@���������ꂽ����ɂ͑��݂��Ȃ������L�O��́A���̌㎟�X�Ɍ�������܂����B�i�`�X�E�h�C�c�ɎE�Q���ꂽ�\���B�G�g�s���ƕߗ��̋L�O��(1976���J)�A�s�E���ꂽ���_���l���ԗ삷��L�O��i1991���J�j�A�\���B�G�g�R�ɂ���ĎE�Q���ꂽ�E�N���C�i��������^���҂��ԗ삷��̏\���ˁi1992���݁j�A�o�r�E���[���ŎE�Q���ꂽ�q���������ԗ삷��L�O��i2001���J�j ���X�B���V�A�͂��̋ߕӂɂ��e�͂Ȃ��U�����d�|���Ă��܂��B�������n�߁A�v�[�`���E���V�A�́A8��23���܂łɁA�E�N���C�i�ɂ�����284�̕�����Y�ɑ�����^���A������j���͑����Ƃ݂��Ă��܂��B�����������̒j�͂ǂ̂悤�Ȑ_�o�̎�����Ȃ̂ł��傤�B
(3)�E�N���C�i�̉��y��
�@�E�N���C�i�͑����̉��y�Ƃ�y�o���Ă��܂��B���@�C�I���j�X�g�ł́A�~�b�V���E�G���}���A�i�^���E�~���V�e�C���A�_���B�b�h�E�I�C�X�g���t�A���I�j�[�h�E�R�[�K���A�A�C�U�b�N�E�X�^�[���B�s�A�j�X�g�ł́A�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�A�X���@�g�X���t�E���q�e���A�G�~�[���E�M�����X�A�V���[���E�`�F���J�X�L�[�Ȃ��B�X���閼�肪����A�˂Ă��܂��B
�@�ނ��l��l���Љ��ɂ͂ƂĂ����ʂ�����܂���B�����ō���͔ނ炪�c�����삵���^���̒������_�����グ�܂��B����́A�i�^���E�~���V�e�C���̃��@�C�I�����A�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�̃s�A�m�ɂ��u�u���[���X��ȁF���@�C�I�����E�\�i�^ ��3�� �j�Z�� ��i108�v�A1950�N�j���[���[�NRCA�X�^�W�I�ł̘^���ł��B���t�͌����̈��ɐs���܂��B���}���e�B�V�Y������z�����B�b�c�̃s�A�m�B��M���߂Ȃ���m�I�R��Ŋy�z����߂�~���V�e�C���̃��@�C�I�����B�u���[���X�́A���}���h���@�C�I�����E�\�i�^�̖{�����A����قǂ܂łɝP�肾�������t�͑��ɂȂ��A����ɂ͑u�₩�ȗD�������Y���܂��B������A���ꂱ�����E�N���C�i�̉��y�Ƃ̓����Ȃ̂�������܂���B
 �@�~���V�e�C���i1904-1992�j�ƃz�����B�b�c�i1903-1989�j�́A�X�^�[�����E�\�A�̈�����邽�߁A1925�N12���A������ă\���B�G�g��E�o�B�܂��h�C�c�ɓ���������l�́A�Ȍ�A�p���ɒ����؍݁A1933�N�ɂ̓j���[���[�N�ɍs�����܂��B�����̍s���̓~���V�e�C���̒����u���V�A���琼���ցv�ɏ�����Ă��āA�����̐��E��A���y����Ɏ��悤�ɂ킩�邱��͋����s���Ȃ���z�^�ł��B�ނ͂��̒����̒��Łu�z�����B�b�c�Ǝ���70�N�ȏ�ɂ킽���Ă̗F�l�ŁA�����炭���̒N�����ނ̂��Ƃ�m���Ă���Ǝv���v�Əq�ׂĂ��܂��B�����A�ނ�͒��N�A��Y��������̗F�Ȃ̂ł��B����ɔނ̕M�́A�X�^�[�����ƃ\���B�G�g�̑̐��ւ̔ᔻ�ɋy�т܂��B
�@�~���V�e�C���i1904-1992�j�ƃz�����B�b�c�i1903-1989�j�́A�X�^�[�����E�\�A�̈�����邽�߁A1925�N12���A������ă\���B�G�g��E�o�B�܂��h�C�c�ɓ���������l�́A�Ȍ�A�p���ɒ����؍݁A1933�N�ɂ̓j���[���[�N�ɍs�����܂��B�����̍s���̓~���V�e�C���̒����u���V�A���琼���ցv�ɏ�����Ă��āA�����̐��E��A���y����Ɏ��悤�ɂ킩�邱��͋����s���Ȃ���z�^�ł��B�ނ͂��̒����̒��Łu�z�����B�b�c�Ǝ���70�N�ȏ�ɂ킽���Ă̗F�l�ŁA�����炭���̒N�����ނ̂��Ƃ�m���Ă���Ǝv���v�Əq�ׂĂ��܂��B�����A�ނ�͒��N�A��Y��������̗F�Ȃ̂ł��B����ɔނ̕M�́A�X�^�[�����ƃ\���B�G�g�̑̐��ւ̔ᔻ�ɋy�т܂��B
�����A�X�^�[������`�̐��͂��܂�ɂ��}���I�ŁA����ɔ�ׂ�q�g���[�ł����������ƃ��x�����Ǝv����B���̍��̋��Y��`�҂̃��[�_�[�̓��V�A�̃A���@���M�����h�ƃ��V�A�̑��ӂ�j���B�����Č��o�����l�X�����Y���Ă��܂����B���̊ԁA���l�̃N���������̃{�X�����݂������낤���H�����������l�ł���B�����Ă����̂ق�̈ꈬ��̐l�Ԃ��A�l�ȏ�̐l�X�̐l����j�łɒǂ����̂��B����Ȃ��Ƃ������A�ǂ̂悤�ȃV�X�e���������Đ������������̂ł͂Ȃ��B�@�E�N���C�i�����̒������B�E�ɂ̓����B�E���y�@������܂��B�n����1853�N�B���[�c�@���g�̖��q�N�T���@�[�E���[�c�@���g���ݗ��Ɋւ���Ă��܂��B���݁A��̒��A�����̉��y�Ƃ̗��������̕��a�Ɩ����̐������āA���X���r�ɗ��ł��܂��B
���[�����X�L�[�哝�̂ɒ`����͐^�Ă̖�̖��H��
 �q�[�@�[�����X�L�[�哝�̓a
�q�[�@�[�����X�L�[�哝�̓a�@�����C�ł��傤���B���̊��܂킵���v�[�`���E���V�A�̐N�U���瑁��N�����o�߂��܂����B�푈�̏I���͖������ʂ��܂���B���́A�c���j�ςŐN���𐳓�������v�[�`���̑�`�Ȃ���̂́A���X�ɁA�P�ǂȂ郍�V�A�������炻���ۂ�������A���͂̍������������~�낳��A�K�R�I�ɐ푈�͏I��� �ƍ����������Ă��܂����B�Ƃ��낪�����ς�炸�v�[�`���̎x�����͍����A�푈�x������70�`80�����߂Ă���ƕ����܂��B����͈�̂ǂ��������Ƃ��B���V�A�����āA����Ȑl�����Ȃ̂��B
�@�j���[�X������A�s��ɕ��͈��Ă���B�P�ނ����}�N�h�i���h��X�^�[�o�b�N�X�͖��O��ς��Ɨe���p�����V�A�l���o�c�A�̂ɑ����Ĕɐ����Ă���炵���B���{��[���b�p���P�ނ��������Ԏs��́A����������đ����Ċ�����悵�Ă���B�A�t���J��UAE���烍�V�A�ɗ����u���v�̃��[�g�͌o�ς̖��j�̖������ʂ����Ă���B���݂��_�Ƃ��D���̂悤���B���ƂقǍ��l�Ɍo�ϐ��ق͂قƂ�Ǘ����Ă��Ȃ��B
�@���V�A�l�̐S�̉���ɂ́A���N�̈�������A�u�������̂ɂ͊������v���_���������Ă���Ƃ����Ă��܂��B�̐��ᔻ������Ζ��E�����B�Ȃ�Ζق��Ă������������B�H�ׂ�Ɏ�������20�`30�N�O�̃S���o�`���t�`�G���c�B��������A���̕�������ۂǃ}�V���B�E�N���C�i�Ő푈������Ă��Ă����������ɉ̕����~�肩����킯����Ȃ��B�����āA���v�[�`���h�̐l�X�͑��X�ɍ����̂Ăč��O���S�B������c�����l�����̓v�[�`���m��h�������B���ꂶ��x�����͉�����Ȃ��B���N3���̑哝�̑I�����v�[�`�������͔ۂ߂Ȃ��B�����łȂ��Ă��I�����ʂ̝s���͂���̕������B���ʁA�ނ͂��n�t�����Ƃ��āA�I�X�Ɛ푈�𑱂���ł��傤�B
�@���V�A����V�R�K�X���~�߂�ꂽ�h�C�c�́A�o�ς�����A��2�����E���O�ɝ������ꂽ�u���B�̕a�l�v�ƌĂ�Ă���Ƃ��B�A�����J���ߓx�ȃE�N���C�i�x���Ƀo�C�f���哝�̂ւ̔ᔻ�����o���Ă���悤�ł��B����͓��������ȑΉ��������c�P�ł͂���܂����B
�@�M���ɖڂ�]����ƁA���Ȃ��͐���A���틟�^���ɕq�r�������L�\�ȍ��h�ȃ��Y�j�R�E������C���܂����B���R�̈�ɁA�n���R���ψ���ł̕���Ə��Ɋւ���d�G���s�ɂ���Ƃ����Ă��܂��B���ꂷ�Ȃ킿�A�����̉}��C���̕\��ł�����܂��ˁB����������푈�ɃE�N���C�i���������Č��C�������Ă���̂ł͂���܂��B
�@�����ŁA�[�����X�L�[�哝�̂ɂ��肢�ł��B�푈�͓��X�s��̐l�X�̖���D���܂��B9��6���A���V�A�́A���G����h�l�c�N�B�R�X�`�F���X�J�̏��X�X�Ƀ~�T�C������������17�l�̖���D���܂����B���ʂɕ�炷��ʂ̎s���ł��B�[�����X�L�[�哝�́A�������ł������ɐ푈���~�߂Ă��������B�푈���~�߂�Ƃ������Ƃ͐푈���~�߂Ȃ��v�[�`���ɏ�������Ƃ������ƁB���s�s�ɂ܂�v�[�`�����͂����ƂɂȂ�B��k����Ȃ��ƌ�����ł��傤�ˁB�ł��A���܈�ԑ�Ȃ��Ƃ͐푈���~�߂邱�ƁB�߂��Ȃ��l�X�̖����~�����ƁB���ꂪ�ł���̂́A�[�����X�L�[�哝�́A���Ȃ��������Ȃ��̂ł��B
�@�v�[�`���́A�M���ɐN�U������N2���A�ꌂ�ł��Ȃ��͍~������Ɗy�ώ����Ă����B�Ƃ��낪���Ȃ��͌����ɍ����܂Ƃߏグ�A���E�𖡕��ɂ��Ă����܂Ŋ撣���Ă����B���E�͊��ɂ��Ȃ��̏�����F�߂Ă��܂��B�����Ő푈���~�߂Ă��A�̎^����l�͂���ǁA����l�͂ǂ��ɂ����܂���B������A�ǂ����푈���~�߂Ă��������B
�@���̉R���v�[�`���Ɖ����ǂ���茈�߂Ē�킷������̂� �Ƃ��Ȃ��͌�����ł��傤�B�Ȃ�A���̏����������Ă��������B
�@��͍����̐������ł��B�����̓[�����X�L�[����A�������Ă��������B�g���ׂČ��ʂ�h�͎̂ĂāA���x���V�A���N�������n��A�h�l�c�N�A���K���X�N�A�w���\���A�U�|���W�G�B�̈ꕔ���������Ă��̂ł��B���ăC�M���X���P�x�b�N�@�Ŏ������J�i�_�ɂ�����t�����X�n�J�g���b�N���k�ւ̑Ή����Q�l�ɂ��Ă������������B���V�A�������I�ɕ��������n��ɐe���V�A�h�̐l������̂Ȃ獑�����̌������Ɉڂ��Ă��炦�����B
�@��ڂ͒���̈��S�ۏ�ł��B�v�[�`������x�ƃE�N���C�i�Ɏ���o���Ȃ�����ɂ͂ǂ�����������B�E�N���C�i��NATO�����B����̓v�[�`�������ۂ��܂��B�Ȃ�A1994�N�̃u�_�y�X�g�o���������o������ǂ��ł��傤�B�u�_�y�X�g�o���Ƃ́A�j����������E�N���C�i�ɑ��ăA�����J�A���V�A�A�C�M���X�̊j�ۗL3���������S�ۏ�����Ƃ������́B���_����́A���V�A���A�N���~�A�N�U����2014�N�ɔj�����Ă��܂��B�������Ȃ���A���̔N�A�āE�p�E�E�N���C�i�̎O���́u�u�_�y�X�g�o���Ɋւ��鋤�������v���Ă���B����������o�������B�����ɏW�c�I���q�����܂ޕK�v�������U����B�v�[�`���ɂ́u����NATO�����͌�����v�ƌ��������B�܂����ĉ��������Ƃ���ŁA�R���v�[�`���ɕ����������؍����͂Ȃ��ł��傤�B
�@�[�����X�L�[�哝�́A2019�N�A���Ȃ����哝�̂ɏA�C�������̌��t���v���o���Ă��������B���Ȃ��͂��������u���ꂩ���A���̓E�N���C�i�����������������ɂ��ނ悤�S�͂�s�����܂��v�ƁB�ǂ�������ڎw���Ă��������B����̂͂킩���Ă��܂��B�ł��A���Ȃ��������ΕK�����͓����B���͂����M���Ă��܂��B
���Q�l������
�f���̐��I�o�^�t���C�E�G�t�F�N�g�u�v�[�`���ƃ[�����X�L�[�v�iNHK-BSP 8.23 O.A.�j
���V�A���琼���ց`�~���V�e�C����z�^�i�t�H�Ёj
CD�`���C�R�t�X�L�[��ȁF������ ��2�ԁu�����V�A�v
�@�@�@�@�@�A���h���E�v�����B���w���F�����h�������y�c�i1965�^���j
CD�V���X�^�R�[���B�`��ȁF������ ��13�ԁu�o�r�E���[���v
�@�@�@�@�@�}���X�E�����\���X�w���F�o�C�G�������������y�c�i2005�j
CD�u���[���X��ȁF���@�C�I�����E�\�i�^��3��
�@�@�@�@�@�i�^���E�~���V�e�C���iVn�j �E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�iP�j�i1950�j
2023.08.16 (��) ��叫�E���R�Y�O�́u���y�݂͂�ȂƂ������v�`�������̊y�ȃA�E���E�J�E���E�g
(1) ���R�Y�O�̓X�[�p�[�X�^�[ �@����A�e���r�ō�N�̑�A���ŃR���T�[�g������E�ނ������R�Y�O����̓��Ԃ�����Ă��܂����B�肵�āu�P����������R�Y�O�v�B�����V���ł́u���`�l���̑��蕨 ���R�Y�O�v���A�ځB�̂ɉf��Ɍ|�\�E�̉�������ݑ�����65�N�B�u��叫�V���[�Y�v�����܂���A�ނ̃q�b�g�Ȃ��܂���A�̂��܂������A�܂��ɉ䂪����̑�X�^�[���R�Y�O�B�����e���r�A�V������A�N�����m�I�ɋ����[���G�s�\�[�h���ǂ����B
�@����A�e���r�ō�N�̑�A���ŃR���T�[�g������E�ނ������R�Y�O����̓��Ԃ�����Ă��܂����B�肵�āu�P����������R�Y�O�v�B�����V���ł́u���`�l���̑��蕨 ���R�Y�O�v���A�ځB�̂ɉf��Ɍ|�\�E�̉�������ݑ�����65�N�B�u��叫�V���[�Y�v�����܂���A�ނ̃q�b�g�Ȃ��܂���A�̂��܂������A�܂��ɉ䂪����̑�X�^�[���R�Y�O�B�����e���r�A�V������A�N�����m�I�ɋ����[���G�s�\�[�h���ǂ����B
�܂����w������������̂��ƁB�����̎O���ƂȂ肩��s�A�m�̉����������Ă���B�w�Z�A��A���Ɏ������Η��Ăĕ����Ă�����A�O���l���o�Ă��āu���ɓ����ĕ����Ȃ����v�ƌ����B�����Ȃ�u�o�[���I�v���Ă������s�A�m������o�����B���Ƃł킩�������ǁA�V���p���́u�p�Y�|���l�[�Y�v�������B���̂������������ĂˁB�����ɋA���Ă��₶�i�㌴���j�Ɂu�������Ńs�A�m�������Ă��炢�����v���Ęb������A�u���̐l�͂Ȃ��A���I�j�[�h�E�N���C�c�@�[�Ƃ����L���ȃs�A�j�X�g���B���O�Ȃ������Ă��炦��悤�Ȑl����Ȃ��v�Ƃ��炭�{��ꂽ�B�ł����ǃN���C�c�@�[����̂���q����ɋ����Ă��炤�悤�ɂȂ����B�@�Ȃ�Ɖ��R����̎O���ƂȂ肪���̃��I�j�[�h�E�N���C�c�@�[�̂�������Ƃ́I�X�[�p�[�X�^�[�͂Ȃ�ׂ����ĂȂ�B����Ȑ��̉��ɐ��܂����̂Ȃ�ł��ˁB
�@���I�j�[�h�E�N���C�c�@�[�i1884-1953�j�́A���킪�����y�E�ɑ���Ȍ��т��c�����s�A�j�X�g����ȉƁB1933�N�A�x���������y��w�̋����Ƃ��ē�x�ڂ̗����̐܁A�߉q�G���̏����������āA�i�`�X�䓪�}�ȃh�C�c�ɋA�����Ȃ������B�ނ̓h�C�c�n���_���l�������̂ł��B�ݓ�����20�N�ԂŁA�ނ̋������s�A�j�X�g�́A�c�����q�A���䖀��q�A�t�W�q�w�~���O�A����H�q�A��ȉƂł͍��c�O�Y�A���H�Y�Ȃ��B�X�����ނ�����A�˂Ă��܂��B�����āA����q�H�ɂ͒e���삱�Ɖ��R�Y�O�������I
�@��ȉƁE�e����ɂ́u�N�Ƃ��܂ł��v1965�A�u���l��v1966�A�u���������B�[�i�X�v1970�A�u�C ���̈��v1976�A�u�ڂ��̖��Ɂv1976�A�u�T���C�v1992�E�E�E�E�E���X��������Ȃ��قǂ̃q�b�g�Ȃ�����܂����A�N���C�c�@�[�̗�������ރN���V�b�N�̍�i�������ł��B�u�s�A�m���t�ȃj�Z��K 213�v�B���̐́A���̋Ȃ�TV���f���ꂽ���Ƃ��������Ƃ��BK213�́uK�v�͉��R��K�ł��胂�[�c�@���g�̃P�b�w���ԍ��ɂ��₩���Ă���B���R����̓��[�c�@���g����̂ق��D���ŁA���h����l���ɃA���x���g�E�A�C���V���^�C����������̂��A�ނ́u���Ƃ̓��[�c�@���g���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��v�Ƃ��������ɂ����̂��Ƃ��B�x�[�g�[���F������Ȃ��ă��[�c�@���g �Ƃ����̂��c�{�ɂ͂܂����悤�ł��B
�@����Ȃ킯�ŁA�ԑg�ł͉��R����̋��t�Ȃƃ��[�c�@���g�̉��Ԃ��̃s�A�m���t�Ȃ����t����܂����B���y�w�҃Q�X�g�Ƃ��ă��[�c�@���g�̌��АΈ�G�搶���o�����Ă��܂��B
�@�Έ�搶�Ɖ��R����A�y���Ń��[�c�@���g�k�`�ɉԂ��炢�������ł����A���̒��ŁA���R����A���������������ł��B�u�˂��Έ䂳��A���̃s�A�m���t�Ȃ��Ȃ��Ȃ��ł��傤�B�ł��A����ς胂�[�c�@���g�͐����ˁB���ȂƂĂ��G��Ȃ���v�B����ɂ͐Έ�搶�A�u���Ή��R�Y�O�A���[�c�@���g�Ɣ�ׂ��Ⴄ����啨���ˁv�ƃA���O�����邵���Ȃ����������ł��B�X�[�p�[�X�^�[�͌������Ƃ��Ⴄ�I
�@���Ƌ����[�������̂́A�u���y�͐^���Ă������v�Ə�X����Ă������ƁB����ȕ��ɁB
�タ���́u��������ĕ������v���o�Ă����Ƃ��A���A�r�b�N�������ˁB���̋Ȃ́A�x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȁu�c��v�ƈꏏ�����ċC�Â��Ă��B�u�W���[�� �W���W���W���W�� �W�����W�����W�����W�����v�`�u�������ނ����� ���[�邱�������v�B���������B���y���Ă��������̂���ȂƎv������B ���́u�N�Ƃ��܂ł��v�������B����A�W���Y�́u���邢�\�ʂ�Łv�����Ȃ�B�uGrab your coat and get your hat�v�`�u�ӂ�����@�䂤��݂��E�E�E�E�E�v�@�Ȃ��A�������肾��B���y���Ă̂͒N�����݂�Ȃ܂˂Ă��āA����łȂ����Ă����B�Ⴄ�����H�@�������A�X�[�p�[�X�^�[�A�킪�ł����B�Ƃ���ʼn��R����A�ʂȂƂ���ł���ȃG�s�\�[�h������Ă��܂����B�H���u�����X�^�[�ɂ��Ă��ꂽ�͉̂f��w��叫�x�V���[�Y�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���B�ł�����A�ŏ��́w��U�߁x���������B�w��w�̎�U�߁x�w�G���L�̎�U�߁x����A����ȂɃq�b�g���Ȃ�������Ȃ����ȁB�w��叫�x�Ń��J�b�^�Ǝv����v
�@���͂͂���Ȏ�叫�ɂȂ肫���Ę_�l����u��叫�I�������̊y�ȏW�v���ǂ����B
(2) ��叫����� �������̊y�ȃA�E���E�J�E���E�g
�@�̗w�E�Ɂu�����̉��`�v�Ƃ����̂������āA����́�~���V�h�i�V�j�E�E�E�Ȃ�ȁB�������ǂ�T���T�[�e�u�c�B�S�C�l�����C�[���v�̖`���̃����f�B�[������N�ł��킩���ˁB������g�����̂͂��������邯�ǁA���������Ԃ̂͏�c�����́u�߂����F��ˁv���ȁB�g�ɂ��ނ܂��̂Ђ��h �̂Ƃ���ˁB���Ƃ́A���z���́u�S���悤�v�g���݂����̂�Â�Ɂh�B�ΐ�Z���u�����̔G�ꂽ���v�g�킽���̂��݂��h�B�T�U���E�I�[���X�^�[�Y�u�`���R�̊C�ݕ���v�g��������Ł@�킩���ӂ��肪�h�B������r�u���l���G���X�p�v�g�ӂ����Ȃ����́h�B�|���܂��u�w�v�g�݂��ڂ��̂���h���X�ق��ɂ����������B���̋Ȃł́u���̃A�}�����A�v�������g�䂫�̂ӂ�݂����݂Ɂh �ȁB
�@���ƁA�^�������������ĉ]���Ă��ˁB�u�w�߂����F��ˁx�����ǂ��A����T���^�i�́u���D�̃��[���b�p�v����v���āB�Ȃ�قǁA���̒ʂ肾�B�m�y�ł́u���������v�̃e�[�}��V�����\���u�p���̋�̉��v�B���ꂩ��u�R�[�q�[�E�����o�v���ȁB
�@���{�̗��s�̂ł́A�܂��́u���Z�O�N���v�g�������䂤�Ђ��h���ȁB���Ƒk���āA���c���m�q�u�ԍ�̖�͍X���āv�`��Y�u���T���w�v�`�D��Ύq�u�N�̖��́v�`���{�֕v�u�����Ԃ̍炭���v�`�W�J�̂�q������́u�ʂ�̃u���[�X�v�`������Y�u�r��̌��v�`�F�{�����w�u�ܖ̎q��S�v�ɍs�����B�u�����̉��`�v�́A�a�m���f�܂��ɃO���[�o���ȃq�b�g���`�ȂB
�@�����͉��̑�D���ȃ��[�c�@���g�B�u�t���[�g�ƃn�[�v�̂��߂̋��t��K299�v��1�y�͂̑�1��肪�A�������肻�̂܂܃u���b�N�i�[�́u�����ȑ�7�ԁv��1�y�͂ɏo�Ă���i1978�N�^���̃n�C�e�B���N�w���F���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�Ȃ�J�n����6�F30������̂Ƃ���j�B
�@���X�g�́u���̖��v��3�Ԃ̓V���[�x���g�́u������D.899��3�� �σg�����v�ɐ����ʂ��B�܂�ŌZ��݂����ȋȂ���B�����V���[�x���g�̌����� ��8�� �n���� �u�O���[�g�vD.944 ��1�y�͂̑�1���͑���c��w�����́u���ɂ̋�v�i�Ê֗T����ȁj�ɂ��̂܂ܓ]�p����Ă���B�܂��A����c�̍Z�́u�s�̐��k�v�̓C�G�[����w�̊w���̂ƃ\�b�N���Ȃ̂��L���Șb���ȁB
 �@�V���[�x���g�Ƃ����Ή̋ȏW�u�����̉́v�́u���̎g���v���A�Ȃ�ƃg�j�[�E�U�C���[�剉1959�N�̉f��u����͏�����v�̎��̂ɂ������蓊�e����Ă���B�u���̎g���v�̍Ō�̈�� Drum heg ich sie auch so true an der Brust�i������l�� ���炵�����ʂ�M�����āj�Ɓu����͏�����v�́g�����������͂������Ƃ����肻���ȋC�������h�̓h���s�V���������B��Ȃ̃t�����c�E�O���[�e�i1908-1982�j�̓h�C�c�l������A�ނ̑̓��ɃV���[�x���g�̐����������Ă����낤�B�ނ̑�\��ɂ́u�^�钆�̃u���[�X�v������B�g�j�[�E�U�C���[�Ƃ����A���̉f��u�A���v�X�̎�叫�v�ɒʍs�l���ɏo�����Ă�����Ă�B�E�B�[���E���P�̂Ƃ����R�������B�ɂ���������m�F���Ă݂Ă�B
�@�V���[�x���g�Ƃ����Ή̋ȏW�u�����̉́v�́u���̎g���v���A�Ȃ�ƃg�j�[�E�U�C���[�剉1959�N�̉f��u����͏�����v�̎��̂ɂ������蓊�e����Ă���B�u���̎g���v�̍Ō�̈�� Drum heg ich sie auch so true an der Brust�i������l�� ���炵�����ʂ�M�����āj�Ɓu����͏�����v�́g�����������͂������Ƃ����肻���ȋC�������h�̓h���s�V���������B��Ȃ̃t�����c�E�O���[�e�i1908-1982�j�̓h�C�c�l������A�ނ̑̓��ɃV���[�x���g�̐����������Ă����낤�B�ނ̑�\��ɂ́u�^�钆�̃u���[�X�v������B�g�j�[�E�U�C���[�Ƃ����A���̉f��u�A���v�X�̎�叫�v�ɒʍs�l���ɏo�����Ă�����Ă�B�E�B�[���E���P�̂Ƃ����R�������B�ɂ���������m�F���Ă݂Ă�B�@���ƃT���E�T�[���X�́u�s�A�m���t�ȑ�2�ԁv��2�y�͂�B�����B�����u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v����B�W�����E�E�B���A���Y���p�N�������ǂ����͂킩��Ȃ����ǂˁB���������Ă�T���E�T�[���X�̓��[�r���V���^�C���i�s�A�m�j��RCA�Ղ����ǁA���̉����ƂĂ��Ȃ������B1958�N�̘^�����������65�N�O�ɂȂ邯�ǃr�b�N�����邭�炢�̐��X�������B�ď�͂悭������B���̃s�A�m�͈ꕞ�̐����܂��ˁB
 �@�o�[���X�^�C���̃~���[�W�J���u�E�F�X�g�T�C�h����v�ɂ̓��[�O�i�[����̓]�p������ˁB����̃��X�g�ɗ����u�T���z�G�A�v�̒��Ɉ�ۓI�ȃ����f�B�[������o���B����u�w�v�́u���̋~�ς̓��@�v��h�[�V�h���[�h�V�E�E�E���B�Η������̃O���[�v���u�����݂̘A����f����ɂ͈��ɂ��~�ς����Ȃ��v�Ƃ���o�[���X�^�C���̃��b�Z�[�W�����߂��Ă���B����̓p�N������Ȃ��ăI�}�[�W������ ���͎v���B
�@�o�[���X�^�C���̃~���[�W�J���u�E�F�X�g�T�C�h����v�ɂ̓��[�O�i�[����̓]�p������ˁB����̃��X�g�ɗ����u�T���z�G�A�v�̒��Ɉ�ۓI�ȃ����f�B�[������o���B����u�w�v�́u���̋~�ς̓��@�v��h�[�V�h���[�h�V�E�E�E���B�Η������̃O���[�v���u�����݂̘A����f����ɂ͈��ɂ��~�ς����Ȃ��v�Ƃ���o�[���X�^�C���̃��b�Z�[�W�����߂��Ă���B����̓p�N������Ȃ��ăI�}�[�W������ ���͎v���B�@�u�E�F�X�g�T�C�h����v�́u�T���z�G�A�v�̒��ɂ͂������ۓI�ȃ����f�B�[�������B�o�ߋ�I�ȁ�V�[�h���~�t�@�\�[�~�h �Ȃ��ǁA������v�Ώ����u���̒J�̃i�E�V�J�v�Ŏg���Ă���B���̐l�A�~�j�}���E�~���[�W�b�N�̐M��҂�����A�����炭�l�̐S�ɐH������悤�ȃ����f�B�[�������Ȃ��낤�ˁB�����炻��Ȃ̂��~�������ؗp���邵���Ȃ��B�����āA�W�u���f��̖����̂́u�Ђ������_�v(��������)��u�₳�����ɕ�܂ꂽ�Ȃ�v�i�����̑�}�ցj�Ń��[�~������B�ŁA�u���̒J�̃i�E�V�J�v��you-tube�̃I�[�P�X�g���ŁuNausica of the Valley of the Wind�v3�F02�`3�F18������Ŋm�F���Ă݂āB����̓p�N�������Ă킩��Ǝv����B
 �@���]����TBS�̃h���}�uVIVANT�v�̉��y�͐�Z������B��Z����Ƃ����A�n������A�ނ̃f�r���[�E�A���o���u�s�[�h�����g�E�p�[�N�v�Ƃ���ɑ����u226 Suite�v�̃v�����[�V�����̑ł����킹�œc�����z�̂���Ɏf�������Ƃ�����B����30�N�ȏ�O�̘b���B���ԂŖ�����Ƙb���Ă����Ƃ��A��K���烔�@�C�I�����̒��ׂ��������Ă����B���Ԃ�o�b�n�̖����t�������Ǝv�����ǁA����͂���͔����������������B������~��Łu�Z�������b�ɂȂ��Ă��܂��v�ƌ��ꂽ�̂����@�C�I���j�X�g�̖��^���q�������B�������̓��A�҂��ɑ҂����X�g���f�B���@���E�X���͂������Č����Ă��ˁB
�@���]����TBS�̃h���}�uVIVANT�v�̉��y�͐�Z������B��Z����Ƃ����A�n������A�ނ̃f�r���[�E�A���o���u�s�[�h�����g�E�p�[�N�v�Ƃ���ɑ����u226 Suite�v�̃v�����[�V�����̑ł����킹�œc�����z�̂���Ɏf�������Ƃ�����B����30�N�ȏ�O�̘b���B���ԂŖ�����Ƙb���Ă����Ƃ��A��K���烔�@�C�I�����̒��ׂ��������Ă����B���Ԃ�o�b�n�̖����t�������Ǝv�����ǁA����͂���͔����������������B������~��Łu�Z�������b�ɂȂ��Ă��܂��v�ƌ��ꂽ�̂����@�C�I���j�X�g�̖��^���q�������B�������̓��A�҂��ɑ҂����X�g���f�B���@���E�X���͂������Č����Ă��ˁB�@������ɂ͓��{��Ƃ̌Z��������B�ȑO�e���r�Ō������A�u����R�̉��G�v��`���p�͊����I�������B44�ʂ̉��ɏd�͂ɔC���Ėn���悹�Ă䂭�B�F���̐ۗ��Ƌ�C�̏@���ς���̂ƂȂ��ĂƂĂ��Ȃ��|�p��i���o���オ���Ă������B���E���E�^���q�̐�Z�O�Z��i���j�A���������ǂ��DNA�������Ă���낤�ˁB
�@����͂����ƁA�uVIVANT�v�Ń����S���̍����ɗ���閾����̉��y�A�����̓G���K�[�u�Е����X�v�� �Ɗ�����u�Ԃ�����ˁB
�@�ł܂��ANHK���h���u���܂�v�̉��y�S���͈����C���Y�Ƃ����l�B���̉��y�A�h���}�̒_�ŗ����̂̓��t�}�j�m�t���̂��́B�܂��������ǁA����������ƍH�v���ق�����ȁB
�@�Ƃ܂��A���낢�돑���Ă��܂������A����ȕ��Ɏ������̊y�Ȃ͍J�Ɉ��Ă���܂��B������12���̑g�ݍ��킹�Ȃ��玗�ʂ��Ă����R�ł��傤�B�ڂ�����𗧂Ă��ɂ���ȂȂ�����y���ނ̂��ꋻ�ł��傤���B�������̊y�Ȃ͂܂��܂�����܂��B�����͂܂����̓����u�N�����m�v�ŁB�{���͂��������肪�Ƃ��B��叫�ł����B
���Q�l������
BS�t�W�u�P���������叫�v2023.7.15 O.A
�����V���u���`�l���̑��蕨 ���R�Y�O�v2023�N7�`8���A��
TBS�h���}�uVIVANT�v���ݕ��f��
2023.07.13 (��) ������ƕρI�H ���s�̂̉̎����낢��
�i1�j���r�[�̎w�̏ꍇ�A�����āu��ǂ̏M�v�@����ATV�̉̔ԑg�ɓo�ꂵ�������O�q����A�u���Ȃ��̐l����ς������́H�v�̖₢�ɑ��A�u�Ȃ�Ƃ����Ă��x�[�g�[���F���w���x�B�Y����Ȃ��y�ȂƂ����Ȃ�w���r�[�̎w�x�v�Ɠ����Ă��܂����B�u���v�͂Ȃ�ł��AN���̃R���}�X������Ă����䕃�オ�u�N���́w���x�v��蒅�����A���̂Ƃ������ɉ���������y�w�Z�̏����k�Ɉ�ڍ��ꂵ�Č����A�a���������̎q���O�q�������Ƃ������Ƃł��B�u���v�Ȃ��肹�ΓO�q����͂��̐��ɐ��܂�Ȃ����� �Ƃ����킯�ł��B
 �@�u���r�[�̎w�v�͓O�q����i���TBS�̂̃x�X�g10�ŕs�ł�12�T�A����1�ʂɋP������q�b�g�ȁB���ꂼ�Y����Ȃ��̂��Ƃ��B���͏��{���A�ȂƉS�͎������B�ł́A���̉̂̉̎����ꕔ���o���Ă݂܂��傤�B
�@�u���r�[�̎w�v�͓O�q����i���TBS�̂̃x�X�g10�ŕs�ł�12�T�A����1�ʂɋP������q�b�g�ȁB���ꂼ�Y����Ȃ��̂��Ƃ��B���͏��{���A�ȂƉS�͎������B�ł́A���̉̂̉̎����ꕔ���o���Ă݂܂��傤�B
�����˒a���Ȃ烋�r�[�Ȃ��@�����a������܂��H ���r�[��7���̒a���B�Ȃ�u�����7���v�Ɨ���̂����ʁB����Ƃ��u�y���h�b�g�̎w�v�ɂ��܂��傤���B�ł��A���ꂶ�ᔄ��܂���ˁB�ł͂Ȃ�8���Ȃ̂��B����͂��Ԃ�A�����������̎��Ƃ��Ă̌�C�̗ǂ����Ƃ����̂ł��傤�B�m���Ɂu�V�`�K�c�v���u�n�`�K�c�v�̕����̂��₷�����i���͂�����B�u�a����7���̃��r�[�A���𐾂����̂�8���B�ʂɂ��������Ȃ��ł��傤�v�ƍːl�쎌�Ə��{���Ƀj�������Č���ꂻ���ł��ˁB�ł��Ȃ��E�E�E�E�E�B
����Ȍ��t�����ɉQ������
�����8�� �ډf���z�̒���
���������̌�
�@�Ȃ��A����͗]�k�ł����A�������Ɂu�o�qSASURAI�v�Ƃ����Ȃ�����܂��āB���̋ȁA�ŋ߂��������@���������̃C���[�W�\���O�Ƃ���TV-CM�ŗ���Ă��܂����A������쎌�����L�쐳���q�͖{���R�����݂���B����RCA���R�[�h����̎d�����Ԃł��B�ޏ��͗m�y�A���͖M�y�Ɛړ_�͂��܂�Ȃ������ł����A������ǂ����Ă���̂��Ȃ��B
�@�����݂䂫����Ɂu��ǂ̏M�v�Ƃ����y�Ȃ�����܂��B�̎��̊j�����L�B
���O�Ǝ��͂��Ƃ��Γ�ǂ̏M�@�u��ǂ̏M�v�́g�ǁh�̓ǂ݂́g�����h�B�Ƃ��낪�݂䂫����A�킴�킴�g�����h�ƃ��r��U���Ă���B�g�����h�Ɠǂ܂������Ȃ�u���z�̏M�v�Ȃ�X���i���ł��B���̓��e�����l��肾���珬�M���Ӗ�����u���z�̏M�v�ł����͂��B�ŏ��͂����������̂�������܂���B�ł����߂Ă��邤���Ɂu�z�v���u�ǁv�����ʓI�ɃV�b�N������Ɗ������̂ł��傤�B�����Łu��ǂ̏M�v�Ə����āu�ɂ����̂ӂˁv�Ɠǂ܂����B�ЂƂ������Lj�̏M�B�����g�ɍӂ�����A���O�̏M�͂������ɂ����� �قǂ̈�̊��B���ꂪ����Ύ��͊C���䂯��B�M�͏���������NjC�����͑�^�D�B�Ȃ�g�ǁh�����������B�݂䂫����ɂƂ��āA�u��ǁi�����j�v�͕K�R�������Ƃ������Ƃł��傤�B���ꂼ�����݂䂫�̊����ł��B����ɂ��Ă������̂ł��B�u���ꂾ���̂��Ƃ� ���͊C���䂯���v�Ȃ�ĂˁB���̋Ȃ�1992�N�̃A���o���uEAST ASIA�v�Ɏ��^����Ă��āA���Ɂu���v�u�a���v�������Ă��� ����͂ƂĂ��Ȃ��A���o���ł���܂��B
�ЂƂ��́@�����ĂЂƂ�
�����Ȃ��킽�����@�g�ɍӂ�����ɂ�
�ǂ����ł��O�̏M���������ɂ����ނ��낤
���ꂾ���̂��ƂŁ@�킽���͊C���䂯���
���Ƃ��u���j�͐�ā@���Ɉ��܂�Ă�
�@�����݂䂫����ŁA�ǂ��ł������b������B
�@�u���C�ł����v�Ƃ����y�Ȃ�����܂��B�y�ȂƂ����Ă������f�B�[�Ȃ��̃Z���t�̂݁B�����܂����́u�k�̍�����v�̐^�t�̌`�B���e�́A�U��ꂽ�����U�����j�̍��̔ޏ��ɓd�b���āu�������������v�Ɖ]���炤�A���Ɍ��ȏ��̂��b�ł��B
�@�u���C�ł����v�Ƃ����A���g�j�I���̐ꔄ�t���[�Y�B�������̃t���[�Y���g���o�����̂͂��H �ׂ��Ƃ���A�ǂ����1989�N�A�X�|�[�c���a�}���������č����ɑł��ďo�����̂悤�ł��B�݂䂫����́u���C�ł����v��1978�N�̃A���o���u�����Ă���Ɖ]���Ă���v�Ɏ��^����Ă���̂ŁA�����炪10�N�ȏ�������B������Ƃ����āA�����݂䂫����̊y�Ȃ��q���g�Ɏv�������Ƃ͍l�����܂���B�P�Ȃ���R�̈�v�ł��傤�B����ɂ��Ă������u���C�ł����v�̒�����̖��ɑ���݂䂫����̈ÁB�D�ΏƂ������Ƃ���ł��B
�@������B�݂䂫����ɂ́u����ɂ��₪��v�Ƃ����y�Ȃ�����܂��B���킸�����ȁA�W�����[�E��c����ɓ����Ȃ������āA����ނ̍ő�̃q�b�g�ȁB���e�́A�W�����[�̂́u�o�Ă䂭�Ȃ珟��ɍs���ȁB�߂肽���Ȃ�Ⴂ�ł������Łv�A�݂䂫����́u�E�֍s��������E�֍s���B�������͍��B�ł��A�S�͂Ȃ�Ă͂��߂ċC�Â��B���̂킪�܂܂��ق����v�B�ǂ������Ă��܂���ˁB
�@�����ŁA���҂̔������ׂ���A�݂䂫����1977�N6��25���i�A���o���u���E��E���E�ƁE���v�Ɏ��^�j�B��c�����1977�N5��21���Ƌ͂�1�����Ⴂ�ł����B����͂ǂ������ǂ������ǂ������Ƃ͌����܂���B������P�Ȃ���R�̈�v�Ƃ������Ƃł��傤�B���e���̓��ł����B
�i2�j�Ȏ҃^�����Ɋւ���
 �@NHK-TV�Ɂu�u���^�����v�Ƃ����ԑg������܂��B���������Ȃ��Ȃ��B�^�������e�n������Ēn���I���ʂ���y�n�y�n�̌`�����t�肾���ԑg�B���̓y�n�ɏڂ������j�ƁA�n���w�ҁA�l�Êw�ғ����^�������ē����Ȃ�����A�����ґ�Ȕԑg�ł��B�����Ő��Ƃ��^�����Ɏ������B
�@NHK-TV�Ɂu�u���^�����v�Ƃ����ԑg������܂��B���������Ȃ��Ȃ��B�^�������e�n������Ēn���I���ʂ���y�n�y�n�̌`�����t�肾���ԑg�B���̓y�n�ɏڂ������j�ƁA�n���w�ҁA�l�Êw�ғ����^�������ē����Ȃ�����A�����ґ�Ȕԑg�ł��B�����Ő��Ƃ��^�����Ɏ������B�@6��24��O.A.�́u�փP���ҁv�ł́A���R�̏��E���c���������R�̏��E�����߂���������ʂ��Č�����܂��āB�^�����Ɗw�҂��A���c�̓S�C�������ɋC�Â���Ȃ��悤�ɋ߂Â����E����������܂��B�����Ő��ƁA�u�^��������A���̓��ȂƎv���܂����v�Ɛu���B�^�����A�l����B�]�̉�H��\�킷�悤�ȁg�L���b �L���b�h�Ăȋ[������B�^�����A�v���o�����悤�Ɂu�R���A�փP���f�w�ł����v�Ɠ�����B�ǂ������̂�����A�����Z�����������Ȃ�ł��ˁB����Ȃ̂��ԑg���ɏ\����͏o�Ă����ł��B�^��������A�m���Ă�����������Ȃ�����ǁA�ǂ������O�܂łɓ��ɋl�ߍ���ł��傤�B��������������L������������o�����̂悤�ȕ��͋C�������B�Ȃ@�ɕt����ł���B�܂��A����ȕ��ɂ��āA�g�C���e����䏊�|�l�E�^�����h�Ƃ����C���[�W������Ă䂭��ł��ˁB
�@�g�|�\�E���s�v�c�h�̂ЂƂ� �u���Ă����Ƃ��I�e���t�H���V���b�L���O�v�ɂ����܂�������x���o�ꂵ�Ȃ����� �Ƃ����̂�����܂��āB�u���Ă����Ƃ��I�v�́A1982�N����2014�N�܂ł�32�N�ԁA�����̂�������O.A.���ꂽ�l�C�ԑg�ł����B�e���t�H���V���b�L���O�͂��̔ԑg�̊ŔR�[�i�[�ŁA�Q�X�g���^�����Ɖ�b���Ă��̗F�B�Ƀ����[���Čq���ł䂭 �Ƃ������́B�ő��o���22��̘a�c�A�L�q�������ł��B�ŁA�L���������킸�A���̌|�\�l�͌Ă�Ă����ł��ˁB8054�������Ă�킯�ł�����B
�@�����܂����قǂ̗L���l����x���o�ꂵ�ĂȂ� �ƋC�Â������B����͂ǂ��������������B��l�̊Ԃɉ�������͂��Ɠ���ŁA���ꂱ��l�������炷�ƁA�ӂƂ�����̂Ƀu�`������܂����B�^�����͂����܂������匙���������̂ł��B���̏́u�^�����R�`�����{�̗w�j�v�Ƃ������R�[�h�ɂ���܂����B
 �@�u�^�����R�`�����{�̗w�j�v�́A1981�N�����̃^����3���ڂ̃��R�[�h�B�I�풼�ォ��30�N�Ԃقǂ̃q�b�g��30���Ȃ��A�ʔ����������ւ��̂ɂ��ēł̂��靈���g�[�N�������ĒԂ����^�����̓Ɖ�LP�ł��B�Ⴆ�A�M�؈�v�u���Z�O�N���v�͔n�؈�v�u���Q�O�N���v�A�O�g�t�v�u���E�̍����炱��ɂ��́v�͎O�g�L�v�u���E�̍����炳�悤�Ȃ�v�A���R��t�u�G�߂̒��Łv�͏��ђs�t�u�{�݂̒��Łv�Ƃ�����B���̂���̃^�����͂Ƃ��Ă��Ė{���ɖʔ��������B���͌���e������܂��B
�@�u�^�����R�`�����{�̗w�j�v�́A1981�N�����̃^����3���ڂ̃��R�[�h�B�I�풼�ォ��30�N�Ԃقǂ̃q�b�g��30���Ȃ��A�ʔ����������ւ��̂ɂ��ēł̂��靈���g�[�N�������ĒԂ����^�����̓Ɖ�LP�ł��B�Ⴆ�A�M�؈�v�u���Z�O�N���v�͔n�؈�v�u���Q�O�N���v�A�O�g�t�v�u���E�̍����炱��ɂ��́v�͎O�g�L�v�u���E�̍����炳�悤�Ȃ�v�A���R��t�u�G�߂̒��Łv�͏��ђs�t�u�{�݂̒��Łv�Ƃ�����B���̂���̃^�����͂Ƃ��Ă��Ė{���ɖʔ��������B���͌���e������܂��B�@���̒��́i�Ȃł͂���܂��j�u�I�[���i�C�g�j�z���v�Ƃ�������̃R�[�i�[�ŁA�^�����͂����܂������Y�^�Y�^�Ƀu�b�^�a���Ă��ł��ˁB���̈ꕔ�n�I�����L�B
�Ƃɂ����A�܂��A�Ȃ�ł���������邩���ē�N�������������Ă��Ă�킯�ˁB����͂Ȃɂ����{�l�̑S�������Ƃ�����ˁA�ȂO�ʂɏo���Ă�̂�B�Ȃ�������Ȃ��āA�I�����������{�l�̌��ɑނ��낤���ɑނ��낤�Ƃ����Ƃ�����ĂĂˁA�Ȃ��ꂪ�C��������O�ɏo�čs�����Ɗe����ł���Ă��킯��ˁB������A���y�̕���ł͂���Ȃ������B�����̕���ł͂��B�܁A�����A�����A���{�l�̒��ɂ͂��A�ςɑR�I�Ȉӎ��A���ɑނ��낤�A�W���W�����悤���Ă����̂͂ˁB�ł����y�̐��E�ɂ͂Ȃ������́B����������������A��������ꂪ������킯����Ȃ��B�ߌ��݂����Ȋ炵�Ă��B���ꂪ�ˁA�C�ɐH��Ȃ��킯��ˁB����ˁA���̂͂��傤���Ȃ����ǂˁA�����A����Ȃ��̂����y�I�ˁB�������q���Z�����̒��w���̃u�X�������܂����B�₳�������Ƃ����Ƃ������Ȃ���ˁB���ꂪ���A�C�ɐH��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ���ˁA�����A���{�̕����͂��͂₲�j�Z�ɂȂ���������Ɠ����Ȃ�B�����ǂ����悤���Ȃ��ˁB���ꎕ�s�͎����^�R����B�@�Ő�Ƃ����Ă�����͔�排����B���ɍŌ�̈�s�͂܂����B���̃��R�[�h�A���܂�ɉߌ�������Ƒ����ցA�₪�āA��背�R�[�h�X�u�V�����v����Д����������́B�Ƃ͂����A�s��ɂ�5�����قǂ͏o������Ǝv���܂��B���������V�����Ղ���ɓ���܂����B
�@������������܂����́u�Ȃ�ł����܂Łv�ƕ��S�����ł��傤���A������^�����́u���߂����v�Ɣ��Ȃ����ł��傤�B�ł��A�a���̋@��Ȃ��܂܍����Ɏ��� �ł��傤���B�^�������e���t�H���V���b�L���O�ɂ����܂������ĂȂ������i�ĂׂȂ������j���R�͂��ꂾ�Ǝv���܂��B
�@�I�b�g�A�{��ɖ߂�܂��傤�B�Ƃ���Ń^�����ł����A�����A�Ȃɂ��̃e���r�ł���Șb�����Ă��܂����B
���̂����A�̗̂̉w�Ȃɂ͕ςȉ̎��������ˁB�Ⴆ����Ȃ́B�u�p�C�v���킦�� ���J�ӂ��āv�����Ă��B����Ȃ��Ƃł���킯�Ȃ���ˁB�@�m���Ƀp�C�v���킦�Č��J�͐����܂���B�ł��A����ȉ̂͑��݂��Ȃ��̂ł��B�e�r�͎q�́u���̗���Ɂv�̉̎��ɂ́u�����ӂ����� ���J�ӂ��āv�Ƃ�����߂�����܂��B����Ȃ�\�ł��ˁB�����ɂƂ͌����ĂȂ��̂ŁB
�@�����ŁA������ȁB����Ђ�́u�Ђ�̃}�h���X����v�ɂ͂���ȉ̎�������B�u�Ȃ̃W���P�c�̃}�h���X����́@�p�C�v�ӂ����� �A�[ �^���b�v�̂ڂ�v�B���A�v���̂ł����A�^�����̒��ł��̓���S�b�`���ɂȂ����������Ȃ����ƁB�����Ɛ����Ă݂�A�m�M�ƓI�_���Łu�p�C�v���킦�Č��J�ӂ��āv�ƍ앶����������̂�������܂���B�Ȏ҃^�����Ȃ��肩�˂܂���ˁB
�@����A�R��H�v�쎌�u���߂���v�̃I�J�V�ȕ�����A���{�~�̃P�b�T�NGS�̎��ɂ��G�ꂽ�������̂ł����A���ʂ̓s���Ŏ���ȍ~�ɉ܂��傤�B�ǂ����A�����҂��������B
2023.06.14 (��) ���n�l���A���Ɖe
�i1�j�J���O�q����̏ꍇ �@5��28���A�������n��A��90����{�_�[�r�[��5�Ԑl�C�̃^�X�e�B�G�[�����D�����܂����B�R��̓_�~�A���E���[���B���̐l�A��N�̓��[�h���[���ɋR�悵��14���ł������A���͍�N�̕����C��������܂����B�Ƃ����̂́A���̔n�A�J���O�q����̎����n������ł��B�J������͍�N�́u�N�����m�v4���ɓo�ꂵ�����w�Z�̓������ŁA�����̔n�����X�S�r�n��Ȃ̂ł��B����������30�N�O�A����l��S���������Ƃ����������ŁE�E�E�E�E����l�͎����Ȃ̃L�����A�����ł������A�u�s���Ă���v�ƃS���t�ɏo�������܂܁A�A��ʐl�ɂȂ��Ă��܂����B�����������C�ŏo�����čs�����l�������Ԍ�ɂ͂��̐��ɂ��Ȃ��I�z����₷��Ռ��ł��B�ޏ��͂��̌㐔�N�Ԑ�����r�ɂȂ��Ă��������ł�������������܂���ˁB
�@5��28���A�������n��A��90����{�_�[�r�[��5�Ԑl�C�̃^�X�e�B�G�[�����D�����܂����B�R��̓_�~�A���E���[���B���̐l�A��N�̓��[�h���[���ɋR�悵��14���ł������A���͍�N�̕����C��������܂����B�Ƃ����̂́A���̔n�A�J���O�q����̎����n������ł��B�J������͍�N�́u�N�����m�v4���ɓo�ꂵ�����w�Z�̓������ŁA�����̔n�����X�S�r�n��Ȃ̂ł��B����������30�N�O�A����l��S���������Ƃ����������ŁE�E�E�E�E����l�͎����Ȃ̃L�����A�����ł������A�u�s���Ă���v�ƃS���t�ɏo�������܂܁A�A��ʐl�ɂȂ��Ă��܂����B�����������C�ŏo�����čs�����l�������Ԍ�ɂ͂��̐��ɂ��Ȃ��I�z����₷��Ռ��ł��B�ޏ��͂��̌㐔�N�Ԑ�����r�ɂȂ��Ă��������ł�������������܂���ˁB�@����Ȕޏ��Ɉ���n�働�[�h�T���u���b�h�I�[�i�[�Y��E�߂�������āA�Ȃ�ƂȂ��ē����̃y�[�W���߂����Ă�����A�ꓪ�̔n�ɖڂ��B�t���ɂȂ����B���G�[�s�[�C���f�B�A�ꃁ�C�v���W���X�L�[��2�Δn��1995�N4��22�����܂�Ƃ���B4��22���͖S���Ȃ�������l�̒a�����I �Ȃ�^���̂߂��肠�킹�ƁA���w�������ӂ����Ƃ��B����l��S������4�N�ځA1997�N�̏H�̂��Ƃł����B���̔n�̓��[�h���C�v���Ɩ��t�����3���������܂����B�o���̓x�A����l�̐��܂�ς��Ƃ̎v������ɁA�S�̒Ɏ�����X�ɖ�����Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
 �@���̌�̒J������̎����n�͖ڊo�܂�������Ԃ�B���ł����f�B�A���o���[�U�́A���R�Ĕn�X�e�[�N�X�iG3�j���A2011�A2012�N�ƘA�e�A2011�N�̃��B�N�g���A�}�C��(G1)�ł́A�A�p�p�l�A�u�G�i�r�X�^�͍̋�3���ƌ����A�Ĕn�������ő傫�ȑ��݊��������܂����B���̑��AG1�o���n�́A���[�h�A���G�X(�e�ԏ�2008)�A�u�����l�b�g�i�I�[�N�X2013�j�A�L���g���t�B�[���i���B�N�g���A�}�C���A�G���U�x�X�����t2014�j�A�G���W�F���t�F�C�X�i�I�[�N�X2016�j�A�I�[���t�H�[�����i�I�[�N�X2018�j�A���[�h���[���i�_�[�r�[2022�j��6���𐔂��܂��B����܂ł̎����n��70���ŗv�����Ƃ�109�B�Ȃ�Ƃ��X�������сA�B�X����X�[�p�[�n��Ƃ�����ł��傤�B
�@���̌�̒J������̎����n�͖ڊo�܂�������Ԃ�B���ł����f�B�A���o���[�U�́A���R�Ĕn�X�e�[�N�X�iG3�j���A2011�A2012�N�ƘA�e�A2011�N�̃��B�N�g���A�}�C��(G1)�ł́A�A�p�p�l�A�u�G�i�r�X�^�͍̋�3���ƌ����A�Ĕn�������ő傫�ȑ��݊��������܂����B���̑��AG1�o���n�́A���[�h�A���G�X(�e�ԏ�2008)�A�u�����l�b�g�i�I�[�N�X2013�j�A�L���g���t�B�[���i���B�N�g���A�}�C���A�G���U�x�X�����t2014�j�A�G���W�F���t�F�C�X�i�I�[�N�X2016�j�A�I�[���t�H�[�����i�I�[�N�X2018�j�A���[�h���[���i�_�[�r�[2022�j��6���𐔂��܂��B����܂ł̎����n��70���ŗv�����Ƃ�109�B�Ȃ�Ƃ��X�������сA�B�X����X�[�p�[�n��Ƃ�����ł��傤�B�@���āA�J���X�Ɂi�H�j���N�㔼��̊��Ҕn�́A�V�n��������3�ΖĔn�A���W�[�k�ƁA��Q�]����5��3���d��2���Ɛ����ɏ�郍�[�h�A�N�A�ł��傤���B���̑��̔n���Ƃɂ��������Ɍ��C�ɑ����Ăق������̂ł��B
�@�����j�̌�����I���̘b������ł��B�V�w�̂���������JRA�̂��̂�����Ƃ������Ƃ������āA���n�ɂ��ȂA�g���N�V�������s��ꂽ�����ł��B�����܂łɐV�Y�̕�O�q���r�ꂻ���ȃ��[�X���܂���B���q����͂܂�����Ȃ������Ƒ匊���Ɣ��j��������B�n���̌������K�v�Ȃ̂ŁA���T��y���̏�O�����ɑ��������ʂ��������ł��B���̊�3�����A��͊撣��܂����l��܂������n���܂ޑ匊�̐��X�B�����������A���o�̂��q�l�ɓ�����n���̃R�s�[�����z�肵�A��ɔz���������n������B��I���ł͖��n���̏o�����[�X�̘^�撆�p�����s�B�Q�b�g�����̂͋��n�ɂ͑S�������̋��用��̌��Z���搶�ŁA�u���܂����A�r�b�N���v�̘A���������Ƃ��B��I���͗B�ꖳ���O���̃A�g���N�V�����ɑ傢�ɐ���オ���������ł��B
�@���z�͂Ƃ����A���n���Ă��Ⴄ���˂Ƃ����A�n���w���̎�ԂƂ����A�l�������ɂ̓A�C�f�B�A�ƍ˂Ɖ^�Ǝ��s�͂�����Ȃ���Ȃ�܂���B������J���Ƃ̃`�[�����[�N�̌����Ȃ̂ł��傤�B�����ւ䂭�ƁA���̏ꍇ�͍˂��Ȃ���Ή^���Ȃ��A�O�q����́u���v�ɔ�ׂ�Ɓu�e�v�̋��n�l���Ȃ̂ł���܂��B
�i2�j�����W�̍��R���鋣�n�l��
 �@�킪���n�l���̎n�܂�́A��w3�N��1966�N�̓��{�_�[�r�[�ł����B�O�N�A�g�ˎ����獑�����Ɉ����z���āA�߂��ɂ��铌�����n��ɉ��h�݂̂�ȂƋ����{�ʂŌJ��o���܂����B����ɓ����ď��������Ƃ����Ȃ�R�[�X�̗��ڂɔ�э���ł��܂����B�Ȃ�čL��Ŕ������� �Ɗ����������̂ł��B�Ƃ��낪�n���̎�ނ����������킩��Ȃ��B�ł���������������ƁA5�^�}�V���E�z�E�A10�V�F�X�L�C�A20�V���E�O���A21�X�s�[�h�V���{���A28�i�X�m�R�g�u�L��200�~�������ă��[�X�����܂����i�����̎��O�����͂��Ă������̂Łj�B2400m�𑖂��ăS�[���ɓ���B�[�b�P��9�Ԃ���э���ł����B12�Ԑl�C�̃e�C�g�I�[�ł��B���̎���9�Ԃ̃[�b�P���͖����ڂɏĂ��t���Ă��܂��B�f���ɂ͏ォ��A9�A24�A28�A25�A16�ƕ��ԁB�����A28�Ԃ�����u�l�����v�Ɗ�їE��ŕ����߂����ցB�����ł������Ɂu������͒P���n������B1�����������ʖڂȂ̂�v�ƌ����ăV�����I �Ȃ�Ƃ��������n���f�r���[�ł����B
�@�킪���n�l���̎n�܂�́A��w3�N��1966�N�̓��{�_�[�r�[�ł����B�O�N�A�g�ˎ����獑�����Ɉ����z���āA�߂��ɂ��铌�����n��ɉ��h�݂̂�ȂƋ����{�ʂŌJ��o���܂����B����ɓ����ď��������Ƃ����Ȃ�R�[�X�̗��ڂɔ�э���ł��܂����B�Ȃ�čL��Ŕ������� �Ɗ����������̂ł��B�Ƃ��낪�n���̎�ނ����������킩��Ȃ��B�ł���������������ƁA5�^�}�V���E�z�E�A10�V�F�X�L�C�A20�V���E�O���A21�X�s�[�h�V���{���A28�i�X�m�R�g�u�L��200�~�������ă��[�X�����܂����i�����̎��O�����͂��Ă������̂Łj�B2400m�𑖂��ăS�[���ɓ���B�[�b�P��9�Ԃ���э���ł����B12�Ԑl�C�̃e�C�g�I�[�ł��B���̎���9�Ԃ̃[�b�P���͖����ڂɏĂ��t���Ă��܂��B�f���ɂ͏ォ��A9�A24�A28�A25�A16�ƕ��ԁB�����A28�Ԃ�����u�l�����v�Ɗ�їE��ŕ����߂����ցB�����ł������Ɂu������͒P���n������B1�����������ʖڂȂ̂�v�ƌ����ăV�����I �Ȃ�Ƃ��������n���f�r���[�ł����B�@�n�������߂Ċl�����̂͂��̔N��6��12���A������Q���ʂł����B�A�A�^�b�N���A�[�}���m�I�[�̘A��5�|7�͔z��910�~�B200�~��1820�~�ƂȂ�܂����B�Ȃ�����ۂ����A�Ƃ����܂�B�����A���d�iJR�j�̈��Ԃ�10�~�B�������������H���̂Ƃ�H��140�~�̎���Ȃ̂ŁA����͂������т̃Q�b�c�ł����B
�@���R���n��ɏ��߂čs�����̂�1967�N11��23���B���̔N�͂����œV�c�܁E�H���s����Ƃ����ϑ��J�Âł����B���ʂ�8�Ԑl�C�̃J�u�g�V���[���D���B�܂����̌��ʂɔn���͎S�s�B�A�H�A�ނ��Ⴍ���Ⴕ�ăI�P���X��������Ă���ƁA���[�ɐl�����肪�B���C�Ȃ����Ă�����A�u����ǂ��ɓ����Ă�H�v�ƃI�A�Z����B���u����ł��傤�v��3�̂����̈�̋����w�����܂����`���ꂪ�n���ւ̑����Ƃ͎v������炸�ł��B�u�����ˁB�����肾��v�Ɛ�~�D��͂܂����B�u����A���x�͂ǂ����v�Ɂu����v�Ƃ����ƁA�u��~�q���ȁv�Ƃ�������A�������n���ꂽ��~�D���o���ƁA�u�����̋��œq�����v�ƃX�S�܂��B�������ĂƎv���Ȃ���ǂ����������Ă��邩��ƁA�����̐�~���o���ċ���A�Ȃ�ƊO��B���ꂩ�牽�x����炳��Ă�����Ƃ��Ƃ�1���~�����グ��ꂿ������B�������ʂɖI�Ƃ͂��̂��Ƃł��B ���Ƃŕ����ƁA����f���X�P�q���Ƃ����܂��ă��N�U�̎������Ȃ����ŁB�ꖜ�~�ōς�ł悩������Ȃ��ƈԂ߂���̃I�\�}�c�ł����B�J�u�g�V���[�͂��̔N�̗L�n�L�O�������܂����B�䂪�t�̋ꂢ�v���o�͋H��̃N�Z�n�J�u�g�V���[�Ƌ��ɂ��� �ł��傤���B
�@���{�r�N�^�[�ɏA�E�����̂�1968�N�B���̔N�̃_�[�r�[��7��7���ɍs���A���[�_�[�r�[�ƌĂ�܂����B���Ǝ��ɖ����������̋��n���ԂƓ������n��ōĉ���܂ł͂悩�����̂ł����A�n���͑�O��B9�Ԑl�C�̕����^�j�m�n���[���A���A�l�C���W�߂�3�� �}�[�`�X�A�^�P�V�o�I�[�A�A�T�J�I�[��K�ڂɁA����悠���Ƃ����Ԃ̓���������߂܂����B���n�͓���I�n�Y���n�������肵�ߐ؎��N�r�������̂ł��B
�@���̌�A�_�[�r�[�ł́A1969�N�_�C�V���{���K�[�h�A1970�N�^�j�m���[�e�B�G�A1971�N�q�J���C�}�C�A1972�N�����O�G�[�X�A1973�N�^�P�z�[�v�Ƃ��Ƃ��Ƃ��O��A���̑��̃��[�X�ɂ��ۗ��������ʂȂ��A���l��V��ƒ����~�X�^�[�̈��ނ��@�Ɂi���܂�W�Ȃ����I�H�j���n�M�����X�ɗ�߂Ă������̂ł���܂��B
�@���n�M�����������̂�1986�N�̓��{�_�[�r�[�ł����B�������̂̓_�C�i�K���o�[�B�Б�O���[�v�ߊ�̏����e�ł����B�S�[���O�u�K���o�[�A�K���o�[�v�Ɛ⋩�A��������Ɓu�������������v�ƂȂ�ӂ�\�킸����U��グ�� �����g�c�P�Ǝ��̎p���ƂĂ���ۓI�ł����iNHK���W�u�k�̑�n�̐킢�v���j�B����͈ꎞ���������m�[�U���e�[�X�g�̑����Z�������̂ł��傤�B�Б�͂��̒���ɃP���^�b�L�[�_�[�r�[�𐧂����č��ŋ��n�T���f�[�T�C�����X��A���B�Y��̓_�[�r�[6���A���̍ŋ��̎e�f�B�[�v�C���p�N�g�͂V���̃_�[�r�[�n��y�o�B���{�ɃT���f�[�T�C�����X�����z���܂��B
�@���̘A���n��2-3�́A�n�����n�߂Ă�����22�N�A�䂪�_�[�r�[���Q�b�g�ł�����܂����B���X�Ȃ����Ȃ���A���˂̂Ȃ��ɂ���������ł���܂��B��1987�N�̃_�[�r�[�͎H���ܔn�T�N���X�^�[�I�[������̂��ߕs�o���A�����[�i�C�X�̗D���ł����B�X�^�[�I�[�A7�����Ԃ�o���̋e�ԏ܂�9�Ԑl�C�ŏ����B���{���A�i�̎����u�e�̋G�߂ɍ������J�v�͋��n�����j�Ɏc�閼�A�i�E���X�ł����B
�@����ȍ~���N�Ԃ́A�V�����n��╟�����n��ɏo�����ċ��n���y���݂܂����B�C�̍��������Ԃ����ƁA���͋��n��͗\�z��J���I�P�ȂǁA�l���Ă��l��Ȃ��Ă��A�a�C�\�X�Ɖ߂�������Ԃ͊y�������Ƃ��̏�Ȃ��B�܂�ł��̐��̓������B�䂪���n�l���ŗǂ̎��ゾ������������܂���B
�@����Ȃ���Ȃ̋��n�����̒��A���C�Ȃ��u�����͂��������N�Ԃǂ̂��炢�������Ă���̂��낤�v�ƌv�Z���Ă݂��Ƃ���A���N70�`80���~�Ƃ����������o�܂����B�܂�����Ȃ��낤�A���₿����Ƃ��������Ȃ��� �Ȃǂƍl���邤���ɁA���̋�������Έ���n��ɂȂ���Ȃ��낤���A�Ǝv�������܂��B�����āE�E�E�E�E
�@1993�N�A�Б�_�C�i�[�X�T���u���b�h�N���u�֓���B���悢���2�̋��n�l���̎n�܂�ł��B��W�p���t���b�h�ɂ̓T���f�[�T�C�����X�̏��Y����т܂��B�O���[�s�A���f�B�[��92�͌�̎H���ܔn�W�F�k�C���B�����Ȃ��Ǝv����200���~�ł̓`�g�肪�o�Ȃ��B�m�[�X�I�u�_���W�O��92�Ȃ�90���~�B����Ȃ�ƍw�����܂����B>
�@���̎����n�̓m�[�X�V���A�[�Ɩ��t����ꗂ�N1994�N8��13���A�V���̐V�n��Ńf�r���[���ʂ����܂��B�����ɏ����B����V��3�X�e�[�N�X(G3)��2���Ə�X�̐��тł��B�������A���̌�͐U��킸�A1996�N6��22���A��_�u�����X�e�[�N�X�v�Œ����S�s�S�̂��ߎ����������~�̍Ŋ��𐋂��܂����B���̂���5�����w���A���ɃJ�[���[�p�b�V����(�g�j�[�r���~�_�C�i�J�[��)�̓I�[�N�X�ƓV�c�܁E�H�𐧂����G�A�O���[���̑S���Ƃ����đ傢�Ɋ��҂��܂�����1���~�܂�B�䂪�����n�m�[�X�V���A�[����}���[�V�����^���܂�6���̒ʎZ���т�6���B�n���������n���u�X�[�_���߁v�ɂ���Ƃ���u�n�ŋ��ׂ������z���Ȃ���v�ŏI�����������̂ł��B
 �@1996�N4��25���A�Б�X�^���I���X�e�[�V������K�˂ăT���f�[�T�C�����X��g�j�[�r���Ɗ�����킹�܂����B���̂Ƃ�����ꂵ�����߂����̂ł��傤���A�g�j�[�r���Ɋ��܂ꂽ���Ղ͍������r�Ɏc���Ă��܂��i�z���g����j�B
�@1996�N4��25���A�Б�X�^���I���X�e�[�V������K�˂ăT���f�[�T�C�����X��g�j�[�r���Ɗ�����킹�܂����B���̂Ƃ�����ꂵ�����߂����̂ł��傤���A�g�j�[�r���Ɋ��܂ꂽ���Ղ͍������r�Ɏc���Ă��܂��i�z���g����j�B�@���̑O�N�A1995�N�ɂ́A��D���ȃV���U���ɉ�ɉY�͂̒J��q��ɏo�����܂����B�ނ̒a����4��2���ɍ��킹��34�̂��߂łƂ��������ɍs�����̂ł��B�����ŎB�����ʐ^�̓e���J�ɂ��č�����ɕۗL���Ă��܂��B
�@�����n�͂������܂��B�V���{�����h���t�A�f�B�[�v�C���p�N�getc�B�ł��A�V���U���������j��ō��̖��n�ƐM���ċ^���܂���B�j�㏉�̌܊��n�Ƃ����̋Ƃ͂������ł����A�_�������[�X�������ė��Ƃ��Ȃ��������ƁA�����Ă�2���͊O���Ȃ��������� �Ȃǂ����̗��R�ł��B���h���t���f�B�[�v���_�������[�X�𗎂Ƃ��Ă��邵3���ȉ�������B�V���U���̐��U���т�19��15��4�s�B4�s�͕���̃I�[�v���ƃg���C�A���̂݁B����قǔ�������т̓V���U����u���đ��ɂ͂��܂���B
�@�V���U���͗�1996�N7��13���A�V���ɗ������܂��B����Ă����Ė{���ɗǂ������I35�A�����n�Ƃ��Ď퉲�n�Ƃ��ē��X����ꐶ�ł����B
�@�Ō�̎����n�}���[�V�����^�����w�����ĊԂ��Ȃ�1998�N�̏t�A���w�Z�̃N���X��J����āA�v���Ԃ�ɉ�����J�������[�h�T���u���b�h�I�[�i�[�Y�Ŕn�吶�����n�߂�����ƕ����܂����B�����Ō�Ŕޏ��͍ŏ��Ƃ����킯�ł��B���̎����n���[�h���C�v���̃f�r���[�ԋ߂̂���ŁA���̓��C�v���̂��Ƃł����ς��������̂ł��傤�B�b���͋��n�̂��Ƃ��肾�����悤�ɋL�����Ă��܂��B���ꂩ��Ƃ������́A�ޏ����g�̎����n��V�����^���̎q�������̏o���܂ŁA���ɂ��܂߂ɏ��𑗂��Ă���܂����B�����āA����͍��ł������Ă��܂��B
�@���̕��́A�V�����^�����ތ�͔n����n�����������艓�������Ă��܂��A�y���݂́A�J������̎����n�̊������ς�B�Ȃ����ޏ��̔n�������̔n�̂悤�Ɏv�����ł��ˁB�J���O�q����A���Ȃ��̈��n������G 1���l��܂��悤�ɁI �����肢�����ɗ͂��Ă߂Ă��܂��B
2023.05.10 (��) �����I��{����ρ`�u���ԁv�Ɋ�
�@4��2���A��{���ꂳ�S���Ȃ�܂����B71�ł����BYMO�ňꐢ���r���A�f��u���X�g�G���y���[�v�̉��y�ŃA�J�f�~�[��ȏ܂���܁B���{�l�Ƃ��čł����E�ɖ���y�������y�Ƃł����B�ނ�ł����������F�肵�܂��B�i�P�j ��{����́u���ԁv�A�����đO�쐴
 �@�����ł����ARCA���R�[�h����A��{���ꂳ��Ƃ͏��������ւ肪����܂����B����́A�O�쐴���O���[�v�u���R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�u�v����Ɨ����邫�������ƂȂ����uKIYOSHI�v�Ƃ����A���o���Ɛ�s�V���O���u���ԁv�̃v�����[�V����(�̔����i)�ɂ����Ăł����B
�@�����ł����ARCA���R�[�h����A��{���ꂳ��Ƃ͏��������ւ肪����܂����B����́A�O�쐴���O���[�v�u���R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�u�v����Ɨ����邫�������ƂȂ����uKIYOSHI�v�Ƃ����A���o���Ɛ�s�V���O���u���ԁv�̃v�����[�V����(�̔����i)�ɂ����Ăł����B�@1982�N�Ă̂�����A��i�ɌĂ�Ă��������܂��B�u���x�A�O�쐴���\���ŃA���o�����o���B���Ă͂��̃v�����[�V���������O����ɂ��肢�������v�B����܂Ő�`2�ۂŎR���B�Y�A�|���܂��A�p���q���Ȃ�J�|�b�v�n��S�����Ă������́A�u�Ȃ�ł܂����̂��H�v�ƈ����܂������u����͉��̂���Ȃ��j���[�~���[�W�b�N�i����J�|�b�v�������̂��Ă��܂����j���B��{����A�����a�F�A��쌰�q�A�ɐ����O�A�㓡�����炪�O��̂��߂ɋȒ��Ă����i�ȂB���[�x�����N�[���E�t�@�C�u�Ƃ͕ʂ́gANOTHER�h��p�ӂ����v�Ɛ�������A�u�Ȃ��点�Ă��������܂��v�ƈ����܂����B
�@�A���o���́A���H�[�J���X�g�O�쐴�ւ̃��X�y�N�g�ɖ����āA�f���炵����i�����т܂��B�^�C�g���̓Y�o���uKIYOSHI�v�B���ł��A����d���쎌�A��{�����E�ҋȂ́u���ԁv���Q���Ă��܂����B
��l�̏�����D�Ԃɏ���Ă���B���O�͍~�肵�����B�u����Ȃ炪���Ȃ�Έ����Ԃ����� ���̂��낪���Ȃ���̂܂܍s���v�E�E�E�E�E�����߂�Ȃ����X�����ɔ�߁A���͗�Ԃɐg���䂾�˂�B�ʂ���������߂āB�@�V���v���ȃ����f�B�[���C���B�����K�ƒZ���K���s�������a���i�s�B�V���Z�T�C�U�[�Ɛ��y��̗Z���ɂ��a�̃e�C�X�g��X�����[���Ŋi�������T�E���h�B��{����̋Z�̍Ⴆ���A ����ƍ~�肵�����Əl�X�Ɛi�ޗ�Ԃ̕��i��n�G�̂悤�ɕ`���o���܂��B���̔����ȐS����V���N�������āB������f����������h�r���b�V�[�I�����E�B�܂��ɍ�{����̐^�����ł��B�O�쐴�̓O���b�T���h��R�u�V���̂Ă�E���̏��@�ł���ȉ̐��E�������ɕ\�����܂����B
�@�u���ԁv�̓V���O���Ƃ���1982�N10���ɁA�A���o����12���ɔ�������܂����B
�@�O�쐴���\���E���H�[�J���߂���R�c�m�ƃN�[���E���@�C�u��1969�N�u����͍������J�������v�Ńf�r���[�B�����Ȃ�~���I������������A�����u���킸�Ɉ����āv�A�u�\�̏��v�A�u���S�v�A�u������ �_�ˁv�A�u���̓��u���[�X�v�A�u���������vetc�ƃR���X�^���g�Ƀq�b�g��A���B�̗w�E�̉���������������Ȃ���X�^�[�ɂȂ��Ă��܂����B����Ȓ��A�m�y�u���̑O��Ɨނ܂�Ȃ郔�H�[�J���X�g�O�쐴�̍˔\�ɍ��ꍞ��J�|�b�v�n�̃\���O���C�^�[�̎v�f����v���� ���̃v���W�F�N�g�����������Ƃ����킯�ł��B
�@�ƊE���Ƃ������邱�̃v���W�F�N�g�́A�e���f�B�A�����̋����Ƒ���ȋ����������Č}�����A�N�[���E�t�@�C�u�{���̔}�́`�e���r�AAM���W�I�A�L�������A�T�����A�������A�V���Ȃǂɉ����AJ�|�b�v�n�̔}�́`FM�����A���y��厏����A�C�h�����Ɏ���܂ŁA�S���ʓI��`�W�J���������܂����B�O��{�l���A�V���L�҂ɗm�y���N����̂��Ƃ�b������A���y��厏�̎Ⴂ���C�^�[�Ɂu�A���o������R���Z�v�g�v���������ƁA���̌��̃v�����[�V�����ɋC��������ĂƂĂ��y�������ł����B���͋t�ɁA���̂̉c�ƁA�̗w�Ȍn�̔ԑg�A�G���A�T�����Ȃǖ��J��̔}�̑̌��ɐV�N�����o�������̂ł��B�v�����[�V�����͖�1�N���B���̒��ŁA�Y����Ȃ��o�����`�悩�������ƁA���s�������ƁA�ʔ����������ƂȂǁA���X��I�����Ă��������܂��B
�@���씭�\��
�@�����O��1982�N�H�A���f�B�A��R�[�h�X�̊F�l�ɃV���O���u���ԁv�ƃA���o���uKIYOSHI�v������I�ڂ��邽�߁A�s���̃p�u���X�g����������čs���܂����B�v���f���[�X�̐��J�������Ǝ���d���������i�s�B���ʃQ�X�g�Ƃ��č�{���ꎁ�ɂ��Q�����������܂����B����30�̍�{�����ǂ�Șb���������H�c�O�Ȃ���S���L��������܂���B���A�g�����h�̋w���̒ʂ�A�Ɠ��̃I�[�������������Ƃ͂悭�o���Ă��܂��B
�A�N�r���o�債���ʐ^�l�K�u�Y�ꎖ��
�@9���^���A�O�쐴�ɂƂ��ď��̌��ƂȂ鏭���G���u�Z�u���e�B�[���v�ւ̌f�ڂ����肢���ׂ��A���c���c���̏W�p�ЂɒP�g��荞�݂܂����B�B�e��������̑O�쐴�̃l�K�Ǝ��Ă����g���āB�}���Ă��ꂽ�����N�v�ҏW���͑����Ɂu���̎ʐ^�Ȃ��a���Ȃ��g����ˁv�ƁA�O���r�A�ł��m�Ă���܂����B�u������I�Z�u���e�B�[���ɑO�삪�v����͏̎^���m�� �ƈӋC�g�X�A��Ђɖ߂炸���A�����ߍ��݂܂����B�A��Ԃɏd�Ȃ��ēd�Ԃ͂��Ȃ�̍��G�A�ʐ^�l�K�̓��������܂�ԒI�ɒu���܂����B�r���ŐȂ����̂ō���B�Ȃ{�[���Ƃ��Ă�����抷�w�B�X�����ƍ~��ăz�[��������Ă��鎞�u���܂����I�v�A�u�Y��ɋC�t���B�d�ԑ��苎��B�w�⎸�����ɓ͂��ċA��B����͂��炢���ƂɂȂ����B�Z�����O�삳����ƈ���Ė���c���m���B�����ʐ^�̐��X�B���Ƃ����낤�Ƀl�K�܂Œu���Y���Ƃ͂Ȃ�s�o�I �䂪�l���ő�̃s���`�ɂ܂�Ƃ����������߂����܂����B
�@�����̌ߑO���A�w����̘A���̓i�V�B����͂����o�Ă��Ȃ����B����Ȏʐ^�A���������B������Ȃ�������ς�ōςނ��̂ł��Ȃ��B�ӔC����ăN�r���B�I������ȁB�ƂŖ�X�Ƃ��Ă��鎞�W�[�� �d�b����܂����B��b������Ɓu�����A�̂�т�ƂɂȂ����ˁ[��B���O����A�ȂY�ꕨ���ĂȂ������v�ƕ����Ȃꂽ�������̘a�v��ێВ��̐��B�u���͑O�삳��̑厖�ȃl�K��d�Ԃɒu���Y��Ă��܂��܂��āv�ƍ����B����ƁA�u������A��i���̖�ǂɒN�^����Ƃ����l��K�˂ȁB�l�K��a�����Ă���Ă��邩��v�B�㎀�Ɉꐶ�B�n������V���B�������ɎQ���܂����B���̕��͏����̖�t����ŁA������d�Ԃ̖ԒI�Ɏ��܂�����̂œ͂��悤�Ǝ����ēd�Ԃ��~�肽�B�����Œ�������ƑO�쐴�̎ʐ^������B�Ƃ����ɐS������̂���TBS�ɘA���BTBS���a�v�䉹�y�������ɘA�� �Ƃ����菇�������悤�ł��B�Ȃ�K�^�B�����A�S�����l�ɏE���Ă�����ǂ��Ȃ��Ă������B�l���������ł��]���Ƃ��܂��B�D�ӂ�����ɏE��ꂽ�K�^�Ƃ��̕��ւ̊��ӂ͈ꐶ�Y��邱�Ƃ͂ł��܂���B
�B�ԍ�̋i���X�ő化�܂̊�
�@LP�uKIYOSHI�v��Associate Producer�FTakashi MAEDA�̃N���W�b�g������܂��B�O�c������B�A�[�e�B�X�g�ƃ��R�[�h���[�J�[���q���������̃R�[�f�B�l�[�^�[�B�����Ȑa�m�ł��B��`�v���W�F�N�g�̑S�Ă�ނƂ̓�l�O�r�ōs���܂����B�u�ł��邱�Ƃ͂��ׂĂ�낤�v�Ƃ̍��ӂ̂��ƃv�����[�V�����͏����ɐi��ł��܂����B����Ȃ�����A���͐ԍ�̋i���X�B�É��̓���X�ł̓X���T�C����̑ł����킹�Ŏ������������܂��B�c�Ƃ���Ă��Ă����X�̒n�����ԏ��ł̃J���I�P�ɂ������ɁA�O�c�����u���̑O�쐴�ɂ���͂ł��Ȃ��v�ƌ����̂ł��B���́u���̓X�͗L�͓X�B�v�]�͕����ׂ��v�ƍR�c�B�u�N�[���E�t�@�C�u�Ȃ炢���m�炸�\���̑O��ɂǂԔ��ǂ��͂�点���Ȃ��v�A�u���ł����ƌ���������Ȃ����v�̉��V�����M���ĕ��i�����ȓ�l�������B�X���ɓ{���������ُ펖�ԂɁB�ł��A�Ō�͑O�c�����O�삳���������Ă���ĐÉ��̃L�����y�[���͖����������ɏI���Ƒ�����܂����B����̈Ⴂ�͂���ǔ���Ƃ����ړI�͈�B���܂͈�u�̂��̂ŁA�ނƂ͂��̌���F�D�W�������܂��B�������A���N��2���A�O�c���͋A��ʐl�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����Ɂu���ԁv�𗬂��������Ĕނ��Âт܂����B�ނ�ł����������F�肵�܂��B
�C���c�p�Y���悵���ꌾ
�@TBS���W�I���u�O�쐴 �j���[�~���[�W�b�N���̂��v�Ȃ���Ԃ�g��ł���܂����B���̒��ő��c�p�Y����ɃC���^�r���[�����݂܂����B�u�O�쐴���w���ԁx�A�X�i�ꂳ�w�~�̃����B�G���x�i���{���쎌�A���r���ȁj�������[�X����ȂǁA�����A���̉̎肪�j���[�~���[�W�b�N�n�̍�Ƃ̋Ȃ��̂��Ă��܂��B���̂�����̕������ǂ��v���܂����v�Ƃ̖₢�ɁA���c�����ĞH���u�����������������͋�����v�B���̑��c�߁I �̗w�E�̑�䏊�A�ј\�̈ꌾ�ł͂���܂����B
�@�uKIYOSHI�v�v���W�F�N�g�́A1983�N4��6���AFM�É��̊J�NjL�O�C���F���g�u���特�y���� KIYOSHI MEETS YOU�v�̃R���T�[�g�ňꉞ�̋����}���܂����B�����o������Tokyo-FM�u�j���[�j���[�W�b�N�E�i�E�v��DJ������Ă����]�_�Ƃ̈ɓ�������ƃf�B���N�^�[�̊�������B�O�쐴�𒆐S�ɃA���o���uKIYOSHI�v�ɎQ�������~���[�W�V���������ɓ��ʕҐ��̃R�[���X�� ���_���q�A�n�Ӑ^�m�q�A�����M�q��z���Ƃ������j�[�N�ō��ȃX�e�[�W�ƂȂ�܂����B�����A��{�����Q���̗\��ł������A���q�l�̓��w�����d�Ȃ����Ƃ̂��ƂŒ��O�ɃL�����Z���B����͂ƂĂ��c�O�ł����B
�@�u���ԁv�͑�q�b�g�ɂ͎��炸���A�O�쐴�̒��łِ͈F�́A�m��l���m�郍���O�Z���[���ȂƂȂ�܂����B���x�̍�{���̐����ɍۂ��A���f�B�A���A�[�e�B�X�g����]�Ƃ������ɐG��Ă��炸�A���������c�O�ł͂���܂��B�������Ȃ���A���̒��ł́A�Ӌ`�[���v���o�̋ȂƂ��Đ��������Ă��܂��B
�@���̌�A��{�����1983�N5�����J�̉f��u���̃����[�N���X�}�X�v(�哇���ē�)�ɔo�D�Ƃ��ďo���A�f�批�y���S�����e�[�}�ȁuMerry Christmas Mr. Lawrence�v����q�b�g�B�����1987�N���J�̉f��u���X�g�G���y���[�v�̉��y��S���B���{�l���̃A�J�f�~�[�܍�ȏ܂ɋP���A�u���E�̃T�J���g�v�Ƃ��ď[���̉��y�l�������ł䂭���ƂɁB���N�A�O�쐴�̓\���̎�Ƃ��ēƗ����ʂ����܂��B1982�`1987�N�́A��{�^�O��ɂƂ��āA���y�l���̈��]�@�̊��Ԃ��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���ł��B
(2) �����I��{�����
 �@��{����Ƃ͂ǂ�ȉ��y�Ƃ������̂��H ���͂���܂Ŕނ̍�i�́A�A���o���uKIYOSHI�v���^�̐��ȈȊO�A�قڃe���r�ł������������Ƃ��Ȃ��A��{����_���u�c�Ȃ͂������܂����Ƃ���B�ł��A���I���_����̊ϕ��Ȃ珑���邩������܂���B�ł́A�����I��{����ς��ǂ����B
�@��{����Ƃ͂ǂ�ȉ��y�Ƃ������̂��H ���͂���܂Ŕނ̍�i�́A�A���o���uKIYOSHI�v���^�̐��ȈȊO�A�قڃe���r�ł������������Ƃ��Ȃ��A��{����_���u�c�Ȃ͂������܂����Ƃ���B�ł��A���I���_����̊ϕ��Ȃ珑���邩������܂���B�ł́A�����I��{����ς��ǂ����B�@4��30���`5��5���A�����V���ɁuSOUND for LIFE ��{���ꂩ�琶�܂ꂽ���́v�Ƃ����Ǔ��L�����f�ڂ���܂����B�e�E�̂����X�̗��h�ȍ�{����_���W�J����Ă��܂��B���̒������ۂɎc�����t���[�Y�����L�B
�ނ��c�������y�́A�l�ނ̌|�p�����̉��y�̒��ŁA�{���̕��@��{����ւ̎v����^�������X���т܂��B�ł������̕��́A��ۂɎc���Ă��S�ɋ����Ȃ��B���y���������Ă��Ȃ��B���̓lj�͕s����������܂��E�E�E�E�E�B�Ƃ��낪���Ɉ�����A��̓I�Ȋy�Ȃ���ނ̉��y���̂��̂Ɍ��y�������͂�����܂����B��������L�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���X�ؓցA���q�Ɓj
���ɑ���D��S�Ǝ��O���q�킶��Ȃ��@�^�ɏ����ȁu�|�p�Ɓv�ł�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���q ��A��ȉƁj
�����Ŏ��s���낵�Ȃ��珃�x�̍������̂ݏo���Ă���iꠌ��h�V�AS.�\���O���C�^�[�j
�N���V�b�N��������Ɗw�ЂƂłȂ��Ə����Ȃ��i�����G���A�V���Z�T�C�U�[�v���O���}�[�j
�������͐����Ă��� ������V�������̂�Nj������ �̋C�T���������i����j
�ŏI�I�ɃT�E���h�A�[�e�B�X�g�̈�Ɏ������i�ɓ��M�G�A���y�]�_�Ɓj
���Ɖ��Ƃ̃V�X�e���A�ւ����Ă����悤�ȍ�i��������i����V��A�l�ފw�ҁj
��{����̓x�[�g�[���F���ɏd�Ȃ��Č�����i���R��q�A���q�ƁE�v���f���[�T�[�j
�h�r���b�V�[�ɓ���W�����E�P�[�W������̃q�[���[�Ƃ����i����j
�u�A�E�g�E�I�u�E�m�C�Y�v�Ƃ����A���o���́uhibari�v�i2009�j�Ƃ�����i�ł́A�����Ƀ����f�B�[�̖��͂Ɖ������u�����v���܂��E�E�E�����E�E�E�o�b�n�̉��y�ɂ�����������A���́u�v�������Ր��������A���͍�{����Ƃ����A�[�e�B�X�g�̖{���Ȃ̂��Ǝ��͎v���̂ł��i���R��q�j�@�������̍�i��you-tube�Œ����Ă݂܂����B2���߂̒P���ȃ����f�B�[��9���ԌJ��Ԃ���܂��B���̃Y�����Ɠ��̉A�e�݂����ĒP�Ȃ�J��Ԃ��łȂ����Ƃ͕������܂��B�����������A�g�����f�B�[�̖��͂������̌����̌������h���������܂���B�g�o�b�n�̉��y�ɂ����o����u�v�������Ր��h�����m�ł��܂���B���������ދ��Ȃ����B�����������グ���L�q�ł����c�O�ł����B
�@�ł��A����͂���Ƃ��āA�u���̃����[�N���X�}�X�v��u���X�g�G���y���[�v�ȂǁA��{���ꂪ�f�批�y�Ɉ₵�����Ղ͑傢�ɏ̎^�����ׂ��ł��傤�B�Ǝ��̐��E��z���Đ��E�Ɋ�����܂��l�����̂ł�����B
�@�o���Z���i�ܗ֊J��̂��߂̍����t���t���E�I�[�P�X�g���y�ȁuEl Mar Mediterrani�v�i1992�j��A�u���y�l�d�t�ȁv�i1970�N��j�̂悤�ȏ����y�A�uⵂƃI�[�P�X�g���̂��߂̋��t�ȁv�i2010�j�Ȃǂ̌��㉹�y������A�e�X�Ǝ��̖��͂�����܂��B
�@�uenergy flow�v�i1999�j��CM�ɂ��g��ꂽ���O������������X������i�A�S������鉹�y�ł��B�ł��ނ́u�l�̓q�[�����O���y�Ƃ����]�����͍D������Ȃ��v�ƌ����B�q�[�����O���̂��̂Ȃ̂ɁB�V�S�Ȃ̂��Ȃ��H
�@�ނ͂܂��u���A��j�A���v�����āu���a�v�u��Вn�̕����v�������܂��B���y�ƂȂ炻������y���Ă߂���� �Ǝv���̂ł����A���y�Ƀ��b�Z�[�W�ȂȂ��A�������̉��邾���Ɖ]���B����ɂ́A�u���y�ɗ͂Ȃ�āA�������܂����v�Ƃ��B�H��̃e�����Ȃ̂����m��܂���ˁB
�@��{����̓}���`�ȍ�ȉƂł��B���R�ȉ��y�Ƃł��B���̎��X���̎�܂܂ɍ���Ă����B���������܂��B���ݏo�������y�͑��l�B����Ț삵����i�̒��ŁA���Ƃ����Ԃ���Y�ꋎ���Ă��܂����Ƃ��A���ɂƂ��āA�ނ̃x�X�g�E�`���[���͕�����Ȃ��u���ԁv�ł��B�u���ԁv�͂܂������䂪��Аl���ň��̊y�Ȃł����B���̋Ȃ��₵�Ă��ꂽ��{����ɍő�̊��ӂ�����܂��B��{���ꂳ��{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�ǂ������炩�ɁE�E�E�E�E�B
���Q�l������
�����V���u���j�ɑz���v2023.4.23
�����V���uSOUND for LIFE�v��{���ꂩ�琶�܂ꂽ���� 2023.4.30�`5.5
NHK-BSP�u��{����100�N�C���^�r���[�v2023.4.8 O.A.
TV�����u�薼�̂Ȃ����y��v�`��{����̉��y�� 2023.4.22 O.A.
LP �uKIYOSHI�v�iRHL8809�jRCA ANOTHER���[�x��
2023.04.05 (��) �tࣖ��`WBC�A�����Ē����݂䂫
�i1�jWBC�͑�J�ĕ��̑����� �@3��9������2�T�Ԃ̓��{��WBC�ɖ�����ꂽ �܂���WBC�����̗l���ł����B���X�����C�^���A��ł̑�J�l����̃Z�[�t�e�B�E�o���g�B���������L�V�R��ł́A�g�c�̓��_3�����A���c��1mm�ƃX���[�o���g�A���_�l�o���̃T���i���ŁB�����A�����J��ł́A���i�`�ˋ��`�����G�`�ɓ��`�吨�`�_���r�b�V���`��J�̓��胊���[�B���ɍŌ�A�g���E�g�Ƃ̐^���������O�U�Œ��߂���J�ĕ��̉����͌㐢�Ɍ��p�����ׂ������̑�c�~�ł����B
�@3��9������2�T�Ԃ̓��{��WBC�ɖ�����ꂽ �܂���WBC�����̗l���ł����B���X�����C�^���A��ł̑�J�l����̃Z�[�t�e�B�E�o���g�B���������L�V�R��ł́A�g�c�̓��_3�����A���c��1mm�ƃX���[�o���g�A���_�l�o���̃T���i���ŁB�����A�����J��ł́A���i�`�ˋ��`�����G�`�ɓ��`�吨�`�_���r�b�V���`��J�̓��胊���[�B���ɍŌ�A�g���E�g�Ƃ̐^���������O�U�Œ��߂���J�ĕ��̉����͌㐢�Ɍ��p�����ׂ������̑�c�~�ł����B �@���̑��A�����͘b�薞�ځB�{��L�����v����_���r�b�V�����Â����F�c���ƃ_���m�A�k�[�g�o�[�̂��������T�V���c�ƃ`�[������ɂ����y�b�p�[�~���E�p�t�H�[�}���X�A�q���z�����P�����̕K�������u���痴���v�A���X�ؘN�l�т̃��b�e�َq�B�����āA�I�R�ē̐M����͂������������E��Ƃ����p�[�t�F�N�g�Ȍ����B���̂��ߗ��z�̏�iNO1�ɍՂ�グ��ꂽ�I�R�ēB�u����ȏ�i�������炢���̂Ɂv�ƌ����T�����[�}���ɁA�u�������͑�J�̂悤�ȕ����������炢���̂Ɂv�ƌ����Ă邺 �Ƃ̔��⑾�c�̃c�b�R�~���������������B
�@���̑��A�����͘b�薞�ځB�{��L�����v����_���r�b�V�����Â����F�c���ƃ_���m�A�k�[�g�o�[�̂��������T�V���c�ƃ`�[������ɂ����y�b�p�[�~���E�p�t�H�[�}���X�A�q���z�����P�����̕K�������u���痴���v�A���X�ؘN�l�т̃��b�e�َq�B�����āA�I�R�ē̐M����͂������������E��Ƃ����p�[�t�F�N�g�Ȍ����B���̂��ߗ��z�̏�iNO1�ɍՂ�グ��ꂽ�I�R�ēB�u����ȏ�i�������炢���̂Ɂv�ƌ����T�����[�}���ɁA�u�������͑�J�̂悤�ȕ����������炢���̂Ɂv�ƌ����Ă邺 �Ƃ̔��⑾�c�̃c�b�R�~���������������B�@�Ƃ܂��A���ǂ��떞�ڂ̑��ł����������͂���ς肱��B������O�A��J�̃��b�Z�[�W�̑S�������L�B
�l�������� �����̂���߂܂��傤 �t�@�[�X�g�ɃS�[���h�V���~�b�g��������Z���^�[��������}�C�N�E�g���E�g�����邵�O��Ƀ��[�L�[�E�x�b�c��������Ƃ� �싅������Ă���ΒN���������������Ƃ�����I�肪����Ǝv����ł����� ������������� ����ς蓲��Ă��܂��Ă͒������Ȃ���� �l��͍��� �����邽�߂� �g�b�v�ɂȂ邽�߂ɗ������ ������������͔ނ�ւ̓�����̂Ă� �����Ƃ������l���Ă����܂��傤 �����s�����I�I�@����ȑf���炵�����͕��������Ƃ�����܂���B�����O���̒����V���ɑ�J�̈ӋC���݂��ڂ��Ă��܂��āA����́u�݂�Ȃ������邱�ƂȂ��A�w���W���[�ɂ́x�Ǝg�ɂȂ�Ȃ��B���������̖싅���ł���悤�A��ɏ��Ă�Ɛ�ւ������v�Ƃ������́B���b�Z�[�W�͂���������ɏC�����������̂ŁA���j�I�����Ƃ����Ă����ł��傤�B���ʂȂ�u����͋�������������͎��ʋC�łԂ����Ă������v������ł��傤���B�ł����ꂶ��v���b�V���[�ɂ͑ł����ĂȂ��B�����̂͂����A�����ǁA������������͓����̂���߂悤�@�ƃX�}�[�g�ɂ܂Ƃ߂邩�畷�����҂͋C���y�ɂȂ�B����̓`�[���́A���Ɏ��s�b�`���[�ɂ͗������Ǝv���܂��B�ނ炪�A�����i�[���o���Ȃ�����A�y�U�ۂœ��ꂽ�̂���J�̌��t�̗͂����������m��܂���B�ł��Ă悵�A�����Ă悵�A�����Ă悵�A�����Ęb���Ă悵�̑�J�I��ł����B
�@���������{��a�I�Ƀ��C�o��������؍����f�B�A��WBC��]���Ă����R�����g���܂����B�u�싅�Ə����đ�J�Ɠǂށv�B�R���A�����݂䂫�́u���ɕt�����O���g�S�h�ƌĂԁv�i�����̕ʖ��j�Ɠ����H���Ɋ؍�����J�ɂ͒E�X������ �Ƃ������Ƃł��傤���B
�@���x�͂܂�����҂̗ǂ��������͂����肵�܂����B�Ⴆ�E�E�E�E�E��J�̍Ō�̈ꋅ�Ɂu�Ȃ�œ`�Ƃ̕X�v���b�g����Ȃ��ăX���C�_�[�������́H�v�Ȃǃg���`���J�������܂���̒�����B��J�̉��l����Z�[�t�e�B�E�o���g�Ɂu������������܂���B�N���[���A�b�v�ł�����v�ƈ�R�����w�\�}�K���̗����������B�I�E���Ԃ����� ������̃�����������B�����ɔ����āA�g�c��3�����̑O�Ɂu��������U����Ƃ��������Â�����v�ȂǁA�������̂������ʂŃs�^��������܂������������ȉ���͕����������\���ł����B
�i2�j�����݂䂫�j���[�E�A���o���ƍH���Í��̑削��
 �@3��1���A�����݂䂫�̃j���[�E�A���o���u���E������Č�������v����������܂����B�R���i�Ńc�A�[���ڍ��A3�N�Ԃ�̐V��Ƃ����đ傢�Ɋ��҂������̕s����������w�����܂����B���ʁA�M�������v���Ɉ��D���������D�����߂�����A�ς��ʑ��l�Ȋy�Ȃ̏W���ɁA�����݂䂫���݂������A���g�������ł����B
�@3��1���A�����݂䂫�̃j���[�E�A���o���u���E������Č�������v����������܂����B�R���i�Ńc�A�[���ڍ��A3�N�Ԃ�̐V��Ƃ����đ傢�Ɋ��҂������̕s����������w�����܂����B���ʁA�M�������v���Ɉ��D���������D�����߂�����A�ς��ʑ��l�Ȋy�Ȃ̏W���ɁA�����݂䂫���݂������A���g�������ł����B�@���[�~���Ȃǃr�b�O�ȃA�[�e�B�X�g�̐V�씭�����ɂ̓e���r�I�o���g��B�݂䂫�������ɂ��ꂸ�A�܂���NHK-BSP�uSONGS�����݂䂫���W�v������܂��āB�z�X�g�͑��m�A�Q�X�g�͍H���Í��B�A�V�X�^���g�i�s���Ƃ��đ��̒��Ԃ̌ˎ��d�K�B�����ŁA���ƌˎ����悹����̂�����H���Í��A���͌��́E�E�E�E�E�B
�@��w�b�h���C�g�E�e�[�����C�g�̉̏I���Łu�J���C�C�I�v�͂Ȃ����낤�A�R�m�[�I �Ŏn�܂�܂��āB�H������A���̋Ȃ̉��߂����܂��B
�����P���ɂ͎����̐g���ł����Ȃ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��� �����琯�C�R�[���撣��l�Ƃ����C���[�W�����ɂ͂���܂� �����Ŏ����̂��Ƃ������ł��Ȃ������莩���ɃS�[���n�_�����ꌩ���Ă��܂����Ƃ��ɁA����A���͂܂��I���Ȃ����đO���������Ă����͂����̋Ȃɂ͂���܂��@�܂��A���߂͐l���ꂼ��ł��� �Ƃ݂䂫��������Ă��邩��ے�͂��܂��A��a���͔ۂ߂܂���B��́A���ɂ͓�ʂ肠���Ď������P���ƌ����ċP���f��������킯�ŁB�ł܂����̉̂͑O������͂�^���Ă���� �Ƃ������́A�e�[�����C�g�͂��ǂ��Ȃ��̖̂����w�b�h���C�g�͌��ʂĂʖ����Ƃ炷�Ƃ����A�������ɂ��Đl���Ƃ�������W�X�ƒԂ����́@�Ɗ����܂��B
�@�ŁA�H������̉��߂͉��߂Ƃ��āA�ǂ������i��̓�l�B�u���̉��߂͍H������̃I���W�i���ł����B�Ȃ�Đ[���I ������ɂȂ�܂����v�Ɛ�^�̃��C�V�����B������Ƃ݂��Ƃ��Ȃ������Ȃ��B
�@�����̖́��i1983�N�̃V���O���j �̍u�߂ł��B�Q�l�̂��߂ɉ̎��̗v����B
�₳�������O���������́@������₷���ƌ���������@�H������A�܂��܂��A�ȏI���Łu�J���C�C�v�ł����B�����Č����ɂ́u����Ȃɖ��O�����邯�ǎ�����ʖڃl���Ă����̂Ȃ́B���̖��ɂ͎��͂Ȃ�Ȃ��B���̖��͂Ƃ��Ă��o���₷�����O�Ȃ�ł��傤�ˁv�Ƃ��܂����B�������Ă����J���i�C�B
���������Ă��炤�ɂ� �S�N�����Ă��܂�����
�悭���閼�O���������́@�Y��ꂸ�炢�ƌ��������
����Y��Ă��܂��ɂ� ��b�����Ă��܂�����
�䂤�q�����q��傤�q�����q�܂��q�����݂Ђ�q�܂��
�����悤�Ȗ��O�͂����������̂� ������ʖڃl
�@���̉̂̃R�R���́A�������̖����₳�����悭���閼�O�̎�����Ȃ̂ɁA�Ȃ�ł��̖��͈�����Ď��͑ʖڂȂ́H�Ƃ������́B���閼�O�́A�������̖��������́A�悭���閼�O�̏ے��Ȃ�ł��ˁB�H������͂��̊W�����u���ǁv�Ƃ����t�ڂ̐ڑ����Ōq����������B�����牽�����������̂��킩��Ȃ��Ȃ����Ⴄ�B����́A�c�O�ł����A���S�ȓǂ݈Ⴆ�ł��B
�@�ԑgOA����A�u���߂�����Ȃ��v�u�ז��Ȃ����v�u�J���C�C���ĉ��Ȃ�v�ȂǁA�H������A�l�b�g�ő削�サ�������ł��B�ԑg�̍Ō�ɃA���o���̌��ߊy�ȁu��Ɂv��PV�{�M�����J���������̂ŁA�����݂䂫�t�@�����������Ă����̂ł��傤�B������A�H������̉��߂����邱�ƂȂ���A�u���݂͂䂫����̓`���҂�v�݂����ȑԓx�ɁA�t�@���̊F����́u���Ȃ��ɉ�������̂�B�̂����Ɍ��Ȃ��Łv�ƕ����� �Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���̒����݂䂫�t����N.Y.������傢�ɂ������ŁA�削��b�͔ޏ����畷�������̂ł��B
�@�����́ABS�t�W2020�NOA�́u�P�������钆���݂䂫�v�̍ĕ����ł��B�����ł��H������͑傢�Ɍ���Ă��܂��B3���Ԃ̒�����̒�����A�H������̂�炩��������Ă锭�������X���o�����Ă��������܂��B
�@���߂Ɂ��n��̐� �ł̔����B�Q�X�g�̃X�m�[�{�[�_�[�␂����A�u�������߂Ē������݂䂫����̋Ȃ́A���w3�N���̎��A�ꂪ�����Ă��Ă��ꂽ���n��̐� �̃V���O���ł����v�ɍH������A�u������ăX�y�V����CD�ł���ˁB�J�b�v�����O����w�b�h���C�g�E�e�[�����C�g���Ⴀ��܂��v�Ɨ����B�u�n��̐��v�̃V���O����2000�N7��19��������w�b�h���C�g�E�e�[�����C�g�̃J�b�v�����O�Ղ��B��B�X�y�V�����ł��Ȃ�ł�����܂���B�m�������Ԃ�݂͂��Ƃ��Ȃ��ł���B
�@��ځB�H������́u�����݂䂫����͓��{�̃G�f�B�b�g�E�s�A�t���Ǝv���܂��v�Ɛ��ꂽ�B���A����͂��܂�ɔ����I��ʓI�ȍl�@�ł��B�s�A�t�̐��͗͋����Đ����͂�����A����͊m���ɂ݂䂫����ɒʂ�����̂ł͂���܂����A���F�����@���قڃ����p�^�[���B�݂䂫����̑��ʂ��Ƃ͉_�D�̍��ł��B����ɁA�݂䂫����́A���̑��ʂȉ̐��ő��l�ȉ̐��E��`���o���܂��B
�@�u����v�`�����Ƃ���������̂ւ̗D�����܂Ȃ����B�u�t�@�C�g�I�v�`��҂��ە�����͋����̐��B�u�d���ׂ��āv�`�ꂵ�ގ҂ւ̃G�[���B�u�����������҂����ׂ̈Ɂv�`�������҂ւ̎����B�u����݁E�܂��v�`���낵���܂ł̏��̏�O�B�u�a���v�`�x���J���g�ŘN�X�Ɖ̂��グ��̏��B�u���Ȃ����C�����Ă��邤���Ɂv�`��i�E�S���`�ʓI�m���E�r�u���[�g���@�B�u�C�v�`���炩�œ����Ȑ��F�B�u���v�`�D���������E�ȃe�C�X�g�B�u�z�[���ɂāv�`�m�X�^���W�b�N�ȃt�H�[�N���B�u�i�v���ԁv�`��X�P�[���̃h���́B�u�~���N32�v�`�▭�Ȍ����B�uNOBODY IS RIGHT�v�`�S�X�y���I�\�E�����B�u�|�̔s�ҕ�����v�`�ł��Ђ����ꂽ�҂ւ̋~�ϐS�B�u���b�v�`�Љ�I�����I�s�𗝂��B�u���̃����[�v�`�l���̐ۗ��E�E�E�E�E����ł��ƂĂ������s�����Ȃ������݂䂫�̉̐��E�I
�@���́A�݂䂫������A����Ђ���������A���ʂȉ̐��ő��l�ȉ̐��E��\�����鐢�E�Ɋ�����V���K�[�i�E�\���O���C�^�[�j �ƍl���Ă��܂��B����Ȃ݂䂫������H������́u���{�̃G�f�B�b�g�E�s�A�t�v�ƈꊇ���Ă��܂����B����͂��܂�ɂ��݂䂫�����m��ȉ߂��锭���ł��B�u���A�݂䂫����23���̊y�Ȃ���������Ă���́v�Ȃ�Ċ��ł��Ȃ��ŁA�݂䂫����̉̂������Ƃ�������ƒ����Ȃ����Ă��������������̂ł��B
�@�Ō�ɁB�i��҂��u�݂䂫����̉̂́A�N�����A���ꎄ�̂��Ƃ�`���Ă��邩�� �Ǝv�킹����̂��K�������Ȃ��ł��傤���v�ƌ����ƁA�H������A�u�ł����̋t������܂���B�����Ƀt�B�b�g������̂Ǝ����ɂ͑S�R�Ȃ���������`���Ă��ċ����Ƃ��A���ʂ���Ǝv���܂��v�Ɨ����B�݂䂫����̉̂����l�́A�e�X���v�X�̋����������Ď��B�i��҂͂��������Ă���킯�ŁA�u���̋t������܂���v�̓g���`���J���������Ƃ���B�����̂��Ƃ������Ă���Ă���Ɗ�����̂�����A���m�̐l�ԑ���m��Ȃ����E����Ă����̂�����B�R���A�|�p��i�̏펯�B�H�����l�b�g�ʼn��シ�闝�R������悤�ȋC�����܂��B
�@2020�N�ɒ��f�����݂䂫����̃R���T�[�g�����N�͕����������ȕ��͋C�ł��B���Ƃ��ẮA2016�N�u���v�ȗ�7�N�Ԃ�ƂȂ�܂��B�ĉ�ł��邻�̓��܂ŁA44���̃A���o�����瓖���̋ȖڂȂǂ�z�����A�y���݂ɑ҂������Ǝv���܂��B
2023.03.15 (��) ���ΐ�]�_��3�e�`�������ȕ]�_���ꂱ��
�i1�j ��搶�ɉE�ɕ킦�̊� �@�ґ���i1895-1987�j�Ƃ������y�w�҂���������Ⴂ�܂��B���{���y�w��n�݂Ɋւ��2��ډ�߂��킪�����y�w�E�̑咷�V�搶�B�{�͂͒Ҏ��̒��q�Ɋւ��邨�b�ł��B
�@�ґ���i1895-1987�j�Ƃ������y�w�҂���������Ⴂ�܂��B���{���y�w��n�݂Ɋւ��2��ډ�߂��킪�����y�w�E�̑咷�V�搶�B�{�͂͒Ҏ��̒��q�Ɋւ��邨�b�ł��B�@�u�ŐV���ȉ���S�W�v�S24��(���y�V�F��)�̓N���V�b�N�̖��Ȃ��قږԗ���������W�B���M�͍����ȉ��y�w�҂̐搶���B��i�̐����ߒ��A�����̏A��i���̂̓��e�\���ȂǁA�q�ϓI������c������ɂ͊i�D�̒���B��X���y���D�ƂɂƂ��Ă͂܂��Ƀo�C�u���I���݂Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B
�@���̒��̃V���[�x���g�F������ ��8�� �n���� �u�O���[�g�v�͒ґ��ꎁ�̎��M�B���̋L�q�����Ă݂܂��傤�B
1828�N3���\����͔ނ̎���9�����O�ł���[�ނ͑傫�ȕ����������āA�������������������Ȃ��ŁA���̑�����Ȃ��ɏ������낵���B�F�l�ɂނ����āu�̂͂�����߂��B�I�y���ƌ����Ȃ����ɂ���v�ƌ������Ƃ������Ă���قǂ��̋Ȃɖ����ɂȂ��Ă����E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�V���[�}������Ȏ҂̒�t�F���f�B�i���g�̂��Ƃł��̕����A��Ȃ��炿�傤��10�N���1838�N3��21���Ƀ����f���X�]�[���̎w���ŒZ�k�����`�ŁA���C�v�c�B�q�̃Q���@���g�n�E�X���t��ŏ������ꂽ�B�@���������ꂾ���̕��͂̒��ɊԈႢ��3����܂��B�`���b�g�������܂���(��)�B
�@�@��Ȃ����̂�1828�N�ł͂Ȃ�1826�N
�@�A�u�̂͂�����߂��E�E�E�E�E�v�͂��̂Ƃ��F�l�ɂނ����Č������̂ł͂Ȃ��A�ȑO�莆�ɏ���������
�@�B�������s��ꂽ�̂�1838�N�ł͂Ȃ�1839�N
�@�@�̓V���[�x���g�̑����ɂ�1828�N3���ƒ��M�ŏ����Ă���̂�����܂��d�����Ȃ��ł��傤�B�V���[�x���g�́A1826�N�ɏ����グ�������ȃn�������y�F����ɒ�o���邽�߂Ɏ�̎蒼�����������̂���L�̓��t�A�Ƃ������ƂȂ̂ł����͗ǂ��Ƃ��܂��傤�B�A�͏��X��肠��ł��B�V���[�x���g�́u�̂͂�����߂��E�E�E
�E�E�v�̃Z���t�́A1824�N3��31���A�F�l�N�[�y���E�B�[�U�[�ւ̎莆�ɏ����ꂽ���́B������g�i1828�N�Ɂj�������h��W�ԈႢ�ł��B���̎莆��������1824�N�ɉ̋Ȃ́i�莆�̂Ƃ���j6�Ȃ�������Ă��܂��A1828�N�ɂ͉̋ȏW�u�����̉́v�Ȃ�20�Ȃقǂ̉̋Ȃ�����Ă��܂��B�Ҏ��قǂ̕��Ȃ�A���o�I�ɂ����͊ԈႦ�Ȃ��łق��������A�Ǝv���܂��B�B�͔N����ԈႦ�������̒P���~�X�ł����A���͂��̃~�X���^�����e���̑傫���ł��B���̏��L����V���[�x���g�����ȑ�8�ԁu�O���[�g�v��CD������炻�̎�����E���Ă݂܂��傤�B
�n�ӌ쎁�i�J�[���E�x�[���w���F�x�������E�t�B���A������UM�j
��{�^�Վ��i�n�C���c�E���[�O�i�[�w���F�x�������������A�R�����r�A�j
�F����F���i�J�[���E�V���[���q�g�w���F��h�C�c�������A�R�����r�A�j
���ђ��Ǝ��i�t�����c�E�R�����B�`���j�[�w���F�`�F�R�E�t�B���A�R�����r�A�j
�x���C���i�w���}���E�A�[�x���g���[�g�w���F���C�v�c�B�q�������A���ԁj
�ēc���ꎁ�i�J�[���E�x�[���w���F�E�B�[���E�t�B��75�������C�u�AUM�j
�@�����̒�����A�n�C���c�E���[�O�i�[�w���F�x���������������y�c(1978�^�� �R�����r�A)�̃��C�i�[�m�[�c�𒊏o���܂��ƁB
���̌����Ȃ������V���[�}���́A�������C�v�c�B�q�̃Q���@���g�n�E�X�nj��y�c�̎w���҂����Ă��������f���X�]�[���̂��Ƃɑ������B�����f���X�]�[�������̋Ȃ����������̂�1838�N3��21���ł���B�@���̃��C�i�[�m�[�c�̒��҂͑�{�^�Վ��i1924-1995�j�B�킪�����y�w��̏d���ł��B���̌��Ђ��A�����N��1838�N�Ƃ̊ԈႢ��Ƃ��Ă���B�݂̂Ȃ炸�A��L5���̕��������~�X�����Ă��܂��i�����̒��ɂ́A�n�ӌ�A�F����F�Ƃ����d���̕��X���܂܂�Ă��܂��j�B���R�������܂ŏd�Ȃ�͂�������܂���B�����͖��炩�ł��B��L���y�]�_�Ə����́A�d���E�삯�o�����킸�A�V���[�x���g�̌����ȑ�8�ԁu�O���[�g�v�̃��C�i�[�m�[�c���M�ɂ����āA��l�ɒґ��ꎁ�̎�ɂȂ�u�ŐV���ȉ���S�W�v���A���������Ɉ��p�����A�Ƃ������Ƃł��B�����A��҂�Wikipedia�ہX���p�_���Ȃǂ����ƂȂ��Ă��܂����A��L���y�]�_�Ƃ̕��X�́u�ŋ߂̎Ⴂ�z�́E�E�E�E�v�Ȃ�Č����܂���ˁB
�@����ɉ��y�V�F�ЂɈꌾ�B�u�ŐV���ȉ���S�W�v�́A���C�i�[�m�[�c���M�ɂ����āA���t�@�����X�I���݂Ȃ̂ł�����A���̂��Ƃ��d�v�����ĕs�f�̌���ӂ邱�ƂȂ��A�d�Ŏ��ɂ͓K�ȉ����������Ă����Ăق����Ǝv���܂��B
�@���j��̎��ۂ͂��̌�̔��@�����ɂ���Ď��X���X�ƕς����̂ł��B�Ⴆ�Γ����ґ��ꎁ�̎�ɂȂ�u�ŐV���ȉ���S�W�v�x�[�g�[���F���F�����ȁ@��8�ԁ@�w�����@��i93�̍��̒��Ɂu�x�[�g�[���F���́w�s�ł̗��l�x�̓A�}�[���G�E�[�[�o���h�ł���E�E�E�E�E�v�Ȃ�L�q������܂����A����͊��ɃA���g�[�j�A�E�u�����^�[�m������ɂȂ��Ă��܂��B���̂����������������Ă��������������̂ł��B
�i2�j �������q�e���̂Ƃ�ł��Ȃ����t�Ɓu���R�[�h�|�p�v�]
 �@�X�����g�X���t�E���q�e���i1915-1997�j�Ƃ����E�N���C�i���܂ꃍ�V�A�̃s�A�j�X�g�B������̈���̗Y�E�G�~�[���E�M�����X�i1916-1985�j���ӔN�R��h�ɕϐg���_�o�̍s���͂������k�ȉ��t���|�Ƃ����̂ɑ��A�����܂ō�������ۂ��Ō�܂ŃX�P�[���̑傫�ȉ��t���т��ʂ��������s�A�j�X�g�ł����B
�@�X�����g�X���t�E���q�e���i1915-1997�j�Ƃ����E�N���C�i���܂ꃍ�V�A�̃s�A�j�X�g�B������̈���̗Y�E�G�~�[���E�M�����X�i1916-1985�j���ӔN�R��h�ɕϐg���_�o�̍s���͂������k�ȉ��t���|�Ƃ����̂ɑ��A�����܂ō�������ۂ��Ō�܂ŃX�P�[���̑傫�ȉ��t���т��ʂ��������s�A�j�X�g�ł����B�@����Ȕނ��������]���āi�H�j�Ƃ�ł��Ȃ��~�X�����ł��������t������Ă��܂��B���[�c�@���g�F�s�A�m���t�� ��27�� �σ����� K595�@�����̓x���W���~���E�u���e���w���F�C�M���X�����nj��y�c�A1965�N6��16���A�u���X�o�[�N����ł̃��C�u�^���ł��B
�@��1�y�� �A���O���B�����I�[�P�X�g���̑O�t���o��81���ߖڂɃs�A�m�̃\��������B4���ߌ�A���q�e���͂ǂ��������Ƃ��A85�`88���߂��I�~�b�g����89���ߖڂɔ��ł��܂��B���̂܂�4���߂��o�߂�����A�I�P�͛߂ޖ���88/89���߂̍����̎������B�\���͓����t���[�Y���J��Ԃ��M�N�V���N�����܂܃I�[�P�X�g���ƍ�������B���[�c�@���g�̏��������݂̂Ȃ����ꂪ���S�ɉ����~�߂��A�܂�ŊԂ̔��������c�Ȏp��I�悵�Ă��܂��܂����B����������͊J�n����̏o�����B�����҂ɗ^�����e���͌v��m�ꂸ�A�܂��ɋ����炵����ʃ~�X��Ƃ��Ă��܂������ƂɂȂ�܂��B�w���҂̃u���e���́A�o�[���X�^�C���Ɠ����n�D�̏����I�ő@�ׂȊ��o�̎�����B���̌�͐}�炸���܂��������ʂ̂Ȃ����t�ɏI�n���邱�ƂɂȂ�܂����B�u���e���̃V���b�N�̑傫�������������m��܂��B
�@�ł͂��̑厸�s���t�̔�]�͂ǂ����������H���R�[�h���̍ō����Ёu���R�[�h�|�p�v�̐V�����]�������Ă݂܂��傤�B
�u���e������ɂ����I�[���h�o�����y�ՂƓ��n�ōs��ꂽ�R���T�[�g�̃��C���^���W�ŁA���ڂ����̂́A��͂胊�q�e�����\���X�g�Ɍ}�������[�c�@���g�́�s�A�m���t�ȑ�27�ԁ₾�낤�B1965�N6��16���̉��t�ŁA50�ƂȂ��Ă܂��Ȃ����q�e���́A���̋����Ȃ�ł̖͂����ʂ��ꂽ���x�ȉ����_�炩���@�ׂɐ������āA���������킢�[�����t������Ă���B��1�y�͂͏����}�����݂��ȂƎv���邪�A����Ɋ����������Ă䂭���t�́A�_�炩�����������Ƌ��ɁA��i�ւ̐[�������ɗ��ł����ꂽ�e���������Ȃ��Ă���A�����L���ł���B�@�Ȃ�Ƃ������A�g���������ꂽ���x�ȉ����_�炩���@�ׂɐ������āh�Ƃ��A�g��i�ւ̐[�������ɗ��ł����ꂽ�e�����h�Ƃ��A�g�t���[�Y�P�ʂ̎��݂ȐL�k��K�x�ɐD������Ȃ���h�Ƃ��A�g���ʊ��̂���^�b�`�h�Ƃ��A�g����I�Ȍ����h�Ƃ��A�T���h�C�b�`�}�����ɂ����A�u�������Ă����J���i�C�v�\�������X�Ƒ����Ă��܂��B�܂��A�����͂���ȏ�Njy�������܂��A�̐S�Ȃ̂́A��������A�N�������Ă��ꔭ�Ŕ��郊�q�e���̃X�b�Ƃ��ɂ͈ꌾ���G��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����āA���̉��t���x�^�J�߂��ċP���u���E�v���ł��Ă��܂��B����Ɍ��]�ғ�l�����E����Ɓu���I�v�ɔF�肳��܂�����A���̑O�㖢���̌����t���u���R�[�h�|�p�v���́u�����̓��I�Ձv�ɍՂ�グ�Ă��܂����Ƃ����킯�ł��B�@�̍莁�̓��R�[�h��Џo�g�������ڂɌ���Ƃ��āi�j�A���q���͂�����Ƃ��������|��o�B���̕����X�b�Ƃ����������Ƃ͂ǂ��l���Ă����_���䂫�܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�̍�a�F ���E�j
BBC�������^�̉����ɂ���A�̃V���[�Y�Ƃ��āA���t�ƂƂ��Ẵu���e�������[�c�@���g�����t�����ۂ̃��C�����W�߂��ꖇ���o�ꂵ���B���t�Ȃ̗��Ȃ̂Ł��27�ԁ�̃s�A�m���t�Ȃ���R�����g���悤�B�������u���e���̓R���`�F���g�̃\���X�g�Ƃ��Ă��\���ɒe����r�O�������킯�����A�����ł̓C�M���X�����nj��y�c��U���Ďw���҂Ƃ��ă��q�e���Ƌ������Ă���B�u���e���̖_���������߂ɕ~���߂��O�~�̏�ŁA���q�e���̓t���[�Y�P�ʂ̎��݂ȐL�k��K�x�ɐD������Ȃ���A�����O�̖��x�̍������y���J��L����B���ʊ��̂���^�b�`�ƁA����I�Ȍ����ɂ�郂�[�c�@���g���߂̌��{�̂悤�ȏG�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���q���u ���E�j
�@���ΐ쎁�́u������������]�Ɓw���E�̖��x�v�̒��ŁA�u�Z�Z�Ȃ�l���̖��_�̂��߂ɂ����A�����A�ނ͂��̃��R�[�h�i�����́u�V���E���v�j�̑�3�y�͂��Ȃ������̂ł��낤�B�������̂ɋC�����Ȃ��Ƃ�������ƒp�����������ƂɂȂ�v�Əq�ׂĂ����܂��B���̌��ɏ]���A�̍�A���q�����͒������ɏ��������A�����Ă��C�Â��Ȃ��������̂ǂ��炩�ɂȂ�܂��B�ǂ���Ȃ̂���[�ǂ��͂��܂��A�ǂ���ɂ��Ă��厸�Ԃɕς��͂���܂���B�������Ȃ̂͂��̃��R�]�����Č���CD���Ă��܂������y�t�@���̕��X�ł��B�ł��܂��A����ɂ́A�u���e���̃s�A�m�ɂ��u�s�A�m�l�d�t�� �g�Z��K478�v�ƃG���[�E�A�������N�̏��̃��e�b�g�u�x��A��ׁA���K�Ȃ鍰��vK165�̑f���炵�����t���J�b�v�����O����Ă���̂ŁA�\�����͎���ł��傤�B���ƂɃs�A�m�l�d�t�Ȃ͂��̖��Ȑ����i�̖����t�ł��B
�@��ȉƃx���W���~���E�u���e���i1913-1976�j�̃��[�c�@���g���t�ƂƂ��Ă̐����ƃX���@�g�X���t�E���q�e���̍����߂���p�t�H�[�}���X�̑Δ䂪�Ռ��I���ʔ����A���̈Ӗ��ł͒��Ղɂ��ċM�d�ՁB����͂ƂĂ����l����CD �Ƃ����邩������܂���B
�@�������L���鐔�疇��CD�̒��ɂ́A���̂悤�Ȓ������Ղ��܂��܂����݂��܂��B����܂����Ă������Љ�ł���Ǝv���Ă��܂��B
���Q�l������
�ŐV���ȉ���S�W������ȕ�1��i���y�V�F�Ёj
CD �u�u���e���A���[�c�@���g�E�R���T�[�g�v�i�L���O���R�[�hKKCC7011�j
���R�[�h�|�p2000�N4�����i���y�V�F�Ёj
�u�V��45�v 1991�N8����(�V����)
2023.02.15 (��) ���ΐ�]�_��2�e�`�u�����X�e���I�^�C�v�I��]�p
 �@����2��قǗՔ�����ꂽ���߁A����ƍ�����ΐ샂�m�ɖ߂�܂����B��1�e�ŏ������悤�ɉ��ΐ쎁�̂��Ɏ�����ʈËL�͂ɐG������āA�����A�����������A�Ȃ�ł��ۈËL�Ƀg���C���Ă݂܂����B����Ă݂��̂����_�[�r�[�n�ƗL�n�L�O�n�̊ۈËL�B�ǂ����ċ����n�Ȃ̂��H ����A��͂�A��N�́u�N�����m�v4���ɓo�ꂵ���J���O�q����̎����n�T�������Ă���e�����ƁB �ޏ��̎����n�͂Ƃɂ��������ł��B���ƈႢ�n��^�������B�����n�͂���܂ŒʎZ100���z���A���N�ɓ����Ă���A���W�[�k(�V�n��/�ʐ^)�A���[�h�A�N�A�Ƃ���2�����Ă��܂��B�T�����ƂĂ��y���݁B�܂�Ŏ����̔n�̂悤�Ɏv���Ă��邩��s�v�c�ł��B�����N���V�b�N������Ƃ����ˁA�Ə���ɔO���Ȃ��牞�����Ă���܂��B
�@����2��قǗՔ�����ꂽ���߁A����ƍ�����ΐ샂�m�ɖ߂�܂����B��1�e�ŏ������悤�ɉ��ΐ쎁�̂��Ɏ�����ʈËL�͂ɐG������āA�����A�����������A�Ȃ�ł��ۈËL�Ƀg���C���Ă݂܂����B����Ă݂��̂����_�[�r�[�n�ƗL�n�L�O�n�̊ۈËL�B�ǂ����ċ����n�Ȃ̂��H ����A��͂�A��N�́u�N�����m�v4���ɓo�ꂵ���J���O�q����̎����n�T�������Ă���e�����ƁB �ޏ��̎����n�͂Ƃɂ��������ł��B���ƈႢ�n��^�������B�����n�͂���܂ŒʎZ100���z���A���N�ɓ����Ă���A���W�[�k(�V�n��/�ʐ^)�A���[�h�A�N�A�Ƃ���2�����Ă��܂��B�T�����ƂĂ��y���݁B�܂�Ŏ����̔n�̂悤�Ɏv���Ă��邩��s�v�c�ł��B�����N���V�b�N������Ƃ����ˁA�Ə���ɔO���Ȃ��牞�����Ă���܂��B�@���āA�ۈËL�̕��ł����A�_�[�r�[�n�����J�^�J����h�E�f���[�X�܂�89���B�L�n�L�O�̓��C�W�q�J������C�N�C�m�b�N�X�܂�67���B�S156���A���ׂē��̒��ɃC���v�b�g�������܂����B�R���A�{�P�h�~�ɂ͍œK�Ȃ�ł��ˁB���̏�A�Ԃňړ������ދ������ɍςނ�ł��B�ڂɓ���Ԃ̃i���o�[�̉���P�^�ɓ��Ă͂܂�n�����ĂыN�����B�Ⴆ�A�Ԕ�1741�Ȃ�1941�N�̃_�[�r�[�n�̓Z���g���C�g�B2405�Ȃ�2005�N�̃_�[�r�[�n�̓f�B�[�v�C���p�N�g�ŗL�n�L�O�̓n�[�c�N���C�Ƃ�������B�_�[�r�[��1932�N����s���Ă���̂ŁA����P�^�ŋȂ̂�23�`31�ƊJ�Â���Ȃ�����(19)45��46�����B����ȊO�͑S�����Ă͂܂�̂ő����Ă���Ԃ̂ق�9���͊Y������B�Ȃ̂ŁA�R�����\�y���߂܂��B�ł͂��낻��{��ɓ���܂��傤�B
�@���ΐ앶���Ń����ʂɋ������Ă����]�Ƃ̒��ł���ۖڗ����݂��u���h���Y�搶�i1926-2001�j�ł��B���̕��A���N�u���R�[�h�|�p�v�̌��]�������A���y���D�҂̑傫�Ȏw�j�ƂȂ��Ă��܂����B���ΐ쎁�̎u���]�͂���Ȋ����ł���܂��B
�E�E�E�E�E���̓K���h�̑�\�̈�l�Ɏu���h���Y������B�ނ̏�������́g�����������h�͂��������E�p�^�[���ŁA���Ƃ��A�}���i�[���z�߂�Ƃ��ɂ́u���t�̓}���i�[�̃C�M���X�l�I�C�����悭�\�ꂽ���̂ŁE�E�E�E�E�v�A�u�A�o�h�͂�͂�C�^���A�l�����ɁA�����������e���n�̍�i���w��������Ƃ��̎��͂�����v�A�u�������Ƀ��[�}�j�A�o�g�̃R�~�b�V���[�i�̖_�͂����������m�I�ȉ��y�����Ɠc���I�ȋC�����E�E�E�E�E�v�Ƃ����������ɂ͂Ă��Ȃ������Ă䂭�B�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A���̕M�@��^����ΊȒP�ɎO����]���o���オ��B�u�ނ́Z�Z�l������A�Z�Z�̋ȂƔ��������������A�⊶�Ȃ����͂����Ă���v�B�@���́Z�Z�̂Ƃ���ɉ�������������̂ł���B
 �@���̎苖�ɁA��N�A�Ђ��Ȃ��Ƃ����ɓ������u���h���Y�u�V�ŁE�s�ł̖��Ȃ͂���CD�Łv�Ȃ�K�C�h�{������܂��B���̖{�ɂ͎u�����������낵�̖��Ȗ������1300�_�����f�ځB���ΐ�]�_�𗧏���̂ɂ���ȏ�̏��͂���܂���i��ؗm�V���肪�Ƃ��j�B�ł́A����Ȏu��������p�������Ă݂܂��傤�B
�@���̎苖�ɁA��N�A�Ђ��Ȃ��Ƃ����ɓ������u���h���Y�u�V�ŁE�s�ł̖��Ȃ͂���CD�Łv�Ȃ�K�C�h�{������܂��B���̖{�ɂ͎u�����������낵�̖��Ȗ������1300�_�����f�ځB���ΐ�]�_�𗧏���̂ɂ���ȏ�̏��͂���܂���i��ؗm�V���肪�Ƃ��j�B�ł́A����Ȏu��������p�������Ă݂܂��傤�B���N�[�x���b�N�̕\���́A�`�F�R�X�����@�L�A�o�g�������A�K�x�Ƀ��}���e�B�b�N�ŁA���Ȃ₩�ȕ\��������Ă���i���[�c�@���g�F�����ȑ�39�ԁA���t�@�G���E�N�[�x���b�N�w���F�o�C�G�������������y�c�̉��t�]�j
�������ɂ������^�[�炵�����i���������邪�E�E�E�E�E�i���[�c�@���g�F�����ȑ�40�ԁA�u���[�m�E�����^�[�w���F�R�����r�A�����y�c�j
���N�����C�^���X�Ȃ�ł͂��i���̍����ƁA��ۂ̂悳�ɂЂ���閼���ł���i�x�����I�[�Y�F���z�����ȁA�A���h���E�N�����C�^���X�w���F�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�j
�����ƂɁA�����̉̂킹���ȂǁA�C�^���A�l�Ȃ�ł͂����̂��B�i�����f���X�]�[���F�����ȑ�3�ԁu�X�R�b�g�����h�v�A�N���E�f�B�I�E�A�o�h�w���F�����h�������y�c�j
���V���C�[�̓C�^���A�l�������A�����̉̂킹�������Q�ɂ��܂��A���̖���I�[�P�X�g���̖L���ȋ����𑶕��ɐ������Ȃ���A�͋������t���s���Ă���i�t�����N�F�����ȁA���b�J���h�E�V���C�[�w���F�A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�j
���S�̂ɁA�����^�[�Ȃ�ł͂��_�a�ȃu���[���X�ƂȂ��Ă��邪�E�E�E�E�E�i�u���[���X�F�����ȑ�1�ԁA�����^�[�w���F�R�����r�A�����y�c�j
�����̔��M�I���t�́A�܂��ɂ��̋����Ȃ�ł͂����̂ł���i�u���[���X�F�����ȑ�1�ԁA�E�B���w�����E�t���g���F���O���[�w���F�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�j
���h�C�c�E�I�[�X�g���A�n�ȊO�̎w���҂́A���̋Ȃ̗����悤�ȉ̂̐��i�������������邱�Ƃ��������A�X�E�B�g�i�[�́A�I�[�X�g���A�o�g�������A�Ȃ̑Έʖ@�I�Ȑ��i���悭���݁A����g������������������Ă����i�u���[���X�F������ ��2�ԁA�I�g�}�[���E�X�E�B�g�i�[�w���F�x�����������̌���nj��y�c�j
�������ɂ��������B���X�L�[�炵�����т��т����s���\���ŁE�E�E�E�E�i�`���C�R�t�X�L�[�F�����ȑ�6�ԁu�ߜƁv�A�G�t�Q�j�[�E�������B���X�L�[�w���F���j���O���[�h�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�j
���`�F�R�X�����@�L�A�̎w���҂ƃI�[�P�X�g���̉��t�������A�X���u�����̌��̂����������������悤�Ȗ������ɂ��ӂꂽ���t���i�h���H���U�[�N�F�����ȑ�8�ԁu�C�M���X�v�A���@�[�c���t�E�m�C�}���w���F�`�F�R�E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�j
�@�o��͏o��͎u���� �Z�Z�����ɁA�Z�Z�Ȃ�ł͂́A�����ɂ��Z�Z�炵�� �̃I���E�p���[�h�I�ŏ���1���قǂōő����̂��肳�܁B�o�J�o�J�����̂ł�����ł�߂Ă����܂����A�܂��ɉ��ΐ앶���ɋU��Ȃ��ł��B�ŁA���ł����H �\�\�C�^���A�l�͐����̉̂킹�������܂��B�`�F�R�X�����@�L�A�̉��t�Ƃ́A�X���u�����̌��̂�����悤�Ȗ�����������B�������A�K�x�Ƀ��}���e�B�b�N�ł��Ȃ₩�ȕ\������B�I�[�X�g���A�̎w���҂͑Έʖ@�I�Ȑ��i���悭���ݓ���g������������������� �\�\�ł����āH���̍��̉��t�Ƃ݂͂ȓ����悤�ȉ��t��������ȁB�������قǂ̉�ꐫ�B����Ȃ���A�̋ɂ݂Ƃ��������悤������܂���B
�@�ŗL�����ŁA�Z�Z�Ȃ�ł͂� �Ƃ���������Ă��A�Z�Z��m��Ȃ��l�ɂ͎��������߂��A�ǂ�ȉ��t�Ȃ̂����T�b�p���`����Ă��Ȃ��B���ꂶ�ᔃ���Ă����̂��ǂ�������Ȃ��B
�@�����M�������]�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�Ⴆ�A�F����F���`�u���ǂ��������|�I�ȃt�H���e�B�b�c���Ő����炷��ʂ́A���Ȃ��爫���̍������B�N�i�b�p�[�c�u�b�V���́w���܃@���₪��x�Ƃ��������������Ă���悤�ł��邪�A���̗V�тɂ͖����q�����Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�i�N�i�b�p�[�c�u�b�V���u�E�B�[���̋x���v�`�u�o�[�f�����v�ւ̌��y�j�B�Έ�G���`�u���Ƃ��̃W�������Ɋւ��Ă͉E�ڍ�ᾂ���K�v�͂Ȃ��B���킸���̃Z�b�g�������̂ł���v�i�V���[���h���E���F�[�O�u���[�c�@���g�F�f�B���F���e�B�����g�W�v�̐��E���j�B�u���搶�Ƃ͌��ƃX�b�|���B�܂�Ŕ��͂��Ⴄ�B�����ɂł����ł����Ĕ��������Ȃ镶�͂ł͂���܂��B
�@���āA����܂łʼn��ΐ앶���ɊԈႢ�Ȃ����Ƃ�������܂����B��������ȏ�̃��T�[�`�͕s�v�Ȃ̂ł����A�Ō�ɂ���������A�u���搶�Ȃ�ł͂̉��t�]�̑S����t�����������Ă��������܂��B
�}�[���[�̒�q�������^�[�A�����^�[�̒�q���o�[���X�^�C���A���̂܂���q���C���o���ł���B����4�l�́A����������_���l���B�C���o�����A�}�[���[�̉��y�����Ɩ��Ē��̂��̂Ƃ��Ă���̂́A�܂��ɂ����������̗���ɂ����̂ł��낤�B�����ł��A�C���o���́A�����ɂ����_���l�炵���A�����������Ղ�ƁA�L��ȉ��F�ʼn̂킹�Ă���A���ƂɁA���x�߂̃e���|�ł�������ƕ\�������I�y�͂ȂǁA���炵���B�^�����D�G���i�}�[���[�F�����ȑ�3�ԁA�G���A�t�E�C���o���w���F�t�����N�t���g���������y�c�j�@4�l�̉��y�Ƃ����_���l�̌��ňꊇ��ɂ��Ę_���Ă���B�܂��ɂ���A�u�������I��]�̋ɒv�Ƃ���������ł��B
�@���ΐ앶���ɂ͂܂���]�Ɛ搶�ƃ��R�[�h��Ђ̊W�ɂ��Ă̂���ȋL�q������܂��B�H���u���]�̐搶���̍s������齉��Ƃ����݉��Ƃ����̂������āA���R�[�h��Ђ̘A���͂��傢���傢�A��Ă������B�����͂�����R�[�h��Ђ��B�c�L�A�C�������Ɓi�Ⴆ�u���R�[�h�|�p�v�́j���]�́g���E�h������Ƃ����āA�S���҂͂������Ƃ��������ċ����B�����₩�Ȉ��ݑオ�A���R�[�h��ЂƐ搶�������т����J�ƂȂ�A���]�Ɏ�����������B�܂��A�����Ă��̐搶�̓��C�i�[�E�m�[�g�i���R�[�h�t���̉�����j���������Ă��炤���A���̂���ɁA�܂������t�ł�������A��������Y��Ȃ��B����̓��R�[�h��Ђ̐搶���ւ̌`��ς��������Ȃ� �Ƃ͂����茾���҂�����B���̌��ʂ������Ă��A�����ł��퓅��������ׂ������݂Ȍ��]���A�܂��܂����������Ȃ��̂ɂȂ�E�E�E�E�E�v
�@���������ΐ쎁�A���R�[�h��ЂƔ�]�Ƃ̖������Y�o���������ĂĂ��܂��B���]�����������ɑ��Ă䂭�̂͊m���ɔ�]�Ƃ̐ӔC�ł͂���܂����A�����������̂̓��R�[�h��Ђł��B���R�[�h��Ђ͉��������]�҂́g���E�h�Ƃ������n�t�������߂�B�h���E�g�̓�������Β��g�Ȃǂ��ł������B����́h���E�g����������グ�̌���łɂȂ邩��ɂق��Ȃ�܂���B�Ȃ��Ȃ�A�i��������ΐ쎁�ɂ��j���R�[�h���D�҂̂قƂ�ǂ��A��]�Ƃ����ɗ��ʗc�t�Ȑl�����ŁA��������Ȃ��̔��f���A�ЂƂ��Ɂh���E�g�̗L���ɒu���Ă��邩�� �Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
 �@�������R�[�h��Ђʼnc�ƂɌg����Ă���1970�N�゠����̐V��������c�̈��������Ă݂܂��傤�B�{�Ђ̃N���V�b�N�S���҂��c�Ə��ɂ���Ă��Ă����v���[�����܂��`�u�����̈ꉟ���̓h�~���S�`�X�R�b�g�`�����@�C���̃��F���f�B�w�I�e���x�S�ȁB�����͔Ղł��B�C�j�V�����i�V���̏������j��傢�ɂ͂���ł��������v�B������ĉ�X�c�Ƃ́u���܂�����A�K���w���R�[�h�|�p�x�́h���E�g���l���Ă���������B�����łȂ���Α�ʂ̕ԕi�������Ă��܂��܂�����v�Ɨv���B�u�撣��܂��v�ƒS���ҁB�����A��������S���҂͌��]�Ґ搶�������A�h���E�g�l����簐i����E�E�E�E�E���ꂪ���R�[�h��Ђ̎p�ł����B���͌��]�ҔԂ��������Ƃ͂���܂��A�ԐړI�ɁA�搶���́g�����݂Ȍ��]�̑��h�̈�[��S���Ă������ƂɂȂ�܂��ˁB���́u�I�e���v�ł����H�m���u���R�[�h�|�p�v�����E�~�܂肾�����ƋL�����Ă��܂��B
�@�������R�[�h��Ђʼnc�ƂɌg����Ă���1970�N�゠����̐V��������c�̈��������Ă݂܂��傤�B�{�Ђ̃N���V�b�N�S���҂��c�Ə��ɂ���Ă��Ă����v���[�����܂��`�u�����̈ꉟ���̓h�~���S�`�X�R�b�g�`�����@�C���̃��F���f�B�w�I�e���x�S�ȁB�����͔Ղł��B�C�j�V�����i�V���̏������j��傢�ɂ͂���ł��������v�B������ĉ�X�c�Ƃ́u���܂�����A�K���w���R�[�h�|�p�x�́h���E�g���l���Ă���������B�����łȂ���Α�ʂ̕ԕi�������Ă��܂��܂�����v�Ɨv���B�u�撣��܂��v�ƒS���ҁB�����A��������S���҂͌��]�Ґ搶�������A�h���E�g�l����簐i����E�E�E�E�E���ꂪ���R�[�h��Ђ̎p�ł����B���͌��]�ҔԂ��������Ƃ͂���܂��A�ԐړI�ɁA�搶���́g�����݂Ȍ��]�̑��h�̈�[��S���Ă������ƂɂȂ�܂��ˁB���́u�I�e���v�ł����H�m���u���R�[�h�|�p�v�����E�~�܂肾�����ƋL�����Ă��܂��B�@����Ȃ���ȂŁA���R�[�h��Ђ̌��]�҂ւ̋����͓��풃�ю��������킯�ł��B��������ΐ앶���ʂ�ł��ˁB���R�[�h��Ђ̌��]�҂ւ̋��������]�̍��������w�����@ �Ƃ�������B�u���h���Y�搶�����̗�ɂ���Ȃ������B����ǂ��납��Ԃ̂����艮�������Ƃ��E�E�E�E�E���R�[�h��Ђ̌��]�ҔԂ́A����Ȑȑ�搶�̂���������āA������C��ꂵ�����Ƃł��傤�B����J���@���������܂��B
�@�u�������͂��߂Ƃ��āA���Β��Y�A��ؐ����A��n�����A����g�j�e���́u���R�[�h�|�p�v���]�҂������Ń��b�^�a�肵�����ΐ�́u�V��45�v�́A�����������Z���Z�[�V�����������N�����܂����B����͂����ł��傤�A�l�Ԃ́A�B���Ă��������^����˂�������A�{��ɂ��E���^�G����̂ł�����B���ΐ���ĒN�H �Ƃ�ł��Ȃ��z�A�����Ă����Ȃ��ȂǁA���ΐ�T�����n�܂�܂����B���l�ɂ��A���ΐ삳��͂��Ȃ��ł����H�̖₢���킹�������̂悤�ɂ������ƕ����܂��B�ł���Ȃ͔̂Ɛl�T���ł͂���܂���B���ΐ쎁���w�E����u��]�̑��v���҂͐^���Ɏ~�߂ăX�L���E�A�b�v��}�邱�Ƃ��d�v�������̂ł��B��������30�N�]�B���{�̔�]�͑����甲���o�����̂ł��傤���H ����Ƃ��A���R�[�h���b�c�̔���グ�����́A����Ȃ��Ƃ͈ӂɉ�Ȃ��������肾���Ă��܂����̂ł��傤���H ������ɂ��Ă��A���R�[�h�Y�ƂɌg��������̂Ƃ��āA�ꖕ�̎₵������������̂ł���܂��B
���Q�l������
�u�V��45�v 1991�N8����(�V����)
�u�V�ŁE�s�ł̖��Ȃ͂���CD�Łv �u���h���Y���i�����V���Ёj
�F����F����I�W3�u���ȂƂƂ��Ɂv(�w�K������)
�u���[�c�@���g �x�X�g101�v�Έ�G�ҁi�V���فj
CD�N�i�b�p�[�c�u�b�V��/�E�B�[���̋x���iKING RECORD�j
CD�V���[���h���E���F�[�O/���[�c�@���g�E�f�B���B���e�B�����g�W�iCAPRICCIO�j
2023.01.11 (��) 2022�^2023�N�܂������y���]
�@�V�t��1�e�́u���ΐ�v2���l���Ă��܂������A1�_�ǂ����Ă��������y�Ȃ��������߂ǂ��������̂��Ǝv�����点�Ă����܁A���̔N���N�n��TV���f�����ɂȂ��ʔ����������ƂɋC�Â��A������������Ƃɂ��܂����B���ΐ샂�m�͏����������܂��B �@�܂����グ�����̂́A��N7��14���A�p���̃V�����E�h�E�}���X�����L��ōs��ꂽ�p���ՃR���T�[�g2022�iNHK-BSP 11��27��O.A.�j�ł��B�I�[�P�X�g���̓t�����X�����nj��y�c�B�w���̓N���X�e�B�A���E�}�`�F�����B1980�N���[�}�j�A���܂�A�����̗L�]���ł��B�Ȗڂ͂��ׂĐe���݂₷�����̂���B�Q�X�g�����ʂł݂ȑf���炵���B�ߔN����y���߂��R���T�[�g�ł����B
�@�܂����グ�����̂́A��N7��14���A�p���̃V�����E�h�E�}���X�����L��ōs��ꂽ�p���ՃR���T�[�g2022�iNHK-BSP 11��27��O.A.�j�ł��B�I�[�P�X�g���̓t�����X�����nj��y�c�B�w���̓N���X�e�B�A���E�}�`�F�����B1980�N���[�}�j�A���܂�A�����̗L�]���ł��B�Ȗڂ͂��ׂĐe���݂₷�����̂���B�Q�X�g�����ʂł݂ȑf���炵���B�ߔN����y���߂��R���T�[�g�ł����B�@�R���i�O�͔N���A�A�p���g�}��������ăp���ɑ؍݁A�t�����X�̂����炱������삯����قǂ̃t�����X�D���ȉ䂪�]���̐^�������Ɂu����ł����čs�����C�ɂȂ��āv�ƁA����DVD�𑗂��Ă��Ƒ��тł����B�R���T�[�g���i�݁A�����߂��ĕ��Ȃ��݁A�₪�Ĕw��̃G�b�t�F��������̂Ƃ�Ƌ��Ƀ��C�g�A�b�v�����B�Ȃ�Č��z�I�I�^�������Ȃ炸�Ƃ��S�[�W���X�ȃp���̏��ɐ��������ЂƎ��ł��B
�@��N�́A�G���U�x�X�������������ꂽ���߂��A�C�M���X�ő�̉��y�C���F���g�u�v�����X���y�Ձv���J�Â���Ȃ������悤�ŁA�ꖕ�̎₵���������Ă����̂ł����A�u�p���ՃR���T�[�g�v�͕���ė]�肠��f���炵���ł����B�Ƃ���ŁA�����\���X�g�̒��ōۗ����Ă����̂̓\�v���m�̃i�f�B�[���E�V�G���ƃs�A�m�̃A���X�E�їǁE�I�b�g�̓�l�ł��B
 �@�i�f�B�[���E�V�G���̓A�����J���܂�̎��\�v���m�̎�B���ڂ̓��F���f�B�F�u�֕P�v����u�����A���͂��̐l���`�Ԃ���Ԃցv�B�L�т₩�Ȕ����ƖL���ȕ\���͂œ��X����p�t�H�[�}���X���I���܂����B�e�p�[��A�X�^�C�����Q�A�L���[�g�ȘȂ܂��B�܂�ŁA�p���̎Ќ��E��Ȋ�������l���E���B�I���b�^�̐����ʂ��̂悤�B���̃A���A�͂܂��\�v���m�̋Z�ʂ𑪂�ɂ͊i�D�̋Ȃł����A�䂪��ł͓��X��A�����N�B�����\�v���m�̎�̑��l�҂̓A�X�~�N�E�O���S���A�����Ǝv���܂����A�ޏ���ǂ��������Ԏ肪���̃V�G����ł͂Ȃ��ł��傤���B����̊��y���݂ł��B
�@�i�f�B�[���E�V�G���̓A�����J���܂�̎��\�v���m�̎�B���ڂ̓��F���f�B�F�u�֕P�v����u�����A���͂��̐l���`�Ԃ���Ԃցv�B�L�т₩�Ȕ����ƖL���ȕ\���͂œ��X����p�t�H�[�}���X���I���܂����B�e�p�[��A�X�^�C�����Q�A�L���[�g�ȘȂ܂��B�܂�ŁA�p���̎Ќ��E��Ȋ�������l���E���B�I���b�^�̐����ʂ��̂悤�B���̃A���A�͂܂��\�v���m�̋Z�ʂ𑪂�ɂ͊i�D�̋Ȃł����A�䂪��ł͓��X��A�����N�B�����\�v���m�̎�̑��l�҂̓A�X�~�N�E�O���S���A�����Ǝv���܂����A�ޏ���ǂ��������Ԏ肪���̃V�G����ł͂Ȃ��ł��傤���B����̊��y���݂ł��B �@�A���X�E�їǁE�I�b�g�̓O���[�O�F�s�A�m���t�� ��3�y�� �����t�B�S�g�ʼn��y�ɂԂ���������̏�M�ƌ���Ȃ������͂ɉ��͑劅�тł����B
�@�A���X�E�їǁE�I�b�g�̓O���[�O�F�s�A�m���t�� ��3�y�� �����t�B�S�g�ʼn��y�ɂԂ���������̏�M�ƌ���Ȃ������͂ɉ��͑劅�тł����B�@�A���X�̎p�́A�I�N�T�[�i�E���[�j�t�w���F�~�����w���E�t�B���Ƌ����������[�c�@���g�F�s�A�m���t�� ��13�� �iNHK-BSP 2022�N2��1�� O.A.�j�ł��q�����Ă��܂������A���[�c�@���g�̉��y�ɖv���������ĉ��y�����т�̒����甭�U������悤�ȉ��t�ɂ����������������̂ł��B�܂��ʂ̔ԑg�i�u�U�E�q���[�}���vNHK-BSP 2022�N7��30��OA�j����A�ޏ��͐��N�O�ɓ�a�E�������d���ǂɜ�茻�ݓ��a���ƒm��܂����B�܂��A���̕a�͓V�˃`�F���X�g �W���N���[�k�E�f���E�v���i1945-1987�j�̖������̐Ⓒ���ɒD�����a�C�ł��B�A���X�������鉹�y�����т̕\��́A���g�̒u���ꂽ���琶�܂��A��u��u���ɂ���C�������o��̕\��Ȃ̂�������܂���B�A���X�ɂ́A���ꂩ����A�ł�����蒷�����t�Ɛl�������łق����A�ƋF��݂̂ł��B
�@�]�k�ł����A�I�N�T�[�i�E���[�j�t�͋C�s�̏����w���ҁB���̘r����2021�N�̃o�C���C�g���y�Ղɓo�ꂵ�Ă��܂��B���ڂ́u���܂悦��I�����_�l�v�B�͋����Ƃ��Ȃ₩����▭�Ɍ���������ޏ��̎w���Ԃ�́A�A�X�~�N�E�O���S���A���̈��|�I�̏��Ƒ��܂��āA�����ł����B
�@���āA�N�����������U�͍P����E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g2023�ƂȂ�܂��B���N�̎w���̓t�����c�E�E�F���U�[�E���X�g�B�n���E�B�[���o�g�A3�x�ڂ̓o��ł��B����͂��Ă����A����x�̂��ꂽ�̂̓v���O�����B�Ō�ɒu����邨���܂�́u���������h�i�E�v�`�u���f�c�L�[�s�i�ȁv�ȊO�A�悭�m��ꂽ�Ȃ͊F���I �������A�����c�����n���̒탈�[�[�t�̋Ȃ��S15�Ȓ�9�Ȃ��߂�Ƃ������ق��B���������[�[�t�̖��ȁu�V�̂̉��y�v���u�I�[�X�g���A�̑��߁v�̓i�V�B
�@����͎w���҃E�F���U�[�E���X�g�̏��]�������ŁA�y�c�̃��C�u�����A���Ȃǂ́u�}���ق���������فA�͂Ă͈�ʉ��y���D�Ƃ܂ň�N������Ŋy�����W�߂܂����v�Əq���B�V���g���E�X�ꑰ�̖���G�h�D�A���g���́u���[�[�t�͓��ʂ̍˔\�̎�����B���E�ς��S���Ⴄ�v�A�܂��A���y�w�҂́u���[�[�t�̋Ȃ͎��G��̗ǂ����y�̉��ɋ����قǐ[���Ȑ��E���L�����Ă���v�Ɨ�^�B�W�҂͂��̓��ق�����v���O�������Ȃ�Ƃ��������H���悤�Ɩ�N�ɂȂ��Ă���B����ȋC�����܂����B
�@���p�[�g���[�����Ă��邱�ƂŗL���Ȗ��w���҃J�����X�E�N���C�o�[�i1930-2004�j�ł��A�^�N�g��������1992�N�̃j���[�C���[�ŁA�u���ƈ�ȁv�u�g���b�`�E�g���b�`�E�|���J�v�u�E�C���U�[�̗z�C�ȏ��[�������ȁv�Ȃǂ̗L���Ȃ��L���[�[�t�̖���2���v���O�����ɓ���Ă��܂����B��������ƁA�E�F���U�[�E���X�g�́A�V���[�x���g�̂悤�ȉ��₩�ȕ��e�Ɏ����킸�A���Ȃ�̕ϐl�H�Ȃ̂�������܂���B�ނ̍���ɒ��ڂ������Ǝv���܂��B
�@����ɂ��Ă��A���̐���オ��͂����܂������̂�����܂��āB����قǂ̃X�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����͂Ƃ�ƌ������Ƃ�����܂���B�j���[�C���[�̒��O�͐V�������m�D���Ȃ̂��Ȃ��A�Ȃ�Ďv�Ă��Ȃ��猩�Ă�����A���N�̎w���҂̔��\������܂����B�N���X�e�B�A���E�e�B�[���}���ł��B2019�N�ɑ���2�x�ڂ̏o���ł��ˁB2019�N�͎������S���������̔N�B�����AFM���ǂ���ŁA������e�[�}�ɓ��Ԃ���������Ƃ����������v���o����܂��B
�@���̓��̗[���ɂ́A�����P��ƂȂ����ǂ��炪�{�����Ă��������|�\�l�i�t���`�F�b�N�i�e�����n�j������܂��āA���y���m���K���܂܂�܂��B���N�̓W���Y�o���h�ƌ��y�Z�d�t�ł����B
�@�W���Y�o���h�́A�����L���[�o���{�[�C�YVS������w�̃o���h�B��������Ɏ���Q�����܂������A�����ɊO��B�v���̃L���[�o���{�[�C�Y���t���t���ƃ����n�����Ȃ��A������w�͉����N�b�L���Ɨ������悭�����������̂ŁB
�@���y�Z�d�t�́A���z70���~�̃X�g���h�ƃK���l��VS���y�����Ŏ�Ă������z600���~�̊y��B����܂��O��I�e�����ɂ܂������}�g���Ȃ��A�I�n�㉹�̂܂܁B���ꂶ��y��̗D�����������͂����Ȃ� �Ǝ��ȕٌ삷����A�ԈႢ�͊ԈႢ�B���e���̈�Ȃł��B
�@���N�O�A�\�v���m�̃v���Ɖ��吶�̕�����ׂŁA���|�I�ɉ��吶�̕������܂��āA�قڑS���O�ꂽ���Ƃ�����܂����B�Ƃ܂��A���y���m�͂Ȃ��Ȃ�����B����Ȓ��ŁAGACKT�l��71�A����B���B������ԑg�̔���Ȃ̂ł��傤���A�ǂ����Ă��ُ킷���܂��B��点�^�f���o��̂����R�ł��傤���B
�@1��3����NHK�j���[�C���[�E�I�y���R���T�[�g�B���N�̎i��͉��o�Ƃ̋{�{���厁�B�����̓e�L�p�L�b�����傳��ł����A����͂ǂ������킯�����g�`�����ڗ����܂����B��N���A�i��̒h�ӂ݂�������Ƃ��ڂ��Ȃ��āA�n���n���̂��ʂ��B������͂��̂�����������܂���B����I
�@�����ւ䂭�ƁA�g���̍���̋��{�ނ����̎i��Ԃ�͂������ł����B���o�ɂ��ւ�炸�A�����邱�ƂȂ��I�n���X������́B���킢����Ɏ����킸�_��������Ă���̂��ȁB�g���ł͂܂��A85�E���R�Y�O���R���T�[�g�����I����錾�B�̂��͒����̖��ȁu�C ���̈��v�B�䂪�w������̓���̃X�^�[ ��叫�A����ꂳ�܂ł����B
�@�����āA�Ȃ�Ă������ă��[�~���B���ʎd���Ă�Call me back���̂��I����āA����ŃI�V�}�C�� �Ǝv�����u�ԁA�\���̂Ȃ������u���Ǝʐ^�v���̂��o�����̂ɂ͑労���B���̋ȁA���̃��[�~��No.1 Favorite Number�Ȃ��̂ŁB�R�����Ȃ̎������₶�Ⓦ�\�\�Y�������������\��Ō�������ł����̂���ۓI�ł����B�\�\�Y����A���[�~������ȂˁB
�@�I�y���R���T�[�g�ɓo�ꂵ���̎�̒��ŋC�ɂȂ����̂̓e�m�[���̑��l�� ����h����B�\���Ԃ́u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv���̂����̂ł����A���܂蒲�q���悭�Ȃ��āB������N��I�Ȑ������H�Ƃ��v���܂������A62�͘V�����ލł͂Ȃ��悤�ȁB���䎁�ɔ�ׂ�A81�̃v���V�h�E�h�~���S��76�̃z�Z�E�J�����X���A����26���A�u�p���@���b�e�B�ɕ������ւ̃R���T�[�g�v�Ə̂���W���C���g�E�R���T�[�g���s���̂͂܂��Ɋ�֓I �ƌ����Ă�����������܂���B
 �@�����̓o��̎�̒��ł͂Ȃ�Ă������ĐX���G����ł��B���̐l�A�����e�p���������Đ�����������B���݂킪���I�y���E�ŗB�ꖳ��̃X�^�[�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�̂����̂̓h���H���U�[�N�̉̌��u���T���J�v����A���A�u���Ɋāv�ł����B
�@�����̓o��̎�̒��ł͂Ȃ�Ă������ĐX���G����ł��B���̐l�A�����e�p���������Đ�����������B���݂킪���I�y���E�ŗB�ꖳ��̃X�^�[�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�̂����̂̓h���H���U�[�N�̉̌��u���T���J�v����A���A�u���Ɋāv�ł����B�@�u���Ɋāv�́A��N�A���w�̓������J���O�q����̈˗��ŃJ�Z�b�g�e�[�v��CD����Ɓi���̌��̓N�����m4���ɏ����Ă��܂��j���s�����Ƃ��ɁA�u�����Ȃ��Ȃ��v�ƈ�ۂɎc���Ă����Ȃł��BCD�����������̒��ɁA�ޏ��̑��ƍZ�ł��铌���w�|��w�̑��Ɛ����W���R���T�[�g�u�����܂��Ⴍ���̉�v(1991�N��1993�N�ɊJ��)�Ƃ����̂�����܂��āB�����ŁA�Ï��p�q����Ƃ����\�v���m�̕����J������̃s�A�m�ʼn̂����Ȃ̈���u���Ɋāv�������Ƃ����킯�ł��B
�@�Ï����J������R���r�́A���̑��ɁA�h���H���U�[�N�u�䂪��̋����������́v��n�[���F��̌��u�����[�E�E�B�h�E�v����u���B���A�̉́v�������B�J������͂܂��A1987�N����ł̃��T�C�^���ŁA�\�v���m�̐X���I���q����Ɓu�E�B�[�� �킪���̊X�v�Ȃǂ����t���Ă��܂��B����炪�Ȃ��Ȃ��f�G�ň�ۓI�������̂ŁA�莝����CD����������o���A���X�����������肵�āA���E�̖��̎�ɂ��u���B���A�̉�50%�v�Ƒ肷��v���C�x�[�gCD�Ȃ����܂����B���V�тŃR���g���[������ꂽ�肵�܂��ĂˁB����܂��Ɂg�J������̋����������́h�Ƃ������Ƃ���B��ʂ̉̂������т�����l�܂�����X�̏o���������̂ŁA����CD�A�������������ꂽ�J������Ɍ��悵�܂����B���̃��C���A�b�v�����L�B�����͘^���N�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�u���B���A�̉́v 50��
01 �G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v(S) 1962
02 �O�͖ق� with�j�R���C�E�Q�b�_(T) �^�}�^�`�b�`�FPO
03 �G���U�x�X�E�n�[�E�b�h(S) 1973
04 �O�͖ق� with���l�E�R��(T) �^�J�������FBPO
05 �A���l���[�[�E���[�e���x���K�[(S) �^�w�����[�g�E�c�@�n���A�XO
06 �o�[�o���E�w���h���N�X(S) �^�t�H�X�^�[�FPO 1992
07 �o�[�o���E�{�j�[(S) �^�}���R���E�V���i�C�_�[�iP�j2002
08 �}���K���[�^�E�f�E�A�����[�m(S) �`�����r�b�V���Ώ�2005
09 �X���G(S) �^��ؗD�l(P) 2022 (TV �u�薼�̂Ȃ����y��)���v
10 �W�����E�R���g���[��(ts) �}�b�R�C�E�^�C�i�[(P)
�@�@�@�@�W�~�[�E�M�����\��(b) �G�����B���E�W���[���Y(ds) 1963
�@ �@�h���H���U�[�N�F�̌��u���T���J�v�`���Ɋ�
11 ���^�E�V���g���C�q(S) �^�Q�[�x���F�x���������� 1958
12 �K�u���G���E�x�j���`�R���@�^�m�C�}���F�`�G�RPO 1982
�@ �@�h���H���U�[�N�F�킪��̋�����������
13 ���B�N�g���A�E�f�E���X�E�A���w���X(S) �^�u���R�X�FSoL 1965
14 �}�O�_���i�E�R�W�F�i�[(S) �^�}���R���E�}���e�B�m�[(P) 2007
15 �A���i�E�l�g���v�R(S) �^���B���[���F�v���nP 2008
16 �V�[�`���X�L�[�F�E�B�[���A�킪���̊X
�@�@�@�@�G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v(S) �^�A�b�J�[�}���FPO
�@�u���Ɋāv�́A���̐����T���J�������鉤�q���v�����Ɏ���̐S���f�I������̉́B�X���G����̓��T���J�̐Ȃ��v����������Ղ�ɉ̂��グ�܂��B�܂��ɐ�i�̉̏��ł����B����A�u���B���A�̉�50%�v�ɉ����ĐV�҂���낤���ȁB�Ȃ�čl���Ȃ���A����͂��̕ӂŁB�����́u���ΐ�v��2�e�Ƃ����܂��傤�B
2022.12.14 (��) �H�̐M�B�`�R���T�[�g2�A��
�@���삩�瓌���Ɉڂ�Z�͍̂ŏ��̓����I�����s�b�N�̔N������A���ꂱ��58�N�B�E�[���A���Ƃ������̂��I���̊ԁA�����\����Ԃ����x�����������͒m��Ȃ����A2�T�A���ōs���������͍̂����߂Ă̂悤�ȋC�����܂��B���̐l�����̌��̃L�C�E�p�[�\���͖命�䂳��B�e�������t�����������Ă��������Ă��鉹�y���Ԃł�����v�w�̌��т̎�ł�����l���̉��l�I�F�l�ł��B�命���͓��呲�ƌ�O�H�����ɋΖ��A�t�B�i���V��������̃g�b�v�߁A�ސE��͊C�O�����̃R���T���e�B���O��Ђ�ݗ��A���쌧�o�ς̋��Z�ʂł̌����ߓI���݂Ƃ������锪�\���s�̎ЊO������A����ɂ͑�w�̔��u�t�߂�ȂǁA���������o�ϐl�Ƃ��Ċ��Ă��܂��B����Ȕނ���悵������̃R���T�[�g�ƃ`�P�b�g���v���[���g�������������y����R�����2�T�A���s��ꂽ �Ƃ����킯�ł��B����́A���ΐ���m���J�艄�ׂ��āA�}篁u�ӏH�̐M�B �R���T�[�g2�A���v�ɐ�ւ������Ă��������܂��B�i1�j��1�T�`��{�R���T����`�@���@�L�O�R���T�[�g�F�C�V���݂ق���̃s�A�m���t
 �@��1�T��11��19��(�y)�A�命�������N�C�s���s���Ă��钷��̑T���E���T���ɊW����F�l�Ɍ������R���T�[�g�ŁA����2�x�ڂ̊J�ÂƂȂ�܂��B��1��́A2019�N�A�命������`�@���@�̕Ƃ��Ċ��J�ÁB���̃A�b�g�z�[���ȕ��͋C�͂ƂĂ��D�]�ł����B3�N�Ԃ�ƂȂ����͖̂��_�V�^�R���i�̉e���ł��B
�@��1�T��11��19��(�y)�A�命�������N�C�s���s���Ă��钷��̑T���E���T���ɊW����F�l�Ɍ������R���T�[�g�ŁA����2�x�ڂ̊J�ÂƂȂ�܂��B��1��́A2019�N�A�命������`�@���@�̕Ƃ��Ċ��J�ÁB���̃A�b�g�z�[���ȕ��͋C�͂ƂĂ��D�]�ł����B3�N�Ԃ�ƂȂ����͖̂��_�V�^�R���i�̉e���ł��B�@�s�A�m�̊C�V���݂ق���͖命���̎O�H��������̏�i�̂��삳��B�p���������y�@�Ɋw�уC�^���A�̃C�u�����ۃs�A�m�R���N�[����3�ʓ��܁B�����Č��݂́A���{����_�ɉ��Ċe�n�Ń��T�C�^���A�����y����ϋɓI�ɍs���A����ɂ́A�R���T�[�g�̃v���f���[�X���i�̎w���ɏ�M�𒍂��ȂǁA���̊����͑���ɂ킽���Ă��܂��B
�@���͑P�����ɂقNj߂��|�����P�������z�[���B�ӔN�̊����k�ւ��s�����������z�{�ɖ{����u���I�َq�̘V�ܒ|�������I�[�i�[�́A�̍��Y�����e100���قǂ́A���R���T�[�g�̎�|�ɂ҂�����̃z�[���ł����B�Ȗڂ͈ȉ��̒ʂ�B
J.S.�o�b�n�i���t�}�j�m�t�ҋȁj�F���@�C�I�����E�p���e�B�[�^��3�Ԃ̃v�������[�h
�h�r���b�V�[�F�x���K�}�X�N�g��
�V���p���F�M��
�V���p���F�J����O�t��
�x�[�g�[���F���F�s�A�m�\�i�^��14�ԁu�����v
�@�C�V������́A�m���ȃe�N�j�b�N�ƒ��B�I�Ŗ����ȃs�A�j�Y���̎�����B�D���ȃs�A�j�X�g�̈�l���V���[���E�`�F���J�X�L�[�i1909-1995�j���Ƃ������Ƃł��B
�@���t�ɐ旧���Ė命�����爥�A�B3�N�Ԃ�̊J�Â���сA��������������|�����|���В��ւ̌����q�ׂ��܂����B�����A���悢��C�V������̓o��ł��B
�@���t�}�j�m�t�ҋȂ̃o�b�n�̃v�������[�h�ʼn��t���X�^�[�g�B���������N�b�L���ƍۗ������x�������ȕ\���ŁA�`�F���J�X�L�[�̒e���V���R���k�i�u�]�[�j�ҁj��f�i�Ƃ����Ă���܂��B
�@�h�r���b�V�[�́u�x���K�}�X�N�g�ȁv�͊C�V�����ӂ̉��ځB���N�O�̔ޏ��̃��T�C�^���ŋȉ�����������Ă������������Ƃ����������v���o���܂��B4�Ȃ���Ȃ�g�Ȃ̑�3�ȁu���̌��v�͒P�Ƃʼn��t����邱�Ƃ������l�C�ȂȂ̂ŋߍ��������@����\����܂����B���Ȃ����A�ǂ��������F�l�b�g���Ƃ��Č�������ł���悤�Ȃ��̂���B���͂��̋ȁA�~�V�F���E�x���t�̂悤�ȃL�����ƒ��܂������t���D���Ȃ̂ł����A�ŋ߂Ȃ��Ȃ����̎�̉��t�ɂ��ڂɂ�����Ă��Ȃ��̂ł��B�����ւ䂭�ƁA���̓��̊C�V������́u���̌��v�̓i�C�X�ł����B�����ȃ^�b�`�ŝR��x�g���Ȃ����ɑu�₩�Ȍ㖡���c���Ă���܂����B����̓V���p����2�Ȃ����l�̈�ۂł����B
�@�x�[�g�[���F���u�����\�i�^�v�́A���l�����V���^�[�v���u���̌����~�蒍�����c�F�����̔g�ɗh�炮���M�̂悤�v�ƌ`�e������1�y�͂ƃ_�C�i�~�b�N�ȑ�3�y�͂̑Δ䂪�A���z���Ƒu�������ۗ������āA�����������\���ȉ��t�ƂȂ�܂����B
�@�O���������A���̊C�V������R���T�[�g�͋Ȃ��ƂɊy�����Ă��߂ɂȂ邨�b�����݂Ȃ���i�݂܂��B������R���T�[�g���S�҂ɂ��]���������B���������ԂŃG�X�R�[�g���Ă��ꂽ�킪�]���̎O�j�r������u�N���V�b�N�̉��t��ɂ͂قƂ�Ǎs�������Ƃ��Ȃ�����ǁA�����̂͂ƂĂ��y���������v�Ƃ̊��z�����ɏq�ׂĂ��܂����B
�@����A���ɂƂ��Ă͂��̓��̃x�[�g�[���F���̃G�s�\�[�h���ƂĂ������[�����̂ł����B����͂���Șb�ł��B
�@�x�[�g�[���F�����u�����\�i�^�v�����悵���̂̓s�A�m�̒�q�ŋM���̖��W�����G�b�^�E�O�C�`�����f�B�������B��l�͑��v�����̊ԕ����������A���e�́u�g���̒Ⴂ���y�Ƃɂ����̖��͂��Ȃ��v�Ƌ����Ȃ������B�Ƃ��낪�A�W�����G�b�^��������������͂Ȃ�Ɖ��y�Ƃ������I ���̖��̓��F���[���E���x���g�E�t�H���E�K�����x���N�B�t�H���͋M���̈�B���e�́g���@���h�x�[�g�[���F���ł͂Ȃ��g�t�H���h�K�����x���N��I�B�܂�͍˔\�����g����D�悵���Ƃ������Ƃł��B
�@�V���p�����u�J����v���������̂͒n���C�ɕ����ԃ}�����J���ł����B�����Ă����x�̕a�̐×{�����˂����l�W�����W���E�T���h�Ƃ̓����s�ł������A�����ɗB�ꎝ�Q�����y����J.S.�o�b�n�́u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�������̂ł��B����J.S.�o�b�n�ƃV���p���̂Ȃ���B�h�r���b�V�[�u���̌��v�ƃx�[�g�[���F���u�����\�i�^�v�̂Ȃ���B�H�v���Â炵���v���O�����ł��B�A�R�[�X�e�B�b�N�ȋ�ԂɁA�X�^�C���E�F�C���ؗ�ɖL���ɋ������A�S���܂�f�G�ȃR���T�[�g�ł����B
�i2�j��2�T�`�T�C�g�E�E�L�l���̃}�[���[�u��9�v
�@��2�T��11��26���i�y�j�A����z�N�g�����z�[���ōs��ꂽ�A���h���X�E�l���\���X�w���F�T�C�g�E�E�L�l���E�I�[�P�X�g��(SKO)�̉��t��B����Ɍ������V�����̎ԑ����猩����ԎR�͈�T�O�ƈ���ĎR������������ቻ�ς����Ă��܂����B�݂̂�ȂŊy�����߂��������c�̕ʑ����C�t�����������v���o���܂����B
�@���t��ł́A�v���Ԃ�ɏ]���̎o���A�^���q�Ƃ߂��݂ɉ�܂����B���̂߂��͍��T�͒��j�̑s�����A��Ď��̑���}�������Ă���܂����B���ӁI �o�̐^�������͏�q��w����̓������E�֔��]�q������B�ւ���̖����Z�C�W�E�I�U�����y�������̍L��Ɍg����Ă��āA���̊W�ʼn��t������ꏏ���邱�ƂɂȂ����Ƃ̂��Ƃł��B�ւ���́u���q����҂̉�v�Ƃ��������Ԓ��w�Z�̓��{�ꋳ�t�B�s�o�Z�ȂǂŊw�Z�ɂ��܂�s����Ȃ������l��A�O�����痈�ē��{�ꂪ�悭������Ȃ��l�����Ƀ{�����e�B�A�ŋ����Ă���ƕ����܂����B�^�ɑ��l�̂��߂ɂȂ邱�Ƃ��Ŏ��H���Ă���B���h�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B��l�͑��ƈȗ�50�N�Ԃ�̍ĉ�����悤�ŁA����Ɉꔑ�����ւ���ƁA��x���܂ł�����ׂ肵���Ƃ��B�����Ȃ̐^������t�����X��̋��t�����A�t�����X��w�Ȃ̊ւ����{�ꋳ�t�����Ă���p���h�N�X�I���ʓ��傢�ɐ���オ��A���̒��Ŏ��̘b���o�āA�ւ��R���T�[�g�̊��z�����]���ꂽ�Ƃ̂��ƁB�ȉ��͂��̊��z���ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�g�E�E�L�l���̃}�[���[�F������ ��9�� �j����
 �@���̉��t��́A�Z�C�W�E�I�U�����{�t�F�X�e�B�o��30���N���ʌ����Ƃ��āA�w���Ƀ{�X�g�������y�c���{�����ŗ������̃A���h���X�E�l���\���X���}���čs��ꂽ�B
�@���̉��t��́A�Z�C�W�E�I�U�����{�t�F�X�e�B�o��30���N���ʌ����Ƃ��āA�w���Ƀ{�X�g�������y�c���{�����ŗ������̃A���h���X�E�l���\���X���}���čs��ꂽ�B�@�t�F�X�e�B�o���̑��ē��V���������3���O��11��23���A4�N�Ԃ��SKO���w���B���t���ꂽ�x�[�g�[���F���́u�G�O�����g���ȁv�͎�c���ꂳ�؍݂��鍑�ۉF���X�e�[�V�����ɓ͂���ꂽ�B���V����́u���y��ʂ��āA�������ɏZ�ޓ����l�ԓ��m�A�݂�Ȃň�ɂȂ�邱�Ƃ��肢�܂��v�ƃR�����g�B��c����́u��������̎w���ŐS�h���Ԃ��鉉�t���F���Ƃ��������ȂŒ������Ƃ��ł��ċ��������܂�܂���v�ƕԂ��B���y��ʂ��Ēn���̈��J���肤���{�ƉF���̌�M���b�Z�[�W�������B
�@���t��̋Ȗڂ̓}�[���[��ȁF������ ��9�� �j�����B���ēƎw���҂Ƃ̑ł����킹�ŁA�l���\���X�͑�7�ԁu��̉́v���Ă������A���V���́u9�ԁv��ؖ]���āA���̉��ڂɗ����������Ƃ����B���V�ɂ̓}�[���[��9�Ԃɓ��ʂȎv�����ꂪ����B��Ȏ҂̃}�[���[���u9�ԁv�ɂ͓��ʂ̎v��������B�܂��́A�}�[���[���u9�ԁv�Ƃ��������ȂɊ��v������J���Ă������B
�@ �}�[���[�������u9�ԁv�ւ̎v��
 �@�x�[�g�[���F���͐��U��9�̌����Ȃ���Ȃ������A����ɑ��������ȍ�ȉƃu���b�N�i�[�A�h���H���U�[�N�A�}�[���[���9�Ȃ��c���Đ����������B�N���V�b�N�̐��E�ł́A������u9�Ԃ̎v�Ƃ��u��9�̃W���N�X�v�ȂǂƂ������A���ۂ�����܂Ƃ��Ɉӎ������̂̓O�X�^�t��}�[���[�i1860�|1911�j�����������̂ł͂Ȃ��낤���B
�}�[���[���A�g�u�����ȑ�9�ԁv���������玀�ʁh�Ƃ������|�ɂ������s���ɋ���Ă����̂͊m���Ȃ��Ƃ̂悤�ł���B1908�N�Ɋ������������Ȃ́A���Ԃ���́u��9�ԁv�Ɩ��Â���͂��̂��̂����A���ۂɂ́A�ԍ������Ō����ȁu��n�̉́v�Ɩ��������̂͂��̕\��ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�x�[�g�[���F���͐��U��9�̌����Ȃ���Ȃ������A����ɑ��������ȍ�ȉƃu���b�N�i�[�A�h���H���U�[�N�A�}�[���[���9�Ȃ��c���Đ����������B�N���V�b�N�̐��E�ł́A������u9�Ԃ̎v�Ƃ��u��9�̃W���N�X�v�ȂǂƂ������A���ۂ�����܂Ƃ��Ɉӎ������̂̓O�X�^�t��}�[���[�i1860�|1911�j�����������̂ł͂Ȃ��낤���B
�}�[���[���A�g�u�����ȑ�9�ԁv���������玀�ʁh�Ƃ������|�ɂ������s���ɋ���Ă����̂͊m���Ȃ��Ƃ̂悤�ł���B1908�N�Ɋ������������Ȃ́A���Ԃ���́u��9�ԁv�Ɩ��Â���͂��̂��̂����A���ۂɂ́A�ԍ������Ō����ȁu��n�̉́v�Ɩ��������̂͂��̕\��ɑ��Ȃ�Ȃ��B�@�}�[���[�̍ȃA���}�́u��z�^�v�ɂ́A�u��9�ԁv�ɂ��ċ͂�����̒��q������E�E�E�E�E�u�ނ́i1909�N�́j�Ă̊ԂɑS�͂��X���Ďd�������A�w��9�ԁx�������������B�����A��������̖��ŌĂԂ��Ƃ��������B�~�ɂȂ�Ɩ��N�̃E�B�[���ł̐����������A�������̏C���ƃI�[�P�X�g���[�V������i�߂Ă����v�i�u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�A���}�E�}�[���[���A�Έ�G�������Ɂ��j�Ƃ������̂��B
�@����ɂ��ƁA�}�[���[�͌����ȁu��n�̉́v��Ȃ̂��Ɓu��9�ԁv��1909�N�ĂɏW�����Ċ��������A���̌�C���ƃI�[�P�X�g���[�V�����������s���Ă������Ƃ�����B�����āA���̌�A�����e��1910�N4���Ɋ�������B���̑O�N�ł���B�����́A���̗��N1912�N6��12���A�u���[�m������^�[�w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�ɂ���čs��ꂽ�B�}�[���[�́u��9�ԁv�̉��t�����ƂȂ������������̂ł���B
�@�����Œ��ڂ��ׂ��́A�}�[���[��9�Ԗڂ̌����Ȃ��������肬��ɂȂ��Ă��g��9�ԁh�Ɩ��t���邱�Ƃ�畏����Ă����Ƃ��������ł���B�����ɂ͎��ւ̋��|�Ɛ��ւ̎������������Ă����͂��ł���B�������Ȃ���A���ɂ́u��9�ԁv�Ɩ�������B�}�[���[�́A�����ŏ��߂Ď��ƌ������������e��錈�ӂ������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�}�[���[�͗c�����납��g�߂Ɋ��x�ƂȂ�����̌����Ă���B5�l�̌Z��̓W�t�e���A�ŁA�������̒�͐S�X����ŁA���͔]��ᇂŖS�����Ă���B���N�����玀�̋��|���o���Ă����B�ނ̎����ς����̂��납��`�����ꂽ�Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@�u��9�ԁv�͕�����Ȃ��}�[���[�̐��ւ̌��ʂ̎��ł���B���������Ɍ��̋��n�͂Ȃ��B���ւ̋���A���̗J�T�A���ւ̜ԚL�A���ւ̎����A���ƌ��������E�C�A���̎�e�B����炪���G�ɗ��ݍ����������Ă���B�u��9�ԁv�͉~�n������ȋZ�@�̒��ɗc�����납�玝�������������ς����Ă���B���y�I�ɂ͋��ɂ̔��ӎ����A�v�z�I�ɂ͓Ǝ��̎����ς����Â��Ă���B�����l���Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B
�@��4�y�͂̓A�_�[�W���B�Ō�Ɋɏ��y�͂�u���̂̓`���C�R�t�X�L�[�̌����ȑ�6�ԁu�ߜƁv���炢�����O�Ⴊ�Ȃ��B�����ɂ͑�1�y�͂��3�y�͂Ɏg�������@���ĂыN������A����ɂ́A�I�Ջ߂��A�̋ȏW�u�Ȃ��q�����̂ԉ́v�̑�4�ȁu�q���͂�����Ƃł������������v�̃��e�B�[�t���]�p�����B�}�[���[�͂܂�Ō��ʂ̑����Z����}���Ă���悤���B����͎���̐��ւ̌��ʂ��A�͂��܂��A����s������Ƃ̌��ʂȂ̂��B�u���[�m�E�����^�[�́u���̌����́A����������ɗn�����锒�_�̂悤�ł���v�ƌ`�e���Ă���B
�A �T�C�g�E�E�L�l���E�I�[�P�X�g���̉��t�Ə��V�����̎v��
 �@���V�������A���h���X�E�l���\���X�Ɂu9�ԁv��ؖ]�����̂́A�ނ�29�N�ԋ߂������{�X�g�������y�c�̍��ʉ��t��(2002�N)�ł��̋Ȃ����t�������ƂƖ��W�ł͂��肦�Ȃ��B����ɂ́A���g�̏��܂߁A���Ă̎蕺�̉��y�ēɑ����ɂ́A�}�[���[�́u��9�ԁv��u���đ��ɂȂ������Ƃ������Ƃ��낤�B
�@���V�������A���h���X�E�l���\���X�Ɂu9�ԁv��ؖ]�����̂́A�ނ�29�N�ԋ߂������{�X�g�������y�c�̍��ʉ��t��(2002�N)�ł��̋Ȃ����t�������ƂƖ��W�ł͂��肦�Ȃ��B����ɂ́A���g�̏��܂߁A���Ă̎蕺�̉��y�ēɑ����ɂ́A�}�[���[�́u��9�ԁv��u���đ��ɂȂ������Ƃ������Ƃ��낤�B�@�A���h���X�E�l���\���X��44�A���g���B�A�o�g�̗L�\�Ȓ����w���҂ł���B���̎�r�̊m�����́A�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g2020�̎w���҂ɔ��F���ꂽ���Ƃł����炩���B
�@�l���\���X��SKO�́A�u��9�ԁv�ɂ����āA�傫�ȍ\������������Ƃ������R�ȗ���̃}�[���[�ݏo�����B���F�͂�▾��߂ŋ���̋N���͑傫���A���k�ȉ����͖����ȃ����f�B�[���C�����B���������Ȃ₩�ȉ̐S����ݍ��ށB
�@���ׂĂ��W���I�y�͂̒���ȃA�_�[�W���́A�����h���̓]���̘A�Ȃ肩�琶����O���f�[�V�����̖������ɑ�炩�Ɏ��ɑ@�ׂɋ����A�J�T�Ɛ��������荬����B�����Č����A�}�[���[���炪�L�����u���ʂ悤�Ɂv�̎w�����̂܂܂ɁA�R����������悤�ɋȂ����B�ǂ��������Ȏ⛋������Ԃ�Y���B
�@�o�[���X�^�C���̂悤�ɏ�O��\�o���鉉�t�����A�u�[���[�Y�̂悤�ɑ��`�������鉉�t�ɋ߂��B�}�[���[���Ă߂������ɂ����镡�G�ȐS���������R�ȗ���̒��ɐ����ɕ\�o�����f���炵�����t�������B
�@�ē��G�Y�`���V�����`�A���h���X�E�l���\���X�B�}�[���[�̉��y��ʂ��āA����̒n�ɁA�V���̉��y�Ƃ̐S��s�������B�܂��ɐ���������̃����[�B���������̂Ȃ������̂ЂƂƂ��������B
2022.11.15 (��) ���ΐ�̉��]�_����ǂ���
 �@�b�͏��X�Â��Ȃ�܂����A1991�N�A�u�V��45�v8�����ɉ��ΐ�u������������]�Ɓw���E�̖��x�v�Ȃ�]�_���f�ڂ���A���ꂪ�N���V�b�N���y�E��h�邪����Z���Z�[�V�����������N�����܂����B����͂����ł��傤�A���̕]�_�A�u���킹�Ă���������A�J���X���T�M�Ƃ�������߂�̂����y��]�ł���B�J���X���J���X�Ƃ�������]�Ƃ͖ő��ɂ��ڂɂ�����Ȃ��B�w�H�����߂ɂ̓N�T���ȁx�\���ꂪ��]�Ƃ̍��E�̖����H�v�ƃ��[�h�ɂ���܂��āA���y��]�Ƃ̐搶���������łԂ����肵�Ă�����i���j�����Ȃ�ł���܂��B���w�����ꂽ��]�Ɛ搶�����A�u���ΐ���ĒN�ȂB���̃C�J�T�}��Y�A��ɋ����Ȃ��v�̑升���ɂȂ����Ƃ��B
�@�b�͏��X�Â��Ȃ�܂����A1991�N�A�u�V��45�v8�����ɉ��ΐ�u������������]�Ɓw���E�̖��x�v�Ȃ�]�_���f�ڂ���A���ꂪ�N���V�b�N���y�E��h�邪����Z���Z�[�V�����������N�����܂����B����͂����ł��傤�A���̕]�_�A�u���킹�Ă���������A�J���X���T�M�Ƃ�������߂�̂����y��]�ł���B�J���X���J���X�Ƃ�������]�Ƃ͖ő��ɂ��ڂɂ�����Ȃ��B�w�H�����߂ɂ̓N�T���ȁx�\���ꂪ��]�Ƃ̍��E�̖����H�v�ƃ��[�h�ɂ���܂��āA���y��]�Ƃ̐搶���������łԂ����肵�Ă�����i���j�����Ȃ�ł���܂��B���w�����ꂽ��]�Ɛ搶�����A�u���ΐ���ĒN�ȂB���̃C�J�T�}��Y�A��ɋ����Ȃ��v�̑升���ɂȂ����Ƃ��B�@����Ȏv���������Ƃ��Ȃ�����ΐ쎁�Ƃ͂��������ǂ�Ȑl���Ȃ̂��H �̂���傢�ɋ����������Ă����Ƃ���A������̒������Ő挎���ɂ�����邱�Ƃ��ł��܂����B�Ƃ���͖ڍ��̟������C�^���A�����X�B�ǂ�ȉ��l������邩�Ɗ��҂Ɛ�ɔ��X�Ɋo���Ȃ���҂��Ƃ����B�Ƃ��낪�A����������ΐ쎁�A�\�z�ɔ����Ă������ĉ��₩�ȕi�̗ǂ��a�m�ł����B�Ƃ͂����Ă��A����ŁA���܌�����s������Ɛꖡ�s����N����J��o����鐳�_�ɂ͗��ɋ݂𐳂����ɂ͂����Ȃ����݂�����܂����B���ł��������̂́u���璺��v�u�R�l���@�v�����ׂĈËL����Ă��邱�ƁB�����̗^�������{�l�̐��_���ɂ��ğ�X�Ƃ��b�ɂȂ�܂����B�܂��A�u���{���ɂ͊ԈႢ����v�Ƃ���������A�Ⴆ�u���[�c�@���g�̌��Ђ����������m��Ȃ������[�c�@���g�{�l�̐��i�������Ă��������肦�Ȃ���C�ł���Ă���w�҂�����v���X�A�b�͐s�������̌o�̂��Y��ĕ��������Ă��܂��܂����B�������ΐ쎁�ɕ�������ہB����́A�J�Ԃ���ꂽ�C�J�T�}��Y�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A���`���̋����_���������������ȕ��A�Ƃ������̂ł����B
�@�Ƃ������ƂŁA����́A���ΐ�u������������]�Ɓw���E�̖��x�v�i�ȉ��u���ΐ앶���v�j���N�����m�I�ɉ�ǂ��Ă݂����Ǝv���܂��B
(1)�Z�C�W�E�I�U���́u�V���E���v�̓g���f���i�C�㕨
 �u���ΐ앶���v�͂����n�܂�
�u���ΐ앶���v�͂����n�܂�
�����Ɋ�ȃX�e���I�E���R�[�h���ꖇ����B�\���͏��V�����̉������̃|�[�g���[�g�ŁA�ނ̔w�i�ɃS�[���f���E�Q�C�g�E�u���b�W���ʂ��Ă���B���̍����ʐ^�������悤�ɁA���R�[�h�̒����͏��V�����w���̃T���E�t�����V�X�R�����y�c�ɂ��g�V���E�h�����ȂŁA�W���P�b�g�𗠕Ԃ��ƁA?1975�A���������{�t�H�m�O����������ЂƏ����Ă���B���̃��R�[�h��������ƌ����E�E�E�����E�E�E��3�y�͖`�������̃e�B���p�j�[�̋��ł��J��Ԃ��̂Ƃ���Ō������Ă���̂ł���B�@���N�O�ɂ����ǂ��͑������́uCD�v�����߂��̂ł����A�c�O�Ȃ��炱�̌��ۂ͋N�����Ă��܂���ł����B���ΐ쎁�̎w�E�́uLP�v������(1975�N)�̂��̂�����ACD���̍ۂɂ͏C�����ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤�B���̂��Ƃ����ΐ쎁�ɂ��b������Ɓu���x�l��LP��݂��Ă������v�ƌ����܂����B�y���݂ɑ҂������Ǝv���܂��B
�@����͂���Ƃ��āA���ΐ쎁�������ł�������肽�����ƁB����́A�u�N�������Ă�����͂��́w�����x�ɂ��Ăӂ���̂����Ɂg���]�h�������Ă����]�Ɛ搶�����A���������A�ǂ̔�]�ł����̂܂��������w�E���Ă��Ȃ��B����͔ނ炪�������ɏ����Ă��邩�A�����Ă��C�Â��Ȃ����̂ǂ��炩���v�Ƃ����R�X���������Ȃ̂ł��B
�@���ΐ쎁�͂���LP�Ղ̃W���P�b�g��������������Β��j���������ł�����̂Ă܂��B
���Ȃ�l���̓W���P�b�g���ɂ��������Ă���B�u����́h�V���E�g�łЂƂ̕��Ր������������߂����������Ƃ�����B����̓X�R�A�����炽�߂Č��_�ɖ߂��ēǂݕԂ��A�ǂ̊p�x���猩�Ă��o�����X�̂悢���`�����グ�Ă���̂ł���B�ނ̓R���T�[�g�ƃ��R�[�h�̕ʂȂ��X�R�A�̂��݂��݂܂ōl�������Ȃ���A���ꂪ�܂�ő������t�̂悤�Ȏ��݂��Ə_����l�����Ă������ƂɑS�����S�������Ă��܂����v�ƃz�߂����ƁA��3�y�͂̌��ł́A�u��3�y�͂̂����Ƃ������o��y�₩�ȃ��Y���A�����y�I�ɐ������ꂽ���t�ɂ��Ă��������Ƃ�������v�A�Ƃ��ꂾ���ł���B���̕s���ȃe�B���p�j�[�́u�����v�ɂ��Ă͈ꌾ������Ă��Ȃ��B���Ȃ�l���̖��_�̂��߂ɂ����A�����A�ނ͂��̃��R�[�h�̑�3�y�͂��Ȃ������̂ł��낤�B�������̂ɋC�����Ȃ��Ƃ�������ƒp�����������ƂɂȂ�B�@���ΐ앶���̊j�Ƃ������ׂ��u��]�Ɛ搶���N�ł��킩��͂��́w�����x���w�E���Ă��Ȃ����Ɓv���m���߂邽�߁A����A����������ق̉��y�������ɍs���Ă��܂����B�v�X�ɖK�˂��ӏH�̏��̓m�́A����C�Ɛ��� �ї�����X�̒��ɂ��肰�Ȃ����咣���錚�����_�݂��āA�����Ȃ���S��������Ԃł����B
�@�������Ă����u�����v�s���Ă��炢�A�����w���F�T���t�����V�X�R�����y�c1975�N5���^���̃h���H���U�[�N��ȁF������ ��9�� �z�Z�� �u�V���E���v�̃��R�]�����J�n�B���ꂱ�ꓖ���炸�Ƃ��A�����e���͍ő�́u���R�[�h�|�p�v�ɍi��Ύ������ƍl���A���ׂ����ʁA����LP��1975�N9�����Łu���E�v�̕]���Ă��܂����B���̃��R�]�̗v������L�B
���̉��t�͑�ϔ������B�h��ȃI�[�P�X�g�����ʂ��˂炤�̂ł͂Ȃ��A�g���������ɗ��R��̖L�x�ȕ\���ŁA�S�тɂق̂ڂ̂Ƃ����D���������Ă���B����������̎w���͂����Ԃ鍎���ŁA�`���̏��t�̕������炷�łɔނ��I�тƂ������̎���o�����X�ւ̂��܂����z������ɂƂ�悤�ɂ킩��B�I�[�P�X�g�������̔ނ̗v���̂��Ƃŏ������Ϗk�����ɂ̂т̂тƂ��Ă���̂́A�ނ̐l���ɗR��̂ł��낤���B�T���t�����V�X�R���͂���܂Ŏ���������������̈�ۂł͂����܂Ő��x�̍����\�������肤��I�[�P�X�g���Ƃ͎v��Ȃ������B������͂邩�ɓ˂���������̂������Ɏ�������Ă���Ƃ������Ƃ́A���������̂ЂƂƂȂ�Ǝv����B�@�I�҂���ؐ������B���̋Ȃ̖{���́u�h���H���U�[�N���A�����J���甭�M�����̍��`�F�R�ւ̋���Ȗ]���̔O�v�ƍl���鎄�́A�����]���鏬��̉��t�\���u�g���������ɗ��R��v���u�ق̂ڂ̂Ƃ����D�����v������ʂ̂��̂Ƃ��������܂���ł����B����ɁA�u�I�[�P�X�g�����������Ϗk�����̂т̂тƂ��Ă���̂͏���̐l���ɗR��v�̌��A�A�����J�L���̖���I�[�P�X�g�����u�Ϗk�����̂т̂тƁv���Ȃ�ē�����O�̂��ƁB���̏ケ��́u����̐l���ɂ��v�Ƃ����B�{���w���҂̋Z�ʂƂ͊W�̂Ȃ��l�����z�߂�Ȃ��I�O��������Ƃ���B����ɂ͂܂��u���x�̍����Ȃ��T���t�����V�X�R�������Ⴆ��悤�ȉ��t���������Ă���̂͏���̂ЂƂƂȂ�̎����v�ƃI�P��݂̂ēx�̐l���]�����J��o���n���B�ق��ɖJ�߂���̂��Ȃ��̂����I�H �������A��3�y�͂̃e�B���p�j�[�́u�����v�ɂ͑S���G����Ă��܂���B���̕�����͂�A�������ɏ����ꂽ�̂ł��傤���B
�i2�j�R���h�̈�Ԓ�q��ؐ���
�@���ΐ앶���ɎR�����Ƃ����ÎQ��]�Ƃ��o�ꂵ�܂��B����ɂ��ƁA�R�����͎��Y�Ƃ̍����ŁA�������ƃ\�A�̃A�[�e�B�X�g�Ȃ�S���z�߂����A�A�����J�ݏZ�̃A�[�e�B�X�g�͊F���Ȃ��Ƃ�����]�ƈ�h�̐��I���݂ŁA���V����������炩�Ȃ�킪�܂܁A���A�����ɂ��������Ȕ�]�Ƃ������Ƃ������Ƃł��B�ނɂ͂���ȃG�s�\�[�h���E�E�E�E�E�R��i�R�����̒ʏ́j���̓R���T�[�g�ɍs�����ɏ����Ƃ������Z�i�H�j�������Ă���B�A�[�e�B�X�g���Ƃ̓����Z�ʂ�����߂Ă����āA���̐����ŏ����B����Ƃ��A�R�⎁�͂��̓��Z�ŃR���T�[�g�]���������B���A���̃R���T�[�g�͓����ɂȂ��ċȖڕύX�����������߁A�V���ɂ͓��鉉�t����Ȃ������Ȃ̔�]���o�Ă��܂��� �Ƃ������̂ł��B��搶�̍Q�ĂԂ�͂������肾�����ł��傤���B
�@������ɎR��h�͌��c�S������킪�����y��]�E�ɂ����Ă���Ȃ�̈�h�𐬂��Ă���A��ؐ����A��n�����A����g�j���炪����ɂ�����Ƃ������Ƃł��B���ł��A�R�⎁�̈�Ԓ�q���O�q��ؐ������ŁA�ނɂ͐e���Ɠ����悤�ȃG�s�\�[�h������悤�ł��B��������L�B
����Ƃ��i�Ƃ����Ă�30�N���O�����j����t�����X�A��̃s�A�j�X�g�̉��y��J����A���ő�����������҂͂��Ȃ��������A������A�����V���ɔ�]���o���B����ɂ��Ɠ��Y�s�A�j�X�g�̉��t�́u�����ɂ��t�����X�A��炵�������Ă������A�C�܂���œ��ꊴ���Ȃ��v�ƍ��肳��Ă����B�Ƃ��낪���̃s�A�j�X�g�͏������������C���Ȃ��A�C�܂���ł��Ȃ��A��r�Ɋ�łȉ��t������^�C�v�Ȃ̂ł���B�����������ɂ��āA�{�C�ł��̃s�A�j�X�g���A�����]�������Ƃ�����A�܂�Ŏ��̂Ȃ���]�ƂƂ������ƂɂȂ�B������A�l�̉\�ǂ���A�ނ͉��ɍs�����ɏ������̂��낤�B�@���͂��̐V���L������ɓ���ēǂ�ł݂܂����B�s�A�j�X�g�͏����O�b����A���͎R�t�z�[��(�����}�n�z�[��)�Ƃ���܂����B���}�n�z�[���͐Ȑ�333�B����Ȃ瓖��N�����ĒN�����Ȃ����������킩��܂��B���ΐ쎁�́u�ނ͉��ɍs�����ɏ������̂��낤�v�͐M�ߐ�������܂��B
�i3�j���ɂ��g���`���J���I��ؐ������̏����O�b�]
�@��ؐ������������O�b�]�����t��ɍs�����ɏ��������ǂ����͕ʂɂ��āA���ΐ쎁�̔��_�́A�g���̂Ȃ���]�Ɓh�Ȃǂ̕������o�Ă��āA���Ȃ苭��B�傢�ɋ������������܂����B�{�͂ł͂�������������[���@�艺���Ă݂悤�Ǝv���܂��B�܂��͂��̐V���L���̑S�������L�B
��N9����3�N�Ԃ̃t�����X���w�������ċA���Ă��������O�b���A���㏉�߂Ă̓Ƒt����J�����B���̎��̓`�J�`�J���Ă��邪�₹�čd���B�ɋ}�A����A�t���[�W���O�Ȃǂ��Ȃ莩�R�ŁA�S�̂Ƃ��ăV���������̕\�����Ӑ}���Ă���悤���B�Ō�ɒe�������x���́u�X�J���{�v�͍r���Ȃ��炻�̌��ʂ̏o�Ă���Ƃ��������A���w���ɂ�����ꂽ��������Ă����Ƃ�����B�������X�J�����b�e�B�ł͂��ꂪ���y�̗l���������Ăǂ���������A���ʈ�_����̕i�̑���Ȃ��\���ɂȂ��Ă����B�V���[�}���́u�q���̏�i�v��o�b�n�́u�����K�I���z�Ȃƃt�[�K�v�Ȃǂł͖��͂��������[���Ȃ�A�Ƃ��Ƀo�b�n�͌y�����̂��͂��ŁA�����Ȉ�т����v���݂��Ȃ������B�x�[�g�[���F���̍�i109�͂����Ɖ��ł�������Ǝv�l���[�����_�I���e��������ԓx���K�v�ł���B
 �@���̉��t��J���ꂽ�̂�1960�N�A��������̒��w�����������͒�����͂�������܂���B���A�������A��؎��������Ƃ��邱�Ƃ͐����ł��܂��B�@����Ƃ���A�����炭�A�t�����X�A��̎��s�A�j�X�g���A�o�b�n��x�[�g�[���F���������Ɖ��t�ł���͂����Ȃ� �Ƃ̐����������ď����ꂽ�̂ł��傤�B�����Ȃ���ΐ쎁������̂������ł��܂��B
�@���̉��t��J���ꂽ�̂�1960�N�A��������̒��w�����������͒�����͂�������܂���B���A�������A��؎��������Ƃ��邱�Ƃ͐����ł��܂��B�@����Ƃ���A�����炭�A�t�����X�A��̎��s�A�j�X�g���A�o�b�n��x�[�g�[���F���������Ɖ��t�ł���͂����Ȃ� �Ƃ̐����������ď����ꂽ�̂ł��傤�B�����Ȃ���ΐ쎁������̂������ł��܂��B�@����ɂ��Ă����̃P�i�V���͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B�u���w���ɂ�����ꂽ�g��h�v���ĉ��H���n�̏��q�w���������̎v���ŗ��w�B�w�u�p�����y�@�v�ŁA��Ȃ��Ƃ邽�ߑ��Ƃ���N�������قǂ̃K���o��������Ɍ������� �g��h�Ƃ͉�����y���I�낭�����ۃs�A�m���e���Ȃ��V������ܔ�]�Ƃɖ��ӔC�Ȃ��Ƃ������Ăق����Ȃ����̂ł��B
�@���͏�������̗B���CD���܂������A��؎��̃P�Ȃ��V���[�}���̂Ȃ�Ƒf���炵�����Ƃł��傤�I �����ɓ����Ă���̂́u�N���C�X�����A�[�i�v�B���x�����X�����^�b�`���琶�ݏo����鉹�͈�����������Ɨ������A���łȑ��`���̒��A���y�����������Ƒ��Â��Ă��܂��B�m���ȃe�N�j�b�N�ƍ�i�ւ̋����Ɛ[���ǂ݁B����炪���R��̂ƂȂ�����ނȂ������t�����o���Ă��܂��B�V�˓I�ȃA���Q���b�`�A���}���̖z���z�����B�b�c�A���S�Őߓx���郋�[�r���V���^�C���Ȃǐ��E�̑�ƂƔ�r���Ă��A�܂��������F�Ȃ��B������肩�A�Ɠ��̂��������ʋC�i�����Y���Ă��܂��B���̌�����悤�ȁu�`�J�`�J���Ă₹�čd�����v���u���ʈ�_����̕i�̑���Ȃ��\���v���u�y�����̂��͂��ň�т����v�������Ȃ��v���Ƃ��u���ł�������Ǝv�l���[�����_�I���e��T��ԓx�̌����v������܂���B����Ȃ��Ƃ��A���̒��g�A�����ȕ��͉͂��Ȃ�ł��傤�B�g�`�J�`�J�������h���Ăǂ�ȉ��H �g�y�����̂��͂��h���ĉ��H �g���ł�������v�l�h���Ăǂ��������ƁH �g�[�����_�I���e��T��h���Ăǂ����邱�ƁH �Ӗ��s���ȕ\���̃I���E�p���[�h�B���̕��͂���͉�����������肽���̂���������Ă��Ȃ��B�������A���������ΐ쎁����悤�Ɂu�s�����ɏ������v�Ƃ����Ȃ�A����Ɏ���疜�܂��ɋ����ꂴ��s�ׂƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���ΐ앶���́A��]�Ƃ������{�ʂŃP�Ȃ������̉������ł͂���܂���B����Ȃ��Ƃ����Ă�����A�����Ă�����A���{�̉��y�����͏I������Ⴄ���I �Ƃ����x���̏��Ȃ̂ł��B�����ł͑���܂���B����A���N�Ō�̃N�����m�����ΐ앶���֘A�ł������Ă����������Ǝv���܂��B
���Q�l������
�V��45 1991�N8����
���R�[�h�|�p1975�N9�����i���y�V�F�Ёj
CD�����O�b���T�C�^���i�[�[�����y�������j
2022.10.12 (��) �x�[�g�[���F���A���̊y�Ȃ��Ă߂��v��
�@�x�[�g�[���F�����A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�ɂ������v���͓��ʂȂ��̂������B����́u�s�ł̗��l�v�̎莆��������炩�����A�ނ̎c�����y�Ȃ�������������m�邱�Ƃ��ł���B����́A�x�[�g�[���F�����Ȃɍ��ݍ��A���g�[�j�A�ւ̎v����T���Ă݂����Ǝv���B �@�u�s�ł̗��l�v�̎莆�ɂ́A�A���g�[�j�A�ւ̐s���邱�ƂȂ�����L����Ă��邪�A�����Ƀx�[�g�[���F���̎����̔O����������B���̑�������v���������x�[�g�[���F���̐^��ł���A�y�ȗ����ւ̃J�M�ƂȂ���̂��B
�@�u�s�ł̗��l�v�̎莆�ɂ́A�A���g�[�j�A�ւ̐s���邱�ƂȂ�����L����Ă��邪�A�����Ƀx�[�g�[���F���̎����̔O����������B���̑�������v���������x�[�g�[���F���̐^��ł���A�y�ȗ����ւ̃J�M�ƂȂ���̂��B�@�x�[�g�[���F�����u�s�ł̗��l�v�̎莆��������4�������1812�N11���A�u�����^�[�m�Ƃ̓E�B�[��������t�����N�t���g�ɖ߂��Ă������B���̂����肩��A�x�[�g�[���F���̋��̓��ɂ̓A���g�[�j�A�ւ̗}������Ȃ�����Ɨ}����ׂ������S����������悤�ɂȂ�B���̂���̓��L�����p���Ă݂悤�B
���߁A���O�̉^���ɑ���S�̉���ɂ�������߁E�E�E�E�E�����A�ꂵ�������B�E�E�E�E�E���O�͂��������̂��߂̐l�Ԃł͂��肦�Ȃ��B�������l�̂��߂̐l�Ԃł������肦�Ȃ��B���O�ɂƂ��ẮA���O���g�̒��ƁA���O�̌|�p�̒��ȊO�ɂ́A�����K���͂Ȃ��B�����_��A�Ȃɑł����͂����ɗ^�����܂��B����l���ɂ������茋�т�����̂͂��������Ȃ��B����Ȃӂ��ɁA���Ƃ̊W�͂��������Ă��܂����E�E�E�E�E�B�@�����̃���A��������T�Ɠǂ߂�悤���BA�Ȃ�A���g�[�j�A��A�AT�Ȃ�A���g�[�j�A�̈��̃g�j�[��T���B�u���O�v�Ƃ́u�������g�v�ւ̌Ăт����ł���B���߂˂Ȃ�Ȃ��h���ƒ��߂���Ȃ��^��Ƃ̊����B�����ɐU����Ď��Ȃ̌|�p�ɖv�����悤�Ƃ���o��B�x�[�g�[���F���̋��̓����`����B
�i1�j�A��̋ȁu�y���Ȃ���l�Ɂv
 �@�x�[�g�[���F���̉̋Ȃ́A�̋ȉ��V���[�x���g�̖�600�Ȃɔ�ׂ�Ώ��Ȃ����̂́A����ł�100�ȋ߂����c����Ă���B���ł��A�A��̋ȁu�y���Ȃ���l�Ɂv��i98 �́A����̗_�ꂪ�����B�쎍�̓A���C�X�E���C�e���X�i1794-1858�j�A1816�N�̍�i�ł���B
�@�x�[�g�[���F���̉̋Ȃ́A�̋ȉ��V���[�x���g�̖�600�Ȃɔ�ׂ�Ώ��Ȃ����̂́A����ł�100�ȋ߂����c����Ă���B���ł��A�A��̋ȁu�y���Ȃ���l�Ɂv��i98 �́A����̗_�ꂪ�����B�쎍�̓A���C�X�E���C�e���X�i1794-1858�j�A1816�N�̍�i�ł���B��1�� �u�̏�ɍ������낵
��2�� �D�F�̖��̒�����
��3�� �V����s���y�����D��
��4�� �V����s�����̉_��
��5�� �܌��͖߂�A��ɉԍ炫
��6�� ������l��A���Ȃ��̂��߂�
�@���̉̋ȏW���A�A���g�[�j�A�Ƃ̊W�������I�ɒf�����Ȃ���A�C�����͕ς�炸���������Ă��鎞���̍�i �Ƃ������Ƃ��l����ƁA�Ӗ��[����������������̂ł���B
�@�x�[�g�[���F���́A�������B�A�Ӌ����̂ɉu�a�����s�����Ƃ��Ɍ��g�I�ɊŌ��s��������w���A���C�X�E���C�e���X�̍s�ׂ�`�������Ċ������A�̎^�ƌ���̎莆�𑗂����B���̕ԗ�Ƃ��đ����Ă����̂����́u�y���Ȃ���l�Ɂv�̎������� �Ƃ����Ă���B���̎��͓����̃x�[�g�[���F���̐S����܂�ɂ��@���ɔ��f���Ă���A�܂�ŁA�ނ������������̂悤�Ȋ��o�ɂ�������B������A�x�[�g�[���F���́A����ɉ��炩�̊֗^�������̂�������Ȃ��A�Ǝv�킹��قǂ��B
�@6�Ȃ𑱂��ĉ��t����A��̋Ȃ����A��1�Ȃ̎�肪��6�Ȃ̖����ɍČ�����S�̂ɓ��ꊴ�������炷�B�`���ɕq���ȃx�[�g�[���F���炵����@�ł���B
�@�S6�Ȃ̒��ł́A�Ȃ�Ƃ����Ă��Ō����߂��6�ȁu������l�� ���Ȃ��̂��߂Ɂv���_���낤�B
�@���̋Ȃ̖`���u������l��A���Ȃ��̂��߂Ɏ����̂������̉̂�����Ă�����v�̃����f�B�[�́A�x�[�g�[���F����1811�N�ɍ�����̋ȁu���l�ɁvWoO 140����̈��p�ł���B�u���l�Ɂv�̎��M���ɂ́u�킽���̂��肢�ō�҂���A1812�N3��2���Ɂv�Ƃ����������݂������āA���ꂪ���C�i�[�h�E�\�������̕M�ՊӒ�ɂ���ăA���g�[�j�A�̂��̂Ɗm�肳��Ă���B
�@�����A�x�[�g�[���F���́A1811�N�A���l�A���g�[�j�A�̊肢���ĕ������̋Ȃ̃����f�B�[���A1816�N�A�̋ȏW�̍Ō�̊y�Ȃɓ]�p�����̂ł���B
�@��6�Ȃ̑�ӂ́u�킽���͂��Ȃ��̂��ߓ�������߂ĉ̂��B���Ȃ������̉̂��̂��Ă��������B����������̉̂ɂ���Ď������������u�Ă����̂���������A���̐S�ƐS���ł������̂ł��v�Ƃ������̂��B���ɍŌ�̍Ō�u���̐S�ƐS���ł������v�̕����ɂ́A�x�[�g�[���F���̗}������Ȃ��^����o���Ă���B�x�[�g�[���F���A���̋��тł���B
�@1812�N�H�A�A���g�[�j�A���E�B�[���𗣂�āA��l�̗��͏I������B�������A�x�[�g�[���F���̐S�̒�����A���g�[�j�A�ւ̎v���������邱�Ƃ͂Ȃ������B�����炭�A�A���g�[�j�A���������������Ƃ��낤�B1811�N�A�M���v�������߂đ������̂̃����f�B�[���A1816�N�A���ꗣ��ɂȂ�����̉̋ȏW�ɓ]�p����Ă���B���ꂱ���x�[�g�[���F���̏������邱�Ƃ��ł��Ȃ��v���̏ł͂Ȃ����낤���B
�i2�j �s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110
�@���߂��������邱�Ƃ̂ł��Ȃ�������u�y���Ȃ���l�ցv���Ă߂��x�[�g�[���F���́A1820�`1822�N�A��i109�`110��3�Ȃ̃s�A�m�E�\�i�^������������B
�@�����Ō��3�̃\�i�^�́A����܂ł̂��̂Ƃ͈�����悵�������Ǎ��̍�i�ŁA�`���I�ɂ͎��R�a�V�Ȕ��z�ŏ�����A�����݁A��Y�A���ӁA�[���A���e�A��]�ȂǑ��l�Ȑ��_���������y�z�̒��ɑ��Â��Ă���B
�@32�Ȃ̃s�A�m�E�\�i�^�́A�x�[�g�[���F����22����51��29�N�ԁA�قڍ�ȉƐl���S�ʂɂ킽���ď�����Ă���B������9�Ȃ�25�N�A���y�l�d�t��16�Ȃ�27�N�B�������l���Ă݂Ă��s�A�m�E�\�i�^�̓x�[�g�[���F�������U�ɂ킽���ĒNj�����������ȃW�������ł��邱�Ƃ�����B�����Ȃ��l���̉��v�҂Ƃ��Đ��ɃA�s�[�����鑤�ʂ������A���y�l�d�t�Ȃ��Ȓ��ɓN�w�I�v���荞���̂������Ƃ���A�s�A�m�E�\�i�^�̓x�[�g�[���F���̓��ʂ̐^��𗦒��ɓf�I����킾�����̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ���A�Ō��3�̃\�i�^�́A32�Ȃ̃s�A�m�E�\�i�^�̏W�听�Ƃ����邾�낤�B
�@���}���E�������͂������u�u�����^�[�m�E�\�i�^�v�ƌĂB��30�� ��i109�̓A���g�[�j�A�̖��}�L�V�~���A�[�l�ɕ�����ꂽ���A����2��i�ɂ��āA�x�[�g�[���F���́u�A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�ɕ�����͂��������v�ƃV���g���[�ւ̎莆�ɏ����Ă���B���A���ʓI�ɁA��31�� ��i110�͒N�ɂ�������ꂸ�A��32�� ��i111�͍ő�̃p�g���� ���h���t����ɕ������Ă���B
�@��30�� ��i109�ɂ́u�y���Ȃ���l�Ɂv�̉��^���I�y�͂̎����1�ϑt�Ɏg���Ă���A�Ƃ�������������B����͗y���ȑ��݂ƂȂ��Ă��܂����s�ł̗��l�A���g�[�j�A�ւ̎v���ɈႢ�Ȃ��B�����A�x�[�g�[���F���̓u�����^�[�m�Ƃƍs�������邤���ɁA�A���g�[�j�A�̕v�t�����c�̍����Ȑl�Ԑ��►�}�L�V�~���A�[�l�̉����ɐG��A���̈�Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ɏ������ƍl�����Ă���B�����ŁA��i109���A�u�����^�[�m��Ƃ̏ے��Ƃ��ă}�L�V�~���A�[�l�ɕ������̂��낤�B
 �@�x�[�g�[���F������31�� ��i110���A���g�[�j�A�ɕ����悤�ƍl�����͎̂������낤�B�σC������A���A�̓A���g�[�j�A��A��������Ȃ����A�ނ̃A���g�[�j�A�ւ̎v��������قǂ܂łɋl�܂����Ȃ͑��ɂ͂Ȃ��ƍl�����邩�炾�B
�@�x�[�g�[���F������31�� ��i110���A���g�[�j�A�ɕ����悤�ƍl�����͎̂������낤�B�σC������A���A�̓A���g�[�j�A��A��������Ȃ����A�ނ̃A���g�[�j�A�ւ̎v��������قǂ܂łɋl�܂����Ȃ͑��ɂ͂Ȃ��ƍl�����邩�炾�B�@�݂��Ɉ����������A���g�[�j�A�͂������Ȃ��B���ꂪ�u�Q���̉́v�ł���B��x�Ȃ炸��x�܂ł��Q���̂ł���B�Q������̘a����10�A�ŁI����͖����Ɍ������t�[�K�ɂȂ���B�Q���������Ƃ͂��ׂĂ𐁂����Ď��Ȃ̓��ɐ�����B����͌��ʂƌ��ӂ�10�A�łł���B����������Ă��ꂽ�̂͏��R���t�b�̉��t�ł���B
�@�x�[�g�[���F���͂��̍�i�Ɋm���ɃA���g�[�j�A�ւ̎v�������߂��B�������A�����̌��ӂ��悹�Ă���B����͓�l�̌��ʂ̃��N�C�G�����B�x�[�g�[���F���͂����l�����̂ł͂Ȃ����B�ł��邩�炱���A�A���g�[�j�A�ւ̌�������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� ��i 110�ŁA�A���g�[�j�A�ւ̎v�������߂��x�[�g�[���F���́A���̌�A����̐����铹����Ȃɖv������B�����Đ��ݏo���ꂽ�A�u�����~�T�ȁv�A�u�f�B�A�x���ϑt�ȁv�A�����ȑ�9�ԁA���y�l�d�t�ȑ�12�`16�ԂȂǂ͔ނ̍�ȉƐl���̍Ō�����錆��ƂȂ����B�����̂Ȃ��ŁA�u�f�B�A�x���ϑt�ȁv�̓A���g�[�j�A�Ɍ��悳��Ă��邪�A�ނ̒��ł́A����炷�ׂĂ̊y�Ȃ��A���g�[�j�A�ւ̎v���̎Y���������̂ł͂Ȃ����낤���E�E�E�E�E����Ȃ��Ƃ����v�����炷�A�Z���Ȃ����H�̖钷�ł���B
���Q�l������
�x�[�g�[���F���u�s�ł̗��l�v�̒T�� ���В��i���}�Ёj
�x�[�g�[���F���㉺ ���C�i�[�h�E�\���������i��g���X�j
CD �x�[�g�[���F���F�A��̋ȏW�u�y���Ȃ���l�Ɂv��
�@�@�@�@�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�iBr�j �C�G���N�E�f���X�iP�j�iDG�j
�ŐV���ȉ���S�W�u���y�ȁv�U�i���y�V�F�Ёj
2022.09.18 (��) �x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v���l�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`���R���t�b�̑�31�ԂɐG�������
�@���R���t�b�̃x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110 ��3�y�́u�Q���̉́v�ɂ�����a��10�A�ł̏Ռ��͂����܂������̂������B�ޏ��́A�x�[�g�[���F���̒Q���͓���Ȃ��̂ɑ���̂ł͂Ȃ��A��蕁�ՓI�ȉ��� �ɑ������ �ƌ���Ă���B���ꂪ���t�҂Ƃ��Ă̂܂��Ƃ��ȉ��߂��낤���A�����炱�����l�̋��ɋ����̂��낤�B�����A���͂����ɂǂ����Ă��x�[�g�[���F���̌l�I�ȐS������Ă��܂��B��ȉƌl�̐S��A���ɗ��S���y�Ȃɓ��e����邱�Ƃ̓N���V�b�N���y�̗��j�ɂ����Ă͂����Ē��������Ƃł͂Ȃ��B�u���[���X�̌����ȑ�1�ԂɃN�����ւ̈�r�Ȏv�����[�����Ă���͎̂��m�̎����B�x�����I�[�Y�́u���z�����ȁv�͂����Ƌ�̓I�B���D�X�~�b�\���ւ̖�������ʗ�����Ƃ����`����ĕ����o�������̂��B������x�[�g�[���F��������̏������v���`���Ă����Ƃ��Ă��ʂɕs�v�c�͂Ȃ��̂ł���B�i1�j�s�ł̗��l�ւ̎莆
 �@�x�[�g�[���F�������̐��U������̂�1827�N3��26���B�����Ɉ₳�ꂽ�莆���������B�������̂̓x�[�g�[���F���{�l�B�����l�Ȃ��B���e�͗����B�����ł̌Ăт������炱�̎莆�̓x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v�Ɉ��Ă��莆�Ƃ��ꂽ�B�s�ł̗��l�Ƃ͉ʂ����ĒN�H�Ȃ��苖�ɂ������̂��H ���X���y���D�ƂɂƂ��ċ����s���Ȃ�����N���Ȃ��ꂽ�̂ł���B������H�邽�߁A�܂��͎莆�̐S��I�����𒊏o���Čf���Ă������B�莆�͎O�M����B
�@�x�[�g�[���F�������̐��U������̂�1827�N3��26���B�����Ɉ₳�ꂽ�莆���������B�������̂̓x�[�g�[���F���{�l�B�����l�Ȃ��B���e�͗����B�����ł̌Ăт������炱�̎莆�̓x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v�Ɉ��Ă��莆�Ƃ��ꂽ�B�s�ł̗��l�Ƃ͉ʂ����ĒN�H�Ȃ��苖�ɂ������̂��H ���X���y���D�ƂɂƂ��ċ����s���Ȃ�����N���Ȃ��ꂽ�̂ł���B������H�邽�߁A�܂��͎莆�̐S��I�����𒊏o���Čf���Ă������B�莆�͎O�M����B7��6����
���̓V�g�A���̂��ׂāA�����g��B�\��ނ����Ȃ����ƂƂ͂����A���̐[���߂��݂͂Ȃ��ł��傤�B�������̈��́A�]����ʂ��Ă����A���ׂĂ̖]�݂��̂Ă邱�Ƃł����A���݂��Ȃ��̂��낤���B���Ȃ������S�Ɏ��̂��̂ł͂Ȃ��A�������S�ɂ��Ȃ��̂��̂łȂ����Ƃ��A���Ȃ��͕ς����܂����B�\�����A���������R�߁A�����Ă��Ȃ��̋C�����𗎂��������Ă��������A�ǂ����悤���Ȃ����Ƃ���肱���ā[
���C���o���ā[���̒����ȗB��̑�Ȑl�A�킽���̂��ׂĂł��Ă��������A���Ȃ��ɂƂ��Ď��������ł���悤�ɁB
7��6�� ���j�� ��
���Ȃ��͋ꂵ��ł�����B�ň��̐l��[���Ȃ��Ƃ�������ɕ邹����A����͂ǂ�ȕ�炵�ł��傤���I�I�I�I�����I�I�I�I���Ȃ��Ȃ��ɂ́E�E�E�E�E�B���Ȃ����ǂ�ȂɎ��������Ă��悤�Ɓ[�ł����͂���ȏ�ɂ��Ȃ��������Ă���[�����炯�����ē����Ȃ��Ł[���₷�݁[�����A�_��[����Ȃɂ��߂����I����Ȃɂ������I�������̈������́A�V�̓a�����̂��̂ł͂Ȃ����낤���[�����Ă܂��A�V�̍Ԃ̂悤�Ɍ��łł͂Ȃ����낤���B
���͂悤 7��7��
�x�b�h�̒����炷�łɂ��Ȃ��ւ̈����̂�A�킪�s�ł̗��l��A�^�����������̊肢�����Ȃ��Ă����̂�҂��Ȃ���A���͊�тɂ݂����ꂽ��A�܂��߂��݂ɒ��肵�Ă��܂��[���S�ɂ��Ȃ��Ƃ������傩�A���邢�͂܂����������łȂ����A�����ꂩ�ł������͐������Ȃ��B�����ł��A���͉����ւ��������Ƃ��炭�����悤�ƌ��S���܂����B���Ȃ��̘r�ɐg�𓊂��A���Ȃ��̂��ƂŊ��S�Ɍ̋��ɂ���v���𖡂킢�A�����Ă��Ȃ��Ɋ�肻���Ď��̍����̉����ւƑ��邱�Ƃ��ł���܂Ł[�����A�߂�������ǂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̏��������̐S���߂邱�ƂȂnj����Ă��肦�܂���B�\�����_��A����ȂɈ����Ă���̂ɁA�Ȃ�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤�B�\���Ȃ��ւ̈����A�������̏�Ȃ��K���ɂ���Ɠ����ɁA���̏�Ȃ��s�K�ɂ��Ă��܂��B�\���̔N��ɂȂ�ƁA�g�p�̂Ȃ����肵���������K�v�ł��B�\�������̊W�ł��ꂪ�\�ł��傤���H�\��Âɂ��āA�����Ăق����[�������[������[�ǂ�Ȃɂ��Ȃ��ւ̓���ɗ܂������Ƃ��[���̂��̂��[���̂��ׂā[���C�ł��ā[�����A���������Â��Ă��������[���Ȃ��̗��l�̂��̏�Ȃ������ȐS���A�����ċ^��Ȃ��ŁB
�i���ɂ��Ȃ���
�i���Ɏ���
�i���Ɏ�������
�@�����܂������S�ł���B���̎莆����ǂݎ���̂́A�x�[�g�[���F���̌���Ȃ�����ł���A��Ɏ��������Ȃ��S��ł���A�����ւ̈����m�M���鑊��ւ̎v���ł���A�����������Ȃ������ւ̒Q���ł���B
�@����炩��A���݂������v�����ł��邱�ƁA�����͊����҂������͌����ł��Ȃ������ɂ��邱�Ƃ��z���ł���B�����āA�x�[�g�[���F���͂�ނɛ߂܂�ʗ��S��U�蕥���ĉ��������邱�Ƃ����ӂ���B�����ւ̕��Ƃ͑����d������Ȃւ̖v���ƍl���Ă������낤�B
�i2�j�s�ł̗��l�����ւ̓���
�@�x�[�g�[���F���̎���A�u�s�ł̗��l�v�Ƃ͒N���H ���x�[�g�[���F�������̈�̃e�[�}�ƂȂ����B
�@�܂��́A�莆�̍ŏ��̔����҃x�[�g�[���F���̔鏑�������F���Ă����A���g���E�V���h���\�̍l�ł���B�V���h���[�́A�x�[�g�[���F���̎�����13�N��ɏ������`�L�u���[�g���B�q�E���@���E�x�[�g�[���F���v�̒��ŁA�u���̎莆��1806�N�Ƀn���K���[�̉���n����W�����G�b�^�E�O�C�`�����f�B�i1782-1856�j�Ɉ��Ăď��������́v�ƌ��\�����B����́A�莆�ƈꏏ�ɂ�����2���̏ۉ�̈���W�����G�b�^�̏ё����������Ƃ��琄���������̂ŁA���W�J���ȍ����ɂ͖R�������̂��������A�x�[�g�[���F���̎��ɍۂ��čł��߂����l���̌�������������A���Ԃ͓����̊ԁA�u�s�ł̗��l�v�̓W�����G�b�^�E�O�C�`�����f�B�ł���ƐM���邱�ƂɂȂ����B�W�����G�b�^�̓x�[�g�[���F�����s�A�m�E�\�i�^��14�ԁu�����v�����悵�������ł���B
�@���̌�A�x�[�g�[���F������s�A�m�E�\�i�^ ��24�� �����悳�ꂽ�e���[�[�E�u�����X���B�b�N�i1775-1861�j�A�x�[�g�[���F�����u�A���_���e�E�t�@�{���v�Ɏv����������Ƃ�����e���[�[�̖����[�t�B�[�l�E�u�����X���B�b�N�i1779-1821�j�A�u�G���[�[�̂��߂Ɂv�̓����҂Ɩڂ����e���[�[�E�}���t�@�b�e�B�i1792-1851�j���͂��߁A�}�O�_���[�l�E���B���}���A�A�}���G�E�[�[�o���g�A�}���[�E�G���f�[�f�B�A�h���e�A�E�G���g�}�����X�A���X�Ɓu�s�ł̗��l�v���̖���������B�x�[�g�[���F���͂Ȃ��Ȃ��������j�������̂ł���B
�@����Ȓ��A20���I�̏��߁A���Ԃ͋}�W�J���}����B1909�N�ɏo�ł��ꂽ�u�x�[�g�[���F���̕s�ł̗��l�v�i�g�}�X���T�����K�����j�Ɨ��N���������ɕ⋭�����`�̏��u�x�[�g�[���F���̕s�ł̗��l�����߂āv�i�}�b�N�X�E�E���K�[���j����A���̎莆�́A�x�[�g�[���F�����A1812�N7��6����7���A�{�w�~�A�̉���n�e�v���b�c�ŁA���̋߂��̉���n�J�[���X�p�[�g�ɂ�����l�Ɉ��Ăď����������Ɗm�肳�ꂽ�B���҂́A�莆�ɏ����ꂽ�u7��6�� ���j���v�Ƃ������t�A�C�ۏA��̉���n�̓����q����Ȃǂ����L�̌��_������o�����̂ł���B
�@�����A���Ƃ́u�s�ł̗��l�v�Ƃ͒N���H �̓���ł���B�J�[���X�p�[�g�̓����q����ɂ͊Y��������4�l�̖��O���������B�A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�A�h���e�A�E�G���g�}���j�ݕv�l�A�G���[�[�E�t�H���E�f�A�E���b�P�j�ݕv�l�A�}���A�E���q�e���V���^�C������܂ł���B
�@�����ŁA�u�s�ł̗��l�v�T���ɎQ�킵����䏊���}���E�������́u�A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�ƃG���g�}���j�ݕv�l�ɑ���x�[�g�[���F���̂��悻�悻�����ԓx�͗��l�Ƃ��Ă̏��������Ȃ��v�Ƃ��ē�l��ނ����B�Ȃ���Ƃ̓�l�͂ǂ��Ȃ̂��E�E�E�E�E�H �������͂���ɂ͌��y�����ɁA���[�t�B�[�l�E�u�����X���B�b�N�ɖ������c�������I���Ă���B�m�[�x���܍�Ƃ������ł͘_�����Ɍ����錋�ʂɏI��点�Ă��܂����B
�@���������j�S�߂��܂Ŕ������u�s�ł̗��l�v�T���̓��͂����ł�������r��Ă��܂��B�����āA�����I���1959�N�A��l�̓��{�l�������A���ɂ��̓�������������̂ł���B
�i3�j���Ёu�s�ł̗��l�v����肷��
 �@1959�N��NHK�����y�c�̋@�֎��u�t�B���n�[���j�[�v�Ɂu���̓`���`�x�[�g�[���F���Ɓ��s�ł̗��l���v�Ƒ肷��G�b�Z�C���f�ڂ��ꂽ�B���҂͐��Ёi1927-2009�j�B���ꂪ���݂ł͒���ƂȂ��Ă���u�x�[�g�[���F���́w�s�ł̗��l�x�̓A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�ł���v�Ƙ_�������E���̘_�l�ƂȂ����B
�@1959�N��NHK�����y�c�̋@�֎��u�t�B���n�[���j�[�v�Ɂu���̓`���`�x�[�g�[���F���Ɓ��s�ł̗��l���v�Ƒ肷��G�b�Z�C���f�ڂ��ꂽ�B���҂͐��Ёi1927-2009�j�B���ꂪ���݂ł͒���ƂȂ��Ă���u�x�[�g�[���F���́w�s�ł̗��l�x�̓A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�ł���v�Ƙ_�������E���̘_�l�ƂȂ����B�@�؎��́A3�ʂ́u�s�ł̗��l�v�̎莆���n�ǁE���@���A�K���^�E���K�[�̌�����A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�ɏƏ������킹�A���}���E���������r��������Ƃ����x�[�g�[���F���̂悻�悻�������ނ���^���̈����B�����߂̃J���t���[�W���Ƒ�����Ȃǂ��āA���ɒ��N�̓䂾�����x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v���A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�Ɠ��肵���̂ł���B�̐��́A���C�i�[�h�E�\������1972�N�̘_���u�x�[�g�[���F���̖��m�̏����ւ̎莆�ɂ��Ă̐V�����v�ɂ���Ċm�ł��闠�t����^����ꂽ�B
�@���Ђ͒��N�̓䂾�����x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v�����������������E�ŏ��̐l���ł���B���̌�u�s�ł̗��l�v�֘A�̒����𑽐����s�A���U���x�[�g�[���F�������ɕ����Ă���B����͓��{���y�E�̑傢�Ȃ�ւ�ł͂Ȃ��낤���B������ɁA�ޏ��ɉ��炩�̘_���s�܂��^����ꂽ�`�Ղ͂Ȃ��B�킪�����y�E�͐̌��т������Əd���A���d���ׂ��ł���Ǝv�����A���������낤���B
�i4�j�s�ł̗��l�̔����ƃx�[�g�[���F��
�@�ł͂����ŁA�s�ł̗��l���A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m(1780-1869)�̔������x�[�g�[���F���Ƃ̊֘A�ɂ����ĒH���Ă������B
�@�x�[�g�[���F������]������ăE�B�[���ɂ���Ă���1792�N�A�ł����������ʂ����̂����[�[�t�E�����q�I�[���E�t�H���E�r���P���V���g�b�N���݂̉��~�������B�|�p�������锌�݂̓p�g�����Ƃ��ăx�[�g�[���F����D���A���̃A���g�[�j�A�̃s�A�m���t��ނɈϑ������B�x�[�g�[���F��21�A���g�[�j�A12�B���̎��_�ŁA�������A�˔\�Ɉ���S�Ə�M�ɖ��������s�̉��y�Ƃɂ����̓����������Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ����낤�B
�@���y�̓s�ō˔\���J�Ԃ����������悤�ɂȂ����x�[�g�[���F���͑��̑����̋M���̓@�ɂ��o���肷��悤�ɂȂ�A�A���g�[�j�A�Ƃ͎��R�ɑa���ɂȂ��Ă䂭�B
�@���̌�A18�ɂȂ����A���g�[�j�A�͕��̊��߂��e��ăt�����N�t���g�̋�s�ƃt�����c�E�u�����^�[�m�ƌ�������B�������Ȃ���A�A���g�[�j�A�ɂƂ��āA�t�����N�t���g�ł̌��������͌����čK���Ȃ��̂ł͂Ȃ������B15�ΔN��̕v�͎v�����[���l�ԂŁA�����ɕs���͂Ȃ��������A�t�����N�t���g�Ƃ����y�n���ɂǂ����Ă�����߂Ȃ������悤�ł���B���̂��߂��A���̊ԁA�Z���I�ȃE�B�[���ւ̗��A������x�����݂Ă���B������1809�N10���A���̊�Ă̕�����������i�����j�ɁA�A���g�[�j�A�͕v��4�l�̎q���Ƌ��ɁA�E�B�[���̎��ƃr���P���V���g�b�N�@�Ɂi�ꎞ�I�Ɂj�����ڂ����ƂɂȂ����̂ł���B
�@���āA�����ɓo�ꂷ��̂��t�����c�̖��x�b�e�B�[�i�ł���B1810�N5���A�t�����N�t���g���瓲��̃E�B�[���ɏo�Ă����ޏ��͌Z���Z�ރr���P���V���g�b�N�@�ɐg�����B������A���̓@�̉��y��ŁA�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^�u�����v���A����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������𖡂키�B�|�p��������s���h�̔ޏ��͂��̍�҂ɉ�����Ɗ肢�A���Ƀx�[�g�[���F���̏Z����T�����ĖK�˂邱�ƂɁB�����ɂ̓E�B�[���ɖ��邢�`�o�A���g�[�j�A�����ē��l�Ƃ��ē������Ă����B�x�[�g�[���F���ƃA���g�[�j�A�A18�N�Ԃ�̍ĉ�����B�`���͋`�o�ƃx�[�g�[���F���̃L���[�s�b�g�����ʂ������Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�x�[�g�[���F����39�B�����ȁu�p�Y�v�u�^���v�u�c���v�A�s�A�m���t�ȁu�c��v�A���@�C�I�������t�ȁA���@�C�I�����E�\�i�^�u�t�v�u�N���C�c�F���v�A���y�l�d�t�ȁu���Y���t�X�L�[�v�A�s�A�m�E�\�i�^�u�ߜƁv�u�����v�u�����g�V���^�C���v�u�M��v �Ȃǂ̌���Q�𐢂ɑ���o���A���ɉ���������������ʑ��ȉƂƂȂ��Ă����B
�@�A���g�[�j�A��30�B���͓I�ȋM�w�l�ƂȂ��Ă����B���̎��̓�l�̋C�����͂������肾�������낤���B2�N���1812�N7���ɁA�x�[�g�[���F��������قǂ̎莆�������̂����炵�āA�^���̎��ɓ����ꂽ�悤�ȃh���}�e�B�b�N�ȍĉ�ɁA��l�̋C�����͑傢�ɗh�ꓮ���A�ǂ����̎��_�ʼn��̔@���R���オ�����ɈႢ�Ȃ� �Ǝv���̂ł���B
�@������ ��7�� �C�����Ƒ�8�� �w�����͂��̂�����̍�i�B��7�Ԃ̓��[�O�i�[���u�����̐_���v�ƌĂ悤�ɖ��������[�����A��8�Ԃɂ͈��炢���K�������h��B�x�[�g�[���F���̐S��̕\��Ƃ����Ȃ����낤���B
�@�x�[�g�[���F���ƃA���g�[�j�A�֒f�̗��́A1812�N11���A�u�����^�[�m��Ƃ��E�B�[�������邱�ƂŁA���̌������}�����B���͎��Ȃ�t�F�[�Y�ɓ���E�E�E�E�E�x�[�g�[���F���́A���̂��ƃX�����v�Ɋׂ����̂��A���������i�������Ă��Ȃ��B����̌���Q�������n�߂�̂�1820�N�ォ�炾�B����Ȓ��A1822�N�ɏ����ꂽ�s�A�m�E�\�i�^ ��31�Ԃ́A�x�[�g�[���F���̃A���g�[�j�A�ւ̎v�����ő���ɏW��Ă��� �Ǝ��͍l����悤�ɂȂ����B�����v�킹�Ă��ꂽ�̂́A������Ȃ����R���t�b�̉��t�ł���B����́A���̂�����ɁA���������[���荞��ł݂����Ǝv���B
���Q�l������
N���@�֎��u�t�B���n�[���j�[�v1959.8.9
�x�[�g�[���F���u�s�ł̗��l�v�̒T�� ���В��i���}�Ёj
�x�[�g�[���F���㉺ ���C�i�[�h�E�\���������i��g���X�j
2022.08.16 (��) ���R���t�b �Ռ��̃N���b�V�F���h
 �@�ҏ�������7��25���ANHK-BSP�̃N���V�b�N��y���ŏ��R���t�b�̃x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110 �̃I���G�A���������B2021�N6��23���A�߂���p�[�V������z�[���ł̎��^�ł���B���3��\�i�^�̒��ŁA�Ƃ������A�x�[�g�[���F���̃\�i�^�̒��Ŏ����ł��D���Ȃ��̋Ȃ����R���ǂ��e�����H �ƂĂ��y���݂������B��1�y�́`��2�y�͂Ɛi�ݑ�3�y�͂ɓ���B
�@�ҏ�������7��25���ANHK-BSP�̃N���V�b�N��y���ŏ��R���t�b�̃x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110 �̃I���G�A���������B2021�N6��23���A�߂���p�[�V������z�[���ł̎��^�ł���B���3��\�i�^�̒��ŁA�Ƃ������A�x�[�g�[���F���̃\�i�^�̒��Ŏ����ł��D���Ȃ��̋Ȃ����R���ǂ��e�����H �ƂĂ��y���݂������B��1�y�́`��2�y�͂Ɛi�ݑ�3�y�͂ɓ���B�@�u�Q���̉́vKlagender Gesang �ƃx�[�g�[���F�����炪�������A�_�[�W������t�[�K�ցB�����čēx�u�Q���̉́v�������B�����ɂ́u���͂āA�Q���vErmattet, klagend �Ə�����Ă���B�Q�����������Ă���̂��B�����Ă��̕����̏I����132���ߖڂ���N���b�V�F���h�t���̘a����10�A�ł�����B�t�[�K�֘A�Ȃ�u���b�W�ł���B�����ŁA���͑����̂B���̐����N���b�V�F���h�I���R�͂�����Ӑg�̗͂�U��i���Ēe���̂ł���B�Ȃ�Ƃ������́B�Ȃ�Ƃ����C�����̓���悤�B���ɍŌ�̈ꌂ�ɂ͋S�C������̂�����B���ꂪ���̉��₩�ȏ��R���t�b�Ȃ̂��ƌ��܂�������ł���B���͂��̕����A����قǂ܂łɋ���Ȓe����������s�A�j�X�g�͂���܂Ō������Ƃ����������Ƃ��Ȃ������B
�@�����ŁA�莝����CD���ׂĂ����߂Ē����Ȃ����Ă݂��B���̂��߂ɏ��R��CD���}篍w�������B�ȉ��́A�x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110��3�y�� ��2�́u�Q���̉́v132�`134���ߕ����̃N���b�V�F���h�x�����̌��،��ʂł���B�x�[�g�[���F���́A�N���b�V�F���h�̑O��ɋ���̋L������������Ă��Ȃ�����A���̑傫�����͉̂��t�҂Ɉς˂��Ă���B�N���b�V�F���h�x���������ʂ̑傫��������A�AB�AC��3�i�K�Ɋi�t���B�S15�v�A�^�����ɗ�L�B�����͘^���N�B�u�v�̓N���b�V�F���h�����̏����B�����ĉ��t�S�̂̊T�v�L����B
�A���g�D�[���E�V���i�[�x�� 1935 B �u�L�b�`���Ɩ炷�v ���ȏ��I�X�^���_�[�h
�C�[���E�i�b�g 1954 B �u���߂̃e���|�ł�������Ɓv ���肰�Ȃ����ܒ~����̐S
�����^�[�E�M�[�[�L���O 1956 C �u�T���ځv ��{�����炩�ȕ\��
�O�����E�O�[���h 1956 B �u�T�����Ɨ����v �������̃t�[�K�̏���
�E�B���w�����E�o�b�N�n�E�X 1963 B �u10�Ŗڂ�}������Ǝ��̉��߁v �I�g���鎩�ݐ�
�E�B���w�����E�P���v 1964 C �u�e�k�[�g�ł�������Ɓv ���Ɍ�����M
�N���E�f�B�I�E�A���E 1966 A �u���ʑ�_�炩�ȋ����v ���������d��������
�A���t���[�h�E�u�����f�� 1973 C �u���ʃN���b�V�F���h���ɋɏ��v �S�̓I�ɋɓx�ɓ��ȓI
�}�E���c�B�I�E�|���[�j 1976 A �u���߂������ς�Ɓv �����ȋZ�I�Ŋm���鑢�`��������
�G�~�[���E�M�����X 1985 B �u���悭�����v �����ɂ��ׂ₩�ȉ̐S
���h���t�E�[���L�� 1987 C �u�������藬�����v �͒W�̋��n������̂܂܂ɕ\�o
�X�����g�X���t�E���q�e�� 1991 C �u�v�����ꏬ�v �����Ȃ܂ł̃X�P�[����
���c���q 2005 A �u�͋����Ō��v �_�o�̍s���͂������y�Â���
������� 2005 B �u���f�̐ߓx�v �����ɉ��₩�ɉ̂�����
���R���t�b 2021 A �u���̋����������x �ő�v �[�����@�� ���J���͋������y�Â���
�@���r�Ɩڂ���郊�q�e���A�[���L���������NB�Ȃ͈̂ӊO�������B�����Ƃ��[���L����84�̃��X�g�E���R�[�f�B���O�ł͂��邪�E�E�E�B�v���^�̃u�����f���̒e�����͗\�z�O�B�|���[�j�A�A���E�A���c�烉���NA�̒��ł́A���R���t�b���Q���Ă���B�Ō��͋��x�Őc������B�����͔C���ɒe���̂ł͂Ȃ��B�S�����߂ĉ��[���ł����ނ̂ł���B�܂�œ��b��̎�ł���B����͓�A�����N�Ƃ����Ă������B�a��10�A�ł̓s�A�m�E�\�i�^��31�ԂɃx�[�g�[���F�����Ă߂��v�����ے��I�ɕ\�ꂽ�ӏ��ł���A�Ǝ��͍l���Ă���B���R�͂�����\�S�ɗ������Ă���B
�@�����ň���f�肵�Ă����������Ƃ�����B����́A���R���t�b�̉��t�ɂ����āACD�ƃe���r�ł͈�ۂ����قȂ�Ƃ������Ƃ��BCD��2021�N2��16��-19���A�e���r�͓��N6��23���̎��^�B���̍�4������B���߂Ɋ�{�I�ȈႢ������͂����Ȃ����A���^�̊��A�f���̗L�����̂������낤���A�e���r�̕��̈�ۂ������B��菬�R�̈Ӑ}�����m�Ɍ��Ď���B������A����4�����Ԃō�i�ւ̓ǂ݂����[������ �Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ����B
�@���グ�����t�͊e�X��]���閼�Ղ��낢���B�[���L���́u�ґz�I�Ȕ������Ɛl�ԓI�Ȃʂ����肪�������������t�v�A�|���[�j�́u�������z�������}����`�̔������v�A�M�����X�́u�Ђ��ނ��ɒNj��������Ă������ׂĂ��W�ꂽ�Ō������ɂӂ��킵���o���h���v�Ȃǂ̕]�����ԁB���������̕]�́A�����āA���ۓI�łǂ����ǂ��f���炵�������悭�킩��Ȃ��B���̑��̕]���T�ˎ����悤�Ȃ��̂��B�Ȃ��[���L����CD�ɂ��Ĉꌾ�B���̔ՁA1989�N�x���R�[�h�E�A�J�f�~�[�܂���܂��Ă���炵���B�Ƃ��낪��3�y�͂̃`���v�^�[���t�[�K�̂Ƃ���ɕt���Ă���B�`���̃A�_�[�W����������2�y�͂Ɋ܂܂�Ă��܂��Ă���̂��B����͒P�����傢�Ȃ�~�X�e�[�N�B�����Ă��܂��Ό���CD���B�I�l�҂͋C�Â��Ȃ������̂��낤���B
�@���Ă����ɁA28�N�O�̏��R�̑Βk�i���y�V�F�Ђ�MOOK�u�N���V�b�N����̋��������v�j������B����ɂ��ƁA�ł����h����s�A�j�X�g�̓A���g�D�[���E���[�r���V���^�C�����Ƃ����B�t�[�K�����A���c�̂���✓�ӓI�ɕ�������̂ɑ����R�͉��y�����Ɏ��R�ɗ����B����͂�����[�r���V���^�C����DNA���B�|���[�j�ɂ��Ắu�����Ɩ����̊�]�������C���E�E�E�E�E����ȂɊ����Ȑl������̂ɁA�Ȃ��������e���Ă���낤�����āE�E�E�E�E�v�ȂǂƘb���Ă���B���R�̌��������悭�\��Ă���B�m���ɁA�����A�|���[�j�͊��Ɋ������ꂽ�s�A�j�X�g���������炵�āA�ޏ��̃R�����g�͂����Ƃ��ł͂���B�������Ȃ���A���R�͓��X�̐��i�ɂ��A�|�p�ƂƂ��āA���܍������n�ɒB������B���݉~�n�̋ɒv�ɂ���|���[�j�ɒǂ������Ƃ͖��_�܂�������͂����Ȃ����A�߂Â����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���B
 �@�����Ď��͒f������B�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110�ɂ����āA���R���t�b�͍ۗ����������t���ׂ������ƁB
�@�����Ď��͒f������B�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110�ɂ����āA���R���t�b�͍ۗ����������t���ׂ������ƁB�@���R�́A�a��10�A�ł��܂߁A�y�ȑS�̂ɂ킽��A���J�Ɋy����ǂݍ��݁A���ׂẲ��ɐ_�o���s���͂�����B�����Ă����Ƀx�[�g�[���F�����ꉹ�ꉹ���Ă߂��Ӗ������o���B
�@��1�y�́B�`���̎����ɖ������\��B�܂�őS�g����ł����悤�ɗD�����C�����������B�W�J���A��1���̓]����8�ϑt�B�O�㖢���A�`���̊v���ƃx�[�g�[���F������̋Z�ł���B���R�͂���8�̕ϑt��ό����݂̃O���f�[�V�����ł�������ƕ`����B
�@��2�y�͂́A�������悭����̂悢�^�b�`�ŁA����I�ȑ�1�y�͂Ƒs��ȑ�3�y�͂̒��Ԃ���������ƌ`������B���̊y�͂̎|��𗝉������ߓx����A�v���[�`���B
�@�����āA��3�y�͂ł���B����̓s�A�m�E�\�i�^�Ƃ��Ăِ͈F�̍\���B�Ɂ\�}�\�Ɂ\�}�B�}�̕����̓t�[�K�Ɣ��s�t�[�K�B3�ӏ��Ƀx�[�g�[���F���{�l���������݂����Ă���B
�u�Ɂv �Q���̉� Klagender Gesang
�u�}�v �t�[�K
�u�Ɂv ���͂āA�Q���� Ermattet klagend
�u�}�v ���s�t�[�K �������Ɍ��C���Ƃ���ǂ��Ȃ��� Nach und nach wieder au flebend
�@�x�[�g�[���F���͉����Ɂu�Q���v�B�����āA�C����蒼���Đ�ɐi�����Ƃ���B�����܂��U���Ȃ��B����ɐ[���u�Q���v���P���Ă���B�h���͂āg�Ă��邩��u�Q���v���Ƃ���Ƃ���ɂȂ�B��1�́u�Q���v�ɂ͌����Ȃ�����16���x�����p������̂͂��̏��B�����āA���ɂ��ׂĂ�U����āA�O�������ĕ��ݎn�߂�̂ł���B
�@�x�[�g�[���F���́A��1�́u�Q���v�̏I���ɁAA��̃I�N�^�[�u3���d�˂̘a����pp��3�A�ł�����B���ꂪ�A��2�́u�Q���v�ł́ADGH�̃I�N�^�[�u6���d�˂̘a�����N���b�V�F���h��10�A�ł�����B��葝�����ꂽ�u�Q���v��U�蕥�����߂̒u�������ł���B�傫�ȒQ����U�蕥�������Ƃ̑�2�̃t�[�K�́A���͋����傫�������ɉH�����B���R�͂��̗���̈Ӗ������������ɗ������Ă���B
�@���R���t�b�́A�s�A�m�E�\�i�^��31�ԁA���ɑ�3�y�͂ɂ��āA��������Ă���B
�x�[�g�[���F���͒N���̎v���Ƃ������Ƃ��ɒQ���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����Ɛ[���A�Ȃɂ��ƂƂ������Ȃ����̂ɓ�x�Q���̂ł��B��x�ڂ͂Ƃ���Ƃ���ɂȂ��ĒQ���āA�����ǂ�������u�t�[�K�v�Ƃ����k���Ȃ��̂�g�ݗ��ĂĂ����āA�Ō�ɂ́A�x�[�g�[���F���炵���͂��h���Ă��āA�S�g���˂���������āA�S�̒ꂩ��E�C���N���オ���Ă���B���ꂱ�����x�[�g�[���F�������A�l�Ԃ����犴�����銴��Ǝv���B�x�[�g�[���F���������������Ȃ��Ȃ�Ƃ�����Y�������āA��Y�̒��Ɏ��Ȃ̂�����������āA�V���������̉��y���������Ă����B�s�A�m�E�\�i�^��31�Ԃ͒P�Ɍ���Ƃ��������ł͂Ȃ��l�ނւ̃��b�Z�[�W�ł͂Ȃ��ł��傤���B�l�Ԃł��邩�炱��������B���y��t�ł�B����Ȃ��Ƃ�O���Ď��͒e���Ă��܂��B�@��x�Q�������Ƃ͗E�C��~�����đO�������ē˂��i�ނ̂ł���B���̘a����10�A�ł͒Q���ւ̌��ʂȂ̂��B���R�͂��������Ă���悤�Ɏv���B�Q���Ɍ��ʂ��鋭�x�Ȉӎu�B�����炱������قǂ̏Ռ��I�ȃN���b�V�F���h�Ƌ���ȍŌ�̈ꌂ���{�����̂��낤�B���R�̓x�[�g�[���F���́u�Q���v���A��̓I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����Ɛ[�����ՓI�Ȃ��̂ƌ����B�\���҂Ƃ��Ă̂��ꂪ���߂Ȃ̂��낤�B�����������A���͂����Ƀx�[�g�[���F���́g�l�I��̓I�h�ȒQ���Ƃ���ɑł����Ƃ��Ƃ���ӎu������B����ɂ��Ă͎���T�����悤�Ǝv���B
���Q�l������
NHK-BSP�N���V�b�N���y�فu�s�A�j�X�g���R���t�b�̐��E�T�v 2022.7.25OA
�x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110 �y���iG. Henle Verlag�j
�x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110 CD�@16W
�ŐV���ȉ���S�W �Ƒt�ȇU�i���y�V�F�Ёj
�N���V�b�N����̋��������i���y�V�F�Ёj
21���I�̖��Ȗ��ՇT�i���y�V�F�Ёj
2022.07.26 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g2
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�����h�q�Ƃ����d���s�A�j�X�g
�i1�j�����h�q�̃v���t�B�[�� �@�@1944.7.25 �쑺�T�v�ƒ����j�q�̒����Ƃ��ĎR�������R���ɐ����
�@�@1944.7.25 �쑺�T�v�ƒ����j�q�̒����Ƃ��ĎR�������R���ɐ�����@�@1948 �˕��w���́u�q���̂��߂̉��y�����v��1�����Ƃ��ăs�A�m��
�@�@�@�@�@�����n�߂�
�@�@1954 �S���{�w�����y�R���N�[�����w���̕���1��
�@�@1959 ���{���y�R���N�[����1��
�@�@1960 NHK�����y�c���̐��E�c�A�[�̃\���X�g�Ƃ��Ĕ��F
�@�@1965 ��7��V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���ő�4�ʂɓ���
�@�@1974 �H��܍�� ���i�O�ƌ���
�@�@2016.7.26�v
�@16��N�����E�c�A�[�̃\���X�g�A21�ŃV���p���E�R���N�[����4�ʓ��܂Ƃ���A����͂����A�����A���{�l�̒N�����ׂ����Ȃ������̋Ƃɂ��ĎႫ�X�^�[�̒a���ł���B���̌�͉��t�҂Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸�A�V���p���E�R���N�[���̐R���ψ��߂�ȂǁA�s�A�m�E�̏����ƌĂꂽ�B
�@�R���N�[����Ƃ������؏�����u���I�Ɖ����v�̒��ɁA���V�A�l��70�߂������R���ψ������o�ꂷ�邪�A�u�d�����ƃo�C�^���e�B�͍����̐������Ȃ��A���y�E�Ɋ���L�����A�����\�͂����r�ɂ��G�ŁA�g�P�]���ۃs�A�m�R���N�[�����ʂ萢�E�ɒʗp����R���N�[���Ɉ�ďグ���̂́A���x���R���ψ����߂Ă����ޏ��̗͂��傫���E�E�E�E�E�v������̋L�q�́A���V�A�l����{�l�A�g�P�]��l���ɒu��������A�܂��ɒ����h�q���̂��́B�����A�����h�q��1995�N����15�N�Ԃ̒����ɂ킽��l�����ۃs�A�m�R���N�[���̐R���ψ����߂Ă���B
�@�ޏ��̎��ɗՂ�ł͊e�E���瑽���̈����̎�����ꂽ�B���̒�����킪�����y�E�̒��V�ł���C�V��q�i1931-�j���̒�����v�ĉ��L�B
�����h�q����A���[�c�@���g�̃j�Z���R���`�F���g�̋����ƂƂ��Ɉ��炩�Ɍe���@���ۃ��[�c�@���g���c���_���c���Ƃ��������䂦���킪�����[�c�@���g�����̑��l�҂Ɩڂ����C�V���̎^�������Ĉ����̎���B��x�X�g�Z���[�����̃��f���ɂ��Ȃ�B�H��܍�Ƃ�v�Ɏ��B���t�ҁA����҂ɉ����āA���M�ƂƂ��Ă������]�������B�����h�q�͂܂��ɋP�������|�p�Ɛl����S�������̂ł���B
�@�����h�q���������B�����ł͂܂��ƁA�l�I�Ƃ������ׂ������o�A����������̉�z����点�Ă����������B�̗L�n��ܘY�������y��w�O�w���̒Ǔ����t��B�����h�q�̓Ƒt�A���������w���FNHK�����y�c�̃��[�c�@���g�̃j�Z���R���`�F���g�̉��t�͎��̔]���ɐ[�����ݍ��܂�A�����ĖY�������邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�ޏ��͂܂��Ƒt�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă��肩�A�s�A�m����̐��E�ɂ��S���𒍂���A�����̎Ⴂ�s�A�j�X�g�̈琬�A�����A�����Ĕy�o�ɂ����N�w�͌X�����ꂽ���Ƃ͎����w�E����܂ł��Ȃ��B
�@�l���̍��ۉ��y�R���N�[���Ŏ��͐���ɘj���ĉ^�c�ψ����Ƃ��āA�R���ψ������Ƃ߂�ꂽ��������̂���`�������Ă������A���݂���C��R��̊O���l�R���ψ��̊F����������Ȏ�J���œZ�ߏグ���r�ɂ͊��Q�̐���R�炳��������Ȃ������̂����������v���o�����B�����B
�@���āA����Ȓ����h�q�ɂ͕ʂ̊炪����B�X�������y�Ƃ̊炪�z�Ȃ�A�A�Ȃ��ł���B
�i2�j�����V�q���o������O���[���Ԃ̏�
�@����V�����̓O���[���Ԃ���Ȃ����܂��Ă䂭�Ƃ����B�̂̃O���[���Ԃ́u�V���u�L����������A�g�C���ɗ�������V�ɔ�����v���͋C�ł���A�ԒI�̃X�[�c�P�[�X�A�I�[�o�[�R�[�g�̗ނ��u���������v�̊����������B���͂ǂ����낤�B�u�ܐ�~�A�Z��~�H������ۂ������������Ȃ�O���[���ɂ��悤��v�������悤�������悤�Ǝ�҂ł��ӂ��B�c�̂�����u�O���[���ɂ��܂فv�Ƃ������ƂɂȂ��āA���ʎԂƉ���ς��Ȃ��l����悵�Ă����B�Ԃ�V�͋������K�L�͑���܂�邵�E�E�E�E�E�B�@����͎����V�q�i1929-2007�j���Ƃ���V���ɓ��e�����S���ł���B���̋L�����琄�@����1990�N�̂��ƂƂ킩��B��������͐���E�̗^�Ӗ쏻�q�Ƃ���ꂽ�����Ȑ����ƁB��W�u�L�v���v�̓x�X�g�Z���[�ƂȂ��Ă���B�����́gH.N���j�h�́u�悭�����v�Ƃڂ����Ă��邪�����h�q���̐l�i����46�j�ɊԈႢ�Ȃ����낤�B�����炭�������j�͑��肪�����Ȑ����ƂƂ͒m��Ȃ������̂��낤�B�m���Ă����炱�̂悤�ȑԓx���Ƃ�Ȃ��l���B�אȂ̂ǂ����̃I�o�n�����݂邱�ƂȂ��������z���Ă���B�u���A�����h�q��B���炶��Ȃ��́v���ĂȊ������낤���B���ɐ������˂ĐȂ��ڂ�A�߂��Ă��Ď̂đ䎌��f�������������B�Ƃ����^���ł���B�����s���ȏ��̎p���`����B�����h�q�̂�����̊�ł���B
�@�ߓ����͎l���̗\�]�����������y�]�����������̃O���[���Ȃ��d���Ŏ���Ă�������B�����������Ă����אȂ̐l���A�s�A�m���t�ƂŃJ���[�̃R�}�[�V������H.N.���j�ɂ悭�����l�ł��������A���͉��̋C�Ȃ��ɂ����Ɖ�������{�����B����Ƃ��̐l�́A�I���ɂ���Ȃ��Ԃ���Ȃ������̂Ŏ��͂���ĂĂ��ݏ������B���̐Ȃ͋։��Ȃł͂Ȃ��B����͂悭�悭�������߂Ă�������Ȃ���������B�@
�@�gN���j�h�̓o���ƋN���オ�邪�������ׂ̎��q�Ɉڂ�A���̕����w�����Ďԏ��ƌ����ł���炵���B�₪�ăy�R�y�R����ԏ��Ƌ��ɔޏ��͐Ȃ��ڂ��čs�����B�����B���͗אȂ։ו���u���đ��O�̌i�F���y����ł����B
�@�₪�ĉ��ԉw�B�gN���j�h�͎��̉ו����w�����āu�����͎��̐Ȃ�I�v�Ƃ�����������B����͂�O���[���Ԃ������͂炭�ł͂Ȃ��B
�i3�j �������b�̎��M���R������
�@�ȉ��͉��y�]�_��H.I.�����畷�����{���̘b�ł���B����1979�N�A���͂��łɉ��y�]�_����|���Ă͂������A�܂��{�E�̓T�����[�}���BTBS�u���^�j�J�ɐЂ�u���Ă�������̏o�������B
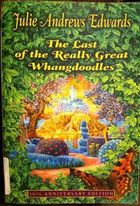 �@����c�ŁA�W�����[�E�A���h�����[�X�����������b�u�̑�ȃ����h�D�[�h���������̈�҂��v��|��o�ł��邱�Ƃ�����B����́A�z���̐��E�ɏZ�ޓ��������h�D�[�h����3�l�̌Z�����T���ɂ䂫�A���̉ߒ��Ől�̂₳������v�����⋦�͂��邱�Ƃ̑�����w��ł䂭�A�t�@���^�X�e�B�b�N�ł��߂ɂȂ银�b���B��͒����h�q�ɂ��肢���悤�Ƃ������ƂɁB�ޏ��͐��Ȑl�C���ւ�s�A�j�X�g�ł���A�v�͊H��܍�Ƃ̏��i�O�ŕ��w�I������\���B�|��͂���̕���H.I.�����̃T���v����p�ӁA�����h�q���Z�ގO�c�̍����}���V������K�˂�B
�@����c�ŁA�W�����[�E�A���h�����[�X�����������b�u�̑�ȃ����h�D�[�h���������̈�҂��v��|��o�ł��邱�Ƃ�����B����́A�z���̐��E�ɏZ�ޓ��������h�D�[�h����3�l�̌Z�����T���ɂ䂫�A���̉ߒ��Ől�̂₳������v�����⋦�͂��邱�Ƃ̑�����w��ł䂭�A�t�@���^�X�e�B�b�N�ł��߂ɂȂ银�b���B��͒����h�q�ɂ��肢���悤�Ƃ������ƂɁB�ޏ��͐��Ȑl�C���ւ�s�A�j�X�g�ł���A�v�͊H��܍�Ƃ̏��i�O�ŕ��w�I������\���B�|��͂���̕���H.I.�����̃T���v����p�ӁA�����h�q���Z�ގO�c�̍����}���V������K�˂�B�@�u����͊C�O�ł̕]���������A���Ȃ��̖��O���������x�X�g�Z���[�͕K���A�����Z�Ǝv����̂ŃT���v���ɖڂ�ʂ��Ă�������������g�����Ƃ��\�ł��v�BH.I.���͐^���ɒ��d�ɐ�������B���āA�ޏ��̕ԓ��́E�E�E
�E�E�B
�@�u���Ȃ��ˁA���͍��Z�����́B���M�̈˗����R�قǂ��Ă����B�����V���ЁA�V���A�͏o�ȂLjꗬ�̂Ƃ������B������f���Ă���̂ɁA�h�u���^�j�J�g�ł����āA����Ȃ킯�̂킩��Ȃ��Ƃ��납��o���Ȃ�Ăł���͂����Ȃ��ł���v�B������ق��B�܂�ŏo�ʼn�Ђ̃p�V���̈����ł���B����ł��ƁA�u��揑�Ɩ͂��a�����܂��B��T�Ԍ�ɂ܂��f�킹�Ă��������̂ŁA���Ԏ��͂��̎��Ɂv�ƍ����āAH.I.���͂��̏�����Ƃɂ����B
�@��T�Ԍ�ɏo�����ƁA�{�l�̑���ɔ鏑������āu���a���蕨�͂��Ԃ����܂��B�Ԏ��͐搶���\���������Ƃ���ł��v�B���͂����Ȃ��`�����ƂȂ����B
�@������A�����h�q�̑�ł��ǂ����邩�B��c�ŁA�쎌�Ɗ�J���q����͂ǂ��� �Ƃ������ƂɁBH.I.���͊�J���ɑŐf����B�u���Ȃł�낵���̂ł��傤���v����ꐺ�������B��J���q�Ƃ����ΐ��X�̃q�b�g�Ȃݏo���Ă����ꋉ�̍쎌�ƁB���M�҂Ƃ��Ă͂�����̕����i��ł���B�u�Ƃ�ł�����܂���B������낵���v�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ŁA��J�̏o���������́u�����܂łɏグ��̂ő��̎d���̓V���b�g�A�E�g�������B���̂���2�T�ԃz�e���Ɋʋl�߂ɂȂ��ďW���������v�Ƃ������̂������B�u�������ł��v��H.I.���̓z�e������z��2�T�ԑ҂����B
�@2�T�Ԍ㊮���������e�����B�����ŁAH.I.���͚X�����B��H.I.���̃T���v�������ɁA�Ƃ���ǂ���ޏ��Ȃ�̎肪�����Ă���B�Ƃ��낪���̒��ŁAH.I.�����P�Ɂu���e���V���ɖڂ�ʂ��v�Ƃ��������ɐV���̋�̖����L����Ă����̂��B����͌����ǂ܂Ȃ���Δ���Ȃ����ƁB�����Ȃ���A��J���́A2�T�Ԃ̊ԂɌ���{����肵�āA�Q�Ƃ��Ă����̂ł���B�Ȃ�Ƃ��������ȑΉ��B�������j�Ƃ͐l�ԂƂ��ĉ_�D�̍��Ƃ����ׂ����B��J���q��u�̑�ȃ����h�D�[�h���������̈�҂��v��20�����̃x�X�g�Z���[�ƂȂ����B
 �@����ɂ͌���k������B���s�O��̂�����AH.I.���̓g���R��g�قōs��ꂽ�C�x���g�ɏ��҂���ďo�������B�Ƃ����ɁA�������j���ՐȂ��Ă����̂ł���B������ɂ�����ɏH�g�𑗂��Ă���BH.I.���A���R�����B�����Đ�����A�������j����A����|�X�^�[�t�̍ŐV��LP���R�[�h�u�O���[�O��ȁF�s�A�m���t�ȑ��v�������Ă����B�W���P�b�g�ɂ́u�ޒ� �Έ�G�l 1979�N�Ă� �����h�q�v�Ƃ̒��M�T�C�����B�u�����Ǝ������y�]�_�����Ă��邱�Ƃ�m�����̂��낤�ˁB����Łw��낵���x�Ƃ����C�ɂȂ����̂��ȁB����ɂ��Ă��A����Ȃ��̎�����ԂƂł��v�����̂��ˁv��H.I.���͋����B�����b�g�Ȃ�����ɂ͂����ɁA�L�v�Ȏ҂ɂ͈�]���ěZ�т�A����Ȓ����h�q�̋C���������Ă���B
�@����ɂ͌���k������B���s�O��̂�����AH.I.���̓g���R��g�قōs��ꂽ�C�x���g�ɏ��҂���ďo�������B�Ƃ����ɁA�������j���ՐȂ��Ă����̂ł���B������ɂ�����ɏH�g�𑗂��Ă���BH.I.���A���R�����B�����Đ�����A�������j����A����|�X�^�[�t�̍ŐV��LP���R�[�h�u�O���[�O��ȁF�s�A�m���t�ȑ��v�������Ă����B�W���P�b�g�ɂ́u�ޒ� �Έ�G�l 1979�N�Ă� �����h�q�v�Ƃ̒��M�T�C�����B�u�����Ǝ������y�]�_�����Ă��邱�Ƃ�m�����̂��낤�ˁB����Łw��낵���x�Ƃ����C�ɂȂ����̂��ȁB����ɂ��Ă��A����Ȃ��̎�����ԂƂł��v�����̂��ˁv��H.I.���͋����B�����b�g�Ȃ�����ɂ͂����ɁA�L�v�Ȏ҂ɂ͈�]���ěZ�т�A����Ȓ����h�q�̋C���������Ă���B�@H.I.���Ƃ͒N�H �䂪�h�����鉹�y�w�ҁE�]�_�Ƃ̐Έ�G�i1930-�j�搶�ł���B��q�����C�V��q���́A�J�ԁA���[�c�@���g�����̑��l�҂Ƃ����Ă��邪�A����͌����̂Ȃ���Ƃ��낤�B�����I�ɂ͐Έ�搶�������l�҂̖��ɂӂ��킵���B����͗��҂̃��[�c�@���g�������ǂ���Ζ����ł���B�Ⴆ�ΊC�V�́u���[�c�@���g�̉��L�v�B�������������B���Łu���N�C�G���v�̏����i1991�j�ɗ�������Ă���̂ɁA�����B�������̊j�S�ł���u�z�U���i�̒����v�ɂ͈ꌾ���G��Ă��Ȃ��B�����Ƃ����A���[�c�@���g�̃������A���E�C���[�i1956�A1991�A2006�j�̘b���J��Ԃ�����邾���ŁA���[�c�@���g���̂��̂ɐ荞�ޕM�@�͌��Ђ��Ȃ��B�������烂�[�c�@���g�̎����������Ă��邾�����B���ꂼ�܂��Ƀ^�C�g���ɒp���Ȃ��g���[�c�@���g�̉��L�h�ł���B
�@�Ђ�Έ�搶�́A�Ⴆ�u�f��̃��[�c�@���g�v�B�s�A�m���t��K595�ɔފ݂̉��������A�u���J�v�̃p�p�Q�[�m�̓��[�c�@���g�̉��g�Ƃ���d��A�u���N�C�G���v�ɖ��ߍ����[�c�@���g�̐^���ǂ݉��������I�ȕM�v�B�����̋L�q�͂����ȂׂĎ��ؓI�E�_���I�ł����[�c�@���g�ւ̈��ɂ��ӂ�Ă���B�C�V�̃��[�c�@���g�_�Ƃ͌��ƃX�b�|���A��J�ĕ��Ɠ����Òq�̍��ł���B�k���Ș_���\���A����ӂ��`�ʁA�����ȕM�v�B�搶�̐��ݏo�����͂͐[���ʔ����B�����Ă����́A����������ׂŔ��f���邱�ƂȂ��{�����˔��������Ȏ��_�ɏ������Ă���B
�@����ȐΈ�搶���A�]�_�Ƃɐ�O����O�̃T�����[�}������A�����h�q�ɂ܂��̌��k������Ă��ꂽ�̂ł���B�搶�ɑ����Ē����h�q��]����Ȃ�u�Ƃ�ł��Ȃ����v�Ƃ������ƂɂȂ낤���B�܂��A���̓�ʐ�����A���[�k�X�`�d���ɗႦ�邱�Ƃ��ł���B�o�[���X�^�C���͎�ɂ���u�����O�E�s�[�v���Y�E�R���T�[�g�v�̒��ŃN���V�b�N���y��high brow�i�����ȁj���y�ł͂Ȃ�exact�i�k���ȁj���y�ƒ�`�����B��������̓N���V�b�N�̌[�֎҂Ƃ��āu�������v�Ǝv��ꂽ���Ȃ��C�����̕\��ŁA�N���V�b�N�ɂ������l�Ԃ͖{���̂Ƃ���ŃN���V�b�N���y���u�����ȁv���y�ƍl���Ă���B�����������A�����ȃN���V�b�N���y�������łȂ��l�Ԃ����t����B�����Ă��ꂪ�����ƕx�ށB����ȃp���h�N�X�����R�Ƃ��đ��݂���̂����̖ʔ����Ƃ������̂��낤�B
���Q�l������
NHK-BS ���ɋ����s�A�m���`�����h�q����̎c�������́i2016 OA�j
�u�L�v���v �����V�q���i�����V���Ёj
�u�̑�ȃ����h�D�[�h���Ō�̈�C�v�W�����[�E�A���h�����[�X���A���C���q��i���w�فj
�u�f��̃��[�c�@���g�v�Έ�G���i�������Ɂj
�u���[�c�@���g�̉��L�v�C�V��q���i�t�H�Ёj
�u���I�Ɖ����v���c�����i���~�Ɂj
DVD ���i�[�h�E�o�[���X�^�C�����j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N
�@�@�@�u�����O�E�s�[�v���Y�E�R���T�[�g�v�iSony Music�j
2022.06.20 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g�P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`���q�b�q�Ɠc�����q
�@�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���A�G���U�x�[�g���܍��ۃR���N�[���A�`���C�R�t�X�L�[���ۃR���N�[���𐢊E3��R���N�[���ƌĂԂ������B�G���U�x�[�g���܍��ۂ́A1937�N�A�����@�C�I���j�X�g �E�W�F�[�k�E�C�U�C�̖��������Ďn�߂����@�C�I�����̃R���N�[�������[�B�`���C�R�t�X�L�[���ۂ́A1956�N�A�K�K�[�������l�ޏ��̗L�l�F����s�𐬌������Đ����ɏ��\�A���A1958�N�A�|�p�ʂł������̗D�ʂ��֎����ׂ��n�݂����B�Ƃ��낪��1��̗D���҂̓��C�o�����A�����J�̃��@���E�N���C�o�[���B���Ă������̃A�����J�Ɛ؎��N�r�̃\�A�B���y�d���������čs��ꂽ��2��͖ژ_���ʂ�\�A�̃E���f�B�~�[���E�A�V���P�i�[�W���D���B�Ƃ��낪�ނ͂��̌�\�A�𗣂�Ď��R��`�w�c�ɖS���������ߓ��ǂ͗D�����������Ƃ����d�ł��ɏo���B�\�A�̎v�f�ɃR���N�[�����h�ꓮ�����Ƃ����킯�ł���B�����̂��\�A�����V�A�̐g����͕ς��Ȃ��B�@�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���̑n�݂�1927�N�B�J�Â�5�N�Ɉ�x�A����̓s�A�m�̂݁A�ۑ�Ȃ̓V���p����i�̂݁A�����̓V���p���̓�̋��t�Ȃ̂ǂ��炩 �Ƃ������Ƀ��j�[�N�ȃR���N�[�����B�Ƃ͂������݃s�A�j�X�g���ł������R���N�[���ł�����B����́A�D���҂ɁA�}�E���c�B�I�E�|���[�j�i1960�j�A�}���^�E�A���Q���b�`�i1965�j�A���c���q�i1970�A2�ʁj�A�N���X�e�B�A���E�c�B�}�[�}���i1975�j�ȂǁA��������s�A�j�X�g������A�˂Ă��邩�炾�낤�B
�@����̓V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���ɂ܂��2�l�̓��{�l�����s�A�j�X�g�����グ�����Ǝv���B
(1) ���q�b�q�`�g���̐l��
 �@�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���̓��{�l�p�C�I�j�A��1937�N��3����ɏo�ꂵ�����q�b�q�i1914-2001�j�ł���B���ʂ�15�ʂ������B�Ƃ��낪�A���O�������h�邪���قǂ̃u�[�C���O�̗����N����B�R�����͋}篁u���ʒ��O�܁v��V�ݎ��^���Ă�������߂��B�R�������A�u���y��i���̓��{�����炱���炠���肪�Ó����낤�v�ƍl�������ǂ����͂킩��Ȃ����A���O�̎��ɂ͋���ɑi���鉽�����������̂��낤�B�V���p���E�R���N�[��95�N�̗��j�̒��ŁA���O�̕s���ɂ���Ď�ܓ��e���ύX���ꂽ�̂͌�ɂ���ɂ����̃P�[�X�����ł���B
�@�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���̓��{�l�p�C�I�j�A��1937�N��3����ɏo�ꂵ�����q�b�q�i1914-2001�j�ł���B���ʂ�15�ʂ������B�Ƃ��낪�A���O�������h�邪���قǂ̃u�[�C���O�̗����N����B�R�����͋}篁u���ʒ��O�܁v��V�ݎ��^���Ă�������߂��B�R�������A�u���y��i���̓��{�����炱���炠���肪�Ó����낤�v�ƍl�������ǂ����͂킩��Ȃ����A���O�̎��ɂ͋���ɑi���鉽�����������̂��낤�B�V���p���E�R���N�[��95�N�̗��j�̒��ŁA���O�̕s���ɂ���Ď�ܓ��e���ύX���ꂽ�̂͌�ɂ���ɂ����̃P�[�X�����ł���B�@�������̓p���Ō��r���̐g�������B�����ň�l�̓��{�l���w���Əo��B��Y�_�j�i1913-1970�j�ł���B���{�Ɛ��m�̕����𗬂ɏ�M��R�₷��Y�ƌ��͈ӋC�����B1938�N�Ɍ����B�ۘY�ƌ��Y�̓���������B
�@�I���A�_�j�͊O���Ȃ̊O�s�c�́E���ە����U����̏����Ƃ��Ċ����B�̕���╶�y�̊C�O���s������|����B�C�^���A�ʼn̕�������̍ۃi���[�^�[�Ƃ��ĎQ�������⌳���q�Əo���������ӋC�����B�_�j�͊��q�ɏ�芷����B
 �@1960�N�A�_�j�Ɗ��q�͔ёq�В��Ƀ��X�g�����u�L�����e�B�v���J�݁B���{���̖{�i�I�C�^���A���E���X�g�����������B�O���R�I�v�A���V���A���{���Y�A���V�����A�t�����N�E�V�i�g���A�s�G�[���E�J���_���A�J�g���[�k�E�h�k�[���A�}�[�����E�u�����h�ȂǍŐ�[�̕����l�̎Ќ���ƂȂ��Ă䂭�B��҂ł́A���܂�Ђ낵�A�~�b�L�[�E�J�[�`�X�A�䐳�́A����܂肱�炪�ۘY�����ɗւ��L���A10��̍r��R���͂������N�_�ɐV�������y�̓����Ă䂭�B�L�����e�B�͐V�������l�𗬂̃T�����ł���A��������[�h����X�^�[�{���H��Ƃ��Ă̖��������S�����̂ł���B
�@1960�N�A�_�j�Ɗ��q�͔ёq�В��Ƀ��X�g�����u�L�����e�B�v���J�݁B���{���̖{�i�I�C�^���A���E���X�g�����������B�O���R�I�v�A���V���A���{���Y�A���V�����A�t�����N�E�V�i�g���A�s�G�[���E�J���_���A�J�g���[�k�E�h�k�[���A�}�[�����E�u�����h�ȂǍŐ�[�̕����l�̎Ќ���ƂȂ��Ă䂭�B��҂ł́A���܂�Ђ낵�A�~�b�L�[�E�J�[�`�X�A�䐳�́A����܂肱�炪�ۘY�����ɗւ��L���A10��̍r��R���͂������N�_�ɐV�������y�̓����Ă䂭�B�L�����e�B�͐V�������l�𗬂̃T�����ł���A��������[�h����X�^�[�{���H��Ƃ��Ă̖��������S�����̂ł���B�@���������ɏo�Ă����̂�1964�N�B�L�����e�B�͊��ɑ��݂��Ă����B���A���̑��݂��m��Ȃ���Βm���Ă����Ƃ��Ă��C��ꂵ�ďo����Ȃǂł��͂��Ȃ��������낤�B��������������̃j�R���X������Ńs�U���܂ނ̂��������ς��������B�������Ȃ��炱���̏�A�̕��X�Ƃ́A��ɂȂ��Ďd���㑽���̊ւ肪�������B
�@BMG�r�N�^�[�ݐЂ�1993�N�A�J���g���[���̂��ЎR���j�Ƃ���17�̏��N�̎�̃f�r���[�Ɍg������B�ЎR���N�͂킪���J���g���[�E�~���[�W�b�N�t�����̃~���[�W�V�����̌�q���B�v���f���[�X�́g���b�V���h���܂�Ђ낵�A��Ȃɂ͋g�c��Y�A�ʒu�_��炪����A�˂�B���R�[�f�B���O�̓i�b�V���r���Ŋ��s�B�f�r���[��uBACK FROM MUSIC CITY�v����������B�������L�O���āA���h�N���R�_�C���Ƀ}�X�R�~�����X�Ȃǂ������A���C�u�C�x���g��h��ɑł��グ���B�����A���͐����`�R�[�f�B�l�[�g(CD�̃N���W�b�g��Creative Co-ordination�j��S�����Ă���A���[�J�[���̐ӔC�҂̈�l�Ƃ��ă��b�V���Ɠ����e�[�u���ɂ��B�|�\�E�̃��W�F���h��O�ɋْ��C�����������Ƀ��b�V���͋C�����ɐ��������Ă��ꂽ�B�b�̐܂ɔނ��������u�̎�����ˁv�͏����B��̑傫���D�����l�Ƃ�����ۂ������B
�@�~�b�L�[�E�J�[�`�X�Ɛ�Y�ۘY���Ƃ́A�uFROM THE MOON FOR THE TREES JUST ROCK�fN ROLL�v�i1994�����̃A���o���j�ł̕t�������ł���B���̃A���o���̓~�b�L�[�E�J�[�`�X�|�\����40���N�L�O�A�ނ̐��E�ςƃ��b�N�����[�������ѕt�����ӗ~�삾�����B���R�[�f�B���O�I������ɉ�c���Ń~�b�L�[�u�t�́u����R���Z�v�g������v���s��ꂽ�B��1�ȁu�Â��̊C�v�ł́A�u����g�Â��ȁh����Ȃ���B�w�g�Â��́h�C�x�Ƃ����ŗL�����B�A�[���X�g�����O�����ɓ��������n�_�̂��Ɓv�Ȃ��]�~�������A���X2���ԁA����Ӑ}��b��������B�{�l�̈ӗ~�Ə�M���Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă������̂ł���B�������O�A��������A�}�X�R�~�������\���s���̃z�e���ő�X�I�Ɋ��s�B�����̎d��͐�Y���B�����ŗB��Ƒ��A�����ǂ������߂Ȃ��l��������������A����Ȉ�ۂ������B�m���ɁA�u���̑]�c���͌㓡�ۓ�Y�A���̓L�����e�B�̑n�ƎҁA�~���[�W�J���w�w�A�[�x�v�̏㉉�͉���������A���O��Ƃ͏Z�ސ��E���Ⴄ�v���Ăȕ��͋C�������Ă����悤�ȁE�E�E�E�E�Ƃ�����A�����{�̕����̓��C�����T�u�����镔���u�L�����e�B�v���琶�܂�Ă����͎̂������낤�B�����S���Ă������X�Ƒ����Ȃ�Ƃ����������Ă��̂͋M�d�ȑ̌��������Ƃ����ׂ����B�Ƃ���ŁACD�̔���グ�́H �܂���������܂���ł����i���j�B
�@����߂����B1958�N�A���q�b�q�͐��E�I�`�F���X�g �K�X�p�[���E�J�T�h�i1897-1966�j�Əo��č�����B���t�҂Ƃ��ĉ~�n�̋��n�ɂ������J�T�h�͒q�b�q���������b�����Ƃ����B�v�̈��̃��`�ɂ���Ēq�b�q�̉��y�͍X�Ȃ鐬�n���݂���B�u3�N�������Ă���Ɣނ̋��n�ɂ��ǂ�����Ǝv���v�Ɣޏ��͉�z���Ă���B���̌��l�́u�f���I�E�J�T�h�v�Ƃ��Đ��E�e�n�ʼn��t����J�����т��B�q�b�q�́A�J�T�h�̎���A�v�̖����������u�K�X�p�[���E�J�T�h���ۃ`�F���R���N�[���v�𗧂��グ���B
�@�̂��狻���������Č��q�b�q��CD�́u�p���̌��q�b�q�v�Ɓu�`���̃s�A�j�X�g�v��2�������L���Ă���B�����[�A�������A�N�[�v�����̃t�����X�o���b�N�̏��i�ɂ��e�肽��T��ȍ��肪�Y���A�f���I�E�J�T�h�̃u���[���X�̃\�i�^�ł͒[���ȏ���ƒ�ɐ��ޏ�M�����悭�o�����X����B�Ƃ͂��������́A�����Ƃ����l�̌܂̕]������������s�A�j�X�g�̌��q�b�q�]���f��������K�ł��낤�B
���̎q�͖{���̌|�p�Ƃł���(2) �c�����q�`���K�̃s�A�j�X�g
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�A���t���b�h�E�R���g�[
�p���Ń��U�[���E�����B�̋��������ޏ��͈̑�ȃs�A�j�X�g�ł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�A���V�A�E�f�E�����[�`��
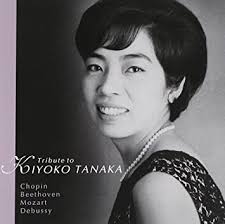 �@�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���ŁA���{�l���̓��҂͓c�����q�i1932-1996�j�ł���B1955�N2���A��5��A�c���͏����ɗ\�I���N���A�B���t�ȂŔe�������{�I10�l�̘g�ɓ���B�����̉��t���̓A���t�@�x�b�g�����������ߓc����9�Ԗڂ̉��t�ƂȂ����B�o�Ԃ܂łق�5���ԁB���Ȃ肫���҂����Ԃł���B�I�s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ�e���I�����Ƃ��ɂ́u�ǂ��e�������قƂ�lj����Ă��Ȃ��B�܂�ł��킲�Ƃ������Ă���悤�ȃs�A�m�������v�Əq�����Ă���B�������̏��炨���炭�W���͂��\���ł͂Ȃ������̂��낤�B�I�[�P�X�g���������Ȃ̌J��Ԃ��ł͉��t���_�����B���ʂ�10�ʁA�Ƃ͂������{�l�����܁B���q�b�q�̏��o�ꂩ��18�N���o�߂��Ă����B�����ł܂��������N����B�R�����̃C�^���A�̓V�˃s�A�j�X�g �A���g�D�[���E�x�l�f�B�b�e�B���~�P�����W�F�����A�c���̏��ʂ�s���Ƃ��ĐR�������~��Ă��܂��B���̎��͒��O���A�c���̎��ɂ͑啨�R�������ق��������̂ł���B�~�P�����W�F���͓c���̓V�˂̖G������m�����̂��낤�B�V�˂͓V�˂�m��Ƃ������Ƃ��B�����āA�c���͂��̃R���N�[���Łu���m�̊�Ձv�Ə̂���ꂽ�B
�@�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���ŁA���{�l���̓��҂͓c�����q�i1932-1996�j�ł���B1955�N2���A��5��A�c���͏����ɗ\�I���N���A�B���t�ȂŔe�������{�I10�l�̘g�ɓ���B�����̉��t���̓A���t�@�x�b�g�����������ߓc����9�Ԗڂ̉��t�ƂȂ����B�o�Ԃ܂łق�5���ԁB���Ȃ肫���҂����Ԃł���B�I�s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ�e���I�����Ƃ��ɂ́u�ǂ��e�������قƂ�lj����Ă��Ȃ��B�܂�ł��킲�Ƃ������Ă���悤�ȃs�A�m�������v�Əq�����Ă���B�������̏��炨���炭�W���͂��\���ł͂Ȃ������̂��낤�B�I�[�P�X�g���������Ȃ̌J��Ԃ��ł͉��t���_�����B���ʂ�10�ʁA�Ƃ͂������{�l�����܁B���q�b�q�̏��o�ꂩ��18�N���o�߂��Ă����B�����ł܂��������N����B�R�����̃C�^���A�̓V�˃s�A�j�X�g �A���g�D�[���E�x�l�f�B�b�e�B���~�P�����W�F�����A�c���̏��ʂ�s���Ƃ��ĐR�������~��Ă��܂��B���̎��͒��O���A�c���̎��ɂ͑啨�R�������ق��������̂ł���B�~�P�����W�F���͓c���̓V�˂̖G������m�����̂��낤�B�V�˂͓V�˂�m��Ƃ������Ƃ��B�����āA�c���͂��̃R���N�[���Łu���m�̊�Ձv�Ə̂���ꂽ�B�@���̂���̓c�����q�̓p�����y�@�Ŗ����y���U�[���E�����B�ɏA���Č��r��ς�ł����B��Ȑ�U�̎��˖r�Y�i1929-2007�j�Ƃ͊��Ƀp�[�g�i�[�Ƃ��ĕt�������Ă���A���̔N�̏H��������B��1956�N�āA��l�͉��y�@�Ń��@�C�I�������U����c���̒�獁�m���ăo�J���X���j�[�X�̒m�l�̕ʑ��ʼn߂����B������A�C�݂ō�ȉȂ̎O�P�W�Ƒ����B�u�����ɂ����ł�v�Ɛ��������p�����y�@��4�l�̋��������Ƃ����Ȃ����B�O�P�͂����Ŋ��q�̃s�A�m�����ɂ���B
����́A����ꂽ��捂̂Ȃ��ɔM�������Ă������̂̐���Ȗz���ł��������낤���B���q���u�_�v�ƌ��킷���̑Θb���A�앧�̖����̐Î₩��R�꒮�������̂������낤���E�E�E�E�E��Ղ̉��������B����͈�̂��̂̉�݂������Ȃ������B���̉i���ɂȂ��铧���Ȏ����ɁB�@����͎O�P�W���c�����q�̎��Ɋ��Ǔ����ł���B�Ȃ�Ƃ������������͂��낤�B�Ȃ̓V���p���̗��K�ȉd�g�Z����i25-6�������Ƃ����B�ǂ�ȉ��������̂��낤���B�|���[�j�̉��t�����肩��z����~�����Ă邵���Ȃ��̂��낤���B�O�P�搶�Ƃ͎d���ł��ꏏ�������Ƃ�����B���̎����̕��͂�m���Ă���Ɖ���܂�ĂȂ�Ȃ��B
�@�V���p���E�R���N�[����̓c�����q�̊���͂����܂��������B�������A�܂��ɂ��ꂩ��Ƃ������q�ɓˑR�a�����P���B��a���P���a�ł���B�f�f�������ꂽ�̂�1968�N4���̂��Ƃ������B���t�ƂƂ��Ă̓���f���ꂽ���q�͌�i�̎w���ɋ��ݑ�w�ŋ��ڂ��Ƃ���A1996�N2��26���ɉi���B���N64�������B
�@�c�����q�̎��ɍۂ��ĐΈ�G�搶�͂���Ȉꕶ���Ă���B
�f�B�k�E���p�b�e�B�Ƃ����s�A�j�X�g�������B�W�l�b�g�E�k���[�Ƃ������@�C�I���j�X�g�������B���ꂼ�ꂲ���킸���Ș^�����c���Ă��̐��������Ă���B�����̘^�����ƁA�������̐l�����������Ă�����ǂ�قǂ̌|�p�ƂɂȂ��Ă������Ǝv����B���̐l�����́h�����Ă�����́g���Ⴄ�̂ł���B���ɐ_�͂��̐��ɂ�����������ȃX�P�[���̐l�Ԃ𑗂�o���Ă����B�c�����q���܂����������_�̑��蕨�̈�l���B�ɂ߂ĉs�q�Ȋ����B�����͂���̒m���Ɨ����B���₢���f�͂ƌ��f�B��������S���x���錵���������S�B�w�͂�ɂ��܂Ȃ������B���y�ւ̈���ƖL���ȏ�B�����̂��ׂĂ��A�����Ȃ�ʂقǔޏ��̑̂ɏ[�����Ă���B�������ޏ��͎������U�ɏo������l�̒��ł��A�l�ԂƂ��čł������ꂽ�A���̌̂ɐ[���h������ɒl����l���Ȃ̂ł���B�@�����Ȑ搶��������������̕M�v�şӐg�̎^��������Ă���B����ȓc�����q�ɑ��Ď����Ƃ������������������菑���L�����ƂȂǂł���͂����Ȃ��B�����������S�R���ɁA�c���ꂽ�ޏ��̃h�r���b�V�[�Ɏ����X���A�[���O���C�̍�����y���ށB����ȂƂ��낪�ւ̎R�ł���B
���Q�l������
�c�����q�`�閾���̃s�A�j�X�g ���J�R��q���i������ЃV���p���j
CD �c�����q�u���m�̊�ցv�i�L���O���R�[�h�j
CD�u�c�����q�̌|�p�v5���i�L���O���R�[�h�j
CD�u�p���̌��q�b�q�v�i�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�j
CD ���q�b�q�u�`���̃s�A�j�X�g�v�i�R�����r�A�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������g�j
2022.05.20 (��) �v�[�`���̃E�N���C�i�N�U�ƃV���X�^�R�[���B�`�̌�����
 �@���V�A�̃E�N���C�i�N�U����2���������o����5��9���̐폟�L�O���B�v�[�`���哝�̂͂���ȉ����������B�u���V�A�͐����ƑΘb�ɂ�鍇���I�ȉ�����ڎw���Ă������ANATO�͎���݂��Ȃ������B�h���o�X�A�N���~�A���܂މ�X�̗̓y�ւ̐N�����������R�Ɛi�߂��Ă����B�댯�͓������ɑ��債�Ă����B���V�A�͐N���ɑ��Đ���ł��Ƃɂ����B����͂�ނȂ��B��̔��f�������B��X�̋`���̓i�`�Y���ӂ����f���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƌ����Ă��ꂽ�l�X�̋L������邱�ƁB���E���̔ߌ����x�ƌJ��Ԃ��Ȃ����Ƃ��v�B���Ȃ����ݍ��N����NATO�̐N����H���~�߂邽�߂Ɨ��R�Â���B�g����Ș_���ɂ�鎩�Ȃ̍s�ׂ̐������ł���B���琄�i����i�`�X�I�N���s�ׂ��i�`�X�r���̂��߂ƌ����A�ߌ����J��Ԃ��Ȃ��ƌ����Ȃ���ߌ��ݏo���Ă���B���s�ɖ������������j�]����_���̓W�J�͂ނ��눣�݂����o����B�J�ԗ\�z���ꂽ�u�푈�錾�v���Ȃ���ŏd�v�����ł���͂��́u�E�N���C�i�v�Ƃ������������Ȃ��B������������틵���獑���̖ڂ炵���`�̐킢����ەt���ĂȂ�Ƃ��x����ۂ������Ƃ����������̉����B1�������O�ɂ͔���f�����u�l�Ԃ̃N�Y�E����ҁv�Ɣl�������C�͉e����߂�B�O��Ȃ��猩��Ί��S�Ȍ��������ł���B
�@���V�A�̃E�N���C�i�N�U����2���������o����5��9���̐폟�L�O���B�v�[�`���哝�̂͂���ȉ����������B�u���V�A�͐����ƑΘb�ɂ�鍇���I�ȉ�����ڎw���Ă������ANATO�͎���݂��Ȃ������B�h���o�X�A�N���~�A���܂މ�X�̗̓y�ւ̐N�����������R�Ɛi�߂��Ă����B�댯�͓������ɑ��債�Ă����B���V�A�͐N���ɑ��Đ���ł��Ƃɂ����B����͂�ނȂ��B��̔��f�������B��X�̋`���̓i�`�Y���ӂ����f���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƌ����Ă��ꂽ�l�X�̋L������邱�ƁB���E���̔ߌ����x�ƌJ��Ԃ��Ȃ����Ƃ��v�B���Ȃ����ݍ��N����NATO�̐N����H���~�߂邽�߂Ɨ��R�Â���B�g����Ș_���ɂ�鎩�Ȃ̍s�ׂ̐������ł���B���琄�i����i�`�X�I�N���s�ׂ��i�`�X�r���̂��߂ƌ����A�ߌ����J��Ԃ��Ȃ��ƌ����Ȃ���ߌ��ݏo���Ă���B���s�ɖ������������j�]����_���̓W�J�͂ނ��눣�݂����o����B�J�ԗ\�z���ꂽ�u�푈�錾�v���Ȃ���ŏd�v�����ł���͂��́u�E�N���C�i�v�Ƃ������������Ȃ��B������������틵���獑���̖ڂ炵���`�̐킢����ەt���ĂȂ�Ƃ��x����ۂ������Ƃ����������̉����B1�������O�ɂ͔���f�����u�l�Ԃ̃N�Y�E����ҁv�Ɣl�������C�͉e����߂�B�O��Ȃ��猩��Ί��S�Ȍ��������ł���B�@���V�A���E�N���C�i�N�U�̑�`�Ƃ������ƁB����́A�u�E�N���C�i���w�h���o�X�n��ɓ��ʂȒn�ʁi������̎������j��^����x�Ƃ���2014�N�̃~���X�N���ӂ𗚍s���Ă��Ȃ��A����ǂ��납���̒n�ŋs�E�܂ōs���Ă���v�Ƃ������̂��B�[�����X�L�[����2019�N�ANATO����������Ɍf���đ哝�̂ɂȂ����B�~���X�N���ӂ������u���A�N���~�A����������ANATO�ɋ}�ڋ߂�}��B�v�[�`���Ɋ�@����������B2022�N2���A�k���~�G�ܗ֏I�Ղ����肩��A���E�Ń��V�A�̃E�N���C�i�N�U����肴�������悤�ɂȂ�B�o�C�f���đ哝�̂͑��X�ɁA�u�A�����J�͌R���I����͂��Ȃ��v�Ɩ��������B���V�A�������N���̈��S�قƂ����͖̂����ł���B2��24���A�v�[�`���̓E�N���C�i�N�U�ɓ��ݐ����B�o�C�f���̐ӔC�͏d���B
�@�A�����J���u���E�̌x�@�v�Ƃ��Ă̗͂�ۂĂȂ��Ȃ����͎̂����ł���B�������Ȃ��琢�E����̑卑�ł���NATO�̃��[�_�[�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�����͐��E�̃��[�_�[�Ƃ��Ă̖������ʂ����Ӗ����������͂����B�Ȃ�ǂ����ׂ����������H �v�[�`�����~���X�N���ӕs���s�������ɂ����̂ł���A�o�C�f����1994�N�̃u�_�y�X�g�o���������o���悩�����̂��B�u�_�y�X�g�o���Ƃ́A�j����������E�N���C�i�ɑ��ăA�����J�A���V�A�A�C�M���X�̊j�ۗL3���������S�ۏ�����Ƃ������̂��B�u�����҂��N�����Ăǂ��Ȃ�B����������Ȃ��Ƃ�������A�����J�ɂ��l��������v�B���߂Ă��ꂭ�炢�͌����ׂ��ł͂Ȃ��������B��������v�[�`���͐N�U�ɓ��ݐ�Ȃ������͂����B�Ƃ��낪�o�C�f���ɂ͂��̈ӎ����Ȃ������B���j�F���������Ă����B����ɂ͊�@���m�͂��B����Ƃ��A���̎��Ԃ�]��ł����Ƃ���E�E�E�E�E�I�H
�@�푈���n�܂�������A���h���閿�F�̈�l�命�䎁���烁�[�����͂����B���V�A���w�҂Ŗ��É��O�����w�w���̋T�R��v����2��26���ǔ��V���f�ڂ̕��͂������B�����ɂ͎������˂Ă���s�����������V�A�l�̐������͂�����ƋL����Ă����B
���V�A�̓��ݓI�Ș_���ɖڂ�������ƁA�u���V�A�l�͗��j���������邪�A���j����w�Ȃ��v�Ƃ�����B�\�A�����A���ė��̎��R�Ɩ����`����Ƃ���O���[�o���Y���̔g�̓��V�A�ɂ��y�B�������A���V�A�ɂ͌×��A�l�̎��R�͎Љ�S�̂̈��肪�����Ă悤�₭�ۂ����Ƃ����l��������B���́u�������̂Ɋ������v�I�ȍl���ɂ��āA�h�X�g�G�t�X�L�[�́u�킪���͖������̌N�吧���A�����炨���炭�ǂ��������R���v�Ƃ����t���I���t���₵���B���V�A�l�̐S���ɂ́A�i���́u�_�̉����v�͗��j�̏I���Ɍ����Ƃ����َ��^�I�Ȋ�]������A���ꂪ�����̌���ɑ��閳�S���������Ă���B�����玩�������l���s���Љ���`������Ƃ��������̃f���N���V�[�������Ă��Ă��A�₪�Ă���ɔ�������S����܂�A�Ăь��͂ɗꑮ�����ȑO�̏�Ԃɖ߂��Ă��܂��B���̍����������V�A�̍�ƃO���X�}���́u��N�̓z��v�ƌĂB�@�Ȃ�قǂƎv�킹����e�ł���B�v�[�`���̎x��������≺�������Ƃ͂������~�܂��ۂ��Ă���̂́A���{�̃v���p�K���_�̂��������ł͂Ȃ��A���V�A�l�������I�Ɏ��ӎ��̕\��ł����邱�ƁB�v�[�`���́u���R��`�͎���x��B���R�𐧌����Ăł�������D�悷�ׂ����v�Ƃ̔������A���Ăւ̌l�I�G�ӂ����ł͂Ȃ��A���V�A�l�C���ɍ����������̂ł��邱�ƁB���Ȃ̔C�������̂��߂Ɍ��@�������s�������Ƃ��A�g��������Ă䂭�h���V�A�l�̐����܂��Ă̂��̂��������ƁB�����A���V�A�����͊�{�������[�_�[�����߂Ă���̂��B���ꂪ���Ƃ������I�ł������ɂ��Ă��E�E�E�E�E���ڂ낰�������v�[�`���̌����Ƃ�����x�����郍�V�A�l�̐����́A�T�R������ʂ��āA���Ȃ薾�m�ɗ����ł����B
 �@���������Ƃ������t����v���N�������̂́A���Ẵ\�A�̍�ȉƃh�~�g���C�E�V���X�^�R�[���B�`�i1906-1975�j�ł���B�ނ̍�i�ɐ푈�O����`�����ȑ�7�ԁu���j���O���[�h�v�A��8�ԁA��9�� ������B�����͑�2�����E��풆����I������܂łɏ����ꂽ��i�ł���B
�@���������Ƃ������t����v���N�������̂́A���Ẵ\�A�̍�ȉƃh�~�g���C�E�V���X�^�R�[���B�`�i1906-1975�j�ł���B�ނ̍�i�ɐ푈�O����`�����ȑ�7�ԁu���j���O���[�h�v�A��8�ԁA��9�� ������B�����͑�2�����E��풆����I������܂łɏ����ꂽ��i�ł���B�@��7�Ԃ́A����ǂ���A1941�N�`1943�N�A900���ɂ킽��i�`�X�E�h�C�c�̃��j���O���[�h�i���݂̃T���N�g�y�e���u���N�j���������`�[�t�ɕ`������i�ł���B�}�����ꂽ���_���Ō�͗͋������g���Ė������B���j���O���[�h�s���̕s���̐��_�͂��Î����Ă��邩�̂悤���B��������345���ڂɓ��n�������ꂽ���̊y�Ȃ́A�����ƃ��W�IO.A.�ɂ��Q��ɋꂵ�ގs�����ە������B���W�I�����h�C�c���́u�g�[���H�����Ȃ����̂悤�ȏ��Ō����Ȃ����t����Ƃ́I ����ȊX���ח�������͕̂s�\���v�Ƌ���ɂ����Ɠ`������B
�@��8�Ԃ�1942�N�H����̃X�^�[�����O���[�h�U�h�킪���`�[�t���B�O������틵�͍D�]���Ă���̂ł��邩��A���͋����`�ʂ��A�Ǝv���邪�A�y�z�͏I�n�d�ꂵ���B�푈�͔ߎS�A��x�ƋN�����Ă͂Ȃ�Ȃ� �Ƃ̃��b�Z�[�W�������̂�������Ȃ��B
�@��9�Ԃ́A1945�N�A�\�A���܂ޘA�����̏�������̍�i�ł���A�x�[�g�[���F���́u���v���z�N����邱�Ƃ�����A���{���ǂ����������E�������̊�ш���s��ȍ�i�����҂����B�Ƃ��낪�������ꂽ�̂́A�y���ň��炬�ɖ��������i�B�܂��Ɍ��������ł���B�푈���I����Ĕނ̋��ɋA�����̂́A�����̊�т������g���������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���������ƌ����悤�����ƌ����悤�������̓��Ȃ�^����\������B���ꂪ�V���X�^�R�[���B�`�Ƃ�����ȉƂȂ̂��B
�@1917�N�̃��V�A�v���̂��ƁA�v���R�t�B�G�t�A���t�}�j�m�t�A�z�����B�b�c�A�~���V�e�C���烍�V�A�̒������y�Ƃ̑������A�����̓����Ɋ������˂č����o���B����Ȓ��A�V���X�^�R�[���B�`�͑c���ɗ��܂葱�����B�X�^�[������`�̓��ǂ��������鉹�y�Ƃ́u�Љ��`���A���Y���v�ɑ��������́A���Ȃ킿�u��������O�i�I�Ȑ^���̌�����ڎw���A��z�����\���B�G�g�l�����_�̉p�Y�I�ȁA�P���������������������A���Ɛ��Ƃ��m�肷��͂ɂ��ӂꂽ���y�I�C���[�W�ŋ��������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������̂������i���V�A��ȉƓ����K����j�B�ނ͂���ɁA���ɏ]���A���ɔw���A���ɝ������Ȃ���A��Ȃ𑱂����B��ȉƂ̊��ɂƂ��čł���Ȃ��ƁB����͎��R�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�Ȃ̂ɁA�V���X�^�R�[���B�`�̓X�^�[�����������̃\�A�𗣂�Ȃ������B�Ȃ��H �ނ̓��V�A�Ƃ���������D���������̂��B���V�A�l�ł��邱�ƂɌւ�������Ă����B��ȉƂƂ��Ď��R�ɉ��y����邱�Ƃ����A�l�ԂƂ��Ď��Ȃ̃A�C�f���e�B�e�B�[�ێ���D�悵���B�s���R���͍�ȋZ�p�Ő��点�����B���ǂ͉B���������̈Í�����������̂Ȃ�����Ă݂�B������͂����Ȃ��B�����͂������Ă��̒n�Ő����Ă䂭�E�E�E
�E�E�V���X�^�R�[���B�`�͂����l�����Ǝv���̂ł���B�c���𗣂�邱�ƂȂ����y�ŋt���̎s���ɐ������]��^�����ނ������^�̈����҂ł͂Ȃ��������B
�@�v�[�`���͈����҂����F���u���V�A�l�ƃE�N���C�i�l�͂��Ƃ��ƈ�̖̂����B�E�N���C�i�̎匠�̓��V�A�Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v�����Ă������݂�����v�Ɛg����Ȏ��_�����ɐN�U�ɓ��ݐ����B�ނ̉Ƒ��͂��̃��j���O���[�h�����Ŏ��̋��|�𖡂�����Ƃ����B�����č��A�ނ͈�̂ł���͂��̃E�N���C�i�s���ɑ��i�`�X�E�h�C�c����Ă��Ɠ����ߌ����������Ă���B�܂�Ōl�̍��݂E�ɐ��炵�Ă��邩�̂悤���B����ȃo�J�ȍs�ׂ����낤���B����ȕs�𗝂��������̂��B����Ȉ����҂�����̂��I
�@�v�[�`�������ݍ��؍s�̃c�P�͑傫���B���E�͈�ĂɃE�N���C�i�̑��ɗ��A�����̍ŐV���킪�E�N���C�i�ɉ^�э��܂��A�t�B�������h�ƃX�E�F�[�f����NATO�����\���ɓ��ݐ����A�ꍑ�̉����j�~�������̗��ڂƏo��B�܂��Ɉ��S�ۏ��̎����ł���B���V�A�v�l�̊C�O���Y�̓����A���ی��ϖ�SWIFT����̔r���AEU�̃��V�A����̌����A����~�A���V�A�Ƃ̃v���W�F�N�g����̊e���̓P�ށA�h�C�c�̃m���h�X�g���[��2�̊��S��~�A�ے��I�ȃ}�N�h�i���h�̓P�ޓ��X�A�����̌o�ϐ��ق́A��l�������GDP�����E��66�ʂ̌o�Ϗ������V�A�ɂƂ��đ傫�ȑŌ��ƂȂ�ɈႢ�Ȃ��B����Ȍ��͎҂����]���郍�V�A�������A�����������s���Ȃ��Ȃ�Ό��͎҂��������B�푈�̎��Ԃ��킩���Ă���Ό��͎҂Ɍ��ł�������B���S�ۏ�ƌo�ϗ��ʂł̎��s�B�v�z�����̔j�]�B�v�[�`���̍s����͌���Ȃ��Â��B
���Q�l������
�N���V�b�N���y�j��n10�u���㉹�y�v�i�p���R���T�[�c�j
�ŐV���ȉ���S�W��3���u�����ȇV�v
���V�A���琼���ց`�~���X�^�C����z�^�i�t�H�Ёj
�T�R��v�u���_ �E�N���C�i��@�v(�ǔ��V���f�W�^��2��26��)
CD �V���X�^�R�[���B�`��ȁF�����ȑ�7�ԁu���j���O���[�h�v
�@�@�@�@�@�@�}���X�E�����\���X�w���F���j���O���[�h�E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�i����EMI�j��
���j���O���[�h ���_���t�ł������� 2016.3.25 O.A�iBS�t�W�j
2022.04.23 (�y) �t�Ȃ̂ɁE�E�E�E�E
�i1�jH.T.����Y.I.����`�ˑR���]���@�挎�A��l�̑�Ȑl��S�����܂����B��l�͕�̉�Ђ̓�����H.T.��90�B������l�͉�Ђ̂��Ă̒��Ԃ�Y.I����ł��B
�@�O�҂͌̋�����̕��ō��Z�̐�y�ł�����܂��B�R���i�ȑO�A�N���N�n�͕K������Ɏf�����l���萻�̂������Ŏ������y���܂��Ă������������̂ł����B���_���������i?�j�̑��q�ɂ͂��N�ʂ��A���ɂ͍����E�B�X�L�[��y�Y�ɂ��������܂����B��������������Ă��̃{�[���y���A���ł���Ɏg���Ă���܂��B�X�}�[�g�ʼn����Ȑa�m�i���疼�j���Z�t�ɐS����̃A�[�������B
 �@������l��Y.I.����͂܂�50��B������Ȃ�ł��Ⴗ����I�����쉹��̃s�A�m�ȑ��A���_�̃e�[�}�̓����F���́u��̃K�X�p�[���v�Ƃ������炽�����̂���Ȃ��B�G�߂��Ƃɉ����̂��܂����̂�H�ו����u������v�A�N���V�b�N�ƃW���Y�e10�l�̉��t�ƂĂ�Z�~�i�[�u�����L�����p�X�v�ȂǁA�y�������Ԃ���������߂����܂����B�ޏ��Ƃ̎v���o�̒��ŁA������Ԃ��ꂵ���������ƁB����́u�N�����m�v2019.2.1�u�{�w�~�A���E���v�\�f�B ���|�[�g�v�����܂��Ă��ꂽ���Ƃł��B
�@������l��Y.I.����͂܂�50��B������Ȃ�ł��Ⴗ����I�����쉹��̃s�A�m�ȑ��A���_�̃e�[�}�̓����F���́u��̃K�X�p�[���v�Ƃ������炽�����̂���Ȃ��B�G�߂��Ƃɉ����̂��܂����̂�H�ו����u������v�A�N���V�b�N�ƃW���Y�e10�l�̉��t�ƂĂ�Z�~�i�[�u�����L�����p�X�v�ȂǁA�y�������Ԃ���������߂����܂����B�ޏ��Ƃ̎v���o�̒��ŁA������Ԃ��ꂵ���������ƁB����́u�N�����m�v2019.2.1�u�{�w�~�A���E���v�\�f�B ���|�[�g�v�����܂��Ă��ꂽ���Ƃł��B
�V�F�C�N�X�s�A�A�M���V�A�ߌ��A�I�y�����A�l�X�ȃW�������ɗ��߂���A������\���l���̕��͂܂Ŋ܂߁A�����܂�Queen�̉��y���@�艺���Ă���u���O�ɂ͂܂��o����Ă��܂���B
�`�т�����V�L���V�ł���
�@�����ŗD���� �u�₩�Ŕ������l�ł����B�S���Ȃ��Ă��܂����ޏ��ɂ̓��[�c�@���g�́u�[�ׂ̑z���v�i�J���y���jK523���悭�������܂��B���̖���̗[�ׂɁ@���͔߂��݂��������@���炬�̍��ւƗ������Ƃł��傤
��̑O�ł��Ȃ��������Ă��ꂽ��@�킽���͕��ƂȂ��Ă����Â������
���݂�̉Ԃ����̕�ɂ��ނ��@�₳�����ڂŌ����낵�ċ����Ă�������
�܂Ƃ������̑��蕨�́@���̊��̔������^��ɂȂ��@�^��ɂȂ��i�Ȃ��ɂ����j
�`���炩�ɂ����肭������
�i2�j�J���O�q����`�ˑR�̃��[���@�����J�A3�����I��낤�Ƃ��Ă���������A���w�Z�̓������̒J���O�q����i�ȉ�H.T.����j���烁�[�����͂��܂����B����܂ŋ��n�̂��Ƃ𒆐S�Ɏ��X���킵�Ă͂��܂������A����͗\�z�O�̒��g�ł����B�u�v���o�̃J�Z�b�g�e�[�v�iCT�j�������Ȃ��ċ@�B�ɂ�������A�e�[�v�����܂��ă_���ɂ��Ă��܂��܂����B���Ƃ܂����{����̂ł����A�ǂ���CT��CD�ɕϊ����Ă����Ƃ����m��܂��v�Ƃ������́B�l�̊�Ԃ��Ƃ����E�E�E�E�E�����4�N�O�ɖS���Ȃ�����̈�P�B�����ł��������̐��_�B�u���ł悯����C�����B���������Ă��������ȁv�Ƒ������܂����BCT�f�b�LSONY��333ESG�́A���܂���3�N�O�AY.I.����̕v�NH.S.���̍H�[�ŃI�[�o�[�z�[�������A�쓮�͖��S�B�Ȃɂ��A���̎���҂��Ă����悤�ȁE�E�E�E�E�B
�@H.T.����Ƃ͌Â��t�������ŁA���߂ďo������̂͂��݂����w4�N���A����̐ē����q�搶�̃s�A�m�����̔��\��ł����B���m�I�Ȋ痧���̔�ѐ�̔��������x�[�g�[���F���̃\�i�`�l ��6�� �w���� ��e���܂��ĂˁB����Ƃ����A�}�g�Ƃ����A���ɉ��y�I�ŏՌ����܂����B���̃o�C�G���i���Ԃ��͎��O�j�Ƃ͉_�D�̍��ŁA���̐l�ɂ͐�ɓG��Ȃ��� �Ǝq���S�Ɏv�������̂ł��B���ꂪH.T.����ł����B�܂��A���͐̂̕���ł��B�ޏ��͂��̌㓌���w�|��w�̃s�A�m�Ȃ��o�ċ��ڂ����܂����B���̂ق��͑�w�̃I�[�P�X�g�����ɓ����ăg�����y�b�g���E�E�E�E�E�܂��A������̘b�͂�߂Ă����܂��傤�B
 �@���āA�����Ă����J�Z�b�g�e�[�v�͑S8�{�B�قƂ�ǂ����揗�������c�̂��́B�����Ȃ̃L�����A�����������ޏ��̂���l���A1980�N��A���挧�ɕ��C�A�₪�ĕ��m���ɏA�C�����A����͂��̂���̂��̂��Ƃ������Ƃł��B
�@���āA�����Ă����J�Z�b�g�e�[�v�͑S8�{�B�قƂ�ǂ����揗�������c�̂��́B�����Ȃ̃L�����A�����������ޏ��̂���l���A1980�N��A���挧�ɕ��C�A�₪�ĕ��m���ɏA�C�����A����͂��̂���̂��̂��Ƃ������Ƃł��B�@�ȂA�A�}�`���A�����̔��t���A�ƌ����Ȃ���B�����c�̎��͂͂Ȃ��Ȃ��̂��́B�����ƐS�����炩�ɐ��ݐ��Ă���̂��������܂��B�F����F���������u���ȂƂƂ��Ɂv�i�w�K�����Ёj�̂��Ƃ����ŁA�u���������������[�c�@���g��u���b�N�i�[�̉��y�ɂ��ʂ��鏃���ȓ�������₵�������������̂ł���E�E�E�E�v�Ə����Ă�����̂��������悤�ȋC�����܂����B
�@�������CT�ɂ͒��揗�������c��1980�N��̉��t��^������Ă��āA�������Ƃɍ����ȍ�ȉƂ̐搶���w������������Q�X�g�o�����ꂽ�肵�Ă��܂��B�Q�l�܂łɂƃ��n�[�T���̘^�����ǂ����������Ă��܂����B�����̒�����A���R���A�咆���A���L�u�A�e�搶���̎w���Ԃ�w���Ԃ�����ǂ��Ă݂܂��傤�B
�@���揗�������c��4�t��1982.6.5�͍�ȉƂ̓��R���搶�i1932-�j���Q�X�g�B���t���ꂽ �u�����Ȗځv�͒����V�����e���Ɍf�ڂ��ꂽ�q���̎�10�҂ɐ搶���Ȃ����������g�ȁB���^���C�Ȏq���̐S���E��`�����f�G�ȍ�i�ł��B���t��ł́A�n���̏��w���̘N�ǂ��Ƃ��č����Ɍq����Ƃ����`���Ƃ��Ă��āA���̎�������R���̉̐��E�ɍX�Ȃ閣�͂�Y���Ă��܂����B
�@���n�[�T���̘^�����ƁA��ȉƂ��\�����������Ƃ����t�҂ɂǂ��`�B����̂��A����ȉߒ�����Ɏ��悤�ɂ킩��܂��B�Ⴆ�Α�1�ȁu�������̐l�v�B���͉��L�B����͂�q���̊����ɂ̓z�g�z�g���S�������܂��B
�@�@�p�p�͂₳�������炨�����@�}�}�͂��킢����J���V�@���͂���ɂł��\������炨����
�@�@�킽���͈Ӓn��������R�V���E�����Ă��@����������
�@���R�搶�́u�����ƃe���|���A�b�v���� ���̋Ȃ̃��B���B�b�h�����o���Ă��������v�u�p�p�͂₳�����́g�₳�����h�ɕt���Ă���X���[�̈Ӗ����l���邱�� �X���[�Ƃ����K�[�g�A�e�k�[�g�A�X�^�b�J�[�g�ȂNjL���̎w��i�A�[�e�B�L�����[�V�����j�ɂ͈Ӗ������邱�Ƃ�m���Ă��������v�u�݂Ȃ���́g�J���V�h�͋C�̔������J���V�ł� ���̃J���V�͕|���J���V�Ȃ̂ł��v�u�킽���͈Ӓn�������� �́g�Ӓn���h�̓e�k�[�g�ŃA�N�Z���g �����Y��Ȃ��Łv�u���t�ɐ����𐁂�����ł��������v�u�x���͋x�݂���Ȃ� ���߂鎞�ԁv�u�ϐg���Ă������� �����͂����ς������vetc �M���ۂ��m�M�������āA���Ƀ��[���A�������Ȃ���A���t�҂������̐��E�Ɉ�������ł����܂��E�E�E�E�E���b�X����ł͉��y�̖������ƕ\��K�����ƕς���Ă��܂����B
�@�s�A�m��H.T����ɂ́u�s�A�m�͔��t����Ȃ��v�u�����Ƌ��� ����Ő������ς��H�v�u�����͍��������[�h����v�u�����Ɖs���e���āv�u�A�N�Z���g���������āv�u�Ë��̂Ȃ����m�ȃe���|�Łv�E�E�E
�E�E���̂��Ƃ̗l�q�͔ޏ��̃��[���łǂ����B
���R�搶�̃s�A�m�ւ̒����͂��Ƃ̂ق��������A�����Ƃ����ƂƂǂ�ǂ�����B�˂��w���邭�炢�撣��܂����B�v���b�V���[������Ȃ��̂�������A�搶���S�z���ēd�b���悤�Ǝv�����Ƃ��B�s�A�m�Ƃ������̂ɉ��߂Ėڊo�ߒE��??���Ē���ŃZ���Z�[�V�������N���܂����B���R�搶�͎��ɂƂ��đ剶�l�ƂȂ�܂����B�@������ԏ����̂́A��4�ȁu�}�}�ցv�̑O�t�ł̂��Ƃ�ł����B
�搶�u������ molto espressivo �����ƕ\����Ղ�ɂ��肢���܂��v�@�M�d�Ȍo���ł����ˁB �@�q���̎��Ƃ����A������Ў���A�X�g���e�B�W�b�N���̎��ɍ�����u�����̂Ȃ݂��v(2003�N�����[�X)���v���o���܂��B���瑐�O�����Ԃ��Ȃ�����̎q���̎���N�ǂ���CD�ł��B�^����ʐ^�B�e�A�R��y��ł̑�����A���������͎�܃p�[�e�B�[���ɂ����锪�瑐����̗D��ȘȂ܂��͌����ĖY��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���쌠�葱���ŕ������ɕ������̂��M�d�ȑ̌��ł����B
H.T.����u���܂���Ƃ���炵���Ȃ����Ⴄ��Ȃ����Ɓv
�搶�u������ ����炵���Ȃ������Ȃ������Ă݂����v�i�唚�j
�@�u�����v�Ƃ�����������́A�X�g���e�B�W�b�N���Ɉٓ������1997�N�A����̑�l�߂��}���Ă����u�V�E�����u���v��z�N���܂��B����͉䂪�Ђƌ_���u�������y��v�Ƃ�����Ђ��S���̏������Z�ɒ��ɖK��̔����鏤�i�B30���~�̍��z�Z�b�g��2000�Z�b�g������グ�钴���͂ȏ��i�ł����B���͂��̉ߒ��ŁA�O�P�W�A�r�ӐW��Y�搶��ƒm�荇���Ď��ɗL�Ӌ`�ł����B��ɁA�r�Ӑ搶�����R�s�̃z�e���̃o�[�Ŕ������M���O�uNHK�I�[�g�}�`�b�N�i�������j�����c�v�Ƃ��u���Ȃ��m���Ă�H�^�R�̓x�[�g�[���F���ɕs���������Ă���Ă��ƁB�Ȃ�ŃG���C�J������̂ɃG���_�R�͂Ȃ���I�v�ȂǁB��ȊE�̃_�W�������̖ʖږ��@�B�Ȃ�Ƃ���ۓI�ȏ��ł����B
�@���揗�������c��JOINTCONCERT1987.3.13�̃A���R�[���ȁu�ЂƂ̒��v�́u�V�E�����u���v�ɂ������Ă��܂��B
 �@1984�N6��9���̒��揗�������c��5�t���10���N�L�O�Ɩ��ł��čs���܂����B�Q�X�g�͑咆���搶�i1924-2018�j�B���w�u�T�b�����v�u���ʂ̂��܂�肳��v�̍�ҁB���f���̒��h���ő�X����������Ƃ̒����O����e���Ȃ���̂��Ă����̂��u���q�̎��v(���蓡����)�ŁA�������Ȃ����咆�Г�̂��q�������搶�ł��B
�@1984�N6��9���̒��揗�������c��5�t���10���N�L�O�Ɩ��ł��čs���܂����B�Q�X�g�͑咆���搶�i1924-2018�j�B���w�u�T�b�����v�u���ʂ̂��܂�肳��v�̍�ҁB���f���̒��h���ő�X����������Ƃ̒����O����e���Ȃ���̂��Ă����̂��u���q�̎��v(���蓡����)�ŁA�������Ȃ����咆�Г�̂��q�������搶�ł��B�@�搶�̃��b�X���͂��������₩�ȋ�C������Ă��܂��B�����ă��[���A�����Ղ�B�����Ȃ̏��������g�ȁu���̕��D�v�̑�1�ȁu���y��̂��Ɓv�̎����D����2�Ԃ̎������L�B
���y��̂��Ƃ͂���Ƃ�������ׂ肵�����Ȃ��@�@�u�킩��Ȃ��v�Ǝv�킹��f�G�Ȏ��͒�����h�q����̍�B�咆�搶�͂��̎��ɗD�������ׂ��悹�܂����B�܂��Ɏ�ʂ̍�i�ł��B�����搶�͉��₩�ɒ��J�Ɏw������܂��B�u�g�N���b�V�F���h�h�͑傫���������i�����X�ɂ��}�ɂ��j���ӎ����āv�up �͏������Ƃ����Ӗ������ǁg�k���Ɂh�Ƃ������o���K�v�v�B�uf �͑傫�������ǁg�����炩�h�Ƃ����Ӗ�������vetc�BH.T.����́u�搶�́w�D�����A�D�����x�Ƃ������t���ƂĂ���ۓI�ł����v�ƌ���Ă��܂��B�܂��u�搶�̎w������e���|�͂ƂĂ��������Ƃ��ēI�m�ŁA�����̃s�A�m�̉���������肢�����ɕ������܂����v�Ƃ��B�����A�m���ɔޏ��̃s�A�m�̃^�b�`�͑@�ׂŏ���������Ă��܂��B
�͗t���q�[���ɂ���܂��ā@�ǂ��܂ł����a�����ǂ�@�ӂ��肫���
�������̃s�A�m���@�܂��ق� �܂���h�炵�Ă邩��
�@���揗�������c��6�t��1986.6.7�͐��L�u�搶�i1955-�j���Q�X�g�B���t���ꂽ�u�}�U�[�O�[�X�̉́v�i�J��r���Y�� ���L�u��ȁj�͍ˋC����ƂĂ��n�C�Z���X�ȍ�i�B���̃R���T�[�g�̖͗l���ޏ��̃��[��������p�����Ă��������܂��傤�B
���L�u�搶�͂��ׂđ����Ńs�A�m�ɎQ���B�s�A�m��2��X�e�[�W�̗��[�ɒu���āA�搶�͎��R�ɁE�E�E�E�E�B���̓X�e�[�W�E�̃s�A�m��7�Ȗڂ́w�\�������E�O�����f�B�x�����サ�܂����B���̋Ȃ͂��Ȃ�JAZZ�I�ŁA�������~�����Ǝv���Ă���ƁA�搶�͎��R�ɔ�э���ł��Ă����B�傢�ɏ�����܂����B���t���I����Ď��͂����ɃX�e�[�W����Ɉ������݂܂������A���搶�͂��q�l�������̂��Ŏ���T���Ă��������āA�X�e�[�W�ɏo�Ă䂭���Ɣ����킹�B���q�l�唚�̃V�[���ł����B�@�Âт��J�Z�b�g�e�[�v�ɕ����搶���̃��b�X���B��M�I�ȓ��R�A�����ȑ咆�A���x�̐��E�E�E�E�E�e�搶���͎O�ҎO�l�̌��ʼn��t�҂����݂ɓ����Ă䂫�܂��B���̎�r�͂܂�Ŗ��@�̂悤�ŁA���ɂƂ��Ă��A���y�Ƃ̐ڂ������čl�����Ă��ꂽ�A����ȋM�d�Ȏ��Ԃł����B
�@CT��CD�̃_�r���O�́ACD��CD�ɔ�ׂ�Α�����Ԃ�������̂ŁA�uGW�܂łɂ͂Ȃ�Ƃ��v��H.T.����ɍ����č�ƂɎ��|����܂����B�ŏ��̓x�^�Ă��ł������ȂƂ��v�����̂ł����A�ǂ������Ȃ�ƁA�Ȃ��Ƃ�Chapter�����܂����B�����ɂ͂��̕����֗��Ȃ̂ŁB�ȖڂƉ��t�҂��������W���P�b�g���쐬�B�i�߂邤���Ɋ���Ă��ăX�s�[�h���A�b�v�B�v������葁���A�قڈ�T�ԂŁACT8�{��CD6���Ƀ_�r���O�����B���A��z�ւő������Ƃ���A�����Ƀ��[�����͂��܂����B
�@�u����Ȃɑ����I GW������Ƃ���v���Ă��܂����̂ɁB�����J�Ɏd�グ�Ă��������ĐS���ܑ̂Ȃ��v���Ă��܂��B�����A�N�㏇�ɂ܂Ƃ߂Ă���������CD����C�ɒ����܂����B���������ς��ɂȂ��Ă��܂��B�f���炵���ɂȂ�܂����B�䂪�l���ɉ����Ȃ��̐S���ł��v�Ƃ̊��z�����܂����B�u�킪�l���ɉ����Ȃ��v�Ƃ܂Ŋ��ł���������Ύ��̂ق����������Ȃ��ł��B�܂����J���ɋC�Â��Ă��ꂽ�̂��{�]�ł��B�u���������J�Ɂv�͎��̃��b�g�[�Ȃ̂ŁE�E�E�E�E�B
�@����ɁA������H.T.����̂���q����Ƃ������Ƃ���A�ޏ��̔M��ȃt�@���ɂȂ����Ƃ������`�O�Ȃ̖����U�搶�Ƃ������������������āA����CD���̘b�������Ƃ���A�u���̂悤 �������������v�Ƃ̗v�]�������������ł��BPioneer��CD���R�[�_�[���@�i�H�jPDR-D50 �͂܂��܂����݁B��l������l�����������ƁB���������܂����B���ł���������K���ł���܂��B
�@H.T.����Ƃ͂܂����n�Ɋւ���b�肪����̂ł�������͂܂�������B�u�t�Ȃ̂Ɂv���낢��Ȃ��Ƃ�������2022�N��3���`4���ł͂���܂����B
2022.03.15 (��) ���D�J���XVS�V�g�e�o���f�B
�@���Ƀ��C�o���͐��X����ǁE�E�E�E�E�{�{����VS���X�؏����Y�A��QVS���ˁA����VS���A��R�N��VS���c�K�O�A�r�[�g���YVS���[�����O�E�X�g�[���Y�A�����݂䂫VS���C�J�R���E�E�E�E�E�N�����m�I�ɍł������[���̂̓J���XVS�e�o���f�B�ł���B(1) ��s����e�o���f�B�`�g�X�J�j�[�j �u�V�g�̐��v�ƌ���
 �@���i�[�^�E�e�o���f�B��1922�N�A�C�^���A�̃y�[�U���ɐ��܂ꂽ�B�y�[�U���̓��b�V�[�j�̐��܂�̋��Ƃ����C�^���A�E�I�y�������̒n�ł�����B�����Đ��܂ꂽ�����ɂ���āA�N��B������Ńp���}���y�@�ɓ��w�A���r��ςB�₪�ăe�o���f�B�ɉH�����`�����X������Ă���B1946�N�A�~���m�E�X�J�����ĊJ�L�O�����ł���B�w���҂̓g�X�J�j�[�j�i1867-1957�j�B���̃I�[�f�B�V�����Ńe�o���f�B�̓g�X�J�j�[�j����u�V�g�̐��v�ƌ��܂��ꂽ�̂ł���B�g�X�J�j�[�j�Ƃ����A�t���g���F���O���[�A�����^�[�ƕ��ѐ��E�O��w���҂Ƃ���ꂽ��䏊�B�v�b�`�[�j�i1858-1924�j�Ƃ̐e���������A�u�{�G�[���v�u�g�D�[�����h�b�g�v�̏������w���A�u�g�X�J�v�Ɓu���X�v�l�v�͏������s��̎蒼���Ɍg��茩���ɑh���𐬌��ɓ����Ă���B�e�o���f�B�͂���Ȍ��Ђ���̂��n�t�����̂��B�́u�{�G�[���v�̃~�~�B�ϋq�́u���̏�Ȃ����炩�Ȑ��v�Ƒ��^�B�Ⴋ�u�X�J�����̏����v�̒a���������B�J���X��1947�N�A�A���[�i�E�f�B�E���F���[�i�ł���ƃC�^���A�i�o���ʂ��������ɂ̓e�o���f�B�͊��ɃI�y���E�̑�X�^�[�������B
�@���i�[�^�E�e�o���f�B��1922�N�A�C�^���A�̃y�[�U���ɐ��܂ꂽ�B�y�[�U���̓��b�V�[�j�̐��܂�̋��Ƃ����C�^���A�E�I�y�������̒n�ł�����B�����Đ��܂ꂽ�����ɂ���āA�N��B������Ńp���}���y�@�ɓ��w�A���r��ςB�₪�ăe�o���f�B�ɉH�����`�����X������Ă���B1946�N�A�~���m�E�X�J�����ĊJ�L�O�����ł���B�w���҂̓g�X�J�j�[�j�i1867-1957�j�B���̃I�[�f�B�V�����Ńe�o���f�B�̓g�X�J�j�[�j����u�V�g�̐��v�ƌ��܂��ꂽ�̂ł���B�g�X�J�j�[�j�Ƃ����A�t���g���F���O���[�A�����^�[�ƕ��ѐ��E�O��w���҂Ƃ���ꂽ��䏊�B�v�b�`�[�j�i1858-1924�j�Ƃ̐e���������A�u�{�G�[���v�u�g�D�[�����h�b�g�v�̏������w���A�u�g�X�J�v�Ɓu���X�v�l�v�͏������s��̎蒼���Ɍg��茩���ɑh���𐬌��ɓ����Ă���B�e�o���f�B�͂���Ȍ��Ђ���̂��n�t�����̂��B�́u�{�G�[���v�̃~�~�B�ϋq�́u���̏�Ȃ����炩�Ȑ��v�Ƒ��^�B�Ⴋ�u�X�J�����̏����v�̒a���������B�J���X��1947�N�A�A���[�i�E�f�B�E���F���[�i�ł���ƃC�^���A�i�o���ʂ��������ɂ̓e�o���f�B�͊��ɃI�y���E�̑�X�^�[�������B�@�J���X�̊肢�̓e�o���f�B�ɏ����A�X�J�����̏����ɂȂ邱�Ƃ������B�C�^���A�e�n�ŕ]�����J���X�����{�R�~���m�E�X�J�����ɏ��߂ēo�ꂵ���̂�1950�N4��12���A���F���f�B�́u�A�C�[�_�v�ł���B����������́A�̒��s�ǂŕ�����~�肽�e�o���f�B�̃s���`�q�b�^�[�������B�Ƃ͂����`�����X�̓`�����X�B�Ƃ��낪�J���X�̂����̋������͂܂��܂��R���g���[������Ă��炸�u�������L���L�����ĕ����Â炭�A���y���o���o���ɂ��Ă���v�ƍ��]���ꂽ�B�X�J�����̒��O�́A�����I�x���J���g���@�̃e�o���f�B�̔����̕����D�̂ł���B
�@��l�����C�o���Ƃ��ď��߂Č��ˁi�H�j�����̂�1951�N�A���I�E�f�E�W���l�C���ł���B���̔N�̓��F���f�B�i1813-1901�j�v��50�N�̃������A���E�C���[�B���I�E�f�E�W���l�C���s������́A�u�֕P�v�̃��B�I���b�^���J���X�ƃe�o���f�B�̃_�u���E�L���X�g�ŏ㉉����Ƃ����i���l����j���Ƃ����v���Ȃ����̕���ƂȂ����B���̎��A���ꑤ��Â̐H����̐ȏ�ŃJ���X�̓e�o���f�B�Ɂu���Ȃ��̃X�J�����ł́w�֕P�x�͎U�X��������ˁv�Ǝ��X�ɌJ��Ԃ����Ƃ����B��o��q���Ă���J���X�̕����������Ȑ��i���o���G�s�\�[�h�ł͂���B�Ƃ��낪���̌����A�ϋq�����f�B�A�����|�I�Ƀe�o���f�B���x�������B�J���X�͂܂��܂��ǂ����Ȃ��B
(2) �X�J�����ł̏��������`���B�X�R���e�B�u�D�ꂽ���D�v�ƃJ���X���^
 �@�J���X�̐��͐��܂�����d�߁A��������ő傫�Ȑ��ʂƍL������Ɍb�܂�Ă����B���A�܂��g���[�j���O����Ă��Ȃ��������ߕ�����ɂ͕s���ȋ��ؐ��Ƃ����������Ȃ������B����Ζ����̑��B����炪�R���g���[�������Α傫�ȕ���ƂȂ�B�����ꂵ���͋��x���ɕς�茀�I�\�����\�ɂ���B����̍L���̓��p�[�g���[�g��Ɋ�^����͂����B�J���X�͉��z�G�e�o���f�B���������Č��r�ɗ�B
�@�J���X�̐��͐��܂�����d�߁A��������ő傫�Ȑ��ʂƍL������Ɍb�܂�Ă����B���A�܂��g���[�j���O����Ă��Ȃ��������ߕ�����ɂ͕s���ȋ��ؐ��Ƃ����������Ȃ������B����Ζ����̑��B����炪�R���g���[�������Α傫�ȕ���ƂȂ�B�����ꂵ���͋��x���ɕς�茀�I�\�����\�ɂ���B����̍L���̓��p�[�g���[�g��Ɋ�^����͂����B�J���X�͉��z�G�e�o���f�B���������Č��r�ɗ�B�@1951�N12��7���A�J���X�̓��F���f�B�́u�V�`���A�̔ӏ��v�ŃX�J�����ɍēo�ꂷ��B�g���[�j���O��ςJ���X�̐��͌����ɃR���g���[������Ă����B�ϋq�͑劅�т𑗂�B�O��́u�A�C�[�_�v��3���ŏI������̂ɑ������7���Ԃ̌����ƂȂ����B�X�J�����͒lj��̏o�����I�t�@�[�A�����Ɏ��̌��������܂�B�J���X�̃t�@���̗ւ����X�ɍL�����Ă䂭�B
�@1952�N1��13���A�J���X�̓X�J�����̕���ɗ������B���ڂ̓x�b���[�j�́u�m���}�v�B�u�m���}�v��1948�N11���̃t�B�����c�F �e�A�g���E�R���i�[���ȗ��A10����28���������Ȃ��Ă�����͂⊮�S�Ɏ�̂����ɓ���Ă����B���ʂ͈��|�I�听���B�R�b���G�[���E�f�b���E�Z�[�����́u����͋��ٓI�ȍL�����������ɒ�����ƒቹ������߂��悤�Ȕ������ɖ����Ă���v�Ɛ�^�B�J���X�͂��Ƀe�o���f�B�ƌ�����ׂ��̂ł���B�����Ă��̂��납��A�X�J�����̊ϋq�̓J���X�hVS�e�o���f�B�h�̗l����悷��悤�ɂȂ����B�����ł͔��Δh�����W���������B�e�o���f�B�h������̃J���X�ɉԑ����[������𓊂�����B�J���X�h���e�o���f�B�h���^�͂ɓ˂����Ƃ����X�A�܂�Ō���̃T�b�J�[�̃T�|�[�^�[���m�̑����̑̂������Ƃ������Ă���B���̃X�J�����͐���͂����Ƃ����̔M���Ԃ���ނ��늽�}���Ă����߂�����B���s������オ��̂����瓖�R���낤�B
�@1953�N�Ɍ��J���ꂽ�f��u���[�}�̋x���v�������J���X�͈�匈�S������B�I�[�h���[�E�w�v�o�[���̂悤�ȃX�^�C����g�ɒ�����ׂ��_�C�G�b�g�ɗ�̂��B������2�N���炸��100kg�������̏d��35kg���ʁA60kg��̍אg�Ŕ������e�p��̌������̂ł���B
�@1955�N�̃X�J�����͐V���J���X�̓ƒd��B�܂��ɔ�Ԓ��𗎂Ƃ������������B1�A2���̓}���I�E�f���E���i�R�Ƃ̃W�����_�[�m�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�B5�A6���͋������L�m�E���B�X�R���e�B�i1906-1976�j���o�ɂ�郔�F���f�B�u�֕P�v�B12���A���N1���̃X�J����1956�N�V�[�Y�����J�������͏\���Ԃ́u�m���}�v�B���ł��u�֕P�v�͓`���I�����Ƃ��č������p����Ă���B�����J�����u�Ԋϋq�͑����̂݃��B�I���b�^�̐����ʂ��̂悤�ȃJ���X�ɖ������ꂽ�Ƃ��B�f�����������猩�Ă݂������̂��I ���B�X�R���e�B�́u�M���V���l�ł���J���X�ɂ͔ߌ����D�̌�������Ă���B�J���X�͗D�ꂽ���D���v�Ɛ�^�����B�J���X�͂��Ɂu�X�J�����̏����v�ƂȂ����B���̂����肩��C�^���A��ǂ���1958�N���炢�܂ł��J���X�̐Ⓒ���������悤�Ɏv���B
�@�J���X�ɏ����̍���D��ꂽ�e�o���f�B�́u��̒������ɗY�{��2�H����Ă������Ƃ͂ł��Ȃ���v�Ƃ̑䎌���c���X�J�������������B�̂��鏗�D�͓V�g�̉̐���ǂ�������̂ł���B�s�����NY���g���|���^���̌���B���g�̓e�o���f�B�����ҁE�D���B�V�V�n�Ő����Ԃ����e�o���f�B�͂��̌�18�N���̊�NY�̊ϋq�Ɉ����ꑱ�����B
�@�Z�����������R�����J���X�A�i�����肵�������𑱂������e�o���f�B�B�}�X�R�~�ɃX�L�����_���X�Șb���U��܂����J���X�A��e�̔�̉������Ȑl������e�o���f�B�B�|�����|�������������^�ɑΏƓI�ȓ�l�������B
�i3�j��l��DIVA�`���I��r
 �@�䂪���y���Ԃł͂ǂ��炩�Ƃ����e�o���f�B�h�������B���͏������e�o���f�B�̕����D���������B�ł��ߔN�A�J���X�̐���������悤�ɂȂ����B�^�C�v�̈Ⴄ��l��DIVA���r��������̂��y�����B
�@�䂪���y���Ԃł͂ǂ��炩�Ƃ����e�o���f�B�h�������B���͏������e�o���f�B�̕����D���������B�ł��ߔN�A�J���X�̐���������悤�ɂȂ����B�^�C�v�̈Ⴄ��l��DIVA���r��������̂��y�����B�@�I�y���́A1600�N�㏉���ɐ��܂�Ĉȗ��A��Ɍ�y�̉��l�������B�����͏㗬�K�����ґ����������o�ď����̑������ɂ��Ȃ����B�ꎞ������Y��ʐ��E�ɗU���Ă�����y�A���ꂪ�I�y�����B�I�y���ɂ͔��������y�Ƃǂ�ǂ�Ƃ����l�Ԗ͗l���������Ă���B�������̂��グ��̎���l�Ԃ̐^���P��̎���A�ǂ�������ݗ��R������B�e�o���f�B���J���X������������̂ł���B
�@���p�[�g���[�I�ɂ͂����炭�J���X�̕����L�����낤�B�u�g���X�^���ƃC�]���f�v�̃C�]���f��u�J�������v�̃J�������ȂǁA�h�C�c���̂�t�����X���̂��e�o���f�B�͂���Ă��Ȃ��B�����A�C�^���A���̂Ɍ���Η��҂̃��p�[�g���[�͂قڌܕ��ܕ��Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B�J���X�����u�m���}�v�A�u�����������[���̃��`�A�v�A�u���f�B�A�v�Ȃǂ̓e�o���f�B�͂��Ȃ��B����e�o���f�B�����u���t�B�X�g�[�t�F���v�A�u�I�e���v�A�u�A�h���A�[�i�E���N�u���[���v�Ȃǂ̓J���X�͂��Ȃ��B�Ƃ�����A�C�^���A�E�I�y���̉��ڂ̑����͓�l�̋��ʂ̃��p�[�g���[�Ƃ������ƂɂȂ�B�ȉ��A�����̒����猵�I����2�̉��ڂ��r�������Ă݂����B
���W�����_�[�m�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�̏ꍇ
 �@1955�N1���A�}���A�E�J���X�̓~���m�E�X�J�����œ��㐏��̃e�m�[�� �}���I�E�f���E���i�R�ƃW�����_�[�m�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�ŋ��������B���i�R�̃V�F�j�G�͕��Ԃ��̂Ȃ���������ł��邪�A�J���X�̃}�b�_���[�i�́A�����m�����A���ꂪ�B��̏o���ł���B�����Ƃ���ɂ��ƁA���̃v���_�N�V�����A�����̗\��̓��F���f�B�́u�C���E�g�����@�g�[���v�������Ƃ����B���ꂪ���i�R�̒��q�������ނ̎芵�ꂽ���̉��ڂɕς�����Ƃ��B�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�̓J���X�̃��p�[�g���[�ł͂Ȃ��B������������Ȃ̂��B
�@1955�N1���A�}���A�E�J���X�̓~���m�E�X�J�����œ��㐏��̃e�m�[�� �}���I�E�f���E���i�R�ƃW�����_�[�m�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�ŋ��������B���i�R�̃V�F�j�G�͕��Ԃ��̂Ȃ���������ł��邪�A�J���X�̃}�b�_���[�i�́A�����m�����A���ꂪ�B��̏o���ł���B�����Ƃ���ɂ��ƁA���̃v���_�N�V�����A�����̗\��̓��F���f�B�́u�C���E�g�����@�g�[���v�������Ƃ����B���ꂪ���i�R�̒��q�������ނ̎芵�ꂽ���̉��ڂɕς�����Ƃ��B�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�̓J���X�̃��p�[�g���[�ł͂Ȃ��B������������Ȃ̂��B�@�}�b�_���[�i�̕������ǂ���͑�3���̃A���A�u�S���Ȃ�������v�Ƒ�4���t�B�i�[���̃V�F�j�G�Ƃ̓�d�����낤�B�u�S���Ȃ�������v�̃J���X�̉̏��B��������́A����̂Ȃ��߂��݂���A��������z���āA痂��������Ă䂱���Ƃ��鋭�����S�Ɨh�邬�Ȃ��o�傪�Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���B�����āA�t�B�i�[���̓�d���B����͂������͂̌������B�Y���̌Ăъ|���ɓ�����J���X�́uSo nio!�v�̐��݁B���{���́u���ł��I�v�����A�J���X�̂́u����I�Ⴂ�Ȃ���I���傠��I�v�Ƃ����������������C������B�̏����V�F�j�G�Ɋ��Y���Ēf����Ɍ������̂ł͂Ȃ��A�ꏏ�ɁA����ނ��뗦�悵�ĕ���i�߂錡���͂�����B���i�R�́A�����̃e�o���f�B�ƈႤ�A�Ɗ��������ǂ����͒m��Ȃ����A�J���X�Ɉ����ς���悤�Ɋ���̌���o����B�̂��I�������l�ɊϏO�͂��������̚��āA���ʂĂ�Ƃ��m��Ȃ�����Ɗ����̗����B�����͑����ɕn�ゾ�����̃��C�u�͋ɂ߂ċM�d�Ș^���ł���B�Ƃ���ł���CD�iCDM26002�j�A���ǂ��Ŏ�ɓ��ꂽ�̂��낤���H
 �@�e�o���f�B�́u�A���h���A�E�V�F�j�G�v���܂������҂̓��i�R�ł���B�\�t�g��1961�N10���̃��C�uDVD�iKIBM1014�j�BNHK����������3��C�^���A�̌��c�̌����ŁA���͂��̔N�V�z���ꂽ����̓���������فB�������Z�����������͔����e���r�ɉf�郂�i�R���e�o���f�B��H������悤�Ɍ������������̂ł���B�v���o�͂��Ă����A�J���X�Ղ���5�N�قnj�ɂȂ邪�A��r����̂ɍ��x���͂Ȃ����낤�B
�@�e�o���f�B�́u�A���h���A�E�V�F�j�G�v���܂������҂̓��i�R�ł���B�\�t�g��1961�N10���̃��C�uDVD�iKIBM1014�j�BNHK����������3��C�^���A�̌��c�̌����ŁA���͂��̔N�V�z���ꂽ����̓���������فB�������Z�����������͔����e���r�ɉf�郂�i�R���e�o���f�B��H������悤�Ɍ������������̂ł���B�v���o�͂��Ă����A�J���X�Ղ���5�N�قnj�ɂȂ邪�A��r����̂ɍ��x���͂Ȃ����낤�B�@�u�S���Ȃ�������v�ɂ�����e�o���f�B�̉̏��͂������ɐ��炩�Ŕ������B�M���̖��炵���炿�̗ǂ��Ǝ���ɖ|�M����Ȃ���������ɐ����悤�Ƃ��錒�C���������ɉ̂���B�t�B�i�[���̃��i�R�Ƃ̓�d���B�e�o���f�B�̉̏�����́A������V�F�j�G�Ƌ��ɋB�R�Ƃ��Ď��o�̗��ɗ��}�b�_���[�i�̈�r�����`����Ă���B���i�R���A�J���X�̎��Ƃ͈Ⴂ�A���x�����Ȏ��l��������M���͋����̂��グ��B�������i�R�Ƃ̓�d�������A�J���X�̏ꍇ�͐키�悤�Ȋ���̌������A�e�o���f�B�̏ꍇ�͕v���w���I��̊������Ď���B���ɋ����[���ΏƂł���B
�����F���f�B�u�֕P�v�̏ꍇ
�@�̌��u�֕P�v�iLa Traviata�j�̓A���N�T���h���E�f���}�E�t�B�X�i1824-1895�j�̋Y�ȁu�֕P�v�iLa Dame Aux Cameilas�j������B�I�y���̃^�C�g��La Traviata�́u�����O�������v�Ƃ����Ӗ������A���{���ł͌���̃^�C�g���ɕ�����B�q���C���̃��B�I���b�^�́A19���I�A�p���Ќ��E�̉Ƃ���ꂽ���݂̏����}���[�E�f���v���V�����f���Ƃ����Ă���B�p���̎Ќ��E�Ŏ��R�C�܂܂ɐ����郔�B�I���b�^�����^�ȐN�A���t���[�h�Əo����ɗ����邪���ǂ͐g�������a�Ŏ���ł䂭�Ƃ�������ł���B
�@��r�y�Ȃ͑�1���̃��X�g�ʼn̂���A���A�u�Ԃ���Ԃցv�B�A���t���[�h�Əo��������B�I���b�^������܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ�����ɏP����u�����A���͂��̐l���v�ɑ����A�e���|�͈�]�A�b�v�ƂȂ��āA�u����ς莄�͉��y�̐��E�ɐ�����̂����������v�Ɩ�����莩���Ɍ���������������ȗ��̉́B���I��DIVA���r����̂ɑ������������̃A���A�ł���B
�@��l�̔�r�̓V���v���ɂ䂫�����B�ǂ��炪�֕P�炵���� �ȂǂƂ�����I�ȗv�f�͔r�����āA�������ǂ��끁�G���f�B���O���ǂ̂悤�ɉ̂��Ă��邩�H �Ō�̉̎� dee volare il mio pensier�i���̎v���͔�щ��j��pensier�́usier�v�������ǂ��̂��Ă��邩�̈�_���r����B
�J���X�i35�j�`�M�I�[�l�w���F�T���E�J�����X�̌���nj��y�c 1958�^��
�@E��6-A��5
�e�o���f�B�i32�j�`�����i�[�����v���f�����w���F���[�}���`�F�`���[���A�nj��y�c 1954�^��
�@A5-G5
�@�ō������ׂ�ƃJ���XE��6�Ńe�o���f�BA5��������Ɍ�5�x���J���X�������B���n�̓J���XA��5�Ńe�o���f�BG5������e�o���f�B�͔����Ⴂ�B������A��Ȃ̂Ńe�o���f�B�̓I���W�i���������ĉ̂��Ă��邱�ƂɂȂ�B�����f�B�[���C�����s���R�ŁA������Ƃ��̂�����߂��͂��������Ȃ��B���̈�_�����ŃJ���X����ʂɌ���̂͒Z���I�ɉ߂���Ǝv�����A���Ȃ��Ƃ��J���X�̕����Ȃւ̌������������^�����Ǝv���B
�@���݂ɂ��̃A���A�������ȉ��^�ʼn̂��Ă���̂́A�����m�����A�C���A�[�i�E�R�g���o�X�ƃX�e�t�@�j�A�E�{���t�@�f�b���̓�l�����ł���B
�@�u�֕P�v�̃��B�I���b�^�A�u�C���E�g�����@�g�[���v�̃��I�m�[���A�u�}�m���E���X�R�[�v�A�u���E�{�G�[���v�̃~�~�A�u�g�X�J�v�A�u���X�v�l�v�A�u�W�����j�E�X�L�b�L�v�̃��E���b�^�A�u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�̃}�b�_���[�i�E�E�E�E�E�����͉䂪�I�y���E�R���N�V�����̒��ł̃J���X�^�e�o���f�B���ʂ̉��ڂł���B�ꐺ�����������Ŕ�����B�����قǂɍۗ��������B��l�������Ɍ��o����DIVA���������������Ă����B �J���X�ƃe�o���f�B�B�ǂ��炪�������A�ǂ��炪�D���� �Ƃ������Ƃ����A���X�̋C���ɍ��킹�Ăǂ�������E�E�E�E�E����܂��I�y������햡�̈�ł���B
���Q�l������
KAWADE�����b�N�u�}���A�E�J���X�v�i�͏o���[�V�Ёj
�ŐV���ȉ���S�W��19���̌��U�A��20���̌��V�i���y�V�F�Ёj
BS���E�̃h�L�������^���[�u�J���XVS�e�o���f�B�v�iNHK-BS�j
�W�����_�[�m�̌��u�A���h���A�E�V�F�j�G�v
�@�~���m�E�X�J���� 1955���C�uCD
�@����������� 1961���C�uDVD
���i�[�^�E�e�o���f�B�^�\�v���m�E�A���A���ȏWCD(POCL4140)
CALLAS IN PORTRAIT CD�iTOCE55575�j
2022.02.25 (��) �k���~�G�I�����s�b�N�`�����Ƌ\�Ԃ̍ՓT
�@���������ǂ��Ȃ�������Ă�́A�k���~�G�I�����s�b�N�B�������Ȃ��Ƃ��N���肷�����Ⴀ�[�B�Ȃ̂ō���͎ɍ\�����ϐ�L�Ƃ����܂��傤�B �@�܂��́A�J�~���E�����G�������B15�̏����Ȃ̂Łg�����h�t�ŌĂ��Ă��炢�܂��B�����G�������̓_���g�c�̋����_�����B�c�̐�͈����̉��Z�Ń��V�A�E�`�[���̗D���ɍv�������B�Ƃ���ȂƂ��A�����G�������̃h�[�s���O�^�f�����o�����B���������ǂ��������ƁH����Ȃ���A�{�l������I�ɕ��p����͂��͂Ȃ����낤����A�g�S�ʔ珗�h�G�e���E�g�D�g�x���[�[�E�R�[�`��h�����p�������ƍl����̂����ʂł��傤�B�h�[�s���O�̌��Ёi�H�j�t�B���b�v�E�V���x�c�L�[�Ƃ�������҂�����ѓ����Ă���悤�����B�Ƃ͂�������I�����I��킸���o�����A�E�g���h�[�s���O�̏펯�B���o���ꂽ��܃g�����^�W�W���͋��S�ǂ̏��܂ŐS���ւ̌����𑣂�����A�X�|�[�c�I��̎��v��up���}���B�����G�������͓V�˂łȂ�ł��ł����Ⴄ����ǁA�܂�15������̗͂��Ȃ��B�B�ꎝ�v�͂��A�L���X�F�Ȃ킯�B���܂��铮�@�̓A���A���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�܂��́A�J�~���E�����G�������B15�̏����Ȃ̂Łg�����h�t�ŌĂ��Ă��炢�܂��B�����G�������̓_���g�c�̋����_�����B�c�̐�͈����̉��Z�Ń��V�A�E�`�[���̗D���ɍv�������B�Ƃ���ȂƂ��A�����G�������̃h�[�s���O�^�f�����o�����B���������ǂ��������ƁH����Ȃ���A�{�l������I�ɕ��p����͂��͂Ȃ����낤����A�g�S�ʔ珗�h�G�e���E�g�D�g�x���[�[�E�R�[�`��h�����p�������ƍl����̂����ʂł��傤�B�h�[�s���O�̌��Ёi�H�j�t�B���b�v�E�V���x�c�L�[�Ƃ�������҂�����ѓ����Ă���悤�����B�Ƃ͂�������I�����I��킸���o�����A�E�g���h�[�s���O�̏펯�B���o���ꂽ��܃g�����^�W�W���͋��S�ǂ̏��܂ŐS���ւ̌����𑣂�����A�X�|�[�c�I��̎��v��up���}���B�����G�������͓V�˂łȂ�ł��ł����Ⴄ����ǁA�܂�15������̗͂��Ȃ��B�B�ꎝ�v�͂��A�L���X�F�Ȃ킯�B���܂��铮�@�̓A���A���Ƃ������ƂɂȂ�B�@��N12��25���A���V�A�I�茠����Ƀ����G������猟�̍̎�B�X�g�b�N�z�����̌����@�ւɑ���ꂽ�B�������ʂ͒ʏ�Ȃ�10���ŏo��Ƃ�������A�N�����ɂ̓��V�A���̓����G�������̗z����F�����Ă��Ă����������͂Ȃ��B�Ƃ��낪���V�A�͌��\���Ȃ������B�Ȃ��H ��������G�������̃I�����s�b�N�o�ꂪ�s�\�ɂȂ����Ⴄ�B�����ŃM���M���o���ăh�T�N�T����ɋ��s�˔j�̍�ɏo���E�E�E�E�E�Ƃ����\���������Ȃ��B
�@���V�A�E�A���`�E�h�[�s���O�@�\�iRUSADA�j�̕Ƃ������IOC�����E�A���`�E�h�[�s���O�@�\�iWADA�j�̑Ή��A�����ăX�|�[�c���ٍٔ����iCAS�j�ْ̍�͈ȉ��̒ʂ�B
��2��8���ARUSADA�Ɍ������ʂ̕����遨�����G�����ɏo���~������ʒB�������G�����ًc�\�����ā�RUSADA�͏����������E�E�E�E�E���ꂪRUSADA�̕��@���܂�ɞB�����ʒ��F�ْ̍�ł���B�����Œ������ׂ���CAS�̏�����IOC�R�[�c��������C���Ă���Ƃ��������B�܂�RUSADA�����V�A�Ƃ������Ƃƕs���Ȃ̂��펯���B���̂�����IOC��CAS�����V�A�̂��ȏL���\�}�������B��B����̃h�[�s���O�ْ�̈�A�̗���͏o�����[�X�ł͂Ȃ����Ƃ����v���Ă���B
��2��11���A�������IOC��WADA�炪RUSADA�̏��������̌����s���Ƃ���CAS�ɒ�i
��2��13���ACAS�������G����W�҂ɕ�����蒲�����s��
��2��14���ACAS���u�����G���͗v�ی�҂�15������ᔽ����Ⴄ�B���������ŏo���~�ɂ���Ύ��Ԃ��̂��Ȃ��_���[�W��^���Ă��܂��B�����̂��Ƃ��l�����Ėk���I�����s�b�N�̌p���o����\�Ƃ���B�������{�P�[�X�͖������̏�Ԃł��胏���G���͂����܂Œ����Ώێ葱���ɂ���v�Ƃْ̍�\�B������IOC�́u�����G����3�ʈȓ��ɓ�������\���Z�����j�[�͍s��Ȃ��v�Ƃ̌������o�����B
�@���A�Ƃɂ��������G�������̏o��͌p���ƂȂ����B���V�A���͂ЂƂ܂����g�������Ƃ��낤�B�������͂��ꂩ��B�����Ɏ���܂ł̃��V�A���̕s���Ȍ����ʂ����Đ^���Ȃ̂��͍���̉𖾂�҂��˂Ȃ�Ȃ��B
�@��́A�Ȃ��������ʂ̕�1������������������ �Ƃ������ƁB���V�A���́u�X�g�b�N�z�����̌��������V�^�R���i�ɜ��������v�Ɛ������Ă��邪�z���g���ˁB���c�̐�I���̗����ɗ����Ȃ�Ă��܂�ɂ��s���R�B����Ȃ���A�����@�ւׂ�Δ���͂�����ˁB����ȊȒP�Ȃ��Ƃ����̂܂܂ɂ��Ă���̂��ς��B
�@������́u�N���X�}�X�E�C�u�ɑc�����S���̖�����������C���O���X���g���Ĉ���ł��܂����B���ꂪ�z�������̌����ƕꂪ�����Ă��܂��v�Ƃ̃����G�������ٖ̕��B����ǂ����Ă����������B���������̖�͏��܂Ȃ̂ɂȂ�ŃO���X�ɗn���o�Ă����̂��ˁB�����������V�A�����̃N���X�}�X��1��7�������B����͂ǂ��l���Ă����b�ł��傤�B����Ȃ��Ƃ�15�̏����Ɍ��킹�Ă܂Ő��������咣���郍�V�A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ�Ȃ낤�B���낵�������ނ������݂��o���܂����B
�@2��17���A���q�V���O���l���s��ꂽ�B�����ɂ͏Ռ��̌��i�����o�����B�����G�������͂܂�ŕʐl�B���E�ō����_���o���܂��������̓V�˃����G���̎p�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B���_224.09��4�ʁB�S�邽�錋�ʁB����܂ŋ���������g��]�h�����Ă��������G��������������͎��炪��]���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�c�̐킪267.45����������l��ł�43.36������������ƂɂȂ�B�h�[�s���O�����̉e���͖��炩���낤�B�o���~�͑I��Ƀ_���[�W��^����Ƃ����ꌩ����Ɍ�����CAS�ْ̍肪�t�ɑI��ɑ���ȃ_���[�W��^���Ă��܂����B����Ȃ��̂ł���B
�@���������ӂ̃����G�������Ƀg�D�g�x���[�[�E�R�[�`�́u�Ȃ�œr�����瓊���Ă��܂����́B�����ł��Ȃ��B�������āv�Ƌl�₵���Ƃ��B���ꂪ�`�[���E�G�e�����Ȃ̂�������Ȃ����A������Ǝc���߂��͂��Ȃ����B��_���̃g���\���́u���Ȃ��͂��ׂĂ�m���Ă���͂��Ȃ̂Ɂv�ƃn�O�����B���̈Ӗ��́H ������ɂ��Ă����V�A�͂��������̂Ȃ��X�P�[�^�[�𑒂��Ă��܂����B����ł������_���͓������V�A�̃V�F���o�R���B���������Д��g�̓���Ƃ����l���Ȃ��g���̂Ď�`�̃v�[�`���E���V�A�͂���ł悵�Ƃ���̂��낤���B�����G�������A�X�P�[�g�������l������Ȃ��� �撣���āI �ƌ��サ�����B�ł��܂����̂��ȁB���Ȃ牞�����܂����B
�@���{����{�ԐD�͎��ȃx�X�g�̉��Z��3�ʁB�ŋ����V�A�̈�p�ɐH�����B�V����̓����_���ł���܂��B
�@���������g�[�}�X�E�o�b�n���̍���̐U�镑���͉��Ȃ낤�ˁB�Z�N�n�������̜d������Ɛe���C�ɋ��Z���ϐ�B���̉f���𐢊E�ɗ�������ł���B��������������Ƒ҂��Ă��������ȁB�d������̓C���X�^�O�����ɒ������Y�}��������̃Z�N�n����Q��i�����B�������{�͂��ݏ����ɂ�����u�Ȃ��������Ɓv�ƌ��킹���B���ꂼ�l�������̍��Ƃ̈��́B�o�b�n����A���͂���Ȓ����̕Ж_��S���̂ł����B�u�n�����b�g���Ő��������������ˁv�Ƃ�����������āB���ꂪ�l�����d�̃I�����s�b�N���_�ł����B���A�K�ߕ��̂Ȃ�Ȃ̂��I
�@�܂��A���q�t�B�M���A�I����̒k�b�B�����G�������ւ̗����̏�����V�A�R�[�`�w�ւ̔ᔻ���ǂ����V��I�B����ȃZ���`�����^���Ȋ��z����Ȃ��āA�h�[�s���O���̂��̂�o�ł���Ƃ����{���I��ǓI�Ȕ������o���Ȃ����̂��Ȃ��B�ł܂��A�h�[�s���O�ō��Ƃ��ċސT���̃��V�A�̑哝�̂��J��ɓ��X�Əo�Ȃ��Ă���̂ɕ���ЂƂ���Ȃ��B���AIOC�̉�Ȃ�ł���I.
 �@�����́A2��7���A�W�����v�����c�̂̈ᔽ�ґ��o�����B��������������W�����v�̊�������̊ԁB�Ȃ�ƃX�[�c�̋K��ᔽ���Ƃ����B���q�̏ꍇ�X�[�c�̌����͑̂���2�|4�Z���`�܂ŁA����ȏ�͈ᔽ�Ƃ����K�肪����B�����͂���邩�H���Z�J�n�O�ɑS���ł���B���������A�����ł͒ʂ��Ă���B�������A����O�̌l��Ɠ����X�[�c�Ȃ̂��B�ᔽ�Əo���͍̂ŏ��̃W�����v����̔����ł������������B����͂܂��悭���邱�Ƃ̂悤�����A�u������������ƈ���Ă����v�Ƃ����B�������ᔽ�Ƃ��ꂽ�m���E�F�[�̑I��́u�ᔽ���o��܂ő����Ă����v�Ƃ̏،����B�ᔽ�҂͓��{�̑��Ƀh�C�c�A�I�[�X�g���A�A�m���E�F�[��4���5�l�B�Ȃ������q�I�����B����ӏ���20�`30����炵���B���q�I��̌������̓|�[�����h�̏����������悤�ŁA���̐l���Ȃ����撣��������ĕ��i�͂��Ȃ��悤�ȉӏ����������܂�������������̂��ˁB�w�i�ɂ͉ߏ�ȃX�[�c����������Ƃ������Ă���ˁB������ɂ��Ă��A�����͌������@�̕W�������K�v�ł��傤�B���������͂܂��߂Ȑl������A�����̂����łƎӍ߂������ǁA�ӂ邱�Ƃ͂Ȃ���B���i�ʂ�ɂ���ė��h�ɔ���B���܂��ܑz��O�̎��̂ɑ���������������B����ɂ��Ă����{�`�[���A7�l�ł�4�ʓ��܂͗��h�ł����B
�@�����́A2��7���A�W�����v�����c�̂̈ᔽ�ґ��o�����B��������������W�����v�̊�������̊ԁB�Ȃ�ƃX�[�c�̋K��ᔽ���Ƃ����B���q�̏ꍇ�X�[�c�̌����͑̂���2�|4�Z���`�܂ŁA����ȏ�͈ᔽ�Ƃ����K�肪����B�����͂���邩�H���Z�J�n�O�ɑS���ł���B���������A�����ł͒ʂ��Ă���B�������A����O�̌l��Ɠ����X�[�c�Ȃ̂��B�ᔽ�Əo���͍̂ŏ��̃W�����v����̔����ł������������B����͂܂��悭���邱�Ƃ̂悤�����A�u������������ƈ���Ă����v�Ƃ����B�������ᔽ�Ƃ��ꂽ�m���E�F�[�̑I��́u�ᔽ���o��܂ő����Ă����v�Ƃ̏،����B�ᔽ�҂͓��{�̑��Ƀh�C�c�A�I�[�X�g���A�A�m���E�F�[��4���5�l�B�Ȃ������q�I�����B����ӏ���20�`30����炵���B���q�I��̌������̓|�[�����h�̏����������悤�ŁA���̐l���Ȃ����撣��������ĕ��i�͂��Ȃ��悤�ȉӏ����������܂�������������̂��ˁB�w�i�ɂ͉ߏ�ȃX�[�c����������Ƃ������Ă���ˁB������ɂ��Ă��A�����͌������@�̕W�������K�v�ł��傤�B���������͂܂��߂Ȑl������A�����̂����łƎӍ߂������ǁA�ӂ邱�Ƃ͂Ȃ���B���i�ʂ�ɂ���ė��h�ɔ���B���܂��ܑz��O�̎��̂ɑ���������������B����ɂ��Ă����{�`�[���A7�l�ł�4�ʓ��܂͗��h�ł����B �@�H����������͊撣�������ǎc�O�������ˁB������������ĂȂ�4��]�A�N�Z���i4A�j�����3�A�e�E�E�E�E�E���ꂪ�ʐ^�������͂��B�\�����ɂ͂ˁB�ł��{�S�͈Ⴄ�Ǝv���ȁB���ʂɂ������l�C�T���E�`�F���ɂ͓G��Ȃ��B�����̔s�҂ŏI����Ă��܂��B�ł�2�A�e�̉��҂Ƃ��ĉ������c���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B����͂���4A�����Ȃ������B�q���̂���̖������Ȃ�����Ă��Ƃł��ˁB
�@�H����������͊撣�������ǎc�O�������ˁB������������ĂȂ�4��]�A�N�Z���i4A�j�����3�A�e�E�E�E�E�E���ꂪ�ʐ^�������͂��B�\�����ɂ͂ˁB�ł��{�S�͈Ⴄ�Ǝv���ȁB���ʂɂ������l�C�T���E�`�F���ɂ͓G��Ȃ��B�����̔s�҂ŏI����Ă��܂��B�ł�2�A�e�̉��҂Ƃ��ĉ������c���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B����͂���4A�����Ȃ������B�q���̂���̖������Ȃ�����Ă��Ƃł��ˁB�@�ł����̃A�N�Z���E�W�����v�Ƃ�������ƂĂ��Ȃ�����B�ŏ���1��]���W�����v��1A�̓m���E�F�[�̃A�N�Z���E�p�E���[�������������B������A�N�Z���E�W�����v�Ȃ��ǁA���ꂪ1882�N�B2A�͂���66�N��A3A�͂��̂����30�N��B�����Ă�������44�N��̍����A4A�͂܂��N���������Ă��Ȃ��Ƃ��������ςȂ��B���̐����͈̋ƂƂȂ�B�H��������4A��k���ւ̃��`�x�[�V�����ɂ����ˁB
�@2��8���A�V���[�g�E�v���O�����B�Ȃ�ƍŏ���4��]�T���R�E�Ńu���[�h�����ɂ͂܂���1��]�ɂȂ��Ă��܂��B�O�̑I�肪�������Ȃ��ǁA�����������͏�ɂ���݂����B�N������������A���̎��̉H������̕X�ɂ�30���炢�̌����������Ƃ�����B�u�X�P�[�g�̐_�l�Ɍ���ꂽ�̂��ȁv�ƃR�����g���Ă������ǁA�ǂ����낤�A����ꂽ�̂ł͂Ȃ������Ƃ����̂ł͂Ȃ��̂��ȁB�ǂ����ɂ��Ă��A�V���[�g��8�ʁB�������͂��납���_������]�I�B�Ȃ��4A���Ԃ����Ȃ��B�t�ɓ���肪������Ȃ��낤���B
�@2��10���A�t���[�`���B�H����4A���B�ɂ������]�|�B�ł��F��I�����̉�]�s���̒��ߕt���ŁB����Ŏj�㏉4A���Z�҂ƂȂ����B������8����4A�̗��K�ő����P�����Ă����Ƃ����B���g�n�w�̉H��������3�x�ڂ̃I�����s�b�N���I������B�u����Ȃ��w�͂�������������Ȃ�����ǐ������ς��撣��܂����v�B����Ȃ�̖������͂������Ǝv���B
 �@2��11���A�����������̃X�m�[�{�[�h�E�n�[�t�p�C�v�̋����_���͗��h�������ˁB�ނ�15�A�ŏ��̌ܗ� �\�`�ŋ�A���̕����ł���B������͂�������A����͋������Ȃ������B���̂���3�R�[�N1440�Ƃ�����̌v2�̐��E�ŒN������ĂȂ���Z�������Ėk���ɏ�荞�ˁB
�@2��11���A�����������̃X�m�[�{�[�h�E�n�[�t�p�C�v�̋����_���͗��h�������ˁB�ނ�15�A�ŏ��̌ܗ� �\�`�ŋ�A���̕����ł���B������͂�������A����͋������Ȃ������B���̂���3�R�[�N1440�Ƃ�����̌v2�̐��E�ŒN������ĂȂ���Z�������Ėk���ɏ�荞�ˁB�@���Z��3�{�̍ō��_�Ō��܂�B�����2�{�ڂ�3�R�[�N1440�𐬌� 91.75�B�g�b�v���m�M�����S.�g�[�}�X��92.50�ɋy��2�ʁB�u�Ȃ�ŁH���E���̑�Z�����߂��̂Ɂv�B�ނ̗\�肪�������B�\��ł͂����ŋ����_�����m�肵��3�{�ڂ͂�����̑�Z���g���C���ĊM������ŏI���B����Ȃ͂��������Ǝv���B
�@�����2�{�ڂƓ����v���O�����ł��̐��x���グ�����I�B�����l��ɂ͂��ꂵ���Ȃ��B����͑z����₷��v���b�V���[�������͂��B�����Ĕ�� 96.00�B����̂��悤�̂Ȃ��p�t�H�[�}���X�������B��������͌����v���b�V���[�ɑł��������B���̃����^���͂�����ق߂Ă��J�߉߂��邱�Ƃ͂Ȃ��B�ł܂��A����̋���j�ݑ��������h���郉�C�o�� �V���[���E�z���C�g�ƌ������̂������V�[������ۓI�������ˁB
�@�����㕽��́u2�{�ڂ̓_���ɂ͔[���������Ȃ������B���̓{�肪3�{�ڂ̗͂ɂȂ����Ǝv���B�̓_��������Ɩ��m�ɂȂ邱�Ƃ��肤�v�ƌ���Ă����ˁB���̍̓_������100�_���_�̌��_�����B�̂̂悤�Ɍ���ꂽ�Z�̒��ł��̊����x�������̂Ȃ炱��ł������A����̕��삭���3�R�[�N1440�̂悤�Ȓ���Փx�̐V�Z���łĂ�����A���_�@�ł͊Ԃɍ���Ȃ��B�����͉��_�@�ɂ��ׂ����낤�B�Z���Ƃɓ�Փx�ɉ������Z�p�_������A���̏o���h���_�Ƃŕ]������B���_�͐V��B�t�B�M���A�Ɠ����������B����Ȃ�A����Z�����قǂɓ_�����オ��A���삭��̂悤�ȕs���͏o�Ă��Ȃ����낤�B�X�P�{�[����Ɉ�l�����肢�������ˁB
�@�W�����v�����ї˘�����͗��h�ł����B�I�����s�b�N8��o��̎t�����I���ē͋�܂ł����������q�̋����_���͎����̂��Ƃ̂悤�Ɋ�����������Ȃ��̂��ȁB�m�[�}���ƃ��[�W�̋���͒���ܗւ́g�t�i�L�`�h�a�삩��24�N�Ԃ���{�I��j���l�ڂ̉������B����ł͋��������j�q�̒c�̐�͖��O��5�ʁB�˘БI��Ƒ���3�I��Ƃ̍������肷�������Ă��Ƃ��ȁB����͓��̊۔�s�����������ǖk���͓��̊ەДx��s������i����j�B
 �@���ؔ��������͂����Ɨ��h�ł����B5��ڂɏo��B3000m�͂����Ƃ��āA���_����1500m�͋�ŏI����āA�ǂ����Ǝv����500m�͋�B���ŗL�͂̏��q�p�V���[�g�͂���100m�Ŏo�̍ؓ߂��܂����̓]�|�i���̂��Ƃ̃}�X�X�^�[�g�ł��R�P��������ˁj�ŋ�B���̃A�N�V�f���g���炽�����̒�1���A��J�Ɍ��ŗՂ�2��17����1000m�A�����I�����s�b�N�V�L�^�ŋ��B�Ō�̍Ō�ŔO��̌l�����_������ɂ����B�v���Ώ��o���2010�o���N�[�o�[��1000m�͍ʼn��ʂ������B�������甇���オ���Ă̐��E��B�����č����Ŋl���������_���͋��P�Ƌ�3�B����͂�������Ȃ��̓V����ł��B����͂܂��A���n���E�f�r�b�h�R�[�`�̑��݂��傫�������B�ނ͑O���R���i�ō������x�ꂽ���킯������ǁA���A�����㔼�A���̓����͖��炩�ɕς���Ă����ˁB�u�X��̏����v�a���ɔނ̗͂͌������Ȃ������Ǝv���B
�@���ؔ��������͂����Ɨ��h�ł����B5��ڂɏo��B3000m�͂����Ƃ��āA���_����1500m�͋�ŏI����āA�ǂ����Ǝv����500m�͋�B���ŗL�͂̏��q�p�V���[�g�͂���100m�Ŏo�̍ؓ߂��܂����̓]�|�i���̂��Ƃ̃}�X�X�^�[�g�ł��R�P��������ˁj�ŋ�B���̃A�N�V�f���g���炽�����̒�1���A��J�Ɍ��ŗՂ�2��17����1000m�A�����I�����s�b�N�V�L�^�ŋ��B�Ō�̍Ō�ŔO��̌l�����_������ɂ����B�v���Ώ��o���2010�o���N�[�o�[��1000m�͍ʼn��ʂ������B�������甇���オ���Ă̐��E��B�����č����Ŋl���������_���͋��P�Ƌ�3�B����͂�������Ȃ��̓V����ł��B����͂܂��A���n���E�f�r�b�h�R�[�`�̑��݂��傫�������B�ނ͑O���R���i�ō������x�ꂽ���킯������ǁA���A�����㔼�A���̓����͖��炩�ɕς���Ă����ˁB�u�X��̏����v�a���ɔނ̗͂͌������Ȃ������Ǝv���B �@�X�P�[�g���V���[�g�g���b�N���^�f�̔��肾�炯�ł����B�m���ɂ��̋��Z�A���낢��Ȃ��Ƃ��N���鋣�Z�Ȃ�ˁB�Ⴆ��2002�N�A�\���g���[�N�̒����B���܂�L�͂łȂ��I�[�X�g�����A�̃u���b�h�o���[Bradbury�Ƃ����I�肪�V���[�g�g���b�N1000m�ɏo�ꂵ�Ă����B2�ʈȓ����K�v�ȏ��X�����Ŏ��������͏�ʂ̓�l���]�|�Ǝ��i�ŏ������ցB��������2�l���]�|�A�����i�ށB���������͍ʼn��ʂ����珇���Ɂi�H�j�Ō���������Ă�����3�l�����X�Ɠ]�|�A�Ȃ�Ƌ����_�����l����������B����Ȃ��Ƃ��肦�܂��H�I�[�X�g�����A�ł�Do a Bradbury�Ƃ����ꂪ�����ɍڂ��Ă���炵���B�Ӗ��́u���Ȃڂ��v�B
�@�X�P�[�g���V���[�g�g���b�N���^�f�̔��肾�炯�ł����B�m���ɂ��̋��Z�A���낢��Ȃ��Ƃ��N���鋣�Z�Ȃ�ˁB�Ⴆ��2002�N�A�\���g���[�N�̒����B���܂�L�͂łȂ��I�[�X�g�����A�̃u���b�h�o���[Bradbury�Ƃ����I�肪�V���[�g�g���b�N1000m�ɏo�ꂵ�Ă����B2�ʈȓ����K�v�ȏ��X�����Ŏ��������͏�ʂ̓�l���]�|�Ǝ��i�ŏ������ցB��������2�l���]�|�A�����i�ށB���������͍ʼn��ʂ����珇���Ɂi�H�j�Ō���������Ă�����3�l�����X�Ɠ]�|�A�Ȃ�Ƌ����_�����l����������B����Ȃ��Ƃ��肦�܂��H�I�[�X�g�����A�ł�Do a Bradbury�Ƃ����ꂪ�����ɍڂ��Ă���炵���B�Ӗ��́u���Ȃڂ��v�B�@2��7���A�j�q1000m�������B�؍��t�@���E�f�z���I�肪1�ʓ��I�������I���ǂ����������ɔ������������Ƃ��Ď��i�A�����I��͌����i�o�B�����ł́A�n���K���[�̃����[�I�肪1�ʓ��I���i�H�W�Q��Ƃ����Ƃ��Ď��i�B�����I�肪�����l�������B
�@�O�҂ł́A�ǂ����Ă��؍��I��͔�������Ȃ��B���ʂɒǂ������Ă���B��҂́A��ɖW�Q�����悤�Ɍ�����̂̓n���K���[�̑I�肾���A����̒����I��̍s�ׂ͖��炩�ȖW�Q���B�T�b�J�[�ł͒����̓J���L�������A�V���[�g�g���b�N�͒����̓J���B�u��n�̉́v���Ⴀ��܂����B
 �@�u���Ȃڂ��v�Ƃ����A�J�[�����O�����R�E�\���[���̍����I�ő�̃T�v���C�Y�B2��17���A�\�I�Ō�ŃX�C�X�Ɋ��s�B����ŃI�V�}�C�Ƒ勃�����Ă�����A�u�������s����v�̕�ɔj���A�ēx�̑勃���B����́u���Ȃڂ��v�Ƃ������_�l�̃v���[���g���ȁB�����̏������̑���͊��s�����X�C�X�B�������S�̃Q�[���ŏ����B������͕����œ��{�������_�����l����3�ʌ����Ɠ����C�M���X������B�C�M���X�̎茘�������^�тɍŌ�܂ŃQ�[���̎哱������ꂸ�Ɋ��s�B�C�M���X�͕����̐�J���ʂ������A���{�ɂ�������ɏI���܂����B�ł��A�O��������_���l���͕���Ȃ��̓V����ł��B
�@�u���Ȃڂ��v�Ƃ����A�J�[�����O�����R�E�\���[���̍����I�ő�̃T�v���C�Y�B2��17���A�\�I�Ō�ŃX�C�X�Ɋ��s�B����ŃI�V�}�C�Ƒ勃�����Ă�����A�u�������s����v�̕�ɔj���A�ēx�̑勃���B����́u���Ȃڂ��v�Ƃ������_�l�̃v���[���g���ȁB�����̏������̑���͊��s�����X�C�X�B�������S�̃Q�[���ŏ����B������͕����œ��{�������_�����l����3�ʌ����Ɠ����C�M���X������B�C�M���X�̎茘�������^�тɍŌ�܂ŃQ�[���̎哱������ꂸ�Ɋ��s�B�C�M���X�͕����̐�J���ʂ������A���{�ɂ�������ɏI���܂����B�ł��A�O��������_���l���͕���Ȃ��̓V����ł��B�@�g�c�[���ԁ`��ؗ[�`�g�c�m�ߔ��`����܌��̃��R�E�\���[���B�M���Ƃ����J�Ō��ꂽ���łȃ`�[�����[�N�Ƃǂ�ȃs���`�ɂ��Ί���₳�Ȃ����邢�`�[���J���[���K�^���Ă���͌��ʂł��傤�B�k���Ȍv�Z�ƕ��O�ꂽ�R�~���j�P�[�V�����\�͂������B�A�Ŏx�������U�[�u�̐�Ք��̑��݂��Y�ꂿ�Ⴂ���Ȃ��B�ޏ��͎j��ŔN���i43�j�̃��_���X�g�ɂȂ����B�f���炵���p�t�H�[�}���X�������Ă��ꂽ���R�E�\���[���Ɋ��t�I
�@���������������Nj\�Ԃɖ������k���~�G�ܗւł����B�h�[�s���O���ւ̕s�����ȑΉ��B�_�Ԍ���������ƌ������������ԁB���s�D���IOC�̎p���B�������i�[�Ől�������J���t���[�W�����钆���B���X�ƊJ��ɗՐȂ���ސT���Ƃ̑哝�́B�ɂ܂��I�����s�b�N�̐������p�B�����e�F����IOC�B�K�ߕ��E�����`�v�[�`���E���V�A�`�o�b�n�EIOC�̂ǂ������g���C�A���O���������Ă���E�E�E�E�E�I�����s�b�N�͌����A�t�F�A�v���C�̐��_�A�l���̑��d�A���E�̕��a�A�����W�Ԃ��Ă����͂��B�I�����s�b�N�����E���ǂ������̐��_��Y��Ȃ��ł������������B�����肤����ł���܂��B
2022.01.25 (��) DIVA�}���A�E�J���X�̃I�y���̎�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�M���V���A�A�����J�A�C�^���A�A�����āu�m���}�v
 �@��N���A�e���r�ʼnf��u�t�B���f���t�B�A�v�i1993�āj���ς��B�g���E�n���N�X������L�\�ȕٌ�m���G�C�Y�ɜ늳���Ζ�������ٌ�m�����������ق����B�����s���Ƃ��ĉ�Б����i�����̉�R�₵�Ȃ���s���Ɛ키���ꂾ�B
�@��N���A�e���r�ʼnf��u�t�B���f���t�B�A�v�i1993�āj���ς��B�g���E�n���N�X������L�\�ȕٌ�m���G�C�Y�ɜ늳���Ζ�������ٌ�m�����������ق����B�����s���Ƃ��ĉ�Б����i�����̉�R�₵�Ȃ���s���Ɛ키���ꂾ�B�@����̏I�ՁA�^�Ɋ����I�ȃV�`���G�[�V�������������B����ŁA�����ٌ̕�m�i�f���[���E���V���g���j�Ə،��̗\�s���K���ɃI�y���E�A���A��������B�Â��ȏ��t����}���A�E�J���X�̉̐��������o���B���L�̓J���X�̉̂ɏd�Ȃ�n���N�X�̑䎌�ł���i�u�v�͉̎��j�B
��D���ȃA���A���`�}���A�E�J���X�`�A���h���A�E�V�F�j�G�`�E���x���g�E�W�����_�[�m�`�}�b�_���[�i�̉̂��`�ޏ��͌����`�t�����X�v���Ŗ\�k���ޏ��̉Ƃɉ��� �ޏ����~�����߂ɕ�e�͎��`�u���̂�肩���̉Ƃ������Ă䂭�v�`���̋�ɂɖ��������@�킩�邩���H���y�킪�n�܂�ƋȂ���]�ɖ����Ă���`�u�����ꂽ�l�ɂ܂Ŕ߂��݂��v�`���̃`�F���̃\���I�`�u���̋ꂵ�݂̒��ň������ɖK�ꂽ�v�`�u���a�ɖ��������������v�`�u�܂�������̂�v�E�E�E�@�J���X�̉̂��A���A�́A�W�����_�[�m�i1867-1948�j�̉̌��u�A���h���A�E�V�F�j�G�v��3���́u�S���Ȃ�������v�ł���B�M���̖��}�b�_���[�i���A�t�����X�v���Ƃ��������̎���ɖ|�M����Ȃ�����A�V�F�j�G�Ƃ̈��Ɋ�]�̓������o���ĉ̂�������Ӑg�̃A���A���i�nj��y�̓Z���t�B���w���F�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�j�B
�@�G�C�Y�ɂ�鎀���ԋ߂ɔ����Ă��邱�Ƃ����o����g���E�n���N�X�́A������V�F�j�G�Ƌ��Ɏ���I�Ԃ��ƂɂȂ�}�b�_���[�i�Ɏ���̉^�����d�ˍ��킹�邩�̂悤�ɁA�܂�œ�l�ŋ��̂悤�ɁA�S�ʂ�������Ԃ����o���̂ł���B�����������̋��сB�f��̒��ŃN���V�b�N���y���g�����ʂ͐��X����ǁA����قǂ܂łɐS����������ʂ͖ő��ɂ�����̂ł͂Ȃ��B
�@�g���E�n���N�X�̔��^�̉��Z�B�]�l�������đウ��}���A�E�J���X�̐⏥�B���̓�����x�ɉ��w�����������N����������͌��ʂ��낤�B����́A���̂悤�Ȋ����̏�ʂ����o��������̃A�[�e�B�X�g �}���A�E�J���X�i1923-1977�j�̃I�y���̎�Ƃ��Ă̐l�������ǂ��Ă݂悤�B
�i1�j�M���V���ƃA�����J
 �@�}���A�E�J���X��1923�N�A�M���V���ږ��̎����Ƃ��ăA�����J �j���[���[�N�ɐ��܂ꂽ�B���͎����Ȗ�t�A��͏㏸�u������������}�}�B�ƒ됶���̃C�j�V���e�B�u�͕ꂪ�Ƃ��Ă����悤���B���ĉ̎���u���Ă�����͖��ɃI�y���̎�̖���������B�ŏ��͒������W�I���������A��Ƀ}���A�̍˔\��m���ď�芷����B�������Ȃ��爤��𒍂����킯�ł͂Ȃ��A�����܂Ŏ��ȗ~���B���̎�i�Ƃ��Ă������B���݊��̔������A�܂荇���̈����o�A����̋�����B�ƒ�̓}���A�ɂƂ��Č����Ĉ��Z�̒n�ł͂Ȃ��A���y�ւ̖v�����������炬�ƂȂ����B�˔\�͏��X�ɖ������������Ă����B
�@�}���A�E�J���X��1923�N�A�M���V���ږ��̎����Ƃ��ăA�����J �j���[���[�N�ɐ��܂ꂽ�B���͎����Ȗ�t�A��͏㏸�u������������}�}�B�ƒ됶���̃C�j�V���e�B�u�͕ꂪ�Ƃ��Ă����悤���B���ĉ̎���u���Ă�����͖��ɃI�y���̎�̖���������B�ŏ��͒������W�I���������A��Ƀ}���A�̍˔\��m���ď�芷����B�������Ȃ��爤��𒍂����킯�ł͂Ȃ��A�����܂Ŏ��ȗ~���B���̎�i�Ƃ��Ă������B���݊��̔������A�܂荇���̈����o�A����̋�����B�ƒ�̓}���A�ɂƂ��Č����Ĉ��Z�̒n�ł͂Ȃ��A���y�ւ̖v�����������炬�ƂȂ����B�˔\�͏��X�ɖ������������Ă����B�@�}���A��13�̎��A��͌̋��M���V���ł̋�������f�B�����c���ăM���V���ɈڏZ�B�}���A�̓A�e�l���y�@�ɓ��w����B�����ŏo��������t�����E�I���\�v���m�̃G���r���E�f�E�C�_���S�i1891-1980�j�B���ꂪ�K�^�������B�C�_���S�̓}���A�̌��Ⴂ�̍˔\�ɍ��ꍞ�ݕ��X�Ȃ�ʏ�M�𒍂����B�����Ƀ}���A�̉ƒ���ł̌ǓƂ�������薺�̂悤�ɉ��������B����Ȋ��̒��A�}���A�͉v�X���y�ɂ̂߂肱�݁A�˔\�͈�C�ɊJ�Ԃ���B
�@1942�N18�A�C�_���S�̐��E�ŃI�y���E�f�r���[���ʂ����B���ڂ́u�g�X�J�v�B�]���͏�X�������B���܂�������E��풆�B�M���V���̓h�C�c���C�^���A�̑S�̎�`���Ƃ̐�̉��ɂ������B�}���A�͌����܂܂ɐ�̌R���̉��t��ɏo���B�Ƃ��낪�I���A���ꂪ�Ђ����Č���Ǖ��A���w���ł���̗J���ڂɍ����Ă��܂��B�}���A�͊��H�����߂ăA�����J�ɖ߂����B
�@�A�����J�ł̊����͂܂܂Ȃ�Ȃ��B���g���|���^���̌���͂��ߎ��I�[�f�B�V�������ׂĂɗ��I�B�M���V���ő����̕]�����Ƃ������炢�ł̓A�����J�ł͒ʗp���Ȃ������̂ł���B�����}���A�̎��M�͗h�邪�Ȃ������B�u���g���|���^���͂����̂��Ă���Ǝ��ɓ���������ł��傤�v�B�L���ȑ䎌�ł���B
�@�a���̒n�A�����J�ƃ��[�c�Ƃ��ẴM���V���B���̏��������̍��͂��̌��l�̐l�Ԃɂ��}���A�̐��U�ɍX�ɐ[��������邱�ƂɂȂ�B�M���V���l�I�i�V�X�ƃA�����J�l�W���N���[���E�P�l�f�B�ł���B
�@�M���V���̊C�^���A���X�g�e���X�E�\�N���e�X�E�I�i�V�X�i1906-1975�j�B�ނ��}���A�̑O�Ɍ��ꂽ�̂�1958�N�A�}���A35�A�I�i�V�X52�̂Ƃ��������B���͂␢�I�̉̕P�Ƃ��Ă̖������ق����܂܂ɂ��Ă����}���A���������A�v���l�M�[�j�̔w�M�A�匀��Ƃ̃g���u���A���̉A��Ȃǂ��d�Ȃ�A�C�����r��ł��������ł��������B����Ȓ��A1959�N�A�I�i�V�X�͎����Â���n���C�N���[�Y�Ƀ}���A�E�J���X�v�Ȃ����҂���B���؋q�D�ƕ������Z�Ȓn���C�B�����ɂ́A����܂ŏo��������Ƃ̂Ȃ��^�C�v�̊��C�ɂ��ӂꖣ�͓I�ȃI�i�V�X������B��ɁA��l�̋��ʂ̒n�M���V���ł̂ЂƂƂ��̓}���A�̐S�����̏�Ȃ��R���オ�点���B���D����ƃ}���A�͕v�Ƃ̗��ʂ����ӂ���B�}�X�R�~�͐��I�̉̕P�Ƒ�x���̗� �ƚ������Ă�B1960�N�A�I�i�V�X�����B1966�N�A�}���A�̓A�����J�̎s������������ăM���V�����Ђ��擾�B�����Ɏ����ă}���A�͂������A���Ԃ���l�̌�����M���ċ^��Ȃ������B���̍��̃}���A�̎莆���c���Ă���B����̓I�i�V�X�u8�N�����̊ԋ��ɐ����Ă��Ă킽���͐S���猾���܂��B���Ȃ��̂��Ƃ��ƂĂ��ւ�Ɏv���S�g�S��������Ă��Ȃ��������Ă��܂��ƁB�����Ă��Ȃ����܂����ɑ��ē����v���ł��邱�Ƃ�����Ă��܂��v�B
�@�Ƃ��낪�ł���B1968�N�A���Ƃ����낤�ɃI�i�V�X�̓P�l�f�B�哝�̖̂��S�l�W���N���[���ƌ������Ă��܂��̂ł���B�}���A�͂��̕��V���Œm�����Ƃ����B��r�ȏ����̋C�����݂ɂ��邠��܂����s�ׁB�I�i�V�X�̓}���A�Ƃ̕t�������̒��A��т��Ď��Ȃ̂킪�܂܂�ʂ��Ă���B�������K���̃}���A���u����Ȃ��͕̂s�v���A�����ɏo�ė����v�ƌĂяo���Ă������Ƃ����B�|�p�𗝉������A�I�y���E�̎���}���A�E�J���X���킪���̊�Ŏ���������B���E�̊C�^�������Ȃ��m��Ȃ����A���̖�ڂŐ���オ��҂̑����������ċ����킯�ɂ͂����Ȃ��B
�i2�j�C�^���A�A�����āu�m���}�v
�@���͏I���Ԃ��Ȃ�����ɑk��B�J���X�̖������E�ɒm��n�����̂͂�͂�I�y���̖{��C�^���A�������B�A�����J�ł̊������܂܂Ȃ�Ȃ����A�A���[�i�E�f�B�E���F���[�i�̎d�����������̂��B1947�N8���A���ڂ̓|���L�F�����̉̌��u�W���R���_�v�B�w���̓Z���t�B���B�����͂܂��܂��̐����������B�����A����ȏ�ɍK�^�������̂́A�w���҂��C�^���A�E�I�y���E�̋����g�D���I�E�Z���t�B���i1878-1968�j���������ƁB�����Ēn���̎��Ɖƃ��l�M�[�j�Əo��������Ƃ������B�J���X�̎��͂�F�߂��Z���t�B���͋��͂Ȏx����&�����҂ƂȂ�A�J���X�ɍ��ꍞ���l�M�[�j�̓C�^���A�e�n�̉̌���̃u�b�L���O�ɋ��B
�@�J���X�̃I�y���̌�������N�x�ʂɌ��Ă������i���ꉉ�ړ�����A��������1�ƌ��j�B
1946�N 0�A1947�N 2�A1948�N 11�A1949�N 11�A1950�N 17�A1951�N 20�@���l�M�[�j�Əo����Ă���̌������͈�ڗđR�㏸��r�B1951�N���s�[�N��1956�N�܂�9�N�A��2�P�^�����������B�J���X�̃��l�M�[�j�ւ̋C���͊��ӂ��爤��ւƕς���Ă䂭�B1949�N�A��l�͌����B��l�̒��́A���l�M�[�j�ւ̕s�M�����萶���A�I�i�V�X�������1958�N�܂ő������ƂɂȂ�B�������͂���ȍ~�����̈�r��H��B
1952�N 18�A1953�N 18�A1954�N 14�A1955�N 11�A1956�N 10�A1957�N 8
1958�N 10�A1959�N 5�A1960�N 2�A1961�N 2�A1962�N 2�A1963�N 0
1964�N 3�A1965�N 4�A1973�N �P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iKAWADE�����b�N�u�}���A�E�J���X�v���J�E���g�j
�@��L���Ԓ��̉��ڐ��x�X�g10�͉��L�̂Ƃ���B
1 �x�b���[�j�F�m���}�i26�j�@���ɑ��ʂȉ��ڂł���B��Ƀx�b���[�j�u�m���}�v�A�h�j�[�b�e�B�u�����������[���̃��`�A�v�A�P���r�[�j�u���f�B�A�v�Ȃǂ̓J���X��������܂Œ����Ԗ�����Ă����A����A�Y���ꂽ�I�y���������B�J���X�ȍ~�����͐��E�̃I�y���n�E�X�ŕp�ɂɏ㉉�����悤�ɂȂ�B���@��������ɐV���ȃ��p�[�g���[���₵���J���X�̌��т͑傫���B���ł��㉉��1�ʂ́u�m���}�v�̓J���X�ő�̏\���ԂƂ��Ė��������A�܂��A�����̉��ڂł��������B
2 ���F���f�B�F�֕P�i20�j
3 �v�b�`�[�j�F�g�X�J�i13�j
4 �P���r�[�j�F���f�B�A�i12�j
4 ���F���f�B�F�A�C�[�_�i12�j
6 �h�j�[�b�e�B�F�����������[���̃��`�A�i11�j
7 �v�b�`�[�j�F�g�D�[�����h�b�g�i8�j
8 ���F���f�B�F�g�����@�g�[���i7�j
9 �x�b���[�j�F�����k�i6�j
10 �|���L�F�����F�W���R���_�i4�j
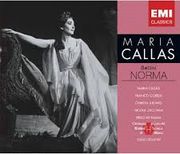 �@1948�N11��30���A�}���A�E�J���X�̓t�B�����c�F �e�A�g���E�R���i�[���̕���ɗ������B�w���̓Z���t�B���B���ڂ̓x�b���[�j�̉̌��u�m���}�v�B�J���X���Z���t�B���̏����ɂ���Ē�����ɂ��ď������ڂ������B
�@1948�N11��30���A�}���A�E�J���X�̓t�B�����c�F �e�A�g���E�R���i�[���̕���ɗ������B�w���̓Z���t�B���B���ڂ̓x�b���[�j�̉̌��u�m���}�v�B�J���X���Z���t�B���̏����ɂ���Ē�����ɂ��ď������ڂ������B�@�u�m���}�v�̕���͋I���O�̃K���A�n���B�m���}�̓��[�}�̎x�z���ɂ���h���C�h���k�ɐ_�̐M�����������m���B��������Ń��[�}�h���̒n�����|���I�[�l�ƈ���������ׂ����w���̐g�ł�����B�m���}�͂���Ȋ������ߍ��J���i�邪�A�Ō�͋C�����ΌY��ɕ���i�߂� �Ƃ�������ł���B
�@�x���J���g���鍂��x�̃e�N�j�b�N�B�_���Ƒ��������݂��镡�G�Ȑ��i�`�ʁB����ȍ��x�ȋZ�ʂ��v�������q���C�����A�J���X�͌����ɉ̂����������B�����̓Z���Z�[�V���i���Ȑ��������߁A�J���X�̖��͈��ɂ��ăC�^���A�S�y�A�����Đ��E�ɒm��킽�����̂ł���B
�@�J���X���C�^���A�̍ō���~���m�E�X�J�����Ɂu�m���}�v�������ēo�ꂵ���̂�1952�N1��16���B���̂���4���܂Ō����͍��v9��B���|�I�听�������߁A�J���X�́u�X�J�����̏����v�ƌĂ��悤�ɂȂ�B�����āA1956�N10��29���A�J���X�͂��Ƀj���[���[�N ���g���|���^���̌���̕���ɗ������B���ڂ́u�m���}�v�B�M�������ϏO��16����̃J�[�e���E�R�[���ŃJ���X�Ɋ��т����B10�N�O�̗\���ʂ�A���b�g�̓J���X�ɂЂꕚ�����̂ł���B1952-1956�A���̂����肪�}���A�E�J���X�̐Ⓒ����������������Ȃ��B
�@1958�N1��2���A���[�}�̌���A���ڂ́u�m���}�v�B���̓��̓W�����@���j�E�O�����L �C�^���A�哝�̂��ՐȂ�����ʂȓ��������B
�@�J���X�͂���1�A2�N�A���̕s����i���Ă����B���x���h�N�^�[�E�X�g�b�v�������邱�Ƃ��������Ƃ����B���̓��͓��ɒ��q�������A�Ȃ�Ƃ���1���͉̂��������A�����܂ł����E�������B
�@��1���̃m���}�͓�m���Ƃ��Ĉꑰ�̍��J���i������ŏo�Ԃ͂ق�15���A�L���ȃA���A�u���炩�ȏ��_��v���܂܂��B��2���͕s���ȗ��l�Ɨ��G��O�Ɍ�����Ԃ���C����ƂȂ�A��25���o�����ς�ƂȂ�i�J���X�A�Z���t�B���w���F�~���m�E�X�J������1960�^�����v���j�B�f�l�l��������2���̕����͂邩�Ɍ����������B
�@�J���X�͂����őł����\���o���B�X�^�b�t�͌p����v�����邪�A�J���X�͎���Ȃ������B�N�����Ă��悤���A�̂��Ȃ����͉̂̂��Ȃ��B�A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă͂ނ��됽���Ȕ��f�������Ǝv���B�����͒��~�B�������Ȃ���}�X�R�~�͗e�͂Ȃ������B�u�C�܂���A�킪�܂܁A����B�哝�̂ɂ����v�Ɣ��𗁂т���B���ɂ͑S�C�^���A�̉̌��ꂩ��{�C�R�b�g����Ă��܂��̂ł���B
�@���̓��́u�m���}�v���N�_�ɁA�J���X�̃I�y���������́A���̐����Ƃ����܂��āi�I�i�V�X�ւ̌X�|���d�Ȃ��āj�}���Ɍ����B��1959�N����͔N�Ԉꌅ�ɗ�������ł��܂��B�����̎�������A�S������1948-1958���������Ƃ������Ă���B�Ȃ�Ƌ͂�10�N�B�I�y���̎�Ƃ��Ĉٗ�̒Z���������B
�@�J���X�̐����́u�m���}�v�Ɏn�܂�u�m���}�v�ŏI��������ƂɂȂ�B�J���X�Ƃ����m���}�B�m���}�Ƃ����J���X�B�u�m���}�v�����s���o��DIVA�}���A�E�J���X�̃I�y���l���ɂ����鋆�ɂ̃��p�[�g���[�������̂ł���B
���Q�l������
KAWADE�����b�N�u�}���A�E�J���X�v�i�͏o���[�V�Ёj
�ŐV���ȉ���S�W��20���̌��V�i���y�V�F�Ёj
CD�x�b���[�j��ȁF�̌��u�m���}�v�S�ȁi�J���X�A�Z���t�B���F�~���m�E�X�J�����nj��y�c���j
CD�}���A�E�J���X�u�i���̃f�B�[���@�v�i����EMI�j
DVD�f��u�}���A�E�J���X �Ō�̗��v�i2005�Ɂj
�U�E�v���t�@�C���[�u�}���A�E�J���X�v�ҁiNHK-BSP 2015.12.12���f�j
2021.12.18 (�y) Come Come Everybody ���烋�C�E�A�[���X�g�����O���v��
�@���ݕ��f����NHK���h���́uCome Come Everybody�v�B���̃^�C�g���A�I�풼�ォ��n�܂���NHK���W�I�u�p��u���v�̃e�[�}�ȂŁA���w�u�؏鎛�̒K�₵�v�̉����p��łł���B���̂̍쎌�͖���J��ō�Ȃ͒��R�W���B�̗w�Ȃ̌����̈�ȁu�D�����S�v�̃R���r���B�u�؏鎛�̒K�₵�v�̒��Łu������� ������� �a������ɕ�����ȁv�Ƃ�����߂����邪�A����̂���M�����������B������ȂƂ�������ɂ͘a���Ɛ���Ă��邱�ƂɂȂ�B����키�̂��낤���H ���ꂪ����ƍŋߋC���t�����B�키����͘a���̒@���؋����ƁB������u������̗F������|���|�R�|���m�|���v�Ȃ̂��B�a���̖؋�VS�K�̕��ہB�������߃h��������ł���B�܂��A����͖��ʘb�B����}�����B �@���h���̕���͑����m�푈�^�������̉��R�B�㔒�ΖG��������q���C���̈��q�������̕v�ƂȂ�w�����ɘA��Ă����Ă�������i���X�̖��O���uDIPPER MOUTH BLUES�v�������B�h�T�b�`���g ���C�E�A�[���X�g�����O�ŏ����̏d�v�Ȃ̃^�C�g�����X���ɂȂ��Ă���B�ނ̃i���[�V��������3���g�A���o���u���y�����`�v�̑�1�Ȃ����́uDipper Mouth Blues�v�ŁA�����Ń��C�͂���ȕ��Ɍ���Ă���B�@
�@���h���̕���͑����m�푈�^�������̉��R�B�㔒�ΖG��������q���C���̈��q�������̕v�ƂȂ�w�����ɘA��Ă����Ă�������i���X�̖��O���uDIPPER MOUTH BLUES�v�������B�h�T�b�`���g ���C�E�A�[���X�g�����O�ŏ����̏d�v�Ȃ̃^�C�g�����X���ɂȂ��Ă���B�ނ̃i���[�V��������3���g�A���o���u���y�����`�v�̑�1�Ȃ����́uDipper Mouth Blues�v�ŁA�����Ń��C�͂���ȕ��Ɍ���Ă���B�@
�������y���n�߂��̂̓j���[�I�����Y�B�����ŏo������̂�����̎t �h�p�p�E�W���[�g �L���O�E�I�����@�[�ł��B�ނ����͎��̗F�ł���A�t�ł���A�e���͂ł���A�̑�ȃN���G�C�^�[�ł����B���͔ނ̃o���h�ŃZ�J���h�E�R���l�b�g�𐁂��Ă��܂����B�t�@�[�X�g�͂������p�p�E�W���[�B���̂���̑�\�Ȃ��uDipper Mouth Blues�v�BDipper Mouth�̓p�p�E�W���[�����ɂ����������ł��B
 �@�i���X DIPPER MOUTH BLUES �ŗ���Ă����̂��T�b�`���́u���邢�\�ʂ�� On The Sunny Side Of The Street�v�������B���q�͂���ɂ������薣�����Ă��܂��̂ł���B���̋ȁA�T�b�`���ɂ͕�����̘^��������B�N�㏇�ɗ�L���Ă������B
�@�i���X DIPPER MOUTH BLUES �ŗ���Ă����̂��T�b�`���́u���邢�\�ʂ�� On The Sunny Side Of The Street�v�������B���q�͂���ɂ������薣�����Ă��܂��̂ł���B���̋ȁA�T�b�`���ɂ͕�����̘^��������B�N�㏇�ɗ�L���Ă������B�@�@�@ 1934.11.7 �p��
�@�@�A 1937.11.15 ���T���W�F���X
�@�@�B 1947. 5.17 �^�E���E�z�[��NY
�@�@�C 1947.11.30 �{�X�g���E�V���t�H�j�[�E�z�[��
�@�@�D 1956.12.11 �j���[���[�N
�@�B�ƇC���R���T�[�g�E���C�u�A���̓X�^�W�I�^���ł���B�D�́u���y�����`�v�Ɏ��^����Ă��邪�A�����ł̃T�b�`���̃i���[�V�����͉��L�̒ʂ�ł���B
1934�N�A��x�ڂɓn�������Ƃ��A10���Ƀp���Ř^���Z�b�V���������܂����B���̓���1�Ȃ��A2�ʂ��g�����{�̒����̃��@�[�W�����ŁA�u���邢�\�ʂ�Łv�ł��B�@�i���[�V�����ƃf�[�^�������ɂ���Ă��邪�A����͂��قNjC�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�{�l�������̒a������1900�N7��4���Ǝv������ł������A����1901�N8��4�������� �Ƃ����b������̂�����B�v�́A�u���邢�\�ʂ�Łv�̍ŏ��̘^���́A�p���Ō��n�̃~���[�W�V�����ƁA1934�N�H�ɍs��ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
 �@�B�ƇC�͂ǂ�������C�u�^���������t�͑ΏƓI�B�B�^�E���E�z�[���́A�����e���|�ɏ�����T�b�`���̖���������̂��������́B�C�͈�]���ăX���[�ȃe���|�ŏ�L���ȉ̏���tp�\��������B�W���b�N�E�e�B�[�K�[�f���itb�j�̟������C�����Ղ�̃I�u���K�[�g�ƃ����E�ȃ\��������Ȃ��B�ǂ�����f���炵�����t�ł���B���̑Δ�A���̊Ԃ킸�����N�]�B���̃T�b�`���A���̕\���͂Ƃ����ׂ����B
�@�B�ƇC�͂ǂ�������C�u�^���������t�͑ΏƓI�B�B�^�E���E�z�[���́A�����e���|�ɏ�����T�b�`���̖���������̂��������́B�C�͈�]���ăX���[�ȃe���|�ŏ�L���ȉ̏���tp�\��������B�W���b�N�E�e�B�[�K�[�f���itb�j�̟������C�����Ղ�̃I�u���K�[�g�ƃ����E�ȃ\��������Ȃ��B�ǂ�����f���炵�����t�ł���B���̑Δ�A���̊Ԃ킸�����N�]�B���̃T�b�`���A���̕\���͂Ƃ����ׂ����B�@���h���Ɏg���Ă��鉹�͇@��1934�N�p���^�����B�T�E���h�͓������s��n�߂��X�C���O�E�W���Y�̍��肪����B�q���C���̈��q�́A�u���邢�\�ʂ�Łv�̃����f�B�[���������݂Ȃ���A���ׂƂ��������A���邭�͋��������Ă䂭���ƂɂȂ�B�펀�����v�����t�����킪�q ���C�����Ǝ����荇���ā`�Y�݂ȂU�蕥���� �܂��͕����o���� ���邢�\�ʂ�ւƁE�E�E�E�E�B
�@�u���邢�\�ʂ�Łv�̓T�b�`���ȊO�ɂ��삵�����̘^��������B����Ȓ��ŁA�䂪�W���Y�F�A����A�t����l�̂��C�ɓ���́H
�@�@MR. Brownie K�F���C�I�l���E�n���v�g���y�c1937.4.26�@�j���[���[�N�^��
�@�@MR. Duke N�F�f���[�N�E�G�����g���E�I�[�P�X�g��1963.2.1 �p�� �I�����s�A����̃��C�u�^��
�@���R�ɂ��W���j�[�E�z�b�W�X�������ŃA���g�T�b�N�X�̖��Z������B�y�����x�̑O�ҁA�����^���Ȍ�҂ƈقȂ���������̂�����̏��낤�B
 �@11��20���A�u���̑f���炵�����E�`���f�Ɠ������W���Y�̐��n�v�Ƒ肷��h�L�������^���[�ԑg��NHK�ŕ��f���ꂽ�B�ԑg�́A�W���Y�E�N���u�̖���u���B���b�W�E���@���K�[�h�v���R���i�Ђ����z����18�����Ԃ�ɍĊJ�������Ƃ������Ă����B�����Ă��̊ԁA�p���f�~�b�N�ɂ���đ���Ȕ�Q�������j���[���[�N�ł́A�����A���ʂ����債���f���[�܂��Ă����� �ƌ���Ă����B
�@11��20���A�u���̑f���炵�����E�`���f�Ɠ������W���Y�̐��n�v�Ƒ肷��h�L�������^���[�ԑg��NHK�ŕ��f���ꂽ�B�ԑg�́A�W���Y�E�N���u�̖���u���B���b�W�E���@���K�[�h�v���R���i�Ђ����z����18�����Ԃ�ɍĊJ�������Ƃ������Ă����B�����Ă��̊ԁA�p���f�~�b�N�ɂ���đ���Ȕ�Q�������j���[���[�N�ł́A�����A���ʂ����債���f���[�܂��Ă����� �ƌ���Ă����B�@�O���~�[�܃g�����y�b�^�[ �L�[�����E�n�����h�́A���l�Ƃ������Ƃ����Œ킪���݂̌��^���������A�j���[���[�N�ݏZ�̓��{�l�s�A�j�X�g�C���Ђ͒����l�ƊԈႦ���Ė\�s�����Ƃ����B
�@����Ȓ��A�s������������~���[�W�V�����������H�㓙�ł悭���t�����̂����C�E�A�[���X�g�����O�́u���̑f���炵�����E What A Wonderful World�v�������B���܂Ȃ��u���̑f���炵�����E�v�Ȃ̂��H
�@���C�E�A�[���X�g�����O�̉̂��u���̑f���炵�����E�v�̖`���̐����́u���炫�琯�v�Ƃ�������B�S�҂ɂ킽��ω��L���͊F���A�����K�݂̂Ő��藧���Ă���B�u���[�m�[�g�̌��Ђ��Ȃ��B���ɃV���v���Ŗ����ȃ����f�B�[�E���C���ł���B����ɃT�b�`���̂��킪�ꐺ�����B
�̖X���G�� �Ԃ��o�����炭�@���ƌN�̂��߂��@�f���炵�����E�Ƃ͓��ʂȐ��E�ł͂Ȃ�����ӂꂽ����̂��Ƃ��B���ʂ͂���Ȃ��A������O����������B�T�b�`���͂����̂��F��B�p���f�~�b�N�̍��A������O������ꂽ�B�����炱���A�T�b�`���́u���̑f���炵�����E�v���S�ɋ����̂��낤�B
����┒���_�� ���Ԃ͋P���j���ƂȂ� ��͐_���Ȃ��̂ƂȂ�
�Ԃ�����̋����������� �F�l�����́u�����������H�v�ƈ��肷��
����Ȍ��i�� ���͈�l�v���@�Ȃ�Ă��炵�����E�Ȃ�
�@�u���̑f���炵�����E�v�������[�X���ꂽ�̂�1967�N�B�A�����J�A���ׂ̎���ł���B�x�g�i���푈�͊g��̈�r��H��A�������@�����������Ƃ͂������ʂ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B���N�ɂ̓L���O�q�t���ÎE����Ă��܂��B���C�̃��R�[�h���ABC�̎В������[�E�j���[�g���͂��̉̂��D�܂��A���̂��ߐ�`�s�ׂ͈�؍s���Ȃ������Ƃ����B����́A�x�g�i���푈��簐i����W�����\�������ւ̜u�x�� �Ƃ�����ꂽ�B���ʁA�C�M���X�ł�1�ʂɋP�����A�����J�ł͕s���ɏI���B
 �@1987�N�A�f��u�O�b�h�E���[�j���O�A�x�g�i���v�����J�����B���r���E�E�B���A���Y������DJ�G�C�h���A���E�N�����i�E�A���x�g�i���ɕ����A�O���̕��m��Ɠ��̃g�[�N�ňԖ₷�镨�ꂾ�B
�@1987�N�A�f��u�O�b�h�E���[�j���O�A�x�g�i���v�����J�����B���r���E�E�B���A���Y������DJ�G�C�h���A���E�N�����i�E�A���x�g�i���ɕ����A�O���̕��m��Ɠ��̃g�[�N�ňԖ₷�镨�ꂾ�B�@���˖C�̂悤�ȋ���g�[�N�ł����Ȃ蕺�m�̐S��h�݂͂ɂ����N�����i�E�A���������A������̕����ŁA�R�����\���ւ����j���[�X������ׂ��Ă��܂��B�^�������Ƃ����W���[�i���X�g���̂Ȃ���Ƃ������̂����A�R�͊댯�l���Ƃ݂Ȃ��č~�����Ă��܂��B�킸��5�����̔C���B�������m�����C�Â����������̃N�����i�E�A�ƋK����D�悷��R�̑Η��̋����������������B
�@�N�����i�E�A�͍Ō�̕����Łu���̑f���炵�����E�v��I�ԁB�����̃x�g�i���ɃT�b�`���̉̂������B�X�N���[���ɂ́A�}�C�N�Ɍ�����DJ�����]�A���m���悹���ČR�̃g���b�N�`�x�g�i���̔��������R�`�c�����i�`���a�Ȑl�X�̕�炵�`����ČR�̔�s�@�`�R����Ɖ��`�������Ԏq�������`�R�ɒǂ����Ă��閯�O�`�Q�����Ɍ˘f�����m�������̉f�����f���o�����B�T�b�`���̉̐����o�b�N�ɉf���o���ꂽ���̌i�F�������N�����i�E�A�ƑO���̕��m�̋��ɋ��ʂɕ������̂������͂����B�Ȃ��I����āA�u���C�E�A�[���X�g�����O�A�̑�ȃT�b�`���v�ƃN�����i�E�A�����߂�B���ꂪ�ނ̍Ō�̌��t�������B
�@���̉f�悪���������ŁA�u���̑f���炵�����E�v�̓A�����J�őh�������C�E�A�[���X�g�����O�ő�̃q�b�g�ƂȂ����B����������20�N��̂��Ƃł���B
�@�W���Y�̐��E�ɍ����C�E�A�[���X�g�����O�̌��т͌v��m��Ȃ����̂�����B�قƂ�ǂ̃W���Y�E�g�����y�b�^�[�ɗ^�����t�@��̉e���B�W���Y�E���H�[�J���ɂ�����X�L���b�g�̑n�n�ƈ����Ƃ����s�����̊m���B�W���Y�̌|�p���Ƒ�O���Ɋ�^�����̑�ȃN���G�C�^�[�ł���H��̃G���^�[�e�C�i�[�B�܂��Ɂg�W���Y�̉��l�h�ƌĂԂɂӂ��킵���A�[�e�B�X�g�������B
�@1950�N��A�A�����J�̓W���Y�����̓Ǝ��̕����Ƃ��Đ��E�ɃA�s�[�����n�߂��B����̓A�����J���f���鎩�R�Ɩ����`�W�Ԃ̃c�[���ł��������B���ɂ͔e���ւ̖�]�ƍ��ʂ̈ӎ�����߂B���C�E�A�[���X�g�����O�́A����ȍ��Ƃ̎v�f�����m�̏�ŁA�W���Y�e�P��g�Ƃ��Ă̖�����S�������B���ɖ����Ɣ߈����߂Ȃ�����A����Ȃ��Ƃ͂����тɂ��o�����ɁA�Ђ����疾�邭�͋������y�𑗂�o���������̂ł���B�����āA���E�͔ނƔނ̉��y���������B
�@�Ō�ɁA�W���Y�̂�����l�̋��l�f���[�N�E�G�����g���̌��t�������Ē��߂����Ǝv���B��l���c������i�̃R���{���[�V�����u�\���`���[�h�v���Ȃ���E�E�E�E�E�B
���C�E�A�[���X�g�����O�̓W���Y�̏k�}�ł�������������������葱���邾�낤�B�킽���͔ނ������������h�������B���C�͕n�R�ɐ��܂�������ɂȂ��Ď��B�����Ĉꐶ�U�A�����l�Ƃ��ď����Ȃ������B�@�{���������ɂ�����A����Ȃ������Ƃ����͂������������A�O�o�AMR. Brownie K �� MR. Duke N �����ɍő勉�̎ӈӂ�����܂��B
���Q�l������
�u���C�E�A�[���X�g�����O�@���y�����`�v 3���gCD
�f��u�O�b�h�E���[�j���O�A�x�g�i���v DVD
A��Ԃōs�����`�f���[�N�E�G�����g�����`�i�����Ёj
Louis Armstrong�`���a120�N �v50�N�ɕ����i�~�Ёj
2021.11.11 (��) MLB�A�����đ�J�ĕ��ɂ��Ďv������
(1)�l�k�a�|�X�g�V�[�Y�����I����� �@11��3���AMLB 2021���[���h�V���[�Y����������B4��2�s�ŃA�X�g���Y��j��`�����s�I���̍��ɂ����̂̓A�g�����^ �u���[�u�X�B26�N�Ԃ�̉h���������B
��O�̃u���[�u�X�̕]���͌����č����͂Ȃ������B������.547�ƒn��D��6�`�[�����̍ʼn��ʁB���Ȃ݂ɍō������̓W���C�A���c��.660�ŁA�������̍���19������B�|�X�g�V�[�Y���̊J�����O�ANHK-BS�u���[�X�|MLB�v�ōs�������[���h�V���[�Y�i�o�`�[���̗\�z���A����҂̍��ؒm�G�����A�E���[�O�̃z���C�g�E�\�b�N�X�ƃi�E���[�O�̃u�����[�Y�A�Q�X�g�̐��M�����A�E���[�O�̃A�X�g���Y�ƃi�E���[�O�̓W���C�A���c�h�W���[�X�i���C���h�J�[�h�j�̏��҂Ƃ�������B���҂Ƃ��u���[�u�X�͖��O�������B
�@11��3���AMLB 2021���[���h�V���[�Y����������B4��2�s�ŃA�X�g���Y��j��`�����s�I���̍��ɂ����̂̓A�g�����^ �u���[�u�X�B26�N�Ԃ�̉h���������B
��O�̃u���[�u�X�̕]���͌����č����͂Ȃ������B������.547�ƒn��D��6�`�[�����̍ʼn��ʁB���Ȃ݂ɍō������̓W���C�A���c��.660�ŁA�������̍���19������B�|�X�g�V�[�Y���̊J�����O�ANHK-BS�u���[�X�|MLB�v�ōs�������[���h�V���[�Y�i�o�`�[���̗\�z���A����҂̍��ؒm�G�����A�E���[�O�̃z���C�g�E�\�b�N�X�ƃi�E���[�O�̃u�����[�Y�A�Q�X�g�̐��M�����A�E���[�O�̃A�X�g���Y�ƃi�E���[�O�̓W���C�A���c�h�W���[�X�i���C���h�J�[�h�j�̏��҂Ƃ�������B���҂Ƃ��u���[�u�X�͖��O�������B�@���[���h�V���[�Y�̓A�E���[�O�̔e�҃q���[�X�g�� �A�X�g���Y�ƃi�E���[�O�̔e�҃A�g�����^ �u���[�u�X�̑ΐ�ƂȂ����킯�����A�Q�[���W�J���s�v�c�������ς��������B
�@��5��̓u���[�u�X��3��1�s�Ɖ���������Ė{���n�g�D���[�C�X�g�p�[�N�ōs��ꂽ�B����u���[�u�X�̍U���łȂ�Ɩ��ۃz�[����������яo���B�u���[�u�X4-0�ƃ��[�h�B������������{���n�ł̖��ۃz�[�������B�����������I���ꂪ���Ղ葛���Ɖ������̂������͂Ȃ��B�Ƃ��낪�����͂킩��Ȃ��B�u���[�u�X �X�j�b�J�[�ḗA���̎����Ō��߂�ׂ����ߑ��߂̎��ł��A�S�Ǎ��r�����[�t�w�̈�p�~���^�[�ɒ]�т��o��Ȃnj�Z���������A9-5�ƃA�X�g���Y�ɋt�]�����������Ă��܂��B�u���[�u�X3��2�s�B�����͑�6��Ɏ����z���ꂽ�B
�@��6��̓A�X�g���Y�̖{���n�q���[�X�g���̃��g�����C�h�p�[�N�Ɉڂ��čs��ꂽ�B�u���[�u�X�̐攭����͑�2��5���_�Ŕs�퓊��ƂȂ��Ă���t���[�h�B����A�X�g���Y�͑�3��A1���_�ɗ}�����K���V�A�B�{���n�Ō��߂���Ȃ������u���[�u�X�Ɩ{���n�ɖ߂ꂽ�A�X�g���Y�B�n�̗��Ɛ��������Đ攭����̍�����A�X�g���Y���L���A3��3�s�Ƃ��đ�7��ɂ��ꍞ�� �Ƃ����؏����������Ǝv��ꂽ�B�������A�t���[�h��1��A1�ۃx�[�X�J�o�[�ɓ������Ƃ��A�Ŏґ��҂ɑ�������ɓ��܂�ĕ������Ă��܂��B�Ƃ��낪���ʂ�7��0�ƃu���[�u�X�̈����B4��2�s�Ń��[���h�V���[�Y�𐧂����B���ƂقǍ��l�ɏ����Ƃ������̂͂킩��Ȃ��B
�@�l�I�ɂ́A���q�̂������N�싅�`�[���̖��O���u�z�����u���[�u�X�v���������̂�����A���̌��ʂɂ܂��͖������Ă���B
�@MLB���I��������A���{�v���싅�̓|�X�g�V�[�Y���̑����ɂ���B�N���C�}�b�N�X�V���[�Y�ȂǂƑ傻���ɖ��ł��Ă͂��邪�A���̎d�g�݁A�Ȃ�Ƃ��s���ȑ㕨�Ȃ̂��B���M�����[�V�[�Y�����I��胊�[�O�D�������܂������ƁA1�ʂ���3�ʂ܂ł�3�`�[���ŕt�������̒Z��������s���B�����V�[�Y�������Č��������Ă���͂��̃`�[�����m�����߂ē��{�V���[�Y�ւ̏o�ꌠ�𑈂��̂ł���B3�ʂ̃`�[�����A1�ʂ̃`�[���ƁA�Ⴆ�A10���Q�[������Ă��Ă��A���[�O��\�`���{��̃`�����X������Ƃ������Ƃ��B����͂ǂ��l���Ă����������B���{��ƃ��[�O�`�����s�I�����ʂƂ��������ۂ�����܂ʼn��x�����o���Ă���B
�@�ł́A�Ȃ�����Ȃ������Ȏd�g�݂����݂���̂��B���R�͂�����B�o�ϗD��A�ׂ��邩��ł���B�N���C�}�b�N�X�V���[�Y�͍Œ�10�ő�18���̎���������B���̎��v�͑傫���B�o�ς̂��߂ɔ�������܂���ʂ�B�������̓��{�̏k�}������悤�ȋC������B
�@����Ɉ��������AMLB�̃��J�j�Y���͋��ʂ��Ă���B�A�����J�����[�O�ƃi�V���i�����[�O��2���[�O���B1�̃��[�O�͓��E���E��3�n��Ɋe5�`�[����15�`�[���ō\�������B���M�����[�V�[�Y��162�������I���āA�n��ʂɏ���1�ʂ̃`�[�����n��D���`�[���ƂȂ�B�{���Ƃ��ă��C���h�J�[�h�Ƃ����V�X�e��������A����̓��[�O�D���ȊO�̃`�[���ŏ���1�ʂ�2�ʂ��ꔭ�����Ō��������n��V���[�Y�ɗՂށB�n��D���̏���1�ʃ`�[���ƃ��C���h�J�[�h�����オ��`�[���A�n��D���̏���2�ʂ�3�ʂ̃`�[�������������s���A���ғ��m�̌�����ŏ������`�[�������[�O�`�����s�I���ƂȂ�B
�@���N�̃i�V���i�����[�O���ɂƂ�B���n��D���E����3�ʁi.547�j�̃u���[�u�X�ƒ��n��D���E����2�ʁi.586�j�̃u�����[�Y�ň�R�B���n��D���E����1�ʁi.660�j�̃W���C�A���c�ƃ��C���h�J�[�h�ŏ����オ�����h�W���[�X�ň�R�B�������������オ�����u���[�u�X�ƃh�W���[�X��������킢�������u���[�u�X���i�V���i�����[�O�̃`�����s�I���ƂȂ����@�Ƃ�������B
�@�u���[�u�X�́A�A�����J�����[�O�E�`�����s�I�� �A�X�g���Y�ƃ��[���h�V���[�Y�őΌ��B���ʁA�u���[�u�X���A�X�g���Y��j�胏�[���h�`�����s�I���ɋP���� �Ƃ����킯�ł���B�܂�A���̕����Ȃ烊�[�O�`�����s�I���ƃ��[���h�`�����s�I�����Ⴄ �ȂǂƂ��������͐����Ȃ��B���Ɍ����Ȏd�g�݂ł���B
�@�Ȃ�A���{�͂ǂ�����ׂ����B������MLB�ɕ키���Ƃł���B���݂̓Z�p�����[�O�e6�`�[���A�v12�`�[���ō\������Ă���B������A�P���[�O��4�`�[������2�n�� �v8�`�[���A�����[�O16�`�[���\���ɕς���B�|�X�g�V�[�Y���́A���M�����[�V�[�Y���̒n��D���`�[�����m�����[�O�`�����s�I���𑈂��A�����オ���������[�O�̃`�����s�I�����m�����{�V���[�Y��킢���{������߂�̂ł���B��������� �n��V���[�Y�`���[�O�`�����s�I���V�b�v�`���{�V���[�Y�̗��ꂪ�܂Ƃ��ɂȂ�A���[�O�`�����s�I���Ɠ��{�ꂪ�Ⴄ�Ƃ����������N����Ȃ��B
�@4�`�[���𑝂₷�̂͗e�Ղł͂Ȃ���������Ȃ��B�����A2004�N�A�u�������I�肪�E�E�E�E�v�Ƌ��E�̃h���ɓłÂ���1���[�O���ڍs�̊�@�ɎN����Ȃ���A�y�V�̐V�K�Q���ŏ��z�������{�v���싅�E�ł͂Ȃ����B����Ăł��Ȃ��͂����Ȃ��B���������݁A���{�ɂ́A�k�C���A�����{�A���A�l���A��B��5�̓Ɨ����[�O������A���v25�`�[�����������Ă���B�������ՂɐV���ȃv���싅�`�[�����������̂��B
�@�Ⴆ�A����Ƀ[���R�[�W�}�C���[�Y�A�É��Ƀ`���b�L���[�Y�A�l���ɃR���s���t�l�t�l�A�������ɃZ�S�h���Y�Ȃ�Ăǂ����낤�B�����4�`�[���B�n�ӍH�v�A�����ď�M������A�K��������ł���͂��ł���B
(2)��J�ĕ��X�[�p�[�X�^�[
 �@MLB 2021�N�x�ɂ������J�ĕ��̊���͂����܂��������B���ł̓� Two-way Player �Ƃ��ăR���X�^���g�ɃV�[�Y����S�����f���炵�����т��c�����B
�@MLB 2021�N�x�ɂ������J�ĕ��̊���͂����܂��������B���ł̓� Two-way Player �Ƃ��ăR���X�^���g�ɃV�[�Y����S�����f���炵�����т��c�����B�@��J�̂���ȑO���W���[3�N�Ԃ̐��т͂Ƃ����E�E�E�E�E2018�N��22�{�ۑ�-4��2�s�A�I�t�ɂ̓g�~�[�W������p����B2019�N�́i���n�r�������Ȃ���j�ŎҐ���18�{�ۑŁB2020�N�͓��ɖ߂��7�{�ۑ�-0��1�s�ł������B�N�X���~���鐬�тɓ��͖��� �Ƃ̐���������͂��߂�B���ꂪ��]���N�̐��тł���B����́A��p�`���n�r���̐����A�H���Ö@�ɂ��h�{�ʂ̉��P�A�Ȋw�I�g���[�j���O�ɂ��̗͋����A�o�����]�[���Ŗ@�̏K���A�f�W�^���c�[�����g�������X�̃`�F�b�N�Ȃǂ������I�ɋ@�\�������ʂł���B����𐬂��������̂͑�J�̐₦�������S�ƂЂ��ނ��ȓw�͂ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�����쑺����͂��Ă���Ȃ��Ƃ������Ă����u�Y�ꂵ�ݍH�v�����o���͌����Ė��ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��v�B��N���獡�N�ɂ����Ă̑�J�͂��̃X�e�b�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂��ɂǂ�ꂩ��̋t�P�������B
�@�����āA�Y��ĂȂ�Ȃ��͍̂��G����A�C�����y���[�E�~�i�V�A��GM�̑��݂ł���B�u�I�t�V�[�Y���̃V���E�w�C�̓w�͂����āA�O�N�܂ł̃V���E�w�C�E���[����P�p���邱�Ƃɂ����v�ƌ��B�V���E�w�C�E���[���Ƃ́A���S�̑傫�������ێ����邽�߂̃��[���ŁA�o�̑O��͋x�{���ɓ��Ă�Ƃ������̂������B2020�N�̃I�t�V�[�Y���A��J�͑O�q�̔@���g�[�^���ȃg���[�j���O������ɉۂ����s�����B�͈̂���傫���Ȃ��J�͂��A�b�v�����B���ʂ͓���ǂ����ƂɌ����ɂȂ��Ă䂭�B�����ڂ̓�����ɂ����VGM����J�̏펞�o��̉\�������o�����B����ł����̕��S�͏��Ȃ��炸����킯�ŁA����������ł͂Ȃ����K�ʂ̌y���ŕ₤�B���̒ɓ��ӂ����W���[�E�}�h���ē��g�V�V���E�w�C�E���[���h���̗p�B�������ď펞�o����ʂ�������J�́A2021�N�V�[�Y���A�����ׂ����𐋂����̂ł���B
�@������2021�V�[�Y���̓��E��J�ĕ��̎�ȃX�^�b�c���L���Ă������B
���Ŏҁ�
�@�ŗ�.257�@����138�@�{�ۑ�46�@�œ_100�@���_103�@����26
�����聄
�@9��2�s�@������130 1/3�@�D�O�U156
�@�Ŏҁ�����Ƃ��Ă��ꂾ���̐��т��c�����̂̓x�[�u�E���[�X�i1895-1919�j�ȗ��Ƃ����Ă���B�x�[�u�E���[�X��1918�N��11�{�ۑ�-13���B1919�N��29�{�ۑ�-9���Ƃ����L�^���c���Ă���B1920�N����͑ŎҐ��ƂȂ������ߓ��̐��т͂���2�N�Ԃ����ł���B1918�N�ɂ�11�{�Ȃ���{�ۑʼn��ɂȂ��Ă���B���N�̑�J�Ɍ�������̂�����Ƃ�������2�������ɓ͂��Ȃ��������Ƃ��B�������㏇���ɂ������[�X�̋L�^�������ɔ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@����J�̐����Ƃ���͂�����A���͂ł���B���ŗ͂Ər���͖{������������Ƃ���Ă���BMLB�j��A�V�[�Y��50�{�ۑ�-20���ۂ�B�������̂͋͂���3�l�B1955�N�̃E�B���[�E���C�Y�i51�{-24���ہj�A1998�N�̃P���E�O���t�B�[Jr.�i56�{-20���ہj�A2007�N�̃A���b�N�X�E���h���Q�X�i54�{-24���ہj�����ł���B�����ނ�͑ŎҐ��ł���B���ł���Ȃ���ނ�ɔ䌨����46�{-26���ۂ��L�^������J�͏̎^�ɒl����B
�@���Ȃ�ʍU�E���E���O�����̑�J�ĕ����ł��[�I�ɕ\���X�^�b�c������B�N�C���e�B�v��100�ł���B5�̕��傪100����A�����A138���ŁA100�œ_�A103���_�A130 1/3�����A156�D�O�U�B���̋L�^�������̂́A���W���[���[�O118�N�̗��j�ł��A��J�ĕ�������l�ł���B
�@10��26���A���j�Ɋ�����L�^���c����2021�N�̑�J�ĕ��ɑ��āAMLB�R�~�b�V���i�[�́u�R�~�b�V���i�[���ʕ\���v���s�����B
�@���̏܂�MLB�̗��j��h��ւ����I��ɗ^��������̂�����A���N����킯�ł͂Ȃ��B��1���1998�N�A����܂ł̃V�[�Y���E�z�[�������L�^�i61�{�j���鍂�����Ńz�[�����������������}�[�N�E�}�O���C��(70�{)�ƃT�~�[�E�\�[�T(66�{)�ɗ^����ꂽ�B�ȗ��A2632�����A���o��̋L�^��������J���E���v�P���i2001�j�A�N��73�{�̃z�[�������L�^��������o���[�E�{���Y�i2002�j�A7�x�̃T�C�E�����O�܂ɋP�������W���[�E�N�������X�i2004�j�A262�{�̈��ł�����N�ԍő����ł��X�V�����C�`���[�i2005�j�ȂǁA���j��h��ւ����B�X����I��ɗ^�����Ă���B��J���h������MLB�̗��j�ɖ���A�˂����ƂɂȂ�B
�@10��28���A��J��MLB�̌���I�肽�����I�ԁgPlayers Choice Awards�h�̔N�ԍŗD�G�I��ƃA�����J�����[�O�ŗD�G����W��܂��ʂ������B��҂�2004�N�ɃC�`���[����܂��Ă��邪�O�҂͓��{�l����܂ƂȂ�B�V�[�Y�����ꏏ�ɐ����MLB�̈ꗬ�I�肽�����A��J���u2021�N�ł������Ȋ���������I��v�ƔF�߂����ƂɂȂ�B����ȑ僊�[�K�[�����̎^������ׂĂ������B
�@�u����ȃs�b�`���O�ƃo�b�e�B���O�͒N���������Ƃ��Ȃ��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�T�C�E�����O��3�x��܂̖����� �}�b�N�X�E�V���[�U�[
�@�u���g�����[�O�őS�̓v���C����12�̏��N�����̂܂ܑ�l�ɂȂ����悤���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�W���C�A���c�̖��ߎ� �o�X�^�[�E�|�[�W�[
�@�u�����˔\�ƗD�ꂽ�l�i�̎����� �K�����W���[���\����I��ɂȂ�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`��J�ƍŌ�܂Ŗ{�ۑʼn��𑈂��� �u���f�B�~�[���E�Q���[��Jr.
�@�u��ԍD���Ȃ̂͌����Ȏp�� 2�ۃx�[�X�ɂ���ƕK�����A���Ă����̂����ꂵ���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�A�X�g���Y�̏����ȑ�Ŏ҃z�Z�E�A���g�D�[�x
�@�u��J�̃v���C�͗��j�I�u�Ԃ��肾�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�ʎZ310�{�ۑł̌����ŋ��Ŏ� �}�C�N�E�g���E�g
�@�Z�p��т����ł͂Ȃ��A�Q���[��Jr��A���g�D�[�x���̎^���錪�����Ɛl�i����J�̍ۗ����͂̈���B�O���E���h��̃S�~���E���A�Ŏ҂��܂����o�b�g���E���ēn���A�R���̃`�F�b�N�ɏΊ�ʼn�����A�t�@�����O���E���h�ɗ��Ƃ����T���O���X�J�ɓ����Ԃ��A�������Ă��{��Ȃ����X�B���{�I��V�������̋ɒv�B��������肰�Ȃ�����Ă̂���X�}�[�g���B���{�l�Ƃ��Čւ炵������ł���B
�@11��18���ɂ́AMLB2021�N�xMVP�����\�����B�����܂ł̗��ꂩ���J�̎�܂͂قڊԈႢ�Ȃ����낤�B�I�l�ψ��̂ЂƂ�S�ċL�ҋ���L�҃{�[�����h���͂����،�����B�u��J�ɓ��[������B�I�l�͊ȒP�������B���C�o���Ɩڂ����Q���[��Jr.���m���ɗ��h�Ȑ��т��c�������A����͑z��ł����鐔���B���łɂ܂������J�̐����͂܂��ɑO�㖢���B�َ����̐��E���B�I�[���X�^�[�Q�[���ł��A�^�e�B�[�XJr.��Q���[��Jr��̃X�^�[�I�肪��J�ɉ���Ęb�����������Ă����B�T�C�����˂���ꏏ�Ɏʐ^���B��҂������B�I��̊Ԃł���J�͓���̓I�ȂB�Ȃ�Ƃ����Ă��A�w���Ŏ҂Ɠ���ł̏o��Ƃ���84�N�̗��j����I�[���X�^�[�Q�[���̃��[����ς������Ă��܂��̂����甼�[�Șb����Ȃ��B���������ł��\��MVP�ɒl�����v�B���\���y���݂ɑ҂������Ǝv���B
�@���͂�X�[�p�[�X�^�[�����Ƃ����Ă�������J�����A�ނ̌��t���ƍX�Ȃ���҂ɋ����c���ł���B�V�[�Y���I������A��J�͂���Ȍ��t�����ɂ����B
�@�u���N�ł������Ƃ����N�o���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��������B�����ɂƂ��Ă��`�[���ɂƂ��Ă��B���N�̐����͍Œ�C���ƍl�������v�B�ނ͎������g�ɍ��N�ȏ�̐������ۂ��Ă���̂��B
�@���G��J�̈�Ԉ�ۂɎc�����R�����g������B9��26���A���Ă�10���A2�������ƂȂ�ŏI�o���A7��10�D�O�U1���_�̍D���Ȃ���Ő��̉���Ȃ������ł��Ȃ��������Ƃ̉�ł̂��̂ł���B
�G���[���X�̃t�@�������c���̂̕��͋C���D�����B��������ȏ�ɏ��������Ƃ����C�����������B�v���C���[�Ƃ��Ă͂��̕����������Ǝv�����l�͖l�Ōl�Ƃ��Ăǂ��`�[���ɍv���ł��邩���l���Ă�肽���B���N�͊���Ȃ��������A�����Ƃ����Ɗy�����q���q������悤��9�����߂��������B�N���u�n�E�X�̒�������ȉ�b�ł��ӂ��悤��9���ɂȂ邱�Ƃ�����Ă���B�@���̔�������A�u��J�͈ڐЂ�]��ł���v�ȂǂƂ̉������o���B��������͐�ǂ݂ł���B��J�͏�ɁA�l�Ƃ��Ăǂ��`�[���ɍv���ł��邩���l���Ă���B�ŗD��̓`�[���̏������B�u�Q�[���ɏ��ĂĂ悩�����v�̃R�����g�����x���ɂ������Ƃ��낤�B
�@�m���ɂ����Ƌ����`�[���Ɉڂ���̓��̂悤�Ȏ��������̂ɂł�����������Ȃ��B�ł���J�̓G���[���X�Ƃ����`�[�����D���Ȃ̂��B���̃`�[���ł��Ƃ����l���͍��̑�J�ɂ͂Ȃ��Ǝv���B���̃`�[���Ńq���q������悤��9�����߂������[���h�V���[�Y�Ɍ������B���ꂪ��J�̍ő�̖]�݂Ȃ̂ł���B�����̐��т����B
�@2020�N�ɏA�C�����}�h���ēA2021�N�ɏA�C�����~�i�V�A��GM�ɂ��G���[���X�̃`�[�����v�̓X�^�[�g��������肾�B���Ƀ~�i�V�A��GM�͕s�U�������A�g�����^ �u���[�u�X���Č��A���[���h�V���[�Y���e�̓����������҂��B�ނɂ̓G���[���X�̎�_���͂�����ƌ����Ă���͂����B����Ƃ��āA��̑���Ȃ��攭����w�Ǝ�̃����[�t�w�ɑ��āA�⋭���܂ߒ����Ȑ�����}���Ă��邾�낤�B�����ɂ�荡�V�[�Y����_�ɐU�������Ŏ҃g���E�g�������͕��A���đ�J�̌���ł��ƂɂȂ�͂����B�����Ȃ�A��J�̃z�[����������������������ɑ�������������B����̓`�[���̏����ɒ�������B��������|�X�g�V�[�Y���i�o�̉\�����o�Ă���B���[���h�V���[�Y���e�ւ̓����J����Ƃ������̂��B����͎��̑z�������A�~�i�V�A�����}�h���̃G���[���X��]���C���́A��J�𒆐S���Ƃ����`�[������ڎw���Ă���̂ł͂Ȃ��� �Ǝv���B
�@���V�[�Y���A�V���G���[���X�̖��i�Ƃ���Ȃ�i���𐋂�����J�̊�����A�傢�Ɋ��҂��������̂ł���B
�@�����Ă��̓����A��J�ĕ��ɂ͑Ō��O�����ƃT�C�E�����O�܂�W�擾��B�����Ă��炢�����Ǝv���̂ł���B���ꂼ��O���A�싅�I��̌��ʂĂʖ����낤�B�ł��ނȂ����Ă���邩������Ȃ��B����Ȋ��҂�������Ă���鑶�݂���J�ĕ��Ȃ̂ł���B
2021.10.20 (��) �H�Ɏ₵������
�@�}�[���[�Ɂu��n�̉́v�Ƃ��������Ȃ�����B�����Ȃɐ��y����ꂽ�̂̓x�[�g�[���F���́u���v�����߂Ă����A���ꂩ��87�N��Ɋ��������u��n�̉́v�͑S6�y�͂��ׂĐ��y����Ƃ����ِF�̍�i�ł���B�����Ă܂����̍\�������ɋ����[���B�@���͍ŋ߁A�s���ǂƂ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ����A�������s����ł���B11���ɏ��ɓ���A�Q���͂悢���A4�������Ɍ��܂��Ėڂ��o�߂�B���͂�������ŁA���̂��Ƃ܂���������Ȃ��Ȃ�̂ł���B�����łǂ����邩�Ƃ����A��l��X(��)����₱���L�����Ăъo�܂���Ƃ��n�߂�E�E�E�E�E����㑍����b38���B�������A�A�����J�哝��14���B���V�A�̎w����12���B�����̎��6���B�ܗ֊J�Òn32����A�l�k�a�n��ʃ`�[��30�B1950�`70�N��̃��R�[�h���܋�21�ȁB����̓V�c�i�q�B���琹���j16�l�B���쏫�R15�l�B�^�c�\�E�m�A�ېV�\���B���\���O�X�L�[�̑g�ȁu�W����̊G�v��10�ȁB�X���^�i�̑g�ȁu�킪�c���v6�ȓ��X�B�����āA�u��n�̉́v��6�Ȃł���B
�@���̒��ɂ͐��E��Y1154�A�͂Ȃ͂������͉~����11�����Ȃ�Ă����������̂悤�Ȑl������悤�����A����͂���A�������鎖���̉䂪�ËL�͂̌��E30�����肪���傤�ǂ����B
 �@���āA�u��n�̉́vDas Lied von der Erde�ł���B����́u�A���g�A�e�m�[���Ə��Ƒ�I�[�P�X�g���̂��߂̌����ȁv�B�\���͉��L�̒ʂ�B
�@���āA�u��n�̉́vDas Lied von der Erde�ł���B����́u�A���g�A�e�m�[���Ə��Ƒ�I�[�P�X�g���̂��߂̌����ȁv�B�\���͉��L�̒ʂ�B�@�@��1�y�� ��n�̈��D���̂����̉�
�@�@��2�y�� �H�Ɏ₵�����́@
�@�@��3�y�� �t�ɂ���
�@�@��4�y�� ���ɂ���
�@�@��5�y�� �t�ɐ��������
�@�@��6�y�� ����
�@�������܂��͊ۈËL����B���������B�ŏ��̂����͓��ɓ����Ă��邪���̂����Y���B��������̓s�x�ƍ����ēx���ɍ��ݍ��ށB������J��Ԃ��Ă��邤���ɁA���Ƃ��L�����Œ肵�Ă���B�s�����̊m�F��Ƃ͋L���Œ�̋M�d�Ȏ��ԂƂȂ�B�����Ă��鎞�A����A���̕��тɂ͖@����������̂ł́A�ƋC�Â����肷��B
�@��1�y�͂Ƒ�6�y�́B��2�y�͂Ƒ�5�y�́B��3�y�͂Ƒ�4�y�́B���v������7�B�T�C�R���̑Ζʓ��m�̐������Βu�̊W�ɂ���A�ƋC�Â��B��Ȃ��e�m�[���A�����Ȃ��A���g�i���b�]�E�\�v���m�j�������͒j���Ə����̑Βu�ɂ��Ȃ�B
�@1��6�̃L�C�E���[�h�́u��n�verde�B��1�y�͂�erde�̓^�C�g����ɂ���A��6�y�͂ɂ͎��̒��ɂ���B���̑��̊y�͂ɂ�erde�Ƃ�����͈�؏o�Ă��Ȃ��B��2�y�͂Ƒ�5�y�͂́u�H�v�Ɓu�t�v�A�G�ߓ��m���B��3�y�͂Ƒ�4�y�͂́u�t�v�Ɓu���v�ŁA����͎Ⴓ�̏ے��̑Βu���B
�@�����̑Βu�̓o�b�n��m�Ԃɂ�����B�}�[���[�͂����ƈӐ}���ĕ��ׂ��ɈႢ�Ȃ��A�Ɗm�M����B���j��̐l���ƐS���ʂ����悤�ȋC���ɂȂ�B���ꂪ�y�����B�ŋ߂���肵������l���u����Ȃ̈Ӗ����Ȃ��v�Ƌ����̂ŁA�����������ƕt�������Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��Ǝv���𗬂������B
�@�u��n�̉́v�̎��́A�����A�K�N�A�Ѝ_�R�A���ۂ̊��������ł���B�e�L�X�g�́A�W���f�B�b�g�E�S�[�e�B�G��������u�ʏ��v�Ȃǂ���āA�ƌ���n���X�E�x�[�g�Q�́u�����̓J�v�ł���B�}�[���[��������������Ă���B���m���y�Ɠ��m�̎��̗Z���B��ȉƂł����Ďw���ҁB���m�Ɠ��m�̒��ԂɈʒu����`�F�R�̐��܂�B�q���̂��납��S�ɕ��������Ă������Ǝ��̖�聁�����ρB���_���l�ł���Ȃ�����@���ẴL���X�g���k�B�����̓w�������}�[���[�̐��_�̍����ɂ���킯������A�����̑I���̓}�[���[�̕K�R������ �Ƃ����Ă����B
�@�����č��A�G�߂ɂ��Ȃ�ő�2�y�́u�H�Ɏ₵�����́v�i���F�K�N�j���B
�@�@�H���͑����Ώ�ɗN�������@���Ȃׂđ��Ԃ�
�@�@�ǓƂɕ����ꂽ�j��܂��G�炵�@�S�̏H�͉ʂĂ��Ȃ��g�����Ă䂭
 �@�̂̓N���X�^�E���[�g���B�q�̃��b�]�E�\�v���m�A�nj��y�̓N�����y���[�w���̃t�B���n�[���j�Aor�j���[�E�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�ł���B�I�P������N���W�b�g����Ă���̂͘^���̍Œ��i1964-1969�j�ɖ��̂��ς�������炾�낤�B�u�H�Ɏ₵�����́v���ǂ����Ȃ̂��͕s�������A���͓̂����Ȃ̂�����ǂ���ł��������B
�@�̂̓N���X�^�E���[�g���B�q�̃��b�]�E�\�v���m�A�nj��y�̓N�����y���[�w���̃t�B���n�[���j�Aor�j���[�E�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�ł���B�I�P������N���W�b�g����Ă���̂͘^���̍Œ��i1964-1969�j�ɖ��̂��ς�������炾�낤�B�u�H�Ɏ₵�����́v���ǂ����Ȃ̂��͕s�������A���͓̂����Ȃ̂�����ǂ���ł��������B�@���[�g���B�q�̊i���������Ĉ��D��X�����̏��̓}�[���[�̐��E�ςɃV���N�����ĕ���Ȃ��B��Ȃ��̂��e�m�[���A�t���b�c�E�����_�[���q�̔����ƋP������̕\���͂���܂����̖{���ƍ��v���đ��̒ǐ��������Ȃ��B�₦�ԂȂ��ڂ�ς��m��̋N�����A�I�g����e���|�̉��A���k�ɓI�m�ɕ\������N�����y���[�̎w���������Ƃ����ق��͂Ȃ��B�܂��ɎO�ʈ�́A�]�l�ɑウ�����������ł���B
�@NHK�͖��N�H�A�e�[�}�������ĉ��y�ԑg�𑗂�o���B���N�̃e�[�}�̓s�A�m���������B�ł����́A�u�H�̓��̃��B�I�����́E�E�E�E�E�v�ł͂Ȃ�����ǁA�H�͂�͂胔�@�C�I�����������B�Ȃ��Ȃ�A�s�A�m�͉Ăɒ��������Ă��܂����炾�B�ď�͐���������s�A�m���f�R�����B�t�Ƀ��@�C�I�����͒����C���N����Ȃ��B���̎C���͖ҏ��ɂ͂����B������A�H�ɂȂ�ƋC���͈�C�Ƀ��@�C�I�����ɌX���B�Ă̓s�A�m�A�H�̓��@�C�I�������B
�@����9��26���A�]���̐^���q����u����NHK-FM�Ŕ����Ւ��̃��@�C�I�������t�Ȃ̕��������邩�畷���Ă݂āv�Ɠd�b���������B�������̉��l���q���^���q�̕v�N�̏]�o�Ƃ����W�ŘA���������Ƃ����킯���B
�@�܊p�Ȃ̂Ř^�����悤�Ǝv���A�����Ɏ��|����B�G�A�`�F�b�N�́A2015�N9��4���A�}�^�`�b�`��N���́u�����e���F���f�B�F����}���A�̗[�ׂ̋F��v�ȗ������炩�ꂱ��6�N�O�ɂȂ�B�����^�����Y��Ă���B�g���Z�c����������o���Ă��ꂱ�ꕱ���B�~�j�R���|��MD���Z�b�g���I�����͕̂����J�n���O�A���荞�݃Z�[�t�������B���{�̌��㉹�y�ɂ͂ƂĂ��a�����ł��邪�A�{�Ԃ���MD��CD�ւ̃_�r���O�Ȃlj��x�������Ă��邤���ɁA�ƂĂ��e���݂��o���Ă����B
�@�����Ւ��́u���@�C�I�������t�ȁv��2020�N5��30���Ɋ�����������A�Ւ����͍��N2���ɐ����B���N76�B���̍�i�����ł���B
�@3�̊y�͂���Ȃ邪�A��1�y�͂ɂ͂Ђ��ނ��ɉ����Ɍ�������M���A��2�y�͂ɂ͐�捂Ȉ��炬���A��3�y�͂ɂ͍��ׂ�ł��j��m���Ȉӎu���A���X�A�����肷��Ȃ܂��̒��ɑ��Â��Ă���B
�@���t�́A���@�C�I�������Č����q�A�w���͍�Ȏ҂̒�q�E�L��~��B2021�N6��25���ɍs��ꂽ���s�s�����y�c ��657�������t��̃��C�u�^���B���ꂪ���E�������������B
�@�Ւ����̕��͔��������i1911-51�j�Ő����{�̃I�[�P�X�g�������������B��ȉƂƂ��Ă������B�����痷�ւ̉ߍ��ȉ��y�����ő̂��A1951�N�ɑ��E�B���N39�Ƃ����Ⴓ�������B���̂Ƃ����j�Ւ���6�A���ݎw���҂Ƃ��Ċ������̎��j������3�������B���ƂȂ����u�t���[�g���t�ȁv�́A���[���b�p�̗l���̒��ɘa�̐��_���I�݂ɐD�荞�܂�A���鐶�C���V����̌ۓ������������閼�Ȃł���B���q�̋��t�Ȃ̖��삪�݂��̈��ƂȂ����̂��s�v�c�ȕ����ł���B
 �@�^�������u���@�C�I�������t�ȁv��CD-R�͓Ւ����̉��l���q����ɂ����肵���B�u�^�����ł��Ȃ������̂Ŗ{���Ɋ����イ�������܂��v�Ƃ̂��Ԏ��Ƌ��ɁA���]�E�\�v���m�̎�Ƃ��ĕv�N�Ւ����̃s�A�m���t�Ř^������CD�u�����Ւ��@�̋Ȃ̐��E�v�i2010�N�^���A�i�~�E���R�[�h�j�������Ă����B�W���P�b�g�ɂ͉̂���̈��q���ƍ�Ȏ҂Ńs�A�m�̓Ւ����̃c�[�V���b�g�ʐ^���g���Ă���B�W���P�b�g������CD���ƁA���v�Ȃ̑f�G�ȊW���`���A�܂������S���܂�v��������B
�@�^�������u���@�C�I�������t�ȁv��CD-R�͓Ւ����̉��l���q����ɂ����肵���B�u�^�����ł��Ȃ������̂Ŗ{���Ɋ����イ�������܂��v�Ƃ̂��Ԏ��Ƌ��ɁA���]�E�\�v���m�̎�Ƃ��ĕv�N�Ւ����̃s�A�m���t�Ř^������CD�u�����Ւ��@�̋Ȃ̐��E�v�i2010�N�^���A�i�~�E���R�[�h�j�������Ă����B�W���P�b�g�ɂ͉̂���̈��q���ƍ�Ȏ҂Ńs�A�m�̓Ւ����̃c�[�V���b�g�ʐ^���g���Ă���B�W���P�b�g������CD���ƁA���v�Ȃ̑f�G�ȊW���`���A�܂������S���܂�v��������B�@�����Ւ��̓p���������y�@�Ō��r��ς�ł���B�t�������̂̓��[���X�E�f�������t���i1902-86�j�B���������ɂ͉��×����t�������I���r�G�E���V�A���i1908-92�j�������B�Ւ��������V�A���ł͂Ȃ��f�������t����I�̂͂ނׂȂ邩�ȂƎv���B���×���NHK�u�f���̐��E�v�̃e�[�}����`���錀���ƓՒ���i�̐������̑Δ䂪��������������B
�@�f�������t���͒��ڃt�H�[�����狳�����Ă͂��Ȃ����A�݂��́u���N�C�G���v�̑��������狤���̈ӎ��͂������͂��ł���B�Ւ���i�̐������̓f�������t����ʂ��ăt�H�[���Ɍq�����Ă���Ɗ�����B
�@CD�ɒ��������Ւ��̉̋Ȃɂ́A�������ꂽ�t�����X�I�����V�Y���A�㎿�Ȕ����A�ߓx���錀���A�c�ɏh��D�����ƔM���A����ɂ͓��{�̃e�C�X�g���o�����X�悭���a���Ă���B�����Ă���͔��������̊i�����������ȉ��y���ƍ��v������̂��낤�B�������q�̉̏��͂��݂��ƂȂ��̂��B���ł��u�H�̓��v�u���܂܂�v�u�Ę��v�̉̏��ɂ͎��ւ̋������ЂƂ��틭����������B
�@�]�k�����A���ݕ��f����NHK��̓h���}�u�V���Ղ��v�œc�Ӑ��ꕯ��������Ւ��͍�ȉƔ����Ւ��̑]�c���ł���B
�@�R���i����U�����������Ɍ����鍡�H�͍�N���͂邩�ɋC���������B�F�B�̗ւ����X�ɕ���������B����͋v�X�ɉ�����F�l����N�����y���[��CD�W�������������B�uOTTO KLEMPER conducts CONCERTGEBOUW ORCHESTRA�v�Ƒ肷��N�����y���[�w���F�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c1947-1961�̃R���T�[�g�E���C�u24���g�Ƃ����c��ȃR���N�V�����ł���B�����B�����A���̓N�����y���[�̑�t�@���ł���B��n�߂�1947�^���̃u���b�N�i�[�̑�4�����Ȃ��Ă݂�B���C�u�̔M�C���q�V�q�V�Ɠ`����Ă���B�X�^�W�I�^���Ƃ͂܂������Ⴄ�N�����y���[�̂�����̊������悤���B�ŐV�}�X�^�����O�ɂ��SACD�n�C�u���b�g�̉��������B���ꂩ��N�����y���[�|�p�̐[���ȐX�ɓ��ݓ��邱�ƂɂȂ�B�܂��Ƀ��N���N���S�J�B�H�Ɏ₵���Ȃ�ʏH�Ɋy�������� �ł���B�[�ӁI
2021.09.25 (��) �q�[ ���c�r��搶�`���� �W�i1964�N���w�ETp�j
�@�O��A���c�r��搶�̈ӌ������f�ڂ��܂������A����͂���ɑ��鎄�̏������q�ׂ����Ă��������܂��B �@�u�ꋿ�vNo.21�Ɂu���[�c�@���g ���N�C�G�� �j�Z�� KV626�`���̕�M�������߂����āv���f�ڂ���܂����B�����No.20�Ɏ����������u���[�c�@���g ���N�C�G�� �ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������v�ɑ��邲�ӌ����ł����B���҂͊��c�r��i1954�N���w�AVa�j�Ƃ���܂��B�ǂ����ŕ����������O���� �Ǝv���߂��炷�ƁA�͂��ƋC�Â��܂����B�Ȃ�ƁA�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�i�u�k�Ќ���V���j�̒��҂̕��ł͂���܂��B���c���������ꋴ��w�̑��Ɛ��ł��邱�Ƃ͂��̖{�̃v���t�B�[�����瑶���グ�Ă���܂������A���̓x�I�[�P�X�g���̐�y�ł����邱�Ƃ�m��A�V���Ȋ����̎v���ɋ���Ă���܂��B�����āA���̗����ȋC��������A���ꂩ�犝�c�搶�ƌĂ��Ă����������������܂��B�Ƃɂ����A�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�͎��ɂƂ��Ă����ւ�ɈӋ`�[�����Ȃ̂ł���܂��B
�@�u�ꋿ�vNo.21�Ɂu���[�c�@���g ���N�C�G�� �j�Z�� KV626�`���̕�M�������߂����āv���f�ڂ���܂����B�����No.20�Ɏ����������u���[�c�@���g ���N�C�G�� �ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������v�ɑ��邲�ӌ����ł����B���҂͊��c�r��i1954�N���w�AVa�j�Ƃ���܂��B�ǂ����ŕ����������O���� �Ǝv���߂��炷�ƁA�͂��ƋC�Â��܂����B�Ȃ�ƁA�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�i�u�k�Ќ���V���j�̒��҂̕��ł͂���܂��B���c���������ꋴ��w�̑��Ɛ��ł��邱�Ƃ͂��̖{�̃v���t�B�[�����瑶���グ�Ă���܂������A���̓x�I�[�P�X�g���̐�y�ł����邱�Ƃ�m��A�V���Ȋ����̎v���ɋ���Ă���܂��B�����āA���̗����ȋC��������A���ꂩ�犝�c�搶�ƌĂ��Ă����������������܂��B�Ƃɂ����A�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�͎��ɂƂ��Ă����ւ�ɈӋ`�[�����Ȃ̂ł���܂��B�@�����u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v��ǂ̂�2013�N��1�����ŁA���̖{����͗l�X�Ȃ��Ƃ������܂����B�H���A���[�c�@���g��i�̒��ɂ́A���C�X�����[�̃V���{���Y�����킩��₷������Ă��邱�ƁB�Ⴆ�A���y�l�d�t�� �j�Z�� K421�i�n�C�h���E�Z�b�g��2�ԁj�I�y�͂ɂ������1���@�C�I�����ɂ��˂�3��@�����Y���B�\�i�^ �σ�����K454�I�y�ׂ̗͂荇�������X���[�Ōq����F���̌`�B���y�l�d�t�� �n���� K465(�n�C�h���E�Z�b�g��6��)�u�s���a���v��1�y�͂ɂ����āA�s���a�̏��t���啔�ɗ��ꍞ���ƁA���C�X�����[�̌��̏ے��ł���n�����ɓ]���邱�ƁA���X�B�����̐�����ǂ��Ɖ��߂Ċy�Ȃ��ƁA���C�X�����[�ɉ����O��̃��[�c�@���g�̐S�����ȑO���͂邩�ɂ�������Ƌ��ɔ����Ă��܂��B
�@����ɂ܂��A���c�搶�͂����q�ׂ��Ă��܂��B�u���[�c�@���g�̉��y�͎��Ȃ̏�C�����A���邢�͊O�E�̎��Ԃ⌻�ۂڈӖ�������`�ʂ����肷����̂ł͂Ȃ��B�������Ȃ���A���[�c�@���g�̉��y������̊�����킩��₷���\�����邱�Ƃɂ����čۗ����Ă��邱�Ƃ͎����ł���B�����łȂ���A���[�c�@���g�̃I�y���������ł�����قǎx������邱�Ƃ��Ȃ������ł��낤�v�B���[�c�@���g�̉��y�̓�����˂������͂��錩���ł��B
�@����ɂ��܂��āA������ۂɎc�����̂́A���̖{�́u���Ƃ����v�ł����B����́A�u���{�l�̃��[�c�@���g�D���͂悭�����Ă��邵�A���{�l�ɂ�鏑�����������B����A�������̖��Ȃ����������Ƃ��ł��āA���������̊��S���o����B���A�Ђ邪�����āA���[�c�@���g���g�͉ʂ����ē��{����{�l��m���Ă������ǂ����ƂȂ�ƁA����͐S���Ȃ��v�Ƃ��������o���Ŏn�܂��Ă��܂����B
�@���͎��A���̓����A��̉����𗧂ĂĂ���܂����B����́u���[�c�@���g�̉̌��w���J�x�̎�l���^�~�[�m�͍��R�E�߂ł͂Ȃ��낤���v�Ƃ������̂ł��B�u���J�v�̑�{�̖`���Ɂg���{�̎�߂𒅂��Ƃ��鍑�̉��q����ւɒǂ��āE�E�E�E�E�h�Ƃ���܂��B�Ȃ����{�̎�߂Ȃ̂��낤���B���[�c�@���g�͓��{�̂��Ƃ�m���Ă����̂��낤���H�Ƒf�p�ȋ^�₪�N���܂����B���{�̉��y���D�ƂɂƂ��ċ����[���͂��̃e�[�}���A����܂łقƂ�ǘ_�����Ă��Ȃ��������Ƃ��s�v�c�Ɋ��������̂ł��B
�@���ꂱ�꒲�ׂ����ʁA�~�q���G���E�n�C�h���i1737-1806�j�ɍ��R�E�߂���l���ɂ����u�L���X�g�҂̒����v�Ƃ����@���������邱�Ƃ�m��܂����B�����āA���̓��{�㉉�������������s�ݏZ�̃h�C�c�l���y�Ƃ̕��ƃR���^�N�g���Ƃ�A���̏㉉�f������Ă��������܂����B���̕��ɂ��܂��ƁA���̏㉉�͂����炭�U���c�u���O�ŏ�������Ĉȗ��̂��̂��낤 �Ƃ̂��ƂȂ̂ő�ϋM�d�ȋL�^�ł��B
�@�~�q���G���E�n�C�h���ƃ��[�c�@���g��Ƃ��e�����������Ƃ͑����Ă���܂����̂ŁA���[�c�@���g�����̏@������ʂ��č��R�E�߂�m���Ă����\�������� �Ɛ������܂����B�������A�؋�������܂���B����ȂƂ��A�o������̂����c�搶�́u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�������̂ł��B
�@�u���Ƃ����v�͂��������܂��E�E�E�E�E�~�q���G���E�n�C�h���̏@�����u�L���X�g�҂̒����v�̃R�[���X�u�J���^�[�e�E�h�~�m�v���A���̂܂܃��[�c�@���g�̃I���g���I�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�vK118=74c�ɂقړ����`�œ]�p����Ă���B�u�L���X�g�҂̒����v��1770�N8��30���A�U���c�u���N�ŏ������ꂽ���A���̂Ƃ����[�c�@���g�́A��1���C�^���A���s�̓r���ŁA�U���c�u���N�ɂ͂��Ȃ������B�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�͖�1�N���1771�N�āA���[�c�@���g���U���c�u���N�ŏ��������̂ł���B���[�c�@���g�����̂悤�Ȏؗp�����Ă���Ƃ������Ƃ́A�u�L���X�g�҂̒����v�̍ĉ����������A�~�q���G���E�n�C�h���̊y�������Ă���������ʂ������Ƃ��Ӗ����Ă���B���́u�L���X�g�҂̒����v�͓��{�̃L���V�^���喼���R�E�߂���l���ɂ����@�����ł���B����15�̃��[�c�@���g�����̌��̕���Ǝ�l���̓��{�l���ӎ������Ɛ������Ă��悢�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����ǂ�Ŏ��́A�u������v�Ɖ��Ƃ����т܂����B���̋L�q�����A���[�c�@���g�����R�E�߂�F�m���Ă������Ƃ̏؋��ł͂���܂��B���������܂Ŏ����u�^�~�[�m�͍��R�E�߁v�̉𖾂��i�݈�̌��_���o�����Ƃ��ł��܂����B���_�z����̐��_�ł͂���܂����E�E�E�E�E�B
�@���̂悤�ɁA���̒��ł́A�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�͂��������̂Ȃ����ł���A���Ҋ��c�r��搶�͌h�����ׂ����y�w�҂ł��B�u�ꋿ�v�ɏ������٘_������Ȑ搶�̖ڂɗ��܂������Ƃ͖]�O�̊�тƂ����ق��͂���܂���B�����āA��������́A�搶�̂��ӌ��ɑ����̏������q�ׂ����Ă������������Ƒ����܂��B
�i1�j���c�搶�̂��w�E
�@�٘_�u���[�c�@���g�w���N�C�G���x�ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������v�ŁA���́A�����悻�ȉ��̂悤�ɋL���܂����B
�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɂ������́u�z�U���i�v�͓��꒲���łȂ���Ȃ�Ȃ��B�W���X�}�C���[�͂��̃~�T�Ȃ́u���ߎ��v���O���Ă��܂����B����������̂��u�����B���Łv�ł���A���̎�_�������̂��u�����Łv�ł���B �u�W���X�}�C���[�Łv�ł́u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v���j�����ƕσ������B�u�����B���Łv�ł̓j�����ƃj�����œ���B�u�����Łv�͕σz�����ƕσz�����œ���Ƃ������́B�u�W���X�}�C���[�Łv�̓~�T�Ȃ̌��ߎ����O���Ă���̂Ő������K�v�B�u�����B���Łv�́�n�����n�ւ̓]���Ȃ̂Ŗ����������Ă���B�u�����Łv�́�n���m�Ȃ̂ŃX���[�Y�B�@����ɂ��Ċ��c�搶�́u18���I�̋���y�ɂ����āA�g2�̃z�U���i�͓��꒲���ŏ����˂Ȃ�Ȃ��h�Ƃ����͉̂��t�҂̕X��D�܂�����������ŁA�����Č��ߎ��ł͂Ȃ��v�Ƃ��āA�������̎�������܂����B���̓��̈�͂����L����Ă��܂��B
�G�[�x�����[���i1703-63�j�́u���N�C�G���v��6�ԂƃK�b�e�B�i1743-1827�j�́u���N�C�G���v�n�����ł́A2�́u�z�U���i�v�͈قȂ钲���A�قȂ�Ȃŏ�����Ă���B�@�����āA�搶�͂������_����܂����B
�c�_�̑O��������s�m���ł���ȏ�A���̑O������̂Ƀ~�T�ʏ핶��1�u�T���N�g�D�X�v�̒���������������Ƃ������Ƃ́A�@���ɂ��s���߂��̗l�Ɏv���܂��B�W���X�}�C���[�́A�����̍�ȉƂ����Ă����ʂ�̂��Ƃ����������ł���A2�́u�z�U���i�v�꒲���ɂ��邱�Ƃ�ړI�ɁA���́u�T���N�g�D�X�v�̒�����ς���K�v�͂Ȃ��l�Ɏv���܂��B�@���̂悤�ɁA���c�搶�͎����~�T�Ȃ́u���ߎ��v�Ƃ��������ɂ͗�O������ �Ǝw�E����܂����B��́u�z�U���i�v�̓��꒲���̓~�T�Ȃ́u���ߎ��v�ł͂Ȃ������̂ł��B
�i2�j�u���ߎ��v�̒����ƃ����B���ł̐���ɂ���
�@���͐٘_�������ɂ�����A�\�Ȍ��葽���́u�~�T�ȁv������������ł����E�E�E�E�E�M���[���E�f���t�@�C�u�p�h���@�̐��A���g�j�E�X�̂��߂̃~�T�ȁv�A�V�����p���e�B�G�u�^�钆�̃~�T�ȁv�A�r�[�o�[�u���N�C�G���v�AJ.S.�o�b�n�u�~�T�ȃ��Z���v�A���[�[�t�E�n�C�h���u�l���\���E�~�T�v�A���[�c�@���g�u�~�T�E�\�����j�X�vK139�i�ǎ��@�~�T�j�A�u�Պ����~�T�vK317�A�x�[�g�[���F���u�����~�T�ȁv�A�V���[�x���g�u�~�T�ȑ�6�ԁv�A�u���e���u�푈���N�C�G���v ���X�B�����͂��ׂāA�z�U���i�͓��꒲���E����Ȃł����B��ȔN���14���I�`20���I�ɂ킽��܂��B�����̂��Ƃ���A�z�U���i�̓��꒲���̓~�T�Ȃ́u���ߎ��v�Ɣ��f�����킯�ł��B
�@������ɐ搶�̂��w�E�ŗ�O�̑��݂����������킯�ŁA����́u���ߎ��v�Ƃ͌�����B�������A���y�j�ォ�Ȃ�̒����ɂ킽���ĂقƂ�ǂ̃~�T�Ȃ������ł������킯�ł�����A������u�ʏ�`�v�ƌ��������邱�Ƃ͋������̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B���Ɏ����Q�l�ɂ����u�����B���Łv�̌��ɓ��点�Ă��������܂��B
�@1995�N�A���o�[�g�E�����B���i1947-�j�͔ނ̔łɂ�郂�[�c�@���g�u���N�C�G���v��C�c�i�`���[���Y�E�}�b�P���X�w���j�̃��C�i�[�m�[�c�ňȉ��̂悤�ɋL���Ă��܂��B
�W���X�}�C���[�͕σ������́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��ƂɁA���́u�z�U���i�v���I���W�i���̃j�����ł͂Ȃ��σ������̂܂܌J��Ԃ��Ă��܂����B���̂��Ƃ͓����̂��ׂĂ̋���y�ɖ���������̂ł���B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł͌㔼���������X���������B���Ȃ킿�A�I���W�i���̃j�����́u�z�U���i�v�t�K�[�g�̒Z�������ւȂ��邽�߂ɐV���Ɍo�ߋ������Č��B�@�����B���́A�W���X�}�C���[�́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɂ������M��Ƃɂ��āA�����̂��ׂĂ̋���y�ɖ�������iin conflict with all church music of the time�j�Ƃ��������������Ă��܂��B����̓����B�������c�搶���w�E�̓��e��m��Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�����B���ł̓��[�c�@���g�u���N�C�G���v��2�̃z�U���i�̒����ɏ��߂ă��X����ꂽ�łł��B���́A�W���X�}�C���[�ł��g2�̃z�U���i�꒲���ɂ���h�Ƃ�������y�́u�ʏ�`�v�ɐ������������B���ł�傢�ɕ]��������̂ł��B
�i3�j�����B���ł�����
�@�����B���ł͊m���ɋ���y�̒ʏ�`�ɐ������܂������A����͉ʂ����ă��[�c�@���g�̂����Ȃ̂��낤���A�ƍl���܂����B
�@���̒��ɂ́A�u���[�c�@���g�̂����ȂǁA�{�l�łȂ���Ε�����͂��͂Ȃ��̂ł��邩��A�l���邱�Ǝ��̂ɈӖ��͂Ȃ��v�Ƃ������������悤�ł����A���͂����͎v���܂���B�����z������������w�͂͌����Ė��ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��ƍl���܂��B
�@�����ŁA���́A���[�c�@���g�́i�u���N�C�G���v�ȊO�́j�~�T�Ȃɂ�����u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒����̊W�ׂ܂����B
�@�~�T�E�\�����j�XK139�u�ǎ��@�~�T�v �u�T���N�g�D�X�v�n�����A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�w����
�@�~�T�E�u�����B�XKI40 �g�����A�n����
�@�O�ʈ�̂̃~�T��KI67 �n�����A�w����
�@�N���h�E�~�TK257 �n�����A�w����
�@�Պ����~�T��K317 �n�����A�n����
�@�����قƂ�ǂ��������̊W�B�g�]�����X���[�Y�ɂł���h�W �Ƃ����܂��B���Ȃ��Ƃ��W���X�}�C���[�Ł������B���ł̂悤�ȁ�n�i�j�����j�Ɓ�n�i�σ������j�Ƃ����W�ł͂���܂���B�����Ŏ����v�������̂́A�u�T���N�g�D�X�v�σz�����A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ����Ƃ����ݒ�ɂ��邱�Ƃł����B����Ȃ�A�o������n�ŁA�]���̍ۂ́��́}�ōς݁A�]�����X���[�Y�ɂȂ���܂��B�����B���ł̂悤�ɁA�o�ߋ��t������K�v������܂���B
�@����������ă��[�c�@���g�́u����������͂����v�Ȃǂƒf���͏o���܂���B�����܂őz���̐��E�ł��B�ł����A�W���X�}�C���[�̐ݒ肵���������̓��[�c�@���g�̈ӎv�ɋ߂��̂ł͂Ȃ��� �ƍl���܂����B
�@�u�ꋿ�vNo.21�̐٘_�ɂ�����\���͉��L�̂悤�Ȃ��̂ł����B
�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�͒����܂ߑS������łȂ���Ȃ�Ȃ��B����́u�~�T�ȁv�̌��ߎ��ł���Í������B��̗�O�����݂��Ȃ��B�@�����́A���ǂݕԂ��Ă݂�ƁA�����Ԃ�O�̂߂�ɂ�����\���ł��B�����ɂ́A���Ȃ̕��@�_�͐�ΓI�ɐ������A�Ƃ���s���ȋC���������肠��Ƃ��������܂��B����ɂ͖�������I�[�\���C�Y����ĂȂ��G�f�B�V�������u�����Łv�Ȃǎ��̂�����肪����܂��B����͂܂����A�����ƌ����ɂȂ�Ȃ��ẮE�E�E�E�E�B����Ȏ����̔O�����N���Ă����������̂͊��c�搶�̌x���ł����B�H���A�u�w�T���N�g�D�X�x�̒���������������Ƃ������Ƃ́A�@���ɂ��s���߂��̗l�Ɏv���܂��v�B
�u�����Łv�̓W���X�}�C���[�̐ݒ肻�̂��̂����[�c�@���g�Ȃ�ł͂̕��@�ɒu���������B���ꂼ�R�����u�X�̗��B���ꂱ�������[�c�@���g�̈ӎv�ɍł��߂��u���N�C�G���v�̌`�Ƃ����Ȃ����낤���B
�@���͐٘_���Č����邱�Ƃɂ������܂����B�u�T���N�g�D�X�v��σz�����ɐݒ肷��͖̂{���Ƀ��[�c�@���g�̂����Ȃ̂��낤���ƁB
�@���̂��߂ɂ́A�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł͂Ȃ��A�u�y�ȁv�Ɓu�T���N�g�D�X�v�̒����̊W��m��K�v������܂��B�ώG��������邽�߁A���[�c�@���g�́u�Z���̃~�T�ȁv�ɍi���Č����s���܂����B���̒m����胂�[�c�@���g�̒Z���̃~�T�Ȃ�2�Ȃł����B
�~�T�E�\�����j�X �n�Z�� K139 �u�ǎ��@�~�T�v�@���[�c�@���g�́A���ȂƂ��Ƀn�Z���Ńn�����A�����铯�咲�̊W��I��ł��܂��B���̂��Ƃ���A���_�f���͂ł��܂��A���[�c�@���g���Z���̃~�T�Ȃɂ����āu�T���N�g�D�X�v�̒�����ݒ肷��ۂɂ́A���咲��I�ԉ\�������� �ƍl���Ă��悳�����ł��B���̌`�́A�c�O�Ȃ���A�٘_�̃j�Z���ƕσz�����Ƃ����W�ł͂���܂���B�����ŁA�W���X�}�C���[�ł��ӂ݂�A�j�Z���ƃj�����A���咲�̊W�B�Ȃ�ƁA���[�c�@���g�̂����ɏ������Ă��܂��B�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�ςݏd�˂��������U�o���ɖ߂��Ă��܂��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �E�E�E�E�E�u�y�ȁv�̓n�Z���A�u�T���N�g�D�X�v�̓n����
�~�T�� �n�Z�� K427�E�E�E�E�E�u�y�ȁv�̓n�Z���A�u�T���N�g�D�X�v�̓n����
�@����ł͂���܂��āA�u�T���N�g�D�X�v���j�����ɌŒ肵�܂��B���́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł��B�W���X�}�C���[�͂����σ������ɐݒ肵�܂����B�����B��������P���܂����B��������[�c�@���g�͂ǂ��ł��傤���B����͑O�f�̂Ƃ���A�قڂ��ׂĂ��������ւ̓]���ƂȂ��Ă��܂��B�n�����Ȃ�w�����A�j�����Ȃ�g�����ł��B���������āA���[�c�@���g�Ȃ�A�j�����́u�T���N�g�D�X�v�ɑ��ăg�����́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v��ݒ肷�� �ƍl���邱�Ƃɖ����͂Ȃ��Ǝv���܂��B�Ƃ����ŁA���̓n�^�ƋC�Â��܂����B���̐ݒ�͎��̌����̏����i�K�ōl�������̂��������Ƃ��B
�i3�j���[�c�@���g�u���N�C�G���v�̐^���Ȍ`�����߂�
�@���[�c�@���g�u���N�C�G���v�̐^���Ȍ`�Ƃ͉����H ���Ȃ킿�A�u�T���N�g�D�X�v�{�u�z�U���i�v�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�{�u�z�U���i�v�̒����͂ǂ�����ׂ����B���̒T���́A���������̑傫�Ȍ����ۑ�ƂȂ�܂����B�����āA���̌o�܂͎���Web-Site�u�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v�ɏ����Ă܂���܂����B�ȉ��A�u���[�c�@���g�w���N�C�G���x�ɂ����钲���𖾁v�̕ϑJ������ɉ����Ď��n��I�ɋL�����Ă��������܂��B
�u�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v2013�N10��15��
�@�u�T���N�g�D�X�v�j�����`�u�z�U���i�v�j����
�@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�g�����`�u�z�U���i�v�j����
�u�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v2019�N6��25��
�@�u�T���N�g�D�X�v�σz�����`�u�z�U���i�v�σz����
�@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ������`�u�z�U���i�v�σz����
�@or
�@�u�T���N�g�D�X�v�σz�����`�u�z�U���i�v�σ�����
�@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�����`�u�z�U���i�v����
2020�N8�����s�u�ꋿ�vNo.20
�@�u�T���N�g�D�X�v�σz�����`�u�z�U���i�v�σz����
�@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ������`�u�z�U���i�v�σz����
�@���̂悤�ȕϑJ���o�āA�u�ꋿ�vNo.20�̌`�ɂ��ǂ蒅�����Ƃ����킯�ł��B�u�ꋿ�v�Ɍf�ڂ����肢�����̂́A���ꂱ�������ɂ̌`�ƗE���߂ł����B����A���c�搶�̂��w�E����Č������݂����ʁA�u�T���N�g�D�X�v�̒����ݒ�i�σz�����j�ɖ�肪���邱�Ƃ�F�����܂����B�Ȃ�ƁA�ŏ��̌`�ɖ߂��ƁA��n�̊y�ȂɁ�n�����݂��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ��ɖ��ȑ㕨�ł��B
�@���[�c�@���g�u���N�C�G���v�^���̌`�̒T���͌��������̂�ł��B���[�c�@���g�͂���Ɋւ��ĉ�����g�̈ӌ��ړI�Ɏc���Ă͂��Ȃ��̂ł�����A�T���͏؋���ςݏd�˂邵������܂���B�܂��ɂ���́u�����̂Ȃ�����v�Ƃ����Ă����̂ł��傤�B�����炱���y�����Ƃ�������̂ł����E�E�E
�E�E�B���̒T���̉ߒ��ŁA���y���Ԃ̗F�l�A��y�������琔�X�̂��ӌ������������܂����B�����́A�^���A�s���A���S���l�X�ł����B
�@����Ȓ��ŁA���c�搶���璸�Ղ������ӌ��͊i�ʂɋM�d�Ȃ��̂ł����B���������߂Ă��������܂����B������f���Ɏ�邱�Ƃ��ł��܂����B����̖��n���ƌ����s�����v���m�邱�Ƃ��ł��܂����B�Ȃ̂ŁA����͔��_�ł͂Ȃ������̘_�ł��B
�@������A���[�c�@���g�u���N�C�G���v�݂̂Ȃ炸�A�l�X�ȉ��y�ɂ��Ă̌�����[�߂Ă䂭����ł��B�����āA�Ȃɂ����A���y��S����y����ł䂫�����Ǝv���Ă���܂��B
�@�@�@2021�N �H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �W
2021.08.25 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�j�Z��KV626�`���̕�M�������߂�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���c�r�� 1954�N���w Va �i�ꋿNo.21�f�ځj
�@����͈ꋴ��w�nj��y�c�̉�u�ꋿ�vNo.21�Ɍf�ڂ��ꂽ���e���ł��BNo.20�Ɍf�ڂ��ꂽ�ٕ��u���[�c�@���g�w���N�C�G���x�ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������v�ɑ��邲�ӌ����ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������������������������������
 �@�{����N���i20���j�ɁA�����W����̃��[�c�@���g�̃��N�C�G���Ɋւ��邲���e���f�ڂ���܂����B�����͒��N���[�c�@���g�Ƃ��̎��ӂ̉��y�ɐe����ł����g�ł��B���R�傫�ȋ����������ēǂ܂��Ă��������܂����B��������̓��e�̓��e�͐��I�Ȃ���ĂŁA���J��ł��B���e�����I�Ȃ̂ŁA�G�z�Ȃ���A����������Ă��ǂ��~�߂Ă��邩���A���������I�ɏ����Ă݂܂��B�F�l�̂��Q�l�̈ꏕ�ɂȂ�K���ł��B
�@�{����N���i20���j�ɁA�����W����̃��[�c�@���g�̃��N�C�G���Ɋւ��邲���e���f�ڂ���܂����B�����͒��N���[�c�@���g�Ƃ��̎��ӂ̉��y�ɐe����ł����g�ł��B���R�傫�ȋ����������ēǂ܂��Ă��������܂����B��������̓��e�̓��e�͐��I�Ȃ���ĂŁA���J��ł��B���e�����I�Ȃ̂ŁA�G�z�Ȃ���A����������Ă��ǂ��~�߂Ă��邩���A���������I�ɏ����Ă݂܂��B�F�l�̂��Q�l�̈ꏕ�ɂȂ�K���ł��B�@��������́A���[�c�@���g�̃��N�C�G���������������삵���W���X�}�C���[�ɍ�ȏ�ɖ�肪���������ƁA�X�ɂ����20���I�㔼�ɕ�삵�����o�[�g
�E�����B���̕����e�ɂ���肪���邱�Ƃ��w�E����āA�Ǝ��̐V�������Ă����Ă��܂��B
�@�����������[�c�@���g�̃��N�C�G���Ɍ��炸�A���ȉƂ̍�i�̌����C������Ƃ������́A�̂���_���ɂȂ肪���Ȑ��i���͂��ł��܂��B���{�ł��A20���I�㔼�Ƀ��[�c�@���g�̍�i�̌����߂����đ����������_��������A�ɂݕ����ɂȂ��Ă��܂��B���̎�̘_���́A���F�����������Ȃ����Ȃ̂ł��B�]���āA�����́A�������������̖�肩��͂�������āA�_�|����������̂��咣�A����Ăɍi���Ĕڌ����������Ƃɂ��܂��B
1�j �W���X�}�C���[�ŁA�����B���ł̉������ŁA��������̂���ĂƂ͂Ȃɂ��H
�@���[�c�@���g�̃��N�C�G���������̂܂c���ꂽ�̂ŁA��ɒ�q�̃t�����c�E�N�T�[���@�[�E�W���X�}�C���[�i1766-1803�j����M�A���������܂����B������W���X�}�C���[�łƌĂт܂��B
�@�W���X�}�C���[�łɂ��ẮA�̂��烂�[�c�@���g�̐^�M�����Ƃ̍����C�ɂ��āA������C�����悤�Ƃ�������������܂����B20���I�㔼�ɃA�����J�̃s�A�j�X�g�A��ȉƁA���y�w�҂̃��o�[�g�E�����B�����A�Ǝ��̕��C���Ă���܂����B����������B���łƌĂт܂��B
�@�������A�W���X�}�C���[�ł��C�����������B���łɂ��A���܂���肪�c��Ǝw�E���ꂽ�_��1�Ɍ���܂��A��ԏd�v���Ǝw�E���ꂽ�̂́A���N�C�G���̑�11�ȁu�T���N�g�D�X�v�Ƒ�12�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�Ƃ���ɑ����u�z�U���i�v�̊Ԃ̒����W�ł��B
�@�W���X�}�C���[�łł͎��̑ɂȂ��Ă��܂��B
�@�@�E�u�T���N�g�D�X�v�F�j�����A�u�z�U���i�v�F�j����
�@�@�E�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�F�����A�u�z�U���i�v�F����
�@��������́A�~�T�ȁi���N�C�G�����܂܂�܂��j�ł́w2�́u�z�U���i�v�͒����܂ߑS������łȂ���Ȃ�Ȃ��x�A�w���ꂪ�~�T�Ȃ̌��ߎ����`���ł���x�A�Ǝw�E����A�W���X�}�C���[�ł�2�̃z�U���i���قȂ钲�����̂��Ă���̂́w�@�����y���̂Ȃ���`�x�ł���A�w�W���X�}�C���[�͂���Ă͂Ȃ�Ȃ��~�X��Ƃ��x�A�Ǝ咣����Ă��܂��B
�@�����B���ł͎��̗l�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�@�E�u�T���N�g�D�X�v�F�j�����A�u�z�U���i�v�F�j����
�@�@�E�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�F�����A�u�z�U���i�v�j����
�@�������āA2�́u�z�U���i�v�͓��꒲���ɓ��ꂳ��܂������A��������́A�����B���ł��u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ������Ƒ����u�z�U���i�v�̊ԂɁA�o�ߋ�����ނƂ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������_�ɒ��ڂ���A�V������Ă��Ȃ���Ă��܂��B
�@��������̂���ẮA���������u�T���N�g�D�X�v����n�̃j�����ɐݒ肵���Ƃ���ɖ�肪����A�������n�̕σz�����ɕς���ƁA�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ���������u�z�U���i�v�σz�����ւ̓]���͖������Ȃ��Ȃ�A�X���[�Y��2�́u�z�U���i�v�̓��꒲�����������ł���A�������u�T���N�g�D�X�v�σz�����Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ������̊Ԃɑ����W�i���S5�x�̊W�ŋߐe���W�̂P�ł��j���o����Ƃ������_�ނ��Ƃɂ��Ȃ�A�Ǝ咣����Ă��܂��B��������̂���Ăł͎��̗l�ɂȂ�܂��B
�@�@�E�u�T���N�g�D�X�v�F�σz�����A�u�z�U���i�v�F�σz����
�@�@�E�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�F�σ������A�u�z�U���i�v�F�σz����
2�j 2�́u�z�U���i�v�����꒲���ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ́A�ǂ������Ӗ����H
�@��q���܂������A�����͒��N���[�c�@���g����ӂ̉��y�ɐe����ł��܂����B�������A�~�T�Ȃ�2�́u�z�U���i�v�����꒲���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�������咣�����قǁA��ΓI�Ȍ��ߎ����`���ł���Ƃ����F���͎����Ă��܂���B
�@�Ȃ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ����z�����̂ł��傤���B�����́A�����2�̗��R������ƍl���Ă��܂��B
�@�~�T�Ȃł́u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́A�ʏ퐫�i�̈Ⴄ���y�Ƃ��č�Ȃ���A���t����܂��B�������Ȃ���A�~�T�̒ʏ핶�ł�2�͑傫�����������u�T���N�g�D�X�v�͂̒��ŁA�u�T���N�g�D�X�v�{�u�z�U���i�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�{�u�z�U���i�v��������A�̂��Ă���̂ł��B�]���āA�������������u�z�U���i�v�Ɋւ��ẮA���ʂȗ��R���Ȃ�����A�����Ȃ������̂��ł����R���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��~�T�̒ʏ핶�Ƃ͂��ׂẴ~�T�ɋ��ʂ���5�̏́i�L���G�A�O���[���A�A�N���h�A�T���N�g�D�X�A�A�j���X�E�f�C�j���w���܂��B
�@18���I�̋���y�ł́A���̊�y���t�Ȃ������ł����A���̎�1�����̉��t�Ƃ����̂����ʂł��������߁A���K���Ԃ͋ɂ߂Č����Ă���A�����ʼn��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����X����܂����B���̂��߁A�����u�z�U���i�v�̎��ɂ́A�������y�������̂����t�҂̕X��D�܂��������̂ł��B���y���قȂ��Ă��A�����������Ȃ�A���ꂾ�����t�҂ɂ����肪���������Ǝv���܂��B�i���[�c�@���g�̌����ȑ�39�� �σz���� ��1�y�͂̏��t�Ǝ啔�̉��~���K�̗ގ����́A���̂悤�Ȕz���̌��ʂ������Ǝv���܂��B���̂��Ƃ́A�����̓N���X�g�t�@�[�E�z�O�E�b�h�̍u�K��ŕ����܂����B�j
�@�������āA���̊Ԃɂ��A2�́u�z�U���i�v�͓��꒲���ŏ����˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����̌��ߎ��̗l�Ɏ����悤�ɂȂ����ƍl�����܂��B���o�[�g�E�����B���́A������u18���I����y�̒ʏ�̊��K�v�Ɖ��߂��Ď���āA��q�̂悤�ȕ����s�������̂ł��傤�B
�@�������Ȃ���A���y��̋K����`���́A�������̓��퐶������芪���Ă���@������̋K���Ƃ͈Ⴂ�܂��B�����ɂ͍�ȉƂ≉�t�Ƃ��A�����Ǝ��R�ɉ��߂��ĐU������]�n������Ƃ������ʂ�����悤�Ɏv���܂��B�����́A2�́u�z�U���i�v�����꒲���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ߎ��A�`���A�K���i�Ƃǂ��\�����Ă��\���܂��j�́A�{���ɂ����Ȃ̂��Ǝ���Ŋm���߂邱�Ƃɂ��܂����B
3�j 18���I�A2�́u�z�U���i�v�͖{���ɓ��������ŏ�����Ă������H
�@�����́A18���I���[�c�@���g���Ⴂ���A����Œ����A�����ĎQ�l�ɂ������U���c�u���N�̉��y�Ƃ������A���̖����ǂ���舵���Ă������ɂ��āA���Ƀ��N�C�G���ɍi���Ē��ׂĂ݂܂����i�����́A�U���c�u���N�́u���n���E�~�q���G���E�n�C�h������v�̑n�ݎ�����̉���Ȃ̂ŁA����̏������o�����̂ł��j�B���y�Ƃ����́A���L��3���ł��B
�E�G�[�x�����[���A���n���E�G�����X�g�i1703-63�j�F1749�N�U���c�u���N�吹���y���B���[�c�@���g��ƂƂ͐e�����A�����[�I�|���g�̋��t�B���[�c�@���g�́A�G�[�x�����[���̊y���������ʂ��Ȃǂ̊w�K�����Ă��܂��B
�E�K�b�e�B�A���C�[�W�i1743-1827�j�F1787�N�U���c�u���N�吹���y���B���[�c�@���g�Ƃ͐܂荇���̈���������i���q�G���[�j�����X�E�t�H���E�R�����[�g���݂̉��Ŋy���߂܂����B
�E�q�[�q�e�[���[�A�W�[�M�X�����g�i1670-1743�j�F1690�N�U���c�u���N�吹���y���B18���I�����U���c�u���N�@�����y���\���鉹�y�Ƃł����B
�@3�l�̃��N�C�G������E���グ�āA2�́u�z�U���i�v���ǂ������������܂Ƃ߂�ƁA���̒ʂ�ł��B
�E2�́u�z�U���i�v�꒲���ŁA�������Ȃ������Ă�����́F�G�[�x�����[���̃��N�C�G��2�ԁA��3��
�E2�́u�z�U���i�v�͓��꒲���Ȃ���A�قȂ����Ȃ������Ă�����́F�G�[�x�����[���̃��N�C�G��5�ԁA�K�b�e�B�̃��N�C�G�� �C�����i1794�N�j
�E2�́u�z�U���i�v���قȂ��������ŁA���قȂ�Ȃ������Ă�����́F�G�[�x�����[���̃��N�C�G��6�ԁA�K�b�e�B�̃��N�C�G�� �n�����i1803�N�j
�E2�́u�z�U���i�v��S�������Ă��Ȃ����́F�r�[�q�e�[���[�̃��N�C�G��
�@����Ŗ��炩�ȗl�ɁA18���I�U���c�u���N�ł́A��ȉƂ͕K������2�́u�z�U���i�v�꒲���ŏ����Ă��܂���B��ȉƂ͎��Ǝ���ɉ����āA�F�X���������Ă���A���ꂪ�e����Ă����Ǝv���܂��B�������咣���ꂽ���ߎ����`���́A�K���������ߎ���`���ł͂Ȃ������̂ł��B
�@���̗l�ɁA�c�_�̑O��������s�m���ł���ȏ�A���̑O������̂ɁA�~�T�ʏ핶��1�u�T���N�g�D�X�v�̒���������������Ƃ������Ƃ͔@���ɂ��s���߂��̗l�Ɏv���܂��B�W���X�}�C���[�́A�����̍�ȉƂ����Ă����ʂ�̂��Ƃ����������ł��B�����́A2�́u�z�U���i�v�꒲���ɂ��邱�Ƃ�ړI�ɁA���́u�T���N�g�D�X�v�̒�����ς���K�v�͂Ȃ��l�Ɏv���܂��B
4�j ��������ւ̂���Ƃ��l��
�@�Ō�ɁA��������ւ̂���Ƃ��l�т��������Ă��������B
�@����A�����́u�ꋿ�v����ł͏��߂ĂƎv���܂����A���[�c�@���g�ɂ��čl���������邲���e�ɐڂ��܂����B��������̒m���A��M�A�G�l���M�[���琶�ݏo���ꂽ���J��ɐG������āA�ٍe���������ƂɂȂ�܂����B��������N���ꂽ���́A���y�w�̕���̖��Ƃ������܂��B����N�����ꂽ��������ɁA�M�������\���グ�܂��B�L��������܂����B
�@��y�ɂ����鉪������̂��咣���A��y�Ƃ��Ďx���ł���悩�����̂ł����A���ꂪ�ł��܂���ł����B��q�̒ʂ艹�y�w�ɗނ������N�Ȃ̂ŁA����I�Ȏ~�ߕ��͋�����Ȃ�����ł��B��������̂��咣�ɂ͓Y�����Ȃ��ڌ�����������Ȃ��������Ƃ����l�т��܂��B�ǂ������������������B
�@�Ⴕ�A���[�c�@���g�ɂ��Ă�����Ȃ�A���v�]������A�ǂ������Ă��������B�����ɗ��Ă邩������܂���B
2021.07.20 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���� �W 1964�N���w Tp�i�ꋿNO.20�f�ځj
 �@���[�c�@���g�́u���N�C�G�� �j�Z�� K626�v�͎��̍ň��̊y�Ȃ̈�ł���B�e�����m�l�̉i���̕ʂ�̍ۂɂ͕K�������B����ȓ��ʂȋ@��łȂ��Ă�������悭�����y�Ȃł�����B�v����ɍD���Ȃ̂��B�Ȃ����낤�H �ƍl����B���ƐÁA���Ɛ��A�q�Ɣ��A���ƈ��B��������l�Ԃ̊������قǂ܂łɍ��݂����a����Ȃ͂Ȃ��B�S���k���A�h���Ԃ��A�����Ĉ��炮�B���y�̑��l���Ɩ{���������ɂ���B
�@���[�c�@���g�́u���N�C�G�� �j�Z�� K626�v�͎��̍ň��̊y�Ȃ̈�ł���B�e�����m�l�̉i���̕ʂ�̍ۂɂ͕K�������B����ȓ��ʂȋ@��łȂ��Ă�������悭�����y�Ȃł�����B�v����ɍD���Ȃ̂��B�Ȃ����낤�H �ƍl����B���ƐÁA���Ɛ��A�q�Ɣ��A���ƈ��B��������l�Ԃ̊������قǂ܂łɍ��݂����a����Ȃ͂Ȃ��B�S���k���A�h���Ԃ��A�����Ĉ��炮�B���y�̑��l���Ɩ{���������ɂ���B�@���[�c�@���g�́A1791�N12��5���A�A��ʐl�ƂȂ����B�����́u���N�C�G���v���₵�āB�����ł��邩��A�����ɂ͑��l�̎��v����B�W���X�}�C���[�̎�ɂ���Ĉꉞ�̊���������܂łɂ́A�R���X�^���c�F�������A�C�u���[�Ɉ˗����铙�A������]�Ȑ܂��������B��������A���푽�l�Ș_������ь����Ă����B�B�ꖳ��̓V�˂��₵�������̍�i�����炵�āA���ʂ̍˔\���ǂ��撣���Ă��^�����銮���`�ɂ͓͂��͂����Ȃ��B�Ƃ͂����A�����ɋ߂Â���w�͂͂������Ǝv���B��{�p���́u���[�c�@���g�Ȃ�ǂ��������v�̈�_�ł���B
(1) �W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̌���
 �@�u���N�C�G���v�ɂ����āA�u���[�c�@���g�́w���N�����T�x��8���߂܂ł������đ�������������v�Ƃ����悭�m��ꂽ��������邪�A�ߔN�̌����ł́u���Ȃ鐶�сv�����̎w��Quam olim da capo����M�ł͂Ȃ����A�Ƃ̎w�E���o�Ă����肵�Ă���B���A����͂��Ă����A���[�c�@���g���₵���`�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂������B���S�Ȍ`�Ŏc���ꂽ�̂́A��1�ȁu���Տ��v�̂݁B��2�ȁu�L���G�v�͂قڊ����B��3�ȁu�{��̓��v�|��10�ȁu���Ȃ鐶�сv�͕��������B��11�ȁu�T���N�g�D�X�v�|��14�ȁi�I�ȁj�u���̔q�̏��v�͋A�Ƃ������̂ł���B
�@�u���N�C�G���v�ɂ����āA�u���[�c�@���g�́w���N�����T�x��8���߂܂ł������đ�������������v�Ƃ����悭�m��ꂽ��������邪�A�ߔN�̌����ł́u���Ȃ鐶�сv�����̎w��Quam olim da capo����M�ł͂Ȃ����A�Ƃ̎w�E���o�Ă����肵�Ă���B���A����͂��Ă����A���[�c�@���g���₵���`�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂������B���S�Ȍ`�Ŏc���ꂽ�̂́A��1�ȁu���Տ��v�̂݁B��2�ȁu�L���G�v�͂قڊ����B��3�ȁu�{��̓��v�|��10�ȁu���Ȃ鐶�сv�͕��������B��11�ȁu�T���N�g�D�X�v�|��14�ȁi�I�ȁj�u���̔q�̏��v�͋A�Ƃ������̂ł���B�@���݂Ɂu���N�C�G���v�S�̂̍\���͈ȉ��̒ʂ�ł���B
1 ���Տ� Introitus�@2 �L���G Kyrie�@3 �{��̓� Dies Irae�@4 ���Ȃ郉�b�p Tuba Mirum�@5 �݂��̑剤 Rex Tremendae�@6 ���R���_�[�� Recordare�@7 ���ꂵ�� Confutatis�@8 �܂̓� Lacrimosa�@9 ��C�G�X�� Domine,Jesu�@10 ���Ȃ鐶�� Hostias�@11 �T���N�g�D�X Sanctus�@12 �x�l�f�B�N�g�D�X Benedictus�@13 �_�̎q�r Agnus Dei�@14 ���̔q�̏� Communio
�@�������M���������̂̓��[�c�@���g�̒�q�̃t�����c�E�N�T���@�[�E�W���X�}�C���[�i1766�|1803�j�ł������B���[�c�@���g�͎��̊ԍۂ܂ŃW���X�}�C���[�Ɂu���N�C�G���v��M�̎菇���������Ă����B�W���X�}�C���[�̎莆���₳��Ă���B
���[�c�@���g���g�̐������Ɂu���Օ��v�u�L���G�v�u�{��̓��v�u��C�G�X��v�Ȃǂ��A�ꏏ�ɉ��t������̂����肵�܂����B�܂��A���̋Ȃ̎d�グ�ɂ��Ĕނ������Ύ��ɘb�������Ƃ�A�I�[�P�X�g���[�V�����̕��@���ɂ��Ď��ɋ����Ă��ꂽ���Ƃ͏O�m�̎����ł��B���͂��̋Ȃ����I�Ȑl�����ɁA�ނ̋����̐Ղ����̒��ɂ��邱�Ƃ��Ƃ��ǂ��������Ă��炦��悤�ɏ�����ΐ������Ǝv���Ă��܂����B�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�Ɓu�_�̎q�r�v�͂܂������V����������Ȃ��܂����B�@����̓W���X�}�C���[���A���C�v�c�B�q�̑��o�ŎЃu���C�g�R�b�v�E�E���g�E�w���e�����Ăɏ������莆�̈ꕔ�ł���B�����璆�ɁA�����荞�ނ��߂̌֒������݂��Ă���͎̂����ł���B�Ȃ̂ŁA��������Ȃ�Ɍ��E����ă��[�c�@���g�̎w�������Ă݂�B
�@��1�ȁu���Տ��v�͊����i�ɂ����̂܂܁B��2�Ȃ͎�̎w���̂݁B��3�ȁ\��10�Ȃ̓I�[�P�X�g���[�V�����Ɗy�ȍ\����̎w���B��11�ȁ\��13�Ȃ͊����y�Ȃ���̓]�p���w���B��̓I�ɂ́A��11�ȁu�T���N�g�D�X�v�́u�~�T�E�\�����j�X �n�Z���vK139�i�ʏ́u�ǎ��@�~�T�v�j�A��12�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�o���o���E�v���C���[�̂��߂̗��K���vK453b�A��13�ȁu�_�̎q�r�v�́u�~�T�ȃn���� ���̃~�T�vK220�́u�O���[���A�v�A�ł���i�����͊e�X����ׂ�Ɩ����ɂ킩��j�B��14�ȁu���̔q�̏��v�́A��1�ȁu���Տ��v�̓r�������2�ȁu�L���G�v�܂ł̌J��Ԃ����w���B
�@��L����A���[�c�@���g�́A�W���X�}�C���[�Ɂi�V���ȋȍ������Ȃ��čςނ悤�ȁj���Ȃ�ڍׂȎw����^���Ă������Ƃ����Ď���B�W���X�}�C���[�̓��[�c�@���g�̎w���ɏ]���Ȃ�Ƃ������ɂ��������B���̓w�͂����������炱�����ȁu���N�C�G���v�͐��ɏo���̂ł���B����ȃW���X�}�C���[�̌��т͂�����̎^���Ă����������̂ł͂Ȃ��B�������Ȃ���A�ނ͐�ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��~�X��Ƃ��Ă��܂��B����͑�11�ȁu�T���N�g�D�X�v�Ƒ�12�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�̒������ɂ��Ȃ��������Ƃł���B
(2) �W���X�}�C���[���~�X��Ƃ����o�܂𐄗�����
�@�O�͂ɋL�����悤�ɁA�W���X�}�C���[�́u�T���N�g�D�X�v�����ɂ�����A�u�~�T�E�\�����j�X �n�Z��K139�v����ɂ����Ǝv����B�u�~�T�E�\�����j�X�v�̓n�Z���A�u�T���N�g�D�X�v�̓n�����B���咲�̊W�ɂ���B�W���X�}�C���[�͂��̕��������P����B�����j�Z���́u���N�C�G���v�ɑ��āu�T���N�g�D�X�v���j�����ɐݒ肵���B���́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł���B������u�~�T�E�\�����j�X�v�ɕ킢�A��U�͉������̃g�����ɐݒ肵���i�Ǝv���j�B�Ƃ��낪����ł͉�����������߂��āA���y���ɒj�����������Ȃ�B�����ŁA�@�B�I�ɒZ3�x�グ�A�σ������ɐݒ肵�������B����ʼn���I�ȉ����͓K�����B���A�ނ͂���Ă͂Ȃ�Ȃ��~�X��Ƃ��B�u�z�U���i�v�̒�������̌������O���Ă��܂����̂ł���B�������āA�����ɁA�u�T���N�g�D�X�v�j�����\�u�z�U���i�v�j�����A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ������\�u�z�U���i�v�σ������Ƃ����@�����y���̂Ȃ���`�������Ă��܂����̂ł���B
�@���[�c�@���g�́A�O�͂̒ʂ�A���Ȃ�ڍׂȎw����^���Ă����Ǝv����B�ɂ�������炸�A�Ȃ�����Ȋ̐t�Ȃ��Ƃ��w�����Ȃ������̂��낤���H ����͂����炭�A���y�Ƃ�����̂����Ȃ��{�͓��R�����Ă��đR��ׂ��ƍl���Ă������炾�낤�B�V�˂̏펯�͖}�f�Ȓ�q�̏펯�ł͂Ȃ������B
(3) �~�T�Ȃɂ�����u�z�U���i�v�̌`
�@�u�z�U���i�v�̓C�G�X��L���X�g�̃G���T��������̍ہA�Q�W�����������Ă̐��gHosanna in excelsis�h�i���ƍ����V�Ƀz�U���i�j�̂��Ƃł���B�~�T�Ȃɂ����āA�u�z�U���i�v�́A�u�T���N�g�D�X�vSanctus�i���Ȃ邩�ȁj�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�vBenedictus�i�j����ꂽ�܂��j���Ȃ̖����ɕt������B��́u�z�U���i�v�͒����܂ߑS������łȂ���Ȃ�Ȃ��E�E�E�E�E���ꂪ�u�~�T�ȁv�̌��ߎ����`���ł���A�Í������B��̗�O�����݂��Ȃ��i���[�c�@���g�u���N�C�G���v�W���X�}�C���[�ł������Ắj�B
�@J.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�A�n�C�h���u�l���\���E�~�T�v�A�~�q���G���E�n�C�h���u���N�C�G�� �n�Z���v�A���[�c�@���g�u�Պ����~�T�vK317�A���[�c�@���g�u�~�T�� �n�Z���vK427�A�x�[�g�[���F���u�����~�T�ȁv�A�V���[�x���g�u�~�T�� ��6�ԁv�ȂǁA�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�͑𐬂��A�e�X�ɕt������u�z�U���i�v�͒����܂ߑS������ł���B��X�A�Ⴆ�t�H�[���́u���N�C�G���v�̂悤�ɁA�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̏ȗ��ȂǁA�ϑ��I�Ȍ`���̂��̂��o�Ă��邪�A�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v���𐬂��y�Ȃɂ����Ă͑S�Ă��̌��ߎ������Ă͂܂�B����͋ߑ�̍�i�A�u���e���́u�푈���N�C�G���v�ɂ����Ă��R��ł���B
(4) �W���X�}�C���[�łɑ���������
�@�W���X�}�C���[�łɑ��Ă͍����܂Ŋ����̉�����Ƃ��Ȃ���Ă����B��Ȃ��̂������Ă������B
���o�C���[�Ł�
�~�����w�����y��w�r�I���Ȃ̎�C�����t�����c�E�o�C���[��1971�N�ɍs�����B�I�[�P�X�g���[�V�����Ɋւ���[�c�@���g�I�i�Ɣނ��l����j�����̉����ł���B�W���X�}�C���[�łɔ䂵�āA�����̓������������Ă���悤�Ɋ�����B
�������h���Ł�
�����ȉ��y�w��H.C.���r���Y�E�����h����1989�N�ɕҎ[�����B1�u���Տ��v�̓��[�c�@���g�A2�u�L���G�v�̓��[�c�@���g�ƃt���C�V���e�b�g���[�ƃW���X�}�C���[�B3�u�{��̓��v����7�u���ꂵ�ҁv�̓A�C�u���[�A8�u�܂̓��v����14�I�Ȃ܂ł̓W���X�}�C���[�Ƃ����W�߃X�^�C���ł���B
�����[���_�[�Ł�
�C�M���X�̉��y�w�҃��`���[�h�E���[���_�[���A�[�c�@���g�I�����̓O��폜���Ӑ}����1983�N�ɍ��ꂽ�B�W���X�}�C���[��������Ƃ����u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v���J�b�g����A�u���N�����T�v�̌�ɃA�[�����E�t�[�K���u�����B���قɂ��đ�_�Ȕłł���B
�������B���Ł�
��L3�ł̓I�[�P�X�g���[�V�����̐��������d�_�ɍs��ꂽ���̂����A���́u�����B���Łv�͏��߂āA�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̃~�X����������I�ȃG�f�B�V�����ł���B���͂ł������Z�Ɍ�����i���ɂ́A��ؗD�l�ŁA�h���[�X�œ������邪�A�����ł͊����ĐG���K�v�͂Ȃ����낤�j�B
(5) �����B���ł̓����Ɩ��_
 �@���o�[�g�ED.�����B���i1947�|�j�́A�A�����J�̃s�A�j�X�g�A��ȉƁA���y�w�ҁB1987�N�A�w�����[�g�E�������O����ɂ��鍑�ۃo�b�n�E�A�J�f�~�[����˗����ĉ����B1991�N�Ɋ����������B
�@���o�[�g�ED.�����B���i1947�|�j�́A�A�����J�̃s�A�j�X�g�A��ȉƁA���y�w�ҁB1987�N�A�w�����[�g�E�������O����ɂ��鍑�ۃo�b�n�E�A�J�f�~�[����˗����ĉ����B1991�N�Ɋ����������B�@�u�����B���Łv�̓����͐��X���邪�A�d�v�Ȃ��̂�2�B�ŏd�v�́A�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v��̒����ɂ��낦�����ƁB������́u�A�[�����E�t�[�K�v�����������Ƃł���B�����ŁA���悢��{�_�̊j�S�ɋ߂Â��̂ł��邪�A���̑O�Ɂu�A�[�����E�t�[�K�v�ɂ�����M�҂̌������q�ׂĂ������B
�@1962�N�A16���߂̃t�[�K�̃X�P�b�`���x�����������}���قŔ������ꂽ�B����̓��[�c�@���g�̐^�M�ł���A�����ܐ����Ɂu���N�C�G���v��5�ȁu�݂��̑剤�v�̒f�͂�������Ă������߁A��8�ȁu���N�����T�v�̖���������t�[�K�̎��Ɣ��肳�ꂽ�B���[���_�[�������B������������p�����B�����A�u���N�����T�v���t�[�K�Œ��߂�����Ƃ����@�����y��̌��ߎ����`���͂Ȃ��B�m���ɂ���̓��[�c�@���g�̐^�M�ł��邩�炵�āA��U�͂��̌`����낤�ƈӐ}�����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�����ʂ����ă��[�c�@���g�́A�Ō�܂ł��̍l�����������������낤���B�W���X�}�C���[��2���߂́u�A�[�����v�ŋȂ�����B���ꂪ���[�c�@���g�̎w���ł͂Ȃ��ƒf���͂ł��Ȃ��A�Ǝ��͍l����B�Ȃ��Ȃ�A���̂��ƁA��9�ȁu��C�G�Y�X��v�Ƒ�10�ȁu���Ȃ鐶�сv�̊e�X�ɂ����������߂̃t�[�K���u����Ă��邱�Ƃ���A�����Ńt�[�K��r������Ƃ����I�����́A�y�ȃo�����X��A���肤��Ǝv������ł���B�W���X�}�C���[���ׂ����u���N�����T�v�G���f�B���O�̑[�u��(�C���ς����)���[�c�@���g�̍ŏI�I�Ȏw���������Ƃ��Ă����������͂Ȃ��̂ł���B
�@�ł͖{�_�ɖ߂낤�B�����B���ł́A�σ������́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɐV���Ȍo�ߋ�������āA�I���W�i���ł���j�����́u�z�U���i�v�ɂȂ����B����ɂ��A200�N���̊ԕ��u����Ă����W���X�}�C���[�ōő�̃~�X�����������`�ƂȂ����B
�@�����A���̑[�u�́A�σ������i��2�j����j�����i��2�j�ւ̓]���ł��邱�Ƃ���A�~���Ȃ炴��菇��]�V�Ȃ�����A���ʁA����4���߂̌o�ߋ�ɐV����3���߂���������Ȃ������B
�@�m���Ɂu�����B���Łv�̂��A�Ń��[�c�@���g�́u���N�C�G���v�͋���y�̓`���ɓK�������̂ɂȂ����B�����������A���̌`�̓��[�c�@���g���v���`�����p���������낤���B���[�c�@���g�������Ă�����ʂ����Ă����������낤���H �����ł͂���ɉ�^������̂ł���B
(6) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�����ł̒�
�@��2�͂ŋL�����ʂ�A�W���X�}�C���[���u�T���N�g�D�X�v�咲�ɐݒ肵���̂͊m���Ɂu�~�T�E�\�����j�X �n�Z��K139�v�ɕ�������̂��������낤�B�������u�~�T�E�\�����j�X�v�̃P�[�X�́A�n�Z���̋ȂɃn�����́u�T���N�g�D�X�v�̐ݒ�ł��邩�炵�āA��n�ɑ��閳�����̐ݒ�ł���B�Ƃ��낪�u���N�C�G���v�ŃW���X�}�C���[���s�����j�Z���ɑ���j�����́A��n�ɑ����n�̐ݒ�ƂȂ�B����̓z�U���i�̒����ꉻ����ɂ͖��ł���A���̂悤�Ȏ���̓��[�c�@���g�̏@���Ȃɂ͗Ⴊ�Ȃ��B���́A�����������̐ݒ肪�ԈႢ�������̂ł͂Ȃ����A�ƍl�����B�Ȃ�ǂ����邩�B
�@�u�T���N�g�D�X�v�̒�����σz�����i��3�j�ɐݒ肷��B�u�z�U���i�v�͓��������̂܂ܒ��߂�B�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̓W���X�}�C���[�ł̂܂ܕσ������i��2�j�Ƃ��A�u�z�U���i�v��σz�����ɖ߂��B
�@�u�����B���Łv�̓W���X�}�C���[���ݒ肵�����������̂܂܂ɂ��Đ��������B���̂��߉~�����������菇��]�V�Ȃ����ꂽ���A�����ł̓W���X�}�C���[�̐ݒ肻�̂��̂����[�c�@���g�ɏ�������`�ɒu���������B���́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�啔����u�z�U���i�v�ւ̓]���́��������邾���ōςށB����ɂ��A����y�̌��ߎ��ł���u�z�U���i�v�̒������ꂪ�X���[�Y�Ɏ�������B���ɃV���v���B�܂��ɃR�����u�X�̗��ł͂Ȃ��낤���B����ɂ́A��n�̊y�ȂɁ�n��������[�c�@���g�I�\�������@����A�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒����������W�ƂȂ�ȂǁA�t�����ʂ��������B
�y��������Ƃ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@ ��{�W���X�}�C���[�ł��g�p�B�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂ݕύX����B
�A �u�T���N�g�D�X�v���u�z�U���i�v�܂߃j��������σz�����Ɉڒ�����B
�B �u�x�l�f�B�N�g�D�X�v���A�W���X�}�C���[�ł̂܂܁A�啔��σ������Ŏn�߁A�����o�ߋ��4���ߖړ��̖���2���Ƀu���b�W���쐬���A�σz�����́u�z�U���i�v�Ɍq����B
�i�x�[�������C�^�[�Ёu�V���[�c�@���g�S�W�v���Ɏ��A�u�Y BENEDICTUS�v��53���ߖڂ������o�ߋ��4���ߖڂɑ�������j�B
�@���������ꂾ���̍�Ƃł���B�����I�ɂ́A�W���X�}�C���[�ł́u�T���N�g�D�X�̓j�����A�����ł͕σz�����Ȃ̂ō��ق͔��������B�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�啔�̓W���X�}�C���[�łƓ���B����I�ɂ��S�����͂Ȃ��B
�� �G�s���[�O��
 �@���[�c�@���g�u���N�C�G���v�W���X�}�C���[�ł�����������1793�N�ȍ~�A���l�̃��[�c�@���e�B�A�������āA���l����������݂��̂��͒m��Ȃ����A���̍ő�̌�肪�K�ɐ�������Ȃ��܂܁A�����N��������Ă���B�����B���ł́A�@�����y�̓`���ɓK���`�ɂ͂Ȃ������A���[�c�@���g�̈ӎv����͉������̂������B
�@���[�c�@���g�u���N�C�G���v�W���X�}�C���[�ł�����������1793�N�ȍ~�A���l�̃��[�c�@���e�B�A�������āA���l����������݂��̂��͒m��Ȃ����A���̍ő�̌�肪�K�ɐ�������Ȃ��܂܁A�����N��������Ă���B�����B���ł́A�@�����y�̓`���ɓK���`�ɂ͂Ȃ������A���[�c�@���g�̈ӎv����͉������̂������B�@�u�����Łv�́A�g���[�c�@���g�Ȃ炱�������͂����h�Ƃ̊ϓ_���琥�����ʂ������B����͂����炭�A���ĒN���C�Â��Ȃ��������@���낤�Ǝv���B�����āA���ꂱ�������[�c�@���g�̈ӎv�ɍł��߂��u���N�C�G���v�̌`�ł͂Ȃ����낤���B
�@�٘_�́A�u�ꋿ�v���l�ł͍ŏ��Ɉɓ����O�N�i1965�N���w�EVc�j�������������Ă��ꂽ�B���ɔނ����c�h�O�Y��y�i1962�N���w�EOb�j�Ɉē����ď̎^�������������A�ƕ������B�c�O�Ȃ�����c��y�͂��̂��ƊԂ��Ȃ��S���Ȃ��Ă��܂������E�E�E�E�E�B���̐^���u���N�C�G���v���u�ꋿ�v���M�ɂđS���E�ɔg�y������ǂ�Ȃɑf���炵�����Ƃ��낤�A�Ǝv���B���̃��[�c�@���g�u���N�C�G���v�̉��t����������������Ȃ邱�Ƃ��A�Ɋ肤���̂ł���B
���Q�l������
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626���T ���M�Ł@�A�C�u���[��M�Ł@�W���X�}�C���[�⊮��
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626 �W���X�}�C���[�Ŋy���i�x�[�������C�^�[�Њ��j
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626 �����B���Ŋy��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�V���g�D�b�g�K���g�E���[�c�@���g�o�Ŋ��j
�u�ŐV���ȉ���S�W�v��22�� ���y�ȇU�i���y�V�F�Ёj
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626 CD
�@�@[�W���X�}�C���[��] �J�[���E���q�^�[�w���F�~�����w���E�o�b�n�nj��y�c
�@�@[�o�C���[��] �V���~�b�g���K�[�f���w���F�R���M�E���E�A�E���E���nj��y�c
�@�@[�����h����] ���@�C���w���F�^�[�t�F�����W�[�N�E�o���b�N�nj��y�c
�@�@[���[���_�[��] �z�O�E�b�h�w���F�G���V�F���g�����nj��y�c
�@�@[�����B����]�@�}�b�P���X�w���F�X�R�b�g�����h�����nj��y�c
���[�c�@���g�u�~�T�E�\�����j�X �n�Z�� �ǎ��@�~�T�vK139 CD
�@�@�N���I�x���[�w���F�P���u���b�W�E�L���O�Y�J���b�W���̑�
���[�c�@���g�u���̃~�T�vK220 CD
�@�@�N�[�x���b�N�w���F�o�C�G��������
�u���[�c�@���g�Ō�̔N�vH.C.���r���Y�E�����h���� �C�V�V�q��i�������_�V�Ёj
�u���[�c�@���g�v���C�i�[�h�E�\�������� �Έ�G��i�V���فj
�u���[�c�@���g�̎莆�v�����p�Y�ҁi���w�فj
�u�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv�Έ�G���i�w��M���Ɂj
�u�f��̃��[�c�@���g�v�Έ�G���i�������Ɂj
2021.06.20 (��) ��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ��u���S���v�Ɓu4�̊K��v�̂��b
�i1�j���S��28�̔w�ԍ� �]�ĖL�̏ꍇ �@6��8���A���C�Ȃ��e���r�̃`�����l�����Ă�����A�v���싅�𗬐�̍�_�^�C�K�[�X�Ɠ��{�n���t�@�C�^�[�Y�̎���������Ă����B�ŋ߂͖싅���p���Ƃ�ƌ��邱�Ƃ̂Ȃ��������A������]�ĖL�������̂ł����������Ă��܂����B
�@6��8���A���C�Ȃ��e���r�̃`�����l�����Ă�����A�v���싅�𗬐�̍�_�^�C�K�[�X�Ɠ��{�n���t�@�C�^�[�Y�̎���������Ă����B�ŋ߂͖싅���p���Ƃ�ƌ��邱�Ƃ̂Ȃ��������A������]�ĖL�������̂ł����������Ă��܂����B�@��_�͂����܂Ō𗬐�5��7�s��7�ʁB�J������̉��i���Ƀu���[�L���������Ă���B���Ƃ���3�A�s�̑厖�Ȃ��̃Q�[���A�ڐ�̖�3�|2�ŏ��������B�����I����A�����̃Q�[���̃|�C���g�ƂȂ����ꋅ��I�肷��u�]�Ă̈ꋅ�v����I�����B�]�Ă͂�����u��_1�_���[�h��5���n���̍U���A1�A�E�g1��2�ہA���E�P���t���J�E���g���獂�l�ɓ������X�g���C�N����{�[���ɊO���X���C�_�[�v�Ƃ����B���l�͂������U��O�U�B���̓`�����X�̉��E��ō�_�̏����ɂȂ����B�ڐ킾�������炱�̑��ɂ��|�C���g�͐��X�������̂����A�u�{�[������U�点��v��ʂ�I�̂͂����ɂ��]�Ă炵���B���ꂱ�����]�ē��@�̋Ɉӂ����炾�B
�@���̎������@�ɑ��𐁂��Ԃ�����_�́A�𗬐�̍ŏI�Ղ�6�A���Ə����i�݁A11��7�s��2�ʃt�B�j�b�V�������߂��B�Z���[�O�E�y�i���g���[�X�ł�����20�A2�ʋ��l��7�Q�[���������Ƒ��Ԑ���������B2�A�E�g�����i�[�Ȃ�����ĎO���_����S�苭����ڂ̂Ȃ��Ő��A�N���[�U�[ �X�A���X�̔��Q�̈��芴�����l����ƁA���`�[���Ƃ̍��͗�R�ŁA���N�̃Z���[�O�͍�_�D���̉\���������������B�v���N�����ΑO��̓����I�����s�b�N1964����_�̃��[�O�D���������B���N������_���D�����邱�ƂɂȂ�A���i�قƂ�ǖ싅���p�Ȃnj��Ȃ������A���̃L�b�J�P�̈�ƂȂ邾�낤�厖�ȃQ�[�������R�]�Ẳ���Ŋ��\�ł������ƂɂȂ�A����͍K�^�Ƃ����ׂ��ł���B
 �@�]�ĖL�ɂ��Ďv���N�������̂͏����i�f��j�u���m�̈����������v�ł���B�L����80�����������Ȃ����w�҂ł��锎�m�͍]�Ă̑�t�@���B�ߋ��̋L���͂��鎞���Ŏ~�܂��Ă��邩��A�]�Ă̔w�ԍ���28�̂܂܂��B���m�͂��������u�]�Ă̔w�ԍ�28�͊��S�����B�S�Ă̖̘a�����̐����Ɠ������Ȃ�M�d�Ȑ����B�ŏ��̊��S����6�B28�̎���496�B����8128�B����33550336�A����8589869056�A���́E�E�E�E�E�B�����傫���Ȃ�قnj�����̂�����Ȃ�B�����܂�30�����������ĂȂ��Ȑ��Ȃv�B
�@�]�ĖL�ɂ��Ďv���N�������̂͏����i�f��j�u���m�̈����������v�ł���B�L����80�����������Ȃ����w�҂ł��锎�m�͍]�Ă̑�t�@���B�ߋ��̋L���͂��鎞���Ŏ~�܂��Ă��邩��A�]�Ă̔w�ԍ���28�̂܂܂��B���m�͂��������u�]�Ă̔w�ԍ�28�͊��S�����B�S�Ă̖̘a�����̐����Ɠ������Ȃ�M�d�Ȑ����B�ŏ��̊��S����6�B28�̎���496�B����8128�B����33550336�A����8589869056�A���́E�E�E�E�E�B�����傫���Ȃ�قnj�����̂�����Ȃ�B�����܂�30�����������ĂȂ��Ȑ��Ȃv�B�@�]�Ă�1966�N�A�h���t�g��1�ʂō�_�^�C�K�[�X�ɓ��c�B�w�ԍ��́A���ꂽ���i1,13,28�j�̒�����28��I�Ԃ̂����A���ꂪ���S���Ƃ͒m��R���Ȃ������Ƃ����B��ɍ]�Ă��₷�ނ܂�Ȏ��т͊��S��28�ɓ����ꂽ���̂�������������Ȃ��B�u���m�̈����������v�́A���̕s�v�c�A�����̔������A���w�̖��͓��������Ă��ꂽ���ɂƂ��ċM�d�ȓǂݕ��ł��邱�Ƃ͊m�����B
 �@��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ�28 �]�ĖL�́A1968�N9��17���̋��l��ŁA�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��l���Ă����B���̎����ŁA����a�v�̎��V�[�Y���D�O�U�L�^353�i1961�N�j���X�V����354�ڂU�̃��C�o�����厡����D���� �Ƃ����̂ł���B�Ƃ��낪353�ڂ����Ŋl���Ă��܂��������ς��B���̎��ŐȂ܂ł�8�l���O�U�Ȃ��ŗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������]�Ă͎����O�̃R���g���[���őł����Ď��s�b�`���O�ɓO���N������O�U����邱�ƂȂ�����ŐȂɌ}����B�����Ďv�f�ʂ艤����354�ڂ�D�����̂ł���B���̃Q�[���ō]�Ă���ԋْ������̂́A������O�U����������ł͂Ȃ��A����̃s�b�`���[������O�̑ŐȂ�2�X�g���C�N�ƒǂ�����ł��܂�����ʁA�O�U�����Ȃ��悤�ɓ������ꋅ������ �Ƃ������炢���ɂ��]�Ă炵���l��H�����b���B���ꗬ�̋Z�p��������̗V�ѐS�ł���B
�@��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ�28 �]�ĖL�́A1968�N9��17���̋��l��ŁA�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��l���Ă����B���̎����ŁA����a�v�̎��V�[�Y���D�O�U�L�^353�i1961�N�j���X�V����354�ڂU�̃��C�o�����厡����D���� �Ƃ����̂ł���B�Ƃ��낪353�ڂ����Ŋl���Ă��܂��������ς��B���̎��ŐȂ܂ł�8�l���O�U�Ȃ��ŗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������]�Ă͎����O�̃R���g���[���őł����Ď��s�b�`���O�ɓO���N������O�U����邱�ƂȂ�����ŐȂɌ}����B�����Ďv�f�ʂ艤����354�ڂ�D�����̂ł���B���̃Q�[���ō]�Ă���ԋْ������̂́A������O�U����������ł͂Ȃ��A����̃s�b�`���[������O�̑ŐȂ�2�X�g���C�N�ƒǂ�����ł��܂�����ʁA�O�U�����Ȃ��悤�ɓ������ꋅ������ �Ƃ������炢���ɂ��]�Ă炵���l��H�����b���B���ꗬ�̋Z�p��������̗V�ѐS�ł���B�@���̔N�̍]�Ă̒D�O�U����401�𐔂����B����̓v���싅�L�^�Ƃ��Ė����j���Ă��炸�A����MLB�̋L�^�i�m�[�����E���C�A��1973�N��383�j��������ƂĂ��Ȃ������ł���B����20�N�Ԃ̍ő��D�O�U����2011�N�_���r�b�V���L��276������]�Ă̋L�^�ɂ͉����y�Ȃ��B�����炭����A�قډi�v�ɔj���邱�Ƃ̂Ȃ����낤�s�ł̑�L�^�ł���B
�@���Ȃ�`����1971�N7��17���A�I�[���X�^�[�E�Q�[���ŋN����9�A���D�O�U�ł���B�I�[���X�^�[�E�Q�[���ł́A����͍ő�3�C�j���O�����������Ȃ��s����������B������3��Ŏ�9�l�A���O�U�͉i�v�ɒ������邱�Ƃ̂Ȃ��L�^�ƂȂ�B�]�Ă͂���ɒ������ɐ����������B�������݂��̋L�^�ɕ��҂͂��Ȃ��B�ł��߂Â����̂�1984�N�̍]��삾�����B�A��8�D�O�U��B�������ƈ�l�ō]�Ăƕ��ԂƂ���܂ł�������B��������Α��Y�ɃZ�J���h�S����ł���Ė��B�ɏI������B����������ɂ͌���k������B�]��͍]�Ă�9�A�����g������h���Ƃ��l���Ă����Ƃ����̂��B9�l�ڂ̑Ŏ҂�U�蓦���O�U�Ő������Ď��̑Ŏ҂��O�U�őł�����10�A���O�U�ƂȂ�Ƃ����̂ł���B�������ɂ͎O�U�����Ă��܂������ł͂Ȃ��L���b�`���[����킷��悤�ȃ����o�E���h�̃J�[�u��I�Ƃ����̂ł���B���ʁA���ꂪ��Â�����S����ł���Ă��܂����Ƃ����킯���B����ȍ]����]�ĂɕC�G����V�ѐS�̎�����ł���B
�@���̌�A�]�Ă͒ʎZ150����B��������A��]�w�Ƃ̊m���A���s��Q�A�S�������Ȃǂɂ�鐬�т̉��~�Ȃǂ���A1976�N��C�z�[�N�X�Ƀg���[�h�����B�w�ԍ���17�ɕς�����B�]�Ă͓�����ȂɈڐЂ�����ł������A��C�̑I�茓�ēE�쑺����Ƃ̉�k�ōl����ς����Ƃ����B�쑺�͈��A����ɂ����������u���N�̍L����i1975�N10��1���j�ȁA����2�X�g���C�N3�{�[���ŁA�ߊ}�Ƀ{�[������U�点�đł���������B����͈Ӑ}���ĕ���������v�B��������]�Ắu���̐l�͂킩���Ă���B���̐l�̉��Ȃ����Ă������v�Ƒ����ɓ�C��������f�����������B
�@1977�N�y�i���g���[�X�̓r���ŁA�쑺�̗͓͑I�ɒ����C�j���O�𓊂����Ȃ��Ȃ��Ă���]�ĂɁu�싅�E�Ɋv�����N����������Ȃ����v�ƃ����[�t����ւ̓]���������B�]�Ă͂���𗹏������B�]�Ă͂��̔N19�Z�[�u���}�[�N���čŗD�G�~������ɋP���B�I��̓K�����������쑺�̌����ȃ}�l�W�����g�������B���݁A���{�̃v���싅�ł͓�����O�ɂȂ��Ă��铊��̕��Ɛ��͖쑺���]�Ă̘A�g���琶�܂ꂽ�̂ł���B�]�Ă͖쑺���u�싅�Ɋւ��錩���͋��E��v�A�쑺�͍]�Ă��u�������m���Ԃ̓��]�����ō��̑�������v�ƌ݂����^������B����ɍ]�Ă͖쑺���u�����̖싅�l���̌�딼�����Ă��ꂽ�ő�̉��l�̈�l�v�Ɗ��ӂ���B
�@�Ƃ��낪���̔N�A�쑺�́A�T�b�`�[�쑺���m�㑛���œ�C����C����Ă��܂��B�]�Ắu�쑺�̂��Ȃ���C�ł��Ӗ��͂Ȃ��v�Ƃ��čL�����m�J�[�v�ɈڐЂ���B����ɂ��Ă��A���̋��E�@��̓��]�E�쑺���炪�Ȃ����̂悤�ȏ����U�̔����ɏ�芷�����̂��H�j���̒��͕s���Ƃ͂����A����͉i�v�̓�ł���B
 �@�L�����m�J�[�v�ł̔w�ԍ���26�B�����Ă��́u�]�Ă�21���v�����܂��̂ł���B1979�N11��4���A��㋅��A�V�J�A�×t�|��������L�����m�J�[�vVS���{�K�Y������ߓS�o�t�@���[�Y�̓��{�V���[�Y��7��B�o��3��3�s�A�ǂ��炪�����Ă��A�`�[�����ē����D�� �Ƃ������Ԃ������B�쑺����͂��̎������u�싅�̖{�����l�܂�����O���̃Q�[���v�Əq�����Ă���B
�@�L�����m�J�[�v�ł̔w�ԍ���26�B�����Ă��́u�]�Ă�21���v�����܂��̂ł���B1979�N11��4���A��㋅��A�V�J�A�×t�|��������L�����m�J�[�vVS���{�K�Y������ߓS�o�t�@���[�Y�̓��{�V���[�Y��7��B�o��3��3�s�A�ǂ��炪�����Ă��A�`�[�����ē����D�� �Ƃ������Ԃ������B�쑺����͂��̎������u�싅�̖{�����l�܂�����O���̃Q�[���v�Əq�����Ă���B�@4-3�ƍL����1�_���[�h����9�ߓS�̍U�����}����B�}�E���h�ɂ�7�烊���[�t�����}���̐�D�]�ĖL�B�Ƃ��낪�]�Ă̓ǂ݈Ⴂ��L���b�`���[�����̑����~�X�Ȃǂ����݃m�[�E�A�E�g���ۂ̃s���`�ƂȂ����B�}����Ŏ҂͍]�ĂƑ�����������ō��X�؋���B�����Ŋē̌×t�������B���_�������z�肵��2�l�̃s�b�`���[���u���y���ɑ��点���B����������]�Ắu����M���ł��Ȃ��̂��v�ƕ����F���ς��B�u���o�C�I�v�A���ɂ��x���`�ɂ��s���ȋْ���������E�E�E�E�E������~�����̂͐e�F�ߊ}�˗Y�������B�ߊ}�̓}�E���h�ɋ삯��肱���������u�u���y���̓u���y���ł�������Ȃ����B���O�����߂�Ȃ牴�����߂Ă���B����ƍl����Ƃ����ǂ���W�����ē�����v�B�ēƂ��Ă̌×t�̑[�u���Ó������v���C�h�����]�Ă̋C�����������ł���B�̂��̂͏�̋�C���@�m���đ��������ߊ}�ł���B���̌��t�ɋC����蒼�����]�Ă͍��X����U��O�U�ɑł����B���ߋ��͍]�Ă̋ɈӃX�g���C�N����{�[���ɊO���J�[�u�������B
�@1�A�E�g���ہA�Ŏ҂�1�ԐΓn�B���悢��`���̃V�[���ł���B��1���J�[�u��������1�X�g���C�N�B�]�Ă͂�������āu�łC�Ȃ��A�����̓X�N�C�Y�v�ƒ��������Ƃ����B����A�Γn�̓X�g���[�g��{�ɍi���Ă������瓖�R���������A�ƌ����B���{�ē͌�N�u�t�@�[�X�g�E�X�g���C�N����s���v�Ƃ��u�X�N�C�Y�����邩��T�C���ɒ��Ӂv�Ƃ������Ă���B����k�Ƃ������̂́A�L���Ɍ��h���������邩��l���X�Ƃ����P�[�X����������́B�����A��2����҂Γn�ɏo���T�C�����u�X�N�C�Y�v�������͕̂�����Ȃ��������B�]�Ă̓L���b�`���[�����ƃT�C�������킵�ăJ�[�u��I������B��������ɓ������]�ẲE�ڂ�3�ۃ����i�[�r�������̃X�^�[�g���f��B�u�X���b�I�X�N�C�Y�v�B�J�[�u�̈���̂܂ܙ�l�ɊO���B�Γn��U��A���҂̓A�E�g�B19���ځA�_�Z�Ƃ��������悤�̂Ȃ��E�F�X�g�E�{�[���������B�����2�A�E�g2�A3�ہA�J�E���g2�X�g���C�N�B�����̓t�@�E���B�����Ċ�Ղ���߂������21���A�������܂��]�Ă̋ɈӁA�X�g���C�N����{�[���ɊO���J�[�u�������B��U��O�U�Q�[���Z�b�g�B�쑺����͍]�Ă�19���ڂ��u�ނ�����܂ŕ���ł���12�N�Ԃ̃v���싅�l���̉ߒ�������Ղ̈ꋅ�v�ƕ]�����B
�@�V���[�Y�𐧂����L���͗��N�������ߓS��j��A�e�B�������ߓS�͓��{��ɂȂ�Ȃ������B��̃`�[���̂܂�2005�N���c�̗��j�����B�s�R�̏����{�����{�V���[�Y�ɏ����ƂȂ�1981�N�Ɉ��ށB�u�߉^�̖����v�Ƃ���ꂽ�B
�@�]�Ă͂��̌�A198�P�N���ēɌ���ē��{�n���ɈڐЂ��D���ɍv���A1984�N�ɂ͍L���E�����ɈڐЂ���N�őޒc�A1985�N�ɂ͕đ僊�[�O�ɒ��킷������̔N���ށA18�N�̖싅�l���Ƀs���I�h��ł����B206��158�s�A193�Z�[�u�A���U�h�䗦2.49�A�ő�����2��A�ő��D�O�U6��AMVP2��A�m�[�q�b�g�m�[�����A�܁A�x�X�g�i�C���Ȃnj����Ȑ��т��c�����B�쑺����A���[��ȂǑ��h�ł���w���҂ɂ͐S���������A�g�c�`�j�A�L���B�N�Ȃǃ\��������Ȃ��Ƃ����ۂ������B���ꂪ�]�ĖL�Ƃ����j�ł���B�C���̕����܂܂ɋZ�p�Ɗ������X�g�C�b�N�ɖ����đ�D���Ȗ싅���ɂ߂��B�L�^�ɂ��L���ɂ��c��ῂ�����̖싅�l���ł���B
�i2�j 4�̊K��24�̔w�ԍ� ���c�T���Y�̏ꍇ
�@�u���m�̈����������v�ɁA���m�ƐV���̉Ɛ��w�̂���Ȃ��Ƃ肪����B�u�N�̌C�̃T�C�Y�͂������ˁv�B�u24�ł��v�B�u24���B4�̊K��B���Ɍ����������v�B�{�͂́A��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ�24 ���c�T���Y�̘b�ł���B
 �@���c�͎��������Ƃ�1�N������4�Ԃ߂��v�����ڂ̑I��B�h���t�g2�ʂō�_�Ɏw������A2014�N�ɓ��c�B�w�ԍ���24�B���X�ɓ��p�������A3�N�ڂ�2016�N�ɂ͊J���X�^������܂łɐ��������B
�@���c�͎��������Ƃ�1�N������4�Ԃ߂��v�����ڂ̑I��B�h���t�g2�ʂō�_�Ɏw������A2014�N�ɓ��c�B�w�ԍ���24�B���X�ɓ��p�������A3�N�ڂ�2016�N�ɂ͊J���X�^������܂łɐ��������B�@���������ėՂ�2017�N�̏t�G�L�����v�B���ڂɍ����e������Ђǂ����ɂ��f���I�ɋN����B�O�̂��ߐf�Ă��������҂��獐����ꂽ�̂́u�]��ᇁB�싅�Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��B����p���K�v�v�B�v�������Ȃ��鍐�������B���A18���Ԃɋy�ԑ��p�B�Ȃ�Ƃ����͎�藯�߂����̂́A��O�ɂ͈Èł��L���邾���B�R����܂̉e���������đ̏d��16kg�������B�싅�Ȃǂ͎v�������Ȃ���Ԃ������B�p��2�������o�������钩�A���c�͖ڂ�ῂ������������B���͉̒������I�H �����Ȋ�]���萶�����B���n�r���̍b�゠���đ̗͂͂Ȃ�Ƃ��A�̏d���߂����B�����A���̂���d�Ɍ�����Ȃǎ��͂̉͑����܂܂������B
�@2018�N�A���c�͉��ق��邱�ƂȂ��琬�I��̌_������ԁB�w�ԍ���124�ɕς��B���c�̌���ɕ�ׂ������Ƀ��n�r���ɗ�މ��c�B���������͖͂߂炸�A���N�A���Ɉ��ނ����ӂ����B
�@2019�N9��26���A���c�͓�R�̌����� ��_VS�\�t�g�o���N �����c�̈��ގ����ɐݒ肵���B�琬�I��̂��߂̈��ގ����͈ٗᒆ�̈ٗ�ł���B8��\�A���c�̓Z���^�[�̎���ɂ��B����1096���Ԃ�̌�����̕��䂾�����B2�A�E�g����2�ہB�Ŏ҂̕�������ł̓Z���^�[�O�q�b�g�B���c�����ɑO�i�A���ڂ��Ȃ����͂łȂ�Ƃ��{�[�����L���b�`�B���̏u�ԁA���c�̍��r��������ꂽ�{�[���͈꒼���ɁA�܂�Ŗ�̂悤�ɁA�z�[���x�[�X�Ɍ������L���b�`���[�~�b�g�ɋz�����܂ꂽ�B�^�b�`�A�E�g�I ��ՂƂ����v���Ȃ������ȃm�[�o�E���h�����������B������x�싅����肽���I ���̈�S�Ŋ撣�葱�������c�T���Y�ւ́A����͖싅�̐_�l�̃r�b�O�ȖJ���������ɈႢ�Ȃ��B�^�Ɋ����̈��ʂ������B
 �@������̈��ރZ�����j�[�B�����ɂ͔w�ԍ�24�̃��j�t�H�[���ɒ��ւ������c�T���Y�������B�u���߂��ɖ싅�𑱂��Ă��Ė{���ɂ悩�����B�_�l�͌��Ă���Ă����Ǝv���܂��B�����b�ɂȂ����݂Ȃ��ܖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����v�B���̎����ɋ삯������R�ē��ࠑ�͉ԑ���n���Ȃ��牡�c�̎����ł����������u�����͂��O�ɑf���炵�����̂������Ă�������B���͉������̔Ԃ��B���Ă��Ă���v�B
�@������̈��ރZ�����j�[�B�����ɂ͔w�ԍ�24�̃��j�t�H�[���ɒ��ւ������c�T���Y�������B�u���߂��ɖ싅�𑱂��Ă��Ė{���ɂ悩�����B�_�l�͌��Ă���Ă����Ǝv���܂��B�����b�ɂȂ����݂Ȃ��ܖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����v�B���̎����ɋ삯������R�ē��ࠑ�͉ԑ���n���Ȃ��牡�c�̎����ł����������u�����͂��O�ɑf���炵�����̂������Ă�������B���͉������̔Ԃ��B���Ă��Ă���v�B�@�����Ȃ��I��Ɉ��ގ�����ݒ肵�����c�B�V�[�Y�����ɂ�������炸�삯������R�ēB��_�͗�Ƃ��Ȃ��₳�����`�[�����B�撣���Ėڎw���ڕW�ɓ��B���Ăق����B���c�ւ̉�����v���Ɛ^�ɉ����������Ȃ鍡�N�̍�_�^�C�K�[�X�ł���B
���Q�l������
NHK-BSP�u�]��21���v1983 O.A.
�����u���m�̈����������v�i����m�q�� �V�����Ɂj
�f��u���m�̈����������v2006
2021.05.20 (��) �F����F�搶�̂���
�@�����O�̒����V���u�����̔��v���Łu�͂܂�u���b�N�i�[�v�Ȃ�L�����������B���Ȃ��u���b�N�i�[�i1824-1896�j�Ȃ̂��͓ǂݎ��Ȃ��������A���̒��ŁA�v�X�ɉF����F�搶�i1930-2016�j�̖��O�������͉̂������������B�Ƃ����̂��A��Ў���A�搶�Ƃ͑����̂���������������ł���B�@�F��搶�́A�u�����L���[���v�Ƃ������싅�`�[���𗦂��Ă���A���R�[�h�E���[�J�[�Ƃ̎������悭�s���Ă����B�����A�r�N�^�[�E�N���V�b�N���̏����l�Ƃ��ĉ��x���v���C�������Ƃ�����B1970�N��̂��Ƃł���B�搶�͐�t�̑�t�@�����������Ƃ���w�ԍ���3(�����ł͂Ȃ�)�A�ē�2�ԓ�ێ�A�搶�̑ŐȂɌ��茩�������炷�ׂĂ��{�[���i�A���l���̓i�V�j�A�Ƃ������ʃ��[���ŃQ�[���͍s��ꂽ�B�Ƃɂ����ł��ėۂɏo�����̂ł���B�Ȃ�Ƃ�����ȃ��[���ł͂��邪�A�搶�̓����L���[���������_���H�[�^���Ȃ̂�����l�Ԃǂ��ɕ���͌��킹�Ȃ��B�܂��ɉF�여�A�����́g�I�����h�Ȃ�Ėڂ���Ȃ��̂��B�s�b�`���[�͒�̒ʖF�����������A������l�̒킳��͑n�����ŕ����p�X�e���Ƃ��������̎���������Ă���A���������������f�B�A�J�����ƕ��Ƃ͓����t���A�̗ד��m�Ƃ����������������B
�@���܂ł��v���o�����̂͑�����̉͐�~�O���E���h�Ƌ߂��̋������ł̑ł��グ�̉��ł���B����ȂƂ��̐搶�́A�]�_�ƂƂ��Ẳs��������D�����፷���ɕς��A��͘a�C�\�X���镵�͋C�ɕ�܂ꂽ���̂ł���B
 �@�F��搶�͕]�_�ƂɂȂ�O�A�l�X�ȍ����c�̎w���҂��C����Ă���w���҂��ނ���{�E�Ƃ�������B����Ȃ��Ƃ���A���̈ꋴ�I�P�̓��y�{��h�Y�Ƃ̓W���C���g�E�R���T�[�g�����x���J�Â��Ă���B2007�N9��14���A�F����FVS�{��h�Y ���M�̋����I�Ƒ肳�ꂽ�R���T�[�g�ɑ����^�B���͓����I�y���V�e�B �R���T�[�g�z�[���B�F�쎁�̓x�[�g�[���F���́u�p�Y�v�A�{�鎁�̓u���[���X��4�Ԃ����C���Ƃ����v���O�������������A�y���������͓̂�l�̉��߂̈Ⴂ������X�y�V�����E�R�[�i�[�������B���ڂ̓u���[���X�́u�n���K���[���ȑ�5�ԁv�B�{��̊y������E���Ȃ������I�ȉ��t�ɑ��F�쎁�̂���͊�z�V�O�B�A�b�Ƌ����e���|�̕ω��ɉ�ꂪ�h�b�ƕ������B�u���̕����ʔ����ł���v�Ɖ]���Ă���悤�ŁA�ƒf�Ɩz���|�����̒m�炸�̉F����F�̖ʖږ��@�ł������B�u���͎ʎ��h�A�搶�͒���۔h�v�Ƌ{��͌����B
�@�F��搶�͕]�_�ƂɂȂ�O�A�l�X�ȍ����c�̎w���҂��C����Ă���w���҂��ނ���{�E�Ƃ�������B����Ȃ��Ƃ���A���̈ꋴ�I�P�̓��y�{��h�Y�Ƃ̓W���C���g�E�R���T�[�g�����x���J�Â��Ă���B2007�N9��14���A�F����FVS�{��h�Y ���M�̋����I�Ƒ肳�ꂽ�R���T�[�g�ɑ����^�B���͓����I�y���V�e�B �R���T�[�g�z�[���B�F�쎁�̓x�[�g�[���F���́u�p�Y�v�A�{�鎁�̓u���[���X��4�Ԃ����C���Ƃ����v���O�������������A�y���������͓̂�l�̉��߂̈Ⴂ������X�y�V�����E�R�[�i�[�������B���ڂ̓u���[���X�́u�n���K���[���ȑ�5�ԁv�B�{��̊y������E���Ȃ������I�ȉ��t�ɑ��F�쎁�̂���͊�z�V�O�B�A�b�Ƌ����e���|�̕ω��ɉ�ꂪ�h�b�ƕ������B�u���̕����ʔ����ł���v�Ɖ]���Ă���悤�ŁA�ƒf�Ɩz���|�����̒m�炸�̉F����F�̖ʖږ��@�ł������B�u���͎ʎ��h�A�搶�͒���۔h�v�Ƌ{��͌����B�@�]�_�ƂƂ��ẲF����F����́A����ȉe�������B���Ƀu���b�N�i�[���悤�ɂȂ����̂͊ԈႢ�Ȃ��搶�̉e���ł���B
�l�͂悭�A�u���b�N�i�[�̓���ȂƂ��āA��4�����ȁu���}���e�B�b�N�v�������邪�A�ڂ��͂ނ���A�����Ȃ�u��8�v�̐��E�ɂƂт������ǂ��悤�ȋC������B�u��8�v�̃A�_�[�W���ƃt�B�i�[���ɂ́A�u���b�N�i�[�̖��͂������������߂��Ă���B�����ɂ́A�[���ґz�ƒ��v������A�V���̏�����A�F���̖�������A�A���v�X�̌�����������A�̑�Ȏ��R�₻���n�������_�ւ̈،h�̐S�ƁA�����Ƃ���������̂̂͂��Ȃ�������A�����̚e����ԁX�̍��肪����B�K�������e���݂₷�����y�ł͂Ȃ����A����͔��ɃX�P�[�����傫���A�������A�����ۂ����O���Ɍ����Ă��邽�߂ŁA���̒��Ɉ�x�ł����荞�߂ΝۓV�̎��J�̂��Ƃ��A�S�������Ă����ł��낤�B
 �@����͎��̒��u���ȂƂƂ��Ɂv�̈ꕶ�����A�������̃u���b�N�i�[�������Ď���B�܂��A�u���b�N�i�[�̉��y�̗����Ɋւ��ẮA�����u���[�c�@�c�g�ƃu���b�N�i�[�v�̒��ɂ���Ȉ�߂�����B
�@����͎��̒��u���ȂƂƂ��Ɂv�̈ꕶ�����A�������̃u���b�N�i�[�������Ď���B�܂��A�u���b�N�i�[�̉��y�̗����Ɋւ��ẮA�����u���[�c�@�c�g�ƃu���b�N�i�[�v�̒��ɂ���Ȉ�߂�����B
�ނ̉��y�́A���̋C�ɂȂ肳���������߂Ē����₷���A���ɉ���������Ђт����[�����邪�A���Ă��̖{���ƂȂ�ƒ����ȊO�ɂƂ炦�铹���Ȃ��̂ł���B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�ނ����̖l�ɂƂ��āA�u���b�N�i�[�͓k�ɏ璷�ŋ���ɂ���䩗m�Ƃ��Ă��݂ǂ��낪�Ȃ������B�v����ɔނ̌|�p�������Ȃ������̂ł���B���ꂪ������˔@�Ƃ��ė����ł����B�}�Ɋ�O���J�����̂ł���B���������̓u���b�N�i�[�D���̗F�l�̌��t�ł������B�w�u���b�N�i�[�̉��y��疗y����x�A����ɂ��ׂĂ��܂܂�Ă����̂��B�@�����Ȃ鎄���u���b�N�i�[����肾�����B�Ȃ̍\�������߂Ȃ��B����Ɂu�\�i�^�`���v�Ƃ���̂Ɏ��Ԃ�����Ȃ��B�Ⴆ���[�c�@���g��x�[�g�[���F����������A��1���Ƒ�2���A���`�W�J���`�Č����̗���A�Č����ɂ������2���̒����̎咲���v�̖@���ȂǁA�����������߂Δ����E�𖾂ł���B�u���b�N�i�[�͂��ꂪ�ł��Ȃ��B��1�A��2�A��3�A�e���ɍۗ��������ق�������ꂸ�A�ǂ�������̂ɋ�J����B�x�[�g�[���F���ȂǂƂ܂���������Ă��݂ǂ��낪�Ȃ��B�܂���K�݂����ȉ��y�Ȃ̂��B���������������Ȃ����Ɗ��o�Ŋy���Ⴆ�������̂��A�܂��͉��y�̌`���������Ȃ��Ɨ��������Ȃ��Ƃ����A����͎��̈����������Ȃ̂�����d�����Ȃ��B
�@����Ȏ����u���b�N�i�[�ɑ����Ȃ�Ƃ��߂Â����̂́A�F��搶�́u�����ȊO�ɂƂ炦�铹�͂Ȃ��v�Ɓu�u���b�N�i�[��疗y�v�Ƃ�����̌[���̂������ł���B�u�N�A�����Z�������v�ƌ����Ă���悤�������B
�@�Ȃ��ɂ��玁���u�l�͂ˁA���������������Ƃ����Ƃ������̂͌��܂��ău���b�N�i�[�̌����ȂȂB������Ɠ��̒����S������ۂɂȂ�B�܂��S�̏��������Ă������Ƃ��납�ȁB���[�c�@���g��x�[�g�[���F������_���B�Ђ��������Ă��܂�����v�Ƌ��Ă������A������u���b�N�i�[�̓������������Ă���Ǝv���B
 �@���̃u���b�N�i�[���̌��̓n���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V���i1888-1965�j�w���F�~�����w���E�t�B���n�[���j�[�i�E�F�X�g�~���X�^�[1963�^���j�ɂ��u��8�v�������B���_������F��搶�̐��E�ɂ��B�`���̂�����u���b�N�i�[�J�n���特�y�����X�ɍ��g���đ�2�����o�������ƁA2�������ɂ��������Ƃ������^�̗I�g����ʉ̂킹���ɏu���ɖ�����ꂽ�B�搶�͓����ɃV���[���q�g�F�E�B�[���E�t�B���iEMI 1963�^���j�������ɕ]���B�ŏI�I�ɂ͒���ޗ��F���t�B���n�[���j�[�iEXTON �T���g���[�z�[���E���C�u2001�^���j��No.1�Ƃ��Ă���i�N���V�b�N�l����100���j�B���͂���炷�ׂĂ������A�ŏI�I�ɍŏ��̃N�i�ɗ����������B����k�u�ܑ͌�ڎu�̌|�ɂ��āu��i�����̂ł͂Ȃ��l�Ԃ�����Ă���B�����������肽���v�ƌ�������A�N�i�̃u���b�N�i�[�͖{�l�ƍ�i�����v���Ă���̂�����ɐ����B���p�Ő[���ȃu���b�N�i�[�̉��y�ɃN�i�̕����ŋ���ȕ\�����h���s�V���Ƃ��Ă���̂ł���B
�@���̃u���b�N�i�[���̌��̓n���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V���i1888-1965�j�w���F�~�����w���E�t�B���n�[���j�[�i�E�F�X�g�~���X�^�[1963�^���j�ɂ��u��8�v�������B���_������F��搶�̐��E�ɂ��B�`���̂�����u���b�N�i�[�J�n���特�y�����X�ɍ��g���đ�2�����o�������ƁA2�������ɂ��������Ƃ������^�̗I�g����ʉ̂킹���ɏu���ɖ�����ꂽ�B�搶�͓����ɃV���[���q�g�F�E�B�[���E�t�B���iEMI 1963�^���j�������ɕ]���B�ŏI�I�ɂ͒���ޗ��F���t�B���n�[���j�[�iEXTON �T���g���[�z�[���E���C�u2001�^���j��No.1�Ƃ��Ă���i�N���V�b�N�l����100���j�B���͂���炷�ׂĂ������A�ŏI�I�ɍŏ��̃N�i�ɗ����������B����k�u�ܑ͌�ڎu�̌|�ɂ��āu��i�����̂ł͂Ȃ��l�Ԃ�����Ă���B�����������肽���v�ƌ�������A�N�i�̃u���b�N�i�[�͖{�l�ƍ�i�����v���Ă���̂�����ɐ����B���p�Ő[���ȃu���b�N�i�[�̉��y�ɃN�i�̕����ŋ���ȕ\�����h���s�V���Ƃ��Ă���̂ł���B �@���[�O�i�[���܂��N�i�b�p�[�c�u�b�V���Ɍ���A�Ƌ����Ă��ꂽ�̂��F��搶�ł���B�����ɁA���̃��B�[�����g�E���[�O�i�[���u�N�i��������v�ƌĂ�Ōh�����Ă����Ƃ����G�s�\�[�h���B�N�i�̃��[�O�i�[�Ő��]�^����ɋ�������̂��u�p���V�t�@���v�i1962�N�o�C���C�g���y�Ղ̃��C�u�^���j�����A�����Ƃ��Ă͂܂���i�̗����ɓ͂��Ă��Ȃ��B���̎��̒��ł̍ō���́u�����L���[���v��1���S�ȁi1957�^���j�ł���B�O�t�Ȃ̖`���A���̓��@���炵�ē��������ʋْ������Y���B�����A�W�[�N�����g�ƃW�[�N�����f�����킷��O���e�肽�郍�}���̍���B�����āA�t���f�B���O�̓o��ŋ����n�邻�̓��@�̕s�C�����d�X�����B����ɂ͑�3��ɂ�����z�����Ȃ���̏�̍��g�B���̃t���g���F���O���[�i1954�N���C�u�^���j�����̐q��Ȃ炴��\���͂ɂ͓G��Ȃ��B�F��搶�͂�����u�����܂ł���ƂȂ�ׂ����܂�������̖����v�Ɛ�^���Ă���B
�@���[�O�i�[���܂��N�i�b�p�[�c�u�b�V���Ɍ���A�Ƌ����Ă��ꂽ�̂��F��搶�ł���B�����ɁA���̃��B�[�����g�E���[�O�i�[���u�N�i��������v�ƌĂ�Ōh�����Ă����Ƃ����G�s�\�[�h���B�N�i�̃��[�O�i�[�Ő��]�^����ɋ�������̂��u�p���V�t�@���v�i1962�N�o�C���C�g���y�Ղ̃��C�u�^���j�����A�����Ƃ��Ă͂܂���i�̗����ɓ͂��Ă��Ȃ��B���̎��̒��ł̍ō���́u�����L���[���v��1���S�ȁi1957�^���j�ł���B�O�t�Ȃ̖`���A���̓��@���炵�ē��������ʋْ������Y���B�����A�W�[�N�����g�ƃW�[�N�����f�����킷��O���e�肽�郍�}���̍���B�����āA�t���f�B���O�̓o��ŋ����n�邻�̓��@�̕s�C�����d�X�����B����ɂ͑�3��ɂ�����z�����Ȃ���̏�̍��g�B���̃t���g���F���O���[�i1954�N���C�u�^���j�����̐q��Ȃ炴��\���͂ɂ͓G��Ȃ��B�F��搶�͂�����u�����܂ł���ƂȂ�ׂ����܂�������̖����v�Ɛ�^���Ă���B �@�搶�ɂ́A������Ȃ̑��ɂ��N�i�̖����̐��X��������ꂽ���A��Ԃ̂��C�ɓ���́u�E�B�[���̋x���v�i�L���O1957�^���j�ł���B����̓E�B���i�E�����c�𒆐S�Ƃ����I�Ȃ�����{�����̋Â�Ȃ���y��i�̂͂��Ȃ̂����A�ǂ������A�N�i�͋C�y�ɒ������Ă͂���Ȃ��B�ǂ������������y������Ȃ̂��B���ł����M���ׂ��̓R���U�[�N�F�����c�u�o�[�f�����v���낤���B�u�o�[�f�����v���Ăǂ�Ȗ��H ���[�c�@���g���A�����̋���̍������ɑ������u�A���F�E���F�����E�R���v�X K618�v�̃C���[�W���炷��Ώ��^���C�ȏ�����z�����邪�A�Ƃ�ł��Ȃ��B�N�i�̎�ɂ�����A�f���[�j�b�V���Ȕ������ɕϐg����̂ł���B���N�̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�ł��A���Ȃ����[�e�B�̎w���ʼn��t���ꂽ���A�ƂĂ������ȂƂ͎v���Ȃ��B���[�e�B�͗D���A�N�i�͋���B���[�e�B�������Ė��͂��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�N�i�̃C���p�N�g�ɂ͉����y�Ȃ��B���ɐ搶���g�����̍����h�Ə̂����N���C�}�b�N�X�ł̋��ǂ̋��t�͋���߂��č������B�搶�͂���ȃN�i�̉��t���g���̂���q�����V�сh�ƌ������B
�@�搶�ɂ́A������Ȃ̑��ɂ��N�i�̖����̐��X��������ꂽ���A��Ԃ̂��C�ɓ���́u�E�B�[���̋x���v�i�L���O1957�^���j�ł���B����̓E�B���i�E�����c�𒆐S�Ƃ����I�Ȃ�����{�����̋Â�Ȃ���y��i�̂͂��Ȃ̂����A�ǂ������A�N�i�͋C�y�ɒ������Ă͂���Ȃ��B�ǂ������������y������Ȃ̂��B���ł����M���ׂ��̓R���U�[�N�F�����c�u�o�[�f�����v���낤���B�u�o�[�f�����v���Ăǂ�Ȗ��H ���[�c�@���g���A�����̋���̍������ɑ������u�A���F�E���F�����E�R���v�X K618�v�̃C���[�W���炷��Ώ��^���C�ȏ�����z�����邪�A�Ƃ�ł��Ȃ��B�N�i�̎�ɂ�����A�f���[�j�b�V���Ȕ������ɕϐg����̂ł���B���N�̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�ł��A���Ȃ����[�e�B�̎w���ʼn��t���ꂽ���A�ƂĂ������ȂƂ͎v���Ȃ��B���[�e�B�͗D���A�N�i�͋���B���[�e�B�������Ė��͂��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�N�i�̃C���p�N�g�ɂ͉����y�Ȃ��B���ɐ搶���g�����̍����h�Ə̂����N���C�}�b�N�X�ł̋��ǂ̋��t�͋���߂��č������B�搶�͂���ȃN�i�̉��t���g���̂���q�����V�сh�ƌ������B�@�F��搶�̓����͒f���ɂ���B�Ƃ�悪��Ɲ�������悤�����\���Ȃ��B�꓁���f�̌����ł���B�d���Ƃ�����g�c�G�a���Ƃ͂������傫���قȂ�B�g�c���̋L�q����̓��R�[�h���Ă������ǂ������킩��Ȃ��i���̂�����́u�N�����m�v2008�N�H�ɏ������Ƃ��肾�j�B�F��搶�͗L�������킹�Ȃ��B�ۂf�ł���B���ꂼ�l�������������E�ł͂Ȃ��낤���B������A���͉F��搶�̂ق���M������B
�@�搶���E�̉��t�́A�قƂ�ǂ����̚n�D�ɍ��������A�H�ɗ�O���������B���̍ł�����̂��A���[�c�@���g�́u������ ��40�� �g�Z�� K550�v�ɂ�����W���[�W�E�Z���F�N���[�������h�nj��y�c�̉��t�i1967�N�X�^�W�I�^���j�ł���B���͂�����u���k�ȑ��`�̒��ɔ����ȃe���|�̗h�ꂪ����B���ꂼ�Z���̋Ɉӂ����ݏo�����^�Ƀ��[�c�@���g�I�Ȗ����v�ƕ]�������B����搶�́A�u��40�Ԃ̃e���|�̓����́A���ꂾ�����}���e�B�b�N�ȕ\�����������Ɗ������锤�Ȃ̂ɁA�ǂ������ōl����ꂽ�v�f�������傭����Ȃ��Ŏc����Ă���v�Ə�����Ă���B�����m��I�ɑ������u�e���|�̗h��v��搶�͜��ӓI�Ɋ�����ꂽ�̂ł���B
�@���t�\���ɂ��Ă̕]���͗l�X�ł���B����ӓI�Ɗ����邩�A���Ƒ����邩�B����͂܂��Ɏ���d�A�Ƃ������l�ɂ���ĈႤ�B�����炱���ʔ����B
�@�p�t�H�[�}���X�ɂ��āu���ӓI���ۂ��v�f�����͎����̊����ł����Ȃ����A��A�����_���I�Ȏړx�ɂ��Ă��錾�t������B��Ў���̔ӔN�A�M�y�n�̏��i����ɂ������āA�������Ƃ����Ƃ��ɉ�������肢���������Ǒ��Y����̌��t�ł���B�H���u���s�̂��q�b�g����閧�́g�Ƒn���ƃC���p�N�g�̋����h���g����Ă炤�Ɏ~�܂�ʊ����x�̍����h�ɂ���v�Ƃ������̂��B�����2005�N�ɍ����5CD-BOX�u���R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�uDOLDEN BOX�v�ɂ����������u�����w�������j�����v�Ƒ肵�����C�i�[�m�[�c�̈�߂ɂ���B�\�������ӓI���ۂ��H �u����Ă炤�Ɏ~�܂�v�Ȃ����͓Ƃ�悪��ł��蜓�ӓI�ƂȂ�B�u����Ă炤�Ɏ~�܂�ʊ����x�̍����v������A�����ɂ͕��Ր�������|�p��i�Ƃ��Ă̊������ĂԁB����͗��s�̂Ɏ~�܂�Ȃ��N���V�b�N���y�ɂ��ʂ���^�����Ǝv���Ă���B����������܂����h����]�_�Ƃ̈�l�ł���B
���Q�l������
�F����F����I�W1���[�c�@���g�ƃu���b�N�i�[�i�w�K�����Ёj
�@�@�@�@�V�@�@�@3 ���ȂƂƂ��Ɂi�w�K�����Ёj
�F����F�ӔC���E�F�N���V�b�N�l����100���i���y�V�F�Ёj
�����Ǒ��Y���F���R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�uGOLDEN BOX���C�i�[�m�[�c
CD �u���b�N�i�[�F������ ��8�� �n�Z��
�@�@�@�@�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�~�����w���E�t�B���n�[���j�[�i1963�^���j
CD ���[�O�i�[�F�y���u�����L���[���v��1�� �S��
�@�@�@�@�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�i1957�^���j
�@�@�@�@�t���g���F���O���[�w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�i1954�^���j
CD �N�i�b�p�[�c�u�b�V���^�E�B�[���̋x���i1957�^���j
�@�@�@�@�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c
CD ���[�c�@���g�F������ ��40�� �g�Z�� K550
�@�@�@�@�W���[�W�E�Z���w���F�N���[�������h�nj��y�c�i1967�^���j
2021.04.15 (��) �}�X�^�[�Y2021 ���R�p���̏����e���l����
���v�����[�O���@2017�N1��25���́u�N�����m�v�ɏ��R�p���̂��Ƃ��������B
���R�p��23�B���E�����N6�ʁA�ăc�A�[�܋������L���O2�ʁAFedEx�����L���O2�ʁB��N���獡�N�x�ɂ܂�����ăc�A�[�Ɠ��{�c�A�[�ł�5��4���̐�т����߂�B����2016�N10���ɍs��ꂽWGC-HSBC�`�����s�I���Y�̏������Ղ�͒��h���������B�ʎZ23�A���_�[�A2�ʂ̃��[���[�E�}�L���C��7�ō��̈�������WGC�j��ő��X�g���[�N���̃I�}�P�t���B���E�͓x�̂��ꂽ�B�}�L���C�́u�q�f�L�͍��T�̃t�B�[���h�ŒN�������܂����S���t��W�J�����B�ނ��`�����s�I���ɂȂ�͓̂��R���v�ƃR�����g�B�}�L���C�͐��E�����N2�ʁA���W���[3���̖���B�W���[�_���E�X�s�[�X���u���ꂩ��ԈႢ�Ȃ����x�����W���[���l��I��v�Ə̂����B�X�s�[�X�͐��E�����N5�ʁA���W���[2���̎��̃z�[�v���B�@2017�N���R�̃��W���[�́A�}�X�^�[�Y11�ʁA�S�ăI�[�v��2��T�A�S�p�I�[�v��14��T�A�S�ăv��5��T �Ƃ܂��܂��̐��тł���B�Ƃ��낪����ȍ~�A���т͉��~�������ǂ�B�}�X�^�[�Y�ɂ����ẮA 2018�N19�ʁA 2019�N32�ʁA 2020�N13�ʁA���E�����N��20�ʂɂ܂ʼn������B�����Ă��ɍ�N���A���V�G���i30�j���C�R�[�`�Ƃ��ă`�[�����R�Ɍ}�����ꂽ�B
���Q�̔��B��̂悢�A�C�A���E�V���b�g�B���ʂȏ��Z�B������������p�b�e�B���O�B���W���[�E�z���_�[�ɂ��Đ��E�����N��ʎ҂��A��l�ɏ��R�p���̑��݂��̂���Ă���B���̏����A���̒j�����W���[���e�̍Ŏ��ߋ����ɂ��邱�Ƃ̏��낤�B���҂͖c��ވ���ł���B�����A�ꌾ�������킹�Ăق����B�S���t�I��ɍD�s���̔g�͕t�����B�D���̂����͂����B���͒��q�����������B���̌�����f�����������K�ȃA�h���@�C�X��^������̂͐�C�R�[�`�������Ȃ��B���R�͖����R�[�`�������Ȃ��B�R�[�`�������Ȃ����ꗬ�S���t�@�[�͈�l�����Ȃ��B���R�p����A���}�ɐ�C�R�[�`��t����ׂ��I���ꂪ���W���[���e�̃J�M�ł���B
 �@2021�N�}�X�^�[�Y�B���R�p���i29�j��4�ō���ʂŌ}�����ŏI���̑O���A�S���t�E�e�B�[�`���O�E�v���̌����������q�ɐu���Ă݂��B�u���R�͏��Ă邩�ˁv�B
�@2021�N�}�X�^�[�Y�B���R�p���i29�j��4�ō���ʂŌ}�����ŏI���̑O���A�S���t�E�e�B�[�`���O�E�v���̌����������q�ɐu���Ă݂��B�u���R�͏��Ă邩�ˁv�B�@�u4�ō��͑傫���B���R��70�ʼn�邱�Ƃ������l���Ă�邱�Ƃ��B��������A���̑I���66���K�v�ƂȂ�B����͂��������o��X�R�A����Ȃ��B���̍��͂ł�����B�����͗D��������ɓq����v�B���ꂪ�����������B�����A�S���t���Ƃ̑��q�Ɍ����Ă����͕s���������B
�@������A�F�l�̏������`���烁�[���������B�u���ꂪ�ŏI����������Ȃ��I�����A4�ō������邩�炱��܂łƂ͈Ⴄ���ȁB�����͂ǂ��H�v�B����ɑ��āA�u4�ō��͂����ĂȂ������Ƃ��B1996�N�A���E�����N1�ʂ̃O���b�O�E�m�[�}����6�ō����Ђ�����Ԃ���ĕ������B���̓����^���B�R�[�`���t�����͍̂ő勉�̍D�ޗ��������̌��ʂ������^���ʂɂ܂ŋy�ԂȂ�\���͂���Ǝv���v�Ǝ��͓������B
�@�������R�̃����^���ʂ��뜜����悤�ɂȂ����̂́A2017�N�̑S�ăv���ƑS�ăI�[�v���̍ŏI���A���̑ΏƓI�ȏ��R�̐킢�Ԃ����������ł���B
�@6���A�G�����q���Y�ōs��ꂽ�S�ăI�[�v���B���R�͎�ʂ�6�ō��̃X�^�[�g�B�U�߂邵���Ȃ��Ō����x�X�g�X�R�A��66��@���o��2�ʃ^�C�Ńt�B�j�b�V�������B
�@8���A�N�G�C���z���[�N���u�ōs��ꂽ�S�ăv���S���t�I�茠�B���R�͎�ʂ�1�ō���2�ʂŃX�^�[�g�B�����̃W���X�e�B���E�g�[�}�X�ƗD�����������������A11�Ԃ�1m��̃p�b���O���A12�Ԃ̓O���[���E�I�[�o�[������`���b�N���A13�Ԃ�1�I�������̊�炸���炸�B�����ǂ����3�A���{�M�[��ł��E�������B
�@��ʂƂ̍��������ċC�y�ɉ���Ƃ��͔����I�ȃX�R�A���o���B�v���b�V���[�̂�����D�������ł͑��̃Q�[���ł͂��Ȃ��悤�ȃ~�X��A������B���ꂪ���W���[�̏d����������Ȃ����A�ł��A����ɑł������Ȃ���Ώ����̏��_�͔��܂Ȃ��B
��2021�N�}�X�^�[�Y�ŏI���̏��R�p����
�@���ď��R�A���N�̃}�X�^�[�Y�͂ǂ����낤���B�͂̂���̂͂킩���Ă���B4����ʂ͖��_��D�̃`�����X�ł���B�ނ������̃S���t������Ώ����Ă��s�v�c�͂Ȃ��B��������ŁA4�͐�ΓI�ȍ��ł͂Ȃ����Ƃ��ߋ��̗��j�͋����Ă���B�ۉ��Ȃ��Ɍ������Ă���v���b�V���[�ɔނ͏��Ă邾�낤���H�ٔ��̍ŏI�����n�܂����B
�@�|11�ŃX�^�[�g�̏��R��1�ԃ{�M�[�̂��Ƒ�2�ԂŃo�[�f�B�[�B���̃o���X�E�o�b�N�͑傫���B5�ԃp�[4�B5m�̃p�[�E�p�b�g�����߂ɑł��ǐ^������荞�ށB���̐ϋɂ���8�ԁA9�Ԃ̃o�[�f�B�[�ɂȂ����āA�t�����g�E�i�C���� �|2�̒ʎZ�|13�B2�ʂ�5�ō�������B�h���C�o�[�̐��x�A�A�C�A���̐�A���m�ȃA�v���[�`�A���肵���p�b�e�B���O�B�Z�p�I�ɕs���͊������Ȃ��B
�@�������Z�҂�65���o�����O���Ɠ����U���_�[�E�V���E�t�F���i27�� �āj�B���R�̍D�v���C�ɂ́u�i�C�X�E�V���b�g�v�ƋC�����ɐ���������B���R���C���悭�v���C�ł��Ă��������B�����A���g�͒��q���オ�炸�A���R�Ƃ�7�ō��������B
�@�����A���悢�揟���̃T���f�[�E�o�b�N�i�C���ł���B��A�[�����E�R�[�i�[�i11�ԁ`13�ԁj�́A13�Ԃ̃��b�L�[����`����-13���L�[�v�B14�Ԃ̓p�[�B����V���E�t�F����12�Ԃ����3�A���o�[�f�B�[�ŏ��R��4�ō��Ɣ����Ă����B�����������L���O6�ʂ̎��͎҂��B
 �@�����Č}����15��530y�p�[5�B�V���E�t�F���̓e�B�[�V���b�g���t�F�A�E�F�C�Ƀr�b�O�E�h���C�u����B���R�̓J�b�g�C���ɑł��������t�F�A�E�F�C�A�V���E�t�F���̌��40���[�h�ɒu���B����������Q�X�g����҂̋{���D��́u������}�����R���g���[���d���̃e�B�[�V���b�g�ł��ˁB2019�N�A�^�C�K�[�����������ɂ��Ԃ�܂��v�ƌ��B�Ȃ�قǁA5�z�[�����c����4�ō��Ȃ���S�^�]�����݂Ă����������͂Ȃ��B�Ȃ�Ύc��236���[�h�����C�A�b�v�Ƃ����������B���������͏��R�A��2�ł�4�A�C�A���Ńc�[�E�I���_���ɂł��B�����ꂽ�{�[���͐����悭��яo���O���[���Ɍ��������I�[�o�[�B�{�[���͖���ɂ����̒r�ɂ��܂����B�����Ȃ��ߑ��B
�@�����Č}����15��530y�p�[5�B�V���E�t�F���̓e�B�[�V���b�g���t�F�A�E�F�C�Ƀr�b�O�E�h���C�u����B���R�̓J�b�g�C���ɑł��������t�F�A�E�F�C�A�V���E�t�F���̌��40���[�h�ɒu���B����������Q�X�g����҂̋{���D��́u������}�����R���g���[���d���̃e�B�[�V���b�g�ł��ˁB2019�N�A�^�C�K�[�����������ɂ��Ԃ�܂��v�ƌ��B�Ȃ�قǁA5�z�[�����c����4�ō��Ȃ���S�^�]�����݂Ă����������͂Ȃ��B�Ȃ�Ύc��236���[�h�����C�A�b�v�Ƃ����������B���������͏��R�A��2�ł�4�A�C�A���Ńc�[�E�I���_���ɂł��B�����ꂽ�{�[���͐����悭��яo���O���[���Ɍ��������I�[�o�[�B�{�[���͖���ɂ����̒r�ɂ��܂����B�����Ȃ��ߑ��B�@�����̃e���r�ŁA�Q�X�g�̒�����K�v���Ɏi��҂��A�u���̏�ʁA���C�A�b�v�͂Ȃ������ł����v�Ǝ���B�����v���́u���肦�܂���B���ꂪ���R�̃S���t�ł�����B�����A���C�A�b�v�Ȃ�����A�Ȃ߂��Ă��܂��v�Ɠ����Ă����B�������낤���B���̈ӌ��͏����Ⴄ�B
�@�e�B�[�V���b�g���A�������]���ɂ��Ĉ��S�ɑł��o�����̂ł���A��2�ł����C�A�b�v����3�I���_���A�Ƃ����I���̂ق�����ѐ�������B�������R������������A�v�����Ԃ͂ނ���u���R�ɂ͂���ȑ��l�����������̂��v�ƈ،h�̔O������̂ł͂Ȃ��낤���B���͂����v�����A���������낤���B
�@���āA���R�̒r�̕�����̑�4�ł̓O���[���I�������A5�I��1�p�b�g�̃{�M�[�ɏI������B�g�[�^�� �|12�B�V���E�t�F���̓o�[�f�B�[�� �|10�B��l�̍��͈�C��2�Ək�܂����B7����������2�B4�A���o�[�f�B�[�Ə�蒲�q�̃V���E�t�F���Ɖ��~�C���̏��R�A16�ԃz�[���Ɍ������B
 �@16��170y�p�[3�B����܂ōŏI���̏I�ՂɁA�l�X�ȃh���}��ł��������r�̖����z�[���ł���B���̈�ۂɂ���̂�1975�N�A�W���b�N�E�j�N���E�X�̌������Ƃ��Ȃ��悤�ȋӊ쐝��Ԃ��2005�N�A�^�C�K�[�̃i�C�L�E�{�[���ł���B�܂��A����͂��Ă����A�I�i�[�̃V���E�t�F���A8��7�Ŗ����A�E����̕���������8�A�C�A����I���B�E�ɑł��o���ĕ��ɏ悹���킾�B�������A���_�t���ăt�F�[�X�����Ԃ�{�[���͍��ɁB���ʁA����ɂ��r�B�����v���́u�~�X�V���b�g����Ȃ���ˁv�͊ԈႢ���B������������R�́A�u��ɍ��ɂ͂����Ȃ��v�ƔO���ĉE�ڂɑł��o���B���̈ӎ����v�����ȏ�Ƀ{�[�����E�ɉ����o�����ƂɂȂ�O���[���E12.5m�ɃI���B����p�b�g���c�����B�t�@�[�X�g�E�p�b�g�������ȃ^�b�`��2m�ɂ���B�����v���́u���ꂪ����O���[���E�W���P�b�g��������ˁv�Ƌ{���v���ɘb��������B���̂Ƃ��肾�B���A���̃p�b�g���O���ă{�M�[�B�V���E�t�F���̓g���v���E�{�M�[�ŒE�������B�|11�̏��R�̑���́A���̎��_�ŁA18�Ԃŏォ��̒����p�[�E�p�b�g���c���U���g���X�ɑ������B�U���g���X�A5m���˂�����Ńp�[�A�|9�Ńz�[���E�A�E�g�B���R��2�ō��̃��[�h�Ŏc��2�z�[���ɗՂނ��ƂɂȂ����B
�@16��170y�p�[3�B����܂ōŏI���̏I�ՂɁA�l�X�ȃh���}��ł��������r�̖����z�[���ł���B���̈�ۂɂ���̂�1975�N�A�W���b�N�E�j�N���E�X�̌������Ƃ��Ȃ��悤�ȋӊ쐝��Ԃ��2005�N�A�^�C�K�[�̃i�C�L�E�{�[���ł���B�܂��A����͂��Ă����A�I�i�[�̃V���E�t�F���A8��7�Ŗ����A�E����̕���������8�A�C�A����I���B�E�ɑł��o���ĕ��ɏ悹���킾�B�������A���_�t���ăt�F�[�X�����Ԃ�{�[���͍��ɁB���ʁA����ɂ��r�B�����v���́u�~�X�V���b�g����Ȃ���ˁv�͊ԈႢ���B������������R�́A�u��ɍ��ɂ͂����Ȃ��v�ƔO���ĉE�ڂɑł��o���B���̈ӎ����v�����ȏ�Ƀ{�[�����E�ɉ����o�����ƂɂȂ�O���[���E12.5m�ɃI���B����p�b�g���c�����B�t�@�[�X�g�E�p�b�g�������ȃ^�b�`��2m�ɂ���B�����v���́u���ꂪ����O���[���E�W���P�b�g��������ˁv�Ƌ{���v���ɘb��������B���̂Ƃ��肾�B���A���̃p�b�g���O���ă{�M�[�B�V���E�t�F���̓g���v���E�{�M�[�ŒE�������B�|11�̏��R�̑���́A���̎��_�ŁA18�Ԃŏォ��̒����p�[�E�p�b�g���c���U���g���X�ɑ������B�U���g���X�A5m���˂�����Ńp�[�A�|9�Ńz�[���E�A�E�g�B���R��2�ō��̃��[�h�Ŏc��2�z�[���ɗՂނ��ƂɂȂ����B�@17��440y�p�[4�B���R�̑�1�ŁB�h���C�o�[���v����悭�U�蔲��FW�ǐ^�ɉ^�ԁB15�ԂƂ͑S�R�Ⴄ�U�߂̃h���C�o�[�B�ȑO�̏��R�Ȃ�Ȃ��Ă�����������Ȃ��������ŁA���̂悤�Ȋ����ȃV���b�g���łĂ��̂́A�Z�p�I�ɂ����_�I�ɂ��A�ނ������������낤�B2�I��2�p�b�g�̃p�[�B2���̃��[�h��ۂ��āA�����A����1�z�[�����B
 �@�ŏI18��465y �p�[4�B2���̓{�M�[���������B�����Ȃ��������h���C�o�[��������ꂽ�{�[���̓p���[�E�t�F�[�h�̕�������`���t�F�A�E�F�C���Z���^�[�ɁB315���[�h�̃r�b�O�E�h���C�u�ƂȂ����B�����v�����{���v�����u����v�ƙꂭ�B��2�Ŏc��134���[�hPW�B���A�ǂ��������R�A�ւȂ��傱�V���b�g�Ńo���J�[�B�{�l��B�o���J�[�V���b�g��3�I��1.5m�B�������S���B2�p�b�g�Ń{�M�[�A�g�[�^���|10�B1�ō��̏����B�ߊ�̃}�X�^�[�Y�����ă��W���[�����e�������B
�@�ŏI18��465y �p�[4�B2���̓{�M�[���������B�����Ȃ��������h���C�o�[��������ꂽ�{�[���̓p���[�E�t�F�[�h�̕�������`���t�F�A�E�F�C���Z���^�[�ɁB315���[�h�̃r�b�O�E�h���C�u�ƂȂ����B�����v�����{���v�����u����v�ƙꂭ�B��2�Ŏc��134���[�hPW�B���A�ǂ��������R�A�ւȂ��傱�V���b�g�Ńo���J�[�B�{�l��B�o���J�[�V���b�g��3�I��1.5m�B�������S���B2�p�b�g�Ń{�M�[�A�g�[�^���|10�B1�ō��̏����B�ߊ�̃}�X�^�[�Y�����ă��W���[�����e�������B�@���R�̒�������͏I������B���́u�����^���ʂ̕s���v�͞X�J�ɏI������B�u4�ō��͂ł����B���Ǝv���v�ƌ��������q�̓ǂ݂͐����������B
�@�����́A�ْ����̒��A�����̃S���t���т������Ƃ��낤�B��͂��C�R�[�`���̂͑傫�������B���R�͌����u����܂Ŏ����̊����𐳂����ƐM����l�ł���Ă����B���������A�q�ώ����Ă����l���ł����B���ꂪ���V�R�[�`���v�B�Z�p�ւ̊m�M�������^���̕s���@�����̂��낤�A����܂ł̃��W���[�Ƃ͈Ⴄ���R�������ɂ����B�܂��A�������E���h�̓���ԁA�F�D�I�ȃV���E�t�F���ƈꏏ�Ƀv���C�ł����̂��K�^�������B���ɂȂ��\��ɂ�Ƃ肪�������̂��ނ̂�������������������Ȃ��B
���G�s���[�O��
�@1936�N�̑�3����A�˓c����Y���I�[�K�X�^�E�i�V���i���̕���ɗ����Ĉȗ��A���{�l�S���t�@�[�̒���͑����Ă����B�����āA�}�X�^�[�Y���e�͂��������{�S���t�E�̔ߊ�ƂȂ�ʂĂȂ����ƂȂ����B
�@1970�N �͖썂�� 12�ʁA1973�N ���菫�i 8�ʁA1986�N ������K 8�ʁA2001�N �ɑ� 4�ʁA2009�N �ЎR�W�� 4�ʁB�����āA2021�N4��11���A���R�p�������ɔߊ�̔��������J�����B���ɒ����������̂肾�����B�����u�[�X�Œ����v���͂��ߊW�҂��j��Ō��t�ɂȂ�Ȃ������̂͂����Ƃ��ł���B
 �@2011�N�A�����{��k�Ђ�����A�}�X�^�[�Y�ւ̏o���畏����Ă������R���������A��Ђ����n�����̐l�����̂��Ɖ����������ďo������f�B���ӂ̋C���������ɐ킢�������[�E�A�}�`���A�̉h�_�ɋP�����B�u���͗D���v�Ə��N����̖�����邬�̂Ȃ��ڕW�ɕς������Ƃ��낤�B�������A���鏟���ւ̊��҂͂������傫�ȏd���Ɖ����Ĕނ��ՂB�������������̂肪�������B������10�N�ڂ̍��N�A���Ƀv���b�V���[�ɑł������Ė��ɒH������B���߂łƂ��I���R�p���I ���ɂ��Ă��A�S���t���D�҂Ƃ��āA�g�����Ă��邤���ɓ��{�l���}�X�^�[�Y�ŗD������p������h���Ƃ����������B���ꂪ���������B���肪�Ƃ��I���R�p���I
�@2011�N�A�����{��k�Ђ�����A�}�X�^�[�Y�ւ̏o���畏����Ă������R���������A��Ђ����n�����̐l�����̂��Ɖ����������ďo������f�B���ӂ̋C���������ɐ킢�������[�E�A�}�`���A�̉h�_�ɋP�����B�u���͗D���v�Ə��N����̖�����邬�̂Ȃ��ڕW�ɕς������Ƃ��낤�B�������A���鏟���ւ̊��҂͂������傫�ȏd���Ɖ����Ĕނ��ՂB�������������̂肪�������B������10�N�ڂ̍��N�A���Ƀv���b�V���[�ɑł������Ė��ɒH������B���߂łƂ��I���R�p���I ���ɂ��Ă��A�S���t���D�҂Ƃ��āA�g�����Ă��邤���ɓ��{�l���}�X�^�[�Y�ŗD������p������h���Ƃ����������B���ꂪ���������B���肪�Ƃ��I���R�p���I�@������̕\���Z�����j�[�ŏ��R�͂������A�����B
�@�u���̑f���炵���I�[�K�X�^�E�i�V���i���̏�ɗ��Ă邱�Ƃ����ꂵ���v���Ă��܂��B�����đ����̃t�@���̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����BThank You�I�v�B����ɒʖ�ɑ�����āA�u�I�[�K�X�^�E�i�V���i���̃����o�[�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����v�Ƃ��������B
�@���ɃV���v���B���R�炵���Ƃ����炵���̂����A�ł���A�I�[�K�X�^�E�i�V���i���E�����o�[�ւ̊��ӂ́A�����ꂸ�Ɍ����Ăق��������B����ɂ́A�����������J�ɁA�ł����̐��������āA�X�s�[�`���Ăق��������B�S�̒��Ɋ��ӂ̋C�������l�X����̂͂킩���Ă���B�V���C�Ȃ̂��m���Ă���B�ł����t�ɂ��Ȃ���Γ`���Ȃ��B�܂����̓����A���W���[���Z�̃Z�����j�[�ŁA��߂���v���������炵���\������A����Ȑ����������R�p���̐���p�����������̂ł���B
2021.03.20 (�y) �����炢�Ȃ� ���炪�t
 �@���шꒃ�Ɂu�߂ł����������炢�Ȃ� ���炪�t�v�Ƃ����傪����B�ꒃ�̐S��́u�������Ďq�������܂�A�t�i�����j���}���Ă߂ł����ɂ͂߂ł������A��炵���������I�ɍD�]�����킯�ł��Ȃ��A���ς�炸����ɔ@���l�ɂ��v�肷����X���B������g�����炢�h�v�Ƃ������Ƃ̂悤���B�̂�������������̊J�Ԃ���肪�������Ă���B�v���싅�̊J�����߂��B�O�N�͏H�ɍs��ꂽ�S���t�̍ՓT�}�X�^�[�Y�́A�P���4���J�Âɖ߂�B�I�����s�b�N�������������t�������{����邾�낤�B�{���Ȃ�Ζڏo�x���S�J�̏t�̂͂����A�C���́g�����炢�h�ł���B����͂�͂�u�R���i�Ёv�̂������낤�B
�@���шꒃ�Ɂu�߂ł����������炢�Ȃ� ���炪�t�v�Ƃ����傪����B�ꒃ�̐S��́u�������Ďq�������܂�A�t�i�����j���}���Ă߂ł����ɂ͂߂ł������A��炵���������I�ɍD�]�����킯�ł��Ȃ��A���ς�炸����ɔ@���l�ɂ��v�肷����X���B������g�����炢�h�v�Ƃ������Ƃ̂悤���B�̂�������������̊J�Ԃ���肪�������Ă���B�v���싅�̊J�����߂��B�O�N�͏H�ɍs��ꂽ�S���t�̍ՓT�}�X�^�[�Y�́A�P���4���J�Âɖ߂�B�I�����s�b�N�������������t�������{����邾�낤�B�{���Ȃ�Ζڏo�x���S�J�̏t�̂͂����A�C���́g�����炢�h�ł���B����͂�͂�u�R���i�Ёv�̂������낤�B�@�R���i�Ђ̓��{�ō�N�̊����́u���v���������A�䂪�Ƃ̂���́u���v�������B���N�A�T�����[�}���𑲋Ƃ����������ߍ����q���A�u�R���i�Ŏ���ł͎d�����ł��Ȃ��B���u�Ɖ����Ă���e���̉Ƃ̗m�Ԃ��������ЂÂ��邩�玖��������Ɏg�킹�Ă���Ȃ����v�Ƃ����B�{�ACD�A�ʐ^�������G�ɂ܂�m�Ԃ��ǂ��������̂��Ǝv�Ă��Ă������̂�����A�n��ɑD�Ƃ���ɔC���邱�Ƃɂ����B6���̂��Ƃł���B�까���A�{��CD���V���̃��b�N�Ɏ��܂蕨�u�m�Ԃ͌����ϐg�𐋂����B����͂���ł悩�����̂����A���̌�䂪�Ƃɂ͈ٕς��������B
�@8���ɂ́A�①�ɂ���~�A�L�b�`���̃K�X�R�����̓_�����ڂ��Ȃ��Ȃ�A9���ɂ̓g�C���̐����ɕs��������A10���ɂ͐���@���A�E�g�ƂȂ����B�����Ȃ��́A���ׂĐV�i�Ɠ���ւ��āA�����ɁA�Â��Ȃ����a���̏���j��Ă����Ԍ˂����C����V���B�Z���20�N�A�ő勉�̃��j���[�A���ƂȂ����B������܂��ɁA2020�N�A�䂪�Ƃ̊����̓��j���[�A���́u���v�Ȃ̂ł���B
�@���j���[�A�����̌��p�́ACD1��1���̋��ꏊ�������ɂȂ������ƁB�ȑO�Ȃ�u����������v�Ǝv���Ă��A���悻�̍ݏ��͔�������o���̂��ʓ|�ŁA�܂��������A�ƕ����Ă������B�Ƃ��낪���͒����������̂�Ɏ�邱�Ƃ��ł���B���q�̌��ё�ł���B
�@3��11���A�����{��k��10�N�̓��Ԃ����Ă�����A�������L���Łu�J�Ԑ錾�v�A�Ƃ̕������Ă����B�ӂƐ]�O�ނ́u�`��������u�v�����������Ȃ�B���ړ��Ă�CD��������B
�@�Ȃ��Ɠ�l�� �����u�� �`��������u�@�F���������B�ЂƂ� �҂����炢�Ă���
 �@�]�̃n�X�L�[���H�C�X�����r���O�ɐS�n�悭�����킽��B�ł�������ƕ�����Ȃ��B�Ȃ��H �����A�i���O�ՂŒ������������̂��B���Г�����1968�N�A�u���߂����H���v�̓��A���o���X�i��u�e��炢�āv�iSJX 1�j�Ɛ]�O�ށu�u���[�X���S���v�iSJX 6�j������܂����Ă����B��c�ꑾ�Y�ɂ��a�����_���ȃW���P�b�g���]�����ĂB�����Ƃ��ẮA��x�X�g�Z���[�̐X�����]�̕����D���ŁA�����pLP�������ċA���ĉ��h�̈������u�ł悭���������̂ł���B���^10�Ȃ����ׂėǂ��������A���Ɂu�`��������u�v�ɖ�����ꂽ�B���炭����CD���オ�����B�����Ă䂭CD�ɋ��ꏊ��ǂ�ꂽLP�Ղ͕ꂪ���Ă����y���̕ʑ��Ɉړ��������A2010�N�A���������������Ƃ��ɁiSJX-6���܂߁j�唼���������Ă��܂����B���ƂȂ��Ă͉���܂�邪�A�c�����͂��ȔՂ��y���ނ����Ȃ��B
�@�]�̃n�X�L�[���H�C�X�����r���O�ɐS�n�悭�����킽��B�ł�������ƕ�����Ȃ��B�Ȃ��H �����A�i���O�ՂŒ������������̂��B���Г�����1968�N�A�u���߂����H���v�̓��A���o���X�i��u�e��炢�āv�iSJX 1�j�Ɛ]�O�ށu�u���[�X���S���v�iSJX 6�j������܂����Ă����B��c�ꑾ�Y�ɂ��a�����_���ȃW���P�b�g���]�����ĂB�����Ƃ��ẮA��x�X�g�Z���[�̐X�����]�̕����D���ŁA�����pLP�������ċA���ĉ��h�̈������u�ł悭���������̂ł���B���^10�Ȃ����ׂėǂ��������A���Ɂu�`��������u�v�ɖ�����ꂽ�B���炭����CD���オ�����B�����Ă䂭CD�ɋ��ꏊ��ǂ�ꂽLP�Ղ͕ꂪ���Ă����y���̕ʑ��Ɉړ��������A2010�N�A���������������Ƃ��ɁiSJX-6���܂߁j�唼���������Ă��܂����B���ƂȂ��Ă͉���܂�邪�A�c�����͂��ȔՂ��y���ނ����Ȃ��B�@�u�`��������u�v�̃I���W�i���E�V���O����1948�N�̔����B�̏��͕��숤�q�B�r�N�^�[�E���R�[�h�̐�㏉�̑�q�b�g�ł���B�쎌��Ȃ͓��C�O�i�{���͎R�㏼��1900-1950�j�B�����ł͒��������ł���B��̖���E�l���ɔV���ɐ旧���ƈ�́A�܂��ɐ��҂Ƃ����Ă����B
�@�`�������낷�u�̍��A�����ċD�J�̋������A�`�����z�����`�L�����`�����`�E�c���g�����Ƃ����I�m�}�g�y�Ƒ��܂��āA���܂�ĎU���Ďv���o�ɕς����̕ϑJ�ɃV���N������B�Ȃ�Ƃ����Z�̍Ⴆ�Ɗ����x�̍������낤�B���Ԃ��Ȃ������ɂ���ȂɃ��_���Ŋi�������̂����܂�Ă����Ƃ́A�܂��Ɋ�ՂƂ��������悤���Ȃ��B
�@�����r�N�^�[���В���ɔz�����ꂽ�̂͐V���c�Ə��������B���̂Ƃ��A������ׂ������Ј������Ė��O�͎R��g�q����Ƃ������B����Ƃ��A���̕��������̒����ƒm�������ɂ͐S��т����肵�����̂ł���B����ɂ܂��A���N1969�N�A��q�b�g�����R�I������u�閾���̃X�L���b�g�v�̍쎌�ҁE�R��H�v�������̒��j�Ŕg�q����̌Z�ƕ����ē�x�т�����ł������B�R���i�ɕY���i���̍����͕��e����Ȃ̂��낤�B
�@�Ȃ����A�g�q����̒a�������t�����X�v���L�O���i�b���Ձj��7��14���Ƃ����̂��L�����Ă���B����菭���N��̃Z���X����f�G�ȏ����������B���C�ɂ��Ă��������邾�낤���B
 �@�u�`��������u�v�ł�����v���o���̂͐�u�����q�ł���B�f��u�j�͂炢��v��11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�ŁA��u������h�T����̎�̃����[���������̉̂��S���B���тꂽ�ꖖ�̃L���o���[�Ƃ���Ԃꂽ�̏����}�b�`���Ăǂ����m�X�^���W�b�N�ȃ��[�h�������o���Ă����B
�@�u�`��������u�v�ł�����v���o���̂͐�u�����q�ł���B�f��u�j�͂炢��v��11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�ŁA��u������h�T����̎�̃����[���������̉̂��S���B���тꂽ�ꖖ�̃L���o���[�Ƃ���Ԃꂽ�̏����}�b�`���Ăǂ����m�X�^���W�b�N�ȃ��[�h�������o���Ă����B�@�Ў��Y�ƃ����[�̏o��̏�ʂ��G�킾�����B�������̓Ђ��ԑ��̋��`�Ń��R�[�h�̃o�C�����Ă���B�ܖЂ낵�́u���Ȃ��̓��v������Ă���B�����ɒʂ肩�����������[�u�����ς蔄��Ȃ�����Ȃ����v�Ɛ���������B������ēЂ���u�s�i�C������ȁB���݂��l����Ȃ����B���̏������Ă��v�B�u�킽�� �̂������Ă�́B�������R�[�h�o�������Ƃ�������ǂˁB�����ɂȂ����ȁB����킯�Ȃ��ˁv�ƃ����[�B�Q���s��̃t�[�e������t�ƃh�T����̉̂������B�݂��̒��ɓ����̓������������̂��낤�A�������Ȃ����S���Ȃ��䎌�̃L���b�`�{�[���������B���ɏo�����邨���������Ƒ��������鋙�`�̕��i�̒��A��l���ʂ̎������₩�ɗ���Ă䂭�B�d���̎��Ԃ����������[���u�ł͂܂��A�ǂ����ʼn���v�ƌ����Ɓu�����A���{�̂ǂ����łȁv�ƕԂ��Ђ���B�ʂ�ہA�����[�́u�Z����A���O�͂Ȃ�Ă������v�Ɛu���B�u���́A�����Ė��̎ԓЎ��Y���Ă�����v�ƓЂ���B�u�ԓЎ��Y�B���Ⴀ�A�Ђ���B�������O���ˁv�ƌ����c���ċ����Ă䂭�����[�E�E�E�E�E�V���[�Y�ō��v4�x�̋������ʂ�����l�́A���ꂪ�ŏ��̏o��������B
�@�u�Ў��Y�Y��ȑ��v�ɂ͏��a�̗w�ƃN���V�b�N�y�Ȃ��ӂ�ɏo�Ă���B�u�`��������u�v�̑��ɂ��u�闈���v�A�u�z�㎂�q�̉S�v�A�V���[�x���g�u���v�A�����X�L�[���R���T�R�t�u�V�F�G���U�[�h�v�AJ.S.�o�b�n�̑g�� ��3�ԁu�A���A�v�ȂǁB���ɁA�k�C���͓����̌���`�_��`�q��ɋ����u�V�F�G���U�[�h�`�Ⴋ���q�Ɖ����v�̗���ȃ����f�B�[�́A�Y��ȑ厩�R�̕��i�ɗn������őf���炵�������B
�@�f��u�j�͂炢��v��1��̕����1969�N8���B�Ȍ�1995�N�܂ō��v48�삪����o����A�����I�f��ƂȂ����B�����͕�����ϑ��I�B1�N�ڂ�2�{�A2�N��3�{�A3�N�ڂ�3�{�Ƃ�����ł���B�ߖڂƂȂ����̂�1971�N12��29�����J�̑�8��u�Ў��Y���́v�i�}�h���i�F�r���~�q�j���낤���B�ϋq���������߂�100���l��˔j�����N����N2�{�~��ꋻ�s�Ƃ����s���̃X�^�C�����蒅�����B��ԂƂȂ����u�Ў��Y�E�E�E�E�E�v�Ƃ����^�C�g������������n�܂�B���݂ɍP��ƂȂ����u���̃v�����[�O�v�͑�9�삩��ł���B
�@�V���[�Y�̏d�v�ȃL���X�g���������͂��̍�i�܂ł��X��M�i1912-1972�j�A��9��|��13�삪�����B�Y�i1914-2005�j�A��14��|�ŏI��܂ł����������i1915-2004�j�ł���B���X�ɖ������邪�A��͂菉��̐X��M�����Q�������B�Ȃ̂ɁA��8����J�㐔�����ŋS�Ђɓ����Ă��܂��B�c�O���ɂ������B���́u�����˂��v�̑䎌�́g�Ƃڂ������ɓЂ���ւ̑��ݐ�Ȃ�������ݏo��h���킢�͗]�l�������đウ�������̊����������B
 �@�N���V�b�N���y�����߂Ďg��ꂽ�̂͑�2��u���j�͂炢��v�ł���B�}�h���i�̉Ďq�i�����I���G�j�ƈ�t�̓����i�R��w�j���f�[�g����i���X�Ńn�C�h���̌��y�l�d�t�� ��67�� �j�����u�Ђ�v��1�y�͂�������B�X�̖��O�́u�����i���X�J�C���[�N�v�ŁA���̂�����̌|�ׂ̍������Ȃ��Ȃ��ł���B�ȑO�A���̏�ʂ͂��܂�ɒZ���Č����Ƃ��Ă������A�u���O�u��イ�����̉������l���v�̒��́u�j�͂炢�� �Ђ���̃}�h���i���v�ŋC�Â����ꂽ�B�����E������BMG����̓����Łu�Ђ���t�@���N���u�v�̉���iNo005153�j�Ƃ������^�����̓Ђ���t�@���B��N����n�܂����u�j�͂炢�� �Ђ���̃}�h���i���v�͂܂�2��f�ڂ��ꂽ���������A�f��ɂ����y�ɂ����w���[�������E�����B���҂�傢�Ɋ��҂��������̂ł���B���݂ɁA�����E������BMG�r�N�^�[�ݐЎ���ɎR�c�ē��F��CD�u�Ђ���N���V�b�N�v�iBVCF1518�j�����E�������Ă���B
�@�N���V�b�N���y�����߂Ďg��ꂽ�̂͑�2��u���j�͂炢��v�ł���B�}�h���i�̉Ďq�i�����I���G�j�ƈ�t�̓����i�R��w�j���f�[�g����i���X�Ńn�C�h���̌��y�l�d�t�� ��67�� �j�����u�Ђ�v��1�y�͂�������B�X�̖��O�́u�����i���X�J�C���[�N�v�ŁA���̂�����̌|�ׂ̍������Ȃ��Ȃ��ł���B�ȑO�A���̏�ʂ͂��܂�ɒZ���Č����Ƃ��Ă������A�u���O�u��イ�����̉������l���v�̒��́u�j�͂炢�� �Ђ���̃}�h���i���v�ŋC�Â����ꂽ�B�����E������BMG����̓����Łu�Ђ���t�@���N���u�v�̉���iNo005153�j�Ƃ������^�����̓Ђ���t�@���B��N����n�܂����u�j�͂炢�� �Ђ���̃}�h���i���v�͂܂�2��f�ڂ��ꂽ���������A�f��ɂ����y�ɂ����w���[�������E�����B���҂�傢�Ɋ��҂��������̂ł���B���݂ɁA�����E������BMG�r�N�^�[�ݐЎ���ɎR�c�ē��F��CD�u�Ђ���N���V�b�N�v�iBVCF1518�j�����E�������Ă���B �@�V���[�Y���Ղ̏H�쑾��i�����͒Í⋧�́j������o�ƓЂ���̗��݂��y���������B��10��A�M�B�ޗLj�h�̗��ĂœЂ����݂��݈���ł���ƁA�ׂ̕�������ޕw�̂������ɂق됌�������̎ᑢ�̐�������u���̌̋��͂ȁA�����͊����Ė��Ƃ����Ƃ����B�������N���A���Ă˂��B���������₨�����͂ǂ����Ă��邩�Ȃ��v�B�R�m�����E�ƓЂ������J����Ƃ����ɂ����͓̂o�B�u�Z�M���v�A�u�o���v�B�u�ǂ����Ă���v�A�u���ς�炸�n���ȕ�炵��v�ƍĉ�ɂ͂��Ⴎ��l�B����ȌZ�M�Ǝɒ�̂����͎��Ɍy�����x�̕���ŁA������l���J�����������̂��B�������Ȃ��炱�̖��R���r�͑�10��ŏI���������Ă��܂��B
�@�V���[�Y���Ղ̏H�쑾��i�����͒Í⋧�́j������o�ƓЂ���̗��݂��y���������B��10��A�M�B�ޗLj�h�̗��ĂœЂ����݂��݈���ł���ƁA�ׂ̕�������ޕw�̂������ɂق됌�������̎ᑢ�̐�������u���̌̋��͂ȁA�����͊����Ė��Ƃ����Ƃ����B�������N���A���Ă˂��B���������₨�����͂ǂ����Ă��邩�Ȃ��v�B�R�m�����E�ƓЂ������J����Ƃ����ɂ����͓̂o�B�u�Z�M���v�A�u�o���v�B�u�ǂ����Ă���v�A�u���ς�炸�n���ȕ�炵��v�ƍĉ�ɂ͂��Ⴎ��l�B����ȌZ�M�Ǝɒ�̂����͎��Ɍy�����x�̕���ŁA������l���J�����������̂��B�������Ȃ��炱�̖��R���r�͑�10��ŏI���������Ă��܂��B�@�H��́A2017�N�A�u�����������������v�Ƒ肷��{�������B���̒��ŁE�E
�E�E�E�R�c�ē��A��1��ŁA�u�������v�u�������v�ƑO�c��ɕs����NG��36����o�������ƁB�R�c�g�̎B�e����͂����h�������ƒ���ł������ƁB�B�e����ɂ����鈭�����ƎR�c�ē̈ӊO�ȊW���B�H�삪�u�j�͂炢��v���~�����o�܁B1996�N8��13���̈������́u���ʂ��v�ł͑O�㖢���̓��O�ȃ��n�[�T�����s��ꂽ���ƁB���ѐM�F�̒���u�������Ȓj �������v�ւ̈�a���B���X���X���^��������M�v�ŕ`�����B�����čŌ�ɁA�u�������Ƃ���ꂽ���̎��Ԃ́A���ɂƂ��Ă͎����̎��������B���Ґl���ō��́[�����́[���������v�ƌ���ł���B���j�[�N�Șe���̉�ژ^�͍����I�f��u�j�͂炢��v�̃A�i�U�[�E�X�g�[���[�̊��������āA�Ȃ��Ȃ������[�����̂��������B
�@�u�j�͂炢��v�́A���̒��ł́A��1�삩���17��܂ł�����̐X���BBEST 10��1�A2�A5�A6�A8�A10�A11�A14�A15�A17�ł���B�܊p������A�Ō�ɁA�u�j�͂炢��vMY BEST 3�������Ă������E�E�E�E�E11�u�Ў��Y�Y��ȑ��v�i��u�����q�j�A17�u�Ў��Y�[�Ă����Ă��v�i���n��a�q�j�A10�u�Ў��Y�����v�i���瑐�O�j�B�ȏ�A����͂��̂ւ�ł��J���ɁB
���Q�l������
DVD�f��u�j�͂炢��v�S48��
CD�u�]�O�ރu���[�X���S���v
CD�u�Ђ���N���V�b�N�v�i����������BMG�r�N�^�[�j
CD�W�u�̉��v
�u�����������������v�H�쑾�쒘�i�����Ёj
2021.02.10 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������
���́F�N���V�b�N�ҁ`�Ȃ��ɂ��炳��ƃ��[�c�@���g�E�R���N�V��������� �@�u��쎍�Ƃ��I�肵�Ē��؏܍�Ƃ��������낷���[�c�@���g�E�R���N�V�����B����͂����܂���v�Ƃ������̃I�t�@�[�ɁA�Ȃ��ɂ����́u�����ˁA���Ђ�肽���ˁB�ł��ˁA�����ŏ����͓̂���B���A���M�̃I�t�@�[�������ĂƂĂ����Ԃ������Ȃ��B������ǂ����낤�A�Βk�Ȃ�\�����ǁv�Ƌt��āB���؏܂��l��������̑�쎍�ƂɎ��M�˗����E������͓̂��R���B���́u�킩��܂����B����ł����܂��傤�v�Ƒ������Ă����B�Βk�̑���͑��k�̖��ABMG JAPAN�̐�y�Ő��N�O�ސE���ꂽ���쏹�����ɂ��肢�����B���쎁�͉�Ў����т��ăN���V�b�N�Ɍg���A�Ȃ��ɂ����Ƃ͓������a13�N���܂�Ƃ������ƂŁA����͓K���������B
�@�u��쎍�Ƃ��I�肵�Ē��؏܍�Ƃ��������낷���[�c�@���g�E�R���N�V�����B����͂����܂���v�Ƃ������̃I�t�@�[�ɁA�Ȃ��ɂ����́u�����ˁA���Ђ�肽���ˁB�ł��ˁA�����ŏ����͓̂���B���A���M�̃I�t�@�[�������ĂƂĂ����Ԃ������Ȃ��B������ǂ����낤�A�Βk�Ȃ�\�����ǁv�Ƌt��āB���؏܂��l��������̑�쎍�ƂɎ��M�˗����E������͓̂��R���B���́u�킩��܂����B����ł����܂��傤�v�Ƒ������Ă����B�Βk�̑���͑��k�̖��ABMG JAPAN�̐�y�Ő��N�O�ސE���ꂽ���쏹�����ɂ��肢�����B���쎁�͉�Ў����т��ăN���V�b�N�Ɍg���A�Ȃ��ɂ����Ƃ͓������a13�N���܂�Ƃ������ƂŁA����͓K���������B�@�I�Ȃ͂Ȃ��ɂ����̈ӌ�����CD�S18���Ɍ���B���t�����̊�]��������Ċe�Ђƌ��A�X���[�Y�ɂ܂Ƃ܂����B�^�C�g���́u�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�����v�A��������2000�N10���ɐݒ肵���B
�@�I�ȂƉ��t�̑I��ɂ͂Ȃ��ɂ����̂�������v�����ꂪ�����ɂ���������B�Ⴆ�E�E�E�E�E
�@������ ��41�� �n�����u�W���s�^�[�vK551�̃u���[�m�E�����^�[�́A�����㋞�����Ă̂��떲���ɂȂ����}�[���[�F������ ��1�� �u���l�v�̎w���҂ł���h�����鉹�y�ƁB�s�A�m���t�� ��20�� �j�Z�� K466�A��24�ԃn�Z��K491�A���y�d�t�� ��4�� �g�Z��K516�A���@�C�I�����E�\�i�^ �z�Z��K304�Ȃǂ̒Z���̋Ȃ́A�t���̎��Ɋ��Y���Ă��ꂽ�i�ʂȋȁB����K304�͎���Ƀ����f�B�[��q�����قǍD���ȋȁB�u���@�C�I�������t�ȑ�4�ԁvK218 �̃n�C�t�F�b�c�̓��[�c�@���g�Ƃ̏o��ƂȂ����f��̎剉�҂ɂ��čō���̃��@�C�I���j�X�g�B�u�t���[���C�\���̂��߂̑����s�i�ȁvK477 �͎������[�c�@���g�̉��y�����Ƃ��������Ȃ��t���[���C�\���֘A�̖��ȁB�u���y�̏�k�vK522 �͊m�����镃�̎��ɍۂ��ď�������Ȃ�ȁi���͂��������Ă���ɌZ�̎����d�ˍ��킹�Ă����̂�������Ȃ��j�B�V�������c�R�b�v�ƃM�[�[�L���O�́u�̋ȏW�v�ɂ͎��g�̖����邪�A���̂܂܉̂���̂��������B
�@�����A�c��͉�����ł���B�Βk�̃^�C�g���́u���[�c�@���g�Ǝ��v�Ƃ����B
�@���̊��͂����̃N���V�b�N�I�W�ł͂Ȃ��B�Ȃ��ɂ��炪�I�ԃ��[�c�@���g�̃R���N�V�����ł���B�Ȃ��Ȃ��ɂ���Ȃ̂��H �Ȃ����[�c�@���g�Ȃ̂��H ������ɂ͂��̈Ӑ}�����m�Ɏ������K�v������B�������Ȃ��ɂ���͒��؏܂��l��������B������͊ԈႢ�Ȃ��ނ̏������낵�������҂���͂����B���ꂪ����ɂ��Βk�ɑ����Ă��܂����̂����珑�����낵�ɕC�G���钆�g�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�C���Ő��������Ă��܂��đ��v�������̂��H ���҂ƕs���ƋC�������������钆�A���悢��Βk�̓��������B
�@�Βk�ꏊ�́A�Ȃ��ɂ����s�����̃z�e���E�I�[�N���̈ꎺ�B�Βk�̉������J�Z�b�g�ɘ^�������͋N�������������̂������`�F�b�N�A������Ȃ��ɂ����Ɍ��Ă��炤�@�Ƃ����i���ɂ����B������C�S���m�ꂽ�ҏW�v���_�N�V�����̏�x���i�ȉ�N���j�Ɉ˗������B
�@�Ȃ��ɂ���VS���쏹�������̃N���V�b�N�k�`�A���[�c�@���g�k�`�͉����ɐi��ł䂭�B�Ȃ��ɂ������N���V�b�N���y�ɖڊo�߂��̂́A���w5�N���̂Ƃ��w�Z�̎��ƂŃx�[�g�[���F���̌����ȑ�6�ԁu�c���v�����Ƃ��B�����ʼn��O�]��z���o���ė܂����E�E�E�E�E����Șb����n�܂��āA���[�c�@���g�Ƃ̏o��̓n�C�t�F�b�c�剉�́u�ނ�ɉ��y���v�Ƃ����f�悾�������ƁA���Z����̓��R�[�h�������Ȃ��Đ_�ے��̃N���V�b�N�i���u���Ԃ�v�ɓ���т��肾�������ƁA���ʂ������邩�Ƃ����Ƃ��C�������[�c�@���g���܂����Ă����A����Ȏ������~���Ă��ꂽ�̂̓��[�c�@���g�̒Z���̉��y�������A���[�c�@���g�̉��y�͒��ށA���[�c�@���g�̉��y�ɂ͌��ƈł�����A�l�Ԃ̂����銴��D�荞�܂�Ă���A�����Ă���Ƃ����[�c�@���g�͉䂪�F�ƂȂ����A���[�c�@���g�̉��y�̓t���[���C�\�������ɂ͌��Ȃ��A���E�l�Ƃ��Ẳ�X�n����̐l�Ԃ̓��[�c�@���g�������Ȃ���Ȃ����A���X�A�b���e�ށB�I�Ȃ≉�t�ւ̂�����肪��t���Ō��݉����Ă���B
�@�N���V�b�N���y�Ƃ̏o��A�ߎS�Ȑ푈�̌��A�쎍�ƂɂȂ������I�Ȍo�܁A������q�ɂȂ��Ă���҂����ߌ��A���[�c�@���g�̉��y�ւ̊o���A���X �Ȃ��ɂ���̐q��Ȃ炴��l���̌��Ɖ��y�ւ̈�����O�œW�J����Ă���B���Ƃ������i�I ���̂悤��6���Ԃ������B�����͖��������e�����ɋ����[���B����Ȃ�ނ���Βk�Ő��������� �ƕG��łB�A��ہAN���Ɂu�听���������ˁB�����N�������o�����炷���Ɍ����Ă��������v�ƌ����ĕʂꂽ�B
�@������AN������u�r���ł�������Ȋ����ł��v�Ə����N�������e�����B���҂ɋ����c��ށE�E�E�E�E�����A����ȁI �ǂ�ň��R�Ƃ����B�m���ɐ����O�̘b�����t�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A�ǂ��t�ł͂Ȃ��B�����ɂȂ�Ȃ��B����ł͑Θb�̗���̃X���[�Y���ɋC�ɂȂ�Ȃ����������H ����͂�A��������̂܂܂Ȃ��ɂ����ɂ��������Ă��A���ׂĂɎ�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B����͏���������Ԃ�������B�����Ȃ��́A�������������ēǂ��t�Ɋ��������̂����Ƀ`�F�b�N�������� �Ƃ����菇�ɐ�ւ��邵���Ȃ��B�����o������߂��B�Ƃ܂��A����Ȃ킯�ŁA����������̓��X���n�܂邱�ƂƂȂ����B
�@A�H���F�Βk�̘^���e�[�v����̏����N�����iN���j�`B�H���F���������C�g�`C�H���F�Ȃ��ɂ���`�F�b�N�����`D�H���F�Z���A�E�e�E�E�E�E�E�����Ȃ�菇A�`C�H���̎������L�����Ă��������BA�̉�������B�Ń����C�g�AB�̉�������C�Œ����i�ϊ������͑����\�L�j �Ƃ�������ł���B
��A���I���W�i��
�w�Z�ň�ԍŏ��ɐe�F�ɂȂ����̂́A����ς�N���V�b�N�D���Ȑl�ԂŁA�����S���Ȃ�����������ǁA�����Ɠ�l���w���̂��ĐU����������A�X�R�A���Ȃ���̂������Ȃ��Ă��B����ŁA��w�N��̕��c���ςƒm�荇������A�ނ͐��Ƃ݂����Ȃ����炳�A�����̍��Z�����猩����B�u�ӂ�A����ȉ��y�����Ă�̂��v�Ƃ������ƂŁA�n���ɂ���āA����ł܂���������y�����Ƃɖڊo�߂��ȁB�ŁA�ނ̉e���ł��̂��납�瑁�����}�[���[�Ƃ������n�߂��킯��B�����^�[�́u���l�v���o�āA�M���[�M���[������O��B
�@����łˁu���������̒����Ȃ��Ⴞ�߂�v���Ă���ꂽ�̂��o���g�[�N��������ˁB���������Ԃ��w�����Ă��������܂�����B����ŃK���K�������āA���Z���Ƃ���܂ŃN���V�b�N�Ђ��������B���є����āu���Ԃ�v�s���āA��t�̃R�[�q�[�ł悭���肬��܂ŔS��������ł���B
��B�����������C�g
�w�Z�ň�ԍŏ��ɐe�F�ɂȂ����̂́A��͂�N���V�b�N�D���Ȑl�ԂŁA�����S���Ȃ��Ă��܂�����ł����A�ނƓ�l���w���̂��ĐU����������A�X�R�A�����Ȃ���A�̂��������Ă��܂����B���̌�A��w�N��̕��c���ς���ƒm�荇���āA���y�����Ƃɖڊo�߂��Ƃ����킯�ł��B�ނ͓����̍��Z�����猩����A���y�̐��Ƃ݂������l�ł����B�ނ̉e���ŁA�������̂��납�瑁�����}�[���[�������n�߂Ă�����ł��B�����^�[�̎w������u���l�v����������āA�}�[���[�����{�̉��y���D�ƂɐZ�����n�߂�����ł����B
�@���ꂩ��A�u���������̒����Ȃ��Ⴞ�߂���v���Ă���ꂽ�̂��o���g�[�N��������B���������Ԃ��w�����Ă��炢�܂����B����ŃK���K�������āA���Z���Ƃ���܂ŃN���V�b�N�Ђ��ł����B���т��āu���Ԃ�v�֍s���āA��t�̃R�[�q�[�ł悭���肬��܂ŔS�������̂ł��B
��C���Ȃ��ɂ��`�F�b�N����
�w�Z�ň�ԍŏ��ɐe�F�ɂȂ����̂́A��͂�N���V�b�N�D���Ȑl�ԂŁA�����S���Ȃ��Ă��܂�����ł����A�ނƓ�l�Ŏw���̂��ĐU����������A�X�R�A�����Ȃ���A�̂����肵�Ă��܂����B���̌�A��w�N��̕��c���ς���ƒm�荇���āA���y�����Ƃɖڊo�߂��Ƃ����킯�ł��B�ނ͓����̍��Z�����猩����A���y�̐��Ƃ݂����Ȑl�ł����B�ނ̉e���ŁA�������̂��납�瑁�����}�[���[���n�߂Ă�����ł��B�����^�[�̎w������u���l�v����������āA�}�[���[�����{�̉��y���D�ƂɐZ�����n�߂�����ł����B
�@���ꂩ��A�u���������̒����Ȃ��Ⴞ�߂���v���Ă���ꂽ�̂��o���g�[�N��������A�X�g�����B���X�L�[��V�A���B���������Ԃ�w�����Ă��炢�܂����B�ɂ�������Ή��y�������āA���Z���Ƃ���܂ŃN���V�b�N�Ђ��ł����B���ё��ߖ��u���Ԃ�v�֍s���āA��t�̃R�[�q�[�ł悭���肬��܂ŔS�������̂ł��B
�@�Ȃ��ɂ����̍ŏI�����͂������Ƃ����ׂ��ŁA���I�ɕ��͂����܂�B���ꂪ���͂̒B�l�̏Ȃ̂��낤�B�ł́A���̂悤�ȗ����������L���Ă����B
�p�[���ƍL���ā��L�喳�ӂŁA�r�ˁ��a�O�A�f���炵���������ɂƂ��đ厖�ȍ�ȉƂ��A�f���炵�����ˏo�����˔\�A�Ό��������悤�Ȑ���ρA�h�[���Ɖ��𗧂Ăā����̂̌����ɁA�u����Ȃ��ƌ����̂͂�߂Ă���v�Ƃ����C�����ɂȂ遨���[�c�@���g������ς��Ă��܂���
�@�Ƃ܂��A����ȋ�ł���B������3�����B����������2000�`3000�ӏ����炢�ɂȂ������낤���B����ꓬ��3�����]��ɋy�B���ߐ�ԍۂɂ́A�Ȃ��ɂ����̏o����̃z�e���ɂ܂�FAX�����邱�Ƃ��������B���\�ȘJ�͂ł͂���������ɂł͂Ȃ������B�����炩�猾���o�������Ƃ�����A���R�ł͂��邪�A�ނ���y������Ƃ������B�Ȃ��ɂ������A���g�̉��y�ς��Œ艻�����̂�����A�����Ɗy����ł���Ă����������̂ł͂Ȃ��� �Ə���Ɏv���Ă���B
�@�ŏ��͎��̒������������������㔼�͊T�ˎ��̃����C�g�ǂ���ő��v�ƂȂ����B�Ȃ��ɂ����Ƃ̂����Œm�炸�m�炸�̓��ɕ��͕\���̃X�L�����g�ɒ������̂�������Ȃ��B����܂��ɁA���؏܍�Ƃ̒��ڎw���ɂ��Ԃ�������ŁA3�����ԁA�����̓��P�����悤�Ȃ��̂������B
 �@�u�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�����vCD18���g41,580�~�i�ō��j�͗\��ǂ���2000�N�H�Ɋ����E�����̉^�тƂȂ����B�d�オ��͏�X�A������ςɊ��āA���琔�\�Z�b�g�����Ă����������B
�@�u�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�����vCD18���g41,580�~�i�ō��j�͗\��ǂ���2000�N�H�Ɋ����E�����̉^�тƂȂ����B�d�オ��͏�X�A������ςɊ��āA���琔�\�Z�b�g�����Ă����������B�@���̏��i���]�����Ă��ʁA�u���[�c�@���g���̃T�v���`�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�������v�i�A�[�e�B�X�g�n�E�X���j�Ƃ����~���[�W�b�N�E�Z���s�[�{����邱�ƂɂȂ����B����ߒ��ŕҏW�҂���A���̖{�Ɍf�ڂ��邽�߂́u�Ȃ��ɂ���̃��[�c�@���g�̌��v�I�ȕ��͂̈˗����������B���ɂ��肢�����Ƃ���A�u�ЂƂ܂���������A�R���N�V��������܂Ƃ߂Ă݂Ă�B���ꂾ�����ꂱ������������v����B��������l�Ɍ����Ă�����������v�ƌ���ꂽ�B���̌㑽���̂������o�āu���[�c�@���g�̌��ƈŁv�Ƒ肷�镶�͂��o���オ�����B���_�Ȃ��ɂ����̕��͂ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A�C���I�ɂ͍���Ƃ�������������B�Ō�ɂ��̕��̈ꕔ���͂̑����Ƃ��Čf�������B
���[�c�@���g�̌��ƈ�
�@�������[�c�@���g�ɏ��߂Ċ��������̂��A���w3�N�̂Ƃ��Ɋς��f��u�ނ�ɉ��y���v�̒��ʼn��t���ꂽ�u�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�v�̑�3�y�͂ł����B���Z�ɓ���ƁA�������y�i���ɒʂ��߁A�N���V�b�N�Ђ��̓��X���߂����̂ł����A���̂���́A�x�[�g�[���F�����}�[���[���X�g�����B���X�L�[���܂�ׂ�Ȃ������Ă��āA���[�c�@���g���������ʂȉ��y�Ƃ����ӎ��͂܂�����܂���ł����B
�@���̌�A�V�����\���̖���̗w�Ȃ̐��E�ɓ���A�Ƃ肠����������q�쎍�Ƃƌ�����悤�ɂȂ�B�Ƃ��낪�u�Z��v�Ƃ��������ɏ������ɂ����Ȃ������悤�ȌZ�Ƃ̊����������܂����B���K���ɋꂵ�݁A�����Ă����̂ɔ��A�}���ςɂƂ���Ă������X�̒��A��ԈԂ߂�ꂽ�͕̂��w�ł����ł������ł��f��ł��Ȃ����[�c�@���g�̉��y�������B
�@����܂Ń��[�c�@���g�₻�̉��y�ɑ��A�M�������g�A�D��A�������A�ǂ��l�A�Ȃǂƕ]����Ă���A�����g�������悤�Ȑ���ς������Ă����̂ł��B�Ƃ��낪�A�l���̕s���Ȏ����ɒ��������[�c�@���g�̉��y�ɁA���͐l�ԂƂ��Ă̈Â���߂��݁A�Y�݁A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��ǓƊ��������A�t�ɂ��ꂪ���ɐ�����E�C��^���Ă��ꂽ�̂ł��B
�@���[�c�@���g�͐l�Ԃ̓��ɔ�߂Ă���Â������ʁA�����I�ȕ��������A�D�������邢���ŕ`���グ���j�㏉�߂Ẳ��y�Ƃł��B����͔ނ̈�����ɑ��ėD�������琬�������Ǝ��͎v���B���[�c�@���g�̉��y�́A�����̖����~���A����h�点�A�i���̖���^���Ă���܂��B�����������[�c�@���g�̌��ƈł�m�����Ƃ��A���[�c�@���g�͎��ɂƂ��āg�䂪�F���[�c�@���g�h�ƂȂ����̂ł��B
�@���[�c�@���g��������18���I�̌㔼�́A���\�[����n�܂��ă��H���e�[���炪���R�E�����E������搂��A�l�Ԃ��{���̎p�ɗ��������錃���̎���ł����B�A�����J���Ɨ����A�t�����X�v�����N�����B�傫�������]�����Ă䂭����̌[�֎v�z�Ƃ����D�̎���Ƀ��[�c�@���g�͗����Ă����̂ł��B�ł����烂�[�c�@���g�̉��y�́A�h�C�c���y�A�I�[�X�g���A���y�A�C�^���A�E�I�y���Ȃǂƌ��肳�ꂽ���̂ł͂���܂���B�{�[�_�[���X�Ő��E�I�Ȃ��́A�܂��ɑS�l�ޓI���y�Ȃ̂ł��B
�@���̂悤�Ƀ��[�c�@���g�ɂ��Ă��܂��܍l���Ă����Ƃ��A���́u�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�����v�̕Ҏ[���v�����܂����B21���I�A�l�ނ̋��ɂ̖ړI�{�[�_�[���X�����a�Ɍ������Đi�ނׂ����E�l�Ƃ��āA�������n����̐l�Ԃ��������y�́A���[�c�@���g�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
 �@�������āu�Ȃ��ɂ����S�W�v�Ɓu�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�����v�ł��t�����������������Ȃ��ɂ��炳��B���a�`�����`�ߘa������m���Ə�M�������ċ삯�������炳��B��Ɏ��R�ƕ��a�̑��������Ă����炳��B�쎍�ƁA��ƁA�N���V�b�N���y�A�]�_�A����������ꂽ�Ɛт͕Ղ��s�ł̌�������Ă��܂��B�̗w�Ȃ̐_�����A���[�c�@���g�̖{�����A���R�ƕ��a�̑�����A�����ĕ��͂��������Ƃ̊�т��A�����Ă����������炳��B�������v���̊�Ǝ��Ɍ�����D�����፷������ۓI�������炳��B����̑�쎍�Ƃɂ��Ē��؏܍�Ƃ̗炳��Ǝd���������Ă�����������N�̌����͎��ɂƂ��Ė��̂悤�ȓ��X�ł����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���̂����͈ꐶ�Y��邱�Ƃ͂���܂���B�����Ă܂����̓����A���y�̂��ƂȂǑ傢�Ɍ�荇���܂��傤�B����܂ŁA�����Ƃ����ƕ����Ă����܂��B�ǂ������炩�ɂ��₷�݂��������B
�@�������āu�Ȃ��ɂ����S�W�v�Ɓu�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�����v�ł��t�����������������Ȃ��ɂ��炳��B���a�`�����`�ߘa������m���Ə�M�������ċ삯�������炳��B��Ɏ��R�ƕ��a�̑��������Ă����炳��B�쎍�ƁA��ƁA�N���V�b�N���y�A�]�_�A����������ꂽ�Ɛт͕Ղ��s�ł̌�������Ă��܂��B�̗w�Ȃ̐_�����A���[�c�@���g�̖{�����A���R�ƕ��a�̑�����A�����ĕ��͂��������Ƃ̊�т��A�����Ă����������炳��B�������v���̊�Ǝ��Ɍ�����D�����፷������ۓI�������炳��B����̑�쎍�Ƃɂ��Ē��؏܍�Ƃ̗炳��Ǝd���������Ă�����������N�̌����͎��ɂƂ��Ė��̂悤�ȓ��X�ł����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���̂����͈ꐶ�Y��邱�Ƃ͂���܂���B�����Ă܂����̓����A���y�̂��ƂȂǑ傢�Ɍ�荇���܂��傤�B����܂ŁA�����Ƃ����ƕ����Ă����܂��B�ǂ������炩�ɂ��₷�݂��������B�@2021�N �t
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�W
���Q�l������
�u�Ȃ��ɂ����S�W�`���Ɗ��т̓��X�vCD21���g�iBMG JAPAN�j
�u�Ȃ��ɂ��� ���[�c�@���g�E�R���N�V�����vCD18���g�iBMG JAPAN�j
�����u�Z��v�Ȃ��ɂ��璘�i���|�t�H�Ёj
�u���[�c�@���g���̃T�v���`�Ȃ��ɂ��烂�[�c�@���g�E�R���N�V�������v�i�A�[�e�B�X�g�n�E�X�j
2021.01.15 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������
 �@��N�̃N���X�}�X�E�C�u�ɂȂ��ɂ��炳����]��э���ł����B���[�c�@���g�́u���N�C�G���v���B�⛌�̋ɂ݂ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̈̑�ȍ�ƂƂ͏��Ȃ��炸��������������ł���B
�@��N�̃N���X�}�X�E�C�u�ɂȂ��ɂ��炳����]��э���ł����B���[�c�@���g�́u���N�C�G���v���B�⛌�̋ɂ݂ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̈̑�ȍ�ƂƂ͏��Ȃ��炸��������������ł���B�@�����2000�N�t�̒�������A�����������낷�j�b�|�������̃X�^�W�I�������B���j�^�[����͓��Ԃ̃G���f�B���O�ȁu�Ύ�҉́v������Ă����B�u����ő�S�W�̃v�����[�V�������I������ˁB�����ꂳ�܁v�ƂȂ��ɂ��炳��B�u�Ȃɂ����̂܂܂��ʂꂷ��͎̂₵���C�����܂��B��낵����N���V�b�N���̂��ꏏ�ɂ��܂��B�Ⴆ�w�Ȃ��ɂ���I�Ȃ̃��[�c�@���g�E�R���N�V�����x�Ƃ��v�B���̌����炱��Ȍ��t����l�ɏo�Ă����B�����Ă��̒�Ă���A���Ƃ̕t�������͉̗w�Ȃ���N���V�b�N�ɍL���邱�ƂɂȂ����B
���́F�̗w�ȕҁ`�쎍�ƁE��ƂƂ��Ă̂Ȃ��ɂ��炳���
 �@�Ȃ��ɂ��炳��Ƃ̂��t�������́A�u�Ȃ��ɂ����S�W�`���Ɗ��т̓��X�vCD21���g52,500�~(�ō�)�Ƃ����A�Ȃ��ɂ���i417�Ȏ��^�̒ʔ̏��i����n�܂����B���̑�S�W��BMG JAPAN���甭�����ꂽ�̂�1999�N2���B���̋H��̍쎍�Ƃ̍�i�͑召��킸�قڂ��ׂẴ��R�[�h��ЂɎU�݁B�����S�������쌴�_���N�́A�Ȃ��ɂ�����̗v���ɉ�����ׂ����R�[�h�e�ЂƂ̐Ղ��d�˂邱��8�N�B����Y�̖��̊����������B
�@�Ȃ��ɂ��炳��Ƃ̂��t�������́A�u�Ȃ��ɂ����S�W�`���Ɗ��т̓��X�vCD21���g52,500�~(�ō�)�Ƃ����A�Ȃ��ɂ���i417�Ȏ��^�̒ʔ̏��i����n�܂����B���̑�S�W��BMG JAPAN���甭�����ꂽ�̂�1999�N2���B���̋H��̍쎍�Ƃ̍�i�͑召��킸�قڂ��ׂẴ��R�[�h��ЂɎU�݁B�����S�������쌴�_���N�́A�Ȃ��ɂ�����̗v���ɉ�����ׂ����R�[�h�e�ЂƂ̐Ղ��d�˂邱��8�N�B����Y�̖��̊����������B�@������͔̔����i�ł���B�����C���ꂽ�̂����������B�܂��͒ʔ̃J�^���O�̍쐬�ł���B�����ł͂Ȃ��ɂ�����ƑΒk�B�u��S�W�v�̃Z�[���X�E�|�C���g���@�艺�����B�ȉ���ۓI�������������v���N�����Ă݂悤�B
���� �@�@�Ƃ���łȂ��ɂ��搶�ɂƂ��Ď����������Ƃ̖��͂Ƃ͉��ł��傤���B�@�u�������v���v�Ƃ��������̐��X�������B���̑��ɂ��A�u�����g���D���ȋȃx�X�g3�́H�v�Ƃ̎���ɂ́A�u�m�肽���Ȃ��́v�u�Ύ�҉́v�u���ɂ͏��w�̂悤�Ɂv��������ꂽ�i���݂Ɏ��́A�u�Ύ�҉́v�u�܌��̃o���v�u�O�b�h�E�o�C�E�}�C�E���u�v�Ƃ������Ƃ��납�j�B����ɁA�쎍�Ə����̈Ⴂ�⎩�g�̍���̕������ɂ��Ă͂���ȕ��Ɍ���Ă���ꂽ�B�u�쎍�Ƃ����̂�4�~100m�����[�̑�ꑖ�ҁB�����̓}���\���A���S�Ɍ̐��E�B�ł��l�̒��ŗ��҂͑Γ��B�����ď����Ƃɓ]�������킯����Ȃ��B���܂��܍��͏����̕����ʔ����Ƃ��������̂��ƁB�����炱�̑S�W���ǂ�������ƂȂ����̂͊m���ł��v�B
�Ȃ��ɂ� ����́u�����ɂȂ邱�Ƃ̊�сv�Ȃ�ł���B�����̌��ɂ�����炸�ɁA�����ɂ��Ă����āA�����̐l�Ƌ������錴���̂悤�Ȃ��̂����݂Ƃ邱�Ƃ��ȁB
�����@�@�u�Ȃ��ɂ����S�W�v�̎��^�y�Ȃ�������ƂȂ��߂������ł��A��l�̕����悭����قǑ��푽�l�ȍ�i�����o������̂��Ɗ��S���܂����A���̑��ʂ����g�����h�Ɗ֘A������̂�������܂���ˁB
�Ȃ��ɂ� �������Ǝv���܂��B�l�̎v�����̂��̂ł͂Ȃ��B���������͂����ł����Ă��A���ꂪ���̒��̐l�����̎v���Ɍq����Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B�Ⴆ�u�Ύ�҉́v�́A�m���Ɏ����̎������݂����Ȃ��̂ł͂��邯��ǁA���ꂾ�����Ⴞ�߂��A�Ǝv���Ă����Ƃ��Ɂu�I���{�����v�Ƃ����t���[�Y���V����~���Ă����B����Ōq�������A�Ǝv�����B�����Ńq�b�g���m�M������ł��B
���� �@�@�Ȃ�قǁA�u�I���{�����v���Ȃ��ɂ�����ƕ�����Ƃ̉˂����ɂȂ����킯�ł��ˁB�܂�����ŁA����܂ł����ƒ�����Ă����̎肪�搶�̉̂őh�����Ƃ����Ⴊ��������܂�����ˁB
�Ȃ��ɂ� ����܂ł̘H���Ƃ͈Ⴄ�H����~���Ă������Ƃ������Ƃ�����܂����A�l�����������Ƃ��́A�̎�ɉ̂킹�邱�Ƃ�O��Ɉ˗�����킯�ŁA���̂Ƃ��Ɏv�����Ƃ́A���̉̎肪�ꐶ���̉̂��̂��Â����ɂ͂����Ȃ��悤�ɂƂ����h�������߂Ă����ł���B
�@�Βk��̕ʂ�ۂɁA�u��������A�w�Z��x�܂��ǂ�łȂ���A�� ��������ɍ����グ�܂���v�ƌ���ꂽ�B������ɂ����������u�Z��v�i���|�t�H�Ёj�ɂ́u��S�W�����ꂳ�܂ł����I�����W�l �Ȃ��ɂ���v�Ƃ̃T�C�����Y�����Ă����B
 �@�O�N�ɔ������ꂽ�Ȃ��ɂ���̏����f�r���[��u�Z��v�́A1999�N3���A�e���r�����Ńh���}�������B�Ȃ��ɂ���̌Z�Ƀr�[�g�������A�Ȃ��ɂ���ɖL��x�i�A�����w�͓��䂩����A�����S���A�]�M���q�ȂǍ��Ȋ�Ԃ�ŋr�{�͒|�R�m�ł���B���̏����L���b�`���āA���A�e�����ƌ��B�h���}���ł́u��S�W�v���m�������A�z��ȏ�̔���グ���ʂ������B
�@�O�N�ɔ������ꂽ�Ȃ��ɂ���̏����f�r���[��u�Z��v�́A1999�N3���A�e���r�����Ńh���}�������B�Ȃ��ɂ���̌Z�Ƀr�[�g�������A�Ȃ��ɂ���ɖL��x�i�A�����w�͓��䂩����A�����S���A�]�M���q�ȂǍ��Ȋ�Ԃ�ŋr�{�͒|�R�m�ł���B���̏����L���b�`���āA���A�e�����ƌ��B�h���}���ł́u��S�W�v���m�������A�z��ȏ�̔���グ���ʂ������B�@�������n�߂Ƃ��āA�e���r�����W�I�ԑg�ւ̃u�b�L���O�A�V���E�G���ւ̋L���H��A���R�[�h�X�ł̔̔������f�B�A�~�b�N�X�E�v�����[�V������W�J�B�قږ����̂䂭���т��グ�邱�Ƃ��ł����B����͖��_�Ȃ��ɂ���̒m���x�ɋ�����̂����A�����u�Z��v�̔��łɋL���ꂽ�u�����ꂳ�܁I�v�̃T�C���ɁA���̑��Ƃ������̓w�͂ɑ����������̊��ӂ̈ӂ�\���Ă��ꂽ���Ƃ������āA���炭���ꂵ���������Ƃ����X�̂悤�Ɏv���o�����B
�@�u�Z��v�͂Ȃ��ɂ��甼���̎����`�I�����ł���B���͖��B�̉��O�]�Ő��܂�A8�ŏI����}���A���N��Ǝo��3�l�Ŗ������̓����s�̖��Ɍ̋��̏��M�Ɉ����g���Ă���B���U���̐����c�肾�����Z����i�����ł͐��V�j�́A2�N�x��ʼnƑ��ƍ����B���ʂȂ炱�����畽���Ȑ������n�܂�͂����������A���̏ꍇ�́A�]�l���y�ʔg������̐l���𑗂邱�ƂɂȂ�B�����Ă���͗Ⴆ�悤���Ȃ����قȑ��݂������Z�Ƃ̊W���̂Ȃ���Ƃ������B�����̖`�����G���f�B���O���u�Z�M�A����ł���Ė{���ɂ��肪�Ƃ��v�Ȃ̂����炻�̈ٗl�������낤�Ƃ������̂��B
�@�V�����\���̖ƂƂ��Ă�������A�Ό��T���Y�Ƃ̉^���I�ȏo������ĉ̗w�Ȃ̍쎍����|����悤�ɂȂ�B1965�N�A�����m��̂��߂ɖ����u�m�肽���Ȃ��́v����q�b�g�B�J�Ԃ����˔\�͉�������z���̔@������o���̗w�E��Ȋ������B
���̃n�������i��W�����j�A���̃t�[�K�i�U�E�s�[�i�b�c�j�A�G�������h�̓`���i�U�E�e���v�^�[�Y�j�A�u�Ԃ̎����v�i�U�E�^�C�K�[�X�j�A���̂����Ȃ݁i���q���q�j�A�V�g�̗U�f�i��W�����j�A�l�`�̉Ɓi�O�c�O�}�q�j�A��ƒ��̂������Ɂi�s�[�^�[�j�A�`���u���[�X�i�X�i��j�A���̓z��i�����`���j�A�h���t�̃Y���h�R�߁i�U�E�h���t�^�[�Y�j�A�N�͐S�̍Ȃ�����i�߉���`�Ɠ������}���`�J�j�A�����ł��ʂ�i�����m��j�A�莆�i�R�I������j�A���Ȃ��Ȃ�ǂ�����i����������݁j�A�J�����i���u��H�j�A�O�b�h�E�o�C�E�}�C�E���u�i�A���E���C�X�j�A�S�̂���i�א삽�����j�A�Ύ�҉́i�k���~���C�j�A���ɂ͏��w�̂悤�Ɂi����N�j�j�A�k����i�א삽�����j�A�܂�i�k���O�Y�j�A�킪�l���ɉ����Ȃ��i�Ό��T���Y�j�A���̖~���́i�ΐ삳���j�AAMBITIOUS JAPAN�I�iTOKIO�j���̑�q�b�g�Ȃ��n�߁A����������4000�ȁB�u�V�g�̗U�f�v�A�u�����ł��ʂ�v�A�u�k����v��3�Ȃ͓��{���R�[�h��܂ɋP���Ă���B
 �@�ȂɓZ���G�s�\�[�h�̐��X�́A������d���̍��ԂɁA��Ђ̃A�[�e�B�X�g�E���[����z�e���̋i�����Ȃǂŕ������Ƃ��ł����B�u�w�ߋ��x�Ƃ������t�͂��̉̂̊̂�����A��Ɉ����Ȃ�������v�i�m�肽���Ȃ��́j�A�u�A�����J�̉ݕ��D���������Ƃ��A�������� ����œ��{�ɋA���A�v�킸�g�n�������I�h���ĉ��Ƃ�����ł����ˁv�i���̃n�������j�B�u�o�q�̊|�������A������ăt�[�K�B�˗������Ƃ��A���ꂵ���Ȃ��Ǝv�����ˁv�i���̃t�[�K�j�A�u�I���{���� �I���{���{�������V����~��Ă����v�i�Ύ�҉́j�B�u��͏��������A���͒j�������B����A�s�[�^�[�̃W�F���_�[�ɏd�Ȃ��v�i��ƒ��̂������Ɂj�E�E�E�E�E�@�����̘b�̓e���r���ł�����Ă��邪�A���̌����璼�ڕ������Ƃ��ł����̂͋M�d�ȑ̌��������B���ɁA�w������ɍD��Œ����Ă����u���̃n�������v���A���̍���ɍ�҂̐푈�̌�������ł��悤�Ƃ͖��ɂ��v���Ă��Ȃ����������ɁA�}�W�b�N�̎햾�����ɂ������Ռ��Ɗ������o�����B
�@�ȂɓZ���G�s�\�[�h�̐��X�́A������d���̍��ԂɁA��Ђ̃A�[�e�B�X�g�E���[����z�e���̋i�����Ȃǂŕ������Ƃ��ł����B�u�w�ߋ��x�Ƃ������t�͂��̉̂̊̂�����A��Ɉ����Ȃ�������v�i�m�肽���Ȃ��́j�A�u�A�����J�̉ݕ��D���������Ƃ��A�������� ����œ��{�ɋA���A�v�킸�g�n�������I�h���ĉ��Ƃ�����ł����ˁv�i���̃n�������j�B�u�o�q�̊|�������A������ăt�[�K�B�˗������Ƃ��A���ꂵ���Ȃ��Ǝv�����ˁv�i���̃t�[�K�j�A�u�I���{���� �I���{���{�������V����~��Ă����v�i�Ύ�҉́j�B�u��͏��������A���͒j�������B����A�s�[�^�[�̃W�F���_�[�ɏd�Ȃ��v�i��ƒ��̂������Ɂj�E�E�E�E�E�@�����̘b�̓e���r���ł�����Ă��邪�A���̌����璼�ڕ������Ƃ��ł����̂͋M�d�ȑ̌��������B���ɁA�w������ɍD��Œ����Ă����u���̃n�������v���A���̍���ɍ�҂̐푈�̌�������ł��悤�Ƃ͖��ɂ��v���Ă��Ȃ����������ɁA�}�W�b�N�̎햾�����ɂ������Ռ��Ɗ������o�����B�@�Ȃ��ɂ����͂܂��A����Ƃ��A����Ȃ��Ƃ������Ă����B�u�̂Ƃ����̂͂ˁA����Ă��܂����犮�S�ɍ�҂̎�𗣂ꂿ�Ⴄ�B���F���f�B�̉̌��w�i�u�b�R�x�́w�ĂׁA�����̗��ɂ̂��āx����Ȃ�����ǁA�킪�z���𗃂ɑ��������Ȃ��ȁB���R�ɂ͂����A�݂�Ȃɓ͂����ĂˁB�q�b�g�͒������l�����߂���̂�����v�A�����ď�Ɍ��ɂ���Ă����̂́u���R�ƕ��a�v�ւ̊肢�������B
�@�Ȃ��ɂ����́u�쎍�̖��͖͂����ɂȂ邱�Ƃ̊�сv�Ƃ������A����͎���Ƃ����s�ׂ̂��Ƃł����Ď����̂��̂������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�ނ��뎁�̑n�����鎍���E�͌��̉�ł���B�����������ɂ͏㎿�Ȍ|�p�̍��肪�Y���B�Ⴆ�E�E�E�E�E�u���̃n�������v����͏��a�Ƃ�������̌��Ɖe�A�u���̃t�[�K�v����̓o�b�n�̃|���t�H�j�[�A�u�Ԃ̎����v�̓o���G�u�����̌v�A�u���̂����Ȃ݁v����̓����V���^�[�v�́u�ɏ��M�v�̎��A�u�[���v����͕��������w�̍���A�u�G�������h�̓`���v����̓m�C�V�����@���V���^�C����̌ƎႫ�c��A�u��ƒ��̂������Ɂv�ł́u�t�B�K���̌����v�̃P���r�[�m�A�u�܌��̃o���v�̓t�����X�E�I�y���̈��ʁA�u���ɂ͏��w�̂悤�Ɂv����́u�^���z�C�U�[�v�̃��F�[�k�X�̗d�����B���̑��V�����\���̉̐��E�͂����ɋy�����B
�@�Ȃ��ɂ���̍�i����͂��̂悤�ȗl�X�ȃC���[�W�����؋��̂悤�ɖc���ł���B������m�̓����E���̂��킸���ɑ��ʂł���B���ׂĂ���������Ȃ��ɂ���̊����ł���B����قǂ܂ł̑��l���A�|�p���͑��̍쎌�Ƃ���͌����Č��������Ȃ��B�@������A�����̍�i�͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂�Ă���̂��H �����炭����́A�ߎS�Ȑ푈�̌��A���������鏺�a�ւ̎v���A���R�ƕ��a�ւ̊��]�A�����邱�ƂȂ��f���V�l�̊��o�A����Ȃ��D��S�A�|�p�ւ̗����Ƌ����A�[�����w�Ƌ��{�A�m���ȐR����A�V���̃Z���X�ƃ��g���b�N�B����炪�ӑR��̂ƂȂ��ĉ��w�������N���������ʂ��낤�B���ꂱ�����V�˂Ȃ��ɂ���̋H�L�Ȃ鎍���E�Ȃ̂ł���B
 �@�Ȃ��ɂ���͂܂��A���R�ł͂��邪�A���������q�b�g�̗v�f�ł͂Ȃ����Ƃ͕S�����m���Ă���B�Ⴆ���w�̖��ȁu�Ύ�҉́v�́A���g�̐l���𓊉e����Ӑg�̎��A�l�\��̃\�[�����߂��C���[�W�������˂�̃����f�B�[�A�n����r��̖k�̑�n�ɍ����悤�ȗY��ȃA�����W�A�k���~���C�̂��肰�Ȃ����c�̂���ꐢ���̉̏��A����炪��̂ƂȂ��ăq�b�g�Ȃɐ��܂�ς�������Ƃ��悭�������Ă���B�q�b�g�̓`�[�����[�N�̎Y���ł���A�쎍�Ƃ̓����[�̑�ꑖ�҂ɉ߂��Ȃ����Ƃ����o���Ă���B�Ƒ��Ƌ����̍D�o�����X�B��������̃q�b�g�Ȃ����܂ꂽ���R�̈�������ɂ���B
�@�Ȃ��ɂ���͂܂��A���R�ł͂��邪�A���������q�b�g�̗v�f�ł͂Ȃ����Ƃ͕S�����m���Ă���B�Ⴆ���w�̖��ȁu�Ύ�҉́v�́A���g�̐l���𓊉e����Ӑg�̎��A�l�\��̃\�[�����߂��C���[�W�������˂�̃����f�B�[�A�n����r��̖k�̑�n�ɍ����悤�ȗY��ȃA�����W�A�k���~���C�̂��肰�Ȃ����c�̂���ꐢ���̉̏��A����炪��̂ƂȂ��ăq�b�g�Ȃɐ��܂�ς�������Ƃ��悭�������Ă���B�q�b�g�̓`�[�����[�N�̎Y���ł���A�쎍�Ƃ̓����[�̑�ꑖ�҂ɉ߂��Ȃ����Ƃ����o���Ă���B�Ƒ��Ƌ����̍D�o�����X�B��������̃q�b�g�Ȃ����܂ꂽ���R�̈�������ɂ���B�@�Ȃ��ɂ���̊�{���O�́u�͔̂���ĂȂ�ځv�ł���B����͍�N�旧���������������Ɠ������B���1970�N�ɂ͔N�ԃ��R�[�h����グ1500�������L�^�B����͈�l�̍�Ƃ������������O�l�����̐����ł��茻�݂��j���Ă��Ȃ��s�ł̋��������Ƃ����B�Ƃ��낪�A����ꂽ����Ȉ�ł��ׂĂ��Z��������������������Ă��܂����̂�����q��ł͂Ȃ��B�u����ł���Ă��肪�Ƃ��v�͐����ȋC�������������낤�B�����������A����قǂ܂ł̎d�ł����Ȃ�����A�u�ނ������b�ɂȂ������A��������l�̌Z�Ȃ̂�����E�E�E�E�E�v�ƌZ��̏�͂����ǂ����Ɏ��������Ă����悤���B���ꂪ�Z��Ƃ������̂�������Ȃ����A��͂�A�Ȃ��ɂ���̐S��̗D�����Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�Ȃ��ɂ�����2000�N1���A�u�Z��v�̎���u����Ԃ�Ԃ�߁v�Œ��؏܂���܂����B����͍쎍�̎���ꎞ�x�߂ď����Ɍ����������Ƃ̈���B����Ȋ��o�������낤���B�u����ŏ����ƂƂ��Ă̔����t�����Ƃ������Ƃ��ȁv�ƏƂ�Ȃ�������ꂵ�����Ɍ���Ă���ꂽ�̂���ۓI�������B����Ȏ��̑�Ȑߖڂ̎����ɑ����Ȃ�Ƃ��ւ������Ă����Ƃ́A�킪�l���̒��ŁA�傢�ɈӋ`�[�����Ƃ������B�����āA�`���̒�āu���[�c�@���g�����܂��v�Ɍq����̂ł���B
���Q�l������
�u�Ȃ��ɂ����S�W�`���Ɗ��т̓��X�vCD21���g�iBMG JAPAN�j
�����u�Z��v�Ȃ��ɂ��璘�i���|�t�H�Ёj
�Ȃ��ɂ��玩�I�WCD�u�ĂׁI�킪�z����v�i������Г����j
2020.12.05 (�y) �`���[���[�E�p�[�J�[�`�L�u�o�[�h�v��ǂ��
�v�X�ɏo������W���Y�̉����ł���B�W�����E�R���g���[���̓`���[���[�E�p�[�J�[���̂��āu�W���Y�̃��[�c�@���g�v�ƌ`�e�����B���҂���܂����V�˂Ƃ����_�ł��̌��t�͐^���ł���B�����V�˂��`�����ꂽ�ߒ��ɂ����Ă͐����ƈقȂ�B���[�c�@���g��5�ō�Ȃ��������̓V�˂������B����`���[���[��15�ŎQ�������W�����E�Z�b�V�����Ńx�C�V�[�E�o���h�̃h���}�[�ɃV���o���𓊂�������قlj��t���t�ق������B�u�݂�Ȃ������������A���Ɍ��Ă���v�ƋZ�p�̏K���ɗ�B�`���[���[�̓V�˂͕s���̐��_�Ɠw�͂̎����������̂��`����Ȃ��Ƃ�����{�Ȃ̂ł���B������{��Ƃ��ĕ��ՂœI�m�B300�Œ����̒��҂���C�ɓǂݒʂ���B�������u�v�A�Ⴆ�u�t���b�e�b�h�E�t�B�t�X�v�i����������ꂽ5�x�̉��j�Ƃ��u�A���N���E�g���v�i���l�Ɍ}�����Ĕڋ��ȑԓx���Ƃ鍕�l�̂��Ɓj�Ȃǂ̐��������ɓK�B�W���Y��A�����J�Љ�ɑa���Ă���ǂł���B����͉��y�ƃA�����J�Љ�ɐ��ʂ�����҂̋��{���낤�B���̑��A�G�s�\�[�h�͖��ځB�u�o�[�h�v�Ƃ����ď̗̂R���B�u�r�o�b�v�v�Ƃ����W���Y�p�ꂪ���ݏo���ꂽ�ߒ��B�u�������܂˂�ȁv�Ƃ����ア�l�Ԃ̂��߂Ă��̒����B���X�A�����グ����肪�Ȃ��A���ׂĂ������[�����̂��肾�B��l�̓V�˃~���[�W�V�����̐�������ʂ��āA�|�p�Ɛl�Ԑ��Ƃ̊֘A�����l���������鋻���s���Ȃ���{�ł���B�W���Y�E�t�@���݂̂Ȃ炸�A�����鉹�y�t�@���ɂ��E�߂������B
 �@����͖��F�쓈���ۖ�i�`���b�N�E�w�f�B�b�N�X���j�u�o�[�h�`�`���[���[�E�p�[�J�[�̐l���Ɖ��y�v�Ɏ������������[�ł���B�쓈������u�E�e�`�����v�̃A�i�E���X������A���w���A��5�͂܂œǂݏI�����Ƃ���ŁA�킯������Amazon�ɓ��e�������̂ł���B���̌�S7�͂����ǂ����̂ŁA�S�҂ɑ������������[�����������Ȃ����B�p�[�J�[�̐q��Ȃ炴��l���Ɣ�ނȂ����y�Ƃ̊֘A�����T���Ǝv���B
�@����͖��F�쓈���ۖ�i�`���b�N�E�w�f�B�b�N�X���j�u�o�[�h�`�`���[���[�E�p�[�J�[�̐l���Ɖ��y�v�Ɏ������������[�ł���B�쓈������u�E�e�`�����v�̃A�i�E���X������A���w���A��5�͂܂œǂݏI�����Ƃ���ŁA�킯������Amazon�ɓ��e�������̂ł���B���̌�S7�͂����ǂ����̂ŁA�S�҂ɑ������������[�����������Ȃ����B�p�[�J�[�̐q��Ȃ炴��l���Ɣ�ނȂ����y�Ƃ̊֘A�����T���Ǝv���B�i1�j�J���U�X�V�e�B�Ƃ�����
�@�J���U�X�V�e�B���J���U�X�B�ƃ~�Y�[���B�ɕ�������Ă���̂́A1820�N�ɓz��B�Ƃ��č��O���ɉ��������~�Y�[���B�ƁA1861�N�Ɏ��R�B�Ƃ��ĉ��������J���U�X�B�̏B�����J���U�X��ƃ~�Y�[���삪��������J�E�E���@���[�ɐݒ肵�����炾�Ƃ����B������Ɗ�ق��Ǝv����������ȗ��j�̎Y�����ƕ�����
 �[�������B
�[�������B�@�`���[���[�E�p�[�J�[��1920�N8��29���J���U�X�B�J���U�X�V�e�B�Ő��܂�A1927�N�̉āA�~�Y�[���B�J���U�X�V�e�B�Ɉ����z�����B�A���g�T�b�N�X�ɏo������͎̂q���̂����e�ɔ����Ă�������������A�{�i�I�ɂ�肾�����̂̓n�C�X�N�[���̃o���h�ɓ����Ă���B���K���A����11�`15���ԁA�����3�`4�N�ԑ������Ƃ����B
�@�`���[���[�͂��̂��납���y�o���h�ɓ���i�C�g�N���u���ʼn��t���n�߂��B�����̃J���U�X�V�e�B�ɂ͉��S���̃N���u�������āA�c�Ƃ�24���ԁA���y����~�ނ��Ƃ͂Ȃ��A���Ɠ����ɁA���t�A�q���A��������Ă����Ƃ����B�܂��ɐ����������ϓI���C����X�������B����Ȏh���ɖ��������̒��A�`���[���[�͉��y�ƍ��킹�}���t�@�i�ɂ�����ނ悤�ɂȂ�B�T�b�N�X�͏��߂��炤�܂��킯�ł͂Ȃ������悤���B�u�ނ̉��͑����ĊÂ����邭�A�Ђǂ��㕨�������B����тɑ����̏�B�͂������A���}�ȏ�̃~���[�W�V�����ɂȂ肻���Ȓ����͂قƂ�ǂȂ������v�Ɖ��y���Ԃ͌���Ă���B����ȃ`���[���[���������A1935�N��12���A���y�Őg�𗧂Ă錈�S�����ăn�C�X�N�[����ފw�����B
�@1936�N�̔ӏt�A�ނ̉��y�l��������Â��鎖�����N����B���M���X�W�����E�Z�b�V�����ɗՂ`���[���[���A���ǂ��ǂ����\����W�J���A�����ɃV���o�������ł����̂ł���B�������̂̓J�E���g�E�x�C�V�[�y�c�̃h���}�[�A�W���[�E�W���[���Y�B�u�������� �������v�̈ӎv�\���������B�`���[���[�͚}�������w�ɗ������邵���Ȃ������B�u�݂�Ȃ�������������ǁA���Ɍ��Ă���v�̋C���������ɍ���ŁB�����ė��N�̉āA�~�Y�[���B�암�̃��]�[�g�n�I�U�[�N�����ł̖ғ��P�ɂ�艹�y�̋Ɉӂ����ށB�s���̃N���u�ɕ��A�����`���[���[�̌��I�i���ɁA�~���[�W�V�������Ԃ́u�M�����Ȃ��قǕς���Ă����v�Ƌ��Q�����Ƃ����B
�@1936�N���ӍՂ̓��A�I�U�[�N�Ɍ������`���[���[�̎Ԃ������܂�ŃX���b�v�����]���̂��N�����B�`���[���[�͘]����3�{�܂���������B��҂͎��ÂɃ����q�l���g�p�B���ꂪ�`���[���[�̐l���ɈÂ��e�𗎂Ƃ����ƂɂȂ閃��ˑ��̌����ƂȂ����B
�@�J���U�X�V�e�B�̓`���[���[�E�p�[�J�[�Ƃ����H��̉��y�ƂK�R�̒��ł���B�����o�Ă���������Ε����߂����B�ނ����Ƃ��A��A�f�B�͂����ɖ��������B�ނ̐l�����ʂ������Ɖe�A���y�Ɩ�����o�������B�����Ă�܂Ȃ��̋��ɂ��č���������Z�̒n�B���ꂪ�`���[���[�E�p�[�J�[�̃J���U�X�V�e�B�Ȃ̂ł���B
�i2�j�`���[���[�E�p�[�J�[�ɂ����鈫�l���@�̂�����
 �@�`���[���[�E�p�[�J�[�͂Ƃ�ł��Ȃ��j�ł���B��ɗF�B�ɂ������Ȃ��A��Ɉꏏ�Ɏd�����������Ȃ��A�Ǝv���B����͂������낤�B�ނ̐l�ԂƂ��Ă̂��炵�Ȃ��͏�O���킵�Ă��邩�炾�B
�@�`���[���[�E�p�[�J�[�͂Ƃ�ł��Ȃ��j�ł���B��ɗF�B�ɂ������Ȃ��A��Ɉꏏ�Ɏd�����������Ȃ��A�Ǝv���B����͂������낤�B�ނ̐l�ԂƂ��Ă̂��炵�Ȃ��͏�O���킵�Ă��邩�炾�B�@�`���[���[�͎��g�̃o���h�����O�ɂ������̃o���h��n��������B�W���[�W�EE�E���[�A�g�~�[�E�_�O���X�A�o�X�^�[�E�X�~�X�A�W�F�C�E�}�N�V�����A�n�[�����E���i�[�h�A�A�[���E�n�C���Y���X�B
�@�ނ̍s��͊ւ�������ׂẴo���h���[�_�[���肱���点���B����́A�A�[���E�n�C���Y�́u�`���[���[�͉�������܂ł̐l���ŏo������Ȃ��ōň��̒j���v�Ƃ̃R�����g�ɏW���B�ނ͒N���^���ł��Ȃ����|�I�ȃp�t�H�[�}���X���������ŁA�z����₷��f�s�̈�����I�悵���B�ނ͐��U�����f���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�������̂قƂ�ǂ�����ɏ������B�����Ȃ���o���h���Ԃ�����B�肽����Ԃ��Ă���������͈̂�l�����Ȃ��B�o���h���炠�Ă���ꂽ�T�b�N�X�����ɓ���ċ��Ɋ�����B�d����ɂ͂��̂܂�Ԃ�Ō����B�N�X������ɓ���邽�߂ɂ͂ǂ�ȉ����ւ����������B������x���̏�K�Ƃł���B�o���h�ɂƂ��Ă���قǖ��f�Ȑl�Ԃ͂��Ȃ��B�����A�ނ̓��̒��ɂ͖���Ɖ��y�����Ȃ������̂��B�n�C���Y���������g�ň��̒j�h�Ƃ������t�ɂ́A�u�]�l�������đウ�������v���C�����邩�����������Ȃ������������Ȃ����Ȓj�v�Ƃ����`���[���[�E�p�[�J�[�ւ̞H��������v�������߂��Ă���B
�@��������Ń`���[���[�͖��ނɗD������ʂ��������l�Ԃ������B�Ӗڂ̃s�A�j�X�g�A���j�[�E�g���X�^�[�͂����q������B
���̃O���[�v���`���[���[�̃N�C���e�b�g�Ƒo���ŏo�����Ă����Ƃ��̂��ƁB���̃Z�b�g���I��������ƁA��������ɉ��t���Ă��������o�[�͎����c���ăX�e�[�W���狎�����B�ނ�͂킽�����ЂƂ�ł����v�Ȃ��Ƃ�m���Ă������A�����m��Ȃ������o�[�h�͎����X�e�[�W�ō����Ă���Ǝv�����B�ނ̓X�e�[�W�ɋ삯���A���t���f���炵�������ƍ����A����ƂȂ����ɕt���Y���ăX�e�[�W���牺�肽�B�ނ͂��̋ƊE�̒N�������ɐe�������B�@�s�A�j�X�g�̃n���v�g���E�z�[�Y�͂����������B
�o�[�h�͎��ɉ������ڂ��Ă��ꂽ�B�܂�ŌZ�M�̂悤�������B�ނ͎��ɁA�u�����̉��y�������ɕۂāA�������g�ɒ����ɂȂ�A����ɂ��ڂ��ȁv�ƒ������Ă��ꂽ�B�����āA�u���̌������Ƃ����A���̂�邱�Ƃ͂��ȁv�ƌ������B�@�Ȃ�Ƃ����e�Ȑl�Ԃ��낤�B�Ȃ�Ƃ����S�̗D�����l�Ԃ��낤�B�����Ɣ��������B�����ƓV�g����������B���G�ɂ܂�Ȃ��`���[���[�̋C���ł���B�ǂ��炪�^���̃`���[���[�Ȃ̂��B�ǂ�����^���̃`���[���[�ł���B
�@�e�a�́g���l���@�h�̋�����������B�u�P�l�Ȃ����ĉ������Ƃ��B�����∫�l����v�B���̈Ӗ��́H�E�E�E�E�E�l�Ԃ͈����Ȃ����̂��B���l�Ƃ͔ϔY�∫�����o���Ă���l�Ԃł���B�P�l�͂�������o���������͑P�l���Ǝv������ł���l�Ԃł���B���������o���琶������̂ł���Ȃ�A�l�ԂȂ�K�����͂��̈��Ƃ������̂����o���鈫�l�̕��������ւ̓��͊J���Ă���E�E�E�E�E�� �������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�@�u���̌������Ƃ����A���̂�邱�Ƃ͂��� Do as I say, not as I do�v�B���̃`���[���[�E�p�[�J�[�̌��t�́A�u���Ȃ̈������o�����l�Ԃ̂܂��Ƃ��ȓ��̋����v�ł���B�e�a�́u���l���@�v�Ƃ͂����������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���̂ł���B
�i3�j�`���[���[�E�p�[�J�[�̉��y
 �@�`���[���[�E�p�[�J�[�����߂ăf�B�W�[�E�K���X�s�[�ɉ�����̂�1940�N6�����������B���̎��K���X�s�[�͂����������B�u���̒j������Ă��邱�Ƃɂт�����V�����B�ނ̂悤�ȉ��̑g�ݗ��ĕ��́A��x�����������Ƃ��Ȃ������B�g�k������قNJ��������v�B���N��l�̓j���[���[�N�ōĉ�A�������d�˂Ȃ���W���Y�̊v���u�r�o�b�v�v�ݏo���B�u�r�o�b�v�v�̓K���X�s�[����������t�����A������@�ɃW���Y�̓_���X�̔��t���y����Ϗ܉��y�ւƒE�炵�A���_���E�W���Y�ւ̓�������B
�@�`���[���[�E�p�[�J�[�����߂ăf�B�W�[�E�K���X�s�[�ɉ�����̂�1940�N6�����������B���̎��K���X�s�[�͂����������B�u���̒j������Ă��邱�Ƃɂт�����V�����B�ނ̂悤�ȉ��̑g�ݗ��ĕ��́A��x�����������Ƃ��Ȃ������B�g�k������قNJ��������v�B���N��l�̓j���[���[�N�ōĉ�A�������d�˂Ȃ���W���Y�̊v���u�r�o�b�v�v�ݏo���B�u�r�o�b�v�v�̓K���X�s�[����������t�����A������@�ɃW���Y�̓_���X�̔��t���y����Ϗ܉��y�ւƒE�炵�A���_���E�W���Y�ւ̓�������B�@�`���[���[�E�p�[�J�[�Ɂg�o�[�h�h�Ƃ����ď̂����߂ėp����ꂽ�̂�1945�N11���̃_�E���r�[�g���ゾ�����B���ɂȂ����͎̂��̂悤�Ȉꌏ����B�`���[���[�̋����o���h�i�W�F�C�E�}�N�V�����y�c�j�̎Ԃ��c�A�[���Ƀ��[�h�o�[�h�i�j���g���j��瀂��Ă��܂����A�`���[���[�͖�������Ƃ̏���l�ɂ�����������u���̃��[�h�o�[�h�𗿗����Ă���Ȃ����v�Ɨ��Ƃ����B�ȗ��A�o���h���Ԃ͔ނ̂��Ƃ��g�o�[�h�h�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B���݂ɃK���X�s�[�́g���[�h�h�ƌĂƂ����B
�@���ΖʂŃo�[�h�̉��y�ɋ��Q�����K���X�s�[�́A5�N��A�u�`���[���[�E�p�[�J�[�͉��̖��m�����ۗ����Ă���B�ނ̂ЂƂ̉����玟�̉��ւƈڂ�Ƃ��̃X���[�Y�ȗ���́A���ɂ͐^���ł��Ȃ������v�ƕʊp�x����̕]����������B
�@�]�_�ƃ��i�[�h�E�t�F�U�[�̌��B�u�p�[�J�[�͂Ƃق����Ȃ����ٓI�ŕ��O�ꂽ�A���g�E�}�����B�ނ̃\���E���[�N�͌��o���Ă���B����1���Ԃ�500�̉��������t���Ȃ�������Ȃ��Ƃ�����A�ނ͂��̂����鉹���ɂȂ�炩�̈Ӗ����������Ȃ��牉�t���邱�Ƃ��ł���v�B
�@�����̎^�����悻�Ƀo�[�h�{�l�͂����b���B�u����͂����̉��y���E�E�E�E�E���͂��ꂢ�ɐ������Ƃ��Ă��邵�A�������������߂Ă��邾���Ȃv�B�Ȃ�Ƃ����הO�̂Ȃ����낤�B�ނ̉��y����ɂ��ݏo�邻���͂��ƂȂ��C�i�́A���������Ă��̂�����ɋN������̂�������Ȃ��B
�@�W�����E�R���g���[���͂���Ȍ��t���c���Ă���B
�p�[�J�[�̓W���Y�̃��[�c�@���g���B���[�c�@���g��35�̐��U�ʼn��y�̂��ׂĂ��Ȃ������A�p�[�J�[��34�ŃW���Y�̂��ׂĂ��Ȃ��������B�@��Ґ쓈���̂��Ƃ����ɂ́u�p�[�J�[�������I�ȈӖ��ŃW���Y�E���������A�_������I�ȗ͂��y�ڂ��Ă����̂�1948�N����܂ł������Ƃ���Ă���v�Ƃ���B����ɕ���āA�o�[�h�̂��̎����̃p�t�H�[�}���X���uThe Savoy Recordings�v�i1944-1948�^���j����T���Ă݂悤�B���݂ɂ���CD-Copy�͐쓈�������������̂ł���B
���o�[�h�̉��̗������̗ǂ��ƘA���̊��炩���͎��^���ꂽ30�Ȃ��ׂĂŊ��m�����B�܂��Ƀo�[�h�̔��āB�܂�Ń��[�c�@���g�u�t�B�K���̌����v���Ȃ̖`���̂悤�ł���B���̕����A������5�b�̊Ԃ�2�x�Ōq����39�̉������A�Ȃ��Ă���̂����A�o�[�h���t�ł钹�����R�ɋ���т܂���s���̂悤�ȉ��^�͂���Ɠ����ł���B�܂��u�o�[�h�v�{�����ɁA�u�ނ͎ʐ^�̂悤�ȋL���͂������Ă����v�Ƃ��邪�A����̓��[�c�@���g��9��������Ȃ�o�`�J����O�s�o�̔�ȁu�~�[���[���v����x�Ŋ��S�ËL�����G�s�\�[�h��A�z��������̂��B
���uKoko�v�i1945�j�ɂ�����͊����鐄�i�͂Ɩ쐫�I���Y���̓X�g�����B���X�L�[�́u�t�̍ՓT�v�̌��n�y�����Ɍq����B�u�o�[�h�v�̖{���ɁA�u�p�[�J�[�̓X�g�����B���X�L�[����D���������v�Ƃ����L�q���������������B
���uChasin' the Bird�v�i1947�j�ɂ�����Έʖ@�I�����f�B�[���C���́A���ݍ�����������������ƕ��������A�u�t�̍ՓT�v�̊ɏ������A�Ⴆ�Α�2���u���Ƃ߂����̐_��Ȃǂ��v�Ȃǂ�A�z������B�o�[�h�ƃX�g�����B���X�L�[�̉��y�ɂ́A�u�s���a���I�����̒��Ɋe�X�̊y�킪����Ȃ��n����������̐������v�Ƃ������ʍ�������悤�Ɏv����B�o�[�h���҂ݏo���������f�B�[�E�R�[�h�u���̋Z�@�̓X�g�����B���X�L�[�̘a���@�ɒʂ��Ă���̂�������Ȃ��B
���uPerhaps�v�i1948�j�ɂ�����}�C���X�̃\���͈ꉹ�ꉹ�����M�ɖ������݊����ۗ����Ă��Ă���B����́A����3�N�O�uKoko�v�̃\�����K���X�s�[�Ɉς˂���Ȃ������}�C���X�̉��y�I�����̏ł���A�s�݂����ȃ��[�_�[�ɑ���o���h���܂Ƃ߂Ă����ނ̃��[�_�[�V�b�v�̊o���ł����邾�낤�B
�@�`���[���[�E�p�[�J�[�̓W���Y�Ɋv���������炵���B�ނ̉��y�͊v�V���ƕi�i��Y�킹���B�ނ̉��ʼn��y�ƃ��[�_�[�V�b�v�̊�b���w�K�����}�C���X�E�f�C���B�X�́A���̌�A�o�܂Ȃ��W���Y��ϊv����������ݑ������B�o�[�h�̓W���Y�̐i�ނׂ������������̂��B
�@2020�N�A�N���V�b�N�̐��E�̓x�[�g�[���F�����a250�N�̃������A���Ō������B�o�[�h�͐��a100�N�B�W���Y�̐��E�͂��قǂ�����Ă͂��Ȃ��B����ȔN�ɁA�u�o�[�h�`�`���[���[�E�p�[�J�[�̐l���Ɖ��y�v��ǂނ��Ƃ��ł��A�`���[���[�E�p�[�J�[�Ƃ��������s���Ȃ����y�l�̊���Ȑl���Ǝ����̉��y��H��̌��ł������Ƃ́A���ɂƂ��Ė���̊�т������B���̂悤�ȋ@���^���Ă��ꂽ��Ґ쓈���ێ��ɍő勉�̎^���Ɗ��ӂ�\���グ��B
���Q�l������
�u�o�[�h�`�`���[���[�E�p�[�J�[�̐l���Ɖ��y�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�`���b�N�E�w�f�B�b�N�X�� �쓈���ۖ�@�V���R�[�~���[�W�b�N���j
CD�uCHARLIE PARKER�`THE SAVOY RECORDINGS�iMASTER TAKES�j�vVol.1,2
CD�u�X�g�����B���X�L�[�F�t�̍ՓT�v �V�����e�B�w���F�V�J�S�����y�c�i1974�^���j
CD�u���[�c�@���g�F�̌����ȏW�v �X�E�B�g�i�[�w���F�V���^�[�c�J�y���E�x�������i1976�^���j
���[�c�@���g��ȁF�̌��u�t�B�K���̌����v�y���i�x�[�������C�^�[�Ёu�V���[�c�@���g�S�W�v�j
2020.11.12 (��) 2020�đ哝�̑I���N�����m�I����
�i1�j�哝�̑I�̓o�C�f�����̏��� �@11��7���A�I������4���ځA�o�C�f���������ɐ������o�����B�u�A�����J�哝�̑I�Ƃ��Ă͉ߋ��ő���7400���[�œ��I�����Ă�������B���̍��̐l�����������炵�������ȏ������B���f�ł͂Ȃ�������ڎw���哝�̂ɂȂ邱�Ƃ����B�����G�����邱�ƂȂ��݂��̈ӌ��d���O�i���悤�B�Ԃ��B�����B���Ȃ��B�����݂͂ȃA�����J�l���v�B�Z�a�Ƌ���������̐錾�������B�Ԑ�����������A�܂��s�҂����҂֏j���̈ӂ������A������ď��҂������̐錾������B���ꂪ�ʏ�̊��킵�����A�g�����v���͔s�k�錾�������S���t�ɋ����Ă����B
�@11��7���A�I������4���ځA�o�C�f���������ɐ������o�����B�u�A�����J�哝�̑I�Ƃ��Ă͉ߋ��ő���7400���[�œ��I�����Ă�������B���̍��̐l�����������炵�������ȏ������B���f�ł͂Ȃ�������ڎw���哝�̂ɂȂ邱�Ƃ����B�����G�����邱�ƂȂ��݂��̈ӌ��d���O�i���悤�B�Ԃ��B�����B���Ȃ��B�����݂͂ȃA�����J�l���v�B�Z�a�Ƌ���������̐錾�������B�Ԑ�����������A�܂��s�҂����҂֏j���̈ӂ������A������ď��҂������̐錾������B���ꂪ�ʏ�̊��킵�����A�g�����v���͔s�k�錾�������S���t�ɋ����Ă����B�@�j��܂�ɂ݂錃��ƂȂ���2020�A�����J�哝�̑I���͂������Ė���}�W���[�E�o�C�f����₪���������B�P�l�f�B�Ɏ�����l�ڂ̃J�g���b�N���k�ɂ��ďA�C��78�A�j��ō���̑哝�̂̒a���ł���B2008�N�A����}�I�o�}���ɔs�ꂽ���a�}�}�P�C�����́u�I�o�}���ɏj���𑗂邾���łȂ��A���̍��̔ɉh�̂��߂ɑP�ӂ𑗂낤�B�ǂ�ȈႢ�����낤�Ƃ��������݂͂ȃA�����J�l�Ȃ̂��v�Ǝx���҂ɌĂт������҂��̂����B���ꂼ�m�[�T�C�h�A�t�F�A�v���[�̐��_�ł���B�Ƃ��낪�A�c�O�Ȃ���g�����v���͂��̐��_���������킹�Ă��Ȃ��悤���B�t�ɁA�u�������̋^�f������B�����̏؋��������Ă���B�ŏI�I�ɘA�M�ō��قɍs�����ƂɂȂ�B�����͂܂��I����Ă��Ȃ��B��i�Ɍ��������j�����瓮���n�߂�v�Ɣ����̐��z���ł���B�����A��̓I�ȏ؋��̒͂Ȃ������̌���������B�����܂ł���Ƃ��͂⋶�C�̍����Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@���s�͖��炩�Ȃ͂��Ȃ̂ɂȂ�����ȗ��s�s�����̂��H �����ɂ��܂����H������Ǝv���Ă��邩�炾�B�������ł��@�쓬���Ɏ������ށB����悭�����������|�����ĐR�c���������A12��8���̊e�B�I���l�̑I�o�ɊԂɍ��킸�A14���̑I���l���[�ʼnߔ����ɒB������҂��o�Ȃ��\�����o�Ă���B�͍��Ȃ�Εs�����ȑI���l�ɓq����Ƃ�������Ȃ��͂Ȃ��B�����Ō��������Ȃ���A�N��������1��6���̉��@�̓��[�Ɏ������܂��B����͊e�B1�[�����猻�L�ߔ�����26�[�������a�}���L���ƂȂ�B���\��������E�E�E�E�E�g�����v���͂���ȃV�i���I��`���Ă���̂��B
�@�ł́A�q�ϓI�ɁA���̉\���͂���̂��낤���B�g�����v���́u�s��������v�ƌ��������ŋ�̓I�ȏ؋��͈�؎����Ă��Ȃ��B�Ȃ̂ŁA�قڏB�T���A�M�n���ٔ����̒i�K�Ŋ��p�ƂȂ邾�낤�B�����S�z�ȓ_�������B��́A�B�ɂ���ċ͍��̏ꍇ���������������F�߂��Ă��邱�ƁB����͐����Ȍ���������A���ԉ҂��ɂ͂Ȃ�B��ڂ́A�X�֓��[�̒������̖��ł���B���N�͐V�^�R���i�̉e��������X�֓��[�̗L�����ד����B�ɂ���ă}�`�}�`�ƂȂ����B�y���V���x�j�A�B���ɂƂ�A11��3���܂ł̏������6���̓����܂ŗL���Ƃ��Ă���B����ɂ��ĘA�M�ō��ق͈ጛ�������s���\�������� �Ǝw�E�������������B�����u���[�������X�֓��[�͖����v�Ƃ����������o�āA���������Ȃǎ葱���Ɏ��Ԃ�������A��L�����̃V�i���I�������̂��̂ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@�����Ȃ�ƃg�����v��Ղ̑�t�]�I�H ���₱��Ȃ��Ƃ͍l���������Ȃ��B���F�̑O�j���[�W���[�W�[�m���N���X�E�N���X�e�B���́u�؋�������Ȃ猩���Ăق����B�Ȃ���Ζ@�쓬���̈Ӗ��͂Ȃ��v�ƌ����A���a�}�̏d�������j�[��@�c���́u�咣�͊Ԉ���Ă���v�Ɣ����B�g�������������n���ꂽ�i�D���B
�@�g�����v�����M�u�A�b�v����ɂ͂����������Ԃ������肻���ł���B���������𒍎�����̂�����ǂ��b���B�Ȃ�����ŏ��������������悤�B���̋@��ɃA�����J�̃I�[�P�X�g�����Ă݂�̂͂ǂ����낤�B�Ƃ͂����j���[���[�N�E�t�B����{�X�g����������ł͔\���Ȃ��B�Ȃ���̍ہA����B�̃I�P�ɍi��̂��ꋻ���B
�i2�j����BSwing State�̃I�[�P�X�g��
�@�o�C�f�����̏���������Â����̂̓y���V���x�j�A�B�ł���B11��3���A�J�[�����̓g�����v����5�|�C���g�̑卷�Ń��[�h�B���̂�����ŁA�ʂ̌���B�t�����_�Ńg�����v���̏������m��B�~�V�K���A�E�B�X�R���V���ł����[�h���āA������4�N�O�̍Č����I�Ǝv��ꂽ�B�A�����J�����ɖ��邢�Ƃ����]�_�Ə����A�Ⴆ���ۃW���[�i���X�g�x�c���j��������́u80���g�����v�����v�Ȃǂƌ����o���B�ʂ̂Ƃ���ł͑O��g�����v������\�z���Ēj���グ���i�H�j�ؑ����Y�����u�����g�����v�̏����v�Ɗ��X�Ƃ��Č���Ă����ƕ����B���̃g�����v���́A4�������A�u�͂����茾���ĉ�X�͂��̑I���ɏ������v�Ƃ܂��J�[�r���ɂ�������炸������錾���Ă��܂��B�Ƃ��낪��閾����Ɨl���͈�ρB�~�V�K���A�E�B�X�R���V���A�y���V���x�j�A�̃��X�g�x���g�n�悪�A���錩�邤���ɐԂ��ɕϐF���n�߂�B�J�Ԃ���ꂽ�u�Ԃ�凋C�O�vRed Mirage�ł���B�g�����v���̔������u�i�y���V���x�j�A�́j70���[�̃��[�h�����@�̂悤�ɏ����Ă������B����ȕs�v�c�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�����ȕ[���W�v����Ύ��̊y���̂͂����v�Ƌ^�S�ËS����C�ɓ]����B�y���V���x�j�A�̓o�C�f�����̐��܂�̋��ł�����{���Ȃ�Ύ��̈����ł����������Ȃ������͂������A�ڐ��������ꂽ�����́A�Ō��TV���_��Łu�������ʃK�X��r�o����t���b�L���O�����ɂ��V�F�[���E�I�C���̌@�͒n�����̊ϓ_���珫���I�ɏk��������肾�v�Ƙb�����o�C�f�����̕s�p�Ӕ�����������������Ȃ��B���̏B�ɂ͐��\���l���̐Ζ��Y�Ə]���҂����邩�炾�B�Ƃ͂����ŏI�I�ɂ́A11��7���A�y���V���x�j�A��20���o�C�f�������l���B�A���]�i�A�m�[�X�J�����C�i�A�W���[�W�A�A�A���X�J���c���Ȃ��獇�v279�ʼnߔ�����D��B���������܂����B
�@�B�s�t�B���f���t�B�A�ɂ͖����t�B���f���t�B�A�nj��y�c������B�n����1900�N�B���w���҂ɂ́A���I�|���h�E�X�g�R�t�X�L�[�A���[�W���E�I�[�}���f�B�A���b�J���h�E���[�e�B�A�V�������E�f���g���Ȃǖ��w���҂�����A�˂�B
�@�t�B���f���t�B�A�ǂň�ۂɎc��ŏ��̎v���o�́A���w���̂���Ɍ����f�B�Y�j�[�f��u�t�@���^�W�A�v�i1940�j�ł���B�w���҂̓X�g�R�t�X�L�[�ŁA���̊i�D�����w���p�ɖ������ꂽ���̂��B��������N���V�b�N���y�ɋ����������͂��߁A�ŏ��ɔ�����LP���I�[�}���f�B�w���F�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�̃x�[�g�[���F���F�����ȑ�5�ԁu�^���v�������B���R�[�h�ԍ���ZL26�B�R�����r�A�E�_�C�A�����h�E�V���[�Y�Ƃ����������s����25cm 1000�~�Ղł���B�����1�N�Ԃقږ����������B�����̏����Ƃ����A1�N�ԓ��L�������������J���ɂ����������炤1000�~�����ׂāB������A����Ǝ�ɂ���1����1�N�Ԓ���������̂��� �Ƃ����킯���B���̏͂��̌�2�N�ԑ����B2���ڂ̓I�C�X�g���b�t�iVn�j�ƃI�[�}���f�B�F�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�̃����f���X�]�[���̃��@�C�I�������t�ȁiZL39�j�ŁA3���ڂ̓x�[���w���F�E�B�[���E�t�B���̃V���[�x���g�̌����ȑ�8�ԁi�����j�u�������v�i�L���OMP��1000�~�j�������B���w���ɂȂ�Ƃ��������������������ăR���N�V�����̃y�[�X���オ���Ă������B
 �@���ݏ��L����t�B�B���f���t�B�A�ǂ̃}�C�E�x�X�g�͂Ȃ�Ƃ����Ă��I�[�}���f�B�w���̃����X�L�[�E�R���T�R�t�F�����g�ȁu�V�F�G���U�[�h�v�i1972�^���j�ł���B�h������ܖ��N�C���̉e������l���Ō�̃X�s�[�J�[�̓^���m�C�ƌ��߂Ă���A2004�N�ATannoy Stirling�̓X�������̂��߂Ɏ��Q�����̂����̂b�c�������B���̂Ƃ������Ă�����3�y�́u�Ⴋ���q�Ɖ����v�̌��̂Ȃ�Ɣ������������Ƃ��I �܂��Ƀt�B���f���t�B�A�ǂ��`�e����u�r���[�h�̌��v���̂��̂������BTannoy Stirling�w�������̂͌����܂ł��Ȃ��B�����āA���݂����̖L���Ŕ����������͌��݂ł���B�Ƃ܂��A���[�W���E�I�[�}���f�B�i1899-1985�j���t�B���f���t�B�A�nj��y�c�̃R���r�Ƃ͐�ʈ���������킯�ł���B
�@���ݏ��L����t�B�B���f���t�B�A�ǂ̃}�C�E�x�X�g�͂Ȃ�Ƃ����Ă��I�[�}���f�B�w���̃����X�L�[�E�R���T�R�t�F�����g�ȁu�V�F�G���U�[�h�v�i1972�^���j�ł���B�h������ܖ��N�C���̉e������l���Ō�̃X�s�[�J�[�̓^���m�C�ƌ��߂Ă���A2004�N�ATannoy Stirling�̓X�������̂��߂Ɏ��Q�����̂����̂b�c�������B���̂Ƃ������Ă�����3�y�́u�Ⴋ���q�Ɖ����v�̌��̂Ȃ�Ɣ������������Ƃ��I �܂��Ƀt�B���f���t�B�A�ǂ��`�e����u�r���[�h�̌��v���̂��̂������BTannoy Stirling�w�������̂͌����܂ł��Ȃ��B�����āA���݂����̖L���Ŕ����������͌��݂ł���B�Ƃ܂��A���[�W���E�I�[�}���f�B�i1899-1985�j���t�B���f���t�B�A�nj��y�c�̃R���r�Ƃ͐�ʈ���������킯�ł���B�@���́A�u�������l�������̂��哝�̑I�𐧂��v�Ɖ]��ꂽ�I�n�C�I�B�ł���B1964�N�ȗ��I�n�C�I�𗎂Ƃ��đ哝�̂ɂȂ����҂͂��Ȃ��Ƃ����B�o�C�f�����͍����𗎂Ƃ��đ哝�̂ɂȂ����̂����璷�N�̃W���N�X��j�������ƂɂȂ�B����������̓P�l�f�B�哝�̈ȗ��Ƃ�������AJFK�Ƃ͂悭�悭��������Ƃ����ׂ����B
 �@�I�n�C�I�B��2�̓s�s�N���[�������h�ɂ͖����N���[�������h�nj��y�c������B�n����1918�N�B���w���҂ł́A�G�[���b�q�E���C���X�h���t�A�W���[�W�E�Z���A�������E�}�[�[�������L���A���݂̓E�B�[���o�g�̃t�����c�E�E�F���U�[�����X�g�����߂邪�A�Ȃ�Ƃ����Ă����M���ׂ��̓W���[�W�E�Z���i1897-1970�j�ł��낤�B�Z����1946�N����1970�N�܂ł̒����ɂ킽���Ȏw���҂ɌN�ՁA�y�c���̓���ւ��A�������g���[�j���O�Ȃǂɂ���Đ��k�ȃA���T���u���������B���̃I�[�P�X�g���ꗬ�Ɉ�ďグ���B���݁A�O�L�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�ƂƂ��ɃA�����J5��I�[�P�X�g���ɐ������Ă���i���̓j���[���[�N�E�t�B���A�{�X�g�������y�c�A�V�J�S�����y�c�j�B
�@�I�n�C�I�B��2�̓s�s�N���[�������h�ɂ͖����N���[�������h�nj��y�c������B�n����1918�N�B���w���҂ł́A�G�[���b�q�E���C���X�h���t�A�W���[�W�E�Z���A�������E�}�[�[�������L���A���݂̓E�B�[���o�g�̃t�����c�E�E�F���U�[�����X�g�����߂邪�A�Ȃ�Ƃ����Ă����M���ׂ��̓W���[�W�E�Z���i1897-1970�j�ł��낤�B�Z����1946�N����1970�N�܂ł̒����ɂ킽���Ȏw���҂ɌN�ՁA�y�c���̓���ւ��A�������g���[�j���O�Ȃǂɂ���Đ��k�ȃA���T���u���������B���̃I�[�P�X�g���ꗬ�Ɉ�ďグ���B���݁A�O�L�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�ƂƂ��ɃA�����J5��I�[�P�X�g���ɐ������Ă���i���̓j���[���[�N�E�t�B���A�{�X�g�������y�c�A�V�J�S�����y�c�j�B�@�Z���F�N���[�������h�ǂ̖����͚삵�������c����Ă��邪�A���̒��̃}�C�E�x�X�gCD�́A���[�c�@���g�F������ ��40�� �g�Z�� K550 �i1967�N�^���j�ł���B�Z�����b���グ�����k�ȃA���T���u�����y�Ȃ̓��O����������Ƀ}�b�`���čō��̃p�t�H�[�}���X�������B�l�I�ɂ��̋ȍŏ�̉��t�Ɗm�M���Ă���B
�@�Ō�́ABlack Lives Matter�^�����g�傷�邫�������ƂȂ����~�l�\�^�B�ł���B���N5��25���A�~�l�\�^�B�ő�̓s�s�~�l�A�|���X�ɂ����āA���l�j���W���[�W�E�t���C�h����͔��l�x���̕s�K�ȍS���ɂ���Ƃ̎��𐋂����B����ɑ���R�c��Black Lives Matter�̑傫�Ȃ��˂�ƂȂ��đ哝�̑I�ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ����B��N�Ⴉ�������l�̓��[�����A�b�v�A����80���ȏオ�o�C�f�����ɓ������V�哝�̒a���̈ꗃ��S�����B
 �@�~�l�A�|���X�ɂ��~�l�A�|���X�����y�c������B�n����1903�N�B���݂̓~�l�\�^�nj��y�c�Ɩ��̂��ς���Ă���B���w���҂ɂ́A���[�W���E�I�[�}���f�B�A�f�B�~�g���E�~�g���v�[���X�A�A���^���E�h���e�B�A�X�^�j�X���t�E�X�N�����@�`�F�t�X�L��A��������ʋ��ҋȎ҂�����A�˂�B���ł��o�F�̓A���^���E�h���e�B�i1906-88�j���낤�B�h���e�B�̖����ŗ͋������y�Â���́A�~�l�A�|���X�ǂ̎���̂悢�����Ǝ��ɂ悭�}�b�`���Ă���B�}�[�L�����[�Ɉ₳�ꂽ�����̘^���̒��ł́A���X�s�[�M�F�������u���[�}�̏��v�i1960�N�^���j�����̃R���r�̓��F���悭�\�����D���ł���B
�@�~�l�A�|���X�ɂ��~�l�A�|���X�����y�c������B�n����1903�N�B���݂̓~�l�\�^�nj��y�c�Ɩ��̂��ς���Ă���B���w���҂ɂ́A���[�W���E�I�[�}���f�B�A�f�B�~�g���E�~�g���v�[���X�A�A���^���E�h���e�B�A�X�^�j�X���t�E�X�N�����@�`�F�t�X�L��A��������ʋ��ҋȎ҂�����A�˂�B���ł��o�F�̓A���^���E�h���e�B�i1906-88�j���낤�B�h���e�B�̖����ŗ͋������y�Â���́A�~�l�A�|���X�ǂ̎���̂悢�����Ǝ��ɂ悭�}�b�`���Ă���B�}�[�L�����[�Ɉ₳�ꂽ�����̘^���̒��ł́A���X�s�[�M�F�������u���[�}�̏��v�i1960�N�^���j�����̃R���r�̓��F���悭�\�����D���ł���B�@�]�k�����A�h���e�B�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����Ă��h���H���U�[�N�̌����� ��9�� �u�V���E���v�i���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c1959�N�^���j�������B���͂����m�����͖̂��F�쓈���ێ��̋�������B�ނ́u�V���E���v�̃x�X�g���t�Ƃ����̂Ő����Ă݂����Ȃ�A�m�l�ŏ���2�����̃R���N�^�[���ȂǁA�����������������|����Ȃ��A�ŏI�I�ɐ쓈���{�l����ݗ^�����Ƃ����㕨�ł���B�Ƃɂ��������Ăт�����̖����t�������B�����ȃe�B���p�j�[�̑ʼn��A�����ď����̂��錷�̋����A���݂ȃA�S�[�M�N�B��ɏI�y�̓R�[�_�̋�O���̃A�b�`�F�����h�ƍŏI����11�b�ɋy�ԁi�N�[�x���b�N��7�b�A�J��������9�b�j�t�F���}�[�^�̑Δ�ɂ͓x�̂��ꂽ�B�]���̔O�����̃����O�g�[���ɋÏk���Ă���B����قǂ̖����t�͖ő��ɂ��ڂɂ��������̂ł͂Ȃ��B���ݏ��L����̂͐쓈����CD�R�s�[�����A�ނɂ͊��ӂ��A������{�`�����Ŏ����������� �ƔO���Ă���B
�@�A�����J�哝�̑I�̓o�C�f�����̏����Əo�����A�g�����v���̈��������͓������܂肻�����Ȃ��A��͂܂��܂��\�f�������Ȃ��B�g�����v����7200���[�Ƃ�����ʕ[���l�����������d���A���f�͏㉺�����E�ɕ��w�����ĉv�X�[�܂�l����悵�Ă���B���@�̔P���ꂪ������\���������A�V�哝�͓̂�������^�c���������邱�ƂɂȂ肻�����B���ׂ����܂�l�q�͂Ȃ��B�����Ȑ��E�͂��K���̂��낤���B
2020.10.05 (�y) �哝�̑I������s�v�c�̍��A�����J��T��
Prologue�`���Ȃ��݂̑S�ăI�[�v���������炵���g��@ �@���Ȃ��݂̑S�ăI�[�v���D���͕ʂ̈Ӗ��Řb����ĂB�����Ԓ��A���l�x�@���\�͂̋]���ɂȂ������l�̖��O���L�����}�X�N����ւ��ő������ēo��B8��31���̏��킩��9��13�������܂łV���̋]���҂̖��O�����E�Ɏ����ꂽ�B�l�퍷�ʂւ̃X�}�[�g�ȍR�c�B�����S�ď��q�v���e�j�X����͗e�F�����B�v���o�����̂�1968�N���L�V�R�ܗւł���B����200m�ŋ����_�����l�������A�����J�̍��l�I��g�~�[�E�X�~�X�������_���̃W�����E�J�[���X�Ƌ��ɕ\����Ō���˂��グ�Đl�퍷�ʂɍR�c�̈ӎv���������B���N4���ɋ��e�ɓ|�ꂽ�������^���̎w���҃L���O�q�t�ւ̒Ǔ��̈Ӗ������߂��ӎv�\���������BIOC�͌��͂ɔ�����Ƃ��ē�l�������B�u�X�|�[�c�ɐ������������܂Ȃ��v�A���ꂪ�����̏K���������킯�ł���B���ꂩ�甼���I�B����͕ς�������̂ł���B�����āA���Ȃ��݂́g�}�X�N�ɍ��l�]���҂̖��O�h�́u�R���i�Ёv�Ɓu���l���v�Ƃ���2020�哝�̑I�̑��_�������������t��o�����B
�@���Ȃ��݂̑S�ăI�[�v���D���͕ʂ̈Ӗ��Řb����ĂB�����Ԓ��A���l�x�@���\�͂̋]���ɂȂ������l�̖��O���L�����}�X�N����ւ��ő������ēo��B8��31���̏��킩��9��13�������܂łV���̋]���҂̖��O�����E�Ɏ����ꂽ�B�l�퍷�ʂւ̃X�}�[�g�ȍR�c�B�����S�ď��q�v���e�j�X����͗e�F�����B�v���o�����̂�1968�N���L�V�R�ܗւł���B����200m�ŋ����_�����l�������A�����J�̍��l�I��g�~�[�E�X�~�X�������_���̃W�����E�J�[���X�Ƌ��ɕ\����Ō���˂��グ�Đl�퍷�ʂɍR�c�̈ӎv���������B���N4���ɋ��e�ɓ|�ꂽ�������^���̎w���҃L���O�q�t�ւ̒Ǔ��̈Ӗ������߂��ӎv�\���������BIOC�͌��͂ɔ�����Ƃ��ē�l�������B�u�X�|�[�c�ɐ������������܂Ȃ��v�A���ꂪ�����̏K���������킯�ł���B���ꂩ�甼���I�B����͕ς�������̂ł���B�����āA���Ȃ��݂́g�}�X�N�ɍ��l�]���҂̖��O�h�́u�R���i�Ёv�Ɓu���l���v�Ƃ���2020�哝�̑I�̑��_�������������t��o�����B(1) ��1��e���r���_��
 �@9��29���A�A�����J�哝�̑I���̏d�v�ȃC�x���g�ł����1��̃e���r���_��s��ꂽ�B���a�}���E�̃g�����vVS����}�̃o�C�f�����Ƃ̑Ό��ł���B���e�I�ɂ͑S���̕s�сB�A�����J�̕��f���ے����铢�_������B�����_���͔��o���Ȃ������̌��������ɏI�n�B�܂��Ɏq���̃P���J�B�g�����v�Ƃ����l���܂Ƃ��łȂ��̂�����\�z�͂��Ă������]��̒ᑭ���ɏ�Ȃ��Ȃ����B�o�C�f�����̓g�����v���������ɐ�王���҂Ɍ��|����X�^�C�����т������A����͑���̃y�[�X�ɏ��Ȃ����߂ɂƂ�����킾�������낤�B
�@9��29���A�A�����J�哝�̑I���̏d�v�ȃC�x���g�ł����1��̃e���r���_��s��ꂽ�B���a�}���E�̃g�����vVS����}�̃o�C�f�����Ƃ̑Ό��ł���B���e�I�ɂ͑S���̕s�сB�A�����J�̕��f���ے����铢�_������B�����_���͔��o���Ȃ������̌��������ɏI�n�B�܂��Ɏq���̃P���J�B�g�����v�Ƃ����l���܂Ƃ��łȂ��̂�����\�z�͂��Ă������]��̒ᑭ���ɏ�Ȃ��Ȃ����B�o�C�f�����̓g�����v���������ɐ�王���҂Ɍ��|����X�^�C�����т������A����͑���̃y�[�X�ɏ��Ȃ����߂ɂƂ�����킾�������낤�B�@�����̓o�C�f�����̏��� �Ƃ����̂��C�O���f�B�A�̑���̌����̂悤���B����������{�̃��f�B�A������]�X�����ǂ��炪�A�s�[���������ɏI�n�����B��������T�˃o�C�f�����L���Əo��B�x�����Ń��[�h����o�C�f������TV���_�ł��������Ƃ����̂�����A����A�u�o�C�f���L���v�Ƃ݂�̂����R�̓ǂ݂��낤�B
(2) �R���i�Ђɑ���g�����v�����̑Ή�
�@�V�^�R���i�E�B���X�ɂ��āA�g�����v�哝�͓̂����A�u�������Ă�99���͖��Q�v�u���_��g�����Ȃ�4���ɂ͊�Ղ̂悤�ɂȂ��Ȃ�v�u���ʼnt��1���ňꌂ�A�����OK���v�Ȃǔ�Ȋw�I�����Ȃ��̔�����A���B�}�X�N�͂��Ȃ��B�W��͋��s����B����ȃR���i���r�ߐ����Ή��͑S�Ă𐢊E�ő�̊������Ɋׂꌻ�݂��i�s�����B�m���Ɂu���S��5%�v�͍��ƍs�����猩����債�������ł͂Ȃ���������Ȃ����A21���l���Ƃ������Ґ��͌��߂����Ȃ��͂��B�����Ă��낤���Ƃ�10��2���A�{�l�̊����������B�������z���C�g�n�E�X����20�����̃N���X�^�[�����̃I�}�P�t���B�V�����ɂȂ�Ȃ����ԂƂȂ����B�R���i�ɑ���s�����ȑΉ��̕Ƃ����ׂ����B
�@�Ή��̕s��ۂƎ��g�̊����B���{�Ȃ�ԈႢ�Ȃ��A�E�g���낤���A�g�����v�ɂ͒v�����ɂȂ�Ȃ��ǂ��납�v���X�ɍ�p���� �Ƃ�������������B����10��6���ɂ͑މ@�B�a�C�ɕ����Ȃ������哝�̂�������B�c�C�b�^�[�Ɂu�R���i�͋����ɂ���Ȃ��B�݂�Ȃ��R���i���Ƃ��ɐ������x�z����Ȃ��悤�ɁB�킪�g�����v�����ŊJ�������{���ɗǂ����m��������B������20�N�O���͂邩�ɂ����C�����B15���̓��_��H�����������肳�v�Ə������ނȂǑ��ς�炸�̃g�����v�߂��B�Ƃ͂����A10��1���ɂ́A�����̋^�������钆�A�}�X�N���������ɑI���W������s����ȂǁA���̔�펯���͂ǂ����Ă��v���X�ɍ�p����Ƃ͎v���Ȃ��B
�i3�jBLACK LIVES MATTER�̂��˂�
�@���Ȃ��݂��S�ăI�[�v�����X�����ŕ\�������̂́A���N5���A���l�x�@���\�͂̋]���ƂȂ������lGeorge Floyd����̖��O�������B�ނ̎������������ɑS�Ăō��܂����̂��uBLACK LIVES MATTER�v�̉^���ł���B�f���ɘA�����Ė\�k���o���B�g�����v�哝�̂͂����}����ǂ��납�ނ��뒧�����^�������B�ێ�h�̖��Ԏ��x�c�u�~���V�A�v�̉��\�ɂ͊���Ԃ�A�u�@�ƒ����vLaw & Order�������ĘA�M�R�̏o������������B���Âł͂Ȃ����f����������B�u�����ȑ�O�𑀂�ɂ͑�������邱�Ƃ��B��L���Ȏ�i���v�Ƃ����q�g���[�̎�@���B�_���͂ނ��u�\����}�����鋭���哝�́v����ۂÂ��邽�߂��B
 �@�g�����v�哝�̂͂܂��I�o�}�����Ō��肵�Ă�����20�����́u�n���G�b�g�E�^�u�}���v�ё��̗p��P�Ă���B�^�u�}�����j��19���I���l�̎��R�̂��߂ɓ����������ƁB��20�����͌��s�A���h�����[�E�W���N�\����7��哝�̂ŁA�g�����v�哝�̂��z���C�g�n�E�X�������ɏё��������قǑ��h����l�����B�I�o�}��������̐��ׂĂ�ے肷��̂��g�����v�����̊̂�����A����͓��R�̑[�u�ƍl���邵���Ȃ��B�I�o�}�P�A�A�C�����j���ӁA�e�K���ACOP21�p�����蓙�ւ̑Ή����R�肾�B
�@�g�����v�哝�̂͂܂��I�o�}�����Ō��肵�Ă�����20�����́u�n���G�b�g�E�^�u�}���v�ё��̗p��P�Ă���B�^�u�}�����j��19���I���l�̎��R�̂��߂ɓ����������ƁB��20�����͌��s�A���h�����[�E�W���N�\����7��哝�̂ŁA�g�����v�哝�̂��z���C�g�n�E�X�������ɏё��������قǑ��h����l�����B�I�o�}��������̐��ׂĂ�ے肷��̂��g�����v�����̊̂�����A����͓��R�̑[�u�ƍl���邵���Ȃ��B�I�o�}�P�A�A�C�����j���ӁA�e�K���ACOP21�p�����蓙�ւ̑Ή����R�肾�B�@�A�����J�ɂ����鍕�l���ʂ̗��j�́A1619�N�A�I�����_�̌R�D���A��Ă���20�l�̃A�t���J�l�z�ꂪ�n�܂�Ƃ����B����͓암�̃^�o�R�_��ւ̘J���͕⋋�̕K�v�����炾�����B18���I�ɓ���Ǝ嗬�̓^�o�R����ȉԍ͔|�Ɉڂ�K�͂��g��B���l�z��̐��͔���I�ɑ���B����ɔ����č��l�Љ�ɊK�w����������B�_��J���҂Ɣ_���̉Ƃœ����n�E�X�J���҂̕����Ȃǂł���B
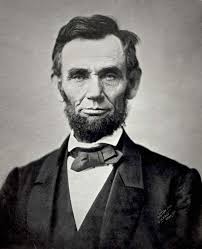 18���I���ɃC�M���X�ŋN�������Y�Ɗv���̓A�����J�ɂ��g�y�B�k���ɍH�Ɣ��W�𑣂����B�����ŕK�v�ƂȂ����̂������J���͂ł���B�k���̐V�����͂��ڂ�t�����̂��암�̍��l�z�ꂾ�����B�u�암�̓z����J�����Ĉ����J���͂��v�B�����J�[���̖k�R������������k�푈�i1861�|1865�j�͂���Ȏv�f�����Ă����̂ł���B
18���I���ɃC�M���X�ŋN�������Y�Ɗv���̓A�����J�ɂ��g�y�B�k���ɍH�Ɣ��W�𑣂����B�����ŕK�v�ƂȂ����̂������J���͂ł���B�k���̐V�����͂��ڂ�t�����̂��암�̍��l�z�ꂾ�����B�u�암�̓z����J�����Ĉ����J���͂��v�B�����J�[���̖k�R������������k�푈�i1861�|1865�j�͂���Ȏv�f�����Ă����̂ł���B�@����ɍ��l���Ƃ����Ă������͕��G�Ȃ��̂�����B���l�����́A���X�z�ꂾ�������l�̐l�����Ȃ��Ȃ��F�߂�����Ȃ��B�B�ɂ�銰�e�x���܂��܂����B���l�Љ�ɂ����Ȃ��炸�K�w������B�������^���̗��j�����Ă��A�����I�����h�̃L���O�q�t�ɑ��āA�}�i�I�����h�̃}���R��X ��������������B�������l�ɂƂĂ���ؓ�ł͊���Ȃ��B
�@����܂ő哝�̑I�ɂ����鍕�l�̓��[���͒Ⴂ�Ƃ���Ă����B�����l�ێ�h�̏W�c�����[�W�Q����ĂĂ��āA���ł̓g�����v�����������Ă���@�ȂǂƂ��������Șb������Ă���B����ȏ�̒��A�l����12���̍��l�[���ǂ��������B�d�v�ȃJ�M�̈�ł���B�f��u�O���[���[�v�ɕ`���ꂽ�Z���}��s�i�B����Ȑ�l�̕s���̓w�͂ŏ���������M�d�ȓ��[�����ǂ����L���Ɋ��p���Ă��炢�������̂ł���B
(4) ���l�̗��ꂩ��A�����J�l�C����T��
�@�������^���̑ɂɂ��锒�l�����`�����Ă������B���ҁuKKK�v�A�i�`�X�̗�������ށu�A�����J�E�i�`�}�v�u�i�V���i���E�A���C�A���X�v�A�l�퍷�ʂ�O�ʂɏo�������l�̗D�ʐ�����낤�Ƃ���m���h�u�A�����J���E���l�T���X�v�A����ɂ́u�v���E�h�E�{�[�C�Y�v�Ȃǂ̋ɉE�ߌ��h�A�u�I���g�E���C�g�v�Ƃ�����V���ȕێ��`�҂܂ŁA���ɑ��푽�l�ł���B�����W�c�͑����āA���l�D�ʂ�W�Ԃ��A���l�l���̌�����J�����A�ږ��ɂ͔��̗�����Ƃ�A���l��̎s�����Ɉًc��������B��`�I�ɂ͕ێ炾����T�ːe�g�����v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�A�����J�ݏZ�̍��ې����w�҂ŋ��w�̘_�q�E�ɓ��ю��͂��Ă���Șb�����Ă����B
�A�����J���O���̌����B����́A17���I�����C�M���X����n���Ă����s���O�����t�@�[�U�[�Y�ɒ[���Ă��܂��B�ނ�́A�X�`�����[�g�����̉p��������ƑΗ����Ēe������ꂽ�s���[���^���i�v���e�X�^���g�̋��k�j�ŁApolitical & religious fanatic���������I�@���I���M�̓k�Ȃ�ł��ˁB�{���I�Ɂu���������������������A�����炨�O�������킦�v�Ƃ��鐸�_�\���̎�����ł�����B����Ȕނ炪�j���[�C���O�����h�E�R���j�[�����100�N��ɓƗ��𐬂��������B���̑�D���ȃt�����X�̗��j�w�҃g�N���B���i1805�|1859�j�́A�A�����J�l���u�拭�ŗc�t�Ȑl��robust & puerile�v�ƌĂт܂����B����͍����ł��ς���Ă��Ȃ���ł��B�@�����2015�N�Ƀe���r���f���ꂽ�u����簃[�~�i�[���v����̈��p�����A������������āA�ɓ����̔����ƌ����Ɋ����������̂ł���B����Ȉɓ����̒k�Ɉ�t�������Ă����������Ƃ�����B�u���A�����s���[���^�������͂��̗ϗ������琶���ɕK�v�ȋΘJ�Ɛߖ�Ƃ������{��`�̐��_����B���ꂪ�A�����J�ɂ����鎑�{��`�̔��W�ɂȂ����Ă䂭�v�ƍl�����}�b�N�X�E�E�F�[�o�[�̌����ł���i�u�v���e�X�^���e�B�Y���̗ϗ��Ǝ��{��`�̐��_�v���j�B���̂悤�ȓy�납��A���b�N�t�F���[�A�J�[�l�M�[�A�t�H�[�h�ȂǃA�����J���{��`�̉��������܂�Ă���̂ł���B
�@�ɓ����̘b�̒��ōł������[���̂́A�u�A�����J�̌����҂́w�拭�ŗc�t�Ȑl�ԁx�ł���w���������������������x�Ƃ��鐸�_�\���̎�����v�Ƃ����������낤���B�܂�ŁA�u�A�����J�E�t�@�[�X�g�v��W�Ԃ��q�����ۂ��ۏo���̃g�����v��������悤�ł͂Ȃ����B
�@�A�����J�l�̐��_�\�����`���������̎������Ă������B����́A��2�����E��풆�̘A�����R�ɂ��V�V���[�㗤���ɍۂ��āA�A�����J�l�i�ߊ��W���[�W�E�p�b�g�����R���S�R�̏����Ɍ������čs�����P���ł���B
�����͂��ꂩ��㗤���ăC�^���A�y�уh�C�c�̌R���Ɛ퓬��������B���N�̒��ɂ́A�C�^���A���邢�̓h�C�c�̌����Ђ����̂����邾�낤�B�������A������o���Ă����B���N�̕��c�����͎��R�������邪�䂦�ɁA�݂�����̍��Ɍ�������đ吼�m��n�����l�����Ȃ̂ł���B��X�����ꂩ��키����̕��c�����́A���N�̕��c�����̂悤�ȁA���ɑς���E�C�������Ă����l�Ԃ����ł���A�z��ł��邱�ƂɊÂĂ����l�Ԃ����������̂��B(�����G�r���u�A�����J�l�v���)�@����́A�A�����J�l�̏h���I�����𑨂�����ł����Ɍւ�Ǝ��M��A���t���錩���ȌP���ł���B��L��̎��Ⴉ��A�A�����J���l�̐S�̉���ɐ��ސ^������Ă������ł���B�����A�u�A�����J�l���ׂĂ͈ږ��ł��肻�̗��j�͐B���������̕��c�͗ꑮ�I�ň����Ƃ����������̂Ď��R�����ߌ̍�����ɂ����E���Ȑl�������B�ނ�̋N�������s���͐����Ōւ�ׂ����̂��B�ږ����낤�����j���낤���A���E�̂�������������l�X�Ȃ̂��B�����āA�ނ�̐��_�͉�X�̒��Ɋm���ɑ��Â��Ă���v�Ƃ������Ƃ��B
�@�ނ�̗��O�̍���ɂ́AWASP�i�A���O���T�N�\���n�v���e�X�^���g���k�̔��l�j�ɏے������̑�Ȑ�l���^�����鐸�_������B�ނ炱�����E���ɂ����J�̒n�A�����J�ɓ��A���{���C�M���X�̈����ɑ��e���g�������Ƃ��Đ킢�Ɨ�������������h�����ׂ��c��Ȃ̂ł���B�č����@�C����2���Ɂu�l���������ۗL���܂��g�т��錠���́A�����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ɩ��L����Ă���̂́A�e���Đ���������̗��j�����邩�炾�B
�@�����S�A���R�A�Ɨ��S�A�E�C�A�J��Ґ��_�A����ۗL�̌����B�����́A�ێ烊�x������킸�A��ʓI�A�����J���l�̂����������i���������đ������j���Ȃ��炸�����Ă��鐫���iDNA�j �ƌ��Ă��I�O��ł͂Ȃ��悤�ȋC������B�g�B��g�����v�h�Ƃ������݂����̂�����ɋN������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B
Epilogue�`2020�哝�̑I������̓W�J�́H
 �@�R���i�ɜ�����g�����v�哝�̂́A�킸��3���Ԃ̓��@�Ŗ��d�Ƃ�������މ@�����݂��B����̋������A�s�[�������������̂��낤���x�����̓g�����v41�� VS�o�C�f��50���Ƃ���ɍL�������B���͋��Əo���ƌ��킴��Ȃ��B��͉v�X�g�����v���s���̗l����悵�Ă����B�ł͂��̌�A�틵�͂ǂ����ڂ���̂��낤���B��Ցw�͉��������Ă��ς��Ȃ��B���͕n���w�܂ޕ����w�̓����ł���B���f�B�A�ɂ͐��̊ϓ_������Ăق����Ǝv���B�u�g�����v���̔����͊�Վx���w�ɂ̓A�s�[�������͂��ł��v�ȂǂƂ������Ӗ��ȃR�����g�͕s�v�ł���B�ł͕����w�̐S���͂�������Ȃ̂��B
�@�R���i�ɜ�����g�����v�哝�̂́A�킸��3���Ԃ̓��@�Ŗ��d�Ƃ�������މ@�����݂��B����̋������A�s�[�������������̂��낤���x�����̓g�����v41�� VS�o�C�f��50���Ƃ���ɍL�������B���͋��Əo���ƌ��킴��Ȃ��B��͉v�X�g�����v���s���̗l����悵�Ă����B�ł͂��̌�A�틵�͂ǂ����ڂ���̂��낤���B��Ցw�͉��������Ă��ς��Ȃ��B���͕n���w�܂ޕ����w�̓����ł���B���f�B�A�ɂ͐��̊ϓ_������Ăق����Ǝv���B�u�g�����v���̔����͊�Վx���w�ɂ̓A�s�[�������͂��ł��v�ȂǂƂ������Ӗ��ȃR�����g�͕s�v�ł���B�ł͕����w�̐S���͂�������Ȃ̂��B�@�o�C�f����₩��́u���ꂪ�o�C�f�����v�Ƃ����炪�����Ă��Ȃ��B�u���̐����͂������v�Ƃ�������Ȏ咣���R�肾�B������̂́u���̃g�����v�ɂ���4�N�Ԃ���������点�Ă����̂��v�Ƃ����g�A���`�E�g�����v�h�̊炾�����B���������̐��������P���Ă����̂��H�����ɑR�ł���̂��H �o�C�f���x���ɂ͕s�������܂Ƃ��B
�@�g�����v������́A�ǂ����������A�u�g�����v�̊�v��������B���̒����ɔe�����Ƃ��Ă��܂���̂��B�A�����J�͈�ԂłȂ���Ȃ�Ȃ��B������g�����v�Ȃ����Ă����B�����A�����J���������Ă����B�g�����v�͎��������̒��ɂ���A�����J�l��DNA�����L���Ă���B
�@�g�����vVS�o�C�f���B���j�ケ��قǂ܂łɕ��f���ۗ������I���킪���������낤���B�c���ꂽ2�x�̂s�u���_��ł͂ǂ���ɕ��������̂��B�����w���ǂ���ɓ]�Ԃ̂��B���l�����͓��[�ɍs���̂��B�O��g�����v�ɓ��[����Rust Belt�̕n���w�͑��ς�炸�g�����v���x������̂��B����BSwing state�͂ǂ���ɐU���̂��B3�����߂�Ƃ�����X�֓��[�͂ǂ��e������̂��B���ɂȂ��d�v������Ă��镛�哝�̌��̑��݂��ǂ����E����̂��E�E�E�E�E����L���Ƃ����o�C�f�����������邩�B�A�����J�l�{����DNA���o�������ăg�����v�����t�]���邩�B11��3���̓��[���ʂ�҂����Ȃ����낤�B������͍��ƏW�v�̒x�ꂩ��N�z�����čō��قɍْ肪�������܂��\��������B�����ŁARBG�M���Y�o�[�O�����̎��������������炷�̂��B�l����M�����l�ς����푽�l�ȃA�����J�Ƃ����������̑I���łǂ�ȍْ�������̂��B���ׂ�2020�哝�̑I���ł���B
���Q�l������
�u�W���Y�̗��j�v���q�v�l���i�V���V���j
�u�A�����J�l�v�����G�r���i�u�k�Ќ���V���j
�u�v���e�X�^���e�B�Y���̗ϗ��Ǝ��{��`�̐��_�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�}�b�N�X�E�E�F�[�o�[���A��ˋv�Y��i��g���Ɂj
�u���l�i�V���i���Y���v�n�Ӗ����i�����V���j �f��u�O���[���[�v�i2015�ājDVD
MX-TV�u����簃[�~�i�[���v2015.2.22 OA
2020.09.05 (�y) ���{������7�N8��������� with Ray�����
���v�����[�O�� �@Ray�����A����ɂ��́B�������w��N���ȂˁB���������̏��w�Z�������R���i�̂��A�ŕϑ��I�ɂȂ������������ǁA���邭����Ray�����̂��Ƃ�����A�����ƌ��C�ɂ���Ă邱�ƂƃW�[�W�͎v����B
�@Ray�����A����ɂ��́B�������w��N���ȂˁB���������̏��w�Z�������R���i�̂��A�ŕϑ��I�ɂȂ������������ǁA���邭����Ray�����̂��Ƃ�����A�����ƌ��C�ɂ���Ă邱�ƂƃW�[�W�͎v����B�@�Ƃ���ŁARay�����A8��28���A���{�W�O�����C�����B�C����1�N�c���Ă̎��C�͈ӊO�������B�ł����a�Ĕ��Ȃ炵�傤���Ȃ����B���̕a�C�A�X�g���X����Ԃ܂����ƕ����Ă���B������b�̎d���͌��������A��Ɉ��{�̏ꍇ�͌ŗL�̑����ȃX�g���X������Ă����͂����B�܂��͒����Ԃ���J�l�ł����Ƃ��̘J���˂��炨���B�������Ȃ��Ƌ����O����ɓ{��ꂿ�Ⴄ����(��)�B
�@������b�ݔC�����͌j���Y���A�A�������͍����h����āA���ꂼ����1�ʂƂȂ����B���͂͒���������ƕ��s���� �Ƃ�������ǁA���{�̏ꍇ�͂ǂ��������̂��ȁB�J����u�|�X�g���{�v�Ŏ������肾���ǁA����Ȃ��Ƃ��Ray�����A�����͈��{������7�N8�����U��Ԃ邱�Ƃ̕����挈���Ǝv���B�Ȃ�Ă������Ďj��Œ������������̂����炱��͑������邵���Ȃ��ł��傤�B�t�������Ă���邩�ȁB
�@���{�W�O����2006�N�A����Y���瑍����b�̍����p�����B���̎�52�B�j��ŔN����㐶�܂ꏉ�̑�����b�ƂȂ�����B�u��ヌ�W�[������̒E�p�v�u���������{�̑n���v�Ȃǂ̃X���[�K�����f���ėE�܂����D�o�������A���a�̒�ᇐ��咰�����������Ă킸��1�N������ƂŎ��߂Ă��܂��B�a�C�Ƃ͂��������𓊂��o�����Ɣᔻ���ꂽ�ˁB
�@���̂��ƁA�����^�}�̎����}�����c�N�v�`�������Y�ƂȂ������A�������t���̕s�ˎ����Ő����͉��~�̈�r�B2009�N�A���ɁA����}�ɐ����̍��𖾂��n�����B
�@�u�������v�����s��ƂȂ�u�����哱�v���f���ĉX�����X�^�[�g���������}�������������A�ŏ������R�R�I�v�́u�Œ�ł����O�v���f�������V�Ԋ�n�ڐ݂������A2011�N�����{��k�Ђł������l�̕�����ꌴ�����̑Ή��̕s��ۂȂǁA�u�����\�́E���s�͖����v��I��B3�l�ڂ���c���F�̎��ɂ͂��͂⎀�ɑ̂ɂȂ��Ă����B����}������3�N3����́u���߂��Ȃ������v�ƕ]���ꂽ�ˁB
�@2012�N12���̑��I���͎����}�������̔{�Ԃ��B6�N�O�A���O�̎��C�ɗ܂������{�W�O�����y�d���������đ����̍��ɕԂ�炢���B�h�_���r�߂��ݖ��3�N�ԁA�����ƍɑ��w������������̂��낤�A���{���͌��Ⴆ��قǂ����܂������܂�ς���Ă����ˁB��I�X���[�K���́u���߂��鐭���v�B�ł�Ray�����A�����ʂɈ��{�����̑��Ղ����ǂ��Ă݂悤�B
(1)�A�x�m�~�N�X�`�O�{�̖�
 �@���{���^����Ɏ��g�̂��A�x�m�~�N�X�������ˁB�@��_�ȋ��Z�ɘa�A���ԓ��������N���鐬���헪�B�@���I�ȍ���������O�{����Ƃ��āB������������邽�߂ɓ���قɍ��c���F�����N�p�����B�ȍ~���c���͈��{�̍ݔC���Ԓ������邱�ƂȂ��W���u�W���u�Ƃ������s��ɗ��������A�x�m�~�N�X���x�����ˁB
�@���{���^����Ɏ��g�̂��A�x�m�~�N�X�������ˁB�@��_�ȋ��Z�ɘa�A���ԓ��������N���鐬���헪�B�@���I�ȍ���������O�{����Ƃ��āB������������邽�߂ɓ���قɍ��c���F�����N�p�����B�ȍ~���c���͈��{�̍ݔC���Ԓ������邱�ƂȂ��W���u�W���u�Ƃ������s��ɗ��������A�x�m�~�N�X���x�����ˁB�@�َ����Ƃ���ꂽ��_�ȋ��Z�ɘa�ŁA�����͏オ�莸�Ɨ��͉�����ٗp�͉��P�����B�בւ͉~���ɓ]�����ێ��x�̍������ɍv�������B15�N�Ԃ̃f�t�����͒E�p�������Ɍ������B�m���Ɉ��̐��ʂ͔F�߂���B�����A�����������͔N����1.1%�Ɣ����Ɏ~�܂�A����������0.5%�̃}�C�i�X�A�����㏸��2�N��2%�̖ڕW�����B�̂܂܁A�����̒��ɍD�i�C���͐��܂�Ȃ������B���x�T�w�����ŒᏊ���w�ɂ͉��b�Ȃ��B�i���͂܂��܂��L�������B�v���C�}���[�E�o�����X������ɉ��P���ꂸ�A���̎؋��͑�������B���ʁA����̍��ۗL����4�����ُ̈�l�BMMT����ݕ����_�͑��v�Ȃ̂��ȁH �A�x�m�~�N�X�͌������������Ŏ��̖����A�����Ƃ͌�����A�Ƃ̕]�����Ó������m��Ȃ��ˁB�ł��A����}������}�V�Ȃ��Ƃ͖��炩���B
�@���̊ԁA����ł�8���A10���Əグ���B���̌��߂�͕͂]���ł���B����ň����グ�͉��̂��߁H ���q������i�ݖ��N1���~������������Љ�ۏ��ɏ[�Ă邽�߂��ˁB�ł��グ�����Ƃŏ���������߂ΐŎ��͌���B������A�����Ȃ�Ȃ��悤�Ɍo�ϐ�����}��̂��u�A�x�m�~�N�X�v�������Ƃ������Ƃ��ˁB�������ۂ͏�������͐}��Ȃ������B����͌o�ϐ���]�X���������������́u�������S�f�U�C���v��`���Ȃ��������炶��Ȃ����ȁB�R���i�ɂ��GDP�_�E�����Ŏ��_�E���͂܂��ʂ̘b������I�~�b�g����B
�i2�j�n���V����Ղ���O��
 �@���{���n���V����Ղ���O�����f�����E�e�����щ�����ˁB�K�⍑���͂����炭�j��ő傾�낤�B���̍s���͕͂]���ł���B�ړI�̓C���t�����܂߂��A�o�̊g���}�邱�ƁB���{�̃g�b�v�E�Z�[���X�}���Ƃ��ĂˁB�ł��Η͔��d�͂��������Ȃ��B�u�p������v�i2015�N�j�ɋt�s������̂��B�������̂��N����������������̂��ߑ��Ȃ��B�V�����ː݂��C���h�l�V�A�ł͒����ɕ�������������A�B��c�����C���h�V�������y�n�������i�܂Ȃ��ēڍ����Ă���悤���B���{����͈�l�Ŋ撣������A�Ⴆ���j�Z�t�Ƌ����ŃA�t���J�̈������Ȃǂ̃C���t��������i�߂�Ƃ��A�����H�v���K�v��������Ȃ����ȁB���{�͂��ᒆ���ɓG��Ȃ�����ꖡ�Ⴄ�Ƃ����ł��o���ׂ������� �ƃW�[�W�͎v���B
�@���{���n���V����Ղ���O�����f�����E�e�����щ�����ˁB�K�⍑���͂����炭�j��ő傾�낤�B���̍s���͕͂]���ł���B�ړI�̓C���t�����܂߂��A�o�̊g���}�邱�ƁB���{�̃g�b�v�E�Z�[���X�}���Ƃ��ĂˁB�ł��Η͔��d�͂��������Ȃ��B�u�p������v�i2015�N�j�ɋt�s������̂��B�������̂��N����������������̂��ߑ��Ȃ��B�V�����ː݂��C���h�l�V�A�ł͒����ɕ�������������A�B��c�����C���h�V�������y�n�������i�܂Ȃ��ēڍ����Ă���悤���B���{����͈�l�Ŋ撣������A�Ⴆ���j�Z�t�Ƌ����ŃA�t���J�̈������Ȃǂ̃C���t��������i�߂�Ƃ��A�����H�v���K�v��������Ȃ����ȁB���{�͂��ᒆ���ɓG��Ȃ�����ꖡ�Ⴄ�Ƃ����ł��o���ׂ������� �ƃW�[�W�͎v���B�i3�j���ē����ƈ��S�ۏ�
 �@2016�N12���A�g�����v�哝���𐢊E�ɐ�삯�Đ^����ɖK�₵���͕̂]���ł���B����Ŕނ̐M��������������ˁB�������ȑ哝�̂�����n���������̂�������Ȃ����A���{�����ē�������Ƃ��Ă���ȏ�A�A�����J�哝�̂ƋC�S���ʂ��Ă��邱�Ƃ̈Ӌ`�͏������Ȃ���B�ł��A�ǂ��炩�Ƃ����g�����v���ɗ��p���ꂽ�������������ˁB�u������v�u�J�W�m���v�ɑ��Ė������Ɂu�n�C�킩��܂����v�͂������Ȃ��̂��B���חA���@�u�I�X�v���C�v�ƃ|���R�c�퓬�@F35�̑�ʍw���͍��v�ق�1���~�B����̓��_���ł��傤�B��}���ŁuIR�@�āv�������ăg�����v�哝�̂̐g���J�W�m���̓��{�i�o���菕������Ȃ�����������A�܂����������đ���̌����Ȃ肾�B���đ哝�̕⍲���{���g���́u��ژ^�v�ɂ��u���{�͂܂�ő��ێ����̂悤�Ȕ����Ńg�����v�哝�̂̂��@�������肵�Ă����v�Ɩ\�I�����B�{�l�������ɑΓ����A�s�[���������āu����ς�ˁv�ƃl�^�o�������Ⴄ�B���B�o�g�Ȃ��獂���W��̒܂̍C�ł������Ĉ���ǂ��Ȃ̂��ȁB�u�Ȃ�ł�Yes�v����Ȃ����{�̌ւ�����������ĊW��z���Ăق������� �ƃW�[�W�͎v����B
�@2016�N12���A�g�����v�哝���𐢊E�ɐ�삯�Đ^����ɖK�₵���͕̂]���ł���B����Ŕނ̐M��������������ˁB�������ȑ哝�̂�����n���������̂�������Ȃ����A���{�����ē�������Ƃ��Ă���ȏ�A�A�����J�哝�̂ƋC�S���ʂ��Ă��邱�Ƃ̈Ӌ`�͏������Ȃ���B�ł��A�ǂ��炩�Ƃ����g�����v���ɗ��p���ꂽ�������������ˁB�u������v�u�J�W�m���v�ɑ��Ė������Ɂu�n�C�킩��܂����v�͂������Ȃ��̂��B���חA���@�u�I�X�v���C�v�ƃ|���R�c�퓬�@F35�̑�ʍw���͍��v�ق�1���~�B����̓��_���ł��傤�B��}���ŁuIR�@�āv�������ăg�����v�哝�̂̐g���J�W�m���̓��{�i�o���菕������Ȃ�����������A�܂����������đ���̌����Ȃ肾�B���đ哝�̕⍲���{���g���́u��ژ^�v�ɂ��u���{�͂܂�ő��ێ����̂悤�Ȕ����Ńg�����v�哝�̂̂��@�������肵�Ă����v�Ɩ\�I�����B�{�l�������ɑΓ����A�s�[���������āu����ς�ˁv�ƃl�^�o�������Ⴄ�B���B�o�g�Ȃ��獂���W��̒܂̍C�ł������Ĉ���ǂ��Ȃ̂��ȁB�u�Ȃ�ł�Yes�v����Ȃ����{�̌ւ�����������ĊW��z���Ăق������� �ƃW�[�W�͎v����B�@2015�N�����ۖ@���i���S�ۏ�֘A�@�j�œ��{�͈��S�ۏ�ɂ����関�m�̗̈�ɓ��ݍ��ˁB���{�����́u�ϋɓI���a�v����Ȃ��搂��Ă��邪�A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��u�W�c�I���q���v�̍s�g�e�F���B�u���{�����@�v��9���ɂ͐��h�q�̊T�O�����Ȃ��W�c�I���q���̍s�g�͔F�߂��Ă��Ȃ��B���{�����́A���̓������@��13���u�l�̑��d�A�����E���R�E�K���Nj��̌����̑��d�v���25���u�������v�Ȃǂ������o���āA���߂ɂ��s�g�\��ژ_�B���������̌��������Ȃ���ꍇ�͏W�c�I���q���̍s�g��������� �Ɖ��߂����B
�@�u�W�c�I���q���v�̍s�g�e�F�͐����S�ۏ�ɂ�����ő�̓]�����B���̑�]�������@�����ł͂Ȃ����߂ɂ���čs���͈̂��Ղɉ߂��邵�A���@�ɑ��Ă����炾 �ƃW�[�W�͍l����B����قǂ̑厖�͐�Ɍ��@�����Ƃ������U�@�ł��ׂ��ȂB
�@�@�ĐR�c���ʈψ���ł́u�����̐����A���R����эK���Nj��̌��������ꂩ�畢����閾���Ȋ�@�v�Ȃ镶�����p�ɂɔ�ь������ˁB���@�w�ҁA�L���҂���́u���@�ᔽ�v�̖Ҕ�������B����ɂ���́u�푈�@�āv���Ƃ��Ĉ�ʎs���̃f���ɔ��W�����B�W�[�W�́u�푈�@�āv�ȂǂƒZ���I�Ɍ��߂��邱���̐l�����Ɂu���S�ۏ���ǂ��l����́H�v�Ɛu���Ă݂������ǁA�����͂܂��u���Ă������B
�@����߂����B�^��}�Ԃ̐R�c�͑S�����ݍ���Ȃ��B���q���̔C���͑�����Ɍ��܂��Ă���̂Ɂu�����Ȃ��v�Ɛ����͌�������B�{���̐�����S�������Ƀm�����N�����Ƃ͂��炩�����肾�B�u�W�c�I���q���������̂����玩�q���̖����͊ԈႢ�Ȃ�������B���̑���A�����J����͕K�����Ԃ�����炤�B�����痝�����Ăق����v�Ɛ��U�@�Řb���c�_�͐i�ނ͂��Ȃ̂� ���Ȃ��B�͂��炩���͈��{�����̐ꔄ�����Ƃ�����߂邵���Ȃ��̂��ˁB�������āA�����͋��s�̌���f�s�B�u���S�ۏ�֘A�@�āv�͉����ꂽ�B
�@���{�́u����œ��ē�������苭�łɂȂ����v�Ǝ��^�����B�ł����ꎩ�^����قǂ̒��g�Ȃ́H �����g�����v�哝�̂̌������Ƃ����ƂȂ��������������̂��Ƃ���Ȃ��́B���{�̋`���͑��������nj��Ԃ�͂���́H ��t�ւ̒����̋��ЂɃA�����J�����ɂȂ��Ă��������t�����́B���Ēn�ʋ���̉��P��v�������́B���V�Ԉڐ݂̑ŊJ��𑊒k�����́B�Ȃɂ�����ĂȂ�����Ȃ����B����Ȃ��Ƃł́u�Γ��ȓ��ĊW�v�Ƃ͂������g�������Ȃ��B�����肾�B�����������@���߂Ƃ����E���Z���g���Ă܂Ŋ撣�����̂�����A��������Ɠ��{�̃����b�g���Ԃ�ǂ��Ă�B�A�����J�Ɍ����ׂ����Ƃ͌������B���@�����ɏI�n�������ł��r�߂��邾���A�ƃW�[�W�͎v���̂��B
�@���{�͐��E�B��̔픚�����B���̓��{���j����p��̃��[�_�[�V�b�v���Ƃ�Ȃ����Ƃ������䂢���肾�B����ǂ��납���A�́u�j����֎~���v�̒����͂��납���c�ɂ��Q�����Ȃ��̂͂ǂ������킯���B�u�j�g�U�h�~���v�i1976�N�j�ɔ�y���Ă��邩�炢�����Ă���Ȃ��B�j�̎P�̉��ɋ������Ă�����Ă��邩��A�����J�ɂ͋t�炦�Ȃ��@���H �j�̎P�͎P�Ƃ��āA�����͓��{�������������ׂ��ł͂Ȃ��̂��ȁB�ł܂��u�h�q�����ړ]�O�����v�Ƃ������āA��������A�o��e�F�����Ⴄ�B�ǂ��l���Ă����{���{�����ׂ��X�^���X����Ȃ��B�����Ray�����A��䂵����肾�ƃW�[�W�͎v���B
�@�u���Ĉ��S�ۏ���v�́A1951�N�u�T���t�����V�X�R�u�a���v�������ɁA�g�c���ƒf�Łi����̐ӔC�������āj�����������{�̈��S�ۏ�̍������Ȃ���B�g�c�̈Ӑ}�́A����ƓƗ����ʂ��������{���R���̓A�����J�Ɉςˌo�ϔ��W�ɐ�O�ł��邽�߁A�Ƃ������̂������B���{�͖{���R���ɂ����ނׂ��������o�ϔ��W�ɉ��Ƃ��ł����BRay�����A����ɂ���ē��{�̐�㕜���������A���E��2�ʂ̌o�ϑ卑�ɂȂ����B�g�c�ɂ͗��h�ȗ��O���������Ƃ������Ƃ��ˁB�g�c�͂܂��u�A�����J�͓��{�̔Ԍ��v�ƌ��������B���̂ӂĂԂĂ����I ����ȋC�T�����{����������Ăق��������Ȃ��B
�i4�j�I�����s�b�N���v�ɂ���
 �@����2020�I�����s�b�N���v�͌��т̈��������Ȃ��ˁB�ł���Ray�����A���̎��̉����Łu�����̓A���_�[�E�R���g���[���v�Ȃ�đ匩��������������Ǒ��v�������̂��Ȃ��B�����́u�����ߊC�̒������牘���x��WHO�������500���̂P�v�Ƃ������Ƃ炵������ǁA���̐����������琧��ł��Ă��� �ƌ�����̂͗��\�����Ȃ����B���{�͎����ɓs���̂������������Ă͂߂�Ȃ����邩��p�S���Ȃ��ƂˁB���͂ނ���A���ɓ��ɂ��܂鉘�����̏������@���������̂܂܁A�Ƃ������Ƃ��B�Z�������̊j�p���������܂����ŁA�����̓��������Ă��Ȃ��B�t�B�������h��10���N�ԕۊǂ���I���J���Ƃ��������ɂ�����Ă��܂����B��������������������B���{�́A�����������Ɋw�ׂ�������Ȃ����B����̃R���i����R��B�������̂͑f���Ɋw�Ԃׂ��B�c�����t���[�Y���u�A�x�m�}�X�N�v�Ɓu�S�[�g�[�E�L�����y�[���v���Ⴈ�������Ȃ������B
�@����2020�I�����s�b�N���v�͌��т̈��������Ȃ��ˁB�ł���Ray�����A���̎��̉����Łu�����̓A���_�[�E�R���g���[���v�Ȃ�đ匩��������������Ǒ��v�������̂��Ȃ��B�����́u�����ߊC�̒������牘���x��WHO�������500���̂P�v�Ƃ������Ƃ炵������ǁA���̐����������琧��ł��Ă��� �ƌ�����̂͗��\�����Ȃ����B���{�͎����ɓs���̂������������Ă͂߂�Ȃ����邩��p�S���Ȃ��ƂˁB���͂ނ���A���ɓ��ɂ��܂鉘�����̏������@���������̂܂܁A�Ƃ������Ƃ��B�Z�������̊j�p���������܂����ŁA�����̓��������Ă��Ȃ��B�t�B�������h��10���N�ԕۊǂ���I���J���Ƃ��������ɂ�����Ă��܂����B��������������������B���{�́A�����������Ɋw�ׂ�������Ȃ����B����̃R���i����R��B�������̂͑f���Ɋw�Ԃׂ��B�c�����t���[�Y���u�A�x�m�}�X�N�v�Ɓu�S�[�g�[�E�L�����y�[���v���Ⴈ�������Ȃ������B�i5�j�k���̓y���
 �@���{�́A�C�����ɂ��c�������ƂƂ��āA�f�v���Ɩk���̓y���������Ă���B�ɍ��̋ɂ݂Ƃ��������ˁB�f�v����͑��肪���肾���炾�ꂪ����Ă�����B�����炱��͒u���Ă����Ƃ��āA�����k���̓y�������B�u���̐���ŏI�~����łv�ƈӋC�����̂̎c�O�Ȃ��玸�s�������B�ǂ����Ƃ����A��́u�ł悵�v�i1965�N���\�����錾����Ƃ���j�Ǝ���n�[�h���������Ă��܂������ƁB������́u�Ƃ肠�����o�ϋ��͂�i�߂Ă��܂����v���Ƃ��B�O���́u�܂��A�ӂ������Č����ė��Ƃ��ǂ����T��v�̂��퓹�B������u�ł��~�ނȂ��v�ƕ�����������Łu�l���v����X�^�[�g����ׂ��Ȃ̂��B���ꂶ������ĕԂ��Ă��Ȃ��B�o�ϋ��͂Ɋւ��ẮA����ނ�̂܂܃X�^�[�g��������A���V�A�̖@�����ł̉^�c�ɂȂ����B�����ƃ��V�A�̎����x�z��F�߂錋�ʂɂȂ���������ˁB���ꂾ���͔�����ׂ��������̂ɂˁB���V�A�����Č����Čo�ς������Ƃ����킯����Ȃ��B�������Ă��鎞���K������B�����炻�̋@�𑨂��Ă�����o���̂��B�u�V�R�K�X���Ă�邩�瓇�Ԃ��v���āB���ꂭ�炢�̂������������Ȃ����A���̍����������Ƃ��킯�Ȃ���B�����m�푈�����A���\�s�N�����ɂ�������炸�A�Ō�̍Ō�ɍU�ߓ����Ă��Ďl���������ߎ�������ł���B�������V�ԃv�[�`����ɁA����ȑΉ��Œʗp����킯���Ȃ��B�u�E���f�B�~�[���v�ȂĂт����ċC�S�m�ꂽ�����Ă��A����͂��������A��������Ă��܂���B�����͈��{�A���Ȃ������}�V�������B���̃C���n���m��Ȃ����V�����ɑ��̌����S���ł��U���ė��ڂɏo���Ƃ������Ƃ��ȁB�u�ɍ��̋ɂ݁v�Ƃ́A27�����Ȃ��牽����߂��Ȃ������������g�̏�Ȃ� �Ƃ������Ƃ��낾�낤�B�ڕW�Ɍf�����u���O���̑����Z�v�͖��c�Ȍ����ɏI����Ă��܂����ˁB
�@���{�́A�C�����ɂ��c�������ƂƂ��āA�f�v���Ɩk���̓y���������Ă���B�ɍ��̋ɂ݂Ƃ��������ˁB�f�v����͑��肪���肾���炾�ꂪ����Ă�����B�����炱��͒u���Ă����Ƃ��āA�����k���̓y�������B�u���̐���ŏI�~����łv�ƈӋC�����̂̎c�O�Ȃ��玸�s�������B�ǂ����Ƃ����A��́u�ł悵�v�i1965�N���\�����錾����Ƃ���j�Ǝ���n�[�h���������Ă��܂������ƁB������́u�Ƃ肠�����o�ϋ��͂�i�߂Ă��܂����v���Ƃ��B�O���́u�܂��A�ӂ������Č����ė��Ƃ��ǂ����T��v�̂��퓹�B������u�ł��~�ނȂ��v�ƕ�����������Łu�l���v����X�^�[�g����ׂ��Ȃ̂��B���ꂶ������ĕԂ��Ă��Ȃ��B�o�ϋ��͂Ɋւ��ẮA����ނ�̂܂܃X�^�[�g��������A���V�A�̖@�����ł̉^�c�ɂȂ����B�����ƃ��V�A�̎����x�z��F�߂錋�ʂɂȂ���������ˁB���ꂾ���͔�����ׂ��������̂ɂˁB���V�A�����Č����Čo�ς������Ƃ����킯����Ȃ��B�������Ă��鎞���K������B�����炻�̋@�𑨂��Ă�����o���̂��B�u�V�R�K�X���Ă�邩�瓇�Ԃ��v���āB���ꂭ�炢�̂������������Ȃ����A���̍����������Ƃ��킯�Ȃ���B�����m�푈�����A���\�s�N�����ɂ�������炸�A�Ō�̍Ō�ɍU�ߓ����Ă��Ďl���������ߎ�������ł���B�������V�ԃv�[�`����ɁA����ȑΉ��Œʗp����킯���Ȃ��B�u�E���f�B�~�[���v�ȂĂт����ċC�S�m�ꂽ�����Ă��A����͂��������A��������Ă��܂���B�����͈��{�A���Ȃ������}�V�������B���̃C���n���m��Ȃ����V�����ɑ��̌����S���ł��U���ė��ڂɏo���Ƃ������Ƃ��ȁB�u�ɍ��̋ɂ݁v�Ƃ́A27�����Ȃ��牽����߂��Ȃ������������g�̏�Ȃ� �Ƃ������Ƃ��낾�낤�B�ڕW�Ɍf�����u���O���̑����Z�v�͖��c�Ȍ����ɏI����Ă��܂����ˁB�i6�j�����`�J�P�`�T�N�����
 �@�X�F����́A2016�N�A�Ēr�דT�����n�݂��v�悵�Ă����X�F�w���u����̍��L�O���w�@�v�ւ̍��L�n���������ɂ����āA��8���~�̒l�����ȂLjٗ�ȑΉ�������݂ŏo�����Ƃɒ[����B�Ēr���ƈ��{�݂͌��Ɂu���{��c�v�̓��u�B�v�z�I�Ɏu��������ԕ����B�j�i�̕��������͎̃L���C�������Ă̂��Ƃƍl����͎̂��R�̗��B�Ƃ��낪�A2017�N2���̍���Łu����Ȃ��W���Ă������ƂɂȂ�A����͂����A������c�������߂�v�ƂԂ���������B���̊ԁA��}�̒����Ȃǂ���A���{���b�v�l�̖����Ȋ֗^����{�����100���~�̊�t�Ȃǂ�����݂ɏo�Ă����i�{�l�͔ے�j�B�����Ŏ͂ǂ��������B�ېg�̂��߂ɂ��Ă̓��u���̂Ă��B�ꎞ�́u���{���悭���邽�߂Ɋ撣�낤�B���̂��߂ɂ͎q�������̋��炪�̐S���v�ƈӋC�����������u���u�������l�v�ƌ��������ĂˁB�Ēr���̖��O�͂������肾�������Ǝ@�����B���{�̑Ή��͂����ɂ���Ȃ��߂���ƃW�[�W�͎v���̂����A����͂��Ă����A���Ԃ͂���Ɏ��ȕ����ɐi�W����B
�@�X�F����́A2016�N�A�Ēr�דT�����n�݂��v�悵�Ă����X�F�w���u����̍��L�O���w�@�v�ւ̍��L�n���������ɂ����āA��8���~�̒l�����ȂLjٗ�ȑΉ�������݂ŏo�����Ƃɒ[����B�Ēr���ƈ��{�݂͌��Ɂu���{��c�v�̓��u�B�v�z�I�Ɏu��������ԕ����B�j�i�̕��������͎̃L���C�������Ă̂��Ƃƍl����͎̂��R�̗��B�Ƃ��낪�A2017�N2���̍���Łu����Ȃ��W���Ă������ƂɂȂ�A����͂����A������c�������߂�v�ƂԂ���������B���̊ԁA��}�̒����Ȃǂ���A���{���b�v�l�̖����Ȋ֗^����{�����100���~�̊�t�Ȃǂ�����݂ɏo�Ă����i�{�l�͔ے�j�B�����Ŏ͂ǂ��������B�ېg�̂��߂ɂ��Ă̓��u���̂Ă��B�ꎞ�́u���{���悭���邽�߂Ɋ撣�낤�B���̂��߂ɂ͎q�������̋��炪�̐S���v�ƈӋC�����������u���u�������l�v�ƌ��������ĂˁB�Ēr���̖��O�͂������肾�������Ǝ@�����B���{�̑Ή��͂����ɂ���Ȃ��߂���ƃW�[�W�͎v���̂����A����͂��Ă����A���Ԃ͂���Ɏ��ȕ����ɐi�W����B�@�Ȃ�ƁA�̔����Ɩ������錈�ٕ�������낪�����悤�ɉ������̂ł���B����͕������������s���������ȋߋE�����ǁB�������̂͐V���ɍ����ȗ����ǒ��ɋN�p���ꂽ���������B���̕��܂��ɐ����̂Ȃ�ł�����ł��C�G�X�}����������B���̂�����Ŝu�x�Ƃ������t����ь������킯�����A���{����������m��ʂ킯�͂Ȃ��ƍ������ꂵ���l�����B�ؐl����ɉ��������쎁�́u�L���ɂȂ��v�u�Y���i�ǂ̋��ꂪ���蓚�����Ȃ��v�̈�_����B�������Đ蔲�������쎁�͂��̌��сi�H�j�ɂ���Ă����Œ������ɑ�o���B���肦�Ȃ����s�s�����B����ł́A����������v���ꂽ�m���L�����A�����̎��E�Ƃ����ߌ���ł��܂����B
�@���͑��͕ېg�̂��߂Ɍ���������������B������̎�����S��������ꂽ�������͗ǐS�̙�ӂɑς����˂Ď���̖����B�܂��ɕs�ˎ��B�O�㖢���B�u�x���낤�������낤���A����ȗ��s�s�͋������͂����Ȃ��B���{�͖����`�̍�����h�邪����s�ˎ��Ɋւ�����̂�����A�����₻�̌����������̂�����A�ǐS���鐭���ƂȂ炱���Őg�������ׂ����������낤�B
 �@�����i�s�Ŗ���݂ɏo���̂����v�w������������B�̙��z�̗F�Ƃ�������v�K���Y�����V���ɍ���w�́u�b��w���V�݁v�Ɉ��{�����ʂȔz�����{���� �Ƃ������̂��B��ՋK����ł��ӂ��Ƃ��āA2013�N�A���{�������グ���u���Ɛ헪����v�\�z�B���̈�Ƃ��Ă̏b��w���V�݂́A�����a�̌����Ȃǂ��̈Ӌ`�͑傫���A���ꎩ�̖��͂Ȃ��B�Ƃ��낪�F�ɂ����āA�����Ȃ炴��o�܂�����ꂽ�̂��B���Q�������s�ɐV�݂�����v�w�����R���ȑ�w�b��w���Ƌ��s�Y�Ƒ�w�̊Ԃŋ����ƂȂ������A�\���_���̏o���h�������Y�傪�����Ă���̂��N�̖ڂɂ����炩�Ȃ̂ɁA���ʂ́u���v�w���v�F�Ƃ��������ƂȂ����B�͂��߂���u���v�w�����肫�v�Ői�߂��̂ł͂Ȃ����ƒNjy���ꂽ���{�́A2017�N7���A�u���v�w������̐\���̎�����m�����͍̂��N��1��20���v�Ɠ��فB���Q������́u2�N�O�ɂ͂������������͂��v�Ƃ̏،����B�e�����ɃS���t�ɋ����闼�҂̉f�������J�����B�ǂ��l���Ă��s���R�ȓ��قɁA�����́A����͌��߂������B�����߂̕��ւ� �ƒ����������̂��B�ޔC�����O���ȏȎ��������O��약��������̏ؐl����ŋ^�f���������Ă��A�������͕ʌ��őO�쎁�𒆏�����ȂǁA���{����邱�Ƃɕ��S����݂̂������A���ꂼ���͂̎������ȊO�̉����ł��Ȃ��B�Ƃ��낪���̔N��11���A���v�w���b��w���́g�߂ł����h�J�Z����B����ȗ��s�s���ɍ����̕���͕�����������ˁB
�@�����i�s�Ŗ���݂ɏo���̂����v�w������������B�̙��z�̗F�Ƃ�������v�K���Y�����V���ɍ���w�́u�b��w���V�݁v�Ɉ��{�����ʂȔz�����{���� �Ƃ������̂��B��ՋK����ł��ӂ��Ƃ��āA2013�N�A���{�������グ���u���Ɛ헪����v�\�z�B���̈�Ƃ��Ă̏b��w���V�݂́A�����a�̌����Ȃǂ��̈Ӌ`�͑傫���A���ꎩ�̖��͂Ȃ��B�Ƃ��낪�F�ɂ����āA�����Ȃ炴��o�܂�����ꂽ�̂��B���Q�������s�ɐV�݂�����v�w�����R���ȑ�w�b��w���Ƌ��s�Y�Ƒ�w�̊Ԃŋ����ƂȂ������A�\���_���̏o���h�������Y�傪�����Ă���̂��N�̖ڂɂ����炩�Ȃ̂ɁA���ʂ́u���v�w���v�F�Ƃ��������ƂȂ����B�͂��߂���u���v�w�����肫�v�Ői�߂��̂ł͂Ȃ����ƒNjy���ꂽ���{�́A2017�N7���A�u���v�w������̐\���̎�����m�����͍̂��N��1��20���v�Ɠ��فB���Q������́u2�N�O�ɂ͂������������͂��v�Ƃ̏،����B�e�����ɃS���t�ɋ����闼�҂̉f�������J�����B�ǂ��l���Ă��s���R�ȓ��قɁA�����́A����͌��߂������B�����߂̕��ւ� �ƒ����������̂��B�ޔC�����O���ȏȎ��������O��약��������̏ؐl����ŋ^�f���������Ă��A�������͕ʌ��őO�쎁�𒆏�����ȂǁA���{����邱�Ƃɕ��S����݂̂������A���ꂼ���͂̎������ȊO�̉����ł��Ȃ��B�Ƃ��낪���̔N��11���A���v�w���b��w���́g�߂ł����h�J�Z����B����ȗ��s�s���ɍ����̕���͕�����������ˁB�@�����}�͖��N����������Ȃ鍑��ŊJ�Â��鍧�e����Â��Ă���B���j�͌Â��n�܂����̂�1952�N���B�����Ŗ��ɂȂ����̂́A���{�����ɂȂ��Ă���̌o��̑���Ɩ���}�ȏ��҂������B2019�N�́u���������v�ɂ͈������@��Ёu�W���p�����C�t�v��\�̏��҂����o�B�I���悩�珵�����x���҂ւ̉ߏ�ȃT�[�r�X�ƌ���̕�U�Ȃǂ���荹�����ꂽ�B�����ɂ��Ĉ��{�́A���ҎҖ���͔p�������Ƃ��A���ҋq�͉����z�e���ɒ��Ŏx�������Ƃ��A�z�e���͌ʈČ��̏ڍׂ͏o���Ȃ��Ƃ��A��ɂ���ĕs���Ȍ���������܂������B����ɂ��Ă������p�����D���Ȑ�������B���������A�u��W�����̂ł͂Ȃ�����������v�̓��قɂ͏����ˁB����͂܂��A���^�}�����x�̍���������c�X�Ƒ����Ă������̂�����A���{�����̐ӔC�ɋA�����Ƃ͂Ȃ��̂����A�̒ʂ��������ӔC�͉ʂ����ׂ��������ˁB�ł��Ȃ������̂͂�͂���߂������������Ƃ������Ƃ��낤�B
�i7�j�ߊ�̌��@����
 �@���@�����ł���B���@�����͈��{�̔ߊ肾���A����͑c���ݐM��̈�u���p�����̂ł��������B�u���@�̎���I�����v�͎����}�̓}���ł�����B�{�ۂ͂������u��9���v�B�u��͕s�ێ��v�̏Ǝ��q���̑��݂Ƃ̖����������ɂ���ĉ�������̂��ړI���B���h�q�̂��߂ɑ��݂��鎩�q�������@�ᔽ�Ƃ��錛�@�w�҂͏��Ȃ��Ȃ��B���A����͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��ƈ��{�͍l����B����т��Ă��̎��_�������ʂ����̂Ȃ�W�[�W�͕]������B�����͂��̍l���Ői�߂��������̂�������Ȃ����A�������u�����v���̂��̂��ړI�ƂȂ��Ă��܂��� �ƃW�[�W�ɂ͉f�����B�����̎葱�����L�����u��96���v�̉���A���@��9���̏����̂܂܂ɂ��āu���q���̑��݂L����v�Ȃ�ϑ��āA�u�ً}���Ԑ錾�v�̐V�K�쐬���X�A���������Ɨh�ꓮ���B����y�Ɂg�Ƃɂ�����������悵�h�Ƃ����v���Ȃ��Ȃ��Ă����B�����̖{�ۂ��u��9���v�Ȃ�����{�ɍi���āA�����ƍ���c���ɂ��̈Ӌ`��S�苭���������c�_��s�����B����ȓw�͂�n���Ɋт��Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��������B�ނɂ͓��ɗ����������o��Ə�M�Ɍ����Ă��� �ƌ��킴��Ȃ��B�c���ݐM��̓��Ă̕s�������̐�����ژ_�u���ۏ��v�ւ̑Ή��ɔ䂵�āA�����{�W�O�́u���{�����@�v�ւ̂���͋C�T�ɂ����ēV�ƒn�قǂ̊J�����������B�u���@�����������ŏ��̑�����b�v�̏̍����~���������̂�������Ȃ����A���傹���ňׂ�����قnjy����Ƃł͂Ȃ������Ƃ������Ƃ��BRay�����A�����������u�����͐������Ȃčs���ׂ��v�i��F����P�j�ƌ����Ă����B
�@���@�����ł���B���@�����͈��{�̔ߊ肾���A����͑c���ݐM��̈�u���p�����̂ł��������B�u���@�̎���I�����v�͎����}�̓}���ł�����B�{�ۂ͂������u��9���v�B�u��͕s�ێ��v�̏Ǝ��q���̑��݂Ƃ̖����������ɂ���ĉ�������̂��ړI���B���h�q�̂��߂ɑ��݂��鎩�q�������@�ᔽ�Ƃ��錛�@�w�҂͏��Ȃ��Ȃ��B���A����͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��ƈ��{�͍l����B����т��Ă��̎��_�������ʂ����̂Ȃ�W�[�W�͕]������B�����͂��̍l���Ői�߂��������̂�������Ȃ����A�������u�����v���̂��̂��ړI�ƂȂ��Ă��܂��� �ƃW�[�W�ɂ͉f�����B�����̎葱�����L�����u��96���v�̉���A���@��9���̏����̂܂܂ɂ��āu���q���̑��݂L����v�Ȃ�ϑ��āA�u�ً}���Ԑ錾�v�̐V�K�쐬���X�A���������Ɨh�ꓮ���B����y�Ɂg�Ƃɂ�����������悵�h�Ƃ����v���Ȃ��Ȃ��Ă����B�����̖{�ۂ��u��9���v�Ȃ�����{�ɍi���āA�����ƍ���c���ɂ��̈Ӌ`��S�苭���������c�_��s�����B����ȓw�͂�n���Ɋт��Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��������B�ނɂ͓��ɗ����������o��Ə�M�Ɍ����Ă��� �ƌ��킴��Ȃ��B�c���ݐM��̓��Ă̕s�������̐�����ژ_�u���ۏ��v�ւ̑Ή��ɔ䂵�āA�����{�W�O�́u���{�����@�v�ւ̂���͋C�T�ɂ����ēV�ƒn�قǂ̊J�����������B�u���@�����������ŏ��̑�����b�v�̏̍����~���������̂�������Ȃ����A���傹���ňׂ�����قnjy����Ƃł͂Ȃ������Ƃ������Ƃ��BRay�����A�����������u�����͐������Ȃčs���ׂ��v�i��F����P�j�ƌ����Ă����B�i8�j����������i�H�j��̕s�ˎ�
�@ �@���������Ɏ����Ẳ͈�@���v�Ȃ̌��E�I���@�ᔽ�^�f�͂Ȃ�Ƃ������܂��������������ˁB���Ă̎Q�@�I�B���̍L���I����̒����2���B�����}�̌��E��5�I���ʂ����Ă���a�茰���c���������B�����͂����ɉ͈䍎�s�c���̍Ȉė�����i���B�c�Ȃ������œƐ�͕������͂��������炩�ɍa��Ԃ����B���{�͂��ča�莁�Ɂu�s���͎̐ӔC�v�i2007�N�Q�@�I����j�Ƃ��u�����ߋ��̐l�v�i2012�N�j�Ȃǂ̋ꌾ��悳��A���O�����������Ă��� �Ƃ����̂��O�ڂ̈�v����Ƃ��낾�B�����Ő����͂����炳�܂ȑΉ��ɏo��B�I�������̋��o���A�͈�w�c�ɂ�1��5000���~�A�a��w�c�ɂ�1500���~�Ƃ����O�㖢���̍�������B���������{�́A�X�^�b�t���l��I���������ɏ풓������������n���肵�Ĉُ�ɔM�̓����������������A�Ȃ�ӂ�\��ʎx����W�J�B�����܂ł��ꂽ��͈�v�Ȃ͉������ł��������Ȃ��ƍl�����ˁB����������o���}�L�܂������B�����͎R�قǂ��邵�A�ނ���c���ĕ����邱�Ƃ��|�������낤�B���ʈė����͓��I�A�a�莁���I�B���{�͌��������𐰂炵�����ƂɂȂ�B�͈䍎�s���͒���̓��t�����Ŗ@����b�̈֎q��^�����O��̏����t���ʂ������B���͎҂̎����̂��߂ɖ@��Ƃ��Ă܂Ŋ撣�������́g���J���h�Ƃ����킯���B����Ȑl�Ԃ��A���Ƃ����낤�ɍ��̖@���i��@����b�ɂȂ�����ł���B�e�^������݂ɏo�����Ǝ��C�i������̍X�R�j�A���{�́u���̔C���ӔC�ł��v�Ǝߖ��������A����ōςޖ�肶��Ȃ��B�{���̈��͒N�ȂႢ�I
�@�s�ˎ����o���{�����Ō�̎~�߂́A2020�N5���̍���O�������������@���������̌��������A�C��肾�����ˁB�l�X�ȕs�ˎ����B�����������̂��낤���A���������ɐ����ɋ߂����쎁���A�����邽�߁A�l�����������{�������ٗ�̌������K��Ă͂߂Ē�N������}��Ȃǂ��̉��ɑ������B�Ƃ��낪���̎v�f�́A���̍��쎁���u�q���}�[�W�����v���s���Ă������Ƃ����o���Ă������Ȃ��W�E�G���h�̂��e���B�������쎁���q���}�[�W���������Ă��Ȃ�����̂܂܌��������ɂȂ��āA�͈�v�Ȃ͏������Ă�����������Ȃ��B�Ȃ�Ƃ��R�������͂̈ł��B
���G�s���[�O��
 �@���{���C��A���ǂ͒����Ɂu�|�X�g���{�v�Ɍ������ē����o���B���ʂ�����܂ł��Ȃ����`�̊��[�����Ō��܂肾�낤�B���J���O����I����Ă�B���߂ċ��ԈˑR����h���k���̎������銴���������ˁB����͂����ƁA�W�[�W���C�ɂȂ����͈̂��{�̑Ή����B�̈Ӓ��̐l�͈�т��Ċݓc���Y������������͂��B����͎����Ƃ��ɔF�߂���m�̎������B�Ƃ��낪�́A8��31���A�K�˂Ă����ݓc���Ɂu���Ȃ��𐄂��v�Ɩ������Ȃ������������B�͍ő�h��98�l��i��������דc�h�̃��[�_�[���B�Ȃ̂ɍדc�h�͐����̎x���ɉ�����B�J�ԁA�ݓc���́u�����Ȃ��v����Ǝ��猩�������ꂽ �Ƃ������B�W�[�W�͊ݓc���̂��Ƃ��D���Ȃ킯����Ȃ�����ǁA���̎d�ł��͂���܂肾�B�l�Ԗ�����ѐ������含���Ȃ�������B�܂��A�����̂��Ƃł͂��邯��ǁB
�@���{���C��A���ǂ͒����Ɂu�|�X�g���{�v�Ɍ������ē����o���B���ʂ�����܂ł��Ȃ����`�̊��[�����Ō��܂肾�낤�B���J���O����I����Ă�B���߂ċ��ԈˑR����h���k���̎������銴���������ˁB����͂����ƁA�W�[�W���C�ɂȂ����͈̂��{�̑Ή����B�̈Ӓ��̐l�͈�т��Ċݓc���Y������������͂��B����͎����Ƃ��ɔF�߂���m�̎������B�Ƃ��낪�́A8��31���A�K�˂Ă����ݓc���Ɂu���Ȃ��𐄂��v�Ɩ������Ȃ������������B�͍ő�h��98�l��i��������דc�h�̃��[�_�[���B�Ȃ̂ɍדc�h�͐����̎x���ɉ�����B�J�ԁA�ݓc���́u�����Ȃ��v����Ǝ��猩�������ꂽ �Ƃ������B�W�[�W�͊ݓc���̂��Ƃ��D���Ȃ킯����Ȃ�����ǁA���̎d�ł��͂���܂肾�B�l�Ԗ�����ѐ������含���Ȃ�������B�܂��A�����̂��Ƃł͂��邯��ǁB�@Ray�����A���{�����͌��߂��������B�ł��u�߁v�̕������|�I�ɑ傫�������ƌ������ˁB�u���v�͂Ƃ����A���������̂������Ő��E�̎�]��c�Ȃǂœ��X�ƒ����Ɉʒu���������ƁB����͍����ɂƂ��Čւ炵�����Ƃł͂�������B6�x�̍����I�����ׂĂɈ��������̂����M���̂����m��Ȃ��B�ł�����͖�}�̂��炵�Ȃ��ɏ�����ꂽ�����B�I���ɏ��Ă������Ă���Ȃ��B���͂ǂ�Ȑ�������邩����B
�@�u�߁v�̑��͓��t�l���@�̐ݒu���ȁB�u���{�ꋭ�v�̌��B�l�����������������͂��̈ӌ������͂ɐ����i�߂邱�Ƃ��ł���B�u�l���������`���@�哱�v�̐�����@�͎�@�Ƃ��Ă͊ԈႢ����Ȃ��B��ɗ��l�Ԃ��܂Ƃ��Ȃ�ˁB�ł����ۂ����͂Ȃ�Ȃ������B��ɗ��l�Ԃ��܂Ƃ�����Ȃ��������炾�B�l����������ꂽ�����͕s�����Ɗ����������̈ӌ��ɉ������d��������������Ȃ������B�����u�u�x�v���Ă���ˁB�ł��������͂ł��Ȃ��B���ʂ̐l�Ԃ������Ă������߂ɂ͂���������d�����Ȃ��Ƃ���͂���B��͂��ɗ��l�Ԃ͑厖����B
�@�����ɖڐ��������邱�Ƃ����A���͂̕ێ��Ǝ���̕ېg��D�悵����������Ƃ��߂̈���B�u�����͍����̂��́v�Ƃ��������}�̓}���͂ǂ��ɍs����������̂��ȁB�����Ɉ��S�ƈ��S��ۏ���̂������̏d�v�Ȗ����Ȃ�A�c�O�Ȃ�����{�����ɂ͂��̊�{���������Ă����ˁB
�@�t���̔C�����K�ޓK���Ƃ͖�����ŁA�C���ӔC�����鎖�Ⴊ���o�����B�O�q�͈̉�@����b�A�����̖h�q��b�A�o�Y��b�A�ܗ֒S����b�AIT�S����b�A����k�����S����betc�Ɩ����ɂ��Ƃ܂Ȃ����B
�@���Ă̏��q�����A�n���n���A��������Љ�ɂ��Ă͑S�����ʂ��オ��Ȃ������A�Ƃ������A�قƂ�ǂ��C���Ȃ������ˁB���Ɋ��҂��邵���Ȃ��ȁB
�@�����`�̏d�v�Ȋ�{�̈���J���͏�ɕ��I�������B������̂��Ȃ��ƌ����A��o���Ă��������͑啔�������h��ŕ���ꂽ�B��������ʂ̌��������Ő����ӔC���ʂ����Ȃ������B����̐������Ǝ��Ȗh�q�̂��߂ɂ͕��C�ʼnR�������B�����Ɉ₷�ׂ����C�ʼn������B���吭���ɕK�v�Ȑ����^�c�̓������͂��Ƃ��Ƃ����Ȃ�ꂽ�B�܂��ɉB���̎����̂��̂������B�����͖��吭���̍����R�Ƒł��ӂ��܂��ɖ����`�ւ̗���s�ׂɑ��Ȃ�Ȃ��B���ꂾ���Ō��߂́u���v���ׂĂ��ł��������ƌ����Ă������傫�ȁu�߁v�������ˁB
�@�u���{�ꋭ�v�Ƃ���ꂽ���͂̈�ɏW���͂܂��A�����}�c���̈ӎ��̒����������ˁB���I���搧������ɗւ��������B��̌����Ƃ���ɂ��Ȃ���킪�g����Ȃ��B������A�����������Ƃ������Ȃ��B�c�_���N���Ȃ��B��C�͑���B���ʂ��͈����Ȃ�B�����p�������͂����Ȃ��B���̂܂܂���{���ɓ��{�͊낤�����B�o�ł�A�C�T������I �������J����̂͌N�����������Ȃ��I�I
�@Ray�����A���{������7�N8����͊m���Ɍ����j��Œ�����������ǁA���j�́u�����������������̐����v�Ƃ����]�����Ȃ���������Ȃ���B�m���Ɂu���߂��Ȃ��������猈�߂鐭���v�ɓ]���͂�������ǁA���߂����g����肾�����B�����āA�����������Ƃɂ���Ĉ����N�����ꂽ�������s�Ɩ����`�ւ̖`���́A���{�����̏������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u���̈�Y�v�Ƃ��ĉi�v�ɋL������邱�ƂɂȂ邾�낤�ˁB�W�[�W�͊肤 �uRay�����̎���ɂ͍���菭���ł��܂��Ȑ������s���܂��悤�Ɂv���ĂˁB�����͂ǂ��� ���E��E���E�ƁE���B
���Ō�̍Ō�ɂ����ꌾ
�@�����V����9��2����3���Ɏ��{�������_�����ɂ��Ɓu���{���������v�̎��ѕ]���́u�傢�Ɂv�Ɓu������x�v�����킹�āu�]������v��71%�������������B�W�[�W�͂�������Ĝ��R�Ƃ����B�Ȃ�Ƃ��ꂪ���ӂȂƁB���{�͂����ɂ͂悭�Ȃ�Ȃ��B�����点�߂āA�����Ɋ�]������Đ����邵���Ȃ����낤�B���̍�����߂�킯�ɂ͂����Ȃ��̂�����B
2020.08.16 (��) �����A���̂��Ƃ��烏�[�O�i�[�Ɩ��t�W�ɑz����y����
�@7�����A���c�J�撷���e���r�Łu����ł����ł����x�ł��vPCR�������\�ȑ̐��Â������Ǝ��ɂ�� �Ƙb���Ă����B����́A���������Ȃ�����Ƃ��ς₵�����̔������낤�B�Ȃ����͂��Ȃ��̂��H���C���Ȃ��̂��H ���l���Ă�����A�j�S�I�Ȃ��邱�ƂɋC�������B���{�̐S�������L�B�V�^�R���i�͑債���V�����m�ł͂Ȃ��B�m���Ɋ����Ґ��͑��������Ă��邪�A���Ґ��͏��O���ɔ�ׂĂ��ɏ��B1000�l���x�Ŏ��S����2.6%�B100�N�O�̃X�y�C�����ׂ̎���39���l�Ɋr�ׂ��猎�ƃX�b�|�����B���l�D���̍����ɂ͓K���ɒ��ӂ𑣂��Ă��������B���̂������Ö�����N�`�����o�Ă��邩�炻��ŃW�E�G���h�B�I�����s�b�N�H��ꂽ����B�ł��Ȃ�����Ȃ��B���ꂾ����B
 �@�����A�m�M�ƓI�g�������Ȃ��h�����ߍ��̂��B���߂��Ƃ������Ƃł͂Ȃ� �u������t�����Ď���҂v�Ƃ������_���낤�B�����l����ƁA�����ȉ�̏��������Ă�GoTo�L�����y�[���A���[�����́u���[�P�[�V�����v�Ȃ�\�V�C�����A�s�m���Ƃ̐ӔC�̂Ȃ��荇���o�g���A�������o���Ȃ�4�i�K�w�W�A���ӂ𑣂������̑��{�����A������Ȃ�������b�A����܂܂̍���A���ׂĂɍ��_���䂭�B
�@�����A�m�M�ƓI�g�������Ȃ��h�����ߍ��̂��B���߂��Ƃ������Ƃł͂Ȃ� �u������t�����Ď���҂v�Ƃ������_���낤�B�����l����ƁA�����ȉ�̏��������Ă�GoTo�L�����y�[���A���[�����́u���[�P�[�V�����v�Ȃ�\�V�C�����A�s�m���Ƃ̐ӔC�̂Ȃ��荇���o�g���A�������o���Ȃ�4�i�K�w�W�A���ӂ𑣂������̑��{�����A������Ȃ�������b�A����܂܂̍���A���ׂĂɍ��_���䂭�B�@���ꂼ�܂��ɕ��u���ƁB���������Ȃ��B������������͓̂�����O�B�n���n����������A�������X�̐����Ɉ���J�͎~�߂��B�ł����߂āA��Õ����͔����Ăق��������̂����A��������������������Ԃɖ��ז���B���͂�����ԂȂ̂Ɂu�܂��N�����Ă��Ȃ��v�̐��{�����B���ꂶ���t��u�`���B�����͑����Ȃ��E�K���_�ȉ��A�x�b�h�͑���Ȃ��A������͊����Ґ��ƌ���������Ď���×{�҂����B�����牽�܂ő̂��炭�B�𗧂������̃A�x�m�}�X�N�ɐ��S���~�������ނ��炢�Ȃ�A���Y�S����PCR�����@��u�G���[�g�C���W�[�j�A�X�v�i�P��1250���~�j���e�s���{����1�䂸�����ő��t�����ق�������ۂǃ}�V�B�o��́Y��6���~�B10�䂸�ł�60���B�ł�����Ȓm�b�����C���Ȃ����낤�B�j�Ă���ȍ��ƂɒN�������B�Q�����Ƃ���ł͂��܂�Ȃ��B�����Ō��_�A�������A�E�g�̉��������҂͈Ӓn�ł����킯�ɂ͂܂���܂���B�ȏ�B
�@���āA8���͐�c���ÂԌ��B��ɖ~�̑����16���͑c���i1990�N�j�ƕ�i2018�N�j��W�����ł���B��y�@�̖@�v�̍s���ɋ���A���N�͕�̎O����ɂ�����B�������̏B��������o�����ăR���i���^�ԂƎv�킹�Ă͂����Ȃ��B�����l���āA����̕�Ɂu�@�v������v�̏���𑗂����B�����̕ԓ��́u�����v�������B������g�ق��Ƃ����h���{�����낤���B
�@�ꂪ�S���Ȃ��ĉ���ނ��Ƃ͑��X���邪�A���̏��������ƕ����Ă����悩�����A�Ƃ����̂����̈���B���ƕ��1944�N10��5���Ɍ����i�͂��o�j�A��1945�N5��20���Ɏ������܂�A8��15���I��A1947�N4��23���ɕ����S���Ȃ����B����2�Ζ����A���Ƃ̎v���o�����낤�͂����Ȃ��B����Ȏ��ɕꂪ�b���Ă��ꂽ���Ƃ̎v���o��2�G�s�\�[�h�݂̂ł���B ��́A�u�x�݂̓��͎����ɂ������ă��R�[�h���Ă���B������w����͂Ȃ�Ƃ����Ȃł����x�Ɛq�˂�Ɓw�g���X�^���ƃC�]���f�x�ƃ{�\���ƈꌾ�ꂢ���v�Ƃ����b�B������́A�u�w���t�W�x���D���ł悭�ǂ�ł����v�Ƃ������ƁB����͂�Â��B����Ȃ�Ŋy���������̂��Ȃ��B�܂��A���������B���������������������邵���Ȃ����� �Ƃ������Ƃ��낤�B
�i1�j���������Ă������[�O�i�[�u�g���X�^���ƃC�]���f�v
 �@���������Ă����̂͂ǂ�ȃ��R�[�h�������̂��B�����͖��_SP���B��|����́u�g���X�^���ƃC�]���f�v�Ƃ����ꂫ��1944�N�`1947�N�Ƃ������ԁB�����͂����A���炦�т����u���Ȍ���Ձv�𗊂邵���Ȃ��B���݂ɂ��炦�т��Ƃ͍�Ɩ쑺�ӓ��̂�����̕M���ʼn��y�]�_���ɗp�������́B�u���Ȍ���Ձv�ɖڂ�ʂ��ƁA���[�O�i�[�u�g���X�^���ƃC�]���f�v�͈�_�����������B���t�̓E�B���w�����E�t���g���F���O���[�w���F�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�i�pEMI�j�B�����ɏ�����Ă��邠�炦�т��̕��͂��������Ă݂悤�B
�@���������Ă����̂͂ǂ�ȃ��R�[�h�������̂��B�����͖��_SP���B��|����́u�g���X�^���ƃC�]���f�v�Ƃ����ꂫ��1944�N�`1947�N�Ƃ������ԁB�����͂����A���炦�т����u���Ȍ���Ձv�𗊂邵���Ȃ��B���݂ɂ��炦�т��Ƃ͍�Ɩ쑺�ӓ��̂�����̕M���ʼn��y�]�_���ɗp�������́B�u���Ȍ���Ձv�ɖڂ�ʂ��ƁA���[�O�i�[�u�g���X�^���ƃC�]���f�v�͈�_�����������B���t�̓E�B���w�����E�t���g���F���O���[�w���F�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�i�pEMI�j�B�����ɏ�����Ă��邠�炦�т��̕��͂��������Ă݂悤�B
�E�B�[���̃t�B���n�[���j�[���̓��̈Зe�������A���т̃t�B���n�[���j�[�������b�ɂ�����ō��̒n�ʂ��ւ��Ă���̂́A�i�`�X���{�̕ی�̂��������낤����ǂ��A�t���g���F���O���[�̓����Ƌz���͂̒v���Ƃ��낪�傫���B�S�[���h�x���N���P���l�̊W�Ńh�C�c�𒀂��邱�ƂɂȂ������A�E��q���Đ������H�҂Ƒ������̂̓t���g���F���O���[�ł���A�q���f�~�b�g�����O�ɕ�������邱�ƂɂȂ������A���ꂪ�������߂ɖz�������̂���͂�t���g���F���O���[�ł������B���̊y�c���ł��悭�������āA�ł��悭���̗͂�������̂̓t���g���F���O���[�ł���B�t���g���F���O���[���邱�Ƃɂ���Ĕ��уt�B���n�[���j�[�͍ő�̔\�͂����A�������ȉ��y����������B����͑��̂����Ȃ�D�G�Ȋy����i����e���̃I�[�P�X�g���Ƃ����ǂ��y�ʂƂ���ł���B�t���g���F���O���[�̎w�������nj��y�̃��R�[�h�͂قƂ�ǂ��Ƃ��Ƃ��ǂ��ƌ����Ă����B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E���[�O�i�[�́w�g���X�^���ƃC�]���f�x�́u�O�t�ȁv�Ɓu���̎��v�A���̕ӂ�������Ă����ׂ��ł��낤�B
 �@�ÐF���R�A�����ܒ~����M�@�ł���B�ǂ�Ȗ{���͖Y�ꂽ���A���w�Z�̐}���قœǂu�t���g���F���O���[�̓i�`�X�̋��͎҂�����A�����J�ł̉��t�͋����Ȃ��v�ƌ������g�X�J�j�[�j�̌��t�Ɋ�������āA�����C���͐e�g�X�J�j�[�j�^���t���g���F���O���[ �ɂȂ��Ă������̂��B�����Ƒ����ɂ��̕��͂�ǂ�ł����悩�����̂ɂƎv���B
�@�ÐF���R�A�����ܒ~����M�@�ł���B�ǂ�Ȗ{���͖Y�ꂽ���A���w�Z�̐}���قœǂu�t���g���F���O���[�̓i�`�X�̋��͎҂�����A�����J�ł̉��t�͋����Ȃ��v�ƌ������g�X�J�j�[�j�̌��t�Ɋ�������āA�����C���͐e�g�X�J�j�[�j�^���t���g���F���O���[ �ɂȂ��Ă������̂��B�����Ƒ����ɂ��̕��͂�ǂ�ł����悩�����̂ɂƎv���B�@�����̃S�[���h�x���N�Ƃ͓����x�������E�t�B���̃R���T�[�g�}�X�^�[�߂Ă����V�����E�S�[���h�x���N�i1909-1993�j�̂��Ƃł���B���_���l�ł��邪�䂦�Ƀi�`�X�������̃x�������E�t�B����ǂ��C�M���X�`�A�����J�ɖS���B�\���E���@�C�I���j�X�g�E�w���҂Ƃ��Ċ���B�ӔN�͓��{�ɋ����ڂ����t������W�J�A1988�N�ɂ̓s�A�j�X�g�R������q�ƌ�������Ȃlj䂪���Ƃ��Ȃ��݂��[���B�S�[���h�x���N�̘^���͌����đ����͂Ȃ����A���[�c�@���g�̃\�i�^�̓����[�E�N���E�X�ƃ��h�D�E���v�[�̃s�A�m�ɂ��V�����̑I�W������B�������L����20���Ȃ́A������������ɈقȂ�ȑ����������R�ɕ\�o����▭�̖��l�|�B�����Ĕނ̈���O�@���l���E�f���E�W�F�X �g�o�����E���B�b�^�h�̓o�����X�ǂ��������������ĐS�n�悢�B�����Ĉ�ȃx�X�g�E�p�t�H�[�}���X��I�ԂȂ�\���̑��l�������郋�v�[�Ƃ�K454���B
 �@����͂��Ă����A�����̃t���g���F���O���[�u�g���X�^���ƃC�]���f�v�́u�O�t�ȁv�Ɓu���̎��v�̉�����4�N�O�Ɏ�ɓ��ꂽ�B�u�t���g���F���O���[�^���[�O�i�[�nj��y�W��2�W�v�Ƃ�������CD�iWARNER CLASSICS�j�ł���B�f�[�^�������1938�N2��11���^���Ƃ���B���������Ă������͂���ŊԈႢ�Ȃ��Ǝv�����B�u���Ȍ���Ձv�̂��Ƃ����ɁA�����O�����u�i���̖{�́jSP���R�[�h�Ƃ������y�����̉��S�����Ղ�����Ă����v�Ə����Ă���̂�����𗠕t����B���������Ă݂�B�Â��^���������͈ӊO�ƃN���A�[�ł���B�n�ɂǂ�����ƍ������h�邬�Ȃ��y��̏�Ƀ��[�O�i�[�̏�O�����˂�₪�ď����B�t�����F���̃��[�O�i�[���E���m���ɔ����Ă����B����������Ă��� �Ǝv���Ɗ��S���ЂƂ����ł���B
�@����͂��Ă����A�����̃t���g���F���O���[�u�g���X�^���ƃC�]���f�v�́u�O�t�ȁv�Ɓu���̎��v�̉�����4�N�O�Ɏ�ɓ��ꂽ�B�u�t���g���F���O���[�^���[�O�i�[�nj��y�W��2�W�v�Ƃ�������CD�iWARNER CLASSICS�j�ł���B�f�[�^�������1938�N2��11���^���Ƃ���B���������Ă������͂���ŊԈႢ�Ȃ��Ǝv�����B�u���Ȍ���Ձv�̂��Ƃ����ɁA�����O�����u�i���̖{�́jSP���R�[�h�Ƃ������y�����̉��S�����Ղ�����Ă����v�Ə����Ă���̂�����𗠕t����B���������Ă݂�B�Â��^���������͈ӊO�ƃN���A�[�ł���B�n�ɂǂ�����ƍ������h�邬�Ȃ��y��̏�Ƀ��[�O�i�[�̏�O�����˂�₪�ď����B�t�����F���̃��[�O�i�[���E���m���ɔ����Ă����B����������Ă��� �Ǝv���Ɗ��S���ЂƂ����ł���B�i2�j���t�W����v�����Ɓ`�����V�c�͂Ȃ����̂悤�ȉ̂��r�̂��낤��
�@���̈�i��3�t�̎ʐ^��1���̃m�[�g�����ł���B�ʐ^�͖{�l�̏ё�2���ƕ���Ǝ�3�l�̉Ƒ��ʐ^��1���B�X�i�b�v�Ȃǂ͊F�����B1���̃m�[�g�͐����������u�����ړ��_�v�̕��̕M�ʂł���B�R�s�[��������̎Y���ł���BA5�T�C�Y�̃m�[�g150�łɂ�������Ə�����Ă���B�y���ŏ��������̂��낤�A���`�ׂ͍₩�Ŕ������B�{���ʂȐ��i���M����B�����Ƃ͈Ⴄ�Ȃ��Ǝv���B�����ɏ���400���قǂ̖ژ^���t���Ă���B�����ɂ́A�Î��L�A���t�W�Ȃǂ̌Ï��A���m���w�A���{���w�A�Y�ȁA���j�A�Ȋw�A��w�A�����A�@���A�v�z�ȂǑ���ɂ킽��W�������̏����̃^�C�g�����L����Ă���B�܂�ŁA�}���ق̕��ޒI������悤���B���g�ŏ������Ă������̂��낤���B����Ƃ���ēǂ��̂��낤���B���ƂȂ��Ă͕s���ł���B
�@���̖ژ^�ɂ́A�u���t�W�v�W�̏��ЂƂ��āA�u���t�W�Ë`�v�u���t�W���T�v�u���t�`���̍l�v�����v14��������ł���B�ꂪ�b���Ă����u���t�W�D���v�̂��ꂪ�؍����B
�@�����u�ߘa�v�̔��Ď҂͍����w�҂̕��w���m�E�����i���Ƃ����Ă���B�o�T���u���t�W�v�Ƃ������Ƃ��炻�̌��Ђł��鎁�ɐ��ʂ��y�̂��낤�B�V�c���疼���Ȃ����Ɏ��镝�L���r�ݐl�� �����E�Ƒ��̏�E���R�ւ̈،h�E����E�l���̈����E���ʂ̔߈��ȂǗl�X�ȏ���r���S4516��Ȃ�u���t�W�v�B�������m�́A���{�l�̊����̌��_�Ƃ������ׂ����̉̏W�̖ʔ������L�߂邽�߂ɑ����̃Z�~�i�[���J�Â��Ă���B�������u�ߘa�v�ɉ��܂�����N�t�A���r���𗁂т�����TV�h�L�������g�����Ă��Ĉ�ۂɎc��V�[�����������B����͈ȉ��̂悤�ȓ��e�������B
�݂Ȃ���A���t�W�͖ʔ����ł���B�����Ɏ����V�c���r�L���ȉ̂�����܂��B�@���̃G�s�\�[�h�������ɋ������͕̂�̂��A�ł���B��͕S�l���̖���ŁA���O�u���ꂭ�炢�͓ǂ�ł����Ȃ����v�ƌ����āu���q�S�l���v�̏����q��n���Ă���Ă����B���̒��Ɏ����V�c�̂��̉̂��i�����̌��ύX����Łj�ڂ��Ă��āA���ꂪ���̕Ћ��ɓ����Ă����̂ł���B
�@�t�߂��ā@�ė���炵�@�����́@�ߊ�������@�V�̍���R
����A�����ɖƂ����Ȃ�B
�@�t���߂��ĉĂ�����ė���炵���@�����z�̈߂������Ă���@���̓V�̍���R��
���ꂨ�������Ǝv���܂��B�����z�������Ă���Ƃ����̂͐Ⴊ�R���𔒂������Ă���Ƃ������ƂȂ�ł��B�Ȃ��Ȃ獁��R�͐_�l���h��_���ȎR�ł�����A�߂Ȃ������킯���Ȃ��B�ƂȂ�ƁA���x�͋G�߂�����Ȃ��B�Ċԋ߂Ȏ����ɐႪ����͂����Ȃ���ł��B����͂�V�c���r�̂�����Ȗ���������Ă���B��������t�W�̖ʔ����Ƃ���Ȃ�ł��ˁB
�@�E�[���A�ĂȂ̂ɐႩ�B�m���ɖ������B�V�c�̉̂�����Ȗ���������Ă�����̂��낤���B��ɂ���Ď��̐S�ɃN�����m�I�u�Ȃ����낤�v�����܂ꂽ�B�����Ă�����A�n�b�ƑM�����B�ȉ��͉𖾂̌o�܂ł���B
 �@7���I���A�p�\�̗��ɏ��������V���V�c�ƍc�@櫗ǂ͋��͂��ĐV�s�����������i�߂Ă����B�Ƃ��낪�u����686�N�V�c�͕���B���S�̒��A櫗ǂ͎v�Ă����B�u�V�c�����p���Ɏw���������q�E���Ǎc�q�͂܂��Ⴂ�B����ɁA�V�s�����͕v�Ǝ��̔ߊ�B�Ȃ�Ύ�����萋���˂Ȃ�Ȃ��B�����͎��������ʂ��ēs�������������̂����ǂɏ��ʂ���̂��ł͂Ȃ����v�ƁB�Ƃ��낪���̐ʐ^�͐Ƃ������ꋎ��B689�N5��7���A���Ǎc�q��28�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��Ă��܂����̂ł���B690�N�A�߂��݂ƌ��ӂ�����櫗ǂ͑��ʁB�����V�c�ƂȂ����B��������694�N�Ɋ����B��a�O�R�Ɉ͂܂ꂽ�V�s�͓��̓s�E�����ɂ����Ȃ����h�ȈЗe���ւ����B�����V�c�͂����ŐV���ȍ��Â����簐i����B697�N�A���ǂ̒��q15�̌y�c�q�ɏ��ʁA�����V�c�Ƃ��đ��ʂ����A����͑���V�c�Ƃ��āA���̌㌩���ƂȂ�B���̍s�����Ɉ��̖ړr������702�N�ɕ���B���N57�������B
�@7���I���A�p�\�̗��ɏ��������V���V�c�ƍc�@櫗ǂ͋��͂��ĐV�s�����������i�߂Ă����B�Ƃ��낪�u����686�N�V�c�͕���B���S�̒��A櫗ǂ͎v�Ă����B�u�V�c�����p���Ɏw���������q�E���Ǎc�q�͂܂��Ⴂ�B����ɁA�V�s�����͕v�Ǝ��̔ߊ�B�Ȃ�Ύ�����萋���˂Ȃ�Ȃ��B�����͎��������ʂ��ēs�������������̂����ǂɏ��ʂ���̂��ł͂Ȃ����v�ƁB�Ƃ��낪���̐ʐ^�͐Ƃ������ꋎ��B689�N5��7���A���Ǎc�q��28�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��Ă��܂����̂ł���B690�N�A�߂��݂ƌ��ӂ�����櫗ǂ͑��ʁB�����V�c�ƂȂ����B��������694�N�Ɋ����B��a�O�R�Ɉ͂܂ꂽ�V�s�͓��̓s�E�����ɂ����Ȃ����h�ȈЗe���ւ����B�����V�c�͂����ŐV���ȍ��Â����簐i����B697�N�A���ǂ̒��q15�̌y�c�q�ɏ��ʁA�����V�c�Ƃ��đ��ʂ����A����͑���V�c�Ƃ��āA���̌㌩���ƂȂ�B���̍s�����Ɉ��̖ړr������702�N�ɕ���B���N57�������B�@�����V�c�͏�L�������ꂩ�̎����Ɂu�t�߂��āv�̉̂��r���̂Ǝv����B�܂��͉̂̒��g��������B
�t�߂��ā@�ė���炵�@�����́@�ߊ�������@�V�̍���R������1���u�����̈ߊ�������v�Ƃ͂ǂ�������
�i������F�t���߂��ĉĂ�����ė���炵���@�����z�̈߂������Ă���@���̓V�̍���R�Ɂj
�@�V�̍���R�͓������̓���Ɉʒu����g�_���V�~��R�h�Ƃ����ɂ߂Đ_���ȎR�ł���B�����V�c�����X���������琒�ߒ��߂Ă������Ƃ��낤�B����Ȑ_���ȎR���ɔ����z�߂��������낤���B�����ɂ��肦�Ȃ��B�Ȃ�u�����̈ߊ�������v�́u�����̈߁v�Ƃ͔����߂ł͂Ȃ��u��v�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���݂ɂ���ɂ��ẮA�O�q�������m�Z�~�i�[�ɂ����錩���ȊO�́A�ǂ̌�������݂Ă��u��v�Ɖ��߂��Ă�����̂͂Ȃ��B
������2���u�t�߂��ĉė���炵�v�̎����͂ǂ��Ȃ̂�
�@����͕����ʂ�u�t����Ăɂ����āv�Ƃ������ƁB�������悤���Ȃ��B
�����،��ʁ�
�@����1�i�����̈߂Ƃ͐�j�ƌ���2�i�����͏t����Ăɂ����āj���� �A�u�V�̍���R�͏t����Ăɂ����Đ�ɕ����Ă����v�Ƃ������ƂɂȂ�B�o�H�O�R�Ȃ炢���m�炸�A�̒n�̕W��153m�̏��R���t����Ăɂ����Đ�ɕ����邱�Ƃ͐�ɂ��肦�Ȃ��B����͖��炩�Ȗ����ł���B�Ȃ���̖������ǂ��������H ���悢��j�S�ɔ���B
�������ŐV���߁�
�@�����V�c�͂��ǂ̂悤�ȐS���Łu�t�߂��āv�̉̂��r�̂��낤���B����𐄑�����B
 �@�����V�c�̐l���̒��ōł����O�ȏo�����B����͑��Ǎc�q�����������Ƃł͂Ȃ��������B�ނ����������ȍc�ʌp���҂ɂ��čň��̑��q�������B�ނ���������689�N5��7������Ԃ��Ȃ��t����Ăɂ����Ă̈�����A�����V�c�i�����͍c�@櫗ǁj�͑������̓������ɗ����Ă����B�����̂悤�ɓV�̍���R�������Ƃ����͖X�̗��܂Ԃ����f���Ă���B�����c�q�͂������Ȃ��B����R����ɕ����Ă����~�̂��� �ނ͂܂����C�ɐ����Ă����B�ł��邱�ƂȂ�u�����߂̂悤�Ȑ�ŕ���ꂽ���̂���ɖ߂��ė~�����v�E�E�E�E�E���������v���ʼnr�̂����̉̂������B
�@�����V�c�̐l���̒��ōł����O�ȏo�����B����͑��Ǎc�q�����������Ƃł͂Ȃ��������B�ނ����������ȍc�ʌp���҂ɂ��čň��̑��q�������B�ނ���������689�N5��7������Ԃ��Ȃ��t����Ăɂ����Ă̈�����A�����V�c�i�����͍c�@櫗ǁj�͑������̓������ɗ����Ă����B�����̂悤�ɓV�̍���R�������Ƃ����͖X�̗��܂Ԃ����f���Ă���B�����c�q�͂������Ȃ��B����R����ɕ����Ă����~�̂��� �ނ͂܂����C�ɐ����Ă����B�ł��邱�ƂȂ�u�����߂̂悤�Ȑ�ŕ���ꂽ���̂���ɖ߂��ė~�����v�E�E�E�E�E���������v���ʼnr�̂����̉̂������B
�t�߂��ā@�ė���炵�@�����́@�ߊ�������@�V�̍���R�@�������ڂ����̂́u�ߊ�������v�́u��������v�̕����ł���B���T�͖��t���Ȃŏ�����Ă���B���t���Ȃ͊����̓��Ď��B�\�������ŕ\�ӕ����ł͂Ȃ��B�Ȃ���u��������v�́u�~������v�ł��悭�͂Ȃ����B�����A�u�����v�Ɓu�~���v�̊|���B�������߂�����ׂĒ��낪�����̂ł���B
�t�߂��ā@�ė���炵�@�����́@�ߊ��������i�~������j�@�V�̍���R�@ �t����Ă̋G�߁A�����V�c�͐_�̎R�ɔ����߂̂悤�Ɍ������������̂ł���B�����Ȃ��͂��̂��̌���Ȃ�Ă��Ƃ�����̂��H���b������ɂ͈�̖��t�W�̉̂��ɏo���B
���������ߖ�
�t���߂��ĉĂ�����ė���炵���@�����z�߂��������悤��
�^�����ȐႪ���̓V�̍���R���Ă��ė~�������̂�
��a�ɂ͌Q�R����ǁ@�Ƃ���� �V�̍���R �o�藧�� ������������@���̉̂̍�҂͘����V�c�A�����V�c�̑c���ł���B����������̈������B�����V�c�͓V�̍���R�ɓo���č���������B��������n��ɗ�����鉌�Ƌ��ɊC��ɂ����߂���ї��̂�����̂ł���B�ޗǂɈʒu����V�̍���R����͌����Č�����͂��̂Ȃ��C��S�ɉf���Ă���B�Ȃ�A�����V�c�Ɍ����Ȃ��͂��̐Ⴊ�����Ă�����s�v�c�͂Ȃ��ł͂Ȃ����B�c���͐_�h��R�̏ォ��C���A�����͎R�̉��������A�e�X������͂��̂Ȃ����z��S�ɉf���B�Ȃ�Ƃ������}�����낤�B
�����͉��������@�C���͂��܂ߗ������@���܂������@�����Ó��@��a�̍���
�@�����V�c�̐S���ɂ́u��̂���G�߂ɖ߂��Ăق����v�Ƃ̊肢���h��B�����ȍc�ʌp���҂������������҂̖��O�ƍň��̉䂪�q��S��������̎����݂����݂��Ă���͂��ł���B�������u�ߊ�������v�ʼn��߂��~�܂�Ȃ�A����͏��Ă̒P�Ȃ��i�ł����Ȃ��B���̎����V�c������ȕ��ȉ̂��r�ނ͂����Ȃ��Ǝv���̂ł���B�����V�c�̕��͓V�q�A�c���͘����A�c��͍c�ɁA�v�͓V���A�Z�͍O���A���͌����A���͕����ƌ����A�\���͐����̊e�V�c�B����ȏ����͂ǂ��ɂ����Ȃ��B��O��㍂�MNo.1�̏����Ȃ̂��B
�@�u��������v�Ɓu�~������v���|���ƂȂ��Ă͂��߂āA�u�t�߂��āv�̉̂Ɏ����V�c�̐^��Ă�B
�@�u�t�߂��āv�̉̂����r�܂ꂽ���̂ł��邩�H ����ɂ��Ă͂܂����g����ł��Ă͂��Ȃ��B�����A���������̉̂����Ǎc�q�̎���ɓǂ܂ꂽ���̂������Ƃ����Ȃ�A���̉��߂��m�肳��Ă������̂ł́@�Ǝv���̂ł���B������ǂ��ł����B
���Q�l������
�u���Ȍ���� ���v���炦�т����i�������Ɂj
���[�O�i�[�F�nj��y�ȏW��2�WCD�iWARNER CLASSICS�j
�@�@�E�B���w�����E�t���g���F���O���[�w���F�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c
���[�c�@���g�F���@�C�I�����E�\�i�^�WCD�iDECCA�j
�@�@�V�����E�S�[���h�x���N�iVn�j ���h�D�E���v�[�iP�j
HNK-BS�u���j�فF�p�\�̗��v2013.2.14 O.A.
NHK-BS�u100���Ŗ����F���t�W�v2014.4.2�`23 O.A.
NHK-BS�u���j��b�q�X�g���A�F�����V�c�̓s�v2015.6.10 O.A.
2020.07.13 (��) 7���G��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�Ȃ����m���E�F�[�A�����ăG�����g������x�[�g�[���F���o�R�����F���܂�
 �@7��5���A�s�m���I���ɍs���Ă����B�O��͖������ƂȂ����r�S���q�ɓ��ꂽ���A����͖����ɖ������B���r�S���q�̃R���i�Ή����������邩�炾�B�u�����A���[�g�v�u���[�h�E�}�b�v�v�u�E�B�Y�E�R���i�v�u���j�^�����O�w�W�vetc������������ł����ƕ��ח��Ă�B���g�������Ή������ł����܂�Ȃ��̂����A���ꂪ�܂����������Ē��g���Ȃ��B��ѐ����Ȃ��B���t�����Ă�����ł��邾�����B�Ђ���̋g���{�m���B�u�o���헪�v�u������v�u�ėv����v�Ƃ��ׂē��{��A���̏�ǂ��Ȃ��������Ƃ�����𐔎��Ŏ����Ă���B�f�R�킩��₷���B�����̈��S����S�ۂ���̂������̑�Ȗ����Ȃ̂�����A�ǂ��炪�������͌����܂ł��Ȃ��B�u���̐l�������B���̐l�̌������ƂȂ畷���Ă�낤���ċC�ɂȂ邵�v�Ƃ������̂������̌��t������𗠕t����B
�@7��5���A�s�m���I���ɍs���Ă����B�O��͖������ƂȂ����r�S���q�ɓ��ꂽ���A����͖����ɖ������B���r�S���q�̃R���i�Ή����������邩�炾�B�u�����A���[�g�v�u���[�h�E�}�b�v�v�u�E�B�Y�E�R���i�v�u���j�^�����O�w�W�vetc������������ł����ƕ��ח��Ă�B���g�������Ή������ł����܂�Ȃ��̂����A���ꂪ�܂����������Ē��g���Ȃ��B��ѐ����Ȃ��B���t�����Ă�����ł��邾�����B�Ђ���̋g���{�m���B�u�o���헪�v�u������v�u�ėv����v�Ƃ��ׂē��{��A���̏�ǂ��Ȃ��������Ƃ�����𐔎��Ŏ����Ă���B�f�R�킩��₷���B�����̈��S����S�ۂ���̂������̑�Ȗ����Ȃ̂�����A�ǂ��炪�������͌����܂ł��Ȃ��B�u���̐l�������B���̐l�̌������ƂȂ畷���Ă�낤���ċC�ɂȂ邵�v�Ƃ������̂������̌��t������𗠕t����B�@�R���i��ő啝�ɒx����Ƃ��������͓s���̗��������Ƃ̍��ʉ���D�悵���B�������Ƃ萟�܂����������̗���ŁB���h�Ə��̈Ӓn���������Ă��Ȃ����r�S���q��NG�B�Ȃ�ΎR�{���Y�H���̐l���{�Ńo�[�j�[�E�T���_�[�X�B���O�͂킩�邪�����ւ̃v���Z�X���낤�߂���B�ېV�̏���ו�͋g���l�C�ɏ悶���O�@�I�ւ̊猩�����s���낤�B�F�s�{�����͌����݂��Ȃ��̂�3�x�ڂ̏o�n�B�s�m���I����Ƃ����v���Ȃ��B���ԉ��^�͖��O�B���Ƃ͖A�����B�����A�킪���q�Ɂu�ǂ�����H�v�Ɛu������u�g�R���i�Ȃ�Ă����̕��ׁh�ƌ������镽�ː��K�ɂł�����悤���v�Ƃ����̂Łu�t�U�P���i�I�v�ƈꊅ���Ă������B����͂�N�����Ȃ��B�����͂����u�㓡�V���v�Ə��������Ȃ���(��)�B
�@���ʂ́A�����J�[��u���ɏ��r�S���q�̍đI�Ƃ����������B�����N�ɓ��ꂽ�����āH����͔閧�ɂ��Ă����܂��傤�B
 �@���Đ���A�r�㏲���s�m���I���݂̔ԑg�̒��Łu�������Đ����Ƃ���Ȃ�ł���B�Ȃɂ��N�ԗ\�Z��15���~�B����̓m���E�F�[�̍��Ɨ\�Z�Ƃقړ����A�X�E�F�[�f�����傫����ł�����v�Ɖ�����Ă����B���́u����v���Ǝv���܂����B�m���E�F�[�̓X�E�F�[�f�����傫���̂����ĂˁB���������̍���������ׂĂ݂�B�܂��̓m���E�F�[�A�l����530���l�AGDP��40���~�B�Ђ�X�E�F�[�f���A1022���l��55���~�B�ف[��A����ς�X�E�F�[�f���̕��������͂ł����B�Ȃ̂ɍ��Ɨ\�Z�̓m���E�F�[����ȂB����͑傫�����{�A���������̖ʓ|�����������{�Ƃ������Ƃ��B�w�i�ɂ͌����E�V�R�K�X���G�l���M�[�����̍�������悤���B���E�K���x�����L���O��5�ʂƃX�E�F�[�f��7�ʂ̏�ɂ���̂����̏��B�����ƏZ�݂悢���Ȃ� �Ǝv���B���݂ɓ��{��62�ʁB�A�����J��18�ʂŃu���W����32�ʂŃt�B���s����52�ʁB��������m��Ȃ������{�A�Ⴗ���Ȃ����H�܂��u����Ȃ̊W�˃G�v�B
�@���Đ���A�r�㏲���s�m���I���݂̔ԑg�̒��Łu�������Đ����Ƃ���Ȃ�ł���B�Ȃɂ��N�ԗ\�Z��15���~�B����̓m���E�F�[�̍��Ɨ\�Z�Ƃقړ����A�X�E�F�[�f�����傫����ł�����v�Ɖ�����Ă����B���́u����v���Ǝv���܂����B�m���E�F�[�̓X�E�F�[�f�����傫���̂����ĂˁB���������̍���������ׂĂ݂�B�܂��̓m���E�F�[�A�l����530���l�AGDP��40���~�B�Ђ�X�E�F�[�f���A1022���l��55���~�B�ف[��A����ς�X�E�F�[�f���̕��������͂ł����B�Ȃ̂ɍ��Ɨ\�Z�̓m���E�F�[����ȂB����͑傫�����{�A���������̖ʓ|�����������{�Ƃ������Ƃ��B�w�i�ɂ͌����E�V�R�K�X���G�l���M�[�����̍�������悤���B���E�K���x�����L���O��5�ʂƃX�E�F�[�f��7�ʂ̏�ɂ���̂����̏��B�����ƏZ�݂悢���Ȃ� �Ǝv���B���݂ɓ��{��62�ʁB�A�����J��18�ʂŃu���W����32�ʂŃt�B���s����52�ʁB��������m��Ȃ������{�A�Ⴗ���Ȃ����H�܂��u����Ȃ̊W�˃G�v�B�@�Ƃ�����A���������m���E�F�[���o�Ă����̂�����A��������͑ދ����̂��ɗF�B�̗ւ�����Ă݂悤�B�m���E�F�[���O���[�O���G�����g�����x�[�g�[���F���������F���B�͂Ă��Ă��܂��Ȃ���܂����I�H
�i1�j�G�����g���̃y�[���E�M�����g�A�����ď@�����y
�@�m���E�F�[�̑�\�I��ȉƂƂ����G�h���@���g�E�n�[�Q���[�v�E�O���[�O�i1843-1907�j���낤�B��\��́u�y�[���E�M�����g�v�B�c���̕����C�v�Z���̋Y�Ȃ̕t�щ��y�ł���B�Ȃ�ƃf���[�N�E�G�����g�������������Ă��đf���炵���B�W���Y�^�N���̗Z���Ƃ����A�ǂ���̑�������ق��Ƃ��Ă�A�Ƃ��������̂������B�Ƃ��낪�G�����g���͕ʊi�B�N���V�b�N�͂����܂őf�ށB�����̉��y�Ƃ��Ċ��S�ɗ��Ƃ����ށB����͂���������Ȃ��G�����g���E�~���[�W�b�N���B
 �@�u���v�����Ɉ����B���̌��ȁA���̓����b�R������Ȃ̂����A�o�����̐����ȃt���[�g�̋�������A�����҂قƂ�ǂ��m���E�F�[�̃t�B�����h�ӂ�̕��i��A�z����B�ł́A�G�����g���ł͂ǂ����B�t���[�g�Ɏn�܂�僁�����I�n��уJ�[�l�C�̃o���g���T�b�N�X�ɒu��������B���Y����3���q�B�o�b�N�ɂ͑Ŋy�킪�������Y�������ށB�悭�����Ƃ������2���q�n�B���ꂪ�Ȃ�Ƃ��▭�Ȃ̂��B�f��u�����b�R�v�i1930�j�̊O�l�����̑�������������B�}���[�l�E�f�B�[�g���b�q���Q�[���[�E�N�[�p�[��ǂ��ė����ŃT�n�������Ɉ���ݏo�����X�g�V�[����������ł���B
�@�u���v�����Ɉ����B���̌��ȁA���̓����b�R������Ȃ̂����A�o�����̐����ȃt���[�g�̋�������A�����҂قƂ�ǂ��m���E�F�[�̃t�B�����h�ӂ�̕��i��A�z����B�ł́A�G�����g���ł͂ǂ����B�t���[�g�Ɏn�܂�僁�����I�n��уJ�[�l�C�̃o���g���T�b�N�X�ɒu��������B���Y����3���q�B�o�b�N�ɂ͑Ŋy�킪�������Y�������ށB�悭�����Ƃ������2���q�n�B���ꂪ�Ȃ�Ƃ��▭�Ȃ̂��B�f��u�����b�R�v�i1930�j�̊O�l�����̑�������������B�}���[�l�E�f�B�[�g���b�q���Q�[���[�E�N�[�p�[��ǂ��ė����ŃT�n�������Ɉ���ݏo�����X�g�V�[����������ł���B�@�]�k�����A�N�[�p�[���f�B�[�g���b�q�̍K�����肢�ʂ��������V�[��������B�ޏ������Ȃ��Ԃɋ��Ɍ��g�ŁuI changed my mind, Good luck !�v�Ə����ė�������̂����A����܂��Ƀ��[�~���u���[�W���̓`���v�B���[�~���̓f�B�[�g���b�q�̑�t�@�������炱�ꂪ�q���g�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��B
 �@�G�����g���ɂ́u�R���T�[�g�E�C���E�U�E�`���[�` CONCERT OF SACRED MUSIC�v�i1965�j�Ƃ����ِF�Ղ�����B�����ʂ�G�����g���̏@�����y�ł���B���C�u���̓v���X�r�e���A���i���V�h�j����B�J�����@���h�̋���ł���B�܂��G�����g���͎q�ǂ��̂����e�ɘA����ăp�v�e�X�g����ɒʂ��Ă����Ƃ����B����炩�琄������ƁA�G�����g���̏@�h�̓J�����@���h�p�v�e�X�g���p�e�B�L�����[�E�p�v�e�X�g�ƍl������B�ł��܂��A����͂ǂ��ł������B�G�����g���������I�L���X�g���k�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��̂�����B
�@�G�����g���ɂ́u�R���T�[�g�E�C���E�U�E�`���[�` CONCERT OF SACRED MUSIC�v�i1965�j�Ƃ����ِF�Ղ�����B�����ʂ�G�����g���̏@�����y�ł���B���C�u���̓v���X�r�e���A���i���V�h�j����B�J�����@���h�̋���ł���B�܂��G�����g���͎q�ǂ��̂����e�ɘA����ăp�v�e�X�g����ɒʂ��Ă����Ƃ����B����炩�琄������ƁA�G�����g���̏@�h�̓J�����@���h�p�v�e�X�g���p�e�B�L�����[�E�p�v�e�X�g�ƍl������B�ł��܂��A����͂ǂ��ł������B�G�����g���������I�L���X�g���k�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��̂�����B�@�@�����y�Ƃ����A��Ў���A�p���q�������ɂ���Ȃ��Ƃ����������Ƃ�����B�u���y�ɂ͏@�����y�ƃ_���X���y�����Ȃ��v���āB��w�œN�w���U���Ă����ނ炵���������Ǝv���ċL���Ɏc���Ă���B1981�N�āA�ƊE�̏d���𑽐������A�t�R�̃��X�g�����u���E�}�[���v�ł�����ґ�ȃf�r���[�E�C���F���g���s�������̂��B�ł��Z�[���X�ɂ͌��ѕt���Ȃ��B�n���Ƀ��C�u���d�˂Ă䂫�����Ƃ����ނ́A���N1���A�ڍ��̃��C�u�E�n�E�X����ăX�^�[�g������B�삯�t������X�͖ڂ��^���B�Ȃ�Ƌq��10�l�����Ȃ��I �ł��������畐���قt�ɂ���܂łɂ̂��オ���Ă����̂�����p���͑債�����̂��B���_����͔ނ̎��͂ƕ�����C�̂Ȃ���Ƃ����A����ŁA����̉��y�u���Ƃ͈قȂ�Ȃ������Ɉ���𒍂��T�|�[�g�����������̕����E�g���m�̌��т��������Ȃ��B���݂ɔނ͖����g�����O�Y�ē̎O�j�ŁA���E�}�[���̎Ў�Ƃ͗c����ł���B
�@�b��{��ɖ߂����B�G�����g���uCONCERT OF SACRED MUSIC�v�́u�_�r�f �_�̌�O�ɂđS�͂����ėx���v�Ƃ����ȂŒ��߂�����B�]���̂ƃ^�b�v�_���X�ō\������邱�̋Ȃ́A�܂��ɏ@���ƃ_���X�̈�̉��ł���B�uCOME SUNDAY�v�Ɠ�����̃R���[��������1�R�[���X24���߂̌J��ւ����B�h�i�ȋ����ł���B������Ă��ĂӂƂ���y�Ȃ�������ł����B�x�[�g�[���F���́u���v�I�y�́u����̉́v�ł���B
�@�u���v�́u����̉́v�́u����̂����������݂��߂��Ƃ����͌Z�퐢�E�͈�v�i�Ȃ��ɂ����j�Ɖ̂��B�G�����g���u�_�r�f �_�̌�O�ɂđS�͂����ėx���v�́u�_�̌�O�őS�͂ŗx��_�r�f�͊��т��F�ɓ͂���v�Ɖ̂��B�u���v��Freude�Ɓu�_�r�f�v��Joy�͓����u���сv�ł���B4���q�C���E�e���|�̗I�R���郁���f�B�[��1�R�[���X24���߂Ƃ����ڂ����ʂ���B�G�����g���͂�������Ƃ��u���v�ɕ`���Ă����\��������B
�i2�j�x�[�g�[���F�����烉���F����
 �@���N�̓x�[�g�[���F�����a250�N�̃������A���E�C���[�B�{���Ȃ�N���͂��ɂ������āu���v���b�V���ɂȂ�͂��B�Ȃ̂ɋ��炭�R���i�����������B�Ȃ�Ƃ���鐣�������Ԃł���B
�@���N�̓x�[�g�[���F�����a250�N�̃������A���E�C���[�B�{���Ȃ�N���͂��ɂ������āu���v���b�V���ɂȂ�͂��B�Ȃ̂ɋ��炭�R���i�����������B�Ȃ�Ƃ���鐣�������Ԃł���B�@���āu���v�ł���B�m���ɉ��y�j��ő勉�ɉ���I�Ȍ����Ȃł���B���̍ł�����̂͐��y�����߂Ď����ꂽ���ƂȂ̂����A���قȂ��Ƃ͂��������B�x�[�g�[���F���͏I�y�́i��4�y�́j�Ɂg�َ��ȁh���y�����邽�߂���H�v���{�����B����́u����̉́v�̎����o�����߂ɁA1�`3�y�͂��`��������肷�ׂĂ�ł������̂ł���B��o���āu����͈Ⴄ�v�A������o���āu���ꂶ��Ȃ��v�A�����čŌ�Ɂu������_���v�Ƃ�����ɁB�䂪�t�E�Έ�G�搶�́u�x�[�g�[���F���͉����l���Ă�B�������ƕ������Ă����āA����܂ł̂͗v��Ȃ��Ȃ�Ă��q����Ɏ��炾��ˁv�ƌ����B�m���ɐ搶�̂�������邱�Ƃ��킩��B�ł����������Ƒ҂��炱���̊����Ƃ����̂�����̂ł� �Ƃ��v���B
�@�������ڂ���̂́A�ł�������Ɂu����̉́v�̎�肪���҂������܂����Ƃ���ɃI�[�P�X�g���Œ���镔���A��4�y�͂̑�93���߁`��188���߂ł���B�ŏ���1�R�[���X�i24���߁j�̓`�F�������ŁA2�R�[���X�ڂɃ��B�I���ƃt�@�S�b�g�������A3�R�[���X�ڂɃ��@�C�I�����������A4�R�[���X�ڂŊNJy�����������S�t�ƂȂ�B���̊ԁA���������f�B�[�������e���|�œ]�����ϑt���Ȃ��J��Ԃ����B�R�[���X���ƂɊy�킪����邩�玩�R�ɃN���b�V�F���h��������B�����đS�t�̃t�H���e�B�V���Œ��߂�����B4�R�[���X96���߁B����Ȏ��͉̒��y�j��ɂȂ��B����A���̌`�A�����Ɏ��ĂȂ����H�E�E�E�E�E�����������F���́u�{�����v���I
�@�u�{�����v��16���߂�1�R�[���X�̎��A�Ǝ��B���]�����ϑt�����ꂸ�ɏI�n�������Y�������e���|�ŌJ��Ԃ����B�ω�����̂͊y��̑g�ݍ��킹�Ɖ��̃_�C�i�~�N�X�̂݁B�t���[�g�̍Ŏ㉹�Ɏn�܂�N�����l�b�g�`�t�@�S�b�g�`���N�����l�b�g�`�I�[�{�G�E�_���[���`�~���[�g�t�����g�����y�b�g�`�e�i�[�T�b�N�X�`�\�v���m�T�b�N�X�`�z�����`�I�[�{�G�`�g�����{�[���ȂǂɎp����N���b�V�F���h����čŌ�ɂ̓I�[�P�X�g���S�t�̃t�H���e�B�V���ŏI���B���̑��ɂ��n�[�v�A�s�b�R���A�C���O���V���z�����A�`�F���X�^���A����͂����F�ʂ̑�^���ł���B����A�\����������[AABB]�~4�{AB�R�[�_ �Ǝ��ɃV���v���B�����͂܂������O�q�u���v�Ɠ��`�����B
 �@�����F���i1875-1937�j�́A�X�y�C�����̕��Ȃ����]������h�̕����ƃC�_�E���r���V�e�C������A�A���x�j�X�̃s�A�m�ȁu�C�x���A�v�̊nj��y�ҋȂ̈˗�����B�Ƃ��낪���̕ҋȂ͊��ɃA���{�X���s���Ă������Ƃ������B�����ŐV���ɃI���W�i������Ȃ��邱�ƂɂȂ�B�̒��������ꂸ�A�C�f�B�A�������Ȃ������F���ɃA�����J�s���������Ă����B�ނ͍�Ȃ𒆒f�����܂܁A1928�N1���`4���A�A�����J���t���s�����s����B�j���[���[�N�A�{�X�g���A�V�J�S�A�N���[�������h�A�T���t�����V�X�R�A���T���W�F���X�A�f�g���C�g�Ȃǂ�K�₵�������F���͊e�n�ő劅�т���B�̒����������D�]�B���t���s�͑听�����ɏI������B
�@�����F���i1875-1937�j�́A�X�y�C�����̕��Ȃ����]������h�̕����ƃC�_�E���r���V�e�C������A�A���x�j�X�̃s�A�m�ȁu�C�x���A�v�̊nj��y�ҋȂ̈˗�����B�Ƃ��낪���̕ҋȂ͊��ɃA���{�X���s���Ă������Ƃ������B�����ŐV���ɃI���W�i������Ȃ��邱�ƂɂȂ�B�̒��������ꂸ�A�C�f�B�A�������Ȃ������F���ɃA�����J�s���������Ă����B�ނ͍�Ȃ𒆒f�����܂܁A1928�N1���`4���A�A�����J���t���s�����s����B�j���[���[�N�A�{�X�g���A�V�J�S�A�N���[�������h�A�T���t�����V�X�R�A���T���W�F���X�A�f�g���C�g�Ȃǂ�K�₵�������F���͊e�n�ő劅�т���B�̒����������D�]�B���t���s�͑听�����ɏI������B�@�����F���͋A���㒼���ɁA���r���V�e�C�����j�̈˗��Ɏ��|����B���̉Ă̂�����A�ނ̓T�����W�������h�������Y�̉ƂŃs�A�m��e���Ȃ���F�l�ɂ���������Ƃ����B�u���̎��ɂ͉������玷�X�Ȃ��̂�����Ƃ͎v��Ȃ������B�l�͂�����S�R�W�J�������ɁA�I�[�P�X�g�����������傫�����Ă䂭�����ŁA�Ȃ�ǂ��J�肩�����Ă݂悤�Ǝv���v�B���ꂼ�u�{�����v�̌`�B�u���v�Ɠ����`���ł���B
�@���̌�I�[�P�X�g���[�V�������{���ꊮ�����݂��u�{�����v�́A1928�N11��22���A�p���E�I�y�����ŁA�C�_�E���r���V�e�C���̃o���G�c�ɂ���ď������ꂽ�B�a�V�ȋȑz�ŏՌ���^�����u�{�����v�́A�o���G���y�̘g���A�I�[�P�X�g���E�s�[�X�Ƃ��Ă������F������̃q�b�g��ƂȂ����B
�@���{�̕]�_�Ə����́u�{�����v�Ƃ����y�Ȃ��ǂ��]�����Ă���̂��B���L����CD�����\�I�ȃ��C�i�[�m�[�c���E���Ă݂�B
340���߂ɂ킽���Ĉ�т��č��܂��{�����̃��Y���ɂ̂��āA�X�y�C������2�̎�肪�p��ς����ɂ���Ԃ����Ƃ����S���Ƒn�I�Ȍ`�����Ƃ��Ă���B�i�~�����V���ՁA���{���j�@�u�S���Ƒn�I�v�u���j�[�N�Ȕ��z�v�u��_����v�u���y�j�� �H�v�ȂǁA�����ċȂ̎a�V�����������Ă���B���̃��C�i�[�m�[�c���T�˂���Ȋ����ł͂��邪�A�u���v�Ƃ̊֘A���Ɍ��y�����L�q�ɂ͂��ڂɂ����������Ƃ��Ȃ��B�u�{�����v���u���y�j��H�Ȏa�V���v�Ɖ]����R���́A�nj��y�̖��p�t�ƌĂ�郉���F���̃I�[�P�X�g���[�V�����̌����������邾�낤���A���Ȃ�̕����͂��̌`���ɋN�����Ă���Ǝv���B
����قǂ܂łɃ��j�[�N�Ȕ��z�Ɋ�Â����y�́A���y�j��ł��H�Ƃ����Ă悢���낤�B �i�u�[���[�Y�ՁA�ēc����j
�Ȃ̏��߂���I���܂ŁA�������ЂƂ̃N���b�V�F���h�łł��Ă���B���ɑ�_����ȍ�ȋZ�@�ł���B�i�A�o�h�ՁA�u���h���Y�j
�@�A�����J���t���s���͂���Ŋ����������u�{�����v�B�����ɐ��ށu���v�Ƃ̊֘A�����ӂ݂�ƁA��������F���̓A�����J���s���ɁA�u���v���u�{�����v�̔��z�̉��炩�̃q���g���̂ł͂Ȃ����B����ȋC�����Ă���̂ł���B��ȉƂ͌����ă^�l�������͂��Ȃ����́B�����炱�̂��Ƃ��ؖ��������͉i�v�ɂ��Ȃ����낤�B�ł����͐M�������B�����F���̌���u�{�����v�A���͂��̃t�H�����́u���v���甭�z�������̂��@�Ƃ������Ƃ��B
���Q�l������
�f���[�N�E�G�����g���u�y�[���E�M�����g�vCD�i1960�^���j
�f���[�N�E�G�����g���uCONCERT OF SACRED MUSIC�vCD�i1965�j
�f��u�����b�R�vDVD�i1930�j
�����F����ȁF�u�{�����v�y���i���y�V�F�Ёj
�����F����ȁF�u�{�����vCD
�@�~�����V���w���F�{�X�g�������y�c�i1956�j
�@�u�[���[�Y�w���F�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�i1993�j
�@�A�o�h�w���F�����h�������y�c�i1985�j
�x�[�g�[���F����ȁF������ ��9�� �j�Z�� ��i125 �y���iDOVER PUBLICATION,INC.�j
�x�[�g�[���F����ȁF������ ��9�� �j�Z�� ��i125 CD
�@�N�����y���[�w���F�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�������c�i1957�j
�@��r��w���F�����V�e�B�E�t�B���n�[���j�b�N�nj��y�c�i1990 �Ȃ��ɂ����j
2020.06.26 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X10
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`PORTRAIT OF SIDNEY BECHET�ɂ�����G�����g���̑I��
�@����̃e�[�}�́A�u�G�����g���͂Ȃ��wPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�x�̃\�������b�Z���E�v���R�[�vss�ł͂Ȃ��|�[���E�S���U�����F�Xts�ɑ��������v�ł���B �@�G�����g���́A�j���[�I�����Y�o�g�̈̑�ȃ~���[�W�V�����A�V�h�j�[�E�x�V�F�ւ̃I�}�[�W���Ƃ��āuNEWORLEANS SUITE�v�̒��ɁuPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v���������B�x�V�F�̓W���Y�̐��E�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�����������҂ɂ��Ė���ł���B����䂦���R�[�f�B���O�ł́A�x�V�F�̒�q�W���j�[�E�z�b�W�X��30�N�Ԃ�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�𐁂�������肾�����B�Ƃ��낪�E�E�E�E�E���̂�����̏��u�G�����g�����`�v����ēx���p�����Ă��������B
�@�G�����g���́A�j���[�I�����Y�o�g�̈̑�ȃ~���[�W�V�����A�V�h�j�[�E�x�V�F�ւ̃I�}�[�W���Ƃ��āuNEWORLEANS SUITE�v�̒��ɁuPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v���������B�x�V�F�̓W���Y�̐��E�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�����������҂ɂ��Ė���ł���B����䂦���R�[�f�B���O�ł́A�x�V�F�̒�q�W���j�[�E�z�b�W�X��30�N�Ԃ�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�𐁂�������肾�����B�Ƃ��낪�E�E�E�E�E���̂�����̏��u�G�����g�����`�v����ēx���p�����Ă��������B
1970�N5��11���A�킽���͔ނɂ�����x�\�v���m�T�L�\�t�H������ɂ����A�uNEWORLEANS SUITE�v�́uPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v�����t������ɂ͂ǂ��������̂��Ǝv�������点�Ă����B����Ɠd�b����A�ނ��|��t���̎���҂̐f�f���Ŏ����Ƃ�m�炳�ꂽ�̂��B

�E�E�E�E�E�ނقǐ��������Ƃ����V���[�}�����̑�ȃX�e�[�W�̌������Ȃ������B�������łȂ��ނ̏o�����͔��ɔ������A�悭�����҂ɗ܂��������̂��B�ނƂ����̑�ȑ��݂������A���̃o���h�́A�����A��x�Ɠ����悤�ȉ����o���Ȃ����낤�B�킽���́A�邲�Ɩ邲��40�N�Ԃ��̂������A�W���j�[�E�z�b�W�X���o����������������������Ƃ����ꂵ���v���ƂƂ��ɁA���ӂ��Ă���B���Ԃ�A�킽���͂����܂�����ꂽ�Ǝv�����A���͐_�Ɋ��ӂ��E�E�E�E�E�B�_��A�Ǝ������т����A���̂��炵�����l�ɏj�����B�_��A�W���j�[�E�z�b�W�X�ɏj�����B�@�G�����g���͂������āA���������̂Ȃ������o�[���������B�������̓�����5��13���ɂ́uNEWORLEANS SUITE�v�̎c��̃��R�[�f�B���O���T���Ă���B�����Ŕނ́uPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v�ŃW���j�[�E�z�b�W�X��30�N�Ԃ�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�𐁂�������肾�����B�����ɔނ̓ˑR�̎��B�V���b�N�łȂ��͂����Ȃ��B�����A�����ɐZ���Ă���͂����Ȃ��B�\����N�ɑ��������̂��B�G�����g���ɋi�ق̑I���������Ă����B
�@�I�����͓�B�i1�j���b�Z���E�v���R�[�v�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�𐁂�����B�i2�j�|�[���E�S���U�����F�X�̃e�i�[�T�b�N�X�ɑ�ւ�����B�G�����g���̋��̓��ɕ��������Ă݂悤�B
�i1�j���b�Z���E�v���R�[�v�̏ꍇ
 �@���b�Z���E�v���R�[�v��1946�N�ɃG�����g���y�c�ɉ����A�ȗ��G�����g�����S���Ȃ�܂ł�28�N�ԁA�Ƃ���邱�ƂȂ��ݒc�����B���̂悤�ȗ�̓n���[�E�J�[�l�C��u���đ��ɂ͂��Ȃ��B���݂ɃJ�[�l�C�́A1926�N�ɉ����A�ȗ�48�N�ԏ�ɃG�����g�j�A���ł��葱�����B�����āA�G�����g�����S���Ȃ���5�������1974�N10���A�t�̂��Ƃ�ǂ��悤�ɗ������čs�����̂ł���B
�@���b�Z���E�v���R�[�v��1946�N�ɃG�����g���y�c�ɉ����A�ȗ��G�����g�����S���Ȃ�܂ł�28�N�ԁA�Ƃ���邱�ƂȂ��ݒc�����B���̂悤�ȗ�̓n���[�E�J�[�l�C��u���đ��ɂ͂��Ȃ��B���݂ɃJ�[�l�C�́A1926�N�ɉ����A�ȗ�48�N�ԏ�ɃG�����g�j�A���ł��葱�����B�����āA�G�����g�����S���Ȃ���5�������1974�N10���A�t�̂��Ƃ�ǂ��悤�ɗ������čs�����̂ł���B�@�J�[�l�C�͍ݒc����т��ăo���g���T�b�N�X����Ɋy�c�̉��䍜���x���������B���A����v���R�[�v�̏ꍇ�́A�T��ɂ͓����A���g�T�b�N�X�ias�j�̓V�˃W���j�[�E�z�b�W�X�������Bas�ɂ����Ă͓�Ԏ�ɊÂ���Ȃ������̂ł���B�Ƃ��낪�z�b�W�X�́A1951�N3������1955�N8���܂ł�4�N�]�A�y�c�𗣂�Ă��܂��i���R�͂��̍ےu���Ă������j�B�������A�y�c�̃G�[�Xas�̍����ˎ~�߂�`�����X�ł͂Ȃ��������B�Ƃ��낪�A�G�����g���͂��̔C���A�E�B���[�E�X�~�X�A�q���g���E�W�F�t�@�[�\���A���b�N�E�w���_�[�\����X�^�[�v���C���[�̈��������ɂ���ăJ�o�[�����̂ł���B���̏�G�[�X�̐Ȃ��z�b�W�X�̂��߂ɋĂ������Ƃ������Ă���B���̂�����̃v���R�[�v�̏₢���ɁB�����̃A���o������A�S���U�����F�X�Ƃ̔�r�������A�T���Ă݂悤�B
�uMASTERPIECES BY ELLINGTON�v�iColumbia�j1950�N12��19���^��
LP����̓������āA�G�����g�������Ԃɔ���ꂸ�v�������A�����W��4�Ȃ�^����������I�ȃA���o���ł���B�uMOOD INDIGO�v�ł�3������Ɋy�c������W���j�[�E�z�b�W�X���}���̗�����������as�����A������Ԃ��Ȃ��S���U�����F�X�̓I�u���K�[�g���̒Z���\�����Ƃ�B���A�v���R�[�v�ɂ�as�̃\���炵���\���͌�������Ȃ��B
�uELLINGTON UPTOWN�v�iColumbia�j1951�N12���`1952�N7���^��
�z�b�W�X�s�݁B�����ɂ́A�u�N�����m�v�G�����g���E�e�[�}�̔��[�ƂȂ����uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\��������B����͐���搶�̉������ăv���R�[�v�Ɣ��������B�u�G�����g�����`�v�ɂ́u�v���R�[�v�̓A���o�[�g�E�V�X�e���E�N�����l�b�g�̃j���[�I�����Y�E�X�^�C���̖���ł���v�Ƃ̌�������B����́A����搶�����́u�f�B�L�V�[�n�̌Â��X�^�C���̉��t�ɂ̓v���R�[�v�̕��������Ă���ƃG�����g���͍l�����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����v����B��l�̋M�d�ȏ،��Ƃ�����B�����A�v���R�[�v��1973�N�u�C�[�X�g�o�[���E�R���T�[�g�v�́u�^�C�K�[�E���O�v�ŁA�j���[�I�����Y�E�X�^�C���̌����ȃN�����l�b�g�E�v���C���I���Ă���B
�uDUKE ELLINGTON LET�fS DANCE SERIES�v�iCapitol�j1953�`1954�N�^��
�z�b�W�X�s�݁B�v���R�[�v��as�́u���ƒ��̌��z�v�Ńe�[�}�����B���̑��ł́A�u�̂͗ǂ������ˁv��S���U�����F�X�̃e�i�[�T�b�N�X�its�j�Ƌ��ɑO�q�I�ȑt�@�ŕ�������u�n�b�s�[�E�S�[�E���b�L�[�E���[�J���v���C���p�N�g�傾�B�u������͈��̂݁v�̃N�����l�b�g���Ȃ��Ȃ��������A�T�b�N�X�E�\���Ƃ��ẮA�uC�W�����E�u���[�X�v�A�u�J�N�e���Y�E�t�H�[�E�g�D�v�A�u�}�C�E�I�[���h�E�t���[���v���ɂ�����S���U�����F�X�̗͋��������ts�̕��Ɉ���̒���������B
�uELLINGTON 55�v�iCapitol�j1953�N�`1955�N�^��
�z�b�W�X�s�݁B�v���R�[�v�́A�uLET�fS DANCE SERIES�v�Ɠ��X���̃A�����W�Łu���ƒ��̌��z�v�����t�B���̑��ł́A����t�@�ł��u�C���E�U�E���[�h�v�����j�[�N�B����S���U�����F�X�́A�u�{�f�B�E�A���h�E�\�E���v�ŁA�E�F�u�X�^�[�ɂ��z�[�L���X�ɂ��Ȃ����j�[�N�ȃ\��������B
�uDUKE ELLINGTON PRESENTS�E�E�E�v�iBethlehem�j1956�N�^��
�v���R�[�vas�́u�C���f�B�A���E�T�}�[�v�͒[���ȃg�[���̒��ɘ����ȋ��D���Y���G���B�ނ̃x�X�g�E�p�t�H�[�}���X���B�ꏏ�Ɏ��^����Ă���z�b�W�X�́u�f�C�E�h���[���v�����ȃx�X�g�Ƃ���������w�̖����t�B��l�̉��F�̈Ⴂ���y���߂�B�Ђ�S���U�����F�X�́u���[���v�Ɓu�R�b�g���E�e�C���v�Ŋɋ}�̑Δ�����Č����ł���B
�@��L�A���o���Q��ʂ��Č����邱�Ƃ́A�v���R�[�v�́A�z�b�W�X�̍ݕs�݂ɍS��炸�A����قǖڗ������T�b�N�X�E�\���͂Ƃ��Ă��Ȃ� �Ƃ������Ƃ��B�z�b�W�X�����z�Ȃ�v���R�[�v�͌��B�v���R�[�v�͂�͂�A�g�̑�ȃo�C�v���C���[�h�������̂��B
�@�G�����g���́u���`�v�̒��ŁA�v���R�[�v�̂��Ƃ������]���Ă���E�E�E�E�E�u���̐_�����������b�Z���E�v���R�[�v�͐��X�̃o���h��n������A1946�N�A�킽�������̃o���h�ɎQ���A�ȗ��������ƈꏏ�ɉ��t���Ă���B���̌o����ʂ��āA�ނ͐����Őa�m�I�ȕ��e�́A�Ќ��ƗD�낳���������l�Ԃɐ��������̂��B���̏�A�����M������鐽���ŃI�[�����E���h�̃~���[�W�V�����ɂȂ����̂ł���v�B
�@�Ђ�A�v���R�[�v�̓G�����g���̂��Ƃ��ǂ��v���Ă����̂��낤���B�s�̃r�f�I�u�s�ł̃f���[�N�E�G�����g���v�ɔނ̃C���^�r���[���₳��Ă���B��������́A�s���o�̃��[�_�[ �f���[�N�E�G�����g���Ƌ��ɒ������y����ꂽ��l�̉��y�Ƃ̍K�������Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���E�E�E�E�E�u�f���[�N�͂܂��ɋ����B�W���Y�̍ō��B�ނƉ��y�����Ɛ��E���P�������̂��B����ȃf���[�N��28�N���ꏏ�ɂ�ꂽ�B����͓����ȊO�̂Ȃ����̂ł��Ȃ��B�����āA���̍��������������݂�ȃf���[�N�Ƃ�肽�����Ă�������v�B
�i2�j�|�[���E�S���U�����F�X�̏ꍇ
 �@�|�[���E�S���U�����F�X�́A�e�i�[�T�b�N�X�̎�C�x���E�E�F�u�X�^�[�̌㊘�Ƃ��āA1950�N�A�G�����g���y�c�ɉ��������B�u�G�����g�����`�v�ɂ́A�u�|�[���͉����������E�F�u�X�^�[�̏o���������ׂĔc�����Ă����v�Ƃ���B�Ў����W���b�N�E�_�j�G���Y�𗣂����Ƃ��Ȃ������ۂ���̃i�C�X�K�C�͌����M�S�ȓw�͉Ƃł��������̂��B�u�ق����������@�C�I����Strolling violin�v�Ƌw�����ĉ��������G�����g�����A���͐^�ʖڂȃS���U�����F�X�̖{�����������Ă����ɈႢ�Ȃ��B����䂦���A�S���U�����F�X�͉������ォ��\���E�v���C���[�Ƃ��Ă̓��p��(���Ƀ��C�u�ɂ�����)�����Ă䂭�B�ȉ����C�u�E�p�t�H�[�}���X�̌o�܂�H���Ă݂悤�B
�@�|�[���E�S���U�����F�X�́A�e�i�[�T�b�N�X�̎�C�x���E�E�F�u�X�^�[�̌㊘�Ƃ��āA1950�N�A�G�����g���y�c�ɉ��������B�u�G�����g�����`�v�ɂ́A�u�|�[���͉����������E�F�u�X�^�[�̏o���������ׂĔc�����Ă����v�Ƃ���B�Ў����W���b�N�E�_�j�G���Y�𗣂����Ƃ��Ȃ������ۂ���̃i�C�X�K�C�͌����M�S�ȓw�͉Ƃł��������̂��B�u�ق����������@�C�I����Strolling violin�v�Ƌw�����ĉ��������G�����g�����A���͐^�ʖڂȃS���U�����F�X�̖{�����������Ă����ɈႢ�Ȃ��B����䂦���A�S���U�����F�X�͉������ォ��\���E�v���C���[�Ƃ��Ă̓��p��(���Ƀ��C�u�ɂ�����)�����Ă䂭�B�ȉ����C�u�E�p�t�H�[�}���X�̌o�܂�H���Ă݂悤�B�@1951�N1��21�����g���|���^���E�I�y���n�E�X�E�R���T�[�g�ł͑������A�uA��Ԃōs�����v�Œ��ڂ̓��X����\�����I���Ă���B1952�N3���ɂ́u�`�F���V�[�E�u���b�W�v�A4��30���}�P���C�Y�E�{�[�����[���ł́u�E�H�[���E�o���C�v�A11��14���J�[�l�M�[�z�[���E�R���T�[�g�ł́u�o�[�h�����h�̎q��́v�A1954�N4��13���G���o�V�[�E�I�[�f�B�g���E���ł͍ēx�uA��Ԃōs�����v�ŁA���X���݊�����\����W�J�B���ڂ��ׂ��́A1953�N3��30���p�T�f�B�i�E�I�[�f�B�g���E���ɂ�����u�f�B�~�k�G���h�E�A���h�E�N���b�V�F���h�E�C���E�u���[�v�̉����ŁA�����ɂ͗���ׂ���u���C�N�̌��`������B�����̌o�܂�����ƁA�|�[���E�S���U�����F�X�́A���c3�`4�N�ɂ��Ċ��Ƀo���h�̒��S�I���݂ɂȂ���������Ƃ��킩��B�����āA���̓`���́u�j���[�|�[�g27�R�[���X�v�Ɍq����̂ł���B
�@1956�N7��8���[��̃j���[�|�[�g�E�W���Y�E�t�F�X�e�B�o���B�g���߂�f���[�N�E�G�����g���E�I�[�P�X�g���̉��t���X�^�[�g����B���t�ς���ĉ��ڂ́u�f�B�~�k�G���h�E�A���h�E�N���b�V�F���h�E�C���E�u���[�v�ɁB�G�����g�����y���ȃs�A�m�Ő擱�B�u���X�ƃ��[�h�̑S�t�`�|���������o�čēx�s�A�m�E�\���ɖ߂����G�����g���͐���悤�Ȋ|��������B�������悤�ɃS���U�����F�X���D�u�ƃe�i�[�T�b�N�X�E�\�����X�^�[�g������B���t�͏��X�Ƀq�[�g�A�b�v�������o�[�̎蔏�q���傫���Ȃ�B�͋�����L���ȃS���U�����F�X�̃v���C�Ɋϋq�͂���߂��g������ь����B�x�肾�����̂܂Ō���ď���͑��R�B�\�����n�܂���6���]��A���͋����̚��ĂƉ����A������27�R�[���X����������B
�@���̓��A15��90���ɋy�ԃG�����g���E�I�[�P�X�g���̃X�e�[�W�̒��ŁA�O�N���A�����z�b�W�X�̃v���C�����҂Ɉ�킸������̂����������A�u�f�B�~�k�G���h�E�A���h�E�N���b�V�F���h�E�C���E�u���[�v�Ō������S���U�����F�X�̃p�t�H�[�}���X�������u�j���[�|�[�g56�v�̓`���ƂȂ����B����͓����ɁA�G�����g���y�c���҂��]�x���E�E�F�u�X�^�[�̌�p�҂ɂ��Ď���W���j�[�E�z�b�W�X�ɔ䌨������T�b�N�X�̃X�^�[���a�������u�Ԃ������̂ł���B
�@�|�[���E�S���U�����F�X���X�^�[�̍��ɉ����グ���u�f�B�~�k�G���h�E�A���h�E�N���b�V�F���h�E�C���E�u���[�v�́A�j���[�|�[�g56�ȍ~�A���C�u�̃N���C�}�b�N�X������Ăѕ��ƂȂ����B�S���U�����F�X�̃T�b�N�X�E�v���C�͎ڂ����Z���Ȃ���i���͂͂���ɑ����Ă䂭�B���ł��uAll Star Road Band, Carrolltown 1957�j�́A���̖����������g���ɂ����āA�j���[�|�[�g�𗽂������̃p�t�H�[�}���X�ƂȂ��Ă���B
�i3�j�f���[�N�E�G�����g���̑I���`�uPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v�̃\����N�ɑ����̂�
�@�܂��̓��b�Z���E�v���R�[�v���B�uPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v�̓x�V�F�ւ̕������̂ł���B����O�܂ł̓W���j�[�E�z�b�W�X�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�𐁂�������肾�����B�Ȃ�A�����̓v���R�[�v�̃\�v���m���K�ȑI���ł͂Ȃ��낤���B�v���R�[�v�͗D�G�Ŋ�p�ȃv���C���[���B�uCONTROVERSIAL SUITE�v�́uBEFORE MY TIME�v�Ŋm���ȃ\�v���m�E�\�������Ă��ꂽ�ނȂ��������h�ɂ�萋���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
 �@�����A�҂Ă�B�z�b�W�X�̃\�v���m���s�\�ɂȂ�������Ƃ����āA��������̂܂܃v���R�[�v�ɑ����͉̂ʂ����đÓ����낤���B�z�b�W�X�������\�v���m�����炱���Ӌ`������B�������A���̋��͍��A����������̃W���j�[�E�z�b�W�X�ւ̑z���ɋ���Ă���B�Ȃ�A�\�v���m�T�b�N�X�����z�b�W�X�ɍS��̂��ł͂Ȃ����B�x�V�F�ւ̃I�}�[�W�������z�b�W�X�ւ̒Ǔ���D�悷��B���ꂪ���̋U�炴��C�������B�Ȃ�z�b�W�X�̒Ǔ��ɑ��������`�Ƃ́H�E�E�E
�@�����A�҂Ă�B�z�b�W�X�̃\�v���m���s�\�ɂȂ�������Ƃ����āA��������̂܂܃v���R�[�v�ɑ����͉̂ʂ����đÓ����낤���B�z�b�W�X�������\�v���m�����炱���Ӌ`������B�������A���̋��͍��A����������̃W���j�[�E�z�b�W�X�ւ̑z���ɋ���Ă���B�Ȃ�A�\�v���m�T�b�N�X�����z�b�W�X�ɍS��̂��ł͂Ȃ����B�x�V�F�ւ̃I�}�[�W�������z�b�W�X�ւ̒Ǔ���D�悷��B���ꂪ���̋U�炴��C�������B�Ȃ�z�b�W�X�̒Ǔ��ɑ��������`�Ƃ́H�E�E�E�E�E�������A�����̓|�[���E�S���U�����F�X�̃e�i�[�T�b�N�X���B�z�b�W�X�͕�����Ȃ��䂪�I�[�P�X�g���̎������B�ނɕ��Ԃ��̂ȂǒN�����͂��Ȃ��������A�͂��Ƀ|�[���������T�b�N�X�̈���̗Y�Ƃ��ăz�b�W�X�ɔ䌨�������B�T�b�N�X�̗��ւƂ����Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ������B�����̓S���U�����F�X�������Ȃ��B
�@�G�����g���͂������ă|�[���E�S���U�����F�X�̋N�p�����߂��B�V�h�j�[�E�x�V�F�ւ̃I�}�[�W�������W���j�[�E�z�b�W�X�ւ̃��N�C�G����I�������̂ł���B
�@�ʂ����Ă��̑I���͂ǂ��ł��������B�A���o���uNEWORLEANS SUITE�v�̑�7�ȁuPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v�ɂ�����X�^�����[�E�_���X�Ɩ���搶�̃��C�i�[�m�[�c�����p����B
�|�[���E�S���U�����F�X�̃v���C�͈̑�Ȃ��̂������B�Z�b�V�����ɂ����āA�~���[�W�V���������������Ă����傫�ȑr�����́A�\�ʓI�ɂ͐T�܂��������B����Ă����B�����A���̊���̓e�i�[�T�b�N�X�E�\���̂₳�����߂����Ɍ����ɕ`���o����Ă���B���̈���ŁA�x�V�F���Y�ꋎ���Ă͂��Ȃ��B���ăW���j�[�E�z�b�W�X�������Ȃ�̂����ł�����悤�ɁA�S���U�����F�X�͂��̖����̊��炩�ȉ��̗�����I�݂ɕ\�����Ă���B�i�X�^�����[�E�_���X �쓈���ێ���j�@�����́A���ē�l�̃I�[�\���e�B�ɂ��L�q�����ŏ\�����낤�B�G�����g���̑I���͊Ԉ���Ă��Ȃ������̂ł���B������A�Ō�Ƀ`���b�s���{�������킹�Ă���������A�W���j�[�E�z�b�W�X�̃\�v���m�T�b�N�X���Ă݂��������I
�ۂ���ŁA�����f���[�N���肱���点�Ă���|�[���i�����f���[�N�̓|�[���̃~���[�W�V�����Ƃ��Ă̎��͂�N���������Ă���j�͂��̃v���C�ɂ����ϏO�����]�����邱�Ƃ͂Ȃ������B���̃|�[���͂܂��ɐ�i�Ƃ�����B�x�V�F�ɕ�����͂��̂��̋Ȃ��A�|�[���ɂ���ăz�b�W�X�ւ̒����ȂƂȂ����B�|�[���̃e�i�[��2���O�ɖS���l�ƂȂ����O���C�g�E�W���Y�}����z���Ă����苃���Ă���B�����ɂ͉�������ƒ�̂悤�ȃG�����g����Ƃ̂��邶�f���[�N�E�G�����g���̐l�ԓI�Ȉ̑傳���ɂ��ݏo�Ă���B�i����v���搶�̃��C�i�[�m�[�c�j
�@����v���A���쏹�v���搶�ɂ��L�q�̈Ⴂ����n�܂����G�����g���T���̗��͍���ŏI��邱�Ƃɂ���B���m�̗̈�ł̗l�X�ȑ����ƌ����͎��ɋ����[���L�Ӌ`�������B��������Ȃɂ����A���؋��̂悤�ȃG�����g���̉��y���E�i�ł������Ƃ������M�d�ȑ̌��������B�����̎��Ԃ������B����͂ЂƂ��ɁA�W���Y�ɑa���������ɁA�^���ɉ����Ă�������������搶�A�����āA����ȏ��͂Ə��������^���Ă��ꂽ���쎁�Ɛ쓈���Ɗ����̂����ӂɂ����̂ł��B�����ɋނ�Ŋ��Ӑ\���グ�܂��B
�@���Q�l������
�@�uA��Ԃōs�����`�f���[�N�E�G�����g�����`�v�i����N�v��@�����Ёj
�@�u�f���[�N�E�G�����g���v�i�ēc�_�꒘ ����Ёj
�@LP�uNEWORLEANS SUITE�v������i�X�^�����[�E�_���X�A����v�����j
�@VIDEO�u�s�ł̃f���[�N�E�G�����g���v�i�ɂ����r�f�I�t�B�����Y�j
2020.05.20 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X9�`�ēx�A����搶�Ƃ̂����A����
�@�R���i�Ђ̒��A�O��]�_�Ƃ̉��{�s�v�����S���Ȃ����B74�A��w�̓����ł�����B�����⍲������̊���͂����ɋy���A�e���r�ɏo������悤�ɂȂ��Ă�����A���̓I�m�ɂ��ĕi�i���犴��������\���ɂ����āA�����̃R�����e�C�^�[�̒��ł��A�o�F�̑��݂������B�^�̈Ӗ��ł̃��g���b�N�Ƃ������̂�g�ɕt���Ă����̂��Ǝv���B�ނ�Ŗ��������F�肷��B�@���āA�{��ɓ��낤�B�����������A�u�N�����m�v�ł́A�G�����g���́uBEFORE MY TIME�v�́gTIGER RAG�h�����ɂ�����\�v���m�T�b�N�X�͒N���H �Ƃ����e�[�}�ɂ��Ă��ꂱ��l���Ă����B���ꂪ�A���쏹�v�搶�̐��ӂ���ɂ���Ăقڔ[���̂䂭���_������ꂽ�B�����́A�A�����J��CD�uELLINGTON UPTOWN�v�ɂ�����X�^�����[�E�_���X�̉����Procope (on both clarinet and soprano saxophone)�Ɩ��L����Ă��邱�ƁB������́A���b�Z���E�v���R�[�v���A�uCORNELL UNIVERSITY CONCERT 1948.12.10�v�ɂ����ă\�v���m�T�b�N�X�𐁂��Ă��鎖�������邱�Ƃ�2�_�������B
�i1�j����搶�ɍX�Ȃ鎿���
�@�Â���������������o���Ă܂ŁA��������������������搶�ɂ͊��ӂ̋C���������`�������B���̍ہA���������Ȃ̂ŐV���Ȏ���������Ă��������B���_���ʂ̃e�[�}�Ɋւ���Č��ł���B�����āA�܂��܂����J�ȉ������������B�ȉ��͂��̂����ł���B
�����⁄4��10��
�@���莆���肪�Ƃ��������܂��B�O�����������Ŗ������Ă���܂������A���̓x�A���������T�����������Ă܂ł��Ԏ��������������ƁA�����������ӂ̋C�����ł����ς��ł��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�����ŁA����A���ɋ��k�ł����A�����������������������������A������낵�����肢�\���グ�܂��B
 �@���̎苖�Ɂu�f���[�N�E�G�����g��1951�`�A�b�g�E���g���|���^���E�I�y���E�n�E�X�v�Ƃ������C�uLP������܂��B���̓��uCONTROVERSIAL SUITE�v�̏������s��ꂽ�悤�ł��̉��t�����^����Ă��܂��B
�@���̎苖�Ɂu�f���[�N�E�G�����g��1951�`�A�b�g�E���g���|���^���E�I�y���E�n�E�X�v�Ƃ������C�uLP������܂��B���̓��uCONTROVERSIAL SUITE�v�̏������s��ꂽ�悤�ł��̉��t�����^����Ă��܂��B�@���̃��C�i�[�m�[�c�͖���搶�ł����A����ɂ��܂��Ɨ�́uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���̓v���R�[�v�Ə�����Ă��܂��B�Ƃ��낪���̓��A1951�N1��21���ɂ͂܂��W���j�[�E�z�b�W�X���ݒc���Ă��܂��B���ʂɍl����ƁA�G�����g���Ȃ�A���̃f�B�L�V�[�����h���̃\�v���m�T�b�N�X���x�V�F�̒�q�z�b�W�X�ɐ�������Ǝv���̂ł��B
�@����搶�́A�z�b�W�X���v���R�[�v�A�ǂ���Ƃ��l���ł��傤���B��͂�A���C�i�[�m�[�c�ǂ���v���R�[�v�ł��傤���B
�@���x�A�߂�ǂ��Ȏ������Ő\�������܂���B�V�^�R���i�ɂ��s���ȏ�ł������܂��B�搶�̂����N��S����F��\���グ�܂��B
����4��15��
�@�G�����g���̃��g���|���^���E�I�y���E�n�E�X�̃R���T�[�g�ɂ�����uBFORE MY TIME�v�ɂ����鋻���[��������ł����E�E�E�E�E�B
�@�uBEFORE MY TIME�v �ƁuLATER�v 2�Ȃ��琬��uCONTROVERSIAL SUITE�v �́A�G�����g���́A1951�N1��21���̃��g���|���^����1951�N12��11��N.Y.�ɂ�����^���̌v2�����t���ĂȂ��悤�ł��B
�@�G�����g����1950�N���r�o�b�v��v���O���b�V���E�W���Y�̂�ѐ������ɐ���ɂȂ����W���Y�E�̏̒��ŁA�u�������ȑO�̎���v�Ɓu���ꂩ��ȍ~�̎���v�Ƃ����^�C�g���ŏ����̃f�B�L�V�[�ⓖ���̃��_���E�W���Y�I�T�E���h��\�������̂��Ǝv���܂��B
�@�uBEFORE MY TIME�v�́gTIGER RAG�h�̉��t�ɂ��ẮA�f�B�L�V�[�n�̌Â��X�^�C���̉��t�ɂ̓z�b�W�X��E�B���[�E�X�~�X���A�v���R�[�v�̕��������Ă���ƍl�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�z�b�W�X�ɂ͂����Ɣނ炵���I���W�i���ȃv���C�����҂��Ă����̂ŁA������Ȃɒ����v���C�ł��Ȃ��̂ŁA�f�B�L�V�[���ɂ�����Ă���v���R�[�v��I�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�V�h�j�[�E�x�V�F�̃v���C�����Ƃ��ƃj���[�I�����Y�̌Â��f�B�L�V�[�X�^�C���Ƃ͏����قȂ�Ǝ��͎v���Ă���A�gTIGER RAG�h ���z�b�W�X�ɐ�������Ӗ��i����������\���Ȃ�Ƃ�����7�̃e�[�}�̈�Ƃ����Z���j���G�����g�����������Ƃ͎v���܂���B
�@�B���͍��苖��1��21���̃��g���|���^����CD����������Ȃ��̂ŁA12��11���̘^�����Ɨ��҂̃v���R�[�v�̃\�����r���邱�Ƃ��ł��܂���B���̓_�͍��x�������Ƃ̉�Ő����̃\����������ׂĂ݂ĉ������B���G�����g���E�f�B�X�R�O���t�B�[�ɂ��Ɩ���搶�̃��C�i�[�ɂ���tp�̃t�@�b�c�E�t�H�[�h�Ƃ����Ƃ������͋L�ڂ���Ă��܂���B�������Avocalist�Ƃ���BETTY ROCHE ��LEO WATSON �̖����̂��Ă��܂��B�ȏ��Q�l�ɋ����܂��B
�@���ɍ��ؒ��J�ȉł��蓖�Y�̃e�[�}�ɂ��Ă��h�����[���g�ƕ]���Ă����������B���ӂ̔O�͐[�܂����ł���B�������������ӏ������Ő������Ă݂�B
�@ �uCONTROVERSIAL SUITE�v�͂�����������t����Ă��Ȃ�
�@���U��3000�Ȉȏ���������Ƃ�����G�����g��������A���̂悤�ȗ�͂����������̂��낤���A����ɂ��Ă��A�����P��A���R�[�f�B���O1��Ƃ͗\�z�O�̏��Ȃ��������B�t�ɑ����̂͂ǂ̂��炢����̂��H�Ⴆ�A��D���ȁuSOPHISTICATED LADY�v�͂ǂ����Ǝv���A�莝���̉������Ă݂��B���^���Ǝv����1933�N2��15���^����Columbia�Ղ���1969�N4��29���u70�o�[�X�f�C�E�R���T�[�g�v�܂ŁA30���N�ɂ킽����16���take���m�F�ł����B����瓯�Ȉى�����ׂ�͎̂��Ɋy�����A�N���V�b�N�����y���ɖʔ����B�N���V�b�N�̏ꍇ�A��i�͊y���ɂ���ČŒ艻����Ă��邪�A�G�����g���̏ꍇ�͍�i���̂��̂��ϖe����B���t���������ꂽ���̂���i�����炾�B��i�̓L�����A�̒��ŗl�X�ɕϗe�����B����B���Ɩ��Ē��̕s���s�ł���B�N���V�b�N�Ƃَ͈����̐��E�B�G�����g���̈̑傳�ł���ʔ����ł���B
�A �G�����g���́uBEFORE MY TIME�v�́gTIGER RAG�h�̉��t�ɂ����āA�f�B�L�[�n�̌Â��X�^�C���̉��t�ɂ̓z�b�W�X��E�B���[�E�X�~�X���A�v���R�[�v�̕��������Ă���ƍl�����̂ł͂Ȃ����B�V�h�j�[�E�x�V�F�̃v���C�����Ƃ��ƃj���[�I�����Y�̌Â��f�B�L�V�[�X�^�C���Ƃ͏����قȂ��Ă��āA�gTIGER RAG�h ���z�b�W�X�ɐ�������Ӗ��i����������\���Ȃ�Ƃ�����7�̃e�[�}�̈�Ƃ����Z���j���G�����g�����������Ƃ͎v���Ȃ��B
�@�uBEFORE MY TIME�v�́hTIGER RAG�h�����̓��b�Z���E�v���R�[�v�̕��������Ă���A�킴�킴�W���j�[�E�z�b�W�X���N�p����K�v�͂Ȃ��B�����G�����g���͍l�����̂ł͂Ȃ����A�Ɛ搶�͂��������̂ł���B��w�Ȏ��̓f�B�L�V�[�n�̃X�^�C�����x�V�F�̃X�^�C�����A�܂��Ă�gTIGER RAG�h�ɂ�����v���R�[�v�ƃz�b�W�X�̓K�����肷��X�L�����Ȃ����A���������Ȑ���搶�̂��ӌ��͑��d���ׂ��ł��낤�B
�@�z�b�W�X�͂܂��A�uCONTROVERSIAL SUITE�v���������ꂽ1951�N1��21����2�����ɂ́A�G�����g���y�c�������Ă���B�����̓�l�̊W���𐄎@����p���Ȃ����A�G�����g���́A�y�c�̎���Ƃ������ׂ��z�b�W�X���������Ƃ̒Ɏ�������Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���B����Ȑ܁A1940�N�ȍ~�\�v���m����ɂ��Ă��Ȃ��z�b�W�X�ɋ͂�10�����߂̒Z���p�[�g�𐁂�����K�v�����G�����g���������Ȃ��������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�������A1940�N�Ƀz�b�W�X���\�v���m�T�b�N�X��u�������R�́A�u�A���g�ƃ\�v���m�̓������Ȃ�M�������{����v�ƃG�����g���ɐ\���o�����p�����ꂽ���߁@�Ƃ����b�����邭�炢���B���X�A�����̏܂���ƁA�G�����g�����D�G�ȃ��[�e�B���e�B�E�v���C���[�ł���v���R�[�v���N�p�����̂�������b�ł���B
�i2�j�z�b�W�X�ƃv���R�[�v�̃\�v���m�T�b�N�X��r
 �@����搶�͂܂��A�ŏ��̂��莆�̒��ŁA�uCORNELL UNIVERSITY CONCERT�v�i1948�N12��10���j�́uREMINISCING IN TENPO�v�ŁA�v���R�[�v�̓\�v���m�T�b�N�X�����t���Ă��� �Ƌ����Ă����������B���͂��̉�����CD������Ă���A���쎁��copy�𑗂��Ă��ꂽ�i�ނ͂܂�����CD copy��搶�ɂ����肵�đ傢�Ɋ��Ă���j�B����ɋ����ׂ��́A�����uREMINISCING IN TEMPO�v�̃X�^�W�I�^���Ձi1935.9.12�j�ł̓W���j�[�E�z�b�W�X���\�v���m�T�b�N�X�𐁂��Ă���̂ł���B�����炭���҂��\�v���m�T�b�N�X�œ����Ȃ����t���Ă���P�[�X�͑��ɂȂ����낤�B
�@����搶�͂܂��A�ŏ��̂��莆�̒��ŁA�uCORNELL UNIVERSITY CONCERT�v�i1948�N12��10���j�́uREMINISCING IN TENPO�v�ŁA�v���R�[�v�̓\�v���m�T�b�N�X�����t���Ă��� �Ƌ����Ă����������B���͂��̉�����CD������Ă���A���쎁��copy�𑗂��Ă��ꂽ�i�ނ͂܂�����CD copy��搶�ɂ����肵�đ傢�Ɋ��Ă���j�B����ɋ����ׂ��́A�����uREMINISCING IN TEMPO�v�̃X�^�W�I�^���Ձi1935.9.12�j�ł̓W���j�[�E�z�b�W�X���\�v���m�T�b�N�X�𐁂��Ă���̂ł���B�����炭���҂��\�v���m�T�b�N�X�œ����Ȃ����t���Ă���P�[�X�͑��ɂȂ����낤�B ������r�������Ȃ���͂Ȃ��B
������r�������Ȃ���͂Ȃ��B�@�z�b�W�X�̃X�^�W�I�^���Ղł́A�Ȃ̖`��20�b�����肩��50�b���x�������Ƃ��ł���B �v���R�[�v�́uCORNELL UNIVERSITY CONCERT�v���C�u�Ղł́A1��03�b�����肩�瓯���x�������B�^�C���̈Ⴂ�̓G�����g����MC�����邩��ŁA���t�ӏ����ڂ��قړ����ł���B �O���̓I�u���K�[�g�Ń\���Ƃ����ɂ͕�����Ȃ����A�撣���ăg���C���Ă݂悤�B
�@�z�b�W�X�͊Â��Z���Ń��B�u���[�g�͑��߁B���ăv���R�[�v�̓X�b�L���u�₩�Ń��B�u���[�g�͏��Ȃ߂ł���B�f�t�H�������đΛ��̐}���ɒu��������ƁA�d���z�b�W�XVS�����v���R�[�v�ƂȂ낤���B���̍��ق́A�A���o���uDUKE ELLINGTON PRESENTS�E�E�E�v�iBETHLEHEM 56�j�ŁA��薾�m�Ɏ��ʂł���B�z�b�W�X�uDAY DREAM�vVS�v���R�[�v�uINDIAN SUMMER�v�B�o����͂̃A���g�ɂ��{�i�I�ȃ\���͑Δ�ۗ��̊�������B
�@�ł́A���̓������́uBEFORE MY TIME�v�gTIGER RAG�h�ɓ��e�E�ƍ����Ă݂悤�B
���u�f���[�N�E�G�����g��1951�`�A�b�g�E���g���|���^���E�I�y���E�n�E�X�v1951�N1��21���̘^��
�@�\�v���m�T�b�N�X�E�\���́A16��������16���߂ɂ킽���ĕp�o���鍂���X�^�C���̋ȑz�B
�@���t�́A���K�s���Ȃ̂����̗��������e��������X���[�Y���Ɍ�����B���F�͂�⊣��������������B
���uELLINGTON UPTOWN�v1951�N12��11���̃X�^�W�I�^��
�@�\���̉��^�͓��l�����ڂ�32���߂Ɣ{�̒����ɂȂ��Ă���B
�@���t�́A�A�����鉹�̗��������N���ŗ�������݂��Ȃ��B���Ɍ����ȃp�t�H�[�}���X�ł���B���F�͍d���Ŋ����������������B
�@����͒��X�ɓ���B���������͉��F�Ɏア�Ƃ��Ă���B�y��Ɍ��炸���̔��ʂ����Ȃ̂��B�Ȃ����͂����A�Ȋw�I�ɕ��͊Ӓ肷�邵���Ȃ��ƍl���A�u���{�����������v�ɖ₢���킹���B�u�����͐���Ӓ肪��ł���A���̂悤�ȊӒ�͂������Ƃ��Ȃ��B�����҂ɉ����Ȃ����낤��������10���͉���Ȃ��Ǝv���v�Ƃ̕ԓ��������B�����Ŏ~�߂�B
 �@�����A���Ƃ͎����̎��𗊂邵���Ȃ��B���x�����x�������Ԃ��E�E�E�E�E���ʁA����ƁA�ǂ��炩�ƌ����A���B�u���[�g���Ȃߐ����n�ɕ������Ă����B��͂肱��̓��b�Z���E�v���R�[�v �Ƃ������_�ɒB�����B
�@�����A���Ƃ͎����̎��𗊂邵���Ȃ��B���x�����x�������Ԃ��E�E�E�E�E���ʁA����ƁA�ǂ��炩�ƌ����A���B�u���[�g���Ȃߐ����n�ɕ������Ă����B��͂肱��̓��b�Z���E�v���R�[�v �Ƃ������_�ɒB�����B�@�G�����g���́uBEFORE MY TIME�v�gTIGER RAG�h�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���Ƀ��b�Z���E�v���R�[�v���N�p�����B1951�N1��21�����g���|���^���ł̏������͏����s���ł��ڂ��Ȃ��������A���K��ς�12��11���̃X�^�W�I�^���ł͎��M�ɖ������p�t�H�[�}���X�����������A�Ƃ������ꂾ�낤���B
�@�O��͋q�Ϗ����A����͉����̂��̂̌���������āA���̌��_���o�����Ƃ��ł����B�����Ԃ��ꂱ��l���Ă����e�[�}�Ɉꉞ�̌����������B�e�[�}�͍��ׂȂ��Ƃł���B���_�͕��}�ł���B�����疳�Ӗ����A�Ɖ]���Ό����Ă����ł͂Ȃ��B���̉ߒ��̒��ŁA�G�����g���̉��y���̂��̂ɐ[���H�����ނ��Ƃ��ł����悤�ȋC�������B���A�ŁA�N���V�b�N�厲�̉��y�l���ɍX�Ȃ镝���������Ǝv���B����͈Ӌ`�[���傫�Ȏ��n�ł���B
�@���āA���Ȃ�ۑ�́A�uPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�v�̃\�����v���R�[�vss�ł͂Ȃ��Ȃ��|�[���E�S���U�����F�Xts�ɂȂ����̂��A�ł���B����ɂ��Ă͍ēx����ɐ摗�肵�����B
���Q�l������
LP�u�f���[�N�E�G�����g��1951�`�A�b�g�E���g���|���^���E�I�y���E�n�E�X�v�iRJL2638�j
CD�uDUKE ELLIGTON CORNELL CONCERT 1948.12.10�v�i01612-65114-2�j
CD�uDUKE ELLINGTON REMINISCING IN TEMPO�v�iCK48654�j
CD�uELLINGTON UPTOWN�v�iCK40836�j
CD�uDUKE ELLINGTON PRESENTS�E�E�E�v�iCDSOL45508�j
2020.04.25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X8
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`��͂�v���R�[�v�A�����Đ��쏹�v�搶
 �@�V�^�R���i�����̒��A�u�����S���Ȃ����B�C�O���f�B�A�́u���{�̊쌀���v�ƌ`�e�������A����͌����Č֒��ł͂Ȃ��Ǝv�����B����쌀���G�m�P���`�������`�u������Ɏ��闬�ꂱ���A���{�̊쌀�̗��j�ɂ����āA����Ӗ��嗬�ɂ��ĉ����ƍl�����邩�炾�B
�@�V�^�R���i�����̒��A�u�����S���Ȃ����B�C�O���f�B�A�́u���{�̊쌀���v�ƌ`�e�������A����͌����Č֒��ł͂Ȃ��Ǝv�����B����쌀���G�m�P���`�������`�u������Ɏ��闬�ꂱ���A���{�̊쌀�̗��j�ɂ����āA����Ӗ��嗬�ɂ��ĉ����ƍl�����邩�炾�B�@4��1���̒����V���ɁA���������̒Ǔ������f�ڂ��ꂽ�B�u���g�����P�����������e���r�v�iTBS�j�̍\����Ƃł����������́A�u���̃R���g�͏��ւ̌������p���̎����������ƋL���B�����āA����́A�����܂������ʂɂ��ƂĂ��Ȃ��m���ɗ��ł����ꂽ���̂������Ƃ��B���͎u���́u�����R�����v���u�J���X�̏���ł��傤�v���D�������A����ȏ�Ƀh���t�𑲋Ƃ������NHK-TV�u�ƂȂ�̃V�����v����D���ł���B������̂́A�܂�ōႦ�Ȃ����ǂ������߂Ȃ����ʂ̂�������B�����܂ł̃L�����͂�����ł�����̂����A�u���̏ꍇ�́{���D�ƒm���������������ɟ��ݏo��̂��B����ȕ��w�I�ȃL�����N�^�[���A�W���b�N�E�������ɂ����āA���Ƃ����������͓I�������B2014.12.16 O.A.�́u�ƂȂ�̃V�����v�͑S�Ҍ��쑵���B�G���f�B���O�E���[���ɂ͓��̉̂��u��v�������B�̓G�m�P���Ƃ̃R���r�Ő������[�S������Ȍ������X�^�[�B���̂�����̌��́A���쏹�v���u�W���Y�ŗx���āv�ɏڂ����B
 �@���쏹�v���Ƃ����A���́u�N�����m�v�̃e�[�}�ł���G�����g���uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���͒N���H �̔��[�ƂȂ������{��CD�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{1�v�̃��C�i�[�m�[�c���M�҂ł���B1924�N���܂�ŁA�O���R�I�v�Ƃ͊w�K�@�����ȁ`����@�w���̓������ɂ��Đe�����[�������������B����Ȑ��쎁�ɁA���͎��A�傢�ɂ����b�ɂȂ��Ă���̂ł���B�����炱������͐���搶�ƌĂ��Ă��������B
�@���쏹�v���Ƃ����A���́u�N�����m�v�̃e�[�}�ł���G�����g���uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���͒N���H �̔��[�ƂȂ������{��CD�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{1�v�̃��C�i�[�m�[�c���M�҂ł���B1924�N���܂�ŁA�O���R�I�v�Ƃ͊w�K�@�����ȁ`����@�w���̓������ɂ��Đe�����[�������������B����Ȑ��쎁�ɁA���͎��A�傢�ɂ����b�ɂȂ��Ă���̂ł���B�����炱������͐���搶�ƌĂ��Ă��������B�@���������ARCA���R�[�h���ꎞ���ꂽ�n����掞��A���l���̃��R�[�h��Ђ��������߁A����E��`�E�c�Ɖ��ł����˂Ȃ炸�A�����W���Y������������������B���̒��ŕҐ�����Ɍg������̂��uSWINGTIME VIDEO�v�Ƃ����r�b�O�E�o���h�E�W���Y�̉f�����m�ŁA���̎������b�ɂȂ����̂�����搶�������B�搶�́A�W���Y�f�l�̎��ɂ��낢�덧�ؒ��J�ɋ����Ă����������B�^�ɂ�����D�����a�m�������B�ږ���Ȃ����Ă����x�m��s�ő҂����킹�Ă̑ł����킹��Z�{�̃��C�u�n�E�X�ɂ��ꏏ�������ƂȂǂ����������v���o�����B�搶�͌���N96�ł����݂ł���B�Ȃ�Ƃ������ƂŁARCA���R�[�h�̌�y�Ō��݃\�j�[�E�~���[�W�b�N�̗m�y�Ґ��Ɍg�����ΌN�ɐ搶�̏Z�����m���߂āA���ʂ̋^���₢���킳���Ă����������B�ȉ��͂��̌o�܂ł���B
(1) ����搶�ւ̎����Ɖ�
�@3�����A���{��CD�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{1�v�̃��C�i�[�m�[�c���M�Ґ��쏹�v�搶�ɁuCONTROVERSIAL SUITE�v�́uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�Ɋւ��Ď����𑗂点�Ă��������B�������������X������Ă����̂�4��3���ł������B
�����l�@���莆���肪�Ƃ������܂����B�����̋L�����\���ɂȂ��̂ňȉ��̂��Ƃ�����Ԏ��ł��܂���B�X�������肢���܂��B�@�Ȃ�Ƃ����X�s�[�h�A�ƂĂ� 96�Ƃ͎v���Ȃ��B����ɂ��܂��āA�̂ƕς��ʗ��`���ɗL��C�����ł����ς��ɂȂ����B����������o���B�Ƃ��낪����ɋ������ƂɁA4��7���ɑ��҂��͂����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���쏹�v
����1��
�搶���uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{1�v���́uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\�����v���R�[�v�Ƃ������ɂȂ������R�������������������B���݂ɖ���v���搶�́A1964�N�����̃R�����r�A��LP�̃��C�i�[�m�[�c�ŁA���̕������u�q���g���E�W�F�t�@�[�\��(�H)�v�Ə����Ă����܂��B
����
�͂�����L�����Ă���܂��A���炭�A�����J�Ղ̍ŐV�̉���ɏ����Ă������̂����p�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���݂ɃG�����g���̃\���X�g��S���L�ڂ��Ă���uDUKE ELLINTON'S STORY ON RECORDS COMPILED by Luciano Massogli, Leheni Pusateni,Giovanni M.Volonte�v�Ƃ����{������܂��āA���̎苖�ɂ͍��g1951-1955�h�̕������Ȃ��̂Ō��ł��܂��A�����N���̏��L���邻�̖{������p�����̂�������܂���B����Ƃ��A�`���ŋL�����悤�ɁA�A�����J�Ղ̉�������p�����̂�������܂���B�����킴�킴�v���R�[�v�̖����o�����̂́A�����̋L�ڂ��Q�Ƃ��Ă���͂��ł��B
����2��
���̌o���ł́A���̐搶�̋L�q�ȊO�Ɂu�v���R�[�v���\�v���m�T�b�N�X�𐁂����v�Ƃ����L�q�T�������͊m�F�ł��Ă���܂���B�������̎��Ⴊ������������������B
����
��L�̏��Ђɂ���Procope��1948�N12��10��Cornell��w�̃R���T�[�g�ŁA�uReminiscing in tempo�v��SS�𐁂��Ă��܂��B���̑��ɂ�1959�N�܂Ō�������܂���B�ȍ~�͖������ł��B
����3��
���̘^�����A1951�N12��11���ɂ̓z�b�W�X�̓G�����g���y�c��ޒc���Ă��܂����A�����ݐЂ��Ă����Ȃ�G�����g���͂��̕������z�b�W�X�ɑ������\��������A�Ƃ��l���ł��傤���B
����
�G�����g�������̕�����SS�\���ɂ������ƍl���Ă����Ƃ���A���R�z�b�W�X�ɐ��������Ǝv���܂��B
����4��
1970�N5��13���^���́u�j���[�I�����Y�g�ȁv�́u�V�h�j�[�E�x�V�G�̏ё��v�ɂ����āA�G�����g���̓T�b�N�X�E�\�����A�v���R�[�v�̃\�v���m�ł͂Ȃ��S���U�����F�X�̃e�i�[�ɑ������̂͂Ȃ����Ƃ��l���ł��傤���B���́A�v���R�[�v���\�v���m�𐁂��̂ł���A�G�����g���͂������v���R�[�v�ɑ������͂����ƍl������̂ł��B
����
�G�����g���́A�\���X�g�Ƃ��ẮA�S���U�����F�X�������ƍ����]�����Ă�������ł͂Ȃ��ł��傤���B
(2) ����搶����̒ǐL
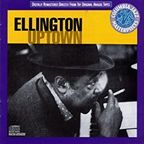
�����d�Ȃ��ւ��L������܂����B��ʂ͎�芸�������̋L�����Ă���Ƃ������Ԏ������̂ł����A���̌㉺�L�̃G�����g��CD2���̃A�����J�Չ����T���o���Č����Ƃ���A���̂悤��Stanley Dance��Patlicia Willard�̉���������āA������v���R�[�v�̃\�v���m�T�b�N�X�Ə����Ă���܂��B���̏������\�j�[�M�Ղ́A1997�N�����Ȃ̂ŁAWillard��2004�N���O�ł�����A���炭�uELLINGTON UPTOWN�v�iColumbia CK40836�j�̃X�^�����[�E�_���X�̉�����Q�l�ɂ����Ǝv���܂��B�@�搶�̂��莆�́A���̂��Ƃ�Patlicia Willard�̉��������������͗v�����Ă��������낤�B�Ƃɂ����搶�́g�L�������ǂ邾���ł͖O�����炸�h�A�̂̉p���������������o���ĉ��Ă����������̂ł���B����͂���Ȃ銴���������B�{���̌����o�����ł��钆�쎁�Ɏ莆�̃R�s�[�𑗂�Ɓu�搶�̉��y�ɑ��鈤��Ə�M�����Đ^���ȑΉ��ɗ܂����ڂ��v���E�E�E�E�v�ƕԐM�����ꂽ�B
�uELLINGTON UPTOWN�v��Stanley Dance�̉p������͎��̂悤�ɂ���܂��B
The two-part �gCONTROVERSIAL SUITE�h premiered at Carnegie Hall is unlike any other Ellington composition in that it looks askance at contemporary Jazz Movement �gBEFORE MY TIME�h is amused and even contemptous reference to the prevalence of Dixieland at that time. Shorty Baker, Russell Procope (on both clarinet and soprano saxophone) and Quentin Jackson �E�E�E�E�E�E
�@�X�^�����[�E�_���X�̉���ɂ͊m�����u���b�Z���E�v���R�[�v�i�N�����l�b�g�ƃ\�v���m�T�b�N�X�j�v�Ə�����Ă���B�_���X�Ƃ����A�A���o���uTHE ELLINGTON ERA 1927�`1940�v�̃��C�i�[�m�[�c�ŁA1964�N�x�O���~�[�܂����i�[�h�E�t�F�U�[�Ƌ��Ɏ�܂����G�����g���]�_�̃I�[�\���e�B�ł���B�Ȃ̂ŁA�uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���̓��b�Z���E�v���R�[�v�ŊԈႢ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B����ɐ搶�̉ɂ́A�uProcope��1948�N12��10���ACornell��w�R���T�[�g�ɂ����āA�wReminiscing in tempo�x�̒���SS�𐁂��Ă���v�Ƃ��邩�炵�āA�g�v���R�[�v�͂��̂ق��Ƀ\�v���m�T�b�N�X�𐁂��Ă��Ȃ����h�����@���ꂽ�B
�@�����������A���������Ă����^�₪100%���������킯�ł͂Ȃ��B����Δ�������Ԃł���B�Ȃ��Ȃ�A�u1970�N5��13���^���́wNEWORLINS SUITE�x�́wPORTRAIT OF SIDNEY BECHET�x�̃\�����A�G�����g�����v���R�[�v�̃\�v���m�T�b�N�X�ł͂Ȃ��|�[���E�S���U�����F�X�̃e�i�[�T�b�N�X�ɑ������v���Ƃ̐��������Ă��Ȃ����炾�B����ɂ��Ă͎���ɉ����Ǝv���B
���Q�l������
���쏹�v���u�W���Y�ŗx���āv�i�����o�Łj
NHK-TV�u�ƂȂ�̃V�����v�i2014.12.16O.A.�j
2020.03.25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X7�`����̓W���j�[�E�z�b�W�X
(1)�u�V�h�j�[�E�x�V�F�̏ё��v�ɂ�����W���j�[�E�z�b�W�X�̉^�� �@�u�j���[�I�����Y�g�ȁv�Ƃ����Ȃ�����B1970�N�A�f���[�N�E�G�����g�����j���[�I�����Y�s�̈Ϗ����āA�j���[�I�����Y�E�W���Y���w���e�C�W�E�t�F�X�e�B���@���̂��߂ɏ������낵��9�Ȃ��琬��g�Ȃł���B5�Ȃ��W���Y���˂̒n�j���[�I�����Y�̗��j�E���y��`�������̉�I�Ȃ��́A���́A���̒n�����̃W���Y�E�v���C���[�A���C�E�A�[���X�g�����O�A�E�F���}���E�u���[�h�A�V�h�j�[�E�x�V�F�A�}�w���A�E�W���N�\�������X�y�N�g�������ɂ��|�[�g���[�g��4�ȁB���y��`����۔h�I��@�Ɛ�B�Ɋ�h���̏�������Ƀo�����X�����G�����g������̌���ł���B
�@�u�j���[�I�����Y�g�ȁv�Ƃ����Ȃ�����B1970�N�A�f���[�N�E�G�����g�����j���[�I�����Y�s�̈Ϗ����āA�j���[�I�����Y�E�W���Y���w���e�C�W�E�t�F�X�e�B���@���̂��߂ɏ������낵��9�Ȃ��琬��g�Ȃł���B5�Ȃ��W���Y���˂̒n�j���[�I�����Y�̗��j�E���y��`�������̉�I�Ȃ��́A���́A���̒n�����̃W���Y�E�v���C���[�A���C�E�A�[���X�g�����O�A�E�F���}���E�u���[�h�A�V�h�j�[�E�x�V�F�A�}�w���A�E�W���N�\�������X�y�N�g�������ɂ��|�[�g���[�g��4�ȁB���y��`����۔h�I��@�Ɛ�B�Ɋ�h���̏�������Ƀo�����X�����G�����g������̌���ł���B�@�����́A1970�N4��25���A�O�q�̃W���Y�E�t�F�X�e�B���@���B���̊G5�Ȃɂ�镔�������ƂȂ����B�����5�Ȃ�4��27���ɁA�|�[�g���[�g��4�Ȃ�5��13���ɁA�j���[���[�N�Ř^������A�u�j���[�I�����Y�g�ȁv�S9�Ȃ̃��R�[�f�B���O�����������B�Ƃ��낪���̊ԂɁA�G�����g���y�c�ɂƂ��ĂƂ�ł��Ȃ��o�������N�����Ă��܂��B���̂�����̌��́A���̃t�F�X�e�B���@�������n�ő̌����ꂽ����v���搶�̃��C�i�[�m�[�c�ɖ��炩�ł���B

���̃��R�[�h�������Ă���ƁA���̖�̃R���T�[�g�̊��������̂��̂��Ƃ̂悤���S���Ă��邪�A���̖�̉��t�����܂͖S���A���g�̑�䏊�W���j�[�E�z�b�W�X�Ō�̃X�e�[�W���t�ƂȂ������Ƃ����S���ʂł���B�z�b�W�X�͂��̃R���T�[�g�̗��X���j���[���[�N�ł���LP�̐����Z�b�V���������ڂɎQ���������A���̃Z�b�V�������z�b�W�X�Ō�̃Z�b�V�����ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B2�x�ɕ�����ꂽ���̃Z�b�V�����A2�x�ڂ̐�����5��13���ɍs���Ă��邪�A�z�b�W�X�͂���2���O��11���ɋ}�������̂������B�Ƃ������Ƃ͂���LP���z�b�W�X�̎��̒��O����ɂ܂������Đ����܂ꂽ�킯�ŁA�G�����g���ɂƂ��Ă��܂��Ɋ��S�[�����R�[�h�ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B�@�搶�̓R���T�[�g��ɁA�G�����g������u���̃��R�[�f�B���O�����ɗ��Ȃ����v�ƗU��ꂽ���A�������������j���[�I�����Y�̊ό����y���ނ��߁A�f���Ă��܂����Ƃ����B�u���l����ƁA�f���[�N�̈�s�ƃ~���[���[�N�ɍs���Ă�����Ǝv�킸�ɂ����Ȃ��B�S���c�O�Ȃ��Ƃ��������̂��B�v�Ɖ���܂�Ă���B���s���Ă�����z�b�W�X�Ō�̃Z�b�V�����ɗ�������̂ɁA�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@��L�����n��Ő������Ă������B1970�N�t�̏o�����ł���B
4��25���u�j���[�I�����Y�g�ȁv��5�Ȃ����n�ŏ����B�z�b�W�X�Q���B
�@�@27���u�j���[�I�����Y�g�ȁv��5�Ȃ����R�[�f�B���O�B�z�b�W�X�Q���B
�@�@���̊ԁA�G�����g���́u�|�[�g���[�g�v4�Ȃ��������邽�߂̍�ҋȍ�Ƃ��s���B
5��11�� �z�b�W�X�}���B
�@�@13���@�u�j���[�I�����Y�g�ȁv�́u�|�[�g���[�g�v4�Ȃ����R�[�f�B���O�B�z�b�W�X�Q���ł����B
�@�u�G�����g�����`�v�ɂ��̂�����̎�L���ڂ��Ă���B
1970�N5��11���A�킽���̓W���j�[�E�z�b�W�X�ɂ�����x�\�v���m�T�b�N�X����ɂ����A�u�j���[�I�����Y�g�ȁv�́u�V�h�j�[�E�x�V�F�̏ё��v�����t������ɂ͂ǂ��������̂��Ǝv�������点�Ă����B����Ɠd�b����A�ނ��|����t���̎���҂̐f�f���Ŏ����Ƃ�m�炳�ꂽ�̂��B�@�G�����g���́A�u�V�h�j�[�E�x�V�F�̏ё��v�Ńz�b�W�X�Ɂg�\�v���m�T�b�N�X�h�𐁂�������肾�����B�z�b�W�X�́A�x�V�F���\�v���m�T�b�N�X�̂��ׂĂ̋Z�@��@�����B��̒�q������A����͓��R�̂��Ƃ��낤�B���ꂪ���R�[�f�B���O�̓���O���]��B�Ȃ�Ƃ����^���B�G�����g���́u�w�V�h�j�[�E�x�V�F�̏ё��x�̃z�b�W�X��z�肵�ď������\�v���m�T�b�N�X�E�p�[�g��N�ɐ������邩�v�Ƃ����I���ɔ�����E�E�E�E�E�ނ̑I���̓|�[���E�S���U�����F�X�̃e�i�[�T�b�N�X�������B
�@�����őf�p�ȋ^�₪������B����́A�Ȃ����b�Z���E�v���R�[�v�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�𐁂����Ȃ��������H�Ƃ������Ƃ��B�x�V�F�Ƃ����\�v���m�T�b�N�X�̋��l�����X�y�N�g����ȂȂ�A�\�v���m�T�b�N�X�ʼn��t���ׂ��ł͂Ȃ��̂��B�u���C�E�A�[���X�g�����O�̏ё��v�ł̓N�[�e�B�E�E�B���A���X�̃g�����y�b�g���A�u�E�F���}���E�u���[�h�̏ё��v�ł̓W���[�E�x���W���~���̃x�[�X��v�X�t�B�[�`���[���Ă���̂�����B
�@�v���R�[�v�́A�A���o���uHi-Fi ELLINGTON UPTOWN�v�́uCONTROVERSIAL SUITE�v�́uBERORE MY TIME�v�ŗ��h�ȃ\�v���m�T�b�N�X�E�v���C��W�J���Ă���i���ƂɂȂ��Ă���j�B�����A�v���R�[�v������قǂ̃\�v���m��������̂Ȃ�A�G�����g���͂Ȃ��u�V�h�j�[�E�x�V�F�̏ё��v�Ŕނ��N�p���Ȃ������̂��H�@�������Ȃ������̂́A�u�v���R�[�v�̓\�v���m�𐁂��Ȃ��A�������͐����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�Ȃ����B�Ȃ�A�u�wBEFORE MY TIME�x�̃\�v���m�E�\���̓v���R�[�v�ł͂Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����B �O��2��25���́u�N�����m�v�ł͒��쎁�́u�V�h�j�[�E�x�V�F���v�����グ���B����̓W���j�[�E�z�b�W�X�̏ꍇ���l���Ă݂����B
(2)������A�W���j�[�E�z�b�W�X�ł́H
 �@�O�́u�G�����g�����`�v�̑����͂������B
�@�O�́u�G�����g�����`�v�̑����͂������B
�ނقǐ��������Ƃ����V���[�}�����̑�ȃX�e�[�W�̌������Ȃ������B�������łȂ��A�ނ̏o�����͔��ɔ������A�悭�����҂ɗ܂��������̂��B�\�\���ꂪ�W���j�[�E�z�b�W�X�������B���ꂪ�W���j�[�E�z�b�W�X�ł���B�ނƂ����̑�ȑ��݂������A�킽�������̃o���h�́A�����A��x�Ɠ����悤�ȉ����o���Ȃ����낤�B�W���j�[�E�z�b�W�X�́A�Ƃ��ɂ͔����������o���A�Ƃ��ɂ̓��}���`�b�N�ȉ����o���A���ɂ͒����ЂƂ����o�I�ƌ����������o�����B�킽���́A�����������ނ̉����̂��āu�Ƃ��Ă��ЂƂ��䂫�����ɂ͂����Ȃ������v�ƌ����Ă���̂����ɂ������Ƃ�����B�u�W�[�v�X�E�u���[�X�v�u�̂͂悩�����ˁv�u�A�C�E���b�g�E�A�E�\���O�E�S�[�E�A�E�g�E�I�u�E�}�C�E�n�[�g�v�u�I�[���E�I�u�E�~�[�v�u���邢�\�ʂ�Łv�u�p�b�V�����E�t�����[�v�u�f�C�E�h���[���v���̑���������̋Ȃ����t�����B�킽���́A�邲�Ɩ邲�ƁA40�N�Ԃ��̒����������A�W���j�[�E�z�b�W�X���o����������������������Ƃ����ꂵ���v���ƂƂ��ɁA���ӂ��Ă���B���܂͐_�Ɋ��ӂ��E�E�E�E�E�B�_��A�W���j�[�E�z�b�W�X�ɏj�����B�@����ӂ��Ǔ����ł���B�u�G�����g�����`�v�ɂ�90�l����~���[�W�V�����̉����v���o�b���o�ꂷ�邪�A�W���j�[�E�z�b�W�X�i1907�|70�j�̂悤�ɋ�̓I��7�Ȃ��̊y�Ȃ������ďq�����Ă���~���[�W�V�����͂��Ȃ��B����̓z�b�W�X���A�G�����g���ɂƂ��āA�����ɓ��ʂȑ��݂����������B�����͂��ׂđf���炵�����A�������ɋC�ɓ����Ă���̂́A�t���̂悤�ɉ��߂������u�f�C�E�h���[���v�ƏH��̂悤�ɑu�₩�ȁu�I�[���E�I�u�E�~�[�v�ł���B�z�b�W�X�̓G�����g���ɂƂ��Đ^�̕������̂��B
�@�Ƃ��낪�ł���B�z�b�W�X�̓G�����g�����Ԃ���������������B1951�N3���`1955�N8���̊��Ԃł���i���[�����X�E�u���E��(tb)�ƃ\�j�[�E�O���A(ds)���ꏏ�Ɏ��߂Ă���j�B���̏o�����͍J�ԁA�u�z�b�W�X�̗��v�ȂǂƂ����Ă��邪�A���Ƃ������ނ���A�����ȉ��y�I���R�ւ̈ӎv�A�����A���h����e���ւ̉��`�ɑ��Ď��R�ɉ��y����肽���Ƃ�������]���ł����������ʂ������A�Ǝv���B����͂܂��A�ނقǂ̍˔\�Ȃ瓖����O�̘b�ł͂���B�Ƃ͂����A�G�����g���ɂ̓V���b�N�������͂��B�y�c�̒��ŁA�z�b�W�X�قǗ]�l�ɂƂ��đウ����݂͂��Ȃ��Ǝv���邩�炾�B�����A�G�����g���͂����炭�A�S���̓��h������ɂ����ɐÂ��ɏ��đ���o�����ɈႢ�Ȃ��B�N�[�e�B�E�E�B���A���X�̏ꍇ�������ł������悤�ɁB������A�z�b�W�X�͋A���Ă����B�����̋��ꏊ�͂��������Ȃ��ƌ���āB����͔ނ̔މ�̉��t���ׂĂ݂�悭�킩��B�Ɨ���삵�����̃��R�[�f�B���O���s���Ă��邪�A�G�����g���y�c�̂��̂̕����i�i�ɂ����̂��B�Ⴆ�Ώ\���ԁu�f�C�E�h���[���v����Ƃ��Ă݂Ă��A�Ɨ�����̃A���o���uIn a mellow tones�v�i1954�^���j���^�̂��̂��A�o�߂��Ă���́uDuke Ellington Presents�E�E�E�v�i1956�j��uand his mother called him Bill�i�r���[�E�X�g���C�z�[���ɕ����j�v�i1967�j�̕������|�I�ɂ����B�C�����������̉����Ⴄ�B�G�����g���̑��݂������Ӗ��łْ̋����݁A�I�[�P�X�g���ŗL�̃T�E���h���\���Ɛ▭�ȐF�ʓI�Z�a���ʂ����̂��낤�B���ǃz�b�W�X�̓G�����g���̏��̓��Ŝf�r���Ă����ɉ߂��Ȃ��B�����ƎO���@�t�̊W�̂悤�ɁB
�@�G�����g���E�I�[�P�X�g�����uCONTROVERSIAL SUITE�v�����������̂�1951�N1��21���A�j���[���[�N�E���g���|���^���̌��ꂾ�����i���̉���RCA�̍�����LP�Œ������Ƃ��ł���B����͖���v���搶�j�B���̎��͂܂��z�b�W�X���ݒc���Ă����B������l�̃A���g�T�b�N�X�t�҂̓��b�Z���E�v���R�[�v�ł���B�ł́A���́uBEFORE MY TIME�v�������C�u�̃\�v���m�T�b�N�X�͒N���������̂��H �G�����g�����V�h�j�[�E�x�V�F��͂Ƃ��ď������i�Ǝv����j���̕����́A�펯�I�ɍl����z�b�W�X�ɐ�������͂��ł���B�Ƃ��낪�A����v���搶�̉�����ɂ́g�v���R�[�v�h�Ƃ���ł͂Ȃ����B���x�����x��������ׂ�B�z�b�W�X���A�v���R�[�v���B����搶����v���R�[�v�ɂ͂ǂ�ȍ���������̂��B
�@��1�͂Ō������悤�ɁA���b�Z���E�v���R�[�v���\�v���m�T�b�N�X�𐁂���̂Ȃ�A1970�N5��13���A�u�V�h�j�[�E�x�V�F�̏ё��v�̃X�^�W�I�E���R�[�f�B���O�ŃG�����g���͔ނ��N�p�����͂����B�������Ȃ������̂́A�v���R�[�v�̓\�v���m�𐁂��Ȃ����炾�B�Ȃ�A1951�N1��21���A���g���|���^���̌���ł́uCONTROVERSIAL SUITE�v�̏����ɂ�����uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���̓W���j�[�E�z�b�W�X�ȊO���肦�Ȃ��B �����āA1951�N12��11���A�uCONTROVERSIAL SUITE�v�̓X�^�W�I�^�����ꂽ�B���̎��ݒc����A���g�T�b�N�X�t�҂̓v���R�[�v�ƃE�B���[�E�X�~�X�ł���B�����A��l�Ƃ��\�v���m�T�b�N�X�͐����Ȃ��B�Ȃ�uBEFORE MY TIME�v�̐��ۗ������\�v���m�T�b�N�X�E�\���͈�̒N�ȂH ���܂��܃j���[���[�N�ɋ����킹���i�\��������j�V�h�j�[�E�x�V�F�Ȃ̂��B����Ƃ��A���̎��ޒc���Ă���W���j�[�E�z�b�W�X���Ăяo���Đ��������̂��H�G�����g���Ȃ炢������\���낤�B����Ƃ��A��͂�A���b�Z���E�v���R�[�v�����U�ɂ�����x�\�v���m�T�b�N�X����Ɏ���Ĉꐢ���̖����t���Ȃ��������̂��B��͓���ĂԁB�^���͂��������ǂ��ɂ���̂��낤���B
���Q�l������
�uA��Ԃōs�����`�f���[�N�E�G�����g�����`�v�i����N�v��A�����Ёj
LP�u�f���[�N�E�G�����g���F�j���[�I�����Y�g�ȁv�i����v������j
LP�u�f���[�N�E�G�����g��1951�`�A�b�g�E���g���|���^���E�I�y���n�E�X�v�i����v������j
2020.02.25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X6�`����̓V�h�j�[�E�x�V�F

1951�N12��11���B DUKE�͒�����NEW YORK 30�ԊX��COLUMBIA�̃X�^�W�I�ŁA���̓��ɏ��߂ă��R�[�f�B���O����uCONTROVERSIAL SUITE�v��PART�P�uBEFORE MY TIME�v�̃��n�[�T�������Ă����B�@���n����i�����ăX�^�W�I����o�ė���DUKE�̑O�ɁA�\�t�@�ɍ������ăE�B�X�L�[���r�߂Ă���BECHET�������B�@����͍��N�A�N�������X�ɒ��쎁���瑗���Ă����u����杁v�̈ꕔ�ł���B�����1951�N12���ABlue Note�̃��R�[�f�B���O�̂��߃j���[���[�N�ɑ؍݂��Ă���V�h�j�[�E�x�V�F����f���[�N�E�G�����g���ւ̓d�b�Ŏn�܂�B�J�Y�I�E�C�V�O������̉��y�Z�҂̑̂łȂ��Ȃ��Ɋy���߂��B�O����ɂ��Ă���A��́uCONTROVERSIL SUITE�v�̑�1�ȁuBEFORE MY TIME�v���X�g�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���̓V�h�j�[�E�x�V�F�ł���A�Ƃ������b�ł���B�u�Ȃ�Ɠ˔��q���Ȃ��v���b�鎄�Ɂu����͂����̓��Ă����ۂ��ł͂Ȃ��v�ƌ����ł͂Ȃ����B�����́A�ǂ��]��ł��ʔ����B����͂��̒�����������Ă݂悤�B
�uHi�I���Ă��ꂽ���B�v��DUKE�A�uGood morning�CDUKE�v BECHET���Ԃ��B
D�u�����n�[�T�������������B�����������H�v
B�u�����A�����Ă���B�Ȃ��Ȃ��ǂ�����Ȃ����B�A�^�}��BLUES���C�J���Ă邵�A����New Orleans Style�̂Ƃ�����J�b�R�ǂ��ȁB�v
D�u�������A���肪�Ƃ��B�ł��ȁA���̌オ�`���b�g�C�ɓ���Ȃ���B�v
B�u���̃T�b�N�X�̃\���̂Ƃ��납�H�v
D�u�����ȂB�������̓X�e�[�W�ł̏����ł�JOHNNY���\�v���m�Ő�������B�����hot��������B�v
B�u���m�͏o�čs�����܂�������Ȃ��`�B�v
D�u����A�����Ȃ�B�@�܂��A���̓��O������߂��ė���Ǝv���Ă���E�E�E�B�������I �ǂ����낤�B���O�A�`�������Ƃ�������Ƃ��됁���Ă���Ȃ����Ȃ��`�H�v
B�uNo way�I �������낤�H ���͍���Blue Note�Ń��R�[�f�B���O���邽�߂ɁA�z�炩��M�����Ɨ�������ė�������A�����Ń��R�[�f�B���O�Ȃ������Ƃ��o���������Ԃ��Ȃ����Ȃ�Ȃ��Ȃ����܂���I�v
D�uMmmm�D�������`�B���O������Ă����ƍō��ɃL�}�����Ȃ��`�B�@�Ȃ��A�������R�[�f�B���O���Ă����O��OK����܂ł̓����[�X���Ȃ����A�����[�X���鎞�����O�̖��O�͐�Ώo���Ȃ����牽�Ƃ�����Ă���Ȃ����Ȃ��`�B�v
B�u��`�D�D�D�B�܂��A���O�ɂ����܂Ō���ꂿ�Ⴄ�ƂȂ��B���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ��`�B�v
D�u�������I ����͂��肪�����I ���Ⴀ�A�������ނ�B�v
BECHET�͈��p�̃\�v���m�T�b�N�X�����o���A����U���āu�����n����ꂽ�݂������ȁB�v�ƂԂ₫�A����ł��C����蒼���A�E�H�[�~���O�A�b�v�����ăX�^�W�I�ɓ����čs�����B���R�[�f�B���O�́A�ܘ_�A�ꔭ�� OK�������B
 �@�����̃V�h�j�[�E�x�V�F�i1897�|1959�j���̌���1���̃��R�[�h�ł���B���N�O�A�����̈��݉�̐ȏ�A�u����ACD�Ƀ_�r���O���Ă���Ȃ����v�ƐΈ�搶����n���ꂽ�̂�Sidney Bechet �uConcert At The Brussels Fair,1958�v��10�DLP�������B�ӊO�Ɏv���āA�u�搶�̓W���Y���������ɂȂ�̂ł����v�Ɛu���Ɓu�������̂͂�������ˁv�ƌ���ꂽ�B�x�V�F�Ɋւ���m���́A�U�E�s�[�i�b�c�́u������Petite Fleur�v�̍�ҁA���炢�����Ȃ��������A�_�r���O���Ȃ��璮���Ƃ���͑f���炵�����̂������B���ł��A�x�V�F�̊ɋ}���݂ȃ\�v���m�T�b�N�X�̖��Z������u�X���j�[�E���o�[�v����A���B�b�N�E�f�B�b�P���\���̟��E�������E�ȃg�����{�[���ɂ��u�C���E�A�E�Z���`�����^���E���[�h�v���o�āA�o�b�N�E�N���C�g���̑u���ȃg�����y�b�g���S�L�Q���ȁu�I�[���E�I�u�E�~�[�v�Ɏ��闬��͊i�i�ɐS�n�悭�A�܂��A����قNJy�����S���a�ރA���o�����ő��ɂȂ��A�Ɗ��������̂��B
�@�����̃V�h�j�[�E�x�V�F�i1897�|1959�j���̌���1���̃��R�[�h�ł���B���N�O�A�����̈��݉�̐ȏ�A�u����ACD�Ƀ_�r���O���Ă���Ȃ����v�ƐΈ�搶����n���ꂽ�̂�Sidney Bechet �uConcert At The Brussels Fair,1958�v��10�DLP�������B�ӊO�Ɏv���āA�u�搶�̓W���Y���������ɂȂ�̂ł����v�Ɛu���Ɓu�������̂͂�������ˁv�ƌ���ꂽ�B�x�V�F�Ɋւ���m���́A�U�E�s�[�i�b�c�́u������Petite Fleur�v�̍�ҁA���炢�����Ȃ��������A�_�r���O���Ȃ��璮���Ƃ���͑f���炵�����̂������B���ł��A�x�V�F�̊ɋ}���݂ȃ\�v���m�T�b�N�X�̖��Z������u�X���j�[�E���o�[�v����A���B�b�N�E�f�B�b�P���\���̟��E�������E�ȃg�����{�[���ɂ��u�C���E�A�E�Z���`�����^���E���[�h�v���o�āA�o�b�N�E�N���C�g���̑u���ȃg�����y�b�g���S�L�Q���ȁu�I�[���E�I�u�E�~�[�v�Ɏ��闬��͊i�i�ɐS�n�悭�A�܂��A����قNJy�����S���a�ރA���o�����ő��ɂȂ��A�Ɗ��������̂��B�@����ȃV�h�j�[�E�x�V�F���v���o�����Ă��ꂽ�̂����쎁�́u����杁v�ł���B�m���ɁuBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\���́A�O��ł��L�����ʂ�A16���������A�Ȃ钴���e�������̃\���ł���B�����������A�p�[�\�l���ɂ̓x�V�F�̃N���W�b�g�͂Ȃ��B����ł��ނ́A�u���ꂪ�x�V�F�Ƃ����͓̂��Ă����ۂ��ł͂Ȃ������̔]���ł͕K�R�Ȃ̂ł��v�ƔM���B�ʂ����Ă��̃R�R���́H
�@���쎁�ɂ����b�Z���E�v���R�[�v�B������ɂ���(�H)�t�Ńq���g���E�W�F�t�@�[�\���B���̈Ⴂ�͘^�����ɂ����̂�����A�m�肳���Έ����������B�\�j�[����̉������Ȃ��̂Ō��߂�킯�ɂ͂����Ȃ����A���X�̏��琣����u1951�N12��11���^���v�̐M�ߐ��������Ǝv���邽�߁A�����͂ЂƂ܂���������c�����B
�@�T�b�N�X�������Ȃރ\�j�[�~���[�W�b�N�̊����́A�T�b�N�X�𐁂��l�ԂȂ�\�v���m�͂��₷���A������v���R�[�v�ł����������Ȃ��A�ƌ����B���쎁�́A���̃\�v���m�T�b�N�X�͌��O��ɏ�肭�A�ǂ��l���Ă��\�v���m���o���҂ł͂��肦�Ȃ��B�v���R�[�v���\�v���m�𐁂����Ƃ����L�^�͑��Ɍ�����Ȃ��̂�����A�v���R�[�v���ɂ͏��������˂�A�ƌ����B
�@����Ȑ܁A1�����{�̂�����A���쎁����lj��̃��[�����͂��B
���A�f�X�N���[�N�����Ȃ���uJAZZ FROM NEW ORLEANS Vol.4�v�����Ă��܂����B ���ɂȎ��� Tr.13�́uI KNOW THAT YOU KNOW�v���Ă݂Ă��������B �㔼�ł��B �ȑO�͋C�ɂ��Ă��܂���ł������A�����A���́u�h�L�b�v�Ƃ��܂����B
 �@�Ȃɂ��u�h�L�b�v�Ȃ̂��H�@�����m���߂邱�Ƃɂ���B�uJAZZ FROM NEW ORLEANS Vol.4�v�͌Ñ�RCA���R�[�h������CD�ŁA�����O���쎁���特���������Ă�����Ă���B������Ȃ������̂Ő쓈��������B
�@�Ȃɂ��u�h�L�b�v�Ȃ̂��H�@�����m���߂邱�Ƃɂ���B�uJAZZ FROM NEW ORLEANS Vol.4�v�͌Ñ�RCA���R�[�h������CD�ŁA�����O���쎁���特���������Ă�����Ă���B������Ȃ������̂Ő쓈��������B�@�uI KNOW THAT YOU KNOW�v�̓V�h�j�[�E�x�V�F�E�A���h�E�q�Y�E�j���[�I�����Y�E�t�B�[�g�E�H�[�}�[�Y�Ƃ������d�t�c�̉��t�ł���B�f�B�L�V�[�����h���̍��t����A�e�[���Q�[�g�E�X�^�C����tb�`�X�g���C�h���s�A�m���o�āA�{�e���|�ɕς�����G���f�B���O���x�V�F���\�v���m�T�b�N�X���D�u�Ƌ삯������B���̊�32����43�b�B�uBEFORE MY TIME�v�̃\�v���m�T�b�N�X�E�\����32����48�b�B�^�C�����t�@���悭���Ă���B�y�ȍ\�����y�z�̓W�J���y��̎g������X�^�C�������Ȃ莗�ʂ��Ă���B�Ȃ�قǁA���ꂪ�u�h�L�b�v�̐��̂��A�ƍ��_����B
�@�G�����g���́uBEFORE MY TIME�v�������ɂ������āA���́uI KNOW THAT YOU KNOW�v���ӎ������\���͑傢�ɂ���A�Ǝv���Ă���i���݂ɂ��̃��R�[�f�B���O��1941�N�ŁA�uBEFORE MY TIME�v�ɐ旧����10�N�O�ł���j�B�G�����g���́A�����m���Ă����\���͂���Ǝv�����A�Ȃ�A�uBEFORE MY TIME�v�̃\�����x�V�F�ɂ���Ăق����A�Ɗ���Ă��Ă����������͂Ȃ��H
�@���҂���ׂ�قǂɁA�u�wBEFORE MY TIME�x�ɂ����āA����قǂ̃\�v���m�T�b�N�X�𐁂���̂̓V�h�j�[�E�x�V�F����q�̃W���j�[�E�z�b�W�X�����l�����Ȃ��v�Ƃ��钆������^������ттĂ���B
�@�A���o���uJAZZ FROM NEWORLEANS Vol.4�v�̃��C�i�[�m�[�c�ɂ́A����ȋL�q������B���҂̓W���Y�]�_�̈���̌��ЁE��a�����ł���B
�����̃W���Y�E�V�[���ł����A�\�v���m�T�b�N�X�͂���������O�ɗp�����Ă��邪�A1920�㏉������50�N�㔼�܂ł͂�������l�̃v���C���[�̂��߂̃W���Y�̊y��ɉ߂��Ȃ������B���̐l�����A�W���Y�E�ŏ��̓V�ߖ��D�̃C���v�����@�C�U�[�Ə̂��Ă��悢�����V�h�j�[�E�x�V�F�ł���B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�x�V�F�ɂ���ăW���Y�y��ƂȂ����\�v���m�T�b�N�X��50�N�㏉�߂܂Ŕނ̓Ƃ蕑��Ƃ����Ă悩�����i�ꎞ�W���j�[�E�z�b�W�X���x�V�F�ɉe������ă\�v���m�T�b�N�X�𐁂��Ă������Ƃ��������j�B�@�����œǂݎ��ׂ��́A�uBEFORE MY TIME�v�^������1951�N������A�W���Y�E�Ń\�v���m�T�b�N�X���܂Ƃ��ɉ��t���Ă���̂̓V�h�j�[�E�x�V�F�B��l�ł���A�����Ă�����l�Ƃ����Ȃ�ނɋ��������W���j�[�E�z�b�W�X�܂ŁA�Ƃ������Ƃł���B����͌������Ȃ��L�q�ł���B�ł́A�G�����g���`�x�V�F�`�z�b�W�X�̊W�����u�f���[�N�E�G�����g�����`�v������p���Ă݂悤�B
�V�h�j�[�E�x�V�F�́A�^�Ɉ̑�ȃI���W�i���e�B���������~���[�W�V�����̈�l�������B1921�N����ނ̉��t�����߂Ē��������A����͎��ɂ͑S���V�����T�E���h�ł���R���Z�v�g�������B�ނƂ�1926�N�̉Ċ��A�������ƈꏏ�ɂ��悤�ɂȂ����B�x�V�F�͂ƂĂ��Ќ�I�Ȃ�Ă������l�Ԃł͂Ȃ��������A����ł��W���j�[�E�z�b�W�X���茳�ɒu���Ĕނɂ��ׂĂ��������B�W���j�[�̃T�L�\�t�H���ւ̃A�v���[�`�̓x�V�F�Ɠ�����������������h�������������Ă����ނ���z�����邱�Ƃ͓�����Ƃł͂Ȃ������B�@�����A�x�V�F�͂��̐̃G�����g���̃I�[�P�X�g���ɍݐЂ��A��Ɋy�c�̎���ƂȂ�W���j�[�E�z�b�W�X�Ƀ\�v���m�T�b�N�X�̎�قǂ������Ă����̂ł���B
�@�G�����g�����uBEFORE MY TIME�v��^������1951�N12��11���̃j���[���[�N�B�ʂ����Ă����ɃV�h�j�[�E�x�V�F���Q�������\���͂���̂��낤���H
�@�x�V�F�A���̎����̏Z���̓p���B�p��������Α吼�m��n���ăA�����J�ɂ���Ă���B���̔N�̏H�A�x�V�F�̓j���[���[�N�ɂ����B1951�N11��5���A�u���[�m�[�g��9�Ȃ̃��R�[�f�B���O���s���Ă���̂ł���i�����̓A���o���uTHE FABULOUS SIDNEY BECHET�v�Ɏ��^����Ă���j�B�����ɂ͑��ς�炸�Ⴆ���\�v���m�T�b�N�X������x�V�F������B�Ƃ͂����A12��11���܂Ńj���[���[�N�ɂ����ۏ͂Ȃ��B�����A�v���Ԃ�̃j���[���[�N�A�؍݂�1����قǐL�����Ƃ��Ă����������͂Ȃ��B
�@����ɂ�����B1951�N12��11���ɘ^�����ꂽ�uCONTROVERSIAL SUITE�v�͒����ɂ킽�肨����Ԃɂ���A���̖ڂ������̂́A1956�N�����̃A���o���uHi-Fi UPTOWN�v�i�ăR�����r�ACL830�j���������ƁB���̎����́A������߂��Ǝv���A�x�V�F�̋q�������郌�R�[�h��ЊԂ̖@���葱���Ɏ��Ԃ�������������A�ƍl�����Ȃ����Ȃ��B
�@���쎁�́u����杁v�x�V�F���̍����͒����Ə؋��ɂ����̂��B������A�Ⴆ�G�����g�j�A���̏،����A�]���̏؋����o�Ă��Ȃ�����ؖ����邱�Ƃ͕s�\���낤�B�uBEFORE MY TIME�v�̃p�[�\�l���ɂ̓��b�Z���E�v���R�[�v�ƃE�B���[�E�X�~�X�̖��͂����Ă��A�V�h�j�[�E�x�V�F�̖��͂Ȃ��B���ʂɍl������肦�Ȃ��̂ł���B�����������A�x�V�F�ƃG�����g���Ƃ̊W���A�x�V�F���^�����Ƀj���[���[�N�ɂ��������̉\���A���̍��W���Y�E�Ń\�v���m�𐁂��Ă����̂̓x�V�F�B��l�Ƃ������Ђ̌����A�uCONTROVERSIAL SUITE�v�̔�����5�N�̒�����v�������ƁA�����ĉ��������̈����̃\�v���m�E�v���C�A�Ȃǂ��l�����킹��ƁA���̃\�v���m�T�b�N�X�E�\������Ƀx�V�F�ł͂Ȃ��A�Ƃ͌�����Ȃ��I�H�E�E�E�E�E����ȓ˔��q���Ȃ��X�g�[���[�ɖ���y����̂��y�����炸��A�Ǝv���Ă���̂ł���B
���Q�l������
�uA��Ԃōs�����`�f���[�N�E�G�����g�����`�v�i����N�v��A�����Ёj
�uJAZZ FROM NEW ORLEANS Vol.4�vCD�i���C�i�[�m�[�c�F��a���j
2020.01.25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X5
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�삯�o�����D�Ƃ́uELLINGTON UPTOWN�v����
 �@�f���[�N�E�G�����g���i1899-1974�j�̂��Ƃ́A�قƂ�lj����m��Ȃ������B626�Ƃ��������ɏ���Ɉ��ʂ������āA���̃V���[�Y���n�߂�܂ł́E�E�E�E�E�B�u�W���Y�^�N���֘A���̒T���v�ȂǂƂ����傻�ꂽ����������Ăǂ��W�J�������̂��H�Ǝv�Ă��Ă������ɋ~���̎�������L�ׂĂ��ꂽ�̂́A�䂪JAZZ�̎tBrownie �쓈���������B�ނ������Ă��ꂽ���X�gB�fs List�Ƀf���[�N�E�G�����g���́u����݊���l�`�g�ȁv�������āA����ɂ�������Ƃ܂����i�N�����m2019.8.16�j�B���ꂩ��Ƃ������́A�䂪���y�����̓��[�c�@���g�̗̈�ɃG�����g�����E�э��B
�@�f���[�N�E�G�����g���i1899-1974�j�̂��Ƃ́A�قƂ�lj����m��Ȃ������B626�Ƃ��������ɏ���Ɉ��ʂ������āA���̃V���[�Y���n�߂�܂ł́E�E�E�E�E�B�u�W���Y�^�N���֘A���̒T���v�ȂǂƂ����傻�ꂽ����������Ăǂ��W�J�������̂��H�Ǝv�Ă��Ă������ɋ~���̎�������L�ׂĂ��ꂽ�̂́A�䂪JAZZ�̎tBrownie �쓈���������B�ނ������Ă��ꂽ���X�gB�fs List�Ƀf���[�N�E�G�����g���́u����݊���l�`�g�ȁv�������āA����ɂ�������Ƃ܂����i�N�����m2019.8.16�j�B���ꂩ��Ƃ������́A�䂪���y�����̓��[�c�@���g�̗̈�ɃG�����g�����E�э��B�@��������A���Ă̂�����A��Ёi�r�N�^�[RCA�j����̈��݉�����āA�����ŃG�����g���b�Ő���オ�����̂����쎁�B�����āA���̎����߂Ēm�����̂����A�ނ͂��̉�Ђ�I�̂̓G�����g�������邩��A�ƌ����Ă͂���Ȃ��G�����g����D���l�Ԃ������B
�@�ȗ��AJAZZ�Ɋւ��āA�I�[���}�C�e�B��Brownie�쓈���ƃG�����g���E�}�j�A�̒��쎁�Ƃ��������������t�����̂ł���B
�@�쓈�����Ă��ꂽ�A���o���uHi-Fi ELLINGTON UPTOWN�{�P�v�̉p������ɁA�G�����g���ƃN���V�b�N���y�̂Ȃ���Ɋւ��鋻���[���L�q������B
�@�G�����g���E�I�[�P�X�g���͑z���͂ɕx�|�s�����[���y�̃A�C�f�B�A���N���V�b�N���y�̓`���ł܂Ƃߏグ��Ƃ����A�قƂ�njǗ������̒n�����ɗ����ĉ��t���Ă���B�G�����g���̃A�����W�̐i���ɂ����āA���̑g���������ɃG�L�T�C�e�B���O�Ȃ��̂ł��낤�ƁA�����ɂ͏�ɃN���V�b�N���y�̎��Ⴊ�������B
�@�|�s�����[���y�̂��悻���ׂĂ̊v�V�́A�ߑ�N���V�b�N�̍�ȉƂ̉e�����łȂ���Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�Ƃ͂����A�����̎Ⴂ�v�V��`�҂����̍��V�^���͂������ĐV�������Ƒn�I�ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����̓f���[�N�E�G�����g�����͂邩�ȑO������H���Ă��邱�Ƃ����炾�B�ނ͍D���ȍ�ȉƂƂ��āA�K�[�V���C���A�X�g�����B���X�L�[�A�h�r���b�V�[�A���X�s�[�M��̖��O�������Ă���B�G�����g���̍�i�ɂ́A�����̍�ȉƂ̉e�����@���Ɍ��Ď���̂ł���B
 �@���̎a�V�œƑn�I�ȃG�����g���E�T�E���h���N���V�b�N�̉e�������ɂ͍l�����Ȃ��A�Ƃ������̕��͎͂��ɋ����[���B�N���V�b�N�l�Ԃ��������鎄���A�G�����g���̉��y�ɖ�����ꂽ�̂͌����ċ��R�ł͂Ȃ������I�H�@�Ȃ�A�ނ̉��y�̒��ɃN���V�b�N�̋Z�@��˂��~�߂Ă�낤�A�ƈ�U�͈ӋC����ł݂����E�E�E�E�E��߂��B�G�����g���̉��y�͍L��ɂ��Đ[���B�r�M�i�[�̎�ɂ�����㕨�ł͂Ȃ��B�����̂Ƃ���́A�N���V�b�N���y�Ƃ̊֘A�������_���Ɋ��m���邠����̃��x���ŊÂ悤�E�E�E�E�E����ł��A���m�ł����̂͂������̈ꌏ�A�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{1�v�̒��̈�Ȃ����B�Ȃ�r�M�i�[�炵���A����́A���̃A���o����_�ɍi��A�G�����������߂悤�B
�@���̎a�V�œƑn�I�ȃG�����g���E�T�E���h���N���V�b�N�̉e�������ɂ͍l�����Ȃ��A�Ƃ������̕��͎͂��ɋ����[���B�N���V�b�N�l�Ԃ��������鎄���A�G�����g���̉��y�ɖ�����ꂽ�̂͌����ċ��R�ł͂Ȃ������I�H�@�Ȃ�A�ނ̉��y�̒��ɃN���V�b�N�̋Z�@��˂��~�߂Ă�낤�A�ƈ�U�͈ӋC����ł݂����E�E�E�E�E��߂��B�G�����g���̉��y�͍L��ɂ��Đ[���B�r�M�i�[�̎�ɂ�����㕨�ł͂Ȃ��B�����̂Ƃ���́A�N���V�b�N���y�Ƃ̊֘A�������_���Ɋ��m���邠����̃��x���ŊÂ悤�E�E�E�E�E����ł��A���m�ł����̂͂������̈ꌏ�A�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{1�v�̒��̈�Ȃ����B�Ȃ�r�M�i�[�炵���A����́A���̃A���o����_�ɍi��A�G�����������߂悤�B�i�P�j�u�p�[�f�B�h�v�ɔF�߂���N���V�b�N�̍���
�@�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�v�Ɂu�p�[�f�B�h�vPERDIDO�Ƃ����Ȃ�����B��Ȃ̓G�����g���y�c�̃g�����{�[���t�҂̃t�@���E�e�B�]�[���B�u�L�������@���v�̍�Ȏ҂Ƃ��Ă��L�����B8��28�b�̊y�Ȓ��A�N���[�N�E�e���[�̃g�����y�b�g�E�\�������ɁA3�̃N���V�b�N�̃����f�B�[������o���B
1:59�Ńh�r���b�V�[�́u���v
2:04�Ń{���f�B���́u�_�b�^���l�̗x��v
7:17�ŃK�[�V���C���́u�p���̃A�����J�l�v
�@�h�r���b�V�[�ƃ{���f�B���̃����f�B�[�͒f�ЂȂ̂ŁA�u���܂��܁v�Ǝv�������A�����Ȃ��t�҂����t�����A���N1952�N3��25���̃V�A�g���E���C�u�ł��A���������f�B�[���ނ���N���Ɋm�F�ł���B�Ƃɂ����A�`���̃��C�i�[�m�[�c�i���ҕs���j�ɋL���ꂽ4�l�̍�ȉƂ̓�2�l�̍��Ղ�������ꂽ�̂ł���B����̓N���[�N�E�e���[�̃\�������Ȃ̂Ŕނ̚n�D�Ƃ��l�����邪�A�G�����g���ɂ́u���̊y��̓I�[�P�X�g�����v�Ȃ閼��������̂�����A�G�����g���̚n�D�ł�����킯���B���_����́A�G�����g�����y�̃N���V�b�N�Ƃ̖{���I�֘A�Ƃ͂قlj������̂����A���̈�[�ł����m�ł����͍̂����̃G�r�f���X�ɂ͂Ȃ邾�낤�B
�i�Q�j�uBEFORE MY TIME�v�ɂ������䏊��l�̐H���Ⴂ
�@�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�v�ɁuTHE CONTROVERSIAL SUITE�v�Ƃ����Ȃ�����B��1�ȁuBEFORE MY TIME�v�A��2�ȁuLATER�v���琬��g�ȁB���݂�controversial�Ƃ́u�_���I�ȁv�Ƃ����Ӗ��ł���B��ӂ͕ʂɂ��āA��1�Ȃ͑O����̃W���Y�ւ̃I�}�[�W���Ƃ��ăf�B�L�V�[�����h�E�W���Y�̃X�^�C���ŁA��2�Ȃ̓R���e���|�����[�ȃe�C�X�g�ō���Ă���B
�@�uBEFORE MY TIME�v�Ƀ\�v���m�E�T�b�N�X�̃\��������B����͋Ȃ̏I��4��56�b����32���߂ɂ킽���đt�����16���������A�Ȃ钴���e�������̃\���ŁA�������L����CD�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{1�v�iSony Music�j�̐��쏹�v�搶�̉���ɂ́A�t�҂̓��b�Z���E�v���R�[�v�Ƃ���B�Ƃ��낪�A���쎁���L��LP�u�G�����g���̐_��(2)�`ELLINGTON UPTOWN�v(���{�R�����r�A)����v���搶�̉���ł́A�i�H�j�t�Ƃ͂����q���g���E�W�F�t�@�[�\���ƂȂ��Ă���B�Ȃ�ƁA���ꉹ���ő�䏊��l�̐H���Ⴂ�I ��̂���͂ǂ��������ƁH �Ⴆ���ׂȂ��Ƃł��[������܂ŒNj�����̂��u�N�����m�v���_�ł���B
�@�G�����g���̉��y�́A��ނȂ������̊C���X�̃\���X�g�����݂ɉj����鑊��̎Y���ł���B�G�����g���E�I�[�P�X�g���������o���B�ꖳ��̐F�ʊ��́A�ނ̑S�̂ƌ�▭�ȃo�����X�œ��������z�����Z�ʂɕ����B�G�����g�����u���̊y��̓I�[�P�X�g�����v�ƌ����̂͂����������Ƃ��낤�B������A�\���݂̍���͑厖�Ȃ̂ł���B�����Ă�A���Ă����b�ɂȂ�����䏊������́u�\���Ɋւ��錩���̑���v�ł���B���N���N���Ȃ����R���Ȃ��B�ł́A������̃��C�i�[�m�[�c���猟���X�^�[�g���悤�B
�����쏹�v���b�Z���E�v���R�[�v��
 �u���̋Ȃ́A��1���w�r�t�H�A�E�}�C�E�^�C���x�Ƒ�2���w���C�^�[�x���琬��f���[�N�̖�S��ł���B1���́A�^�C�g���ʂ�A�f���[�N�������̉��y���`������܂ł̉ߋ��̗��j�̏��X�̃T�E���h��Ԃ��Ă���B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E���b�Z���E�v���R�[�v��ss�ŁA�A�b�v�E�e���|�ɏ����2�r�[�g�̏���\�����A�ȑf�ȑS���t�̃X�E�B���O�ŁA���߂�����B�v
�u���̋Ȃ́A��1���w�r�t�H�A�E�}�C�E�^�C���x�Ƒ�2���w���C�^�[�x���琬��f���[�N�̖�S��ł���B1���́A�^�C�g���ʂ�A�f���[�N�������̉��y���`������܂ł̉ߋ��̗��j�̏��X�̃T�E���h��Ԃ��Ă���B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E���b�Z���E�v���R�[�v��ss�ŁA�A�b�v�E�e���|�ɏ����2�r�[�g�̏���\�����A�ȑf�ȑS���t�̃X�E�B���O�ŁA���߂�����B�v�^�����F1951.12.11
���[�h�̃p�[�\�l���F�W�~�[�E�n�~���g��(cl,ts)�A�E�B���[�E�X�~�X(as)�A���b�Z���E�v���R�[�v(as,cl)�A�|�[���E�S���U�����F�X(ts)�A�n���[�E�J�[�l�C(bs)
����搶�́A��L�p�[�\�l������v���R�[�v�Ƃ����Bss�i�\�v���m�E�T�b�N�X�j�̃N���W�b�g������Ό��܂�Ȃ̂��낤���A�Ȃ����ߐ搶�̌o���l����v���R�[�v�Ɗ���o�����̂��낤�B
������v���q���g���E�W�F�t�@�[�\����
 �u�w�R���g�����@�[�V�����g�ȁx�́A���̃��R�[�f�B���O�̔N�A1952�N�̃G�����g���̍�ŁA�I���W�i���Ղ̎��́gTone Parallel to Harlem�h�ɑ����ē�����Ă���V��̏��g�Ȃł��邪��ӂ́u�_���Ƃ̑g�ȁv�Ƃł������ׂ����B���Ղ̃��C�i�[�m�[�g���Ȃ��̂ł��̋ȂɊւ��ĉ��̉�������Ă��Ȃ����A�����Ă݂�ƑO���͏����̃W���Y�̌`���A�����f�B�[�A�n�[���j�[�ɑ���l�������ނƂ������́A�㔼�͌�̎���i���݁j�̃W���Y�Ƃ������Ƃł��낤�B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�e�C���Q�C�g�E�X�^�C����tb���o�Ă��邵�N�C�b�N�E�e���|�̃\�v���m�E�T�b�N�X�E�\���i�W�F�t�@�[�\���H�j���y�����B�v
�u�w�R���g�����@�[�V�����g�ȁx�́A���̃��R�[�f�B���O�̔N�A1952�N�̃G�����g���̍�ŁA�I���W�i���Ղ̎��́gTone Parallel to Harlem�h�ɑ����ē�����Ă���V��̏��g�Ȃł��邪��ӂ́u�_���Ƃ̑g�ȁv�Ƃł������ׂ����B���Ղ̃��C�i�[�m�[�g���Ȃ��̂ł��̋ȂɊւ��ĉ��̉�������Ă��Ȃ����A�����Ă݂�ƑO���͏����̃W���Y�̌`���A�����f�B�[�A�n�[���j�[�ɑ���l�������ނƂ������́A�㔼�͌�̎���i���݁j�̃W���Y�Ƃ������Ƃł��낤�B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�e�C���Q�C�g�E�X�^�C����tb���o�Ă��邵�N�C�b�N�E�e���|�̃\�v���m�E�T�b�N�X�E�\���i�W�F�t�@�[�\���H�j���y�����B�v�^�����F1952.8.10
���[�h�̃p�[�\�l���F�W�~�[�E�n�~���g��(cl)�A�q���g���E�W�F�t�@�[�\��(as)�A���b�Z���E�v���R�[�v(as)�A�|�[���E�S���U�����F�X(ts)�A�n���[�E�J�[�l�C(bs)
�@����搶�́A��L�p�[�\�l������q���g���E�W�F�t�@�[�\���H�Ƃ����B���ڂ��ׂ��́A���Ղ̃��C�i�[�m�[�g���Ȃ����ƁA��[�H]��t�������Ƃ��B
�@������̌�����������̂́A���R�[�h��Ђ������������Ƀ\���t�҂̕\�����Ȃ��������炾�낤�B���{�̃G�����g���E�t�@���́u�\�����N���v���d�����邩��A�Ȃ��ꍇ�͑S�p�[�\�l���̒�����A�����肪�����t���邵���Ȃ��B
�@��̐��Ō���I�ɈႤ�̂͘^�����ł���B�������1951.12.11�ɂ́A�p�[�\�l���ɃW�F�t�@�[�\���̖����Ȃ��B�������1952.8.10�ɂ́A�W�F�t�@�[�\��������B����̓q���g���E�W�F�t�@�[�\�����E�B���[�E�X�~�X�̌㊘�Ƃ���1952�N3���ȍ~�ɉ����������炾�B�o���ɋ��ʂ���̂̓��b�Z���E�v���R�[�v�ł���B���̃��[�h�t�҂͂�������l���ɓ���Ă��Ȃ��̂ŁA��������ɏ]���B���ƁA����搶�́g1952�N�̃G�����g���̍�h��1951�N�̊ԈႢ�ł���B
�@�܂����肷�ׂ��͘^�����ł���B����͂��̑��̓Y�t�����̐��x���猩�Ă������1951.12.11�����������ł���BBrownie�쓈�����u���ؗ͂ɂ����Ă͐���搶�̕����M���ł���Ǝv���v�ƌ����B�����A����͐��m���������߁A���݁A��Ђ̌�y��Sony Music�̃N��&�W���Y�E�Z�N�V�����ɂ�������ɒ������˗����Ă���B
�@���ɒ��ڂ��ׂ��́A����搶���A�p�[�\�l���Ƀv���R�[�v�̖�������̂ɃW�F�t�@�[�\��(�H)�Ƃ������Ƃ��B�쓈���́u����搶�͘_���I�ɞB���ȕ����͂�����̂̊����͑��d���ׂ����v�ƌ����B�搶�͊��o�I�Ƀv���R�[�v�Ƃ͎v���Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@�����͂Ƃ��ɘ_�����B�N���V�b�N�ɂ�����ȗႪ����B���[�c�@���g�̃z�������t�ȑ�3�Ԃ͂���1783�N�i27�j�̍�ȂƂ���Ă����B������t�����X�̊w�҃h�E�T�����t�H�A�́u�o���h�����炢���āA����ȎႢ����̍�i�ł͂Ȃ��v�Ɗm�M����1788�N�Ȍ�̍�i�ł���Ə������B��N����͗������̂����A�|�p�T���ɂ����Ċ��������o�͑�Ȃ̂ł���B
�@�Ƃ������ƂŁA���͖���搶�̊��������o���y���ł��Ȃ��B�v���R�[�v�Ƃ��Ȃ��������Ƃ��ǂ����Ă�����������B�����搶����������������u�Ȃ��A�v���R�[�v�Ƃ͎v���Ȃ������̂��v���m���߂邱�Ƃ��ł����̂ɁA�Ɛ^�Ɏc�O�Ɏv���̂ł���B����A����搶�͌�N96�ł������ł��邩�炵�āA���̌��ɂ��Ă��q�˂������Ǝv���Ă���B�_�|�͂������uBEFORE MY LIFE�̃\�v���m�E�T�b�N�X�E�\�������b�Z���E�v���R�[�v�Ƃ��������͉����v�ł���B
�@��䏊��l�̐H���Ⴂ�Ɋւ���A�u�^�����̓���v�Ɓu����搶�����v����������̂́A�����ɂ��ƁA2���ȍ~�Ƃ̂��Ƃł���B�{���͂����ʼn��߂Ę�ɍڂ�����肾���A�Ō�ɁA���쎁�ƈӌ������������e�ɂ��ď����G��Ă��������B
�@���쎁�̌����̓��j�[�N�ŁA�u���̃\�v���m�E�T�b�N�X�E�\���̓V�h�j�[�E�x�V�G���W���j�[�E�z�b�W�X�ȊO�ɍl�����Ȃ��v�Ƃ����̂ł���B�\�v���m�E�T�b�N�X�̐��I���݂ɂ��Ė���̃x�V�G�́A�z�b�W�X���������Ď����̋Z�@���ׂĂ��z�b�W�X�ɓ`�������Ƃ����Ă���B���̃\�����x�V�G�Ƃ����͓̂˔��q���Ȃ������邪�A�z�b�W�X�̉\���͂���̂��낤���B����́A���̋����[�����ɑ��Ĉ��̌�����������Ǝv���B
���Q�l������
CD�uHI-FI ELLINGTON UPTOWN�{�P�v�iSony Music�j���쏹�v���
LP�u�G�����g���̐_��(2)�`ELLINGTON UPTOWN�v�i���{�R�����r�A�j����v�����
�uA��Ԃōs�����`�f���[�N�E�G�����g�����`�v�i����N�v��A�����Ёj
�u�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv�i�Έ�G���A�w��M���Ɂj
2019.12.15 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X4
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�K�[�V���C���u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\��
 �@12��1���A�a�J�`���z�[���AMondaynight Jazz Orchesutra�i������MJO�j��46���������ɍs���Ă����BMJO��1974�N�n�݂̃A�}�`���A�E�W���Y�E�o���h�B���́u���{�ꈤ�z�̂����o���h�v�B�����o�[�̈�l�����Ẳ�Ђ̗��F�E���ѐ��Ǝ��Ƃ�����������2004�N�ȗ����N���������ʂ��Ă���B���т���͑n�ݎ҂̈�l�Ō��݃o���h�E���[�_�[���g�����{�[���t�҂Ƃ��Ċ������ł���B�N���Ƃɑ��������e�[�}��݂��Ă��āA�Ⴆ�A2011�N�́A�����{��k�Ђ���̕���������āu���E�͓��̏o��҂��Ă���v�B���N��2020�����I�����s�b�N�Ɉ���ŁuFive Colors in Jazz�v�B�ܗփJ���[���݂̋Ȃ��W�߂��\���������B
�@12��1���A�a�J�`���z�[���AMondaynight Jazz Orchesutra�i������MJO�j��46���������ɍs���Ă����BMJO��1974�N�n�݂̃A�}�`���A�E�W���Y�E�o���h�B���́u���{�ꈤ�z�̂����o���h�v�B�����o�[�̈�l�����Ẳ�Ђ̗��F�E���ѐ��Ǝ��Ƃ�����������2004�N�ȗ����N���������ʂ��Ă���B���т���͑n�ݎ҂̈�l�Ō��݃o���h�E���[�_�[���g�����{�[���t�҂Ƃ��Ċ������ł���B�N���Ƃɑ��������e�[�}��݂��Ă��āA�Ⴆ�A2011�N�́A�����{��k�Ђ���̕���������āu���E�͓��̏o��҂��Ă���v�B���N��2020�����I�����s�b�N�Ɉ���ŁuFive Colors in Jazz�v�B�ܗփJ���[���݂̋Ȃ��W�߂��\���������B�@����A��Ԃ̒��ڂ͏��т���̃g�����{�[���E�\���B10���N�O�傫�Ȏ�p���s���Ĉȗ��\�����Ƃ��Ă��Ȃ���������A���ɂƂ��Ă͏����m�ƂȂ�B���ڂ�1948�N�̃X�}�b�V���E�q�b�g��u���[�E���f�B�ɍg���o���B���[�����X�E�u���E�����\�����Ƃ�f���[�N�E�G�����g���y�c�łł̉��t���B�g�����{�[���̃\���͋ȓ�����B���т���͎��Ɍ����ɐ��������B�����E�Ȃ��ƃu���E���畉���ł���B�Ƃ��낪�T�b�N�X�E�\�������G���f�B���O��2���߂��u������Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ����̓g�[�����X�E�u���E���ɂȂ��Ă��܂���(��)�B�ł�����͂����h�B�܂��́A���S�����I���f�g�E�I�I
�@MJO�̊y���݂̈�͖���̃v���̃Q�X�g�B����̓��B�u���t�H���t�҂̑�ԑP�V����B���₩�ŃX�}�[�g�Ȗ��肾�B���{�Ɉ��Ƃ����^���ԂȌ��Ղ��������鋿���ɉ��͖����̃��[�h�B���ɃR���{�ɂ��}���V�[�j�̖��ȁ�Ђ܂�� �͔�ѐ�̔������������B�A���R�[���́�z���C�g�E�N���X�}�X�B�a�J�̖�A�C���~�l�[�V�����̒����N���X�}�X�E���[�h�ɐZ��ƘH�ɂ��B�䂪�Ƃ̔N�Ɉ�x�̐��W���Y�̌��͂������ďI������B
���U�E�T�[�h�E�X�g���[���E�~���[�W�b�N��
 �@���B�u���t�H���Ƃ����~���g�E�W���N�\���B�ŏ��ɔނ̃v���C�ɏo������̂́uMJQ�ƌ����I��i�v�Ƃ���LP���R�[�h�B�w����1961�N9��17��������A���Z��N���B�䂪�l�����̃W���Y�E���R�[�h�����ꂾ�����B�����̗F�l���A�R���g���[���u���b�V���E���C�t�v��A�[�g�E�u���C�L�[���W���Y�E���b�Z���W���[�Y�ɖ����ɂȂ��Ă������Ƃ��l����A����͂��Ȃ胆�j�[�N�������Ǝv���B�܂��A���̚n�D���N���V�b�N���������炱��Ȓ��ԓI���R�[�h�Ɏ肪�L�т��Ƃ������Ƃ��B
�@���B�u���t�H���Ƃ����~���g�E�W���N�\���B�ŏ��ɔނ̃v���C�ɏo������̂́uMJQ�ƌ����I��i�v�Ƃ���LP���R�[�h�B�w����1961�N9��17��������A���Z��N���B�䂪�l�����̃W���Y�E���R�[�h�����ꂾ�����B�����̗F�l���A�R���g���[���u���b�V���E���C�t�v��A�[�g�E�u���C�L�[���W���Y�E���b�Z���W���[�Y�ɖ����ɂȂ��Ă������Ƃ��l����A����͂��Ȃ胆�j�[�N�������Ǝv���B�܂��A���̚n�D���N���V�b�N���������炱��Ȓ��ԓI���R�[�h�Ɏ肪�L�т��Ƃ������Ƃ��B�@���̃��R�[�h��1960�N��ɑ䓪�����u�U�E�T�[�h�E�X�g���[���E�~���[�W�b�N�v���[�������g�̈�B����v���搶�̃��C�i�[�m�[�c�ɂ́A�uMJQ�̎�Ɏ҃W�����E���C�X��MJQ�ƃI�[�P�X�g���̋����ɂ���S�I��LP��������v�Ƃ���B�ȃ^�C�g���ɂ́u�f�B���F���e�B�����g�v�A�u�p�b�T�J���A�v�A�u�R���`�F���g�v�A�u�L�������v�ȂǃN���V�b�N�I�l���������ԁB�T�N���ƌ����A�N���V�b�N�̗l���̒��ɃW���Y�̗v�f�ƌ��㉹�y�̃e�C�X�g��Z���������V�����̉��y�Ƃ������Ƃ��납�B
�@���㉹�y���Ƃ����Ă�����قǐ���������͂Ȃ��}�C���X�ɂ�����M���E�G���@���X�̋����Ɏ��Ă���B����ȃI�[�P�X�g���̋����̒����~���g�E�W���N�\���̃��@�C�u���X�C���M�[�ɓ˂��i�ށB�m���ɂ��̑u�����͐S�n�悢�B�����A����̓~���g�E�W���N�\���̃��@�C�u������ۂɎc��Ȃ��B���̃I�[�P�X�g���v��̂��Ȃ��H�Ƃ����̂������Ȋ��z�������B
�@���Ƀ~���g�E�W���N�\�������̂́AMJQ�u���̃J���e�b�g�v�Ƃ���LP���R�[�h�B���̃X�^���_�[�h�Ȃ��W�߂��R���s���[�V�����ŁA�w������1966�N5���B���̒��́������̂��Ƃ�����₩�� �ɖ�������B���̃X�C���O���A�u�����͋ɏ�̐S�n�悳�B��͂�A�uMJQ�ƌ����I��i�v�ɂ�����I�P�͕s�v�A�Ɖ��߂Ċ��������̂ł���B
�@���i�[�h�E�o�[���X�^�C���́A�ނ�TV�ԑg�u�����O�E�s�[�v���Y�E�R���T�[�g�v�̒��ŁA�N���V�b�N�ÓT�h�̉��y���g�k���ȁhexact���y�ƌ`�e�����B�W���Y�́A�A�����J�̍��l�i�A�t���E�A�����J���j�̉̂��t�ł�J���̂�u���[�X���Ɛ��m���y���o����Đ��܂ꂽ���̂�����A���Ƃ��ƃN���V�b�N�̗v�f�͂Ȃ����Ȃ��B������ɃW���Y�̖{���́u���R�v�B����́A�k���Ŋy���̂���N���V�b�N���y�Ƃ͑��e���v�f���B�܂��A���q�v�l���́i���ߕt���ł͂��邪�j�u�W���Y�ɂ����ăN���V�b�N�ɂȂ����́B����́g�X�C���O���h�Ɓg�A�h���u�h���v�ƌ����B�f���[�N�E�G�����g���ɂ́�X�C���O���Ȃ����Ӗ����Ȃ� �Ȃ�y�Ȃ�����B���Ƃقǂ��悤�ɁA�W���Y�ƃN���V�b�N�͓���݂ɂ������y�Ȃ̂��B����𗝋��ō��̂����悤�Ƃ���A�݂��̓�����������ăA�W���X�g�����邵���Ȃ��B���ꂪ�u�T�[�h�E�X�g���[���E�~���[�W�b�N�v�̖{���Ȃ���̂��ƌ��E��������B����Ȓ��ŁA�W���Y�^�N���Z���̍ŗnj`��T���Ă䂭�ƁA�K�[�V���C���́u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�ɍs�������̂ł���B
���K�[�V���C���u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�͐����ȁ�
 �@�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�́u���v�\�f�B�v�͋����ȂƖ��N���V�b�N���y�̈�`���B�������̃����f�B�[�𐧖�Ȃ����R�Ɍq�����y�Ȍ`���ŁA�u�u���[�v�́g�u���[�X���h�Ƃ��g�J�T�ȋC���h�ȂǃW���Y�̃C���[�W���B�^�C�g������W���Y�^�N���Z���̎p���z�N�����B
�@�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�́u���v�\�f�B�v�͋����ȂƖ��N���V�b�N���y�̈�`���B�������̃����f�B�[�𐧖�Ȃ����R�Ɍq�����y�Ȍ`���ŁA�u�u���[�v�́g�u���[�X���h�Ƃ��g�J�T�ȋC���h�ȂǃW���Y�̃C���[�W���B�^�C�g������W���Y�^�N���Z���̎p���z�N�����B�@���\���ꂽ�̂�1924�N2��12���A�|�[���E�z���C�g�}������Â���u�ߑ㉹�y�̎����vAn Experiment in Modern�Ƃ������y������B���t�}�j�m�t��X�g�����B���X�L�[���ՐȂ����Ƃ�������N���V�b�N�E��������ڂ��ꂽ�Â��������̂��낤�B�z���C�g�}�����ڎw�����̂́A�_���X�̔��t�ł͂Ȃ��Ϗܗp�̃W���YSymphonic Jazz�������B�v���O�����ɂ̓n�[�o�[�g��t�������A�J�[����o�[�����ȂǃN���V�b�N�^�|�b�v�X�E�̑�䏊������A�ˁA�����ӗ~�삪���\����邪�A�Ȃ��B���Ɍ��ӊ�����Y�����A���X�O�ɓo�ꂵ���̂��W���[�W�E�K�[�V���C���i1898�|1937�j�������B�N�����l�b�g�E�\�����n�܂�ƁA�ϋq�͈֎q�ɍ��蒼���A�g�̂�h�炵�A�Ō�ɂ͑������̔��芅�тƂȂ����B�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�͈��ɂ��Ē��O�̐S��͂̂ł���B�����̐V���́u�A�����J�l�̃A�����J�l�ɂ��A�����J�l�̂��߂̉��y���a�������v�Ə̎^�����B���t������J�[���̒a�������������ƂɈ���ł̃R�����g�ł���B���̂�����̗l�q�́A�f��u�A�����J�����y�v�i1945�āj�ɕ`����Ă���B
 �@�Ƃ��낪�A�A�����J���\���鉹�y�ƃ��i�[�h�E�o�[���X�^�C���́A���̋Ȃɑ��āA�ȑz�̖L�������m�肵������ȕ]���������Ă���B�u�w���v�\�f�B�E�C���E�u���[�x�̓����P�����Ɛ������킹�������ЂŃo���o���̕��߂��Ȃ����ɂ����Ȃ��B�������i�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��ȂƂ́A�P�ɐ������������ƂƂ͈Ⴄ�̂��v�ƁB����͂��Ȃ�h煂ł���B���ʂ���ނ������������Ă���͍̂\���ʂƌ��Ď��邪�A�u�n�C���̒ʂ�ł��v�Ƃ͔[���ł��Ȃ��B�Ȃ��������̂��u�N�����m�v�̃~�b�V�����Ƃ������́B�ł́A�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B�o�[���X�^�C���������悤�ȁA����ȂɐƎ�Ȃ��̂Ȃ̂��B����́E�����悤�Ǝv���B�f�ނ́A���{�l�o�[���X�^�C���̃s�A�m�Ǝw���F�R�����r�A�����y�c�A�O���[�t�F�ҋȂ̊nj��y�łɂ�鉉�t�i1959�N�^���A���t����16��26�b�j�Ƃ���B
�@�Ƃ��낪�A�A�����J���\���鉹�y�ƃ��i�[�h�E�o�[���X�^�C���́A���̋Ȃɑ��āA�ȑz�̖L�������m�肵������ȕ]���������Ă���B�u�w���v�\�f�B�E�C���E�u���[�x�̓����P�����Ɛ������킹�������ЂŃo���o���̕��߂��Ȃ����ɂ����Ȃ��B�������i�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��ȂƂ́A�P�ɐ������������ƂƂ͈Ⴄ�̂��v�ƁB����͂��Ȃ�h煂ł���B���ʂ���ނ������������Ă���͍̂\���ʂƌ��Ď��邪�A�u�n�C���̒ʂ�ł��v�Ƃ͔[���ł��Ȃ��B�Ȃ��������̂��u�N�����m�v�̃~�b�V�����Ƃ������́B�ł́A�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B�o�[���X�^�C���������悤�ȁA����ȂɐƎ�Ȃ��̂Ȃ̂��B����́E�����悤�Ǝv���B�f�ނ́A���{�l�o�[���X�^�C���̃s�A�m�Ǝw���F�R�����r�A�����y�c�A�O���[�t�F�ҋȂ̊nj��y�łɂ�鉉�t�i1959�N�^���A���t����16��26�b�j�Ƃ���B�@�`���A���f�I�ȃN�����l�b�g�̃O���b�T���h�ɑ������̂܂ܑ�1�̎�肪�����B���ɂ������Ă�悤�ȑ�2�̎�肪�o��ƁA�قǂȂ��s�A�m����3�̎���t�łI�P�̑S�t���͂���ŁA�ŏ��́g�J�f���c�@���s�A�m�E�\���h(�ȉ�KPS)�ɓ���B�����܂ł�3�̎��́A���Y���̓V���R�y�A�R�[�h�̓u���[�X�ŁA�ۉ��Ȃ��ɃW���Y�̐��E�ɕ��荞�܂��BKPS���I����āA�I�P�̑S�t����n�����̑�4�̎�肪�o��Ɖ��y�Ƀh���C�u��������A��2�������Ƃ��ăX�C���O�������Ղ�ɃI�P�ƃs�A�m��簐i����B�ǂ̃��E���E�E�~���[�g�ɓ������2�Ԗڂ�KPS�ɓ���ƁA���̌㔼�Ńg�����̑�5�̎�肪����ω����Ȃ���傫���W�J�B�s�A�m�E�\�����r���ƁA���Ńz�����̑�6�̎�肪���邭�Y��Ɏp������Andantino moderato con espressione�B�܂�œV��Ɉ���̌����������ނ悤�ȃX�P�[��������]���B�|�[���E�z���C�g�}���y�c�̃e�[�}���B���̂���3�Ԗڂ�KPS���o�āA�I�P�ƃs�A�m����6�������ɐ���オ��A1�\3�̎����ĂыN�����R�[�_���`�����ďI���B
�@���̊y�������Ȃ���CD����Ƃ����x���J��Ԃ��A�悤�₭�y�ȕ��͂��I���B�z�b�ƈꑧ�����u�ԁA�Ȃ̍\���̔閧���M�����B�܂��Ɉ���̌��ł���B�ŁA���������ƁB����́A�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\���̓V�����g���[�ł��� �Ƃ������Ƃ������B
�@ ��1�|3���|KPS1�\��4���\KPS2(��5���)�\��6���\KPS3�\��1�|��3���
�A ���ł���KPS2��4��30�b�B�����2���������O����ׂ�ƁA�O��8���A�㔼8���B�S��16���̊y��
�@ �����傤��2�������Ă���B
�B ���̒����́A��1�|3���̓u���[�X�E�R�[�h�A��4���Ƒ�6���̓��W���[�E�R�[�h�őΏ̂Ƃ�
�@ ��B
�@KPS2�𒆐S���Ƃ��ć@�͌`��I�Ώ́A�A�͎��ԓI�Ώ́A�B�͒����I�Ώ̂𐬂��B����3�v�f���ׂĂɂ킽��Ώ̐��͂܂����S�ǂ̃V�����g���[�Ƃ�����B������ɁA�Ȃ̏I�Ղɂ����āA�قƂ�ǂ̎�����A�����R���p�N�g�ɗ��܂��Ȃ���R�[�_���`�����邠����̗���͐▭�ŁA����ɂ��ȑS�̂ɒ��悢���ꊴ���^�����Ă���B����ɔ�ׂ�ƁA�Ⴆ�A�������v�\�f�B�Ŗ��ȂƂ���郊�X�g�́u�n���K���[�����ȑ�2�ԁv�̕�����قǃo���o���ł܂Ƃ܂肪�Ȃ��B�����Ȃāu���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v���u��i�Ƃ͂����Ȃ��v�ƒf����̂��A�o�[���X�^�C���̌����Ӗ�������Ȃ��B
�@����ɂ�����d�v�ȃ|�C���g������B�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̒_�Ƃ��������6���Andantino moderato con espressione�̎��ԓI�ʒu�ł���B�o��O10���A���̌�6���A����͂ق��u�����䗦�v�B�K�[�V���C���͍ō��̎����ŏ�̈ʒu�ɒu�����̂ł���B����͂����A�Ώ̐��ƕ��������ȍ\���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B�o�[���X�^�C������������ �ł���B
�K�[�V���C���́u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�ɂ��Ă�������Ă���B
���ɂ͂��̉��y�����̃A�����J�̖��؋��Ƃ��ĕ��������@�{�l�����瓖����O�Ƃ͂����A�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v��]���Ă���قǓI�m�ȃR�����g�͂Ȃ����낤�B�j���[���[�N�Ƃ�����s��̑��l���Ƌ������A�����J�̉��y�I���؋�����点���̂��B
���炪����Ȑl��̂�ڂ�
���炪�u���[�X��
���炪�s��I�����̉��y�I���؋��Ƃ���
�@�K�[�V���C���ɂƂ��ăA�����J�͐��܂������j���[���[�N�ƃC�R�[���������B�ނ̑̓��ɂ̓j���[���[�N�������o��������S�b�^�ϓI���o���Z�݂��Ă����B�����ɂ̓W���Y���u���[�X���������B������u���[�X�E�R�[�h�ŋȂ������͎̂��R�Ȃ��Ƃ������B����́A�ނ̉̋ȁ�Somebody loves me���The man I love�����Ύ����ł���B�N���V�b�N�E�s�A�m�̑f�{���������B������A�K�[�V���C���̒��ɂ̓W���Y�ƃN���V�b�N�͎��R�Ȍ`�ŋ������Ă����B
�@�|�[���E�z���C�g�}������u�V���t�H�j�b�N�E�W���Y�v��Ȃ̈˗������K�[�V���C���́A���̎�܂܂ɁA�͂�3�T�Ԃň�̍�i�������グ���B�t�@�[�f�B�E�O���[�t�F�́A�����܂��nj��y�@��g�ɕt���Ă��Ȃ������K�[�V���C���ɑ����ăI�[�P�X�g���[�V�������{�����B����������i���K�[�V���C���́u�A�����J���E���v�\�f�B�[�v�Ɩ��t�������A���̌�A�Z�A�C���̏�����e��āu���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�ɉ��߂��B�����ɂ́A�W���Y�ƃN���V�b�N�̃e�C�X�g�����R�ɗn������ł����B��������́A�j���[���[�N�̋������N�₩�ɕ����яオ�����B����������́A�_�̉���Ƃ����Ă������قǂ́A�`���I�ɂ������Ȍ`�Ԃ�L�����B���̍�ȉƂ��A���������˂Ė������Z����}���Ă������̃c�M�n�M�ɂ����Ȃ�Ȃ��������̂��A�K�[�V���C�����������炱���W���Y�^�N���ӑR��̂̃A�����J���\���閼�Ȃ����܂ꂽ�̂��B
�@����́A�W���Y�̐_�l�f���[�N�E�G�����g���̒��ɃN���V�b�N��T���Ă݂悤�B
���Q�l������
�u�W���Y�̉�������v�i����v�����A���}�n�~���[�W�b�N�G���^�e�C�������gHDS�o�ŕ��j
�u�W���Y�̗��j�v�i���q�v�l���A�V���V���j
�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�i���c�b�j�`�ŐV���ȉ���S�W��7���i���y�V�F�Ёj���
�f��u�A�����J�����y�vDVD�i1945�N�āj
���i�[�h�E�o�[���X�^�C���u�����O�E�s�[�v���Y�E�R���T�[�g�vLD�K�C�h�u�b�N
�@�@�@�@�@�i������Г��{�A�[�g�E�Z���^�[�ҁj
�K�[�V���C����ȁF�u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�vCD
�@�@�@�@�@���i�[�h�E�o�[���X�^�C���̃s�A�m�Ǝw���F�R�����r�A�����y�c�i1959�N�^���j
2019.11.05 (��) �Ǔ� ���瑐�O����
 �@10��24���A���瑐�O���S���Ȃ����B88�������B���߂�TV�h���}�ŋ���������_��͋������Ⴍ��Ȃ���Ǔ����Ă����B���̒��Łu���̕��̐���������Ȃ��Ȃ�̂��ƂĂ��҂����v�Ƙb���Ă����̂���ۓI�������B�����A�������瑐����̐��ɖ�����ꂽ�҂̈�l���B���_�A�������ƋC�i�͌����ɋy���ŁA����ɂ��Ă͑q�{���́u�S�̊�킳�����̐l�̔������Ƃ��ďo�Ă���B���̐l�ɂ͐^���̂ł��Ȃ����_�̔���������Ɋ����Ă����v�Ƃ����b�ɏW���B
�@10��24���A���瑐�O���S���Ȃ����B88�������B���߂�TV�h���}�ŋ���������_��͋������Ⴍ��Ȃ���Ǔ����Ă����B���̒��Łu���̕��̐���������Ȃ��Ȃ�̂��ƂĂ��҂����v�Ƙb���Ă����̂���ۓI�������B�����A�������瑐����̐��ɖ�����ꂽ�҂̈�l���B���_�A�������ƋC�i�͌����ɋy���ŁA����ɂ��Ă͑q�{���́u�S�̊�킳�����̐l�̔������Ƃ��ďo�Ă���B���̐l�ɂ͐^���̂ł��Ȃ����_�̔���������Ɋ����Ă����v�Ƃ����b�ɏW���B�i�P�j�����̂Ȃ݂�
 �@�u���瑐����̐��v�ƌ������̂́ABMG�����2003�N�A�ޏ��̘N��CD�̐���ɏ��Ȃ��炸�g���������ł���iExecutive Producer�ɖ���A�˂Ă���j�BCD�̔���オ90�N��I�Ղ���E��������ɓ]���A��Ђ��ł�����肪�V�j�A�������i�̊J���ŁA���̕�����C���������B����Ȓ��A�����v���f���[�T�[C.O�삪���Ă����̂��u���瑐�O�N��CD�v�������B�����������̊����ŁA�T���o���Ă����̂����܂��Ȃ����s���ꂽ���w���̕���v�����W�u�����v�������B���y���o�b�N�ɔ��瑐����ɘN�ǂ��Ă��炨���Ƃ����킯���B
�@�u���瑐����̐��v�ƌ������̂́ABMG�����2003�N�A�ޏ��̘N��CD�̐���ɏ��Ȃ��炸�g���������ł���iExecutive Producer�ɖ���A�˂Ă���j�BCD�̔���オ90�N��I�Ղ���E��������ɓ]���A��Ђ��ł�����肪�V�j�A�������i�̊J���ŁA���̕�����C���������B����Ȓ��A�����v���f���[�T�[C.O�삪���Ă����̂��u���瑐�O�N��CD�v�������B�����������̊����ŁA�T���o���Ă����̂����܂��Ȃ����s���ꂽ���w���̕���v�����W�u�����v�������B���y���o�b�N�ɔ��瑐����ɘN�ǂ��Ă��炨���Ƃ����킯���B�@�o�����Ɏn�܂��āA���e�̌����A���R�[�f�B���O�A�W���P�b�g�ʐ^�B��A�v�����[�V�����̑ł����킹�ȂǁAC.O.�삪���ƂȂ��Ď����x�X��������B�V���F�A�C���A��㏼�|���A���R�[�f�B���O�E�X�^�W�I�A�ʐ^�X�^�W�I���X�A�����������Ŕ��瑐����ɂ������@��������B
�@���瑐����Ƃ̎d���͓��ʂȎ��Ԃ������B�ǂ�ȂƂ��ɂ��A�Ⴆ�ΎB�e�����т��Ƃ��ɂ��A����Ȋ������Ȃ������B�����ɂ͏�ɉ��₩�ŗD������Ԃ��������B�����₩�Ȏ��Ԃ����ꂽ�B����͖ܘ_���瑐����̐l�ƂȂ�ɋ�����̂����A�������u�A���v�̎R�{���q�i�����В��j�A���c����i���В��j�����̃A�[�e�B�X�g�E�t�@�[�X�g�ׂ̍₩�ȃ}�l�W�����g�ɕ����Ƃ�����������͂Ȃ��B
�@��������CD�u�����̂Ȃ݂��v�iBVC4-34001�j�͎��ɑf�G�ȍ�i�ƂȂ����B�r�[�g���Y���J�[�y���^�[�Y�̊y�Ȃ�X�r�V���̃s�A�m���V���Z�T�C�U�[�A�Ð쏹�`���̃M�^�[�ŐV�^���A������o�b�N�ɔ��瑐����ɘN�ǂ��Ă����������S11�҂ł���B
�e���݂₷���������r�[�g���Y���J�[�y���^�[�Y�̊y�Ȃ𔖂������ɃA�����W�������y�ɁA�@�D�����������A�ł��ǂ����z�Ƃ������瑐����̐����������d�Ȃ�BC.O.�삪������R�s�[�͂����ł���B
Healing Voice�{Music�@���̐��ŖJ�߂�ꂽ���B���̐��Ŏ���ꂽ���B���̏Ί�A���̍��̗܁B���ׂĂ̎v���o�Ƃ̍ĉ�����ɂ���B�S����鎍���S�ɍ��܂ꂽ���y�Ƃ́A�����������������R���{���[�V�����B���A���W�u�����v�����瑐�O�̎���̐����S��B�r�[�g���Y���J�[�y���^�[�Y�̉��Ȃ̎�����Ƌ��ɑt�ł��邷�ׂĂ̐l�X�̔�������̋L�^�B
 �@�����������9��9���ɂ͋���R��y��̓X���ŃT�C����������s�����B�����̐�`�}�̂��d�����A���̒��̃X�|�[�c���̋L�҂��u��������ACD���Ă���Ƃ�����B��܂���v�ƌ����̂ŁA�����q�ɕ����čw���E����B�h�_���锪�瑐����Ƃ̃c�[�E�V���b�g�ʐ^�̎������������A���̎��́u����A�ǂ����āv�Ƃ�����Ƃт����肵�����瑐����̐������ł����Ɏc���Ă���B�����܂Ŏ��l�p�ɎB���Ă��ꂽ���́A�Ǝv���Ă�����A���̎ʐ^�������̃X�|�[�c�V���������Ă��܂��B�Ȃ�ƃJ�����ڐ��I�u�����A������̎ʐ^����Ȃ����C�v�����E�������̂ł���B
�@�����������9��9���ɂ͋���R��y��̓X���ŃT�C����������s�����B�����̐�`�}�̂��d�����A���̒��̃X�|�[�c���̋L�҂��u��������ACD���Ă���Ƃ�����B��܂���v�ƌ����̂ŁA�����q�ɕ����čw���E����B�h�_���锪�瑐����Ƃ̃c�[�E�V���b�g�ʐ^�̎������������A���̎��́u����A�ǂ����āv�Ƃ�����Ƃт����肵�����瑐����̐������ł����Ɏc���Ă���B�����܂Ŏ��l�p�ɎB���Ă��ꂽ���́A�Ǝv���Ă�����A���̎ʐ^�������̃X�|�[�c�V���������Ă��܂��B�Ȃ�ƃJ�����ڐ��I�u�����A������̎ʐ^����Ȃ����C�v�����E�������̂ł���B�@CD�u�����̂Ȃ݂��v���A���܁A���߂Ē����Ă݂�B���^�Ȏq���̌��t�����瑐����̗D���������S���Ă���B�u���������Ƃ��݂��K���K���܂킵�Ă���v�u�����Â��Ȃ��Ă������炩�����������Ă��Ȃ��v�A�u���M���o�������ɁA�����������̂���ڂ���łƂ�������������Ă��ꂽ�v�u�y�j���̒��Ƃ��Ƃ��ɂ�����͓��n�֏o�������v�u���ӂ낾���͂悤������30�~�ł����˂���70�~�v�u�v�����X��肨�������̊�����Ă����ق����������낢�Ƃ���������͂����v�E�E�E
�E�E���������q���̓���̌��t���Ƒ��̐S�̌𗬂ⓖ���̐������f���o���B��ׂ̂Ȃ����C�Ȏv�������瑐����̗D�������ōX�ɖc��ށB��������e�͂ł���B�����Ă���ƐS�����R�ɂȂ��ށB�ŋ߂�����Ɠ{��₷���Ȃ��Ă����B���ꂩ������邾�낤�B����Ȏ��͂���CD�����Ǝv�����BAmazon��������u�ē��ׂ̌����݂Ȃ��v�Ƃ���B�Ȃ�Ƃ��������Ă��炢�������̂ł���B
�i�Q�j���瑐�O����̏��M���j����
�@2004�N2��4���A�u���瑐����̏��M���j����v���s��ꂽ�B1997�N�̎����J�͂Ɉ��������āA�O�N�̏H�A���������͂���͂������j���̉�ł���B
�@���N�l�ɂ́A�C�V��NHK��A�����V��Y���{�e���r��A���}�v�t�W�e���r��A�Έ�ӂ��q�A��R�����A�v�����F�Ȃǂ̃v���f���[�T�[�A�r�{��Ƃ̑q�{���A�R�c����Ȃ��B�X���閼�m������A�˂��B���̉�Ёi����BMG�t�@���n�E�X�j���A�O�N���瑐�����CD�����Ă��邲���ʼn^�c������`�������B
 �@�܂��A��䏊�E�X�ɋv�\�������t�̔���������B90�����ɑ����͂��ڂ��Ȃ��A���A���C�͌��C�u���͂ˁA���͂ˁA���̐l�ƌ��������������A�E���v�Ȃ�Ă��Ƃ����������n���B
�@�܂��A��䏊�E�X�ɋv�\�������t�̔���������B90�����ɑ����͂��ڂ��Ȃ��A���A���C�͌��C�u���͂ˁA���͂ˁA���̐l�ƌ��������������A�E���v�Ȃ�Ă��Ƃ����������n���B�@��������d���e���̈��A�ɓ���B�Έ�ӂ��q����́u����ƃe���r�ł��ꏏ�����Ă��������܂������A�����A�^�������ŃL���L�����Ă���p���������т܂���B�����Ă������Ɖƒ�������ď��D�𑱂��Ă���������B�����Ƃ��Ă��������h���Ă��܂��v�B���ьj�����́u���瑐�����̌�����������������A�Ƃ������u�V�[����������ꂽ���Ƃ��ƂĂ��K���ł����v�B���c�������́u�V��O��コ�A��˂̗��j�̒��Ŕ��瑐����قǂ��킢���l�͂��Ȃ��A�ƌ����Ă��܂���.�v�B�R�c���ꎁ�́u���瑐����͎��̒��ł͖���40��A�ƂĂ�����������̑�{�͏����Ȃ��v�B�Y�͐A�ؓ�����B�Ȃ����₯�ɋ�s���ۂ��B�u�F�X�����Ă������A�݂�Șb����������B���̐l�ɍ����M�͂Ȃ�Ēx������v�ȂǂƉ��X�����B�{�l����Ԓ��������B���������ӔC�j�ł���B
�@��������͔o�D���Ԃ₨�F�B�Ɉڂ�B��坎O���v���́u���͉ƒ�ɂ����锪�瑐����̑f���m���Ă܂��B�U�ߗl�̒J����g�ē̂��Ƃ��w�搶�A�搶�x�ƌĂ�ŁA����͂���͂����������������b���Ă���B���D�Ƃ��Ă��V�c�É�����M�͂����炤���炢���h�Ȃ�ł����A������Ƃ��Ă���ϗ��h�Ȑl�Ȃ�ł��v�B�W����i����́u���Ȃ��̏����ȑ̂���o��t�@�C�g�������Ƃ������S���Ă��܂��v�B���؊�т���́u�M�͂��ǂ̒��x�̂��̂�����܂��A���瑐����͌|�\�E�ɂ����ċH�L�Ȑl���̎�����B�c�������Č}�����Ȃ��v�B���R���q����u�N���d�˂Ă���������������̑��݂ł��v�B�g��v���q����́u����������w���X�v�l�x�����āA�Ȃ�Ă��ꂢ�Ȑl�Ɗ��Q���܂������A���������ɂ��������锪�瑐����͑S�R�ς���Ă��Ȃ��v�B�c�������́u�l�̔o�D�f�r���[�ł��ꏏ�����̂����瑐����ł����B���ꂪ���̌ւ�ő�ȕł��v�B�݂Ȃ��������t�ŏj���Ă��ꂽ�B
�@���m�ρX�̕��X�̏j�����āA�Ō�ɔ��瑐����̂����A�ł���B�u�Ȃ܂����̂œۋC�Ȏ��������܂ł���Ă���ꂽ�̂��A�݂Ȃ��܂���������L�ׂĎx���ɂȂ��Ă������������A�ł��B���肪�Ƃ��������܂����v�B�����āA���̂��Ɓu����ǂ܂��Ă��������܂��B�Ƃ��Ă��������Ȃ�ł��v�ƑO�u�����āACD�u�����̂Ȃ݂��v����u�����������̂�߂��肵�Ⴕ��v����gOh my love�h���o�b�N�ɘN�ǂ����B���������͋C�̂��j���̉�ɑ��������G���f�B���O�������B
�@���瑐����́A��̒��ŁA�u�J����2��19����92�ɂȂ�܂��B�����ɂ��Ĉ��A�������������̂ł����A�Ȃɂ�����̂��ߊ����܂���ł����B�F�l�̂����ӂ͂��Ȃ炸�`���܂��v�Ƙb���Ă����B��̗l�q�͂��炩���r�f�I�Ŏ��߂Ă����̂ŁA�����ɕҏW�A�G���f�B���O�̓V���b�g�f�����q���āu�����̂Ȃ݂��v�́�The Long and Winding Road��킹�A73���ɂ܂Ƃ߂��B
�@����A�u�ē̒a�����ɊԂɍ����悤�ɍ��܂����B���瑐����ɂ��n�����������v�Ɗ�������VHS���������ɓ͂���ƁA�u���ǂ��͉����B���Ă��Ȃ������̂ŁA������܂��v�Ɗ��ł��ꂽ�B�ē͂����Ɣ��瑐����ƈꏏ�Ɍ��Ă��ꂽ�Ǝv���B
�i�R�j�u���X�v�l�v�Ɓu�j�͂炢��v
 �@���瑐�O�̃I�y���f��u���X�v�l�v�͐����B�Ƃɂ������ɂ��������B���̒��ɂ���Ȕ���������������̂��Ǝv�킹�镗��ł���B�e���̌|�҂�������̂��A�����ق�A�����ԑ�A�P�����Ƃ�����X�^�[�Ȃ̂����̏ؖ����낤�B�B�e�́A1954�N�A���[�}�x�O�`�l�`�b�^�B�e���B�O�N�u���[�}�̋x���v���B�����Ƃ���ł���B�I�y���f�悾����I�y���̎�̉̂ɍ��킹�ĉ��Z������B�A�t���R�Ȃ�ʃA�t�t���ł���B���ꂪ���Ɍ����ɛƂ܂��Ă���B�̂Ɛ����̋������Ȃ��B����ɉ����āA���̕\��̕ω��ł���B�ɂ���ĉ̎��ɘA��Ėڂ܂��邵�������R�ɕω�����B�Ⴆ�A��2���A�V���[�v���X���s���J�[�g������̎莆�X����ɓǂݕ��������ʁB���邢�\���u�܂�A�u���ɂ܂��߂�B���̉s�q�Ȕ����ɉs��������������̂����A�����ɂ��ꂪ�A���Ɏ��R�Ȃ̂ł���B����B�炪�A10��31�������V���̒Ǔ����̒��Łu����G�q����͋Z�ŕ\������B���瑐����͋C�����ŕ\������v�Əq�ׂĂ���̂́A�����������Ƃ��낤�B����͂����A�V���̂��̂Ƃ����v���Ȃ������B�������A���瑐�����1999�N�̎�L�ł��������Ă���B
�@���瑐�O�̃I�y���f��u���X�v�l�v�͐����B�Ƃɂ������ɂ��������B���̒��ɂ���Ȕ���������������̂��Ǝv�킹�镗��ł���B�e���̌|�҂�������̂��A�����ق�A�����ԑ�A�P�����Ƃ�����X�^�[�Ȃ̂����̏ؖ����낤�B�B�e�́A1954�N�A���[�}�x�O�`�l�`�b�^�B�e���B�O�N�u���[�}�̋x���v���B�����Ƃ���ł���B�I�y���f�悾����I�y���̎�̉̂ɍ��킹�ĉ��Z������B�A�t���R�Ȃ�ʃA�t�t���ł���B���ꂪ���Ɍ����ɛƂ܂��Ă���B�̂Ɛ����̋������Ȃ��B����ɉ����āA���̕\��̕ω��ł���B�ɂ���ĉ̎��ɘA��Ėڂ܂��邵�������R�ɕω�����B�Ⴆ�A��2���A�V���[�v���X���s���J�[�g������̎莆�X����ɓǂݕ��������ʁB���邢�\���u�܂�A�u���ɂ܂��߂�B���̉s�q�Ȕ����ɉs��������������̂����A�����ɂ��ꂪ�A���Ɏ��R�Ȃ̂ł���B����B�炪�A10��31�������V���̒Ǔ����̒��Łu����G�q����͋Z�ŕ\������B���瑐����͋C�����ŕ\������v�Əq�ׂĂ���̂́A�����������Ƃ��낤�B����͂����A�V���̂��̂Ƃ����v���Ȃ������B�������A���瑐�����1999�N�̎�L�ł��������Ă���B
�B�e�O�̎x�x�ɂ�3���Ԃ�����������Ƒ�ςł������A��������ւ́A�̂ƁA�̂��������҂����荇�킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł����B�{�E�̃I�y���̎�i�I���G�b�^�E���X�N�b�`�j�̐��ɍ��킹�āA���m�ɔ��������A�����g���{���ɉ̂��Ă���悤�ɁA��̂ɂȂ�Ȃ���A�������Ȃ��킯�ł��B�I�y���ɂ��Ȃ��݂��Ȃ��A�C�^���A����킩��Ȃ����ɂƂ��ẮA�s���ȂǂƂ����Ȃ܂₳�������̂ł͂���܂���ł����B�B�e���n�܂�܂ŁA���������A�����Ă����Ă��A�Q�Ă��o�߂Ă��A���X����̃I�y���ɂ�����߂̐����ł����B����ł��n���̂悤�Ȃ��鎞�����߂���ƁA���y���C�����悭�̂̒��𗬂��悤�ɓ����Ă��āA�C�^���A��ɂ������Â���Ă��܂����B�i���E�����Њ��u�D�������ԁv���j�@�Ȃ�Ɓg�n���̂悤�ȁh�ꂵ�݂𖡂���Ă����̂��B���l���̎^���锪�瑐�O�̎��R�̂̉��Z�́A�P�ɓV���̂��̂ł͂Ȃ��A���̗��ɂ͖ڎw���ΏۂɌ������Ĉ�r�ɏW�����鑽��ȓw�͂��������̂ł���B
 �@���瑐����́u�j�͂炢��v�V���[�Y�Ɉ�x�o�����Ă���B1972�N�A�N������̑�10��u�Ў��Y�����v�̃}�h���i���̖��ł���B�u�j�͂炢��v�͑�8��u�Ў��Y���́v(�}�h���i�͒r���~�q)�ŏ��߂ē���100���l��˔j�B�������炫������N2��~��ꋻ�s�ƂȂ�A�����ʂ荑���I�f��ƂȂ��Ă䂭�B�u�Ў��Y�����v�͑�9��g�i���S���Ƒ�11���u�����q�ɋ��܂ꂽ�܂��ɑS�����̍�i�ł���B�N���V�b�N���y���ӂ�Ɏg���Ă���̂��y���݂̈�B���B���@���f�B�F�u�l�G�v�A���[�O�i�[�F�u�����L���[���̋R�s�v�A�x�[�g�[���F���F�u�X�v�����O�E�\�i�^�v�Ȃǂ����ʓI�ɑ}������Ă���B
�@���瑐����́u�j�͂炢��v�V���[�Y�Ɉ�x�o�����Ă���B1972�N�A�N������̑�10��u�Ў��Y�����v�̃}�h���i���̖��ł���B�u�j�͂炢��v�͑�8��u�Ў��Y���́v(�}�h���i�͒r���~�q)�ŏ��߂ē���100���l��˔j�B�������炫������N2��~��ꋻ�s�ƂȂ�A�����ʂ荑���I�f��ƂȂ��Ă䂭�B�u�Ў��Y�����v�͑�9��g�i���S���Ƒ�11���u�����q�ɋ��܂ꂽ�܂��ɑS�����̍�i�ł���B�N���V�b�N���y���ӂ�Ɏg���Ă���̂��y���݂̈�B���B���@���f�B�F�u�l�G�v�A���[�O�i�[�F�u�����L���[���̋R�s�v�A�x�[�g�[���F���F�u�X�v�����O�E�\�i�^�v�Ȃǂ����ʓI�ɑ}������Ă���B�@���瑐����̂���コ��́A�������E�Ў��Y�̗c����Ƃ����B�O��i�܂ŁA�Ђ���͌��܂��ă}�h���i�ɐU���Ă����̂����A���́u�����v�͂Ȃ�ƃ}�h���i�̕����D�ӂ����Ƃ�������I�Ȑݒ�ƂȂ����B�����͋T�˓V�_�ł̓�l�̂����ł���B�b�������Ⴂ��������コ�u�Ђ����ƈꏏ�ɂ���ƁA�Ȃ��C�������z���Ƃ���́B�Ђ����Ƙb���Ă���ƁA�������͐����Ă���ȃ@���āA����Ȋy�����C�����ɂȂ�́B�Ђ����ƂȂ�ꏏ�ɕ�炵�Ă������Ǝv�����́v�ƌ��䎌�ɁA�Ђ���͓��]�A�ւ��ւ��Ƃ��̏�ɍ��荞�ށB�ϋq���u���蓾�Ȃ��v�Ƌ����B���̃V���[�Y���w�̖���ʂŌ������}�h���i���瑐�O�̉��₩���Ɛ^��������������\��́A�o�[�`�����ƃ��A�����s�������đf���炵���B
�@���瑐�O����͐����Ă��܂����B�s�������Ɖ�������e�͂������A�c�ɂ��Ȃ₩�Ȑx�����߂��H�L�ȏ��D�������B���̉��Z�́A�D�����������z�Ƃ����Ȃ܂��̒��A���Â�ߊ삪���R�Ɏ��݂Ɍ��������B���̉A�e����������������͂܂�Ń��[�c�@���g�̉��y���̂��̂��B��Ԃӂ��킵���̂́u�A���F�E���F�����E�R���v�X�v���낤���BK618���Ȃ���ނ�ł����������F�肷��B
2019.10.25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X3
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�A���h���E�v�����B���A�I�����[����
 �@�A���h���E�v�����B���i1929�|2019�j�͓��قȉ��y�Ƃł���B�Ⴂ����̓W���Y�E�s�A�j�X�g�A���̌�̓N���V�b�N�̐��E�ɓ]�����w���҂ƂȂ����B�N���V�b�N�̐��E�ł͎w���҂ƃs�A�m�̓��͒������Ȃ��B�����^�[�A�t���g���F���O���[�A�o�[���X�^�C���A�o�����{�C���A�A�V���P�i�[�W�������ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B�v�����B�����w���҂ƃs�A�j�X�g�̓������A���ƈ�����悷�̂́A�W���Y�E�s�A�j�X�g����̓]�g�ł��邱�Ƃ��B�A���h���E�v�����B�������A�N���V�b�N�̗��j300�N�A�W���Y�̗��j100�N�̂Ȃ��ŃI�����[�����B�ꖳ��̑��݂Ȃ̂ł���B
�@�A���h���E�v�����B���i1929�|2019�j�͓��قȉ��y�Ƃł���B�Ⴂ����̓W���Y�E�s�A�j�X�g�A���̌�̓N���V�b�N�̐��E�ɓ]�����w���҂ƂȂ����B�N���V�b�N�̐��E�ł͎w���҂ƃs�A�m�̓��͒������Ȃ��B�����^�[�A�t���g���F���O���[�A�o�[���X�^�C���A�o�����{�C���A�A�V���P�i�[�W�������ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B�v�����B�����w���҂ƃs�A�j�X�g�̓������A���ƈ�����悷�̂́A�W���Y�E�s�A�j�X�g����̓]�g�ł��邱�Ƃ��B�A���h���E�v�����B�������A�N���V�b�N�̗��j300�N�A�W���Y�̗��j100�N�̂Ȃ��ŃI�����[�����B�ꖳ��̑��݂Ȃ̂ł���B�@�x�������̗T���ȃ��V�A�n���_���l�̉ƒ�ɐ��܂ꂽ�v�����B�������y�ɖڊo�߂��̂́A1935�N�A6�̂Ƃ����e�ɘA����čs�����t���g���F���O���[�w���F�x�������E�t�B���̉��t������Ƃ����B���ڂ̓u���[���X�̌����ȑ�3�ԂƑ�4�ԁB���̂���̃h�C�c�̓q�g���[�̃i�`�X���������������E���Ɍ������r��ł���B�t���g���F���O���[�Ƃ����A�O�N�A�i�`�X�ɔw��������ȉƂ̃q���f�~�b�g��i�삵�����߁i�����q���f�~�b�g�����j�A���ǂ���x�������E�t�B�����n�߂Ƃ��邷�ׂĂ̗v�E����C����Ă����B���N�A�a�����������Ċy�d�ɕ��A�������A�v�����B�����N�����������̂͂���Ȏ����̃R���T�[�g�������B���_���l���Q���n�܂��Ă����s���ȏ�̒��A6�̏��N�̋��Ƀt���g���F���O���[�̉��y�͋���ɓ˂��h�������B���̎��̐S�����Ɂu����͎��ɂƂ��đ厖���������B�M���o��قNJ��������B�����͐�Ɏw���҂ɂȂ��Ă��ƌ��S�����v�Əq�����Ă���B
�@���̌�A�v�����B����Ƃ̓i�`�X�̔��Q��ăA�����J�ɓn��B�S�����_���l�̂��ߕ��͎��E�A�v�����B�����N�̓W���Y�E�s�A�j�X�g�Ƃ��Ĉ�Ƃ��x���邱�ƂɂȂ����B�����Ɏw���҂ւ̖�������Ȃ���B
 �@���A�v�����B���͂܂��W���Y�E�s�A�j�X�g�Ƃ��ē��p�������A1956�N�^���́u�}�C�E�t�F�A�E���f�B�v�ł��̒n�ʂ�h�邬�̂Ȃ����̂ɂ���B�V�F���[�E�}���ids�j�A�����C�E�r�l�K�[�ib�j�Ƃ̃s�A�m�E�g���I�̉��t�́A��i�ŃX�C���O�����Q�̃p�t�H�[�}���X�������B����v���搶��CD�̃��C�i�[�E�m�[�c�ɁA�u�v�����B���̃s�A�m�͂Ƃ��Ƀt�@���L�[�ɁA�Ƃ��ɃZ���V�e�B���ɁA�Ƃ��Ɋ�ш�t�ɕ\������B����Ȋy�����Z�b�V�����͂R�l�ɂƂ��Ă��Y����Ȃ����̂ƂȂ����ł��낤�v�Ə����Ă���B���̕]�̂Ƃ���A���̃A���o���͔����Ɠ����ɑ�q�b�g�B�Ȍ�Q�N�Ԃ��`���[�g�̏�ʂɗ��܂�Ƃ����A�W���Y�E���R�[�h�Ƃ��ċ�O�̃q�b�g�������O�Z���[���L�^�����̂ł���B
�@���A�v�����B���͂܂��W���Y�E�s�A�j�X�g�Ƃ��ē��p�������A1956�N�^���́u�}�C�E�t�F�A�E���f�B�v�ł��̒n�ʂ�h�邬�̂Ȃ����̂ɂ���B�V�F���[�E�}���ids�j�A�����C�E�r�l�K�[�ib�j�Ƃ̃s�A�m�E�g���I�̉��t�́A��i�ŃX�C���O�����Q�̃p�t�H�[�}���X�������B����v���搶��CD�̃��C�i�[�E�m�[�c�ɁA�u�v�����B���̃s�A�m�͂Ƃ��Ƀt�@���L�[�ɁA�Ƃ��ɃZ���V�e�B���ɁA�Ƃ��Ɋ�ш�t�ɕ\������B����Ȋy�����Z�b�V�����͂R�l�ɂƂ��Ă��Y����Ȃ����̂ƂȂ����ł��낤�v�Ə����Ă���B���̕]�̂Ƃ���A���̃A���o���͔����Ɠ����ɑ�q�b�g�B�Ȍ�Q�N�Ԃ��`���[�g�̏�ʂɗ��܂�Ƃ����A�W���Y�E���R�[�h�Ƃ��ċ�O�̃q�b�g�������O�Z���[���L�^�����̂ł���B�@�v�����B���͂܂��A�f�批�y�ɂ������E�ҋȎ҂Ƃ��č˔\���B�u�}�C�E�t�F�A�E���f�B�v�i1964�N�j���͂��߁A�u�M���������ӂ́v�i1963�N�j�ȂǃA�J�f�~�[�ҋȏܓ����S���܁B�O���~�[��܂��������B�W���Y���|�b�v�X�̐��E�ő���̖�������ɂ����v�����B���́A1960�N��ɓ�����ɔO��̃N���V�b�N�̎w���҂ւ̓�����ݎn�߂�B �@�t�̓t�����X�̖����s�G�[���E�����g�D�[�B�o�[���X�^�C���̏Љ�����B�L�����A�̃X�^�[�g�́A�{�l�H���u�n�}�ɂȂ��悤�ȏ����Ȓ��v�������Ƃ����B���̌㌤�r���d�ˌo����ς݁A1968�N�ɂ̓C�M���X�̖���A�����h�������y�c�̉��y�ēɂȂ�B
�@���R�[�h��Ђ�RCA�B���̃v�����B���Ƃ̏o��̓����h�������y�c���w���������H�[���E�E�B���A���X�F�u��Ɍ����ȁv��LP�������B�����̃N���V�b�N�E�̓J���������x�[���̑S�����B���̂悤�ȃh�C�c�����h�^����������RCA���[�x���́A�ʃ��C���̏��i�Ő키�����Ȃ������B������g��惂�m�h�ł���B�L���b�`�E�R�s�[�́g�����s��I�I��ɂ̔��Ɛ_��������ɕ`��������I�h�B��������S���̐V�ăZ�[���X�}�����������́A���X���������h��ȊŔ������Ă��炢�g���ɓw�߂����̂ł���B�Z�[���X�̓\�R�\�R���������A�ǂ��v���o�Ƃ��Ďc���Ă���B
�@���߂�CD�Œ����Ɖ����������S��B�ł����Ƃ������A���t�͗��h�����A�ȂƂ��Ă͂���قǖʔ������̂ł͂Ȃ��B���i�Ƃ��ẮA��͂��惂�m�̈���o�Ȃ��A�Ƃ����Ƃ��납�B
�@�v�����B����RCA�Ɉ₵�����X�̘^���̒��ŁA�o�F�̓��C�����E�t�B���Ƃ̃x�[�g�[���F���u�c���v�i1987�N�^���j���Ǝv���B���R�ȃe���|���ƗD�����������S�n�悢�B�L�����A�̏����ɋ����u���[�m�E�����^�[�̌O�������Ƃ������Ƃ����A���́u�c���v�A�Ȃ�ƂȂ������^�[�̃e�C�X�g����������B���݂ɁA��P�y�͂̃^�C���𑪂�ƁA�v�����B���́i���̌J��Ԃ��������Ɓj10�F00�B�J��������8�F50�A�x�[����9�F33�A�����^�[��9�F49�ŁA�����^�[�ɍł��߂��B���_�^�C�������ʼn��t�̎��͑���Ȃ����A��̖ڈ��ɂ͂Ȃ�B��������������A�e���|���Ƃ��Ȃ₩�ȋ����̒��ɁA�S�Ȃ��������^�[�̉e�����Ď���̂ł���B����͉B�ꂽ�����ł���B
�@�v�����B����RCA�̌�AEMI�APhilips�ATelarc�ADG���ɂ������̘^�����₵���B���̎莝���͂����̓��̂ق�̈ꕔ�ł����Ȃ����A�����Ȃ��x�^�����Ă�����̂��R����B���̋@��ɂ������r��������̈ꋻ���낤�B
�@�ŏ��Ɏ��グ��̂����t�}�j�m�t��ȁu������ ��2�ԁv�ł���B�I�P�͓��������h�������y�c�ŁARCA�Ղ�1966�N�AEMI�Ղ�1973�N�̘^���B
�@��r�����͓��R��3�y�́B���̖ȁX���郍�}���`�b�N�x�͔��[�Ȃ��A�{�ƃ`���C�R�t�X�L�[���G��Ȃ��I�H
�@RCA�Ղ́A�؊ǂ̃\������������ƕ�������B�N�����l�b�g���t�Ȃ̊ɏ��y�͂̎�B�\���S�̂Ƃ��ẮA�v�����B�����L�̉����Ńx�g���Ȃ��R����u�₩�ł���B����ɑ��AEMI�Ղ́A�؊ǂ̃\���ƌ����o�����X�悭�n�������A�����̂��̂��A���Ɍ����_�炩���������B�e���|�����߂��قƂ�Ǖς��Ȃ����ARCA�Ղ�苿���Ɍ��݂�����F���ł���B�W���Y�ł����A�R���{�ƃo���h�E�T�E���h�̈Ⴂ���낤���B�Ȃ̃��}���`�b�N�Ȑ��i���炢���āA������EMI�ՂɌR�z���オ��B
�@���́A�����X�L�[���R���T�R�t�̌����g�ȁu�V�F�G���U�[�h�v�̑�3�y�́u�Ⴋ���q�Ɖ����v���r���悤�BRCA�Ղ̓����h�������y�c�ŁA1968�N�BRHILIPS�Ղ̓E�B�[���E�t�B���ŁA1981�N�̘^���ł���B
�@�܂�RCA�Ղł���B���킳���G�ɕ`�����悤�ȕ\���B�t���[�W���O���i�������B�I�P�̉��F�������h�����炵��������������������B�����ȃV�F�G���U�[�h��f�i�Ƃ�����X�}�[�g�ȉ����ł���B
�@PHILIPS�Ղɂ�����v�����B���̉��߂͊�{�I�ɂ�RCA�Ղƕς��Ȃ��B�^�C����2�b�Ⴄ�������B�Ⴂ�̓I�P�̃T�E���h�ł���B�E�B�[���E�t�B���́A�I�[�\�h�b�N�X�ȃ����h�����ɔ�ׂ�ƁA�Ɠ��̉��₩�������B�����Ńv�����B���́A�e�k�[�g�̓x��������⋭�ߏ��������Z���ȕ\�������݂�B���ꂪ�E�B�[���E�t�B���̉��F�Ƒ��܂��ēƓ��̐F���������o���B�������邱�ƂŁA�����ȃV�F�G���U�[�h�ɗd�����������B�����ɁA��̃I�[�P�X�g���̓������������v�����B���̂��Ȃ₩�Ȋ����ƃe�N�j�b�N�̍Ⴆ�����Ď���B�ǂ����I�Ԃ��͂��D�ݎ���ł���B
 �@�Ō�́A�K�[�V���C���́u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�ł���B���̋Ȃ̓W���Y�ƃN���V�b�N���Z�������A�����J���y�̑�\�I����ł���A�����ɂ͎Ⴋ�K�[�V���C���̏�M�ƓV�˂��������ڂ�����ɋl�܂��Ă���B�W���Y�E�s�A�j�X�g�ɂ��Ďw���҂ł���A���h���E�v�����B�������܂��Ɂu���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̐\���q�Ƃ����邾�낤�B�v�����B�����A1998�N�A�K�[�V���C�����a100�N�ɁA�s�A�m�ƃx�[�X�Ƃ����V���v���ȕҐ��́u�K�[�V���C���E�\���O�u�b�N�v�Ƃ����Ǔ��I���Ղ��₵���̂��K�[�V���C���ւ̌h���̕\��Ƃ�����B
�@�Ō�́A�K�[�V���C���́u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�ł���B���̋Ȃ̓W���Y�ƃN���V�b�N���Z�������A�����J���y�̑�\�I����ł���A�����ɂ͎Ⴋ�K�[�V���C���̏�M�ƓV�˂��������ڂ�����ɋl�܂��Ă���B�W���Y�E�s�A�j�X�g�ɂ��Ďw���҂ł���A���h���E�v�����B�������܂��Ɂu���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̐\���q�Ƃ����邾�낤�B�v�����B�����A1998�N�A�K�[�V���C�����a100�N�ɁA�s�A�m�ƃx�[�X�Ƃ����V���v���ȕҐ��́u�K�[�V���C���E�\���O�u�b�N�v�Ƃ����Ǔ��I���Ղ��₵���̂��K�[�V���C���ւ̌h���̕\��Ƃ�����B�@�O�̘^�������邪�����ł͐V�������̓���r����BEMI�Ղ̓����h�������y�c��1971�N�̘^���BPHILIPS�Ղ̓s�b�c�o�[�O�����y�c��1984�N�̘^�����B
�@EMI�ՁA�v�����B���̃s�A�m�͐ꂪ�ǂ��X�C���O���ɖ����Ă���B�I�P�Ƃ̊|���������M�C�����蔗�͏\���B�`���̃N�����l�b�g�͖���h�E�y�C�G�ŕ���Ȃ��AAndantino moderato�̎��(�|�[���E�z���C�g�}���y�c�̃e�[�})��ɏo��g�����{�[���E�\�������ɉ��y�I�B�W���Y�I�X�s���b�g�Ɉ�ꂽ�P�����������ł���B
�@Philips�Ղ̓A�����J�̃I�P�ɑ����Ă��邩����W���Y�I���Ǝv�������ł��Ȃ��B�s�A�m�̃^�b�`�́A�s�������������d���A�I�P�̕\����\�t�g�ŗD�����B����͂���Ŕ������̂����A�Ⴋ�K�[�V���C���̏�M��EMI�Ղ̕��ɐF�Z�����łB�v�����B���̑�\���1���Ɩ��ꂽ��A���͂��߂炢�Ȃ��u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�vEMI�Ղ𐄂��B
�@�W���Y�ƃN���V�b�N�����L����v�����B���͋��t�̒B�l�ł�����B�W���Y�E�s�A�j�X�g����ɂ́A�|�b�v�X�̖��ԃ_�C�i�E�V���A�Ƃ́u�_�C�i�E�V���O�X�A�v�����B���E�v���C�Y�v�i1959�N�^��Capitol�j��u�P�E�Z���E�Z���v�ł�����݃h���X�E�f�C�Ƃ́u�f���G�b�g�v�i1961 CBS�j�Ȃǂ�����A�N���V�b�N����ɂ͐l�C�̉̕P�L���E�e�E�J�i���Ƃ́uKIRI SIDETRACKS�v(1991 PHILIPS)�Ȃǂ�����B�̎�̌����������Ă��悭���Ȃ��咣����v�����B�������ɃX�}�[�g�ł���B����Ȍ����ȃp�t�H�[�}���X���A��L�A���o��42�Ȃ̒����犸���Ĉ�ȑI�ԂƂ���A�uKIRI SIDETRACKS�v���^�́u�L���[�g�v���B�g�W���Y�S�ƒ��ڂ��C�h�A����ȃe�E�J�i���̈ӊO�Ȉ�ʂ��A�X�C���O�����ӂ��v�����B���̃s�A�m�Ɨ��ݍ����A�C���p�N�g����R���{���[�V���������o�����B�Ȃ��Ȃ��̒������̂ł���B
 �@�v�����B���́A2009�N����ANHK�����y�c�̎�ȋq���w���҂߂��B���̂��A�ŁA�e���r��ʂ��ĔӔN�̎��|�����\���邱�Ƃ��o�����͍̂K�^�������B�^��ł������̂��L���ƁE�E�E�E�E���[�c�@���g�F������ ��36�ԁu�����c�v�A�K�[�V���C���F�s�A�m���t�� �w���A�����O�u�O���[���v�A�v���R�t�B�G�t�F�����ȑ�5�ԁA�u���[���X�F�h�C�c�E���N�C�G���A���V�A���F�g�D�����K���������ȁA�}�[���[�F�����ȑ�9�ԁA�����ău���[���X�̌����ȁu��3�ԁv�Ɓu��4�ԁv�Ȃǂł���B
�@�v�����B���́A2009�N����ANHK�����y�c�̎�ȋq���w���҂߂��B���̂��A�ŁA�e���r��ʂ��ĔӔN�̎��|�����\���邱�Ƃ��o�����͍̂K�^�������B�^��ł������̂��L���ƁE�E�E�E�E���[�c�@���g�F������ ��36�ԁu�����c�v�A�K�[�V���C���F�s�A�m���t�� �w���A�����O�u�O���[���v�A�v���R�t�B�G�t�F�����ȑ�5�ԁA�u���[���X�F�h�C�c�E���N�C�G���A���V�A���F�g�D�����K���������ȁA�}�[���[�F�����ȑ�9�ԁA�����ău���[���X�̌����ȁu��3�ԁv�Ɓu��4�ԁv�Ȃǂł���B�@�u���[���X�̑�3�Ƒ�4�́A�`���ŏ������ʂ�A�v�����B�����w���҂�ڎw�����������ɂȂ��������̋Ȃł��邪�A�Ƃ�킯��3�Ԃɂ͎v�����ꂪ�[���悤���B����͔ނ̂���Ȍ��t����M����B�u�u���[���X��4�̌����Ȃ͔��������ʂɑi���Ă�����̂�����B��1�Ԃ͌��I�B��2�Ԃ͓c���I�B��3�Ԃ͏H�̂悤�Ɏv���I�ł����Ƃ肷��قǔ������B��4�Ԃ͑s��ȃh���}�v�B��3�ւ̃R�����g���ЂƂ����I�ő��ƈ�����悷�����B
�@2010�N11��6���ANHK���y�Ղł́u��3�����ȁv�̉��t�͑f���炵�������B���݂̂Ȃ����R�ȗ���̒��ɁA�����ނ悤�ɉ����������A���ƈ������u�����h���ꂽ���M�Ȃ܂ł̉���Ԃ����o���Ă����B�^�N�g��u�����u�Ԃ̉��₩�ȏΊ炪�ƂĂ��`���[�~���O�������B�����ɂ͏��N�̂悤�Ȗ��C�����������B������������A���N���A�t���g���F���O���[�����������h�点�Ă����̂�������Ȃ��B
�@2019�N2��28���A�A���h���E�v�����B���͊҂�ʐl�ƂȂ����B���N����̖���Y�ꂸ�Ǝ��̉��y��T���������������Ȑl���������B
2019.09.22 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X2
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�W���Y�̖��� ���[�c�@���g�����t���� �̊�
���x�j�[�E�O�b�h�}���̏ꍇ�� �@�g�X�C���O���h�x�j�[�E�O�b�h�}���i1909�|1986�j�ƃN���V�b�N���y�Ƃ̌q����͐[���B�܂��A�y�c�̃e�[�}�ȁu���b�c�E�_���X�v�̓E�F�[�o�[�́u�����ւ̊��U�v�����ȁB���̑��ɂ��A�����F���́u�{�����v�A�p�K�j�[�j�́u�J�v���[�X��24�ԁv�A�����f���X�]�[���́u�t�̉́v�A�v���R�t�B�G�t�́u�s�[�^�[�ƘT�v�ȂǁA�N���V�b�N�̖��Ȃ��A�����W�A���Ȃ̃��p�[�g���[�Ƃ��Ă���B�����܂łȂ�A�O��́u�N�����m�v�ŏ������N���V�b�N�̃W���Y���Ɖ���ς��͂Ȃ��̂����A�ނ͈ꖡ�Ⴄ�ʂ����B�N���V�b�N�̊y�Ȃ����̂܂܃V���A�X�ɉ��t����̂ł���B�����ɂ́g�X�C���O���h�O�b�h�}���̎p�͂Ȃ��B�����N���V�b�N�̈�N�����l�b�g�t�҂����邾�����B
�@�g�X�C���O���h�x�j�[�E�O�b�h�}���i1909�|1986�j�ƃN���V�b�N���y�Ƃ̌q����͐[���B�܂��A�y�c�̃e�[�}�ȁu���b�c�E�_���X�v�̓E�F�[�o�[�́u�����ւ̊��U�v�����ȁB���̑��ɂ��A�����F���́u�{�����v�A�p�K�j�[�j�́u�J�v���[�X��24�ԁv�A�����f���X�]�[���́u�t�̉́v�A�v���R�t�B�G�t�́u�s�[�^�[�ƘT�v�ȂǁA�N���V�b�N�̖��Ȃ��A�����W�A���Ȃ̃��p�[�g���[�Ƃ��Ă���B�����܂łȂ�A�O��́u�N�����m�v�ŏ������N���V�b�N�̃W���Y���Ɖ���ς��͂Ȃ��̂����A�ނ͈ꖡ�Ⴄ�ʂ����B�N���V�b�N�̊y�Ȃ����̂܂܃V���A�X�ɉ��t����̂ł���B�����ɂ́g�X�C���O���h�O�b�h�}���̎p�͂Ȃ��B�����N���V�b�N�̈�N�����l�b�g�t�҂����邾�����B�@�O�b�h�}���ƃN���V�b�N�̌��т��͏��N���ɑk��B�n�������_���n�ږ��̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�O�b�h�}���ɉ��y�ւ̔����J�����̂̓��_������i�V�i�S�[�O�j�ŁA���ꂪ10�̂Ƃ��B���N�ɂ̓n���E�n�E�X�Ƃ����Z�c�������g�̏��N�o���h�ɓ��c�B�߂��߂��Ɠ��p������킵�����N�ɁA�t�����c�E�V�F�b�v�Ƃ������V�J�S���y��w�̋��t���N���V�b�N�̊�b��@�����ށB�O�b�h�}���́A�v���t�҂Ƃ��Ċ������n�߂�12�̂Ƃ��ɂ͊��ɃN���V�b�N�̑t�@��g�ɕt���Ă����̂ł���B
�@1932�N�A���Ȃ̊y�c�������B1935�N�ɂ̓p���}�[�E�{�[�����[���̐��������������ɐl�C�������B�u�X�C���O�̉��l�v�Ƃ��ăW���Y�E��Ȋ�����悤�ɂȂ�B�o���h�����Ɋւ���Ă����̂��W�����E�n�����h�i1910�|1987�j�B�ނ́A�O�b�h�}���͂��߃r���[�E�z���f�C�A�J�E���g�E�x�C�V�[�A�{�u�E�f�B������@�A�ĉ��y�E�ɂ������v���f���[�T�[�Ƃ��ėE����y���邱�ƂɂȂ�B���݂ɔނ̖��A���X�̓O�b�h�}���̍Ȃł���B
�@�n�����h�͂܂����炪�r�I����e���قǂ̃N���V�b�N�ʂŁA�v�����̃s�A�m�̘r������e��Ƌ��Ƀj���[���[�N�̎���ł悭���T�C�^���E�p�[�e�B�[���Â��Ă����B1935�N�̏H�A����ɎQ�������O�b�h�}���̓n�����h�̃J���e�b�g�Ƌ��Ƀ��[�c�@���g�́u�N�����l�b�g�d�t�ȁv�����t�����B�����Ńn�����h�̓O�b�h�}���ɂ��������B�u�Ȃ��x�j�[�A�N�̃N�����l�b�g�̘r�͖{�����B���j�̐A�����J�ł́A�N���V�b�N�̓V���A�X�i�{�i�I�A�����j�A�W���Y���|�s�����[���y�̓��C�g�i�y���A�ᑭ�j�Ƃ����Ό����܂��܂����[���B�N�������̉��y����邱�Ƃɂ���āA���̕ǂ�˂��j��b�ɂȂ�Ί��������v�B���̌�A�O�b�h�}���̃W���Y�ƃN���V�b�N�̓��͖{�i������B�{�Ƃ̃W���Y�ł́A1938�N�A���́u�J�[�l�M�[�z�[���E�R���T�[�g�v�ŃL�����A�̐Ⓒ��z���A����A�N���V�b�N����ł̊������ۗ����Ă���B
�@�����A�����J�ɈڏZ���Ă��������o���g�[�N�́A�u���@�C�I�����A�N�����l�b�g�ƃs�A�m�̂��߂̃R���g���X�c�v�i1938�N�j����ȁA�O�b�h�}���Ɩ����@�C�I���j�X�g ���[�[�t�E�V�Q�e�B�Ɍ��悵�Ă���B���̍�i�́A�ނ�3�l�ɂ�郌�R�[�f�B���O�����邪CD���͂���Ă��Ȃ��B�q���f�~�b�g�̃N�����l�b�g���t�Ȃ̓O�b�h�}���̈Ϗ���i�B�����āA�N�����l�b�g�̐�ΓI���ȃ��[�c�@���g�́u�N�����l�b�g���t�ȁv�Ɓu�N�����l�b�g�d�t�ȁv��RCA�ɘ^�������茻�݂ł��������Ƃ��ł���B���̑��������ʼn��t������i�Ƃ��ẮA�E�F�[�o�[�́u�N�����l�b�g���t�ȑ�1�ԁ���2�ԁv�A�N�����l�b�g�����t�ȁA�u���[���X�̃N�����l�b�g�d�t�ȁA�\�i�^��1�ԁA��2�ԁA�h�r���b�V�[�́u�����ȑ�1�ԁA�j�[���Z���́u�N�����l�b�g���t�ȁv�A�X�g�����B���X�L�[�́u�G�{�j�[�E�R���`�F���g�v�A�~���[�́u���@�C�I�����A�N�����l�b�g�ƃs�A�m�̂��߂̑g�ȁv�A�R�[�v�����h�́u�N�����l�b�g���t�ȁv�A�o�[���X�^�C���́u�v�������[�h�A�t�[�K�ƃ��t�v�ȂǁA�����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B
�@�����̎����́A�O�b�h�}���������ɃN���V�b�N���y�ɐ��ʂ���M���X���Ă��������B�����A�O�b�h�}���ɂ�����N���V�b�N���y�́A�����薼�𐋂����W���Y�E�}���̕Ў�Ԃȍ�Ƃł��A�R�}�[�V�����Y���ɗx�炳�ꂽ�L�����m�Ȃǂł͌����ĂȂ��A�ꉹ�y�ƂƂ��Ă̐^���ȍs�ׂ��̂��̂Ȃ̂ł���B
���[�c�@���g��ȁF�N�����l�b�g���t�� �C���� K622
�@�@�x�j�[�E�O�b�h�}���i�N�����l�b�g�j �V�������E�~�����V���w���F�{�X�g�������y�c
�@�@1956�N7��9���A�^���O���E�b�h �o�[�N�V���[���y�ՃR���T�[�g�z�[���ł̘^��
 �@����CD�͌����Ƃ��Č��ݒ������Ƃ��ł���B����A���߂Ē����Ă݂����f���炵�����t�ł���B���킩�[���ȘȂ܂��̒��ɗ͋����Ɛߓx����̐S���▭�ɓ��������\���͐^�ɐ����͂�����B�~�����V���F�{�X�g�����̂�═���ȕ\��C�ɂ͂Ȃ邪�A�Ƃ͂����A���x�̍�����l�̋����̓��[�c�@���g�ŔӔN�̋��n�̈�ʂ�I�m�ɕ\�o����B
�@����CD�͌����Ƃ��Č��ݒ������Ƃ��ł���B����A���߂Ē����Ă݂����f���炵�����t�ł���B���킩�[���ȘȂ܂��̒��ɗ͋����Ɛߓx����̐S���▭�ɓ��������\���͐^�ɐ����͂�����B�~�����V���F�{�X�g�����̂�═���ȕ\��C�ɂ͂Ȃ邪�A�Ƃ͂����A���x�̍�����l�̋����̓��[�c�@���g�ŔӔN�̋��n�̈�ʂ�I�m�ɕ\�o����B�@���̋Ȃ͖��Ȃɂ������������B�E�B�[�����T��ȍ���̃v�����c�A�I�m�ȃe�N�j�b�N���猘���ȕ\���������郉�C�X�^�[�A�ߓx�����ă��}���e�B�b�N�ȃV�t�����A���X�B�����̒��ŁA�O�b�h�}���̉��t�́A�Z�p�ƕ\���͂ɂ����āA�܂��������F�͂Ȃ��B����̂̓t���[�o�[�̈Ⴂ�����B����͂����D�݂̖��ł���B�䂪�t�E�Έ�G�搶�́u�N�����l�b�g�̖��l�͐��������A���[�c�@���g�̋��t�Ȃőf���炵���̂́A�Â��̓��W�i���h�E�P���A���I�|���g�E�E���b�n�A�x�j�[�E�O�b�h�}���B�����ł̓��`���[�h�E�X�g���c�}�����v�ƒ����u���[�c�@���g�E�x�X�g101�v�̒��ŏq�ׂĂ�����B�M������Έ�搶���A�v�����c�����C�X�^�[�������u���āA�O�b�h�}���̖��������Ă���̂͒��ڂɒl����B�ނ̃N���V�b�N���z�����m�̏ł���B
�@�Ƃ��낪���̉��t�̕]���́A�������A����قǖF�������̂ł͂Ȃ������B�����̃��R�[�h�]������̂ŁA�������ē]�ڂ���B
���̗F�l���u������O�b�h�}���Ƃ����z�̓W���Y�̃v���[���[����B�����烂�[�c�@���g�Ȃ�ėǂ��킯�Ȃ����v�ƌ������B���ȂÂ�����Ƃ���͂���B�O�b�h�}���̓��Y����������邱�Ƃ��x�����A�T�d�ɂ����ē��O�ɉ��t���Ă���B�]���āA���□�͂Ȃ����A��{���q�B�Ƃ͂����A�~�����V������������Ђ����߂Ă��邽�߂��A�v���̂ق��ǂ������B�Жʂ́u�N�����l�b�g�d�t�ȁv�ŁA���{�ł��̓�Ȃ̑g�ݍ��킹�͏o�Ă��Ȃ�����A�ʂɂ����Ă��L�Q����Ȃ����낤�B�@����́u���R�[�h�|�p�v1957�N7�����A�ؑ��d�Y���̃��R�[�h�]�ł���B�\�z�ʂ�̒�]���ł���B�u�W���Y�E�v���[���[�����[�c�@���g�Ȃ�Ă������܂����v�Ƃ���N���V�b�N���̏ォ��ڐ����A���A���ƉM����B����͂܂��ɓ����̉䂪����]�E�̈�ʓI�����������̂��낤�B�u�Ȃ�Ƃ�������̂̓~�����V���̂������v�Ƃ����j���A���X�����̕\�ꂾ�B�ł��A�{���ɂ������낤���H ���́A���̉��t�̐����̈��̓~�����V���ł͂Ȃ��O�b�h�}���ɂ��� �Ǝv���Ă���B
 �@�u�x�j�C�E�O�b�h�}������v�Ƃ����f�悪����B�u�O�����E�~���[����v�̃q�b�g�̗��N1955�N�ɐ��삳�ꂽ�A�����J�f��ł���B�薼�ǂ���A�u�X�C���O���v�x�j�[�E�O�b�h�}���̐�����������J�[�l�M�[�z�[���E�R���T�[�g�܂ł̂��悻30�N�Ԃ̕��ꂾ�B�W�[���E�N���[�p�A�e�f�B�E�E�B���\���A���C�I�l���E�n���v�g���A�n���[�E�W�F�[���X��̖��肽���{�l���o��A���t��ʂ��ӂ�ɂ���̂��Ƃɂ����y�����B�����A���̒��ړ_�͕ʂ̂Ƃ���ɂ���B�O�b�h�}���̃��[�c�@���g�Ƃ̊֘A�ł���B������ȉ��ӏ������ŁB
�@�u�x�j�C�E�O�b�h�}������v�Ƃ����f�悪����B�u�O�����E�~���[����v�̃q�b�g�̗��N1955�N�ɐ��삳�ꂽ�A�����J�f��ł���B�薼�ǂ���A�u�X�C���O���v�x�j�[�E�O�b�h�}���̐�����������J�[�l�M�[�z�[���E�R���T�[�g�܂ł̂��悻30�N�Ԃ̕��ꂾ�B�W�[���E�N���[�p�A�e�f�B�E�E�B���\���A���C�I�l���E�n���v�g���A�n���[�E�W�F�[���X��̖��肽���{�l���o��A���t��ʂ��ӂ�ɂ���̂��Ƃɂ����y�����B�����A���̒��ړ_�͕ʂ̂Ƃ���ɂ���B�O�b�h�}���̃��[�c�@���g�Ƃ̊֘A�ł���B������ȉ��ӏ������ŁB�@ ���N����̎t�t�����c�E�V�F�b�v�̑䎌�u���炵����A�x�j�[�B40�N�����Ă����킵��6�N�Œǂ��z���Ƃ́B�������K�Ȃ͂����B���T����̓��[�c�@���g���v�B
�A �O�b�h�}�����W�����E�n�����h�@�Ńv���̃I�P���o�b�N�ɉ��t����̂����[�c�@���g�́u�N�����l�b�g���t�� ��3�y�́@�����h�v�B���ۂ́u�N�����l�b�g�d�t�ȁv�̕����������A�f��ł͌��ʂ��l���Ă�����ɍ����ւ��Ă���B���̐��ۗ������x�j�[�̉�����ڂ̓�����ɂ��������̍ȃA���X�́u�ƂĂ�����������v�ƐS�̓��𖾂����B����ɑ��ăx�j�[�́u���[�c�@���g�̗͂��v�ƕԂ��B
�B �z�[���p�[�e�B�[�ŃO�b�h�}�����u�������[�Y�E�I�u�E���[�v�𐁂������Ƃ̃A���X�̑䎌�u���[�c�@���g�݂����ɔ�����������v�B
�@�W���Y�E�}���̐���杂Ɂu���[�c�@���g�v�Ƃ����䎌��3����o�Ă���B�O�b�h�}���ƃ��[�c�@���g���J�̕\�ꂾ�B
�@����A�~�����V���̏ꍇ�͂ǂ����낤���B1950�N�`60�N��ARCA�̊Ŕw���҂������~�����V���͖c��Ș^�����c���Ă���B���ӂ̃t�����X���͓̂��R�̂��ƂȂ���A�h�C�c���ɂ����Ă��A�o�b�n�A�n�C�h���A�x�[�g�[���F���A�V���[�x���g�A�����f���X�]�[���A�V���[�}���A���[�O�i�[�A�u���[���X�ȂǑ����̃��R�[�f�B���O������B�Ƃ��낪���[�c�@���g�����́A���̒m�����A���̃O�b�h�}���Ƃ̋��t�ȂƁu�t�B�K���̌����v���Ȃ����Ƌɒ[�ɏ��Ȃ��B�~�����V���قǂ̑啨�Ȃ�A�]�߂�����ł��^���ł����͂��B���ꂪ�Ȃ��Ƃ������Ƃ́H �ނ͂���قǃ��[�c�@���g���D�݂ł͂Ȃ��������A�s���肾�����I�H �R���T�[�g�ł̋L�^�͂���̂�����I舂Ȃ��Ƃ͌����Ȃ�����ǁE�E�E�E�E�E�B
�@�b��CD�ɖ߂����B�O�b�h�}���̂���͎��ɒ��J�ŗ��ꂪ�X���[�Y�B�Ђ�A�~�����V���̕\��͂ǂ����f���C�Ȃ������ł��炠��B�O�b�h�}���̕����y���Ƀ��[�c�@���g�I�Ȃ̂��B����͗��҂̃��[�c�@���g�Ƃ̋������ƕ�������I�H �d���ؑ��d�Y���Ƃ͐^�t�̌����ƂȂ����B
���`�b�N�E�R���A�̏ꍇ��
�@�`�b�N�E�R���A�i1941�|�j�̓N���V�b�N���y�������������Ƃ����B���[�c�@���g�ɂ��������Ȃ������Ƃ��B���R�͕ێ�I�Ō`���I�ɉ߂��邩��B�W���Y�̖{���̈�ɃA�h���u������킯������A����͓��R�̊��o�ł���B�Ƃ��낪�ނ̃N���V�b�N�ς���ς�����o�������N����B����́A1981�N�h�C�c�Œ������t���[�h���q�E�O���_�̃��[�c�@���g�̃s�A�m���t�Ȃ̃R���T�[�g�������B�u���̂Ƃ��͐g�̖т��悾�قǃ]�N�]�N�����B���[�c�@���g������Ȃɐ_��I�ɕ����������Ƃ͂Ȃ������B�l�̓O���_���e�����[�c�@���g�ɖ������ꂽ�B�R���T�[�g�̌�A���̂��Ƃ��O���_�ɓ`������A�Ȃ���x�ꏏ�Ƀ��[�c�@���g����낤�Ǝ����|����ꂽ�v�Əq������B�O���_�̃��[�c�@���g�����Ɖ���������̂��͕s�������A�Ƃ������A�ނ�̎v���͂��̂������[�c�@���g�́u2��̃s�A�m�̂��߂̋��t��K365�v�̋����Ō����B�A�[�m���N�[���F�A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�̃I�P���Ń��R�[�f�B���O�i1983�N�j���������Ă���B
 �@�A�[�m���N�[�����A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�ǂ̒e�ނ悤�Ȋy�z�ɏ���āA�v����̂悢�`�b�N�E�R���A�ƈ��S�T�|�[�g���{���O���_�̃R���r�̓��[�c�@���g���o�i���l���Ƃ̂��߂ɍ�����t�̋L�O��I��i��ƕ\������B�A���_���e�y�̝͂R����Ȃ��Ȃ����B�������I�ȃM�����X������I�P�����e���y���C�A�{���v�[�Ղ𗽂��B�A���T���u�����i�i�ɂ����i�������A�A���Q���b�`�{���r�m���B�`�̊ɋ}���݂̖��l�|�͕ʊi�j�B�c�O�Ȃ̂́A�J�f���c�@�������ʂ肾�������ƁB�O���_�̃��[�c�@���g���t�Ɋ��������`�b�N�E�R���A�Ȃ�A���̕����͂܂������A�J�f���c�A���炢�͓Ǝ��̂��̂ł���Ăق��������B
�@�A�[�m���N�[�����A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�ǂ̒e�ނ悤�Ȋy�z�ɏ���āA�v����̂悢�`�b�N�E�R���A�ƈ��S�T�|�[�g���{���O���_�̃R���r�̓��[�c�@���g���o�i���l���Ƃ̂��߂ɍ�����t�̋L�O��I��i��ƕ\������B�A���_���e�y�̝͂R����Ȃ��Ȃ����B�������I�ȃM�����X������I�P�����e���y���C�A�{���v�[�Ղ𗽂��B�A���T���u�����i�i�ɂ����i�������A�A���Q���b�`�{���r�m���B�`�̊ɋ}���݂̖��l�|�͕ʊi�j�B�c�O�Ȃ̂́A�J�f���c�@�������ʂ肾�������ƁB�O���_�̃��[�c�@���g���t�Ɋ��������`�b�N�E�R���A�Ȃ�A���̕����͂܂������A�J�f���c�A���炢�͓Ǝ��̂��̂ł���Ăق��������B�@�����āA�ɂ߂��͏\���N��ɂ���Ă���B
���[�c�@���g��ȁu�s�A�m���t�� ��20�� �j�Z�� K466�A��23�� �C���� K488�v
�@�@�`�b�N�E�R���A�i�s�A�m�j
�@�@�{�r�[�E�}�N�t�@�[�����w���ƃ��H�[�J���F�Z���g�E�|�[�������nj��y�c
�@�@1996�N2���A5���A�Z���g�E�|�[���Ř^��
 �@�`�b�N�E�R���A�����[�c�@���g�����̃s�A�m���t�Ȃ̌���Ɏ��g��CD�̈ӗ~��ł���B�����̓{�r�[�E�}�N�t�@�[����(1950�|)�B�`�b�N���9�ΔN���̃��H�[�J���X�g�ŁA1988�N�ɂ́uDon't Worry, Be Happy�v�őS��No.�P�ƃO���~�[��3�����l���B�N���V�b�N�E�ł������ɃL�����A��ς݁A1994�N����Z���g�|�[�������nj��y�c�̏�C�w���҂ɏA���Ă���B�ِF�̓�l�����Ȃɒ��ށB
�@�`�b�N�E�R���A�����[�c�@���g�����̃s�A�m���t�Ȃ̌���Ɏ��g��CD�̈ӗ~��ł���B�����̓{�r�[�E�}�N�t�@�[����(1950�|)�B�`�b�N���9�ΔN���̃��H�[�J���X�g�ŁA1988�N�ɂ́uDon't Worry, Be Happy�v�őS��No.�P�ƃO���~�[��3�����l���B�N���V�b�N�E�ł������ɃL�����A��ς݁A1994�N����Z���g�|�[�������nj��y�c�̏�C�w���҂ɏA���Ă���B�ِF�̓�l�����Ȃɒ��ށB�@�{�v���W�F�N�g�ɂ��ă`�b�N�E�R���A�͂����q�ׂ�B�u�{�r�[���l���N���V�b�N�̉��y�Ƃł���ȉƂł��Ȃ��B��{�I�ɂ̓W���Y�E�~���[�W�V�������B���ʓ_�͓�l�Ƃ��N���V�b�N����D�����Ƃ������ƁB������l�����̓N���V�b�N�̉��y�Ƃ����Ƃ͈���������ŃN���V�b�N�𑨂��悤�ƍl�����B���[�c�@���g�����t����Ƃ��̓W���Y�Ɠ����悤�Ɏ��R�ȋC�����ɂȂ��B���������̍�ȉƂƂ͈Ⴄ�B���[�c�@���g�̃����f�B�̓W���Y�Ɠ����ŁA���̎��̋C���łǂ̂悤�ɂ����t�ł���v�B
�@�ł́A���C���̑�20��K466�̉��t�ɂ��čl�@���Ă݂悤�B�`���ɂ̓{�r�[�̃��H�[�J�����u�����B�y��I�����ɂ�閳���̃A�J�y���ň����Ȃ��B���������`�b�N�̃s�A�m�E�\���B�Ԓf�Ȃ��I�P�̑O�t�ւƌq����B�I�P�̕\��͏_�炩���Ĕ������B�{�`�����̃s�A�m�E�\���o��܂łɎ��X�s�A�m�����荞�ނ��A����̓C���g������s�A�m�E�\���ɓ����u�ْ̋�����䖳���ɂ���̂Ŕ����Ȃ��B�J���[���C�X�̑O�ɃJ���[�p���͐H�ׂȂ����������B��1�y�͂Ƒ�3�y�͂̃J�f���c�A�͓Ǝ��Ȃ��̂ɒu�������Ă���B�X�p�j�b�V�����i�{�l�k�j�e�C�X�g���a�V���B��2�y�͂͑������̃I���E�p���[�h�B���X�A�y�ȑS�̂��W���Y�I���R���ɖ����Ă���B
�@�����̉��t��͐��y�Ȃ��Ȃ���ΐ��藧���Ȃ������B1783�N3��23���A���[�c�@���g�̎��쉉�t��̃v���O�������₳��Ă��邪�A10�Ȓ�4�Ȃ����y�Ȃł���B�{�r�[�̃��H�[�J���͂����z�N������B
�@���[�c�@���g����������̃R���`�F���g��e���Ƃ��͋C���ɂ���ĉ��t��ς��Ă����Ƃ����Ă���B���ɃJ�f���c�A�ɂ����ẮB�����A���[�c�@���g�̓A�h���u�̖��肾�����̂��B�`�b�N�̃s�A�m�͂���ɑ����Ă���B
�@���̃v���W�F�N�g�͈ꌩ�`����j��悤�Ɍ����邪�A���̓��[�c�@���g�̐��_��h�点�鎎�݂Ȃ̂��B���̂悤�ɁA�A�C�f�B�A�͑f���炵���B�����A���̉��t����͊������`����Ă��Ȃ��B���́H �����͖{�ۂɂ�����`�b�N�̃s�A�m�̋Z�ʂɊւ���Ă���B
�@�^�b�`���Â��B�G�b�W�������Ȃ��B�������������B����̃����n�����Ȃ��B���ɋP�����Ȃ��B�A�S�[�M�N���s���R�B�ʐ^������ƃX�^�C���E�F�C�̂悤�����o�Ă��鉹�̓t�H���e�E�s�A�m���B�Ƃɂ������ɂ���{�ł���Ȃ��̂��̂̉��t���S���ƂȂ��̂ł���BK365�ł̓O���_�̃T�|�[�g�Ɗy�Ȃ̓�Փx�ɂ���ĉB����Ă����^�̎��͂��A�c�O�Ȃ��獡��I�悵�Ă��܂����̂ł���B
�@���Ȃɂ͖��Ղ������BK466�ɂ̓J�[�]�����u���e���AK488�ɂ̓J�[�]�����Z���B����璴�h���̖����ɂ͔䂷�ׂ����Ȃ��A�����x�̐����ɂ������y�Ȃ��B
�@�`�b�N�E�R���A�ƃ{�r�[�E�}�N�t�@�[�����̃��[�c�@���g�E�v���W�F�N�g�B�A�C�f�B�A�͑f���炵���������A�\���͂����ڂ��Ȃ������B�u�ِ̍���������g�����v�ł���B���[�c�@���g��������ǂ��e�������H�ǂ�ȃR���T�[�g���\���������H�@�ނ�̓�����������͂܂��Ƃ��ł���B���̓����A�C�f�B�A�ƕ\�������v���������x�̍����p�t�H�[�}���X�̎��������������̂ł���B
�@������グ����̃��[�c�@���g�B�O�b�h�}���̃N�����l�b�g���t�Ȃƃ`�b�N�E�R���A�̃s�A�m���t�ȁB�O�b�h�}���͑�ꋉ�̓��Ŋј^�����������A�R���A�͖���N�Ɏ~�܂����B�u�X�C���O���v�̏̍��͈ɒB����Ȃ������̂ł���B
���Q�l������
�x�j�[�E�O�b�h�}���̃��[�c�@���gK622 CD�̃��C�i�[�m�[�c�i����I�O�a���j
�`�b�N�E�R���A�̃��[�c�A���gK466��K488 CD�̃��C�i�[�m�[�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g�j�[�E�V���[�}�����A�ߓ����m��j
���[�c�@���g�E�x�X�g101�i�Έ�G�ҁA�V���فj
�f��u�x�j�C�E�O�b�h�}������vDVD
2019.08.16 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X1
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�W���Y�̖���̓N���V�b�N�̖��Ȃ��ǂ������������H
�@1956�N6��26���A�V�˃g�����y�b�^�[ �N���t�H�[�h�E�u���E���i1930�|1956�j����ʎ��̂Ŗ��𗎂Ƃ����B25�A�Ⴗ���鎀�������B���ɂƂ���626�Ƃ��������͓��ʂȈӖ�������B�䂪���y�����̃��C�t�E���[�N�ł��郂�[�c�@���g�u���N�C�G���v�̍�i�ԍ����P�b�w��626������ł���B �@�u�P�b�w���v�i���R�䒘�j�Ƃ�������������B�^�C�g���ǂ���A���[�c�@���g�̍�i�ԍ��P�b�w�������ɓW�J����鉹�y�����T�X�y���X�ŁA�㉺��900�ŗ]�̒��҂ł���B
�@�u�P�b�w���v�i���R�䒘�j�Ƃ�������������B�^�C�g���ǂ���A���[�c�@���g�̍�i�ԍ��P�b�w�������ɓW�J����鉹�y�����T�X�y���X�ŁA�㉺��900�ŗ]�̒��҂ł���B�@����̖`���A�k�t�����X�̓J���[�̊C�݂Ńh�[�o�[�C���Ɍ������Ďw��������j���o�Ă���B��������Ă��鏗������B�j�̓C�M���X������{�A�邽�߁A�C�H�C����n�邪�A��s�@�̔ԍ���626���Ƃ��āA��炸�ɂ܂��J���[�Ɉ����Ԃ��Ă���B�����Œj�Ə��͍ĉ�B�u�ƂĂ�626�Ƃ����ԍ��̔�s�@�ɂ͏��Ȃ��v�Ƙb���j�����́u�ς�����l�v�Ǝv���B���R�o�������l���������݂��̉ߋ��̒��Ŕ������Z���ɂȂ����Ă����B��l����x�ڂɉ�͕̂���̃��X�g�ɂȂ�̂����A�����Ɏ���܂łɍĎO�̎E�l���������̍s����X�ŋN����B�����ɂ͕K���P�b�w���ԍ����֗^���Ă����E�E�E�E�E�Ƃ܂��A����ȗ���̏����ł���B
�@�����Ƃ����P�b�w���ԍ����o�Ă���B���̐�70�]�B����̓��[�c�@���g�����̃E�B�[���A�U���c�u���N�A�v���n�A�}���n�C���A�x�������A�p���B�܂��A�A�}�f�E�X���s�ЁA�W���X�}�C���[�搶�A���q�̃A���C�W�A�A�h���i�E�A���i�i�����A���i�j�A�e�L�t�B�K���A�i���l�������[�c�@���g�ɓZ��閼�O���p�ɂɓo��B�o��l���ɂ̓t���[���C�\���̉��������B�����́A�M�҂̕��X�Ȃ�ʃ��[�c�@���g���̏��낤�B����A���X�r�A���̕`�ʓ��Z���ȑ��ʂ����邯��ǁA���[�c�@���g�D���ɂ̓P�b�w�����݂����ŏ\���Ɋy���߂�B
�@�u�P�b�w���ԍ��ɂ͐��E�̓�����������B����Ă���B���[�c�@���g�̉��y�͐_�������Ɏp��ς��ĉ�X�l�ނɔ��M���ꂽ���b�Z�[�W���v�B����͏������ɂ���\�������A����̗��ꂩ��A�Ȃ�ƂȂ�����Ȋ��������Ă���B�u�f���̓䂪������Ƃ��F���̐X�����ۂ��𖾂����v�Ƃ���u�����̗��_�v�ɂ��ʂ���悤�Ɏv���Ă��邩��s�v�c�ł���B
 �@�u�N�����m�v����́A�N���t�H�[�h�E�u���E���̖����ł���626�Ɓu���c���N�vK626�ɏ���Ɉ����������A�W���Y�ƃN���V�b�N�̊֘A���ɂ��čl���Ă݂悤�B�����̗͗ʂ��炵�āA�~�����Ă��d�����Ȃ�����[���肹���ɋC�y�Ɏ��g�����A�Ȃǂƍl���Ă������A���T�C�g�̎�ɎҁE�쓈���ێ����狻���[�����X�g�������Ă����I
�@�u�N�����m�v����́A�N���t�H�[�h�E�u���E���̖����ł���626�Ɓu���c���N�vK626�ɏ���Ɉ����������A�W���Y�ƃN���V�b�N�̊֘A���ɂ��čl���Ă݂悤�B�����̗͗ʂ��炵�āA�~�����Ă��d�����Ȃ�����[���肹���ɋC�y�Ɏ��g�����A�Ȃǂƍl���Ă������A���T�C�g�̎�ɎҁE�쓈���ێ����狻���[�����X�g�������Ă����I�@���͎��̃W���Y�̎t���ł���B�����ăN���t�H�[�h�E�u���E���̑�t�@���ł���B�����烁�[���ł̔ނւ̌Ăт����́gBrownie�쓈�h���ł���B�W���Y�Ɋւ���^�₪�������炷���ɔނɐu���B100���K�ȕԓ�������B����͌l�I�ɐ����Ǝv���B���͂܂��A���̑씲�ȉp��́����͗͂ŃW���Y�̖����𑽐��|��A�u�}�C���X�E�f�C���B�X�w�J�C���h�E�I�u�E�u���[�x�n��p�v�iDU BOOKS�j�A�N���t�H�[�h�E�u���E���u�V�˃g�����y�b�^�[�̐��U�v�i���y�V�F�Ёj��������A�����̓~���[�W�b�N�E�y���N���u�܍ŗD�G�o�ŕ���܂�Amazon���y����x�X�g�Z���[�̑�1�ʂɋP���ȂǁA�܂��Ɏz�E�̌��Ђł���B����͌��I�ɐ����B
�@�����Ă������X�g�iB's List�Ɩ��t����j�ɂ́A�W���Y�E�v���C���[���^�������N���V�N��35�_���L�ڂ���A���^�A���o�������L����Ă���B�P�s�{�̊��̂��߂ɍ쐬�������̂��Ƃ��B����͎��ɂ��肪���������B�}�C���X�E�f�C���B�X�A�W�����E�R���g���[���A�\�j�[�E�������Y�A�f���[�N�E�G�����g���Ȃǃr�b�O�E�l�[�����ڔ������B�ނ炪�N���V�b�N�Ȃ��ǂ��������Ă��邩�H���X�g�����Ă��邾���Ń��N���N����B����A����𗘗p���Ȃ��Ƃ����I�����͂Ȃ��I
�@�܂��́AB's List�̒�����ʔ������Ȃ��̂��B�C�P�����Ȃ��̂�I�ԁB������u�W���Y�̖���̓N���V�b�N���Ȃ��ǂ������������H�v�Ƃ��Ċ���A�p�^�[��A�Ƃ���B���ɁA���X�g�𗣂�A�u�W���Y�̖���N���V�b�N���Ȃ����t�v�Ƒ肵�A�W���Y�E�v���C���[�̃N���V�b�N���ȃ\�m�}�}���t��]�_�B������p�^�[��B�Ƃ���B�Ō�́u�W���Y�^�N���Z���̎��݁v�Ƒ肵�āA�W���Y�ƃN���V�b�N���y�Z���̎��݂���i���̊ϓ_����l�@�B������p�^�[��C�Ƃ���E�E�E�E�E����Ȍv�悪�����ɏo���オ��BBrownie���ʂɑ労�ӂł���B
�@626�Ƃ��������łȂ������u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X�B�O�҂��W���Y�A��҂��N���V�b�N�̏ے��Ƃ��đ����A���҂̊֘A����T�闷�ɏo�悤�B����͏�L3�̂����p�^�[��A�ɂ��Ę_���Ă݂����B
���p�^�[��A���W���Y�̖���̓N���V�b�N���Ȃ��ǂ������������H
 �@ B's List�ōŏ��ɖڂ��������̂��W�����E�R���g���[���u���B���A�v�ł���B�u���B���A�v�̓��n�[���̊�̌��u�����[�E�E�B�h�E�v��2���`���ŁA�z�C�Ȗ��S�l�n���i���̂��ˋ�̌̍��|���e���F�h���`���̃��u�E�\���O�B���}���e�B�b�N�Ŗ��͓I�ȃA���A�ł���B
�@ B's List�ōŏ��ɖڂ��������̂��W�����E�R���g���[���u���B���A�v�ł���B�u���B���A�v�̓��n�[���̊�̌��u�����[�E�E�B�h�E�v��2���`���ŁA�z�C�Ȗ��S�l�n���i���̂��ˋ�̌̍��|���e���F�h���`���̃��u�E�\���O�B���}���e�B�b�N�Ŗ��͓I�ȃA���A�ł���B�@����́A��N�������ꂽ�R���g���[���̖����\�A���o���A���̖����u�U�E���X�g�E�A���o���v�Ɏ��^����Ă���B�p�[�\�l���́A�R���g���[���its�j�A�}�b�R�C�E�^�C�i�[�ip�j�A�W�~�[�E�M�����\���ib�j�A�G�����B���E�W���[���Y�ids�j�B�g�����̃J���e�b�g�h�ł���B�^����1963�N3��6���B�u�W�����E�R���g���[�����W���j�[�E�n�[�g�}���v�̃��R�[�f�B���O�̑O���ł���B
�@�W�����E�R���g���[���i1926�|1967�j�́A1960�N�A�}�C���X�̃O���[�v�𗣂�Ǝ��̓�����ݎn�߂�B�u�}�C�E�t�F�C���@���b�g�E�V���O�X�v�i1960�N10���^���j�ł́A�\�v���m�E�T�b�N�X����ɑ㖼���g�V�[�c�E�I�u�E�T�E���h�h�œƎ��̐��E�𐄂��i�߁A�A���@���E�M�����h�F�Z���ӗ~��u�C���v���b�V�����Y�v�i1961�^62�N�^���j�A����ɂ̓q�b�g��u�o���[�h�v�i1961�^62�N�^���j�A�����āA��L�A�ِF�̃��H�[�J���̖��Ձu�W�����E�R���g���[�����W���j�[�E�n�[�g�}���v���A�����閼�Ղ����X�ɐ��ݏo���Ă䂭�B����ȑ����ɘ^�����ꂽ�̂��u�U�E���X�g�E�A���o���v���^�̋Ȃ����ł���B���n�[���́u���B���A�v�A�i�b�g�E�L���O�E�R�[���̃q�b�g�ȁu�l�C�`���[�E�{�[�C�v�A����̃I���W�i����2�ȁA�u�C���v���b�V�����v�̒Z�k�ŁA���X�A�f�͓I�őS�̓I���ꊴ�Ɍ�����B�����n���I�o�����̃o�����X�iBoth Directions at Once�j �Ƒ�������������邪�A����قǂ��������Ȃ��̂ɂ��v���Ȃ��B�ꖇ�̃A���o���Ƃ��Ă܂Ƃ܂����^���ł͂Ȃ������A�ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ��낤���B50���N���̊ԁu�I�N���v�ƂȂ��Ă����̂͂��̂��߂��낤�B
�@�����̒��ł́A��͂�u���B���A�v���o�F�ł���B������̋Ȃ����ԃA���o���u�o���[�h�v�̐��k�ɂ܂�������Ƃ͎���قɂ��郊���b�N�X�������܂�Ȃ������B���̃X�g�C�b�N�ȃR���g���[��������Ȓ��Ղ������������Ă����̂��A�Ǝv���B�ْ����ɖ������A���o���Q�̒J�Ԃɍ炢����ւ̉Ԃ̎�B
�@�R���g���[���́u���B���A�v���̌��́A13�̂��냉�W�I�Œ������A�[�e�B�E�V���E�y�c�̉��t�������������i����ɐ旧���ă|�[���E�z���C�g�}�������グ�Ă���j�B���t�ɋ��D��������̂͂��̂��߂����B�u�����[�E�E�B�h�E�v�̏�����1905�N�B��������A���n�[���`�|�[���E�z���C�g�}���`�A�[�e�B�E�V���E�Ɨ���A1963�N�ɃR���g���[�����^���B���A�S�n�悭�������Ƃ��ł���B���̉���̃����[�����N���^�W���Y�E�t�@�������ɐs����Ƃ������̂��B
 �@���́A�R���g���[���Ƒo���̋��l�\�j�[�E�������Y�i1930�|�j�ł���B���N�����̔ނ����������Ƃ����̂������BB�fs���X�g�ɂ͂Ȃ���`���C�R�t�X�L�[�F������ ��6�� �u�ߜƁv ��1�y�� ��2���������B����YouTube�Œ����Ă݂�B�p�[�\�l���́A�������Y(ts)�A�W�~�[�E�N���[�������h(tb)�A�M���E�R�M���X(p)�A�E�F���f���E�}�[�V����(b)�A�P�j�[�E�f�j�X(ds) �B���^�A���o���́u�\�j�[�E�������Y�E�v���C�Y�v��1957�N�̘^���B1957�N�̓������Y�̑S�����ɂ�����A�̐S���郔�B���B�b�h�ȃv���C�͑f���炵���B���{��^�C�g���́u�ߜƁv����A�z���郁�����R���b�N�ł͂Ȃ��A�gpathetique�h�{���̈Ӗ��ł���g�����I�ȁh�p�t�H�[�}���X���������B�������Y�͂܂��A�N���V�b�N���y�ւ̋����ʂ��̂�����A1986�N�ɂ̓W���Y�^�N����Z�������u�e�i�[�E�T�b�N�X�ƃI�[�P�X�g���̂��߂̋��t�ȁv����ȁE���t���Ă���B
�@���́A�R���g���[���Ƒo���̋��l�\�j�[�E�������Y�i1930�|�j�ł���B���N�����̔ނ����������Ƃ����̂������BB�fs���X�g�ɂ͂Ȃ���`���C�R�t�X�L�[�F������ ��6�� �u�ߜƁv ��1�y�� ��2���������B����YouTube�Œ����Ă݂�B�p�[�\�l���́A�������Y(ts)�A�W�~�[�E�N���[�������h(tb)�A�M���E�R�M���X(p)�A�E�F���f���E�}�[�V����(b)�A�P�j�[�E�f�j�X(ds) �B���^�A���o���́u�\�j�[�E�������Y�E�v���C�Y�v��1957�N�̘^���B1957�N�̓������Y�̑S�����ɂ�����A�̐S���郔�B���B�b�h�ȃv���C�͑f���炵���B���{��^�C�g���́u�ߜƁv����A�z���郁�����R���b�N�ł͂Ȃ��A�gpathetique�h�{���̈Ӗ��ł���g�����I�ȁh�p�t�H�[�}���X���������B�������Y�͂܂��A�N���V�b�N���y�ւ̋����ʂ��̂�����A1986�N�ɂ̓W���Y�^�N����Z�������u�e�i�[�E�T�b�N�X�ƃI�[�P�X�g���̂��߂̋��t�ȁv����ȁE���t���Ă���B�@�������Y�́A�N���t�H�[�h�E�u���E���Ƃ̘^�������Ȃ��炸���邪�A�u���A�E�X�^�f�B�E�C���E�u���E���v�i1956�N�^���j�Ɋ܂܂��3�̃p�t�H�[�}���X�������B�G���[�V���i���ȃu���E���̃g�����y�b�g�ƍ����ȃ������Y�̃e�i�[�E�T�b�N�X���}�b�`���đf���炵���B
�@�������Y�ƃu���E���͓����N�ŁA����626�Ȃ���ł���ʈ���������B�u���E�����t�B���f���t�B�A�̎����V�J�S�Ɍ������r���A��ʎ��̂Ŗ��𗎂Ƃ����̂�1956�N6��26���ł��邪�A���̐����O�܂œ����X�e�[�W�i���@�[�W�j�A�B�m�[�t�H�[�N�̃R���`�l���^���E���X�g�����j�ɗ����Ă����̂����h���}�[ �}�b�N�X�E���[�`�������B���[�`�̓������Y�Ƃ̃��R�[�f�B���O�̂��߈ꑫ��Ƀj���[���[�N�Ɍ������Ă���B�����āA6��22���A����������l�́A�g�~�[�E�t���i�K���ip�j�A�_�O�E���g�L���X�ib�j�Ƌ��ɁA����u�T�L�\�t�H���E�R���b�T�X�v��^�������B6��22���ɗ��j�I���Ղ��₵���������Y�ƃ��[�`�A����A6��26���ɖ��𗎂Ƃ����u���E���BK622�́u�N�����l�b�g���t�ȁv�AK626�́u���N�C�G���v�B����܂�����Ȏ�荇�킹�ł���B
�@�`���C�R�t�X�L�[�u�ߜƁv�Ȃ���ł�����B�u�ߜƁv�̑�2�y�͂�5�^4���q�ŁA�����Ȃł͂Ȃ��Ȃ������Ȃ����������q�B�W���Y�ł��R�肾���A���̔��q���g������q�b�g�E�i���o�[�ɁA�f�C���E�u���[�x�b�N�E�J���e�b�g�́u�e�C�N�E�t�@�C�u�v�i1959�N�^���j������B������̂̓|�[���E�f�X�����h(as)�ŁA�ނ̃��[�_�[�E�A���o���u�O���b�h�E�g�D�E�r�[�E�A���n�b�s�[�v(1964�N�^��)���^�́u�v�A�[�E�o�^�t���C�v�́A�v�b�`�[�j�̉̌��u���X�v�l�v���C���[�W�����ȁB�̃��m�ł̓T���E���H�[���̖���������i�A���o���u�A�b�g�E�~�X�^�[�E�P���[�Y�v1957�N�^���Ɏ��^�j�B�T���E���H�[���Ƃ����A�u�����@�[�Y�E�R���`�F���g�v�����܂�ɂ��L���B����͈ȑO�AJ.S.�o�b�n�̃��k�G�b�g�g�����̕ҋȔłƂ����Ă������A�ߔN�N���X�e�B�A���E�y�c�H�[���g�̍�i�Ɣ��������B�y�c�H�[���g�̓o�b�n�Ɠ�����̍�ȉƂŁA�o�b�n�����ȃA���i�E�}�O�_���[�i�̂��߂ɍ���Ă�����u���K���v�̒��ɔq�،f�ڂ��Ă������߉i�N�����v���Ă������́B�Ƃ�����A�����4�r�[�g�ɕϊ��E�|�b�v�X�Ɏd���ĂăW���Y�E�V���K�[�̃T���E���H�[���ɉ̂킹���̂̓v���f���[�T�[�̌d��B�f���炵����i�ł���B
 �@���͒鉤�}�C���X�E�f�C���B�X�́u�X�P�b�`�E�I�u�E�X�y�C���v�i1960�N�^���j���B����͕ҋȎ҃M���E�G���@���X�Ƌ����ŃX�y�C���̈�ۂ�Ԃ���5�Ȃ��琬��A���o���B���̖`���̋Ȃ����h���[�S�́u�A�����t�F�X���t�ȁv��2�y�̓A�_�[�W�������`�[�t�ɂ����uConcierto De Aranjuez�v�ł���BH�G�I���A���@��Ƃ߂���18���I�X�y�C���������������h���[�S�ɑ��A�O�N�̃A���o���u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�Ń��[�h��@���ɂ߂��}�C���X�́A����ɉ����A�h���A�A�t���M�A�A�C�I�j�A���̐��@�Ƀu���W���A���E���[�h�܂ł���������o���āA�v�������������ɂ܂Œy�����̂ł���B
�@���͒鉤�}�C���X�E�f�C���B�X�́u�X�P�b�`�E�I�u�E�X�y�C���v�i1960�N�^���j���B����͕ҋȎ҃M���E�G���@���X�Ƌ����ŃX�y�C���̈�ۂ�Ԃ���5�Ȃ��琬��A���o���B���̖`���̋Ȃ����h���[�S�́u�A�����t�F�X���t�ȁv��2�y�̓A�_�[�W�������`�[�t�ɂ����uConcierto De Aranjuez�v�ł���BH�G�I���A���@��Ƃ߂���18���I�X�y�C���������������h���[�S�ɑ��A�O�N�̃A���o���u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�Ń��[�h��@���ɂ߂��}�C���X�́A����ɉ����A�h���A�A�t���M�A�A�C�I�j�A���̐��@�Ƀu���W���A���E���[�h�܂ł���������o���āA�v�������������ɂ܂Œy�����̂ł���B�@�쓈���ۖ�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�n��p�v�ɂ��E�E�E�E�E�}�C���X�́u�X�P�b�`�E�I�u�E�X�y�C���v�̃��R�[�f�B���O���I��������ƁA�u����̒��͋���ۂ������B���̂Ƃ�ł��Ȃ��Z�b�V�������I��������́A���ׂĂ̊�����オ��A���y���C���N��Ȃ������v�Əq�����A���̌��N�ԁA�X�^�W�I�ɓ���Ȃ������A�Ƃ����B����ɁA�u���̃A���o���́A�����̂����V�N�ȃo�b�N�O���E���h�E�~���[�W�b�N�����߂�l�X��������B�����āA����͂܂��ŗǂ̃W���Y�����������ł���ŋ��̉��y�I�A���w�I�����𖡂킢�����Ǝv���l�X���������������v�ƃ}�[�e�B���E�E�B���A���X�͎w�E����E�E�E�E�E���܂�̉ߍ��ȃ��R�[�f�B���O�ɐ��������s���ʂĂ��}�C���X���������A���̉��y�I���ʂ͐�傾�����̂ł���B
�@�t�����X�̃W���Y�E�s�A�j�X�g �W���b�N�E���[�V�F�i1934�|�j�́A1959�N�AJ.S.�o�b�n���̃s�A�m�E�g���I�u�v���C�E�o�b�n�E�g���I�v�������B�����Ɂg�v���C�E�o�b�n�h�̑��l�҂ƂȂ����B�w������A�����̃W���Y�i���ł悭���������̂ł���B�ȗ��A�����o�[�̓���ւ����͂�����̂́A�����܂ň�т��āg�v���C�E�o�b�n�h���т��Ă����B�m���Ɉꎞ����悵���X�^�C���ł���A���L�̝R����͌��݂����A�W���Y�̑�햡�ł���X�����͊Ƃ��킴��Ȃ��B���Ȃ̎p�𗯂߂Ă��߂������炾�낤���B����Ȃ�A�I�X�J�[�s�[�^�[�\���E�g���I���A�A���o���u�v���[�Y�E���N�G�X�g�v(1964�N�^��)�́u�}�C�E�����E�A���h�E�I�����[�E�����v�̃G���f�B���O�ł݂����AJ.S.�o�b�n�u���A�l�̖]�݂̊�т�v�̈�ߑ}���̕����y���ɃW���Y�炵���Đ��ł���B
 �@���Ăǂ�K�ɍT�����́A�f���[�N�E�G�����g���y�c�̃`���C�R�t�X�L�[��ȁu����݊���l�`�v�g���i1960�N�^���j�ł���B����B�fs List���A�ō��ɐH�w�����ꂽ�̂͂���B�f���[�N�E�G�����g���i1899-1974�j�ƃ`���C�R�t�X�L�[�̑g�ݍ��킹�Ȃ�āA�z�������ĂȂ��������̂�����B
�@���Ăǂ�K�ɍT�����́A�f���[�N�E�G�����g���y�c�̃`���C�R�t�X�L�[��ȁu����݊���l�`�v�g���i1960�N�^���j�ł���B����B�fs List���A�ō��ɐH�w�����ꂽ�̂͂���B�f���[�N�E�G�����g���i1899-1974�j�ƃ`���C�R�t�X�L�[�̑g�ݍ��킹�Ȃ�āA�z�������ĂȂ��������̂�����B�@�u����݊���l�`�v�́A�`���C�R�t�X�L�[�ӔN�̃o���G���y�̌���B�n���̋Z�ɂ�鑽�ʂʼnؗ�ȋ����ɔ��������悹�����y�́A�q�ǂ��������̐��E�ւƗU���B���̊����x�̍����I�[�P�X�g���[�V�����ɃG�����g���͂ǂ��Ή������̂��낤���H
�@�u��������̗x��v�́A���Ȃ̃t�@���^�X�e�B�b�N�Ȗ����E����u���[�W�[�ȃX���[�E�X�C���O�̐��E�֓]�����Ă���B����́u���ƒ��̌��z�v�I�e�C�X�g���B���݂Ƀ^�C�g���́gDance Of The Sugar-Plum Fairy�h�ŁA����̌���́gDanse ole la Fee-Dragee�h�B���B�ł́u�h���W�F�v�A�A�����J�ł́u���ߋʁv�A���{�ł́u��������v�B���ʂɑS���Ⴄ�ʌَ̉q�����U�蓖�Ă��Ă���̂��ʔ����B
�@�u�Ԃ̃����c�v�́A���Ȃł͉ؗ�ȏI�ȂƂ��Ė����ɒu����Ă��邪�A�G�����g���̓��X�O�Ɉڂ��y���ȃ_���X�E�~���[�W�b�N�Ɏd���ĂĂ���B�܂�ŁuA��Ԃōs�����v�̃X�C���O���B���{�̕������s��̃_���X�E�z�[���ւ̖��Ȃ�ϊ��ł���B
�@�����čŌ�ɒu�����̂��u�A���r�A�̗x��v�B�G�����g�����L�̃n�[���j�[�Ƒ��l�Ȋy�����g���ăG�L�]�`�b�N�Ȑ��E��`���o���B�A�z����̂̓Y�o���u�L�����o���v�B
�@�`���C�R�t�X�L�[�������������ꂽ����̃`�F���X�^���g���Ȃǂ��č��グ�����ʂʼnؗ�Ŏa�V�ȋ������A�G�����g���͓Ǝ��́g�G�����g���E�T�E���h�h�ɗ��Ƃ����ݑS���ʌ̉����E�����o���邱�Ƃɐ��������B�S9�Ȃ́A���Ȃ̎p���قƂ�Ǘ��߂Ă��Ȃ��A�܂��ɁA�G�����g���E���[���h���̂��̂��BCD�̃N���W�b�g�ɂ͂Ȃ����A�A�����W�ɂ̓r���[�E�X�g���C�z�[�����ւ���Ă���͂����B�N���V�b�N�Ƃ����f�ނ����ăW���Y�Ƃ�����i������n��������l�̋�����ƂɓV����ł���B
�@���p�^�[��A����ʂ��Ċ��������ƁB����́A�N���V�b�N���y�̌��^�𗯂߂Ă�����̂قǂ܂�Ȃ��A�v���C���[�ŗL�̉��y�ɂȂ���Ă�����̂قǖʔ����A�Ƃ������Ƃ��B�W���Y�͂���ς�W���Y�łȂ���ΈӖ����Ȃ��B
���Q�l������
�u�P�b�w���v�㉺�i���R�䒘 ���t���Ɂj
�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�n��p�v�i�A�V�����[�E�J�[�����A�쓈���ۖ� DU BOOKS�j
�W�����E�R���g���[���u�U�E���X�g�E�A���o���vCD���C�i�[�m�[�c
�@�@�@�i�A�V�����[�E�J�[�����A�����d��j
2019.07.13 (�y) ���@��9�������}�����Ă��Ԃ��ׂ�
 �@�Q�@�I�ł���B7��21���A���������N�ɓ��[���悤���H �����s���Ƃ��Ă��ɂȂ������I���ł���B���_�͂��������邪�A�����́u���@���� �����v�����グ�悤�B�ǂ���玩���}�����{�����́A�˂����ƃ{�����o��u�N�����v�����A�R�b�`�ɖڂ�������������������ƍl���Ă���悤���B�u�����Ɍ������Č��@����������c�_������҂�I�Ԃ̂��B����c���̐Ӗ���������đS���c�_���炵�Ȃ��̂���I�ԑI�����v�Ɛ����ɋ��ԁB�����Ǝ��M���肰�ł���B�Ȃ�A�c�_�ɉ���点�Ă����������ł͂Ȃ����B
�@�Q�@�I�ł���B7��21���A���������N�ɓ��[���悤���H �����s���Ƃ��Ă��ɂȂ������I���ł���B���_�͂��������邪�A�����́u���@���� �����v�����グ�悤�B�ǂ���玩���}�����{�����́A�˂����ƃ{�����o��u�N�����v�����A�R�b�`�ɖڂ�������������������ƍl���Ă���悤���B�u�����Ɍ������Č��@����������c�_������҂�I�Ԃ̂��B����c���̐Ӗ���������đS���c�_���炵�Ȃ��̂���I�ԑI�����v�Ɛ����ɋ��ԁB�����Ǝ��M���肰�ł���B�Ȃ�A�c�_�ɉ���点�Ă����������ł͂Ȃ����B�@���@�����ő�̃|�C���g�́u��9���v�ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�����}�̉����Ă��o�Ă���̂ł����������B���̑O�ɂ܂��͌��s�̏��m�F���Ă������B
�����@��9����
1�@���{�����͐��`�ƒ�������Ƃ��鍑�ە��a�𐽎��Ɋ��A���Ђ̔��g����푈�ƕ��͂ɂ��Њd���͕��͂̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��Ă͉i�v�ɂ�����������B
2�@�O���̖ړI��B���邽�߁A���C��R���̑���͂́A�����ێ����Ȃ��B���̌�팠�͂����F�߂Ȃ��B
 �@��1���̃|�C���g�́A�u���ە��������������i�Ƃ��Ắv�̕����ł���B�����ǂݍ��߂A����ȊO�̎�i�����h�q�͍m�肵�Ă���A�Ƃ̉��߂͉\���B
�@��1���̃|�C���g�́A�u���ە��������������i�Ƃ��Ắv�̕����ł���B�����ǂݍ��߂A����ȊO�̎�i�����h�q�͍m�肵�Ă���A�Ƃ̉��߂͉\���B�@��2���̃|�C���g�́A���c�ς�11�����Ƃ�����u�O���̖ړI��B���邽�߁v�̕����ł���B���ꂪ�܂��ɐ▭�B�u�O���̖ړI�v�Ƃ́u���ە��������������i�Ƃ��Ă̕��͍s�g���������v���Ƃ�����A�u���h�q�v�̂��߂̐�͂̕ێ��͂��̌���ł͂Ȃ��A�Ɖ��߂��邱�Ƃ̓M���M���\���B�����A���q���́u���h�q�v�̂��߂ɑ��݂�����荇���Ƃ������Ƃł���A�g�c�����q��������������������ɂ���B
�@�����}���@�������i�{���̂g�o������B��������ɁA�ނ�́u��9�������v�̎v�f���l�@����`���@�w�҂̉ߔ������u���q���͈ጛ���v�ƍl���Ă���A�Ɛ�o������ŁA���@��13���������o���B�����ɂ́u�����A���R�y�эK���Nj��̌����ɂ��ẮA�����̕����ɔ����Ȃ�����A���@���̑��̍����̏�ŁA�ő�̑��d��K�v�Ƃ���v�Ƃ��邩�炵�āA���҂��ɂ���Ă��̌������N�Q���ꂽ�獑�͂����r�����錠�����`����������B�����u���q�̑[�u�v�ł���B���̂��߂̑g�D�Ƃ��Ă̎��q���͍����ł���A���@�ɖ��L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��`�Ƃ����Ȃ�B
�@���̘_���͗]��ɂ��I�߂��邪�A���͂��̂��Ƃ����A�u��9�����̂��̂�������N�����Ȃ��ق����s���������v�Ƃ̍��_�������B�ꂷ�邱�Ƃ��B�O�q�̂Ƃ���A���@��9���́A���߂ɂ��A���h�q�̂��߂̌R���͕ێ��\�Ɠǂނ��Ƃ��ł���B���ꂾ�ƃR�R�~�܂�B�����A�ʓI���q���X�ɂ͏W�c�I���q���ɂ܂Ř_�����y�Ȃ��B������A��13���������o�����Ǝ��͍l����B
�@�����̊ϓ_����A�����}�����Ă������Ă݂悤�B
�����@��9�������}�̂�������f�ā�
1��2���͂��̂܂܂�9���̂P�Ƃ��A9����2��������B
��9��2
1 �O���̋K��͉䂪���̕��a�ƓƗ������A���y�э����̈��S��ۂ��߂��K�v�Ȏ��q�̑[�u���Ƃ邱�Ƃ�W�����A���̂��߂̎��͑g�D�Ƃ��Ė@���̒�߂�Ƃ���ɂ����t�̎�����t������b���ō��̎w���ē҂Ƃ��鎩�q����ێ�����B
2 ���q���̍s���͖@���̒�߂�Ƃ���ɂ�荑��̏��F���̑��̓����ɕ�����B
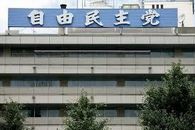 �@���̈ẮA�A���^�}�E�����}�́u�����_�v�ɔz�����Ă���̂͂����܂ł��Ȃ����A�|�C���g�́u�K�v�Ȏ��q�̑[�u�v�Ƃ��������ɂ���B����͎�ς�����₷���A���ʁA��̐��ɖR�����\���ŁA���ꂱ���������}�Ă̑_���Ȃ̂ł���B
�@���̈ẮA�A���^�}�E�����}�́u�����_�v�ɔz�����Ă���̂͂����܂ł��Ȃ����A�|�C���g�́u�K�v�Ȏ��q�̑[�u�v�Ƃ��������ɂ���B����͎�ς�����₷���A���ʁA��̐��ɖR�����\���ŁA���ꂱ���������}�Ă̑_���Ȃ̂ł���B�@�K�v���ǂ��������߂�͎̂��̌��͂ł���B�����ڐ��Łu���������v�Ǝv���Ă����͂��K�v�ƌ��Α[�u���Ƃ��B����������A�������Ɏ�ނ��킸���q�̑[�u���Ƃ��A�Ƃ������Ƃł���B����͊댯�ɂ܂�Ȃ����A�u���h�q�v�݂̂��m�肷�錻�s��9���𖾔��Ɉ�E����B
�@���s��9���́A�O�q�̂Ƃ���A�u���h�q�̂��߂̎��q���v�͐��F���Ă���Ɖ��߂ł���B�ł́u���h�q�v�Ƃ͉����B�h�q�Ȃ̂g�o�ɂ��̋K�肪�f�ڂ���Ă���B
�u���h�q�v�Ƃ�
���肩�畐�͍U�������Ƃ��ɂ͂��߂Ėh�q�͂��s�g���A���̑ԗl�����q�̂��߂̕K�v�ŏ����ɂƂǂ߁A�܂��ێ�����h�q�͂����q�̂��߂̕K�v�ŏ����̂��̂ɂ�����Ȃnj��@�̐��_�ɂ̂��Ƃ����I�Ȗh�q�헪�̎p���������B�@�����Ɏ�����Ă���u���h�q�v�Ƃ́A���肩��U�����Ă͂��߂ĉ\�ƂȂ�h�q�͂̍s�g�̂��Ƃł���A�搧�U����F�߂�u�ʓI���q���v�Ƃ���ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ����A�u�K�v�ŏ����v�Ƃ��������ɂ���Ƃ���A�h�q�́����͂̍s�g��ێ��͕K�v�ŏ����ɂƂǂ߂���̂ł���B�����āA�����͌��@�̐��_�ɂ̂��Ƃ������̂ƌ���ł���B�����A���q�����NJ�����h�q�Ȃ��u���h�q�Ȃ�Ό��@�̐��_�ɂ̂��Ƃ��Ă���v�ƔF�����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@������ɁA�u�����}�����āv�ɂ́u�K�v�ŏ����v�̕������Ȃ���u���h�q�v�̊T�O���Ȃ��B���s���@�Ƃ̐��������������Ƃ͖��炩���B��������͓��R�Ӑ}�������ƁB�ł́A�u�����}�����āv�̖{�ӂ͉��Ȃ̂��H
�������Ăɐ��ސ����̖{�Ӂ�
�@�d�v�|�C���g�́A�ω������u���q�v�̊T�O�ł���A�u�K�v�Ȏ��q�̑[�u�v�Ƃ��������ł���B
�@���q���ɂ͌ʓI���q���ƏW�c�I���q��������B���{�͐��A�W�c�I���q���Ɋւ��āA���̌����ۗ̕L�͔F�������A���@��s�g�ł��Ȃ��Ƃ����O��ň��S�ۏ���l���Ă����B���{�����@�̐���Ɋւ����������d�Y�́A�u���a���@�v���ł̍��̐i�ނׂ����������A��������p�����g�c�́A�T���t�����V�X�R���a���Ɠ��Ĉ��ۏ���������ē��{�̓Ɨ���}��A�o�ϔ��W�ɂ�镜���̑b��z�����W�������B���h�q����u���a���@�v�̕W�Ԃ����A�����{�̕����ɂ����āA�l������ł��L���Ȏ�i�ł���A����Ӗ��m�M�ƓI���������Ȑ헪�������̂ł���B
�@���ꂪ�ߔN�A�Ƃ݂ɕς�����B���Ɋ낤���Ȃ̂ł���B������l�̈Ӑ}�����m�ł����ɁA�ߎ���I���삵�������Ȃ��}�f�Ȏw���҂��������ӂ邤���Q���I�悵�Ă���B����͍��Ƃ̊�@�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@����ł́A2015�N�ɐ��肳�ꂽ���ۖ@���i�u���a���S�@�������@�v�Ɓu���ە��a�x���@�v�j�ł���B����ɂ��A�W�c�I���q���̍s�g���e�F����A���q���̊������������g�傳��邱�ƂɂȂ����B�����́u���̑�������������A�����̐����A���R�y�эK���Nj��̌��������ꂩ�畢����閾���Ȋ댯������v�ꍇ�Ɍ���A�Ƃ̑��g��݂��Ă��邩��A���q���̊������ی��Ȃ��g�傷�邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ɛ�����B������ɁA�u���Ƃ̑�������������邩�ۂ��v���u�����̍K���Nj��̌�����������邩�ۂ��v���A���̔��f�͐������������́B�Ȃ�A�����̈ӌ��ɂ���ďW�c�I���q���͈̔͂��ی��Ȃ��g�傳���댯���͑傢�ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�������킩�肾�낤�B�u�����}�����āv�͌��s���@�Ƃ̐�������Ƃ��Ăł��A�W�c�I���q����e�F����u���ۖ@���v�𐳓�������_��������̂��B
�@�u�����}�����āv�́A�h�����Đ��h�q�܂ŔF�߂��9���ɁA�ʓI���q����ʂ�z���ďW�c�I���q���܂ł����e�F����������悤�Ƃ����A�������̂��̂̂Ƃ�ł��Ȃ��Č��ł���A���ƌ��͂̍s���߂��闧����`�̌����ɂ���������̂��B�ō��@�K���錛�@�ɂ����Ȃ��펯�͋������͂����Ȃ��A���ێЉ�ɑ��Ă��p�����������Ƃ��̏�Ȃ��㕨�Ȃ̂ł���B
�@���{�����͍��N5��3�����@�L�O���̐����Łu���q�����ጛ�ƌ�����̂͐S�ꂵ���B���ׂĂ̎��q�������ւ�������ĔC����S���ł�������������v�Əq�ׂ��B���̑��݂����@�ɖ��L���邱�Ƃɂ���āA�ނ�̑����s�ׂɕ����A�Ƃ������ƂȂ̂����A����͂����܂ł����O�ɉ߂��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̂��߂ɖ���q���ē����������͂�������킯�ŁA�x�@�������h�m��������ł���B�Ȃ�Δނ�̑��݂����@�ɖ��L����̂��H
�@���q���L����̂́A�ނ�̌ւ�d���邽�߂Ƃ��������A���̗��ɂ́A���q�����W�c�I���q���ɂ܂Ŋg�傷�邱�Ƃ����@�ɂ���ė��t�������A�Ƃ�����݂��B����Ă���B����ɂ��A�u���ۖ@���v�������������B�\�ʂ��ꂢ���Ƃ���ׂĐ^�����B���B����̓}���J�V�\�Ԃ̈��{�����̏퓅��i���B�x����Ă͂����Ȃ��B
�@���I���搧�Ƃ����d�g�݂Ɩ�}�̕s�b��Ȃ������Œ����������p��������{�����B���̂܂܂����A11���ɂ́A�j���Y�̍ݔC���ԋL�^2886�����Ďj���1�ʂƂȂ�B�X�ɁA�������͂�����c���̎O���̓���ێ��ł���A�ߊ�̌��@�����̔��c���\�ƂȂ�A�������[���{�ɂ������邱�Ƃ��ł���B��A�̃����J�P��肾�����Ƃ��Ă݂Ă��A�܂Ƃ��Ȑ_�o�̎�����Ȃ�Ƃ����ɐg�������đR��ׂ��Ȃ̂ɁA�p�����������Ȃ���������B����Ȏ�ウ�邱�Ƃ��ł��Ȃ����ǂ������A��Ȃ��A���炵�Ȃ��B �����邩���Ȃ��Ƃ́A�܂��ɂ��̂��Ƃ��B
�@����\�͂Ȃ������}�Ɩ��\�͌����̖�}�ł́A�ނ͂��̂܂ܘA�ȂƐ����̍��ɋ����葱���邾�낤�B����Ȃ��Ƃ������Ă����̂��H �Ȃ�Ƃ���A�������Ă�肽���Ǝv���͎̂������ł͂Ȃ��͂����B�Ȃ�ǂ�����H
���œ|���{������ �t�]�̔��
 �@����̑I���Ŗ�}�ɓ��[���Ă��ǂ��������}�̏����ɏI���A�����ς��Ȃ��͖̂ڂɌ����Ă���B�Ȃ�ǂ�����B���̔��́A������[�������ĉ������͂ɓ�����A�Ƃ����t�]�̔��z�ł���B�����E�����E�ېV�̉������͂����@�����̔��c���ł���O���̓���ێ����Ă��B�����A�Q�c�@�̉������͋c��164���m�ۂ��Ă��̂ł���B�I����A�^�}�͂����̂悤�ɁA���Ă��ׂĂ�M�C���ꂽ�Ƃ��āA���̗͂ɕ������킹�S������������W�J���邾�낤�B�������t���ڂ��B�y���Ȃ鑍����2020�N�̒ʏ퍑��Ŕߊ�́u�������c�āv���o����B�����Ŋ̐S�Ȃ̂́A��}���{���܂����c�_��^���ɐM�O�������Ďd�|���邱�Ƃ��B�u�������v�ł͂Ȃ��A��̓I�ɉ����̑ΈĂ������đ����邱�Ƃ��B�����āA��}������g�݁u��������āv�����B���̂́u�����}�����āv�ɕ킦�����B�Ⴆ����ȕ��ɁE�E�E�E�E
�@����̑I���Ŗ�}�ɓ��[���Ă��ǂ��������}�̏����ɏI���A�����ς��Ȃ��͖̂ڂɌ����Ă���B�Ȃ�ǂ�����B���̔��́A������[�������ĉ������͂ɓ�����A�Ƃ����t�]�̔��z�ł���B�����E�����E�ېV�̉������͂����@�����̔��c���ł���O���̓���ێ����Ă��B�����A�Q�c�@�̉������͋c��164���m�ۂ��Ă��̂ł���B�I����A�^�}�͂����̂悤�ɁA���Ă��ׂĂ�M�C���ꂽ�Ƃ��āA���̗͂ɕ������킹�S������������W�J���邾�낤�B�������t���ڂ��B�y���Ȃ鑍����2020�N�̒ʏ퍑��Ŕߊ�́u�������c�āv���o����B�����Ŋ̐S�Ȃ̂́A��}���{���܂����c�_��^���ɐM�O�������Ďd�|���邱�Ƃ��B�u�������v�ł͂Ȃ��A��̓I�ɉ����̑ΈĂ������đ����邱�Ƃ��B�����āA��}������g�݁u��������āv�����B���̂́u�����}�����āv�ɕ킦�����B�Ⴆ����ȕ��ɁE�E�E�E�E�����@��9���}��������ā�
1��2���͂��̂܂܂�9���̂P�Ƃ��A9����2��������B
��9��2
1�@�O���̋K��́A�䂪���̕��a�ƓƗ������A���y�э����̈��S��ۂ��߂����h�q�̊T�O�Ɋ�Â��A�K�v�ŏ����̎��q�̑[�u���Ƃ����Ƃ�W���Ȃ����̂ł���B���̂��߂̎��͑g�D�Ƃ��āA�@���̒�߂�Ƃ���ɂ��A���t�̎�����t������b���ō��̎w���ē҂Ƃ��鎩�q����ێ�����B�@�u��}��������āv�ɂ́A���̂悤�ɁA�u�䂪���ɂ����鎩�q�̑[�u�Ƃ́g���h�q�h�ł��邱�ƁB���̂��߂́g���s���������q���h�ł��邱�Ɓv�L����B���@��9�����瓱���o�������̘_���͐����ŗh�邬�Ȃ����̂��B�������A���{�������咣���鎩�q���̖��L���������Ă���B�����āA��9���Ƃ͐������̂Ȃ��u�����}�āv�Ɛ^���������̘_�w��̂ł���B
2�@���q���̍s���͖@���̒�߂�Ƃ���ɂ�荑��̏��F���̑��̓����ɕ�����B
�@���̏����́A�ǂ����猩�Ă��u��}��������āv�ɕ�������B���{�������ǂ�Ȃɐ����ɋ���ł��A���̐����������Ƃ͂ł��Ȃ��B�u��}��������āv�͊ԈႢ�Ȃ����I
�@�����ŁA�������͂��������������ł悵�B�����A���̗͂ŋ��s�����c�����炻��͂Ȃ��悵�B�������[�ɓ˓���������B���ʼnɂ���Ă̒��Ƃ͂��̂��Ƃ��B������2020�N�㔼�ƂȂ邾�낤�B�I�����Ԓ��A��}�A���͓O��I�Ɂu�����}�����āv��@���܂���B�����Ȃ���́g��Δ��h�����ׂ����B�u��}��������āv���f���āA�u�݂Ȃ���A��̈Ă�����ׂĂ��������B�ǂ��炪�܂Ƃ����͈�ڗđR�ł��傤�B���q�Ƃ������̍ی��Ȃ��푈�ɓ˂��i�ނ��Ƃ�e�F����w�����}�����āx���ʂ����č����ɍK���������炷�ł��傤���v�ƃL�����y�[����łĂ����B�����Ɓu�������v�̈�僀�[�������g�������N����͂����B�����Ȃ�A�u�����}�����āv�͍������[�ŊԈႢ�Ȃ��ی�����邾�낤�B�����āA����͂܂��A��������瑍�����͐�����g���@���ɏI�~����łh���Ƃɂ��Ȃ�B���ʁA���{���t�͑����E�������͂Ȃ��A�u���ۖ@���v���K�R�I�Ɍ��͂������B�܂��ɁA��ΓI�t�]�̔��I�I��X�����́A�Ō�̍Ō�ŁA���̌��疳�p�Ȉ��{�W�O�Ƃ���������b�Ɉ�A�������Ă�邱�Ƃ��ł���̂��B
�@������A���͍��̂Ƃ���A7��21���̓��[���ɂ͉������͂ɓ��[�������ł���B�����A���̑I���ʼn������͂��O���̓�������A�M�O�̂Ȃ����{�����́u���@�����v����艺���Ă��܂����낤����B���ƈ�T�ԁA�����x�^�[����^���ɍl����B�`���ō���قǖ����I���͂Ȃ��A�ƌ������̂͂����������R�Ȃ̂ł���B
2019.06.25 (��) �����x���̃��c���N�A�����āA�V���������ł̒�
�y�����x���̃��[�c�@���g�u���N�C�G���v�z �@6��8���A�w�K�E�`���[�L�O��q���ɍs�����B�����{��k�Е����x���R���T�[�g�ɎQ�����邽�߂ł���B���s�ψ���͐R�w�@��w������̗L�u�ō\���B���s�ψ��̈�l�A��͕��e�q����̂��U���ŁA2014�N���疈�N���������Q�������Ă��������Ă���B���݂ɁA��͕�����́A�u�N�����m�v�ɂ����x���o�ꂵ�Ă���i���j�A�_�X�g���A�E�z�[���f�B���O�X����c�O��j���̂��o���܂ł���B
�@6��8���A�w�K�E�`���[�L�O��q���ɍs�����B�����{��k�Е����x���R���T�[�g�ɎQ�����邽�߂ł���B���s�ψ���͐R�w�@��w������̗L�u�ō\���B���s�ψ��̈�l�A��͕��e�q����̂��U���ŁA2014�N���疈�N���������Q�������Ă��������Ă���B���݂ɁA��͕�����́A�u�N�����m�v�ɂ����x���o�ꂵ�Ă���i���j�A�_�X�g���A�E�z�[���f�B���O�X����c�O��j���̂��o���܂ł���B�@�����x���R���T�[�g�̑�1���2012�N�B�ȍ~���N�s��ꍡ�N��8��𐔂���B���v���Ɗ�t�����A���A�{��A�����e���̔�Ј⎙�ǎ�����ɑ����Ă���B��k�Ђ���8�N�A���{�����̐S����������K���ڂ݂̎x���������������A�n���ɖ��N���������x����ςݏd�˂Ă���̂́A���h�Ƃ������͂Ȃ��B
�@���N���t�ɐ旧���ė�q���s����B�ȉ�������
�i���@��w�@������ ���J���玁�@�R�w�@��w�̓v���e�X�^���g�E���\�W�X�g�h�̃~�b�V�����X�N�[�������_�B���̃K�E�`���[�L�O��q���ɂ͗��h�ȃp�C�v�I���K�����ݒu����Ă���B���̓I���K���̋����ɏ悹�Čh�i���ɐi�s����B�������A���̓��I�ꂽ�^���̂��̂��A�����N�ǂƐ������B�_��q�ݔ�Вn�ɋF�������x���̌p���𐾂��肤�B
�t�y�@��w�I���K�j�X�g �z��ɓ�����
�O�t
����
�]���̐ď� �u�u�̏�̎�̏\���ˁv��1-2��
�����N�� ���[�}�̐M�k�ւ̎莆 ��3��23-24��
���� �u�߂��͂��Ă���������v
�]���̐ď� �u�u�̏�̎�̏\���ˁv��3-4��
�j��
 �@���N�̃R���T�[�g�́A�֓��^�m���i1stVn�j�A�~���M�Y�i2ndVn�j�A��������Y�i�ula�j�A�{��g�u�iVC�j�e�����琬��}�e�B�A�X�E�X�g�����O�X���t�ɂ�郂�[�c�@���g�u���N�C�G���vK626�������B���́A�}�e�B�A�X�E�X�g�����O�X�́u���c���N�v�͍�N�̕����x���R���T�[�g�ŗ\�肳��Ă����B�Ƃ��낪�A���t����������A���[�_�[��1���@�C�I�������V�������ˑR�̔���œ|��A�}篑���𗊂�ł��̂����A�Ƃ����o�܂�����B���C���́u���c���N�v�͔ޖ������Ă͕s�\�̂��߁A�ȖڕύX��]�V�Ȃ�����ẴR���T�[�g�������B
�@���N�̃R���T�[�g�́A�֓��^�m���i1stVn�j�A�~���M�Y�i2ndVn�j�A��������Y�i�ula�j�A�{��g�u�iVC�j�e�����琬��}�e�B�A�X�E�X�g�����O�X���t�ɂ�郂�[�c�@���g�u���N�C�G���vK626�������B���́A�}�e�B�A�X�E�X�g�����O�X�́u���c���N�v�͍�N�̕����x���R���T�[�g�ŗ\�肳��Ă����B�Ƃ��낪�A���t����������A���[�_�[��1���@�C�I�������V�������ˑR�̔���œ|��A�}篑���𗊂�ł��̂����A�Ƃ����o�܂�����B���C���́u���c���N�v�͔ޖ������Ă͕s�\�̂��߁A�ȖڕύX��]�V�Ȃ�����ẴR���T�[�g�������B�@����Ȃ킯�ŁA���N�́u���c���N�v�͌��y�d���E�ߊ�̃p�t�H�[�}���X�������̂ł���B�y���́A�W���X�}�C���[�ł���Ƀy�[�^�[�E���q�e���^�[���i1780-1851�j����v���������y�l�d�t�ɒu�����������̂��V�������������������A������q�e���^�[�����V���^�m���łł���B
�@�V�������g�̎�ɂȂ�Ȗډ���́A��i�ւ̓��@�A��Ȏ҂ւ̌h���A��Вn�ւ̋F�肪���߂�ꂽ�f���炵�����̂��B���̈ꕔ�������܂�ł݂�E�E�E�E�E�u�w�{��̓��x�̓��[�c�@���g�̊y�Ȓ��ł����Ƃ��h���}�e�B�b�N��������Ȃ��v�A�u�~�����肤��]�����₩�ɉ̂���v�i���R���_�[���j�A�u�A�e�ɕx�����K�I�ȓ]���́A�Ō�́A���炬�ɖ����F��l�ɗ��������v�i���ꂽ�ҁj�A�u�W���X�}�C���[�̕�M�����ł��ɂ߂Ċ����x�������A���[�c�@���g���g���₵���f�ނ̊֗^���傫���Ǝv����v�i�_�̎q�r�j�A�u��1�`2�Ȃ̓]�p�̓��[�c�@���g�̎w���ɂ����̂ƍl�����Ă���A���y�I�ȓ��ꊴ������������v�i���̔q�̏��jetc�E�E�E�E�E�E�����́A��M�≹�y���͂Ɋ�����̕\�������܂݁A���Ɏ����ɕx�݊ܒ~���[���B�M�҂̉��y�I�Z���X�Ɠ��@�͂̐[���A�����āA�����̖L����������������B�m��̃o�����X�̌�����������B
�@��q���Ɍ��̃n�[���j�[���h�i�ɂƂ��ɗH���ɋ����B���k�Ȕ������ł���B�t�҂̐^���Ȏv������Ԃɕ����邩�ȏ�M��瞂�B�y��݂̂̋��������炩�A�z���͂����X�ɂ������Ă��A�]���ɁA�ЊQ���̏�A�k�Ј⎙�ǎ�����̎x���ւ̊��ӕ����z�N��������B��q���ɉ���ꓯ�̎v�����A�Ƃ��ɗ�(Lacrimosa)�ƂȂ�A�Ō�ɂ͉i���̌�(Lux aeterna)�ƂȂ��āA��Вn�Ɍ����Ĕ�ѕ������E�E�E�E�E����Ȏv�������N���Ă��ꂽ�����̉��t�������B���̂悤�Ȋ����̏��^���Ă��ꂽ�V���^�m�����ƃ}�e�B�A�X�E�X�g�����O�X�A�����Ďx���R���T�[�g���s�ψ��̊F���܂ɂ����������ӂ���݂̂��B
�@������Ɏc�O�Ȃ���A������W���X�}�C���[�̃~�X�͐�������Ă��Ȃ������B���́u�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̌��v�ɂ��ẮA2015�N3���`10���̃N�����m�u���c���N�Ɏa�荞�ށv�ɏ����Ă���B����͂����@��Ȃ̂ŁA���̑��������݂����B
�y���c���N�����a�ł̒z
 �@2015�N10��15���N�����m�`���c���N�Ɏa�荞�ށu�����B���ł̌��_�Ɖ����ł̒v�ł́A�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̌��̐����@���Ă����B�ő�̌��Ƃ́u�T���N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�̒������Ⴄ���Ƃł���B�u�w�T���N�g�D�X�x�Ɓw�x�l�f�B�N�g�D�X�x�ɂ�����w�z�U���i�x�͓��������œ������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�E�E
�@2015�N10��15���N�����m�`���c���N�Ɏa�荞�ށu�����B���ł̌��_�Ɖ����ł̒v�ł́A�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̌��̐����@���Ă����B�ő�̌��Ƃ́u�T���N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�̒������Ⴄ���Ƃł���B�u�w�T���N�g�D�X�x�Ɓw�x�l�f�B�N�g�D�X�x�ɂ�����w�z�U���i�x�͓��������œ������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�E�E�E�E�E����̓J�g���b�N�̃~�T�Ȃɂ����錈�ߎ��ł���A�×���O�͈�Ȃ���Ƃ����݂��Ȃ��B����������̂������B���łŁA����B��̐������łƂ�����B�A������ƂĊ��S�ł͂Ȃ��B�����B���ł́A�W���X�}�C���[���ݒ肵�����������̂܂ܓ��P������ł̓��ꉻ�������B����́A�σ���������j�����ւ̓]���ŁA��2�����2�Ƃ������G�Ȃ��́B���̂��߁A3���߂̃u���b�W��݂��Ď���������Ȃ������B���ʁA�o�ߋ�S�̂��u�z�U���i�v�{�̂����i���ԓI�Ɂj�����Ȃ�A�Ƃ����s���R�����Ă��܂����B���������[�c�@���g�̈ӌ��Ɋ��S�ɂ͑����Ă��Ȃ��B�ł͂ǂ����邩�H
�@����́A�u���[�c�@���g�Ȃ炱�������͂��v�Ƃ������_�ɗ����A������ǂ���ɉ�������`�����A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̕σ������Ƃ����������g�����i��1�j�ɕς��Ă��܂��̂ł���B��������A����ׂ��u�z�U���i�v�̒����̃j�����i��2�j�ɖ߂��ɂ́�1�������邾���ōςށB����Ȃ�3���߂��̃u���b�W�͕s�v�A2��������Ύ������B�������u�T���N�g�D�X�v����u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ւ̉������ւ̈ڍs�̓��[�c�@���g�̏퓅�B���ꂪ���̒�Ă������B������u����A�Łv�Ƃ��悤�B
�@�{���V���ɒ���̂͐i�����������ŁA���t���āu����B�Łv�ł���B
�@A�ł��u�T���N�g�D�X�v�̒��������̂܂܂ɂ��āu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒�����ς���A�Ƃ������̂��������AB�ł͋t�Ɂu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒��������̂܂܂ɂ��āu�T���N�g�D�X�v�̒�����ς���A�Ƃ����A�C�f�B�A���B����́uA�ł��X�Ƀ��[�c�@���g���v�ɂ������̂ł���B
�@���[�c�@���g�̃~�T�Ȃɂ́A�\�����鐔�Ȃ̒��ŁA��Ȃł��ʌn���̒����i��n�̏ꍇ�́�n�A�܂��͂��̋t�j�������������́A�����W���X�}�C���[�ł́u���N�C�G���v�̂悤�Ɂ�n�̊y�Ȃ̒��Ɂu�T���N�g�D�X�v�̂悤�ȁ�n�̋Ȃ�������ނ̂��̂͋H�ł���i�����m�����A���̂悤�ȗ��J.S.�o�b�n�u�~�T�ȃ��Z���v�ɂ��邭�炢�ł���j�B�]���Ă`�ł͂܂����[�c�@���g�̈ӌ��ɂ͉����̂��B
�@������B�łł���B�u�T���N�g�D�X�v�̒�����σz�����i��3�j�ɂ���v�̂ł���B��������A�u���c���N�v���ׂĂ̋Ȃ��t���b�g�n�ƂȂ��胂�[�c�@���g�I�ɂȂ�B
�@�����ݒ肵����ŁA�u�T���N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v��]�������ɂ��̂܂ܕσz�����i��3�j�Œ��߂�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�i�σ�������2�j�����̒����ɖ߂��ɂ́A��1�����邾���ōςށB�t�ɁA�u�T���N�g�D�X�v�̃z�U���i����1�O�����σ������ɕϊ����Ă����A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�̓\�m�}�}�A�������s�̃W���X�}�C���[�ł̂܂܂ł悢�B�W���X�}�C���[�ł̑��d�Ƃ����ϓ_�Ȃ�A�����炾�낤���B�ł��A���y�̗��ꂩ��͑O�҂�������Ȃ��B
�@���͒�����ς��邱�Ƃɂ��u�T���N�g�D�X�v�̉���̕ω������A���s�j������B�ĕσz�����ւ̕ϊ��͋͂������オ�邾���A�܂����Ȃ����낤�B�V���Ɋy���������قǂ̎����Ȃ��B�������݂�2����������Ώ\���B���ɃV���v���ł���B
�@���������낤���H����A�ł�����ɏ���B�ł̒ł���B���s�ł��D�ꂽ�����łƂ���郌���B���łɔ�ׁA�u���[�c�@���g�Ȃ炱�������͂��v�Ƃ����ϓ_����A����̓��[�c�@���g�̈ӎv�ɍX�ɋ߂��Ȃ����Ǝv���B
�@���[�c�@���g�Ō�̍�i���A���̍ő�̌�肪�K���Ȍ`�Ő�������Ȃ��܂܁A�����N�������ꂽ�B�����B���ł́A�@�����y�̓`���ɂ͑��������A���[�c�@���g�̈ӎv����͉��������B�Ƃ͂����A���ꂪ�W���X�}�C���[�ő�̌��ɂ��ėB�ꐥ��������ł���A���̔ł͑S�����݂Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A���������{�l�Ƃ��Ď��g��ؗD�l�ł́A�@�����y�ɑ��w�[�����y�Ƃ炵����ʁA�}�t���߂ȉ����Ɏ~�܂��Ă���B
�@�u���c���N�v�����[�c�@���g�̈ӎv�ɍł��߂��`�Œ�������A�Ƃ����͎̂��̐��U�̃e�[�}�ł���B���̓x�A�}�e�B�A�X�E�X�g�����O�X�̃R���T�[�g�����������ɁA���̍ő�̃|�C���g�ɂ��āA�قڗ��z�ɋ߂��`�Ō��_�������o���ꂽ���Ƃɑ傢�Ɋ�т������Ă���B�u���N�C�G���v�����܂��200�N�]�̊Ԃɉ��l�̃��[�c�@���e�B�A�������āA���l����������݂��̂��͒m��Ȃ����A�u����B�Łv�́A�ނ�̒N�����C�Â��Ȃ��������@�ł���B���̂Ƃ���A�œK�ɂ��Đ���̕��@�Ǝ������Ă���B�����āA�V���̃��[�c�@���g���K������ł������̂Ɗm�M����B�u�����ˁI���������Ƃ����������v�Ȃ鐺���������Ă�������(��)�B���́u���c���N�v���t����������������Ȃ邱�Ƃ��A�Ɋ肤���̂ł���B
2019.05.25 (�y) ���z�`���O��5����
(1)���E�̉�����̂��� �@���O��5���Ƃ������A�G�ߊO��̏W�����J�ɐ^�ē������B�u�₩���[�h�͂ǂ��ւ��B2100�N�ɂ͓����̋C����44�x�ɂȂ�Ƃ������B������������Ȃ����ǁARay�����You�N�̎���͑�ς��ˁB
�@���O��5���Ƃ������A�G�ߊO��̏W�����J�ɐ^�ē������B�u�₩���[�h�͂ǂ��ւ��B2100�N�ɂ͓����̋C����44�x�ɂȂ�Ƃ������B������������Ȃ����ǁARay�����You�N�̎���͑�ς��ˁB�@����͂��Ă����A5���͎��̐��܂ꌎ�B���N�����͏��a20�N�i1945�N�j5��20�������A���ꂷ�ׂĂ̐�����5�̔{���B���鎞�A���E�̃z�[���������E���厡�����������ƋC�Â��ăn�b�Ƃ����B������́A���a15�N�i1940�N�j5��20�����܂�B�z�[������868�{�̐��E�L�^�����邱�ƂȂ���A�����̂͋L�^�����l�����B���āA�㏬���c�_�C�G�[�z�[�N�X�𗦂��Ă���1996�N5���̂��ƁB�A���̕s�b��Ȃ������Ԃ�ɁA������t�@�������ēɐ������Ԃ����̂ł���B���U�ő勉�̋��J�ɉ�����͖����̂܂܂����Ƒς����B����e���r�ԑg�ŁA�u���̎��A�w���̃����E�A����Ȃ��̓����₪���āx�Ǝv���܂���ł������v�Ƃ̃C���^�r���A�[�̖₢�����ɁA������͂����������B�u�܂������v���܂���ł����B�������Ă����悤���Ȃ��悤�ȕs�b��Ȃ����������Ă�����ł��B���������悭���ɗ��Ă��ꂽ�Ǝv���܂���B���̂Ƃ������Ԃ��Ă��ꂽ�l����ԉ��������Ă��ꂽ��ł��B���̐l�������{���̃t�@���Ȃ�ł��v�B�Ȃ�Ƃ����傫���I �I�R����ԓx�ƕ��O�ꂽ�l�ԗ͂Ɋ������邵���Ȃ������B����ȋy�т����Ȃ��̑�Ȑl���Ɛ��N�������������Ă���B�u�W�Ȃ����낤�v�ƌ����Ă��A�邩�Ɋ��ł���̂ł���B���J���~�肩�����Ă��A������̂悤�Ɏ~�߂���悤�ɂȂ肽�����̂ł���B���݂ɁA���E�_�C�G�[�z�[�N�X�͎�����3�N����{��ɋP���B�_�C�G�[�z�[�N�X�͍����̍ŋ��R�c�\�t�g�o���N�z�[�N�X�ɘA�Ȃ�B�v���A���ē��������͌�̃z�[�N�X�����̋N�_�������̂����m��Ȃ��B
(2)�}�㏸�̍L���J�[�v
�@5���Ƃ����Ό�B��Ƃ����L���J�[�v�B���N�͓��Ɏv�����ꂪ����B�P���Șb�ŁA���ԂƂ̃v���싅���[�O�D�����ăR���e�X�g�ŃZ���[�O���L���ɓ��[���Ă��邾���̂��ƁB�܋��͔��X������̂����A���������ꂾ���̂��ƂŃV�[�Y����ʂ��Ă��싅���y���߂�B
�@���G�A�L���̏o���͍ň��������B�\��������������4��16���̎��_�ł͎؋�8�̍ʼn��ʁB���ꂪ5���ɓ���Ɛl���ς�����悤�ȉ��i���B���ɂ͎�ʂɖ��o���B�܂��Ɍ�ƌ��܂����}�㏸�I �����́A����w�̈�������邱�ƂȂ���A�Ȃ�Ƃ����Ă���C�E��ؐ���(24)�̊o�����낤�B��͍��V�[�Y�����牤����Ɠ����w�ԍ��P��w�������B�ۂ��ڐЂ��Ďキ�Ȃ����Ƃ���ꂽ���Ȃ��B����ȈӒn�����u�ɉ����āA���ݑŌ��O����̃g�b�v��Ɛ肷�鐨���B��������͖̂ܘ_���[�O4�A�e�B�X��3�A�e���Ȃ�������ł��Ă��Ȃ����{�ꂾ�낤�B���v���싅�j���Ђ������Ă��A���[�O3�A�e���ʂ����Ȃ�����{����l��Ȃ������`�[���̓Z���[�O�ł͈���Ȃ��B���N�͂ǂ̃`�[������_��s��ō���͗l�B����Ƃ��L���J�[�v�ɔ����o���Ăق������̂ł���B
 �@�p���[�O�̓\�t�g�o���N�ɓq���Ă��邪�A�ʔ����̂͊y�V�C�[�O���X�ł���B��N�ʼn��ʂ̃`�[�����A���{�A�݂̓Ŕ������Ȃ���A��ʂŊ撣���Ă���B�Ƃɂ����`�[���Ɋ��C������B�I�肪���������Ɩ������Ă���B���Ă��ċC�������������玩�R�ɉ����������Ȃ�B����͕��Ηm��V�ē̎�r�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�ނ͏��␢���39�A�ŔN���ē��B���Z�͂��Ă̖���PL�w���B�⌇�ŃL���v�e���߂��Ƃ����ς���B�����̊ē��ނ̓����͂Ɩ����ȓ��]�����̂��Ƃ����B
�@�p���[�O�̓\�t�g�o���N�ɓq���Ă��邪�A�ʔ����̂͊y�V�C�[�O���X�ł���B��N�ʼn��ʂ̃`�[�����A���{�A�݂̓Ŕ������Ȃ���A��ʂŊ撣���Ă���B�Ƃɂ����`�[���Ɋ��C������B�I�肪���������Ɩ������Ă���B���Ă��ċC�������������玩�R�ɉ����������Ȃ�B����͕��Ηm��V�ē̎�r�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�ނ͏��␢���39�A�ŔN���ē��B���Z�͂��Ă̖���PL�w���B�⌇�ŃL���v�e���߂��Ƃ����ς���B�����̊ē��ނ̓����͂Ɩ����ȓ��]�����̂��Ƃ����B�@�ނ̔\�͂������`���̃Q�[��������B1998�N8��20���A�Ă̍b�q�����X����PL�Ή��l��ł���B����17��9�|7�ʼn��l�����������̂����A���������オ���7�_��D��ꂽ�͍̂��Z����ł͌�ɂ���ɂ����̃Q�[���������B����͂��̂��Ƃ̌�����Ńm�[�q�b�g�m�[������B���A�`�[����D���ɓ����Ă���B
�@���āA���̎�����PL��3�ۃR�[�`�߂��̂��L���v�e�����������B�ނ͉��l�̃L���b�`���[�̓��삩�狅���ǂݎ��A�����̎��́u�s���v�ω����̎��́u�_���v�Ƒ吺���Ŏ҂ɓ`���Ă����Ƃ����B�Ŏ҂ɂƂ��ė���{�[���̋��킪����q�b�g�̊m���͊i�i�ɏオ��B�����̏���̎��т��ӂ݂�ƁA���̃G�s�\�[�h�̐M�ߐ��͍����B
�@���͑��ƌ�A���u�Б�`�g���^�����Ԃ��o�āA2007�N�h���t�g7�ʂŊy�V�ɓ��c������ڗ���������͏o�����A2011�N��͊O�ʍ�����B���ތ�A�y�V�̈琬�R�[�`�`��R�ē`��R�w�b�h�R�[�`���o��2019�N�����R�ēɏA�C�B�v���싅�j��A�ʎZ37���łƂ������тň�R�ēɏ��l�߂��͕̂������B���]�Ɛl�ԗ͂Œ��_���ɂ߂��̂��B�ِF�ē�����y�V�C�[�O���X����ڂ������Ȃ��B
(3)�C���Ȃ���MD���R�[�_�[
�@5���ɂ́A�J�Z�b�g�f�b�L�ɑ�����MD���R�[�_�[�̏C�����ς�œ͂���ꂽ�B���܂�ς�����悤�ɖ��Ă����B�喞���̕����ł���B�^�Ԃ̓\�j�[MDS-S1�B�w�������̂�1996�N8���B�O�N�ɂ�Windows95�����������ȂǁA���傤�ǎ���̕ϊ����������B����䂦��MD�̎����͒Z�������B�C���ɐ������Ԃ������������A���_�I�[�f�B�I��y���̗�؎��ɂ��A���i�̒��B����ς������Ƃ̂��ƁB���܂⊮�S�ɉߋ��̈╨�ɂȂ�ʂĂ��̂�����d�����Ȃ��B����Ȃ��̂��A�Ȃ��C���������Ƃ����A����͂���Ȃ�ɋM�d�ȃ\�t�g�����邩�炾�B
 �@��͓��ږؑ��F�q�̉̂��u�Q�Ԑ߂���l���́v(���c�܂��ƍ쎌�A�l���͐l���)�ł���B���̉�����1981�N�����̃I���W�i���ŃJ�Z�b�g����MD�Ƀ_�r���O�������́B���݂ł͍ő����ڂɂ�����Ȃ����A�����B�ł͂��̉̎����B
�@��͓��ږؑ��F�q�̉̂��u�Q�Ԑ߂���l���́v(���c�܂��ƍ쎌�A�l���͐l���)�ł���B���̉�����1981�N�����̃I���W�i���ŃJ�Z�b�g����MD�Ƀ_�r���O�������́B���݂ł͍ő����ڂɂ�����Ȃ����A�����B�ł͂��̉̎����B
���߂ƌ����ā@�f���Ɉ����@4�s�ځu�߂��獛��v�́u�߂���v�͕����֎~�p��ɂ����s�ł͂��ׂẲ������u��ڍ���v�ƂȂ��Ă���B����͓��R�Ȃ̂����A�u��ڍ���v�ł͖�����������B�n���ȏo��Ȃ�A�u��ڍ���v�͂��������̂ł���B�n���ȏo����������A�����������ɏ��X�ɋC�������X���Đ��ɂ͖ӖړI�ɍ��ꂿ������̂ł���B���̎��Ԍo�܂̋@�����̎��̖��Ȃ̂Ɂu��ڂڂ�v�ł͏����Ă��܂��B�ؑ��F�q�Ղ́A�ŏ��́u�߂���v���������A�����ϗ��K��Ɉ����|�����āA�u��ځv�ɕς����B��䏊���c�܂��ƂɂƂ��Ă���͐؎��N�r���m���������Ƃ��낤�B
���������ā@���̋C�ɂȂ���
�n���ȏo����@�����ɉ�����
�悹�����̂Ɂ@�߂��獛��
�Q�Ԑ߂���@���́@���̐l����
�@��ڂ́A�u���[���X�̃��@�C�I�������t�� ���y�͂̃J�f���c�@����16����W�߂�MD�ł���B���y�F�BK�����炢���������B���@�C�I�����̓C�^���A�̖��胋�b�W�F�[���E���b�`(1918�|2012)�B�܂��u�u�]�[�j�v�̃J�f���c�@���܂ޑS�Ȃ̉��t�i�m�[�}���E�f���E�}�[�w���F�V���t�H�j�A�E�I�u�E�����h�������j�B���������A�����҃��A�q����M���Ƀ��b�`���g�̂��̂܂ō��v16�̃J�f���c�@�����^����Ă���B
�@����MD���Q�l�ɁA�莝����CD��20W�̃J�f���c�@�������Ă݂��B
�����[�[�t�E���A�q��
�@�e�B�{�[�A�k���[�A�I�C�X�g���b�t�A�t�����`�F�X�J�b�e�B�A�V�F�����O�A�O�����~�I�[�A���^�[�A
�@�n�[���A�����Z���Ȃ�14�_
���t���b�c�E�N���C�X���[
�@�N���C�X���[�A���j���[�C���A�t�F���X��3�_
�����b�V���E�n�C�t�F�b�c
�@�n�C�t�F�b�c�A���[�s����2�_
���i�^���E�~���V�e�C��
�@�~���V�e�C��
���}�b�N�X�E���[�K�[�ƃW�����W���E�G�l�X�R
�@�M�h���E�N���[����
�@���[�[�t�E���A�q��(1831�|1907)�����|�I��1�ʁB�����҂̈Ќ��Ƃ͂����z��O�̕肾�����B��̑O�ɂ́A�N���C�X���[�A�n�C�t�F�b�c�A�~���V�e�C��������B���@�f���E���[�s�����h������n�C�t�F�b�c���g���Ă���̂����j�[�N���B
�@�J�f���c�@�́A�I�[�P�X�g�����~�߂ă\���X�g�̋Z�ʂ��֎����邽�߂̘g������A�e�l�e�l�őR��ׂ��Ȃ̂����A���t�҂��Ǝ��ɍ��Ƃ������ꂪ�n�C�t�F�b�c�A�~���V�e�C��������œr��Ă��܂��Ă���̂̓`�g�₵���B
�@����̃��@�C�I���j�X�g�̂قƂ�ǂ����A�q�����g�p���钆�A�M�h���E�N���[�����i1947�|�j����l�䂪���������B�J�������Ƃ̏��^���������A�q�����������A�o�[���X�^�C���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�Ձi1982�N�^���j�ł̓}�b�N�X�E���[�K�[���A�A�[�m���N�[���w���F���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�Ձi1996�N�^���j�ł̓W�����W���E�G�l�X�R���g�p���Ă���B���̓��ِ��������ނ̎������ł���B�܂��A�x�[�g�[���F���̃��@�C�I�������t�Ȃł́A�N���C�X���[�ł��嗬�̒��A�N���[�����ɂ́A�A���t���[�g�E�V���j�g�P�i1980�N�j�Ǝ��g�Łi1993�N�j��2��̘^���������āA���Ɍ�҂̓x�[�g�[���F���̃s�A�m�p�ҋȔłɎ����ꂽ���i�B��قɕ������邪�J�f���c�@�̖{����˂��Ă���B���������Η��N�̓x�[�g�[���F���̐��a250�N�B���̐́A�������A���E�C���[�̖ڋʏ��i�Ƃ��Ĕ����A���ݔp�Ւ��̃s�[�^�[�E�[���L���e���u���@�C�I�������t�ȃs�A�m�Łv�̕�����]�݂����B
(4)�S�ăv���Ə��R�p��
 �@5��19���A���N�̃��W���[��2��E�S�ăv���S���t�I�茠���������B��O�A4���̃}�X�^�[�Y�ŕ����D���𐋂����^�C�K�[�E�E�b�Y�i43�j�̃��W���[�A�e�Ƃ킪���R�p���i27�j�̃��W���[�����e�����҂��Đ���オ�������A�^�C�K�[�͗\�I�����A���R��16�ʂƂ������ҊO��̌��ʂɏI������B�������̂̓u���b�N�X�E�P�v�J(29)�B���̗D���Ő��E�����L���O��1�ʂƂȂ����B��Ԃ���肢�������Ȃ��B�P�v�J����͓����������낤�B
�@5��19���A���N�̃��W���[��2��E�S�ăv���S���t�I�茠���������B��O�A4���̃}�X�^�[�Y�ŕ����D���𐋂����^�C�K�[�E�E�b�Y�i43�j�̃��W���[�A�e�Ƃ킪���R�p���i27�j�̃��W���[�����e�����҂��Đ���オ�������A�^�C�K�[�͗\�I�����A���R��16�ʂƂ������ҊO��̌��ʂɏI������B�������̂̓u���b�N�X�E�P�v�J(29)�B���̗D���Ő��E�����L���O��1�ʂƂȂ����B��Ԃ���肢�������Ȃ��B�P�v�J����͓����������낤�B�@���R�̔ߊ�͓��{�l���̃��W���[���e�ł���B���ݔ\�͂����Ă��j��ł����W���[�ɋ߂����{�l�I��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�u���l���Ă����������Ȃ����݁v�ƌ����ċv�����B�����A���̂܂܂ł͖������B�R�[�`�����Ȃ��ӌŒn�������邱�ƂȂ���A�ő�̌��O�́u�S���t�ɑ���l�����v�ł���B
�@���̎������u�D�������Ȃ��v�ƈӗ~�ނ��o���ŗՂB������̃C���^�r���[�ł́u5�ԃz�[����W�{�M�[��ł��Ă��܂������A�g�b�v�Ƃ̍����l���Đ�ӂ��ނ����v�ƌ�����B��X���j�㏉�̓��{�l���W���[�e�҂��������̂�����{�l�͂Ȃ����炾�낤�B�Ȃ̂ŋC�����͉���B��ʂ���_���Ȃ̂ł���B�m���ɁA�S���t�͓���B�������ŏ�̃v���[�����Ă��A�������ǂ��v���[�������҂�����Ε�����B�����͎��������̃v���[�ɏW�����邵���Ȃ��B��邾������ĕ������炵�悤���Ȃ��B�،��u����[��߂��v�̋��n�ł���B
�@���̎����A���R�͑�����ӎ��������Ď��������������B90�N�قǑO�A�{�r�[�E�W���[���Y(1902�|71)�́u�g�I�[���h�}���E�p�[�h��ɂ���v�ƌ������B1930�N�A28�ŃA�}�`���A�Ƃ��ĔN�ԃO�����h�X������B���A���̂܂܈��ނ��ă}�X�^�[�Y�E�g�[�i�����g��n�n�B�����ƌĂꂽ�`���̃S���t�@�[�ł���i�ŋ߃��W�F���h�Ƃ����������悭���ɂ��邪�A���W�F���h�Ƃ͂��������l�̂��ƁA�y�X�����g��Ȃ��łق������̂��j�B�����̓}�b�`�E�v���[�̎���ł���B�ڂ̑O�̑����|���Ώ����Ƃ�������ɁA�{�r�[�E�W���[���Y�͊����Č������̂ł���B�ΐ�҂�ɂ���ȁA�p�[��ɃQ�[�����s���ƁB���R�͂���⼌����̂ɖ����邱�Ƃ��B��������Γ��͑邩������Ȃ��B
2019.04.25 (��) ���̃I�[�f�B�I�j
 �@����A�J�Z�b�g�E�f�b�L���C������ĉ䂪�Ƃɓ͂����B�͂��Ă��ꂽ�̂�BMG����̎d������I����̂�����S���B���_�I�[�f�B�I�N���u�Ƃ��������I�[�f�B�I�̏C���H�[�ɏ������Ă���B�Z�p�҂͓�l���āA���̃J�Z�b�g�E�f�b�LSony TC-K 333ESG��S�������̂̓h�C�c�l�Z�t�������ł���B�u���̐l�����ł��B�h�C�c�l�͂�邱�Ƃ��O�ꂵ�Ă��܂��B���x���c����������ł���v��S���B�̏�͋쓮�n���������d�C�n�܂Ŏ�����Ă��ꂽ�悤�ŁA�܂��Ɋ����ȃI�[�o�[�z�[���ł���B�Â��J�Z�b�g�E�e�[�v�����X������B�������Ȃ��Đ̂̃\�t�g���܂���BCD���m���ɉߋ����ĂыN�������A�J�Z�b�g�͎��^���Ă��镪�x�����͂ł����B���[�P�[�X�̉��ɖ����Ă����e�[�v�̎��쎩���R���g�ɂ͏����B�肵�āu�͂ޒ��Ԃ����`��ЕсA�|�\�l�сv�B��Ет͏��a�����ɈڐЂ�����Ђ�W��\��E���암���ƌ_��f�B���N�^�[I���ƃW���Y�]�_�Ƃ̐��쏹�v����4�l�Ŗ����B�����Ɉ����ЎВ���Y�������ނƂ����X�g�[���[�B�|�\�l�т́A�o�D�̉����ÁA�������A�������A���q�M�Y�B�i�s���͒O�g�N�Y�B�p�N�����͊m�����߉Ɛ�Ƃ��������B
�@����A�J�Z�b�g�E�f�b�L���C������ĉ䂪�Ƃɓ͂����B�͂��Ă��ꂽ�̂�BMG����̎d������I����̂�����S���B���_�I�[�f�B�I�N���u�Ƃ��������I�[�f�B�I�̏C���H�[�ɏ������Ă���B�Z�p�҂͓�l���āA���̃J�Z�b�g�E�f�b�LSony TC-K 333ESG��S�������̂̓h�C�c�l�Z�t�������ł���B�u���̐l�����ł��B�h�C�c�l�͂�邱�Ƃ��O�ꂵ�Ă��܂��B���x���c����������ł���v��S���B�̏�͋쓮�n���������d�C�n�܂Ŏ�����Ă��ꂽ�悤�ŁA�܂��Ɋ����ȃI�[�o�[�z�[���ł���B�Â��J�Z�b�g�E�e�[�v�����X������B�������Ȃ��Đ̂̃\�t�g���܂���BCD���m���ɉߋ����ĂыN�������A�J�Z�b�g�͎��^���Ă��镪�x�����͂ł����B���[�P�[�X�̉��ɖ����Ă����e�[�v�̎��쎩���R���g�ɂ͏����B�肵�āu�͂ޒ��Ԃ����`��ЕсA�|�\�l�сv�B��Ет͏��a�����ɈڐЂ�����Ђ�W��\��E���암���ƌ_��f�B���N�^�[I���ƃW���Y�]�_�Ƃ̐��쏹�v����4�l�Ŗ����B�����Ɉ����ЎВ���Y�������ނƂ����X�g�[���[�B�|�\�l�т́A�o�D�̉����ÁA�������A�������A���q�M�Y�B�i�s���͒O�g�N�Y�B�p�N�����͊m�����߉Ɛ�Ƃ��������B�@S���ƃR�[�q�[�����݂Ȃ���A�����I�[�f�B�I�k�`�ɉԂ��炩����B����LINNSONDEK�̃^�[���E�e�[�u�������āu��͂胂�[�^�[�̓x���g�E�h���C�u�Ɍ���܂��ˁv�Ƌ����������Ă��ꂽ�̂͊����������B����́A80�N��ACD����̓����ŏ��ł��Ă��܂��I�Ɩ{�C�Ō��O���}篍w�������p�����^�[���E�e�[�u���i���ʂ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��������j�B33��]�݂̂ł����x�����������Ƃ������V���v���`�B����𒆐S�ɁA�A�[��SME 3010R�A�J�[�g���b�WOrtofon MC20W�̑g�ݍ��킹�����̃A�i���O�E�v���[���[�ł���BS���̂��A�ŃI�[�f�B�I�̋L�����S���Ă����B������@��ɁA�䂪�I�[�f�B�I����U��Ԃ��Ă݂悤�B
(1) ���n�� 1950�N��`�w������1960�N��
�@�n�܂�̓r�N�^�[�̖ƐŃv���[���[�B1950�N��A���w4�N���̂����ɔ����Ă�������B33�A45�A78��]�̉ώ��ŃA�i���O�E���R�[�h���ׂĂɑΉ�����B�j�̓T�t�@�C�A�T���_�C�������h�̃��l�b�g�^�B5���X�[�p�[�E���W�I�Ɍq���Œ������B�ŏ��ɔ����Ă�������\�t�g�́A�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^�u�����v�ƃV���p���́u���z�����ȁv��2���gSP�ŁA�t�҂̓C�O�i�c�B�E�����E�p�f���t�X�L�A�|�[�����h�̎ł�����B����SP�A�u�����v��CD������Ă��邪�u���z�����ȁv�͌������Ƃ��Ȃ��B�����A�ǂ��炩�Ƃ���������̕����悭�����Ă�������A�ł��邱�ƂȂ畷���Ă݂������̂��B�\�t�g�͏����A�t�B�[�h���[�F�{�X�g���E�|�b�v�X�nj��y�c�́u�y���V���̎s�ꁕ�h�i�E��̗��v�A�n�C�t�F�b�c�́u�c�B�S�C�l�����C�[���v�A���[�r���V���^�C���́u�V���p���F�p�Y�|���l�[�Y�v���̃V���O���Ղ���A�I�[�}���f�B�́u�^���v�A�I�C�X�g���b�t�́u�����f���X�]�[���F���@�C�I�������t�ȁv�A�x�[���́u�������v����10�D1000�~�ՁA�g�X�J�j�[�j�́u���v�u�u���R�v�A�t���g���F���O���[�́u�p�Y�v�u�u��4�v�A���j���[�C���Ƃ̃u���[���X�FVn���t�ȁA�����^�[�̃��[�c�@���g3������ȁA�x�C�k���́u�u��1�v�ȂǁA�����͂܂����ׂă��m�����ՁB�X�e���I�Ղ������̂�1958�N�ȍ~�ł���B�����͏������߂Ĕ������̂����A�����͏T���̗[��ꎞ�A�䂪�ƂōÂ��L�����R�[�h�R���T�[�g�������B���w���̎����I�ȁA����A�N�C�Y���o��B�Ⴆ�A�x�[�g�[���F���̌����ȁu�p�Y�v�̑�1�y�͂������āu������ĉ���A�z���邩�H�v�ƎO���o�肷��B�����́u�A���v�X�R�����s�R����i�|���I���R�v�B�������������c�ꂩ��܋���Ⴄ�Ƃ����Z�i�B�t���낤�ɁI(��)
�@�V�X�e�������I�ɕς�����̂͑�w�ɓ��钼�O�ł���B1964�N�̑�w�����B�c���Ɏ��s���āA���_�������Ă����ɂ��������|�����B�u�����ꋴ��Ɏ�����A�c���̓��w���������J���ɂ��������v�B���w�ɗ����č����Ȃ�Ă��肦�Ȃ��A�ł��A���w�������͎~�ޖ���������ɂȂ��Ă���̂�����A��������ł͂Ȃ��A�Ǝv�����̂��낤�A��͑��f��OK���Ă��ꂽ�B���́A�����̊w�͌X�����A���o�����Ȗڂ͂Ȃ������ԓI�Ƀ\�R�\�R�A����䂦�A�����̕��ɏ��Z����ƍl���Ă����B�܋�15���~���l���ł�������I�[�f�B�I���g�߂�I �����A�����������ƁA�ꋴ�̎����܂ł�2�T�Ԃ͎��ɕ������̋l�ߍ��ݑ��B���ʁA���i�ƃI�[�f�B�I���Q�b�g�B�K�^�̋ɂ݂ł���B
�@���̎���15���~�͍���100���~�ȏ�ɑ������邾�낤�B�����A���[������30�~�B�w�H�̃J���[��70�~�B4�����̉ƒ����z4500�~�B���d�iJR�j����10�~����������B15���~�Ƃ������s�����ȑ�����D���ȃI�[�f�B�I�ɓ����ł���I ���ꂱ��Ƌ@���I�����Ȃ���A�o�Ă��鉹��z������B�y�����Ȃ��킯���Ȃ��B�܂��Ɏ����̂ЂƎ��������B�l���Ă݂�Ƃ��̎����䂪�l���̐Ⓒ���I�H���Ƃ͗����ڂ̎O�x�}(��)�E�E�E�E�E�����āA��ɂ������u��
�@�@���R�[�h�E�v���[���[
�@�@�@�J�[�g���b�W�F�I�[�f�B�I�E�e�N�j�JAT5
�@�@�@�A�[���F�I�[�f�B�I�E�e�N�j�J�̃X�^�e�B�b�N�E�o�����X�^
�@�@�@�^�[���E�e�[�u���F�����d�q�@��TEIC�̃x���g�E�h���C�u��
�@�@�A���v
�@�@�@LUX�̃g���C�E�C���E�����E�A���v�i�v�����C����AM-FM�`���[�i�[��3�_��̌^�j
�@�@�X�s�[�J�[
 �@�@�@Goodman Triaxiom 10
�@�@�@Goodman Triaxiom 10�@�I�[�f�B�I�E�e�N�j�J�͓����V���̃I�[�f�B�I�E���[�J�[�ō������݁B�����d�q�@��TEIC�͌��݃e�B�A�b�NTIAC�ALUX�̓��b�N�X�}���ɎЖ����ς���Ă���BGoodman�Ђ͉p���L���̃X�s�[�J�[�E���[�J�[���B���ƌ���Ђ��邱�ƂɂȂ�r�N�^�[�̋@��͑I��O�B�R���|�[�l���g�E�^�C�v�ɗǕi���o���̂͂���10�N�゠����ƂȂ�B
�@������͏H�t���́u�����Ёv�Ƃ����I�[�f�B�I�X�B���ׂ͋@��ʂɃo���o���ŁA�ŏ��ɓ��������̂�LUX�̃A���v�������B�҂����ꂸ�Ɋ����̑��u�Ɍq���Ē����Ă݂�B�\�t�g�̓��[�O�i�[�́u���[�G���O������3���ւ̑O�t�ȁv�i�N�����y���[�w���F�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�j�̃X�e���I�Ղł���B�j�𗎂Ƃ��B�����Ȃ��яo���Ă����I�P�̋��t�B�u�ȂA����́I�v�B����܂ł̉��Ƃ͕ʊi�̊��B���̈��|�I���͂ɂ����������Q����݂̂������B���̌�A����ȏ�̏Ռ���̌��������Ƃ��Ȃ��B�s�v�c�Ȃ��Ƃł���B���u�͒���̎��Ƃɒu��������A�A�Ȃ���ƁA��ڎU�ɃI�[�f�B�I�E���[���ɋ삯�����̂��B
�@�����̈����Ղ́A�O�o�N�����y���[�̃��[�O�i�[�nj��y�ȏW��2�W�A�����^�[�̃u���[���X�����ȑS�W�A�A���Z�����́u�W����̊G�v�u�V�F�G���U�[�h�v�A�[���L�����o�[���X�^�C���̃x�[�g�[���F���u�c��v�A���q�e���̃��t�}�j�m�t �s�A�m���t��2�ԁA�����p����J.S.�o�b�n�F�g���I�E�\�i�^�W�A�}�C���X�E�f�C���B�X�u�g�����y�b�g�E�u���[�v�A�n���[�E�x���t�H���e�u�J�[�l�M�[�E�z�[���E�R���T�[�g�v���A�X�e���I�Ղ������Ȃ����B
(2) ��Ј����� 1970�N��`�����܂�
�@1975�N�A�������@�ɐV���Ɉڂ�A��V�������C���E�A�b�v�͉��L�̂Ƃ���B
�@�@���R�[�h�E�v���[���[�F
�@�@�@�J�[�g���b�W�FERAC STS455E�A�^�[���E�e�[�u�����A�[���F�r�N�^�[JLB 51
�@�@�A���v�FDENON PMA500
�@�@�X�s�[�J�[�F�r�N�^�[SX3�U
�@�e��Ђ̃r�N�^�[���i���g�ݍ��܂ꂽ�B�I���̗��R�́A�����̍D�݂ɂ����̂����A���А��_���������̂��낤�B�A�i���O�E���R�[�h������I�ɑ���2000�������B
�@�ȉ����C���E�A�b�v�̕ϑJ�����n��ŋL���Ă������B(�@)���͍w���N�B
�@�@�J�[�g���b�W�F
�@�@�@Ortofon MC10�U(1981)�@�t�B�f���e�B�E���T�[�`(FR) FR7(1981)
�@�@�@Ortofon SPU-GE(1982)�@�I�[�f�B�I�E�e�N�j�J AT33E(1982)
�@�@�@Ortofon MC20�U(1984)�@B&O MMC1(1984)�@DENON DL103LC�U(1985)
�@�@�@Ortofon MC20W (2004)
�@�@�A�[���F�t�B�f���e�B�E���T�[�`FR64S�i1980�j SME 3010R (1982)
�@�@�^�[���E�e�[�u���F�}�C�N�����@ BL77�i1981�j LINN SONDEK LP12 (1982)
�@�@CD�v���[���[�F�g���I DP1100(1984)�@SONY CDP555ESD(1987)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �A�L���t�F�[�Y DP 57 (2005)
�@�@�A���v�F�r�N�^�[AX7D�i1980)�@�A�L���t�F�[�Y C200L�{C300L (1986)
�@�@�@�@�@�@�A�L���t�F�[�YE 350 (2010)
�@�@�X�s�[�J�[�FRODGERS PM410(1981)�@VISONIC DAVID6000(1985)
�@�@�@�@�@�@�@�@HARBETH HL Monitor Compact(1988)
�@�@�@�@�@�@�@�@TANNOY Stirlig-HE (2004)�@ALRJORDAN Entry S (2004)
�@��L�̑��ɁAFM�`���[�i�[�A�J�Z�b�g�E�f�b�L�AMD�v���[���[�ACD���R�[�_�[����LD�v���[���[�Ȃǂ̉f���n�A�����g�����X�A�^�[���e�[�u���E�V�[�g�Ȃǂ̃A�N�Z�T���[�܂œ����ƁA�w�������@��E�p�[�c�͗D��100�_���B���̒��ŁA�������ŋL�������A���炭���ꂪ�I�̃��C���E�A�b�v�ƂȂ邾�낤�BCD�v���[���[�ƃA���v�����{���A���̓��[���b�p���ł���B�@��̕ϑJ������Ƒ傫�Ȑߖڂ͓���邱�ƂɋC�Â��B1982�N��2004�N�ł���B
�@1982�N�ACD�����B�f�W�^������̓����ł���B�I�[�f�B�I�E�t�@���Ƃ��Ă͔ۂ����ł��Ή�������Ȃ��BCD�̐�`����́g�����悭�Ď�舵���ȕցh�ł���B�������������͂����܂Ōl�̊��o������A�悢���͍D���ȉ��ƌ��������悤�B��舵�����ȕւ͗L�����ǁA��ɂ́u�ʓ|�䂦�ɖʔ����v�Ƃ������ʂ�����B�����A�I�[�f�B�I�͐^�Ɍl�I�Ȑ��E�Ȃ̂��B������A���Ȃ̍D�݂��A�f�W�^���ƃA�i���O�ɓK���ɔ��f���������Ǝv�����B�����ł܂����ł����̂��A�i���O�E�v���[���[�ł���BCD�̎���ɗ~�����@�킪�����Ă��܂��A�Ɩ{�C�ōl��������ł���B���ʁALINN-SME-Ortofon�̑g�ݍ��킹�ƂȂ����B�f�W�^���̕��́A�i�����ɂ݂Ȃ���i�߂邱�Ƃɂ��āA�ЂƂ܂��g���I��CD�v���[���[DP1100���w�������B1986�N�ɂ̓A���v���A�L���t�F�[�Y�̃Z�p���[�g�E�^�C�vC200L�{P300L�ɑւ����B���̐V���i��AUX�[�q��啝�ɑ��₷�ȂǁA�f�W�^�����f���`���@�\�Ή��^�ŁA����A����ɉ������O���[�h�E�A�b�v�������B
 �@2004�N�͎��̒�N�O�N�B����ɂ߂Čl�}�^�[�Ȃ̂����A�䂪�I�[�f�B�I�j�ɂ����Ă̓��l�T���X�Ƃ������ׂ�����I�ȔN�ƂȂ����B�呠��b�ɑސE���̑O�|����\���A���āA���ɓ���̃X�s�[�J�[����ɓ��ꂽ�B�p����TANNOY�ł���B�ō����AUTOGRAPH�͍���̉ԁB�̗~��������Berkeley�͍ő����^�C�v�B�Ȃ�ƑI�̂�Stirling�������B�Ƃ��낪�v���ʂ�ɖ��Ă���Ȃ��B�����d���āg�����h�Ƃ͂قlj����B�����̓A���v�ƌ��āA���K�̃I�[�o�[�z�[���ɏo�������܂�悭�Ȃ�Ȃ��B����͌o�N�敾�H �ł�18�N�͑������Ȃ����A�ȂNj^�S�ËS�̖��A2010�N�ɓ��Ђ̃v�����C����̌^�A���v E350�ɑւ����B����Ɓu�������炵���v��悤�ɂȂ����B�s�A�m���܂��܂��ł���B2005�N��CD�v���[���[���A�L���t�F�[�YDP 57�ɑւ��Ă������A���̂����̂Ȃ��@��̓X�s�[�J�[�̓�����f���Ɉ����o�����B����TANNOY�������̉��ɂȂ����Ǝv�����B���͂ƂĂ��������Ă���B���̂悤�ɁA�����܂�TANNOY�ɍS�����͍̂�ƁE�ܖ��N�S�̉e���ł���B����ɂ��Ă͎��͂ŏq�ׂ����B
�@2004�N�͎��̒�N�O�N�B����ɂ߂Čl�}�^�[�Ȃ̂����A�䂪�I�[�f�B�I�j�ɂ����Ă̓��l�T���X�Ƃ������ׂ�����I�ȔN�ƂȂ����B�呠��b�ɑސE���̑O�|����\���A���āA���ɓ���̃X�s�[�J�[����ɓ��ꂽ�B�p����TANNOY�ł���B�ō����AUTOGRAPH�͍���̉ԁB�̗~��������Berkeley�͍ő����^�C�v�B�Ȃ�ƑI�̂�Stirling�������B�Ƃ��낪�v���ʂ�ɖ��Ă���Ȃ��B�����d���āg�����h�Ƃ͂قlj����B�����̓A���v�ƌ��āA���K�̃I�[�o�[�z�[���ɏo�������܂�悭�Ȃ�Ȃ��B����͌o�N�敾�H �ł�18�N�͑������Ȃ����A�ȂNj^�S�ËS�̖��A2010�N�ɓ��Ђ̃v�����C����̌^�A���v E350�ɑւ����B����Ɓu�������炵���v��悤�ɂȂ����B�s�A�m���܂��܂��ł���B2005�N��CD�v���[���[���A�L���t�F�[�YDP 57�ɑւ��Ă������A���̂����̂Ȃ��@��̓X�s�[�J�[�̓�����f���Ɉ����o�����B����TANNOY�������̉��ɂȂ����Ǝv�����B���͂ƂĂ��������Ă���B���̂悤�ɁA�����܂�TANNOY�ɍS�����͍̂�ƁE�ܖ��N�S�̉e���ł���B����ɂ��Ă͎��͂ŏq�ׂ����B�@�\�t�g�̐��́A������CD��LP���t�]�B���ł�4000�������B������ɁA�唼�̓A�i���O�^����CD���A����ADD�ł���B�^��������1960�|70�N��B�D�݂͂ǂ����Ă������炠����ƂȂ�B�ł͂����ŁA�䂪���ɂ̈����Ղ������Ă������B���l���Ɏ����Ă䂫����LP��CD��2�_�ÂB
��LP��
 ���l������ǂ����^�����_�[���b�q�����W
���l������ǂ����^�����_�[���b�q�����W�t���b�c�E�����_�[���b�q�i�e�m�[���j
�n���X�E�J���X�e�w���F�O���E���P�����y�c
1965�|66�N�^���@�|���h�[��������Ё@MGW5269
�@�@35�Ƃ����Ⴓ�Ŕ߉^�̎��𐋂����s���o�̖��e�m�[�� �����_�[
�@�@���b�q�̖��̏��B
�@�@�����͂Ƃɂ��������A�����ɂ��ĊÔ��B�|���͍��M�ɂ��ď�M�I�B
�@�@�u�J���E�~�I�E�x���v�̓p���@���b�e�B�ɁA�u�O���i�_�v�̓h�~���S
�@�@�ɏ���B
�@�@�^�����悭�A���̃T�E���h�͖L���ŖF���ACD�͉����y�Ȃ��B
�}�[���[��ȁF������ ��9�� �j����
�W�����E�o���r���[���w���F�x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c
1964�N�^���@����EMI�@EAC85035-36
�@�@��4�y�̓A�_�[�W���̌��B����قǂ܂łɐS�h���Ԃ��鉹�͂Ȃ��B
�@�@�^���m�C����ы����A�}�[���[���ԚL����B
�@�@����܂��ACD�Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��B
��CD��
 ���[�c�@���g��ȁF�s�A�m���t�� ��23�� �C���� K488
���[�c�@���g��ȁF�s�A�m���t�� ��23�� �C���� K488�N���t�H�[�h�E�J�[�]���i�s�A�m�j
�W���[�W�E�Z���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c
1964�N�^�� ���j�o�[�T���E�~���[�W�b�N UCCD3429 ADD�^�C�v
�@�@�R��ƋC�i���Y���J�[�]���̃s�A�m�ɁA�z�Ƃ����e�肽��Z����
�@�@�E�B�[���E�t�B�������ދɏ�̃��[�c�@���g�B��2�y�̓V�`���A�[�m
�@�@�̓��O�����������͂��Ƃ��悤���Ȃ��B
���[�c�@���g��ȁF�Z���i�[�h���f�B���F���e�B�����g�W
�V���[���h���E���F�[�O�w���F�U���c�u���N�E���[�c�@���e�E���nj��y�c
1986-90�^�� CAPRICCIO���[�x�� 10CD�@DDD�^�C�v
�@�@���F�[�O�̐��k�ȍl�ɗ��ł����ꂽ���[�c�@���g�̉����E�B����́A�����銽�тƖ�������
�@�@�����A���[�c�@���g�̐t�̑������̂��̂ł���B
(3) �ܖ��N�S�Ɓu�����̉��v
 �@�l�͌ܖ��N�S�i1921�|80�j�̂��Ƃ��g�I�[�f�B�I�̋����ҁh�ƌĂԁB��r�ɉ��ƌ��������p�͐^�����̂��́B����ŁA�C�ɐH��ʂƓ��肵������̋@���@���ʂ��B����͂܂��Ɂg���C�h�̈�B�I�[�f�B�I�l�E�ܖ��N�S�̖��͂͐^���Ƌ��C�̋����ɑ��Ȃ�Ȃ��B�u�r�_�v�ŊH��܂��l�����̂��A���������ɗ~���������X�s�[�J�[����ɓ���邽�߂������Ƃ��B����ɂ́A�����������̂͂������ł������y�����߁A�ƌ�������B���ł��A�^���m�C�ɑ��鈤���͐[���B�ނ̖����u�����̉��v�͎��̊w�����ォ��̈��Ǐ��ŁA�����u�̃��C���E�X�s�[�J�[���^���m�C�ɗ����������̂́A�ԈႢ�Ȃ����̖{�̉e���ł���B�����āA�I�[�f�B�I���u�Ɂg�������炵���h�������Ƃ����߂��̂��ܖ����̊����ɂ����̂��BAUTOGRAPH��Stirling�ł͑�l�Ǝq���ł͂��邯��ǁB�ȉ��A�u�����̉��v����^���m�C�Ɋւ��镔�������āA�ܖ��N�S�́u�^���m�C���v��T���Ă݂����B
�@�l�͌ܖ��N�S�i1921�|80�j�̂��Ƃ��g�I�[�f�B�I�̋����ҁh�ƌĂԁB��r�ɉ��ƌ��������p�͐^�����̂��́B����ŁA�C�ɐH��ʂƓ��肵������̋@���@���ʂ��B����͂܂��Ɂg���C�h�̈�B�I�[�f�B�I�l�E�ܖ��N�S�̖��͂͐^���Ƌ��C�̋����ɑ��Ȃ�Ȃ��B�u�r�_�v�ŊH��܂��l�����̂��A���������ɗ~���������X�s�[�J�[����ɓ���邽�߂������Ƃ��B����ɂ́A�����������̂͂������ł������y�����߁A�ƌ�������B���ł��A�^���m�C�ɑ��鈤���͐[���B�ނ̖����u�����̉��v�͎��̊w�����ォ��̈��Ǐ��ŁA�����u�̃��C���E�X�s�[�J�[���^���m�C�ɗ����������̂́A�ԈႢ�Ȃ����̖{�̉e���ł���B�����āA�I�[�f�B�I���u�Ɂg�������炵���h�������Ƃ����߂��̂��ܖ����̊����ɂ����̂��BAUTOGRAPH��Stirling�ł͑�l�Ǝq���ł͂��邯��ǁB�ȉ��A�u�����̉��v����^���m�C�Ɋւ��镔�������āA�ܖ��N�S�́u�^���m�C���v��T���Ă݂����B
1964�N7��25���A�͂��C���z���Ă��Ƀ^���m�CGuy R.Fountain Autograph�͎��̉Ƃɓ͂���ꂽ�B���͗܂����ڂꂽ�B�E�E�E�E�E�Ȃ�Ƃ������������낤�B�Ȃ�Ƃ̂т₩�Ȓቹ���낤�B����Ȃɂ݂��݂������A���M�ŁA�₽������قǍ��M�ɓ����Ƃ��������������͕��������Ƃ��Ȃ��B�������Ȃ�Ƃ����ቹ���̂Ђ낪��ƁA���̃o�����X�̂悳�B�s�A�m�̔������͂��Ƃ��悤���Ȃ��B�@�u�����̉��v�ɂ͌ܖ����́u�^���m�C���v���l�܂��Ă���B���ׂ��ė܂𗬂��A���������Ȃ����Ǝ�������V�z���Ă��܂��B�����܂����Ƃ��������悤���Ȃ��B�^���m�C�������o�������`�e����\���͂��������������`�u�₽������قǍ��M�v�u�����̂悤�ɐ���������v�u�^�Ȃ̌������ŕ��ł�悤�ɏ_�炩���v�u��m��ʐ[���ɗ�������v���X�B��������Ƃ͈Ⴄ�B�X�Ɂu�X�s�[�J�[��I�Ԃ��Ƃ͐������̈Ⴂ�ɂȂ���v�Ƃ܂Ō��y����B�����͂�����B���ɂ������m�ł����A�����͉����y�Ȃ��B������A���́A����̖��\��Q����l�𐒔q���邾�����B�����A�߂Â����Ƃ�������߂Ă͂��Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�ܖ��N�S�́A���ɂƂ��āA�o������̍���ł���A�u�����̉��v�͉i���̓��W�Ȃ̂ł���B
���͐V�z�̉ƂɈړ]�����B���R�[�h��������30��B�V��͍������ȑO�̃��X�j���O�E���[���ȏ�ɑf���炵�����Ŗ��Ă���邾�낤�Ɗ��҂����B���ꂪ�Ăɑ��Ⴕ�āA�G�R�[�̂Ђǂ��A�����ɑς��ʉ��������B�ቹ�͂�����A���̂悤�ɂ���₩�ɔ����Ă���Ȃ��B�J�[�g���b�W��A���v��ւ��Ă݂����ʖڂ������B�����̂͑��u�ł͂Ȃ����x�̕������B�����Ȃ�A���́A�h�����u�̎�������V���Ɍ��Ă˂Ȃ�Ȃ��B���ɂ͎؋���������ꕶ�̂����킦���Ȃ��B���������Ă˂Ȃ�܂��B���N�����邩�A�^���m�C��������ɖ炷���߂ɁA�����ȕw�l�����͂Ό}����ɂӂ��킵�����������͗p�ӂ��˂Ȃ�Ȃ����낤�B���ꂪ����̐ӔC�Ƃ������̂��낤�B
�I���W�i����folded horn�Ɏ��߂�ꂽ�^���m�C�́A�������͔����̂悤�ɐ��������Ė�̂ł���B���̉��̂Ђ낪��Ɣ������ɂ͐����̂ށB�^�Ȃ̌������ŕ��ł�悤�ɏ_�炩����������B�����āA�ቹ�́A��m��ʐ[���ɗ�������悤�ɉʂĂ��Ȃ����тĂ䂭�B
�D�G�Ȃ炴��Đ����u�ł́A�V�����e�B�́u�W�[�N�t���[�g�v�ɂ����āA�o���҂̈�l��l���}�C�N�̑O�ɂ�����ĉ̂��B�܂�X�s�[�J�[��t�ɏo�ԂɂȂ����j�⏗������o�Ă͏�����̂ł���B�ނ�̑��͕���ɂ��Ă��Ȃ��B�����ȃI�[�f�B�I�]�_�Ɛ搶���������Ă��ꂽ�R���N���[�g�E�z�[���Ȃ�㕨���܂��ɂ���B���͂���ǂ��p�͌�����
�E�E�E�E�E�H��ł���B�H��̉̂��t�B�K���Ȃǐ^�������B�R���N���[�g�E�z�[����@���ʂ����̂͂��̗��R���B�킪�^���m�C�ł͐���悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��B�X�e�[�W�̑傫���ɔ�Ⴕ�āA�����ɓo�ꂵ���l�Ԃ̌����̂��B�ǂ�قǔx���ʂ̑傫�����ł��ޏ���ނ̑��̓X�e�[�W�ɗ����Ă���B�܂�ʍĐ����u���ƁA�X�s�[�J�[���̂��B
�����s�A�m�ł��x�q�V���^�C���ƃx�[�[���h���t�@�[�ł͈Ⴄ�B�s�A�m�Ƃ����y��̉��ł��A���̈Ⴂ�͂����I������҂́A�������̈Ⴂ�ɂȂ���ꍇ�����Ă���B���킢�b���B���������������ɂȂ���Ӗ��ł��A�킽�������̓^���m�C��I�B
�@�@���Q�l������
�@�@�u�����̉��v�ܖ��N�S���i�V���Ёj
�@�@�u�V���߁\�����̉��v�ܖ��N�S���i�V���Ёj
�@�@�u�ܖ��N�S �I�[�f�B�I���v�i�V�����Ɂj
2019.03.31 (��) ����v���搶�̎v���o
 �@�ŋߐ��ɍ������̔����������A�����ɋ��S�ǂ���S�؍[�ǂ̊댯������ƈ�t���狺����āA�������I���܂ł͊O�o���l���������Ă���B����Ȉ�����̓����A���{����p�فu����v���V�l�}�E�O���t�B�b�N�X�W�v�ɍs���Ă����B�₦���ޖ�Ԃ��g���z�C�̒��ԂȂ��r�I�ƌ����Ă��邽�߂ł���B
�@�ŋߐ��ɍ������̔����������A�����ɋ��S�ǂ���S�؍[�ǂ̊댯������ƈ�t���狺����āA�������I���܂ł͊O�o���l���������Ă���B����Ȉ�����̓����A���{����p�فu����v���V�l�}�E�O���t�B�b�N�X�W�v�ɍs���Ă����B�₦���ޖ�Ԃ��g���z�C�̒��ԂȂ��r�I�ƌ����Ă��邽�߂ł���B�@���{��͊��q�̗y����A���ʂ����Ȃ��ƒn�����X�B���p�ق��܂��w����^�N�V�[�Ő��\���̉��u�n�B���}�ω���z�e���̌����Ɍ��B�̂��̃z�e���ɂ͘^���X�^�W�I�������āA��N�S���Ȃ������c�T��Y����̃��R�[�f�B���O�ɗ�����������Ƃ����������v���o�����B
 �@���̔��p�W�ɍs�����ƌ��߂��̂͂��Ẳ�Ђ̌��T���̂��U�����������A���f�����L�b�J�P�͐��N�O��ƌ���TV�u�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�������B�����m�A�l�����L����^��s���̃A���e�B�[�N�ɉ��l����������ԑg�ł���B�Ӓ�i�͖���v���i1909�|1994�j���̕M�ɂȂ�▋�̃X�^�[�̏ё��f�b�T���悾�����B
�@���̔��p�W�ɍs�����ƌ��߂��̂͂��Ẳ�Ђ̌��T���̂��U�����������A���f�����L�b�J�P�͐��N�O��ƌ���TV�u�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�������B�����m�A�l�����L����^��s���̃A���e�B�[�N�ɉ��l����������ԑg�ł���B�Ӓ�i�͖���v���i1909�|1994�j���̕M�ɂȂ�▋�̃X�^�[�̏ё��f�b�T���悾�����B�@1994�N�����A������ɁA���N�̉f�攭��100�N���L�O���āu100�l�̃n���E�b�h�X�^�[��`���v�Ȃ�˗����������B�l���̑����Z�Ƃ��đ̒��s�ǂ̒����|��������������������u���ɂ��ė͐s���A�A��ʐl�ƂȂ��Ă��܂��B�u�Ӓ�c�v�ɓo�ꂵ���̂͂��̈��Ƃ������ׂ�26���̃f�b�T����ƎG���u�f��̗F�v���W���̕\���p�`���b�v�����́u�ƍَҁv�̖��G���悾�����B�˗��l�E���{����Y���̊�]���i��300���~�B�����A������̗l�X�ȋƐт�m���Ă͂������̂̐��̉�Ƃł͂Ȃ��̂�����A����ȂƂ��낪�Ó����낤�Ǝv���Č��Ă����B�Ƃ��낪�Ӓ茋�ʂ͂Ȃ��1300���~�I�I�����̊Ӓ肾�������A�搶��m��҂Ƃ��Ă͎��Ɍւ炵�����ʂ������B�ԑg�ł͂܂��A���������́u������̊i�������G�ɂ͕��w��i�ɕC�G����g���h������v�Ƃ���^����A�u�⑰�̕�����a�������搶�̈�i������W����̌`�ŏЉ�Ă��������v�Ƃ����˗��l�̊o�傪�Љ��Ă����B
�@�u����v���V�l�}�E�O���t�B�b�N�X�W�v�ɂ́A�u�Ӓ�c�v�ɓo�ꂵ�����26�_���܂ސ搶�����U�Ŏc������i366�_���W������Ă����B�����͂܂��ɁA20���I�G���^�e�C�������g�����̗��j���̂��́B�ďC�͍��{���ł���B
 �@�u�Ӓ�c�v�ɓo�ꂵ���▋�̃X�^�[�̃f�b�T���́A�O���^�E�K���{�A�}���[�l�E�f�B�[�g���q�A�C���O���b�h�E�o�[�O�}���A�W�����G�b�^�E�}�V�[�i�A�t�����\���[�Y�E�A���k�[���A�u���W�b�g�E�o���h�[�A�I�[�h���[�E�w�v�o�[���A�J�g���[�k�E�h�k�[���A�����A���E�M�b�V�����̏��D�w�A�W�����E�M���o���A�n���t���[�E�{�K�[�g�A�W�F���[���E�t�B���b�v�A�t�����N�E�V�i�g���A�|�[���E�j���[�}���A�G�����B�X�E�v���X���[���̒j�D�w�ō��v30���B���ł��I�[�h���[�E�w�v�o�[����3�����邩��搶�̂��C�ɓ��菗�D�������̂��낤�B2���̓}���[�l�E�f�B�[�g���q�ƃ����A���E�M�b�V���B���Ƀ����A���E�M�b�V���i1893�|1993�j�ɂ��ẮA�u�����A���E�M�b�V���ɉ���v�Ƒ肷�������̒��M���e�ƋL�O�ʐ^���W������Ă����B�ޏ��́A1987�N�A94�ʼnf��u�����̌~�v�Ƀx�e�B�E�f�C���B�X�ƘV�o�����ŏo���A��^�������A2�N���1989�N�A��������o����ċL��������͊����̎�L�Ȃ̂��B���ɂƂ��ă����A���E�M�b�V���́A�I�[�h���[�E�w�v�o�[�����o�[�g�E�����J�X�^�[�剉�̐������u�����ꂴ��ҁv�ŁA���[�c�@���g�́u���z�� �j�Z�� K397�v��e���V�[������ۂɎc���Ă���B
�@�u�Ӓ�c�v�ɓo�ꂵ���▋�̃X�^�[�̃f�b�T���́A�O���^�E�K���{�A�}���[�l�E�f�B�[�g���q�A�C���O���b�h�E�o�[�O�}���A�W�����G�b�^�E�}�V�[�i�A�t�����\���[�Y�E�A���k�[���A�u���W�b�g�E�o���h�[�A�I�[�h���[�E�w�v�o�[���A�J�g���[�k�E�h�k�[���A�����A���E�M�b�V�����̏��D�w�A�W�����E�M���o���A�n���t���[�E�{�K�[�g�A�W�F���[���E�t�B���b�v�A�t�����N�E�V�i�g���A�|�[���E�j���[�}���A�G�����B�X�E�v���X���[���̒j�D�w�ō��v30���B���ł��I�[�h���[�E�w�v�o�[����3�����邩��搶�̂��C�ɓ��菗�D�������̂��낤�B2���̓}���[�l�E�f�B�[�g���q�ƃ����A���E�M�b�V���B���Ƀ����A���E�M�b�V���i1893�|1993�j�ɂ��ẮA�u�����A���E�M�b�V���ɉ���v�Ƒ肷�������̒��M���e�ƋL�O�ʐ^���W������Ă����B�ޏ��́A1987�N�A94�ʼnf��u�����̌~�v�Ƀx�e�B�E�f�C���B�X�ƘV�o�����ŏo���A��^�������A2�N���1989�N�A��������o����ċL��������͊����̎�L�Ȃ̂��B���ɂƂ��ă����A���E�M�b�V���́A�I�[�h���[�E�w�v�o�[�����o�[�g�E�����J�X�^�[�剉�̐������u�����ꂴ��ҁv�ŁA���[�c�@���g�́u���z�� �j�Z�� K397�v��e���V�[������ۂɎc���Ă���B�@�f���`�p�̃|�X�^�[��130�_�]�B�u�]���v�u�����������y�v�u���R�����Ɂv�u���̂̈����v�u���т��v�u�V��V�~�̐l�X�v�u��O�̒j�v�u�ւ���ꂽ�V�сv�u�������v�u�t�����`�E�J���J���v�u����Ȃ����Y�v�u���삳��A������炩�Ɂv�u�����I���t�F�v�u���v�u���Ƃ����u�v�u��l�͔����Ă���Ȃ��v�u����v�Ȃǖ��삪�Y�����̂��Ƃ��ɕ��ԁB�e�ɂ��B�e�����G���A���������̂ŁA���́u�ւ���ꂽ�V�сv�A���s��T���́u�����p���i�X�̓��v�AA���́u���삳��A������炩�Ɂv�ƁA�e�X���C�ɓ���f��̑O�ŋL�O�ʐ^���B�荇�����B
 �@�|�X�^�[�ȊO�Ŗڂ����������́B����́A�t�����\���[�Y�E�T�K���̏����u����Ȃ��������x�v�i�V�����Ɂj�̕\���G�ł���B�|��{��1961�N5���ɑ�1�ł����s�i�����o���q��j�B���N6���A�C���O���b�h�E�o�[�O�}���A�A���\�j�[�E�p�[�L���X�A�C���E�����^���̍��L���X�g�ʼnf�扻����A10���ɂ͓��{�ł����J���ꂽ�B�����c�ɂ̍��Z�����������́A����́u�u���[���X�͂��D���v�Ɏ䂩��āA�ǂ݊ς����̂ł���B���̎��w�������{��������f�U�C���̂��̂ŁA�����̃N���W�b�g�ɂ͏��a37�N�i1962�N�j�P��25�� ��4�� �艿70�~�Ƃ���B���̔ł͌��ݐ�ł̋M�d�i�B���̈̕�ł���B������`���Ƃ���̕\���G�́A�C���O���b�h�E�o�[�O�}���̔��e�Ɣw��ɃI�[���E�u���[���X�E�v���O�����̃R���T�[�g�E�|�X�^�[����������Ă���B�ʎ��I�ł͂��邪�D�����^�b�`�̏ё��B�|�X�^�[�ɂ͓��t�A���A�Ȗړ��̏���m�ɂ��肰�Ȃ��`�����B�W����Ƃ����F�����́A�R���ȕ���̃��[�h�Ɍ����Ƀ}�b�`���Ă���B
�@�|�X�^�[�ȊO�Ŗڂ����������́B����́A�t�����\���[�Y�E�T�K���̏����u����Ȃ��������x�v�i�V�����Ɂj�̕\���G�ł���B�|��{��1961�N5���ɑ�1�ł����s�i�����o���q��j�B���N6���A�C���O���b�h�E�o�[�O�}���A�A���\�j�[�E�p�[�L���X�A�C���E�����^���̍��L���X�g�ʼnf�扻����A10���ɂ͓��{�ł����J���ꂽ�B�����c�ɂ̍��Z�����������́A����́u�u���[���X�͂��D���v�Ɏ䂩��āA�ǂ݊ς����̂ł���B���̎��w�������{��������f�U�C���̂��̂ŁA�����̃N���W�b�g�ɂ͏��a37�N�i1962�N�j�P��25�� ��4�� �艿70�~�Ƃ���B���̔ł͌��ݐ�ł̋M�d�i�B���̈̕�ł���B������`���Ƃ���̕\���G�́A�C���O���b�h�E�o�[�O�}���̔��e�Ɣw��ɃI�[���E�u���[���X�E�v���O�����̃R���T�[�g�E�|�X�^�[����������Ă���B�ʎ��I�ł͂��邪�D�����^�b�`�̏ё��B�|�X�^�[�ɂ͓��t�A���A�Ȗړ��̏���m�ɂ��肰�Ȃ��`�����B�W����Ƃ����F�����́A�R���ȕ���̃��[�h�Ɍ����Ƀ}�b�`���Ă���B�@�W���Y�ɂ����ʂ���Ă���������́A���C�E�A�[���X�g�����O�A�f���[�N�E�G�����g���A�x�j�[�E�O�b�h�}���A�J�E���g�E�x�C�V�[�A�`���[���[�E�p�[�J�[�A�r���[�E�z���f�C�A�i�b�g�E�L���O�E�R�[�����A���R�[�h�E�W���P�b�g��A�f�b�T�����������肪���Ă���B���̑��A�A�[�e�B�X�g�̗������̎ʐ^�␔�X�̕]�_���W������Ă����B
 �@���Ɩ���搶�Ƃ̏o��͍�����30�N�قǑO�A�����A�������N���������Ǝv���B���̂���RCA���R�[�h����n�����ɈڐЁB���l���ł̃X�^�[�g���������߁A���O�̃W���Y�̕Ґ������Ȃ���Ȃ�Ȃ������BCHOICE�Ƃ����č��̃W���Y�E���[�x���ƌ_��100W�قǂ�CD�𐧍삵���B���̒��̂������̉�������搶�ɂ��肢�����B�搶�̒��M���e��2���苖�Ɏc���Ă���B���ƈႢ�A�ʏ̃y���Ƃ���200���l�ߌ��e�p���ɖ��N�M�ŏc�����ŏ�����Ă���B
�@���Ɩ���搶�Ƃ̏o��͍�����30�N�قǑO�A�����A�������N���������Ǝv���B���̂���RCA���R�[�h����n�����ɈڐЁB���l���ł̃X�^�[�g���������߁A���O�̃W���Y�̕Ґ������Ȃ���Ȃ�Ȃ������BCHOICE�Ƃ����č��̃W���Y�E���[�x���ƌ_��100W�قǂ�CD�𐧍삵���B���̒��̂������̉�������搶�ɂ��肢�����B�搶�̒��M���e��2���苖�Ɏc���Ă���B���ƈႢ�A�ʏ̃y���Ƃ���200���l�ߌ��e�p���ɖ��N�M�ŏc�����ŏ�����Ă���B�@���̓��̂ЂƂA�A�C���[���E�N���[���u�W�F���g���E���C���vSHCJ1012�̃��C�i�[�m�[�c�͂����n�܂�`�u�A�C���[���E�N���[���̓G���E�t�B�b�c�W�F�����h��T���E���H�[���̂悤�ȑ僔�F�e�����̃X�[�p�[�X�^�[�قǂ̃r�b�O�E�l�C���ł͂Ȃ����A�W���Y�E���H�[�J���ɊS�̐[���t�@���̕�����͕ʊi�I�ɍ����]���������Ă������͔h ���w�̖��̎�Ƃ������ׂ��ЂƂȂ̂����A1987�N(8��15��)�ɂ�����46�̎Ⴓ�ŋA��ʐl�ƂȂ����v�B���̂��ƁA�ޏ��̃L�����A�`�|���`�������̗l�q�`���YCD�̓����`�Ȗډ���Ƒ����B�\�L�ɓ����������āA�������ɂ́Z���ł���A�ȏ�̎Z�p�����ɂ̓A���_�[���C�����������B�\���͖����ŊȌ��B��i�̓�����I�m�ɑ�����B�u���l�ɂ킩��₷���v���|�Ƃ����搶�̕M�v���̂��̂��B�s�Ԃɂ͉��y�ƃA�[�e�B�X�g�ւ̈���Y���A�������Ƃ�������m��̃o�����X�͏�ɐ▭�B�m�ł��邻�̃X�^�C���͂����h�邬�Ȃ������B
�@����Ȑ搶�Ƃ̈�Ԃ̎v���o�́u���e�̎��v�ł���B���ߐ肪�߂Â��Ƃǂ��炩��Ƃ��Ȃ��d�b�����������B�搶�͂�����ЂɌ��e�������Ă��Ă����������B�u�����v�ƌy���E��������Č����B�������ȃW���P�b�g�𒅂��Ȃ�80�̐搶�������ɂ����B���̐܁A�u�͂�����A�W���A���̃p���v�ƌ���������y�Y�����Q���Ă����������B�u�����ǂ����\����܂���v�ƌ����Ɓu�ȁ[�ɁA�ʂ蓹�����V�C����������C������������v�Ƌ�B������̐����������O�z�ɗ�������AB1�́u�W���A���v�Łu�`���R���[�g�p���v���A������̕��Ђ܂ŗ��Ă��������Ă����̂��B��Ђ�߂��̋i���X�Ő搶���炢�낢�남�b�����B�ł��A�f���W���Y�ɑa�����͂��������̋@���Q��Ă������ƂɂȂ�B�����ƒm��������A�A�[�g���G���^�e�C�������g�̐�����������搶����l�X�ȏ��������������Ƃ��ł������낤�B�c�O�����d�����Ȃ��B�����A�{�[���Ɛ����Ă��������͐搶�̈̑傳��F���ł����A�M�d�Ȏ��Ԃ�L���ɔ�₷�\�͂��Ȃ������Ƃ������Ƃ��B����Ȑl�ԂɁA�搶�͐^�ɗD�����ڂ��Ă����������B�L��]��m���ƌo���������Ȃ���A�������Ђ��炩�����ƂȂ������Ĉ̂Ԃ�Ȃ��B�_���f�B�[�ʼn����B�u�{���̃J�b�R�悳�Ƃ͉����v�������Ă����������B����搶�Ƌ��L�ł������Ԃ͂��������̂Ȃ��ł���B���ꂩ����f���W���Y�ɐڂ��邽�тɎv���o�����Ƃ��낤�B�`���R���[�g�p���̍���Ƌ��ɁB
�@�@���Q�l������
�@�@���{����p�فu����v���V�l�}�E�O���t�B�b�N�X�W�v�o�W�ژ^
�@�@����v���F�W���Y�̉�������i������Ѓ��}�nH�o�ŕ��j
�@�@�A�C���[���E�N���[���u�W�F���g���E���C���vCD
�@�@�u�Ȃ�ł��Ӓ�c�vTV���� 2011.11.3 OA
2019.02.25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ ���
��O�́F���{�����Ɛ���������Δ䂳�����@RECTUS��INVERSUS�̓o�b�n�u�����t�[�K�v�ɂ����đ��Ȃ��B�\����� ��Ζ����I���ȓ���Ƃ����Ă������B���͂ɂ����鐼�������͂ɂ����鐼���������ł���B���́A�፷���̐�ɐ����͉������Ă������A�Ƃ������Ƃł���B�T��ɂ������āA�ނ̈₵�����t�A�Ⴆ�u��F����P�v�������ǂ݉����̂��������A���ꂾ���ł͖ʔ����Ȃ��̂ŁA���̓��{�̐����ƏƂ炵���킹�Ă݂�̂��ꋻ���ƍl����B�J�ԁA���{�ꋭ�Ƃ����Ă���̂ł��邩��A�����̓V���v���Ɉ��{�����Ɛ����̎v�z��Δ�E�l�@���Ă݂����B
(1) �č��ɒǐ����邾���̈��{�O��
 �@2016�N11���A�哝�̏A�C��҂����ꂸ�A���E�ł��̈�ԂɃg�����v�哝�̂̌��ɂ������ł��������{�B����͂܂��A���ē����̏d�v�����l����Ƃ����Ĕ���ɂ͓�����Ȃ��B�ނ���f�����͕]���ł���i�u�h�i���h�v�Ƃ����Ăт����͂�߂ė~�������j�B�����A���ŋ߂̃j���[�X�͂��������Ȃ��B�����^���Ƃ͂܂��ɂ��̂��ƁB�Ȃ�ƁA���{���u�g�����v�哝�̂��m�[�x�����a�܂ɐ��E�����v�Ƃ����̂ł���B���R�́A�k���N�̋��Ђ@��������Ƃ��B�m���ɁA���{�̏��k���N�̃~�T�C����������̂͊�����ł͂���B�����A�g�����v�哝�̂̕��a�����������X�̍s�ׁE�E�E�E�E�C�X���G����g�ق̃G���T�����ւ̈ړ]�B���V�A�Ƃ�INF�S�p���̔j���B�C�����̊j�J���Ɋւ��鍑�ۍ��ӂ���̗��E�Ȃǂ͎��m�̎����B������m������Ő��E����Ȃ͂����x���H�Ƃ����ׂ����B �v���i�V�A��펯�A���ۊ��o���@�̔��͖Ƃ�Ȃ��B�ǂ��l���Ă��݂��Ƃ��Ȃ��b�ł���B
�@2016�N11���A�哝�̏A�C��҂����ꂸ�A���E�ł��̈�ԂɃg�����v�哝�̂̌��ɂ������ł��������{�B����͂܂��A���ē����̏d�v�����l����Ƃ����Ĕ���ɂ͓�����Ȃ��B�ނ���f�����͕]���ł���i�u�h�i���h�v�Ƃ����Ăт����͂�߂ė~�������j�B�����A���ŋ߂̃j���[�X�͂��������Ȃ��B�����^���Ƃ͂܂��ɂ��̂��ƁB�Ȃ�ƁA���{���u�g�����v�哝�̂��m�[�x�����a�܂ɐ��E�����v�Ƃ����̂ł���B���R�́A�k���N�̋��Ђ@��������Ƃ��B�m���ɁA���{�̏��k���N�̃~�T�C����������̂͊�����ł͂���B�����A�g�����v�哝�̂̕��a�����������X�̍s�ׁE�E�E�E�E�C�X���G����g�ق̃G���T�����ւ̈ړ]�B���V�A�Ƃ�INF�S�p���̔j���B�C�����̊j�J���Ɋւ��鍑�ۍ��ӂ���̗��E�Ȃǂ͎��m�̎����B������m������Ő��E����Ȃ͂����x���H�Ƃ����ׂ����B �v���i�V�A��펯�A���ۊ��o���@�̔��͖Ƃ�Ȃ��B�ǂ��l���Ă��݂��Ƃ��Ȃ��b�ł���B�@2017�N7���A���A�̊j����֎~���̍̌��ɓ��{�͕s�Q�������ߍ��B����܂��ɕč��Ǐ]�B�����ɃA�����J�̊j�̎P���ɂ���Ƃ͂����A�B��̔픚�����Ƃ�ׂ��ԓx�ł͂Ȃ��B���{�̍��ƂƂ��Ă������������ׂ������ł���B�L����������^���Ƃ��K�b�J�����Ă���B
�@�k���N�ɑ��Ắu�O�ꐧ�فv�Ƃ���܂��A�����J�ɕ���ċ��Ԃ̂݁B2�����̕Ē���]��k��O�ɁA�g�����v�哝�̂��u��j�����}���Ȃ��v�ƃe���V������������ƁA�u�����郌�x���ň�v�B���Ăŋٖ��ȘA�g��ۂ��Ƃ��m�F�����v�Ƌ�̐��ɖR�������e�ł���������B���ς�炸�̏���ʁB�f�v�����C������B���含�̃J�P�����Ȃ��B���ꂶ��A�������ɔn���ɂ���Ă����傤���Ȃ��B���{�͂����i�����ׂ����B�u�g�����v����A�A�����J�������̊j�����̂܂܂ɂ��Ėk���N�ɔp�������߂�̂̓X�W���ʂ�Ȃ��B�܂��͋M�����j���k������p����������ׂ��B��������Ζk���N�̊j�p�����X���[�Y�ɐi�ނ̂ł́v�B����Ȃ���������R�b�`�������͂��B�f�v�������̎������͂߂邩������Ȃ��B�ł��܂������ł��傤�ˁB���̕��ɂ́B
�@��F���͌���
�@���̂��߂ɐ������ē����̂��邱�Ƃ����H���āA���Ƃ͍��Ƌ��ɓ|��Ă��悢�Ǝv���قǂ̐��_���Ȃ�������A�O���Ƃ̌���(�O��)�͂��܂��^�Ȃ��B���̍�������ł��邱�Ƃɋ�����Ȃ��k���܂��Ă��܂��āA���Ƃ��N����Ȃ��悤�ɂƖ��C������āA���̍��̌����Ȃ�ɂȂ�Ȃ�A�y�̂╎����A�D�܂������ۂ͂������Ĕj�k���Ă��܂��A�I���ɂ͂��̍��̊����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����̂Ȃ̂��B�i��F����P��17�͂��j�@���{�����̎��含�Ȃ��ΕĖӏ]�O�����k���N�ɂ��y�̂�����@���Ɍ������ĂĂ���B
(2) �t�ًɂ܂�k���̓y�ԊҌ���
 �@���{�͌��̏p��m��Ȃ��B�k���̓y��肪�܂��ɂ���B�v�[�`���哝�̂Ƃ̉�k�͓�\����ɋy��ł���悤�����A���d�˂�Ⴂ�����Ă���Ȃ��B�u�܂������̐M���W��z���āA����������ɉ����̕�����T��B���̂��߂Ɍo�ϋ��͂��s������v�E�E�E�E�E���ꂪ���{�̐헪�炵����100���Ԉ���Ă���B�I�펞�A���\���������Ȃ��炻������ĉ䂪���ŗL�̗̓y��s�@�苒�����ȍ����V�A�BKGB�o�g�ŖړI�̂��߂ɂ͎�i��I�Ȃ��S��B���̃v�[�`���B����ȍ��A����ȑ哝�̂�ɐM�����z����Ǝv�����Ǝ��̂��ԈႢ�Ȃ̂��B������������ɑ���L���Ȏ�i�͗B���݂ɕt�����ނ��Ƃ����Ȃ��B�卑���V�A�Ƃ����ǂ��A�i���Ɍo�ςɂ����āj���{�̋��͂��~���������K������B�����҂Ă����B���N�ł��h�����邱�Ƃ��B
�@���{�͌��̏p��m��Ȃ��B�k���̓y��肪�܂��ɂ���B�v�[�`���哝�̂Ƃ̉�k�͓�\����ɋy��ł���悤�����A���d�˂�Ⴂ�����Ă���Ȃ��B�u�܂������̐M���W��z���āA����������ɉ����̕�����T��B���̂��߂Ɍo�ϋ��͂��s������v�E�E�E�E�E���ꂪ���{�̐헪�炵����100���Ԉ���Ă���B�I�펞�A���\���������Ȃ��炻������ĉ䂪���ŗL�̗̓y��s�@�苒�����ȍ����V�A�BKGB�o�g�ŖړI�̂��߂ɂ͎�i��I�Ȃ��S��B���̃v�[�`���B����ȍ��A����ȑ哝�̂�ɐM�����z����Ǝv�����Ǝ��̂��ԈႢ�Ȃ̂��B������������ɑ���L���Ȏ�i�͗B���݂ɕt�����ނ��Ƃ����Ȃ��B�卑���V�A�Ƃ����ǂ��A�i���Ɍo�ςɂ����āj���{�̋��͂��~���������K������B�����҂Ă����B���N�ł��h�����邱�Ƃ��B�@����ɂ܂����̂́A����̃y�[�X�ŕ������i��ł��܂��Ă��邱�ƁB�܂����a���A�������ɗ̓y�����`1956���\�����錾�ɂ͎匠�̋K�肪�Ȃ��`�����o�ϊ����̓��V�A�̖@�̉��Ł`�s��Ƃ������j�܂���A���������ςȂ��̑̂��炭�B�s���ɐ苒�����̂͐���Ȃ̂�����u�ӂ�����ȁv�Ɗ��R�ƌ������ׂ��Ȃ̂ɂւ�ւ���Ă邩�瑊��̃y�[�X�ɛƂ܂����Ⴄ�B�O���͊Ԕ����ꂸ�Ɍ����ׂ����������Ƃ��̗v�B��t������Ŏ��s���Ă���B�u�l���ꊇ�v�u�̓y��������ɕ��a���v�u�匠�����{�͓��R�v�u���V�A�̖@�̉��ł͍s��Ȃ��v�u���j�܂��Ȃ��̂͂ǂ������v�Ə�Ɏ咣�������Ȃ�������Ȃ��B
�@�u�ł��v�͕��ĂƂ��Ď��ׂ������B�m���ɁA1945�N2���̃����^��k�ŁA�ĉp�����V�A�̓��{�ւ̎Q��𑣂��A���̌��Ԃ�ɓ슒���Ɛ瓇�̈����n���F�����̂������B�������Ȃ���A�瓇�ɖk���l�����܂܂�邩�ۂ��͖����ӎ����B�Ȃ�A�u�l���͐瓇�Ɋ܂܂�Ȃ��B�s�@�苒�͔F�߂Ȃ��v����X�^�[�g���ׂ��Ȃ̂��B����́A����̎咣����u���j�܂���v���Ƃɂ��Ȃ�B�����́A���҂̌������̒��ԃ��C���Ō�������̂������B�����獂���ڐ��ŃX�^�[�g���B����͌��̃C���n���B���{�͂���ȊȒP�ȗ����������Ă��Ȃ��B�u���{�ŗL�̗̓y�v�Ƃ���������O�̌��������ŋ߉e����߂Ă����B�n�[�h���������邱�Ƃ������ɂȂ������I�ɔF�߂����悤�Ƃ������_�Ȃ̂��B�Ȃ����U�@�Ő������悤�Ƃ��Ȃ��̂��B�����ɖ₢�����Ă���Ȃ��̂��B���̕��͂����������B����Ȏ㍘�ŕs�����Ō�����Ȃ����ɑ厖�ȗ̓y����C���Ă͂����Ȃ��B
�@���{�́u�v�[�`���哝�̂ƗF�D�I�Ȏ����̔C�����ɖ�����������̂��g���v�Ƃ������A�F�D�I�Ǝv���Ă���͎̂��������B�u�E���f�B�~�[���v�ȂĂт����Ă�����͒m���Ղ�ł͂Ȃ����B�g���Ƃ����͉̂B�ꖪ�B�ނ͂����u���̖k���̓y�������������ŏ��̑�����b�v�Ƃ����h�_���~���������Ȃ̂��B���e�͂ǂ�����A�����������ʂ���j�ɍ��ݕt�����������Ȃ̂��B���Ȃ��̉�~�������߂ɑ�ȗ̓y��蔄�肷�邱�Ƃ͒f���Ăł��܂���B�����Ȃ����Ȃ��ׂ��́A�u�C�����ɉ����v�ȂǂƂ������I�Ȗ�]���L�b�p���Ǝ̂Ă邱�ƁB�����āA���{�̐������X�Ǝ咣���āA�������̐Ȃ𗧂��ƁB���ꂵ���Ȃ��B�ł������ł��傤�ˁB
�@��F���͌���
�@�����J�߂��悤�Ƃ��Ă���Ƃ��́A���̐g�͂�����邱�Ƃ��o��ŁA���������H���A���`��s�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂱ���A���{�̖{���̎d���ł���B���{�����������{���̎g�����ʂ����Ȃ��Ȃ�A���{�́u���@�x�z���v�Ƃ������A������������ɂ�������̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��āA���͂�{�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B�@���{�͍��A�k���̓y���ɉ����āA���肩�猾���������茾���ĉ��甽�_�����A�����o�ϋ��͐��i��}�낤�Ƃ��Ă���B�����ɂ͐^�̋@��Ƃ������̂�����B�厖���s���ɂ͂��̋@�����܂ő҂ׂ����A�Ɠ�F���͐����B
�@�^�̋@��Ƃ����̂́A�����ɓK���A���̂Ƃ��̐������ו��܂ł����炩�ɂ�����ŁA�s������@��Ƃ������ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�i��F����P��18�A38�͂��j
(3) ���@�ɑ��閳��
 �@���{�͌��@�������ߊ肾�Ƃ����B���́A��9���Ɂu���q���̑��݁v�L���邱�ƁB���R�͍��̂��߂ɖ���q���ē������q���������I�ɔF�m���邽�߁B�������Ȃ���u���q���������킢�����v�Ȃ��_������B�����܂ł͂܂��������B���͔ނ̏�������@�_���B�H���A�u�����̂܂܂ɂ��āA�w���q���x�Ƃ������t�L����v�B����͌����}�ӎ����������������A����͂��Ă����A����Ȃ��Ƃ��ł���̂��H���@��9���1���́u�����̔�������푈�ƁA���͂ɂ��Њd�܂��͕���̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��Ă͉i�v�ɂ�����������v�A��2���́u�O���̖ړI��B���邽�߁A���C��R���̑��̐�͂́A�����ێ����Ȃ��v�ł���B���C��R�Ƃ͎��q���̂��Ƃł���B���@��9���́u�����ێ����Ȃ��v��搂��Ă��邪�A�u�O���̖ړI��B���邽�߁v�Ȃ̂�����A�g���ە��������������i�h�Ƃ��Ă͕ێ����Ȃ��Ƃ������ƁB�����A�����łȂ����e�����h�q�ɂ����Ă͂��̌���ł͂Ȃ��B����������A���h�q�̂��߂̎��q���ێ��͈ጛ�ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB�������p�_�͂��ꂪ�������B
�@���{�͌��@�������ߊ肾�Ƃ����B���́A��9���Ɂu���q���̑��݁v�L���邱�ƁB���R�͍��̂��߂ɖ���q���ē������q���������I�ɔF�m���邽�߁B�������Ȃ���u���q���������킢�����v�Ȃ��_������B�����܂ł͂܂��������B���͔ނ̏�������@�_���B�H���A�u�����̂܂܂ɂ��āA�w���q���x�Ƃ������t�L����v�B����͌����}�ӎ����������������A����͂��Ă����A����Ȃ��Ƃ��ł���̂��H���@��9���1���́u�����̔�������푈�ƁA���͂ɂ��Њd�܂��͕���̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��Ă͉i�v�ɂ�����������v�A��2���́u�O���̖ړI��B���邽�߁A���C��R���̑��̐�͂́A�����ێ����Ȃ��v�ł���B���C��R�Ƃ͎��q���̂��Ƃł���B���@��9���́u�����ێ����Ȃ��v��搂��Ă��邪�A�u�O���̖ړI��B���邽�߁v�Ȃ̂�����A�g���ە��������������i�h�Ƃ��Ă͕ێ����Ȃ��Ƃ������ƁB�����A�����łȂ����e�����h�q�ɂ����Ă͂��̌���ł͂Ȃ��B����������A���h�q�̂��߂̎��q���ێ��͈ጛ�ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB�������p�_�͂��ꂪ�������B�@�Ƃ��낪�u���q���v�Ƃ��������L����A���̈Ӗ��������������K�v�������邱�ƂɂȂ�B�������A2016�N����̈��ۖ@���Ŏ��q���̖����͐��h�q���щz���ďW�c�I���q���ɂ܂ŋy��ł���B���̕\�����@���l����ƁA�ƂĂ��u�����̂܂܂ɁA�t��������v�����ł͍ς܂���Ȃ��B�����́A���{�I�ɏ��������āA�u���q���̖����L�v���邱�Ƃ��K�v�����A�������ׂ��d�v�Č��Ȃ̂��B
�@���{�������Ă͕t���n�I�Ŏ��Ɉ����B��3����݂��āu�O���ɂ����Ď��q���̑��݂�r�����Ȃ����̂Ƃ���v������ł�����������Ƃ���̂��I�H ���̍ō��@�K���錛�@�ɑ��Ă���͎���ɂ܂锭�z�ł���B�����ɂ����e�����`�A�u���@�����������ŏ��̑�����b�v�̉h�_��~������{�̉�~���M����B�ŋ߂́A�u���q����W�ɒn�������̂��͓I�Ȃ̂́A���@�Ɏ��q�������L����Ă��Ȃ�����v�ƓI�O��̋Y���������o���n���B��̉��̊W������H ���̐l���⏬���Ƒ����ɂ͂���������ł���B�K�v�Ȃ̂́A�v�X�댯�𑝂��C���ɐg�𓊂��鎩�q�����ɁA�m�ł���Ӌ`�Ɩ��_��^���邽�߂̏��A�c�_���d�˂č����ɒ��ْ���ς˂邱�Ƃ��B�ł��A����̉h�_��D�悷����{�́A7���̎Q�@�I�ʼn������͂��O���̓�����肱�߂Α��f�O����͂��B���ʂ��܂ł̐M�O�͂Ȃ����낤�B�܂��A���{�̂��߂ɂ͂��̕����]�܂�������ǁB
�@��F���͌���
�@�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��A�����ɂ��Ȃ�����������݁A�^�̐S���т��A�l���x���悤�Ȏ�͎g���Ă͂Ȃ�Ȃ��B��������߂A�ڂɂ͉��������Ă��A��ɍs���������đ������A������̂��B�}���Ή��Ƃ������Ƃł���B�i��F����P��7�͂��j�@���{�������ȕ��@�Ō��@�������s�����Ƃ��Ă���B��F���́A���܂����ł͂Ȃ��^�S�����������ɂ��Ȃ��������ɓO����B���ꂪ�������@�Ɛ����B�������҂��ׂ����B
(4) �����J�P���ɂ�����s���A�R�A�B���A���͂̎�����
 �@���{��2017�N�A�X�F��肪���o�������̍���Łu�����Ȃ��ւ���Ă����Ȃ�A������b������c�������߂�v�ƌ��������B
�@���{��2017�N�A�X�F��肪���o�������̍���Łu�����Ȃ��ւ���Ă����Ȃ�A������b������c�������߂�v�ƌ��������B�@���w�Z�ݗ���ژ_�ސX�F�w���ɍ����ȗ����ǂ͍ŏI�I�ɁA����10���~�z���̍��L�n��1��3400���~�ň��������B����������̑ݕt�����������ٗ�̔z�������āB���̗���́A���w���������E�Ēr�דT���ɂ��A2014�N4�����{�v�l�E���b�����w����K��Ă��猀�I�ɕς�����Ƃ����B�w�����͂��̎��̎ʐ^��傫�ȏ�����Ƃ��Ďg�������X���[�Y�ɐi�߂Ă����̂ł���B�v�l�ƍ����Ȃ��q���v�l�t���{�E���̑��݂����炩�ɂȂ����B���ꂾ���ŁA�v�l�̊֗^�͖��炩�B�����Ȃ̌���������������o�����B�͌����ʂ莫�߂Ȃ�������Ȃ��͂��B������ɁA�����Njy�����Ɓu����͑����d�ɂ͊ւ���Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ő\���グ���v�ƏX�������������n���B���͂≽����������ł���B
�@���{��c��ʂ��Đe���������Ēr���ɑ��ẮA���������o����Ɓu�������Ȃ��v�̘A���A�u�������l�v�Ƃ܂Ō����ē�����łB���u�Ǝv���Ă����l�Ԃ����̎�̂Ђ�Ԃ��B�Ēr���͎��]�������ꂽ���Ƃ��낤�B
�@���v�w�����������\�}�B���{�͍���ŁA�u���v�w�������Ɛ헪����Ƃ��ďb��w���̌��݂�\�����Ă��邱�Ƃ́A2017�N1��21���܂Œm��Ȃ������v�ƌ����B�F�l�ւ̕X��ے肵���B�����̏���A�����M����Ƃ������������B�R�͖��炩�ŁA������Ȃ����U���قɒl����B��A�̑����̒��A�u�x�Ȃ�s�����ȗ��s�ꂪ���܂ꂽ�B�Ȃ��s�������Ƃ����A�u�x�����l�Ԃ��u�x�ɒl���Ȃ�����ł���B���͂͌����̂��߂Ɏg�����́B������Ƀ����J�P���i�ŋ߂͒����f�[�^�s������荹���j���猩����̂́A�������Ƃ͗����̉R�ƕs���ƉB���ɕ���ꂽ���{�����̌��͂̎������ł���B
��F���͌���
�@�����̏�ɗ������Ƃ́A�Ȃ�T�݁A�i�s�𐳂������A遂荂�Ԃ邱�Ƃ����߁A���ʌ��������Ȃ��悤�ɋC�������A����̐E���ɐ��サ�č����̎�{�ƂȂ�A�����̋ΘJ������J�Ǝv�����Ƃ��Ȃ���A�����͍s���ɂ����B�@��L�͓�F�����A�V���{�̈ېV����̑���Q�������́B���ꂪ���̂̌����Ɉ��{�����ɓ��Ă͂܂�B�Ȃ�T�ނ��ƂȂ��i�s���s���B�F�l�̕X�͐}�邪�ڂ͍����������Ă��Ȃ��B�s���������Ȃ�Ɛl���̂āA�R�����A�B����}��B�}����˂�������Ԃɏo��遂�V��B���ʌ��������O�̎؋���ł��A��@���������č��{�I������}�낤�Ƃ��Ȃ��B�p��m��S���Ȃ���ΐߑ����Ȃ��B�����̎�{�Ƃ͒��������͂̎������������ɂ���B��������͂���Ȃ��Ƃł͐����͍s���ɂ������͈ێ��ł��Ȃ��Ɛ����B���{�͑����u��F����P�v��ǂނׂ��ł���B�ő���x��A����N�X���͂Ȃ������m��Ȃ����E�E�E�E�E�B
�@�ߑ������A�`�����d�A�p��m��S�������ƁB���̂悤�Ȏp���������Ȃ��Ȃ�A���͈ێ��ł��Ȃ��B�i��F����P��S�A16�͂��j
���Q�l������
��F����P�i�����������j�p��\�t�B�A����
2019.02.01 (��) �N�C�[���u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v���|�[�g
�@�f��u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v���b��ł���B�ϋq����700���l�A���s����100���~��˔j�B�A�J�f�~�[�܂̍�i�܁A�剉�j�D�܂Ȃ�5����Ƀm�~�l�[�g���ꂽ�B�N�C�[���E�t�@���ł����b�N�E�t�@���ł��Ȃ������ςĂ��܂����B�f���炵�������B�䂪�l���Ŋ��������f��x�X�g5�ɓ���B���̗��R�̈�̓t���f�B�E�}�[�L�����[�̑s��Ȑ������܁B������͈��|�I�ȉ��y�̗́B���Ƀ^�C�g���y�ȁu�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v�̐����ł���B����́A���ȁu�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v�ɏœ_�āA���̒�m��ʖ��͂ɔ����Ă݂����B(1) �u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v�T�v
 �@��{�w�~�A���E���v�\�f�BBOHEMIAN RHAPSODY�́A�N�C�[��QUEEN4���ڂ̃A���o���u�I�y�����̖�v�̐�s�V���O���Ƃ��āA1975�N9���ɐ��ɏo���B�쎌�E��Ȃ̓t���f�B�E�}�[�L�����[�i1946�|1991�j�B�N�C�[���̓C�M���X�̃��b�N�E�o���h�B�����o�[��4�l�B�t���f�B�ivo,key�j�̓C�[�����O���p��w�Ńf�U�C�����A�u���C�A���E���C�ig�j�̓C���y���A����w�œV���w���A���W���[�E�e�C���[�ids�j�̓����h����ȑ�w�Ŏ��w���A�W�����E�f�B�[�R���ibs�j�̓����h����w�œd�q�H�w���A�v�X�w���Ȃ�̃C���e���W�c�ł���B
�@��{�w�~�A���E���v�\�f�BBOHEMIAN RHAPSODY�́A�N�C�[��QUEEN4���ڂ̃A���o���u�I�y�����̖�v�̐�s�V���O���Ƃ��āA1975�N9���ɐ��ɏo���B�쎌�E��Ȃ̓t���f�B�E�}�[�L�����[�i1946�|1991�j�B�N�C�[���̓C�M���X�̃��b�N�E�o���h�B�����o�[��4�l�B�t���f�B�ivo,key�j�̓C�[�����O���p��w�Ńf�U�C�����A�u���C�A���E���C�ig�j�̓C���y���A����w�œV���w���A���W���[�E�e�C���[�ids�j�̓����h����ȑ�w�Ŏ��w���A�W�����E�f�B�[�R���ibs�j�̓����h����w�œd�q�H�w���A�v�X�w���Ȃ�̃C���e���W�c�ł���B�@�����A5��57�b���̒��ڃV���O���̓��W�I�ǂ�OA���Ȃ��Ƃ��āA���͂͑唽�B�����A�����o�[�͉�����B�����A�C�M���X�̃��W�I�ǂ�2�ǂ݂̂��������A���̂����̈�L���s�g���E���W�I��DJ�P�j�[�E�G�x���b�g�i�f��ɂ���u�o��j�����̋Ȃ��C�ɓ���M�S��OA����Ə��X�ɉ����A11���ɂ͑S�p��1�ʂ��l���A���̂܂�9�T�A����1�ʂ̑�q�b�g�ƂȂ����B�q�b�g�̔w�i�ɂ̓C�M���X�̐��������f���Ă���Ƃ����B�����̃C�M���X�̓T�b�`���[�O��B�I�C���V���b�N�̉e���ŏT��3���͒�d�A���Ɨ��������u�C�M���X�a�v�Ƃ�����Â����ゾ�����B����Ȑ�������A���������V���O���̑唼���y�����邢�m���̋Ȃ���B�{���u���̃C�M���X�̉��y�t�@���̓E���U�����Ă����B�����ɏd������́�{�w�~�A���E���v�\�f�B���o�ꂵ�đ�q�b�g�ƂȂ����B�j�㏉�Ƃ�����v�����[�V�����E�r�f�I�̌��p���q�b�g�̈���Ƃ����B�Ƃ͂����A�ő�̗v���͊y�Ȃ̃p���[�ł��邱�ƂɈ٘_�͂���܂��B���t�ƃR�[�_�ɋ��܂ꂽ�o���[�h�A�I�y���A���b�N�̎O���\���B�o���[�h�E�p�[�g�́A�t���f�B�̗ނ܂�ȉ̏��͂����I�R��E�����肾���B�I�y���E�p�[�g�́A��ȃA�C�f�B�A��180��d�˂��Ƃ������d�^���̌��ʂɂ�胆�j�[�N�����k�Ȏd�オ����݂���B���b�N�E�p�[�g�́A�G���[�V���i���ȃn�[�h���b�N�E�T�E���h�ő�c�~��z���B���t�ƃR�[�_�͓N�w�I�Ӗ��[���Ȍ��t�őS�̂�����B�u���C�A���̃M�^�[�E���[�N�͂Ƃ��ɏ�M�I�ɂƂ��ɍ��M�Ɋe�p�[�g���q���B��{�w�~�A���E���v�\�f�B�́A�������đ��ʁA���т₩�Ő_��I�A�܂�Ŗ��؋��̂悤�ȍ�i�Ȃ̂��B
(2) �{�w�~�A��
�@��{�w�~�A���E���v�\�f�B�̃{�w�~�A���Ƃ̓{�w�~�A�ɏZ�ސl�̈Ӗ��B����ɁA���Q�̖��E�W�v�V�[�̕ʏ̂ŁA��������h�����āA���Ȃ̎�`�咣��ς����Ɏ��R�C�܂܂ɕ�炷�l�X�̏ے����ł�����B�t�����X��́u�{�G�[���v�ŁA�v�b�`�[�j�̓����̃I�y���́A�p���ɏZ�ރ{�w�~�A���̎�҂����̕��ꂾ�B���v�\�f�B�͋����ȂƖ�A�����Ԃ銴��I�Ŏ��R�ȋȑz�̍�i�������B������u�������v�Ƃ����Ӗ�������B�f��ŁA�t���f�B���u����͏��������v�ƌ�����ʂ����邪�A����܂��Ă̂��̂��낤�B�m���ɓ��Ȃ�S�������ɓf�I�����S�͈̂�҂̏�������
 �����B
�����B�@�t���f�B�́A1946�N�A�A�t���J�̉p�̃U���W�o���i���݂̃^���U�j�A�j�Ő��܂ꂽ�B�c�����̓C���h�ʼn߂����A���̌�Ăѐ��n�ɖ߂邪�A1964�N�Ɋv�����u���������߁A�C���O�����h�̃~�h���Z�b�N�X�B�ɈڏZ����B���ꂼ���Q�A�܂��Ƀ{�w�~�A���ł���B�U���W�o���Ƃ����z���E�T�s�G���X���˂̒n�B��X�̑c��͂�������_�ɐ��E�e�n�ɕ��Q���Ă������B�l�ނ��̂��̂��{�w�~�A�����Ƃ���t���f�B�������^�����̖{�ƃ{�w�~�A���Ȃ̂��B
(3) �A�E�g�T�C�_�[���}�C�m���e�B
�@�t���f�B�̗��e�̓y���V���n�C���h�l�B�@���̓]���A�X�^�[���ł���B�C�M���X�Љ�ɂ����Ă���͌��R���鏭���h�ł���B�f��ɂ��ƁA�c��������g�p�L�X�^����Y�h�Ɲ�������Ă����悤���B�t���f�B�̂�����̑��ʁA���I�w���ɂ��āA�f��̒��ł���ȏ�ʂ�����B���U�̗F�l���A���[�E�I�[�X�e�B���Ɂu�l�̓o�C�Z�N�V���A���Ȃv�ƍ�������ƁA�ޏ��́u���Ȃ��̓Q�C�@�C�Â��Ă�����v�ƕԂ��B�ǂ���ɂ��Ă����I�}�C�m���e�BLGBT�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�����͍��قNJ���ł͂Ȃ��B�t���f�B�͍��ʂ̐l�������ł����̂��B
�@��{�w�~�A���E���v�\�f�B�̃I�y���E�p�[�g�ɂ͗l�X�Ȑl�Ԃ��o�ꂷ��B�K�����I�A�t�B�K���A�X�J�����[�V�����X�B�K�����I�E�K�����C�i1564�|1642�j�́A�����̐�ΓI���Ђł��鋳��ɑ��u����ł��n���͉���Ă���v�ƐM�O���Ȃ��Ȃ������B�t�B�K���̓J�����E�h�E�{�[�}���V�F�i1732�|1799�j�̋Y�ȁu�t�B�K���̌����v�̎�l���B���̑�5���ŁA��l�̗̎�ɑ��u���́A�M���A���Y�A�g���A�K�����ׂĂ������Ăӂ�Ԃ�B���������������ɓ���邽�߂ɂȂɂ������H���܂�Ă����A�������ꂾ���̂��Ƃ���Ȃ����B����Ɉ����������̂���Ȃ́A�ǂ����̔n�̍��̈�l�B���ɑR����ɂ͌��d�p���M���S�m�S�\���X���邵���Ȃ��v�Ɣ����B����܂��ɃA�E�g�T�C�_�[�̔������_�B�X�J�����[�V���̓C�^���A���̓����Ŏ���̈������Ė��B�ނ�O�l�͂�����ăA�E�g�T�C�_�[���}�C�m���e�B�B�t���f�B�͎����Ɠ��������̂���l������j����I�яo�����̂��B
(4) �V�F�C�N�X�s�A�ƃM���V����
�@�f��̒��ŁA�u����̓M���V���ߌ��ƃV�F�C�N�X�s�A�̋@�m�ɗ��ł�����Ă���v�Ƃ����t���f�B�̑䎌������B���̑䎌�Ɗy�ȂƂ̊֘A����������B
�@�M���V���ߌ��̗l���͎O����B�A�C�X�L�����X�́u�I���X�e�C�A�v�O����͂��̑�\�I��i�B���[�O�i�[�́u�w�v�����̗l���ށB��{�w�~�A���E���v�\�f�B�̎O���`��������P���Ă���B�t���f�B�̌��t�́A���e�ł͂Ȃ���̂��Ƃ��w���Ă���Ǝv���B
�@�ł́A�V�F�C�N�X�s�A�Ƃ̊֘A�́H �`���̎��́u����͌����H����Ƃ������̌��H�v�����A����̓n�����b�g�̗L���ȑ䎌�u������ׂ��� �����ׂ��� ���ꂪ��肾�v�ɕ�������B�I�y���E�p�[�g�ɂ���u���ƈ�ȁv�̕����́u�}�N�x�X�v��3���ɂ��̂܂o�Ă���B�܂��A����C�M���X�̎��҂́u���t�ƃR�[�_�́w�����������Ƃ���Ȃ�nothing really matters�x�̓}�N�x�X�́w�l���͉e�ɉ߂��Ȃ� �l�Ԃ͈���Ȗ��ҁx�ɒʂ���v�Ǝw�E������ŁA�u��{�w�~�A���E���v�\�f�B�ɂ̓V�F�C�N�X�s�A�̃G�b�Z���X���l�܂��Ă���v�Ɛ����B�{�l���C�M���X�̎��҂������̂����炱��͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�M���V���ߌ��ƃV�F�C�N�X�s�A�����ނ̂������{�w�~�A���E���v�\�f�B�̐[���͌v��m��Ȃ����̂�����B
(5) �N���V�b�N���y
 �@�t���f�B�̓N���V�b�N���y�A���ɃI�y�����D���ł���B�u�i���̐����v�Ƃ����Ȃɂ́A���I���J���@�����̉̌��u�����t�v�̈�߂��g���Ă���B�f��ɂ�3�̃I�y���E�A���A���o�ꂷ��B��Ȗڂ̃v�b�`�[�j�F�u���X�v�l�v�́u���鐰�ꂽ���Ɂv�́A���A���[�ƈꏏ�̏�ʂŗ����B���̃r�[�[�F�u�J�������v����u���͖�̒��i�n�o�l���j�v�́A��{�w�~�A���E���v�\�f�B���V���O���ɑ��������Ȃ��Ƃ���v���f���[�T�[�Ƀt���f�B�����_�����ʂŗ����B�O�Ȗڂ̃v�b�`�[�j�F�u�g�D�[�����h�b�g�v���烊���E�̃A���A�u���������������A���q�l�v�́A�߂��ɏZ�ނ悤�ɂȂ������A���[�Ɠd���̌��Ō�M�����ʂŗ����B
�@�t���f�B�̓N���V�b�N���y�A���ɃI�y�����D���ł���B�u�i���̐����v�Ƃ����Ȃɂ́A���I���J���@�����̉̌��u�����t�v�̈�߂��g���Ă���B�f��ɂ�3�̃I�y���E�A���A���o�ꂷ��B��Ȗڂ̃v�b�`�[�j�F�u���X�v�l�v�́u���鐰�ꂽ���Ɂv�́A���A���[�ƈꏏ�̏�ʂŗ����B���̃r�[�[�F�u�J�������v����u���͖�̒��i�n�o�l���j�v�́A��{�w�~�A���E���v�\�f�B���V���O���ɑ��������Ȃ��Ƃ���v���f���[�T�[�Ƀt���f�B�����_�����ʂŗ����B�O�Ȗڂ̃v�b�`�[�j�F�u�g�D�[�����h�b�g�v���烊���E�̃A���A�u���������������A���q�l�v�́A�߂��ɏZ�ނ悤�ɂȂ������A���[�Ɠd���̌��Ō�M�����ʂŗ����B�@�u�J�������v����{�w�~�A���E���v�\�f�B�b�̃o�b�N�ŗ����̂́A�{�w�~�A���q����Ƃ��Ď��R�Ɍ��т��B�v�b�`�[�j�̓�Ȃ����A���[�Ƃ̏�ʂŎg��ꂽ�̂́A�ޏ��̌��g�I����A�I�y���̓�l�̃q���C���ƃ����N���邱�Ƃ�F�m�����X�^�b�t�̈Ӑ}���낤�B����ɂ́A���X����͓��{�l�A�J�������̓W�v�V�[�i���}�j�A�����E�̓^�^�[���i���j�l�ŁA�O�҂Ƃ��ٖM�l�ɂ��Ĕ��K�̐g�̏ゾ����A����̓t���f�B���g�Əd�Ȃ邱�Ƃ��������Ă̂��Ƃ��낤�B
�@�I�y���E�p�[�g�͂��̂��̃Y�o���̃N���V�b�N�B�Ⴆ�u�t�B�K���̌����v��u�h���E�W�����@���j�v�̏I�Ȃ̎�ł���B�I�y���I�升����\�o���邽�߃����o�[���I�[�o�[�E�_�r���O��180����{�����̂͗L���Șb�B�������s��̃V���Z�T�C�U�[��p���Ȃ������̂́A�N�C�[���Ȃ�ł͂̃N���V�b�N�I�E�l�C���̕\�ꂾ�낤�B���C���ł́A���̃I���W�i��������}�����Ă���i�f��̃G���f�B���O�ł���u���C���E�G�C�h �E�F���u���[�E�X�^�W�A��1985�D7.13�v�ł́A���Ԃ̐���o���[�h�E�p�[�g�݂̂̃p�t�H�[�}���X�ƂȂ��Ă���j�B
�@�t���f�B�̊y�Ȃœ��M���ׂ��͓]���̖��ł���B�u�`���̃`�����s�I���v�ł́A�T�rWe are the champions�ɓ���Ƃ��AC�}�C�i�[��F�ɓ]���A�Ȓ��̓]������������B����ɔ����āA��{�w�~�A���E���v�\�f�B�̃o���[�h�E�p�[�g�́AB��ŃX�^�[�g����������9���ߖڂ���C�}�C�i�[��E��E��}�C�i�[�ƕω�����B���̗���́A���܂�ɂ��X���[�Y�ŁA�]�������������Ȃ��B���̐��k�Ȏ��R���͂܂��ɓV�˂̋Z�B���[�c�@���g�I�ł���B�Ⴆ�u�A���F�E���F�����E�R���v�X�v�̂悤�ȁB���������A�f��ŁA�t���f�B���s�A�m����������Ԃ��Ēe����ʂ����邪�A�f��u�A�}�f�E�X�v�ł����l�ȏ�ʂ��������B���Ղ̍������t�Ȃ̂�������������Ă���H
�@�O�͂Ō��y�����O���\���Ƃ����X�^�C���̓o���b�N���y�̒�Ԍ`�ł���\�i�^�`���ɂȂ���B�܂��A���t�ɂ�������ߕ���u�ǂ����ɂ������ĕ��͐����̂� �l�ɂ͂����������Ƃ���Ȃ��v�́A�R�[�_�̒��߂ʼn�A����B���̎�@�́AJ.S.�o�b�n�́u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv��t�����N�̏z�`���Ɍĉ�������̂ŁA���G�Ȋy�Ȃɓ��ꊴ��^������ʂ�����B��{�w�~�A���E���v�\�f�B�̓N���V�b�N���y�̗v�f���ځA���x�����Ă��O���邱�Ƃ��Ȃ��B
(6) �t���f�B�͒N���E�����̂�
�@��{�w�~�A���E���v�\�f�B�̃o���[�h�E�p�[�g�̖`���u�}�}�A���������l���E���Ă���Mama,just killed a man�v�͋��B���ɂ��т���ė���Ȃ��B������́A�Ȃ̊Ԓ��A��̂�����E�����̂��H�Ȃ�^����������葱����B�����������A�����_���I�ɉ𖾂���͕̂s�\���낤�B�Ȃ��Ȃ�A���̎��͌l�I�ے���������B�`���ł��u����͌����Ȃ̂��A����Ƃ������̌����v�ƓB���h���Ă�����B���߂͗����ł͂Ȃ����ςɗ��邵���Ȃ��B
�@���́A�o���[�h�E�p�[�g��2�R�[���X�ڂɂ���u�^���ƌ�������face the truth�v�Ƃ������t���N�T�C�ƒ��������B�^���ƌ��������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H ����̓t���f�B���Q�C���B�����ɐ��ʂ�����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂��B�Ȃ�A�t���f�B�͒N���E�����̂��H �����͎����Ɓu�������g�v�Ɠ����o�����B����܂ł̎������E���V���������ɐ��܂�ς��B�����A�ߋ��Ɍ��ʂ������ɐ����錈�ӂ������Ƃ������ƁE�E�E�E�E���̊ϓ_����S�̂����킽���Ƃ��ׂēǂ݉������悤�Ɏv�����B�ߋ��Ɩ�������������ꌩ����Ȏ����X���X���Ɖ𖾂��ꂽ�悤�ȋC�������B��{�w�~�A���E���v�\�f�B�̓t���f�B�E�}�[�L�����[���V���ȑ����ݏo�����ӂ̎������Ȃ̂ł���B
�@�f��̃��X�g20���̃��C�u�E�V�[���ł́A�G�C�Y�ɗ����������t���f�B���ӂ̃p�t�H�[�}���X���J��L������B��X���A�u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v�Ƃ����y�ȁ��f��Ɋ�������̂́A�u�^���ƌ��������v�{�u���Ӂv�Ƃ������ʂ̃L�C�E���[�h�ɂ��B����Ȍ������ł���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@����ȕ��ɉ��߂����݂����A�ƑP�ɂ����Ȃ����Ƃ͏��m���Ă���B�u�|�p�Ƃ͔��̑n���҂ł���B����|�p��i�Ɋւ���ӌ����܂��܂��ł��邱�Ƃ́A���̍�i���a�V�����G�Ȑ����͂ɂ��ӂ�Ă���؋��ł���v�Ƃ����I�X�J�[�E���C���h�̌��t������B�Ȃ�A�|�p��i�ł����{�w�~�A���E���v�\�f�B�́A�g�����l�ɂ���Ĉӌ����܂��܂��Ȃ͕̂K�R�h�Ƃ������ƂɂȂ�B�����͂܂��A���b�N���S�҂��₩�N�C�[���E�t�@���̎����A�f������������ɂ��āA�Ȃ���Ȃ�ɂ���̈ӌ��������o�������Ƃ�f���Ɋ�ׂ����̂��ȁA�Ǝv���̂ł���B
�@2��25���̓A�J�f�~�[�����B�ʂ����āu�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v�͍�i�܂ɋP���̂��B���~�E�}���b�N�͎剉�j�D�܂��l���̂��B���ɂȂ��y���݂Ȃ��Ƃł���B
���Q�l������
�f��u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v�i��20���IFOX 2018�N�j
���I�����́u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�E�l�����vNHK-BS 2002�NOA
�u�v���~�A���E���C�� QUEEN�vNHK-BS 2014�N OA
Live at Wembley Stadium DVD
QUEEN ROCK Montreal&Live-Aid DVD
�N�C�[���E�O���C�e�X�g�E�q�b�c 1,2,3 CD
�N�C�[���u�I�y�����̖�vCD
�{�[�}���V�F���A�Έ�G��u�t�B�K���̌����v�i�V���فj
2019.01.20 (��) �N���N�n�G���E���y�с`�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�Ə���
(1) �j���[�C���[�R���T�[�g�̃e�B�[���}���͑z��O�̑f���炵���@�N�̐�������������12��27���AFM���ǂ���̃f�B���N�^�[Noririn�����삩��d�b����B�u�}�ł����A1��4���ɏo���ł��܂��H�v�Ƃ����B���T���j�́u��������Ȃ����v�Ƃ����ԑg�̐V�t�ꔭ�ڂ��u�N���V�b�N�Ŗ��J���v�I�Ȓ��g�ɂ������Ƃ����B�A�ؓ�����Ȃ����A�u�҂��Ă܂����Əo�����悤�v�Ƒ����B
 �@�\���̓C�m�V�V�`������ځ`�V�N�Ƃ����B�܂���ȖځB���x�̃C�m�V�V�ɒ��ڈ����y�ׂ����A�Ȃ��B�����ōł��u���˖Ґi�ȃN���V�b�N�͉��H�v�ɐ�ւ���ƁA�u�V���ƒn���v�Əo���B��3���̂���͕������`�����ŌÂ�CM�\���O�̌��Ȃł�����݁B�X�^�[�g�͂���Ɍ��܂�B���́u������ځv�B��N�̊������u�Ёv�������悤�ɁA�����͂܂��ɍЊQ�̎��ゾ�����B�ő�̂��̂�2011�N�̓����{��k�Ђ��B�k�Ј�P�����4��10�Ɉ�ۓI�ȉ��t��������B�u�v���V�h�E�h�~���S�E�R���T�[�g�E�C���E�W���p��2011�v�ł���B���̂���A�����̉e���ŁA�����̊C�O�A�[�e�B�X�g���h�^�L�������钆�A�h�~���S�́u��D���ȓ��{�̊F���܂̏����ł��͂ɂȂ�v�Ƃ̎v���ŁA����Ă��Ă��ꂽ�B�R���T�[�g�̏I�ՁA�ϋq�ƈꏏ�Ɂu�ӂ邳�Ɓv�𗬒��ȓ��{��ʼn̂��B���ɐS���܂��ʂ������B�v����1996�N7��7���A��Əf��Ƃōs�����u3��e�m�[���v���{�����ł��A���{��Łu��̗���̂悤�Ɂv���̂������A�h�~���S�����̓�l�����[�h���Ă����B�A���R�[���͏\���ԁu�O���i�_�v�B�����ŁA2�Ȗڂ�1994�N�h�W���[�X�^�W�A���E���C�u�̃e�C�N��I�Ȃ����B���݂Ƀh�~���S�́A��N�x�����������̌���ŁA���F���f�B�́u�}�N�x�X�v�̃^�C�g���E���[���������Ă���B77�̉̏��͂܂��܂����݂ł���B
�@�\���̓C�m�V�V�`������ځ`�V�N�Ƃ����B�܂���ȖځB���x�̃C�m�V�V�ɒ��ڈ����y�ׂ����A�Ȃ��B�����ōł��u���˖Ґi�ȃN���V�b�N�͉��H�v�ɐ�ւ���ƁA�u�V���ƒn���v�Əo���B��3���̂���͕������`�����ŌÂ�CM�\���O�̌��Ȃł�����݁B�X�^�[�g�͂���Ɍ��܂�B���́u������ځv�B��N�̊������u�Ёv�������悤�ɁA�����͂܂��ɍЊQ�̎��ゾ�����B�ő�̂��̂�2011�N�̓����{��k�Ђ��B�k�Ј�P�����4��10�Ɉ�ۓI�ȉ��t��������B�u�v���V�h�E�h�~���S�E�R���T�[�g�E�C���E�W���p��2011�v�ł���B���̂���A�����̉e���ŁA�����̊C�O�A�[�e�B�X�g���h�^�L�������钆�A�h�~���S�́u��D���ȓ��{�̊F���܂̏����ł��͂ɂȂ�v�Ƃ̎v���ŁA����Ă��Ă��ꂽ�B�R���T�[�g�̏I�ՁA�ϋq�ƈꏏ�Ɂu�ӂ邳�Ɓv�𗬒��ȓ��{��ʼn̂��B���ɐS���܂��ʂ������B�v����1996�N7��7���A��Əf��Ƃōs�����u3��e�m�[���v���{�����ł��A���{��Łu��̗���̂悤�Ɂv���̂������A�h�~���S�����̓�l�����[�h���Ă����B�A���R�[���͏\���ԁu�O���i�_�v�B�����ŁA2�Ȗڂ�1994�N�h�W���[�X�^�W�A���E���C�u�̃e�C�N��I�Ȃ����B���݂Ƀh�~���S�́A��N�x�����������̌���ŁA���F���f�B�́u�}�N�x�X�v�̃^�C�g���E���[���������Ă���B77�̉̏��͂܂��܂����݂ł���B�@�ǂ�K�͂Ȃ�Ƃ����Ă��E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�ł���B�N���V�b�N�E�t�@���ɂƂ��Ă͐V�N�P��̃C���F���g�B����������ĔN�͖����Ȃ��B�n�܂����̂�1939�N12��31���A�w���҂̓N�������X�E�N���E�X�i1893�|1954�j�B�����̓i�`�X�̓������B�s���̃K�X�������ړI�������Ƃ����Ă���B��2���1941�N1��1���B�Ȍ㖈�N�����ɍs����悤�ɂȂ�B���݂ɁANHK�g����1951�N��1������4��ڂ����A���ƂȂ��č����Ɏ��邪�A�����1954�N�̌������V�t�����̂��߉��̋��Ȃ���������A�Ƃ����̂����̗��R�B�����A�����̔N���N�n�̑剹�y�C���F���g���A�^�t�̌`�ō��̃X�^�C���𐬂��Ă���̂��ʔ����B����w���҂̃N�������X�E�N���E�X�́A�I����1946�`47�N�́A�i�`�X�̋��͎҂ƌ���āA���[�[�t�E�N���b�v�X�ɂ��̍������邪�A1948�N���畜�A�A�ʎZ12��𐔂����B1955�`79�N�̓R���T�[�g�}�X�^�[�̃E�B���[�E�{�X�R�t�X�L�[��25��߂�B���@�C�I������e���Ȃ���̃X�^�C���́A�����c�����n���E�V���g���E�X��f�i�Ƃ�������́B1980�`86�N�̓������E�}�[�[����7��B1987�N�͒鉤�J���������ŏ��ōŌ�̓o��B��������A���o�d���Ȃ��Ȃ�B�]���āA�{�X�R�t�X�L�[�̘A��25��̋L�^�͍���܂��j���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�I���͖��炩�ł͂Ȃ����A�l�C�Ǝ��͂����˔������ꗬ�w���҂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̒��̃x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�́A�J�����X�E�N���C�o�[�i89�A92�j�ƃW�����W���E�v���[�g���i08�A10�j�B�O�҂͐▭�Ȃ铝�����A��҂͎���Ȃ���x���Ƃł����������B�f���炵�����ƍb�����������ł���B���{�l�w���҂͏��V�����i02�j�̂݁B�͂����Ď��͂����ꂪ�H
 �@���āA79��ڂ̍��N�̓N���X�e�B�A���E�e�B�[���}���ł���B1959�N���܂�59�h�C�c�̎w���ҁB���݃h���X�f�������̌���nj��y�c�̎�ȁB���ӂ̓��[�O�i�[�B���ɐ��n�o�C���C�g���y�Ղł̊���͖ڊo�܂����A���ē߂郏�[�O�i�[�̑\���o���̊o�����悭�A�߁X�A�o�C���C�g���y�ՁE���y�ږ�̍��ɏA�����Ƃ��m��������Ă���B����ȁA���܂��ɏ{�Ȏw���҃e�B�[���}�����U��j���[�C���[���y���݂łȂ��킯���Ȃ��B������FM�̃l�^�T�������܂�̂�����A�����ȏ�Ɏ��ڂ��Â炵���B�Ƃ͂����S�z������B�Ȃ����āA�e�B�[���}���͋����ŋ��ʁB���p�[�g���[�̒��S�͏d���ȃh�C�c�{���B���ł������ȃE�B���i�E�����c�Ƃ͐��Ɩ��A�Ƃ̐���ς��������B�Ƃ��낪�A�n�܂��āA����ȞX�J�͂����ɐ�����B�\���͑傫���C�����͑@�ׁA���y�͊��������Ɩ�������B���������O�Ɍ�����Ί�͋��ʂƂ͗����Ɏ��Ƀ`���[�~���O�B�ŏI�y�Ȃ́u���f�c�L�[�s�i�ȁv���I���ƁA���͎��R�ƃX�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����ƂȂ����B����͌��\���������ƂŁA�����\�N�ł́A�������[�e�B�ɂ��o�����{�C���ɂ����[�^�ɂ��Ȃ������B���O�������ɖ����������̏B�j���[�C���[�̃e�B�[���}���͑z��O�̑f���炵���������B
�@���āA79��ڂ̍��N�̓N���X�e�B�A���E�e�B�[���}���ł���B1959�N���܂�59�h�C�c�̎w���ҁB���݃h���X�f�������̌���nj��y�c�̎�ȁB���ӂ̓��[�O�i�[�B���ɐ��n�o�C���C�g���y�Ղł̊���͖ڊo�܂����A���ē߂郏�[�O�i�[�̑\���o���̊o�����悭�A�߁X�A�o�C���C�g���y�ՁE���y�ږ�̍��ɏA�����Ƃ��m��������Ă���B����ȁA���܂��ɏ{�Ȏw���҃e�B�[���}�����U��j���[�C���[���y���݂łȂ��킯���Ȃ��B������FM�̃l�^�T�������܂�̂�����A�����ȏ�Ɏ��ڂ��Â炵���B�Ƃ͂����S�z������B�Ȃ����āA�e�B�[���}���͋����ŋ��ʁB���p�[�g���[�̒��S�͏d���ȃh�C�c�{���B���ł������ȃE�B���i�E�����c�Ƃ͐��Ɩ��A�Ƃ̐���ς��������B�Ƃ��낪�A�n�܂��āA����ȞX�J�͂����ɐ�����B�\���͑傫���C�����͑@�ׁA���y�͊��������Ɩ�������B���������O�Ɍ�����Ί�͋��ʂƂ͗����Ɏ��Ƀ`���[�~���O�B�ŏI�y�Ȃ́u���f�c�L�[�s�i�ȁv���I���ƁA���͎��R�ƃX�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����ƂȂ����B����͌��\���������ƂŁA�����\�N�ł́A�������[�e�B�ɂ��o�����{�C���ɂ����[�^�ɂ��Ȃ������B���O�������ɖ����������̏B�j���[�C���[�̃e�B�[���}���͑z��O�̑f���炵���������B�@�ł́A����I�Ȃ��悤���H �I���ԍۂɂ�����u�ːi�|���J�v�H ���N�͓��ҏC�D150�N������A���x�̃C�m�V�V���ӎ������̂��H �ł������Ȃ��B���̈�O�����[�[�t�E�V���g���E�X�̃����c�u�V�̂̉��y�v�B�e�B�[���}���̃X�P�[�������Ȃ̑s�傳�Ƀh���s�V���ƛƂ܂��������t����w�̖����������B���̋Ȃ́A��w�����J�Â��镑����̔������L�O���ď�����A������1868�N�����疾�����N�B�������c�����疾���ւƕς�����N�B����͕�������V�����ɕς�鍡�N�ɑ��������ł͂Ȃ����B���́A�E�B���[�E�{�X�R�t�X�L�[�w���F�E�B�[���E�t�B��(73�N�^��)������B3�Ȗڂ͂���Ɍ���B�����āA���߂͒�ԁu���f�c�L�[�s�i�ȁv�B���V����2002�N�j���[�C���[�R���T�[�g�̃��C�u�E�e�C�N��I�B
�@1��4���[��6������̐��{�Ԃ́A�p�[�\�i���e�B�̉��R�������u�j���[�C���[�R���T�[�g�v�����Ă����Ă��ꂽ���A������A30���ԁA�I�n�a�₩�ɐ��ځA�܂��͐������ɏI������B��������܂����Ăт�������B
(2) NHK�g�����o��́u����v�ɂ͐�ʉ�������܂���
 �@��A���ANHK�g���̍���ł́A���o����ʂ������̗w�R�[���X�O���[�v�u����v�����������B�Ȃ����āA�����o�[�̈�l���m�荇��������ł���B���̖��͌���đ�32�A�����o�[�ŔN���B���̃����o�[���|�\�E����̓]�g�g�Ȃ̂ɑ��ނ�������w���ނʼn��������Ƃ����ς���B�ł͂��̌o�܂��B
�@��A���ANHK�g���̍���ł́A���o����ʂ������̗w�R�[���X�O���[�v�u����v�����������B�Ȃ����āA�����o�[�̈�l���m�荇��������ł���B���̖��͌���đ�32�A�����o�[�ŔN���B���̃����o�[���|�\�E����̓]�g�g�Ȃ̂ɑ��ނ�������w���ނʼn��������Ƃ����ς���B�ł͂��̌o�܂��B�@�b�͎��̑�w����ɑk��B1964�N�����ܗւ̔N�ɑ�w���ƂȂ��ď㋞�������A���N�x�͋g�ˎ��ɋ����\�����B4������ԁA�F�l�Ƃ̓��������ɂ��ƒ��͌�2,250�~�Ɗi���B����Ȃ���Ή��Z�܂����������߁A��N�ڂ���͍������ɓ]�������B���̉��h�̑�Ƃ������Ƃ����āA�������Z���^�[�̕������������B
�@��ؐ搶�͑�̃N���V�b�N�D���B���̂����������āA�̂��搶�Ȃ̂Ƀt�����h���[�ɐڂ��Ă����������B���r���O�ɂ͉p�������[�t�F�f�[���̃X�s�[�J�[���������i���������������o���Ă����B���̉��������ĕꉮ�ɖ����̂悤�ɓ���т��������̂ł���B�����Œ������N���X�e�B�A���E�t�F���X�̃��@�C�I�����̔��������ł��͂�����Ǝ����Ɏc���Ă���B���l�����邭�C�����ȕ��ŁA���ɂ͉Ƒ����m�̂��t�������ɔ��W�B�ċx�݂ɂ͈�ƂŎ��̒���̎��Ƃɗ��Ă��������قǂɁB���̐܁A���s�����������h�̏Z�l�����N�Ɠ�l�Ő搶���������A�A�ꗧ���đP�������̏�R�����ɍs���A�A�ؓ��̉f��u�j�b�|�����ӔC�V���[�Y�v��^���āA���Ό����d�������̕�������V���{���ʂ��グ������i���Y�j���s�����B���ʂ͌������s�ɏI��������A����ȃo�J�����w���̒�Ăɂ��t�������Ă�������C�����Ȑ搶�������B
�@�搶�ɂ͓�l�̂��삳���āA�����A�o�����q����w�Z���w�N�A�������}�q�����ŏ��w��N���������B���}�q�����̈��̂̓������R�B�����ʼn��ȏ��̎q�ŁA��u�S�r�A�g���v���̂��̂��z�X����̐�����ۓI�������B�����͗���A���̌����ɍۂ��A���l���ؐ搶���v�Ȃɂ��肢���悤�Ƃ������ƂɂȂ�A��؉Ƃ�K�₵���B�����ōĉ���������R�͒��w���ɂȂ��Ă��āA����̑O�Ńs�A�m�̒e�������I���Ă��ꂽ�B���[�~���A������P�A�`���[���b�v�A�Ȃ�ł�������B�s�A�m�����܂����������݁B�����Ŕ�I���ł̗]�����˗����邱�ƂɁB�Ȃ́A���̓����������ň�ԛƂ܂��Ă������[�~���i�����r��R���j�́u�Ђ������_�v�Ɍ���B�{�Ԃ��f���炵���̏��ʼn��̊��т𗁂т��B1975�N6��7���̂��Ƃł���B�����������A���N��A���̉̂́A���[�~�����m�荇���̎q�����S���Ȃ������Ƃ����e�B�[�t�ɏ������ȁA�Ƃ������ƂɋC�Â��B�����͌������ɑ��������i�J�b�^�I �W�b�N���̎���ǂ߂Δ���͂��Ȃ̂ɁA���������Ɏ��𗝉����Ă��Ȃ��������Ɖ䂪�g�̊Ԕ������ɒp������������ł���B
�@����͂��Ă����A�������R�͂��̌�A��コ��Ƃ�����s���ƌ����B�j�̎q���o�Y�B���ꂪ�đ�����ł���B���w���̂���䂪�Ƃɗ��āA���q�̒��I�ƈ�����o�X�P�b�g�E�{�[���ɋ����Ă����̂��v���o���B�ނ͂��̌�A�������ȑ�w�ɐi�w�A�Ȋw�҂�ڎw�����A����Ȃ�����A�������R����d�b������B�u�đ�����w�𒆑ނ��ĉ̗w�R�[���X�O���[�v�ɎQ��������Č����́v�B�u���������A��߂Ƃ��ȁB����Ȃ����킯�Ȃ����āB�������������������Ɠ����������ł������A���������Ȃ���v�ƌ��������̂́A�������߂�������̑́B�Ȃ�Ή������邵���Ȃ��ƁA���A���㕶��Y���Ēʔ̏��i�u���[�h�̗w��S�W�v�����B�����đ������������̗w�R�[���X�O���[�v�����u����v�ł���B�u����v�́g���͍g���I�e�F�s�I�h�Ȃ�X���[�K�����f���A���J�̒n�X�[�p�[�K�����t�����`���C�Y�ɋ��10�N�A��N��A���A����NHK�g���o��̖����������̂ł���B���߂łƂ��đ��B�N�������č�������肪�N������������ǁA4�l��v�c�����Ċ撣�낤���B����͂�l�����낢��ł���B
���t�^��
�@��N12��30���ATV�Ō������{���R�[�h������ň���������Ƃ�����B���R��͗�N�A10�Ȃ̗D�G��i�܂̒������܂��I���Ƃ����d�g�݂ł���B��܂́A���{��ȉƋ����ÂȂ̂ŁA���{�l��ȉƂ̍�i�������̎��i�͂Ȃ��͂��B1979�N�A�䂪RCA���R�[�h�̐���G���́A�u�����O�}��YMCA�v�œ���q�b�g�������ɂ��S��炸�A�O���Ȃ��������ƂŁA���O�̗܂�ۂ݁A��X�����������������v�����������̂ł���i��܂̓W���f�B�E�I���O�u�������āv�j�B�Ƃ��낪��N���̃��R��A�D�G��i��10�Ȃ̒��ɊO���Ȃ��܂܂�Ă����BDA PUMP�́uUSA�v�ł���B�i���TBS���Z�A�i�́A�u����10�Ȃ̒�����h�_�����܂��I��܂��v�Ɖ��x���A�i�E���X�B���ǁA�uUSA�v�̎�܂͂Ȃ������̂����A������O���Ȃ�OK�ƋK�ς�����̂��A����Ƃ��u��܂͕s�v�����m�œ��ꍞ�̂��BDA PUMP�uUSA�v�͍ːl�E���C�W���O�v�����N�v�В��ƃh�����h��Y���̍ŋ��^�b�O�̃o�b�N�A�b�v�ɂ��A������I�H
�@�Ƃ͂����A���܂̔T�؍�46�u�V���N���j�V�e�B�v�ƁuUSA�v�������ɔ�ׂ�A�uUSA�v�̕�����܂ɑ��������͖̂����ł���B�y�Ȃ̃C���p�N�g�A�q�b�g�̓x�����A��O�ւ̃A�s�[���x�A�x���w�̕��L���A������������Ă���B�����̊Ԃ��u�����Ȃ��H�v�Ɗ������ɈႢ�Ȃ��B�܂��A���R��ł͂悭���邱�Ƃ����B�O���[�o������ɁA���낻��u�O���ȕs�v�̐�����O������ǂ����낤�B�ł��A���̋ƊE�A�̎��͐V�������ňӊO�ƌÂ��B�͂Ă��āA����̐i���₢���ɁH ���낢��l��������ꂽ���R�[�h��܂ł����B
2018.12.25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ �O��
 �@12��16���i���j�ANHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I������B����F�ѐ^���q�A�r�{�F�����~�z�A���y�F�x�M�����Ƃ��������g���I�ɂ�鐧��w�B���ł��x�M�̃e�[�}���y���������B�E�s�ȃI�[�P�X�g���ɋ��܂�āA���A���i���G�L�]�`�b�N�ȃ����f�B�[��d���ɉ̂��B���[���͈ېV�����������p���̃p���[���A���ԕ��͓썑�̌Ǔ��ɗ����ꂽ�h���\���A����͂܂��A�����̐l��������ȉ^���ƕs���ȓ�ʐ������ے�����B�Ȃ��Ȃ������ȉ��y�������B�h���}�̏o���͂܂����ʂ��낤���B��������ANHK��̓h���}�͂��̔N�̗��j�ԑg�̗�����哱���邩��A���ꂪ�y���������B
�@12��16���i���j�ANHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I������B����F�ѐ^���q�A�r�{�F�����~�z�A���y�F�x�M�����Ƃ��������g���I�ɂ�鐧��w�B���ł��x�M�̃e�[�}���y���������B�E�s�ȃI�[�P�X�g���ɋ��܂�āA���A���i���G�L�]�`�b�N�ȃ����f�B�[��d���ɉ̂��B���[���͈ېV�����������p���̃p���[���A���ԕ��͓썑�̌Ǔ��ɗ����ꂽ�h���\���A����͂܂��A�����̐l��������ȉ^���ƕs���ȓ�ʐ������ے�����B�Ȃ��Ȃ������ȉ��y�������B�h���}�̏o���͂܂����ʂ��낤���B��������ANHK��̓h���}�͂��̔N�̗��j�ԑg�̗�����哱���邩��A���ꂪ�y���������B�@�e���r�͗��j���̂��D���ŁA�悭���邵�C�ɓ��������̂�DVD�Ɏc���Ă���B2018�N�x�Ŏc�����ԑg�͗D��100�{���B���̒��Ŗ����E�ېV���m��30���߂��B���̔䗦�͗�N��荂���B��͂��͂̉e�����낤�B���{�j�ł́A�퍑�A�]�ˁA�����E�ېV�A����O�゠����̎��オ�Ƃ�킯�ʔ����̂ŁA���̗���͊��}�������B
�@2018�N�Ō�́u�N�����m�v�́A���̈�N�Ō����ԑg�A�ǂ{��b�ɁA�ېV�̋��l�E���������ɔ��肽���B�ނ̓�ʐ����AJ.S.�o�b�n�u�t�[�K�̋Z�@�v�����t�[�K�ɋ[���āARECTUS�i���u�`�j��INVERSUS�i�]��`�j�̓�͂őΔ�A���������̌��Ɖe���l�@�������Ǝv���B
���́FRECTUS�`���������̌�
 �@�����ӎO�i1861�|1930�j�̖����u��\�I���{�l�v�́A���{���\����5�l�̌��o�����l�������グ�Ă���B���������i1827�|1877�j�́A�㐙��R�A��{�����A���]�����A���@��Ɍނ��Ċ���������B���҂̐����ւ̐M���x�����낤�Ƃ������̂��B���ł̊��s��1894�N�B�^�C�g���́uJapan and the Japanese�v�A�p��ŏ�����Ă���B�����ł�1908�N�ŁA�^�C�g�����uRepresentative men of Japan�v�ɕς����B����͐��E�̈̐l6�l��`�����G�}�\���́uRepresentative men�v�i1850���s�j�ɕ�������́B
�@�����ӎO�i1861�|1930�j�̖����u��\�I���{�l�v�́A���{���\����5�l�̌��o�����l�������グ�Ă���B���������i1827�|1877�j�́A�㐙��R�A��{�����A���]�����A���@��Ɍނ��Ċ���������B���҂̐����ւ̐M���x�����낤�Ƃ������̂��B���ł̊��s��1894�N�B�^�C�g���́uJapan and the Japanese�v�A�p��ŏ�����Ă���B�����ł�1908�N�ŁA�^�C�g�����uRepresentative men of Japan�v�ɕς����B����͐��E�̈̐l6�l��`�����G�}�\���́uRepresentative men�v�i1850���s�j�ɕ�������́B�@�����͉����ł̑O�����Ɂu�N���ɕ����Ă����A�킪���ɑ��鈤���͂܂��������߂Ă�����̂́A�킪�����̎������̔��_�ɁA���͖ڂ�����Ă��邱�Ƃ͂ł��܂���v�ƋL���Ă���B
�@���قɑ�\�����悤�Ȑ����̕��^���ł��镶���J����W�Ԃ��A�x�������E�B�Y���Ƃ��f�������E�����̐킢�ɏ�������B�u��\�I���{�l�v�������ꂽ�̂́A�����ېV�����40�N���o���A�܂��ɂ���Ȏ����ł���B�O�����́A����ȓ��{�Ɍ��C�������������̐S���@���ɕ\���Ă���B�u���{�ɂ͐��m���Ԃ�̗E�܂����l�Ԃ��肶��Ȃ��A���Ɛl�ƕ��a��������^�̈̐l�������̂���v�Ƃ̎v�������߂Ă��̏��𐢊E�ɔ��M�����ł���B
�@�����͖����ېV�ɉʂ����������̖����������L���B
�����ېV�Ƃ����v�����A�����Ȃ����ĉ\�ł������ł��傤���B�،˂�O���i�����j���������Ƃ��Ă��A�v���́A����قǏ����ł͂Ȃ��ɂ���A���Ԃ�������݂��ł���܂��傤�B�K�v�������̂́A���ׂĂ��n�������錴���͂ł���A�^�������o���A�u�V�v�̑S�\�̖@�ɂ��ƂÂ��^���̕������߂鐸�_�ł���܂����B�@�v�����n�������������͂������ł���A����ɓ˂�����Łu1868�N�̓��{�̈ېV�v���͐����̊v���������v�ƒf���������ƁA�����͔ނ̐����������琸�_�`���`�l�i�ւƘb��i�߂�B
�@�����́A���ɒl����قǂ̖���ł͂Ȃ��A�F���̑�˂ɂ����ẮA�g�����ȉ��h�Ɉʒu����Ƃɐ��܂ꂽ�B�u����̂̂낢�A���ƂȂ������N�ŁA���Ԃ̊Ԃł́A�܂ʂ��v�Œʂ��Ă����Ƃ����B��������Ƒ傫�ȖڂƍL����������Ƃ��鑾������j�ɂȂ����B�Ⴂ���납��z���w�ɐe���݁A�T�̎v�z���T�������B�����悭���������r�B���ɗނ��݂Ȃ��قǐ�����̗~�]���Ȃ������B�g�̉��̂��Ƃɂ����Y�ɂ����S�B���j������̂������������Ƃ��Ȃ��B�������Ƃ������ŁA�l�̕����ȕ�炵���A�����Ă����������Ƃ͂��Ȃ������E�E�E�E�E�����́A����Ȑ����̐��i��\���G�s�\�[�h�������Ă���B
��ځB�������{���̉���ɕ����ŎQ��������A���߂ɑޏo�����B������ŒE�������ʂ�������Ȃ������̂ŁA���J�̒�����l�����ŕ��������B���ɂ���������ƁA��ԂɌĂю~�߂��A���������̂Ǝv���g����K�˂���B�u�����叫�v�Ɠ����邪�A��Ԃ͐M�p�������ʉ߂����Ȃ��B�����ŁA�����͎������ؖ����Ă����N��������܂ŁA�J�̒��ɗ����s�������B���炭���āA��q��̔n�Ԃ��ʂ肩����A�悤�₭�o�邱�Ƃ��ł����B�@�����̃G�s�\�[�h�́A�����̖{���́u�҂v�ł��邱�Ƃ����B�A�������͂������]���B�u�@��ɂ͓�킠��B���߂��ɖK���@��Ɖ�X�̍��@��Ƃł���B���Ԃłӂ��ɂ����@��͑O�҂ł���B�������^�̋@��́A�����ɉ������ɂ��Ȃ��ĉ�X�̍s������Ƃ��ɖK�����̂ł���B�厖�ȂƂ��ɂ́A�@��͉�X�����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B
��ځB�l�̉Ƃ�K�₵�Ă��A���̕����������悤�Ƃ����A���̓�����ɗ������܂܂ŁA�N�������R�o�Ă��āA�����������Ă����܂ő҂��Ă����B
�@���R����c��́A1867�N10���A�u�吭��ҁv�\���o�Ƃ���������ɑł��Ăł��B���̂܂܂ł͑̍ق����̉��v�ɏI���A�^�̐V��������͗��Ȃ��B������������邽�߂ɁA�����͂����܂ŕ��͂ɂ�铢���ɍS�����B�����āA�u�������Áv�`�u��C�푈�v�Ƃ����t�]�̗����������̂ł���B����Ȃ����Ė����ېV�͂Ȃ������B���ꂼ�����̉]���u���o�����@��v�ł���B
�@�����āA������ǂނ����ɁA�ӂƁA���������Ƃ����l�����͉����ɍ������Ă���Ǝv�����������B
�J�j���}�P�Y�@��j���ăm���T�j���}�P�k��v�i�J���_�����`�@�m��ʎ҂Ȃ��{���u�J�j���}�P�Y�v�̈ꕔ�ł���B�����͌��y���Ă��Ȃ����A��j�̐����͊ԈႢ�Ȃ���т��炢���������낤�B�g����j���Ďl���h�Ƃ����̂́A���܂�ɑ�H���ł���A�a��Ȍ����̃C���[�W�ƍ���Ȃ��Ə�X�v���Ă����B�������`�����z�������炻��ł������̂����A��a���͐@���Ȃ������B���ꂪ�A�����ƌ��т����Ƃ��A���ꂢ�ɕ��@���ꂽ�B�a�̏��Ŏ蒠�̐�[�Ɂu�J�j���}�P�Y�v���L�����Ƃ��A�{���̓��̒��ɂ͐����������������B�u��v�ȑ́v�u�|���Ȃ��v�u�{��Ȃ��v�u�Â��ɏ��v�u����������ɓ��ꂸ�ɑ��l�̂��߂ɐs�����v�u�����Ă���l�Ԃ�����Ă����Ȃ��v�u�悭�w���K������v�u�f�N�m�{�[�v�u�J�߂��邱�Ƃ�]�܂Ȃ��v�u������咣���Ȃ��v���X�A�����͂��Ƃ��Ƃ������̐��i�����ɍ��v����B�����̔_�{��`�̌X���͔_�w�Z�Ɋw�����Ƌ��ʂ���B�����ȕ����ł���B�J�ԁA���f���͓����Ԋ��o�g�̃L���X�g�ҁE�֓��@���Y�i1877�|1968�j�Ɖ]���Ă��邪�A�֓��͓����̍ł������Ȓ�q�������Ƃ����B������A�u�J�j���}�P�Y�v�ɐ����̐��_�����e����Ă��邱�Ƃ̗��t���ƂȂ�͂��Ȃ����B���͊m�M����B�{���u�J�j���}�P�Y�v�̐l�����͊ԈႢ�Ȃ����������ł���ƁB�ނ��낱��܂ŁA���w�҂����j�w�҂��A���̂��Ƃɂ����l���y���Ȃ��������Ƃ��s�v�c�ł���B
�|�n�i�N�@���V�e�у��Y�@�C�c���V�Y�J�j�����b�e�C��
����j���Ďl���g���X�g���V�m����^�x
�A�������R�g���@�W�u�����J���W���E�j�����Y�j
���N�~�L�L�V���J���@�\�V�e���X���Y
�~���i�j�f�N�m�{�[�g���o��
�z���������Z�Y�@�N�j���T���Y
�T�E�C�E���m�j�@���^�V�n�i���^�C
�@�͂̍Ō�ɁA�@���ƂƂ��Ă̓������m�M���������̗�I�̌��ɐG��Ă��������B
�Ƃ���ł킪��l�����A����A�D��ŎR�����������Ă���Ƃ��A�P���V���琺�����ډ��邱�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Î�Ȑ��т̒��ŁA�u�Â��Ȃ�ׂ��� still small voice�v���A�����Ɛ��E�̂��߂ɖL���Ȍ��ʂ������炷�g����ттĐ����̒n��Ɍ��킹��ꂽ���Ƃ��A������ƚ������Ƃ��������̂ł���܂��B���̂悤�ȁu�V�v�̐��̖K�ꂪ�Ȃ������Ȃ�A�ǂ����Đ����̕��͂��b�̒��ŁA����قǕp��Ɂu�V�v�̂��Ƃ����ꂽ�̂ł���܂��傤���B�@�u�Â��Ȃ�ׂ����v�Ƃ͗a���҂��V���_���畷�����̂��ƁB�V�[�ł���B�V�̌[���ɏ]���u�h�V���l�v���P�Ƃ�����̎g����簐i���������́A�Ō�A���g�̐M�����т��ʂ��Ė��������B�܂��ɏ}���ł���B�����́A���������Ƃ����C�������X�g�T�����C�̒��ɃC�G�X�E�L���X�g���d�ˍ��킹�Ă����̂�������Ȃ��B
���́FINVERSUS�`���������̉e
�@�{�͂ł͐����̉e�����̑��ʂɌ��y���Ă݂悤�B�����ɓ�̎j��������B
 �@�܂��́A�ԏ����O�Y�i1831�|1867�j�̈ꌏ�ł���B�ԏ��͐M�B��c�˂̔ˎm�B�]�˂ɏo�ĉp�����@���K�����A���s�Ɏ��m���J���B�剺���ɎF���ˎm���������Ƃ���A�˂̕��w�����Ƃ��ď��ق���A���s�̎F���˓@�Ŕˎm800���ɉp�������@��������B�F���̌R���𗖎�����p���ɐ�ւ���w���I�������ʂ������B
�@�܂��́A�ԏ����O�Y�i1831�|1867�j�̈ꌏ�ł���B�ԏ��͐M�B��c�˂̔ˎm�B�]�˂ɏo�ĉp�����@���K�����A���s�Ɏ��m���J���B�剺���ɎF���ˎm���������Ƃ���A�˂̕��w�����Ƃ��ď��ق���A���s�̎F���˓@�Ŕˎm800���ɉp�������@��������B�F���̌R���𗖎�����p���ɐ�ւ���w���I�������ʂ������B�@����ŁA�V����ɂӂ��킵�����{�Ɛ����݂̍���𗧈Ă����B���@�͕��ʑI���őI�o���ꂽ��@���c��ŁA�s���͋c������Ȃ���t�����c�@���t���ɂ���čs���B�N�ł������u�ĂȂ����鋳�琧�x�̊m���B�ʂẮA���m�̑̊i�����}�邽�߂̓��H����Ɏ���܂ŁA���ɐ�i�I�ȓ��e�ŁA���̍�{���n�́u�D������v�ɐ旧�B�C�M���X���g�ق̒ʖ�A�[�l�X�g�E�T�g�E�́A���L�Ɂu�����́A���{�̑���ɍ����c���ݗ�����Ƃ�����i�I�v�z�̎����傾�����v�ƋL���Ă��邪�A����͂����炭�ԏ��̎��肾�낤�B
�@�ԏ��́A���@�E�����̐������Ă�m�������Ƃ��Ƃ��F���ɓ`�����ċA�˂��钼�O�A1867�N9���A�F���̎h�q�E���������Y�Ɏh�E���ꂽ�B�ԏ����F���̌R���@����m��߂��Ă��܂������Ƃ������Ƃ����B�����͕s���̂܂܂����A�������֗^���Ă������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���������Y�i1839�|1877�j�͖����ېV���@�ɋ˖엘�H�Ɖ����A�������t�Ƌ��A���c�ȑ���Ƌ��ɖ����̎l��h�q�̈�l�ɐ������錕�̒B�l�ł���B��̓h���}�̍ŏI�������܂ł��Ȃ��A����푈�ɂ����čŌ�̍Ō�܂Ő����̖T��ɂ��ĉ^�������ɂ�����l���B��l�ɂ͌䂵���������̎����傾���A�����̖��߂łȂ牽�ł������B�t�ɐ����������Ȃ���Γ����Ȃ��l�ԂȂ̂ł���B
�@�F���̌R�����v�̉��l���A����̑�`�i�s���j�̂��߂ɐ�̂Ă�B���ꂽ�ق��͂��܂������̂ł͂Ȃ��B�����̔��Ȉ�ʂł���B
�@������͑��y���O�i1839-1868�j�Ɛԕ���̃P�[�X�ł���B�ނ��������̐l�Ԃł���B�����ېV�v���ɂ����Ă͗l�X�Ȑߖڂ����邪�A�F���E�ېV���͂ɂ�����ő�̐��O��́A�吭��ҁi1867.10.
14�j�`�������Â̑卆�߁i���N12.8�j������̏��R����c��̔S�荘�������낤�B�����̖������U�����Ă܂Ōc��̔r�˂�}�����̂����A�圤�Ȍc��͎��r�̌�������点�Ȃ��B���͂═�͓����������͂Ȃ��B�����œ������̂������������B���S�̑��y�ɖ����A�ԕ���ɑ������N�������A�����˂����{���F�����~���P���悤�Ɏd������B�ԕ���́A�]�˂̒��Ŗ���̂悤�ɁA���E���D�E�����E���E���J��Ԃ��B�����Č��܂��ĎO�c�̎F���˓@�ɓ������ށB�]�˂ł͂��̃e���W�c���u�F����p���v�Ƃ����ċ��ꂽ�B�~�߂́A�]�ˎs������̏����˓ԏ��̏P���������B���ɐꂽ���{�͎F���˓@�̖C�������s�B1867�N12��25���̂��Ƃł���B���̒m�点���������́u����Ő�̌������o�����v�Ƃق����Ƃ����B
�@���͓����̑�`���V���{�R�͒��H�����̐킢���J��B�����āA�]�ˏ閳���J��A��C�푈�̏������o�ĈېV�v����B������B��A�̗���̒��A�����̓����͍ۗ����Ă���A�܂��ɐ����Ȃ��肹�ΈېV�͐��炸�A�ł������B���āA���͂��̌�ł���B
�@�]�˂Ŏ蕿�𗧂Ă����y���O�E�ԕ���̊J���̖����́A�Ꝅ�E�ł����킵���p������s���Ȑ���̒��A�V���{�R���X���[�Y�ɐi�R�����邱�ƁB�u�V���{�͔N�v������v�ƐG����Ȃ���敺�Ƃ��ē��i�����̂ł���B���ꂪ�����̎w���ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�킢�͐V���{�R�̏����Ŗ������B�V���{�X�^�[�g�B�������Ȃ���A���A������I���B�u�N�v�����v�ȂǗ��s�ł���͂����Ȃ��B�����Ő����͐M�����Ȃ��d�ł����s���B�u�N�v�����v�͐��{�̕��j�ł͂Ȃ��B����ȋU��G�������ԕ���́u�U���R�v�ł���Ƃ��āA���y�ȉ����������Y���Ă��܂��̂ł���B�w���𒉎��Ɏ��s�����l�Ԃ����Y����B������I �ړI�̂��߂ɂ͎�i����Ȃ����̊v���ƁE���������́A������̊�ł���B
�@��͂ɂ킽�萼�������̌��Ɖe�����Ă����B���ɂ͗��\������B�l�Ԃ͓�ʐ������B�����̋��Ɏ�Ă�܂ł��Ȃ��A����Ȃ��Ƃ͖����ł���B�����A���e�Ǝc�E�`�����̓�ʐ��͕s���ɂ��ċ���B��l�̔�ł͂Ȃ��B�ꖇ�̎ʐ^���c���Ă��炸�䂦�ɕ��e��������B����Ƃ��͉p�Y����Ƃ��͋t���B�]���͓V�ƒn�B�l���͖��ƈÁB���̂ƂĂ��Ȃ��U���B�L������X�P�[���B�����ē�B���̍��R��̊������������̖��͂Ȃ̂��낤�B����́A����Ȑ��������̎v�z�ɓ��ݍ���ł݂����B
���Q�l������
�u��\�I���{�l�v �����ӎO���i��g���Ɂj
100��de�����u��\�I���{�l�vNHK-TV
��̓h���}�u�����ǂ�vNHK-TV
�U�E�v���t�@�C���[�u���������vNHK-BS
�p�Y�����̑I���u����I����푈�vNHK-BS ��
2018.11.25 (��) �W�l�b�g�E�k���[�^�`�H��̓V�˃��@�C�I���j�X�g���Â�
(1) �ߔN�������u���[���X�̃��@�C�I�������t�� �@����A�����В�����u�}�p�ŃR���T�[�g�ɍs����Ȃ��Ȃ����̂ŁA�悩�����琥��v�ƘA���������������B�����s�����y�c�T���g���[�z�[�������A�w���͏���a�T�A���@�C�I�����E�\���̓��C�E�`�F���ŁA�Ȗڂ̓u���[���X�́u���@�C�I�������t�� �j���� ��i77�v�Ɓu������ ��4�� �z�Z�� ��i98�v�̓�ȁB�����2008�NGW���E�t�H���E�W�����l�����ŃV���[�x���g�́u�O���[�g�v���Ĉȗ������A���@�C�I���j�X�g�̃��C�E�`�F���͒��ڂ̎��B��Ԏ��ł����t�ɊÂ��邱�Ƃɂ����B
�@����A�����В�����u�}�p�ŃR���T�[�g�ɍs����Ȃ��Ȃ����̂ŁA�悩�����琥��v�ƘA���������������B�����s�����y�c�T���g���[�z�[�������A�w���͏���a�T�A���@�C�I�����E�\���̓��C�E�`�F���ŁA�Ȗڂ̓u���[���X�́u���@�C�I�������t�� �j���� ��i77�v�Ɓu������ ��4�� �z�Z�� ��i98�v�̓�ȁB�����2008�NGW���E�t�H���E�W�����l�����ŃV���[�x���g�́u�O���[�g�v���Ĉȗ������A���@�C�I���j�X�g�̃��C�E�`�F���͒��ڂ̎��B��Ԏ��ł����t�ɊÂ��邱�Ƃɂ����B�@�����В��Ƃ͂��̂Ƃ���A�u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃł���������B���������ׂĂ��T���g���[�z�[���B�܂��́A�B�蓦����2016�N5��8���̃W���j�[�k�E�����Z��(Vn)�ƃ������B�FN���̃��C�u�^���BD�|R�ŕ�U�������������ƁB���́A��N10��2���A�I�P�����̎w���ҁE�{��h�Y��17�̎��p�E���E�N���v�t�B�b�`���iVn�j�ɂ��R���T�[�g�����ꏏ�������ƁB�����č���ƁA����u���[���XVn���t��at�T���g���[�z�[���O����i�H�j�ł���B
�@����̃u��4�͎茘���D���B�����͂Ȃ����A������K�c���Ƃ�����̂��Ȃ��B���̃u��4���̌��̓t���g���F���O���[�F�x�������E�t�B��1948��LP�ł���B�������w�����������́A��l����u�����~�������̂��邩���H�v�Ɩ��ꂽ��A���܂��ăm�[�g�ɏ������߂Ă���u�w���\�背�R�[�h�E���X�g�v����u����A���ꂢ���ł����v�Ɛ}�X�����Â������̂��B���̂k�o�͑��̏��q�̂������炢�����������́B���ꂽ���́u�����^�[�̃u��4�v�����肢�����̂����A�u���O�i�[�̂��Ȃ������̂ł���ɂ����B�X�̐l�͂�����������Č����Ă���v�Ȃ镶�͂��Y���Ă������B�u���O�i�[����˂���v�ƙꂢ�����ǂ����͕ʂƂ��āA�����ăr�b�N���̖����t�I �ŏ��̉�H���i�v�ɐL�тĂ䂭�̂ł́A����ȗI�v�������������A���������N���o�郍�}���̖z���ɋ����P��ꂽ�B�Ƃ܂��A����ȑ̌�������̂ŁA�u��4�͗]���̉��t�łȂ��Ƌ��Ɏh����Ȃ��̂��B
�@���āA���C�E�`�F���̋��t�Ȃł���B1989�N��p���܂��29�B�J�[�`�X���y�@�ŃA�[�����E���U���h�Ɏt���B2009�N�A�G���U�x�[�g���܍��ۉ��y�R���N�[���ōŔN���D��������ނł���B
�@���̓��̃u���[���X�́A�f���ȉ��y���Ƃ悭�ʂ�������}�b�`���ĉ��y�����������Ƒ��Â��Ă����B���݂ɁA�y��̓X�g���f�B���@���E�X�E���A�q��1715�i����͈ȑO���i�і�̊y�킾�����͂��B�ݗ^���͓��{���y���c�ł���j�ŁA�J�f���c�@�����A�q���̂��́B�܂��Ƀ��A�q���s�����̍D���������B
�@���C�E�`�F���������Z�����N���v�t�B�b�`�����f���炵���B�Z�p�ɔj�]�͂Ȃ��y���ɋL������Ȏ҂̈Ӑ}�ɂ������i�Ɗ������j�A�t�҂̌�������Ȃ�Ɋ��m�����B����������������Ȃ��B�t�����F����4�Ԃ���Ȃ����A�S�����V�݂͂ɂ���悤�ȋ����B
�@����Ȏ��A���̓W�l�b�g�E�k���[���B�����ɂ̓��@�C�I�����{���̖��͂�����B���@�C�I�����̂��Ƃ��t�B�h��fiddle�ƌĂԂ��A�ꌹ�̓��e����Łg�l���s�����h�Ƃ����Ӗ�������i�Έ�G���u�N�����@�C�I�������E�������v���j�B�����҂������ɋ�藧�Ă�悤�ȁA���C�Ƃ������閂�͂ł���B
(2) �W�l�b�g�E�k���[�A���̂��܂�ɂ�����ȉ��y�Ɛl��
 �@�W�l�b�g�E�k���[�i1919�|1949�j�̃u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃ�4�̘^�����₳��Ă��邪�A�k���[28�A1948�N5��3���n���u���N�ł̃��C�u�^�������t�^�����ɌQ���Ă���B�����̓n���X�E�V���~�b�g���C�b�Z���V���e�b�g�w���F�k���h�C�c���������y�c�B
�@�W�l�b�g�E�k���[�i1919�|1949�j�̃u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃ�4�̘^�����₳��Ă��邪�A�k���[28�A1948�N5��3���n���u���N�ł̃��C�u�^�������t�^�����ɌQ���Ă���B�����̓n���X�E�V���~�b�g���C�b�Z���V���e�b�g�w���F�k���h�C�c���������y�c�B�@�����̃I�P�Ńz�����������O���Ȃǂ����Ȃ�ʋْ������Y���B�����O�t�̂��Ɩ��������ēo�ꂵ���\���E���@�C�I�����̉��Ƃ������́B�H���������ɒ���I�B�����ɂƂ�߂��ꂽ�悤�Ȉٗl���B�`���ŐS��h�݂͂ɂ��ꂽ������͐��т̎q�r�̂��Ƃ����J�ɐg���ς˂邾�����B
�@�u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃ̑�1�y�͂͐q��ł͂Ȃ��B�������āA���̐����̑��l���ł���B���ʃ\�i�^�`���ɂ����ẮA��1���Ƒ�2���̑��ɂ͈������������̕����I��肪���邾�����B�Ƃ��낪���̋Ȃɂ͂Ȃ��6���̕�����肪����B�u���[���X�͂���瑽�l�ȑf�ނ��n���̋Z�Ő��k�Ȉ�i�ɕς���B�H��̖��H�Ɖ]����R���ł���B
�@�k���[�͂����8�̎��̊e�X�̓����������Ȃ܂łɒe������o���B�`����B��1���̋C�����Ƒ�2���̈����̑Δ�B���̊Ԃɓ_�݂�������́A���Ɍ��������ɉs�����ɏ�M�I�Ɏ��ɐȂ����ɂ܂������ɈЌ����h�����ɓ��ۂ�X���ĉH�����B���̑��ʂȕ\���͂̓u���[���X�̖{����]���Ƃ���Ȃ��\�o����B�܂�Ŗ��؋��̌i�ςł���B
�@�n�C�t�F�b�c�A�I�C�X�g���t�A�~���V�e�C���A�V�F�����O�A�O�����~�I�[�A�V�Q�e�B�A�t�����`�F�X�J�b�e�B���X�A�B�X���閼�肽���ƒO�O�ɒ�����ׂĊm�M�����E�E�E�E�E�����̃��@�C�I���j�X�g�̒N�����k���[�̉��ł͐F��B����͂܂��Ɋ�Ղ̖����ł���B������A��ꂪ��Ȏ҂̐��a�n�Ƃ����̂�����Ă��邩������Ȃ����B
�@�ꂪ�悭�������̂������B��������ƕ����яオ��������B�B������r��������߁B����ŁA�\��ɂ͟���悤�ȏ�M�Ɛ��ݐ����C�i���h��B���܊���o���ߓx����|���^�����g�����͓I�B��O������߂Ɗy������݂ɑ���ō��x�̋Z�p�Ƒ��ʂȕ\���͂����A����ȉ��y�Ƃ��ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂�Ă����̂��낤���B
�@1919�N8��11���A�p����5�l�Z��̖����q�Ƃ��Ă��̐��ɐ������W�l�b�g�E�k���[�B�唌���̓t�����X�̍�ȉƃV���������}���[�E���B�h�[���B�ނ́A�����m�����A93�Ƃ����N���V�b�N���y�j��v�N�ō���̍�ȉƂł���B����Ɉ��������W�l�b�g�̂Ȃ锖���I ���A����͌�q����B
 �@�c�����Ƀ��@�C�I���j�X�g�Ƃ��Ă̋����ꂩ���B���̌�11�Ńp�����y�@�ɓ��w�B�����ŏo��������@�C�I�������t���W���[���E�u�[�V�����i1877�|1962�j�ł���B�ނɂ��āA��ƃG�h�D�A�[���E�}�l�̖ÃW�����[�E�}�l�́u�T���T�[�e�͐��m���Ə������ɂ����Ă͌����ȍ˔\�̎����傾���A�Y�傳�Ɍ�����B���̓_�W���[���̃��@�C�I�����͓Ɠ��̕��i�ƋC�i���Y���v�ƕ]���Ă���B���́u�c�B�S�C�l�����C�[���v�̍�Ȏ҂ɂ��đ僔�@�C�I���j�X�g�̃T���T�[�e�𗽂��Ƃ����̂��B�_�_�́u�Y�傳�v�Ɓu�C�i�v�͌�̃W�l�b�g�ɒʂ�����̂�������B
�@�c�����Ƀ��@�C�I���j�X�g�Ƃ��Ă̋����ꂩ���B���̌�11�Ńp�����y�@�ɓ��w�B�����ŏo��������@�C�I�������t���W���[���E�u�[�V�����i1877�|1962�j�ł���B�ނɂ��āA��ƃG�h�D�A�[���E�}�l�̖ÃW�����[�E�}�l�́u�T���T�[�e�͐��m���Ə������ɂ����Ă͌����ȍ˔\�̎����傾���A�Y�傳�Ɍ�����B���̓_�W���[���̃��@�C�I�����͓Ɠ��̕��i�ƋC�i���Y���v�ƕ]���Ă���B���́u�c�B�S�C�l�����C�[���v�̍�Ȏ҂ɂ��đ僔�@�C�I���j�X�g�̃T���T�[�e�𗽂��Ƃ����̂��B�_�_�́u�Y�傳�v�Ɓu�C�i�v�͌�̃W�l�b�g�ɒʂ�����̂�������B�@�W���[���E�u�[�V�����̋��������k���[�ȊO�̉��y�Ƃ����@�C�I���j�X�g���S�ɗ�L����ƁE�E�E�E�E�w�����N�E�V�F�����O�A�N���X�e�B�A���E�t�F���X�A���[���E�{�x�X�R�A�C�����[�E�M�g���X�A�~�V�F���E�I�[�N���[���A�~�V�F���E�V�����@�����F�A�N�����E�n�X�L���A�W�����E�}���e�B�m���A�Ȃ��B�X���閼�肪���ԁB
�@����Ȉ̑�ȃ��@�C�I���j�X�g�E���t�̌O�������W�l�b�g�́A15�ő�1�B�G�j���t�X�L���ۃ��@�C�I�����E�R���N�[���ɗՂ����D������B180�l�̌��҂̒��ɂ͓���24�̃_���B�b�h�E�I�C�X�g���t�������B���܂�Ɉ��|�I�ȃW�l�b�g�̉��t�����I�C�X�g���t�͌̋��̍ȂɈ��Ă������������Ă���B�u�킸��15�̃k���[�삪�A���B�G�j���t�X�L�̉d�w�Z���i��1�ԁj�̋��t�Ȃ�e�����Ƃ��A�l�͂܂�ň����̂悤�ɑf���炵���Ǝv�������Ȃ������B�ޏ�����1�ʂœ��R���v�B9�ΔN���̏����ɑł��̂߂���2�ʂɊÂ��I�C�X�g���t�͂��̌㐢�E�I�僔�@�C�I���j�X�g�ɂȂ�B�����Đ��X�̖��Ȃ�^������B���̒��ɂ̓k���[�Ƌ��ʂ̋ȁA�Ⴆ�A�u���[���X�A�V�x���E�X�̋��t�ȁA�V���[�\���́u���ȁv�Ȃǂ�����̂����A���݁A���҂̉��t����ׂĂ��A�k���[�̈��|�I�D�ʂ͕ς��Ȃ��B�R���N�[���ł̓��_����26�_�Ƃ����卷�������Ƃ������A���̍��͉i���ɖ��܂�Ȃ��������ƂɂȂ�B���ꂾ���ł��k���[�̓V�ː����킩�낤�Ƃ������̂��B
�@�k���[�̎t�͂�����l����B�p�����y�@�̏��������i�f�B�A�E�u�[�����W�F�i1887�|1979�j�ł���B10�Ńp�����y�@�ɓ��w�B���̑��n�Ԃ�̓k���[�Ƃ����ʂ��A��������Ȃ��w���B�h�[�������̓k���[�̑唌���Ƃ�������������B��ȉƂƂ��ẮA���[�}��܂̎��_�ɊÂ邪�A�w���������̃����i1893�|1918�j��1913�N�Ɏ�܁B�o�̋w���������`�ƂȂ����B�ޏ��̍�i�u�[�������v�͌��I�ْ����ɖ����A�u�s�G�E�C�G�X�v�͌h�i�Ɛ����������o���B����̑Ώ̂������ȓ��i�ł���B���݂ɃI�P����̊y�F�t���[�g�̒Җ{�v�̎t�E�у����q�̖��̓����E�u�[�����W�F����Ƃ������̂��Ƃ����B
�@�i�f�B�A�͎w���@���w�сA25�Ŏw���҂Ƃ��Ă̊������J�n�A���̌���x�����Ė���I�[�P�X�g����U���Ă���B���݂ł͒������Ȃ��Ȃ��������w���҂̐�삾�B
�@����҂Ƃ��Ă̕���́A�a���@�A�Έʖ@�A�y�ȕ��́A�\���t�F�[�W���Ƒ���ɂ킽��B��l�����m�ρX�E�E�E�E�E��ȉƂ̓A�X�g���E�s�A�\���A�A�[�����E�R�[�v�����h�A���@�[�W���E�g���\���A�w���҂̓��i�[�h�E�o�[���X�^�C���A�C�[�S���E�}���P���B�b�`�A�X�^�j�X���X�E�X�N�����@�`�F�t�X�L�A�s�A�j�X�g�ł̓f�B�k�E���p�b�e�B�A�N���t�H�[�h�E�J�[�]���A�_�j�G���E�o�����{�C���A�W���Y�E�̃N�C���V�[�E�W���[���Y�A�L�[�X�E�W�����b�g�A�h�i���h�E�o�[�h�A�~�V�F���E���O�����ȂǁB�܂����Y�����̂��Ƃ��ł���B
�@�k���[�͂��̈̑�ȋ��t����A��Ȗ@�Ɗy�Ȃ̓ǂ݂��w�B���Ђ���R���N�[���ɉ����āA15�Ƃ����Ⴓ�ŁA��ɋ������X�g���|�[���B�`�����āu�_�̂悤�ȑ��݁v�ƌ��킵�߂��I�C�X�g���t���t�����ɗD�������V�ː������A�����Đ��܂ꂽ�����̏�ɁA�Z�p���W���[���E�v�[�V�����A���y�����i�f�B�A�E�u�[�����W�F����������|��ꂽ���̂������̂ł���B
�@���B�G�j���t�X�L�E�R���N�[����A�W�l�b�g�͗m�X���鉉�t������W�J����B1935�N11���A�I�C�Q���E���b�t���w���̃x�������E�t�B���Ƃ̋����Ɏn�܂�A1936�N�ɂ̓E�B�����E�����Q���x���N�A1943�N�ɂ̓w���}���E�A�[�x���g���[�g�A1945�N�w���}���E�V�F���w���A1946�N�w���x���g�E�t�H���E�J���������Ƃ̋����Ń��[���b�p��Ȍ��A1947�N�ɂ̓V�������E�~�����V���w���̃j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�A�Z���Q�C�E�N�[�Z���B�c�L�[�̃{�X�g�����Ƃ̋������ŃA�����J�㗤���ʂ����B
�@���̃A�����J�����ł̔����͎�̊O�����܂����A�u���̉��t�Ƀu���[���X�̓W�l�b�g�E�k���[�̗��ɂȂ����ɈႢ�Ȃ��v�i�w�����h�g���r���[���j�A�u���y�̒m���Ǝ���ƃG�l���M�[�A����Ȍ��Ɗ�������n��ꂽ�p���W�F���k�B�����ō����ƒ��g����ۓI�ȏ����́A�Ќ��̂���X�e�[�W�}�i�[�Œ��O�𖣗������v�i���[���h�E�e���O�����j�A�u���̌������قƂ���悤�ȉ��t�ɂ͐^�����Ƌ��������Ïk����Ă���Ɠ����ɋC�����܂ł̐ߓx��ۂ��Ă���B���̂悤�ȃu���[���X��Vn���t�Ȃ����̊X�Œ������͉̂��V�[�Y���Ԃ肾�낤���B�Ⴓ���݂Ȃ����M�Ƌ����̈Ќ��Ɨ}���Ƃ��Ƃ��Ɋ��Y���悤�ȉ��t���v(�U�E�^�C���Y)etc ��^�̗��Ƃ͂��̂��Ƃ��낤�B���ɁA�u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃւ̍����]�����ڗ��B
�@�������A����ȃL�����A�̐Ⓒ�ɂ����W�l�b�g�ɉ^���̓�������Ă���B
 �@1949�N10��28���A�G�[���E�t�����X �p�����j���[���[�N�s���̃��b�L�[�h�E�R���X�e���[�V�����@�́A3�x�ڂ̃A�����J�E�c�A�[�Ɍ������W�l�b�g����悹�ăI�����[��`���ї������B�����Đ����Ԍ�E�E�E�E�E�吼�m��ɕ����ԃ|���g�K���̃A�]���X�����̃T���~�Q�����ɒė��B��q���48���S�������S�B�W�l�b�g�E�k���[�́A�Z�̃s�A�j�X�g �W�����Ƌ��ɁA�A��ʐl�ƂȂ����B�����Ă܂��A���R�ɂ��A���@�ɂ̓{�N�V���O���E�~�h�������҂̃}���Z���E�Z���_�����j���[���[�N�ő҂��l�G�f�B�b�g�E�s�A�t�Ƃ̈��������ɏ�荞��ł����i����O�k����W�l�b�g�ƃZ���_���̎ʐ^���₳��Ă���j�B�s�A�t�̖��ȁu���̎]�́v�����܂ꂽ�̂͂��̂������Ƃ̂��Ƃł���B
�@1949�N10��28���A�G�[���E�t�����X �p�����j���[���[�N�s���̃��b�L�[�h�E�R���X�e���[�V�����@�́A3�x�ڂ̃A�����J�E�c�A�[�Ɍ������W�l�b�g����悹�ăI�����[��`���ї������B�����Đ����Ԍ�E�E�E�E�E�吼�m��ɕ����ԃ|���g�K���̃A�]���X�����̃T���~�Q�����ɒė��B��q���48���S�������S�B�W�l�b�g�E�k���[�́A�Z�̃s�A�j�X�g �W�����Ƌ��ɁA�A��ʐl�ƂȂ����B�����Ă܂��A���R�ɂ��A���@�ɂ̓{�N�V���O���E�~�h�������҂̃}���Z���E�Z���_�����j���[���[�N�ő҂��l�G�f�B�b�g�E�s�A�t�Ƃ̈��������ɏ�荞��ł����i����O�k����W�l�b�g�ƃZ���_���̎ʐ^���₳��Ă���j�B�s�A�t�̖��ȁu���̎]�́v�����܂ꂽ�̂͂��̂������Ƃ̂��Ƃł���B�@�h���̖�������ꂽ�V�˃��@�C�I���j�X�g�́A�������ċ͂�30�N�̐��U�ɖ����~�낵���B�����A�t�����N�̃��@�C�I�����E�\�i�^��`���C�R�t�X�L�[�̋��t�Ȃ̃��R�[�f�B���O�v�悪�������Ƃ����B�ǂ�ȃp�t�H�[�}���X�������Ă��ꂽ���낤�B���Ɏ��ɉ��Ƃ��Ăł��������������I �ł��A���ʂĂʖ��B�₳�ꂽ�^���������Ȃ��B���͖��N10��28���ɂ́A�W�l�b�g�E�k���[�̃u���[���X�̋��t�ȂƌZ�W�����Ƃ̑�3�ԃ\�i�^���B�G�s���[�O�ɃV���p���̉d�n�Z���m�N�^�[�����B�W�l�b�g�E�k���[�͉i���Ɏ��̐S�̓��ɐ���������B
���Q�l������
�W�l�b�g�E�k���[�E�U�E�R���N�V���� 7���gCD
�����E�u�[�����W�F�F�u�[�������vCD
���@�C�I�����̉��`�`�W���[���E�u�[�V������z�^
�@�@�@�@�@�}���N�E�\���A�m�� �K���Еv��i���y�V�F�Ёj
�N�����@�C�I�������E�������F�Έ�G���i�V���Ёj
2018.10.27 (��) �X�g���f�B���@���E�X�l�@�`��ՁA���̐^��
(1) �X�g���f�B���@���E�X�W�ɍs�� �@����A���@�C�I�����̖���X�g���f�B���@���E�X�W�ɏo�������B�ꏊ�͘Z�{�E�X�A�[�g�M�������[�B�肵�āu�X�g���f�B���@���E�X300�N�ڂ̃L�Z�L�W�v�B���E�Ɍ�������600���قǂ̃X�g���h�̂���21�����W�����Ă���Ƃ����B����͌������킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@����A���@�C�I�����̖���X�g���f�B���@���E�X�W�ɏo�������B�ꏊ�͘Z�{�E�X�A�[�g�M�������[�B�肵�āu�X�g���f�B���@���E�X300�N�ڂ̃L�Z�L�W�v�B���E�Ɍ�������600���قǂ̃X�g���h�̂���21�����W�����Ă���Ƃ����B����͌������킯�ɂ͂����Ȃ��B�@���ɒ�������A���傤�ǎ������n�܂�Ƃ��낾�����B�y��̓X�g���f�B���@���E�X �O�����B���A�A�_���X�A�N���C�X���[ Stradivarius Greville, Adams, Kreisler 1726�B�����ʂ肱��͂��Đ��I�̖���t���b�c�E�N���C�X���[�̎�ɂ��������́B�����̑t�҂͐�v�ێ��I�B�܂��O�Y���b�q�̃s�A�m���t�ŃG���K�[�u���̈��A�v�����t�B��������ݍ��ނ悤�ȉ��F�̓G���K�[�̈��̕\���Ƀs�b�^���������B���͑��AJ.S.�o�b�n�̖����t���@�C�I�����E�p���e�B�[�^��2�Ԃ���u�V���R���k�v�B�M���ł͂��������֊s���Â�������ꂽ�̂́A�y��̐������A�͂��܂��t�ҔT���ȂƂ̑������B���������A�N���C�X���[���e��J.S.�o�b�n�͒��������Ƃ��Ȃ��B
�@�Ϗܒ��̂��w�l���n���œ|���Ƃ����n�v�j���O�̂��ƁA�ʂ̃X�g���h�Ƃ̒�����ׂ��s����B�y��́u�_�E���B���`�vDa Vinci 1714�B�����ނ�ɓ����Ȃ��t�����B�Ȃ�Ɖ����S�R�Ⴄ�I ������юU��悤�ȎW�R�Ƃ��������������B�N���C�X���[�̂����Ƃ芴�ƃ_�E���B���`�̋P���B���ɕ������X�g���f�B���@���E�X�̐������������B
�@���悢��W�����ցB�ꕔ���ɖ���21�����Ђ��߂��B�Ȃ�Ƃ��s�ςł���B�ē��ɂ��ƁA�X�g���f�B���@���E�X�͍��ꂽ�����ɂ��A�����A������A�������A�ӔN����4�ɕ�����邻�����B�S�W���i�̔����ȏ�11�����������i1700�|1726�j�̃��m�������B

�@�ł��C�ɂȂ����̂́A�����Œ������u�_�E���B���`�v�ł���B���̖���Ɣ�ׂ��ꍇ�A���ʂ̊�́A�Ⴂ�͕������Ă������������Ȃ��B�Ƃ��낪�w�ʂȂ画��i�B�eOK�������̂ŎB�����ʐ^���f�ڂ���j�B�k�C�^���A�̗�C�̒��Œ����N�����d�˂��ؖڂ���d�ɂ��A�Ȃ��Č����Ȗ�l������ł���B���̔������� �W���i�����ꂾ�����B�������ꖇ�ł���B���ׂĂ݂���A������11���̓��A�ꖇ��5���A��6���������B
�@�w�ʂ̑f�ނ̓��[�v���ł���B����߂čd���B�d����D�悷��Ȃ�ꖇ�������͂��B�Ȃ̂ɓ�����B���̂����肪�A�X�g���f�B���@���̊����ł���ʔ����Ȃ̂��낤�B���s���낷��V�ˁI
�@�u�_�E���B���`�v�Ɩ��������̂̓A���g�j�I�E�X�g���f�B���@���i1644-1737�j���g���Ƃ����B���Ȃ̍ō���������F���Ď����ō���̌|�p�Ƃ̖����������Ƃ��B�Ȃ���������W�b�N���Ƃ��̉��ɐZ���Ă݂����B�ƂɋA���āA�u�_�E���B���`�v��������R���e���c��T������A���CD�ɑ��������B���V���ݎq�̃\���ɂ��u���[�c�@���g�F���@�C�I�������t�ȑS�W�v�i�t�B���b�v�E�A���g�������w���F�E�B�[�������nj��y�c �̋����j�ł���B�N���W�b�g�ɂ��ƃv���f���[�T�[�͒��V�@�K�B�䂪�����@�C�I���������E�C���̌��ЂŁA����TSUNAMI VIOLIN�̐���҂��B���t�҂����l�ŁA���q���́u�X�g���f�B���@���E�X�W�v�̎��s�ψ����̒��V�n�����B���������V���ݎq���͖��FH���������ڂ��Ƃ鏮����w�̋q�����������Ă����悤���B����������̉����B
�@�g�p�y��́A��1�ԁ`��3�Ԃ̓X�g���f�B���@���E�X�u���}�m�t�v1731�A��4�ԂƑ�5�ԁu�g���R���v�́u�_�E���B���`�v�ł���B�����铯�ȑS�W��CD�̒��ł�����̃X�g���h��e�������Ă���̂͂��ꂵ���Ȃ��B�����@�C�I�������悭�m�钆�V���̃v���f���[�X�ł���A����͂܂��A�������J�����[�^�E�g�E�L���E��\�E���h���́g���R�[�h�ɂ͂ł������̕t�����l���h�̐��_�����f���Ă���B
�@�S�Ȓ��A��5�ԁu�g���R���v���Q���Ă����B���@�C�I�����̋��������т₩�Ŕ������A��ɐ���������悤�ȑu����������A�Ɗ������B���Ɂu�_�E���B���`�v�͊��Ғʂ�̉������Ă��ꂽ�A�Ǝv�����B�����A����́u�_�E���B���`�v�ƕ������Ă������炻�̂悤�Ɋ������A�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B��������ςȂ��ɗ�����������A�X�g���h�Ǝw�E�ł������낤���H �X�g���h���������Ɗ��m�ł���̂ł͂Ȃ��A�X�g���h�ƔF�����Ă��邩�炢�����Ɋ�����̂ł���B���ꂼ�X�g���h���������̑�Ȃ����ρB�u�����h�͂Ȃ̂��B�ł́A�Ȃ��X�g���h�����������Ȃ�u�����h�͂�L����悤�ɂȂ����̂��B
(2) �N�����@�C�I�������E������
 �@�u�N�����@�C�I�������E�������v�i�Έ�G�� �V���Ёj�B���ɕ����ȃ^�C�g�������A���ꂼ���@�C�I�������y�Ɋւ��閼���ł���B�^�C�g������A����̃��@�C�I�����͂��̖{���̋����������Ă���A�Ƃ������҂̒Q�����`����Ă��邪�A�`���̃��@�C�I���j�X�g �E�W�F�[�k�E�C�U�C�i1858�|1931�j���e���u�������X�N�v����n�܂镨��́A���@�C�I�����Ƃ����y��̖��͂�_���I�l�ɂ���ēI�m�ɉ����������Ă����B�L�q����X�g���f�B���@���E�X�̐_���ǂݎ���āA���̕s�v�c�Ȗ��͂Ɛ^���ɔ����Ă݂悤�Ǝv���B
�@�u�N�����@�C�I�������E�������v�i�Έ�G�� �V���Ёj�B���ɕ����ȃ^�C�g�������A���ꂼ���@�C�I�������y�Ɋւ��閼���ł���B�^�C�g������A����̃��@�C�I�����͂��̖{���̋����������Ă���A�Ƃ������҂̒Q�����`����Ă��邪�A�`���̃��@�C�I���j�X�g �E�W�F�[�k�E�C�U�C�i1858�|1931�j���e���u�������X�N�v����n�܂镨��́A���@�C�I�����Ƃ����y��̖��͂�_���I�l�ɂ���ēI�m�ɉ����������Ă����B�L�q����X�g���f�B���@���E�X�̐_���ǂݎ���āA���̕s�v�c�Ȗ��͂Ɛ^���ɔ����Ă݂悤�Ǝv���B�@���܁A5���~�̃X�g���f�B���@���E�X��200���~�̌��ピ�@�C�I�������A���̌������ň�l�̉��t�ƂɌ��Œe���Ă�������Ƃ��A�ʂ����Ăǂꂭ�炢�̐l���������Ă��邾�낤���H �����炭�A����Ȏ����͋��낵���Ď��݂邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�Ȏ����ł���ɈႢ�Ȃ��B�����Șb�A���@�C�I�����̃v�������ƂĂ����m�ɂ͂������Ă�ꂸ�A�ԈႦ��l�����o���邩������Ȃ��B�N�����i�̖���i�X�g���f�B���@���E�X�Ȃǁj�ƂāA5���~��200���~�̂悤�ȋɂ߂ė�R�Ƃ��������̍�������킯�ł͂Ȃ��A�ƒ��҂͐����B���ɁA���N�O�A�����J�ōs��ꂽ�u�X�g���f�B���@���E�XVS���ピ�@�C�I�����̒�����ׁv�Ȃ�Â��ŁA�W�܂������̓��̃v�������̐��𗦂�2�`5���������Ƃ��B�����Ȃ鎄���A�O���A�e�����u�|�\�l�i�t���`�F�b�N�v�ŁA20���~�̃X�g���h��200���~�̃��@�C�I�������������Ⴆ�Ă��܂����i����������j�B
�@����ɒ��҂́A���{�l�́u���̃��@�C�I�����́g���������h�v�Ƃ����\�������邪�A���m�l��sonority�Ƃ�response�Ƃ������[�h���g���B�y�킪�q���ɔ������邩�A�悭�苿�����A�Ƃ����\�����A�ƌ��B�̂Ƃ��Ẵ��@�C�I�����́u��v�̍������Ȃ��A���F�͉��t�҂���郂�m�Ƃ������_�Ȃ̂ł���B
�@2013�N��NHK�ōs��ꂽ�����ɂ��A�X�g���h�ƌ��ピ�@�C�I�����̍��͎w�����Əo���B�ߏ���ւ̉��̏o�����ˏo���Ă���̂��B���ꂪ�A�X�g���h�̉����z�[���̍Ō��܂œ͂��閧�ƌ��_���Ă����B�A����������̋����̎��B���F�Ƃ͕ʕ��ł���B
�@����ł̓N�����i�̃��@�C�I�����̒l�i�Ƃ͈�̂Ȃ�̒l�i�Ȃ̂��B����́A���@�C�I�����̌Â����킽���͊y��ł͂Ȃ��u�����i�v�A���̒l�i�Ȃ̂��A�ƒ��҂͉]���B
�@�����̉��l�����߂�ɂ͓`�����K�v�ł���E�E�E�E�E�A���g�j�I�E�X�g���f�B���@���͂��̐��U�Ŏd�グ�̌��ߎ�ƂȂ�j�X�̒�����ς��Ă���B�������̂���͒x�����̃j�X�B�������x�����߁A�h���Ă͊������h���Ă͊������̍�Ƃɒ���������v�����B���̍H�����������̉������߂��傫�ȗv�����A�Ƃ����B�Ƃ��낪�X�g���h�̕]�����オ�蒍���������n�߂�ƁA�v���Ɏd�グ��K�v�������A�������̃j�X�ɕς�����Ȃ��Ȃ����B�����ŁA�X�g���f�B���@���͌Â��j�X�̏�����p�����Ă��܂����B������A�����������Ɠ������͉̂i�v�ɍ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ꂪ�A�X�g���f�B���@���E�X�̉��̐_������`���̈���B
�@�����̓`����M�ɂ܂ō��߂��҂����A���ꂪ�p���l�y�폤�q���ꑰ�ł���B�ނ��18���I����20���I�ɂ����āA5��ɂ킽��A�X�g���f�B���@���E�X���N�W���C�����X�̓�����I�m�ɔc������B����ɂ́A�y��X�̕ϑJ�̗��j��O�O�ɒ��ׁA���ɂ͘b���āA�`���Ƃ��čI���ɛƂߍ���ł䂭�B�������āA�����Ƃ��Ă̌��\����caption�������ɍ��グ���B�����āA���ɂ́A�N�����i�̖���Ɋւ���Ӓ�E�C���E�]���i�l�Â��j�̐��E�ō��ɂ��ėB��̌��ЂƂȂ����B�X�g���f�B���@���E�X�_�b�E�M�̊����ł���B�����č����Ɏ���܂Ńq���ꑰ�̉������Ӓ�]���͐�ΓI�Ȃ��̂Ƃ��Ă܂���ʂ��Ă���B
�@�X�g���f�B���@���E�X�̉��l�Ƃ͂Ȃ낤�H �������Ɍ����čl����E�E�E�E�E�܂��́A�j��ō��̃��@�C�I��������҃X�g���f�B���@�����A�x�����j�X�Ŏd�グ���������킾�Ƃ������ƁB�����Ă��ꂪ���S�������������ĂȂ��Ƃ������ƁB�����͌��R���鎖���ł���A���̋H�����͓������������B����ɕt������̂��Č����ł���B�ޗ����t�H�����������Đ^���邱�Ƃ͏o�����A���Ƀj�X�ɂ��Ă͂��̏����������čĐ��͑S���s�\�ł���A�ƁB
�@�ł́A�{���ɍČ��͕s�\�Ȃ̂��낤���B�܂��̓X�g���h�Ɠ��̐[�g�F�̒x�����j�X�B��H�̌��t������蕔�ʂ̂���זE�������鎞��ł���B���̉Ȋw�̗͂Ȃ�A�j�X�̐������͂ȂǁA���Ƃ��ȒP�ɂł���̂ł͂Ȃ��낤���B���ɁA2010�N�A���[���b�p�̌����`�[���ɂ���āA�X�g���h�̃j�X�́g�����g���Ă�����ʓI�ȃj�X�������h���Ƃ��������Ă���B���͍ގ��B�\�ʂ̃X�v���[�X���w�ʂ̃��[�v���Ɠ����x���d�x���ގ��̖؍ނ�I�яo���̂͊m���ɓ����������Ȃ��B�X�g���f�B���@�������B���Ă����p�i���F�b�W���̐X�����o�����Ƃ��Ă������̃��m�ł͂Ȃ��B�����A����̋Z�p�������Ă���g�����ɉ��H���邱�Ɓh�͂���قǓ�����ƂƂ͎v���Ȃ��B�����āACT�X�L�����łȂ�A�^�̃X�g���h�Ɛ������ʃt�H�[�����Č�����̂�����ł͂Ȃ����낤�B���ɁA���E���ŃX�g���h�Č��̎��݂��Ȃ���Ă���B
�@�������A����ŁA�N�����i�̊y��̒��ɂ͐����Ă��ċ����̎キ�Ȃ��Ă�����̂������͂��A�ƒ��҂͉]���B�؍ނ̍ގ���J�ł���B�����o�Ă���Ԃ��イ���̖ؐ��̓��͐U����������B���Ƃ��A�����傪�v���t�҂Ȃ�A��������Ԃ������o���B����Ă���300�N�ԗ]�A����̓��͐U���������Ă���̂ł���B�؍ނɂ͎���������B�ǂ�Ȃɍd���ċ����ł��U���ɑ���ϐ������E�ɋ߂Â��i�z���Ă���j�Ƒz�������̂ł���B������A������������A����Ȋw�̗͂���g���čČ������X�g���h�̕����{���̃X�g���h�����g�悭��h�\��������̂ł́H
�@�����������A����ȑf�l�̖ϑz�����������̂悤�ɁA�X�g���f�B���@���E�X�͍����𑱂���B����́A�X�g���h�������ʊi�����炾�B300�N�قǑO�A�h���Ɗ��C�̊X�N�����i�ŁA�X�g���f�B���@���Ƃ����ނ܂�Ȃ�V�ːE�l���A���s������d�ː����X���č��グ���i�X�́A�䌨������̂Ȃ���̑��݂Ƃ��Č���ɌN�Ղ��Ă���B�����̎��݂́A�Č��ł����Ē��z�ł͂Ȃ��B���g�ގ҂����̐S���ɂ́A�u�ǂ��z�������v�ł͂Ȃ��u�ǂ��������v�Ƃ̊�]�����Ȃ��B���ނ̂ł͂Ȃ��^����Ɏ~�܂��Ă���B������A���܂ł����Ă��z�����m�����Ȃ��B�z�����m�ɂ͓G��Ȃ��B���̎����������u�X�g���f�B���@���E�X�̊�Ձv�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�@2002�N���ł́u�N�����@�C�I�������E�������v�ɋL���ꂽ�X�g���h�̒l�i��5���~�������B���݂�15�|20���~������̂悤���B�\���N�łȂ��3�`4�{�B�X�g���f�B���@���E�X�E�o�u���͂��܂ő����̂��낤���B
���Q�l������
�u�N�����@�C�I�������E�������v�Έ�G�� �i�V���Ёj
�u���[�c�@���g�F���@�C�I�������t�ȑS�W�vCD�iCAMERATA�j
�@ �@�@���V���ݎq�iVn�j�t�B���b�v�E�A���g�������w���F�E�B�[�������nj��y�c
�u�����̃��@�C�I�����`�X�g���f�B���@���E�X�̓�vNHK-BS 2013�N�P��OA
2018.09.30 (��) �����FM���ǂ���
�@9��20���A��2�N�Ԃ�点�Ă���������FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v���I�����B�����Ƃ��Ă͐r���c�O�����A�u�����ցE�E�E�Ί�����v�Ȃ�ԑg���I���̂�����d�����Ȃ��B�@FM���ǂ���̓R�~���j�e�BFM�ł���B9��23���t�����V���ɂ��ƁA�ŋ߂̓R�~���j�e�BFM�̊J�ǂ������Ă��邻�����B2011�N�̑�k�Јȗ��A��M���Ƃ��Ď����̂��J�ǂ𑣂��ӌ������܂�������Ƃ��B����Ȓ��ɂ����āAFM���ǂ���͊J��21�N�̘V�܂Ȃ̂��B
 �@���̗F�l�ɂ��̃����L���O���̑������u�I���R���v�n�Ǝ��̃����o�[N�������āA�ނ̗F�l��FM���ǂ����I���������B�����������Ђ�I����EM���ǂ���ɓ]�E�����̂����N2���B�u�Ȃɂ��������͂Ȃ�������H�v��N���ɑ��k������A�N���V�b�N�ԑg�͂ǂ����ƁA���ɂ���������Ă����̂ł���B
�@���̗F�l�ɂ��̃����L���O���̑������u�I���R���v�n�Ǝ��̃����o�[N�������āA�ނ̗F�l��FM���ǂ����I���������B�����������Ђ�I����EM���ǂ���ɓ]�E�����̂����N2���B�u�Ȃɂ��������͂Ȃ�������H�v��N���ɑ��k������A�N���V�b�N�ԑg�͂ǂ����ƁA���ɂ���������Ă����̂ł���B�@���ꂩ�炠�ꂱ��l�߂āA�u�g�߂ȑ�ނ���N���V�b�N���y�ɂȂ���v���R���Z�v�g�ɁA�u�����ցE�E�E�Ί�����v�Ƃ���3���Ԃ̐��ԑg�̈�R�[�i�[�Ƃ��āA�u�����N���V�b�N�v���n�܂����B�����͖�����3�ؗj���̗[��5�������30���ԁB�����̓p�[�\�i���e�B�[�̓ޗǒ��q����B���̒ʏ̂͂Ȃ�ƂȂ��g�����̃N���V�b�N��������h�Ɍ��܂�B
�@��1��OA��2016�N9��15���B����́u�j�͂炢��v�N���V�b�N�B�Ђ���̕��䊋���Ė��͍]�ː��ׂ̗ɂ��ĕ����G���A���B�剉�̈��������S���Ȃ����̂�1996�N8��4���Ŗv��20�N�B�R�c�m���ē̓N���V�b�N�ɑ��w���[���A�f��̒��ɂ̓N���V�b�N���y���ӂ�ɏo�Ă���B�n���̃��W�F���h�ɂ��đS����̓Ђ���u�j�͂炢��v���N���V�b�N���y�Ɍq����\���́u���N���v�R���Z�v�g�ɑ升�v�B�X�^�[�g�͂��ꂵ���Ȃ������B
 �@48��̒�����I�̂͑�11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�i1973�N8��4�����J�j�B�}�h���i�͐�u�����q������h�T����̎�̃����[�����B�����������a�̃q�b�g�Ȃ��ӂ�ɓo�ꂷ��B����Ђ�u�z�㎂�q�̉S�v1951�A���숤�q�u�`��������u�v1947�A�R���i�q�u�闈���v1950�B�����3�Ȃ́A�����[������������L���o���[�ʼn̂��Ȗڂ��B��l�̏o��͖k�C���ԑ��B�u�������̐������Ă��Ԃ��݂����Ȃ���ˁv�ƌ��������[�Ɂu����A���Ԃ�����B������㓙�Ȃ���˂���ȁE�E�E�E�E�v�Ɖ�����Ў��Y�B�݂��̒��ɓ����������o������l�͂܂�ŗ��l���[�h�B����A���̃}�h���i�Ƃ͂Ȃ���C���B�������ő���4��Ƃ����̂�������B�����A�}�C�E�x�X�g�͑�17�쑾�n��a�q�}�h���i�́u�Ў��Y�[�Ă����Ă��v�i1976�N7��24�����J�j�B�F��d�g�ƓЂ���̂���肪�▭�ŁA�V���p���́u�ؗ�Ȃ��~���ȁv���g���Ă���B����͕���D�����������A�܂��ʂ̘b���B
�@48��̒�����I�̂͑�11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�i1973�N8��4�����J�j�B�}�h���i�͐�u�����q������h�T����̎�̃����[�����B�����������a�̃q�b�g�Ȃ��ӂ�ɓo�ꂷ��B����Ђ�u�z�㎂�q�̉S�v1951�A���숤�q�u�`��������u�v1947�A�R���i�q�u�闈���v1950�B�����3�Ȃ́A�����[������������L���o���[�ʼn̂��Ȗڂ��B��l�̏o��͖k�C���ԑ��B�u�������̐������Ă��Ԃ��݂����Ȃ���ˁv�ƌ��������[�Ɂu����A���Ԃ�����B������㓙�Ȃ���˂���ȁE�E�E�E�E�v�Ɖ�����Ў��Y�B�݂��̒��ɓ����������o������l�͂܂�ŗ��l���[�h�B����A���̃}�h���i�Ƃ͂Ȃ���C���B�������ő���4��Ƃ����̂�������B�����A�}�C�E�x�X�g�͑�17�쑾�n��a�q�}�h���i�́u�Ў��Y�[�Ă����Ă��v�i1976�N7��24�����J�j�B�F��d�g�ƓЂ���̂���肪�▭�ŁA�V���p���́u�ؗ�Ȃ��~���ȁv���g���Ă���B����͕���D�����������A�܂��ʂ̘b���B�@�u�Y��ȑ��v�ɑ}���̃N���V�b�N�́A�k�C���̌����疗y����Ђ����BGM�Ƃ��ė���郊���X�L�[���R���T�R�t�́u�V�F�G���U�[�h�v��3�y�́u�Ⴋ���q�Ɖ����v�Ɩ��E�����炪�_��œ|�ꂽ�Ђ�����}���ɍs����Ԃ��T���}�Εt�߂𑖂邠����Ŕ킳��J.S.�o�b�n�uG����̃A���A�v�̓�ȁB���Ɂu�V�F�G���U�[�h�v�̗D���Ń��}���`�b�N�ȃ����f�B�[�͉Ă̖k�C���̑厩�R�ɂ悭�������B
�@11��24���̓I�y���̓��B�����ŃI�y���Ɉ���ނ�T���Ă�����A�s�R���Y�́uPPAP�v�ɂԂ����������B�g�y���p�C�i�b�v���A�|�[�y���h�̒_�̓p�s�̉��̂Ȃ���B���ѕt�����̂̓��[�c�@���g�̉̌��u���J�v�́u�p�A�p�A�p�v�̓�d���B����́A���h���p�p�Q�[�m�Ɨ��l�p�p�Q�[�i�̃f���G�b�g�E�\���O�ŁA�̂̑O�i�S�Ă��u�p�v�����ŏo���Ă���B1791�N�̏H�ɏ������ꂽ�u���J�v�������E�B�[���̊ϋq�́A�������āu�p�A�p�A�p�v�Ɖ̂��܂����������ȁB�s�R���Y�̌��c�̓��[�c�@���g���I�H�@���̑��ɂ��p�s�q�b�g�Ȃ́u�x��|���|�R�����v�A�u�����̏��[�ɂ�E������v�Ȃǂ�����B�ł�����A�A�C�f�B�A�|��ŎȂ������B
�@2017�N2��16���́A���y�R���N�[�����ނɂ��Ē��؏܂Ɩ{����܂�W��܂������c���u���I�Ɖ����v�����グ���B�����܂Ŏc����4�l�̃R���y�e�B�^�[�A���Ԑo�A�h�`����A�������A�}�T���E�A�i�g�[�����v�X�e�����Ȃ��|���Ȃ��珬���̑S�e��30���ł܂Ƃ߂��B����͂܂��ɒ����̑�ށB�����̃^�C�~���O�́A���؏�܂̒���ɂ��Ė{�����ܑO�Ɛ�D�������B
 �@12��21���́u���N���IX�fmas�N���V�b�N�v�B���I�i���h�E�_�E���B���`�́u�T���o�g�[���E�����f�B�v����w���f���̃I���g���I�u���T�C�A�v�́u�n�������E�R�[���X�v�Ɍq����B�u�T���o�g�[���E�����f�B�v���_�E���B���`�̐^��Ƃ������Ƃ��m�肵�āA�j��ō���508���~���t�����Ƃ̃j���[�X�����ꂽ�̂�11�����{�B��₠���āA���D�҂�UAE�̃��[�����E�A�u�_�r�Ɣ����������B
�@12��21���́u���N���IX�fmas�N���V�b�N�v�B���I�i���h�E�_�E���B���`�́u�T���o�g�[���E�����f�B�v����w���f���̃I���g���I�u���T�C�A�v�́u�n�������E�R�[���X�v�Ɍq����B�u�T���o�g�[���E�����f�B�v���_�E���B���`�̐^��Ƃ������Ƃ��m�肵�āA�j��ō���508���~���t�����Ƃ̃j���[�X�����ꂽ�̂�11�����{�B��₠���āA���D�҂�UAE�̃��[�����E�A�u�_�r�Ɣ����������B�@���̊G��Ɓu�n�������E�R�[���X�v�͗e�Ղɒ����B�T���o�g�[���E�����f�BSalvator Mundi�̓C�^���A��Łg���E�̋~����h�̈Ӗ��B���T�C�AMessiah�̓��e����Łg�~����h�̂��ƁB�w���f���́u���T�C�A�v�̒��ł͍����ȁu�n�������E�R�[���X�v���Q���ėL�����B508���~���������ǂ����H �G��f�l�̎��͕���Ȃ����B
�@2018�N�̃X�^�[�g��1��18���B���N�q����Łu�q���̃����c�v���A��������h�r���b�V�[�u���v���A�V�N�̕������E�B�[���E�t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g����u���f�c�L�[�s�i�ȁv��I�ȁB���邭�u�₩�ɃX�^�[�g������B�ԑg�̃I�[�v�j���O�̓h���[�u�u�X���j���_�̃����c�v�ɂ��Ă��邪�A���̌�͕ϑ��I�[�v�j���O�𑽗p�����B���̕�����ȗ]�v�Ɋ|�����邩�炾�B
�@2��15���̓{���f�B���u�_�b�^���l�̗x��v�ł̃I�[�v�j���O�B���̋ȁA�O��̓~�G�ܗփ\�`���̊J��Ŏg���Ă���A�������獡�N�̕����ܗււƌq����B�����g�g�C�t�F���́u�X�P�[�^�Y�E�����c�v�͏��q�X�s�[�h�X�P�[�g500m�̏����ޏ��A�v�b�`�[�j�u�g�D�[�����h�b�g�v����u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�͒j�q�t�B�M���A�̉H�������ƉF�쏹���ւ̉����ȂƂ��đI�ȁB���ʁA��16���ɂ͏��������A17���ɂ͉H�������A�F�삪��_�����l���B���ʂ͔��Q�������I�H
 �@5���͔���I���F�u�܌��̃o���v���I�[�v�j���O�B�o���Ɉ���Ń��n���E�V���g���E�X�U�̃����c�u�썑�̂�v�A�܌��Ɉ���Ń����f���X�]�[���̖����̏W����u�܌��̂��敗�v��I�ȁB�u�썑�̂�v�̓V���[���q�g���E�B�[���E�t�B���i1963�N�^���j�̉��t��I���A�E�B�[���E�t�B���̉��F�ɃV���[���q�g���▭�̖��t�������Ă���܂��ɖ��l�|�B�^������ɋ����킹���w���Ҋ��G�V�́u�_���I�v�̋��т��G�s�\�[�h�Ƃ��ďЉ���B
�@5���͔���I���F�u�܌��̃o���v���I�[�v�j���O�B�o���Ɉ���Ń��n���E�V���g���E�X�U�̃����c�u�썑�̂�v�A�܌��Ɉ���Ń����f���X�]�[���̖����̏W����u�܌��̂��敗�v��I�ȁB�u�썑�̂�v�̓V���[���q�g���E�B�[���E�t�B���i1963�N�^���j�̉��t��I���A�E�B�[���E�t�B���̉��F�ɃV���[���q�g���▭�̖��t�������Ă���܂��ɖ��l�|�B�^������ɋ����킹���w���Ҋ��G�V�́u�_���I�v�̋��т��G�s�\�[�h�Ƃ��ďЉ���B�@���t�ɂ�����Ȃ�ɍS�����B�O�q�V���[���q�g�́u�썑�̂�v���n�߁A�x�����I�[�Y�u���z�����ȁv��4�y�́u�f����ւ̍s�i�v�̓o�[���X�^�C�����j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�i1963�N�^���j�A���B���@���f�B�́u�l�G�v�̓A�[�����C�E���W�`���t�c�i1959�j�A�h���H���U�[�N�́u�V���E���v�̓N�[�x���b�N���x�������E�t�B��(1972)�A�X���^�i�u�����_�E�v�̓N�[�x���b�N���`�F�R�E�t�B�� �T���g���[�z�[���E���C�u�i1991�j�A�z���X�g�u�f���v�̓{�[���g���j���[�E�t�B���n�[���j�A�ǁi1966�j�A�V���[�x���g�́u���v�̓o�[�o���E�{�j�[�̃\�v���m�i1994�j���X�B
�@6��21���̓O�����J�u���X�����ƃ����h�~���v���ȂŃI�[�v���B���̃������B���X�L�[�����j���O���[�h�E�t�B���̉��t�i1965���C�u�j�͐����̈��B�l�ނ����B�����ō��x�̃A���T���u���ł���B���̉�́A�J�Ò��̃��V�A�E���[���h�J�b�v�Ɉ���Ń��V�A���y���W�Ƃ����B�v���R�t�B�G�t�̃o���G���y�u�����I�ƃW�����G�b�g�v����u�����^�M���[�ƂƃL���v���b�g�Ɓv�A���t�}�j�m�t�́u���H�J���[�Y�v�A�V���X�^�R�[���B�`�́u�W���Y�E�����c��2�ԁv�ȂǁA���j�[�N�Ȗ��ȂŌł߂��B���_����W���p���ւ̉������Y�ꂸ�ɍs���B�\�I���[�O�˔j�͓V���ꂾ�����I
�@7���́u�E���g���}���̉́v�ňӕ\��˂��X�^�[�g���B������́g�ϐg�h�N���V�b�N�B�N���V�b�N�ƕϐg�y�ȂƂ̑Δ���y����ł����������B�x�[�g�[���F���̃s�A�m�\�i�^�u�ߜƁv��2�y�́��r���[�E�W���G���u�����̓t�H�[�G�o�[�v�A�y�c�H�[���g�̃��k�G�b�g���T���E���H�[���́u���o�[�Y�E�R���`�F���g�v�A�z���X�g�̑g�ȁu�f���v����u�ؐ��v�����������u�W���s�^�[�v��3�ȁB����͓��փE�P������悾�����B
�@�Ƃ܂��A����Ȃ���ȂŐςݏd�˂���34��B�g�p�y�Ȃ�96�ȁB��ȉƕʃx�X�g���W�v������A��1�ʂ̓��[�c�@���g�i8�ȁj�A��2�ʂ��x�[�g�[���F���A���n���E�V���g���E�X�A�`���C�R�t�X�L�[�i�e5�ȁj�A��5�ʂ��V���p���i4�ȁj�������B����ς莄�̃i���o�[�P�̓��[�c�@���g�ȂƉ��߂ĔF����������B
�@2�N�Ԃ́u���N���v�͎��ɕ��ɂȂ����B�����łȂ��Ă��s����ȕ��X�֔��M���邽�߂ɁA����ӂ�Ȓm���͂��ꂱ�꒲�ׂăL�`���ƏC�������B�g�������������������ĂȂ��Ƃ����S�O�����ɍw�������B�Ȃ̂ŁA�o���������͖��x�̂��ƁB�A��ɗ���������ň�t�������������ɂ͎����o���͕K���ƂȂ����B�����A����Ȃ��Ƃ͂��\���Ȃ��B�V���牽���������~��āA�g�߂Ȏ��ۂƉ��y�����܂����ѕt�����Ƃ��̍��g���͉����ɂ��ウ�����������B�����āA8��16���̃o�[���X�^�C�����a100�N�̉A�ꂪ�S���Ȃ������Əd�Ȃ������Ƃ�t�������Ă����B��́u������ˁI�v�Ƃ͌���Ȃ����낤�B�u���N���v�Ɍg��邱�Ƃ����Ƃ̂ق����ł����̂�����B
�@�Ō�ɁA�������̔ԑg�ɓ����Ă��ꂽN����I���A����h�f�l�̎���D�������[�h���Ă��ꂽ�ޗǒ��q����A�f�B���N�^�[��O�N�Ɣނ�������p���ő�{�̃O���[�h�A�b�v��}���Ă��ꂽNoririn�A���A�ȉ����������݂��Ă��ꂽH�����A�����M�S�ɕ����Ă���������F�В��A�����ĐÂ��ɉ������Ă��ꂽ�S����ɁA�S���犴�ӂ�\���グ�܂��B�@
2018.08.31 (��) �킪����Â��
�@2018�N8��16���A�ꂪ���������B���N97�B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̓��͕�̕��E���̑c���ł��鉪�������Y��������̖����������B�c���́A���~�ŃR�`���ɖ߂��Ă��Ă����킯������A����~�̂��̓��u�F�q�s�����I�v�ƌ����Ȃ���A�ꋎ���Ă��܂����̂��낤�B�@1947�N4���A���̕��E�����S���Ȃ��Ă����A�c���͎�������q���Z�ސV���ɏo�����A�u�F�q�s�����I�v�Ǝ��炪�Z�ޒ���ɘA��A�����B71�N����j���J��Ԃ��ꂽ�̂��I�H
�@6��15�������A�ꂪ�q�f�����̂ŔO�̂��ߋߏ��̊|������̕a�@�ɍs���B�O���܂ŁA�V����玄�̍�����J���[����H�ׂĂ�������A�H�����肩���₯���낤�ƌy���l���Ă������A�Ȃ�Ƒ����@�A�]���������̐鍐�����B
�@��N�H�A���̋v�q�����S���Ȃ��Ă���}�Ɍ��C���Ȃ��Ȃ����͎̂��������A����ł��g�̉��̂��Ƃ͂��ׂĎ����ōs�������y�[�X���ς�邱�ƂȂ������Ă���A2��21���̒a�����̐܂Ȃǁu�܂���100��ڎw�����ˁv�Əj�������̂�����A��������Ƃ��̃V���b�N�͌v��m��Ȃ����̂��������B
�@����҂��܂ɁA�u��������Ȃ���v�v�Ɖ]����4���Ԃ̎�p�ɑς����B�����C�����ŕK���ɐ����悤�Ƃ����B�����������A�v���̂ق��a�̐i�s�������A���@������ŋA��ʐl�ƂȂ����B�{���ɂ����Ƃ����Ԃ̎��Ԃł������B�l�Ԃ̍Ŋ��Ƃ����̂͐l���ꂼ�ꂾ�낤���A��̏ꍇ�́A�ɂ݂��ꂵ�݂�����قǑi���邱�ƂȂ��A����ɐ��b���������ɁA�܂�ň�w�̕�����������悤�ɁA�X�}�[�g�ɗ������čs�����B
�@��͎����̎����l�l����Ԃ��Ƃ�D�悷��l�������B�S���Ȃ�ԍۂ܂ŋ������e���P��T�b�J�[�E���[���h�J�b�v�D�������Ă����ւ̏܋��t���Ƃ��A�N���N�n�̂������A���݂������AUNO���Ȃǂւ̏܋��ȂǁA�݂�Ȃ���Ԋ�������y����ł����B
�@���N�A�i�Z�コ�S���Ȃ������A�ނ̌��t���Ď��ɂ����������B�u���������A�l�Ԃ͓�x���ʂ��ĂˁB��x�͓��̂����Ƃ��A��x�ڂ݂͂�ȂɖY���ꂽ�Ƃ��B���͖Y����Ȃ��ł����邩�ȁv�ƁB���́u���������݂͂�Ȃɂ����v���o����������c���Ă�̂�����A���܂ł��Y����邱�Ƃ͂Ȃ����v�ƕԂ����B�܂�ō���̂��Ƃ̂悤�Ɏv���N�������B
�@�u���������v�Ƃ����̂́A�]���̐^���q���c���̂���ɕt������̈��̂��B�n����ƂŌo����C����Ă����ꂪ�A�ƂɋA���Ă��Z�ՕЎ�ɖ�Ȃׂ����Ă���̂������]�����A�u�����ЂƂ�����ӂ����������Ă�ˁv�ƌ��������Ƃ���������́B60�N�قǐ̘̂b�ł���B�ȗ��e���݂͂�ȕ���u���������v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�B��͂��̈��̂���̂��C�ɓ���ŁA�ŋ߂͑\���������ĂԂ̂��āA�uRay������You������g���������h���ˁB���̍܂ŁA����������g���������h�ƌĂȂ�������v�Ƃ����x�������B
�@���w4�N���ɂȂ������A�u�Ȃɂ��K���������Ȃ����B���K���ƃs�A�m�A�ǂ����������́H�v�Ɛu���ꂽ���́A�����Ɂu�K���v�Ɠ������B�����s�A�m�͏��̎q�̐ꔄ�����Ǝv���Ă������炾�B�u�����Ȃ́v�ƈ�U���ꂾ�������A������A�u����ς�s�A�m�ɂ��Ȃ����B�搶���߂����������v�B�Ȃ�A�Ȃ�Őu�����̂� �Ȃ̂����A�]�������Ȃ��B�������玄�͑f���������̂��B�����ɁA�x�[�g�[���F���u�����v�\�i�^�ƃV���p���u���z�����ȁv��2���gSP���^����ꂽ�B�s�A�m�̓C�O�i�c�B�E�����E�p�f���t�X�L�[�i1860�|1941�j�B�u���̐l�A�|�[�����h�̎�������v�ƕ�ɋ�����ꂽ�B����2�ȁA�펞������Ƃɂ������~����ŔՂ��C����قǒ��������̂ł���B
�@���̌�A�����LP�`�X�e���I�ƈڍs���邪�A����ɔ������̃n�[�h���ƐŃv���[���[�`�X�e���I���u�ւƐi�W�B�����ł���̍��͂̐��b�ɂȂ����B�����A���̂Ƃ��u�s�A�m�v�������t���Ă���Ȃ�������A���̃N���V�b�N���y�ւ̋����͊��N����Ȃ�������������Ȃ��B����͕�ւ̍ő勉�̊��ӂł���B
 �@���āA��̓��@���ɂ悭�������Ȃ�����B�u���[���X�́u���@�C�I�����E�\�i�^ ��3�� �j�Z���v�ł���B���ɑ�2�y�͂�Adagio�B�Ȃ�Ƃ��������D�����ȑz�Ȃ̂��B����ł��ĕi�i������B�v���b�V���[�̂��������A�ە�����鉹�y����������鉹�y���~���������̂��낤�B
�@���āA��̓��@���ɂ悭�������Ȃ�����B�u���[���X�́u���@�C�I�����E�\�i�^ ��3�� �j�Z���v�ł���B���ɑ�2�y�͂�Adagio�B�Ȃ�Ƃ��������D�����ȑz�Ȃ̂��B����ł��ĕi�i������B�v���b�V���[�̂��������A�ە�����鉹�y����������鉹�y���~���������̂��낤�B�@���C�ɓ���Ȃɂ�My Best���t��I�яo���̂��䂪�퓅�B�n�C�t�F�b�c�^�J�y���A�V�Q�e�B�^�z���V���t�X�L�[�A�V�F�����O�^���[�r���V���^�C���A�k���[�Z���A�X�[�N�^�p�l���J�A�O�����~�I�[�^�V�F�x�b�N�A�t�F���X�^�o���r�[�A�`�����^�t�����L�A�����h�R���B�`�^�I�s�b�c�A�����[���@�^�A���f���V�F�t�X�L�[�ȂǏ\�����̎莝��CD�̒�����My Best�ɑI�肵���̂́A�i�^���E�~���V�e�C���̃��@�C�I�����ƃE���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�̃s�A�m�ɂ��1950�N�^���̃��m�����Ղ��B
�@��v���̕i�ʂ���D�����͂����܂ł��Ȃ����A���M���ׂ���22���ߖځB���̑t�҂������ċ��t���钆�A�~���V�e�C�����z�����B�b�c�̃R���r�͗}�����ꂽ�D�낳�������o���B�D�����̒�ɐ��_�̐x�������ށB
 �@�i�^���E�~���V�e�C���A1903�N���E�N���C�i�̃I�f�b�T���܂�B�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�A1903�N�E�N���C�i�̃L�G�t���܂�B�~���V�e�C���̓z�����B�b�c�̂��Ƃ��u�ނƂ�70�N���̗F�l�ŁA�����͑��̒N�����ނ̂��Ƃ�m���Ă���͂����v�ƒ����u���V�A���琼���ցv�ŏq�ׂĂ���B����A�z�����B�b�c�͒���u�z�����B�b�c�̗[�ׁv�̒��Łu1921�N���Ƀ~���X�^�C���Ɖ�����B�ނƂ͐��U�̗F�l�ɂȂ�ꏏ�Ƀf���I�̃��T�C�^�����J���M�d�Ȓ��ԂƂȂ����v�Əq�ׂĂ���B���̌�A1925�N�A��l�͘A�ꗧ���ăA�����J�ɖS������B�܂��ɐ�F�ł���B��l�͐��U�ɂ킽��삵�����̃��C�u���������Ă���B�Ȃ̂ɁA���R�[�h�͂��̃u���[���X�́u�\�i�^ ��3�ԁv�̂݁B���ɕs�v�c�Ŏc�O�Șb�ł���B80�N��Ƀ~���V�e�C�����u���H���[�W���i�z�����B�b�c�̈��́j�A�����l��͎Ⴍ�Ȃ��B����������������e�̂�������悤��v�ƁA�t�����N�Ɓu�N���C�c�F���v�̃��R�[�f�B���O���Ă����Ƃ����B���A���ǒ������������̊��͌��ɏI������������B
�@�i�^���E�~���V�e�C���A1903�N���E�N���C�i�̃I�f�b�T���܂�B�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�A1903�N�E�N���C�i�̃L�G�t���܂�B�~���V�e�C���̓z�����B�b�c�̂��Ƃ��u�ނƂ�70�N���̗F�l�ŁA�����͑��̒N�����ނ̂��Ƃ�m���Ă���͂����v�ƒ����u���V�A���琼���ցv�ŏq�ׂĂ���B����A�z�����B�b�c�͒���u�z�����B�b�c�̗[�ׁv�̒��Łu1921�N���Ƀ~���X�^�C���Ɖ�����B�ނƂ͐��U�̗F�l�ɂȂ�ꏏ�Ƀf���I�̃��T�C�^�����J���M�d�Ȓ��ԂƂȂ����v�Əq�ׂĂ���B���̌�A1925�N�A��l�͘A�ꗧ���ăA�����J�ɖS������B�܂��ɐ�F�ł���B��l�͐��U�ɂ킽��삵�����̃��C�u���������Ă���B�Ȃ̂ɁA���R�[�h�͂��̃u���[���X�́u�\�i�^ ��3�ԁv�̂݁B���ɕs�v�c�Ŏc�O�Șb�ł���B80�N��Ƀ~���V�e�C�����u���H���[�W���i�z�����B�b�c�̈��́j�A�����l��͎Ⴍ�Ȃ��B����������������e�̂�������悤��v�ƁA�t�����N�Ɓu�N���C�c�F���v�̃��R�[�f�B���O���Ă����Ƃ����B���A���ǒ������������̊��͌��ɏI������������B�@�~���V�e�C���͂܂��A�u���V�A���琼���ցv�̒��ŁA�u�u���[���X�̎����y�͍D���ł͂Ȃ����A���@�C�I�����E�\�i�^�͑S���̗�O���B�����ē��ɑ�1�ԃg�����̑�1�y�͂��D�����v�Əq�ׂĂ���B���A���͂�����������������B�u�~���V�e�C������A��D���ȑ�1�Ԃł͂Ȃ��A��3�Ԃ����R�[�f�B���O���Ă���Ă��肪�Ƃ��B����قǑf���炵����2�y�͂͑��ɂ���܂���B�܂��ɐ_������I�Ȗ����ł��v�ƁB
 �@��̓��@���ɖ����ꂽ�Ȃ����������B�x�[�g�[���F���́u�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110�v�ł���B���̋Ȃ̓t�[�K�������ꂽ��3�y�͂����ɗL�������A���Ƃ����Ă������̂͑�1�y�͂��B�`���̑�1���̍��M�Ȃ�D�����B���̎���]�����Ȃ���8��J��Ԃ������̃V���v���ȓW�J���̗l���B���ꂼ�A�\�i�^�`�����Ɍ��܂Œǂ��l�߂��g�`���̊v�����h�x�[�g�[���F���V�˂̏ł���B
�@��̓��@���ɖ����ꂽ�Ȃ����������B�x�[�g�[���F���́u�s�A�m�E�\�i�^ ��31�� �σC���� ��i110�v�ł���B���̋Ȃ̓t�[�K�������ꂽ��3�y�͂����ɗL�������A���Ƃ����Ă������̂͑�1�y�͂��B�`���̑�1���̍��M�Ȃ�D�����B���̎���]�����Ȃ���8��J��Ԃ������̃V���v���ȓW�J���̗l���B���ꂼ�A�\�i�^�`�����Ɍ��܂Œǂ��l�߂��g�`���̊v�����h�x�[�g�[���F���V�˂̏ł���B�@My Best�̓|���[�j�i1977�N�^���j�B���ɂ̌`���̒��ɍ��M�ȗD������X�����s�A�j�Y���̋ɒv�I�ł���B���̂���̃|���[�j�͖{���ɑf���炵���B
�@�g���������h�F�q��͐l�ɗD���������O�����ɐ������B��L��Ȃɒʂ���l���������Ǝv���B
�@�@�@���Q�l������
�@�@�@�u���V�A���琼���� �~���X�^�C����z�^�v
�@�@�@�@�@�@�i�^���E�~���X�^�C���A�\�������E���H���R�t�����A������c����i�t�H�Ёj
�@�@�@�u�z�����B�b�c�̗[�ׁv�f���B�b�h�E�f���o�����A�������u��i�y�Ёj
2018.05.25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l2�`�G�~�[���E�x�����i�[
�@�g�[�}�X�E�G�W�\��(1847�|1931)���A�����L�^�E�Đ�����g�t�H�m�O���t�h�����������̂�1877�N12��5���B��������I�[�f�B�I�̗��j���n�܂����E�E�E�E�E�Ƃ܂��A��X�̏펯�͂����ł���B�Ƃ��낪�A�ނɐ���l�Ԃ������悤���B�t�����X�̎��l�Ŕ����Ƃ̃V�������E�N���X�i1842�|1888�j�ł���B�N���X�͍l�Ă����@��̎d�l���ނ��������āA1877�N4��30���Ƀt�����X�̉Ȋw�A�J�f�~�[�ɗa����B12��5���A�G�W�\���̔��\�����A�J�f�~�[���J������ƁA�����Ȃ���A�����ɂ̓G�W�\���ȏ�ɖ{�i�I�Ȓ~���@�̎d�l���������Ă����̂ł���B�G�W�\���ɐ�邱��7�����B�������Ȃ���A�N���X�ɂ͎����̎������Ȃ�����i���ł��Ȃ��������߂ɒ��z�Ɏ~�܂炴��Ȃ������Ƃ����킯���B�t�����X�͔ނ̌��т�]�����A1948�N�����ACC�f�B�X�N��܂ɂ��̖��𗯂߂��BACC�Ƃ�Academie Charle Cros�̓������ł���B �@�G�W�\���́g�t�H�m�O���t�h�́A������h�����~���ɘ^�����鏊���V�����_�[�����B�@���O�ɂ����G�W�\���́u�����[����̗r Mary has a little lamb�v�𐁂����ށB���ꂪ���E���̘^���Ƃ����B�������G�W�\���͓����ɗL�\�Ȏ��ƉƂł��������B�g�t�H�m�O���t�h���ɓ����\�����A���i�����s����Ёu�G�W�\���E�X�s�[�L���O�E�t�H�m�O���t�v��ݗ�����B�������Đ��ɏo���g�t�H�m�O���t�h���������A�G�W�\���̈ӂɔ����ăT�b�p������Ȃ������B�^���E�Đ��ɂ�����j�Ɖ��a�Ƃ̐ڐG�����S�łȂ��Ə\���ȉ��ʂ������Ȃ��B�����S���o�Ȃ��P�[�X��������قǁB�v����ɏ��i�Ƃ��Ă̊����x�����n�������̂��B
�@�G�W�\���́g�t�H�m�O���t�h�́A������h�����~���ɘ^�����鏊���V�����_�[�����B�@���O�ɂ����G�W�\���́u�����[����̗r Mary has a little lamb�v�𐁂����ށB���ꂪ���E���̘^���Ƃ����B�������G�W�\���͓����ɗL�\�Ȏ��ƉƂł��������B�g�t�H�m�O���t�h���ɓ����\�����A���i�����s����Ёu�G�W�\���E�X�s�[�L���O�E�t�H�m�O���t�v��ݗ�����B�������Đ��ɏo���g�t�H�m�O���t�h���������A�G�W�\���̈ӂɔ����ăT�b�p������Ȃ������B�^���E�Đ��ɂ�����j�Ɖ��a�Ƃ̐ڐG�����S�łȂ��Ə\���ȉ��ʂ������Ȃ��B�����S���o�Ȃ��P�[�X��������قǁB�v����ɏ��i�Ƃ��Ă̊����x�����n�������̂��B�@�d�b�������A���L�T���_�[�E�O���n���E�x���̃��H���^�������̋Z�t�`�`�F�X�^�[�E�x���ƃ`���[���Y�E�e�B���^�[�̓t�H�m�O���t�̉��ǂɒ���B���Ǔ_�́A�����V�����_�[�����b�N�X�E�R�[�e�B���O�ɁA�n���h�N�����N�쓮���[���}�C�T�����[�^�[�ɕϊ����A�U�����Ɛj�Ƃ̌Œ�Ƀ��[�Y�E�J�b�v�����O���������ƁB����ɂ��j�̒ǐ��������サ�^���E�Đ��������啝�ɉ��P���ꂽ�B�x�����e�B���^�[�́A1885�N�A������g�O���t�H�t�H���h�Ɩ��t���A�G�W�\���Ɏ��ƒ�g�����������������B�Ȍ�A���҂͒~����̔e�������郉�C�o���ƂȂ����B�{�Ƃ̈Ӓn������G�W�\���́A�V�����_�[���\���b�h�E���b�N�X�ɕϊ�����Ȃlj��ǂɗ�ށB1890�N��ɂ́A�W�����j�E�x�b�e�B�[�j���o��B�j�ɃX�o�C�_�[����������Ȃlj���������I�Ɍ��コ����B������A�̗���̒��A�V�����_�[���~����̐��\�͔���I�Ɍ��サ�A�ƊE�̓V�����_�[�S��������}���邱�ƂɂȂ�B
�@�V�����_�[�����łȂ��ꂽ�^���ɂ́A�G�W�\���̐����͂��߁A�u���[���X�́u�n���K���[���� ��1�ԁv�̎��쎩���A��s�A�j�X�g ���[�[�t�E�z�t�}�����N����̃s�A�m���t�A�t���[�����X�E�i�C�`���Q�[���̐��A�C���F�b�g�E�M���x�[���̃V�����\���A���\�v���m �l���[�E�����o�̉̂Ȃǂ�����B
�@���āA���悢��x�����i�[�̓o��ł���B�ނ������A�G�W�\���̃V�����_�[���~������R�y���j�N�X�I�]���ŕ����A���R�[�h�̖����������v�ҁE���J�҂ł���B
�@�G�~�[���E�x�����i�[�i1851�|1929�j�́A1851�N�A�h�C�c�̓n�m�[���@�[�ɏZ�ރ��_���n���l�Ŋw�҂̉ƒ�ɐ������B�w�Z�����14�܂ŁA���̌�͉Ƃ̏�������`�����A1870�N�A�����푈���u������ƁA��Ƃ̓A�����J�ɈڏZ�����B�G���N�g���j�N�X�ɋ������������x�����i�[�́A�j���[���[�N�̎���N�[�p�[�E���j�I���ŕ����w�Ɠd�C�H�w���w�ԁB�ނ̓w�͂̓x���̓d�b��̉��LjĂ̓����擾�Ƃ����`�Ŏ������ԁB�x���͂�������ƂƂ��Ƀx�����i�[�����H���^�������ɍ̗p�����B�����I�ɁA��y�ł���x�����e�B���^�[�̒~������ǂɌg������͂��B�Ȃ�A���ɂ��̎��_�ŃG�W�\���Ƃ̑Ό��̖G�肪���������ƂɂȂ�A�������������ł���B
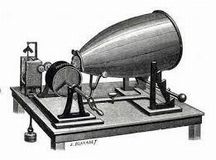 �@�x�����i�[���A������]�f�B�X�N�����g�O�����t�H���h���\�z�������������́A1883�N�A
�X�~�\�j�A�������قŌ����g�t�H�m�[�g�O���t�h�������B1857�N�A�t�����X�l�Z�t���I���E�X�R�b�g���l�Ă����@��B�M��̔��Ŏ������A�X�X��Y�t�������������ĉ��̔g�`���L�^����Ƃ������́B��Ɏ��͉�]����h������̓��Ɋ�����A�X�ɐ����ȃK���X��ɋL�^����悤�ɂȂ����B��]�h�����̓G�W�\���́g�t�H�m�O���t�h�̐��ƂȂ�A�����K���X�̓x�����i�[�́g�O�����t�H���h�̔��z�ɂȂ������B�����Ώۂ��琳���̋@�킪���܂��B�Ȋw�̖ʔ������B
�@�x�����i�[���A������]�f�B�X�N�����g�O�����t�H���h���\�z�������������́A1883�N�A
�X�~�\�j�A�������قŌ����g�t�H�m�[�g�O���t�h�������B1857�N�A�t�����X�l�Z�t���I���E�X�R�b�g���l�Ă����@��B�M��̔��Ŏ������A�X�X��Y�t�������������ĉ��̔g�`���L�^����Ƃ������́B��Ɏ��͉�]����h������̓��Ɋ�����A�X�ɐ����ȃK���X��ɋL�^����悤�ɂȂ����B��]�h�����̓G�W�\���́g�t�H�m�O���t�h�̐��ƂȂ�A�����K���X�̓x�����i�[�́g�O�����t�H���h�̔��z�ɂȂ������B�����Ώۂ��琳���̋@�킪���܂��B�Ȋw�̖ʔ������B�@�g�t�H�m�[�g�O���t�h�͓������������͂������A�����̂��̂̍Đ��͏o���Ȃ������B���ꂪ�A2008�N�A�ߔN�̋Z�p�ɂ�艹�Ƃ��čĐ����ꂽ�B���ꂪ�l�ލŌÂ̘^���Ƃ����B
 �@�g�t�H�m�[�g�O���t�h����q���g���x�����i�[�́A������]�����ɂ��~����J���ɖv���A1884�N�A�x���Ђ�����Ɨ����ʂ����B�����āA1887�N�A���Ɋ����i�����\����9��26���j�B������]�f�B�X�N�����g�O�����t�H���h�̒a���ł���B�x�����i�[�́A�L�O���ׂ���ꐺ�Ƃ��āA�u���炫�琯 Twinkle, twinkle little star�v��N�ǂ����B���̓��������ݎ����\�ł���B
�@�g�t�H�m�[�g�O���t�h����q���g���x�����i�[�́A������]�����ɂ��~����J���ɖv���A1884�N�A�x���Ђ�����Ɨ����ʂ����B�����āA1887�N�A���Ɋ����i�����\����9��26���j�B������]�f�B�X�N�����g�O�����t�H���h�̒a���ł���B�x�����i�[�́A�L�O���ׂ���ꐺ�Ƃ��āA�u���炫�琯 Twinkle, twinkle little star�v��N�ǂ����B���̓��������ݎ����\�ł���B�@�G�W�\���́g�t�H�m�O���t�h�ƃx�����i�[�́g�O�����t�H���h�Ƃ̍��ق́A�����E�`�Ԗʂł́A�����^�Ɛ����^�ł��邪�A�@�\�ʂł͕����̗ʎY�̉ۂƂ������ƂɂȂ�B�g�t�H�m�O���t�h�̉~��������Ȃ̂ɑ��A�g�O�����t�H���h�̃f�B�X�N�͗e�ՁB���ꂪ�A�g�O�����t�H���h�����������ő�̗v���ł���B
�@����̃��R�[�h�����H���́E�E�E�E�E�������~�Ղł���u���b�J�[�Ձv������E�j�b�P�����b�L���{�����u���^���E�}�X�^�[�v�ʁ������b�L���{�����u�}�U�[�v�����j�b�P���E�N���[�����b�L���{�����u�X�^���p�[�v�ʁB�X�^���p�[�ʼn����r�j�[���̃f�B�X�N���v���X�A�f�B�X�N���̊����B�X�^���p�[�̉��a�����Ղ�����}�U�[�ɖ߂�B�ꍇ�ɂ���Ă̓��^���E�}�X�^�[�ɂ܂ŁB�ۑ����ʎY���e�ՁB�x�����i�[�́g�O�����t�H���h�͓������炱�̋@�\������Ă����̂ł���B
�@�x�����i�[�́A1895�N�A�t�B���f���t�B�A�Ɂu�x�����i�[�E�O�����t�H���Ёv��ݗ��B�~����ƊE�͂܂��G�W�\���E�V�����_�[�����̎���B�㔭�́g�O�����t�H���h�͋��̑D�o���������A���X�ɉ��ǂ������A�G�W�\���̉��ɔ����Ă䂭�B�����Đ��ɂ͔e�҂ƂȂ�̂����A����̓x�����i�[��l�̗͂ɂ����̂ł͂Ȃ��B���R�[�h�t�����ɑ傫�ȑ��Ղ��c������l�̓��m��Y���킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@��l�ڂ̓G���h���b�W�E�W�����\���i1867�|1945�j�ł���B�W�����\���̓j���[�W���[�W�[�B�L�����f���o�g�̋@�B�Z�t�B�ނ̍��[���}�C�������\���������߁A�x�����i�[�́g�O�����t�H���h�ɍ̗p�����B1900�N�܂ł�5�N�ԂŔ[�������[���}�C��25.000�ɒB�����B�������A���̂���A�x�����i�[�E�O�����t�H���ЂɂƂ�ł��Ȃ���肪�����オ��B�c�Ƃ�S�����Ă����V�[�}���Ƃ����j���A�T�E���h�{�b�N�X���̓����Ɋւ��A�i�ׂ��N�������̂ł���B������ė������̂��W�����\���������B���ʂ͏��i�A�A���g�O�����t�H���h�Ƃ������O�͎g�p���Ȃ��Ƃ������������B������A�̗���̒��A�W�����\���̓x�����i�[�̋����o�c�҂ƂȂ�A�̋��̃L�����f���ɖ{�ЁE�H����ڂ��u�r�N�^�[�E�g�[�L���O�}�V���Ёv���������B1901�N�̂��Ƃł���B
�@��l�ڂ̓t���b�h�E�K�C�X�o�[�O�i1873�|1951�j�ł���B�K�C�X�o�[�O�̓h�C�c�n�A�����J�l�B�x�����i�[�Ƃ�1891�N�ɏo��^���Z�t�߂��B1897�N�A�x�����i�[���p���O�����t�H���Ђ�ݗ�����ƁA���A�����h���ɕ��C�B�ړI�̓��R�[�f�B���O�B��������̉��y�l�Ԃ������K�C�X�o�[�O�͐������B���[���b�p�����삯����A�^��������簐i����B 1898�N8��2���A�h���z�e���̋߂��̃p�u�œ����A�}�`���A�����̎肩��X�^�[�g�����K�C�X�o�[�O�̘^���B���̈�H���₪�đ�͂ƂȂ�c��ȉ��y�̋L�^���₳���B����ȃA�[�e�B�X�g�̈�[���L���Ă������B
�����Պy��t�ҁ�
�G�h�D�A���h�E�O���[�O�A�Z���Q�C�E���t�}�j�m�t�A�A���o�[�g�E�V�����@�C�c�@�[�A�E���f�B�~�[���E�h�E�p�n�}���A���[�[�t�E�z�t�}���A�C�O�i�b�c�E�����E�p�f���t�X�L�[�A�A���g�D�[���E�V���i�[�x���A�E�B���w�����E�o�b�N�n�E�X�A�A���t���b�h�E�R���g�[�A�A�E�g�D�[���E���[�r���V���^�C���A�}���O���b�g�E�����A�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�A�����_�E�����h�t�X�J
�����y��t�ҁ�
�p�u���E�f�E�T���T�[�e�A���[�[�t�E���A�q���A�t���b�c�E�N���C�X���[�A�����E�N�[�x���b�N�A�~�b�V���E�G���}���A���b�V���E�n�C�t�F�b�c�A���[�[�t�E�V�Q�e�B�A�W���b�N�E�e�B�{�[�A�p�u���E�J�U���X
���̎聄
�G�����R�E�J���[�\�[�A�e�B�g�E�X�L�[�p�A�x�j���~�[�m�E�W�[���A�q���[�h���E�V�����A�s���A�Q���n���g�E�q���b�V���A�V�������E�p���[���A�l���[�E�����o�A�W�F�����f�B���E�t�@�[���[�A���b�e�E���[�}���A�G���U�x�[�g�E�V���[�}��
���w���ҁ�
�A���g�D�[���E�g�X�J�j�[�j�A�E�B���w�����E�t���g���F���O���[�A�u���[�m�E�����^�[�A �E�B�����E�����Q���x���N�A�t�F���b�N�X�E���C���K���g�i�[�A���I�|���h�E�X�g�R�t�X�L�[
�@20���I�̉��t�j�������B�X���鉉�t�Ƃ����ł���B�����̉��͐ԔՂƂ��Č��݁A�唼�͕���CD�Œ������Ƃ��ł���B���R�[�f�B���O�E�v���f���[�T�[�̃p�C�I�j�A �t���b�h�E�K�C�X�o�[�O�̑��Ղ́A��y�̃E�H���^�[�E���b�O�iEMI�j�Ɏp����A�J�^���O�͏[���̈�r��H�����B
�@1897�N�n���̉p�O�����t�H���Ђ́A1931�N�A�p�R�����r�A�Ђƍ�����EMI�ɁA1901�N�n���̃r�N�^�[�E�g�[�L���O�}�V���Ђ́A1929�N�A���W�I��RCA�ɔ�������RCA�r�N�^�[�ɁB �V�����_�[�^�~����̔̔���ЕăR�����r�A�Ђ�1888�N�A�R�����r�A�E�t�H�m�O���t��ݗ��B1906�N�A�R�����r�A�E�O���t�H�t�H���ЁB1938�N�ACBS�R�����r�A�ƂȂ�B
�@1898�N�ݗ��̃n�m�[���@�[�̃x�����i�[�E�O�����t�H���Ђ̖{�Ё��H��́A�N���V�b�N��僌�[�x���A�h�C�c�E�O�����t�H���ЂƂȂ�B
�@�~����̃t�H�[�}�b�g�����ɏ��������x�����i�[�́A���R�[�h���y�Y�Ƃ̑b��z�����B�G�W�\���̎c�荁�͐h�����ăR�����r�A�E���R�[�h�ɕ�̂Ƃ��Ďc��݂̂��B�ʂ����Ă��̍��͉��������̂��H
�@���_�A�ő�̍��̓t�H�[�}�b�g�ł���B�����A�������ĂȂ�Ȃ��ϓ_�́A��l�̉��y�ւ̎v������̍��ł͂Ȃ��낤���B�m���ɁA�G�W�\���́g�t�H�m�O���t�h�ɂ��A�u���[���X��z�t�}���ȂǁA�̑�ȉ��y�̘^��������B��������́A�A�[�e�B�X�g����̋����v�]�ɂ����̂��B����ɑ��A�x�����i�[�́A��Аݗ��̓�N��ɂ͉��y��i���Ɏx�Ђ�ݗ����A�L�\�ȕ�����h��������I�E�ϋɓI�ɖ{��̉��y��^��������̐����Ƃ����B���ꂼ�A�n�[�h�ƃ\�t�g�̗��ւɂ��A���R�[�f�B���O���y�𐢂ɍL�߂邱�Ƃ���}���Ă����ł͂Ȃ����B�����̑�ʐ��Y���\�ɂ��鐅���f�B�X�N�����́A�x�����i�[�̗��O�ƌł����т��Ă����̂ł���B
�@�x�����i�[�́g�O�����t�H���h�́A�a������SP���R�[�h�`1948�NLP���R�[�h�`1958�N�X�e���I�E���R�[�h�Ɛi���A1982�N�����CD�ɏ���܂ŁA���a�����܂ꂽ�f�B�X�N�𐅕��ɉJ�[�g���b�W�ʼn����E���Ƃ�����{�@�\��ς��Ȃ��܂܁A���R�[�h�̎嗬�ł��葱�����B�G�W�\���𗽉킵���G�~�[���E�x�����i�[�̒m���x�͂����Ƃ����Əオ���Ă�����ׂ��ł���B
�@�����Ȃ鎄�́A���R�[�h���y�Y�Ƃɏ]�������I�̊ԃT�����[�}�������𑗂��Ă����B�����āA�����܂����y�𐏈�̎�Ƃ��āA�܂��A�[�������l���𑗂��Ă���B�x�����i�[�̂��A�ł���B�g��������[�x��RCA�r�N�^�[�́ACBS�R�����r�A�ƕč������僌�[�x���B���̓�̃��[�x���́A����A�\�j�[BMG�Ƃ��č��ꂳ��Ă���B����͂�A����͕ς��I
���Q�l������
�@���R�[�h�̐��E�j ���r�Y���i���y�V�F�Ёj
�@�ԔՓ`��CD�Z�b�g�iBMG�W���p���t�@�~���[�N���u����j
�@���ł��ǂ�I�[�f�B�I�̐��I�i�Вc�@�l���{�I�[�f�B�I����j
2018.04.25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l1�`�j�R���E�e�X��
�@�����w�ҁE�����L�ꎁ�������V���ɘA�ڒ��́u���I���t�v�͖��ނ̖ʔ����ł���B�����w����_�ɂ��āA�G��A�N�w�A���w�A�X�|�[�c�A�f��A���jetc�Ƙb�͑���ɍL����B�@�ō��ɋ������䂩�ꂽ���̂̈�ɁA2016�N8��4���̃A���h�E�}�k�[�c�B�I�Ɋւ���L�ڂ��������B���l�T���X3�唭���̈���ň���̑c�O�[�e���x���N�͗L�������A�A���h�́A��������̎n�c���Ƃ��B���^���Ɗe��t�H���g�̊J���A���C�A�E�g�̕W������}��N��������������{�����������B���ꂼ�����j�ɂ�����v���B�ނȂ����Ă͍����̏��Е����͌��Ȃ��B������ɁA�O�[�e���x���N�͒N�����m���Ă��邪�A�A���h�E�}�k�[�c�B�I��m��l�͏��Ȃ��B���������������߂ĕ������O�������B���j��A�L���Ȑl���̉A�ɉB��Ă��邪�A���̐l�Ɠ����A�ۂނ��낻�̐l�ȏ�̈̋Ƃ𐬂��������l�Ԃ͊m���ɑ��݂���B
�@����́A�m��ʎ҂Ȃ��������G�W�\���i1847�|1943�j�𗽉킵���m��ꂴ��̐l�̈�l�A�j�R���E�e�X���ɃX�|�b�g�Ă�B
 �@�j�R���E�e�X��(1856�|1943)�̓N���A�`�A���܂�̃Z���r�A�l�B�c��������N���ɂ����Č�ɃG�W�\�����錳�ƂȂ������̌��������B���4�̂Ƃ����삵�ċ߂��̏���ʼn����ԁB�u�����A�����J�ɍs���āA�i�C�A�K���e�z�𗘗p���ė͂����v�Ƃ���������ށB������̓O���[�c�H�ȑ�w�Ŋώ@���������d�C�@�B�̐����q���甭����傫�ȉΉԁB�����q�s�v�ς��A�������Ȃ��u��w�𗬃��[�^�[�v���B�e�X�����U�̖��u�𗬃V�X�e�����p���v�̖G��ƂȂ����B
�@�j�R���E�e�X��(1856�|1943)�̓N���A�`�A���܂�̃Z���r�A�l�B�c��������N���ɂ����Č�ɃG�W�\�����錳�ƂȂ������̌��������B���4�̂Ƃ����삵�ċ߂��̏���ʼn����ԁB�u�����A�����J�ɍs���āA�i�C�A�K���e�z�𗘗p���ė͂����v�Ƃ���������ށB������̓O���[�c�H�ȑ�w�Ŋώ@���������d�C�@�B�̐����q���甭����傫�ȉΉԁB�����q�s�v�ς��A�������Ȃ��u��w�𗬃��[�^�[�v���B�e�X�����U�̖��u�𗬃V�X�e�����p���v�̖G��ƂȂ����B�@1884�N�A28�̉āA�e�X���͂��̖��������ĐV�V�n�A�����J�ɓn��B�G�W�\���ւ̏Љ�����ɁB�e�X���ƃG�W�\���B�����j�ɋP����l�͂������ĉ^���̏o����ʂ������B
�@���̂���̃G�W�\���͐��U�̐Ⓒ���B�~���@�A�Y�f�������b��A���M�d�������X�ɔ����B�d�������̂��߂̓d�͎��Ƃɂ����o���Ă����B�d�͕����͒����B�G�W�\����������I�̂́A�����A�𗬂ɂ��Ђ�֓d���̂��������Ă�������B�Z�p�����n�������̂��B
�@����Ȑ܁A�G�W�\���̖��@�����e�X���͒����ɍ̗p�����B���������𐄐i����G�W�\���ɁA�e�X���͌𗬂̗D�ʂ�����B����݂��Ȃ��G�W�\���B����͎��Ԃ̖�肩�H
�@�Ƃ͂����A�m�M����u�𗬃V�X�e���v�ł͂��������A��l�Ŏ����ł���͂����Ȃ��B�Ȃ�A�����ɍ��𗎂������A���Ԃ������ăG�W�\����������邵���Ȃ��ƍl�����B�G�W�\���͍ŐV�̏��C�D�ɑ������ꂽ�������d�@���̏Ⴗ��ƁA�e�X���ɏC���𖽂���B�e�X���͐v���Ɍ�����˂��~�߁A�O��ō�Ƃɓ�����A����ŏC���������������B�e�X���̃X�L����F�߂��G�W�\���́A�l�X�ȋ@�B�̐v��ނɔC����悤�ɂȂ�B��肪�����������e�X���͎d���ɖv���A�傫�Ȑ��ʂ��グ���B
�@���鎞�A�J�����̒������d�@�̖��_�ɋC�Â����e�X���́A���Ǎ���āB�G�W�\���͎���A����������5���h���̃{�[�i�X�����B��������A�e�X�������A�ʂ�̃{�[�i�X��v���B�Ƃ��낪�G�W�\���̔����͑z��O�B�u�Ȃ�Ɛ^�Ɏ��̂��B�N�̓A�����J���̃��[���A�Ƃ������̂��킩��Ȃ��̂��ˁv�B�e�X���L����B���E�B
�@��l�̌��ʂɂ́A�u�����v�u�𗬁v�Ƃ����t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�����邪�A���̑��̗v�����������Ȃ��B�G�W�\���̎t�͕�B���K�̋���͎Ă��Ȃ��B�e�X���͍H�ȑ�w�Ő��w�╨���w�̊�b��@������ł���B��Ղ̍��͗�R�B�G�W�\���̑b�́u�w�́v�B�u�V�˂�99���̊���1���̃C���X�s���[�V�����v�ɑ�\�����悤�ɁA�n���Ɏ����E�o����ςݏd�˂Č��_���^�C�v�B�e�X���́A���ς��d�A��̓I�ȍ�Ƃɓ���O�ɂ͓��̒��ɖ����\�z�}���`����Ă���^�C�v�B�G�W�\�����������u�V�˂Ƃ�99���̓w�͂ɂ���1���̑M���̂��Ƃł���v�͗L���ȑ䎌�B���i�I�ɂ������Ɣ��̃��A���X�gVS���z�Ɣ��̃��}���e�B�X�g�B�e�X���͂������]���B�u�G�W�\�����������̎R�̒�����j�������悤�Ƃ�����A�I�̋Εׂ��������Ęm����{��{���אj��������܂ł�葱���邾�낤�B�킽���́A���_�ƌv�Z�ł��̘J�͂�90���ߖ�ł���͂����Ƃ킩���Ă���߂����ڌ��҂ł���v�B��b�\�͂��^�C�v�����i���Ⴄ�B�e�X�����G�W�\�����Ԃ������͕̂K�R�ł���B
�@�G�W�\���̂��Ƃ��������e�X���Ɏ��{�̎�������L�ׂ��̂̓E�F�X�e�B���O�d�C��Ђ������B�Ђ����ɍ̗p���Ă����P���𗬃V�X�e���ƃe�X���̑��w�V�X�e�������ѕt������I�Ȑi���𐋂���B����ɂ��A��K�͔��d�ƍ��d�����d���\�ƂȂ��āA�d�͋����̌��������}��ꂽ�B����A���������́A���d���X���������A���d�����͂�������2�`3Km�B���̂��߈��肵���d�͋������s���ɂ́A�삵�����̔��d�����K�v�Ƃ����\���I��_��������܂܂ł������B
�@�����܂Œ����V�X�e���ɍS��G�W�\����GE�ЂɈ�����n�����̂́A1893�N�A�V�J�S�ŊJ�Â��ꂽ��������������B
�@���X�̌𗬋@�B�A�����g���u�A���d�Ɩ����̔����i�̓W���A�����āA�ɂ߂��̓X�y�N�^�N���ȕ��d�����������B�G�W�\���̓t�H�m�O���t�i�~���@�j�L�l�g�X�R�[�v�i�f��j�ȂǂőR���邪�A�͔ۂ߂Ȃ������B�܂��ɂ��̔�������𗬓d�C�̏����𐢊E�ɍ�������C���F���g�ƂȂ����̂ł���B
�@�������A�e�X���͍����g���d���̕ψ�����l�āB�㖼���ƂȂ������U�ψ���u�e�X���R�C���v�ł���B����ɂ��Ɩ����u�́A�G�W�\���̔��M�d���𗽉킵�āA����̃l�I���T�C����u�����̐�삯�ƂȂ����B
�@���N�A�i�C�A�K���J����Ђ��A��ɂ�鐅�͔��d���p���ւ̓��D��}��ƁA���債���̂�2�ЁB�e�X���̃E�F�X�e�B���O�ЂƃG�W�\����GE���������A�������ƂɃK�`�K�`�̒����h������GE���𗬂ɈƑւ����Ă����B���ʁA���d�̓E�F�X�e�B���O�A���d��GE��I��B�e�X���̌𗬃V�X�e���̏����ƂȂ����B�u�i�C�A�K���e�z�Ɍ𗬓d�̓V�X�e�����\�z����v�Ƃ����e�X�����N����̖������Ɏ��������̂ł���B
�@�����ŁA���{�̓d�͎��Ƃ����Ă������B�N�_��1883�N�����̓����d�͂̑O�g�E�����d����ЁB�����̓G�W�\���̒���������i�߂Ă����B�L�[�}���͓�l�A�␂�M�F�Ɠ����s���B�␂�͌𗬂̗D�ʂ��������ē����ɐi��������A�����͂����܂Œ����ɍS��A���ʁA�␂�ގЁB���ɏo�������d����Ђ�ݗ��B�e�X���̌𗬃V�X�e���𐄐i�����B���ꂪ60Hz�����B����A�����̓����d����Ђ́A�x����Ȃ���𗬂̗D�ʂ�F�m�A�I�̂̓h�C�cAEG�Ђ̃V�X�e���ŁA���ꂪ50Hz�B�������ē��{�ɂ�50�^60�������������̂ł���B���ڂ͒��쌧�B���삪60�œ�����50�B���쌧�o�g�̎��́A���Z����܂ł�60�̃��R�[�h�E�v���[���[���A��w�����50���g�����B�܂��A�ʒi�s�ւ͂Ȃ���������ǁB
�@�d�̓t�H�[�}�b�g�푈�ɏ��������e�X���́A�u���E�V�X�e���v�̍\�z�Ɍ������B1901�N�u�Z���`�����[�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�_�������A20���I�̖��J����������L�O��I�_���ƂȂ����B�����ɂ́A�����ɂ��d�͂̑��d�Ə��`�B�̃V�X�e���A���Ȃ킿�A�����d�M�A���W�I�����A�ʐ^�d���A�t�@�N�V�~���Ȃǂ̋Z�p��������Ă����B����ɐΒY�̌͊������z���čĐ��\�Ȏ��R�G�l���M�[�ɂ܂Ō��y���Ă���B�u���E�V�X�e���v�́A�������肵�������\�z�䂦���A�s��߂���헪�䂦���A�r���ڍ����Ă��܂����A�����ɐ��荞�܂ꂽ�e�X���̐�i�I�A�C�f�B�A�́A�g�����W�X�^�E���W�I�A���W�R���A�P�C�^�C�d�b�`�X�}�t�H�A�d�C�����ԁA���{�b�g�Z�p�A���z�M�╗�͔��d�ɂ܂łȂ����Ă䂭�B
 �@�N���X�g�t�@�[�E�m�[�����ē̉f��u�v���X�e�[�W�v�i2006�N�āj�ł́A�f���B�b�h�E�{�E�C���j�R���E�e�X���������Ă���B�X�e�B�[�u�E�W���u�Y����j�Ƃ��]����C�[�����E�}�X�N�̃e�X�����[�^�[�Y�̓A�����J�ŐV�s�̎����ԉ�ЁB�Ж��͂������j�R���E�e�X���ɗR������B�����d�C�����Ԃɓ������A��͎ԃ��[�h�X�^�[�͈��|�I�l�C���B���ڂ̗U�����[�^�[�△�����d�V�X�e���̓e�X���Z�p�̔��W�`���B�j��ő�̃I�^�N�ƌĂ�A�}�b�h�T�C�G���e�B�X�g�ɂ�����A�˂��g�G�W�\����k���オ�点����V�ˁh�j�R���E�e�X���͊ԈႢ�Ȃ�����ɐ��������Ă���B
�@�N���X�g�t�@�[�E�m�[�����ē̉f��u�v���X�e�[�W�v�i2006�N�āj�ł́A�f���B�b�h�E�{�E�C���j�R���E�e�X���������Ă���B�X�e�B�[�u�E�W���u�Y����j�Ƃ��]����C�[�����E�}�X�N�̃e�X�����[�^�[�Y�̓A�����J�ŐV�s�̎����ԉ�ЁB�Ж��͂������j�R���E�e�X���ɗR������B�����d�C�����Ԃɓ������A��͎ԃ��[�h�X�^�[�͈��|�I�l�C���B���ڂ̗U�����[�^�[�△�����d�V�X�e���̓e�X���Z�p�̔��W�`���B�j��ő�̃I�^�N�ƌĂ�A�}�b�h�T�C�G���e�B�X�g�ɂ�����A�˂��g�G�W�\����k���オ�点����V�ˁh�j�R���E�e�X���͊ԈႢ�Ȃ�����ɐ��������Ă���B
2018.03.05 (��) �����ܗ� ��l�̒��쌧�l���_���X�g�̖��ƈ�
�@���͒��쌧�o�g�ł���B������A�����ܗւɏo�ꂵ����l�̒��쌧�l�A�X���[�g�̓�����傫�ȊS�������Ēǂ����B�X�s�[�h�X�P�[�g�̏����ޏ��ƃm���f�B�b�N�����̓n���œl�ł���B�����_���̍ŗL�͌��Ƃ��ĕ����ɏ�荞��l���������A�Ђ���A�Ђ��Ɩ��Â����B�����_���Ƃ��������ڕW�����ɒ���l�������͉̂��������̂��H(1)�����_������،��ɂ��Ȃ����������ޏ��̏ꍇ
 �@�����ޏ��́A1986�N5��26���A���쌧����s�Ő��܂ꂽ�B����s�ƕ����đ����ɓ��ɕ����̂́A����s���R�����w�Z5�N��6�N�̂Ƃ��̎��̒S�C�E�c���a�Y�搶�̂��Ƃ������B�c���搶�͎��������k�������Ďq�ǂ��������Ȃ������B�q�������炱�̒��x�ŁA�Ƃ������o�͂Ȃ��A��Ɉ�l�O�̐l�ԂƂ��Ĉ����Ă��ꂽ�B����Ӗ��ς���̐搶�ł���B�W���j�A�ƃV�j�A����ʂ��Ȃ��A���V�A���q�t�B�M���A�̃G�e���E�g�D�g�x���[�[ �R�[�`��f�i�Ƃ�����B������A�搶�̌����ɂ͗��������������Ƃ����X�������B�����f��u���ɉ˂��鋴�v�̊��z�������������̂��ƁB�Ȃɂ�番����Ȃ��܂܁u�ƂĂ����������v�ƈ��ՂɌ����͂ɑ��A�u�N�͈�̉��Ɋ��������̂��B�푈�̔ߎS���ɂ��B����Ƃ����̒��ł����߂��l�Ԃ̖��͂��ɂ��B���ɑ��Ăǂ����������������Ȃ��ƁA�N�̕��͂͐i�����Ȃ��v�Ȃ�ԃy���������������B�����͗����ł��Ȃ��������s�v�c�ɋL���Ɏc���Ă���B���A�ŏ��X�ɁA�������L���Ƃ��͋�̓I����Ɋ�Â��Ę_���I�ɏ����A�Ƃ����K�����g�ɂ����Ǝv���Ă���B
�@�����ޏ��́A1986�N5��26���A���쌧����s�Ő��܂ꂽ�B����s�ƕ����đ����ɓ��ɕ����̂́A����s���R�����w�Z5�N��6�N�̂Ƃ��̎��̒S�C�E�c���a�Y�搶�̂��Ƃ������B�c���搶�͎��������k�������Ďq�ǂ��������Ȃ������B�q�������炱�̒��x�ŁA�Ƃ������o�͂Ȃ��A��Ɉ�l�O�̐l�ԂƂ��Ĉ����Ă��ꂽ�B����Ӗ��ς���̐搶�ł���B�W���j�A�ƃV�j�A����ʂ��Ȃ��A���V�A���q�t�B�M���A�̃G�e���E�g�D�g�x���[�[ �R�[�`��f�i�Ƃ�����B������A�搶�̌����ɂ͗��������������Ƃ����X�������B�����f��u���ɉ˂��鋴�v�̊��z�������������̂��ƁB�Ȃɂ�番����Ȃ��܂܁u�ƂĂ����������v�ƈ��ՂɌ����͂ɑ��A�u�N�͈�̉��Ɋ��������̂��B�푈�̔ߎS���ɂ��B����Ƃ����̒��ł����߂��l�Ԃ̖��͂��ɂ��B���ɑ��Ăǂ����������������Ȃ��ƁA�N�̕��͂͐i�����Ȃ��v�Ȃ�ԃy���������������B�����͗����ł��Ȃ��������s�v�c�ɋL���Ɏc���Ă���B���A�ŏ��X�ɁA�������L���Ƃ��͋�̓I����Ɋ�Â��Ę_���I�ɏ����A�Ƃ����K�����g�ɂ����Ǝv���Ă���B�@���ƋL�O���W�u����܁v�̌㏑������ۓI�������B�uࣁX���邾��܂̖ڂƐ^�ꕶ���Ɍ����͕s���̓��u���B�����ɂݐ����Ă��̒��ɔ�э���ł䂭�E�C�Ǝ��s�͂��B���̊ۂ݂́A�s���݁A���a��ڋ����̂肱���Ĉꑫ�ꑫ�����Ő^���Ȑ����𑱂�����̂̌������C���𖧂��ɒX���Ă���v�ȂǁA�搶�̕\���͓N�w�I�ł��炠�����B
�@�����ޏ��̌��t�ɂ��N�w�I�ȓ�����������B����s�q����H �c���搶�Əd�Ȃ�B
�u�����Ђ����狆�ɂ̊�����v
�u�����Ɉ�b�ł�������������������v
�i���肪�j�u���Ă����Ȃ��Ă��ꏏ�v
�u�X�ƑΘb������v
�u�w�тƌo����ςݏd�˂��҂������v
�u������^��������̂͗L�� ���狁�߂���͖̂����v
�@�����̌��t�́A���_����_���ɂ�����2014�\�`�ܗւ�5�ʂɊÂ����J�̌�A���ɕ������ŝg�������ߒ��Ő��܂ꂽ���̂��B�הO��ł��������Ȃ��Ɍ��܂Œǂ����ޖ����̓w�́B�X�P�[�g�Ɉ�r�ɑł����ނ܂�ŋ����҂��B�u��ԍ����Ƃ��납��̌i�F�����n�������v�ƊԐړI�\���Ȃ�������_�������ɂ����\�`�̎��Ƃ͈Ⴂ�A�u�����_���v�Ƃ������t����،��ɂ��Ă��Ȃ��B�����_�����~�����Ȃ��͂����Ȃ��̂ɁB
�@2014�N�A�����ޏ��͒P�g�I�����_�ɓn�����B�\�`�ŃX�s�[�h�X�P�[�g�S���_����7�����l�����I�����_�ɁA����̑���Ȃ�������T�����������B�t�������R�[�`�́A1998�����2006�g���m��3�̋����_���ɋP�����}���A���k�E�e�B�����B14���狣�Z�X�P�[�g���n�߂��Ƃ����x�炫�B�g���m��500m�ł̓X�^�[�^�[�Ƃ̌ċz�����킸�Ƀt���C���O���i�B2002�\���g���[�N�̓��_���Ȃ��B�ޏ������܂�m��A�X���[�g�������B�ޏ��̑̌����ׂĂ��A27�Ƃ��������ĎႭ�Ȃ����ĕ��ҏC�s�̗��ɏo�������̗ƂɂȂ����ƍl���Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B
�@�e�B�����������ɓ`�������̂��u�{�����L�vBOZE KAT�̃t�H�[���B�Ƃ��낪�A����������邽�߂̒Ⴂ�p���Ɋ���Ă������߁A��̂��N�������̎p���Ɋ��o�I�ɓ���߂Ȃ��B�I�����_�؍ݒ��Ɏ��ȋL�^���X�V���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ł������͊т����B�u���s���悤���������悤�������̑I���B������M���Đi�ށv�Ƃ̐M�O�ŁB
�@2016�N4���A2�N�Ԃ̃I�����_�C�s���I���ċA���B�M������R�[�`�M�B��w�����E���鋧�[���Ɠ�l�O�r�Ńt�H�[���ł߂ɗՂށB�I�����_�̕��^���ł͂Ȃ������ޏ��Ǝ��̃t�H�[���̏K���ł���B�u22�����v��v�̃X�^�[�g�������B
�@���s����̖��A�H�蒅�����̂��ŐV�X�|�[�c�Ȋw�u�q�b�v���b�N�v���_�B�ꖇ�̍��Ղ����E�ʁX�ɓ��삳���銴�o�B���̂��߂ɍ��Վ��ӂ̋ؓ���Е����ӎ����Ēb����B���Ղɓ��������g���[�j���O��10��ނ����B����ɂ�荜�Ղ̌X�����Ȃ��Ȃ�̊������肵�����ŕX�������������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�X�̃R���g���[�����X�Ƃ̑Θb�̐i���ł���B���ɃJ�[�u�ł̌��ʂ������������B
�@�a�̐��_�������ꂽ�̂������̓Ǝ����̈�B����R�[�`�̌�y�������O��������Õ��p�̃m�E�n�E�Ɛ��_���K������B�ꖇ���̉��ʂɂ��g���[�j���O��O�q�u���肪���Ă����Ȃ��Ă��ꏏ�v�̐��_�͍���������`�����ꂽ���̂ł���B
�@�I�����_���`��BOZE KAT�ƍŐV�X�|�[�c���_�Ƙa�̋Z�@�̗Z���B���狁�߂���͖̂����Ƃ����������×~�������ɗh�邬�Ȃ��t�H�[���������������B
�@2016�^17�V�[�Y������n�܂��������̉��i���͎~�܂�Ƃ����m�炸�A��Ɂg�����̋����h500���̓��[���h�J�b�v15�A���A���O�̌�����24�A���Ƃ������ނ̋����������܂ܕ����ܗւɓ˓������B
�@2018�N2��18���A�X�s�[�h�X�P�[�g���q500���B36�b94�B�ܗV�ł̗D���B���{���q�X�s�[�h�X�P�[�g�j�㏉�̋����_���������B���Ɋ��郉�C�o���E�����Ԃւ̋C��������A���L�^�ɕ����ϋq�𐧂��邱�Ƃ��Y��Ȃ��B�t�F�A�ɐ킢�����Ƃ̎v�����ǂݎ�ꂽ�B
�@�����_�����m�肵�Ă܂��삯������̂̓��C�o���E�����Ԃ̂��ƁB�u��������̃v���b�V���[�̒��悭������ˁB�`�����b�\�I���Ȃ��̂��Ƃ����X�y�N�g���Ă���v�Ɛ����������B
�@�W�Q�̈Ӑ}�����炩�Ȋ؍��l�X�^�[�^�[�̍��C�ɃX�^�[�g�ł�⓮�h���Ȃ�������ɂ̊�����������������Ɛ�D�̃X�^�[�g���炠���t�]������������X���[�Y�Ȋ���������������ԂƂ̍��B����͍Ō�̃R�[�i�����O�������B�o�߂����X�s�[�h�𐧌�ł����ɂ��o�����X����������ɑ��A�����͂��̑����ŋ�����������ƕX���������Ƃ��ł����B���̓��̂�̒��Ŗ����ꂽ���ɂ̊��肪�y�d��ʼnh���ւƓ����Ă��ꂽ�̂��B
�@�ǂ������������_�����Ƃ��A�����̔]���ɕ������́B����͎x���Ă��ꂽ�����̐l�����ւ̊��ӂ̋C�������������낤�B���ɂ̊�����K�����邽�߂Ɋւ���Ă��ꂽ�l�����B��w���o���㏊���悪������Ȃ��Ƃ��Ɏ�������L�ׂĂ��ꂽ����a�@����F�v�������B�Ί�ƐH���ŐS�Ɖh�{���P�A���Ă��ꂽ���Ẵ`�[�����C�g���V�u�䂳��B�ď�̎��]�ԃg���[�j���O���T�|�[�g���Ă��ꂽ�K�p�\�w���B�����J�����O�ɖS���Ȃ����e�F�E�Z�g�s����̂��ƂȂǁE�E�E�E�E�B
�@������̃C���^�r���[�������ޏ��͂������B
�u��������������������F�߂Ă�������݂Ȃ�����ɂ��Ă��ꂽ�B����Ȃ݂Ȃ���ɕ邱�Ƃ��ł������ƁB�ꏏ�ɂ��ꂵ���C���������L�ł������ƁB���ꂪ��Ԃ��ꂵ���v
�@���ɂ̊���ň�̒��_���ɂ߂������́u�ܗւ̃S�[���̐�ɂ܂�����ׂ����̂�����v�ƌ������B����͐��E�L�^�ւ̒���B�����ޏ���3���ɍs���鍂�n�J���K���[�ł̍��ۑ��Ő��E�V�L�^36�b36�ɒ��ށB
(2)�����_���ɍS��܂������n���œl�̏ꍇ
 �@�n���œl�́A1988�N5��26���A���쌧�k���܌S���n���Ő��܂ꂽ�B���n����1998����ܗւ̃W�����v���Z���B�n���͂�������ăm���f�B�b�N���Z�ɖڊo�߁A�����_������悤�ɂȂ����B
�@�n���œl�́A1988�N5��26���A���쌧�k���܌S���n���Ő��܂ꂽ�B���n����1998����ܗւ̃W�����v���Z���B�n���͂�������ăm���f�B�b�N���Z�ɖڊo�߁A�����_������悤�ɂȂ����B�@���ꂩ��20�N�B�m���f�B�b�N�����̃G�[�X�ɐ��������n���œl�ɕt����ꂽ�w���́u�V���o�[�R���N�^�[�v�B2014�\�`�ł̋�_���ȍ~�A���[���h�J�b�v2014�^15�V�[�Y���ő���2�ʁA2015�^16�ł͐��E�I�茠��_���B�Ȃ�قǁu�V���o�[�R���N�^�[�Ɂv�ɑ�������(�H)��тł���B����Ɉ�O���N�����n����2017�^18�̃I�����s�b�N�E�V�[�Y���Ō����ȕϐg���ʂ����B�I�����s�b�N���O�̌̋����n���܂�4�A���A���[���h�J�b�v���������L���O1�ʂ������A�����_���ŗL�͌��Ƃ��ĕ����ɏ�荞�B���̎��̌��t�B
�u�����A��_���͗v��Ȃ��v
�u�����_�����l��Ȃ�A�l���ē�����O�Ǝv���������āA�l��B�v
�@�Ȃ�قǁA�ނ̐�������݂�u��_���͗v��Ȃ��v�̑䎌�͒ɂ��قlj�����B1998����ܗւ̋����_���X�g�����G�ۂ́A�u���͊���A��͌��ɁA���͈��g�v�Ȃ閼����f�����B�n���͂�����̌��ɂ����𖡂킢�����Ȃ��̂��B�������́A��҂̌��t�u�l���ē�����O�̏Ŋl��v�ɂ͈������������B�l�������Ƃ��Ȃ��̂Ɋl����܂ōl����B������ƕs���߂��͂��Ȃ����Ǝv�����B�낤���l�����Ǝv�����B�m���f�B�b�N�����̑O���̓W�����v�B����قǎ��R�ɍ��E����鋣�Z�͂Ȃ��B�|�C���g�������Ƃ͂������̏Ō��ʂ͑傫���ς��B����͎��͂ł͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ȃ̂ɁB�u�����_���ւ̎����S�v�Ɓu�l����ɂ܂ł̌��y�v�B���̔������n�������B
�@2��14���A�m���f�B�b�N�����m�[�}���q���B�O���̃W�����v�̌��ʁA�n���͎O�ԖځA���C�o�� �G���b�N�E�t�����c�F���͌ܔԖڃX�^�[�g�B���̍��͂���8�b�B�㔼�̃N���X�J���g���[�́A�܂�Ń\�`�̃��v���C�����邩�̂悤�ȁA��l�̈�R�ł��ƂȂ����B�����ǂ����4���ڂ̓o���ŁA�ґR�ƃX�p�[�g�����t�����c�F���ƌ����ɒǂ�������n���Ƃ́A�͊��ɂ����Ă��̍��͗�R�������B�t�����c�F�����A�n����B�\�`�Ɠ������ʂƂȂ����B
�@2��20���A���[�W�q���ɐ�J�������B�W�����v�͎�ʁB�㔼�̃N���X�J���g���[�̓g�b�v�E�X�^�[�g�B24�`34�b��Ƀh�C�c�l�I��3�l���W�c�ōT����B�����1992�A���x�[���r���A1994�����n�������c�̋����_���X�g�������i�͗��z�I�X�^�[�g�ƌ��������B�n���̓m�[�}���q���̔��Ȃ���n�C�y�[�X�ŐϋɓI�ɓ������݂�}��B�����X�L�[������Ȃ��B���b�N�X�̃~�X���H �h�C�c3�l�O�����Ńq�^�q�^�Ɖ����Ă���B�Ȃ�Ƃ������C�����A�Ǝv���Ԃ��Ȃ�3���ڂň��ݍ��܂�A�����Ȃ�5���B�h�C�c�������_����Ɛ肵���B
�@�s���ɁA���b�N�X�̑I���~�X�����������낤���A�ő�̂��̂́A���C�o���̃h�C�c�l�I��3�l���w��Ɍł܂������Ƃ��낤�B���{�������_�����l�������q�p�V���[�g��}�X�X�^�[�g������܂ł��Ȃ��A�W�c�����ŕ������߂�ΌX�̃X�^�~�i�������}��邩�炾�B
�u����͌����Ă��邪������������Ȃ��B�܂����낢��l���Ȃ��Ă͂����Ȃ��v
�@�m�[�}���q���̌�Z�́A�s�U�ƕ������t�����c�F�����{�Ԃɂ�������ƍ��킹�Ă������ƁB���̓ǂ݈Ⴂ�B���[�W�q���ő�̔s���́A�O�q�̂悤�ɁA���C�o���̃h�C�c��3�l�̏W�c���͑̐������R�����Ă��܂������ƁB�܂��ɐl�m�����`���������B
�@�I�����s�b�N�ŋ����_�����l��͎̂���̋Ƃ��B����܂ŁA�����ē��R�Ƃ���ꂽ�A�X���[�g�̂����������l���l�ꂸ�ɎU���Ă��������Ƃ��낤�B�����������ȃp�t�H�[�}���X�����Ă��A���C�o��������Ε�����B�z��O�̏��x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�������Ȃ����Ƃ��x�X����B���ꂪ�����Ƃ������̂��B
�@���Z�̗����A�S���{�X�L�[�A���́u�n���̘]�����A�I�����s�b�N�O�ɁA���܂��Ă����v���Ƃ𖾂炩�ɂ����B�Ȃ�A�N���X�J���g���[�̊������͋����Ɍ������̂�������B����������Ă̊撣�������܂ł̘J����̎^�ɒl���邱�Ƃ͊m�����B
�@�ł��A���͊����Č��������B�n���̔s���͐S�\���ɂ������ƁB�����_�����~�����̂̓A�X���[�g�Ȃ瓖�R���B��������͑��ΓI�Ȃ��̂��B������撣���Ă��l�m�̋y�Ȃ����Ƃ�����B�������쌧�l�ɂ��āA����������a�����̏����ޏ��Ɠn���œl�������́B����́A�����̖��Ɂu���Ă����Ȃ��Ă��ꏏ�B�����Ђ����狆�ɂ̃p�t�H�[�}���X�����邾���v�Ƃ������n�ɒB�������ۂ��̍��ł͂Ȃ��������낤���B
2018.02.15 (��) �������`�j�ϓV�ڂ��烂�[�c�@���g�u�A�f���C�[�h���t�ȁv���l�@����
 �@��N12��20���ɕ��f���ꂽTV�����u�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�B�ԑg�̖����Ӓ�m�E�������V�����̊Ӓ肪�b��ƂȂ��Ă���B
�@��N12��20���ɕ��f���ꂽTV�����u�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�B�ԑg�̖����Ӓ�m�E�������V�����̊Ӓ肪�b��ƂȂ��Ă���B�@�����̃��[�����X�̓X�傪���������q�ɑ��āA��̎���̂悢�����ł����f��B�u�Ȃ�ł��Ӓ�c �n�܂��Ĉȗ��ő�̔����B12�|3���I������v����ɕ����Ȍ��z�ŏĂ��ꂽ�j�ϓV�ڂɊԈႢ�������܂���B���{�ɂ���j�ς͂�������3�_�B���ׂč���ł��B�����́A�����4�_�ڂ��m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��v�E�E�E�E�E���ʁA�t�����t������Ӓ�z2500���~�I
�@�Ƃ��낪����Ɉق�������l�������ꂽ�B���������Ȃ̓��|�ƁE���Ӎg����ł���B�u���̒��q�͎���������y�Y�i���B�s�ꂶ��1400�~���炢�Ŕ��Ă�B���z�̐l�Ȃ�݂Ȓm�Ă��B������j�ϓV�ڂł���͂��Ȃ���v�B
�@�͂Ă��āA�ǂ��炪���������H 2500���~VS1400�~�B�Ӓ�mVS���n�̂����|�ƁB����͖ʔ����}���Ɨl�q�����Ă��邪�A�������_�͏o�Ă��Ȃ��悤���B���|�̐��Ƃ���u�Ȋw�I�ȕ��͂��v�Ƒ�������TV�������̓_���}���̈��B���M��������͂�������A�ǂ���炨�����������H �������V�� ���I�̑��R�I�H
�@�N���V�b�N���y�̐��E�ɂ����b�͗l�X����B����Ȓ�����A�{���́A���[�c�@���g���I�̊�쎖���u�A�f���C�[�h���t�ȁv���Ƃ�グ�Ă݂����B
�@���[�c�@���g�̃��@�C�I�������t�Ȃ͑�1��K207�����5��K219�܂ł�5���^��B��6�ԁA��7�Ԃ͋U��Ƃ���Ă���B
�@��6�� �σ����� �͓���K268�Ƃ����ԍ����������A�P�b�w����6�łł�Anh.C14.04�Ƃ����ԍ��ɕύX�����BAnh�̓h�C�c���anhang�̗��ŕ��Ƃ����Ӗ��BC�́u�U��A�܂��͋^�`�����i�v�̈�B��7�ԃj������K271i�Ƃ����ԍ��̂܂܂ł��邪�A����Ȃ��^�킵����i�ɑI�ʂ���Ă���B���̂��ߗ��҂Ƃ��u�V���[�c�@���g�S�W�v�ɂ͓����Ă��Ȃ��B
�@�����ł����ƃP�b�w���ԍ��ɂ��ċL���Ă��������B���[�c�@���g��35�̐��U�̒��Ŗc��Ȑ��̍�i���c�����B�ނ�1784�N��2�����玩�M�́u��i�ژ^�v�������Ă��āA����ȍ~�̍�i�́g��r�I�h��ȔN�オ����ł��邪�A����ȑO�̍�i�́A�܂Ƃ܂����L�^���Ȃ����ߐ����͍�����ɂ߂�B���̏�A�o�ŎЂ��y����ړI�Ń��[�c�@���g�̍�i�ƋU��P�[�X�����Ȃ��炸���݂����B����ȉ]���鳖��鲂̃��[�c�@���g��i�Q�ɁA�������ɔԍ��i�ǔԁj��^�����̂����[�g���B�q�E�t�H���E�P�b�w���i1800�|1877�j�ł���B�P�b�w����600�ȗ]��̃��[�c�@���g��i���A�u���M�ژ^�v�����ɁA�y����̋L�q�A�莆�A���̑����X�̎�����ǂ݉����āA�Ȃ�Ƃ���i���ƂɒǔԂ�t���I�����BK1�\K626�B1862�N�B�u���[�c�@���g��i�ژ^�v�̒a���ł���B
�@�Ƃ͂����A����Ŋ����ł��낤�͂����Ȃ��A���̌�����8�ł𐔂���B���ɃA���t���[�g�E�A�C���V���^�C���ɂ���3��(1937�N)�A�t�����c�E�M�[�O�����O��ɂ���6��(1964�N)�̉���͑啝�Ȃ��̂ƂȂ����B
�@�P�b�w���ԍ��̊�{�͊������ɕ��ׂ邱�Ƃł��邩��A�N��ύX����������i�͔ԍ���ς���K�v��������B���̂��߉����i�̓P�b�w���̃I���W�i���ԍ��Ɖ���ԍ��L����B
�@�Ⴆ�A�D��ȃ��k�G�b�g�ł�����݂́u�f�B���F���e�B�����g ��17�� �j�����v�̃I���W�i���ԍ���K334�B����ԍ���K320b�ł���B����͌��̌��ʁA�u�f�B���F���e�B�����g��17�ԃj�����v�́A�m�肵�Ă����i�u�Z���i�[�h��9�ԃj�����w�|�X�g�z�����x�vK320�̂�������2�ԖڂɊ����i1�Ԗڂ�2�̍s�i��320a�j�������A�Ƃ������Ƃŗ^����ꂽ�ԍ��ł���i���݂�K320b�̒���Ɋ�������������A���̍�i��320b A�ƕ\�L�����j�B
�@�����Ȃǂł�K320b(334)�Ȃǂƕ\�L����ꍇ�����邪�ACD���̓I���W�i���ԍ���K334�݂̂̕\�L����ʓI���B�����N�㏇�Ƃ����ژ^�̃R���Z�v�g�͕����邪�A�I���W�i���ԍ��̐Z���x�̍��������d����Ă���̂��낤�B
�@Anh�����BC�ԍ��t���́u�U��A�܂��͋^�`�����i�v�Ƃ����̂͑O�q�̂Ƃ���ł���B
 �@���āA�u�A�f���C�[�h���t�ȁv�ł���B1933�N�A�V���Ƀ��[�c�@���g�̃��@�C�I�������t�ȂƂ����s�A�m�E�X�R�A���o�ł��ꂽ�B�Z���҂́A�t�����X�̃��@�C�I���j�X�g�ō�ȉƂ̃}���E�X�E�J�T�h�V���i1892�|1981�j�B���͖��s�A�j�X�g ���x�[���E�J�T�h�V���B�H���u10�̃��[�c�@���g�̎��M������Z�������B���ʏ�ɂ́w�A�f���C�[�h�����Ɍ���x�Ƃ����������݂�����v�Ƃ����G�ꍞ�݂������B���[�c�@���g10�̎��M���A���̃s�A�m�Z���ŁA�A�f���C�[�h�����Ɍ���Ȃ鏑�����݁B�����ɂ��ӎU�L���b�ł͂Ȃ����B
�@���āA�u�A�f���C�[�h���t�ȁv�ł���B1933�N�A�V���Ƀ��[�c�@���g�̃��@�C�I�������t�ȂƂ����s�A�m�E�X�R�A���o�ł��ꂽ�B�Z���҂́A�t�����X�̃��@�C�I���j�X�g�ō�ȉƂ̃}���E�X�E�J�T�h�V���i1892�|1981�j�B���͖��s�A�j�X�g ���x�[���E�J�T�h�V���B�H���u10�̃��[�c�@���g�̎��M������Z�������B���ʏ�ɂ́w�A�f���C�[�h�����Ɍ���x�Ƃ����������݂�����v�Ƃ����G�ꍞ�݂������B���[�c�@���g10�̎��M���A���̃s�A�m�Z���ŁA�A�f���C�[�h�����Ɍ���Ȃ鏑�����݁B�����ɂ��ӎU�L���b�ł͂Ȃ����B�@�A�f���C�[�h�����Ƃ̓t�����X�������C15���Ɖ��܃}���[�E���O�U���X�J�̊Ԃɐ��܂ꂽ�l���}���[�E�A�f���C�[�h�E�h�E�t�����X�i1732�|1800�j�̂��ƂŁA�t�����X�v���Œf����̘I�Ə��������C16���̏f��ɂ�����B���̈����|���p�h�[���v�l�Ƃ̊m���A�����}���[�E�A���g���l�b�g�Ƃ̊W���A�t�����X�v���ɂ��^���̈Ó]���A���̔g���̐l���͂Ȃ��Ȃ��L���b�`�[�Ȃ��̂�����B
�@ �@�J�T�h�V�������̘b������������̈�l�Ƀh�C�c�̍����ȉ��y�w�҃t���[�h���q�E�u���[���i1893�|1975�j�������B�u���[���̓i�`�X�̌�p�w�҂�J.S.�o�b�n�̌����҂Ƃ��Ă������B�����u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�ɂ͂���ȃo�b�n�����҂Ƃ��Ă̌��������Ď���B����́u�o�b�n�͂��̔ӔN�ɂ����ċ���y�ւ̐S����̊W�������Ȃ������v�Ƃ������́B�o�b�n��_��������h�C�c���y�j�ɂ����āA���̌����͂���Ӗ�����I�������B�Ƃ��낪�A��̔����A�Ⴆ�Ώ��������J�[���t�����̗��O�̋L�q��J���^�[�^�㉉�̕p�x�Ȃǂ���A�ӔN�̃o�b�n������y�ɔw���������Ƃ���u���[���̌����͐����͂��������ƂɂȂ����B���̂�����ɁA�ނ̐i��̋C���ƌ��̊Â��Ƃ����\�����ʂ��_�Ԍ�����B
 �@�u���[���́A�J�T�h�V�����������u�A�f���C�[�h���t�ȁv�ɔ�т����B�J�T�h�V���������Ƃ����Ƃ������[�c�@���g�́g���M���h���������ɁA�����^��ƔF�߂Ă��܂����B�����āA�u�A�f���C�[�h���t�ȁv�͖ڏo�x��(�H)�u���[�c�@���g��i�ژ^�v��3�ł�K.Anh.294a�Ȃ�ԍ����^�����A����i�ɔF�肳�ꂽ�B
�@�u���[���́A�J�T�h�V�����������u�A�f���C�[�h���t�ȁv�ɔ�т����B�J�T�h�V���������Ƃ����Ƃ������[�c�@���g�́g���M���h���������ɁA�����^��ƔF�߂Ă��܂����B�����āA�u�A�f���C�[�h���t�ȁv�͖ڏo�x��(�H)�u���[�c�@���g��i�ژ^�v��3�ł�K.Anh.294a�Ȃ�ԍ����^�����A����i�ɔF�肳�ꂽ�B�@���N1934�N�A�����@�C�I���j�X�g ���[�f�B�E���j���[�C�������̋Ȃ����R�[�f�B���O����B���̘^����CD������Ă��āA�Ȗڕ\�L�́u���@�C�I�������t�� �j���� K.Anh.294a�w�A�f���C�[�h�x�v�ƂȂ��Ă���B�������Ă݂����A10�̎��M������̍�i�i�Ƃ̐G�ꍞ�݁j�Ƃ͂����A���悻���[�c�@���g�炵����ʓ��e�ł���B�����f�B�[���C���̂Ȃ�Ƃ��������I�u�X�̐��ԁv���H �悭���܂��A����ȋȂ�F�肵�����̂��A�������Ȋ��z���B
�@�u�A�f���C�[�h���t�ȁv�̖��H�͂ǂ��ł��������B�w�҂̋^�`���������A�J�T�h�V���́A1977�N�A���Ɏ������ł����グ�����ł��邱�Ƃ�F�߂��B���\����44�N�ڂ̂��Ƃ������B�����āAK.Anh294a �Ƃ������ԍ���K.Anh.C14.5�Ƃ����u�U��A�܂��͋^�`�����i�v�ɑI�ʂ��ꂽ�B�J�T�h�V���ɂ��Ă݂�A44�N�Ԃ��x���ʂ��A���R�[�f�B���O�܂Ŏ����A�u�U��v�̊���Ƃ͂����u���[�c�@���g��i�ژ^�v�Ƀ^�C�g�����c�����̂�����A�Ȃ��҂��ׂ���������Ȃ��B
�@��쑛���͂Ȃ����₽�Ȃ��̂��H ���N�O�̍����͓��玖���̂悤�ɁA��͂��������邾�낤�B���Ƃ́A����ʖ��_�~�H �l���x�������H �l�͊O�ςŊȒP���x�����B
�O�ςƂ������͈̂�ԂЂǂ��U��ł��邩������Ȃ��@�Ȃ��A�u�A�f���C�[�h�v�l�^�́A���N�O�����P�j������A�����͕O�R������������������B�Ɋ��Ӑ\���グ�鎟��ł��B
���ԂƂ������̂͂��������ɂ����ނ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A�u�x�j�X�̏��l�v���
���Q�l������
���{�������F���[�c�@���g��������j�i�u�k�Ќ���V���j
���ы`�����F�o�b�n�`���̓��ǂ��i�t�H�Ёj
���[�c�@���g��ȁF���@�C�I�������t�� �j���� K.Anh294a�u�A�f���C�[�h�vCD
2018.01.15 (��) 2018�N�n�G���`�A���Q���b�`�AABC�\�z�Ȃ�
(1)�A���Q���b�`�������Ȃ� �@��N12��25���t���̒����V���Ɂu�A���Q���b�`�������Ȃ��v�Ƃ������o�����������B�L���́A������w�̖��s�A�j�X�g �}���^�E�A���Q���b�`(1941�|)���A���N���ۂ������Ă����E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�Ɛ��ɋ��������Ƃ������̂ł���B���ڂ̓��X�g�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁB�w���̓_�j�G���E�o�����{�C���B���R�́A�������t�Ƃ����ۂ��Ă����E�B�[���E�t�B��������Ɩ�˂��J����������Ƃ̂��ƁB����ȖڂŔN�����̃E�B�[���E�t�B�� �j���[�C���[�R���T�[�g��������A�m���ɐ��l�̏����c�����m�F�ł����B
�@��N12��25���t���̒����V���Ɂu�A���Q���b�`�������Ȃ��v�Ƃ������o�����������B�L���́A������w�̖��s�A�j�X�g �}���^�E�A���Q���b�`(1941�|)���A���N���ۂ������Ă����E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�Ɛ��ɋ��������Ƃ������̂ł���B���ڂ̓��X�g�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁB�w���̓_�j�G���E�o�����{�C���B���R�́A�������t�Ƃ����ۂ��Ă����E�B�[���E�t�B��������Ɩ�˂��J����������Ƃ̂��ƁB����ȖڂŔN�����̃E�B�[���E�t�B�� �j���[�C���[�R���T�[�g��������A�m���ɐ��l�̏����c�����m�F�ł����B�@�ł͂����납�炩�Ǝv���A�莝���̉f���ׂĂ݂��B2010�N�ɂ͏���������B�]�k�����A���̔N�̎w���҂̓W�����W���E�v���[�g���i1924�|2017�j�ŁA�킽���̒��ł͍ō��̃j���[�C���[�R���T�[�g�̈�B���ɖ`���̊�̌��u��������v���Ȃ̃j���A���X�L���ȕ\���ɂ͐�����������̂��B
�@����ȑO�̎莝���f����1992�N�A�J�����X�E�N���C�o�[�i1930�|2004�j�܂ők�邪�A�����ɂ͏����c���̎p�͂Ȃ��B���̃N���C�o�[�������̈��ŁA�I�P�Ƃ̈�v��̂���ɏ�����̂Ȃ��̖����ł���B���ɂƂ��ẴE�B�[���E�t�B�� �j���[�C���[�R���T�[�g�̃x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�́A�����A1992�N�N���C�o�[��2010�N�v���[�g���Ƃ������ƂɂȂ�B����͂��Ă����A�v����ɁA�E�B�[���E�t�B���ɏ����c�������߂ēo�ꂵ���̂�1992�N����2009�N�̊ԂƂ������Ƃ����������B���Ƃ̓l�b�g�����ł���B���̌��ʁA�y�F����i�E�B�[���E�t�B���̓����g�D�j�������̓��c���������̂�1997�N�A�Ƃ������Ƃ��m�F�ł����B
�@�����Œ����V���̋L���ɖ߂낤�B�������̂̓��[���b�p�x�ǒ��̐��͎��B
�ޏ��ƃE�B�[���E�t�B�����u�ĂĂ������͉̂��������̂��B�y����K�ˁA�{�l�ɒ��ځA�����Ă݂��B�u����܂ʼn��t���Ȃ������̂́A�������ЂƂ�����Ȃ��I�P����������ł��v���Ђɂ����˂炸�A��肽���Ȃ����Ƃ�����ł����ޏ��Ȃ�̂�����肾�����B�@�ȁ[�B1990�N��㔼�Ə����Ă���ł͂Ȃ����B�����Ɠǂ݂Ȃ͂�B�ł��܂��A�����Ƃ��Ē��ׂ����A�Ŗ��p�t�H�[�}���X�ɍĉ�A�ĔF���ł����̂�����悵�Ƃ��悤�B
1842�N�ɐݗ����ꂽ�E�B�[���E�t�B���͏�C�̎w���҂�u���Ȃ��C�Ӓc�̂ŁA�����̌��ꂩ��I��郁���o�[�͒��N�A�j�������������B�����̓��c��F�߂��̂�1990�N��㔼����B���݂�148�l�̑t�҂̂���1�����������B
�@���̋L���ɃP�`������ς�̓T���T���Ȃ����A��͂�u�N�����m�v���_���猩��ƕ�����Ȃ��B�����c�����ЂƂ�����Ȃ����Ƃ��l�b�N�������̂Ȃ�A1997�N���琔�N�̎��_�ŏo�����Ă������Ă��������͂Ȃ��B20�N�͂����ɂ���������B������A���Q���b�`�́u�������ЂƂ�����Ȃ��I�P����������v�Ƃ����̂͗��R�����Ƃ��ď\���ł͂Ȃ��B�L�\�ȋL�҂Ȃ�{���̗��R�������o�����Ɛ荞���낤�B�������A���o�����u�������Ȃ��v�Ƒ��i�ɐU�肩�Ԃ����̂�����A���̓��e�ł͂����ɂ����r���[���B�y����K�ˁA�{�l�ɒ��ڕ������̂ɁA���������Ȃ��b�ł���B�Ȃ�A���̗��R�����Ȃ�ɒT���Ă݂悤�B
�@���͂��˂��˃A���Q���b�`�ɑ��s���������Ă���B���_���t��̂��Ƃł��낤�͂��͂Ȃ��A�����ł͍ł��D���ȃs�A�j�X�g�̈�l���B�Ȃ�A����͉����Ƃ����A���p�[�g���[�̕�ł���B�l�C�Ȃ���肽����Ȃ��X�����ڗ��̂��B
�@�ώG�ɂȂ邩��A�R���`�F���g��CD�ɍi��ƁA����Ă���̂́A���[�c�@���g�ł́A��18�ԁA��19�ԁA��20�ԁA��21�ԁA��25�ԁB�x�[�g�[���F���ł͑�1�ԁ���2�ԁB�`���C�R�t�X�L�[�̑�1�ԁA�V���p���̑�1�ԁ���2�ԁA���X�g�̑�1�ԁA���t�}�j�m�t�̑�3�ԁA�v���R�t�B�G�t�̑�3�Ԃ���F���ȂǁB�Ȃ��̂́A���[�c�@���g�̑�23�ԂƑ�27�ԁA�x�[�g�[���F���̑�4�ԁA��5�ԁu�c��v�A�O���[�O��u���[���X��1�ԁ���2�ԁA���t�}�j�m�t�̑�2�ԂȂǁA�v���̃s�A�j�X�g�Ȃ炱�����Ēe��������l�C�Ȃ����\�����Ă���B�V���p���E�R���N�[���Ŕޏ��̈�O�̗D���҃}�E���c�B�I�E�|���[�j�i1942�|�j�Ɣ�ׂĂ����̍��͗�R���B
�@�ł��܂��A����͂��قǒ��������Ƃł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B���j�[�N�߂��閼��x�l�f�B�b�e�B���~�P�����W�F���͂��Ă����A20���I�����Ă̋����E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�ɂ��Ă��A���t�}�j�m�t�̑�2�Ԃ�O���[�O�͒e���Ă��Ȃ��B���p�[�g���[�́A��Ƃ̏ꍇ�A���t�҂̍D�݂��̂��̂�����A���R�́u�e�������Ȃ�����v�ōς݂̘b���낤�B�E�B�[���E�t�B�����o���ł��A�����̃��p�[�g���[��e�������������B20�N�̃^�C���E���O�̐����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�ł͕ʊp�x����B�u�A���Q���b�`�͈Õ������v�Ƃ����\������B������Õ����K�v�ȋ��t�Ȃ̑�Ȃ̃��p�[�g���[�������Ȃ��B�����A�����y�ɃV�t�g���Ă���̂͂��̂��߂��Ƃ��B�Ƃ͂����A��N5��12���A���ˌ|�p����Œ������A���V�����w���F���ˎ����nj��y�c�Ƃ̃x�[�g�[���F���F�s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ͈Õ��������B�E�B�[���E�t�B���Ƃ̏������Ȃ̃��X�g�F�s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ��̂������݂̊y�ȁB���_�Õ��Œe�������낤�B��������^�C���E���O�̐����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�l�C�Ȃ̃��p�[�g���[�̏��Ȃ����A�Õ��̕s������A�^�C���E���O�̐ϋɓI�ȗ��R�ƌ��т��Ȃ������B�c�O�����y���f�B���O�ɂ��邵���Ȃ��B�u���Ȃ�ɒT���Ă݂悤�v�ȂǂƑ匩�h������ɂ��Ă͏�Ȃ��b�ł���B���̃����������́A�ޏ��ɐ��i�𑣂����ƂŐ��炻�����I�H�u�A���Q���b�`����A����ƃE�B�[���E�t�B���Ƌ������Ă��ꂽ�̂�����A���㏭�����ł������烌�p�[�g���[�𑝂₵�Ă����Ă��������ȁB���ˌ|�p����̃A���R�[���Œe�����V���[�}���u����v���V���I�����������������ɁA���߂ă��[�c�@���g��23��K488�̑�2�y�́u�V�`���A�[�m�v�����ł��������Ă����������������܂��v�B�I�V�}�C�B
(2)���w�̒���� ABC�\�z�u�ؖ��v�`����]�������_���f�ڂ�
�@����͒����V����N12��17���̌��o���ł���B���͐��w����̋��ŁA���Z�`��w��ʂ��ċɒ[�ɐ��т����������B�Ƃ��낪�ߔN�}�ɐ��w���D���ɂȂ����B����͉��������肪������悤�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B�������N���Ă����̂��B�ʔ����Ɗ�����悤�ɂȂ����̂��B�L�b�J�P�́u���m�̈����������v�B����m�q�̏������������剉�̉f����B�u�]�Ă̔w�ԍ�24�͂S�̊K��v�u220��284�͗F�����v�u�I�C���[�̓���ei�� + 1 = 0 �Ȃ�Ɣ��������̌`�v�Ȃǂ̑䎌�����ɐV�N�ɋ������̂ł���B
 �@���ꂩ��Ƃ������́A���w�֘A�̕�f���TV���W�ԑg�Ȃlj�����ʂ܂܋����{�ʂŋ����Ă����B�f��u�O�b�h�E�E�B���E�n���e�B���O�v�i1997�āj�̒��Ɂu����Ȓ藝�͌����Ȃ̂悤�ɃG���e�B�b�N���v�Ȃ�đ䎌������ƁA��R���ꂵ���Ȃ��Ă��܂��B������ƃL�U�����Lj����Ȃ��B�G���e�B�b�N�Ƃ����Ȃ�}�[���[�����肩�B�����`�e�����m�[�u���Ȃ烂�[�c�@���g�Ńt�@���^�X�e�B�b�N�Ȃ�x�����I�[�Y���ȁA�ȂǂƏ���ɑz�����Ċy����ł���B
�@���ꂩ��Ƃ������́A���w�֘A�̕�f���TV���W�ԑg�Ȃlj�����ʂ܂܋����{�ʂŋ����Ă����B�f��u�O�b�h�E�E�B���E�n���e�B���O�v�i1997�āj�̒��Ɂu����Ȓ藝�͌����Ȃ̂悤�ɃG���e�B�b�N���v�Ȃ�đ䎌������ƁA��R���ꂵ���Ȃ��Ă��܂��B������ƃL�U�����Lj����Ȃ��B�G���e�B�b�N�Ƃ����Ȃ�}�[���[�����肩�B�����`�e�����m�[�u���Ȃ烂�[�c�@���g�Ńt�@���^�X�e�B�b�N�Ȃ�x�����I�[�Y���ȁA�ȂǂƏ���ɑz�����Ċy����ł���B�@�u�|�A���J���\�z�v��1904�N�Ƀt�����X�̐��w�҃A�����E�|�A���J���i1854�|1912�j���������u�P�A����3�������l�̂�3�������ʂƓ������v�Ƃ������́B�u�P�A����3�������l�́v�Ƃ����F����R�Ŋ����Ĉ���������ʂƓ����悤�ɂǂ��ɂ����������炸�Ɏ茳�ɖ߂��Ă���B���ꂪ�ؖ������ΉF���̌`���𖾂����B����ȁA�ƂĂ��Ȃ��s��ȗ\�z�ł���B������A2006�N�A���V�A�̐��w�҃O���S���[�E�y�����}���i1966�|�j���ؖ������B�ނ́A�ؖ���A�܋����t�B�[���Y�܂����ۂ����܂p�������Ă��܂����B
�@�|�A���J���\�z�͏ؖ���100�N��v�������A300�N���₵���̂��u�t�F���}�[�̍ŏI�藝�v�ł���B����́A�t�����X�̐��w�҃s�G�[���E�h�E�t�F���}�[(1607�|1665)���������u3�ȏ�̎��R��n �ɂ��āAxn + yn = zn �ƂȂ鎩�R���̑g (x, y, z) �͑��݂��Ȃ��v�Ƃ����藝�B�C�M���X�̐��w�҃A���h�����[�E���C���Y�i1953�|�j���A�J�R�E�u�����_����|����ɏؖ��ɐ����B10�̎��ɕ������������������B1995�N�̂��Ƃ������B
 �@����Ȓ��ŁA��тʂ��ċ�����������ꂽ�̂��u���[�}���\�z�v�ł���B����������2011�N�ɕ��f���ꂽNHK-BS�u�f���̖��͂Ɏ���ꂽ�l�����`���[�}���\�z�������̂́H�v�������B
�@����Ȓ��ŁA��тʂ��ċ�����������ꂽ�̂��u���[�}���\�z�v�ł���B����������2011�N�ɕ��f���ꂽNHK-BS�u�f���̖��͂Ɏ���ꂽ�l�����`���[�}���\�z�������̂́H�v�������B�@�u���[�}���\�z�v�́A�h�C�c�̐��w�҃x�����n���g�E���[�}��(1826�|1866)��1859�N�ɏ������g�f���̕��сh�Ɋւ���\�z�Łu�[�[�^���̔��̂O�_�͂��ׂĈ꒼����ɂ���͂����v�Ƃ������m�B
�@�f���Ƃ�1�Ǝ��g�̐��ȊO�ɖ������� 2�A3�A5�A7�A11�A13�A17�A19�A23�E�E�E�E�E�Ɖ��X�Ƒ������̐����B���鎞�͈�u���ďo���������Ǝv���Ύ��͂Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ȃ��A�ȂǁA�_�o�S�v�A�S���������Ȃ��B�u�[�[�^���v�͑f�����Ő��藧��������A���ꂪ���O���t��������̖@�����������Ȃ�A�ꌩ���̖������Ȃ��f���̕��тɖ@���������o���邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�u���[�}���\�z�v�̉��ł���B
 �@���[�}���\�z�̏ؖ��ɁA���w�҂̝g���͖��X�Ƒ����Ă������A150�N�ԏؖ�����Ȃ��܂܍����Ɏ����Ă���B�Ⴆ�A�f��u�C�~�e�[�V�����E�Q�[���v�i2014�N�āj�ŕ`���ꂽ�C�M���X�̐��w�҃A�����E�`���[�����O�i1912�|1954�j�́A�i�`�X�̈Í��@�G�j�O�}�̉�ǂɂ͐����������̂́A���[�}���\�z�ɂ͎��s�A���E�����B���̑��A�W�����E�i�b�V���A�S�b�h�t���C�E�n�[�f�B�[�ƃW�����E���g���E�b�h�ȂǁA�V�˂ƌĂꂽ�����̐��w�҂���������ɗ����������A���_�ُ���������ȂǁA���Ƃ��Ƃ��s�ꋎ���Ă����B�j��ő�̓��Ƃ�����R���ł���B
�@���[�}���\�z�̏ؖ��ɁA���w�҂̝g���͖��X�Ƒ����Ă������A150�N�ԏؖ�����Ȃ��܂܍����Ɏ����Ă���B�Ⴆ�A�f��u�C�~�e�[�V�����E�Q�[���v�i2014�N�āj�ŕ`���ꂽ�C�M���X�̐��w�҃A�����E�`���[�����O�i1912�|1954�j�́A�i�`�X�̈Í��@�G�j�O�}�̉�ǂɂ͐����������̂́A���[�}���\�z�ɂ͎��s�A���E�����B���̑��A�W�����E�i�b�V���A�S�b�h�t���C�E�n�[�f�B�[�ƃW�����E���g���E�b�h�ȂǁA�V�˂ƌĂꂽ�����̐��w�҂���������ɗ����������A���_�ُ���������ȂǁA���Ƃ��Ƃ��s�ꋎ���Ă����B�j��ő�̓��Ƃ�����R���ł���B�@�g���[�}���\�z�ɗ����������͎̂��E�s�ׁh�Ƃ���ꂽ20���I���o�āA�ߔN�A���̕���Ƃ̊֘A����V���ȓ����������Ă����B�q���[�E�����S�����[���m�ƃt���[�}���E�_�C�\�����m�̏o��ɂ��ʎq�����w�Ƃ̘A���B�A�����E�R���k���m�ɂ�����w����̃A�v���[�`�B�ȂǂȂǁA�����̗��ꂩ��u����w���g���đf���̈Í���������Ƃ��X�����ۂ��������g�����̗��_Theory of Everything�h����������v�Ƃ̌��_��������Ă�����B�u���[�}���\�z�v�̏ؖ��������̓���𖾂���`�Ȃ�ăt�@���^�X�e�B�b�N�Șb���낤�I �ʂ����Ă���ȓ�������ė���̂��H ���������Ă���Ԃɏo�����A����͍ō��ɃG�L�T�C�e�B���O�ȏu�ԂɂȂ邾�낤�B
�@�b�����ɖ߂����B��N12�������V���̋L����
���N�ɂ킽���Đ��E���̌����҂�Y�܂��Ă������w�̒����uABC�\�z�v���ؖ������Ƃ���_�����A���ۓI�Ȑ��w�̐�厏�Ɍf�ڂ���錩�ʂ��ɂȂ����B���M�҂͋��s��w������͌��������]���V�ꋳ���i48�j�B�����I�̐��w�j��A�ő�̋ƐтƂ���A�_�����f�ڂ���邱�ƂŁA���̓��e�̐������������ɔF�߂��邱�ƂɂȂ�B�@����̓U�N���Ƃ�����
1�ȊO�ɓ����������Ȃ����̐���A�AB��A�{B��C�̎��AABC�̑f�����̐ς̎���͕K��C�����傫���Ȃ��@�Ƃ������̂ŁA����͌���������Ȃ��Ă��A���̊ȗ������ꂽ�����͈ꉞ�����ł���B�����Ȃ�Ƃ����������Ȃ��ĉ������悤�ȋC�ɂȂ�B�܂��A�]�������Ƃ������{�l���������Ƃ����̂��g�߂Ɋ�����B�������A�ނ�48�B���w�̃m�[�x���܂Ƃ�����t�B�[���Y�܂́g���i��40�Έȉ��h�Ƃ����N����������āA��܂ł��Ȃ��������B
�@�ȂǂȂǁA�u���m�̈����������v�����������ɁA���w���e�[�}�ɂ����l�X�ȕ���ɏo����B�[�������͂ł��Ȃ��Ƃ��A�����̔������A�i������l�Ԃ̎��O�ȂǂɃ��}���������邱�Ƃ͂ł���B���ꂪ�y�����B�f��u���m�̈����������v�̃��X�g�E�V�[���Ɂu�Ă̂Ђ�ɖ������悹 �ЂƎ��̂����ɉi����������v�Ƃ����E�B���A���E�u���C�N�̎�������邪�A�܂��ɂ��ꂱ�����l�ԂƂ������̂̓����ł��胍�}���Ȃ̂ł͂���܂����BAI�������甭�B���Ă����̊��o�͐l�Ԃɂ��������Ȃ����̂��Ǝv���Ă���B
2017.12.10 (��) �ꋴ��w�I�[�P�X�g��47�N�Ԃ�̓�����
�@�u�@����X��v12�����u���D����v�ɁA�����������u�ꋴ��w�nj��y�c43��������v�Ȃ郌�|�[�g���f�ڂ��ꂽ�B�����o�[�̊������Ղ̍ۂɃ����_���ɉ���Ă͂������̂́A�u������v�̌`�ňꓰ�ɉ��̂�1970�N�ȗ��ƂȂ�B����s����u���O�������v�Ƌ��������̂����A�K��Ŏ~�ނȂ��Ƃ͂������������������A�����e����͂قlj����P�Ȃ郌�|�[�g�ɊÂ���Ȃ������B����ł͂��~���s���ɂ��A�ڍׂ����������Ȃ����B�܂��͂��̌����e����B�ꋴ��w�nj��y�c43�� ������
 �@���EXPO70 �u���[���X�u�h�C�c�E���N�C�G���v���t��ł̓�����ȗ�47�N�Ԃ�A�������E�{��h�Y�N�̎w���ɂ��T���g���[�z�[���u�u���[���X�̗[�ׁv��L�u�Ŋӏ܂�����10��3���A�u���V�g�v���֓X��9����������낦���B
�@���EXPO70 �u���[���X�u�h�C�c�E���N�C�G���v���t��ł̓�����ȗ�47�N�Ԃ�A�������E�{��h�Y�N�̎w���ɂ��T���g���[�z�[���u�u���[���X�̗[�ׁv��L�u�Ŋӏ܂�����10��3���A�u���V�g�v���֓X��9����������낦���B�@�u�}�G�X�g���A�w�̕\��▭��������v�u�\���E���@�C�I�����̃p�E���N�͐����˔\���v�ȂǁA�ЂƂ�����O���̃R���T�[�g�k�`���������Ƃ́A�����o�[���Q�̓����̃A���o����v���O���������Ȃ���̉�ڂƋߋ��ɘb���s�������B�u�ʐ^�A�������ɂ݂�ȎႢ���v�u�����W�C�T���i��C�w���҂̈��́j�Ɂw�u��1�x��肽���Ɛ\���o�����A�Ȃ��Ȃ�OK����Ȃ�������ȁv�u���̉��ACD�����Ē��������A����ς�q�h�������v�u���O�̉��h�͂܂�Ő����v�u�w���ՂŃ`�P�b�g���Ă��ꂽ�̂����̉Ɠ��v�u�w���ɂ��Ă��������Ƃ��v�u�ȂƃR���T�[�g�O���̓��X�v�u�w���I�Ɖ����x�͓ǂނׂ��v�ȂǂȂǁA�lj��x�y�̂ЂƎ��������B
�@������@�ɁA����~�ޖ������Ȃ̖쑺���N�Ə������N��������11���ŁA�����āA�������Ă��܂����H��m�N�Ɨ�ؗ�j�N�ƎR�c�L�N�̒Ǔ������ɁA���ꂩ��͊u�N���炢�ɏW�܂낤�A�Ƃ̎v�����V���ɎU����B�i�Q���ҁj���c�쎡�A�c�����p�A�Җ{�v�A�n��M�O�A���c���O�A�ێR�O���A�{���ܕS���A�{��h�Y�A�����W�i���Ӂj
�@�ȏオ�����e�ł���B����Ȃ�܂��܂���̕��͋C���͂߂悤���A�{�`�����̎����͂���6�����x���������疳���Ȃ���̂ƂȂ��Ă��܂����킯���B�ł́A�C�����V���ɍX�Ȃ閡�t�������݂����B
(1) �{��h�Y �w���҃f�r���[20���N�L�O�R���T�[�g�g�u���[���X�̗[�ׁh
�@�w���ҁE�{��h�Y�B�ꋴ��I�P����̓I�[�{�G�t�ҁB���ӋZ�͋}(Allegro)������(Adagio)�B1966�N3�N���̒�����t��̃x�[�g�[���F���̌����ȑ�3�ԁu�p�Y�v��2�y�́u�����s�i�ȁv�́A�[�݂̂���������爣�D���N���o���i�̃p�t�H�[�}���X�������B�������獂�����y�������ݏo�Ă����B
�@����Ȕނ��A1995�N�A�\�H���}���Ĉ�O���N�B�v���w���҂ւ̓�����ݎn�߂�B�����āA������2�N���1997�N�A��1��̉��t����J���B���̌�A���C�����E�t�B���A�T���N�g�y�e���u���N���A�X���o�L�A�E�t�B���A�����t�B���ȂLjꗬ�I�P���w���A�E�B�[���w�F�����z�[����T���g���[�z�[���A�h���H���U�[�N�E�z�[���Ȃǐ��E�̞w����ʼn��t�A�B�X����L�����A��ςB�����āA�{�N10��2���A�T���g���[�z�[���ŁA�f�r���[20���N�L�O�R���T�[�g�g�u���[���X�̗[�ׁh���J�ÁB�I�P�͓����j���[�V�e�B�nj��y�c�B����ɍ��킹�āA��炪�I�P�̓�����J�Ẩ^�тƂȂ����킯�ł���B
 �@�D�u���Ⴝ��u��w�j�T���ȁv���I���ƁA�p�E���E�N���v�t�B�b�`���N���o��B�ނ͋{��N���R���ψ��߂�u�u���[���X���ۃR���N�[���v���@�C�I��������2017�N�̗D���ҁB�E�B�[���o�g�̎㊥17�B���Ȓ��̖��ȁu�u���[���X�F���@�C�I�������t�� �j�����v������Ȏ�҂����v�����ȁE�E�E�E�E�Ƃ̕s���́A�\�����n�܂��đ��A�X�J�ɏI������B�ǂ��炩�Ƃ����Ήs���ׂ߂̉��Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��������y�̍\�����̂��̂��ƂĂ��Ȃ��傫���̂��B�u���[���X���L�̏�M������ɔ�߂����}���e�B�V�Y���̕\�o�I ��D���ȃN���X�`�����E�t�F���X�i1933�|1982�j��f�i�Ƃ������B�����̕����P�j��(���{�A�[�g�E�Z���^�[�В�)���u���͂▼��̈�I�v�ƐV���ȍ˔\�Ƃ̏o��Ɋ��Q������B�A��̃r�[���������������B
�@�D�u���Ⴝ��u��w�j�T���ȁv���I���ƁA�p�E���E�N���v�t�B�b�`���N���o��B�ނ͋{��N���R���ψ��߂�u�u���[���X���ۃR���N�[���v���@�C�I��������2017�N�̗D���ҁB�E�B�[���o�g�̎㊥17�B���Ȓ��̖��ȁu�u���[���X�F���@�C�I�������t�� �j�����v������Ȏ�҂����v�����ȁE�E�E�E�E�Ƃ̕s���́A�\�����n�܂��đ��A�X�J�ɏI������B�ǂ��炩�Ƃ����Ήs���ׂ߂̉��Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��������y�̍\�����̂��̂��ƂĂ��Ȃ��傫���̂��B�u���[���X���L�̏�M������ɔ�߂����}���e�B�V�Y���̕\�o�I ��D���ȃN���X�`�����E�t�F���X�i1933�|1982�j��f�i�Ƃ������B�����̕����P�j��(���{�A�[�g�E�Z���^�[�В�)���u���͂▼��̈�I�v�ƐV���ȍ˔\�Ƃ̏o��Ɋ��Q������B�A��̃r�[���������������B�@�����A�{��N�ɕ������Ƃ���A��l�Ƃ��A�育�����\���̉��t�ɖ钆��2���܂Ő���オ��A���̓x�[�g�[���F�����V�x���E�X���H �܂Řb���L�������Ƃ��B���������琥���Ă݂����B�ǂ��炩�Ȃ�A�t�F���X�̖���������V�x���E�X�̂ق����ȁH
�@�g�u���[���X�̗[�ׁh�̍Ō���������̂́u�����ȑ�1�ԁv�B�v���O�����̒��ŁA�{��N�́u�u���[���X�͎��̈�ԍD���ȍ�ȉƁv�ƌ������Ă���B�E�s�ŏ�M�I�B�����ȉ��t�������B���̋Ȃ͂܂��A1967�N�A��X�I�P�Ō�̒�����t��̃��C�����ڂł��������B�����̓c�����p�N���I�t�@�[�����Ƃ���A��C�w���ҁE�������g�W�C�T���Ɂu���O��ɂ͂܂������B�������v�ƁA�Ȃ��Ȃ�OK��Ⴆ�Ȃ������Ƃ��B���̈ꌏ�A����̓�����ŏ��߂Ēm�������A�͂Ă��āA���̓��̋{��N�̉��t��V���̃W�C�T���͂Ȃ�ƕ]���邾�낤���B
(2) ��C�w���Ҕ����g�W�C�T���h���g����̂���
 �@�ꋴ��I�P�̏�C�w���҂͔������g�搶�i1899�|1981�j�B���́g�W�C�T���h�BN���̑O�g�V�����y�c�̑n�������o�[�̈�l�ŁA�p�[�g�͑�2���@�C�I�����B�u�{�����������N���V�b�N�v�Ƃ���CD�u�b�N�̒��ɁA�������`�F�����K���ɐV����K��錏�����邪�A���̃����o�[�\�ɂ͊m���ɔ������g�̖��O������B�����O�q�̕��E��j���⏬�V�����̎t���E�ē��G�Y�̖���������B�W�C�T���͂Ȃ��Ȃ��債�����y�l�������̂��B
�@�ꋴ��I�P�̏�C�w���҂͔������g�搶�i1899�|1981�j�B���́g�W�C�T���h�BN���̑O�g�V�����y�c�̑n�������o�[�̈�l�ŁA�p�[�g�͑�2���@�C�I�����B�u�{�����������N���V�b�N�v�Ƃ���CD�u�b�N�̒��ɁA�������`�F�����K���ɐV����K��錏�����邪�A���̃����o�[�\�ɂ͊m���ɔ������g�̖��O������B�����O�q�̕��E��j���⏬�V�����̎t���E�ē��G�Y�̖���������B�W�C�T���͂Ȃ��Ȃ��債�����y�l�������̂��B�@�u�ꋿ�v�Ƃ����ꋴ��w�nj��y�c�̓��l�������邪�A����2017�N7�����ɁA2�N��y�̍���������e�́u�����W�C�T���̐V�����y�c�w���x���t���s�L�v�Ȃ郋�|���f�ڂ��ꂽ�B���s���Ԃ�1938�N4��1���|5���B���s�L�͐V���̋@�֎��u�t�B���n�[���j�[�v�Ɍf�ڂ���A3����4���������搶�̒S���������B������ꕔ��������B
�@���a13�N4��3���A�ڂ̊o�߂��Ƃ��ɂ́u���������ȱ�v�Ǝv�������A�r���v�͍ő�6������������ċ���B�����͖��É��s���ߌ������߂̈��闷�ق��B������ߑO8�����É����̋D�Ԃɏ�荞�܂Ȃ���Όߌ�2�����ɉ�������K�ɊԂɍ���ʂƉ]���̂�����A��������Q�V�����ċ�����B�����͍��x�̗��s���̍ŋ��s�R�̓��ŁA��X�Ƃ��Ă͖w�Ǘ�̂Ȃ�6���Ɖ]�����N�������A8������12���߂��܂Ŗ�4���ԋD�Ԃɗh���A�ߌ�2�������2���Ԃ̗��K�����A7�����牉�t�����낤�Ɖ]���B�������ő����s3���ڂŊF�啪�O���b�L�[�ɂȂ��Ă���ゾ���瑊���Ȃ��̂��B�@���������̒��A��X�̎���ŏI���������1�鉉�t��B�I�P�}���̊�т��`����Ă���B�����̂��ς��Ȃ��Ȃ��Ǝv���B�����������A���͐펞�^�������B���t���s�̏���4��1���ɂ́A���̍��Ƒ������@�����z����Ă���B����Ȏ���̃��|�͎��ɋM�d�ȋL�^�ł���B���t�Ȗڂ���
�@���ӂ̃v���O�����́A��́A�É��E���É��ł�������Ńx�[�g�[���F���̑�8�����Ȃ�������Ȃ̂ŁA���K�͈ĊO��������I���ڎZ�ŋ�����A�����떼�É��̉��t���т����܂�F�����Ȃ������̂ŁA���[�[���V���g�b�N�搶�ɑ������悭�����i��ꂽ�B
�@�]�O�̗��s�ɂ͑�̊��ɉ����Ă͋��s�Ɉ��A���ɓ��ƂȂ��Ă���A���x���߂ċ��s�̉��t�����~�߂āA���ɎO�ӊJ�Â��鎖�ɂ����̂ŁA�ʂ����ĎO�Ӓ�����ّ�z�[�����A�t�@���Ŗ��ߐs�������邩�A�Ɖ]�ӏ��Ȃ���ʋ^�O����X�����҂̊ԂɎ�����Ă�B�R��ɁA���������J���Č���Ƃǂ����A��X�̌��O�́A���\�A�P�Ȃ�X�J�ɉ߂��Ȃ���������������A�������̑�ϏO���M���I���āH���Ȃĉ䂪�V�����}���Ă��ꂽ���A���͎v�킸�ړ��̔M���Ȃ�̂��o�����B���b�V�B�j�̏��ȁu�Z���B���̗����t�v�Ɏn�܂�A�Ō�̃x�[�g�[���F���́u��8�����ȁv�Ɏ���܂ő��l��ْ����ɑf���炵���o���h���ʼn��t���I������B�ʂẮA�A���R�[���̃u���[���X�̃n���K���A���_���X�v��5�Ԃ܂ł��B
��ƁA����3��Ɂu�u��1�v������B����������̈������B
�@�I�P����A���K�ʼn����O�����тɃW�C�T�������ɂ܂ꂽ���̂��B�������ɂ݁B�R���b�I �ł�����ȋْ����A�����Ȃ������B�l���_���[���Ƃ��Ă���܂�Ȃ��B
�@�������ăW�C�T���̑��Ղ���ڂ���ɂ��A�����l�̌O�����Ă����Ȃ��ƁA���X�Ȃ���v���B���̓`���̖��w���ҁE���[�[�t�E���[�[���V���g�b�N�i1895�|1985�j�̉��ʼn��t���Ă����Ȃ�āI ����ȃW�C�T�������炱���A�s�A�m�̈�������q(1922�|1996)�A���@�C�I�����̒ҋv�q�i1926�|�j�ȂǁA�{���w���I�P�ł͍l�����Ȃ��悤�ȏd�����������Ă��ꂽ�̂��B�����W�C�T�� �f�G�Ȏv���o�����肪�Ƃ��I
(3) Orchestra's 11
�@10��3���A�u���V�g�v���֓X�B47�N�U��̃I�P������ł���B�쑺���i�e�B���p�j�[�j���������i�g�����y�b�g�j���d�����̓s���Ō��ȁB�W�܂����̂�9���B�����o�[������������A���o���ƃv���O�����Ȃǂ����Ȃ���̘̐b���猻���܂ŁA�b�͐s���Ȃ������B
 �@�������c�����p�i�r�I���j�͌��̋��̉F���ɏZ�ށB2013�N�ɁA�Ƃ̑�����I�P����̃I�[�v�����[���E�e�[�v��������CD���B������l�^�Ɏ����u�@����X��v(2014�N1����)�Ɓu�N�����m�v�i2013�N9��15���j�Ɍo�܂Ǝv���o�b���������B���̈�A�̗�������x�͓c�����u�ꋿ�v�i2014�N4�����j�ɏ����Ă���B�O���̃R���T�[�g�ł�P�Ȃɐw���A�{��̎w���Ԃ��^���ʂ�����O�Ɍ��Ă����B�u�w�̕\��▭��������v�͔ނ̔����B�����W�C�T���Ɖ��ڂ����c����̂��ނƕ������̎d���������B
�@�������c�����p�i�r�I���j�͌��̋��̉F���ɏZ�ށB2013�N�ɁA�Ƃ̑�����I�P����̃I�[�v�����[���E�e�[�v��������CD���B������l�^�Ɏ����u�@����X��v(2014�N1����)�Ɓu�N�����m�v�i2013�N9��15���j�Ɍo�܂Ǝv���o�b���������B���̈�A�̗�������x�͓c�����u�ꋿ�v�i2014�N4�����j�ɏ����Ă���B�O���̃R���T�[�g�ł�P�Ȃɐw���A�{��̎w���Ԃ��^���ʂ�����O�Ɍ��Ă����B�u�w�̕\��▭��������v�͔ނ̔����B�����W�C�T���Ɖ��ڂ����c����̂��ނƕ������̎d���������B�@���������n��M�O�i�z�����j�B1�N���̂Ƃ��A������t��̃`�P�b�g��ɍ�������̊w���Ղɏo�������B�Ȃ��Ȃ�����Ȃ����A�B�ꔃ���Ă��ꂽ���吶�������B���ꂪ�ނ̉��l�ł���B���^�ʖڂȔn��Ȃ�ł͂̃G�s�\�[�h���B���ݓ��a���n�r�������撣���ďo�Ă��Ă��ꂽ�B�A�H�������ŁA�Ȃ�ƂȂ����c�ɂ����������̂�����A�����w�ň��݂Ȃ����Đ̘b�̑����������B
�@�{��h�Y�̎w��������������B�ɓ������v�̈ꋴ��w�����u���ɂ����āA�����V���t�H�j�J�\�𗦂��Ă̒�����t��N�J�Â��Ă���B2010�N�ȗ�13��𐔂��A��w�ƒn��Z���̊F�l�Ƃ̌𗬂Ɉ���Ă���B
�@�Җ{�v�i�t���[�g�j�̓I�P����̖���B���t���[�e�B�X�g�у����q�i1926�|1974�j�̒�q�B2�N���Ƃ��A�Óc�m��w�A���T���u���E�t�B�I���[�^�Ƃ̍������t��ŁA�ނ̃\����J.S.�o�b�n�́u�nj��y�g�� ��2�ԁv�����t�������Ƃ�����B����͂����v�����̃p�t�H�[�}���X�������B���̌�����(1975�N)�ł́A���̒�����u�|���l�[�Y�v�Ɠ��{�̋ȁu���҂����v���I���Ă��ꂽ�B���̓��A���̂��Ƃ�b������A�Ȗڂ͖Y��Ă����B�ނقǂ̖���͉��t�̏ꂪ���X���������낤����A����͂܂��~�ނ����܂��B���c�쎡�i�g�����{�[���j�͊w�Ҕ��B������[���Â��Ɏv������^�C�v���B�����������E�̎��Ɠ������h�̏Z�l�������B�����͂������I�P�̘A���̂��܂��ƂȂ��āA���X�Ȃ閃���Ə��X�̎������ɐ����o�������̂��B�����ɂ悭�����ێR�O���i�`�F���j�́A���̑c�ꂪ��������ɂ��肪�Y����Ȃ��A���Ȃ�Ƃ������A�����Ȃ̂ɍ�������Ƃ͂��肪�������肾�����ƌ��B�ނ̌������ŁA�����Ǝ��Ł�u�䂪�ǂ��F��v���̂����̂����������v���o���B���c���O�i�g�����y�b�g�j�͏_�a�Ȑa�m�B�ŋ߁A���l�ƃR���T�[�g�ɂ悭�o������Ƃ����B�I�P�̓������v���̎w���҂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�M���Ȃ����l�ւ̏ؖ��̂��߁A�O�������Ȃ������ނɁA���̓��̃v���O������n�����B�{���ܕS���i�t���[�g�j�͍���̐��b�l�B�{���Ȃ�A4�N�O�A�c���Ƙb�������������˂����Ȃ������̂����E�E�E�E�E�B�R���N�[���̐R�����ł�����{��Ɂu�w���I�Ɖ����x��ǂނׂ��v�Ɗ��߂��̂͂��̒j�B���ɂ��A�u�@����X��v�ւ̌f�ڂɊւ��ėl�X�A�h���@�C�X�����ꂽ�B���݂ɔނ̌Z�̋{���痢���́A�\�j�[�̑n�n�ҁE��[�厁�̔鑠���q�B���̃g���j�g�����̎����I�����҂��B�`�F����n�݁A�w�������N���A�C�O�̊��G�V�̎w���̉��Ŋ����A�Љ�l�ɂȂ��Ă���́A��炪2�N��y�̓��i�������i�z�����j�Ƌ��ɓ�������y�c�Ŋ��ꂽ�������B�����āA�������W�i�g�����y�b�g�j�́A���ʑ�ɋ��n�V����u���s�ސT�ȃI�P�}���������B����Ȏ��ɃN���V�b�N���y�̖ʔ����������Ă��ꂽ�͓̂����̘A���ł���B��N���������Ėl�������B��N��ɂ܂���܂��傤�B
2017.11.16 (��) �J�Y�I�E�C�V�O������FM���ǂ���20���N�A�����āA���߂łƂ��ޗǂ���I
�@FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v�ŐS�����Ă��邱�ƁB����͉��y�̊O�����甭�z����A�Ƃ������ƁB���X�i�[�́A�N���V�b�N���y���D���Ȑl�������Ȑl���A�S����l���Ȃ��l���A�l�X���B�����特�y���������ƊԌ������܂��Ă��܂��B�@���߂�10���́A�Ǐ����X�|�[�c�̏H���甭�z���A����t�������i�[�`�F�N�u�V���t�H�j�G�b�^�v�Ɍ��т����B�u�V���t�H�j�G�b�^�v���X�|�[�c�Ղ̂��߂ɏ����ꂽ���y�ŁA����̏����u1Q84�v�ɏd�v�ȏ�����Ƃ��ēo�ꂷ�邩��ł���B�������߂Ă�������10��5����A�m�[�x�����w�܂̓J�Y�I�E�C�V�O���ɁA�Ƃ̕���э���ł����B�u�̑�Ȋ���̗͂��������ŁA�����̐��E�Ƃ̂Ȃ���̊��o���A�s�m���Ȃ��̂ł����Ȃ��Ƃ�����m��Ȃ����𖾂炩�ɂ����v�����ܗ��R�B�Ȃ�����ł͂Ȃ��C�V�O���������̂��H ����ɂ��Ă͊m�ł��鎝�_�����邪�A�܂��̋@��ɁB
 �@�J�Y�I�E�C�V�O���̍�i�ׂĂ݂���A�u��z�ȏW�v�Ƃ����̂��������B�^�C�g������u���N���v�ƌ��ѕt���������B�Ȃ�R�b�`�ɐ�ւ��邩�B�z�b�g�Șb�肪�����Ɍ��܂��Ă���B���N��2���͒��؏�܍�u���I�Ɖ����v������čD�]����������������B�����u��z�ȏW�v�����߂ď��X�ɑ��邪�ɂ͍ő��J���B�������Amazon�ɔ���������A�͂����Ƃ��͕��������߂��Ă����B300�łقǂ̕��ɖ{��5�̒Z�҂����璷�����育��B�^�C�g���ʂ�S�щ��y�֘A�̘b�B�����ɂ͊Ԃɍ���Ȃ���������ǁA�ʔ����ǂނ��Ƃ��ł����B
�@�J�Y�I�E�C�V�O���̍�i�ׂĂ݂���A�u��z�ȏW�v�Ƃ����̂��������B�^�C�g������u���N���v�ƌ��ѕt���������B�Ȃ�R�b�`�ɐ�ւ��邩�B�z�b�g�Șb�肪�����Ɍ��܂��Ă���B���N��2���͒��؏�܍�u���I�Ɖ����v������čD�]����������������B�����u��z�ȏW�v�����߂ď��X�ɑ��邪�ɂ͍ő��J���B�������Amazon�ɔ���������A�͂����Ƃ��͕��������߂��Ă����B300�łقǂ̕��ɖ{��5�̒Z�҂����璷�����育��B�^�C�g���ʂ�S�щ��y�֘A�̘b�B�����ɂ͊Ԃɍ���Ȃ���������ǁA�ʔ����ǂނ��Ƃ��ł����B��1�сF�V�̎�
�@����̓��F�l�`�A�B���������߂Ă���N�V�������W���Y�E�V���K�[���A�J�t�F���̃|�[�����h�l�M�^���X�g�ɔ��t���˗��B�^�͂ɕ����ԃS���h������Ȃ�����z�e���̑��Ɍ������Ō�̃��b�Z�[�W���̂��B���ӂɌ���Ȃ������Ȃ̔����Ȃ����苃�����������郉�X�g�͊������́B�v�w�̏���������▭�Ȍ����B�����Ɍ����������ȃe���|���B�V�̎�̐l�����炳�肰�Ȃ����ݏo�鉜�`�B����邵���Ȃ��^���̙R���B�l�X�Ȋ���������A�[���Â��ɉ₩�ɁA���F�l�`�A�̉^�̗͂���ɗn������ł䂭�B5�ђ��̍ō��삾�B
��u���̓t�F�j�b�N�X�v�u������ۂ����v�u�����E�t�H�[�E�}�C�E�x�C�r�[�vetc
��2�сF�~���Ă�����Ă�
�@�w�����㋤�ʂ̗F�l�������j���������B���̕v���猻�݂̕v�w�����̊�@���~���Ă���ƈ˗����ꂽ�j�Ɣނ̍ȂƂ̊ԂɋN�����Ȃ��b�B����̓����h���B�u���o�[�}���v�̓r���[�E�z���f�C�ƃT���E���H�[���̂ǂ��炪�����H�Ȃǂ̖₢������A���X�g�ŗx��T���E���H�[�����N���t�H�[�h�E�u���E���́u�p���̎l���v��8���ԑ����A�Ƃ��銨�Ⴂ�i���ۂ�6��19�b�j�ȂǁA�����[���B
��u���o�[�}���v�u�p���̎l���v�u�r�M���E�U�E�r�M���vetc
��3�сF���[���o���q���Y
�@�C�M���X�l�\���O���C�^�[���A�Ă̊ԉ̍��̂��ߖK��Ă���o�v�w�̃J�t�F�ŁA�d���ɂ��v�w�����ɂ��s���l���Ă���X�C�X�l�̒��N�~���[�W�V�����v�w�Əo��B���[���o���̔��������R�Ɉ͂܂�āA�݂��̉��y���A�l�����A���������B�ݒ肳�ꂽ���䂪�G���K�[�̐��a�n�ɋ߂��A�Ȃ��Ȃ��Ɋy���߂��B
��u�_���V���O�E�N�C�[���v�A�G���K�[�A���H�[���E�E�C���A���Y�A���i�[�`�F�Netc
��4�сF��z��
�@�ʑ��̈������琮�`��p�����s�A�p��̃��n�r���Ńz�e���ɑ؍݂��邱�ƂɂȂ����r�B�҂̃W���Y�E�T�b�N�X�����Ɠ��������ŗו����̏Z�l�ƂȂ��Ă���Z���u�L���l�i��1�сu�V�̎�v�̍ȂƓ���l���j�Ƃ����A�炪��т��邮�銪���̓�l���A�n���E�b�h�̍����z�e����ɌJ��L���邿����Ɩ��C���ȃR���f�B�[�B������Bang
&Olufsen�i�f���}�[�N�̂������ȃR���|�j���ݒu����Ă���Ƃ͂Ȃ�ƃZ���u�ȃz�e���I
��u�j�A�l�X�E�I�u�E���[�v�A�r���E�G���@���X�A�`�F�b�g�E�x�C�J�[�A�E�F�C���E�V���[�^�[etc
��5�сF�`�F���X�g
�@����́A�A�h���A�C�ɖʂ�������C�^���A�̓s�s�B7�N�O�A�n���K���[�l�h�T����`�F���N�ƈ���قǔN��̃`�F����e���Ȃ����˔\���������ڂƋ����邱�Ƃɒ����������Ƃ̌𗬂��n�܂�B�ޏ��̓��P�ŐN�͌��錩���B�A�����̃X�^�[�Ɗ��҂������A�����͈ӂɉ���Ȃ��j�ƌ������邱�ƂɁB�N�͍����܂��A�h�T����ɊÂĂ���B
��u���e���F�`�F���E�\�i�^�A���t�}�j�m�t�F�`�F���E�\�i�^
�@���ʂ���ݒ�͕v�w�̊�@�Ȃ̂����A�nj㊴���A�Ȃ�ƂȂ��z�����J�Ƃ��Ă���B�Ȃ����Ǝv������A����̒��ߕ��������B�`�ڂ��ɉ����킩��H �͂����Ĕޏ��͐������̂��낤���H �����킩��Ȃ��E�E�E�E�E�ȂǁA�����Ȃׂăt�����Ƃ����G���f�B���O�Ȃ̂ł���B�u������������������ő�ɂ��Ă��邱�ƁB����͐S���`���邱�ƁB���͂���������A�N�����͂ǂ������邾�낤���B�l�Ԃ͌o�ϊ��������ł͕s�\���A�l�ԂƂ��Ă̊�������������Ƃ��d�v���v�B�������TV�u�J�Y�I�E�C�V�O���̔��M�����v�ł̔������B�ނ͓��������邾���B�����ĉ����t���Ȃ��B�ǂ������邩�͓ǂސl�̎��R�B�������Ă������ꂵ���B�ł����Ă���Ȃ��Ă��\��Ȃ��B������������邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂�����B�z�����J���Ă���̂͂��ꂪ���R���낤�B
�@12��10���̓m�[�x���܂̎����B�J�Y�I�E�C�V�O���̎�܂̕ق��y���݂ł���B
 �@11���́u���N���v�Łu��z�ȏW�v�����グ�悤���ƈ�x�͍l�����B�N���V�b�N�Ȃ����������o�Ă��邵�A���肪�u���y�Ɨ[�����߂���܂̕���v�ŁA�u�[���v�́u�����q�v�́u�H�͗[���v�ɂ��q����B�ł�������Ǝア�B����Ȑ܁A�f�B���N�^�[��Noririn����uFM���ǂ���v���卆�Ȃ�ԑg���q��n�����B�ǂނƁu11��30���͊J��20���N�v�Ƃ̕�������э���ł����B���ꂾ�I �J��20���N�Ɉ����|���āu20�v���L�C���[�h�ɑI�Ȃ��悤�B
�@11���́u���N���v�Łu��z�ȏW�v�����グ�悤���ƈ�x�͍l�����B�N���V�b�N�Ȃ����������o�Ă��邵�A���肪�u���y�Ɨ[�����߂���܂̕���v�ŁA�u�[���v�́u�����q�v�́u�H�͗[���v�ɂ��q����B�ł�������Ǝア�B����Ȑ܁A�f�B���N�^�[��Noririn����uFM���ǂ���v���卆�Ȃ�ԑg���q��n�����B�ǂނƁu11��30���͊J��20���N�v�Ƃ̕�������э���ł����B���ꂾ�I �J��20���N�Ɉ����|���āu20�v���L�C���[�h�ɑI�Ȃ��悤�B�@�܂��́g��20�ԁh�Ɩ��̕t���Ȃ̑�\�Ƃ��āA���[�c�@���g��ȁF�s�A�m���t�� ��20�� �j�Z�� K466 ��I�Ȃ���B�����̓j�Z���Ƃ��������B���[�y�͉͂A�T�Ȃ��獕�����̂悤�Ȕ�����������B�����ɋ��܂���2�y�͕͂σ������B�ΏƓI�ɖ��邭���炬�ɖ������ȑz���B20���N�ɑ���������2�y�͂����͂�����B
 �@���t�̓}���^�E�A���Q���b�`�̃s�A�m�ƃN���E�f�B�I�E�A�o�g�w���F���[�c�@���g�nj��y�c�B�A���Q���b�`�́A���N��5���A���ˌ|�p�قŏ��V�����F���ˎ����nj��y�c�Ńx�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ����B������f���炵�����t���������A�A���R�[���ɒe�����V���[�}���́u����v�������������B���y���V����삯�܂���Ă����B
�@���t�̓}���^�E�A���Q���b�`�̃s�A�m�ƃN���E�f�B�I�E�A�o�g�w���F���[�c�@���g�nj��y�c�B�A���Q���b�`�́A���N��5���A���ˌ|�p�قŏ��V�����F���ˎ����nj��y�c�Ńx�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ����B������f���炵�����t���������A�A���R�[���ɒe�����V���[�}���́u����v�������������B���y���V����삯�܂���Ă����B�@2�Ȗڂ́A���ȉ�20�̂Ƃ��̍�i�����͂�����B20�܂łɂ����Ƃ�����i�������Ă���l�́A�_���^�V�˂ƌĂꂽ�l�����Ɍ�����B�V�˃��[�c�@���g�́A�I�y��������ȁA�s�A�m���t�Ȃ⃔�@�C�I�������t�ȂȂǁA���ɂ�������̖��Ȃ������Ă���B�ނɕ�������炸�����̂̓V���[�x���g�B�u�̋ȉ��v�ƌĂꐶ�U��600�Ȉȏ�̉̋Ȃ�������V���[�x���g�����A20�܂łɂȂ�Ɣ�����300�Ȉȏ������Ă���B
�@�����́A�V���[�x���g20�A1817�N�̍�i�A�̋ȁu�܂��v�����������������B20�̂Ƃ��ɍ�����̋Ȃ́A���̑��Ɂu���Ɖ����v�u���y�Ɋāv�Ȃǂ�����A�L���ȁu�����v��u���v�͂���ȑO10��̍�i�B�ނ̑��n�Ԃ肪����������B
�@���́A�N���X�e�B�A���E�t���[�h���q�E�_�j�G���E�V���[�o���g�i1739�|1791�j�B�����Q�[�e��x�[�g�[���F���́u���v�̍쎍�ҁE�V���[�́A��y�i�ɂ�����h�C�c�̎��l���B
�@�ł́A�V���[�x���g��ȁF�̋ȁu�܂��v���G���[�E�A�������N�̃\�v���m�A���h���t�E�����Z���̃s�A�m�ł����肷��B�G���[�E�A�������N(1933�|)��20���I���\����I�����_�̖��\�v���m�B�����ȉ̐��Ɩ��������ӂ��̏��ŁA�������j���u�܂��v�̊������������p�������ɕ\�����Ă���B
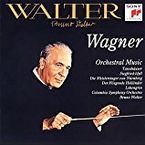 �@�Ō�̈�Ȃ̓n�v�j���O�I�Ȃ��B ����11��25���́u���N���v�p�[�\�i���e�B�[�ޗǒ��q����̒a�����Ȃ̂��B�����͟Ӑg�̋ȃv���[���g�Œ��߂悤�ł͂Ȃ����B�I�̂����[�O�i�[��ȁF�W�[�N�t���[�g�q���ł���B���ꂼ�A�N���V�b�N�̗��j�ɂ����āA���ɁE�ō��̃o�[�X�f�[�E�v���[���g���Ǝv���̂ł���B
�@�Ō�̈�Ȃ̓n�v�j���O�I�Ȃ��B ����11��25���́u���N���v�p�[�\�i���e�B�[�ޗǒ��q����̒a�����Ȃ̂��B�����͟Ӑg�̋ȃv���[���g�Œ��߂悤�ł͂Ȃ����B�I�̂����[�O�i�[��ȁF�W�[�N�t���[�g�q���ł���B���ꂼ�A�N���V�b�N�̗��j�ɂ����āA���ɁE�ō��̃o�[�X�f�[�E�v���[���g���Ǝv���̂ł���B�@���[�O�i�[�͍�ȉƃ��X�g�̖��E�R�W�}�ƌ����B56�̂Ƃ��Җ]�̒j�̎q���a���B���̂Ƃ���Ȓ��̊y���u�W�[�N�t���[�g�v�ɂ��₩���āA�W�[�N�t���[�g�Ɩ��������B�y���̒��Łu�W�[�N�t���[�g�͐��E�̕�v�Ƃ����䎌�����邪�A���������j�̎q�͂܂��Ɂg���[�O�i�[�̕�h�������B����ȁA�������Ă��ꂽ������ւ̊��ӂ̋C���������߂č�����̂��u�W�[�N�t���[�g�q�́v�ł���B
�@1870�N12��25���A�R�W�}�̒a�����̒��A�R�W�}���܂�2�K�̐Q���ŐQ�Ă��鎞�ԂɁA�K�i��15�l�̊y�t��z�u�B�Â��Ɏn�܂������y�͏��X�ɉ��ʂ𑝂��Ă䂭�B�R�W�}�A�����̒��A���y���B�Q�ڂ���Ńh�A���J����ƁA�K���ɒʂ���K�i�ŕv���[�O�i�[���w�����鏬�I�[�P�X�g���������̒a���j���̋Ȃ�t�łĂ���B���̎��̃R�W�}�̊����₢���ɁI���Ή��y�j��̋��l�̃v���[���g�A���Nj��̃X�P�[���ł͂Ȃ����B
�@�Ȃ́A��Ȓ��̊y���u�W�[�N�t���[�g�v�Ȃǂ���A����̓��@���g���č\������Ă���B
�@�u���̕��a�v�̓��@�Ƃ��u���E�̕�v�̓��@�ȂǁA���[�O�i�[���I���@�́A�D��������ɖ��������̂���B�ނ̃W�[�N�t���[�g�ւ̈���ƃR�W�}�ւ̊��ӂ̔O���悭�\��Ă���B�Ƃ������ƂŁA�{���Ō�̓��[�O�i�[�u�W�[�N�t���[�g�q�́v���A�ޗǂ���ւ̂��a�����v���[���g�Ƃ��Ă��͂�����B���t�́A�u���[�m�E�����^�[�w���F�R�����r�A�����y�c�B
�@�u���[�m�E�����^�[�i1876�|1962�j��19���I����20���I�ɂ����Ċ���B�g�X�J�j�[�j�A�t���g���F���O���[�Ƌ���3��w���҂ƌĂꂽ�����B�u�W�[�N�t���[�g�q�́v�̎����ɖ������X�P�[���̑傫�ȕ\���́A���Ȓ�����̖����t�ł���B
�@�ޗǂ���,���a�������߂łƂ��B�����āAFM���ǂ���20���N���߂łƂ��B�ЂƂ܂��A���Ȃ�10�N�Ɍ����Ċ撣���Ă䂫�܂��傤�B
2017.10.25 (��) ���r�S���q�̎��s�`��]�����]��
�@10��23���̒����ɗx�� ���I�� ���������A��]�S�s�̕����B�O��u�N�����m�v�ł́A�u������i������Ώ��r�E��]�͏��Ă�v�ƒ������A�\����ς���A�u�����i�����Ȃ���Ώ��r�E��]�͕�����v�Ƃ������Ƃ�����A����͓��R�̌��ʂ������B���I��������B�@������b�E���{�W�O�B�X�F�E���v���Ɍ��錠�͂̎��I���p�B�����B���Ƃ����s�s���̉B���B��Ђ̌ւ���Ȃ��ă��ւ̒Ǐ]�B���ӂ̌��Ђ��Ȃ�����^�c�B�������p�����������������̉R�B��҂ւ̘����ȑԓx�B�Ȃ�ӂ�\��ʉ����H��B����ȏ����̌��{�s�݂����Ȓj�ɓ��{�̐�����C���Ă����킯�ɂ͂����Ȃ��B����Ȑ܁A�Վ�����`���ɓ`�Ƃ̕����B���U���I���ł���B�_���́u�����Ă��ׂĂ����Z�b�g����v�A�ژ_���́u���Ȃ珟�Ă�v�B�܂��Ɏ��ȓs�������̐E���s�g�B����Ȕڗ�Ȑ����s�ׂ��ɋ����킯�ɂ͂����Ȃ��B�����I���͑��ΓI�I���s�ׁB�M���Ȃ�������ɏ��ĂȂ��B�����Ɍ��ꂽ�̂����r�E��]�̓}�������B
�@���r�S���q�́A��N�A����ю̂Đg�ŗՂs�m���I�𐧂��A���N�A�s�c�I�ɂ��叟���B���{������|���͔͂����������B���U���I����z�肵�A2���ɂ́u��]�̓}�v�̏��W�o�^���ς܂��Ă������B�Ƃ͂������̎����A����˂��ꂽ�͎̂����B�����s���͔ۂ߂Ȃ��B�����A���{�����ւ̔ᔻ�������܂ō��܂�D�@�͂������Ȃ��B�ł��ďo��͍̂������Ȃ��I
�@9�����{�A�u��]�̓}�v�͌��}�����B�Η����͈��{�����B�X���[�K���́u���e�ȉ��v�ێ�v�Ɓu������݂̂Ȃ������v�B�����Ďg�����u�ێ�v�Ƃ������[�h�ɏ��r�炵�����������̂́A����ɂ����͔ۂ߂Ȃ������B�u������݂̂Ȃ������v�����͂Ɍ������B���{������Η����ɐ키�̂Ȃ�u�������̖o�Łv�Ƃ��A������A�u�����Ōւ肠�鐭���v�Ƃ����Ó��������̂ł͂Ȃ��낤���B�}�d�グ�̌����_�Ԍ�����B
�@���r�S���q�́A���̑I�����u�����I��I���v�ƈʒu�Â��A��C�ɐ����D���ژ_�B�܂��ɑ叟���I�V�������ڂ̐킢�ł���B�u�����I���v�Ȃ�A�ߔ���233�̋c�Ȋl�����K�v�ŁA���̂��߂ɂ͂���ȏ�̗i�����s���B����ɁA�����D�悵���ۂ̎�ǂ̊炪�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������b�͍���c���Ɍ�����B���r�͓����s�m���B�����Ď���o�n���邩���܂��Ă���Ȃ�̐l�Ԃ𗧂Ă邩�B��ґ��ꂵ���Ȃ������B
�@���}�̗��O�ƃX���[�K���A�I���̑�`�Ɛ헪�͍\�z�����B���Ƃ͌��җi���ł���B���i�}�}��E�O�����i�́A�Â����O�̂܂܂ł͐킦�Ȃ��Ƃ��āA�ۂ��Ɓu��]�̓}�v�ւ̕��������݂��B��]�̓}�̑����猩��ƁA���i�}���E�O�c�@�c���̐��͖��͓I�B���җi���̑傫�Ȋj�ƂȂ肤��B�A����肪�o�邱�̏B�������A���r�͋�ʂ��B�u�S���������l���͂��炳��Ȃ��v�B�������O���قɂ���҂̔r���������B���i�}��������}�̎��s�͗��O�̈قȂ�҂̊W�ߐ��}���������ƁB���̓Q�ނ܂��Ƃ������r�̌��ӂ͐����̂͂��������B
�@���F�̂��ߌ��҂�10�����́u���菑�v�ւ̃T�C�������߂�ꂽ�B���̎菇�ɂ��ԈႢ�͂Ȃ������B���}�ɂ����闝�O�̈�v�͈����x�s���Ȃ̂�����B���͌��t�����������B�L�҂���̗U���������ɂ���u�r������v�͋���߂����B���̌��t�������ς����B
�@�u�r���v�Ƃ������t�����܂�Ă��܂������R�̈�͑I�ʂ̎厲�Ɂu���S�ۏ�v��u�������Ƃł͂Ȃ��������B���r�̐������O����ӂ݂Ăǂ����Ă�������Ȃ��T�O�B����́u���S�ۏ�v�ɂ�����Â��̑̎����B�u���@����C�R�[�����a�v�Ƃ���Z���I�Â��̍\���B���r�ɂƂ��āu���S�ۏ�v�Ƃ͐���ď��������́B���̊�{���قɂ���҂͎�����Ȃ��B������u�r���v�Ƃ����������t���o�Ă��܂����̂��B
�@�����ɂ����āA�u���S�ۏ�v�قǔ����Ȗ��͂Ȃ��B�푈�����Ɛ�͕s�ێ���W�Ԃ���u���@��9���v�̉��A���q���Ƃ������炩�ȌR�������\���I�����B���h�q��W�Ԃ��Ȃ�����W�c�I���q���s�g���\�Ȃ炵�߂���ۖ@�������������Ή��ɛs�ޖ����B���ē����Ɏ���Čo�ϔ��W�𐋂��Ă��������{�̗��j�B�B��̊j�픚���ł���Ȃ���j����p����咣�����Ȃ��W�����}�B��n�̑唼������ɒu���s�����B���s�s�Ȓn�ʋ���B��j�O�����̎���]�X��j�ۗL�̐���_�܂ŁB���O�����������j�w�i�����@���߂ɂ����Ă��A���X�̖���������p���h�b�N�X�ɖ����������Ȃ̂ł���B�����̍l���������l�B�č��̎P���A�����m�ƌ����s���@����邱�Ƃ����ŕ��a���B�������ƍl���镽�a�{�P�̐l�����B���ē����ւ̉ߐM����Ăɖӏ]����l�X�B���̋��Ђ�K�v�ȏ�ɐ���R���u���ҁB�o�ϕ��S���l�����Ɏ���h�q�������閳�S�C�ȗE�ҁA�ȂǂȂǁB�������Ƃ������Ƃ͈����S�Ɩ��ڂɊւ���Ă���B�����S�͗�����������ɍ��E���ꏟ�����B�����犄���Ȃ��B��������߂��Ȃ��B�����t�����Ȃ��B���ƂقǍ��l�ɁA���S�ۏ�͈�ؓ�ł͍ς܂���Ȃ��B�����ƂɂƂ��āA����قǖ��Ȗ��͂Ȃ��̂��B
�@���r�S���q�́A�u���ۖ@���v��I�ʂ̍őO��Ɏ����o�����B���ꂪ����Ȃ鏝��[�߂��B�u���S�ۏ�v�ɖ��S�ȗL���҂ɂ��A���N�A���{�������擱�����A���^���قɏI�n���c�_�s���̂܂ܗ͂Â��̌��ɂ���ĉ��������u���ۖ@���v��A�̗���́A���Ȃ��炸�L���Ɏc���Ă���B����O�ŕ����オ�����u�j�~�v�R�[���̉f�������A���ɋL�����Ă���͂����B�u���ۖ@���v�́A�����Ɍq������{�������̔��[�ł��������B
�@�����炵�āA�u���ۖ@���v���u���݊G�v�ƂȂ����u�ԁA�L���҂͋��Q�����B�u�ȂA���{�����Ɠ�������Ȃ����v�B���r�S���q�ƈ��{�W�O�̓��ꎋ�B�����Ă������r�S���q�������ꗎ����B���{�����������e���鐳�`�̋R�m�ł͂Ȃ��Ȃ����̂ł���B�u�r������v�̃t���[�Y������ɔ��Ԃ��������B���߁E�ዷ���̔��������e����^����B�u�����D��͎��̎��v�͊o��ƈ�ѐ��̂Ȃ����A�u���҉ߔ�����i���ł��Ȃ���A���r���͏o�Ȃ��v�́A���Ȃƕېg��I�悵���B�����͉����x�I�ɓ]�������Ă������B���r�S���q�́A�l���̂����Ƃ��厖�Ȏ����ɁA�֒f�̃e�[�}��I��������Ă��܂����B���f�Ƙ����̎Y���H ���r�S���q�̒v���I�ȃ~�X�e�C�N�������B
�@�����ɂ͕\�Ɨ�������B�I�ʂɂ����āA���ň��S�ۏ��₤�̂͂����B�\�ł͕ʂ̃e�[�}�A�����ƒP���œ�����̂Ȃ����̂Ŗ₤�ׂ��������B�Ⴆ�A�u���{�����@�v���炩�ۂ��H���x�́B�܂��́u���炷��v��r�����āA���Łu���ۖ@���v��₤�B�����őI�ʂ���������B�\�͗D�������Ō������B���Ԃ͕\�������Ă��Ȃ��̂�����B
�@�I���́u�ǂ������邩�v�ɐ����������̂����B�������Ԓm���Ă����̂͏��r�S���q�������͂��ł���B�ߔN�̔ޏ��̏����́u�����ɗ������������C�Ȏ�ҁv�����������Ƃł͂Ȃ��������B���ꂪ�A���F���ґI�шȍ~�A�u�r�����鋭�ʏ��v�u���Ȍ��͎҂𗽂������ҁv�ɉf���Ă��܂����B���Ԃ͈����B�}�X�R�~�͐���u�ꏏ�Ɏʐ^��3���~�v�u�s���t�@�[�X�g�s�c���}�v�u��]�̓}�͖��i�}�̋��ړ��āv�ȂǂȂǁA�����^�A������掁B���܂�ɖ��ߑ��I �ł�����͂����̘b�B�u�u���Ȃ��^�ʖڂȎ�ҁv�}��K�j�́u��������}�v�ɒ��ڂ��ڂ�B����̃e�[�}�ł���͂��́u���{�������̋��e�v���u���r�S���q�̎��ԒNjy�v�ɂ���ւ��B���r�ɋt���A���{�ɏ����B���S�ɒ��ڂ��ς���Ă��܂����B�����������Ԃ̏o�����B������������B
�@�u��]�̓}�v�͂Ȃ�Ƃ��ߔ����ȏ��i�������B�c��͎��g�̏o�n�����݊�����u�~�X�^�[X�v�̗i���B�~�X�^�[X�̖��͋����O�B���ꂪ���������u��]�̓}�v�t�]�̔��z�������B
�@�u���r����A�o�Ă��o�Ȃ��Ă����ӔC�v�Ƃ͎����̃z�[�v����i���Y�̉������������A���̝����@����B��̕��@��������������\�Ƃ��č����ɑ��荞�ނ��Ƃ������B���r�͓s���ɐ�O���A�����͍����Ɏ�r������B���ꂼ�K�E�̈�肾�����͂��B�i�J�ł́A�u���r�������ɏo����̓s�m���ɋ������v�͗��z�������A�u�����i���v�̒��z�͂قƂ�Ǖ�����Ȃ������j�B
�@�Ƃ��낪�A���Ă̒ʂ�A10���̌������A�u��]�̓}�v�̌��҃��X�g�ɋ����O�̖��͂Ȃ������B���r�ɂ��̃A�C�f�B�A���Ȃ������̂��H ���������̂ɒf��ꂽ�̂��H ���߂ăg���C���炵�Ȃ������̂��H �i�v�ɂ킩��Ȃ����낤�B������ɂ��Ă��A���̎��_�ŏ����͂����B�����i���Ƃ����K�E�Z���J��o�����A�����������Ȃ���̑I����́A�����}�����A��]�̓}�S�s�Ƃ����������}�����B���t�̕|�����v���m�炳�ꂽ�I���������B
�@�u��]�̓}�v�̏o���ň��{�������œ|�����҂������I���͌��Ă̒ʂ�̌��ʂɏI������B���{�W�O�́A���Ă͂��ׂă��Z�b�g���ꂽ�ƉA�łق����ށB�X�F�E���v�w�����͖��𖾂̂܂ܕ���A�č��ւ̖ӏ]�͂���ɋ��܂�A���O�������含�Ȃ��̒Ǐ]�ɏI�n����B�j����֎~�̈ӎv�\���̎��������o�����A���d��u������ɂ��������̌��@�����_�c���n�܂�B���������܂��܂����𗘂��������B���̋������A���鐣�����B
�@���r�S���q�͕������B��]����]�ɕς�����B�}�X���f�B�A�͈�Ăɕs��ۂ�@���B�ł��҂��Ăق����B�������ꌎ�O�A���Ԃ͔ޏ��Ɂu�œ|���{�����v��������̂ł͂Ȃ��������B�ޏ��ɋ����̋��e��������̂ł͂Ȃ��������B�u�r���v�Ƃ����ꌾ�͂���قLj�煂Ȍ��t�Ȃ̂��B���}�����O�̈Ⴄ���̂�r�����邱�Ƃ�����قLj������ƂȂ̂��B����Ȃ��ƂŐ^�̋������̂��点�Ă��܂��Ă����̂��B�L�\�Ȑ����Ƃ�ׂ��Ă��܂��Ă����̂��B���{�����͍������{������������ƌ��߂Ȃ�������Ȃ��B
2017.10.04 (��) ���r�S���q�K���̃T�v���C�Y�`�Ō�̈��̓~�X�^�[X�̏o�n��
�@�߂܂��邵���ς�鐭�ǂ̒��A���r�S���q��10��3�������f�������B�u100�����͏o�܂���B�s���ɐ�O���܂��v�u��]�̓}�͉ߔ���233�l�ȏ�̌��҂�i�����Đ����D���_���܂��v�B�}�X���f�B�A�͂��̖�����˂��B�o�n�����ɉߔ������Ƃ��͂��͂Ȃ��E�E�E�E�E�����Ƃ��ł���B�����A���̌����ȏ��r�S���q���A�Ӑ}�Ȃ�����Ȗ������������邾�낤���H �K����������͂����I�Ǝ��͓ǂށB�@10��2���A���x�����h�E�}��K�j���V�}�u��������}�v�ݗ���\�������B���I�����ǂ͓��X�����ڂ܂��邵���ς��B���ɔL�̖ڂ��B����Ŗ��i�}�̉�̂͌`�̏�ł��m�肵���B�Ƃ����ɖ������I����Ă���W�ߐ��}�̉�͎̂��Ɋ�����B
�@�u��]�̓}�v�͌��݁A���i�}�Ƃ̍������ŃS�^�S�^�̗l����悵�Ă���A�Ɛ��Ԃɂ͉f��B�ł�����Ȃ��ƁA���r���ɂƂ��Ă͑z����B�}�X���f�B�A�͍����Ƃ������A���r���͍ŏ����獇���Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B�I�ʂł���B������A�ꕔ�����E���u�S������������̓T���T���Ȃ��v�����͊�����j���т����܂ŁB���r���O����k�ł��̊�{�͊m�F���Ă���͂��B�Ȃ̂ɁA�O�������u�S������v�ƌ������̂͊��Ⴂ���ォ�m�M�Ƃ��B�ǂ���ɂ��Ă����߂�͓̂�����O�B���ɂ��Ƃ������^�}�����̋����������͂����Ȃ��B
�@���{�́u����E���O���̂ĂĖ썇���鐭�}�ł����̂��H�v�`�ƌ������邪�A����͓I�O��B2009�N����E���Ђ̘b�B�u��]�v�͐���E���O����v������������I�ʂ��Ă���̂��B
�@�����[�����́u����Ȃ��A�I���ړ��Ă̐����킹�v�`����͈Ⴄ�B�����邩��u���x������r���v����̂��B
�@�R�������}�ψ����́u�������l��Ȃ��l���������O��ς��������Ŋl���͂����Ȃ��v�`������ǂ��Ȃ́B�}��͍����̈�v��}���ē����Ă���̂����猩����Ă��������ȁB
�@���Y�}���r���L�ǒ��́u��]�̓}�͎����}�̕⊮���͂��v�`����͂��̒ʂ�B���������̂��ċ�������B
�@�l�C�ҁE����i���Y�́u��]�̓}�͖��i�}�̃R�X�v���B���r����͏o�Ă��o�Ȃ��Ă����ӔC�B���܂��ɂ��̃W�����}�Ɋׂ��Ă���v�`���ΐi���Y�A�����͂�����B�u�o�Ă��o�Ȃ��Ă����ӔC�v�B���āA���r�S���q�u��]�̓}�v����ɂǂ��Ή����邩�H������̃e�[�}���B
�@�����̔ᔻ������t�����̂��낤�A�u��]�̓}�v�̐����͌����C���B�ŐV�̐��_�����i10��1���t�j�ł́A�u���łǂ̓}�ɓ��[����H�v�ɑ��A�u�����v24.1�A�u��]�v14�B�u�܂����߂ĂȂ��v��42.8�B�}�X���f�B�A�͊�]��14��s�U�ƌ���B�m���ɂ��̂܂܂ł͏��ĂȂ��B���A����Ȑ����͈��ɂ��ĕς��B�|�C���g��42.8�̖��}�h�w���B�����A42.8�̓�27����]�ɗ����A�c��15.8���S�������ɂ����Ă��A41��39.9�ŏ��Ă�B����͓��[���܂łɎ�������������ƁB�ł邱�Ƃ͂Ȃ��B2�T�ԋ��A�܂����Ԃ̓^�b�v������B
�@10��3���A�u��]�̓}�v��1�����F���192�������\���ꂽ�B�ߔ�����233�܂�41���B����ȏ�̐������������܂łɊԂɍ��킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����10��6�����B����͌��\�Z�����B�ł����Ƃ���������ɂ͏o���Ă��邾�낤�B
�@���̊ԋ͂������A�u��]�̓}�v�Ɋ֘A����b����₳�Ȃ����Ƃ��̐S���B�u�O�s����v�������B������̔ᔻ���劽�}�B�}�삳��̐V�}�����A�ǂ�������肭�������B���߁E�ዷ���̎����u���r����233�l���҂𗧂Ă��Ȃ���Ώo�Ȃ��v�Ɓu�����D��͎��̎��ł����v�́u�I�C�I�C�I�C�v�����E�E�E�E�E���r���͌������𖽂����������������Ƃ����B�}�u�o�Ȃ��B�����Ő����D��v�ƌ����Ă���̂�����B�܂��ɐ^�t�B�{���Ȃ��ł���You�fre fired�B�܂��A���\�Ԃ肪�I�悵��������̂�����A������́H
�@���ƁA���ӂ��ׂ��́u���O�E����v�łԂ�Ȃ����ƁB�����ق�������Ƃ����āA�Ⴆ�A�u���x�����r���v��P���肵�Ȃ����ƁB�����܂Łu���v�ێ�v�u�����v���т����ƁB���_�u������݂̂Ȃ������v�͑i��������B
�@���r�����u���ۖ@�����Ύҁv������Ȃ��̂Ȃ�A��N�̈��ۖ@������Ŕ��������Г}�c���͂��������Ȃ��͂��A�Ƃ����ӌ��ɑ��Ă͂������_��������E�E�E�E�E����}�c���̒��ɂ́u���ۖ@���v���̂��̂ɔ��̐l����������łȂ��l������B���̂��̂ɔ�����l�ɂ͂������肤�B�����ł͂Ȃ��A���̎��̐����^�c�ƃ}���J�V���i�ɔ������l�����A���̐l�����͎����B�u���v�ɂ͓��ނ���B��ʓI�Ɍ��Ȃ��łق����B�����OK�B
�@��p�̊j�́u���{�����̎����v��O��I�ɓ˂��܂��邱�ƁB������݂̂Ȃ������́u��]�̓}�v�͑̎��I�ɂ���Ȉ��{�����Ƃ͖����ɈႤ���Ƃ���т��Ď咣�������邱�Ƃ��B���́A���}�̃S�^�S�^�Ř_�_���Y���n�߁A�u���{�����̎����v�u��`�Ȃ����U�v���B�����B����͎����̎v���ځB��q�ዷ���̎����u������Ȃ�o�Ȃ��v�͏��r���̉�~�ƂƂ���B����͏o���Ȃ����ƁB�����܂ō����t�@�[�X�g���т����Ƃ��B
�@10��6���܂ł́A����21.1�A��]14�̂܂܂ł����B�����Ȃ�T�v���C�Y���o���̂��B���_�����ŁA�u���r�����m�������߂ďo�n����̂͗ǂ��Ǝv�����v�ɑ��A�u�v��Ȃ��v��72���B���̐����͑傫�����ς��Ȃ����낤�B�Ȃ�Ώ��r���͏o��ׂ��ł͂Ȃ��B�ނ��{�l�͏o��C�͂Ȃ��͂��B�Ȃ�A�ǂ�����H
�@�o�n���Ȃ���ΐ����͎��Ȃ��B�ł��o�Ȃ��B���̖�������C�ɉ���������@�B����́A���r���͂��̂܂܂ɁA�������O�������Ől�C�������ĉ�����u��]�̓}�v�̊ŔɂȂ肤��~�X�^�[X���o�n������B���ꂵ���Ȃ��B�~�X�^�[X�͏��r���Ƌ�����\�ƂȂ�A�I�����ŔŐ키�B�L���b�`�t���[�Y�́A�u�s���͏��r �����̓~�X�^�[X�v�B��l�ň��{�����̎�����˂��܂���B��v�e�[�}�͉��v���Ƒ�9�������Ă��K�����B���x�����ɑ��ẮA���ӂ̈��S�ۏ�ōU�߂܂���B�u���Ȃ����͂ǂ�����ē��{��������Ȃ̂��v�B����ł����B
�@�������łɂ͑�����b�w���I���Ń~�X�^�[X�̖��O�������B���{�W�O�ސw�B���̃V�i���I����������I�H ����ȃ~�X�^�[X�����݂���̂��H ���{�ɂ�������l����̂ł���I
�@�~�X�^�[X�̖��͋����O�B�ނ͌��݃t���[�̐g�B���TV�̃��M�����[�ԑg�u�����O�ƉH���T��v���I���������B���E������ނ����Ɖ]�����A���āu20,000���Ȃ��v�ƌ����ďo���l�ł���B�����Ă����������͂Ȃ��ł͂Ȃ����B�o�n���́u��]�v���u�ېV�v���B�u���r�������v�̓Ŕ����f������A�ǂ���ł��\��Ȃ��B��]�̏ꍇ�͋�����\�A�ېV�̂܂܂Ȃ狤���ŁB10��6���A�u��]�̓}�v���u���{�ېV�̉�v�̂ǂ��炩�̃��X�g�ɋ����O�̖��O������B���ꂼ���r�S���q�Ō�̈��B���h���̃T�v���C�Y���B
�@��������2011�N�A�����C�̂��̂Ƃ��R�̂��̂Ƃ����Ȃ������Y�ƃ^�b�O��g��ŁA���s�m�����s��W�I�������������т�����B���x�̑����͏��r�S���q�B�܂��ɍŋ��^�b�O�ł͂Ȃ����B
�@��l���I���J�[�̒d�ォ��u�����{������|�����I�`�����X�͍����I�v�ƌ���U�肩�����B����͔��͂���܂���B��C�ɕ��������B�R�������B���{�����͉�œI�s�k�B���ꂪ�A�����l����u��]�̓}�v�K���̃V�i���I�ł���B
�@�ێ��吭�}��s����������������邾�낤�B�ł��悭�l���Ăق����B����܂ŁA1955�N�ȍ~60���N�i���̊�10�N��������j�́A�ێ�i�����}�j���ł̐������̌J��Ԃ��ł͂Ȃ��������B�Ȃ�Γ������ƁB�}���ʂȂ�ْ����������B���x�����́A��������}�Ƌ��Y�}�ɂ��C������B���ɂ͈�������ł��炤�B�ێ�ƃ��x�����̂��ݕ������͂����肵���B���i�}�̉�̂ł����`�ɂȂ����B
�@���͋������ɏo�n�̈ӎu�����邩�Ƃ������ƁB���r�����u��������A���Ȃ����ꏏ�ɐ���Ă����A�ԈႢ�Ȃ����Ă܂��B���Ȉ��{������|���܂��傤�B�����`�����X�B�ꏏ�ɂ������ł͂���܂��B���͓����ܗւ��I���܂ł͓s�m���ɐ�O���܂��B���̌�͍����̏�ł��Ȃ��Ɨ͂����킹�Ċ撣�����B��������A���̃`�����X���������Ȃ���͂Ȃ����Ⴀ��܂��ƁB�����f���I�v�ƌ������A�������͏�������͂��ł���B�j��������̂��̐�ڈ���̃`�����X�ɓq���Ȃ���͂Ȃ��ł͂Ȃ����B
�@�O�s����Ȃ��͓�����A���̕����ɉ߂��Ȃ������B���r�S���q�������O�̍ŋ��^�b�O�ŁA�����{�������Ԃ��ׂ��Ăق����B���ꂪ���̖��ł���B�P�Ȃ��z�ŏI��邩������Ȃ����A�N������Ă��̂悤�ȃX�g�[���[��`���������ł������̊����B
2017.09.29 (��) ���ς�8�N�����ł���Ă���I�H�`���r�S���q�́u���̐�͏��Ă�I�v�Ɠ���
 �@���{���t������b�́A9��28���A�O�c�@���U��f�s�����B�u����˔j�v���U���������B���U���R�́A�u2019�N�ɑ��ł������ł̎g�����̕ύX�Ɩk���N�̋��Ђւ̑Ή��v�ɑ��č����̐M��₤���ƁB����͌��O�B�{���́u���Ȃ珟�Ă�v�B
�@���{���t������b�́A9��28���A�O�c�@���U��f�s�����B�u����˔j�v���U���������B���U���R�́A�u2019�N�ɑ��ł������ł̎g�����̕ύX�Ɩk���N�̋��Ђւ̑Ή��v�ɑ��č����̐M��₤���ƁB����͌��O�B�{���́u���Ȃ珟�Ă�v�B�@����Ȍ�t�����U�������Ă����̂��I�ł��M���Ȃ��B�ǂ��������̂����̕NJ��A�ƔY��ł�����A�Ȃɂ�����ς���Ă����B���r�S���q���V�}�u��]�̓}�v�𗧂��グ���̂ł���B�}���͍��N2���ɏ��W�o�^�ς݂Ƃ������甲���ڂ��Ȃ��B����ɂ��Ă����̏���ς̃X�s�[�h���B���Ƃ������āA���ʗ\�z�܂ł����Ă݂悤�B�L�C���[�h�́u�NJ��v�Ɓu8�N�����v���B
(1) ���{����A���Ȃ��ɂ͖O���O����
�@����̉��U�͑�`�Ȃ��̌�t���A���{�̖{���́u���Ȃ珟�Ă�B�����Ă��܂����ׂĂ̓��Z�b�g���v�Ƒ命���̍����͊����Ă���B�����č����̌�������A���̕��ɂ͐M���������Ȃ��Ƃ̎v�����蒅���Ă���B�������Ŗ����Ȃ��B�����Č����ΉR�����B�R���ɍ�����C���Ă͂����Ȃ��B�u���J�ɐ����ӔC���ʂ����v�ƌ����Ȃ��獑����B��R���ɂ��O�V�𗝗R�Ɍ��ȁB�o�Ă����Ǝv������u���v���Əb��w���ݗ��̘b�͂������Ƃ��Ȃ��A�����s�ւ̐\����m�����͍̂��N��1��20���v�����āB��́A�N���M����́I ���Ɛ헪����܂ŗ����グ�āA�g���S�̗F�h�̕X��}��B��������͂̎��I���p�Ƃ����B���卑�ƂɂƂ��čł�����܂����s�ׂ��B���̈�_�����Ŏ��C�͓��R�B�Ȃ̂ɁA�����H��ɗ]�O���Ȃ��B���U�����̈�B�u����}�̓S�^�S�^�A���r�V�}�͏����s���A�������肪���Ȃ����Ȃ珟�Ă�B�����Ă��܂��R�b�`�̂��́B���ׂă��Z�b�g�A�V�����V�����V�����B�O��̌��@�����A�����ܗւ͊J�Í��̎A�ݔC�L�^�̍X�V�ȂǁA�����ƂƂ��ĕ`����������������B�����͉������ł����U���B��`�Ȃǂ���Ⴕ�Ȃ��B��t���ŏ\�����v�Ƃق����ށB�Ȃ�Ƃ��Ƒ��B����Ȑl�Ԃɍ��Ƃ̒���C������킯���Ȃ��B������サ���Ȃ��ł͂Ȃ����B�ł��M���Ȃ��B�R����肪�Ȃ��Ă����i�}�͏I����Ă���B�ېV�͏{���߂����B���܂��狤�Y�}�ł��Ȃ��ł��傤�B���̕NJ��B������߂邵���Ȃ��̂��I�H �����ɍ��R�ƌ��ꂽ�̂����r�u��]�̓}�v���B
(2)�u��]�̓}�v�̏o���ŏ͈�ς���
 �@9��25���A���{�����̉��U�`10��22�����I���̕\���ɐ旧���āA���r�s�m���́u��]�̓}�v�ݗ���錾�����B27���ɂ͌��}�\���B���������Z�b�g����B�����܂ł̌��}�ւ̉ߒ������Z�b�g������}��ƂȂ����B�j�̂̓�{���́A�u���e�ȉ��v�ێ琭�}�v�Ɓu������݂̂Ȃ������v�B�����}�Ɠ����ێ�Ƃ��Ȃ���A���v��W�Ԃ���B������v�A�א썑���V�}�̗���B����͎a�V���B��吭�}�����̗\��������B�I���X���[�K���� �@������݂̂Ȃ����� �A����ł̈ꎞ�I���� �B�E�����Ȃǂł���B���i�}�ɑ��ẮA�}���m�̘A�g�͂Ȃ��ƓB���h���B����A���i�}�̉�̑_���B���Ԃ͐i�݁A���i�}�͉�̍����̕������B�V�}�̐w�e�͌���14���B�ŏI�I�ɂ�3���̌��҂�i������悤���B�s�m���Ƃ̓̑��܂ւ̕s���ɑ��ẮA�u�O�X�C�҂̐Ό��m�����T1���̓o���ʼn��̂�����A�����o�����Ă��鎄�ɂł��Ȃ��킯���Ȃ��ł���v�ƈ�R�B����҂̓O�[�̉����o�Ȃ��B��������Ȃɂ����A�s�m�����E�`�o�n������ �Ƃ̉������B�ł��A����͂�肷���B���q�ɏ��߂��Ȃ����������B�Ǝv�����ǁA���O��̓V�˂͂�����Ⴄ��������Ȃ��E�E�E�E�E���rVS���{�Ƃ����Η����������ɍ��グ���B�ł́A�I������ǂ��키�H
�@9��25���A���{�����̉��U�`10��22�����I���̕\���ɐ旧���āA���r�s�m���́u��]�̓}�v�ݗ���錾�����B27���ɂ͌��}�\���B���������Z�b�g����B�����܂ł̌��}�ւ̉ߒ������Z�b�g������}��ƂȂ����B�j�̂̓�{���́A�u���e�ȉ��v�ێ琭�}�v�Ɓu������݂̂Ȃ������v�B�����}�Ɠ����ێ�Ƃ��Ȃ���A���v��W�Ԃ���B������v�A�א썑���V�}�̗���B����͎a�V���B��吭�}�����̗\��������B�I���X���[�K���� �@������݂̂Ȃ����� �A����ł̈ꎞ�I���� �B�E�����Ȃǂł���B���i�}�ɑ��ẮA�}���m�̘A�g�͂Ȃ��ƓB���h���B����A���i�}�̉�̑_���B���Ԃ͐i�݁A���i�}�͉�̍����̕������B�V�}�̐w�e�͌���14���B�ŏI�I�ɂ�3���̌��҂�i������悤���B�s�m���Ƃ̓̑��܂ւ̕s���ɑ��ẮA�u�O�X�C�҂̐Ό��m�����T1���̓o���ʼn��̂�����A�����o�����Ă��鎄�ɂł��Ȃ��킯���Ȃ��ł���v�ƈ�R�B����҂̓O�[�̉����o�Ȃ��B��������Ȃɂ����A�s�m�����E�`�o�n������ �Ƃ̉������B�ł��A����͂�肷���B���q�ɏ��߂��Ȃ����������B�Ǝv�����ǁA���O��̓V�˂͂�����Ⴄ��������Ȃ��E�E�E�E�E���rVS���{�Ƃ����Η����������ɍ��グ���B�ł́A�I������ǂ��키�H�@���r���͑I�������ň��{������O��I�ɒ@���B��]�����߂Ă��̓��e�����L
�L���҂̊F�l�A�ʂ����Đ��������̂܂܂ł����̂ł��傤���B�^�f���B�������ӔC���ʂ����Ȃ��B�d���l���t�ƌ����Ȃ���A�d���������ɂ����Ȃ���U�H ��̒N�̂��߁B�ǂ��������Ďd�������Ă���́B�ǂ��l���Ă������̂��߂̐����Ƃ͂����܂���B�������͍����t�@�[�X�g�u������݂̂Ȃ������v��ڎw���܂��B(3)�u��]�̓}�v�����̃V�i���I
����ŕ��̎g�r���A�c������̖������⍂������̕��S�y���ɕύX�ł����B���\�ł��傤�B�ł����̐M��₤���Ƃ����U���R�ɂȂ�̂ł��傤���B�ނ���A�������S���ւ̓���������邱�Ƃ��挈�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����B���{�̎؋���1000���~���Ă��܂��B���̏d�v�ۑ��摗�肷��Ȃ�A����͖�����w�����q�������ɕt�������ƂɂȂ�̂ł��B
���{����A���Ȃ�������I�ڂ������@��9���̉����āB����͂����������ł����H ��1����2���̏����̂܂܂ɁA���q���̑��݂L������āA����Ȃ��Ƃ��{���ɉ\���Ƃ��l���Ȃ̂ł����H ��2���ɂ́u��͕͂ێ����Ȃ��v�u���̌�팠�͔F�߂Ȃ��v�Ƃ͂����菑����Ă��܂��B�R���ł��鎩�q���̑��݂��ǂ����L����Ƃ��������̂ł����H ��3����݂��āA�u��1���y�ё�2���ɂ����ẮA���q���̑��݂�r�����Ȃ��v�Ƃł����邨����ł����B������܂₩���Ƃ����̂ł��B���ۖ@���ł��ꂾ�������Ȃ��肢���������@�ɁA�܂����S�����������Ȃ̂ł����B����ł͌��@���������B����͌��@�ɑ���`���ł��B�������������_�҂ł��B�ł�����ȏ����̂��s����`�̉����͍l���Ă���܂���B�u��]�̓}�v�͍����̂��߂̉�����ڎw���܂��B
�����͂܂������r��B�p�F�̓����܂��������A�j�p�����������������B����ȏŁA�����C���h�Ɍ����̃Z�[���X�ł����H���ߑ��ł�������܂���B�������͌���0�̍H�����쐬���܂��B���{���B��̔픚���Ƃ������Ƃ����Y��Ȃ�ł����B���A�̊j����֎~��c���������܂����ˁB�k���N�̊j���ł̓A�����J�ɒǏ]�������B�{���A�j�p��𐢊E�ɑi���Ă���k���N�ɒ�~�𑣂��ׂ��Ȃ�ł��B���{�Ȃ炻�ꂪ�ł���͂��B�k���̓y�����A�v�[�`���哝�̂̃y�[�X�ɛƂ܂��Ă��܂����B�̓y����I�グ���āA�o�ϋ��͂ɓ��ӁH ����ŁA�ǂ����ė̓y���Ԃ��Ă����ł����B�������́A�ێ�͕ێ�ł����v�Ɋ����������s���܂��B
���r����̘e���A����A�א염���������ł߂�B�E������M���i����B��l�Ƃ��l�C�͂܂��܂����݁B���̌��i�͖��͓I�B����U���Ǝ��Ȑ���ɏ��X�����������Ă��\��Ȃ��B�I���Ȃ�đ��Θ_�B�������ׂ��ɂ͑������ꗂɂ͖ڂ��Ԃ낤�B
�@�����ŁA�u�N�����m�I�v��_�\�����E�E�E�E�E�u��]�̓}�v����i�B�����}��œI�s�k�B������������I�H �u���Ă�v�Ɠ����{�͉��U��P�����S���ł́H
�@���{�����́A�u�ڕW�́H�v�̎���ɑ��A�u�����^�}�͈�������������S���̂��ړI�B�����}�ƍ��킹�ĉߔ�����233���ڕW���v�ƕ\���B���L287�c�Ȃƈ��|�I�ߔ������ւ���}�}���̎�C�����B�u��]�̓}�v�̑䓪�ɋ���ɂ��Ă���؋��B�n�[�h���������ăM���M��������}��ژ_�����B���U�錾��̋L�҉���I�~�b�g�̎㍘�B�Ȃ�Ώ��r����A�����͎v�����Ĉ�����n���Ă�낤�B���߂̐��_�����ł͎����}�x������30����ɋ}�~�����Ă���B
�@�萔465�̓���͏��I����289�A����\176�B�ߔ�����233�B�O�@�̌��L���͂́A����287�A����35�A���i87�A���Y21�A�ېV15�A���R2�A�Ж�2�A������23�A����3 �B���̐����A10��22���ɂ͂ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤���H
�@��]�̓}�i�z���������i�}���܂ށj170�B�ېV���̂܂�15�B���Y����ێ���20�B����������ێ���35�B��������20�B�����Z����Ǝ�����205�B�啝�ɒP�Ɖߔ����������A�A���^�}�Ƃ��Ă�240�Ɖߔ����M���M���B����͉�œI��s�B���{�A���ӎ��C�͕K���̑̂��B
�@�ȏオ���̑�_�\�������A���������������Ό����ĕs�\�ł͂Ȃ��B����}����������2009�N�̐������I���B�����̖��}�h�w�����[���ɑ����^��ŁA���[����69���B����330�l�̗i����308�c�Ȃ��l�������B
�@����ɕ킦�A���[���������Łu��]�̓}�v��200�l�߂����҂𗧂Ă���A170�c�Ȃ͌����Ă���B�����āA������̂�����H���B
�@���������ŁA�����}���Q�Ԃ��āu��]�v���ƘA����g��ǂ��Ȃ邩�H ����205VS�A��235�i��]170����35�ېV15�v�V�n��������15�j�ƂȂ萭����オ��������B�ł́A�����}����������\���͂���̂��H �����}��1993�N�א쐭���ł͘A���^�}�������B���̂킸��6�N��A�������A���ւƐQ�Ԃ��Ă���B�����Ă����������Ȃ��b�ł͂Ȃ����B���r�����A�u���ّI�͂���ɓ��[�H�v�Ȃ鎿��ɁA�u�����}�̎R����\���ȁv�ƃT�����������̂́A������A�Ȃɂ��̃V�O�i����������Ȃ����I�H
�@�Ȃ�ƂȂ�������オ�����Ă����H ���ӂ���C�ɓ����Ƃ��A��Ղ����܂��B�������ς��B1993�N�א�A�������̒a���B2001�N����Y�̒�R���͂ւ̒���B2009�N����}�̐������B���ׂċN���܂́u�NJ��v�B�����āA2017�N���r�S���q�̋t�P�B���ς�8�N�����ł���Ă���I�H
�@����ɂ��Ă�5�N�O�̎����}���ّI�ŕ����g�ɏ��A���т�H���A���H�����߂��s�m���I���A�@�u���̏o�������Ȃ���̏o�n���������r�S���q���A���܂��ɓV�����ɂ܂�������B�Ȃ�Ƃ��s�ςł���B���X�����m����m���ȖځA���������Ȍv�Z�A���f�����Ǝ��s�́A�l�S�����̗́A�ނ܂�ȓx���B�����ƂƂ��Ă̎������}���`�ɔ��������r�S���q�����NJ���Ŕj����~����ł͂Ȃ��낤���B
�@������������8�N�Ԃ�̐�����オ�N���邩������Ȃ��B�����łȂ��Ă����{�̐��̕���͕K���ƌ���B10��10�������`22�����J�[�B���X���X�ƕς�鑍�I���̏��I�m�Ɍ�����Ă��������Ǝv���B
2017.09.20 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`��ҁu��F���������v
�@�ł͋�Cafe ELGAR�X��i�ȉ�E���j����̃��[���̑����B�u���_�`���������́v��14�i��{�̑S�e�ł���B 14 ���ȋi���w���C�I���x
14 ���ȋi���w���C�I���x�w���̈��A�x������Ă���B
�������ƌ��������킹�ɍ����Ă���E���B�Â��ɂ͂Ȃ�����ł���B
������ �u�����ł����B�G���K�[���D���ł����v�@���������������̑䎌�́A���̕������ł��u�����Ɂw�G���K�[�̃~�j�`���A�[���x������̂��f���炵���v�������B���ۂ̑�{�́u����Αf���炵���v������A�Ȃ����Ƃ��������Ă���B
�E���@�@�u�����ł��˂��v
������ �u���Ɂw�G���K�[�̃~�j�`���A�[���x�͑f���炵���v
�E���@�@�u�m�[�}���E�f���E�}�[�̖��Ղł��ˁv
������ �u�����A�ނ��w������G���K�[�͐�i�ł��v
�E���@�@�u���̒��ł��w���̈��A�x�����ɂ����ł��˂��v
������ �u�i�����w���j�R���ł��ˁv
�E���@�@�u�����A���̔Ղ̓A�����W�����ƈ���Ă����ł���v
������ �u�����A�m���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�����Ɂw�G���K�[�̃~�j�`���A�[���x������Αf���炵����ł����ˁv
������ �u����[�A�f�G�ȕ��Ƃ��m�荇���ɂȂ�܂����v
�E���@�@�u�����A���̓X�ŏ��߂đ��̕��Ƙb������ł��܂��܂����v
������ �u�킽���͂˂��E�E�E�E�E�v
�E���@�@�u�͂�?�v
������ �u�F�B�����Ȃ���ł���E�E�E�E�E�i�����ď��j
�@�@�@�@�@�܂��ĉ��y�̂��b�ł�����Ȃlj��Ƃ͎v���Ă��Ȃ������v
�E���@�@�u����͋��k�ł��E�E�E�E�E�܂����ڂɂ������Ƃ�����ł����v
�������A�E���̕����ɋ���������
�@�h���}�̉������ēx������������A��{�ʂ�ɊԈႢ�͂Ȃ������B���̕����Ⴆ�ł���B�܂����ɐ����͂Ȃ��Ǝ������Ă��鎄�������Ⴆ�������́A���́u�v�����݁v�Ɓu���҂̕s���ĂȔ����v�ł���B
�@��l���]�~�����܂�ɂ������͂�����������A�����Ŗ鉉�t�̓f���E�}�[�u�~�j�`���A�[���v�́u���̈��A�v�ɈႢ�Ȃ��Ǝv������ł��܂����B���̎��_�Ŏ��́u�~�j�`���A�[���v���Ă��Ȃ��̂����环�ʂł���͂����Ȃ��B���������������̎ᏼ���j�̔��������Ȃ�s���āB�������ƌ�������悤�Ȕ����B��{�����Ȃ��畷���Ίm���Ɂu����Αf���炵���v�Ȃ̂����A�v�����݂���u����̂��f���炵���v�ƕ������Ă����������͂Ȃ��B�Ƃ͂����A�u���_�v�X�^�b�t�ɁA���Ȃ��Ƃ����ӂ͂Ȃ������B�O��u�N�����m�v�ł́u�X�^�b�t�̗ǎ����^���v�Ƃ��鎄�̔����͐T��œP���Ă��������B
�@���āA��������E������M�d�Ȏ����������������̂�����A�u���_�`���������́v��14�i���m�肷��܂ł̌o�܂��A���̊ϓ_���瑍�����Ă������B����5���͂������肢�����B

2003�N�^���A���fTV�̏��ē炵���l����E���ɓd�b������B�u�w�G���K�[�̃~�j�`���A�[���x�i�m�[�}���E�f���E�}�[�w���j�̃A�i���O�E���R�[�h��T���Ă��邪�A�ǂ����Ŏ�ɓ�����@�͂Ȃ����B���J�L�剉�́w���_�x�̏�����Ƃ��Ďg�������v�@�ȏオ�u���_�v�`�u���������́v��14�i�ɂ܂���A�̗���ł���B���̕��f������������F�B���N5���́u�N�����m�v�Łu��b���e�Ɖ��t���Ⴄ�v�Ǝw�E�B����Ɋ���~�߂�ꂽE�����A�����Ă��ꂽ�E�E�E�E�E�ȏオ����̓^���ł���B
E���uCD����Ȃ̂Œ��Õi��T���������@���Ȃ��Ǝv�����A�悩�����玄���L��LP�Ղ����݂����܂��傤�v�Ɖ����ALP�u�~�j�`���A�[���v�̃W���P�b�g��݂��o���B
�u���_�v�X�^�b�t�́A������Ƃ��ăW���P�b�g���g���邱�Ƃ��m�F�B�r�{�̟N�䕐�����͋r�{���ɒ���B��14�i���a�J�̖��ȋi�����C�I���ɐݒ�B���J�L�����鐙���E���Ǝᏼ���j�̑��������ׂ荇�킹�ʼn�b�B��b�̃e�[�}���A�g�f���E�}�[�́u���̈��A�v�i�u�~�j�`���A�[���v���^�j�h�ɐݒ�BCafe ELGAR�̃E�F�u�T�C�g�����Q�l�Ɂu�f���E�}�[�́w���̈��A�x�͑��Ƃ̓A�����W���Ⴄ�v�Ȃǂ��]�~�荞�ށB
���C�I���ŗ����͓̂��R�f���E�}�[�́u���̈��A�v���]�܂����A�X�^�b�t�͉����擾�ɑ��邪�A�����܂łɌ�����Ȃ��B�擾�ł����̂̓A���h�����[�E�f�C���B�X�w���FBBC�����y�c��CD�B��ނȂ�������g�����Ƃɂ���B
�g�p���鉹�̓A���h�����[�E�f�C���B�X�ՁA��l���]�~�̓f���E�}�[�ՁB������ǂ�����H�N�䎁�͑������̑䎌���u�����Ɂw�G���K�[�̃~�j�`���A�[���x������Αf���炵����ł����ˁv�Ƃ����B����ŁA�Ȃ�Ƃ���������킹���̂ł���B ���X�g�ŁA���͎����̍������������������A���u��ŁA�E�����������LP�u�~�j�`���A�[���v�����B���ꂼE���̌����B���S�[���ɃW���P�b�g�����߂鑽�����B�S�̒��Łu���C�I���ł͒����Ȃ������f���E�}�[�́w���̈��A�x���o����̊y���݂ɂ��āA�������肨�߂��ʂ����Ȃ����A�Ƃ������b�Z�[�W���B�����E���A���Ȃ��Ƃ�����l���v�ƂԂ₢���ɈႢ�Ȃ��B
�@�v�����݂ɂ���F�ƂƂ��ɔ��Ȃ��ׂ��́A�u���̔Ղ́A�A�����W�����ƈ���Ă����ł���v�̌���ӂ������ƁB�u�A�����W���Ⴄ�v�Ȃ�ǂ��Ⴄ�̂��������ׂ��������̂ɁE�E�E�E�E�B���̂��߁A����A����������قS�e�́u���y�������v�ŁA�u���̈��A�v�G���K�[�̃I���W�i���̃I�[�P�X�g�������m�F���ʁB�R�s�[���Ď����A��A�ƍ��B���̌��ʂ����L�B
�@ �y��Ґ��́A�t���[�g�A�I�[�{�G2�A�N�����l�b�g2�A�t�@�S�b�g2�A�z����2�A���y5��
�A �������t�ł郔�@�C�I�����Ɂu�\���Łv�Ƃ����w���͂Ȃ��@
�B ���̑��� sul A.��A���Œe�� �Ƃ����w��������
�G���K�[�̎��쎩���Ձi1929�^���j�́A����������@�C�I�����̃\���Œe���Ă���A���ꂪ��Ȏ҂̈Ӑ}�ƍl���Ă��������낤�B
�u���_�v�Ŏg��ꂽ�A���h�����[�E�f�C���B�X�Ղ́A����������y���t�B���͂قڃI���W�i���y���ʂ�B
�f���E�}�[�Ղ́A��������\���Œe���Ă���S�̂ɍ�Ȏ҉��t���K�͂Ƃ��Ă���悤�Ɏv���iE���́u�f���E�}�[�͍�ȎҔՂ��Ă���\���������v�Ƃ���������Ă���j�B�������A�e�y��̉̂킹���ɂ͑傫�ȍ�������A�f���E�}�[�Ղ̕������ߑ�I�ȋ��������Ă���B
�ꕔ�Ől�C�̍����J�[�����E�h���S���Ղ́A���j�[�N�őf���炵�����A�Ǝ��̃A�����W�őS���ʕ��̊�������B
�@���_�Ƃ��ẮA�����E���̑䎌�u�f���E�}�[�̂́A�A�����W�����ƈ���Ă����ł���v�͓I�m�ł͂Ȃ��B�u�f���E�}�[�̉��t�͍�ȎҁE�G���K�[�̈Ӑ}�ɉ��������́B���Ƃ͈���������܂��v�����肪�K���낤�B�ł��A����ł́A��u�Œʂ�߂���h���}�̑䎌�Ƃ��ẮA�킩��ɂ�����������Ȃ��B
�@�Ƃ����ꎄ�̌�F�̂����ŁAE���Ə��X�̂���肪�ł����̂͊y�����̌��ł������B����̌����Ƃ�����ł���BE���́A�w���̂��납��C�M���X���y�ɋ����������A1980�N��A�u���R�[�h�|�p�v�́u���R�[�h���k���v�Ȃ�R�[�i�[�ɁA�G���K�[�́u���̈��A�v�̂��X�X���Ղ�q�˂Ă���B�����ʼn҂̏o�J�[������A�f���E�}�[��LP�uSOLILOQUY�v�iRCA�̗A���ՂŁA�u�~�j�`���A�[���v�̑O�g�j���Љ�Ă�����Ă���B����30�N�ȏ���̘̂b�B�N�G���Ⴄ�B���̌�A�G���K�[�Ɋւ��X�����������Ɗ肤�悤�ɂȂ�A2002�N�A���� Cafe ERGAR ���o�X�B����͂�A�����܂��� ELGAR ���I
 �@�G���K�[�̐��a�n�ɂ�3�x���s���ꂽ�Ƃ����BCafe ELGAR �̌����́A���a�n�E�X�^�[�̗ג��O���[�g�E���[�����@���i�G���K�[�͂����ɂ��Z��ł����j�̋�s�����f�����Ƃ��B���b���Ε����قǁACafe ELGAR �ɍs���Ă݂��������A�����āA�X�傩��G���K�[�b�����������A�Ƃ̎v���͕��B���A���͂�������Ȃ��BCafe ELGAR �͍��N��9���ɕX���Ă��܂����B
�@�G���K�[�̐��a�n�ɂ�3�x���s���ꂽ�Ƃ����BCafe ELGAR �̌����́A���a�n�E�X�^�[�̗ג��O���[�g�E���[�����@���i�G���K�[�͂����ɂ��Z��ł����j�̋�s�����f�����Ƃ��B���b���Ε����قǁACafe ELGAR �ɍs���Ă݂��������A�����āA�X�傩��G���K�[�b�����������A�Ƃ̎v���͕��B���A���͂�������Ȃ��BCafe ELGAR �͍��N��9���ɕX���Ă��܂����B�@�Ō�ɁAE�����炨�������������[���b���B�u���̈��A�v�̉p��̌���� Love's Greeting�B�A�|�X�g���t�BS�̏��L�i�͌����u�l�v�B���{���u���̈��A�v�� Greeting of Love �Ȃ�ΑÓ��B������ Love �ׂ�ƒj�����猩���g�����̗��l�h�Ƃ����Ӗ�������B�G���K�[�����̈Ӗ��� Love's Greeting �Ƃ����̂Ȃ�A���{���́u���l�̈��A�v�Ƃ���̂����������A�Ƃ������́B
�@�Ȃ�قǁA�Ǝv�����u�Ԉ�̃^�C�g�������ɕ����BA Midsummer Night's Dream �ł���B���̏��L�i���u�l�v�ł͂Ȃ��B�ʏ�Ȃ� A Dream of Midsummer Night �̂͂��B�ʂ����ăV�F�C�N�X�s�A�̈Ӑ}�₢���ɁH
�@���C�Ȃ����ׂĂ�����A�G���K�[�̐��a�n�E�X�^�[�i�k��52�x12�� ���o2�x13���j�ƃV�F�C�N�X�s�A�̐��a�n�X�g���g�t�H�[�h���A�|�����G�C���H���i�k��52�x19�� ���o1�x71���j�́A�����E�F�X�g�~�b�h�����Y�B�A�����ɂ��Ė�30�q�͓����\�����q���炢�Ƃ��Ȃ�߂����ƂɋC���t�����B������ʔ��������ł���B
2017.09.05 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`�O�ҁu�N�����m�v�L�q�͕s���m
 �@����A���T�C�g�̎�Î�K������A��Cafe ELGAR�̓X��Ƃ���������̃��[�����]������Ă����B5��15���t���u�N�����m�v�`�u�G���K�[�w���̈��A�x�ƃh���}�w���_�x�ɓZ���ʔ��b�v��ǂ�ł��������Ă̂��̂������B���T�C�g�̓c�C�[�g��t�X�^�C�����̂��Ă��Ȃ����߃��[������̂͋H�B���ꂾ���ɋ����ÁX�E�E�E�E�E�ǂ�ł݂�ƁA���҂Ɉ�킸�Z�����e�̂��̂������B
�@����A���T�C�g�̎�Î�K������A��Cafe ELGAR�̓X��Ƃ���������̃��[�����]������Ă����B5��15���t���u�N�����m�v�`�u�G���K�[�w���̈��A�x�ƃh���}�w���_�x�ɓZ���ʔ��b�v��ǂ�ł��������Ă̂��̂������B���T�C�g�̓c�C�[�g��t�X�^�C�����̂��Ă��Ȃ����߃��[������̂͋H�B���ꂾ���ɋ����ÁX�E�E�E�E�E�ǂ�ł݂�ƁA���҂Ɉ�킸�Z�����e�̂��̂������B�@�܂��́A���̕��͂�v�Ă������B
2013�N11��6���̌ߌ�A���C�Ȃ��h���}�u���_�v�̍ĕ��f�����Ă�����A�����ɃG���K�[�u���̈��A�v���o�ꂵ���B�V���[�Y2��7�b�u���������́v�ł���B����͖��ȋi���E�a�J���C�I���ƌ���ꂽ�B���J�L�����鐙���E���Ǝᏼ���j�����鑽�������Ƃ̂����ł̉�b�B�@�Ƃ܂��A�u���_�v�X�^�b�t�ւ̔��Ȋ��N�Œ��߂Ă���B�ȉ��͂���ɑ��鋌Cafe ELGAR�X�傩��̃��[���ł���B
�������@�����ł����@�G���K�[���D���ł���
�E���@�@ �D���ł��˂�
�������@���ɂ��́u�~�j�A�`���A�v�͑f���炵��
�E���@�@ �m�[�}���E�f���E�}�[�̖��Ղł���
�������@�ނ̎w������G���K�[�͂�����i�ł���
�E���@�@ ���̒��ł��u���̈��A�v�����ɂ����ł���
�������@����ł��ˁi�Ə�����w�����j
�E���@�@ ���̔Ղ������̂ƃA�����W������Ă����ł���
�������@�m���Ă܂��@�����ɃG���K�[�́u�~�j�A�`���A�v������̂��f���炵��
�@�@�@�@�@ ����A�f�G�ȕ��Ƃ��m�荇���ɂȂꂽ
���ȋi���ŗאȂƂȂ��������E���Ƒ��������͈ӋC�����B��l�͂����Ŗ��Ă���u���̈��A�v���]�~����荇���B�p���ʂ̉E���́A�L�b�p���Ɓu�m�[�}���E�f���E�}�[�i1919�|1994 �C�M���X�̉��y�w�ҁ��w���ҁj�́w���̈��A�x�͑��̔łƂ̓A�����W���Ⴄ�v�ƌ����B
���́A�����ŏ��߂āu�~�j�A�`���A�vMiniatures�̑��݂�m�邱�ƂɂȂ�A��������CD���w���B�u���̈��A�v�ɒ����������B����͑f���炵���A�����W�����t�ŁA�����E���̑䎌�ɊԈႢ�͂Ȃ������B
�G���K�[�̎�ɂȂ�I�P�łł́A����������y���t�ŃX�^�[�g���邪�A�f���E�}�[�ł̓\���E���@�C�I�����Ŗ��₩�Ɏn�܂�B�����ɖ؊NJy�킪���݂Ȃ���A���X�ɃX�g�����O�X�̌��݂������Ă䂫�N���C�}�b�N�X���`���A�Ō�̓z�����������▭�ȋ����̒��Â��ɏI���B�G���K�[�łɔ䂷�Ƃ�莺���y�I���B�G���K�[���I�P�ł�������ۂɈӐ}�����̂́A�I���W�i���̃f���I�Ƃ͈Ⴄ�Y��ȃI�[�P�X�g���I�������������낤���A�f���E�}�[�͋t�Ƀf���I���u�������A�����W�����݂��̂��낤�B���̂�����̗��҂̎v�f�̈Ⴂ���ʔ����B
�u���_�v���f��4�N��A���N4����FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v�Łu���̈��A�v���̂�グ���B�����ʼn��߂ăh���}�̘^������A�����ŗ����u���̈��A�v���������蒮���Ă݂��B�u�I���I�v�Ɗ������̂ł���B����́A�f���E�}�[�Ղ̉��ł͂Ȃ��I�E�E�E�E�E���ׂ���A�A���h�����[�E�f�C���B�X�w���FBBC�����y�c�̍�Ȏ҃A�����W�łƔ��������B����͑䎌�ɋU�肠��ł���B��̂Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N�������̂��낤���H
�h���}�ɓo�ꂷ��R���e���c��LP���R�[�h�ł���B�E�����������Ƀv���[���g���錏�ł�������ƃW���P�b�g���f���Ă���B����͕�����Ȃ��f���E�}�[�́u�~�j�A�`���A�v�B���̉����g���Ή�����͂Ȃ������͂��B�Ȃ̂ɂ������Ȃ������̂́A����Ȃ�̎���������̂��낤�B�����ŁA��ނȂ��A���h�����[�E�f�C���B�X�Ղ��g�����B�u�䎌�Ƃ͐H���Ⴄ���A�ǂ�������͂��Ȃ��v�ƃv���f���[�T�[�������������������ۂ��͕s�������A�Ƃ�����A���ՂȑI�������Ă��܂����̂͊ԈႢ�Ȃ��B�u�m�[�}���E�f���E�}�[�̂͑��̔łƂ̓A�����W���Ⴄ��ł��v�Ɛ����E�����]�~����点��̂Ȃ�A�����͉������ł����̉���T���o���Ďg���̂����m�����l�Ԃ̗ǎ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��낤���B�u���_�v�X�^�b�t�̖ҏȂ𑣂������B
�u�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v��ʔ����q�ǂ������܂����B�u���������́v�����f���ꂽ�̂�2003�N11���̂��Ƃł��B���̂��뎄�͋��s��Cafe ELGAR�Ȃ�J�t�F���c��ł���܂����i���łɕX���Ă���܂��j�B�@�Ȃ�ƁA�ԑg�Ƀf���E�}�[�́u���̈��A�v�������A������LP�W���P�b�g��݂��o���ꂽ���Y�҂���̃��[���������̂ł���B����ɂ��A�u���������́v�̃I���W�i�����f����2003�N11���ł��������ƁA����͓��f�e���r�ł��邱�ƁA�r�{�͟N�䕐������ł��邱�ƁA�Ȃǂ������B���ł����ڂ́A�݂��o���ꂽ�̂̓W���P�b�g�݂̂ł��������ƁB�Ȃ�A���̉����͍̂�o���Ȃ��B�^�₪����@�ł����B�k�o�Ղ̒�����݂��o���Ȃ��̂́ACD��l�b�g�z�M����̍��̎Ⴂ���X�ɂ͑z���ł��Ȃ����Ƃ�������Ȃ����A��X�Â�����̐l�ԂɂƂ��Ă͓��R�̍s�ׁB�Ֆʂɏ�����������Ԃ������Ȃ�����A�Ղ��Ƒ݂��o���͖̂{���ɐM�p�̂�����g�߂Ȑl�Ɍ����Ă������̂��B
���m�Ȍ����͉����Ă���܂��A���f�̂��������ē��炾�����Ǝv���̂ł����A�X�ɓd�b���������Ă��܂����B
�u�G���K�[�̃~�j�`���A�[���̃��R�[�h��T���Ă���̂�����ǁA�ǂ����Ŏ�ɓ������@���Ȃ����v�Ƃ����₢���킹�ł����B���Ƃ��E�`�͈��H�X�ł����āA���R�[�h�X�Ȃǂł͂���܂���B���A���Ճ}�j�A�����������O�A�ނ��ɐ�̂ɂ���R������܂����B�����Łu���ÔՂ�T���������@�͂���܂��A�}�j�A�b�N�ȃ��R�[�h�����ɁiCD����̍��ł́j�_�����ނ悤�Șb�ł��v�Ɛ\���グ��Ɨ��_���ꂽ�悤�ŁA�Ȃ�ł��h���}�Ő��J�L���剉�Ȃ̂����A������Ŏg�������̂ŒT���Ă���Ǝ����b����܂����B�C�̓łɊ������̂ƁA���̂�̂��l�D������u�悩�����炨�݂����܂��傤���BLP�Ղ������Ă��܂����E�E�E�E�E�v�Ƃ��`����������ł��B����ēx�d�b�������āu��͂肨�݂����������B�������ł����肭������Ό��\�ł��̂Łv�Ƃ̐\���o������A�W���P�b�g�����ł����A���݂������Ƃ���������������܂��B
�u���������́v�͟N�䕐���Ƃ������̋r�{�ł��B����Cafe ELGAR�̃E�F�u�T�C�g�i�X�ƂƂ��ɍ폜�j���Q�Ƃ��ċr�{�������ꂽ�ӂ�������A���̃T�C�g�ł̓f���E�}�[�́u�~�j�`���A�[���v�𖼔ՂƂ��ďЉ�Ă��܂����i�킽�����̋L�q�j�B�u�A�����W���قȂ�v�Ə������̂��u�~�j�`���A�[���v�����ՂƏЉ���̂����͎��Ȃ�ł��ˁB�G���K�[�����Ŗ��������F�E���z���ꂳ������̃A���o���Ɋւ��Ă͑傫���̂�グ�Ă��܂���B
�킽�������u���������́v�����ĉ����ɗ��_�����܂����B�����A��{�i�W���P�b�g�̕ԗ�ɓ��f���炢�������܂����j������ƁA�����t�ł����A�u�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v�̋L�q�͐��m�ł͂���܂���B
�@����ɁA���肪�����̂́A�h���}�̑�{�̑S�e��Y�t���Ă������������ƁB�����āA���̋�Cafe ELGAR�X��̕��́A���R�A�����Ŋ|�������������Ⴄ���Ƃ��F�����Ă���������B���̏�ŁA���̋L�q�����m�ł͂Ȃ��Ƃ��������B���������ǂ����H �����͎���ŁB
�@�����̎ʐ^�͋�Cafe ELGAR�ł���B���s�ɂ��������̓X�������K�˂Ă݂����Ǝv���Ă������A���[���ɂ�����悤�ɁA�c�O�Ȃ���X�����Ƃ����B
2017.08.15 (��) �^�Ă̖�̖��`�V�F�C�N�X�s�A ���ꂱ��
�@�����I�Ƃɂ��������B�Q�ꂵ�����Ė������Ă���B���������u�^�Ă̖�̖��v���Ă���܂����ˁB�Ƃ������ƂŁA�����́u�^�Ă̖�̖��v�`�V�F�C�N�X�s�A�ɕ��������Ă݂悤�B �@���ɂƂ��āu�^�Ă̖�̖��v�Ƃ���A�����f���X�]�[����Ȃ̌����y���܂����ɕ����ԁB�S10���Ȃ̒��ł́A�u�����s�i�ȁv���_���g�c�̒m���x�����A�u�X�P���c�I�v�u��z�ȁv�u�����҂����̗x��v�ȂǁA���z�I�Ŋy�������Ȃ���t���B
�@���ɂƂ��āu�^�Ă̖�̖��v�Ƃ���A�����f���X�]�[����Ȃ̌����y���܂����ɕ����ԁB�S10���Ȃ̒��ł́A�u�����s�i�ȁv���_���g�c�̒m���x�����A�u�X�P���c�I�v�u��z�ȁv�u�����҂����̗x��v�ȂǁA���z�I�Ŋy�������Ȃ���t���B�@�����f���X�]�[��(1809�|1847)��17�̂Ƃ��ɂ��̋Y�Ȃ��ςĊ����B�����ɏ��Ȃ������グ��B���ꂩ��17�N��A�v���C�Z�������t���[�h���q�E�E�B���w����4���̖��ɂ��S�Ȃ����������B8��24���́u���N���v�ł́A�u��z�ȁv��������|���悤���ȁB
�@�Y�Ȃ́A�E�C���A���E�V�F�C�N�X�s�A�i1564�|1616�j�̍�ŁA1596�N����̍�i�B�^�C�g���́uA Midsummer Night's Dream�v�ł���B���炷���́A�u�Ƃ���̓M���V�� �A�e�l�ߍx�̐X�B�����ɂ͂�����������������Ɖ����A�d�����Z�ށB��g�̒j�������āA���������Ă��Ȃ��畃�e�Ɍ�������Ă���ȂǁA���������������Ă���A�X�ɖ������ށB�X�̒��ł��ꂱ�ꂠ������A�d���̌v�炢�ɂ���āA��g�̒j���͂߂ł�����������v�Ƃ������́B
�@���낢�뒲�ׂĂ��������ɁA������ƕs�v�c�Ȏ����ɋC�������B����͓��{��^�C�g���B���y�̏ꍇ�́u�^�Ă̖�̖��v��{�����A�Y�Ȃɂ́u�^�Ă̖�̖��v�Ɓu�Ă̖�̖��v�̓�ʂ肠��B����͂ǂ��������ƁH�ǂ��炪�����Ȃ́H�u�N�����m�v�I�T���S���N���Ă����B
(1)�u�^�Ă̖�̖��v���u�Ă̖�̖��v��
�@�ŏ��̖�́A���{�ߑ㕶�w�̐��ҁE�ؓ�疗y�i1859�|1935�j�B���̃^�C�g���́u�^�Ă̖�̖��v���B�����Midsummer ���ʂ�u�^�Ắv�Ɩĉ����a���͂Ȃ��B
�@����Ɉق��������̂��y����m�i1886�|1979�j�B��4����1��A�V�[�V���[�X�̑䎌�Ɂu�����ƁA�܌��Ղ̉Ԃ�E�����Ƃ��āv�Ƃ��邩��A5��1���O��̏o�����ƕ�����B���{�ł͏t�B�Ď��Ƃ����ǂ��p���̖�͏����炸�����炸�A�܂��Ƃɉ��K�B���������āu�^�āv�͂��������B���߂āu�Ă̖�̖��v�Ƃ��ׂ��B1940�N�̂��ƁB
�@1960�N�A���c�P���i1912�|1994�j���A�j���A���X�͈قȂ邪�A����ɑ����B�Ȍ�u�Ă̖�̖��v�h���吨���߁A���c���Y�u�������a�q������ɕ키�B���A�ʂ����Ă����̂����̌X���B�䂪�u�N�����m�v�I���������L�B
�@�܂��u�܌��Ձv�̌��B�u�܌��Ձv�Ƃ��������͑�4����1��A�V�[�V���[�X�̑䎌�Ƃ���2�x�o�Ă���B�u����Ō܌��Ղ̍s���͖����ɏI������v�Ɓu�����ƌ܌��Ղ̉Ԃ�E�����Ƒ��N�����Ă��̐X�ɂ����̂��낤�v�B��x�Ȃ炸��x�܂ł��Ȃ�u�܌��Ձv�͒e�݂ŏ��������̂ł͂Ȃ����낤�B�V�F�C�N�X�s�A�͂��̏o�������u�܌��Ձv�ɐݒ肵�Ă���͖̂��炩���B�Ȃ�Ύ�����4�����`5�������B
�@���ɁA�^�C�g���uA Midsummer Night's Dream�v��������BMidsummer Night �� Midsummer Day �̑O��̂��ƁBMidsummer Day �Ƃ͐����n�l�̏j���̂��Ƃ�6��24���B�����n�l�͕ʖ�����҃��n�l�Ƃ����A�C�G�X�E�L���X�g�ɐ�������������ҁB���܂ꂽ�̂��L���X�g�̔��N�O�Ƃ������Ƃ���A6��24����a�����Ƃ��Ă��̓����j���ƒ�߂��B����ŁA�Ď��ՂƂ����̂������āA����͕����ʂ�Ď��̓��ɑ��z���j���Ղ̂��ƁB6��21��������B�����͑S���ʂ����A�قړ������ɂ��邽�߁A����������I�ɓ��ꎋ�����悤�ɂȂ����BMidsummer Day �Ƃ����A�u�����n�l�̏j���v�ł���u�Ď��Ձv�ł���Ƃ����悤�ɁB
�@�u�Ă̖�̖��v�h���c�P���̌������́A�uMidsummer Day �͐����n�l�̏j����6��24���BMidsummer Night �͂��̑O��B������g�^�Ắh�ł͂Ȃ��g�Ắh�ł���B�������A�Ď��̍�������w�Ď��O��̖��x�Ƃ̒�����B�w�Ă̖�̖��x���Ó��ł���v�Ƃ������́B �@���c���́A�^�C�g���������玞��������o���A�u6���́A���{�ł͐^�Ă���Ȃ��v�Ƃ���B�����́u�܌��Ձv�ւ̌��y�̓i�V�B�o������5���ł���̂Ƀ^�C�g���� Midsummer Night �Ƃ��������B������ǂ��l����H �ȉ��͎��̌����ł���B
�@�p�a���T�������Ă݂�Bmidsummer �̌`�e���ɂ́u�^�Ắv�̑��Ɂu�^�Ă̂悤�ȁv�Ƃ����Ӗ��E�p�@������B�p��Ƃ��� midsummer madness �� �勶�� �Ƃ̕��L������B���� midsummer �́u�^�Ă̂悤�ȃn�`�����`���ȁv�Ƃ����j���A���X�ɂȂ邾�낤�B�Ȃ�� A Midsummer Night's Dream �́u�^�Ă̂悤�ȃn�`�����`���Ȗ�̖��v�ł���B����Ȃ�5���ł�6���ł��������A����̓��e�ɂ��s�b�^�����B���_�����{���Ƃ��đ��������̂́u�^�Ă̖�̖��v�ł���B
 �@�ێq��K�I���߂̓V�F�C�N�X�s�A�̐��_�ɂ�����Ȃ��B�V�F�C�N�X�s�A�͐l�Ԃ������Ďێq��K�ő����Ȃ��B�l�ԓ��m�̊W���̒��ŁA�_��ɑ�����̂ł���B������l�ԁA������l�ԁB�P�s�����s���A������������A�P���̌��ߕt���͂��Ȃ��B�u����ł����̂��v�ł���u���ꂪ�l�ԂȂ̂��v�ł���B���̕ӂ�́A���c���Y�u�u�V�F�C�N�X�s�A�̐l�Ԋw�v�Ŗ��炩�B����͑f���炵���{�����A���ꂾ���ɁA���c���u�Ă̖�̖��v�Ȃ͎̂c�O���B
�@�ێq��K�I���߂̓V�F�C�N�X�s�A�̐��_�ɂ�����Ȃ��B�V�F�C�N�X�s�A�͐l�Ԃ������Ďێq��K�ő����Ȃ��B�l�ԓ��m�̊W���̒��ŁA�_��ɑ�����̂ł���B������l�ԁA������l�ԁB�P�s�����s���A������������A�P���̌��ߕt���͂��Ȃ��B�u����ł����̂��v�ł���u���ꂪ�l�ԂȂ̂��v�ł���B���̕ӂ�́A���c���Y�u�u�V�F�C�N�X�s�A�̐l�Ԋw�v�Ŗ��炩�B����͑f���炵���{�����A���ꂾ���ɁA���c���u�Ă̖�̖��v�Ȃ͎̂c�O���B�@���������A�u�Ă̖�̖��v����A�^�C�g���Ƃ��ăL���b�`�[����Ȃ��B���C�J�R���̂��u�Ă̖�̖��v�ŁA�T�U���̂��u�Ẳʎ��v���ᔄ��܂����B��͂�u�^�Ă̖�̖��v�ł���u�^�Ẳʎ��v����Ȃ��ƂˁB
(2)�V�F�C�N�X�s�A�ʐl����������Ƃ���
�@�V�F�C�N�X�s�A�͒N�^������ �Ƃ���ʐl���͐������B���̎�̘b�͗��j�D���ɂ͂��܂�Ȃ��B���͂����������A��������̗ށA�Ⴆ�A��{���n�E���̍����͐��������H �W���M�X�J���͋`�o�ł���H �G���͏G�g�̎��q�ł͂Ȃ��H �������q�s�ݐ��A�m�ԔE�Ґ��A���X�������m���܂߂āA�����ɂ��Ƃ܂Ȃ��B�Ƃ͂����A�V�F�C�N�X�s�A�ʐl���̑����́A��i�̖��͂Ɠ䑽���l���̂Ȃ���Ƃ��낤�B
�@�����ŁA�V�F�C�N�X�s�A�ʐl�����ׂĂ������邱�Ƃ͕s�\�B10��20���Ⴋ���Ȃ��悤���B��O��_���Ă����r���[�B�Ȃ�A�����ł��M�ߐ��������ƍl���������������グ�悤�B����́u�w�����[�E�l���B�����v�ł���B
�@���c���Y�u���ɂ��ƁA�V�F�C�N�X�s�A�̐l�Ԋς͗c���N���ɂ�����Ɖ^�̕������݂ɉe������Ă���Ƃ����B���W�����͏����ɐ������A�V�F�C�N�X�s�A�����܂ꂽ���N�ɂ͒���c���ɁA4�̎��ɂ͒����ɂ܂łȂ������̖��m�B�Ƃ��낪10���߂������납��o�ϓI�ɖv���i���l���x������Ɏ��s�����Ƃ��j�B�N������`���z�����ꂽ�c�N������A��]�A���͂̂��ׂĂ��悻�悻�����Ȃ鏭�N���ցB���Ԃ̎�����m�邱�ƂɂȂ�B
�@���c�����͂܂��A�V�F�C�N�X�s�A���o�ϓI���R�����w�ɍs���Ȃ��������Ƃ��A�앗�ɍD�e����^���Ă���ƌ����B�����̓��l�T���X���B��w�ɍs�����[�}������{�ƂȂ�B�����A�ϐ�������Ƃ���ÓT��`�B��������o��������A���Ǝ��R���|�Ƃ���V�F�C�N�X�s�A�����}����`�����܂ꂽ���ǂ����H
�@�ނ̎�N���̐l�����A�V�F�C�N�X�s�A�����̐F���������߂��킯�����A������ł��Ȃ����Ƃ�����B�ނ̍�i�ɂ����Γo�ꂷ��O���̒n�E�E�E�E�E�u���F�j�X�̏��l�v�Ɓu�I�Z���v�̓��F�l�`�A�A�u�����I�ƃW�����G�b�g�v�̓��F���[�i�A�u�n�����b�g�v�̓f���}�[�N�A�u�^�Ă̖�̖��v�̓A�e�l�A�u���Ⴖ��n�Ȃ炵�v�̓p�h���@�ȂǁB�����ɕK�v�ȊO���̒m�������K�������̂��H �Ƃ��낪�A�V�F�C�N�X�s�A�̓C�M���X���O�ɏo���`�Ղ͂Ȃ��B�O�����O���{��̒m������������\���������̂ł���B�����ŁA��l�̐l���ɃX�|�b�g�����������B���̐l�̖��̓w�����[�E�l���B���B
 �@�w�����[�E�l���B�����V�F�C�N�X�s�A���́A�ӊO�ƐV�����A2005�N�A�E�F�[���Y��w���r���V���^�C�������炪���\�����B�w�����[�E�l���B���i1562�|1615�j�́A�I�b�N�X�t�H�[�h��w���o�ĊO�����ƂȂ����l���B�V�F�C�N�X�s�A�Ƃ͐e�ʓ��m�ł���A�����N��͂قړ����B�V�F�C�N�X�s�A�̃p�g�����ł���T�E�T���v�g�����Ƃ��e���������悤���B�c����Ă��镶�̂��V�F�C�N�X�s�A��i�Ƌ߂��Ƃ��B�ő�̃|�C���g�͊O�������������ƁB�V�F�C�N�X�s�A�ł͒m�肦�Ȃ��͂��̊C�O�{��̂�������⎖��A�O����̒m���Ȃǂ��n�m������L�����A�������Ă������Ƃ��B�V�F�C�N�X�s�A�ɊC�O�n�q�̌`�Ղ��Ȃ����Ƃ��l�����킹��ƁA���̃l���B�����V�F�C�N�X�s�A���ɂ���������̂�����B
�@�w�����[�E�l���B�����V�F�C�N�X�s�A���́A�ӊO�ƐV�����A2005�N�A�E�F�[���Y��w���r���V���^�C�������炪���\�����B�w�����[�E�l���B���i1562�|1615�j�́A�I�b�N�X�t�H�[�h��w���o�ĊO�����ƂȂ����l���B�V�F�C�N�X�s�A�Ƃ͐e�ʓ��m�ł���A�����N��͂قړ����B�V�F�C�N�X�s�A�̃p�g�����ł���T�E�T���v�g�����Ƃ��e���������悤���B�c����Ă��镶�̂��V�F�C�N�X�s�A��i�Ƌ߂��Ƃ��B�ő�̃|�C���g�͊O�������������ƁB�V�F�C�N�X�s�A�ł͒m�肦�Ȃ��͂��̊C�O�{��̂�������⎖��A�O����̒m���Ȃǂ��n�m������L�����A�������Ă������Ƃ��B�V�F�C�N�X�s�A�ɊC�O�n�q�̌`�Ղ��Ȃ����Ƃ��l�����킹��ƁA���̃l���B�����V�F�C�N�X�s�A���ɂ���������̂�����B�@�����A�l���B�����C�R�[�� �V�F�C�N�X�s�A�������A�Ƃ͎v���Ȃ��B�߂����ԕ�����������A���k����E�����҂������\���͑傫���B�V�F�C�N�X�s�A��i���ق�̋͂������������ĂȂ������Ƃ����A���̓���ɒNjy���Ă��錤���҂̐��Ɂu�������������v�����鎑�i���Ȃ����A����ȑf�l�l���������Č��킹�Ă��炦��Ȃ�A�u�w�����[�E�l���B���̓V�F�C�N�X�s�A��i�ɏ��Ȃ��炸�֗^���Ă���v�A�ƍl������̂ł���B
���Q�l������
�u�Ă̖�̖��v���c���Y�u��i����U�u�b�N�X�j
�u�n�����b�g�v�@�@�@�@�V
�u�V�F�C�N�X�s�A�̐l�Ԋw�v���c���Y�u���i�V���{�o�ŎЁj
2017.07.25 (��) �ẴN���V�b�N���y�`�u�����N���V�b�N�v����
 �@������3�ؗj���ɏo������FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v�B���āA���X�����j���[�A���B�V�f�B���N�^�[Noririn������́A�p�[�\�i���e�B�[�ޗǒ��q����Ƃ̑����s�b�^���B�X�^�W�I�͂���[�h��t�ɕω��B���A�N���V�b�N�������������ė����I�H ����ȕ��͋C�������ɓ`���̂��A�u������y���������܂����v���X�u���N���v�ւ̓��������X�ɑ����Ă��܂����B���ꂵ������ł��B7���͉ĂɈ��I�ȂŁB
�@������3�ؗj���ɏo������FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v�B���āA���X�����j���[�A���B�V�f�B���N�^�[Noririn������́A�p�[�\�i���e�B�[�ޗǒ��q����Ƃ̑����s�b�^���B�X�^�W�I�͂���[�h��t�ɕω��B���A�N���V�b�N�������������ė����I�H ����ȕ��͋C�������ɓ`���̂��A�u������y���������܂����v���X�u���N���v�ւ̓��������X�ɑ����Ă��܂����B���ꂵ������ł��B7���͉ĂɈ��I�ȂŁB(1) ���B���@���f�B�́u�l�G�v����u�āv��3�y��
 �@�܂��͖��h����̃��B���@���f�B���t���t�ȁu�l�G�v����u�āv��3�y�͂��C�E���W�`���t�c�i�A�[��2�x�ڂ̘^���j�̉��t�ŁB�����r�N�^�[�̎Ј�������1960�|70�N��̓o���b�N���y�̑�u�[���B��ڂ������̂��u�C�E���W�`�̎l�G�v�ł����B
�@�܂��͖��h����̃��B���@���f�B���t���t�ȁu�l�G�v����u�āv��3�y�͂��C�E���W�`���t�c�i�A�[��2�x�ڂ̘^���j�̉��t�ŁB�����r�N�^�[�̎Ј�������1960�|70�N��̓o���b�N���y�̑�u�[���B��ڂ������̂��u�C�E���W�`�̎l�G�v�ł����B�@�u�C�E���W�`�̎l�G�v��6W�̘^��������A���v�v300�����̔���グ�B�ŏ��͏��ナ�[�_�[ �t�F���b�N�X�E�A�[���̃��@�C�I�����Ƒt�Ձi1955�N���m�����^���j�ŁA���ꂪ�u�l�G�v�̐��E���^���B2�ڂ͓����A�[���̃X�e���I�Ձi1959�N�^���j�B3�ڂ����x���g�E�~�P���b�`�̃\���i1969�N�^���j�B���ꂪ�N���V�b�N�E�B��̃~���I���Ƃ����钴����q�b�g��ƂȂ�܂����B�ł��܂��A����̓A�[���Ղ̖��~���̎����B�u�l�G�v�͎������@�C�I�������t�ȂȂ̂ŁA�\���E���@�C�I�������傫�Ȕ�d���߂܂����A�A�[�����f�R�B�Z�ʂ��Ⴂ�܂��B���݂ɃA�[���́A�䂪�h������Έ�搶�̂���l�ł���q����̎t�B�ޏ��͌��݃T���t�����V�X�R�̌���I�[�P�X�g���̃��@�C�I�����t�҂Ƃ��Ċ������ł��B
(2) 3��e�m�[�� 1994�N���T���W�F���X�E�h�W���[�X�^�W�A������
 �@�Ă͖�O�C���F���g�̃V�[�Y���B�����ł����́A1994�N�́u3��e�m�[���E�h�W���[�X�^�W�A�������v���Ƃ�グ�܂��B
�@�Ă͖�O�C���F���g�̃V�[�Y���B�����ł����́A1994�N�́u3��e�m�[���E�h�W���[�X�^�W�A�������v���Ƃ�グ�܂��B�@3��e�m�[���A���͎��A1996�N6��29���̓��{�����ɍs���Ă܂��āB��Əf��Ƌ��ɁB�A���R�[���Ɂu��̗���̂悤�Ɂv���c�X�Ƃ������{��ƘN�X��������ʼn̂����̂��Ƃ�킯��ۓI�ł����B
�@3��e�m�[���̊��́A�z�Z�E�J�����X�̔����a�S���j���ɂƃv���V�h�E�h�~���S�ƃ��`�A�[�m�E�p���@���b�e�B�����āA�܂����T�b�J�[�E���[���h�J�b�v�E�C�^���A���J�Êԋ߁B3�l�Ƃ���̃T�b�J�[�t�@���Ƃ������Ƃ������āA�b�̓g���g�����q�ɐi�݁A�����̑O��ՂƂ��čs��ꂽ�̂���1��B1990�N7��7���A���[�}�̓J���J���嗁��Ղł̊J�Âł����B
�@���̌�A�T�b�J�[�E���[���h�J�b�v������O��J�ẤA2002�N���ؑ��̉��l�A���[�i�����܂őS4��𐔂��A����ȊO�ł́A1996�N���{��������Ƃ������E10���������ȂǁA2003�N�܂ő����܂����A2007�N�A�p���@���b�e�B�̎��ɂ���ďI����������̂ł��B
�@�����20��قǂ̌����̒��ŁA3�l���ō��̃p�t�H�[�}���X���������̂��A1994�N7��16���A���[���h�J�b�v�E�A�����J�����̑O��ՂƂ��āA���T���W�F���X�E�h�W���[�X�^�W�A���ōs��ꂽ�����ł��傤�B
�@�z�Z�E�J�����X47�A�v���V�h�E�h�~���S53�A���`�A�[�m�E�p���@���b�e�B58�B�܂��ɐⒸ����3�l�B�e�l�����Ȃ�����ɃA�s�[������I�y���E�A���A�̋����B�t�ɁA3�l�����͂������Ĉ�Ȃ��d�グ��a�C���������̃R���{�B���̑Δ䂪�▭�ł����B����Ȓ��ŁA�����I�̂�3�l���u�}�C�E�F�C�v���̂��p�t�H�[�}���X�B
�@�u�}�C�E�F�C�v�̓t�����N�E�V�i�g��(1915�|1998)�̑�\�ȁB���X�̓V�����\���B��������|�[���E�A���J���g�V�i�g���̂��߂Ɂh�p�ꎌ�����Ȃ��蒼���������́B1969�N�ɔ��������ƃ����O�E�Z���[���L�^�B�V�i�g���̉̎�l���̃V���{���E�\���O�ƂȂ�܂����B
�@�܂��A�J�����X���i�������̂��o���A�h�~���S����M�I�Ɍq���A�p���@���b�e�B�����҂̕��i�Ő���グ�āA�O�d���ŃG���f�B���O�B3�l�̈����̉̏��ɁA�O��ɐw������V�i�g�����X�^���f�B���O�ʼn�����B�S�Ȃ������ޓ��A�u�u���{�[�v�̙ꂫ�B����Ȍ��i���f����ʂ��ē`����Ă���A���Ɋ����I�ȃV�[���ł����B�V�i�g���ƃp���@���b�e�B�́A��1995�N�A�u�}�C�E�F�C�v�̃f���G�b�g�^�����d�グ�A���������e�C�N�݂͌��̃������A���o���ɃL�b�`���Ǝ��߂��܂����B�V�i�g���́u�}�C�E�F�C�`�t�����N�E�V�i�g��80th�A�j�o�[�T���[�v�A�p���@���b�e�B�́u�p���@���b�e�B�`�U�E�O���C�e�X�g�E�q�b�c50�v�ł��B
�@���������ɍs��ꂽ���[���h�J�b�v�����́A�u���W�����C�^���A��j���ėD�����܂����B��Y��ĂȂ�Ȃ��̂́A���̃A�����J�E���[���h�J�b�v�́A���̃h�[�n�̔ߌ����Ȃ���Γ��{�����o����ʂ����Ă������ł����B�T�b�J�[���{��\�͎���t�����X���ŔO��̏��o����ʂ����A�Ȍ�5���A���o�ꂵ�Ă��܂��B���݁A���{��\��2018�N���V�A�E���[���h�J�b�v�Ɍ����ăA�W�A�ŏI�\�I�̐��O����}���Ă��܂��B��ʂɗ����Ă͂��܂����A2�ʃI�[�X�g�����A��3�ʃT�E�W�A���r�A�Ƃ͏����_���P�B�ǂ��炩�ɏ��ĂΌ�����A�������������ł͊낤���B���Ƃ��Ăł�8��31���A�z�[���̃I�[�X�g�����A��ɏ����ăX�J�b�ƌ��߂������́B�����A�݂�Ȃʼn������悤�I
(3) �T���E�T�[���X��ȁF�g�ȁu�����̎ӓ��Ձv����u�����فv
 �@3��e�m�[���Ƃ������C���E�f�B�b�V���̂��Ƃ́A�u�₩�ȃf�U�[�g�ƎQ��܂��傤�B
�@3��e�m�[���Ƃ������C���E�f�B�b�V���̂��Ƃ́A�u�₩�ȃf�U�[�g�ƎQ��܂��傤�B�@7���ɂ́u�C�̓��v������܂��B�C�֘A�̖��Ȃ͐��X����܂��āB�Ⴆ�h�r���b�V�[�̌������u�C�v�B����́A�y���̕\���ɖk�ւ́u�_�ސ쉫�Q���v���\��t���Ă���̂ʼn�X�ɂ͓���݂��[���B�u���e���́u�l�̊C�̊ԑt�ȁv�͉̌��u�s�[�^�[�E�O���C���X�v����̊nj��y�ȁB�C���O�����h�����E�k�C�̍r������C�ݕ��i���ڂɕ����т܂��B���H�\���E�E�B���A���Y�Ɂu�C�̌����ȁv�Ƃ����̂�����܂����A����Ɓu��Ɍ����ȁv�͊����̃N���V�b�N�̑���H �������Ђ����Ă�1970�N�O��̓��{�r�N�^�[�̃N���V�b�N�́A�t�B���b�v�X��RCA�̔e�������^�������B�u�C�E���W�`�̎l�G�v�ő�q�b�g�����t�B���b�v�X�ɁA���C�o���S�ނ��o����RCA���ƕ����ł��ďo�������삪�A�A���h���E�v�����B���w�������h�������y�c ���H�\���E�E�B���A���Y��Ȃ́u��Ɍ����ȁv�Ɓu�C�̌����ȁv�ł����B�u�l�G�v�ɂ͋y�Ԃׂ�������܂��A�N���V�b�N�Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ��̃Z�[���X���L�^�����ƋL�����Ă��܂��B�w���̃A���h���E�v�����B��(1928�|)�̓W���Y�E�s�A�j�X�g����̓]���ҁB�������Ƃ��Č��݂̔ނ��f�r���[�͊����̂̎w���҂������̂ł��B
�@�Ƃ܂��A�u�C�v�֘A�Ȃ͐F�X����܂����A�Ȏ��́A������L���b�`�\����Ȃ��B�u���N���v�ɂ̓V���[�g���C���p�N�g���œK�Ȃ̂��B�����őM�����̂��u�����فv�ł����B�C�`���`�����ق̘A�z�͂��ꂵ���������ي肢�܂��傤�B���Q�̓K���x�ɖƂ��āB
�@�u�����فv�̓t�����X�̑��ȉƃT���E�T�[���X�i1835�|1922�j�̑g�ȁu�����̎ӓ��Ձv��7�ȖځB���t����2�������Ȃ���A��x��������Y����Ȃ���ہB���z���E�_�銴�E�������̃g���v���E�Z���X�B�����ق̐�������O�ɕ����т܂��B���̉����̋Z�́A�������j�㏉�̉f�批�y�̍�ȉƃT���E�T�[���X�̓V�ː��I
�@�閧�̓T�E���h�B�����o���y��̓O���X�n�[���j�J�B���̊y��A�Ȃ�Ƃ��́u���͓d�C�ł���v���Ƃ��ؖ������x���W���~���E�t�����N�����i1706�|1790�j�̔����Ȃ̂ł��B���ʼn������������C���O���X���w�ŎC���ĉ����o���̂��O���X�n�[�v�B������y��Ƃ��Ċ����������̂��O���X�n�[���j�J�ŁA�ގ��g�u�A�����j�J�v�Ɩ������܂����B1761�N�̔�����A��q�b�g�ƂȂ�A�Ȃ�ƃ��[�c�@���g�����̊y��̂��߂Ɂu�O���X�n�[���j�J�̂��߂̃A�_�[�W���n���� 617a�v�Ȃ�Ȃ������Ă��܂��B
�@�Ƃ��낪�ł��B�����܂ŃO���X�n�[���j�J�̂��b�����Ă����̂ɁA������������CD �V�������E�f���g���w�������g���I�[�������y�c�Ղ́A�O���X�n�[���j�J�ł͂Ȃ��`�F���X�^���g�p���Ă���̂ł��B����ł��Ȃ̕��͋C�͓`���̂ł����A�N���V�b�N��������Ƃ��ẮA���Ƃ��I���W�i���̃O���X�n�[���j�J�łł������������������B�͎��炸�c�O���ɁI ���ɐ\����܂���B����A�O���X�n�[���j�J�Łu�����فv����肷�ׂ��撣��܂��B�Q�b�g�����łɂ́A�K���u���N���v�ł����������邱�Ƃ������܂��B
�@�܂��܂��ҏ��������܂��B�u���N���v�����8��24���B�����q�u�Ă͖�E�E�E�E�E�v���������������o���āA��Ƃ������e�[�}�ɍl���Ă��܂��BNoririn�ցA�u��{���������V�N�v�B�ޗǂ���A�u�܂��y����������ׂ肵�܂��傤�v�B�ł͗����܂��B
2017.07.15 (�y) �h�L�������g�`�V���[���h���E���F�[�O��K137���𖾂���
�@����A�ƊE�̖��F�A�o�Ńv���f���[�X��Ђ��c��F������u�E�b�J��1���]���ɔ����Ă��܂������A�悩�����琥��v�Ƒ�1863��m��������t��̂��U�������B���_�u���Łv�Ƃ������ƂɂȂ�A6��30���ANHK�z�[���ɏo�������B�V���[�}���̉̌��u�Q�m���F�[���@�v���ȁ`�`�F�����t�� �C�Z���`�V���[�x���g�̌����� ��8�ԁu�O���[�g�v�Ƃ����ȖځB���̃v���O�����A���ɋ��ʂ��Ă��āA�I�y���Ă����ƔO������Ȃ������V���[�}���ƃV���[�x���g�̍�i�ō\���B�V���[�x���g�̌���u�O���[�g�v�̔����҂̓V���[�}���B�`�F�����t�Ȃ̃\���X�g�A�^�[�j���E�e�c���t�̃A���R�[���Ȃ�J.S.�o�b�n�̖����t�`�F���g�� ��1�Ԃ̃v�������[�h�ŁA�o�b�n�́u�O���[�g�v�̏����҃����f���X�]�[�����h����������ȉƁB�ȂǂȂǁA����Ȋ֘A���������̃R���T�[�g�́A�p�[���H�E�������B�̖����ȉ���肪�S�n�悭�A�����̎��Ԃ��߂������Ƃ��ł����BF���ɑ労�ӂł���B�@�����AF���Ɍ�烁�[���������Ƃ���A���Ԃ����[���̒��ɋ����[���ꕶ���E�E�E�E�E�B
�@�u������I�v�Ǝv�����͍̂Ō�̒i���A�u�f�B���F���e�B�����g �σ����� K137�̑�1�y�͂Ƒ�2�y�͂̏��������ւ��ĉ��t���Ă���v�Ƃ��������B����͍ŋ߁A���������߂����V���[���h���E���F�[�O�́u���[�c�@���g �Z���i�[�h���f�B���F���e�B�����g�W�vCD���w���E��������F�����C�Â��ꂽ�ꌏ�ŁA�����͕s�o�ɂ��A�S���F�m���ĂȂ��������B�����A�莝����CD���邱�ƂɁBK137�̎莝���́A�C�E���W�`���t�c�i1972�N�^���j�A�o�E���K���g�i�[�w���F���c�F�������y���t�c�i1976�j�A�p�C���[�������nj��y�c�i1977�j�A�{�X�R�t�X�L�[�w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�i1978�j�A�^�[���q�l�d�t�c�i1993�j�A�����ăV���[���h���E���F�[�O�w���F�U���c�u���N�E�J�����[�^�E�A�J�f�~�J�i1986�j�ł���B���������A���b�����т�Ă��܂������A���ꂩ�炷���A�V���[���h���E���F�[�O�̃��[�c�@���g���w���A�����n�߂Ă��܂��B���Ղ����Έ�搶�̕]�_���A�s�V�b�ƃ{�b�N�X�Ɏ��߂܂����B�܂��A�L���ǂ�����������ł����A�u�Ȃ������Ƒ����A���肵�Ȃ������̂��H�v�̎v���ɋ���܂��B�f���炵���I
���F�[�O�̌����A�l�@����ł��傤���A�Ⴆ���f�B���F���e�B�����g K137�B��1�y�͂Ƒ�2�y�͂̏��������ւ��ĉ��t���Ă��܂��B���ꂾ�Ƌ}�|�Ɂ|�}�ɂȂ�܂��̂ŁA�������ɂ��̂ق������R�ɁA�炵���������܂��B
�@F�����w�E�̒ʂ�A���F�[�O�Ղ̂ݑ�1�y�� Allegro di molt �` ��2�y�� Andante �ŁA����5�_�͑�1�y�� Andante �`��2�y�� Allegro di molt �̏����BF���̋L�q�ɏ]���A���F�[�O�Ղ͋}�|�Ɂ|�}�A���͂��ׂĊɁ|�}�|�}�̕��т��B
�@�Ȃ�Ίy���͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�H �����A�u�V���[�c�@���g�S�W�v�ׂ�ƁA��1�y�͂� Andante �ő�2�y�͂� Allegro di molt �������B�u�V���[�c�@���g�S�W�v�́A�h�C�c�̑��o�ŎЃx�[�������C�^�[���A�펞���M�C���������Ă��郂�[�c�@���g�y���̃X�^���_�[�h�B�قƂ�ǂ̉��t������ɏ�������͎̂��R�̐���s�����B���AK137�ɂ����āA���F�[�O�������i��1�y�͂Ƒ�2�y�͂́j���������ւ��Ă���B�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��H ���t�ƂƂ��Ă����y�w�҂Ƃ��Ă����ꗬ�̃��F�[�O���A�Ӑ}�Ȃ����ăX�^���_�[�h����E����͂����Ȃ��B
�@�V���[���h���E���F�[�O(1912�|1997)�Ɋւ��鎄�̒m���́H �܂��A�n���K���[�̖����@�C�I���j�X�g�ł��邱�ƁB���ɁA��ɂ��郔�F�[�O���y�l�d�t�c�́u�o���g�[�N ���y�l�d�t�ȑS�W�v�i1954�N�^���j�������]���Ă������ƁA���炢�̂��̂��B�ނ̃��[�c�@���g���t�̑f���炵���������Ă��ꂽ�̂́A�䂪�����[�c�@���g�����̑��l�ҁE�Έ�G�搶�ł���B
�@����́A�V���[���h���E���F�[�O�w���F�U���c�u���N�E�J�����[�^�E�A�J�f�~�J�́u���[�c�@���g �Z���i�[�h���f�B���F���e�B�����g�W�vCD�S10���̃Z�b�g�̐��E���B�ȉ��������Ă��Љ��B
1940�N�ォ��50�N��ɂ����Đl�C�̃g�b�v���䂭���F�[�O�l�d�t�c�𗦂��Ă����V���[���h���E���F�[�O�́A���ތ㋳�ڂ��Ƃ����U���c�u���N�̃��[�c�@���e�E�����y�@�̋��t�����őg�D�����J�����[�^�E�A�J�f�~�J�𗦂��āA���[�c�@���g�̃Z���i�[�h��f�B���F���e�B�����g�̘^�����A1980�N��㔼�ɍs�����B�����͑S����10����CD�Ɏ��߂��A�l�ނ̈�Y�Ƃ������ׂ��n�ʂ��߂Ă���B�����A���[�c�@���g�̃Z���i�[�h��f�B���F���e�B�����g���~�����Ƃ����l������Ƃ���A���͂��߂炤���ƂȂ����̃Z�b�g�𐄂����̂ł���B���Ƃ��̃W�������Ɋւ��Ă͉E�ڍ�ᾂ���K�v�͑S���Ȃ��B���킸���̃Z�b�g���悢�̂ł���B�ނ̉��y�̗N���o���錹��͔�ނȂ���M�ƈ��ł���B�����Ă���ɕ��s����Z�p��̐������B�ǂ��炪�����Ă����y�͓i�ɂȂ邪�A��������Ă��鐔���Ȃ����y�Ƃ����F�[�O�Ȃ̂ł���B
 �@����́A�搶�ďC�́u���[�c�@���g�E�x�X�g101�v�i�V���فj�̃R�[�i�[�Έ�G�́�����1�����I���̂��́B�������̕��͂ɏo�����킵���̂�2006�N�����肾�������B����܂ŁA���̂悤�ȁu�l�̌܂̌��킸�ɂ���������̂��v�I�^�C�v�̐��E���ɂ��ڂɂ����������Ƃ��Ȃ������B�����܂ŃL�b�p���ƒf������]�_�Ƃɏo��������Ƃ��Ȃ������B����͎��ɋ���Ȉ�ۂ������B���F�[�O�̑��ɂ��A�搶�̐��E�Ղ��������肵�����A�����x�ɑN��Ȋ����������N����B�x���W���~���E�u���e���w���F�C�M���X�����nj��y�c�́u�����ȑ�25��K183�A38��K504�A40��K550�v�A�N���t�H�[�h�E�J�[�]���iP�j���u���e���́u�s�A�m���t�� ��20��K466�A��27��K595�v�A�V���e�B�b�q�E�����_��(S)�̃��[�g�W�A�t�����`�F�X�J�b�e�B(Vn)���u���[�m�E�����^�[�́u���@�C�I�������t�� ��3��K216�v�A�W�����[�h���y�l�d�t�c�́u�n�C�h���E�Z�b�g�v�A�M�[�[�L���O(�o)�̃s�A�m�E�\�i�^�A�u�����hK511�v�A�z���V���t�X�L�[(�o)�́u���z��K397�v���X�A�܂����Y�����̔@���̖����Q���B�������Ă����炫�肪�Ȃ��̂ŁA�����Ĉꌾ�Ŋ����Ă��܂��A�u�����������́v�Ƃł����������B���������������y���������Ă���B�����Ĉ��炬�����ւ̊��͂��N���Ă���A����ȉ��t����Ȃ̂��B���ł��A�V���[���h���E���F�[�O�́u�Z���i�[�h���f�B���F���e�B�����g�W�v�͈����ŁA��ɍ��E�ɒu���Ē����Ă����B�u���l���ւ��̈ꖇ�v�Ƃ����Ȃ�A���킸����Ƃ������̕ł���B
�@����́A�搶�ďC�́u���[�c�@���g�E�x�X�g101�v�i�V���فj�̃R�[�i�[�Έ�G�́�����1�����I���̂��́B�������̕��͂ɏo�����킵���̂�2006�N�����肾�������B����܂ŁA���̂悤�ȁu�l�̌܂̌��킸�ɂ���������̂��v�I�^�C�v�̐��E���ɂ��ڂɂ����������Ƃ��Ȃ������B�����܂ŃL�b�p���ƒf������]�_�Ƃɏo��������Ƃ��Ȃ������B����͎��ɋ���Ȉ�ۂ������B���F�[�O�̑��ɂ��A�搶�̐��E�Ղ��������肵�����A�����x�ɑN��Ȋ����������N����B�x���W���~���E�u���e���w���F�C�M���X�����nj��y�c�́u�����ȑ�25��K183�A38��K504�A40��K550�v�A�N���t�H�[�h�E�J�[�]���iP�j���u���e���́u�s�A�m���t�� ��20��K466�A��27��K595�v�A�V���e�B�b�q�E�����_��(S)�̃��[�g�W�A�t�����`�F�X�J�b�e�B(Vn)���u���[�m�E�����^�[�́u���@�C�I�������t�� ��3��K216�v�A�W�����[�h���y�l�d�t�c�́u�n�C�h���E�Z�b�g�v�A�M�[�[�L���O(�o)�̃s�A�m�E�\�i�^�A�u�����hK511�v�A�z���V���t�X�L�[(�o)�́u���z��K397�v���X�A�܂����Y�����̔@���̖����Q���B�������Ă����炫�肪�Ȃ��̂ŁA�����Ĉꌾ�Ŋ����Ă��܂��A�u�����������́v�Ƃł����������B���������������y���������Ă���B�����Ĉ��炬�����ւ̊��͂��N���Ă���A����ȉ��t����Ȃ̂��B���ł��A�V���[���h���E���F�[�O�́u�Z���i�[�h���f�B���F���e�B�����g�W�v�͈����ŁA��ɍ��E�ɒu���Ē����Ă����B�u���l���ւ��̈ꖇ�v�Ƃ����Ȃ�A���킸����Ƃ������̕ł���B�@�ł́A�Ȃ����F�[�O��K137�̑�1�Ƒ�2�y�͂����ւ����̂��낤���H �Έ�搶�Ƃ͖����uEBIS��v�Ȃ���݉�ł��ꏏ�����Ă��������Ă���B���͌b����K�[�f���E�v���C�X���̃r�A�E�z�[���u������C�I���v�B7����12���B�Ȃ�A�����ł��q�˂��悤�Ƃ������ƂɂȂ�AF�������U������������B
�@�Έ�搶�Ƃ́A2006�N�A���[�c�@���g���a250�N�Ɋ�悵���uTHAT�fS MOZART�`���ꂾ���������[�c�@���g���킩��v�iBMG JAPAN�j�̉�������肢���Ĉȗ��̂��t�����������A���̔��w���ːU��ɂ͂����������Ă���B�ŁA���̉�����̒��ɁA�u�w�f�B���F���e�B�����g�σ�����K137�x�́A�O���K136��138��3�ȃZ�b�g�ō�Ȃ��ꂽ�B�]�������́A��2���C�^���A���s����A�������N1772�N�̍�i�Ƃ���Ă����B���̍����́A���[�c�@���g�̎��M�̊y����Ԃ����J�o�[�E�y�[�W�ɁA1772�N�Ƃ����g���l�̕M�Ղɂ�鏑�����݁h������������v�Ƃ����L�q������B����́A������L�b�J�P�Ɏ��₳���Ă����������B�搶�̌��������L�B
���[�c�@���g����i�ژ^�����珑���n�߂��̂́AK449�u�s�A�m���t�� ��14�� �σz�����v����ŁA1784�N�̂��ƁB����ȑO�ɁA�����Ƃ����ژ^�͂Ȃ��BK137�͉�����ɂ��������ʂ�A���l�i�����o�ŎЁj���Ԃ��ĕ\���ɍ�ȔN����������Ă���B�y�͂̏������A��1�y�͂� Andante�A��2�y�͂� Allegro di molt�A��3�y�͂� Allegro assai �Ƃ��āB������A���̏������X�^���_�[�h�ƂȂ��Ă���̂����A����ɂ��ẮA�uAndante �Ŏn�܂�f�B���F���e�B�����g�͕s���R�v�Ƃ��āA�ȑO����c�_����������ł���B�@�Ȃ�قǁA���[�c�@���g�����ď����R�炵������~�X������B�܂��Ă⑼�l�̍�Ƃɂ����Ă��₾�BF�������F�[�O�̋}�|�Ɂ|�}���u�炵���v�Ƃ��������A���������B�O�l�̈ӌ������v�����B
�h�C�c�l�͎ێq��K�I���f������B�t�����X�l�͊������d��B�Ⴆ�A�u�z�������t�ȑ�3�� �σz�����v�ł����ˁB�h�C�c�l���[�g���B�q�E�t�H���E�P�b�w���i1800�|1877�j�́A���[�c�@���g�̎��M��i�ژ^�ɍڂ��Ă��Ȃ��̂�����A����ȑO�̍�i�Ɣ��肵��K447�Ƃ����ԍ���^�����B����A�W�����W���E�h�E�T�����t�H�A�i1874�|1959�j�Ƃ����t�����X�̉��y�j�Ƃ́A�o���f�����炵�Ă���ȎႢ����̍�i�ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ�1788�N�ȍ~�̍�i���Ɛ��_�����B���̌������A�P�b�w���E�J�^���O��6�ł̕ҏW�Ɍg���h�C�c�̊w�҂����́u���̂悤�Ȃ����Ƃ�����i���A���[�c�@���g�����M�ژ^�ɏ����R�炷�͂����Ȃ��v�Ƃ��Ď���Ȃ�������ł��ȁB�Ƃ��낪��N�A�A�����E�^�C�\���̉���I���@�ɂ�錟�ŁA���̍�i��1787�|89�N�̍�i�Ɣ��肳�ꂽ�B�t�����X�l�̊������������������ƂɂȂ�܂��ˁB
���[�c�@���g�ɂ������R�炵��������Ă��ƁB�܂��Ă�A���l���Ԃ���K137�̊y�͂̏���������ւ���Ă��܂��Ă��Ă�����s�v�c�͂Ȃ��Ǝv���܂���B���̓��F�[�O�̏����Ɏ^�����܂��B
�@���߂āA��̊y�́A���� Andante �y�͂����Ă݂��B3���q�n�ŁA���A���ɔ�����2�܂܂��̂́A�`���y�͂Ƃ��Ă��Ȃ�̈�a��������B���t�Ȃ炢���m�炸�A����ȏo�����͂��܂�Ⴊ�Ȃ��B��͂�AAndante �͑�2�y�͂ɒu���ׂ����B�������A�}�|�Ɂ|�}�̓o���b�N�ȗ��̒���B��������[�c�@���g��15�������̂�����A��܂���������R�ł͂Ȃ����B��������������A���o�I�ɁA���̕������|�I�ɍ��肪�����B�X�ɁA�莝��CD�\���Ȃ̃f�B���F���e�B�����g��S��������AK137�ȊO�ŁA�ɏ��y�͂Ŏn�܂�Ȃ͊F���������B��������ŏ\���ł͂Ȃ����B�����ƒm���������[�c�@���g���t�̎g�k�V���[���h���E���F�[�O���AK137�ōs������1�Ƒ�2�y�͂̏����ύX�́A���[�c�@���g�̈Ӑ}�ɉ������̂Ɗm�M����B
�@�ʂ�ۂɁA�Έ�搶���|�c���Ƃ�����������B�u���̂悤�ȕς�������Ƃ��������̂́A�Ȃ��Ȃ����Ă��炦�Ȃ��Ăˁv�B���₢��搶�B���̒��͐��X��X�B�^���͍Ō�ɂ͕�����܂���B
�@�]�k���ЂƂ� �@�V���[���h���E���F�[�O�́u���[�c�@���g �Z���i�[�h���f�B���F���e�B�����g�W�v�̉�����AK137�����͂����Ȃ��Ă���i�����͓ƌꂾ�����L����Ă���p��Łj�B
The Divertimento K137, on the other hand, introduced by an Andante movement, which is followed by a brief movement in sonata form (Allegro di molt).�@���₨��A���̉���A���ۂ̉��t�Ɛ^�t�̓��e�B�킴�킴�y�͂����ւ������F�[�O�̈Ӑ}�����������Ă�B��������̓Q���n���g�E���@���^�[�X�L���w���Ƃ����U���c�u���N��w�̋����B�Ȃɂ�獂���ȕ��炵���B�܂����A���t�������ď�����������H ����Ȃ��Ƃł́A���̐́u�V��45�v�Ɂu������������]�Ɓw���E�̖��x�v�����������ΐ�搶�ɁA�u���t�����Ɍ��]�������v�]�_�ƃ��X�g�ɓ����ꂿ�Ⴂ�܂���I
[�a��] �f�B���F���e�B�����gK137�́A����ɔ����i���FK136�ƈ���āj�A�A���_���e�y�͂Ŏn�܂�A�\�i�^�`���ŏ����ꂽ�Z���A���O���E�f�B�E�����g�y�͂Ɉ����p�����B
���Q�l������CD��
���[�c�@���g�E�x�X�g101 �Έ�G�ďC�i�V���فj
�鉤���特�y�}�t�B�A�܂� �Έ�G���i�w�����Ɂj
�V���[���h���E���F�[�O�^���[�c�@���g �Z���i�[�h���f�B���F���e�B�����g�W �iCAPRICCIO�j
THAT'S MOZART�`���ꂾ���������[�c�@���g���킩��iBMG JAPAN�j
2017.06.26 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� ��ҁ`4�l�ڂ̃��i���U�͒N�H
�@�t�����X�̌��w�Z�t�p�X�J���E�R�b�g�́A����J������p���āA����u���i���U�v���B���s�̃��i���U�̉���3�l�̃��i���U���B��Ă��邱�Ƃ������B���̌��ʁA���@�U�[�����̃��f���u���U�E�W���R���h�v�l�v��3�l�ڂ̃��i���U�ł��邱�Ƃ����������B�܂��ɐ��I�̑唭���I2015�N12���̂��ƁB���s�̃��i���U�́A3�l�ڂ̏�ɏd�˕`�������u4�l�ڂ̃��i���U�v�Ȃ̂ł���B�ʂ����āA���̃��f���͒N�Ȃ̂��H�����x���g�E�U�b�y���̒�����
 �@���x���g�E�U�b�y����1932�N���܂�̃C�^���A�̗��j�ƁB�U�b�y���́A����u���i���U�̃��f���̓W���R���h�v�l�v�ɔ[���ł��Ȃ������B���R�́u�t�B�����c�F�̏��l�t�����`�F�X�R�E�f���E�W���R���h�̍ȃ��U�̂悤�ȕ��}�Ȑl�����A�ʂ����Ă��̂悤�Ȑ[������������ё���ƂȂ�슴����Ƃɗ^���邱�Ƃ��ł��邾�낤���H�v�Ƃ����^�₾�����B���_�A�ނ̓W���R���h�v�l�̑f���m��R���Ȃ��B�����A���}�ȃt�B�����c�F�̍����̍Ȃ��A�������D���������ɖ����������_��I�ł��炠��u���i���U�v�̃��f���ł���Ƃ͓���v���Ȃ������̂��B���̒����̓p�X�J���E�R�b�g�̓����ɂ���ďؖ������̂����A�U�b�y���͂���ȑO����Ǝ��Ƀ��i���U�T���𑱂��Ă����B�����Ă��̐��ʂ́u����A���i���U�v�Ƃ���1���̖{�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�E�e�����̂�2011�N�B����͂��̏��ɉ����āu4�l�ڂ̃��i���U�v�ɔ���B
�@���x���g�E�U�b�y����1932�N���܂�̃C�^���A�̗��j�ƁB�U�b�y���́A����u���i���U�̃��f���̓W���R���h�v�l�v�ɔ[���ł��Ȃ������B���R�́u�t�B�����c�F�̏��l�t�����`�F�X�R�E�f���E�W���R���h�̍ȃ��U�̂悤�ȕ��}�Ȑl�����A�ʂ����Ă��̂悤�Ȑ[������������ё���ƂȂ�슴����Ƃɗ^���邱�Ƃ��ł��邾�낤���H�v�Ƃ����^�₾�����B���_�A�ނ̓W���R���h�v�l�̑f���m��R���Ȃ��B�����A���}�ȃt�B�����c�F�̍����̍Ȃ��A�������D���������ɖ����������_��I�ł��炠��u���i���U�v�̃��f���ł���Ƃ͓���v���Ȃ������̂��B���̒����̓p�X�J���E�R�b�g�̓����ɂ���ďؖ������̂����A�U�b�y���͂���ȑO����Ǝ��Ƀ��i���U�T���𑱂��Ă����B�����Ă��̐��ʂ́u����A���i���U�v�Ƃ���1���̖{�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�E�e�����̂�2011�N�B����͂��̏��ɉ����āu4�l�ڂ̃��i���U�v�ɔ���B��4�l�ڂ̃��i���U��
�@�_�E���B���`��1513�N�A���f�B�`�Əo�g�̋��c���I10���̒�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`(1479�|1516)�̗U�����A���[�}�ɋ����ڂ��B�W�����A�[�m�́A��ƁA�����ƁA�B���p�t�A�z�R�Z�t�ȂǁA�Ƒn���̂���|�p�Ƃ�Z�p�҂��W�߂邱�Ƃ��D�B�_�E���B���`�͔ނ̔�̂��ƁA�o�`�J���ɏZ���ƃA�g���G���\���邱�Ƃ��ł����B�����ɂ̓t�B�����c�F����g���Ă����u���i���U�v���������B�W���R���_�̖����̏ё����`���ꂽ�܂܂́B�_�E���B���`�͂��̃L�����o�X�ɂǂ������4�l�ڂ̃��i���U���d�˂��̂��낤���H
�@�����Ɉ�̎�|���肪����B���@���A���S���̔鏑��1517�N�Ɏc�������L�ł���B�A���S�����Ɣ鏑���A�t�����X�ɏZ��65�̃_�E���B���`�̃A�g���G�ɍs�������̂��̂ł���B
���カ���Ẵt�B�����c�F�o�g�̉�ƃ��I�i���h�E�_�E���B���`�́A��X��3���̊G�������Ă��ꂽ�B���̂�����2���́u����҃��n�l�v�Ɓu���A���i�Ɛ���q�v�A����1���͂��鏗�������R�̂܂܂ɕ`�����G�ŁA�����҂̓W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�ł���B�@���̋L�q�ɂ����钍�ړ_�͓�B���́A1503�N�A�_�E���B���`���A�t�B�����c�F�Ń��U�E�W���R���h�v�l�������n�߁A���������˗���ɂ��n�炸�ɁA���ɓ]�X�Ƃ����u���i���U�v���A1517�N�A����2�N��ɍT�����_�E���B���`�̃t�����X�̃A�g���G�ɑ��݂��Ă������ƁB���́A�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�Ƃ������̃L�C�E�p�[�\�����o�ꂵ�����Ƃ��B
�@�_�E���B���`�́A�u�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�̔������āA3�l�ڂ̃��i���U�̏�ɁA4�l�ڂ̃��i���U���d�˕`�������v�̂ł���B
�@�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�Ƃ͂ǂ�Ȑl���ŁA�_�E���B���`�͔ނ���N��`���悤�˗����ꂽ�̂��H
���W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�Ƃ����j��
 �@�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�́A1479�N3��12���A���f�B�`�Ƃ̖����q�Ƃ��Ă��̐��ɐ������B���N����A�u�o���̉Ԃ̂悤�ɂ͂�Ƃ��A���̂悤�ɉ���Ȃ��A���������ƍl���[���Ȗڂ����Ă����v�Ə̂��ꂽ�W�����A�[�m�́A�e�p�[��ŕ��w�I�f�{������A���܂�Ȃ���Ƀh���E�t�@���̎���������Ă����B���������c�H�̎���A���f�B�`�ƂɊ����̍Г�~�肩����A�e�n��]�X�Ƃ�����A���̊ԗl�X�Ȍ|�p�ɐG��A���̎����͂���ɖ������������Ă䂭�B
�@�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�́A1479�N3��12���A���f�B�`�Ƃ̖����q�Ƃ��Ă��̐��ɐ������B���N����A�u�o���̉Ԃ̂悤�ɂ͂�Ƃ��A���̂悤�ɉ���Ȃ��A���������ƍl���[���Ȗڂ����Ă����v�Ə̂��ꂽ�W�����A�[�m�́A�e�p�[��ŕ��w�I�f�{������A���܂�Ȃ���Ƀh���E�t�@���̎���������Ă����B���������c�H�̎���A���f�B�`�ƂɊ����̍Г�~�肩����A�e�n��]�X�Ƃ�����A���̊ԗl�X�Ȍ|�p�ɐG��A���̎����͂���ɖ������������Ă䂭�B�@1505�N����́A���Ȃ�̊��ԁA�C�^���A�����̒��E���r�[�m�ɑ؍݂����B�������̒n�́A�C�^���A�S�y����A���w�҂�|�p�Ƃ��W�������̒��S�n�B�C�^���A�ōł��������Ƃ���ꂽ�h�D�J�[���{�a�ł́A��������b�ƕi�̂悢��k����ь����A�W�����̂͊F�S�n�悢���Ԃ��߂����Ă����B���@�͂܂��Ɋ���̏�B����ȎЌ��̏�ɂ����āA�W�����A�[�m�͌|�p�╶�w�ɂ�����w���̂䂦�ɍۗ��������݂ŁA�ނƂ̌��ۂ�]�ނ��w�l�͌��₽�Ȃ��B����ȏ̒��A�ނ͉^���̏����Əo��B�p�`�t�B�J�E�u�����_�[�j�ł���B
�@�W�����A�[�m�ƃp�`�t�B�J�̌��ۂ������L�^�͎c���Ă��Ȃ��B�������Ȃ���A���̊W���́A�E���r�[�m�̃T���^�E�L�A�[������̋L�^������H�邱�Ƃ��ł���B
1511�N4��19���̐��y�j���A�T���^�E�L�A�[������ɒj�̓����ݎq���̂Ă��Ă����E�E�E�E�E�Ԃ�V�͋��n��E�����B�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�������̗{�q�Ƃ��Ď��ꂽ�E�E�E�E�E�W�����A�[�m�ƃp�`�t�B�J�̔o�q�Ƃ��ĔF�m���ꂽ�B���W�����A�[�m�ƃp�`�t�B�J��
�@1511�N4��19���A�T���^�E�L�A�[������ɓ����ݎq���̂Ă��Ă����B���̒j�̎q�́A�����㒼���ɃE���r�[�m�̎̂Ďq�{��@�Ɉ����n����A�p�X�N�����[�m�Ɩ��t������B�����3����ɂ́A�o���g�����I�Ƃ����j�̉ƒ�Ɉ�������Ă䂭�B�����ɂ͎����\�ȍȂ�����A��V�ړ��Ăɓ����ݎq��a���邱�Ƃ́A�������������Ƃł͂Ȃ������悤���B�����Đ�������A�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`������A���̎q�������̏��q�ƔF�m���A�C�b�|�[���g�Ɩ�������B����͗]�k�����A�C�b�|�[���g�́A�M���V���_�b�ɓo�ꂷ��q�b�|�����g�X�̂��ƁB�ނƌp��t�F�[�h���Ƃ̋֒f�̈��̕����1962�N�̉f��u����ł������v�i�W���[���X�E�_�b�V���ē� �����i�E�����N�[���剉�j�ɕ`����Ă���B���q�ɐ����I�Ȗ���t���Ȃ��̂̓��f�B�`�Ƃ̓`�������A�M���V���_�b����̈��p�̓W�����A�[�m�̃Z���X���낤�B
�@�C�b�|�[���g�̕�e�̋L�^�́A�̂Ďq�{��@�̎����ɖ��L����Ă���B�u��e�̖��̓p�`�t�B�J�B�W�����@���j�E�A���g�j�I�E�u�����_�[�j�̖��v�ƁB�u�����_�[�j�Ƃ̓E���r�[�m�ł͋��w�̈ꑰ�ŁA�W�����@���j�E�A���g�j�I�́A�s�s�Q����A�s�������߂����m�������B�����̋�������A�p�`�t�B�J�͋��{������A�{��ɂ��o���肵�Ă������낤���Ƃ͗e�Ղɑz�������B�����ŁA�Ќ��E�̉Ԍ`�W�����A�[�m�ɏo������ƂȂ�q���Y���Ƃ��A�z����z����Ƃ����邾�낤�B�Ƃ��낪�A�p�`�t�B�J�͏o�Y��Ԃ��Ȃ��S���Ȃ��Ă��܂��B�W�����A�[�m���C�b�|�[���g���������ɗ����Ƃ��ɂ́A�ޏ��͊��ɂ��̐��ɂ��Ȃ������̂ł���B
���W�����A�[�m�ƃC�b�|�[���g��
�@�W�����A�[�m�́A�C�b�|�[���g��F�m����������炭�E���r�[�m�ɗ��܂������A���̂���A���[�}���c�R�̓t�����X�Ƃ̐퓬�̍Œ��������B���@���̌Z�W�����@���j(1475�|1521)�Ƌ��ɃW�����A�[�m����n�ɕ����A1512�N�ɂ͒D�҂����t�B�����c�F�ɋ����\�����B1513�N�A�W�����@���j�̓��[�}���c���I10���ƂȂ����B����ɔ����W�����A�[�m�����[�}�ցB�����āA�F�l�_�E���B���`���o�`�J���Ɍ}�����̂ł���B
�@�W�����A�[�m�͐��ȃt�B���x���^�Ƃ̊ԂɎq�͂Ȃ������B�C�b�|�[���g�̓W�����A�[�m�̍ŏ��ɂ��ėB��̎q�������̂��B�W�����A�[�m�̓o�`�J���ŃC�b�|�[���g��������{�炵���B�Ƃ��낪1516�N�A�W�����A�[�m�͌��j�̂��߂ɂ��̐�������B�c���ꂽ�C�b�|�[���g��5�B���̌�͔����̋��c���I10���ɂ���Ĉ�Ă��A���@���ɂ܂ŏ��l�߂�̂ł���B
�@�����܂ł͎j���Ɋ�Â��B�ȍ~�͑z���̐��E�ł���B
��4�l�ڂ̃��i���U�͒N�H��
�@1513�N�ȍ~�A�o�`�J���{�a�ł́A���c�̒�W�����A�[�m�E�f�E���f�B�`�Ƒ��q�C�b�|�[���g�A�����āA���I�i���h�E�_�E���B���`�����s���R�̂Ȃ������𑗂��Ă����B�u����A���i�E���U�v�̒��҃��x���g�E�U�b�y���́ANHK-BS�u4�l�̃��i���U�v�̒��ł����q�ׂĂ���B
�C�b�|�[���g�͋͂�3�ł��B��������Ɂu�}�}�͉����H�v�Ɛq�˂Ă��܂����B�z������ɁA�W�����A�[�m�̓_�E���B���`�ɂ������������̂��Ǝv���܂��B�u���Ȃ��̑z���͂ŁA���q�̕�e��`���Ăق����v�ƂˁB��e�̎p�𑧎q�Ɏc�����߂Ɂu���i���U�v�� �`���ꂽ�̂ł��B�@���́A�T�b�y���̃C���^�r���[��������ǂ�ŁA4�l�ڂ̃��i���U�́u�C�b�|�[���g�̕�p�`�t�B�J�v�Ǝv���Ă����B�Ƃ������A�m�M����Ɏ������B�p�`�t�B�J�̓W�����A�[�m�ɂƂ��ē��ʂȏ����������B���������𗬂����p�`�t�B�J�ȊO�̏����Ƃ͎q��������Ă��Ȃ��B�C�b�|�[���g�����W�����A�[�m�̗B��|���ւ��̂Ȃ��������B�u�}�}�͉����H�v�Ƃ�����3�̈����̂��߂ɕ�e�̏ё���p�ӂ��Ă�肽���I �������T��ɂ̓t�B�����c�F����Ăъ����背�I�i���h�E�_�E���B���`������B�W�����A�[�m���_�E���B���`�Ɉ˗�����͎̂��R�̗���ł͂Ȃ����B
�@�������āA�_�E���B���`�́A�������킹���u3�l�ڂ̃��i���U�v�̏�Ɂu4�l�ڂ̃��i���U�v��`���n�߂�B�W�����A�[�m����p�`�t�B�J�̗e�e���M��i�߂�B�q��������Ƃ����ړI�ɍ��킹�A�����𐳖ʂɌ�������B�p�`�t�B�J�̉^�����v�������Î�����r���𒅂����H �����⎩���̕�J�e���[�i�̖ʉe��������Ă����H �������āu4�l�ڂ̃��i���U�v�͌��s�̃��i���U�ɋ߂Â��Ă䂭�B
 �@�������Ȃ���A1516�N3��17���A�W�����A�[�m�͕s�A�̐l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂����Ă��u���i���U�v�͈˗���ɓn��Ȃ������̂��B�W�����A�[�m�̎���A�_�E���B���`�́A�t�����\��1���̗U���ɉ����A���|���[�Y��߂��̃N���[�̊قɈڂ�B�V���Ȋ��̒��A�_�E���B���`�̓��i���U�̊�����ڎw�����B���͂�˗���͂��Ȃ��B���ߐ���Ȃ��B���f���ɌŎ�����K�v���Ȃ��B�_�E���B���`�͐^�Ɏ��R�Ȕ��z�Ń��i���U�ƑΛ������B���̍�Ƃ͎��ʂ܂ő����B�`���i�ނ����Ɂu���i���U�v�́A���X�Ɍ����𗣂�A�_�E���B���`���z�����闝�z�̕�e�����������ɕϗe���Ă������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������Ȃ���A1516�N3��17���A�W�����A�[�m�͕s�A�̐l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂����Ă��u���i���U�v�͈˗���ɓn��Ȃ������̂��B�W�����A�[�m�̎���A�_�E���B���`�́A�t�����\��1���̗U���ɉ����A���|���[�Y��߂��̃N���[�̊قɈڂ�B�V���Ȋ��̒��A�_�E���B���`�̓��i���U�̊�����ڎw�����B���͂�˗���͂��Ȃ��B���ߐ���Ȃ��B���f���ɌŎ�����K�v���Ȃ��B�_�E���B���`�͐^�Ɏ��R�Ȕ��z�Ń��i���U�ƑΛ������B���̍�Ƃ͎��ʂ܂ő����B�`���i�ނ����Ɂu���i���U�v�́A���X�Ɍ����𗣂�A�_�E���B���`���z�����闝�z�̕�e�����������ɕϗe���Ă������̂ł͂Ȃ����낤���B�@1519�N5��2���A���I�i���h�E�_�E���B���`�͉i���̖���ɂ����B�T��ɂ͍Ō�܂ŕM����ꑱ�����u���i���U�v�������B�D���������ɖ����������_��I�ȏ݂�X���āB
����L��
�@�u���i���U�v�́A���E�ł����Ƃ��m��ꂽ�A�����Ƃ������ꂽ�A�����Ƃ��̂�ꂽ�A�����Ƃ��p���f�B�����ꂽ���p��i�Ƃ����Ă��܂��B������A�u���i���U�v�̃��f���͒N���H �Ƃ����₢���A���Ԃ̋������䂭�͓̂��R�ł��B����܂ŁA�����������l�̊w�ҁE�D���Ƃ����������Ă����ł��傤���B�ȉ��͂��̎Y���̈ꕔ�ł��B
���U�E�W���R���h�v�l�A�~���m���܃C�U�x���E�_���S�i�A�~���m���̈����`�F�`�[���A�E�K�b�����[�j�A�t�����J���B����ݕv�l�R���X�^���c�@�E�_���@���X�A�}���g���@��܃C�U�x���E�f�X�e�A�p�`�t�B�J�E�u�����_�[�j�A�C�U�x���E�O�A�����_�A�J�e���[�i�E�X�t�H���c�@�A���I�i���h�̕�J�e���[�i�A��q�̃T���C�A���I�i���h�{�l�iWikipedia�����p�j�@���̚삵�����������i���U�̖��͂̏ؖ��ɑ��Ȃ�܂���B�A���A�����̂قƂ�ǂ̓p�X�J���E�R�b�g�ɂ��g���i���U�����h�ȑO�̐����B���Ƃ��ẮA�W���R���h�v�l��3�l�ڂ̃��i���U�ł���A�p�`�t�B�J�E�u�����_�[�j����4�l�ځ��^�̃��i���U�̃��f���ł���A�Ɗm�M������̂ł��B�����A�p�`�t�B�J�̎p���_�E���B���`�͌��Ă��Ȃ��B�ŏ�����z���ŕ`�������Ȃ������B�������A�_�E���B���`�́A���̊G���˗��l�ɓn�����ƂȂ��A���ʂ܂ŕM����ꑱ�����B�`���Ε`���قǁu���i���U�v�́A�����̃��f�����z���A�z����̏ё��ƂȂ��Ă䂭�B��̖ʉe������������������Ȃ��B�l���ŏo����������̐l�X�̈�ۂ����������������Ȃ��E�E�E�E�E������A���̂悤�Ȏ����Ɛ_��ƕ��Ղ��h�����̂ł��B�l���̍Ŋ��ɒ��n�����u���i���U�v�������A�_�E���B���`���ǂ����߂����z�̏������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���Q�l������
�u����A���i�E���U�v���x���g�E�U�b�y���� ���쏃�q��i���e�Ёj
�u4�l�̃��i���U�v�`�g��̔��h���f���̐^�� NHK-BS�v���~�A�� 2017.5.17 OA
2017.06.20 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� �O�ҁ`�B��Ă����W���R���_
��4�l�̃��i���U�� �@���E�ň�ԗL���ȊG��u���i���U�vMona Lisa�́A�C�O�ł́A��ʂɁu�W���R���_�vLa Gioconda�ƌĂ�Ă���B���f�����W���R���h�v�l�Ƃ����̂����̗��R�B�������Ȃ���A���̐��̂́A��ݕv�l�A�i�|�����܁A�}���g���@���܃C�U�x���E�f�X�e�A���l�A��e�A�����l�Ɛ��w�A��q�̃T���C�A�ʂĂ͖{�l���܂Ő����̉����E�������Ȃ���A����ł��Ȃ��܂܍����Ɏ����Ă���B�ʂ����āu���i���U�v�̃��f���͒N�H���ꂼ���p�j��ő�̃~�X�e���[�����}���I�H
�@���E�ň�ԗL���ȊG��u���i���U�vMona Lisa�́A�C�O�ł́A��ʂɁu�W���R���_�vLa Gioconda�ƌĂ�Ă���B���f�����W���R���h�v�l�Ƃ����̂����̗��R�B�������Ȃ���A���̐��̂́A��ݕv�l�A�i�|�����܁A�}���g���@���܃C�U�x���E�f�X�e�A���l�A��e�A�����l�Ɛ��w�A��q�̃T���C�A�ʂĂ͖{�l���܂Ő����̉����E�������Ȃ���A����ł��Ȃ��܂܍����Ɏ����Ă���B�ʂ����āu���i���U�v�̃��f���͒N�H���ꂼ���p�j��ő�̃~�X�e���[�����}���I�H�@�W���R���_���́A���l�T���X�̉�ƁE���p�j�����ƃW�����W���E���@�U�[���i1511�|1574�j�̒����u�|�p�Ɨ�`�v���̋L�q�A�u���I�i���h�̓t�����`�F�X�R�E�W���R���h�̂��߂ɔނ̍ȃ��U�̏ё�������������v�ɂ��B�����L�ꎁ�ɂ��A���@�U�[���́A��ƂƂ��Ă͑債�����Ƃ͂Ȃ��炵���B�ނ̊G�́A���ł͂��邪���ői���͂ɖR�����Ƃ����B���ʁA��ɔ[�����͂����Ȃ��Ƃ����˔\������A�[�������ʃ_�E���B���`�ȂǁA�y�т����Ȃ�������q��Ƃ������悤���B�m��ȓV�˃_�E���B���`�ƙ{���ʂȏG�˃��@�U�[���B�ʔ����Δ�ł���B
�@�{���ʂ������͌����҂Ƃ��Ď��ׂ��厖�Ȏ����Ȃ킯�ŁA���̙{���ʂȔ��p�j�����Ƃ̋L�q���A�����ԁA����Ȃ�̌��Ђ����������Ă����͎̂����ł���B
�@�p�X�J���E�R�b�g�Ƃ����t�����X�l���w�Z�m������B���N�O�A���[�������p�ق���u���i���U�v�̓����̐F�ʂ̕������˗����ꂽ�̂��@�ɁA���̖���ɛƂ�B�Ǝ��ɍl�Ă����}���`�E�X�y�N�g���E�J�������g��2��4000����f�̒������摜�ɂ��A�u���i���U�v�Ƃ����G����ۗ��ɂ��邱�Ƃɐ����B�_�E���B���`���ǂ������o�H�ōŌ�̉�Ɏ������̂�������݂ɏo���B�����ɂ́A�Ȃ��4�l�́u���i���U�v�������̂ł���B�܂�A�_�E���B���`��3�l���d�˕`�����č��́u���i���U�v�ɒH�蒅�����̂��B
�@1�l�ڂ̃��i���U�̓f�b�T���B2�l�ڂ͐���}���A�B3�l�ڂ́H 4�l�ڂ͐��E�����Ă������s�̃��i���U�A���[���b�p�Łu�W���R���_�v�ƌĂ�Ă���ё��ł���B���i���U�̐^�������Ƃ́A3�l�ڂ�4�l�ڂ̃��f������肷�邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
��3�l�ڂ��W���R���_��
 �@�p�X�J���E�R�b�g�ɂ���Č��s�u���i���U�v�̉����������l�̃��i���U���o�Ă����B3�l�ڂ̃��i���U�ł���B�������ׂ�ƁA3�l�ڂ́A�����������A�炪�ׂ��A�ڂ��i�������āj�������������Ă���B�����ɂ��ẮA�@���̏㕔�ɒ����т̃��{�������� �A���|�����F�[���������ʂ����V���N �B�������璆�����͂��ɂ͂ݏo���B�ȂǂȂǁA���s���i���U�Ƃ͂����Ԃ�Ⴄ�B
�@�p�X�J���E�R�b�g�ɂ���Č��s�u���i���U�v�̉����������l�̃��i���U���o�Ă����B3�l�ڂ̃��i���U�ł���B�������ׂ�ƁA3�l�ڂ́A�����������A�炪�ׂ��A�ڂ��i�������āj�������������Ă���B�����ɂ��ẮA�@���̏㕔�ɒ����т̃��{�������� �A���|�����F�[���������ʂ����V���N �B�������璆�����͂��ɂ͂ݏo���B�ȂǂȂǁA���s���i���U�Ƃ͂����Ԃ�Ⴄ�B�@�G���U�x�b�^�E�j���l�����j�Ƃ��������j�Ƃ�����B�����j�Ƃ́A���f���̕�������G�悪�`���ꂽ����ƒn�����肷��B�u���E�e�n�̌Ñ�y�ь���̕����v�Ƃ��������̐}�ӂ�����B�l�X�ȊK���E�E��ʁA����ʁA�n��ʂɐl�X�̕������܂Ƃ߂����́B����ɓ��Ă͂߂āA���f�����`���ꂽ�����n�����肷��B���y�ł����A�ԊO���Ōܐ����������[�c�@���g��i�̍�ȔN�����肵���A�����E�^�C�\�������Ɏ��Ă���B
�@���j�́A3�l�ڂ̃��i���U�̕������ƍ��E�l�@����B�@���̕t���ւ����\�ɂ��邽�߂̒����т̃��{���ƇA�V���N�̌��|�����F�[���́A1400�N�㖖�|1500�N�㏉���̃t�B�����c�F�ŗ��s�����X�^�C���Ɠ���B����ɇB�����̒������͂��ɂ͂ݏo�������́A1500�|1505�N�̗��s�ƌ���B�ȏォ��A3�l�ڂ̃��i���U�́u1500�N�㏉���Ƀt�B�����c�F�ݏZ�̏�����`�������́v�ƌ��_�t�����B���ɘ_���I�I �Ȃ�A���̏����͒N���H
�@�ߔN�A�n�C�f���x���N��w�Ō���I�ȏ؋����������ꂽ�B�_�E���B���`�ƕt�������̂������t�B�����c�F�̖�lA.���F�X�v�b�`�̑����̗]���Ɂu���I�i���h�E�_�E���B���`�͂��܂��܂ȊG�Ɏ��|�������B�Ⴆ���U�E�f���E�W���R���h�̓������B1503�N10���v�Ƃ̏������݂��������̂��B
 �@���I�i���h�E�_�E���B���`��1452�N�A�t�B�����c�F�̖k��40km�̃��B���`���ɐ��܂ꂽ�B���B���`���̃��I�i���h����ł���B����A�u�t�B�K���̌����v�̌���ҁA�J�����E�h�E�{�[�}���V�F�Ɠ����B������̓t�����X�l�����B
�@���I�i���h�E�_�E���B���`��1452�N�A�t�B�����c�F�̖k��40km�̃��B���`���ɐ��܂ꂽ�B���B���`���̃��I�i���h����ł���B����A�u�t�B�K���̌����v�̌���ҁA�J�����E�h�E�{�[�}���V�F�Ɠ����B������̓t�����X�l�����B�@���Z���E�s�G�[���i1424�|1504�j�͌��ؐl�B���I�i���h����J�e���[�i�̂����̒��ɂ���ɂ��S��炸�A�t�B�����c�F�̋������̖��ƌ������Ă��܂��B���I�i���h�������������ɂȂ����̂͂��̂��߁B�Ȃ��̂ď������B�ŎZ���̂��́B�c���ꂽ���I�i���h�͕�̈������g�ɎĈ�B�Ƃ��낪���̐V�ƒ�Ɏq�����ł��Ȃ��������߃��I�i���h�͕��Ɉ�������t�B�����c�F�ցB���Ə���ȁI �ň��̕�Ƃ̕ʂ�B���̌�A�ނ̐S�̓������̖ʉe�������邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B
�@�t�B�����c�F�ō˔\���J�Ԃ������_�E���B���`�́A1482�N�A�~���m���h���B�[�R�ɏ�����~���m�����ցB�����Ō���u�Ō�̔ӎ`�v��`�����A1499�N�t�����X�R���N�U�������߃��F�l�c�B�A�֒E�o�B��1500�N�A�t�B�����c�F�ɕ����߂����B76�ɂȂ��Ă������Z���E�s�G�[���͌��ؐl�Ƃ��Ė������݁B�ڋq�ɍ����t�����`�F�X�R�E�f���E�W���R���h�������B����ɁA�ނ̍ȃ��U�̎��Ƃ̗אl�Ƃ����ԕ��B��������̉��l�̏ё��搻��̌����ɂȑ��q�ɐ��b���Ă���Ă��s�v�c�͂Ȃ��B�����ɂ͍ߖłڂ��̋C�������������̂�������Ȃ��B
�@�����̏y�ї��j�I�؋�����A�_�E���B���`�́A1503�N�A�t�����`�F�X�R�E�f���E�W���R���h�v�l���U�̏ё����`���n�߂��A�Ƃ����̂͋^���̂Ȃ������ƍl������B���@�U�[���̋L�q���ԈႢ�ł͂Ȃ������B�܂������̏ё����B��Ă��܂��Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ��������낤���B�u�W���R���_�v�͌��s�́u���i���U�v�ł͂Ȃ��A���̔w��ɂЂ�����ƉB��Ă���3�l�ڂ̃��i���U�������̂ł���B���ꂼ�A500�N�Ƃ����N�����o�ē��B�����Ռ��̌��_�B�C�M���X�̔��p�j��A.�O���A���f�B�N�\���́A������u���j��ς�������ׂ������v�ƕ]���Ă���B
�@�_�E���B���`�́A1516�N�A���[�}�ɗ����B���i���U���g���āB�Ƃ������Ƃ́A1503�N�ɏ����n�߂��W���R���h�v�l�̏ё���͈˗���ɓn��Ȃ��������ƂɂȂ�B�������Ȃ��������炾�B���R�͕s�������A�[�������ʓm��ȓV�˃_�E���B���`�Ȃ炠�肤�邱�ƁB����s�v�c�͂Ȃ��B�u�����O���m�̗�q�v�u�r��̐��q�G���j���X�v�ȂǂȂǁA�����̍�i�͐����B���@�U�[���́u�ӔN�̃��I�i���h�͂����̈������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������v�Ƃ܂ŏq�ׂĂ���B
�@���[�}�ɓn�����_�E���B���`�͌g�т��������̃W���R���_�v�l�̏ё��̏��4�l�ڂ̃��i���U���d�˕`�������B���s�́u���i���U�v�ł���B�Ȃ�A���̃��f���͒N�Ȃ̂��H ����͎���̂��y���݁B
���Q�l������
�u4�l�̃��i���U�v�`�g��̔��h���f���̐^�� NHK-BS�v���~�A�� 2017.5.17 OA
�u�����L��̓��I���t�v�`�����̉��l��������� �����V��2016.7.28�f��
�u�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv�Έ�G�� �V���Њ�
2017.05.25 (��) ���{�ƃg�����v�A���߂�̂͂ǂ����H
�@�C�̌������ł́A�g�����v�哝�̂��A��s���`�̑́B���V�A�^�f��A�̗��ꂪ�A1972�N�E�H�[�^�[�Q�[�g�����ɍ������Ă��邱�Ƃ���u���V�A�Q�[�g�v�ƌĂ�Ă���B�@�䂪���{�ł́A�X�F���œ����������{�ɁA���x�͉��v�w����肪���������B���݂��u�����������v�ƔF�ߍ������Ă̒����}�������O��B��l�̍s�����͂����ɁH
(1) �g�����v�哝�̂̏ꍇ
 �@��N�̑哝�̑I�I�ՁA���V�A�̃T�C�o�[�U���Ƀg�����v�w�c���֗^�����^�f�����钆�A�������Ԑl�̑哝�̕⍲���t�����������ă��V�A��g�ƐڐG�����^��������B�g�����v�哝�̂�2���A�t�����⍲������C�A������}��B���̗����AFBI�����W�F�[���Y�E�R�~�[���Ɍ������䎌���u�ނ͂����l������A���̌��͕����Ă����Ă���v�B�Ȃ�R�����I�^���������C����FBI�����Ɂu�����l�������ڂɌ���v���ƁI ���̔�펯�B�c�t������B
�@��N�̑哝�̑I�I�ՁA���V�A�̃T�C�o�[�U���Ƀg�����v�w�c���֗^�����^�f�����钆�A�������Ԑl�̑哝�̕⍲���t�����������ă��V�A��g�ƐڐG�����^��������B�g�����v�哝�̂�2���A�t�����⍲������C�A������}��B���̗����AFBI�����W�F�[���Y�E�R�~�[���Ɍ������䎌���u�ނ͂����l������A���̌��͕����Ă����Ă���v�B�Ȃ�R�����I�^���������C����FBI�����Ɂu�����l�������ڂɌ���v���ƁI ���̔�펯�B�c�t������B�@������ɁA�R�~�[�����́A���V�A�^�f�Njy���~�߂�͂����Ȃ��B5���ɂ͑{����p�̑��z��v����������}��B
�@5��10���A���o�����ꂽ�g�����v�哝�̂́A�R�~�[��������C�����B���R�́u�����d�������Ȃ������v�B��������R�ɂȂ��ĂȂ��B�����d�������Ȃ��������āA�����ɂƂ��Ăł���B
�@��11���A�g�����v���́A���V�A�̃��u���t�O���Ƃ̉�k�ŁA�C�X���G�����瓾���uIS�Ɋւ���ō����x���̋@���v��R�炵���Ƃ̋^��������B����z���g�Ƀz���g�H �g�����v���A�c�C�b�^�[�Łu�e���ƍq��̈��S�Ɋւ��鎖�������V�A�Ƌ��L�����������v�ƌ����Ă����z���g�ȂB�G���C���Ƃ����Ă��܂����Ƃ������o���Ȃ��B�ō����x���̋@���Ƃ͓����������炱�����L�ł�����́B������3���ɉI舂ɒ����Ĝ݂�Ȃ��B����ȃv�����V�v���̂Ȃ��哝�̂����Ă������낤���B���܂�̍����ɃA�����J�����͍��ҏȂ̐^���Œ��u�Ȃ�ł���Ȑl�Ԃ�哝�̂ɑI������̂��v�B���ꂪ�x����38���B
�@5��17���A����͂܂����Ǝi�@�Ȃ������B��������Ɨ����đ{���N�i���ł�����ʌ��@���Ƀ��o�[�g�E�����[����C�������B�����[���͌����ŗL�\�A�l�]�������B�A�����J�ŋ��̌��@���Ƃ����Ă���B����ɂ��ăg�����v���́u��X�̍����Ђǂ�������B���̂܂Ƃ܂���ꗂ���l�K�e�B�u�Ȏ��ۂ��v�Ɛ�����B�����������Ⴂ�܂����A�݂�Ȃ��Ȃ��̂����ł��傤�ɁB
�@���݁A�g�����v�哝�̂͒�����K���B�S���͂������肾�낤���H �A����ɂ́A�R�~�[�����،����邱�ƂɂȂ邾�낤��@���������B
�@����ɂ���āA�g�����v���̃��V�A�Ƃ̊W�Ǝi�@�ւ̉������������邱�ƂɂȂ�B�{���E������̌��ʁA�g�����v���̕s���s��������݂ɏo��A���Ȃ�i�K�́A�哝�̂̒e�N�ł���B���@��50���Œe�N���������A��@��3����2�ʼn������B
 �@�u���V�A�Q�[�g�v�ƌĂ��̂́A�j�N�\���哝�̂����C�����u�E�H�[�^�[�Q�[�g�����v�ɍ������Ă��邩�炾�B1972�N�đI���ʂ������j�N�\���B�w�c���I�����Ԓ���������̖���}�{���ɓ�������d�|�����Ƃ����^�f�B�؋������Ƃ��Ă̘^���e�[�v�̑��݂����o�B���ʌ��@���A�[�`�{���h�E�R�b�N�X�͂��̒�o�𔗂�B���ރj�N�\���̓R�b�N�X����C�B�����ŁA�c��͒e�N��ڎw���B���@�ői�ǂ����B�j�N�\���ϔO�B���C�����ӂ���B1974�N�̂��Ƃ������B
�@�u���V�A�Q�[�g�v�ƌĂ��̂́A�j�N�\���哝�̂����C�����u�E�H�[�^�[�Q�[�g�����v�ɍ������Ă��邩�炾�B1972�N�đI���ʂ������j�N�\���B�w�c���I�����Ԓ���������̖���}�{���ɓ�������d�|�����Ƃ����^�f�B�؋������Ƃ��Ă̘^���e�[�v�̑��݂����o�B���ʌ��@���A�[�`�{���h�E�R�b�N�X�͂��̒�o�𔗂�B���ރj�N�\���̓R�b�N�X����C�B�����ŁA�c��͒e�N��ڎw���B���@�ői�ǂ����B�j�N�\���ϔO�B���C�����ӂ���B1974�N�̂��Ƃ������B�@�^�f���o���{�����~�v���������̉�C�����ʌ��@���A�C�B��A�̃g�����v�E�P�[�X�̗���́u�E�H�|�^�[�Q�[�g�����v�ɍ�������B�u���ꂩ��40�N�I�v�����B
�@�A�����J�j��A�C�����Ɏ��C�����哝�̂̓��`���[�h�E�j�N�\��������l�B�e�N�Ɋ|�������哝�̂́A�A���h���[�E�W�����\���ƃr���E�N�����g���̓�l�����A�e�N�͕s�����B�ʂ����āA�g�����v�͂ǂ��Ȃ邩�H �M���ł��鐔���Ȃ��R�����e�[�^�[�̈�l���{�s�v���́u���@�Œe�N�i�ǂ��������Ă��A��@3����2�Ƃ����n�[�h���͍����B�e�N�����͓���v�ƓǂށB���A���͂����͎v��Ȃ��B
�@���疳�p�ȃg�����v�ɁA���C�̑I�����͂Ȃ����낤�B�Ȃ�Βe�N�B�ߋ��̎���������Ă݂悤�B�܂��́A1867�N�A�A���h���[�E�W�����\���̏ꍇ�B�ߏ�͗��R��b�̉�C�B�����̈Ⴂ�ɒ[���āA���{�����̔�ƕs�Ƃ���The Tenure Law��j�������ƁB���ɁA1999�N�A�r���E�N�����g���̏ꍇ�B���K���Ƃ́g�s�K�ȊW�h���I�悵���X�L�����_���B����Γ����I���B�����Ɋr�ׂ�ƁA�g�����v�哝�̂́u�����̉�C�ƍō����x���̋@���R�k�ƓG���Ƃ̌����v�Ƃ���3�̍ߏ�́A���ʂƂ��ɂ͂邩�ɏd���B�哝�̂̎������̂��̂Ɋւ����ł�����B
�@��C�͍s�����A�Č��͍����}�^�[�Ɏ~�܂����W�����\���E�P�[�X�ɂ����āA��@�̍̌��͋͂�1�[���i�̔ی��j�������B�g�����v�E�P�[�X�́A��C�͎i�@�ɋ߂��̈悩�A�Č��͑����̊֗^�ɂ��y�ԁB���̍��͐r��B�W�����\���E�P�[�X��1�[���̔ی��Ȃ�A�g�����v�E�P�[�X��������Ă�����s�v�c�͂Ȃ��B���́A�g�����v���̒e�N�����̉\���͂��Ȃ荂���ƌ���B�E�H�[�^�[�Q�[�g������2�N�B���������Ȃ�̎��Ԃ͂����邾�낤���A��X�́A�A�����J�哝�̏��̔�ƂƂ����O�㖢���̃V�[���ɁA�����ꑘ�����邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B
�@�Ⴆ�e�N���������Ȃ��Ă��A���́A�A�����J���A�܂����B�O�������Ɩ����`������Ȃ�ɋ@�\�����_�̎��R���܂��܂����݂ł��邩��B����Ɉ��������A�䂪���{�͂ǂ��Ȃ̂��I�H
(2) ���{�̏ꍇ
 �@���āA���x�͓��{�A���{�ł���B�X�F�����ǂ���瓦�������Ǝv��ꂽ���ɁA�u���v�w�����v�����o�����B�����̂��Ƃ̓J�P�B����������Ȃ����[�́I
�@���āA���x�͓��{�A���{�ł���B�X�F�����ǂ���瓦�������Ǝv��ꂽ���ɁA�u���v�w�����v�����o�����B�����̂��Ƃ̓J�P�B����������Ȃ����[�́I�@���v�w���������̉��v�K���Y���͈��{�́g���S�h�̗F���������B�m�荇�����̂̓A�����J���w����Ƃ�������A���ꂱ��40�N�B�S���t���H�����悭���A�Ƒ�����݂̕t���������Ƃ����B
�@���v�w�����R���ȑ�w��7�N�O����b��w���V�݂�ڎw�����A15��ɂ킽��\���͂��Ƃ��Ƃ��p������Ă����B�Ƃ��낪�A�A�x�m�~�N�X���Ɛ헪����\�z���o���ċ}�i�W�B���ȏȂ���F������A���t�A���Q�������s�ɁA�J�w�̉^�тƂȂ����B�����Ɉ��{�̓��ʂȗ͂��������̂ł͂Ȃ����H���ꂪ�u���v�w���^�f�v�ł���B�ȉ��͂��̌o�܁B
2015�N6���@���Ɛ헪���惁�j���[�ɁA4�̏��������̏�ŁA�@5��17���A�����V�������Ɂu�V�w���w�����̈ӌ��x�v�Ƃ̌��o�������B�u�Z�Z���t�{�R�c���Ƃ̑ł����킹�T�v�i�b���w���V�݁j�v�Ƃ̑薼��2016�N9��26���t�̓��t�{�̈ӌ��������ȏȐE�����쐬�����������o�Ă����Ƃ������́B�����ɂ́A�u2018�N4���J�w���O��ɁA�t�Z���čŒZ�̃X�P�W���[�����쐬���A���L�������������v�u����͊��@�̍ō����x���������Ă��邱�Ɓv�Ə�����Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@ �b��w���V�ݏ������lj������
2016�N3���@���s�Y�Ƒ�w���b��w���V�݂ɖ������グ��
2016�N6���@�O���ꎁ���ȏȎ��������ɏA�C
2016�N8���@�n���n���S����b���Δj�Ύ�����R�{�K�O���Ɍ��
2016�N9�|10���@���ȏȂ��u�����̂��ӌ��v�ȂǂƋL���ꂽ�������쐬
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�쎁�����A�ȓ����L�̈Č��ƂȂ�
2016�N11���@�u�b��w�����Ȃ��n��Ɍ���v�Ƃ̕��j�����\�����
�@�@�@�@�@�@�@�@ �ߗׂɏb��w�������鋞�s�Y�Ƒ�w�f�O
2017�N8���@���v�w���ɔF�̌��ʂ�
2018�N4���@�����s�ɉ��R���ȑ�w�b��w���J�w�̗\��
�@�������̏O�@���Ȉψ���B���̐^�U���������Ж��}�����c���ɑ��A���{�́u���̕������U����������A���Ȃ��ӔC������̂��v�Ɯ����B���炩�Ɋ�����Ԃ��Ă����B�g�Ɋo�����Ȃ��̂Ȃ�A��ÂɌ������ؖ�������������̘b�Ȃ̂ɁB
�@�{���́A���͎҂��A���̌��͂𗔗p���l�I�ȗ��v���p��}��Ƃ����A���吭���ɂ���܂������Ă�₤���́B��}���������ɂ��̐^�U��₤�͓̂��R�̍s�ׂł����āA����������ɔے蜘������̑ԓx�͂����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂��B
�@�����[�����́u�������v�ƌ��߂��A���ȏȂ́u���ȏ�7�l�̊����ɕ��������s���A�ȓ��̋��L�t�H���_���������A�Y�����镶���̑��݂͊m�F�ł��Ȃ������v�Ƃ���Y�T���Ȍ��ʕB�ɓZ��镉�̗v�f��������ɂȂ��ĉB�ł��A�������}�邢���̎���B�X�F���Ɠ����l����悵�Ă����B
 �@�Ƃ��낪5��24�� ���Ԃ͈�ρB�O���ȏȎ��������E�O��약���̓Ɛ荐�����u�T�����t�v�Ɍf�ڂ���A�����A�L�҉���J���ꂽ�B�ȉ������v��B
�@�Ƃ��낪5��24�� ���Ԃ͈�ρB�O���ȏȎ��������E�O��약���̓Ɛ荐�����u�T�����t�v�Ɍf�ڂ���A�����A�L�҉���J���ꂽ�B�ȉ������v��B�@���Ɛ헪����ɂ����鍡���s���v�w�����R���ȑ�w�b��w���̐V�݂ɂ��āA���͕��ȏȑ��̎������g�b�v�Ƃ��Ċւ���Ă����B���A���ƂȂ��Ă���8���̕����́A�����ݐE���Ɏ��ۂɋ��L���Ă����킯�ŁA�m���ɑ��݂��Ă����̂͊ԈႢ�̂Ȃ��������B���������̂��Ȃ������Ƃ͌����Ȃ��B�u2018�N4���̊J�w��O��Ƃ��A������t�Z���čŒZ�̃X�P�W���[�����쐬���L���Ă������������B����͊��@�̍ō����x���������Ă��邱�Ɓv�Ȃ郌�N�i�����p�̃��������j�́A���ȏȂ̐�勳��ۂ̐E�����A���t�{�̓����R�c���̂��Ƃ�K��ď��������̂ŁA������̂�9��28���ł���B�ǂ���10��17���ɂ́A�u���ȑ�b���m�F�����ɑ�����t�{�̉v�Ƒ肷�郌�N��������B�����ɂ́u�}�̋c�_�͕s�v�A2018�N4���J�w�͌��莖���ő�O��B����͑����̈ӌ��ł���v�Ƃ���A���t�{����̍ŏI�ʍ��ɓ��������̂������B
�@�{�Č��́A���v�w���̌ŗL���������o��@��͏��Ȃ��������A�W�҂̊Ԃł́u�Öق̋��ʗ����v�Ƃ��Đi��ł����B����Ȓ��ŁA�����o�������҂Ƃ��ẮA4�̏������N���A���Ăق����Ə�ɑi���Ă������A�[������������Ȃ��܂܉�����ꂽ�B�ɂ߂ĐƎ�ȍ����̂��ƂɋK���ɘa���s���A���������ł���ׂ��s���̂�������c�߂�ꂽ�Ƃ��킴��Ȃ��B
�@�悭�������܂Ō������������ꂽ���̂��B���ɉ���I�B���ݑޔC���Ă���Ƃ͂������߂̑O�C�҂Ŏ������̃g�b�v���A�ӂ����������ς�Ƙ_���I����̓I�ɏq�ׂĂ���̂�����A�܂��^���Ȃ��̂ƍl����̂����R���낤�B���������������Ǝv���B�����A������������[�����̌��́u�����ɂ��āA���ȏȂ̒������ʂł͑��݂��m�F�ł����A���t�{�ɂ��A�w���@�̍ō����x���x�Ƃ��w�����̂��ӌ��x�Ƃ������������͂Ȃ��Ƃ̕��Ă���B�s�����c�߂�ꂽ�Ƃ̎w�E�͂܂�����������Ȃ��v�Ƃ̖��^�������J��Ԃ��̂݁B����Ɂu�����g���ӔC�҂̎��ɂ��������������������̂Ȃ�A�����œ��X�ƌ����ׂ�����Ȃ��������v�Ƃ܂Ō����B�����̎������g�b�v���A����Ȃ��ƌ�����킯�Ȃ����낤�ɁI ����Ȃ��Ƃ͊��[��������ԕ������Ă�͂��ł��傤�B���X�����I ����Ɂu�O�쎁�́A�V�����肪�����������A���玫�߂�ӌ����������ɒn�ʂɂ����݂��A���_�̌������ᔻ�𗁂тĂ���Ǝ��C�����l�v�ƌl�U�����u�`������B�ǔ��V�����X�N�[�v�����Ƃ����u�O�쎁�o��n�o�[�ɒʂ��v�̓��˂������Ȃ������B�u�ؐl����ɂ͏o��v�Ƃ̑O�쎁�̌��܂�����}�̗v���ɂ��A�����}���Έψ����́u���Ȃ��v�Ɠ˂��ς˂�B���R�͌����K�v���Ȃ��炵���B�Ȃ��Ȃ�u�ʔ����b���������̖{���Ƃ�������Ă���v���炾�������B�����������Ⴂ�܂����A�����`�̍����Ɋւ�邱��قǖ{���I�Șb������܂����I�H �������������ɂ����͂Ȃ��B�^���𖾂̂��߂ɂ͒f���ďؐl��������ׂ����B�����^�}�c���̗����Ȃ�NO�̈�ĕ��˂��a�I�ł���B�}�X���f�B�A�̑Ή������ʂ邢�B�E�C���錳����VS���ƌ��͂Ƃ����\�}���͂�����ƌ������̂�����A�܂��͑O�쎁�̐^�U�������Ɍ����ׂ��Ȃ̂ɁA�u���͓���v�A�u�؋����v�ȂǁA�]�_�ƁA�R�����e�[�^�[�̗ނ̑唼���ے�_���B��Ɏ��w�ǂ�����(�H)����ǔ��n���r�������B�^���̋C�T��������ꂸ�A�����ɛZ��p�����肪�ڗ��B�܂�Ŏh�q�Ԃ̑́B
�@����Ȃʂ�ܓ��ɐZ������{�A5��3���ɂ͌��@�������ĂȂ���̂������o���Ă����B2020�N��ړr�Ɂu���@��9���Ɏ��q���̑��݂𖾕��\�L����B��1�C2���͂��̂܂܂Łv�{�u��������̖������v�Ƃ������́B�u��͕s�ێ��v���������2�������̂܂܂ɂ��Ắu���q���̖����\�L�v�B���������ǂ�����āH�ǂ������ӂ̏�����ƁB�����}�ւ̔z�����_�Ԍ�����B���@�������ߊ�Ƃ����Ȃ�A�Ȃ����U�@�ł��Ȃ��̂��B���{�Ă���Đ����₤�ׂ��B���ꂪ���@�Ɍ������p���Ƃ������́B����̕\���͌��@�ɑ��Ď��炾�I
�@�}�Ɏ����o���Ă����u��������̖������v�����ɕs���R�B�{���ɂ��ꂪ�ŗD�悳���ׂ����ĂȂ̂ł����H ����Ȃ�����̃n�[�h���͒Ⴂ����B�ېV�ւ̔z���H �o�J�������Ⴂ���Ȃ��B��̂��Ȃ��̑_���͉��H �������`�B�Ƃɂ����ς���Ⴂ���B�j�㏉�߂Č��@��������������b�Ȃ閼���₷���ƁB�Ⴂ�܂����H �D�悷�ׂ��͍����������Ȃ̖��_�B�u�������炸�A�������炸�A�n�ʂ���������ʐl�͎n���ɍ���B�����A���������l�łȂ�����Ƃ̑�Ƃ͂Ȃ����Ȃ��v�`���������̌��t�����A���{�͂܂��ɋt�B�⏬�ȃg�b�v��Ղ����̕s�K�I
�@���V�A�Q�[�g�Ɖ��v�w�����B�ʂ����č���̓W�J�́H ���v�w���}�^�[�́A������b���A���S�̗F�̕X��}�邽�߁A���Ɛ헪�ɂ��̗v�f�荞�݁A���������r�����A���̎�����}�����B���S�Ȃ鐭���̎������B���ĂȂ������Ȍ����̗��p�B���V�A�Q�[�g�ɕC�G����ߏ�ł���B
�@�R�~�[�O�����A�����[���ʌ��@���B�Njy����}�X���f�B�A�B�A�����J�ɂ͂܂����`�����݂���B�g�����v���C�̉\���͍����B
�@������{�B���������ƁA�ېg�ɑ��邨��l�B�}������}�X���f�B�A�B���{�ɂ͈Ӓn�̌��Ђ��Ȃ��B����A���ꂪ�A�^���̉𖾂Ȃ��܂ܖ��������ׂ��ꂽ��A���{�ɖ����͂Ȃ��B�u�V�����݂Ȓʂ�v����ȏ�Ȃ����Ƃɐ��艺����B�Ȃ�Ƃ������Ƃ������ł����Ăق����B���{��M�������̂����E�E�E�E�E�B
2017.05.15 (��) �G���K�[�u���̈��A�v�ƃh���}�u���_�v�ɓZ���ʔ��b
 �@NHK-E�e���Ɂu����N���V�b�N�v�Ƃ����ԑg������B4�����҂Ńp�[�\�i���e�B�����������A����܂ł̉��H����Z���Γc�˗ǃR���r�͔��Q�������B�Γc���́u�r�܃E�G�g�Q�[�g�p�[�N�v�V���[�Y���Ől�C�̒�����ƁB�N���V�b�N�ɂ����w���[����i���ɂ����Ȃ�����o���B���܂�ʂԂ炸�A�ق�킩���[�h�ŏ���݁A�D���x��B���Z����͏�����ȉƁB�D�������͋C�̂��o�������������ʐF��������B���D�̎mF�������Z����̑�t�@�������A����͂��Ă����A�ޏ��̃s�A�m��e���Ȃ���̉���́A�����ɉB���ꂽ�ȑz�̔閧��P��o���A�Ȃ̖{��������ɂ��Č����B���������ɕ�����₷���B5�N�Ԃ�200����d�˂����̃R���r�����i�v�S�ǂ̕z�w�Ǝv���Ă������A4�����҂ő����Č�サ�Ă��܂����B�c�O���ɁI
�@NHK-E�e���Ɂu����N���V�b�N�v�Ƃ����ԑg������B4�����҂Ńp�[�\�i���e�B�����������A����܂ł̉��H����Z���Γc�˗ǃR���r�͔��Q�������B�Γc���́u�r�܃E�G�g�Q�[�g�p�[�N�v�V���[�Y���Ől�C�̒�����ƁB�N���V�b�N�ɂ����w���[����i���ɂ����Ȃ�����o���B���܂�ʂԂ炸�A�ق�킩���[�h�ŏ���݁A�D���x��B���Z����͏�����ȉƁB�D�������͋C�̂��o�������������ʐF��������B���D�̎mF�������Z����̑�t�@�������A����͂��Ă����A�ޏ��̃s�A�m��e���Ȃ���̉���́A�����ɉB���ꂽ�ȑz�̔閧��P��o���A�Ȃ̖{��������ɂ��Č����B���������ɕ�����₷���B5�N�Ԃ�200����d�˂����̃R���r�����i�v�S�ǂ̕z�w�Ǝv���Ă������A4�����҂ő����Č�サ�Ă��܂����B�c�O���ɁI�@�����ēo�ꂵ���̂́A�o�D�̍������T���B�V�V���[�Y�́A�y�ȕ��͂����G�s�\�[�h���d�_�B���ɂƂ��Ă͂ǂ�������������邪�A�����Č������V���[�Y�̕����悩�������ȁB�ł��A�V�V���[�Y�́u�����N���V�b�N�v�ɑ����̃l�^����Ă��ꂻ���ł���͂���Ŋy���݂��B��1��́u�G���K�[ ���̈��A�v�������B����́A���̋Ȃ̃N�����m�I���_�ɂ��ʔ��b������I�������B
�@�u���̈��A�v�͌���uSalut D�famour�v�B��Ȏ҃G�h���[�g�E�G���K�\�i1857�|1934�j�������̍ȃA���X�ɍ���L�O�Ƃ��đ������ȁB���}���e�B�b�N�Ŕ���������閼���i�ł���B
�@�^�C�g���͓����G���K�[���p��ŁuLove�fs greeting�v�Ƃ������A�h�C�c������̍���҂̗v�]�ŁuLiebesgruss�v�ɕς���B������o�ŎЂ��g�t�����X��̕����L���b�`�[�h�ƌ��������ǂ����͕s�������A�ŏI�I�Ƀt�����X��ɗ����������Ƃ����o�܂����B�I���W�i���̊y��Ґ��̓��@�C�I�����ƃs�A�m�̃f���I�B�A���X�̓G���K�[�̃s�A�m�̒�q����������A�ޏ����s�A�m�A�G���K�[�����@�C�I������e���Ƃ������H�ɑ��������̂������B�o�ł�1886�N�A�G���K�[29�B��Ɏ��g�I�[�P�X�g���ɕҋȂ���B
 �@���̂���̃G���K�[�́A�܂��A�̋��E�X�^�[�i���̃E�X�^�[�E�\�[�X�̔��˒n�j�̉��y���t�B�A���X�̉Ƒ��͌����ɑ唽�B��������̂͂��A�ޏ��̕��w�����[�E���o�[�c�͌�ɗ��R�����ƂȂ��ăT�[�̏̍���^������D�G�ȌR�l�B����̃G���K�[�Ƃ�����C�̂��̂Ƃ��R�̂��̂Ƃ����Ȃ����̉��y���t�B���������o�[�c�Ƃ��C�M���X�����A�G���K�[�̓J�g���b�N�Ə@�����Ⴄ�B�����Ă��ɁA�u�������ł��G���K�[�ƌ������܂��v�Ƃ������͊������Ă��܂��̂ł���B����ȏ��œ�l�͍���B�u���̈��A�v�̒a���B���ԕ��A�z�������g�����ւ̓]�������Ɍ���阺���ȗJ���̕\��́A���̋��̌o�܂��Î�����H
�@���̂���̃G���K�[�́A�܂��A�̋��E�X�^�[�i���̃E�X�^�[�E�\�[�X�̔��˒n�j�̉��y���t�B�A���X�̉Ƒ��͌����ɑ唽�B��������̂͂��A�ޏ��̕��w�����[�E���o�[�c�͌�ɗ��R�����ƂȂ��ăT�[�̏̍���^������D�G�ȌR�l�B����̃G���K�[�Ƃ�����C�̂��̂Ƃ��R�̂��̂Ƃ����Ȃ����̉��y���t�B���������o�[�c�Ƃ��C�M���X�����A�G���K�[�̓J�g���b�N�Ə@�����Ⴄ�B�����Ă��ɁA�u�������ł��G���K�[�ƌ������܂��v�Ƃ������͊������Ă��܂��̂ł���B����ȏ��œ�l�͍���B�u���̈��A�v�̒a���B���ԕ��A�z�������g�����ւ̓]�������Ɍ���阺���ȗJ���̕\��́A���̋��̌o�܂��Î�����H�@������̃G���K�[�́A�l���ς�����悤�ɐ��i�B�s�i�ȁu�Е����X�v�S5�ȁA�u�G�j�O�}�ϑt�ȁv�A�`�F�����t�ȃz�Z���A�s�A�m�d�t�ȃC�Z���A�Ȃǐ��X�̌������ȁB�C�M���X���\����̑�ȍ�ȉƂƂȂ����B�A���X�����ނ̃~���[�Y�������̂ł���B��ɔނ́u���̍�i��������̂Ȃ�A�܂��ȂɊ��ӂ��ׂ����v�ƌ����Ă���B�u�����̐����͍Ȃ̂������v�A�G���K�[�͂��̂��Ƃ�N���������Ă����̂ł���B
 �@���āA�������炪�{��ł���B����2013�N11��6���̌ߌ�A���C�Ȃ��h���}�u���_�v�����Ă����B���i�قƂ�ǂ��̃h���}�͌��Ȃ�����A���̓��͗]���ɂ������̂��낤�B�Ƃ��낪�A���́u���_�v�V���[�Y2��7�b�u���������́v�ɁA�G���K�[�u���̈��A�v���o�ꂵ���̂ł���B
�@���āA�������炪�{��ł���B����2013�N11��6���̌ߌ�A���C�Ȃ��h���}�u���_�v�����Ă����B���i�قƂ�ǂ��̃h���}�͌��Ȃ�����A���̓��͗]���ɂ������̂��낤�B�Ƃ��낪�A���́u���_�v�V���[�Y2��7�b�u���������́v�ɁA�G���K�[�u���̈��A�v���o�ꂵ���̂ł���B�@����͂Ƃ��閼�ȋi���B�a�J�̃��C�I���Ƃ����������ǂ����낤�B���J�L�����鐙���E���iS�j�Ǝᏼ���j�����鑽�������iT�j�Ƃ̂����ł̉�b�����L�B
T�@�����ł��� �G���K�[���D���ł����@���ȋi���ŗאȂƂȂ��������E���Ƒ��������͈ӋC�����B��l�͂����Ŗ��Ă���u���̈��A�v���]�~����荇���B�p���ʂ̉E���́A�L�b�p���Ɓu�m�[�}���E�f���E�}�[�i1919�|1994 �C�M���X�̉��y�w�ҁ��w���ҁj�́w���̈��A�x�����̔ՂƂ̓A�����W���Ⴄ�v�ƌ����̂ł���B
S�@�D���ł��˂�
T�@���ɂ��́u�~�j�A�`���A�v�͑f���炵��
S�@�m�[�}���E�f���E�}�[�̖��Ղł���
T�@�ނ̎w������G���K�[�͂�����i�ł���
S�@���̒��ł��u���̈��A�v�͓��ɂ����ł���
T�@����ł��ˁi�Ɖ��̏o�Ă�������������j
S�@���̔Ղ������̂ƃA�����W������Ă����ł���
T�@�m���Ă܂� �����ɃG���K�[�́u�~�j�A�`���A�v������̂��f���炵��
�@�@����A�f�G�ȕ��Ƃ��m�荇���ɂȂꂽ
�@���͎��A���������܂ŁA�f���E�}�[�ɂ��u���̈��A�v�������Ƃ��Ȃ���A���^�A���o���u�~�j�A�`���A�v�̑��݂��m��Ȃ������B�w���҂Ƃ��Ẵf���E�}�[�Ȃ�A�N�X���T�C�g�́u�`���C5�v�i�`���C�R�t�X�L�[�����ȑ�5�ԁj�R�[�i�[�Œm��A���̉��t�̑f���炵���͏n�m���Ă����B���R�ȗ���ɂ�����ȑz�̎��݂ȕω����▭�ŁA���́u�`���C5�v�R���N�V�����̒��ł��ŏ�ʂɈʂ��邨�C�ɓ��艉�t�̈���B�����ɁA���̕��f�ł���B�������ł����������Ȃ��āA�����A�m�[�}���E�f���E�}�[�w���F�{�[���}�X�E�V���t�H�j�G�b�^�̉��t����u�~�j�A�`���A�v�̕���CD���w���B�u���̈��A�v�ɕ����������B�����E���̌����Ƃ���A����͑f���炵���A�����W�����t�������B
�@�G���K�[�̎�ɂȂ�I�P�łł́A����������y���t�ŃX�^�[�g���邪�A�f���E�}�[�ł̓\���E���@�C�I�����Ŗ��₩�Ɏn�܂�B�����ɖ؊NJy�킪���݂Ȃ���A���X�ɃX�g�����O�X�̌��݂������Ă䂫�N���C�}�b�N�X���`���A�Ō�̓z�����������▭�ȋ����̒��Â��ɏI���B�G���K�[�łɔ䂷�Ƃ�莺���y�I���B�G���K�[���I�P�ł�������ۂɈӐ}�����̂́A�I���W�i���̃f���I�Ƃ͈Ⴄ�Y��ȃI�[�P�X�g���I�������������낤���A�f���E�}�[�͋t�Ƀf���I���u�������A�����W�����݂��̂��낤�B���̂�����̗��҂̎v�f�̈Ⴂ���ʔ����B
�@�u���_�v���f��4�N��A���N4���́u���N���v�Łu���̈��A�v�����グ���B�����ʼn��߂ăh���}�̘^������A�f���E�}�[�Łu���̈��A�v���������蒮���Ă݂��B�����ŁA�u�I���I�v�Ɗ������̂ł���B�����łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����҂̉����S���Ⴄ�̂ł���B�f���E�}�[�ł̎�������\���E���@�C�I�����Ȃ̂ɑ��A�h���}�̉��͂Ȃ�ƌ��y���t�ł͂Ȃ����B 4�N�O�C�Â��Ȃ������͕̂s�o�����A�܂����ƃ`�F�b�N�Ȃǂ��Ă��Ȃ������̂�����d�����Ȃ��B���łɁA�h���}�̉�������肷�ׂ������������ʁA�A���h�����[�E�f�C���B�X�w���FBBC�����y�c�̍�Ȏ҃A�����W�łƔ��������B����͊ŔɁA�Ƃ������A�䎌�ɋU�肠��ł���B��̂Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N�������̂��낤���H
 �@�h���}�ɓo�ꂷ��R���e���c��LP���R�[�h�ł���B�E�����������Ƀv���[���g���錏�ł�������ƃW���P�b�g���f���Ă���B����͕�����Ȃ��f���E�}�[�́u�~�j�A�`���A�v�B���̉����g���Ή�����͂Ȃ������͂��B�Ȃ̂ɂ������Ȃ������̂́A����Ȃ�̎���������̂��낤�B������A�v���I�ȃL�Y���������̂����m��Ȃ��B �Ȃ��1998�N�ɂ͕�������Ă���CD���g���悩�����̂����A�������炩�̎���Ŏ�ɓ���Ȃ������H ����Ƃ��A���P�n�̏a�J�u���C�I���v���L�̃A���h�����[�E�f�C���B�X�w���FBBC���Ղ��g�����^���Ă��܂����H �u�䎌�̒����Ƃ͐H���Ⴄ���A�ǂ�������͂��Ȃ��v�ƃv���f���[�T�[�������������������ۂ��͕s�������A�Ƃ�����A���ՂȑI�������Ă��܂����͎̂����ł���B�u�m�[�}���E�f���E�}�[�̂͑��̔ՂƂ̓A�����W���Ⴄ��ł��v�Ɛ����E�����]�~����点��̂Ȃ�A�����͉������ł����̉���T���o���Ďg���̂����m�����l�Ԃ̗ǎ��Ƃ������̂��낤�B�u���_�v�X�^�b�t�̖ҏȂ𑣂������B
�@�h���}�ɓo�ꂷ��R���e���c��LP���R�[�h�ł���B�E�����������Ƀv���[���g���錏�ł�������ƃW���P�b�g���f���Ă���B����͕�����Ȃ��f���E�}�[�́u�~�j�A�`���A�v�B���̉����g���Ή�����͂Ȃ������͂��B�Ȃ̂ɂ������Ȃ������̂́A����Ȃ�̎���������̂��낤�B������A�v���I�ȃL�Y���������̂����m��Ȃ��B �Ȃ��1998�N�ɂ͕�������Ă���CD���g���悩�����̂����A�������炩�̎���Ŏ�ɓ���Ȃ������H ����Ƃ��A���P�n�̏a�J�u���C�I���v���L�̃A���h�����[�E�f�C���B�X�w���FBBC���Ղ��g�����^���Ă��܂����H �u�䎌�̒����Ƃ͐H���Ⴄ���A�ǂ�������͂��Ȃ��v�ƃv���f���[�T�[�������������������ۂ��͕s�������A�Ƃ�����A���ՂȑI�������Ă��܂����͎̂����ł���B�u�m�[�}���E�f���E�}�[�̂͑��̔ՂƂ̓A�����W���Ⴄ��ł��v�Ɛ����E�����]�~����点��̂Ȃ�A�����͉������ł����̉���T���o���Ďg���̂����m�����l�Ԃ̗ǎ��Ƃ������̂��낤�B�u���_�v�X�^�b�t�̖ҏȂ𑣂������B�@����Ȃ���ȂŁA�܂��܂����ȂɓZ���ʔ��b������I���Ă��܂��܂����B���ꂩ����A�������čׂ₩�ȁu�N�����m�v�I���_�ɁA�܂��܂������������Ă䂫�������̂ł���܂��B
2017.03.25 (�y) �u���Ȃ����g���v��� ����
�@�ŋ߁A�u�f���̎v���v�Ƃ����䎌���x�������B�L�����ɂ��ƒf���̎v���Ƃ́u�����������قǂ̋ꂵ�݁v���Ƃ��B��ςȂ��̂��B��̓T�b�J�[���{��\�̃L���v�e�����J�����I��B2018�T�b�J�[�E���[���h�J�b�v�E�A�W�A�ŏI�\�I�̑��� UAE���O�ɉ���ŗ��E�B���̐܂ɔ��������t�ł���B���ʂ�2�|0 ����ɒe�݂���������������B���J���̑���E����K���S�[����������ȂǁA�ނ́u�f���̎v���v�͋g�Əo���B �@������́A�b��̐X�F�w���������E�Ēr�דT���̒��j���Ύ��̑䎌�u���͒f���̎v���ł��傤�v�ł���B�ؐl����Ɍ��������̋C�����𐄎@�������̂��B
�@������́A�b��̐X�F�w���������E�Ēr�דT���̒��j���Ύ��̑䎌�u���͒f���̎v���ł��傤�v�ł���B�ؐl����Ɍ��������̋C�����𐄎@�������̂��B�@�Ēr���ϔN�̖��u���w�Z�J�݁v�ɂ���قǎ^�����Ă����l�������A2��8���A���̌�������݂ɏo���Ƃ���ɂ悻�悻�����Ȃ��Ă������B��ɁA�h�����Ă�܂Ȃ����{����u�������l�v�i2��23���\�Z�ψ���j�ƌ���ꂽ�̂́A�v������ɂ��铯�u�Ǝv���Ă��������ɃV���b�N�������B�₪�āA���{�͔F������߁A�J�Z�͐�]�I�ƂȂ����B�����������͉̂����Ȃ��B�������m�邱�Ƃ͂��ׂĂԂ��܂���B�u���Ȃ����g���v�E�E�E�E�E���Ύ����������́u�f���̎v���v�Ƃ͂��̂��Ƃ������B
�@3��23���̍���ؐl����ɓo�ꂵ���Ēr���́u�^�ɓ��{���̂��߂ɂȂ�q������Ă����Ƃ�������҂̗��ꂩ��A���N��4���Ɂw����̍��L�O���w�@�x���J�Z�ł���悤�A����܂Ŋ撣���Ă܂���܂����v�Ɛ�o�����B���ڂ��ׂ��q�͎���2�_�ł���B
�@�@�@�@ ���{���b���t������b�v�l�́A�Ēr���̎v�z�ɋ����X�F�w���˖{�c�t����x�X�K��B2015�N9��
�@�@�@�@�@5���ɂ͍u�����s�����w�Z�̖��_�Z���ɏA�C�����B�����A�Ēr��������100���~�̊�t�����b�v�l��
�@�@�@�@�@�������B�u���{�W�O����v�Ƃ��āB�ꏊ�͗��������B��l����̏ɂāB
�@�@�@�A ���b�v�l�֗���d�ɂĈ˗������ꌏ�ɂ��A�v�l�t�����{�E���E�J���b�q������A2015�N11��15���A
�@�@�@�@�@�Ēr����FAX���͂����B�u�����Ȗ{�Ȃɖ₢���킹�A���L���Y�R������������B����ł͂�
�@�@�@�@�@��]�ɉ����Ȃ����A�������������Ƃ��Ă�������Ă䂫�����B��������ēx���������B����͏��b�v
�@�@�@�@�@�l�ɂ����Ă���v�Ƃ�����|�̂��̂������B
�@���{�����́A2��17���A�O�@�\�Z�ψ���Łu�F�ɂ����L�n�̕��������ɂ���������͂Ȃ��B����Ȃ��W���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�A������b������c�������߂�Ƃ������Ƃ��A�͂�����Ɛ\���グ�Ă����v�Əq�ׂ��B�����A��ρI���ƂȂ�u�Ȃ�Łg�Ȃ��h�Ƃ܂Ō����Ă��܂����̂��v�ƌ�������肾�낪�A���������̂͂��傤���Ȃ��B
�@�@�������Ȃ�A�����͐X�F�w���ɐ[���ւ���Ă������ƂɂȂ�B�A�������Ȃ�A���b�v�l�͈�A�̌��Ɋ֗^���Ă������ƂɂȂ�B�ǂ��炩����ł��ؖ������A���{�����͐E�������˂Ȃ�Ȃ��B���m�ɓ͂Ȃ��̂�����B
�@3��24���̎Q�@�\�Z�ψ���ɂ����āA���b�v�l���Ēr�v�l�̊ԂŌ��킳�ꂽ�삵�����̃��[����J��FAX�ɂ��Ă̎��^�������������B���[���Ɋւ��ẮA���e�I�ɖ��Ȃ��Ƃ���������������Ȃ����A��������������A��l������قǂ܂łɐe���Ȋԕ����������Ǝ��̂����Ȃ̂��B
�@����ɁA��̒J����FAX�ɏ��b�v�l���ւ���Ă������ۂ��̋c�_���������������A����Ȃ��̂͋c�_�ȑO�̖��ł���B�u�J������l�Ƃ��č����ȂɏƉ���v�Ƃ��銯�[�����̕ق�A�u���ǂ͈�ʂ���̖₢���킹�ɂ͏�ɐ��ӂ������Ă��������Ă���v�Ƃ����������E�����ȗ����ǒ��̔����ȂǏΎ~�疜�B���̌ւ荂�������Ȃ���E���̐���œ����킯���Ȃ��ł͂Ȃ����B������b�v�l�̈˗������炱���������̂ł���B����͜u�x�̃��x�������֗^�ȊO�̉����ł��Ȃ��B����ȗ����͗c�t�����ɂ�������B
�@�����āA����2015�N�H�����肩���Ēr���������g�_���h�������n�߁A�����̈ٗႪ�A�����ĔF�Ɏ���킯�ŁA����ł��֗^�Ȃ��ƌ������鑍���́A�펯�ɑa�����Ԓm�炸�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@���������A�펯��P���Ȃ��Ăł��A��펯��掂��Ă��A�Ȃ�ӂ�\�킸�g�b�v����낤�Ƃ���̂́A���R�Ƃ͂����A�l�Ԃ̍s�ׂƂ��ď�Ȃ�����B�X���ł��炠��B
�@��}�́u���b�v�l�A������{�m����8�l�̏ؐl����v�v�]�����ۂ���|���U�E�����}�����ψ����̎x���ŗ��I�k�ق�������B����m���Ȃǂ́u���ōs���v�Ƃ܂Ō����Ă�̂��B�s�������Ƃ����l���Ȃ����₷��H �Ēr���͌Ă�ł����b�v�l�͌ĂȂ��B�ǂ��ɐ�����������̂��B�Ēr������́u�����J�����v����H ��̂ǂ��������Đ�������Ă�̂��B�|������A������A���삳��A���̕������A�{���Ɏ����̐l�����p���������Ȃ��̂��낤���B�ނ�͎����̎q��ɋ����Ď���̎p��������̂��H ���̐����Ƃ�������̈�̂ǂ��ɐ��`������I�H
�@�}�X�R�~��]�_�ƁE�R�����e�[�^�[�����e���I �F����A�����ȂׂĐ������B��\�i�̓e���[�ɓ��Ɠc��j�Y�����肩�ȁB�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��`���E�`����Y�B�Ēr�������R�ƌ��߂��A���{�v�Ȃ̏̎^�i��ɏI�n����B���̂���҂ǂ��ɂ���H �����ꂽ�̂́u100���~����v�Ɋւ����z�I�����B�u�Ēr�������b�v�l��100���~�����o���������Ȃ������̂ł������t�Ƃ����̂ł́v�Ȃ�ĂˁB���f�B�A���z���ł��̂�������Ȃ����āB�^�}�c���̉\�b���܂�ܒ����Ȃ����āB��X�����߂Ă�̂�FACT�����Ȃ���B���ꂶ��u�̎��R�x�����L���O�v�����E��72�ʂȂ̂��������Ⴄ�B�I�C�I�C�A�؍��������Ȃ��I
�@�Ēr�����J�Z��\�肵�Ă������w�Z�̎p�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��낤���H ����͌��݉^�c���̒˖{�c�t��������Έ�ڗđR�B�܂������̔��f�����ڂ��Ȃ��c�q�ɋ��璺������a������B���ۖ@���𐧒肵�����{���̎^���u�K���o���v�G�[���̘A�āB���ʓI�����̉��s�B�Ƃ�ł��Ȃ����̂��B
�@���璺��͐l�Ԃ̖{����搂������������T�ɔے�ł��Ȃ��Ƃ�����m���ɂ���B�������Ȃ���A������b���ƌď̂��u���Ƃ̂��߂̎��ȋ]���v�Ƃ���B����́A��{�I�l����ۏႷ��u���{�����@�v�Ƃ͑�����Ȃ��O�ߑ�I�Ȃ��́B1948�N�A����ł��̎��������c���ꂽ�㕨�Ȃ̂��B����Ȃ��̂����ȋʏ��̂��Ƃ����q���c�q�ɈÏ�������Ȃǎ��������r�������B���@�ᔽ�ɖ���Ă����������Ȃ�������j�Ȃ̂��B
�@����ȏ��w�Z�̊J�݂ɂ�����A���{�͂�������̋��͂��{�����B�O��Ȃ��ɘa�̃I���p���[�h�B���������Ă̋��͑̐��B���̒��_�ɂ͓��t������b������B��̂���͂ǂ��������ƁH ��������J�M�́u���{��c�v�ɂ���B
�@�u���{��c�v�Ƃ́u���������{�̍Č��ƌւ肠�鍑�Â���̂��߂ɁA�����ƍ����^���𐄐i����v���Ԓc�̂ł���i���{��cHP���j�B�ł́A���̃X���[�K���́H
�@�@�@�@ �c���𒆐S�ɁA�������j�A�����A�`�������L����Ƃ������j�F��������
�@�@�@�A ��̌R�ɂ�艟���t����ꂽ�����@�ɑ��莩��̎�Ōւ肠��V���@��n������
�@�@�@�B ���̖��_�ƍ����̖������^���ێ�̐����̎���
�@�@�@�C ���{�l���×����玝�����I���_���͂����ދ���̑n��
�@�@�@�D ��v�ҒǓ��̔O��Y�ꂸ�ɕ��a�ƈ��S�̂��ߎ��͂ō������Ƃ������_�����N����
�@�@�@�E �������h�̐S�Ő��E�Ƃ̗F�D���ނ���
�@��X�͓��{�l�ł���B���{�����ł���B���{�×��̕����`������萢�E���a�ɍv������Ƃ������O�͈����낤�͂����Ȃ��B�A���s���߂���Ɗ댯��������B�c�q�ւ̋��璺��̋����A�l��荑�Ƃ��d�錛�@����A�r����`etc �����͎�����t�s������̂��B�X�F�w���̋���͂��̋���𑽕��ɓ����B���݂ɁA�Ēr�דT���͓��{��c�̉^�c�ψ��ɖ���A�˂Ă���B
�@�u���{��c�v�ɂ��u���{��c����c�����k��v�Ȃ�g�D������B���x���͂�����u���{��c�v�̗��O�Ɏ^�����鍑��c���̏W�܂�ł���B�������281���B�S����c����39�����߂�B����ɁA���s��3�����{���t�̊t��������ƁA���{�����E�����������͂���19����14��������A�˂�B���Ƃ����苒���I ���{���t���u���{��c���t�v�Ƃ�����R���ł���B���݂ɁA�ؐl���ⓙ�Ŗ��O���o�����{�쎡�A���O�A���r�˔��e�c��������ł���B
�@�����A�Ēr�����u���{�̍l���Ɏ^�������h�\���グ��v�ƌ������̂ɂ͂���Ȕw�i���������̂��B���{�������ԈႢ�Ȃ��Ēr���̋�����j�ɋ����Ă����B���݂��u����ɂ��铯�u�������B������A��q���O���ېg�ɑ��鑍�������āu�Ȃ��H�v���b��u����v�Ɗ����u���Ȃ����g���v�ƂȂ����̂ł���B
�@�������́A�u�Ēr���̃f�^�������v��������ƂŁA�ނ̎咣��ے肵�A��������낤�Ƃ��Ă���B�ł��悭�l���Ăق����B�Ēr�����掂��邱�Ƃ́A�ނƗ��O�������鑍�����Ȃ߂邱�ƂɂȂ�̂ł���B
 �@�m���ɁA�Ēr�דT���́A���̐M���⋳�痝�O�ɂ����Ď������̂�����B�^�c�ɂ����邤����L�����@���Ȃ��B�����������A������Ēr���ɁA���t������b���{�W�O���͋��^�����Ă����̂ł���B���̏؋��̈�Ƃ��āA2012�N9��11���t�́u�c�t���ی�҈��ĖK�⌇�Șl�я�v������B�u�����}���ّI�o�n�ɂ�����������A�ȑO����̋M���K�₪�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B���ɐ\����܂���B����K���K�₲���A�����Ă��������܂��v�Ƃ������̂��B�����܂ŋ����Ă����̂ł���B�^�����Ă����̂ł���B�Ȃ�����ʂ������ł͂Ȃ����B���ꂪ�����Ȃ��̂Ђ�Ԃ��̔�排����A�֗^�ے�A�����̈��B���ׂĂ͕ېg�̂��߁B�Ēr���͂��̔ڗɗ��_�����B�l�Ԑ��ɋ^����������B�����ĖJ�߂��Ȃ��Ēr�דT�Ƃ����j�ɓ��t������b���{�W�O�͈��z�������ꂽ�̂ł���B��X�͂��̂悤�ȃg�b�v��Ղ����Ƃ�㵒p�̔O���ւ����Ȃ��B��肫��Ȃ��B���{����ɂ́A���{��������b�Ƃ��Ă̌ւ���Ȃ�Ƃ����߂��Ă��������������̂ł���B
�@�m���ɁA�Ēr�דT���́A���̐M���⋳�痝�O�ɂ����Ď������̂�����B�^�c�ɂ����邤����L�����@���Ȃ��B�����������A������Ēr���ɁA���t������b���{�W�O���͋��^�����Ă����̂ł���B���̏؋��̈�Ƃ��āA2012�N9��11���t�́u�c�t���ی�҈��ĖK�⌇�Șl�я�v������B�u�����}���ّI�o�n�ɂ�����������A�ȑO����̋M���K�₪�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B���ɐ\����܂���B����K���K�₲���A�����Ă��������܂��v�Ƃ������̂��B�����܂ŋ����Ă����̂ł���B�^�����Ă����̂ł���B�Ȃ�����ʂ������ł͂Ȃ����B���ꂪ�����Ȃ��̂Ђ�Ԃ��̔�排����A�֗^�ے�A�����̈��B���ׂĂ͕ېg�̂��߁B�Ēr���͂��̔ڗɗ��_�����B�l�Ԑ��ɋ^����������B�����ĖJ�߂��Ȃ��Ēr�דT�Ƃ����j�ɓ��t������b���{�W�O�͈��z�������ꂽ�̂ł���B��X�͂��̂悤�ȃg�b�v��Ղ����Ƃ�㵒p�̔O���ւ����Ȃ��B��肫��Ȃ��B���{����ɂ́A���{��������b�Ƃ��Ă̌ւ���Ȃ�Ƃ����߂��Ă��������������̂ł���B
2017.03.15 (��) 3���́u���N���v�́u����VS�N���V�b�N�v�̏t�Ό�
�@��N10���Ɏn�߂�FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v�������N���߂����B���s����̘A�����������A�挎�́u���؏�܍�w���I�Ɖ����x��ǂ݉����v�͍D�]�������B�e�[�}���^�C�����[���������ƂƒZ���s�A�m�Ȃ�I�Ȃ������Ƃ����J�b�^���B�����́A�d�g�ɏ���Ă����ɏ����Ă����Ă��܂��B������A�d��������y���Z���������̂��낤�B�l�ߍ��݉߂����L���b�`�\�ɁB�Ȃ�ƂȂ��R�c�����߂��C�������B �@3����16�����������B�e�[�}���u�t�v�ɐݒ肵���B�N���V�b�N�ɂ�����t�̖��Ȃ͑��X����B�x�[�g�[���F���́u�X�v�����O�E�\�i�^�v�A�V���[�}���̌����ȑ�1�ԁu�t�v�A�����f���X�]�[���́u�t�̉́v�A���B���@���f�B�́u�l�G�v����u�t�v�ȂǂȂǁB�����������I�ȁE������Ă��܂�Ȃ��B�ꖡ�Ⴄ���t��������B���ꂼ�N�����m���_�Ƃ������̂��B
�@3����16�����������B�e�[�}���u�t�v�ɐݒ肵���B�N���V�b�N�ɂ�����t�̖��Ȃ͑��X����B�x�[�g�[���F���́u�X�v�����O�E�\�i�^�v�A�V���[�}���̌����ȑ�1�ԁu�t�v�A�����f���X�]�[���́u�t�̉́v�A���B���@���f�B�́u�l�G�v����u�t�v�ȂǂȂǁB�����������I�ȁE������Ă��܂�Ȃ��B�ꖡ�Ⴄ���t��������B���ꂼ�N�����m���_�Ƃ������̂��B �@����Ȑ܁A���ݗF�B��N����u���{�̉̂ƃN���V�b�N����ׂĂ݂���v�ƒ�Ă��Ă��ꂽ�B�ނ͔ԑg�̋M�d�ȃ��X�i�[�Ŏ��Ɍ������_���o���������m�B���ꂢ�������B�u�t�v���̂����{�̏��̂ƃN���V�b�N��Δ䂳���Ă݂悤�B�܂��́A�u�t�v�̏��̂Ƃ����Ή��H �Ǝ���ɐu���Ă݂�B��ʂ́u�t�������v�u�t�旈���v�u�t�̏���v�u�ԁv�Ƃ܂��͗\�z�ʂ�B�����̉̂Ƌ��ʂ��鐢�E�ς̃N���V�b�N�͉����낤�H �t���t���A�ʔ����Ȃ��Ă����I
���w�u�t�旈���v VS ���[�c�@���g�̉̋ȁu�t�ւ̓���v
�@�@�u�t�旈���v�i���n�䕗�쎍�j
�@�@�t�旈���@���������@���邫�͂��߂��@�݂������
�@�@�Ԃ��@���́@���傶��͂��ā@������֏o�����Ɓ@�҂��Ă���
�@�@�u�t�ւ̓���v�i�N���X�e�B�A���E�I�[���@�[�x�b�N�쎍�A�Έ�s��v��j
�@�@���Ă��傤�����@�C�����̂���5����@������ �X���܂��ɂ��Ă�
�@�@������ ����̐�ׂ�ɂ́@�����Ȃ��݂�̉Ԃ��炩���Ă�ˁI
�@���āA������̉̂͏t�̉����̂��Ă���̂��H ����́g�t���҂��ǂ������q���̋C�����h�ł���B�ł�������Ƒ҂Ă� �u�t�旈���v�͂����Ƃ��āA�u�t�ւ̓���v�͂Ȃ�5���Ȃ́H ���{�ł́A5���Ƃ����Ώt�Ƃ�����菉�Ăł��傤�B����������J�M�̓r�[����CM�\���O�ɂ������I
�@���̐́A1950�|60�N��{�j�[�E�W���b�N�X���̂����T�b�|���E�r�[����CM�\���O�Łg�~�����w���`�D�y�`�~���E�H�[�L�[�h�Ƃ����̂�����܂����B���̉̂̐S�́u���E�̃r�[���̖��Y�n�͖k��45�x�O��ɂ���v���B���ׂĂ݂�ƁA�~�����w���͖k��48�x8���A�D�y��43�x3��44�b�A�~���E�H�[�L�[��43�x3��8�b�ƁA�m���ɂقړ����ܓx�B�u�t�ւ̓���v�̍쎍�҃N���X�e�B�A���E�I�[���@�[�x�b�N(1755�|1821)�̓n�m�[���@�[�o�g�B�n�m�[���@�[�̓~�����w����肳��ɖk�Ŗk��52�x�B������t���x���B�t��5���A�Ƃ����̂�������̂��B

�@�̋ȁu�t�ւ̓���v�̓��[�c�@���g�ŔӔN1791�N�̍�i�B���̃����f�B�[�͍Ō�̃s�A�m���t�ȁu��27�� �σ����� K595�v�̑�3�y�͂̃e�[�}�ɂ��g���Ă���B
�@�u�t�旈���v�̍쎌�ґ��n�䕗�i1883�|1950�j�́A�V�����͎�����̏o�g�B�k���̐l�͏t��҂C�������l��{�����I�H
�@�]�k�����A��t�͖��݂̂̕��̊�����A�ł�����݂́u���t���v�i�g�ۈꏹ�쎍�A���c�͍�ȁj�́A�J�ԁu�t�ւ̓���v�Ɏ��Ă���ƚ�����A�X�ɋv�\�́u�m������v�͐��u���t���v�̃p�N���Ƃ�����B�ł��܂��A����ȗ�̓L�����Ȃ��B
���́u�ԁv VS �`���C�R�t�X�L�[�u�Ԃ̃����c�v
 �@��t�̂����̋��c��E�E�E�E�E�Ŏn�܂鏥�́u�ԁv�́A�u�r��̌��v�̍�ȉƑ�����Y�i1879�|1903�j�̑�\��̈�B���w�u�������v���ނ̍�i�B��͉䂪���̐��m���y�t�������x������ȉƂ̈�l���B�쎍�̕����H�߁i1872�|1967�j�͓������܂�̍����w�҂Ŏ��l�B���Ɂ���g���g�Ƃ��Ƃ��ƁA�Œm����u�������V�R�v������B�Ȃ��A1956�N�A���c�������⋴�e�ɁA��Ғ��M�u�ԁv�̉̔肪���Ă�ꂽ�B
�@��t�̂����̋��c��E�E�E�E�E�Ŏn�܂鏥�́u�ԁv�́A�u�r��̌��v�̍�ȉƑ�����Y�i1879�|1903�j�̑�\��̈�B���w�u�������v���ނ̍�i�B��͉䂪���̐��m���y�t�������x������ȉƂ̈�l���B�쎍�̕����H�߁i1872�|1967�j�͓������܂�̍����w�҂Ŏ��l�B���Ɂ���g���g�Ƃ��Ƃ��ƁA�Œm����u�������V�R�v������B�Ȃ��A1956�N�A���c�������⋴�e�ɁA��Ғ��M�u�ԁv�̉̔肪���Ă�ꂽ�B�@�Δ䂳����ԂɈ��N���V�b�N�Ȃ́H ���[�c�@���g�u���݂�v�A�r�[�[�̉̌��u�J�������v����u�Ԃ̉́v�A�V���[�}���̉̋ȏW�u�~���e�̉ԁv�A�V���[�x���g�A�E�F���i�[�́u���v�A�}�N�_�E�F���́u���Ɋv�A�t�H�[���u�C�X�t�@�n�����K�N�v�AR.�V���g���E�X�̌��u��̋R�m�v�ȂǂȂǁB�ӊO�Ə��Ȃ��I�H
 �@�����́A�`���C�R�t�X�L�[�́u�Ԃ̃����c�v��I�ڂ��B�O��o���G�Ō�̍�i�u����݊���l�`�v����̃i���o�[�B���q�ƃN�������u���َq�̍��̖��@�̏�v�ł̕�����ɏo������B�X�y�C���`�A���r�A�`�����`���V�A�`�t�����X�ȂNJe���̗x��̂��ƁA�ԗւ������ėx��Q���ƂȂ�B���ꂪ�u�Ԃ̃����c�v���B�ؗ�Ń��}���e�B�b�N�B�t�����ɑ����������|�I���N���N���I �����A�u����݊���l�`�v�̓N���X�}�X�̕��ꂾ���炻����Ȃ��H ���������A�C�����t�Ȃ炻��ł悵�B��ȔN��1892�N�B�`���C�R�t�X�L�[���S���Ȃ�O�N�̍�i���B
�@�����́A�`���C�R�t�X�L�[�́u�Ԃ̃����c�v��I�ڂ��B�O��o���G�Ō�̍�i�u����݊���l�`�v����̃i���o�[�B���q�ƃN�������u���َq�̍��̖��@�̏�v�ł̕�����ɏo������B�X�y�C���`�A���r�A�`�����`���V�A�`�t�����X�ȂNJe���̗x��̂��ƁA�ԗւ������ėx��Q���ƂȂ�B���ꂪ�u�Ԃ̃����c�v���B�ؗ�Ń��}���e�B�b�N�B�t�����ɑ����������|�I���N���N���I �����A�u����݊���l�`�v�̓N���X�}�X�̕��ꂾ���炻����Ȃ��H ���������A�C�����t�Ȃ炻��ł悵�B��ȔN��1892�N�B�`���C�R�t�X�L�[���S���Ȃ�O�N�̍�i���B���́u�t�������v VS ���n���E�V���g���E�X�U�̃����c�u�t�̐��v
�@��t������ �t������ �ǂ��ɗ��� �R�ɗ��� ���ɗ��� ��ɂ������E�E�E�E����C�V�쎍�A�������ȁB���́u�̋��v�̃R���r�B���݂Ɂu�t�̏���v���������B����� Spring has come ������t�����^������̉́B���āA�N���V�b�N�́H
�@�I�̂̓��n���E�V���g���E�X�U�̃����c�u�t�̐��v�B������t�̋Ȃ��炱���I���R�̈�́u�j�͂炢��v�ł���BFM���ǂ���̓d�g�͓Ђ���̌̋������Ė��ɂ��͂��̂��B
 �@�u�t�̐��v���A�f��u�j�͂炢��v�ŏ��߂Ďg��ꂽ�̂́A��8��u�Ў��Y���́v�i1971�N12��29������j�ł���B�}�h���i�͒r���~�q�����関�S�l�M�q����B��ߓV�e�ɋi���X�u���[�N�v���J���B��ڂڂꂵ���Ђ���͓��Q�B����Ȃ�����A�M�q����̈�l���q����ߓV�̋����Œ��Ԃɓ��ꂸ�ɂ���p�������˂��Ђ���́A��v���Ă��A������܂イ�𓐂ݏo���q�������݂�Ȃƍ]�ː�ɏo�ċY���B�]�ː�̓y��ł͂��Ⴎ�Ђ���Ǝq�������B�����ɗ����̂��u�t�̐��v�Ȃ̂��B���x������V�[���ɖ�������t�̃����c�B�h���s�V���̃V���N���B�����āA�M�q����̑��q�͗F�B�̗ւɓ��ꂽ�B�Ђ���̗D�����ɐS�ł���閼�V�[�����B
�@�u�t�̐��v���A�f��u�j�͂炢��v�ŏ��߂Ďg��ꂽ�̂́A��8��u�Ў��Y���́v�i1971�N12��29������j�ł���B�}�h���i�͒r���~�q�����関�S�l�M�q����B��ߓV�e�ɋi���X�u���[�N�v���J���B��ڂڂꂵ���Ђ���͓��Q�B����Ȃ�����A�M�q����̈�l���q����ߓV�̋����Œ��Ԃɓ��ꂸ�ɂ���p�������˂��Ђ���́A��v���Ă��A������܂イ�𓐂ݏo���q�������݂�Ȃƍ]�ː�ɏo�ċY���B�]�ː�̓y��ł͂��Ⴎ�Ђ���Ǝq�������B�����ɗ����̂��u�t�̐��v�Ȃ̂��B���x������V�[���ɖ�������t�̃����c�B�h���s�V���̃V���N���B�����āA�M�q����̑��q�͗F�B�̗ւɓ��ꂽ�B�Ђ���̗D�����ɐS�ł���閼�V�[�����B�@�u�Ў��Y���́v�́A�V���[�Y�̒��Łg�ߖځh�ƂȂ�������I��i�ł�����B��́A�ϋq���������߂�100���l�̑��������ƁB�ō��̂����������E�X��M�͂��̍�i���Ōゾ�������ƁB����ɁA���̍�i�ȍ~�A�N���Ƃ��~�̔N2�샍�[�e�[�V�������m�����ꂽ���ƁB�����āA�^�C�g���́g�Ў��Y�h�Ƃ��������͂��̍�i���@��34��i�ɕt�����邱�ƂɂȂ�B
�@�u�t�̐��v�́A���̌�u�j�͂炢��v��9��u�Ė����v�A��30��u�Ԃ������Ў��Y�v�A��41��u�Ў��Y�S�̗��H�v�ɂ��g��ꂽ�B�S4��B���̋L���ł́A�����N���V�b�N�Ȃ�����قǎg��ꂽ��͑��ɂȂ��B�R�c�ē͂�قǂ��̋Ȃ����C�ɓ���Ȃ̂��낤�B
�@�����c�u�t�̐��v��1883�N�̍�i�B�V���g���E�X���؍ݒ��̃u�_�y�X�g�łƂ���p�[�e�B�[�ɏo�ȁB�����ŋ��m�̗F�l���X�g�Əo��B���X�g�͂��̉Ƃ̏���l�Ƒ����ŘA�e�B�V���g���E�X�͂������ɂ��̏�Ń����c����ȁB�o�����̂��u�t�̐��v�������B57�̃V���g���E�X��71�̃��X�g�B�V�l�Ƃ͎v���Ȃ���X�����Ɉ�ꂽ�����c�B��僂�e��ȉƂȂ�ł͂̃G�s�\�[�h���B
�@�ŁA�uFM���ǂ���v�����A����3���܂ł̗\�肾�������A�D�]�ɂ��H4���ȍ~�������邱�ƂɂȂ����B��邩��ɂ͊撣���Ă������B���[�� ���L�� ���ʔ����I�I
����������
���[�c�@���g��ȁF�̋ȁu�t�ւ̓���v
�@�@�G�f�B�b�g�E�}�e�B�X�i�\�v���m�j
�@�@�x�����n���g�E�N���[�i�s�A�m�j�@1972�N�^��
�`���C�R�t�X�L�[��ȁF�o���G�u����݊���l�`�v���u�Ԃ̃����c�v
�@�@�W�F�C���Y�E�����@�C���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�@1992�N�^��
���n���E�V���g���E�X�U��ȁF�����c�u�t�̐��v
�@�@�E�B���[�E�{�X�R�t�X�L�[�w���F�E�B�[���E���n���E�V���g���E�X�nj��y�c�@1984�N�^��
2017.02.25 (�y) �Ǔ� �D���O�`�̂͐S�ł���������
(1)��Ȑl���̃X�^�[�g�ƍ�����j �@�D���O�B�{�����c���Y�B1932�N6��12�� �Ȗ،����J�S�D�����o�g 2017�N2��16�������B�Éꐭ�j�i1904�|1978�j�A�����Lj�i1907�|1993�j�A�l���ɔV���i1917�|1990�j�A�g�c��(1921�|1998)�A������(1932�|2008)�A�s�쏺��i1933�|2006�j��Ƌ��ɏ��a�̗̉w�ȉ��������z�����A�Ō�̑��ȉƂ������B
�@�D���O�B�{�����c���Y�B1932�N6��12�� �Ȗ،����J�S�D�����o�g 2017�N2��16�������B�Éꐭ�j�i1904�|1978�j�A�����Lj�i1907�|1993�j�A�l���ɔV���i1917�|1990�j�A�g�c��(1921�|1998)�A������(1932�|2008)�A�s�쏺��i1933�|2006�j��Ƌ��ɏ��a�̗̉w�ȉ��������z�����A�Ō�̑��ȉƂ������B�@���F�E�Ñ����ɂ��A�D������͏�Ɂu�̗w�Ȃ͎����厖�B�������������ď��߂Ă����̂����܂��v�ƌ����Ă����������B�ނ̍�i�͂قƂ�ǂ�����B������A���_���쎌�Ƃ���ΕK�v�ƂȂ�B�ŏ�����͍�����j�i1930�|1956�j�������B�o��͓��m���y�w�Z�i���������y��w�j�B�����ɃR���v���b�N�X�����D���͂���錧���܂�̍���Ƃ͋C���˂Ȃ��b�����ł����B�u���͈��قŎ��������A���O�͓ȖؕقŋȂ����v������̌��B��l�͐��ɂ�ɂ���ʼn̂���葱�����B��i���g���ē��X���R�[�h��Ђ����B
 �@���R�[�f�B���O���ꂽ�ŏ��̋Ȃ́A�t�����Y�u�������l���v�i1955�N8�� �L���O���R�[�h�j�������B�����Ă��̔N��11��10�������A�R���r��4�� �t�����Y�u�ʂ�̈�{���v����q�b�g����B�q�b�g�̗v���̈�ɁA�D���̃N���V�b�N�̑f�{���������B���̍�i�͕ҋȂ��s���Ă��邪�A���Y���͂Ȃ�ƃJ�������́u�n�o�l���v�ł���B���̃��[�c�͏��N����ɕ������Z�̃n�[���j�J�ɂ��u�h���S�̃Z���i�[�h�v�ɂ���B
�@���R�[�f�B���O���ꂽ�ŏ��̋Ȃ́A�t�����Y�u�������l���v�i1955�N8�� �L���O���R�[�h�j�������B�����Ă��̔N��11��10�������A�R���r��4�� �t�����Y�u�ʂ�̈�{���v����q�b�g����B�q�b�g�̗v���̈�ɁA�D���̃N���V�b�N�̑f�{���������B���̍�i�͕ҋȂ��s���Ă��邪�A���Y���͂Ȃ�ƃJ�������́u�n�o�l���v�ł���B���̃��[�c�͏��N����ɕ������Z�̃n�[���j�J�ɂ��u�h���S�̃Z���i�[�h�v�ɂ���B�@���ɁA����E�D���R���r�̖��͓��{�S���ɒm��킽�����B�������^���͈Ӓn�����B����͗��N�x���j�ł��̐��������Ă��܂��B�������ꂩ��Ƃ������̊|���ւ��̂Ȃ����_�̎��I �D���̖��O�͂������肾�������낤���B��l�̈��ƂȂ����u�j�̗F��v�i�،���j�͗܂Ȃ��ɂ͒����Ȃ��B�u���͂��O�̕��܂Ő�����v�A�Ȍ�A�D���́A����̖�����9��8���ɂ́A�ނ̌̋��}�Ԏs�Ŗ��N�����������y���{�𑱂����B�Ƃ͂������_��T���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�E�E�E�E�B
�@�u�ʂ�̈�{���v���̂����t���́A�u�������߂Ă������̂͂��ꂾ�B���̃X�^�C���������ꂩ��̎������v�Ɗm�M�����Ƃ����B���̎����̏t���́A1954�N�Ɂu���x����v�̔����I�q�b�g�ɂ���č����I��X�^�[�ƂȂ��Ă����B�������Ȃ�Ƃ����t�@���́u���x����v�����߂�B���̂܂܉������̉̂��ŏI����Ă��܂��̂��H �Ɗ�@�����点�Ă����B�����Ɂu�ʂ�̈�{���v�ł���B���D�Ɗi���B�܂��Ɏ��Ȃ̐i�ނׂ����B�u�ʂ�̈�{���v�͉̎�t�����Y�̋~����ƂȂ����̂ł���B����́A�u�S�ō��S�ł������v�D�����ڎw������ƂƉ̎�̗��z�̌����������B���̌�A�D����i�͉̎�̍s������Ƃ炷�T�Ɠ��ƂȂ��Ă䂭�̂ł���B
�i2�j���c�p�Y�u�����v�`��㏉�̃~���I���a��
 �@���a���̗̂Y�E���c�p�Y���X�^�[�_���ɉ����グ���̂́u�����v�i�������\�쎍�A�D���O��ҋȁj�ł���B�Q�ȂŊ��Ɉ�Ƃ𐬂��Ă������c�́A1958�N�A��䏊�E�Éꐭ�j�Ɍ���������āu���@���̈ꐶ�v�ʼnX�����̗w�E�Ƀf�r���[���ʂ������s���B��������̎��オ�����B�����́A��ނ��T�E���h�����@���A�Q�Ȃ̈���o�Ȃ��������ƁB��������v�����̂��D���������B�m�y�I�A�����W��������A�E�Q�ȏ��@��B�����ŏo���オ�����̂��A�Q�Ԃ̊��m�E��c�O�g����l���̎��{�{������f�i�Ƃ�����3���q�̋ȁu�����v�������B�܂��ɌÉ�E�Q�ȘH���̑ɁB�Éꂪ�����͂����Ȃ����A���c�̎������i�� �V�h�v���_�N�V�����j�̎В��E����K�Y�͊o������߂Ēk���B�̗w�Q��LP�̑}���ȂƂ��Đ�s�����A��������̃V���O���E�J�b�g�Ƃ������(�H)�ɏo�āA1961�N11���ɔ���������q�b�g�B��㏉�̃~���I�����L�^�B���c�͂���ʼn���������������ʑ�X�^�[�ƂȂ����B����Ă��Ȃ��A����A���ꂽ���炱���A�É�̓{��͓������܂�Ȃ������Ƃ����B�u�����v�Ȃ����đ��c�p�Y�Ȃ��B�����ł��D���͉̎�̉^����ς����̂ł���B
�@���a���̗̂Y�E���c�p�Y���X�^�[�_���ɉ����グ���̂́u�����v�i�������\�쎍�A�D���O��ҋȁj�ł���B�Q�ȂŊ��Ɉ�Ƃ𐬂��Ă������c�́A1958�N�A��䏊�E�Éꐭ�j�Ɍ���������āu���@���̈ꐶ�v�ʼnX�����̗w�E�Ƀf�r���[���ʂ������s���B��������̎��オ�����B�����́A��ނ��T�E���h�����@���A�Q�Ȃ̈���o�Ȃ��������ƁB��������v�����̂��D���������B�m�y�I�A�����W��������A�E�Q�ȏ��@��B�����ŏo���オ�����̂��A�Q�Ԃ̊��m�E��c�O�g����l���̎��{�{������f�i�Ƃ�����3���q�̋ȁu�����v�������B�܂��ɌÉ�E�Q�ȘH���̑ɁB�Éꂪ�����͂����Ȃ����A���c�̎������i�� �V�h�v���_�N�V�����j�̎В��E����K�Y�͊o������߂Ēk���B�̗w�Q��LP�̑}���ȂƂ��Đ�s�����A��������̃V���O���E�J�b�g�Ƃ������(�H)�ɏo�āA1961�N11���ɔ���������q�b�g�B��㏉�̃~���I�����L�^�B���c�͂���ʼn���������������ʑ�X�^�[�ƂȂ����B����Ă��Ȃ��A����A���ꂽ���炱���A�É�̓{��͓������܂�Ȃ������Ƃ����B�u�����v�Ȃ����đ��c�p�Y�Ȃ��B�����ł��D���͉̎�̉^����ς����̂ł���B�i3�j�u��̓n���v�𑶑��������̗̂�
�@�����S���t�ɛƂ��Ă���1970�N��A�x���ɒʂ��l�߂��̂��u�Ė��S���t��v�ł���B��ߓV�̗�����̍]�ː�͐�~�ɂ������B���̓Ђ��u�j�͂炢��v�̓������ŁA�C���E�v���C�̃{�[�����E���Ă��܂�����A���j��Ƃ̃L�����o�X�Ɉ��Y�����肵�ăg���u���������N�������̃S���t��ł���B4�z�[���\���ŁA�P�A3�Ԃ��p�[3�A2�A4�Ԃ��p�[4�B2�ԃe�B�[�̘e����u��̓n���v����������B���Ԃ́A�����̕����V�E�ߓ�������Ɖ�Ђ̗F�lI���B�݂�ȓƐg�A600�~�œ�������܂Ńv���C�������Ƃ́A�����u��r�v�ŕ��C�𗁂сA�Ă������Œ��߂�B
�@���܂��ɕs�v�c�łȂ�Ȃ��̂́u��r�v�ł̕��C�̈ꌏ�ł���B��r�Ƃ����ΉĖڟ���J�菁��Y�Ȃǂ��ۛ��ɂ������嗿���B���̕��C�ɃS���t���I������X�������ŐZ�����Ă䂭�̂ł���B�ߓ�����́u��r�̓S���t���̐l�����ɊJ�����Ă���v�Ƃ����Ȃ���擪����ė��h�Ȓ뉀�X��舕����Ă䂭�B���߂����ɑ�����l�B�����̃S���t�E�L���b�v�Ɋ������̃|���V���c�B�����̂��q�����~������b�����Ɍ��Ă���B�i�����镗�C�͂���3�l�A���ɃS���t�@�[�炵���l����x����Ƃ������������Ƃ��Ȃ��B���ɂ��Ďv���Ύ��ɕs�v�c�ȑ̌��B����A�ߓ��}�W�b�N�I�H �u���̓t���[�c�p�[���[�����̂����Ȃv�Ɛ̉ʕ��X�ɋ߂��������ɓX��ƌ��܂��Ď��߂Ă��܂����ߓ�����B���܂���ǂ����Ă���̂��낤���H
 �@����Ȃ�����A������c��c������A�u�S���t��̗��p�v�ɂ����n�Ō����A���P�[�g�������Ƃ�����B�u�Ė��S���t��v�Ɓu��̓n���v�̑��p�����������Ƃ����B�A���P�[�g�ɉ�X�́u�����͉�珎���̃S���t��B��ɑ����Ăق����v�Ɠ��������A�S���t��͐��N��ɔp�~�A��̓n���͎c�����B�u��̓n���v���c�����͈̂�ɑD���̔��Ăō��ꂽ���́u��̓n���v�̂������ł���B
�@����Ȃ�����A������c��c������A�u�S���t��̗��p�v�ɂ����n�Ō����A���P�[�g�������Ƃ�����B�u�Ė��S���t��v�Ɓu��̓n���v�̑��p�����������Ƃ����B�A���P�[�g�ɉ�X�́u�����͉�珎���̃S���t��B��ɑ����Ăق����v�Ɠ��������A�S���t��͐��N��ɔp�~�A��̓n���͎c�����B�u��̓n���v���c�����͈̂�ɑD���̔��Ăō��ꂽ���́u��̓n���v�̂������ł���B�@�u��̓n���v�i�Ζ{���R�I�쎌�A�D���O��ҋȁj�́A1976�N10���A�������Ȃ��݁u�����v��B�ʂłЂ�����ƃ����[�X�B�������Y����Ă������B�Ƃ��낪��O�����̔~��x���Y�����̋Ȃ��o�b�N�ɗd���ȗx����I����Ə��X�ɐ��ԂɐZ���B1983�N�ɂ͑����̉̎�ɂ�鋣��ƂȂ�A�����o�����א삽�������N���̃��R�[�h��܂��l�������q�b�g�ƂȂ����B�N�X�Ɖ̂��グ��א�������͂Ȃ����A�������̉����ۂ��ƌ����̂��܂��̕����D���̈Ӑ}�ɒf�R���v���Ă���B�D���́u�������͎̉̂葆���M�B�א�̂̓��[�^�[�t���D�v�ƕ]�����B
�@���̉̂́A�A�C�h���Ƃ��ăf�r���[���u���сv�Ń��R�[�h��܂��l�����������Ȃ��݂̐V���n���J���B�D���̍�鉉�̂͂������̉̏��ɍX�Ȃ閁�����������B�݂̂Ȃ炸�A���̃q�b�g�ŁA�����̊�@�ɂ������u��̓n���v�Ɋό��q���E���A���݂������Ė��`���˖�؊Ԃ����C�ɍs�������Ă���B�D���͉����̕����������~�����̂ł���B
�i4�j�u�݂��ꔯ�v�̊��
�@������j�Ƃ����|���ւ��̂Ȃ����_���������D���ɂƂ��āA���̌��߂鑶�݂͐���N�Y�i1925�|2010�j���������낤�B���Ƀv���E�f�r���[���Ă����D���ƍ쎌�Ƃւ̓���͍����Ă�������Ƃ̏o��́A���l�J�`100���N�L�O�̍쎍�R���N�[���������B�R�����߂Ă����D������Ԃɉ���������̎��u�l���q�}�h���X�v�͌���1�ʂɋP���B�u�l���q�}�h���X�v�͑D�����Ȃ�t������Ђ�̉̂ŁA1957�N5���A�R�����r�A���烊���[�X���ꂽ�B�D���̌������őҖ]�̃R�����r�A�ꑮ�ƂȂ�������́A�Ђ�̉̂𐔋ȏ������q�b�g�ɂ͎���Ȃ������B
�@���쁕�D���R���r�́A�k���O�Y�̑�2��u�Ȃ݂��D�v�ŊJ�ԁA����u����Ȃ��ꗷ�v�ւƂȂ���B���̃X�P�[���������쁕�D���R���r�ɂ����o���Ȃ����E�ł���B
�@�D���́A1960�N�A�Ζ{���R�I�Ƃ̃R���r�ŁA�̂��o�����ō����Ƃ�����ȁu���D�g�~��v�����Ђ�Ɂi�����}���̔����������āj�̂킹�A���R�[�h��܉̏��܂������Ƃ�B�D���O��́u�Ђ�̖��ȁv�a���������B
�@�������́A1964�N�A�N���E���ɈڐЁB�Ђ�Ƃ̐ړ_��������B�u�Ђ�ɖ��Ȃ��v�͐���̍�Ɛl���̖Y�ꕨ�ƂȂ����܂܍Ό��͗���Ă������B
 �@�`�����X��1987�N�ɂ���Ă����B�����������ɑ̒���������̂܂ܓ��@�×{���Ă����Ђ�̍ċN����ɐ��쁕�D���R���r���N�p���ꂽ�̂ł���B�f�B���N�^�[�̒ŁA����͕��������J���ɔ�ԁB�����Ȃ��Ȃ�������ł��Ȃ��B�����ԑ؍݂̌�A����͖�̊C�ɏo�Ă݂��B�r���Ƃ��ĊU�ĂȂ��C���Ƃ炷����ɖڂ����܂����B����͂��̎p�ɂЂ���d�˂�`���Ɉ����݂�����Ȃ���̂Ƃ������O�ɓ���������Ǎ��̎p�B���ꂾ�I ��i�������ׂ��Ƃ͌��t�̒��o�ł���E�E�E�E�E�����ē͂��ʎv���̎��`�F�鏗�̐����Ȃ��`�t�͓�d�Ɋ������� �O�d�Ɋ����Ă��]��H�`�����ʐS���Ƃ炵�Ă�����A�ȂǂȂǁA����̐l������a���o���ꂽ�t���[�Y���Ђ�̎p�ɓ��e����B��Y�̖��u�݂��ꔯ�v�̎��͎Y�����グ���B����N�Y�Ӑg�̈�삾�����B�����������Đ���͊m�M�����B��ɂ����̂��a������ƁB�����ǂ���ΑD���͕K�������Ȃ������A����͂��̂��Ƃ�N�����悭�m���Ă����̂��B
�@�`�����X��1987�N�ɂ���Ă����B�����������ɑ̒���������̂܂ܓ��@�×{���Ă����Ђ�̍ċN����ɐ��쁕�D���R���r���N�p���ꂽ�̂ł���B�f�B���N�^�[�̒ŁA����͕��������J���ɔ�ԁB�����Ȃ��Ȃ�������ł��Ȃ��B�����ԑ؍݂̌�A����͖�̊C�ɏo�Ă݂��B�r���Ƃ��ĊU�ĂȂ��C���Ƃ炷����ɖڂ����܂����B����͂��̎p�ɂЂ���d�˂�`���Ɉ����݂�����Ȃ���̂Ƃ������O�ɓ���������Ǎ��̎p�B���ꂾ�I ��i�������ׂ��Ƃ͌��t�̒��o�ł���E�E�E�E�E�����ē͂��ʎv���̎��`�F�鏗�̐����Ȃ��`�t�͓�d�Ɋ������� �O�d�Ɋ����Ă��]��H�`�����ʐS���Ƃ炵�Ă�����A�ȂǂȂǁA����̐l������a���o���ꂽ�t���[�Y���Ђ�̎p�ɓ��e����B��Y�̖��u�݂��ꔯ�v�̎��͎Y�����グ���B����N�Y�Ӑg�̈�삾�����B�����������Đ���͊m�M�����B��ɂ����̂��a������ƁB�����ǂ���ΑD���͕K�������Ȃ������A����͂��̂��Ƃ�N�����悭�m���Ă����̂��B �@����������D���́A�a�ݏオ��̂Ђ���u�C�������ۂ��v�Ŗ����Ă����B�Ђ�̕Ԏ��́u�e�͂��Ȃ��Łv�������B�D���́A�ō����ɂЂ�23�́u���D�g�~��v��蔼������D�������Ă����B����͑����������C�Z���ɐݒ肵���Ƃ������ƁB���̒��͕ω��L�����S���Ȃ��A�̂���u�����ŕi�ʂ���Q���v�̒��Ƃ����Ă���i�}�b�e�]�����u�V�nj��y�@�v���j�B�Ђ�̔ӔN�̘Ȃ܂��Ƀs�b�^���ł͂Ȃ����B
�@����������D���́A�a�ݏオ��̂Ђ���u�C�������ۂ��v�Ŗ����Ă����B�Ђ�̕Ԏ��́u�e�͂��Ȃ��Łv�������B�D���́A�ō����ɂЂ�23�́u���D�g�~��v��蔼������D�������Ă����B����͑����������C�Z���ɐݒ肵���Ƃ������ƁB���̒��͕ω��L�����S���Ȃ��A�̂���u�����ŕi�ʂ���Q���v�̒��Ƃ����Ă���i�}�b�e�]�����u�V�nj��y�@�v���j�B�Ђ�̔ӔN�̘Ȃ܂��Ƀs�b�^���ł͂Ȃ����B�@�D���������Ă������Ƃ͂�����������B4�s�ځu�����ē͂��ʁv�́u���ʁv�������A�Z�O�x�����S�ܓx���A�����AD-F�ɂ��邩D-A�ɂ��邩�H ���������A�D���͊��S�ܓx��D-A��I��ŕ��ʂɂ����B�Ƃ��낪�A�Ђ�͖{�ԂŒZ�O�xD-F�ʼn̂����̂��B�����Ƃ��̕��������B�D���͍Ō�̍Ō�Ɏ����ĂȂ��Ђ�̐������������Ƃ����B
�@���̕�����CD�Ō����Ă݂�ƁA�ʔ������ƂɋC�������B2�R�[���X�ڂ̂��̕����A�̎��ł́u���̐����䂭�v�́u�䂭�v�̕����A�u���v��F�̉������Ђ�ɂ��Ă͒������Â��̂��B�Ђ�̉����̐��m���͐��E�̏펯�ŁA������������A����قǂ̕s���肳�́A����������������Ȃ��Ǝv����قǁB�D���̖������e�𗎂Ƃ����H����Ƃ��Ђ薳�ӎ��̋C�����H
 �@���R�[�f�B���O��10��9���A�R�����r�A�E�X�^�W�I�B��ɂ���Ĉꔭ�����^���B�����ȂЂ�̉̏��������B�������Ė��ȁu�݂��ꔯ�v���a���B12�������[�X�B�Ђ艉�̔ӔN�̌���ƂȂ����B�Ђ肪���E����̂͂���2�N��ł���B
�@���R�[�f�B���O��10��9���A�R�����r�A�E�X�^�W�I�B��ɂ���Ĉꔭ�����^���B�����ȂЂ�̉̏��������B�������Ė��ȁu�݂��ꔯ�v���a���B12�������[�X�B�Ђ艉�̔ӔN�̌���ƂȂ����B�Ђ肪���E����̂͂���2�N��ł���B�@�D���͕s���o�̑�̎����Ђ�̔ӔN�Ɏ���̑��蕨�������B�����ɂ���́A������j�S���㖳��̃R���r�ƂȂ�������N�Y�Ƃ́u��l�ŏ�������Ђ�̖��Ȃ���낤�v�Ƃ����Öق̖��̎����ł��������B���ɂ����o���ʂ��Ђ�̃q�b�g�Ȃ����]���Ă������낤���F����ւ̊|���ւ��̂Ȃ��v���[���g�ɂȂ����B�u�݂��ꔯ�v�����A���X�g�E�`�����X�ɓq�����O�҂ɂ���Ղ̃R���{���[�V�����������̂ł���B
�@�D���̐M���́u�̂͐S�ł��������́v�B�ނ͉̂�S�ō�����B���̉̂ʼn̎�̍쎌�Ƃ̐l����ς����B���̉̂ŕ����҂������܂����B�����Ă��ꂩ����ނ̍�����͉̂i���ɐ��������邾�낤�B���a�̗w�̋��� �D���O�� ���炩�ɁB
���Q�l������
�D���O���u�̂͐S�ł��������́v�i���{�o�ϐV���Ёj
���a�͋P���Ă����`��ȉƑD���O�̐��E�iBS-TX 2015.4.8 OA�j
�@�@�@�@�@�@�@�@ �`�Ǎ��̉̕P �������Ȃ��݂̐��E�iBS-TX 2015.10.7 OA�j
���a�̗w��������`�쎌�Ɛ���N�Y�iNHK-BS 2013.9.6 OA�j
2017.02.15 (��) ��156�؏�܍�u���I�Ɖ����v�͂Ȃ��Ȃ��̌��삾
 �@1��19���ɑ�156��H��܁E���؏܂̔��\���������B���؏�܍�E���c�����u���I�Ɖ����v���s�A�m�R���N�[���̘b�ƕ������̂ʼn�R�������N�����B�����߂��̏��X�ɍs�����i��BAmazon�������25���ɂ͂��͂��Ƃ������̂ő������B��ɂ���������500�y�[�W�]�̑��ŃY�V���Əd���B�������������̂͋��A�Ɠǂݎn�߂邪�A�ǂ������O���O���������܂�Ă䂭�B�����Ƃ��Ă͒��������X�s�[�h�œǂݐ��Ă��܂����B
�@1��19���ɑ�156��H��܁E���؏܂̔��\���������B���؏�܍�E���c�����u���I�Ɖ����v���s�A�m�R���N�[���̘b�ƕ������̂ʼn�R�������N�����B�����߂��̏��X�ɍs�����i��BAmazon�������25���ɂ͂��͂��Ƃ������̂ő������B��ɂ���������500�y�[�W�]�̑��ŃY�V���Əd���B�������������̂͋��A�Ɠǂݎn�߂邪�A�ǂ������O���O���������܂�Ă䂭�B�����Ƃ��Ă͒��������X�s�[�h�œǂݐ��Ă��܂����B�@�u���I�Ɖ����v�͌���ł���B�����̖ʔ��������ׂĔ����Ă���B���Ȃ�̖ʔ������̒�`�Ƃ́A(1)����̍\�����������肵�Ă��邱��(2)�o��l�������͓I�ł��邱��(3)�\���͂��m���Ȃ��ƁA�ł���B�ł́A�����3�̃|�C���g�����������Ă䂱���B
�i�P�j ���łȍ\��
�@�u���I�Ɖ����v�̓s�A�m�R���N�[����ɂ���2�T�Ԃ̕���B���҂̃C���^�r���[�ɂ��ƁA�{��͍\�z12�N�A���������́A�l�����ۃs�A�m�R���N�[���ŁA�I�[�f�B�V�����ŏ����オ���Ă�������ҁi�R���e�X�^���g�j���ō��ʂ��l��A���̐���������Ă��̃V���p���E�R���N�[���𐧂����Z���Z�[�V���i���Ȉꌏ�������Ƃ��B�V���p�����ۃs�A�m�R���N�[����5�N�Ɉ�x�J�Â���鐢�E�ō���̃s�A�m�R���N�[���B���D���҂ɂ́A�|���[�j�A�A���Q���b�`�A�c�B�����}���Ȃ��B�X���閼�肪����A�˂�B
�@���āA���̈ꌏ�̎�̓|�[�����h�o�g�̃s�A�j�X�g�A���t�@�E�E�u���n�b�`�i1985�|�j�B2003�N�̕l�����ۂ�1�ʂȂ���2�ʂƂȂ�A2005�N��15��V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���ŗD������������Ă��܂����̂ł���B
�@�����̕���ƂȂ�F���]���ۃs�A�m�R���N�[���͕l�����ۃs�A�m�R���N�[�������f���ŁAS���ۃs�A�m�R���N�[���̓V���p�����ۃs�A�m�R���N�[���̂��ƁB�u���n�b�`�͈ꕔ�o��l���ɓ��e����Ă���B
�@�F���]���ۃs�A�m�R���N�[���́A��1���\�I��90���A��2����24���A��3����12���A�{�I��6���ő�����B���̊�2�T�ԁB�\�I���Ƃɒʉߎ҂̔��\������A���̓s�x�l�����i���Ă䂭�B�����čŌ�Ɉ�l�̗D���҂����܂�̂�����A�ǎ҂͂��₨���Ȃ��ɂ��̌��I�W�J�Ɉ������܂�Ă䂭�B�ʂ����ėD���͒N�I�H �����A������R���N�[���ɐݒ肵�����_�Ŋ��Ɍ��łȍ\���͂����B�����ȏc�����`������Ă���̂ł���B
�i�Q�j���͓I��4�l�̓o��l��
���Ԑo 16��
����Ƀs�A�m�������Ȃ��{�I�Ƃ̑��q�B
�����O�ɑ��E������q�����Ȃ����ƂŗL���Ȑ��E�I�s�A�j�X�g�A���E�W�E�t�H���E�z�t�}������́g�M�t�g�h�Ƃ����ݒ�B
���y���F���R���`�j�V�r�B���R�z���Ȍ���ƕ]�����
�@�@�@�u���y�̐_�l�Ɉ�����Ă���v�i�h�`����̑䎌�j
�h�`���� 20��
�V�ˏ����Ƃ��ăf�r���[���Ȃ����13�œˑR���y�E����p���������B
�����͍ň��̕�̎��B�u�������V�ˏ����v�͂��̃R���N�[���ɍċN��������B
���y���F�i�`�������Ńi�C�[�u
�@�@�@�u�L�т₩�ŖL���A�ł��A�����Ƃ���悤�ȓ��@�͂�����v�i���t�̖��E�l��t�̑䎌�j
�������� 28��
����o�g�A�Ȏq�����̃T�����[�}���B
�t�c�[�̂��������ۃs�A�m�R���N�[���ɏo��B
���y���F�����^�C�v
�@�@�@�u���y�͓V�˂����̂��̂���Ȃ��B���ʂ̐����҂̉��y�������Ă��������낤�v�i�{�l�̕فj
�}�T���E�J�����X�E�����B�E�A�i�g�[�� 19��
����W�����A�[�h���y�@�̌����w���B
��̓y���[�̓��n�O���A���̓t�����X�̕����w�ҁB
���y���F�쐫�I�Ȃ̂ɗD���A�s��I�Ȃ̂Ƀi�`�������B�������ꂽ��ށB
�@�@�@�u�}�T���̓X�^�[�B������B�I�[��������B�����Đ��܂ꂽ�f���炵�����y��������B���������x�Ŋ��e��
�@�@�@���_�͂�����v�i�t�i�T�j�G���E�V�����@�[�o�[�O�̑䎌�j
�@��҂̐ݒ�Ƃ��Č����Ȃ̂́A4�l�̃R���e�X�^���g�i����ҁj�̉��y���̗L��悤�ł���B�l�Ҏl�l�B�N�₩�ȐF����������B���E�̖��s�A�j�X�g�͂����ȂׂĂ���4�l�̃^�C�v�ɏW���A�Ƃ����v�킹����ɍI���ȃT���v�����O���B��҂̎芵�ꂽ��ʂ��`����B
�@4�l�͊e�X�^����w�����Đ����Ă����B�����āA�����͉ߋ��̂��鎞���A�݂��Ɍq����������Ă���B�Ⴆ�A�������͓V�ˏ����h�`����̃t�@���������B����ƃ}�T���͗c������������A�}�T���̕��̃t�����X�s���ŗc���̍��ʂꂽ�܂܂ɂȂ��Ă����B�}�T���̎t�E�V�����@�[�o�[�O�͐o�̎t���E�W�E�t�H���E�z�t�}���̒�q�������B����ȏ��A2�T�Ԃ̃R���e�X�g�̊ԁA�}�T���ɂ͈���ɑ���W�����S���萶���A����͐o�̖z�����ɐS�䂩���B�ȂǂȂǁA�R���e�X�^���g�Ƃ��Ẵ��C�o���S�Ɛl�ԂƂ��Ă̏����������B�▭�ȉ���������ɍʂ�Y����B
�i�R�j��z�����\����
�@�c���Ɖ������������藍��ł����͗͂����n�ł͖��͔����ł���B����Ƀ��A���e�B��^�����𐁂����ނ͕̂\���͂ł���B
�@���y��`���邱�Ƃ͓���B�Ȃ��Ȃ�A���y�ɂ͌`���Ȃ��A�F���Ȃ��A���ԂƋ��ɏ����ċ����Ă��܂����̂�����B��������m����ɂ́A���t�҂̃e�N�j�b�N�̍I�فA����ړ��̓x�����A�y�ȉ��߂̓K���x�ȂǁA�݂͂ǂ���̂Ȃ��l�X�ȗv�f�����Ȃ̕������ő���F�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�������ɕ��͉��B�����ł́A�L�x�Ȍ`�e���A�I�m�Ȕ�g�A�m���̗��t�����K�v�Ƃ����B���m�͂Ɠ`�B�͂̕����ł���B
 �@���c���i1964�|�j�̕\���͔͂�}�ł���B�u���y�͂ŕ\���v�Ƃ�������̋Z�����x�Ɏ������Ă���̂��B���̑�z�����\���͂ŁA���y�̓������A���̌|�p�A�Ⴆ�Ε��w�⊈���ԂƂ̔�r�ɂ����ĉ�͂��A���w�Ƃ̐e�a������F���_�ɂ܂Ŋg����B�X�ɂ́A���t�s�ׂ̖{���ɔ���A�����邱�Ƃ̈Ӗ�������B��u�Ɖi���I �\���̗��͓N�w�̈�ɂ܂Ŕ��Ă���B����͋��炭�A�ޏ����ASF����A�z���[����A��������̃}���`��Ƃł��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ����낤�B
�@���c���i1964�|�j�̕\���͔͂�}�ł���B�u���y�͂ŕ\���v�Ƃ�������̋Z�����x�Ɏ������Ă���̂��B���̑�z�����\���͂ŁA���y�̓������A���̌|�p�A�Ⴆ�Ε��w�⊈���ԂƂ̔�r�ɂ����ĉ�͂��A���w�Ƃ̐e�a������F���_�ɂ܂Ŋg����B�X�ɂ́A���t�s�ׂ̖{���ɔ���A�����邱�Ƃ̈Ӗ�������B��u�Ɖi���I �\���̗��͓N�w�̈�ɂ܂Ŕ��Ă���B����͋��炭�A�ޏ����ASF����A�z���[����A��������̃}���`��Ƃł��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ����낤�B�@�s�A�m���K���I�[�P�X�g���̌o�������邪�A�����ĉ��y�̐��Ƃł͂Ȃ��B���̂��߁A��i�̍\�z��A3�N���ƂɊJ�Â����l�����ۃs�A�m�R���N�[���ɑ��������ʂ������܂������Ƃ����B���X���������y�I�f�{���A�l�X�ȉ��t���W���������邱�ƂŐ��n���A�ނ܂�ȉ��y���m�͂�g�ɒ������Ǝv����B��V�I���y���m�͂Ɛ�V�I���͗͂��Z������z�����\���͂ƂȂ��ċH�L�Ȍ���̂ł���B
����z�����\���͂̎��၄
�܂��Ƀ��[�c�@�c�g�́A������Ɠ˂�����������̃����f�B�B�D�̒����珃�����Q���J������ւ̘@�̉Ԃ̂��Ƃ��A�Ȃ�̂��߂炢���A�^�����Ȃ��B�~�蒍�����R�̂��Ƃ����肢���ς��Ɏ~�߂�̂݁`���Ԑo ��1���\�I�u���[�c�@���g�F�s�A�m�E�\�i�^K332�v�̉��t��]���āB�@���_�����͂ق�̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B�����Ȃ܂ł̌����͕���̐����Ɍ�����B�Y��ĂȂ�Ȃ��̂́A���̍���ɐl�ԂƉ��y�ւ̈����т��ė���Ă��邱�Ƃ��낤�B�u���y���ĂȂ�Ă��炵���I�v�̃t���[�Y�����x����邱�Ƃ��B�ǂ�ł��ċC���������₩�ɂȂ�̂͂��̂��߂��B�ǂݏI����ĐS���D�����Ȃ��̂͂��̂��߂��B�u���I�Ɖ����v�����A���y��������҂ւ̎���̃M�t�g�ł���B
������E�E�E�{���ɁA�S���E�E�E�₽���A�Èłɗh��鉊�B�����ۂ��A�����̓������Y���Ă��������B�߂܂��邵��������邽������̐����B������ł͏����A�����Ă͌���A�����Ə㉺���A���ɑ傫���A���ɂ��ڂ�ŏ������Ȃ�`�h�`���� ��2���\�I�u���X�g�F����Z�I���K�ȁu�S�v
�����͎v����₩�ȓ������B�ς�����Ə��̉��̂悤�ɉ₩�ɁA�d���ȉ����������悤�B�Ȃ�����ɐF��������B����̓y�g���[�V���J�̐F�B���邭�A���_���ȁA�G�X�v���ɖ������A����ꂽ�F�ʂ��B�K������C�M���X�C�݁A�����ă��[���b�p�ւƗ������Ă���݂������`�������� ��2���\�I�u�X�g�����B���X�L�[�F�y�g���[�V���J����̎O�y�́v
�o���g�[�N�̉��́A���H���Ă��Ȃ��ۑ��̂悤�`�}�T���E�J�����X�E�����B�E�A�i�g�[�� ��3���\�I�u�o���g�[�N�F�s�A�m�E�\�i�^�v
�@�Ō�Ɉ�B�^�C�g���́u���I�Ɖ����v�Ƃ͉����Ӗ�����̂��낤���H �g���I�h�ɂ��Ă͍�i�̖`���u�e�[�}�v�̍��Ɂu���E���j�����鉹���v�Ƃ̌`�e������B�g�����h����̂͑�O���\�I����ڂ̃z�[���̊O�B����Ԑo���u���̉��ŖA�������v�Ƃ��ĕ����B
�@��҂̈Ӑ}�͂���Ƃ��āA���Ȃ�̏���ȉ��߂����������������ƁE�E�E�E�E�g���I�h�͌y�₩���Ɩ��킢�[���̏ے��B�s�A�j�V���B�g�����h�͗͋����Ɣ��͂̏ے��B�t�H���e�V���B�������y�̂͂Ă��Ȃ��傫���L�����\���Ă���H �ʊp�x����l�@����A�g���I�h�͒n��̐��A�g�����h�͓V��̐��`���t�s�ׂɂ͗��҂̐����������Ȃ��H
�@�Ƃ���ŁA2��16����FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v�ł́A���́u���I�Ɖ����v�����グ����肾�B���Ԙg��15���Ȃ̂ŁA�~����͋֕��B���̈����Ȃ͐���߂��邱�ƁB�G�b�Z���X�������ɒ��o�ł��邩���|�C���g�ɂȂ�B�g�b�`������܂���悤�ɁE�E�E�E�E�B
2017.01.25 (��) 2017�N���G���u�X�|�[�c�v�ҁ`with Ray�����
 �@Ray�����A����̓X�|�[�c�҂Ƃ������B�܂��͑告�o�A�H���̗��̗D�����炾�ˁB��H���̗� �{��������30�� ��錧���v�s�o�g �c�q�̉Y�����B���ꏊ14��1�s�ŏ��D���B��72�㉡�j���a�������B��֍݈�31�ꏊ�ł̏��i�͎j��Œx�B�l�Җ��u�H���̗��v�ɂ́g�H�Ȃ鐨���ŋ삯�オ��h�Ƃ����Ӗ�����������������A�H�Ȃ�x���ŋ삯�オ�����B���{�l���j��19�N�U��B�u�҂��Ă܂��� ����Ȃ��I�v�Ȃǂ̕������X�|�[�c�����������Ă���B���̃f�C���[�X�|�[�c����_�l�^���O�������A�e���r���u����Ȃ��v�̘A�āB
�@Ray�����A����̓X�|�[�c�҂Ƃ������B�܂��͑告�o�A�H���̗��̗D�����炾�ˁB��H���̗� �{��������30�� ��錧���v�s�o�g �c�q�̉Y�����B���ꏊ14��1�s�ŏ��D���B��72�㉡�j���a�������B��֍݈�31�ꏊ�ł̏��i�͎j��Œx�B�l�Җ��u�H���̗��v�ɂ́g�H�Ȃ鐨���ŋ삯�オ��h�Ƃ����Ӗ�����������������A�H�Ȃ�x���ŋ삯�オ�����B���{�l���j��19�N�U��B�u�҂��Ă܂��� ����Ȃ��I�v�Ȃǂ̕������X�|�[�c�����������Ă���B���̃f�C���[�X�|�[�c����_�l�^���O�������A�e���r���u����Ȃ��v�̘A�āB�@�ł��ARay�����AJiiji�͑傢�ɕ���A�����B�������ă}�X�R�~�̂͂��Ⴌ�U��B���������A��Âɍl���Ăق����B���j�R�c��̓��K�ɁA���j�́u��ւœ�ꏊ�A���D�����A����ɏ����鐬�т��������͎m�v�Ƃ���B�H���̗��̑O�ꏊ��12��3�s��2�����D���B����́A�M�T�Ԉȗ�8�l�̉��j���A�ŊÏ��i�ȂB�O�N�̍ő����͎m����Jiiji����������������C�̓T���T���Ȃ��B�Җ]�̓��{�l���j�a���ɑ��o����n�V���O�̂͋����B����ǁA�}�X�R�~�́u����Ȃ��v�̃��j�]���ɂ͈�a�������o���Ȃ��B�ꌾ�̈���炢�����Ă������Ǝv�����ǂȂ��B�x�e�����]�_�Ƃ̐��R�M�����܂ł��u���j���i���Ȃ��B������O�B���ꏊ���D�����v�Ȃǂƕ�����Ă�B�ꏏ�ɂȂ��Ċ��ł���_���ł��傤�A�]�_�Ƃ�����̂��B���������Â����̎������o�E���Ȃ߂�B���N�̍����A�u�Җ]�̓��{�l�D�� ���j�a�����v�ȂǂƂ��Ă͂₳�ꂽ�Տ��e�ȂA���ꏊ5��10�s�ő�֊ח������B�����グ�邾�������グ�Ă��Ƃ͒m����B�}�X�R�~�͐����̗�ÂȃE�H�b�`���[����ׂ��Ȃ��A���ꂶ�Ⴝ���̃~�[�n�[���B�ǂ����g���j�h�H���̗������^���^������A��̂Ђ�Ԃ��Œ@����ł��傤�A�����̂悤�ɁB�H���������ȁB�撣���Ă������I
�@Jiiji���H���̗�����������ő�̗��R�́A�ނ��u�K�`���R�v�i���C�͑��o�����j���Ƃ������ƁB�䂪���F�Ñ����ɂ��u���o�E�͏����������B���݂̑���͓��풃�ю��B�ŋ߂̓����S���ݏ�����𗘂�����B���̒��ŁA�H���̗��͉��̒m�����B��̃K�`���R�͎m���v�B�����炱��܂Ŋ̐S�ȂƂ���ŕ����Ă����̂����B�����A�H���̗��͈����ׂ��قڗB��̃N���[���ȗ͎m�Ȃ̂��B
�@�H���̗����p�E�Ɉ������ꂽ�͖̂S����e���i�����j���̗�1952�|2011�j���B��H�y�A�H���̗������Q�ɒǂ��l�߂���̐▽�̏�ʁB�u����v�Ƃ����e���̐������������悤�ȋC�������Ƃ����B�ނ̎t���́A���ł��A6�N�O�ɖS���Ȃ�����e���Ȃ̂��B
�@��e���͎��g�����j�ɏ��i�����Ƃ�30���Ă����B���A�a�Ƃ������a������Ă������B��������z���ė��h�Ȑ��т����߂邱�Ƃ��ł����̂́A�l���݊O�ꂽ�w�͂ɂ����̂��BVHS�r�f�I�E���R�[�_�[�𐔂����Œׂ��قnj����M�S�������Ƃ����B������Jiij�͋H���̗��ɐi������B�u�t���ɕ킦�v�ƁB���w���̂Ƃ��̍앶�Ɂu�w�͂œV�˂��z���Ă��v�Ə����Ă������ˁB
�@�H���̗��͂����ɗ��Ċm���ɋ����͂Ȃ����B������D�������B�ł��A�悭�l���Ăق����B���ꏊ�̎����͉ʂ����ĉ��j�ɑ����������̂������̂��I�H
�@�I�Ր��U��Ԃ�B11���ډ�����12���ڐ��ɂ͊i������ɂ���Ƃ̏����B13���ڂ͕s�폟�B14���ڈ�m���͗��������������ŏ����B��H�y�͐_������I�t�]�����B���l�E���Ƃ��������̌^�ɂȂ�����B�����A�����Ɏ����Ă䂭���ɖ�肪����B��т����菇�߂Ă��Ȃ��B�K�R�I�ɑ��o���s����ɂȂ�B������ǂ����邩�H
�@�̐���Ⴍ���đf�����E�ő���̑O�~�c����邱�Ƃ��B��������Α���̑̂��������������₷���B���̎菇���o����Γ��ӂ̌^�Ɏ����Ă䂭�m���������Ή��͂��g�ɂ��͂��B���ꂪ���j�Ƃ��Ă̈��芴�Ɍq����̂��B
�@�H���̗��̍ő�̗��_�͊��ȑ̂��낤�B���y�U�ȗ��x�ꂪ��������������Ƃ����̂͋��ٓI�B���_�͏o�m�Â���������Ȃ����ƂƂ��B�ł����ꂩ��́A���������Ă��肶�Ⴂ���Ȃ��B���j�Ȃ̂�����B���Q�ȉ�3���j�̗͂����~���Ƃ͂����A��ԊC�A�M�̊�Ȃǐ����̂�����肪�͂����Ă��Ă���B�X�s�[�h�����̋Ȏ҂������Ă����B���j�Ƃ��Ďė��ɂ́A����܂ł̂悤�ȍs�������������̗̑͗��݂ł͑ʖځB���l�߂̍U�߂��̐S�ƂȂ�B��̓I�ɂ́u�Ⴂ�̐����E�O�~�c���獶�l�v���m�����邱�Ƃ��B���̂��߂ɂ́A����̎������������ǂ�����Γ��ӂ̌^�Ɏ����Ă䂯�邩�A���̎菇���K�����邵���Ȃ��B�o�m�Â��ϋɓI�ɍs���ׂ��B��e���ɕ���ăr�f�I�����p���悤�B���̃��R�[�_�[�̓f�W�^��������قƂ�lj��Ȃ�(��)�B�撣��H���̗��I�g���j�̖��ɒp���ʁh�悤�ɁB
 �@Ray�����A�������ѐD�\(27)����BJiiji�̎q���̍��A1950�\60�N��A���{�̃e�j�X�E�ł́A���Ό����i1932�|2017�j�Ƌ{��~�i1931�|�j���G�[�X�B�����ő�̑��̓f�r�X�E�J�b�v�B�C���h�ɂ̓N���V���i���A�N�}�[���B�I�[�X�g�����A�ɂ̓��[�Y�E�H�[���A�z�[�h�Ƃ������肪���Đ��E���o�ꂷ�猵�������ゾ�����B
�@Ray�����A�������ѐD�\(27)����BJiiji�̎q���̍��A1950�\60�N��A���{�̃e�j�X�E�ł́A���Ό����i1932�|2017�j�Ƌ{��~�i1931�|�j���G�[�X�B�����ő�̑��̓f�r�X�E�J�b�v�B�C���h�ɂ̓N���V���i���A�N�}�[���B�I�[�X�g�����A�ɂ̓��[�Y�E�H�[���A�z�[�h�Ƃ������肪���Đ��E���o�ꂷ�猵�������ゾ�����B�@�����{��̋�������1955�N�S�ăI�[�v���ł̒j�q�_�u���X�D�����낤�B����4������{�l���m�ł̃_�u���X�D���͎j�㏉�ɂ��ėB��Ƃ���������ł���B
�@Jiiji�����܂������ƑO�A1920�N��ɂ͌F�J���i1890�|1968�j�Ɛ����P���i1891�|1977�j�Ƃ������I�肪���āA�F�J�̓A���g���[�v�ܗւŋ�_�����l���i���ꂪ���{���̌ܗփ��_���j�A�����̓E�B���u���h���Ńx�X�g4�ɐi�o�����B
�@���Ɩڗ������o�����́A1995�N�A�����C���̃E�B���u���h���̃x�X�g8���炢���B������A���̋ѐD�̊���̓e�j�X�E�t�@���ɂƂ��Ă͖��̂悤�ȃI�n�i�V�A�`�����͌l�Ƃ��ď���4����e�Ȃ̂��B
�@���N�̑S���I�[�v���ł��̃`�����X�͂���ė����B�ѐD�̃����L���O�͑�5�ʁB�����L���O1�ʂ̃}���[��2�ʂ̃W���R�r�b�`��4����O�Ɏp�������Ƃ����g�����N����B�ѐD�̃��W���[�����e������܂ňȏ�Ɍ�������ттĂ����B4���̑���́A���E�����N17�ʂȂ���ߋ����W���[���j��ő�17��̗D�����ւ郍�W���[�E�t�F�f���[(35)�B�����N17�ʂ̓P�K�ɂ�钷�����E�������B�p���Ƃ���x�X�g4�ɂ͓�����͎҂��B�ѐD�ɂ͂�����˔j����� ������H�̊��҂�������厖�Ȏ����B
�@�o���͔��Q�������B�T�[�u�A�X�g���[�N�S�ĂŃt�F�f���[�����|�B�Q�[���E�J�E���g4�|0�ƃ��[�h�B���̃Z�b�g�͂��납���̂܂܃X�g���[�g�ŏ����肻���Ȑ����B�Ƃ��낪�A���t�F�f���[�B�t�@�[�X�g�E�T�[�r�X�̊m�����オ��ɂ�A�З͐���Ƃ����鋭��ȃt�H�A�A���m�ȕЎ�ł��̃o�b�N�E�X�g���[�N���Ⴆ�A�T�[�u���{���[��������ɋ}���݂̍U���ɋѐD�͏��X�ɉ�����₪�Ėh�����ɁB�����āA�t���Z�b�g�̖��t�F�f���[�����������B
�@Ray�����A�ǂ��ŗ��ꂪ�ς�������H �f�l��Jiiji�ɂ͂悭����Ȃ����A�s���́H �Ɩ����A�u���́����_�����̃^�t���̌��@�v�Ɠ����邱�Ƃ��ł���B���̖ʂł����A�t�F�f���[��ŋѐD�͓�x�̃h�N�^�[�E�P�A���Ă���B���O�̃u���X�x�����ۂŒɂ߂����\���̓����ꂪ�Ĕ��H ����̃t�F�f���[�ُ͈�Ȃ��B�ŏI�Z�b�g�����E�����v���̈�ɂ��̍����������͂��B
�@���_�ʂł����Έꗬ�ł͂��邪�������ꗬ�Ƃ͂����Ȃ��B�u������v�Ǝv�����������ɕ���S��ۂĂ邩�B2014�N�̑S�ăI�[�v���B�������ŃW���R�r�b�`�ɏ����A�����̓t�F�f���[���o�Ă���Ǝv������A�i���̃`���b�`������ƂȂ����B�����Ă�l�Ԃ͂��������`�����X��K�����m�ɂ�����́B�X���A�`�����X�����Ƃ���ՂѐD�̓X�g���[�g�̊��s�B�����č���̏ł�4���s�ށB���䖲���Ō��������͂������A�u������v�Ǝv�������̐S�̗h��I�H ������ǂ���菜�������ۑ肾�B
�@�������N�A�t�F�f���[�`�W���R�r�b�`�Ƃ�����Ή��҂��N�ՁB���̉��͓��������������Ȃ��Ǝv���Ă����j�q�e�j�X�E�ɕω��������Ă����B�ނ�ƂĐ�ΓI���݂ł͂Ȃ��Ȃ����B�Q�Y�����̎���֓˓��H �ѐD�̃��W���[���e�̊��������Ă����B������������ттĂ����B�Ȃ�Ƃ��������Ăق����B�����ė��j�ɖ��O������łق����B���̂��߂ɂ́u���́����_�̃^�t���v��g�ɒ����邱�Ƃ��B����܂ʐ��i���B�u�������͐��i�ɂ��� �E�тďI��� �����Ȃ��v�i�喳�ʎ��o�j�̐��_�ŁB
 �@Ray�����A������l�A���E4�����_���I�肪�����B�S���t�����R�p��(23)���B���ݐ��E�����N6�ʁB�ăc�A�[�܋������L���O2�ʁBFedEx�����L���O2�ʁB�����́A��N���獡�N�x�ɂ܂�����ăc�A�[�Ɠ��{�c�A�[�ɂ�����5��4���̐�сB���ł��A���M���ׂ���WGC�|HSBC�`�����s�I���Y�i2016�D10�D27�|30�j�̗D�����낤�BWGC�i���E�S���t�I�茠�j�V���[�Y�͏����W���[�̊i�t���B�o��I������W���[�ƕς��Ȃ��B�Ƃɂ������R�̏������Ղ肪�����܂��������B�ʎZ23�A���_�[�A2�ʂ̃��[���[�E�}�L���C(27)��7�ō��̈�������WGC�j��ő��X�g���[�N���̃I�}�P�t���B���E���x�̂��ꂽ�̂��B�}�L���C�́u�q�f�L�͍��T�̃t�B�[���h�ŒN�������܂����S���t��W�J�����B�ނ��`�����s�I���ɂȂ�͓̂��R���v�ƃR�����g�B�}�L���C�͐��E�����N2�ʁA���W���[3���̖���Ȃ̂��B�W���[�_���E�X�s�[�X(23)�����R���u���ꂩ��ԈႢ�Ȃ����x�����W���[���l��I��v�Ə̂����B�X�s�[�X�͐��E�����N5�ʁA���W���[2���̎��̃z�[�v�B
�@Ray�����A������l�A���E4�����_���I�肪�����B�S���t�����R�p��(23)���B���ݐ��E�����N6�ʁB�ăc�A�[�܋������L���O2�ʁBFedEx�����L���O2�ʁB�����́A��N���獡�N�x�ɂ܂�����ăc�A�[�Ɠ��{�c�A�[�ɂ�����5��4���̐�сB���ł��A���M���ׂ���WGC�|HSBC�`�����s�I���Y�i2016�D10�D27�|30�j�̗D�����낤�BWGC�i���E�S���t�I�茠�j�V���[�Y�͏����W���[�̊i�t���B�o��I������W���[�ƕς��Ȃ��B�Ƃɂ������R�̏������Ղ肪�����܂��������B�ʎZ23�A���_�[�A2�ʂ̃��[���[�E�}�L���C(27)��7�ō��̈�������WGC�j��ő��X�g���[�N���̃I�}�P�t���B���E���x�̂��ꂽ�̂��B�}�L���C�́u�q�f�L�͍��T�̃t�B�[���h�ŒN�������܂����S���t��W�J�����B�ނ��`�����s�I���ɂȂ�͓̂��R���v�ƃR�����g�B�}�L���C�͐��E�����N2�ʁA���W���[3���̖���Ȃ̂��B�W���[�_���E�X�s�[�X(23)�����R���u���ꂩ��ԈႢ�Ȃ����x�����W���[���l��I��v�Ə̂����B�X�s�[�X�͐��E�����N5�ʁA���W���[2���̎��̃z�[�v�B�@���Q�̔��B���芴����A�C�A���E�V���b�g�B���ʂȏ��Z�B������������p�b�e�B���O�B���W���[�E�z���_�[�ɂ��Đ��E�����N��ʎ҂��A��l�ɏ��R�p���̑��݂��̂�����Ă���B���̏����A���̒j���ѐD�ȏ�Ƀ��W���[�ɋ߂����Ƃ̏��낤�B�f�l��Jiiji���Ƃ₩���������Ƃ͂Ȃ����A�ꌾ�������킹�Ăق����B�S���t�I��ɍD�s���̔g�͕t�����B�D���̂����͂����B���͒��q�����������B�f�����������������̂͐�C�R�[�`�������Ȃ��B���R�͖�����C�R�[�`�������Ȃ��B��C�R�[�`�������Ȃ����ꗬ�S���t�@�[�́AJiiji�̒m�����F�����B���O�͂��ꂾ���ł���B
�@�ăc�A�[3���͓��{�l�ő��^�C�B�c���̓��W���[�̂݁B���{�l�̃��W���[���e�́ARay�����A���ăS���t�ɐZ����Jiiji�̖��ł�����B ��킭�}�X�^�[�Y���ȁB���g���E�R�[�m�͖썂���A�W�����{���菫�i�A���E�̃G�I�[�L�،��A�V�˒�����K�炪�Ղ�ʼnʂ����Ȃ����������A���R�Ȃ炫���Ƃ���Ă����͂��B���N�̏��R����ڂ������Ȃ��B
2017.01.15 (��) 2017�N���G���u���O��v�ҁ`with Ray�����
 �@Ray�����A�V�N���߂łƂ��B4���ɂ͐i���A�y���M���g���ˁB�܂�Jiiji�ƌ����ŗV�ڂ��ˁB���������A�����g�����v�̊���������ˁB�e���r�ɉf�邽�тɁu�g�����v�I�g�����v�I�v�̘A�āB�ł��˂��ARay�����B�����͍�������Ȃ��B11���ɂ͏��̋L�҉�����������ǁA���̂��Ƃ�͉������I�����ȃ��f�B�A�̎����͂����ŕ������߂��B�����ɑ��Ĕl�|����̂͂܂������邯�ǁA���₷�炳���Ȃ����Ă��Ƃ͐^�ɗR�X�������Ȃ̂��B�����āA�����`�̍��Ȃ�ł��傤�B�����ɂ͒m�錠�������邵�A���f�B�A�͓˂�����œ�����O�B�����哝�̂͐��E�L���̌��l�Ȃ���B�����ӔC����ł��傤�ɁB���̐l�������������Ď�������߂�ȂA�����Ă͂Ȃ�Ȃ��\���B�����݂̍����ے肵�Ă���Ď��ɋC�����Ȃ��̂��Ȃ��B���������̎q�����݂����V�B��Ȃ��Ȃ郏�B
�@Ray�����A�V�N���߂łƂ��B4���ɂ͐i���A�y���M���g���ˁB�܂�Jiiji�ƌ����ŗV�ڂ��ˁB���������A�����g�����v�̊���������ˁB�e���r�ɉf�邽�тɁu�g�����v�I�g�����v�I�v�̘A�āB�ł��˂��ARay�����B�����͍�������Ȃ��B11���ɂ͏��̋L�҉�����������ǁA���̂��Ƃ�͉������I�����ȃ��f�B�A�̎����͂����ŕ������߂��B�����ɑ��Ĕl�|����̂͂܂������邯�ǁA���₷�炳���Ȃ����Ă��Ƃ͐^�ɗR�X�������Ȃ̂��B�����āA�����`�̍��Ȃ�ł��傤�B�����ɂ͒m�錠�������邵�A���f�B�A�͓˂�����œ�����O�B�����哝�̂͐��E�L���̌��l�Ȃ���B�����ӔC����ł��傤�ɁB���̐l�������������Ď�������߂�ȂA�����Ă͂Ȃ�Ȃ��\���B�����݂̍����ے肵�Ă���Ď��ɋC�����Ȃ��̂��Ȃ��B���������̎q�����݂����V�B��Ȃ��Ȃ郏�B�@�����܂��A�N���������̃n�j�[�E�g���b�v�b���o�����獢�邾�낤���ǁAJiiji�͂ނ���o��������������Ȃ����Ǝv���B�����A���������Ȃ�B�R�Ƃ��ďؖ�������������̘b�����B�l�^�����Ă䂷������́A����݂ɏo�������A�����J�̂��߂����B���̂܂܃v�[�`���Ɏ������������Č����Ȃ�ɂȂ���A����ۂǃ}�V����Ȃ����Ȃ��B
�@���v�������w�E����ďo�����������u���q�ɏ���v�H �I�C�I�C�A����Ő��Ԃ��[��������Ė{�C�Ŏv���Ă���̂��ˁB�c�t���ۂ��Ęb�ɂȂ��B
�@��N�H�̗����ŁA���{����́u�E���W�~�[���v�ƌĂт����Ă����Ƃ���Ă����ǁA�v�[�`���Ɠn�荇���ɂ͂��l�悵�ۏo�����ᖳ���B�ނ̓X�^�[�����ȗ��̗⌌���ȂB�e���̂��߂ɂ͂Ȃ��Ă��B�ߋ�������Δ���ł���B����ȑ���ɁA�Ȃ�Ōo�ϋ��͂�P�Ƃō��ӂ����Ⴄ�̂��B3000���̋��o�����āH ��炸�ڂ�������Ɍ��܂��Ă�ł��傤�B�u�̓y���Ȃ����Čo�ϋ��͂Ȃ��v���炢�̎��A�����Ȃ��̂��˂��B����͌o�ςō����Ă����A�҂Ă����B�K�������Ă���B�����ŏ��߂āA�u���͂��܂��傤�B���̑��A���̘b�����܂��傤���v�B����ŃC�j�V���e�B�u������B�L���ɕ������^�Ԃ��Ƃ��ł���B������A�ă��ڋ߂ŕK�v�i�V�ɂȂ邩������Ȃ�����ǁA�Ȃ�Ύd�|���Ȃ��̂������B�҂ĂΊC�H�̓��a���肾�B���{����́u�����̎�ŗ̓y������������v�Ƃ������Ⴂ�܂����A�厖�Ȃ̂́g���Ȃ��̎�Łh�������邱�Ƃł͂Ȃ��g�����`�Łh�������邱�ƁB���j�ɖ��O���c�������͉̂��邯�ǁA���ꂪ���v�ɔ�������{���]�|�ł��傤�ɁB�����́u�҂v�����Ȃ������̂ɊԈႦ���B���ɏ����͂���������B�������Ԃ������Ȃ��厸�ԁI�I ���܂�̊Â����U��Ƀv�[�`�������q�������Ă��Ȃ����Ȃ��B���ꂶ�፡��܂��܂��r�߂�ꂿ�Ⴄ��B�s�v�c�Ȃ̂͂����@���Ȃ��}�X�R�~�B�I�C�I�C�A�N�������ŋC���ꂿ������̂����I�H
�@���{������������������������̔������i���_�R�����[���B�n���ђˎs�̎s�����������ɓq���}�[�W����������Ăďo���Ȃ��Ȃ������l���ł����̎������B�u20�ɂȂ����牽���Ⴄ���H �w���\�s�A�E�l�A�����A��B����܂ł̓p�N���Ă����NA�ōς��A20����͕K�����O���o��B�O�Ȏ҂Ƃ������Ƃ��ꐶ���ĉ��B���ꂪ�Ⴂ�B���̎��o�������Ċ撣���Ă��������v�I�[�C�I�C�I�C�A���ꂪ�ꍑ�̕������̐V���l�ւ̂͂Ȃނ��̌������ȁH �R�����g����C�ɂ��Ȃ�Ȃ��B����܂��A�g�����v�E���x���B���E�����{���r�������I
�@����ɂ��Ă��A�g�����v����A���̂܂܂���A���ӁA�A�����J�����̎��]�̐����������Ă��������B�u����ȓz�A�哝�̂ɂ����Ȃ������v���ĂˁB
 �@Ray�����A�����l�^��������B2019�N1��1�����猳�����ς�邻������B�É��̐��O�ވʂ̂��ӌ�����A���܁A�L���҂̘b�������̐^���Œ��B����Ƃ��ẮA�É��̂��ӌ��d����B�c���T�͂�ς����Ɉ�����̓��ʖ@�őΏ�����A�̂悤���ˁB�܂��܂������ӂ̏����Ή����BJiiji�͂��̉��}�[�u�ɔ����B���s�̖@�̉��ł̑Ώ����\�����炾�B����͊ȒP���āA�ې���u�����ƁB
�@Ray�����A�����l�^��������B2019�N1��1�����猳�����ς�邻������B�É��̐��O�ވʂ̂��ӌ�����A���܁A�L���҂̘b�������̐^���Œ��B����Ƃ��ẮA�É��̂��ӌ��d����B�c���T�͂�ς����Ɉ�����̓��ʖ@�őΏ�����A�̂悤���ˁB�܂��܂������ӂ̏����Ή����BJiiji�͂��̉��}�[�u�ɔ����B���s�̖@�̉��ł̑Ώ����\�����炾�B����͊ȒP���āA�ې���u�����ƁB�@���@��5���ɂ͂�������B�u�c���T�͂̒�߂�Ƃ���ɂ��ې���u���Ƃ��͐ې��͓V�c�̖��ł��̍����Ɋւ���s�ׂ��s���A���̏ꍇ�ɂ͑O���1���̋K������p����v�i�O���1���̋K��Ƃ́u�V�c�͍������s���������Ɋւ��錠�\��L���Ȃ��v�Ƃ����K��̎��j�B
�@�c���T�͑�16���ɂ́A�u�V�c�����N�ɒB���Ȃ��Ƃ��́A�ې���u���B�V�c���A���_�Ⴕ���͐g�̂̏d�����͏d��Ȏ��̂ɂ��A�����Ɋւ���s�ׂ��݂����炷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��́A�c����c�̋c�ɂ��A�ې���u���v�Ƃ���B�܂���17���ɂ́u�ې��͐��N�ɒB�����c�����A�C����B���̏����͍c�ʌp���̏����ɏ�������v�Ƃ���B
�@������Ray�����A����̎��Ԃ́A�ې���u�����ׂĉ��������b�B���c���q��ې��ɂ���B����ł����܂��B�������Ă����āA�K�v�Ȃ�Ό��@�E�@����ς���B���Ԃ͂�����ł�����̂�����B����A�Ȃ��������Ȃ��H ����́A����V�c���u���a�V�c���吳�V�c�̐ې����������̕s���R���i�M�N�V���N���j��m�邩�炵�āA�ݒu�͍D�܂����Ȃ��v�Ƃ̂��l��������A�Ƃ������Ƃ炵���B�ł������ƍ��Ƃł͎��オ�Ⴄ�B����{�鍑���@���ł́A�V�c�́u�_���ɂ��ĐN���ׂ��炸�v�ł���u���̌���ɂ��ē������𑍝�����v���l�_�Ȃ̂��B�����@���ł͍����̌��\��L���Ȃ��ے����B�����ʒu���S���Ⴄ�B�d�݂��S�R�Ⴄ�B���C�ɂȂ��邱�Ƃ͂Ȃ��͂��B���{���L���҂��Ȃ����̂��Ƃ�i�����Ȃ��̂��B�������悤�Ƃ��Ȃ��̂��B�u�ې��ݒu�̏����v������������H �@���ߎ��݂̈��{�����������������Ⴂ�܂����B����ł�����������Ƃ����̂Ȃ�g����ɏ�����h�Ȃǂ̕�������������������̘b�ł��傤�ɁB
 �@Ray�����A���V�c���͂��Ƃ��Ɗ낤�����x�ł͂����B�����`�Ƃ̖��������Ă���B���{�����@�̑�1���ɂ́u�V�c�́A���{���̏ے��ł�����{���������̏ے��ł����āA���̒n�ʂ́A�匠�̑�������{�����̑��ӂɊ�v�Ƃ���B��2���́u�c�ʂ́A���P�̂��̂ł��āA����̋c�������c���T�͂̒�߂�Ƃ���ɂ��A������p������v���B
�@Ray�����A���V�c���͂��Ƃ��Ɗ낤�����x�ł͂����B�����`�Ƃ̖��������Ă���B���{�����@�̑�1���ɂ́u�V�c�́A���{���̏ے��ł�����{���������̏ے��ł����āA���̒n�ʂ́A�匠�̑�������{�����̑��ӂɊ�v�Ƃ���B��2���́u�c�ʂ́A���P�̂��̂ł��āA����̋c�������c���T�͂̒�߂�Ƃ���ɂ��A������p������v���B�@�����A�c�ʂ́u���P�̂��̂ł���Ȃ���A����̋c�������c���T�͂̒�߂ɂ��p������v�킯���ˁB���{�Ƃ������́A2677�N�ԁA�V�c�����ƂƂ����T�O�𐧓x�I�ɂ����_�I�ɂ��p�����Ă����B�����̑命�����V�c���̌p���������T�O�Ƃ��đ����Ă���B�p��������Ă���B������ɂ��̒n�ʂ́A�c���T�͂Ƃ����@���ɑ����Ă���B�ʏ�̖@���Ɠ��l�A����ʼn����ł���B�܂�A�V�c�̒n�ʂ₻�݂̍���́A�����̈ӎv�Ɉς˂��Ă�����Ă��ƁB�����̈ӎv�ɂ��V�c���Ƃ������x���̂��̂�p�~���邱�Ƃ����ĉ\�Ȃ̂��B�c�ʂ𐢏P����Ƃ������j�I�p�����̊T�O�ƍ����匠��W�Ԃ��閯���`�̗��O���������Ă���B���������B���ɐ������Ă���B
�@������ǂ������Ă����́I�H���ꂪ���{�Ȃ낤�B�푈�����ƕ��͂̕s������搂��Ȃ��玩�q���Ƃ����g�R���h�������S�ۏ�̌`�Ԃ�����B���S���̐_�ƕ�������������̂������B���������ۂށB�F������B������e�F���Î�B���ꂪ���{�̂����Ƃ���B���������ȂƂ���B
�@Ray�����A���������B�܂��́A���ꂪ���{���A�ƔF������B���̖����ɒ@�����ށB�������ɁA���Ⴀ�ǂ�����A���l����BJiiji�����ɒm�b�͂Ȃ��B������Ray������̐���Ɋ��҂����B
�@�e�������₽�Ȃ��BIS�{�̂̐��ށH�Œn��I�ɂ͂ނ���g�債�Ă���B��N�Ẵj�[�X�ƔN���x�������ł̃g���b�N�˂����݁B�e�����X�g�͎s���ɕ������̒��Ŏ����䂫�N�����B�e���͂܂��V���ȃX�e�[�W�Ɉڂ����B���E�͂���ɓ������ɂȂ�B�r���̘_���B�E�X�����i�ށB�g�����v�哝�̂̒a�����p����EU���E�����̌���B�t�����X�ł͔�EU�E���ږ��E�ɉE���E�y���́u��������v�̐����������B�h�C�c�ł������P���u�L���X�g�����哯���vCDU�̋��S�͂������A���ږ����f����u�h�C�c�̂��߂̑I�����vAfD���䓪���Ă����B����4���̃t�����X�哝�̑I�Ń��E�y���������Ă��܂�����B����8���\10���h�C�c�̘A�M�c��I���Ő����^�}���啝�Ɍ�ނ��Ă��܂�����B����͂���EU�͕��邵���Ȃ����낤�B�g�����v�哝�̂��a�����鐢�̒����B���肦�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B
�@Ray�����AAI�̐i�����������ˁB�V���ɂ��ƁAAI�́A����MARCH��̊֊֓����Ȃ��֎�����w��˔j�ł�����͂����ɔ����Ă���炵���B�������͌���l�Ԃ���������X�Ƌ߂Â��Ă���悤���B2045�N�ɂ͘J���̂P���͘d����Ƃ��B�Ȃ�Ƃ������̒��I �ł��ˁAAI�̐l�Ԃ��z�����Ȃ��\�͂́u�z���́vimagination�����āBJiiji�͂Ȃ�قǂƎv���B�����āAJiiji���҂ݏo�����u���c���N�v�����̐�����u�~�̗��v�̓����������́AAI�ɂ͉𖾕s�\�ȗ̈悾�Ǝ������Ă����B���ꂩ����u�z���́v����������Ɩ����Ă䂫�����ˁB���ꂪJiiji�̐����铹���B�����Ray�����A�܂����b���悤�B
2016.12.25 (��) �{�u�E�f�B������蒆���݂䂫
 �@����A�����݂䂫�u���`���̉��̃A���J�f�B�A�vat �ԍ�ACT�V�A�^�[�ɍs���Ă����B�N���A�݂䂫����ɉ�̂�2002�N����̍P��s���B���������܂���N�����B��Ў��ォ��̗F�l�ł���A���݂̂䂫�ӏ܂̎t�ł�����B�ޏ��݂̂䂫���̌���1981�N�A�h���}�u�����搶�v�̈��ʂŗ��ꂽ�u����v�������Ƃ����B���ƒ��w1�N���I �����ő����R�[�h���A�������̃A���o�����w���B���̌�A�����݂䂫�̑S�R���e���c�����W�A�S���C�u�A�S�ǂݕ��A�S������̌����Ă����̂ł���B�u�C��v�u����v�u�z�[���ɂāv�u���ρv�u�^�N�V�[�h���C�o�[�v�u����݁E�܂��v�u�������v�u�G���[���v�u�ٍ��v�u���Ȃ����C�����Ă��邤���Ɂv�u��ȁv�u�̕P�v�u�ēy�Y�v�u�N�̂����ł��Ȃ��J���v�u�t�@�C�g�I�vetc�@����10�A���o����ʂ̖��ȌQ�𒆊w���Œ����Ă���B����́u���v�Łu�g�̂̒��𗬂��܁v�Ƃ�������ȉ̂����邪�A�ޏ��̐g�̂̒��ɂ͒����݂䂫��DNA���ԈႢ�Ȃ�����Ă���B
�@����A�����݂䂫�u���`���̉��̃A���J�f�B�A�vat �ԍ�ACT�V�A�^�[�ɍs���Ă����B�N���A�݂䂫����ɉ�̂�2002�N����̍P��s���B���������܂���N�����B��Ў��ォ��̗F�l�ł���A���݂̂䂫�ӏ܂̎t�ł�����B�ޏ��݂̂䂫���̌���1981�N�A�h���}�u�����搶�v�̈��ʂŗ��ꂽ�u����v�������Ƃ����B���ƒ��w1�N���I �����ő����R�[�h���A�������̃A���o�����w���B���̌�A�����݂䂫�̑S�R���e���c�����W�A�S���C�u�A�S�ǂݕ��A�S������̌����Ă����̂ł���B�u�C��v�u����v�u�z�[���ɂāv�u���ρv�u�^�N�V�[�h���C�o�[�v�u����݁E�܂��v�u�������v�u�G���[���v�u�ٍ��v�u���Ȃ����C�����Ă��邤���Ɂv�u��ȁv�u�̕P�v�u�ēy�Y�v�u�N�̂����ł��Ȃ��J���v�u�t�@�C�g�I�vetc�@����10�A���o����ʂ̖��ȌQ�𒆊w���Œ����Ă���B����́u���v�Łu�g�̂̒��𗬂��܁v�Ƃ�������ȉ̂����邪�A�ޏ��̐g�̂̒��ɂ͒����݂䂫��DNA���ԈႢ�Ȃ�����Ă���B�@���āA�u���̉��̃A���J�f�B�A�v�ł���B���ς�炸������͔ۂ߂Ȃ��B�ł��܂��A�����2�N�U��̍ĉ��䂦�A�����͒͂߂��B�v���O�����Ɂu�m�Ã��|�v�i�O�c�˕������j�Ƃ����U�������t���Ă��āA���̂�����������B��Ԃ�N�����̉�������B
�@��v�o��l����3�l�B�肢���E�����l���i�����݂䂫�j�A�o�[�̑㗝�}�}�E�L�F�V���i�������j�A�K�[�h�}���̍�����j�i�Γc���j�B�ꏊ�͕��������܂��Ă���n�����B����l�͂����̏Z�l�A�j�͂������Ǘ�����Ǘ���Ђ̃K�[�h�}���B�Ƃ��낪���̎O�l�A�]�ˎ���͓V���N�Ԃ���̐��܂�ς��B��j�i���r�j�Ɛl���i�l�g�j�͕v�w�B�V���͎����L�����܁B�V��2�N�A�Q�[�ƈꏏ�ɑ�^��������Ă���B������邽�߂ɐl���͐l���ɂȂ�B���Ă䂱���Ƃ��邷���܁B�l�g�͂����U�蕥�����r�ɑ����B�l�g���l���ɂȂ����̂����͂��Č��r�͐�ɐg�𓊂���B
�@�����Č���ɖ߂�B�n�����͍ЊQ���̕����H�ɂȂ�^���������̂��B���ɂ��̓�������B����l�͒E�o��}�邪�o�����ǂ���Ă���B������吅�B�����ɋ�j�������킪����Ă���B�u���͑̂��傫��������Ȃ��B��l�ōs���āv�ƓS�Ăɓ���V���B�Ȃ�Ύ����c��Ɛl���B��j�̗��͓�l������S�ĂɃ��[�v���|���ĒE�o�B���ւƔ�ї��B�o�b�N�ɂ́�India Goose�������B�����I�ȃ��X�g�������B
�@�������]�������������ƁH �l��VS���R�A�lVS���ԁA�։��]���B���̉������ĐS�̎����l�ŃA���J�f�B�A�i�������j�ɂ��Ȃ�B��Ȃ̂͐l���l���v���S���B��ɂ���Ē����͌��Ȃ��B�������Ȃ��B�݂�ȂɔC�����A�ł���B�����玄��͏���ɉ��߂���B
�@�����́A���H�A�u�O�r�v�Ƒ肷��x�X�g�E�A���o�����o�����B�^�C�g���u�O�r�v�ɂ��Ĕޏ��͂����]���B�u�O�r�B�O�r�m�X�Ƃ��A�O�r����Ƃ������ӂ��Ɏg���܂����A�n�������A���E�o�ς��A�����������l����ƁA�l�ނ͂Ȃ��Ȃ��̑O�r����Ƃ������܂����A�Ƃ͂����A�����̖��ɂ��ł肪���ɂ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ƍl����ƁA�l�ނ͂Ȃ��Ȃ��̑O�r�m�X�Ƃ�������ł͂������܂��B�ǂ���ɂ��Ă��߂����Ƃ��ɖ߂�Ȃ����Ƃ����݂͂�Ȃɕ����Ȃ�ł���ˁB�ŁA�]�k�ł����ǁA���͉�������Ă��g���������ł��āA��������悤��������悤�Ǝv���Ȃ���A�����Ԃɍ���Ȃ������p�����c���ł��ˁB���ꂪ����ǂ����Ƃɂ��������ς����Ă����܂��āA��ւƐi�߂ΐi�ނقǂȂ����Z�����Ȃ��Ă����B�܂莄�̐l���́A�]���Ă݂�ΑO�r���Z�A�Ƃ����������ƂɂȂ��Ƃ�킯�ł������܂��v�B�����炵���e���܂����Ă��邪�A���̊j�S��˂��B
�@2011.3.11�����{��k�Ђɂ��āA�����́u���̗�ɘR�ꂸ���̍�i�ɂ����Ă��A�������\���T������A�\����ύX������Ȃ����Ԃ��A�������N�����v�ƍ�������B�l�X�ȃA�[�e�B�X�g���u�����ɂł��邱�Ɓv�ƌ����ĉ̂��������肵�����A�����͉������t�͔����Ȃ������B������A��2012�N�H�̃A���o���u��铔�v�Ɂu�|�̔s�ҕ�����v�Ƃ����y�Ȃ���ꂽ�B���̎��͂������B�u���ݓ|���ꂽ�� ���݂ɂ���ꂽ�� �����͂����~�܂肾�낤�� �]�݂̎��͐�Ă� �~���̎��͐�Ȃ��v�B���̖��\�L�̑�k�Ђ͂�����]�݂�ł��ӂ����B����ȂƂ���]�����ĂȂ�Č����Ȃ��B�ł��~���̎��͐�Ă͂��Ȃ��B�����M���悤�ƁB
�@�i�����g�債�Ă���B�n�����Љ���Ă���B�������ĂȂ����̓���炵�̗������ڂ���L�C��@�������̑�������̕����̂��̂��H �����邽�߂ɓ�ɂȂ邵���Ȃ��l�X�������ߏo�������Ƃ̕����̂��̂��H �݂�ȓ����l�Ԃ���Ȃ����I�H�����݂䂫�͂����̂��i��i�v���ԁj�B
 �@�{�u�E�f�B�������m�[�x�����w�܂��Ƃ����B�u�A�����J�̉��y�̓`���ɐV�������I�ȕ\����n�������v�����ܗ��R�ł���B
�@�{�u�E�f�B�������m�[�x�����w�܂��Ƃ����B�u�A�����J�̉��y�̓`���ɐV�������I�ȕ\����n�������v�����ܗ��R�ł���B�@�O�i�u�A�����J���y�̓`���v�Ƃ͔ނ̋ȍ��̂��Ƃ��낤�B�J���g���[�A�t�H�[�N�A�u���[�X�A���b�N�A�S�X�y���ȂǁA�A�����J�̓`�����y���������ĉ���������̂��f�B�����̏킾�B��i�u�V�������I�ȕ\���v�͕����ʂ�ނ̎��̐��E�B���w�܂�����A�J�f�~�[�͂����ɏ܂�^�������ƂɂȂ�B�����Ŏ��͍l����B�{�u�E�f�B�����̉��y���ĉ����낤�B�������͂Ȃ̂����āB
�@NHK-BS�ŁuMaster of Change�`�{�u�E�f�B�����͕ς��v�Ƃ����ԑg���������B�f�B�����̑�\������C�u�f���ŒԂ�Ƃ������́B���̑S17�Ȃ𒆐S�ɁA�ނ̉��y�������Ă݂��B
�@���_�͂����ɏo���B�f�B�����̉��y�́u�����E�p�^�[���̌|�p�v���Ƃ������ƁB�l���̗l�X�Ȋ�ɐ����Ă��邯��ǁB
�@1�T��2�̃����f�B�[�Łu����v�����A�u���ߑ䎌�v�Œ��߂�B�����āA��������J��Ԃ��B�u���ߑ䎌�v���Ȃ��ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B�ɂ߂ăV���v���B�u���ɐ�����āv1963�A�u���悭�悷��Ȃ�v1963�A�u�}�C�E�o�b�N�E�y�[�W�Y�v1964�A�u����͕ς��v1964�A�u���R�̏��v1964�A�u���C�N�E�A�E���[�����O�X�g�[���v1965�A�u�J�̓��̏��v1966�A�u�A�C�E�V�����E�r�[�E�����[�X�g�v1967�A�u�V���̔��v1973�A�u�u���[�ɂ��炪���āv1975�A�u�n���P�[���v1976�A�u���j�[�E�u���[�X�v1981�A�u���C�Z���X�E�g�D�E�L���v1983�ȂǁA�قړ����\���̃����E�p�^�[���B������̎蕨�������āA�Ⴆ�u���ɐ�����āv�̓X�s���`���A���E�\���O�� No more auction block �����~���ɂȂ��Ă���̂͗L���Șb�B�ł��܂��A����͐ӂ߂�ɂ�����Ȃ��B�悭���邱�Ƃ�����B
�@�ȓI���ʂ���l�@����A�O�������Ȃ��R�[�_���Ȃ��B�����قڃi�V�B�]�����Ȃ��B���Y���͂قƂ�ǂ�4���q�n�B���`�̓V���v���B�C���E�e���|�B�����͂Ԃ�B�A���͋H�B
�@���I���ʂ��璭�߂�ƁA�u����v�����̕\���͑������Əے����̃~�b�N�X�B���Ȃ����B�u���ߑ䎌�v�͔�g�I��ۓI�B��r�I����e�ՁB�u����v�ł́A���t�����o�I�ɕ��荞��ʼn��Ɋ����u���ߑ䎌�v�ň��g�̒��n��}��B����ɂ͎��R�Ȋ����B�ے�����o�[�g�E�W�����\�����瓾���X�L�����B�B�S���B���A�E�F�b�g���h���C�A������蔽���̌|���B�C���E�e���|�̎����B�����̓����B���������̃g���b�v���o�B���b�Z�[�W���͂�����̂́A�ǂ��炩�Ƃ����A���ł����̂Ŋ�����|�p�ł���B
�@�����l����ō�����u���C�N�E�A�E���[�����O�E�X�g�[���v Like A Rolling Stone ���ɂƂ�B

��A���@A��B�́u����v��C�́u���ߑ䎌�v�B�����͈�ؕω��Ȃ��B���́A�u����v�ł͕ω������A�u���ߑ䎌�v�̊j How does it feel �� Like a complete unknown Like a rolling stone �͌Œ肵����1�s�����������ς��āA4��J��Ԃ��B
Once upon a time you dressed so fine
You threw the bums a dime in your prime, didn't you?
People'd call, say, "Beware doll, you're bound to fall"
You thought they were all kiddin' you
��B��
You used to laugh about
Everybody that was hangin' out
Now you don't talk so loud
Now you don't seem so proud
About having to be scrounging for your next meal.
��C��
How does it feel
How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?
�@�����݂䂫�͂ǂ����낤�B�u�ȁv�̓����f�B�A�X�B���������ʓI�Ɏg���B�]���̖����N�₩�B�O����������B���y���S�n�悭�����B�u���v�́A�l�̐S���A���R���A�l�ԎЉ���A�I�m�ɕ`�ʂ���B�����ɂ́A������m�b������B�����N�w�B�{�u�E�f�B�����Ƃ͐����̋ȍ��B�����u�����ǂ����Ԃ��ׂ��v�̒��Ɂg�炢���낤��Ƃ���h�Ȃ镶���������ł���BN�����ɂ��A�݂䂫����̓f�B�������D���Ȃ̂��������B
�@�����l����ō�����u����v���ɂƂ�B

��A���@A�͑O�����B����f�B�����ɂ͂Ȃ��B�Ȃꂻ�����Ȃ����ǂ́u���v�͑�����#�B���̎�@���f�B�����ɂ͂Ȃ��B�����f�B�[�E���C���͂�ǂ݂Ȃ����y�I�ɗ����B���̗v�f���f�B�����ɂ͂Ȃ��B���I���ʂ��猩��ƁAA�ō��̐S����̂��AB�Ŗ����̍D�]���������AC�Ő��̐ۗ�������B�����_���I�ɗ����B���̌`���f�B�����ɂ͂Ȃ��B
���͂���Ȃɔ߂����� �܂�����ʂĂ�
������x�ƏΊ�ɂ� �Ȃꂻ�����Ȃ�����
��B��
����Ȏ�����������˂� �����b������������
����Ȏ�����������˂� �����Ə��Ęb�����
�����獡���͂��悭�悵�Ȃ��� �����̕��ɐ�����܂��傤
��C��
�܂��܂��� ����͂܂�� ��є߂��J��Ԃ�
�����͕ʂꂽ���l������ ���܂�ς���Ă߂��肠����
���𑱂���l�X�� �����̋��ɏo�����
���Ƃ�����͓|��Ă� �����ƐM���ăh�A���o��
���Ƃ������͉ʂĂ����Ȃ� �₽���J���~���Ă��Ă�
�߂���߂����@����͂߂��� �ʂ�Əo����J��Ԃ�
�����͓|�ꂽ���l������ ���܂�ς���ĕ����o����
�܂��܂���@����͂܂�� �ʂ�Əo����J��Ԃ�
�����͓|�ꂽ���l������ ���܂�ς���ĕ����o����
�����͓|�ꂽ���l������ ���܂�ς���ĕ����o����
�@�O�����̖��������u����v1975�A�Ƃɂ����A�����l�͂����Ɖ̂��u�^�N�V�[�h���C�o�[�v1979�Ɓu�������v1980�A��҂��܂��u�t�@�C�g�I�v1983�A�^�̘A�ъ��Ƃ́H�����u��ǂ̏M�v1989�A���ɂ̕�����`���u�i�v���ԁv1991�A�l���ɖ��ʂȌ����Ȃ�ĂȂ��u�a���v1992�A�Ԃ����̕s�v�c�ȗ́u���v1992�A����Ȃ鎜���u��ƌN�̊ԂɁv1994�A�˂�����̔��w�u�i���̉R�����Ă���v1995�A�����Ȃ��҂ւ̃G�[���u�n��̐��v2000�A�h���ւ̗D�����፷���u�w�b�h���C�g�E�e�[�����C�g�v2000�A�������I�X�P�[�����u��̗��̔w�ɏ���āv2003�A�˂��i�ގ҂ւ̓I�m�ȏ����u���D�v2006�A�l�Ԃ̍s���߂����|�߂�u�V���v2009�B
�@���푽�l���ʁB�����A����ɂ͋��P��x����N�w�����ށB�g�^�ʖڂɐ�����҂ւ̃G�[���h������A�g��҂ւ̗�܂��h������B�l���l���v���g�D�����h�g�������h�����āg�����h������B���͊���̉A�e�����w�ɏd�Ȃ荇���A�̏��\���ɂ����ẮA�Ȓ��ɍ��킹�A�����A�����A���F�܂ł����l�X�ɕ\���ς���B�ό����݂܂��ɖ��؋��B���m�g�[���̃{�u�E�f�B�����Ƃ͑S���َ��̐��E���`�����Ă���B�ǂ��炪�����Ƃ͌����Ȃ��B�S���ʂ̐��E�ςȂ̂�����B�ł��D�������Ȃ猾����B���̓{�u�E�f�B�������D�����������݂䂫�̕���ꡂ��ɍD���ł���B
���Q�l������
�����݂䂫�u��� ���̉��̃A���J�f�B�A�v�����v���O����
�uMaster Of Change�`�{�u�E�f�B�����͕ς��vNHK-BS�v���~�A��
�u�{�u�E�f�B����30���N�L�O�R���T�[�g�vNHK-BS�v���~�A��
�uSONGS�����݂䂫�`21���I�̉̕P�vNHK-TV
2016.12.10 (�y) �ێR�O����Ǔ����t��
�@���̃I�[�P�X�g�������͑�w���Ƃ��ȂďI�������������A�g�߂ɁA���Z�`��w�`�Љ�l�ƁA���Ȃ��I�P�����𑱂���l�Ԃ�����B�����s����35�B�]���̒��j���B�y��̓`�F���B����́A���Ɠ������썂�Z�ɓ��w�A�I�[�P�X�g�������ɂ����胔�@�C�I�������`�F�����Ŗ����ނɁA�w���I�P�̐�y�Ƃ��Ď��������������ʂ��B�u�`�F���ɂ��Ă悩������v�Ə��Ȃ��炸���ӂ���Ă���B���썂�Z�ł́A���@�C�I������e�������̉��l�Əo��A�c����w���O�l���\�T�C�G�e�B�[�ł́A�E�B�[���ɉ��t���s�����s�A�O��Z�F�C��ł͒�����t��R���X�^���g�ɃI�P�����𑱂��Ă���B �@����Ȕނ��s�͂��ĊJ�Âɂ��������R���T�[�g���A11��19���A���旧������قōs��ꂽ�B�肵�āu�ێR�O �Ǔ����t��v�B�ێR����́A���썂�Z�I�P�ős�����2�N��y�B�p�[�g�͓����`�F���B�ʎ��͂Ȃ������̌�y�ł�����킯���B���썂�Z�`������w�`�L�����E�r�[���ƈ�т��ăI�[�P�X�g�������𑱂��Ă����B�Ƃ��낪�s�^�ɂ��a���ɏP���A��N10��17���A���̒Z�����U����Ă��܂��B
�@����Ȕނ��s�͂��ĊJ�Âɂ��������R���T�[�g���A11��19���A���旧������قōs��ꂽ�B�肵�āu�ێR�O �Ǔ����t��v�B�ێR����́A���썂�Z�I�P�ős�����2�N��y�B�p�[�g�͓����`�F���B�ʎ��͂Ȃ������̌�y�ł�����킯���B���썂�Z�`������w�`�L�����E�r�[���ƈ�т��ăI�[�P�X�g�������𑱂��Ă����B�Ƃ��낪�s�^�ɂ��a���ɏP���A��N10��17���A���̒Z�����U����Ă��܂��B�@�����ŁA�s�������ێR����̒Ǔ����t������B���Z�E��w�E��ЂƑS���ɎU���ނ̃I�P���ԂɌĂт����A60�]���̑�I�[�P�X�g���A�}�����}�E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�������B��N�Ԃ̗��K���o�āA�R���T�[�g�J�Ẩ^�тƂȂ����̂ł���B
�@�s����͉^�c�����o�[�Ƃ��ă`�F���t�҂Ƃ��āA���l�̂͂鍁����̓��@�C�I�����ŎQ���B��e�̂߂��݁A��̏r�A���Z�̐�y�Ƃ��Ď����Q���B
�@���ʂ̃R���T�[�g�Ƃ͈Ⴂ�A�X�e�[�W�ɂ͊ێR����̈�e�ƈ���̃`�F�����u����A�s���J��̎����q�ׂ��B�ێR����Ƃ̏o��Ɏn�܂�A���y�������A���K�M�S�ȁA���͂𖾂邭����ނ̑f���炵���l���ɐG��A���O�̎�����Ǔ����t�������������܂ł��A�Â��ɐX�ƌ�����B�g���y�ŊێR�����Ǔ����悤�h����Ȓ��Ԃ̋C�������ق��āA�s����A�����ȃX�s�[�`��������I
�@�ŏ��̋Ȃ́AJ.S.�o�b�n�uG����̃A���A�v�B�����ȋF��̒��ׂł���B�ȏI���Ŗٓ��B���ɏW���S�����ێR����Ǔ��̔O�ň�ɂȂ�B�{���̎w���́A�ێR����̃L�����E�t�B������̃g���[�i�[���q���w���҂̑哇���k���ł���B
�@2�Ȗڂ́A���[�c�@���g�u�A���F�E���F�����E�R���v�X�v�B�u����}���A�l���琶�܂ꂵ�A��C�G�X�E�L���X�g�̂܂��Ƃ̌�̂�v�Ɖ̂��B���[�c�@���g�A���̔N�A�����b�ɂȂ�������n�o�[�f���̃V���g�[���������Ƃ̖��ʂ����ׂ��������ȁB���͍����Ȃ������̓��̓I�[�P�X�g���łł̉��t���B�ҋȎ҂͒��썂�Z�I�P�ږ�̐搶�Ƃ̂��ƁB�ێR������悭���t�����������B�u���썂�Z�ŃA���F�E���F�����E�R���v�X�v�͏��߂Ē��������A�����ɂ��ď��p�ȋ����B�Ȃ����A��Z�E���썂�Z�̃O���E���h���]���ɕ����B
�@3�Ȗڂ̓h���H���U�[�N�́u�`�F�����t�� ���Z���v�B�\���X�g�͐_�ސ�t�B���n�[���j�[�̎�ȃ`�F���t�ҁE�R�{�T�N���B�ێR����̐搶�ł���B�R�{���̌����T�C�g�ɂ́A�ێR����ւ̈���ӂ�镶�͂��Ԃ��Ă���B��q�Ƃ������F�B�̊W�ɋ߂��B�Y�P�Y�P�����ɂ��̂������ێR�������Ă��܂�Ȃ��B����ȐS��Ɣނ����������O�����Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���B�h���H���U�[�N�̃`�F�����t�Ȃ́A10�N�O�A�ێR����̒���I�P����A�R�{�����\���ŋq�������y�Ȃ��Ƃ��B�ނ�������A�u�搶��10�N�O���炻��Ȃɐ������ĂȂ��݂����ł����ǁA���v�ł����H�v�ƕ]���邾�낤�Ƃ��B
�@���t�͂܂��ɓ����B��2�y�͂͋F�肻�̂��́B��ɒ��ԕ��A�̋ȁu��l�ɂ��āv�]�p�̐�����t�ł�X�����͊����̋ɂ݂������B�u�����g��l�ɂ��āh���B�R�m�����E�I�v�A����ȎR�{���̋��ѐ����������Ă���悤�������B
�@�v���O�����̃��X�g�̓u���[���X�́u������ ��1�ԁv�B�ێR�����Ԃ̂��C�ɓ���Ȃ��Ƃ����B2�x�̎�p�̍ۂɂ��̋Ȃ̑�4�y�͂��ėՂ������B�u���[���X��21�N�̍Ό������������̖���ɂ́A��Y�A�v���A��M�A���ہA�F��A����A�����Ȃǐl�Ԃ̎v�����F�Z���l�܂��Ă���B���̓��̓I�P�S�����ێR����̂��Ƃ�z���S����ɂ���搂��グ���B
�@�A���R�[���̓G���K�[�u�G�j�O�}�ϑt�ȁv�����9�ϑt�u�j�����b�h�v�B�w���̑哇�����A���O�̊ێR����ƁA�������������u���z�̃R���T�[�g�v�k�`�ɉԂ��炢���Ƃ��̂��ƁB�A���R�[���͉��ɂ��悤�H�ɓ�l����v�����̂��u�j�����b�h�v�������Ƃ����B
�@�G���K�[�̗F�l�A�E�O�X�g�E�C�G�[�K�[�̃C�G�[�K�[�͎�l�Ƃ����Ӗ��B�����ɓo�ꂷ��m�A�̑��j�����b�h�͎��̖���B����Ȍq����Ŗ����������̕ϑt���́A���M�ɂ��ď���ӂ�閼�ȁB�G���K�[�̗F�l�ւ̌h�����Â��B�}�炸�����ʂ������ƂɂȂ����哇���̖_�ɂ��I�P��ۂ̔M���́A�G���K�[����āA�ێR������u�j�����b�h�v�ɂȂ��炦���B���Ɋ����I�ȃG���f�B���O�������B
�@�uG����̃A���A�v�ɂ͒������A�u�A���F�E���F�����E�R���v�X�v�ɂ͋��D���A�h���H���U�[�N�u�`�F�����t�ȁv�ɂ��J���A�u���[���X�u������ ��1�ԁv�ɂ͋F�O���A�u�j�����b�h�v�ɂ͖��A���ꂼ��ɏh��A�ێR����ƃI�P���Ԃ����Ē��O�Ƃ̊Ԃ��s���������B���ׂĂ��Ӗ��[���I�Ȃ������B���́A����܂ŁA����قǂ܂łɈӋ`�̂���I�Ȃɏo��������Ƃ��Ȃ��B���t��I����āA��������Ƃ��Ȃ��ێR�����m�̊ԕ��Ɏv�����B���y�̗͂Ȃ̂��A���ɕs�v�c�Ȋ��o�������B�ނ͂������̐��ɂ͖߂��Ă��Ȃ��B�ł��ނ͍K���҂���B����Ȑ����R���T�[�g������Ă��炦������B�����āA���̓��̂��Ƃ́A�W�܂����݂�Ȃ̐S�̒��ɂ��܂ł������Ɛ��������邾�낤����B
�@�s����A�}�����}�E�t�B���̊F����A�哇���k����A�R�{�T�N�搶�B�����l�ł����B�F���܂̉������v���͂����ƓV���̊ێR����ɓ͂������Ƃł��傤�B�����������̒Ǔ����t��ɎQ��ł��Ė{���ɂ悩�����B���肪�Ƃ��������܂����B
2016.12.05 (��) ��������̂��ƂȂǁ`with Ray�����
�@Ray�����v���Ԃ�I �������߂ɂ͕x�������{�Ŏ��O�̂��j���������ˁB�Ԃ����ׂׂ��悭�������Ă���B�����A3���B��You����̖ʓ|���悭���邵�A�݂�ȂƊy�������b���ł��邵�A�_���X�����ɂȂ����BRay�����̐����������̂�Jiiji�̊y���݂��B���ꂩ�����낵���ˁB�����̂��b�́A��������BJiiji�̎v���o�̏ꏊ�Ȃ�B �@11��21���A�o�o�����̂��a�����ɁA��������ɍs���܂����B�J�����[�^�E�U���c�u���Nwith�x�Ă䂸�q�i���@�C�I�����j�A�w���̓n���X�C�F���N�E�V�F�����x���K�[�ŁA���[�c�@���g�̃��@�C�I�������t�Ȃ̑S�ȉ��t��B�`�P�b�g��M������̃v���[���g�B����E�B�[�������̌�������ɂ��U������������F���Ɠ��N�z�̃N���V�b�N�E�t�@���ŁA���偨�O�H�������t�B�i���V�����E�R���T���^���g��Ђ̎В��Ƃ�����m�B�������璇�ǂ����t�����������Ă��������Ă����ȗF�l�̈�l�����A�o�ςɊւ��邲������Jiiji�T�b�p���킩�炸�Ȃ̂��B
�@11��21���A�o�o�����̂��a�����ɁA��������ɍs���܂����B�J�����[�^�E�U���c�u���Nwith�x�Ă䂸�q�i���@�C�I�����j�A�w���̓n���X�C�F���N�E�V�F�����x���K�[�ŁA���[�c�@���g�̃��@�C�I�������t�Ȃ̑S�ȉ��t��B�`�P�b�g��M������̃v���[���g�B����E�B�[�������̌�������ɂ��U������������F���Ɠ��N�z�̃N���V�b�N�E�t�@���ŁA���偨�O�H�������t�B�i���V�����E�R���T���^���g��Ђ̎В��Ƃ�����m�B�������璇�ǂ����t�����������Ă��������Ă����ȗF�l�̈�l�����A�o�ςɊւ��邲������Jiiji�T�b�p���킩�炸�Ȃ̂��B�@���[�c�@���g�̃��@�C�I�������t�Ȃ͑S����5�ȁB���ׂ�1775�N�A���[�c�@���g19�̍�i���B���̔N���[�c�@���g�́A�U���c�u���N�{��I�P�̃R���T�[�g�}�X�^�[�̐E�������i���Ƃ̒����������B�Ȍピ�@�C�I�������t�Ȃ͈�Ȃ������Ă��Ȃ��B
�@�J�����[�^�E�U���c�u���N�͑f���炵�������B�V�����h�[���E���F�[�O�Ƃ̋H�L�Ȗ��Ձu�f�B���F���e�B�����g���Z���i�[�h�W�v10���gCD�ł��̌����ȃA���T���u���͏n�m���Ă������A�������Đ��ŕ����ƁA�����Ȕ����ɏ������t������B�x�Ă���̃��@�C�I�������L�т₩�Ŕ������B���̊ɋ}���݂̕\���́A���[�c�@���g�̓��ƐÁA���ƈÂ̑Δ���o�����X�悭�����o���Ė��������B�x�e���ԁA���R�A���F��H���ɏo��B11����13�A���A�����͂���4���ڂ��Ƃ����B���ς�炸�̃R���T�[�g�̋S�A���݂ł���B�ނ̔���́A�I�P���\���ƁA�x�Ă���ɂ͐h���������B
�@���āA�b��51�N�O�ɑk��B1965�N�̏t�A�ꋴ��w�nj��y�c �t�̉��t��̉�ꂪ���̐�������������BJiiji19�̖{�i�I�I�[�P�X�g���E�f�r���[�B�p�[�g�̓g�����y�b�g�B��N�Ԃ̗��K�̐��ʂ��������������̂ł���B�����Jiiji�̐��ꕑ��ɁA���������i��̃j�b�N�l�[���j�����삩��㋞�����h�̑�Ƃ����؉Ƃ��S���ŗ���Ƃ����ߔM�Ԃ�B�Ƃ��낪�E�E�E�E�E�E�B
�@Jiiji�̉��y�Ƃ̓�ꏉ�߂͂���������߂Ă��ꂽ�s�A�m�B���w�Z4�N���B�搶�̖��͐ē����q�搶�B�������ĉ������ɕς��B������͔�������Ƃ������삶��L���ȃs�A�m�t�҂ɂȂ��Ă���Ƃ��B���āA���͍˔\�J�ԁI�H �Ƃ�Ƃq�Ƀo�C�G���𑲋ƁB�\�i�`�l�ƃc�F���j�[30�Ԃɓ���B���̍����Ⓒ���B�Ƃ��낪�ȍ~������ɓ˓��B�c�F���j�[���I���Ȃ��܂ܖ��O�̑ł���ƂȂ����B���ݔ\�͂ɂ��w�͂���\�͂ɂ������Ă����Ƃ����킯���B
�@���w2�N���̂Ƃ��I�[�P�X�g�������ł����̂ŁA���@�C�I�������n�߂��B�搶�́A����\�b�h�̎O�ː搶�B�Љ���������͉̂ԉ��h���X���[�J�[���w�@�̉ԉ��F�]�@���B���N���炢�łȂ�Ƃ����t�ɉ�����悤�ɂȂ����B���p�[�g���[�́A�V���[�x���g�́u�R���s�i�ȁv�A�P�e���r�[�u�y���V���̎s��v�ȂǁB�u�M�[�M�[�v�ƕω����邽�тɃR���T�[�g�}�X�^�[�����ɂ܂ꂽ�����B�R���}�X�̖��͔��؏Y����B�ނ����͖S���B����ȃI�P�����A���є��ō��������܂��Ēf�O�B�˔\�ɂ��^�ɂ��������ꂽ���t���������B
�@���Z����͉��y�����≓��������ɏW���B�u��w�ɍs������I�P�����v�����`�x�[�V�����ɁB
 ����āA�I�[�P�X�g�������肪�u�]��w�̏����ɂ��Ȃ����B���w���đ��I�P�������ʂ����B�I���G���e�[�V�����ŁA��y�́u�o���́H�v�ɁA���@�C�I�����͒e���Ȃ��ɓ������̂Łu����܂���v�Ǝ��B�u�Ȃ�A�g�����y�b�g�͂ǂ��B���E�`�ɂ͒N�����Ȃ�����v�Ɛ�y�B���A�u�Ȃ����Łv�B���ɃC�[�W�[�Ȃ��́B�����āA�Љ�ꂽ��������̊w���E����L��Y�搶�ɂ��ďT�ꃌ�b�X�����݂������N�ԁB2�N���̏t�A�����u���ł̓��w�����t�̃v���E�f�r���[���o�āA���̓����}�����̂ł���܂����B
����āA�I�[�P�X�g�������肪�u�]��w�̏����ɂ��Ȃ����B���w���đ��I�P�������ʂ����B�I���G���e�[�V�����ŁA��y�́u�o���́H�v�ɁA���@�C�I�����͒e���Ȃ��ɓ������̂Łu����܂���v�Ǝ��B�u�Ȃ�A�g�����y�b�g�͂ǂ��B���E�`�ɂ͒N�����Ȃ�����v�Ɛ�y�B���A�u�Ȃ����Łv�B���ɃC�[�W�[�Ȃ��́B�����āA�Љ�ꂽ��������̊w���E����L��Y�搶�ɂ��ďT�ꃌ�b�X�����݂������N�ԁB2�N���̏t�A�����u���ł̓��w�����t�̃v���E�f�r���[���o�āA���̓����}�����̂ł���܂����B�@���C�����ڂ��I���A���R�[���ƂȂ����B�A���R�[���Ȃ́A���[�c�@���g���3�̃h�C�c���ȏW����u����V�сvK605-3�B�q��������V�т����ă��b�p�̉��Ƌ��ɋ����Ă䂭�l��`�������Ȋy�ȁB�����A�ӊO��1791�N�A���[�c�@���g�S���Ȃ�N�̍�i�Ȃ̂��B
�@�y����n���ꂽ�͖̂{�Ԃ̑O���������B�S�������ō��t�B���ՂȋȂ䂦�F������Ȃ��̑́B�Ƃ��낪����������ꓬ�B���b�p��͂����g�����y�b�g�́AC�|C��F�|F�̃I�N�^�[�u�̘A���B�������ȏI���͉������郉�b�p�䂦�s�A�j�b�V���̃n�C�g�[���B�g�����y�b�g�ň�ԓ���̂�����A��N�C�s�̖��n�҂ɂ͏��F�������e�N�j�b�N�Ȃ̂��B�����Ǝv�������肩��u���v�B�A�}�`���A�͖{�Ԃɋ����̂�����v�ȂǂƖ��ӔC�ɂ����Ă��āA�������čӂ���̓x���𐘂����B
�@���āA���悢��{�Ԃ̃A���R�[���B�O���̓�̓t�H���e�Ȃ̂ʼn��Ƃ�����B�����ăG���f�B���O�B�������郉�b�p�̉��̓s�A�j�b�V���B�^�^�[�^�^�[�^�^�[�@�y�b�B������̉Q�B���ׂ����Ă�����܂�����O���I�I �Ȃ�Ƃ��ق�ꂢ�f�r���[�ƂȂ����̂ł���܂��B��Ȃ͓x�������ł͏���Ȃ��B Ray�����AJiiji�͂ˁA��������Ƃ������̂��Ƃ��v���o����B
�@���̌�̓I�P�����������ɐ��ڂ��A���Ȃ̐��X�����t���邱�Ƃ��ł����B�x�[�g�[���F���̌����ȁu�p�Y�v�u�^���v�u�c���v�u8�ԁv�B�s�A�m���t�ȑ�4�ԁB���@�C�I�������t�ȁB�V���[�x���g�u�����������ȁv�B�u���[���X�̌����ȑ�1�ԁB�`���C�R�t�X�L�[�̃��@�C�I�������t�ȁB���[�c�@���g�̃s�A�m���t�ȑ�26�ԁu�Պ����v�ȂǂȂǁB
�@�\���X�g�ɂ́A���@�C�I�����̒ҋv�q�A�C��`�Y�B�s�A�j�X�g�Ɉ�������q�ȂǁA�g�ɗ]�鍂���ȑt�҂Ƌ����ł����B����͈�ɂ������Ɖ�炪�w���ҁE�������g�搶�̈Ќ��̎����B�搶�́A�䂪���I�[�P�X�g���̑c�u�V�����y����v�̑n�݃����o�[�B������j�i�����O�q�̕��j�A�֓��G�Y�i���V�����̎t�j��Ƌ��ɉ��t�A�{�V���������w�ɖK�ꂽ���Ƃ�����B����ȁA�䂪���I�[�P�X�g�������̃p�C�I�j�A�̈�l�Ȃ̂�����A�u����Ȋw���I�P�����ǁA���ނ�v�ƌ������̂��B�N���V�b�N���y�Ɖ������Ԃ����Ƃ�4�N�Ԃ́A�܂��Ƀo���F�̑�w�����������B
�@Ray�����A����قNJy���I�[�P�X�g���������������ǁAJiiji�͏A�E�Ƌ��ɗ��ꂿ�������B�I�[�P�X�g�����g�߂ɂȂ��������炩�ȁB�g�����y�b�g�͉����傫����������h�ł͂Ȃ��Ȃ����K���ł��Ȃ��������炩�ȁB���R�[�h��Ђɓ����āA�N���V�b�N���������y����Ȃ��ƔF�������߂����炩�ȁB���R�͒肩����Ȃ�����ǁA�Ƃɂ����I�P�͑��Ƃ��Ă��܂����̂��B�ł��N���V�b�N���y�͂������ɂ���BRay�����Ƃ��A�������y�̘b�����悤�ˁB
2016.11.15 (��) �����̃��[�O�i�[�̌�
 �@�u���̊����A���N�͏H���Ȃ��킢�ȁv�A�Ȃ�Ă��v���Ă������ɗF�lF�����烁�[�����������B�u11��6���A����������ق́w�����L���[���x�s����܂����H�ǂ��Ȃł��v�B�ނ͔N�Ԃ��Ȃ�̐��̃R���T�[�g�E�`�P�b�g��Â܂Ƃ߂ė}���Ă���B���Ɠ��N�����A�ꕔ����Ђ̌�����䂦�A�ً}�̗p�������邱�Ƃ��x�X�B����ȂƂ��͉ɂ��������Ă��鏬���������ڂ�Ղ��邱�ƂɂȂ�B���[���ɋ������������Ē��ׂ�ƁA�Ȃ�ƃE�B�[�������̌���̃��[�O�i�[�u�����L���[���v�ł͂Ȃ����I�H�����ڂ�Ȃ�Ă�������Ȃ��B�����͒��h���̃v���`�i�E�y�[�p�[�B67,000�~�����I�I ���j���A����ɍs���Ȃ��Ȃ�Ƃ͂��̂�����͂炢�Ȃ��A�Ɣނ̋����ɓ���A��Ԏ��ʼn��b�ɗ����邱�Ƃɂ����B�@�����҂ɁA��Ў��ォ�炨���b�ɂȂ��Ă���o�Ńv���f���[�X��Ђ��o�c����F�В������U�������B������ʁA�����y�������t�����������Ă��������Ă���ƊE�̐�y�ł���B�ő��ɂȂ��@��䂦�A�������̌f�����o�b�N�ɋL�O�B�e�����������B
�@�u���̊����A���N�͏H���Ȃ��킢�ȁv�A�Ȃ�Ă��v���Ă������ɗF�lF�����烁�[�����������B�u11��6���A����������ق́w�����L���[���x�s����܂����H�ǂ��Ȃł��v�B�ނ͔N�Ԃ��Ȃ�̐��̃R���T�[�g�E�`�P�b�g��Â܂Ƃ߂ė}���Ă���B���Ɠ��N�����A�ꕔ����Ђ̌�����䂦�A�ً}�̗p�������邱�Ƃ��x�X�B����ȂƂ��͉ɂ��������Ă��鏬���������ڂ�Ղ��邱�ƂɂȂ�B���[���ɋ������������Ē��ׂ�ƁA�Ȃ�ƃE�B�[�������̌���̃��[�O�i�[�u�����L���[���v�ł͂Ȃ����I�H�����ڂ�Ȃ�Ă�������Ȃ��B�����͒��h���̃v���`�i�E�y�[�p�[�B67,000�~�����I�I ���j���A����ɍs���Ȃ��Ȃ�Ƃ͂��̂�����͂炢�Ȃ��A�Ɣނ̋����ɓ���A��Ԏ��ʼn��b�ɗ����邱�Ƃɂ����B�@�����҂ɁA��Ў��ォ�炨���b�ɂȂ��Ă���o�Ńv���f���[�X��Ђ��o�c����F�В������U�������B������ʁA�����y�������t�����������Ă��������Ă���ƊE�̐�y�ł���B�ő��ɂȂ��@��䂦�A�������̌f�����o�b�N�ɋL�O�B�e�����������B�@��1���`���A���Â����˂�悤�Ȑ����������B�����オ��B���ʂĂ��W�[�N�����g�i�N���X�g�t�@�[�E���F���g���X�j�������Ɠo��B�t���f�B���O�i�A�C���E�A���K�[�j�̊قɂ��ǂ蒅���B�����Ƀt���f�B���O�v�l�W�[�N�����f�i�y�g���E�����O�j�������B�u��������A�����v�ƌ����W�[�N�����g�ɁA�u�V�N�Ȑ������������܂��v�ƊO�ɏo�Đ�������Ŗ߂��Ă���B�u���]�݂̂悤�ɂ��Ȃ��̊���������A���������������Ă��܂����v�ƃW�[�N�����f�B���̏�ʂɗ����u�W�[�N�����f�̓��@�v�̂��������ʔ������I �Â��y�₩�A�܂�ʼnH�т̂悤�Ȍ��̋����I���ꂼ�܂������E�B�[���̉��B�̂��Ƃ낯�����ɂȂ�B���X�Ɏ����̏u�Ԃ�����Ă����B
�@��l�́A���͗c�����뗣�ꗣ��ɂȂ����o�q�̌Z���B�u�~�̗��͉߂����舤�Ət�����т��v�Ɖ̂��W�[�N�����g�Ɂu���Ȃ��������t�ł��v�Ɖ�����W�[�N�����f�B������͂܂�ŃC�^���A�E�I�y���̗��킳�B�W�[�N�����g�́A����܂ŒN���������Ȃ����������g�l���R�̊����甲�����u���������̓W�[�N�����g�Ɩ����v�Ɛ錾�B�z�[����t�ɋ����n��u���̓��@�v�B�����͍ő�̌�����A���[�O�i�[�̐^�������B��l�̌����C�ɔR���オ�菗�͎q���h���B���ꂼ���[�O�i�[�E���[���h�̕s�v�c���B�����s���R�������������Ȃ����y�̗́B����͂��Ă����A�s��������Ȃ����_���H�[�^���i�g�}�X�E�R�j�G�`���j�[�j�́A�䂪���ɂ��ď����m�R�c�����L���[���̃��[�_�[�E�u�������q���f�i�j�[�i�E�V���e�����j�ɁA�W�[�N�����f�ɔ���^����悤�����邪�A�𗝉������u�������q���f�͔ޏ������i���̈��������u�������q���f�̖{���ŁA��c�~�́u�u�������q���f�̎��ȋ]���v�Ɍq����j�B���ꑽ�������Ȃ�_�ɔw�����u�������q���f�͊�R�Ŗ���ɂ�����A����ɉ�������B�u���̓��@�v����A�z����҂���������u�W�[�N�t���[�g�̓��@�v���o�āA�u�܂ǂ�݂̓��@�v���Â��ɑt�ł��钆�A�S�O���̖��������B
�@�w���҂̃A�_���E�t�B�b�V���[��1949�N�u�_�y�X�g���܂�B�E�B�[�������̌���A�~���m�E�X�J�����A���g���|���^���̌���ȂǁA���E���̒����ȃI�y���E�n�E�X���w�����Ă���B�o�C���C�g�ł�2001�N�A�}�������V�m�[�|���̑���Ƃ��āu�w�v���w���B�Z���Z�[�V���i���ȃf�r���[���������B
�@���o�̂׃q�g���t��1957�N�^�����V���^�b�g�̐��܂�B�U���c�u���N�E���[�c�@���e�E���Ŋw�сA�����͔o�D�Ƃ��Ċ���B1994�N���牉�o����|���A2014�N�ɂ̓U���c�u���N���y�Ղ̑����|�p�ēɏA�C���Ă���B�{�����́u�����L���[���v�́A�E�B�[�������̌���̏o�����Ƃ���10�N���̒�]���鉉�ڂł���B
 �@�E��ɔ����C���A����ɃK�C�h�u�b�N�B���C���̓v���`�i�E�y�[�p�[�̃I�v�V�����ő�2�Ƒ�3�̖��Ԃɏܖ��B�K�C�h�u�b�N�͓����̂e�В�����u���f�̃I�y���v�i���w�ي��j�̃|�[�^�u��������B���ꂪ���Ɏg�����肪�����B����܂��A���̂悤��5���Ԃ������B
�@�E��ɔ����C���A����ɃK�C�h�u�b�N�B���C���̓v���`�i�E�y�[�p�[�̃I�v�V�����ő�2�Ƒ�3�̖��Ԃɏܖ��B�K�C�h�u�b�N�͓����̂e�В�����u���f�̃I�y���v�i���w�ي��j�̃|�[�^�u��������B���ꂪ���Ɏg�����肪�����B����܂��A���̂悤��5���Ԃ������B�@�I���㑦F��Ƀ��[����łB�u�f���炵���̈��B���ɃI�P�̉��F�͕M��ɐs�����������B�̎���v�X�n�C���x���ł������A�Ƃ�킯�W�[�N�����f���y�g���E�����O�̏�i�œ���������ӂ������Ɋ����B�S�̓I�ɖ��������ꂽ�����������L���[���Ƃ�����ہB�����̃��[�O�i�[�̌��ł����B�Ɋ��Ӑ\���グ�܂��v�B
�@F�В��Ƃ́A�y����t�Ƃ������������̂����A���j���̖�䂦����̂��y���݂Ƃ������ƂŁAJR���w�������ɂĂ��ʂꂵ���B
�@�y���u�����L���[���v�̓��[�O�i�[�L���̑��u�j�[�x�����O�̎w�v��1��̉��ځB����u���C���̉����v��2��u�W�[�N�t���[�g�v��3��u�_�X�̉����v�ƂƂ��ɖc��ȕ�����`������B
�@���q�����g�E���[�O�i�[�i1813�|1883�j���u�w�v�̍\�z���n�߂��̂�1848�N�B�ŏ��ɏ�������{�̃^�C�g���́u�W�[�N�t���[�g�̎��v�ŁA�ȉ��u�Ⴋ�W�[�N�t���[�g�v�A�u�W�[�N�����g�ƃW�[�N�����f�v�A�u���C���̉����̗��D�v�ƁA��{�͕����k��A1852�N�Ɋ����B��Ȃ͐i�s�ʂ�ɏ�����A�r���������f�����������A1874�N�A�S�Ȃ������B�\�z�J�n�������26�N�̔N��������Ă����B
�@���[�O�i�[�́A�u�w�v�̑�ނ����B�̐_�b��`������̗p���Ă��邪�A���̌��T���l�@���Ă������B
�@ �u�j�[�x�����Q���̉́v
12�|3���I�����������Q���}���̉p�Y�������ŁA��l���W�[�N�t���[�g�̐��U��w�`���ȂǁA�u�w�v�̒��j�𐬂����g�݂��̗p����Ă���B�W�[�N�t���[�g�̃p�[�g�i�[�Ƃ��āA���ȋ]���ɂ��l�Ԑ��E��V���Ȓ����ւƐ擱����u�������q���f�̌��^�������ɂ���B
�A �u�G�b�_�v
13���I�ɕҎ[���ꂽ�k���_�b�ŁA�n��\�n��\�V��Ƃ������E�̍\����A�_�X�A���l���A��ւȂǁA�u�j�[�x�����O�̎w�v�̍��g�݂�e������������̂��Ă���B��_�I�[�f�B���͑�_���H�[�^���ɕς�铙�X�B�܂������ɋL����Ă���u���O�i���N�v�Ƃ����_�X�̏I���̌��́A��3��u�_�X�̉����v�Ɠ���T�O�ł���B
�B �u�I���X�e�C�A�v�O����
�M���V���̔ߌ����l�A�C�X�L�����X�iBC525�\456�j�̎O����B���̐�����܂�������̍��q�Ə㉉�`�����u�w�v�̍\���ɉe����^�����ƍl������B���[�O�i�[��4��Ƃ����Ɂu����ɑ���3��̌��v�Ƃ����̂́A�A�C�X�L�����X�ւ̃I�}�[�W�������邩�B
 �@�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�S4��́A1876�N8��13���A��1��o�C���C�g���y�Ղŏ������ꂽ�B���̓��[�O�i�[������i�㉉�̂��߂����ɍ�����o�C���C�g�j�Ռ���B���݂ɋ��͂�ɂ��܂Ȃ������͎̂��̃o�C�G�����������[�h���B�q2���i1845�|1886�j�ł���B�ނ͏��N����Ƀ��[�O�i�[�̉̌��u���[�G���O�����v�ɖ�������A���Ȃ̋���̓������u���[�G���O�����v��F�ɏ���قǓ��ꍞ�B���z��Nj����郏�[�O�i�[�̍\�z�͔�剻�̈�r�����ǂ邪�A�S���҃��[�g���B�q2���Ɏx����~�̎v���͔��o���N����Ȃ������B���̌��ݔ�p�͍��ƍ�����j�]������قǐr�剻�����Ƃ����B����ɂ��ē��{�̂���L�����@�C�I���j�X�g�́A���܂�TV�̃N���V�b�N�u���Ƃ��ɏo�Ă��āA�u���[�O�i�[�͎��̍��������Ԃ炩���Ď����̌������点���v�ƃg���`���J�����Ƃ��ǂ��Ő邤���A�������Ԃ炩�����̂ł͂Ȃ��B�����̕������ꍞ�̂��B������1886�N6��13���̒��A�ŕώ��̂ƂȂ��Ĕ��������B�����͓�A����ꂽ�w���́u�����v�������B�ނ̋���m�C�V�����@���V���^�C����́A�h�C�c���w�̊ό������Ƃ��ĘA���ό��q�œ�����Ă���B
�@�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�S4��́A1876�N8��13���A��1��o�C���C�g���y�Ղŏ������ꂽ�B���̓��[�O�i�[������i�㉉�̂��߂����ɍ�����o�C���C�g�j�Ռ���B���݂ɋ��͂�ɂ��܂Ȃ������͎̂��̃o�C�G�����������[�h���B�q2���i1845�|1886�j�ł���B�ނ͏��N����Ƀ��[�O�i�[�̉̌��u���[�G���O�����v�ɖ�������A���Ȃ̋���̓������u���[�G���O�����v��F�ɏ���قǓ��ꍞ�B���z��Nj����郏�[�O�i�[�̍\�z�͔�剻�̈�r�����ǂ邪�A�S���҃��[�g���B�q2���Ɏx����~�̎v���͔��o���N����Ȃ������B���̌��ݔ�p�͍��ƍ�����j�]������قǐr�剻�����Ƃ����B����ɂ��ē��{�̂���L�����@�C�I���j�X�g�́A���܂�TV�̃N���V�b�N�u���Ƃ��ɏo�Ă��āA�u���[�O�i�[�͎��̍��������Ԃ炩���Ď����̌������点���v�ƃg���`���J�����Ƃ��ǂ��Ő邤���A�������Ԃ炩�����̂ł͂Ȃ��B�����̕������ꍞ�̂��B������1886�N6��13���̒��A�ŕώ��̂ƂȂ��Ĕ��������B�����͓�A����ꂽ�w���́u�����v�������B�ނ̋���m�C�V�����@���V���^�C����́A�h�C�c���w�̊ό������Ƃ��ĘA���ό��q�œ�����Ă���B�@���[�O�i�[���A����̖��̓��B�_�Ƃ��ăo�C���C�g�j�Ռ�������A���ꂪ���O�l���A���̐��n�Ƃ��č�������܂Ŕ��W�������Ă���A�ɂ́A��l�̏����̑��݂�����B
�@�܂��͍ȃR�W�}�i1837�|1930�j�B���ȉƃ��X�g�ƃ}���[�E�_�O�[���ݕv�l�Ƃ̊Ԃɂł����s�ς̖��B�w���҃n���X�E�t�H���E�r���[���[�i1830�|1894�j�v�l�����������[�O�i�[�ɑ���B�����āA���[�O�i�[��59�̎��A�҂��ɑ҂����j���ށB���[�O�i�[�A���에���B瞂鈤��𒍂��Łu�W�[�N�t���[�g�q�́v����Ȃ����B���ꂪ���̖�S�̉[�O�i�[�̊y�Ȃ��H���b��قǂ̗D�����Ɉ��Ă���B
�@��S�ƂƋ������Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�W�[�N�t���[�g�E���[�O�i�[�i1869�|1930�j�́A�ǂ�ȋ��҂��Ǝv������A���ꂪ�Ȃ�ƐS�D�����������҂Ƃ������琢�̒��͕�����Ȃ��B�����ɋ����̂Ȃ��W�[�N�t���[�g�ɁA�Ȃ�Ƃ��ԉł��ƃR�W�}���I�̂��C�M���X�������B�j�t���b�h�i1897�|1980�j�B��l���������������̂�1914�N�̃o�C���C�g���y�Ղ������B�W�[�N�t���[�g44�A���B�j�t���b�h17�B�߂ł��������A���B�[�����g�i1917�|1966�j�ƃE�H���t�K���O(1919�|)�̓�ׂ���B�R�W�}�ƃ��B�j�t���b�h�B��l�̏����̓��[�O�i�[�̌�����������B�u�������q���f�����E�ɒ����������炵���悤�ɁB
�@1930�N4���ɃR�W�}�����B���N8���A���ǂ��悤�ɃW�[�N�t���[�g���S���Ȃ�B��l�̈⎙�͂܂�10��B�����œ��p���������̂����S�l���B�j�t���b�h�������B�����̈�r�����ǂ��Ă����o�C���C�g�̍������Ē��������Ɉ�����B�����Ɏ��s�����̂��q�g���[�Ƃ̃W���C���g�������B��l�̃Q���}���E�t�@�[�X�g�̎v�z�����v�B�q�g���[�̗����Ƀo�C���C�g�̖��^���ĉ������B�ޏ��́u�q�g���[�Ƃ̏o��͉^���������v�Əq�����Ă���B
�@�₪�Đ����������B�[�����g�ƃE�H���t�K���O�́A���o�ƂƂ��ĉ���������������ʒn�ʂ�z���A���o�C���C�g�̉��������z���グ��B���݂̃o�C���C�g�������l�̏����G�t�@�ƃJ�^���[�i�̓E�H���t�K���O�̖����B�J�^���[�i�����o����2015�N�o�C���C�g�́u�g���X�^���ƃC�]���f�v�́A�Z��Ƃ����������r������ȂǁA����I�ȃv���_�N�g�Ƃ��ĕ]�����ĂB
�@�u�g���X�^���ƃC�]���f�v�͎��ɂƂ��ē��ʂȋȂł���B�Ȃ��Ȃ�A���̋Ȃ������ƕ��e�Ƃ̐����Ȃ��ړ_�̈������B
�@���͎���2�ɖ����Ȃ�����ɖS���Ȃ����B�����牽�������Ă��Ȃ��B���e���`���̋��菊�͕�̋L�������Ȃ��B���ƕꂪ���������̂�1944�N3��5���B�������܂ꂽ�̂�1945�N5��20���B�����S���Ȃ����̂�1947�N4��23���B��͎���A��Ē����Ɏ��Ƃɖ߂邱�ƂɂȂ����B�͂�3�N�̌��������ŁB
�@���ꂩ��70�N�B��͌���95�B����100���ȓ��̋����ɏZ�ށB���]���������Č��N�B�����A����A�|���A�����A���ׂĎ����ł��B���[���͎��݁B�ʃ��[�����B�r�f�I�̃^�C�}�[�^���OK�B�y���݂́A�N�C�Y�ԑg�Ŏ��Ƌ������ƁB����̖��ƒ��d�b�����邱�ƁB���Ƒ\���ɂ��ʒ�����邱�ƁB�e���m�l�ɕ��𑗂邱�Ɠ��X�B
�@����ȕ�ɕ��Ƃ̎v���o�͂Ɛq�˂�B�u�قƂ�ǂȂ��̂�v�Ɠ�����B�����ɑh��L���Ƃ����A���͋x���A�����ɕ��������Ĉ�S�Ƀ��R�[�h���Ă������ƁA���炢���ƁB����Ƃ��u�Ȃ�Ƃ����ȁH�v�Ɩ₤�ƁA�ڂ����Ɓu�g���X�^���ƃC�]���f�v�Ȃ�ԓ����������Ƃ��B�E�[���A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�����ł͂Ȃ����B
 �@���̒����Ă����u�g���X�^���ƃC�]���f�v�̃��R�[�h�͉��Ȃ̂��H ���ׂĂ݂��B�v������|����́A���炦�т����u���Ȍ���Ձv�㉺�������B���炦�т��́u�K�`�����߂蕨�T�v�̏����ƁE�쑺�ӓ��i1882�|1963�j�̉��y�W���[�i���X�g�Ƃ��Ẵy���l�[���B�㉺����ʂ��āu�g���X�^���ƃC�]���f�v�Ɋւ���L�q�͈�ӏ��B
�@���̒����Ă����u�g���X�^���ƃC�]���f�v�̃��R�[�h�͉��Ȃ̂��H ���ׂĂ݂��B�v������|����́A���炦�т����u���Ȍ���Ձv�㉺�������B���炦�т��́u�K�`�����߂蕨�T�v�̏����ƁE�쑺�ӓ��i1882�|1963�j�̉��y�W���[�i���X�g�Ƃ��Ẵy���l�[���B�㉺����ʂ��āu�g���X�^���ƃC�]���f�v�Ɋւ���L�q�͈�ӏ��B
������A���[�O�i�[�́u�g���X�^���ƃC�]���f�v�́u�O�t�ȁv�Ɓu���̎��v(60196�|7)�������ׂ����낤�B�t���g���F���O���[�̃��[�O�i�[�Ƃ������̂́A���Ɍ����Ȃ��̂����A�܂�ɉ��t����̂́u�g���X�^���ƃC�]���f�v�����ŁA�{���ł����܂蒮����Ȃ��Ƃ����B�@�������B�t���g���F���O���[�����Ȃ������̂��B���_SP�Ղ̂͂��B���i�i���o�[�炵�����̂��L����Ă��邪���ׂ悤���Ȃ��B�Ȃ�A�u�t���g���F���O���[���S�f�B�X�R�O���t�B�[�v�������Ă݂�B78��]SP�Ղ�2�_�������B
�@�@�@�@�@1930�N�^�� �x�������E�t�B���u��1���ւ̑O�t�Ȃƈ��̎��v�i�ƃO�����t�H���j
�@�@�@�@�@1938�N2��11���^�� �x�������E�t�B���u��1���ւ̑O�t�Ȃƈ��̎��v�i�pHMV�j
�@�������L����t�����F���́u�g���X�^���v�́A1952�N�^�� �t�B���n�[���j�A�nj��y�c�Ƃ́u�S�ȔՁv�����B���̃t���O�X�^�[�g�̃C�]���f�Ƃ̋��������A��O���̖����ŁA�^������60�]�N���o�Ă�����z������̂��Ȃ��B����͂��Ă����A���̒����Ă����u�g���X�^���v�́A�������Ԃ��猩�Ă��A���炭��L2���̂ǂ��炩���낤�B������T�����ĂĒ����Ă݂������̂ł���B
���Q�l������
���炦�т����u���Ȍ���Ձv�㉺���i�������Ɂj
���f�̃I�y�����ʔ�2�u�����L���[���S�ȁv�i���w�فj
�t���g���F���O���[���S�f�B�X�R�O���t�B�[�i�f�B�X�N�E���j�I���ҁj
�_�X�̉����`�o�C���C�g�����i2013�NNHK-BS���f�j
2016.10.25 (��) �{�u�E�f�B�����̃m�[�x����܂�P��
 �@10��13���A�X�E�F�[�f���E�A�J�f�~�[�̓{�u�E�f�B����(1941�|)�Ƀm�[�x�����w�܂����^����Ɣ��\�����B�Ƃ��낪�A15���t�����V������ɂ́u�A�J�f�~�[�͖�ʂ��d�b���|�����������A���͎��Ȃ��B13���̃��X�x�K�X�ł̃R���T�[�g�ł��A�f�B�����̓m�[�x���܂ɂ��Ĉꌾ���G��Ȃ������v�Ȃ���B12��10���̎��^���ɏo�Ȃ���̂����Ȃ��̂��B�R�����g����̂��ǂ��Ȃ̂��B�f�B���������ɓ����́u���̒��v�I�H
�@10��13���A�X�E�F�[�f���E�A�J�f�~�[�̓{�u�E�f�B����(1941�|)�Ƀm�[�x�����w�܂����^����Ɣ��\�����B�Ƃ��낪�A15���t�����V������ɂ́u�A�J�f�~�[�͖�ʂ��d�b���|�����������A���͎��Ȃ��B13���̃��X�x�K�X�ł̃R���T�[�g�ł��A�f�B�����̓m�[�x���܂ɂ��Ĉꌾ���G��Ȃ������v�Ȃ���B12��10���̎��^���ɏo�Ȃ���̂����Ȃ��̂��B�R�����g����̂��ǂ��Ȃ̂��B�f�B���������ɓ����́u���̒��v�I�H�@�f�B�����̌����l�X�[�W�[�E���g���i��2��A���o���u�t���[�z�C�[�����vFreewheelin�f�̃W���P�b�g�Ɉꏏ�Ɏʂ��Ă��鏗���j�́A�u�{�u�́A�������������������ŁA�v�̂��悭�A�K�v�Ȑl��k�����Ă銨���s�������v�Əq�����Ă���B�u���������ŋ삯�������A�@�ɏ悶��̂����܂������v�Ƃ͗F�l�̃~���[�W�V���� �W�����E�R�[�G���̃f�B�����]���B�v����Ɂu���������œ����ǂ��āA���������ׂ������킩���Ă���l�ԁv�Ƃ������Ƃ��낤�B�ނ͍����̉s�q�ȓ��]�ʼn����l���Ă���̂��낤���B
�@����ŁA�{�u�E�f�B�����́u�����ɍ������j�v�Ƃ������Ă���B����Ȕn���ȂƂ��������Ȃ���A�{�l�������q�ׂĂ���f����You Tube�ɂ���̂�����ԈႢ�Ȃ��B�u�����͉����́A�������B�N�ɂ��āH�i�ߒ������B�ǂ��́H�n�ォ�����Ȃ����E���B�Ȃ�̂��߂ɂ����āH ���݂̒n�ʂ邽�߂��B���̂��Ƃ͍�i�̃o�[�Q���Z�[������v�B�C���^�r���A�[�̓��B�W�����g�E�N���X�e�B�A���B���ꂪ�������̂��͓���ł��Ȃ����A���e���炢���ĉf��u�m�[�E�f�B���N�V�����E�z�[���v�i�}�[�e�B���E�X�R�Z�b�V�ē�2005�N�j�̍����낤�Ǝv����B
 �@���̃C���^�r���[�������Ă݂悤�B�܂��A�����̂Ƃ͂��̂��Ƃ��H ���̌��̓A���o���u�lj��̃n�C�E�F�C61�v�ɉB����Ă���B�����Highway61 Revisited�B����u����61�����ĖK�v�ł���B
�@���̃C���^�r���[�������Ă݂悤�B�܂��A�����̂Ƃ͂��̂��Ƃ��H ���̌��̓A���o���u�lj��̃n�C�E�F�C61�v�ɉB����Ă���B�����Highway61 Revisited�B����u����61�����ĖK�v�ł���B�@�܂��ARevisited�ł���B����̓C�[�������E�E�H�[�i1903�|1966�j1945�N�̏����u�u���C�Y�w�b�h�ĖK�vBrideshead Revisited����̈��p�ɈႢ�Ȃ��B�f�B�����͂��̎�̕��w�͊ԈႢ�Ȃ��ǂ�ł���͂�������B�A���o����1�Ȃ́u���C�N�E�A�E���[�����O�E�X�g�[���vLike a rolling stone�ł���B����1�R�[���X�ڂ̃V�`���G�[�V���������M���̖v����`�����u�u���C�Y�w�b�h�ĖK�v�̃X�g�[���[���̂��̂ł͂Ȃ����B�ł��A����́A�����Ƃ��悤����CD����ɂ��Ȃ�����A���̓Ƃ�悪�肩������Ȃ����E�E�E�E�E�B
�@���ɁAHighway61�ł���B����61������49�����̌����_�́u�N���X���[�h�`���v�Ƃ����āA�{�u�E�f�B�������h������u���[�X�̃M�^���X�g���V���K�[ ���o�[�g�E�W�����\���i1911�|1938�j���u�����ɍ����ăe�N�j�b�N����ɓ��ꂽ�v�Ƃ����`���̏ꏊ�B�`�����d��f�B�����Ȃ�ł͂̕����ł���B
�@����炩��A�u�n�C�E�F�C61�ւ̍ĖK�́A�����Ǝ�����邽�߂������v�Ƃ̌��_�������o����͂��Ȃ����B����ɁA�^�C�g���ȁu�lj��̃n�C�E�F�C61�v�̉̎��ɂ́A�A�u���n�����_����u�킽���̂��߂ɂ��O�̑��q���E���B�n�C�E�F�C61�Łv�Ƌ����ɕ�����`�ʂ�����B���݂ɃA�u���n���̓f�B�����̕��e�̖��O�ł�����B�f�B�����̓n�C�E�F�C61�ō������B�����{�[�������u���͑��ҁv�ɂȂ����B�u�lj��̃n�C�E�F�C61�v��1965�N8��30�������B�{�u�E�f�B����24�A6���ڂ̃A���o���ł���B
 �@���Ȃ錟�́A����������͒N���H�ł���B�f�B�������u�i�ߒ����v�ƌĂ��͉̂ʂ����ĉ��Ȃ̂��H ����́u�C���~�i�e�B�v�B�C���~�i�e�B�̓V���E�E�r�W�l�X�̐��E�𑀂郆�_���n�̗��g�D�B18���I���Ƀ��X�`���C���h�Ƃ��t���[���C�\���ƍ��̂����č�����閧���Ђł���B�f�B�����̃��S�ɂ̓C���~�i�e�B�̃V���{���E�}�[�N�u�S�\�̊�v���f�U�C������A�C���~�i�e�B�̃����o�[�E���X�g�ɂ͔ނ̖��O���F�߂���B�C���~�i�e�B�̃��X�g�ɂ́A���ɁA�}�h���i�A�r�����Z�A�f���B�b�h�E�{�E�C�A���f�B�[�E�K�K�A�A���W�F���[�i�E�W�����[�炪����A�˂�B
�@���Ȃ錟�́A����������͒N���H�ł���B�f�B�������u�i�ߒ����v�ƌĂ��͉̂ʂ����ĉ��Ȃ̂��H ����́u�C���~�i�e�B�v�B�C���~�i�e�B�̓V���E�E�r�W�l�X�̐��E�𑀂郆�_���n�̗��g�D�B18���I���Ƀ��X�`���C���h�Ƃ��t���[���C�\���ƍ��̂����č�����閧���Ђł���B�f�B�����̃��S�ɂ̓C���~�i�e�B�̃V���{���E�}�[�N�u�S�\�̊�v���f�U�C������A�C���~�i�e�B�̃����o�[�E���X�g�ɂ͔ނ̖��O���F�߂���B�C���~�i�e�B�̃��X�g�ɂ́A���ɁA�}�h���i�A�r�����Z�A�f���B�b�h�E�{�E�C�A���f�B�[�E�K�K�A�A���W�F���[�i�E�W�����[�炪����A�˂�B�@�m���ɁA1965�N���@�ɔނ͈̏�ς����B�T�E���h�̓��b�N�ɓ]���A���͑��w�I���h���I�ɂȂ����B���y�ɂ�����A����قǂ̌��I�ω��́A���[�c�@���g�̃t���[���C�\������ɕC�G����B�u�lj��̃n�C�E�F�C61�v�̃��[�h�E�V���O���u���C�N�E�A�E���[�����O�E�X�g�[���vLike a rolling stone�͏��̃x�X�g10������ʂ����A�S�ċy�у��[���b�p�e�n80�ӏ��̑�K�̓R���T�[�g�E�c�A�[�����s����B
�@�����āA51�N���2016�N�A�{�u�E�f�B�����̓m�[�x�����w�܂����^�����B�m�[�x�����c�ƃ��X�`���C���h�̐e���W�͗��j�I�����B�����ɁA�{�u�E�f�B�����`���_���`�C���~�i�e�B�`�m�[�x���� �̃��C������������ƕ����яオ��B
�@�X�E�F�[�f���E�A�J�f�~�[�����\�����A�{�u�E�f�B�����̎��ܗ��R�́u�A�����J�̉��y�̓`���ɐV�������I�ȕ\����n�������v�ł���B����͂܂��ɂ��̒ʂ�ł���B
�@�{�u�E�f�B�����̖{���̓��o�[�g�E�A�����E�c�B���}�[�}���B���V�A�n���_���l�ł���B�{�u���N�A�ŏ��̉��y�̌���10�̎��A�����z�����ƂɎc���Ă����r���E�������[��SP���R�[�h�������B������L�b�J�P�ɁAAM���W�I�ŁA�n���N�E�E�C���A���Y��W���j�[�E���C�̃J���g���[�A�}�f�B�[�E�E�H�[�^�[�Y�̃u���[�X�A�W���[�W�E���B���Z���g�̃��b�N�����[���A�I�f�b�^�A�E�f�B�E�K�X���[�̃t�H�[�N�E�\���O�ȂǁA�A�����J���y�̖{���ɐe���B�����Ă���炪DNA�Ƃ��Ĕނ̑̓��ɒ~�ς��ꂽ�B
�@���ł��A�ł��G�����ꂽ�̂̓E�f�B�E�K�X���[�̉��y�������B�u�ނ́A�Ɠ��ȃT�E���h�ő�Ȃ��Ƃ������Ă����B�l�ɂ͓��ʂɕ��������B�t�H�[�N�͖l���l���Ɋ����Ă��邱�Ƃ�`���Ă���v�����̐i�ނׂ����̓t�H�[�N�ƌ�����̂��B
 �@1961�N1���A19�̃{�u�́A�̋��~�l�\�^����Ƀj���[���[�N�̓O���j�b�`�E���B���b�W�ɂ���Ă���B���l�A�����E�M���Y�o�[�O�i1926�|1997�j�͂������g20���I�̃{�w�~�A�h�ƌĂB�ǂ�ȗl�q���m�肽����A�I�[�E�w�����[�́u�Ō�̈�t�v��ǂ߂����B
�@1961�N1���A19�̃{�u�́A�̋��~�l�\�^����Ƀj���[���[�N�̓O���j�b�`�E���B���b�W�ɂ���Ă���B���l�A�����E�M���Y�o�[�O�i1926�|1997�j�͂������g20���I�̃{�w�~�A�h�ƌĂB�ǂ�ȗl�q���m�肽����A�I�[�E�w�����[�́u�Ō�̈�t�v��ǂ߂����B�@�{�u�́A���C�u�E�X�|�b�g�ʼn̂��A�m�荇�������Ԃ̉ƂɐQ���܂肵�A�����ɂ���{���ނ��ڂ�ǂB���̒��ɂ́A�E�F�[���Y�̎��l�f�B�����E�g�}�X�̎������������낤�B�����{�[�̎��ɂ��G�ꂽ���낤�B�{�u�E�f�B�����Ɩ����悤�ɂȂ����̂͂��̂��납�炾�B�s���Ȏ���B�L���[�o��@�͊j�̋��|�����A���ʁA�Ό��A�\�̗͂��������r��Ă����B���O���ċc�_�������B�{�u�͊O�̐��E�Ɗւ�炸�ɐ����Ă͂����Ȃ������i�X�[�W�[�E���g���j�B�����Ė��ȁu���ɐ�����āvBlowin�f in the wind���a������B1962�N�̂��Ƃł���B
�l�͂����̓�����߂@�l�Ƃ��ĔF�߂��邾�낤���@�u���ɐ�����āv�͎����ɏ�����B�������^���̃V���{���E�\���O�ƂȂ����B�f�B�����͈��̒����ƂȂ����B���B���b�W�̃t�H�[�N���A�Z���^�[��Ɏ҃C�W�[�E�����O�̓f�B�����̉��y���u����̍l�����g���f�B�V���i���ȋȂɏ悹��B�����獡���ꂽ�̂�200�N�O�̋��������v�ƕ]�����B�Â���܂ɐV��������B�s���s�A�̖��̎v�l���B
�������͂����̊C��n��@���l�ɉH���x�߂���̂�
�����̖C�e����ь����@�E�C�͉i�v�ɂȂ��Ȃ�̂�
������ �F�� ���ɐ�����Ă���@���ɐ�����Ă���
�@�����A�f�B�����͂����Ɏ~�܂肽���Ȃ������B�ނ͍�������u���̉̂͂悢���������킩��Ȃ����ǁA����ɍ������B�̂�����ĉ̂��l�Ԃ��Љ�̖��ɑ��铚���������Ă���A�ƃ}�X�R�~�͎v������ł���B����ȘA���ɉ������������B���������B�����o�J�ǂ����l�̉̂ɂ��ď������낤�B�����̂��Ă��邩�l�ɂ��悭�킩��Ȃ��̂Ɂv�B���b�e����\�肽����}�X�R�~�Ǝ��R�ɉ��y����肽���f�B�����̊Ԃɂ͂������[���a���ł��Ă����B���̂�����l�W�ɂ������W���[���E�o�G�Y�i1941�|�j�͂����������u���Ԃ̓{�u���^���Ƃ����g���l���ɕ����߂悤�Ƃ����B���̎��͌����Ȃ��悤�ɁB�ł��ނ͂����Ȍi�F�������������̂�v�B�f�B�����͎��R��~�����B�Â���܂�V������ɕς������Ȃ����B�����ɂ���Ȃ�V�������낤�Ǝ��݂��B���̓������u�lj��̃n�C�E�F�C61�v�A�Ƃ�킯�u���C�N�E�A�E���[�����O�E�X�g�[���v�ł͂Ȃ��������B���Ƃ������ɍ������ɂ��Ă��B
�@�u�{�u�E�f�B�����Ƀm�[�x���܁v�̃j���[�X�́A�ӏH�̓��{���삯�������B�����A�����A�g���`���J���A�l�X�ȃR�����g����ꂽ�B
�@�g�c��Y(1946�|)�́u�f�B���������Ȃ�������A�ƍl����B�{�u�E�f�B�������������獡��������悤�ȋC������B�����̂��Ƃ���������n�܂����Ɩl�͎v���̂��v�ƃR�����g�����B�t�@�W�[�Ȍ����������A�͂����茾���Ă��܂��u��������������̂̓f�B�����̂��������v�Ƃ������Ƃ��낤�B�X�g���[�g�Ɍ���Ȃ��̂͑�Y�̃v���C�h���B
�@1970�N11���A�g�c��Y�̓t�@�[�X�g�E�A���o���u�t�̎��v�������[�X�����B���̃A���o���̓f�B�����̉e���Ȃ����Č��Ȃ��B�u�����܂ł����Ė�������v�́A�u���悭�悷��Ȃ�vDon�ft think twice, It�fs all right�ɍ������Ă���B�u�j�̎q�E���̖��v�ł̒�����q�Ƃ̃f���G�b�g�́A1963�j���[�|�[�g�E�t�H�[�N�E�t�F�X�e�B�o���ł̃f�B�����ƃW���[���E�o�G�Y���C��������̂��낤�B
�@����ŁA�u��v�ɂ�����R���u���v�ɓ����t�̊Î_���ς��Ȃǂ́A�����낤�Ǝ��̊������B���Ă���Ǝw�E�����u�����܂ł����Ė�������v�ɂ��Ă��A����̓����f�B�[���C���̂��ƂŁA�̎��ɂ����Ă͑�Y�̌��������Ă���B�����ɂ́A���߂Ȃ���̑O������������B�T���߂Ȃ���u���ɂ͎��̐�����������v�Ǝ咣���Ă���ł͂Ȃ����B�u�C���[�W�̉́v�ɂ̓V�j�J���ȃG�X�v���Ƃ������ׂ����̒��@����Ǝ��̎��_������B
�@1972�N�ɂ̓A���o���u���C�ł��v��CBS�\�j�[���烊���[�X�B�P�Ȗځu�t�������ˁv����x�̂����B�M�^�[���G���L�Ɏ����ւ��A�V���Z�T�C�U�[���������G���L�T�E���h�B�f�B�������u�lj��̃n�C�E�F�C61�v�ł�����ϊv�Ɠ������B���������́u�t�������ˁv�̓f�B�����̎���u�u�����h�E�I���E�u�����h�v�̑�6�ȁu�����t�B�X�E�u���[�X�E�A�Q�C���v���ێʂ��̗l�����B�p�N���Ƃ����Ă��d�����Ȃ����x���ł���B���_�p�N���̓����f�B�[���T�E���h�ʂ̂݁B���̓p�N���l���Ȃ��B����������đ�Y�ƌ��ʂ����Ƃ����t�@���������炵���B�ł��A�p�N�����C�ɂ��Ă�����i�|POP�͕����܂���B�Â��ɏ��Ă��܂��̂���ԁB���ɂ������̂����������Ă���̂�����B
�@�g�c��Y�́A�u�t�̎��v1970�ł́u�t���[�z�C�[�����v1962����A�u���C�ł��v1972�ł́u�lj��̃n�C�E�F�C61�v1965�Ɓu�u�����h�E�I���E�u�����h�v1966����A�r��ȉe�����č�����B�ނ�5�ΔN��̃f�B�����̉e��ǂ������Ă����B
�@�f�B�����̃m�[�x����܂̕���āA����ꂢ�q����͈����̃R�����g���o�����B�u�f�r���[���������т��ē`���̂��̂��Ă����l�B�č��Ƃ����A���j���Â��Ȃ����œ`����������l�����炱���A�]�����ꂽ�̂ł͂Ȃ�������v�B���ɓI�m�A�A�J�f�~�[�̐^�ӂ����⑫���Ă���B
�@���N��܂�S�҂����Ă���n���L�X�g�̈�l�́u���コ��̓f�B�������D���B���ł���͂��ł��B�����ȉ��y�������i�ɂ͏o�Ă��邪�A�f�B�����͕ʊi������v�B�E�[���A���ł��邩�Ȃ��B�����������G�Ȃ̂ł͂Ȃ�������B�ł��܂��A����������������̂Ȃ��������������Ȃ̂����B���ꂩ����A���̎�������オ���ł��傤���ˁB
�@SONY-BMG�Ζ��̗F�lS���́uCD�̃I�[�_�[���ʏ��200�{�ƎE�����Ă��܂��B�m�[�x���܂̉e���̑傫�����������Ă��܂��v�Ƙb���Ă��ꂽ�B����Ɂu�f�B�����͂���܂Ő��X�̏܂�������Ă��܂����A��܂̏�ɗ��Ȃ��������Ƃ͂Ȃ��������A�R�����g���邱�Ƃ��Ȃ������v�Ƃ��B�Ȃ�A�m�[�x���܂ɑ��Ă������ɂ͏o�邪���ق����A�Ƃ����X�^�C�����т��̂��I�H �B��Ƒ��j�{�u�E�f�B��������ڂ������Ȃ��B
���Q�l������
�f��u�m�[�E�f�B���N�V�����E�z�[���vDVD
�{�u�E�f�B����CD
�@�@�@�u�t���[�z�[�����v
�@�@�@�u�lj��̃n�C�E�F�C61�v
�@�@�@�u�u�����h�E�I���E�u�����h�v
�g�c��YCD
�@�@�@�u�t�̉́v
�@�@�@�u���C�ł��v
2016.10.15 (�y) FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v
 �@���a�̖����j�E�ȋт̓������o�}���Ă����JR����������w�B�_���^�̊J�����E�肪�w�������ɏo��ƃt�����[���[�h�Ƃ������X�X������A������i�ނƒ��قǂɁuFM���ǂ���v�̃X�^�W�I������B���g��84.3MHz�B���G���A�́A�]�ː��S��A�]����A�n�c��A������A�s��s�A�Y���s�̈ꕔ�B�J�ǂ�1997�N11��30���A���N20���N�̐ߖڂ��}����R�~���j�e�BFM�����ǂł���B
�@���a�̖����j�E�ȋт̓������o�}���Ă����JR����������w�B�_���^�̊J�����E�肪�w�������ɏo��ƃt�����[���[�h�Ƃ������X�X������A������i�ނƒ��قǂɁuFM���ǂ���v�̃X�^�W�I������B���g��84.3MHz�B���G���A�́A�]�ː��S��A�]����A�n�c��A������A�s��s�A�Y���s�̈ꕔ�B�J�ǂ�1997�N11��30���A���N20���N�̐ߖڂ��}����R�~���j�e�BFM�����ǂł���B�@���āA���A�������炱��FM���ǂ���ŁA�u�����N���V�b�N�v�Ƃ����ԑg����点�Ă�����Ă���B���T�ؗj���̗[��5�������肩���7���ԁB�g������h�Ƃ����̂�3���Ԃ̐��ԑg�̈�R�[�i�[�Ȃ̂ŃL�b�`���Ƃ͎n�܂�Ȃ����炾�B����́A�u������ �Ί�����v�Ƒ肷�錎�\���̑сA�ߌ�3������6���܂ł�DJ�ԑg�B�ؗj���̃p�[�\�i���e�B�[�͓ޗǒ��q���B
�@�L�b�J�P�̓��R�[�h��Ў���̗F�lN���B�ނƂ�20���N���̕t�������ŁA�悭�S���t�����ɂ����B�S����2000�N�O��A�^�C�K�[�E�E�b�Y�̑S�����ƍ��v����i���ꂪ�ǂ������j�B�z�[���E�R�[�X�͓Ȗ،��̃W�F�C�E�Z����CC�i���P���g�XGC�j�ŁA�����̓v���C�������̂��B
�@N���̗F�l��I���Ƃ��������f�B���N�^�[�����āA���N�]�E���������FM���ǂ���Ŋ��𗧂��グ�����B���Ă̓N���V�b�N���l���Ă��邪�A�N���K���Ȑl�����Ȃ����낤����N���ɑ��k������A���ɂ���������Ă����Ƃ�������B���N�S���Ȃ������R�M�v���u�F�l�̗F�l�̓A���J�C�_�v�ƌ��������A���̏ꍇ�u�F�l�̗F�l�͕�������ҁv�������B
�@���k���āA���R���Z�v�g���\�z�B���������������o���N���V�b�N�͂������H ���̐S�́A�u�N���V�b�N���y�́ACM�A�f��A�h���}�A�����A�X�|�[�c�ȂǃG���^�[�e�C�������g�̐��E�̒��ɚ삵�����݂���̂ɁA�݂Ȃ���A�Ȃ��Ȃ��e���߂Ȃ��ł���B���������܂��q���ł������Ɛg�߂Ɋ�������̂ł͂Ȃ��낤���v�B�J�����_�[�E�N���V�b�N�Ȃǂ����낤�H �Ⴆ�A���̓����N�^�̒a�����Ȃ炻�̐l�Ɉ��I�Ȃ�����B�u�h�V�̓��v��������Œ�����ȉƃV�x���E�X�̊y�Ȃ�I��Ńg�[�N���铙�X�B������Y��ĂȂ�Ȃ��̂͒n��̃e�C�X�g�B�Ⴆ�]�ː��o�g�̗L���l�ƃN���V�b�N�Ƃ��B�g�߂Ȏ��ۂƃN���V�b�N���y�����т���A����g���������N�̃N���V�b�N�h�͎��̓��ӋZ�I�H �ʔ����Ȃ��Ă������B
�@I���H���u���̓i�C�X�ł��B�����b�����A���������ڎВ��ɘb�����������v��FM���ǂ���r�c�В��Ƃ̍��k�̏��݂��Ă��ꂽ�B6���̂��Ƃ������B���݂������R�[�h��ЂƂ����o���������Ęb���e�݁A�u�ł́A�ߌ�̑єԑg������ʼn��y�Ύ��L�I�ȃR�[�i�[������Ă݂܂��傤���v�ƕ��������o��B�ו���I���Ƌl�߂āA�Ƃ������ƂɂȂ����B���Ƃ͒��g���悩�B
�@��������ɋ�̉����ׂ��A�T�ꌎ�j���̑z��ŁA8���̉��z��{�������Ă݂��B���̕�������Ō������₷�����낤�Ǝv���āB
�@8��1���́A���I�ܗւɏo�ꂷ��n���o�g�X�C�}�[�r�]���Ԏq�̘b�肩��A�_�����X�E�~���[��ȁu�u���W���̏��v�Ɍq����B8���́u�R�̓��v�Ɉ��݁u�A���v�X�����ȁv���B15���͋��~�ɂ��A�̋����Â�Ńh���H���U�[�N�́u�ƘH�v��n���o�g�̎ڔ��̋M���q�������R�̉��t�ŁB22���́A1969�N8���Ɏn�܂����u�j�͂炢��v����ŏ��Ɏg��ꂽ�N���V�b�N�ȁA�n�C�h���̌��y�l�d�t�ȁu�Ђ�v�B
�@I�����Ǔ��Ƀv���[���B���A�������o��B�u������ �Ί�����v�ؗj���S���p�[�\�i���e�B�[�̏����A�i�������������Ă��ꂽ�Ƃ̂��ƁB����������ċ��c�B���̕��͓ޗǒ��q����B�J�Ljȗ��̃p�[�\�i���e�B�[��20�N�̃x�e�����B�t�@���������B���y�S�ʁA�ߒ������A�̕���ȂǑ���|�̂ЂƁB���̊��Ă����O�ɐ��ǂ��Ă���Ă��āA���A���܂��傤�A�Ƃ������ƂɁB�R�[�i�[�E�^�C�g���́u�����N���V�b�N�v�B���̌ď̂́u�����̃N���V�b�N��������v�B�܂��A�������B�Ƃ����킯�ŁA���҂�10������7���Ԃ̃R�[�i�[���X�^�[�g����^�тƂȂ����B
 �@����ɐ旧���A9��15���ɂ́A�������̃Q�X�g�Ƃ��ďo���A�R�[�i�[�a���̍��m����点�Ă����������B���A����Ɂu�Ђ���N���V�b�N�v�����B�f��̕��䂪�����G���A�ɍ��v���Ă��邱�ƁB�Ђ����������N�v��20�N�Ƃ������ƁB�ނ̖�����8��4���ŁA1973�N�̓������ɕ���ꂽ��11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�ɂ̓N���V�b�N���ӂ�Ɏg���Ă��邱�ƁB�ȂǂȂǁA�ԑg�e�[�}�́g���������N�̃N���V�b�N�h�Ƀh���s�V�����B�����X�L�[���R���T�R�t�́u�V�F�G���U�[�h�v�AJ.S.�o�b�n�u�f����̃A���A�v�A�V���[�x���g�́u���v�𗬂��A��ʂƗ��߂ăg�[�N�����B�ޗǂ���͗��x�e�����B���܂����[�h���Ă��ꂽ���A���߂́A�オ����ςȂ��̋����ԁB���͖����Ǝ��o�����B���e�͗ǂ������̂ɂȂ��B���̃w�^�N�\�߂��I
�@����ɐ旧���A9��15���ɂ́A�������̃Q�X�g�Ƃ��ďo���A�R�[�i�[�a���̍��m����点�Ă����������B���A����Ɂu�Ђ���N���V�b�N�v�����B�f��̕��䂪�����G���A�ɍ��v���Ă��邱�ƁB�Ђ����������N�v��20�N�Ƃ������ƁB�ނ̖�����8��4���ŁA1973�N�̓������ɕ���ꂽ��11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�ɂ̓N���V�b�N���ӂ�Ɏg���Ă��邱�ƁB�ȂǂȂǁA�ԑg�e�[�}�́g���������N�̃N���V�b�N�h�Ƀh���s�V�����B�����X�L�[���R���T�R�t�́u�V�F�G���U�[�h�v�AJ.S.�o�b�n�u�f����̃A���A�v�A�V���[�x���g�́u���v�𗬂��A��ʂƗ��߂ăg�[�N�����B�ޗǂ���͗��x�e�����B���܂����[�h���Ă��ꂽ���A���߂́A�オ����ςȂ��̋����ԁB���͖����Ǝ��o�����B���e�͗ǂ������̂ɂȂ��B���̃w�^�N�\�߂��I�@���o���ʂ�A10������̖{�ԂŐ��̓i�V�A�u�Θb�^�^�������v�ɂ��Ă��������B�f�B���N�^�[�͕���5�N���܂��O���B���̑��q����܂����Ⴂ�I �N���V�b�N�ɂ͑S������݂��Ȃ��Ƃ̂��Ƃ����A�^�ʖڂŔM�S�����牽����͂Ȃ��B���[�e�[�V�����́A�u�T�ؗj���̓�T�����^�B�������݁A10��6����OA�ρB13���͎��^�ς݁B20����27������13���Ɏ��^�B����ȃX�P�W���[���ƂȂ��Ă���B
�@����ł́A�u�ޗǒ��q�̂����N���V�b�N�v10���̃��C���A�b�v���A������J�����Ă��������܂��B
��10��6�����]�ː��o�g��ƁE�Γc�ߗǂƃN���V�b�N�i�����ς݁j
�Γc�ߗǂ͍]�ː��o�g�B�f�r���[��u�r�܃E�G�X�g�Q�[�g�E�p�[�N�v����x�X�g�Z���[�ƂȂ�B���̏����ɂ͐��X�̃N���V�b�N���y���o�ꂷ��B�ނ̑��w�̐[���䂦�̂��Ƃ��낤�B�����́A��l�������߂ăN���V�b�NCD����ʂ�I�яo���A�����ōw�������`���C�R�t�X�L�[��ȁu���y�Z���i�[�h�v�����2�y�́u�����c�v�����������������B��10��13�����C���E�����^���Ɓu�u���[���X�͂��D���v�i���^�ς݁j

�C���E�����^����1921�N10��13�����܂�B1946�N�u�͗t�v���̂����X�^�[�_���ɏ��A�u���E�̗��l�v�ƌĂꂽ�B�{�Ƃ̓V�����\���̎肾���A�f��ɂ��������o�����Ă���B�����́A�ޏo��1961�N�̉f��u����Ȃ��������x�v�i����̓T�K���̏����u�u���[���X�͂��D���v�j����A�}���ȂƂ��ėL���ɂȂ����u���[���X��ȁu �����ȑ�3�� �w�����v�̑�3�y�͂������肷��B��10��20�������E���̃R���T�[�g�L���̓��[�c�@���g�̉��t��
���N10��20���́u�V���L���̓��v�B�Ƃ���Ő��E�ŏ��߂ẴR���T�[�g�L���͉��H ���ꂪ���ƃ��[�c�@���g�̉��t��̐V���L���B�Ƃ���1764�N6��5���B�Ƃ���̓����h���B�u���[�c�@���g���l�͓V�^�̐_���ł����A���̋@��ɁA���̈̑�Ȑ_���Ԃ���A�F�l�ɂ��ڂɂ�������̂ł���܂��E�E�E�E�E�v�Ƃ������́B�L���d�|���l�̓��[�c�@���g�̕����I�|���g�B�����h���؍ݒ��ɑ召�̃z�[���◿���X�Ő��͓I�ɃR���T�[�g�������s�����B�����̓����h���؍ݒ��ɏ������u�����ȑ�1�ԁv�ƁA�Ō�̌����� ��41�ԁu�W���s�^�[�v�̏I�y�͂��r�ׂĂ��������B��10��27�����j�R���E�p�K�j�[�j�̉��y
���@�C�I�����̖���ɂ��č�ȉƂ̃p�K�j�[�j�́A1782�N10��27���A�C�^���A�̃W�F�m���@�Ő��܂ꂽ�B���̐l���݊O�ꂽ���t�e�N�j�b�N����A�u�����ɍ������j�v�Ƃ��̂��ꂽ�B���̃i�|���I���̖����璞������ȂǁA���������j�V�r�B�ނ̐����͌��O��̎����ɂ��\��Ă��āA����ɂ̓V���[�x���g�̈ꐶ����8���Ԃʼn҂��������Ƃ��B�����́A���@�C�I�������t�ȑ�2�ԁu���E�J���p�l���v�����3�y�͂��B���̃����f�B�[�͌�Ƀ��X�g���s�A�m�ɕҋȂ��đ�q�b�g�ƂȂ����B�@�Ƃ܂��A����Ȋ����ł���܂��B�L�O���̂Ȃ��u���v�͂Ȃ��A�N���V�b�N�Ȃɂ����肪�Ȃ��̂�����A�l�^���s���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�u�ǂ��ɂ��Ȃ邳�v�ƋC�y�ɂ���Ă䂫�����B
2016.09.26 (��) ��Ղ̖�`�g���E�n���N�X�Ƒ����̓^��
 �@2016�N9��16���i���j�B���Ƃ��s�v�c�ȏ��ł���܂����B�u�y����t��낤���v�Ɛ̂̒���4�l�Ő\�����킹�ďW�܂����̂��_�c�́u�܂�v�B�����́u��ԁv�ƕ��ԋ����̖��X�B����17�N�i1884�N�j�̑n�ƂŁA�u��ԁv�ɔ䂵�����I�ƕ]���̓X�B
�@2016�N9��16���i���j�B���Ƃ��s�v�c�ȏ��ł���܂����B�u�y����t��낤���v�Ɛ̂̒���4�l�Ő\�����킹�ďW�܂����̂��_�c�́u�܂�v�B�����́u��ԁv�ƕ��ԋ����̖��X�B����17�N�i1884�N�j�̑n�ƂŁA�u��ԁv�ɔ䂵�����I�ƕ]���̓X�B�@4�l�Ƃ́AT����i69�j�AA����i65�j�A�g����i64�j�Ǝ��i71�j�BH����͖^���̉̎�̃}�l�[�W���[�Ō����B���̎O�l�̓T�����[�}�����Ƒg�B�S�����Ԃɓs�������g���B�W�������̂͗[��5���������B
�@�Ƃ肠�����r�[���Ŏn�߂āA�킳�A�Ă�Ղ�Ȃǂ����Ȃ���A�����l�^�A�X�|�[�c�l�^�A�|�\�l�^����⌖�����߂����Ă���6������A�Ă����ׂ̃e�[�u����4�l�̊O�l�l����s�����Ȃ����B���̏u�ԁA�Ζʂ�T���u�g�g�g�g�g���E�n���N�X�����v�Ə����ł�߂������B�A�ł������Ă�̂��Ƃ����Q�Ă悤�B�E���ɖڂ����ƁA�܂������g���E�n���N�X�������B�ŐV��u�n�h�\����̊�Ձv�̌��J�ɍ��킹�����v�����[�V�������Ȃ̂͒m���Ă����B �E�ׂ�A����́u�ւ��A�������R�B�ł��A�����������͑������Ă��ɂ����Ƃ��Ă����̂���V�ł��v�ƁA��������������m�y�S�������������ɂ킫�܂��Ă���B���������Ȃ��̂�T����B�u���A��t�@���ȂB������ƍs���Ă���v�Ɠ��l�̑O�ɂ��Ⴕ���o���B�����J�^�R�g�Œ����Ă���B���̃n���N�X���̓j�R�j�R�����Ă���Ă���BT����A���������ĐȂɖ߂��A�����̋ɂ݁B�u���A�ނ̉f��Łw�O���[���}�C���x����ԍD��������A�����������B�Ȃ�ĕԂ��Ă������͕������v�B�悩��������Ȃ������b���ł��āB�u�����l�ł��ˁB�C�����A�e���݂₷���A�Ȃ������������Ƃ��v��H����B�u�C��������v�Ǝ��B�u�����������ꂻ��B�C�����Ȑl�v�B�������A���������ς���Ă���ȁB
�@����s�́A�g���E�n���N�X�A�X�^�C���X�g�炵���i�Ⴄ���ȁj�����A�o�D�̗��I�i������Ⴄ���j�N�ASP���i����܂��Ⴄ���j�X�L���w�b�h�̋��ʂ��������4���B30�������肰�Ȃ����ł��傤���B�Ȃ�ƂȂ��݂��������悤�ɂȂ��āA�܂��A���������ċC�����オ���āB����Ȑ܁A�n���N�X������X�Ɂu�ǂ��̉�ЁH�v�Ɛu������A�uBMG�O�g��RCA�v�Ƃ����P��œ�����B����ȂƂ����Ԃ�K��������X���[�Y�Ȃ̂ɂƉ����ł݂Ă��A�ނ͂��̓����p�ŕʍs���B�n���N�X���́u�����̉�Ђ��H�v���ĂȊ����������̂ŁA�u�G�����B�X�E�v���X���[�̉�Ђ��v�ƃn�b�L���������Ƃ���A�uOh Elvis�INice�I�v�Ƃ����B�����āA�����Ȃ�uLove me tender love me true �E�E�E�E�E�v�Ɖ̂��o�����Ⴀ��܂��B���₨��A���ɋC�����ŏ�肪�����I �Ȃ�����オ���Ă������B
�@�n���N�X���ɓ��s�̐N����ȃJ�����Ńp�`�p�`����Ă���B�Ȃ��Ȃ��̒j�O�B�Ȃ�ƂȂ������|�������Ȃ��āA���uYour camera is LEICA�H�v�Ƃ���Ă݂��B�N�uNo, This is Nikon�v�B�����Ă܂���B�ŁA����Ɏ��A�uNo No It�fs LEICA�v�Ƃ�������ƁA�uLike a bridge over troubled water I will lay me down�v�Ɓu�����ɉ˂��鋴�v�̃T�r���̂����Ⴂ�܂��ĂˁB�N�̓L���g���B�Ƃ��낪�n���N�X���A�����ŁuWhen you�fre weary feeling small�E�E�E�E�E�v�Ɠ�����̂��n�߂邶�Ⴀ��܂��I �T�r�����m��Ȃ���X�́A�n���N�X���ɍ��킹�Ȃ���A�T�r�ɂ�����u���C�J �u���b�W �I�[�o�[ �g���u���h�E�H�[�^�[�E�E�E�E�E�v�Ƒ升���i�ł������ʁj�B��͈�C�ɐ���オ��A���Đe�P�̗ւ͂����Ȃ�ō����ɒB�����̂ł���܂��B
�@�����Ȃ�ƁA�C�����ȃn���N�X���͂���Ƀq�[�g�E�A�b�v�B�u�X�L���L���̂����v�Ƃ������ƂɁB�莝���̃X�}�z�Ƀ��[�}���̉̎����o���āA�N���[�ɂ������Ȃ���u�E�G���@���E�C�e�@�A�[���R�I�I�I�v�Ɖ̂��o���B���̍����I�̗w�ȂȂ�̎����v�ȉ�X�͎��R�ɏ��a�A�ēx�升���Ɂi��͂菬���ʁj�B
 �̂��I����āu���̉̂��S�đ�1�ʂɋP�����̂�1963�N�ł����v�Ǝ��BT������������Ɂu���̉̂̃����f�B�[�̓x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�R���`�F���g�w�c��x�ƃ\�b�N���Ȃ�ł���v�ƈ��]�~�B�n���N�X���͂����j�R�j�R���Ă���B�{���ɂ����l���B���x��SP���AH������w�����āu���Ȃ��́w�^�N�V�[�h���C�o�[�x�̔o�D�݂������v�B�����A�u�^�N�V�[�h���C�o�[�v�Ƃ������o�[�g�E�f�E�j�[���ł���B�{�����Ȃ��H �����̊��Ⴂ�ɂ��Ă��A�����C�͂��Ȃ�H����ł����B
�̂��I����āu���̉̂��S�đ�1�ʂɋP�����̂�1963�N�ł����v�Ǝ��BT������������Ɂu���̉̂̃����f�B�[�̓x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�R���`�F���g�w�c��x�ƃ\�b�N���Ȃ�ł���v�ƈ��]�~�B�n���N�X���͂����j�R�j�R���Ă���B�{���ɂ����l���B���x��SP���AH������w�����āu���Ȃ��́w�^�N�V�[�h���C�o�[�x�̔o�D�݂������v�B�����A�u�^�N�V�[�h���C�o�[�v�Ƃ������o�[�g�E�f�E�j�[���ł���B�{�����Ȃ��H �����̊��Ⴂ�ɂ��Ă��A�����C�͂��Ȃ�H����ł����B�@����ȗ���̒��A�n���N�X���A�₨��X�}�z�����o�����B����B�u���̐l�������Ɋ���āv�n�C�A�|�[�Y�B�܂������̎ʐ^��������ɃG���C���ƂɂȂ낤�Ƃ́I
�@��������I�ՁA�������̒i��肪������Ȃ��炵���n���N�X������s�ɁAA�N���u����͂������Ă��������āE�E�E�E�v�Ƌ����B�uSmell good �I�v�ƃn���N�X���B�����āA���悢�悲��s�ސȂ̎��ԁB�Ȃ�Ɖ�X�Ɏ��U���Ă���܂����B��X�������オ���ĕʂ�̂����A�B
�@�Ȃ�Ƃ���1���Ԕ��B���̃A�J�f�~�[�剉�j�D�܂�2�x�܂Ŋl�������X�啨�X�^�[���u�܂�v�ŗׂ̐ȂɁB����ȋ��R���Ă���̂��Ȃ��B�����Ă����̂����B���H�̖����Ɩ����̊ԂɋN�����܂��ɕs�v�c�̏��A��Ղ̖�ł����B
�����
�@��Ղ̖邩��O���ڂ̒��AA����d�b�B�u��������A�G���C���ƂɂȂ��Ă܂��B�g���E�n���N�X����X�Ƃ̎��B��ʐ^�����g�̃c�C�b�^�[�ɏグ�āA�����������I�v�B �Ȃɂ��̎��̎ʐ^���I�H SNS�ɑa���������p�\�R�����J���Ă݂�ƁA�Ȃ�R�����[�I �n���N�X���Ɖ�X�̎ʐ^�����������ɏo����Ă���ł͂���܂��B�^�C�g�����uRocking Tokyo with my crew. HANX�v�B������Amy crew���ĉ������̂��Ƃ��܂�ł�H���肪������������B����ɂ��Ă����̊g�U�U��B���ꂪSNS�̈З͂Ƃ������̂��B
�g���E�n���N�X�̎��B��Ɏʂ荞��őS���E�Ɋg�U������@�ȂǂȂǁA����ȏ������݂̃I���E�p���[�h�B�T�ˊy�������͋C���~�߂Ă�悤�����A���G�ȐS�����`�����B���̐S�́A�u�ǂ����Ă��t�c�[�̃T�����[�}���B�g���E�n���N�X�̂悤��VIP�Ƌ��R�����킹��͂����Ȃ��B��͂�f��W�̂��G���C����ƌ���̂��Ó����낤�B�ł���������R�����킹���t�c�[�̂��������������Ƃ�����A�Ȃ�ƑA�܂������Ƃ��낤�B�������₩�肽����v�ĂȂƂ��납�B���ɂ́A�u����͊p���F�ɈႢ�Ȃ��v�Ƃ��u���ʂ�NHK�̉�ł́H�v�Ȃ��̓I�����c�C�[�g���BSNS�̏������ݎ�́A����₱���z���͂����ď����Ȃ��A�Ɗ��S��������ł���B
�W���p�j�[�Y���b�p���C���T�C�R�[
1214�����̃g���E�n���N�X�̃t�H�����[�͂������
�S���E�ɃW���p�j�[�Y���b�p���C���g�U����ċ��M
�g���E�n���N�X�߂�����y������
�����g���E�n���N�X�ƈ��݂���
���ׂ̗̓��{�l�̂��������A�܂����Ȃ�
����͉f��W�̂��̂����� ����Ⴛ����
�����킹����ʐl�Ȃ킯�Ȃ����낤���ǁA
���̂������V���̋������ɂ���T�����[�}�����̂�������ǂ�����
�@����A���̎ʐ^�A�e���r�ł��I���G�A�����n���B9��21���̒��A�w�R��������d�b�A���u��������A���̎ʐ^�w�Ƃ��_�l�I�x�ɉf��܂���v�B�����t�W�e���r�ɐ�ւ���ƁA�o�܂����B�u�n���N�X�����B��ʐ^�v�B���̌�ATBS�u�����`�����I�v�u���l�̃u�����`�v�ɂ��o�ꂵ�܂����B
�@���F����̔������������A���[����d�b�̗ނ�40�����B�ŏ��A�g������u����A�������肳��Ȃ��́H �n���E�g���N�X�Ƃ��v�Ƌ^���̖ڂ�������ꂽ�ꌏ�́A�S���E�Ɋg�U��������̑厖���Ƒ��������̂ł���܂��B
�@�Ђ��Ȃ��Ƃŋ����킹���g���E�n���N�X���B���߂Őڂ��āA���̋C�����Ȑl���ɂ������薣������܂����B����̊���Ɖf��u�n�h�\����̊�Ձv�̑�q�b�g��S���炨�F�肢�����܂��B����������ɍs���܂���[�[�[�I�I
2016.09.25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 4 �`�{���g �Z������4 �}���J�i���̊���
�i1�j�{���g�s�ł̋����� �@�I�����s�b�N�̉����㋣�Z�ł��邱�Ƃ͏O�ڂ̈�v����Ƃ��낾�낤�B���ł�100m�͉ؒ��̉��B�ߋ��A100m�̃X�^�[�Ƃ��Ĉ�ۓI�Ȃ̂́A1936�x�������̃W�F�V�[�E�I�[�G���X�A1964�����̃{�u�E�w�C�Y�A1984�A�g�����^�̃J�[���E���C�X�炾�B���j�ɖڂ�]����ƁA1964�����̃h���E�V�������_�[�A1972�~�����w���̃}�[�N�E�X�s�b�c�A�����Ă����ߔN�̃}�C�P���E�t�F���v�X������B�����A���͂ɂ����ė���ɂ͓G��Ȃ��B����́A���j�͊炪�����Ȃ�������͊炪�����邵�A���Ƃ����Ă��ő��̌��������͂��B����ȃI�����s�b�N�̉E���㋣�Z�Z�����E�j��ő�̃X�^�[�Ƃ����A�E�T�C���E�{���g�i30�� �W���}�C�J�j�������đ��ɂȂ��B
�@�I�����s�b�N�̉����㋣�Z�ł��邱�Ƃ͏O�ڂ̈�v����Ƃ��낾�낤�B���ł�100m�͉ؒ��̉��B�ߋ��A100m�̃X�^�[�Ƃ��Ĉ�ۓI�Ȃ̂́A1936�x�������̃W�F�V�[�E�I�[�G���X�A1964�����̃{�u�E�w�C�Y�A1984�A�g�����^�̃J�[���E���C�X�炾�B���j�ɖڂ�]����ƁA1964�����̃h���E�V�������_�[�A1972�~�����w���̃}�[�N�E�X�s�b�c�A�����Ă����ߔN�̃}�C�P���E�t�F���v�X������B�����A���͂ɂ����ė���ɂ͓G��Ȃ��B����́A���j�͊炪�����Ȃ�������͊炪�����邵�A���Ƃ����Ă��ő��̌��������͂��B����ȃI�����s�b�N�̉E���㋣�Z�Z�����E�j��ő�̃X�^�[�Ƃ����A�E�T�C���E�{���g�i30�� �W���}�C�J�j�������đ��ɂȂ��B�@�{���g�ȑO�A����j�q100m�ŘA�e���ʂ������̂́A1984���T���[���X��1988�\�E���̃J�[���E���C�X�����B200m�͊F���B������ł�100m�A200m�A400m�����[�̃g���v�������_���X�g�́A1936�x�������̃W�F�V�[�E�I�[�G���X�A1956�����{�����̃{�r�[�E�����[�A1984���T���[���X�̃J�[���E���C�X�̃A�����J3�I�肾���ł���i���A�I�[�G���X�ƃ��C�X�͑��蕝���т̂��܂����łS���j�B
�@�E�T�C���E�{���g�͍���̃��I��100m�A200m�A400m�����[�ŋ��B����ŁA�Ȃ�ƁA3���A���̃g���v�����A�ʎZ9���l������Ƃ�����L�^��ł����Ă��B����܂ŘA�e�͈�l�A�P�N�g���v�����͎O�l�Ƃ������j�̒��ŁA�Ȃ�ƈ�l�Ńg���v������3�A���Ƃ����A���قƂ��������悤�̂Ȃ��L�^��B�����Ă��܂����̂ł���B�������A2008�k���A2012�����h���A2016���I��3���ɂ킽��o�ꂵ�����Z�͋�����B����قǔ������L�^�����邾�낤���I�H �܂��ɁA�O�㖢���A��O���̋������ł���B
�@�{���g�̕��݂��A100m�̋L�^�ʂ��璭�߂Ă݂悤�B2008�k���ł�9.69�B2009���E�I�茠��9.58�̐��E�V�L�^�i����͌����j�B2011��緐��E�I�茠�̓t���C���O�Ŏ��i�B2013�����h����9.63�B������2016���I��9.81�B�ȏ�̗��ꂩ��A�ނ̃s�[�N��2009�|2012�ɂ������ƍl������B�Ȃ�A2011�̐��E�I�茠���i�́A�M���M���̃X�^�[�g�Ő��E�L�^�X�V��ژ_���ʂ̃~�X�������̂ł͂Ȃ��낤���H �{���g�ɂƂ��đz����I�H ���̌�͋L�^���̂āA�댯��`����������D�悵���B���͂����������Ă���B���̈�A�̗�������Ă���ƁA�E�T�C���E�{���g�Ƃ����s���o�̃A�X���[�g���A�����Ɏ��Ȃ�m�肻�̎��X�� �����ׂ��p�t�H�[�}���X���Âɉ��������������Ă���B2020������ނ͖ڎw���Ȃ��Ƃ����B100m�͌Q�Y�����̐V����ɓ˓������B
�@����܂�����邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���闤�㋣�Z�̋L�^�����������B����́A�G�~�[���E�U�g�y�b�N�i1922�|2000�`�F�R�j��1952�w���V���L�őł����Ă��A������5000m�A10000���A�}���\���̗��㒷�����g���v�������_���ł���B5000m��10000m�̃_�u�����͍����Ń��n���h�E�t�@���[�i�p�j��2�A�e�̂��܂����ŒB�����Ă��邪�A�}���\���͏o�ꂷ�炵�Ă��Ȃ��B�ߔN�́A10000���ƃ}���\����W�o��͂܂����肦���A����]���̂��Ƃ��Ȃ�����A���̃U�g�y�b�N�̋L�^�ƕ��Ԃ��Ƃ͂Ȃ����낤�B
�@�U�g�y�b�N�͂��̂��܂�̋����ɁA�l�ԋ@�֎ԂƂٖ̈����Ƃ����B�ނ����㋣�Z���u�������������́A�䂪���Ѝu���i1905�|1998�j��1936�x�������ł̑��肾�����Ƃ����B��L�^�̉A�ɓ��{�l����B�ւ炵�����肾�B
�@�����ŁA����Ȃ�]�k����B�{���g�ȑO�ɁA���㋣�Z��3���A���_�u�����i����2���̓g���v���j���l�����I�肪����B���̐l�̖��̓��C�E���[���[�i1873�|1937�āj�B��ڂ͂Ȃ�Ɨ��������тƗ��������тƗ����O�i���сB1900�p����1904�Z���g���C�X�ŁA�������Ɨ������Ɨ����O�i�̃g���v���A1908�����h���ł͗����O�i���т����~�ƂȂ������߃_�u���B���v8�̋����_�����l�������B����ɁA�M���V�������Q�I���M�I�X�P���̒ɂ�����s��ꂽ1906�A�e�l���ԑ��ł��A��2���l���B���v10�́A�}�C�P���E�t�F���v�X�ɔj����܂ŁA�I�����s�b�N�ő������_���Ƃ��ăM�l�X�ŔF�肳��Ă����悤���B���݂ɁA1906���ԑ��́A���݁A�I�����s�b�N�̌����L�^���疕���B���������тƗ��������т�1912�X�g�b�N�z�����ȍ~�p�~�ƂȂ����B���̒��ɂ͖ʔ����L�^��������̂��B
�i2�j�Z�����T�����C4 ��_���̉���
 �@���I�E�I�����s�b�N��̃����_���Ȉ��݉�ŁA�u�ł����������u�Ԃ́H�v�Ƃ����b�ɂȂ����Ƃ��A�̑��c�́A�����q���̌l�����A�^�J�}�c�E�y�A�A�������A�x�C�J�[䝏H�ȂǂȂNj��̃P�[�X�����X�o�Ă������A����Ȓ��A�N���������ɂ����̂͗���j�q400m�����[�̋�_���������B���{��2008�k���œ����_�����l�����Ă��邪�A���̂Ƃ��͗\�I�ŋ����A�����J�ƃC�M���X�̎��i�������Ă̂��̂����������ɍ���̋�͐��{���l�������B
�@���I�E�I�����s�b�N��̃����_���Ȉ��݉�ŁA�u�ł����������u�Ԃ́H�v�Ƃ����b�ɂȂ����Ƃ��A�̑��c�́A�����q���̌l�����A�^�J�}�c�E�y�A�A�������A�x�C�J�[䝏H�ȂǂȂNj��̃P�[�X�����X�o�Ă������A����Ȓ��A�N���������ɂ����̂͗���j�q400m�����[�̋�_���������B���{��2008�k���œ����_�����l�����Ă��邪�A���̂Ƃ��͗\�I�ŋ����A�����J�ƃC�M���X�̎��i�������Ă̂��̂����������ɍ���̋�͐��{���l�������B�@����g���b�N�ł̋�_���́A1928�A���X�e���_���l�����]�i1907�|1931�j�̏��q800m�ȗ�88�N�Ԃ�B�����ʔ������ƂɁA���̋�_���A�l���ɂƂ��ď��̌��̂Ԃ����{�Ԃ������Ƃ����B���ӂ�100m�ŗ\�I�����������߁A���o����800m�ɋ}篃G���g���[�������́B��Ԃ炶��A��Ȃ��̎��O���B������ɂ��Ă�����ł͋N���蓾�Ȃ���Ղ��B
�@�l���͂܂��A���q����E�ɂ����āA���E�I�ȍv�������Ă���B�ߑ�I�����s�b�N�̑c�N�[�x���^���́A�u�X�|�[�c�͋R�m�����_�������߂���j���̍s�ׂ��B�������珗����q���Ȃǎア���̂��������˂Ȃ�Ȃ��v�Ǝ咣�A�I�����s�b�N�ɏ��q���㋣�Z��g�ݓ���邱�Ƃ����₵�Ă����B���ꂪ�A���̃N�[�x���^���̌��t�Ƃ͐M�����Ȃ����������A1920�N��͂܂������̎��̎��ゾ�����̂��B����Ȑ܁A1926�C�G�[�e�{���g���q�I�����s�b�N���h�ɓ��m���炽����l�o�ꂵ���l���́A100m��3�ʁA���蕝���тł͗D������ȂǁA���������D��������BIOC�́A���̐l���̃Z���Z�[�V���i���Ȋ�������āA1928�A���X�e���_���ŏ��q�����e�F�����̂ł���B
�@���{����E�ɂ����āA�I�����s�b�N�̃g���b�N���Z�ł̋����_���͂܂��Ȃ��B��_���͐l�����]�����A�j�q�͖��������B�Z�����T�����C4�������������j�q400m�����[�̋�_���́A������A�ƂĂ��Ȃ����l������B����ɁA37�b60�Ƃ����^�C���́A�ߋ�10���̗D���^�C���Ɣ�ׂĂ݂Ă��A5�ԖڂɈʒu���闧�h�Ȃ��̂��B
�@ ��1���ҎR�������i24�j�͔��Q�̃X�^�[�g�_�b�V���A��2���Ҕђ��đ��i25�j�̓g�b�v�E�X�s�[�h�����̔\�́A��3���ҋː��ˏG�i20�j�͍I�݂ȃR�[�i�����O�A�ŏI���҃P���u���b�W�i23�j�͏��ʂ𗎂Ƃ��ʂ��ԂƂ��A�e�X�̎��������\�ɔ������ă`�[���ɍv���B���Q�̃`�[�����[�N�������i�k�� ���̃A���J�[�����鎡���k�j�B�ނ�̒��ɁA�N��l9�b��͂��Ȃ��B�V�[�Y���E�x�X�g�Ō���ƁA���̃W���}�C�J�͑S��9�b��A���̃J�i�_��9�b���l�A3���Ȃ��玸�i�����A�����J���S��9�b��B���͂ł͈��|�I�ɗ����{���A�|���l�Ȃ���2���ɐH�����̂��B
�@4�l�̃V�[�Y���E�x�X�g�̒P�����v�^�C����40�b57������A�o�g���p�X�ɂ��2�b97���Z�k�����v�Z�ɂȂ�B���̓��{�̒Z�k���ƒZ�k���̓W���}�C�J�A�J�i�_�A�A�����J�����|���Ă���B����́A���h�Ŕ|�����Z�p�̒b�B�A���[�X���O�܂ŋl�߂��k���Ȍv�Z�A�����āA���E�ɒ��킷��ʊ��ȗE�C�B�O�ʈ�̂̎Y���������B2020�����Ƀ{���g�͂��Ȃ��B���̎�4�T�����C�̕��ϔN���27�A�Z�����������i�[�Ƃ��čł����̏���N��ɒB����B�X�̑��͂��グ�o�g���p�X�ɂ���ɖ�����������A���̋����_���������Ă���I�H
�i3�j�}���J�i���̊���`�u���W������ԕ�������
 �@���I�ܗ֊J�Í��u���W���͈��킸�ƒm�ꂽ�T�b�J�[�����ł���B���[���h�J�b�v�D��5��͐��E�ő��B����������������ʐ��ENo1�����Ȃ̂����A�u���W�������ɂ͖Y�ꕨ������B�����J�Ð��E���ł̗D�����B
�@���I�ܗ֊J�Í��u���W���͈��킸�ƒm�ꂽ�T�b�J�[�����ł���B���[���h�J�b�v�D��5��͐��E�ő��B����������������ʐ��ENo1�����Ȃ̂����A�u���W�������ɂ͖Y�ꕨ������B�����J�Ð��E���ł̗D�����B�@1950�N7��16���A��4��T�b�J�[�E���[���h�J�b�v �������[�O�ŏI��u���W���E���O�A�C�B�����J�Ẫu���W���͏��Ă��[���h�J�b�v���D���Ƃ������ԁB���͂��̓��̂��߂ɐV�K���������G�X�^�W�I�E�}���J�i���������B���ʂ�1�|2�̋t�]�����B����������ϏO�͗��_�����E�҂܂ŏo��呛���ƂȂ����B�ȗ��A���̏o�����́u�}���J�i���̔ߌ��v�Ƃ��ău���W�������̃g���E�}�ƂȂ����B
�@2014�N�A���̃g���E�}�𐰂炷�`�����X���K���B��20��FIFA���[���h�J�b�v �u���W�����ł���B�Ƃ��낪�A7��8���̏������Ńh�C�c�ɂP�|�V�Ƃ������J�I��s���i���Ă��܂��B�}���J�i���̔ߌ��ɑ����~�l�C�����̔ߌ��B�s���͐F�X��肴�����ꂽ���A�ő�̈��̓l�C�}�[���̕������ꂾ�����B
�@2016�N8��21�� ���I�ܗ֒j�q�T�b�J�[�����B�u���W���̑���͈����̃h�C�c�B���������̃}���J�i���������B����120�����߂��Ă�1�|1�̂܂܌����������A������PK��Ɏ������܂��B��U�̓h�C�c�B�o��4�l�ڂ܂ŃS�[���B�h�C�c��5�l�ڂ͓r���o��̃y�[�_�[�[���B������u���W���̃L�[�p�[ �E�F�x���g�����j�~�B�u���W����5�l�ڂ͍����L���v�e����S�����l�C�}�[���������B�R�����B�������B�u���W���̋������܂����B�}���J�i���͊���̉Q�B�l�C�}�[���͍����B�����ɂ͗l�X�Ȏv���������������Ƃ��낤�B�u���W����66�N�Ԃ̃g���E�}�𐰂炵���B���߂łƂ��l�C�}�[���I���߂łƂ��u���W���I�I ���I�ܗւ�ʂ��āA�u���W������ԕ������u�Ԃ������B
�@PK������Ȃ��牽��������������̂��������B�������������낤�Ǝv�����u�ԑM�����������B�������A����PK����g5�A���|�C���g�h����Ȃ����I ���{�Ɋ�Ղ��ĂыN������5�A�����A�u���W�������̔ߊ���悹�āA�Ō�̍Ō�A�}���J�i���Ɍ��ꂽ�̂��B���ꂼ�������J�̏I�H
�@17���Ԃ̍ՓT�͏I������B����s���A�����s���A�����̕s���A�e���̋��ЁA�u�a�̌��O�A�h�[�s���O��蓙�A�l�X�Ɏ�肴�����ꂽ���I�ܗւ��������A�Ȃ�Ƃ������Ƀt�B�i�[�����}���邱�Ƃ��ł����B���{�̓��_��41�i�������_��12�j�Ɖߋ��ō����L�^�����B�����ɂ͕s�f�̓w�͂ƕs���̐��_���������B�Ί�������܂��������B���A����炪���n���̂悤�ɔ]�����삯����B�I�菔�N ���������肪�Ƃ��I �I�����s�b�N���I����Đ��E�͂܂�����ɖ߂�B4�N�㓌���ܗւ�2020�N���A����菭���ł��悢���E�ł����Ăق����Ɗ肤�B
2016.09.07 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 3 �`�_���Ƌ��j ���ƌ|�����I�H
(1) �_���j�q�S�K�����_���̉����@�_���͓��{�̂��ƌ|�ł���B����͓��{�Ŏn�܂����X�|�[�c�ł���A�I�����s�b�N�̐������Z�ɍ̗p���ꂽ�̂�1964���������瓖�R���낤�B����ɗ��j������A�_���ƃI�����s�b�N�Ƃ̐[���Ȃ��肪�킩���Ă���B
 �@�_���̊J�c�͉Ô[���ܘY�i1860�|1938�j�B�w������A�D�G�Ȑ��т����߂���A�̊i�n��̂��ߑ��̐��k���炽�т��і\�s�����B���Ō��������߂ł���B�����Ȃ��Ĕނ�����Ԃ��Ă��A�Ƃ̎v���Ō˂�@�����̂��_�p�̓��ꂾ�����B�����O�̌����S�ł߂��߂��Ə�B�A�̂��拭�ɂȂ��Ă���B����͂܂��A�z������������A�ނ����������̂́A�ᛎ����̐��i������ɗ��������A�����S�������Ȃ��Ă������Ƃ������B�C�s�ɂ���āA�v�����������_�̈��肪����ꂽ�B���������I �_�p�ɂ͐l�����߂�͂�����A�ƌ�����̂ł���B
�@�_���̊J�c�͉Ô[���ܘY�i1860�|1938�j�B�w������A�D�G�Ȑ��т����߂���A�̊i�n��̂��ߑ��̐��k���炽�т��і\�s�����B���Ō��������߂ł���B�����Ȃ��Ĕނ�����Ԃ��Ă��A�Ƃ̎v���Ō˂�@�����̂��_�p�̓��ꂾ�����B�����O�̌����S�ł߂��߂��Ə�B�A�̂��拭�ɂȂ��Ă���B����͂܂��A�z������������A�ނ����������̂́A�ᛎ����̐��i������ɗ��������A�����S�������Ȃ��Ă������Ƃ������B�C�s�ɂ���āA�v�����������_�̈��肪����ꂽ�B���������I �_�p�ɂ͐l�����߂�͂�����A�ƌ�����̂ł���B�@���t�ɂȂ������ܘY�͐��k�����ɏ_�p�������悤�Ǝ��݂��B�Ƃ��낪�܂Ƃ��Ȏw�쏑���Ȃ��B�{���_�p�͎��H�I��g�p������A�Z�𑼐l�ɒm��ꂽ���Ȃ��A���I�Ȃ��́B�w�쏑���Ȃ��͓̂��R�������B�����Ŏ��ܘY�͎����邱�Ƃɂ����B���̋Z�́A���_�I�ɑg�ݗ��Ă�B�������ĒN�ł��K���\�ȃ}�j���A�������グ���B�����E���Z��������J���E�������ւ̈ڍs�B����ߑ�I���v�ł���B�����ɁA�����鑤�ɂ��������鑤�ɂ��J���ꂽ�_�p���u�_���v���a�������B���y�̂��߂̖{���n�u�u���فv�̐ݗ���1882�N�B���̂Ƃ�9����������u�҂�1926�N�ɂ�37,000�l�ɖc��オ�����B�����āA���݁A���E�̏_���l����150���l���A���I�ܗւɎQ����������138�����𐔂���قǂɂȂ����B
�@1909�N�̂�����A�Ô[�̂��ƂɁA�ߑ�I�����s�b�N�̑n�n�҃N�[�x���^������A��������BIOC���ۃI�����s�b�N�ψ��A�C�̗v���������B�����A�I�����s�b�N�ɂ͖����A�W�A����̎Q���͂Ȃ������B�N�[�x���^���̓X�|�[�c�w���҂ɂ��ċ���҂̉Ô[�ɂ��̔C��������̂ł���B�Ô[�͑������A��1911�N�ɂ͑���{�̈狦���ݗ��B�����āA1912�X�g�b�N�z�����ܗ֎Q�������������B�����ɂ́A�g�����Ƃ�����Ȃ��̂�����h�Ƃ����N�[�x���^���ƉÔ[�̃X�|�[�c�ɑ��闝�O�̍��v���������B�Ô[���ܘY���_���̕��ł�����{�̈�̕��ƌ�����R���������ɂ���B
 �@���I�ܗւœ��{�_���͒j�q���S�V�K�����_���i����2�j�l�������������B�����1964�����ȗ�52�N�Ԃ�̉����ł���B�Ƃ͂���������4�K�����������獡��̉��l�͑傫���B���J�҂͑��ɑI�肾���A�ēE���N���̗͂�����ɏ���Ƃ����Ȃ����̂�����B
�@���I�ܗւœ��{�_���͒j�q���S�V�K�����_���i����2�j�l�������������B�����1964�����ȗ�52�N�Ԃ�̉����ł���B�Ƃ͂���������4�K�����������獡��̉��l�͑傫���B���J�҂͑��ɑI�肾���A�ēE���N���̗͂�����ɏ���Ƃ����Ȃ����̂�����B�@���M��̐����œ��ʃR�[�`�̖�����S�������́A�w���̐��ɏ��Ȃ��炸�^��������Ă����B�ړI�ӎ��̔������h�A���_�_�d���̎w���A�B���ȒS�����Ȃǂł���B���́A2012�����h���Œj�q�����_��0�Ƃ����j�㏉�̋��J�̐ӔC������Ď��C�������̌���A34�Ƃ����Ⴓ�ŊēɏA�C�B���˂Ă��猜�Ă̈琬�̐��̉��v�ɓ��ݐ����B�S���R�[�`���̓����ɂ��I��X�̓����ɍ��킹���R�[�`���O�B�������e�m���������h�̎��{�B��������ȋ����_�������`����̒E��B�f�[�^���͂ɂ�鐔���I�v�f�̗��t���B�ȂǂȂǁA���_�Ώd��`���獇����`�ւ̈ڍs���s���B���Ƃ����āA���_�����Ȃ�����ɂ����킯�ł͂Ȃ��A��\�̌ւ�������Ƃ�i����������������B
�@73�s���ŋ����_���ɋP������쏫���́A���|�I���i���Ō����ɐi�ށB�����ł��A�����������݂ɂ���{�����Ƃ��������̋��������������B��オ���������u���͋����_���ɍł��߂��j�v�ƌ��������Ă����ʂ�ƂȂ����B�u�v���b�V���[�ɂȂ�܂��H�v�Ƃ����L�Ғc�̎���ɁA���́u�ނ͂�����G�l���M�[�ɂ���^�C�v�B�����犸���Ă��������v�Ɠ������B�I��̓��������������Ή��B������u�悭�ς����ȁv�ƃt�H���[���Y��Ă��Ȃ��B
�@90�s�������_���̃x�C�J�[䝏H�̌�����͑ΏƓI�������B2��17�b�ŗL����D���ƁA��������U�߂��T���������}��B2�x�̎w�����邪���_����ۂ��ď����B90�s�����̋����_���Ƃ��������𐬂��������B
�@�����_�������߂���l�̌����̐킢�Ԃ�͑ΏƓI�������B�����̈�{�Ƌ͍��̓�����B����ł��������͋����B���̏_������A���N���̐��̏ے��ł͂Ȃ����B
�@�����_����4�l�A60�s�����������A66�s���C�V�����A81�s���i���M�K�A100�s���H�ꗴ�V��́A�����ă��_�����l�ꂽ���Ƃ̊�т����ɂ����B����ڎw�����A�~�ޖ���3�ʌ����ɉ�������̐�ւ����A�݂�Ȃ���Ă̂����̂��B100�s��������v��̋�_�����A�������}�鐢�E���҂Ɋ��R�Ɨ����������������������h�ȃ��_���������B
�@�������|�[�J�[�t�F�C�X���т��ʂ�����ゾ���A���ׂĂ��I�������A���ɂ܂��Ă����������u�Ō�܂ł�����߂��ɐ킢�����A�݂�ȂŃo�g�����Ȃ��Ă��ꂽ�B���_���X�g7�l�͗��j�ɖ������B�ւ�Ɏv���v�ƁB
�@���́A2000�V�h�j�[100�s���ŃI�[����{�����ŋ����_�����l��������A2004�A�e�l�ł̓��_���Ȃ��̋�`���r�߂��B�V���ƒn���𖡂�����j�̉��v�������B����́A���āA�Ô[���ܘY���_�p���_���ւƕϊv�������_�Ƒ��ʂ�����̂�����B����Ȏv����������Ă��ꂽ���ƌ|�_���̕����������B
(2) ���j���{�̕����́H
�@���{���j�A���̃I�����s�b�N��\�I��̑I�l��́A�u�h���W���L�^��˔j�����I�l��̏��2����I�o����v�ƂȂ��Ă���A���m���E�������ɂ����Ă��Ȃ�[���䂭���̂�����B�����2001�N�A�O�N�̃V�h�j�[�ܗ֑I�l�������ċN��������t�������܂��A���{�I���v���s�������ʂ��B�I�苭����Ɋւ��Ă��A���ēƌʃR�[�`�A���A�Ɗ֘A�c�̂Ƃ̘A�g���~���ɋ@�\����悤�ɂȂ����B�_���ɐ�邱��15�N�A���ʂ̓��_���l�����ɗ�R�ƌ���Ă���B���v�ȑO��3���i�V�h�j�[�A�A�g�����^�A�o���Z���i�j��6�i����1�j�Ȃ̂ɑ��A�Ȍ��3���i�A�e�l�A�k���A�����h���j�ł�24�i����5�j�ƁA�啝�ɑ����Ă���̂��B
 �@���I�ܗւ̃��_����1���͔������̋��j�j�q400m�l���h���[�̋��B���������ˑ��i���j�Ƃ�W�\���䂾�����B���j��W�\����́A1956�����{�����ȗ�60�N�Ԃ�Ƃ������܂��t���������B
�@���I�ܗւ̃��_����1���͔������̋��j�j�q400m�l���h���[�̋��B���������ˑ��i���j�Ƃ�W�\���䂾�����B���j��W�\����́A1956�����{�����ȗ�60�N�Ԃ�Ƃ������܂��t���������B�@�����{������W�\�����200m���j���B�����Ð쏟�A�₪�g�����O�������B�����{����1956�����䂪�I�����s�b�N���N�ŁA�������w������������ꡂ��씼�����瑗���Ă��郉�W�I�̎��������ɕ������������̂��B�ł����������̂�17�̍��Z���R���B�̊������B���j�j�q400m��1500m���R�`�B�I�[�X�g�����A�̃}���[�E���[�Y�Ƃ̈�R�ł��B���ʂ͗���ڂƂ��₾�������A���̃f�b�h�q�[�g�Ɋ����������̂��B�I�����s�b�N�㑁��c��w�ɐi�w�����R���́A200m��400m�Ő��E�V�L�^�������A1960���[�}�ł�400m��800m�����[�ŋ�_�����l���B1964�����I�����s�b�N�ɂ��o�ꂵ�Ă���B�ł����ӂƂ����̂�200m�����A�ɂ��܂��̂́A�����I�����s�b�N��ڂɂȂ��������ƁB���������̂�1968���L�V�R�V�e�B����ł���B
 �@���I�ܗւ�����̋��j�����_���́A���q200m���j���̋������G�B�V���̌��o���́u���� �R�[�`�M�����v�������B�R�[�`�̖��͉������u�B��l�Ő�����������10�N�Ԃ��������̂ł���B�ܗ֏��o���2008�k����7�ʁB�Ƃ��낪2012�����h���͏o����Ă��܂��B�����́A�L���X�C�~���O�E�N���u�̏o�g�ł��Ȃ��A���ۑ��ł̗D���o�����[���B����ȎG���̂悤�ȑI��̍˔\�ɍ��ꍞ�R�[�`�����_��ڎw���Ĉ�������B�����̐S���ɋ��C�Ǝ�C���������^�S�ËS��������������B�u�����_���Ȃ�Ȃ����v�B�R�[�`�͂�����ە��B10�N�͂���Ȋ����̘A�����������Ƃ��낤�B����Ȏt��ɃI�����s�b�N�̐_�l���Ō�ɂقُ̂ł���B�M�������邱�Ƃ̑���������Ă��ꂽ�����_���������B
�@���I�ܗւ�����̋��j�����_���́A���q200m���j���̋������G�B�V���̌��o���́u���� �R�[�`�M�����v�������B�R�[�`�̖��͉������u�B��l�Ő�����������10�N�Ԃ��������̂ł���B�ܗ֏��o���2008�k����7�ʁB�Ƃ��낪2012�����h���͏o����Ă��܂��B�����́A�L���X�C�~���O�E�N���u�̏o�g�ł��Ȃ��A���ۑ��ł̗D���o�����[���B����ȎG���̂悤�ȑI��̍˔\�ɍ��ꍞ�R�[�`�����_��ڎw���Ĉ�������B�����̐S���ɋ��C�Ǝ�C���������^�S�ËS��������������B�u�����_���Ȃ�Ȃ����v�B�R�[�`�͂�����ە��B10�N�͂���Ȋ����̘A�����������Ƃ��낤�B����Ȏt��ɃI�����s�b�N�̐_�l���Ō�ɂقُ̂ł���B�M�������邱�Ƃ̑���������Ă��ꂽ�����_���������B�@���q���j��200m�̋����_���͓��{�j��3�ځB��O��1992�o���Z���i�̊�英�q�B�u���܂Ő����Ă������ň�ԍK���ł��v�����j�I�R�����g�Ƃ��Ďc��B���̑O��1936�x�������̑O���G�q�B������́ANHK�A�i�E���T�[�͐��O�ȁi1898�|1970�j�́u�O���K���o���v�̃A�i�E���X�����j�Ɏc��B���������I��̖��O�ƃK���o���̘A�āB���̃V���v�������l�����Y�t�����B�����������A�I�����s�b�N�����̍ō���́A2004�A�e�l�̑��j�q�c�̂ł�NHK�����x�m�Y�A�i�E���T�[��u���đ��ɂȂ��B
�@�ߊ�̒j�q�c�̋����_���܂ł��ƈ�l�A�y�c�m�V�̓S�_�̉��Z���c���̂݁B�y�c�����i�ʂ�̉��Z������Γ��{��28�N�Ԃ�̋����_���������炳���Ƃ����ŁA���̃A�i�E���X�͐��܂ꂽ�B
�@�u�y�c���y�c�ł��邱�Ƃ��ؖ�����Γ��{�͏����܂��E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�L�g�̐V���ʂ��`���������� �h���ւ̉˂������I�I�v�B�����̏I�~�͕y�c�̒��n�ɐ����̋������Ȃ����v�����B�O�U��ŁA���ꂩ��n�܂鉉�Z�̈Ӗ������Ɠ��{�`�[�����u����Ă�����Ȍ��ɕ\���B���݂̂Ȃ��y�c�̉��Z���D�����m�M�����闬��̒��A�䂸�̌ܗփe�[�}�E�\���O�w�h���̉ˋ��x�������N�����ăs�^���ƌ��߂��B�����x�m�Y�A�ꐢ���̖����q�������B
�@���{���j�`�[�������I�ܗւŊl���������_����7�i����2�j�B���݂ɃA�����J��33�i����16�j�B���̑卷���t�]����͖̂�����ł���A�ǂ��ۛ��ڂɌ��Ă����ƌ|�ƌĂԂɂ͋C��������B���������̐́A1930�N��ɁA���ƌ|�Ƃ���ꂽ���オ�������B1932���T���[���X�͋����_��5�A��5�A��2�̍��v12�ő�1�ʁB���̂Ƃ�2�ʂ̃A�����J��10�i����5�j�B����1936�x������������4�A��2�A��5�̍��v11�Ńg�b�v�B2�ʂ̃I�����_��5�i����4�j�B���j���{�̉�������ł���B�����āA1940�N��12����͓������J�Òn�ƌ��܂�B����Ȓ��A���{�͐푈�ւ̓����܂�������ɐi��ł����B1939�N�A�h�C�c���|�[�����h�ɐN�U���A��2�����E���̖������ė��Ƃ����B���E��̈����ɁA�I�����s�b�N�������͒��~��]�V�Ȃ����ꂽ�B���E�̎�҂��X�|�[�c�ŋ��������͂��������������Z��́A�w�k�o�w�s�s��̉��Ɏ���đ����Ă��܂��B1943�N10��21���̂��Ƃ������B
�@���j ���ƌ|�����ցB���͔������B�ނɂ̓}�C�P���E�t�F���v�X�Ƃ����������{������B2000�V�h�j�[����2016���I�܂�5���ɏo��B23�̋����_�����l��������O���̃X�[�p�[�E�X�C�}�[�ł���B���̓r�����Ȃ��L�^�͗]�l�̋y�ԂƂ���ł͂Ȃ����A�����ł��߂Â��w�͂͂��ׂ����낤�B�t�F���v�X�́A���o��̃V�h�j�[�ł́A���_���Ȃ��ɏI����Ă���B����̍ŏ��̃I�����s�b�N�͓����_���l���������B�撣��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�I�H
�@���q�͒r�]���Ԏq���낤�B���I�ܗւł�7��ڂɏo��B���_���������Ȃ��������A���ӂ�100���o�^�t���C�ł͓��{�V�L�^��5�ʓ��܂��ʂ������B�܂�16�B����̐����Ɋ��҂������B
�@�������ƌ|�������ʂ������_���Ƃ܂��܂��r��̋��j�B�ʂ����āA2020�����ł́A�ǂ�ȃp�t�H�[�}���X�������Ă����̂��낤���B������4�N�オ�y���݂łȂ�Ȃ��B
2016.08.31 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 2 �`���P�b�g���Z ��Ղ�5�A���|�C���g
�@8��21���̒����V���Ɂu�^�J�}�c��5�_�v�Ƃ������o�����������B�o�h�~���g�����q�_�u���X�ō��������F�y�A�������_�������߂��u5�A���|�C���g�v�̂��Ƃ��B��������āA�u5�_���B���ɂ��������悤�ȁE�E�E�E�E�v�����������Ē��ׂĂ݂��B����́u5�_�v���e�[�}�Ƀ��P�b�g���Z����z���Ă݂����B(1) �ѐD�\�̏ꍇ�F96�N�Ԃ�̓����_��
 �@���E�����N7�ʂŗՂe�j�X�ѐD�\�̓����_���l���͌����������B3�ʌ������悩�������A���͏��X�����̃K�G���E�����t�B�[�X�i��11�ʁj��̕��ɂ�苭���������o�����B
�@���E�����N7�ʂŗՂe�j�X�ѐD�\�̓����_���l���͌����������B3�ʌ������悩�������A���͏��X�����̃K�G���E�����t�B�[�X�i��11�ʁj��̕��ɂ�苭���������o�����B�@�Z�b�g�E�J�E���g1�|1�A�����̑�3�Z�b�g�̓^�C�u���[�N�ւƂ��ꍞ�ށB3�|4���瑊��ɓ�{�̃T�[�r�X�E�G�[�X�����߂���3�|6�ƃ}�b�`�|�C���g�������B1�|�C���g���ꂽ�u�ԃ����h���Ɠ����x�X�g8�~�܂�A���_���̉\���͂O�B�܂��ɐ�̐▽�̊R���Ղ��ł���B�Ƃ��낪�ѐD�͂������玝���O�̔S�苭��������B����܂ŕs���肾�����t�@�[�X�g�E�T�[�r�X��2�{���đ����ɓ���5�|6�B���㑊���W�t�H�[���g���o�āA����6�|6�ŕ��ԁB�����Ȃ�Ɨ���͋ѐD���B�ł��Ȃ������肩��2�|�C���g��A��A8�|6�Ƌt�]�A�����𐧂����B�܂��Ɏ��O��5�A���|�C���g�������B�킢�I�����R�[�g�E�T�C�h�ŕ��i�ő��ɋ����Ȃ��ѐD�������Ă����B�����ɋꂵ���������̏ł���B���݂ɁA�t���Z�b�g��あꂽ�Ƃ��̏���78���́A���̃W���R�r�b�`������������1�ʂł���B
�@�������Ń����N2�ʂ̃}���[�ɔs�ꂽ�ѐD�͓����_����������3�ʌ����ɗՂށB����͌����E�����N1�ʂɂ���2008�k���ܗւ̋����_���X�g ���t�@�G���E�i�_���i�X�y�C�� 5�ʁj�B�ΐ퐬�т͉ߋ�1��9�s�B��G�ɋѐD�͓��X�Ɨ������������B�Z�b�g�E�J�E���g1�|1�A�ŏI��3�Z�b�g���O�ɂ�����Ƃ����n�v�j���O���B�݂��̃g�C���b�g�E�u���[�N�ŁA�ѐD���Ȃ�ƃi�_����7���Ԃ��҂������̂ł���B������A���ȗ���ő�2�Z�b�g���������C���]���H ���Ƃ���{�{�����̐�@�H ��Ŕ��������Ƃ����A�����҂��������̃g�C���Ɉē������Ƃ����P���~�X�������悤���B���̂��߂Ȃ̂��ǂ��Ȃ̂��A��3�Z�b�g�͏I�n�ѐD�y�[�X�Ői�݁A�����B�O��̃��_�����l�������B���{�e�j�X�E96�N�Ԃ�̃��_���������B�u���{��w�����ď��̂͐S�n�悩�����v�B�ѐD������̃R�����g�ł���B���E�̃j�V�R��������w�����Ċ撣���Ă����̂��B
�@96�N�O�A1920�A���g���[�v�ܗւŁA���{�̌F�J���(1890�|1968)�̓e�j�X�E�j�q�V���O���X�ƃ_�u���X�i��������Y�ƃy�A�j�ŋ�_�����l�����Ă���B���ꂱ�����䂪���I�����s�b�N�̃��_����1���ł���B���̌�e�j�X���Z�́A1924�p���̂���60�N�ȏ���̊ԃI�����s�b�N����p���������ƂɂȂ�B���R�́A�����Ƀv���^�A�}�̃I�[�v������i�߂����ۃe�j�X�A���Ɓu�A�}�`���A���́v��������������IOC�Ƃ̐܂荇���������B���������̂�1988�\�E���B��7��IOC��T�}�����`�����f�����u�A�}�`���A���́v�����̌��ʂ��B
�@����͂܂��A�ʂ̘b�����A�A���g���[�v�ܗ� ����j�q1500m�̋�_���X�g �t�B���b�v�E�m�G�����x�[�J�[(�p1889�|1982)�́A1959�N�A�m�[�x�����a�܂���܂����B�I�����s�b�N�̃��_���X�g�Ńm�[�x���܂���܂����҂͌�ɂ���ɂ��ނ����ł���B
(2)���J���Ɛΐ�����̏ꍇ�F�싅 �����Ɍ�����
 �@�싅�̊�����ڊo�܂��������B�j�q�́A�c�̂ŋ�A�V���O���X�Ő��J�������B���q�͒c�̂œ��B�A���̔M���킢�ɗ͕��������A���ł��A���M���ׂ��͐��E�����N6�ʐ��J�̊��낤�B
�@�싅�̊�����ڊo�܂��������B�j�q�́A�c�̂ŋ�A�V���O���X�Ő��J�������B���q�͒c�̂œ��B�A���̔M���킢�ɗ͕��������A���ł��A���M���ׂ��͐��E�����N6�ʐ��J�̊��낤�B�@�l�V���O���X�������̑���͐��E�����N1�ʂ̒����n���A���J12��S�s���̐��E���҂ł���B�n����3�Q�[����A�悷�邪�A���J��2�Q�[����A��B���ꂪ���J�ɌX�����鏟���̑�6�Q�[���B1�|2�Ɛ��J�r�n�C���h��̃|�C���g�A�n���T�[�u�̏�ʁB�Ȃ�Ƃ�����27�����[�̎������J��L����ꂽ�̂ł���B������͔̂n���B���̗�Ò����Ȑ��E���҂��v��������̗Y���т��グ���B�����ɑ厖�ȃ|�C���g���������̏ł���B�����ڂɔn�����I�n���[�h��ۂ����̃Q�[�������̂ɂ���B�Q�[���E�J�E���g4�|2 �̐ɔs�B�����㐅�J�́u���߂ď��Ă邩������Ȃ��Ǝv�����v�ƌ�����B����ɂ́u�����╉���邩������Ȃ��v�Ǝv�킹�����Ƃ��낤�B���J�͊m���ɐ��E���҂�ǂ��l�߂��B�ނ͂��̂���3�ʌ����ɗՂ݁A�h�C�c�̃T���\�m�t��j���ē����_�����l���B���{�싅�j�㏉�̃I�����s�b�N�l���_���X�g�ƂȂ����B
�@�c�̐�͏��q�̋w�h�C�c��j���Č����ɐi�o�B����͖��_���Ғ����B�����O�A���J�́u�l���S�����Ă����_�����l���v�ƌ���Ă����B�����̏[���Ԃ肪�`����䎌�ł���B
�@��1�����𗎂Ƃ��A������Ή��肪���������2�����ɓo��B����͌����E�����N1�ʌ�3�ʂ̋��ρB�������12��S�s���̋����������B
�@�c�̐��3�Q�[���������B�Q�[���E�J�E���g2�|2�̍ŏI��5�Q�[���B���J��7�|10�ƃ}�b�`�|�C���g�������Ă��܂��B�i�㑊���3�|�C���g���B��̐▽�̃s���`�B���������J�A����͈���Ă����B�Ȃ�Ƃ������狭�C�ɑł��܂���5�A���|�C���g��������B12�|10�Ƒ�t�]�B���������߂��B����ŁA�c�̐��1�|1�̃^�C�Ɏ��������A���̌�A�_�u���X�A�V���O���X�Ɨ��Ƃ��A���Ғ����̉��͕����Ȃ������B��_���B������P���j�q�j�㏉�ł���B
�@���J�͐��E�����N3�ʂɏ����A1�ʂ�ǂ��l�߂��B�����̏[���Ԃ�͐����̈��ł���B����U��Ԃ�u�싅�l���ň�Ԃ̏[�����B���I�͂��̓r�ゾ�v�Əq�������B�܂��܂��L�т�I���Ƃ��������������ł͂Ȃ����B
�@�]�k�����A�J�Ԑ��J�̉H�c�z�掗���b��ɂȂ����B���̉H�c�z�悶��u�I�C�I�C�I�C�v�ƂȂ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��Ƃ���B�ł��ނ̓}�X�R�~�̖₢�����ɂ����R�ƑΉ�����B�啨�ł���B�܂��ނ́u�u�[�X�^�[���v����������B�u�[�X�^�[�Ƃ́A���P�b�g�̃��o�[�ɓ\��ƃX�s���ʂ������З͂����傷��⏕�܂̂��ƁB���ۑ싅�A�����֎~�����@��܂����A�����̐����s���̂��߁A�������ԂƂȂ��Ă���B���J�͗E�C�������Ă��̌����i�������Ă���B�싅�E�̌��S�Ȕ��W�̂��߂ɁB�ނ̑싅�ɑ���^���Ȏp�����̎^�������B
 �@���q�͒c�̐�œ����_���B�������h�C�c��ŏ��Ă鎎���𗎂Ƃ��������肻���ɂȂ��Ă����O�l�����悭�撣�����B�����ėՂ�3�ʌ����͓���B�Z���Ԃł̋C�����̐�ւ��������̂��B�����́A�S���Z��ʂ����{��3�ʌ����̏��������������Ɗ����邪�ǂ����낤�B���̐́A�{�ԂɎア�ƌ���ꑱ�������{�I��B���̎�҂͎��ɗ��������B
�@���q�͒c�̐�œ����_���B�������h�C�c��ŏ��Ă鎎���𗎂Ƃ��������肻���ɂȂ��Ă����O�l�����悭�撣�����B�����ėՂ�3�ʌ����͓���B�Z���Ԃł̋C�����̐�ւ��������̂��B�����́A�S���Z��ʂ����{��3�ʌ����̏��������������Ɗ����邪�ǂ����낤�B���̐́A�{�ԂɎア�ƌ���ꑱ�������{�I��B���̎�҂͎��ɗ��������B�@���q�c��3�ʌ����̑���̓V���K�|�[���B�g�b�v�E�o�b�^�[������(���E�����N8��)���ڐ�̖��s���Ƃ�����������̒��A��Ԏ�ɓo�ꂵ���̂̓G�[�X�ΐ����(6��)�������B�ΐ�́A������ƂȂ�V���O���X1���Ŕs�ނƂ����A�ň��̃X�^�[�g����Ă��܂��Ă����B�������A�c�̐�ł͌����ɗ�������A�����܂Ŗ��s�Ƃ��̐ӔC���\���ɉʂ����Ă���B����̃t�F���E�e�B�A���E�F�C�i4�ʁj�̓V���K�|�[���̃G�[�X�B2012�����h�����Őΐ�̓����_����j�����̑��肾�B
�@�����J�n�A�ΐ�̏o���͍ň��B����̗h���Ԃ�ɑS���Ή��ł����A����3�|7�ƃ��[�h�����B���̌��⎝���������A����7�|10�ƃQ�[���E�|�C���g�������Ă��܂��B�����Ŕޏ��͊J���������B�v����̂悢�V���b�g���h��A���X�ɗ�҉�B�Ȃ��5�A���|�C���g��12�|10�Ƒ�t�]�B��1�Q�[�������̂ɂ����B�Ȍ�����ł��A�邱�ƂȂ���������|�B�厖�Ȏ��������̂ɂ��ă^�C�ɖ߂����B�����h���̃��x���W���ʂ������̂ł���B
�@�����_�u���X�ł͕������ɓ��̔N�̍��R���r�������B���̃V���O���X�́A�ɓ������i9�ʁj���X�g���[�g�ŏ����A���{�͓����_�����l�������B�u��y��������Ԃ�ŕԂ��Ȃ��v�Ə킹����������15�̌��s��v�������B
�@�ɓ��̊�������邱�ƂȂ���A�c�̐퓺���_���̗����҂͐ΐ삾�낤�B�o��S�����Ŕ����B3�ʌ���������������𗎂Ƃ����ȗ����f�������B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�����ɂ�5�A���|�C���g���������̂ł���B������L���v�e���i�̕����́u�������������Ă���ł����B�݂�ȂɊ��ӂ��Ă��܂��B�ꂵ���ꂵ���I�����s�b�N�ł����v�Ƌ������Ⴍ��Ȃ���b�����B
�@�C�����̗D�����������炵���R�����g�����A�p���邱�Ƃ͂Ȃ��B�ΐ�̃V���O���X���핉���Ƃ���������@�����̂́A���Ȃ��̃V���O���X �x�X�g�S�i�o�̊撣�肾�����B����������������Ȃ��`�[���������܂ň��������Ă��ꂽ�̂�����B���_��������ƂȂ��ł͑�Ⴂ�B����Ԃł悭���������Ă��ꂽ�B�싅�O�l���ɓV����ł���B
�@�싅���I�����s�b�N�̐������Z�ƂȂ����̂�1988�\�E������ŁA�j���V���O���X�ƃ_�u���X��4��ځB2008�k������j���c�̂���������B��r�I�ŋ߂̂��Ƃł���B����܂ŋ����_���͂قڒ������Ɛ�B���{�̖ڕW���A�œ|�����ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���́A�j�q�͐��J�A���q�͈ɓ����낤�B���J�͍����Ő��E�����N3�ʂ�|��1�ʂ�ǂ��l�߂��B���ƈ���ł���B�c�̐�𐧂���ɂ͐��J����������l�ق����B�ɓ��͂܂�15�B����܂��܂������Ȃ�B�ޏ��̋Z�p�ƃ����^���̋����͍����݂��łɈꋉ�i�ł���B�����ɂ͕�����F�n�ߗL�]�Ȏ�肪�����ƕ����B���q������炪�����Ɉ�ĂA�œ|���������ł͂Ȃ��B4�N��̓����I�����s�b�N���y���݂ł���B
(3)�^�J�}�c�E�y�A�̏ꍇ�F�h���̋����_����
 �@�o�h�~���g�����q�_�u���X���{��\�́A������Ə��F�����I�̃^�J�}�c�E�y�A�B�R���r��g��łP0�N�A�O���h���ܗւł̓t�W�J�L�E�y�A�ɑ�\��������A�����͐��E�����N1�ʁA���X�̋����_�����Ƃ��ă��I�ɏ�荞�B�����ɏ����i������ɗՂށB����̓y�f���Z�������^�[���q���̃f���}�[�N�E�y�A�i6�ʁj�B�������ł͗D�����̈�p�������̒����y�A�i2�ʁj��j���Ă���B�ʎZ�ΐ퐬�т̓^�J�}�c�E�y�A��7��4�s�B�����I�D�ʂ͂�����̂́A�g���������i��l�Ƃ�180cm�O��j����l�̓T�E�X�|�[�A�����N2�ʂ�j���������ȂǁA��G�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B����ɁA�^�J�}�c�E�y�A�͒����y�A��z�肵�Ă����悤�ŁA���̑z��O�Ƃ����̂͏�ʑI��ɂƂ��ď��Ȃ��炸�s����������̂Ȃ̂��B���X�����O�g�c�̔s���ɂ����ꂪ���������낤�B
�@�o�h�~���g�����q�_�u���X���{��\�́A������Ə��F�����I�̃^�J�}�c�E�y�A�B�R���r��g��łP0�N�A�O���h���ܗւł̓t�W�J�L�E�y�A�ɑ�\��������A�����͐��E�����N1�ʁA���X�̋����_�����Ƃ��ă��I�ɏ�荞�B�����ɏ����i������ɗՂށB����̓y�f���Z�������^�[���q���̃f���}�[�N�E�y�A�i6�ʁj�B�������ł͗D�����̈�p�������̒����y�A�i2�ʁj��j���Ă���B�ʎZ�ΐ퐬�т̓^�J�}�c�E�y�A��7��4�s�B�����I�D�ʂ͂�����̂́A�g���������i��l�Ƃ�180cm�O��j����l�̓T�E�X�|�[�A�����N2�ʂ�j���������ȂǁA��G�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B����ɁA�^�J�}�c�E�y�A�͒����y�A��z�肵�Ă����悤�ŁA���̑z��O�Ƃ����̂͏�ʑI��ɂƂ��ď��Ȃ��炸�s����������̂Ȃ̂��B���X�����O�g�c�̔s���ɂ����ꂪ���������낤�B�@�������n�܂�B�s���͓I�������B���V�[�u�͂��v���̂ق����サ�Ă����f���}�[�N�E�y�A�Ɍ˘f�������A�T�[�u�E�R���g���[���������B�Â�������������B�{���̃y�[�X��͂ݐ�Ȃ��܂ܑ�1�Q�[���𗎂Ƃ����B���I�ɗ��Ă��珉�߂ẴP�[�X�������B��2�Q�[���͒n�͂����ĒD��B�^�C�Ɏ������ނ��A�s�C���Ȃ̂́A����y�A���A�_�����J�����㔼�A���Q�[���ɔ����X�^�~�i������}���Ă���悤�Ɍ��������Ƃł���B
�@�ŏI�Q�[���B��������������_���B�������ӂ�f���}�[�N�E�y�A�̋t�P�ɁA�^�J�}�c�͂�������q���o�Ȃ��B���ȃ��[�h�̂܂܃Q�[���͏I�ՂցB�C���t����16�|19�A����1�_�Ń}�b�`�|�C���g�Ƃ������n�ɗ�������Ă����B�u����������ʂɂȂ����玄�����̕��������ƐM�����v������̍����̃R�����g�ʂ�A�����œ�l�͑h��B
�@���F���E��O�ɃJ�b�g����17�|19�B����������̗��������N���X�E�{���[������18�|19�B���F���C�̋��ł�19�|19�B�����̑_�����܂����{���[��20�|19�t����B�����̃R���g���[���E�{���[�肪�l�b�g�Ɉ����|��21�|19�B�������I ���ɂ�5�A���|�C���g�B�����̋��łƊɋ}�A���F�̑M���Ǝv����A��l�̐▭�ȃR���r�l�[�V�������ԊJ����3���Ԃ������B�����āA���{�o�h�~���g���E���҂��ɑ҂��������_���B�����̐V���ɂ́u�^�J�}�c��5�_�v�Ƃ������o����������B
�@�ѐD�A���J�A�ΐ�A�^�J�}�c�B�ނ�̃��I�ܗւɂ́A�y�d��ł��u5�A���|�C���g�v���������B��������Ԃ��ꏊ���Ⴄ�ނ�̃Q�[���̒��ɁA���ʂ���5�|�C���g���������B�ѐD�̗��j���ĂыN������5�|�C���g�B���J�̉��҂̈�p�������5�|�C���g�B�ΐ�̃`�[�����~����5�|�C���g�B�^�J�}�c�̉h���ɘA�Ȃ�5�|�C���g�B���ׂẮA1�_�����Ȃ���̐▽�̏�ʂŏo�������B�����ɂ́A������M���錈���Ă�����߂Ȃ��C�������������B���R�̈�v�ƌ�������܂ł����A�����܂ő����Ɖ������������ɂ͂����Ȃ��B���炩�̕����B����͂�����A�I�����s�b�N�̐_�l���A����������ʂ̂��߂ɂ���܂ʐ��i��ςݏd�˂Ă����A�X���[�g�����ɑ������A��Ղ̃v���[���g�������̂ł͂Ȃ����낤���B
2016.08.25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 1 �`�g�c�ƈɒ������ē����ƃx���j���G�t
 �@8��22���A17���Ԃɂ킽���ČJ��L����ꂽ���I�ܗւ��������B����͑�31��ŋߑ�ܗ֊J�n����120�N�B�Ƃ��낪�Ñ�I�����s�b�N�͂Ȃ��1200�N�̗��j�����邻�����B����͐����B���̐헐�̐��̒���4�N�Ɉ�x�̃I�����s�b�N���p�����Ă����I ���O�͕��a�B�|���X�Ԃ̐퓬���x�킷�邽�߂̑[�u�ł��������B���a�̊T�O�͋ߑ�ܗւ̊�{���O�Ƃ��Ė��X�ƈ����p����Ă���B
�@8��22���A17���Ԃɂ킽���ČJ��L����ꂽ���I�ܗւ��������B����͑�31��ŋߑ�ܗ֊J�n����120�N�B�Ƃ��낪�Ñ�I�����s�b�N�͂Ȃ��1200�N�̗��j�����邻�����B����͐����B���̐헐�̐��̒���4�N�Ɉ�x�̃I�����s�b�N���p�����Ă����I ���O�͕��a�B�|���X�Ԃ̐퓬���x�킷�邽�߂̑[�u�ł��������B���a�̊T�O�͋ߑ�ܗւ̊�{���O�Ƃ��Ė��X�ƈ����p����Ă���B�@���{���l���������_��41�͎j��ő��B�S���t������112�N�Ԃ�B���X�A������g�j�㏉�h�g���N�Ԃ�h�̃t���[�Y��������ь������B��͂�I�����s�b�N�͗��j�B���̎��_�Ń��I�ܗւ���ڂ��Ă������B
(1) �g�c�ƈɒ��̖���
�@���q���X�����O58k���ɒ��]��4�A�e�͏��q���̉����B������4�A�e��_�����g�c���ۗ��͋�B���Â����B120�N�̗��j�̒��A�����ɓ�l�̃��W�F���h�a�����I�����s�b�N�̐_�l�͋����Ȃ������̂�������Ȃ��B�ł́A��l�̍��͉��������̂��H ���O�҂��I舂Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A�����Ďא������Ă���������A���X�����O�̃X�^�C���Ɣw�����d���̍��ł͂Ȃ��������H
 �@�ɒ��̌�����͍Ō�4�b�ł̋t�]�����������B����܂ŁA�قڊ�Ȃ��Ȃ������Ă����啑��̏����ŁA���͍̋��B�͂̐��������������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B����ł��M���M���̂Ƃ���ŗ������̂́A��肩����グ�����芴����ޏ��̃��X�����O�E�X�^�C���A�����A�g�����Ȃ��X�^�C���h�ɂ����̂������Ǝv���B
�@�ɒ��̌�����͍Ō�4�b�ł̋t�]�����������B����܂ŁA�قڊ�Ȃ��Ȃ������Ă����啑��̏����ŁA���͍̋��B�͂̐��������������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B����ł��M���M���̂Ƃ���ŗ������̂́A��肩����グ�����芴����ޏ��̃��X�����O�E�X�^�C���A�����A�g�����Ȃ��X�^�C���h�ɂ����̂������Ǝv���B�@�g�c�̃X�^�C���́A�S�������قǂ������^�b�N���d���̍U���^�B�X�s�[�h�ƃL����g��Ƃ���B33�A�������̋g�c������2�v�f�����Ă����B�����āA����͑z���ł����Ȃ��̂����A�ޏ��̑̂͂��͂�{���{���������̂ł͂Ȃ����H�܂��A���Z�����ɏW���ł����Ȃ��������X�^�[�I��Ƃ��Ă̏h�����������B����܂ŁA�g�c�̌ܗւł̐킢�Ԃ�́A���|�I�U���͂ɂ���đ���̐�ӂ�r��������A�Ƃ����X�^�C���B��������ݍ��ރI�[�����̒����甭�U���Ă����B�Ƃ��낪�A����͂��ꂪ�Ȃ������B�̗͂̐����Ƒ̒��s�ǁI�H ����܂��ɁA�Ԃ����{�ԂŗՂ̂͂��̏؋��ł͂Ȃ��������B�����ĕ����łȂ��v���b�V���[���������B�����ē��R�������R���X�^���g�ȏd���B�S�����̂��߂ɂǂ����Ă��������Ȃ��Ƃ����V���ȏd���B�f�邱�Ƃ��ł����͂��̑I��c�叫�������Ĉ����Ă��܂����ӔC���B�O���̎����Ŗ�����l�������l�������Ƃ̋t���B�傪�����4�A�e�B���錾�s�s�����������S���B�ȂǂȂǁA���X�̏d�ׂƐ�Ή��҂Ƃ��āu�����˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����v���b�V���[�ɁA�������̍ŋ������������Ԃ���Ă��܂����I�H
�@���ɋ�3�����ޏ��ɂƂ��āA��_���͈Ӗ����Ȃ���������Ȃ��B�ł��A�p���邱�Ƃ͂Ȃ��B���Ȃ������Ȃ�������A�����6�K���ŋ����_��4�Ƃ����傫�Ȏ��n�͂Ȃ������B�����܂ŏ��q���X�����O���������Ă������т͌����ĐF����̂ł͂Ȃ��B
�@�I�����s�b�N�A�e�̋L�^�͒j�q��4�B�ߋ�3�l�������Ȃ��B�~�Փ����̃A���E�I�[�^�[�i1956�����{�����|1968���L�V�R�j�A���蕝���т̃J�[���E���C�X�i1984���T���[���X�|1996�A�g�����^�j�A�����āA�����ŒB���������j200m�l���h���[�̃}�C�P���E�t�F���v�X�ł���B�t�F���v�X�͂���ɉ�����400�����h���[�����[�ł��č��`�[���̈���Ƃ���4�A�e��B���B�l�����������_������23�B���ʂ��J�[���E���C�X�A�k���~���9�����炱�̐��͂ƂĂ��Ȃ��B����܂��j���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B����Ɉ��������A���Ẵ��C�o���ɂ��ė��F���C�A���E���N�e�̋����ߕ߂͏�Ȃ��̌���B
(2) �����ƃx���j���G�t���J
 �@�̑��j�q�̃G�[�X�����q�����������p�t�H�[�}���X�͌����̈��ɐs����B2012�����h�����Œ����̌�o��q�������̓�����A�u�c�̂ŋ��v�������t�ɁA�L���v�e���Ƃ��ă`�[�������������Ă����B�����h���̃����o�[��l��l�������𐋂��A���ƒ��n�̃X�y�V�����X�g���䌒�O���������j��ŋ��`�[���Ƃ��ėՂB�\�I�̕s�U�̓����h���̓�̕����H�Ɗ뜜���ꂽ���A�����ł͊e�l�����������\���ɏo�������B�R�����j�͂���n�ŗ�����������ӂ̂�ւŔ҉�A�c���C�T�͗\�I�̕s�U���猩���ɗ�������`�[���ɐ����������B
�@�̑��j�q�̃G�[�X�����q�����������p�t�H�[�}���X�͌����̈��ɐs����B2012�����h�����Œ����̌�o��q�������̓�����A�u�c�̂ŋ��v�������t�ɁA�L���v�e���Ƃ��ă`�[�������������Ă����B�����h���̃����o�[��l��l�������𐋂��A���ƒ��n�̃X�y�V�����X�g���䌒�O���������j��ŋ��`�[���Ƃ��ėՂB�\�I�̕s�U�̓����h���̓�̕����H�Ɗ뜜���ꂽ���A�����ł͊e�l�����������\���ɏo�������B�R�����j�͂���n�ŗ�����������ӂ̂�ւŔ҉�A�c���C�T�͗\�I�̕s�U���猩���ɗ�������`�[���ɐ����������B�@���䌒�O�͒��n�Ə��ň����̉��Z���I�A���������͈���x���Q�̉��Z�ōv���A�����āA�����q���͂�����l6��ڃt���o�ꂵ�G�[�X�̏d�ӂ��ʂ������B����2�ʃ��V�A��2.641�̍������ċ����_�����l���B�c�̂̋���2004�A�e�l�ȗ�3���Ԃ肾�����B
�@�����q���̌l�����́A�c�̈ȏ�Ɍł��Ǝv��ꂽ�B�����h�����ł́A�Ō�̓��ڂ��c���Ăقڈ��S���B�S�_�ł͗���Z�R�[���}����������������}��y���̓W�J�B����2�ʂ�2.659�̑卷�����鈳������������B
�@�Ƃ��낪����͂Ƃ�ł��Ȃ��I�肪���ꂽ�B�I���O�E�x���j���G�t22�B����܂ł̓v���b�V���[�Ɏキ�̐S�ȂƂ���ŕK������Ă������̃E�N���C�i�̐V�s���A�ʐl�̉��Z���p���A3���[�e�[�V�����ȍ~�I�n���������[�h����B�u����Ȃ͂��ł́H�v�������̌��̓W�J�ƂȂ����B�ŏI���[�e�[�V�����̓S�_���c���Ă��̍���0.91�ƍL�����Ă����B�S�_��D�X�R�A�͓���7.I�Ńx���j���G�t6.5�B���̍��{0.6�B�����������ȉ��Z�����Ă��A�x���j���G�t�Ƀ~�X���Ȃ���Ε�����B���Ƃ͂قڋt�]�s�\�̑卷�ƍl���Ă����悤���B
�@��ɉ��Z�����̂̓��[�h����Ă�������B���ӂƂ���S�_�����A���I�֗��Ă���Ƃ������́A�c�̗\�I�ŗ����A�����ł͘A���Z�̗��ꂪ�~�܂�|0.6�̑�~�X��Ƃ��ȂǁA�ǂ����v�킵���Ȃ��B�c�̐�\�I�E������12���Z�{�l����5���Z���o�Ă�18��ڂ̉��Z�͋��炭�S�I�蒆�ő��B��J�͋Ɍ��ɒB���Ă����B����ȕs��������Ă����͂��̓��������A�u�_���͊����Čv�Z���Ȃ��B�������������x�X�g�̉��Z�����邱�Ƃ����ɏW�����悤�v�ƌ��߂��B�u����Ȃ͂��ł͂Ȃ��v����u�x�X�g��s���������v�ւ̓]���B����S���h���Ă����B���ʁA�m�[�~�X���������n�B15.800�B�܂��Ƀp�[�t�F�N�g�ȃp�t�H�[�}���X�������B�Ȃ�Z�ʁI�Ȃ鐸�_�́I�I�����q���͓y�d��Ŋ�ՂƂ��������悤�̂Ȃ����Z�𐬂��������̂ł���B
�@�ŏI���Z�҃x���j���G�t�́AE��x2���Ƃ�D��x�ȉ��Ƃ����A�����Ɣ�ׂĂ��Ȃ蕽�Ղȃv���O������ɂ��Ȃ��B�����Ē��n�B����O�ɓ��ݏo���̂���������B14.800�B0.099���̑�t�]�B�����̌l����2�A�e�����܂����B1�_���ȓ��ł̏�����2009�N���E�I�茠�ʼn��҂ƂȂ��Ĉȗ����̏o�����B���\�L�̌������������Ƃ��B�̑����Z�j��Ɏc�閼�����������B
 �@�킢�I���������́u�l�����ō���قǕ������Ȃ����A�Ǝv���������͂Ȃ������B�i�S�_�ł́j����ŕ����Ă������͂Ȃ��Ƃ������Z���ł����B���������o�Ȃ����炢�o�������B�����̌��E���������C������B���Ɂi�x���j���G�t�Ɓj������珟�ĂȂ���������Ȃ��v�Əq�������B���E���8�A�e���̐�Ή��҂ɂ��Ă��̑䎌�B�����s���ʂĂ��������������Ƃ��`����B�����āA�����ɂ͎��Ȃ�m�葊���F�߂鐬�����������������B
�@�킢�I���������́u�l�����ō���قǕ������Ȃ����A�Ǝv���������͂Ȃ������B�i�S�_�ł́j����ŕ����Ă������͂Ȃ��Ƃ������Z���ł����B���������o�Ȃ����炢�o�������B�����̌��E���������C������B���Ɂi�x���j���G�t�Ɓj������珟�ĂȂ���������Ȃ��v�Əq�������B���E���8�A�e���̐�Ή��҂ɂ��Ă��̑䎌�B�����s���ʂĂ��������������Ƃ��`����B�����āA�����ɂ͎��Ȃ�m�葊���F�߂鐬�����������������B�@������̋L�҉�ŁA�����ɐ��������₪��B�u�卷���t�]�ł����̂́A���Ȃ����R���ɍD����Ă��邩��ł͂Ȃ����H�v�B�u����͂��肦�Ȃ��B�R���͌������v�ƌ��������̖T�炩��x���j���G�t���a�荞�B�u�X�R�A�͐_���Ńt�F�A�Ȃ��́B�����̓L�����A�̒��ŏ�ɍ����_���o���Ă��Ă���B����͖��ʂȎ��₾�v�Ǝ���҂��o�b�T���B����Ɂu���͐��E��N�[���Ȕނ̂��Ƃ�ǂ������Ă����B�ނƈꏏ�̕���ɗ��Ă�̂͑f���炵���o���Ȃ̂��v�Ɖ��҂ւ̃��X�y�N�g��\���B���ɑu�₩�������B��l�͌ł��J�Ō���Ă����B
�@�����̌l����2�A�e�́A1972�N�~�����w��������j�i1946�|�j�ȗ�44�N�Ԃ�̉����ł���B���̉����Ƃ����I��͂ƂĂ��Ȃ��B�o�ꂵ��1968���L�V�R�A1972�~�����w���A1976�����g���I�[����3���ŁA�l�����������_���͒c�̑�����3���܂�8�B����͓��{�l�l�l�������_�����̋L�^�ł���B
�@���{�̑̑��j�q�c�̂�1960���[�}�A1964�����ł����B�]����1960�|1976�I�����s�b�N5�A�e���ʂ����Ă���B���ƌ|�Ƃ���ꂽ�R���ł���B
�@���ꍑ�A�e�̋L�^�͂������A��ɂ͏オ������̂ŁA�j�q400�������[�̃A�����J�E�`�[����8�A�e�i1920�A���g���[�v�|1956�����{�����j�B�j�q�_�����т̂�͂�A�����J���Ȃ��16�A�e���Ă���i1896�A�e�l�|1968���L�V�R�j�B
�@���{�`�[���ŔN���̔��䌒�O�́u��������̌�p�҂ɂȂ肽���v�ƌ�����B���̂��߂ɂ�6��ڍ����ς̗͂����邱�Ƃ��B�����̂悤�ɁB�ނ��I�[�����E���h�̎��͂�g�ɒ����A �c�̐�œ����̏o�Ԃ�3��ڂ܂łɍi�ꂽ��A�̑��j�b�|���̖����͖��邢�B2020�����ܗւ�傢�Ɋ��҂��������̂ł���B
�@�g�c���ۗ��A�ɒ��]�A�����q���B���̓��{�����ނ܂�ȃA�X���[�g�����́A���ꂼ��̌`�ŃI�����s�b�N����߂��������B���̃p�t�H�[�}���X�͊����ȊO�̉����ł��Ȃ��������A����ŁA�����Ƃ��h���Â���ꂽ�l�Ԃ̉ߍ�������X�ɉ��߂ċ����Ă��ꂽ�B
2016.08.10 (��) �X�R�b�`�E�E�C�X�L�[�ɂ܂��G�g�Z�g��
�@�����s�m���I�͏��r�S���q��₪���������B�Ό��T���Y�����q����ɂ���Ă��ċt���ˁu�����ρv�Ɲ�������ƁA�����Ė��Łu�����ςŗ��܂����B���͂炢��v�ƌ����Ă̂���B�X�^�[�g�Łu�c������U���܂��v�Ɣ��j�������āA�ɋ}���݁A�u��肱�O���[���v�̗ւ��L���Ă䂭�B�u�O�̂悵�v�̔����z�i����Ό����̃Z���t�j��u�s���̒�ɏI�~���v���������Ȃ�����l�����ł͏��F�����ɂȂ�Ȃ������B�܂��̓��f�^�V���f�^�V�B���r����A�u�g�D�ψ���͓����s�̉���������Ȃ��v�ȂǂƃA�z�Ȃ��ƌ����i�������ȊO�̉����ł��Ȃ��ł��傤�Ɂj�X��N���A�݂��Ƃ��Ȃ����炢��l���Ȃ������}�s�c�A��ɑ�ςł��傤���A�撣���Ă��������ȁI�@���I�ܗցB����8��9���ŁA���{�̋��́A�������i���j�j�q400m�l���h���[�j�A��쏫���i�_���j�q73�L�����j�A�̑��j�q�c�̂�3�𐔂����B�����͏����ē��R������Ă������̂����Ƀv���b�V���[����ς������Ǝv���B�悭���b�e�N���}�V�^�I�I���̗\�z�͑��ʎZ��11�B�Ƃ͂����A���Ƃ͋g�c���ۗ����l���Ă��ꂽ�炻��ł����B
 �@�u�N�����m�v�̓E�C�X�L�[�b��2�e�Ƃ����܂��傤�B���T�̊y���݃h���}�u�������E�n�[�g�v�̂P�тɁA�u���Ɣ��v�Ƃ������^�C�g���́A�g�Ⴄ���̃E�C�X�L�[���A���͓����~�n���ɂ���������̃��m�������h�Ƃ����e�[�}�̘b���������B���́u�o�����F�j�[�v�B���́u�O�����t�B�f�B�b�N�v�B
�@�u�N�����m�v�̓E�C�X�L�[�b��2�e�Ƃ����܂��傤�B���T�̊y���݃h���}�u�������E�n�[�g�v�̂P�тɁA�u���Ɣ��v�Ƃ������^�C�g���́A�g�Ⴄ���̃E�C�X�L�[���A���͓����~�n���ɂ���������̃��m�������h�Ƃ����e�[�}�̘b���������B���́u�o�����F�j�[�v�B���́u�O�����t�B�f�B�b�N�v�B�@�O�����t�B�f�B�b�N�E�V���O�������g�́A1887�N12��25���A�X�R�b�g�����h�̃E�C���A���E�O�����g���X�y�C�T�C�h�n���̃_�t�^�E���ɑn�݂����O�����t�B�f�B�b�N�������ŎY�ݏo���ꂽ�B�t���[�e�B�[�ň��݂₷���t�̍��肪����ƌ`�e�����B

�@�o�����F�j�[�E�V���O�������g��1892�N�A�O�����g�������~�n���ɊJ�݂�����2���������̐��i�B�Z�M���O�����t�B�f�B�b�N�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�V���������咣���������������B�O�����t�B�f�B�b�N�̏t�ɑ��H�̖��Ƃ��B
�@�����S���������̂́A����~�n�����ꌴ������������S���Ⴄ�������ݏo�����A�X�R�b�`�E�E�C�X�L�[�̉��[���ł��邪�A����ȏ�ɖʔ��������̂͑n�ƔN�̕����ł���B
��1887�N�̓f�B�X�N���N��
 �@�g�[�}�X�E�G�W�\��(1847�|1931)���A�����~���^�t�H�m�O���t�������̂�1877�N�B�~���`�̎����ɉ��g�����ޕ����ŁA���̘^���͎��g�̐��ł́u�����[����̗r�v�B����ɁA��N�u���[���X���s�A�m��^�����Ă���B�����A�t�H�m�O���t�́A�ʎY���������A�L�����y����ɂ͎���Ȃ������B
�@�g�[�}�X�E�G�W�\��(1847�|1931)���A�����~���^�t�H�m�O���t�������̂�1877�N�B�~���`�̎����ɉ��g�����ޕ����ŁA���̘^���͎��g�̐��ł́u�����[����̗r�v�B����ɁA��N�u���[���X���s�A�m��^�����Ă���B�����A�t�H�m�O���t�́A�ʎY���������A�L�����y����ɂ͎���Ȃ������B�@����{�I�ɉ��ǂ����̂��n�m�[���@�[�o�g�̋Z�t�G�~�[���E�x�����i�[�i1851�|1929�j�ł���B�x�����i�[�́A������]�~���`�̃t�H�m�O���t���A180�x�]���A������]�~�Օ����ɂ��O�����t�H���������A���p���ɐ����B���^���͎��g�̘N�ǂɂ��u�L���L�����v�B�����A�t�H�m�O���t�ɂƂ��đ������B���̃X�^�C���������݂܂ő����f�B�X�N�����̌��^�B�m���x�̓G�W�\����ꡂ��ɗ��x�����i�[�����A�I�[�f�B�I�̔��W�ɂ͓������₻��ȏ�̍v�������Ă���B
�@�b����≡���ɂ���邪�A8��4���̒����V���ɁA�����L�ꎁ���A�A�ځu���I���t�v�̒��ŁA�����[�����Ƃ������Ă���B���l�T���X3�唭���̈���ň���p�̓O�[�e���x���N�i1398�H�|1468�j�̔����ŁA����͎��m�̎��������A�C�^���A�l�A���h�E�}�k�[�c�B�I�i1450�H�|1515�j�̑��݂�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁB�ނ����́A�O�[�e���x���N�̈�����������^�����A�y�[�W�������A�e��t�H���g�i���������j���J�����A���C�A�E�g�𐮂����B����ɂ�菑�Ђ͏��^���������^�т��\�ƂȂ����B����Ɍq����{�̌��^�����ꂽ�̂ł���B�܂��ɁA�x�����i�[�̃O�����t�H���ł͂Ȃ����B��X�́A�O�[�e���x���N��G�W�\���̖��O�͒m���Ă��邪�A�}�k�[�c�B�I��x�����i�[�ɂ͂��a���B���j��m�邱�Ƃ͏d�v�ł���B
�@�x�����i�[���O�����t�H�������������̂�1887�N�B�O�����t�B�f�B�b�N�E�V���O�������g�a���Ɠ����N�ł���B���̌�A1895�N�A�t�B���f���t�B�A�Ƀx�����i�[�E�O�����t�H���Ђ�ݗ��B1897�N�ɂ́A�����̃o���[�E�I�[�E�F���ƃt���b�h�E�K�C�X�o�[�O�������h���ɔh�����A�p���O�����t�H���Ђ�ݗ��B�K�C�X�o�[�O�̓C�^���A�A���V�A�Ȃǃ��[���b�p���삯����A�J���[�\�[�Ȃǖ��̎�̃��R�[�f�B���O�����X�ɍs�����B���ꂪ�����̕�ɐԔՂ̋N���ł���B
�@�t�B���f���t�B�A�̃x�����i�[�E�O�����t�H���Ђ͌��RCA�r�N�^�[�ɂȂ�B�p�O�����t�H���Ђ͌��EMI�B�x�����i�[���A1898�N�A�̋��n�m�[���@�[�ɐݗ������p�O�����t�H���Ђ̎q��Ђ͌�̃h�C�c�E�O�����t�H���B���s�̐��E���W���[�E���[�x���̂��Ȃ�̕����̓x�����i�[��[���Ƃ���̂ł���B
��1892�N�͂킪�c���a���̔N��
�@���̕���̑c���͉��������Y�Ƃ����B�o�����F�j�[���������ł���1892�N�i����25�N�j�ɐ��܂�A1990�N�i����2�N�j98�Ŗv�����B�����`�吳�`���a�`������4����������B�������܂ꂽ�Ƃ���53����������45�N�Ԃ��t�������������ƂɂȂ�B�䂪����Ray&You�Ƃ́A���ꂩ��20���N������t���낤����A����͒����B
�@���������ɁA�v���o�͑��X����B�͂��܂���s�i�H�j�������B�����_���ɋL���Ă������B���w���̂���A�悭�X�L�[�ɘA��čs���Ă�������B�Q�����f�̐H���ł͎��Q�������ɂ���ɃX�L�[�`�i�؏`�j����ԁB�u���q����ł����H�v�Ɛu�����Ɖ�R�@�����悭�Ȃ�A�A���Ă��c�ꂳ��Ɋ��������ɐ������Ă����B�f��ɂ��悭���������B��瓌�f�̎��㌀�ŁA�u�J�����q�v�u�g�E���v���ɋ���点�����̂������B�����Ă��āA�ӂƌ�����A���߂Ɋv�C�𗚂��Ă������Ƃ��x�X�B������A�炪�Ԃ���ꂠ�����Ă����̂ŁA���ׂ���A�����w�A�N���[������ɓh���Ă������Ƃ��������B�����ɓo���Đᗎ�Ƃ������Ă�����A�����Ē�ɗ����A�Γ��Ăׂ̗ɒ��n�����B�Y����������͖Ƃ�Ȃ������Ƃ��낾���A�������䎌�́u���̂����z�͗��������Ⴄ�v�������B���g�����ǂ�D���ŁA�H�ׂ邽�сu����Ȃ��܂����̂͂Ȃ��v�����Ȃ������B���͎q���S�ɑ傢�Ɉ�a�����o�������̂��B���c�ꂳ�ׂ̉ƂŖ����Ă���ƁA���̉ƂɌ������ĕ��d�̏����u�`�[���v�Ɩڈ�t�ł��炷�̂��킾�����B�����Ԃ̒��Q�����ۂŁA���̊Ԃ͒N�����Ă��N���Ȃ������B�ӎނ͈��ɃL�b�`�����{��M��1���B����ȉ����ȏ���Ȃ������B�����Ă���l�ɂ͋C�O�悭����݂��Ă�������قƂ�ǕԂ��Ă��Ȃ������炵���B��\�ɑ����A�����̋���30���~�i����500���~�H�j�����܂����ꂽ�B�싅����D���ŁA�N�Ɉ�x�s�c����ł�鋐�lVS���S������x���ꏏ�����B���̐��N���A�^�ߗ�v������ꂽ�̂����c������̂������ł���B���o���D���ŁA�������Ȍ��܂��ɏ��]���Ă����B�D���ȉ̎�͎s�ۂƓޗnj��}�A�̂����D�悵���B���S����x���̃h���ƌĂꂽ�B�D���́u���ȐS�v�������B
 �@�ő�̎v���o��1964�N�A���̑�w�����̎��B����2�ƍ���1�ɃG���g���[������A�����͂����Ȃ��s���i�B�オ�Ȃ��Ȃ���������1�������ɒʂ�����A�c������A�����オ��A��w�̐�y�E�n���̑啨��c�m����P���Y���̂Ƃ���ɃX�����ōs���Ă��܂����B�I�C�I�C���������A�����珬�₳��ł��������͖�������B�ł��A����Ȃ��c������̈�����ꂵ�������B���_�A���i�����Ƃ��͑傢�Ɋ��ł���܂����B
�@�ő�̎v���o��1964�N�A���̑�w�����̎��B����2�ƍ���1�ɃG���g���[������A�����͂����Ȃ��s���i�B�オ�Ȃ��Ȃ���������1�������ɒʂ�����A�c������A�����オ��A��w�̐�y�E�n���̑啨��c�m����P���Y���̂Ƃ���ɃX�����ōs���Ă��܂����B�I�C�I�C���������A�����珬�₳��ł��������͖�������B�ł��A����Ȃ��c������̈�����ꂵ�������B���_�A���i�����Ƃ��͑傢�Ɋ��ł���܂����B�@����������a�̂̒��ł̍ō�����i�H�j�́A���V�c�É��a���̎��ɉr��
�@�@�@�@���̌�q�́@���܂��m�炷�@�T�C�����́@���ɍ��킹�ā@�ł��������Ђ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1933�N12��23��
�@���̂Ƃ������܂�ɂȂ������m���V�c�É��́A2016�N8��8���A�u���O�ވʁv�ɓZ��邨�C������\�����ꂽ�B����͏���B�����ʂł���B
���Q�l������
�u���R�[�h�̐��E�j�v���r�Y���i���y�V�F�Ёj
�u���ł��ǂ�I�[�f�B�I�̐��I�v�i�Вc�@�l ���{�I�[�f�B�I����50���N�L�O�j
2016.07.25 (��) �b����`�s�m���I�A���z���̃g�̓g���`���J���̃g
 �@�s�m���I�́A7��31���̓��[���Ɍ����āA�j��ő�21���̌��҂ɂ������ȑI����̐^�Œ��B���̂���18���͖A�������������3���B�͂��o���ɁA���h�q��b�E���r�S���q(64��)�A��������b����茧�m���E���c����(64��)�A�W���[�i���X�g�E���z�r���Y(76��)�B
�@���ڂ́A���ɂ̌�o����}������E���z�r���Y�T���B�X���[�K�����u�K�����f100���v�B�I�b�g�h�b�R�C���z�T���B�ǂ��Ȃ���������̂�B�����A���̐l�̂���g���`���J�����m�Ȃ̂ł��B
�@�s�m���I�́A7��31���̓��[���Ɍ����āA�j��ő�21���̌��҂ɂ������ȑI����̐^�Œ��B���̂���18���͖A�������������3���B�͂��o���ɁA���h�q��b�E���r�S���q(64��)�A��������b����茧�m���E���c����(64��)�A�W���[�i���X�g�E���z�r���Y(76��)�B
�@���ڂ́A���ɂ̌�o����}������E���z�r���Y�T���B�X���[�K�����u�K�����f100���v�B�I�b�g�h�b�R�C���z�T���B�ǂ��Ȃ���������̂�B�����A���̐l�̂���g���`���J�����m�Ȃ̂ł��B�@2015�N�ANHK-TV���f�́u�j�b�|���̕��a���l����`�W�c�I���q���s�g�e�F�́H�v�Ƒ肷�铢�_��ŁA���z�T���A�u�ǂ�����č������̂ł����H�v�Ɩ���A�u�ǂ��̍����U�߂Ă���Ƃ����̂ł����B����Ȃ��̋��\�^�ϑz�ł���v�Ƃ����B���S�Ȃ镽�a�{�P�y�V�V�l�B����͉��₩�ɘb���Ă���̂Ɉ�l�������Ă�߂����Ă�B���������ċc�_���i�܂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���z�T���A�m������̊X�������ŁA�u���̔��_�͕������������Ă��邱�Ƃł��v�Ȃ���������Ă��܂������A���ɂ͂ƂĂ������Ƃ͎v���Ȃ��B
�@���N�O�A�u���o�̉��y��T���v�݂�����TV�h�L�������^���[�ԑg������܂��āB���o�̉��y�A���������̂������ɗ������y�ł��ˁA����z�T�������E�e�n��K�˕����Ď����̎��o�̉��y��T���o���A�Ƃ������e�B�����������y�͒T���o�����̂���Ȃ��āA�l���̒��Ō��܂��Ă�����̂�����A��掩�̂��g���`���J���ł͂���̂ł����A�o�Ă���͗ւ������ăg���`���J���ł����B�ǂ��W�J���邩���Ă�����A���z�T���A�����������Ȃ���A�s����X�Łu���A����A�����̑����ŗ������y��T���������Ă���̂ł��B�Ȃɂ������Ȃ���܂��v�ƕ����܂���B�j���[�I�����Y�̃W���Y�E�s�A�j�X�g�ȂA�r�b�N�����Ėڂ��_�ɂȂ��Ă��܂����B�I�C�I�C�A����Ȃ��́A�����Ō��߂����ĂˁB���ꂪ�M���̂��������u�������v�ł������B
�@���z�T���A�Q�@�I�̌��ʂɊ�@���������āA�s�m���I�ɏo�錈�ӂ������Ƃ��B�Ȃ�œs�m���I�Ȃ́H �Ȃ�����ł��傤�ɁB�����Ȃ��S�s�����u���{�{��̐��v�̏��ѐߎ��̕����A�܂��X�W�����͒ʂ��Ă�B�����ł��܂��Ƀg���`���J���B
�@���r����Ɂu���̐l�Ȃ珟�Ă���������Ƃ����āA����������Ȃ��a�ݏオ��̐l��S���o�������Ƃ������̂ł͂Ȃ��v�Ɲ�������āA�u�K�����҂ɑ��鍷�ʂ��v�ƃL���Ă܂����B���r����A�u�a�ݏオ��v�̓`�g�܂����������ǁA�u����Ȃ��v�͓������Ă�B���ꂪ�؋��ɓ��̂��{�l�A����ɂ͌��y���Ȃ������B�{���͂����������ׂ��Ȃ̂ɁB�܂��A����F�߂Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B
�@���N���̐��n�E�����ɂāB�u�݂Ȃ���A���̗F�l�������ɋ삯���Ă���܂����v�ƐX�i����Љ�B�X������I���ƁA�n�C���悤�Ȃ�B������Ȃ�ł�����͂Ȃ��B���������������u����������ƂȂꌾ�����Ăق��������v�ƃK�b�N���B���N����O�ɁA�V�l��Â�����ȂǁA���_��b���̂����҂̎g���ł��傤�ɁB�������A���_���Ȃ��̂��B
�@�ő�̑��_�̈�u�ҋ@�������v�ɂ��Ă��A�ł���̐����Ȃ��̂����z�T���B���c���́u1�����ȓ��ɉ����v���O���������B�撷�Ƌl�߂�v�A���r����́u�ۈ�ƍ���҂��n�C�u���b�h�����{�݂����B�Ƃ𗘗p����B�K�����ɘa����v�ȂǁA��̐����A�C�f�B�A������B���z�T�������u�����Ǝ{�݂����B�ۈ�m�̋��^�����P����v�ƁA�t�c�[�̂��ꂳ��~�܂�̊ϔO�_�B
�@����Ă����u�I������v������ƁA���r����̗��ɂ́A�u�e�����Z�L�����e�B���{�i���v�Ƃ���B���c���́A�g�o�ŁA�I�����s�b�N��Ƃ��āu�e���ƃT�C�o�[�U���ւ̖��S�̔����v���f���Ă���B���A���z����̃}�j���t�F�X�g�ɂ̓e���̃e�̎����Ȃ��B�Z�L�����e�B�̃Z�̎����Ȃ��B����Ⴛ���ł��傤�B�u�����A�k���N�̍U���͖ϑz�v�ƕ��C�ł��������l������A���{�Ńe���ȂNjN���蓾�Ȃ��A�Ɩ{�C�ōl���Ă���̂ł��傤�B
�@�j�[�X�ł̐V��̃e���A�_�b�J�̃��X�g�����l���e���A�g���R�̋�`�����e���A�~�����w���̃V���b�s���O�E���[���e���˂ȂǂȂǁA�e���͐V���Ȓi�K�ɓ���A���Ă͈��S���������{�A���{�l���^�[�Q�b�g�Ɖ������B���̏���A���z�T���A�Ȃ�ƐS����H �����s�̈��S����ǂ�����H ���̔\�V�C�Ȋy�V�Ƃ��x�����ƘA�����Ă���Ă�����̂�����B�����l�A���ȃA�s�[�����Ƒ�����A�u�����͏I��̗��N�ɏ��w�Z�ɓ��w�����B���̓��{���Ԃ��Ɍ��Ă����B������A���j������ڂ������ł��v�A�Ȃ����Ă܂������A�ǂ��ł��傤�B�u���j������ځv���āA���������̖��ł͂Ȃ��A�ǂ����������̖��ł��傤�B��������ڂ�����̂Ȃ�A���̂��ƃZ�L�����e�B��ɂ͖ڂ��䂭�͂��ł����B
�@�ŁA�u�I�헂�N���w�Z���w�v�ƌ�������̍��������Ȃ������ɁA�u���A�I��̎�20�ł��āv�Ƃ��������B�{�P�������Ă����I�H
�@�X�������ŁA�u���z�͂ȂA�������茾���āA�s���̂��ƌ���Ȃ�����Ȃ����ƁB�ł��ˁA�����o�J����Ȃ���������܂���B����Ȃ�ɂˁv�����Ă��B��w��������Ȃ�����A���ꂩ������܂����።���ł���B����ɖ��́A�g����Ȃ�Ɂh�Ƃ����C������������炩��Ǝg�����Ⴄ���ƁB�����M�p�ł��Ȃ��̂͂��̔\�V�C���B�g����Ȃ�Ɂh�����ē����s�m�������܂�Ǝv���Ă��ł����H ���Ȃ��A�L���҂��o�J�ɂ��߂�����Ȃ��ł����H �}�j���t�F�X�g�ɂ́u�s���̕s�����������܂��v�Ƃ���܂����A���Ȃ����s�m���ł��邱�Ƃ���Ԃ̕s���Ȃ�ł���B
�@���t�̏����X�L�����_�����ɂ��ẮA�u���������v��A�Ă��邾���B�u������m���Ă���̂��v���̋L�Ғc�̎���ɂ́A�u�ٌ�m�Ɉ�C���Ă���v�̈�_����B�����̌��Ō�낤�Ƃ��Ȃ��B���������u�����Ƃ͐����ӔC���ʂ����ׂ��v�Ǝ咣���Ă���W���[�i���X�g�����̗L�l�B
�@�u�����傫�ȗ͂������Ă���v�Ƃ��B����w�O�ŕw����A�u����͐����I�ȗ͂Ƃ������Ƃ��v�Ɩ���A�u���A���A����͂����̊��z�ł��B�������m�F�����킯�ł͂Ȃ�����A�T���܂��v�ƃg�[���E�_�E���B�u�傫�ȗ͂��������Ǝv��ꂽ���R�́v�Ɛu�����ƁA�u���R�͂���܂���B�l�̊��ł��B���̓W���[�i���X�g�ɂȂ���51�N�ԁA�������Ɏd�������Ă��܂�������v�����Ă��B�s���������ł��ꂿ�Ⴝ�܂�Ȃ��B
�@���������l�Ԃ�m���x�����ŒS���o����}����}���B���ɖ��i�}�s�A��\�E�����m���������h�^�o�^���͌����Ⴈ������B�u���r�S���q�����肤��v�ƌ�������A�Γc����ɐF�C���������Ǝv������A�É�Ζ����ƌł�����B���̗����ɂ́A�}��\�̌������ƕ����Ē��z�i���B���������I ���̐ߑ��̂Ȃ��B�o�J�ۏo���B
�@�s���̊F����A�����������������L����A��@�ӎ��F���̕��a�{�P���x�����X�g�E���z�T�������͂�߂܂��傤�B
�@�I���킪�i�ނقǂɁA�ނ̒��g�̂Ȃ��͎����ƘI�悳��Ă���͂��ł����A�|���̂͌���ڂ̂Ȃ��������B���̎�Ɏア��ł���ˁB�X�e�L�[�Ƃ�����������ĂˁB�̒}���N��A�ܖ؊��V�Ȃǂ����ލ��B���}���X�E�O���[�ňꌩ�C���e�����B�Ȃ����݂�ȋ�B�o�g�B����͊W�Ȃ����B���̂ނ您����A��������Ɩڂ����J���Ă��������ȁB
�@�I�����\���\���㔼��B����܂ł̓��������Ă��A���z�T���͈��2�`3�P�������������B�����������͏����c���ƐX�i��ɔC������B
 �{�l�ɏ��B���r����Ƒ��c����10�P���O��Ɛ��͓I�B���z�T���ɂ͔M�ӂ����ӂ������Ȃ��B�s���Ɏ咣�����Ă��炢�����Ƃ����M�ӂ��A�ł��邾����������̓s���ƐG�ꍇ�����Ƃ������ӂ��������Ȃ��B����A�����̔炪������Ȃ����߂̎��Ȗh�q��H
�{�l�ɏ��B���r����Ƒ��c����10�P���O��Ɛ��͓I�B���z�T���ɂ͔M�ӂ����ӂ������Ȃ��B�s���Ɏ咣�����Ă��炢�����Ƃ����M�ӂ��A�ł��邾����������̓s���ƐG�ꍇ�����Ƃ������ӂ��������Ȃ��B����A�����̔炪������Ȃ����߂̎��Ȗh�q��H�@���z�m�������j�~�ł���A���Ƃ͓�l�̂����̂ǂ���ł��H �ŕ��鉤������ ���͎����������̂�����` ���́A�ǂ��炩�Ƃ����A����^�}�̈Ђ��鑝�c�������A����C�^����H�̏����t���r������̂�B
2016.07.05 (��) �u�b�V���~���Y����u�_�j�[�E�{�[�C�v����������
 �@����A�F�l�Əo�������_�ے��B�H�����ς�8������B�u�܂����������B��t�������v�ȂǂƘb���Ȃ�������Ă���ƁA�ʂ�̌������A����K�قǂ̏��ɂ�����ꂽ�����̃o�[���������B�u�W�F�C�E�e�B�b�v���v�B�悵���낤�Ƃ������ƂɂȂ�B�o�[�Ƀt�����Ɠ��邱�ƂȂǖő��ɂȂ������Ȃ��H �ŋ߃n�}���Ă���h���}�uBAR�������E�n�[�g�v�̉e���Ȃ̂ł���B
�@����A�F�l�Əo�������_�ے��B�H�����ς�8������B�u�܂����������B��t�������v�ȂǂƘb���Ȃ�������Ă���ƁA�ʂ�̌������A����K�قǂ̏��ɂ�����ꂽ�����̃o�[���������B�u�W�F�C�E�e�B�b�v���v�B�悵���낤�Ƃ������ƂɂȂ�B�o�[�Ƀt�����Ɠ��邱�ƂȂǖő��ɂȂ������Ȃ��H �ŋ߃n�}���Ă���h���}�uBAR�������E�n�[�g�v�̉e���Ȃ̂ł���B�@�uBAR�������E�n�[�g�v�͌ÒJ�O�q�̃}���K��TV�h���}���������́B�����~�����}�X�^�[�́A�`���ɂЂ�����ƘȂރo�[������B�����ɏo���肷��l�X�̗l�X�Ȑl�Ԗ͗l���`�����B1���2�G�s�\�[�h�B�b�ɂ͕K���������݁A�u����o�ꂵ�����������炽�߂Ă��Љ�����܂��v�Ȃ�}�X�^�[�̌��ߑ䎌�`���̉���Œ��߂�B����͐l�ł͂Ȃ����ł���B
 �@6��20�����f�̎���̓A�C���b�V���E�E�C�X�L�[�́u�u�b�V���~���Y�E�V���O�������g�v�B�~���}�X�^�[�̒��߉���́u1608�N�A�k�A�C�������h�Œa���������E�ŌẪE�C�X�L�[�������E�u�b�V���~���Y�������ō����A�C���b�V���E�E�C�X�L�[�ł��B�唞����݂̂��g���A3�����������Ƃ����A�C���b�V���`���̐��@�ɂ��A�܂�₩�ł₳������������Ɏd�オ���Ă��܂��B�ǂ��������������̕����ƌ����ɍL����t���[�e�B�[�Ȗ��킢�y���݂��������v�������B�܂��A�����ł́u�u�b�V���~���Y�E�V���O�������g�́A���܂ꂽ���q���K�����N����̂��b������Ƃ����A�s�v�c�Ȃ����Ȃ�ł��v�Ƃ̑䎌���������B
�@6��20�����f�̎���̓A�C���b�V���E�E�C�X�L�[�́u�u�b�V���~���Y�E�V���O�������g�v�B�~���}�X�^�[�̒��߉���́u1608�N�A�k�A�C�������h�Œa���������E�ŌẪE�C�X�L�[�������E�u�b�V���~���Y�������ō����A�C���b�V���E�E�C�X�L�[�ł��B�唞����݂̂��g���A3�����������Ƃ����A�C���b�V���`���̐��@�ɂ��A�܂�₩�ł₳������������Ɏd�オ���Ă��܂��B�ǂ��������������̕����ƌ����ɍL����t���[�e�B�[�Ȗ��킢�y���݂��������v�������B�܂��A�����ł́u�u�b�V���~���Y�E�V���O�������g�́A���܂ꂽ���q���K�����N����̂��b������Ƃ����A�s�v�c�Ȃ����Ȃ�ł��v�Ƃ̑䎌���������B�@�u���ɂȂ����܂����H�v�Ƃ����W�F�C�E�e�B�b�v���̃~�X�g���X�ɁA�v�����āu�u�b�V���~���Y�E�V���O�������g���X�g���[�g�Łv�ƌ����Ă݂��B�X�^�b�t����������̂������A���͋C���\�t�g�ŐS�n�悢�B���炭���������ߐF�̉t�̂��o�Ă���B�Ȃ��������Ƃ��߂��B�������ƌ��Ɋ܂ށB�u�Ȃ�قǁB���ꂩ�I�v�v�킸�S�̒��ŋ���ł����B���ɉ��₩�ŏ�i�ȍ���Ɩ��B�Ȃ�ƂȂ��������������݂����Ă���B�~���}�X�^�[�̑䎌�ɋU��Ȃ����B�Ǝv�����u�ԁA�t�[���Ɠ��̒��Ɂ�_�j�[�E�{�[�C �̃����f�B�[��������ł����B
 �@�����₱�ꂪ�g�u�b�V���~���Y�����N����̎v���o�h�̕��������Ă�Ȃ̂��H�E�E�E�E�E ���ɂƂ��Ắu�_�j�[�E�{�[�C�v���̌��́A�n���[�E�x���t�H���e�i1927�|�j�̃J�[�l�M�[�z�[���E���C�u1959�ŁA���w�`���Z�����肾�����낤�B�����܂����̃n�X�L�[�ɂ��ĉ�����i����悤�ȉ̏��ɖ�����āA�����ʂ�Ղ��C����قǒ��������̂ł���B
�@�����₱�ꂪ�g�u�b�V���~���Y�����N����̎v���o�h�̕��������Ă�Ȃ̂��H�E�E�E�E�E ���ɂƂ��Ắu�_�j�[�E�{�[�C�v���̌��́A�n���[�E�x���t�H���e�i1927�|�j�̃J�[�l�M�[�z�[���E���C�u1959�ŁA���w�`���Z�����肾�����낤�B�����܂����̃n�X�L�[�ɂ��ĉ�����i����悤�ȉ̏��ɖ�����āA�����ʂ�Ղ��C����قǒ��������̂ł���B�@���C�u�̌㔼�A�u�}�}�E���b�N�E�A�E�u�[�u�[�v����u�_�j�[�E�{�[�C�v�u�N�E�N�E���E�N�E�N�E�p���[�}�v���o�ă��X�g�́u�}�e�B���_�v�Ɏ��鐷��オ��́A���ꂼ���C�u�E�p�t�H�[�}���X�̋ɒv�Ɗ������B�Ȍケ��ȏ�̂��̂ɏo����Ă͂��Ȃ��B�J�ł̓N���C�}�b�N�X�́u�}�e�B���_�v�ɃX�|�b�g�������������A���͂��݂��݂Ƃ����u�_�j�[�E�{�[�C�v���D���������B�ꏏ�ɒ����Ă�������x���t�H���e�E�t�@���Ɖ�������ƁA1974�N�A����T���v���U�ł̗��������ɏo�������̂��A���������v���o�ł���B���݂Ɍ��݁A�x���t�H���e��6�N��̉䂪������݁B��������肾�B
�@BS�|TBS�ɁuSONG TO SOUL�v�Ƃ����ԑg�������āA���ȂɓZ���a����b�Ȃǂ������B�O�ɘ^�悵���u�_�j�[�E�{�[�C�v��BD-R�����o���Ă݂��B
 �@���̐̃A�C�������h�Ƀ��[���[�E�_�[���E�I�L���n���Ƃ����̎傪�����B17���I�����A�p�����W�F�[���Y1��(�ԑg�e���b�v�̓W���[�W1���ƂȂ��Ă��邪���)���A�A�C�������h�ɏ�荞��ŁA�ނ̗̒n��D���Ă��܂��B�n�[�v�e���ł��������I�L���n���͔߂��݂̋C�������n�[�v�ɏ悹�Ėa�����B���ꂪ�u�_�j�[�E�{�[�C�v�̌��^�Ƃ����Ă���B
�@���̐̃A�C�������h�Ƀ��[���[�E�_�[���E�I�L���n���Ƃ����̎傪�����B17���I�����A�p�����W�F�[���Y1��(�ԑg�e���b�v�̓W���[�W1���ƂȂ��Ă��邪���)���A�A�C�������h�ɏ�荞��ŁA�ނ̗̒n��D���Ă��܂��B�n�[�v�e���ł��������I�L���n���͔߂��݂̋C�������n�[�v�ɏ悹�Ėa�����B���ꂪ�u�_�j�[�E�{�[�C�v�̌��^�Ƃ����Ă���B�@���͗���A���y���t�W�F�[���E���X�i1810�|1879�j�͖k�A�C�������h�̃f���[���ɂقNj߂����}�o�f�B�Ƃ��������Ȓ��̘H�n���ŁA�W�~�[�E�}�b�J���[�Ƃ����Ӗڂ̗��|�l�̒e�����@�C�I�����̒��ׂɐS�D����B���������W�F�[���͂�����̕����āA�_�u�����̃W���[�W�E�y�g���Ƃ����F�l�ɑ���B���w�̍̏W�Ƃł��������y�g���́A����Ɂu�����h���f���[�̉�The Londonderry Air�v�Ƃ����^�C�g�������o�ł���B1851�N�̂��Ƃł���B
�@�����I�قnj�A�A�����J�̓R�����h�B�ɁA�}�[�K���b�g�E�E�F�U���Ƃ��������������B�ޏ��̓A�C�������h�ږ����e���u�����h���f���[�̉́v�Ɏ䂩��A�C�M���X�ɏZ�ތZ�A�t���f���b�N�E�E�F�U���Ɋy���𑗂�B�t���f���b�N�ٌ͕�m�����쎌�̐S�����������B�y���������ނ́u�_�j�[�E�{�[�C�v�Ƃ���2�N�قǑO�ɏ��������Ă͂߂Ă݂�B����ƃh���҂����A�����Ƀn�}�����B���ȁu�_�j�[�E�{�[�C�v�̒a���B1912�N�̂��Ƃł���B���̎��ɂ́A�u�ʂ�A���A���A�F��v�ȂǁA�l���l���v���^��A�M�����Â��Ă���B�u�_�j�[�E�{�[�C�v�́A�₪�Ďn�܂��1�����E���̒��A���ɏo�������m�ւ̎v�����d�˂Ȃ���A�L���Â��ɐZ�����Ă����̂ł���B
�@1912�N�Ƃ����A���̃^�C�^�j�b�N�����v���̂̔N�B���̂Ƃ��A�j���[���[�N�ɂ����f�C�r�b�h�E�T�[�m�t�Ƃ������̖����Z�m���A���R�^�C�^�j�b�N������œd���ꂽ�����M���𑨂����B���A��厖�ƌ�����ނ͎O���O�ӁA�s���s�x�Ń^�C�^�j�b�N������̖�������M���~���̃L�C��@���������B�ނ̌��g�I�ȍs�ׂ�800�l�̖����~�����Ƃ����Ă���B������A�����̏d�v����m�����A�����J��RCA��ݗ��B�T�[�m�t�͌o�c�w�ɖ���A�˂̂��ɎВ��ɂ܂ŏ��߂�B�n���[�E�x���t�H���e��RCA���[�x���̃A�[�e�B�X�g�B�ނ́u�_�j�[�E�{�[�C�v�ɂ�1912�N�Ƃ����ړ_���������̂ł���B
 �@���āA���x�́u�u�b�V���~���Y�v�ł���B�Ўj��R�����Ă݂�B�k�A�C�������h�E�A���g���E���B�u�b�V���~���Y�̗̎�g�[�}�X�E�t�B���b�v�X���́A1608�N�A���̉p�����A�W�F�[���Y1����������Ƌ���^����ꂽ�B���ꂪ�u�u�b�V���~���Y�������a���������������� Distillery�v�̋N���ł���B
�@���āA���x�́u�u�b�V���~���Y�v�ł���B�Ўj��R�����Ă݂�B�k�A�C�������h�E�A���g���E���B�u�b�V���~���Y�̗̎�g�[�}�X�E�t�B���b�v�X���́A1608�N�A���̉p�����A�W�F�[���Y1����������Ƌ���^����ꂽ�B���ꂪ�u�u�b�V���~���Y�������a���������������� Distillery�v�̋N���ł���B�@�W�F�[���Y1���́A1608�N�A�E��Ńu�b�V���~���Y�ɏ����Ƌ���n���A����ŃI�L���n���̗̒n��D��������B���̌��ʁA�A�C���b�V���E�E�C�X�L�[�̖��i�ƃA�C�������h�̖��́u�_�j�[�E�{�[�C�v���a�������̂ł���B
�@�u�_�j�[�E�{�[�C�v�Ɉ�̂ǂꂾ���̃��@�[�W���������邩�͌��������Ȃ����A������@��Ɏ莝����CD����������o���A�w�������AYou-Tube�Ō�������������āA�ł�����蕷���Ă݂��B�n���[�E�x���t�H���e�i���C�uV�A�X�^�W�I�^���A�䎌����V�j�A�G�����B�X�E�v���X���[�i�u�����t�B�X��舤�����߂āv���j�A�r���O�E�N���X�r�[�A�A���f�B�E�E�B���A���X�A�f�B�A�i�E�_�[�r���A�}�n���A�E�W���N�\���A�L���O�X�E�V���K�[�Y�A�P���e�B�b�N�E�E�[�}���A����Ђ�i�����N �j�A�t���b�c�E�N���C�X���[�iVn�\���j�A�W�F�[���Y�E�S�[���E�F�C�i�t���[�g�E�\���j�A�O�����E�~���[�A�r���E�G���@���X�A�L�[�X�E�W�����b�g�A�V���E�I�[�X�e�B���A�T���E�e�C���[etc�B
�@�u�_�j�[�E�{�[�C�v�䂪���t�@�����X�̓n���[�E�x���t�H���e�̃��C�u�u�����A���������œ��M���ׂ��̓v���X���[�ƃN���C�X���[�������B�G�����B�X�E�v���X���[�i1937�|1977�j�̂�1974�N�^���B�S���Ȃ鐔�N�O�Ƃ������Ƃ��l����ƁA�ނ̉̂���߈�߂����ɟ��݂�B�t���b�c�E�N���C�X���[�i1875�|1962�j�́A�P�R�[���X���ƂɃI�N�^�[�u�グ�A�Ō�̓߂��n�߂̃L�C�ʼn�ڂ���B�V���v���ȋȂɂ̓V���v���ȋZ�@�őΉ��������ƒ�������B�܂��ɖ��l�|�ł���B
�@�uBAR�������E�n�[�g�v�ŃE�C�X�L�[�Ƀn�}���āA�z�[���E�o�[�̂��߂̃}�C�E�{�g��������n�߂��B��n�߂Ɂu�u�b�V���~���Y �V���O�������g10�N�v���w���B�V���b�g�E�O���X���A�f�p�[�g4�����͂������āA�C�ɓ��������̂��Ă����B���̂��Ƃ́A�ԑg�Œm�����u�O�����t�B�f�B�b�N12�N�v�Ɓu�}�b�J����12�N�t�@�C���I�[�N�v������������Ă݂悤�B�o�b�N�ɁA���̓��̋C���ɍ������u�_�j�[�E�{�[�C�v�Ȃǂ𗬂��Ȃ���B
2016.06.19 (��) �b����`�u�}�X�]�G�̓t�H�[�N���v���c�T��
 �@�}�X�]�G����6���P5���A���E�������Ĉꉞ�̌��������܂����B�N�����m�I�ɂ͐��ʐ��Ď��グ��قǂ̂��̂ł͂Ȃ��̂ŁA�v���o���܂܁A��ۂɎc�����t���[�Y�������_���ɉӏ��������ďI���ɂ��܂��傤�B���Ƃ͋C�̌����܂܁A�G�����B
�@�}�X�]�G����6���P5���A���E�������Ĉꉞ�̌��������܂����B�N�����m�I�ɂ͐��ʐ��Ď��グ��قǂ̂��̂ł͂Ȃ��̂ŁA�v���o���܂܁A��ۂɎc�����t���[�Y�������_���ɉӏ��������ďI���ɂ��܂��傤�B���Ƃ͋C�̌����܂܁A�G�����B�@�u�}�X�]�G�̓��b�N����Ȃ��B�t�H�[�N���BRock�fn Roll�I�v�i���c�T��j
�@�u�������܂��v
�@�u��O�҂̌������ځv
�@�u�������͊��肪�悭�����₷���Ƃ��������͋�̓I�Ő����͂�����B��@���͂Ȃ��K���v�u�W�҂Ƃ͊W�ҁB���Ȃ��́A�����F��Ƃ������Ƃ������m�Ȃ��̂��v�i�}���V�̑P�O�j
�@�u�����̋@���Ɋւ����Ȃ̂ł��b���ł��Ȃ��v
�@�u���I�ܗւ�O�ɂ������̎����A�I���������瓌���͍����������̂ɂȂ�B���͒m���Ƃ��ē����s�̖��_����肽���v
�@�u�ł�����ؕ��B�����ۂ͑��h���ׂ����v�i�����}�s�c�����j
�@�u�����}����ԋꂵ�����ɏo�čs�����l�𐄑E���邱�Ƃɑ�`�͂Ȃ��B���͉������Ȃ��v�i����i���Y�A2014�N�s�m���I�ɂ����ẴR�����g�j
�@���ł������Ƃ����m�������̂́A�����������̂ɂȂ��Ă���A���̒��{�l�������ł��邭���ɁA�C�P�V���[�V���[�Ɓu�����̖��_����肽���v�ƌ��������Ƃ��ȁB�B��}�X�]�G�̌��т́A�u���������K���@�v���V���̃U���@�ł��邱�Ƃ𐢊Ԃɒm�炵�߂����ƁB�}�X�]�G���͕X�R�̈�p�B�����Ƃ͑����ꏭ�Ȃ��ꓯ���悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���͂��A�Ƃ������Ƃ������Ă��ꂽ�B���P���O��̖@���͖��Ӗ��B���}�ɉ��肷�ׂ��ł���B
�@�����s���ɃA���P�[�g���������A�����s�m���ɖ]�ގ����̑�1�ʂ�87���Łu�����ɃN���[���v�����������ȁB���̒Z���ρB���ɃN���[���Ȃ炾��ł������̂ł����H ���ꂶ�ᓌ���̏����͐S�z���B�ɖ]�ނ��Ƃ́u�P�Ƀ��B�W�����A2�Ɏ��s�́A�R�Ƀ��[�_�[�V�b�v�v����Ȃ��̂��Ȃ��B�}�X�]�G�ɂ͂���炷�ׂĂ��������Ă��āA�����ς���������E�������₵�Ă����A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�@�|�X�g�E�}�X�]�G�A���̊�]�́i���Ə��m�Łj����i���Y�B�ނ̋B�R���鐳�_�ƈ�ѐ��͌��o���Ă���B�s�m������ܑ̂Ȃ��Ƃ����ӌ������邯�ǁA�A�����J�哝�̂ɂ͏B�m���o���҂����Ȃ��炸����킯�ŁA���{�����Ă�������Ȃ����B�ނ͍��ATPP�̒�R���́E�_���ƌ����ɐ���Ă���B�d���M�S�Ȏᕐ�ҁB�s�m��������Ď������w��ő�����b�B�V���������B������Ȃ����Ȃ��B�撣��i���Y�I
 �@���K�����炢�������������^��CD�u���r��̂Ђ蓇�������v�iNHK-FM1989�N12��O.A.�j�͊y���߂܂����B���{�̗��s�̎j�����ׂĒm��s��������낳��̃E���`�N�ɂ͖{���ɃV�r���܂����ˁB�u�߂������v�̃I���W�i���ł���k����Ղ̉̏����������̂��ő�̎��n�B�Ђ�̃����C�N�łƂ͑S���̕ʕ��B�W���Ȗ��^�B�Ђ�ł��ɕ����Ă����X�ɂ́A�Ȃ�Ƃ�������Ȃ��̏��B�Éꐭ�j�͓���Łu���͗܂��������v����肽�������̂ł��傤�B
�@���K�����炢�������������^��CD�u���r��̂Ђ蓇�������v�iNHK-FM1989�N12��O.A.�j�͊y���߂܂����B���{�̗��s�̎j�����ׂĒm��s��������낳��̃E���`�N�ɂ͖{���ɃV�r���܂����ˁB�u�߂������v�̃I���W�i���ł���k����Ղ̉̏����������̂��ő�̎��n�B�Ђ�̃����C�N�łƂ͑S���̕ʕ��B�W���Ȗ��^�B�Ђ�ł��ɕ����Ă����X�ɂ́A�Ȃ�Ƃ�������Ȃ��̏��B�Éꐭ�j�͓���Łu���͗܂��������v����肽�������̂ł��傤�B�@�t�^�Ƃ��Ėʔ��������̂͒f�R���c�p�Y�́u���z�ɋF�낤�v�i�쎌�F�ԏ�d ��ȁF�R�{�䐰1968�j�B���R���鑾�z�͒j�̐����@�̋��̎R���@��ЂƂ肽����l�@���̋A���҂��Ă���@���z�ɋF�낤��̍K�����E�E�E�E�E���c�搶�A��ւ̑z����GS�T�E���h�ɏ悹���D�u�Ƃ��Ԃ��𗘂�����B���̂�GS�ł͔���Ђ�u�^�Ԃȑ��z�v�����m��Ȃ��������ɂƂ��Ď��ɐV�N�ł����B
�@1980�N�㏉���A�����O�쐴����̃\���E�V���O���u���ԁv�̃v�����[�V���������Ă������̂��ƁB�쎌������d���A��Ȃ���{���ꂾ�������̂�����A���c�搶�Ɂu�����������������͋�����v�Ɠ{��ꂽ���Ƃ�����܂����B���͉̂��̂̑��̒��ł��ׂ��A�Ƃ������ƂȂ�ł��傤�B�ł��A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�搶�͂��̂ӂ��̂��O��GS����Ă���ł��ˁB�܂��A�������I �Ƃɂ����A���c�p�Y�́u���z�ɋF�낤�v�̓u�b�`�M���̌���Ȃ̂ł��B
�@����u�������i����l���v�Ȃ�TV�ԑg�����܂����B���̒��ŁA�����܂������u����͒����݂䂫�v�ƍ����B���̂������u����킦�Ȃ��B�ʂ̉F��������C������v�Ɣ�������ƁA�Q�X�g�̓��₩���|�l�������r�b�N�����邱�Ƃ�����B�Ȃ͊m���u����v�Ɓu�����v�������Ă܂����ˁB�u�ޏ��̏����Ƃ��Ă̎��_�E���̑������E�l�����A����͒j�������ɑz�����ď�������̂ł͂Ȃ��v�Ȃ邢���������Ă��܂������A�`���b�g�Ⴄ�����B�������L�Ƃ����͔̂ނ̈Ӓn�H �u�����v�͂����Ƃ��āA�u����v�́A�����Ƃ����g�ɓ���킯���Ȃ��X�P�[�����B�j���̍��ł͂Ȃ��i�̈Ⴂ�B�����̉̂͋��P�A�݂䂫����͓N�w�A�Ǝ��͏���ɍl���Ă���B�܂��A���Ǝ҂Ƃ��ĔF�߂����Ȃ��C�����͕�����܂����B
�@���y�]�_�Ƃ̓c�ƏG���������u�����E�\���O�X�`���|�~���Ƃ݂䂫�̈��̂������v�i�p�앶�Ɂj�̒��ŁA����Ȃ��Ƃ������Ă���B
�����݂䂫�́u����v�����Ƃ��A����͒j�̉̂Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���A�Ǝv�����B�u����v�Ƃ����^�C�g���Ƃ����A�����̃V���K�[�E�\���O���C�^�[�̋ȂƂ��Ắg�Љ�h�h���������炾�B60�N�ォ��70�N��ɂ����āA�j�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[�����́A��l�Ɂg����h���̂����B���ѐM�N�ɂ��Ă��g�c��Y�ɂ��Ă��A����ɑ��āA�ǂ������������邩���e�[�}�������Ƃ����Ă����B���̃V���K�[�E�\���O���C�^�[��������̂����オ�����B
 �@�j���̂��u����v�͐키����ł���B���т́u�F��v����̏ے��B���F��@�閾���O�̈ł̒��Ł@�F��@�킢�̉���R�₹�E�E�E�E�E�B�{�u�E�f�B�����́u����͕ς��Times They Are a-Changin�f�v�́u����v����{�I�ɂ͓����B���b�Z�[�W�E�\���O�ł���B������A�j�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[���̂��u����v�ւ̓c�Ǝ��̍l�@�͐������B�����A�����݂䂫�́u����v�ɑ���ނ̍l�@�͊Ԉ���Ă���B�g�Љ�h�h�ł����B�Ȃ��B
�݂䂫���̂��u����v�͗���䂭�u���v���B�m�Ԃ́u�����͕S��̉ߋq�ɂ��� �s�������N���܂����l�Ȃ�v�̌������N�B����̈Ӗ����{���I�ɈႤ�̂ł��B���ꂪ�؋��ɂ́A�f�B�����́u����v���g�ς��h�ɑ��āA�݂䂫����̂���́g���h�Ɓg����h�B�݂䂫����́u����v�͓���̎����ΏۂƂ��Ă��Ȃ��B������ޏ��́u����v�͕��ՂȂ̂ł��B����Ɍ����A�j�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[�͎����G������B�����݂䂫�͎���Ɠ�������B�����݂䂫�͒j���̂�����Ƃ����T�O��ʂ̎��_�ő������B�����璆���݂䂫�͐����̂ł��B
�@�j���̂��u����v�͐키����ł���B���т́u�F��v����̏ے��B���F��@�閾���O�̈ł̒��Ł@�F��@�킢�̉���R�₹�E�E�E�E�E�B�{�u�E�f�B�����́u����͕ς��Times They Are a-Changin�f�v�́u����v����{�I�ɂ͓����B���b�Z�[�W�E�\���O�ł���B������A�j�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[���̂��u����v�ւ̓c�Ǝ��̍l�@�͐������B�����A�����݂䂫�́u����v�ɑ���ނ̍l�@�͊Ԉ���Ă���B�g�Љ�h�h�ł����B�Ȃ��B
�݂䂫���̂��u����v�͗���䂭�u���v���B�m�Ԃ́u�����͕S��̉ߋq�ɂ��� �s�������N���܂����l�Ȃ�v�̌������N�B����̈Ӗ����{���I�ɈႤ�̂ł��B���ꂪ�؋��ɂ́A�f�B�����́u����v���g�ς��h�ɑ��āA�݂䂫����̂���́g���h�Ɓg����h�B�݂䂫����́u����v�͓���̎����ΏۂƂ��Ă��Ȃ��B������ޏ��́u����v�͕��ՂȂ̂ł��B����Ɍ����A�j�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[�͎����G������B�����݂䂫�͎���Ɠ�������B�����݂䂫�͒j���̂�����Ƃ����T�O��ʂ̎��_�ő������B�����璆���݂䂫�͐����̂ł��B�@���͗������ނƂ����݂䂫����́u����v���B
����Ȏ�����������˂Ɓ@�����b�������������@�u����v�ɂ�3�̃��@�[�W����������B1975�V���O���u�̓I�P���A1976�A���o���u���̐����������܂����v�u�̓V���v���ȃM�^�[���A1993�A���o���u����`Time goes around�vV�͌����I�P�ŁB���̎��̋C���ɍ��킹�ĕ����B��Ԃ悭�����̂̓V���O��V���ȁB�]�k�����A1993V��1975�N���}�n���E�̗w�ՂŒ������Ăяo���̍�{��̃i���[�V�������������B�u�G���g���[�E�i���o�[30�B���{�B�쎌��Ȓ����݂䂫�B�ȁw����x�B�S�����݂䂫�v�B
����Ȏ�����������˂Ɓ@�����Ə��Ęb�����
������@�����́@���悭�悵�Ȃ��Ł@�����̕��Ɂ@������܂��傤
�@�݂䂫����A���N�̔N���`�N�n�́u���`���̉��̃A���J�f�B�A�v�̍ĉ����Ƃ��B�䂪�݂䂫���y�̎t���m����炻���A�����������B�N���s���A������y���݂ł���B
2016.05.30 (��) �t�������Y �g�ēx�h�Ⴂ���炯�̉��y�u��
�@�u�ѐ搶�����������w�I�v�Ƃ���TV�ԑg������܂��B�l�C�\���Z�u�t�E�яC���l�X�Ȗ₢�Ɂu�m���Ă�v���u�����v������Ƃ������́B����Ȃ���A�����Z�Ɍ��܂��Ă�̂ł����A���Ă��܂����̂́A�g11���~�̃X�g���f�B�o���E�X���o�ꂷ��h�Ƃ̗\��������������B�ł͂��̖��ł��B[���]
���@�C�I�����̖���X�g���f�B�o���E�X�̍ޗ��ɂȂ�i�X�v���[�X�ƃ��C�v���j�͐V���̖�ɐ�o�������̂��g���B�Ȃ����H
 [��]
[��]�V���ɐ�o�����͐����Ƃł�Ղ�̊ܗL�ʂ����Ȃ�����A�����Ă��ĕ���ɂ����B�����Ă���Ƌ�������������B
�@���̉ŗѐ搶�́u�������I�v�Ƃ����Ă��܂������A�����s���͔ۂ߂܂���ł����B����́A�u�Ȃ��V���̖�ɐ�o�����͊����̓x�����������̂��v�Ɓu�ǂ������͊����Ɋ������̂�����A�ŏ��̒i�K�ł̊ܗL�ʂ͂��قNJW�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ�����_�B�ł��܂��A���������ł��܂���A�̂����Ȃ��Ƃ͌����܂��B�u�V�����́v�Ƃ������t������悤�ɁA�~�ς��ꂽ�i�N�̒m�b�Ȃ̂ł��傤�B
�@���āA����̌Ăѕ��̓��@�C�I�����̒����r�ׁB���@�C�I���j�X�g�{�{�Η���11���~�X�g���f�B�o���E�X��30���~���@�C�I������e���āA�ѐ搶�ɓ��Ă�����Ƃ������́B�����ꏏ�ɂ���Ă݂܂����B�Ȗڂ́u�^�C�X���ґz�ȁv�`����30�b�قǁBA�͂ȂL���L���Ƒ��������BB�͂�⏁���̂��鉹�B���̉�B�E�E�E�E�E�����ɊO��܂����B���̎��������������ƂȂ��Ȃ��I�H�ł��܂��ATV�̑e���ȃX�s�[�J�[�Ȃ�ԈႦ�Ă����傤���Ȃ��H ���@�C�I�����t�҂̋Z�ʂ������č����o�Ȃ��H �����Ǝ��炢�����܂����B
>
�@�ѐ搶�����Ɠ���B�ŊO��B���āA������q�ѐ搶�ɂ͂��̑��ɂ����M�����[�ԑg������������܂��āA���̈���u���ł���u���v�B5��3���́u�t�������Y�搶�̉��y���đf���炵���u���v�`�u�L���ȂɉB���ꂽ�ӊO�Ȑ^���v�ł����B�с��t�����R���r�́u���y�u���v�͍��x��4��ځB1��ڂ͕s���B2��ڂɂ��Ă�2014�N8��5���́u�N�����m�v�Ŏ�グ�Ă��܂�����A�����̂�����͂������������B�����ł̊ԈႢ��10���B�͂����茾���Ă��������B���͎��A�e�����ɂ́u�ǂ������Ȃ琳�m�Ɂv�ƕ����ŏ������Ă����܂����B
�@3��ڂ͏�������܂�������{�ς���Ă���܂���B�ł��A�l�̔�������炤�̂���l�C�Ȃ������Ԃ̖��ʁA���������̂͂悻���Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪������]��̍����Ɏ��̐��`�����ق��Ă����Ȃ��I�Ƃ����킯�ōēx��グ�����Ă��������܂��B
���u�^���v�̉��t�̎d���͓��{�ƊC�O�Ƃł͈Ⴄ�H��
�@�t�����搶�́A�u�x�[�g�[���F���̖��� �����ȑ�5�ԃn�Z���w�^���x�́A���{�ƊC�O�ł͉��t�̎d�����قȂ�B�w�^���x�Ƃ����ď͓̂��{�����̂��̂ł���A������ӎ�������{�l�w���҂ɂ�鉉�t�͂����ɂ�����炵���[���ȉ��t�ɂȂ�A�ӎ��̂Ȃ��C�O�̉��t�͌y�������ƂȂ�v�Ƃ������Ⴂ�܂��B
�@���������ɏo�������{�̉f���́A���쌧���{�[�u���Z���y���u����y���I�[�P�X�g���B���ꌻ�����Z����OBOG�ɂ��A�}�`���A�E�I�[�P�X�g���B�w���҂������B���̉��t���āA�F����u�E�[���A�Ȃ�قlj^���ɋ�Y���銴�����`����Ă���v�����āB�A�z�炵���ĕ������Ⴈ���I �������t�̂��Ƃ��Ƃ₩�������Ă��Ȃ��ł���B���{�ɂ�33���̃v���̃I�[�P�X�g��������̂�����A����炢�́u�^���v�̉f��������ł��傤�ɁB�e���r�ǂȂ��炻�ꂭ�炢�p�ӂ��Ă��������ȁB���������蔲�������̔ԑg�̈����ۂ��Ȃ�ł���B
 �@�C�O�̉��t�Ƃ��Ĉ��������ɏo�����̂̓j�R���E�X�E�A�[�m���N�[���i1929�|2016�j�̎w���ɂ����́B���̕��̓s���I�h�y��i�Êy��j���t�̑�ƂŁA�|���͎��Ƀ��j�[�N�B�y�������Ɖ]�����u�c��{�L�{�L�B���_���y������ꂽ���ɂ͂��Ȃ����ɕ��������ł��B
�@�C�O�̉��t�Ƃ��Ĉ��������ɏo�����̂̓j�R���E�X�E�A�[�m���N�[���i1929�|2016�j�̎w���ɂ����́B���̕��̓s���I�h�y��i�Êy��j���t�̑�ƂŁA�|���͎��Ƀ��j�[�N�B�y�������Ɖ]�����u�c��{�L�{�L�B���_���y������ꂽ���ɂ͂��Ȃ����ɕ��������ł��B�@���������āA�t�����搶�̂悤�Ɂw�^���x���t�̍��ق́g���{�ƊC�O�h�̍��A�Ƃ������́g���_���y��ƃs���I�h�y��h�̍��A�ƌ���������ׂ��ł��傤�B
�@���̓�̉��t���r�ׂėt�����搶�H���A�u���{�̉��t�͋�Y���銴�����`����Ă���ł��傤�B���{�ł́w�^���x�̉��t���@���Ă͎̂��͂����ł���B�������Ԃɂ���ĉ��̂��ۂ��v�B�y���߂��ċ�����Ȃ�B
�@��ɏo�����`���u�_�_�_�_�[���v�~2 �̃^�C���͓��{7�D8�b�A�C�O5�D7�b�B�m���ɁA��Ɍ����Ắu���{�͏d�X�����C�O�͌y���v�����̃^�C����������M����B�ł͂��̂ق��̊C�O�̉��t�͂ǂ��Ȃ̂��H
�@�鉤�J�������i1962�x�������E�t�B���Ձj��6�D5�b�B�����ƒ�]����J�����X�E�N���C�o�[�i1974�E�B�[���E�t�B���Ձj��8�D5�b�B���j�I���ՂƂ�����t���g���F���O���[�i1947�x�������E�t�B���Ձj��12�b�B��Ƀt���g���F���O���[�Ȃǂ́A�搶�̕\�������A�g��Y���ʂĂ��Ȃ������h�悤�ȉ��t�ł���B
�@���ƂقǍ��l�Ɏw���҂ɂ���ă}�`�}�`�B�w���҂Ƃ����̂́A�y�����������ȑ�O�҂̎��ɑς�����悤�ȉ��t��ڎw�����́B�����āA���{�͂����C�O�͂����A�ȂǂƂ����P���Ȑ}���̒��Ɏ��܂���̂ł͂Ȃ��̂ł��B�������ȗ�����������ɏo���āA�g���ꂪ���ׂĂɋ��ʂ��鎖�ہh�Ƃ���Z���I�_�]�͗t�����搶�����ӂ̊��B�����ȂȂ�ł��ˁB
���u�J�������O�t�ȁv�͉^����Ŏg�����Ⴂ���Ȃ���
 �@�t�����搶�A�����͉^����̉��y�ł��B�u�V���ƒn���v�u�N�V�R�X�E�|�X�g�v�u�J�������O�t�ȁv�����t���āA����������������B�u���̒��ň�^����ɓK���Ȃ����y������܂��B����́w�J�������O�t�ȁx�B���̉��y�͎E���̏�ʂ̉��y�Ȃ�ł��ˁv
�@�t�����搶�A�����͉^����̉��y�ł��B�u�V���ƒn���v�u�N�V�R�X�E�|�X�g�v�u�J�������O�t�ȁv�����t���āA����������������B�u���̒��ň�^����ɓK���Ȃ����y������܂��B����́w�J�������O�t�ȁx�B���̉��y�͎E���̏�ʂ̉��y�Ȃ�ł��ˁv�@�u�E���̏�ʂ̉��y�v���āA�ǂ��Ȃ̂��Ȃ��H �m���ɗ�́g�W�����W���J�W���J�W���J�h�̃����f�B�[���A��4���ł��`���R���Ɗ���o������A100���ԈႢ����Ȃ�����ǁA�Ȃ�Ă������āu�O�t�ȁv�͑�1���̖��J���̉��y�ł��B��������A���̋ȁA�{���ɉ^����̒�ԋȂȂ̂�����H ���̌o���ł͉^����ŕ��������Ƃ��Ȃ��B�o������8�r�[�g�ŋ삯�����Ƀs�b�^���Ȃ̂ł����A�u�����m�̃e�[�}�v�̒��ԕ���4�r�[�g�B�}�ɕ����e���|�ɗ�����B���ꂶ��A�������鐶�k�͎~�܂����Ⴄ���B�^�C�����S2��30�b�̂����A4�r�[�g������52�b�A�S�̂̂P�^�R������B�K���Ȃ��Ǝv���ǂȂ��B�ł��܂��A�^����͋삯�������肶��Ȃ�����悵�Ƃ��܂����B�d���̋�����˂��Ă��ẮA�u���匾���ȁB�Ȃɂ��@���Ƃ��Ă�킯����Ȃ��v���ē{��ꂻ�����B�����ƁA����ǂ����ŕ������䎌�I�H
�@�܂��܂��ׂ������Ƃŋ��k�ł�����_�B�܂��́u�V���p���̓s�A�j�X�g�Ƃ��čŏ��ɃX�^�[�ɂȂ����l�v�Ȃ�Ă����Ⴂ�܂������A����Ⴂ�܂��B���X�g�ł��B���X�g��1811�N���܂�B10�̂Ƃ��ɂ͐_���Ƃ��ăR���T�[�g�͑����̏�悵�Ă���B�V���p����1810�N�̐��܂�B�V���p�����F�m���ꂽ�̂̓p���ɏo�Ă��Ă���B�p���ɏo���̂�20�Ȃ̂ŁA���X�g���10�N�߂����Ƃ̂��Ƃł��ˁB
�@������́A�搶�u�w�n���K���[���ȁx�̓u���[���X�̃f�r���[��v�Ǝ��M�������Ă������Ⴂ�܂�����������A�E�g�B��i�ҁj�Ȃ����̂�1858�N�A25�̂Ƃ��B3�Ȃ���s�A�m�E�\�i�^��20�̍�i�B������V���[�}���ɒ��������̂��L�b�J�P�Ŋy�d�f�r���[���ʂ�������ł��B���ꉹ�y�j�̏펯�ł����ǁB
�@���łɁA�����ꌾ�B�t�����搶�́u�n���K���[���ȁv�̂��b��Wikipedia���̂܂�܁B���܂�Ɉ��ՁB�����҂��o�J�ɂ��Ă܂����B�ҏȂ𑣂��܂��B
���u�y�[���E�M�����g�v�́u���v�͎ܔM�̃T�n���������e�[�}��
 �@�Ō�͋ɂߕt���B�搶�H���u�w�y�[���E�M�����g�x�́w���x�͎ܔM�̍������e�[�}�������v�B�����Ƃ��ƁA���ق��Ă���������B���Ȃ��ŏ��̍u���ŁA�u�O���[�O���m���E�F�[�̃t�B�����h���C���[�W���č�����B�����炱�̂悤�Ȑ������ɖ����Ă���v�Ȃ�Ă���������Ă܂�����ˁB�����Y�ꂿ������̂��ȁB���̂Ƃ����́u����̓����b�R�̊C�݂�����v�ƃe�����̍L��ɓ`���܂����B�����ǂ��ǂ����m��܂��A���������̂͂�������ǁA���x�́g�ܔM�̍����h�ł����I ���Ȃ��͖{���ɖʔ����l�ł���B
�@�Ō�͋ɂߕt���B�搶�H���u�w�y�[���E�M�����g�x�́w���x�͎ܔM�̍������e�[�}�������v�B�����Ƃ��ƁA���ق��Ă���������B���Ȃ��ŏ��̍u���ŁA�u�O���[�O���m���E�F�[�̃t�B�����h���C���[�W���č�����B�����炱�̂悤�Ȑ������ɖ����Ă���v�Ȃ�Ă���������Ă܂�����ˁB�����Y�ꂿ������̂��ȁB���̂Ƃ����́u����̓����b�R�̊C�݂�����v�ƃe�����̍L��ɓ`���܂����B�����ǂ��ǂ����m��܂��A���������̂͂�������ǁA���x�́g�ܔM�̍����h�ł����I ���Ȃ��͖{���ɖʔ����l�ł���B�@�m���Ƀ����b�R�̓T�n�������Ő��[�̍��ł͂���܂����A��{�ɂ͂�������܂��B
�����b�R�̓쐼�C�݁B���q�сB�������������������n�ʂɕ~���ċ����̑삪��������Ă���B�т̚��Ƀn�����b�N������ނ��Ă���B�����ɏ������b�g���z�A�m���E�F�[�ƃA�����J�̍�����|�����̂��������Ă���B���z�̏��^�{�[�g���_�̏�Ɉ��グ���Ă���B�������B �y�[���E�M�����g�A���h�Ȓ��N�̐a�m�ɂȂ��āA���������s���A�����̓�d�ዾ���`���b�L����Ԃ牺���āA��̒[�̎�l�Ȃɗ����Ĉ��A�����Ă���B�R�b�g�����A�o�������A�t�H���G�[�x���R�b�v���y�уg���[���y�[�e���E�X�g���[�����H��Ɍ����Ă��傤�ǐH�����I����铂ł���B�i�Y�ȁu�y�[���E�M�����g�v�C�v�Z���� ��R���Y��j�@�����̂Ƃ���A�ꏊ�̓����b�R�̊C�݁B���q�̗тɃn�����b�N�B�����̑�B�ǂ����Ă��ܔM�̍�������Ȃ��B�ނ���f��u�J�T�u�����J�v�̃����b�R�ɋ߂��B�搶�H���u�O���[�N����́A�T�n���������������Ƃ��Ȃ�����A���̂悤�ȑu�₩�ȉ��y�ɂȂ����v���Ă��B���ꂶ��A�O���[�N����ɓ{���܂����B�u�������C���[�W���āA����ȋȏ������c�A����킯�Ȃ����낤�B���L������Ă�̂��A���́v���ĂˁB
�@�ł͖{���͂���܂ŁB�t�����搶�A���ނ�������Ɛ^���ɂ���Ă��������ȁB�u�`�̑O�Ƀ`���b�g�������ׂ�ςނ��ƂȂ�ł�����B����̐��i�Ɋ��҂��܂��B�T���i�� �T���i�� �T���i���B
2016.05.15 (��) ���̒� ���L������Ă����悤�ŁI�H with Ray�����
�@Ray�����A�N��3�ɂȂ����ˁB����Jiiji�Ƃ����ʂɂ��b�ł��邵�A�H�ו��ɂ��D���������Ȃ��B�g�}�g�A�ɂ�A�u���b�R���[�A���ԁA�����R���A�[���A�Ȃ�ł�������A���Ȃ̂͌Ӗ��������ȁB��You����̖ʓ|���悭�݂邵�A�������Ȃ��o�`�����ɂȂ��Ă����ˁB�@�Ƃ���ŁA���̐��̒��A�ǂ����ρB������watch���Ȃ��ƂˁB�N�����̖����͍��̎{���Ɍ������Ă���̂�����B
�@�܂��͓����s�m���C�Y�i�}�X�]�G�j����B�悾���āA�ʑ��s���Ɍ��p�Ԃ��g�p���Ă������Ƃ��o���đ�Q�āB���̑O�ɂ͖@�O�ȊC�O�o����B�܂����Ă��u���t�v�̃X�N�[�v�����B�����͂܂��A�{�l�H���u���[���ɑ����Ă邩����Ȃ��v�ł���������ǁA�����̐������������U�L�ڂ̓A�E�g���ˁB�Q�c�@�c�������2013�N��2014�N�̂������O�����ɉƑ��Ɛ�t�̉���z�e���ɑ؍݂����o��371,100�~���u��c��v�̖��ڂŋL�ڂ��Ă����Ƃ������́B�����ɂ܂��A�o��͏o��́B�u�����v�̖��ڂŊG����w������́A����߂��̃��X�g������V�n���X�A�ʑ��߂��̉�]���i�ł̉Ƒ��Ƃ̐H�������Ɍv��B�����ŐE���ɚ���̂̓}�N�h�i���h�������ŁA�������s�E��������ɃN�[�|�������ɍs������n���B��A�́g�Q�X�̋ɂݑ����h�ɁA���ɐ^�œo��̐}�I
 �@�����āA5�^13�̋L�҉�ŋ����̎ߖ��I �Ƒ����s����c��Ƃ��Čv�サ�����ɂ��Ă͂����̂��܂����B�u�m���ɉƑ����s���������A�ً}�ɕK�v�������A�Ƒ��Əh���������������ʼn�c���s�����B�ً}�̕K�v�Ƃ͑I���̂��ƂŁA���̓������Ȃ������B���͉�c�ƐS���Ă����̂ł����v�サ�����A��͂肩���Ȃ鍬���͂܂����Ǝv���A�����폜���ĕԋ����邱�Ƃɂ����v�B
�@�����āA5�^13�̋L�҉�ŋ����̎ߖ��I �Ƒ����s����c��Ƃ��Čv�サ�����ɂ��Ă͂����̂��܂����B�u�m���ɉƑ����s���������A�ً}�ɕK�v�������A�Ƒ��Əh���������������ʼn�c���s�����B�ً}�̕K�v�Ƃ͑I���̂��ƂŁA���̓������Ȃ������B���͉�c�ƐS���Ă����̂ł����v�サ�����A��͂肩���Ȃ鍬���͂܂����Ǝv���A�����폜���ĕԋ����邱�Ƃɂ����v�B�@�L�҂̎���u�N�Ɖ�c���s�����̂��H�l�������ł������Ă������������v�ɑ��Ắu�����I�ȋ@���Ɋւ�邽�߁A�͍����T�������v�Ƃ����B����������H�u�@�ɐG��Ȃ����فv��ٌ�m�Ƃ��߂����킹�������ł��傤�B�}�����炦�̃t�B�N�V����������A��������͂����Ȃ��B�Ƒ��Ƃ̈Ԉ����s�̕����Ő����I�@���Ɋւ��d�v�ȉ�c�ł����H �悭���܂������V���[�V���[�Ƃ���ȉR��������́B���̋ɂ݁I �����p���������݂��Ƃ��Ȃ��B�ڗ����݂݂������B����Ȍ����ʂ�Ɩ{�C�Ŏv���Ă�̂�����B��͂肱�̕��`���[�j���O�������Ă�B�{�l�͓����ꂽ����ł��邩������Ȃ����A���Ōł߂��R�Ȃǂ����o����B�t�ɕt�����ލޗ�����T����������̂��B
�@����ɂ��Ă��}�X�R�~�L�҂̊Â����Ȃ��ƁI�u��c�����o�[�̖��O�́H ���������I�@���ł����B��c�̌��ʁA�߂ł����s�m���ɓ��I�����̂�����A���O���������Ƃɉ��̎x�Ⴊ����́B���߂Ȃ�A�l�������ł������B 5�l�H10�l�H ���܂��̏�ł��������������Ȃ��Ɠs���͔[�����܂����B�ŁA����Ȃɑ厖�ȉ�c�Ȃ�c���^������͂��B�������肢�����v�B���ꂭ�炢�Ȃ��ƌ����Ȃ��̂��ˁB���Ȃ����͍����̑�َ҂ł��傤�B��X�̕����������Ƃ������Ǝ��₵�Ă���Ȃ��ƍ���Ȃ��B
�@���C�͎��Ԃ̖�肾�낤�ˁB�R�͕K���\�����B�^�J���̎��͑���������̂�����@���܂��܂������o��͂��B���t�ɂ���3�̖����悤���B6���ɂ͓s�c��n�܂�B�����͕K���B�@�I�ɓ�����Ă��s�M���Ƃ����s������̏d���ɑς�����͂����Ȃ��B����X�|�[�c���̒����ɂ��Ǝ��C���ׂ���93���������Ƃ��B���ɋ������Ă��A����2018�N�̓s�m���I�ł͕K��������B�����ܗւ̐��ꕑ������Ɖ����BRay�����A�ŋ߂̌��ȁA�����ӂ̈ꌾ���}�X�]�G����Ɂ��u�A�E�g����ˁI�v
�@��������̕��A�͂Ȃ����Ȃ��B�ނ̃P�[�X�́A�Ό����ォ��̊���Ŏ��������āA�������ɂ��ꎩ�̂܂����̂ł����A�[���̌�����̎d�����Ԉ�������߂ɃA���n���Ɋׂ��������B�u5000���~�͐��������B�L�ژR��ł����B�ނ�Œ������܂��v�Ǝӂ����Ⴆ�悩�������B�ނ̐����p���͌������B�����Ƃ̗����������A�ނ̂悤�ȃ^�C�v�͋M�d����Jiiji�͎v���B�ށA���͍��Z�̌�y�ȂB
�@Ray�����A�Ō�Ɉꌾ�B�K����Â̐��������K���@�̉��ł́A�g���[���K�����������@�h���������Ă���͂��B�}�X�]�G��P�[�X�͕X�R�̈�p���B���}�ɉ������ׂ����ˁB
 �@�C�̌����������炢���ƂɂȂ��Ă�ˁB�ǂ����h�i���h�E�g�����v�����a�}�̌��ɂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ������B����}�̓N�����g���Ō��܂肾�낤���ǁA5�^10�̃E�F�X�g�E�o�[�W�j�A�ł͔s�k�A�T���_�[�X���H���������ĂĂ܂����m���o�Ȃ��B���̗���A�����̍��B���[����肪�v�����ɂȂ肩�˂Ȃ��N�����g���B�g�����v�哝�̒a���̉\������������ттĂ����I�H
�@�C�̌����������炢���ƂɂȂ��Ă�ˁB�ǂ����h�i���h�E�g�����v�����a�}�̌��ɂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ������B����}�̓N�����g���Ō��܂肾�낤���ǁA5�^10�̃E�F�X�g�E�o�[�W�j�A�ł͔s�k�A�T���_�[�X���H���������ĂĂ܂����m���o�Ȃ��B���̗���A�����̍��B���[����肪�v�����ɂȂ肩�˂Ȃ��N�����g���B�g�����v�哝�̒a���̉\������������ттĂ����I�H �@�g�����v���i�̗��R�H �A�����J�������A�����J�̌�T�̗��j�ɋC�Â������ƁB�O���[�o�����A�x�T�w�̗D���A������N���A�j�s�g�U�̌��z�B���ʐ��܂ꂽ�̂́A�c��Ȋi���Ɣ���Ȏ؋��Ɛ��E�̍����B�ő�̍ߐl��IS�q�u�b�V�����B�I�o�}�����҂𗠐����B�ނ�������Change�ɑS�Ă����Ă������Č}�����̂�7�N�O�B�ނȂ�ς��Ă���邩������Ȃ��B����Ă���邩������Ȃ��B�ł������ς��Ȃ��B�C���c�蔼�N���̐��ˍۂŃ��K�V�[���ɂ����S�B����Ȃ����̐�����ς��Ă������Ă���I
�@�����Ƀg�����v�����ꂽ�B�A�����J�E�t�@�[�X�g�B�A�����J�̖��_�����߂��B�O�ɍ\���ȓ�����������B�R�������Ȃǂ�߂��܂��B����ȗ]�T�������ɂ͂Ȃ��͂����B�����̍��͎����Ō�点��B�k���N���������Ȃ�A���{���؍����j�����Ă����B�e�����X�g�̃C�X�������k�A�ٗp�����������L�V�R�l����������Ȃ��B���������L���Ȃ炻��ł������ĂˁB
�@�A�����J�̍�ȉƃ`���[���X�E�A�C���X�i1874�|1954�j�Ɂu�����̂Ȃ�����v�Ƃ����I�[�P�X�g����i������B�g�����y�b�g�̖₢�����Ƀ~���[�g��t�������y�킪������B�������o�Ȃ��܂ܐÂ��ɋȂ͏I���B
�@�g�����v�̉����͂܂��Ɂu�����̂Ȃ�����v�ł���B�����̏o�Ȃ�����Ɖ��Z�b�g�ɂ������悭�����邾���B�u�A�����J�l�̌ٗp�����������̃��L�V�R�l���D���Ă���B���Ⴀ�ǂ�����H�v������B�u�����ɒ���ȕǂ�z���B��p�̓��L�V�R�l�ɕ��킹��v���B�r�����m�Řb�ɂȂ�Ȃ��B�A�����ŏI���͂��B���ꂪ�ł���B�哝�̂ɍł��߂��j�ɂȂ��Ă���B�Ȃ����H �Љ�̕s�𗝂ɐ��ʂ�����������Ă��邪���Ƃ��̍��o�B�����̓L�e���c�ł�����N�͌����I�B�A�����J�̕���������i�V���i���Y�����h������B�ߌ��ȕ����������M�Ɖf��M����������B�s������薲��B������A�q�g���[�Ɠ���@�I�H �A�����J�̕a��������B
�@�g�����v�l�C�̖{���́H�u�{���v�u���s�́v�u��~�i�V�v�����������邱�ƁB�Ђ��t���łȂ����Ȏ����L�x�ɂ��u�{���v��������B�u���s�́v�����肻���ɉf��B��������ĉ������̐��������߂����Ƃ��Ă���B�����Ɍ����悤�Ƃ��A�����J�̖��_�����悤�Ƃ��Ă���B����́u��~�v����Ȃ��B�܂₩���ł��\��Ȃ��B�x����Ă�낤����Ȃ����B
 �@Ray�����A�c���p�h�u�[�����������ˁB�Ό��T���Y���������u�V�ˁv�i���~�Ɂj��70�����̃x�X�g�Z���[���L�^���Ă���Ƃ��BJiiji�́u���z�̋G�߁v�����ނ̍�i��ǂ�łȂ��āA���̂Ƃ����������͂̒t�ق��Ƌ��Ȏv�z����A�����Ă܂œǂދC�����ĂȂ��������ǁA�悭�������̂ŁAI�搶���݂��Ă����������BJiiji�B��̊S���́A��t���̈������ɂȂ���1972�N�A�������ł̊p�h����̌y����ʂ��������A�c�O�Ȃ���Ȃ�̋L�q���Ȃ��������B���ꂪ�m�F�ł��������͓ǂޕK�v���Ȃ��̂��B
�@Ray�����A�c���p�h�u�[�����������ˁB�Ό��T���Y���������u�V�ˁv�i���~�Ɂj��70�����̃x�X�g�Z���[���L�^���Ă���Ƃ��BJiiji�́u���z�̋G�߁v�����ނ̍�i��ǂ�łȂ��āA���̂Ƃ����������͂̒t�ق��Ƌ��Ȏv�z����A�����Ă܂œǂދC�����ĂȂ��������ǁA�悭�������̂ŁAI�搶���݂��Ă����������BJiiji�B��̊S���́A��t���̈������ɂȂ���1972�N�A�������ł̊p�h����̌y����ʂ��������A�c�O�Ȃ���Ȃ�̋L�q���Ȃ��������B���ꂪ�m�F�ł��������͓ǂޕK�v���Ȃ��̂��B�@���~�ɁE����O�K�E�d�|���l�Ɛ��E�̃X�^�[�Ό��T���Y���g��ŁA�Y�b�R�P�����ƃI���p���[�h�̍����̐����ɁA�H��̐����ƁE�c���p�h���l�^�ɗh���Ԃ��q����Α�O�̓C�`�R���ł���B���ꂼ�q�b�g�̖@�����̂��́B
�@�J�Ԍ����Ă����g�R���s���[�^�[�t���u���h�[�U�[�h�g�l���炵�̒B�l�h�Ȃ�p����]�́A�܂��ɐ}���B���ҐΌ��T���Y�́u�挩���ɖ��������z�̐��m���v�i5�^4�����V���j�Ƃ܂Ƃ߂Ă��邪�A�L���b�`�[����Ȃ��ȁB
�@Ray�����AJiiji�͂����v���B�p����̍ő�̂悳�́A�u��~���Ȃ��������Ɓv����Ȃ����ƁB�����ɂ����Đ��͗͂Ȃ肾����A�����u�����҂������łȂ��҂����w�c�Ɉ�������遁���r�B���̂��߂ɂ͑���̐S��h�݂͂ɂ��遁�l���炵�B�I���ɏ����ߏ������邽�߂ɋ����g�������������B�����������A����͂����܂ł���i�B�ړI�͓��{�����ς��邱�ƁB���W����_�C�i�~�b�N�ȍ��Ɉ�Ă邱�ƁB�����������������āB�����ɉ�~�͂Ȃ��B�g�����̍K���̂��߁h������݂̂��B�������}�X�]�G�Ƃ̈Ⴂ�B�܂��A��ׂ�͎̂���ł����B
�@�g�����v������ɋ߂��B���͗~�Ɩ��_�~�͂��邯�Nj��K�~�͂Ȃ��B���͗~�Ƃ͑哝�̂ɂȂ邱�ƁB�ނ̖��_�Ƃ̓A�����J�̕������B��������������K�~�͂Ȃ��B�Ƃɂ����A�������̗��v�Ɍq����Ȃ炻��ł����B���Ȃ��Ƃ�����܂ł̂Ђ��t���R���哝�̂��͂���Ă��ꂻ���ȋC������B���ꂪ�A�A�����J�̎�N�w�E�n���w�̖{���Ȃ̂��B
�@Ray�����A�g�����v���哝�̂ɂȂ�����A���{�͍���݂�������BJiiji�͕��C�����ǂˁB���{�́u�킪�����j�����킯���Ȃ��v�u���Ĉ��ۂ͐���v�Ǝ����̂悤�ɏ��������B�Ό��T���Y�͊j�ۗL�_�ҁB���ׂ̋������́u�k���N�͊j�ۗL���ƂȂ������A�搧�U�������邽�߂ł͂Ȃ��B�o�����X���ێ������a��ۂv�Ɠ}���Ő錾�����B�ȂA����ۗL��i���Ɠ����䎌�ł͂Ȃ����B�k���N�͗��ɓK���B�A�����J�哝�̂��u�j�̂Ȃ����E��ڎw���v�Ƃ��ꂢ���ƌ����ăm�[�x���܂�����������A�n���ł͍ŐV�j����̊J��������B�V���Ȋj�J���������B���̖����I�u�����Ȃ�p�����Ă��猾���v�͐^�����B
�@���{�͊j�ƁA�^�u�[�������ɁA���������ׂ��ł͂Ȃ��낤���B�A�����J�̎����哝�̍ŗL�͎҂��A�u�������������Ȃ��B���q�͎��͂ł��v�Ƃ����Ȃ�A�c�_���邵���Ȃ����낤�B��i���Ŏ��q�𑼍��ɔC���Ă���͓̂��{�����B�g�����v�̌������͓I�O�ꂶ��Ȃ��B�u9������v�ƌ�����������A���̉����ɂ��Ȃ�Ȃ��B�܂��A���{�̈��S�ۏ�͂ǂ�����x�����H��^���ɍl���邱�Ƃ��B��9���̋c�_�͂��̎����B���{���A������ ���肦�Ȃ� ���茾���ĂȂ��ŁA�g�����v�̑䓪�����̍D�@�Ƒ����邱�Ƃ��B
�@�A�����J�R���P�ނ�����ǂ�����H ��25���l�̎��q�����B���Ɖ��l�K�v�Ȃ́H ����͂��̂܂܂ł����̂��B�j�͂ǂ�����B�������́B���@�ւ̏[���́B���̂��߂ɖh�q��5���~�ɂ������ς݂��K�v�Ȃ́H �����͂ǂ�����B�ڐ�̍팸�A����ő��ł���Ԃɍ���Ȃ��B�����ȗ��̈����E�����̐��̑Ŕj�E���v�B�����A���ʉ�v200���~�̐���������Ȃ����낤�B10����20���I �h�q��͂����ɋy�������Ă��̌��Ď����͉�������BRay�����A�����́A���a�{�P����ڂ��o�܂������@��A��Jiiji�͎v���B
2016.04.25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�7�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ñ��̎����Ȃ�������u���˂̉ԉŁv�͒a�����Ȃ������I�H
�@����̃e�[�}�́u���ȁw���˂̉ԉŁx�a���̗��ɂ͒Ñ����́w���˂̗����x���������v���Ƃ̏ؖ��ł���B���̂��߂ɂ́A�g�쎌�ҁE�R��H�v�͉��炩�́u�O���v���Ȃ���u���˂̉ԉŁv�Ȃ鎌���������Ƃ��ł��Ȃ������h���ƁA���́u�O���v�������Ñ��́u���˂̗����v�ł��邱�ƁA���ؖ���������B �@�R��H�v�i1936�|�j�͓��{���\����쎌�Ƃł���B�I���R�����쎌�ƕʃV���O���E�q�b�g�E�����L���O��10�ʁi���Ȃ݂Ɍ��݁A1�ʂ͏H���N�A2�ʈ��v�I�A3�ʏ��{���j�B
�q�b�g�Ȃ͎v�������ׂ邾���ł��A���E�͓�l�̂��߂Ɂi���ǒ���1967�j�A�p�Ђ̔��i�U�E�^�C�K�[�X1968�j�A�閾���̃X�L���b�g�i�R�I������1969�j�A������ˑR�i�g���E�G�E���A1969�j�A�������������i�Ԃ���1971�j�A���˂̉ԉŁi�������~�q1972�j�A�w���X�̋i���X�iGARO1972�j�A�ЂȂ����̉ԁi�A�O�l�X�E�`����1972�j�A������Ă̓��i�V�n�^��1973�j�A��l�ł������i���݂���1974�j�A���߂���i�R�{�R�E�^���[1974�j�A����ɂāi�]���`�G�~1974�j�A���S�����i����ܘY1975�j�A�K���_�[���i�S�_�C�S1978�j�Ȃǖ����ɉɂ��Ȃ��B
�@�R��H�v�i1936�|�j�͓��{���\����쎌�Ƃł���B�I���R�����쎌�ƕʃV���O���E�q�b�g�E�����L���O��10�ʁi���Ȃ݂Ɍ��݁A1�ʂ͏H���N�A2�ʈ��v�I�A3�ʏ��{���j�B
�q�b�g�Ȃ͎v�������ׂ邾���ł��A���E�͓�l�̂��߂Ɂi���ǒ���1967�j�A�p�Ђ̔��i�U�E�^�C�K�[�X1968�j�A�閾���̃X�L���b�g�i�R�I������1969�j�A������ˑR�i�g���E�G�E���A1969�j�A�������������i�Ԃ���1971�j�A���˂̉ԉŁi�������~�q1972�j�A�w���X�̋i���X�iGARO1972�j�A�ЂȂ����̉ԁi�A�O�l�X�E�`����1972�j�A������Ă̓��i�V�n�^��1973�j�A��l�ł������i���݂���1974�j�A���߂���i�R�{�R�E�^���[1974�j�A����ɂāi�]���`�G�~1974�j�A���S�����i����ܘY1975�j�A�K���_�[���i�S�_�C�S1978�j�Ȃǖ����ɉɂ��Ȃ��B�@�W�������́A�̗w�ȁA���́AGS�A�t�H�[�N�A�A�C�h���AJ�|�b�v�ɂ킽�蕝�L���B�앗�͗���搂����̂������^�b�`�͏�i�B����������i�������B
�@�R�㎁�̏��q�b�g�́u���E�͓�l�̂��߂Ɂv�����A�f�r���[�Ȃ́u���v�B���̋Ȃ͏����a�q����싪�̃f���G�b�g�E�\���O�ŁA�g�c���̍�ȁB��̓s���ɂ����j���̔M��������B���N�̑�q�b�g�ȁA�����a�q���t�����N�i��́u�����i�C�g�N���u�v�Ɍq����H���ł���B
�@�ł́A�g�R��H�v�͉��炩�́u�O���v���Ȃ���u���˂̉ԉŁv�Ȃ鎌���������Ƃ��ł��Ȃ������h���Ƃ̏ؖ��ɓ���B
�@�u���˂̉ԉŁv�̍ő�̓����͒n������B�����u�����n�\���O�v�ł���Ƃ������ƁB�����Łu�����n�\���O�v�̒�`��_���Ă��n�܂�Ȃ��̂ŁA�g�n���̓������̂̌ď̂Ƃ��ĕ֗��Ȃ̂Ŏg�p����h�Ƃ������x�ł��e�͊肢�����B
�@�u�O���v���Ȃ������珑���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ́u�����I�ɂ͏������Ȃ��v�ƌ�����������B�Ȃ�A�R�㎁�̍�i�Ɂu���˂̉ԉŁv�ȊO�́u�����n�\���O�v�����邩�ۂ��A������������B����A�u���˂̉ԉŁv�������I�ɏ����������ƂɂȂ邵�A�Ȃ���u�O���v���Ȃ���Ώ����Ȃ��������ƂɂȂ�B
�@�ł́A�R�㎁�ɂ́u���˂̉ԉŁv�ȊO�̂����n�\���O�͑��݂���̂��A��T���Ă݂悤�B
�@�R�㎁�Ɂu���˂̉ԉŁv�ȊO�̂����n�\���O�����邾�낤���H ���_���猾�����B�R��H�v�̍�i�ɂ́u���˂̉ԉŁv�ȊO�́u�����n�\���O�v�͑��݂��Ȃ��B�ނ̍�i���������邩�͒m�炸�A�S�����������킯�ł͂Ȃ�����ǁA�܂�����͊ԈႢ�Ȃ����̂Ɗm�M����B
 �@�Ȃ�A�u�����̏��v�i�U�E�s�[�i�b�c1971�j�Ɓu��ド�v�\�f�B�[�v�͂ǂ��Ȃ̂��H �Ƃ̋^�₪�������Ă��������B����ɂ��Ă͂����������������B
�@�Ȃ�A�u�����̏��v�i�U�E�s�[�i�b�c1971�j�Ɓu��ド�v�\�f�B�[�v�͂ǂ��Ȃ̂��H �Ƃ̋^�₪�������Ă��������B����ɂ��Ă͂����������������B�@�����o�g�̎R�㎁�ɂƂ��āA�u���������v�Ȃ鎌�������Ă�����s�v�c�͂Ȃ��B�g�߂��s��́u���������v�Ƒa�����n���́u���˂́����v�ł͐ړ_�͊B�ʘg�ƍl���Ă������낤�B
�@�ł́A�u��ド�v�\�f�B�[�v�ɂ��āB���̉̂͂��Ƃ��ƎR�㎁�̔��z�ł͂Ȃ��B�����̃r�N�^�[�̃f�B���N�^�[�E�ߓc�N�玁���A��O�̑�q�b�g�ȁE���R��Y�́u�������v�\�f�B�v�̃p���f�B�[�Ƃ��Ĕ��Ă������́B�����˃R���r�C���痢�����ɉ̂킹���A����Ί�惂�m�ł���B�R�㎁�͒ߓc�f�B���N�^�[�̔����ɏ]���ď����������B�Ώۂ���O���Ă����B
�@�R�㎁�͓������܂�̓����炿�B�c���̍�����̂��キ���ʂ̉�Ћ߂��������������ߍ쎌�Ƃ�ڎw�����Ƃ����B����ȎR�㎁������A�n���ւ̗��ȂǂقƂ�njo�����Ȃ������͂��B�n�����o�Ƃ������̂�̎��I�Ɏ����Ă��Ȃ������I�H ����́A�ނ̍�i�Q�������ڗđR�ł���B
�@�R��H�v�͎����I�ɂ����n�\���O�������f�{���������Ȃ��B�ނ̎����I���z����́u���˂̉ԉŁv�͐��܂꓾�Ȃ��B�u���˂̉ԉŁv�́A���炩�́u�O���v���Ȃ���Ώ������Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B
�����̍쎌�Ƃ������遄
�@�����A����ł͂܂��s�\���B���𑼂̍쎌�Ƃւ��g����K�v������B�R�㎁�Ɠ��X���̍쎌�Ƃ͂ǂ����������H �����ނ�̍�i�Ɂu�����n�\���O�v�����݂��Ȃ���A�R�㎁�ɓ��ِ��͂Ȃ����ƂɂȂ�B�t�ɔނ�̍�i�ɁA�u�����n�\���O�v�����ʂɑ��݂���̂ł���A�R�㎁�́g�����n�\���O�Ȃ��h�́A�R�㎁�Ǝ��̐����Ɣ��f�ł��邾�낤�B
�@����ł́A�N�Ɗr�ׂ邩�B�R�㎁�Ɠ��X���̍쎌�Ƃ����B�L�C����[�h�́A������A������A���W�������A�q�b�g�ȗʎY�A�t���[�쎌�ƁB�H���A1930�N�㐶�܂�AGS�`�̗w�ȉ��������1960�\80�N��𒆐S�Ɋ����t���[�쎌�ƁE�q�b�g���[�J�[�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B
�@�����ɊY������쎌�ƂƂ��āA���v�I�i1937�|2007�j�A�Ȃ��ɂ���i1938�|�j�A���{�~�i1939�|�j����グ�����B����3�l�Ȃ當��͂Ȃ��낤�B�܂��ɉ̗w�j���ʂ������쎌�Ƃ�������ł���B
�����v�I�̃P�[�X��
�Ìy�C���E�~�i�F�A�k���A�\�o�����A�L�㐅���A�ዷ�̏h�A�����������{�C�A�{�q�����w���A�Ó숣�́A���s���甎���܂ŁA���s�̏��̎q�A���捻�u���̐l�A�݂��䂫������ etc
�@���������v�I�A���ɑ��ʂȁu�����n�\���O�v�Q�ł���B���v�͎R�㎁�̈�Ή��̓�����q�b�g���[�J�[�B����ɓn��W�������͋��ʂ����A�Ⴂ�͉��̂̔䗦�B���v�I�̂ق������|�I�ɍ����B�����o�g�̎R�㎁�ƒn���o�g�i���Ɍ��W�H���j�̈��v�Ƃ̍����H
���Ȃ��ɂ���̃P�[�X��
�Ύ�҉́A�Ìy�ցA���̂ɂ킩�J�A���u���[�X�A�T���i�����l�A�悱�͂ܕ��� etc
�@�Ȃ��ɂ���͑��ʂȍ�Ƃł���B���s�̂̍쎍�ƂɂȂ�܂ł̓V�����\���̖ƂƂ����B�N���V�b�N���y�ɂ����w���[���B�����ɓ����Ă���͍�Ƃɓ]�i�A2000�N�ɒ��؏܂��l�����B���悻�u�����n�\���O�v�ɂ͉��̂Ȃ������ȃ^�C�v�����A����ł���L�̍�i������B
�����{�~�̃P�[�X��
�ԑ��q��S�A�Ìy�̊C�A�J�̌y���A�_�˂Ŏ��˂���A���s�_�ˋ���A���̏��A�������ł̒���A�u���[���C�g�E���R�n�}�A�J�̃��R�n�}�A�r���[�e�B�t���E���R�n�} etc
�@���{�~�̍앗�́AGS�̃V���{���ȁu�u���[�E�V���g�E�v�ɑ�\�����悤�ɁA�m�y�u���������B���Ƀo�^�L���B����ȍ앗�Ȃ̂ɂ��ꂾ���́u�����n�\���O�v������B
�@���������낤���H �����̂悤�ɁA��L3�l�̃q�b�g�쎌�Ƃ͂��Ȃ�̐��̂����n�\���O�������Ă���B���݂Ɉꐢ�㉺�̔�����q�E���{���ł��A�u�ނ�����v�l�v�u��E��E�� �Ó�v�u���R�n�}�E�`�[�N�v�Ȃ��i������B
 �@�Ȃ̂ɁA�R��H�v�͂����n�\���O����؏����Ă��Ȃ��B�B��u���˂̉ԉŁv�������ẮB���̎����́A�u���˂̉ԉŁv���R��H�v�̍�i�Q�̒��ŋɂ߂ē��قȑ��݂ł��邱�Ƃ��B����ɂ��̂��Ƃ́A�g�u���˂̉ԉŁv���a�����邽�߂ɂ͉��炩�́w�O���x�������h���Ƃ̏ؖ��Ȃ̂ł���B
�@�Ȃ̂ɁA�R��H�v�͂����n�\���O����؏����Ă��Ȃ��B�B��u���˂̉ԉŁv�������ẮB���̎����́A�u���˂̉ԉŁv���R��H�v�̍�i�Q�̒��ŋɂ߂ē��قȑ��݂ł��邱�Ƃ��B����ɂ��̂��Ƃ́A�g�u���˂̉ԉŁv���a�����邽�߂ɂ͉��炩�́w�O���x�������h���Ƃ̏ؖ��Ȃ̂ł���B�@�����āA���́u�O���v�������A�Ñ����́u���˂̗����v�������̂ł���B����͑O�͂����ǂ݂���������Ζ��炩���낤�B�Ñ��̎G���u���}�v�ւ̉���Ɓu���˂̉ԉŁv�����[�X�Ƃ̎��n��I�֘A�B�J�ԗ��z����u���˂̉ԉŁv�a����b�Ƃ̕����B�̎��̋��ʓ_ etc�B
�@�����I�Ɂu�����n�\���O�v���������Ȃ��쎌�ƁE�R��H�v�͒Ñ����́u���˂̗����v�Ƃ����G�������i�ɐG������āu���˂̉ԉŁv���������Ƃ��ł����̂ł���B��������A���a�̗w�̖��ȁu���˂̉ԉŁv�͒Ñ����́u���˂̗����v���Ȃ�������A���̐��ɐ��܂�邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�{�_�͍������ł͂Ȃ��B�܂��Ă�A����ȂǂƂ�������͖ѓ��Ȃ��B����ɕq���ł���ׂ��쎌�Ƃ͏�ɐV����������{�����߂Ă���B�{�_�R�㎁�̃P�[�X���쎌�ƂƂ��ē�����O�̍s�ׂ��B�R�㎁�́u�ԉŁv�ƒÑ��́u�����v���r�ׂ�A���炩�ɑO�҂������Ă���B�v���ƃA�}�̍��ł���B������Ñ��́u���˂̗����v������X�^�b�t���L���X�g�Ő��ɏo���Ƃ��Ă��A�u���˂̉ԉŁv�̐����ɂ͋y�Ԃׂ����Ȃ��������낤�B
�@�����ꌾ�B�Ñ��̍�i���u���˂̉ԉŁv�Ƃ������̖��Ȓa���Ɉ���Ă����B���̂��Ƃ��������߂Ă����������������ł���B�������̐t�̃������A���Ƃ��āB
[���܂�]
 �@�R��H�v�B�쎌�ƁB1936�N���܂�B�����s�o�g�B1959�N�u���}�v�́u�����a�q�̂������� �̎���W�v�։���B�����i�u���v��1�ȓ��I�B�s��̒j���̗�����B�g�c���̍�Ȃŏ����a�q����싪�̃f���G�b�g�ŃV���O���Ք����B
�@�R��H�v�B�쎌�ƁB1936�N���܂�B�����s�o�g�B1959�N�u���}�v�́u�����a�q�̂������� �̎���W�v�։���B�����i�u���v��1�ȓ��I�B�s��̒j���̗�����B�g�c���̍�Ȃŏ����a�q����싪�̃f���G�b�g�ŃV���O���Ք����B�@���N9���A�쎌�����F�v�E��ȋg�c���̃R���r�A�����a�q���t�����N�i��̃f���G�b�g�Łu�����i�C�g�N���u�v�����B�s��̃i�C�g�N���u�ɍ炭������B��q�b�g�B
�@�Ñ����B��Ј��B1945�N���܂�B���ꌧ�o�g�B1972�N�u���}�v�́u�������~�q�̂������� �̎���W�v�։���B�����i�u���˂̗����v���I�B���˓��C���� �����̗��S�B
�@���N4���A�쎌�R��H�v�E��ȕ������W���̃R���r�A�������~�q�̉S�Łu���˂̉ԉŁv�����B���˓��C���� �ԉł̐S��B��q�b�g�B
2016.04.10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�6�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����B�t�̒u���y�Y
�@�O��܂ŁA�Ñ����̑�����A�u���˂̉ԉŁv�����[�X�܂ł̌o�܂����Ă����B�쎌�Ƃ��u���Ñ����A�����⎩���̍�i���̗p���ꂽ�̂ł͂Ȃ����H�Ǝv���Ă��s�v�c�̂Ȃ����ۂ����������B1972�N�� �G�����}�ցu���˂̗����v������`2���� �����X�|�[�c�Ɂu���˂�����v�̗\���L���`3��24�� ���\�����̕�A�Ƃ�����A�̗���B�����A4��10���u���˂̉ԉŁv���R��H�v�̍쎌�i��Ȃ͕������W�j�Ń����[�X�A�Ƃ��������ɏI������B�@����́A������쎌�ƁE�R��H�v���̑�������l�@���Ă݂悤�B�{���͓���ȂǂƂ��������ȈČ��ł͂Ȃ�������������Ȃ��B������L�b�J�P�ƂȂ�����������Ȃ��A�Ƃ������x�̂��̂��B����ł��A���ȁu���˂̉ԉŁv�ɐe�F�E�Ñ����̃A�C�f�B�A�������Ȃ�Ƃ��ւ���Ă��邱�Ƃ��𖾂ł�����A����͂���Ŋ������ł͂Ȃ����B���ꂼ�t�̒u���y�Y�ł��肻�̉𖾂ւ̎��s�������������̗F��̏ɑ��Ȃ�Ȃ��A�Ǝv����̂ł���B
�����˂́u�����v�Ɓu�ԉŁv�̋��ʓ_�A�����Đt�̒u���y�Y��
 �@�Ñ����̏������u���˂̗����v�̃V�`���G�[�V�����͈ȉ��̒ʂ�
�@�Ñ����̏������u���˂̗����v�̃V�`���G�[�V�����͈ȉ��̒ʂ��@���͐��˓��C�̏����ɏZ�ޕ�e�Ɠ�l��炵�̏��̎q�B�ނ͂܂��A�F�B�ȏ���l�ȑO�̑��݂ɉ߂��Ȃ��B3�����O�ɓ����o�Ė{�y�ɏA�E�����B���19�ʼnł��ł�������A�����N���ɂȂ��������C�ɂ����Ă���B�ł��A����ȕ�e�ɔނ̖��O�͂܂������Ȃ��B�ނ���Җ]�̎莆�������B�����ɂ́u���̋x�݂ɂ͋A��v�Ə����Ă���B���҂ɋ����c��ށB���́A���˂̗[��Ɂu���̗��������āI�v�ƋF��B
�@�R��H�v�́u���˂̉ԉŁv�͈ȉ��̒ʂ�
�@���͐��˂̂Ƃ��铇�ɏZ�ޏ��̎q�B�ʂ̓��ɏZ�ޔނ̂��Ƃ֍������łɍs���B�c����́u�s���ȁv�Ƌ����B�j�������狃�����肹���ɕ�����ꂳ���厖�ɂ��Ă˂Ɨ@���B���܂ꂽ���ɕʂ�������ނ̏Z�ޓ��Ɍ������B���Ȃ��Ƃ��ꂩ�琶���Ă䂭�̂��B���˂̗[�Ă��͓�l�̖�o���j���Ă���Ă���B
�@���ʂ��郏�[�h��o���Ă݂悤�B�O�҂��Ñ��A��҂��R�㎁�ł���B
�u��v�Ɓu�ꂳ��v�@�Ñ��̃P�[�X�͌����S�҂��A�R�㎁�͉̂ł��䂭�ԉłƂ�����{�I�ȈႢ�͂��邪�A���䑕�u�͋����قǎ��ʂ��Ă���B��тƂ��A���˓��C�̓��ɏZ�މœ���O�̖��̐S����A�Ƒ��ւ̎v�������ߔ��������R��w�i�ɁA��l�̂ʼnr�������Ă���B
�u19�v�Ɓu�Ⴂ�v
�u�ł����v�Ɓu���łɍs���v
�u���˂̗[��v�Ɓu���˂͗[�Ă��v
�u���Ȃ��v�u���v�͓����
������ߒ��͂��遄
�@�܂��́u���˂̉ԉŁv�a���ɓZ��闠�b�����f�B�A���甲�����Ă݂悤�B

�����͏����O�ɁA���~�q�Ɂu���A���łɍs���́H�v�ƕ��������Ƃ�����B��ˉ��y�w�Z����Ȃő��Ƃ����قlĵɓq���Ă������~�q�́A�����ς�ƕԂ��B�u���͍s���܂���B�ꐶ�A�̎�ł�������ł��I�v
���̈ꌾ�����������ŁA�����̐S�ɂЂƂ̃A�C�f�B�A�����܂ꂽ�B�Ԃ��Ȃ�20���}���郋�~�q���A���߂ĉ̂̒��Łu�œ���v�����Ă�낤�Ƅ����B
�쎌�Ƃ̎R��H�v�́A���̈˗��ɂ������A��������Ă��܂��B�u���������ł��B�œ�����̂����w���̉ԉŁx�ƁA���˓����e�[�}�ɂ����w���˂̗[�Ă��x�ƁB�Ƃ��낪�A�ǂ����s���Ɨ��Ȃ��̂ŁA�f�B���N�^�[�̉��苪����Ɠ�l�Ń\�t�@�[�Ɉ�������Ԃ��Ă��܂����v
�ƁA���̏u�Ԃ������B����Ȃ�Γ�����킹�āu���˂̉ԉŁv�ɂ��Ă��܂����ƁB���̒�Ăɉ�����u���ꂾ���I�v�Ɛ����r�炰�A����������i�����n�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�A�T�q�|�\�v2013�N12��5�����j

�u���˂̉ԉŁv����͂�����Ղł��ˁB���������Ȃ�ł��B���ʂ͋Ȑ悩���悩 �Ȃ�ł��ˁB�����搶���R��搶���܂������ʂ̂Ƃ���ō��n�߂āA�t���Ƃ�������������s�^���ƍ�������ł��B������Ď��͒����������܂����B�@��L���璍�ړ_��v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i NHK�|BS�u���a�̗w��������F�������W�̐��E�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2014�D9�D14 OA �������~�q�k�j
�@�ŏ��̃R���Z�v�g�́g�ԉŁh�������B
�A�R�㎁�́u���̉ԉŁv�Ɓu���˂̗[�Ă��v�̓��p�ӂ����B
�B�Ñ��́u���˂̗����v�͏��Ȃ��Ƃ�1�����߂ɂ͊������Ă��邪�A�R�㎁�́u���˂̉ԉŁv�����]�Ȑ܂��o�āA���������̂͑����Ĉꌎ���B�Ñ�����ŎR�㎁����Ȃ͖̂��炩���B
�@��L���b�́A���o�������̊����Ȃ����Ȃ������Ȃ��Ƃ����n��I�ɊԈႢ�͂Ȃ����낤�B���e���T�ːM�ߐ��������Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�R���������b�g���K�v�����Ȃ����炾�B������Ђ������镔��������܂��āc
�c�B����́A�u���̉ԉŁv�ɂ͖��m�ȑn�엝�R��������Ă��邪�u���˂̗[�Ă��v�ɂ͂Ȃ��A�Ƃ�����_���B�v���̍쎌�ƂȂ̂�����ǂ�Ȏ�����낤���s�v�c�͂Ȃ��͂��A�Ȃ������ɂ������̂��H �Ƃ̐����������Ă��������B�ނ��ł���B�����������A�u�R�㎁�͓Ǝ��ɂ́w���˂́����x�Ȃ鎌�͏������Ȃ��v�Ƃ��閾���ȍ���������B����͎���Ŏ������Ƃɂ��邪�A�v����Ɂg�R�㎁�͉��炩�̃L�b�J�P���Ȃ���u���˂̗[�Ă��v���u���˂̉ԉŁv���������Ƃ͂ł��Ȃ��h�Ǝ��͍l���Ă���B����A�����m�M���Ă���B���̃L�b�J�P�������Ñ��́u���˂̗��́v�������A�Ƃ����̂����̌��_�ł���B�ł́A���̃X�g�[���[���܂Ƃ߂Ă݂悤�B
�������~�q�̑�4�e���ǂ����邩�H �n�Ӄv���`���[�i�[�p�C�I�j�A�w�c�ɂƂ��Ă���� �傫�Ȗ�肾�����B�O�N�̃f�r���[��u���̏鉺���v���~���I�����L�^�����������������A����ɑ����u���Ղ�̖�v�u�Ⴀ����̒��v�͂�����B�w�c�ɂƂ��đ�4��͏�����A���s�͋�����Ȃ��A�܂��ɔw���̐w�������B��Ȃ͕������W�A�쎌�͎R��H�v�Ɍ���B��������u���˂̉ԉŁv�a���̓�Y���n�܂����̂ł���B�@�ȏオ�A�����\�z�����u���˂̉ԉŁv�����`�����܂ł̌o�܂ł���B���n��ɊԈႢ�͂Ȃ��A���e���قڃ��f�B�A�I�o�ɏ����Ă���B�����A�R�㎁�́u���˂̉ԉŁv�쎌�̉ߒ��Ɏ��I�Ȑ����������Ă���B�����ɂ͎����������Ȃ��B�����炱��͍��̂Ƃ��뉼���̈���o�Ȃ��B�����A�����u�R��H�v�͒Ñ����́w���˂̗����x������Ȃ��Q�l�ɂ��āw���˂̉ԉŁx���쎌�����v�ƒf���ł���B����͂��̍������J�������Ă��������B
1971�N12��24�� �����u���}�v2�����Ɂu�������~�q�̂������́v��W���f�ڂ����B�����1972�N1��31���B���I���\��3��24�������5�����B����̓��[�i�[�p�C�I�j�A�E���R�[�h���암�B
1972�N1�� �u���}�v�������Ñ����́A�u���˂̗����v���쎌�A���傷��B3���ɂ͎R�z�V���������R�܂ʼn��т�B�u�Ⴀ����v����u���˓��v�ւ̓]���͏����ɐV���n�������炷�͂��A�Ɠ���ł̂��̂������B
������ ��Ȃ̕������W�A�쎌�̎R��H�v�A�n�E�X�E�f�B���N�^�[�̉��苪���������~�q��4�e�V���O���̃R���Z�v�g��c���J���B��������u���~�q���̂̒��ʼnԉłɁv�̈Ă��o��B�R��͑������|����u���̉ԉŁv���쎌����B
2�� �R�オ�A�u���̉ԉŁv������ɒ�o�B����[�������B����A1�������ߐ�̕��}�����̓��[�i�[�p�C�I�j�A�̉�c���ɏW�܂��Ă����B���̐�13���]�B
����A�����i���ᖡ�B���̎�̕�W��V�Ȃ̃q���g�ɂ���̂͋ƊE�̏펯���B�����Ă����i�ɖڂ����܂�B�^�C�g���́u���˂̗����v�B����s���Ƃ�����̂�����A���R��ɘA���B�u���˓���Ɏ��������ė~�����v�ƈ˗��A�����Ɂu���˂̗����v�̉̎���n���B�R��A�������Ɂu���˂̗[�Ă��v���쎌�A����Ɏ��Q�B����ƎR�� ���Ɋ������Ă���u���̉ԉŁv�ƕ��ׂČ����B�����ō��̈Ă��o�āu���˂̉ԉŁv�Ȃ�^�C�g�������܂����B
�R��́A���A��ƂɎ��|����B������ߐ肪�߂����߁A����́A���s���ĕ����ɍ�Ȃ��˗��B�g����͐��˓��B�^�C�g���́u���˂̉ԉŁv�h�Ɗm�F�̏�ŁB�������Ď��ƋȂ͕ʁX�ɓ����i�s�ō��ꂽ�B�o���d�オ���ĕt�����킷�Ǝ��Ȃ��s�^���ƍ��v�B�u���˂̉ԉŁv��Ղ̒a���ƂȂ����B
2��28�� �����X�|�[�c�ɁA�R���T�[�g�̏ڍׂ�`����L�����o��B�����Ɂu���~����x�͉ԉł���v�Ȃ�V�ȍ��m���B�Ñ��́A����͎����̍�i�ł͂Ȃ����H �Ƒ����_����B
3��24�� �u���}�v5�����ɁA�u�w�������~�q�̂������́x�͌��ݐR�����̂��ߓ��I�Ҕ��\�͎����ƂȂ�v�|�f�ڂ����B�Ñ��b��B
4��10�� �������~�q�̑�4�e�V���O���u���˂̉ԉŁv�i�쎌�F�R��H�v ��ȁF�������W �ҋȁF�X������Y ���[�i�[�p�C�I�j�A�E���R�[�h�j�����������B
4��24�� �u���}�v6�����ɁA���I�삪���\�����B�����ɒÑ��̍�i�͂Ȃ������B
2016.03.25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�5�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����A�Ñ��A��̂����̊ԁI
�@1972�N2�����̂�����A���i���C�[�X�^���̈�p�ŒÑ������ɂ����������B�C�[�X�^���͐V���̉w�߂ɂ��郌�R�[�h�c�ƃ}���̂��܂��ł���B�u�����X�|�[�c�ɏ����̃R���T�[�g�L�����o�Ă��Ă��B���x�̃V���O���͐��˓��C�����䂾�Ƃ�������Ȃ����B���������ĉ��́w���˗��x�����I������Ȃ����ȁv�B���̃g�[�������Ȃ�ジ���Ă���B�u����͂��邩������Ȃ��ȁv �����������������Ă����B�Ñ����G�����}�ɉ��債���u���˂̗����v�́A��X�̊Ԃł́u���˗��v�Ɖ]���悤�ɂȂ��Ă����B���㔭�\��3��24��������5�����B���ƈꃖ�����炸�B���҂ɋ����ӂ���B�����āA �@3��24�������̕��}5�����ɂ͂���������Ă����B
�@3��24�������̕��}5�����ɂ͂���������Ă����B�@�@�@�@[����тƂ��m�点]
�@�@�@�@�{���Łu�썹�D�̂������́v�Ɠ����ɓ��I���\�̗\��ł������A
�@�@�@�@�u�������~�q�̂������́v�́A���݁A�R�����̂��߁A���\�͎���
�@�@�@�@���}6�����i4��24�������j����ōs���܂��B
�@�@�@�@���傳�ꂽ�݂Ȃ��܂ɁA����ł���ѐ\���グ�܂��B
�@�Ȃ�ƁA���\�����I �R�����H �C�ɂȂ邯��ǁA�Ƃɂ����҂����Ȃ��B���̊ԁA��X���ǂ�ȉ�b�����킵�Ă����̂��͍��ƂȂ��Ă͎v���o���Ȃ����A�y���݂ɑ҂��Ă������Ƃ����͊m���ł���B�Ƃ��낪�I�I
�@4��10���A�������~�q�̐V�Ȃ��蕨����Ŕ������ꂽ�B�^�C�g���́u���˂̉ԉŁv�B�쎌�R��H�v ��ȕ������W�B���㔭�\��2�T�ԑO�̏o�����������B�Ñ��ł͂Ȃ������B�����������Ƃ��B���������Ē����Ă݂�B�f���炵���Ȃ������B�꒮���Ĕ����Ƃ킩��B�����A�u���˂̉ԉŁv�́A�����シ���ɉ����A�q�b�g�X�����}�i�B���{�̗w��܂̃O�����v���ɋP��1972�N�x�̑�\�ȂƂȂ����̂ł���B
 �@�@�@�@���˂̉ԉ�
�@�@�@�@���˂̉ԉ��@�@�@�@���˂͓����ā@�[�g���g�@�@���Ȃ��̓��ց@���łɍs����
�@�@�@�@�Ⴂ�ƒN�����@�S�z���邯��ǁ@�@�������邩��@���v�Ȃ�
�@�@�@�@�i�X���Ɓ@����Ȃ炷��̂�@�@�c����@�s���ȂƋ�����
�@�@�@�@�j��������@�������肹���Ɂ@�@������@�ꂳ��@�厖�ɂ��Ă�
�@�@�@�@���܂��́@�����ȑD���@�@���܂ꂽ�����@�����ɂȂ��
�@�@�@�@����]�̌������Ł@������l�����Ɂ@�@�ʂꍐ������@�܂��o����
�@�@�@�@�����瓇�ւƁ@�n���Ă䂭�̂�@�@���Ȃ��Ƃ��ꂩ��@�����Ă��킽��
�@�@�@�@���˂͗[�Ă��@�����������@�@��l�̖�o�@�j���Ă����
�@���}6�����ɂ͗\���ǂ�����I�삪���\���ꂽ�B
�@�@�@�@���I��1�ȁu�������́v�i�͌��K�Y�j
�@�@�@�@���I��2�ȁu���悤�Ȃ�̐��v�i���c���ق�j�u���݂����d�ԁv�i�y�{�M�K�j
�@�Ñ����́u���˂̗����v�ł͂Ȃ������B����Ⴛ�����낤�B�u���˂̉ԉŁv�̂��ƂɁu���˂̗����v�͂��肦�Ȃ��B�Ȃ���1�ȁu�������́v�́A4�������8��10���A�������~�q�̑�5�e�V���O���u���̂ɂ킩�J�v�̂a�ʂɎ��^���ꂽ�B
�@�Ñ��́A�������A���̂��Ƃ��������������A�R���m�q�ɔF�߂���Ȃǂ��āA���Ȃ����R�[�f�B���O�����悤�ɂȂ�B��Ђł͔��F����Đ��암�ֈٓ��ƂȂ����B�ނ��g������ő�̃q�b�g�Ȃ́u�O�N�ڂ̕��C�v�i1982�N �q���V���L�[�{�[�j�ł���B
�@���[�c�@���g�̉̌��u�t�B�K���̌����v��3���̖`���ŁA�A���}���B�[���@���݂��A�����̎���ɋN����s�v�c�ȏo�������b���ʂ�����B��u���Ȃ��Ƃ��肾�B�����̎莆�A���Ԏg���̍s���ƍȂ̂��낽���A�j���������э~���ƁA�ʂ̒j���������Ɩ����o��E�E�E�E�E�v
�@���̌��ɗႦ��A40�N�O�̏o�����́E�E�E�E�E�u���ɖ����B�������~�q�̍쎌��W�ɒÑ�������A�X�|�[�c���Ɏv�킹�Ԃ�ȋL���A���㔭�\�̉����A�����V�`���G�[�V�����̐V�Ȕ����v�Ƃ����Ȃ�B
�@1972�N1���\4����4�����Ԃɉ����N�������̂��H���ƂȂ��Ă͎��̂��悤���Ȃ����A���������邱�Ƃ͂ł���B�����𗧂Ă�������E�ؖ����邱�Ƃ͂ł���B
�@���̉������u�R��H�v�͒Ñ����́w���˂̗����x������Ȃ��Q�l�ɂ��āw���˂̉ԉŁx���쎌�����v�ł���B����͂��̉������ؖ�����B
2016.03.10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�4�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����@�Ñ����Ƃ����j
���Ñ����Ƃ����j���@�Ñ����B���R�[�h��Ў��ォ��̗F�lM.K.�̃y���l�[���B���R�G�V�̏�������q�����������B1945�N���܂�̓����N�B���X�T�����[�}�������C�͂Ȃ��A��������ڎw���Ă���A�얖���ɒ�q���肵�ďC�s���Ă������A����ς�H��Ȃ���ƁA��Ђɓ����Ă����B�u�Ƀu�����Ȃ��c������B��ɐƂ��S�D�����B�e�����ł���B�ڕW�B���ӎu�Ǝ�̎��Ƃ́A��������������Ȃ����n�������āA�d���ɗV�тɂ悭�s�������ɂ����B�e�����ɂ����i�͖��������A��������D���Șb��ƂԂ���Ƃ����Ȃ��`��ɂȂ�B���o�A���n�A�싅�ȂǃX�|�[�c�S�ʁA���̗̉w�ȁA���Ƃ͐����A���@�̐��E�ȂǁA���̏ڂ������ƂƂ�������Ȃ��B
�@������㑍����b�̖��O���炢�͏o�Ă��邪�A�ނ̏ꍇ�̓P�^�Ⴂ�B�����_���ɍ���c���̖��O�������A�����ǂ���ɏ����h���Ƃ��̗��j�I���ꂪ�Ԃ��Ă���B�Ⴆ�A���h�q��b�E���쎛�ܓT�́H�Ɩ₤�Ƃ���B����ƁA�����͊ݓc�h�B�傫�ȗ���͍G�r��B����͊ݓc���Y�O����b�ŁA���̑O�͌Éꐽ�������h�ꁨ�{���ꁨ��ؑP�K���啽���F���O���ɎO�Y���r�c�E�l�ɑk��A�Ƃ�������B����c�����ׂĂ����ɓ����Ă���悤���B���Ƃ͖��@�Љ�̌n��Ƃ��̗���B�L��\�͒c�̗�㊲���̖��O���X���X���Əo�Ă���B����ɁA�告�o�̗���10�l�̊NJ������Ƃ��̗���ȂǁA����܂��X���X���Əo�Ă���̂ł���B
 �@�Z�{�Ɂu�_�[�o���v�Ƃ����X�i�b�N�������āA��Ђ��I���ƒÑ��Ǝ��͖��ӂ̂悤�ɒʂ����B���̌o�܂͂Ƃ����E�E�E�E�E�I�[�i�[�E�}�X�^�[�͂t���B�u���͒E�T�����ĊJ�X��������B�w�_�[�o���x�͎��߂���Ђ̖��O��Ղ�����ł��v�Ɨ�������������ɍ��������B�܂����̒e����肪���Ȃ��Ĕނ��������Ă���B�������ɂ��I���Ƃ͂����Ȃ��B�̂͂܂��܂������M�^�[���_���B�܂�őŊy��̑́B��X�̕��������炩�}�V�������̂ŁA�u������A�������疈�ӗ��Ă�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�J�������H�͇@���X�͐��ӇA�e�����͉s�ӇB��V�͈��ݑ�Ƒ��E�B�J�������Ƃ������^�_���_��ł���B
�@�Z�{�Ɂu�_�[�o���v�Ƃ����X�i�b�N�������āA��Ђ��I���ƒÑ��Ǝ��͖��ӂ̂悤�ɒʂ����B���̌o�܂͂Ƃ����E�E�E�E�E�I�[�i�[�E�}�X�^�[�͂t���B�u���͒E�T�����ĊJ�X��������B�w�_�[�o���x�͎��߂���Ђ̖��O��Ղ�����ł��v�Ɨ�������������ɍ��������B�܂����̒e����肪���Ȃ��Ĕނ��������Ă���B�������ɂ��I���Ƃ͂����Ȃ��B�̂͂܂��܂������M�^�[���_���B�܂�őŊy��̑́B��X�̕��������炩�}�V�������̂ŁA�u������A�������疈�ӗ��Ă�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�J�������H�͇@���X�͐��ӇA�e�����͉s�ӇB��V�͈��ݑ�Ƒ��E�B�J�������Ƃ������^�_���_��ł���B�@���̃��p�[�g���[�́A�����낤�A������P�A�r�؈�Y�Ȃǃt�H�[�N���B�Ñ��͏��ш��A�n�N��Ȃlj��̒��B����ʼn̂��Ē����ď��āA�I������ɌJ��o���āB�A��͂قƂ�njߑO�l�B�H�ɓX�����B�d���A���v�Ȃ́H �Ԃ�20��A����͂�A�y��������ł����B
�@�Ñ���������A���ɂ��������Ă����B�u���O�A�Ȃ����Ȃ����H ���܁A���������Ă�����A�ȏ�����T���Ă�v�B���͂Ƃ����A�y��������������̂́A�w������A���h�̒��ԂƉ��Ȃ����������Ƃ�������x�B�ł��܂��A����Ă݂邩�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�Ñ������������A�����ɑz��̎�̎w��������B����͐X�i��A����͓��\�q�Ƃ����悤�ɁB�w���ɏ]���Ȃ�t���y�����N�����B�o���オ��ƃM�^�[�ʼn̂������ŏC���A�Ƃ����菇�B�Ñ��̎��̓v���u�]�����ɍ����x���ŕ����L���B�҂�g���I���lj��̂���u�ݏ֖��v���t�H�[�N���́A����������݁u���Ȃ��Ȃ�ǂ�����v���|�b�v�̗w�܂ŁA���\�o���G�e�B�[�ɕx��ł���B�قڋȕ������A���̃��x���Ɩ�����[�������邵�����傤���Ȃ��B
�@���N���o�ƃX�g�b�N�����܂�B�܊p�����甄�荞�������B�Г��O�̗F�l����f�B���N�^�[�ɂȂ��ł��炤�B���l���ɉ�B�b�͕����Ă���邪�AYes��No���Ȃ��B�Ñ��͂����m�炸�A���͎����ɍ˔\���Ȃ��͔̂����Ă��邩��A���荞�݂ɂ����͂��Ȃ��B�u���́A����A�܂��܂������Ǝv���̂ł����A�A���o���̈�Ȃɂł��g���Ă��炦�܂��v�B�u���܂�ŒႢ�B
 �@������AT���Ȃ�f�B���N�^�[�ɔ��荞�ۂɂ�������ꂽ�B�u�����A�̎��z�肵�ċȂ��˗�����Ƃ��A�܂��f�l����ɂ͗��܂Ȃ���B����̓V���O���ł��A���o���ł��������ƁB��Ƀv���ɗ��ށB�Ȃ��Ȃ�80���̊����x���ۏႳ��邩��ˁB�f�l����Ɋ��҂���̂́g���ꂻ��p�̉́h�Ȃ���Ȃ��B���̐l�������̋C�������Ƃ��Ƃ߂ď��������́B���̐l�̍����~�ނɎ~�܂ꂸ���o�������́B���̐l�ɂ����\���ł��Ȃ����I�ȍ�i�B���������f�l�Ɋ��҂���̂͂����������̂Ȃv�B�����͉��₩�����B�R����ӎv�\���������BT���Ƃ͒ߓc�N�炳��B�a���܃L���O�X�u�Ȃ݂��̑��v�A�����a�q�u�A���Ă�����v�A�O�P�p�j�u�J�v�A�C���痢�����u��ド�v�\�f�B�[�v�ȂǂȂǁA70�N��ɗ��đ����Ƀq�b�g�������r�N�^�[�̃G�[�X�E�f�B���N�^�[���B�ނ͂قǂȂ�40��̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B�R���m�q���u���̂̒��v�̃��f���Ƃ����Ă���B
�@������AT���Ȃ�f�B���N�^�[�ɔ��荞�ۂɂ�������ꂽ�B�u�����A�̎��z�肵�ċȂ��˗�����Ƃ��A�܂��f�l����ɂ͗��܂Ȃ���B����̓V���O���ł��A���o���ł��������ƁB��Ƀv���ɗ��ށB�Ȃ��Ȃ�80���̊����x���ۏႳ��邩��ˁB�f�l����Ɋ��҂���̂́g���ꂻ��p�̉́h�Ȃ���Ȃ��B���̐l�������̋C�������Ƃ��Ƃ߂ď��������́B���̐l�̍����~�ނɎ~�܂ꂸ���o�������́B���̐l�ɂ����\���ł��Ȃ����I�ȍ�i�B���������f�l�Ɋ��҂���̂͂����������̂Ȃv�B�����͉��₩�����B�R����ӎv�\���������BT���Ƃ͒ߓc�N�炳��B�a���܃L���O�X�u�Ȃ݂��̑��v�A�����a�q�u�A���Ă�����v�A�O�P�p�j�u�J�v�A�C���痢�����u��ド�v�\�f�B�[�v�ȂǂȂǁA70�N��ɗ��đ����Ƀq�b�g�������r�N�^�[�̃G�[�X�E�f�B���N�^�[���B�ނ͂قǂȂ�40��̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B�R���m�q���u���̂̒��v�̃��f���Ƃ����Ă���B�@�����A�����Ƃ����B�e�Z�킶�Ⴀ��܂����A�����Ɏg���`���͂Ȃ��B�\�R�\�R�̋ȂȂ炢����ł��]�����Ă��邵�A�u�悩������A���o���ɂł��v����A�����ɂ��u���Ⴗ����B�����c�Ə�����@�������ŏ��l�߂��ߓc�����猩����A��������w�͂������ɔ��[�Ȍ������鎄�Ȃ́A�Â����̋ɂƉf�������Ƃ��낤�B���͋}�ɋC�p���������Ȃ�A�Ñ��Ƃ̃R���r���������Ė{�Ƃɐ����o�����Ƃɂ����B�Z�{�ؒʂ��͑����Ă������B
 �@1972�N�̔N�������X�A�Ñ������̂Ƃ���ɂ���Ă��Ă����������B�u���}2�����ɏ������~�q�̐V�Ȃ̉̎���W���������̂ʼn��債���B�ǂ�ł݂Ă���v�B���e�p���ɂ́u���˂̗����v�Ƃ�����т̎����������B�����ꂽ�p������������Ă����B
�@1972�N�̔N�������X�A�Ñ������̂Ƃ���ɂ���Ă��Ă����������B�u���}2�����ɏ������~�q�̐V�Ȃ̉̎���W���������̂ʼn��債���B�ǂ�ł݂Ă���v�B���e�p���ɂ́u���˂̗����v�Ƃ�����т̎����������B�����ꂽ�p������������Ă����B
�@�@���˂̗����@���˓��C�̓���ɎႢ���̐Ȃ����S���Ԃ��Ă���B�u���˂̗����v�Ƃ����^�C�g���������B�u��������Ȃ����v�ƌ������ɒÑ��͂����݂�����B�u���~�q�́A�f�r���[�Ȃ��w�鉺���x�ő�3�e���w�Ⴀ����x�B��r�I���ƂȂ��ڂ̔w�i�ŗ��Ă���B���S�́w�f�B�X�J�o�[�E�W���p���x�́A���N�͂���ɐ���オ��A3���ɂ͎R�z�V���������R�܂ʼn��т�B�Ȃ�ΐ��˓��C�͂ǂ����낤�Ǝv�����̂��B�E���A�����Ō����̂��Ȃ��A��S�̏o�����v�B�����`��Ԃ�͎育�����A���̏��B����v�̂ɂ́A5�����i3��24�������j�ɂĔ��\�Ƃ���B�����ꏏ�ɑ҂��������C�����ɂȂ��Ă����B
�@�@���˂̏����ɐ�������
�@�@�Ȃɂ��������A��Ă���
�@�@�����o��������O��
�@�@���Ȃ��̕ւ�܂����Ȃ�
�@�@�t���߂��Ă����̓���
�@�@���������́@���̂���
�@�@����\��ʼnł�����
�@�@��Ȃd���ŕ��������
�@�@���O�܂����ƕ�����Ă�
�@�@���Ȃ��̖��O�܂�������
�@�@�h���C�����ō������܂�
�@�@���̓�����@�����Ă䂭
�@�@���x�A��Ə����Ă���
�@�@���Ȃ��̎莆���ɕ���
�@�@�S�҂����Đj�d��
�@�@��ɂ����Ȃ����ꂵ����
�@�@�B���ʎ����̗���
�@�@���˂̗[��@�����Ă�
2016.02.25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�3�`�l���ɔV���̃��j���[�A�����
�@�ꂽ�ƌ������� ���̖��͋����Ă������������͎牮�_�u�����֖߂��Ă����ł�v�̖`���ł���B���̋Ȃ��A����N�Y�쎌���l���ɔV����ȂƂ������Ƃ͌�Ŕ���̂����A�����������w���̎��ɂ͒m��R���Ȃ������B�Ƃɂ������ɂ����̋Ȃ��D���ł��܂炸�A���R�[�h���������Ȃ��������A��������ēc�ɂ̖������W�I�ŕ����܂��������̂��B����́A�u�l�͋����������v�u�L���߁v�Ȃǂ̃q�b�g�����牮�̊y�Ȃ̒��ł́A��r�I�n���ȕ��ނɑ�����B�@�n���Ȃ���D���Ƃ����y�Ȃ͌��\������̂ŁA���l�l���猩��u���ŁH�v�Ȃ̂��낤���A�D�������ɗ����͂Ȃ��B�Ⴆ�A�O�Y����u�����v�A�t�����N�i��u���Ɠ�l�Łv�Ȃǂ�����B�u�����v�͓��N�q�쎌 �n�v�n���M��� 1958�N�̍�i�B�����̃T�i�g���E���ŖS���Ȃ��Ă��܂����l�Ƃ̒W��������B��ԑ����炠�Ȃ��͎��̈���ǂ݂Ƃ�� �j���߂ē�������܂��āE�E�E�E�E���L�����̉B�ꂽ���Ȃł���B
�@�u���Ɠ�l�Łv�͕l���ɔV���̍쎌��Ȃ�1967�N�̍�i�B���̋Ȃ̂悳�͎����ꂪ��ɋC�Â����B�u���A�t�����N�i��̍��x�̋Ȃ�������A���R�[�h�����Ă��Ă�v�B��͑吳���܂ꂾ���A�D�݂͖M���m�A�t�����N�i��ł����A�u�N�����v�n�����u���u�E���^�[�v�n���D�ށB�u�₩�ȃJ���g���[���́u���Ɠ�l�Łv�́A�܂��ɛƂ�Ȃ������B���ꂩ��50�N�I ��͍��N2��21���Ŗ�95�ɂȂ����B�a�C������A�O�x�̐H���������ō��B�F�m�ǂ̋C�z�Ȃǔ��o���Ȃ�������ǍD�B���[�����o���o������肵�Ă���B��̓N�C�Y�ŁA���X���Ƌ��������B���܂����@�������Ȃ���B
�@�쎌��Ȃ̓��͍��ł͉����������͂Ȃ����A�t���[��Ƃ��o������1960�N��ȑO�A������ꑮ��Ǝ���ɂ͂��܂肢�Ȃ��B�p�C�I�j�A�͓��C�O�i1900�|1950�j���H �u�`��������u�v�u�N�҂Ăǂ��v����\��B���Ԃ��Ȃ����̉̂����A�������Ă��Â���S�����������Ȃ��B���ɃV�����Ă���B�����̃Z���X�ƕi�̂悳�͑��q�̍쎌�ƁE�R��H�v�Ɏp����Ă���B���̔g�q������f�G�Ȑl�������B���Ƃ́A�������i1932�|2008�j�����邪�A��͂�A���̕���ł́A�l���ɔV���i1917�|1990�j�����ʂƂ��ɍʼnE�����B
 �@�ߓ������e���r�ԑg�̒��ŁA�n�}�N�����͂��������Ă����B�u�Ȃ͍����̂ł͂Ȃ��āA�Y�ނ��̂Ȃ�ł��B�S�̂����ɐF�X�Ȉ����o���������āA���̎��X�̋C�����ɏ]���Ĉ����o���Ă��邾���Ȃ�ł���B�����玄�͍�ȉƂł͂Ȃ��Y�ȉƂȂ�ł��v�B����͂�A����̓��[�c�@���g�I ���Ȃ������ɎY�ݏo�����̂��[���������B
�@�ߓ������e���r�ԑg�̒��ŁA�n�}�N�����͂��������Ă����B�u�Ȃ͍����̂ł͂Ȃ��āA�Y�ނ��̂Ȃ�ł��B�S�̂����ɐF�X�Ȉ����o���������āA���̎��X�̋C�����ɏ]���Ĉ����o���Ă��邾���Ȃ�ł���B�����玄�͍�ȉƂł͂Ȃ��Y�ȉƂȂ�ł��v�B����͂�A����̓��[�c�@���g�I ���Ȃ������ɎY�ݏo�����̂��[���������B�@�쎌��Ȃ̃q�b�g�Ȃ́A�u�l�͋����������v�i�牮�_1959�j�A�u�܂���Ȃ�v�i��{�㑼1965�j�A��o�����炢���v�i�}�C�N�^��1966�j�A�u���̃t�������R�v�i�����P�F1966�j�A�u�[���������Ă���v�i�U�E�X�p�C�_�[�Y1966�j�A�u�閶�� ������L��v�i�Ό��T���Y1967�j�A�u�݂�Ȗ��̒��v�i���c���q1969�j�ȂǁB��Ȃł́u�����̃u���[�X�v�i����N�͍쎌 �]�O��1967�j�A�u���̂����Ȃ݁v�i�Ȃ��ɂ���쎌 ���q���q1968�j�A�u�l�����낢��v�i���R��O�Y�쎌 ���q���q1987�j�ȂǑ����B�̗w�ȁA�t�H�[�N�A�O���[�v�E�T�E���Y�Ǝ��ɑ��ʁB�Ƃ������A�W�������z�����n�}�N���E���[���h�̊ς��B����́A�V�ˁE�l���ɔV���̃��j���[�A���E�q�b�g����グ��B
���l�����낢�끄
 �@���q���q�́i�����炭�j�ő�̃q�b�g�ȁu�l�����낢��v�́A�n�߂�B�ʌ�₾�����B1987�N�����ATBS�n���y�o�ʼn�ЁE�����́ATBS�h���}�u�O�ǂ��܁v�̎��̂����B�O�l�̌\�H�������������������Ȃ��������������܂������Đ����Ă䂭����B�̎�ɓ���49�̓��q�𗧂āA�쎌�ɒ��R��O�Y�A��Ȃɕl���ɔV�����N�p�B�オ���Ă����y�Ȃ��u�Ԃ���݁v�B�܂��܂��̏o���B����ōs�����ƂɂȂ�B�ł́AB�ʂ��ǂ�����H �����Ńn�}�N������A�u�傿���A�̍�����Ȃ����邩�炱��Ɏ������ւ��Ă݂āH�v�ƒ��R�ɒ����̂��u��̂���`���v�������B
�@���q���q�́i�����炭�j�ő�̃q�b�g�ȁu�l�����낢��v�́A�n�߂�B�ʌ�₾�����B1987�N�����ATBS�n���y�o�ʼn�ЁE�����́ATBS�h���}�u�O�ǂ��܁v�̎��̂����B�O�l�̌\�H�������������������Ȃ��������������܂������Đ����Ă䂭����B�̎�ɓ���49�̓��q�𗧂āA�쎌�ɒ��R��O�Y�A��Ȃɕl���ɔV�����N�p�B�オ���Ă����y�Ȃ��u�Ԃ���݁v�B�܂��܂��̏o���B����ōs�����ƂɂȂ�B�ł́AB�ʂ��ǂ�����H �����Ńn�}�N������A�u�傿���A�̍�����Ȃ����邩�炱��Ɏ������ւ��Ă݂āH�v�ƒ��R�ɒ����̂��u��̂���`���v�������B�u��̂���`���v
�@�@�@�@��̂��钬�́@�l�̍D���Ȓ�
�@�@�@�@�ǂ������}���́@���肪����
�@�@�@�@����オ���ā@�U��Ԃ��Ă݂��
�@�@�@�@���͏������@�����Ȃ��Ă���
�@�@�@�@���̐Ԃ������̏����ȑ��Ł@���U���Ă��ꂽ���̐l
�@�@�@�@�v���o�͂ǂ�Ȃɉ����Ȃ��Ă��@�����Ă��܂��͂��Ȃ�
�@�@�@�@�v���o�悱��ɂ��́@�l�͍�������̏�
�@�@�@�@�U��Ԃ鏬���ȁ@�v���o�̒�
�@���ꂪ�u�l�����낢��v�ɐ��܂�ς��B
�u�l�����낢��v
�@�@�@�@����ł��܂����Ȃ�ā@�Y�肵����
�@�@�@�@�o�����R�X���X�������@�͂�Ă����܂���
�@�@�@�@�����݂�����������@�悭���w������
�@�@�@�@����������@�ӂ߂ċ����Ă���������
�@�@�@�@�˂����������ł���@�Ⴂ����@�˂����m�ł���Ⴂ����
�@�@�@�@���Ȃ��ɗ܂������ς��@�܂̒��ɎႳ�������ς�
�@�@�@�@�l�����낢��@�j�����낢��
�@�@�@�@�������Ă��낢��@�炫������
�@���́A�ŏ��ɏオ���������C�g���� ����ł�����ŏ������ �I�ȓ��e�������Ƃ��B����ł͂����̈��߂Ȃ����q�ɍ���Ȃ��Ƃ��čă��j���[�A�������̂����݂̎��B���̏オ������Đ���w�́u�l�����낢��v���}�A�ʂɔ��F�����̂ł���B
�@4��21��������A�Ȃ̓W���W���ƃq�b�g�`���[�g���㏸�B�R�c�M�q��R���b�P�̕��^�����ʂ��ǂ����ƂȂ�ŏI�I��130�����̃Z�[���X���L�^�B���q�A�n�}�N���̔ӔN�������q�b�g�ƂȂ����B
�@ �@�����̂悤�ɁA���j���[�A���O�ƌ�ł͎����܂������Ⴄ�B�u��̂���`���v�̓n�}�N�����̈��ȁE���܂�݂̂��߂Ɏv���o�̒n�E���ق�ɏ��������̂̂悤���B�ł��܂��A���̂܂܂ł͔���Ђ肪�̂��Ă�����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���ꂪ�AB�ʂƂ��������߂ɂȂ�ƂȂ�(�H)��������o���Ă��āA�ʂ̐l�Ԃ����ěƂ߂��疢�\�L�̑�q�b�g�Ȃɐ��܂�ς��B�Ȃ�Ƃ������w�����I �ȍ��̖��d�s�v�c�ł͂Ȃ����I�H �g�l�����낢��h�Ƃ����t���[�Y�����ɃL���b�`�[�B�q�b�g�̑傫�ȗv�����낤�B�Ȃɂ��A17�N��A���̑�����b����������p���č���ق������̂�����B
���܂���Ȃ灄
 �@�l���ɔV���쎌��ȁA��{��1965�N�̃q�b�g�ȁu�܂���Ȃ�v�́A���́u�܂��悤�Ȃ�v�������Ƃ����b�B
�@�l���ɔV���쎌��ȁA��{��1965�N�̃q�b�g�ȁu�܂���Ȃ�v�́A���́u�܂��悤�Ȃ�v�������Ƃ����b�B�@�@�@�@�܂��悤�Ȃ�@����Ȃ�܂���@�܂�����܂�
�@�@�@�@���Ȃ��͎��̂��F�B�@���̐��͔߂������Ƃ��炯
�@�@�@�@���Ȃ��Ȃ��ł͂ƂĂ��@�����Ă�������������܂���
�@���ꂪ�u�܂���v�ɕς��
�@�@�@�@�܂���Ȃ�@����Ȃ�܂���@�܂��������܂�
�@�@�@�@�N�͖l�̗F�B���@���̐��͔߂������Ƃ��炯
�@�@�@�@�N�Ȃ��ł͂ƂĂ��@�����Ă����������Ȃ�
�@���C�ȏ��N�������ɖڊo�߂Ċ�т�Â��ɉ̂�������B����Ȑt�̐Ȃ����ăX�}�b�V���E�q�b�g�ƂȂ����B�̂��肪��{�ゾ���炱�̕ύX�͓��R�Ƃ����Γ��R�����A�u����v���u����v�֕ς�������ƂŁA��C���悭�Ȃ莕�ꂪ�������B������Ƃ������ƂŊy�Ȃ̃C���[�W���ς��A��������j���[�A��������ł���B
2016.02.10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�2�`�u�܂��������܂Łv�͈��v�I���g�̃p���f�B
�@�@�@�@�@�`���ւ� ������Ȃ� �@�����@�����q�K�́A���{�l�Ȃ�m��ʂ��̂Ȃ��L���ȋ�́A1895�N11��8���A�C��V���i���݂̈��Q�V���j�Ŕ��\���ꂽ�B
�@�@�@�@�@�����@��ǎU��Ȃ�@������
�@����́A����2�����O��9��6���A�����C��V���ɍڂ����N���낤�Ėڟ��̋�ł���B
�@�����A���͏��R���w�̋��t�Ƃ��āA�q�K�͕a�C�×{�̂��߁A���R�ɂ����B�������A1895�N8��27���\10��17���̊ԁA�q�K�͟��̉��h�ɋ��Ă���B��̋�͂��̎����ɑ��O�サ�ĎY�܂ꂽ�̂ł���B����2�N�O���q�ŎQ�T���Ă���A���̎��̏�i���v�������ׂĂ̂��̂��B�q�K�̓Y�o�����̋���x�[�X�ɂ����̂��낤�B���̎q�K�̖���͟��̃p���f�B�������̂ł���B�㔭�̍�i���x�[�X���z����̂͂悭����b�B�e�F�̓�l�Ȃ���͋N���Ȃ��B
���u�܂��������܂Łv�͈��v�I���g�̃p���f�B��
 �@�p���f�B�Ƃ́A�u�����̍�i�����ς����h���m��������i�v�ƒ�`�����̂����ʂ����A�N���V�b�N�̐��E�ł́A�K���������h���m�ɍS��Ȃ��B���ы`�����̖����u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�ɂ́u�w�~�T�ȃ��Z���x�̍ŏI�y�͂́A�O�����A�̒��̊y�͂̃p���f�B�A���Ȃ킿�A�������y�ɈقȂ����̎����������̂ł���v�Ƃ����L�q������B�����A�����Ƃ�����̒��Ń����f�B�[�̓\�m�}�}�ɂ��ĉ̎���ς����Ƃ��p���f�B�Ə̂��Ă���B1971�N�̑�q�b�g�u�܂��������܂Łv���܂��ɂ��̃p�^�[���B��҂�����̍�i��ύX���Ă���̂�����A���`�q�K�ȏ�ɖ��͂Ȃ��B
�@�p���f�B�Ƃ́A�u�����̍�i�����ς����h���m��������i�v�ƒ�`�����̂����ʂ����A�N���V�b�N�̐��E�ł́A�K���������h���m�ɍS��Ȃ��B���ы`�����̖����u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�ɂ́u�w�~�T�ȃ��Z���x�̍ŏI�y�͂́A�O�����A�̒��̊y�͂̃p���f�B�A���Ȃ킿�A�������y�ɈقȂ����̎����������̂ł���v�Ƃ����L�q������B�����A�����Ƃ�����̒��Ń����f�B�[�̓\�m�}�}�ɂ��ĉ̎���ς����Ƃ��p���f�B�Ə̂��Ă���B1971�N�̑�q�b�g�u�܂��������܂Łv���܂��ɂ��̃p�^�[���B��҂�����̍�i��ύX���Ă���̂�����A���`�q�K�ȏ�ɖ��͂Ȃ��B �@�u�܂��������܂Łv�ɂ͌��Ȃ�����B�Y�[�E�j�[�E���[�́u�ЂƂ�̔߂��݁v�B�쎌�F���v�I�A��ҋȁF���������B1970�N�����̃O���[�v�T�E���Y�y�ȁB�q�b�g�ɂ͎���Ȃ������B�܂��͉̎������Ă݂悤�B
�@�u�܂��������܂Łv�ɂ͌��Ȃ�����B�Y�[�E�j�[�E���[�́u�ЂƂ�̔߂��݁v�B�쎌�F���v�I�A��ҋȁF���������B1970�N�����̃O���[�v�T�E���Y�y�ȁB�q�b�g�ɂ͎���Ȃ������B�܂��͉̎������Ă݂悤�B�@�@�@�@��������������@�����̏I����
�@�@�@�@�@ �w�̂т����Ă݂Ă��@���������Ȃ�
�@�@�@�@�@ �Ȃ������݂��������@�Ȃ����ނȂ�������
�@�@�@�@�@ �������ā@�͂��܂�@�ЂƂ�̔߂��݂�
�@�@�@�@�@ ��������Ă����Ł@�������߂����Ă�����
�@�@�@�@�@ ���̎��ӂ���������� ���邾�낤
�@�ł́u�܂��������܂Łv��
�@�@�@�@��܂��������܂Ł@�����鎞�܂�
�@�@�@ �@�@�ʂ�̂��̂킯�́@�b�������Ȃ�
�@�@�@�@ �@�Ȃ������݂��������@�Ȃ����ނȂ�������
�@�@�@�@ �@�������ɏ����@���ׂĂ��Ȃ�������
�@�@�@�@ �@�ӂ���Ńh�A�����߂ā@�ӂ���Ŗ��O������
�@�@�@�@ �@���̎��S�������� �b�����낤
�@�u�܂��������܂Łv��1971�N�����B�����f�B�[�͂��̂܂܂Ɉ��v�I���̎���啝�ɕύX�B�̏��͔���I���F�B���N�̃��R�[�h��܂ɋP����q�b�g�ƂȂ����B
�@���ʁi�����\�L�j�v�z�́u���݂����̒����牽�����݂���v�ł��邪�A���҂̍��͗�R���B�u�ЂƂ�̔߂��݁v�́A��҂ɂ��Ɓg���ۓ����ō��܂����N�̌ǓƁh���r���́iWikipedia�j�̂悤�����A�������Ȃ��Ə��c���ł��Ȃ����A�����ɂ����X�����B�����ւ䂭�Ɓu�܂��������܂Łv�́A�ʂ�䂭�j���̏�i����������ƕ����сA��l�����ӂ��������ƁA���̌�ʁX�ɗ͋��������Ă䂭���낤���Ƃ����m�ɉr���A�܂������ǂ����ň������������͂��A����ȑO�����Ȏ�Ɨ]�C������B�����ȃ����C�N�ł���B�����f�B�[�͑S���ς�炸�A�A�����W�������n���͂�����{�͕ς���Ă��Ȃ��B��q�b�g���̗v���͈�ɉ̎��̕ύX�ɂ������B
�@���_�A�̂���̈Ⴂ���傫���B�Y�[�E�j�[�E���[�̃��[�h����H�[�J�����c�`�l�i1946�|�j�͐L�т̂��鍂�����������̎��͔h�B�u�����T���S�ʁv�̃q�b�g������B����A����I���F�i1943�|2012�j�́A�̗w�E�����Ă̐����h���H�[�J���X�g�B�����̐L�ѐ��̃c�����ʂ̖L�����͔䌨����҂Ȃ����̗͋����̏��͈����ł���B���c���Ȃ��Ȃ��̗͗ʂł͂��邪���肪��������B
�@�u�܂��������܂Łv�Ƃ����^�C�g���́A���䐳�ē�1950�N�̉f��Ɠ����B����͍쎌�ƈ��v�I�i1937�|2007�j�̏퓅��i�B���̑��ɂ��f��^�C�g�����p�̗�͑����B�u����Ȃ��������x�v�i����I���F�j�A�u����ɂ��₪��v�u�T�����C�v�i��c����j�A�u��� ���� �����v�i��㏇�j�A�u�w�b�h���C�g�v�i�V�������j�A�u���F�����{���v�i���c�~�q�j�A�u������l�Łv�i�Ό��T���Y�j�A�u���ɂāv�i����������݁j�A�u������v�i�ߓc�_��j�A�u��������v�u����ΗF��v�i�X�i��j�A�u�ފ݉ԁv�i�X���q�j�A�u�g���v�i�ΐ삳���j�ȂǁA�a�m�ɂ܂�����B
�@���v�I�͍L���㗝�X�̏o�g�B�܂��A�̎�̓����܂���i�̕�������ł��o���C���[�W���\�z����B�������A���̃C���[�W���ߋ��̌|�p��i�ɃV���N�������Ǝ��̃X�g�[���[���`���B�ו���_�����ꉻ���č\�z�B�^�C�g���͂��̂܂ؗp�B4���Ԃ̃h���}�̊����I �Ȃ�Ƃ������ȐE�l�Z�ł���B
�@���v�I�̍쎌�ƌ��@��1���ɂ͂�������B�u����Ђ�ɂ���Ċ��������Ǝv���闬�s�̖̂{���ƁA�Ⴄ���͂Ȃ����̂ł��낤���v�B���́g�Ⴄ���h�������v�I�̃I���W�i���u4���Ԃ̃h���}�v�Ƃ��������B�܂��ɕs���s�ł���B�������i��5000�]�B���R�[�h���5��A���쎌��7��͍쎌�ƂƂ��čő��B���U�V���O������6834�����͗��2�ʁB���݂ɑ�1�ʂ͏H���N��1�������ł���B
���u�@�E�q�咬�u���[�X�v�̏ꍇ��
 �@�̎���ς��Č���ȏ�Ƀq�b�g������͑��ɂ�����B���a�����ƃ_�[�N�z�[�X�́u�@�E�q�咬�u���[�X�v�����̃P�[�X�B
�@�̎���ς��Č���ȏ�Ƀq�b�g������͑��ɂ�����B���a�����ƃ_�[�N�z�[�X�́u�@�E�q�咬�u���[�X�v�����̃P�[�X�B�@�u�@�E�q�咬�v�u���[�X�̌��Ȃ́u����Ȃ� ����Ȃ� ���悤�Ȃ�v�B�쎌�F����N�Y�A��ҋȁF�R�H�i��A�k������̉̂�1962�N�̔����B
�@�@�@�@���Ԃ��p���\���@�����Ɖ�
�@�@�@�@�@ ���̖������ڂ�@�������������
�@�@�@�@�@ ���̂͂���́@�돬��
�@�@�@�@�@ ����Ȃ�@����Ȃ�@���悤�Ȃ�
�@�@�@�@�@ ���`�����ƚe���ā@��������
�@�u����Ȃ��ꗷ�v�u�݂��ꔯ�v�ȂǁA�{�i���̂̋�������N�Y�����̍�i�ŁA�̂ǂ��ȃJ���g���[���̎��B�k������̒��ł́A��\�ȁu�Ⴂ�ӂ���v�u�Y��Ȃ����v�Ɋr�ׂă}�C�i�[�E�q�b�g�Ƃ������Ƃ��납�B
�@10�N���1972�N�A�_�[�N�z�[�X�̕��a������������Ɉڂ��Q�����̂Ɏd���Ē������̂��u�@�E�q�咬�u���[�X�v���B
�@�@�@�@���Ƃ��Ă˂Ɓ@�����Ă���
�@�@�@�@�@ ���킢���̖��́@���ԂȂ̂�
�@�@�@�@�@ �Ȃ��ɋ��������@�@�E�q�咬��
�@�@�@�@�@ ����Ȃ� ����Ȃ�@��������܂�
�@�@�@�@�@ �܂��ӂ��ā@���悤�Ȃ�
�@���Ȃƕς��Ȃ��͍̂�Ȃ̎R�H�i�ꂾ���B�ҋȂ́A�R�H�i�ꂩ�瓡�����d�ցB�M�^�[�Ɏn�܂�̂ǂ��ȓc�ɂ̕��i����g�����y�b�g�|���R�e�R�e�̘Q�����̃��[�h�Ɉ�ς����B�쎌�́A��䏊����N�Y������̃R���f�B�A���E�o���h���[�_�[���a�����ցB�c�ɂ̒W���������ꂩ�琷��ꏗ�̈����ւƃX�C�b�`�B���̑�_�ȏ�ʓ]�����ȑz�Ɖ��w�����A���吧��500���X�^�[�g�̃��R�[�h��200�����z���A������͂邩�ɗ�������q�b�g�Ɖ������B�܂��Ɋ�Ղ̃��j���[�A���������B
�@�����́A�{�j�Y�Ƃ҂�g���I�́u���݂̂��v�Ɏn�܂�a���܃L���O�X�u�Ȃ݂��̑��v�ȂǁA�����n���̂̉Ԑ���B���̗�����q�b�g�ɔ��Ԃ��������B
2016.01.25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊ԂɂP�`����Ђ�u�߂������v�͓�Ԑ���
 �@1��17����You����a�����琔���Ă��傤��5�����ځB����Jiiji�̌Ăт����ɂ����C�ɔ�������悤�ɂȂ����ˁB���̂܂܌��₩�Ɉ���Ăق����Ȃ��B
�@1��17����You����a�����琔���Ă��傤��5�����ځB����Jiiji�̌Ăт����ɂ����C�ɔ�������悤�ɂȂ����ˁB���̂܂܌��₩�Ɉ���Ăق����Ȃ��B�@���āA���܂��܂��̓��̒����V���Ɂu�p�N���o�ρv�Ȃ�L�����o�Ă����B�����ɂ́g�R�s�[�͕K�������n�������ޏk��������̂ł͂Ȃ��A�ނ���C�m�x�[�V�������h������P�[�X�����݂���h�Ƃ���B�p�N���m��_�H ��N�ܗփG���u������肪�����オ�����悤�ɁA���̒��p�N���Ɉ��Ă���B�p�N���̑ɂ͑n�������I���W�i���e�B���B�ƂȂ�A���̒��̍�i�͂��ׂăp�N���ƃI���W�i���̊Ԃɑ��݂��邱�ƂɂȂ�B
�@������͖͕�̏d�v��������B�m�Ԃ̕s���s�͌ÓT�Ȃ����Ă͑��݂��Ȃ��B�R���b�P�̌|�̓p�N�����I���W�i�����H �������͓�����s�K�v�B�ʔ��������ł����B
�@�����ŁA����̃e�[�}�ł���B������ƁA�Ⴆ�A�p�N���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��`�Â��͂��Ȃ��B�x�[�X�������Ă���Ƃ͕ʕ��ɕω�������i����グ�邾���B�ω��`�ƃx�[�X�Ƃ̊W�����l�@���Ă݂悤�B�B�ꂽ��x�[�X�ɈӊO���A����i�V��H �ω��̉ߒ��ɋ����A����i�V��B����͂���Ŗʔ��������B�܂��͗��s�̂���B
������Ђ�́u�߂������v�͓�Ԑ�����
 �@���U1500�Ȃ��̃��R�[�f�B���O���s��������Ђ�i1937�|1989�j�B����͂ƂĂ��Ȃ����ʂ��B����Ț삵�����̒����炨�C�ɓ���y�Ȃ�3�ȋ�����ƌ�����A���̏ꍇ�A�u��̗���̂悤�Ɂv�u���Ղ�}���{�v�u�`���\�O�Ԓn�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�D���͍D���A�c�_�ɂȂ�Ȃ����A���I�w�b�h�E���C����t����Ȃ�A�u��̗���̂悤�Ɂv�͋��ɂ̐l���\���O�B�u���Ղ�}���{�v�͖��������镨�ꐫ�B�u�`���\�O�Ԓn�v�̓}�h���X��̃m�X�^���W�[�B�Ƃ������Ƃɂł��Ȃ낤���B�|���āA�g��\��h�͉����H�Ƃ̖�ɂ́A�����ɋ�����B�q�ϐ������߂��邵1�ȂɌ����邩��ł���B�ł��A�����Ă���ł͘b���O�ɐi�܂Ȃ��B�Ȃ�Ί����Č������Ă��܂����B����Ђ�̑�\��́u�߂������v�ł���B
�@���U1500�Ȃ��̃��R�[�f�B���O���s��������Ђ�i1937�|1989�j�B����͂ƂĂ��Ȃ����ʂ��B����Ț삵�����̒����炨�C�ɓ���y�Ȃ�3�ȋ�����ƌ�����A���̏ꍇ�A�u��̗���̂悤�Ɂv�u���Ղ�}���{�v�u�`���\�O�Ԓn�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�D���͍D���A�c�_�ɂȂ�Ȃ����A���I�w�b�h�E���C����t����Ȃ�A�u��̗���̂悤�Ɂv�͋��ɂ̐l���\���O�B�u���Ղ�}���{�v�͖��������镨�ꐫ�B�u�`���\�O�Ԓn�v�̓}�h���X��̃m�X�^���W�[�B�Ƃ������Ƃɂł��Ȃ낤���B�|���āA�g��\��h�͉����H�Ƃ̖�ɂ́A�����ɋ�����B�q�ϐ������߂��邵1�ȂɌ����邩��ł���B�ł��A�����Ă���ł͘b���O�ɐi�܂Ȃ��B�Ȃ�Ί����Č������Ă��܂����B����Ђ�̑�\��́u�߂������v�ł���B�@ �@�̎�̖��͂��\������v�f�Ƃ́H �̏��͂Ɛl�ԗ͂ł���B�p�t�H�[�}���X�͂��̓����̂ƂȂ��Č����킯������A��T�ɉ̏��͂Ƃ����Ă������ɂ͕K�R�I�ɐl�ԗ͂��������Ă���B�̏��͂�_����Ƃ��ɂ��̎��_�͌������Ȃ��B���ɔ���Ђ�̏ꍇ�ɂ́B
�@�̎�E����Ђ�̖��͂͂��̍ۗ������̏��͂ɂ���A�Ƃ����͈̂٘_�̂Ȃ��Ƃ��낾�낤�B������A�Ђ�̉̏��͂Ƃ́H �@�m���Ȕ������J�j�Y�� �A�L���ȕ\���� �B�\���̑��l�� �����肾�낤�B����߂����������Ă���������A�A�͂P�y�Ȃɂ�����\���̖L�����ł���B�͗l�X�ȃ^�C�v�̊y�Ȃ��̂����Ȃ��\���̑��l���ƍl���Ă������������B
�@���s�̗̂��j100�N�̒��ŁA�̂̍I���̎�͐�������B�������ނ�͓��ӂȗ̈�ɂ����ē��������ɉ߂��Ȃ��B�����n�ɗႦ��Ȃ�A�Z�����͓��ӂ����������͕s����Ƃ����悤�ɁB����Ђ�́A�Z���������������A�ł��_�[�g���A�ǔn����d�n����A�n�C�y�[�X�ł��X���[�y�[�X�ł��A�A���ł��x�{�����ł��A�����ł����s�ł������V�����ł��A�Ⴆ�����ɕs��������Ă��Ă��A���ՂȂ�����B�����Ȃ郌�[�X�ɂ����Ă��t�@���̊��҂𗠐�Ȃ��B�V���U���A�V���{�����h���t�A�I�O���L���b�v�A�f�B�[�v�C���p�N�g�A�Ȃǂ̔\�͂����B����Ђ�Ƃ����̎�́A�̎�Ƃ������݂��`�����邷�ׂĂ̗v�f�ɂ����ė]�l�̉����y�Ȃ��Z�ʂ�����Ă���A����Εʊi�Ȃ̂ł���B
�@�Ђ�ɔ䌨������B��̉̎�͂������Ȃ��݂ł͂Ȃ��낤���B�ޏ��́A�v���^�����S���Ȃ���1992�N9��21���ȍ~�A��،��Ɏp�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B������x���������Ƃ����肢�͕����肾���A����ł́A����ʖ��Ƃ̒��߂������B
�@���͓ƒf���I�����������x�X�g�E�A���o�����悭���o���Ă͒����Ă���B�S17�ȁA�قǂ悭�R���g���[�����ꂽ����\�������炵���B�����̂ЂƂƂ����B��ԍD���ȏ����̎�́H�Ɩ����A�����S�O�Ȃ��������Ȃ��݂Ɠ����邱�Ƃ��ł���B
�@�����������A�D��������x�O�����ĉ̏��݂͂̂ɏƏ������킹��A�������́A�@�ł͝h�R������̂̇A�ł͏��X�B�ł͉����A����Ђ�ɋy�Ȃ��B�ł͂�����o�[�`�����Ɍ����Ă݂悤�B
�@�܂��A�������̗l�X�ȃ^�C�v�̎����́A�Ⴆ�A�u�l�̂��肢�v�u���сv�u�����߂̊X�v�Ȃǂ��̂�����Ђ�̉̏���z�����Ă݂Ăق����B���̒��ɁA�Ђ�߂ƂȂ��Č����ɕ������Ă���̂������邾�낤�B����́A�������̎����̂��ׂĂɂ����Ă����邱�Ƃ��B
�@���x�́A�Ђ�̎����́A�Ⴆ�A�u�l����H�v���A�z���̒��ŁA�������ɉ̂킹�Ă݂悤�B�\�c�Ȃ��I�����A�₩����炩���ɂ����ĂЂ�ɂ͈������Ɗ�����͂����B���܂��܈�Ȃ�z�肵�����A���́A�Ⴆ�A�u�_�v�u�^���Ԃȑ��z�v�u�`���\�O�Ԓn�v�ł��������Ƃ������������B
�@�������Ȃ��݂͕\���͂ɂ����Ă͔���Ђ�Ɣ䌨�����邪�A�\���̑��l���ɂ����ċy�Ȃ��B
�@�u�߂������v�́A�ŏ��A����Ђ�̎����̂ł͂Ȃ������B1960�N�A�R�����r�A���R�[�h�̐V�l�E�k����Ղɑ�䏊�Éꐭ�j���������낵�����́i�쎌�͐Ζ{���R�N�j�B�Ȃ̗͂Ɏ��M�������Ă����Éꂾ�������A���҂ɔ����đS������Ȃ��B���߂���Ȃ��É�͈ꎞ�k���O�Y�ɉ̂킹�悤�Ǝv�����������������炵���B�������A�k����1963�N�A�V���N���E�����R�[�h�ɈڐЁB���̃A�C�f�B�A�͖�������B
�@�u�߂������v���Ђ�̉̂ł����m��Ȃ����Ȃǂ́A�Éꂪ�����j���ōl���Ă����Ƃ͈ӊO�������B�����Ƃ��A�j���ŏ��S���̂��̂͒������Ȃ����A�����悭�ǂ߂A�j�̂ł����������Ȃ����Ƃ����邪������B
�@�Éꐭ�j���u�߂������v�������납�����Ђ�ɉ̂킹�����Ɗ肤�悤�ɂȂ������͒肩�ł͂Ȃ��B�k����Ŕ���Ȃ���������Ȃ̂��A�͂��܂��A�Ђ�̃����[�X�̒��O�Ȃ̂��B����͂Ƃ������A�u�߂������v�́A�r�[�g���Y�����ɕ���1966�N6���A����Ђ�̐V�ȂƂ��ă����[�X���ꂽ�B
�@�����ɓ������āA�É���͂��ߊW�҂́A�u�߂������v�����l�̎����̂��������Ƃ����S�ɔ�ɂ��Ă����悤���B�����Ђ肪��Ԑ����������͂��͂Ȃ��Ƃ̊뜜����ł���B�Ƃ���ŁA�I���W�i���̎�E�k����̏����₢���ɁH �M���ł������ȃl�b�g�L���ɁA�u1966�N8��9�����S�A���N30�v�Ƃ���B�Ђ�Ք���������3������B���Ȃ�����^�����낤���B
�@�u�߂������v�Ƃ��������̂̑䎌�ł��邪�A�ŏ��̘^���ɂ͂Ȃ������Ƃ̂��ƁB���������́A�����N�̐V�h�R�}����6�|7�������̃��n�[�T�����A1�R�[���X��̊ԑt���ԉ��т���Ɗ������Ђ�̃A�C�f�B�A�������B�����ł��ꂪ�]�����ĂсA�t�@������̗v�]�ŁA�u�߂������v�䎌���胔�@�[�W�������^���A��1967�N3���A4�ȓ���33��]�V���O���Ձi���݂̃~�j�E�A���o���H�j�Ŕ������ꂽ�B�Ȍケ�ꂪ��ԂƂȂ�A�䎌�Ȃ��I���W�i���E���@�[�W������m��l�͏��Ȃ��B�����Ȃ鎄�����������Ƃ��Ȃ��A����Ƃ������Ă݂����C������B
 �@��ȉƑD���O�͌����u���ƃ����f�B�[�ō\�����ꂽ�̂Ƃ������F���̕\���҂��̎肾�Ƃ������������ł��邪�A���̉̎肪��Ƃ̈Ӑ}���ĉ̂��A�܂�y�Ȃ���Ƃ̎肩��D������Ď����̂��̂ɂ��Ă��܂����Ƃ��ɂ߂ċH�ɂ������݂���B����Ђ�Ƃ����̎肪�����������B�����m��B��̗�ł���v�i�D���O���u�̂͐S�ł��������́v���j�B
�@��ȉƑD���O�͌����u���ƃ����f�B�[�ō\�����ꂽ�̂Ƃ������F���̕\���҂��̎肾�Ƃ������������ł��邪�A���̉̎肪��Ƃ̈Ӑ}���ĉ̂��A�܂�y�Ȃ���Ƃ̎肩��D������Ď����̂��̂ɂ��Ă��܂����Ƃ��ɂ߂ċH�ɂ������݂���B����Ђ�Ƃ����̎肪�����������B�����m��B��̗�ł���v�i�D���O���u�̂͐S�ł��������́v���j�B�@�������Ȃ��݂ɋH��̖��ȁu��̓n���v��������̊E�̑�䏊�D���̌��t�����ɏd���B�ނ̕��ӂ�ǂ݉����A����Ђ�Ƃ����̎�́A���ׂẲ̎�E��Ƃ����z�����B�ꎊ���̑��݂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�킪�h�����鉹�y�]�_�ƁE�����Ǒ��Y���́u�w�����A�����܂ł̉̎�͏o�ė��܂����ˁB�����ł��傤�H�x����Ђ�̘b�ɂȂ�ƁA��Ă��̐l�����������B���̓s�x�l�͂��Ȃ����B�g�s���o�̓V�ˁh�Ƃ������t�́A���̐��E�ł͔ޏ���p���Ǝv���Ă���B���̖��͂ɒ��킵�āA�̗w�j�ɖ����c���쎌�A��ȉƂ������A��������ō�i������B���삪�����͂��ł���v�ƒ����u�������̗��s�́v�̒��ŏq�ׂĂ���B�ꗬ�̍�Ƃ������A�������āg����Ђ�̂��߂Ɂh�y�Ȃ�����̂ł���B
�@�u�߂������v�Ƃ����̂́A����Ђ�Ƃ����H��̓V�ˉ̎�ɏ��荇�����Ƃɂ���āA�܂������V���������������܂ꂽ�B�j�ƕʂꂽ���̗҂����Ɛ@���Ă������Ȃ����������ɑ����ĐX�Ɖ̂��グ��Ђ�̉̏��ɒ�����͐�������A�������u�߂������v�͂Ђ艉�̂̑�\��ƂȂ��Ă������̂ł���B�ʔ����̂́u�߂������v���ŏ��͖����Ȃ��V�l�̎�̎����̂������A�Ђ�̂��߂ɍ��ꂽ�Ȃł͂Ȃ������A�����A����Ђ�́u�߂������v�͓�Ԑ����������A�Ƃ��������ł���B
���Q�l������
�D���O���F���̗������u�̂͐S�ł��������́v�i���{�o�ϐV���Ёj
�����Ǒ��Y���F�u�������̗��s�́v�i�}�K�Ёj
2016.01.10 (��) > ���ƃZ���X�̊��S��`�҃u�[���[�Y�̎��𓉂�
 �@�V�N���X�A������k���N�ŕs���ȃj���[�X������钆�A�t�����X�̖��w���ҁE��ȉƂ̃s�G�[���E�u�[���[�Y���]��������ł����B1��5���A�h�C�c�̃o�[�f���o�[�f���A���N90�B
�@�V�N���X�A������k���N�ŕs���ȃj���[�X������钆�A�t�����X�̖��w���ҁE��ȉƂ̃s�G�[���E�u�[���[�Y���]��������ł����B1��5���A�h�C�c�̃o�[�f���o�[�f���A���N90�B�@�u�[���[�Y�͉����B�������̑�D���ȉ��y�Ƃ̈�l�ł���B�Ƃ͂����ނ̃L�����A���G�Ȃ��ǂ������Ă����킯�ł͂Ȃ��B��������ȉƂƂ�����ʂ͘I�قǂ��m��Ȃ��B������A�u�[���[�Y�̑S�̑��ȂǕ`����킯���Ȃ��B�ȉ��́A�܁X�Ɋ������w���҂Ƃ��Ă̈�ۂ𗊂�ɍ\�z�����f�ГI�ƒf�I�u�[���[�Y�Ǔ����ł���B
�@�܂��̓��p�[�g���[�ɂ��āB�t�����X�l������x�����I�[�Y�A�h�r���b�V�[�A�����F���Ȃǂ̃t�����X���́A����̍�ȉƂ�����X�g�����B���X�L�[�A�o���g�[�N�A�V�F�[���x���N�A���@���[�Y�Ȃǂ̋ߌ�����̂��������߂�͓̂��R�B�h�C�c���̂́A���[�O�i�[�A�}�[���[�͂��邪�A�x�[�g�[���F���A�u���[���X�͋ɏ��B���V�A�E�X�����n�͂قڊF���B���Ƀ��j�[�N�ł���B
 �@�w���҃u�[���[�Y�̃L���b�`�E�R�s�[�́H�u���ƃZ���X�̊��S��`�ҁv�͂ǂ����낤�B���̏́A�o���g�[�N�i1881�|1945�j�̃s�A�m���t�ȑS3�Ȃ̘^���i2001�N�\2003�N�j�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���Ȃ̘^���͑��ɂ��������邪�A�u�[���[�Y�͍̂ۗ����Ă���B�Ȃɂ��Ƃ����A�P�Ȃ��ƂɃs�A�j�X�g�ƃI�[�P�X�g����ς��Ă��邱�ƁB�����āA���̋N�p���e�X�̋ȑz�Ƀs�V�����ƛƂ��ނȂ������x�������Ă��邱�Ƃł���B
�@�w���҃u�[���[�Y�̃L���b�`�E�R�s�[�́H�u���ƃZ���X�̊��S��`�ҁv�͂ǂ����낤�B���̏́A�o���g�[�N�i1881�|1945�j�̃s�A�m���t�ȑS3�Ȃ̘^���i2001�N�\2003�N�j�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���Ȃ̘^���͑��ɂ��������邪�A�u�[���[�Y�͍̂ۗ����Ă���B�Ȃɂ��Ƃ����A�P�Ȃ��ƂɃs�A�j�X�g�ƃI�[�P�X�g����ς��Ă��邱�ƁB�����āA���̋N�p���e�X�̋ȑz�Ƀs�V�����ƛƂ��ނȂ������x�������Ă��邱�Ƃł���B�@�@��1�ԁ@�N���X�e�B�A���E�c�B�}�[�}�� (P)�@�V�J�S�����y�c
�@�@��2�ԁ@���C�t�E�I���F�E�A���X�l�X (P)�@�x�������E�t�B���n�[���j�[
�@�@��3�ԁ@�G���[�k�E�O�����[ (P)�@�����h�������y�c
�@��1�Ԃ́A����ȃ��Y����O�ʂɉ����o����Ƃ��������������o���B�s�A�m�͂܂�őŊy��B�Ô��Ȋ������ؔr�����������R��ɏI�n����B�u�[���[�Y���N�p�����̂́A�c�B�}�[�}���ƃV�J�S���B���㐏��̃��B���e�B�I�[�]�E�s�A�j�X�g�ƃI�P�B�c�B�}�[�}���̓P�^�Ⴂ�̋��łŋȂ̖\�͐���\�o���A�V�J�S���͖��������ꂽ�e�N�j�b�N�Ő��k�ɉ�����B�����̌��Ȃ����t�ł���B
�@��2�ԁB�s�A�m�͑�1�ԂƓ������Ŋy��I�����I�P�Ƃ̋������͂�����̕��������B���A���T���u���d���Ŏ����y�I�Ƃ�����B�����Ńu�[���[�Y���N�p�����s�A�j�X�g�̓m���E�F�[�o�g(����)���̃A���X�l�X�B�I�P�̓x�������E�t�B���ł���B�A���X�l�X�́A���X���������Ǝ����y�I�f�{�i���\�������y�t�F�X�e�B�o������Ɂj��ɋȂ̖{����˂��Č����ł���B�x�������E�t�B���Ƃ̃A���T���u�����S�n�悢�B
�@��3�Ԃ̓o���g�[�N���̔N�̍�i�B�Ō��17���߂��c���đ��E�B�F�l��ȉƃe�B�{�[���E�V�F���C�����������B��Ȃ̌o�܂͑��q�ւ̎莆����M����B�u���O�̕ꂳ��̂��߂Ƀs�A�m���t�Ȃ������B���x�����t����A���������̑����ɂ͂Ȃ�͂����v�B����\�������o���g�[�N�̓s�A�j�X�g�̍ȃf�B�b�^�E�p�[�X�g�����o���g�[�N�̂��߂ɑ�3�Ԃ��������̂ł���B���̂��߁A�O2����Z�I�I�ɂ͈Ղ����A�Ȓ����R��I�ł���B�u�[���[�Y�͂���ɐl�C�����s�A�j�X�g�A�G���[�k�E�O�����[��z�����B�����Ɠ��̗D�����i�C�[�u�ȏ���Y�����t�B�����h�������_��ɗ���Ŕ������B
�@�o���g�[�N��3�Ȃ̃s�A�m���t�Ș^���B�����ɂ̓u�[���[�Y�Ƃ����w���҂̂��ׂĂ��Ïk����Ă���B�y�Ȃ̓��������ɂ߁A���t�҂̎���������߁A���̂����č������x�̍�i�Ɏd�グ��B���S��`�҃u�[���[�Y�̐^�������B���E�̃N���T���Ɂu���m�����l�ԂŊ��S��`�҂���Ȃ��������̂��ˁH�v�Ƃ������������邪�A����͂�������u�[���[�Y�ɓ��Ă͂܂�B
�@�m���ȑ�NJςƍו��ɋy�ԕ��͗́B���x�ɕ`�����v�}�������ɋ������\���́B�Y�ݏo���ꂽ���y�͔����������������ׂ̂��Ƃ͔��o���������Ȃ��B���ꂼ�ދH�Ȃ�Z���X�ƍ��x�ȃX�L���̎����B�܂��Ɂg���ƃZ���X�̊��S��`�ҁh�Ȃ̂ł���B
�@�u�[���[�Y�̓�����m�������̘^��������B�x�����I�[�Y�̉̋ȏW�u�Ă̖�v�i2000�N�^���j�ł���B�����ł��ނ͑��ɗ�����Ȃ����t�����B
�@�u�Ă̖�v�̓t�����X�̃��}���h���l�e�I�t�B���E�S�[�e�B�G�̎��Ƀx�����I�[�Y�i1803�|1869�j���Ȃ�����6�Ȃ̉̋ȏW�B���t�́A�ŏ��̓s�A�m�A��Ɋnj��y�ł�������B�g��̐��h�g���߂����h�g�r�߂̈Łh�g�V�g�̗��h�Ȃnj��z�I�ŗd�C�Y�����Ƀ��}���e�B�b�N�Ŕ����������f�B�[���悹�A�����ŐF�ʊ�����I�[�P�X�g���̋����̒��ɁA�����̐��E�����o���Ă���B
�@�u�Ă̖�v�̘^���̂قƂ�ǂ������̃\���ʼn̂��Ă��钆�A�u�[���[�Y�͕����̉̎���N�p�����B��1, 6�Ȃ��\�v���m�A2, 3�Ȃ��o�X�A4, 5�Ȃ��e�m�[���Ƃ�����B�o�X�ɂ���2�ȁu��̐��v�ȂǁA�����ŕ����Ȃꂽ���ɂ͂��Ȃ�̈�a��������B�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��A�Ǝv���Ē��ׂ�ƁA�Ȃ�Ƃ��ꂪ�nj��y�ł̃I���W�i���`�������B�ނɂ͔ނȂ�̈Ӑ}������M�O���������̂��B�u�[���[�Y�̓��قȌ�������B
�@7�ΔN��̎w���҃��i�[�h�E�o�[���X�^�C���́u�N���V�b�N���y�Ƃ́H�v�Ƃ������Ɂu�k���ł��邱�Ɓv�Ɠ����Ă���B���ꂼ�܂��Ƀu�[���[�Y�̓����ł͂Ȃ��낤���B�������{�l�������v���Ă���H ����ȓ�l�̉��y�͂܂��ɑɂɈʒu����Ƃ����邾�낤�B��M�I emotional �ȃo�[���X�^�C�� VS �m���I intellectual �ȃu�[���[�Y�̐}���ł���B
 �@��l�̕\���҂Ƃ��Ă̈Ⴂ���ł��ۗ��̂��x�����I�[�Y�́u���z�����ȁv���B��l���̌���������M�I���z�I�ɑ�����o�[���X�^�C���i�j���[���[�N�E�t�B��1963�^���j�B�m���I�D��ɕ\������u�[���[�Y�i�N���[�������h��1996�^���j�B�O�҂̃x�X�g�͑�4�y�́u�f����ւ̍s�i�v�ł����҂̂���͑�2�ȁu������v���B���̃u�[���[�Y�̐߉̂Ȃ�ƃ`���[�~���O�Ȃ��Ƃ��I �ɓI�ȓ�́u���z�����ȁv�B������N���V�b�N�ӏ܂̑�햡�B�ǂ���������I�Ȗ����ł���B
�@��l�̕\���҂Ƃ��Ă̈Ⴂ���ł��ۗ��̂��x�����I�[�Y�́u���z�����ȁv���B��l���̌���������M�I���z�I�ɑ�����o�[���X�^�C���i�j���[���[�N�E�t�B��1963�^���j�B�m���I�D��ɕ\������u�[���[�Y�i�N���[�������h��1996�^���j�B�O�҂̃x�X�g�͑�4�y�́u�f����ւ̍s�i�v�ł����҂̂���͑�2�ȁu������v���B���̃u�[���[�Y�̐߉̂Ȃ�ƃ`���[�~���O�Ȃ��Ƃ��I �ɓI�ȓ�́u���z�����ȁv�B������N���V�b�N�ӏ܂̑�햡�B�ǂ���������I�Ȗ����ł���B�@ �@���̂ق��ɂ��u�[���[�Y�́A�}�[���[�̌����ȑS�W�i�E�B�[���E�t�B���j�A�X�g�����B���X�L�[�u�t�̍ՓT�v�u�y�g���[�V���J�v�i�N���[�������h�ǁj�A�h�r���b�V�[�nj��y�ȏW�i�N���[�������h�ǁj�A�����F���nj��y�ȏW�i�x�������E�t�B���j�A���[�c�@���g���x���N13�A���[�c�@���g��Պ�����x�[�g�[���F���u�c��v�iBBC�� C.�J�[�]��P�j�A���[�O�i�[�̊y���u�j�[�x�����O�̎w�vDVD�i�o�C���C�g�j�Պǁj�Ȃǐ��X�̖����t���c���Ă��ꂽ�B�X�Ɍ��y����ƍی����Ȃ��̂Ŋ������邪�A���ׂĂ͂��������̂Ȃ���Y�ł���B�����ɂ́A�Ώۂ��˂�圤�ȊႪ����B��Ԃ�Y���D��ȋ���������B���_�Ɍĉ����鐴���ȕi�i������B�����āA�����́A������̊����𑪂郊�g�}�X�������ł�����B���ꂩ����������������鎩���ł��������̂ł���B���ƃZ���X�̊��S��`�҃u�[���[�Y ���炩�ɁI�I
2015.12.28 (��) 2015�N�����k with Ray�����
�@��������Ray������ɂȂ����H ����2��8�����ł����BJiiji�Ƃ������b���ł���悤�ɂȂ����ˁB �Ƃ���ŁA8���p�p�ɓn�����uJiiji���70�N�Ɏv���v�͓ǂ�ł��ꂽ���ȁB�����ƁA�܂��ǂ߂�킯�Ȃ����B�傫���Ȃ����琥��ǂ�łˁB
�Ƃ���ŁA8���p�p�ɓn�����uJiiji���70�N�Ɏv���v�͓ǂ�ł��ꂽ���ȁB�����ƁA�܂��ǂ߂�킯�Ȃ����B�傫���Ȃ����琥��ǂ�łˁB�@�Ƃ����킯�ŁA�v�����܂܁A�C�̌����܂܁A���s���A�ƒf�A�Ό��A�x���ŗ�A�ō��N��U��Ԃ��Ă݂܂��傤�B
�@���N�̊����́u���v�������ˁB���ۖ@���A�e���̕s���A�}���V�����̈��S�s���A�ȂǂȂǁB����͂���œ������Ă��ˁB�͂Ă��āAJiiji�̍��N�͉��������낤�B9���ɂ͖�ῂœ|��ċ~�}�ԁ����@�B10���ɂ̓I�y���n�E�X�œ]�|�B����Jiiji�̍��N���u�|�v���ȁB
�@���N�̓I�����s�b�N�C���[�B2020�N�͓������B����Ȓ��A�V�������Z���͂��߂Ă�ˁB�g�D�ψ����̐X�P�N�����������������ށB�u�l��B�Ă������Ȃ��BA�Ă�ASEAN�̂���݂������v�����Ă��B
�@��́A�O�ς����Ŕ��f����Z���X�����B���Z��Ƃ����͈̂�ɑI��̎g������A��Ɋϋq�̌��₷���S�n�悳�B�O�ςȂ�ē�̎��Ȃ̂ɁB���������l���g�D�ψ���̉�������̐l�͂���Ă��Ȃ��B�L�c�͒j����������~�����̂��������B
�@�����u�I���͌��߂闧�ꂶ��Ȃ�����A�ʂɍ\���Ȃ����B�L�҂ɐu���ꂽ���痦���ɓ������܂ł��v�Ȃ�ċt�M�����Ă��́B�݂��Ƃ��Ȃ��B���̐l�̂��疳�ӔC�̋ɂ݁B2001�N�A�F�a���̐��Y���Z���̑D���P�����q���ɃA�����J�̌��q�͐����͂ƏՓ˂����n���C�����̂̂Ƃ����A����Ă��S���t�����̂܂ܑ������Ⴄ���A�\�`�Ő�c�^������V���[�g�Ń_���������Ƃ����u���̖��A�̐S�ȂƂ������]�ԁB�ǂ������킯���v�Ȃǂ̌y���B�g�D�ψ������������Ƃ��u2020�N��82�B
 �Ȃ�Ƃ�����܂ŘV�X���N�����撣�肽���v���Č��������ǁA�����\���ɎN���Ă܂����B�A�g4�N�B���������ǂ��܂ŎN���Ⴂ�I�H
�Ȃ�Ƃ�����܂ŘV�X���N�����撣�肽���v���Č��������ǁA�����\���ɎN���Ă܂����B�A�g4�N�B���������ǂ��܂ŎN���Ⴂ�I�H�@�X����̎����͂��Ă����A12��22���A�V�������Z���A�ĂŌ��܂����ˁB���܂�ǂ���ł�������A�Ԃɍ�����������A��Jiiji�͎v���Ă������ǁA����Ȃɂ��g���܂݂̗l���B
�@�������������A���̑I�藝�R�́B�ő�̗��R�͍H�������āB�����\�����Ă��Ƃ炵���BA�Ă�B�Ă�2019�N11�������B���Ƃ��o������Č����Ă����M�p�����������Ȃ��́B�Ȃ�őf�l�������\���f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��́H ���x���������ǁA���Z��͑I��Ɗϋq�ւ̔z�������B���ꂪ�a�Ă������Ă�Ȃ�R�b�`�ł��傤�BB�Đv�҂̈ɓ��L�Y�������匾���̂͂����Ƃ����B���O�ɂ́uA�Ă��肫�Ői��ł����B���̕��̓X�P�[�v�S�[�g�v�B���ꂪ�{���Ȃ���肾���B�G����ɂ͐ӔC�Ȃ����ǂˁB
�@�뜜�͂����꒚�B���̃U�n�E�n�f�B�g�����uA�Ă̊�{�\���̓E�`�̃p�N���v�ƌ�������A������A�قƂ�Ǔ�������Ȃ��́B����͝��߂邼�B���̂�����A���O�[���������̂Ȃ��B
�@�G���u���������݂��Ƃ��Ȃ������ˁB����O���L���҂̌��،��ʂ��o�����ǁA��ꎟ�R���ŕs�����������Ƃ̂��ƁB���O��8�l�ɎQ����v�����Ă��āA�ꎟ�R���ł��̂����̓�l�̓_�����B���Ȃ������̂ŁA�ψ����ٗʂʼn������Ƃ��B����m���ɕs���B���A��Ԃ̖��́A�u���쎁�̍�i�͍ŏI�R���܂ł��ׂčő����[����������A�o�����[�X�Ƃ̔ᔻ�͂�����Ȃ��v�Ƃ������ؕ��B�Ȃ����B7��8�Ԃɕs���������Ă��P�Ԃɂ͉e���Ȃ�������Ȃ������āB���n�̐i�H�W�Q���Ⴀ��܂����B����ȃA�z�����܂���ʂ�A�}�X�R�~����莋���Ȃ��B�e���r�̃R�����e�[�^�[��������ʌ��@���ĂȂ��ŁA��l���炢�͋C�����Ă�B�������u������݂�ȃA�z�v�Ƃ����̉���Ȃ��B
�@�s���Ƃ�����FIFA���u���b�^�[���8�N�Ԃ̎��i��~�����������ꂽ�ˁB�ߏ���v���e�B�j���ւ�1��7000���~�̕s�����^�B���ۂ̓R���i��������Ȃ��͂������ǁA��������낤�B�u���͐�Ζ߂��Ă���v���Č������Ƃ��B�}�b�J�[�T�[���Ⴀ��܂����B8�N���87�B���̕��ǂ��܂ŗ~�����������́I�H
 �@�T�b�J�[�Ƃ����AFIFA�N���u�E���[���h�J�b�v���T���t���b�`�F�L���̐킢�Ԃ�͌����������B�������œ�đ�\���o�[�v���[�g�ɐɂ������s�ꂽ���ǁA3�ʌ����ŁA�A�W�A���ҁE�L�B�P��ɋt�]�����B�N�ԗ\�Z500���~�A���̒����̐����R�c��10����1�ɂ������Ȃ��L�������B�ɉ����̏�Ȃ��I�I �X�ۈ�ē̃��b�g�[�́u��������肵�ԂƂ��D��v�B�X�^�C���͌��瑬�U�B���ꂼJiiji�����߂���{�̃T�b�J�[���B�T�b�J�[����́A�����A��\�ē�X�ێ��ɑւ���ׂ��B����������V�A�͐���オ�邼�[�[�I
�@�T�b�J�[�Ƃ����AFIFA�N���u�E���[���h�J�b�v���T���t���b�`�F�L���̐킢�Ԃ�͌����������B�������œ�đ�\���o�[�v���[�g�ɐɂ������s�ꂽ���ǁA3�ʌ����ŁA�A�W�A���ҁE�L�B�P��ɋt�]�����B�N�ԗ\�Z500���~�A���̒����̐����R�c��10����1�ɂ������Ȃ��L�������B�ɉ����̏�Ȃ��I�I �X�ۈ�ē̃��b�g�[�́u��������肵�ԂƂ��D��v�B�X�^�C���͌��瑬�U�B���ꂼJiiji�����߂���{�̃T�b�J�[���B�T�b�J�[����́A�����A��\�ē�X�ێ��ɑւ���ׂ��B����������V�A�͐���オ�邼�[�[�I�@�X�|�[�c���łɃt�B�M���A���H�������B�O�����v����t�@�C�i���Œ@���o�����g�[�^��330.43�̓��_�͗]�l���Ȃ��ĉz���������̍��ˁB�ނ͂��̎��̃C���^�r���[�Łu�v���b�V���[�͊����܂��B��������̂ł��B�����瓦��悤�Ƃ͎v��Ȃ��B�����������̂��Ǝv���ĕt�����������Ȃ��v�݂����ȈӖ��̂��Ƃ�����ׂ��Ă����B���Ƃ��ȒP�ɔ��ł�悤�Ɍ����Ă���͂�l�ԁB�v���b�V���[�͊����Ă���B����܂��đΉ�����H������͑債������B
�@�����Ŏv���N�������̂͑̑��̃G�[�X�����q���̃����h���ܗցB�ނ͈���ڂő厸�s����炩���ă��_���̊�@�Ɋׂ����Ƃ������������B�u�I�����s�b�N�ɂ͖����������ł����˂��B�����ƈႤ���͋C�ł����B�����f���ăv���b�V���[����Ȃ��v�ƁB�����ƈႤ�Ƃ������Ƃ̓v���b�V���[�Ȃ�ł���B�����F�߂悤�Ƃ��Ȃ��͔̂ނ̎コ���낤�ˁB
�@�v���b�V���[�͂���Ƃ����H���ƂȂ��Ƃ��������B���E�ō��N���X�̍��݂ɂ����l�̍����R���BRay�����A�ǂ��炪�������͔����ˁB������̂͂����A�����N�B�N���u�v���b�V���[�͂���v�ƌ����ł������A�^�̍��݂ɓ��B�����Jiiji�͎v���B
�@12��24���ɉ����ꂽ���l�����ĉғ��̔����ɂ��āB4���ɂ́A����n�ق̔���p���ٔ������u�V�K����͊ɂ₩�߂��Ĉ��S�����m�ۂ���Ȃ��v�Ƃ������A����A�я��ٔ����́u�V�K����͍ŐV�̉Ȋw�E�Z�p�I�m���Ɋ�Â��n�k����߁A���S��d�v�Ȏ{�݂ɂ͓��ɍ��x�ȑϐk���̊m�ۂ����߂����e�ɂ͍�����������v�Ƃ��č����~�߉����������������B�V���ȏ؋����o�ĂȂ��̂ɁA�����Č����ٔ����ŁA�ʂ̍ٔ������^�t�̔����������B�i�@������ł�����ł����H �i�@�̖����Ƃ͉����H�@�̌���������邱�ƁA���͂�@�ɂ���ă`�F�b�N���邱�Ƃ��낤�B�ٔ����̌��͈ٓ�������d���Ȃ��Ƃ��āA���̐^�t�̔����͌���������͂قlj����B�����̍����e�������B�ꂷ��B
�@���N3���ŁA�e�����u�X�e�[�V�����v�̌Êوɒm�Y���~���悤���BJiiji�͂��̐l����������劽�}�����A�J�ł̓L�i�N�T�C�\����ь����Ă�ˁBTBS�́u�j���[�X23�v�݈̊䐬�i�L���X�^�[���~���炵���B���N3���ɂ�NHK�u�j���[�X�E�H�b�`9�v�̑�z����L���X�^�[���~���Ă���B���̈�A�̍~�����������̈��́I�H �{�����Ƃ�����A�Ƃ�ł��Ȃ����_���������A������}�X�R�~����Ȃ��B
�@12��28���A�Ԉ��w����O�i�̕����Ă����B���ؑo���̊O������g�ŏI�I���s�t�I�ɉ������ꂽ�Ɗm�F�����h�Ƃ̋����������������B�v����ɁA�؍��͍��ケ�̌��Ɋւ��ăK�^�K�^����Ȃ��Ɩ����킯���B���̓P���ɂ��Ă͋ʒ��F�Ŏc�������ǁAJiiji�͒P���Ƀ��J�b�^�Ǝv���B���͖k���̓y���B
�@���ۖ@���ɂ������A�̃S�������ȂǁA���N�����{�����̉��\���ڂɗ]�����ˁB�����}���ɋc�_���Ȃ��Ȃ��Ă���B�}�c���͊������g����������ӖړI�ɂ��Ȃ������B�ᔻ�͂��@�x�A�R���͂̉�͓E�܂��B9���̑��ّI�A�����[�̈��{�đI�����T�^���B�����}�̊F����A���ꂶ�Ⴝ�܂��ł��傤�B�����͐������̑��݂��B�l�Ԃ���Ȃ��̂����ĂˁB�����}���̂͂�������Ȃ��������ǂȂ��B�ێ�{���ɑ����x���������݊��������Ă����B�G�r��B���͂ǂ����B�Éꐽ�A�ݓc���Y�B���{�̌����Ȃ�B���{�ꋭ�̕⊮���͂ɐ��艺�����Ă���B����͏��I���搧���낤�B
�@����A��}�Ɋ��҂��邩�H ����}�͏I����Ă��邵�A�ېV�͕���B�܂Ƃ��Ȃ̂͋��Y�}�����H ���ꂶ�Ꭹ���ƍفE���{�ꋭ�͉i�v�ɑ������Ⴄ�B���̕NJ��I
�@Jiiji�͐������\�Ȗ�}���~������B�ł������ɂ͖����B�Ȃ�A�ʂ̓X�J�ł����W�ɂ�鐔�ł̑R�����Ȃ��B����͗��N�Ă̎Q�@�I�B�錍�͖�}���̈�{���B
 �@����Ȓ��A12��24���̒����V���Ɂu���Y�}�u�ʈψ������ɐڋ߁v�Ȃ�L�����o�Ă����B�e�[�}�͎������\�Ɏ��~�߂�������g��}�����h�B���̂��߂ɋ��Y�}�͈�I�������̑I���헪���̂Ă邻���ȁB���Y�}�A�����M�[�̖���}���g��}������h�ʼn�����悤���B�Ȃ���Y�}�͎v�����ē}����ς��Č��W���͂̊j�ɂȂ�����ǂ����낤�B�g���{���x�����}�h�Ƃ��B����Ȃ������H �����Ȋ��҂��N���Ă���B
�@����Ȓ��A12��24���̒����V���Ɂu���Y�}�u�ʈψ������ɐڋ߁v�Ȃ�L�����o�Ă����B�e�[�}�͎������\�Ɏ��~�߂�������g��}�����h�B���̂��߂ɋ��Y�}�͈�I�������̑I���헪���̂Ă邻���ȁB���Y�}�A�����M�[�̖���}���g��}������h�ʼn�����悤���B�Ȃ���Y�}�͎v�����ē}����ς��Č��W���͂̊j�ɂȂ�����ǂ����낤�B�g���{���x�����}�h�Ƃ��B����Ȃ������H �����Ȋ��҂��N���Ă���B�@����ɂ��Ă����Y�}�Ə����Y�����g�ނƂ͊u���̊��BJiiji�ɂƂ��Ă�RCA��CBS�ƍ��̂����ȏ�̏Ռ������I�I
�@�Ƃ����킯��Ray�����A2015�N�����܂��ˁB���N�͌ܘY�ۃ|�[�Y��u�V���C�g�E�T���_�W���v�u�����Ă܂����v�Ȃǂ̌��ߕ�����������ˁBJiiji�Ƃ��F�X���b�ł���悤�ɂȂ����B���N�͂������g�ɐi���������You�N���Ђ悱�g�ɓ����Ă���ˁB���o�����̊ј\�̌����������B
�@2016�N�\�N�B�k�C���V�����J�ʁA�ɐ��u���T�~�b�g�A���I�ܗցA�Q�@�I�A�A�����J�哝�̑I���Ȃǃj���[�X�͖ڔ������B���ސ錾���������O�A���@�����A�����n���A�����ĉғ��A�����{�����A�����̖�]�A���؊W�A�̓y���A�W�c�I���q���Ɠ��ē����A������A�e����A�n�����g���A�ُ�C�ہA�i�C�����A�d�͎��R���A�Ȃǂ�����ڂ������Ȃ��B����A���N�͂���܂ŁB���N���������N�ł���܂��悤�ɁI�I
2015.12.10 (��) �e���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂��H
�T���g���͂Ȃ�ƌ������낤���H �@���N����������1����������B11��13�����j���ɂ̓p���œ��������e�����N�����B�]����130�l�B�v���V�������[�E�G�v�h�P�������͐����C�������߂���1��7���������B�����āA�㓡����E�Q�����i2���j�A�`���j�X�����كe�������i3���j�A���V�A���q�@���j�����i10���j�A�g���R�ɂ�郍�V�A�퓬�@���āi11���j�����N�����B12�������A�ăJ���t�H���j�A�B�ŋN�����e���ˎ������e���ƒf�肳�ꂽ�B�e���r�Ńt�����X�l���u���N�̓e���Ɏn�܂�e���ɏI������N�������v�ƌ���Ă���p����ۓI�������B�e�����������Ă���B�����Ƃ���ɂ��ƈ�N�ԂɋN����e��������1������z����炵���B
�@���N����������1����������B11��13�����j���ɂ̓p���œ��������e�����N�����B�]����130�l�B�v���V�������[�E�G�v�h�P�������͐����C�������߂���1��7���������B�����āA�㓡����E�Q�����i2���j�A�`���j�X�����كe�������i3���j�A���V�A���q�@���j�����i10���j�A�g���R�ɂ�郍�V�A�퓬�@���āi11���j�����N�����B12�������A�ăJ���t�H���j�A�B�ŋN�����e���ˎ������e���ƒf�肳�ꂽ�B�e���r�Ńt�����X�l���u���N�̓e���Ɏn�܂�e���ɏI������N�������v�ƌ���Ă���p����ۓI�������B�e�����������Ă���B�����Ƃ���ɂ��ƈ�N�ԂɋN����e��������1������z����炵���B�@�����C�X�����ߌ��h�֘A�̃e���������N���邽�тɁA�u�e���ɋ����Ȃ��v�u�f���ċ����Ȃ��v�u���{�������đΊ݂̉Ύ��ł͂Ȃ��v�Ȃǂ̕�������ь����B�m���ɂ��̒ʂ肾�B�����A����ȑO�㖢���̐}�������o�����̂͒N���H���{���W�I�ɂȂ����̂͒N�̂������H
�@����A���E��k���������̂́A�e�����X�g�̎c�E�Ȏ�����̂��͖̂ܘ_�����A�ނ��낻������A�t�����X�Ƃ����������̒��ɁA�������������ɂ���אl�̒�����e�����X�g���Y�܂�o���Ƃ��������ł͂Ȃ����낤���B
 �@���V���̉f��u��nj��v�̒��ŎO�D�q�Y�����鑺��Y���́u���̒��Ɉ��l�͂��Ȃ��B�����������邾�����v�ƌ����B�܂��A�u�ԂЂ��v�̐V�o����́u����܂Ő������n���Ɩ��m�ɑ��ĉ����������Ƃ����邩�H�v�Ɛ����Ɏg����₤�B
�@���V���̉f��u��nj��v�̒��ŎO�D�q�Y�����鑺��Y���́u���̒��Ɉ��l�͂��Ȃ��B�����������邾�����v�ƌ����B�܂��A�u�ԂЂ��v�̐V�o����́u����܂Ő������n���Ɩ��m�ɑ��ĉ����������Ƃ����邩�H�v�Ɛ����Ɏg����₤�B�@�g���m�h���g���ʁh�ƒu��������A�u�����e�����X�g���Y�ށB�n���ƍ��ʁB�������琶�ݏo����鑞���B�����o�ł��Ȃ�����e�����X�g�͎Y�܂ꑱ����v�Ƃ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����B
�@�n���ƍ��ʂɋꂵ�ސl�Ԃ��݂�ȃe�����X�g�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B��̗v����o�ł�����ׂĂ��Ȃ��Ȃ�킯�ł��Ȃ��B���R�Ƃ����s������e���ɑ���l�Ԃ�����B�����āA�ނ����荞�ރl�b�g���[�N������B�e���̃C���t���ł���B
�@�e���Ɛ키�Ƃ������Ƃ́A����̍�������ςޘb�ł͂Ȃ��B�����́A�n���ƍ��ʂɌ��������A�e���̃C���t������ł��邱�ƂɈӂ𒍂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���ۘA���͐��E���a��ڎw���Đݗ����ꂽ�B���̍��A���A���Ɉ��S�ۏ�ɂ����āA�@�\���Ȃ��͍̂��X������C�܂܂ɐU�������炾�B���v�Ƃ������̃G�S���ŗD�悷�邩�炾�B�V���A�ւ̑Ή��ɂ͒��\�����ی�������B���C�X���G���̐錾�ɃA�����J�͎^�����Ȃ��B�V���A���߂���A���V�A�ƃg���R�̑Η����\�ʉ�����B�g���R�̓��V�A�̐퓬�@�����āA���V�A�̓g���R�ɕ���B�R���o�ς̗��ʂŁB�����Ĕ�排����B�܂��ɓD�d���B�푈��ԁB���������IS�͂ق����ށB
�@�V���A�̌���͂ǂ����B���b�J�A�J���\�t���B�W���X�~���v���ȗ��A�����R�i�A�T�h�����R�j�Ɣ��̐��R�i���R�V���A�R�j�̑����������B�����ɃA���J�C�_�n�̃k�X�������IS�����ށB�����R�̓��V�A�A���̐��R�̓A�����J���x������B���V�A�͔��̐��R������B���̐��R�ɂ̓g���R�n�퓬�����������烍�V�A�ƃg���R�͓G����BIS�ɑ��Ă͕āA���A�p�A�\�A�Ƃ���������B�����ʂȐ퓬�s�ׂ̒��A�Z���̋]���͂��Ƃ�f����������傷��B�]������������̂͂����߂̂Ȃ����Ԑl���B�������Ă���قǕ��G����ȏ����������낤���I�H
�@���Ȃɂ��厖�Ȃ̂��H �݂�Ȃ킩���Ă�B�킩���Ă��邭���ɂł��Ȃ��BNPT�����āu�������͎��������邪�A���O��͎��ȁv�Œʂ�܂����I�H �e���̃G�S���܂���ʂ�卑�̋��ی���������荑�A�̈��S�ۏ�͋@�\���Ȃ��B���A���A���낻��폟��VS�s�퍑�̐}����`���ς�����ǂ����낤�H �ǂ��l���Ă����̉��ɓ��Ƃ��u����Ă�Ȃ�ĕςł���B���������Ȃ����ǂǂ������܂Ƃ��Ȃ́H�ǂ������D�G�Ȃ́H �m�[�x���܂�106��14�I COP21�����āA�����̑Ή��̕s�����B�����������̐��ʂ���������c�A�s�[���̏�ɉ߂��Ȃ��B�`���̂Ȃ��ڕW�ݒ�ɉ��̈Ӗ�������Ƃ����̂��B�n�����g���ƃe�������т������������B
�@�������̋N�_�͌Â��I���O�ɑk��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ߑ�̂���͑�ꎟ���E��펞�̃T�C�N�X�E�s�R����ł������E��펞�̃C�X���G���������낤�B
�@�卑�͂��̒鍑��`�I�_���Œ����𑀂��Ă����B��~�������t���Ă����B�o�J�ɂ��Ă����B��ɋߔN�̃A�����J�́u���R�v�u�����`�v�Ƃ����g�A�����J�̐��`�h�Ȃ���̂�W�Ԃ��䂪����ʼn�����Ă���B�����̗��ɃG�S���B���āB�u�C���N�푈�v���D�Ⴞ�B
�@�e�����X�g�̉����ƌ��ߕt���j����J���̌��������������B�����ĉ���B�Ƃ��낪�A��ɕ����Ȃ��Ȃ�ƕ�������B���̒n�������̂܂ܕ��u����BIS���Y�ޓy��ƂȂ����B�A���u�̐l�X�͉]���u���R�������`�������B�ق��Ƃ��Ă��� Not Freedom, Not Democracy, It's Dignity�v�ƁB�A�����J�̐��`�Ȃ�ăN�\�H�炦�����ĂˁB
�@�c�E�ȍs�ׂɓ{����o����͓̂�����O�B�x�d�Ȃ�؍s�͌����ċ��������̂ł͂Ȃ��B�u�e���ƓO��I�ɐ키�v�Ƃ̐錾�����R�ł���B�t�����X�̓��V�A�ƘA�g���C�M���X���ĉ�����B�h�C�c���t�����X�̌���x���ɖ����o��B�L�u�A�������̐}�ł���B����ŁA�A�����J�c��̓V���A���������ۂ����B�h�C�c�ł����ꋑ�ۂ��������A��̃t�����X�n�挗�c��I���ł́A�ږ��r�˂��f����ɉE���}FN����吭�}�������链�[���W�߂��B������A�̗���̓e�����X�g�ƃC�X�������k�̓��ꎋ�ɂȂ���B����Ȃ��ƂŖ{���ɖ�肪��������̂��H ���ʂ̉����������̊g����Y�ނ����ł͂Ȃ��̂��B
 �@���{�̐����Ƃ́u�Ί݂̉Ύ��ł͂Ȃ��v�ƌ����B���̒ʂ�ł���B���{�͏W�c�I���q���s�g�ɓ��ݐ����B�A�����J�Ƃ̘A�g��[�߂��̂�����A������������͓��ނƊŘ��B�������p���ɂȂ�Ȃ��ۏ�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B������A�e�����X�g�̗�����h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ńe�����X�g���Y�܂����E�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɍq��e���ɂ͍ő���̒��ӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ͗^�}����}���Ȃ��͂����B��������ۂƂȂ��Ă̑R�K�v�ȂƂ����B�Ȃ̂ɁA�Վ�����͊J����Ȃ��B�����Ƃ̍ő�̎g���͂ȂH �����̖����A�������A��邱�Ƃ��낤�B�G�ɕ`�����݂̈ꉭ��������������ꉭ�����S��}��ق����挈�ł͂Ȃ��̂��B
�@���{�̐����Ƃ́u�Ί݂̉Ύ��ł͂Ȃ��v�ƌ����B���̒ʂ�ł���B���{�͏W�c�I���q���s�g�ɓ��ݐ����B�A�����J�Ƃ̘A�g��[�߂��̂�����A������������͓��ނƊŘ��B�������p���ɂȂ�Ȃ��ۏ�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B������A�e�����X�g�̗�����h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ńe�����X�g���Y�܂����E�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɍq��e���ɂ͍ő���̒��ӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ͗^�}����}���Ȃ��͂����B��������ۂƂȂ��Ă̑R�K�v�ȂƂ����B�Ȃ̂ɁA�Վ�����͊J����Ȃ��B�����Ƃ̍ő�̎g���͂ȂH �����̖����A�������A��邱�Ƃ��낤�B�G�ɕ`�����݂̈ꉭ��������������ꉭ�����S��}��ق����挈�ł͂Ȃ��̂��B>
�@�e���������N���邽�тɕ��������̎�]�͌����B�u�����Ȃ闝�R�����낤�Ƃ��A���̂悤�ȍs�ׂ������킯�ɂ͂����Ȃ��v�ƁB�m���ɂ��̒ʂ肾�B�����A�u�����Ȃ闝�R�v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂��H �������A�l����ׂ����ł͂Ȃ����B
�@�g�D�ɂ��e���A�l�ɂ��e���B���l������������e�����Y���B�e���Ƃ̐킢�͊m���ɐV���Ȓi�K�ɓ������Ǝv����B���E�́A���{�́A���̎��Ԃɂǂ��Ώ����ׂ����H �킩��Ȃ��B�����Ƃ��ɂ킩��͂����Ȃ�� The answer is blowin�f in the wind ���B�ł����ꂾ���͂�����B�u�e���ނȂ瓯���Ɏ���̋�������F�����ׂ����v�ƁB
�@J.P.�T���g���i1905�|1980�j�͎��̏����O�ɂ����������B�u�w���E�́A�X���s���ŁA��]���Ȃ��x ���ꂪ���ɐ����V�l�̐Â��Ȑ�]���B�������́A�܂���������ɒ�R����]�̒��Ŏ���ł䂭�B�����A���̊�]�͍��o���˂Ȃ�Ȃ��v�B�ނ��������Ă�����A�Ȃ�ƌ������낤���H
2015.11.25 (��) ���E�싅�v���~�A12 ���ؐ�̔s��
�@8����I�����3�|0�B���E�싅�v���~�A12�������B���W���p���͂��ƈ���2�_�ȓ��ɗ}����Ώ����Ƃ����ŁA9��؍��Ő��̖ҍU������3�|4�Ŕs��B�D���͖��Ə������B11��19���A�����h�[���ł̏o�����������B �@�攭�̑�J�ĕ��́A7��܂�1�q�b�g11�D�O�U�̉����Ŋ؍��Ő��ɂ����錄��^���Ȃ������B�����āA8��A���v�ۗT�I�ē͑��{�V��ɃX�C�b�`�B���{��8���3�l�ŕЕt���A�c����1�C�j���O�A8�Ԃ���̍U�����c���݂̂ƂȂ����B���{�̏����͖ڑO�������B
�@�攭�̑�J�ĕ��́A7��܂�1�q�b�g11�D�O�U�̉����Ŋ؍��Ő��ɂ����錄��^���Ȃ������B�����āA8��A���v�ۗT�I�ē͑��{�V��ɃX�C�b�`�B���{��8���3�l�ŕЕt���A�c����1�C�j���O�A8�Ԃ���̍U�����c���݂̂ƂȂ����B���{�̏����͖ڑO�������B�@9��؍��̍U���B���{�͐擪���̑�łɃq�b�g�������B���̑�łɂ��q�b�g�B�ŏ���1�Ԃɖ߂�A3�ې���j���ۑŁB1�_��Ԃ��ꖳ��2�A3�ہB��ԑŎ҂ɂ͓��p������ɂ����ꎀ���B��������2�_���B�}篏���T�����}�E���h�ɁB3�ԑŎ҂ɉ����o���̎l���B1�_���B�s�b�`���[����_�r�Ɍ��B�l�ԗ���_2�_�^�C�����[��ۑŁB�؍�4�|3�Ƌt�]�B�����x�����B����Ȉ����̂悤�ȓW�J���������Ă��������낤���H
�@���E���A�؍��Ƃ̏����� �Ƃ���Ύv���N�������͖̂k���I�����s�b�N�ł���B2008�N8��22���A���{��\�i���̎��͖������W���p���̖��̂͂Ȃ��j�͓����؍�����̏�������6�|2�Ŕj�ꂽ�̂������B���R�̂��Ƃ��ᔻ�������N����B�H���u�厖�ȏ�ʂł́g��h�̍єz�v�u���ǂ��O���[�v�̎�]�w�v�u�L�͑I��̑��������E�v�ȂǂȂǁB�ē�����́u�����̎コ���o���v�ƌ����Ȃ�����ٖ����J��Ԃ����B
�@�����A���̔s��B�N���ǂ������낤���A���ʂ�6�|2�̊��s�B9����c����4�_�r�n�C���h�Ƃ����W�J�́A���{�̖싅�t�@���̂قƂ�ǂ���������߂Ă����͂��ł���B
�@���������������Ƃ́A����̃P�[�X�͖k���ܗւƂ͑S���Ⴄ�Ƃ������Ƃ��B���̑��́A9��1����c����3�|0�Ń��[�h�A���̏ŕ��������ƂȂ̂ł���B���������肦�Ȃ��ŕ����Ă��܂������ƂȂ̂ł���B���{���̖싅�t�@���́u����ŏT���y����������������郏�C�v�ƐS��点���B����Ȗ싅�t�@���̊y���݂���u�̂����ɒD�������Ă��܂������ƂȂ̂ł���B
�@�s�������Ƃ��悭�g���錾�t�Ɂu����͌��ʘ_���v�Ƃ����̂�����B���ʘ_�Ȃ�N�ł�������ƁB���̒ʂ肾�B�ł������́A���ʘ_�������o���Ăł��ᔻ����Ă�����ׂ������Ȃ̂��B�u�l�Ԃ��z���ł��邱�Ƃ͐l�Ԃ��K�������ł���v�B�W���[���E���F���k�̌��t�ł���B��������Ȃ�A���̃Q�[���́A�u����ɂ������ׂ��������Ƒz���ł���̂Ȃ�A���̂Ƃ��������ׂ��������v�Q�[���Ȃ̂ł���B
�@�܂��A�u�����ɕs�v�c�̏������� �����ɕs�v�c�̕����Ȃ��v�Ƃ���⼌�������B���������ɂ͕K�����R������ł���B���������R��o���Ă������Ƃ����������̏����Ɍq����̂ł���B
�@�s��̂��ƁA�}�X���f�B�A�ł͔s���������������B�u�Ȃ���J��7��܂łō~�������H�v�u�L���b�`���[���̃��[�h�E�~�X�v�u7, 8��̃`�����X�ɒlj��_�����Ȃ������v�ȂnjʓI�s���B����ŁA�����������ǓI�s��_�Ƃ��āA�u�����̕��������Ȃ������v�u���p����I�o���Ȃ������`�[���Ґ��̃~�X�v�Ȃǂ��B�����āA����炷�ׂĂɊւ��ӔC�͊ēɋA�����ׂ����̂ł���B
�@�������h����싅�l�E�쑺���玁�́A���[�_�[�́u��@�Ǘ��\�́v�����ׂ��ƌ����B�����A�u��ɍň���z�肵�čőP�̑��łׂ��v�ƁB
�@���v�ۊḗA���O�A�u����̓N���[�U�[�����߂Ă��Ȃ��B���Ȃ��猈�߂��݂����v�ƃR�����g���Ă����B
�@���݁A���{�v���싅�E�̃N���[�U�[�ɂ͊O���l���肪�N�Ղ��Ă���B�Z���[�O�D���̃��N���g�̓o�[�l�b�g�B���{��p���[�O�̃\�t�g�o���N�̓T�t�@�e�ł���B���{�l�N���[�U�[�͑S���ނ�������B���Ă̑喂�_���X�؎�_�A���W�F���h�]�ĖL�͂��Ƃ�荂�Ðb��A�␣�m�I�N���X�����Ȃ��ǂ�̔w��ׁB���v�ۊē̑��O�̃R�����g�ɂ͎~�ނȂ��������B
�@���n�܂���11��8�����珀�X����16���܂ŁA6�����ɂ�����4�l�̃N���[�U�[�̓����͂ǂ����������H �V���̓��L�V�R��œ��_�^�C�����[���A����̓x�l�Y�G����ŋt�]�^�C�����[��ł���}���Ɏ��s�B�������ɍς̂͑Ő��̂��A�B����̓v�G���g���R���3�����z�[�}�[�𗁂т�B�B�ꖳ��ɓ������R��͐V�l�Ōo�����厖�ȏ�ʂŎg����قǂ̐M�����͂܂��Ȃ��B���ǐM���ł���N���[�U�[�͈�l������Ȃ������B
 �@����Ȓ��A��ی����Ă����̂��攭���璆�p���ɉ�������{�������B3����5�C�j���O��땕���Ă����B�u�؍���͔ނ��N���[�U�[�Ɂv�A���v�ۊē͂������f�����̂��낤�B�����A������̃C���^�r���[�Łu��J�̂��Ƃ͑��{�ƌ��߂Ă����v�ƌ���Ă���B
�����܂ł͎~�ނȂ��B�^����ꂽ��͂łȂ�Ƃ���肭�肷��̂��ē̏d�v�ȐӖ�������B�����؍���͂����\�z���Ă����B
�@����Ȓ��A��ی����Ă����̂��攭���璆�p���ɉ�������{�������B3����5�C�j���O��땕���Ă����B�u�؍���͔ނ��N���[�U�[�Ɂv�A���v�ۊē͂������f�����̂��낤�B�����A������̃C���^�r���[�Łu��J�̂��Ƃ͑��{�ƌ��߂Ă����v�ƌ���Ă���B
�����܂ł͎~�ނȂ��B�^����ꂽ��͂łȂ�Ƃ���肭�肷��̂��ē̏d�v�ȐӖ�������B�����؍���͂����\�z���Ă����B�@�����A���{�ɂ͕s���ޗ����O�������B��́A�{���͒��p���Ƃ��Ă̐��ʂł����ăN���[�U�[�Ƃ��Ăł͂Ȃ��������ƁB��ڂ̓N���[�U�[�Ƃ��Ă̌o�����F���ɋ߂��������ƁB�O�ڂ́A11��16���A���X�����v�G���g���R��Ŗ��ʂȓo��������ꂽ���ƁB�����A8��A7�|0�ƃ��[�h�g�N�������Ă����Ă�h�œo������ꂽ���Ƃł���B���ێ����ł͂ƂĂ��Ȃ��v���b�V���[��������B1��̓o�͕��i�̎����̐��{�̃G�l���M�[�������B�Ӗ��̂Ȃ��o�͔����Ă��ׂ��������B���̈Ӗ��Ȃ����ĊQ����݂̂̋N�p���j�]���Ăԉ����ƂȂ�B
�@�{�ԁA�\��ʂ葥�{��8��o�B3�l�ŕЕt����B9��A�擪�Ŏ҂�5���ڂ��q�b�g�A���Ŏ҂�3�Ԏ�ɂ�2���ڂ�ɑł���A4�Ԏ�ɂ͎����B�ꎀ����ꂸ���ۂŏ���Ƀ}�E���h������ň��̌��ʂƂȂ����B���̂��Ƃ����K�v�͂Ȃ��B�����ŏ����͌��܂����̂�����B�N���[�U�[���i������������ꂽ���肽�����A�����̋N�p�ɂ��A�����ӂ��ƕ��ꋎ���Ă������̂ł���B
�@���{��8���Ɏ��߂��̂�9��˔@���ꂽ���R�͉����H �^���͖{�l�݂̂��m�鎖���낤���A���͓����Ǝv���B��͖ڂɌ����Ȃ���J�̒~�ρB�����攭����̑��{���{���������@�����{�I�ɈႤ����Ȃ��~���Ƃ����C������蔲���Ă������Ƃ��炭����̓I���_�I��J�ł���B������A�v�G���g���R��̋N�p�̓A�z�Ȃ̂��B������́A�N���[�U�[�Ƃ��Ă̌o���s���ƃv���b�V���[�B���{���\����N���[�U�[�喂�_�E���X�͌����u9��1�C�j���O��}������v���b�V���[�͕����ł͂Ȃ��v�ƁB
�@3�_���[�h�A��ɕ������Ȃ����ؐ��9��P�C�j���O�B���X�̉]���g������Ȃ��h�̐��{�t���̃v���b�V���[�����̓��̑��{�ɏP�����������̂ł���B�������ڂɌ����Ȃ���J�����̓I�ɂ����_�I�ɂ��~�ς���Ă����B�ł��ꂽ�J�E���g���画��Ƃ���A���炩�ɏ������}���ł����B�������}���͔̂�J�ɂ�鍪�C�̌���������ł���B
 �@���āA���v�ۊēł���B�u��J�̂��Ƃ͑��{�Łv�͎~�ނȂ���p�������B�{�E�̃N���[�U�[�������A����܂łɁA���炩�ȕs����I�悵���ȏ�A���{��I�������̂�������B�ő�̖��̓Q�[���̐��ڂ̒��ŏ_��ȑΉ������Ȃ��������ƁB�����A��J��\��ǂ���~�����Ă��܂������Ƃł���B
�@���āA���v�ۊēł���B�u��J�̂��Ƃ͑��{�Łv�͎~�ނȂ���p�������B�{�E�̃N���[�U�[�������A����܂łɁA���炩�ȕs����I�悵���ȏ�A���{��I�������̂�������B�ő�̖��̓Q�[���̐��ڂ̒��ŏ_��ȑΉ������Ȃ��������ƁB�����A��J��\��ǂ���~�����Ă��܂������Ƃł���B�@��J��7��܂Ŋ؍��Ő��ɕt�����錄��S���^���Ȃ��B���V�[�Y������̉������������B������������85�B�]�͂͏\���A�����̓o���Ȃ��B���V�[�Y���Ō�A�S�͂��o�����ĂԂ��|��Ă�OK�Ƃ����������B
�@��������Ȃɂ����A���̓��̑�J�Ȃ�2���2�_�ȓ��ɗ}����̂͗e�Ղ̋ƁB�����炭�����������낤�B�����ɂ����ď����߂̍őP��́A�~���ɕs��������鑥�{�ւ̃X�C�b�`�ł͂Ȃ��A��J���Ō�܂ł������邱�Ƃ������B����̌����邱�Ƃ�����B���ꂪ�����̓S���ł�����̂�����B
�@�؍��`�[���͑�J���Ɂu����Ă��ꂽ���B�����₱���͂����邩���v�Ə����ւ̊��҂��萶�����ɈႢ�Ȃ��B���v�ۊē���������A���s�b�`���[����サ���Ƃ��������o�𖡂�������Ƃ�����ł��傤�B���[�V�A��������łĂ�ƁB�ނ͈�ԑ厖�ȏ�ʂł��̂��Ƃ�Y��Ă����B�Ŏ҂Ƃ��Ă̌o�����������Ȃ������B
�@���ؐ�ő�̔s���͊ē���J�𑱓������Ȃ��������Ƃɐs����B�Q�[���͐������ł���B�\���s�\�Ȏ��Ԃ͕K���N����B�����Ă⍡��͂悢���ɓ]�������Ԃ������B�Ջ@���ς̑Ή��������w�����̐Ӗ��ł���Ȃ�A���v�ۊēɂ͂��̗E�C�ƌ��f�͂������Ă����B�쑺�C�Y���ɏ]���A��@�Ǘ��\�͂Ɍ����Ă����B�u�ň���z�肵�őP�̑���u����v�\�͂Ɍ����Ă����B�u�ň���z��v�Ƃ͉₩�N���[�U�[���{�̗���B�u�őP�̑�v�͑�J�̑����ł���B
�@������̊ēk�b�͂����ł���B�u��J�̂��Ƃ͑��{�ƌ��߂Ă����B9��̌p�������s�������B���_�ŏI���Ȃ������͎̂��̐ӔC���v�B�ȂႢ���̃R�����g�́I �N���[�U�[���i�҂����ɂ��p����s���ɂ���Z���X�̂Ȃ��B�����ɂ����ӔC�����o���Ȃ��\�V�C���I �s���͂���ȑO�ɂ����Ȃ��ł����I�H ������������̃g���`���J���ł���B
�@�R�����g����@����ɁA���v�ۊḗA���{�ւ̃X�C�b�`�͊ԈႢ�ł͂Ȃ������ƍl���Ă���悤���B�\��ʂ���т����܂ł��ƁB�ǂ����J������ɂ�������B���_���d�����Ă���B
�@����Ɏ@����ɁA�ނ͑��{�ɐ��ޕs�������m�ł��Ă��Ȃ������̂ł́H ��J�̂��ƍ����̑��{�Ȃ�2�C�j���O��ɗ}���Ă���邾�낤�A�Ɗy�ώ����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B��J�����{������A����̃����[�͔\�͂̉E��������B����Ő��ɂƂ��Ă͂�������Ⴂ�܂��̗���B����ɂ��C�Â��Ă��Ȃ������H ���@�͂̌��@�ƍ����Ȃ��y�Ϙ_�B�w�����Ƃ��čł��������ׂ����Ƃł���B
�@�w�����Ƃ��Ă̋^�╄�͂܂�����B����͔ނ��헪�Ɛ�p�̈Ⴂ�𗝉����Ă��Ȃ����Ƃł���B�헪�Ƃ͑�ɓI����ŕ����𑨂������ł����������߂ɍ̂���@�̂��ƁB��p�͂�����������邽�߂̋�̓I�ʓI�퓬�̂����B�؍���ł̐헪�́u����Ő����������i���u���ė}�����݁A���Ȃ��`�����X�𒅎��ɂ��̂ɂ��ăQ�[���̎哱�������邱�Ɓv�ł���A��p�́u�O�����ȓ�����������J��攭�B�~���ɂ͖{������NO1�̑��{���N�p���邱�Ɠ��v�ł������͂��B�����A��p�͐헪�𐄐i����p�[�c�ł��邩�猳�X�Ջ@���ςɕς��Ă�����ׂ����̂Ȃ̂��B�����߂ɂ́u���{�̃����[�t�v�Ƃ�����p�ɔ�����K�v�͂��炳��Ȃ��̂ł���B
 �@���v�ۊḗA����ʂ��āA�I�o����4�l�̋~������قƂ�ǂɃN���[�U�[���i����������������A������������ׂ��͓��̖{�l�������̂ł͂���܂����B
�@���v�ۊḗA����ʂ��āA�I�o����4�l�̋~������قƂ�ǂɃN���[�U�[���i����������������A������������ׂ��͓��̖{�l�������̂ł͂���܂����B�@���͒f������B���v�ۗT�I�����ēł�����莘�W���p���͂܂Ƃ��Ȑ킢�͂ł��Ȃ��B�I��͑f���炵���B���̃����o�[�Ȃ琢�E�𐧂��ē��R�̐�͂Ƃ�����B
�@���͒���B�ē�ς���ׂ��ƁB���ꂪ�ł��Ȃ��̂Ȃ�A�ނ��A3�����ԁA�쑺���玁�̌��ɒʂ킹�邱�Ƃ��B�ʂ��Ċēw���w���邱�Ƃ��B�쑺�C�Y����@������ł��炤���Ƃ��B�쑺���͓��{�̖싅�̃��x������Ƌ��E�̔��W��S����肤�^���Ȗ싅�l���B���v�ۊē����@���Ή����}������Ă����͂��ł���B
�@�@�@�@�Q�l�����F�u�l���ōł����101�̂��Ɓv�쑺���璘 �C����
2015.11.10 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 ���
�i1�j�u���z�����ȁv�͓���P�[�X �@���i�[�h�E�o�[���X�^�C�����j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�i�ȉ�NYP�j�ɂ��u���z�����ȁv�i�ȉ��u���z�v�j�̘^���͓����B
�@���i�[�h�E�o�[���X�^�C�����j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�i�ȉ�NYP�j�ɂ��u���z�����ȁv�i�ȉ��u���z�v�j�̘^���͓����B�@�@��1�� 1963�N5��27���^�� �}���n�b�^���E�Z���^�[
�@�@��2�� 1968�N3��5���^�� �t�B���n�[���j�b�N�E�z�[��
�@���i�z��Y���ɂ��ƁA�o�[���X�^�C����NYP�́A�g������ɍĘ^���͂��Ȃ������h�炵���B�]���āu���z�v�͗�O���̗�O�ł���ƁB������L�ۂ݂ɂ��Ă�����A�u�O�ҁv��ǂ�ł��ꂽH��������A�u�Ę^�́A�w���z�x�̑��ɂ��A�`���C�R�t�X�L�[�́w�����ȑ�4�ԁx�ƃx�[�g�[���F���́w�����ȑ�7�ԁx������܂���v�Ƃ̎w�E���������B�����ɁA�o�[���X�^�C����web-site�uLeonard Bernstein�v���Љ�Ă��ꂽ�B�����ɂ́A�o�[���X�^�C���̃f�B�X�R�O���t�B�[�����t��̃f�[�^���ׂĂ��ڂ��Ă���B���ɂ��肪�����B�����`���Ă݂�ƁA�m���ɂ��w�E�ʂ肾�����B�܂��͂���2�̃P�[�X�������悤�B
���`���C�R�t�X�L�[�u�����ȑ�4�ԁv
�@�@��1�� 1958�N9��30���^�� �Z���g�E�W���[�W�E�z�e��
�@�@��2�� 1975�N4��28���^�� �}���n�b�^����Z���^�[
�@�o�[���X�^�C���̃j���[���[�N�E�t�B����C�w���҂Ƃ��Ă̍ݔC���Ԃ�1958�N����1969�N�܂ŁB���̊Ԃɂ�����^�����ׂ�ƁB
 �@1958�N����1960�N2���܂ł́A�Z���g�E�W���[�W�E�z�e�������S�B1960�N2������1969�N�́A�}���n�b�^���E�Z���^�[�ƃt�B���n�[���j�b�N�E�z�[���̕��p�B�Z���g�E�W���[�W�E�z�e���̖��O�̓v�b�c���Ə�����B�z�e�����̎���A�����ʁA�@�\�ʓ��������̐��������Ɉڂ����Ƃ������Ƃ��B���_�ANYP���A1962�N����A�{���n���J�[�l�M�[�E�z�[������t�B���n�[���j�b�N�E�z�[���i�����J�[����Z���^�[���G�C�u���[�E�t�B�b�V���[�E�z�[���j�Ɉڂ������Ƃ�������낤�B�}���n�b�^���E�Z���^�[�ƃt�B���n�[���j�b�N�E�z�[���͔�r�I�ϓ��Ɏg���Ă���A�N��I�ɂ��ȖړI�ɂ��ۗ�������͊������Ȃ��B
�@1958�N����1960�N2���܂ł́A�Z���g�E�W���[�W�E�z�e�������S�B1960�N2������1969�N�́A�}���n�b�^���E�Z���^�[�ƃt�B���n�[���j�b�N�E�z�[���̕��p�B�Z���g�E�W���[�W�E�z�e���̖��O�̓v�b�c���Ə�����B�z�e�����̎���A�����ʁA�@�\�ʓ��������̐��������Ɉڂ����Ƃ������Ƃ��B���_�ANYP���A1962�N����A�{���n���J�[�l�M�[�E�z�[������t�B���n�[���j�b�N�E�z�[���i�����J�[����Z���^�[���G�C�u���[�E�t�B�b�V���[�E�z�[���j�Ɉڂ������Ƃ�������낤�B�}���n�b�^���E�Z���^�[�ƃt�B���n�[���j�b�N�E�z�[���͔�r�I�ϓ��Ɏg���Ă���A�N��I�ɂ��ȖړI�ɂ��ۗ�������͊������Ȃ��B�@��̃`���C�R�t�X�L�[�́u�����ȑ�4�ԁv�B�^���Z�p�Ɋւ��ẮA��1��ڂ̓X�e���I������2��ڂ͐��n���B�^������2��ڂ̕��������ǍD�B�Ȃ�A�Ę^����������B �@���̃J�e�S���[�ɓ���̂��A�A�C���X�́u�����ȑ�2�ԁv�i1951�N��1988�N�j�A�R�[�v�����h�́u�����ȑ�3�ԁv�i1964�N��1985�N�j���B�O�҂̓��m�����ƃX�e���I�A��҂̓��R�[�h��Ђ̈Ⴂ�B��薾���ȗ��R������B
���x�[�g�[���F���u�����ȑ�7�ԁv
�@�@��1�� 1958�N10��6���^�� �Z���g�E�W���[�W�E�z�e��
�@�@��2�� 1964�N5��4����26���^�� �}���n�b�^���E�Z���^�[
�@�x�[�g�[���F���́u�����ȑ�7�ԁv�i�ȉ��u�x�g7�v�j������闝�R�H ����́A�^�����̈Ⴂ�ȏ�ɁA�����ȂƂ��Ă̗����ʒu�ɋN������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B�����ʒu�Ȃ�ĕςȌ��t���g�����̂́A���ɓK�ȕ\������������Ȃ���������ŁA�v����ɁA�u�x�g7�v�́A�x�[�g�[���F����������S9�Ȃ̌����Ȃ̒���1�Ȃł���A�Ƃ����P���Ȏ����̂��Ƃł���B�����A��2��^���̓x�[�g�[���F�������ȑS�W�̈�ł͂Ȃ��낤���H �����������ăf�B�X�R�O���t�B�[�����Ă݂��B
�@�o�[���X�^�C���́A1961�N9��25���ɑ�5�ԁu�^���v��^���A1964�N5��18���́u���v�܂ŁA2�N8�����̊ԂɃx�[�g�[���F���̌����ȑS9�Ȃ�^�����Ă����B���͂��ׂă}���n�b�^����Z���^�[�A�܂��ɑS�W��ژ_��ł̘^���������̂ł���B�S�W�Ȃ�u�x�g7�v������͓̂��R�B�Ę^���͂Ȃ��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�@����ŁA�������w�E�̍Ę^���̗��R�͉𖾂��ꂽ�B�c��́u���z�v�݂̂ł���B
�@�o�[���X�^�C����NYP�́A�Ȃ��g�u���z�v�����h���Ę^�������̂��낤���H ��1��1963�N�}���n�b�^���E�Z���^�[�B��2��1968�N�t�B���n�[���j�b�N�E�z�[���B�p�b�ƌ��C�Â��̂̓z�[���̈Ⴂ�B�t�����`���C�Y�ł̉����c�����������H �Ȃ�A�Ę^�͑��̊y�Ȃɂ��y��ł���͂��ŁA���R�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A���q�̒ʂ�A���R�[�f�B���O�ɂ����邱����̉��̎g�p�p�x�ɂ͕肪�Ȃ��A�ǂ��炩������g�p����ϋɓI���R�͌��o���Ȃ��B�Ȃ��u���z�v������������̓����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@���Ƃ́A�P���ɁA�g��1��ڂɂȂ�炩�̕s��������h�Ƃ������R�B�ł��A���̑�1��ڂ͂��Ȃ�̖����t�B�Ę^��y���ɗ��킵�Ă���B�^�������Ȃ��B�Ȃ�Ȃ������āH ��͐[�܂����ł���B
�i2�j1968�N3��5�� �t�B���n�[���j�b�N�E�z�[��
�@�o�[���X�^�C����NYP�ɂ���2��ڂ́u���z�v��1968�N3��5�� �t�B���n�[���j�b�N�E�z�[���Ř^�����ꂽ�B�O��g�����A����(SMK60968)�ɂ́A��1��ڂ́u���z�v�ƁgBerlioz Takes A Trip�h�i�x�����I�[�Y�̃T�C�P�f���b�N�ȗ��s�j�Ȃ�o�[���X�^�C���̃i���[�V�����ɂ��u���z�v�̉�������^����Ă���B���̃i���[�V�������^����1968�N3��5���Ȃ̂ł���B�����web-site�ׂ�Ɠ������Ɂu�^���̒a���v�Ƃ����i���[�V���������^���Ă��邱�Ƃ����������B������75DC395-7�Ȃ�K�i�ԍ���3���gCD�Ƃ��ē��{�ՂŔ�������Ă���i�������͕s���j���A�I���W�i����LP���낤�B�ł͂��̓��e���L���Ă������B�i�@�j�����t�͘^�����B
 �@�@1 �x�[�g�[���F���F�����ȑ�3�ԁu�p�Y�v�i1964.1.27�j>
�@�@1 �x�[�g�[���F���F�����ȑ�3�ԁu�p�Y�v�i1964.1.27�j> �@�@2 �p�Y�̒a���i1965.12.20�j
�@�@3 �x�[�g�[���F���F�����ȑ�5�ԁu�^���v�i1961.9.25�j
�@�@4 �^���̒a���i1968.3.5�j
�@�@5 �x�����I�[�Y�F���z�����ȁi1968.3.5�j
�@�@6 �x�����I�[�Y�̃T�C�P�f���b�N�ȗ��s�i1968.3.5�j
�@�m���t�{����i���[�V�����n��3�g���^�������ȉ���A���o���ł���B�o�[���X�^�C���͂��̍��A�u�����O�E�s�[�v���Y�E�R���T�[�g�vYoung People�fs Concert�i�ȉ�YPC�j�Ƃ������N�����̂��߂̃R���T�[�g���s���Ă����B�y���ȃg�[�N�ʼn��y�̖{���ɔ���y�����Ă��߂ɂȂ�R���T�[�g�BCBS�|TV�̃l�b�g���[�N��ʂ��đS�Ẳƒ�ɕ��f����A��̐l�C�ԑg�ƂȂ��Ă����B�́A1958�N����1970�N�܂ŁA53��𐔂��Ă���B���̊��Ԃ�NYP��C�w���ҍݔC���Ԃ��Ă���A���̎����������Ă��Ă��A�o�[���X�^�C���̗͂̓���悤�������낤�Ƃ����C���F���g�ł���B�ނ��A����قǂ܂łɁAYPC�ɍS�������R�͉����H ����͔ނ��N�������y�̌��p��M���Ă������炾�B�q������̉��y�̌����A�����ɐl���ɍʂ�^���邩�A�Ƃ������Ƃ�m���Ă������炾�B
�@�o�[���X�^�C���́A�Βk�W�̒��ŁA����Ȃ��Ƃ�����Ă���B
�����O�́A���C�̂Ȃ����N�������̂ɁA���y�̂������ŁA���͂���ȍ~�A�����邱�Ƃ����]����悤�ɂȂ�A�����ĉ��y�����ɂƂ��Đ����ɂ����������̂ɂȂ����̂ł��B�@�ނ͂܂��A�������������^���闧��ɂȂ������Ƃ̎g���Ɗ�т������Ă����̂��낤�B����ȃo�[���X�^�C���̗��O�����Z������Ă������Ƃ͂Ȃ��I�I �����ŗ����グ��ꂽ�A���o����悪���ꂾ�����B�ȉ��͎��̑z���ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iL.�o�[���X�^�C���^E.�J�X�e�B���I�[�l�u���y����v�y�Њ����j
�@����1968�N2������BCBS���R�[�h�̃v���f���[�T�[�A�W������}�N���[�A�̓o�[���X�^�C���ɂ�����Ă����B�u���j�[�A���k������B�N��YPC���n�߂Ă���10�N�ɂȂ�B���ς�炸�����l�C���B�����A�S�Ăɂ͓͂����A���E�ɂ͓͂��Ȃ��B������A���R�[�h��YPC����肽����v�B�o�[�X�^�C���u�ʔ����ˁB�ŁA�ǂ�ȋȂ������H�v�BM�u�N�ł��m���Ă�L���ǂ��낪�������낤�B1�����ᕨ����Ȃ�����3�����炢�͍�肽���ˁv�BB�u�w�^���x�Ƃ��w�p�Y�x������H���t�̓A�����m�ł����낤�v�BM�u�E���A�ł��Ȃ��A������C���p�N�g���~�����B�Z�[���X��|�C���g���ˁB�Ƃ���Ŏ��̒���͂Ȃ��������H�v�BB�u�w���z�x�����ǁv�BM�u�h���s�V�����B�����I����Ƀ��R�[�f�B���O�ł��Ȃ����ȁv�B �@������A�����A���炭�E�E�E�E�E�B����Ƃ������͂���H �m�M�͎��Ă܂��A��l�̊Ԃɂ���ȉ�b�����킳�ꂽ�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���܂��B
�@�������āA�o�[���X�^�C����NYP�́A1968�N2��29���A3��1,2,4���́u���z�v�����C���Ƃ�����������̒���A3��5�� �t�B���n�[���j�b�N�E�z�[���ŁA���A���o���̂��߂ɁA�u���z�v�S�ȁA�i���[�V����2�{�̎��^���s�����B4���Ԃ̗͉��̂��Ƃ̃��R�[�f�B���O�͑N�x�A�W���͂ɖ�肠��H���₢��A����̓o�[���X�^�C����NYP�̏퓅�B1960�N�̃}�[���[��4�ԁA1961�N�̃}�[���[��3�ԁA1965�N�̃}�[���[��7�ԂȂǂ����̃X�^�C���B�S�z�ɂ͋y�Ȃ��B
�@��ɍĘ^�������Ȃ��o�[���X�^�C�����A�u���z�v�����͗�O���������R�H �����2��ڂ̘^���̖ړI���A���E�̏��N�����ɉ��y�̑f���炵����͂������o�[���X�^�C���̗��O�ɍ��v�������̂��������ƁB�����āA�u���z�v�������o�[���X�^�C���ő�̂��C�ɓ���Ȃ����������ł͂Ȃ����낤���B
�@�u���z�v���o�[���X�^�C���̂��C�ɓ���Ȃ������؋�������BYPC�ł�1���f�ň�l�̍�ȉƂ�������グ��̂͒������Ȃ��B53��̒��ŁA�x�[�g�[���F���A�X�g�����B���X�L�[�A�V�x���E�X�A�R�[�v�����h�Ȃ�10�l�ɋy�ԁB�����A�ہX��Ȃ����Ƃ����̂́u���z�v�ƃx�[�g�[���F���̉̌��u�t�B�f���I�v�����Ȃ��B�o�[���X�^�C�����ł��h������I�y�����u�t�B�f���I�v�Ƃ����͎̂��m�̎����B1989�N�x���������R�̎]�́u���v���t��ł̃R�����g�͗L�����B�Ȃ�u���z�v�͍ő�̂��C�ɓ���I�P�ȂƂ����邾�낤�B
�@�m���ɓ�́u���z�v���r�ׂ�ƁA�i�i��1��ڂ̂ق����D��Ă���B��2��ڂ́A������2�̃i���[�V�������^���d�ׂɂȂ����H
�@�u�^���̒a���v���u�x�����I�[�Y�̃T�C�P�f���b�N�ȗ��s�v��������15���قǂ̎ڂł���B���̒��ŁA�o�[���X�^�C���̓s�A�m��e���A�����Ɏ���܂ł̃��@�[�W���������ʂ���Č�����ȂǁA���ɍ��ؒ��J�Ɏ���i�߂�B��������15���̃i���[�V���������A���^�ɂ͂��̉��{���̎��Ԃ��₵���ɈႢ�Ȃ��Ǝv����B
�@1968�N3��5�� �t�B���n�[���j�b�N�E�z�[���B�o�[���X�^�C���͂��̓������ŁA��̃i���[�V�����Ɓu���z�v�S�Ȃ����^�����B���ɉߍ��Ȏ��Ԋ��ł���B�����A�o�[���X�^�C���͂�������m�ŗՂ̂ł���B���E�̏��N�����ɉ��y�̑f���炵����͂������B���̈�S�ŁB������A���̂��Ƃʼn��t�̊����x�Ȃ�����������Ȃ��B�ł�����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������B�����͔ނ̐M�O�����������Ƃ�ׂ��Ȃ̂��B�o�[���X�^�C���̗�O�͔ނ̉��y�ւ̎v���̏������̂ł���B
2015.10.25 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 �O��
�@�u�o�ΑO�̎ԂŒ����g���C���o��N���V�b�N�h����Ă�v�ƎR�`�P�g���C���̑��q�������Ă����B�X�|�[�c��ӓ|���ǂ��������̐������Ɛq�˂Ă݂�ƁA�Ȃɂ��u����C�s�̃}�[�P�^�[���o�БO�ɃN���V�b�N���y���ċC��������v��ʂ�TV�ŊςāA���₩�낤�Ǝv�����̂��������B���݂ɂ��̋Ȃ̓`���C�R�t�X�L�[�́u���@�C�I�������t�ȁv�őI�Ȃ��`���t������B�u�C���Ƃ����I�v�ĂȂ킯�ő����I�Ȃɓ���B�^�C�g���́u���̃N���V�b�N�v�Ƃ����B�@�w�肳�ꂽ�u�`���C�R���v�����ɁA�u�^���z�C�U�[���ȁv�u�t�B�������f�B�A�v�u�Е����X�v�ȂǂȂǁB����Ȓ��ɁA�x�����I�[�Y�u���z�����ȁv����u�f����ւ̍s�i�v����ꂽ�B���̋ȁA�Ō�̓M���`�����o�b�T��������̂����A�����ւ��ǂ蒅���܂ł̍s�i�����Ɍ��C�Ŕ��͂ɖ����Ă���̂ł���B���X�g�������悤�ɂ���Ă͓��X�̃S�[���Ɗ������Ȃ����Ȃ��B
 �@�ǂ����Ȃ�g��Ԍ��C�̏o��h���t���ƍl���A�莝��CD20�����̒�����I�̂����i�[�h��o�[���X�^�C���i1918�|1990�j�w���FNYP�i�j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�j�̂��̂������B���i�́A���g�����n���p�Ȃ��S�ɃO�C�O�C�����Ă���B���̂͂�������̐����͖͂��Ղ̗_�����~�����V�����J�������������y�Ȃ��B�����j�[�I ���ꂵ���Ȃ��B���q���܂����f������������y�Ƃ͎v��Ȃ����낤�B�C�����C�ɂ́gROYAL EDITION�h�d�l1968�N3��5���A�j���[���[�N�̃����J�[���E�Z���^�[�ł̘^���Ƃ����p���̃N���W�b�g�B�ȉ��uR�Ձv�Ƃ���B
�@�ǂ����Ȃ�g��Ԍ��C�̏o��h���t���ƍl���A�莝��CD20�����̒�����I�̂����i�[�h��o�[���X�^�C���i1918�|1990�j�w���FNYP�i�j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�j�̂��̂������B���i�́A���g�����n���p�Ȃ��S�ɃO�C�O�C�����Ă���B���̂͂�������̐����͖͂��Ղ̗_�����~�����V�����J�������������y�Ȃ��B�����j�[�I ���ꂵ���Ȃ��B���q���܂����f������������y�Ƃ͎v��Ȃ����낤�B�C�����C�ɂ́gROYAL EDITION�h�d�l1968�N3��5���A�j���[���[�N�̃����J�[���E�Z���^�[�ł̘^���Ƃ����p���̃N���W�b�g�B�ȉ��uR�Ձv�Ƃ���B�@�����Ă����u�e���A�ō�����v�Ƒ��q����A���������B���f�^�V���f�^�V�B���ʘb�͂���ŏI���̂����A�{��͂��ꂩ��B�������t�������肢�����B
 �@���͂���A������wH�������炨�肵�ăR�s�[����CD-R�������B������CD�R���N�V�����͂Q�����I�I���Ւ��ՋM�d�Պe�킨��葵���B�������~������̂͂قڂ���B����Ȃ��Ƃ��R���e���c�̌���Ɠ���̌��ʂ���I�m�ɋ����Ă����A�܂��ɏN�W�Ƃ̐��������ł���B
�@���͂���A������wH�������炨�肵�ăR�s�[����CD-R�������B������CD�R���N�V�����͂Q�����I�I���Ւ��ՋM�d�Պe�킨��葵���B�������~������̂͂قڂ���B����Ȃ��Ƃ��R���e���c�̌���Ɠ���̌��ʂ���I�m�ɋ����Ă����A�܂��ɏN�W�Ƃ̐��������ł���B�@�o�[���X�^�C���́u���z�v�́A�R�s�[�����܂܂낭�ɕ������ɐ��N�ԁA���q�̃��N�G�X�g�ł���Ɠ��̖ڂ������Ƃ����킯���B�����Ȃ�ƃR���N�^�[�̒[����B�{�ՂŎ����Ă������Ȃ���̂��B�l���ɑ���B
�@�����AAmazon�ׂ�B�Ȃ��B����̂̓t�����X�����ǁi1976�N�^���j�̂݁B����͏��L���Ă���BR�Ղ̓`���[���Y���q�̎ʐ^��\4�Ɏg�����C�M���X������p�B�̋L�O�Ղ����ɔp�Ղ͂��������Ȃ����B�����A����قǂ̉��t�B��������Ă��Ă����������Ȃ��͂��B
 �@�����Ȃ��͒��Õi�����낤�B�Ƃ����킯�ŁA�a�J�̃��R�t�@����`���Ă݂��B���ړ��Ă�R�Ղ͂Ȃ��������A�u�N���V�b�N���ȏW��4���v�Ƃ����o�[���X�^�C���̃j���[���[�N�E�t�B���Ձu���z�����ȁv���������i�ȉ��u���ȏW�Ձv�Ƃ���j�B�N���W�b�g��1968�N3��5���j���[���[�N�^��������T�����ŊԈႢ�Ȃ��B���������i��350�~ ���b�L�[�I���������߂Ē����Ă݂��B���̌��ʂ́E�E�E�E�E�B
�@�����Ȃ��͒��Õi�����낤�B�Ƃ����킯�ŁA�a�J�̃��R�t�@����`���Ă݂��B���ړ��Ă�R�Ղ͂Ȃ��������A�u�N���V�b�N���ȏW��4���v�Ƃ����o�[���X�^�C���̃j���[���[�N�E�t�B���Ձu���z�����ȁv���������i�ȉ��u���ȏW�Ձv�Ƃ���j�B�N���W�b�g��1968�N3��5���j���[���[�N�^��������T�����ŊԈႢ�Ȃ��B���������i��350�~ ���b�L�[�I���������߂Ē����Ă݂��B���̌��ʂ́E�E�E�E�E�B�@�Ȃ����X�J�X�J���Ă���B�������܂������Ȃ��B�ς��Ȃ��Ǝv���AR�Ղƒ�����ׂ�B���t���S�R�Ⴄ�ł͂Ȃ����H����͈�̂ǂ��������Ƃ��I �����j���[���[�N�E�t�B�������^�����ňႤ���t�I�I���āA�ǂ����悤�B�t�g�v�����̖̂{����������o���B�u�����t�ƃ��R�[�h�E�R���N�V����2001�v�i���R�[�h�|�p�ʍ�1979�N���j�ł���B������͎w���҂̕��i�z��Y�i1926�|1990�j�B�o�[���X�^�C���̐M��҂��B���̖{�̊����ɂ́A�u�]�������}�������t�E�v�Ƒ肷�镟�i���Ɖ��y�]�_�ƁE���c���ꎁ�̑Βk���ڂ��Ă��āA���ꂪ�ʔ����B�����ʔ������āA�܂�ő�l�Ǝq���̃f�B�X�J�b�V�����B��͂�w���҂͊i���Ⴄ�I �]�k�͂��Ă����B
�@�ł́A���̃o�[���X�^�C���̍��̈ꕔ�����������Ă��������B
���ꂪ���̋Ȃ̃x�X�g�E���R�[�h���Ǝv�����R�[�h���A�o�[���X�^�C���̂��̂ɂ͐��������邪�A�����ł́A�o�[���X�^�C���̌|�p��m���Ŕ��ɋ����[����̂ЂƂƂ��ăx�����I�[�Y�́u���z�����ȁv�������Ă������B�ނƂ��Ă͋ɂ߂Ĉٗ�̂��Ƃ����A�o�[���X�^�C���͂��̋Ȃ�3�x�A�^�����Ă���B��1��ڂ�1963�N�̘^���Ńj���[���[�N�E�t�B���A2��ڂ�1968�N�Ńj���[���[�N�E�t�B���A������3��ڂ��t�����X�����ǂƂ̂��̂�1976�N�̘^���ł���B�������������ςȖڈ��Ƃ��ăe���|���r����Ɓ\�\�e���|���������y�����E������̂łȂ����Ƃ͉]���܂ł��Ȃ����\�\1��ڂ��x�߂�2��ڂ��S�̂�4���߂������A3��ڂ����Lj�Ԓx���e���|�łƂ��Ă���B������ɍĘ^�������Ȃ������o�[���X�^�C������r�I�Z�����̊Ԃɂ��Ȃ��������ƁA����ɂ���ł����������g�{��h�̃I�[�P�X�g���ƍāX�^���������Ƃ́A60�̂��̎w���҂̂��C���X�̏ؖ��ł��낤���B
 �@��͂�A�o�[���X�^�C�����j���[���[�N�E�t�B���́u���z�v�͓��ނ������̂��B�^���N��1963�N��1968�N�B��������2����CD�̃N���W�b�g���o��1968�N�^���Ƃ������Ƃ́A�ǂ��炩�������ԈႦ�Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@��͂�A�o�[���X�^�C�����j���[���[�N�E�t�B���́u���z�v�͓��ނ������̂��B�^���N��1963�N��1968�N�B��������2����CD�̃N���W�b�g���o��1968�N�^���Ƃ������Ƃ́A�ǂ��炩�������ԈႦ�Ă��邱�ƂɂȂ�B�@�q�Ղ�51��18�b�B���ȏW�Ղ�47��45�b�B���ȏW�Ղ��S���߂������B���i���̋L�q�g�P��ڂ��x�߂�2��ڂ��S�̂łS���߂������h�Ă͂߂�ƁAR�Ղ�1��ځB���ȏW�Ղ�2��ځB����R�Ղ�1963�N�A���ȏW�Ղ�1968�N�^���Ɛ���ł���B������m�肷�邽�߂ɁA1963�N�^���ƃN���W�b�g���������A����CD����肵���B�^�����͂�������� May 27, 1963, at Manhattan Center, New York City �Ƃ���B���t���Ԃ��s�^����v�B������ׂ��R�ՂƑS�������B����āAR�Ղ�1963�N�̑�1��^���Ɗm��ł����B�K�R�I�ɖ��ȏW�Ղ�1968�N�̑�2��^���Ƃ������ƂɂȂ�BR�Ղ̘^�����N���W�b�g�̓A�����J�̕Ґ��S���҂́g�E�b�J���E�~�X�h�������̂��낤�B����͂����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ����A���肤�邱�ƁB�܂��͈ꌏ�����B
�@�c��^��́A�o�[���X�^�C���͈ٗ�Ƃ�����Ę^�����Ȃ��s�������Ƃ������Ƃł���B3��ڂ̃t�����X�����ǁi1976�N�^���j�́A���i���̌������g�{��̃I�P�h�̉����~���������Ƃ������Ƃ�����A�����͂���ɏ]���A�Ώۂ���O�����Ă��������B
�@�ł́A�����j���[���[�N�E�t�B���Ƃ�1963�N��1968�N2�̘^���ɍi�낤�B���i���L�q�ɂ́u������ɍĘ^�������Ȃ������o�[���X�^�C������r�I�Z�����̊Ԃɂ��Ȃ������v�Ƃ���B�g������ɍĘ^�����Ȃ������h�o�[���X�^�C���Ȃ̂�����A�͂�5�N�ł����������I�P�ł̍Ę^�͈ٗᒆ�̈ٗ�Ƃ������Ƃ��B���i���͂��̗��R�ɂ��ďڍׂȌ��y�͂��Ă��Ȃ��B�o�[���X�^�C���̌��Ђɂ��Ă̓`�g������Ȃ��B���A�s�Ԃ���A�g1��ڂ̘^���ɖ����ł��Ȃ���������h�Ɠǂݎ��Ȃ����Ȃ��B
�@�Ȃ�A2��ڂ̉��t���͂��ł��悭�Ȃ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪���ꂪ�^�t�Ȃ̂��B�O�q�����悤�ɂP��ڂ͔��͋P�����ׂĂɂ킽���čō��B2��ڂ͏������e�C���Ȃ��J�T�J�T�̉��t�Ȃ̂��B�ȒP�Ȕ�r�Ƃ��āA�I�y�͂̏��̉��̈Ⴂ���Ăق����B�P��ڂ͖̂��邭�[���悭�ʂ�f���炵�����B2��ڂ͈̂Â��Čy�������ۂ��B�N�������Ă��꒮�đR�B�_����t����P���100�_�A2���40�_�B����A���S�Ȃ���������I�I����Ȃ��Ɠ��̃o�[���X�^�C��������ʂ͂����Ȃ��B���i���s�Ԃ́u�����ł��Ȃ��čĘ^���v�́A�S���̌����O��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�Ȃ����͂Ȃ�Ȃ̂��H ���ނ́u���z�v�ɂ͂ǂ�ȈӖ�������̂��H���̉𖾂����g�N�����m�I�h�ł͂���܂��B�����͎���ŁB
2015.10.15 (��) ���c���N�Ɏa�荞�� �ŏI��`�u�����B���Łv�̌��_�Ɖ����ł̒�
�i1�j�����B���ł̌��_ �@���o�[�g������B���ł́A�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̌��ׁ��u�z�U���i�v�̒����Ⴂ ����������I�ȁu���c���N�v�����łł���B
�@���o�[�g������B���ł́A�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̌��ׁ��u�z�U���i�v�̒����Ⴂ ����������I�ȁu���c���N�v�����łł���B�@����y�ł́A�ƂȂ�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɂ�����u�z�U���i�v�������łȂ���Ȃ�Ȃ� �Ƃ������ߎ������݂���B�W���X�}�C���[�͂���ɏ]��Ȃ������B�Ƃ������A�����m�炸�ɕ�M���Ă��܂����A�Ƃ����������������낤�i�ڍׂ́u�N�����m�v6.25�j�B
�@11�u�T���N�g�D�X�v�͓��i��2�j�A����ɑ����u�z�U���i�v�����B�����܂ł͂����B���͂��̎����B12�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v��σ������i��2�j�A�u�z�U���i�v���\�m�}�}�σ������Ōq���Ă��܂����B���ɓ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁB
�@����͋���y�̓`���ɔ�����B�u���c���N�v�ȊO�̋���y�ł��̌��ߎ�������ĂȂ���i�͌Í������B�̈�����݂��Ȃ��B�u���c���N�v�ő�̃~�X�Ƃ�����̂͂��̂��߂ł���B�Ƃ��낪�a������200�N���̊ԁA�Ȃ����������ꂸ�ɂ����B����Ƀg���C�����̂������B���łł���B
�@�u�T���N�g�D�X�v�͓��@�u�z�U���i�v�����@�����B���́A�@�A�̓W���X�}�C���[�łP�i�I�[�P�X�g���[�V�����͕ʁj�B�B�V���߂̌o�ߋ��}�����A�C�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɂ�����u�z�U���i�v���u�T���N�g�D�X�v�Ɠ����j�����ɖ߂����B����ŋ���y�̓`���ɓK�����̂ł���B
�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�͕σ�����
�B 7���߂̌o�ߋ�
�C�u�z�U���i�v����i�]���͕σ������j
�@�o�ߋ�́A�σ�����B���D�Ɍq���邽�߁AB��|Dm�|A��5�|Dm�Ȃǂ̓]����7���߁i����4���߁j�ɂ킽���ďd�˂Ă䂭�B���ɘ_���I�ȍ�Ƃł���B����͕σ������́�2�����́�2�Ɉڍs���邩�炵�āA���͑�ςȍ�ƂȂ̂��B������{3���߂��̌o�ߋ傪�K�v�ƂȂ����̂ł���B�����A���͂�����莋����B
�@�����B���łɂ�����o�ߋ�ƃz�U���i�̒������i�}�b�P���X�ՂŁj������ƁA7���߂̌o�ߋ��35�b�A�z�U���i��31�b�Ȃ̂ŁA�啔���o�ߋ傪�����Ƃ����A���o�����X�������Ă���B����ł����A�{������}�N���������Ƃ������ۂ��B3���߂�t����������Ȃ������̂́A�ЂƂ��ɕσ����������Ƃ��������ȓ]���ɂ��̈�������B������ł��Ȃ����H3���߂�t���������ɓ]���ł���A�Ȃ̗��ꂪ�X���[�Y�ƂȂ�o�����X�����P�����B����ȉ���I�ȉ�������̂��낤���H
�i2�j�u���c���N�v�����ł̓R�����u�X�̗���
�@�������ڂ����̂̓W���X�}�C���[�̐ݒ肵���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̕σ������Ƃ��������ł���B�����B���͂�������̂܂܂ɂ����B�ʂ����Ă���͐�ΓI�Ȃ��̂Ȃ̂��H�u�T���N�g�D�X�v�����Łu�x�l�f�B�N�g�D�X�v���σ������B���̂悤�Ȍ`�̐ݒ�����[�c�@���g�͂��Ă���̂��낤���B���̍�i�Ō�����B
�@ �ǎ��@�~�T K133�@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł́u�z�U���i�v�́A�u�T���N�g�D�X�v�Ɠ��������ɖ߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A���[�c�@���g�͑��݂̒�����]�����Ղ����̓��m�ɐݒ肵�Ă���B
�@�@ �u�T���N�g�D�X�v�n�����@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�w����
�A �N���h�E�~�T K257
�@ �@�u�T���N�g�D�X�v�n�����@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�w����
�B �O�ʈ�̎���̃~�T K167
�@�@ �u�T���N�g�D�X�v�n�����@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�w����
�C �~�T�E�u�����B�X K140
�@�@ �u�T���N�g�D�X�v�g�����@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�n����
�D ��~�T�� K427
�@�@ �u�T���N�g�D�X�v�n�����@�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�C�Z��
�@�D�́u�T���N�g�D�X�v�n�����A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�C�Z���̊W�́A���s���B�����L���̓\�m�}�}�Ȃ̂œ]���͎��ɃX���[�Y�B�@�|�B�́u�T���N�g�D�X�v�n�����A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�w�����͉������̊W�B������O�ւ̓]���ƂȂ邩��A���O�Ɂ���O�������B������X���[�Y�Ȉڍs���\�ł���B�C���������̊W�ŁA�������邾���B
�@�W���X�}�C���[�łɂ�����u��������ւ̓]���v�Ȃǂ����߂�ǂ��ȗ�͊F�����B�W���X�}�C���[���u���c���N�v�ŔƂ����~�X�́A�u�z�U���i�v�̒������ɂ��Ȃ������Ƃ����ȑO�ɁA�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒������u�T���N�g�D�X�v�Ƃ͖��֘A�̒����ɐݒ肵�Ă��܂������Ƃɂ���B�����Ă���́A���[�c�@���g�Ȃ��ɂ��肦�Ȃ��ݒ�Ȃ̂��B
�@�W���X�}�C���[�́u�T���N�g�D�X�v����ɐݒ肵���B�咲���j�Z�������瓯�咲�̐ݒ�ł���B���̎���́A���̏@����i�ɂ������������A�Ȃ����͂Ȃ��B���������āu�T���N�g�D�X�v�̓��͌Œ肷��B
�@���Ƃ́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒����ݒ�ł���B���[�c�@���g�̎��Ⴉ�炵�Ă��A�����͉������ɐݒ肷��̂��x�X�g���낤�B���̉������̓g�����B�����A�����ł́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒������g�����ɐݒ肷��B�������ꂾ���ł���B�g�����́��B�u�z�U���i�v�ɂ����āA�����������ł�����i���j�ɓ]������ɂ́A�������邾���B����Ȃ�o�ߋ�̒lj��͕s�v�B���O�AC�̉��Ɂ��t���邾���ōςށB
�@�u�����B���Łv�̂悤��3���߂̌o�ߋ�������A����a���@����g���Ă̓]���͕s�v�B�u�z�U���i�v�Ƃ̃^�C����o�����X�������h�����Γ̕���ł͂Ȃ����I�I
�@���O�̓W���X�}�C���[�ł���ꉹ���������Ă��܂����Ƃ����A���̒��x�͊뜜����ɋy�Ȃ����낤�B�o�X�̍ʼn�����18���ߖڂ�D2�ƂȂ邪�A����̓M���M���W��������Ɏ��܂�B���̐����͖��Ȃ��B
�@���̑��̕����Ɋւ��Ă͍S��Ȃ��B�W���X�}�C���[�łł��o�C���[�łł������B�������A�A�[������t�[�K�͍̂�Ȃ��B���[�c�@���g�̐^�̈Ӑ}���ǂ����s�������炾�i�N�����m8.10�j�B
�@�W���X�}�C���[�̕�M��������200�N�]�B����y�̓`����Ƃ����W���X�}�C���[�̃~�X�́A����Ɓu�����B���Łv�ɂ���Đ������ꂽ�B�Ƃ��낪����́A�W���X�}�C���[������Đݒ肵���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒�����s�N�Ƃ������߂ɁA�������`�ɂ���ɂ͓�����y�Z�@�Ə��߂̒lj���K�v�Ƃ����B��Ύ�����K�v�̂Ȃ����̂�ς��Ȃ����������߂ɁA�J���]�V�Ȃ����ꂽ�킯���B������\�Ȃ炵�߂��̂́A�����B���̍�ȉƂƂ��Ă̋Z�ʂɑ��Ȃ�Ȃ����B
�@���ɂ͋Z�͂Ȃ��B�����獪�{����������B��������ΐ������`�փV���v���Ɉڍs�ł���B�����������B���ňȏ�Ƀ��[�c�@���g�̈ӌ��ɍ��v���Ă���B��ΓB200�N���̊ԒN��l�C�Â��Ȃ������P���ȕ��@�B�����ł����R�����u�X�̗��B�W���X�}�C���[�ł̍őP�̐����@�B������A���j�I�����ł́I�H �F�l�̂��ӌ��������������B����ł́A�������āA�����ɂ킽�����u���c���N�v���I���ɂ������Ǝv���܂��B
���Q�l������
���[�c�@���g�u���N�C�G�� ��Z�� �����B���ŁvK626 CD�{�����
�@�@�@�}�b�P���X�w���F�X�R�b�g�����h�����nj��y�c
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626 �y��
�@�@�@�����B���Łi�V���g�D�b�g�K���g�E���[�c�@���g�o�Ŋ��j
�@�@�@�W���X�}�C���[�⊮�Łi�x�[�������C�^�[�Њ��j
2015.09.25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��11�`�u�����B���Łv���܂�3�̔ł��l�@����
�@���Ƀ����B���łɂ��ǂ蒅�����B����܂ŁA�o�C���[�ŁA�����h���ŁA���[���_�[�łƌ��Ă������A�ɘ_����Ύ��ɂ́g�ǂ��ł������h�łł������B���x���w�E���Ă���Ƃ���A�W���X�}�C���[�ōő�̌��ׂ́A11�u�T���N�g�D�X�v��12�u�x�l�f�B�N�g�X�v�̃z�U���i���قȂ邱�ƁA�ł���B�O�R�ł͂��̍ő�̃~�X����u���Ă��邩��g�ǂ��ł������h�̂ł���B�u�����B���Łv�͂����Ƀ��X����ꂽ�B���̒T���������������Ɩ{�i������̂ł���B����͂܂��u�����B���Łv���l�@�����̂Q�̔łɂ��G��Ă��������B����Ō��s�́u���c���N�v�قڂ��ׂẴG�f�B�V�������l�@���邱�ƂɂȂ�B�i1�j�����B����
�@���o�[�g�ED�E�����B���i1947�|�j�́A�A�����J�̃s�A�j�X�g�A��ȉƁA���y�w�ҁB1987�N�A�w�����[�g�E�������O����ɂ��鍑�ۃo�b�n�E�A�J�f�~�[����u���c���N�v����̈˗�����B�����B���̓������O�Ƃ̓�l�O�r�Ŋ����A���[�c�@���g�v��200�N��1991�N8���A�������O�̎w���ŏ������ꂽ�B
 �@�����B���ł̓������}�b�P���X�Ղ̉����������p���Ă������B�A���Ղ̂��ߖ|�K�v���������A����ɂ��Ă͖��FBrownie�쓈���ɂ����͂����������B���̔���Ȃ����������Ƃ��ȒP�ɖĂ��܂��A�܂��Ƀv���̋Z�ł���B
�@�����B���ł̓������}�b�P���X�Ղ̉����������p���Ă������B�A���Ղ̂��ߖ|�K�v���������A����ɂ��Ă͖��FBrownie�쓈���ɂ����͂����������B���̔���Ȃ����������Ƃ��ȒP�ɖĂ��܂��A�܂��Ƀv���̋Z�ł���B
��i����������ɂ������āA�W���X�}�C���[�̓��[�c�@���g�̎��̒���Ƀ��[�[�t�E�A�C�u���[���肪�����������̃V�[�N�G���X��𗧂Ă邱�Ƃ��ł����B�ނ͂����Əd�v�Ȏ����\�\�u�݂��̑剤�v�̂��߂̑Έʖ@�̌�����u�܂̓��v����߂�����A�[�����E�t�[�K�̖`�����L���ꂽ�X�P�b�`�\�\�����p���邱�Ƃ��ł����ł��낤�B�Ƃ��낪�A�ނ͂��̃t�[�K����炸�Ɂu�܂̓��v���̘a���Œ��߂������Ă��܂����B�@��L����킩��Ƃ���A�����B���ł̊j�S�͓�B�u�A�[�����E�t�[�K�̐V���ȍ�ȁv �Ɓu�z�U���i�̒������킹�v�ł���B
�u�T���N�g�D�X�v�̌㔼�́A�W���X�}�C���[�ł̉��F�̖������������A�u�z�U���i�v�����́u�~�T�� �n�Z���v�����f���ɂ��ă��[�c�@���g�̋���y�̃X�^�C�������������B�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɂ�����u�z�U���i�v�́A�I���W�i���ł�����łȂ���Ȃ�Ȃ����߁A�����ɃX���[�Y�ɂȂ��邽�߂̐V���Ȍo�ߋ��������B
�@�u�A�[�����E�t�[�K�̐V���ȍ�ȁv�� ���[���_�[�łɎ����œ�ڂł���B���[�c�@���g���M�́u�A�[�����E�t�[�K�v�̃X�P�b�`���₳��Ă���Ƃ������Ƃ́A���[�c�@���g���g��x�͖ژ_�킯�ł��邩��A�g���C���鉿�l�͏\���ɂ��邾�낤�B
�@�����B���́A�A�[�����E�t�[�K�Ɏ���u�܂̓��v�̓����̒��ŁA�W���X�}�C���[�łƂ̎�̕ύX�����s���Ă���B��͑�21���߂̃J�b�g�B������͑�23���߁i�W���X�}�C���[�ł�24���ߖځj�̍����ŁA�o�X���J�b�g���e�m�[���̉��^��ς��Ă���B
�@�����āu�A�[�����E�t�[�K�v�ɓ���B�����88���߂Ƃ�������Ȃ��́B���[���_�[�ł��10���߂قǒ����B���������ł͂Ȃ��A4�̐����̘A�g���k�����≹�^�̑g���킹�̖����A�����B���łɈ���̒���������B
�@�����A��͂�u�����B���Łv�̍ő�̌��т́u�z�U���i�̒������킹�v�ł��낤�B���̋���y�̓`�������E�����W���X�}�C���[�̃~�X���A200�N�̔N�����o�āu�����B���Łv�ł���Ɛ������ꂽ�̂ł���B����́A����y�ɐ��ʂ����o�b�n���t�̌��Ѓw�����[�g�E�������O�i1933�|�j�ɕ����Ƃ��낪�傫���̂ł͂Ȃ����B�ނƂ̋�����Ƃ̒��A�����B���́A�]���̂��߂̌o�ߋ�������āA�I���W�i���́u�z�U���i�v�i���j�ɂȂ����̂ł���B���̏ڍׂɂ��Ă͎���ɉ��B
�i2�j��ؗD�l��
 �@��ؗD�l�i1981�|�j�ł́A��؉떾�w���F�o�b�n�E�R���M�E���E�W���p���̉��t�i2013�N�^���j��CD������B�����Ă݂����ʁA������ɋL����Ă�������R���Z�v�g�Ǝ��^���ꂽ���t�Ƃ̊Ԃɍ��ق����݂��邱�Ƃ����������B����͎���2�_�B
�@��ؗD�l�i1981�|�j�ł́A��؉떾�w���F�o�b�n�E�R���M�E���E�W���p���̉��t�i2013�N�^���j��CD������B�����Ă݂����ʁA������ɋL����Ă�������R���Z�v�g�Ǝ��^���ꂽ���t�Ƃ̊Ԃɍ��ق����݂��邱�Ƃ����������B����͎���2�_�B
�@�Z�N�G���c�B�A�i3�u�{��̓��v�|7�u���ꂵ�ҁv�j�̓A�C�u���[���̗p����Ƃ����Ȃ���A5�u�݂��̑剤�v��2���ڂɋ��ǂ̃u���[������B����͕�����Ȃ��W���X�}�C���[�łł���B�@�@�͑債�����ł͂Ȃ����A�A�̓o�b�n�E�R���M�E���E�W���p���̉��t�����Ɏc�O���B�w���҂̗�؉떾����2012�N���C�v�c�B�q�s����o�b�n�E���_�������^����Ă��鐢�E���F�߂�o�b�n�̌��ЂȂ̂�����A��������߂����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ł���B
�A��{�I�ɃW���X�}�C���[�łd���邪�A�Z�@�I�ɉ��P���ׂ��_����L���ׂ����R������Ƃ��Ɍ����Ă͕ύX�����A�Ƃ����Ȃ���A��ɉ��P���ׂ��u�z�U���i�v�̒�������u���Ă���B
�@��ؔł̍ő�̓����́u�܂̓��v�̈������낤�B�W���X�}�C���[�̏�������Amen��Requiem�ƒu�������A���̂��ƂɐV���ɍ�Ȃ����u�A�[�����E�t�[�K�v���Ȃ��Ă���B�m���ɂ���͎j�㏉�̎��݁B����͂���ŃA�C�f�B�A���Ƃ͎v�����A�������ꂾ���B�c�O�Ȃ���A�ϋɓI�ȈӖ������o���Ȃ��B�t�[�K��39���߂Ƃ��Ȃ菬�K�́B�X�P�[�����̖R�����͔ۂ߂Ȃ��B
�@��������ڂ́u���Ȃ郉�b�p�v�ٔł̓Y�t�B�g�����{�[���E�\���̑�5���߈ȍ~���t�@�S�b�g�ɒu�������Ă���B��؎��́A�����Ƃ��āA���o�ł̊y���i1800�N�u���C�g�R�b�v�Ёj�ɂ��̎w�������邱�ƁB1796�N�A�R���X�^���c�F��Ȃ̉��t�̍ۂɂ����̌`���������ƁB�t�@�S�b�g�ɒu�������邱�Ƃɂ�鋳�`�I�Ӗ������B�Ȃǂ������Ă���B�u���c���N�v�̕s�v�c���X�ɐ[�܂�G�s�\�[�h�ł͂���B
�@�Ō�Ɉꌾ�B����CD�ɂ̓N���X�g�t�E���H���t�Ƃ����l�̊y�ȉ���i�I�R�z�q��j���t���Ă��邪�A���̒��ɂ���ȋL�q������B
���[�c�@���g��1971�N7����Ȃ̃��e�b�g�u�A���F�E���F�����E�R���v�X�v�@1791�N��1971�N�Ƃ����E�b�J����~�X�B���R�[�h��Ђ̍Z���}���͓w�X���ӂ�ӂ�ׂ��炸�A�ł���B
���[�c�@���g�̂��߂�1971�N12��10���ɒǓ��~�T���Ƃ�s��ꂽ�B
�i3�j�h���[�X��
 �@�_���J���E�h���[�X�i1939�|�j�̓C�M���X�̍�ȉƁB�ނ́A1991�N�^���u�h���[�X�ŁvCD�̉�����̒��ł����q�ׂĂ���B
�@�_���J���E�h���[�X�i1939�|�j�̓C�M���X�̍�ȉƁB�ނ́A1991�N�^���u�h���[�X�ŁvCD�̉�����̒��ł����q�ׂĂ���B
���[�N�V���[�E�o�b�n�����c���1984�N�ɈϏ��������́u�V�Ń��N�C�G���v�ł́A�ł������m�M�����Ă���@�Ō��Ă��ӂ���܂��悤�Ƃ����B�܂�A���[�c�@���g�̑��`�Ɏ������͂߂��ނƂ��Ă��A���̏��@�ɋ����A���̍�Ȗ@�ɂ��Ȃ萸�ʂ��Ă���18���I�̍˔\������ȉƂɑ��Ă���悤�ɂ͂��܂肵�����Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��B�@�c�O�Ȃ��炱�̕��́A���̓lj�͂ł͗����ł��Ȃ��i�����̂����m��Ȃ����A������C�͋N���Ȃ��j�B�����悤�Ɂu�h���[�X�Łv���̂��̂��Ȃ��Ȃ��̑㕨�������B
�@�ő�̓����́u�܂̓��v�B���[�c�@���g���M���~�߂�8���ߖڂ܂ł́i���R�Ȃ���j����������ɁA����ȍ~�̓W���X�}�C���[���S�����̑n��B�u�A�[�����E�t�[�K�v��120���߂��z���钷�傳���ւ�i?�j�����B
�@�u�T���N�g�D�X�v�ł́A�u�z�U���i�v���W���X�}�C���[�ł�2�{�ȏ�̒����ƂȂ��Ă���B���̉����͈����Ȃ��i�W���X�}�C���[�͕̂n��Ƃ̕]������j�B����ɁA�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�͂�������Ɠ��ɍ��킹�Ă���B����͂Ȃ��Ȃ��I �Ǝv�����̂����̊ԁA�Ȃ���������20���߂قǒZ���B�܊p�]�����Ē��������킹���̂Ɏڂ�ς��Ă��܂��Ă���B����ł͂Ȃ�̈Ӗ����Ȃ��ł͂Ȃ����B
�@�u�_�̎q�r�v�͔�r�I�W���X�}�C���[�łd���Ă��邪�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒��Ղ͌���e���Ȃ��B���X�Ȃ܂ł̃N�����l�b�g�̃I�u���K�[�g�́i�����Ă����r���ăo�Z�b�g�E�z�������g�����j���[�c�@���g�̈Ӑ}�݂ɂ�����̂����A���[�c�@���g���M�́u���̔q�̏��v�̃C���g���ɑ啝�Ȏ�������Ă���̂����������Ȃ��B �u�z�U���i�v�̒������킹������ׂ����������邪�A�����āA�Q�e���m�Ƃ͉]��Ȃ��܂ł��A���Ȃ胆�j�[�N�ȑ㕨�ł��邱�Ƃ͊m���ł���B
���Q�l������
���[�c�@���g�u���N�C�G�� ��Z���vK626 CD�{�����
�@�@�@�u�����B���Łv�}�b�P���X�w���F�X�R�b�g�����h�����nj��y�c
�@�@�@�u��ؗD�l�Łv��؉떾�w���F�o�b�n�E�R���M�E���E�W���p��
�@�@�@�u�h���[�X�Łv�m�����g���w���F�����h���E�N���V�J���E�v���C���[�Y
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626 �y��
�@�@�@�����B���Łi�V���g�D�b�g�K���g�E���[�c�@���g�o�Ŋ��j
�@�@�@�W���X�}�C���[�⊮�Łi�x�[�������C�^�[�Њ��j
2015.09.10 (��) ���70�N�Ɋāi��ҁj�`��㕜���A������Jiiji�̒�
�@Ray�����A�O��̃e�[�}�͓��{�̔s���������ˁBJiiji�̒���͂ǂ����������ȁH �����Ŏw�E�����R���̑̎��I�Ȍ��ׂ͌���ɂ��m���ɗ���Ă����B�g�b�v�͂�����A�g�D�̓Z�N�V���i���Y���Ŗ��ӔC�̎��B�n�R�����͂��������B���ԂŌ������I�����s�b�N���������̑̂��B�V�������Z����G���u�����������P��Ƃ����e�C�^���N�Ȍ����Ȃ̂ɒN���ӔC�����Ȃ��B�{���Ȃ�A�������ȑ��ƐX�g�D�ψ����͉��炩�̐ӔC�͎��ׂ����Ǝv�����ǁA���������ȁH�@������厖�Ȗ��́A��ʑ�O�ɐӔC�͂Ȃ��������H �Ƃ������ƁBJiiji�̃}�}�͏I�펞��24�B�u���Ɓu���{��������Ȃ�čl�������Ȃ��������B����18�Ŏ����ǂ����̂��߂ɗ��h�ɓ���������A�߂�������ǁA�悭�撣�����ƌ����Ă�����v�ȂǂƘb���B�܂��A������u�����������v�Ȃ�Č������A�����͑�{�c���\�Ɂu���I�I�v������ł����B���炭���{�����̑命���͂���Ȋ�����������Ȃ����ȁB����ޏ������̐ӔC���H ���₢�₱��̓}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̖�肾�낤�BRay�����A����͂����炩��b��i�߂Ă������B
�i5�j���{�l�͐푈�̐��ڂ��ǂ�������Ă����́H
�@���ϓI���{�����́A�펞���ANHK�̃��W�I�A�V���A�j���[�X�f��Ȃǂ�����Ă����B�����@�ւ͂��ׂĐ��{�̓������ɂ���������A���͍��̎v���̂܂܂������B�v���p�K���_���Ă���B�s����D�ʁB�A�s��A��A���B�N�������Ă̈�������̊J���B�A���n����ł͂Ȃ��哌�����h���̊m���ƁA�O�����ƂȂ���߂�������B�����̐�Ӎ��g�A�푈�̐��������ړI���ˁB
�@����ȕ��蕷�������Ƃǂ��Ȃ�H �����͌R�̐i�U���x������������ԁB�����^�ʖڂȓ��{�����́A�g�����̂��߂Ɂh��D�悵�l�̋]���͓�����O�ƍl����B�Ԏ��i�����ʒm�j��������҂��A�u�����̂��߂ɗ��h�Ɏ���ŗ����v�ƌ����đ���o���B���Ƒ������A�ꉭ���ʍӂ��B
�@���O�͈Î��Ɏア�B���������ƉR���^���Ǝv�����ށB�}�X�E���f�B�A�ɂ��ӎv�̓����B�̕|���������ɂ���B����͒��x�̍��������ꌻ��ɂ��ʂ���b����B
�i6�j���{�́A���A�ǂ�����ĕ��������́H
�@1945�N�A�s��Ɠ����ɁA���R��`�A�l��`�A�����`�̔g��������B���{�͈�C�ɂ��̗���Ɉ��ݍ��܂�Ă䂭�B����̓G�E�S�{�ĉp�́u�M�u�E�~�[�E�`���R���[�g�v�������Ă���铲��̐i���R�ƂȂ�B���Ă���e�āB���{�l�������Ȃ�ς�����B�g�i���I�m���l�h�Ȃ镶���l���o�������B�����₱�̕ς��g�̑����A�ߑ��̂Ȃ������{�l�̓����Ȃ̂�������Ȃ��B���̗���ɉ䖝�ł��Ȃ������͎̂O���R�I�v�����A����͂܂��ʂ̋@��ɁB
 �@�A�����R���i�ߊ��̓_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�i1880�|1964�j�B1945�N8��30���A�����D�u�ƍ~�藧�����BGHQ�{���͍c�����x�̑O ��ꐶ���r���ɒu���ꂽ�B���{�͔ނ̎w���̉���̎���ɓ���B�����ŁA�u�|�c�_���錾�v�̓^���������Ă������B�u���̌쎝�v�̏����t����v�]�������{���{���������A�A�����R�̕ԓ��́u���{���̑̐��͘A�����R�̉��ɒu�����v�B�v�́A�A�����R�̈ӂ̂܂܁B���S�Ȗ������~���̒ʒB�������B�����1945�N9��2���A�����p��~�Y�[�����D��B���{�̑�\�͎��̊O����b�E�d�����������B
�@�A�����R���i�ߊ��̓_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�i1880�|1964�j�B1945�N8��30���A�����D�u�ƍ~�藧�����BGHQ�{���͍c�����x�̑O ��ꐶ���r���ɒu���ꂽ�B���{�͔ނ̎w���̉���̎���ɓ���B�����ŁA�u�|�c�_���錾�v�̓^���������Ă������B�u���̌쎝�v�̏����t����v�]�������{���{���������A�A�����R�̕ԓ��́u���{���̑̐��͘A�����R�̉��ɒu�����v�B�v�́A�A�����R�̈ӂ̂܂܁B���S�Ȗ������~���̒ʒB�������B�����1945�N9��2���A�����p��~�Y�[�����D��B���{�̑�\�͎��̊O����b�E�d�����������B�@�}�b�J�[�T�[�̍ŏ��̖���͍��̌쎝�ւ̑Ώ��B�V�c�̏����������B���Ă̏펯���炷��A�V�c�͐푈�̍ō��ӔC�ҁA���Y����Ă����������Ȃ��B�����A�����J�̐��_�́u�V�c�ɉ��炩�̐ӔC�Njy���v���唼�������悤���B���ʂ́u�V�c���ێ��v�B���̌쎝�͊������B����́A�}�b�J�[�T�[�́A�V�c�ɑ���D��ہi���Ζʎ��Ɏ��������j�Ǝ���̃~�b�V�����B���̂��߂ɂ͕s���Ƃ��������B��ƌ��������܂������ʂ������B�����āA�V�c�́A1946�N1��1���A�l�Ԑ錾���s���_�̍�����~��A�V���@���Łu�ے��v�ƂȂ����B
�@���Ȃ�Ɩ��͌R���̉�̂Ɛ푈�ƍߐl�̍ٔ��B���{�ɓ�x�ƍĂѐ푈���N�������Ȃ����Ƃ��_�����B1946�N�ɓ����یR���ٔ��i�����ٔ��j�ŁA�����p�@�A�L�c�O�B��7����A����Ƃ̔��������Y���ꂽ�B
�@�܂��͐�㏈���̑������I������B�V�c���ێ��ƌR���̉�́B�}�b�J�[�T�[�̑[�u�͐����������̂��H ���{�ɂƂ��Ă���͂悩�����̂��H��ؓ�ł͑���Ȃ��B�����A������{����������l�X�Ȗ��⍬�������̐��̐����N�_�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B������A����̉𖾂ɐ��[�u�̌��͕s���ȂB
�@���͌��@�̐���B���Ă�GHQ�������{���������̎���������B��9���ɂ����鈰�c�C���i�g�O���̖ړI��B���邽�߁h�̓Y���j�͓��ɗL������BJiiji�͉��x�ǂ�ł��L���̈Ӗ��������킩��Ȃ����A����͒u���Ă������B���z��1946�N11��3���i�����̓��j�A�{�s��1947�N5��3���i���@�L�O���j�������B
�@Ray�����A���{�����@�̎O�{���́u�����匠�v�u���a��`�v�u��{�I�l���̑��d�v���ˁB���̂����A�u�����匠�v�Ɓu��{�I�l���̑��d�v�͕���Ȃ��Ɉێ����ׂ����낤�B���́u���a��`�v�i���@��9���j���B���X�ƕω����鍑�ۏ�ɂǂ��Ή�������ׂ����B����ɂ��Ă͋c�_���c��ނ���ʂ̋@��ɉ�B���Ƃ́u�O���v�B����͓��{�����@�̐��_���Ïk����Ă���d�v���������A���̒��ɂ͐�ɐ������ׂ����������݂���A��Jiiji�͍l���Ă�B�ǂ������āH�����ŒT���Ȃ����B
�@�Ō�Ɉꌾ�B���{�����́u���̌��@�̓A�����J�̉����t��������A�������ׂ��v�����ȁB�����A�����}�̉����Ă̓X�J���B������`�������ĂȂ������͂ɂ��i�i���Ȃ��B������AJ iiji�͂��������������B
 �@Ray�����A���͓��{�̓Ɨ��B��̂���̉�����B����̓T���t�����V�X�R�u�a���Ŏ��������B��������1951�N�A�{�s�͗�1952�N�������B���{�̐ӔC�҂͑�����b�E�g�c�B�����͓�����킪�n�܂�������B����Ȏ����A���{���S���ʂŕ��a�������ԂȂ͕s�\�Șb�B���{�̓A�����J�̐����Ƃ̍u�a��D�悵���B�����疢���Ƀ\�A�Ƃ͕��a�������ׂĂ��Ȃ��B�k���̓y�����������̂܂܁B�܂����̂Ƃ������ɒ��������u���Ĉ��S�ۏ���v�͓��{�̈��S�ۏ�̍��i�ƂȂ��č����Ɏ����Ă���B
�@Ray�����A���͓��{�̓Ɨ��B��̂���̉�����B����̓T���t�����V�X�R�u�a���Ŏ��������B��������1951�N�A�{�s�͗�1952�N�������B���{�̐ӔC�҂͑�����b�E�g�c�B�����͓�����킪�n�܂�������B����Ȏ����A���{���S���ʂŕ��a�������ԂȂ͕s�\�Șb�B���{�̓A�����J�̐����Ƃ̍u�a��D�悵���B�����疢���Ƀ\�A�Ƃ͕��a�������ׂĂ��Ȃ��B�k���̓y�����������̂܂܁B�܂����̂Ƃ������ɒ��������u���Ĉ��S�ۏ���v�͓��{�̈��S�ۏ�̍��i�ƂȂ��č����Ɏ����Ă���B�@�����A����ēƗ����ʂ��������{�́A�����ׂ��X�s�[�h�ŕ����𐋂���B�g�c�̌o�ϗD�搭��Ɩ��Ԃ̊��͂̑�����ʁBJiiji�A�����͖��Ԃ̊��͂ɒ��ڂ������B�u���{�l�͗D�G�ȂI�v�Ƃ������M�B�u�������Ȃ�ł���I�v�Ƃ����E�C�B��㏉���ɂ���ȏ����̂��C�������o�������W�F���h��4�l�����B�Ë��L�V�i�A����G���A���V���A����`�j���B
 �@�Ë��L�V�i�i1928�|2009�j�́g�t�W���}�̃g�r�E�I�h��搂�ꂽ���j�I��B�I�풼��Ɍ���Ď��X�ɐ��E�L�^���X�V���Ă������B�܂���1948�N�̓��{�I�茠�B
�@�Ë��L�V�i�i1928�|2009�j�́g�t�W���}�̃g�r�E�I�h��搂�ꂽ���j�I��B�I�풼��Ɍ���Ď��X�ɐ��E�L�^���X�V���Ă������B�܂���1948�N�̓��{�I�茠�B�@���{�͔s�퍑�A1948�N�����h���E�I�����s�b�N�ɂ͎Q����������Ȃ������B�����ŃI�����s�b�N�Ɠ������ɓ��{�I�茠���J�Â���B�Ë���400m��1500m���R�`�ɏo��B�����D�����邪�A���̃^�C���̓����h���ܗւ̋����_���I��̋L�^��y���ɗ������B���1500m�̃^�C��18��37�b�t���b�g�̓����h���ܗւ̋L�^���41�b���������|�I�Ȃ��̂������B��1949�N�A����Đ��E���j�A���ɕ��A�������ꂽ���{�͑S�đI�茠�ɏo��B�G�[�X�Ë���400m�A800m�A1500m�����ׂĐ��E�V�L�^�ň����A���E�ɂ��̖������������B�u�t�W���}�̃g�r�E�I�vThe Flying Fish of Fujiyama�͂��̂Ƃ��A�����J�̐V�����h�ӂ��ĕt�������́B���̉������A�܂��H�Ǝ�����܂܂Ȃ�Ȃ����{�l�ɁA�ǂꂾ���E�C��^�������͑z���ɂ������Ȃ����B
�@����G���i1907�|1981�j�͓��{�l���̃m�[�x����҂��B1934�N�ɔ��\�����u���Ԏq�v�̑��݂��m�F����A1949�N�m�[�x�������w�܂���܂����B�m�[�x���܂̑n�݂�1901�N�B�����I���o�Ẳ����͐��̓��{�l�ɒm�̎��M��A���t�����B�푈�ɂ͕��������lj��������{�l�͗D�G�ȂƂ������M�B�ނ��1���Ƃ��āA���݂܂łɒʎZ22�l����܁B����̓A�W�A�ł̓_���g�c�̐������B���݂ɂ��̔N��2���ɂ͑�3���g�c���t�������B����Ɍq����g�c�H���̊�_�ƂȂ����N�ł������B
 �@���V���i1910�|1998�j���u������v�Łu���F�l�e�B�A�f��Ձv�����q�܂���܂����̂�1951�N�B���̌�́u���E�̃N���T���v�̊���͂����m�̒ʂ肾���A����ȑ��������ɐ��E�O��f��Ղ̃O�����v�����l�����Ă����Ƃ́I�I������������B�|�p�E�|�\�W�������ł̎��M�B����ɑ����̂�1958�N���V�����̃u�U���\�����ێw���҃R���N�[���D�����ȁB
�@���V���i1910�|1998�j���u������v�Łu���F�l�e�B�A�f��Ձv�����q�܂���܂����̂�1951�N�B���̌�́u���E�̃N���T���v�̊���͂����m�̒ʂ肾���A����ȑ��������ɐ��E�O��f��Ղ̃O�����v�����l�����Ă����Ƃ́I�I������������B�|�p�E�|�\�W�������ł̎��M�B����ɑ����̂�1958�N���V�����̃u�U���\�����ێw���҃R���N�[���D�����ȁB�@���{�f��E�̗����ɍ��V���ʂ����������͑傫���B�ϋq������50�N��Ƀs�[�N���}���A1958�N�ɂ͔N��11���l��˔j����B���݂�2014�N��1��6�疜�l���B
�@����`�j�i1923�|2003�j�́A1952�N5��19���A���E�t���C���I�茠�����Ń_�h�E�}���m�ɏ������{�l���̐��E�`�����s�I���ɂȂ����B���̓��{�l�������M�ɉ�����B���7�N�A���{�l�ɂǂꂾ���E�C��^�������I�]�k�����A1955�N5��30���A�p�X�J���E�y���X�Ƃ̃��^�[���}�b�`�i5��KO�����j�Ŏ�����������96.1���́A�e���r�E�̋L�^�Ƃ��Ė����ɔj���Ă��Ȃ��i�ǂ�����đ������̂��Ȃ�!?�j�B
�@���͂�7�N���炸�̊ԂɁA�X�|�[�c�A���R�Ȋw�A�|�\�̊e����ɂ����āA���������E�I�����𐬂���������L4�l�����A�s��̒Ɏ�������{�l�ɐ�����E�C��^�����M��A���t�������J�҂ɂ��ē��{�����̉e�̌����Ԃ��B���Ȃ�g�b�v�N���X�̍����h�_�܂��낤�B
�i7�j�Ɨ���̓��{�̕��݁A�����āAJiiji����̒�
�@�g�c�\���R��Y�\�ݐM��\�r�c�E�l�\�����h��\�c���p�h�E�E�E�E�E1947�N���{�����@�{�s�A1950�N���N�푈�A1951�N�T���t�����V�X�R�u�a�������A1952�N�{�s�A1964�N�����I�����s�b�N�A1965�N���؊�{�������A1968�NGNP���E��2�ʁA1970�N��㖜���A1972�N����ԊҁA���������ȂǁA��A�̗���̒��A���{�͌����Ȍo�ϕ������ʂ����B1980�N��ɂ͉��������}���u�W���p����A�YNO1�v�Ȃ闬�s������܂ꂽ�B����͈��S�ۏ���A�����J�Ɉˑ����A�R���Ɋ|����͂��̗\�Z���o�ϐ���ɂ����g�c�̊�{�����������ʂ��낤�B�����A���̗��Ɋ����̖���s�݁A����炪�������̂܂ܕ��u����A���B���Ă����������������Ȃ��B�����́A���ӔC���Ȃ���̎���O��͂̌��������{�I�����ɋN��������̂��Ǝv���B���S�ۏႵ����A���@��肵����A�k���̓y�A��t�����A�|���Ȃǂ̗̓y���A�������A������A�]�R�Ԉ��w���A�����A�ȂǂȂǁA������{�ɂ͖�肪�R�ς��Ă���B
�@�ʂ����ċg�c�̐���͐����������̂��H �ނ̗��O�͓��{�̂��߂ɂȂ����̂��낤���H Ray�����A���̖��ӎ����Y�ꂿ�Ⴂ���Ȃ��A��Jiiji�͍l����B
�@���̗��j�̓A�����J�ˑ��̗��j�ł�����B��������{�̓A�����J�̑��݂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B�����A�ʂ����Ă��̂܂܂ł����̂��B�ˑ����}���Ɋׂ��Ă͂��Ȃ����B���{�l�̌ւ��Y��Ă͂��Ȃ����I�H �A�����J�ˑ��Ɠ��{�l�̌ւ�B���̃o�����X���ǂ���邩�I�H
�@Ray�����A���{�ɐ��܂ꂽ�������͍K�^���B���E�����n���Ή����ˁB������A�������́A���̑f���炵�������{�������Ƃ����Ƃ������ɂ��Ă����Ȃ�������Ȃ��B�₪�ė���N�����̎���ɂ́A�^�ɋP����ւ�ׂ����ł����ė~�����A��Jiiji�͎v���B
�@�����ȌN�����ɂ��肢�������B�l�Ԉ�l�ЂƂ�̗͔͂��X������̂��B�����A�����`�͂��̔��X����͂����W���đ傫�ȗ͂Ƃ���A�ł��i�V�X�e���̂͂����B�̗͉͂Ƒ��̗́A�Ƒ��̗͍͂��̗͂��B�܂��̗͌͂��グ��B�̗͂̌���͗��j������ڂ��B�Ȃ��Ȃ�A���j�͌���Ɍq�����Ă��邩�炾�B���j���ɂ��Č���̏�͌��Ȃ����炾�B�u���j�͌J��Ԃ��v�Ƃ��u���j�͌��݂Ɖߋ��Ƃ̑Θb�v�Ƃ��]����̂͂��̂��߂��B���j������ڂ��B�܂��͂��̓w�͂�ɂ��܂Ȃ��ŗ~�����B���ꂪJiiji����̒��B
2015.08.25 (��) ���70�N�Ɋāi�O�ҁj�`���{�͂Ȃ��������̂��H
 �@Ray�����A���N�͐��70�N�Ƃ����ߖڂ̔N�B�I��L�O���̑O��8��14���ɂ́u���{�k�b�v���ł��ˁB�ʂɏo�����ƂȂ��̂ɂˁB�l�������ɔz�������łɂ��N�\�ɂ��Ȃ�Ȃ����e�������B�i�����郏�C�c�[�b�J�[�����Ƃ͌��ƃX�b�|���I �܂��A�����������Ⴄ�����ׂ��ፓ�Ƃ͎v�����ǁE�E�E�E�E�B
�@Ray�����A���N�͐��70�N�Ƃ����ߖڂ̔N�B�I��L�O���̑O��8��14���ɂ́u���{�k�b�v���ł��ˁB�ʂɏo�����ƂȂ��̂ɂˁB�l�������ɔz�������łɂ��N�\�ɂ��Ȃ�Ȃ����e�������B�i�����郏�C�c�[�b�J�[�����Ƃ͌��ƃX�b�|���I �܂��A�����������Ⴄ�����ׂ��ፓ�Ƃ͎v�����ǁE�E�E�E�E�B�@17���ɂ͒킭���܂ꂽ�BYou����B���ꂩ���l���ǂ���������Ɛ����Ă����ė~�����B�����ŁA�N�����ɘb���Ă����������Ƃ�����B70�N�O�A���{���ւ�����푈�̂��Ƃ��B�N�����ɂ͖ܘ_�̂��ƁA�p�p���}�}����ɂ������͂Ȃ��͂����BJiiji��1945�N5��20�����܂�B�푈���I������̂͂��̔N��8��15��������A0��3�����ŏI����}�������ƂɂȂ�B
�@0������푈�̋L���͂���͂����Ȃ�����ǁAJiiji��Jiiji��Baba�����A���ꂩ��}�}����A�����͘b���Ă��邩��A�Ⴂ�l���͐푈��g�߂Ɋ����Ă��镔���͂��邩�ȁB������N�����ɂ�Jiiji���b�������Ȃ��B
�@�ǂ�ȕ��ɘb�������H ���n��Ōo�܂�b���H ���܂�ʔ����Ȃ��Ȃ��B������ARay����u�Ȃ��H�v�Ǝv�������z�肵�Đi�߂�A�Ƃ����̂͂ǂ����낤�B���̕����������N�������m��Ȃ��ˁB���ꂩ��N�����́A�w�Z��Љ�ɏo�Đ푈�̂��Ƃ�����������@����邾�낤�B����ȂƂ�Jiiji�̘b����ɂȂ�Ί������ȁB
�@��{�������m�푈�i1941�N12��8���`1945�N8��15���j�ɒu�����B��������������ق����킩��₷������ˁB���{�́A�Ȃ��卑�A�����J�Ɛ킢�s�ꂽ�̂��H Ray�����A����͂��ꂪ�e�[�}���B
�i1�j���{�͂Ȃ��A�����J�Ɠ����H�ڂɂȂ����́H
�@���̑�킪�n�܂�O�܂ŁA���{�͊C�O�ɑ����̌��v�������Ă����B�x���������f���������ېV�i1868�N�j�ȗ��A�푈�ɕ��������Ƃ��Ȃ���������A�����̐험�i�����������Ă������Ă킯���B�����푈�i1895�N�j�ł͑�p�A���I�푈�i1905�N�j�ł͒����E�֓��B�A�����̓씼���A��ꎟ���E���ł͒����E�R���ȂȂǁB1910�N�ɂ͊؍��������B
�@�����Ŏ~�߂Ƃ���悩�����̂ɁA���{�͂���Ȃ�̓y�g���ڎw�����B�����1929�N���E�勰�Q�ɂ�鐢�E�I�s���Ȃǂ��w�i�ɂ͂������B�l�����������āA���{���������ł͐H���A�����̊m�ۂ�����Ȃ����B���ꑦ���鍑��`���A���n����̔��z�ȂB
 �@���{�͊��H�𒆍��̑�n�ɋ��߂��B1931�N�A���B�������N�����B���쎩���łˁB�����Ė��B�ɏ�荞�ݏZ������y�n��D���A���Y�𗪒D�����B�����ɁA�u���B���v�Ȃ���̂����݂����B�����Ō�̍c��E���V�o����V�i1906�|1967�j��S���o���āB�g���X�g�G���y���[�h���B���{�́u�k�̊y���v�Ƃ������č��������B�����̓��{�l���������߂Ė��B�ɓn�����B
�@���{�͊��H�𒆍��̑�n�ɋ��߂��B1931�N�A���B�������N�����B���쎩���łˁB�����Ė��B�ɏ�荞�ݏZ������y�n��D���A���Y�𗪒D�����B�����ɁA�u���B���v�Ȃ���̂����݂����B�����Ō�̍c��E���V�o����V�i1906�|1967�j��S���o���āB�g���X�g�G���y���[�h���B���{�́u�k�̊y���v�Ƃ������č��������B�����̓��{�l���������߂Ė��B�ɓn�����B�@����ɓ��{��1937�Nḍa�����������������ɒ����Ƃ̐킢���g�債�Ă䂭�B�����푈���B���{�l�̒��ɂ́A�u���̐푈�͐N���푈�ł͂Ȃ��v�Ȃ�Č����l�����邪�A����͑傫�ȊԈႢ���B���͂��g���đ����̗̒n�ɓ��ݍ��ݐl������Y�𗪒D���x�z����E�E�E�E�E����͂ǂ����Ă��u�N���v�ł���u�A���n�x�z�v���B���{�l�́A�܂��A�n�b�L���Ƃ��̔F�������ׂ����A��Jiiji�͎v���B���{�͂Ȃ�ł����F�߂�����Ȃ��̂��낤�H �u�|�c�_���錾�v���m��Ȃ��݂��������A���j�̕�������Ȃ���B
�@���̓����Ɂu�҂����v���������̂��A�A�����J�������B�u����ȏ㒲�q�����Đi������A�������~�߂�v�B�o�ϐ��ق��ȁB�����̐푈���s�ɐ�ΕK�v�Ȏ����A����͐Ζ��ƓS�B�����̖R�������{�́A�q��@�p�K�\�����Ƌ��S�̑唼���A�����J����̗A���ɗ����Ă����B�������~�߂��邱�Ƃ́A�푈���~�߂�Ɖ]����ɓ������B�ł������A�ǂ��ɂ��~�܂�Ȃ��B����ǂ�����H �A�����J�ȊO���瓾������B����͓���A�W�A�B�}���[�����A�t�B���s���A�C���h�l�V�A�B������𗪒D����Α��v�B�������f���āA���{�̓A�����J�̒u������������P�ނ��ׂ��v���R�����B�������āA���{�́A�����h���킢���n�߂邱�ƂɂȂ����B
�i2�j���{�͑卑�A�����J�ɏ��Ă�Ǝv���Ă����̂��낤���H
�@���{�l�ɂ́u�A��A���̈ӎ��v���������B�������͐�ɕ����Ȃ��Ƃ����y�Ϙ_���ˁB�o�b�N�ɂ������̂́A�_�����������Ƃ����錳���i1274��1281�N�j����I�푈�ł��̑卑���V�A�ɏ������Ƃ����v�����݁B�ł��A��Âɔ��f����A���I�̏����͐�グ�̃^�C�~���O�̂Ȃ���ƁB�A�����J�̒��قōI����Ɂg�u�a�Ɏ������h�����̘b�B���{�C�C��Ńo���`�b�N�͑���j�����Ƃ����Ă��A�G�n�ɏo�����ď������킯����Ȃ��B����̐i�H��j�����B�卑�ɏ��Ă�͂��{���ɂ������̂��A�Ɩ₤�ׂ��������̂��B
 �@����Ȓ��A�g�A�����J�Ɛ�����畉����h�ƍl���Ă����R�������̒j�������B�A���͑��i�ߒ����E�R�{�\�Z�i1884�|1943�j���B�ނ͎Ⴂ���̃A�����J���w�ł��̍��̒�͂�m�肷����قǒm���Ă����B������ΕĐ푈�ɂ͔��������B����Ȕނ����ĊJ���������^��p�U���̎w�����ƂȂ�^���̔���I �����ɂ́A���ƌl�Ƃ̊W�A���O�ƐE���̂��߂������A�ȂǁA���ՓI�ȃe�[�}������ł����B
�@����Ȓ��A�g�A�����J�Ɛ�����畉����h�ƍl���Ă����R�������̒j�������B�A���͑��i�ߒ����E�R�{�\�Z�i1884�|1943�j���B�ނ͎Ⴂ���̃A�����J���w�ł��̍��̒�͂�m�肷����قǒm���Ă����B������ΕĐ푈�ɂ͔��������B����Ȕނ����ĊJ���������^��p�U���̎w�����ƂȂ�^���̔���I �����ɂ́A���ƌl�Ƃ̊W�A���O�ƐE���̂��߂������A�ȂǁA���ՓI�ȃe�[�}������ł����B�@������Ǝv���Ă����R�{���o�������_�͂������B�u������ɂȂ�Γ��{�͕K��������B������A�`���ʼn�œI�Ō���^���ėD�ʂ̂܂ܒZ���ōu�a�Ɏ������ށB���{�̂Ƃ�ׂ����͂��ꂵ���Ȃ��v�B�ނ̂��̍l���́A���I�푈�̌o�܂�O���ɒu���Ă̂��̂������낤�B1941�N12��8���A�^��p�U�����s�B�����m�푈�̖u���������B
�@�����A�A�����J�͂���قNJÂ��͂Ȃ������B�~�X���d�Ȃ�u���z���v�ʒB���x��A���ʁA�U���͐��z���Ȃ��s�ӑł��Ɖ����B�ڋ��ғ��{��O��I�ɒ@���ׂ��I�哝�̃��[�Y�x���g�̋c����͍�����������B�A�����J�̓����S�ɉ��_�����B�R�{�̌�Z�������B�������āA���{�͓ޗ��ւ̑����ݏo�����B
�i3�j���{�͂Ȃ��������́H
�@�����A���͂��Ⴉ�����B�������Ȃ��B�H�Ɨ͂��y�Ȃ��B���X������͍l���Ă��Ȃ������B�ȂǂȂǁB�ł��A�s���͂��ꂾ������Ȃ��B�C���A�g�D�̖ʂ���AJiiji�̎v�����܂܂ɉӏ������ɂ��Ă݂悤�B
�@�s�s�_�b�̕��Q�@���{���D���������̂́A�^��p�U�����甼�N�قǂɉ߂��Ȃ������B���Ƃ͔s��ւ̓���]���藎���Ă䂭�B����3�N8���������n��ŋL���Ă������B
���{�͋����A�Ō�͕K�����A�Ƃ������o�������������B���̍����Ȃ�遂肪���S�`���f�ƂȂ��ă_���_���Ɛ�ǂ������錋�ʂƂȂ����B����ɂ���Q�͐r��I �]����310���l�̂���200���l�͂��͂⏟�Ă�͂����Ȃ��Ō�̈�N�Ő��������́B�����瑁�߂Ɏ~�߂Ă����悩�����̂��B�ł��A����͌��ʘ_�B
�A���_�_�d���Ɣ�Ȋw��
���{���m�̎m�C�͍����B���{�͐_�Ɏ���Ă���B�����畉���Ȃ��A�ȂǁA��Ȋw�I�Ȑ��_�_�����𗘂����A��Âȓǂ݁A�Ȋw�I�ȑΏ���r�������B����́A���C�e�C��ɉ�����i�ߒ����̞��u�V�C�_����M���S�R�ˌ�����v�≫���ł̕�����͑�a�̌��E���ȂǂɓT�^�I�ɕ\��Ă���B�_���݂���푈�ɏ��ĂȂ���ˁB
�B���ߌn���̕s�
�ĉp�ł͐푈���s�̍ō��ӔC�҂��͂����肵�Ă����B���[�Y�x���g�哝�̂ƃ`���[�`�����B���{�̏ꍇ�A�`���I�ɂ͓V�c�����A�ӔC�����Ȃ��ے��I���݂ɉ߂����A�����I�ȍō��ӔC�҂����Ȃ������B���ꂪ�A�O�����h��f�U�C���̌��@�������炵�A���̂��߁A�푈�ɕs���ȍ��̗L�@�I�A����j�Q�����B����ɂ́A�푈�I���̃^�C�~���O���������B
�C�g�D�̍d����
�u�㊯�̖��߂͐�v�u�ꕺ��������\�����v�ȂǁA�ォ��̖��߂͐�ΓI�B���ݓI�ӌ���������ے肳���B����Ȑ��_���y���g�D�̍d�����ݏ_��ȑΉ���j�B
�D���D��̗��O�ƒ����I�W�]�̂Ȃ�
�[����̐v���O�͐��\�d���Ōl�̈��S�͓�̎��B���ʁA�n�����c�m�̖����댯�ɎN���ꏙ�X�Ɍ����B�����I�W�]���Ȃ����瑀�c�m�琬�̃V�X�e�����s���B��[�������Ȃ��B���ʁA�푈�����ɂ͏n�����c�m�����Ȃ��Ȃ�B�Ȃ�Z�p�s�v�̑̓�����B���ꂪ���U���a���̈���ɂ��B
�E����̕s��
�A�����J�R�͈Í�����ǂ��~�b�h�E�F�[�C��ɏ�������B�R�{�����̎��i1943�N4��18���j���Í���ǂɂ�蓋��@��҂��������ꂽ���߁B�i�`�X�E�h�C�c���j�ꂽ����́A��Ǖs�\�Ƃ���ꂽ�Í���g�G�j�O�}�h�̉�ǁB�A�����̏����͏���̏����ł��������B
1941�N12��8���@ �^��p�U���i4�j�Ȃ������Ƒ����I��点�邱�Ƃ��ł��Ȃ������́H
1942�N 6���@�@�@�@�~�b�h�E�F�[�C��
1943�N 2���@�@�@�@�K�_���J�i���P��
1944�N12���@�@�@�@���C�e�C��
1945�N 3���@�@�@�@�������ח�
�@�@�@�@�@3��10���@�������P
�@�@�@�@�@6���@�@�@�@�����
�@�@�@�@�@7��26���@�|�c�_���錾�ʒB
�@�@�@�@�@8�� 6���@�L����������
�@�@�@�@�@�@�@ 9���@���茴������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�A�Q��
�@�@�@�@�@�@�@15���@�ʉ����� �I��
�@�푈���I��点��͎̂n�߂邱�Ƃ�����A�Ƃ悭������B�������낤�A�X�|�[�c�̐��E�ł��u���߂Ȃ����_�v�������Ȃ���ˁB�푈�����A���͂⏟���ڂ͂Ȃ����������f���Ă����������Ȃ��̂Ƃ��ɂ��A�R���̈ӌ��͋��d�ŁA���ɗ��R�ɂ����Ắu�O��R��`�{�y����_�v�������������B�ނ�Ɂu�ꉭ���ʍӁv�Ƃ������ɋ����Ζق����Ⴄ�B�l�ԁA�А��̂悳�ɂ͎ア�̂��B
�@����A�C�R�̈ӌ��́u�G�ɗL���Ȉꌂ��^���ď����ł��L���ȏ�����ču�a�Ɏ������ށv�����u�ꌂ�u�a�_�v���B�V�c�͂�����x�����Ă����Ƃ������Ă���B
�@�ǂ���ɂ��Ă��A���~���Ƃ����l���͂Ȃ��B�푈���I��点�����t������b�E��؊ё��Y�i1868�|1948�j���Y�̂́A����ȌR���Ƃ̂��߂������������B
 �@1945�N7��26���A�u�|�c�_���錾�v��������ꂽ�B�A�����̕āi�g���[�}���哝�́j�A�p�i�`���[�`���j�A���i�Ӊ�Α��j�����{�ɑ��āg�������~���h�𑣂��錾���B���������؎͂������܊t�c���J���t���̈ӌ����B�O����b�̈ӌ��́u���̌쎝�v�����̏����t����B���R��b�́u���̌쎝�͓�����O�B��̂͏��K�͒Z���ԁB�R��͓̂��{�̎�ŁB�푈�ƍߐl�ٔ������{�ōs���v�̏���������Ȃ��B�펯�I�ɍl���āA���R��b�Ă͘A���������ۂނ͂����Ȃ��B�ł��A��c�Ƃ����̂͋��d�_�ɉ����ꂿ�Ⴄ���́B��͎~�ޖ����u�f�ŋ��ہv��ł��o������Ȃ������B���݂Ɂu���̌쎝�v�Ƃ͓V�c���S�̓��{���̌`�Ԃ����A�Ƃ������Ƃ��B
�@1945�N7��26���A�u�|�c�_���錾�v��������ꂽ�B�A�����̕āi�g���[�}���哝�́j�A�p�i�`���[�`���j�A���i�Ӊ�Α��j�����{�ɑ��āg�������~���h�𑣂��錾���B���������؎͂������܊t�c���J���t���̈ӌ����B�O����b�̈ӌ��́u���̌쎝�v�����̏����t����B���R��b�́u���̌쎝�͓�����O�B��̂͏��K�͒Z���ԁB�R��͓̂��{�̎�ŁB�푈�ƍߐl�ٔ������{�ōs���v�̏���������Ȃ��B�펯�I�ɍl���āA���R��b�Ă͘A���������ۂނ͂����Ȃ��B�ł��A��c�Ƃ����̂͋��d�_�ɉ����ꂿ�Ⴄ���́B��͎~�ޖ����u�f�ŋ��ہv��ł��o������Ȃ������B���݂Ɂu���̌쎝�v�Ƃ͓V�c���S�̓��{���̌`�Ԃ����A�Ƃ������Ƃ��B�@���ʁA�A�����J�͊�����������̌��������̑�`�������B�����āA���s�����B�����A���̐��{��7��26���̎��_�Łu�|�c�_���錾�v��������Ă���Ό��������͂Ȃ������͂��A������Ȃ����Ȃ�������͎�ȍɑ��Ƃ��Ă������Ȃ��̂��A�ȂǂƂ������j�ς����邪�A���Ӗ����B��t�͂���ł��ł���B�����̓��{�ł́A�܂��s�\�������A��Jiiji�͎v���B���ꂪ�ł���̂͐_�l�������Ȃ��I
�@��͂��̌���u�|�c�_���錾�v��������Ɍ����ɗ����������A����8��15���̋ʉ������`�I���ɂ��������B6���ɍL���A9���ɒ���ւ̌��������A�\�A�̎Q��A�̂��Ƃ������B�V�c�́u���Ɗ̒_���Ƃ炵����ł��������炱���o�����̂��v�Ɨ�؎��]�����B
�@�t�c�Ŕ������������R��b�E����Ҋ�͌R�̈ӂ�ʂ��Ȃ������Ƃ��Ď������Ă���B�܂��A�e�n�ɎU����Ă���300���̌R���̒��ɂ́A�g�ꉭ���ʍӁh������œV�c�̈ӎv�ɏ]��Ȃ����m�����Ȃ��炸�����B���ƂقǍ��l�ɐ푈���I��点��͓̂����B
�@Ray�����A����őO�҂��I���܂��B����͌�ҁu�����{�̕����v�ɂ��Ă��b���悤�B
2015.08.10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��10�`���[���_�[�ł͖�肠��I
 �@���[���_�[�ł̓C�M���X�̉��y�w�҃��`���[�h�E���[���_�[��������u���c���N�v�����ł̈�B�ނ̈Ӑ}�͔[�c�@���g�I�����̓O��폜�ł���B���̔ł��g�����ŏ��̘^���́A�����Ҏ��g�̊ďC�ɂ��1983�N9���ɍs��ꂽ�B���t�̓z�O�E�b�h�w���G���V�F���g�����nj��y�c�B������CD�ɂ́A�Έ�G���̍\���ɂ�������t���Ă���B�����ɂ́A���N�C�G����Ȃ̌o�܁A�W���X�}�C���[�ł̖��_�A���[���_�[�ł̓����A���[���_�[���g�̃R���Z�v�g���A�Έ䎁�̌����Ɖ��t�]�ȂǁA���肾������ŏ[���������e�ƂȂ��Ă���B
�@�ł͂���CD�Ɖ�����ɂ��������āA���[���_�[�ł�ǂ݉����Ă䂫�����B
�@���[���_�[�ł̓C�M���X�̉��y�w�҃��`���[�h�E���[���_�[��������u���c���N�v�����ł̈�B�ނ̈Ӑ}�͔[�c�@���g�I�����̓O��폜�ł���B���̔ł��g�����ŏ��̘^���́A�����Ҏ��g�̊ďC�ɂ��1983�N9���ɍs��ꂽ�B���t�̓z�O�E�b�h�w���G���V�F���g�����nj��y�c�B������CD�ɂ́A�Έ�G���̍\���ɂ�������t���Ă���B�����ɂ́A���N�C�G����Ȃ̌o�܁A�W���X�}�C���[�ł̖��_�A���[���_�[�ł̓����A���[���_�[���g�̃R���Z�v�g���A�Έ䎁�̌����Ɖ��t�]�ȂǁA���肾������ŏ[���������e�ƂȂ��Ă���B
�@�ł͂���CD�Ɖ�����ɂ��������āA���[���_�[�ł�ǂ݉����Ă䂫�����B�@�܂��̓��[���_�[�̉����R���Z�v�g����B�Έ�G���̕��͂ł���B
�z�O�E�b�h�͓��{�ɗ����Ƃ��̍u���i1984�N2���j�ŁA�����̍s���Ă����Ƃ��G��̉��ꂨ�Ƃ��ɂ��Ƃ��Ă����B�����u�����g�̗L���ȊG��u��x�v�́A�Â���̊G���Ƃ���M�����Ă������A����̉�������Ă݂��疾�邢�^���̊G�������Ƃ����A���Ȃ����b�����Ă������A����ނ����`���[�h�E���[���_�[�̊v���I�ȁg�����Ƀ��[�c�@���g�̗v�f�����Ɋ�Â����h�u���N�C�G���v����グ���̂��A��������̎v�l�Ɋ�Â��Ă̂��Ƃł��낤�B�]������ĐM�����Ă������[�c�@���g���𐳂��A�����Ȏp�ɖ߂��A���̈̑�ȍ�Ƃ�����ł���B���Ȃ��Ƃ�����̘^���ɂ́A��M�����W���X�}�C���[�̜��ӂ�~�X�̕����́A�قƂ�Ǐ�����Ă���Ƃ����ėǂ����낤�B���ؓI�Ȍ��������̑�Ȑ��ʂł���B
 �@����͎w���҃z�O�E�b�h�̘b�����A�u��������v�Ƃ̕\��������̂ŁA���[���_�[�̃R���Z�v�g�ƒu�������Ă��������낤�B�܂��A��ǂ��ĐΈ䎁�����[���_�[�ł̎^���҂Ɣ���B
�@����͎w���҃z�O�E�b�h�̘b�����A�u��������v�Ƃ̕\��������̂ŁA���[���_�[�̃R���Z�v�g�ƒu�������Ă��������낤�B�܂��A��ǂ��ĐΈ䎁�����[���_�[�ł̎^���҂Ɣ���B�@�`���̈�b�́u�����u�����g�́w��x�x�͒����Ԗ��`�����G��ƍl�����Ă����B�Ƃ��낪20���I�ɓ���A����Ƃ���A�\�ʂ̃j�X�̗ɂ�鍕���݂����A����`�����G��Ɣ��������v�Ƃ����L���Ȃ��́B���̗Ⴆ�͍����I�u��x�v�^���̎p�̓��[�c�@���g�A�����j�X�̍����݂̓W���X�}�C���[�Ƃ������ƂɂȂ�B�W���X�}�C���[�͗��������L�Q�҂Ŏ����͐^�������N���鐳�`�̖����H ���ꂶ��W���X�}�C���[�����z�I �Ȃ�Ύ������[���_�[�̉R��\���Ă��B
�@���[���_�[�ł̓����͓�B�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v���o�b�T���Ǝa��̂Ă����ƁB�u�܂̓��v�ɃA�[�����t�[�K��Y�t�������ƁB�ł͏���ǂ��Ē��g�����Ă݂悤�B
�i�P�j�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v���J�b�g
�@���[���_�[�̍�Ƃ́u���N�C�G���`���v�̔r������n�܂�B
���̓`���̂悭�m��ꂽ�����́A���łɎ��̕a�ɖ`���ꂽ���[�c�@���g���A�����[�b�N���݂̎g�������̐�����̎g�҂Ǝv�����݁A�����ɂȂ��Ďd���ɂ�����A�����̂��߂̃��N�C�G�����������Ƃ��A�����Ȓ�q�̃W���X�}�C���[�ɁA�r���Ŏ��������ꍇ�̎c��̎d�グ���ɂ��āA�ڍׂȎw����^�����A�Ȃǂƌ���Ă����B���A�W���X�}�C���[�̎d���ɂ́A���[�c�@���g�̈Ӑ}�����f���Ă��Ȃ��Ƃ�����A����ł������̔ł�F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�@���[���_�[�͖��炩�ɁA�g�W���X�}�C���[�̎d���ɂ̓��[�c�@���g�̈Ӑ}�����f���Ă��Ȃ��h�ƍl���Ă���B�ނ͂��̍������A1791�N10��8�|9���A���[�c�@���g���o�[�f���ŗ×{���̃R���X�^���c�F�Ɉ��Ă��莆�����p���Ă��������B
�ȏ�̎莆�́A�ǂ����Ă��A���̉e�Ɏ�����ċ����Ă���l�Ԃ̂��̂ł͂Ȃ��B�܂��A�ǂ����߂��Ă݂Ă��A���̂Ƃ��W���X�}�C���[�̓E�B�[���ɂ͂��炸�A�o�[�f���ɂ����͖̂��炩�ł���B�ƂȂ�ƁA���N�C�G���̑��k�Ȃǂ͂ł��Ȃ����ƂɂȂ�B���ۂ�1791�N�̎莆�����Ă䂭�ƁA�W���X�}�C���[�͉��ɂ킽���ăE�B�[���𗯎�ɂ��Ă���A�����Ȃ�ƃ��[�c�@���g�͂��̒�q�ɁA1��2�������b�X�������Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���Ƌ^�������Ȃ�B�@���̃��[���_�[�̌����͂������Ȃ��̂��B�܂��́A���[�c�@���g�̐��i��c�����Ă��Ȃ��B���[�c�@���g���g�����̏Ɨ����Ȏ莆�������h���Ƃ́A�悭���邱�ƁB�Ⴆ�A1778�N7��3���p�����畃�Ɉ��Ă��莆�B���ۂɂ͖S���Ȃ��Ă����̂��Ƃ��d�a�Ƃ��ē`���A�w�b���ς��܂��x�Ƃ��āA����V���t�H�j�[�i��31�ԁu�p�������ȁvK297�j�ւ̑劅�т����X�Ƃ��ď����Ă���̂ł���B
�@����ɁA���̊��ԁA�W���X�}�C���[���E�B�[���ɂ��Ȃ���������Ƃ����āA1��2���������b�X�����Ԃ����Ȃ������Ƃ́A�]��ɒZ���I���߂ł͂���܂����B
�@���Ƃ������ł������ɂ��Ă��A���[�c�@���g�̓V�˂������Ă���A�`����1��������Ύ������B�W���X�}�C���[�͂��̂��ƁA�i�R���X�^���c�F�Ƌ��Ɂj�E�B�[���ɖ߂��Ă���̂ł��邩��A���Ԃ͏\��������قǂ������͂��ł���B
�@���[���_�[�́A�ޓƎ��̌����ɂ��A�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̓�̊y�͂��J�b�g�����B�Ƃ��낪�����������́u�_�̎q�r�v�͎c�����B����͖����ł́H �ނ̌������͂����ł���B
�Ƃ��낪�u�_�̎q�r�v�́A����قNJm�M�������ď��O���Ă��܂����Ƃ��ł��Ȃ��B�o�X���܂߂Ă̎l�����́A1775�N�ɏ����ꂽ�n�����̃~�TK220�u���̃~�T�v�̃O���[���A�̕����ɂ��Ȃ蕄������Ƃ��낪����B�܂����Ƃ̂ق��ɂ������O���[���A���������悤�ȕ������o�Ă���B�����̌��ۂ͈�̂ǂ������Ӗ������̂��낤���B�W���X�}�C���[�����[�c�@���g�̍�i���I�ɐ蔲���ē\�荇�킹�g�������[�c�@���g�h����낤�Ƃ����̂��낤���B����Ƃ��A�R���X�^���c�F�������āA�W���X�}�C���[�ɓn�����Ƃ��������U�炵�̎��̓��e���A�����Ō��������̂��낤���B�@���̕����́u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v���u�^���̃��[�c�@���g�̍��Ղ͂Ȃ��A�]���Ċ��S�ɃW���X�}�C���[�̂��̂ł��邱�Ƃ́A���ɂƂ��Ă͑S���^���]�n�̂Ȃ����̂ł���v�ƒf�������Ƃ̕��͂ł���B�g���ՂȂ��h�ƒf�肵�Ă��邪�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̎�������u�o���o���E�v���C���[�̂��߂̗��K���vK453b����̈��p�ł��邱�Ƃ͔F�߂Ă���B�Ȃ閵���I
�@�u�_�̎q�r�v�ɂ��p���f�B�[���ۂ�F�߂Ă���̂�����A�B��u�T���N�g�D�X�v�������p�Ȃ��ƍl��������s���R�B���͂�����u�ǎ��@�~�T�v����̈��p�ƍl���Ă��邪�i�N�����m5.15�j�B
�@���[���_�[���A�u�T���N�g�D�X�v�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�u�_�̎q�r�v�̂����A�O��҂��J�b�g���āu�_�̎q�r�v�����c�����R���B���ł���B���[�c�@���g�̍��Չ]�X�ƌ����Ȃ�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v���J�b�g���闝�R���Ȃ��B�I�[�P�X�g���[�V�����̖��Ȃ璼�������B��҂��J�b�g������c���B�����ɘ_���̈�ѐ����Ȃ��B�ǂ�Ȍ`�ł���200�N�����݂��Ă�����i������̐l�Ԃ���̂Ă�ɂ́A�����ȍ����Ɗm�M���s���ł���B�ނ̍�Ƃɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�n��҂ւ̖`���A�͌���������������Ȃ����A�����Ȃ��_���I�Ȕł����͔F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�Q�j�A�[������t�[�K
�@���[���_�[�ł̂�����̓����́A�A�[������t�[�K�ł���B�����1962�N�A�x�����������}���قŔ������ꂽ���[�c�@���g���M16���߂̃t�[�K�̃X�P�b�`�����[�ł���B���ꂪ�u�܂̓��v����߂�����t�[�K�̃X�P�b�`�Ɠ��肳�ꂽ�̂́A�����ܐ����Ɂu���N�C�G���v�́u�݂��̑剤�v�̒f�͂�������Ă������ƂȂǂɂ��B
�@���[���_�[�ł����ɏo���̂�1980�N��B�X�P�b�`��������20�]�N�B���̒m�����A���ꂪ�u���c���N�v�ŏ��̃A�[�����E�t�[�K�}���łł���B
�@���[���_�[���A�u�܂̓��v�ɂ����āA�W���X�}�C���[����������9���ߖڂ����S�ʃJ�b�g���A�S���V������蒼������ɃA�[������t�[�K���Ȃ����̂́A�ނ̃R���Z�v�g�ɓK�������̂ŁA���̑[�u�ɂ͈�ѐ�������B���������͒��g�ł���B
�@�ނ͂��̏������������Ɂu���Տ��v�̐��������p���Ă��邪�A�����ɂ����Ė`������ڂ���Ӗ����ǂ��ɂ���̂��H�S�������Ă��A�I�Ȃł̍ēx�̈��p���ǂ���������̂��H�ނ͏I�ȁu���̔q�̏��v�����̂܂c���Ă���̂ł���B
�@���[���_�[�́u�A�[�����E�t�[�K�v�́A80���߂ɋy��Ƃ��钷��Ȃ��́B�Z�N�G���c�B�A���t�[�K�Œ��߂��͂Ȃ��͂Ȃ��i�~�q���G���E�n�C�h����2�́u���N�C�G���v�Ȃǁj���A�����̏@�����y�̓`���ł���A�Ƃ܂ł͂����Ȃ��B���[�c�@���g�����̂悤�ȃX�P�b�`���c�����Ƃ������Ƃ́A�A�[������t�[�K�Œ��߂邱�Ƃ���U�͖ژ_�A����͊m�����낤�B����must�Ȃ�A�X�P�b�`���W���X�}�C���[�ɓn�����͂����B�W���X�}�C���[�́A���ʁA�t�[�K�ɂ��Ȃ������̂�����A�X�P�b�`��j�������͂����B�t�̎w�������Ȃ������Ǝv��ꂽ���Ȃ�����ł���B�X�P�b�`���c���Ă����Ƃ������Ƃ́A���[�c�@���g���W���X�}�C���[�ɓn���Ȃ��������ƂɂȂ�B�n���Ȃ������̂�����must�ł͂Ȃ������B�������́A�r���Ń��[�c�@���g�̋C���ς�����B�t�[�K�łȂ��Ƃ��悢�I�H �Ƃ������ƂɂȂ�Ȃ����B
�@�܂��A����͐����ɉ߂��Ȃ��B�����A���͊m�M���Ă���B�A�[������t�[�K�̓��[�c�@���g��must�ł͂Ȃ������A�ƁB�Ȃ��Ȃ�A���́A���̕����Ƀt�[�K��u�����ƂɁA���o�I�ɓ���܂Ȃ����炾�B�W���X�}�C���[�łɂ�����t�[�K�y�͂́A2�u�L���G�v9�u��C�G�X��v10�u���Ȃ鐶�сv14�u���̔q�̏��v�ƕ��ԁB�����Ɂu�A�[�����E�t�[�K�v������ƁA8�|9�|10�ƃt�[�K���R�������ƂɂȂ�B�t�[�K�̈�ۂ͋���ł���B�H���C�����ۂ߂Ȃ��B������A���̓W���X�}�C���[�̓�Amen�I�~���x������B���̃V���v���Ȋ����I���ꂼ�W���X�}�C���[�̑M���A������[�c�@���g�̈Ӑ}�H
�@�ł́A����CD�A���������̕]���͂ǂ��������̂��H �u���R�[�h�|�p�v1984�N12�����ł́A��l�̑I�]�q�̂�����l�����E���Ă��邩��A�]���͂܂��܂��Ƃ������ƂɂȂ낤���B���̉��t�]�ɋ����͂Ȃ����A�������ɑ�ϋ����[���L�����ڂ��Ă����B��䏊�E�g�c�G�a�搶�i1913�|2012�j�̘A�ځu�����̈ꖇ�v�ł���B��ɍŌ�̒��߂��������B�O�i�ɉ��t�]�Ȃǂ�����Ă��邪�A���������Ă��������B
�i�t�^�j�g�c�G�a�搶�̕]�_
�S�Ȃ̌��т̃t�[�K�́A�W���X�}�C���[�̂��̂Ƃ���ė������A���[���_�[�́u�����{���Ȃ�A���̂ڂ���}�ɘr���グ�����̂��I�v�Ƃ�������̏����������Ă���B�ނɂ́A�����Ƀ��[�c�@���g�̕M����ؓ����ĂȂ��Ƃ͐M������Ȃ��̂��낤�B���������͊��������A�c���Ă��܂����B�@�j�āA�Ȃ邱�ƁI �F����A�������C�Â��ł��傤�B�搶����g�S�Ȃ̌��т̃t�[�K�h�Ƃ͏I�ȁu���̔q�̏��v�̃t�[�K�̂��ƁB�����2�u�L���G�v�����̂܂܌J��Ԃ������̂����烂�[�c�@���g�̐^�M�����B�W���X�}�C���[�̂��̂ł͂Ȃ��B�g���[�c�@���g�̕M����ؓ����ĂȂ��Ƃ͐M������Ȃ��h�]�X����Ȃ��A�܂��Ƀ��[�c�@���g�{�l�̎�ɂȂ��ΓI�^�������Ȃ̂ł��B����Ɂg���������A�c���Ă��܂����h�ł����āI �N���{�l�̐^�M���������܂����B
�@����Ȓ��펯����{�ō����]�_�ƂƂ������䏊���������Ȃ������I�I�M�����܂����I�H ����͂����A������ʂ�z���āA�������Ȃ��̂ł���܂��B
�@�ŁA���[���_�[�łł����H ��肠�肷���ł��B
���Q�l������
���[�c�@���g�u���N�C�G�� ��Z���vK626
�@�@�@�z�O�E�b�h�w���F�G���V�F���g�����nj��y�cCD �{�����
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626 �y���i�x�[�������C�^�[�Њ��j
�@�@�@���[�c�@���g���M�Ł@�A�C�u���[��M�Ł@�W���X�}�C���[�⊮��
2015.07.25 (�y) ���c���N�Ɏa�荞��9�`�����ς������o�C���[��
�@�u���c���N�v�ɂ̓W���X�}�C���[�ňȊO�ɗl�X�Ȕł����݂���B�����͂��ׂăW���X�}�C���[�ł̌��ׁi�H�j�����肷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B��������́A�����̔ł��W���X�}�C���[�łƂǂ��Ⴄ���̌��ɓ��肽���B��r����ϓ_�͓�B�I�[�P�X�g���[�V�����ʂƍ\���ʁB�I�[�P�X�g���[�V�����ɂ��ẮA�����������Ȃ���y�����r������������B����͊��ɒN��������Ă��邱�Ƃł���A���Ƃ��������Ȃ��B�����g�N�����m�h�I�ł͂Ȃ�����A�y�������āA�\���ʂ��d������B�@���グ��ł͂S�B�o�C���[�ŁA�����h���ŁA���[���_�[�ŁA�����B���ŁB�U�N���Ɖ]���āA�O��҂͂قڃI�[�P�X�g���[�V�����ʂɌ����A���҂͍\���ʏd���^�ł���B����͑O��҂����グ��B
���o�C���[�Ł�
 �@�t�����c�E�o�C���[�̓~�����w�����y��w�r�I���Ȃ̎�C�����B�R���M�E���E�A�E���E�����t�c�̃����o�[�ł�����B������1971�N�B�����t�c�ɂ��u�o�C���[�Łv�̘^����1974�N�ɍs��ꂽ�B
�@�t�����c�E�o�C���[�̓~�����w�����y��w�r�I���Ȃ̎�C�����B�R���M�E���E�A�E���E�����t�c�̃����o�[�ł�����B������1971�N�B�����t�c�ɂ��u�o�C���[�Łv�̘^����1974�N�ɍs��ꂽ�B�@�o�C���[�̈Ӑ}�͂���CD������̔ގ��g�̒��q�ɖ����ɋL����Ă���B
�@���[�c�@���g�̎����������Ɏ��o�����Ƃ���w�́i���̐V�ł͂���ȊO�̂��Ƃ͈Ӑ}���Ă��Ȃ��j�̂��߂ɁAF.X.�W���X�}�C���[�̌��т�Ⴍ���ς���悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ނ͂��̍�i���㐢�̂��߂ɉ��t�\�Ȃ��̂Ƃ����̂ł����āA���̂��Ƃ͂˂ɕς�邱�ƂȂ����̋~��҂Ɋ��ӂ���˂Ȃ�Ȃ��B�������Ȃ���ނ̕⊮�̌��ׂ��A�i�v�ɕs�ςȂ��̂Ƃ��Ă��܂Ă����ׂ��ł͂Ȃ��B�@�W���X�}�C���[�̌��т͂����ƕ]�����������ŁA�⊮�̌��ׂ͐����ׂ��Ƃ��Ă���B���ɂ܂Ƃ��ł���B�⊮�̌��ׂ́g�[�c�@���g�I�h�����ƌ�����������B���͈̔͂́A�قڃI�[�P�X�g���[�V�����Ɍ����Ă���A�A�[������t�[�K��t��������A�z�U���i�̒����𐳂�����͂��Ă��Ȃ��B
�@�ł́A�o�C���[�ł̉���_���W���X�}�C���[�łƔ�r���Ȃ��烉���_���ɒH���Ă݂悤�B�u�o�C���[�Łv�Q�lCD�́A�l���B���E�}���i�[�w���F�A�J�f�~�[�����nj��y�c�Ձi1977�N�^���j�Ƃ����B
��2�u�L���G�v
�@�I������2���ߖڂւ̃A�E�t�E�^�N�g�ɁA�e�B���p�j�[�ƃg�����y�b�g�ɂ���������B����́A�����ߑO����؊ǂƓ��ꃊ�Y��������ł����e�B���p�j�[���g�����y�b�g���A���̂��ׂĂ̊y�킪���ꃊ�Y���Ŗ��Ă���̂ɁA���������������Ă��邱�Ƃ̕s���R����⊮�������̂��낤�B�W���X�}�C���[�̃E�b�J���E�~�X�Ɠǂ��I�H
��5�u�݂��̑剤�v
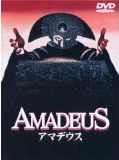 �@�`��2���ځA�u�NJy��ɂ��g�u���[�h�Ƃ��������̎�v���J�b�g�B�����̓W���X�}�C���[�Ő���̈�ۓI�����B�Ȃ�A���̃J�b�g�̓o�C���[�ł̖ڋʁI�H �ߏ�I���ʂ̐����B�ς��̓o�[���X�^�C���Ձi1988�^���j�ŁA�����ɃI���K���̋��t������B���A����͂����ɂ����ˁI �ߏ������l����A����������l������B���̒��F�X�ł���B
�l���B���E�}���i�[�́u���c���N�v���K�^���̓o�C���[�łł���B�ނ́A�܂��A�f��u�A�}�f�E�X�v�i1984�N����j�ł́A���y�ēƉ��t��S�����Ă���B���̉f��̒��Łu�݂��̑剤�v���|���邪�A����͊NJy��̍����̎����B�Ȃ�ƃW���X�}�C���[�ŁI�I ���K�^���ł̓o�C���[�ł��̗p���Ă���}���i�[���A�f��ł̓W���X�}�C���[�ł�I�����Ă���B�f��ɂ͔Z���ȃW���X�}�C���[�ł������Ɣ��f�����̂��낤���B�����[�������ł���B
�@�`��2���ځA�u�NJy��ɂ��g�u���[�h�Ƃ��������̎�v���J�b�g�B�����̓W���X�}�C���[�Ő���̈�ۓI�����B�Ȃ�A���̃J�b�g�̓o�C���[�ł̖ڋʁI�H �ߏ�I���ʂ̐����B�ς��̓o�[���X�^�C���Ձi1988�^���j�ŁA�����ɃI���K���̋��t������B���A����͂����ɂ����ˁI �ߏ������l����A����������l������B���̒��F�X�ł���B
�l���B���E�}���i�[�́u���c���N�v���K�^���̓o�C���[�łł���B�ނ́A�܂��A�f��u�A�}�f�E�X�v�i1984�N����j�ł́A���y�ēƉ��t��S�����Ă���B���̉f��̒��Łu�݂��̑剤�v���|���邪�A����͊NJy��̍����̎����B�Ȃ�ƃW���X�}�C���[�ŁI�I ���K�^���ł̓o�C���[�ł��̗p���Ă���}���i�[���A�f��ł̓W���X�}�C���[�ł�I�����Ă���B�f��ɂ͔Z���ȃW���X�}�C���[�ł������Ɣ��f�����̂��낤���B�����[�������ł���B��7�u���ꂵ�ҁv
�@�`�������5���߁A�P�A�R���ځu�e�B���p�j�[�ƃg�����y�b�g�̍����̎�v���J�b�g�B�S�̓I�Ƀg�����{�[�����`�コ���k������B�ߏ薡�t���̐����ł���B
�@�������f��u�A�}�f�E�X�v�ƑΔ䂷��Ɩʔ����B�a���̃��[�c�@���g���A�T���G���Ɏ��ׂ��Ɍ��`���Ŋy�������������ʂ̉��y�́u���ꂵ�ҁv�B���y�A�t�@�S�b�g�ƃg�����{�[���A�e�B���p�j�[�ƃg�����y�b�g�A���y��ȂǁA�����ł��A���ɐ��m�ɃW���X�}�C���[�ł��Ȃ����Ă���̂ł���B�u���ꂵ�ҁv�Ń��[�c�@���g���������̂́A���y�Ɩ؊ǁA�ጷ�Ƒ�1���@�C�I�����܂łȂ̂ŁA�f��̕`�ʂ͎j���I�ɂ͊ԈႢ�����A���_�T���G���ɏ�����点��̂��f��Ȃ�ł͂̃t�B�N�V�������B���t����͖��_�}���i�[���A�J�f�~�[�����ǁB�O���Ɠ����p���h�N�X�������ɂ���B����Ȋp�x����f��Ɖ��y��Δ䂵�Č���̂��ꋻ�ł���B
��8�u���N�����T�v�̍����p�[�g�̉���
�@��24����3���ڂ�4���ځA�e�m�[���̏㏸���`���J�b�g�B�僁���̃\�v���m�ƃo�X�����~���`�Ȃ̂Łi�A���g�͋x�~�j�A�g�e�m�[�������㏸�h�Ƀo�C���[�͈�a�����o�����̂����B���l�ɂ͍��ׂȂ��Ƃ��{�l�ɂƂ��Ă͌������Ȃ��d�厖�H �̎��̗F�l�f�B���N�^�[�ɂ�����ȃ^�C�v�������悤�ȁB
��11�u�z�U���i�v�����̌J��Ԃ�
�@�I�����Łgin excelsis�h���J��Ԃ����Ƃɂ��4���߂�lj����Ă���B�z�U���i�̋K�͂̕n�コ�������ł������������Ӑ}���B���[�c�@���g�̑��̊y�Ȃł��悭���鎖��Ƃ̂��ƁB����́A�V���v���œK�ȑ[�u�Ƃ�����B�������A���̌`���̂����̂̓o�C���[��2�ł���ł���B
�@�ȏオ�A��r�I������̍��ق��F�m���₷�������ł���B���̑��ɂ��Ă͎�L�̗��R�ɂ�芄�������Ă��������B
�@�R���M�E���E�A�E���E����CD�̉�����ɁA������ƋC�ɂȂ镔��������B��≡���Ɉ��邪�G��Ă��������B���͍͂����ގ��Ƃ���B
�u�܂̓��v����߂�����A�[�����ɂ��I�����]����⊴���I�Ƀs�A�m�ŏI������̂ɑ��āA�o�C���[�łł̓t�H���e�ŏj�ՓI�ɏI���̂ł����āA���̕����ʍ��ŐG�ꂽ�悤�Ȃ��̋Ȃ̐��_�ɂӂ��킵�����Ƃ͈�ڗđR�ł���B�@�����f�������ƌ��������Ȃ�̂��g�N�����m�h���_�B�g�]���h���g�W���X�}�C���[�Łh�ƒu���������邩��A�����W���X�}�C���[�ł̒�ԉ��t�Łg�A�[�����h�̕������Ă݂��B���ʂ́A�����^�[�A���q�^�[�A�J�������A�x�[�����t�H���e�B�K�[�f�B�i�[�A�R���{�A�W�����[�j�̓��]�E�t�H���e�B�ǂ��ɂ��g�����I�ȃs�A�m�h�͑��݂��Ȃ������B�v���ɂ���͔ł̖��ł͂Ȃ��A���߂̖��ł͂Ȃ��낤���B�������͕ʍ��Łg�����i��3�ȁ|��8�ȁj�͍Ō�̐R���ɑ���،h�Ƌ~�������߂�F����̂����́h�Əq�ׂĂ��邩��g�t�H���e�ŏj�ՓI�ɏI���h�̂����������Ɖ��߂����̂��낤�B�͋����I��邩�A�����I�ɏI��邩�A�D�����I��邩�B���߂͊e�l�e�l�B�Ȃ��A�W���X�}�C���[�ł̊y���ɂ̓s�A�m�\�L�͂Ȃ��B
�@�b��{��ɖ߂����B�o�C���[�͉�����̒��ŁA�u���̔ł͂����炳�܂Ȍ�T���炱�̍�i����߁A���[�c�@���g�̌����i�̉������E�������悤�ɂ��\�Ȍ���I�[�P�X�g���p�[�g�̒��֎�������ŁA���[�c�@���g�̑����́����������A���̌��h�肩�������邱�Ƃ�_���Ƃ��Ă���v�Ƃ��q�ׂĂ���B
�@�o�C���[�͂܂��������̖ړI�̂��߂ɃI�[�P�X�g���[�V���������肵���B�u�N�����m5.15�v�ł��w�E�����Ƃ���A�W���X�}�C���[�͎��Ȍ����~�������B������ޓƓ��̖����o��B�o�C���[�́A���̃W���X�}�C���[���L�̌����ς��킬���Ƃ��āA���[�c�@���g�{���̗l���ɋ߂Â��悤�Ƃ����̂ł���B
�@�m���Ɂu�o�C���[�Łv�́A�����I�ɂ́A�i�W���X�}�C���[�łɔ�ׁj�X�b�L���ƕ�������B���ꂪ���[�c�@���g�{���̋����Ƃ����������������Ȃ��Ǝv���B�����A�W���X�}�C���[�ł̌��I�Z�������̂Ă������B�g�f��ɂ͂��ꂪ�����Ă���h�Ɠ�����A���y�ē��R�`����I�̂��낤�B���y�ɋ��߂���̂͊����ł���B�S�ɂǂ��������ł���B�����͗����Ƃ��ē��܂�����ŁA�C�����Œ��������̂ł���B
�������h���Ł�
�@�����ȉ��y�w��H.C.���r���Y�E�����h����1989�N�ɕҎ[�����B�R���Z�v�g�́u��M��Ƃ̓��[�c�@���g�Ɠ�����̐l�����̕����K���Ă���ƐM����v�Ƃ������́B����1�u���Տ��v�̓��[�c�@���g�A2�u�L���G�v�̓��[�c�@���g�ƃt���C�V���e�b�g���[�ƃW���X�}�C���[�B3�u�{��̓��v����7�u���ꂵ�ҁv�̓A�C�u���[�A8�u�܂̓��v����Ō�܂ł̓W���X�}�C���[�Ƃ��������̊W�߃X�^�C���ł���B
 �@���܂茟�ɒl���Ȃ����A�W���X�}�C���[�łƂ̖ڗ��������ق��y���L���Ă������B�u�����h���Łv�Q�lCD�́A���@�C���w���F�^�[�t�F�����W�[�N�E�o���b�N�nj��y�c�ՂƂ����B
�@���܂茟�ɒl���Ȃ����A�W���X�}�C���[�łƂ̖ڗ��������ق��y���L���Ă������B�u�����h���Łv�Q�lCD�́A���@�C���w���F�^�[�t�F�����W�[�N�E�o���b�N�nj��y�c�ՂƂ����B��3�u�{��̓��v
�@��2���ߖڂ̃g�����y�b�g�̃��Y���B�e�B���p�j�[�ƕʃ��Y���̂������ꖡ�ɖR��������������B
��5�u�݂��̑剤�v
�@��2���ߖ؊ǂ́u�u���[�v���Ȃ��͓̂��R���낤�B
��7�u���ꂵ�ҁv
�@�`����5���߁u�e�B���p�j�[�ƃg�����y�b�g�̍����̎�v��2�A4���ڂɂ���B�W���X�}�C���[�ł�1�A3���ڂƂ͊ԋt�ł���B
�@����Ɍ����A�����h���łƂ́g�Ō�܂ł�萋�����W���X�}�C���[�ɓr���œ����o�����A�C�u���[���@�B�I�ɍ������h�����̂��́B�����I�ɂ����A�֓����Z�����Ɋ��������������Ȃ����݂��Ă���`�Ƃł����������B�ƂĂ��A�����u���[�c�@���g�Ō�̔N�v�i�������_�Ёj���������l�̎d�ƂƂ͎v���Ȃ��B��̂ǂ��ɕҎ҂Ƃ��Ă̈ӎu������̂��B�ǂ��ɈӖ�������̂��B�B�ꂠ��Ƃ���A���[�[�t�E�A�C�u���[�̎d�������̖ڂ������Ƃ������Ƃ��炢���낤���B
���Q�l������
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z���vK626 �y���i�x�[�������C�^�[�Њ��j
�@�@���[�c�@���g���M�Ł@�A�C�u���[��M�Ł@�W���X�}�C���[�⊮��
���[�c�@���g�u���N�C�G�� ��Z���vK626
�@�@�V���~�b�g���K�[�f���w���F�R���M�E���E�A�E���E���nj��y�cCD �{�����
�@�@�}���i�[�w���F�A�J�f�~�[�����nj��y�cCD
�@�@���@�C���w���F�^�[�t�F�����W�[�N�E�o���b�N�nj��y�cCD
2015.07.10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��8�`���ׂĂ̓��[�c�@���g�̎w��
�@�u���c���N�v�ɂ�����W���X�}�C���[�̕�M��Ƃ̌��́A�O�͂܂łŁA��12�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�܂ł����������B���̒��ŁA�W���X�}�C���[�ő�̎��s��11�u�T���N�g�D�X�v��12�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒��ɑ��݂��Ă��邱�ƁA���{�̕]�_�E�ɂ͂��̔F�����Ȃ��Ɠ����w�E�����B���Ƃ͓�͂��c���̂݁B13�u�_�̎q�r�v��14�u���̔q�̏��v�ł���B�@�m���ɁA���y�E�ɂ́A�W���X�}�C���[�̕�M��Ƃ��g���[�c�@���g�̈ӎv�ɔ����Ă���h�Ȃǂ̗��R�Ő��F���Ȃ�����������B�Ȃ�u�����ɂ̓��[�c�@���g�̈ӎv������B�w��������v���Ƃ��i�ؖ��Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ă��j�������邱�Ƃ��ł���A�W���X�}�C���[�łւ̒����͘a�炮�͂����A�Ƃ̎v���������Ă���Ă����B���̓W���X�}�C���[�̌��т��m�肵�����̂ł���B�N���V�b�N���́A�T���S�Ȃ��`����`�Ƃ�����Ȃ����ЂƂ��Ɉ�𓊂������̂ł���B
�@����e���r�ō쎌�ƁE���{�����A���g�̃V���[�x���g�u�~�̗��v�a��Ɋւ���N���V�b�N�E�̔����ɂ��āA����Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ����B�u�N���V�b�N�̈̂��搶�ŁA�w�~�̗��x��60�Ή߂��Ȃ���Ή̂��Ȃ��ƌ����l�����邯�ǁA����͂���������ˁB������l��31�ŁA���ɔj��Ď��o�̗�������Ƃ������e�ł���B�ނ���60�߂�����̂��Ȃ���ˁv�B�ꗝ�A���I ���ƂقǍ��l�ɁA�ʐ��E�̐l�����͏_��ɕ������l���邵�A�N���V�b�N�E�͂Ȃɂ��̂����m��Ȃ����A�g���`���J���Ȍ��Ђ��܂���ʂ��Ă���̂ł���B
�@�Ƃ͂����A����́A�Ǝ��̔����͉����Ȃ������B�����A���[�c�@���g�w���̍��Ղ�������x�T�����Ă邱�Ƃ��o�����B�{�͂ł͂�����������p����Ɏ~�߂����B
��13�u�_�̎q�r�v��
�@��13�Ȃ́u�_�̎q�r�vAgnus dei�ł���B�g���̍߂������������_�̎q�r �ނ�Ɉ�����^�����܂��h�Ɖ̂��B�W���X�}�C���[�̖`���̃����f�B�ɂ��āA���c�a�M���̓��@�C����CD�̃��C�i�[�m�[�c�̒��ł����q�ׂĂ���B

�`����肪1775�N��Ȃ̃~�T�ȃn����K220�́u�O���[���A�v�ɂ����铯��̎��̊y�߂ɍ������Ă���̂͋��R�ł��낤���B�@�u�~�T�� �n���� K220�v�́A���[�c�@���g20�ΑO��̍�i�ŁA�ʏ́u���̃~�T�v�Ƃ����Ă���B�������̕�������ׂĂ݂�ƁA�m���ɍ������Ă���B�������A�Ή������������Ă��āA�u���̃~�T�v�̕��̉̎������� qui tollis peccata peccata mundi�ł���̂ɑ��u���N�C�G���v�ł�Agnus dei,qui tollis peccata mundi�ƂȂ��Ă���B�u���R�ł��낤���v�Ƃ̈��c�����ɂ��ẮA�u���̍����Ԃ�͋��R�ł͂Ȃ����[�c�@���g�̎w���ƍl����������R�ł���v�ƌ��_�������B
�@�f�b�J�̃v���f���[�T�[�A�G���b�N�E�X�~�X�́A�K�[�f�B�i�[�Ղ̃��C�i�[�m�[�c�ŁA����ȕ��ɏq�ׂĂ���B
�u�I�[�X�g���A���y����v��1987�N1�����ɂ́A�u�T���N�g�D�X�v�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�u�_�̎q�r�v��3�̏͂ɂ����āA�A�E�g���C�������Ƃ͂����A���[�c�@���g�̍�Ȃ̉\������������n�����[�g�E�N���[�l�X�̕��͂��f�ڂ��Ă���B����ɂ��ƃS�Z�b�N�́u���N�C�G���v�i�܂������Ȃ����[�c�@���g�͂��̋Ȃ�m���Ă����Ǝv����j�́A�������̓_�Ń��[�c�@���g�́u���N�C�G���v�Ɏ��Ă���A����ɂ��ꂪ�u�_�̎q�r�v�Ɏ��Ă���̂ł���i���炩�ɃW���X�}�C���[�͂��̍���Ȏd�����ʂ�����ŁA�S�Z�b�N�̍�i���Q�l�ɂ����ƍl������j�B�@�����S�Z�b�N�u���N�C�G���v��CD�����B�S�Z�b�N�i1734�|1829�j�Ƃ����A�����������w���̂Ƃ����y�̎��Ԃŋ��ނƂȂ������́u�K���H�b�g�v�̍�҂ł���B�傻�������������O����������ł������̂ł���B���āA�����̌��ʂ́H
�@�c�O�Ȃ���A���̃n�����[�g�E�N���[�l�X�̕��͂����p�����G���b�N�E�X�~�X���́A�܂������̌����O��Ƃ��킴��Ȃ��B�g�������̓_�Ŏ��Ă���h�Ƃ������A�ǂ������Ă���̂��낤���H ��̃S�Z�b�N�́u���N�C�G���v�ɂ́u�T���N�g�D�X�v�͂��邪�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�͂Ȃ��A�u�z�U���i�v�����݂��Ȃ��B�u�_�̎q�r�v��1���\�R�\�R�̂��Ȃ菬�K�͂Ȋy�͂ŁA���͎��Ă������Ȃ��B���������ăS�Z�b�N�ɂ͕����́u���N�C�G���v������̂��H�Ǝv���u�N���V�b�N���y��i���T�v�i�O�ȓ��j������s���B���_�͓�A�Nj��͕s�v�Ƃ����Ă��������B
�@�����͂ЂƂ܂��A�u���̃~�T�vK220�Ƃ̊֘A�������o�������Ƃł悵�Ƃ��悤�B
��14�u���̔q�̏��v��
�@����͂���������v���Ȃ��B1�u���Տ��v��19���ߖځA���̑O�t����u�_���^������ɂӂ��킵���̓V�I���Ȃ�vTe decret hymnus Deus in Sion �ƃ\�v���m�E�\�������镔������Ō�܂ł�30���߁B2�u�L���G�v�̑S52���߁B���v82���߂̉��y�����̂܂�14�u���̔q�̏��v�ɓ��Ă͂߂��B
�@�R���X�^���c�F�́u������������[�c�@���g�́A�W���X�}�C���[��T��ɌĂсA�������̍�i����������O�Ɏ���������A�`���ɏ������t�[�K���J��Ԃ����ƁB�܂����̕����Ɋւ��āA���łɃX�P�b�`�������̂��A�ǂ��ɂǂ̂悤�ɓ��Ă�ׂ����A���w�������v�Əq�����Ă���B���̒��́g�`���ɏ������t�[�K���J��Ԃ����Ɓh�Ƃ́A�g14�w���̔q�̏��x�ł�2�u�L���G�v�̃t�[�K���J��Ԃ��ׂ��h�Ƃ������[�c�@���g�̎w���ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�����ԋ߂ɂ������[�c�@���g���A�Ō�ɂ��̂悤�Ȏw�����������͎̂��ɋ����[���B�~�T�Ȃ̍ŏI�y�͂̉��y��ȓ��ł̊��g�p�y�͂��\�m�}�}���ěƂ߂�Ƃ����̂́A�����̊��K�Ƃ��Ă͒��������Ƃł͂Ȃ��Ƃ����B���̎�@����ʂɃp���f�B�[�i���p�j�ƌĂԂ��A�g�߂Ȏ���Ƃ��Ă�J.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v������B���̋Ȃ́A��ҍŌ�̍�i�Ƃ����_�Łu���c���N�v�Ƌ��ʂ���B�o�b�n�����̖����u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�i���ы`���� �t�H�Ёj�ɂ͂�������B

�o�b�n������\�����u���Z���~�T�ȁv����Ȃ��Ă������Ƃ́A�������ɍl�����邱�Ƃł���E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E���̂悤�ɁA�u���Z���~�T�ȁv�̍�Ȓ��Ɏ���\�����Ă����ł��낤�o�b�n�̐S���I�́A�u���N�C�G���v�Ǝ��g���[�c�@���g�̂���Ɣ�r�ł��悤�B�������A�܂��Ⴂ�A����̋N���̌��������[�c�@���g�����ƌ��I�ȑΖʂ������̂ɑ��A�V��̃o�b�n�̏ꍇ�́A���ɑ���o�傪���łɏo���Ă�����������Ȃ��B�@�u�~�T�� ���Z���v�Ɓu���N�C�G���v�B��̈��Ɏ��g�e�X�̑��ȉƂ̊���̈Ⴂ���ǂݎ��Ėʔ����B
�@���������A���̎�@���p���f�B�[�ɂ��āA�X�Ȃ�l�@��i�߂Ă݂悤�B�Q�l���͓������u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�ł���B
�@�u�~�T�� ���Z���v�̍ŏI�ȁu���ɕ��a��^�����܂��vDona nobis pacem�́u�O���[���A�v�̒��́u���� ���Ɋ��ӂ����vGratias agimus tibi�̃����f�B�����p���Ă���B
�@�o�b�n�����ƃt���[�h���q�E�X�����g�i1893�|1980�j�́u�w�~�T�ȃ��Z���x�̍ŏI�y�͂́A�������琶�܂ꂽ�A�܂������Ԃɍ��킹�̍�i�ł���v�Ǝ咣����B���ڂ��ׂ��͂��̍����A���y�͂̈Ӗ������̍��فB�u���ɕ��a��^�����܂��v�Ɓu���� ���Ɋ��ӂ����v�ɂ͂��̈Ӗ��ɂ����Đ��������Ȃ��Ƃ����̂ł���B����͎�����������o�b�n���������}�����܂�Ԃɍ��킹�����́A�Ƃ��������ł���B
�@����ɁA�u���ɕ��a��^�����܂��v�́u�������݂��܂��v�ɒʂ��A�u����݂��܂��vKyrie eleison�̏͂Ƃ͐�����������A����Ȃ�Α��������A�ƁB �@���͂����ǂ�ł��ăn�^�Ǝ��ł����B�u���N�C�G���v�ɂ����郂�[�c�@���g�̎w���͂܂���Kyrie eleison�̌J��Ԃ��ł͂Ȃ����I�u���̔q�̏��v�ɂ͒��ځu����݂��܂��v�̕����͂Ȃ����u�����������ނ�̏�ɏƂ炵���܂��vLux perpetua luseat eis�ȂǁA���l�̈Ӗ����Ă߂��Ă���B�X�����g���ɏ]���A�u�L���G�v�̃p���f�B�[�ɂ͊m�ł��鐮����������Ƃ������Ƃ��B�̈ӂ��H���R���H ���[�c�@���g�̎w���́A�u�~�T�� ���Z���v�ɂ�������Ƃ̃o�b�n�ւ̔��H�������z�������ɂ̎w�����������ƂɂȂ�B
�@�ȏ�ŁA�u���c���N�v�����Ɍ����ăW���X�}�C���[���s������M��Ƃ̍l�@���ꉞ�I��点�Ă��������B�Ō�ɁA��������Ӗ��ŁA�����̃|�C���g���ӏ������Ŏc���Ă��������B�W���X�}�C���[�̂����̍�Ƃ́A�������Ă܂Ƃ߂Ē��߂Ă݂�ƁA�[������쐬�����Ō��4�y�͂ɂ����ẮA���ׂă��[�c�@���g�̎w�����������\�������������i�A�B�D�E�j�B�����́A���[�c�@���g�̃����ł���������Ȃ�����A�i�v�ɏؖ�����邱�Ƃ͂Ȃ����낤���A���̒��ł��̉\���͍���v�X�m�M�ɋ߂Â����Ƃ��낤�B
�@�@ 8�u���N�����T�v�ɂ����āA���[�c�@���g���c�����u�A�[�����E�t�[�K�v�̃X�P�b�`���g�킸�ɁA��̘a���ŃV��
�@�@�@�v���ɒ��߂��B����͓����̏@�����y��̊��킵�ł͂Ȃ����ߌ��߂�����[�u�Ƃ����Ă��������낤�B
�@�A 11�u�T���N�g�D�X�v�̓��[�c�@���g�́u�ǎ��@�~�T�� K139�v������p�����B
�@�B 12�u�x�l�f�B�N�g�X�v�̎�����̓��[�c�@���g�́u�o���o���E�v���C���[�̗��K�� K453b�v������p�����B
�@�C 11�u�T���N�g�D�X�v��12�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɕt�������́u�z�U���i�v�̒��������킹�Ȃ������̂́A�W��
�@�@�@�X�}�C���[������y�̓`����m��Ȃ���������ł���A���ꂪ�u�W���X�}�C���[�Łv�ő�̃~�X�ł���B
�@�D 13�u�_�̎q�r�v�`���̃����f�B�́A���[�c�@���g�u���̃~�TK220�v�́u�O���[���A�v�̓����̎�����������p��
�@�@�@���B
�@�E 14�u���̔q�̏��v�̉��y�����́A1�u���Տ��v�̓r������� 2�u�L���G�v�S�y�͂��\�m�}�}�J��Ԃ����B
���Q�l������
���[�c�@���g�u���N�C�G�� ��Z���vK626
�@�@���@�C���w���F�^�[�t�F�����W�[�N�E�o���b�N��CD �����
�@�@�K�[�f�B�i�[�w���F�C�M���X�E�o���b�N��CD �����
���[�c�@���g�u���̃~�T�vK220
�@�@�N�[�x���b�N�w���F�o�C�G�������� CD
J.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v
�@�@�W�����[�j�w���F�o�C�G�������� CD
�S�Z�b�N�u���N�C�G���v
�@�@�h�D���H�w���F�}�[�X�g���q�g���y�@�����ǁ������cCD
�u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�i���ы`���� �t�H�Ёj
2015.06.25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��7�`�W���X�}�C���[�̎��s�͂Ȃ��N���Ă��܂����̂��H
�@�W���X�}�C���[�́u�T���N�g�D�X�v���j�����ŏ����Ă���B�u���c���N�v�̎咲�̓j�Z��������A�u�T���N�g�D�X�v�Œ����ɓ]�����킯���B�咲���Z���Łu�T���N�g�D�X�v�������B�����`���̂鑼�̃~�T�Ȃ̗�������������Ă݂悤�BJ.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�@���Z�����j�����@�Z���̃~�T�Ȃɂ����āA�_�̐_�����]����u�T���N�g�D�X�v�Œ����ɓ]����P�[�X�͒������Ȃ��BJ.S.�o�b�n�̏ꍇ�͕��s���i����m�j�A���͂��ׂē��咲�i�剹������j�ւ̈ڍs�ł���B���������āA�W���X�}�C���[���u���c���N�v��M�ɂ����āA�u�T���N�g�D�X�v�咲�ł���j�����ɓ]�������ƁA���ꎩ�̂͂Ȃ����͂Ȃ��i�t������u�z�U���i�v�������j�����j�B���́A���́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒�����σ������ɐݒ肵�A�u�z�U���i�v���A�i�j�����ɖ߂����Ɂj�σ������̂܂I��点�Ă��܂����A���Ƃɂ���B���ꂪ�u�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̎��s�v�ł��邱�Ƃ͑O��w�E�����Ƃ���ł���B
���[�c�@���g�u�n�Z���~�T�ȁvK427�@�n�Z�����n����
���[�c�@���g�u�ǎ��@�~�T�vK139�@�n�Z�����n����
�n�C�h���u�l���\���E�~�T�ȁv�@�j�Z�����j����
�@���́u�z�U���i�v�̒����Ȃ̂ł��邪�A���̑O�ɁA�W���X�}�C���[���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v��σ������ɐݒ肵�����R��T���Ă݂����B
���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v��σ������ɂ����o�܂𐄗����遄
�@��12�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�vBenedictus�́A�u�j����ꂽ�܂��v�Ƃ����A�g�_�̌䖼�ɂ����ė�����̂ɏj������h�Ɖr����R��I�Ȋy�͂ł���B�O�q�̂Ƃ���W���X�}�C���[�͂����σ������ɐݒ肵���B���͂������قɊ�����B�u�T���N�g�D�X�v�j�������u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ������I�I
 �@�W���X�}�C���[�́u�T���N�g�D�X�v���j�����Ŏd�グ�����ƁA�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�Ɏ��|����B�Q�l�ɂ����̂́A���[�c�@���g�́u�o���o���E�v���C���[�̂��߂̗��K���vK453b�̈�߁B����́u�ŐV���ȉ���S�W�v��22���Ɋy���t���ʼn������Ă��邪�A�܂��ɂ��̒ʂ�A�^���]�n�̂Ȃ������`�ł���A���[�c�@���g�̎w���ɈႢ�Ȃ��Ɗm�M��������B
�@�W���X�}�C���[�́u�T���N�g�D�X�v���j�����Ŏd�グ�����ƁA�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�Ɏ��|����B�Q�l�ɂ����̂́A���[�c�@���g�́u�o���o���E�v���C���[�̂��߂̗��K���vK453b�̈�߁B����́u�ŐV���ȉ���S�W�v��22���Ɋy���t���ʼn������Ă��邪�A�܂��ɂ��̒ʂ�A�^���]�n�̂Ȃ������`�ł���A���[�c�@���g�̎w���ɈႢ�Ȃ��Ɗm�M��������B�@ �@�]�k�ƂȂ邪�A���́u�ŐV���ȉ���S�W�v��22���u���[�c�@���g�w���N�C�G���x�v�i���y�V�F�Њ� ���їΒ��j�̉���Ɉꌾ�B���ҁE���їΎ��ɂ͑O����G�ꂽ���A�����ł��܂��u�z�U���i�̒����v���X���[���Ă���B�ł͂��́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̉���S�������Љ�悤�B
��ꃔ�@�C�I�����ɐ擱����ăA���g�Ə������߂āu��̌䖼�ɂ��ė������ҁv�Əj������B��6�x��s������Ƃ��邱�̐����́A���[�c�@���g��1784�N�����A�����̏����̒�q�ɗ^�����u�o���o���E�v���C���[�̂��߂̗��K���v�Ƃ��Ēm�����Ȃ̎�����iK453b�j�̖`���Ɍ��o�������̂Ƃ�������̎p�����Ă��邽�߁A�W���X�}�C���[���Ɨ͂Ŏd�グ���Ƃ����y�͂ɂ����Ă��A�t�̊y�z�ďo�ɑ傫���ˑ����Ă������Ƃ𗠕t���Ă���B�Ə��l�������̐������\���ɉ̂��グ�āA�Ō�̓h���`�F�ŐÂ��Ɏ�������ƁA�O�Ȍ����́u�z�U���i�v�̃t�K�[�g����A�A��ǂ���̂��߂�����ƂȂ�B�@�O�i�͖��Ȃ��B�݂̂Ȃ炸�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̏o�T�����炩�ɂ���āA�傢�ɎQ�l�ɂȂ����B���������Ȃ��͍̂Ō�̕��́B��Ɂg��ǂ���́h�Ƃ��������ɂ͕����B�g��ǂ���łȂ��h���Ƃ��A���͖��ɂ��Ă���̂ł���B
�@���y�V�F�ЂƂ����A�킪���N���V�b�N�o�ŊE�̍ő��ɂ��ă��b�J�Ƃ����錠�Ђ��鑶�݁B���̒P�s�{�̊j�ł���u���ȉ���S�W�v�͊y�ȉ���̐����Ƃ��ڂ����BCD����������҂́A������Q�l�ɂ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂ł���BCD������̂قƂ�ǂ��u�z�U���i�̒����v���X���[���Ă����̂͂���ɋN������I�H ���Ђ��L�ۂ݁I�E�ɕ킦�I �Ȃ�Ƃ��������ł���B�����Ɉ��Ă��܂����B�{��ɖ߂낤�B
�@�W���X�}�C���[�́A�����f�B�E���C�����l�d���ʼn̂킹�邱�ƂƂ��A�܂��A�u�T���N�g�D�X�v�Ɠ���̃j�����ʼn��d�グ�������B
�@���̃P�[�X�A�\�v���m�E�\���̍ō�����C��ƂȂ�B�u���c���N�v�̃\�v���m��\���̍ō����́u���R���_�[���v�ɂ�����A�B���[�c�@���g�̑��̏@���Ȃ����Ă��u�Պ����~�T�ȁvK317��G�A�u�~�T�� �n�Z���vK427��A�ł���B�ō�����A�`G�����肪�Ó��BC��͂��܂�ɂ������I�I�����ŃW���X�}�C���[��3�x�������B��������ō�����A�ƂȂ�B����ňꌏ�����B
�@�������ăW���X�}�C���[�́A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̒������@�B�I�ɕσ������ɐݒ肵�Ă��܂����B�ȏオ���̐����ł���B
���W���X�}�C���[�ɂ́u�z�U���i�v�������킹�̊ϔO���Ȃ�������
�@�ʂ����āA�u�T���N�g�D�X�v����u�x�l�f�B�N�g�N�X�v�ւ̒����̈ڍs[�j�������σ�����]�͑Ó����ۂ��H ���[�c�@���g�̑��̗�����Ă݂悤�B
�u�Պ����~�T�ȁvK317�@�n�������n�����@���C�Â����낤���B�u�Պ����~�T�v�������A���͑S��5�x�����������ւ̈ڍs�ł���B����͈�ɁA���[�c�@���g���A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v���u�T���N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�ƒ��������킹��A���̓]���̍�Ƃ�O���ɒu���Ă�������ł���B����������咲�ɓ]������ɂ́������炷�i�������́������₷�j�����B�]���̓X���[�Y�ɍs����̂ł���B
�u�ǎ��@�~�T�vK139�@�n�������w����
�u�O�ʈ�̂̃~�T�vK167�@�n�������֒���
�u�~�T�E�u�����B�X�vK140�@�g�������n����
�u�N���h�E�~�T�vK257�@�n�������w����
�@�W���X�}�C���[���s�����u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�σ������̐ݒ�B���̏ꍇ�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�������̃j�����ɖ߂��͎̂���̋ƂƂȂ�B�Ȃ��Ȃ�������2�ւ̈ڍs�ƂȂ邩��ł���B�]����O���ɒu���ĂȂ��؋��ł���B
�@�W���X�}�C���[�̓��̒��ɂ́A�u�w�T���N�g�D�X�x�ɂ�����w�z�U���i�x�Ɓw�x�l�f�B�N�g�D�X�x�ɂ����邻�ꂪ�A�����܂ߓ����łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����@�����y�̕s���������݂��Ă��Ȃ������B�����āA���[�c�@���g�ɂ����ẮA��q���܂�������Ȋ�{���̊�{��c�����Ă��Ȃ��Ƃ͎v���������ɁA�����Č��ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ������B�]��ɂ��P���Ȍ��_�����A���ɂ͂����Ƃ����l�����Ȃ��̂ł���B
�@�������āA�u���c���N�v�́A�u�T���N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v���Ⴄ���ł���Ƃ����A���y�j�������Ȃ���`�Ɏd�オ���Ă��܂����B�����āA�u�W���X�}�C���[�Łv�́A���݂����̌`�̂܂܉��t���ꑱ���Ă���B��������邽�߂ɏo�Ă����̂��u�����B���Łv�ł���B���A���̔łɂ��Ă͔ł̔�r�̍��ŏڂ������グ�����B
���Q�l������
�u�ŐV���ȉ���S�W�v��22�� ���y�ȇU�i���y�V�F�Ёj
2015.06.15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��6�`�W���X�}�C���[�ő�̎��s
�@���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�B���[�c�@���g��i�����w�̐l�C�Ȃɂ��āA���N�C�G���j�㐏��̌���Ƃ̕]�����������̖��Ȃ��A���́A���y�j��A�B�ꖳ��̋K���ᔽ�����Ă���B��������A�u���c���N�v�́A�@�����y�̓`���ɔ����鎖�����������قɂ��ėB��̊y�ȂȂ̂ł���B���Ȃɂ͗l�X�Ȕ閧���B����Ă���Ƃ����̂͂悭�����b�����A����͒��ł����W���̕s�v�c���ł���B����͂�����e�[�}�ɏq�ׂ����Ă��������B�@�u���c���N�v�ɂ�����W���X�}�C���[�̕�M��Ƃɂ��ẮA���j�I�ɗl�X�Ȕ�����B�����́u���c���N�Ɏa�荞�ނP�v�i3��10���j�ŏ������Ƃ���ł���B�t���[�c�@���g�Ƃ̃I�[�P�X�g���[�V�����̈Ⴂ�B�t�������c�����u�A�[������t�[�K�v���������ƂȂǁB�����A���Ɍ��킹��A���̓�́A���ɑ���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A�債�����ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����Č����Ȃ�A�I�[�P�X�g���[�V�����͂����܂ł����t���ł���A�ߑ��̂悤�Ȃ��́A���g���ς��킯�ł͂Ȃ��B�܂��g�A�[������t�[�K�h�́A�u���c���N�Ɏa�荞��4�v�i4��29���j�Ŏw�E�����Ƃ���A�u���N�C�G���v�̓`���ł͂Ȃ����炾�B
�@�����W���X�}�C���[�̕�M�ŗB�ꌩ�߂����Ȃ����́E�E�E�E�E����́u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�̒���������łȂ����Ƃł���B���ꂼ�A�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̎��s�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���u�z�U���i�v�ɂ����錈�ߎ���
�@�u�z�U���i�v�̓C�G�X��L���X�g���G���T��������̍ہA�Q�W�����������Ă̐��gHosanna in excelsis�h�i���ƍ����V�Ƀz�U���i�j�̂��Ƃł���B�~�T�Ȃɂ����āA�u�z�U���i�v�́A�u�T���N�g�D�X�vSanctus�i���Ȃ邩�ȁj�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�vBenedictus�i�j����ꂽ�܂��j���Ȃ̖����ɕt������B���̓�́u�z�U���i�v�͒����܂ߑS������łȂ���Ȃ�Ȃ��E�E�E�E�E���ꂪ�u�~�T�ȁv�̌��ߎ����`���ł���A�B��̗�O�����݂��Ȃ��B
�@�ȉ��A���[�c�@���g�O��̎���̑�\�I�ȃ~�T�Ȃɂ�����u�T���N�g�D�X�v�A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�A�u�z�U���i�v�̒������L���Ă������B
J.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�@�T���N�g�D�X�i�ȉ�S�j�@�j�����@�����̒ʂ�A�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�͑𐬂��A�e�X�ɕt������u�z�U���i�v�͒����܂ߑS������ł���B��X�A�Ⴆ�t�H�[���́u���N�C�G���v�̂悤�ɁA�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̏ȗ��ȂǁA�ϑ��I�Ȍ`���̂��̂��o�Ă��邪�A�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v���𐬂��y�Ȃɂ����ẮA��́u�z�U���i�v�͗�O�Ȃ������܂ߓ���ł���B����͋ߑ�̍�i�A�u���e���́u�푈���N�C�G���v�ɂ����Ă��R��ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �x�l�f�B�N�g�D�X�i�ȉ�B�j�@���Z��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �z�U���i�i�ȉ�H�j�@��
�n�C�h���u�l���\���E�~�T�v�@S=���@B=�j�Z���@H=��
�~�q���G���E�n�C�h���u���N�C�G�� �n�Z���v�@S=�n�Z���@B=�σz�����@H=�σz����
���[�c�@���g�u�Պ����~�T�vK317 �@S=�n�����@B=�n�����@H=�n����
���[�c�@���g�u�~�T�� �n�Z���vK427 �@S=�n�����@B=�C�Z���@H=�n����
�x�[�g�[���F���u�����~�T�ȁv�@S=�j�����@B=�g�����@H=��
�V���[�x���g�u�~�T�� ��6�ԁv�@S=�σz�����@B=�σC�����@H=�σ�����
�@�ł́A�u���c���N�v�ɂ����ăW���X�}�C���[����M�����O�҂̊W�₢���ɁH
�T���N�g�D�X�����@�z�U���i�����@�Ȃ�ƁA����ł���ׂ���́u�z�U���i�v�̒������قȂ��Ă���I�u�T���N�g�D�X�v�́u�z�U���i�v�͓��A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂���͕σ������B�J��Ԃ������̂悤�ȗ�͐����̃~�T�Ȃ̒��ɑS�����݂��Ȃ��B�W���X�}�C���[��M�́u���c���N�v�������B��̗�O�Ȃ̂ł���B���ꂼ�W���X�}�C���[�ő�̎��s�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�t�̌����u�Ƃ�܂̃W���X�}�C���[�v���̐S�ȂƂ���ŏo�Ă��܂����I�I�̂ł���B
�x�l�f�B�N�g�D�X�������@�z�U���i������
���킪���]�_�E�̈ӎ��x�����遄
�@���͌��݁u���c���N�v��CD��26�����L���Ă���B�����^�[�A�V���[���q�g�A�x�[���A�J�������A���q�^�[��A�h�C�c�n���������B�V�����e�B�A�f�C���B�X�A�A�o�h�A���[�e�B�A�o�����{�C���A�A�[�m���N�[���ȂǁA����ɑ������w���҂����B���b�t���A���C���X�h���t��~�T�̓T��̒��ōs��ꂽ���́B���ɂ́u���N�����T�v�̑�W���߂Œ��f�A�ˑR���b�N���y�ɗl�ς�肷��L�����m�܂ł���B�قƂ�ǂ��W���X�}�C���[�ł����A�o�C���[�ŁA���[���_�[�ŁA�����h���ŁA�����B���ł��ꉞ������Ă���B
�@����͂Ȃɂ��R���N�V�����𐁒��������ċL�����̂ł͂Ȃ��i���_����قǂ̃��m�ł�����܂��j�A�W���X�}�C���[���Ƃ����ő�̃~�X���A�킪���{�̕]�_�Ə��搶�ɂ����Ăǂ�قǂ̔F�������邩��m�肽����������ł���B�ł́A���̌��ɓ��낤�B
�@26�_��CD�̂����A������t����20�_�B���̒��ŁA�u��̃z�U���i�̒������Ⴄ���Ɓv�ɐG��Ă������͂ǂꂭ�炢����̂��H
�@�u���c���N�v�����Ƃ��A�W���X�}�C���[�̕�M���O���킯�ɂ͂����Ȃ����낤�B�Ȃ�A���̒��Ŕނ̔Ƃ����ő勉�̃~�X�ɂ��ẮA���Ȃ�̊m���Ō��y����Ă���͂��ł���B�����\�z���ėՂ��ł��������A���ʁA�傫���O�ꂽ�B���̐��͂Ȃ�ƈ�ł������B����͎��ɂƂ��ċ����ȊO�̉����ł��Ȃ��B��̂킪���̕]�_�Ə����͉����l���Ă���̂��I�H
�@�m���Ɏ��̏��L����u���N�C�G���v��CD�͈ꕔ�ɉ߂��Ȃ����낤�B�����������A���Ղƒ�]������̂�e�ł̑�\�I�ȃR���e���c�͂قږԗ����Ă���A�i�ʕ��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B�ꎖ�������Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A�T�v���炢�͒͂߂�R���N�V�����Ƃ̎����͂���B�ł́A�u�z�U���i�v�̒����Ɍ��y�����B��̉���������Љ��B
 ���c�a�M���̉�����i�u���[�m�E���@�C���w�� 1999�N�^��CD�j
���c�a�M���̉�����i�u���[�m�E���@�C���w�� 1999�N�^��CD�j
���[�c�@���g�A�Ђ��Ă�18���I�ɂ�����u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɂ�����gHosanna in excelsis�h�̃t�K�[�g�́A���̊y�͂Ɓu�T���N�g�D�X�v�̒����قȂ�ꍇ�́u�T���N�g�D�X�v�̒��ɖ߂����Ƃ���O�̂Ȃ������������̂ɑ��A�W���X�}�C���[�͕σ������̂܂܃t�K�[�g��W�J���Ă��܂����i���̌��̓h�D���[�X�łƃ����B���łł͒�������Ă���j�B����̓W���X�}�C���[���Ƃ������̒��ł��ő勉�̌��ɐ�������B�@���ꂪ�u�W���X�}�C���[�̃~�X�v�ɐG�ꂽ�B��̕��͂ł���B���݂ɂ���CD�́u�����h���Łv�ł���B���������A���ڒ��ȉ�������������Љ�Ă������B�����͑S�āu�W���X�}�C���[�Łv�ł���B
 ���c���ꎁ�i�J�[���E�x�[���w��1971�N�^���j
���c���ꎁ�i�J�[���E�x�[���w��1971�N�^���j
�u�T���N�g�D�X�v�E�E�E�E�E�㔼�̓A���O���A4����3���q�ɓ]����B�������o�X�A�e�m�[���A�A���g�A�\�v���m�̏��ʼn�����炩�ȋ����̃t�[�K���`�Â����Ă����B�@�z�U���i�������g��炩�ȋ����h�̃t�[�K�ƕ\������Ă��邪�A�u�z�U���i�v�Ƃ����������Ȃ��A���_�A�����ɂ��G��Ă����Ȃ��B���@���̂��̂����ɑ�炩�ȕ��͂ł���B
�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�E�E�E�E�E�A���O���A4����3���q�̌㔼�ɓ����āA�����ɂ��t�[�K������Ђ낰����B
�C�V�V�q���i���b�t���w��1955�N�^���j
�u�T���N�g�D�X�v�E�E�E�E�E�ȉ��̕����̓W���X�}�C���[�����グ�������ł���B�܂��A�_�[�W���A���A�S����4���q�i�ȉ��ȗ��j�B�@���Ȃ̒��������L����Ă���Ƃ������Ƃ́u�z�U���i�v�̒����̈Ⴂ��F�����Ă�����͂��B�g�Ⴄ�h�u�z�U���i�v�Ȃ̂Ɂg�O�Ȃɂ݂�ꂽ�h�̕����B����͖����B���_�o�B�C�V�V�搶�Ƃ����A���{�l�B��̃��[�c�@���e�E�����_���c���ɂ��Ă킪�����[�c�@���g�����̑��l�҂Ƃ����Ă����䏊�ł���B��䏊�Ȃ�A�u�O�Ȃ͓��A�����͕σ������B���ꂼ�W���X�}�C���[�ő�̃~�X�ł���v���炢�̕\�����~���������B
�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�E�E�E�E�E�A���_���e�A�σ������A4����4���q�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�e���|�̓A���O��4����3���q�ƂȂ�A�O�Ȃɂ݂�ꂽ�u���ƍ����V�Ƀz�U���i�v�݂̂������t�[�K�������Ă���B
�@�ȉ��A���ϓI���ڒ��^��3�_�܂Ƃ߂ė��L�����Ă��������B
 �����͎��i���q�^�[�w��1961�N�^���j
�����͎��i���q�^�[�w��1961�N�^���j
�u�T���N�g�D�X�v�E�E�E�E�E�㔼�ɂ͒Z�������X����gHosannna�h�̃t�[�K���Â��B�Ζ؈�q���i�J�������w��1975�N�^���j
�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�E�E�E�E�E�Ō�ɃT���N�g�D�X�Ɠ����gHosanna�h�̃t�[�K������Ԃ����B
�u�T���N�g�D�X�v�ł͎�̉h�������炩�ɉ̂��A�㔼�̓t�K�[�g�Ɉڍs����B�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̓��[�c�@���g�ɂ����������Ƃ��ėp�����A�d���ɂ��R��I�ɓW�J�����B�㔼�͑O�͂̂���Ɠ��l�̃t�K�[�g�B���їΎ��i�R�[�v�}���w��1989�N�^���j
�u�T���N�g�D�X�v�E�E�E�E�E���R���_�[����z�N����������Ɋ�Â��ȗ��ȃt�K�[�g�������B�@�����́A��l�Ɂu�g�����z�U���i�h������Ԃ����v�ƋL�q����Ă���B�ɂ܂�Ȃ��b�ł���B�Ƃ͂��������́A�܂��A�u�z�U���i�v�Ƃ������������邾���܂���������Ȃ��B���ɂ́A�e�Ȃ̒����Ɣ��q�̗�L�Ɏ~�܂��Ă�����̂��炠��B�������I���{�̕]�_�Ə����I�I�ł���B
�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�E�E�E�E�E��Hosanna���̃t�K�[�g����A���Ē��߂�������B
�@�Ȃ��u�����B���Łv�����^�����}�b�P���X�Ձi2002�N�^���j�́A�A���Ղɂ��A�ق��p��͂���g���ĖĂ݂����A�����ɂ́u�W���X�}�C���[�̃~�X�v�����L����Ă����B�u�����B���Łv�́A��������邱�Ƃ��ő�̖ړI�̈�Ƃ����킯�����瓖�R�Ƃ����Γ��R�ł͂��邯��ǁB����ɂ��Ắu�ł̔�r�v�̍��Ō��y�������B
�@����́u�W���X�}�C���[�ő�̎��s�v�͂Ȃ��N���Ă��܂����̂��H���̃~�X�e���[�ɒ��킷��B
2015.05.25 (��) ����ł����̂� ���{�I�Iwith Ray�����
�@Ray�����R���j�`���B���̂Ƃ���N�����C���Ȃ̂ŁAJiiji�͐S�z���Ă�B���������āA�A���p���}���E�Q�[���ɍs�����ˁI �@���ĂƁA5��20���̍���ŁA���Y�}�E�u�ʈψ����̎���ɁA���{���������ǂ���ǂ낾���������ȁB�Ȃɂ���u�|�c�_���錾�v��m��Ȃ������Ƃ��B�������ɁAVoice�ł̔��������Ă����m�֖��̋ɂ݁B�u�|�c�_���錾�Ƃ����̂́A�č������q���e��2�������Ƃ��ē��{�ɑ�ςȎS���^������A�w�ǂ����x�Ƃ���ɂ������������̂��v�����Ă��B�R���ԋt�I �錾���o���ꂽ�̂�1945�N7��26���B����������8��6����9��������ˁB������̗�؊ё��Y���t���A���ۂ߂A���������͔�����ꂽ�I�H �Ƃ��낪�A���t�͂�����āu�َE���f�Ő푈������簐i����v�Ȃ鐺�����o�����B����ŕč��ɓ����̑�`��^���킯�B���{�͐푈�I���̋@��������������x������̂��낤�B
�@���ĂƁA5��20���̍���ŁA���Y�}�E�u�ʈψ����̎���ɁA���{���������ǂ���ǂ낾���������ȁB�Ȃɂ���u�|�c�_���錾�v��m��Ȃ������Ƃ��B�������ɁAVoice�ł̔��������Ă����m�֖��̋ɂ݁B�u�|�c�_���錾�Ƃ����̂́A�č������q���e��2�������Ƃ��ē��{�ɑ�ςȎS���^������A�w�ǂ����x�Ƃ���ɂ������������̂��v�����Ă��B�R���ԋt�I �錾���o���ꂽ�̂�1945�N7��26���B����������8��6����9��������ˁB������̗�؊ё��Y���t���A���ۂ߂A���������͔�����ꂽ�I�H �Ƃ��낪�A���t�͂�����āu�َE���f�Ő푈������簐i����v�Ȃ鐺�����o�����B����ŕč��ɓ����̑�`��^���킯�B���{�͐푈�I���̋@��������������x������̂��낤�B�@�u�ʈψ����͑�6��8�����莋���Ă���悤�����AJiiji�͂ނ����12���ɒ��ڂ������B�u�|�c�_���錾�v��12���ɂ͂�������B��ӂ́u���a�I�X���̐ӔC���鐭�{���������ꂽ��A��̌R�͓P�ނ���v�B�Ȃ̂ɕČR�͖����ɓ��{�ɒ������Ƃ�B�r�����f�B���͂��ꂪ�����Ȃ��ē��������e������������B���{����Ƀe�����Đ킦�Ƃ͌���Ȃ�����ǁA�h���Ԃ肮�炢�͂����Ăق����B
�@�u�|�[�c�}�X���v�͒m��Ȃ��Ă��܂�������邪�A�u�|�c�_���錾�v��m��Ȃ��ᑍ����b�͖��܂�Ȃ����B�܂��Ă�A�u��ヌ�W�[������̒E�p�v�͂��Ȃ��̌��ߑ䎌�ł��傤�B�g��ヌ�W�[���h�Ȃ���̂́A�u�|�c�_���錾�v����n�܂��Ă���炳�B
�@�挎���A���ׂ����^���^�������ŃA�����J����u�����q�����q�v����Ċ��ł��݂��������ǁA�݂��Ƃ��Ȃ������炠��Ⴕ�Ȃ��B�ւ����������������Ȃ��BJiiji�A���ɕs������������B���ꂶ��u���̓z��v�g��E�Ƃ������E������ �ƂĂ��K�� �����炢�����ɂ����Ă� �ז����Ȃ����� ���Ȃ��D�݂̂��Ȃ��D�݂̏��ɂȂ肽���h�����B�����A�A�����J�͔��芅�т���ł��傤��B�n���ɂ��Ȃ���B
 �@5��20���͂܂��A���{�W�O������b�̍ݔC������1242���ƂȂ��āA�c���E�ݐM����z�������Ƃ��b��ɂȂ����ˁB�{�l�H���u�ݐE�����ł͂Ȃ��A���𐬂�������������肾�v�ƁA���ς�炸�邱�Ƃ͂������Ƃ��B�u���{�̒��ɂ݂͊��Z�ށv�ȂǂƂق��������w�҂�����B�ł�Ray�����A��[���l���Ă݂悤�B�c���́A�T���t�����V�X�R���������Ɏ~�ޖ����t�����ꂽ���ۏ��̕s���������A�����Ȃ�Ƃ��������邽�߂Ɋ撣�����B����A���́A���@���߂�ς��Ă܂Łu�W�c�I���q���v��e�F����Ƃ�������ւ̉ߏ�T�[�r�X��}��Ȃ�����A���E�̒ɂ݂ɂ͎���݂��Ȃ��⍓�Ή��B���������ǂ����������Ďd�����Ă���Č��������Ȃ�B�c���̐��_��Ղ͈����Ŕ��āB���͍��i����j���������ĂɎC����B�c���Ƒ��A�܂�Ŋԋt����Ȃ����B
�@5��20���͂܂��A���{�W�O������b�̍ݔC������1242���ƂȂ��āA�c���E�ݐM����z�������Ƃ��b��ɂȂ����ˁB�{�l�H���u�ݐE�����ł͂Ȃ��A���𐬂�������������肾�v�ƁA���ς�炸�邱�Ƃ͂������Ƃ��B�u���{�̒��ɂ݂͊��Z�ށv�ȂǂƂق��������w�҂�����B�ł�Ray�����A��[���l���Ă݂悤�B�c���́A�T���t�����V�X�R���������Ɏ~�ޖ����t�����ꂽ���ۏ��̕s���������A�����Ȃ�Ƃ��������邽�߂Ɋ撣�����B����A���́A���@���߂�ς��Ă܂Łu�W�c�I���q���v��e�F����Ƃ�������ւ̉ߏ�T�[�r�X��}��Ȃ�����A���E�̒ɂ݂ɂ͎���݂��Ȃ��⍓�Ή��B���������ǂ����������Ďd�����Ă���Č��������Ȃ�B�c���̐��_��Ղ͈����Ŕ��āB���͍��i����j���������ĂɎC����B�c���Ƒ��A�܂�Ŋԋt����Ȃ����B�@���{�����ɂ��肢�B���j���w��ŃA�����J�ɂ����咣���Ăق����B�u�w�|�c�_���錾�x�ɂ́g���{�����卑�ƂɂȂ������̌R�͓P�ނ���h�Ƃ������Ă���B�g������o�Ă����h�Ƃ͌���Ȃ��B�݂̎������̂ŁB�Ȃ�A���߂ď��X�ɓ��{�̒n�ʌ����}���Ăق����B����̕��S�y���ɂ����͂��Ăق����B���{���U�߂�ꂽ��K�����Ɩ��Ăق����v���āB���ꂭ�炢�̂��Ƃ������Ă��o�`�͓�����Ȃ��Ǝv�����ǂˁB
�@1980�N��A���̊��[�����E�㓡�c�����́A���[�K�����璆�]�������ւ́u�@���|�C�Ɏ��q���̊C�O�h�����v�Ȃ�v���ɁA��Ƃ��Ď���c�ɐU��Ȃ������Ƃ����B�u����Ȃ��Ƃ�����ΕK����ɂȂ�B���̓��{�ɂ��̊o�傪����̂��v�Ƒ����ɔ������̂��B���͂�������̂܂܈��{����ɂԂ������B�����̓C�����E�C���N�푈�B����͒����̋��ЁB������n�����Ⴄ�̂ŁA���{�����̉]���u�W�c�I���q���s�g�v��100�����͂��Ȃ��B�u���͍s�g�O�v���v�ɂ܂Ƃ��ɊY������Ȃ�A�i���ە��a�x���Łj����x���ɓO���邱�Ƃ��ł���̂Ȃ�A�M���M�����@�̐��_�ɔ����Ȃ��Ɖ��߂��Ă��B���ē����̋����́A���Ȃ��炸���\�����ւ̗}�~�͂ɂȂ肤�邾�낤�B
�@�����������A���f����l�Ԃ��낤����Ȃ��B�����́A����}�E���c�����\�̎���ɁA�u�@�������͗�O�Ƃ��ĔF�߂���v�Ɠ��ق��Ă���B��O���ĂȂH ���̈���Łu������@���ԁv�ɊY������Ƃ����������B���ۖ@��A�u�@���|�C�v�͕��͍s�g�ɑ�������炵������A�u�O�v���v�ɏƍ������Ƃ������Ƃł����H �z��̓z�����Y�C�����낤���A�ł����ꂪ�A�u���{�̑�������������A�����̍K���Nj��̌��������ꂩ�畢����閾���Ȋ댯�v�Ȃ̂ł����H �u�W�c�I���q���v�̌��@���߂��k�ق�M�������������ق��A����A�u��������̌������~�܂�Ζk�C���œ����ґ��o�B����܂��ɑ�����@���ԁv�Ȃ�āA�܂�����������Ɍ����O�������Ă���B�����l���̎�i�͑��ɂ�����ł�����܂���B����Ȃ��ƁA���w���ł�����܂��B����Ȏq���_�}�V���{�C�Œʂ�Ǝv���Ă�̂��Ȃ��B���{��]�͍������r�߂Ƃ�̂��ˁI�H�u������@���ԂɌo�ϖ��������o���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ��������}���܂Ƃ��Ɍ����Ă���B���ݎ��̂����@�ᔽ�̌����}���}�g���Ƃ́I Jiiji�A�z���g�ɏ�Ȃ��Ȃ郏�B
�@��@�Ǘ��̐��̌�����낤���̋ɂ݁BIS�l�������ŘI�悵������������̏��ԁB������u�Ή��Ɍ��͂Ȃ������v�Ƒ������鎖�Ȃ����`�B���ɖ��ӔC�B�������낤�ɁA������b���@�Ƀh���[�����������������Ԃ����u���ꂿ������B����Ȋ�@�Ǘ��̊Â���������܂����B���̒����ł���B���E�͂����Ə��Ă邺�B
�@Jiiji���뜜����̂́A�Ǝ�ɂ܂�Ȃ�����̏�Ɂu�ϋɓI���a��`�v�Ȃ���̂��\�z���悤�Ƃ���낤���B���ۖ@���������o�O�ɑΕĊm�Ă��܂��y�����B����ȏ㊊�肩�O�̂߂�̊댯�����B
�@�܂��́A��@�Ǘ��̐����m�����邱�ƁB���O�̏��Ԃ����邱�ƁB������鎩�o�Ɗo��������ƁB���{�l�̌ւ�������ƁB���{�������ߍ��̃g�b�v�ɂ����̈ӎ������܂�Ȃ�����AJiiji�́u�W�c�I���q���s�g�v��F�߂�킯�ɂ͂����Ȃ��̂��B
 �@������Ray�����A�����O���̔s�k�ɂ��āB5��17���ɍs��ꂽ���s�\�z�̏Z�����[�́A�^��69��4844�[ �� ����70��5585�[�Ƌ͍��Ŕ����������BJiiji�͎^���������B���{�Ƒ��s���݂��̃R�~���j�P�[�V�������Ȃ����ʂȓ�d�s���𐂂ꗬ���Ă���Ƃ�����A��������Ȃ��ς���ׂ����Ǝv�������炾�B�N��ʂɌ����70��ȏ��60�������B20�|30���60�����^���B�����̂Ȃ��N���͕ێ�A�����ɐ������҂͉��v��]�B�����͒N�̂��̂��B�݂�Ȃ̂��́B����͂����B�ł��A�ǂ��炩�Ƃ����Ζ�������������ׂ�����Ȃ����B��҂̈ӌ������ނׂ�����Ȃ����B���̑I���Ɍ����Ă͖����W������K�p���Ăق��������ȁi����Ȃ����������H�j�B�N���[��1�����A��ҕ[��1�����A�Ƃ��ˁBRay�����AJiiji�͂����N�����̎�����l����B��������ł���܂��悤�ɂ��ĂˁB
�@������Ray�����A�����O���̔s�k�ɂ��āB5��17���ɍs��ꂽ���s�\�z�̏Z�����[�́A�^��69��4844�[ �� ����70��5585�[�Ƌ͍��Ŕ����������BJiiji�͎^���������B���{�Ƒ��s���݂��̃R�~���j�P�[�V�������Ȃ����ʂȓ�d�s���𐂂ꗬ���Ă���Ƃ�����A��������Ȃ��ς���ׂ����Ǝv�������炾�B�N��ʂɌ����70��ȏ��60�������B20�|30���60�����^���B�����̂Ȃ��N���͕ێ�A�����ɐ������҂͉��v��]�B�����͒N�̂��̂��B�݂�Ȃ̂��́B����͂����B�ł��A�ǂ��炩�Ƃ����Ζ�������������ׂ�����Ȃ����B��҂̈ӌ������ނׂ�����Ȃ����B���̑I���Ɍ����Ă͖����W������K�p���Ăق��������ȁi����Ȃ����������H�j�B�N���[��1�����A��ҕ[��1�����A�Ƃ��ˁBRay�����AJiiji�͂����N�����̎�����l����B��������ł���܂��悤�ɂ��ĂˁB�@�������̔s��̕ق́u���������A�����Ɩ����ɐs����v�Ǝ��Ɍ��������B�\����u�₩�������B�ł��u���߂���ېV�̓}�̌ږ�ٌ�m�ɂł��ق��Ă��炢�܂���v�͂܂��������ȁB��k�ɂ���B�������琭���ƈ��ނƂ����w���̐w�̒���A�����̐i�H��������Ⴂ�����B�u����H�s�ޓ]�̌��ӂ���Ȃ������́v���ċ^�O��������B���̂ւÂ���ȁB
�@�]�c���i���́u�����O�Ƃ����H�L�Ȑ����Ƃ��x������Ȃ������v�Ƃ��ē}��\���C��\�������ˁB�H�L�I Jiiji�������v���B���̐����̕NJ���˂��j��͔̂ނ������Ȃ��A�Ƃ܂Ŏv���Ă�����B2008�N�ɐ����ƃf�r���[�B2012�N�܂ł͂悩�����B�T���͐Ό��T���Y�Ƒg��ō����ɑł��ďo�����ƁB���������B�܂��͑��ł���ׂ��������B�g��������������B�Ό��́u�����Ƒg�߂A������q���ő����̖ڂ����邩���v�Ɩژ_�B����Ή�~�B2013�N�ɂ͈Ԉ��w��������яo���B�u�Ԉ��w�Ȃ�Ă��̎���ǂ��̍�������Ă����B�K�v�Ȑ��x�������B����Ȃ��Ƃ͒N�ł��킩���Ă�v�ƂԂ��Ă��܂����B���ꂪ��2���T���B���_�ł������Ă͂����Ȃ����Ƃ�����B����ȍ~�����l�C�͋}�~���B���ɏ����ɁB����̔s���̈�͏����[�̗���������A����͋������ȁB
�@�ނ̕s�K�͎Q�d�����Ȃ��������ƁB���߂Ȃ��������ƁB�l�Ԃ͕s���S�B������A�厖���s���ɂ͕⍲����l�Ԃ���ɕK�v�ȂB���������̏����E���A�L�b�G�g�̍��c�����q�A���N���̖q��A�i�|���I���O���̃I�X�}�����X�B
�@�u�����͌��f������́B�������f���ƒf�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��v���钘���Ȑ����Ƃ̌��t���B�����O�̑��_�͐����������B�����A�e�_���ƒf�ɑ����B�ƒf������̂��Q�d���B���Q�d�Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ƃ��L�\�ȕИr��������A�ނ͕K��������Ă������낤�BRay�����AJiiji�͂������Ƃ��Ă��c�O���B
�@����}�́A�������ނňېV�̈ꕔ����荞�߂�A�ƒ�����Ă��邻���ȁB�N��������@���n���̂�҂B�u�n�`���v���Ƃ��B��}�ĕ҂̖�����C����Ă���̂��˂��B�ǂ��܂Ŕ\�V�C�Ȃ��̐��}�́B�W�߂�������Ă���Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��A�����Ƃ������}���O���\�z����̂��挈�ł��傤�ɁB�ł܂��A���c��\�́A���{�����́u�����v�c�_�ɂ͎Q�����Ȃ��Ɩ��������B����Ŗ�}�̐ӔC���ʂ�����́H ���Ȃ�u�Έāv���o���ē��X�Ƌc�_����̂���}�ł���B����c���ł���B���͂�A����}�ɕt����N�X���Ȃ��B
�@Ray�����A���@�����AJiiji�͎^�����B68�N�ԉ����[���B����ȍ��͓��{�����B�Ƃ͂����A�悯����̂܂܂ł�����B�ł��A��͂����ɍ���Ȃ������͂���BJiiji����ɕς���ׂ����Ǝv���̂͑O�����B�u���a�������鏔�����̌����ƐM�`�ɐM�����āA����̈��S�Ɛ�����ێ����悤�ƌ��ӂ����v�̕����B�����͌������ˁBIS�͕��a�������鍑�ł����B����Ȃ��l�D���̗��O���f���Ă�����r�߂��ē�����O�B�쌛�h�͉����l���Ă�낤�B
�@������Ƃ����Ď����}�̉����Ă͂������Ȃ��̂��Ȃ��B���q�����u���h�R�v�ƌĂԂ̂͂܂������B��9���u�O���̋K��́A���q���̔�����W������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ������q���̋�����������BJiiji����ɗe�F�o���Ȃ��̂͑O���Ȃ̂��B�u���{�����́E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�a�сA�Ƒ���Љ�S�̂��݂��ɏ��������č��Ƃ��`������v�Ȃ镔���B�u�Ƒ����݂��ɏ��������v�����āH �傫�Ȃ����b����B�l�̗̈�ɓ��荞�݂����B���Ȃ��l�͂ǂ�����́B�������������Ȃ��l�����Ă��܂���B�����̋��ȏ�����Ȃ�����B���Ƃ��������K�������Ⴂ����B���������Ƃ̖\����A���ꂪ������`�B����Ȋ�{�܂��Ȃ����Ă͑S�ʓI�ɐM�p�ł��Ȃ��ȁB���͂ɂ��i�����Ȃ��BJiiji�́A���@�A���ɑO�������́A�i�����K�v���Ǝv���B
�@����A�N�ɗ��������B�u���̍���c���ɂ͋��{���Ȃ��v�Ə�X���Ă��Ƃ̐Ό��T���Y��搶�ɂł����肢���܂��傤���B����A�~�߂Ƃ����B�u���z�̋G�߁v���_�ŏ����ꂽ���ɂ́A�u���{�ڋ������@�v�ɂȂ����Ⴄ����ˁB
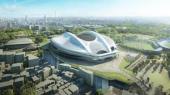 �@���āARay�����B�����I�����s�b�N��5�N�ゾ�BRay�����͏��w��N���B�ꏏ�Ɍ��ɍs�����ˁB���̃��C�����ƂȂ��������Z���v�悪��q���Ă��邻���ȁB�������������Ȋw��b��SOS���M���B�u����������ƊԂɍ���Ȃ���������������B�I�����s�b�N�͉����Ȃ��ł��������B���ݔ���c�����đ�ρB500���قǓs���o���Ă���Ȃ����v�B�����A�s�m���T�C�h�͗����ł��܂����ˁB�v�}��猚�ݗ\�Z���A�ύX�Ɏ����ύX�B���������Ԃɍ����̂��Ȃ��B500���~�͈����Ȃ����ǁA�I�X�v���C�w����2�|3�@���点�Α��P�o�ł��܂����B���̎��̏�K�̌��ה�s�@�́A���{�Ƀo���o���z������āA����̉ʂĂ͎��q�������킳����ł��傤�B17�@��3600���~�����āB�������������ɂ��Ă�B�S���͒��J���h�q�����B���̕��A�u����̈��ۖ@���Ŏ��q���̃��X�N�͍��܂�Ȃ��v�Ȃ�ĕ��C�Ō����B���������Ȃɍl���Ă�낤�B�u���܂�Ȃ��v�Ȃ�ĒN���v���ĂȂ����A�u���܂�Ȃ��v�Ȃ�A�����J�͊�Ȃ��B�����̈Ӑ}�ɂ���������Ă��Ƃł���B�܂��A�g�V�r���A���E�R���g���[���h�������ĂȂ��l������A���傤���Ȃ������ˁB�ł��A����������펯�Ȑl�Ԃ����{�̈��S�ۏ�̒��ł́A�S�z����Ȃ��Ăق�����������ˁB����������NHK���䏟�l��Ƃ����A�W���u�W���u�ɘa���̍��c���F����قƂ����A���{����̎�芪���́A��Ȃ��������Ă��܂���B����Ȏ����}�̓V���𑱂������Ă����́H ��}�݂̂Ȃ���A�撣���Ă�I �ƃG�[���𑗂��āA������ARay�����A�����͂���܂ŁB
�@���āARay�����B�����I�����s�b�N��5�N�ゾ�BRay�����͏��w��N���B�ꏏ�Ɍ��ɍs�����ˁB���̃��C�����ƂȂ��������Z���v�悪��q���Ă��邻���ȁB�������������Ȋw��b��SOS���M���B�u����������ƊԂɍ���Ȃ���������������B�I�����s�b�N�͉����Ȃ��ł��������B���ݔ���c�����đ�ρB500���قǓs���o���Ă���Ȃ����v�B�����A�s�m���T�C�h�͗����ł��܂����ˁB�v�}��猚�ݗ\�Z���A�ύX�Ɏ����ύX�B���������Ԃɍ����̂��Ȃ��B500���~�͈����Ȃ����ǁA�I�X�v���C�w����2�|3�@���点�Α��P�o�ł��܂����B���̎��̏�K�̌��ה�s�@�́A���{�Ƀo���o���z������āA����̉ʂĂ͎��q�������킳����ł��傤�B17�@��3600���~�����āB�������������ɂ��Ă�B�S���͒��J���h�q�����B���̕��A�u����̈��ۖ@���Ŏ��q���̃��X�N�͍��܂�Ȃ��v�Ȃ�ĕ��C�Ō����B���������Ȃɍl���Ă�낤�B�u���܂�Ȃ��v�Ȃ�ĒN���v���ĂȂ����A�u���܂�Ȃ��v�Ȃ�A�����J�͊�Ȃ��B�����̈Ӑ}�ɂ���������Ă��Ƃł���B�܂��A�g�V�r���A���E�R���g���[���h�������ĂȂ��l������A���傤���Ȃ������ˁB�ł��A����������펯�Ȑl�Ԃ����{�̈��S�ۏ�̒��ł́A�S�z����Ȃ��Ăق�����������ˁB����������NHK���䏟�l��Ƃ����A�W���u�W���u�ɘa���̍��c���F����قƂ����A���{����̎�芪���́A��Ȃ��������Ă��܂���B����Ȏ����}�̓V���𑱂������Ă����́H ��}�݂̂Ȃ���A�撣���Ă�I �ƃG�[���𑗂��āA������ARay�����A�����͂���܂ŁB
2015.05.15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��5�`�u�T���N�g�D�X�vSanctus�́u�ǎ��@�~�T�v�̈��p
�@�W���X�}�C���[�̕�M��Ƃ́A���悢�攒����Ԃ���̑n��ɓ���B10�u���Ȃ鐶�сvHostias�܂ł́A�i8�u�܂̓��v�������āj���[�c�@���g����������g�݂��c����Ă����B����Δ����i�B�ނ͂قڃI�[�P�X�g���[�V�����ɏW������悩�����B����11�u�T���N�g�D�X�v����͉����Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��y���ɂ��w���͍����܂Ŋm�F����Ă͂��Ȃ��B�Ƃ͂����A�Ƃɂ������ɂ��A�W���X�}�C���[�͍��グ���B����͉��y�j��Ɏc���̋Ƃł���B�@�ނ́A�u�w�T���N�g�D�X�x�w�x�l�f�B�N�g�D�X�x�w�_�̎q�r�x�͂܂������V�������������܂����v�Ƃ����莆���c���Ă���B�����A�ǂ��l���Ă��g�܂������h���[�c�@���g�̎w���Ȃ����Ă��ꂾ���̕�M���o����킯�͂Ȃ��B����͎��̒����Ɗm�M�ł���B��������́A���̏؋��T���̗��ɏo��B
���T���N�g�D�XSanctus�́u�ǎ��@�~�T�v����̈��p�ł��遄
 �@�܂��͌��_����\���グ�����B�u���c���N�v��11�ȁu�T���N�g�D�X�vSanctus�́A���[�c�@���g�u�ǎ��@�~�T�v�̈��p�ɂ���č��ꂽ�B�`��3����Sanctus Sanctus Sanctus�̐����́u�ǎ��@�~�T�v�̓��ӏ��ƑS�������ł���B�W���X�}�C���[�͂��̕������Œ肵�����ƁA�S�̂��܂Ƃߏグ���Ǝv����B
�@�܂��͌��_����\���グ�����B�u���c���N�v��11�ȁu�T���N�g�D�X�vSanctus�́A���[�c�@���g�u�ǎ��@�~�T�v�̈��p�ɂ���č��ꂽ�B�`��3����Sanctus Sanctus Sanctus�̐����́u�ǎ��@�~�T�v�̓��ӏ��ƑS�������ł���B�W���X�}�C���[�͂��̕������Œ肵�����ƁA�S�̂��܂Ƃߏグ���Ǝv����B�@�`��3���߂ɂ��āA���҂���ׂ�Ȃ�y��������ׂ�Ȃ肵�Ă������������B�����̈Ⴂ�͂���ǁA�S�����������ł��邱�Ƃ����邾�낤�B���̈�v�����[�c�@���g�̎w���Ȃ����ċN���邾�낤���B���R�ƍl��������s���R�ł͂Ȃ��낤���B����܂Ŏ��́A���̂��Ƃ��w�E���Ă���L�q�ɑ����������Ƃ��Ȃ��B������s�v�c�B�W���X�}�C���[���A���[�c�@���g�̎w���ɂ��A�u�T���N�g�D�X�v�`���̐������u�ǎ��@�~�T�v������p�����̂͊ԈႢ�Ȃ��Ɗm�M����̂ł���B
�@�u�ǎ��@�~�T�v�́u�~�T�E�\�����j�X �n�Z���vK139�̒ʏ́B1768�N�A�E�B�[���ŐV�����ꂽ�ǎ��@����̌������̂��߂ɍ�ȁA��Ҏ��g�̎w���ɂ���ď������ꂽ�B���[�c�@���g12�A������23�N���O�̂��Ƃł���B
�@���[�c�@���g�͉�X�}�l�̗�����y���ɒ������V�˂ł���B�V�X�e�B�[�i��q���̖�O�s�o��9���́u�~�[���[���v���ꔭ�ËL�������ƁB�����ȑ�36�ԁu�����c�v��������4���Ԃŏ����グ�����ƁB�ȂǁA���̓V�ːU���������b�͖����ɉɂ��Ȃ��B32�̍�i�ł�������ȑ�41�ԁw�W���s�^�[�x�̏I�y�́u�h�E���E�t�@�E�~�v�̉��^�͏��N����ɋN�������邵�A�u���c���N�v1�u���Տ��v�̃e�[�}��15�̍�i�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�̏I�Ȃ̃e�[�}�Ɠ����ł���B�����炭�A�ނ̑O���t�ɂ́A�ߋ��̍�i��100�������̋������Ȃ���������Ă���̂��낤�B12�̂Ƃ��̐���������ڑO�ɂ����S���Ă��Ȃ��s�v�c�͂Ȃ��̂ł���B
�@���[�c�@���g��11�u�T���N�g�D�X�v�Ɏ��|���낤�����Ƃ��ɂ́A�������ւ̗]�͂��c���Ă��Ȃ������B���悢��l���̍Ŋ������A�؉H�l�����Ƃ��A��q�ɕ�M������ɓ�����A�ނ́A�����̉ߋ��̍�i����̈��p���w�������̂ł���B����́A�����葁���ƓK���ɂ����āA�ŏ�̕��@�������B�`�B��i���g��i���w�����āh�Ȃ̂��g�����������āh�Ȃ̂��͕s���ł��邪�B�w�҂̒��ɂ́A�u�����͂������Ǝv���邪�A�W���X�}�C���[�͎��͕�M���A�s�[���������������߂ɂ�����p�������v�Ə�������̂�����B
�@�u�T���N�g�D�X�v�́A���R�̐_�E��C�G�X�E�L���X�g�ւ̎^����\���ȂŁA�������u�z�U���i�vOsanna in excelsis�i���ƍ����V�Ƀz�U���i�j�̘A�ĂŌ��ԁB����̓~�T�Ȃ̓`���̌`���ł���B�u�z�U���i�v�Ƃ́A�L���X�g���G���T��������̍ۂɁA���O�����������Ă̋��т̂��ƁB�����āA����Ɏ��ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̖����œ���́u�z�U���i�v������Ԃ����B������~�T�Ȃ̌��ߎ��ƂȂ��Ă���B
 �@�u���c���N�v�ɂ�����u�T���N�g�D�X�v�i�u�z�U���i�v���܂ށj�̋K�͂͏������B�S38���߁B���t���Ԃɂ���2�����炸�BJ.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�̂���́u�z�U���i�v������3����v����B�i�i�̍��ł���B
�@�u���c���N�v�ɂ�����u�T���N�g�D�X�v�i�u�z�U���i�v���܂ށj�̋K�͂͏������B�S38���߁B���t���Ԃɂ���2�����炸�BJ.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�̂���́u�z�U���i�v������3����v����B�i�i�̍��ł���B�@�W���X�}�C���[���u�T���N�g�D�X�v�����̂悤�ȃR���p�N�g�Ȍ`�ɂ܂Ƃߏグ���̂͐������낤�B����́A�����ł���K�͂ȃ��N�C�G���Ɖ]��ꂽ�~�q���G���E�n�C�h���́u���N�C�G�� �n�Z���v�̍\���ɂ��K���Ă��邩�炾�BM.�n�C�h���́u�T���N�g�D�X�v�́A�S���t����34���ɑ���1��30�b�B�W���X�}�C���[�̂����51���ɑ���2���B���҂قړ����䗦�ł���i���t���Ԃ͖�����CD���Q�l�ɂ����j�B�O�͂ŋL�����Ƃ���A���[�c�@���g���u���N�C�G���v��Ȃɓ�����ł��Q�l�ɂ����̂̓~�q���G���E�n�C�h���������킯������A�W���X�}�C���[�ɂ��ԈႢ�Ȃ��`�B���Ă���͂��ł���B
�@�W���X�}�C���[�́u����^�����ăR���p�N�g�ɂ܂Ƃߏグ��v�\�͂ɂ͒����Ă����B����́A���[�c�@���g������̈⌾�ȁu�z�������t�� ��1�� �j�����v�ɂ����ĂƂ��B����ɂ��āA�����E���̌����͂��邪�A�u���[�c�@���g ���̒m��ꂴ��⌾�v�i�Έ�G���u�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv�Ɏ��^�j���e�L�X�g�ɏq�ׂĂ݂����B
 �@���[�c�@���g�͐��U��4�̃z�������t�Ȃ��������B���̒��́u��1�� �j�����vK412�^514���A���̓��[�c�@���g�̎���Ɋ������ꂽ���Ƃ����������B20���I�㔼�̂��Ƃł���B
�@���[�c�@���g�͐��U��4�̃z�������t�Ȃ��������B���̒��́u��1�� �j�����vK412�^514���A���̓��[�c�@���g�̎���Ɋ������ꂽ���Ƃ����������B20���I�㔼�̂��Ƃł���B�@���̊y�Ȃ��u��1�ԁv�Ɗm�肵���̂̓��[�g���B�q�E�P�b�w���i1800�|1877�j�ł���B�ނ́A���[�c�@���g��600�Ȉȏ�ɋy�Ԗc��Ȋy�Ȃ�����ȔN�㏇�ɒʂ��ԍ���ł����l�B��i�ɕt�����Ă���K�̓P�b�w���̓������ł���B�ނ����A���[�c�@���g�����j��ő�̌��J�҂̈�l���B
�@�P�b�w���́u�z�������t�� �j�����v�̊������m��ɒ��肷��B��y�͐��̂��̊y�ȁB��1�y�͂ɂ�1782�N�̍�Ƃ����o�ŎЂ̏������݂�����A��2�y�͂̊����y���ɂ́u1797�N4��6�� �����j���v�Ƃ�����ȋL�q���������B�ނ͂�����u��1�y�͊����㉽�炩�̎���Œ��f������A��2�y�͂������グ�S�Ȃ����������v�ƍl���A��ȔN�̓���ɂƂ肩����B
�@��1�y�͂̊����N�͏������݂ɏ]��1782�N�Ƃ����i��̌����ɂ����ۂ�1791�N�ƒ������ꂽ�j�B�����K412�Ƃ���B���͑�2�y�͂̋L�q�ł���B1797�N�ɂ̓��[�c�@���g�͂��̐��ɂ��Ȃ��B������ǂ����߂���H �P�b�w���́g1797�N��10�N�O�A1787�N�h�Ƌ����Ɍ��߂Ă��܂����B�����K514�Ƃ���B���[�c�@���g�ɂ͔N����ӂ����ċL���Ȃ�����������ł���B��������͖��炩�Ɉ��Ղ��B
�@�Ă̒�A�������������B�J�g���b�N�̐��T�Ԃ́A�u�t���̓��̎��̖����̒���̓��j�����ŏI���Ƃ���T�v�ƌ��߂��Ă���B����ɓ��Ă͂߂�ƁA1787�N��4��6���͐����j���ł͂Ȃ��B1797�N��������ł���B����͈�́H �����̋^����������A�����Ȍ��_�������o�����̂̓A�����E�^�C�\���i1926�|2000�j�Ƃ����C�M���X�̊w�҂ł���B�ނ�1975�N�����10�N�̍Ό��������āA�������t�s���̃��[�c�@���g�̍�i���A�Ђ��[����m�肵���B���̕��@�͎g�p�ܐ����̊Ӓ�ɂ����̂ŁA�ڍׂ͏ȗ����邪�A�a�V�ɂ��ĉȊw�I�A�܂��ɉ���I�ȊӒ���@�������B
�@���_�������L�����B��2�y�͂̊������t��1792�N4��6���̐����j���B���������̂͂��̃W���X�}�C���[�������B�^�C�\���͎g�p�ܐ����̊���o���ƕM�Ղ̊Ӓ肩�炱�̌��_���o�����B���[�c�@���g�����̈��͓�������̂ł���B
�@��2�y�͂ɂ́A�z�����̃\���E�p�[�g�ƃX�P�b�`���L���ꂽ�ʂ̖����̊y�����c����Ă����B�^�C�\���ɂ��ƁA����̓��[�c�@���g�̐^�M�ł���B�W���X�}�C���[�́A��������ɃI�[�P�X�g���[�V�������{���Ȃ��������������ƂɂȂ�B�Ƃ��낪��̊y�����ׂ�Ɗ�ȓ_����������ƂȂ�B�ӏ������ɂ��Ă݂悤�B���[�c�@���g�̏�����������A�A�W���X�}�C���[����M���������y����B�Ƃ���B
�@��1�y�͂ɂ̓I�[�{�G�ƃt�@�S�b�g�Ƃ���2��ނ̊NJy�킪�܂܂�邪�AB�ɂ̓t�@�S�b�g�������@�@�̃P�[�X�́A���[�c�@���g�̑��̊y�Ȃł͐�ɂ��肦�Ȃ��B�W���X�}�C���[�̃E�b�J���E�~�X���̈ӂ��ǂ��炩�ł���B���̓W���X�}�C���[�炵���E�b�J���E�~�X�ƍl���邪�A����͂��Ă����A���͇A�ł���B
�@ ������
�AA��135���߂���B��141���߂ł���
�@�A�Ɋւ��Ă̓W���X�}�C���[���g���������h�͖̂��炩�ł���B����6���ߑ����̌����́A67���ߖڂ���̃z�����̃\���E�p�[�g�Ɂu�V���Ȑ������������v���Ƃɂ����̂Ȃ̂ł���B�{���ɂ��A����́g�a���҃G���~�A�̈��́h�̂P�߂Ƃ̂��ƁB���̉̂����T�Ԃɉ̂�����̂ł��邱�Ƃ���A���̏��Ƃ̓W���X�}�C���[�̃��[�c�@���g�ւ̈����̈ӁA�ƒ��҂͐������Ă���B���A�ʂ����āH
�@�W���X�}�C���[���������u1792�N4��6�������j���v�Ƃ������t�́A�R���X�^���c�F�i�����[�c�@���g�j���u���N�C�G���v��M�Ɏw�������A�C�u���[�������o��������ł���B�ނ̒��ɂ́A�u���܂����₪��v�Ƃ����C�����Ɓu�w���N�C�G���x������������̂͂��̎����������Ȃ��v�Ƃ��������S���t�c�t�c�ƗN���Ă����Ǝv����B�g�G���~�A�̈��́h�}���̃R�R���B����́A���[�c�@���g�ւ̈����̈ӂƂ��������A���Ȃ̎��͂��ߏ��]�������t�ւ̂����₩�ȓ��ĕt���ł͂Ȃ������낤���I�H �ނ͂���ɂ��C�������Z�b�g���A�u���N�C�G���v��M�����Ɖ]����ƂɌ������ĕ��ݏo�����̂ł���B
�@���́A���́g�G���~�A�̈��́h�̐������āu������H�v�Ǝv�����B�ǂ����ŕ��������Ƃ�����B����͍���u���c���N�v�𖾂ɂ����蕷�����A�~�q���G����n�C�h���́u���N�C�G�� �n�Z���v��1�Ȃ�Te decet hymnus,Deus,in Sion�̕����������B���̐����́u���c���N�v����ӏ��̂���Ƃ͎O�x�Ⴂ�̑����t���[�Y�B���ꂪ�u�G���~�A�̈��́v��1�߂ł��邩�ǂ����͖��������A����͂��Ă����A���̃��[�c�@���g�|�W���X�}�C���[�|�~�q���G���E�n�C�h���̌��т��ɕs�v�c���o����̂͊m���ł���B
�@���āA�����Ŏ��������������ƁB����́A�u�W���X�}�C���[�͖����̑f�ނɃX�p�C�X�𒍓�����Ȃǂ��đS�̂��܂Ƃߏグ��˂�����v�Ƃ������Ƃ��B�u�z�������t�ȑ�1�ԁv���A�g�G���~�A�̈��́h�̃t���[�Y�𒍓����邱�Ƃɂ���ă������R���b�N�ȐF�ʂ������A����Ȃ閣�͂��t������Ă���B��搶���͂ǂ��v���悤���A���ɂ͂���������B�����Ă݂Ă������������B�����A67���ߖڂ���̃t���[�Y�Ƀn�b�Ƃ������邱�Ƃ��낤�B
�@�ނ͂܂����炾�����u�T���N�g�D�X�v���A�t����̎w���𗊂�ɂ���Ȃ�ɍ��グ���B���[�c�@���g�̎w���Ƃ́H�u��11�ȁw�T���N�g�D�X�xSanctus�́A�w�ǎ��@�~�T�x�����p����v�������B���ꂪ���̐����ł���m�M�ł���B
�@�����āA�W���X�}�C���[�͎��Ȃ�^�[�Q�b�g12�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ւƐi�ށB�Ƃ��낪�ނ͂����łƂ�ł��Ȃ��~�X��Ƃ��̂ł���B
���Q�l������
���[�c�@���g�u�~�T�E�\�����j�X �n�Z��K139 �ǎ��@�~�T�vCD
�@�@�@�N���I�x���[�w���F�P���u���b�W�E�L���O�Y�J���b�W���̑�
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z�� K626�vCD
�@�@�@���q�^�[�w���F�~�����w���E�o�b�n�nj��y�c�������c
�~�q���G���E�n�C�h���u���N�C�G�� �n�Z���vCD
�@�@�@�{���g���w���F�U���c�u���N�E���[�c�@���e�E���nj��y�c
J.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z�� BWV232�vCD
�@�@�@���q�^�[�w���F�~�����w���E�o�b�n�nj��y�c�������c
���[�c�@���g�u�z�������t�ȏW�vCD
�@�@�@�^�b�N�E�F�� �z�����Ǝw���F�C�M���X�����nj��y�c
�u�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv�Έ�G���i�w��M���Ɂj
2015.04.29 (��) ���c���N�Ɏa�荞��4�`�u�܂̓��vLacrimosa�ɂ����郂�[�c�@���g�̎w��
�@�u���N�C�G���v�Ɋւ���W���X�}�C���[�̂���ȏ،����c���Ă���B���C�v�c�B�q�̑�艹�y�o�ŎЃu���C�g�R�b�v�E�E���g�E�w���e���ֈ��Ă��莆�ł���B���[�c�@���g���g�̐������Ɂu���Օ��v�u�L���G�v�u�{��̓��v�u��C�G�X��v�Ȃǂ��A�ꏏ�ɉ��t������̂����肵�܂����B�܂��A���̋Ȃ̎d�グ�ɂ��Ĕނ������Ύ��ɘb�������Ƃ�A�I�[�P�X�g���[�V�����̕��@���ɂ��Ď��ɋ����Ă��ꂽ���Ƃ͏O�m�̎����ł��B���͂��̋Ȃ����I�Ȑl�����ɁA�ނ̋����̐Ղ����̒��ɂ��邱�Ƃ��Ƃ��ǂ��������Ă��炦��悤�ɏ�����ΐ������Ǝv���Ă��܂����B�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�Ɓu�_�̎q�r�v�͂܂������V����������Ȃ��܂����B�@���̓R���X�^���c�F�ł���B
��l�̎��̋߂����Ƃ�m�������A�W���X�}�C���[�Ƙb�����Ă���A�������̍�i����������O�ɂق�Ƃ��Ɏ���ł��܂�����A����ɂ��������čŏ��̃t�[�K���Ō�̋Ȃł��肩�����Ă����悤�ɗ���ł��܂����B�@��L��̏،��͐��낪�������Ă���B�W���X�}�C���[�̑O���u���[�c�@���g�̋��������������Ƃ�F�߂Ă���v�����͐^���B�㔼�����́g�܂������h�Ƃ����`�e�����������|��B�g���[�c�@���g�̎w�����Ȃ������h�Ǝ��邩��ł���B���́A�����ɓ������Ắu���ׂĂɂ킽�胂�[�c�@���g�̎w�����������v�ƍl������̂ł���B�����łȂ���Β��낪����Ȃ����炾�B
�@���̎莆�̑_���B����̓W���X�}�C���[�̎���PR���낤�B���̂Ƃ�26�B�Ⴋ��ȉƂɂƂ��ėL�͏o�ŎЂւ̃A�s�[���͑傫�ȈӖ������B�u3�Ȃɂ��ẮA���[�c�@���g�̗͂��肸���ׂĎ��͂ō�Ȃ����v�ƌ֎��������C�����͂悭����B
�@�R���X�^���c�F�̏،��͐������ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ��낤���B�u�I�ȁw���̔q�̏��x���w�L���G�x�̃t�[�K�Œ��߂�Ƃ����Z�̓W���X�}�C���[�ł͎v�����Ȃ��v�Ǝv���邩�炾�B�A���g����ɂ��������āh�̌��͕s���ł���B����Ƃ����قǂ̎��Ⴊ���Ɍ�������Ȃ�����B
1 ���Տ� Introitus �@2 �L���G Kyrie �@3 �{��̓� Dies irae 4 �@���Ȃ郉�b�p Tuba mirum �@5 �݂��̑� ��Rex tremendae �@6 ���R���_�[�� Recordare �@7 ���ꂵ�� Confutatis �@8 �܂̓� Lacrimosa �@9 ��C�G�X ��Domine,Jesu �@10 ���Ȃ鐶�� Hostias �@11 �T���N�g�D�X Sanctus �@12 �x�l�f�B�N�g�D �XBenedictus �@13 �_�̎q�r Agnus Dei �@14 ���̔q�̏� Communio
�@�����ʼn��߂āA�W���X�}�C���[�ׂ̈��������u���N�C�G���v�����`���m�F���Ă��������B�����ڎw���̂̓��[�c�@���g�̃W���X�}�C���[�ւ̎w���𖾂炩�ɂ��邱�ƁB�����A�u���N�C�G���v�̊����`����A�[�I�ɒH��A�g���̌`�ɗ����������߂ɂ̓��[�c�@���g����ǂ̂悤�Ȏw�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������h���𖾂��邱�Ƃł���B
�@��1�ȂƑ�2�Ȃ̓��[�c�@���g�̎�ɂ�芮���ς݁i��2�Ȃ̓t���C�V���e�b�g���[�̕�M����A���j�Ȃ̂ŏ��O�B�ΏۂƂȂ�̂́A��3�ȁ|��14�ȁB���̂�����3�ȁ|��7�ȁA��9�ȁA��10�Ȃ̓I�[�P�X�g���[�V�����̖��Ȃ̂ł��܂�H�w�������Ȃ��B��B��8�A11�|14�Ȃ͍�Ȃ������䂦���ɋ����[���B����ł́A��8�ȁu�܂̓��v���珇��ǂ��Ďa�荞��ł䂱���B
�i�P�j��8�ȁu�܂̓��vLacrimosa
 �@���[�c�@���g��8�u�܂̓��v�̂W���߂܂ł������ĖS���Ȃ����A���ꂪ��M�ł���E�E�E�E�E�Ƃ����̂�����ł���B���A�ߔN�A10�u���Ȃ鐶�сv�̖���Quam olim da capo�̎w������M�ł͂Ȃ����A�Ƃ̎w�E���łĂ����B�����A����肷��͍̂���ɂ��āA�{�҂̎�|����Y����B����ڑO�ɂ������[�c�@���g�̃y���͊����ւ̈ӎu�Ƒ̒��̃M���b�v�ŕ��ʂ̂���������f�r�������낤���A��M���ǂ����낤���u���[�c�@���g�̎w�����𖾂���v���ƂƂ͊W���Ȃ�����ł���B
�@���[�c�@���g��8�u�܂̓��v�̂W���߂܂ł������ĖS���Ȃ����A���ꂪ��M�ł���E�E�E�E�E�Ƃ����̂�����ł���B���A�ߔN�A10�u���Ȃ鐶�сv�̖���Quam olim da capo�̎w������M�ł͂Ȃ����A�Ƃ̎w�E���łĂ����B�����A����肷��͍̂���ɂ��āA�{�҂̎�|����Y����B����ڑO�ɂ������[�c�@���g�̃y���͊����ւ̈ӎu�Ƒ̒��̃M���b�v�ŕ��ʂ̂���������f�r�������낤���A��M���ǂ����낤���u���[�c�@���g�̎w�����𖾂���v���ƂƂ͊W���Ȃ�����ł���B�@�u�܂̓��v�ɂ�����ő�̃|�C���g�́A���[�c�@���g�͂��̊y�Ȃ��g�t�[�K�Œ��߂�����h�ƌ��߂����Ƃɂ���B���̏؋��́A�E�H���t�K���O�E�v���[�g�ɂ���Ă����炳�ꂽ�B1962�N�A�ނ̓x�����������}���ق̑��e�̒�����A���[�c�@���g�̎�ɂȂ�16���߂̃t�[�K�̃X�P�b�`�������̂ł���B
�@����ɂ��āA���y�]�_�ƁE�E�R�뎁�́u�w�܂̓��x�̍Ō�Łw�Z�N�G���c�B�A�x�S�̂���߂�����w�A�[�����x�́A�t�[�K�Ƃ��č�Ȃ���̂��`���ł���A���[�c�@���g�������炭���̂��肾�����v�i�V�����e�B�w���E�B�[���E�t�B��1991�^��CD�̃��C�i�[�m�[�c�j�Əq�ׂĂ���B
�@�����ő����A�u�ŐV���ȉ���S�W�v�i���y�V�F�Ёj����A���[�c�@���g�ȑO�́u���N�C�G���v�ׂĂ݂��B�I�l�Q���i1425?�|1497�j�A�s�G�[���E�h�E���E�����[�i1460?�|1518�j�A���b�X�X�i1532?�|1598�j�A�r�N�g���A�i1584?�|1611�j��4�Ȃ��ΏۂƂȂ���A�u�Z�N�G���c�B�A�v�̑��݂��̂��̂��Ȃ������B���݂Ɂu�Z�N�G���c�B�A�vSequentia�Ƃ́u�����v�Ɩ�A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�ł����A��3�ȁ|��8�Ȃ̑��̂̂��Ƃł���B
�@���ɁA�u���N�C�G���vCD�W����A���[�c�@���g�Ȍ�́u���N�C�G���v�Łu�Z�N�G���c�B�A�v�̍Ō���u�A�[�����vAmen�Œ��߂�����y�Ȃ��Ă݂��B�Y������̂̓V���[�}���A���F���f�B�A�T���E�T�[���X�A�h���H���U�[�N�����A�����ɂ̓t�[�K�̌��Ђ��Ȃ������B����ł́u�w�A�[�����x�̓t�[�K�Ƃ��č�Ȃ���̂��`���v�Ƃ͂ƂĂ������Ȃ��B�Ȃ�A���[�c�@���g���������u�t�[�K�Œ��߂����v�ƍl�����̂́A����y�̓`������ł͂Ȃ��A�ʂ̗��R�����@���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
 �@�����m�����u�A�[�����E�t�[�K�v���̗p���Ă���u���N�C�G���v�́A�~�q���G���E�n�C�h���́u�n�Z���v�Ɓu�σ������v�����ł���B�u�n�Z���v��1771�N�A�u�σ������v��1806�N�̍�i�B���́A���[�c�@���g�u���N�C�G���v�̃��f���̓~�q���G���E�n�C�h���u���N�C�G�� �n�Z���v�ɂ���A�u�A�[�����E�t�[�K�v�̗̍p����������A�ƌ���i�u�σ������v�̓��[�c�@���g����̍�i�j�B
�@�����m�����u�A�[�����E�t�[�K�v���̗p���Ă���u���N�C�G���v�́A�~�q���G���E�n�C�h���́u�n�Z���v�Ɓu�σ������v�����ł���B�u�n�Z���v��1771�N�A�u�σ������v��1806�N�̍�i�B���́A���[�c�@���g�u���N�C�G���v�̃��f���̓~�q���G���E�n�C�h���u���N�C�G�� �n�Z���v�ɂ���A�u�A�[�����E�t�[�K�v�̗̍p����������A�ƌ���i�u�σ������v�̓��[�c�@���g����̍�i�j�B�@�u���N�C�G�� �σ������v�́A���[�c�@���g�u���N�C�G���v�Ƃ̊ԂɊ�ȕ��������݂���B���̈�쓯�m�́u���N�C�G���v�ɂ́A���Տ�Te decet hymnus,Deus,in Sion�̕����ɁA�S�������������g���Ă���̂��i���݂Ɂu�n�Z���v�̓����ӏ��ɂ��O�x�Ⴂ�����̐������p�����Ă���j�B����͋�����@�u�g�[�k�X�E�y���O���[�k�X�v�ł��邪�A���̓n�C�h���͂��̐��@��1770�N�����̏@�����u�L���X�g�҂̒����v�i�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�j�ł��łɗp���A���[�c�@���g��1771�N��Ȃ̏@�����u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�ɂ����q���Ă���i���̌��́u�N�����m�v2012.12.25�ɏڂ����j�B���A�ȏ�͂����܂ŗ]�k�B
�@�~�q���G���E�n�C�h���i1737�|1806�j�́A�����Ȃ̕����[�[�t�E�n�C�h���̒�A1763�N����U���c�u���N�{��Ɏd���A�����ō��߂���ȉƂł���B���[�c�@���g�Ƃ̐e���Ȃ��������L���ł���B�Ⴆ�Ίy�Ȃ̑ݎB�s���`�̂Ƃ��ɋȂ����������Ă���B�U���c�u���N����A�~�q���G����n�C�h���́A��Ȃ́u���@�C�I�����ƃ��B�I���̂��߂̓�d�t�ȁv���������ɊԂɍ���Ȃ��Ȃ胂�[�c�@���g�ɋ��������B�E�B�[������́A�t�Ƀ��[�c�@���g���A�}篃R���T�[�g�Ō����Ȃ��K�v�ɂȂ�A�~�q���G����n�C�h���̌����Ȃ�q�����i�����ȑ�37�ԁj�B�O�q�u�g�[�k�X�E�y���O���[�k�X�v�̌����R��ł���B
 �@�u���N�C�G�� �n�Z���v�́A�~�q���G���E�n�C�h�����d�����i���V�M�X�����g�̎��𓉂�ŏ����グ��ꂽ�B���̊y�Ȃ�p���āA1771�N12��31���A�U���c�u���N�吹���ő�i���Ǔ��̃~�T���s��ꂽ���A���[�c�@���g���q�������ɗՐȂ����L�^���c���Ă���B
�@�u���N�C�G�� �n�Z���v�́A�~�q���G���E�n�C�h�����d�����i���V�M�X�����g�̎��𓉂�ŏ����グ��ꂽ�B���̊y�Ȃ�p���āA1771�N12��31���A�U���c�u���N�吹���ő�i���Ǔ��̃~�T���s��ꂽ���A���[�c�@���g���q�������ɗՐȂ����L�^���c���Ă���B�@���́u���N�C�G���v�͋���y�̓`���ɓƎ��̌��𒍓����Č����ł���B�����Ƃ��Ă͋K�͂��傫���A�n���̃I�[�P�X�g���[�V�����͐[���������������������Ă���B����15�A�܂���K�͂ȃ~�T�Ȃ����������Ƃ̂Ȃ����[�c�@���g���傫�Ȋ����������낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�����āA20�N��A�ނ��u���N�C�G���v�����ɂ������āA�܂����ɕ����ё傢�ɎQ�l�Ƃ����̂́A���́u���N�C�G�� �n�Z���v�������Ɗm�M����B
�@�ł́A���̏؋��ƂȂ闼�҂̋��ʓ_���w�E���Ă������B��́u�܂̓��v�̃A�[�����E�t�[�K�B������́u���Ȃ鐶�сv�ɂ�����Quam olim da capo�̎w���ł���B
�@�~�q���G����n�C�h���́u���N�C�G�� �n�Z���v�́u�܂̓��v�͗��h�ȃt�[�K�Œ��߂������Ă���B����A���[�c�@���g�́u�܂̓��v���A�[������t�[�K�Œ��߂�������肾�����B���������̂悤�Ȍ`�͑��̍�ȉƂ́u���N�C�G���v�ɂ͌�������Ȃ��B���ꂪ���_�B
�@���[�c�@���g�́A10�u���Ȃ鐶�сv�̖�����Quam olim capo�iQuam olim�ɖ߂�j�ƋL���A9�u��C�G�X��v�̃t�[�K���J��Ԃ����Ƃ��w�������B����A�~�q���G����n�C�h���́u���N�C�G�� �n�Z���v�ɂ��A�S�������������{����Ă���B���ꂪ���_�ł���B
�@�Ȃ�A���̌`�͋���y�̒ʗ�Ȃ̂��H ���̖��ɂ��āA�u�A�[�����E�t�[�K�v�̂Ƃ��Ɠ���4�̊y�ȂŌ����Ă݂�E�E�E�E�E�V���[�}���͔ہA���F���f�B���ہA�T����T�[���X�͍\���Ⴂ�A�h���H���T�[�N�����������������B���������Ă��̌`�͋���y�̒ʗ�Ƃ܂ł͂����Ȃ��B���[�c�@���g�͒ʗ�ɏ]�����̂ł͂Ȃ��A�~�q���G���E�n�C�h������{�ɂ����Ƃ������Ƃ��ł���B�Ƃ͂����A�~�q���G���E�n�C�h���|���[�c�@���g�|�h���H���U�[�N�Ƃ���������u�Ă�3�̃��N�C�G���ɁA��̉B�ꂽ���ʓ_���������Ƃ͋����[�X�̕����ł������B
�@�{�͂̑����B���[�c�@���g�́u�܂̓��v�ɂ�����W���X�}�C���[�ւ̎w���́u�A�[������t�[�K�Œ��߂�v�ł������B
�@�W���X�}�C���[�́A���[�c�@���g���u�A�[�����E�t�[�K�v16���߂̃X�P�b�`���₵���ɂ��S��炸�A9���ߖڂ���̕�M�̂��Ƃ�Amen�ɓ����Ă����V���v���ɒ��߂�Ɏ~�߂��B �Ȃ��W���X�}�C���[�̓��[�c�@���g�̎w���ɔw�����̂��H �u�t�[�K�v�ׂ͉��d�������B�����Ȃ����̂͏����Ȃ��I �����͒P���ɂ����l���邵���Ȃ����낤�B���[�c�@���g���ŏ��̎w�����W���X�}�C���[�ɂ��Ȃ������̂����̕ӂ�Ɍ����̈�[������̂�������Ȃ��B
�@�Ƃ͂����A��9���߂��烉�X�g��30���߂܂ł̕�M�͗��h�Ȃ��̂��B��8���߂����9���߂ցA���[�c�@���g����W���X�}�C���[�ւ̃o�g���E�^�b�`�ȂǁA���̈�a�����Ȃ��B��Amen���Ȃ��Ȃ������I�ł���B
�@�u�Z�N�G���c�B�A���t�[�K�Œ��߂邱�Ɓv������y�̓`���Ȃ炢���m�炸�A�i��������������j�����ł͂Ȃ��̂ł��邩��A�W���X�}�C���[�̂��̑[�u�͂��Ȃ����s���Ƃ͌�����Ȃ��Ǝv���B
�@�A�[������t�[�K�̃X�P�b�`���������ꂽ1962�N�ȍ~�A�������Ƀt�[�K����Ȃ����V�Łu���N�C�G���v���������o�������i���[���_�[�ŁA�����B���łȂǁj�B�u�t�[�K�Œ��߂�v�̓��[�c�@���g�̈Ӑ}�Ȃ̂�����A���̎��݂��̂��̂͂����đR��ׂ����̂��B�����A���߂����Ȃ��̂́A����𐳓��������������߂̃W���X�}�C���[�łւ̕s���ȕ]���̘_���ł���B����ɂ��Ă͌�i�A�u�ł̔�r�����v�̍��ōs�������B
�@�u�܂̓��v��P��Amen�̓Œ��߂��W���X�}�C���[�̏��Ƃ́A�������t�[�K�Œ��߂����������[�c�@���g�̈ӎv�ɔ�����A�Ƃ͂悭�������_�]�ŁA�m���ɂ��̒ʂ�ł���B�����A�W���X�}�C���[���̘_���͐T�ނׂ����낤�B���[�c�@���g�̃X�P�b�`������ɂ��S��炸�A�Ȃ̖��n�ȃe�N�j�b�N���g�����Ƃ������Ƃ����A���ȐӔC�͈͓̔��ŕʂ̌`�ł܂Ƃߏグ���ނ̑n���s�ׂ́A�ނ���^����Ă�����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B���͂����v���B�W���X�}�C���[ Good job�I�ł���B
���Q�l������
�u���[�c�@���g�Ō�̔N�vH.C.���r���X�E�����h���� �C�V�V�q��i�������_�V�Ёj
�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v���c�r�꒘�i�u�k�Ќ���V���j
�~�q���G���E�n�C�h���u���N�C�G�� �n�Z���vCD
�@�@�@�{���g���w���F�U���c�u���N�E���[�c�@���e�E���nj��y�c
�@�@�@G.Kraus�����C�i�[�m�[�c
���[�c�@���g�u���N�C�G�� �j�Z�� K626�vCD
�@�@�@�V�����e�B�w���F�E�B�[����t�B���n�[���j�[�nj��y�c
�@�@�@�E�R�뒘���C�i�[�m�[�c
2015.04.12 (��) ���c���N�Ɏa�荞��3�`�R���X�^���c�F ���̌����ȍٗ�
���R���X�^���c�F�̕������@���[�c�@���g���S���Ȃ��Ė��S�l�ƂȂ����R���X�^���c�F�i1762�|1842�j�B���ꂩ��A7��0�Γ�l�̎q��������Đ����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�́A���Y�ǂ��납�A�����z�i3,000�O���f���Ƃ��j�̎؋����c���Ă��ꂽ�B���ʂ̃e�[�}������ƂȂ����͎̂��ɓ��R�̂��Ƃ��B
 �@�R���X�^���c�F�́A�v�̎����T�Ԃ��o���Ȃ�12��11���A�c��ɔN���̎x���ƕv�̎؋��ԍς̂��߂̃R���T�[�g�J�Â̋���\���A������B����́A���[�c�@���g��4�N�ԋ{���ȉƂƂ��ē��������тɂ����̂��낤�B����ɁA�E�B�[���c��́u���[�c�@���g�̖��S�l�ƈ⎙���E�B�[���ō������邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�ʁv�ƌ��c����B���[�c�@���g�̎�����B�R���X�^���c�F�ɒǂ����������n�߂��B����W���[�i���X�g�́u�q���ƕv�̔���Ȏ؋�������A�m�̑܂̏�ł��ߑ��������S�l�v�ƌ`�e����B�R���X�^���c�F�́A�g���[�c�@���g�̍����������S�l�h�Ƃ�������I���_��w�i�ɁA���͓I�ɍs�������B�ƐŊٌ���u���J�v�����̎��v�̈ꕔ��B�����c�A�h���X�f���A���C�v�c�B�q�A�x�������Ȃǂ̊e�s�s�ŃI�y���̌�����łB�y����B�Ȃǂ��āA���ɂ͕v�̎؋���S�z�ԍς����B�Ȃ��Ȃ��̂���ł���B
�@�R���X�^���c�F�́A�v�̎����T�Ԃ��o���Ȃ�12��11���A�c��ɔN���̎x���ƕv�̎؋��ԍς̂��߂̃R���T�[�g�J�Â̋���\���A������B����́A���[�c�@���g��4�N�ԋ{���ȉƂƂ��ē��������тɂ����̂��낤�B����ɁA�E�B�[���c��́u���[�c�@���g�̖��S�l�ƈ⎙���E�B�[���ō������邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�ʁv�ƌ��c����B���[�c�@���g�̎�����B�R���X�^���c�F�ɒǂ����������n�߂��B����W���[�i���X�g�́u�q���ƕv�̔���Ȏ؋�������A�m�̑܂̏�ł��ߑ��������S�l�v�ƌ`�e����B�R���X�^���c�F�́A�g���[�c�@���g�̍����������S�l�h�Ƃ�������I���_��w�i�ɁA���͓I�ɍs�������B�ƐŊٌ���u���J�v�����̎��v�̈ꕔ��B�����c�A�h���X�f���A���C�v�c�B�q�A�x�������Ȃǂ̊e�s�s�ŃI�y���̌�����łB�y����B�Ȃǂ��āA���ɂ͕v�̎؋���S�z�ԍς����B�Ȃ��Ȃ��̂���ł���B�@���̌�R���X�^���c�F�̓f���}�[�N�̊O�����Q�I���N�E�j�R���E�X�E�j�b�Z���i1762�|1826�j�ƍč��B�j�b�Z���͍Ȃ̘b�����Ƀ��[�c�@���g�̓`�L�������i�u���[�c�@���g�`�v1829���s�j�B�R���X�^���c�F��80�̒�����S���A27,000�O���f���i6,500���~�j���̍��Y���c�����B
�@���[�c�@���g�̎���A��r�I�����i�K�Ő�����̖ړr�͂������̂́A�R���X�^���c�F�ɂƂ��āA�u���N�C�G���v�����̕�V50�h�D�J�[�e���i60���~�j�͈����͂Ȃ��B�o����Α��ڂɎd�グ�����B�ޏ��́A����ւ̐\���ƕ��s���āA������ɂ��ӂ𒍂��B
�@�R���X�^���c�F���A�܂��˗������̂̓��[�[�t�E���I�|���g�E�A�C�u���[�i1765�|1846�j�������B�A�C�u���[�����B���ߐ��1792�N3���Ǝw�肵���B�Ƃ��낪�A�����Ɏ����Ă����y���ɂ́A��3�Ȃ����7�Ȃ܂ł̕�M�Ƒ�8�ȁu���N�����T�v�̃��[�c�@���g���y�����~�߂��ӏ�����͂�2���߂������������A��9�ȁ\��14�Ȃɂ͑S�������߂Ă��Ȃ������̂ł���B
�@����́A�R���X�^���c�F�̑z����H����Ƃ��z��O�H ����͂Ƃ������A�ޏ����ŏ��Ɉ˗������̂��A�Ȃ��W���X�}�C���[�ł͂Ȃ��A�C�u���[�������̂��H �ɂ��Ă͋c�_�̗]�n���c��B�Ȃ��Ȃ�A�R���X�^���c�F�́u�����ԋ߂ɍT�������[�c�@���g���A�w���N�C�G���x�̊����菇��`�������̂̓W���X�}�C���[�ł���v���Ƃ�N�����m���Ă�������ł���B
�@�ȉ��A��N�����ꂽ�u���[�c�@���g�A�w���N�C�G���x���W���X�}�C���[�֓`���v�̏�3����L�������B
���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�������ւ�ȔM�ӂ������č�Ȃ��܂����B���������Ă���ƁA�W���X�}�C���[���A����ށi���[�c�@���g�j�ƈꏏ�ɁA�ނ����������̂��̂�Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B���������W���X�}�C���[�̓��[�c�@���g����{���̃��b�X�������̂ł��B���[�c�@���g���W���X�}�C���[�ɂ悭���������Ă����̂��������Ă���悤�ł��B�u���������A���J�̒��œ˂����Ă�A�q���݂�������Ȃ����B���܂Ōo���Ă��킩�����v�A���������ƁA�H�y�������A�W���X�}�C���[�ɂ͖����ȏd�v�ȕ������������Ă��܂����v�i1827�N5��31���t���R���X�^���c�F����}�N�V�~���A���E�V���^�[�h���[�t�ւ̎莆���j�@�����̎��Ⴉ��A���[�c�@���g���w����������̓W���X�}�C���[�ł��邱�Ƃ��������B�Ƃ��낪�A���̏���R���X�^���c�F�Ɩ��ł��邱�Ƃ���A����炪�u�R���X�^���c�F�̍��b�v�ł���Ƃ�����������������̂��������B�Έ�G�搶�Ȃǂ́u����́A�g�W���X�}�C���[�̕�M�����́A���[�c�@���g�̒��`�ł��邩�炵�āA�����ł���h�Ƃ����������߂̃R���X�^���c�F�̍��b�ł���A�R�ł��邱�Ƃ͖����ł���v�Ƃ܂Œf�����Ă���B���A�ʂ����āH
���̓��[�c�@���g�̍Ō�̓��X�ɂ��Ă��b���Ȃ���Ȃ�܂���B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�W���X�}�C���[�����[�c�@���g�̃x�b�h�̖T��ɂ��܂����B�u���N�C�G���v�̕����ӂƂ�̏�ɒu���Ă���A���[�c�@���g���A�����������Ƃǂ�����Ďd�グ�邩�A�Ƃ����Ӑ}��������Ă��܂����B
�E�E�E�E�E���[�c�@���g���Ō�ɂ��Ă������Ƃ́u���N�C�G���v�̃e�B���p�j�[�̃p�b�Z�[�W���A���ʼn̂����Ƃ��邱�Ƃł����B���ł��܂����ꂪ�������Ă���悤�ł��B�i���[�c�@���g�̎��̑O���A1791�N12��4���̗l�q��`����R���X�^���c�F�̖��]�t�B�[�̎莆�B�`�Z�j�b�Z���Ɉ��Ă����́j
�S���Ȃ鏭���O�ɁA���[�c�@���g�͕v�l�ƃW���X�}�C���[�Ƌ��Ɂu���N�C�G���v���̂������A�������̊y�͂͗܂𗬂��قǔނ�J�T�ɂ����B�����āu�����l������A���ꂪ�ł��d�v�ȂƂ��낾�v�ƌ����Ȃ���A�܂��u���R���_�[���v�i��6�ȁj�Ǝ�v�ȃp�[�g���������B���ꂪ�I���ƁA�W���X�}�C���[��T��ɌĂсA�������̍�i����������O�Ɏ���������A�`���ɏ������t�[�K���J��Ԃ����ƁB�܂����̕����Ɋւ��āA���łɃX�P�b�`�������̂��A�ǂ��ɂǂ̂悤�ɓ��Ă�ׂ����A���w�������B�i�C�M���X�̍�ȉƃ��B���Z���g�E�m���F���v�Ȃ��R���X�^���c�F�Ƃ̉�b�����Ƃ�1829�N�ɏ�������L�A�o�ł�1955�N�j
���W���X�}�C���[ ��͂肠�������Ȃ��恄
�@���[�c�@���g�^�R���X�^���c�F�^�W���X�}�C���[ ����ȊW�ł��������Ƃ͑O��q�ׂ��Ƃ���ł���B
�@�R���X�^���c�F�́A1791�N6�����{�\7�����{�܂Ńo�[�f���ɑ؍݂��Ă��邪�A�㔼����̓W���X�}�C���[��������Ă���B�E�B�[���ɖ߂�7��26���l�j���o�Y�B�N�T���@�[�Ɩ����B���̂��Ƃ���A���̎q�̓��[�c�@���g���F�́g�N�T���@�[�h�E�W���X�}�C���[�̎q�ł͂Ȃ����Ƃ̉��������܂��B9���A���[�c�@���g�v�ȃv���n�ɍs���I�y���������B�W���X�}�C���[���s�B10��7���R���X�^���c�F�ƃW���X�}�C���[�A�ēx�o�[�f���ɁB10��14���A�E�B�[���̃��[�c�@���g����o�[�f���̃R���X�^���c�F�ւ̎莆�ɂ́u�^�Ƃ͍D���Ȃ悤�ɂ����܂��v�Ƃ���B�^�͖��_�W���X�}�C���[�̂��ƁB���ꂼ���F�̏H
�@�����1791�N�̈�A�̓�������A�u�R���X�^���c�F���A�w���N�C�G���x�̊����̈˗����A�ŏ�����W���X�}�C���[�ɂ��Ȃ������̂́A�킩��ʂ킯�ł͂Ȃ��B�g�O�l���сh�̓�l�̒j�̂����̂ЂƂ肪�����c������i�̐K�ʂ������A�����ЂƂ�ɂ�����Ƃ����̂��A�͂����邱�Ƃɂ������Ȃ��v�i�u���[�c�@���g�A���̒m��ꂴ��⌾�v�Έ�G���j�Ȃ錩�����o�Ă���B
�@����ȑ��ʂ��m���ɂ��������낤���A�R���X�^���c�F���u���N�C�G���v�̊������A�C�u���[�Ɉ˗������̂́A���[�c�@���g�̈ӎv�ɂ����̂��낤�B���[�c�@���g�̓W���X�}�C���[���g�Ƃ�܁A�傫�ȃ��o�i�o�J�j�h�Ɖ]���Ĝ݂�Ȃ������̂ɑ��A�A�C�u���[�̎��͍͂����]�����Ă����B�����ɔނ��������A�C�u���[�̏ؖ����ւ̐��E��������B
���ɏ������鎄�́A�����L���郈�[�[�t�E�A�C�u���[�����A���̖�������ƃA���u���q�c�x���K�[�̍���ł���A�������肵����b�̂����ȉƂł���A�����y�ɂ�����y�̗l���ɂ��������ʂ��A�|�p�̋Ȃ̕���ɂ��n�����Ă���A���̂����������ꂽ�I���K���t�҂�N�����B�[�A�t�҂ł��邱�Ƃ�F�߂܂��B��Z�Ɍ����A����قǂ̐V�i��ȉƂɁA�ɂ��ނ炭�́A���ї����肪���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�iWikipedia�j�@�܂��ɐ�^�ł���B�����̗��ꂩ��A�u���N�C�G���v�����ւ̃��[�c�@���g�̈ӎv����͂���Ƃ����Ȃ�B�u�W���X�}�C���[�ł͂Ȃ��A�C�u���[�Ɉ˗����ׂ��B�ނ̂ق����D��Ă���̂�����B�������A�ׂ��Ȏw���͂��ׂăW���X�}�C���[�ɂ��Ă���B�T��ɂ����̂̓��c����������B�x�X�g�͓�l�ɋ��͂����邱�Ƃ��v�B�R���X�^���c�F�����̎w�����Ă������Ƃ͂܂��ԈႢ�Ȃ����낤�B
�@�R���X�^���c�F�ɂ��Ă��A�u���[�c�@���g���w�������̂̓W���X�}�C���[�v�Ȃ邱�Ƃ͏\�����m���Ă���B������܂ł��Ȃ��B������A�傢�Ɍ˘f���B�u�Ȃ��W���X�}�C���[����Ȃ��́H��l�̎��͍��Ȃ�Ď��ɂ͔���Ȃ��v�B�����������A�����ŏ��炷�ׂ��͕v�̎w���ł���B
�@�R���X�^���c�F�́A���[�c�@���g�̈ӌ������݃W���X�}�C���[�ɒʒB�B�u�A�C�u���[�ɗ��ނ��Ƃɂ�����B���̐l���������������炵�傤���Ȃ�����Ȃ����B�����炱���͔ނɋ��͂��Ă���Ă������v�B�W���X�}�C���[�ނ����B�u�Ȃ�����B���[�c�@���g�t���狳���������̂͂��̉������B������̂Ȃ����Ă݂ȁv�B���S�l�Ƃ킯�A���̒j�ɒs�b���܁H��������B
�@����ȓ�l�̏𗠕t����R���X�^���c�F�̋��q���c���Ă���B�O�o�A�u�R���X�^���c�F����}�N�V�~���A���E�V���^�[�h���[�t�ւ̎莆�v�̌㔼�����ł���B
�������̋Ȃ���������悤�ɂƃA�C�u���[�ɓn�����̂́A�����i�ǂ����Ă��������͎v���o���Ȃ��̂ł����j�W���X�}�C���[�ɂ��炢�炵�Ă�������ł��B����Ƀ��[�c�@���g���g���A�C�u���[�����������Ă��܂����B�@�����ȃR���X�^���c�F���u�v���o���Ȃ��v�͂��͂Ȃ��̂����A����͂Ƃ������A�ޏ��̓W���X�}�C���[�̋��͂������Ȃ��܂܁A�A�C�u���[�ɒP�ƈ˗��B1791�N12���A4�����̊�������āB���������ăA�C�u���[�u�����܂ł�����t�B�����ق��v�B�����ǂ�����R���X�^���c�F�B�W���X�}�C���[�͂ނ��ꂽ�܂܂��B�����ŁA���̍�ȉƂɓ����邪�f����B�ő��W���X�}�C���[�������Ȃ��B�������Ă���ꍇ����Ȃ��B�u�W���X�}�C���[�A�@�������Ă������B���������Ȃ��v�B�g�������ɁA���������A���ʕ�V������Ȃ�Ɏ�茈�߂����Ƃ��낤�B�C��R��̃R���X�^���c�F�ɂ��Ă݂�A����͂��₷�����Ƃ������H �W���X�}�C���[�A�u���傤���˂��Ȃ��B����Ă�邩�v��ӎd���Ȃ��A���S�U�}�[�~���Ŏ���B���[�c�@���g���`�̎w���ɏ]��1792�N12���A��_�ɂ����̑�d���ɃP���������B�������ă��[�c�@���g���₵�������̑��u���N�C�G���v�͌��������������̂ł���B
�@���̂�����̃R���X�^���c�F�̍ٗʂ͌����Ƃ����ق��͂Ȃ��B�܂��͖S�v�̈ӌ��ɉ����ē����B����ʂƌ�����_��ɑΉ��B�����ɂ�������B��ʂ��_�����B�����ւ̋����ӎu�B�_��ȑΉ��́B痂������s�́B�l���炵�̔\�́B�ޏ��Ȃ�A�ǂ�Ȏ���ł������������낤�B���Ȑ��Ȃǂ����H�炦�I�H
�@�Ђ�W���X�}�C���[�B�ނ͊m���ɍ�ȉƂƂ��Ă͖}�f��������������Ȃ��B��ȉƂɂ͑n���͂��v�������B�M���ƌ��������Ă������B�W���X�}�C���[�ɂ͂��ꂪ�R���������B�����u�^����ꂽ���̂��܂Ƃ߂�����\�́v�ɂ͒����Ă����B�����āA�f���J�V�[�ɂ͖R�������ʁA�����̂Ȃ���_�����������킹�Ă����B�t���[�c�@���g���u�Ƃ�܁A�傫�ȃ��o�v�ƕ]�����̂͂܂��ɂ��̋C�����w���Ă̂��Ƃ��낤�B����Ȃ��ƂɁA���ꂪ�����ւ̑傫�ȃp���[�ƂȂ����̂ł���B
�@�m���ɁA�R���X�^���c�F�̉�z�́A�u�W���X�}�C���[�̎�ɂȂ�w���N�C�G���x�̓��[�c�@���g���`�ł���v���Ƃ𗠂Â����������߂̌�t��������Ȃ��B�����ɂ����āA���b�̉\���͔ے�ł��Ȃ��B�����������A�W���X�}�C���[���u���N�C�G���v���M�������������Ƃ͕�����Ȃ������ł���A�ނɂ��̎�̍˔\�����������Ƃ��m�����B���Ȃ��Ƃ��A�C�u���[���́B�����A���[�c�@���g�͂���ɋC�Â��Ȃ������B�����C�Â��Ă�����A�ŏ�����W���X�}�C���[��E�߂��͂��ł���E�E�E�E�E���䉺�Â� �ׂ̎Ő��͐��B���̓V�˃��[�c�@���g���A�W���X�}�C���[�́g�܂Ƃ߂�����\�́h�͊��m�ł��Ȃ������̂ł���B
���Q�l������
�u���[�c�@���g�Ō�̔N�vH.C.���r���X�E�����h���� �C�V�V�q��i�������_�V�Ёj
�u���[�c�@���g�v���C�i�[�h�E�\�������� �Έ�G��i�V���فj
�u���[�c�@���g�̎莆�v�����p�Y�ҁi���w�فj
�u�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv�Έ�G���i�w��M���Ɂj
�u�f��̃��[�c�@���g�v�Έ�G���i�������Ɂj
2015.04.01 (��) ������ƕς������̒��� with Ray �����
�@���[��Ray�����B���C�ŕۈ牀�ɒʂ��Ă邩���B�Ђ悱�g����肷�g�ɐi�������ĂˁB�I���f�g�E�I ����ɁA�Ăɂ͂��o�����ɂȂ��ˁB���ꂩ������邭���C�Ŋ撣�낤�I�I�@���ĂƁA���N�ɓ����ăj���[�X���ς��B�s������t�B �l�������I������Ƃ���ŁA�U��Ԃ��Ă��������B�v�����܂܂ɂˁB
 �@2���A�V���A�œ�l�̓��{�l��I�r�ɏ��Y���ꂽ�B�C�X�����ߌ��h�̖\���͎~�܂�Ƃ����m��Ȃ��B3��18���ɂ̓`���j�W�A�̔����قŃe���������B�ό��q���_�����{�l3�l���܂�21�l���E�Q���ꂽ�B��u�u�Ȃ�Ŋ댯�n�тɍs���́H�v�Ȃ�Ďv�������ǁA����̓C�^���A���̃I�v�V���i���E�c�A�[�B���s�q�ɐl�C�̒n���C�N���[�Y�̓r���������̂��B���ꂶ��܂����傤���Ȃ��B����C�����邵���Ȃ���ˁB�Ɛl�̓`���j�W�A�̃C�X�����ߌ��h�u�A���T�[���E�V�����[�A�v�Ƃ��BIS�ɒ����𐾂��O���[�v���������B
�@2���A�V���A�œ�l�̓��{�l��I�r�ɏ��Y���ꂽ�B�C�X�����ߌ��h�̖\���͎~�܂�Ƃ����m��Ȃ��B3��18���ɂ̓`���j�W�A�̔����قŃe���������B�ό��q���_�����{�l3�l���܂�21�l���E�Q���ꂽ�B��u�u�Ȃ�Ŋ댯�n�тɍs���́H�v�Ȃ�Ďv�������ǁA����̓C�^���A���̃I�v�V���i���E�c�A�[�B���s�q�ɐl�C�̒n���C�N���[�Y�̓r���������̂��B���ꂶ��܂����傤���Ȃ��B����C�����邵���Ȃ���ˁB�Ɛl�̓`���j�W�A�̃C�X�����ߌ��h�u�A���T�[���E�V�����[�A�v�Ƃ��BIS�ɒ����𐾂��O���[�v���������B�@2010�N�Ɏn�܂����A���u�̏t�́A�����`���j�W�A�̃W���X�~���v�������[�������B�g�y�����A���W�F���A�A�G�W�v�g�A���r�A�A�V���A�B�����ȂׂĂ��܂������Ă��Ȃ��B���r���[�A�s����A��������B�B�ꐬ�������̂��`���j�W�A�Ƃ����Ă����B�Ƃ��낪�ǂ������B���Ɨ��͂ނ���オ���Ă���B�������̐����͂����Ƃ��悭�Ȃ�Ȃ�����Ȃ����I IS�ɓ������҂̐��͐��E�ő�Ƃ��B���̎����A���̏ے��E�������������Ƃւ̐���!? �ނ�̘c�_���������ɂ���B
�@�C�G�����̓����ɃT�E�W�A���r�A����������ˁB2012�N�A�������A���u�̏t�ŃT���n�ƍِ���������B���哝�̃n�f�B�b�萭�����a�������B���������ɔ����ăV�[�A�h�̉ߌ��h�g�D�t�[�V�h���䓪�i����̓C���N���V���A�ɂ�����IS�Ƒ����j�B�t�[�V�h���C�������x���B�����V�[�A�h������ˁB�����ŃX���j�h�̃T�E�W�A���r�A���n�f�B�����x���ɉ�����Ƃ����킯���B�ŁA���̌��ɂ̓A�����J������B�������A�A�����J�́A��IS�ł̓C�����ɋ�������Ƃ�����d�\���B
�@���ăC�G�����͓�k�ɕ�����Ă���A�k�C�G�����̓A�����J�A��C�G�����̓��V�A���o�b�N�������B���X�Ύ�͓���Ă��B���݁A��ɂ́u�A���r�A�����̃A���J�C�_�v�Ɩ����X���j�h�̉ߌ��h�����āA�����1���A�p���ŃV�������[�E�G�u�h�Ђ��P�����Ă���B
�@����͂�A�Ȃ�ĕ��G�B �����h�A���̐��h�A�X���j�h�A�V�[�A�h�A�A���J�C�_�AIS�A�T�E�W�A���r�A�A�C�����A�A�����J ���藐�ꗍ�ݍ����B���ɕ��G����B���������̏k�}���ˁB�ŁA���̂悤�ȏ͉ʂĂ��Ȃ��L�������Ȃ��������낤�B�e���̃O���[�o�����I�H Ray�����AJiiji�̓��͍����̋ɂ݂��B
 �@�����Ƃ����A3��25���A�h�C�c��LCC�W���[�}���E�E�B���O�X�̒ė����́B���{�l2�l���܂ޓ����150�l����]������Ă����B
�@�����Ƃ����A3��25���A�h�C�c��LCC�W���[�}���E�E�B���O�X�̒ė����́B���{�l2�l���܂ޓ����150�l����]������Ă����B�@���ǂ́A�����c�m�̃A���h���A�X�E���r�b�c�Ƃ����j���Ӑ}�I�ɒė���}�����ƒf�肵���B�@�����R�b�N�s�b�g���o�����Ɠ�������{���A���ɋy�Ƃ����BJiiji�͎v�����B�u�O����J�����Ȃ��̂��Ȃ��v���āB���͂���A2001.9.11���������e���ȗ��A�e�����X�g�̐N����h�����߂ɂ������Ă���Ă��B����͂�A�����ɂ��e���̉e�B�Q�����Ⴄ�ˁB�O�G�ɋC���Ƃ��Ă������������ꂿ������B�܂��ɑz��O�I �����A���̕����c�m�A�Z�ʂ��R�����A���̏��t����u�Ζ��s�v�̐f�f��������Ă����Ƃ�������Ȃ��B���a�Ƃ��Ԗ������Ƃ��B�a�l�ɑ��c�������Ⴂ���Ȃ���B���}�ȑK�v���B���c�m�̐��_�`�F�b�N���`���t����Ƃ��ˁB���E���ň���ɔ�Ԕ�s�@�͐��\���@�Ƃ������Ă���B�����낤��Ȃ��낤����A���낵���ď��Ȃ����I�I
�@��ˉƋ���́A3��27���̊��呍��ŁA���̋v���q�В��̏����Ō����B�o�܂͕���A���̂Ƃ���̐e�������̈��������݂͂��Ƃ��Ȃ������ˁB�������Ђǂ��V���o�_�o�ŁB�܂��A�C�����͉���܂���B�u�C�����͂����������Ⴈ���悤�ɂȂ����v�Ƃ������Ƃł���B����������i�H���̉VS�J�W���A���H���В��B�ێ�VS���v�B�ǂ���̎咲���������͐��ƂɔC����Ƃ��āARay�����A����Jiiji�̂������Ƌ�͑�˂Ȃ�B�H�삪���A�܂�10�N�\�R�\�R�Ȃ̂ɁA���߂���Ă�������Ă�B�R���ō����i���H ��h�̈�ۈ�����Ȃ��B
�@�����Ȃ��́A�v���q�В��Ɋ撣���Ă��炤�����Ȃ��ˁB������Jiiji�̒�āE�E�E�E�E�Ƌ���q�̋C���͒��n�b�s�[�B������A�C���Ŕ��킹�悤�B�C���[�W�헪���B�Ж��A���S�A�L���b�`�R�s�[�Ȃǃg�[�^���ō����m�a�Ɉ�C����B�S�@��]�A�擪�ɗ��͕����̃W�����k�E�_���N��낵���v���q�В��B�u�m�[�T�C�h�Ń��X�^�[�g��v �u�₩�C���Ŗ҃_�b�V���B����Ō��܂肳�I�H
 �@�����́ARay�����A�����n����B��������m���́u���V�Ԋ�n���O�ڐ݁v������ɓ��I�����̂�����A�Ӗ�Ö��ߗ��čH�������~�߂ɏo��͓̂��R�̍s���B���́u����͐��N�O����̓��č��ӎ���������l�X�Ɛi�߂邾���v�Ƒ���ɂ��Ȃ��B�ł����āA�㋞�����m���ɉ���Ƃ����Ȃ��B�����́A��ˉƋ��Ȃ�����A�b�������Ȃ�����B�������{�̍��ƌ��ł���B���Ԃ����ăA�����J�̊�F����M���Ă���ƁA��������ɑ�������ꂿ�Ⴄ���B���{�����͈�̂ǂ������Đ�������Ă��I�H
�@�����́ARay�����A�����n����B��������m���́u���V�Ԋ�n���O�ڐ݁v������ɓ��I�����̂�����A�Ӗ�Ö��ߗ��čH�������~�߂ɏo��͓̂��R�̍s���B���́u����͐��N�O����̓��č��ӎ���������l�X�Ɛi�߂邾���v�Ƒ���ɂ��Ȃ��B�ł����āA�㋞�����m���ɉ���Ƃ����Ȃ��B�����́A��ˉƋ��Ȃ�����A�b�������Ȃ�����B�������{�̍��ƌ��ł���B���Ԃ����ăA�����J�̊�F����M���Ă���ƁA��������ɑ�������ꂿ�Ⴄ���B���{�����͈�̂ǂ������Đ�������Ă��I�H�@���̎��Ԃ̔��[�͔��R�R�I�v�B�u���Ă̍��ӎ����v�������Ӗ�Èڐ݂��u�Œ�ł����O�v�ƂԂ��グ�āA����̊��S�����B���Z���Ȃ��̂ɂˁB���{�����ɂ��Ă݂�A���c���]�v�Ȃ��Ƃ����Ă��ꂽ���A�ł���Ȏ��ԂɂȂ���������A�ƍ���ł邾�낤���A�t�Ɍ���A�ނ́g�F���̐��_�h�����S�ۏ�̐��������N�����Ƃ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�Ƃ͂����A�悾���Ă̓��V�A�`�N���~�A�ɏ�荞��Łu���V�A�̐������v�����������Ă�B����c������̗���H �����Ȃɂ����Ȃ��ŁA�����ΐ��ɋA���Ăق������i�B�F���l�Ȃ�ł���B
�@���������ق炪�A�u���ۖ@���v�̂̕��߃A�����J��K�₵�āA�u�����q�����q�v����ċA���Ă����ˁB�u�]���������������v�����Ă��B������O����B�A�[�~�e�[�W�E�i�C�E���|�[�g���Ђ����珅�炵�Ă����B�������������A�����J�ɁgEverything OK�h�͂�߂悤��B�̐S�Ȃ̂́A���̃^�C�~���O�𗘗p���āA����̊�n���S�y���ƒn�ʋ�����P���Ă��邱�ƂȂB�������̕��S�𑝂₷�̂����班�����炢����ɗv���������ăo�`��������Ȃ����낤�ɁB
�@���{�����́A��������A�u���{�����@�͑f�l�iGHQ�j��1�T�Ԃō�������́B����������ō�蒼���v�ȂǂƂ₯�ɈА����������ǁA�̐S�ȂƂ���ł̓A�����J�ׂ�����Ȃ�ȁB������c������̗���H ���ނ��獑���̕��������Ă�B���������ƍق������낤���炳�B
�@�������哱����AIIB�i�A�W�A�C���t��������s�j�B�C�M���X�̎Q���ŃK�����Ɨ��ꂪ�ς�����ˁB�h�C�c�A�t�����X�A�C�^���A�Ȃ�EU�����A�u���W���A���V�A�A�I�[�X�g�����A���\���A�Q����47�J���ɂ��y�B���Ċ��S�ɉᒠ�̊O�B����������b�̃R�����g���A�����J�ǐ��ɏI�n���邾���B�Ȃ�̎��含���Ȃ��B
�@���̖��͑傫�����B�A�W�A�̃C���t�����݂̌o�ϋK�͂͐r��B1000���~�Ƃ��B�����̓A�����J�Ǐ]�A�������������Ă�ꍇ����A�ق�Ƃ͂Ȃ���Ȃ��B���������Ƃ�������NJς̂��鐭���Ƃ��ق����B���{=��������ǂ��ɂ��Ȃ��B
�@�����ŁA��t����ɂ��āB��N11��5���ɁA���{�͓�����]��k�̎��O���ӏ��Ȃ���̂����킵���B�����ɂ́u��t�����ɂ����đo���ɈقȂ錩�������邱�Ƃ�F������]�X�v�Ƃ������B���̂Ƃ�����Jiiji�͋C�ɂȂ��Ă����B�����ɂ���邼���āB �Ă̒�A3��23���̒����V���ɁA�u�����́A������position�ƖāA�w���{�����j�㏉�߂Ă����ɗ̓y��肪���݂���ƔF�߂��x���Ƃ��A�����J�ŐG�����Ă���v�Ƃ̋L�����o����B
�@���̕����ʂ����K�ߕ��Ɨ����b�������������߂ɁA����ȍ��v���������ł������Ⴄ����A�����������₾�B���܂���Q�Ăāuposition����Ȃ� view���v�Ȃ��������Ă����x�����āB���{�Ăق�ƊO���I���`�ł���B
�@��t���͂���ŏ����A�����ȁB1972�N�A�c���p�h�̕s�p�Ӕ����Ɏn�܂��āA1978�N�A�������u�����ɂ͒m�b���Ȃ� ������Ɉς˂悤�v�ɕ��c���v�����������������ƁB���̗���͒������Ӑ}�I�Ɏd�|�������̂Ȃ̂ɒN���C�Â��Ȃ��B�u��t�ɗ̓y���͑��݂��Ȃ��̂�����A������Ɉς˂���Ȃɂ��Ȃ����v���炢�Ȃ��Ƒ������Ƃ��Ȃ���_����������B�u��������YES�Ɠ����v�Ȃ�C���n���m��Ȃ��B�����āA����A���{�����̔\�V�C���o�B���������Ⴈ���B
�@����Ȃ��́A�̂̒����̋��ȏ����u��t�����͓��{�̗̓y�v�ƔF�߂Ă���̂�����A�I�R�ƑΉ�����悩������ł���B�����炩��͉��������o���Ȃ��B�Ȃɂ��]��ꂽ��A�u����Ⴈ�������v�Ƒ��ӎv�\�����Ă����B�ł��A�����܂ŗ�����x���肵���B �Ȃ�����A����������邵���Ȃ���ˁB����ɂ͂����Ƙ_���I�Ɂu���j���v�Ƃ��Ęb���������Ƃ��B��������Ί��H�����o���邩���B�����Č����������{�̂��̂ƔF�߂Ă�������ˁB����͗�������B
�@�A�z�������Ȃ��Ă����Ƃ���ŁARay�����A������Ƃ����X�|�[�c�����ďI���ɂ��悤�B
 �@�v���싅���J�������ˁB�Ȃ�Ă����������c�����̍L���J�[�v���A���b��B�L���b�`�t���[�Y�́u�j�C�v�B������1�����BMLB�ł�������Ɛ攭���[�e�[�V������������l������A�܂��܂�����ˁB�싅�Ɏ��g�ގp�����Ƃɂ����^�����B���݂͑̂̋��x���Ɠ����̒��J�����Ȃ��B�̗͂Ƃ����A�_���r�b�V�����}�[�N����J���S�z�͂����B���c�撣�� BZ�̃e�[�}�ɏ�����D�u�ƁI �D���̍s���H�ǂ��ł�������B
�@�v���싅���J�������ˁB�Ȃ�Ă����������c�����̍L���J�[�v���A���b��B�L���b�`�t���[�Y�́u�j�C�v�B������1�����BMLB�ł�������Ɛ攭���[�e�[�V������������l������A�܂��܂�����ˁB�싅�Ɏ��g�ގp�����Ƃɂ����^�����B���݂͑̂̋��x���Ɠ����̒��J�����Ȃ��B�̗͂Ƃ����A�_���r�b�V�����}�[�N����J���S�z�͂����B���c�撣�� BZ�̃e�[�}�ɏ�����D�u�ƁI �D���̍s���H�ǂ��ł�������B�@�Ō�ɃT�b�J�[�B�������������āA�S���{�̊ē��n�����z�W�b�`�����A�C�����ˁB���[���h�J�b�v�̎��т��x�X�g16�~�܂肶�ᕨ����Ȃ����A�����A���̎����ɕ����Ă��債������Ȃ����C�A�Ǝv���Ă��B�ł����̐l�Ȃ��Ȃ��ł��B���єz�Ō����܂����B�u��Ώ����v�̋����ӎu�B�I��̖ڂ����Č��M���ۂ��B��ʏ��W�S���e�X�g�ɂ�鋣���ӎ��̊��N�B�����̓U�b�P���[�j����ɂ͂Ȃ��������́B���̎��_�u����d���v�̈ӎ������肻�����B������āA�`�[���Ɉ�̊��Ɩ����������܂�Ă��B���_�A���{��\�������Ƃ���ɂ͎��Ԃ�������B���E�ƑΓ��ɐ킦��̂�30�N�悾�낤�B�ł��A���̐l�̃T�b�J�[�̓C�C�B���Ă��Ċy�����B����͌@��o�����B�I�V�������۔��������̂̓_�e����Ȃ������I�I
�@����ARay�����A�����͂����Bye Bye���BJiiji�͂��ł����o�}���ɂ�������A�܂������̏Ί�Ō}���ĂˁB
2015.03.25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��2�`��ȎO�p�W
�����̔N1791�N���@1791�N12��5���A���[�c�@���g�͎��B���V���e�t�@�����@�̎��S�o�^���ɂ́u�}�������]�M�v�Ƃ���B���������[�}�`�M�B�Ǐ�͎��]�ƍ��M�B���[�c�@���g�͏��N����ɍŏ��̔���ɏP���A�Ȍ�3�|4��̍Ĕ��𐔂��Ă����Ƃ����B���̕a�͈�Ƃɍ����Ȃ�₪�Ď��Ɏ���Ƃ���Ă���̂ŁA�����炭�A���̌����Ă͐������̂��낤�B���A���ɂ��H�Ȃ�V�˂̚�܂����ɁA�������߂��菔����������ł����B
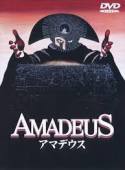 �@�f��u�A�}�f�E�X�v�i1988���J�j�ɂ́A��l���̃T���G�����u�������ł����A���R�͂�̍˔\�ɑ��鎹�i���v�ƓƔ������ʂ�����B���{�����́A�Z�сu���[�c�@���g�̔��y�v�̒��ŁA�u���[�c�@���g�͔~�ł������B���Â��Ăł��̂����@���E�X���B�[�e���j�݂Ƃ����E�B�[������̉��l�i�ނ����������Ƃ��āA�o�b�n�ƃw���f�����w��ł���j�B��҂��������e�����키���A�f�l�Ö@�̔߂����ŁA����̗ʂ�����ē��^�������ߎ��v�Ə����Ă���B���̑��A�t���[���C�\���ɂ��ŎE���A�R���X�^���c�F�Ɛl���A�b���ߑ����ȂǂȂǁB���������͂��ׂđz����̉����B���}���N�X��n�ɖ������ꂽ��̂������s���s���ł́A�ؖ��̂��悤���Ȃ��B
�@�f��u�A�}�f�E�X�v�i1988���J�j�ɂ́A��l���̃T���G�����u�������ł����A���R�͂�̍˔\�ɑ��鎹�i���v�ƓƔ������ʂ�����B���{�����́A�Z�сu���[�c�@���g�̔��y�v�̒��ŁA�u���[�c�@���g�͔~�ł������B���Â��Ăł��̂����@���E�X���B�[�e���j�݂Ƃ����E�B�[������̉��l�i�ނ����������Ƃ��āA�o�b�n�ƃw���f�����w��ł���j�B��҂��������e�����키���A�f�l�Ö@�̔߂����ŁA����̗ʂ�����ē��^�������ߎ��v�Ə����Ă���B���̑��A�t���[���C�\���ɂ��ŎE���A�R���X�^���c�F�Ɛl���A�b���ߑ����ȂǂȂǁB���������͂��ׂđz����̉����B���}���N�X��n�ɖ������ꂽ��̂������s���s���ł́A�ؖ��̂��悤���Ȃ��B�@�ł͂����ŁA�u���N�C�G���v�̔������Ă��玀�Ɏ���܂ł̔��N�Ԃ��A�����ƐU��Ԃ��Ă݂悤�B1791�N7���A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�̒�������B���̂Ƃ��͉̌��u���J�v�̍�Ȓ��ŁA�܂�����ł��Ȃ��B���̏�A�V���ȃI�y���A�u�c��e�B�[�g�̎��߁v���˗�����A9���A�v���n�ɍs���㉉�B��Ȋ���50�����̗���ƁB�E�B�[���ɖ߂�A9��30���A�u���J�v�̏������}����B��q�b�g�B10�����u�N�����l�b�g���t�ȁv����ȁB�u���N�C�G���v�ɖ{�i�I����B�u�w���N�C�G���x�͎����̂��߂ɏ����Ă���B���͓ł�ꂽ�v�ƍȂɘb�����̂͂��̂���B11��18���A�t���[���C�\���̂��߂̃J���^�[�^�u��炪��т����炩�ɍ�����v������̎w���ʼn��t�B���ꂪ���̍Ō�̏�ƂȂ�B11��20���ɐQ���݁A�u���N�C�G���v�̍�Ȃɐ�O������A12��5���Ɏ��S�B�u���N�C�G���v�����̂܂܈��B
�@�̒��s�ǂɊׂ�̂�10�����B11�����ɂ͐Q������ɂȂ�A�ꃖ�����炸�Ŏ��Ɏ������B���ɂ������Ȃ��B���̂������Ȃ����l�X�ȉ����̂ł��낤�B���������A�l�Ԃ̎��Ƃ������̂́A�T���猩��A�����ȂׂĂ������Ȃ����̂Ȃ̂�������Ȃ��B�{�l�̋ꂵ�݂͖{�l�����킩��Ȃ��̂�����B
�@�Ƃ͂����A�����͎��������̏�ł͂Ȃ��B���[�c�@���g�̓ˑR�̎��ɂ���āA�ȃR���X�^���c�F�͂ǂ��������̂��B�u���N�C�G���v�����̌o�܂́H �����ɓI���i���Ă䂱���B�܂��́A���[�c�@���g�^�R���X�^���c�F�^�W���X�}�C���[�̊W���l�@����B
����ȎO�p�W��
 �@�R���X�^���c�F(1762�|1842)�͈��Ȃ̗_�i�H�j�������B�\�N���e�X�̍ȃN�T���e�B�b�y�A�g���X�g�C�̍ȃ\�t�B�A�ƕ���ŁA���E�O�别�ȂƂ��Ă�Ă���B���̓�l�͂Ƃ������A�R���X�^���c�F�ɂ����Ă͔G��߂̗l�����Z���B���[�c�@���g�_�b�`���̋]���ҁH �H���A�u���[�c�@���g�͐����Ȃ�V�ˁB�R���X�^���c�F�͘Q��Ƃŕ��C���̈��ȁv�u�U�߂��E�B�[���ō�Ȃɗ��ł���Ƃ��A�Ȃ͉�����ґ�O���������v�ȂǁA�ӔN�̕n�R�������Ȃ̂����ɂ��V�˂�i�삷��B���[�́A�����I�|���g�̎��X�Ȃ܂ł̌������B����R���X�^���c�F��̐��͓I�Ȍ�������A������ɂ���悤���B
�@�R���X�^���c�F(1762�|1842)�͈��Ȃ̗_�i�H�j�������B�\�N���e�X�̍ȃN�T���e�B�b�y�A�g���X�g�C�̍ȃ\�t�B�A�ƕ���ŁA���E�O�别�ȂƂ��Ă�Ă���B���̓�l�͂Ƃ������A�R���X�^���c�F�ɂ����Ă͔G��߂̗l�����Z���B���[�c�@���g�_�b�`���̋]���ҁH �H���A�u���[�c�@���g�͐����Ȃ�V�ˁB�R���X�^���c�F�͘Q��Ƃŕ��C���̈��ȁv�u�U�߂��E�B�[���ō�Ȃɗ��ł���Ƃ��A�Ȃ͉�����ґ�O���������v�ȂǁA�ӔN�̕n�R�������Ȃ̂����ɂ��V�˂�i�삷��B���[�́A�����I�|���g�̎��X�Ȃ܂ł̌������B����R���X�^���c�F��̐��͓I�Ȍ�������A������ɂ���悤���B�@1777�N�A21�̃��[�c�@���g�͕�A���i�E�}���[�A���ė��ɏo���B�ړI�͋{��ւ̏A�E�B�؍݂����}���n�C���ł͖��A���Ɠ����A�ŏI�I�ɂ͒f����B�����I�|���g�͎��̖ړI�n�p���ɗ��������悤�Ƃ��邪�A���[�c�@���g�͂Ȃ��Ȃ������グ�Ȃ��B�����̓}���n�C���{��t���̎�A���C�W�A�E�E�F�[�o�[�i1760�|1830�j�j�ւ̓��ꍞ�݁B���͂Ɣ��e�����˔�������ށB�����͈��̃R�[���X�E�K�[���ɉ߂��Ȃ������ޏ��̍˔\�������������[�c�@���g�́A��l�O�r�C�^���A����̖�������B
 �Ƒ����җ�Ƀo�b�N�A�b�v�B��������͑��q����Ƃ̊Ŕɂ��Đ���オ�낤�Ƃ��郌�I�|���g�̈ӎv�ɔ������B���q���E�F�[�o�[�Ƃɓ����ĂȂ���̂��A�Ƃ����킯���B���[�c�@���g�͏a�X���̈ӂɏ]���p���֗��������B
�Ƒ����җ�Ƀo�b�N�A�b�v�B��������͑��q����Ƃ̊Ŕɂ��Đ���オ�낤�Ƃ��郌�I�|���g�̈ӎv�ɔ������B���q���E�F�[�o�[�Ƃɓ����ĂȂ���̂��A�Ƃ����킯���B���[�c�@���g�͏a�X���̈ӂɏ]���p���֗��������B�@�p���ł̏A�E�������s���A���̏�A�a�ōň��̕�܂ł��S�����Ă��܂��B�p���������[�c�@���g�ɂƂ��čň��̓s�s�������B���S�̋A�H�A�}���n�C���ŃE�F�[�o�[�Ƃɗ��������A���̑ԓx�͈�N�O�Ƃ͑ł��ĕς���Ă�Ȃ��B���[�c�@���g�ɔ��@���ꂽ�A���C�W�A�̍˔\�͂��̊ԂɌ����ԊJ���A�}���n�C���{�쌀��̉Ԍ`�ɏo�����Ă����B�E�F�[�o�[�Ƃ͋��̗����B�����Ȃ��͋ʂ̗`�ɏ悹��B�g���s��̃��[�c�@���g�Ȃڂ���Ȃ������̂ł���B
�@���͗����1781�N�A���܂�̋��U���c�u���N�ƌ��ʂ������[�c�@���g�́A�E�B�[���Ŏ����������y�ƂƂ��Ă̑����ݏo�����B�����Őg�����̂��E�F�[�o�[�ƁB��Ƃ́A�A���C�W�A�̏o���i�E�B�[���{��t���o�D���[�[�t�E�����Q�ƌ����j�ɔ����E�B�[���Ɉڂ�Z��ł����B�����ɂ����̂������̍ȃR���X�^���c�F�i1762�|1842�j�B�A���C�W�A�̖��������B���I�|���g���R���B�����A����̃��[�c�@���g�͐܂ꂸ�A���N�߂ł�����������B�������h���̖��Ƃ̌����B�s�͂����̂͂���̕�e�Ƃ����}���B�ނ͕��ւ̎莆�ɂ����������u�����Q�ƌ����������i�A���C�W�A�̂��Ɓj�͉R���ňӒn���ŃR�P�b�g�ł��B�R���X�^���c�F�́A�������Ĕ��l�ł͂���܂��X���͂���܂���B�˔\�͂���܂��A�ȂƂ��āA��Ƃ��ċ`�����ʂ����邾���̏\���ȏ펯������܂��v�B
�@���[�c�@���g���A�A���C�W�A�̂��Ƃ��L�b�p���ƒ��߂āA�S��R���X�^���c�F�������Č����������ǂ����͒肩�ł͂Ȃ��B�A���C�W�A�ɑ��A���Ȃ��炸�����������Ă������낤���Ƃ́A���̌�ޏ��ƊW�����������Ƃł��ؖ������B�l�����낢��A���������낢��B�����Ă�V�˃��[�c�@���g�B���̐S��͌v��m��Ȃ��I�H
�@���[�c�@���g�̐l���ɂ͐����̏������o�ꂷ��B���[�c�@���g�w�ҍ����p�Y���������Ă��鏗�����L���Ă݂�ƁE�E�E�E�E�A���C�W�A�E�E�F�[�o�[�A�}���A�E�A���i�E�e�[�N���A�i���V�[�E�X�g�[���X�A�J�e���[�i�E�|���f�B�[�j�A�J�^���[�i�E�J���@���G���A�W�F�m�[���A���[�[�t�@�E�A�E�G�����n���}�[�A���M�[�i�E�X�g���i�U�b�L�A�h�[���X�E�V���g�b�N�A�e���[�W�A�E�t�H���E�g���b�g�i�[�v�l�A���[�[�t�@�E�h�D�[�V�F�N�v�l�ȂǂȂǁB�̎�A�s�A�j�X�g�A���@�C�I���j�X�g�A�M���̕v�l�A���k�ȂNJ�Ԃ�����ʂł���B �@�R���X�^���c�F���Ȑ��̍����̈�͕��C���B�Ƃ��낪�A�U�߂̕������{����肾�����Ƃ������Ƃ��B
�@ �@�����������[�c�@���g�v�Ȃɂ�9�N�Ԃ�6�l�̎q�������܂ꂽ�i���l�����͓̂�j�Ǝl�j�̓�l�����ł��邪�j�B������ɂ���A�R���X�^���c�F�̌��������́A�D�P�Ǝq��Ă̖�����ꂾ�������ƂɂȂ�B���̂��ߔޏ��͋r�ɂƂ������a�������Ă��܂��B�E�B�[���ߍx�Ƀo�[�f���Ƃ�������n������B����͗������܂ݕۗ{�n�Ƃ��Ă̗��j���Â��B�R���X�^���c�F�͓����̂��߂��̒n�ɒ��������邱�Ƃ��x�X�������B�����ɁA���[�c�@���g���A�����҂Ƃ��Ďw�������̂���q�̃t�����c�E�N�T���@�[�E�W���X�}�C���[�i1766�|1803�j�������B�ʂ����ă��[�c�@���g�̈Ӑ}�₢���ɁH
�@1791�N�̎O�l�͂ǂ����������B ���[�c�@���g35�A�R���X�^���c�F29�A�W���X�}�C���[25�B�v�̓E�B�[���ŃI�y�������B�Ȃ͋ߍx�ŕۗ{�B�����ɕt���Y���Ⴋ����B10���܂ł͌��C���������[�c�@���g�B�u���J�v�����Ȃ���o���̎肽���Ƃ̔h��Ȍ𗬂��������H 7���A�R���X�^���c�F�͎l�j���Y�ށB���[�c�@���g�͂Ȃ�Ƃ��̎q�Ƀt�����c�E�N�T���@�[�Ɩ����B�W���X�}�C���[�̖��O���̂܂܁B����͉����Ӗ�����H ������W���X�}�C���[�̎q�H ���[�c�@���g���F�H �E�[���A�V�˂̐S��͌v��m��Ȃ��I
�@9���A���[�c�@���g�̃v���n�ւ̗��ɂ̓R���X�^���c�F�ƃW���X�}�C���[�����s�B�E�B�[���ɖ߂��āu���J�v�̏������}����B10���A���[�c�@���g�͋��c��A�R���X�^���c�F�ƃW���X�}�C���[�̓o�[�f���ցB�����ŁA���[�c�@���g����R���X�^���c�F�ւ̎莆�ł���B���t��10��8���B
�ڂ������̎莆�������Ă��鍡�A���݂͋C���悭�������ɂ����Ă���낤�ˁB���݂����Ȃ��ƂƂĂ����т�����B�����d�����Ȃ���A�����ɂł������āA��T�Ԃ��݂ƈꏏ�ɉ߂��������B�ł������Ȃ�ƁA�d���ɂ͂܂������s�s���ɂȂ�Ȃ��B�E�E�E�E�E�ɂ͂ڂ��̖��ɂ����āA����ł��𐔃y�A�����Ă���B�_�̖��ɂ����ĕs�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�B��̕@���U���K�j������ł��̂��������A��̖ڂ�ʂ����������A�����邩���Ă�邪�����B�@�E�E�E�E�E�����́A�R���X�^���c�F�̓�Ԗڂ̕v�j�b�Z���������Ă��邪�A���R�W���X�}�C���[�̖��O������B���̕��������Ȃ��āA���[�c�@���g�̓W���X�}�C���[���o�J�ɂ��Ă���Ƃ����͂��Ă��Ȃ��Ƃ������搶��������B���������A���[�c�@���g��������{���N�\�Ɍ����̂́A��ɐe���̏�Ȃ̂��B����͔ނ̑��̎莆�Ƒ���Ƃ̊W������Έ�ڗđR�B�W���X�}�C���[�̂ق��ɂ́A�N�����l�b�g�̖���V���^�[�h���[������A�z�����̖��l���C�g�Q�v������ł���B
�@���[�c�@���g���W���X�}�C���[�̎��͂��Ă������ۂ��͕ʂƂ��āA�ނ����[�c�@���g��ƂɂƂ��āA�����ɐg�߂ł���A����ȑ��݂��������Ƃ͊ԈႢ�̂Ȃ������ł���B
�@�u���[�c�@���g�͗D�����R���X�^���c�F�������Ă����B�������A����͂���Ƃ��āA�ق��̏��ɋC�������̂ɕς��͂Ȃ��������A�ނ̕��C�̍��͐[���Ĉ���Ɏ~�܂�Ȃ������v�i���C�i�[�h�E�\���������u���[�c�@���g�v���j
�@�����̕��C���̃��[�c�@�c�g�B���̕v�����荞���j�̏���W���X�}�C���[�B�Ԃŗh���Ȃ̃R���X�^���c�F�B���̊�ȎO�p�W���A�u���N�C�G���v�����̓����ɔ����Ɋւ���Ă���̂ł���B
���Q�l������
�u���[�c�@���g�v���C�i�[�h�E�\�������� �Έ�G��i�V���فj
�u���[�c�@���g�̎莆�v�����p�Y�ҁi���w�فj
�u�f��̃��[�c�@���g�v�Έ�G���i�������Ɂj
�u���[�c�@���g���T�v�i�~���Ёj
�u���̌a�v���{�������i���t���Ɂj
�u���[�c�@���g�Ƃ̗��v���[�����i���y�̗F�Ёj
2015.03.10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��1�`���z�ȃW���X�}�C���[
�����c���N�Ɏa�荞�ݐ錾���@���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�͎��̍ň��̋Ȃ̈���B�e�����m�l�̎��ɍۂ��Ă͕K�������B����ȓ��ʂȋ@��łȂ��Ă��A����悭�����Ȃł�����B�v����ɍD���Ȃ̂ł���B�Ȃ����낤�H�ƍl����B���ƐÁA���Ɛ��A�q�Ɣ��A���ƈ��B��������l�Ԃ̊������قǂ܂łɍ��݂����a����Ȃ͂Ȃ��B�S���U�邦�A�h���Ԃ��A�����Ĉ��g����B���y�̖{���������ɂ���B
�@���[�c�@���g�́A1791�N12��5���A�A��ʐl�ƂȂ����B�����́u���N�C�G���v���₵�āB�����ł��邩��A�����ɂ͑��l�̎��K�v�Ƃ���B�����Ɏ���܂ł����]�Ȑ܂�����B�o������o�����ŁA�������������̘_�����₦�Ȃ��B�Ȃ�Ƃ����ȑ㕨�ł���B���ꂾ���ɁA�N�����m�I�ɁA�ʔ����B������Ƃ����āA�y�����낭�ɓǂ߂Ȃ����ɁA���I��͓͂y�䖳���B�Ȃ�A�f�l�Ȃ�ɁA����鳖��鲂ɂ��Ĕ�ѐ薣�͓I�Ȗ��Ȃɏ����ł��߂Â�������B�����v���Ďa�荞��ł䂭�B
�����z�ȃW���X�}�C���[��
 �@�t�����c�E�N�T���@�[�E�W���X�}�C���[�i1766�|1803�j�́A���[�c�@���g�̈��ƂȂ����u���N�C�G���vK626�������������l�ԂƂ��āA���y�j�ɎW�R�Ƃ��̖����c���Ă���B���̖����̌�����A��������ꂪ�������Ƃ��ł���̂́A�ЂƂ��ɔނ̌��тɂ����̂��B����͑傢�Ȃ�̋ƂƂ���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̎Ⴋ���[�c�@���g�̒�q�̕]���́A���܂�F�������̂ł͂Ȃ��̂ł���B����ǂ��납�A��̊w�҂͔ނ��u���\�v�Ă�肵�Ĝ݂�Ȃ��B
�@�t�����c�E�N�T���@�[�E�W���X�}�C���[�i1766�|1803�j�́A���[�c�@���g�̈��ƂȂ����u���N�C�G���vK626�������������l�ԂƂ��āA���y�j�ɎW�R�Ƃ��̖����c���Ă���B���̖����̌�����A��������ꂪ�������Ƃ��ł���̂́A�ЂƂ��ɔނ̌��тɂ����̂��B����͑傢�Ȃ�̋ƂƂ���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̎Ⴋ���[�c�@���g�̒�q�̕]���́A���܂�F�������̂ł͂Ȃ��̂ł���B����ǂ��납�A��̊w�҂͔ނ��u���\�v�Ă�肵�Ĝ݂�Ȃ��B�@�܂��́u���N�C�G���v�̍\�������Ă������B����̐i�s�ケ��͕K�{������B�敪�͗l�X���邪�A�ώG��������邽�߁A�I�[�\�h�b�N�X��CD��track�ɕ킢�����B�ŏ��P�ʂ�1�ȂƂ�����ׂĂɉ��p���������炾�B
1 ���Տ� Introitus �@2 �L���G Kyrie �@3 �{��̓� Dies irae �@4 ���Ȃ郉�b�p Tuba mirum �@5 �݂��̑剤 Rex tremendae �@ 6 ���R���_�[�� Recordare �@ 7 ���ꂵ�� Confutatis �@8 �܂̓� Lacrimosa �@9 ��C�G�X�� Domine,Jesu �@10 ���Ȃ鐶�� Hostias �@11 �T���N�g�D�X Sanctus �@12 �x�l�f�B�N�g�D�X Benedictus �@13 �_�̎q�r Agnus Dei �@ 14 ���̔q�̏� Communio�@���[�c�@���g�����S�Ȍ`�Ŏc�����̂́A��1�Ȃ����B��2�Ȃ͂قڊ����B3�|10�Ȃ͕��������B11�|14�Ȃ͋������B�W���X�}�C���[�́A���Ȃ��Ƃ��S14�Ȓ�12�Ȃ��M�������Ă���̂ł���B����͗��h�ȋƐтł��邩�炵�āA���́A�W���X�}�C���[���\���ɂ͔��ł���B
�@�������Ȃ���A���̂��搶���́A�W���X�}�C���[�̕�M�ɂ̓��[�c�@���g�̈ӂɂ�����ʕ��������X����Ǝw�E����B����𐳂����߂Ɋ����̔ł��o������B�o�C���[�Łi1971�j�A���[���_�[�Łi1981�j�A�����h���Łi1990�j�A�����B���Łi1991�j�Ȃǂł���B���ʓ��̏o�ŔN������Ă������͂���قlj����̘̂b�ł͂Ȃ��B�����҂͎���̐��������咣���邽�߂ɁA�W���X�}�C���[�ł��Ȃ߂�B��\�I�Ȃ̂́A���[���_�[�ł̍쐬�҃��`���[�h�E���[���_�[�ł���B�ނ́A���������đ���o��������CD�̉�����ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���[�c�@���g�́u���N�C�G���`���v�́A�u���[�c�@���g�͒����Ȓ�q�̃W���X�}�C���[�ɓr���Ŏ��������ꍇ�̎c��̎d�グ���ɂ��ďڍׂȎw����^�����v�Ȃǂƌ���Ă����B�W���X�}�C���[�̔łɂ͍��f����悤�Ȏ��̈���������Ǝv���̂͐������̂��A���邢�́A����Ȃ��Ƃ��l����͖̂`���Ȃ̂��B�����A�W���X�}�C���[���{���Ƀ��[�c�@���g�̎w���ʂ�Ɏd�グ���̂Ȃ�A�ނ̔ł̓��[�c�@���g�̐^�M�̎��Ɉʂ�����̂ł���A�ނ������ꂪ�]�v�Ȍ��o��������ƁA���[�c�@���g�̈Ӑ}���Ȃ��邱�ƂɂȂ�ł��낤�B�������A����Ɨ����ɁA�������̓`�����R�ł���A�W���X�}�C���[�̎d���ɂ́A���[�c�@���g�̈Ӑ}�����f���Ă��Ȃ��Ƃ�����A����ł������̔ł�F�߂˂Ȃ�Ȃ��̂��낤���H�@�\���������₩�����A�����ɂ́A�W���X�}�C���[�ւ̕s�M�����肠��ƌ��Ď���B�X�ɔނ́A�g���[�c�@���g�̃W���X�}�C���[�ւ̓`���h���̂��̂ɂ����X������B
���x�̓��j�ɍs����B�ꏏ�ɃJ�W�m�ɍs���āA���j�ɂ͈ꏏ�ɋA���Ă��悤�BP.S.���A�̑���ɁA�W���X�}�C���[�ɂ̓n�i�Ƀp���`������킹�A�����S�c���Ƃ���Ă���E�E�E�E�E����́A1791�N10��7���A���[�c�@���g����o�[�f���ŗ×{���̍ȃR���X�^���c�F�ւ̎莆�ł���B���̂Ƃ��̃W���X�}�C���[�̓E�B�[���ɂ͂��炸�A�o�[�f���ɂ���͖̂��炩�ł���B�ƂȂ�ƃ��N�C�G���̑��k�Ȃǂ͂ł��Ȃ����ƂɂȂ�B���ۂ�1791�N�̃��[�c�@���g�̎莆�����Ă䂭�ƁA�W���X�}�C���[�͉��ɂ킽���ăE�B�[���𗯎�ɂ��Ă���A�����Ȃ�ƃ��[�c�@���g�͂��̒�q�ɁA1���2�����b�X�������Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���Ƌ^�������Ȃ�B�i���̔N�ȑO�ɃW���X�}�C���[�����[�c�@���g�ƒm�荇���Ă���L�^�͂Ȃ��j�B�@����ɁA���[���_�[�̒Njy�́g�W���X�}�C���[�̔\�́h�ɋy�ԁB
�@���̐����ԑO�̗l�q���A�]�t�B�[�i�R���X�^���c�F�̖��j�̌��t������p���Ă݂悤�B�u�W���X�}�C���[�����[�c�@���g�̃x�b�h�̉��ɂ��܂����B�L���ȁw���N�C�G���x�̕����|���z�c�̏�ɒu���Ă���A���[�c�@���g�͎��������Ƃ��̎d�グ���������Ă��܂����v �ǂ���炱�̕ӂ肪�A�`���̔��˒n�ł���B�Ƃ���]�t�B�[���������[�c�@���g�̂��̍Ō�̌��t�ɂ��ċL�^���Ă���̂��낤���H �K���Ȃ��ƂɃR���X�^���c�F�̉�z������B�u�v������\�������Ƃ��A�W���X�}�C���[�Ɍ������āA���������������̂܂���A�ŏ��̃t�[�K���Ō�̏͂Ɏg���悤�Ɍ����܂����v�i�R���X�^���c�F����u���C�g�R�b�v���̎莆1799�D3�D27�j ���������[�c�@���g���W���X�}�C���[�̔\�͂�Ⴍ�]�����Ă������Ƃ���l����ƁA�����ƗL�\�ȉ��y�ƂɈϏ������ɁA���������d�v�Ȏw�����W���X�}�C���[�ɗ^�������Ƃ��D�ɗ����Ȃ��Ƃ��낪����B���[�c�@���g�̎���A�R���X�^���c�F���S�l�́A�����ɂ̓W���X�}�C���[�ɗ������Ƃ͂��Ȃ��������Ƃ������Ă���B�ޏ��͂܂����[�[�t�E�A�C�u���[�ɗ��B�A�C�u���[�����[�c�@���g�̎��̏������������Ă���A���[�c�@���g�͐��N�O����ނ������]�����Ă����B�@���[���_�[�́A�u���[�c�@���g�̃W���X�}�C���[�ւ̓`���v�ɋ^������B������Ɂu���[�c�@���g�̓W���X�}�C���[�̔\�͂�]�����Ă��Ȃ������v�ƌ��ߕt����B���̏��u�R���X�^���c�F���ŏ��ɃW���X�}�C���[�Ɉ˗����Ȃ��������Ɓv�ɒu���B���ꂪ���[���_�[�̎O�i�_�@�ł���B
�@�Ȃ�A���[���_�[�́u�W���X�}�C���[�Łv�ɂǂ�Ȏ���{�����̂��H����ɂ��ẮA��قǁA�e�ł̔�r�̏͂ōs�������B
�@�f�b�J�̃v���f���[�T�[�̃G���b�N�E�X�~�X�͂����]���Ă���B�u�W���X�}�C���[�̓��[�c�@���g�̔ӔN�̒�q�ł���A�֗����ł���A��������̃J���ł���A���Ԃ̂Ȃ��Ƃ��ɂ̓��`�^�e�B�[���H���������ł���A���[�c�@���g�s�݂̎��̉�����̂���肾�����B���[�c�@���g�́A���킢�����Ȃ��ƂɁA�W���X�}�C���[���܂Ƃ��Ɉ��������Ƃ��Ȃ����̂̂悤�ł���B�����łȂ���A���̃W���X�}�C���[���w���N�C�G���x�̍�Ȃ̂����������[�c�@���g�ɂ����Ƃ��Ă����̂ɁA�R���X�^���c�F���A�C�u���[�Ɏd�グ���ϑ����闝�R���Ȃ��ł͂Ȃ����v
�@�ǂ����A�W���X�}�C���[���\���ő�̍����́A�u�R���X�^���c�F�����[�c�@���g�̎���w���N�C�G���x������������̂��A�W���X�}�C���[�ł͂Ȃ��A������l�̒�q�A�C�u���[�������v���Ƃɂ���悤���B�ŏ��Ɉ˗������A�C�u���[�͗L�\�Ō�ɂ����W���X�}�C���[�͖��\�Ƃ����}���ł���B�ʂ����Ă���ȒP���ȉ��߂ł����̂��낤���H
�@���ʂ��ɋL�����B���[�[�t�E���I�|���g�E�A�C�u���[�i1765�|1846�j�́A�̊����܂�4�������|�������̂́A���[�c�@���g�̔������i8�Ȃ̂���5�Ȃɏ��������������ŁA�����o���Ă��܂����̂ł���B�ނ��u�L�\�v�Ƃ���]�_�Ɛ搶�́A������u���[�c�@���g�̍�i�Ɏ��������Ȃǂ͂������܂����Ƃ����h�ӂ̕\��v�ȂǂƂ̂��܂��B��k���قǂقǂɂ��Ăق����B���ꂼ���\�̏ł͂Ȃ����B
�@�ł́A�W���X�}�C���[�͂ǂ��������̂��H �ނ͊撣�����B���[�c�@���g�̂��߂ɁB�R���X�^���c�F�̂��߂ɁB1792�N3���A�����o�����A�C�u���[����y�������A���炭�N���ɂ͊��������Ă���i1793�N1��2���ɔ�����̏����L�^������j�B�R���X�^���c�F�́A�D�F�̕��̒j�ɂ��̊y����n���A�ǂ���c��50�h�D�J�[�e���i60���~�j��������B���̋��z�͐��O�̕v�̔N�_��6�����ɑ����������������B
�@����́A�W���X�}�C���[�́u���N�C�G���v�����̌o�܂ƃR���X�^���c�F���ނ���ɂ������R��T���Ă݂����B
���Q�l������
���[�c�@���g�u���N�C�G���vCD
�@�@�`�W���X�}�C���[�� �P���e�X�w���F�E�B�[���E�t�B�� �����
�@�@�`���[���_�[�� �z�O�E�b�h�w���F�G���V�F���g������ �����
2015.02.25 (��) �A�����J���u���c���N�v�ŔƂ�����
 �@1964�N1��19���A�{�X�g���̐��\���ˑ吹���ŁA�O�N11�����e�ɓ|�ꂽ�̃P�l�f�B�哝�̂̒Ǔ����T���s��ꂽ�B�W�����EF�E�P�l�f�B�i1917�|1963�j�̓A�����J�j��B��̃J�g���b�N���k�̑哝�̂��������߁A�J�g���b�N�̓T��Ɋ�Â��A�~�T���Ƃ肨���Ȃ�ꂽ�̂ł���B�I�ꂽ���y�̓��[�c�@���g�́u���N�C�G���vK626�B���������[�c�@���g�Ƒ�����P�l�f�B�B�Ⴍ���Ė��O�̍Ŋ��𐋂������̓��m�Ɉ��ށA�Ȃ�Ƃ���͑��������I�Ȃ������낤�B
�@1964�N1��19���A�{�X�g���̐��\���ˑ吹���ŁA�O�N11�����e�ɓ|�ꂽ�̃P�l�f�B�哝�̂̒Ǔ����T���s��ꂽ�B�W�����EF�E�P�l�f�B�i1917�|1963�j�̓A�����J�j��B��̃J�g���b�N���k�̑哝�̂��������߁A�J�g���b�N�̓T��Ɋ�Â��A�~�T���Ƃ肨���Ȃ�ꂽ�̂ł���B�I�ꂽ���y�̓��[�c�@���g�́u���N�C�G���vK626�B���������[�c�@���g�Ƒ�����P�l�f�B�B�Ⴍ���Ė��O�̍Ŋ��𐋂������̓��m�Ɉ��ށA�Ȃ�Ƃ���͑��������I�Ȃ������낤�B�@�˗��ɂ���ď����n�߂����̂́A���̗\������A�g�����̂��߂ɏ����h�Ƃ����ϔO�Ɏ����Ă��������[�c�@���g�B�����ɂ͎���̉^����Q���ԚL������B����́A�ˑR�̋��e�ɂ���ėm�X����O�r��D��ꂽ�Ⴋ�哝�̖̂��O�Ɍĉ�����B
�@�G�[���b�q�E���C���X�h���t�w���{�X�g�������y�c�ƕ����̍����c�A�����ĂS�l�̃\���X�g�����B�ނ�͖`�����犴��̃G���W������t�ɏ����B���̉̐��͜ԚL���A�V��̑哝�̂ɓ͂��Ƃ���ɋ����킽��B�{���u���N�C�G���v�̖����͎��҂����炩�ɓV�ɑ��邽�߂̂��̂��B�Ƃ��낪����͑S���Ⴄ�B�哝�̂ƈꏏ�ɂȂ��ċ����A�Q���A�߂��ށB���瞂�B����قǂ܂łɊ����I�ȁu���c���N�v�͑��ɂȂ��B������҂ƍ�҂Ɖ��t�҂��O�ʈ�̂ƂȂ����A����ُ͈�Ȗ����t�Ȃ̂ł���B
�@���͂��̎����^����2006�N�����̕�����CD�iBMG JAPAN�j�Œ������B���̂悤�ȁu���c���N�v�������Ė{���ɂ悩�����Ǝv�����B���̂Ƃ��A���Ĉ��ǂ������͂�z�N�����B�ے�I�ȕ��ʂ̂���́A�ܖ��N�S���u�����̉��v(�V����)����u���Ɖ��y�v�Ƃ����͂ł���B

�@�P�l�f�B�����Ƃ��A���V�����[�c�@���g�́u���N�C�G���v�ŏI�n�����̂͒m��ꂽ�b�����A���̂Ƃ��̎������R�[�h���r�N�^�[����o�Ă���B���C���X�h���t�̎w���ŃI�P�̓{�X�g�������y�c�������A�Ƃ��������������قǖ��Ӗ��ȃ��R�[�h���������B�E�E�E�E�E�����E�E�E�E�E�@�������p�ɂȂ��Ă��܂����B�����ɂ͌ܖ����̌�T�ƌd�Ⴊ�������Ă���A�Ǝ��͎v���B��T�́u���R�[�h�𐢊E�Ɍ������Ĕ���o�������Ƃ̓A�����J�̖`���v�Ɛ�̂Ă����ƁB�d��́u�A�����J�͌�T�̏��˂������Ă���v�Ƃ����������B
�@����ǁA�������N�C�G�������Ƃ߂˂Ȃ�ʗ���ɂȂ��āA���Ƃ������Ƃ́A�E�̎����^���̃��R�[�h�͍ȃW���N���[�k�̂��߂����̂��̂ł���A��������i�����A����o�����Ƃ̖`���ɂ��Ăł���B�m���ɁA����o�����Ƃő��V�ɎQ�ʑ吨�̐l�́A���Ƃ��Ύ��̂悤�ɔޏ��̋������������A����A�P�l�f�B�̖������F��͂��邾�낤�B���������ꂪ�P�l�f�B���g�ɂƂ��Ĉ�̂Ȃ�Ȃ̂��B�ޏ��̐g�ɂƂ��Ă��B���҂��ł��厖�Ȃ��Ƃ��A�����J�l�͊Ԉ���Ă���B���̗���ł���͌�����B���N�C�G����ɂ���͓̂��R�Ȃ��Ƃ��B�^�����ĉi���L�O����̂������B�������������E�Ɍ������Ĕ���o�����Ƃ͂Ȃ��B���҂��Ƃ́A�̂����ꂽ�Ȃ̂��Ȃ��݂ɓ���̗܂𗬂����Ƃł���킯�͂Ȃ����A���̋Ɛт�J�ߏ̂��邱�Ƃ��A���S�l�ւ̂������ɂȂ�Ȃ�A�����L�Ɏ��Ȃꂽ�l�ɂ���͉����L�ł����ƖJ�߂�悻�悻�����ƁA�ǂꂾ���Ⴄ���B���������҂ɑ��A���̈⑰�ւ̎v�����������ȊO�̒������Ȃǖ{���͂���킯�͂Ȃ��̂ł���B���V�̎������R�[�h���āA���̗��v�ʼnƑ���⏕���悤�Ƃ����Ȃ�b�͕ʂł���B���̒��͂��������h煂ɂł��Ă���B���������⏕�̕K�v�Ȃ��哝�̂̃��R�[�h������A�����B�������傭�A�A�����J�l�̓P�l�f�B���ÎE�������ƂŊԈႢ�A���S�l��������邱�Ƃł�����ɑ傫�Ȍ���Ƃ����B�A�����J�Ƃ������́A���[�c�@���g�̂��́u���N�C�G���v1�����Ƃ��Ă݂Ă���T�̏��˂������Ă��鍑���Ƃ킩��B
�@��T�ɂ��Ă̗��R�������A�uRCA�����R�[�h�𐢊E�Ɍ������Ĕ���o���Ă��ꂽ���A�Ŏ��͐��ɂ��H�Ȃ郂�c���N�̖��������v�Ƃ������Ƃɐs����B�l�I�����Ƃ����Ȃ���B�ܖ����̌����������ł��邩�炾�B
�@�d��́A���݂܂��ɂ��̒ʂ�̌��ʂ��o�Ă���Ƃ������Ƃ��B�ԈႢ�Ȃ��A�����J�Ƃ������͌�T�̏��˂������Ă����̂ł���B
�@���70�N�B���R�Ɩ����`�̔����̉��A���E�Ɏ���̒鍑��`���S���������Ă����A�����J�B�x�g�i���푈�i1960�|75�j�A�p�ݐ푈�i1991�j�A�A�t�K�j�X�^�������i2001�j�A�C���N�푈�i2003�j�͂��߁A�C�X���G�������ւ̉��S�i1947�j�A�C�������C���N�푈�ɂ�����C���N�x���i1979�|90�j�A���̑��A�R���S�A�C���h�l�V�A�A�J���{�W�A�A���I�X�A�`���ւ̉���ȂǁA���̐g����Ŗ����ɂ܂�����͎~�܂�Ƃ����m��Ȃ��B�傢�Ȃ邨���������ł���B���ʁA���E�ɚ삵�����̋]���҂ݏo���Ɏ������B��ɃC���N�푈�ւ̑�`�Ȃ�����ƒ��r���[�ȓP�ނ́A���E�̃��[�_�[���鐳�`���ӔC�����Ȃ������ɂ��āAIS�Ƃ����낵�������ݏo�����Ƃ��Ȃ����B
�@�t�����X�̎v�z�ƃA���N�V�E�h�E�g�N���B���i1805�|1859�j�́A�����u�A�����J�̖����`�v�̒��ŁA17���I�ɃC�M���X����A�����J�ɓn�荇�O�������������l�X�̐����ɂ́u�����I�@���I���M�� Political & Religious Fanatic�v������A�ނ�́u���������������������Ă��̍l���𑼂ɉ����t����X��������v�Ɛ����Ă���B����͍����̃A�����J�鍑��`��\�����Ă��邪�A����Ȃ��Ƃɂ��̐����̓C�X����������`�҂Ɠ����ł���B
�@�ܖ��N�S���u�����̉��v���������̂�1960�N��ł���B�ނ��u���c���N�v���猩�������A�����J�ւ̊뜜�́A40�N�ȏ���o�����A���̐��������ؖ����ꂽ���ƂɂȂ�B����́A�g�N���B���̌����ɏ���Ƃ����Ȃ��d�Ⴞ�����Ƃ����͂��Ȃ����낤���B
���Q�l���f�B�A��
�u�����̉��v�ܖ��N�S���i�V���Ёj
���[�c�@���g�u���N�C�G���v(���C���X�h���t�w���{�X�g�������y�c��) CD
TV����簃[�~�i�[�� 2�^22 O.A.�iMX-TV�j
2015.02.10 (��) �����Ƀ��N�C�G����
 �@ISIL�ɂ����{�l�l�����Y�̃j���[�X�́A���̒��ɁA����܂ő̌��������Ƃ̂Ȃ����o���䂫�N�������B�e�����X�g�̍s�ׂ��̂��̂́u�c�E�E�E�ڗ�v�Ȃǂ̌`�e�ŕ\��������B�Ƃ��낪�u��E�Q�҂͓��{�l�v�Ƃ����v�f�������ƈ�C�Ɋ��o�͍�������B���ɂƂ��Ắu���o�̍����v�́A�������u�_���I�ɑ����ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@ISIL�ɂ����{�l�l�����Y�̃j���[�X�́A���̒��ɁA����܂ő̌��������Ƃ̂Ȃ����o���䂫�N�������B�e�����X�g�̍s�ׂ��̂��̂́u�c�E�E�E�ڗ�v�Ȃǂ̌`�e�ŕ\��������B�Ƃ��낪�u��E�Q�҂͓��{�l�v�Ƃ����v�f�������ƈ�C�Ɋ��o�͍�������B���ɂƂ��Ắu���o�̍����v�́A�������u�_���I�ɑ����ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�@�㓡������댯�n�тɋ�藧�Ă����̂͂Ȃ����̂��H ���{�����͂Ȃ������Ă��̂悤�ȉ����������̂��H
�@�㓡����̐S���ɂ́A��ނɂ�܂�ʉ������������̂��낤�B�u��������� �����Ȃ���̂ƒm��Ȃ��� ��ނɂ�܂�� ��a���v�B�����ĐϔN�̌o������u�����ɂ��ē�������� �����V���炴��Ȃ�v�̐S���������Ǝv����B�g�c���A�̓y���[�ւ̒��k���Ɏ��s������A�ӋC�Ɋ������y���[�̐i���ɂ��A�ɌY�ɂ͎���Ȃ������B������ISIL�ɂ͏�̌��Ђ��Ȃ������B
�@�uISIL�Ɠ������ӏ����ɑ��l���x���̂��߂�2���h�������o����v�u�킪���̓e���ɂ͌����ċ����Ȃ��v�u�ނ�ɍ߂����킹��v
�@�����܂ŗE�܂����s�p�ӂɑ�_�ɔ���������{�̃��[�_�[�͂��Ȃ������B����A�����ŁA���{�����̕��������Ă���͎̂~�߂悤�B���ɂ͂��̐�����ł��Ȃ��B���������邱�ƁB����́u���{���A���{�l���A�e���ɎN�����댯�����ĂȂ��قǂɍ��܂����v�����āu���{�͐l����荑�ے�����D�悷�鍑�ɕϖe�����v�Ƃ������Ƃ��B
�@������ǂ�����H ���҂��ǂ��v������H �����͂����A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�������Ȃ��I�I
���u���c���N�v�͜ԚL�̉̂���
 �@���I��2000�N�B���R�[�h��ЃX�g���e�B�W�b�N����ɏ������Ă������́A�u���N�C�G���v10�Ȃ����^����CD�Z�b�g�𐧍삵���B���[�c�@���g�A�x�����I�[�Y�A�u���[���X�A���F���f�B�A�t�H�[���A�u���e���ȂnjÍ��̖��Ȃ���B���I���Ɂu���N�C�G���v�A���ꂼ�i�D�̊��Ǝv�����͎̂������H ����グ�͎S�s�I �Ⴍ���Ȃ���C�̎���A���ɋꂢ�̌��������B���A�u���N�C�G���v�̑�\�I���Ȃ̐��X��O�O�ɕ������߂��A�Ƃ������n�͎c�����B
�@���I��2000�N�B���R�[�h��ЃX�g���e�B�W�b�N����ɏ������Ă������́A�u���N�C�G���v10�Ȃ����^����CD�Z�b�g�𐧍삵���B���[�c�@���g�A�x�����I�[�Y�A�u���[���X�A���F���f�B�A�t�H�[���A�u���e���ȂnjÍ��̖��Ȃ���B���I���Ɂu���N�C�G���v�A���ꂼ�i�D�̊��Ǝv�����͎̂������H ����グ�͎S�s�I �Ⴍ���Ȃ���C�̎���A���ɋꂢ�̌��������B���A�u���N�C�G���v�̑�\�I���Ȃ̐��X��O�O�ɕ������߂��A�Ƃ������n�͎c�����B�@���F���f�B�̉₩���A�t�H�[���̐������Ȃǁu���N�C�G���v�ɂ͊e�X�̍��肪����B�l�X�Ȍ`������B����Ȓ��A�Ǎ��Ȃ܂łɛ������鍂��̓��[�c�@���g�ł������B
�@1791�N7���̂����A�D�F�̕��𒅂����m��ʒj�����[�c�@���g��q�˂Ă����B�u���N�C�G������Ȃ��Ăق����B�O����50�h�D�J�[�e���B����������A����50�B�A���˗���𖾂����ʂ��Ɓv�B�j�͂��������c���Ɩ��O���������ɗ����������i���̌��́A�R���X�^���c�F�̌�Y���ł���Q�I���N�E�j�R���E�X�E�j�b�Z���i1762�|1826�j�����������[�c�@���g�ŌÂ̓`�L�u���[�c�@���g�`�v���o�T�ł���j�B
�@���[�c�@���g�͈����邱�Ƃɂ���B�Ƃ��낪�A�ނ͂��̂��납�Ȃ�̈˗�������Ă��āA�����ɂ͒���ł��Ȃ������B���ł��啨�͉̌��u���J�v�B���̃I�y���A�啔����7���ɂ͏o���オ���Ă������A���C�o������̓��������Ă̏C�����A�o���҂̓��ւ��̗v�]���ŁA�����ƖZ�����B����Ȓ��A�X�Ȃ���̈˗����������ށB���I�|���g2���̃{�w�~�A���Ƃ��Ă̑Պ����̂��߂̏j��I�y���u�c��e�B�g�D�X�̎��߁v�ł���B������̏�����9��6���B�ꏊ�̓v���n�B�����̔n�Ԃ̒��ł���Ȃ���ȂǁA���[�c�@���g�Ȃ�ł̗���Ƃ��Ȃ��ĂȂ�Ƃ��Ԃɍ��킹��B�Ȃ�Ƃ����V�˂Ԃ�B
�@�E�B�[���ɖ߂�Ɓu���J�v�̎d�グ�ɖv���B�����9��30���ɏ������}���邱�Ƃ��ł����B�u���J�v�́A�X�^�[�g�����D�]�A�]�����]�����Ăԑ�q�b�g�ƂȂ����B���̌�A���F�V���^�[�h���[�̂��߂Ɂu�N�����l�b�g���t�� �C�����v�������グ���̂�10��7���B���̂����肩�����Ɨ��������āA�u���N�C�G���v�Ɏ�肩���ꂽ�Ǝv����B
�@�Ƃ��낪�a���͐Â��Ƀ��[�c�@���g�̓��̂�I�݂����Ă����B�̒��͓��ɓ��Ɉ�������B�E�ъ�鎀�̉e�ɋ����Ȃ���A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�̕M��i�߂�B����Ȃ�����A���[�c�@���g�͍ȃR���X�^���c�F�ɂ����]�����B�u���́w���N�C�G���x�͎����g�̂��߂ɏ����Ă���悤�ȋC������B�l�͂������������Ă����Ȃ����낤�Ƃ����m���ȗ\�������Ă���B�l���ł�ꂽ���Ƃ͊m�����B�ڂ��͂��̍l������ǂ��������Ƃ��o���Ȃ��v�B�̒��̈����ɖϑz����������B�u���N�C�G���v�͂���ȏ��ō�Ȃ��ꂽ�̂ł���B���܂ł���2�������炸�B
�@���[�c�@���g���u���N�����T�v�̑�8���߂܂ŏ����グ���Ƃ��A�_�͔ނɂ���ȏ�̐��������Ȃ������B1791�N12��5���̂��Ƃł������B
�@���[�c�@���g�͓V�˂ł���B���y�j��䌨������̂Ȃ��V�˂ł���B5�ō�Ȃ����A6�ŏ����É��ɉy�����A8�ŃV���t�H�j�[�������A14�ŃI�y���������B��O�s�o9���̍����Ȃ��ꔭ�ËL���A4���ԂŃV���t�H�j�[�������グ��B����R���g���[�������݁B��̎��ɗՂ�ł́A�����ȃV���t�H�j�[�������A���̎��̕���āu��k���y�v�Ɓu�D��ȃZ���i�[�h�v���ɏ����グ��B
�@����ȃ��[�c�@���g���l���̍Ō�̍Ō�Ŏ��������炯�o�����������y�B���ꂪ�u���N�C�G���v�������B�u���N�C�G���v�́A���[�c�@���g�̍ō����삩�ǂ����͕ʂɂ��āA�B�ꖳ��̌���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�Ō�̒��߂̏u�ԂɁA�ނ͉��y�ɗ܂��邱�Ƃ������ꂽ�̂ł���i�A�����E�Q�I���j�@�u���N�C�G���v�̍ŏ��̕����u���Օ��v�u�L���G�v����u�{��̓��v�B�����āu���ꂵ�ҁv�u���N�����T�v�B����ȉ��y�̓��[�c�@���g�̑��̂ǂ��ɂ�����͂��Ȃ��B�������ԚL�B����̖z���B���_�u�����ȁv�Ƃ��Ă̈����̗v�f�͂�����̂́A�����Ɉٗl�ȋ������䂫�N������������B�V�ˍ�ȉƂ��z�������g�̐l�ԂƂ��Ă̋��сB���ړI�ȜԚL�̐��B�����āA����͐������₳�ꂽ�l�Ԃ̔ߒɂ��ł�����B
�m���ɔނ̎�ɂȂ�ŏ��̕��������l�ɂ́A���y�����y�Ɍ��ʂ���ٗl�Ȑh������������ł��낤�B�����āA���ꂪ��ł��čs�����I�c�@���g�̓��̂�͕킵�Ă���l���܂��܂��ƌ���ł��낤�i���яG�Y�j
������̂܂܉��y�̊O�Ɉ��Ă����i�����[�c�@���g�����������Ƃ�����Ƃ���A���́u���N�C�G���v�������Ăق��ɂ͂Ȃ��i�Έ� �G�j
�@����́A�����̋�ɎU�����l���I�Ȉ�l�̓��{�l�Ɠ����ł͂Ȃ����B������A���A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v���B�_��A������^�����܂��I
���Q�l������
�u���[�c�@���g�Ƃ̎U���v�A�����E�Q�I���� �����p�Y��i�����Ёj
�u���I�c�@���g�v���яG�Y���i�V�����Ɂj
�u�f��̃��[�c�@���g�v�Έ� �G���i�������Ɂj
�u���[�c�@���g�v���C�i�[�h�E�\�������� �Έ� �G��i�V���فj
2015.01.25 (��) �f��u�o���N�[�o�[�̒����v�Ƒh��
���o���N�[�o�[�̒������@����A�f��u�o���N�[�o�[�̒����v���ς��B�u�a����v���̕��ŁB�u�a����v�͉��OB�̓�����łW���O��̏W���B�O��Ƃ����̂́A�����o�[�Œ肹���A�o�ȋ��v�����̂��߁B�N���50�|70��B�j���䗦6�F2�B�J�Â͊�{����B���̕��u�f��ӏ܁v�A��̕��u���݉�v�̎��Ԋ��B���c�ʼnf���I�сA�ςāA���������̂�H�����B�b��́A��������̉f�悩��A���y�A�|�\�A�X�|�[�c�A�{�A�����A�Ƒ��A�F�l�A�d���A�̘b�Ƒ���ɓn��B���Ɋy�����B���Â��l��������Ȃ��Ǝv���u�Ԃł���B
�@�u�����͊m���ɑ厖�B���̂��Ƃ͉������Ă���邩��B�ł��A��ԑ厖�Ȃ��Ƃ͉������Ă���Ȃ����v�̓W���Y�E�s�A�j�X�g�H�g�q�q����̌��t�B��ԑ厖�Ȃ��Ƃ��������Ă���Ȃ��Ȃ�A�����͂قǂقǂɂ�������킯�ŁA����͍ő勉�̖������Ǝv���B�]�숻�q�́g���n�̃X�X���h���y���ɐ����͂�����B���ɂƂ��āB�g��ԁh���g�^�Ɂh�ƒu��������A�u�a����v�͐^�ɑ厖�Ȃ��̂̈�ł���B
 �@�u�o���N�[�o�[�̒����v�́u�����v���ĉ����Ǝv������싅�`�[���̖��O�������B�������߁u�o���N�[�o�[�����R�v�Ƃ������Ƃ��납�B�A�j�}���Y60�N��̃q�b�g�ł�����݂̃t�H�[�N�\���O�ɁuThe House Of The Rising Sun�v�Ƃ����S������B���{���́u�����̂�����Ɓv�B���ꂾ�Ɓu������������Ƃ����� �u�₩�Ȃ�v�I�ȏ�i��A�z���邪�A���́uThe Rising Sun�v�Ƃ��������̔��t�h�̂��b�B�u�����O�v�����肪����B���݂ɁA�����������݂͂��̃^�C�g���ʼn̂��Ă���B�̂��o���� ���������̂̓j���[�I�����Y�́u�����O�v�Ƃ������̏��Y���������i���F���}�L�j �u�o���N�[�o�[�̒����v�����^�I�H
�@�u�o���N�[�o�[�̒����v�́u�����v���ĉ����Ǝv������싅�`�[���̖��O�������B�������߁u�o���N�[�o�[�����R�v�Ƃ������Ƃ��납�B�A�j�}���Y60�N��̃q�b�g�ł�����݂̃t�H�[�N�\���O�ɁuThe House Of The Rising Sun�v�Ƃ����S������B���{���́u�����̂�����Ɓv�B���ꂾ�Ɓu������������Ƃ����� �u�₩�Ȃ�v�I�ȏ�i��A�z���邪�A���́uThe Rising Sun�v�Ƃ��������̔��t�h�̂��b�B�u�����O�v�����肪����B���݂ɁA�����������݂͂��̃^�C�g���ʼn̂��Ă���B�̂��o���� ���������̂̓j���[�I�����Y�́u�����O�v�Ƃ������̏��Y���������i���F���}�L�j �u�o���N�[�o�[�̒����v�����^�I�H�@�����ḍa����������^��p�U��������܂ŁB����̓o���N�[�o�[�̓��{�l�X�B�����ɂ́A���{�l�ږ��𒆐S�Ƃ����u�o���N�[�o�[�����v�Ƃ����싅�`�[�����������B�J�i�_�̃��[�O�ɏ���������A�̗͋Z�p�ɗ��`�[���͖��N�ʼn��ʂ̎㏬�`�[���B����Ȃ��ו����c���A����20�N������̂�����A�V�L���v�e���̃A�C�f�B�A�ɂ��˔@�ڊo�߂�B�o���g���ۂ���g�����@���͖싅���u���C���E�x�[�X�{�[�����B����т�m�����`�[���́A���錩�鋭���𑝂��A���ɂ͗D������܂łɁB�ٍ��œ������{�l�ږ��̖��̌����ԂƂȂ����̂ł���B���A�푈�̑����͔ނ�ɈÂ��e�𗎂Ƃ��n�߂�B�����āA�^��p�U�����Ȃ��āu�o���N�[�o�[�����v�̗��j�͏I���̂ł���B
�@�ē͐Έ�T��B2014�N�x���{�A�J�f�~�[��i�܂Ɗē܂��u�M��҂ށv�Ŏ�܁B32�̏r�p���B�ȕv�ؑ��A�T���a��A�����[���A���͂Ȃ��Ȃ��̍D���B�e�l�̃Z���t���ɓx�Ɏ��R�Ȃ̂́A�ē̈ӌ����D�������Ă�B�����_�s�A�ߌ��C��A�吙�������������Ƙe���ł߂�B���ɍ����̂��܂��͈����B��łŖ����Ō��h������A���̂����Ƒ��v���̗D���������A�Â����{�̕��e�����I�݂ɕ\�����Ă����B
�@�����s�ɑg�Z�b�g���܂������B�펞���̃J�i�_���{�l�X�̎��������Ƀ��A���B�d���ȍ�����������B�Έ�u�����h�̏㎿�����`����Ă���B
�@�J�i�_�ɖ���y���C��n����������ꂽ�����Ɍ˘f�����{�l�ږ��B�����^�ʖڂ��ƋΕׂ������킸�����ɐ������B�����ɔނ�ɖ����^�Ԗ싅�`�[�����������B�₪�Ă��̂ъ��푈�̉e�B���ĊJ��B�]�V�Ȃ����ꂽ���U�B����Ȏ���w�i�Ƃ����ŕ�炷�l�X�̋@���������ɕ`���ꂽ��ꋉ�̌�y��i�������B
���h����
 �@��������A���{�ł̓v���싅�`�[�����a���i1934�N�j�B����ɐ旧���{��A�����J����`�[�����ĂB�x�[�u�E���[�X�A���[�E�Q�[���b�N���i����I�[���X�^�[�E�`�[���ł���B������{�I���̃G�[�X�͋��s���Ƃ𒆑ނ��č��������h���i1917�|1944�j�������B
�@��������A���{�ł̓v���싅�`�[�����a���i1934�N�j�B����ɐ旧���{��A�����J����`�[�����ĂB�x�[�u�E���[�X�A���[�E�Q�[���b�N���i����I�[���X�^�[�E�`�[���ł���B������{�I���̃G�[�X�͋��s���Ƃ𒆑ނ��č��������h���i1917�|1944�j�������B�@1934�N11��20���A���㋅��B�̋r�����X�Əグ�^�������瓊�����ރX�g���[�g�͚X����グ�A�x�[�u�E���[�X���n�߂Ƃ���僊�[�K�[����9�̎O�U��D���A���_��7�[��Q�[���b�N�ɑł��ꂽ�{�ۑł�1�_�̂݁B������0�|1�̐ɔs���������A���̉����͓`���Ɖ������B
�@���̃V���[�Y�A���{�`�[����16��S�s�B�͒ʎZ0��4�s�B���㋅��ȊO�ł̓��b�^�ł��ɑ����Ă���B
�@���̔N12���͑�ꍆ�v���E�`�[���u����{�����싅��y���v�i���E�ǔ����l�R�j�ɓ��c�B1936�N�ɂ͓��{�E�Ɩ싅�A���������A�̖싅�l���͗m�X�̂͂��E�E�E�E�E�B�Ƃ��낪�A�e�𗎂Ƃ����̂́A��͂�푈�������B�N�㏇�ɔނ̖싅�l���Ɛ푈�Ƃ̊֘A�������L���Ă݂悤�B
1936�N ���{�E�Ɩ싅�A�������B�v���싅���[�O��X�^�[�g�@��n�ł͎�֒e�𓊂���������B�����v���싅����̎�֒e�͓G�w�Ɍ��������O��Ĕ�Ƃ����B��֒e�̏d���͖싅�{�[����3�{���B�̌��͂��������Ă������B1940�N�����A�������͂����{�i�h�I�[�o�[�X���[�����͏o���Ȃ������B�T�C�h�E�X���[�Z�I�h�ɓ]�������������V���P�s �m�[�q�b�g�E�m�[�����P��Ƃ������сB�Ȃ�Ɣ�}�I�����̑�������łȂ��؋����B
�@�@�@�@�@13��2�s �m�[�q�b�g��m�[�����B��
1937�N 24��4�s1�� MVP�l�� �m�[�q�b�g�E�m�[�����B��
1938�N 1�x�ڂ̏o�� �����푈�ɏ]�R
1940�N �����A��
�@�@�@ �@ 7��1�s �m�[�q�b�g�E�m�[�����B��
1941�N 9��5�s1��
1942�N 2�x�ڂ̏o�� �����m�푈�ɏ]�R
1943�N �����A��
�@�@�@ �@ 0��3�s ��͊O�ʍ���
1944�N 3�x�ڂ̏o�� �펀
�@2�x�ڂ̏o����͌������E�B�A���_�[�E�X���[�ɕς����0��3�s�ɏI���B��Ȃ���͊O�ʍ��B������3�x�ڂ̏o���Ő펀�B�㊥27�B�܂��ɐ푈�ɖ|�M����s�����ꂽ�싅�l���������B
�@ �@�ʎZ����53��15�s2���B���ꂾ������Α債�������ł͂Ȃ��B�����������A�푈�Ƃ����������Ȃ��^���Ɛ킢�Ȃ���A�����邱�ƂȂ�����̐E����S�����Ђ�����싅�ɑł����h���Ƃ����싅�l�̐��U�́A�������z���ĉ�X�̋��ɔ�����̂�����B�ނ̌��т��̂��Đ��܂��Ȃ��u�h���܁v�����肳�ꂽ�B
�@������ �ʏ��B�F ���c���� ���R�� �]�ĖL �K�c�^�� ��Ήp�Y �_���r�b�V���L �c������etc�B�X����攭�����^����܂ɖ���A�˂�B�Ȃ��_�l�E���l�E����l�̈���a�v�̖��O���Ȃ��̂́A�����Ώۂ��Z���[�O�Ɍ���ꂽ����B���݂Ƀp���[�O��1���͖�i1990�N�j�ŁA�Ȍ�Z�p�����[�O���ΏۂƂȂ�B����܊���B�������]���ł͂Ȃ����{���ɗ^����ꂽ1981�N���b��ƂȂ����B��҂͈�l�Ɂu�Ȃɂ����~���������܁v�ƌ����B���ꂱ�����h���̈̑傳�̏ؖ����낤�B
�@�O���̒n�Ől�m�ꂸ�싅�ɑł����ޓ��{�l�������B�푈�ɖ|�M����Ȃ�����^����ꂽ�싅�l����t�����������V�˓��肪�����B�펞���̃J�i�_�Ɠ��{�B�����m������Ŗ싅�ɏ�M���X�������{�l�����B��҂�Δ䂳�����j���ڂ݂�ʔ����B���N�͏I��70�N�B���j���Ăъo�܂��Ȃ���A�����ɂƂ��ĈӋ`����ߖڂƂ��������̂ł���B
2015.01.13 (��) �V�N�Ɋ� with Ray�����
 �@���[��Ray�����I 2015�N�������J�����ˁB���N�͐��70�N�̐ߖڂƂ��BJiiji�͏I��̔N�̐��܂ꂾ����A����70�B������5�����܂ꂾ���烌�b�L�Ƃ����풆�h�����I�H�������낤�i�ǂ����H���j�B�V�c�É����A�N���̂����t�ŁA��̓I�ɗ��j�F���Ɍ��y���ꂽ���ǁA���̉e��������̂��Ȃ��B�u���70�N�̐ߖځv�A�}�X�R�~�̑O�̂߂肪�ڗ��̂͋C�̂������B����Ƃ����{�����̐������}�X�R�~��������������Ă�̂��Ȃ��B
�@���[��Ray�����I 2015�N�������J�����ˁB���N�͐��70�N�̐ߖڂƂ��BJiiji�͏I��̔N�̐��܂ꂾ����A����70�B������5�����܂ꂾ���烌�b�L�Ƃ����풆�h�����I�H�������낤�i�ǂ����H���j�B�V�c�É����A�N���̂����t�ŁA��̓I�ɗ��j�F���Ɍ��y���ꂽ���ǁA���̉e��������̂��Ȃ��B�u���70�N�̐ߖځv�A�}�X�R�~�̑O�̂߂肪�ڗ��̂͋C�̂������B����Ƃ����{�����̐������}�X�R�~��������������Ă�̂��Ȃ��B�@�����́A���̐��70�N�̐ߖڂɁA�Ȃɂ��u���{�k�b�v�Ȃ���̂��o���炵���B���50�N�Ɂu���R�k�b�v�A60�N�Ɂu����k�b�v���o���̂�����A�o�����Ǝ��̂��Ƃ₩����������͂Ȃ�����ǁARay�����A���͓��e���ȁB���ɁA���S�ۏ�Ɋւ��ẮB
�@����閧�ی�@�i����́A�Ď��@�֑̐����s�\���̂܂{�s���ꂿ������j�A����A�o�O�����̓P�p�i���{������̏��l���A��Ȃ��j�A�����āi�t�c����Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ���@�ɂ��j�W�c�I���q���̍s�g�e�F�B���̕����A��{�I��Jiiji�͔����B�ł��A���@�I�ɑI�ꂽ�א��҂����@�I�ɍ��̕��������߂�͓̂��R�Ȃ̂�����A�����������͏]�������Ȃ���ȁB�����A�r�̂悤�ɂ��ƂȂ������Ă���������Ă���Ȃ��B������l�ЂƂ肪�������肵���l���������Č����ׂ����Ƃ͌����B���X��X�������ƕ\���B���ꂪ�̐t�ȂB
�@���͂͂����Ȃׂāu���O�̓o�J���v������Ɏ��B�q�g���[�������Ⴞ�B�ނ͕��͂Ńh�C�c�𐪕������킯����Ȃ��B�Q�W�S���𗘗p���A�I���A�c���ʂ��č��@�I�Ɏ���i�߂��B
�@�����̃h�C�c�́A��ꎟ���E���`���E�勰�Q�̂�������āA�ɓx�ɔ敾���Ă����B�d�����Ȃ��B�C���t���B������B���Ƃւ̕s�M������B�����̌ւ�Ȃǘ_����ɂ��Ȃ��B �q�g���[�͂����ɂ����B�����_����`���f���A�[���A�����̗D�ʐ�������A�h�C�c�����̈����S�Ǝ����S�ɉ�����B���������f���ĐN���푈���N�����o�ϐU����}�����B�ٗp�g��̂��߂ɐ푈�𐳓��������Ƃ�������ˁB
�@�����ēV���̉����͂Ŗ��O�����B�Q�W�S���̗��p�B�܂��ɐ����̓V�ˁB�t�����X�̎v�z�ƃM���X�^�[���E���E�{���i1841�|1931�j�́A�Q�W�S���̓������A�u�Q�W�͈Î��Ɏア�v�u�Q�W�͔����f���Ɏア�v�Əq�ׂĂ����B
�@���{�����́u�������{�����߂��v�u�o�ύŗD��v�Ɖ]���B�u�������{�v�́u�A�[���A�����̗D�ʁv�A�u���Z�ɘa�ɂ���čD�i�C�����o������Ԃ̂Ȃ��o�ϐ���v�́u�푈�����Ă��o�ϐU����v�ƕ������Ȃ����H �A�x�m�~�N�X�̘A�Ă̓q�g���[�E���g���b�N�ƌĉ�����B����A���{�����̓q�g���[�ɒʂ��̐}�����ȁH
�@�V�N���X�A�V���b�L���O�ȃj���[�X����������ł����B1��7�������A3�l�̃t�����X�l�C�X�������k���p���̐V���Ђ��P���B�L�҂�12�l��������Ď��S�����B�ƍs�㓦��������Ɗi�̓�l�͈���H���ɗ��Ă�����A�Ō�͎ˎE�������A�����Ŏ���ꂽ�l��4�������S�B�����Čx��1���A���҂͍��v17���ɒB�����B�C�X�������ւ̊S�����܂���������A�Ɛl�̓C�G�����̃A���J�C�_����̎w�߂ɂ��ƍs�ɋy�Ɛ������Ă����������B
�@�ƍs���@�A�ߌ��h�g�D�̑��l���A���ď����ɂ�����C�X���������͂̊g��A�ߌ��h�ɓ������҂̑���A�C�X�������ւ̖{���I�ȗ��A�_����ׂ��͑��X����B���AJiiji�ő�̌��O�ɂ��Ė���́A�u�W�c�I���q���s�g�ɂ����{�ւ̃e���̋��Ђ��啝�ɑ��傷��̂ł͂Ȃ����v�u���{�����ɂ��̐S�ς��肪�o���Ă���̂��ǂ����v�Ƃ������Ƃ��B
�@���ď����ɂ�����e���Ή��̗��O�́A�u�������Ȃ��p����l�����d���D�悷�邱�Ɓv���B���ʁA�l�������E���ɂ���B���̂��ƂŐ��Ԃ������Ȃ��B�ʂ����āA�e���ɖƉu���̂Ȃ����{�͂ǂ��Ώ��������Ȃ̂��H
�@��N���V�h�j�[�ŋN�����ߌ��h�ɂ��l�������B�I�[�X�g�����A���u�������C�M���X�̃C�X�������Q���Ɏx���v��\�������̂������A�Ƃ����Ă���ˁB�|���̂́A���̑��ɂ��A�x���M�[�A�J�i�_�ȂǁA����܂ŃC�X�����ߌ��h�̕W�I���肦�Ȃ����ŋN�����Ă��邱�ƁB������A�W�c�I���q�����s�g����A���{���C�X�����ߌ��h�̕W�I�ɂȂ肤��Ƃ������ƂȂB
�@�e�����X�g�Ƃ̐푈�͂���܂łƂ͑S���Ⴄ�l����悵�Ă���͎̂�������ˁB���Ă̐푈�͍����m�̗����̑����������B�݂��ɍ���������őΛ�����B���m����낤���{�^���ł�낤���A��{�͕ς��Ȃ��B�����猩���₷�����킢���ɂ��m�`������B�����A�e���푈�ɍ����͂Ȃ��B�m�`�Ȃ������Ȃ蕽���ȓ���ɓ��荞�ށB�������܂��̂͏������B
�@���_�A��X�̓e���ɂ͋����Ȃ��B�ނ炪�ǂ�Ȍ������f���悤���A���ꂪ�ނ�ɂƂ��Ă����ɐ��`�ł��낤���A���@���Ԉ���Ă���̂�����A�O��I�ɐ키�����Ȃ��B���{���������ƈꏏ�Ƀe���Ɛ키���Ƃ��A�����������߂��Ȃ�]���܂���i�{���́A�A�����J�Ɍ����������Ƃ����邯��ǁA�g�b�`���J�������߂Ă������j�B�����A�����ŐS�z�Ȃ͉̂�炪���[�_�[�̓��@�x�����Ɗo��Ȃ̂��B
�@���{�����́A�W�c�I���q���s�g�̕|���������ƔF�����Ă���̂��낤���H Jiiji�́A�ނ̏���ʂ̌��������Ă���ƁA�ƂĂ������Ƃ͎v���Ȃ��B�\�V�C���O�̂߂�ő����Ă�B���ɕ|���B
�@�����́A�W�c�I���q���s�g�ɂ�����u�������ԁv�̊T�O�`���ɕK���̑̂����A����͊����T�O��O��Ƃ������̂��B�e���Ƃ̐푈�`�Ԃ͂��͂�َ����Ɉڍs���Ă���i�O�q�����悤�ɂ���͐��E�̏펯���j�B�W�c�I���q���̍s�g�ɂ���āA�����̂ǐ^�ŃC�X�����ߌ��h�ɂ��l�������⎩���e�����N���Ȃ��ƁA�N���f���ł��܂����H
�@�N���Ă���Q�ĂĂ��x����ł��B���{����A�����Ƒz�肵�Ă��܂����H ���̊o�傪�ł��Ă��܂����H ���̂Ƃ��A���Ȃ��͂ǂ��Ώ��������ł����H �l�������E���ɂ��ĔƐl�ˎE��D�悷�鉢�Č^���̂�H ����Ƃ��A���ς�炸�u�l�̖��͒n�������d���v�ȂǂƉ]���ė����������H �Ή������߂ĂȂ��̂Ȃ�A���ƑΌ�����o�傪�ł��Ă��Ȃ��̂Ȃ�A�W�c�I���q���s�g��O�̂߂�Ői�߂�ׂ�����Ȃ��B�c�_��s���������̃R���Z���T�X�Ă�����ׂ��A�ł��B��ɁB
�@�����͂܂��A����A�V�N�̃��b�Z�[�W���������B�u���{���A�ĂсA���E�̒��S�ŋP�����Ƃ��Ă䂫�����v�ƁB�٘_�͂Ȃ��B�����A�ނ��ڎw���u�P�����{�v���ĉ��H
�@Jiiji�͊肤�B���N�o�����ł��낤�u���{�k�b�v�Ȃ���̂��A��~�ɂ��炸�������������]�ށu�P�����{�v�ł����Ăق����ƁB�\�z��NO�ł����ˁB�c�O�Ȃ���B
�@�������͌Q�W���B�Î��Ɏア�������f���ɂ��ア�B���͂͂����ɂ����ށB�����A�x����Ă͂����Ȃ��B��l�ЂƂ肪�����Ȃ�Ȃ�������Ȃ��B�R���������B�^���𑨂���B���̒��Ɋ�����点��B�{�������ɂ߂�B����S��Y���ȁB��ɍl����B
�@�Ȃ��ARay�����AJiiji�͂��ꂩ����l��������B���E�����{���������A�{���ɂ���ł����̂����āB���Ȃ��̎��オ���悢���E�ł���悤�F��Ȃ���ˁB
2014.12.25 (��) 2014�����_����� with Ray�����
 �@���[��Ray�����I���N�����悢��I��肾�ˁB�����́u�Łv�����āB���C�Ȃ��ˁB�ł��AJiiji�͊y����������BRay�����̂��A�ŕۈ牀�̃T���^�N���[�X�ɂȂ�������ˁB�H�����A�Փˎ��́�G�t�@�C�i��V�̓����̂��Ƃ��A�u����͒N�ɂ��o����o������Ȃ�����A���N���N���܂����v�Ȃ����Ă����ǁAJiiji�̃T���^�N���[�X�̌��������C������������B�����I�H �ق�Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��B
�@���[��Ray�����I���N�����悢��I��肾�ˁB�����́u�Łv�����āB���C�Ȃ��ˁB�ł��AJiiji�͊y����������BRay�����̂��A�ŕۈ牀�̃T���^�N���[�X�ɂȂ�������ˁB�H�����A�Փˎ��́�G�t�@�C�i��V�̓����̂��Ƃ��A�u����͒N�ɂ��o����o������Ȃ�����A���N���N���܂����v�Ȃ����Ă����ǁAJiiji�̃T���^�N���[�X�̌��������C������������B�����I�H �ق�Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��B�@�ł�Ray�����A�����_�������珇�s���v���̂܂܍s�����B
�@�܂��́ASTAP�זE�����B12��19���A�����̌��؎������ʂ��o���ˁB�uSTAP�זE�͍쐻�ł��Ȃ������v�B�u�Ȃ������v�ƌ���Ȃ��Ƃ��낪�����I���ˁB�Ȋw�I�Ȃ̂��ȁB
�@�͂Ă��āA�����͂��������Ȃ����낤�Ȃ��B���ە����q����uSTAP�זE�͂���܁[���B200����܂����v���Č�������ˁB����͋�������B�ǂ��l���Ă��ˁB�ޏ��ɂ́AHPD�����Z���p�[�\�i���e�B��Q�i���Ȃɉߏ�ɒ��ڂ��������Ƃ���s���l�����Ƃ鐸�_��Q�j�̌X���������Ȃ����ȁB��������Ȃ��ƁA
 Jiiji�Ƃ��Ă͐���������B
Jiiji�Ƃ��Ă͐���������B�@���ڂ́A�u�Č������̉ߒ��ŁA�m���ɁiSTAP�זE����������j�ΐF�̌u�����o���B�ł�STAP�ł͂Ȃ������v�Ƃ������\���e�B���ە�����́u�ΐF�̌u���v�\�זE�Ɗ��Ⴂ�����낤�B��́A�S���Ȃ�������F�����Z���^�[���Ɠ�l�O�r��Nature�_�����܂Ƃߏグ���B�����āA���̉ߒ��ŝs�����������BRay�����A�^���͂���ȂƂ��납�Ȃ��B
�@���䎁�T�C�h����H��E�E�E�E�E���X���������Ȋw�҂��g���\�זE�炵�����́h�����o�����B���䎁�́A�u�ΐF�̌u���v��STAP���ۂ̉\��������A�Ɠ��B�\��������̂Ȃ瑁���ҏ����B�_�����܂Ƃߏグ�ĔF�m�����A���������B���̌�A�������O�ōČ������ɐ�������A�����������̎蕿�ƂȂ�B����Ȃ͉̂Ȋw�̐��E�ł͓���̂��Ƃ�����B
�@�����āA�ނ��哱���_���������������B�����ł̃X�L�������͍��䎁�̓��ӋZ�������͂��B�����āANature�ɍڂ����B�u���̖��\�זE�v�̒a���������B
�@�_���쐬�ߒ��ɂ����āA�uNature�f�ځv�����ȋʏ��ƂȂ����B���ꂪ�Ȋw�҂̂���ׂ��p�����쒀�����B�{���]�|�B�ړI�̂��߂ɂ͎�i��I���B���ꂪ�s���������B Ray�����A���̌o�܂�4��16���̍��䎁����v���N�����ƃs�^�����������B��������L�B
�@STAP���ۂ�O��Ƃ��Ȃ���Ηe�Ղɐ����ł��Ȃ��f�[�^������B�������A�_���S�̂̐M�������ߌ��s���ɂ��傫�����Ȃ�ꂽ�ȏ�ASTAP���ۂ̐^�U�̔��f�ɂ͗������O�̗\�f�̂Ȃ��Č������K�v���B��U�����邱�Ƃ��悵�ƌ��߂��ȏ�A���_�I�ɁASTAP���ۂ͌����ׂ������ɂȂ����ƍl����K�v������܂��B�@���䎁�̌�Z�́i�ܘ_�A����STAP�זE���Ȃ��������Ƃ����j�l�b�g�Љ�ƃ}�X�R�~�́g�R�����h���ߏ��]���������Ƃ��낤�B
�@����ɂ��Ă��A���̗����̎������`�[���E���[�_�[���V�T�ꎁ�̃R�����g�͍��������ȁB�u����̂悤�ɁA���j�^�[��u�����A�����҂�ƍߎ҈����ɂ����悤�Ȍ��ؕ��@�͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȋw�Ƃ͂����������̂���Ȃ��v�����āB�J������������Ă��B�Ȋw�͎������ׂĂ���Ȃ��̂��ˁB���肾�ȁB
�@���������������������ANature���u���N��10�l�v�ɑI�ꂽ�̂͂����j���[�X�������BiPS�זE���g�������E���̈ڐA��p�̐����B�Ԗ����Đ����āu������ϐ��v�̊��҂��~�����B�����̌��Ɖe�������ˁB
 �@Ray�����A�����������͓��������BJiiji�̓ǂ݂͂ˁA�w��ɂ̓t�B�N�T�[X��������Ă��ƁB��TIME���ւ̌f�ڂ����Ĕވ�l�ŏo����͂����Ȃ����낤�B��ԃN�T�C�̂̓v�����[�^�[���������ǁA����u6000���~�̑��Q�����v�i�ׂ��N������������ˁi11��25���j�BJiiji�̓ǂ݂͊O�ꂽ���H NO���B
�@Ray�����A�����������͓��������BJiiji�̓ǂ݂͂ˁA�w��ɂ̓t�B�N�T�[X��������Ă��ƁB��TIME���ւ̌f�ڂ����Ĕވ�l�ŏo����͂����Ȃ����낤�B��ԃN�T�C�̂̓v�����[�^�[���������ǁA����u6000���~�̑��Q�����v�i�ׂ��N������������ˁi11��25���j�BJiiji�̓ǂ݂͊O�ꂽ���H NO���B�@�t�B�N�T�[X����ԋ����̂́A�u�����͓����S�W����Ȃ������v���Ƃ�m���Ă����A�m���Ă��Ȃ���ꏏ�ɓ������A�����g�O���������h���Ƃ��o���邱�ƁB�O���Ȃ�i�ׂ͐������Ȃ����������т�B���炭�t�B�N�T�[X�́A�u�����͓��́w�ŏ����畷�����Ă����x�ƌ����͂����Ȃ��v�Ɗm�M�����낤�ȁB�u�m��Ȃ���������R���T�[�g��g�B�x���ꂽ�v�Œʂ���Ɠ��낤�B
�@���̊��ҁB�����͓������u���Ȃ������͍ŏ�����i�����������邱�Ƃ��j�m���Ă����B�O�������������ɁB���܂��牽����I�v�Ɩ@��ŊJ�����邱�ƁB�K���o�������͓��I
�@���̗��̂̓N���V�b�N�W�ҁB�S�[�X�g���C�^�[���o�O�͒����āA�o������͔��ɉ��B���ɍ��������̂����ؐ��i�Ƃ����]�_�ƁB�u�R�����ĕ�����剻����K�v�͂Ȃ������v�Ȃ�Ă����Ƃ��炵�����ƌ��������ǁACD�̃��C�i�[�Ȃ����Ď����グ�����{�l�Ȃ���ˁB���疳�p���r�������B�Ȃ�Ray�����A���ꂶ��N���V�b�N�E���悭�Ȃ�Ȃ���B�݂�Ȃ����ƌ����ɂȂ�����̂ɂȁB���Ƃ��Ƃ��債�����Ƃ���ĂȂ�����B
 �@Ray�����A�ł��������I���B�N���݂͂�ȖZ��������A�����̓s���ł��Ȃ��łق������B��������{�̘������ȓs�����U���Ă����B����ɂ��ẮA�����V�������т悵�̂��Ƃ�������Ƃ��������Ă������ǁA�ق��̒N�����I���˂Ă����ȁB�u���V������̑I���ŕ��̗����Ƃ��S����B�@���I���搧�A�����B���{�W�O�C�}�X�R�~�v�B����[�A���ɓI�m�B�V����I ���Ƃ��Ƃ��̐l�܂��Ƃ��ȉ����_�҂�Jiiji�͑O���炨�C�ɓ��肾�����B�ȉ��A�e�[�}�����q�����Ă�����āAJiiji�̌������I���悤�B
�@Ray�����A�ł��������I���B�N���݂͂�ȖZ��������A�����̓s���ł��Ȃ��łق������B��������{�̘������ȓs�����U���Ă����B����ɂ��ẮA�����V�������т悵�̂��Ƃ�������Ƃ��������Ă������ǁA�ق��̒N�����I���˂Ă����ȁB�u���V������̑I���ŕ��̗����Ƃ��S����B�@���I���搧�A�����B���{�W�O�C�}�X�R�~�v�B����[�A���ɓI�m�B�V����I ���Ƃ��Ƃ��̐l�܂��Ƃ��ȉ����_�҂�Jiiji�͑O���炨�C�ɓ��肾�����B�ȉ��A�e�[�}�����q�����Ă�����āAJiiji�̌������I���悤�B�@�@���I���搧�͏����h�̖��ӂf���Ȃ�����A���A���I���搧�ɖ߂��ׂ����B���̂܂܂��Ǝ����ƍق��ʂĂ��Ȃ������B������A�z��͐�Ες��Ȃ��ȁB���I���搧�Ƃ����͓̂�吭�}���ŋ@�\������̂�����A��}���炽�Ȃ��ƍ���̂�B����A����}�H �����͐����S���\�̓i�V��������ς݁B��}�ĕҁH������o�J�̏W�܂�͂�͂�o�J������Ӗ����Ȃ��B�Ȃ�A�J���X�}�����Ƃ̏o����҂����Ȃ�����Ȃ����B���ꂶ��A�_���݁B�������̎��A20�N�䖝���ď���i���Y�ɓq���邩�H Jiiji���Ⴄ�Ȃ��B
�A�@�����̑唼�́u�ǂ����ς��Ȃ�����v���Ē��߂Ă�B�l���邱�Ƃ��~�߂�����Ă�B�����猠�͂̂Ȃ����܂܁B����͏�Ȃ��B�����K�������Ƃ�������ƐM���悤���B�l���邱�Ƃ��~�߂Ȃ��ōs�������B���ꂪ�l�ԂƂ������̂���B�����݂䂫���̂��Ă��邶��Ȃ����B�u�]�݂̎��͐�Ă��A�~���̎��͐�Ȃ��v���āi�u�|�̔s�ҕ�����v�j�B
�B�@���{�����͊댯���B�ނ̐����s���͍����̂ق��������Ă��Ȃ��B�ƌP��w�����ĉ�~�����Ă��邾�����B�܂��́A�W�c�I���q���s�g�e�F���ȁB��@�͋������������AJiiji�͏W�c�I���q�����̂��̂ɔ��͂��Ȃ��B���̃��[�_�[�ɂ����Ƃ������O�Ɗo�傪����ˁB�Ƃ��낪�ǂ����낤�H
�@�W�c�I���q�����s�g���Ċ�Ԃ̂̓A�����J����ˁB�Ȃ���Ԃ��Ƃ����Œ����Ⴄ�́H�u����Ă�邩�牫��̊�n���S���y������v���炢�����Ȃ��̂����B�����̂Ƃ���͐Δj�̂ق����Ȃ�ڂ��}�V����B
�@�ł����āA������g���ƃe���W�I�̉\�����������Ă��ƁB�I�[�X�g�����A�������Ⴞ�B���{����ɂ��̊o�傪�o���Ă�̂��ȁH���ĕ��c���u��l�̖��͒n�����d���v�Ȃ����Ă��悤�ɁA�e����ɂ����āA���{�͉��ĂƂ͍��{�I�ɍl�������Ⴄ�B�܂��A�C�X�����ߌ��h���Ȃ�����قǂ܂ł̍s���ɑ���̂��B���̂�������{�����ł��Ă�̂��ȁB���̔\�V�C����j�������Ă�Ƃ͎v���Ȃ����ǂˁB
�@���ꂩ��A���@�����͒N�̂��߂ł����H�����̂��߂ł��傤�B���Ȃ��̖ړI�́A�c������̔ߊ�̎����A�����Ď����̖��O����j�ɍ��ނ���? ������`�̐^�t�����������}�����Ă�ǂ߂A�����Ƃ����v���Ȃ����A�Ȃ�Ray�����I
�@������]��k���O�o������肾�����B�����ʂ̏K�ߕ��ɉ���������߂ɗ̓y��̂��ˁB�u��t�����y�ѓ��V�i�C�X��ŋْ���Ԃ������Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�����ňقȂ錩����L���Ă��邱�Ƃ�F������v���Ƃ��B����܂ł̎咣�́u��t�����ɗ̓y���͑��݂��Ȃ��v��������Ȃ������́H ���ꂶ��A�u��t�����͓��{�ŗL�̗̓y�v�Ȃ�Č����Ȃ��Ȃ�B�����˔j���ɒ������ǂ��o�邩�B�A���^�͂���Ȃ��Ƃ��ǂ߂Ȃ��̂��ˁB
�C�@���̃}�X�R�~�͍��������B����̑I���ŁA�����}����u�ᔻ�I�ȕ��藬���Ȃ��悤�Ɂv�Ȃ�ʒB���������āH ����́u�ǐ��v�ł���B�Ȃ������Ƒ����Ȃ��́H�{��Ȃ��́H ���R�ȕ��������`�̍�������Ȃ��̂��ˁB
�@Ray�����A�Ō�ɃI�}�P�B�X�|�[�c�E��ځB�삯���łˁB�܂��́A�e�j�X���ѐD�\�B����͋��ق������B�����N��17�ʁ�5�ʁB�S�ăI�[�v�����D���B�c�A�[�E�t�@�C�i���̓x�X�g4�B�e�j�X�E�Ńp���[�̂Ȃ����{�l�̑䓪�͖����Ǝv���Ă������A�����ɕ����Ă��ꂽ��B���N�������W���[V���B�S���t�ƃT�b�J�[�A�������肹����B���X�����O�g�c���ۗ��̐��E���15�A�e�͂ƂĂ��Ȃ��L�^�B�e����S�������N�Ȃ̂Ɉ̂��̈��B�̑������q���̐��E�I�茠�l����5�A�e�������B���W�F���h�E�����I��42��7�x�ڂ̃I�����s�b�N�ŋ�ƃ��[���h�J�b�v��V�͕����ʂ背�W�F���h���Ȃ��B�t�B�M���A�H�������̃I�����s�b�N����GP�t�@�C�i���D���͌����B�������̃A�N�V�f���g���u�D�@�v�Ƒ����钴�|�W�e�B�u�u���ɓV���ꂾ�B�Y�ꂿ�Ⴂ���Ȃ��̂̓\�t�g�{�[�������R��q�B���E�I�茠��2�A�e�B���B�\�t�g�{�[����2020�����ܗւŕ����炵������A38�A�����ŋ��Ȃ�ޏ������W�F���h�B�����Ƃ��邺�A�ޏ��Ȃ�B�Ō�ɍŐV�z�b�g�j���[�X���B�N�x���_�����߂�o�h�~���g���E�X�[�p�[�t�@�C�i���ŁA����������F�����I�y�A�����q�_�u���X�ŗD���A���E��ɁB�����h���ܗ։��҂̒����y�A��j���������ɉ��l�͑傾�B
�@Ray�����AJiiji�͗��N���D��̊�Ǝv������S��Y�ꂸ�Ɋ撣���B��낵���ˁB�ł͊F�l�A2015�N���ǂ��N�ł���܂��悤�ɁI�I
2014.12.10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���11�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�b�n��3�̕s���s�u�o�b�n�̓��[�~���̐擱�t�v
�@���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�i1685�|1750�j�͂悭���w�҂ɏy������B�m���ɁA�u�t�[�K�̋Z�@�v�ɂ�����w�I�p�`������ނׂȂ邩�ȂƎv���B�ł��A���ꂾ������蕿�Ȃ�����~�܂�B�����ɁA�u���y�̐����v���h���Ă���Ƃ��낪�A�o�b�n�̃o�b�n����R�����낤�B�@������A���y�̐����Ƃ́H ���y�̏ؖ��Ƃ́H ��X�����y���ē�����́A���y�ɋ��߂���̂Ƃ́H ����́A�u�����v�Ɓu�����v�B���āA���b�N�E�A�[�e�B�X�g�̊p���q�����u���y�ɂ̓_���X�~���[�W�b�N�Ə@�����y�����Ȃ��v�Ǝ��Ɍ�������Ƃ����邪�A�������H
�@�o�b�n�̉��y�́A�u�����v�i�h���Ԃ�j�Ɓu�����v�i���炬�j�ɖ����Ă���B���y�̐����������Ă���B������A��ɑ�����ȉƂ�G������B�����̋@��Ɏg����B�i���ɐ���������B
�@����́A����ȃo�b�n�̉��y���A����A�����J-POP�̒��ɁA�ǂ����Â��Ă��邩�H ��T���Ă݂����B������s���s�ł���B
�����C�J�R���̏ꍇ��
�^���̏u�Ԃł����BJ.S.�o�b�n�́u�g�b�J�[�^�ƃt�[�K �j�Z���v�����߂Ď��ɂ����Ƃ��̂��ƁB���t�ɂł��Ȃ��B�d���ɑł��ꂽ�悤�ȃV���b�N�I�I ����܂ŁA���y�͕��ʂɒ����Ċy���ނ��̂������̂ɁA�����ŏ��߂āu�����������v�Ƃ����Փ��ɋ��ꂽ�̂ł� �i�u�f�r���[40�N ���͂ĂȂ����v2012�NNHK���W���j�B�@���[�~��12�A�������w�@���w�ɓ��w�����Ă̂���̌��ł���B�����āA���N�A�v���R����n�����́u���e�v�ɏo��B
�I���K�����t�B�[�`���[�������̋Ȃ��āA�����ɂ��ł��邩������Ȃ��B�M�^�[�ł͂Ȃ��L�C�{�[�h�̃��b�N�B���b�N�Ƌ���y�����n������悤�ȉ��y���B
 �@�u���e�v�̓o�b�n�uG����̃A���A�v�����ȁB�u�g�b�J�[�^�ƃt�[�K �j�Z���v�ɐG������uG����̃A���A�v�Ŏ���i�ނׂ������m�M�������[�~���BJ.S.�o�b�n�����A���[�~���ɉ��y�ւ̓����J�������擱�t�������B
�@�u���e�v�̓o�b�n�uG����̃A���A�v�����ȁB�u�g�b�J�[�^�ƃt�[�K �j�Z���v�ɐG������uG����̃A���A�v�Ŏ���i�ނׂ������m�M�������[�~���BJ.S.�o�b�n�����A���[�~���ɉ��y�ւ̓����J�������擱�t�������B�@���[�~���̃t�@�[�X�g��A���o���u�Ђ������_�v�́A1973�N�A���[�~��19�̍�i�B�^�C�g���ȁu�Ђ������_�v��Â��ɒ����B�L�C�{�[�h�ƃI���K���̋����B�Iꡂ���e���|�B�u�Ђ������_�v�̌������Ɂu���e�v��������B�ޕ���J.S.�o�b�n������B
�@�����A���w�Z�̋���Łu�g�b�J�[�^�ƃt�[�K�v�ɏo���Ȃ�������A�����v���R���E�n�������u���e�v�����Ȃ�������A���[�~���͕��ʂ̂�����ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B����J.S.�o�b�n�Ȃ��肹�A�X�[�p�[�X�^�[�E���[�~���͒a�����Ă��Ȃ������I�H
�������݂䂫�̏ꍇ��
�@�o�b�n�Ɂu��� �l�̖]�݂̊�т�v�Ƃ����y�Ȃ�����B�J���^�[�^��147�ԁu�S�ƌ��ƍs���Ɛ����Łv�̒��̃R���[��(�^����)�B�����f�B�[�́A�i�����Ȃ������A�Ȃ艄�X�Ƃ��ďI��肪�Ȃ��B�����o���b�N�I���������ł���B
�@��L���X�g�����䂪��� �Ǝ�C�G�X�E�L���X�g�邱�Ƃ��ł�������}���A�̐S����r���B�h�i���Ɗ�тɖ��������������B
 �@�����݂䂫�Ɂu����v�Ƃ����Ȃ�����B1978�N�̃A���o���u�����Ă���Ɖ]���Ă���v�ɓ����Ă���y�Ȃ����A�r���𗁂т��̂�1981�NTBS�h���}�u�����搶�v�ɑ}�����ꂽ�Ƃ��B
�@�����݂䂫�Ɂu����v�Ƃ����Ȃ�����B1978�N�̃A���o���u�����Ă���Ɖ]���Ă���v�ɓ����Ă���y�Ȃ����A�r���𗁂т��̂�1981�NTBS�h���}�u�����搶�v�ɑ}�����ꂽ�Ƃ��B
�V���v���q�R�[���̔g�ʂ�߂��Ă䂭 �ς��Ȃ����𗬂�ɋ��߂��@����8���ߕ������A���H�[�J����3����4��J��Ԃ��t�F�[�h�E�A�E�g�ŏI���B������܂��������������B�o�b�n�́u���A�l�̖]�݂̊�т�v�Ɠ����\���ł���B
���̗�����~�߂ĕς��Ȃ����̂� ��������҂����Ɛ키����
�@�V���v���q�R�[���͑i���̏��a�B�ϊv�����₷��ǂւ̒��킾�B�ǂ̌������ɂ����]��ڎw���A�V���v���q�R�[���͉i���ɑ����B����}���A�̊�т̐�ɂ���]������B�����݂䂫���o�b�n�����������̔ޕ��Ɋ�]�����Ă���B
���R���B�Y�̏ꍇ��
 �@�����ł́A�u�N���X�}�X�E�C�u�v�����グ�悤�B���̋Ȃ́A�R���B�Y���Ɨ����[�x���u���[���v�𗧂��グ�Ă̑�P��A���o���uMelodies�v�ɑ}�����ꂽ�B1983�N�̂��Ƃł���B
�@�����ł́A�u�N���X�}�X�E�C�u�v�����グ�悤�B���̋Ȃ́A�R���B�Y���Ɨ����[�x���u���[���v�𗧂��グ�Ă̑�P��A���o���uMelodies�v�ɑ}�����ꂽ�B1983�N�̂��Ƃł���B�@1988�N�AJR���C���N���X�}�X�E�L�����y�[���̃e�[�}�\���O�Ƃ��Ďg�������ƁA���ꂪ�����ɛƂ��q�b�g�B�N���X�}�X��\���O��No.1��ԋȂƂ��Ē蒅�����B
�@�u�N���X�}�X�E�C�u�v�̊ԑt�ɂ͒B�Y�̃X�L���b�g����ۓI�ɓ���B����́u�p�b�w���x���̃J�m���v�����^�B�ł́A�ǂ��Ńo�b�n�ƌq����̂��H
�@�u�J�m���v�̍�҃��n���E�p�b�w���x���i1653�|1706�j�́A�h�C�c�E�o���b�N�̍�ȉƂŁA���y�j�I�ɂ́A�t�[�K��R���[���O�t�Ȃ̔��W�ɍv�����Ă���iWikipedia���j�B ���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�̕��A���v���W�E�X�i1645�|1695�j�́A���y�ƂƂ����Ă��A�C�[�i�n�̂����Ȃ����b�p�����B��Ȏd���͒��̍��䂩�玞���������郉�b�p�𐁂����Ƃ������B����ȕ��e����Ƃ̉��y���t�Ƃ��Ĕ��H�̖�𗧂Ă��̂��A�e���̂������p�b�w���x���B���̂Ƃ����n���E�Z�o�X�e�B�A���͂܂����܂�Ă��Ȃ��B
�@��������̂̓��n���E�N���X�g�t�i1671�|1721�j�B���n���E�Z�o�X�e�B�A����14�ΔN��̒��Z�ł���B�p�b�w���x���͔M�S�ȋ���҂ŁA���n����N���X�g�t���Z�ݍ��܂��A3�N�Ԃ݂����苳����{�����B�Έʖ@�𒆐S�ɍ�ȋZ�@�S�ʂɂ킽�����Ƃ����B
�@1695�N�A���A���v���W�E�X�����E�B�܂�10�̃��n���E�Z�o�X�e�B�A���́A�I�[���h���t�ɏZ�ޒ��Z���n���E�N���X�g�t�̌��ɐg���邱�ƂɂȂ�B�킪�����[�l�u���N�Ɉڂ�Z�ނ܂ł�5�N�ԁA�Z�͓O��I�ɉ��y�̊�b��@�����ށB���ꂱ�����p�b�w���x�����`�̍�ȋZ�@�B���y�̕��̕��̓p�b�w���x���������̂ł���B
�@�����ɁA�p�b�w���x�������n���E�N���X�g�t�E�o�b�n�����n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�Ƃ�����{�̐����`�����ꂽ�B�p�b�w���x������_�Ƃ��āA�R���B�Y��J.S.�o�b�n���q�������̂ł���B�O���S���I���̂���_�Ƃ��ă}�C���X�Ƃi.S.�o�b�n���q�������悤�Ɂi11��10���u�N�����m�v�j�B������ƁA�������肩�H �ł��܂��A�X�̓N���X�}�X�E���[�h��F�B�G�ߕ������������������� Merry Christmas�I
2014.11.25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���10�`�o�b�n��2�̕s���s�u���ϗ��v
 �@�V���p���Ɂu�O�t�ȁv��i28�Ƃ�����i������B�S�Ă̒��i�L�C�j���g����24�̋ȏW�B�z��́A����̃n�����Ƃ��̕��s���E�C�Z������ɁA��n�̒����E�Z������̐��̏��Ȃ����ɕ��ׂ�12�ȁA���Ɂ�n�̒��Z����̑������ɕ��ׂ�12�ȁB�n�����Ɏn�܂�j�Z���ŏI���S24�ȏW�ł���B
�@�V���p���Ɂu�O�t�ȁv��i28�Ƃ�����i������B�S�Ă̒��i�L�C�j���g����24�̋ȏW�B�z��́A����̃n�����Ƃ��̕��s���E�C�Z������ɁA��n�̒����E�Z������̐��̏��Ȃ����ɕ��ׂ�12�ȁA���Ɂ�n�̒��Z����̑������ɕ��ׂ�12�ȁB�n�����Ɏn�܂�j�Z���ŏI���S24�ȏW�ł���B�@�u��c�ݎ_ ���[����ł��v��CM�ł�����݂̑�7�ԃC�����A�u�J����v�̃j�b�N�l�[����������15�ԕσj���������ɗL���B����2�Ȃ͊m���ɑf���炵�����A����22�Ȃ́H���܂����߂��A�����̒��ł͖��ȂƂ͌�����ȏW�ł���܂��B
�@�V���p���i1810�|1849�j�����̋Ȃ����������̂�1839�N�̃}�W�����J���B���s�����̂͗��l�W�����W���E�T���h��ƁB���Q�����y���͗B��AJ.S.�o�b�n�́u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�������������B
�@���̈ꌏ����A�V���p�����u�O�t�ȁv�����ɂ������čł��Q�l�ɂ����̂̓o�b�n�́u���ϗ��v���������Ƃ��ǂݎ���B��������̂͂��A�u���ϗ��v�́A�u�O�t�ȁv�Ƃ܂������������ŏ����ꂽ��g�̋ȏW�Ȃ̂ł���i2����48�Ȃ��邪�\���͑S�������B�Ȍ�A�ώG��������邽�ߑ�1��24�Ȃ�ΏۂƂ��ďq�ׂ����Ă��������܂��j�B
�@����́A�V���p������{�ɂ����o�b�n�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�i��1��BWV846�|869�j�̒��ɁA�s���s��T���Ă݂����B
���o�b�n��2�̕s���s�F���ϗ��N�����B�[�A�ȏW��
�@���ڂ͋ȏW�̕\�����B�����ɂ͂�������B
Das wohltemperirte Clavier�A���邢�́A���ׂĂ̑S���Ɣ����i�������ƍ������j��3�x�i�܂�h���~�Ɋւ��Ă��j�Z3�x�i�܂背�~�t�@�Ɋւ��Ă��j�p���č��ꂽ�O�t�Ȃƃt�[�K�B�@wohltemperierte �͉p��ɒu���������well-tempered�B�u�K�x�ɒ������ꂽ�v�Ƃ����Ӗ��B�N�����B�[�A�͌��Պy��̑��́B������u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�Ɩ��B������Ε��ϗ��Ƃ͉�����H
�@���s�̉��K�i�h���~�t�@�\���V�j���`�������ߒ��������ƒ��߂Ă݂�ƁE�E�E�E�E�B�܂��́u�̂��肫�v�B����́u�O���S���I���́v��9�|10���I�B���̌�A�r�U���e�B���i�����[�}�鍑�j�ɂ����āA���K�́u������@�v�̖��̂��Ƃɐ��������B8����̂Ŕ���Octoechos�ƌĂꂽ�B���̌�G�I���A���@�A���N���A���@�A�C�I�j�A���@���lj�����S����11���ƂȂ�B
�@���̒�����A�C�I�j�A���@�������K�i�h���~�t�@�\���V�j�A�G�I���A���@���Z���K�i���V�h���~�t�@�\�j�ɐ����A���s�̉��K�ɂȂ����Ă䂭�B
�@�u���ϗ��v�Ƃ́A�����K�ƒZ���K�ɂ����鉹�̍��ᕝ���ϓ������������@�B1�I�N�^�[�u�̉�����12��������12���ϗ����ł���ʓI�B���s�̉���ł���B����́A����̃s�A�m������Έ�ڗđR�B1�I�N�^�[�u�Ⴂ�̃h�ƃhނ̊Ԃɂ́A�����E�������킹��12����B�ד��m�̌��̎��g�����̓I�N�^�[�u�̎��g����1�^12�ɓ�������Ă���B�g�I�N�^�[�u12���������@�h�Ƃł������悤���B�u���ϗ��v�Ƃ͂��܂���Ă����̂��B
�@�u���ϗ��v������n�߂��̂�1700�N����B�o�b�n��15�B����܂ł́A11�̋�����@���e�X�Ɨ����ėp�����A���ݏ�����͕s�\�������B�剹�������i�ׂ̉����m�̍��፷�j���o���o��������ł���B�u���ϗ��v�͉��������̂��߁A12���S�Ă��剹�ɂȂ肤��B���������āA12�̒����K�A12�̒Z���K�A�����āA11������@���i�Ȃ�Ƃ��j�J�o�[�ł���H ���ׂĂ̊y��̍��t���\�ƂȂ�B�܂��ɖ��\�����@�B
�@�Ƃ��낪�A����ł͓�����O�́u���ϗ��v�́A�����ɐZ�������킯�ł͂Ȃ������B������߂���c�_�����܂ł��������̂ł���B�`���ɍR����V�����͂́A�������ĎY�݂̋ꂵ�݂����B
 �@�o�b�n�́u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�́A����ȏ��Ŋ��������B1722�N�̂��Ƃł���B�o�b�n�́u���ϗ��v�̉\���E���������m�M�����̂��낤�B�����āA�����O�̒T���S�A���w�ғI���͔\�͂���g���āu���ϗ��v�̊T�O�������ɋ�������̂ł���B
�@�o�b�n�́u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�́A����ȏ��Ŋ��������B1722�N�̂��Ƃł���B�o�b�n�́u���ϗ��v�̉\���E���������m�M�����̂��낤�B�����āA�����O�̒T���S�A���w�ғI���͔\�͂���g���āu���ϗ��v�̊T�O�������ɋ�������̂ł���B�@�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�́A�O�t��Praeludium�ƃt�[�KFuge����g�Ƃ��ĕ��ϗ���12�����K��12�Z���K�����Âg����24�̋ȏW�B
�@�n�����ƃn�Z���A���͔��������d�n�����E�d�n�Z���Ə����オ��A�Ō�̓������E���Z���Œ��߂�B�S24�Ȃł���B
�@������ƈꌾ�B�����^�Z���̑g�ݍ��킹�Ɋւ��Ă����A�o�b�n�͓��咲�i�n�����ƃn�Z���j���Z�b�g�ɂ��Ă��邪�A�V���p���͕��s���i�n�����ƃC�Z���j���Z�b�g�Ƃ��Ă���B
�@���꒲���̌ď̂Ɋւ��A���Ⴗ����̂������B�o�b�n���d�n�����Ƃ����Ă�����̂��V���p���͕σj�����Ə̂��Ă���B�u���ϗ��v�ɂ����āA������24�ʂ肵���Ȃ����A�ď̂́i���_�I�ɂ́j42�ʂ肠��̂�����A����͕s�v�c�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A�ނ��둊��_�����ƍl�����ق��������̂�������Ȃ��B
�@�X�Ɉꌾ�B�A���h���E�W�C�h�i1869�|1951�j�́A�u�V���p���́w�O�t�ȁx��i28�͋Ȏ햼�ɑS���V���ȈӖ����^�����Ă���B�w�O�t�ȁx�Ƃ����A19���I���߂͎�ɁA�����s���Ă����������t�́w�O�t�x�̏K���ƌ��т��čl�����Ă����B�V���p���̍�i28�́A�����������т��������ς�ƒf�ׂ��l���o���ꂽ�̂��Ƃ����悤�v�i�u�V���p�� �Ǎ��̑n���ҁv�W���E�T���X���� ��v�ی��� �t�H�Њ��j�Əq�ׂĂ���B
�@���A���̂͂�����ƈႤ�B�o�b�n�́u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�̃^�C�g���ɂ́u�O�t�Ȃƃt�[�K�v�Ƃ���B�V���p���́u�O�t�ȁv��i28�͖��炩�Ƀt�[�K�ł͂Ȃ�����A�u�O�t�ȁv�Ƃ����������o�b�n����q�����B�����͌ォ��t�������B���ꂼ�o�b�n�ւ̃I�}�[�W���H �P���ɂ����l�������B
�@�V���p���u�O�t�ȁv�o����A�u�O�t�ȁv�Ƒ肷��s�A�m�Ȃ͐��X�o�ꂵ�Ă���B�h�r���b�V�[�i1862�|1918�j�͑�1��12�ȁA��2��12�ȁA�S24�Ȃ́u�O�t�ȁv��������B���t�}�j�m�t�i1873�|1943�j�͐��U��27�Ȃ́u�O�t�ȁv��������B���̂���24�Ȃ͑S�Ă̒����ŏ�����Ă���B�o�b�n�|�V���p���|�h�r���b�V�[�|���t�}�j�m�t�ƘA�Ȃ�200�N�̃����[�B������s���s�̌`�ł���B
�@�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v���A19���I�̍����ȉ��y�ƃn���X�E�t�H���E�r���[���[�i1830�|1894�j�̓s�A�m�Ȃ́u�����v�ƌĂB����́A�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�����̌�̃s�A�m���y����S�Ẳ��y�̎w�j�ƂȂ������Ƃ��Ӗ�����i���݂Ɂu�V���v�̓x�[�g�[���F���̃s�A�m�\�i�^32�ȁj�B
�@�V���[�}���i1810�|1856�j�́u�o�b�n�́w���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�x���ƂƂ��邱�ƁB��������A�ԈႢ�Ȃ��A���h�ȉ��y�ƂɂȂ��v�i�u���y�Ƃ̖����v�w�R�T���ҥ�� ���}�n�~���[�W�b�N���f�B�A���j�Ɖ]���Ă���B�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�͉��y���u���҂ɂƂ��Ẵo�C�u���ł���Ƃ������Ƃ��B
�@�o�b�n�́u���ϗ��v�̗��_���\�z�����킯�ł͂Ȃ����A���H���铹��������Ȍ`�ō��グ���B���p���ւ̍v���B�FLED�̃m�[�x�������w��ҁE�����C���̌��тƓ����H
�@�o�b�n�Ȍ�̉��y�Ƃ͉����ȂׂāA�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�����y���̑b�Ƃ����B�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�����܂�Ȃ�������A�u���ϗ��v�̐Z���͂����Ƃ����ƒx�ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�ߑ㉹�y���W�ւ̉ʂĂ��Ȃ��v���B�o�b�n�ɂ�����s���s�̌`�ł���B
���Q�l������
�o�b�n����L���鐢�E�i������꒘ �t�H�Ёj
�V���p���Ǎ��̑n���ҁi�W���E�T���X���� �t�H�Ёj
���y�Ƃ̖����i�w�R�T���ҁE�� ���}�n �~���[�W�b�N ���f�B�A�j
�u���ϗ� �N�����B�[�A�ȏW �S�� �X�r���g�X���t�E���q�e���i�s�A�m�j�v
�@�@�@CD���C�i�[�m�[�c�i���쐴�꒘�j
2014.11.10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���9�`�o�b�n�s���s����1�u�Έʖ@�v
�@�킪���F�A���T�C�g�̎�Ɏ� Brownie K�������w�}�C���X�E�f�C���B�X�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�n��p�x�iDU BOOKS���j���������ꂽ�̂ŁA�����ɋ��߂ēǂ�ł݂��BJAZZ�j��ɎW�R�ƋP������A���o���a���̌o�܂����X�̏،����������I�ɓW�J����B�،��̓~���[�W�V�����Ɏ~�܂炸�A�v���f���[�T�[�A�]�_�ƁA���R�[�h��ЁA�}�X�R�~�ɂ܂ŋy�Ԃ���AJAZZ����芪�����y�ƊE�̏������ɕ����яオ��B���Ւa���̃h���}�ƃ��R�[�h���y�j�̋����B�G���^�e�C�������g�ƃh�L�������g������������ꋉ�̓ǂݕ��ƂȂ��Ă���BK���̖���f���炵���B�����I�w�p���ƈӖ�I�킩��₷�������˔����Ă܂��Ɋ����B���̏��̉��l������ɍ��߂Ă���B �@�A���o���u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�i1959�^���j�̃L�C���[�h�̓��[�h�i���@�j�B�R�[�h�����ɂ�������܂ł�JAZZ�̏펯��ł��j��������I�ȃA���o���ł���B
�@�A���o���u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�i1959�^���j�̃L�C���[�h�̓��[�h�i���@�j�B�R�[�h�����ɂ�������܂ł�JAZZ�̏펯��ł��j��������I�ȃA���o���ł���B�@���y�̗l���̓|���t�H�j�[�i�������y�j�ƃ��m�t�H�j�[�i�a�����y�j�ɑ�ʂł���Ƃ���AJ.S.�o�b�n�i1685�|1750�j�̊��������玞��̓��m�t�H�j�[�������B�o�b�n���ɂ߂��Έʖ@�i�|���t�H�j�[���`�����鉹�y�Z�@�j�͔ނ̎����Ȃ��Ė��v����B����A�}�C���X�E�f�C���B�X�i1926�|1991�j�̃��[�h��@�̓O���S���I���́i������@�j�ɍs�����B�{���̒��ɂ́A�~�N�\���f�B�A���A�t���W�A���A�C�I�j�A���Ȃǂ̋�����@������ь����B�o�b�n�̑Έʖ@�͂��̔��W�`������A�}�C���X�̓o�b�n���щz���āg�Â���K�˂��h�킯���B
�@�o�b�n�ƃ}�C���X�̐ړ_���A �~�N�\���f�B�A���i������@��7�F����\�Ƃ���7�����K�j�����Ɍ����Ă݂�B�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�̑�5�ȁu�t�������R�E�X�P�b�`�v�͑S5�Ȓ��ł����[�_���Ȋy�ȂƂ���邪�A�����ɂ̓~�N�\���f�B�A�����p�o����B�Ђ�A�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�́u�N���h�v��1�ȁu��͐M���B��Ȃ�_���v�̓~�N�\���f�B�A���݂̂��琬��B
�@�w�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�n��p�x�ɂ́A�r���E�G���@���X���u�}�C���X�Ƃ킽���̓s�A�m�ʼn���T��Ȃ���A���R�[�f�B���O�ʼn��t����5�̃X�P�[���ɂ��ǂ蒅�����v�ƌ��������肪����B�u5�̃X�P�[���v�́A�c�O�Ȃ��玄�̎��ł͎��ʂł��Ȃ����A���̓��̈���~�N�\�f�B���A���ł��邱�Ƃ͔���B
�@�o�b�n�́u�~�T�� ���Z���v�ƃ}�C���X�́u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v����́A���ʂ���~�N�\���f�B�A������������B�}�C���X���o�b�n��������z���ėy�������֘A�Ȃ��Ă���B���y�̕s�v�c���I�ʔ����I ������s���s�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�Ɏ��������ďo�������I�[�l�b�g��R�[���}���̃t���[�E�W���Y�́A�����u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�ȏ�̏Ռ����W���Y��V�[���ɗ^�����B���A���͂��قǂ̕]���͎c���Ă��Ȃ��B���̂��H�s�Ղ܂��Ă��Ȃ����炾�B�u�Ȃɂ������Ԃ��v�͌|�p���肦�Ȃ��B
�@�w�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�n��p�x�ɂ��ƁA�u�}�C���X�̉��y�́A�������ă����f�B�ƃ��Y�����犮�S�ɂ͌��ʂ��Ȃ������B���L�̃g�[���A�t���[�W���O�A���Y������ɕێ����Ă����v�Ƃ���B�ނ̉��y�́A�g�]�l���Ȃ��đウ����h�Ɓg����Ă炤�Ɏ~�܂�Ȃ������x�̍����h��L���Ă����̂��B�ނ͂܂������������Ă���u��肷���Ă̓_���ȂB���̃o�����X������v�B�o�����X�̏d�v�������o����B�����A�}�C���X�͕s���s�܂��Ă����̂ł���B
�@�}�C���X�̓R�[�h�̑����𗣂ꔭ�z�̎��R�����[�h�ɋ��߂��B�o�b�n���܂����[�h�ƃR�[�h�̋��Ԃɐ����A���ʁA�|�p�ƂƂ��Ă̎g����S�������B���̊�Ղɂ͕s���s������B
���o�b�n�s���s����1�F�Έʖ@��
 �@��q�����Ƃ���A���y�̗l���̓|���t�H�j�[�ƃ��m�t�H�j�[�ɑ�ʂ����B���m���y�̋N���Ƃ����O���S���I���̂́A�P�ꐺ������Ȃ郆�j�]���̍����ȂŁA9�|10���I�ɂ��̒a�����݂�B���ꂪ���X�ɐ����𑝂₵�|���t�H�j�[�i�������j���y���`������B�����\���l�T���X�̓|���t�H�j�[�̍Ő����ƂȂ�B16�|17���I�ɃI�y�����a������ƁA��{�̐����ɘa���̔��t�����鉹�y�A�������m�t�H�j�[��������������B17���I������18���I�́A�I�y���̔��B�ɔ������m�t�H�j�[���嗬�ƂȂ�A�|���t�H�j�[�͎���x��̉��y�ƂȂ肳�������B���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�i1685�|1750�j�����������̂͒��x����Ȏ����ł���B����Ȏ���ɁA�o�b�n�́A�|���t�H�j�[�̍�ȋZ�@�ł���Έʖ@�ɑł����ށB�܂��ɂ���͎���x��̍s�ׂ������B
�@��q�����Ƃ���A���y�̗l���̓|���t�H�j�[�ƃ��m�t�H�j�[�ɑ�ʂ����B���m���y�̋N���Ƃ����O���S���I���̂́A�P�ꐺ������Ȃ郆�j�]���̍����ȂŁA9�|10���I�ɂ��̒a�����݂�B���ꂪ���X�ɐ����𑝂₵�|���t�H�j�[�i�������j���y���`������B�����\���l�T���X�̓|���t�H�j�[�̍Ő����ƂȂ�B16�|17���I�ɃI�y�����a������ƁA��{�̐����ɘa���̔��t�����鉹�y�A�������m�t�H�j�[��������������B17���I������18���I�́A�I�y���̔��B�ɔ������m�t�H�j�[���嗬�ƂȂ�A�|���t�H�j�[�͎���x��̉��y�ƂȂ肳�������B���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�i1685�|1750�j�����������̂͒��x����Ȏ����ł���B����Ȏ���ɁA�o�b�n�́A�|���t�H�j�[�̍�ȋZ�@�ł���Έʖ@�ɑł����ށB�܂��ɂ���͎���x��̍s�ׂ������B�@�o�b�n���ɂ߂��Έʖ@�́u�t�[�K�̋Z�@�vBWV1080�ɍł������Ɍ���Ă���B�u��{�v�͂S���߂̃e�[�}�B���̉�����u���]�v�u�g��v�u�k���v�u���s�v�����A������l�X�ɑg�ݍ��킹�W�J������
 ���j�b�g19�̏W���̂��u�t�[�K�̋Z�@�v�ł���B
���j�b�g19�̏W���̂��u�t�[�K�̋Z�@�v�ł���B�@19�Ȓ��̔����͑�7�ȁiContrapunctus7�j���낤�B�u�ό`��{�`�̏k���v�u�ό`���]�`�v�u�ό`���]�`�̏k���v�u�ό`���]�`�̊g��v�ŃX�^�[�g����4�̐����́A�ό����݂Ɍ`��ς��▭�ɗ��ݍ����Ȃ���l�X�Ɛi�ށB�����ɂ���̂͊w�I��捔����B
�@1750�N�āAJ.S.�o�b�n�́u�t�[�K�̋Z�@�v�̊�����҂����ɐ����������B�z��̎w�����y��̎w����Ȃ��܂܂Ɂi���̂��ߖ����ɑS�̑��̊m�肪�Ȃ��j�B�₳�ꂽ�Ȏq��͎��M���𗊂�ɁA2�N��Ȃ�Ƃ��o�łɂ��������B���ꂽ�̂͋͂�30���B���ł͑Έʖ@��i�̍ō���Ƃ����u�t�[�K�̋Z�@�v���A�����͂����Ɏ���x��̎Y�����������́A����͏ł���B
�@�o�b�n�́A�Έʖ@������x��̋Z�@�ƔF�m���A������ɂ߂��i���������B���U�̍Ō�ɁB�o�b�n�Ɂu�Ȃ�����Ȋ��̍���Ȃ��d���������̂��H�v�Ɛu���Ă��u�����������珑���� �������ꂾ���v�Ƃ��������Ȃ����낤�B�����A�ނ̋��̓���`���Ă݂�A�l�X�Ȏv���������Ă���B�����䂭���̂ւ̓��ہH�㐢�ւ̎g�����H�Ȃ܂ł̐E�l�����H�|�p�ƍ��H �S�Ă����Ă͂܂�悤�ȋC������B
�@�u�Έʖ@�v�́A�Ⴆ�t�[�K�Ƃ����`�ŁA�o�b�n�̍�i�ɂ͑������݂���B�L���ȁu�g�b�J�[�^�ƃt�[�K�j�Z���v���͂��߂Ƃ��鑽���̃I���K���ȁB�u���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�v�S48�ȂȂǂ̃N�����B�[�A�i���Պy��j�ȁB�Έʖ@�́A�ނ̐��U��ʂ����傫�Ȗ��肾�����B�u�t�[�K�̋Z�@�v�͎��̊ԍۂɓ��˂ɐ��܂ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A��ȉƃo�b�n�̏W�听�ł��������B
�@�u�t�[�K�̋Z�@�v�ɂ����āA�S�Ẳ����͈�_�̋������Ȃ��Ƃߍ��܂�ėh�邬�Ȃ��B���̎p�`�͊w�I���k���̋ɂ݂ł���A���y�͐�捔��Ɛ����Ȑ��_�ɍʂ���B
�@�o�b�n���ɂ߂��u�Έʖ@�v�͔ނ̎����Ȃ��ď��ł������Ɍ������B�m���ɁA����̓��m�t�H�j�[�܂�������B�����������A����͉��y�j�̒��ɏl�X�Ǝp���ꐶ��������B
�@���[�c�@���g�Ō�̌����� ��41�ԁu�W���s�^�[�v�͑s��ȃt�[�K�ŋȂ���߂�����B������4����f�ނƂ��đ剾����g�ݏグ���V�˃��[�c�@���g�B�ނ̔w��ɂ̓o�b�n������B�x�[�g�[���F���́A���y�l�d�t�̂��߂́u��t�[�K�v��i133�������A�u�����~�T�ȁv�́u�O���[���A�v�Ɓu�N���h�v�ɂ̓t�[�K���K�͂Ɏ����ꂽ�B�t�����N�̖���u���@�C�I������\�i�^ �C�����v�̏I�y�͂̓J�m���B�x�����I�[�Y�́u���z�����ȁv��5�y�͂�X�s�[�M�̌������u���[�}�̏��v�́u�{���Q�[�[���̏��v�ɂ��t�[�K�̔j�Ђ���������B�ߑ�ł́A�V���X�^�R�[���B�`���u�����ȑ�2�ԁv�ŁA�Ȃ��27�������̃|���t�H�j�[�����Ă���B���ׂăo�b�n�����������Έʖ@�̉e���ł���B
�@�������A�Ȃ�Ƃ����Ă������[���̂̓A�[�m���g�E�V�F�[���x���N�i1874�|1951�j�̃P�[�X���낤�B�ނ�1932�N�u�o�b�n��12���v�Ƃ��������̒��ŁA�o�b�n���u�ŏ���12�����y�Ɓv�Ə̂����B
�o�b�n�̓l�[�f�������h�̑Έʖ@�̔�p��L���Ă����B���Ȃ킿�A�u7�̉����݂��ɁA���̓����̒��ŋN���邠���鋿�����ЂƂ̋��a���̂悤�ɔc�������悤�Ȉʒu�ɂ����炷�Z�p�v�ł���B���̔�p��ނ́u12���Ɋg��v�����B�o�b�n�́i�t���I�ɕ\������j�u�ŏ���12�����y�Ɓv�Ȃ̂ł���B�@����̓V�F�[���x���N�̃o�b�n�ւ̑����̔O�ɑ��Ȃ�Ȃ��B����̑㖼���ł���12�����y�̑b�������炵���̂̓o�b�n�ł���Ƃ����̂�����B20���I�ő�̊v���҂Ƃ�����V�F�[���x���N���ł��^�����ȉƂ��o�b�n�������B�V�F�[���x���N�����y�j�̑S�Ă��щz���ăo�b�n�ƌq����B���̎��������o�b�n�̈̑傳�̏ؖ��ł͂Ȃ��낤���B12�����y�̐���͂��Ă����āB
�@�O���S���I���̂��疬�X�Ɨ��ꂫ���|���t�H�j�[�Ƃ����Â��l���B�o�b�n�́A���̉��y�Z�@�ł���u�Έʖ@�v���Ɍ��܂ŒNj������B����́A�ߋ����������q����s�ׂ������B����䂦�A�ߑ㐼�m���y�̓o�b�n���N�_�Ƃ���B�u���y�̕��v�Ƃ�����R���B�܂��Ɂu�s���s�v���̂��̂ł���B
���Q�l������
�}�C���X�E�f�C���B�X�u�J�C���h�E�I�u�E�u���[�v�n��p
�@�@�i�A�V�����[�E�J�[���� �쓈���ۖ� DU BOOKS�j
�o�b�n����L���鐢�E�i������꒘ �t�H�Ёj
�o�b�n �`���̓��ǂ��i���ы`���� �t�H�Ёj
2014.10.25 (�y) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���8�`�u���ɕa��Łv�̐[��
�����]��̉��� �@���̋傪�r�܂ꂽ�̂͌��\7�i1694�j�N10��9���B�S���Ȃ����̂�12���B���̊ԁA�m�Ԃ͈ȑO�r��̒��������Ă��邾��������A�u�͖�v�̋�͎����Ō�̋�ł���B�Ō�̋�Ȃ�u�����̋�v���A�Ƃ��������ł͂Ȃ��炵���B�Ȃ��Ȃ�A�m�Ԃ͂��̋�Ɂu�a����v�Ɩ��ł������炾�B���̏�A�m�Ԃ͏�X�u�Òr��v�̋�ȍ~�͂��ׂĂ������̋�ł���A�Ɩ�l�Ɍ���Ă��������ȁB����Ȕw�i����A�u�����̋傩�ۂ��v�̋c�_���������B�����A�����́A�����āu�a����v�Ƃ����m�Ԃ̐[�ӂ�T��ׂ����낤�B
�@���̋傪�r�܂ꂽ�̂͌��\7�i1694�j�N10��9���B�S���Ȃ����̂�12���B���̊ԁA�m�Ԃ͈ȑO�r��̒��������Ă��邾��������A�u�͖�v�̋�͎����Ō�̋�ł���B�Ō�̋�Ȃ�u�����̋�v���A�Ƃ��������ł͂Ȃ��炵���B�Ȃ��Ȃ�A�m�Ԃ͂��̋�Ɂu�a����v�Ɩ��ł������炾�B���̏�A�m�Ԃ͏�X�u�Òr��v�̋�ȍ~�͂��ׂĂ������̋�ł���A�Ɩ�l�Ɍ���Ă��������ȁB����Ȕw�i����A�u�����̋傩�ۂ��v�̋c�_���������B�����A�����́A�����āu�a����v�Ƃ����m�Ԃ̐[�ӂ�T��ׂ����낤�B�@����u���삩�ʍ삩�v�Ȃ�c�_������B�ȉ��́u�ʍ�_�v�̑�\��B
�u�͖�v�̋�́A���Ƃ��Ă݂Ă����܂�o���͂悭�͂���܂��B���Ȃ��Ƃ��m�Ԃ́A���U�Ɉ₵��1������̔���̒��ɁA����Ȑꎚ�̓����̂Ȃ��A�U���̂���͂��̂悤�ȋ������Ă͂��܂��B�E�E�E�E�E�����Ȃ�A�u�͖�v�̋�́A�ւ荂���o�~�t���A�Ō�Ɍւ���̂Ă��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹���˂Ȃ��ّ̂̋�ł���i�������j�j�@��i�̕]���͐l�l�X�B����������Ă��������B���̊S���͂�����B�Ȃ��u���ɕa��Łv�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��B�u���ɕa�݁v�ł͂����Ȃ��̂��B�u���ɕa��Łv��6�����A���]��B�u���ɕa�݁v�Ȃ�A�����Ӗ���5�����Ɏ��܂�̂ɁB
�@����́A�u�s���s�v���o�b�n�Ƃ̋��ʐ��Ȃǂ��ꎞ����āA�Ȃ��A����O�ɂ����m�Ԃ́A�����Ď��]��́u���ɕa��Łv�ɍS�����̂��H ���l���Ă݂����B
���ώ��̂��Ȃ��Ɂ�
�@�l�͕K�����ʁA�����A���̎����͒N���m��Ȃ��B���ꂪ�l�̎��ɑ��鋤�ʔF�����B�����A�Ȃ��l�͕��C�Ȃ̂��H�K�����ʂƕ������Ă��Ȃ��畽�C�ł�����̂͂Ȃ��Ȃ̂��H ����́A�P���ɁA���͉�����̂��Ƃƍl���Ă��邩�炾�낤�B
�@������A����ڑO�ɂ����l�͂ǂ��Ȃ̂��H �܂��A���̔F���̂Ȃ����ɂ͕�����Ȃ��B�Ȃ�Α��l�̌������p���邵���Ȃ��B�ȉ��́A���[�c�@���g�̏ꍇ�ł���B
���[�c�@���g�͌����Ă��̂悤�ȗ��̋��ѐ���`����悤�ȍ�i�����������Ƃ͂Ȃ������B�������A�ނ�����\�����A���������҂̂��߂̉��y�ł���u���N�C�G���v�������˂Ȃ�Ȃ������Ƃ��A���͒P�Ȃ�\���ł͂Ȃ��A��̎��Ԃ̂悤�ɁA�ނ̏�ɂƂ�����ł��낤�B�������Ď��ɒ��ʂ����Ƃ��A�|�K���鍐�������҂̂悤�Ɂ|�ނ͌�����悤�Ȋ�����Ď��˂�قǂ̋��E�҂ł��Ȃ���A�y�e���t�ł��Ȃ������B���ɂ����͂Ȃ������̂ɁA�����Ȃ�������̋ꂵ�݂ɉ�����̂ł������B�l�Ԃ̍����u���̂ɕʂ��������v���́u�ٗl�Ȃ炢�ʂ�v�̉́A�ԚL�̉́A�����̉́A�̉́A���т̉́A�����Ď��g�ւ̔҉̂��ł����������̂������B�@����́A�Έ�G���u�f��̃��[�c�@���g�v�i�������Ɂj�̈�߂ł���B����\�����Ď��ɗՂl�Ԃ̐S���ł���B�����čŌ�̍�i�̗l���ł���B�����ɂ���̂́A�ԚL�ł���A�����A�A���сB�u���N�C�G���v�͎��g�ւ̔҉̂��B
�@������A�m�Ԃ̏ꍇ�͂ǂ����H
�m�Ԃ͐����̂͂��܂ɂ����B�u�������Ď��ɂ����ɂȂ��Ĕ���ł�����܂����A�����͍��̓��ɐS���Ă߂ĔN��50�������Ă��܂����B��������ĐQ�Ă��Ă��A�v���͒��_���|�̂����������܂悢�ڂ��߂�ΎR���쒹�̐��ɂ��ǂ낭�B�����������Ƃ͖ώ��Ƃ����Ă��܂��߂�ꂽ�B�����Ȃ邤���͔o�~��Y��Ď��ɂ����v�ƌ������B����ɔm�Ԃ́A�u����͎����̋�ł͂Ȃ��B�����a���̋�ł���B���̂悤�ȋ�����͖̂ώ��ł���v�Ƒ������B
 �@����͗��R���O�Y���u���}�m�ԁv�i�V�����Ɂj����u���͖͌�������߂���v�̈�߂ł���i���҈��p�̌����͎x�l�́u�����L�v�j�B�u����O�ɂ��āA�ώ����̂ċ��肽���̂����A���̂悤�ȋ������Ă��܂����B���ꂼ�ώ��ł���v�Ƃ̔m�Ԃ̌��́A���[�c�@���g�̃P�[�X�ɋ����قǍ�������B�u�͖�̋�v�͎��g�ւ̔҉̂ł���B
�@����͗��R���O�Y���u���}�m�ԁv�i�V�����Ɂj����u���͖͌�������߂���v�̈�߂ł���i���҈��p�̌����͎x�l�́u�����L�v�j�B�u����O�ɂ��āA�ώ����̂ċ��肽���̂����A���̂悤�ȋ������Ă��܂����B���ꂼ�ώ��ł���v�Ƃ̔m�Ԃ̌��́A���[�c�@���g�̃P�[�X�ɋ����قǍ�������B�u�͖�̋�v�͎��g�ւ̔҉̂ł���B�@���ɗՂ�œV�˂́i�V�˂ł��j�Ȃ����Ėώ����̂ċ��肪�������̂Ȃ̂��B������}�l�ɂ����Ă���H
���u���v���B�����m�ԁ�
�@�u���ɕa��� ���͖͌�� �����߂���v�̉��߂ɂ��āA���R���O�Y�́u���}�m�ԁv�̒��ŁA�u���ɕa�݁A�����̒��Ŕނ͖͌�����܂悢�����Ă���̂������i�R�{���g��j�Ɩ��̂���ʓI�ł���v�Əq�ׂĂ���B�E�[���A���ɕ��I �O�o�������j�́u�U���̂���͂��̂悤�ȋ�v�ɂ��ʂ���A����͖�H
�@�����������A�ق�Ƃ��ɂ��̋�́A�u�ꎚ�̓����̂Ȃ��A�U���̂���͂��̂悤�ȋ�v�Ȃ̂��낤���B�f���ĈႤ�A�Ǝ��͍l����B
�@�u���ɕa��ł��܂��Ă��A�o�~�̖��͖͌�̒��������߂����Ă���v�B���ꂪ�킽���̖�ł���B�|�C���g�́u���v�B����O�ɂ��Ȃ���A�ǂ����Ă����̋��n�ɂ͒B�����Ȃ��B�܂��܂����ɐ�Ȃ��B���Ƃ͔o�~�̖��B�����Ĕo�~���ɂ߂邱�ƁB���̓��ɏ]���Ȃ�A�o�~��Y��Ď��ʂׂ��Ȃ̂����A�����͂����Ȃ��B���ꂪ�u�ώ��v�Ɣm�Ԃ͔F�m���Ă���B������u���v�Ȃ̂ł���B
�@�v����ɁA�m�Ԃ́u���ɂ��Łv�̂��ƂɁu���v���B�����̂ł���B������u���ɕa�݁v�ł͂����Ȃ��B�u���ɕa��Łi���j�v�Ȃ̂ł���B�m�Ԃ̐S���ɂȂ肱���됟�܂��u���v�������Ă���B
�@�킽���͗��ɕa��ł��܂����B�������肭�邱�Ƃ����m���Ă���B�{���Ȃ�ΐS���炩�ɂ��������Ȃ�������Ȃ��B�u�����������v�A�u�ł��v�A�u�Ȃ����v�A���͖͌�������߂����Ă���B�o�~�̖����܂����������͂Ȃ��̂��E�E�E�E�E���ꂪ�킽���̉��߂ł���B
�@�u�͖�̋偁�ʍ�v�_�҂ɂ́u���v�͌����Ă��Ȃ��B�u���v���B�����u�͖�̋�v�́A���̕����ŗ]�C�������B�ꎚ���ʂ̏���䂭�B�r�A刁A�ώ��B�u���v�����u�͖�̋�v�̃L�C���[�h�B
�@�m�Ԃ͏�X�u�����s�����Ȃ��v���悵�Ƃ��Ă����B�ނ͍Ō�ɁA���ɂ́u�����s�����Ȃ���v���r��ŗ������čs�����̂ł���B
���G�s���[�O�`�ԉ� 1694�N10��9������z���遄
�@�킽���͂��̂Ƃ��A���}�������������ɗ��Ă��邱�Ƃ�m���Ă��܂����B�Ȃ�Ύ����̋�ł��r�������B����A�������N�A�u�킽�����r�ވ���傪�����v�Ɩ�l�����ɐ����Ă�������ɂ́u�����v�ƌ����Ă͂����Ȃ��B�������u�����v�͎������ꂽ���̂��r�ނ��́B�c�O�Ȃ���킽���͎���������Ȃ��B���ꂽ���Ȃ��B���ɂ����āA�݂��̂��̂��Ƃ͒���ƌ��߂Ă������B�a�C�������Ē���ɍs�������B�l�͂����ώ��Ƃ����܂��B�m���ɂ킽���͖ώ��Ɏ����Ă��܂����B���ꂩ����܂��A�o�~�̓�����݂����Ƃ����ώ��ɁB
�@����ȂƂ��A�˔@����ȋ傪�����т܂����B��U�́A����u���ɕa��ł��v�ƍl���܂������A�����ɂ�߂܂����B����ł͂����ɂ��x�^�B�킽���̖ώ��������ɂłĂ���B�����������Ă���B7�������h���B�Ȃ�A�Ⴂ����悭������Z�Łu���ɕa��Łv�Ƃ��悤�B����Ȃ�u���v���B��ĐS�n�悢�B�ۂݍ��ނ��ƂŃ��Y�������܂��B�]�C�����܂��B��X��l�����ɐ����Ă����u�����s�������v�ɂ��K���B����ł悵�B�킽���͋哪�Ɂu�a����v�Ə�������܂����B
�@�������x�l���Ăт܂����B�u�����B��Ă��邱�Ɓv�u�ώ�������ł��邱�Ɓv�ɋC�Â����ǂ�������������������ł��B��Z�͂��̂܂܂Ɂu�Ȃق�����閲�S�v�ł͂ǂ����H�Ɩ₢�܂����B�x�l�͂��炭�l���āu������ł��悢�ł��v�Ɠ����܂����B�����Ȏx�l�̂��Ƃł�����A�u�Ȃق�����閲�S�v�ɋG�ꂪ�Ȃ����Ƃ��炢�͂����ɔ���͂��B�l���Ă����̂́u���͂Ȃ����̂悤�Ȗ₢�����������̂��낤���H�v�Ƃ������Ƃ������ł��傤�B
�@�킽���́u���B���v�̃q���g��ނɌ����Ă��܂����B�u�������Ď��ɂ����ɂȂ��Ĕ���ł�����܂����A�����͍��̓��ɐS���Ă߂ĔN��50�������Ă��܂����B��������ĐQ�Ă��Ă��A�v���͒��_���|�̂����������܂悢�ڂ��߂�ΎR���쒹�̐��ɂ��ǂ낭�B�����������Ƃ͖ώ��Ƃ����Ă��܂��߂�ꂽ�B�����Ȃ邤���͔o�~��Y��Ď��ɂ����v�B����Ɂu����͎����̋�ł͂Ȃ��B�����a���̋�ł���B���̂悤�ȋ�����͖̂ώ��ł���v�ƁB
�@�ނ��킽���̐[�ӂɋC�Â������ǂ����B����͂킩��܂���B�����A�������Ă����A�����N�����u�͖�v�̋�̐^�ӂ�ǂ݉����Ă����B�킽���͂����M���āA�������A�V��Ō�����Ă���̂ł��B
���Q�l������
���}�m�ԁi���R���O�Y�� �V�����Ɂj
�m�Ԃ̐��E�i�R����C�� �p��I���j
�o��̉F���i���J��D�� �������Ɂj
�f��̃��[�c�@���g�i�Έ�G�� �������Ɂj
2014.10.10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���7�`�ʂĂ��Ȃ��s���s
���s���s�̋偄�@�m�Ԃ����B����ɒ������̂͌��\2�N�i1689�N�j5��13���B�����ŁA�V���ԂƂ����������ق�j���Ė��傪���܂��B
 �@�i���܁A�đ��[�������邱�����ق́A�́A���m�������Y�X�������͂��Ȃ��h���������̐Ղł���j
�@�i���܁A�đ��[�������邱�����ق́A�́A���m�������Y�X�������͂��Ȃ��h���������̐Ղł���j�@�߉^�̕����`�o�Ɠ����O��̉h�͐����B�m�Ԃ͎����������v��������̂Ƃ��Ă�������ɏĂ��t�����B��O�ɍL����đ��B���̐����͉����Ȏp�ɁA�S�͙R�����Ƃ��Â̖��ւƒy����B
�@���̑O���ɂ́A�u�w���j��ĎR�͂��� ��t�ɂ��đ��݂���x�Ɗ}�����~���āA���̈ڂ�܂ŗ܂𗎂Ƃ��ׂ͂�ʁv�Ƃ���B���p�������͂����܂ł��Ȃ������̎����E�m��̂��́B
�@���͔j��Ă�����������R�͂̕���ƍ��͖S�����m�̖���������Y����ʂ̉đ��B�m��̎��Ɣm�Ԃ̋�B���̑Δ䂱���s���s�̘Ȃ܂��B�m�Ԃ͋Ɉӂ�͂̂ł���B
�@�u�����̂ق����v�ɂ����āA3����r��������Ƃ��đO��̋�̐���������ƁA�O�i7�͂�0�A��i7�͂�9�B���̒��������ق����m�Ԃ��u�s���s�v�ɖڊo�߂����낤�B����͍s���̂قڔ����B�u�����̂ق����v�A��������́A�܂��Ɂg����̐X�h�B���̎��R���Ӗ��[���A�X�P�[�����́A�O���̔�ł͂Ȃ��B
�@����猆���O�ɂ��āA���͂◝���͗v��Ȃ����낤�B�Ɉӂ�͂�҂́g�s���s�̋C�z�h�Ɓg���������ꂽ���_�h������������ł����B�܂��́A����ł̂������B
 �@�i���ׂĂ�����������悤�ɁA���N�~�葱����܌��J���A���̌��������͉������č~��c�����̂��낤���B�i�����j��`����悤�ɁA�����͍����Ȃ��W�R�ƋP���Ă���j
�@�i���ׂĂ�����������悤�ɁA���N�~�葱����܌��J���A���̌��������͉������č~��c�����̂��낤���B�i�����j��`����悤�ɁA�����͍����Ȃ��W�R�ƋP���Ă���j�@�����ł͐����̖����w�E���Ă������B�܂��A�O���̂����ݍ��݁B�u�J���v�u�O���̑��v�u�O��̊��v�u�O���̕��v�u����U�莸���v�u�l�ʐV���Ɂv�u��̋L�O�v�ȂǁA�Z�����͂̒��A���ꂾ���̐���������߂���B�����āA��ɂ́u�܌��J�v�ł���B�܂ɂ͓��������łтĂ���̌ܕS�N�̍Ό������Ԃ�B�������ĂыN�������Y���Ɣ��́B�����N�����u�Ă�s���s�̊T�O�B�m�ԉ~�n�̋Z�ł���B
�@�����ɁA�܂������َ��ȋ��z����m�Ԃ̓V�˂ɒ��ڂ��B���̑O��̋�u�����v�Ɓu�g�̉ԁv���{�����ċP���̂ł���B
�@��O�̍g�Ԃ��牻�ώp�̏����Ɏv�����߂���B���Ȃ₩�ȑz���͂𖡂킢�����B
 �@�i���Ύ��͑S�R�A�[���̒��ɐÂ܂肩�����Ă���B���̐Î�̂Ȃ��ŁA��̐��������A��ɂ��݂Ƃ���悤�ɕ������Ă���j
�@�i���Ύ��͑S�R�A�[���̒��ɐÂ܂肩�����Ă���B���̐Î�̂Ȃ��ŁA��̐��������A��ɂ��݂Ƃ���悤�ɕ������Ă���j�@��̐����g�Ղ��h�Ɗ����Ƃ邵�Ȃ₩�Ȃ�����B���ꂼ�A�u�Òr��v�ŊJ�Ⴕ���ԕ��̋ɁB������ʼnr�ދɒn�B�m�Ԃ̂�����͐Â��Ȃ�F���ɒʂ��Ă���̂��낤���B
�@���Ắu���߂ė����v�������B����͖T�ώ҂̖ڂł���B���肵���u�����v�ɂ͓����҂̓˂����݂�����B���R�ւ̈ؕ|������B
�@�u���炽�ӂ� �t��t�� ���̌��v�i�����j�ƑΒu���Ȃ���B17�����ɘU������ׂ��s�傳�B
 �@�i���{�C�̖�̍r�C�̂��Ȃ��ɍ��n����������B���̌Ǔ��ւ����āA���ɓV�̐삪�傫����������Ă���j
�@�i���{�C�̖�̍r�C�̂��Ȃ��ɍ��n����������B���̌Ǔ��ւ����āA���ɓV�̐삪�傫����������Ă���j�@��O�ɍ��n���������悤�������܂����A���\���Ȃ��B���̐��_�̎��R���B�Ȃ�Ƃ����X�P�[�����I
�@�u�V�̉́v����̋�ŁA���m�̃t�B�N�V�����B�V��l�ԊE�ցB���̏�ʓ]���̌������A�N�₩���B�n���Ҕm�Ԃ̐^�������B
�@�o���̋�u�s���t�� ���e������ �ڂ͗܁v�ƑΒu�B���͓��Y�̖��Y�B�L�B�e�����l�X�Ƃ̕ʂ�ƍs���H�̎₵���B�������̈Ӗ����d�˂鐸���Ȑv�B���ɍ��������x�ł���B�u�����̂ق����v150�����o�ē��B�������̎����̋��n�����A���n�Ɓu�s���s�v�m���̏ؖ����B
�@ ���s���s�͕��Ղ̌�����
�@�m�Ԃ̋�Ɂu�s���s�v��T���Ă������A�s���s�͂Ȃɂ��o��Ɍ������T�O�ł͂Ȃ��B����ǂ��납�A�ނ�������̉c�݂ɏh���{���O�ł���A���̒��̎��ۂ��������������{�����ł�����B�����ɔm�Ԃ̕��Ր�������B
�@�Ⴆ�H �悭������u��a���v�Ƃ������t���l���Ă݂悤�B����́A�����ʂ���{�l����������̗L��l�ł���A���L�������I���_�̏ے��ł���B
�@���̂��̌��t�Ƃ̏o��́A���҂ɂ���Ă����炳�ꂽ�B���n3���̃{�N�T�[���҂́A1967�N�A���R�ƌ���Đ��E�`�����s�I���ɂȂ�B�����̋����B�܂��ɃV���f�����E�{�[�C�������B���̎�����̃����O��ŁA�ނ́A�u�{�N�A���}�g�_�}�V�C�ŏ������v�Ƌ��̂ł���B���{�ꂪ���ڂ��Ȃ����{�l�{�N�T�[���������u���}�g�_�}�V�C�v�Ƃ������t�̏Ռ��́A�^�ɋ������B
�@������́A�g�c���A���낤�B�u��������� �����Ȃ���̂ƒm��Ȃ��� ��ނɂ�܂�� ��a���v�u�g�͂��Ƃ� �����̖�ӂ� �����ʂƂ� ���ߒu���܂� ��a���v�͂��܂�ɂ��L�����B
�@�����V��9��14���t�u�V���l��v�́u��a���v���e�[�}�B�����ɂ́A�u�w��a���x�������j�㏉�߂ēo�ꂷ��̂́w��������x�́w�����̊��x�ŁA�����������q�̋�����j����邭����ɁA�����̊w�₪��b�ɂ����Ă����̑�a���ł���v�Ƃ����L�q������B
�@����ɑ����āA�u���яG�Y�́A��a���͂����炭���̌��t�������낤�Əq�ׂĂ���B�����̂���A���w�͒j�̂��̂������B���̂������ȂȒm���Ƃ͔��́A�_��Ȑ������m�b����a���ł���A�w�l�Ԑ��̋@���x�ɒʂ����D���������ȐS���w���Ă���̂��A�Ɓv�Ƃ���B
�@�����A��a���́u�����̊w�⁁���w����ɍ��グ�����{�Ǝ��̂��Ȃ₩�Ȑ��_�v���Ƃ����̂ł���B��������A�u�����Ƃ����s�Ղɓ��{�Ƃ������s���d�˂��n�����v�B���ꂼ�A�m�ԁu�s���s�v���̂��̂ł͂Ȃ����B
�@�s�ς̐^���ɗ��s�Ƃ����b�q��B���ꂪ�u�s���s�v�B���̊T�O�����A�Ȋw�A�|�p�A�|�\�A�N�w�A�@���A�X�|�[�c�A�����A�o��etc ���̋y�ԂƂ���͉ʂĂ��Ȃ��B�u�s���s�v�͂܂��ɕ��Ղ̌����Ȃ̂ł���B
2014.09.25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���6�`�u�����̂ق����v�Ɂu�s���s�v��T��
���u�s���s�v�Ƃ��� �T�O�͂�����ق����̂��H�� �@�m�Ԃ��u�����̂ق����v�̗����I�����̂��A���\2�N�i1689�N�j9���̂��ƁB���̌�A�ނ́A�S���Ȃ�1694�N�܂ŁA5�N�̒����ɂ킽���Đ��Ȃ��d�˂�i����̓V���[�x���g�́u�~�̗��v�̃P�[�X�ɍ������Ă���j�B�r���O���_�����蒼��������B�Βu���l�����\�����ł߂�B�u�s���s�v�́A���̂悤�ȍ�Ƃ̒��ŁA�T�O�Ƃ��āA�m���Ȃ��̂ɂȂ��Ă������̂��낤�B�������q�ɐ������̂́A�����I���Ă��炻�̔N�̕�ꂠ����܂ŁA�Ƃ��̖̂{�ɂ͏����Ă���B
�@�m�Ԃ��u�����̂ق����v�̗����I�����̂��A���\2�N�i1689�N�j9���̂��ƁB���̌�A�ނ́A�S���Ȃ�1694�N�܂ŁA5�N�̒����ɂ킽���Đ��Ȃ��d�˂�i����̓V���[�x���g�́u�~�̗��v�̃P�[�X�ɍ������Ă���j�B�r���O���_�����蒼��������B�Βu���l�����\�����ł߂�B�u�s���s�v�́A���̂悤�ȍ�Ƃ̒��ŁA�T�O�Ƃ��āA�m���Ȃ��̂ɂȂ��Ă������̂��낤�B�������q�ɐ������̂́A�����I���Ă��炻�̔N�̕�ꂠ����܂ŁA�Ƃ��̖̂{�ɂ͏����Ă���B�@�������A�m�Ԃ̈�u���p���Łu�����̂ق����v���o�ł����̂�1702�N�B�u�������v�Ɂu�s���s�̊T�O�v���L�����̂���������Ƃ����B
�@�ȏ������A�u�s���s�v�̊T�O�́u�����̂ق����v�̗��̒�����ق��Ă������ƂɂȂ�B�Ȃ�A����͂ǂ̂�����Ȃ̂��H
�@�|�p�Ƃ͊T�O�`���̂��߂ɍ�i�ݏo���킯�ł͂Ȃ��B���ݏo���ꂽ��i�ɊT�O���h��̂ł���B������A��i�̒��Ɂu�s���s�v����T������B
���̖��Ƃ����s�Ձ�
�@���Ƃ��Ɓu�����̂ق����v�͉̖���q�˂闷�ł���B�̖��Ƃ͌Ðl���̂��r���̒n�B����Εs�Ղ̏ꏊ�B����܂��ė��s���悹��n��s�ׂ��o�~�B���ꂼ�A�u�����̂ق����v�̖ړI�ł���B
�@4��20���A�m�Ԃ��b��̗��ɍs���B�����͌h�����鐼�s���u���������������v�Ɖr�ꏊ�B���̖��͍����c��ڂ̂������Ɏc���Ă����B�l�͌h������Ðl�i���ɂƂ��Ă̓��[�c�@���g�̂悤�ȁj���̒n�ɗ��ĂΊ��S���ЂƂ����B�������͈̐l���}�l���W�Ȃ��B�m�Ԃ̊��S�͂������肾�����낤���B�����ň�� �c�ꖇ �A���ė������� ������ (���̐́A���s�@�t��������������̉��ŁA�������S�ɂӂ����Ă��邤���ɁA�����������������ɂ܂����ēc�ꖇ��A�����d�������B����́A���s��S���˕��a�ɑ�������̈Ӗ������߂����z�������B�₪�āA��ɕԂ��āA�����ʂ̎v���Ŗ��̂��Ƃ𗧂����邱�Ƃɂ���)�B
 �@4��21���A���͂̊ցB�m�Ԃ́u�S���ƂȂ������d�˂�܂܂ɁA���͂̊ւɂ�����ė��S��܂�ʁv�Ə����B���͂̊ւ��z���āA����ƁA�݂��̂��̗��̎u���ł܂����Ƃ����̂ł���B����͏����Ɂu�t���Ă���̋�ɁA���͂̊։z����ƁA������_�̂��̂ɂ��ĐS���͂��A���c�_�̏����ɂ��ЂĎ����̎�ɂ����E�E�E�E�E�v�Ƃ��邩��A�m�ԂɂƂ��āA���͂̊։z���������݂��̂��̗��ւ̓�����������B�[��𗧂���1������A�m�Ԃ́u���悢��݂��̂����I�v�ƋC�������������Ƃ��낤�B
�@4��21���A���͂̊ցB�m�Ԃ́u�S���ƂȂ������d�˂�܂܂ɁA���͂̊ւɂ�����ė��S��܂�ʁv�Ə����B���͂̊ւ��z���āA����ƁA�݂��̂��̗��̎u���ł܂����Ƃ����̂ł���B����͏����Ɂu�t���Ă���̋�ɁA���͂̊։z����ƁA������_�̂��̂ɂ��ĐS���͂��A���c�_�̏����ɂ��ЂĎ����̎�ɂ����E�E�E�E�E�v�Ƃ��邩��A�m�ԂɂƂ��āA���͂̊։z���������݂��̂��̗��ւ̓�����������B�[��𗧂���1������A�m�Ԃ́u���悢��݂��̂����I�v�ƋC�������������Ƃ��낤�B�@�m�Ԃ́u���͂͌É̖̂����v�ƋL���Ă���B�������A�\���@�t�A�������A��������̌̎������p���Đ̂��������ށB�����A�m�Ԃ͂����ŋ���r��ł��Ȃ��B�u�s�Ձv�ɂ܂��u���s�v���悹�Ă��Ȃ��̂ł���B
�@5��1���A�R�ł́A�É̂ɂ������q�˓��������̓`���ɑ����āu���݁v��T���B���B�ɗ����ꂽ�����́A5���[�߂̐ߋ�ɏҊ����Ȃ��̂ŁA���̓y�n�̐A���u���݁v���p���Č��ɂ������A�Ƃ����`���ł���B���̌̎��l�ɖ₤���u���݁v��m����̂͂��Ȃ��B�m�Ԃ̋��ɍ��̂̎v�����N��������B
�@5��2���A�M�v�̗��B�����ł́A�L���ȌÉ́u�݂��̂��� ���̂Ԃ������� �N�䂦�� ���ꂻ�߂ɂ� ���Ȃ�Ȃ��Ɂv�i�� �Z�j�Ɉ���q�˂���A���c�ɂ��R�ォ�痎�Ƃ���ē��[�ɔ������܂��Ă����B�p�`���ς���Ă��܂����̖��ɁA�m�Ԃ́u��������ׂ����Ƃɂ�v�i����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��j�Ƌ����B�����ň�� ���c�Ƃ� ����Ƃ�� ���̂Ԑ����i���A��̕c�������Ă��閺�����̎�����݂Ă���ƁA�̈߂ɂ��̂Ԑ���������Ƃ��̎�������̂�āA�Ȃ�Ƃ��Ȃ������j
�@�����A�ђ˂̗��ł́A�`�o�̒��b�����ꑰ�̋��Ղ�q�� ���������� �܌��ɏ��� ���� �i5���A�[�߂̐ߋ���ԋ߂��̂ŁA���������Ɏ����̌��j���ł���B���̋`�o�̑�����ٌc�̋����A��������ɏ����Ăق������̂��j�Ɖr�ށB����́A�������̕�E�ڗ����R�㉤���ŁA�`�o�̑����ƕٌc�̋������ĉr���́B�߉^�̕����`�o�ւ̃I�}�[�W���ł���B���̎v���͕���Ŋ�������B
�@5��4���A�}���B�R�Ō���������H�����m�Ԃ��A���������̕�ɎQ�낤�Ƃ������A���肩��̌܌��J�������čs�������Ȃ������B�}���� ���Â��܌��� �ʂ��蓹�i�}���͂ǂ̂ւȁB���̌܌��J�̂ǂ������s���ɂ��s���Ȃ��j�B�����̖̉��ɁA��x�܂ł�������Ȃ��������鐣��������������B
�@�����A����B�\���@�t���u���G�� ���͂��̂��� �Ղ��Ȃ� ����o�Ă� ��͗���ށv�Ɖr�̖��E���G�̏��ň�� ����� ���͓�� �O���z���i�x���̂��납��A�������҂�������Ă������G�̏��B���̓�̏��ɂR���������āA�悤�₭����Ƃ��ł��܂�����j�B���̋�͒�q�̋������S�ʂɑ������u���G�� �������\�� �x���v�ւ̕ԗ�Ƃ��ĉr���́B������������]�˂͍��̌����낾�����B�R�������������A����ɏ������Ă���B�����āA���̏��́A�@�t�̎���ɂ͂Ȃ��������́B���̕����Ɋ��S���ЂƂ����̔m�ԁB�Ό��̌o�܂ɗ����������B
�@5��5���A���ł́A��ƂŔo�~�̐S��������E�q�傩��̖��̎萻�̊G�}�����炤�B����������ɔm�Ԃ́A�ʓc�E����ł͓����r���A�̉��͌Í��a�̏W�̓��́A�\���̐��Ԃł͕��ؘa�̏��̉̂��A���X�ÂԁB���̊G�}�ɂ́u���̍ד��v�Ƃ��������k�c�쉈���̓���������Ă���B�^�C�g���u�����̂ق����v�́A�������玷�������̂��낤�B
�@���E�q��Ɋ��ӂ����߂Ĉ�� ����ߑ� ���Ɍ��� ���܂̏��i�����͒[�߂̐ߋ傾���A����ߑ��i�Ҋ��j��A�z������悤�ȁA�������肵�����̐��ߏ������ׂA����ߑ��̂悤�ɎC���A���̌��r������Ă���邾�낤�B���ߏ��̑��܂̑��蕨�A���肪�Ƃ��������܂��j�B
�@�m�Ԃ́A���̂��ƊG�}�𗊂�ɉ̖���q�˂ĉ��B5��8���́A��c�̋ʐ�i�\���@�t�j�A���̐i����@�]��j�A���̏��R�i�u�Í��a�̏W�v���́j�A�߂����i�u�Í��a�̏W�v���́j�A�����̉Y�i�u�Í��a�̏W�v���́j��5�ӏ��ɋy�B�Ƃ��낪�A�m�Ԃ́A�����̖̉���O�ɂ��āA���g�ł͋���r��ł��Ȃ��B
 �@5��9���A�����ɒ��D�B�������O�̖`�����Ɂu�����̌��܂ÐS�ɂ�����āv�Ƃ��邭�炢������m�ԂɂƂ��Ċi�ʂȏꏊ�B�����A�̖��̕�ɂ݂��̂��̒��ł�����̖̉��������Ȃ̂��B�Ƃ��낪�A�����ł��m�Ԃ͋���r�܂Ȃ������E�E�E�E�E���m�ɂ́A���r�ނ��{���Ɍf�ڂ��Ȃ������̂ł���B
�@5��9���A�����ɒ��D�B�������O�̖`�����Ɂu�����̌��܂ÐS�ɂ�����āv�Ƃ��邭�炢������m�ԂɂƂ��Ċi�ʂȏꏊ�B�����A�̖��̕�ɂ݂��̂��̒��ł�����̖̉��������Ȃ̂��B�Ƃ��낪�A�����ł��m�Ԃ͋���r�܂Ȃ������E�E�E�E�E���m�ɂ́A���r�ނ��{���Ɍf�ڂ��Ȃ������̂ł���B�@5��12���A�������o���A�Ί��o�R�ŗ�������ɒ������B���̊Ԃɂ��̖�6�ӏ���ʉ߂��Ă���B�����Ă܂��A�����ł��m�Ԃ͋���r��ł��Ȃ��B�̖��ɗ��s���悹�Ă��Ȃ��̂ł���B
����7�́�
�@�������ڂ����͔̂m�Ԃ̒��قł���B�m�Ԃ͔o�~�t�����璾�قƂ́u����r�܂Ȃ��v���Ƃł���B�O�͂ɏ������Ƃ���A�m�Ԃ́A5��5�����Łu����ߑ� ���Ɍ��� ���܂̏��v�ƓǂB����Łu�đ��� ���ǂ��� ���̐Ձv�Ɖr�ނ̂�5��13��������A���V���Ԃ��̒����ɂ킽��A�����r��ł��Ȃ��B�����ł͈��r��ł��邩��A���m�ɂ́A�u�r��ł��Ȃ����Ƃɂ��Ă���v�̂ł���B
�@���������u�����̂ق����v�ɑ����ĉ]���A�u�ق̔�v�u���̏��R�E�����̉Y�v�u�����_�Ёv�u�����\�����̓V�H�v�u�����\�Y������v�u�����\���ގ��v�u�Ί��v��7�́i�u�����̂ق����v�p�쏑�X�ҎQ�Ɓj�ɂ킽��A�m�Ԃ̋傪�s�݂Ȃ̂��B���������̊ԁA�̖��K���10�ӏ��]��ɋy��ł���B�m�Ԃ��u�����̂ق����v�ɐ��������ق�7�́B����قǂ̋́A�����������đ��ɂȂ��B
�@������A���͉̋����Ӗ�����̂��낤���H �m�Ԃ��A���̖ړI�Ă܂ői�������������ƂƂ͂����������������̂��H
�@�u�����̂ق����v�͏����ȋI�s���ł͂Ȃ��B�����I�����m�Ԃ��A�S���Ȃ�܂ł�5�N�ԁA���Ȃ����������w��i�ł���B�����ł͈��r��ł���ɂ��S�炸�f�ڂ��Ȃ������B�\�ǂ̋�̂��Ɓu�\�ǂ͂���ȋ傪�ł������A���̂ق��͏����̐�i�Ɋ����������܂�A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�ƌ����������B
�@�u���X�� ��X�ɂ������� �Ă̊C�v �����ʼnr���̋�A�m�Ԃɂ��ẮA�m���ɕ��}�ł���B�i�F���̂܂�܂ł���B������O�����̂͗����ł���B�����A���l�m�ԂȂ�A���Ȃ�5�N�ԂŁA����łȂ��Ƃ��A����Ȃ�̋�͍�ꂽ�͂����B�o�~�̎t�����A����̒n�ŁA��q���r�߂Ďt���r�߂Ȃ��������Ƃ����J�Ɗ����Ȃ��͂��͂Ȃ��B�����A�m�Ԃ͂������Ȃ������B�����Ă��Ȃ������B
�@���J��D�́u�����̂ق�������ށv�i�����ܐV���j�̒��ŁA�����̋�������ē���Ȃ������̂́A�m�Ԃ́u�œ_�͂����v�������Ɖ]���B�O���ł��̐�i���^�������A�����Ɉ�������A�b���ł������������낭�Ȃ��B�����Ŋ����ē���Ȃ������B���ʁA�����Ƃ������ɂ̖̉���������̂܂c����A�u�����̂ق����v�̐��E�͎������ĉʂĂ��Ȃ��L���邱�ƂɂȂ����ƁB
�@����͂���ŁA�����ł���B�����A���́A����ȏ�̈Ӑ}��������̂ł���B
�@�m�Ԃ́A�u����v���O�̂V�͂��ɂ��邱�ƂŁA�n���̓�Y�A�����A�u�s�Ձv�ɏ悹�āu���s�v�����o�����Ƃ̓�����������������̂ł͂Ȃ����낤���B�����Ɂu�s���s�v����ق����邱�Ƃ��Î������̂ł͂���܂����B�m���Ɂu�����̂ق����v�́A�u����v���疼�傪��������悤�ɕ��o����̂ł���B
�@��7�͂́A�m�Ԃ����ߍ��Í��ł���B�����A�u�m�ԃR�[�h�v�B�u�m�ԃR�[�h�v�́A�����Ɂu�s���s�v����ق����݂��邱�ƂƁA����n�܂閼��̗ʎY����X�Ɏ������Ă���B����ȋC������̂ł���B
[�Q�l����]
�@�@�u�����̂ق����v�i�p�쏑�X�ҁj
�@�@�u�m�Ԃ����̂ق����v�t�\�Ǘ����L�i�������j�Z���@��g���Ɂj
�@�@�u�����̂ق����v����ށi���J��D���@�����ܐV���j
2014.09.05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���5�`�m�Ԃɂ�����u�s���s�v�̊T�O
���u�s���s�v�̏o���� �@�u�s���s�v���A�m�Ԃ����B�������ɂ̌|�p�I���n�̈�ł��邱�Ƃ͎��m�̎������B�ł́A�ނ́A���ǂ��ł��̊T�O���J�������̂��낤���E�E�E�E�E �I�s���H�莆�H����Ƃ����L�H
�@�u�s���s�v���A�m�Ԃ����B�������ɂ̌|�p�I���n�̈�ł��邱�Ƃ͎��m�̎������B�ł́A�ނ́A���ǂ��ł��̊T�O���J�������̂��낤���E�E�E�E�E �I�s���H�莆�H����Ƃ����L�H�@�N�����m�I�T���S�ł��낢�듖�����Ă݂����A�u���ꂾ�v�Ƃ������̂ɂ͂Ԃ���Ȃ������B�ł��܂��A����͂��قǕs�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�Í��́u������v�ɂ͂��̎肪���\���邩�炾�B
�@���Ƃ��A�x�[�g�[���F�����������Ƃ����u�^���͂����˂�@���v�B��̌����ȑ�5�ԁu�^���v�̋w���̗R���ƂȂ����䎌�����A����͒�q�̃V���g���[���u�t�͂��������܂����v�ƋL���Ă��邾���ŁA�^�U�̂قǂ͕s�����B
�@���l���̕]�_�Ɛ搶���u�V���[�x���g�́A�O�����f���E�K�V���^�C�����s�̐܂Ɂw�n�����̑傫�Ȍ����Ȃ��������x�Ǝ莆�ɏ����Ă���v�ƋL�q���Ă���̂ŁA�V���[�x���g�̎莆���\�Ȍ��蓖�����Ă݂����A����ȋL�q�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B�����́A�ނ̗F�l���ʂ̗F�l�Ɉ��Ă��莆�̒��ɂ������B
�@���ƂقǍ��l�ɁA�o���Ƃ������̂͂����ƒ��ׂȂ��Ă͔���Ȃ��B������Δm�Ԃ́u�s���s�v�̏o���₢���ɁH
�@����́A�m�Ԃ̒�q�E���䋎���i1651�|1704�j�́u�������v�̒��ɂ������B�H���u�Ԗ�ɁA��ڕs�Ղ̋�A�ꎞ���s�̋�Ƃ��ӂ���B�����ɕ����ċ�������A���̌��͈�Ȃ�v�ƁB����͋��������������̂����A�m�Ԃ̋����ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�L���X�g�̋�������q�ɂ���Č��ꂽ�悤�ɁB�܂��́A���ꂪ�u�s���s�v�Ƃ������t�̏o���ƍl���Ă������낤�B
���u�s���s�v�Ƃ����T�O��
�@�ł́u�s���s�v�Ƃ͂ǂ̂悤�ȊT�O�Ȃ̂��낤���H
�@�u�s�Ձv�́u�s�ρv�u�`���v�u���K�v�A�Ȃǐ̂���ς��Ȃ����́B�u���s�v�́u�v�V�v�u���s�v�u�����v�ȂǁA���V�������́B���Ȃ킿�A�u�s�Ձv�͎�����ĉi���ɕς��Ȃ����́B�s�ς̐^���B�u���s�v�͎���ɑΉ����ė����ω�������́B
�@�ꌩ�Η�����悤�Ɍ�����u�s�Ձv�Ɓu���s�v�́A���҂Ƃ��d��ׂ��T�O�ł���A���͈�B���̃o�����X�̍������������o�~�̉��`�A�m�Ԍ|�p�̍����Ȃ̂ł���B
 �@�u�������v�̕ʂ̕����ɂ́u�a�̗D���̏�ɂ��ւ����܂ł�����삵������A�o�~���R�̏�ɂ����q��̋C�F���삹��́A�蕿�Ȃ���ׂ��v�i�D�������̖{���̐��i�Ƃ��Ă���a�̂ł������̂悤�ɍH�v�����Č��ʂ��オ��悤�ɍ���Ă���̂ɁA���R�ȕ\����������Ă���o�~�ɂ����āA����������O�̗l�q����ɍ��̂ł́A��҂̎蕿�͂Ȃ����낤�j�Ƃ���B����͋����̋��m�Ԃ��]�������t�ł��邪�A������u�s���s�v�Ƃ����T�O�Ɏ�����^������̂ł���B
�@�u�������v�̕ʂ̕����ɂ́u�a�̗D���̏�ɂ��ւ����܂ł�����삵������A�o�~���R�̏�ɂ����q��̋C�F���삹��́A�蕿�Ȃ���ׂ��v�i�D�������̖{���̐��i�Ƃ��Ă���a�̂ł������̂悤�ɍH�v�����Č��ʂ��オ��悤�ɍ���Ă���̂ɁA���R�ȕ\����������Ă���o�~�ɂ����āA����������O�̗l�q����ɍ��̂ł́A��҂̎蕿�͂Ȃ����낤�j�Ƃ���B����͋����̋��m�Ԃ��]�������t�ł��邪�A������u�s���s�v�Ƃ����T�O�Ɏ�����^������̂ł���B�@�a�̗D���́A��X�̘a�̂ɂ���Ēz����Ă����A����Εs�Ղ̐��E�B�o�~���R�́A�����Ɉ��o�闬���̖��f�ł���i�R����C���u�m�ԕS�����v�x�m�����[�j�B
�@����ɁA�����́u�O���q�v�ɂ͂�������B�u��ϖ���������͎̂��R�̗��Ȃ�B�ω��ɂ��炴��A�����炽�܂��v�i���w���ω����邱�Ƃ͎��R�̗��ł���A�ω��ɂ���č�i�̌|�p�������シ��j�B�����A�ω��������|�p�̍����B�u�s�Ձv���u���s�v���d��m�Ԃ̌|�p�ς��M����B
�@
�@���{�l�Ȃ�m��ʎ҂Ȃ����̋�́A�u�ԕ��J��̋�v�ƌĂ�Ă���B�m�Ԃ̍앗����܂����L�O��I�ȋ�Ƃ����킯���B
�@�ł͂��̋�̉�������I�Ȃ̂��H �m�Ԃ͂܂��u�^�� ���̉��v�Ɖr�ށB�����Œ�q�̑��p����܂��u�R����v�Ƃ����B�����m�Ԃ��u�Òr��v�ƒ����A���̌`�ƂȂ����B
�@���p���u�R����v�Ƃ����̂́A�Í��W�ɂ���悤�ɁA�u�^�ɂ͎R���v�Ƃ����`���܂������́B����Ό��ߎ����B�m�Ԃ́u�w�^�ށx���炵�āA�g�^�͖����́h�Ƃ������ߎ������ɔj���Ă���̂�����A�����Ɂw�R����x�ł͊v�V�̈Ӗ����Ȃ��A�ʔ������Ȃ��v�ƍl�����̂��낤�B����J��D���́u���K�ɂƂ����̂ł��Ȃ��A���K��^��������ᔻ����̂ł��Ȃ��B���̂ǂ�������z�����s�v�c�ȐV������ԂɁw�Òr��x�Ƃ������t�͂���v�Əq�ׂĂ���i�u�o��̉F���v�������Ɂj�B���̋傪���������̂�1686�N�̏t�B�����Ɂu�s���s�v�Ɓu���s�v�D��̌|�p�ς̖G�肪����B
�@�u�s���s�v�Ƃ����T�O�͔m�ԈȑO�ɂ��������B������i1363�H�\1443�H�j�̊m�������u�\�v�̗l���ł���B����́A�u��������v��u�ɐ�����v�Ȃǂ̌ÓT��̏�Ŏ����o�����A��O�ɂ킩��₷���\���������́B������́A�쌀�̌��ߎ��A���҂̖����A���䑕�u�����Œ肵�A������L�@�I�Ɍ��т��V�X�e���Ƃ��Ċm�������B�u�\�v���܂��u�s�Ձv�Ȃ���̂Ɂu���s�v���������V���ȉ������Ȃ̂ł���B
 �@�����킪�\�̋Ɉӂ��L�����u���p�ԓ`�v�́A15���I�����̐����A����͐��E�ŏ��̌|�p�_�Ƃ����Ă悭�A�������A����ɖ��v���Ȃ����Ր������B
�@�����킪�\�̋Ɉӂ��L�����u���p�ԓ`�v�́A15���I�����̐����A����͐��E�ŏ��̌|�p�_�Ƃ����Ă悭�A�������A����ɖ��v���Ȃ����Ր������B�@�u���p�ԓ`�v��́u���V�ɉ]�Ӂv�̒��ɁA�u�s���s�v�ɒʂ���ꕶ������B�u���Ƃ���A���̌|�A���̕����p���Ƃ��ւǂ��A���͂��o�Â�ӂ�܂Ђ���A��ɂ�����т������B���̕��āA�S���S�ɓ`���ԂȂ�A���p�ԓ`�Ɩ������v�i���ɐ\�y�̌|�́A��y�̎c�����^���p���ł������̂ł͂��邪�A����Ɏ����̗͂Ŕ�������������������Ă����Ȃ�A���̏���Ȃ����Ƃ��B��y�̕�������āA�S����S�ɓ`���u�ԁv�ł��邩��A���̏����̖����u���p�ԓ`�v�Ƃ����̂ł���j�B
�@����ɂ́A�����̗R����������Ă���킯������A�u���p�ԓ`�v�̊j�S�����Ƃ����Ă��������낤�B������́A�\�y�i�\�j�Ƃ����|�́A��{�A��y����p�����́i�ʂ̏͂ł́u���^���v�̏d�v��������Ă���j�ł��邪�A�Ǝ��̂����������ŏ�ł���A�Ɛ����B���ꂼ�܂��Ɂu�s���s�v�̊T�O���̂��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���y�]�_�Ə����Ǒ��Y������A�ȑO�����˗��������e�̒��ɖ������������������Ƃ�����B����́u���s�̂��q�b�g����閧�́A�w�Ƒn���ƃC���p�N�g�̋����x�Ɓw����Ă炤�Ɏ~�܂�ʊ����x�̍����x�ɂ���v�Ƃ������̂��B
�@�u�Ƒn���ƃC���p�N�g�̋����v�͌��ƑN�x�ł���u���s�v�B�u����Ă炤�Ɏ~�܂�ʊ����x�̍����v�́A�`���ɍ����������芴�ł���u�s�Ձv�B
�@�u���������s�̂̐��E����Ȃ����v�ƕ̂ނȂ���I�Í������A��i�Ƃ������̂͂��ׂăq�b�g��ژ_��őn����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�n��̓��@���ǂ�����A���_�������ł��ꉺ���b�ł���A���l�ɔF�m���ꂽ���Ƃ�����]�Ȃ����đn���͂��肦�Ȃ����炾�B�����炱��́A�܂��Ɂu�s���s�v�̊T�O���̂��̂Ƃ����邾�낤�B�������y�́A�m�Ԃ�����������܂��Ă������̂Ǝv����B
[�Q�l����]
�@�@�u�����̂ق����v�i�p�앶�Ɂj
�@�@�u�����̂ق�������ށv���J��D���i�����ܐV���j
�@�@�u�o��̉F���v���J��D���i�������Ɂj
�@�@�u�m�ԕS�����v�R����C���i�p��\�t�B�A���Ɂj
�@�@�u�m�Ԃ̐��E�v�R����C���i�p��I���j
�@�@�u�ԓ`���v�i���p�ԓ`�j������� �쐣��n��i�u�k�Е��Ɂj
�@�@�u���R�c���ƃN�[���E�t�@�C�u �S�[���f��BOX�v������i�����Ǒ��Y�� BMG JAPAN�j
2014.08.05 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�������Y �ԈႢ���炯�̉��y�u��
�@Ray�����A����ɂ��́B�����˂��B�N���A�u���N�̓G���j�[�j���������āv�Ȃ�Č������z�́I �܂��A�\��͓���B����[�Ȃ��ˁB �@�Ƃ���ŁAJiiji�A����́A�{���Ă͂��Ȃ����A�����Ă����������Ƃ�����B�����7��29���e���r�������f�́u�яC�̍��ł���u�� �N���V�b�N���猻�㉹�y�܂ł̗�����w�� �t�������Y�̉��y���Ėʔ����u���v�ɂ��ĂȂB����́A��������q�̃J���X�}�\���Z���t�E�яC�����E�I���@�C�I���j�X�g�t�������Y�������ĉ��y�̍u�`�����������́B�^�C�g���ɂ���悤�ɃN���V�b�N���y���猻��̃|�b�v�X�܂ł̗����₷���u�`������e�B�O�����āu��^�̗��v�����������ȁB����͂��̑�2�e�炵���B
�@�Ƃ���ŁAJiiji�A����́A�{���Ă͂��Ȃ����A�����Ă����������Ƃ�����B�����7��29���e���r�������f�́u�яC�̍��ł���u�� �N���V�b�N���猻�㉹�y�܂ł̗�����w�� �t�������Y�̉��y���Ėʔ����u���v�ɂ��ĂȂB����́A��������q�̃J���X�}�\���Z���t�E�яC�����E�I���@�C�I���j�X�g�t�������Y�������ĉ��y�̍u�`�����������́B�^�C�g���ɂ���悤�ɃN���V�b�N���y���猻��̃|�b�v�X�܂ł̗����₷���u�`������e�B�O�����āu��^�̗��v�����������ȁB����͂��̑�2�e�炵���B�@Jiiji�̗F�l��A�N��N�N�Ȃu��邩�猩�āv�Ɠ������[�������ꂽ�قǁB��������ˁB�ł��ȁA����Jiiji�A���̗t�������A���v�����ȁA�ƐS�z���Ȃ��猩����B�Ȃɂ��낱�̕��A�ȑO�u�N�����m�v2009�D6�D29�Ŏw�E�����Ƃ���AJ.S.�o�b�n�̐��n�����C�v�c�B�q�ƊԈႦ���Ⴄ�悤�ȎG�Ȑl�Ȃ�łˁB
�@���������ς肾�����B�Ӑ}�͈����Ȃ��A�������B�N���V�b�N���W���Y��b�N�ɂǂ��Ȃ����Ă��邩�ӂ̃��@�C�I������e���Ȃ���b���Ă����킯������A�����w�Z�̍u�`��l�p�l�ʂ̃N���]�_�Ɛ搶�̘b���ʔ����̂͊m�����B�ł��ˁA�Ԃɋ��ރG�s�\�[�h�A���b�A���ꂪ�܂����B�\��ǂ���u�ԈႢ���炯�v�ȂȁB
�@Jiiji�A�����ŗt�������̊ԈႢ�����炢���炢��������Ē������邱�Ƃɂ����B�グ�������y�������Ȃ�āA����ȍ��_����Ȃ��B�ԈႢ�͕��u�ł��Ȃ������̘b���B�܂��A����̐搶�̂��߂ɂ��Ȃ邱�Ƃ����ˁB����A�ȉ��A����ǂ��ĊԈᕔ������ׂĂ������B
���o�b�n�̓~�T�̂��߂̋Ȃ������Ă��Ȃ���
 �@�t�����搶�́A�uJ.S.�o�b�n�͋�����~�T�̂��߂��Ȃ��������v�Ƌ��܂������A����A���S�ȊԈႢ�B�o�b�n�̓v���e�X�^���g���k�łˁB�v���e�X�^���g�Ƀ~�T�͂Ȃ��B�~�T�̓J�g���b�N�̓T��B������o�b�n�̓~�T�̂��߂̋Ȃ͏������ɂ������Ȃ��B
�@�t�����搶�́A�uJ.S.�o�b�n�͋�����~�T�̂��߂��Ȃ��������v�Ƌ��܂������A����A���S�ȊԈႢ�B�o�b�n�̓v���e�X�^���g���k�łˁB�v���e�X�^���g�Ƀ~�T�͂Ȃ��B�~�T�̓J�g���b�N�̓T��B������o�b�n�̓~�T�̂��߂̋Ȃ͏������ɂ������Ȃ��B�@�������A��Ȃ�����O������B�u�~�T�� ���Z���v�B����̓o�b�n�Ō�̍�i��2���Ԃ��z�������B�N�Ɉ˗����ꂽ�����s���B���t���ꂽ�`�Ղ��Ȃ��B�����A�v���e�X�^���g���k�̃o�b�n���A�Ȃ��l���̍Ō�ɁA�J�g���b�N�̗l���̃~�T�Ȃ��������̂��H����͂܂��𖾂���Ă��Ȃ��N���V�b�N�j��̓�B�t�����搶�I����̓N���V�b�N�̏펯�����牟�����Ă����Ă��������ȁB
���o�b�n�͔�Ќ�I�H��
�@�t�����搶�H���u�o�b�n�͎Ќ�I�ȂƂ���͂܂�łȂ��A����ɂ����肫���ŋȂ������Ă����v�B�E���A��������ɒ[�����錾���l���B�ނ̓��C�v�c�B�q�ŋ���̉��y��������Ă�������A�u�c�B���}�[�}���̃R�[�q�[�n�E�X�v�Ƃ����J�t�F�̏�A�������B�����͐�y��ȉƃe���}���̌o�c�łˁB�����R�[�q�[�����݂ɗ��Ă�����������Ȃ��A�����Ŏ���̃J���^�[�^�Ȃ��t���đ傢�ɐ���オ���Ă����B����u�R�[�q�[�E�J���^�[�^�v�͂���Ȏ����̍�i�B������A�t�����搶�A�u����ɂ����肫��v�͂�����ƌ�����������Ȃ�������B
���E�l��ȉƂ̊��聄
�@�t�����搶�́A�u���B���@���f�B�A�o�b�n�A�w���f���A�n�C�h���A���[�c�@���g�v��5��ȉƂ��ꊇ��ɂ��āA�u�E�l�̎���B��ȉƂ͌ق���i���l���M���j�̂��߂����ɋȂ��������v�Ƃ��Ă��邪�A�����Ƀ��[�c�@���g������̂͊ԈႢ���B�ނ�1781�N5���ɃE�B�[���ɈڏZ���A�{��ɏA�E�ł��Ȃ��������̂�����A���쉉�t��̃`�P�b�g�����Ő������Ă�����B�ނ������������y�Ƃ̑�ꍆ�ȂB
���n�C�h���͌������Ēn���H��
 �@�t�����搶�́u�n�C�h���͑匙���B�������Ēn���B���y�͎l�p���ăK�c�K�c���Ă��邩��v�Ƌ�B�����ƌ����͎̂��R�B�����̖�肾����ˁB�����ǁA���̃n�C�h���]�͂ǂ����Ȃ��B�n�C�h�����ăE�B�b�g�ɕx������������Łu�p�p �n�C�h���v�ƌĂ�݂�Ȃɐe���܂�Ă����B������Ȃ������āg�l�p���ăK�c�K�c�h����Ȃ��B�ނ���D��ŏ_�a�BCM�ł悭���ꂽ�u�����ȑ�101�� ���v�v��2�y�͂⌷�y�l�d�t�ȁu�Ђ�v�Ȃ��������ł����ˁB���y�l�d�t�ȁu�c��v�̑�2�y�͂̃e�[�}�́A���݂̃h�C�c���̂ɂȂ��Ă���BW�t�̌����ł̓}���J�i���ɂ��̋Ȃ����炩�ɗ��ꂽ����A�t�����搶�A����Șb�ł�����A���^�C�����[�������̂ɂˁB�܂��A�����ȂႵ�傤���Ȃ����B
�@�t�����搶�́u�n�C�h���͑匙���B�������Ēn���B���y�͎l�p���ăK�c�K�c���Ă��邩��v�Ƌ�B�����ƌ����͎̂��R�B�����̖�肾����ˁB�����ǁA���̃n�C�h���]�͂ǂ����Ȃ��B�n�C�h�����ăE�B�b�g�ɕx������������Łu�p�p �n�C�h���v�ƌĂ�݂�Ȃɐe���܂�Ă����B������Ȃ������āg�l�p���ăK�c�K�c�h����Ȃ��B�ނ���D��ŏ_�a�BCM�ł悭���ꂽ�u�����ȑ�101�� ���v�v��2�y�͂⌷�y�l�d�t�ȁu�Ђ�v�Ȃ��������ł����ˁB���y�l�d�t�ȁu�c��v�̑�2�y�͂̃e�[�}�́A���݂̃h�C�c���̂ɂȂ��Ă���BW�t�̌����ł̓}���J�i���ɂ��̋Ȃ����炩�ɗ��ꂽ����A�t�����搶�A����Șb�ł�����A���^�C�����[�������̂ɂˁB�܂��A�����ȂႵ�傤���Ȃ����B�����[�c�@���g�A���߂č�Ȃ����͉̂��H��
�@�t�����搶�H���A�u���[�c�@���g��8���炢������Ȃ��Ă��܂����E�E�E�E�E�v�B����́u5�v�̊ԈႢ�ł��ˁB�P���~�X�B8�̂Ƃ��ɂ̓V���t�H�j�[�������n�߂�����A�搶�A����Ɗ��Ⴂ�����̂����B
�����[�c�@���g��500�Ȃ��炢�Ȃ�����Ă���H��
�@500�Ȃ��Ăǂ�����o�Ă����̂��Ȃ��B�Ō�̍�i�́u���N�C�G�� �j�Z���vK626������A600�Ȃ��炢���������Ǝv�����ǁA������������A�U����������̂��Ȃ��B�U��܂��͋^���̂���̂�40���炢������A�����Ɩ�590�ȁB�ق�A����ς�600�Ȃ�������B�搶�A���܂�l�������Ȃ��ł���������B
�����@�C�I�����͔��B���Ă��Ȃ���
�@�t�����搶�u�y��̔��B�Ƌ����A������g���Ĕ���ɂ����ȉƁ����t�Ƃ��o�Ă����B�܂��̓p�K�j�[�j�v�Ƌ��Ĕނ̘b�X�ƂȂ����܂����B���g�Ɠ������@�C�I���j�X�g�̘b������M�������ˁB�Ƃ��낪�ł��E�E�E�E�E�B
�@�p�K�j�[�j�́u�����ɍ��������������Ƀe�N�j�b�N����������v�Ƃ���ꂽ����Z�I���@�C�I���j�X�g����ȉƁB�ނ�11���̃X�g���f�B���@���E�X�������Ă����������B�搶�������m�̂悤�ɁA�X�g���f�B���@���E�X��17�|18���I�ɍ���ă\�m�}�}�B�܂�������͉������Ă��Ȃ��B������A���@�C�I�����Ɋւ��Ắu�y��̔��B�v�͓�����Ȃ���ł���B�s�A�m�͂���ł����̂ł����B
�����[�O�i�[�͉��l�����Ԃ炩���ā�
 �@�t�����搶���[�O�i�[�͂������Ȃ悤�ŁA�����������B�u���[�O�i�[�͈��l�ł��B�j�F�n�̉��l�����āA���̉��l�����[�O�i�[�ɍ��ꍞ�B���[�O�i�[�͂��̉��l�����Ԃ炩�������̗\�Z��S�������܂����v�B���ꂶ��[�O�i�[�͐F���t�ɂȂ����Ⴄ�B������Y�ނ�ˁB����A�z���g�̂Ƃ�������b���܂��傤�B
�@�t�����搶���[�O�i�[�͂������Ȃ悤�ŁA�����������B�u���[�O�i�[�͈��l�ł��B�j�F�n�̉��l�����āA���̉��l�����[�O�i�[�ɍ��ꍞ�B���[�O�i�[�͂��̉��l�����Ԃ炩�������̗\�Z��S�������܂����v�B���ꂶ��[�O�i�[�͐F���t�ɂȂ����Ⴄ�B������Y�ނ�ˁB����A�z���g�̂Ƃ�������b���܂��傤�B�@�o�C�G�����������[�g���B�q2���i1864�|1886�j�͏��N���ォ�烏�[�O�i�[�ɓ���Ă����B�m�C�V�����@���V���^�C��������u���[�G���O�����v�̕���őS�ʑ�������قǁB��ɁA���z�̌��ꌚ�݂ɓ˂��i�ރ��[�O�i�[�ɗ��悵�Ď�����B���̂��A�ŁA�o�C���C�g�j�Ռ��ꂪ���������B�����ʁA���̍����������A���Ɣj�]�ɂȂ����Ă��܂����B�Ƃ܂��A���ꂪ�^���B�j�F�Ń��[�O�i�[�ɓ��ꍞ��Ȃ��A�����ɔނ̌|�p�������Ă������A�����ă��[�O�i�[���g���Ԃ炩�����h�킯����Ȃ��B���l�̉������Q�������A�؋����ݓ|������A���l�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����ǁA�����ɂ͂����Ɛ_�o���g���Ăق����ȁB
�����F���f�B�̍앗��
�@�u���F���f�B�́A���������I�Ȃ��̍��̂��Ɨ��j���e�[�}�ɃI�y����������v�Ɛ搶�͂��������B�ŁA��\��Ƃ��Ēe�����̂��u�֕P�v�́u���t�̉́v�B����Ⴄ�ł��傤�B �u�֕P�v�̓A���N�T���h���E�f���}���t�B�X����̔ߗ����́B�m���ɁA���F���f�B�ɂ����āA���j���m�͎�v�ȃW�������Ȃ̂Řb�ɊԈ�͂Ȃ�����ǁA��������u�A�C�[�_ ��s�i�ȁv�������e���Ăق��������ȁB����Ȃ���j���Ƃ�����B���낪�����B�ׂ₩�Ȑ_�o���ق����ł��ˁB
���搶�̃I�y�����̌��k��
 �@�搶���I�y���̖{��Œɂ������������Ƃ̗�Ƃ��āA�A���[�i�E�f�B�E���F���[�i�ł̑̌��k�����b�����ꂽ�B�u�ƂȂ�ɍ������C�^���A�̂��������C��������ŏo���オ���āA���ɘb�������Ă����ł��B�n�܂��Ă���̂ɂł���B�ł��A�D���ȉ̎肪�̂������Ɩق��Ē��������Ă���B�I���Ƃ܂�����ׂ肾���B���ɃI�y�����G���W���C���Ă��ł��ˁB�G���^�[�e�C�������g�Ƃ��āB�f���炵���̌��ł����v
�@�搶���I�y���̖{��Œɂ������������Ƃ̗�Ƃ��āA�A���[�i�E�f�B�E���F���[�i�ł̑̌��k�����b�����ꂽ�B�u�ƂȂ�ɍ������C�^���A�̂��������C��������ŏo���オ���āA���ɘb�������Ă����ł��B�n�܂��Ă���̂ɂł���B�ł��A�D���ȉ̎肪�̂������Ɩق��Ē��������Ă���B�I���Ƃ܂�����ׂ肾���B���ɃI�y�����G���W���C���Ă��ł��ˁB�G���^�[�e�C�������g�Ƃ��āB�f���炵���̌��ł����v�@�A���[�i�E�f�B�E���F���[�i�́A�Ñネ�[�}�̖�O���Z��Ղ��I�y���ꉻ�������̂�����A16,000�l���e�̑��O�̌���ȂB�����瑽���̂�����ׂ�͑��v�Ȃ�ł��B�ł��A�C�O�̂قƂ�ǂ̃I�y����͉����B�L���p2000���炢���Ȃ��B�����Ń��C���Ƃ�����ׂ�͂܂����ł��傤�B����Șb��^�ɎāA�����̃I�y���n�E�X�œ������Ƃ������c�}�~�o���ꂿ�Ⴄ���B�e���r�������F�l�A���ꂮ��������ӂ��B����ȃP�[�X�̘b����ʘ_�ł���ׂ�Ȃ��ł��������ȁB
���O���[�O�́u���v�̓t�B�����h�H��
�@�u�O���[�O��ȁw�y�[���M�����g�x�́w���x�����ł��ˁB����̓m���E�F�[���t�B�����h�̖k���̊������̕��i�����ɂ�����ł��v�Ɛ搶�͂��b�ɂȂ�܂������A�c�O�A�Ⴄ��ł��B
�@����͎�l���y�[���������b�R�̊C�݂Ŗڂ��o�܂����Ƃ��̏�i�����y�ɂ������́B�܂��A�u�O���[�O�̓��̒��̃C���[�W���t�B�����h�������v�\�����Ȃ��Ƃ͂����Ȃ�����A���S�Ɂ~�Ƃ͂����܂��ˁB�ł�����͂����Ȃ�ł���B
���}�[���[�̌����Ȃ̍�����
 �@�搶�͂��������܂����u�}�[���[�̌����Ȃ͖��ӂǂ����ŕK�����t����Ă���B�Ȃ�����قǂ܂łɐl�C������̂��H����́A�ނ��I�[�P�X�g���̂��ׂĂ̋Z����g���āA�����Ɋy�������y����邩�Ƃ������Ƃɓw�͂�������ł��v
�@�搶�͂��������܂����u�}�[���[�̌����Ȃ͖��ӂǂ����ŕK�����t����Ă���B�Ȃ�����قǂ܂łɐl�C������̂��H����́A�ނ��I�[�P�X�g���̂��ׂĂ̋Z����g���āA�����Ɋy�������y����邩�Ƃ������Ƃɓw�͂�������ł��v�@�����������ƈႤ�Ȃ��B�ǂ������āg�y�����h�̕����B�}�[���[�قǎ��ƌ�����������ȉƂ͂��Ȃ�������ł��B�ނ̍�i�͎��ƌ����������ƂŐ��藧���Ă���Ƃ����Ă��ߌ�����Ȃ��B�ǂ����ǂ����Ęb�������Ɓu�N�����m�v���ɂȂ��Ă��܂��̂Ŏ~�߂܂����A�����������Ƃł��B�m���ɁA�y�����Ȃ�����܂���B�����ȑ�1�ԁu���l�v�Ƃ������͂ˁB�ł��A�ނ̉��y�̖{���́u���y�v�̂ǂ��炩�Ƃ����u���v�ł���A��Jiiji�͊m�M�������Č�����B���Ȃ��Ƃ��u�����Ɋy�������y����邩�v�ɕ��S������ȉƂł͂���܂��B�n�C�B
���K�[�V���C���ƃ����F���̃G�s�\�[�h��
�@�t�����搶�́A�u�K�[�V���C���ɋ��������ꂽ�����F���͂��������܂����B�w�̃����F�����ꗬ�̃K�[�V���C���ɋ����邱�Ƃ͉����Ȃ��x�ƁB�K�[�V���C���͂������č�Ȃ̕������Ȃ��疼�ȁw���v�\�f�B�[�E�C���E�u���[�x���������̂ł��v�Ɛ��������B�c�O�I���ꎞ�n�t�B
�@�W���[�W�E�K�[�V���C���́A1924�N�u���v�\�f�B�[�E�C���E�u���[�v�̐����ň��N���V�b�N��ȉƂ̒��ԓ�����ʂ����܂��B�Ƃ��낪���̋Ȃ̃I�[�P�X�g�������́A�O���[�t�F���������B�K�[�V���C���͂܂��I�[�P�X�g���[�V�����ɒ����Ă��Ȃ������̂ł��B�����Ŕނ͈�O���N���ĊC��n��t�����X�Ń����F���̖��@�����B�����F���ɂ͒f���܂����A�Ȃ�Ƃ��I�[�P�X�g���[�V�������}�X�^�[�B���ȁu�p���̃A�����J�l�v�������グ���B���ꂪ�^���B���j�͐������݂͂܂��傤�B
���u�{�����v�ł�W�~�X�e�[�N��
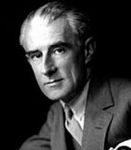 �@�搶�̓����F���́u�{�����v���L�C�{�[�h�Œe���Ȃ��������Ă���܂����B�u�������Y��������ŁA���ꂪ���X�Ƒ�����ł��v�ƌ����Ȃ���@���Ă��ꂽ���Y���B���ꂪ�Ⴄ�Ȃ��I �ߖڂ̑�R�����B����Ȃ�q����O�����Ⴄ����Ă��B
�@�搶�̓����F���́u�{�����v���L�C�{�[�h�Œe���Ȃ��������Ă���܂����B�u�������Y��������ŁA���ꂪ���X�Ƒ�����ł��v�ƌ����Ȃ���@���Ă��ꂽ���Y���B���ꂪ�Ⴄ�Ȃ��I �ߖڂ̑�R�����B����Ȃ�q����O�����Ⴄ����Ă��B�@����ɁA�搶�A�����̂��ƂŃ~�X�̏�h��B�u�����͑厸�s�B�u�[�C���O�̗��v�����āB�I�b�g����͂ǂ��������Ƃ�B���͂ˁA�搶�A�u�{�����v�Ƃ����Ȃ͍ŏ�����]�����悩�����B�ϋq�M���Ƃ܂ł͂����Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��u�u�[�C���O�̗��v����Ȃ������B�o���G���y�����珉���̓o���G�ƈꏏ�B�ŁA���̔Ō����ꂽ���N����̓t���[�̃I�[�P�X�g���ȂƂ��Đ��E���ő�q�b�g������B���̃����F�����u�Ȃ�����ȋȂ��]�������B���d�s�v�c�v���b�����قǁB�u�u�[�C���O�̗��v���āA��̒N���畷�����Ⴂ�I ���������Ȃ��Ɣ�������˂��I�I
�@�͂Ă��āA���E�I���@�C�I���j�X�g�t�������Y��搶�̑�]���u�`�ɒ��X�Ƌꌾ��悵�Ă܂���܂����B�u�Ȃ������܂ł��������́v�ƌ���ꂻ���ł����AJiiji�̐^�ӂ́A�u�搶�ɂ͂�����Ă������������v�̈�_�B���ӂ͂Ȃ��̂ł���܂��B�z�X�g�̗ѐ搶�́u�w�Z�ł͋����Ă���Ȃ��悤�Ȗʔ����b�̂��A�ŁA�N���V�b�N���y�ɋ����������Ă��ꂽ�l���������B����͑f���炵�����ʂł��v�Ɣԑg�`���Řb����܂����B����͂ЂƂ��ɁA�t�����搶�̒m���x�Ɖ��t�҂Ƃ��Ă̑f�{�A�����čI�݂Șb�p�̎����ł��B�����w�E�����̂́A�Ԃɋ��ރG�s�\�[�h�̐^�U�ɂ��Ă����B����������������̂��ƁB����b����Ȃ���ł��B
�@�t�����搶�́A�u��l�̋x��CLUB�v�iJR���s�j�ɂ��ƁA9���ɑS���R���T�[�g�E�c�A�[���X�^�[�g������R�B�R���T�[�g�O�ɂ͉��߂��̏��X�X�Œn���̐l�X�ƐG�ꍇ�����̉f�������̓��̃R���T�[�g�ŗ����B�I������烁���o�[���X�^�b�t�ƕK���ł��グ����邻���ȁB�R�~���j�P�[�V���������R���T�[�g���̊�{������A����͂���ő�ȍs�ׁB
�@����ȖZ�������Ԃ�D���̂͑�ςƂ͎v���܂����A�u�`�̑O�ɂ́A���������m�F��Ƃ����Ăق����B����ς���蕥���āA�j�������߂Ȃ����Ăق����̂ł��B���n������̂ł�����A����ȂɎ��Ԃ͂�����Ȃ��Ǝv���܂��B���ꂪJiiji����̂��肢�ł��B
�@���̂܂܂ł́A���������̊�悪�ܑ̂Ȃ��B�N���V�b�N���y���D�҂������Ƃ����Ƒ��₵�Ă䂫�����ł���ˁB�搶�̍���̐��i�Ƃ������ɂ��F��\���グ�܂��B
2014.07.25 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g �ԊO�ҁ`�o���I�@���d�F�̂Ƃ�ł��Ȃ��_�]
 �@Ray�����A����ɂ��́B1�����Ԃ�W�t���I����āA���̂Ƃ�������Jiiji�͗��������Ă����B����́u�N�����m�v�̍\�z�Ȃ����Ȃ���ˁB�Ƃ��낪7��19���t�u�����V���v�ɘ@���d�F�Ȃ���̂Ƃ�ł��Ȃ��uW�t�_�v�i�C���^�r���[�`���̕]�_�j���f�ڂ��ꂽ�B�肵�āuW�t�̌��E�v�B�ǂݏo���ƁA�����A���������Ă��傤���Ȃ��B�����t�����Ă����B�ł�����ȉ���Ȃ����m�ɌW���Ă��Ă��n�܂�Ȃ��B��_���I�B�ݓI�B�ƑP�I�B�ォ��ڐ��̃g���`���J���_�B�����疳������Ɍ���E�E�E�E�E�Ǝv���Ă������A�ǂ����Ă��C���������܂�Ȃ��B2011�N�Ȃł���W�t�D���̎��Ƃ܂����������������̂��i�u�N�����m�v2011.7.31�����Q�Ƃ��������j�B
�@Ray�����A����ɂ��́B1�����Ԃ�W�t���I����āA���̂Ƃ�������Jiiji�͗��������Ă����B����́u�N�����m�v�̍\�z�Ȃ����Ȃ���ˁB�Ƃ��낪7��19���t�u�����V���v�ɘ@���d�F�Ȃ���̂Ƃ�ł��Ȃ��uW�t�_�v�i�C���^�r���[�`���̕]�_�j���f�ڂ��ꂽ�B�肵�āuW�t�̌��E�v�B�ǂݏo���ƁA�����A���������Ă��傤���Ȃ��B�����t�����Ă����B�ł�����ȉ���Ȃ����m�ɌW���Ă��Ă��n�܂�Ȃ��B��_���I�B�ݓI�B�ƑP�I�B�ォ��ڐ��̃g���`���J���_�B�����疳������Ɍ���E�E�E�E�E�Ǝv���Ă������A�ǂ����Ă��C���������܂�Ȃ��B2011�N�Ȃł���W�t�D���̎��Ƃ܂����������������̂��i�u�N�����m�v2011.7.31�����Q�Ƃ��������j�B�@�Ȃ̂ŁA�Ō�ɏ������Ă������������B�Ȃ�ׂ��A�Ȃł����̎��̂悤�ɗ�ÂɁB�ł��A���肪���܂�ɂ���_���I������A����ނ��o���ɂȂ����Ⴄ�����H
�@�܂��@�����̂��ӌ������̂܂܋L�ڂ��A���ɂ���ɑ���Jiiji�̔��_�������B����Ȍ`�Ői�߂����B[�@��]�͘@�����̂��ӌ��B[Jiiji]��Jiiji�̔��_�ł��B
[�@��]
�@�O��2010�N��A�t���JW�t�ŁA���{��\�̉��c���j�ē͑��O�A�O��I�ɖh����d�������u�����Ȃ��T�b�J�[�v�֓D��I�ɕ��j�]�����܂����B�m���ɂ����1�����[�O�͓˔j�ł��܂������A�u1�_�ł��D�����v�Ƃ����T�b�J�[�{���̐��_����́A�قlj����R���Z�v�g�������B
[Jiiji]
�@���Ȃ��́A��i�ŁA�u���W����7�|1�ŏ������h�C�c���u7�_������Ă��܂��āA����̓T�b�J�[�ł͂Ȃ��v�Ɣᔻ���Ă��܂��B�ł��A�u1�_�ł��D�����v�Ƃ����̂��T�b�J�[�{���̐��_�Ƃ��������̂Ȃ�A���̎����̃h�C�c�����A�M���̃R���Z�v�g�ɍł����v�����킢���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ɗ�����Ƃ͂��̂��Ƃł��ˁB
[�@��]
�@�T�b�J�[�͂ǂ��炩���h��ɓO����ƃQ�[�����̂��������Ȃ��Ȃ�B���{�\�M���V����͂��̓T�^�ł��B�^���̉�����������Ă܂ŁA�������҂��鏟���ɂ������B����ȁu�X�|�[�c�̎��v�ɂ͕t�����������Ȃ��BW�t�͂��낻����E���A�Ƃ��Â��v���܂����B
[Jiiji]
�@�Ȃ�ł����A���̔ߊϘ_�́B���{�|�M���V����́u�X�|�[�c�̎��v�ł���uW�t�̌��E�v���Ƃ��������B�@�����͂Ȃ��u���{�̋��Ƀ��X�����A����̂���������v�Ƃ��������ɂ����Ȃ��̂�����B���ɔݓI�B
�@�M���V���͓��{��̑O���AFW�̃~�g���O���̕����ޏ�Ō��J�[�h���g���A�i����Ӗ��j�U��̗v�̃J�c���j�X�����b�h�J�[�h�ꔭ�ޏ�Ŏ����Ƃ�����s���`�Ɍ�����ꂽ�̂ł��B�����Ŏ������킪�A�u��肫���Ĉ��������Ɏ������ށv�������B�ǂ̃`�[���ł���������ł��傤�B���ꂪ�ǂ����āu�^���̉�����������Ă܂ŁA�������҂��鏟���ɂ������v���ƂɂȂ�̂��B�u�^���̉����v���苁�߂Ă�����A�Q�[���ɂȂ�܂����B
�@�M���V���͎����ӓ|�̃`�[���ł͂Ȃ��u���瑬�U�v�^�ł��B1�����[�O�ŏI�R�[�g�W�{���[����̏����͂��̏B�����āA�����̊��҂ɉ��������Ɍ����g�[�i�����g�i�o���ʂ������B����̂ǂ��������̂��Ȃ��BJiiji�͗����ɋꂵ�݂܂��B�u�Q�[�����̂��������Ȃ��v�uW�t�͂��낻����E�v�u�X�|�[�c�̎��ɂ͕t�����������Ȃ��v�ł����āH �t�����������Ȃ��͎̂��̂ق��ł���B���Ȃ��Ƃ����ƑP�I�l�ԂƁB
[�@��]
�@����w�����Ƃǂ��������L�����o�Ă��܂��B���̈�Ⴊ�R�����r�A�̑I�肪�u���W���̃l�C�}�[���̔w���ɂЂ������B���܂�������ʂł��B�̈ӂ��ǂ����Ƃ������ł͂Ȃ��A���̂��߂Ɏ��ɂ��̂��邢�Ńv���[����Ƃ����������Ƃ��N���Ă��܂��B
[Jiiji]
�@�u���̃v���[�͍���w����������N�����K�R�̏o�����v�Ƃ�������肽���̂ł��ˁB�m���ɃR�����r�A�ɂ͌����L�����j������܂��B1994�N�G�X�R�o���̔ߌ��ł��B�I��́A�u�w�}������ΎE���ꂿ�Ⴄ�v�Ǝv���ăv���[���Ă��邩������܂���B�Ȃ�A���̂悤�ȃv���[���N���Ă��܂��̂ł��傤���H �I���ԍۂ̂��̎��ԑтɋɓx�ȃ��t�v���[���o�Ă��܂������Ƃ��A�Ȃ��u����w�������v���ʂȂ̂��B�_���ɔ����߂��܂��B
�m�@���n
�@�u�ڕW�͗D���v�Ƃ����{�c�̔����̐^�ӂ͕�����܂��A�����u�����ł�����Ȃ������Ă��Ȃ��v�Ƃ����v�����������̂ł͂Ȃ����B�\�����\ �{�c���g���A�����ւ̂�����肪�����̏_���D���Ă����悤�ȋC�����܂��B
�mJiiji�n
�@�{�c�\�S�̐^�ӂł����B����́A�ނ̂���܂ł̃T�b�J�[�l�����ڂ݂�Ζ����Ȃ��ƁB�˔\�̂Ȃ���������ɍs�����߂ɂ́A�ǂ��炢�ڕW���������āA�l�̉��{���̓w�͂�����B�ނ͂�������Ď�������߃T�b�J�[�l�������ł����B�����Đ��ɍ��N�A���w���̂Ƃ��ɕ`�����u�Z���GA��10�Ԃ�����v�Ƃ����������������B�����������Ƃł��B
�@�ނ������Ŗ{���̒��q���o�Ȃ������̂́A�������������ꏊ�Ō��ʂ��o�Ă��Ȃ��ő����A����ɔ�������s���ɂ�鏟�����̌��@�A�a�C�ɂ��̒��s�ǂȂǂ��d�Ȃ��Ă̂��Ƃł��B�����āu����w�����ď����ɂ���������v���ʂł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A��A�t���J���ł́A�����C�����Ńv���[�����̂ɏ����������Ă��邶�Ⴀ��܂��B�Ȃ�A���Ȃ��̂�������颏����ւ̂�����肪�����̏_���D���Ă�������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B����́A�ނ̕s�������Ȃ��̃e�[�}�ɖ�����肱�����������̂��ƁB��_���I�ł��B
�m�@���n
�@�T�b�J�[�̖��͂́u�R�̂悤�Ɏv�������Ȃ����Ƃ��A�s�b�`�̏�ŋN����u�Ԃ�ڌ����邱�Ɓv�ł����A����𖡂��킹�Ă��ꂽ�̂́A�I�����_ �t�@���y���V�[�̃w�f�B���O�V���[�g�����ł����B������ł̃Q�b�c�F�̃V���[�g�͊m���Ɍ����ł������A����������ʂŋP���̂͐^�̃X�^�[�łȂ��Ă͂Ȃ炸�A�܂��A�X�^�[�\���R�̃Q�b�c�F�����߂Ă��A���������������邱�Ƃ��ł��܂���B
[Jiiji]
�@�u�t�@���y���V�[�̃w�f�B���O�V���[�g�����v�́g�����h�Ƃ��������Ɉ���������܂����A����͒u���Ă����܂��傤�B���̓Q�b�c�F�̂ق��ł��B
�@�v��u�V���[�g�����߂����Ǝ��̂͌����ł��A�Q�b�c�F���Ⴀ�܂�Ӗ����Ȃ��v�Ƃ������Ƃł����B�Ȃɂ���������ł��ˁB�h�C�c�Ȃ�N���[�[���~�����[�Ȃ�悩�����̂ł����H ������A�ނ���^�̃X�^�[����Ȃ��Ƃ���A�X�[�p�[�X�^�[�̃��b�V�����߂ăA���[���`�������Ă悩�����̂ł����B�u�v�������Ȃ����Ƃ��N���邱�Ƃ��T�b�J�[�̖��́v�Ƃ��������̂Ȃ�A�����̐V�l�����߂��ق�������ۂǁu�v�������Ȃ��v�Ǝv���܂����ˁB���������v�������Ȃ��j���[�t�F�C�X��T���̂�W�t�̊y���݂̈�Ȃ��ǂȂ��B����̃n���X�E���h���Q�X��2006�N���b�V�Ռ��̃f�r���[�ȂǁB
�@Jiiji�ɂ́A�Q�b�c�F�̃S�[���̓h�C�c�̋����̏ے��Ƃ��ď\�����͂�����̂ɉf��܂����B�o�����X�̂悢�`�[���̍ŔN���ɂ��Ď��ƂȂ����o�C�G�����E�~�����w���̑I��B�ē����_������đ��荞�Ō�̐�D�B����ȃQ�b�c�F��ے肵����h������D���ē�ے肷�邱�ƂɂȂ�܂���B�ق�Ƃ��̕��͂������Ȑl�ł��B
[�@���n
�@1���������𑱂��Ă�����̊ԂɕK�������ł�����߂ȑI�肪�o�Ă�����̂ł����A����͂�����s�݂ł����B�B��A�E���O�A�C�̃X�A���X�ɂ͈��̂��킢���������܂������A������߂Ƃ����邩�ǂ����B02�N�̓��ؑ��Ńu���W���̃��i�E�h���O�������O�p�`�ɂ���c������Ȕ��`�Ńv���[���A�D���g���t�B�[��������Ă��܂����B���������u�ςȐl��������߂����Ȃ��珟�v�Ƃ����y�������Ȃ��A�݂�Ȃ��K�v�ȏ�ɖ{�C�ɂȂ��Ă��܂����B
[Jiiji]
�@�u�X�A���X�ɂ��킢���v�ł����B���̊��ݕt���Ɂu���킢���v�˂��B�Ђǂ������B�R�����g����C���Ȃ��Ȃ郏�C�B�u���i�E�h�̔��^�v��������߂Ŋy���������āH ����A���b�x���Ɂg�����܂��h�ł��t��������C�����ނ̂��ˁB�^�ʖڂɂ��[�[�A�R�m�I�I
[�@��]
�@����Łu�������Ƃ��ꍏ�������Y�ꂽ���v�Ƃ����u�Ԃ��������܂����B���E�ō�GK�̈�l�A�X�y�C���̃J�V�����X�̓I�����_���5���_�����B�ނ�����Ȃ����ŕ���Ă��܂��A�Ƃ�����ʂ͌����Č������͂Ȃ������B
[Jiiji]
�@�������ɖڂ������܂����B�����Jiiji�Ƃ͈Ⴄ�Ȃ��B�J�V�����X�̎S�߂Ȏp�͌������Ȃ��Ƃ����͕̂����邯�ǁAJiiji�͂����������A������Q�Ăӂ��߂������t�@���y���V�[�ƃ��b�x���̕��ɖڂ������܂��B��l�̃S�[���͎��ɃG�L�T�C�e�B���O�ł����B���̐l������Ə��X������Ȃ����Ȃ��B�|�W�e�B�u����Ȃ��ł���B
[�@��]
�@�u���W����7���_���������́A�����T�b�J�[�ł͂Ȃ��B�h�C�c��7�_������Ă��܂������Ƃ͉ʂ����Đ����Ȃ̂��B�������A���������Ƃ����_�ł͐����Ȃ̂ł����A�u�T�b�J�[���T�b�J�[�ł͂Ȃ����̂ɂ��Ă��܂����v�Ƃ����_�ɂ����ẮA�X�����s�������Ƃ����v���܂���B�N�����h�C�c��\�̐��_���͂����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�ǂ��܂œ_������̂��A�ʔ����������Ă݂悤�A�Ƃ������炢�̋C�����ɂȂ��Ă����Ǝv���̂ł����A�ǂ����Ă�7�_������Ă͂����Ȃ��B���������邵�A�l�̓�����O��Ă���Ƃ����v���Ȃ��B
[Jiiji]
�@������Jiiji�Ƃ͈Ⴄ�B�@�����́A�h�C�c�̍U�����A�u�����~�߂Ă���v�ƍ��肷�閳��R�̑���ɂ���ł����Ǝ��X�ɐ��ق������郊���`�̂悤�ȍs�ׁA�ƍl���Ă�����悤�ł��B�u�l�̓�����͊O��Ă���v�Ƃ��������̂ł�����B��������͒f���ĈႢ�܂��I�I
�@�h�C�c�����鎞�_�܂ōU���̎���ɂ߂Ȃ������̂́A�T�b�J�[�̕|����m���Ă��邩��B�u���W���̕|����m���Ă��邩��Ȃ̂ł��B3�_�����炢���Ⴂ�Ђ�����Ԃ���邩������Ȃ��ƁB���Ȃ��́u�����I����Ă���������ɂ߂�ׂ��ł���v�Ƃ�������肽���̂ł��傤���A���������Ã`���������́A�I��̋C������m��Ȃ��l�̃Z���t�ł��B�X�|�[�c�������̂ɂƂ��čő�̋��J�́A�@���̂߂���邱�Ƃł͂Ȃ��A����Ɏ��������邱�Ƃ�����ł��B
�@������̗��R������܂��B��\�I��ɂƂ���W�t�́A�A�s�[���̂��߂̍ō��̕���ł�����܂��B���M�����[���肬��̑I��A�{���܂�������̂Ȃ��I��A�ނ�͍���̂��߂ɑS�͂Ńv���[����B������_�����ɍs���B�����ɂ͑I��Ƃ��Ă̎�����肪����B������u�l�̓��ɊO��Ă���v�ƕЕt�����Ⴂ����̂ł��B
�@����ɂ́A�����������ƁA�`�[���̒��q���̂����ۂɂ��������Ȃ����Ⴄ�B���Ԃ������Ȃ��Ȃ�B���ꂪ�Q�[���̏�ł��邱�Ƃ��A�ēE�I��݂͂Ȓm���Ă���B������₽��Ɏ�͔����Ȃ��B
�@�Ƃ͂����A�O���I�����5�_�̓Z�[�t�e�B�E���[�h�B�㔼�͖��炩�Ɏ���ɂ߂Ă��܂����B�_��������͓̂r���o��̃V�����������ł�������B���Ȃ��ɂ͂��̂�����̎���𗝉����Ăق��������B
�@�h�C�c���^���ɍU���𑱂����̂͑���������Ȃ��܂łɒ@���̂߂����������߂ł͂Ȃ��A���҃u���W���ւ̃��X�y�N�g�������B�u���W���ɂƂ��ẮA�����邱�Ƃ̕����^���ɍU���𑱂����邱�Ƃ������J�������̂ł��B�����̖{���������Ă��܂���ˁB
[�@��]
�@���͍����W�t�ł́A��\���N�Ԃ�ɐS���牞������`�[��������܂����B�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i��\�ł��B1914�N�ɓ����̎�s�T���G�{�ŋN�����I�[�X�g���A�c���q�ÎE�������A��1�����E���̈������ɂȂ����B���ꂩ��100�N�A20�N�߂��O�܂ŎE�������Ă����O�̖������A�I�V���̐s�͂ň�̃`�[�������AW�t�ɎQ�������B����͂����������邵���Ȃ��B�|�����|�C������ŏ����������Ƃ��͂܂��Ɂu�I�V�����T�b�J�[�v�Ƃ��������̖������ɂ��ӂꂽ�킢�Ԃ�ŁA���̉X�����ɂ܂����܂��܂����B���̍ɂȂ��Đ^�钆�ɂȂɂ�����Ă���̂��낤�A�Ƃ��v���܂������B����͎��l�ł͂Ȃ��A�l�ނ̖��Ȃ̂ł��B�T���G�{��������100�N�ł���I�������痈�Ă����\�������Η������z���AW�t�ŏ����������B���̊�Ղ��A���{�ƊW�̐[���I�V�����������������Ƃ��A�S����j�����ׂ��Ȃ̂ł��B
[Jiiji]
�@���̒i�AJiiji�͑S�ʓI���ł͂���܂���B20�N���̕��������z���ĎO�̖�������ɂȂ��đ�\�𑗂荞��W�t�ɏ����������B���������{�ɓ���ݐ[���I�V���̐s�͂ɂ���āB�����Jiiji���f���ɏj�����܂��B�������A�@�����̂͂���������U���ɉ߂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B1914�N�̃T���G�{��������x�܂ł����p����Ă��܂����A�ʂ����Ă��̎����A�ߔN�̖��������ƒ��ڂ̂Ȃ��肪����̂�����H
�@�����͐푈�E������_�����ł͂Ȃ��̂ŁA�v�����ăU�N�b�ƌ����Ă��܂��܂����A�u�T���G�{���������������ɋN������1�����E���́A���ė̒鍑��`�I�v�f���A�����g�咷�������Ă�������K�͐푈�B�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i�����́A�\�A��́����Y��`�ޒ��̗���̒��ŋN���������[�S�[�X���r�A����ɔ��������Ԃ̕����v�ł��B���҂̊Ԃɒ��ړI�Ȃ���͂Ȃ��B�������������ɂ��Ă��o�����̖{���͂܂�ňႤ�B��������������A100�N�O�̎������ߔN�̕����Ɋ֘A���邪���Ƃ��̕\���́A�����ɂ��B���B�܂₩�����@�B����100�N�Ƃ����������A���Ɋ֘A�t�����������߂̕M�҂̈Ӑ}�I�ȉ�����Jiiji�͔��f���Ă���܂����B
�@�Ƃ͂����A�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i�E�`�[���̐킢�ɐ[��܂���͎̂��R�ł��B�ł́A������ɁA�R�[�g�W�{���[���̐킢�Ԃ�͂ǂ��Ȃ̂��B�ނ�́A����������������AW�t�Ŋ撣�邱�Ƃɂ���Ē��߂悤�Ƃ����B�h���O�o�̑i�������͐��E���̐l�X���m���Ă��܂��B�܂��A�O�q�M���V����\�́A�܂��܂��������Ɨ��ɂ������������A����s��Ƃ����R���Ղ����甇���オ�茈��T�ɐi�o���邱�ƂŌە����悤�Ƃ����B�@������A�����T���G�{�̒n�Ɏv����y����̂Ȃ�A�A�t���J��M���V���ɂ��v�����Ă���������B
�@���̃C���^�r���[�̕���ɂ́u���̊��Ҕw�����ƃQ�[���̖��͎��� �܂��߂��������{�v�Ƃ���܂��B����������Ɓu���̊��҂�w����Ȃ���Q�[���̖��͂����傷�� �s�^�ʖڂɂ��ׂ����������{�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����BJiiji�͂��₾�ȁB����w����Ȃ�W�t�Ȃ�āB����w�����Đ^�ʖڂɂ�邩��W�t�͖ʔ����̂��B���̃v���b�V���[��w�����Ċ撣�邩��A�����ɂ��M�������Ȃ��̂��Ȃ��B������@�����Ƃ͍��{�I�ɈႤ�Ƃ������Ƃł��B
�@��O�����T�b�J�[�����ꍇ�A�T�b�J�[�ɑ��Đ[������ƌ������������Ă�����ׂ��ł��B���̏�ɐ��I�m��������ΐ\�����Ȃ��̂ł����A���ꂪ�Ȃ��Ƃ��X�|�[�c�̖{�����炢�͗������Ă��Ăق����B�c�O�Ȃ���@���d�F���ɂ͂��ׂĂ��Ȃ��B�Ȃ�A�����T�b�J�[�ɑ��Č��ׂ��ł͂���܂���B
�@�Ȃł����̎��������������̂ł����A���̕��̌��ɂ́A�u���͈�ʐl�Ƃ͈Ⴄ���_�������Ă���B���肪�����q�����ׂ��v�Ƃ�������̂悤�Ȃ��̂��������܂��B�Ƃ��낪���ꂪ���ׂĂɓI�O��A�g���`���J�����r�������B����͂��͂∣���ʂ�z���Ċ��m�̈�Ȃ̂ł����A�{�l�A����ɂ͂܂������C�Â��Ă��Ȃ��B�@�����̔ߌ������ɂ���ł��ˁB
�@�Ō�ɒ����V���ɂ��ꌾ�B2011�N�Ȃł����W���p����W�t�D���̂Ƃ����A�@�����̕]�_���f�ڂ��Ă��܂��ˁB��ǂ���A�ނ̘_�]�������ɒ���̑㕨��������͂��B��V���̋M�ЂȂ�B���̌����Ȃ��A�����Ă����m�����A������������t�������āA�����{���ɔ���Ȃ��ŁA��������X�ƌf�ڂ���Ƃ́A�V���ЂƂ��Ă̗ǎ����^�킴��܂���B���t�Ƃ������̂́A��������o���Ŕ��f�����ׂ��ł͂Ȃ��̂ł��B�ҏȂ𑣂������B �Ō�ɋL���Ɍf�ڂ���Ă���@�����̗������L���āA�����̒��߂Ƃ����Ă��������܂��B�����ǂ��肪�Ƃ��������܂����B
�@���d�F�F1936�N���܂�B������w�����A���{�w�����A�������C�B�����u�{���@���[�v�l�_�v�u�\�w��]�錾�v�u�X�|�[�c��]�錾�v�ȂǑ����B
2014.07.20 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g6 �` �h�C�c�D���Ƒ���
�@����[Ray�����AW�t�����ɏI������ˁBJiiji�͂����܂ł������茩���̂͏��߂Ă���������A��P���͂����Ƃ����Ԃ�������B�e�ʂ�TOTO��������̂�������Y�����ˁB�h�C�c�D����I�������̂�K�����B�ނ̓T�b�J�[���m�AJiiji�̎t�����B�Ȃ��TOTO��1998�t�����X����ܘA�e�Ƃ������琦���B����ȕ]�_�Ƃ͈�l��������B�������BJiiji�������͓��Ă������ǁA����|���g�K���ɓq���Ă���悤���ᖳ�����B�������Ɍ������X�����悤�B�ł́A�����Ƃ����܂��傤�B���h�C�c�D���A���̋����̔閧��
 �@������́A�h�C�c��1�|0�ŃA���[���`�����~���A24�N�Ԃ�4�x�ڂ̗D�����������B�Ɠ����ɁA��ĊJ�ÂŃ��[���b�p�͏��ĂȂ��Ƃ����W���N�X�������߂Ĕj�����B
�@������́A�h�C�c��1�|0�ŃA���[���`�����~���A24�N�Ԃ�4�x�ڂ̗D�����������B�Ɠ����ɁA��ĊJ�ÂŃ��[���b�p�͏��ĂȂ��Ƃ����W���N�X�������߂Ĕj�����B�@�S7�����A6��0�s1���A���_18�A���_4�A�����_����0�A�����_����4�B����ɓ��M���ׂ��́A�搧���ꂽ��������������������ƁB�ǂ�������W�J���Ȃ�����A�}�C�y�[�X�Ŏ������^�ׂ�B�������Ǝv���A�u���W����7�|1�ŕ��ӂ��锚���͂�����B���芴�Ɣ����͂����ɂ��Ĉ��|�I�ȋ����𐢊E�Ɏ������B���̋����͈�̂ǂ����痈��̂��낤���H
 �@�����̃A���[���`����A�����_�̃V�[����U��Ԃ��Ă݂悤�B�����㔼8���B�{�A�e���O�iCB�j���獶�T�C�h�̃N���|�X�iMF�j�ցB�N���|�X�̓V�������iFW�j�ɁB�V�������̓h���u���Ői�ݑ���f�B�t�F���_�[�������t����B�E�O���ɃX�y�[�X���ł���B�����ŁA�������Ă����Q�b�c�F�iFW�j���X���X���Ǝ߂ɑ��肱�݃S�[���O�ɁB�����ɃV����������̃N���X���h���s�V���̃^�C�~���O�œ���B�Q�b�c�F�͋��Ńg���b�v���������V���[�g�B�h�C�c�D�������߂�S�[���ƂȂ����B
�@�����̃A���[���`����A�����_�̃V�[����U��Ԃ��Ă݂悤�B�����㔼8���B�{�A�e���O�iCB�j���獶�T�C�h�̃N���|�X�iMF�j�ցB�N���|�X�̓V�������iFW�j�ɁB�V�������̓h���u���Ői�ݑ���f�B�t�F���_�[�������t����B�E�O���ɃX�y�[�X���ł���B�����ŁA�������Ă����Q�b�c�F�iFW�j���X���X���Ǝ߂ɑ��肱�݃S�[���O�ɁB�����ɃV����������̃N���X���h���s�V���̃^�C�~���O�œ���B�Q�b�c�F�͋��Ńg���b�v���������V���[�g�B�h�C�c�D�������߂�S�[���ƂȂ����B�@�{�A�e���O�|�N���[�X�|�V�������|�Q�b�c�F�B���̖��O�߂Ă��āu����H�v�Ǝv�����B�o�C�G�����E�~�����w���̑I����肶��Ȃ����i�V�������������āj�B�T�b�J�[�ʂȂ瑦���ɋC�Â��������AJiiji�Ƃ�����܂Ƃ��Ɍ��������͖̂{����Ƃ����₩�t�@���B����Ɗ��Â����������ɁA�h�C�c��\�S���̏����N���u�ׂĂ݂��B
�@���ʁA�m�C�A�[�i(GK) �A�{�A�e���O(CB)�A���[��(SB)�A�V���o�C���V���^�C�K�[�iMF�j�A�N���[�X(MF)�A�~�����[(FW)�A�Q�b�c�F(FW)�A�Ȃ��7�l���o�C�G�����E�~�����w���̑I�肾�����I�I
�@�L�[�p�[����t�H���[�h�܂ŁA�v���v�����N���u�̃����o�[����߂Ă���B����N���u���[�g�Ƃ��Đ���Ă���l�����B���������̃N���u�́AUEFA�`�����s�I���Y���[�O�e�ҁi2012�^13�V�[�Y���j�Ƃ��������B�A�g�����x���k���Ȃ̂��ނׂȂ邩�Ȃ��B
�@W�t�͊W�߃`�[�����m�̐킢���B�I��͕��i�ʁX�̃N���u�Ŋ������Ă���B��\�Ƃ��Ă̗��K�⋭�������͂��̍��Ԃ�D���čs����B�`�[���Ƃ��Ċ�����鎞�Ԃ͂ƂĂ����Ȃ��B������A�T�˂ǂ̃`�[�����A�g�̕s��������Ă���B
�@�T�b�J�[�̓X�y�[�X�ƃ^�C�~���O�𑀂�A�g�̃Q�[�����B�_����邽�߂ɁA�X�y�[�X�Ƀ^�C�~���O�悭�p�X�𑗂�o���A�����ɔ�э��ʂ̑I�肪�t���[�̏�ԂŃV���[�g����B����������ʂ������ɑ�����肾���邩�������̕�����ڂ��B�A�g�̃Q�[������R���ł���B
�@���R�A����N���u�̑I�肪�����`�[���قǘA�g�x�͍����B���ꂪ�h�C�c�B�����A�h�C�c�́A�`�[����Ґ��������_�ŁA�A�g�x�ɂ����āA���ɑ��̃i�V���i���E�`�[���̏�ɂ���B���`�[�����A�g���̂��̂ɕ��S���Ă���Ƃ��A�h�C�c�͂���ɖ����������Ă���B���X���鍷������ɑ�Ȃ��̂ɂȂ�B�h�C�c�����̔閧�B���̈�[�͂����ɂ���B
 �@���[���ḗA�o�C�G�����̑I������Ƀ`�[�������グ���B�������܂��Ă��邩���Ƃ̓V���v���B���łȎ��ɃX�p�C�X��U��|��������B���ʁA���ׂĂɃo�����X�̂����`�[�����o���オ�����B
�@���[���ḗA�o�C�G�����̑I������Ƀ`�[�������グ���B�������܂��Ă��邩���Ƃ̓V���v���B���łȎ��ɃX�p�C�X��U��|��������B���ʁA���ׂĂɃo�����X�̂����`�[�����o���オ�����B�@������ɏo�ꂵ���I��14���̔N��z�́A20��O����5�A�㔼��7�A30�オ2�A���ϔN���26.4�B���݂ɁA�ŔN���͖{���ŗ��ō�16���_���}�[�N����36�̃N���[�[�A�ŔN���͌�����ŗD�������߂链�_���������o����22�̃Q�b�c�F���B
�@���A�q���E���[�����w��������悤�ɂȂ���10�N�B�h�C�c�͍��������ċ����`�[������簐i���Ă����B�u���f�X���[�K�̏[���A���琬�̉��v�A������`�̔r���ȂǁA�����Ȃ邽�߂̘J�����Ƃ�Ȃ������B����̗D���͂��̎����ł���B
�@����ɁA�h�C�c�̐����Ƃ���́A�����_�_�Ɏ~�߂��ɁA�`�����E���x�����V�X�e���Ƃ��Ċm���������Ƃɂ���i�Ⴆ�Ύ��琬�@�ւ̕t�݂����[�O�����̏����Ƃ���Ȃǁj�B������A���̗���͈�ߐ��ł͂Ȃ��B�h�C�c�E�T�b�J�[�̗D�ʂ͓����h�炮���Ƃ͂Ȃ����낤�B���{�T�b�J�[�w�Ԃׂ��ł���B
���u�`�[���E���b�V��Ƃ����`�[����
�@�A���[���`���́u�`�[���E���b�V�v�Ƃ������̃`�[���������ėՂB�킢�Ԃ�͎��Ɋ�B���b�V�́A�{�[�����߂���ʂ肷���Ă��ǂ킸�ɃX�^�X�^�����Ă���B�`�����X�ŃA�N�Z���������邽�߂̃X�^�~�i�����B�f�B�t�F���X�w�͑哶�B�ł����b�V�͓_���l�邩�炻��ł����B�O���[�v���[�O�ł�4�_����Ă���B
�@�Ƃ��낪�A�����g�[�i�����g�ɓ���△���_�B�m���ɑ����f�B�}���A�̌���͒ɂ��������B�䂪�tK�����́u�A���[���`�����D�����邽�߂ɂ́A���b�V���O�������点�邩�����Ȃ��v�ƌ������O�Ɍ���Ă����B�Ȃ�Ƒ�_�Ȕ����Ǝv�������A�I����Ă݂�Ƃ��̈Ӗ����悭��������B�_�����Ȃ��̂Ȃ�A�{�[����ǂ�������I�����ꂽ�ق����������̂ˁB�A���[���`���͏��D���B���b�V��MVP�ɁB�u����H�v�Ǝv�����̂�Jiiji����������B��͂�A�A���[���`���͊�`�������B�I�V�����u���̂̓h�C�c�ł���ׂ����v�ƌ�����C�����͂悭�킩��B
�@�Ō�Ɉꌾ�B�������I�����_��㔼46���A���b�x���̌���I�V�[����j�~�����}�X�P���[�m�̃v���C�ɖ{���̃x�X�g�E�Z�C�r���O�܂��B
��GK�͑�L�쁄
 �@�O�ɂ����������ǁA���̑��̓S�[���L�[�p�[�̑�L��B�ō���́u�x�X�g�E�S�[���L�[�p�[�v�ɋP�����h�C�c�̃m�C�A�[�ň٘_�̂Ȃ��Ƃ��낾�낤���A���̂ق��ɂ����m�ρX�A��ۂɎc����GK�͐��������B
�@�O�ɂ����������ǁA���̑��̓S�[���L�[�p�[�̑�L��B�ō���́u�x�X�g�E�S�[���L�[�p�[�v�ɋP�����h�C�c�̃m�C�A�[�ň٘_�̂Ȃ��Ƃ��낾�낤���A���̂ق��ɂ����m�ρX�A��ۂɎc����GK�͐��������B�@�u���W����Ńt�@�C���Z�[�u��A�����`�[���������g�[�i�����g�ɓ��������L�V�R�̃I�`�����BPK�퍰�̃Z�[�u�Ń`���Ƃ̎����ɏI�~����ł����u���W���̃W�����I�E�Z�U�[���B�R�X�^���J�Ƃ�PK��Ńs���`GK�ɋN�p�����p�ƃt�@���n�[���̊��҂ɉ������I�����_�̃N�����B���̃I�����_�Ƃ�PK��łQ�Z�[�u���ʂ����������Ăэ��A���[���`���̃������B���邷����������Ǝd���͂���i�C�W�F���A�̃G�j���A�}�B�݂�Ȍ��h�̎d���l�������B
���Ԃ̃A���_�[23�g���I��
 �@��q�����Ƃ���A�h�C�c�̗D���S�[�������߂��̂�22�̃}���I�E�Q�b�c�F�������B����͑��171���_�ڂ̃������A���E�S�[���B1998�t�����X����u�o��32�`�[���A�S������64�v�Ƃ������s�����ɂȂ������A171���_�͂��̂Ƃ��̃t�����X���ƃ^�C�L�^���B�㔼43���A���[���ē��u���������߂铭���̂ł���I��v�Ƃ��đ��荞�h�C�c��22�́A�������҂ɉ����Ă��ꂽ�B
�@��q�����Ƃ���A�h�C�c�̗D���S�[�������߂��̂�22�̃}���I�E�Q�b�c�F�������B����͑��171���_�ڂ̃������A���E�S�[���B1998�t�����X����u�o��32�`�[���A�S������64�v�Ƃ������s�����ɂȂ������A171���_�͂��̂Ƃ��̃t�����X���ƃ^�C�L�^���B�㔼43���A���[���ē��u���������߂铭���̂ł���I��v�Ƃ��đ��荞�h�C�c��22�́A�������҂ɉ����Ă��ꂽ�B�@�l�C�}�[���͏��X�����ŏd�����A�ނ�W�t�͂����ŏI������B�l�C�}�[�����������u���W���E�`�[���͏������Ńh�C�c�ɗ��j�I��s���i�����B�J��O����D�����������ߊ撣�葱����22�̎�҂ɂƂ��āA���ɖ��O�Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂����B�ł��A�ނ̃��[���h�J�b�v�͎n�܂�������B���V�A�`�J�^�[���ŋP�����Ƃ�Jiiji�͐ɋF��܂��B

�@�{���ł����ڂ𗁂т�20��́A�R�����r�A�̃n���X�E���h���Q�X�i23�j���낤�B6�S�[�������������P�Ƃ̓��_���ɋP�����B�E���O�A�C��Ō������{���[�E�V���[�g�́A���ꂼ�X�[�p�[�S�[���Ƃ��������B�m���ȋZ�p�Əu���̏��f�Ǝv����̂悳�I �t�@���y���V�[�̃X�y�C���퓯�_�S�[���Ƌ��ɖ{���̃x�X�g�E�S�[����Jiiji�͔F�肷��B
���킢����ł����͕��Ȃ���
�@�����Ŋ����グ���n���X�E���h���Q�X�́A�g���[�h�}�l�[112���~�������ă��A���E�}�h���[�h�ɈڐЂ���͗l���B�N���X�e�B�A�[�m���n���X�̃��A�����b�V���l�C�}�[���̃o���T�Ƃ̉��������́A�����烏�N���N����ˁB
�@�J����̎�R�߂������Y�ꎁ���b��ɁB�����ʼn�����PK�W���b�W�́u����������v�Ƃ̃R�����g���G�w���炠�����B�ᔻ�����ꂽ�����̌�̃W���b�W���ɂ��Ȃ�H �����ɂ�邯�ǁA�t�@�E���̉��s�ڂɗ]��B�Ȃ�Ƃ��Ȃ�A���ɃR�[�i�[�L�b�N���̈������荇���B������Ȃ��Ȃ�@�B�̓����l���āB
�@�I�����_��\�ē̃t�@���n�[���́A�C���O�����h�̃}���`�F�X�^�[�E���i�C�e�B�b�h�ւ̏A�C�����܂��Ă���B����^�i�͎g���Ă��炦�邾�낤���B
�@�Z���b�\���̊`�J�j��Y�́A�V�V�n�����߂ăX�C�X�ɗ��������B�傫���Ȃ��Ė߂��Ă���邩�Ȃ��B
�@�U�b�N���U���̐�D�Ƃ��ēo�p�������t�����^�[���̑�v�ۉÐl�́A�s�o�ɂ�����������������������B�Ȃɂ���Ƃ�Ⴂ�I
�@�u���W���D����\�z�����]�_�Ƃ̊F�l���i�h�C�c��O���ł��A�܂����M�������ď����Ă����l�����j�A�Z���W�I�z���M���ɁA�����X�A�k�V�A�s���A���A���c�A�����A���q�A�{�V�~�V�F���̖ʁX�B��̂�����������Ă����Ⴂ�B�ȂɁHJiiji�����ƁB���V�͗\�z�͂��Ƃ��A����������������B
�@���{�T�b�J�[����́A���̑����������ɐV�ē����߂�������݂������B����ǂ���v�����ȁI
�@�ߊ삱�������AW�t�u���W�����͏I������B�Q�����i�ƒn��j��203�B�Ȃ�ƍ��A������193��葽���̂��B�D�����������A�������]�ƌ��������āA����͂��͂�~�߂��Ȃ����E���ہBJiiji�́A����܂Ƃ��Ɍ���悤�ɂȂ����̂ŁA���ꂩ��܂��܂��y���݂ɂȂ����B���Ɖ����邩�Ȃ��B�܂��́A4�N�ネ�V�A�ʼn�܂��傤�B
2014.07.13 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g5 �` �Ō�ɒ]�t�@���n�[���єz
�@������Ray�����A��ق�3�ʌ���킪�I�������B3�|0�ŃI�����_�����B��͂�u���W���͑h���Ă��Ȃ������B����ፓ����ȁA���̗��j�I��s�̂��ƒ��O���ŗ�������Ƃ����̂́B�����Ȃ��́A�V�ē̉��A�l�C�}�[���A�I�X�J������𒆐S�ɃX�b�L���ƍďo�����邵���Ȃ��ȁB�@�I�����_�̃G�[�X ���b�x���́A������̃C���^�r���[�Łu���͋���ہB��邾��������B����3�ʂ͌ւ�Ɏv���v�Ƃ��Ȃ�����A���O�ɁA�����ɂ����Ȃ��������������ɂ��ݏo�Ă�����B
�@�I�����_�͂Ȃ������ɐi�߂Ȃ��������B�Ȃ��A���[���`���ɕ����Ă��܂����̂��H ������PK�킾���������ɔs����˂��Ƃ߂�͓̂���B�ł��A�����͑f�l�I�u�N�����m�v���_�ŒT���Ă݂悤�B���͉����O�����ē�����3���ڂ̃J�[�h�ɂ���A��Jiiji�͌����B
���I�����_�Ō�̃J�[�h�̓t���e���[����
 �@�����O��6���A�I�����_ �t�@���n�[���ē͍Ō�̃J�[�h������B���X�����R�X�^���J��ł́APK��̂��߂�GK��ウ��Ƃ���W�t�j��ނ����Ȃ����ɏo�Č������������ނ���������A�������ځi0�|0�j�̂��̏�ʁAJiiji�͓��R���̍�ɏo����̂Ǝv���Ă����B
�@�����O��6���A�I�����_ �t�@���n�[���ē͍Ō�̃J�[�h������B���X�����R�X�^���J��ł́APK��̂��߂�GK��ウ��Ƃ���W�t�j��ނ����Ȃ����ɏo�Č������������ނ���������A�������ځi0�|0�j�̂��̏�ʁAJiiji�͓��R���̍�ɏo����̂Ǝv���Ă����B�@�Ƃ��낪�A�t�@���n�[���͕ʂ̃J�[�h������B�t�@���y���V�[�ɑウ�ăt���e���[�������������BJiiji�͐����u������v�Ǝv������B����͑O�q�����Ƃ���A�Q�[���̐��ڂ��R�X�^���J��ƍ������Ă������炾�B�������A�R�X�^���J��́A�X�i�C�f����2�{�̃V���[�g��������Ƃ���������PK���҂����ɏ����Ă����Ǝv����A����ȃI�����_���|�I�D���̃Q�[���B���ʁA�ډ��̃A���[���`����́A�}�X�P���[�m�ɑ�\�����悤�ȁA���ۂ̋����A���[���`���̃f�B�t�F���X�Ɏ���Ă��A������͂邩�Ƀ`�����X�̏��Ȃ��Q�[���������B
�@�w�����Ƃ��āAPK���z�肷��̂͂ނ���A���[���`����̕��Ȃ̂ɁB�u����H�v�Ǝv�������R�͂����ɂ���B
�@�Ƃ͂�������܂ŁA������������Q�[���̗����ǂ݁A�I�m���̂��̂̎��ł��Ă����t�@���n�[���єz�ł���B����Ȕނ̌��f������K������������͂����Ƃ��v�����B����́A�uGK���v�����Ȃ��̂�����APK��ȑO�ł̌�����]�Ƃ������ƁB�����ƒ[�I�Ɍ����uPK�����肽���Ȃ������v����ł͂Ȃ����B���̖ړI�̂��߂ɁA�t�@���y���V�[���t���e���[���̕����x�^�[�Ɠ���Ō�コ�����B�Ȃ�A�킢����ς��Ă���B�t���e���[���̍����������p���[�v���C�𑽗p����͂����ƁBJiiji�͂����ǂ�Ő��ڂ���������B�Ƃ��낪�A�Q�[�����e�ɂ͂܂������ω��������Ȃ������̂��B
�@PK��������ăt���e���[���𓊓������̂Ȃ�A�I�����_�͎��ɕ������œ_�����ɂ����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�ނ̍��������������p���[�v���C�荞�݂Ȃ���B�����łȂ��Ă͒��낪����Ȃ�
�@�Ƃ��낪�A�I�����_�͂���܂łǂ���̃Q�[���^�т𑱂����B����́A�܂�ŁAGK���̃J�[�h������R�X�^���J��̂悤�ȁA���₻��ȏ�Ɏ���I�Ȑ킢�Ԃ肾�����B ���̖����͂ȂI����܂ŁA�ł肷�ׂĂ������ł����t�@���n�[���єz���A���߂ĕs���ɉf�����u�Ԃ������B
���A���[���`���Ō�̃J�[�h�̓}�L�V�E���h���Q�X��
 �@�A���[���`���̃T�x�[���ḗA�틵�����Ȃ���Ȃ�ƂȂ���a���������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�����k���ȃt�@���n�[���єz���A�����͂ǂ������������B�����̋��ʂ��Ă��Ȃ��B������A�Ȃɂ��ɖ����Ă���H �͂����肵�Ă���̂�PK����������Ă��邱�ƁB�Ȃ�Ȃɂ��Ȃ�ł���������ł��B
�@�A���[���`���̃T�x�[���ḗA�틵�����Ȃ���Ȃ�ƂȂ���a���������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�����k���ȃt�@���n�[���єz���A�����͂ǂ������������B�����̋��ʂ��Ă��Ȃ��B������A�Ȃɂ��ɖ����Ă���H �͂����肵�Ă���̂�PK����������Ă��邱�ƁB�Ȃ�Ȃɂ��Ȃ�ł���������ł��B�@�����O��11���A�ނ������Ō�̃J�[�h�́A�}�L�V�E���h���Q�X�̓����������B�}�L�V�E���h���Q�X34�B3�x�ڂ̃��[���h�J�b�v�B�\�I�ł͐����Ȃ��o��Ȃ���3���_��������ȂǐM���ł���x�e�����E�A�^�b�J�[�ł���B
�@�Q�[���͐Â��ɗ���A����PK��ɓ˓����Ă������B
���^����PK�큄
�@��s�̓I�����_�B�t�@���n�[���ē�1�Ԏ�Ɏw�������̂̓t���[���������B�t�@���y���V�[���i���Łj���Ȃ�����Ƃ͂����A�����̓t���[���Ŗ{���ɂ悩�����̂��H�t���[���̓f�B�t�F���_�[�A�������R�X�^���J�Ƃ�PK��ł͏R���Ă��Ȃ��B�R�X�^���J��̃I�[�_�[�́A�t�@���y���V�[�`���b�x���`�X�i�C�f���`�J�C�g�B���ׂăx�e�����Ōł߂Ă����B
�@PK���1�Ԏ�̓v���b�V���[��������B�����̓��b�x���̌J�グ��������������Ȃ����ȁB�����A����l���I�[�_�[�����܂肢���肽���Ȃ������̂Ȃ�A�t���e���[���Ƃ�������������͂��B�ނ͑�ڐ�̃��L�V�R��ŋt�]��PK�S�[�������߂Ă���B�������A���̓��t�@���n�[���������Ō�̃J�[�h�̑I��B�єz�ɂ��K���B�Ă̒�i�H�j�t���[���͊O�����B
�@�A���[���`���̂P�Ԏ�̓L���v�e���̃��b�V�B��ǂ���̋N�p�B���������B���̂��ƃI�����_��3�Ԏ�̃X�i�C�f�����O���A4�\�܂ŃA���[���`��3�|2�ƃ��[�h�B4���ɃA���[���`�������߂�Ώ��������Ƃ����W�J�ƂȂ����B�A���[���`����4�Ԏ�̓}�L�V�E���h���Q�X�B�T�x�[���ē��Ō�ɐ����J�[�h�̑I�肾�����I ���h���Q�X�͗��������Č��߂��B�Q�[���̓A���[���`���̏����Ŗ�������B
�����єz�͂Ȃ��]����
�@�ǂ����������������t�@���n�[���єz�B�I����ƃQ�[�����̖����BPK��ɂ�����L�b�J�[�̐l�I�B����܂Ő����R�炳���k�����ŏ����i��ł��������ɂ������������N�������̂��낤���H
�@�����߂̐�p�ɓO���Ă����t�@���n�[���ēB�������̈���ŁA���Ȃ��炸�ᔻ���������悤���B���Ƃ��A2�|0�ŏ��������`�����̉�ŁA�u5�l���ŏI���C���ɓ����Ď�����ł߂��@�͂������Ȃ��̂��H�v�Ɩ₤�L�҂ɑ��u�t�ɌN�ɕ��������B�U���T�b�J�[�Ƃ͂ȂB���͏����߂ɂ���Ă���v�Ɛ����r����V�[�����������ƕ����B
�@�R�X�^���J��A���єz�Ƃ��ꂽ�GK��㣂ł́AGK�N�����̒����s�ׂ����Ƃ��ꂽ��A���GK�V�����b�Z���̕s�����`����ꂽ��������B
�@����ȊO��Ȃ̌������ɁA�������́u���E��̐�p�Ɓv�i�`�[�����[�g�̃J�C�g�̌��j���A���ӎ��̂����Ɋh������Ă����̂��낤���B�uGK���v�Ƃ������g���҂ݏo�����ō��̐�D���A��Ɏg���ׂ��Ƃ���ŕ��Ă��܂�������B����͒N�ɂ�����Ȃ��B���̓t�@���n�[���̋��̂����ɖ����Ă���B
�@����A�A���[���`�� �T�x�[���ē̓V���v���ɃI�[�\�h�b�N�X�ɐ킢��i�߂��B��邾�����A�`�����X�ƂȂ�Α��U���d�|����B�����̌v��ʂ�ɁB����̖�������������PK��B�����āA�Ō�̃J�[�h��M���ł���x�e�����ɐ����BPK��͂��̃}�L�V�E���h���Q�X���I�~����ł����B��Âň��芴����єz�������B
�@�ςݏグ�Ă����єz���A���炩�̎הO�ɂ���āA�Ō�ɒ]�I�����_�B�v��ɉ����ău���邱�Ƃ̂Ȃ���p���т��Ō�ɏ��������߂��A���[���`���B�єz�̎���d�̈��������̍s�������߂��A���ɋ����[���Q�[���������B
�@�I�����_�͏��D���̖���f���ꂽ�B�A���[���`����28�N�Ԃ�3�x�ڂ̗D���Ɍ������h�C�c�Ƒΐ킷��B���[���h�J�b�v�����悢���l�߂��}�����B
2014.07.11 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g4 �` ��Ƃ̓_�r�h���C�X
 �@�˂��ARay�����I Jiiji�͍��A���R�Ƃ��Ă���B���[���h�J�b�v�łƂ�ł��Ȃ����Ƃ��N������������炾�B�������ŊJ�Í��u���W����1�|7�Ńh�C�c�ɑ�s�����B���������������E�������R�Ƃ����B�m���Ƀh�C�c�͋����B�����炭���̂܂ܗD�����邾�낤�B�����A�u���W���̕������͂��܂�ɂ����������B�܂��Ƀ~�l�C�����̈����������B
�@�˂��ARay�����I Jiiji�͍��A���R�Ƃ��Ă���B���[���h�J�b�v�łƂ�ł��Ȃ����Ƃ��N������������炾�B�������ŊJ�Í��u���W����1�|7�Ńh�C�c�ɑ�s�����B���������������E�������R�Ƃ����B�m���Ƀh�C�c�͋����B�����炭���̂܂ܗD�����邾�낤�B�����A�u���W���̕������͂��܂�ɂ����������B�܂��Ƀ~�l�C�����̈����������B�@�싅�E�̒m�b�ҁE�쑺���玁�͏�X�u�����ɕs�v�c�̏������� �����ɕs�v�c�̕����Ȃ��v�ƌ����Ă���B�s�v�c�̏����͊m���ɑ��݂���B���{�T�b�J�[�ł����A1996�N�A�A�g�����^�ܗւł̒ʏ́u�}�C�A�~�̊�Ձv���������B�ł��u�s�v�c�̕����v�͑��݂��Ȃ��B�����ɂ͕K�����R������B�����͏�ɂ��̎p���Ŗ싅������Ă������獡��������A�Ɩ쑺����͌����B
�@������A�u���W����s�ɂ͗��R������̂��B�����Jiiji�Ȃ�ɍl���Ă݂悤�Ǝv���B�s�����v�����܂܂����炤�Ƃ������@�����邪�A����͎~�߂悤�B�A�`�R�`�œ�����O�ɚ������f�Ђ��W�߂������Ă܂�Ȃ��B���������喡�ȁi�H�j�Q�[�������V���v���Ɏa��Ɍ���B�������A�����͊����Đ�Ƃ��w�����悤�B�ނ̐S����ǂ������A�_�Ɛ��̐ӔC�Njy������B����A�a�V���u�N�����m�v�I����Ȃ����H
�@��s�̋N�_�̓h�C�c�̐搧�B���̐ӔC�҂́H �_�r�h���C�X�B�����A�_�r�h���C�X�������j�I��s��A����ƂȂ̂��B
���ēƃQ�[���L���v�e����
 �@�u���W���́A���X�����̃R�����r�A��ŁA�l�C�}�[�����d�����A�`�A�S�V�E�o���J�[�h�ݐςƁA�h�C�c��ł͓�l�̌����]�V�Ȃ�����Ă����B�l�C�}�[���͂���܂łS���_�̃u���W���̐�ΓI�G�[�X�B�`�A�S�V�E�o�̓L���v�e���ɂ��Ď���̗v�B�u���W���́A��G�[�X�Ƒ单���A�܂��ɔ�Ԋp�����Ő키���ƂɂȂ����̂��B
�@�u���W���́A���X�����̃R�����r�A��ŁA�l�C�}�[�����d�����A�`�A�S�V�E�o���J�[�h�ݐςƁA�h�C�c��ł͓�l�̌����]�V�Ȃ�����Ă����B�l�C�}�[���͂���܂łS���_�̃u���W���̐�ΓI�G�[�X�B�`�A�S�V�E�o�̓L���v�e���ɂ��Ď���̗v�B�u���W���́A��G�[�X�Ƒ单���A�܂��ɔ�Ԋp�����Ő키���ƂɂȂ����̂��B�@������Ƃ����Č�����͂ł��Ȃ��B64�N�Ԃ�ɏ����Ă��������J�×D���̃`�����X���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�`�[���͂���Ȏg����w�����Ă����B�����Ƀu���W���̔ߌ����������B
�@�h�C�c���O�ɁA�ē̃X�R�����ƃ`�A�S�V�E�o�ɑ��Q�[���L���v�e����C����ꂽ�_�r�h���C�X�́A���O�ɑł����킹���������Ƃ��낤�B
�@�X�R�����ēu�h�C�c�͋����B�E�`�͍U���Ǝ���̗v�����Ȃ��B��̐▽���B�����A������킯�ɂ͂����Ȃ��B�����J�Â�D���ŏ���A���ꂪ�������ɉۂ���ꂽ�g�������炾�B�_�r�h�A�L���v�e���͂��O�ɔC����B���ꂷ���l�̕��܂Ŋ撣���Ă���v
�@�_�r�h���C�X�u�킩��܂����B�`�A�S�̑���ɃL���v�e���Ƃ��Ă݂�Ȃ���������܂��B�f�B�t�F���X�̗v�ɂȂ�܂��B���C���̐�����������܂��B�l�C�}�[���̑���ɍU�����撣��܂��B�`����ł��R�����r�A��ł��S�[���������āA���q���オ���Ă���̂ő��v�B�C���Ă��������v
�@�X�R�����ēu�f�B�t�F���X�A�}�[�J�[�A�U���A�`�[���̓����B��ς����撣���Ă���B���O�������Ȃ�����ȁB�~�����[�̃}�[�N�������B����悹���炢����B�������͕�����킯�ɂ͂����Ȃ��B�m���Ƀh�C�c�͋����B�킢����m���Ă���B���_����������������̃y�[�X���B��ɋ����ȁB��炪���q���o���O�ɐ搧���Ď哱��������B�����͂��ꂵ���Ȃ��v
�@Jiiji�͂���Ȃ���肪�������Ƒz�������B�_�r�h���C�X�͐^�ʖڂȒj���B�ӔC����g�ɔw�����ăs�b�`�ɗ������B�`�[���E���[�_�[�Ǝ���̗v�B���ꂾ���Ȃ�悩�����B�Ƃ��낪�A�ނ̓l�C�}�[���̌��܂Ŗ��߂悤�Ƃ����B�m���ɍU���̒��q�͂悩�����B���������g�[�i�����g�ɓ����Ă����2���_�������A�����_�̃l�C�}�[���𗽉킵�Ă����̂��B������A�U���̎���܂Ő����������B�����ɗ��Ƃ������������B
���N�_�͐搧�_��
�@�O��11���A�h�C�c���̃Z�b�g�v���[�͉E�T�C�h����̃R�[�i�[�L�b�N�������B�h�C�c�́A������܂ł�5�����ŁA�Z�b�g�v���[����4���_�������Ă���B�ł����ӂ��ׂ��u�Ԃ��B�_�r�h���C�X���}�[�N������ꂽ�̂�4���_�̃~�����[�B�悹�Ă͂����Ȃ������Ƃ��댯�ȃG�[�X�������B
�@�L�b�J�[���R�钼�O�A�~�����[�̓X���X���ƃt�@�[�T�C�h�Ɉړ�����B��������čQ�Ă��_�r�h���C�X�́A�ǂ����A����̑I��ɐi�H���ǂ����u�~�܂��Ă��܂��B���̊Ԍ���˂��āA�{�[���̓t���[�̃~�����[�̑����ɁB�����āA�E���ŃS�[�������߂��Ă��܂����B�����Ă͂����Ȃ��搧�_�������B
�@���炩�Ƀ_�r�h���C�X�̃}�[�N�E�~�X�B�������ł��̂��Ȃ�������Ȃ���ʂ������B���낻���ɂȂ������R�́A�}�[�N�ւ̕s�O��B�ނ̓��̒��ɂ́A���[�_�[�V�b�v�Ǝ���ƍU���̎O�v�f���ϓ��ɋl�܂��Ă������炾�B
���ޗ��̒�ց�
�@�u�Ȃ�Ƃ����~�X���B�������Ȃ��Q�[���ŁA����ɐ搧����Ă��܂����B��������ԏ悹�Ă͂Ȃ�Ȃ�����̃G�[�X�ɁB���������ɂƂ�Ԃ��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��B���̂͒N���B�����������Ȃ��v�B�܂��܂��O�̂߂�ɂȂ�B����͂܂��܂����낻���ɂȂ�B
�@23���B�h�C�c�ɒ�����˔j����A�N���[�[�ɒlj��_��������B���[���h�J�b�v�ʎZ16�S�[���̐V�L�^�������B�ŏI���C���̕s�����Ɩ_�����̃f�B�t�F���X�w�B���C�������ӂ�W���͂�����������܂��_�r�h���C�X�̉ߎ��������B
�@2�_�̃r�n�C���h�B�`�[���̋��n�B�Q�[���L���v�e�� �_�r�h���C�X�́A�����ő��݊��������Ȃ�������Ȃ������B���Ԃ��ە����A�����Ă�����߂Ȃ��킢�ɓ����˂Ȃ�Ȃ������B�������ނɂ��̋C�͎͂c���Ă��Ȃ������B�����̐^�ʖڂȐ��i���Ђ������̂��낤���B�u�~�X�������͎̂������B�������A�厖�ȏ�ʂŐ�ɔƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��~�X�������B����ȊԔ����Ȑl�Ԃ��ǂ����Ă݂�Ȃ��ł���v
�@�ނ͂����Őꂽ�B�`�[�����ꂽ�B�u���W������w�͑̂����v���X���������B���Ƃ̓h�C�c�̂Ȃ����܂܁B�`�[���͋}���]���藎����悤�ɓޗ��̒�ɒ���ł������B
���s�v�c�̕�������Ȃ�������
 �@�u���W�����j�I��s�̌����́A�_�r�h���C�X���d�ׂ�w�������������Ƃɂ���B������₷���uA����Ƃ̓_�r�h���C�X�v�ƒf�肵�Ęb��i�߂����Ă������������A���킹�Ă��܂����̂̓X�R�����ē��B�w�����̐ӔC���I��ȏ�ł���̂͂����܂ł��Ȃ��B���ɊḗA������̃C���^�r���[�Łu�����̓u���W���ɂƂ��Ďj��ň��̓����B�I��̋N�p���p�A�����̉^�ѕ������߂��̂͂��̎����B�ӔC�͂��ׂĎ��ɂ���v�ƌ���Ă���B
�@�u���W�����j�I��s�̌����́A�_�r�h���C�X���d�ׂ�w�������������Ƃɂ���B������₷���uA����Ƃ̓_�r�h���C�X�v�ƒf�肵�Ęb��i�߂����Ă������������A���킹�Ă��܂����̂̓X�R�����ē��B�w�����̐ӔC���I��ȏ�ł���̂͂����܂ł��Ȃ��B���ɊḗA������̃C���^�r���[�Łu�����̓u���W���ɂƂ��Ďj��ň��̓����B�I��̋N�p���p�A�����̉^�ѕ������߂��̂͂��̎����B�ӔC�͂��ׂĎ��ɂ���v�ƌ���Ă���B�@�T�b�J�[�����u���W���̔ߌ��B���[�̓G�[�X�ƃL���v�e���̗��E���B����ɂ́u�J�Í��D������������v�Ƃ�������̃~�b�V�������������B�����߂Ɋē͍ł��M������I��ɂ��̎g����������B�w�����ꂽ�Q�[���L���v�e���́A�ӋC�Ɋ����d�ׂ�w�������B���ꂪ�w��������Ȃ����̂Ɗ����A���g�̒��q�̂悳������𐿂����킹���B
�@�v���b�V���[�Ƃ������͔̂w�����d�ׂ̎��ʂɔ�Ⴗ��B����������̑I��ł��l�Ԃ�������x�Ƃ������̂�����B�Q�[���L���v�e�����w�������d�ׂ͌l�̌��E���͂邩�ɒ��������̂������B�����w�����Ă��܂����_�r�h���C�X�B�����w���킹�Ă��܂����X�R�����ēB���j�I��s�ő�̗v���͂����ɂ���B
�@�ł͂ǂ�����悩�������H �d�ׂ���l�ɔ킹���ɕ��U����B���Ȃ��Ƃ��~�����[�̃}�[�J�[�̓_���e�ɂ��ׂ��������B�ŏI���C���̐�����܂ߎ�����ł߂Ă������菟�@��҂B����ɍ����ʒu�Ńv���X�������đ��߂ɍU���̉��E�ށB�u�����Ȃ��畉�����炵�Ⴀ��߂��v�ƊJ������B�ł��܂��A����͌��ʘ_�B���������Ă���̍Ղ肾�B
�@�_�r�h���C�X�͎�����A�������Ⴍ��Ȃ���u���ׂẴu���W���̐l�����Ɏӂ肽���B�����͐l���ň�Ԕ߂������ɂȂ����B���낢��Ȃ��Ƃ��w�ׂ��v�ƌ�����B
�@�_�r�h���C�X��A�����A�v�������苃���������BJiiji�͉���B�ɂ��قlj����B�ł��A�����~��A���̑�s�́u���́v�͂��悤�B�ǂ�ȕ����ɂ��u�s�v�c�̕����v�͑��݂��Ȃ��̂�����ˁB�u���낢��Ȃ��Ƃ��w�ׂ��v�̂Ȃ�A�����Ƒ��v�B�����ւ̃X�e�b�v�͂�������n�܂�̂�����B
�@�����āA�O�ʌ���킪����Ă���B�����A�u���W���������ŗ�������͖̂������B�Â��Ɍ���肽���Ǝv���B
2014.07.08 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g3 �` �x�X�g4�o����
�@�Ȃ��ARay�����I ���[���h�J�b�v �u���W���������Ƀx�X�g4���o�������B�����g�[�i�����g1���Ə��X�����͌����������������ˁB�ł��AJiiji�͔��Ȃ����B�Ƃ������A�ǂ݂̊Â��Ɩ��n�����v���m�炳�ꂽ�ˁB�O���[�v���[�O�͊m���ɔh��Ȏ��������������B�S�[�����ʎY�A48������136�S�[���͎j��ő����������B���E�̐����́u�U���^�v�Ǝv�����B������A�O�X��́u�N�����m�v�Łu���{�͊����Ď���^�ł����ׂ��v�Ȃ�Ē�Ă���������B�@�Ƃ��낪�ǂ������A����T�ɓ����s�^���Ɠ_������Ȃ��B12�����̑����_��23�B1�_����7�����A���_PK�팈����3�����A2�_����2�����B���ׂď����_�̐ڐ����B�������Ō�̍Ō�܂łǂ����ɓ]��ł����������Ȃ��W�J�B����[�A�ْ��̘A���BJiiji����̊��B�ł��A���ꂼ�T�b�J�[�Ɗ��\�����ˁB
�@����͈�̂ǂ��������R���낤�H ����͊ȒP�Șb�B�����܂ŏオ���Ă���`�[���͉����ȂׂĎ�����ł��B���E�̋����͋��łȎ���͂�y��ɃQ�[����g�ݗ��ĂĂ���Ƃ������ƁB�����b���u���������̃T�b�J�[�͍U���^�B2�_���ꂽ��3�_�������v�Ȃ�Ďq�����݂����Ƃ������Ă������{�́A�̃��x���ł����Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂��B ������AJiiji�͌��������B���{�́u����^�ł����ׂ��v����Ȃ��u������ł߂�͓̂��R�̂��ƁB���ׂĂ͂�������n�܂�B�ꂩ��o�����v�ƁB�ł́A�o����������4�`�[���������_���Ɍ��Ă������B
�u���W���`�����ȃl�C�}�[��
 �@���X�����R�����r�A��B�l�C�}�[���͂Ȃ�ƐҒō��ܑS��4�T�ԁI Jiiji�͍��ށA�R�����r�A��18�Ԃ��B���̎���ƂȂ�ׂ��u���W���̃G�[�X�𑒂苎�������t�E�v���C���B
�@���X�����R�����r�A��B�l�C�}�[���͂Ȃ�ƐҒō��ܑS��4�T�ԁI Jiiji�͍��ށA�R�����r�A��18�Ԃ��B���̎���ƂȂ�ׂ��u���W���̃G�[�X�𑒂苎�������t�E�v���C���B�@1950�N�}���J�i���̔ߌ����琋�ɏ����Ă����`�����X�B�_�l�y�����Ȃ����Ȃ����������J�Âł̗D���B���̃~�b�V��������g�ɔw������22�̎ᕐ�҂̖��͖��c�ɂ��ł��ӂ��ꂽ�B�����Ȃ��́A�u���W����B�T�b�J�[�����̒�͂������Ă���I
�@�����H�_�r�h�E���C�X��FK�S�[���B�㔼23���B�E���C���T�C�h����͋����R��o���ꂽ�{�[���̓o�[�̎�O�ŃX�g���Ɨ������B�b�ł͂Ȃ��C���T�C�h������o�b�N�X�s���ʂ��������B�����痎����B�p���[�ƋZ�p�̂܂��ɋ��ɂ̖���]�{�[���B�����Â炢�Ƃ����鍡���̃{�[���łȂ������_�r�h�E���C�X�B�ނ͂Ȃ��DF�B�������ނ́A�u�u���W���͈�ۂ��B�l�C�}�[�������ɕ��S���|�������Ȃ��v���Đ錾���Ă����̂��B���ꂼ�����̒�͂���Ȃ����B
 �@�u���W���ɂƂ��āA����T�P���̃`����͎��̂ق����������B1�|1�̂܂�PK��ցB�����ŗ����͂��������̂��A���_GK�W�����I�E�Z�U�[���������B�ނ�2010��A���Ő�Ƃ̉����𒅂����Ă����B���I����͂�ނȂ��̃J�i�_�E���[�O�ցB�فX�Ɨ��K�ɗ�ރZ�U�[���B����Ȕނ��\���A�������̂��ēX�R�����������B
�@�u���W���ɂƂ��āA����T�P���̃`����͎��̂ق����������B1�|1�̂܂�PK��ցB�����ŗ����͂��������̂��A���_GK�W�����I�E�Z�U�[���������B�ނ�2010��A���Ő�Ƃ̉����𒅂����Ă����B���I����͂�ނȂ��̃J�i�_�E���[�O�ցB�فX�Ɨ��K�ɗ�ރZ�U�[���B����Ȕނ��\���A�������̂��ēX�R�����������B�@�ނ̓`����PK��3�{�~�߂��B����͂����_������Ƃ��������悤���Ȃ������B�����āA�u���W���͏������B�����ꂵ���킢����J������āA�叫�̃`�A�S�V�E�o�ƃl�C�}�[���͕ӂ�݂炸�ɋ������B�����n���}�X�R�~�͔ᔻ�����Ƃ����B�ȂɌ����ĂƂ���������B�u�����J�×D���v�Ƃ����v���b�V���[���ǂ�Ȃɑ�ςȂ��̂Ȃ̂�!? �����㔼�c��30�b�A�`����9�ԃs�j�[�W���̃V���[�g������5mm����������A�u���W���͂����ŕ����Ă�����ł���B�������玟�̃`�����X�͐��\�N��B����ȏC������������Ă����I�肪�A�����Ă���ƊJ�����ꂽ�B�����ĉ��������I �n���Ȃ�����Ă���Ă���������B
�@�l�C�}�[���̌�����~�ߌł������ŖڕW�ɓ˂��i�ރX�R�����ēƑI�肽���BRay�����A�N���Ȃ�ƌ������ƁAJiiji�̓u���W�������������B���{�ɔ�ׂĂȂ���ґ�ȖڕW�A�m���ɂ����Ȃ��ǁA�����ɂ͉����̑�ς�������B�����ȃl�C�}�[���I�Ō�ɒ��ԂƏ�������Ȃ����I�I
�I�����_�`�Ⴆ�킽��t�@���n�[���єz
 �@W�t�A����܂œ�A�����J�嗤�J�Âł́A���[���b�p�̗D���͂Ȃ��B�����₱�̃W���N�X�˂��j��̂̓I�����_�H ����ȋC�ɂ�����قǁA����̃I�����_�͏���Ă���B
�@W�t�A����܂œ�A�����J�嗤�J�Âł́A���[���b�p�̗D���͂Ȃ��B�����₱�̃W���N�X�˂��j��̂̓I�����_�H ����ȋC�ɂ�����قǁA����̃I�����_�͏���Ă���B�@�T�b�J�[���Ă���Ȃɐ헪�I�����������H�Ǝv�킹��t�@���n�[���ē̍єz�Ȃ̂��B�ӏ������ɂ��Ă݂悤�B
(1)�O���[�v���[�O����X�y�C����ɂ����錘�瑬�U�@�I�����_��͎O�H�G�E�X�i�C�f���`���b�x���`�t�@���y���V�[�͋���30�B�����{�B���J�Â͂����B�����Ɣނ�́u���������Ȃ��v�Ǝv���Ă���͂��B���`�x�[�V�����͍������B
���k�ȃp�X�E�T�b�J�[�̃X�y�C�����A�S�ǂ̂T�o�b�N�Ŏ���A�ł�Đ��x���Ⴍ�Ȃ�������̃p�X�E�~�X��˂��A�X�s�[�h����J�E���^�[�őł��̂߂����B
(2)����T��1��탁�L�V�R��ł̕ό����݂̃t�H�[���[�V����
�O���͒��Ղ��ȗ�����DF����̃����O�E�p�X���d�p�B�ȃG�l�ő�����ꂳ���A����̗̑͂��������A�������㔼�Ɏ������ލ������B�㔼���_���ǂ�������W�J�ɂȂ��ADF�����A�T�C�h��FW�𑝂₷�B���_�Ȃ炸�Ƃ݂�30���A�t�@���y���V�[�ɑウ�Ē��g�̃t���e���[���𓊓��A�p���[�v���[�ɐ�ւ���B10��ڂ�CK�B�t���e���[���̃}�C�i�X�E�p�X�ɃX�i�C�f���̉E����M�B�����ɓ��_�Ƃ����B���̂��ƃ��b�x����PK����菟���z���B�ɉ���3�x�̃t�H�[���[�V�����ύX�ŏ�������������ȋt�]�����������B
(3)���X���� �R�X�^���J��̌��J�[�h�̎g����
0�|0�̂܂ܐ��ځB�I�����_�̌���2�������B�I���ԍہAGK�̃V���b�Z�����N�����ɑウ���B�N������PK��ɒ�����GK�B�Ȃ�Ƃ��ꂪ3���ڂ̃J�[�h�������̂��BPK��B�v�f�ʂ�N�����̓R�X�^���J��PK��2�{�~�߁A�I�����_�ɏ����������炵���BPK��p�ɍŌ�̈ꖇ���B����ȍ��A�ʂ�����W�t�j��ɂ������̂��낤���H
�@�u����̃I�����_�E�T�b�J�[�́A����̍U���𗘗p�������A�N�V�����̃T�b�J�[�ɓO���Ă���v�ƃt�@���n�[���B����Ɍĉ����U���̑��搫���Ăэ��ރT�b�J�[�B������A�ǂ�ȑ���ɂ��ό����݂ɑΉ��ł���B������\�ɂ��Ă���̂͊ē̍єz�ƑI��̕\���͂��B
�@���������̃T�b�J�[���т��Ώ��Ă�ƐM�����݂��ꂪ�ł��Ȃ��������{�B���������������̃T�b�J�[�Ƃ����̂��ԈႢ�����������B���ƃX�b�|���B�x�͂̕x�m�ƈꗢ�ˁB���{�l�Ƃ��āA���̍��ɜ��R�B�{�c�́u�D������v�͂�͂肨�����܂��������H �I�����_�E�T�b�J�[�͐��n�̋ɂɒB���Ă���B
�@����A�����I�����_���R���܂Œǂ��l�߂��R�X�^���J�̐킢�Ԃ�������������B�|�C���g�̓f�B�t�F���X�B5�o�b�N�̃��C�����䂪�Ȃ�Ƃ������ŁA�����|�����I�t�T�C�h��12�{�i�O���[�v���[�O�̃C�^���A��ł�11�{�j�B���{���w�Ԃׂ��͂��̂�����ł́B
�@�������A�u���W���̑�����h�C�c�B4���_�̃~�����[�͐�D���B�ǖʑŊJ�̐�D�V�����������Q�̑��݊��B���[���̒��q���オ���Ă����̂ōU��ɕ����o��̂��D�ޗ��B���Ƃ̓}�W�V�����E�G�W���̕����҂����B�Y��ĂȂ�Ȃ��̂�GK�m�C�A�[�̑��݁B�u���f�́A�E�C�A�L�b�N�̐��m���v���ׂĂ����˔�������ΓI���_���B
�@�m�C�A�[�̑��ɂ��A�{���͗D�G��GK���ڗ��B���L�V�R�̃I�`���A�A�A���W�F���A�̃G���{���A�R�X�^���J�̃i�o�X�A�u���W���̃Z�U�[���A���X�BGK�Ԑ���ł���B
�@������̏������A�I�����_�ɑ�����A���[���`���B�����܂ŁA�G�[�X�E���b�V��4���_���قڂ��ׂĂ̓��_�ɗ��ޑ劈��B�X�[�p�[�X�^�[�������W�t�̕���ŋP���Ă���B�C�O�A�C�������q���グ����A�f�B�}���A�̕�������͒ɂ��B�A���[���`���̗D���́A��͂胁�b�V�̏o������B
�@����Ray�����A�܊p�����炱����Jiiji�̑�_�\�z���B�����̓h�C�c�I�����_�B���̂̓I�����_���B�����A�ŏ��ɏ������Ƃ���AJiiji����������̂͒f�R�u���W���B�撣��u���W�� �����̈АM�ɂ����āB
2014.06.30 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g2 �` �O���[�v���[�O�Ɉٕ�
�@���[���ARay�����I ���[���h�J�b�v �u���W�������O���[�v���[�O���I�������B���{�͔s�ނ�����������ǁA�R��͂��ꂩ�炾�B����Jiiji �e�����u�D������ToTo�v������Ă���B�ǂ��ɓq���������āH �p�����������猾��Ȃ��B�ł��܂��������B���������Łu�|���g�K���v�B���Ƃ̓����ɂ́u��������I�ς��Ă�����������v�Ȃ�Č���ꂽ���ǁA���u�ѓO�B����ς茂���B�c�O�I�@�Ƃ܂��A�l�I�Ȃ��Ƃ͂��������āA�O���[�v���[�O�������_���ɑ������Ă������B
 �@B�g�B�Ȃ�Ƃ��r�b�N�������̂́A�O�҃X�y�C���̂܂����̔s�ނ������ˁB��1��̃I�����_��BPK�Ő搧�������̂́A�����͂����܂ŁB�J��o���ꂽ�I�����_�{���̔����ɁA�I����Ă݂��1�|5�̑�s�B�I�����_��2010������̐�J���ʂ��������ƂɂȂ�B����͂�A������t�P�������I����A�t�@���E�n�[���ē̌����������B5�|3�|2�̕z�w�ŃX�y�C���̓����������ɏ������B�I�����_�͂��̂��ƁA�I�[�X�g�����A�A�`���ɂ������ē��X��1�ʒʉ߁B���N�̃I�����_�͋����B����D�����ɖ����o���B
�@B�g�B�Ȃ�Ƃ��r�b�N�������̂́A�O�҃X�y�C���̂܂����̔s�ނ������ˁB��1��̃I�����_��BPK�Ő搧�������̂́A�����͂����܂ŁB�J��o���ꂽ�I�����_�{���̔����ɁA�I����Ă݂��1�|5�̑�s�B�I�����_��2010������̐�J���ʂ��������ƂɂȂ�B����͂�A������t�P�������I����A�t�@���E�n�[���ē̌����������B5�|3�|2�̕z�w�ŃX�y�C���̓����������ɏ������B�I�����_�͂��̂��ƁA�I�[�X�g�����A�A�`���ɂ������ē��X��1�ʒʉ߁B���N�̃I�����_�͋����B����D�����ɖ����o���B�@�X�y�C���́A�I�����_�E�V���b�N�������ʂ܂܃`���ɂ��s��A�S32�`�[�����ő��Ŏp���������ƂɁB�Ȃɂ��g���܂݂̖��J�����B
 �@�I�����_ �t�@���y���V�[�̌|�p�I���_�S�[���ƃ��b�x���̒���X�s�[�h�����Ɉ�ۓI�������ˁB�Ȃɂ��A���b�x���̑��́A100���Ɋ��Z�����10�b2�����Ă��B�ƂĂ��Ȃ��B�ł��A�����Ƌ������̂́A���̕��e�ł܂�30���������Ă��ƁI
�@�I�����_ �t�@���y���V�[�̌|�p�I���_�S�[���ƃ��b�x���̒���X�s�[�h�����Ɉ�ۓI�������ˁB�Ȃɂ��A���b�x���̑��́A100���Ɋ��Z�����10�b2�����Ă��B�ƂĂ��Ȃ��B�ł��A�����Ƌ������̂́A���̕��e�ł܂�30���������Ă��ƁI�@F�g�A���[���`�� ��2��̓C������B���b�V�̌����S�[���͌����������B�����2006�h�C�cW�t�f�r���[�͉X�����������ǁA���҂��ꂽ2010��A�t���J���͑S�R�_���B�o�����h�[���i�N�ԍŗD�G�I��܁j��4�N�A���Ŋl���Ă钴�X�[�p�[�X�^�[���A�ꍑ�A���[���`������u���b�V�̓o���Z���i�ł͉҂����ǁA���̂��߂ɂ͓������v�Ȃ�Č���ꂿ����āA1986�N�D���̗����҃}���h�[�i�ɕ]���͉����y�Ȃ��B
 �@���̎����A������ł߂�C�����̏p���ɛƂ�0�|0�̂܂܈����������Ǝv��ꂽ�A�f�B�V���i���E�^�C���B���b�V�̍�����M�I�~�h���E�V���[�g���l�b�g�����ɓ˂��h�������B�f�B�t�F���_�[���L�[�p�[�̎��E���Ղ��u�̃^�C�~���O���Ղ��A���������Ȃ��ӏ��Ƀs���|�C���g�ō��킹��n���̃e�N�j�b�N�I �`�[���������ɓ��������ʂ�̃X�[�p�[�S�[���������ˁB
�@���̎����A������ł߂�C�����̏p���ɛƂ�0�|0�̂܂܈����������Ǝv��ꂽ�A�f�B�V���i���E�^�C���B���b�V�̍�����M�I�~�h���E�V���[�g���l�b�g�����ɓ˂��h�������B�f�B�t�F���_�[���L�[�p�[�̎��E���Ղ��u�̃^�C�~���O���Ղ��A���������Ȃ��ӏ��Ƀs���|�C���g�ō��킹��n���̃e�N�j�b�N�I �`�[���������ɓ��������ʂ�̃X�[�p�[�S�[���������ˁB�@�A���[���`���͑�3��Ńi�C�W�F���A��3�|2�ʼn����A�S���Ō���T�ցB���b�V�͂��̎����ł�2�S�[���������A�g�[�^��4�S�[���ő������_����ʃ^�C�Ƒ�ԗւ̊���B����ł����A�A���[���`�������́A����b�V�͍��̂��߂ɂ͓����Ȃ���Ȃ�ĉ]��Ȃ��͂����B
�@������l�̃X�[�p�[�X�^�[ ���߂̃o�����h�[����҃N���X�e�B�A�[�m�E���i���h������|���g�K�����p���������BG�g ����h�C�c��0�|4�ő�s�B��2��A�����J��́A������O���[�v���[�O�s�ނƂ����w���̐w�B�c��1�������1�|2�̐�̐▽�B�����ŁAC.���i���h�▭�̃N���X�Ƀo��������э��݃S�[���I�|���g�K�� ��̔�ꖇ�q����̊��B�����A��3��K�[�i��2�|1�ŏ��������̂̓����_���Ŕs�ށB�h�C�c��̑�s���ɂ������B�X�y�C�������C�x���A������ŁI
�@C.���i���h�͋͂�1���_�ɏI������ˁB�����炭�������������ĂȂ������낤�B����Ƃ�EU�`�����s�I���Y�E���[�O�ŔR���s�����H �m���ɁA�{���̃X�s�[�h�ƃL�����Ȃ������ȁB�����܂Ŕނ�W�t�͂܂�2���_�B���b�V�Ɏ������E��2�ʂ̍�����肪���̂܂I���͂����Ȃ��B���V�A���������B�撣��N���X�e�B�A�[�m�I�I
�@D�g�͎��̃O���[�v�B��������̂͂��AW�t�D���o�����R�`�[����ം��B�S��D���̃C�^���A�A�Q��̃E���O�A�C�A�P��̃C���O�����h�A0��̃R�X�^���J���B��O�̗\�z�́u�o�����̎O�b�B�R�X�^���J�͂���J����v�B�Ƃ��낪�M�b�`�����A2���ڂ��I���ő��Ō����s�i�o�����߂��͉̂ᒠ�̊O�̃R�X�^���J�I �C���O�����h���\�I�����B�G�[�X ���[�j�[W�t���S�[�������炸�������B���ꂼ�ő�̃~�X�e���[�H�I�����ăR�X�^���J�B���O�̋��������ł́A���{��3�|1�ŏ����Ă���B�܂��A���K�������ᑪ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ȁB
�@�Ō�̈�g�̓C�^���A�E���O�A�C�̒��ڑΌ������B�����_�ŏ���C�^���A�́A�㔼�G�[�X �o���e�b���������A���炩�Ȉ��������_���ɏo��B�Ђ�A�����˂Ȃ�Ȃ��E���O�A�C�͏I�Վ��O�̃S�[���ŏ����B���e�B�x�[�V�����̍������s�����߂��ˁB
�@�E���O�A�C�̃G�[�X �X�A���X���A�C�^���A�̑I��Ɋ��݂��A�ޏꁕ9�����̏o���~�����ƂȂ����̂��b��ɁB
�@���[���b�p�̌Í����s�ށA�����L���O�ʼn��ʂ̃R�X�^���J�Ɠ�Ă̗Y�E���O�A�C���i�o����D�g�́A����Ӗ��{�����ے�����O���[�v��������Jiiji�͎v���B
 �@���{���U����C�g�A�S����ʒʉ߂̃R�����r�A�͋������B��G�[�X �t�@���J�I�������Ă��A22�n���X�E���h���Q�X������ė]�肠�銈��B�Ȃɂ��X�^�[�a���̗\�����炷��B����T�Ő����������N�������B
�@���{���U����C�g�A�S����ʒʉ߂̃R�����r�A�͋������B��G�[�X �t�@���J�I�������Ă��A22�n���X�E���h���Q�X������ė]�肠�銈��B�Ȃɂ��X�^�[�a���̗\�����炷��B����T�Ő����������N�������B�@�D�����A�g�u���W���Ƌ���G�g�h�C�c�͕]���ǂ���̋����ł͂������ˁB�u���W���́A�G�[�X �l�C�}�[����4���_�Ɛ�D���B���̑I��A�g�̔\�͂��e�N�j�b�N���j��ō�����Ȃ�������B�����A�u���W���̎�_�́A�s���`�̂Ƃ����_�I�x���ƂȂ�I�肪���Ȃ����ƁB�l�C�}�[���ɂ����܂ŕ��킹��ƃp���N�����Ⴄ���I
�@�h�C�c�́A�t�H���[�h���O�H�G�����݁B���ł��~�����[�͑������n�b�g�E�g���b�N��B���B�x�e���� �N���[�[�͒ʎZ15�S�[���Ƃ��ă��i�E�h��W�t�ő����_�L�^�ɕ��B�V���̃o�����X���悭�A�D�����̍ʼnE�����ȁB
 �@���_������������B�g�b�v���l�C�}�[���A���b�V�A�~�����[��4�_�B���b�x���A�t�@���y���V�[�A���h���Q�X��6�l��3�_�ő����Ă���B
�@���_������������B�g�b�v���l�C�}�[���A���b�V�A�~�����[��4�_�B���b�x���A�t�@���y���V�[�A���h���Q�X��6�l��3�_�ő����Ă���B�@���݂�Jiiji���I�ԃx�X�g�E�S�[���́H �I�����_ �t�@���y���V�[�̑X�y�C����ł̓��_�S�[�����B�������̃����O�E�p�X��ǂ������钆�AGK�J�V�[�W���X�̓��������ę�l�Ƀw�f�B���O�ɕύX�������f�͂Ƒn���͂̐����I �{�[���͑O�i����GK�̓���ɔ�������������`���S�[���l�b�g�ɒ��e�����B�`�[���͂��̓��_�e�����C�ɉ��҃X�y�C�������ݍ���ł䂭�B�Q�[���̗�����ꔭ�ŕς����Ƃ����Ӗ��ł��A���ɂ̃x�X�g�S�[���Ƃ�����ˁB
�@���_�́A�O�q���b�V�̑C�����팈���S�[���B����w�����ӔC�������x�ȋZ�p�������o�����낤�B���ꂼ�G�[�X�̏ؖ����ȁB
�@����T�ʉߍ���n��ʂɌ���ƁE�E�E�E�E����āE�k�Ă�8/10 ���[���b�p6/13 �A�t���J2/5 �A�W�A0/4�B��͂�u��ĊJ�Â�W�t�͓�Ă������v�͐����Ă����B�A�W�A�͘g�����炳�ꂿ�Ⴄ���B
�@�����A���悢�挈���g�[�i�����g�B32��16�ɍi���A��������I���̃T�o�C�o���E�Q�[�����n�܂�B�ْ��̓x�������}�㏸�B��u����Ƃ��ڂ������Ȃ��B �����Ȃ�A�u���W���A�h�C�c�A�I�����_�A�A���[���`����4�����H �����g���̗\�����\���B���ہA�㉺�̍����k�܂��Ă邩��A�����E�J�E�J�o�������B�䕗�̖ڂ̓R�����r�A�A���L�V�R�A�R�X�^���J������H �D���\������̃u���W�����B�����ĉ]���Ȃ�I�����_���B
�@����ł����āARay�����B�|���g�K��������������āAJiiji�͂ǂ����������悤���ȁB�������A�u���W���ɂ��悤�B93�킪��オ�q���Ă����ŁB�܂��܂��y���߂邼�I
2014.06.26 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g1 �` ���{�I���Jiiji�̒�
�@���[���ARay�����I �N�͂�����ɂȂ����ˁB�������ȁB������悤�ɂȂ��āA��l�Ɠ������т�H�ׂāA�ۈ牀�Ō��C�ɉ߂����Ă�B�݂�ȂɃj�R�j�R�B������݂�Ȃ��j�R�j�R�B������Ray�����A���̒��q���B�����Jiiji�����C�ɒ��B�@2014���[���h�J�b�v �u���W�����B�T�����C�u���[�E���{�̃L�C���[�h�́u����T�i�o�̌��͏���v�������B����͢�N�����m�1��10���ɏ������Ƃ���B�����A���ĂΓ˔j�E������ΐ�]�B�Ƃ��낪�R�[�g�W�{���[���ɋt�]�����BJiiji���̎��_�Œ��߂��B�������A��2��M���V���Ƃ͈��������̂��e���B����ő�3��́A���ڂ̂Ȃ��R�����r�A�ɏ������K�{�A���A�M���V�����R�[�g�W�{���[���Ɉ��������ȏ㓾���_���ŏ���A�����Ȃ��Ȃ���������B����Ă݂Ȃ���ᔻ���Ƃ͂����A���F����͖������B����ł��}�X�R�~�́u�M���悤�v�A�I��́u�\�������������߂Ȃ��v�̈�_����B�܂��A�����������Ȃ��̂͂킩�邯�ǁAJiiji�͐���������������B����ȏł��ꂪ�o�����Ȃ�A�Ȃ�ŏ���ł��Ȃ������́B�o���Ȃ������́B�Ȃ�ŁA�I��݂̂Ȃ���y�э��ɂȂ���������̂���Ďv���킯�B�x����ȁA�������ɁB
 �@6��25�����A�O���[�v���[�O��3��B����T�i�o�����߂Ă���R�����r�A�́A�]�T�Ń����o�[8�l������ւ��Ă����B����Γ�R���ȁB����Ȃ������Ɛ����v�����B�O����1�|1�Ő܂�Ԃ��B���_�e�̓A�f�B�V���i���E�^�C���̉���̃w�b�h�B��͂肱�̒j�������Ȃ��I���̎��_�ŕʉ��̃M���V���́A�Ȃ��1�|0�ŃR�[�g�W�{���[�������[�h���Ă���ł͂Ȃ����B���� �M���V���ɂ��̂܂܂����Ă�����āA���{���_������ď�����A������܂����̂܂������I �Ȃ�āA�}�Ɋ�]���������Ⴄ�����������I
�@6��25�����A�O���[�v���[�O��3��B����T�i�o�����߂Ă���R�����r�A�́A�]�T�Ń����o�[8�l������ւ��Ă����B����Γ�R���ȁB����Ȃ������Ɛ����v�����B�O����1�|1�Ő܂�Ԃ��B���_�e�̓A�f�B�V���i���E�^�C���̉���̃w�b�h�B��͂肱�̒j�������Ȃ��I���̎��_�ŕʉ��̃M���V���́A�Ȃ��1�|0�ŃR�[�g�W�{���[�������[�h���Ă���ł͂Ȃ����B���� �M���V���ɂ��̂܂܂����Ă�����āA���{���_������ď�����A������܂����̂܂������I �Ȃ�āA�}�Ɋ�]���������Ⴄ�����������I �@�Ƃ��낪�A�R�����r�A�́A�㔼������G�[�X ���h���Q�X�����Ă����B�`�[���̓�����ρB�R�[�g�W�{���[����h���O�o�����Ɠ������ہB�㔼10�������z���S�[���������B�������Ȃ����{�͂ނ�݂ɑO������Ŏd�|���A�H������J�E���^�[2���B���ʂ�1�|4�̊��s�B3�����g�[�^��2�s1���B����T�ւ̓��͕����ꂽ�B
�@������A���̌��ʂ́H�ƍl������A8�N�O�Ƃ悭���Ă���B2006�h�C�c���B��1��I�[�X�g�����A��1�|3�̋t�]�����B��2��N���A�`�A��0�|0�̃h���[�B��3��u���W����1�|4�Ɗ��s�B�Ȃ�A�����B8�N�O�Ƃ���Ȃ����B�S���i�����Ƃ��I
 �@�R�[�g�W�{���[����ł́A�_���ʂ���_��������ɂ��ւ炸�A�t�ɋC������������������B�M���V����́A�L���v�e���̑ޏ�A�|�C���g�Q�b�^�[�̕������ŁA�G�[�X����10�l������Ƃ������|�I�L���ȏ̒��A�����_�̑̂��炭�B�R�����r�A��́A��R����Ɋ��s�Ƃ�����Ȃ��B�����ɂ���̂́A���g�̂Ўコ�Ɨ����͂����鐢�E�̕ǂ������B
�@�R�[�g�W�{���[����ł́A�_���ʂ���_��������ɂ��ւ炸�A�t�ɋC������������������B�M���V����́A�L���v�e���̑ޏ�A�|�C���g�Q�b�^�[�̕������ŁA�G�[�X����10�l������Ƃ������|�I�L���ȏ̒��A�����_�̑̂��炭�B�R�����r�A��́A��R����Ɋ��s�Ƃ�����Ȃ��B�����ɂ���̂́A���g�̂Ўコ�Ɨ����͂����鐢�E�̕ǂ������B�@�����オ������E�����|�C���g���A�Q�[���̗���̒��ő�����ƁA�����B�R�[�g�W�{���[����O��16���A�u�{�c���搧�_����������v�ƃR�����r�A��A�O���̓y�d��A�u����̓��_�S�[���̌�v���B�����������邩�ǂ������˔j���ۂ��̕����ꓹ�B�o���Ȃ������̂͗͂�����Ȃ��������炾�B����A�ǂ���������H ���̌��������ւ̓���B
�@�m���Ƀi�V���i���E�`�[���̊ē͑�ςł���B���ʂ����ׂĂ�����B�Ƃ͂����A�U�b�P���[�j�ēɂ͊��I���ȁB����ɕ����ĕ����オ����������̂��A����̃M���V����͂�邱�Ƃ��V���o�_�o�������B
�@�攭�ɍ�����O���đ�v�ہB����͂܂��悵�Ƃ��āA��������ɔz�����̂͊ԈႢ�������B�R�[�g�W�{���[����œ��{�̉E�T�C�h�����ĕ���������A����̈ӎ��̂��鉪����A�Ƃ����Ӑ}�͕����邯�ǁBJiiji�t�@�C����R�����ƁE�E�E�E�E�ނ̃|�W�V�����́A���߂̑�\��15�������A��2��ɑ��E��13��ƈ��|�I�ɑ����B�ނ͉E�����B������������o�Ȃ��̂��B�f�[�^���ؖ����Ă�̂ɁA�U�b�N���������H �M���V����ŁA���肪�E��������ԈႢ�Ȃ����_���Ă����ʂ���������Jiiji�͌��Ă���B W�t�����������ɂ͔ނ̃S�[������ΕK�v�������̂ɁA�Ȃ�Ƃ��c�O�I�U�b�N�єz�ő�̃~�X���B
�@�V���o�_�o�Ƃ����A�I�Ղ̃p���[�v���[�������B�����o�[�I�o�����炱��͕��Ă����͂��Ȃ̂ɂˁB�܂���ŋg�c�����߂Ăł�����D�єz�Ə̂���ꂽ���ǁA����A�g�Ƃ͏o�Ȃ������B
�@������A���g��c�����܂܃Q�[���Z�b�g���Ă����̂��[���ł��Ȃ��B�ē������͂��������Ȃ������̂ɁA�Ȃ�̂��߂ɘA��Ă��Ă�̂�B���ϐg���O�Ԗڂ̑���ɃN���X22�{���Ă����̂����ȁB���C����̂����Č���������B
�@�U�b�N������撣�����낤���ǁA�O�l�Ƃ����̂����܂��������䂢�ˁB�^�ɋC���������ĂȂ����̂ȁB�u���{�̃T�b�J�[�v�����Ȃ���{�l�ē̂ق���������Ȃ��̂��ȁB
�@�u���W���̃X�R�����A�h�C�c�̃��[���A�I�����_�̃t�@���n�[���A�C�^���A�̃v�����f�b���A�X�y�C���̃f���{�X�P�A�A���[���`���̃T�x�[���A�t�����X�̃f�V�����A�|���g�K���̃x���g�A�����������B�݂�Ȏ����ē��B
�@���{�͓r�㍑������O�l�ē���w�ԕK�v������A�Ƃ����̂������B�ł��A���{�Ɉꗬ�͗��Ȃ��B�I�V�����炢�̂��̂������B�g���V�G�`�W�[�R�`�U�b�P���[�j�A�������ǒ����E�A�t���J���ւ̎R�B����������{�l�̕������ڂ��}�V����Ȃ����Ȃ��B
�@���c�p��������͂ǂ�������B�I��Ƃ��Ă̎��т��\���A���_�h�����ˁB�l�]�ɋ^�╄���邪�J���X�}���ŃJ�o�[����B�ł��A�܂��u�����T���̗��v����Ă�Ȃ�_�����낤���ǁB����\�̋{�{�P�����ēƂ̕����Ă�炵������A�ނł��܂��������B
�@�q���Ȃ�ēx���c���j�Ƃ����������B�ł��ށA����͊Â����W�]�������Ȃ��B�u�R�[�g�W�{���[���͉^���ʂ����Ȃ����A�t�H���[�h�Ɏ���̈ӎ����B��������{����B�M���V���͐��_�������Ə��������Ƃ��Ȃ��B�g���Ղ��B�R�����r�A���t�@���J�I�����Ȃ����債�����ƂȂ��v�Ȃ�đS���g���`���J��! �J�����O�A�ق�̒Z���ԃ��[���b�p�ɍs�������炢����A���E�͌����Ȃ������Ƃ������Ƃ��ȁB
 �@�Ȃ�A�{�c�\�S�͂ǂ����낤�B�ނ͍l���������h������ēɂ̓s�b�^������Ȃ����ȁBNHK�v���t�F�b�V���i���B��{�c����ɂƂ��ăv���t�F�b�V���i���Ƃ͉��H��Ƃ�������ɑ��u�����̎d���ɐ^���ł���l�v�Ɠ������B�i�C�X���B�S�s���������ǁu���E��v�Ƃ����X���[�K�������낷���Ƃ͂Ȃ��B�ēƂ��Ėڎw����������Ȃ����B���_���N����̘b�����ǂˁBJiiji�͂���܂Ō��C�ł��������ǁA�������Ȃ��B
�@�Ȃ�A�{�c�\�S�͂ǂ����낤�B�ނ͍l���������h������ēɂ̓s�b�^������Ȃ����ȁBNHK�v���t�F�b�V���i���B��{�c����ɂƂ��ăv���t�F�b�V���i���Ƃ͉��H��Ƃ�������ɑ��u�����̎d���ɐ^���ł���l�v�Ɠ������B�i�C�X���B�S�s���������ǁu���E��v�Ƃ����X���[�K�������낷���Ƃ͂Ȃ��B�ēƂ��Ėڎw����������Ȃ����B���_���N����̘b�����ǂˁBJiiji�͂���܂Ō��C�ł��������ǁA�������Ȃ��B�@Jiiji�͍��A�u���{��\�ɂ���قǏ��������߂Ă����̂��v���Ďv���Ă�B�܂��A�{�c�̌����Ă邱�ƂƊԋt�����ǂˁBW�t���e�ɂ͂ƂĂ��Ȃ��N�����|�������A�����ƒ����ڂŌ��Ă������ǂ������āB���̃X�y�C��������76�N���|�����Ă�����B���͂��̉ߓn�������āB������A�R�����r�A��̑O�A�L���v�e�����J�����������悤�ɢ�����Ɍq����悤�Ȏ��������̃T�b�J�[��\������v�ł�����B�����߂Ă邱�Ƃ����ʂ����Ă��ƂłˁB
�@���̈Ӗ��ł͎����������W�Ԃ��Ă����u�U���T�b�J�[�v���\�R�\�R�ł�����Ȃ����B��R����ɂ́B��������A�u���������̃T�b�J�[�v���Ă����̂��u�U�����܂���T�b�J�[�B�����2�_���ꂽ��3�_���T�b�J�[�v�Ŗ{���ɂ����̂��H���Ď��B������������K�v�������Ȃ������Ďv���̂��B
�@�Ƃ����̂́A�����W�t�͓_��荇��̗l���B������A�t�]�������p���B����܂ł̃O���[�v���[�O�̊炪�ς���Ă�B�U���T�b�J�[�Ԑ��肾�B�S�̂Ƀ��x���̒�グ�������ď㉺�̍����k�܂��Ă�B�m���ɓ��{�͐i�����Ă邯�ǁA���E�͂����Ɛi�����Ă���B�g�̔\�͂ŗ����{���A���E�Ɠ��������������Ă��A�����ڂ͂Ȃ���Ȃ��낤�����āB
�@Jiiji����Ă������̂́u���̃T�b�J�[�v���B�����Đ��E�̋t���s���A���{�T�b�J�[�̃A�C�f���e�B�e�B�[���m������B�싅�ł������ł���u�Ő��͐����v���āB�U��������̕����v�Z�ł���B�A���[���`���ƌ݊p�ɐ�����C�������D�Ⴞ���A���ăC�^���A�̓J�e�i�`�I�Ƃ�����������W�t��4�x�������Ă���B
�@�u�ǂ����������邩�v�́u�ǂ�����Ε����邩�v�Ɍq����B�u���̃T�b�J�[�v�̈ӎ��͍U���ɂ������e�����y�ڂ��͂��BJiiji�͂����l����B
 �@��������肾�����Ꮯ�ĂȂ��B������A�����X�g���C�J�[����ΓI�G�[�X�̈琬���K�v�ɂȂ�B�唗�A��v�ہA�`�J�A�{�c�A����A����B�ނ炶�ᐢ�E���x���ɂ͂قlj����B�X�s�[�h�A�h���u���Z�p�A�V���[�g�́A��u�̔��f�́A�A�C�f�B�A�A�z���́A�E�C�A�v����A���O�B���ׂđ���Ȃ��B�܂��A���肪�M���M�����B�l�C�}�[���A���b�x���A�t�@���y���V�[�A���b�V�AC.���i���h�璴�ꗬ�͖����ɂ��Ă��A�X�A���X�A���h���Q�X�A�h���O�o�A�~�����[�A �y�����^ �N���X�����Ȃ���ᐢ�E�ł͐킦�Ȃ��B�u�����Ȃ�Ȃ�Ƃ����Ă����v�u��C����ς����Ă����v���Ă���K�v�Ȃ�B
�@��������肾�����Ꮯ�ĂȂ��B������A�����X�g���C�J�[����ΓI�G�[�X�̈琬���K�v�ɂȂ�B�唗�A��v�ہA�`�J�A�{�c�A����A����B�ނ炶�ᐢ�E���x���ɂ͂قlj����B�X�s�[�h�A�h���u���Z�p�A�V���[�g�́A��u�̔��f�́A�A�C�f�B�A�A�z���́A�E�C�A�v����A���O�B���ׂđ���Ȃ��B�܂��A���肪�M���M�����B�l�C�}�[���A���b�x���A�t�@���y���V�[�A���b�V�AC.���i���h�璴�ꗬ�͖����ɂ��Ă��A�X�A���X�A���h���Q�X�A�h���O�o�A�~�����[�A �y�����^ �N���X�����Ȃ���ᐢ�E�ł͐킦�Ȃ��B�u�����Ȃ�Ȃ�Ƃ����Ă����v�u��C����ς����Ă����v���Ă���K�v�Ȃ�B�@�����ĉs���U�߂�B�U��̃o�����X���Ƃ�Ȃ���B������u���瑬�U�v�B���̂ق��������Ɠ��{�ɍ����Ă���BJiiji�͂����m�M����B
�@�킢�I����ē��c���������B�u���E�͍L���v�ƁB�����ł������ł������ł��Ȃ��B�u�L���v�̂��B�L������A���푽�l�ȑ���Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������ނ�͓��X�ω����Ă���B�i�����Ă���B�����炱���h�邬�Ȃ����{�Ǝ��̃T�b�J�[���K�v�Ȃ̂��B�N�Ƃ��Ⴄ�ǂ��Ƃ��Ⴄ���{�����̃T�b�J�[�B���ꂪ����ɋt�s�����u���̃T�b�J�[�v����Jiiji�͍l����B
�@���ʁA���́A�g�D�A�̋������A���ׂ����Ƃ͂��肪�Ȃ��B������AJiiji�̓V���v����3�ɍi�肽���B
�@�@�@�@Jiiji�O�̒�
�@�@�@�@�@�@�@�ē͓��{�l
�@�@�@�@�@�@�A���̃T�b�J�[�ւ̑�]��
�@�@�@�@�@�@�B�����X�g���C�J�[�̈琬
�@����̊F����ɂ��肢����B�u���{�̃T�b�J�[�v���ĉ�? ��^���ɍl���Ă��������B�ē����߂�̂͂��̂��Ƃ��B�����V�N�I�I
2014.06.25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���4
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�u�����̂ق����v�Ɍ���Βu Contraposition �̖�
�������ƌ��R���@���\2�N1689�N����3���A�m�Ԃ݂͂��̂��Ɍ����Đ[��̈��𗷗������B��Z�܂ł͏M�A��������͒n��̗��ƂȂ�A�����A�Ȗ��o�ē����R�Ɍw�ł��̂�4��1���������B���̒n�ʼnr��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���炽�ӂ� �t��t�� ���̌�
�����A�Ȃ�Ƃ��肪�������Ƃ��B���̎R�̐t��t�́A���Ă̗z�����肩�A�����R�̈Ќ��ɗ����āA�Ƃ�P���Ă���B
 �@�m�Ԃ͑O���Ɂu�̂͂��̎R���w��r�R�x�Ə��������A��C��t���V���Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ��A�w�����x�Ɖ����Ȃ��ꂽ�B��t�͐�N��̖����̔ɉh��\������Ă����̂��낤���E�E�E�E�E�v�Ə����Ă���B
�@�m�Ԃ͑O���Ɂu�̂͂��̎R���w��r�R�x�Ə��������A��C��t���V���Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ��A�w�����x�Ɖ����Ȃ��ꂽ�B��t�͐�N��̖����̔ɉh��\������Ă����̂��낤���E�E�E�E�E�v�Ə����Ă���B�@�u���炽���Ɓv�ɂ́A�t��t�̗z���Ƌ�C�ɑ���h���̔O�����߂��Ă��邪�A���̔w��Ɍ��݂̕��a�������炵������ƍN�����Ă���͎̂������낤�B�����A�m�Ԃ͓��Ƌ{�ɎQ�w���Ă���B�Ƃ��낪�A�O���ɂ���ɂ��A���Ƌ{�ƉƍN�ւ̒��ړI���y�͂Ȃ��B�����ɕ����A������\�����ē��R�����A�m�Ԃ͂������Ȃ������B�ނ��u�����̂ق����v�ŋL�����̂́A�u�����ɋ�C�̈̋Ƃ��ÂсA���݂̔ɉh�ԁv���Ƃ������B�Ȃ�Ƃ������Ő[���|�ł��낤���B�������A�����R��C�̃C���[�W�͑Βu���錎�R�ɃX���[�Y�Ɍq����B���҂Ƃ��C�����̒n������ł���B
�@�ł́A2�������6��8���A���R�ʼnr����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�̕� ��������� ���̎R
�ċ�ɍ������т���_�̕�B���̓����_���A�[�ׂƂƂ��ɁA���������X�ɕ���Ă����āA�₪�ĎO�����̌��̒��ɁA�o�H�O�R�̍ō��R���p���������B
 �@�u���̎R�v���g���R�h�Ɓg���ɋP���R�h�̑�������ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�R�ɓo��Ԃɖ�ɂȂ��Č��R����������ɏƂ�P���������A�Ƃ��������̕��i�̔w��ɂ́A�����_������������ĎR�ɂȂ����Ƃ����V�n�n���̊T�O���s�ށB���䂪�쌱���炽���ȏC�����̒n�����Ƀ��A���e�B���\�����B
�@�u���̎R�v���g���R�h�Ɓg���ɋP���R�h�̑�������ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�R�ɓo��Ԃɖ�ɂȂ��Č��R����������ɏƂ�P���������A�Ƃ��������̕��i�̔w��ɂ́A�����_������������ĎR�ɂȂ����Ƃ����V�n�n���̊T�O���s�ށB���䂪�쌱���炽���ȏC�����̒n�����Ƀ��A���e�B���\�����B�@���āA�Βu�����̋�ł���B�u���v�Ɓu���v�B�u�����v���u���̌��v�A�u���R�v���u���̎R�v�B�����C�����̎R���m�B�����́u�z���v�Ɓu�����v�B�w��Ɍ������u���j�v�Ɓu�V�n�n���v�B�����܂ő����ƁA�m�Ԃ͈Ӑ}���ē�̋��z�����ƍl���邵���Ȃ��B���Ɍ����ȑΒu Contraposition �ł���B
�@ �����̂͂��߂ƏI��聄
�@�u�����̂ق����v�ɂ͂�����g�̑Βu������B���̂͂��߂ƏI���̔Ԃł���B
���̂͂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���t�� ���e������ �ڂ͗����̏I���
�߂��䂭�t��ɂ���ŁA�l�ԂȂ�ʒ��܂ł����A���̖ڂ͗܂ł���ށB���A���ɏo�鎄�ǂ����͂݁A�݂�Ȃŕʂ��ɂ���ł��ꂽ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �ӂ��݂ɕʂ� �s���H���@�������̋�͐�Z�ł̂��́B1689�N3��27���A�[�삩��F�l�����ƏM�ɏ��A��Z�ō~��ĕʂ��ɂ���ʼnr�B���I���̋�͑�_�B���N9��6���A�����ŗF�l�����ƕʂ�A�ЂƂ�M�œ��Y�Ɍ��������B�J�{���T����ɐ��_�{��ڎw���āB
���̂ӂ��Ɛg�Ƃ��ʂ��悤�ɁA���͌�����l�X�ƕʂ�āA���Y�ɏo�����悤�Ƃ��Ă���B���傤�ǔӏH�̋G�߂���A���ʂ̎₵�����ЂƂ����g�ɂ��݂�B
�@�t3���ƏH9���B���̂͂��߂ƏI���B��Z�Ƒ�_�B���{�̓��Ɛ��B�w�i�ɂ͗F�l�����Ƃ̕ʂ�A�M�A��B���ʂȏ̒��ɕ\�����d�Ȃ�B�S��������̑Βu�̖��ł���B
�@�u�s���t��v�ŗ����n�߁A�u�s���H���v�ŗ����I����B���̎n�߂ƏI���̑Βu�����A�m�Ԃ��u�����̂ق����v�ɍ��߂��\���ւ̋����ӎ��̕\��ł���B
���m�� �Βu�̈ӎ���
�@�u�����̂ق����v�́A�P�Ȃ�I�s���ł͂Ȃ��B�ނ��뢋I�s���w��ƌĂԂׂ���i�ł���B�����A�n����܂�ł���̂ł���B����́A���s�����\�ǂ́u���s���L�v�ɔ䂷�Ƃ������̐H���Ⴂ�����邱�Ƃ��痠�t�����Ă��������B
�@�m�Ԃ́A��̎�́A�G�s�\�[�h�̕t���ȂǁA���Ȃ��炸��������Ă���B�����āA�����I����ĖS���Ȃ�܂ŁA5�N�̒����ɂ킽��A���Ȃ��d�˂Ă������B
�@����́A�u�����̂ق����v���A���Ȃ̌|�p�̏W�听�Ƃ��Ċ����Ȃ��̂Ɏd�グ�����Ƃ������łȈӎv�̕\�ꂾ�낤�B����̂܂܂̎������|�p�I�����x�̗D��B
�@�Ȃ�A�S�̂�����k���ɍ\���������ƍl����͎̂��R���B��̎�̑I���A�ʒu���A�蒼�����X�B���ʁA��i�Ɂu�Βu�v�̗v�f���������ꂽ�̂ł���B�o�b�n���u�~�T�ȃ��Z���v�Ɂu�Ώ́v�荞�悤�ɁB
�@�m�Ԃ̑Βu Contraposition �ƃo�b�n�̑Ώ� Symmetry�B��l�́A���U��q������i�̒��ɁA�ӎ����đ��`�����\�z�����B���{�Ɛ��m�B�o��Ɖ��y�B����W�������̈Ⴂ��������A��l�ɂ͋��ʂ̈ӎ��������Ă����B����́A�^�̌|�p�����鋁���҂Ƃ��Ă̐^�������̂��̂������B
2014.06.10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���3�`J.S.�o�b�n �V�����g���[�̈ӎ�
���o�b�n�ƃV�����g���[���@J.S.�o�b�n�̍�i�ɂ́A�g�V�����g���[�̈ӎ��h�������Ă�����̂�����B���ꂪ�A1,000���z����o�b�n�̍�i�Q�̒��ɂǂ�قǂ��邩�͕s�������A�����Ȏ��Ⴊ���Ȃ��炸���݂��邱�Ƃ͊m���ł���B
�@�Ⴆ�A�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�ɂ��V�����g���[�I�\�}�����Ď���B�O��́u�N�����m�v�ł́A�O�w�\���̉𖾂ȂǁA���_��������ɒu���čl�@�������A����͏c����ɖڂ�]���Ă݂�B
�@30�̕ϑt��^����Ɋ���ƁA�O����1�|15�A�㔼��16�|30�ƕ�������B���̋��ڂ�15�ϑt��16�ϑt�̑���Ƀo�b�n�̈ӎu������Ă���̂��B
�@1�|14�͑S�ăg�����ŏ�����Ă��邪�A��15�ϑt�ł̓g�Z���ɕς��B����܂ł̌y�����������A�����Ȃ�J����тт���捂Ȑ��E���g����̂ł���B����őO���ɏI�~����łƁA�㔼�̑�1�ȁ���16�ϑt�͈�]���ăM�������g�ȃt�����X�����ȂƂȂ�B�X���[�ȒZ������ɓx�Ɋ����Ȋy�z�ւ̓]���B�����ɂ̓N���p�X�̂悤�Ȓf�w���������B���̃����n������15�|15�̃V�����g���[�ӎ��ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�O���P�����̒Z���́A�㔼�ł͑�21�ϑt�Ƒ�25�ϑt�ɓ����g�Z���Ō�����B�o�b�n�́A����3�̒Z���ϑt�ɂ��אS�̒��ӂ��O�E�㔼�̃o�����X������Ă���B�֊s���Ē��f�e���|�̑�21�ϑt�����ɁA�B���͌Ђ����15�ϑt�ƃX���[�ȑ�25�ϑt��z���B�������R���[�x�̃o�����X���▭�B���Ɍ����ȍ������ŁA�����ɂ��o�b�n�́g�V�����g���[�̈ӎ��h���ǂݎ���̂ł���B
���~�T�� ���Z���u�N���h�v�ɂ�����V�����g���[�\����
�@J.�r.�o�b�n�̃V�����g���[�̈ӎ��́A�Ō�̍�i�u�~�T�� ���Z���v��u�N���h�v�Ɍ����Ɍ����Ă���B����́A�h�C�c�̃o�b�n�����҃t���[�h���q�E�X�����g�i1893�|1983�j�������Ă���A���݂ł͒���ƂȂ��Ă���B�]�k�����A�s�ю����u�w�~�T�� ���Z���x�́w�N���h�x�����łȂ��S�̂��V�����g���[�\���ɂȂ��Ă���v�Ƃ̌����_���\�i�u�N�����m �o�b�n�R�[�h�v2009�D3�D21�`6�D1�j���Ă��邪�A���_�A�w�����͂Ȃ�̔������Ȃ��i���j�B
 �@�~�T�Ȃɂ�����u�N���h�v�́u�j�P�A�M���v�Ƃ��Ă�A381�N�A��1�R���X�^���e�B�m�|���X����c�ō̑����ꂽ�u�~�T�ʏ핶�v���e�L�X�g�Ƃ��Ă���B�J�g���b�N���k����O�ʈ�̂���_�A�L���X�g�A������тɗB�ꕁ�Ղ̃J�g���b�N�����M����v�Ƃ����~�T�̊j�S�����Ȃ��A���݂Ɏ���1600�]�N���̊ԁA�ꌾ�����ς��Ȃ��s�ς̐M�ł���i���̌��ɂ��Ắu�N�����m�v2010�D1�D29�ɏڂ����̂ŁA���Q�Ƃ���������K���ł���j�B
�@�~�T�Ȃɂ�����u�N���h�v�́u�j�P�A�M���v�Ƃ��Ă�A381�N�A��1�R���X�^���e�B�m�|���X����c�ō̑����ꂽ�u�~�T�ʏ핶�v���e�L�X�g�Ƃ��Ă���B�J�g���b�N���k����O�ʈ�̂���_�A�L���X�g�A������тɗB�ꕁ�Ղ̃J�g���b�N�����M����v�Ƃ����~�T�̊j�S�����Ȃ��A���݂Ɏ���1600�]�N���̊ԁA�ꌾ�����ς��Ȃ��s�ς̐M�ł���i���̌��ɂ��Ắu�N�����m�v2010�D1�D29�ɏڂ����̂ŁA���Q�Ƃ���������K���ł���j�B�@���ăo�b�n�͂�����ǂ��\���������B�ȉ����̍\���L����
�@ �����F���͐M���A�B��Ȃ�_���@�����̂Ƃ���A�o�b�n�́u�~�T�ʏ핶�v��9�ɕ����ċȕt���������B���̂悤�ȁu�N���h�v9�y�͍\���́A�ŌẪ~�T�ȃM���[���E�h�E�}�V���[�u�m�[�g���_���E�~�T�ȁv�i14���I�j�ȗ��A���y�j��ɗ�͂Ȃ��B�Ⴆ�A�x�[�g�[���F���u�����~�T�ȁv��5�A�V���[�x���g�u�~�T�ȑ�6�ԁv��3�ł���B
�A �����F���͐M���A�B��Ȃ�_�� �S�\�̕���
�B ��d���F���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g��
�C �����F����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾����
�D �����F����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����
�E �����F���͐M���A�����ɂ��肵���Ƃ��A�O���ڂɂ�݂�����
�F �A���A�F���͐M���A��Ȃ鐹��A�����̗^���傽����̂�
�G �����F�߂̎͂��̂��߂Ȃ�B��̐����F��
�H �����F���҂̂�݂�����Ɨ����̐����Ƃ�҂��]��
�@�ł́AJ.S.�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�́u�N���h�v9�y�͂̃V�����g���[�\�}���l�@���Ă݂悤�B��L�\���\�����Ȃ��炨�ǂ݂������������B
�@�C�D�E�͂��ׂč����Œ��S���B���̊O���B�^�F���\���B�X�ɊO�̇@�A�^�G�H�������ȂƂ����\���E�E�E�E�E���ꂪ�o�b�n���Ӑ}�����V�����g���[�Ȃ̂ł���B
�@�ړI�H ����̓o�b�n�̌`���ɑ�����ӎ����낤�B�V�����g���[�\���������炷���ɂ̈��芴��S�̂̊̂ł���u�N���h�v�ɐA�������̂́A��̊O�`���i���y�Ȃ̘Ȃ܂��j���d��o�b�n�ɂƂ��āA�ނ��듖�R�̍s�ׂ������Ǝv����B
�@�������A�C�D�E�ƍ����Ȃ�3�A������̂́A�u�~�T�� ���Z���v�S27�y�͒��A���̕��������B�C�D�E�͊e�X�L���X�g�́u���a�v�u���Y�v�u�����v�̃G�s�\�[�h�ŁA�܂��Ɂu�L���X�g�̐��U�v�̊j�S���B�����������Ȃ�3�A���ō\������C���p�N�g�̋����I �o�b�n�̃V�����g���[�ւ̋���Ȉӎ����ǂݎ���B
 �@����ɒ��ڂ��ׂ��́A�v���e�X�^���g���k�Ƃ��Ẵo�b�n�̈Ӑ}�ł���B����͑����A���S���̒��S�Ɂu���Y�v��u�������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B����ɂ��ẮA�o�b�n�����̖����u�o�b�n �`���̓��ǂ��v�i���ы`���� �t�H�Ёj�ɖ��炩�Ȃ̂ŁA���Y�ӏ����������Ă��������B
�@����ɒ��ڂ��ׂ��́A�v���e�X�^���g���k�Ƃ��Ẵo�b�n�̈Ӑ}�ł���B����͑����A���S���̒��S�Ɂu���Y�v��u�������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B����ɂ��ẮA�o�b�n�����̖����u�o�b�n �`���̓��ǂ��v�i���ы`���� �t�H�Ёj�ɖ��炩�Ȃ̂ŁA���Y�ӏ����������Ă��������B
��u�N���h�v�ɂ����āA�u�\���˂ɂ����v�̊y�͂����S�I�ʒu���߂邱�Ƃ́A�v���e�X�^���g�̐��_�ƍ��v����B���̊y�͂𒆐S�ɒu�����߂ɁA�o�b�n�͌�ɂȂ��āA�킴�킴�A������̊y�͂ł������u�䂩�炾���v�Ɓu���͐M���A�B��̎�v�Ƃ�藣���A��̊y�͂ɒ����Ă���قǂł���B���̎�������X�����g�́A���^�[�̐_�w�̐_���Ƃ������ׂ��A���Y�҃L���X�g���S�v�z����㈂����B�J�g���b�N�̋����ɏ]���A���Y�ł͂Ȃ��A�C�G�X�̕��������S�I�ʒu���߂�B����ɑ������āA���̋��j���ƁA�����Ղ̗�q�́A�J�g���b�N�̋���A�v���e�X�^���g�̋���ɂ���āA�قȂ�����d��L����B���^�[�h�̃o�b�n�́A���������Ď��̋��j���̂��߂ɔ��Ɏ�̍����Ȃ�5�ȑn�������̂ɑ��A�����Ղ̂��߂ɂ́A�B��A�����ȃI���g���I����Ȃ����ɉ߂��Ȃ��B�@�u�~�T�� ���Z���v�́A�v���e�X�^���g���k�ł���o�b�n���A���U�̍Ō�ɁA���������̗͂�s�����ď����������J�g���b�N�̗l���ɑ������~�T�Ȃł���B�Ȃ��A�o�b�n���v���e�X�^���g�ɂ͑��݂��Ȃ��u�~�T�v�Ƃ����`�����Ȃ��ď����˂Ȃ�Ȃ������̂��H ���A�n���̓������A�����̃o�b�n��i�̒��ł���тʂ��ċ����[����i�ł���B
�@�������̋Ȃɖ�����ꂽ�̂�2008�N�̂��ƁB���ꂩ��6�N�B�u�o�b�n �`���̓��ǂ��v�̒��ҁE���ы`��������N�S���Ȃ�ꂽ�B�搶�ɒt�قȎ����������肵���Ԏ��������������̂��A���������z���o�ƂȂ��Ă��܂����B
�@����ȁu�~�T�� ���Z���v���A���A���̒��ɑh���Ă����B�����ʂƂ����ׂ��ł���B鳖��鲂ɂ��Ė��͂��ӂ�邱�̍�i�́A���̂��Ƃ��A�m�ԂƂ̐ړ_��T��M�d�ȑΏۂƂ��āA���グ�邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@����́A�m�ԁu�����̂ق����v�ɂ�����V�����g���[�̍\�}���l�@����B
2014.05.25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���2�`�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�Ɍ���F����
 �@���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�i1685�|1750�j�́u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv���o�ł��ꂽ�̂�1742�N�B�u�����̂ق����v��1702�N������A�u���邱��40�N�B�h�C�c�Ɠ��{�B�������ꂽ��̍�i�ɉ��炩�̋��ʍ�������Ƃ���A����͂���ŁA�Ȃ��Ȃ��̃��}���ł͂Ȃ����B
�@���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�i1685�|1750�j�́u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv���o�ł��ꂽ�̂�1742�N�B�u�����̂ق����v��1702�N������A�u���邱��40�N�B�h�C�c�Ɠ��{�B�������ꂽ��̍�i�ɉ��炩�̋��ʍ�������Ƃ���A����͂���ŁA�Ȃ��Ȃ��̃��}���ł͂Ȃ����B�@�y�Ȃ̐����������ẮA�����Â��ꂽ�G�s�\�[�h������̂ŁA�ȒP�ɐG��Ă��������B�o�b�n�̈���q�Ō��Պy��t�҂� ���n���E�e�I�t�B�[���E�S�[���h�x���N���A�u��l�̃J�C�U�[�����N���݂̕s���lj����̂��߂̉��y������Ă��������B����A�����e���Ă������������̂Łv�ƃo�b�n�Ɉ˗������̂����[�B�o�b�n�����B���̂Ƃ��S�[���h�x���N��14�B�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�͋Z�I�I�ɂ����Ȃ�̓�Ȃ䂦�A14����H�ƁA���̃G�s�\�[�h�̐^�U��₤���������邪�A�����͐[���肷��K�v�͂Ȃ����낤�B�S�[���h�x���N���_���������\��������̂�����B�m���A���疼�g�e�I�t�B�[���h�́A���[�c�@���g�Ɠ������B
�@�Ȃ��u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�͒ʏ̂ŁA�o�b�n���g���t�����\��́u2�i���Օt���N�����B�`�F���o���̂��߂̃A���A�Ǝ�X�̕ϑt�v�ł���B
�@�o�b�n�̂���y�̍�ȉƂɃf�B�[�g���q�E�u�N�X�e�t�[�f�i1637�|1707�j�����āA�ނ̃`�F���o���ȁu���E�J�v���c�B�I�[�U�i�n��A���A�Ɋ�Â��ϑt�ȁj�v�Ƃ����y�Ȃ��u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�ɂ悭���Ă���Ƃ����Ă���B������ׂ�ƁA32�̋Ȑ���g�����Ƃ����������A�\����̋��ʓ_�͊m���ɂ���̂ŁA�Q�l�ɂ����\���͏\�����邾�낤�B�A���A�o�b�n���y�Ȃɐ��荞�[���ȊT�O�͗]�l�̋y�Ԃ��̂ł͂Ȃ��B
����{�\����
 �@���P�ϑt�́A�O��16���߁~n�{�㔼16���߁~n(n=�Por2)�̓`���B����i2�Ȃ̂݉E��j�̓A���A�Ɍ���ꂽ32�̊���x�[�X�ɐi�s����B
�@���P�ϑt�́A�O��16���߁~n�{�㔼16���߁~n(n=�Por2)�̓`���B����i2�Ȃ̂݉E��j�̓A���A�Ɍ���ꂽ32�̊���x�[�X�ɐi�s����B�@�O��Ɏ��Ƃ��Ắu�A���A�v��z�u�A�A���A�|30�̕ϑt�ȁ|�A���A �Ƃ�����A�I�ȑS32�Ȃ̍\���ł���B
�@32������1�ϑt��16�̔{�����ߓ��Ɏ��܂�A32�̏W���̂��`������B�����ɂ����w�I�ȍ\���ł���B
���O�w�\����
A��@1�@4�@7�@10�@13�@16�@19�@22�@25�@28
B��@2�@5�@8�@11�@14�@17�@20�@23�@26�@29
C��@3�@6�@9�@12�@15�@18�@21�@24�@27�@30
�@30�̕ϑt�͏�L�̂悤�ȎO�w�\�������B�c��3�ϑt��1���j�b�g���`���A�S�̂�10���j�b�g�\���Ƃ����w�I�ȍ\���ł���B����ABC�͊e�X���m�Ȑ��i��тт�B
�@A��͑��ʂȗl���̃I���p���[�h�B��4�ϑt�̓��k�G�b�g�A��7�ϑt�̓W�[�O�A��10�ϑt�͑��d�ȃo���b�N���t�[�K�A��13�ϑt�͖����ȃC�^���A���V���t�H�j�A�A��16�ϑt�̓M�������g�ȃt�����X�����ȁA��22�ϑt�̓u�[���A�����đ�25�ϑt�̓T���o���g�̎���B�C�^���A�A�t�����X�A�C�M���X�B�e���l�X�ȗl���ɐ��ʂ����o�b�n�Ȃ�ł̗͂�ł���B
�@B��̓e�N�j�b�N�Nj��̗�Ƃ�����B�~�f�B�A���E�e���|�̑�2�ϑt�ŃX�^�[�g�A��5�ϑt�ő��e���ɕω�����ƁA�~�f�B�A�������݂Ȃ���A��29�ϑt�܂ŗl�X�ȓ�Փx�̃e�N�j�b�N��v������B
�@�Œ��ڂ�C��ł���B�e�ϑt��3���̃J�m���i��27�ϑt��2���A��30�ϑt��4���j�ŁA�����̉������͑�3�ϑt���P���A��6�ϑt��2���A�ȉ�1���Â㏸�B��27�ϑt��9���Œ��߂�B���R���鐔��͂����ɂ��o�b�n�I���B
���N�I�h���x�b�g��
�@C��̍Ō��30�ϑt�́A10���̃J�m���Ƃ����Ɂu�N�I�h���x�b�g�v���̗p�B�N�I�h���x�b�g�͓����̉���Ȃǂŗ��s���������l�ʼn̂��Y��̂̂��ƁB�u�������Ƃ����������A���������ŁA�����Łv�Ɓu�L���x�c�ƃJ�u������ǂ��o�����A�ꂳ���𗿗�����Ώo�Ă䂩���ɂ��̂Ɂv�����̂̉̎��B�S�ǂ̑��`�̒��A�˔@�������~悐��B�������Ȃ��o�b�n�̈�ʂł���B
���S�[���h�x���N�ϑt�Ȃ̉F������
�@�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�Ŋv���I���t�𐬂��������O�����E�O�[���h�́A�u���͖ړI�ł͂Ȃ��o���_�ł���A�ϑt�Q�͉~��`���̂ł����Ē����ł͂Ȃ��B�����ĉ�A����p�b�T�J���A�́A���̋O���ɂƂ��ē��S�~�̒��S�ƂȂ�v�ƌ����B�~��`���A���������`�B�A���A�𒆐S�Ƃ��铯�S�~�B�ނ͂����Ƀt���N�^���������Ă���B
�@�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv���k���ȋK�����Ɋ�Â����l�H�\�z�����B32�̉������j�Ƃ���32�i16�̔{���j���߂̕ϑt�Ȃ�32�W�܂��Ĉ�̍\�z�����`���B�ƑS�̂͑����`�𐬂��~�O����`���B�n���ɑ��錎�̌��]�A���z�ɑ���n���̌��]�A��͌n�ɑ��鑾�z�n�̌��]�B�����̉~�O���̑����`�̘A���������A�F���̐ۗ�����t���N�^�����ł���A�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv���F���ɂ��Ƃ�����̂́A�܂��ɂ��̕����Ȃ̂ł���B
�@�u�F���̐v�҂ł���n���傪������v�}�𐔎��ŕ\�������v�E�E�E�E�E���ꂪ���㗝�_�����w���ɂ̖���B�X�����ۂ���̐����ŕ\�����Ɓ������̗��_���_�̐����ւ̓��B�ł���B
�@���_�����w�̋S�˃G�h���[�h�E�E�B�b�e���i�v�����X�g�������������j�́A�u�_�̐����v�ɍł��߂��Ƃ����M���_�������A���̒��ŁA�u�F���̍������������ƂȂ�u���b�N�z�[���̒�ɂ�10�����̐��E�����݂���v�Ɛ����B
�@��X�̏펯��4�����܂ŁB10�����ȂǑz������ł��Ȃ����A�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv��10���j�b�g�͂����₱��ɒʂ���̂ł́B�ł��܂��A����͂�����ƃR�W�c�P�ɉ߂��邩�H
�@2008�N�m�[�x�������w�܂���܂����킪�����_�����w�̎���암�z��Y���m�́A�u�����Ȕ������͕����^���ɂ���v�Ɨ\�����A�q�b�O�X���q�����ւ̓�����B���́u�����ɔ����������̒��ɂ���낤���v�����u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv��30�ϑt�u�N�I�h���x�b�g�v���B
�@��Ɠ��c��F�́u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�ɐl�Ԃ̓����ǂݎ��A�ꃖ���̓��L�ŒԂ�u�S�[���h�x���N�ϑt���L�v���������B�y�ȂɖL���ȏ���D�荞�܂�Ă���
 ���炱�����낤�B
���炱�����낤�B�@�A���A�Ŏn�܂�A30�����o�ăA���A�ɉ�A����B�ꃖ���Ƃ������̗���A���̌J��Ԃ��B���̉i����A�̊T�O�����A�܂��Ɂu�����̂ق����v�̏����u�����͕S��̉ߋq�ɂ��� �s�����ӔN���܂����l�Ȃ�v�ɒʂ���B
�@�u�����̂ق����v�ʼnF���������m�ԁB�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�ɉF���荞�o�b�n�B�O�[���h2�x�ڂ̘^�����Ȃ���A�u�����̂ق����v��ǂށB���̒��œ�l�̕`�����F�����������A�E�B���A���E�u���C�N�̎��̒f�Ђ��^���ƂȂ��ċ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă̂Ђ�ɖ������悹�@�ꎞ�̂����ɉi����������
2014.05.05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���1�`�m�Ԃ̉F����
�@4��21���A�m���t�B�N�V������Ɛ_�R�T�m������ւ肠��B�����ɂ́u���ꂩ��t�B�N�T�[X��T���čL���ɍs���Ă��܂��B���x����A�l����u�����Ă��������v�Ƃ���܂����B���悢��_�R���A�j�S�Ɏa�荞�ނ��H�I ���҂��܂��傤�B�����͓��ɂ��Ă͑O��܂łŏ����������̂ŁA�_�R������̃A�N�V���������莟��A�킫�܂��������Ă����������Ǝv���܂��B �@���āA����́A�u�m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌����v�Ƒ肵�Đ���B�^�C�g���A���i�ɍ\�������I���v���ȁH �ł��A���ɕ����Ȃ��������̂ŁB�܂��A�����ɉ��炩�̗������t���悵�Ƃ��悤�A�ƋC�y�ɂ�肽���Ǝv���܂��B
�@���āA����́A�u�m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌����v�Ƒ肵�Đ���B�^�C�g���A���i�ɍ\�������I���v���ȁH �ł��A���ɕ����Ȃ��������̂ŁB�܂��A�����ɉ��炩�̗������t���悵�Ƃ��悤�A�ƋC�y�ɂ�肽���Ǝv���܂��B�@�o���E�����m�ԁi1644�|1694�j�Ɖ��y�̕��E���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�i1685�|1750�j�B������{�A����h�C�c�B��1���L�����u�ĂĂقړ�������ɐ�������l�B �ʂ����Ĕނ�̍�i�ɂǂ�ȋ��ʐ�������̂��H ���ꂼ�܂��Ɋi�D�Ȃ�u�N�����m�e�[�}�v�̗\���B��1��́A�u�����̂ق����v�����`���̌�����m�Ԃ̉F���ςɔ���܂��B
���u�����̂ق����v�����`���̍\�}��
�@�u�����͕S��̉ߋq�ɂ��āA�s�����ӔN���܂����l�Ȃ�v�E�E�E�E�E����͔m�ԁu�����̂ق����v�����̏����o���A���l���m�̌��ŁA�a�̔o��ɑa�����ł��̂���m���Ă��閼���ł���B�����������A���ɂ͂ǂ����V�b�N�����Ă��Ȃ������B�Ȃ��H
�@���̌����A�莝���̃K�C�h�u�b�N�i�u�����̂ق����v�p�쏑�X�ҁj�ɂ͂�������B�u���͉i���̗��l�ł���B���Ȃ킿�A�������������ĔN���A�n�܂�ƏI�����J��Ԃ��Ȃ���A���ݑ����Ď~�ނ��Ƃ͂Ȃ��v�B�Ȃ�قǁA����₷���B���ӂ����݂Ȃ��Ȃ����Ă���B���̃K�C�h�{���哯���ق��B
�@�u�ł��A�҂Ă�v�Ǝ��͂����v���Ă����B�u�A�v�����ޑO�i�ƌ�i�͓������Ƃ������Ă���B�ߋq�Ɨ��l�B���t�͈Ⴆ�Ǔ����Ӗ��B�����ƔN�B�ڂ����Ⴆ�������ԂƂ����T�O�B
�@�m�Ԃ͔o�l�ł���B�ŏ��̎����Ŗ����̐��E��\���ō���̕\���҂ł���B�o��͖��ʂ��ɗ͔r����B���ʂ����Ă���ɂ͂Ȃ��͂��B
�@�m�Ԃ́A�����ł́A�u�����̂ق����v�ɋ���ڂ��Ă��Ȃ��B�����A���ۂɂ͍���Ă���B�u���X�� ��X�� �������ĉĂ̊C�v�B������Ȃ��J�b�g�������H ��i�̏o�������邾�낤���A�{���ŁA���X�̗l�X�ȗl�q�������s�����Ă��邩�炾�A�Ƃ����Ă���B�������X�g�C�b�N�ɖ��ʂ�r���m�ԁB
�@����Ȕm�Ԃ��A�Ȃ��u�������Ɓv���x���J��Ԃ��̂��낤���H ���`�̔z���ƕ��ӂ̋��������邾�낤�B���������A���̔m�Ԃ������ē������Ƃ��J��Ԃ��B�����ɂ͗��R������͂����B

�@���q�����t����R�`�ɓ]�ɂȂ����̂ɂ������āA3�����{�A�m�ԉ��̗��Ύ��ɍs���Ă݂��B�k���̏t�͂܂�����1000�i�]�̐Βi�ɂ͂܂��Ⴊ�c���Ă���B���̒��ł́A�����ʼnr���� �Ղ��� ��ɂ��ݓ� ��̐� �͖��_�̂��ƁA�����������Ă����B�����Ⴍ�͂Ȃ��g�ɂ́A��c��}�ȐΒi�͑��ꂵ����B��x�݂��āA�}��̏����������̗y���ɐ�_���������B���̂Ƃ��ł���B�`���̍\�}���ǂ߂��̂ł���B
���m�Ԃ̉F���ρ�
�@�u���Ɠ��v�͕��ݑ����闷�l�ł���B���́u���Ɠ��v�́u�N�v�̓��ɂ���B�N���܂����ݑ����闷�l�ł���B���������O�������B�����Ƃ�������ĉ��O�B���Ɠ��͎��ł��蓯���ɉq���Ƒ��z��A�z����B���̍\�������F���ł͂Ȃ����I �����n���̎�������A�n���͓��̎�������B���z�n�͋�͌n�ɓ�����E�E�E�E�E�t���N�^�����A�A������F���̍\���B�܂��ɔm�Ԃ̉F���ςł���B
�@�O�q�̌����́A�������܂Ƃ܂��Ă͂��邪�A�m�Ԃ̐^�ӂ������Ƃ��Ă���B�����ƔN���ꏏ�����ɂ��Ď��Ƃ��Ċ����Ă���B���ꂪ���ՁB��ǂ݂ł���B
�@���́A�u�����ƔN�v�Ɏ��ƉF���������݂��̘A�����������������B�u�����͉i���̗��l�B���������N���܂������i���̗��l�ł���v�ƖB�����A�u�����͔N�̒��ʼni���ɓ����A���̔N���܂������悤�ɓ����Ă���v�ƁB�ꌩ���ՂȔ����͒P�Ȃ�J��Ԃ��ł͂Ȃ������I
�@�F���Ƀt���N�^����������ɂ́A�n����������ƂȂ�B�R�y���j�N�X���n�������������̂�16���I���A���{�ɓ����Ă����̂�18���I���Ƃ����Ă���B�m�Ԃɂ͒m��R���Ȃ��B�����������A�m�Ԃ͉F���̃t���N�^���������m���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�����炱���A���̂悤�ȏ����o���ƂȂ����B�F���ւ̊��m���o��̊�{��Ƃ������̂悤�ȕ��͂����������̂ł͂Ȃ����B
�@����̔o�l�E���J��D���́u�w�Ղ��� ��ɂ��ݓ� ��̐��x�Ɖr�m�Ԃ́A������ɚe����̐����Ȃ���L��ȉF���̊Ղ�����������Ă����̂ł͂Ȃ����v�ƌ����i�u���J��D���u���̍ד���ǂށv�����ܐV���j�B
�@���̋�́A�ԕ��J��̋�u�Òr�� �^��т��� ���̉��v�Ɠ����\�������Ă���B�u���̉��v�Ɓu��̐��v�͌����̉��B�u�Òr��v�Ɓu�Ղ���v�͐S�̒��̑z���̐��E���B�m���ɖ��������̐��͐Â��ł͂Ȃ��B�����A�m�Ԃ͂����Ɂu�Ղ����v�������Ă����B�F���̐Â����ł���B
�@�X�A��X�A�R�A�_�A��E�E�E�E�E���R�ƈ�̂ƂȂ����R���̘Ȃ܂��̒��A��̐����[�X�Ɩ苿���B�m�Ԃ���������ԂɁA�G�߂����Ⴆ�g�������ƁA�����ɉF���ւ̖����̍L���肪���m�ł����悤�ȋC�������B
�@�m�Ԃ͂��̂��ƌ��R�ŁA�_�̕� ��������� ���̎R �Ɖr�ށB�ċ�Ɖ_�����ĎR�B���ꂼ�V�n�n���ł���B���̑O�i�A�m�Ԃ́u���R�ɂ̂ڂ�B�_���R�C�̒��� �X��̂ڂ鎖�����A�X�ɓ����s���̉_�ւɓ��邩�Ƃ��₵�܂�A���₦�g�������āA����ɂ̂ڂ�A���v�Č�����v�Ə������B�u�����s���̉_�ցv�͑��z�ƌ����^�s���������̈Ӗ��B�܂��ɉF���ɕ������낤�Ƃ���m�Ԃ������ɂ���B
�@�V���ʼnr�� �r�C�� ���n�ɉ����� �V�̉� �͋���ׂ��X�P�[���̋�ł���B�m�Ԃ̉F���ς������Ȃ܂łɌ����Ă���B
�@�m�Ԃ́A�u�����̂ق����v�ŁA������Ƃ���ɉF�������Ă���B�`���̈ꕶ�͊��ɂ����\�����Ă���̂ł���B
2014.04.15 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����7�`�����ȉƂ̘_�]
�@�m���t�B�N�V������Ɛ_�R�T�m���Ɏ莆��������2�T�ԗ]��A�܂�����������܂���B����͂����Ƃ��āA�ނɂ͂Ȃ�Ƃ������̊j�S�ɔ����Ă��炢�������̂ł��B�@����Ȑ܁A����ҏW�v�����c�ޖ��F�i�Ƃ����Ă����y�jF������u�ǔ��V���ɍ����͓��Ɋւ���]�_���o�Ă��܂������A�ǂ݂܂����H ���Ȃ�Â����̂ł����v�ƑŐf����B�Â��낤���A�����͓����m�Ȃ�Ȃ�ł��̎��́A���������Ă����������B�ǂ�ł݂�ƁA���ꂪ�Ȃ��Ȃ������[���B�Ȃɂ�猻�㉹�y�̕s�т������������B�ꂵ�Ă���悤�ŁB
��ȉƁE�א�r�v���̓ǔ��V���]�_�i2��19���t�j

�@�܂��͕]�_���e���������Ă��������܂��B
�@�����������m���y�́A�������j�Ɠ`���̏�ɐ��������ƂĂ��������ꂽ�|�p�l���̈���B���̃G�b�Z���X�́u����v�ł͂Ȃ��u���v���̂��̂����ςݏグ�邱�Ƃɂ���ĉ��y�����Ƃ���ɂ���B�G���{���[�V�����i��l�̌|�p�Ƃ��S���𒍂��ō�i���d�グ�邱�Ɓj�������厖�Ȃ̂ɁA�����͓����̖��O�Ŕ��\���ꂽ��i�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�@���̕]�_�A�ꌩ���_�Ɍ����邪�A���̓g���`���J���ȑ㕨�ł���B�ȉ���������������B�|�C���g���\�������̂ŁA�ΏƂ��Ȃ��炨�ǂ݂���������K���ł���B
�@���y�ŗp�����錾��́A�ߋ�1���I�̊Ԃɑ傫���ω������B20���I�����ɃV�F�[���x���N��X�g�����B���X�L�[�Ȃǂ��A�e���݂₷���n�[���j�[�ɑ���V���������ݏo�����̂ɂ͗��R������B��������āA19���I���̃X�^�C����ܒ��I�Ɏ�����悤�Ƃ����Ƃ���ɁA���y�Ƃ��Ă̎コ������B
�@���y�ɐ[���ʂ����l�͉���ʂ��Č���Ă�����̂��u�{���v���ǂ������I�Ɍ������͂������Ă���B������Ɏc�O�Ȃ̂́A���������ڗ����������͓����ƈꏏ�Ɏd�������Ă������y�W�҂̒��ɂ��Ȃ������Ƃ������Ƃ��B
�@���[���b�p�ł͋Ȃ̃^�C�g���ɘf�킳��邱�ƂȂ��u���v���̂��̂��������ᖡ���A��]����ԓx������B���������̂悤�Ȗ��̓��[���b�p�ł͋N���肦�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���{�̉��y�E�́A�����ƒ������Ăق����B�����łȂ��ƁA���E�Ɍւ�悤�Ȗ{���̉��y�́A���܂ł����Ă����̍�����͐��܂�Ȃ����낤�B
�@�א쎁�́u�����͓��̍�i�ɂ̓G���{���[�V�������Ȃ��v�Ƃ����B�����Ȃ鍪�����炩�͕s�������A�Ƃɂ������ɂ��u��҂��S���𒍂������ۂ��v������Ƃ͑債�����́B�������C�s�̍�ȉƂł���B���́A�u�V�_����́g�����͓��̍�i�h���A�S���𒍂��ŏ������v�Ɗm�M����B�ނ́A�א쎁�������u����v���������̂ł͂Ȃ��A�����͓��̎w�����ɏ]���āu�����̂��̂����ςݏグ�āv������Ƃ��v���Ă���B�א쎁�Ɂg�����ł͂Ȃ��h�ƌ�����؍����͐V�_����ɂ͂Ȃ��͂����B
�@���[�c�@���g�́A���ƂȂ����u���N�C�G���v���A�����[�b�N���݂Ƃ����M������̒����ɂ���ď������B����͔��݂��u�����̍�������̂Ƃ��Ĕ��\���邽�߁v�̂��̂������B�ނɂ��������������������ł���B�������A���݂̎g���́A���[�c�@���g�ɂ��̎|��`�����m�����Ă���B
�@�����͓��̃P�[�X�͂���ƍ������Ă���B�����͓������݂ŐV�_���̓��[�c�@���g�B�����̓��@�ƍ�i�̊����x�͔�r���ׂ����Ȃ����A�͂܂������ς��Ȃ��B�m���ɁA���N�C�G������Ȃ��郂�[�c�@���g�̑n�����_�́A�u���̖������̐�̏�ɂ���v�Ƃ���M���M���̏̒��A��l�ɂ͗ʂ肦�Ȃ������̗̈�ɓ��B���Ă����B�u����T��v����Ȃ���V�_���̐��_�����u���N�C�G���v����Ȃ��郂�[�c�@���g�ɔ䌨����͂����Ȃ��B�����������A���[�c�@���g�͐S���𒍂������V�_���͂����ł͂Ȃ������ƁA��O�҂����ߕt���Ă������̂��낤���H
�@�V�F�[���x���N�ƃX�g�����B���X�L�[���u�������y����E���V�������������߂��v�̂ɂ͗��R������E�E�E�E�E�Ƃ��������̂Ȃ�A���̗��R�����Ăق����B�܂��A���ꂪ�������ɂ���A�u��������āA19���I�̃X�^�C����ܒ��I�Ɏ�����悤�Ƃ����v���Ƃ��A�Ȃ�����y�I�Ɏア����ƂɂȂ�̂��H ������V�_���͔����y��{�ƂƂ����ȉƂł���B�g�����͓���i�h�͏������҂��ɉ߂��Ȃ��B���y�I�Ɏォ�낤�������낤���A�����҂̈ӌ��ǂ���ɍ���������ł���B������}�g���Ɏāu�ア�v�ƒf����Ȃ��A�����m�B�����Ⴂ���r�������B
�@�u�����͓����̎���ɖڗ��������Ȃ������v���Ƃ��c�O�����Ă�����悤�����A��̎��͉������҂����̂��낤�B�ڗ�����������A����́u�{���v����Ȃ�����~�߂悤�A�Ƃ������Ƃɂł��Ȃ����Ƃ����̂��B����Ȗڗ���������Ƃ͎v���Ȃ����A����͂��Ă����A�u����̐l�Ԃ́A���̂ɋC�Â��Ă������A�������̓O���������v�\���ɁA���͍l���y�Ȃ��̂��낤���B
�@�u���̂悤�Ȗ��́i�ڗ���������j���[���b�p�ł͋N���肦�Ȃ��v�Ƃ�������邪�A�N���V�b�N���y�̖{��ŋU��E����E���̗ނ��������Ă��邱�Ƃ����͂������Ȃ��̂��낤���B��������炦�Έ���̖{�ɂȂ�قǂ����A�Ⴆ�A�u�N�����m�v2��26���t�́u�A�f���C�[�f���t�ȁv�̃P�[�X��������Ώ\�����낤�B���̃��[�c�@���g�̂��̂ƋU���Ĕ��\���ꂽ��i�́A�^������������܂�44�N���̔N�����₵�Ă���B���̊ԂɃ��R�[�f�B���O�܂ł���Ă���ɂ��S�炸�B
�@����ɂ������B���[�c�@���g�̌����ȑ�37�Ԃ́A�����ł́A�u��1�y�͏��t�������������ׂĂ��~�q���G���E�n�C�h���̍�ł���v���Ƃ��������Ă��邪�A100�N�]������̐^��������݂ɏo�Ȃ������B���[���b�p�ɖڗ���������̂Ȃ�A�U��Ɣ��f�����܂ł���قǂ̎��Ԃ��|����͂����Ȃ��ł͂Ȃ����B
�@�����́A�u�ڗ��������郈�[���b�p�ł͋N���肦�Ȃ��v�ȂǂƂ���������ĂȂ��ŁA�l�Ԃɗ^���������ς̕|����f���ɔF�����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B
�@���������A�m�̓������킸�A�N���V�b�N�E�ɂ����錻�㉹�y�͎̏S�邽����̂Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B���v�I�Ɍ������킯�ł͂Ȃ����A���s�R���T�[�g�ɂ����錻�㉹�y�̐�߂�䗦��10���ɖ����Ȃ����낤�B�N���V�b�N�̐��E�́A17���I������20���I���܂ł̍��X300�N�Ԃɐ��ݏo���ꂽ��i�ʼn���Ă���̂ł���B����̍�ȊE�̏������ɂ��������̂ł��邩�̏ł���B�א쎁�͂���Ȑ��E�̒��ō�ȍs�ׂ��c�ݑ����Ă���l�Ȃ̂��B
�@�א쎁�̌o���B1955�N�L�����܂�B�x�������|�p��w���B�����܁A�T���g���[���y�܁A���C���K�E���y�܁AARA-BMW���W�J�E���B���@�܂ȂǓ��O�̒������y�܂���܁A���ۓI�]���������B2012�N�ɂ͎����J�͂����^����Ă���i�ȏ�Wikipedia�j�B������B�X����o���B�킪����ȊE�̏r�p�Ƃ����邾�낤�B�Ȃ�A�����̖{�������ɂ߂钼�����Ăق����B���́u���{�̉��y�E�͂����ƒ������Ăق����B�����łȂ��ƁA���E�Ɍւ�悤�Ȗ{���̉��y�́A���܂ł����Ă����̍�����͐��܂�Ȃ����낤�v�ƌ����A��������̂܂��ɂ��Ԃ��������B�U��Ńr�b�O�E�r�W�l�X��B�����Ă��܂������y�E�̒����ۂɑ��I�O��Ș_�]������ɂ���������A�^���Ɏ��Ȃ̌|�p������簐i���Ă��������������̂��B
�@�א�r�v�H �ǂ����Œ��������O���ȁA�Ǝv���ċߔN�̃t�@�C����`���Ă݂���A�Ȃ�ƁA��N7��8���A�T���g���[�z�[���̐��ˎ����nj��y�c�����Ŕނ̍�i���Ă����I�u�����I�[�P�X�g���̂��߂́��J�ԇU���v���{�����ł���B��ۂ́H �����Ȃ���̃q���[�h�����p���㉹�y�B�����́H�����A�����͓��u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v�ɂ͋y�Ԃׂ����Ȃ��ł��傤�H�I
�@����́A�א쎁�ւ̔��_�ɏI�n���Ă��܂����B���ʁA���㉹�y�ւ̔�掂Ɏ~�܂�A�����}��`���Ȃ�������������Ȃ��B�Ƃ͂����A���y�E�̎��҂̔������ƑP�I�ŔݓI�Ȃ͎̂������B�����̕s��������������ᔻ����Ɏ~�܂��Ă���B�����I�ӎ����_�Ԍ�����B�܂��͂������琳���Ăق����̂��B
�@�Ƃɂ������ɂ��A�g�����͓���i�h�͔��ꂽ�̂ł���B��O�̎x�����̂ł���B�Ђ�A���㉹�y�͑����̐l�ɒ����Ă��炦�Ă��Ȃ��̂ł���B���O�́g�����͓���i�h�ɂ͐�������Ă����������㉹�y�ɂ͐���Ȃ��̂ł���B�W�҂͂��̎����ɂ����Ɛ^���Ɍ��������ׂ����B�����ƌ����ł���ׂ����B���y�͒f���Ĉꕔ���҂̂��̂ł͂Ȃ��B��O�̂��̂��B�������x�[�g�[���F����⼌��Ɏ����X����ׂ��ł���E�E�E�E�E�u���y�͐V�����n���������o�����������B�����Ď��́A�l�ނ̂��߂ɁA�Ô��Ȏ��������炷�o�b�J�X���v�i�w�R�T�����u���y�Ƃ̖���2�v���j�B
2014.04.01 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����6�`�q�[ �_�R�T�m�l
 �@���̃V���[�Y�A4��ŏI���\��ł������A�������������A����ő�6��𐔂��Ă��܂��܂����B��͂�A鳖��鲕��G����Ȏ����̏Ƃ������Ƃł��傤���B
�@���̃V���[�Y�A4��ŏI���\��ł������A�������������A����ő�6��𐔂��Ă��܂��܂����B��͂�A鳖��鲕��G����Ȏ����̏Ƃ������Ƃł��傤���B�@����ATV�u�~���l���v�ɁA�����͓���̐��̂�\�����m���t�B�N�V������ƁE�_�R�T�m�����o�ꂵ�A�����[���b�����܂����B�H���u���̎����ɂ͂܂��𖾂ł��Ă��Ȃ��l��������B�������ނ𑱂����̎����̑S�e���𖾂������v�B������t�B�N�T�[X�H�ƐF�߂����������́A�����_�R���Ɏ莆�������܂����B�u����Ƃ��t�B�N�T�[X�̑��݂�˂��~�߁A�p�[�t�F�N�g�ȉ𖾂��ʂ����Ăق����v�ƁB�ȉ����̎莆�����f�ڂ��܂��B�ʂ����Ă���͎��̒����ɖ𗧂��H
�q�[ �_�R�T�m�l
�@�܂��́A�_�R�l�����̍����͓������Ɋւ��邲�����ɂ��A�S����h�ӂ�\���܂��B ���́A�ȑO���R�[�h��ЂɋΖ����Ă����ꉹ�y�t�@���ł��B�{���y�������������������́A3��19���A�u�~���l���v�ɂ�����_�R�l�̔����ł��B�u��ނ̒��ŁA�܂��𖾂ł��Ă��Ȃ��l����������A�V�_����̑O�ɂ��S�[�X�g���C�^�[�������\��������B�m���t�B�N�V������ƂƂ��āA�S�e�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɍ������ނ𑱂��Ă䂫�����v�Ȃ��|�̘b������܂����B���́u�܂��𖾂ł��Ă��Ȃ��l���v�Ƃ��������ɋ����������܂����B�Ɛ\���܂��̂��A���������}�X�R�~�ɓo�ꂵ�Ă��Ȃ��d�v�l��������͂����ƍl���邩��ł��B�����āA�Ȃɂ�瓾�̂̒m��Ȃ��ł̂悤�Ȃ��̂ɘA�Ȃ��Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��B
�@������A�_�R�l�����낤�Ƃ��Ă���u�𖾂ł��Ă��Ȃ��l���v�Ǝ����l���Ă���A�̑��݂͓�����������Ȃ��I �}�X�R�~�͂̕ǂ����Ă������{�ʂɂȂ肪���ł��B����䂦�A���́A�_�R�l�̃W���[�i���X�e�B�b�N�Ȏ��_�Ɛl���I�Ȏp���ɋ����E���҂�����̂ł��B
�@���́A���̎������A�u�����͓��̌��ɂ͎d�|���l�����݂���v���Ƃ��ɂ͌��Ȃ��A�ƍl���܂��B���̉𖾂Ȃ����Ď����̑S�e�͉��肦�Ȃ��I
�@�����͓��͑���l�`�B����𑀂�l�`�t������B������u�t�B�N�T�[X�v�Ƃ������܂��BX�͌l�H�c�́H
�@�ŏ���X�̎w���ʂ�ɓ����Ă��������͓����A������X�̎�ɕ����Ȃ��قǂɂ��̑��݂���剻���Ă������E�E�E�E�E���ꂪ�����̎��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���́A�_�R������t�B�N�T�[X�̉������҂������܂��B
�@�����t�B�N�T�[X�̑��݂��m�M�����̂́A�T�����t2��13�����̔N�\�������Ƃ��ł����B2001�N9���A�āuTIME�v���Ɂu�����͓��͌���̃x�[�g�[���F���v�Ȃ�L�����f�ڂ��ꂽ�B������d���̂͒N���H �����͓����P�Ƃŏo����͂����Ȃ��A�ƒ������܂����B�Ȃ�A�č��̃}�X�R�~�ɉ��炩�̃c�e������l�Ԃ��d���ɈႢ�Ȃ��A�ƁB���R�[�h��Ђɂ����l�ԂƂ��Ă��̂�����̎���͂悭�킩��̂ł����A������o�������Ƃ��ɂ͕K���Z�[���X�|�C���g����������o���܂��B�Ȃ�����o���B�ł����グ��ƌ����Ă������B���ꂪ�Ȃ���}�X�R�~�͑���ɂ��Ă���Ȃ�����ł��B���ꂪ���̏ꍇ�A�uTIME�v���ւ̘I�o�������B�܂��ɒ��W���̕���ł����B�t�B�N�T�[X��h�͂����ɍ����͓��X�g�[���[�̊g���}���Ă������̂ł��傤�B
�@���̂��Ƃ́A�N�\�ɏ]���ăt�B�N�T�[X���ǂ��d�|���A�����͓����ǂ����������������Ȃ�ɒǂ��Ă݂܂����B����Ƃ��ׂĂ̒��낪�����Ă���悤�Ɋ������܂����B����������͎̂߉ނɐ��@�ł��傤���A���͂�_�R�l�����X�����Ă��镔�������邩�Ƒ����܂��B�Ȃ̂ŁA�����������疢���m�[�}�[�N��������Ȃ��������܂߁A�|�C���g�������L�����Ă��������܂��BNHK�̌��́E�����͎��m�̎����ɂ��A�����ł͊����ĊO�����Ă��������܂��i�������̂́A�Éꎁ�͂��ׂĂ�m���Ă���ANHK�����l�ł���A�Ɗ����Ă͂���܂��j�B
1996�N�@�f��u�H���v�̉��y��S���B�V�_�����Љ������B�@�_�R�l�ɂ́A�����̕��������ɂ������̌�����]�������܂��B��������A�t�B�N�T�[X�̎p�������Ă���B�w��̈ł������Ă���B�_�R���̖ڎw�������̑S�e�𖾂ɖ𗧂��̂Ɗm�M�������܂��B�ł́A���L�|�C���g���L�����Ă��������܂��B
1999�N�@�Q�[�����y�u�S���ҁv�S��
2001�N�@�uTIME�v�ɋL���f��
2007�N�@���`�{�u�����ȑ�1�ԁv�����Ɠ������ɕ]�_�������r��HMV�T�C�g�Ɋy�Ȃ��^����
�@�@�@�@�@�@�u�������v��UP�B
2008�N�@�H�t�����L���s���̊̓���Łu�����ȑ�1��HIROSHIMA�v������
2011�N7���@���{�R�����r�A���CD�uHIROSHIMA�v����
2013�N6��15������ �uHIROSHIMA�v�S���c�A�[�X�^�[�g
���P�F �����͓��ɐV�_�����Љ���͉̂���̌�y���@�C�I���j�X�g�ƂȂ��Ă��邪�A���Ƀt�B�N�T�[X�̑��݂�����̂ł͂Ȃ����B
����2�F �uTIME�v�L���荞�̂͒N���H���ꂪ�t�B�N�T�[X�ł͂Ȃ����B
����3�F �u�S���ҁv�̉��y���Ȃ����̂͒N���H���y�ƊE�ƃQ�[��(�V�Z�S��)�ƊE�̐ړ_�Ƀt�B�N�T�[X�͂���H �������ł̐ړ_�H
����4�F ���y�]�_�ƁE�����r���́u�������v��������B����́u���`�{�v�̐��E�̌`���Ƃ��Ă��邪�A���̂́u�����ȑ�1�ԁv��^�Ə㉉�̐���ł���B��Ȃ̂́A���̎��_�Ŋy�Ȃ̉����Ȃ����ƁB�Ȃ�A�����Ƀs�A�m��e���Ȃ肵�ă��N�`���[�����l��������͂��B���̗��ɂ��t�B�N�T�[X�̉A��������B���N�`���[�����̂́A������V�_����H ���̐�������ɏ㉉�����Ɍ����ăt�B�N�T�[X�̓����͉������Ă䂭�B�����͍����͓��X�g�[���[�`����d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�Ƃ��낾�B
����5�F �H�t�L���s���ɔ��荞�̂͒N���H���炭�\�����Ă͍����͓��{�l���낤���AX�͗��œ����Ă����͂��ł���B
����6�F �R�����r�A�ƍ����͓��̊ԂɌ��킳�ꂽ�_�̃`�F�b�N������Ɖ��炩�̕����������Ă���̂ł́B ���ڌ_�H�Ԑڌ_�H �ԐڂȂ�ΊԂɓ����Ă���l�Ȃ�c�̂��t�B�N�T�[X�̉\���������B�����͓��A�R�����r�A�A�t�B�N�T�[X�̎O�҂��ǂ�������茈�߂����Ă��邩���d�v���Ǝv���B
����7�F �S���c�A�[�̎�Î҂́H ����ɂ��Ắu�T���f�[����2��23�����v�ɋ����[���L��������B��Î҂̃T�����E�v�����[�V�����́u�T�����t2��13�����v���o�钼�O�̃R���T�[�g�ŁA�m��ʂӂ�����č����͓��O�b�Y��܂����Ă����l�q��������Ă���B�T�����͖{���ɒm��Ȃ������̂��H
����8�F 3��7���A�����͓������u���Y�ꂽ�L�҉�̃������e���������̂͒N���H ���̋L�҉�͍����͓�����l�Ŏd�����Ƃ��ꂽ���A�ʂ����Ă������H �����͓������ɒu���Y�ꂽ�����i�w�����j�ɂ́A�ʐl�̏������݂����������A���̐l�Ԃ��t�B�N�T�[X�̈���ł���\���H
�@�ȏ�͂����܂ʼn����ŁA���Â���؋��͂���܂���B���A�����Ƃ��Ă���قǓI�O��Ƃ��v���Ă͂���܂���B�_�R�l���ڎw���u�S�e�𖾁v�ɕK������ɗ��Ɗm�M�������܂��B���͂₱��猟�͎n�߂Ă��������邩������܂��A�����K�v�Ȃ���A�������������������܂��B�_�R�l���p�[�t�F�N�g�ȁu�S�e�𖾁v�𐬂��������邱�Ƃ�S���炨�F��\���グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@2014�N3��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ ��
2014.03.20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�Ȃ̂�
�@Ray�����I �ŋ߁A���̒��́u��������ς��v���B���N�̐H�i�U���Ɏn�܂��āA�U�x�[�g�[���F���ASTAP�זE�^�f�ȂǂȂǁB�t�Ȃ̂ɂ����Ƃ��C�������܂��B����Ȑ܁A���{��������Ȃ������������BJiiji����͌������Ȃ��B���܂Ŗق��Ă�������ǁA�����͌��킹�Ă����Ȃ���A�Ƃ����C���ȂB�@���{�����́A3��15���̎Q�c�@�\�Z�ψ���Łu�͖�k�b�͌������Ȃ��v�Ɩ��������B��N���͖����_�Ђ������Q�q����������̂ɁB�^�t�B�܂��ɂ���A���{�R�x���B
 �@1993�N�E�͖�k�b�͌������ׂ��ȂB�����āA�u�����{�R�̊֗^�v�𗠂Â��鎑�����ǂ��ɂ��Ȃ��B���؍��Ԉ��w�̘b���L�ۂ݂ɂ��č��グ��������B���̐������A���荑�̌����Ȃ�ɂȂ��āA���������A�����ɕs���Ȃ��Ƃ����甭�\����������B���ʂ��肦�Ȃ���ȁA����Ȃ��ƁBJiiji�ɂ͖����ɓ䂾�B�؍��͂�����Ă��ɂǂꂾ�����{�ɂ����������B���ꂩ��ǂ��܂ł����낤�Ƃ��Ă���̂��B�A�����J�Ɍ��ĂĂ�u�Ԉ��w���v�����̏ے��B�ȂA��k�b�\���Ă��������A�������̖��͕s��ɂ��飂Ɗ؍����Ɍ���ꂽ�Ƃ���������ǁB�������ꂪ�{���Ȃ�A���l�D���̑�Â����B���v�̑������l����A���[�����E�͖�m���Ƃ����e�F�����{����͍��A����Ȃ��A��������������[�b�B
�@1993�N�E�͖�k�b�͌������ׂ��ȂB�����āA�u�����{�R�̊֗^�v�𗠂Â��鎑�����ǂ��ɂ��Ȃ��B���؍��Ԉ��w�̘b���L�ۂ݂ɂ��č��グ��������B���̐������A���荑�̌����Ȃ�ɂȂ��āA���������A�����ɕs���Ȃ��Ƃ����甭�\����������B���ʂ��肦�Ȃ���ȁA����Ȃ��ƁBJiiji�ɂ͖����ɓ䂾�B�؍��͂�����Ă��ɂǂꂾ�����{�ɂ����������B���ꂩ��ǂ��܂ł����낤�Ƃ��Ă���̂��B�A�����J�Ɍ��ĂĂ�u�Ԉ��w���v�����̏ے��B�ȂA��k�b�\���Ă��������A�������̖��͕s��ɂ��飂Ɗ؍����Ɍ���ꂽ�Ƃ���������ǁB�������ꂪ�{���Ȃ�A���l�D���̑�Â����B���v�̑������l����A���[�����E�͖�m���Ƃ����e�F�����{����͍��A����Ȃ��A��������������[�b�B�@���{����͉͖�k�b�ɔᔻ�I����������A������Ƃ������͊��҂��Ă����̂ɁA�c�O���ɁI���n�Ȏ��Ȕ��f�Łu�����Q�q�v�����s�����̂Ȃ�A���߂ă^�J�h�Ƃ��Ă̈�ѐ���ۂ��Ă��炢����������B�R�����̊j�Z�L�����e�B�E�T�~�b�g�`�I�o�}�哝�̖̂K���E�K�̗���̒��Ő��ʂ��o���������߁H ���ꂶ��A�����ɂ��ꓖ����I�B���O�̂�������Ȃ��B�v�X�؍��ɑ�������ꂿ�Ⴄ�B�p�ۜ��哝�̂�����Ɂu�K���Ɏv���v�Ȃ����ĉ������Ȃ��̂��ˁB���j�͂����ƌ�����ׂ��ȂB���̊�{���Ȃ��ĂȂ��I ����Ƃ��u�����Q�q�v���s�̔����H ���ꂶ��A�^�t�B�u�����Q�q�v�����A�����Ⴂ���Ȃ�������B
 �@�����́A�����_�ЎQ�q�ŁA�u���̂��߂ɐ�������X�ɑ����̔O��\���v�ƌ����B����A�C�����͉��邪�s�ׂ����B�����ɂ͂`����Ƃ����J����Ă����ł���B����A�n�߂��̂͂���Ӗ��d���Ȃ����Ƃ�������������Ȃ��B�����A�Ō�̈��������͂������Ⴂ���Ȃ������B���ɂ�������{�l�]���Ґ���200���l�Ƃ����Ă���B���̂����̔����ȏ�͍Ō�̈�N�ł̂��́B������Ɣ����Ă��Ȃ���_���_���ƈ����������R���̍߂͑傫���B���U�Ƃ������d����l���I�ȍ��������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁB��肽���Ꭹ���œ˂����߁A���l�ɂ�点��ȁI �ނ炪��ǂ������ƌ��ɂ߂Ă���A���U���Ȃ������B���������������P�������������Ȃ�������������Ȃ��B
�@�����́A�����_�ЎQ�q�ŁA�u���̂��߂ɐ�������X�ɑ����̔O��\���v�ƌ����B����A�C�����͉��邪�s�ׂ����B�����ɂ͂`����Ƃ����J����Ă����ł���B����A�n�߂��̂͂���Ӗ��d���Ȃ����Ƃ�������������Ȃ��B�����A�Ō�̈��������͂������Ⴂ���Ȃ������B���ɂ�������{�l�]���Ґ���200���l�Ƃ����Ă���B���̂����̔����ȏ�͍Ō�̈�N�ł̂��́B������Ɣ����Ă��Ȃ���_���_���ƈ����������R���̍߂͑傫���B���U�Ƃ������d����l���I�ȍ��������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁB��肽���Ꭹ���œ˂����߁A���l�ɂ�点��ȁI �ނ炪��ǂ������ƌ��ɂ߂Ă���A���U���Ȃ������B���������������P�������������Ȃ�������������Ȃ��B�@�푈�Ŗ��𗎂Ƃ������X�̈⑰�́A�`����Ƃɂ��R���ɂ���ȂǍ��킹�����͂Ȃ��͂����B���J���Ă����������Ƃł���B
�@1978�N�A�����i�F�Ƃ����{�i��A����Ƃ����J�����Ƃ����Ă���ˁB�����_�Ђ͓Ɨ������@���@�l�B�_���̗��O�ɏƂ炵�čs�������J��s�K���Ƃ͂����Ȃ��B������A��������ᔻ����̂͊ԈႢ�B�ނ͋{�i�Ƃ��Ă̎d���������܂ł��B
�@���́A�����̒����������Ɂu�����Q�q�v���邱�ƂȂ�B���@��20���ɂ́u���������̌����v���L����Ă���B�����Ƃ����I�@���@�l�Ɂu�����Q�q�v����A���ꂪ���@�ᔽ�Ȃ̂��ǂ��Ȃ̂��H Jiiji�͂���A���S�Ȉጛ���Ǝv���Ă���B�����甽���Ă���B����́A����ŐR�c���ׂ��d��Č�����B��������܂�܂ŁA�ǂ����Ă��s��������A�l�Ƃ��čs���Ȃ�����B�Q�q���Ɂu���t������b�v�Ə����Ȃ��ł��B
�@�N���̒�`�]�X�Ƃ������E�؍��ւ̉e�����ǂ����Ƃ������O�ɁA�u�������͍������ł���v�Ƃ����F���ɗ����˂����Ȃ���B
�@1972�N�A�������́u���{�R����`�͓����l�����ʂ̓G�v�Ƃ����������o�����B�����颎������e�[�[��B���̎E�c���p�h�͂���Ɉق������Ȃ������B�ق������Ȃ���A���ۓI�ɂ͗��������ƊŘ��B���̐�t���Ɋւ���������́u��X�ɂ͒m�b���Ȃ��E�E�E�E�E�v�����������B���̎������c���v�͉��̔����������Ȃ������B
�@�b��߂����B������A���{�����́u���R����`��G�ƊŘ����ł���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����ł���B���ې��_�ł́B�����璆���͌����Q�q��ᔻ����킯�B���{����ɂ͂��̔F�����Ȃ��B�u�Ȃ�ő����猾���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��́v�Ɩ��������ɂ��v���Ă���B
�@�Q�q��̊C�O�̔����A���ł��A�����J�܂����́u���]�����v�Ƀr�b�N������n���B��͂��Ȃ�ȁB�c�C�b�^�[�Łu���������ˁI�v�Ȃ����Ă��̋C�ɂȂ��Ă邩�炱���������ƂɂȂ�B���t�⍲���E�q�����́u�������̕������]�����v�Ɏ����Ă͘b�ɂȂ�Ȃ��B����ȑ��߂�u���Ă��邩��\���Ɏ��~�߂��|����Ȃ��B�v�X���̉��l�ɂȂ����Ⴄ�B
�@���̈��{���t���ꌾ�Ō����A�u遂聕�y�����t�v���ĂƂ����ȁB����ʂ̌o�ϐ����C�R�[�����t�S�ʎx���A�I���ɏ��ĂȂ�ł�OK�Ƃ������Ⴂ�B����܂���遂�B�킪���h�q�̍����Ɋւ��Č����A���@�����Ȃ����ĉ��߂ʼn^�p���悤�Ƃ��Ă���ˁB�C�G�X�}������̎���ψ���ŝ��ށB�t�c���肪��ō���ł̋c�_�͌�B����ɓ��t�@���ǂł́u���̑̑��v���n�߂Ă���Ęb�B���ɁA���ՂŌy���B�ꓖ����I�B�����̏퓹����E���Ă���̂ɁA���̔F�����Ȃ��B�����Z���X�̌��@����B
�@���̑��l���Ɏ����ẮA�Ⴆ�AHHK��̖��䏟�l�A���t�@���ǒ����̏�����Y������͂����_�O�B��ʏ펯������������x���l�Ԃ������̗v���ɔz����ȂA����̃��x���̒Ⴓ��I�悵�Ă���Ă��Ƃ��B���`�́E���[�������܂��܂Ƃ��Ȃ�ŏ������Ă͂��邯��ǁB
�@�u��ヌ�W�[������̒E�p�v�Ƃ������ĐF�X��낤�Ƃ��Ă��邪�A�����������B����閧�ی�@�ANSC�n�݁A�W�c�I���q���s�g�e�F�ȂǁAJiiji�A���ׂĊ�Ȃ��������Č����Ⴈ���B����A�o�O�����̌��������A�����A�o���ˁB�����̌����͓��R�̂悤�ɓ��������Ƃ��邾�낤���B�����̂��ȁA�{���ɂ���ŁB
�@������A���{�����B�����Ƃ��������}�������Ă�B���̐ʐ^�������Ă���������B100�N��ɂ�5�疜�l�ɂȂ����Ⴄ��ł���A���{�̐l���B������ږ��̑啝����ł����B�����������Ƃ�����A���Ղŏꓖ����I�����Č�����́B���ꂶ��ARay�����̎��オ�S�z�łȂ�Ȃ��B���{���ǂ��Ɉ��������Ă䂫������? �ǂ��������ɂ������̂��H ��ǓI�ɐ^�ʖڂɍl���Ă�I �I�V�}�C�I�I
2014.03.11 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����5�`�t�B�N�T�[X�̑���
 �@Ray�����A�����͓����o�Ă����ˁBJiiji�͑O��ŏI���ɂ��悤�Ǝv�������ǁA���肪�o�Ă����Ⴕ�傤���Ȃ��B��������������Ȃ���ȁB����́AJiiji�̂Ԃ₫�ł������B�ŁA�O�ɂ��`�����ƌ��������ǁA���̎����ɂ̓t�B�N�T�[������B�����łȂ�����낪����Ȃ��B�����A�t�B�N�T�[X�B ���_Jiiji�����ꂪ�N�����͔���Ȃ����ǂˁB
�@Ray�����A�����͓����o�Ă����ˁBJiiji�͑O��ŏI���ɂ��悤�Ǝv�������ǁA���肪�o�Ă����Ⴕ�傤���Ȃ��B��������������Ȃ���ȁB����́AJiiji�̂Ԃ₫�ł������B�ŁA�O�ɂ��`�����ƌ��������ǁA���̎����ɂ̓t�B�N�T�[������B�����łȂ�����낪����Ȃ��B�����A�t�B�N�T�[X�B ���_Jiiji�����ꂪ�N�����͔���Ȃ����ǂˁB�@3��7���̋L�҉�B�������납�����̂́A�d��l�����Ȃ��������ƁB�����͓�����A������l�ł�������āH���肦�Ȃ���B���_X�Ƃ͑ł����킹�ς݁B�u�Ƃɂ������O�������\�ɗ��āB���܂łǂ���ɂȁB�Ȃɂ������Ă��\��A�����������ɂ����͋y�ʂ悤�Ɂv�Ȃ�Ă����܂߂��Ă��B
�@���ʁA�L�҉�̓��R�[�h��Ђƃv���_�N�V�����������ł����BJiiji�������̂���A����̎肪�\�s�������N�����Ă��A���̂Ƃ������āA��Ђ��d���Ă�������̂��B������r�V�b�Ǝd������̂ɂȁB�ꏏ�ɂȂ��Ėׂ�������B���ꂪ�m�`���Ă��낤�ɁB
�@�����͓��̑_���́A�u�S�W���ԁv�����肷�邱�Ƃ������ˁB���͕�����悤�ɂȂ�܂����B�蒠���Ԃ��܂����B�����lj����c�ނ�Ō��t�����܂��������Ȃ���ł��B����A��������Ƃ����ē�����嗋����C�J����Ă��ł���B���͕������邪�c�ށB������A�⏕�I�Ɏ�b�ʖK�v�Ȃ�ł���A���B���܂����ƍl���������B����ŕ⒮������Ȃ����Ƃ������ł����Ⴄ���B�ŁA���͕������Ă��邱�Ƃ��ؖ����āA3�N�O�܂ł͕����Ă��Ȃ��������Ƃɂ���B�}�X�R�~�͍��̖��������˂��Ȃ�����A3�N�O�}�f�͋c�_�̑ΏۊO�ɂȂ�B���Ƃ��u�S�W�҂������܂ʼn���̂͋^��ł��v�Ȃ����Ă��A100���̔��ɂ͂Ȃ�Ȃ����ˁB�u�S�W�v�̎����͊m���ɂ������A���Ă��Ƃ��Ȃ�ƂȂ��v�킹��B�E�[���A�����Ȑ^���ő傫�ȉR���B���B�E�}�C�˂��B
�@�����ō���̂͐V�_����́u�ŏ����畷�����Ă����Ǝv���v�Ȃ̂ŁA�u�ނ͉R�������Ă���v�Ƌ������킯���B
�@�V�_�����u������߂悤�v�Ɓg���x�h�����������Ƃɑ��A�����͓��́g����h�Ǝ咣�B�����A�ǂ��ł�������B�̖�肶��Ȃ�����B�V�_����������̂́g700���~�h�ɑ��A�����͓��́g���300���~��v���������Ƃ��������h�B�����������Ȃ��́B�V�_����A�u�g�[�^����700���~���炢�������Ǝv���܂��v���Č����Ă���疵���͂Ȃ��B���A�u�V�_����́w�s�A�m�̂��߂̃��N�C�G���x�͂ڂ��̌���ł����Č����Ă邯�ǁA���ꂾ���Ď��̐v�}�ǂ���ɏ��������́B�S�O���v�B��������Ȃ��́B�ӂ���̋��삾���Ă����C���ςނ�ł���B
�@�}�X�R�~�͖{���������ĂȂ��ˁB��b�ʖȂ��ŕԎ��������Ƃ��B�⒮��t�����������Ȃ����Ƃ��B�T���O���X�͕K�v���낤�Ƃ��B�ǂ��ł��������A����Ȃ��ƁB���@��A�Ȃ̈�t���ٌ�m���M�ՊӒ�m�Ȃ�킩�邯�ǁA�ǂ�����TV�ǂ́u�Ӎ߂̃v���v�܂œ������B������TV���ɂ���ȁB�b���Ƃ����炩��Ƃ����炩��قǃt�B�N�T�[X�̎v���c�{�Ȃ̂ɁB
�@���ꂩ��e���r�ǁB�e���b�v�Ɂu�������y�v���Ă��������ǁu�������y�v����B���㉹�y�͖������y�A���}���h�܂ł͒������y�B������B�ł��A�����͓��̉��y�́u�����v�̂ق��������������i�j�B
�@Jiiji����ԏ����̂́A�u�V�_����𖼗_�ʑ��ői���܂��v���ȁB���_�̂Ȃ��l�Ԃ��u���_�ʑ��v�ō��i�ł����B������炢������Ȃ��́B��������A���X����݂ɏo��B�t�B�N�T�[X�ɔ���邩���B���[�J�[���v���_�N�V�������Q�Ă邼�B�g�m���Ă����Ɓh���o�����Ⴄ�I �����猾���Ƃ����ǁA�u���i�v�͐�ɂȂ���B������킯���Ȃ��B
�@Jiiji�̒��ځB�܂��́A�����͓����u���̎��`�{�̉R�̃f�b�`�グ�ɐV�_�������S���Ă����v�ƌ��������ƁB�u���y��w�ɂ��s���Ȃ��ō�Ȃł����ɁA���N����̑̌���D�荞�߂����B����ɂ͎��̂��Ƃ��\�m�}�}��������ǂ��ł����v�ƐV�_�����Ă����������āB����͂��肤�邩���ȁB�V�_����A�����ɂ��C���セ�������A���̍����͓��̔��͂ʼn�������ꂽ���������Ⴄ�B�u�V�_����A���Ⴛ�ꂢ�������܂��B��낵���ł��ˁv�ĂȊ����ł��B��������S�Ƃ����̂��ǂ����B�ł��A������o�����̂̓��[���ᔽ�����B�����܂Ō����Ȃ�t�B�N�T�[X�̂��Ƃ��o�����Ăق�����ˁB�u�؏������������l�����܂��B���͌�����܂܂ɉ����������ł��B���͂����̑���l�`�ł��v���ĂˁB
�@�@Jiiji�ő�̒��ڂ́A�����͓������ɒu���Y��Ă����������B���̕M�Ղ͔ނ̂��̂ł͂Ȃ������B���Ŕނ��������T�C���Əƍ����ďؖ����ꂽ�ȁB����N���������H �t�B�N�T�[X�B�����A�u�t�B�N�T�[X�����v�BJiiji�����I���Ƀt�B�N�T�[X�̉e�������B �t�B�N�T�[X�́A�O�̔ӁA�����͓��ɂ�������ƃ��N�`���[�����낤�ˁB�\������l�ł�点�ė��ő���B���ꂼ�܂��Ƀt�B�N�T�[X�̂����B�}�X�R�~���A�����Łu������v�Ǝv��Ȃ���B�Ƃ��_�l�̏��q�q���ȂA�u�N�����������āA����Ȃ��Ɩ�肶��Ȃ�����v���āA�̂����Ƀ��|�[�^�[��{����Ă����ǁA�������ĂȂ��Ȃ��B�V�b�J�����Ă�B��������ԑ厖�ȂƂ���Ȃ���B
�@���ꂶ��AJiiji���A�����͓��͒P�ƔƂ���Ȃ��A���Ɂu�t�B�N�T�[������v���čl����悤�ɂȂ������R�����b���悤�B����͕Ď�TIME�ւ̃u�b�L���O���B2001�N9���A�u�����͓���͌���̃x�[�g�[���F���I�v��TIME���Ԃ��グ�āA���̃��[�������g�̓X�^�[�g�����B����́A���̌�̓W�J�ɂƂ��đ傫�ȕz�ƂȂ����B���y�ƊE�ł͂ˁB�����ł������Ƃ����Ƃ��ɂ͐�`�ޗ����~�����B�݂�Ȍ����ɂȂ��Ă����T���B���B�f�b�`�グ��B���ꂪ�A����ATIME�̋L��������������[�킯�BTIME�̂��n�t���Ȃ璴�W�����B�ł��ȁA���̍����͓��ɂ���Ȃ��Ƃ��o���邩�˂��B�p�������ׂꂻ���ɂȂ��B�ă��f�B�A�Ƀc�e�����肻�����Ȃ��B����ȍ����͓�����l�ŏo����킯���Ȃ��B���ꂪ�C�Â����L�b�J�P���B
�@����ɂ��̑O�A1996�N�́u�H���v�̉f�批�y�S���B�������ȉƂƂ��ĉ��̎��т��Ȃ������͓��ɉf�批�y�̘b�ȂǕ������ނ킯���Ȃ����ĂˁB
�@������A�����͓��ɂ̓t�B�N�T�[������B���Ȃ�����낪�����B���ꂪ�t�B�N�T�[X�B����͌l���W�c���H
�@�ł́A�Ō�ɁAJiiji�̍l���鍲���͓����[�������g�����n��ɂ܂Ƃ߂Ă������B�w��Ƀt�B�N�T�[X�������Ȃ���ǂ�ł݂Ă��������B����������́A���͂Ȃ�����̐��_�ɉ߂��Ȃ����Ƃ����f�肵�Ă�����B
1990�N��@�@�@�@�����͓��ƃt�B�N�T�[X�m�荇���B�@�t�B�N�T�[X �c�O���[��I�R���T�[�g���ꂩ�炾���Ă����̂ɁB�O�b�Y������̂Ƀ��[�B�c�O���ɂ̃t�B�N�T�[X�B�ł��܂��A�����܂ł���Ό�̎����B 3��10���́u�~���l���v�ŁA�{�����u�{�ACD�A�R���T�[�g�A���ꂩ�瑹�Q�����̘b���o�Ă���ł��傤�B�܂��܂��ڂ������܂���v�Ȃ����Ē��߂Ă����ǁA���킯�Ȃ����낤�B�����̎���i�߂�悤�Ȃ��Ƃ����B����A���オ��낵���悤�ŁE�E�E�E�E�B
1996�N�@�@ �@�@�@�t�B�N�T�[X�A�f��u�H���v�̉��y�������͓��Ɉ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɐV�_�������Љ�B�Ȍ���͓�l�ɔC���āA�A�ɉ��B
1999�N�@�@�@�@�@ �t�B�N�T�[X �Q�[���u�S���ҁv�̉��y�����B�����͓����̍�����u�S�W�v���B
2001�N 1���@�@�@�u�����ȃ��C�W���O�T���v�i�S���҃T���g���j�����B
�@�@�@ �@ 9���@�@�@X�̔��荞�݂ɂ��uTIME�v���ɍ����͓��̋L���f�ځB
2003�N 3�� �@�@ �����͓����˗������u�����ȑ�1�� ����T��v�V�_���������B
2007�N10���@�@�@�����͓����`�u�����ȑ�1�ԁv�u�k�Ђ��甭���B
�@�@�@�@ 11���@�@�@�����r�� �u�����ȑ�1�ԁv��������HMV-HP�Ɍf�ځB
2008�N 9�� 1���@�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v�L���s�ŕ��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̖͗l��TBS�uNEWS23�v�ŕ��f�B
2011�N 7��20���@���{�R�����r�A����CD�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v18�����̑�q�b�g���L�^�B
2013�N 3��31���@NHK�X�y�V�����u���̐����v���f�B�����͓��u�[������I�ɁB
2013�N 6��15���@�R���T�[�g�E�c�A�[���X�^�[�g�B
2014�N 2�� 6���@�V�_�����L�҉�B
�@�@�@�@�@3�� 7���@�����͓��玁�L�҉�B
2014.03.01 (�y) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����u�ŏI��v�`���ؐ��i�͂Ƃ�ł��Ȃ�
 �@�O��́A���y�]�_�Ƌ����r���̎����ւ̊ւ��ɂ��ċL�q�����B�ނ���̒��ڃR�����g�����킯�ł͂Ȃ����A�Ȃɂ��A�u�y�ȂɊ��������̂����珑���肪�N���낤���W�Ȃ����낤�v�I�Ȉӌ����l�ÂĂɓ`����Ă���B�y�Ȃ����ɏ����āA�悭�܂��A�p�����������Ȃ����������̂��Ǝv���B
�@�O��́A���y�]�_�Ƌ����r���̎����ւ̊ւ��ɂ��ċL�q�����B�ނ���̒��ڃR�����g�����킯�ł͂Ȃ����A�Ȃɂ��A�u�y�ȂɊ��������̂����珑���肪�N���낤���W�Ȃ����낤�v�I�Ȉӌ����l�ÂĂɓ`����Ă���B�y�Ȃ����ɏ����āA�悭�܂��A�p�����������Ȃ����������̂��Ǝv���B�@�N���V�b�N���y�E�ɂ͂��̂悤�Ȑ}�X�����]�_�Ƃ͐���������悤�ŁA����Ƃ�グ�钷�ؐ��i�������̗ނ��B�܂��́A���̃v���t�B�[����Wikipedia����B
���ؐ��i�F1958�N���������܂�̉��y�w�ҁB������w���w�����p�|�p�w���ƁB������w��w�@�������������������B1997�N�A���m�_���u�t�F���b�`���E�u�]�[�j�`�I�y���̖����v�ŋg�c�G�a��܁B�@�͂��߂ɁA�V�_����̗����A2��7�������V���Ɍf�ڂ��ꂽ���؎��̃R�����g�����Љ��B�u�����͓����̊y�Ȃ����Ă͂₳�ꂽ�̂͂Ȃ����v�Ƃ����₢�ɓ�����`�Ŏ�����Ă���B
�i����͂Ȃ����Ƃ����j���̒��O�̂قƂ�ǂ́A�����������Ȃ��A�픚�Ƃ����u����v�Ȃ��ɉ��y���������Ƃ��Ȃ����炾�B�ǂ�Ȑl��������̂��Ƃ��������ꂪ�����炷�C���p�N�g�́A�N���V�b�N���y�̊_�����Ȃ������B���������A���������ĕ�����剻����K�v�͂Ȃ������B�����A�����͓�����ƍ�ȉƂ����̐ӔC�ł͂Ȃ��B���邱�Ƃ����l���Ȃ����R�[�h��Ђ�A���Ă͂₵�����f�B�A�����߂��B�@�ꌩ�����Ƃ��Ȉӌ��ɕ�����B���ꂾ����ǂ��́u�Ȃ�قǓK�Ȃ��w�E�v�Ǝv���邾�낤�B���������A���؎����A�����͓����[�������g�̓����ɂ���l�Ԃ������Ƃ�����ǂ����납�H �ނ�18�������̃Z�[���X��������CD�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v�̃��C�i�[�m�[�c�i������j�������Ă���ł���B
�@���C�i�[�m�[�c�́A�\���ɂȂ��Ă���A��ꕔ�́u�����ȕ����_�v�Ƃ������ׂ��͍�ł���B�܂��́A���������Ă��������B���A���Ȃ蒷��ł��邽�߁A�����͓��Ƃ����������p�ɂɏo�錋�т̕����𒊏o����B
�����͓���̌����ȁsHIROSHIMA�t
21���I�̓��{�ɉ\�Ȍ����Ȃ̎p
�@���30�N�o���āA���߂ă��[���b�p���y�̕����ւ̑Γ��ȎQ�����������ɔF�߂�ꂽ���{�̑n��B���̔F�m�̃v���Z�X�̂����Ȃ��ɐ��܂ꂽ�����͓��炪�����Ă���̂́A���łɎ���̔�����F�m�������m���y�̕����ł���B���ă}�[���[�̂悤�ȉ��y���������Ǝ��̂��A���{�l�ɂƂ��ĂȂ�̈Ӗ��������Ȃ������B�������Ⴂ�������̂ł���B�܂��u�q���V�}�v����ɂ��邱�Ƃ́A�t�ɗ]��ɐ�������тт����ē�������B�������Ȃ��獲���͓��͂����������ݒ�ƃe�[�}�E�f�ނ̐ݒ肪�A�l�̋�Y�Ƃ��Č���悤�ɂȂ������j�I�ʒu�ɂ���B�����ł͂��͂�u�����Ȃ̗��j���I������v�Ƃ������j�F�����̂����j�I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�m�̓������킸�A�����̍�ȉƂ������ӂ����ь����Ȃ������͂��߂�����B���������u���@�_�v�P���A�����͓��͂����ăq���V�}����ɂ���B�ނ̋�Y�͂��ׂĂ�������͂��܂��Ă��邩�炾�B�@���͂��̑O�i�ŁA���́A�}�[���[�`�V���X�^�R�[���B�`���o�Č}�����u�����Ȃ̎���ꂽ30�N�v�Ƃ����_���J�����Ă���B�����ł́A�A�E�V�����B�b�c�ƃq���V�}�����������ɏo���A���m�A���ł��������S��`�̕����_���A�����Ȃ̎嗬�����Ɩk�ƃA�����J�Ɉڂ��Ă䂭�ߒ���������Ă���B�ړI�́A�����͓��̌����Ȃ����m���y�̗��j�̒��Ő����I�ʒu���߂邱�Ƃ��ؖ������������߁A�ł���B�Ȃ��Ȃ��傻�ꂽ�����Ȃ̂��B
�@�����͓��ɂƂ��āu�q���V�}�̂��ƂŌ����Ȃ��������Ɓv�͂������R�ȍs�ׂł������B����A�ނɂƂ��Č����Ȃ́A�܂��Ƀq���V�}�̂��Ƃł��������Ȃ������̂ł���B�q���V�}�̂��Ƃɏ����ꂽ�����ȑ��ԁsHIROSHIMA�t�B����́A���̂��܂�ɑ傫�ȗ��j�I���X���̊l���ƁA�����ɐ⋩�������苃���悤�ɍ��߂�ꂽ�ɁX�����܂ł̌l�I��Y�ɂ���āA21���I�ɐ���������ɂƂ��Ă��܂�ɂ����X�����B����͈꒮���Ă���ł����S�ł���鉹�y�ł��邪�A�������A��������ꂪ���̒���ŁA�`���I�ɂ͊A�a�Ȍ����Ȃ������ł�������Ɗ����邱�Ƃ�����Ƃ���A�����21���I�̂���ꂪ���܂�ɂ����̍�i��[���u�����v���A���̐��E�Ɂu�����v���Ă��܂��Ă��邩��ɂ����Ȃ��B
�@���؎��́A�u�����ȑ�1�ԁv�������͓��ɂ���ď����ꂽ�K�R��������A�Ō�ɂ����f������|�����͓����q���V�}�������͕̂K�R�ł���A���̌����Ȃ͈꒮���āu��������S�ł���鉹�y�v�ł���ƁB���̕��͍͂����͓����픚�ł��邱�Ƃ��ɂ͏����Ȃ��B
�@����́A���y�����_�̈߂��肽�����͓���^�_�ł���B����Ӗ��A�����r�̐��������z������̂��B�܂��ACD�̃��C�i�[�m�[�c�����炱��͂���ł������낤�B���������Ȃ��͔̂ނ̔\�V�C�ȕϐS�U��ɂ���B�����Ŗ`���̒����V���̃R�����g�ɗ����Ԃ��Ă������������BCD�̃��C�i�[�m�[�c��2011�N7���B�����̃R�����g��2014�N2���B���̊Ԃ̕^�ϐU��ł���B�����Y�ꂽ�i�t��������j�����Ƃ��ł���B
�@�����V���̃R�����g�B��ʘ_�Ƃ��Ă͂��̒ʂ肩������Ȃ��B���т́u���邱�Ƃ����l���Ȃ����R�[�h��Ђ�A���Ă͂₵�����f�B�A�����߂��v�ɁA���������ł���B�����A���́A���؎����������̐l�Ԃ������Ƃ������Ƃ��B���R�[�h��Ђ̒������ĉ���������������ƁB���Ă͂₵���i�Ƃ����j���f�B�A�ɓ����������ɂȂ��Ă��邱�ƁB����́A���邱�Ƃ����l���Ȃ����R�[�h��ЂƉR�����Ă܂ŕ�����剻�������f�B�A�ւ̋��͂ł͂Ȃ��̂��B
�@�����̐�������Ƃ��ɂ͏��B�`���낤���ƂȂ�ΐg�������B�����ڋ��Ƃ�������ǁA�l�Ԃ͎ア���̂����炻���܂łȂ�܂�������B�����Ȃ��̂́A���W���Ȃ���̔ᔻ�ł���B�Ȃɂ��u���R�[�h��Ђ����f�B�A�����߁v���B�u���������߂��v�ƌ����Ă���ɂ��Ăق����B
�@��͊y�ȉ���ł���B������y�T�͔����ɂ��āA��ۂɎc��t���[�Y���������Ă��������B
�����ȑ�1�ԁsHIROSHIMA�t�i2003�j �y�ȉ��
�L���̔픚�ł����ȉƂ̍����͓��B���̊ԁA��Ȏ҂͑S�W�ƂȂ�g�́E���_�̂Ƃ��Ɍ��������̒��ō�Ȃ͑�����ꂽ�B���������ꂵ�݂̒��Ŋ���������i�B���������W�J�̔w��ɁA�u��Y��˂������Ċ���Ɏ���v�Ƃ����x�[�g�[���F���I�ӎu������ł���B���̍����̓����́A��ɉߍ��ł�����̂́A�����ɔ������B�����ȁsHIROSHIMA�t�ł́A�����̂��Ƃ��u�^��������@���v�B���̕��ł�͂�畏����f�r���Ȃ���ߋ��𑖔n���̂悤�ɒǑz����B�u���b�N�i�[�I�ȑ��̒�������B�ނ���}�[���[�̌����ȑ�3�Ԃ̏I�y�͂ɕC�G����s��ȉ��y�B��������]�̌����܂Ԃ����~�Ղ���悤�ȃz�����őS�Ȃ͒��߂�������B�@�ꕔ�Ɠ���ǂݎ��邱�ƁA����́A���炩�ɒ��؎��́u�����͓�����v�܂��ď����Ă���A�Ƃ��������ł���B�����͓���́u�픚�S�W�̍�ȉƁv�ł���A�Ƃ�������ς��Ȃ��āu�����ȑ�1�ԁv��J�ߏ̂��Ă���A�Ƃ�������B��{�I�ɁA���̂��Ƃ����͂ǂ�������������͂Ȃ��BCD�̃��C�i�[�m�[�c�������ꍇ�A���[�J�[������ꂽ��������ɏ����̂͏퓹�����炾�B
�@�����������A�u���̒��O�̂قƂ�ǂ͕���Ȃ��ɉ��y�����Ƃ��Ȃ��v�ȂǂƁA�ォ��ڐ��E�����͕ʂȂ錾�����͂��Ăق����Ȃ��B�u���͎���������������ł��v�Ƒf���Ɍ����ׂ��ł͂Ȃ��̂��B
�@�C�ɂȂ邱�Ƃ����������B����͐V���R�����g�̖`���̌��u���̒��O�̂قƂ�ǂ́A�����������Ȃ��A�픚�Ƃ�������Ȃ��ɉ��y���������Ƃ��Ȃ����炾�v�̕����B�g�����������Ȃ��h�̑O��ɓǓ_�u�A�v�����邱�Ƃ��B���ꂪ���邱�ƂŁA�g�����������Ȃ��h�Ƃ������߂́u���̒��O�̂قƂ�ǁv�����Ƃ���q��ƂȂ�A�u�픚�v�ɂ�����C����ƂȂ�B�Ȃ�Β��؎��́A���̒��O���u���������������Ȃ��v�ƌ������Ă��邱�ƂɂȂ�B�������Ƃ�������ꂴ�鍂��Ԑl�ԁB�s���������܂�Ȃ��C�����B���������ď������L�҂̃T�C���Ȃ̂�������Ȃ����B
�@�g�Ƃ�Ȃ���h�Ȃ���������邯��ǁA�`���s���̏ɁA�˂�����ł��܂������������ɂ����������̂��{���Ȃ̂ɁA�C�^�`�̍Ō�Ȃ�Ƃ����Ȃ���ɁA��ʒ��O����M���̂����ɉ��y�ƊE�ƃ}�X�R�~��ᔻ���ē�����łB���������̂Ȃ�Â��ɐg�������Ȃ����B�R�����g����Ȃ�������Ă���ɂ��Ă��������B���ꂼ�}�X�����̉ʂČ��疳�p�̌����B�����������`���̔j�Ђ��Ȃ��G�Z�]�_�Ƃ��̂��邩����{�̉��y�E�͂����Ƃ��悭�Ȃ�Ȃ��I�I ���e���̈�Ȃł����B
�@�Ȃ��A������Ȃ��āu�����͓��A�ځv�͏I�����܂��B���R�́A����ȏ�͐��_�ɂȂ��Ă��܂�����B�m���ɏ�������Ȃ����Ƃ͂���܂����A���y�j��̘b�Ȃ炢���m�炸�A����͌��ݐi�s���̎����B�x�@�ł��Ȃ��̂ɏ؋����Ȃ����ݍ��ނ킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B �{���́A�����͓���Ƃ����\�ʏ�̃y�e���t���P�Ƃōs�������̂ł͂Ȃ��Ɗm�M������̂ł��B���鎞�_����w��ɂ̓t�B�N�T�[�������ɈႢ�Ȃ��B�����łȂ���Β��낪����Ȃ��B�t�B�N�T�[�͑傫�ȈłɌq�����Ă���Ǝv���܂��B�ƂȂ�A�����͓��͈���ȑ���l�`��������Ȃ��̂ł��B���炭�A�����͓������͍���}�X�R�~���珙�X�Ƀt�F�[�h�A�E�g���Ă䂭���ƂɂȂ�ł��傤�B�c�O�ł͂���܂����B
2014.02.25 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����3�`�����r�̑O�㖢���̐�����
 �@���A�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v�������グ���]�_�Ƃ����ɔ��W�܂��Ă���B�������̕����͂ǂ����Ǝv�����B�����͌l�̎��R�A�����Ă������āB���͎����A�u�����ˁv�Ǝv�������ł���B�ԑg���͖Y�ꂽ���ANHK�̍����͓��ԑg�����ċ������N���A�uHIROSHIMA�v��CD�����߂Ē����Ă݂��B�d���łȂ��Ȃ������Ȃ���Ȃ����B�q���[�h�����p�̌��㉹�y������ۂǂ܂����B�����A�ł����𗁂тĂ���]�_�Ƃ̕��͂�ǂނƁA���ꂪ�Ռ��ƂĂ��Ȃ��B�����Ă����Ȃ��Ȃ����B���̕]�_�̎�͋����r�B�N���V�b�N�́i���Ɏ�҃I�^�N�́j�J���X�}�I�]�_�Ƃł���B
�@���A�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v�������グ���]�_�Ƃ����ɔ��W�܂��Ă���B�������̕����͂ǂ����Ǝv�����B�����͌l�̎��R�A�����Ă������āB���͎����A�u�����ˁv�Ǝv�������ł���B�ԑg���͖Y�ꂽ���ANHK�̍����͓��ԑg�����ċ������N���A�uHIROSHIMA�v��CD�����߂Ē����Ă݂��B�d���łȂ��Ȃ������Ȃ���Ȃ����B�q���[�h�����p�̌��㉹�y������ۂǂ܂����B�����A�ł����𗁂тĂ���]�_�Ƃ̕��͂�ǂނƁA���ꂪ�Ռ��ƂĂ��Ȃ��B�����Ă����Ȃ��Ȃ����B���̕]�_�̎�͋����r�B�N���V�b�N�́i���Ɏ�҃I�^�N�́j�J���X�}�I�]�_�Ƃł���B�@�܂��́A�����r���ւ̔�����Љ��B
�@�c����w�����̋����r���ăz���g���l�Ȃ�ł��傤�B�S�[�X�g���C�^�[���g���č�Ȃ��Ă������\�t�̉R���������Ȃ����x�̐l�ԂȂ獡�������E����ׂ��ł́H �_�]�͏ォ��ڐ��̂��̂���B����قǂӂ�Ԃ��Ă���̂Ȃ炳��������������̂��A�Ǝv������A�u��ȉƂł��蒮�o��V�ҁv���Ă��������͓���̉��y���A�R�ƌ��������u��Y�ɖ������f���炵�����́v�Ƌ����ɂ����^���Ă��܂��B��͂�ނ͎����̌����ɐ�������Ă��邾���́A�����č�ȉƂ̌����ł������y�f�ł��Ȃ����\�Ȃ̂ł��傤�B�@�ł́A�����r�́u�����͓��]�_�v�Ƃ͂����Ȃ���̂��H ���Ȃ�̒����Ȃ̂ŗv�Ĉ��p�����Ă��������iHMV-HP2007�N�f�� �����r�̌�����������u���E�ň�ԋꂵ�݂ɖ����������ȁv���j�B
�@�f�߂����ׂ��͍����͓��A�m�g�j�ł����A����ɑ����āA���傤����]�_�Ƃ��������̈Ӗ��ŐӖ����ׂ��ł��傤�B���̕M���͋����r�ł��ˁB�ނ̍����͓��_�]�́A���ѕ���ʂ�z���āA����Ӗ����j�I�Ȓ֎��I�_�]�Ƃ������������ł��B
�@�����Ƃ��ߌ��I�ȋ�a�ɖ����������Ȃ��������l�͒N���H�������������ǓƂɔY�x�[�g�[���F�����낤���B�y�V�~�X�g�������`���C�R�t�X�L�[���B����Ƃ��A�Ȃ̂��ƂŔY�}�[���[���B������E���ɑ��݂��邷�ׂĂ̌����Ȃ����킯�ł͂Ȃ����A�m���Ă���͈͂ł悢�Ƃ����Ȃ�A���̓��͌��܂��Ă���B�����͓���́u�����ȑ�P�ԁv�ł���B�@����͑��^�E�O�㖢���̕]�_�B���S�Ȑ������̗ނ��B���͂���܂Ő������̐�������ǂ�ł������A����قǂ܂ł̂��̂ɏo��������Ƃ͂Ȃ��B�܂��Ɂg���m�Ƃ̑����h�ł���B�o�ꂷ���ȉƂ́A�x�[�g�[���F���A�`���C�R�t�X�L�[�A�}�[���[�A�V���X�^�R�[���B�`�A�u���b�N�i�[�ȂǁA�����Ȃ̑��ȉƂ̖��O���Y�����ƕ��ԁB�����͓������y�j�㊥��������ȍ�ƂƓ���ɂ��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�^����B
�@���������A����Ȃɂ��[���ȋȂ������������͓��Ƃ͂ǂ�������ȉƂ��B�ނ�1963�N�L���ɐ��܂�Ă���B���������ȉƂ��u�������A�y�d�̂�₱�����l�ԊW�ȂǂɊ������܂�邱�Ƃ��悵�Ƃ����A�Ɗw�̓���I�B
�@���́A�ނ͔��ɑ傫�ȓ��̓I�ȃn���f�B�L���b�v������Ă���B�Ȃ�ƁA����Ƃ����犮�S�Ɏ����������Ȃ��̂��B����ǂ��납�A�Ђǂ�����Ŏ��ʂ悤�Ȏv�������Ă���̂��B�������A�ނ͂����l�Ɍ���Ȃ��悤�ɂ��Ă����B�m����̂����������B��Q�Ҏ蒠�̋��t������ł����B�����̉��y����Œ����Ă��炢�����ƍl���Ă������炾�B
�@�ނ̂Ƃ���ɂ̓e���r�ԑg�����Ȃ����Ƃ����b�����x���������Ƃ����B�m���ɁA�����������Ȃ���Q�҂����y�ɑł����ނȂ�āA�����ɂ��e���r���D�݂����Șb���B�����A�����͓��͏�Q�𗘗p���ėL���ɂȂ邱�Ƃ����B�e���r�ǂ���́u���������L���ɂȂ�`�����X�Ȃ̂ɁA�o�J����Ȃ����v�ƌ���ꂽ�Ƃ����B�L���ɂȂ�A�Ȃ�Ȃ��͖��ł͂Ȃ��B������A�����͍�Ȃɑł����݂����������Ƃ����̂��ނ̌��������B�}�[���[�́u���������̎��オ����ė���v�ƌ��������A�����͓��������Ă���Ԃɐ������悤�ȂǂƂ͍l���Ă��Ȃ��B����Ȃɂ����ȂŊ�łȐl�Ԃ́A���̒��ɂقƂ�ǂ��Ȃ����낤�B
�@���̍����͓����A�����̔�����Ԃ����{���u�k�Ђ���o�����B���̓��e�́A����ׂ����̂��B�����Ă��邾���ł��s�v�c�Ȃ��炢�̔ߎS�ȏɔނ͂���B�Ȃ̂ɁA���̂��������O�ō�Ȃ𑱂��Ă���̂��B�{�ɋL���ꂽ���̗l�q��ǂ�Œ����������Ȃ��҂͂��Ȃ����낤�B�L���ɂȂ��ă`�����`�������Ă���ɂȂǂȂ��B�����Ă��邤���ɁA�����邤���ɁA�����ׂ����̂����������Ȃ��̂��B
�@���͍����͓��̗��e�͍L���Ŕ픚���Ă���B���ꂪ�ނ̌��N�ɂ��e�����Ă���̂��B�����͂���Ă��Ȃ����A�\���͍������낤�B�ނ͌����A���y�ȊO�͂ǂ��ł������A���ׂĂ���Ȃ��A�ƁB�������A����ǂ��납��u��u���A���┭���Ƃ̐킢�Ȃ̂��B����͐l���Ƃ������n���ƌĂԂׂ��ł͂Ȃ��̂��B�����͓��͒n���̒��ɂ���B������A�����Ȃ��K�v�Ȃ̂��B�N���V�b�N���K�v�Ȃ̂��B���t������Ȍ����ȑ�P�ԁB����͂܂��ɖ������ŏ����ꂽ�̂ł���B
�@�����̃L�C���[�h�𗅗Ă݂�B�L���|���S�Ɏ����������Ȃ��|����|��Q�Ҏ蒠�|�e���r�ԑg�|�픚�|���y�ȊO�͂���Ȃ��|���┭���|�n���|�����ȁ|�N���V�b�N�E�E�E�E�E�܂�Ŗ{�l�̍������ڂ������̂悤�B�܂��ɖ{�l�ɐ�������āA�����A�����͍����͓��̕��g���̂��̂Ɏv���Ă���B�����āA�����͂��ׂċU��̏��Y�Ɣ��������A���͂₱�̕��͂͂�����A�u���E�ōł��ߌ��I�ŋ�a�ɖ������]�_�v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����I�Ȃ̂́A�y�Ȃ��̂��̂ւ̌��y�͒ʂ��Ղő唼�͋U��Ȏ҂ɂ܂��G�s�\�[�h�ɏI�n���Ă��邱�ƁB����͎��Ɋ���ȉ��y�]�_�Ƃ����ׂ����B
�@�������A�����ׂ����ƂɁA���̕]�_�������ꂽ2007�N11��6�����_�ł́A�����͓��́u�����ȑ�1�ԁv�͉��t����Ă����Ȃ����CD���Ȃ��B�ނ́A�Ȃ�Ƃ��̕����A�u�y���v�Ɓu���`�{�v�����𗊂�ɏ������̂ł���B�����Ȃ��������I���ʏo���܂���悱��Ȍ|���B�����f���X�]�[���Ȃ炢���m�炸�B
�@�u�k�Ў��`�{�u�����ȑ�1�ԁv�̔�����10���B�]�_�f�ڂ�11��6���t��������A���������̖{�ɋ��R�o������Ƃ͎v���Ȃ��B���̃X�s�[�h���́A�u�k�Ђ���̓����������Ӗ�������̂��B���_�E�E�E���`�{�ƕ]�_�̓Z�b�g�ł���B
�@�܂��A���̎��_�ł́A�uHIROSHIMA�v�Ƃ����T�u�^�C�g�����t���Ă��Ȃ��B�����āA�ȗ����������ɂ́A�u���t�������ւ̍���v���X�Əq�ׂ��Ă���B�����Ƃ����Ă������B
�@����ɂ��Ă��A�����͓��̑�R��M�����āA���ꂾ���̕��͂������Ă��܂��鋖���r�Ƃ͈�̂ǂ������l���Ȃ̂��낤���B��������ʂ�z���Ĉ����̈�ɂ܂ŒB���Ă��܂������l�H �����A���̖����u���̃I�y�����I�v�i�m���MOOK�j�̖������I�m�ȃI�y�������_��ǂނɂ��A�ނ����̂悤�ȃy�e���t�ɃR�������x�����悤�Ȕ\�V�C�l�ԂƂ́A�ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B�Ȃ�A�o�����[�X�H
�@�ł́A���`�{���������̕]�_���獲���͓����[�������g�����n��Œǂ��Ă݂悤�B
2007�N10���@�@�@ �u�k�� �����͓����`�u�����ȑ�1�ԁv���@�X�^�[�g��2007�N10�������̍����͓��̎��`�{���B�������̍u�k�Ђ̒S���҂͐�`��敔�̎R�㏹�O�Ƃ����j�ł���i�É�~�璘�F�u���̐����\�����͓���vNHK�o�Ŋ����j�B�ނ����ɖ{���Љ�A�ԑg����f�B���N�^�[�É�~��ɍ����͓���������Ǝv����B�����A���ׂĂ͍u�k�ЂƋ����r�̃^�b�O����n�܂����I�H
�@�@�@ �@11�� 6���@�����r �]�_�u���E�ň�Ԕ߂��݂ɖ����������ȁvHP�Ɍf��
2008�N 9�� 1���@�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v���L���ŏ����@�L���s���܂���
�@�@�@�@�@9��15���@TBS�}���N��NEWS23�Łu�L���R���T�[�g�v�̖͗l����f
2011�N 7��20���@���{�R�����r�A����CD�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v����
2013�N 3��31���@NHK�X�y�V�����u���̐����`������������ȉƁv���f
2013�N 6��15������@�u�����ȑ�1��HIROSHIMA�v�S���c�A�[�J�n
�@����ȑO�ɖڂ�]����ƁA���ڂ��ׂ��ߖڂ�3����B
1996�N�@�f��u�H���v�̉��y�������͓����S���@�����ɂ́A�܂��A�u�k�Ђ��É�������r��NHK���R�����r�A���o�ꂵ�Ă��Ȃ��B�����������͓��͈�l�ł���Ă̂����̂��낤���H ��Ȕ\��0�̍����͓��ɉf�批�y�̈˗����������ނ킯���Ȃ��B�A�����J�E���f�B�A�Ƀp�C�v������Ƃ͎v���Ȃ��B�ł͂��������N�������𒇉���̂��H ���炭����́A�����͓��ƐV�_�������т����l���i�������͏W�c�j�B�t�B�N�T�[X�I
1996�N�@����l�����A�����͓��ɐV�_�����Љ�
2001�N�@TIME���Ɂu����̃x�[�g�[���F���v�ƏЉ���
�@�t�B�N�T�[X�́A1996�N���납��z��ł��A���`�{�����A�����ȑ�1�ԏ����ACD�����ANHK�X�y�V�����A�S���c�A�[�ɘA�Ȃ鍲���͓����[�������g���A�A�ɓ����ɌJ���Ă����Ǝv����B�����r�̐������́A���̈�A�̗���̒��A�v�����[�V�����E�c�[���Ƃ��ď\�S�̖������ʂ����͂��ł���B
�@��������łȂ��A���̍����͓��^���ҁi�O�}�������Ȃǁj���A���o��u�Ȃ��̂��̂Ɋ��������̂�����E�E�E�v�Ɠ����悤�ȕ������ɏI�n���Ă���B���܂�݂��Ƃ��C�C���̂ł͂Ȃ����A�܂��A�悵�Ƃ��悤�B�����A�����ǂ����Ă������Ȃ��̂́A�V�_���L�҉�̗����̒����V�������ɁA�C�P�V���[�V���[�Ɣᔻ���������Ă�����疳�p�̕]�_�Ƃ̂��Ƃł���B����ɂ��Ă͎���B
2014.02.20 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����2�`�{���ɒm��Ȃ������̂��H
 �@�����͓������ŁA�S�[�X�g���C�^�[�Ƃ������݂ɊS���W�܂��Ă���߂����邪�A����͂����������ł͂Ȃ��B�A�C�h�������`������܂ł��Ȃ��A���̑��݂��̂��̂ɕs�����͂Ȃ��B������ATBS-TV�T���f�[���[�j���O�����R�[�i�[�ŁA�����Ɗ֘A���āu�S�[�X�g���C�^�[�v���e�[�}�ɂ����̂͌����͂��ꂾ�B
�@�����͓������ŁA�S�[�X�g���C�^�[�Ƃ������݂ɊS���W�܂��Ă���߂����邪�A����͂����������ł͂Ȃ��B�A�C�h�������`������܂ł��Ȃ��A���̑��݂��̂��̂ɕs�����͂Ȃ��B������ATBS-TV�T���f�[���[�j���O�����R�[�i�[�ŁA�����Ɗ֘A���āu�S�[�X�g���C�^�[�v���e�[�}�ɂ����̂͌����͂��ꂾ�B�@���̎����̊j�S�́u�U���v�ł���B�����O�A�b��ɂȂ������t���B�������̋U���́A�g�o�i�x�C�h���g�Łh�ƋU�������x�A�G�r�ɂ͈Ⴂ�̂Ȃ������Ȃ��̂��������A������͑�Ⴂ�B0��100�Ɍ�����U���B�����̈����͔�r�ɂȂ�Ȃ��B
�@����́A�����͓���Ƃ����y�e���t�́u�U���v�i���S�W�̍�ȉƁj�ɊW�҂͖{���ɋC�Â��Ă��Ȃ������̂��H�Ƃ����e�[�}�ɂ��čl�@����B�����u�ŏ�����C�Â��Ă����v�ƂȂ�A�y�e���t�ƃO�����������ƂɂȂ�A����͌|�p�E������W�Ԃ��郌�R�[�h���[�J�[�A���������ǂɂƂ��ĉ�œI�_���[�W�ƂȂ�B������A�W�҂́A�����ł����Ă������Ă�����Ȃ��͂��B���������āA���͍���B���_�͏o���Ȃ��B�������̂�����t�ƂȂ邾�낤�B
�@���R�[�h���[�J�[�i���{�R�����r�A�j�����_��HP�ɂ͂�������i�v��j
�@���Ђ͍����͓��玁�Ɋւ����A�̕���сu�S�[�X�g���C�^�[�v�Ƃ����V�_�����̋L�҉�̓��e���m�F�������܂����B�����͓��玁��ȂƂ���铖�Д������i�ɂ��ẮA���̍�Ȏҕ\���Ɍ�肪���邱�Ƃ������������܂������Ƃ���A���Ђ͊��ɊY�����i�̏o�ׂ���єz�M�̒�~���s���A����ɏ����X�ɑ��ẮA�Y�����i�̔̔����~�����肢���Ă���܂��B���ЂƂ������܂��ẮA���i�������_�ɂ����Ă͑S���z������Ă��Ȃ��������Ԃł���A�����͓��玁�ɑ��Ă͋�������������Ă���܂��B�@���R�[�h�������̃R�����r�A�́A�uCD�wHIROSHIMA�x������2011�N7�����_�ł́A��i�͍����͓����̐^��ł���{�l�͑S�W�ł���ƔF�����Ă����B�������Ȃ���A���̓x����炪�����ł͂Ȃ��Ɣ��������B����͂���߂Ĉ⊶�ł��蕮�����������̂ł���v�Ƃ��������ł���B�{���ɒm��Ȃ������Ƃ����K���̑i��������B
�@�܂��A�����͓��玁�̒��͂́A3�N�قǑO����́u���t���������鎞������܂łɁv���Ă����Ƃ̂��Ƃł���܂��B���ЂƂ������܂��ẮA�{�l����́u�S�W�v�ł���Ƃ̐������Ă���A���̐������^���ł���Ɗm�M���Ă���܂����̂ŁA����̎Ӎߕ����̓��e�ɂ��ẮA�ɂ߂Ĉ⊶�ł���܂��B
�@CD�u������ ��1�� HIROSHIMA�v�̃v���_�N�V�����m�[�g�ɂ͂�������
�@�����͓����g�͂��̍�i���ł̉��y�ƌĂ�ł��܂��B�����Ƃ�����Έ��ɏے������u�Łv�B�����\���������̉��y�Łu�Łv�̐[���������āA�t�ɏ����ȁu���v�̑�����m�邱�Ƃ��ł���B80���̗����o�āA�Ō�̓V���R�[���X���������Ƃ��̊����B����͂܂��Ɉłɍ~�蒍���u��]�̏����v�Ɋ������܂��B�k�Ђ��N��������ɂ́A���̂悤�Ȑ[���ȓ��e�̍�i��l�X�͋��߂Ă���̂��낤���Ƃ����s�������������Ƃ�����܂������A�t�ɁA�������炱���A�������͂��̉��y��K�v�Ƃ��Ă���̂��Ɗ����Ă��܂��B�@���̕��͂�CD�̃C�����C�E�J�[�h�Ɏ��܂��Ă���B���L�������A���炭�R�����r�A�̍����͓��S���v���f���[�T�[�E���씎�V���ɂ���ď����ꂽ���̂ł��낤�B��Ȏ҂ւ̌h�ӁA��i�ւ̊����A�����ĉ��t�҂ւ̊��ӂ��M���q�ׂ��Ă���B����҂Ƃ��Ă̐^���Ȏg�������`����Ă���B�����ǂނƁA���̎��_�ł́A���쎁�́g�����͓����y�e���t�ł���h�Ȃ�Ă��Ƃ͘I�قǂɂ��v���Ă��Ȃ����Ƃ��`����B
�@������̗D�ꂽ��i�����R�[�h�Ƃ��Č㐢�Ɏc�������A���̐���҂̑z����������i�ݏo���Ă��ꂽ�����͓�����A�����Ė��������������Ă��ꂽ��F���l����Ɠ��������y�c�ɁA�S����h�ӂƊ��ӂ���������Ǝv���܂��B
�@�V�_���L�҉��A�����������C�^�[�_�R�T�m�����쎁�Ɏ��₵���Ƃ���A�u�����͓�����̌��t��M���Ă����悤�Ǝv���܂��v�Ƃ̕ԓ����������������B���̉���ĂȂ��u�M���Ă��������v�ł���B������ǂ��ǂށB�u���̂��Ƃ��M���Ă��������v���H
�@�{�����X�N�[�v�����u�T�ԕ��t�v�i2��20�����j�ɂ���
������m��u�S���ҁv�̔̔����E�J�v�R���̊W�҂͂���������B�u�����͓����w�S�W�ɂȂ����x�Ɛ錾�����ȍ~���A�ނ̎����������Ă��邱�Ƃ́A�Г��ł͊F���m���Ă���Öق̗��������ł����v�@���\�t�͐��Ԃ��\���Ƃ��A�g����������ނ��̂��B�g���ɂ܂ʼnR�����͔̂��邪�A�����ɂ��Ă��܂��C���g���K�v���Ȃ��Ȃ�B���̓V�˓I���\�t�ɂƂ��Đ��O���͂���̂��́B�Г��ł́g�F���m��Öق̗��������h�Ƃ���������������B
�@�����͓�����CD�́A�u�����ȑ�1�ԁwHIROSHIMA�x�v��18�����A�u�����̃\�i�^�v��10������グ�Ă���Ƃ����B�u���@�C�I�����̂��߂̃\�i�`�l�v���A�t�B�M���A�̍����I�肪�g�����Ƃ����蓯���x�̃Z�[���X��������ł������낤�B�P�A�[�e�B�X�g��40�|50�����BDVD������B���グ���z��10���~�ȏ�B����͂�����A���A�[�e�B�X�g�̈����B�Г��\���͂������A��Њ����Ƃ̉�H�̏���݂���ꂽ���낤�B�c�ƃT�C�h���A���̐����̂܂܁A�V�����ǂ�ǂ��[�X���Ăق����Ɗ肤�B��A���A�[�e�B�X�g����В����`���z������B ���h�S�Ōł܂����C�J�T�}�t�����R�[�h��Г��łǂ�ȑԓx������Ă������͑z���ɓ�Ȃ��B
�@AERA2.17���̍����͓��L���u�����ʈ�a�� �R���x���ꂸ�v�ɂ́A�R�����r�A�̒S���҂���ނɗ�������Ă���l�q���L����Ă���B��b�ʖ���ꏏ�ɁB���R�[�h��Ђ̃A�[�e�B�X�g�S���i�f�B���N�^�[���`�S�������˂�ꍇ������j�́A�����͓��̂悤�ȑ啨�̏ꍇ�A�ǂ�Ȏ�ނɂ��K��������B�����ɂ��������Ă��̋@��͑����邩��A�l�Z�����ꏏ�Ƃ������Ƃ��悭����B�������悯��C�S���m���B�����łȂ��Ƃ���͈ڂ�B�����͓����Ƃ��̒S���҂̊W�͂ǂ��������낤���B�܂��A���R�[�h��Ђɂ����ẮA�����A�[�e�B�X�g�Ƃ̐e���x�́A����S���̕�����`�S�����͂邩�ɑ傫���̂��펯�ł���B
�@���R�[�h��Ђ͂��Ă����A�{���̐^�̎d�|���l�́A�É�~��Ȃ�Ɨ��n�̐���v���f���[�T�[�ł���B�ނ������͓��l�^��NHK�ɔ��荞���{�l���B��l�̐e���x�͎����u���̐����v�iNHK�o�Łj�ɏڂ����B�����ɂ́A�Éꎁ���u�F�l�Ƃ��č����͓����̃}���V������K�ˁA��Вn�̂��Ƃ����ꂱ��b���������v�Ƃ���B�͂����āA�����͓��́A�g�F�l�h�̑O�ł��u�S�W�̉��Z�v�����Ă����̂��낤���B
�@2��12���ANHK�����u�����҂̕��ɂ͐^���ƈႤ���e��`���Ă��܂������Ƃ����l�т��邵���Ȃ��B���ʂƂ��Ă��܂��ꂽ�B�C�����Ȃ������v�Ƃ̃R�����g�����\���ꂽ�B�u�m��Ȃ������v�Ɓu������̂͊O���v�̋������B����̃P�[�X�A�m���ɐ���͊O���v���_�N�V�����ł��邪�ANHK�̑����i�ԑg�v���f���[�T�[�j�Ƃ͖��ڂȊW������̂��펯�B���҂͎���������̊W�ł���B
�@�X�N�[�v���u�T�����t�v�𒆐S�ɁA�����͓��@���͉����x�𑝂��Ă���悤�Ɍ�����B�����ڂɂȂ����ΏۂɃ}�X�R�~�͂����e�͂Ȃ��B����Ă������Ēɂ߂���B���A�W�҂��ł�����Ă��邱�ƁB����́A�ۗ��ɂ���Y�^�Y�^�ɂȂ��������͓��́u���ꂶ�ጾ�킹�Ă��炤���ǁA�W�҂͍ŏ�����E�E�E�E�E�v�Ƃ������P�N�\�̈ꌂ�ł͂Ȃ����낤���B
�@���R�[�h�E�v���f���[�T�[�Ɣԑg����v���f���[�T�[�A���R�[�h��Ђ�NHK�́u�m��Ȃ������v�B�F����͂ǂ��v���邾�낤���B
2014.02.16 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����P�`��O���̎���
 �@CD�s���̂��̎���ɁA�������A�N���V�b�N�Ƃ����j�b�`�ȃW��������18������グ�����Ǝ��̋��قȏ�ɁA��Ȏ҂��U�҂������Ƃ��������͓������B�܂��ɑO�㖢���A��O���̂��͂Ȃ��ł���B�i�N���y�ƊE�ɐg�����������̂Ƃ��āA�������ւ����Ȃ����Ƃ͊m���ł���B
�@CD�s���̂��̎���ɁA�������A�N���V�b�N�Ƃ����j�b�`�ȃW��������18������グ�����Ǝ��̋��قȏ�ɁA��Ȏ҂��U�҂������Ƃ��������͓������B�܂��ɑO�㖢���A��O���̂��͂Ȃ��ł���B�i�N���y�ƊE�ɐg�����������̂Ƃ��āA�������ւ����Ȃ����Ƃ͊m���ł���B�@�S�[�X�g���C�^�[���̑��݂����炩�ɂȂ����ȏ�A����A�l�X�Ȏ����≯������яo���Ă��邾�낤�B�����{�ʂ̎��A�����̖{������O��鎖�A�ȂǂȂǁB �u�N�����m�v�ł́A�����̘b�ɂ͌������������A������}�X�R�~�ɂ͏o���Ȃ��Ǝ��̍l�@�����݂����Ǝv���B
�@���̎����͖{���I�ɍ��\�����ł���B�����͓������S�W�̍�ȉƂɂȂ肷�܂��A�R�Ōł߂������̃X�g�[���[�����グ�āA���Ԃ��\�����B���ɂ����̈������Ƃł���B�������Ȃ��琢�Ԃ��\���Ȃ�Ă��Ƃ́A���R�[�h�ƊE�ł͂���قǒ��������Ƃł͂Ȃ��B�����ւ������̎��Ⴊ����B���\�q�f�r���[����ł���B
�@��N�A���疽�������̎�E���\�q�B�ޏ��̃f�r���[�ɓ������āA�d�|���l�i���R�[�h��Ђƃv���_�N�V�����j��2�̉R�������B���R�́u���̂̐���w�������h���̏����v�Ƃ������`���壂ɍ��킹�邽�߂ł���B
�@���̂Ƃ����̎��N���18�B18�͏����Ƃ͂����Ȃ����碐�`���壂ƍ���Ȃ��B�Ȃ��17�ɂ��悤�B�����ŁA�N���1���̂����B���ꂪ��1�̉R�B�h���̏����́g�h���h���������邽�߂̃X�g�[���[����낤�B�S�ӂ̕�ƈꏏ�ɗc�������痬�������Đ��v���������B�R�́g�S�Ӂh�̕����B���ۂ͎㎋���x�ŁA���ꂪ��2�̉R�B
�@�������ē��\�q��1969�N9���Ƀf�r���[���u���ԂɃX�^�[�̍����ˎ~�߂�B�A���o��2��Ń`���[�g37�T�A��1�ʂƂ����L�^�́A�����j���Ă��Ȃ��B�ޏ��̉̏��ƃX�g�[���[�ɍ�ƌܖ؊��V�́u���\�q�̉̂́w���́x�ł͂Ȃ��w���́x�ł���v�Ƃ���������Ŏd�|���l�̈Ӑ}���㉟�������B�ܖ؎��́A���R�ɂ��A�����͓����ɑ��Ă����������A���[�������g���T�|�[�g���Ă���B����ȋ�ɁB
�@�q���V�}�́A�ߋ��̗��j�ł͂Ȃ��B��x�Ɖ߂�������Ԃ��Ȃ��Ɛ������������́A���܌��݁A�ӂ����т̔ߌ�������Ԃ��Ă���B�����͓��炳��̌����ȑ��ԁsHIROSHIMA�t�́A���̍ō��̒����Ȃł���A�����ւ̗\�����͂�����Ȃł���B����͓��{�̉��y�E�����E�ɔ��M���鍰�̌����ȂȂ̂��B�@�ܖ؊��V�������悤�ɐ�^�������\�q�ƍ����͓���B�����悤�ɉR�̃X�g�[���[�Ŋg����}������l�B���A����I�ɈႤ�͖̂{�l�̗͗ʂƉR�̓x�������B���\�q�͂��ĂȂ������������H��̉̂���ł���A�����͓��͉�����y�I�X�L�����������킹�Ȃ������̃y�e���t�B���̉R�͔�掂ɂ͓�����Ȃ������Ȃ��̂����A�����͓��̉R�͔ڗ����ϋ����������ނ��B�����ŕ\���A���\�q�̏ꍇ��90��100�ɂ�����x�̉R�����A�����͓��̃P�[�X��0��100�ɂ��邽���̈�����R���B
�@������A�N���V�b�N�̐��E�ł͂ǂ����H �U��E���E����A�l�X���邪���Ƃ��ă��[�c�@���g��쎖�������Љ��B�t�����X�l���@�C�I���j�X�g�ō�ȉƂ̃}���E�X�E�J�T�h�V���i1892�|1981�j�́A1933�N�A�������Z���҂Ƃ��āu���[�c�@���g��ȃ��@�C�I�������t�ȑ�7�ԁv���o�ł����B���[�c�@���g�̎��M�����������炾�Ƃ����B����ɂ���ɂ́A���[�c�@���g10�̂Ƃ��̍�i�ŁA���C15���̒����A�f���C�[�h�P�Ɍ��悳�ꂽ�Ƃ̈�b���t���Ă����B
�@���ȉƂ̐V�씭���ɐ��Ԃ͐F�߂��������B�t���[�h���q�E�u���[���Ƃ������[�c�@���g�̌��Ђ��^��ƌ��_���AKonh.294a�Ƃ����F��ԍ����^����ꂽ�B���R�[�h��Ђ��g�����o���AEMI�́A�V�ˏ��N���[�f�B�E���j���[�C���̃��@�C�I�����ŁA���R�[�f�B���O���s�����B���̘^���͖��������Ƃ��Ďc���Ă���B
�@�Ƃ��낪1977�N�ɂȂ��āA�J�T�h�V���́A����͎������������삾�ƔF�߂邱�ƂɂȂ�B�������炱�̌��ɋ^�������Ă����A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���̒Njy�̌��ʂ������B�ނ́u���M����������v�Ƃ̗v�����J�T�h�V�������X�ɋ����Ƃ����[�ƂȂ����i������A�����͓��Ɂu��Ȃ��Ă���Ƃ����������v�ƌ������Njy����Δ��o�����͂��ł���j�B
�@�J�T�h�V���������������@�� ����𐢂ɑ���o�����߁B�J�T�h�V����Ȗ��`�ł͒N������ɂ��Ă���Ȃ����A���[�c�@���g�̍�i�Ȃ烌�R�[�h�ɂȂ�B�����āu���������[�c�@���g�̍�i���v�Ƃ̕]����A���l�A�łق����ށB�����I �Ƃ����}�����B
�@�J�T�h�V���́A�g�J�T�h�V����ȁh�ł͑���ɂ���Ȃ�����A��������[�c�@���g�̍�ȂƋU�����B�Ȃ������ĉ��t����Ƃ����X�L�������邩��o�������Ƃ��B
�����͓��́A��Ȃ̋Z�p�����t�̋Z�p���Ȃ���ɁA���l�ɏ���������i������ƋU�����B�@�ړI�͖����Ƌ��B�J�T�h�V���Ƃ͌���I�ɈႤ�B�����āA�ߋ��̂����Ȃ鎖��Ƃ����v���Ȃ��B�܂��ɋ�O���̎����Ȃ̂ł���B
�@�Ȃ��������̂͊m���ɐV�_���������A�w�����o�����͍̂����͓��炱�̉����B���̎d�g�݂�������͉̂�������A�������Ȃ���Δނ̍�i�����ɏo�邱�Ƃ͂Ȃ������B������ނ����ɐ�Ε��]����͓̂�����O�B�]���Ȕނ͈ꐶ���ɂ��Ă���B�����͓��͍����������Ă����B
�@�����͓��́A���Z�Ɣ��荞�݂̓V�ˁA�����A�����̍��\�t�Ȃ̂��B����ȔނɓV�[���~���B�u�������A�S�W�����Ƃ��B��������Ε��ʂ��ǂ߂Ȃ����Ƃ��떂������B�S�W�ō�Ȃ��ł���ƂȂ�A�܂��Ɍ���̃x�[�g�[���F���B��ΓB�����͈�C�ɏオ��B���W�F���h�ɂȂ��v�B�R�Ōł߂������X�^�[���\�����n�߂�B����Ȕނ̋��U�ɗx�炳��ă��R�[�h�E���[�J�[�A���y�]�_�ƁA���f�B�A����肾���B
�@���ʂ̐l�Ԃ͉R�����قǗǐS�̙�ӂɉՂ܂������̂����A�����͓��Ƃ����l�́A���ꂪ�����ƂȂ��āA�₪�Ă̓z�����m�Ǝv�����ށB���������^�C�v�̐l�ԂȂ̂��낤�B
�@�S�[�X�g���C�^�[�̐V�_����͍˔\�����ȉƂł���B���i�͐^�ʖڂ��̂��̂ɂ݂���B�ŏ��̂����͂悩�����B�w�����ǂ���ɍ�Ȃ��邱�Ƃ͋Z�p�̃X�L���E�A�b�v�Ɍq���邵�A��w�u�t�̐��P�����̍�ȗ��������Ă���B���������Γ��B�������A�����̍�����y�Ȃ����ɂȂ��Đ��̒��ɗ����B�f���Ɋ������B
�@���A���炭���āA�����͓��̖\��������ʕ����Ɍ����������B��Вn�ɏo���������Ȕ�Ў҂��\���B�g��҂��x���A���̉������������B
�@�����ȉ��y�l�Ԃ��A���U�ɖ������y�e���t�̍s��Ɋ������Ȃ��Ȃ�B���̂܂܂̊W�𑱂��邱�Ƃɋ��|���o����悤�ɂȂ�B
�@�����āA���ɐV�_���͑ς����Ȃ��Ȃ萢�ԂɌ��\�����B�u���͔ނ̃S�[�X�g���C�^�[�ł����B���͔ނ̋��Ǝ҂ł��B�ނ͋Ȃ͍��܂���B���ʂ������܂���B���ׂĂ̋Ȃ͎������܂����B�ނ̃s�A�m�͏��S�҂̈���o�܂���B�ނ͎����������܂��B����ȏ㐢�̒����\�����Ƃ͏o���܂���v
�@����́A�uHIROSHIMA�v�̍�i�]���ƃ����X�^�[���������w�i�ɂ��Č��y�������B
2014.02.10 (��) Jiiiji�̂Ԃ₫�`�t�ĂԃN���V�b�N
�@���[���ARay�����I 2��4���͗��t�B��̏�ł͂����t���B�ł����̓��A�����͐Ⴊ�~���āA�܂��܂�����Ȏ����͂Ȃ�������ˁB������Jiiji�͑M�����B�~������ȂΏt�����炶�B�C��͓~�ł��C���͏t�ցB�����A�N���V�b�N���y���ďt����肵�悤�B�肵�āu�t�ĂԃN���V�b�N�v�B�ł́A�I�Ȃ̎n�܂�n�܂�[���I�I�@�܂��A�t�Ƃ����A�����f���X�]�[���i1809�|1847�j�́u�t�̉́v�B�����ԁB���̋Ȃ̓s�A�m�ȏW�u�����́v�̒��ɓ����Ă���B�V�˃����f���X�]�[�����A�o�̃t�@�j�[�̌��t����M���āA�̂̂Ȃ��s�A�m�Ȃ��v�������B�̎����Ȃ��Ă��l���̂��悤�ȃs�A�m�ȁB������A���̋ȁA�s�A�m���̂��Ă�B�����A�`���g�^�[�������h�̏㏸�������������ł킩���ˁB�t�����̊�тɖ������ȁB�l�C�Ȃ����ɃI�[�P�X�g���n�ߑ����̕ҋȂ�����BJ-Pop�Ȃ�Yuming�u�t�悱���v���H
 �@�����́A�����c�u�t�̐��v�B�����c�����n���E�V���g���E�X�U�i1825�|1899�j���A�u�_�y�X�g�؍ݒ��A�F�l�̃t�����c�E���X�g�ƈꏏ�̃p�[�e�B�[�ő����I�ɍ�����Ƃ����Ă����B58�A�ӔN�̍�i�����A��Ȏ�3�x�ڂ̌����O�̃E�L�E�L�����C�b�p�C�I�����ʂ�tࣖ����ĂƂ��B�L�����f�B�[�Y�́u�t��ԁv�I�H
�@�����́A�����c�u�t�̐��v�B�����c�����n���E�V���g���E�X�U�i1825�|1899�j���A�u�_�y�X�g�؍ݒ��A�F�l�̃t�����c�E���X�g�ƈꏏ�̃p�[�e�B�[�ő����I�ɍ�����Ƃ����Ă����B58�A�ӔN�̍�i�����A��Ȏ�3�x�ڂ̌����O�̃E�L�E�L�����C�b�p�C�I�����ʂ�tࣖ����ĂƂ��B�L�����f�B�[�Y�́u�t��ԁv�I�H�@�u�t�̐��v�́A�R�c�m���ē����C�ɓ���݂����ŁA�u�j�͂炢��v�̑�8��u�Ў��Y���́v�Ƒ�9��u�Ė����v�ŁA���đ����Ɏg���Ă����B
�@�V���[�}���i1810�|1856�j�̌����ȑ�1�ԁu�t�v�́A1841�N�̍�i�B�O�N�A���̃N�����ƌ������A�܂��ɍK���̐Ⓒ�̂��낾����A���g�����Ȃɔ��f���Ă���ˁB�t���r�A�h���t�E�x�b�J�[�̎��ɐG������ď������B
�@�u�t�Ɋv�̓O���[�N�i1843�|1907�j�̃s�A�m�ȏW�u�R��i�W�v�̑�5�ȁB�`���A�t��������肵�̂ъ��悤�ȉ���ɁA�x���t��S�҂�����k���l�̋C������������悤���ˁB�u�k���̏t�v�ɔ@���̓`�g���Ղ��ȁH
 �@���B���@���f�B�i1678�|1741�j�̃��@�C�I�������t�ȁu�l�G�v�́u�t�v���悭�m���Ă���B���y�j��ŏ��̕W�艹�y�Ƃ����Ă悭�A3�̊y�͂ɂ͑��X�\�l�b�g�i���j���t���Ă���B��1�y�͂́g���������͊y�����̂��t�Ɉ��A�𑗂�h�A��2�y�͂́g�Ԃ��炫�����q��ŗr�����͋�����B�����ȔԌ����������茩����h�A��3�y�͂ɂ́g�r�������j���t����̉� �t���j���ėx�肾���h���Ăȋ�ɂˁB���̃\�l�b�g��`�ʂ��郔�B���@���f�B�̃f�b�T���͕͂�����Ȃ��ˁB
�@���B���@���f�B�i1678�|1741�j�̃��@�C�I�������t�ȁu�l�G�v�́u�t�v���悭�m���Ă���B���y�j��ŏ��̕W�艹�y�Ƃ����Ă悭�A3�̊y�͂ɂ͑��X�\�l�b�g�i���j���t���Ă���B��1�y�͂́g���������͊y�����̂��t�Ɉ��A�𑗂�h�A��2�y�͂́g�Ԃ��炫�����q��ŗr�����͋�����B�����ȔԌ����������茩����h�A��3�y�͂ɂ́g�r�������j���t����̉� �t���j���ėx�肾���h���Ăȋ�ɂˁB���̃\�l�b�g��`�ʂ��郔�B���@���f�B�̃f�b�T���͕͂�����Ȃ��ˁB�@�C�M���X�̍�ȉƃf�B�[���A�X�i1862�|1934�j�̊nj��y�ȁu�t ���߂ẴJ�b�R�E���āv�́A�W���F���̏t���B�I�P�̕Ґ����������A�}����������������������B�悭�����ƃJ�b�R�E�̖������������Ă����B���͋C�͋{�铹�Y�u�t�̊C�v������B
�@�x�[�g�[���F���i1770�|1827�j�̃��@�C�I�����E�\�i�^��5�Ԃ́u�t�v�Ƃ����j�b�N�l�[���ŌĂ�Ă����B����͋Ȓ�����o�ŎЂ��������́B���̖��̂Ƃ���A�t�炵�����}���e�B�b�N�Ȗ��x���ɖ����Ă���B������Y�́u�ԁv�ƃ����f�B�[���d�Ȃ邼�I
�@�x�[�g�[���F���ɂ͋w�����̖��Ȃ��������ǁA�{�l�����Â������̂Ƃ����łȂ����̂ɕ����邱�Ƃ��ł���B�O�҂́A�����ȑ�3�ԁu�p�Y�v�A��6�ԁu�c���v�A�s�A�m�E�\�i�^��8�ԁu�ߜƁv�ȂǁB��҂͌����ȑ�5�ԁu�^���v�A�s�A�m�E�\�i�^��14�ԁu�����v�A�s�A�m���t�ȑ�5�ԁu�c��v�Ȃǂ��B����Ȃ��Ƃ������Ă����Ɩʔ�����B
 �@�A�����J�̍�ȉ� �R�[�v�����h�i1900�|1990�j�̃o���G���y�u�A�p���`�A�̏t�v��1945�N�̃s���[���b�c�@�[���y��܍�B�A�p���`�A�̓A�����J���k���Ɉʒu����A�p���`�A�R���̂��ƁB�������A�^�C�g���͌�t������A�A�p���`�A��`�ʂ������y�Ƃ����킯����Ȃ��B�܂��A���͋C���m���Ă��ƁB�g�Ȃ͑S����8�Ȃ��琬�邪�A�����ł͑�7�ȁu�V�F�[�J�[�h�̊y�Ȃɂ��ϑt�ȁv��I�ڂ��B�f�ނ̓R�[�v�����h�����ӂ̃A�����J�������f�B�[�B3�����炸�̒���5�̕ϑt��D�荞�ޓV�ˋZ�������Ă�B�J���b�Ɛ��ݐ����A�����J�̏t�B�悵�������낤�u�t�������ˁv�̎����Ƒ����B
�@�A�����J�̍�ȉ� �R�[�v�����h�i1900�|1990�j�̃o���G���y�u�A�p���`�A�̏t�v��1945�N�̃s���[���b�c�@�[���y��܍�B�A�p���`�A�̓A�����J���k���Ɉʒu����A�p���`�A�R���̂��ƁB�������A�^�C�g���͌�t������A�A�p���`�A��`�ʂ������y�Ƃ����킯����Ȃ��B�܂��A���͋C���m���Ă��ƁB�g�Ȃ͑S����8�Ȃ��琬�邪�A�����ł͑�7�ȁu�V�F�[�J�[�h�̊y�Ȃɂ��ϑt�ȁv��I�ڂ��B�f�ނ̓R�[�v�����h�����ӂ̃A�����J�������f�B�[�B3�����炸�̒���5�̕ϑt��D�荞�ޓV�ˋZ�������Ă�B�J���b�Ɛ��ݐ����A�����J�̏t�B�悵�������낤�u�t�������ˁv�̎����Ƒ����B�@�t�̋G��Ɂg�Ђ�h������B������A�Ō�Ɂg�Ђ�h�y�Ȃ�3�����Ă݂悤�B�`�g�������ȁH �`���C�R�t�X�L�[�i1840�|1893�j�́u�Ђ�̉́v�́A�s�A�m�ȏW�u�l�G�v��3���ȁB���V�A�̏t�ɂ͂ǂ������D���Y���ˁB�����݂䂫�u�t�Ȃ̂Ɂv�̈����ƒʂ���H �n�C�h���i1732�|1809�j�́u�Ђ�v�́A�L���Ȍ��y�l�d�t�Ȃ�1�ȁB�����ɂ��p�p�E�n�C�h���炵���̂ǂ��ȋȂ���ˁB�Ō�̓C�M���X�̍�ȉƃ��H�[���E�E�B���A���Y�i1872�|1958�j�́u�����Ђ�v�B�g���@�C�I�����Ɗnj��y�̂��߂̃��}���X�h�ƕ��肪�t���Ă���B�Ђ肪���Ɍ������ĕ����オ���i��`�������@�C�I�����̉B�ꂽ���Ȃ��B
�@����Ray�����B�������ďt��҂��܂��傤�B�F�l���A�������p�ł����炨�\���o���������B�A���A���݂����邾���ł����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�ĂԃN���V�b�N
�@�@�@�@�@�@�@�P�@�t�̉́i�����f���X�]�[���j
�@�@�@�@�@�@�@�Q�@�t�̐��i���n���E�V���g���E�X�U�j
�@�@�@�@�@�@�@�R�@������ ��1�ԁu�t�v���� ��1�y�́i�V���[�}���j
�@�@�@�@�@�@�@�S�@�R��i�W��袏t�Ɋ�i�O���[�O�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���t�ȁu�l�G�v���u�t�v�i���B���@���f�B�j
�@�@�@�@�@�@�@�T�@��1�y��
�@�@�@�@�@�@�@�U�@��2�y��
�@�@�@�@�@�@�@�V�@��3�y��
�@�@�@�@�@�@�@�W�@�t ���߂ẴJ�b�R�E���āi�f�B�[���A�X�j
�@�@�@�@�@�@�@�X�@���@�C�I�����E�\�i�^ ��5�ԁu�t�v(�x�[�g�[���F��)
�@�@�@�@�@�@�P�O�@�o���G�g�ȁu�A�p���`�A�̏t�v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�V�F�[�J�[�h�̊y�Ȃɂ��ϑt�ȁv�i�R�[�v�����h�j
�@�@�@�@�@�@�P�P�@�u�l�G�v����3���u�Ђ�̉́v�i�`���C�R�t�X�L�[�j
�@�@�@�@�@�@�P�Q�@���y�l�d�t�ȁu�Ђ�v�����1�y�́i�n�C�h���j
�@�@�@�@�@�@�P�R�@�����Ђ�i���H�[���E�E�B���A���Y�j
2014.01.25 (�y) �N���E�f�B�I�E�A�o�h�Ǔ�
 �@1��20���A�C�^���A�̖��w���҃N���E�f�B�I�E�A�o�h���S���Ȃ����B1933�N���܂ꂾ����A���V�����i1935���j�A�Y�r���E���[�^�i1936���j��Ɠ�����ł���B��N�H�̗������~�߂ł���ȗ\���͂������B80�͂܂��܂��Ⴂ�̂ɁA�a���ɂ͏��ĂȂ������B�ߔN�̐i���ɂ͖ڂ�������ׂ����̂�����������A�{���Ɏc�O�ł���B
�@1��20���A�C�^���A�̖��w���҃N���E�f�B�I�E�A�o�h���S���Ȃ����B1933�N���܂ꂾ����A���V�����i1935���j�A�Y�r���E���[�^�i1936���j��Ɠ�����ł���B��N�H�̗������~�߂ł���ȗ\���͂������B80�͂܂��܂��Ⴂ�̂ɁA�a���ɂ͏��ĂȂ������B�ߔN�̐i���ɂ͖ڂ�������ׂ����̂�����������A�{���Ɏc�O�ł���B�@���y�̐F�����́A�f�B�I�j�\�X���A�|���B�t���g���F���O���[���g�X�J�j�[�j�B�h�C�c���C�^���A�B�Z�����u���B�Â�薾�E�E�E�E�E�����������̒��ɐ���������������ƕ����яオ��u�A�|���I�������v�B�x�������E�t�B���̒c�����u�J����������ɔ�ׂ�Ɖ��������ɂȂ����B�ォ�牺�܂ŃX�R�A�̉�����������v�Ə،�����B���y���́A��ς��q�ρB���ӂ�莩�R�B�s�����^���B�Ƃ������Ƃ��납�B
�@�ނ��w�������ŐS���������ƁB����́u�g���̎n���h�ւ̋C�����v�ł���B���̂��Ƃ̓��[�X�E�I�[�P�X�g���̃��n�[�T���f���Ŋ������B�I�[�P�X�g���͉��̎n�����d�v�ł���B�����̃p�[�g�̒e���������Ⴂ���Ȃ��B�����̏o�����������̒e����ɐS�����߂ēn���̂ł���B��ق������Ԃ���������e���n�߂�̂ł͂Ȃ��B�O�̒e���肩��C���������߂Ď��̂ł���B�u�݂��ɕ��������\�́B����͂Ƃ��ɉ��y����Ƃ��������v�ƃA�o�h�͂����B����Ȕނ̐M���́A�ӔN�ɂȂ�قNj��łƂȂ�O�ꂵ�Ă䂭�B
�@���́u�����L�����p�X�v�Ȃ�T�C�g�ŁA���Ȃ̖����t�I�т��s���Ă���B�܂��y�Ȃ�I�сA�����ƒ�]�̂��鉉�t�͉k�炳���ɂ��̑��\�Ȍ���̉��t���W�߂�B�������̂�50�_�A����20�_���炢�ɂȂ�B���������ׂĕ����A10�_���m�~�l�[�g����B����ɂ�����A�u���C���h�ŕ�����������܂Œ�������ŁA�u���ɂ̃x�X�g�v����_�I�肷��B�I��̊�͓ƒf�Ō��ߍ��y�Ȃ̗��z�I���ł����ł���B�s�ʂ̃|�C���g�͂R�A�u�e���|�v�u�T�E���h�v�u�߉v�B���ʁA��]���閼�Ղ��X���i�����܂�ꍇ������A�m�[�}�[�N�Ղ��I�肳��邱�Ƃ�����B���ꂪ�ʔ����B���݁A50�y�Ȃ̑I�肪�I���A���x�~���Ă��邪�A����܂łŁA�A�o�h�֘A�́u���ɂ̃x�X�g�v��3����B
 �@�܂��́A�u���[���X�u�����ȑ�2�ԃj�����v�i�x�������E�t�B��1988�j�ł���B���̃��i�[�h�E�o�[���X�^�C���́A�u���[���X�̉��y���u���̖��͔͂ޓ��L�̓��̒��ɐ���ł���B�ÓT���ƃ��}�����B�d���Ɛ����B���i�ƌ��� �ȂǂȂǁB�����A�Ȃ̂�B�Ȃ̂�����Ȃ��B�܂��ɁA�����a瀂������A�u���[���X�����Ă��̂悤�Ȍ����ȋْ����鉹�y��n�点�A�ǂ����Ƃ��Ă��u���[���X�̐��ł����₫�����鉹�y��n��o�������̂��v�ƕ]�����B�܂��Ɏ����A����͓N�w���B�h�C�c�I�_���琼�c�N�w�u�����I���ȓ���v�ցB���ꂼ�A�ʎ�S�o�u�F������v�A�Ԓ˕s��v�u����ł����̂��v�B�����A�u���[���X�̓u���[���X�B����ł����̂��u���[���X�A�Ȃ̂��B�A�o�h�́g�u��2�h�͂܂��Ƀo�[���X�^�C���̒�`���̂��́B�J�Ԍ�����g�u���[���X�̓c�������ȁh�Ȃ�Ă���Ȃ��̂ł����āA����͂܂��ɓV��̐��ł���n�ォ��̋F��A�u���[���X�̚������̂��̂Ȃ̂��B
�@�܂��́A�u���[���X�u�����ȑ�2�ԃj�����v�i�x�������E�t�B��1988�j�ł���B���̃��i�[�h�E�o�[���X�^�C���́A�u���[���X�̉��y���u���̖��͔͂ޓ��L�̓��̒��ɐ���ł���B�ÓT���ƃ��}�����B�d���Ɛ����B���i�ƌ��� �ȂǂȂǁB�����A�Ȃ̂�B�Ȃ̂�����Ȃ��B�܂��ɁA�����a瀂������A�u���[���X�����Ă��̂悤�Ȍ����ȋْ����鉹�y��n�点�A�ǂ����Ƃ��Ă��u���[���X�̐��ł����₫�����鉹�y��n��o�������̂��v�ƕ]�����B�܂��Ɏ����A����͓N�w���B�h�C�c�I�_���琼�c�N�w�u�����I���ȓ���v�ցB���ꂼ�A�ʎ�S�o�u�F������v�A�Ԓ˕s��v�u����ł����̂��v�B�����A�u���[���X�̓u���[���X�B����ł����̂��u���[���X�A�Ȃ̂��B�A�o�h�́g�u��2�h�͂܂��Ƀo�[���X�^�C���̒�`���̂��́B�J�Ԍ�����g�u���[���X�̓c�������ȁh�Ȃ�Ă���Ȃ��̂ł����āA����͂܂��ɓV��̐��ł���n�ォ��̋F��A�u���[���X�̚������̂��̂Ȃ̂��B�@�u�u��2�v���u�c���v�ɂȂ��炦���̂̓h�C�c�l�W���[�i���X�g�A�����^�[�E�j�[�}���i1876�|1953�j�Ƃ����l�炵�����A���{�̕����ɂ͂��̃t���[�Y���×����Ă���B���݂ɁA���̎莝�������Ճ��C�i�[�m�[�c��7�������̃t���[�Y���܂Ƃ��Ɏ��グ�Ă��邪�A���̉��I�v���͕����́B�N���V�b�N�̓ǂݕ����܂�Ȃ��킯�ł���B �A�o�h�́u�u��2�v�A�F�����̓g�X�J�j�[�j�I�����A�e���|�̓t���g���F���O���[�ɋ߂��B���Ȃ݂ɁA���t���Ԃ́A�g�X�J�j�[�j37��17�b�A�t���g���F���O���[40��51�b�A�A�o�h40��47�b�i��1�y�͒��J��Ԃ��������j�ł���B
 �@�u���[���X�u�s�A�m���t�� ��2�� �σ������v�i�x�������E�t�B���A�s�A�m�F�A���t���b�h�E�u�����f��1991�j����i�ł���B
�@�u���[���X�u�s�A�m���t�� ��2�� �σ������v�i�x�������E�t�B���A�s�A�m�F�A���t���b�h�E�u�����f��1991�j����i�ł���B�@���̋Ȃ́A�C�^���A���s�̎Y���ŁA�u���[���X�̃C�^���A�ւ̓��ۂɈ��Ă���B�܂�ŃA���f���Z���ɂ�����u�������l�v�H �u���[���X�I�F���̒��ɃC�^���A�̐n�����ށB���Ԃ���Ɨz���A���x���ƌy�₩���A�A�o�h���u�����f���Ղ͂��̃o�����X���ō��Ȃ̂��B�A�o�h�ɂ͖��F�|���[�j�Ƃ̋����Ձi�x�������E�t�B��1995�j�����邪�A�u�����f���Ղɂ͉����y�Ȃ��B��Ƀs�A�m�ɂ����閧�x�̍��͗�R�ŁA���ꂼ�i���ɐF�����Ȃ�����I�������B
�@���t�Ȃł́A�����[���@�Ƃ̃u���[���X�u���@�C�I�������t�� �j�����v�i�x�������E�t�B��1993�j�A�[���L���Ƃ̃��[�c�@���g�u�s�A�m���t�� ��12�� �C���� K414�v�i�����h�������y�c1982�j�Ȃǂ��f���炵���B
 �@�Ō�́A�}�[���[�u������ ��2�� �����v�i���c�F�����j�Պnj��y�c2003�N8�����^���C�uCD&DVD�j�ł���B���̋Ȃ́A�����Ɏn�܂�A�����Ȑl���̉�z�A�����̌����A�_�ւ̉�A�A�����ĕ����ŏI���B���Ɛ��ƕ����Ƃ����l�Ԃ̑������鍪���I�{���������ɂ���B���t�҂��S�Ɏ����ӎ����Ă��Ȃ��Ƃ��̉��y�͕`���Ȃ��B
�@�Ō�́A�}�[���[�u������ ��2�� �����v�i���c�F�����j�Պnj��y�c2003�N8�����^���C�uCD&DVD�j�ł���B���̋Ȃ́A�����Ɏn�܂�A�����Ȑl���̉�z�A�����̌����A�_�ւ̉�A�A�����ĕ����ŏI���B���Ɛ��ƕ����Ƃ����l�Ԃ̑������鍪���I�{���������ɂ���B���t�҂��S�Ɏ����ӎ����Ă��Ȃ��Ƃ��̉��y�͕`���Ȃ��B�@�����������A�o�h�́A���̕�����u�����v�������B�a���������ăI�[�P�X�g���ւ̈ӎv�O�ꂪ��苭�łɂȂ����B�_�ւ̋F������������낤�B2003�N8��19���A�u�����A���ׂĂ�����Č������v�Ɣނ͌������B���y�ɐV���Ȑ������������܂ꂽ�̂ł���B
�@�u�A�|���I�������v�̊�͂��̂܂܂ɁA�R�~���j�P�[�V���������ɂȂ������ʁA���y�ɗ͂������A��ЂƂ̉��Ɉӎu���U��B���ׂẲ����������L�@�I�Ɍq����B�c���̐��������Ƃ����\��͂ǂ����B���ɏ݂����X���Ă���B���y���邱�Ƃ̊�тɖ������ӂ�Ă���B�܂��ɉ��y�������Ă���B�a���_�@�ɉ��y�����I�ɕς��A�ނ̌|�p�͂����Ɋ��������B�A�o�h�����c�F�����́A�w���҂ƃI�[�P�X�g���Ƃ����W�����ĂȂ��̈�ɒB�����A��Ղ̃R���r�ƂȂ����B
�@�u��p�O�ɔ�ׂđ̏d��2K���������B�̒��������Ԃ邢���B���y�̒T���ɂ͌��E�͂Ȃ��B���ꂩ����V�������y�n���ւ���܂ʒNj��𑱂������v�B�����b���Ă���10�N���A�A�o�h�͐��ɋA��ʐl�ƂȂ��Ă��܂����B�܂��܂������̑f���炵�����y��n�����Ă��ꂽ�͂��Ȃ̂ɁB�{�l�A�ǂ�Ȃɂ����O�������낤�B2002�N�A�A�o�h���x�������E�t�B�����������Ƃ��A�x�������̐l�X�͔ނ̕s�݂�Q�����B���A���E�̉��y�t�@���͔ނ̕s�݂�Q���B
�@�u�n�܂�͂��������ɑ��鈤��B�l�ɑ��鈤�ł��蕨���ւ̈����v����������b���Ă����A�o�h�́A���̌��t�ʂ�A�����{��k�Ќ��2011�N8��9���ɂ́A���c�F�����Ń}�[���[�́u�����ȑ�10�ԃA�_�[�W���v�����t���Ă��ꂽ�B�u���y�����Ƃ��A������ʂŊF�l�̎x���ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��v�Ƃ������b�Z�[�W�ƂƂ��ɁB����͂܂��ɋF��̉��y�������B2013�N�H�ɂ́A��Вn���Ԗ₷��\�肾�����ƕ����B�N���E�f�B�I�E�A�o�h�͐l�Ԉ��̌|�p�Ƃ������B
�@�u���y�ɂ����Ē��ق͂ƂĂ��d�v���B�������ق̒��Ɋɂ₩�ɏ����Ă䂭���̂�����B�����āA���ق͉i���ɑ����v�i�h�L�������^���[�f���u���ق��v2003���j����������A�o�h���g���A���ق̒��ɏ����Đ����Ă��܂����B�߂����B�₵���B�����́A���ꂩ��A��̉��������̂��낤���H
2014.01.20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�G���^����
�@Ray�����A��͂ǂ������B�悾���āA�M��40�����o���Ⴄ����AJiiji�͐S�z������B�Ԃ����̑���������˔������]�������������S�������ǂˁB�n���͖��\�L�̊��g�̂悤�ŁA�A�����J���C�݂���A�݂���ɂ�炾���Ă��B���ׂȂLj����Ȃ��悤�ɂˁB �@2014�N���U�A�܂��̓E�B�[���E�t�B�� �j���[�C���[�R���T�[�g�B������Ȃ����N�͎n�܂�Ȃ��B���N�r�b�N�������̂́A�m���Ă�Ȃ���������1�Ȃ������������ƁB�Ō�ɂ݂�ȂŁu�����܂��Ă��߂łƂ��v�ƈ��A����u���������h�i�E�v�Ɖ��S�̂��蔏�q�Ő���オ��u���f�c�L�[�s�i�ȁv�̒��2�Ȃ������ƂˁB
�@2014�N���U�A�܂��̓E�B�[���E�t�B�� �j���[�C���[�R���T�[�g�B������Ȃ����N�͎n�܂�Ȃ��B���N�r�b�N�������̂́A�m���Ă�Ȃ���������1�Ȃ������������ƁB�Ō�ɂ݂�ȂŁu�����܂��Ă��߂łƂ��v�ƈ��A����u���������h�i�E�v�Ɖ��S�̂��蔏�q�Ő���オ��u���f�c�L�[�s�i�ȁv�̒��2�Ȃ������ƂˁB�@�w���̓_�j�G���E�o�����{�C���i1942�|�j�B�u�G�W�v�g�s�i�ȁv�A�����c�u����l ����Ƃ�v�A�u���a�̞��L�v�Ƃ����I�Ȃɔނ̃|���V�[���\���B�����\���E�\���a�B�o�����{�C���̓A���[���`�����܂�̃��V�A�n���_���l�ŁA�C�X���G���ƃp���X�`�i�̘a�����肢�A�����Ǝ��H���Ă���w���҂ȂB�C�X���G���ƃA���u�����̍����I�[�P�X�g���A�E�F�X�g=�C�[�X�^���E�f�B���@���nj��y�c�̊������A�p���X�`�i�n�A�����J�l�w�҃T�C�[�h�ɋ����āA���i���Ă���B�u���a�����Ԃ�������Ȃ��A��l�ЂƂ肪�݂��̈ӎv��ʂ��铹��T�����H���Ă䂭���Ƃ�����v�Ƃ����ނ̃��b�Z�[�W��^���Ɏ~�߂悤�B����͉�X�̓����E���ؖ��ɂ��ʂ��邱�Ƃ��Ǝv���B
�@��N��12��25���ɂ́A���N�P��̏��c�a���u�N���X�}�X�̖v�iTBS�j�������B��1���2001�N������A����13��𐔂���B���̑�1��́A�R���B�Y�Ƃ̂���肪�b��ɂȂ����B�ԑg�`���ŎR���̎莆���Љ�ꂽ�B�u���������o�ď��c����Ɂw�N���X�}�X�C�u�x���̂��Ă��炦�鎞��ɂȂ����Ƃ͊��S���ʁv���ĂˁB����́A�u�A�[�e�B�X�g���m���݂����h��������p�t�H�[�}���X�̏����낤�v�Ƃ������c�̌Ăт����ɑ��Ă̂��́B���������Ȃ�����A�o���ɂ͎���Ȃ������B����͎R���ɂƂ��Ă͓��R�̂��ƂŁA�e���r�ɂ͂܂��o�Ȃ�����A���傤���Ȃ��B�ނ���A���c�ɑ��Đ^���ɕԎ������������Ƃ��A����I�������Ǝv���B��l�͉��y�����Ⴄ����������S���ړ_���Ȃ���������A�s���������ꂽ��������B�ł��A������������y�Ƃ������ʂ̏�̒��ł����Ƒ��葱���Ă�����l�A5�ΈႢ�����Ǎ���ɂ͐�F�ӎ��݂����Ȃ��̂�����낤�ˁB
 �@2013�N�̃Q�X�g�͋g�c��Y�B�������1���B���L�����A���i�����ׂĂ����낤����B�Ƃ��낪�A�Ȃ����̏��c�̑ԓx�́B���ߌ��͈ꐶ�����Ⴂ����̂���B�����낤�͑�l������j�R�j�R���ė����Ă邯�ǁA�t�@������݂���u�������Ȃ��̂��v�����B�����āA�����낤�͂ˁA�����ŋȍ���āA�̂��āA�R���T�[�g����āA���R�[�h�o���āA�q�b�g����B��������J-POP�A�[�e�B�X�g�̑c�B���ׂĂ̓��͂����낤�ɒʂ���B�ʊi�̃J���X�}�Ȃ̂��B�����݂䂫���u�����낤����͕ʊi�B���h���邵���Ȃ��l�v���Č����Ă���B�N��a���A��؉�V�A�����A���Â�����ɂȂ�܂������邯�ǁA�����낤�ɑ��Ă͂����͐�ɋ�����I�I
�@2013�N�̃Q�X�g�͋g�c��Y�B�������1���B���L�����A���i�����ׂĂ����낤����B�Ƃ��낪�A�Ȃ����̏��c�̑ԓx�́B���ߌ��͈ꐶ�����Ⴂ����̂���B�����낤�͑�l������j�R�j�R���ė����Ă邯�ǁA�t�@������݂���u�������Ȃ��̂��v�����B�����āA�����낤�͂ˁA�����ŋȍ���āA�̂��āA�R���T�[�g����āA���R�[�h�o���āA�q�b�g����B��������J-POP�A�[�e�B�X�g�̑c�B���ׂĂ̓��͂����낤�ɒʂ���B�ʊi�̃J���X�}�Ȃ̂��B�����݂䂫���u�����낤����͕ʊi�B���h���邵���Ȃ��l�v���Č����Ă���B�N��a���A��؉�V�A�����A���Â�����ɂȂ�܂������邯�ǁA�����낤�ɑ��Ă͂����͐�ɋ�����I�I�@�ł��ˁA�u���z�v�̃T�r�ŏ��c���t�����R�[���X�ɂ̓]�N�b�Ƃ������B�����낤�̂��n�X�L�[���������j���ۂ����ɁA���c�̐��ݐ����n�C�g�[������������āA�Ȃ�Ƃ��▭�ȃn�[���j�[����������ȁA���ꂪ�B�ԓx�͈������ǁA���ꂾ���̂��̂����Ă������狖�����Ⴈ�����B���y�Ɛl�Ԃ͕ʂ��Ă��Ƃ����ˁB
�@�@�����̃����E����A�u�S�c�����͌ӎU�������B���ӋC�Ɂw�����̉��y�x�iPHP�������j�Ȃ�N���V�b�N�{�����������A�ǂ�Ȃ��̂��A�����āv�ƌ����Ă����B�ނ̓��x�����X�g������A���{�W�O�M�҉E����Ƃ�NHK�o�c�ψ��܂Ŗ��߂�S�c�������ȂȁB�Ƃ͂����A���������ēǂ�ł݂���A���ꂪ���\�ʔ����B���グ���y�Ȃ�26�ȁB�y�ȉ���Ɖ��t�]�Ƃ����\���B���ɑO���̊y�ȉ�������������B�����Ɠ����O�ꂵ�����X�^�C���ŏ�����Ă��邩��A�Ȃ��Ȃ����g���Z���B�D�~�ɂ��ӂ�Ă���̂��B
 �@�Ⴆ�u�W����̊G�v�́u�r�h���i���ԁj�v�̌��B�u���\���O�X�L�[�w�W����̊G�x��10�Ȃ���Ȃ�g�ȂŁA�e�F�̉�ƃn���g�}�����₵���G����C���X�s���[�V�������č�Ȃ����W�艹�y�B��4�ȁg�r�h���h�́A�|�[�����h��ŋ��Ԃ̈Ӗ������A���̋Ȃ̊G���������肳��Ă��Ȃ��B�i���\���O�X�L�[�̎莆����j�|�[�����h�ŕ`���ꂽ���Ƃ͕������Ă���̂����A�c���Ă���̂́A���m�ƌQ�W�Ƌ���ƃM���`�����`���ꂽ1���̃f�b�T�������B���ׂĂ݂�ƁA�g�r�h���h�ɂ́w�s����ꂽ�l�X�x�Ƃ����Ӗ����������v�B�����A��4�Ȃ͏d���Ԃ��������Ԃł͂Ȃ������ɋs����ꂽ���O��`�������̂������\���������A�Ƃ������́B�a�V�I Jiiji�́A�q���̂���A���W�I�h���}�u�^�c�\�E�m�v���Ă������ǁA���̃e�[�}�Ȃ����́u�r�h���v�������B�Ȃ�قǁA������Ȃ��Đl���B����ȓ��ʂɈ���������u�r�h���v���D�~�A�ʔ���������B
�@�Ⴆ�u�W����̊G�v�́u�r�h���i���ԁj�v�̌��B�u���\���O�X�L�[�w�W����̊G�x��10�Ȃ���Ȃ�g�ȂŁA�e�F�̉�ƃn���g�}�����₵���G����C���X�s���[�V�������č�Ȃ����W�艹�y�B��4�ȁg�r�h���h�́A�|�[�����h��ŋ��Ԃ̈Ӗ������A���̋Ȃ̊G���������肳��Ă��Ȃ��B�i���\���O�X�L�[�̎莆����j�|�[�����h�ŕ`���ꂽ���Ƃ͕������Ă���̂����A�c���Ă���̂́A���m�ƌQ�W�Ƌ���ƃM���`�����`���ꂽ1���̃f�b�T�������B���ׂĂ݂�ƁA�g�r�h���h�ɂ́w�s����ꂽ�l�X�x�Ƃ����Ӗ����������v�B�����A��4�Ȃ͏d���Ԃ��������Ԃł͂Ȃ������ɋs����ꂽ���O��`�������̂������\���������A�Ƃ������́B�a�V�I Jiiji�́A�q���̂���A���W�I�h���}�u�^�c�\�E�m�v���Ă������ǁA���̃e�[�}�Ȃ����́u�r�h���v�������B�Ȃ�قǁA������Ȃ��Đl���B����ȓ��ʂɈ���������u�r�h���v���D�~�A�ʔ���������B�@���t�]�������Ȃ��B�u���t�}�j�m�t �s�A�m���t�ȑ�2�ԁv�ł́A���A�N�������Ȃ��N���C�o�[���̉��t�i���̃x�X�g1�j�ɐG��Ă���̂��Ȃ��Ȃ������A�u���v�ł̓t�����F���ŏ�̉��t���u�E�B�[���E�t�B��1952�D2�D3���C���v�ň�v�����i�o�C���C�g�ł͎^�ۂ������ꂽ���j�B�����E�����ɂ́u��i�Ɛl�Ԃ͐藣���đ�����ׂ��v�ƌ����Ă������B
�@�������N�����̂ŁA�f��u�i����0�v���������A���ꂪ�܂�����! �������B��l���̋{���v���́A���̎���ɁA���̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ����Ƒ��̂��߂ɐ������т邱�Ƃ�I��s�C��肾�B�����ł͂��肦�Ȃ��͂��̘b�Ȃ̂ɁA�[����������B���̃��A���e�B�Ɛ����͂͐�����B���܂�̗ǂ��ɁA�A�蓹�A���A�{���w���A�������ǂ�ł���B�A���A����̂́A�o��l�����S���f��̃L���X�g�Ɣ�����Ⴄ�B�ł��܂��A����͂��傤���Ȃ����ȁB
�@�m�[�x���܂Ɋւ���閧����50�N����ւŁA�u1963�N�̃m�[�x�����w�ܑI�l�ŁA�Z�~�t�@�C�i��6���g�ɎO���R�I�v���c���Ă����v���Ƃ����炩�ɂ��ꂽ��B���{���w�����ƂŎO���ƌl�I�ɐe���̂������h�i���h�E�L�|������́A�u����ŁA�O���ɏ\���Ȏ��i�����������Ƃ��ؖ����ꂽ�B5�N���1968�N���ŗL�͂Ƃ����Ȃ���A���ʂ͐�[�N�����l�����B�O���́A����ŁA������20�N�A���{�l�̎�܂͂Ȃ��Ƃ��āA�X�����U�邱�Ƃ�I�̂ł͂Ȃ����v�Ə����Ă���i�����V���j�B���A����͈Ⴄ�Ǝv���B�m�[�x����܂��O���̎��������E����قǂ̂��̂������Ƃ͓���v���Ȃ��B���������ǁB�����A�L�[�����e���r�̑Βk�Łu�w�m�[�x���܂͐�[�ɂ��O���ɂ����������炵���x�Ƃ���剪�����̈ӌ��ɂ͓����ł��v�ƌ��������A����͗����ł���B��܂�����[�͏܂̏d�݂ɉ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����I�B�O������܂��Ă�����A�܂��܂��f���炵����i�ݏo���āA���̂悤�ȋ��C�ɑ��邱�Ƃ͂Ȃ������H �m�[�x�����w�܂͎��ɕs���B�Ȃ�����t���́A���N���ɂȂ�Ȃ���l��Ȃ��̂��H Jiiji�́u���̂܂܂ł͉i���Ɋl��Ȃ��v�ƍl����҂ł����A�܂����ؕs���䂦�A�܂��A������B
2014.01.10 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�X�|�[�c��
�@���������u�r�[�g�������͐U��q�A������Ԃ�Ȃ��v�i�����V���j�Ƃ��A�u�l���Ƃ̓S�[���̎�O�ŐU��Ԃ���́v�i�T�b�|���E�r�[��CM�j�Ȃ����āA�����̂����ɂȂ�������ĂˁB�ł��܂��������A���̐l�ɂ̓e�������邩��B�@�u�N�����m�v���X�^�[�g����6�N�ځA�V���A�X�l�^��������������킯����Ȃ����A�����V�K�ȃ��m����낤���ƁB�����A�肵�āuJiiji�̂Ԃ₫�v�B�����������X�|�ł���Ă�R�����݂����ȁB�Ȃ�ł��A���B���R�C�܂܁B�Y�o�Y�o�a���ăe���ʼnB���B����ȋC�y�Ȃ̂������Ă��������ȂƁBJiiji�Ƃ����̂́A������N�������܂�܂��āA�݂�ȂɁu�������v�ƌĂ��悤�ɂȂ������������B�ł����āA�e���邯�ǁA���͉����B�{���ɉ�������ł���A���ꂪ�B�Ăт����́g�Ȃ�Ray�����h�ł������BRay���ĂȂɁH��������B�����B������A�\���\���n�߂Ă݂܂����B
 �@�Ȃ�Ray�����A�����͂Ȃ�Ă������āu�����w�`�v�������ˁB�����\�����Ԃ�5�l��5���ԑ�ōs�����Ⴄ���琦�����B���N�͓��m��̈����B3��Ńg�b�v�ɖ��o�āA���Ƃ͉e�����܂��Ȃ��B�W�J�I�ɂ͂܂�Ȃ������B���n�]�͋�������ǂˁB�ē̑唪����͂�����Ƃ���ׂ肷���B�헪�͉B���Ƃ����ق��������̂ɂȁB�ԂőI��ɔ���Q�L���F�X���������B���ꂶ��I��̓��̓p���p������B�����ւ䂭�Ɠ��m��̎���ē͎��ɃV���v���A�u�U�߂�I��b����肾���v�B���s�͂��̍����ȁB
�@�Ȃ�Ray�����A�����͂Ȃ�Ă������āu�����w�`�v�������ˁB�����\�����Ԃ�5�l��5���ԑ�ōs�����Ⴄ���琦�����B���N�͓��m��̈����B3��Ńg�b�v�ɖ��o�āA���Ƃ͉e�����܂��Ȃ��B�W�J�I�ɂ͂܂�Ȃ������B���n�]�͋�������ǂˁB�ē̑唪����͂�����Ƃ���ׂ肷���B�헪�͉B���Ƃ����ق��������̂ɂȁB�ԂőI��ɔ���Q�L���F�X���������B���ꂶ��I��̓��̓p���p������B�����ւ䂭�Ɠ��m��̎���ē͎��ɃV���v���A�u�U�߂�I��b����肾���v�B���s�͂��̍����ȁB�@�ʔ��������͈ꍆ�ԉ���̐��Â���B�u�X�g���C�h���@������x���������ł���B�Ȃ̂ŁA�����̂��Ȃ����Ċ��Ⴂ���܂����ǁA�^�C�������2��30�b��ŗ��Ă܂�����A���̑��̕��S�͐����Ǝv���܂���v�i���m�R�b�`���I ����ɂ��Ă��ށA�I�莞��͐��������B�ɂ��������B1980�N�������ہB�ܗւQ�A�e�̃`�F���s���X�L�[�����|���ėD���B���X�N���s�Q���̟T���𐰂炵���B�܂��1948�N�̌Ë��L�V�i�B�������X�N���ܗւɎQ���ł��Ă���A�ԈႢ�Ȃ������_���������낤�ˁB�}���\���̋��͂����i�v�ɂȂ����낤����A���X�N���s�Q���̓j�b�|������E�ɂƂ��Ă����j�I�ɍ������ȁB
�@������������ƁB���̌J�グ�X�^�[�g���Ă����̎~�߂Ă���Ȃ����Ȃ��B����݂����ɗD���������܂�Ȃ��Ƃ��́A10�ʈȓ��ɓ��邩�ǂ����̃V�[�h�������ɋ������ڂ�B�Ƃ������A���N������̕����ʔ�����B�Ƃ��낪�J��グ������Ă邩��A�����ڂ̏��ʂ��{���̏��ʂ���Ȃ��B�ʔ������̂����Z���Ȃ��猩�Ȃ��Ⴂ���Ȃ��Ȃ�āA�����҂�n���ɂ��Ă��ˁB�e���r�͂��������q�������Ƃ��q����Ȃ������Ƃ������Đ����Ă��邯�ǁA����Ȃ̂��A�V�[�h�������̕����ʔ�����B������A�����ڂǂ���̏��ʂŁA���E���E�V�E�N�B
 �@���N�̃X�|�[�c�A�܂��̓\�`�~�G�ܗցB�����A����1�����ł���Ă���B�O��o���N�[�o�[�Ŋl��Ȃ����������_���A����͊��҂������ˁB�܂��͏��q�W�����v�̍������������B�e���}�[�N�p�����܂��܂�������A�T���E�w���h���N�\�����o�Ă�����R�������A���[���h�J�b�v��5��ŗD���̃A�u�o�N���A���n�������ɋ��G���B�����ǁA�ǂ����낤�A���{�I��̒��ŋ��Ɉ�ԋ߂��͔̂ޏ����낤�ˁB17�A�撣���āI�I
�@���N�̃X�|�[�c�A�܂��̓\�`�~�G�ܗցB�����A����1�����ł���Ă���B�O��o���N�[�o�[�Ŋl��Ȃ����������_���A����͊��҂������ˁB�܂��͏��q�W�����v�̍������������B�e���}�[�N�p�����܂��܂�������A�T���E�w���h���N�\�����o�Ă�����R�������A���[���h�J�b�v��5��ŗD���̃A�u�o�N���A���n�������ɋ��G���B�����ǁA�ǂ����낤�A���{�I��̒��ŋ��Ɉ�ԋ߂��͔̂ޏ����낤�ˁB17�A�撣���āI�I�@��c�^�������� �H���ȁB�c�O�����ǁA���̂܂܂ł̓L�����i�ɏ��ĂȂ��B�e��������̍��얫���u�~�X�����Ȃ������������ł��傤�v�Ȃ�āA�\�V�C�����Ă����ǁA�����@�͂�����A�g���v���E�A�N�Z���邱�ƁB��Փx�ɍ��Ȃ̂�3��]+3��]����b�_���Ⴂ�B����n�C�E���X�N�����[�E���^�[���B����ኄ�ɍ���Ȃ��B������~�߂ăv���O�������������B�����ɂ������L�����i�̏�ɍs���̂�������Ⴄ�B�ł��܂��A���̕ӂ�̓R�[�`�ɔC���āA��X�͉������邵���Ȃ���ˁB���ނ������R�[�`�B�撣��^�������I�I�I
�@�t�B�M���A�������̏o��͘A���̃q�b�g���ˁB�܂��A�K�������Γ��R�����ǁB�ނ͂��Ǝv���ȁB�H�������W�\��������ҁB ���G�`���������邯�ǁA��l�̂ǂ��炩�ɋ����l���Ăق������I�t�B�M���A�͒j���Ƃ��ō��ɖʔ����B�Ƃɂ�������Ȃ�Ƃ��B���ނ��j�b�|���B�c�̐������ł�B
�@�ʔ����̂̓n�[�t�p�C�v�̕�������B15�̒��w���B���[���h�J�b�v�ŋ����������ˁB���҃V���[����z���C�g�̉���h�邪�����H�I
�@�~�G�E���{���l�����������_�����ĈӊO�Ə��Ȃ��̂��B����܂ł�������9�B�W�����v70�����̊}�J�K���i72�D�y�j�A�m���f�B�b�N�j�q�c��2�i92�A���x�[���r����94�����n�������j�A�X�s�[�h�E�X�P�[�g500m�̐����G�ہA�W�����v�E���[�W�q���̑D�ؘa��A�W�����v�j�q�c�́A���q���[�O�����J���p�A�V���[�g��g���b�N�̐��J�x���i�ȏ�98����j�A���q�t�B�M���A�r��Í��i06�g���m�j�B
�@���āA�\�`�ł͂���ɏ�ς݂ł��邩�ȁH�ōōō���5�i�����A��c�A�H��or�����A�t�B�M���A�c�́A�X�P�[�g500���̉����j�A�Œ�Ȃ�[�����B�撣��j�b�|���I�I�I
 �@�N���N�n�A�㌴�_���̃e���r�o�܂���͖ڗ����Ă��B�ō��̔N�̃I�t�����瓖�R���낤�ȁB�ށA�S���t�����܂���B�Ƃ�˂邸�́u�X�|�[�c���͉����I�v�B60���[�h�A�v���[�`�����L���b�`��2���B���K�i�V�̃e�B�[�E�V���b�g�͂����Ȃ�ǐ^��280���[�h�B�C�[�O���E�p�b�g�������ɓ���ăv���i�ΐ쁕�J���j�ɏ����B�z�[���E�C���E���������Ɛ��Z���`�B����͂⎝���Ă郏�B�ł��A��Ԃ悩�����͔̂N���́u�T���f�[�E���[�j���O�v�̔����B�����ƒ�����ւ́u�J�c�I�I�v���ˁB���̓�l�A���Ƃ��邲�ƂɃ��W���[�E���[�O��ᔻ����B�僊�[�K�[�����ɂ���B�u����Ȃւڃo�b�^�[�͗��Ƃ��Ă����Γ�������v�Ƃ��ˁB�㌴�̑O�ł܂����������̂�����A�u���͋��c����ƒ��{����ɃJ�c�ł��B���W���[�E���[�O�͂���ȊÂ�����₨�܂ւ��v���āB�]���d����������Ă����������Ƃ�������Ȃ�����䏊�V�l��焈Ղ��Ă���Jiiji�ɂƂ��āA�㌴�N���́u�J�c�I�I�v�͑�u�A�b�p���I�I�v���B�㌴�N���B���N���撣���āI�I���������B
�@�N���N�n�A�㌴�_���̃e���r�o�܂���͖ڗ����Ă��B�ō��̔N�̃I�t�����瓖�R���낤�ȁB�ށA�S���t�����܂���B�Ƃ�˂邸�́u�X�|�[�c���͉����I�v�B60���[�h�A�v���[�`�����L���b�`��2���B���K�i�V�̃e�B�[�E�V���b�g�͂����Ȃ�ǐ^��280���[�h�B�C�[�O���E�p�b�g�������ɓ���ăv���i�ΐ쁕�J���j�ɏ����B�z�[���E�C���E���������Ɛ��Z���`�B����͂⎝���Ă郏�B�ł��A��Ԃ悩�����͔̂N���́u�T���f�[�E���[�j���O�v�̔����B�����ƒ�����ւ́u�J�c�I�I�v���ˁB���̓�l�A���Ƃ��邲�ƂɃ��W���[�E���[�O��ᔻ����B�僊�[�K�[�����ɂ���B�u����Ȃւڃo�b�^�[�͗��Ƃ��Ă����Γ�������v�Ƃ��ˁB�㌴�̑O�ł܂����������̂�����A�u���͋��c����ƒ��{����ɃJ�c�ł��B���W���[�E���[�O�͂���ȊÂ�����₨�܂ւ��v���āB�]���d����������Ă����������Ƃ�������Ȃ�����䏊�V�l��焈Ղ��Ă���Jiiji�ɂƂ��āA�㌴�N���́u�J�c�I�I�v�͑�u�A�b�p���I�I�v���B�㌴�N���B���N���撣���āI�I���������B�@�}�[�N�̑僊�[�O�s�������܂����̂��悩�����ˁB���~�O�ؒJ�����_��G�ɂ͉Ȃ�����? ������ԂŁA�쑺���o�Ă��āA�}�[�N���u�쑺�ē��������l�ł��v�ƌ����Ă��̂͊����������˂��B���삶��Ȃ�����ˁB������B�������B�����Ȃ��B�}�[�N��A�ǂ��ɓ����Ă��ŏ��͏ł炸�ɍs�������B10���O��ł�������ˁB�l���͒����B���������K���ĂȁB
�@6���ɂ̓T�b�J�[�E���[���h�J�b�v������B�\�I�u���b�N�A���{��C�g�B�R�����r�A�i���E�����N4�ʁj�A�M���V���i12�ʁj�A�R�[�g�f���{���[���i17�ʁj�B�\�I�ʉ߂Ɋ��҂��邯�nj������ł���B�l�͂悭���[���h�E�����L���O�Ȃ�ĊW�Ȃ��Ƃ������ǁA�����B���{��47�ʂ����B�T�b�J�[�m��Ȃ��l��������_�����Ǝv���̂����R�B2��1�s�����邯�ǑS�s������B�Ƃɂ���6��14���̃R�[�g�f���{���[����ɏ������Ȃ��ȁB��������I���B�����݂����ŏ����͑����B�\�I�ŕ�������l�C�}�[���ł����Ċy�������A���炢�Ȋo��͂��Ă������ق����������B�撣��j�b�|���I�I�I
 �@�{�c�\�C�͐��ɔO���AC�~��������B���J�b�^�ˁB�����܂ł͔ނ̎v���`�����Ƃ���̃T�b�J�[�l���B�����A�����͂��ꂩ��B���_�ɋ߂Â��߂Â��قǓ��͌������Ȃ�B�~�����͍��G���[�O13�ʂƒ�����B�ŊJ��{�c��l�ɋ��߂Ă�B�`�[�����t�@�����B���������̃v���b�V���[�́B���ĂΒ��ꗬ�ɁA������Ε��ʂ̑I��ɁB�撣��{�c�B���E�̔����R�W�J���悤���B�����ă��[���h�J�b�v�œ��{���x�X�g8�ɓ����ă��I�I
�@�{�c�\�C�͐��ɔO���AC�~��������B���J�b�^�ˁB�����܂ł͔ނ̎v���`�����Ƃ���̃T�b�J�[�l���B�����A�����͂��ꂩ��B���_�ɋ߂Â��߂Â��قǓ��͌������Ȃ�B�~�����͍��G���[�O13�ʂƒ�����B�ŊJ��{�c��l�ɋ��߂Ă�B�`�[�����t�@�����B���������̃v���b�V���[�́B���ĂΒ��ꗬ�ɁA������Ε��ʂ̑I��ɁB�撣��{�c�B���E�̔����R�W�J���悤���B�����ă��[���h�J�b�v�œ��{���x�X�g8�ɓ����ă��I�I�@�{�c�Ƃ͈����̒����r��͉��z�������B��N���AJ���[�O�A���lF�}���m�X��2�������c���Ĉ�������1�ł��D���Ƃ����B�����A�Ȃ��2�A�s�ő勛���Ă��܂��B�Ő��ɂ������܂�r��̎p���Y����Ȃ����B�N�����V�c�t���l�����̂����߂Ă��̋~���������B
�@����Ɛ�����55�l�����������������ˁB�u�X�|�[�cKYOKUGEN2014�v�ł̂��ƁB���w���̃T�b�J�[���N��55�l�Ŏ���Ă�B�������l����ē��_������̂��B�����珬�w���ł�55�l�ł���B�O���E���h���l�Ŗ��܂��ăX�y�[�X���Ȃ�����B�V�тƂ͂��������������B�����ԑg�̒��ŁA���b�V�Ɗ`�J�j��N��40���[�g����̃S�~���ɏR����ꂽ�̂������B����͂�A�v���̐��������������܂����B����Ȃ���ȂŁA�T�b�J�[�E���[���h�J�b�v�A���ނ��j�b�|���I�x�X�g8���I�I
�@�Ō�Ɉ�B��A���ɂ�����{�N�V���O�AWBA���E���C�g�t���C���^�C�g���}�b�`�A�`�����s�I���䉪����VS��3�ʃA���o���[�h�i�j�J���O�A�j��͐��������������l�B18��S��15KO�Ƃ����ŋ��̒���҂͈ꔭ�_���̐ڋߐ�ށB�`�����s�I���͂����▭�ɂ��킵�Ȃ���I�m�ȃp���`���q�b�g���܂���B�䉪�͋��������I����҂̓^�t�������BKO�����Ȃ�Ȃ��������ō��Ɋy���߂���B
�@�{�N�V���O�E�ɂ͂�����l�S�b�h�E���t�g�ٖ̈�������WBC���E�o���^�������ҎR���T�����B���̐l���������B�ƂĂ��Ȃ���B�T�c���B�ɓ��ꉤ�Ґ���Ăт����Ă��邪�A�����Ȃ����낤�ȁB�������T�c�͊ԈႢ�Ȃ��}�b�g�ɒ��ށB���̓�l�ǂ��܂ŏ��������邩�B���̋�u���̖h�q�L�^12���j���Ăق������B����A �����̓R���܂ŁB���̓G���^���҂Ƃ������B������ҁI�I
2013.12.15 (��) �b����`Global�N���X�}�XSongs
�@2000�N�O��A���R�[�h�ƊE�ɃR���s���[�V�����E�u�[���Ƃ������ۂ��N���āA������R���sCD���悭����܂����B�l�X�ȃA�[�e�B�X�g�̋Ȃ�1���ɓ����Ă���̂ŁA�̂̓I���j�o�X�ƌĂ�ł��܂����B�Ґ��ɓ������ẮA�u�����͎��Љ����Łv�Ƃ����\�����킹����������܂��āB���Ƃ́A�蔄��s�\�ȃA�[�e�B�X�g�����āA���Ƃ��ΎR���B�Y�A�|���܂��ABZ�A�v���X���[�Ȃǂ�NG�B�����݂䂫�A�T�U����I�[���X�^�[�Y�͏����tOK�ŁA���C�J�R����NG�ł��r��R����OK�ȂǁB��鑤�͂����̐�����C�ɂ��A���ɓ����Ђ˂������̂ł����B�@�X�́A�N���X�}�X�E���[�h��F�B�A�����J����A�u���b�N�E�t���C�f�[����O�̔���グ�ŔN�����킪��C�ɐ���オ���Ă���Ƃ��B�z���C�g��n�E�X�̃N���X�}�X�E�c���[���_���B�����őM���܂����BMy Christmas Compi-CD�̊��B����Ȃ�W���������A�[�e�B�X�g������Ȃ��A�m�y�E�M�y�E�N���V�b�N�A���R�C�܂܂ɍ��܂��B�肵�āuGlobal �N���X�}�XSongs�v�A�Ґ��̎n�܂�n�܂�[�I�I
 �@�܂��́A���炪�R���B�Y�́u�N���X�}�X �C�u�v�B����͕���Ȃ��B����N���X�}�X�E�\���O�̃N���V�b�N�Ƃ������閼�Ȃł��B�ԑt�̃A�E�J�y�����u�p�b�w���x���̃J�m���v�Ƃ����̂��X�}�[�g�B���傪����Ƃ���A�i�l�I�߂��闝�R�ł����jRCA�i���̂������R�[�h��Ёj����ڐЁAMOON RECORDS�ݗ��i1983�N�j����̍�i���������ƁB�������ꂪRCA�ݐЎ���̍�i��������A�ǂ�ȂɃ��J�b�^���Ƃł��傤���ĂˁB
�@�܂��́A���炪�R���B�Y�́u�N���X�}�X �C�u�v�B����͕���Ȃ��B����N���X�}�X�E�\���O�̃N���V�b�N�Ƃ������閼�Ȃł��B�ԑt�̃A�E�J�y�����u�p�b�w���x���̃J�m���v�Ƃ����̂��X�}�[�g�B���傪����Ƃ���A�i�l�I�߂��闝�R�ł����jRCA�i���̂������R�[�h��Ёj����ڐЁAMOON RECORDS�ݗ��i1983�N�j����̍�i���������ƁB�������ꂪRCA�ݐЎ���̍�i��������A�ǂ�ȂɃ��J�b�^���Ƃł��傤���ĂˁB�@�ł��A�B�Y����Ƃ̎v���o�͕s�łł��B1979�N�H�A�ނ̏�����uMOONGLOW�v�ɍ��킹�S���v�����[�V�����s�r�������̂����������v���o���܂��B�e�n�ŁA��Ђ̉c�Ə��A����X�A�����ǁA�V���ЁA�^�E�����Ȃǂ͓I�ɉ�������̂ł��B�d�����[��ɋy�сA����̎d�グ������̃��[������������B�v���f���[�T�[��K���Ƌǂ̗L�͎҂������ăW��������͂�B�܂��A�悭�����܂����B
�@�u�r�[�g���Y�͉e����Ɍ��܂��Ă��邩�璮���Ȃ��v�u�^�o�R�͐��ƊW�Ȃ��v�u�厖�Ȃ̂̓}�X�R�~����Ȃ��B�l�̃��R�[�h�ڔ����Ă���Ă��郌�R�[�h�X�̊F����v�����肪�A�ނƂ̉�b�œ��Ɉ�ۂɎc���Ă���䎌�B�������A�^�o�R���͎~�߂Ă���悤�ł��B
�@�uMOONGLOW�v��������ƌ������̂́A�Г��ŒB�Y�������グ���uAir RECORDS�v���e����������B�ނ́A������_�@�ɁA���N�́u���C�h�E�I���E�^�C���v���o�āi�R�}�[�V�����I�ɂ��j�r�b�O�ɂȂ��Ă䂭�̂ł��B
�@���݂ɁgAir�h�̃��S�͋g�c���ގq���A�B�Y���Ƃ̉�b���Ɍ��g�ő��菑���������̂Ƃ��B�܂��ɁA�����A��l�͉��y�����̃p�[�g�i�[�ł����B
 �@���̋g�c���ގq������v���o�[���l�ł��B�m��l���m��J-POP�̐_�l�I���݁B�ޏ��̈ڐА�͌��܂��ĐV�K�̃��R�[�h��Ђ������̃��R�[�h��Ђ̐V����B����́A�ޏ����n�[�h�i��Ђ̋K�́j�ł͂Ȃ��\�t�g�i�X�^�b�t�j��D�悵�����ƁB���R�[�h��ЂɂƂ��ẮA�u�g�c���ގq������v���Ƃ���Ђ̃O���[�h�E�A�b�v�ɂȂ���B����ȑo���̈ӌ������v�������ʂȂ̂ł��傤�BSOHBI���A�ޏ����X�e�C�^�X�Ƃ��ė����グ�����R�[�h��Ђ̈�ł����B���͂����Ŕޏ��̃v�����[�V�����Ɍg���܂����B�o��������̎��́i����ȁj�����ɂ��}�C�i�X�E�X�^�[�g���A���X�ɏ�����A�Ō�ɂ킩�荇�����i�Ǝv���Ă���j�ł��J�́A���̍��Y�ł���ւ�ł�����܂��B�u�ڂ��́i�Ɣޏ��͌����j�[�������ɂ����Ă̈�u�̐F�B���ł����ł��Ȃ��B�����A���ɋ߂��F���D���Ȃ�ł��BTwilight zone�v�u�}�X�^�[�e�[�v�̓n�h�\����Ɏ̂ĂĂ��܂����v�u���ꂳ�܁A�����C�ł����H�v�ȂǂȂǁA���ɉs���A���ɗD�����A�ْ������A�S���炢����̋M�d��4�N�Ԃł����B
�@���̋g�c���ގq������v���o�[���l�ł��B�m��l���m��J-POP�̐_�l�I���݁B�ޏ��̈ڐА�͌��܂��ĐV�K�̃��R�[�h��Ђ������̃��R�[�h��Ђ̐V����B����́A�ޏ����n�[�h�i��Ђ̋K�́j�ł͂Ȃ��\�t�g�i�X�^�b�t�j��D�悵�����ƁB���R�[�h��ЂɂƂ��ẮA�u�g�c���ގq������v���Ƃ���Ђ̃O���[�h�E�A�b�v�ɂȂ���B����ȑo���̈ӌ������v�������ʂȂ̂ł��傤�BSOHBI���A�ޏ����X�e�C�^�X�Ƃ��ė����グ�����R�[�h��Ђ̈�ł����B���͂����Ŕޏ��̃v�����[�V�����Ɍg���܂����B�o��������̎��́i����ȁj�����ɂ��}�C�i�X�E�X�^�[�g���A���X�ɏ�����A�Ō�ɂ킩�荇�����i�Ǝv���Ă���j�ł��J�́A���̍��Y�ł���ւ�ł�����܂��B�u�ڂ��́i�Ɣޏ��͌����j�[�������ɂ����Ă̈�u�̐F�B���ł����ł��Ȃ��B�����A���ɋ߂��F���D���Ȃ�ł��BTwilight zone�v�u�}�X�^�[�e�[�v�̓n�h�\����Ɏ̂ĂĂ��܂����v�u���ꂳ�܁A�����C�ł����H�v�ȂǂȂǁA���ɉs���A���ɗD�����A�ْ������A�S���炢����̋M�d��4�N�Ԃł����B�@�u�N���X�}�X�E�c���[�v�̓N���X�}�X�E�\���O�̉B�ꂽ���ȁB�����ՁuBELLS�v�i1986�N�����[�X�j�ɓ����Ă��܂��B����CD�A3000�������v���X�����炸�A�ޏ����璼�ڂ����������M�d�Ȉꖇ�B���������F��Ƃ���߂� ������S���߂ăN���X�}�X�E�c���[����́E�E�E�E�E�x���C�����̐��A�Â��Ȑ����͂̑f���炵�������ł��B
 �@�����͗m�y�B�r���O��N���X�r�[�́u�z���C�g�E�N���X�}�X�v�́A��Ԓ��̒�ԂȂ̂ł���͊O���Ȃ��B�ł��A�D�݂̓y���[�E�R���Ȃ̂ł���������^�B���̐́A�p�b�g�E�u�[�����悭�����܂������A�ŋ߂��܂肩����܂���ˁB���Ԃ̃n�~���O�A���\�悩�����̂ł����B
�@�����͗m�y�B�r���O��N���X�r�[�́u�z���C�g�E�N���X�}�X�v�́A��Ԓ��̒�ԂȂ̂ł���͊O���Ȃ��B�ł��A�D�݂̓y���[�E�R���Ȃ̂ł���������^�B���̐́A�p�b�g�E�u�[�����悭�����܂������A�ŋ߂��܂肩����܂���ˁB���Ԃ̃n�~���O�A���\�悩�����̂ł����B�@�z���C�g�ɑ��Ă̓u���[�H �G�����B�X��v���X���[�́u�u���[�E�N���X�}�X�v�B�ނɂ͎^���̂̃A���o��������̂ŁA��������u�A�f�X�e�E�t�B�f���X�v���������낤�B�}���C���͓���܂���B���̋ȁA�D������Ȃ�����ŁB
�@�G�����B�X���v���o�[���A�[�e�B�X�g�ł����B1973�N1��14���A�n���C����̉q�����p����Ԃ̈�ہB�č�̉��h�ʼnc�ƒ��ԂƐH������悤�Ɍ����������Ƃ́A���̃��C�u�Ղ́A2������Ƃ��������Ƃ��Ă͒��X�s�[�h�̔����ɁA�C�������Ď��g���̂ł��B
�@����i�V������N���V�b�N������܂��傤�B�����̓x�X�g�E�Z���[�u�J�������^�A���F�E�}���A�v����u���悵���̖�v�Ɓu�A���F�E�}���A�v�i�O�m�[�^�o�b�n�j���BRCA�ƃf�b�J�Ƃ̒�g�Ŏ����������̊��B�\�v���m�Ə��̓��I���^�C���E�v���C�X�B����̓f�b�J�̌��Ղł����ARCA�ɂ̓J���������v���C�X�́u�J�������v�Ƃ������x�X�g�Z���[������܂��B
�@�b��o���h�́u���ށv���A�̎�����N���X�}�X��\���O�Ƃ����Ă����ł��傤�B����� �N���X�}�X��L�����h���̓��� �h��Ă��邩�� ���O�̈��̓��͂܂� �R���Ă��邩���E�E�E�E�E�N���X�}�X�A���R�����ė��ꗣ��ɂȂ��Ă�����l����������z���B���Ƀ��}���`�b�N���Z���`�����^���B
�@���C�J�R���̓�ȁu���b�a�ő҂N���X�}�X�v�Ɓu���l���T���^�N���[�X�v���K���B�ޏ��̉̂͂��ׂĉf����������ł���B�������ƁA70�N��A�}�C�E��E�X�L�[�E�u�[���̍����v���o���܂��B���̂���A�݂�ȎႩ�����I�j�b�|�������C�������I�I�u���l���T���^�N���[�X�v�́u�}�}���T���^�ɃL�X�������v��J-POP�łł��傤�B
 �@BZ�́u�����̃����[�E�N���X�}�X�v����D���ȋȁB�܂��5���Ԃ̒Z�ҏ����B90�N��킪�J���I�P�S�����ɂ̓}�C�E�N���X�}�X�E�\���O�̒�Ԃł����B�Ƃ��낪�A���͑��q���̂��Ă�A����͏��� �ł��ˁB �܂ł�����Ȃ��ł�����悤�ȋC�����Ă��� ��������������߂��� ���ނ����ɖ���ǂ��������@�N�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��͂��߂ĕ|���Ǝv���� �l��������Ƃ������ƂɋC�����������̃����[�E�N���X�}�X�E�E�E�E�E�T�r�̎����ׂĂ�������ł���B�Î_���ς��Ȃ��B
�@BZ�́u�����̃����[�E�N���X�}�X�v����D���ȋȁB�܂��5���Ԃ̒Z�ҏ����B90�N��킪�J���I�P�S�����ɂ̓}�C�E�N���X�}�X�E�\���O�̒�Ԃł����B�Ƃ��낪�A���͑��q���̂��Ă�A����͏��� �ł��ˁB �܂ł�����Ȃ��ł�����悤�ȋC�����Ă��� ��������������߂��� ���ނ����ɖ���ǂ��������@�N�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��͂��߂ĕ|���Ǝv���� �l��������Ƃ������ƂɋC�����������̃����[�E�N���X�}�X�E�E�E�E�E�T�r�̎����ׂĂ�������ł���B�Î_���ς��Ȃ��B�@�ł́A�Ō�ɋȖڕ\���f�ڂ��Ė{�͂���܂��B�Ȃ��A����Compi-CD����]�̕��͂��C�y�ɂ��\���o���������B�ܘ_�A�i�ł��̂ł��݂����邾���ł����B
�@�@�@�@�@�@Global�N���X�}�XSongs
�@�P�@���悵���̖� �iL.�v���C�X���J�������j
�@�Q�@�z���C�g�E�N���X�}�X �iB.�N���X�r�[�j
�@�R�@�u���[��N���X�}�X �iE.�v���X���[�j
�@�S�@�N���X�}�X �C�u �i�R���B�Y�j
�@�T�@���� �i�b��o���h�j
�@�U�@���l���T���^�N���[�X (���C�J�R��)
�@�V�@�N���X�}�X����u �iSAS�j
�@�W�@�A���F�E�}���A �iP.�R���j
�@�X�@�N���X�}�X�E�c���[ �i�g�c���ގq�j
�P�O�@�A�f�X�e��t�B�f���X �iE.�v���X���[�j
�P�P�@���b�a�ő҂N���X�}�X �i���C�J�R���j
�P�Q�@�����̃����[��N���X�}�X �iBZ�j
�P�R�@�z���C�g�E�N���X�}�X �iP.�R���j
�P�S�@�I�[�E�z�[���C�E�i�C�g �iJ.�f���o�[�j
�P�T�@�A���F�E�}���A �iL.�v���C�X���J�������j
�P�U�@�����[�E���g���E�N���X�}�X �iH.�}���V�[�j�j
�P�V�@���悵���̖� �iC.�A�g�L���X�j
2013.12.05 (��) �ӏH�f�́`���N�̏H�͉�A���e�[�}
[�I�[�h���[�E�w�v�o�[��]�@ �@����A�F�l���j���[���[�N���s����A���Ă����B���܂�Ɋ�����Autumn in New York�Ȃ��Cold in New York�̎�����Ƃ��B�H�̃j���[���[�N�Ƃ����Ζ��ȁu�j���[���[�N�̏H�v���v���o���BJAZZ�}�C�X�^�[��K�����������f�N�X�^�[�E�S�[�h���̃e�i�[�E�T�b�N�X�ɂ�鉉�t�������B�������R����݂��ފ����̕\����͂��B���A�Ȃ�Ƃ����Ă����ɂƂ��Ẵj���[���[�N�̏H�́A�f��u�e�B�t�@�j�[�Œ��H���v�ł���B�I�[�h���[�E�w�v�o�[���i1929�|1993�j������z���[�E�S���C�g���[�̕v�������ăW���[�W�E�y�p�[�h�������Ƃ̗��Ɂu�A��悤�Ɍ����Ă���v�ƌ����V�[���B���̏ꏊ���Z���g������p�[�N�ŁA�͗t���������̃x���`�Q�̕���Ȃ�Ƃ��j���[���[�N�Ȃ̂ł���B
�@����A�F�l���j���[���[�N���s����A���Ă����B���܂�Ɋ�����Autumn in New York�Ȃ��Cold in New York�̎�����Ƃ��B�H�̃j���[���[�N�Ƃ����Ζ��ȁu�j���[���[�N�̏H�v���v���o���BJAZZ�}�C�X�^�[��K�����������f�N�X�^�[�E�S�[�h���̃e�i�[�E�T�b�N�X�ɂ�鉉�t�������B�������R����݂��ފ����̕\����͂��B���A�Ȃ�Ƃ����Ă����ɂƂ��Ẵj���[���[�N�̏H�́A�f��u�e�B�t�@�j�[�Œ��H���v�ł���B�I�[�h���[�E�w�v�o�[���i1929�|1993�j������z���[�E�S���C�g���[�̕v�������ăW���[�W�E�y�p�[�h�������Ƃ̗��Ɂu�A��悤�Ɍ����Ă���v�ƌ����V�[���B���̏ꏊ���Z���g������p�[�N�ŁA�͗t���������̃x���`�Q�̕���Ȃ�Ƃ��j���[���[�N�Ȃ̂ł���B�@���N�̓I�[�h���[���S���Ȃ���20�N�B�e���r�͓��W�ԑg�▼��̃I���G�A�iNHK-FM��7�{�j���œ��킢��������B�o�F�́uBS���j�فF�w���[�}�̋x���x�`�g�Ԏ��h�̗��̒��Łv�i2010�NOA�̍ĕ����j�������B1950�N��A�Ԏ��^�������̃n���E�b�h�ŁA����ɐ^�����������������ē� �E�B���A���E���C���[�i1902�|1981�j�A�N���W�b�g�\���ɔ����I���₳�˂Ȃ�Ȃ������r�{�� �_���g���E�g�����{�i1905�|1976�j��̋ꓬ���`�����B�Ȃ��A�r�{�Ƃ̃N���W�b�g���C�A���E�}�N�������E�n���^�[�������̂��B�Ȃ��I�[���E���P�ɂȂ����̂��B�Ȃ������Ȃ̂��B���X�A�l�X�ȋ^�₪�����������𖾂���Ă䂭�B����Ǝ���w�i�Ƃ̊֘A�ɋ����͐s���Ȃ��B
�@���݂Ɏ��̃I�[�h���[�f�楃x�X�g3�́A����N�㏇�Ɂu���[�}�̋x���v�i1953�j�u��������̏�v�i1957�j�u�e�B�t�@�j�[�Œ��H���v�i1961�j�B��������L���b�`��t����Ƃ���A�g�|�p���ƌ�y���������ɗZ����������h�g����Ȃ��̃����E�R���f�B�[�h�g���h���L������i�h�Ƃ������Ƃ��납�B�I�[�h���[�͉i���Ȃ�B
[�G���K�[]
�@�H�ɒ����N���V�b�N�̖��ȂƂ��ẮA�G�h���[�h��G���K�[�i1857�|1934�j�ӔN�̌���u�`�F�����t�� �z�Z���v�Ɏ~�߂��h���B���ׂĂ̐������ӏH�̐F�����B�C���O�����h���C�݂��霂Ƃ�����r���Ǝ⛋�ƗJ�D�B���ʂɂ͐Ԃ������Â��ɔR������B�H�̕���͓��ɑ�3�y�̓A�_�[�W���Ŋ�����B�Ƒt�`�F���̕��߂����̂��x���锺�t�͌��y��ƃN�����l�b�g�ƃz���������B�y��Ґ��܂ł����ӏH���̂��̂Ȃ̂��B�`����肪�����Ŋ҂�\���͗։�̒��B�W���N���[�k�E�f���E�v��(1945�|1987)�̗��j�I�����i1965�^���j�Œ��������B
[�����݂䂫]
 �@11��25���́A�N�Ɉ�x�̒����݂䂫�w�ŁB���N�͑肵�āu���H��VOL1�v�B�����������͂�4���Ԃ��������߁A�`�P�b�g�擾�ɋ�J�������Ȃ�Ƃ������肱�߂��B
�@11��25���́A�N�Ɉ�x�̒����݂䂫�w�ŁB���N�͑肵�āu���H��VOL1�v�B�����������͂�4���Ԃ��������߁A�`�P�b�g�擾�ɋ�J�������Ȃ�Ƃ������肱�߂��B�@����́A1989�N�̑�1��17�����̑����炢�B�u���v�ɒ�^�͂Ȃ��A�Ȃ�ł�����łȂ�ł��Ȃ��A����g�����݂䂫�A�C�����̕����܂܂ɍ��̊��h�Ȃ̂��B�ł́A���̑����炢�Ƃ́H �܂��A����͂��Ă����A�u���v�ɍs���l�́A�����܂ߑ����ꏭ�Ȃ��ꒆ�����̋��c�l�̋�����q�����ɂ䂭�킯������A�u���肪����v�Ǝ�������ł����̂��B�����A����������������肪�����B
�@�S22�Ȃ̒��ł̈�Ԋy�Ȃ́u���̃����[�v�B�������߂Č����u���`24����0�����v�i2004�N�j�̃N���C�}�b�N�X�ʼn̂��Ă���B�̈ꐶ�����ł͒H�蒅���Ȃ��Ƃ��Ă� ���̃o�g���͂�� �肢�������p���ł䂯��������Ƃ��đ����ł���ƁA���̃t���[�Y���g�ɐZ�݂�悤�ɂȂ��Ă����B���̐��ɑ債�����͎̂c����͂����Ȃ�����ǁA�q�ɑ��ɉ����������p���ł������ �����Ȃɂ��̎������Ԃ��Ƃ����邩���B�������_�C�i�~�b�N�ȋC�����ɂ�������B
�@�j���[�E�����[�X�̃A���o���u�\��P�v�ɂ́u����v��DVD���I�}�P�ɕt���Ă���B2011�N1���A���ۃt�H�[�����ł̃��C�u�f�����B���_�������Ă���B�u����v�̃e�[�}�́u����v�B�����݂䂫�����̃e�[�}���낤�B����ȉ̂��f�r���[���ɐ��܂ꂿ����Ă���B��̊�Ղ��Ǝv���B
�@����ŁA�u����v�̐��K���@�[�W������4�ɂȂ����B�V���O��(1975) �A�f�r���[�E�A���o���u���̐����������܂����v�i1976�j�A21���ڂ̃A���o���u����`Time goes around�v(1993)�A�����č���̉f���B�ǂ���݂ȑf���炵���B
[���C�J�R��]
 �@�������ɏ��C�J�R���̃j���[�A���o���uPop Classico�v���������ꂽ���A������̃I�}�PDVD�͐V���ɃV���[�e�B���O�����u�Ђ������_�v�ł���B�u�Ђ������_�v�̓f�r���[�E�A���o���u�Ђ������_�v�̃^�C�g���ȂŁA����Ӗ����[�~���̌��_�Ƃ�����ȁB���N�̉āA�{��x�ēŌ�̒��ҁu�������ʁv�̃G���f�B���O�Ɏg��ꌩ���Ȍ��ʂ����Ă����B
�@�������ɏ��C�J�R���̃j���[�A���o���uPop Classico�v���������ꂽ���A������̃I�}�PDVD�͐V���ɃV���[�e�B���O�����u�Ђ������_�v�ł���B�u�Ђ������_�v�̓f�r���[�E�A���o���u�Ђ������_�v�̃^�C�g���ȂŁA����Ӗ����[�~���̌��_�Ƃ�����ȁB���N�̉āA�{��x�ēŌ�̒��ҁu�������ʁv�̃G���f�B���O�Ɏg��ꌩ���Ȍ��ʂ����Ă����B�@DVD�̃N���W�b�g�ɂ�Yumi Arai�~Yumi Matsutoya�Ƃ���B�I���W�i���̉̏��ɖ{�l�̃��H�[�J����t�����A�X�g�����O�X�E�A�����W��ς��Ă���i�{�{���Y�����C�J�����j�B����ɂ���āA�S�̂̋������L���ɂȂ�ȂɈႤ�\���������B�������݂��Ǝv���B
[�G�s���[�O]
�@�I�[�h���[�̉�ځA�G���K�[�̗։�A�����݂䂫�Ə��C�J�R���̌��_��A�B���N�̏H�͉�A���e�[�}�H
�@11��8���A���q���q���S���Ȃ����B��D���������ޏ����Â�őS�ȏW���B���̂���コ��x�X�g3�́A�u���炽�����L�v�i1956�j�u����ɗ�����v�i1963�j�u�l�����낢��v�i1987�j���B���Ɂu����ɗ�����v�� ����Ȃ�ĂȂ����Ă��S�͖��̃G�������h �̌��������B�牮�_�̂��Ⴊ�ꐺ�Ƃ���コ��̐��ݐ����������Ȃ��������Ă���B�▭�ȃ}�b�`���O�Ȃ̂��B
�@�ޏ��̖��͂́A�e���݂₷���ƕi�̂悳�̓����Ƃ�������������B�ǂ����c�ɂ��ۂ��Ăǂ����C�����B�N���V�b�N�̐��E�ł̓r���M�b�g�E�j���\���H ����ɂ��Ă����X�g�E���R�[�f�B���O�ƂȂ����u���炽���̏��a�v�͊����I�������B���̎O���O�A����ł̘^���ł���B�s��Ȏ����̉́B����͐l�̐�����Ȃ��B�ފ݂���̉��삾�B������ẮA�݂䂫�����[�~�����������ł��܂��B����コ�� ���炩�ɁB
2013.11.20 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊��2�`�u�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I���Y�v
[�h����2013�N] �@�u�`�[���̏����ɖ𗧂������B���̋C���������ł��B���̌��ʃ`�[���������ɏ����i��ł����B����Ȋ��̒��œ�������Ȃ�Ė{���ɍK���B�����邱�Ƃ��y�����Ă��傤���Ȃ��B���������āA20��̍����K���V�����ɂ���Ă���悤�ȋC�������ł��v�Ə㌴�͌����B�싅���ł����тƏ[�����ɖ������Ă���B
�@�u�`�[���̏����ɖ𗧂������B���̋C���������ł��B���̌��ʃ`�[���������ɏ����i��ł����B����Ȋ��̒��œ�������Ȃ�Ė{���ɍK���B�����邱�Ƃ��y�����Ă��傤���Ȃ��B���������āA20��̍����K���V�����ɂ���Ă���悤�ȋC�������ł��v�Ə㌴�͌����B�싅���ł����тƏ[�����ɖ������Ă���B�@����Ȑ킢�̒��Ń}�[�N����37�l�A���A�E�g��27�����A�������_�́AMLB�j��2�Ԗڂ̋L�^�ƂȂ����B
�@�����āA9��20���A�`�[���͐��ɒn��D�������߂��B�㌴�́A���M�����[��V�[�Y���ʎZ73�����ɓo�A4��1�s21�Z�[�u�A�h�䗦1.09�ƕ���̕t���悤�̂Ȃ����тŃ`�[���ɍv�������B
�@�`�[�����㌴�����̐����̂܂܃|�X�g�E�V�[�Y���ɓ˓��B�O�N���҃^�C�K�[�X��j�茩���A�����J�����[�O�E�`�����s�I���ɋP���i10��19���j�B�㌴�͂����ł���ԗւ̊���������A5�����ɓo�A1��0�s3�Z�[�u4����9�D�O�U���l�������_�Ƃ������|�I�����ŁAMVP�ɑI�ꂽ�B��������ŃC���^�r���A�[�́u��������̎p���ǂ�ȋC�����Ō��Ă����H�v�̎���ɁA���q�̈�^����́gexcited�h�Ɠ������т𗁂т��B
�@�����A���[���h�V���[�Y���B����̓i�V���i�����[�O�̔e�ҁE�Z���g���C�X�E�J�[�W�i���X�B���[���h�V���[�Y11��̗D�����ւ閼�傾�B2011�N�A�e�L�T�X������W���[�Y����A���O�̑I�l�R��ɋ������㌴�ɂƂ��āA�܂��ɂ���͖��̕���ƂȂ����B�u�����܂ł�����A����30�`�[����2�`�[���������Ȃ��̂����A����4�|7���������Ȃ��̂�����A�����̂Ȃ��悤�ɂ�邾���ł��v�B
[�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I��]
�@10��26���A�o��1��1�s�Ō}�����G�n�u�b�V���E�X�^�W�A���ł̃V���[�Y��3��́A���ɂ������������ƂȂ����B
�@�Ȃ�ƁA�O�ێ�̑��ۖW�Q�Ń��b�h�\�b�N�X�̃T���i�������B���[���h�V���[�Y�j�㏉�Ƃ��������ł̌����́A�}�E���h�ɂ����㌴�ɂƂ��āA�傢�Ɏς���Ȃ����c�����B
�@������A�㌴�̓`�[�����[�g�ƃr�f�I�����Ă����������B�u���x���Ă������Ȕ���ł����A�R�����������f�������炵�傤���Ȃ��ł��v�B
�@������A�����Ƃ͉��ɑ��Ă������̂��H ������A�㌴�́A�O�ێ肪�g�̈Ӂh�ɖW�Q�������ۂ�����ɂ����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����B�f���ł́A���҂��|�ꂱ�O�ێ���T���ē]�т�����B���̎��O�ێ肪���҂̑����̈ӂɈ����|���Ă���悤�Ɍ����Ȃ����Ȃ����A�����łȂ��Ƃ�������B�m���ɔ����ł���B
�@���[���u�b�N��R�����Ă݂�B�����ɂ́u�̈ӂł���]�X�͊W�Ȃ��v�Ƃ���B�̈ӂł��낤�ƂȂ��낤�ƁA�|�ꂱ�O�ێ肪���҂̖W�Q�ƂȂ����Ɣ��肳�ꂽ��A����͑��ۖW�Q�Ȃ̂ł���B�Ȃ�A���̏ꍇ�͂܂������Ȃ����ۖW�Q���B
�@�܂��A�ς���Ȃ������ł���A�㌴�͂�����������邱�Ƃ͂Ȃ��B��ւ��̂悳�gNew day�h�ł���B
�@10��27���A��S��A1��2�s�̃��b�h�\�b�N�X�́A����𗎂Ƃ��Ɖ�����|������A��ɕ������Ȃ��Q�[���������B
�@�J�[�W�i���X�ɐ搧��������4��̃x���`�ŁA�I���e�B�[�Y�̓i�C�����W�ߞ������B���{�ł����~�w���B�u��������Ă���B���̃`�����X���݂��݂������Ă����̂��B�����͐�ɕ������Ȃ��Q�[���Ȃ��B���������낤�v�B�ߋ���x�̗D���������炵����C�̈ꊅ�ɁA�`�[���͖ڂ���܂��B5��A�I���e�B�[�Y���炪�˔j����A�h�����[�̋]���t���C�œ��_�B6��A2�A�E�g�����i�[�Ȃ�����A3�ԃy�h���C�A���q�b�g�A4�ԃI���e�B�[�Y�͊ј\�̎l���B�����ŁA5�ԃS�[���X�͊����ꝱ�A�Ӑg�̃X���[�����E�z�[��������������B4�|1�Ƌt�]�B���̈�ł����A�V���[�Y�̗������C�Ƀ{�X�g���Ɉ��������l����ꔭ���������A������Y�̂̓I���e�B�[�Y�̗L�`���`�̑��݊��������B
�@�㌴��9����o�B�q�b�g�P�{���������A�Ō�̃A�E�g�������h�E�Ŋl�����B�t�@�����ē������u�㌴�ɂ͑�Z��������v�̏H �㌴�̃n�C�^�b�`���O���E���h�ɗx��B����́A��3��̑��ۖW�Q����ɑ����V���[�Y���B�����̓���A���͒����ȊO�̉����ł��Ȃ��B�㌴�H���u������������ςȏI�����B���������V���[�Y�Ȃ�Ȃ��ł����ˁv�B����őo��2��2�s�B�܂��ɁA�{�V���[�Y�A�^�[�j���O�|�C���g�̃Q�[���������B
 �@��4��̋t�]�����Ő����Â������b�h�\�b�N�X�́A������5�A6����l���Č������[���h��`�����s�I���ɋP�����B�z�[���ł̗D�������1918�N�ȗ�95�N�Ԃ�B�O�N�x�ʼn��ʂ���̗D���̓��[���h�V���[�Y�j���x�ڂł���B10��30���A����ɕ����X�^�W�A���Ɂu�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I���Y�v�����ꂽ�B
�@��4��̋t�]�����Ő����Â������b�h�\�b�N�X�́A������5�A6����l���Č������[���h��`�����s�I���ɋP�����B�z�[���ł̗D�������1918�N�ȗ�95�N�Ԃ�B�O�N�x�ʼn��ʂ���̗D���̓��[���h�V���[�Y�j���x�ڂł���B10��30���A����ɕ����X�^�W�A���Ɂu�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I���Y�v�����ꂽ�B�@���[���h�V���[�Y�A�㌴��5�����ɓo���A�Q�Z�[�u�h�䗦�O�̑劈��B�V���[�Y���e�̑傫�Ȍ����͂ƂȂ����B�C���^�r���[�ŏ㌴�́u�܂����̒��̂悤�ł��B�Ƃɂ��������x�݂����v�ƁB���q�̈�^����́A�����̂�������́H�̎���Ɂugood�v�ƃL�b�p���B���̌��t�ʂ�A�܂��Ɂggood job�h�A����A����͂����ƂĂ��Ȃ��������B�A�����J�ɗ���4�N�ڂ̍��N2013�N�A38�Ώ㌴�_���͂��ɖ싅�l���̒��_���ɂ߂��̂ł���B
 �@��C�I���e�B�[�Y�́A16�Ő�11���ŁA�ŗ��D686�A6�œ_�ŃV���[�YMVP���l���B����Ȃ����낤�B�r�b�O�E�p�s�̈��̂Őe���܂��`�[���̎x���́A���̑��݊��ƃo�b�g�ł����`�[���̊�@���~�����B��������ŁA�ނ́u�킪�X�{�X�g���I����MVP���t�@���ƃe�������̔�Q�҂ɕ����܂��v�ƃX�s�[�`�����B
�@��C�I���e�B�[�Y�́A16�Ő�11���ŁA�ŗ��D686�A6�œ_�ŃV���[�YMVP���l���B����Ȃ����낤�B�r�b�O�E�p�s�̈��̂Őe���܂��`�[���̎x���́A���̑��݊��ƃo�b�g�ł����`�[���̊�@���~�����B��������ŁA�ނ́u�킪�X�{�X�g���I����MVP���t�@���ƃe�������̔�Q�҂ɕ����܂��v�ƃX�s�[�`�����B�@�g�N���̂��߂Ɂh�͑傫�ȗ͂�^���Ă����B�u�����ŗ��_�����킪�X�{�X�g���̂��߂Ɂv��������̎v�����`�[���ɒc�����Ăэ��ݗD�������������B���������Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
�@������l�Y��ĂȂ�Ȃ��I��B����̓Z�b�g�A�b�p�[���c�V�����ł���B���M�����[�E�V�[�Y����71�����ɓo��28�z�[���h�������Q�[���̏I�Ղ�فX�ƒ��߂��B���[���h�V���[�Y�ł́A5�����ɓo���Ėh�䗦0�̊���
 �������B
�������B�@���͔ނ̐����������ƂȂ�����3��Ɍ����B7��m�[�A�E�g1��2��2�|2���_�̏�ʂœo�B�擪�Ŏ҂�3�ۑł�ł���2�_������A2�|4�Ə����z���������B�����[�t���s�B���_�i�H�j�B�Ȃ����m�[�A�E�g3�ۂƒlj��_�̃s���`�B���݂̓���Ȃ�K�^�K�^�ƕ����Ƃ���B���A���̂��ƕK���ɂȂ��Č㑱��f���A2�_���̂܂��R�̍U���ɖ]�݂��Ȃ����B�l�Ԃ����玸�s������B�N������������Ƃ͂��傤���Ȃ��B�Ƃɂ����ڂ̑O�̂Ȃ��ׂ����Ƃ�S�͂ł�邾�����B���̏�ʂɔނ̋����������B�����āA�����̑�4��A�O���ł��ꂽ�z���f�C���Ƃ�A�V�b�J���Ǝ��Ԃ����B�����ȃv�������������B�ނ��A�㌴���l�A�E�I�x�ё������甇���オ�����ǂ��o���҂Ȃ̂ł���B
�@�S.15�{�X�g���̔ߌ������z���Ẵ��[���h�V���[�Y���e�I�I ���߂łƂ��I�{�X�g��&���b�h�\�b�N�X�B�����āA�㌴�A�c�V�B�D������̖�A�{�X�g���̊X�́uKoji Koji�v�̃R�[�W�E�R�[���ɕ�܂ꂽ�B���{�l�Ƃ��Ď��Ɍւ炵�����i�������B
�@���ׂĂ��I����āA�㌴�͂����������B�u���������[���h�V���[�Y���e�̃}�E���h�ɂ���Ȃ�āA���̂܂����A�����A�v���Ă��݂Ȃ������B�ł��A���ꂪ�S�[������Ȃ��B�܂��L�є��͂���Ǝv���Ă���v�B�������㌴�B�܂��܂��i���������Ȑ������B������S�ɂ�����悤�Ɂu�̂ɋC�����āA�P�N�ł������v���[���Ă���I�I�v�Ɗ肤�B
2013.11.10 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊�ՂP�`����́u�X�C�[�g��L�������C���v����n�܂���
�@���G��MLB���[���h�V���[�Y�́A�{�X�g���E���b�h�\�b�N�X6�V�[�Y���Ԃ�8�x�ڂ̗D���Ŗ�������B2013�N10��30���t�F���E�F�C�E�p�[�N�A���̗D������̃}�E���h�ɂ����͉̂�炪�㌴�_���������B�J�����A���������N������Ȍ�����\�z�������낤���B[�X�C�[�g��L�������C��]
�@�J�����ĊԂ��Ȃ�4��15���A�{�X�g���ŁA5�l�̎��҂�299�l�̕����҂��o����S�����N�����B�{�X�g���}���\�����j�����ł���B
 �@����5�����4��20���A���b�h�\�b�N�X���C�����Y�̎������s���Ă���t�F���E�F�C�E�p�[�N�Ƀj�[���E�_�C�A�����h������ꂽ�B�u�X�C�[�g�E�L�������C���v���̂��]���҂𓉂ނ��߂ɁB
�@����5�����4��20���A���b�h�\�b�N�X���C�����Y�̎������s���Ă���t�F���E�F�C�E�p�[�N�Ƀj�[���E�_�C�A�����h������ꂽ�B�u�X�C�[�g�E�L�������C���v���̂��]���҂𓉂ނ��߂ɁB�@�u�X�C�[�g�E�L�������C���v�́A�j�[���E�_�C�A�����h1969�N�̃q�b�g�ȁB���N���璓���A�����J��g�ɕ��C���铖�����w���̃L�������C���E�P�l�f�B���C���[�W���č�����Ƃ����B���b�h�\�b�N�X�����̉̂��A���Z���Ƃ����̂́A�{���n�{�X�g�����P�l�f�B�Ɖ��̓y�n����������B2002�N���烌�b�h�\�b�N�X8�̍U���O�ɗ�����Ă���B
Where it began I can�ft begin to know when�@�j�[���E�_�C�A�����h�̉̐��ƃ��b�h�\�b�N�X�E�t�@���̑升�����X�^�W�A����t�ɋ����n�����B�V�܂œ͂��Ƃ���ɁB�`�[���̎�C�f�r�b�h�E�I���e�B�[�Y���u�����ɕ������Ɋ撣�낤�BStay strong! �v�ƃ{�X�g���s�����ە������B�O�N�x�A�����J�����[�O���n��ʼn��ʂɂ��ĉ��n�]���Œ�̃`�[���́A�uB strong�v�������t�ɐ킢�̓r�ɂ����B�u�X�C�[�g�E�L�������C���v�̉̐��Ƌ��ɁB
But then I know It�fs growin�f strong
Hands, Touchin�f hands
Reachin�f out Touchin�f me Touchin�f you
Sweet Caroline
Good times never seemed so good
�E�E�E�E�E�E�E
[�ŋ��̃N���[�U�[]
 �@2013�N�A�㌴�́A�V�V�n���b�h�\�b�N�X�́u���p���v�Ƃ��ăV�[�Y���̃X�^�[�g������B�N���[�U�[�i�}������j�́A�p�C���[�c����ڐЂ����W���G���E�n�����n�����������A�I�̌̏�Ő���𗣒E�B�㌴�ɔ��H�̖���Ă�ꂽ�B6��21���̂��Ƃł���B�J���ȗ��A���V�[�Y���̍D�����i�����W���[�Y�ݐЁA37�����ɓo�A�h�䗦1.75�j���ێ����Ă����㌴���������A�N���[�U�[�ɂȂ��Ă���͈�i�ƋP���𑝂��A����ɔ����`�[���̐������������Ă������B����́A���G����A�C�����W�����E�t�@�����ē��A�s�b�`���[�o�g���������߁A�㌴�̃N���[�U�[�Ƃ��Ă̎�����������������Ƃ����Ă���B�ނ͂܂��A���b�h�\�b�N�X�̃s�b�`���O�R�[�`�����2007�N�A���[���h�V���[�Y���e�̎��т����B
�@2013�N�A�㌴�́A�V�V�n���b�h�\�b�N�X�́u���p���v�Ƃ��ăV�[�Y���̃X�^�[�g������B�N���[�U�[�i�}������j�́A�p�C���[�c����ڐЂ����W���G���E�n�����n�����������A�I�̌̏�Ő���𗣒E�B�㌴�ɔ��H�̖���Ă�ꂽ�B6��21���̂��Ƃł���B�J���ȗ��A���V�[�Y���̍D�����i�����W���[�Y�ݐЁA37�����ɓo�A�h�䗦1.75�j���ێ����Ă����㌴���������A�N���[�U�[�ɂȂ��Ă���͈�i�ƋP���𑝂��A����ɔ����`�[���̐������������Ă������B����́A���G����A�C�����W�����E�t�@�����ē��A�s�b�`���[�o�g���������߁A�㌴�̃N���[�U�[�Ƃ��Ă̎�����������������Ƃ����Ă���B�ނ͂܂��A���b�h�\�b�N�X�̃s�b�`���O�R�[�`�����2007�N�A���[���h�V���[�Y���e�̎��т����B�@�㌴�̃X�g���[�g�E�{�[����140�L����O���B�ω����́A�قڃX�v���b�g�iSplit-finger fastball�j�I�����[�B������2��ނ̃{�[�������g���Ă��Ȃ��B�������X�g���[�g�́AMLB�̃N���[�U�[���A�ł��x�����ނɑ����邾�낤�B�ł́A�Ȃ��㌴�͂���ȕn��ȕ���ł���قǂ̐��ʂ���������̂��B
�@�ނ́u�����A�X�s�[�h���o���������o�������ł���B�o���Ȃ�����ǂ������瑬���������邩�H�v����B�ɋ}������̂����̈�ł����A�t�H�[���̊ɋ}�Ƃ����̂������ł��v�ƌ����B�t�H�[���̊ɋ}�I ���߂ĕ������t�ł���B�𖾂��ׂ��A�r�f�I�Ŕނ̓����t�H�[�����J��Ԃ����邪�A�S������Ȃ��B�m���Ȃ̂́A�X�s�[�h�E�K���\����y���ɒ����鋅����������A�Ƃ������Ƃ��B�z���ƃt�H�[���ɂ����d�̊ɋ}�B�ނ̐ꔄ�����ł���B
�@�X�v���b�g�́A���ޓ�{�̎w�̊Ԋu���t�H�[�N�E�{�[���ɔ�����ĐB���������āA�t�H�[�N�ȏ�̃X�s�[�h�ł��茳�ŋȂ���B�㌴�̂́A���ɂ��̓x�������������悤���B����G��͔ނ̃X�v���b�g��]���Ă��������B�u�ނ������̂́A�t�H�[�N���܂������Ɍ����邱�ƁB�������U�肵���Ⴄ�B�r�̐U��ƃ{�[���̋O���ł��������������ł��傤�ˁB���������t�H�[�N�𓊂��铊��͂����͂��Ȃ��v�i11��3��TX�u�\���������v���j�B���ɏ�̃X�v���b�g�i���䂪�����t�H�[�N�j�Ȃ̂��B
�@�㌴�̂���ȑ䎌���������o��������B�u�̂͂����Ƒ����̕ω������g���Ă��܂����B����łȂ��ł����̂��H ���킲�ƂɊ����x�̍������邩��Ȃ�ł��B���M�x�̍��ł����ˁB�z���������Ƒg�ݗ��ĂĂ��A���߂ɂ������{�[�����̂ɗ͂��Ȃ���Αł���Ă��܂��B�������猈�ߋ����A�����x���������M���ɍi�荞�����B�ł���Ă��w���Ⴀ�Ȃ����x�Ɣ[���������{�[���B���ꂪ�ڂ��ɂ̓X�v���b�g��������ł��v�B�㌴�_���̃X�v���b�g�́A�ғ����킬���Ƃ������Ɏc�����Ō�̃E�B���j���O�E�V���b�g�������̂ł���B
�@�R���g���[���Ƃ���������������Ȃ��B�ނ̓��������Ă���ƁA�قƂ�ǂ̃{�[�����A�L���b�`���[���\�����܂܂̃~�b�g�ɋz�����܂��B�t���͔��ɏ��Ȃ��B
�@�N���[�U�[�Ƃ��Ă̓K���ɂ��G���K�v������B�N���[�U�[�́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�Q�[���̏I�Ջ͍��̏�ʂŋN�p�����B�}����`�[���ɏ����������炷���A���s����Ε�����B���s�ɒ�������|�W�V�����ł���B�W�J�͐�����������A�u�����͖����v���������B���̃v���b�V���[�͑z����₷��B�u�f�������ł����v�͎������낤�B�㌴�ɂ͂�����͂˂̂��鎑����������Ă���B
�@�܂��́A���O�ꂽ�����S�B���������ł���B����́A�ނ��싅�G���[�g�łȂ��������ƂɋN������̂��낤�B
�@���C��w�t�������Z����̓G���[�g���R�`�I�̓�Ԏ�s�b�`���[�B���R�h���t�g�ɂ��|���炸�A���t��ڎw���Ă̑�w�ɂ����s�B�Q�l������]�V�Ȃ������B��N�ԁA���H�H���Ȃǂ̃A���o�C�g�����Ȃ���A�Ȃ�Ƃ����̈��w�ɓ��w�B�����őf�����J�ԁB���l�̃G�[�X�Ƃ��Ċ���B2009MLB�I���I�[���Y���c�B3�����ځA�E�I�x�ѕ����f��B���ފo��B�ǂ�ꂩ��̒E�o�B���ĂŔw�����u�w�ԍ�19�v�́A19�ΘQ�l����̈�N�Ԃ�Y��Ȃ����߂��B
�@������ɁA��ւ��̂悳�Ƃ������Z�ł���B����������o�̉\��������N���[�U�[�ɂ̓s�b�^�����B�l�Ԏ��s�͕K������B�������X���������Ă��Ă͖��܂�Ȃ��B�uNew day!�v�Ƃ����Ȃ����ɑO�����������́uPositive thinking�v������B
�@�����グ���X�v���b�g�E�t�B���K�[�E�t�@�X�g�E�{�[���B�H�v���Â炵���X�g���[�g�B���̓�̑g�ݍ��킹�ɂ��V���v���ȓ����p�B���Q�̐����́B�����ȓ����S�B�V���̐�ւ��̂悳�B����炪���w�������N�����āA�㌴�_���Ƃ����ŋ��̃N���[�U�[��グ���B�����āA���悢��A�ނ�2013�N�h���̃S�[���Ɍ������đ���o�����B
2013.10.31 (��) �b����`�V��S�g����
 �@�ˑR�̎��ɂ͂����r�b�N������̂���ł��邪�A���x�̓V��S�g������]��قNj��������̂͂Ȃ��B�����V���A�ڎ��́uCM�V�C�}�v�́A92�̕�Ƃ��ǂ��䂪�Ƃ̈��ǃR�����ŁA���T���j���͂���������Ċy�����ӌ���������̂����ۂ������̂ɁE�E�E�E�E�B
�@�ˑR�̎��ɂ͂����r�b�N������̂���ł��邪�A���x�̓V��S�g������]��قNj��������̂͂Ȃ��B�����V���A�ڎ��́uCM�V�C�}�v�́A92�̕�Ƃ��ǂ��䂪�Ƃ̈��ǃR�����ŁA���T���j���͂���������Ċy�����ӌ���������̂����ۂ������̂ɁE�E�E�E�E�B�@�Ō�ƂȂ����uCM�V�C�}�v10��16���ɂ́A�u�����₩�ȃA���`�L���v�Ƃ����^�C�g���ŁA�����̃O���[�o���[�[�V���������ɏ��C���悭�a���Ă����B�u���Ƃ��A�n����̐l�������A�݂�ȃ��j�N���𒅂āA�݂�ȃr�b�O�}�b�N��H�ׂȂ���A�݂�ȃg���^�̃N���}�ɏ���Ă���G�A���̒��ɕ`���Ă݂邾���ŋC�����������v�Ǝw�E����B�Ȃ�قǁA���̂܂܃O���[�o���[�[�V�����Ƃ�炪�i�߂��肤�邩���A�ŁA�����Ȃ�����m���ɋC��������邢��ȁA�Ƌ�������B
�@����ȁg�V�쎁���݁h���v�킹��R�����f�ڂ�5����Ɂg�V��S�g���� ���N80�h�̕�ł���B������20���i�Ȃ���]��̑O���I�j�̓��j�łɂ́A�u�j���[�X�̖{�I�`1964�N�ɔ��ꂽ�{�v�Ƒ肵�āA����ȋL�����ڂ��Ă����B���̓����I�����s�b�N�̔N�̃x�X�g�Z���[����4���̖{��I��œI�m�ɘ_�������́B������A�����]��͋����ȊO�̉����ł��Ȃ������B
�@�V��S�g�Ƃ������O���킽���̔]���ɏĂ������͔̂�r�I�ŋ߂̂��ƁB2008�N�w���x���g�E�t�H���E�J���������a100�N�L�O�C���[�ɂ�����NHK����TV�̓��Ԃł������B
�@����͐���ɂ킽��A�V�삳�J�������̖��͂ɂ��Č��Ƃ������̂ŁA�܂��A�ʂ��ՁA���ʂ̃t�@���̈���o�Ȃ����ՂȂ��b�Ƃ������́B���Ɋ��S������̂ł͂Ȃ������A�Ƃ������A��O���|�p�����͉������ׂ��Ƃ̈�ۂŁA�܂��A���̕]���������B�Ƃ����̂��A���̍��A���Ƃ��Δ]�w�ҁE�Ζ،���Y�Ȃǂ��A�m�������ɃN���V�b�N�����A���ꂾ���Ȃ�܂������邪�A���E�t�H���E�W�����l�̃A���o�T�_�[�����A����Ɏ~�܂��Ă���܂������邪�A�Z���{�܂ŏo���n���B���ꂪ�܂��t�ق��̂��́B����ł��܂��A�{�Ƃ̔]�Ȋw�Ȃ���̂������Ƃ���Ă��������邪�A���ꂪ�Ȃ�Ƃ����e���̋ɂ݁B���_�ȗՏ���̐ē�������A�����n�Ȕ]�Ȋw�Ώd�̊댯�����w�E����A���J�l�b�g���_��v�������ƁA�������Ȃ���2�N�ԃi�V�̂ԂāB�����b���G�O���S�B�ē����͈�x�͍R�c���邪���Ƃ͑�l�̑Ή��A�Njy�����B�Ζ؎�����̕ԓ���҂`�B���̏�ԁA�����p�����̑̂��炭�B
�@����Ȓ��ł̓V�삳��̖�O���Ԃ肾��������A�����Ă悢��ۂł͂Ȃ������B���̏�A�ǂ��ł��������ǁA�r�[�g����������́u���X�H�q�ɐU��ꂽ�v�ȂǂƝ��������n���B
�@�Ƃ��낪�A�V�삳��́A�{�Ƃɂ����ẮA�Ζ؎��Ƃ͌��ƃX�b�|���������B���̎�ɂ���u�L����]�v�͓ǂ��Ƃ͂Ȃ����A�O�q�́uCM�V�C�}�v�͂��������ǃR�����ƂȂ��Ă������B���X�O10��9���u�ʕi�̍��ցv�͏G��B���̗v��͂����ł���B
�@7�N��̃I�����s�b�N�Ɍ����ĐV��������ȋ��Z������邻�����B�����Ă����ɂ́A�����ŗD��̎̊|�����B�҂Ă�A���̕��i50�N�قǑO�̓����̋�C�������肶��Ȃ����B�ł��Ȃ��A�I�����s�b�N�͂������A����͂��̂���Ƃ�������ς���Ă���B�u�����͑P�H ���̎q����������������̂Ȃ炢�����A���̎������ܓˑR�������n�߂悤���̂Ȃ炻��͂����ߌ��ł���v�ƁA�o�ϊw�҂̃V���[�}�b�n����������Ă���B�@�I�����s�b�N�ɕ�����Ă��鍡�A��������ƌx����炷�B�{����8���l���e�̋��勣�Z�ꂪ����́H ���̂Ƃ��������A���������B�V�l�ł��������Ȃ��Ⴂ���Ȃ��́H �f�p�ȋ^��𓊂�������B�u�ʕi�v�Ƃ������t�����邶��Ȃ��́B���{���ڎw���͂��ꂶ��Ȃ��̂��ȁB���̍s�����Ɏ�����^���Ă����B
�@�ނ����̒����̕i�]��ł́A���ʂ�1�i2�i�ƌĂ����ȁB�ŁA���̐R���̃��m�T�V�ł͂͂���Ȃ����A������Č��I�Ȃ��̂��u�ʕi�v�ƌĂ�ŕ]�������Ƃ����B
�@�ʕi�B�����˂��B���E��1�ʂƂ�2�ʂƂ����ʂ������������ȍ������A�푈���������Ȃ��u�ʕi�v�̍����������A���̍��ɂ͂��ꂾ���̎Љ�I�E�����I���Y������B
�@���������ʕi�̍���8���l�̋��Z��͂���Ȃ��B���H�����̘H�����ւ��邩���āH����Ⴀ�A���܂ł��傤�B
�@30�N�ȏ�R�����𑱂��Ă��������V���ɂ́A�A���V�삳��Ǔ��̋L�����ڂ����B���̒������ۓI�Ȓf�Ђ��E���Ă݂�B
�S�������̂́u�����������炵�Ȃ��A���������ȕ��́v�B�u�ڂ��v���Ԃ₭�e���݂₷�����̂ŁA������Љ���o�T���Ǝa�����B�Љ�̕��͋C�Ɏ��܁A���ǂ��������ɂ��܂��Ȃ�����A�o�ύŗD��łȂ��V�����u�L�����v�ɖڂ�������悤�A���[���A���ӂ�镶�͂ŌJ��Ԃ��ǎ҂ɑi�����B(10��21�� �R�c���ށj�@���������m���ȖڂƐ^�����������铴�@�́B�m���̒~�ςɂ����p�̖��B�l���䂫����y�����E�ȕ��͗͂Ɛl���B���グ��e�[�}�͂����V�N�Ő���͏�Ɏa�V�������B�����āA���{�Ƃ�����������Ȃ������A��ɂ��̍s�������Ă��Ă����B�V�삳��̕��͂́u�L����]�v�̘g���Č��㕶���_���̂��̂������B���炩�ɁI�I
�_����Ώۂł͂Ȃ������L���Ƃ������̂��A���߂Ĕ�]�̑ΏۂƂ����̂��V�삳�����B�i10��22�� ���o�ƁE��� ���O�j
��{�̐c�ƃ��[���A���l���ƕ��͂��т��Ă����B�������̎��݂��Ő�����Љ���G�X�Ɛ����A�̂Ԃ�Ȃ������ɗJ�����܂݂Ȃ���B���j���̐V�����₵���Ȃ�B�i10��22�� �V���l��j
�V�삳��uCM�V�C�}�v�̌��e���͂��̂́A���T���j���̂�������B���[���ɂ͂������b�Z�[�W��Y���Ă��ꂽ�B�������Ə��A�Y�t���ꂽ���e���J���A���̏u�Ԃ��y���݂������B���Ԃ���U��グ���悤�ȕ\���͓͂��Ȃ��B���ƂłȂ��l���ǂ�łǂ������邩���厖�B�̂Ԃ炸�A���P�I�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�s����]�����[���A�ł���B���g�̓s���ł͈�x���x�ڂ��Ȃ��܂܁A�uCM�V�C�}�v��1132��ŘA�ڂ��I�����B�i10��23�� �wCM�V�C�}�v�S���E�c���z�q���j
2013.10.25 (��) �b����`�u�x�[�g�[���F���ƃx�[�g�z�[�t�F���v
���x�[�g�z�[�t�F�����@�Έ�G�搶���v�X�ɑ傫�ȒP�s�{���������̂ŁA�����ǂ�ł݂��B�u�x�[�g�[���F���ƃx�[�g�z�[�t�F���v�i���X���فj�ł���B���[�c�@���g�̃X�y�V�����X�g�Ǝv��ꂪ���Ȑ搶�����A�Ƃ�ł��Ȃ��A���̃x�[�g�[���F���_�ɂ͋ɏ�̖ʔ���������B
�@�x�[�g�z�[�t�F���|�{���̔����𒉎��ɂȂ���Ƃ����Ȃ�Ƃ����B���{�ł̓x�[�g�[���F���Œ蒅���Ă���B�����Ă��̖��ɂ͎����̑㖼���u�y���v���t������|�y���x�[�g�[���F���B
�@�Έ�搶�́A�Ȃɂ��A�u�\�L��ς���ׂ��v�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�蒅���Ă��܂����x�[�g�[���F���̃C���[�W�����������Ƃ����̂�
 ����B
����B�@�x�[�g�[���F���́A�\���ʐ^�̉E�����i���[�[�t�E�J�[���E�V���e�[���[��A1820�N�j�B�̂���̂��Ȃ��݂̉�ŁA����͔�����߂ɔ������ꂽ���̂��Ƃ����B��������B�͍̂�ȉƂ̏ё��悪�����ɂȂ����������B���݂̃A�C�h���ʐ^�ł���B
�@�������͎����ɋ߂��Ƃ����ё���i���B���u�����g�E���[�[�t�E���[���[��A1815�N�j�B��������x�[�g�z�[�t�F���B�����A���̖{�͋����̃x�[�g�[���F���ƑΔ䂳���Ȃ�������Ƃ��Ẵx�[�g�z�[�t�F���ɔ���A�a�V�����̏�Ȃ��x�[�g�[���F���_�Ȃ̂��B����́A���̏ے������W�́u�h���v�����グ�Ă݂����B
���E�F�����g���̏������`��W�́u�h���v���
�@���ł͂قƂ�lj��t����Ȃ��Ȃ����x�[�g�[���F���̊nj��y�ȂɁu�E�F�����g���̏����v�Ƃ����Ȃ�����B�Ȃ����t����Ȃ��̂�?�@�����͊ȒP�A�ʍ삾����ł���B�Ƃ��낪���̍�i�A���O�̃x�[�g�[���F���ő�̃q�b�g�Ȃ������Ƃ����ł͂Ȃ����I
�@������̓��n���E�l�|���N�E�����c�F���i1772�|1838�j�B���̃��g���m�[���̔����҂��B�ނ͂��̂���p���n�����j�R���Ƃ��������y����A���̋@�B�d�|���̃I�[�P�X�g���ɉ��t������y�ȂF���Ă����B
�@1813�N6���A����ȃ����c�F���ɁA��D�̃j���[�X����э���ł����B�C�M���X���|���g�K���A���R���X�y�C���k���̃��B�g�[���A�̒n�Ńt�����X�R��ł��j�����̂ł���B�w�����������̂́A�S�̌��݂ƈٖ����Ƃ�E�F�����g�����݃A�[�T�[�E�E�F���Y���[�i1769�|1852�j�B�i�|���I�������ʂ̓G�Ƃ���A�������͏����ɕ������������i�E�F�����g�����R�͓�N�ハ�[�e�����[�̐킢�Ńi�|���I���Ɏ~�߂��h�����ƂɂȂ�j�B���X������ɕq�ȃ����c�F���́A�D�@�����Ƃ���Ƀx�[�g�z�[�t�F���ɘb������������B�u�E�F�����g�����R�̏������̂���푈���y������Ă��������܂��B�w���[���E�u���^�j�A�x�w�S�b�h�E�Z�C�u�E�U�E�N�C�[���x�̃����f�B�[�Ȃǂ����ʓI�ɑ}�����āB�����������Q���܂����̂Łv�ƁB����ɁA�u�����ɁA�t���E�I�[�P�X�g���E���@�[�W�������i�߂Ă��������B���b�p�⏬���ۂ��Ƃ荞��ŁA�틵��E�܂����������h�h��ɕ`���Ă������������̂ł��v�ƁB���i�͏����t��ȂȂ��f�ŋ��ۂ���ւ荂���x�[�g�[���F�������A���̂Ƃ��͉�������B��͂胁���c�F���͋H��̎d�|���l�Ȃ̂��낤�B����Ȃ�3��e�m�[�����Ԃ��グ��悤�Ȃ��̂��B
�@�����c�F���̑_���̓Y�o���I�������B���̏���ނ̎v�f�ɉ��S�����B1813�N10���A���C�v�c�B�q�ɂ����ĘA���R����������ƁA�A�����͍X�Ȃ�폟���[�h�ɕ������������B
�@�p���n�����j�R���Ŏ艞���������c�F���́A�t���E�I�[�P�X�g�����t��ŏ����ɏo��B12��8���A�E�B�[���ōs��ꂽ�u�E�F�����g���̏����v�����́A5000�l���̊ϋq�����đ听�������߂�B���t���I���Ɨ��̂悤�ȔM�������ߐs�������Ƃ����B�x�[�g�[���F����O�̑劅�тł���B���̐����ŁA12��12���A���N1��2���A27���Ɨ��đ����ɒlj������������B�����āA�ɂ߂��͂��̃E�B�[����c�ɂ�����L�O���y��B���̖͗l���q�̃V���h���[�͂��������Ă���B
���̈�N�ԂɃx�[�g�z�[�t�F���������X�̉h�_�A����ނ̈ꐶ�̊ԂɎ����ׂẲh�_�ɂ܂�����̂��̂�1814�N11��29���Ȃ̂ł���B���[���b�p�̂قƂ�ǂ��ׂẲ����̋M������̐����I�����̂��߂ɃE�B�[���ɏW�܂��Ă������A���̐l��������v���͂��āA����11��29�����A�x�[�g�z�[�t�F���̂悤�Ȉ��̌|�p�Ƃ����키���Ƃ̂ł��Ȃ��悤�ȁA�ő�̉h�_�Ə^�ɋP�����Ɏd���ďグ���̂ł������B�@���ҐΈ�搶�́A�u�x�[�g�z�[�t�F�����l���ōő�ɂ��Ă͂₳�ꂽ�Ƃ��́A�w���x�̏����i1824�N5��4���j�ł��w�^���x�w�c���x�̃_�u�����t��i1808�N12��22���j�ł��Ȃ��B�����1814�N11��29���E�B�[����c�Î��̈�w�E�F�����g���̏����x���t������v�ƒ��Ă����B
 �@�����ǂ�ŁA����u�E�F�����g���̏����v�i�I�[�}���f�B�w���F�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�j�����߂Ē����Ă݂�B��p�鍑���ے����郁���f�B�[�̈��p�A�����ۂɐi�R���b�p�A�苿����C�̉��B���̂��̂̉��y�ł���B����z���g�Ƀx�[�g�[���F���H �ƒN�����b���i�ł���B�������A�����������1813�N�̑O�N�A�ނ͌���u�����ȑ�7�ԁv�������Ă���B���n�ȏ����̍�i�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�����ǂ�ŁA����u�E�F�����g���̏����v�i�I�[�}���f�B�w���F�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�j�����߂Ē����Ă݂�B��p�鍑���ے����郁���f�B�[�̈��p�A�����ۂɐi�R���b�p�A�苿����C�̉��B���̂��̂̉��y�ł���B����z���g�Ƀx�[�g�[���F���H �ƒN�����b���i�ł���B�������A�����������1813�N�̑O�N�A�ނ͌���u�����ȑ�7�ԁv�������Ă���B���n�ȏ����̍�i�ł͂Ȃ��̂ł���B�@�ʍ�Ɗ��с\���̑Δ������ɂ����ȉƂ̐l���̔�����Ŕj����B����Ύ����x�[�g�z�[�t�F���̖\�I�ł���B�����������A���̏��͒P�Ȃ�\�I�����ł͏I����Ă��Ȃ��B���͂ɂ���Ȍ�������B
1814�N�̃x�[�g�z�[�t�F���́A�O���I�ɂ́A�m���ɁA�����ɐ����s��Ă����B�}�ɑԓx���傫���Ȃ����𑽂̂��̐l������Ă���B�������A����͊O����̂��ƂŁA�ނ̐��݈ӎ��̂ق��́A�u�E�F�����g���̏����v�Ƃ������ȉ��y�̔����I�Ȑ����ɂ���Đ[�������ĐF�����߂Ă����B����͐�]�I�Ȃł����Ƃ������E�E�E�E�E�B�@���������ؓI�ɖ\�����k�ɕ`���i���̃��C�i�[�h�E�\�������ł��{���Ɋւ��Ă͉����y�Ȃ��j�B���������A���̗��ɂ���ꂵ�݂ƈ�a���������Č������Ȃ��B�����Ƀx�[�g�[���F���ւ̈���Ƒ��h���ǂݎ���B���ꂼ�Έ�搶�̖{���ł���B������A�u�x�[�g�[���F���ƃx�[�g�z�[�t�F���v�͑f���炵���̂ł���B
2013.10.10 (��) ���I�u���R�����_�v�ŏI��`����ɎE���ꂽ���R�葥
[11] ���R�葥�̑_���@��O�A���S�́u�S���ȁv�Ƃ����Ɨ������Ȃ��������A���܂��Ȃ��^�A�Ȃ̈ꕔ�ɑg�ݓ�����u�^�A�ȓS�����ǁv�ƕς�����B���ꂪ�A1949�N6���A�u���{���L�S���v�Ƃ������ЂɂȂ����B���̏��㑍�ق����R�葥�ł���B�����̍��S�́A�����ɂ��l���������������A���̐���35���l�𐔂��Ă����B��ʉ��ق�GHQ�̋}���������B
 �@����ȍ��S�ɏ�荞�ޑ��ق̔C���́g���h�ł��肻�̐E�ӂ́g�n�R�܁h�Ƃ������B���R��I�̂́A���S�̐ӔC�҂ł���GHQ��CTS�i��ʊǗ�����j�̒��V���O�m���Ƃ����Ă���B�ނ̏����́u���ق͐����I�w�i�������Ȃ����́v�ł���A�Z�p���o�g�S����؎����^�l�Ԃ̉��R�͂���ɍ��v���Ă����B
�@����ȍ��S�ɏ�荞�ޑ��ق̔C���́g���h�ł��肻�̐E�ӂ́g�n�R�܁h�Ƃ������B���R��I�̂́A���S�̐ӔC�҂ł���GHQ��CTS�i��ʊǗ�����j�̒��V���O�m���Ƃ����Ă���B�ނ̏����́u���ق͐����I�w�i�������Ȃ����́v�ł���A�Z�p���o�g�S����؎����^�l�Ԃ̉��R�͂���ɍ��v���Ă����B�@�g�c�����̎v�f�́A�g�C�G�X�}���h�Ɓg�g������h�ł���B���R�́A����ɂ����v����Ǝv��ꂽ�B
�@���̎��߂������R�͔Y�݁A������̍����h��ɑ��k����B�����͂��ƓS�����ǒ��A���R�̓������B�������A�u���R��A���S�̍������͐��{�̕��j�Ȃ���A�ߕs���Ȃ��������B�I�������A�����S���قƂ������������Ă��ɐ����ƂɂȂ�A���̂悤�ɁB������ł����������v�ƌ��������ǂ����͒m��Ȃ����A���R�̐S�ɂ����������Ǝu�����萶���Ă������Ƃ́A�l�X�ȏ،���������炩���B����ɁA���R�́A�g�c�������A�ő����Ă��������E�O�Y�`��ɂ����k���A�ŏI�I�ɑ��ِE������B
�@���قɏA�������R�͂ǂ��Ώ��������B��ȃ|�C���g��3�B���ꂪ�A�ނ�������錴���ƂȂ����̂ł���B
�@�܂�����ʉ��قւ̔����ł���B�����͂��̐���10���l�Ƃ͂����o�����B���̃��X�g�ɍ��h���A�J����荞�ނ̂��u�����t�@�~���[�v�Ƃ��Ă͓��R�̑_���������B�Ƃ��낪�A���R�́A���[�����E���c�b�q������́u�J�g���h�̊���17�l�����ك��X�g�ɓ����ׂ��v�Ƃ̗v�������ۂ���ȂǁA����ɓO��I�ɔ�������B���[�����̗v���͓��t������b�̗v���ɓ������B���R�͋g�c�̈ӌ��������ƂɂȂ�B���R�̗\�����ʋC���ɐ������͖ʐH������B
�@���R�͂܂��A�����̊�{�{���u�S���d���v���i�ɂ��T�d�ŁA�v��̂قƂ�ǂ��X�g�b�v�����B����́A�u�d���ɔ�����p���ߖ�ł���Ή��ق�5���l�ł��ށv�Ƃ����l������ł������B
�@����ɁA���S�ɖ��������E�̎��Ƀ��X�������B�u�Ǝ҂̖������A�o��͔����ōςށv�Ƃ̔F�����炾�����B
�@�����͔ނ̐��`���̌��ꂾ�낤�B�u�ނ͗ǂ������������`���� �Z�ʂ������Ȃ��v�E�E�E�E�E���R�Ƃ����l�Ԃ�\������ł���B����Ɏ��́A�u�l���v�u�����v�u�C���v�Ƃ���������t�����������B���R�͐l���I�Ō����ȋC�����鐳�`���������B
�@�E�B���r�[��G2�́A��ʉ��قɕ֏悵�ăA�J�̈�|��}�肽�������B�W���p���E���r�[�`�č������������Ԃ莑���̌o�σ��C���́A�d�����i�ɂ�鍑�S�̗����z��������ژ_��ł����B�����J���̓d�͗������܂߂āB���������́AG2�y�уW���p���E���r�[�̈ӌ��ɏ]�����R�������Ƃ����B�����ɂ͉�~�Ǝg�������������Ă����B
�@�ނ�́A����̌����u�����Ƃ�����̖ړI�Ō��ꂽ�t�@�~���[�v�ł���B�ނ�̍s����ɗ����͂����������R�́A���͂�ז��҈ȊO�̉��҂ł��Ȃ������̂ł���B
[�I��] ����ɎE���ꂽ���R�葥
�@�u�����t�@�~���[�v���`�������{�̐ʐ^�Ƒ�`�����B����́A�������邱�ƂȂ��Ɨ������A���{���A�W�A�ɂ����锽���̖h�ǂƂ��邱���������B���R�@���͂��̎ז��ɂȂ����B�ނ�͉��R�E�����B�E�l�Ƃ������ɂ̎���ŁB���̍s�ׂ͐�ɋ��������̂ł͂Ȃ��B�������A�ނ�̒��ɂ͑�`�������������B�����u���{���h�C�c�ɂȂ��Ă������̂��v�Ƃ������Ƃł���i���_����͌�����ɉ߂��Ȃ��̂����j�B�\�A���܂ޑS���ʂ̕��a���������Ȃ��ēƗ����悤�Ƃ���A���{�͐^����ɕ��f�����B����ł������̂��H �����u�����t�@�~���[�v�͂��������邽�߂Ɋ撣���Ă���̂��E�E�E�E�E�ނ�̒��ɂ́A����Ȏg�������h���Ă������̂ł���B
�@���R�����̂��ƁA���S��Ɂu�O�鎖���v�i7��15���j�u���쎖���v�i9��10���j�����đ����ɋN����B����ɂ��A�J�g���h���͂͒��������S�͂������A��ʉ��ق���������Ă������B
�@���S�́A���ڑ��ى���R�V�Y�̉��A�d�����i�������A�d�͊J���Ƃ����݂Ȃ���A�ߑ㉻���}���Ă䂭�B���F���Y�͓��k�d�͉�Ɏ��܂����B
�@��㑧����߂Ă��������́A��̐���̓]���ɂ�葧�𐁂��Ԃ��A�ĕ҂ւƑǂ��B�@�g�c���t�́A���{���̖h�ǂƂ��ׂ��A�A�����J�Ƃ̒P�ƍu�a�Ɍ������ē˂��i�ށB�����̗��N1950�N�ɖu���������N�푈�́A�ނ�̑�`���㉟�����A�ČR������x�@�\�����i���q���̑O�g�j�̕Ґ��A�u���Ĉ��ۏ��v�̕����F���镗�����`����Ă������B
�@�������āA�u�T���t�����V�X�R���a���v�́A�u���Ĉ��ۏ��v�ƃZ�b�g�ŁA1951�N9��10���ɒ���A��1952�N4��28���ɔ������ꂽ�B���7�N�A���{�ɂ���ƓƗ��������炳�ꂽ�̂ł���B�����҂͋g�c�Ɣ��F���Y���B
�@�u���a��`�v�E�u�푈�����v��W�Ԃ���u���{�����@�v�i1947�N���z�j�̉��A���e�ꂪ�������q���Ƃ����R���������A�Ɨ�����A�����J�R������������{�Ƃ������̌`�͂��̂Ƃ��`������A�����܂�60���N�ԑ����Ă����̂ł���B
�@���̐��{�́A�u���{�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����т̌���̉��ɁA������i�߂Ă������B�m���ɁA�������̔ߌ��́A���N�����̗������܂ł��Ȃ��A�悵�Ƃ��Ȃ��B��������ŁA�h�C�c�́A�����ߌ����̂́A���ɂ͋����ȍ��ƂƂȂ����B���̏n�����o�āA���͂�A�N�݂邱�Ƃ̂Ȃ����͌^���Ƃ��h�C�c�͍��グ���̂ł���B
�@���j��u�����������������v���y���Ɍ����ׂ��ł͂Ȃ��B�����ɁA�u�������v�ƌ���͈Ӗ����Ȃ��B���͖߂��Ă��Ȃ��̂�����B
�@�����A��X�͂��̍��ɏZ��ł���B���{�Ƃ������E�ɗނ����Ȃ���`�Ƃ��]���ׂ��`�̍��ō����Ă���B���ꂪ�����ł���B
�@1945�N�\1952�N�B���̊ԁA���{���̂��������̐�������ɂ߂�͓̂���B�m���ɓ��{�͕������ꂸ�ɂ��B�����A���̈���ŗl�X�Ȗ����c�����B���S�ۏ�B����̋]���B�̓y���E�E�E�E�E�ؖ��͎���҂��˂Ȃ�Ȃ��B
�@�ǂ�ȍ��Ƃ��A��O�Ȃ��A���O�̋]�����ςݏd�˂����j�̏�ɐ��藧���Ă���B�]���͂��̏ꂵ�̂��ł͂Ȃ��A�����̊�]�ɂȂ�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����łȂ���Ώ����͕�����Ȃ��B�����ڎw���̂������ł���A���ꂪ���Ƃ̗ǐS�Ƃ������̂��B ������A����̂����͉������ׂ����H�@���z���肶��Ӗ����Ȃ��B��s���Ă��肶��i�����Ȃ��B
 ���j�𐳂����������邱�Ƃ��B����������ڂ�{�����Ƃ��B���ꂱ�����A���{�Ƃ��������܂��Ƃ��ȕ����ɓ��������ɂȂ�B�����M����B���R���ق̎��ʂɂ��Ȃ����߂ɂ��B
���j�𐳂����������邱�Ƃ��B����������ڂ�{�����Ƃ��B���ꂱ�����A���{�Ƃ��������܂��Ƃ��ȕ����ɓ��������ɂȂ�B�����M����B���R���ق̎��ʂɂ��Ȃ����߂ɂ��B�@����9��19���A���͎��̌���ɍs�����R���ْlj���ɍ������Ă����B�ߏ��̎q��������Ă��āu����Ȃ�Ȃ́H�v�Ɛu������A�u����͂ˁA���R����Ƃ����l�̔�ȂB�́A���̋߂��̐��H�œd�Ԃ�瀂���Ď�������B�����ǁA�Ƃ��Ă������l����������A�Y��Ȃ����߂ɂ��̔������v�Ƙb���Ă�����B�����͋G�߂͂���̏����������������A��͒��H�̖����B���炭�����������B
2013.09.15 (��) �b����`�ˑR�̑������
�@��і��q�̒m��l���m�閼�ȂɁu�ˑR�̑�����́v�Ƃ����Ȃ�����B�ޏ��̏ꍇ�A����͕ʂꂽ���l�����6�N�ڂ̉ԑ����������A���̏ꍇ�́A�����I�O�̉����������������B�@�ҏ��^��������7�����A��w�I�P�����̗F�l�c�����p�N���珋�����������͂����B�̋��F���s�̉Ƃ������ނׂ��ƍ���������Ă�����A�����̃I�[�P�X�g���i�ꋴ��w�nj��y�c�j�̘^���e�[�v���o�Ă����Ƃ����B�uCD����ƒ��v�Ƃ������̂ŁA�u���������v�ƕԎ����������B�b���Y�ꂩ����9���ɓ�����������A5����CD�������Ă����Ƃ����킯�ł���B
�@���́A�I�[�v�����[���E�e�[�v�̒���40�N�ȏ���Q�Ă����̂ŁA�Đ�����ς������Ƃ����B��������̂͂��A���R�[�h��Ђ̂悤�ɁA���x�Ǝ��x��K���ɕۂ��ĕۊǂ��Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�e�[�v���m���\��t���Ă���B��������ߊ������Ĕ������B������M�����Ɏ��Ԃƌo�������B�����Ǝ҂��炩�Ȃ�̋��z����ꂽ�悤�����A�S�苭���������������̐��܂Œl�����������B�������������������������Ă��̂�����̌��͖͂������݂ƌ����B
�@���́A1964�N�A�����I�����s�b�N�̔N�ɁA��w�ɓ����ď㋞�B���ɖ�����ꂽ���߁i�H�j�N���V�b�N�ɋQ���Ă�������A�킫�ڂ��U�炸�ɃI�[�P�X�g�����ɓ��������B30�����炸�̐w�e������A��]�����100�����ꂽ�B����܂ŁA�s�A�m�ȊO�̊y��̌o���͂Ȃ��B�y��I�т́A�I���G�������A��y�i�m�����@�C�I�����̈ɓ��a�F��y�������Ǝv���j�Ɩʒk�ŁB�u�o���́H�v�u����܂���v�A�u��肽���y��́H�v�u���Ɂv�A�u����A�E�`�ɂ͍��g�����y�b�g�����Ȃ�����A�ǂ��B����Ȃ��������ĂȂ�����A��N�����b�X������X�e�[�W�ɏオ����v�u�ł͂��������Ă��������܂��v�B���ɂ��������Ȃ��̂��B
�@�����A�����g�����y�b�g�u�]���������͂����ƃ��j�[�N�������B�I���G���̋A�蓹�A�ӂƁu�N���V�b�N�͉����D���Ȃ́H�v�Ɛu���Ă݂�ƁA�u�Ȃɂ��m����v�Ɠ�����B�u�����I ����A�Ȃ�Ńg�����y�b�g�Ȃ́H�v�u�i�D�������炾��v�B�܂�ʼn�������_�C�n�c��CM�ł���(�`���b�g�Â���)�B�ނ̓X�L�[���Ƃ̃J�P���`�B���ɖ����ō����Ȃ�������B����C�������āA�������̉��h�ɓ���Z��A���x���ꏏ�ɃX�L�[�ɏo�������B�ނ͑��ƌ�ŗ��m�̎��i�����A��v���������o�c���Ă���B
�@��������̃g�����y�b�g��U�̊w���E����L��Y����ɕt���āA��N�Ԃ̖ғ��P�̖��A����̂��A1965�N��N���̂Ƃ��������B
�@�����Ă���5����CD�ɂ́A�ꋴ��w�nj��y�c1964�N����1967�N�܂ł̉��t�����^����Ă���B���������āA���́A���̂�����3���i1965�A1966�A1967�N�̒�����t��j�̒��ŁA�P�����������т₩�Ɂi�H�j�g�����y�b�g�𐁂��炵�Ă���̂ł���B���ł���N��1965�ƎO�N��1966�͈�ې[���B
 �@�܂��́A��N���A1965�N11��24���A�����u���ł̑�13�������t��B�Ȗڂ́A�`���C�R�t�X�L�[�̃��@�C�I�������t�Ȃƃx�[�g�[���F���́u�c���v�ł���B�`���C�R�t�X�L�[�̃\���X�g�́A�m���̃R���T�[�g�}�X�^�[���o�ēƗ���������̐l�C���@�C�I���j�X�g�C��`�Y����i1936�|�j�B�Ȃ�����ȑ啨���A�Ǝv���邩������Ȃ����A���͉�X�̏�C�w���ҁE�������g�搶�i1899�|1981�j�ɂ���B�F����W�C�T���ƌĂ�ĕ��ꂽ�搶�́A�m���̑O�g�̖��Ԍ����y�c���R�c�k⩁A�߉q�G����ƌ��������킪�������y�^���̑n�n�҂̈�l�Ƃ����d���Ȃ̂ł���B�Ȃ̂ŁAN���̌�y�C�쎁�Ɂu�����A������ƃE�`�̊w���I�P�Ƌ������Ă���Ă���v�ƌ�����̂��B
�@�܂��́A��N���A1965�N11��24���A�����u���ł̑�13�������t��B�Ȗڂ́A�`���C�R�t�X�L�[�̃��@�C�I�������t�Ȃƃx�[�g�[���F���́u�c���v�ł���B�`���C�R�t�X�L�[�̃\���X�g�́A�m���̃R���T�[�g�}�X�^�[���o�ēƗ���������̐l�C���@�C�I���j�X�g�C��`�Y����i1936�|�j�B�Ȃ�����ȑ啨���A�Ǝv���邩������Ȃ����A���͉�X�̏�C�w���ҁE�������g�搶�i1899�|1981�j�ɂ���B�F����W�C�T���ƌĂ�ĕ��ꂽ�搶�́A�m���̑O�g�̖��Ԍ����y�c���R�c�k⩁A�߉q�G����ƌ��������킪�������y�^���̑n�n�҂̈�l�Ƃ����d���Ȃ̂ł���B�Ȃ̂ŁAN���̌�y�C�쎁�Ɂu�����A������ƃE�`�̊w���I�P�Ƌ������Ă���Ă���v�ƌ�����̂��B�@�W�C�T���́A�C�쎁�̑��ɂ��A�s�A�m�̈�������q���i���ڂ̓��[�c�@���g�u�Պ����v�j�A���@�C�I�����̒ҋv�q���i�x�[�g�[���F���̋��t�ȁj�ȂǁA�w���I�P�ɂƂ��ẮA�_�̏�̑��݂Ƃ��������悤�̂Ȃ����ꗬ�A�[�e�B�X�g���Ă�ł��ꂽ�B���X�Ȃ���A�W�C�T���̎��͂Ɋ��Q�������ł���B
�@40���N�Ԃ�ɒ����A�C�삳��̃��@�C�I�����́A�Ȃ�ƃ`���[�~���O�Ȃ��Ƃ��B���m�����̕n�����������ǁA���̑f���炵���͂�������Ɠ`����Ă���B�[���ȘȂ܂��̒��A�̂��ׂ��Ƃ���͂�������Ɖ̂��B�m��̃o�����X�̂悢�A����͖����t���B�莝���̂ł̓p�[���}���̉��t�ɋ߂����H ���̕������ǂ����1���g�D�b�e�B�������܂��܂�����ɐ����Ă��Ĉ��S�����B�f�l�̋ɂ݂̃I�[�P�X�g���ł��A����Ɉ��������āA����̒��ł͐���̃p�t�H�[�}���X�ł���B�Ƃ͂����A��͂�l�l�ɂ͕��������Ȃ��B�p���������B
�@���́A1966�N12��12���A�O�N���̂Ƃ��̒�����t��B��X���}�l�[�W�����g�������v���o�[�����t��ł���B�u����s�S�̃z�[���Łv�������t�ɁA���߂ČՃm��z�[���ŊJ�Â����B������ɂȂ������������A���ߍ��킹��ׂ������Ƀ`�P�b�g�����B��y��K�ˍL�������܂������B�R�l���g���Ĉ������팸�����B�����āA�Ȃ�Ƃ������ɂ��������B
�@�Ȗڂ́A�V���[�x���g�u���U�����f���ȁv�A�x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�� ��4�ԁA������ ��3�ԁu�p�Y�v�ł���B
 �@�s�A�m�E�\���͈����q�q����B���̕��A�r�����邱�ƂȂ���Ⴍ�đ�ςȔ��l�I �W�C�T�������ɒu���C�Ǝv���A���n�[�T�����狹�������B��Ɍ��Ƃ�ďo�����A����肷���ĉ��O���B�u�V�b�J�����A���̂ق琁�����b�p�I�v �ł��{�Ԃ̓o�b�`���������B
�@�s�A�m�E�\���͈����q�q����B���̕��A�r�����邱�ƂȂ���Ⴍ�đ�ςȔ��l�I �W�C�T�������ɒu���C�Ǝv���A���n�[�T�����狹�������B��Ɍ��Ƃ�ďo�����A����肷���ĉ��O���B�u�V�b�J�����A���̂ق琁�����b�p�I�v �ł��{�Ԃ̓o�b�`���������B�@���C���y�ȂɑI�u�p�Y�v�́A�g�����y�b�g����r�I����̂����A�������Ă݂�ƁA��͂�p���������B���肭���ł���B�Ƃ͂����A���x�����������Ɋ���Ă��邩��s�v�c�Ȃ��̂��B�@
�@���̓v���O���������S���������A�ꕔ������ՓI�Ɏ茳�Ɏc���Ă���B�y�[�W���߂���ƁA������l�ЂƂ�̊炪��������������ł���B
�@�t���[�g���H��m�B�u�p�Y�v��4�y�͑�4�ϑt�Ɓu�u��1�v��4�y�̓A���y���E�z��������̃\���������ł���B�����řz�X�����ނ̉�����������Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B������������ɒɂށI
�@�H��N�̉��h�͍����w�̂������ɂ���������A�����K��������B�T2���͗��K�B���̑��̓��́A�߂��́u�@��v�u���[�W�i�v�ŃR�[�q�[�����݁A���ȋi���u�W���s�^�[�v�ɓ���Z��A�}�[�W���������B�܂�ŌZ��̂悤�ɉ߂��������̂��B���y�ւ̑��w���[���A�o�b�n�̎����y�͔ނ��狳������B�����^�[�́u�p�Y�v���u����͐����ˁv�ƃ|�c���Ƃ��������t���]���ɏĂ����Ă���B��w���V�˂ŁA�u�قƂ�ǃ}�X�^�[�������������A���e����ł���낤���ȁv�Ȃ�Č����Ă��������B�X���Z�̏o�g�ő��Ɏ��̌�y�ɓ�����B���j�ŏ����Ȓj�������B
�@����Ȕނ��A�݂��ɎЉ�l�ɂȂ���1969�N5���ɋA��ʐl�ƂȂ��Ă��܂��B ���~���̓S�����璆�����ɐg�𓊂����̂��B���̕�����O���A��ɂ���ă}�[�W�����Ŗ�x���A�������ɁA���h�̂����u�H�ꂳ��Ƃ����l����d�b�����������v�Ƌ����Ă��ꂽ�B��Ђ̘A���悵�������ĂȂ��������́A�u�Ȃ낤�H�����ɂł��d�b���Ă݂悤������v�ƋC�ɂ����߂��ɐQ�Ă��܂����B�����āA�����E�E�E�E�E�B�u����Ȃ��ȁI���������Ȃ��H �����͍Ō�̍Ō�ɁE�E�E�E�E�B���������Ƒ������h�ɖ߂��Ă�����I�I�v�B�t�̒ɍ��ɂ��Đh������v���o�ł���B��1970�N�A�����݂̂�ȂŁA�����œ��키���̓t�F�X�e�B�o���z�[���ŁAJ.S.�o�b�n�u���Z���~�T�ȁv�i�������E�}�[�[���w���j���Ȃ���A�ނ�Ǔ������B�܂����ӂ�Ďd�����Ȃ������B
�@�H��N�Ǔ����t����d�����̂̓I�[�{�G���{��h�Y�B�ɏ��y�͂̃t���[�W���O�͐�i�������B���ɂ悭�̂��̂ł���B�u�p�Y�v��2�y�́u�����s�i�ȁv��u�u��1�v�̑�2�y�͂̃\�����D�Ⴞ�B�ނ͑��ƌ�ґR�Ǝw���̕������āA���܂ł͗��h�ȃv���w���҂ɂȂ��Ă���B
�@�t���[�g���{���ܕS���͑ʟ����̒鉤�B��������A�E���Ȃ�����F��v�m�ɂȂ����`�F�����ێR�O���A�ނ̌������ł́A���Ə����ŁA�u�䂪�ǂ��F��v���̂����ȁB��������̊w���Ղʼn^���̏o������Č��������z�������n��M�O�B�o�ϊ�撡�ɍs�����W�F���g���}���A�Ŋy����쑺���B������l�̃g�����y�b�g�E�Â��Ȃ�D�����c���O�͋�s�}���ɂȂ����B�p�c�Ȑ��˂��ۃN�����l�b�g����ؗ�j�͍��͌̐l���B���܂�ɂ��܂����Ă��̂Ƃ��ɂ͐Ȃ��Ă����t���[�g���Җ{�v�́A�@����قōs�������̌�����I���ŁA�u���҂����v�Ɓu�o�b�n�̃|���l�[�Y�v�̖����t�����Ă��ꂽ�����E�E�E�E�E�ȂǂȂǁA�������������̖ʁX�ł���B
�@�����āA�Ȃ�Ƃ����Ă��A�c�����p�N�ł���B�y��̓r�I���B�N�ԃX�P�W���[���̗��āA�ċG���h�̎d��A���ڂ̌���A���T���A�\�Z���āA�w���҂Ƃ̘A�g�A��E��y�Ƃ̃p�C�v���ȂǁA�������S�ƂȂ��Ĉ����������B�S�������������₩�ɁB������݂�ȋC�����悭�������B��M�ƗD���������������}�l�[�W���[�������B
�@�����č���A�ˑR�̑�����̂�͂��Ă��ꂽ�B�����I�̎�����z���A�t�̂��������̂Ȃ����オ�߂��Ă����B���肪�Ƃ��A�c���N�B�����Ղ��̊��ӂ��I�I
2013.09.02 (��) �b����`�u�������ʁv���ς�
 �@�{��x(1941-�j�̍ŐV��u�������ʁv���ς��B���̐v�Җx�z��Y�i1903-1982�j�̔����Ɩx�C�Y�i1904-1953�j�̏����u�������ʁv�����̂��������ꂾ�B
�@�{��x(1941-�j�̍ŐV��u�������ʁv���ς��B���̐v�Җx�z��Y�i1903-1982�j�̔����Ɩx�C�Y�i1904-1953�j�̏����u�������ʁv�����̂��������ꂾ�B�@�x�z�́A�����m�푈�J��O�ɁA���E�Ɋ����鐫�\�����퓬�@�̐v���d�グ���B�C�R�̉ߍ��ȗv�����N���A���Ċ������ꂽ���̐퓬�@�����u���v�i���͏�퓬�@�j�ł���B���x�A�q�s���ԁA�i�����\�A���쐫�ȂǁA�����A���E�ɂ���ȏ�̂��̂͂Ȃ��A�P�P�Ȃ�Ζ��G�̐퓬�@�������B�uF4F�͏㏸�́A�q�����A�X�s�[�h�A���ׂĂɂ����ė��ɗ���Ă����v�B����̓~�b�h�E�F�[�C���F4F���J���Đ�����ČR�p�C���b�g�̏،��ł���B�A�����J�́A���ʍ��ł���ɑR�����B1�@�̗���2�@�����Ă����B�����͎m��l�Ȃ甒�Q�ɂ����Ă闝�����B�����āA�푈�����A���͐��ɂ͓��U�̔�s�@�Ƃ��đ����m�ɎU���Ă������B���������҂̋M�d�Ȗ��Â�ɂ��āB
 �@�x�z��Y�̓v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̎d����S�������B�Ȃ̂ɁA���̌��ʂ͖��c�Ȃ��̂ƂȂ����B�ނ̎�ɂȂ�퓬�@�́A���U�Ƃ������̖��d�ȍ��̓���ƂȂ�A�����̗L�\�Ȏ�҂����ɒǂ�������̂��B
�@�x�z��Y�̓v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̎d����S�������B�Ȃ̂ɁA���̌��ʂ͖��c�Ȃ��̂ƂȂ����B�ނ̎�ɂȂ�퓬�@�́A���U�Ƃ������̖��d�ȍ��̓���ƂȂ�A�����̗L�\�Ȏ�҂����ɒǂ�������̂��B�@�ނ̖��O���͂܂��ɂ����ɂ������B�I��̑O�N�A�u�_�����U���v����������Z���̈˗������Ƃ��̔ނ̐S��ɁA���̂�邹�Ȃ����@���ɕ\��Ă���i�x�z��Y���u���`���̒a���Ɖh���̋L�^�v�p�앶�ɂ��j�B
�����̑O�r�����҂��A�����ċA�邱�Ƃ̂Ȃ��̓�����U���ɏo�����Ă䂭�B�V���ɂ��A�ނ�͌����Ƃ������������߁A�j�ɂ͐Â��Ȕ����������ׂĔ�s�@�ɏ�肱��ł������Ƃ����B���̏�i��z�����������ŁA���������ς��ɂȂ��āA���͂Ȃɂ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ނ炪�j�݂Ȃ����荞��ōs������s�@����킾�����B �悤�₭�C���Ƃ�Ȃ����A���̐킢�œ��e���������l�X�ɑ����Ă��̎��������̂��Ǝ����Ɍ����������Ȃ���y�������������A�����Ȃ���܂����ڂ�Ăǂ����悤���Ȃ������B ���Ɏ�Ȃ��œ��U�����������镶�ȂǏ�����͂����Ȃ������B�Ȃ����{�͏��]�݂̂Ȃ��푈�ɔ�э��݁A�Ȃ���킪����Ȏg����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�������̂��Ƃ��S�Ɉ����������Ă����B�@�X�^�W�I�W�u���͊��R�ł���B���}�X�R�~�͂������Ď��グ��B���̌���������NHK����O�ł͂Ȃ��B�ǂ��납�A��������������Ȍ��������̔Ԑ����������Ă����̂��ƐS�z�ɂȂ邭�炢�̃��C�V�����B
�@8��26�����f�́u�v���t�F�b�V���i�� �{��x1000���̋L�^�`�V��a�� �m��ꂴ�镑�䗠�v�́A�����ʂ�1000���Ԃɂ��y�ԁu�������ʁv�̐���o�܂�ǂ��������h�L�������g�ł���B
 �@�ԑg�S�ʂ�ʂ��A�{��́A�x�z��Y�ւ̌h���ƍ�i�ɍ��߂�v���������B�u�x�z�͔�������s�@����肽�������B�����A����͔ނɎE�C�̕������点���v�u�x�z�͂��߂��̎���̐l�X�́A�������̗͂�s�����Đ������B�w�������ʁx�Ƃ����̂͌���������̕��������Ă���A����������ł���A���̒��Ő����悤�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂��v�u���ꂪ�A����Ƃ�������A�k�Ђ��N�������̎���̓����ɂȂ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��v
�@�ԑg�S�ʂ�ʂ��A�{��́A�x�z��Y�ւ̌h���ƍ�i�ɍ��߂�v���������B�u�x�z�͔�������s�@����肽�������B�����A����͔ނɎE�C�̕������点���v�u�x�z�͂��߂��̎���̐l�X�́A�������̗͂�s�����Đ������B�w�������ʁx�Ƃ����̂͌���������̕��������Ă���A����������ł���A���̒��Ő����悤�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂��v�u���ꂪ�A����Ƃ�������A�k�Ђ��N�������̎���̓����ɂȂ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�@�x�z��Y���u��ɐS�Ɉ����������Ă������Ɓv�Ƃ́A�u��킪�A�Ȃ����U�̔�s�@�Ƃ��Ďg��ꑽ���̑O�r�����҂̖���D���Ă����Ă��܂����̂��v�Ƃ������Ƃ������B������{�l�̈ӎv�Ƃ͈Ⴄ�g����������Ă��܂����A���̕s�����A���O���ł���B�����A���ꂪ�푈�̏h���ł�����B���̂��Ƃ��ނ͉����Ă����B�����炱���A�߂����̂ł���B
�@�f��u�������ʁv�ɂ́A�c�O�Ȃ���A���̎��_���������B�x�z�̔߂������O�����`����Ȃ������B�u�i�x�z�̎d���́j���ꂽ�d�����Ƃ������Ƃ��������ĂȂ��Ƃ܂�Ȃ��v�Ƌ{��͌����Ă͂�������ǁB
�@�f��u�������ʁv�͗�킪���܂��܂ł̕��ꂾ�B�x�z�̔߂��݂́A��킪�v�҂̎�𗣂�Ă���̂��́B������u�x�z�̋�Y���ł��d�����Ȃ��v�Ƃ�����������낤�B
�@�ł����͕�����Ȃ��B�ނ̐l�����ǂ��ŋ�낤�Ƃ��A���̔ߌ���m����{�l�Ƃ��ẮA�����ɐv�҂̋�Y�������ƐF�Z���\��Ă��Ăق����Ɗ肤�B�x�z��Y�ւ̃I�}�[�W���͂��̋�Y�ɂ�����������ׂ��ł͂Ȃ����A�ꐶ�w�������������̏\���˂ɂ����B ���X�g�A���̒��A�J�v���[�j�Ƃ̒ʂ��Ղ̑Θb�ł܂Ƃ߂Ă��܂��A���ꂪ�{����w�Ȃ̂�������Ȃ����A����ł͕s���Ȃ̂ł���B
�@�x�z�������̋Z�t�ƃh�C�c�̍H������@������A���ӂ���V���[�x���g�́u�~�̗��v��6�ȁu���ӂ��܁v������Ă����ʂ�����B�{��͖x�z�Ɂu�w�~�̗��x���B�ڂ������̗��ƈꏏ���ˁv�Ƃ����䎌�����Ă������B���̍s�������Î�������ʂƂ����邪�A���Ȃ��20�ȁu������ׁv��I�Ȃ���B���̉̂͂���Ȉ�߂Ō���� �͍s���˂Ȃ�Ȃ� �N���߂��Ă������Ƃ̂Ȃ����̓����B
�@�����u�������ʁv�Ƃ̃h�b�L���O�B����͂���ł������낤�B����́g�����̂悢���[�h�~���[�W�b�N�h�̎�ł����Ȃ�����ǁB
�@�Ō�Ɉꌾ�B�^�C�g���E���[���ɗ����r��R���u�Ђ������_�v�͐��������B�� ���܂�ɂ��Ⴗ������ �����v������ ����ǂ����킹�@����������Ȃ� �����ĕ����オ��@��ɓ���� ��������Ă䂭 ���̎q�̖��͂Ђ������_ �E�E�E�E�E���[�~���́A�m���r�u���[�g�Ȃ��炠���̏�O���߂��̏��́A�x�z��Y�̋�Y���A�Ⴋ���U�����̍���u�₩�ɕ�ݍ��݁A�����߂��݂̝R��Ő��߂������B�܂�ŁA���̉f��̂��߂ɏ������낵�����̂悤�Ȍ����ȃ}�b�`���O�ɂ��āA�{��x���`����Ȃ������̕����A���������₤�悤�ȁA��Ղ̃h�b�L���O�������B
�@�{���A9��2���A�{��x���ނ̃j���[�X������Ă����B���������A�u�I���������\���B�������Ԃ��̂��̂����Ȃ���v�iNHK�u�v���t�F�b�V���i���v�j�Ƃ������t���C�ɂȂ��Ă͂����B���̎���A72�͎Ⴂ�B����Ȃ̂Ɂu�������Ԃ����Ȃ��v�Ƃ́A�ǂ��������ƁH
�@�Ƃ������A�ꎞ����悵�����������ނ���B����̏I���͂����҂����B�{��ēA�����Ԃ����l�ł����B
2013.08.25 (��) ���I�u���R�����_�v5�`���������̏
[9] �����̏�Ə��a�d�H�����@����͂����������B�u���̂���̐��E��͂ǂ��������̂��B���̒��œ��{�͂ǂ̂悤�ȗ���ɗ�������Ă����̂��B���ꂳ���킩��A���R���Ȃ��E���ꂽ�̂����킩�邾�낤�v�ƁB�{�͂ł͂����ǂ݉����Ă݂����B
 �@���̓��{���ǂ����邩�H �}�b�J�[�T�[������GHQ�̓����͓��{�̍������������B�����m�푈�̏����A�gI shall return�h�̑䎌���c���ăt�B���s���P�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�ނ̓��̒��ɂ́A�펞���̓��{�l�̕|���A���̂̒m��Ȃ��A�����т���Ă����Ǝv����B���̖����́A�v�����ނƂƂĂ��Ȃ��p���[�œ˂��i�ށB��x�ƍĂѐ키�C���N�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�R���ƍ����̉�̂�}��A��ӂ̉��E�ނ��Ƃ��B���Y��`�҂𗘗p���Ăł��B
�@���̓��{���ǂ����邩�H �}�b�J�[�T�[������GHQ�̓����͓��{�̍������������B�����m�푈�̏����A�gI shall return�h�̑䎌���c���ăt�B���s���P�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�ނ̓��̒��ɂ́A�펞���̓��{�l�̕|���A���̂̒m��Ȃ��A�����т���Ă����Ǝv����B���̖����́A�v�����ނƂƂĂ��Ȃ��p���[�œ˂��i�ށB��x�ƍĂѐ키�C���N�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�R���ƍ����̉�̂�}��A��ӂ̉��E�ނ��Ƃ��B���Y��`�҂𗘗p���Ăł��B�@�Ƃ��낪�A���E��̓A�����J�̎v�f�Ƃ͕ʂȕ����ɕ��ݎn�߂�B�����ł́A�ёE�������Y�}�̐��͂������A�Ӊ���p�ɒǂ����B�h�C�c�ł́A����������]�V�Ȃ����ꂽ�B���N�����������̊�@�ɎN���ꂾ���B���X���݉�����\�A�̗͂Ƌ��Y��`�g��̋��ЂɁA�A�����J�̊�@���͋Ɍ��ɒB�����B���{���A�W�A�̔����̖h�ǂɂ���K�v�����������̂ł���B���͂⍜�����̂܂܂ł͂����Ȃ��B���Y��`�҂��r�����˂Ȃ�Ȃ��B�����o�ϗ͂Ƌ��łȃC���t�������ČR�����K�v�Ƃ����Ɏ������̂��B��̐���̓]���ł���B
�@GHQ�����A�]���̕��j���т������j���[�f�B�[���h�z�C�b�g�j�[��GS�i�����ǁj�Ɣ������f����ێ�h�E�B���r�[��G2�i�Q�d��2���j�̎哱���������\�ʉ����Ă���B����ɃP����t�����̂�1948�N6�����u���a�d�H�����v�������B�ێ�h���AGS�����P�[�W�X�卲�̎��r��}�邽�߁A�����q�ݕv�l�Ƃ̕s�σX�L�����_����\���B���̉ߒ��ŁA�u�������Z���Ɂv�ɗ��ޏ��a�d�H�ƈ��c���t�̑����d������݂ɏo���B
�@�ێ�h�Ƃ́A�P�[�W�X��Ǖ��������E�B���r�[�A���c���t��|�������g�c�A�g�c�̑��߂�GHQ�ɃI�[���}�C�e�B�Ɋ炪�������F���Y�ȂǁB���̃O���[�v�������A��������������Ƃ�����̖ړI�Ō��ꂽ�t�@�~���[�������B
�@���̌��ɂ��ẮA���{�����������u���{�̍������v�i���t���Ɂj�̒��Ō��y���Ă���B
GHQ�����ǂ̖d�卲�́A�����Ǔ��ł���Ԓ��𗎂Ƃ��悤�Ȍ��͂������A���{�̐�̐������Ă̒��S�I���݂��������A���̐���͔��ɍ����I���Ƃ����̂ň��͋��Y��`�҂ł͂Ȃ����Ƃ�����]������AGHQ��G2�ɗF�l�𑽂������Ă���g�c���t�̖d�v�lS����G2�ƈꏏ�ɂȂ��Ă��̑卲����{���狎�炵�߂悤�Ƃ���������v�悳��A���̂��߂ɑ卲�̔�s����{�����炵�߂�ޗ��̎�����͂ޕK�v������Ƃ����̂ŁA�v�R����S�����痊�܂�Čx�����ɒ��������Ă����B�@���̕��͂͏��{���������p�������㍑�x�����ē����̉�z�L�̈ꕔ�B�����̖d�卲�̓P�[�W�X��S�������F���Y�A�v�R���Ƃ͓����Ȃ̒����ǒ��ł���B������������F���Y�̈Ö��U�肪�`����B
�@�u���a�d�H�����v�́A�P�[�W�X���A�����J�ɒǂ����A���c���t��ׂ����B1949�N1���̉��U���I���ł́A�g�c�Η����閯�厩�R�}����������3���g�c���t���a���B�g�c�́A���̌�A1954�N12���܂ŒʎZ2616���i���3�ʁj�Ƃ��������ɂ킽���Đ����������A�����{�̑b���\�z���Ă䂭�B����AGHQ�ł́A�P�[�W�X��GS�͋��S�͂������A�E�B���r�[��G2�Ɏ哱�����ڂ��Ă䂭�B���ꂪ���R�������N���锼�N�O�A��̌����u���̂���̏�v�ł���B �����āA�������܂��ɐ�̐���̓]���_�ł����āA����ȍ~�A�����Ƃ������ʂ̗��O�Ō��ꂽ�g�c�Η�������{���{�ƃE�B���r�[���哱����������GHQ�́A���{���A�W�A�ɂ����锽���̖h�ǂƂ��邽�߂̍��Â����i�߂Ă䂭���ƂɂȂ�B
[10] �h�b�W�E���C���ƃW���p���E���r�[
�@��͂���Ɍ����B�u�h�b�W�E���C���Ƃ͂Ȃ����̂��H�n���[�E�J�[���͂Ȃɂ���낤�Ƃ��Ă����̂��v�B
�@���Y��`�̋��Ђ́A���X���X�Ƒ��債�Ă䂭�B�A�����J�Ƃ��ẮA�������ł��H���~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɓ��{���̖h�ǂɂ���K�v���������B�A���̐����ƃA�W�A�̍H�ꉻ�ł���B
 �@�W���Z�t�E�h�b�W�ɂ��A�u�o�ψ���9�����v�i�ʏ̃h�b�W�E���C���j�����ꂽ�̂́A1949�N2���̂��ƁB�P�j��360�~�̒P��בփ��[�g�̐ݒ�A�l�������ɂ�鍇�����Ȃǂ����q�Ƃ������{�o�ύĐ��̎w�j�ł���B�o�ύĐ��Ƃ����ƕ������͂������A�A�����J�̖ژ_���͓��{�o�ς������悭���������A���v���z���グ�邱�Ƃ������B�P�j��360�~�́A��O��72�{�Ƃ������~�����[�g�ł���B�����b���A��O��72����1�̓����œ��{�̎��Y����ɓ���킯�ł���B
�@�W���Z�t�E�h�b�W�ɂ��A�u�o�ψ���9�����v�i�ʏ̃h�b�W�E���C���j�����ꂽ�̂́A1949�N2���̂��ƁB�P�j��360�~�̒P��בփ��[�g�̐ݒ�A�l�������ɂ�鍇�����Ȃǂ����q�Ƃ������{�o�ύĐ��̎w�j�ł���B�o�ύĐ��Ƃ����ƕ������͂������A�A�����J�̖ژ_���͓��{�o�ς������悭���������A���v���z���グ�邱�Ƃ������B�P�j��360�~�́A��O��72�{�Ƃ������~�����[�g�ł���B�����b���A��O��72����1�̓����œ��{�̎��Y����ɓ���킯�ł���B�@�W���p���E���r�[�i�A�����J�Γ����c��American Council on Japan�j�́A�A�����J���{�Ƃ̓��{�ɂ����铊�����v�m�ۂ�ړI�ɍ��ꂽ�g�D�Ƃ�����B���S�l�����n���[�E�J�[���B�ނ�́A��O��72����1�Ƃ����������œ��{�̗��������Ƃ��ł��A����ׂ���̉����ŕK�R�I�ɉ~���l�オ�肷��A�X�ɔ���ȗ��v���]���荞�ށB�A�����J���A��̐���̖��̉��ɁA�s�퍑���{�Ɏd���o�ς�㩂������h�b�W�E���C���������B����ȃA�����J���{����{�ɓ������邽�߂̑����̈���u�č������������Ԃ莑���v�ŁA������Ǘ�����̂����{�J����s�A����̏��ђ��́A���F���Y�̐l���ł���B
�@����ɋ����ׂ����ƂɁA�u�W���p���E���r�[�v�̔w��ɂ̓��b�N�t�F���[���c��J.P.���[�K���ЂȂ����_���n���{������t���Ă���B�A�����J�́A�h�b�W�E���C���ƃW���p���E���r�[�̃Z�b�g���Ȃ��āA���{�o�ς����܂ł���Ԃ�����\�}�����グ���̂ł���B
�@�����ɂ͎������K�v�ł���B���̐����̎������[�g���h�b�W���C���`�W���p���E���r�[�̘g�g�݂̒��ɂ������Ƃ�����I�H�E�E�E�E�E�B
�@1948�N6���u���a�d�H�����v�`1949�N1����3���g�c���t�̐����`2���h�b�W�E���C���̒`7�����R�����B���̈�A�̗���̒��ɂ����A���R������������������E�E�E�E�E����͂��������Ă���̂ł���B
2013.08.10 (�y) ���I�u���R�����_�v4�`����̘b ���
[7] ����̘b ��ҁ`���R�����ɂ����@����̘b�͂��悢�扺�R�����ɂ���������B�{���̎R��ł���B��������͕�����̎�������L����B������́A�ܘ_�A���ҁE�ēc�N�F���ł���B�ēc���́A�^���Ɏ�����d�˂����ŁA�̈ӂɓI�O��Ȏ���������Ȃ���A���肩��{���g�[�N�������o���Ă����B���ʁA���̂����͎����̊j�S�ɔ������B
�@�Ō�܂ŁA��̌�����u�����v�Ɓu�t�B�N�T�[�v�̋�̖��͏o�Ă��Ȃ����A�W�O�\�[�p�Y���̂��Ƃ��A�ނ̌��t�̒f�Ђ��Ȃ����킹��A�����̐^���͌����Ă���B����́A����̌��t���^��������ł���B
�@�Ȃ��A����1992�N2���A�ꏊ�͓Ȗ،���s�̖�Ƃ̉��~�ł���B
�\���������A���̂��덑�S�Ɋ֘A���Ă���������������܂����ˁB���R�����Ƃ�
�u�����A�������ȁv
�\���R����ɖʎ��͂������̂ł����H
�u��������Ƃ��炢�͂���v
�\�����Ȃ�A�����ɂ��ĉ����m���Ă�Ⴀ��܂���
�u�������m���Ă邳�v
�\�Ȃ����R����͎E���ꂽ��ł��傤�ˁH
�u���̂���̎Љ����l����킩�邾�낤�v
�\��̍��S�̑�ʉ��قł����B���R����͘J�g���h�ɍ��܂�Ă����A�Ƃ����b�͂���܂��ˁB
�u�n���Ȃ��Ƃ������ȁB�A�J�̍������ǂ��ɉ����ł���B����ȑ傻�ꂽ���Ƃ�����킯���Ȃ��v
�\�������A�J�g���h�̔ƍs���𐭕{��GHQ����`���܂�����ˁB���̌��ʁA���Y�}�͋��S�͂��������S�̑�ʉ��ق͈�C�ɉ�������܂����B
�u�\�ʂ�������������Ȃ�B����������́g���ʘ_�h���B�����Ǝ�����L���Ă݂�B�ǂ����̐V���L�҂̏������Y����M����ȁB���̂���̐��E��͂ǂ��������̂��B���̒��œ��{�͂ǂ̂悤�ȗ���ɗ�������Ă����̂��B���ꂳ���킩��A���R���Ȃ��E���ꂽ�̂����킩�邾�낤�v
�\����Ȃ��͂�A�A�����J�̖d���ł����H
�u�����͌����Ă��Ȃ��B�E�B���r�[�͎����𗘗p�����������B�h�b�W�E���C���Ƃ͂Ȃ����̂��B�n���[�E�J�[���͉�����낤�Ƃ��Ă����̂��B������l����B�������Η����鐢�E��̒��ŁA���{�͏�ɃA�����J�Ɠ������ɗ����Ă���B�ߋ����A���݂��A���ꂩ������B�����A�����J����Ȃ��ă\�A�ɐ�̂���Ă�����A�ǂ��Ȃ��Ă����Ǝv���H���{�͓��h�C�c�݂����ɂȂ��Ă�����������Ȃ����B�����H���~�߂��̂��}�b�J�[�T�[�₨�ꂽ���ȂB���Ĉ��ۏ��͂Ȃ�̂��߂ɂ���H�A�����J�̕s���ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͌����ׂ�����Ȃ��v
[8] ��̘b��������
�@����̘b�͂����܂łł���B�����ǂ݉����u���R�����v�������Ă���B�܂��́A�����Ŏ������L�C���[�h���Î����邱�Ƃ��B�����ɖ����u���Đl�Ԃ̌q������������邱�Ƃ��B�����Ĕނ�̈Ӑ}��ǂݎ�邱�Ƃ��B�^���͎����Ɩ��炩�ɂȂ邾�낤�B
����̌㌩�l���O�Y�`��
�_�C�������h�͂قƂ���E�B���r�[�iGHQ�Q�d��2�����j�������Ă�����
�g�c���͂����̋����g���ĒǕ���ĎɂȂ���
�悭���Ă��̂����F���Y
���Ƃ��n���[�E�J�[����
�m���ɉ����L���m���͐e�F������
�Љ�Ă��ꂽ�̂͊��̂��삳��i��c�����j
���ꂽ���������Ƃ����ЂƂ̖ړI�Ō��ꂽ�t�@�~���[��������
�����̂��Ƃ��������m���Ă邳
���̂���̐��E��͂ǂ��������̂��B���̒��œ��{�͂ǂ̂悤�ȗ���ɗ�������Ă����̂��B���ꂳ���킩��A���R���Ȃ��E���ꂽ�̂����킩�邾�낤�B
�E�B���r�[�͎����𗘗p�����������B�h�b�W�E���C���Ƃ͂Ȃ����̂��B�n���[�E�J�[���͉�����낤�Ƃ��Ă����̂��B������l����B�������Η����鐢�E��̒��ŁA���{�͏�ɃA�����J�Ɠ������ɗ����Ă���B�ߋ����A���݂��A���ꂩ������B
�����A�����J����Ȃ��ă\�A�ɐ�̂���Ă�����A�ǂ��Ȃ��Ă����Ǝv���H���{�͓��h�C�c�݂����ɂȂ��Ă�����������Ȃ����B�����H���~�߂��̂��}�b�J�[�T�[�₨�ꂽ���ȂB
�@����܂ł��W���[�i���X�g�̊Ԃł͖���̖��O�͉��x���������Ă����B�������A�C���^�r���[�ɐ����������̂͂��Ȃ������B���̕��˖����i�L���m�������̃C���^�r���[�ɐ����������߂Ă̓��{�l�j�ł���A��ɁA�u����ɂ͂ƂĂ����낵���ĉ�Ȃ������v�ƍ������Ă���B
�@����ȑ啨�ł���L�[�}���ł�������������A���߂ăC���^�r���[�ɉ������B����́A������ǂ����߂���̂ɂƂ��āA�^�ɉ���I�ȏo�����ł���A����قǂ̏Ռ��͂Ȃ��B���̃C���^�r���[�����A����܂����R�����̐^���ɔ��낤�Ƃ������ׂĂ̐l�X�̍ŏI�ړI�n�������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���Ƃ͖�̘b�̐^�U�ł��邪�A�����_���I�Ɏ����邱�Ƃ͍���B�Ȃ��Ȃ�A�����́A�������琔�\�N�o�������݂ł����������ꂳ��Ă��炸�A��̘b���ƍ�����m���鋾���Ȃ����炾�B�����Ȃ��͚k�o�����Ȃ��B�M�����邩�ۂ��Ƃ��������I�H
 �@�����g����{���̂��Ƃ������Ă���h�Ɗm�M����̂́A���̂Ƃ��̔ނ̌��������l�Ԗ{���̎p���Ǝv������ł���B�R�����Ȃ��ɂ������Ǝv���邩��ł���B
�@�����g����{���̂��Ƃ������Ă���h�Ɗm�M����̂́A���̂Ƃ��̔ނ̌��������l�Ԗ{���̎p���Ǝv������ł���B�R�����Ȃ��ɂ������Ǝv���邩��ł���B�@����̑O�ɁA�̋�y�����ɂ������ԁi�Ƃ������[���J�Ō��ꂽ���F�Ƃ������ق����������낤�j�̑������ꂽ�B���̒j�́A����ւ�����厖�ɂ��ċ����������^���ɗ������������Ƃ��Ă���B�l�ԂƂ������̂́A����̎v����N���ɑ����Ď���ł䂫�����Ɗ肤���̂��B���ꂪ�]���ɉ]���ʂ��̂Ȃ�Ȃ�����ł���A�����ׂ��l�Ԃ��^�ʖڂł������قNjC�������O�����ɂȂ�B
�@�Ėڟ��́u������v�͂܂��ɂ������������ł���B�g�����̎v���������l�Ԃ����ꂽ�玀�˂�h����Ȑl�Ԃ̕��Ղ̐S���`���Ă��邩�炱���A���̏����͉i���̃x�X�g�Z���[���肦�Ă���B
�@��̑O�ɂ��������l�Ԃ����ꂽ�̂ł���B�����Ȃ玩���̎v�����~�߂Ă����B�^�ʖڂɌ@�艺���Ă����B���̂�������Ƃ̖{���̈Ӗ������Ă����B�܂��ɁA�u������v�ɂ�����g���h�����ꂽ�̂ł���B����͎ēc�N�F��M�p�����B�����āA�C���悭����A�ʂ�ۂɁu�܂��V�тɗ����B�����͊y���������v�Ɩ{�����������̂ł���B����̘b�͐^���ł����B��͂��̒���ɔ]�[�ǂœ|����Ȃ����ĖS���Ȃ����B
�@����n�ߎ����Ɋւ�����l�����ɂ́A���{�̓����Ɂu�\�A���ւ�邱�Ƃ̋��Ђƕ��Q��j�~�����v�Ƃ�������������B��������u�����Ă������瓌�h�C�c�݂����ɂȂ��Ă��܂�����������Ȃ��v�́A�����A�u���{������Ă�����������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��B�����炱��͐��`�̍s�ׂł���ƁB
�@�u���R�͒N�ɎE���ꂽ���H�v�Ƃ����^��́A���{�������u���R�����̖��ߎ҂��N�ł��邩�͉i�v�ɔ���ʂ��낤�v�ƌ����悤�ɁA����d�����ł���B����ēc�Ɍ������āu�܂����ȁB���͂܂����B�܂��W�҂������Ă���B����10�N�A����A���ꂪ�����Ă��邤���͂��߂��B����v�ƌ����Ă���B
 �@�A�����J�����������ق̋g�c�t�@�C���ɂ́ACIA�����Ȃ����J�����ۂ��Ă���閧������13�y�[�W������Ƃ����i�t�����j���u�閧�̃t�@�C�����v�V�����Ɂj�B���J�͂��ɂȂ�̂��낤���B�����ɂ͏Ռ��̎������B����Ă���͂����B��������́A���{�Ƃ����������݂̌`�ԂŐi�ތ���A���炭���J����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B
�@�A�����J�����������ق̋g�c�t�@�C���ɂ́ACIA�����Ȃ����J�����ۂ��Ă���閧������13�y�[�W������Ƃ����i�t�����j���u�閧�̃t�@�C�����v�V�����Ɂj�B���J�͂��ɂȂ�̂��낤���B�����ɂ͏Ռ��̎������B����Ă���͂����B��������́A���{�Ƃ����������݂̌`�ԂŐi�ތ���A���炭���J����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�@�Ȃ�A�����A�u���R���ق͂Ȃ��E���ꂽ�����E����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������v�ƒu����������ǂ����낤�B��́A����Ȃ炢���A�Ǝ������Ă���悤�Ɏv���B�u�N�ɎE���ꂽ���v�͌l�Ɏa�荞�ނ��A�u�Ȃ��E���ꂽ���v�͗��j�����邱�ƂɂȂ�B�u���̂���̐��E��Ɠ��{�̗����ʒu�A���ꂳ���킩��g���R�͂Ȃ��E���ꂽ���h�������Ă���v�Ƃ�������̌��t�ɂ́A�ނȂ�����̎v��������ł���B
2013.07.22 (��) �b����`�f��u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�v������
���O�����@�x�[�g�[���F����ȁF���y�l�d�t�� ��14�� �d�n�Z�� ��i131�E�E�E�E�E����́u���v�����������ƁA�x�[�g�[���F���̑n�삪���y�l�d�t�Ȃ݂̂Ɍ��������ŔӔN�̌���ł��B�u���v�Ŏ���̗��z�𐢊E�Ɍ����č��炩��搂��������x�[�g�[���F���́A���̂��ƁA�����Ȃ�O���I���b�Z�[�W�������邱�Ƃ̂Ȃ����y�l�d�t�̐��E�ɖv�����Ă䂫�܂��B�E�ъ�鎀�̗\���̒��A�Ђ����玩�Ȃƌ����������B�����ɂ͂����Ȃ鋳�P���֒����̍ق��Ȃ��B���Ȃ̓��ʂ���O���o����4�̌��y��ɑ����ēf�I�����B�ŔӔN�ɓ��B�������Ȃ̐S��̎��R�ȓ��e�B���ꂪ�x�[�g�[���F���̌�����y�l�d�t�ȂȂ̂ł��B
�@���ł��A��14�ԍ�i131�͓ˏo������i�ł��B�O�㖢���̊�ɐ���ꂽ�圤�Ȃ܂ł̔������B���܌����銰���̕\��B�V���[�x���g������5���O�A�F�l�ɗ���ʼn��t�������̂������܂��B
�@�O�㖢���̊�Ƃ�7�y�͍\���Ɓu�x�܂��ʂ��ĉ��t����v�̎w���B�ʂ����ăx�[�g�[���F���̈Ӑ}�́H
 �@���̓�ƌ����������f��ɏo��܂����B���[�����E�W���o�[�}���ē̑�2��u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�vA Late Quartet�ł��B�W���o�[�}���̓}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�ŕ����w�̔��m���ƃI�y���[�V�����Y���T�[�`�̏C�m�����擾�����ς��B���H�w�I�v�l���N���V�b�N���y�̌���ɂǂ�ȃA�v���[�`�������邩�����ÁX�B�����ƁA����́g�N�����m�I�h�A���O���B�f������ɍl����A���ȂɐG������ĕ`���ꂽ�l�ԊW�̘c�A�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B
�@���̓�ƌ����������f��ɏo��܂����B���[�����E�W���o�[�}���ē̑�2��u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�vA Late Quartet�ł��B�W���o�[�}���̓}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�ŕ����w�̔��m���ƃI�y���[�V�����Y���T�[�`�̏C�m�����擾�����ς��B���H�w�I�v�l���N���V�b�N���y�̌���ɂǂ�ȃA�v���[�`�������邩�����ÁX�B�����ƁA����́g�N�����m�I�h�A���O���B�f������ɍl����A���ȂɐG������ĕ`���ꂽ�l�ԊW�̘c�A�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�@�ꏏ�Ɍ����̂͂����̉f�恕���ݒ���4�l�g�B�܂��ɃJ���e�b�g�B�W���b�L�Ў�̊ӏ܌㊴�z��ŁA�u��1���@�C�I�����̒j����2���@�C�I�����ƃ��B�I���v�w�̖��ɖ{�C�ɗ�����Ȃ�ĕs���R������A�����炱�̉f���60�_�v�ƌ��������ɑ��āAK���́u�j���̊W�ɕ������͂Ȃ����A�����n�[�ł̃f�[�g�͕��͋C������オ����́v�ƈꌾ�B�Ȃ�قǁA�����Ă݂�A���i�[�`�F�N�ƃJ�~���̕s�ς̗��͍̍�37�����A���[�O�i�[�ꑰ�̑g�ݍ��킹�͈ٗl�Ȃ��̂�����B����ɔ�ׂ���̃P�[�X�A��X�s���R�Ƃ͂����Ȃ����B�Ȃ�Β����A�u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�v�͏G��ł��B
������̗��ꁄ
�@�`�F���̃s�[�^�[�i�N���X�g�t�@�[�E�E�H�[�P���j��25�N���������匷�y�l�d�t�c�u�t�[�K�v�̍ŔN���ҁB���̐́A�ʂ̎l�d�t�c�ŁA���������o�[���S���Ȃ������Ƃʼn��U�������Ƃ��A�S��������ł���B�Ȃ�Ƃ��̖S���Ȃ��������o�[�̖������l�d�t�c�̃��B�I���t�҃W�����G�b�g�i�L���T�����E�L�[�i�[�j�ł���B
�@��1���@�C�I�����̃_�j�G���i�}�[�N�E�C���@�j�[���j�́A�\���ł�����Ă�����قǂ̎��͎҂����A����̐M�����玺���y�ɓq���Ă���B�W�����G�b�g�Ƃ͈ȑO�����������悤���B
�@��2���@�C�I�����̃��o�[�g�i�t�B���b�v�E�V�[���A�E�z�t�}���j�́A�u�t�[�K�v�ɎQ�����A�W�����G�b�g�Ɉ�ڍ��ꂵ�Č����B��l�̊Ԃɂ̓A���N�T���h���i�C���[�W�F���E�v�[�c�j�Ƃ�����l��������B
�@25�N��3000����̌��������Ȃ��Ă������J���e�b�g�ɓ˔@�ٕς��N���邱�ƂɁB�L�b�J�P�̓`�F���̃s�[�^�[�̈��ޖ��B�p�[�L���\���a�̏����Ƃ����f�f���������̂��B�ނ͐̌���������U�����͂������Ȃ��B������A�V�����`�F���X�g��T���ƌ����B
�@���o�[�g�́A������@��ɁA�������������Ă���l���������o�[�ɂԂ���B�u���̎l�d�t�c�̓_�j�G���̌����Ȃ肾�B�J�`���Ɛ��������Č����Â�B�Õ��ł��Ȃǂ����Ƒ����������ׂ����B�����Ȃ����ĉ������y���B�����Ŏ��ƌ��ő�1�����̂͂ǂ����v�ƁB
 �@���o�[�g�͍Ȃł��郔�B�I���̃W�����G�b�g�Ɉӌ������߂邪�A���ӂ�ꂸ�A�t�ɢ�Ȃ�����ȂƂ��ɂ���Ȗ����o���̣�ƂȂ�����B���o�[�g�́A�u������艴�����Ƃ������ƂȂ̂��v�ƕ���A�������Ƃ��Ă��ŏ��F�B�ƈ������ɂ��Ă��܂��B���̏�Ɋy���Y�ꂽ���ƂōȂɂ̓o���A�ň��̎��ԂɁB
�@���o�[�g�͍Ȃł��郔�B�I���̃W�����G�b�g�Ɉӌ������߂邪�A���ӂ�ꂸ�A�t�ɢ�Ȃ�����ȂƂ��ɂ���Ȗ����o���̣�ƂȂ�����B���o�[�g�́A�u������艴�����Ƃ������ƂȂ̂��v�ƕ���A�������Ƃ��Ă��ŏ��F�B�ƈ������ɂ��Ă��܂��B���̏�Ɋy���Y�ꂽ���ƂōȂɂ̓o���A�ň��̎��ԂɁB�@�����̏��[�́A�����ł͂Ȃ��ʂ̒j�̍˔\��]�����Ă���B�����������̗͐̂��l��������������Ȃ��B���̋C������Փ��I�ɕʂ̏��ɑ���B����͎��R�Ȃ��ƁB�ݒ�̂��܂��ł���B
 �@���o�[�g�ƃW�����G�b�g�̖��E�A���N�T���h���͍˔\�L���ȃ��@�C�I���j�X�g�ŏC�s���̐g�B���e�͔��̂��߂Ƀ_�j�G���Ƀ��b�X�����˗�����B���A���ꂪ�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɁB
�@���o�[�g�ƃW�����G�b�g�̖��E�A���N�T���h���͍˔\�L���ȃ��@�C�I���j�X�g�ŏC�s���̐g�B���e�͔��̂��߂Ƀ_�j�G���Ƀ��b�X�����˗�����B���A���ꂪ�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɁB�@�̍����炭30���炢�B���̓�l�����������悤�ɂȂ�B�ŏ��ɏ����d�|���A��ɒj���{�C�ɁB���o���āA��e�W�����G�b�g�͖�����B���ɃA���N�T���h���͕�e�ɂ��̎��i����B�R���T�[�g�ŗ�����B�����ق����炩���������ƁB���o�[�g�͕��e�Ƃ��ă_�j�G���Ƀp���`�ꔭ�B��l�͕ʂ�邪�A���a�������ƒ�ɂ����肪�c��B
�@�s�[�^�[�̈��ސ錾�������N�������l�X���a�݁B�e�l�e�l�̎v�������ɃR���T�[�g�̓���������Ă���B�Ȃ̓x�[�g�[���F���́u���y�l�d�t�� ��i131�v�B�ʂ����ĉ��t�͖����S���ł���̂��낤���B�����Ċe�l�̐l���̘c�݂ɉ����͂���̂��H
�����y��m��s����������w��
 �@�X�^�b�t�́A�u�t�[�K�v�Ƃ������y�l�d�t�c���A���݂���3�̒c�̂���G�s�\�[�h���E���č\�z�����悤�ł��B�O�@���l���l�d�t�c����́A�ŔN���҂̃`�F���X�g�̈��ނƉ��U���B�C�^���A���y�l�d�t�c����́A����1�l�ƒj��3�l�Ƃ����\�����B�G�}�[�\�����y�l�d�t�c����́A���@�C�I���j�X�g2�l����1�Ƒ�2�����݂ɒe���X�^�C�����E�E�E�E�E���̑g�ݗ��Ă͌����̈��B�X�^�b�t�̕��L���m��������Ƀ��A���e�B�������炵�܂����B
�@�X�^�b�t�́A�u�t�[�K�v�Ƃ������y�l�d�t�c���A���݂���3�̒c�̂���G�s�\�[�h���E���č\�z�����悤�ł��B�O�@���l���l�d�t�c����́A�ŔN���҂̃`�F���X�g�̈��ނƉ��U���B�C�^���A���y�l�d�t�c����́A����1�l�ƒj��3�l�Ƃ����\�����B�G�}�[�\�����y�l�d�t�c����́A���@�C�I���j�X�g2�l����1�Ƒ�2�����݂ɒe���X�^�C�����E�E�E�E�E���̑g�ݗ��Ă͌����̈��B�X�^�b�t�̕��L���m��������Ƀ��A���e�B�������炵�܂����B�@�u�\���X�g�̍˔\������̂ɁA�Ȃ��J���e�b�g�����̂��H�v�Ƃ̖₢�Ƀ_�j�G���͂��������Ă��܂��B�u�\���X�g�͗����痷�ցA���̓s�x�Ⴄ�w���҂ƃI�[�P�X�g���ʼn��t����B��x�Ɖ��Ȃ���������邾�낤�B����ʼn��y��[���Nj��ł��邾�낤���B�̑�ȍ�ȉƂւ̒������ʂ����邾�낤���B���y�l�d�t�c�͖������t���A���N�����������o�[�ʼn��t����B�ӌ������������C�����Ȃ��特�y�����グ�Ă䂭�B���͂��ꂪ�{���̉��y�̎p���Ǝv���v�B���t�҃T�C�h���猩�������y�̖{���������Ɍ������ĂĂ��܂��B
�@���b�X�������ɃA���N�T���h���A�Ɍ������u�܂��̓x�[�g�[���F���̓`�L��ǂ߁v������Ӗ����߂̖{����˂��Ă���B�X�^�b�t�����y�������Ă���ł��B
�@�s�[�^�[�͉��y�@�Ń`�F���������Ă��܂��B���k��O�ɂ���Șb�����邱�Ƃ��E�E�E�E�E�u�����p�u���E�J�U���X�i1876�|1973�j�̑O�ŏ��߂Ēe�����Ƃ��̂��ƁB�i.�r.�o�b�n�́w�����t�`�F���g�ȑ�4�ԁx�́w�v�������[�h�x��e���Ȃ����ƌ����Ēe�������A�オ��܂����čň��̏o���������B���Ɂu�A���}���h�v��e���Ăƌ���ꂽ�B���ꂪ�����ƍ����B�Ƃ��낪�ނ͎��ɂ����������B�w�Ȃ��Ȃ��悩������B�撣��Ȃ����x���āB���͔n���ɂ��ꂽ�悤�ȋC���ɂȂ��ĕs�����������B���ꂩ��A���N�o���Ĕނɏo������B���͂����ς��̃`�F���X�g�ɂȂ��Ă����B�ނɁw���̂��Ƃ������Ă��܂����H�x�Ɛu���Ɓw�����Ă����x�ƌ����āA�����Ȃ�`�F����e���������B���̂Ƃ��̎��̉��t���Ƃ����āB�w�N�͂����e�����B���̕����A���Ƀ��j�[�N�ł悩������x���āB�ނ͎��̉��t�������Ă��Ă��ꂽ�B����ŁA�����Ƃ��낾����_�߂Ă��ꂽ�̂��v
�@���̘b�͊����I�ł����B���_�t�B�N�V�����ł��傤���A�J�U���X�Ȃ炱���������낤�Ɣ[���������܂��B����́A�J�U���X�Ƃ����|�p�Ƃ̖{���𑨂��Ă��邩�炱���\�Ȃ��ƁB�L���͂͐��ӂɒʂ��A������_�߂邱�Ƃ͍˔\��L���B�l����Ă�A����͋����Ǝv���܂��B
�@���݂�J.S.�o�b�n�́u�����t�v�́A�J�U���X��13�̂Ƃ��A�o���Z���i�̊y��X�̕Ћ��Łi�y�����j���������́B���̓������ɁA�u�����t�v�͗��K�Ȃ���|�p��i�ւƕϖe�𐋂���̂ł��B
�@�s�[�^�[�̖S�v�l�ɖ��̎�A���l���]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�������A�C���[�W�̒��ʼn̂��V�[������ۓI�ł����B���������i�ł������A�^�C�g����������܂���? �N�������Ă��������B
�@�u�x�܂��ʂ��ĉ��t���ׂ��v�Ƃ����x�[�g�[���F���̎w�����₪�āg�����̋����h�������N�������Ƃ���A�����c�����m�Ɖƒ�����a�݂ɃC���[�W�Ƃ��ďd�˕���̌��I�W�J��}���Ă���B�y�Ȃ̓����������܂��k���ɍ�i�ɓ��e�������̂͌����Ƃ��������悤������܂���B
�@�܂��A�j���[���[�N�Ƃ����X�̎������A����Ɛ▭�Ƀ}�b�`���āA��ʂɍX�Ȃ郊�A���e�B��^���Ă������Ƃ��t�������Ă����܂��B
�����Ƃ����T�O��
�@�f��`���Ɉ��p���ꂽT.S.�G���I�b�g�̎��gFour Quartets�h���ے��I�ł����B
�]�݂��������Ȃ������ߋ��@�l�d�t�c�̃����o�[�����X�̉ߋ����ߌ��݂������Ɍ������Ă��܂��B�e�l���w�����e�X�̎����̏W���̂��u�t�[�K�v�Ƃ������y�l�d�t�c�̌��݂Ȃ̂ł��B�����o�[���ς���āA�u�t�[�K�v�̍s�����͉ʂ����Ăǂ��Ȃ�̂�? �����o�[�̐l���ɉ����͂���̂��H����ɂ͎��̋A�������ׂĎ���邱�Ƃ���n�߂邵���Ȃ��̂�������܂���B
�Ƃ������������Ȃ������ߋ�
�����Ƃ����݂Ƃ������ɋA������
�������܂��������Ɓ@�l�Ԃ͎��ɂ͍R���Ȃ�
�@�f��25�N�ڂ̌��y�l�d�t�v�ɁA�x�[�g�[���F���̎w���������ɓ��e���Ă���̂͗����ł��Ă��A�u��i131�v�ɍ��߂��x�[�g�[���F���̈Ӑ}�͂܂�������܂���B����������Ƃ�������̂��ǂ����A�����������܂���B�ł������낤�Ƃ���w�͂͂��Ă䂫�����Ǝv���܂��B
�@�m���Ȃ��Ƃ́A������A�u���y�l�d�t�� ��14�� �d�n�Z�� ��i131�v�̓x�[�g�[���F���������̎��̎������g�ł����Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�v���Ԃ�Ɍ��������̂���f��ɏo��܂����B�]�C�ɐZ�鎄�����J���e�b�g���ݍ��݂Ȃ���A����̖�͐Â��ɗ���������Ǝ���ǂ�����Ă䂫�܂����B�܂��s�������I
2013.07.20 (�y) �b����`�T�v���C�Y�A���̃R���T�[�g
�@���̗F�l��F����Ƃ����ꕔ����Ђ̉���В������܂��B�ނ͐��ˎs�o�g�ŁA��̃N���V�b�N�E�t�@���B��Ђ������A���ݐ��ˌ|�p�ق��T�|�[�g���Ă��܂��B�@����7��8���A�|�p�ُ����̃I�P�E���ˎ����nj��y�c�̃T���g���[�z�[�������ɂ��U�����s���Ă��܂����B
�@���̓��́A��Ђ̕��������̈�Ƃ��ẮA�Ј��N���V�b�N���y�ӏ�Day�B���������ɐ��荞�܂��Ă����������Ƃ�������B�J���O�A���s�����F�lT�N�Ƌ��ɁA���z�[���ł̃��Z�v�V��������Q�������Ă��������܂����B

�@�`���A�|�p�ق̗����̕�����̈��A���B�u�{���́A��قǖS���Ȃ������I�P�̃��@�C�I���j�X�g���c�v�q����̒Ǔ��Ƃ��āA�v���O�����ɐ旧���ă��[�c�@���g�����t���܂��v�ƁB�����ŏ��߂Ē��c������]��ɐڂ��āA���i���ƂŒ��ׂ���A5��28���A�A�����J�̂�����ŖS���Ȃ�ꂽ�Ƃ̂��ƁB���N71�A�����a�����������ł��j�B���̉��a�řz�Ƃ������c�������ɂ��Ȃ��Ȃ�āI ��N1���A�����T���g���[�z�[���A�V�c�c�@���É��������̉��t��ł��D�u����R���T�[�g�~�X�g���X�U�肪�قɏĂ����Ă���
�E�E�E�E�E�B
�@�J����҂B���Â��Ɩ��̒��A�Â��Ƀ����o�[�������Ă��܂��B���c����Ǔ��̉��t�ł��B����Ɍ��������ɑ������u�ԁA�X�D���Ɖ��y���͂��܂�B�Ȃ�Ƃ����₳���������I ���[�c�@���g�A�f�B���F���e�B�����g K136 ��2�y�́B�Ƃ��̂Ƃ��A�w���҂ɋC�Â��܂����B���������B�Ȃ�Ƃ��������V�����������̂ł��B�ނ́A���ˌ|�p�ُ���ْ��E�g�c�G�a���̐����ɔ����A���ڂ��p��������B
 �@���y�͋�Ԃ�Y�������V��Ɍ������B�e�l�̎v�������V�̓����ƈ�̂ƂȂ��āA�܂�ʼn��ɗ삪���ڂ������̂悤�B�ꉹ����Ƃ��v���̘U��ʉ��͂Ȃ��A���̋����͎����ɖ����A�߂��݂͓����Ŕ������B�l�����Ȃ��قǂ̂������Ƃ����e���|�Ȃ̂ɁA��_���邱�Ƃ͂Ȃ��B�����K136���̂͏��߂āB�Ƃ������A����Ȑ������y�͏��̌��B
�@���y�͋�Ԃ�Y�������V��Ɍ������B�e�l�̎v�������V�̓����ƈ�̂ƂȂ��āA�܂�ʼn��ɗ삪���ڂ������̂悤�B�ꉹ����Ƃ��v���̘U��ʉ��͂Ȃ��A���̋����͎����ɖ����A�߂��݂͓����Ŕ������B�l�����Ȃ��قǂ̂������Ƃ����e���|�Ȃ̂ɁA��_���邱�Ƃ͂Ȃ��B�����K136���̂͏��߂āB�Ƃ������A����Ȑ������y�͏��̌��B�@���̎v���A���̉��́A�V��̒��c����ɊԈႢ�Ȃ��͂��Ă���A�����m�M�B���y�ɁA�����܂ŐS�����߂�����̂Ȃ̂��I �ƁA�����ł������Y��Ă��܂��܂����B
�@�Ȃ��I����āA���V����͉������킸�Â��ɑ��ɏ����Ă䂭�B�i�N�̉��y���Ԃ𓉂ސ����Ԃ̂��߂����ɋ삯�����̂ł����B�����F�����m��ʃT�v���C�Y�������Ƃ��B���ɂ͂܂��ɋH�L�Ȃ�̌��ł����B���c�v�q����A���炩�ɁI�I
�@���̂��Ƃ̃v���O�����́A���E�����N���w���ōא�r�v��ȁu�����I�[�P�X�g���̂��߂̊J�ԇU�v�i���E�����j�A�����D�̃s�A�m��������Ẵx�[�g�[���F���̑�3���t�ȁA�Ō�ɃV���[�x���g�̌����ȑ�8�ԁu�O���C�g�v�B�y���������܂����B
�@�����Ă�����A���x�͎��I�ȃT�v���C�Y���E�E�E�E�E���\�j�[�~���[�W�b�N��H���Ə��z�[���ő��������̂ł��B���z�[���Ƃ������Ƃ͔ނ�F������̏��҂Ƃ������ƁB�ނ͔N��100�{�ȏ�̃R���T�[�g�ɑ����^�ԃN���V�b�N��D���l�Ԃɂ��āA�ӏ܂̒B�l�B�s���������ɂ́A�����R���T�[�g�]���A�b�v���Ă���B��������[�Ȃ��̂���Ȃ��A�S�̂�͂ނƓ����ɍו��̃p�t�H�[�}���X��Ȗ��ɕ`���o���B�X�Ɩ��K���������鍂�x�ȓ��e�B���̎��A�ʁA�X�s�[�h�A�܂��Ɉꋉ�i�̉��t�]�Ȃ̂ł��B������������u�x�C�̃R���T�[�g���L�v��`���Ă݂Ă��������B
�@���āA�����H�����Ȃ������ɁHH�����g�������Ȃ��H�h�Ǝv���������ł����B�햾�����E�E�E�E�EH����F���̑�w�̌�y�ŁA�����u�N���V�b�N���y������v�̃����o�[�A40�N���̕t�������������̂ł��BH���̎���g�ł́AF���Ǝ��̊W�́h�ɑ�F���́A�u�b���Β����Ȃ�̂Ŗ��v�BF�������ɑ�w�̌�y�Ɨc����B����ȗF�B�̗ւł����B
�@�����ЂƂ�ABMG����̌�y�Ō��݃\�j�[�̍��c�ɂ���A�������Ă��āA�ނ͓��s��T�N�Ƃ͓����c�Ƃ̊��̔т�H�������B������T�v���C�Y�B�I����20�N�Ԃ�̓�l�Ǝ��Ōy����t�A�̂��肪�̘b�ɉԂ��炫�A�C�����ΏI�d�ԍہB��}���ŗ��r�R���Ɍ������܂����B���X�̃T�v���C�Y���v���[���g���Ă��ꂽF����Ɋ��ӂ��Ȃ���B
2013.07.17 (��) �b����`�\�����G���蕱���L
�@5��25���t�����ŗ\�������Ă����������Ƃ���A�u�N���V�b�N�\�����G����v�Ȃ���̂��A7��7���A���E���a���q��A�ŎĂ��܂����B�����̓G���g���[�N���X�A�܂��A����҃R�[�X�ł��B��������60���A100��̃X�N�G�A�i4���j�����ł��B�ł͂����A6�T�Ԃ̕����L�ɂ��t���������������B �@���������́A5��12��O.A.�́u�薼�̂Ȃ����y��v�`�u�N���V�b�N�\�����G�I�茠�v�B���@�͖ʔ�����������B�\�����̂�5��23���B�ڕW�́A���_��1000�|�C���g�B��ʃN���X�ł���V���o�[�R�[�X�̎��������ɂȂ邩��ł��B���̃|�C���g�A�Ȃɂ��TOEIC�̕��l�i�A�������疞�_��990�_�j�ɕ���Ă���悤�ł����A�ώG�ɂȂ�̂ňȉ����_��100�_�Ƃ��ċL�q���܂��B
�@���������́A5��12��O.A.�́u�薼�̂Ȃ����y��v�`�u�N���V�b�N�\�����G�I�茠�v�B���@�͖ʔ�����������B�\�����̂�5��23���B�ڕW�́A���_��1000�|�C���g�B��ʃN���X�ł���V���o�[�R�[�X�̎��������ɂȂ邩��ł��B���̃|�C���g�A�Ȃɂ��TOEIC�̕��l�i�A�������疞�_��990�_�j�ɕ���Ă���悤�ł����A�ώG�ɂȂ�̂ňȉ����_��100�_�Ƃ��ċL�q���܂��B�@�����A�u�����e�L�X�g�v�Ɓu�������W�v�����݁A�����I �l�ߍ��ݍ�ƊJ�n�ł��B��w�����ȗ�50�N�Ԃ�́u�v��Go�I
�@�܂��́A�f�̂܂܂ŁA�u�������W�v����ߋ��������Ă݂�B���ʂ�95����B���v���Ԃ�15���B����͂Ȃ��Ȃ��̏o���B100�_��������Ȃ����ƋC��������B�����Ƃ�낤�Ǝv�������A�u�ߋ���v�͂��ꂾ���B�������A���N�n�߂č��N��2��ڂȂ̂��B��w�̉ߋ���͊m��7�N���V�b�J���������̂ɁA�ȁ[��Đ̂��v���o������B
�@�u�����e�L�X�g�v�ɂ́A�u�o��́A�e�L�X�g����8���A���Ƃ�2���͂���ȊO����v�Ƃ̎w�삠��B�Ȃ�Γ��R�A�u�����e�L�X�g�v�̃}�X�^�[����{�ƂȂ�B
�@�e�L�X�g�́A�u���j�ҁv�u��ȉƕҁv�u��i�ҁv�ɕ�����Ă���A�u���j�ҁv�͒�������o���b�N�A�ÓT�h�A���}���h���o�Č���܂ŁB�u��ȉƕҁv��36�l�B�ł����̐l�I�A�T�e�B�A�X�N�����[�r���������Ă��āA�x�����I�[�Y�A�t�����N�A�O���[�O�A�V�x���E�X�����肪�O�ꂿ����Ă�̂͂������ȃZ���X�H �ł��܂��������A���ɓ����Ă͋��ɏ]���ł���܂��B�u��i�ҁv��95�ȁB����͂���ł����ł��傤�BJ.S.�o�b�n1000�ȁA�V���[�x���g900�ȁA���[�c�@���g600�ȁB����Ȓ�����I�Ԃ̂�����A������̍D�݂������Ă��n�܂�Ȃ��B
�@�ڕW��90�_�Ȃ炱�̂܂܂�OK�Ȃ̂ł��傤���A100�_�ɒu��������ɂ́A�e�L�X�g�ȊO��2���̑ۑ�B�͈͖����͋��낵���B�e�L�X�g�ȊO�ƈ���Ɍ������A����͖c��B�ł���邵���Ȃ��B
�@�����ō��B����܂Œ��ߍ��f���t�@�C���u���ȒT��A�}�f�E�X�v�u�薼�̂Ȃ����y��v�uNHK�V���t�H�j�[�z�[���v�u�����N���V�b�N�v�u���Ȃւ̓��v�u���y�̐��܂ꂽ�X�v�ȂǂȂǂ��A�����炢�ă`�F�b�N���ĕK�v�����i�Ǝv������́j��@���������B���̑��ACD�̃��C�i�[�m�[�c��F�l�̞w�R�y�������������u���y�Ƃ̖����v�ɂ��ڂ�ʂ����B���s���āu�����e�L�X�g�v��ǂ݂Ȃ���ŃA���_�[���C���������܂��낤�B������ہX3�T�ԁB
�@�����āA���̂��ƁA�����Ŗ����쐬���A�J��Ԃ����ɓ�����Ƃ�2�T�ԁB�Q�l�܂łɎ����쐬�������z��肩��10������L�i������4���ɂ͂����j�B
�@���q�����g�E���[�O�i�[�̑��q�E�W�[�N�t���[�g�̍ȂŁA�S�v�̌���p���Ńo�C���C�g���y�Ղ̉��y�ē߂��̂́H�@����Ȗ�������Ă��邤���ɁA�Ȃ��350��ɖc��オ���Ă��܂��܂����B������ƃ����߂��I ���ʓI�ɂ͂��ꂪ�w�ɂȂ����̂ł����A���傤���Ȃ��B���̐����͕ς����Ȃ��B
�A�p�����y�@�Ń����F�����������t�����X�l��ȉƂ͒N�H
�B���@�C�I������G�������Œe���Ȃ́uG����̃A���A�v���L���ł����A������G�������Œe���u�i�|���I���E�\�i�^�v�̍�Ȏ҂́H
�C���b�V�[�j���g�V�����[���[�̃��[�c�@���g�h�ƌĂ�ȉƂ͒N�H
�D�x�[�g�[���F�����s�A�m�E�\�i�^��26�Ԃ��u���ʁv�Ɩ��������̂́A����M���Ƃ̕ʂ�̂��߁B���̋M���Ƃ́H
�E�Z���r�A���y�w�̊�b��z���A�Z���r�A�̃o�b�n�ƌĂꂽ���y�Ƃ́H
�F���[�c�@���g���A�E�B�[���̃��[�c�@���g�n�E�X�i�ȑO�̓t�B�K���n�E�X�j�ɏZ���Ԃ́A����N���牽�N�܂ŁH
�G�C�^���A�����g�X�J�[�i�n�����b�J���܂�̍�ȉƂ��l������
�H�x�[�g�[���F���͈��z�����B�ł́A�ނ��E�B�[���ň����z�����͉���H
�I���̃��F���f�B�̃I�y���̒��ŁA���Ԃ͂���͂ǂ�H�\�\�i�u�b�R�@�֕P�@�I�e���@�t�@���X�^�b�t
�@�Ō��1�T�Ԃ͑��܂Ƃ߂̃A���[�A���X���ԁB�������Ă���Ƃ���Ƃ����łȂ��Ƃ�����V�b�J���d�������āA100�������ɋ߂Â�������B
�@�����Ė{�ԁA���ʂ́H�E�E�E�E�E98�_�ł����B�c�O�I �����ʒm�͂��ꂩ��ł����A���ɉ�HP�ɃA�b�v����Ă���̂œ������킹���������ʂł��B�ԈႦ��2��͎��̒ʂ�B
�E ���C�v�c�B�q�́u�J�t�F�E�c�B���}�[�}���v�Ƃ����R�[�q�[�n�E�X�̏�A�������̂͒N�ł��傤�@�O�҂̐�����J.S.�o�b�n�Ȃ̂Ƀ����f���X�]�[���ɁA��҂̓v���R�t�B�G�t�Ȃ̂ɃV���X�^�R�[���B�`�ɂ��Ă��܂��܂����B��͂薞�_�͓�������B����ɉ������̂́A�ԈႦ��2��͂Ȃ���u�����e�L�X�g�v�Ɍf�ڂ���Ă����I �Ƃ������ƁB����̓e�L�X�g��������Ɣc�����ĂȂ������؋��B��w����50�N�B�f���ɎX�L���̗�F�߂���܂���B�X�L���Ƃ͚k�o�ƏW���͂ł��B
�E �鐭���V�A�̖����ɐ��܂�9�ōŏ��̃I�y������ȁB������Ƒ��ɔ�I�����Ƃ������ȉƂ͒N�ł��傤
�@��e�L�X�g������낻���ɂȂ����̂́A����ɉۂ������㖽�߁u100�_���_�v�̕��Q�ł����B�u�e�L�X�g�ȊO����Q���v�Ƃ����ڂɌ����Ȃ��v���b�V���[�ł����B���̃v���b�V���[���A���ŗL�̍ی��Ȃ��G�N�X�v���[���[�C���ɁA�{���̔��Ԃ�������������Ƃ������ƁB�ߋ�����������ȍ���x�̖��͏o��킯���Ȃ��̂ɁA�ǂ��ɂ��~�܂�Ȃ��B�킩�����Ⴂ�邯�ǂ�߂��Ȃ��B�ł��܂��A���ꂪ���̐����ƒ��߂�B�����āA����350��̓V���o�[�N���X�ɂ����Ɩ𗧂ƈԂ߂�B
�@�����������A�O��I�ɋl�ߍ�����6�T�Ԃ́A�[���������Ɋy�������Ԃł����B�W�����邽�߁A�P��̌�����݉��ƒf�Ŗ{�Ԉȍ~�ɃX���C�h������A���Ԃ���u���̂悤�Ȏ��ȓs���͘a�𗐂��B�P�V�J�����I�v�����E���Ă��܂�����B�ł��A�y���������B�z���g�A���A���������̑f���ɍD���Ȃ�ł���B����2�`�����l��������ł́A��ɂ���Ė{��������n���ɂ��镗������ł����A���͊y���Ⴂ�܂����B����Ȃ��ƌ����ƁA�ނ�͂܂��u����Ȃ��̂��y���ރA�z������v�Ȃ�āA��������̂��ȁI�H�傫�Ȃ����b�����āB
�@���āA350�⒆�A�����݂��L�����Ă���̂�7�|8�����炢�ł��傤���B�Y�ꂽ�牯����܂ŌJ��Ԃ��������B�ł́A���N�̃V���o�[�N���X�Ɍ������� Fight�I�I
[���z����]
�@���B�j�t���[�g�E���[�O�i�[�@�A�t�H�[���@�B�p�K�j�[�j�@�C�I�b�t�F���o�b�N�@�D���h���t����@�E�V���e�t�@���E���N���[�j���b�c�@�F1784�|1787�N�@�G�{�b�P���[�j�ƃv�b�`�[�j�@�H79��@�I�֕P�i�u�֕P�v�������t�F�j�[�`�F����ŏ����B���̓~���m�X�J�����j
2013.07.10 (��) ���I�u���R�����_�v3�`����̘b �O��
[5] �i�ߓ�����肷���@�u���̎�����������̂́A������������A�Z��������Ȃ��v�B���̏Ռ��̑䎌���{���̊̂ł���B�������͔̂ѓ����b�q�A���҂̑�f��A�u�Z����v�ƌ����̂́u���R�����`�Ō�̏،��v�̒��҂̑c�� �ēc�G�i1901�|1970�j�̂��Ƃł���B�ēc�́A�펞���͓����@�ւɏ����A�����u�����Y�Ɓv�Ƃ�����Ђɋ߂Ă����B�����Y�Ƃ͎����O���ڂ̃��C�J�r����3�K�ɂ������f�Չ�ЂŁA�В�������i1915�|1998�j�Ƃ������B�����̂������O�z�{�X�Ƃ͒����ʂ�n���Ă����A�n���o������͐��\���[�g���̎��ߋ����ɂ���B�ēc�G��1901�N���܂ꂾ����A���R����������48�ł���B
�@�u�i�ߓ��vAB�ƃt�B�N�T�[�́A�����̑S�e��m���Ă���B���R���Ăяo����C�́A�������A�ŌJ�邱�Ƃ��ł��鐔���Ȃ��啨�̂ЂƂ�B�{���ł́A�u�����L�O�̓��v�����߂錏�i1966�N�j�ŁA���̑�����b�Ɗ������A���������h��Ɠc���p�h��d�b��{�ő���C�̎p���`����Ă���B
�@�{���̖ړI�́A���R�����̔w�i�Ƀ��X�����邱�Ƃł���B����͐^�Ɛl�̓���Ɍq������̂��B�^�Ɛl�Ƃ́u�����v�Ɓu�t�B�N�T�[�v�Ɓu�i�ߓ��v�ł���B
�@���Ҏēc�N�F�́A�{���̒��Łu���̑c���炪����Ӗ��ʼn��R�����̓����҂ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��v�ƒf������B����Ӗ��Ƃ́A���̎����̕��G���������\���B�O�q�̂Ƃ��莖���Ɋւ��l�Ԃ�100�l���Ƃ������Ă���B�������A�c���E�ēc�G���P�Ȃ�100����1�łȂ����Ƃ͓ǂ߂Δ���B����ǂ��납�����̒��j�ɂ������Ƃ�ނ͊m�M���Ă���B����͑c���{�l�Ƃ̎v���o�A�e���̌����Ȃǂ��琶�����؋��Ƃ��Ē�o�����B���x�������悤�ɖ{���̓��ِ��Ɖ��l�͂����ɂ���B
�@�ނ́A�u�i�ߓ��v�̈�l��c���E�ēc�G�Ɠ��肵���B�����Ă�����l��c���̏�i�E�����Y�ƎВ�����Ƃ����B���̂��ƁA���҂���ɍs�����C���^�r���[���f�ڂ���B�����ǂ߂A���҂̐��_�ɊԈႢ�Ȃ����Ƃ������邾�낤�B ���āA�u�i�ߓ��vAB�͓��肳�ꂽ�B�c��́u�����v�Ɓu�t�B�N�T�[�v�ł���B���������̔�������e�Ղɐ��������͂����B�u�N����������H�v�͎��͈ȉ���ǂ߂Ύ����Ɩ��炩�ɂȂ邾�낤�B
 �@���҂́A������g�ƂĂ��Ȃ��l���h�ƌ`�e����B�o���͓Ȗ،���s�̖����ꑰ�B����ׂ̒��q�Ƃ��āA1915�N�ɐ��܂ꂽ�B���Ƃ́A���݁A�c���̖����������u����L�O�فv�ƂȂ��Ă���B
�@���҂́A������g�ƂĂ��Ȃ��l���h�ƌ`�e����B�o���͓Ȗ،���s�̖����ꑰ�B����ׂ̒��q�Ƃ��āA1915�N�ɐ��܂ꂽ�B���Ƃ́A���݁A�c���̖����������u����L�O�فv�ƂȂ��Ă���B�@�펞���͓d�C�Z�t�Ƃ��Ė��B�S���̊J���ɏ]���B�����푈�Ō��т�������B�����@�ֈ��ŃX�p�C�s�ׂ�����Ă����悤�ł���B�����āA�I���A�����Y�Ƃ𗧂��グ���B
�@�ł́A����ւ̃C���^�r���[�ł���B1992�N2���̂��Ƃł���B�ēc���̏T�����L�҂��Ă̖�s���́A�s�����ł̖ⓚ�A���Ζʂ̏Ռ��ȂǁA�h�L�������^���[�Ƃ��Ă܂��ɃT�X�y���X�t���Ȗʔ���������B���A��ނȂ���������B����������͒�����ǂ�ł������������B�Ȃ��A�C���^�r���[�O���́A����̈�l���̌`�Ƀ����C�g�����B���̕�������₷������ł���i�㔼�̓C���^�r���[�`���Ōf�ڂ���j�B
[6] ����̘b �O�ҁ`���R�����܂�
�@����͂��Ƃ��Ɗw�Z���o�Ă������a�d�H�ɓ�������B����ŁA�����Ă����ɁA�В��i�X�ޝ�j�ɗ���ő嗤�ɍs�����Ă�������B�ŏ��͂��ƂȂ������S�Ȃ�����Ă������A�ދ��łˁB����ŌR���ɂȂ��ď�C�Ɂu��@�ցv��������B���̂Ƃ��ɁA�����������ׂ��ĂȁB����œ��{�ɋA���Ă��āA�����Y�Ƃ�������B
�@�u��@�ցv�̌㌩�l�͎��ʗ_�m�v�H ��k�����Ȃ�B���̍��A���ʂ́A�e���̒��Ԃ����ԉ����ς������B����̌㌩�l���O�Y�`���i1898�|1971�j�B����ɓ����p�@���B
�@�����Y�Ƃ͈���Ō����ΌR���Y�Ƃ��B���S�̕��i�����C�̒e�A�R�̋L�O�A���o����x���g�C���X�q�܂ō���Ă����B�������ނ�A�����ĉƋ��������B�H��͖k��Z�A�����A���q�A�\���A�ɂ������B
 �@���̐e���i����ׁj�ƎO�Y�`�ꂪ�u���{����^�c��v�Ƃ����̂�����ă��C�J�r����4�K�ɒu�����B�����Y�Ƃ̏�̊K���B�펞���ɍ�����������w�ւ�l�b�N���X�Ȃ̋M�������o���������낤�B�����ׂ��ċ��̉��ז_�ɂ��āA�S�������ɏW�܂��Ă����B���{���̋��̔����͂����ɂ�������Ȃ����ȁB
�@���̐e���i����ׁj�ƎO�Y�`�ꂪ�u���{����^�c��v�Ƃ����̂�����ă��C�J�r����4�K�ɒu�����B�����Y�Ƃ̏�̊K���B�펞���ɍ�����������w�ւ�l�b�N���X�Ȃ̋M�������o���������낤�B�����ׂ��ċ��̉��ז_�ɂ��āA�S�������ɏW�܂��Ă����B���{���̋��̔����͂����ɂ�������Ȃ����ȁB�@�g�����H �펞���͕������B�B���Ȃ�ǂ��ł��ʗp����B�I���͐����Ɏg�����B�g�c���t�̐����������B�g�c���i1878�|1967�j�͂����̋����g���ĒǕ���ĎɂȂ����B�܂�A�g�c���t��������̂͂����̐e���ƎO�Y�`��ȂB���̌�A�ݓ��t�܂łقƂ�ǂ��̋����g��ꂽ�ˁB
�@�_�C�������h�́A�قƂ���E�B���r�[�iGHQ�Q�d��2�����j�������Ă������BM�������Ēm���Ă邾�낤�BM�͂Ȃ��M���m���Ă邩�H �J����}�[�J�b�g�iGHQ�̌o�ωȊw�Ǒ�2�ǒ��j��M�Ƃ������ƂɂȂ��Ă�炵�����A����̓E�B���r�[�̗���������W���Ђ�����Ԃ������́B����M���B
�@���C�J�r����3�K���E�`�ł��̏オ�O�Y�`��̎������������B�s���̈ꓙ�n������݂�ȏW�܂��Ă����B�E���͂������A�J�������B��炪���Y�}�̏����A�ǂ�ǂ��Ă����B
 �@�����Ƃ����������B�悭���Ă��̂����F���Y�i1902�|1985�j���B�ނ͂܂��A�����ɂ͐����ƂƂ͂����Ȃ����A�����͓������B���Ƃ͎Љ�}�̐������L�B�g�c��ݐM����������Ƃ��������B�����Ƃ��Ă̂͌����Ȃ��łˁB�݂�ȃE�`�̋����ړ��ĂɏW�܂��Ă���B
�@�����Ƃ����������B�悭���Ă��̂����F���Y�i1902�|1985�j���B�ނ͂܂��A�����ɂ͐����ƂƂ͂����Ȃ����A�����͓������B���Ƃ͎Љ�}�̐������L�B�g�c��ݐM����������Ƃ��������B�����Ƃ��Ă̂͌����Ȃ��łˁB�݂�ȃE�`�̋����ړ��ĂɏW�܂��Ă���B�@�ݐM����i�Y��������j�o�����̂͂��ꂶ��Ȃ��B�{���Ɋ݂��������͔̂��F���Y�Ɩ��v�A���Ƃ��n���[�E�J�[���i�W���p���E���r�[���j�̈�l�j���B���͒����ƌÑ��͏o���Ă�����B�E�B���r�[�ɒ��k�����ĂȁB�E�B���r�[�͎O�Y�`�ꂩ��Љ�ꂽ�B�O�Y����Ƃ����̂͂ƂĂ��Ȃ��啨�łˁB���{�̉e�̑哝�̂Ƃ����Ă������B�E�B���r�[���g�c�����E�̑啨���A������肪�����オ������ɎO�Y����̂Ƃ���ɑ��k�ɍs������B
�@���̂���GHQ��GS��G2�Ɋ���Ă����̂͒m���Ă��邾�낤�B�E�`��G2�̑��������B����Ŕ����H��Ƃ��ˁB�܂��A�A�J��肾��B
�@�m���ɉ����L���m���͐e�F�������B�Љ�Ă��ꂽ�̂͊��̂��삳��i�G���U�x�X�E�T���_�[�X�z�[������c�����j�������B�E�B���r�[��G2�̉��ɃL���m���@�ւĂ̂�������B�{���̊��@�ɖ{����u������Łu�{���u�����`�v�ƌ���ꂽ�B�\������14�|5���B�C���͋ɓ��n��ɂ�����h�������B�܂��A�A�J��肾�B���{�����ɑ���ߕߌ��������̂����l�������B�u�{���u�����`�v�͈���u���@�K�I���s�����v�������B
�@����Ă邱�ƂƂ͗����ɕ\�����̐����͔h�肾�����B�{���n�E�X�ł͖閈�p�[�e�B�[���Â���A�܂�ŕʐ��E�̑̂������B�q�l�́A���x�����̐ē����A���䐽��Y�s�m���A�c���h��x�����āA���F���Y�ȂǁB���D�̋��}�`�q�A�����������āA�̂��̂��Ă��B
�@�L���m���͂������������B�}�X�R�~�͋S�݂����ɏ������ǂˁB���l�̎���ɂ��V�тɍs�����B���F���Y��ē������ꏏ�������B�ē����L���m���ɏЉ���̂͋g�c�����F���낤�B�L���m���͓���������łˁB�܂��ŏ��ɃE�B�X�L�[�Ƙd�G�Ōx�@�̐e�ʂ���ȂÂ���B�����ē��{�̌x�@�蒠�݂����Ȃ̂�������Ă��A���ꂳ������ǂ��ł������������o������Č����Ă��B������������Ƃ���Ƃ��ɂ͎��X��Ă����B
�@����́u�����Y�Ɓv��G2�̎d��������Ă�������A�L���m���@�ւƂ͌Z��݂����Ȃ��̂������B�L���m���̎d���������Ƃ����������o�������Ƃ��������B���ꂽ���͔����Ƃ����ЂƂ̖ړI�Ō��ꂽ�t�@�~���[���������B
�@�r���ۂ����Ƃ��������B�A�J��������Ă��āA���̒��Ɍ��e��˂�����ȁB�L���m���͂����̓��̏�ɁA�ꔭ�Ԃ����ނB���̖т��ł��邭�炢�ɂ��B����Őu���u�e�ۂƋ��Ƃǂ����������H�v�B������������ŁA��d�X�p�C�ɂȂ�B�ɓ����Ȃ��̌����B
�@GS�i�����ǁj�̓z��A�z�C�b�g�j�[�Ƃ��P�[�W�X�ɂ�������B������������̓A�J�̖����������B�P�[�W�X�ƒ����v�l�̂��Ƃ͒m���Ă邩���H ���ɂ������d�^���������B������d�g�̂͂��ꂽ�����B����͎O�҂̗��Q�W�����S�Ɉ�v�����B�g�c�͈��c���t��ׂ����������B�E�B���r�[�̓P�[�W�X��Ǖ������������B�������͏��d�̐X����ɉ����������B�ŏ��Ɍv���������̂̓E�B���r�[�Ƌg�c�Ɣ��F���Y�����B����ł����ē������������B�L���m���͒��ڂ͗���ł��Ȃ��B�����͓����g���̂͂��܂蓾�ӂ���Ȃ������B�r���ۂ����Ƃ���傾�����B
�@�ēc���������ł����B�P�[�W�X���V���Ђ�x�@�Ɉ��͂������Ă�������A�n���[�E�J�[���̂Ă��g���ăA�����J�̐V���ɏ��𗬂����͎̂ēc�������B
2013.06.25 (��) ���I�u���R�����_�v2�`�Ɛl�̍s����ǂ�
[3] ����͑��E�ł��� �@�����A�x�����͑{�����J�n�B�A���̕ɁA�u���E�H�v�u����A���E�v�ȂǁA�͑��R�ƂȂ����B�x�������ł��ӌ���������A��ۂ͎��E�A��ۂ͑��E�œ����Ă����B�Ƃ��낪���炭���āu���E�v�u���E�v�̌��_�t�����Ȃ��܂ܑ{���͑ł���ꂽ�B������1950�N2���A�u���Y�t�H�v�Ɓu�����v�ɁA�{���̗���ƏI���ɂ��ď����ꂽ�u���R�����v�Ȃ���̂��f�ڂ��ꂽ�B����͈�ۂ̈ӌ�������ł���A�ÂɎ��E���ق̂߂������̂������B
�@�����A�x�����͑{�����J�n�B�A���̕ɁA�u���E�H�v�u����A���E�v�ȂǁA�͑��R�ƂȂ����B�x�������ł��ӌ���������A��ۂ͎��E�A��ۂ͑��E�œ����Ă����B�Ƃ��낪���炭���āu���E�v�u���E�v�̌��_�t�����Ȃ��܂ܑ{���͑ł���ꂽ�B������1950�N2���A�u���Y�t�H�v�Ɓu�����v�ɁA�{���̗���ƏI���ɂ��ď����ꂽ�u���R�����v�Ȃ���̂��f�ڂ��ꂽ�B����͈�ۂ̈ӌ�������ł���A�ÂɎ��E���ق̂߂������̂������B�@�����A����͂ǂ����Ă����E�ł���B�ł͂��̗��R�������B
�@ �����̌��ʁA�����������Ȃ��B����͎���瀒f�ł���B
�A 瀒f����̖k��Z���A�����i�s�����Ɣ��Έʒu�Ɍ����������Ă����B���E�Ȃ猌���͐i�s�����ɂ����t���Ȃ��B
�B ��������̓S���l�Ԃ��A�}�O���Ƃ����Ċ�����瀎��̂Ɏ��炪�Ȃ��Đ_���Ȑ��H�������͂����Ȃ��B
�@����ɁA�ւ��ʂɂ�錩�������̋U���H����l������A���E�ȊO�ɍl�����Ȃ��B���R���ق͝f�v����E�Q������H�Ɉ�����ꂽ�̂ł���B���킸�u���E�v�ƒf�肵�A�����O��ɘb��i�߂�B
[4] �Ɛl�̍s����ǂ�
�@���R���ق͂ǂ̂悤�ɝf�v����E�Q���������ꂽ���H ���������̎��s�Ƃ̑�����u�����v�Ƃ��Ă����ǂ��Ă݂����B���ꂾ���̎��������炵�āA��ʂɂ���ď������邪�A�����Ƃ��čł����������Ǝv�����̂��u������v�Ń`���C�X���Ă��܂����B�Ԉ���Ă��\��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�{�_�̏d�_�́A�����̎��ɂ���̂ł͂Ȃ��A���@�ƎЉ��̍l�@�ɂ��邩��ł���B
�@�u�����v����u�t�B�N�T�[�v��ʂ��Ĉ˗������u�i�ߓ��vA��B�́A�t�B�N�T�[�Ƌ��Ɏ��s�v��𗧂Ă�B���̐ʐ^�ɂ��������āu���s�����v��z�u�A�������w������B�i�ߓ�A�Ƃa�͉��R�Ɗ猩�m��ł����邽�ߝf�v���̂��̂��s���A����v���C���O�}�l�W���[�ł���B����ŁA���啨C�ɉ��R���ق̌Ăяo�����˗�����BC�́u7��5��9�F30�̊J�X����ɎO�z�{�X�ɓ���X���d�����ɗ����v�Ɖ��R�ɘA���B���R��C�̌������Ƃɂ͒����ł���BC�Ƃ͂��������ԕ��������BC����d�v�������炤�i��肾������������Ȃ��B������A��������邽�߉^�]��ɗl�X�ɖ����Ď��ԍ��킹�����Ă���̂��B���R��C�Ƃ͂���܂łɂ��x�X����Ă���B�^�]��ɂ��m��ꂽ���Ȃ����߂��AC�̎����������≓���ő҂�����̂��킾�����B
�@���������̉��R�̕s���ȍs���i�^�]��ւ̖��߂̖����̂Ȃ��j�́AC�̎w�߂𒉎��Ɏ�邽�߂̎��ԍ��킹�ł���A�^�]��ɂ��J���t���[�W���������ʂł���B
�@���R�͎w�肳�ꂽ�����ɍs���i�u���R�����v�ɂ��Ɓu�����̓X���ɖڌ�����Ă���v�j�B�w��̔�����C�͂��Ȃ��B���̑���AA��B�������B�ނ�́u���R����AC����͗����Ȃ��Ȃ�܂����B���������ނ̑҂ꏊ�Ɉē����܂��傤�v�ƌ����āA���R�𑣂��n�����ɏo��B�����ʼn��R�͒m�荇���̏��쎛�����Ƃ����j�ɖڌ������B �@A��B�͉��R���Ԃɏ悹�A���Ȃ錻��Ɍ������B�����ɂ�C�͂��Ȃ��B����ɋ��ʂ̓��{�l����n�炪�����B�ꏊ�͂Ȃɂ��̍H��̂悤���B�������E�l����B�u���s�����vD�͉��R���ق�\�s����������̖��A�E�Q�����B
�@�[��A�u���s�����v�d�͎��̂��^�яo���A���S����k��Z�����Ԃ̃��[����ɒu�����B
�u���s�����v�ɂ͕ʓ������������B���E�U���O���[�v�ł���B���R���يċ�ߕ���E�������炩���ߌ��߂Ă��������R�̑ւ��ʂɒ�����B�u�ւ��ʁv��F�Ƃ���BF�̑������u���R�����v�̖ڌ��،��ɉ����Ēǂ��Ă݂�B
�@F�́A7��5���a�J��11�F23�̐s�n���S�ɁA�O�z�O�w�����荞�݁A��l�̒j�̑��ށB�ڌ��҂Â���̂��߂��B�ō~���B�n���S�w�����ł͌C�����ɖڌ�����Ă���B
�@�������ɏ�芷���ܔ���w�ʼn��ԁB13�F43�B���D���Ɂu���̕ӂɗ��ق͂Ȃ��ł����v�Ɛu���B���D���͖��L���ق�������B
�@F�͖��L���قɍs���B�����̏����E�����t�N�Ɂu���炭�x�܂��Ăق����v�ƍ����āA2�K�̎l�����̕����Ɉē������B�u�h�����v�ƌ���ꂽ�̂Łu����͊��ق��Ă���v�ƒf��B�ւ��ʂ�����M�Ղ͎c���Ȃ��͂��ł���B���炭�����ɂ��āA���Ԃ��Ԃ��B17�F30�A�h��200�~�����ق��o��B
�@�ܔ���w���H�t�߁A�g���l����K�[�h���Ȃǂ��Ԃ�Ԃ�ƕ����B��冋o���ɕ����������������B�����~�܂�l���������Ă��镗���B���̂�����̖ڌ��،��A���B
�@�U���H��͂����܂ŁBF�́A������łɂ܂���Ďp���������iF�͗��Ƃ������N�l�ŁA�ւ��ʂ��I���������ɂȂ���1955�N�H�ɏ����ꂽ�A�Ƃ����،�������j�B
�@7��6�������A0�F24����k��Z�w���o��������씭���ˍs�̏I�d2401M���A�����w�Ƃ̒��Ԓn�_�t�߂ɂ������������Ƃ��A�^�]�m��瀎��̂炵�����̂������B�ʕ�����w�����m�F�A���ꂪ���S���ى��R�葥�̕ς��ʂĂ��p�������B
2013.06.10 (��) ���I�u���R�����_�v1�`�����̖{���Ƃ���܂�
[�O��]�@���̉�Ў���̗F�l�ɌK���뒼�N�Ƃ����j������B�ނ̕��͌K���������m�B���R�����Ŕ�Q�҉��R�葥���㍑�S���ق̌�����S������������ł���B���ʂ̗F�l�ɓc���\��Y�N�����邪�A�ނ͂���ȊW�ŁA�̂���u���R�����v�ɂ͎�̂ق��S���[���B�c��������A���ŋ߁u�ʔ�������ǂ�ł݂���v���u���R�����`�Ō�̏،��v�Ƃ������ɖ{������B
�@���͂���܂ŁA�u���R�����v�ɂ��āA
 �g�I���N���������S�e���𖾂���Ă��Ȃ����S�֘A�̎����̈�ŁAGHQ�����炩�̌`�Ŋ֗^���Ă���h���x�̔F�������Ȃ������B�ŏ��ɖڂ�ʂ����u���Ƃ����v�ɂ́A�N��悵�������u�ǂ̉��R�����֘A�̖{�����������o�������ł������v�Ƃ���B�ޏ��̌��Ȃ�M�p�ł���A�Ɠǂݏo������A��͂�ԈႢ�͂Ȃ������B�����ɁA���̒��͉��R�����ň�t�ɁB���܂炸�A���{���͎��s�Ƃ̃A�W�g�i�������Ǝv�����ꏊ�j�ɍs���Č���ȂǁA�܂��Ƀ}�C�E�u�[���Ɖ����Ă��܂����B�ʐ^�͎��s�Ƃ������Ƃ����A�W�g�i���݂͕ʂ̌����j�ŁA���̂Ƃ��ɎB�������̂��B
�g�I���N���������S�e���𖾂���Ă��Ȃ����S�֘A�̎����̈�ŁAGHQ�����炩�̌`�Ŋ֗^���Ă���h���x�̔F�������Ȃ������B�ŏ��ɖڂ�ʂ����u���Ƃ����v�ɂ́A�N��悵�������u�ǂ̉��R�����֘A�̖{�����������o�������ł������v�Ƃ���B�ޏ��̌��Ȃ�M�p�ł���A�Ɠǂݏo������A��͂�ԈႢ�͂Ȃ������B�����ɁA���̒��͉��R�����ň�t�ɁB���܂炸�A���{���͎��s�Ƃ̃A�W�g�i�������Ǝv�����ꏊ�j�ɍs���Č���ȂǁA�܂��Ƀ}�C�E�u�[���Ɖ����Ă��܂����B�ʐ^�͎��s�Ƃ������Ƃ����A�W�g�i���݂͕ʂ̌����j�ŁA���̂Ƃ��ɎB�������̂��B�@�{���̍ő�̔���́A�W���[�i���X�g�ł������ҁE�ēc�N�F�����A�u���̑c���������Ɋ֗^���Ă����\��������v�Ƃ��Đ荞��ł����A���̃X�^�C���ł���B���E�����E���x�@�������AGHQ�⋤�Y��`�҂̉������肴���������A���ɂ͎����ƂȂ�A60�N�ȏ�o�������݂������^�����͂߂Ȃ��䑽�������ɑ��āA����͉���I�ȍ\�}�ł���B
�@���{�����́A����11�N��ɁA���̉��R�������܂ރm���t�B�N�V�����W�\�����B�u���{�̍������v�ł���B���̒��ŁA�u���R�����̖��ߎ҂��N�ł��邩�͉i�v�ɔ���ʂ��낤�v�Ə����Ă���B���҂͂�����ǂ������C�����ŏ������̂��낤���H ���̒����ł́A�u�i�v�Ɍ��ɏo���Ȃ����낤�v�̃j���A���X�ɋ߂����̂�������B�u�����Ă������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��B
�@����́u�N���V�b�N�̓�������v�Ƃ͖Ⴄ�R�e�R�e�̌Y�������ł���A�����Ȑ��{�v�l�̖����D��ꂽ�������Ԃ�k���������厖���ł���B�����Ɋւ�����l�Ԃ́A�Ԑڂ܂ʼn�����ƁA100�l���Ƃ��B�������A��������60���N�O�ɋN�������������炵�āA���ۂɊ֗^�����l�̉��l���͂܂������Ă���\��������A���X����܂łȂ瑶���҂͑������ɏ�邾�낤�i���҂̎ēc�������̂����̈�l���j�B����ɁA�����͓��{�Ƃ������Ƃ̍����Ɋւ����̂ƍl�����邩��A���̐^���͐�ɂ��o���邾�낤�A�Ƃ̗\��������B
�@����ȁg�厖���h�������Ƃ��Ǒf�l�������{�ʂŌ�茋�_�t����Ȃ͂������܂����̋ɒv���B�����玄���������A�u�i�v�ɔ���Ȃ����낤�v�ƌ��Ԃ����Ȃ��A����ȗ\���͂ʂ����Ȃ��B�����������A�����͌����Nj��������Ȃ�̂��u�N�����m�v���_�H �����Ȃ邤���́A�u���R�����`�Ō�̏،��v���e�L�X�g�ɂ��āA������ǂ݉����Ă䂫�����B����́A���I�u���R�����_�v�ł���B
[1] ���R�����̖{��
 �@�ǂ�Ȏ����ɂ��K�����@������B�����ĔƐl������B�Ɛl�ɂ͒P�ƔƂƕ����Ƃ�����B���@�̂���l�Ԃ����ڎ�������ꍇ�ƈ˗�����ꍇ������B���R�����͂���炪�������镡�G�Ȏ����ł���B���̍\�}�������𗧂Ăē��ɓ���Ă����Ȃ��ƁA�ǂ�ł��ăg�b�`������B���ɂ��́u���R�����`�Ō�̏،��v�Ƃ����{���������B���Ԉ�ʂ̖ڂɐG��Ă��邱�Ƃ��Ȃ����ƁB�̂̂��ƍ��̂��ƁB���l�̍l���Ǝ��g�̍l���B�\�Ɨ��B����炪���n��ɏ]�킸�ɏo�v����B���҂̒m���Ă��邱�Ƃƒm��Ȃ����ƁA�m���Ă���̂Ɍ����Ȃ����ƁA�������Ԓf�Ȃ��s�������B���ʂɓǂ�ł���Ƃ��炪�邩��A�y�[�W�������Ԃ��m�F���Ė��߂���J��Ԃ��B���Ɍ����������B
�@�ǂ�Ȏ����ɂ��K�����@������B�����ĔƐl������B�Ɛl�ɂ͒P�ƔƂƕ����Ƃ�����B���@�̂���l�Ԃ����ڎ�������ꍇ�ƈ˗�����ꍇ������B���R�����͂���炪�������镡�G�Ȏ����ł���B���̍\�}�������𗧂Ăē��ɓ���Ă����Ȃ��ƁA�ǂ�ł��ăg�b�`������B���ɂ��́u���R�����`�Ō�̏،��v�Ƃ����{���������B���Ԉ�ʂ̖ڂɐG��Ă��邱�Ƃ��Ȃ����ƁB�̂̂��ƍ��̂��ƁB���l�̍l���Ǝ��g�̍l���B�\�Ɨ��B����炪���n��ɏ]�킸�ɏo�v����B���҂̒m���Ă��邱�Ƃƒm��Ȃ����ƁA�m���Ă���̂Ɍ����Ȃ����ƁA�������Ԓf�Ȃ��s�������B���ʂɓǂ�ł���Ƃ��炪�邩��A�y�[�W�������Ԃ��m�F���Ė��߂���J��Ԃ��B���Ɍ����������B�@������A�����𗧂Ă���ɉ����Ď����̍\�}�ɓ���Ă����K�v������B�Ԉ���Ă��Ă�����Ă����̂ł���B�����̂��߂ɁB�ԈႢ�ɋC�Â����炻�̎��_�ŏC����������B����ɁA���̉����ɂ��������Ď����̖{���������Ȃ�ɗ������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@�u���R�����v�ɂ́u�����v������B�������˗������u�i�ߓ��v������B�����Ɓu�i�ߓ��v�𒇉��u�t�B�N�T�[�v������B�u�i�ߓ��v�́u���s�����v��Ґ�����B�u���s�����v�ɂ͂������̖���������B�ނ�ɂ͖�������������������Ȃ��B��������s�����͑S�̑���m��Ȃ��B�����̌��ɂ͋���ȁu�Q�v������B����͎���Ƃ�������łǂ������p���[�ł���E�E�E�E�E���ꂪ�����B
�@�u���R�����v�͒P�Ȃ�E�l�����ł͂Ȃ��B���Ƃ����A���{�����đ̌��������Ƃ̂Ȃ����ׂ̒��ŁA�e�l�������߂��~�]�Ƒ�`���ӑR��̂ƂȂ��ĎY�݂����ꂽ�������ł���B�����Ă���鳖��鲂����߂����̍s�����́A�N�������������ƂȂ��č��ɑ����Ă���B���E�ɂ��ޗ�̂Ȃ����{�Ƃ������̌`�E�L�l�́A�ԈႢ�Ȃ��u���R�����v�̎���ɕ����t�����ꂽ���̂��B������܂��ɁA�u���R�����v��ǂ݉������Ƃ��A���セ���ď����̓��{�����ʂ����Ɍq����̂ł���E�E�E�E�E���ꂪ�{���ł���B
[2] �����̂���܂�
�@�܂��́A�\�ʂɌ����鎖���̂���܂������Ă����B
�@1949�N ���a24�N7��5���A���S���㑍�����R�葥�i1901�|1949�j�́A�����ǂ��蒩8��20���A�吼���Y�̉^�]����Зp�Ԃɏ���đ�c��r��̎�����o�č��S�{���Ɍ��������B�Ԃ��䐬��ɂ������������Ƃ��A���R�́u��������̂Ƃ���Ɋ��̂������v�ƙꂢ���B�u��������v�����厩�R�}�̐�����E�����h����w�����̂Ȃ̂����������̍��������Ȃ̂��́A���݂��s���̂܂܂��B�u��������v�ւ͈����Ԃ����ɁA�Ԃ����S�{���ɂ���������̂�O�ɂ��āu������������������O�z�֊���Ă���v�Ɖ��R�͑吼�^�]��ɖ�����B�����w�k���K�[�h�ł́u���؉��ł��悢����A�܂������s���Ă���v�B���؉��O�Łu�܂��J�X���Ă��܂���ˁv�Ƒ吼�B�Ԃ��O�z�i���{���{�X�j�֊�B�������܂��J�X�O�A������ɂ́s9�����J�X�t�̎D���|�����Ă����B�u�����A��܂����v�Ɂu����v�B����A�u�_�c�w�։���Ă���v�Ɣ��Ε������w���B�_�c�w�ɍs���B�u�����ɂȂ�܂����v�ɂ́u����v�Ǝ��U��B�吼�͂����{���ɍs�����̂Ɖ��߂����܂��悤�Ƃ����Ƃ���A���R�́u�E�Ȃ����Ă���v�Ǝw���B�E�܂��Ē����ʂ�ɏo��ƉE�܁A����3���ڌ����_��
 �u�O�H�i��s�j�{�X�֍s���Ă���v�B���S�{���O��ʂ蔲���邠����ʼn��悤�Ɂu�������������s���v�B�Ԃ͎O�H��s�i�������c��s�j�ɓ����B���̂Ƃ�9�F05�A���R�͒��ɓ���20����ɏo�Ă���B���R�͎����ɂ��炢���炩�̋��������o�����B9�F25�u������s�����傤�ǂ悢���낤�v�Ɖ��R�B�Ԃ͎O�z����̒��ԏ�ɓ���B���R�́u�܂��A�J���ĂȂ���Ȃ����v�ɑ吼���u�����l�������Ă��܂���v�B���R�͎Ԃ��o�ē�����Ɍ����������A�߂��Ă��đ吼�Ɂu5�����炢������҂��Ă��Ă���v�ƌ����c���X���ɏ������B���̂Ƃ�9�F37�B���ꂪ�吼�̌������R�̐������Ō�̎p�������B
�u�O�H�i��s�j�{�X�֍s���Ă���v�B���S�{���O��ʂ蔲���邠����ʼn��悤�Ɂu�������������s���v�B�Ԃ͎O�H��s�i�������c��s�j�ɓ����B���̂Ƃ�9�F05�A���R�͒��ɓ���20����ɏo�Ă���B���R�͎����ɂ��炢���炩�̋��������o�����B9�F25�u������s�����傤�ǂ悢���낤�v�Ɖ��R�B�Ԃ͎O�z����̒��ԏ�ɓ���B���R�́u�܂��A�J���ĂȂ���Ȃ����v�ɑ吼���u�����l�������Ă��܂���v�B���R�͎Ԃ��o�ē�����Ɍ����������A�߂��Ă��đ吼�Ɂu5�����炢������҂��Ă��Ă���v�ƌ����c���X���ɏ������B���̂Ƃ�9�F37�B���ꂪ�吼�̌������R�̐������Ō�̎p�������B�@�����āA7��6�������A����̖k��Z�ƈ����̒��Ԍܔ���̐��H��ŁA���R���ق�瀎��̂ƂȂ��Ĕ������ꂽ�B
�@�ȏオ�u���R�����v���N����1949�N7��5��������6�������܂ł̉��R���ق́g�����h�ł���B
2013.05.25 (��) �b����`���O��G�߂�
�@����A�O�Y�Y��Y���A80�˂ŃG���F���X�g�o���ɐ����A�ō���҂̋L�^��ł����Ă܂����B�O�Y���v���E�X�L�[���[�Ƃ��Ďn�������͎̂��̊w������̍��B�X�L�[�O���̎����������̂Ŏ��ɓ���̑��݂ł����B�u�L�����[�^�[�E�����Z�v�Ƃ��������~�ŃX�L�[�̃X�s�[�h�������������Z�������āA�����Ő��E�L�^����������ȂǁA���E���҂ɂ����Ċ��Ă����̂��v���o���܂��B�������̉e�����āA�z�[���E�Q�����f�̎u�ꍂ���u�F�̓��v��u����R�v�ł́A�`���b�J�����̃X�s�[�h��������Ă��܂����B �@�ނ̌��C�̔錍�́u�ڕW�����v���Ƃ������ł��B�ڕW��������ꂪ�����b��ɂȂ�B�l�����[������Ƃ������Ƃł��ˁB���u�J���e�b�g�I �l���̃I�y���n�E�X�v���ς遄
 �@�v�X�Ɍ����f��A�u�J���e�b�g�I �l���̃I�y���n�E�X�v���A�e�[�}�̈�͘V�N���̐����b��B�_�X�e�B���E�z�t�}�����ē�i�ł��B
�@�v�X�Ɍ����f��A�u�J���e�b�g�I �l���̃I�y���n�E�X�v���A�e�[�}�̈�͘V�N���̐����b��B�_�X�e�B���E�z�t�}�����ē�i�ł��B�@���N���a200�N���}����W���[�b�y�E���F���f�B�i1813�|1901�j��28��̃I�y������Ȃ��܂������A�{�l�́A�u���̍ō�����͂��̒��ɂ͂Ȃ��B����́w���y�ƌe���̉ƁxCasa di Riposo���v�ƌ����܂����B����͒ʏ́u���F���f�B�E�n�E�X�v�ƌĂ�郊�^�C�A�������y�Ƃ̘V��̂��߂ɍ��ꂽ�e���̉Ƃ̂��ƁB���y�Ƃ̘V�l�z�[���ł��B�f��u�J���e�b�g�v�̕���́A�u���F���f�B�E�n�E�X�v����u�r�[�`�����E�n�E�X�v�A�C�^���A����C�M���X�ɕ����ς��ēW�J���܂��B
�@�u�J���e�b�g�v�Ƃ̓r�[�`�����E�n�E�X�S�l�̏Z�l�̂��ƁB������́A�}�M�[�E�X�~�X�A�g���E�R�[�g�l�C�A�r���[�E�R�m���[�A�|�[���[���E�R�����Y�̖��D�����B�}�M�[�E�X�~�X�͉��N�̖��v���}�E�h���i�Ńg���E�R�[�g�l�C�Ƃ͌����̌o��������B���̏o���S�̂����œ�l�͕ʂ�邪�A�j�͈������̋C���������������Ă���B4�l�͂��ă��F���f�B�̉̌��u���S���b�g�v�ŋ��������̎蒇�Ԃ������B���̂�����̐ݒ�Ɣz���Ɖ��Z�͏G��ŁA�V���̐S���A���̕ω��A�X�l�̐��i����Ɏ��悤�ɕ������Č����B�܂��ɁA�J���e�b�g�����Ȃ���햡���̂��̂ł��B�n�E�X�����̕���i�ς����������������Ċi�������B���X�o�����鉝�N�̖���̉��t��ʂ��n�b�Ƃ��ăi�C�X�B�n�E�X�̏Z�l���e���r��ʂɌ������ʂł́A���̍ō��Ɍ����ȃe�m�[���A�W�����E���B�b�J�[�X���F�̏^�𗁂тĂ��āA�E�[���A���ꂾ���͂��������܂���ł����B
�@�u�J���e�b�g�v�ɂ͂�����A�u���S���b�g�v�̎l�d���Ƃ����Ӗ������������āA�o�c��̃r�[�`�����E�n�E�X���~�����߂̃K���E�R���T�[�g��4�l���̂����ڂ��w���Ă��܂��B
�@����̏I�Ղɂ́A�}�M�[�E�X�~�X�ƃg���E�R�[�g�l�C�̊Ԃ̂킾���܂肪�����āA��l�͌����𐾂��̂ł����A������N�̌��B���Ă�������́u����ł����̂��v�ƈ��g���邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ċ����̃��X�g�V�[���B�̌��u���S���b�g�v��3������̎l�d���u���������̉�����v���n�܂�E�E�E�E�E�Ƃ��̏u�ԁA�����Ȃ��ʂ̓^�C�g���E���[���Ɉڍs���A�����ւ��̉���������o���܂��B
�@���҂͐��y�Ƃ���Ȃ��̂Ő����ւ��͓��R�Ȃ̂ł����A��ʂ����ʂłȂ��Ȃ����̂́A�������q�����̊�������܂����B�ł��A�悭�l����ƁA���̕��@�����Ȃ������Ƃ��v���Ă��܂��B
 �@���͂��̎l�d���A�Ȃ�Ƃ��ߎS�ȏ�ʂʼn̂���̂ł��ˁB�W���_�i�}�M�[�E�X�~�X�j���v��������݁i�g���E�R�[�g�l�C�j���A�t�V�_�����i�|�[���[���E�R�����Y�j���������Ă���B���ނ��̕��e�E���S���b�g�i�r���[�E�R�m���[�j�́A���̃W���_�ɁA���݂���߂����悤�Ƃ��Ă��̏�ʂA���猩���Ă���B����̃W���_�̉̂́u�s���Ȑl�v�Ƃ��u���ɂ�����ȕ��ɚ�������v�Ƃ��̒Z���t���[�Y����B�Ȃ��Ă���̓e�m�[���哱�^�̎l�d���B�������ʂ�������A�������̃}�M�[�E�X�~�X�̑��݊�������Ă��܂����ɈႢ�Ȃ��o�����X�Ȃ̂ł��B
�@���͂��̎l�d���A�Ȃ�Ƃ��ߎS�ȏ�ʂʼn̂���̂ł��ˁB�W���_�i�}�M�[�E�X�~�X�j���v��������݁i�g���E�R�[�g�l�C�j���A�t�V�_�����i�|�[���[���E�R�����Y�j���������Ă���B���ނ��̕��e�E���S���b�g�i�r���[�E�R�m���[�j�́A���̃W���_�ɁA���݂���߂����悤�Ƃ��Ă��̏�ʂA���猩���Ă���B����̃W���_�̉̂́u�s���Ȑl�v�Ƃ��u���ɂ�����ȕ��ɚ�������v�Ƃ��̒Z���t���[�Y����B�Ȃ��Ă���̓e�m�[���哱�^�̎l�d���B�������ʂ�������A�������̃}�M�[�E�X�~�X�̑��݊�������Ă��܂����ɈႢ�Ȃ��o�����X�Ȃ̂ł��B�@�����A���̃e�m�[���̃����f�B�[�͂Ƃ�킯�f���炵���B�Ô��ɂ��ď�M�I�B��ʉ]�X��ʂɂ���A����قǕ���Ƀt�B�b�g��������͂Ȃ��̂ł́A�Ǝv�����Ⴄ�B�����ɁA���y�̖��͂�����܂��B���F���f�B�̐���������܂��B�����ł̓C���X�g�D�������^���E���@�[�W���������x�����x������āA����̃��[�h���Ɉ���Ă��܂����B
�@���̑��A�N���V�b�N�y�Ȃ͖��ځB�I�Ȃ������Ă��āA���Ƃ��A�V���[�x���g�̉̋ȁu�V�����B�A�Ɂv�́A�V�F�C�N�X�s�A�̎��B�n�C�h���̌����ȑ�100�ԁu�R���v�̑�3�y�́u���k�G�b�g�v�́A�����h���̋��s�t�U����������̒����ɂ���ď����ꂽ���́B���������y�l�d�t�� ��78�ԁu���̏o�v�̓n�C�h�����C�M���X���s����A��������ɍ��ꂽ���́B�R�~�J���ȍ����Ȃ̓C�M���X�̃I�y���b�^��ƃA�[�T�[�E�T�����@���́u�~�J�h�v����E�E�E�E�E�Ƃ�����ɁA�C�M���X�֘A�̊y�Ȃ����܂����荞��ł��܂����B
�@�A��̃G���x�[�^�[�i�f��ق�6�K�j�ł͂�����Ƃ����n�v�j���O���B�f����ꏏ����4�l�i������J���e�b�g���j�ł̉�b���A�u�w�g�X�J�x���̂����O�B�l�X�E�W���[���Y�i1936�|�j�̓C�M���X�������\�v���m�B����80�߂�����nj����ȉ̐��������ˁv�Ǝ������D�~�B����ƁA����̎R�̎蕗���l�A�����肩��u���]���Ă�̂��̐l�A�����ւ��Ɍ��܂��Ă邶��Ȃ��v�I�g���肦�Ȃ����h���@���ɏ[�����Ă䂫�܂����B�g�z�z�I �W���[���Y���j�̐��̋�����m�鎄�́A�u�g�X�J�v�̃��R�[�f�B���O���Ȃ����ƂƑ��܂��āA����͔ޏ��́u���̉̐��v�Ɛ��������̂ł����A�E�[���A�ʂ����Ď����́H �Ƃ͂����A�G���x�[�^�[���ł̉�b�̓G�`�P�b�g�ᔽ�B���ȁB
�@ �@�����āA�W�C����J���e�b�g�͗[���̏a�J�̊X�ɌJ��o���܂��B���������̕��́A�V���ɓ�l�̒��Ԃ�������ăZ�N�X�e�b�g�Ɖ����A�f��A���y�A�����A�����A�X�|�[�c�A���a���g���ȂǁA�Ȃ�ł�������̃e�[�}����ь����܂��B���̖����u�a����v�B���̌��C�`�̉�����A���ɂƂ��Ă��������Ȃ������̂ЂƎ��Ȃ̂ł���܂��B
���N���V�b�N�\�����G���聄
�@����ATV�u�薼�̂Ȃ����y��v�����Ă�����A���̓��̉���́u�N���V�b�N�\�����G�I�茠�v�B���CD�V���b�v�̃N���V�b�N�\�����G4�l���A�N�C�Y�`���ł��̒m�������������Ƃ������e�ł����B���y�m���������A�h���~�t�@�h���A�`�Ԗ͎ʋȓ��āA�L���v�V��������A�^�������בւ��A���t�ғ��ăq�A�����O�ȂǂȂǁA�Ȃ��Ȃ��̃n�C�E���x���B���ڔ��ڎQ�����������́A�D���ҁiHMV�̋v�ۂ���j�ɂ͎��������Ȃ��������̂́A��2�ʂ̎R��y��E�{�c����Ƃ͍D�������ł��܂����B
�@�����āA�ԑg�̍Ō�ɂ́u�N���V�b�N�\�����G����v�̈ē�������܂��āB��Փx�̏��ԂɁA�G���g���[�A�V���o�[�A�S�[���h�A�v���`�i��4�̃N���X������A�K���G���g���[�N���X�������K�v������A��������7��7���Ƃ̂��ƁB�Ȃɂ��Ȃ��A����Ă݂����ƐS�Ɍ��߂āA�\�����ނ��Ƃɂ��܂����B1000�_���_�����A�V���o�[�E�N���X�̎����Ə��Ƃ̂��ƁB�܂��͂����ڕW�ɂ���Ă݂܂��B�O�Y�����f��u�J���e�b�g�v�قǂł͂Ȃ�����ǁA������V�N�̖ڕW�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�����A��w�����ȗ��̎��̎n�܂�ł��B�����͌��\�y�������I �o�ߓ��́u�N�����m�v�ŁB
2013.05.15 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��12�`���{�����u���[�c�@���g�̔��y�v��ǂ��
 �@�u���J�v���������ɋ����[�������ɂԂ������B�^�C�g���́u���[�c�@���g�̔��y�v�A���҂͏��{�����B�u���̌a�v�Ƃ����Z�ҏW�̒��̈��ŁA��ҍŔӔN�̍�i�ł���B�܂����A�����Ƀ��[�c�@���g�֘A�̏��������낤�Ƃ́I�������A���[�c�@���g�́g���y�h�Ƃ̓V�J�l�[�_�[�̂��Ƃ��Ƃ����ł͂Ȃ����B���a�̋��������[�c�@���g�ɂǂ����邩�H �����ÁX�œǂ�ł݂��B
�@�u���J�v���������ɋ����[�������ɂԂ������B�^�C�g���́u���[�c�@���g�̔��y�v�A���҂͏��{�����B�u���̌a�v�Ƃ����Z�ҏW�̒��̈��ŁA��ҍŔӔN�̍�i�ł���B�܂����A�����Ƀ��[�c�@���g�֘A�̏��������낤�Ƃ́I�������A���[�c�@���g�́g���y�h�Ƃ̓V�J�l�[�_�[�̂��Ƃ��Ƃ����ł͂Ȃ����B���a�̋��������[�c�@���g�ɂǂ����邩�H �����ÁX�œǂ�ł݂��B�@����́A���{�̕������̒j���A���n�ݏZ�̏����ʖ�Ƌ��ɁA�E�B�[���̓��[�c�@���g���̒n������Ƃ����`�Ői�s����B
�����}���N�X��n��
�@�j�Ə��́A�ŏ��A���[�c�@���g����������Ă��鐹�}���N�X��n�ɍs���B���[�c�@���g�̖����͍ʼn����̈����ōs���A�����ꏊ�͖����ɔ���Ȃ��E�E�E�E�E�Ƃ����������グ��B
��l�Ԃ��炨�낳�ꂽ���[�c�@���g�̈�[�́A���̋�����n�ɍŒ�̗����Ŗ������ꂽ�B�L�^�ɂ��Ƒ��V����܂߂ĂW�O���f��56�N���C�c�@�[�i���{�~��21,300�~�j�A�n�Ԃ̔�p��3�O���f���i7,500�~�j�ł������Ƃ����B���[�c�@���g�Ƃ����낤���y�Ƃ��ǂ����Ă��̂悤�Ȉ��������ꂽ�̂��B�ނ̉Ƃɋ����Ȃ������Ƃ����̂���̗��R���B������́A���V�▄���̈�́A�S�b�g�t���[�g�E���@���E�X���B�[�e���j�݂��Ƃ�d�����B�j�݂̕��̓}���A�E�e���W�A�̎���ł������B���q�̒j�ݎ��g�͊O�����A�{��}���َi���A�@���ƁA���R�Ȋw�ҁA�|�p�ʂł���A���[�c�@���g�̗F�l�ł������B���̒j�݂��Ȃ��Ƀ��[�c�@���g�̈�̂�n���ҕ��̖��������ɂ����̂��H�E�E�E�E�E�B
 �@�����₢�����������́A�����ׂ����_���o���B
�@�����₢�����������́A�����ׂ����_���o���B
�����Ɉ�̐�������B���[�c�@���g�͔~�łɜ���Ă����Ƃ����̂��B���[�c�@���g�͊댯�ȎЌ�V�Y�̏ꏊ�ɑ������Ă����B�ނ͔~�łɜ�����Ǝ��o����ƁA�~����F�l�̃X���B�[�e���j�݂ɋ��߂��B�X���B�[�e���̕��e�͂����قǂ��ӂꂽ�悤�Ƀ}���A�E�e���W�A�̎���ł����āA�~�ł̓�����ɐ���܂��J�������������B����܂͗L�łȂ��߂Ɋ댯������ċɓx�ɔ��߂��ď�������Ă����B���e�͂��̏������n�m���Ă������A���q�̃X���B�[�e���͐���łȂ����߂��̕��ʂ�����ă��[�c�@���g�ɗ^���Ă����B���[�c�@���g�͐��⒆�łɜ���Ċ������A��������Ɏ��B���[�c�@���g�̎��S�o�^��ɂ���u�}�������]�M�v�ł��邪�A���̏Ǐ�͂܂��ɐ��⒆�ł̏Ǐ̂��̂Ȃ̂��B��[�̐���͎��㐔�\�N�o�Ă��̓��ɍ��Ղ��c��B�j�݂͎����̎��s��m���Ă����B���[�c�@���g�̑��V�Ɩ�����v���̂��Ƃ������ŏI�������A��[���炻�̏؋����o��̂�h�����߁A�����ꏊ������ӂ�ɂ����̂ł���B�@���̂ق��ɁA���[�c�@���g���̒��O�̏Ǐ�i��Q�ϑz�Ȃǁj���u���⒆�Łv�̂��̂ł��邱�ƁA���̂��Ƃ�m���Ă����ȃR���X�^���c�F���A17�N�Ԃ���Q��ɍs�����A�s�����Ƃ��ɂ����̏ꏊ���x��l�ɐq�˂Ȃ��������ƁA�Ȃǂ������āA���̐��𗠕t���Ă���B�R���X�^���c�F�̌��ɐ����͂��������A����͖ʔ����A�����炵���͏o�Ă���B
���A���E�f�A�E�E�B�[�����ꁄ
�@���́A�u���J�v���������ꂽ����ł���B�����́A�ʖ�̏����ƒj�ɂ�������������B
�u�t���C�n�E�X�͐̂̃E�B�[����̒��F�ɂ���܂��B���̓E�B�[���삪���H�̉���ʂ��Ă��āA��������͌����܂���B18���I�̂��낱�̂ւ�̓R�����[�c���F���g�Ƃ����n���ŁA�E�l�̎d����A���ԏ����A����A��뉀�A�����225�˂̖��Ƃ������������ł��B���̎��n����n��̌��т̂��߂ɐ��{�͒n�ł�����ԖƏ������̂ŁA���̖ƐłɈ���Ńt���C�Ƃ��������ł����̂ł��v�@���̕����A�Έ�G�搶�ɂ��f��������A�u�����搶�̂́A������ƈ���Ă��܂��ˁv�ƌ���ꂽ�B�u���J�v���������ꂽ�̂̓t���C�n�E�X���́u���B�[�f������v�ŁA���݂́u�A���E�f�A�E�E�B�[������v�Ƃ͏ꏊ���Ⴄ�B�V�J�l�[�_�[�́A1791�N�A�u���B�[�f������v�Łu���J�v�������������ƁA�c��ɕʂ̓y�n�ł̌��ݔF��\���A�t�����c�E�C�G�[�K�[�̐v�ɂ��A1801�N�Ɋ��������̂����݂́u�A���E�f�A�E�E�B�[������v�ł���B���{�����̕��͂���́A�t���C�n�E�X�̐Ւn�ɍ��̌��ꂪ���Ă�ꂽ�悤�ɓǂ߂邪����͈Ⴄ�A�Ƃ̂��Ƃł������B
�u�ڂ��͂��܁A�E�B�[����̒��F�������Ƃ�����ƐŒn�т̑�뉀�Ɍ��Ă�ꂽ�ؑ��ŋ������A���ăV�J�l�[�_�[���o�c���Ă������t���C�n�E�X����A���݂̃A���E�f�A�E�E�B�[������̒��ɂ��܂��E�E�E�E�E�v
���u���{�̎�߁v�ɐG��遄
�@�u���J�v�́g���{�̎�ߖ��h�ɂ������͌��y���Ă���B
�V�J�l�[�_�[�̑�{�ɂ́A�^�~�[�m�́u���{�̎�߂𒅂��v�Ƃ����g����������B����Ȃ̂ɏ����ɋ߂��Ƃ������Ƀ^�~�[�m�����{�̎�߂𒅂��ߑ����Ȃ��B����͂ǂ��������Ƃ��낤�ˁv�ƒj���������B�u�w���̃g�����������̂�Y�ꂽ�x�Ƃ����b�������Ƃ�����܂��v���͋����Ȃ������Ɍ������B�u�ڂ������������Ƃ�����B�ꂵ����ɂ����ł��߂�Ȃ��ƁA�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ�����ˁB����ɐG��Ă���̂͂܂��ǐS�I�ł��B������Ƃ����݂�ȓ����Ă���̂�����ˁB������Ȃ����Ƃɂ͂����ʂ�����ƌ����悤�ɂˁv�@�u�^�~�[�m�͂Ȃ����{�̎�߂𒅂Ă���̂��v�ɂ��Đ������ǂ����_���Ă��邩�H ��������ԋ����[�������������B�m���Ɂg�݂�ȓ����Ă���h�Ƃ�����A�������ɓ��ݍ��̂͗��h�ł���B�����A�������ҊO��Ƃ��킴��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����͂��ׂĐ��_�̈���o�Ȃ�����ł���B
�u�n���K���[�𗷋��s���Ă���Ƃ��̃V�J�l�[�_�[�̓]���A�X�^�[�������ł͂Ȃ��A�����Ɠ����̖��b�����ɂ����낤�B�Ȃɂ���t�r���C�̒�̎����ɂ�������������B ���{�̃J���M�k�Ƃ������t���Ðl�̊Ԃɓ`����Ă����ɈႢ�Ȃ��B�X�T�m�I�ƃ��}�^�m�I���`�̐_�b�����̓������ʂ��琼�����ʂւƓ`�����Ė��b�ɂȂ����̂��V�J�l�[�_�[�������A�I�y���ɋr�F�����̂��낤�v
���y���V���v�z��
�@���̂��Ɛ����́A�u���J�v�̓t���[���C�\���̉e���͊F���A���ׂăy���V���v�z�Ő��藧���Ă����A�Ƃ����Ǝ��̉��߂��I����B�Ƃ��낪�A���ꂪ���Ȃ�̖\�_�ŁA�_�������܂����������Ă���̂ł���B
�u���J�v�ƃt���[���C�\���̊W�H ����Ȃ��̂͑S�R�Ȃ��B��������т���̂͂������������Ƃ��낾�B�t���[���C�\���Ȃ�đ�H�����̈�Ƃ��甭�W�������́B�Ǝ��̏@���͉����Ȃ��B�y���V���̃]���A�X�^�[���͐������Â��B�C�X���G���l�̏@���͋����ɂȂ����B�����L���X�g���B�����āA�C�X�������A�����A�����B�ȏ�̂ǂ�Ƀt���[���C�\���̏@���͌��������Ă���̂��ˁH �t���[���C�\�����K�N�\���R����g�D�Ƃ��Ă̑̍ق����������ꂽ�B�������A�t���[���C�\���̍��ۓI�Ȕ�����`�͊e���ɑ����̋��҂đ傫�Ȑ��͂ƂȂ����B���ǂ낢�����[�}�@�����́A�t���[���C�\����G�Ƃ��Ēe���ɂƂ肩����B�����鐭���I�A�Љ�I�A�d���t���[���C�\���̂����ɂ���悤�ɂȂ�B�t�����X�v�����ނ�̎d�Ƃ��Ƃ������킳���L�߂��B�u���J�v�̔�V�̓t���[���C�\���̃��f�����Ƃ����āA�˂��܂��ĉ��߂��錴���ƂȂ��Ă���B�@���̒��q�́A�c�O�Ȃ���A�[��������ɒl���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�u�Ȃ��w���J�x���t���[���C�\���Ɗ֘A���Ȃ��̂��v�Ƃ������R�����������Ă��Ȃ����炾�B������A�����͓�̌����w�E����ɂƂǂ߂����B
�V�J�l�[�_�[�͊m���Ƀt���[���C�\���Ɗւ�肪�������B�������A�ނ̑�{�ɂȂ��u���J�v�̓t���[���C�\���Ƃ͂Ȃ�̊֘A���Ȃ��B
�@��́A�t���[���C�\���́A�u���̎v�l�������A��������̏@���ł͂Ȃ��A�w�[�֎v�z�x�ɂ����A�l�Ԃ̗������d���v���̂ł��邱�ƁA������u�@���F���Ȃ��ē�����O�v�ł���u�@���ɂ���ē���̐������Ȃ��v�Ƃ������C�\���̊�{�����������Ė������Ă��邱�ƁB�����́g�t���[���C�\���̏@���h�Ƃ����������A���̊ϓ_����i���Z���X�ł���B
�@��ڂ́u���J�̑�{�̓V�J�l�[�_�[�̎�ɂȂ�v���̂��Ƃ��āA�g���[�c�@���g�̉���h�������Ƃ��Ă��邱�Ɓi�������͊����Ė������Ă��邱�Ɓj�B���[�c�@���g���u�V�J�l�[�_�[�Ƌ����ŕ�����\�����Ă������v���Ƃ́A�V�J�l�[�_�[�w�҃R�����c�B���X�L�[�ɂ���ďؖ�����Ă���B�����́A�j�́u�ڂ����V�J�l�[�_�[�ɂ��ĉ]���Ă���͎̂�Ƃ��ăR�����c�����X�L�[�́w�V�J�l�[�_�[�`�x�i�{�i�P�Y����j�ɋ����Ă���v�Ə����Ă���ɂ��ւ�炸�B
�@�Ȃ�A���̎v�z�I�w�i�𐴒��͉��ƍl�����̂��H ����̓y���V���v�z�ł���Ƃ���B���҃U���X�g���̖��̗R���͌Ñ�y���V���̏@���]���A�X�^�[���ł��邱�ƁB�]���A�X�^�[���ɂ����āA�P�_�͂V��V�g�ō\������A�P���͂R���ŏz����B�V���ɐ��܂�邽�߂ɂ͂R�̏C�s��K�v�Ƃ���ȂǁA�R�ƂV���d�v���ƂȂ��Ă���E�E�E�E�E�����̗��R�ɂ��A�u���J�v�̓]���A�X�^�[�����j�Ƃ���y���V���v�z�����̔w�i�ɂ���Ǝ咣����B
�@����͂���ł����̂����A�u�t���[���C�\���̉e���͊F���v�Ƃ��u�R�����c�����X�L�[���w�G�W�v�g���^�[���X�x�ɍS���ăG�W�v�g�̉e�����̂ĂĂ��Ȃ��̂͂��������v�ȂǁA�y���V���v�z�ȊO�����ׂĔr���I�ɉ������̂͂ǂ����Ǝv���B
�@���X�A�u���J�v�Ɍ��炸�����̃W���O�V���s�[���́A�Ȃ�ł�����̃S�b�^�ϓI�G���^�[�e�C�������g�������B�u�t���[���C�\���v���u�y���V���v���u�G�W�v�g�v������Ɍ����u���{�v���A�v�́g�Ȃ�ł�����h�������̂ł���B
�@�������A���̍�i�̒��ŁA�u���b�⓶�b�W�Ȃǂ���ނ����B���@���o��A�d�����o��A�������o��v�Ə����Ă���ł͂Ȃ����B���ꑦ���A�����̃W���O�V���s�[���́g�Ȃ�ł�����h�Ɩ{�l���،����Ă���̂ł���B�����̔r���I�y���V���v�z�_�́A���S�Ȏ��Ȗ������������Ă���B
�@�܂��A�u�V�J�l�[�_�[�̃y���V���v�z�͔ނ̐��x�ɂ킽��n���K���[�����s�œ����v�Ƃ��Ă��邪�A�����������
 �������s���ō����Ǝ�B����Ȃ�u�^�~�[�m���R�E�ߐ��v�̕����Ȃ�ڂ��܂����Ǝv���̂́A���掩�^�ł��傤���B
�������s���ō����Ǝ�B����Ȃ�u�^�~�[�m���R�E�ߐ��v�̕����Ȃ�ڂ��܂����Ǝv���̂́A���掩�^�ł��傤���B�@�^�C�g���u���[�c�@���g�̔��y�v�Ɋւ��A�g�Ȃ��V�J�l�[�_�[�����[�c�@���g�̔��y�Ȃ̂��v��������錏���A���܂�Ɏx���ŗ�Ŗœ����Ă��܂��B�������̏��a�̋������A��V�˃��[�c�@���g�ׂ͉��d�������Ƃ������Ƃ��B
�@���{�����́A��͂菺�a�̃h�L�������^���[�̕����悭�������B�ނ������u���a�̍������v�Ŏ��グ���u���R�����v�Ɋւ��āA�ŋߒ��ڂ��ׂ��{�����ꂽ�B����͂��̖{�����グ�A�Ȍサ�炭�����ɂ��ĒT�����Ă䂫�����B�@
[�Q�l����]
�u���̌a�v���{�������i���t���Ɂj
�u�V�J�l�[�_�[�v�����i���}�Ёj
�u�t���[���C�\���ƃ��[�c�@���g�v���c�r�꒘�i�u�k�Ќ���V���j
2013.04.25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��11�`���R�E�߂́u���J�v�̒��ɐ����Ă���
�@���[�c�@���g���u���J�v�ɍ��R�E�߂���������o�����̂́A�~�q���G����n�C�h���̉��y���u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v����Ƃ����̂͑O�q�����Ƃ���ł���B���[�c�@���g�́A�u�E�R���h�m�v�̒��̐���������̉��y���u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�i1771�N��ȁj�̏I�Ȃɓ]�p���Ă�������A�ނ̔]���ɂ́A15�̂Ƃ����獂�R�E�߂����܂�Ă������ƂɂȂ�B�@�����́A���̌��ƂȂ鉹�y���Ȃ���̂��y��ȉƃ~�q���G���E�n�C�h���Ɏ�قǂ����Ă��炤�̂��ړI�������낤�B���̂Ƃ��n�C�h�������{�Ƃ��Ē����̂��u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�������B���̒��Ɏ�X���[�c�@���g�̐S�ɋ������������������B���ꂪ�u�J���^�[�e�E�h�~�m�v�ŁA������ɓ]�p�����B�܂��Ɉ�ڂڂ�̎�ł���B
�@�����āA���̐����͂܂��A���[�c�@���g�̈��ƂȂ�������u���N�C�G���v�i1791�N��Ȗ����j�ɂ��]�p���ꂽ�B���̉ӏ��͓��Օ� Introitus�́�V�I���ɂĎ^�̂���ɕ�����͂ӂ��킵 �킪�V���Te decet hymnus ,Deus in Sion�̕����B�\�v���m�E�\�������Ɍh�i�ȉ̏�������Ƃ���ł���B��Ƃ̌ܖ��N�S�͂������u���悻�\�v���m�̓Ə��ŁA���̏o�����قǂɌh�i�Ŕ������r���𑼂Ɏ��͒m��Ȃ��v�ƒ����u�����̉��v�̒��ŏ����Ă���i��^���邱�̐������A���͉ʂ����āg�~�q���G���E�n�C�h���̐����h�ƒm���Ă������ǂ����H �����[���Ƃ���ł͂���j�B
�@���[�c�@���g�́A15�̂Ƃ��ɋ��������������̏��܂Ŏ����������̂ł���B�����܂Ŏv�����ꂠ����������炱���A�u�w���J�x�̂Ƃ��ɑh�荂�R�E�߂�z�N�������v�Ƃ���̂͌����Ė����Ȑ��_�ł͂Ȃ��ƍl����B�F����͂ǂ��v���邾�낤���B
�@�u�J���^�[�e�E�h�~�m�v�̐����͍Ō�ɂ͂܂����݂̐e�ɖ߂��Ă������B�~�q���G����n�C�h���́u���N�C�G�� �σ������v�i1806�N��ȁj�ł���B�ʒu�͓������Օ��B���݂����ł����������B������������낤���B�~�q���G���E�n�C�h���́A���[�c�@���g�̎�����15�N���1806�N8��10���A�U���c�u���N�ʼni���̖���ɂ����B�U���c�u���N���܂�̃��[�c�@���g�����U�̂قƂ�ǂ�ʂ̒n�ʼn߂������̂ɑ��A�ʂ̒n�Ő��܂ꂽ�n�C�h���̓U���c�u���N�ɗ��Ă��玀�ʂ܂ł��̒n�𗣂�邱�Ƃ͂Ȃ������B�U���c�u���N���߂���A���ɑΏƓI�Ȑl���𑗂����e�F���u�ł������B
�@�u�J���^�[�e�E�h�~�m�v�̐����́A�a�����Ă���36�N���̊ԁA��l�̍�ȉƂ̊Ԃ�]�X�Ƃ��A���̊ԂɁu���J�v�ɏ��ڂ����B�Ȃ�Ƃ����s��ȃX�g�[���[���낤�B���R�E�߂́u���J�v�̒��ɐ����Ă���B�^�~�[�m�ƍ����Ȃ�E�C�Ōq�����Ă���B���{�l���[�c�@���e�B�A���ɂƂ��Ă܂��ɋɏ�̊�тł͂Ȃ����B�ł́A�܂Ƃ߂Ă��̗�����������߂Ă��������B
�@�~�q���G���E�n�C�h�����y���u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v1770 �\ ���[�c�@���g���y���u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v1771 �\ �i���[�c�@���g�̌��u���J�v1791�j �\ ���[�c�@���g�u���N�C�G���v1791 �\ �~�q���G���E�n�C�h���u���N�C�G�� �σ������v1806
 �@�Ō�ɂ��f�肵�Ă����������Ƃ�����B�u���J�v�Ɋւ��āA1791�N9��30���A�������̃R�X�`���[�����z�����ƂɎc���Ă���B�������^�~�[�m���B����������Ɍf���邪�A���̈ߑ��ǂ����Ă��u���{�̎�߁v�Ƃ͎v���Ȃ��B�����̃V�J�l�[�_�[���g�����ɂ܂ŋL�����̂ɂȂ��H �Ƃ����^�₪�c��B����ɂ��Ă͂��������������B
�@�Ō�ɂ��f�肵�Ă����������Ƃ�����B�u���J�v�Ɋւ��āA1791�N9��30���A�������̃R�X�`���[�����z�����ƂɎc���Ă���B�������^�~�[�m���B����������Ɍf���邪�A���̈ߑ��ǂ����Ă��u���{�̎�߁v�Ƃ͎v���Ȃ��B�����̃V�J�l�[�_�[���g�����ɂ܂ŋL�����̂ɂȂ��H �Ƃ����^�₪�c��B����ɂ��Ă͂��������������B�@�V�J�l�[�_�[�́A���߂�����ɂ͓��{�̈ߑ���T���ɖz���������Ƃ��낤�B�����A���肬�肾�������߁A���t����Ȃ��܂������}���Ă��܂��B�u�ЂƂ܂����͊J���āA���t�������璅��������v�B�Ƃ��낪�A�u���J�v�͏�������吷���A�\�z�O�̑�q�b�g�ƂȂ����B�������Ă��܂��������̂��́B�u�^�~�[�m���{�̎�߁v�͂������ނ̓��̒���������Ă������̂ł���B
�@���́A�u���J�v�̎�l���^�~�[�m���u���{�̎�߂𒅂����q�v�Ɛݒ肳�ꂽ�̂́A���[�c�@���g�����R�E�߂𓊉e���������߂ƌ��_�t���邱�Ƃ��ł����B����͐��E���̌����Ǝ������Ă���B�Ȃ��Ȃ炻��́A����܂ŁA���̖��ɐG��Ă���̂��炠�܂茩�������Ȃ����炾�B���̒m����肻��͈ȉ��̓�ł���B
�u����т₩�ȓ��{�̎�߁i��{�ɂ����w������Ă��邪�A���ۂɂ͌Ñ�G�W�v�g�ł��邩�疳�Ӗ��ł���j�𒅂��^�~�[�m���E�E�E�E�E�v�i���y�V�F�Ёu���ȉ���S�W�v�C�V�V�q�����j�@����ɂ��g���Ӗ��h�Ƃ��������C�V�V���̂͘_�O�Ƃ��āA�y�VBLOG�̎R�c�������͖ʔ����B���@�艺���Ă���������Ί������B
�I�y���u���J�v�̖`���ɉ��q�^�~�[�m�����{�́u�����v�𒅂ēo�ꂷ��B���̓��{�̍��Ղ��ǂ����邩�B�����A�x�X�g�Z���[�ƂȂ����̂��A���Z�����E�t�H���E�c�B�[�O���[�E�E���g�E�N���b�v�n�E�[���̏����u�A�W�A�̃o�j�[�[�P�v�ł���B�^�C�Ŋ����R�c��������l���ɂ��������ł���B�t�H���E�c�B�[�O���[�̏����͗����̈���ɂ悭�������ꂽ�l�C���ڂɂȂ��Ă����B���ꂪ���[�c�@���g�̃I�y���u���J�v�ɑ傫�ȉe����^�����ƍl������B���q�^�~�[�m�̃��f���̈�l�͎R�c�����������̂ł���B�i�y�VBLOG�uUFO�A�K���^�̃V�����o���v2011�D9�D7���j
�@ �@���́A���ŋ߁A���钴�啨��Ƃ��u�^�~�[�m���{�̎�ߖ��v�ɐG��Ă���̂�m�����B���a�̋����E���{�����ł���B�^�C�g�����u���[�c�@���g�̔��y�v�B����͂��̋����[���Z�ҏ��������グ�����B
2013.04.15 (��) �b����`���N�̃}�X�^�[�Y�͓����15�ԃ^�C�K�[�̑�3�łŏI�����
 �@4��14���A�}�X�^�[�Y���������B�D���̓A�_���E�X�R�b�g�B�}�X�^�[�Y�ڂ�_���A���w���E�J�u�����Ƃ̃v���[�I�t�𐧂������X���鏟���������B�I�[�X�g�����A�͏��D���B�O���b�O�E�m�[�}���̌��ʂĂʖ������Ɏ��������̂ł���B
�@4��14���A�}�X�^�[�Y���������B�D���̓A�_���E�X�R�b�g�B�}�X�^�[�Y�ڂ�_���A���w���E�J�u�����Ƃ̃v���[�I�t�𐧂������X���鏟���������B�I�[�X�g�����A�͏��D���B�O���b�O�E�m�[�}���̌��ʂĂʖ������Ɏ��������̂ł���B�@����ɂ͖��Ղ̔����ɂ��ނ��̂ł͂Ȃ����A���ɂƂ��č��N�̃}�X�^�[�Y�́A����ځA�D�����{���̃^�C�K�[�E�E�b�Y��15�ԑ�3�łŏI����Ă����B�Ȃ��Ȃ�A���̓^���قNj����[�����ۂ͂Ȃ��������炾�B
�@2013�N4��12���A15�Ԃɂ������������^�C�K�[��E�b�Y�͗h�邬�Ȃ��v���[�Ŏ�ʂ�����Ă����B�����āA���̑�3�ŁB�c�苗��85���[�h�B���b�^���Ƃ����e���|�ł��s���ł��o���ꂽ�{�[���͈꒼���Ƀs���Ɍ������B�N�̖ڂɂ��i�C�X�E�V���b�g�Ɖf��������A�{�[���͒��ڃs���ɓ�����A�����悭�قڒ��p�������Ɍ�����ς��A�����ƌ����ԂɃO���[��������������r�ɗ����Ă��܂����̂ł���B����̒�����K�v���́u�s���ɓ������Ă��Ȃ���A�o�[�f�B�[�m���̒n�_�Ɏ~�܂��Ă����v�ƒf���������A�i�C�X��V���b�g�����ʂ͒r�B�^�C�K�[�͑ł��������ƂɂȂ����B���̏��u�Ŗ�肪�N�����̂ł���B
�@���̃P�[�X�ł́A4�ʂ�̕��@������i�S���t�K��26�|�P���j�B
�@�@ �r�̒��̃{�[�������̂܂ܑłi�����j
�@�A �r�ɗ������ӏ�����1�N���u�����O�X�ȓ��Ńs���ɋ߂Â��Ȃ��ʒu�Ƀh���b�v1�Ŕ��ɂđł�
�@�B �r�ɗ������ӏ��ƃs�������Ԍ������Ƀh���b�v��1�Ŕ��őł�
�@�C �O�ł����ӏ�������Ȃ��߂��Ƀh���b�v��1�Ŕ��őł�
�@�^�C�K�[�́A�r�܂ōs���ď��m�F�A��3�ł�ł����Ƃ���ɖ߂�A�O�̃{�[���̈ʒu����Q���[�h�t�߂Ƀh���b�v��1�Ŕ���������5�łƂ��đł����B�{�[���͌����Ƀs�����Ɋ��A������Ȃ�1�p�b�g�Œ��߁A���̃z�[����6�Ńz�[���A�E�g�����B
 �@���Ă��̏��u�̉�����肾�����̂��H �r��������Ԃ����i�K�Ň@�ƇA�͕s�̗p�B�����A�B��I�̂Ȃ�A�{�[�����r�ɗ������_�ƃs�������ԃ��C������ǂ̈ʒu����ł��\��Ȃ������B�Ƃ��낪�^�C�K�[�͑O�ł����ꏊ�ɖ߂����̂�����C��I���ƂɂȂ�B�Ȃ�ΑO�Ń{�[���ʒu�́g����Ȃ��߂��h�Ƀh���b�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����2���[�h�قnj���Ƀh���b�v���đł����B����́g����Ȃ��߂��h�Ƃ͊Ř�Ȃ��B���������Ă���́u�돊����̃v���[�v�ł���2�Ŕ��B���̃z�[���̐������Ő��́u8�v�ƂȂ�B�^�C�K�[�͂�����u6�v�Ə����ăX�R�A��o�����̂����畴����Ȃ��ߏ��\���B���炩�Ɏ��i�Ȃ̂ł���B
�@���Ă��̏��u�̉�����肾�����̂��H �r��������Ԃ����i�K�Ň@�ƇA�͕s�̗p�B�����A�B��I�̂Ȃ�A�{�[�����r�ɗ������_�ƃs�������ԃ��C������ǂ̈ʒu����ł��\��Ȃ������B�Ƃ��낪�^�C�K�[�͑O�ł����ꏊ�ɖ߂����̂�����C��I���ƂɂȂ�B�Ȃ�ΑO�Ń{�[���ʒu�́g����Ȃ��߂��h�Ƀh���b�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����2���[�h�قnj���Ƀh���b�v���đł����B����́g����Ȃ��߂��h�Ƃ͊Ř�Ȃ��B���������Ă���́u�돊����̃v���[�v�ł���2�Ŕ��B���̃z�[���̐������Ő��́u8�v�ƂȂ�B�^�C�K�[�͂�����u6�v�Ə����ăX�R�A��o�����̂����畴����Ȃ��ߏ��\���B���炩�Ɏ��i�Ȃ̂ł���B�@ �@�^�C�K�[�̈ӎ����ǂ��������̂��𐄑����Ă݂�B�ł������ɂ����āA�^�C�K�[�͇B�ƇC�����������B�����A�O�ʼnӏ�����̑ł������Ȃ̂�����A�C��I��ł���͂��Ȃ̂ɁA�u����Ȃ�ǂ��܂ʼn������Ă������v�B�ƍ������Ă��܂����B������A���̓��̋��Z�I����̋L�҉�ŁA�u2���[�h�������ł����v�Ɓi�܂��~�X�ɋC�Â����Ɂj�������Ă���B�e���r�ɂ͑O�ł̃e�B�{�b�g�Ղ��͂�����Ɖf���Ă����B��������������҂���u�돊����̃v���[�ł́H�v�Ƃ̈ӌ������X�͂����Ƃ����B�����v���������p���ɂ͋C�Â��Ă��Ȃ��B�������ς���Ȃ���������Ă������B
�@�ł́A�u�}�X�^�[�Y�ψ���v�͂ǂ��������u����������E�E�E�E�E�����́u���Ȃ��v�Ƃ��ăX�R�A�����̂܂ܔF�߂锭���������B�Ƃ��낪�����A�u�돊����̃v���[�ɊY�����邽�߁A15�ԃz�[���̃X�R�A��2�Ŕ�������8�Ƃ���v�ƑO����|�����B�Ȃ�A�u�i�ߏ��\���ɂ��j���i�ł͂Ȃ����H�v�Ƃ̋^��ɑ��ẮA�u������X�R�A��o�O�Ɉψ�����Y�v���[�ɂ��āw�����x�ƔF�����Ă��肻�̌�ψ���ْ̍肪�ύX�ɂȂ������̂ł��邩��A�X�R�A��L�ɂ͓�����Ȃ��B����́w�S���t�K��33�|7�F�ψ�������ȑ[�u�Ɣ��f�����ꍇ�͋��Z���i�̔���Ə�������y�����邱�Ƃ��o����x�ɑ����čْ肵�����̂ł���v�Ɛ��������B�S���t�K��33�|7�́A2011�N�ɐ��肳�ꂽ��r�I�V�������̂ŁA�n�����g���ْ�ƌĂԂ������B
�@����͈ꌩ���ɓK���Ă���悤�����f���ĈႤ�B�������ɂ������̂́A�u�X�R�A��o�O�ɐ����ƔF�肵���v�Ƃ����ψ���̌������ł���B���E�ō�������i�鋣�Z�ψ����A�N�����Ă��u�돊����̃v���[�v�������łȂ��ƊŘ��Ƃ͐�ɂ��肦�Ȃ��B����ł������Ă����������̂Ȃ�A�O���Ɂu�����v�Ƃ������Ƃ������Ɂu�s���v�ƕς�������Ƃւ̂͂�����Ƃ����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�������������u�^���v�͂������E�E�E�E�E�^�C�K�[�́u�돊����̃v���[�Ƃ͔��o���v�킸��15�ԃz�[���̃X�R�A���U�Ƃ��ăX�R�A�J�[�h���o�����v�B���̂Ƃ��u�ψ���v�͉����C�Â��Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪���̓������҂���^��̐����͂����B�u�ψ���v�͑����m�F����B���炩�Ɂu�돊����̃v���[�v�Ɣ����A2�Ŕ���8�ł���B�^�C�K�[��6�Ƃ��ăX�R�A�J�[�h���o�ς݂Ȃ̂�����A�X�R�A�ߏ��\���Ŏ��i�ł���B��ρI�����ǂ�����I�H
�@�����Ŏ�����[�u���A�u�O���͈ψ�������Ƃ����̂�����I��ɍ߂͂Ȃ��v�Ƃ����X�g�[���[��肾�����B���ꂪ���U�Ȃ͖̂��炩�ł���B�J��Ԃ����A���̏�ʂ������āu�돊����̃v���[�v�łȂ��Ƃ��鋣�Z�ψ��́u�}�X�^�[�Y�ψ���v�̒��ɂ͈�l�����Ȃ��͂������炾�B�u�ψ���v�͎���̕s��ۂɂ��ă^�C�K�[���~�����̂ł���B�Ȃ�����Ȃ��Ƃ����āH ����͌��킸�����Ȃ��B���ْ̍�ɑ��I��̒��ɋ^��̐����オ�����Ƃ������A���R���낤�B�{�l�����āg�ψ���ْ�͕s���h�Ƃ����ɔF�������͂��ł���B����ȋC������������܂܂̂Q���Ԃ́A�t�ɐh�������ɈႢ�Ȃ��B���̂悤�Ȏv�f���������̎��Ȃ���ْ�́A�Ђ��Ă͑I����X�|�C��������̎���i�߂邱�Ƃ��A�ψ���͈Ȃ��Ė����ׂ��ł���B
�@�u�}�X�^�[�Y�ψ���v�͂܂��A�����ЂƂ̃~�X��Ƃ��Ă����B����́A����o�ꎑ�i�����Ă��Ȃ��ΐ�ɂ����҂������Ƃł���B�}�X�^�[�Y�͏��ҋ��Z�ł��邩�炵�āA��Î҂����߂��̂����炢������Ȃ����Ƃ���ӌ��������B�������͔[���ł��Ȃ��B����܂��v�f�������������ŏI�I�ɑI����_���ɂ���B�ΐ���A��������ނ��邭�炢�̋C�T���Ȃ��ƍ���̑听�͖]�߂Ȃ����낤�B
�@IOC�̃��X�����O�O���AWBC�A�����J���\�̉^�c�A�告�o�������̕��A�A���{�_���A���̋�����A�ȂǂȂǁA�����̃X�|�[�c�E�͂ǂ������������B������o�ς��s���s�������s�s�œ����Ă��Ă��A�X�|�[�c���炢�͌����ł��肽���ł͂Ȃ����B�}�X�^�[�Y���I�����s�b�N���A���܂�ӂ����Ă���ƁA���̂��������ۂ������ꂿ�Ⴂ�܂���B
2013.04.10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��10�`���[�c�@���g�ɍ��R�E�߂��~�ՁI
�����C�o������̓������@�u�����A�A�}�f�E�X�A��ς���B�����̓}���l�����̌��ꂪ�V��������Ă�������s���Ă������ˁB���́w�t�@�S�b�g�����J�X�p�[�A�܂��͖��@�̃c�B�^�[�x�́A�w���J�x�Ɠ����w�W���j�X�^���x���l�^�ȂB����z���ꂽ���Ă킯���B�ł��܂��A����Ȃ��Ƃ͂��݂��l�A�ʂɂǂ����Ă��Ƃ͂Ȃ����A���������N�Ƃ��ŏ��̎d���ɃP�`���t�����Ⴉ�Ȃ��ˁv
�@���������Ȃ���A�V�J�l�[�_�[���u���J�v��Ȓ��̃��[�c�@���g�̎d����ɔ�э���ł����̂́A1791�N6��8���A�^�钆�̂��Ƃ������B
�@�}���l�����̓��I�|���g������̃{�X�ŁA�A���E�f�A�E���B�[�f�������V�J�l�[�_�[�Ƃ̓E�B�[���̑�O��������郉�C�o���ł���B��N�O�ɖS���Ȃ����c�郈�[�[�t2���i1741�|1790�j�́A�h�C�c��ɂ���O�I�y�����W���O�V���s�[���̐U���ɏ��͂�ɂ��܂Ȃ������B���̂������������āA��̌���͎v���������s�����s�����Ƃ��ł����̂ł���B
�@�V�J�l�[�_�[���炱�̘b�������[�c�@���g�́A6��11���A���I�|���g������ɑ����^�B�ό���A�o�[�f���ŗ×{���̍ȃR���X�^���c�F�Ɏ莆�������B�u�Ȃ�Ƃ����C���o�����ƁA�V�����I�y���w�t�@�S�b�g�����x�����Ɍ���ɏo���������A�����͑��X��������ŁA�����������̂���Ȃ��v�E�E�E�E�E����Ⴛ�����낤�A�V�˂����g��Ȓ��̌���Ɣ�ׂĂ���̂ł���B�����������̂ł���͂����Ȃ��B
�@�Ƃ͂����A����̊S���͍�i�̌|�p�I���l�ł͂Ȃ��B�����邩�ۂ��ł���B����͍D�X�^�[�g����̌��R�~���L�C���B���̂��߂ɂ͏o���邾���̎�͑ł��Ă������ق��������B�����������瑊��ɕt��������B
�@6��12���̖��J�����B��l�͍쌀�ɂ��ċ��c�B�u�A�}�f�E�X�A���炪�w���J�x�́A�w�t�@�S�b�g�����x�ƃl�^�͓����ł��A�t���[���C�\���̗v�f�����Ȃ�l�ߍ��肵������A�܂��A�����������ʉ��͂ł��Ă���B�ł��A�O�̂��߂����ꖡ�~�����C�������B���ꂪ������Α哖����͊ԈႢ�Ȃ����v�ƃV�J�l�[�_�[�B�u�������ˁA�l�̐̂̍�i�w�G�W�v�g���^�[���X�x����C�V�X���I�V���X�M��������Ă邵�A�N�̃n���K���[�y�Y�̃y���V���v�z�����܂����ƍ������Ă��邩��ˁB�V�J�l�[�_�[�A���̏�N���~�����̂͋���ȃC���p�N�g�����イ����ȁB��ڂŕ����鍷�ʉ��ˁB�ł��A�������Ȃ��Ȃ��̓�肾�v���[�c�@���g�A���Ă邽�߂ɂ͂����^���ł���B����܂ł��A�u�C�h���l�I�v�ł͋r�{�����x�������������������A�u�t�B�K���̌����v�͎����̂��ߗl�X�ȉ���p���Ă���B
�@�|�C���g�́u���ߎ�v�ł���B�����ŁA�V�J�l�[�_�[�A�uOK�A�A�}�f�E�X�A����ɂ͂������������������B���Ƃ́A���ߎ�B����͌N���l���Ă���B����Ȃ���ˁv�A���������āA���[�c�@���g�̌������������B
���������{�̉��q�Ɂ�
 �@1791�N�V���A���[�c�@���g�́A���ȂƑ�2���`���������āu���J�v�̂قƂ�ǂ������グ�Ă����B����ȃ��[�c�@���g�ɕʂ̃I�y���̒���������B�u�c��e�B�g�X�̎��߁v�ł���B����́A���^�X�^�[�W�I�̑�{�ɂȂ�I�y����Z���A�ŁA�O�N���ʂ����I�[�X�g���A�c�郌�I�|���g2���i1747�|1792�j�����������˂�{�w�~�A�̎�s�v���n�ł̑Պ����ɗՂލۂ̏j�����Ƃ��Ĉ˗����ꂽ���́B���[�c�@���g�́u���J�v�𒆒f���Ă���Ɏ�肩����B8��25���A�ނ́A�ȃR���X�^���c�F�ƒ�q�̃W���X�}�C���[���āA�v���n�Ɍ����ďo���A�̌��u�c��e�B�g�X�̎��߁v�́A9��6���A��������Ŗ����������ꂽ�B���̃I�y���A�����ɂ͎����͂�18�������������Ă��Ȃ��B�W���X�}�C���[�Ƀ��`�^�e�B�[���H�����������Ƃ͂����A����͋��ٓI�ȃX�s�[�h�ł���B�����ɂ����[�c�@���g�̕��O�ꂽ�V�ːU�肪�`����B
�@1791�N�V���A���[�c�@���g�́A���ȂƑ�2���`���������āu���J�v�̂قƂ�ǂ������グ�Ă����B����ȃ��[�c�@���g�ɕʂ̃I�y���̒���������B�u�c��e�B�g�X�̎��߁v�ł���B����́A���^�X�^�[�W�I�̑�{�ɂȂ�I�y����Z���A�ŁA�O�N���ʂ����I�[�X�g���A�c�郌�I�|���g2���i1747�|1792�j�����������˂�{�w�~�A�̎�s�v���n�ł̑Պ����ɗՂލۂ̏j�����Ƃ��Ĉ˗����ꂽ���́B���[�c�@���g�́u���J�v�𒆒f���Ă���Ɏ�肩����B8��25���A�ނ́A�ȃR���X�^���c�F�ƒ�q�̃W���X�}�C���[���āA�v���n�Ɍ����ďo���A�̌��u�c��e�B�g�X�̎��߁v�́A9��6���A��������Ŗ����������ꂽ�B���̃I�y���A�����ɂ͎����͂�18�������������Ă��Ȃ��B�W���X�}�C���[�Ƀ��`�^�e�B�[���H�����������Ƃ͂����A����͋��ٓI�ȃX�s�[�h�ł���B�����ɂ����[�c�@���g�̕��O�ꂽ�V�ːU�肪�`����B�@����͋I��1���I�̃��[�}�B���݂̍c��e�B�g�X�i79�|81�݈ʁj�ܑ̔I�т����鈤�����B�^���̈��Y����e�B�g�X�͐M�����镔�����疽��_���邪�A����Ȏ��߂ł��̖d���������B�܂���N���������F�X�r�A�X�ΎR�̑啬�ɔ������Ƃ̈�厖�ɂ��K�ȏ��u���Ƃ�ȂǁA���̎�r�͖��N�̖��ɒp���Ȃ����̂������B
�@��i�̕]���́A���N�O���n�ő哖�����������u�t�B�K���̌����v��u�h���E�W�����@���j�v�ɂ͔䂷�ׂ����Ȃ��������A�g�e�B�g�X�̎��߁h�̓��[�c�@���g�̔]���ɋ������܂�邱�ƂɂȂ����B
�@�v���n�ł̎d�����I�������[�c�@���g�́A9���̔��A�E�B�[���ւ̋A�H�ɂ��B�����A���Ƃ́u���J�v�B���͂��̏h��ł���B���[�c�@���g�́A�V�J�l�[�_�[��������ꂽ�u����Ȍ��ߎ�v��Y�ꂽ���Ƃ͂Ȃ������B�����Ă��ɂ��ꂪ�M�����̂��B
�u�c��e�B�g�X�̎��߁v�͂悭�������B������Ȃ��������A����͈�����i����Ȃ��B���������ƕ]�������������邾�낤�B�Ȃ�Ƃ����Ă��e�B�g�X�̐l�i�̑f���炵���B���A���^�X�^�[�W�I���B����̌��I�W�J�̒��A�e�B�g�X�̍����Ȑ��_�����ݏo��B���Ɍ����Ȏ�r���B�E�E�E�E�E�҂Ă�I ���^�X�^�[�W�I�Ƃ����A�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v���ނ̑�{�������ȁB���̂Ƃ��́A�~�q���G���E�n�C�h���ɑ��k���������B�ނ͍��������̏@�����������Ă��ꂽ�B�����A����́u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�Ƃ������B�e�B�g�X�ƃe�B�g�X���B���R���B������H�e�B�g�X�A�E�R���h�m�B�E�R���h�m���āA�m�����{�̓a�l�������ȁB���R�E�߁A���{�l���E�E�E�E�E����͎a�V���B�p�~�[�m����{�l�ɂ�����ǂ����낤�B����͂����A�C�f�B�A���v�i���̂Ƃ��܂��^�~�[�m�̓p�~�[�m�������I�j
 �@���[�c�@���g�̓��̒��ŁA�u���J�v�Ɓu�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�����т����B���[�c�@���g�ɍ��R�E�߂��~�Ղ��A����̉��q�Ɏp��ς����̂ł���B�ނ͑����V�J�l�[�_�[�ɘb���B��������V�J�l�[�_�[�A�u�A�}�f�E�X�A�����̓O�b�h�E�A�C�f�B�A���B�悭�M�����ˁB�E�R���h�m�����Ȃ��m��Ȃ����A���{�l�Ȃ�C���p�N�g�\������Ȃ����B�ڐV�������_��I���B���I�|���g�����ꂶ��A�v�������낤�B���łɂǂ����B�p�~�[�m���^�~�[�m�ɕς�����B�C�V�X�Ɏd����]�҂̓p�~�[�m�����ǁA�����̓^�~�[�m�ɂ��悤�B�e�B�g�X�ƃe�B�g�X�����瓪������T�������B�^�~�[�m�̕�����C���������ˁB�K�R�I�Ƀ^�~�[�i�̓p�~�[�i���ȁB����A�����͋��B��q�b�g�ԈႢ�Ȃ����v�A�����������q���^�~�[�m�ʼn������p�~�[�i�B�^�~�[�m�́u���{�̎�߂𒅂����q�v�ƌ��߂�ꂽ�̂ł���B
�@���[�c�@���g�̓��̒��ŁA�u���J�v�Ɓu�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�����т����B���[�c�@���g�ɍ��R�E�߂��~�Ղ��A����̉��q�Ɏp��ς����̂ł���B�ނ͑����V�J�l�[�_�[�ɘb���B��������V�J�l�[�_�[�A�u�A�}�f�E�X�A�����̓O�b�h�E�A�C�f�B�A���B�悭�M�����ˁB�E�R���h�m�����Ȃ��m��Ȃ����A���{�l�Ȃ�C���p�N�g�\������Ȃ����B�ڐV�������_��I���B���I�|���g�����ꂶ��A�v�������낤�B���łɂǂ����B�p�~�[�m���^�~�[�m�ɕς�����B�C�V�X�Ɏd����]�҂̓p�~�[�m�����ǁA�����̓^�~�[�m�ɂ��悤�B�e�B�g�X�ƃe�B�g�X�����瓪������T�������B�^�~�[�m�̕�����C���������ˁB�K�R�I�Ƀ^�~�[�i�̓p�~�[�i���ȁB����A�����͋��B��q�b�g�ԈႢ�Ȃ����v�A�����������q���^�~�[�m�ʼn������p�~�[�i�B�^�~�[�m�́u���{�̎�߂𒅂����q�v�ƌ��߂�ꂽ�̂ł���B�@�����āA�V�J�l�[�_�[�́u���J�v�`���̃g�����ɂ����������B
TAMINO kommt in einem prachtigen javonischen Jagdkleide rechts von einem Felsen herunter, mit einem Bogen,aber ohne Pfeil�Geine Schlange verfolgt ihn�D����9�����{�A�����ɂ͐������c�������������B
�i�^�~�[�m�͂���т₩�ȓ��{�̎�߂ɐg���݊�̌�납��p�������B��ɂ͋|��������
���邪��͂Ȃ��B�����āA��납��ւ��ǂ������Ă���j
���Q�l������
�u���[�c�@���g�v���C�i�[�h�E�\���������A�Έ�G��i�V���فj
�u���[�c�@���g�Ƃ̎U���v�A�����E�Q�I�����A�����p�Y��i�����Ёj
�u���J�`�鋳�I�y���v�W���b�N�E�V���C�G���A�����p�Y ����N����i�����Ёj
�u�V�J�l�[�_�[�v�����i���}�Ёj
�u���[�c�@���g�̎莆�v�����p�Y�i���w�فj
�u���[�c�@���g�̔��y�v���{�������i���t���Ɂj
2013.03.25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��9�`�E�B�[���ł̍ĉ�Ɓu���J�v�ւ̒���
[�E�B�[���ł̍ĉ�]�@���[�c�@���g���A�U���c�u���N�ŃV�J�l�[�_�[�ƕʂꂽ1780�N11��5���ȍ~�A��l�����ĉ�����͒肩�ł͂Ȃ��B
�@���[�c�@���g��1781�N5���A�E�B�[���ɒ�Z���邪�A��1782�N7���A�W���O�V���s�[���u��{����̗U���v���㉉�B�N��12����̏㉉���d�˂�q�b�g�ƂȂ����B���̕]���������V�J�l�[�_�[�́A1784�N11���A�P�����e���匀��ł�������グ���B4�N�O�A�ĉ�𐾂���������l�Ȃ�A���̎��_�ʼn���Ă����\���͑傫���Ǝv���B
 �@�V�J�l�[�_�[��1789�N6���A�E�B�[���̃t���C�n�E�X����i���A���E�f�A�E�E�B�[������j�ɕ����߂����B�����ō������Ă����O�ȃG���I�m�[���������S���������߁A���H��ʊ�ŏ�荞��ł���߂����i�D�ł���B����ɂ̓G���I�m�[�����Ăі߂����Ƃ��B������ɂ��Ă��A�O��̃t�����`���C�Y����ɓ��ꂽ�V�J�l�[�_�[�́A�G�l���M�b�V���Ɋ�������B���X�̎ŋ��ɍ������āA�u�d���̉��I�x�����v�u���҂̐A�܂��͖��@�̓��v�Ȃǂ̃����w���E�I�y�����㉉�����B����炪�A����ׂ��u���J�v�Ɍq�����Ă䂭�B�V�J�l�[�_�[�A���̂Ƃ�38�B�ːl���l���ő�̏[�������}�����̂ł���B
�@�V�J�l�[�_�[��1789�N6���A�E�B�[���̃t���C�n�E�X����i���A���E�f�A�E�E�B�[������j�ɕ����߂����B�����ō������Ă����O�ȃG���I�m�[���������S���������߁A���H��ʊ�ŏ�荞��ł���߂����i�D�ł���B����ɂ̓G���I�m�[�����Ăі߂����Ƃ��B������ɂ��Ă��A�O��̃t�����`���C�Y����ɓ��ꂽ�V�J�l�[�_�[�́A�G�l���M�b�V���Ɋ�������B���X�̎ŋ��ɍ������āA�u�d���̉��I�x�����v�u���҂̐A�܂��͖��@�̓��v�Ȃǂ̃����w���E�I�y�����㉉�����B����炪�A����ׂ��u���J�v�Ɍq�����Ă䂭�B�V�J�l�[�_�[�A���̂Ƃ�38�B�ːl���l���ő�̏[�������}�����̂ł���B�@����̃��[�c�@���g�A���̍��͌o�ϓI�ɍň����ł���B�Ƃɂ����������Ȃ��B�����͑�������̂����A�Ȃ����؋��Ńs�[�s�[���Ă���i���{�������u���[�c�@���g�̔��y�v�ɂ́u1790�N1������10���܂ł̃��[�c�@���g�̎؋��͑��z1425�O���f���ɂ��B�����v�Ƃ���j�B���݂�1789�N�̔N���́i���C�i�[�h�E�\�������̎��Z�ɂ��Ɓj1483�|2158�O���f���ŁA���{�~�Ɋ��Z�����297���~�\432���~�ł���B����͈�Ƃ����ʂɐ������Ă䂭�ɂ͏\����������z�ł���B�Ȃ̂ɂȂ��A�����Ȃ鑽�z�̎؋������˂Ȃ�Ȃ��������H
 �@���y�w�҂͋ꂵ�܂���ɍȃR���X�^���c�F�̘Q��̂����ɂ����B�g�R���X�^���c�F���Ȑ��h�ł���B�ł��A����͔��������������Ă��Ȃ��B����́A���[�c�@���g�̎���ɂ�����ޏ��̐�����r�̌��������猾����̂ł���B�����̍�i���q�i����ɂ͏�v�j�ɖ����Ċ��������A�y����A�{��ƌ����Ĉ⑰�N����E�E�E�E�E�Ȃǂ��Ď؋���ԍς��~������B���������ɉ��h�����J�ƁA���h�l�i�f���}�[�N�l�̊O�����E�Q�I���N�E�j�R���E�X�E�t�H���E�j�b�Z���j�ƍč����ă��[�c�@���g�̓`�L����������B���ꂪ���[�c�@���g���̖{�i�I�`�L�ƂȂ����B�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA��肭����ł������������̕���B����͊ԈႢ�Ȃ��e�̌����B�R���X�^���c�F�̕�}���A�E�`�F�c�B�[���A�E�E�F�[�o�[�́A���h���̏����Ŗ������[�c�@���g�ɉł��������{�l������ł���B
�@���y�w�҂͋ꂵ�܂���ɍȃR���X�^���c�F�̘Q��̂����ɂ����B�g�R���X�^���c�F���Ȑ��h�ł���B�ł��A����͔��������������Ă��Ȃ��B����́A���[�c�@���g�̎���ɂ�����ޏ��̐�����r�̌��������猾����̂ł���B�����̍�i���q�i����ɂ͏�v�j�ɖ����Ċ��������A�y����A�{��ƌ����Ĉ⑰�N����E�E�E�E�E�Ȃǂ��Ď؋���ԍς��~������B���������ɉ��h�����J�ƁA���h�l�i�f���}�[�N�l�̊O�����E�Q�I���N�E�j�R���E�X�E�t�H���E�j�b�Z���j�ƍč����ă��[�c�@���g�̓`�L����������B���ꂪ���[�c�@���g���̖{�i�I�`�L�ƂȂ����B�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA��肭����ł������������̕���B����͊ԈႢ�Ȃ��e�̌����B�R���X�^���c�F�̕�}���A�E�`�F�c�B�[���A�E�E�F�[�o�[�́A���h���̏����Ŗ������[�c�@���g�ɉł��������{�l������ł���B�@�R���X�^���c�F���Ȑ��̍����͋��K���o�̂Ȃ��ƕ��C�ł���B�O�҂͓I�O���҂͂��݂��l�Ƃ������Ƃ��낾�낤�B���[�c�@���g��Ƃɂ��������������̂́A�g�݂��̎��R�z������e�F�����������Ɓh�Ƃ����Ȃ����Ȃ��B����ŁA���[�c�@���g�u�q������D�����v�����邪�A����͂܂��ʂ̋@��ɁB
�@ ���[�c�@���g�̓E�B�[���ɒ�Z���Ă����B�V�J�l�[�_�[�̓E�B�[���𒆐S�Ɋ������₪�Ė{���n�Ƃ����B��������l�̓t���[���C�\���ł���A���˂Ă���ӋC�����������̓��m�ł���B���݂��u���J�v�ɒ��肷��܂łɁA�����C�\���̃��b�W�ŏo��`�����X�͂�����ł��������͂��ł���B�������̋L�^���Ȃ������ł���B
[���J�ɒ���]
�@���ċ��������߂��V�J�l�[�_�[�́A���N�̖����[�c�@���g�Ƃ̋�����Ƃɒ��肷��B1791�N3���A���������ă��[�c�@���g�Ɂu���J�v�̍�Ȃ��˗������B���[�c�@���g�͑������B���K�ʁE�|�p�ʂ��炱��͓��R�̐���s���ł���B��{�͖��_�V�J�l�[�_�[���������B�����͂Ƃ����A���ꂼ�܂��ɋ�����Ƃ������B��l�͂��݂��̎����ɗe�͂Ȃ����o�����Ȃ���A�Ƃ͂����A�a�₩�ȃ��[�h�Ŏd����i�߂Ă������B����Ȏd���Ԃ���������͂������u�V�J�l�[�_�[�v������p����B
�V�J�l�[�_�[�w�҃R�����c�B���X�L�[�ɂ��A�ӂ���̂��Ƃ�𖾂���������1���̃������c����Ă���R�B
�u�E�H���t�K���O�ց@�������N�̃p�E�p�E�p�𑗂�Ԃ��B���Ƀs�b�^���̋Ȃ���B�������͂Ȃ����낤�B���ӗ�́\�\�ʼn���@�V�J�l�[�_�[�v
����́A���[�c�@���g���v���n�ɗ������O�A9���̂��Ƃ������B�ӂ���͏�ʂ��Ƃɋ������č\�����Ă������̂ł����āA���y���قƂ�ǍŌ�܂ł����Ă������Ƃ��A�ŋ��̓W�J����������l��������Ă����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�܂肱�̍����̊�ڂ́A��ʏ�ʂ������Ɍ��h�����邩�A�ł����āA�S�̂̎v�z�ł͂Ȃ��B
 �@��́\�\�Ƃ́A�V�J�l�[�_�[�����[�c�@���g�̂��߂Ƀt���C�n�E�X����̕~�n���ɗp�ӂ����d����̂��Ƃ��낤�B���݂̓U���c�u���N�Ɉړ]����Ă���ʏ́u���J�����v�ł���B�ȃR���X�^���c�F�́A���̂��둫�̓����̂��߃I�[�X�g���A�̉���n�o�[�f���Ő×{���������B�V�J�l�[�_�[�͈�l�c���ꂽ���[�c�@���g���d���ɏW���ł���悤�ɖ؍��̏��������Ă������̂ł���B�V�J�l�[�_�[�̋C���̓�����������낤�Ƃ������̂��B�A�����E�Q�I���͂��̒����u���[�c�@���g�Ƃ̎U���vPromenades Avec Mozart�̒��ŁA�u���J�����v���u���̊������̍��̉��ɐX�̍��肳���z������ł������낤�B�v���ɔނ́w���J�x�Ƃ�����i�ɂ��̍�������߂Ă����ɂ������Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B
�@��́\�\�Ƃ́A�V�J�l�[�_�[�����[�c�@���g�̂��߂Ƀt���C�n�E�X����̕~�n���ɗp�ӂ����d����̂��Ƃ��낤�B���݂̓U���c�u���N�Ɉړ]����Ă���ʏ́u���J�����v�ł���B�ȃR���X�^���c�F�́A���̂��둫�̓����̂��߃I�[�X�g���A�̉���n�o�[�f���Ő×{���������B�V�J�l�[�_�[�͈�l�c���ꂽ���[�c�@���g���d���ɏW���ł���悤�ɖ؍��̏��������Ă������̂ł���B�V�J�l�[�_�[�̋C���̓�����������낤�Ƃ������̂��B�A�����E�Q�I���͂��̒����u���[�c�@���g�Ƃ̎U���vPromenades Avec Mozart�̒��ŁA�u���J�����v���u���̊������̍��̉��ɐX�̍��肳���z������ł������낤�B�v���ɔނ́w���J�x�Ƃ�����i�ɂ��̍�������߂Ă����ɂ������Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B[���J�̌��{]
�@�V�J�l�[�_�[���y��ɂ����̂́A1789�N�ɏ㉉�����u�d���̉��I�x�����v�ł���B����͓����̒����Ȏ��l���B�[�����g�i1733�|1813�j���Ҏ[�����u�W���j�X�^���v�Ƃ�������W�̒��ɂ������B�I�x�����������@�̊p�J�́u���J�v�Ɍq����B�u�W���j�X�^���v�Ɏ��߂��Ă���������̕���A���[�x�X�L���g��́u�����A���邢�͖��J�v���d�v�ł���B�V�J�l�[�_�[�͂��̕���̒��́A�����̔�������l�����~�o����V�`���G�[�V�������u���J�v�ɓK�p�����B
�@������[�c�@���g�͂ǂ����B���Ă����悤�ɁA�ނ��r�{���ɂ͑傢�ɊS�������Ă����B�ނ̓��ɕ����̂�1773�N�ɍ��1789�N�ɉ���������u�G�W�v�g���^�[���X�v�ł���B��������̓G�W�v�g�Ƃ�������ƃt���[���C�\���F���q�����Ă䂭�B
�@������x��{���ł���ƁA���[�c�@���g�͑����ȍ��Ɏ��|�������B�Ƃ��낪6���A��{�ύX��]�V�Ȃ������鎖�Ԃ���������B���āA���[�c�@���g�ƃV�J�l�[�_�[�͂���ɂǂ��Ή������̂��B
���Q�l������
�u���[�c�@���g�v���C�i�[�h�E�\���������A�Έ�G��i�V���فj
�u���[�c�@���g�Ƃ̎U���v�A�����E�Q�I�����A�����p�Y��i�����Ёj
�u���J�`�鋳�I�y���v�W���b�N�E�V���C�G���A�����p�Y ����N����i�����Ёj
�u�V�J�l�[�_�[�v�����i���}�Ёj
�u���[�c�@���g�̔��y�v�i�Z�ҏW�u���̌a�v���j���{�������i���t���Ɂj
2013.03.10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��8�`�t���[���C�\���ւ̓���
�@���[�c�@���g���V�J�l�[�_�[���t���[���C�\���ł���B���X�ӋC����������l�ł��邪�A���݂��t���[���C�\���ɂȂ������Ƃ����т�����苭�łȂ��̂ɂ����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�u���J�v���܂��Ƀt���[���C�\���E�I�y���Ȃ̂�����A�u�t���[���C�\���v�͏d�v�ȃL�C���[�h�Ƃ������ƂɂȂ�B[�t���[���C�\�����ĂȂɁH]
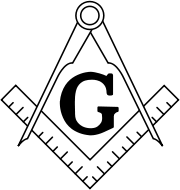 �@��ʂɃt���[���C�\��Freemason�Ƃ����Ή���̂��Ƃł���A���̑g�D�̓t���[���C�\�����[Freemasonry�Ƃ������A�ȉ��l�@����ɓ�����T�O�I�ď̂ɂ��Ă��u�t���[���C�\���v�Ƃ����Ă��������B
�@��ʂɃt���[���C�\��Freemason�Ƃ����Ή���̂��Ƃł���A���̑g�D�̓t���[���C�\�����[Freemasonry�Ƃ������A�ȉ��l�@����ɓ�����T�O�I�ď̂ɂ��Ă��u�t���[���C�\���v�Ƃ����Ă��������B�@�t���[���C�\�����g�D�I�ɂ�������Ƃ����`�ɂȂ����̂�18���I�̃C�M���X�ł���B1717�N6��24���A�����n�l�j���̓��ɁA�����h����4�̃��b�W�̓���g�D�Ƃ��ă����h���E�O�����h���b�W���ݗ����ꂽ�B���ꂪ�ߑ�t���[���C�\���̒a���ƂȂ����B
�@�u�ߑ�t���[���C�\���v�����Ɍq����ƍl��������j�I���ۂ́A���ؐ��ɒ��x�̍��͂���A���Ȃ葽��ɂ킽��B��������X������͎̂�|����O���̂ŁA�����ł͊Ȍ��ɗ���ɂƂǂ߂����B
�@�Ñ�G�W�v�g�A�M���V���A�y���V���̔鋳�I�W�c����͋V���̃X�^�C�����A�����́u�����R�m�c�v����͋R�m�����_���A15���I�ɋN�������u�o���\���c�v����͔鋳�I���i���A�����C�M���X�̐H�i�����I���C�\���j�g������́A���C�\����b�W�Ƃ����ď̂�s���̋K�͂��A�ߑ�t���[���C�\���Ɍq�������ƍl������B
�@�ߑ�t���[���C�\���Ƃ������̂��ꌾ�ŕ\���A�u�����̑��݂Ɛl�Ԃ̍��̕s�ł�M���A�F���Ɨϗ��Ɗw����d�āA���̗��O���邢�͋������V���ƃV���{���œ`����c�́v�Ƃ������ƂɂȂ낤�B
�@�t���[���C�\���̎v�z�I�o�b�N�{�[���́A�������[���b�p��Ȋ����Ă����u�[�֎�`�v�ł���B�[�֎�`�͉p���enlightenment�u�ÈłɌ��Ă�v�Ƃ����Ӗ��B���{���u�[�֎�`�v�ɂ͢���m�֖��ȏ�Ԃ��[����Ƃ������߂����Ă���B�u�ÈŁv���u���m�֖��v�����̐��̂��ƁB���������āA�u�[�ցv�Ƃ͋��̐��i�J�g���b�N�̋��`�𒌂Ƃ��钆���ȗ��̓`���I�Ȑ�Ύ�`�̐��j����̒E�p�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����̗͂�M���A���K�A���M�A�Ό�����J�����ꂽ�^�Ɏ��R�Ȑl�Ԓ��S��`��ڎw�����̂��B�Ƃ͂����A�t���[���C�\���ɂ͏@����r������l�����͂Ȃ��B�f���鐸�_�́u���R ���� �����v�ł���B�i���c�r�꒘�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�u�k�Ќ���V���Q�Ɓj�B
[���[�c�@���g����]
�@���[�c�@���g���t���[���C�\���ɓ�����̂�1784�N12��14���A�E�B�[���ɒ�Z���Ă���3�N�ڂ̔N���̂��ƁB���b�W���́u���P�v�ł���B������A����͓˔��I�ȏo�������������Ƃ��������ł͂Ȃ��B�ނ������܂ł̓�����H��ƁA�����ɂ͕K�R�Ƃ��������͂�����ƌ����Ă���B
�@ �@1772�N�A16�̃��[�c�@���g�́u�����A���Ȃ��J��vK148�Ƃ������A���A����Ȃ��Ă���B�u�N�ă��C�\���� �����ĉ̂� ���������n���̋��܂ŕ�������̂��v�Ǝn�܂�A����́u�����n�l�v���b�W�̏j�Ղ̂��߂���̂ł���B��1773�N�ɂ́A�g�r�[�A�X�E�t�H���E�Q�[�v���[��{�́u�G�W�v�g���^�[���X�v���������A�����������Ȃ����C�\�������i�u�N�����m�v1��31���Q�Ɓj�B
�@�u�G�W�v�g���^�[���X�v�̑�{��҃Q�[�v���[�j�݂̓t���[���C�\���ł��邪�A���[�c�@���g���o������t���[���C�\���͂��̂ق��ɂ���������B11�A����Ŝ�����V�R���̎��Â����Ă��ꂽ�I���~���b�c�i���`�F�R�j�̃��H���t��t�B�}���n�C���E�I�[�P�X�g���̎w���҃N���X�`�����E�J���i�r�q�B�v�t�@���c�I���̎��]���I�b�g�[�E�t�H���E�Q�~���Q���j�݁B�E�B�[����Z���ォ�琢�b�ɂȂ����t�@���E�X���B�[�e���j�݁A�N�����l�b�g�t�҂̃V���^�[�h���[�Ȃǂł���B
�@�킯�Ă��A�E�B�[���{��}���ْ��E�S�b�g�t���[�g�E�t�@���E�X���B�[�e���j���i1733�|1803�j�̓E�B�[������̃��[�c�@���g�ő�̉��l�ł���B1782�N4��10���̎莆�Ɂu�l�͖����j���X���B�[�e���j�݉Ƃɍs���܂����A�����ł̓o�b�n�ƃw���f���ȊO�͉��t����܂���B���͍��A�o�b�n�̃t�[�K�̊y�����W�߂Ă��܂��v�Ƃ���Ƃ���A���[�c�@���g�͖����j���A�X���B�[�e���Ƃ̃T�����ɓ���Z�����B�j�݂͌��O�����ŁA�d�����h�C�c�e�n�ɗ���������ۂɁA�o���b�N�̊y���𑊓����N�W���Ă����B���[�c�@���g�̓T�����Ŋy����ǂݒ������t���邱�Ƃɂ��A�o�b�n�ւ̑��w��[�߁A�Έʖ@�ɖ����������邱�Ƃ��ł����B���̉e�����F�Z�����ꂽ���Ȃ̈��Ƃ��āu���z�ȃj�Z���vK397������B��捂Ƃ�����̒��ɍ��M���ƌy���������悭�Z�������s�A�m�Ȃ̌���ł���B�܂��A�ӔN�̖���Ɍ����|���t�H�j�[�̌����������̃T�����Ŋw���Ƃ̎������낤�i�u���J�v���ȁA�u�W���s�^�[�����ȁv�̍ŏI�y�́A�u���N�C�G���v�́u�L���G�v�Ȃǁj�B
�@�j�݂͂܂��A���[�c�@���g�̗\�t��̂悫�����҂ɂ��Ďx���҂������B�ނ̗\�t��͑S������1784�N�̃V�[�Y���ɂ͉������173���𐔂������A1788�N�ɂ͂Ȃ��1���ɂȂ��Ă��܂��B���̞X�J�������ƂȂ��Ă��܂����킯�ł��邪�A�Ō��1���������Ȃ�ʃX���B�[�e���j�݂��̐l�������B����ɁA�ނ́A1791�N12��5���A���[�c�@���g�̎��ɂ����葒�V�̎�z���s�����}���N�X��n�ł̖����ɗ���������B
�@�A���g���E�V���^�[�h���[�i1753�|1812�j�͐e�F�i�����F�j�ł���B�V�˓I�ȃN�����l�b�g�t�҂ɂ��ăM�����u���[�B�r�����[�h��P�[�Q���V���^�b�g�i�㒌�Y�j�ȂǓq�����Ń��[�c�@���g���J���ɂ��Ă����Ƃ����B�J���ɂ���Ȃ�������[�c�@���g�͔ނƂ̌�F����߂Ȃ������B����ǂ��납�A��ѐ�̖��Ȃ�ނ̂��߂ɏ����Ă���B�N�����l�b�g�d�t��K581�⋦�t��K622�Ȃǂł���B
�@�E�B�[���Ŏ����������[�c�@���g�͎��R�i����]�ɔR���Ă����B���̍c�郈�[�[�t�̓t���[���C�\���Ɋ��e�Ȑ�����Ƃ����B�F�l�ɂ��t���[���C�\������������B���N���ォ�琢�E�����Ĉ炿�A����̍˔\��M���A���R�Ȑ��_��搉̂��郂�[�c�@���g���E�B�[���Ńt���[���C�\���ɓ�����͎̂��R�Ȑ���s���������낤�B��������������b�W�u���P�v�̃}�X�^�[�́A���ă}���n�C���Ő��b�ɂȂ����I�b�g�[�E�t�H���E�Q�~���Q���j�݂������B���r���X�E�����h���́u�����炭���[�c�@���g���ŏ��Ƀt���[���C�\���ɗU�����̂͂��̒j�݂������̂ł͂Ȃ����v�i�����V���u���[�c�@���g�v�Έ�G��j�Əq�ׂĂ���B
�@���[�c�@���g�͔M�S�ȉ���������B����͔ނ��A���b�W���ŃX�s�[�h���i���ʂ��������Ƃł����t������B�u�k��v�ʊK���X�^�[�g��3�������炸�Łu�E�l�v�ʊK�ɓ��B�A���̂P������ɂ́u�e���v�ʊK�ɂ܂ŏ��l�߂��B����ɁA1785�N�����Ƀn�C�h����3���ɂ͕����I�|�I���������Ă���B�����āA�t���[���C�\���̂��߂ɐ������̊y�Ȃ�������B�܂��ɖ͔͓I�ȉ���������Ƃ�����B
�@[�t���[���C�\���Ƃ��ẴV�J�l�[�_�[]
�@������V�J�l�[�_�[�͂ǂ�ȃt���[���C�\���������̂��H����ɂ��ẮA�W���b�N�E�V���C�G���u���J�`�鋳�I�y���v�i�����p�Y�E����N����A�����Ёj�����̂܂ܓ]�p����B
���[�c�@���g�ƃV�J�l�[�_�[�����b�W�̓��u�ł������Ƃ����̂͒ʐ��ɂȂ��Ă��邪�A����͔����������m�łȂ��B�V�J�l�[�_�[�́A�������Ƀt���[���C�\���ł��������A�����̂��ǂŁu�E�l�v�ʊK�ȏ�ɏ��i���邱�Ƃ��Ȃ��A���[�Q���X�u���N�̔ނ̃��b�W�u�O���J�[���v����1789�N5��4���ɔj�傳��Ă����B����ɂ͈ӌ����قɂ��邳�܂��܂Ȕ��_������ɂ�������炸�A�ŋ߂̗��j�w�҂́A�ނ��E�B�[���̂����Ȃ郍�b�W�ɂ��ӂ����ю�����邱�Ƃ͂Ȃ������ƍl����X���ɂ���B�@����ɂ��ƁA�V�J�l�[�_�[�́A�t���[���C�\���Ƃ��ẮA���[�c�@���g�ƈႢ�A���Ȃ�̗����������Ƃ�����B�Ƃ͂����A�t���[���C�\���Ƃ�����l�̋��ʍ����u���J�v�Ƃ����������I����𐢂ɑ���o�����߂̍ł��d�v�ȗv�f���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
2013.02.25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��7�`�l���ő�̓]�@
 �@�l�ɂ͎��Ƃ��Đl����ς��Ă��܂��قǂ̓]�@������B�V�˂ɂ��}�˂ɂ�����͕����u�ĂȂ��B���[�c�@���g�̏ꍇ�A�����1781�N�A25�̃E�B�[���������B
�@�l�ɂ͎��Ƃ��Đl����ς��Ă��܂��قǂ̓]�@������B�V�˂ɂ��}�˂ɂ�����͕����u�ĂȂ��B���[�c�@���g�̏ꍇ�A�����1781�N�A25�̃E�B�[���������B�@3��16���A���[�c�@���g�̓E�B�[���ɓ��������B���ڂ̂��������́A�E�B�[�����K���̑�i���q�G���j���X�E�R�����h�i1732�|1812�j�̌Ăяo�������A���[�c�@���g�ɂ́A���̋@��ɃE�B�[���ŏA���������悤�Ƃ����ژ_�����������B
�@�R�����h�̍��_�́A��������鉹�y�Ƃ̗D�G�����c��͂��߃E�B�[���̋M���Ɍ����t�������Ƃ������́B��l�̎v�f�̈Ⴂ�͗���ׂ�����̉Ύ��s��ł����B
�@���[�c�@���g�́A�����������̓�����A�����Ȃ��i����ẪR���T�[�g�ɏo����������B�����͋M���̎��@�ł��B3���ɂ͂���ȉ��t�4��𐔂����B�ЂƂ܂��A��i���̊�𗧂Ă��̂����A����͗L�͋M���Ɋ�邱�ƂŏA�E�ւ̓����J����Ɠ����߂ł���B
�@�₪�āA���[�c�@���g�ɂ́A�M�����璼�ڂ�����������悤�ɂȂ�B�܂��A�ނ̍˔\�������Ă���Γ��R�̂��ƁB�Ƃ��낪��i�����ז��ɓ���B������̉��t��ɂ͋����o���Ȃ��B�����ɗ����I�t�@�[�͂��ݏ����B������͖̂{�l��ẪR���T�[�g�����B�v����Ƀ��[�c�@���g�̎��R���������A�g�p�l�Ƃ��Ă̘g�Ɏ~�߂������Ƃ����̂ł���B
�@��i���ɂ��Ă݂�A���[�c�@���g�͈��̂��������y�Ƃɉ߂����A����������Ōٗp���Ă���Ă���̂�����A����͓��R�̑[�u���낤�B�Ƃ��낪�A���[�c�@���g�͍��x�����͋��C�������B�~�����w���Łu�C�h���l�I�v�𐬌����������肾���A�V���̃E�B�[���́A4�x�ڂ̗��K�ɂȂ邪�A�������đ劽�}����Ă���B���ɍ���A�R���T�[�g�͑吷���B�R�����h�������Ȃ�������Ƃ����Ɖ���������������͂��E�E�E�E�E����ȋC�������\�ꂽ�莆������B
���łɂ��m�点�����悤�ɑ�i���͂����Ŗl�ɂƂ��đ傫�Ȏז��҂ł��B�Ȃ����ƌ����A�ڂ����u����v�ł̉��t��Ŋm���Ɏ�ɓ����͂�������100�h�D�J�[�e����ނ̓t�C�ɂ��Ă���܂����B�ڂ��̓P�����e���匀��Ō|�p�Ɓi���S�l�j����̃R���T�[�g�ɏo�����܂����B���肪��~�܂��n�߂���ēx�e�������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B���O���l��m�����ȏ�A�����ʼn��t�����Â�����ǂ�Ȃɂ��ׂ������Ƃł��傤�ˁH ����Ȃ̂ɁA���̑�i���̃o�J������������Ȃ��̂ł��B�����̌ق��l���ׂ��邱�Ƃ�]�܂��A�������������̂ł��B�@�i1781�N4��4���A�E�B�[�����畃�ցj�@100�h�D�J�[�e���́A���݂Ɋ��Z�����120���~�B����ł���B�������{�C�ł������Ƃ����Ɖ҂���͂��Ƒ��������[�c�@���g�B�u�g�p�l�Ȃ牴�̌������Ƃ��̂����R���낤�B�e����������������ق��Ă���Ă���B�����Y��Ă���̂����̎�m���v�ƕ̂ޑ�i���B����͎��Ԃ̖�肾�����B�����āA���ɂ��̓�������Ă���B
�@���[�c�@���g�́A�ŏ��͑�i���̌������Ƃ����B�������邤���ɁA�u��͂莩���̃p�t�H�[�}���X�͎�B���͐����v�Ƃ����m�M�����悤�ɂȂ�B����͂������낤�A�N�����ă��[�c�@���g�̂悤�ȓV�˂ɏo��������Ƃ͂Ȃ��̂�����B���M���o�����[�c�@���g�́A��i���Ɂu��Ă𝛂˂��Ȃ����O�̃R���T�[�g�v�̊J�Ë���\���o��B��i���͓��R�̂��Ƃ��p�� �u�ӂ�����ȁB���O�͎��̎g�p�l���B���������ł̎d���͏I��肾�B2�T�Ԉȓ��ɃU���c�u���N�ɋA��B��ʔ�͑O���œn������v�B����ɑ��ă��[�c�@���g �u�ł����͂��B�}�Ȃ���ق�������B�{��Ɍق��Ȃ��Ă��A�����͂����Ŏ��R�ɉ��y�������ĐH�ׂĂ䂯�鎩�M������v�B��i���ɂ͐�A�����ɂ͊m���Ȏ育�����������Ƃ������[�c�@���g�̎莆�����L�B
�l�͂܂����킽���ς�����Ԃ��Ă��܂��B�l�̔E�ς͂��܂�ɂȂ������Ǝ����ɂ������Ă��܂������A���ɂ͂��܂���Ȃ��Ȃ�܂����B�l�͂����U���c�u���N�Ɏd����s�K�Ȑg�ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B�����͖l�ɂƂ��čK���ȓ��ł����B�l���A�z�̂Ƃ���ɓ����Ă䂭�ƁA�����Ȃ�u�Ƃ���ŁA���Ⴂ�́A�����̂��H�v�u���ӂ̂���ł������A���Ȃ�������t�ł����v�B����ƁA�z�͈�C�ɂ܂������Ă܂����B�u���O�݂����Ȃ��炵�̂Ȃ���m�͌������Ƃ��Ȃ��A���܂��̂悤�Ȗ��߂����낻���ȓz�͂��Ȃ����v�E�E�E�z�́A�ڂ���500�t���[�����i150���~�j�̋�����������Ă���Ɩʂƌ������ĉR�����A�ڂ��̂��Ƃ��u�낭�łȂ��v�A�u�����v�ƌĂсu�n���v�Ă�肵�܂����B�E�E�E���ɖl�͌����ς�����Ԃ��Ă��Č����Ă��܂��� �u�ł͋M���͎��ɂ��s���Ȃ̂ł��ˁv�B�u�ȂM�l�́I�킵�������C���H�n������I�h�A�͂��������B�킩�邩�A����Ȉ���ȏ��m���q�ɂ����p�͂Ȃ��v�u�l�������M���ɗp�͂���܂���v�u�����A�o�Ă䂯�v�E�E�E�����Ŗl�͕������o�Ȃ���u���ꂪ�Ō�ł��A�����i���\���j�����œ͂��܂��v�B�ň��̂�������A�����Ă��������B�l��������������̂́A��������Ƃ������A�x�������̂ł͂���܂��H�E�E�E�l�̍K�^�͍�����Ǝn�܂�܂��B�@�i1781�D5�D9�@���I�|���g�ցj�@����ɑ��āA���I�|���g�́A��Q�ĂŎ莆���������̂��낤���A�c�O�Ȃ��猻�݂͎c���Ă��Ȃ��B�����炭�A�C�����Q�������[�c�@���g���j��̂Ă��̂��낤�B���I�|���g�̎莆�̓��[�c�@���g�̕Ԏ�����e�Ղɐ����ł���̂ŁA�Ȃ�����ď������Ă��������B
���q��A�Ȃ�Ă��Ƃ����Ă��ꂽ�̂��B�����u���\�v���o����������Ƃ����̂��B�Ȃ�A�����ɓP�Ȃ����B�������A�E�H���t�K���O�A�t���[�ɂȂ��ĐH�ׂĂ䂭�̂͑�ςȂ��Ƃ��B�ŏ��͂���ق₳��邾�낤���A�E�B�[���̂��q�͂����O����B���O�̐����铹�͋{��߂����Ȃ��B�������O�̐E�ꕜ�A���i���ɂ��肢���Ă���A�܂��R�N���o���Ă����̂����B���g�ᓪ�ŋ����Ă��������Ȃ����B����ȉ������i���ɏ|�����Ƃ͉������B�����ӂ��ēP�Ȃ����B���ꂪ��Ԃ������@���B�킵�́A�����U���c�u���N�ł���Ă��������Ȃ��̂���B���̗���������͎@���Ă���B���́A���Ɍ�������ĕ��Â��Ⴈ��낤���A��ɂȂ�����ƕ�����B�������Ƃ͌���Ȃ��B��������̌����Ƃ���ɂ��Ȃ����B�@�i1781�D5�D14����H ���I�|���g���烂�[�c�@���g�ցj�@���[�c�@���g�͂������肵���B���̕��e�Ȃ炫���Ɖ������Ă����Ǝv�����̂ɁA�Ȃ�̂��炭�I ����܂Ŏ��Ɍ������Ƃ��ɗD�����A���y�̓��ɓ����Ă��ꂽ���̕��e���A�܂����E�E�E���L�͗L���Ȏ莆�ł���B
�����ȂƂ���A���Ȃ��̎莆�ɂ́A�����̈�s���ڂ��̕��e�����o���܂���B�����Ǝq���̖��_���C�����A�ŏ�̈���Ɉ�ꂽ���e�ł͂���܂���B�ꌾ�Ō����A�ڂ��̂�������ł͂���܂���B�l�����\��P����A���ɂ��ڗ�ȓz�ɂȂ艺����̂��킩��܂��B��i���𖼌N�ƌ����Ƃł����������̂ł����B�@�i1781�D5�D19 ���[�c�@���g���烌�I�|���g�ցj�@�������āA���[�c�@���g�́A�U���c�u���N�ƕ��ƂɌ��ʂ��A�V�V�n�E�B�[���Ŏ����������y�ƂƂ��Ă̓�����ނ��ƂɂȂ�B���`���镃�e�ɑ��A�����܂ł����ς�Ƌ��C�Ɏ����̋C������\�����̂͐��܂�ď��߂Ă̂��Ƃ������B���̐錾�̗��ɂ́A�㉉��������́u�C�h���l�I�v�̃C���[�W�����̓��ɂ�������ƍ��ݍ��܂�Ă����H ����ȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂ł���B�䂪�q�ւ̈���䂦�ۂ���ꂽ�^���ɔY�ݗ����������N���^�̉��C�h���l�I�̍����Ȏp�B����Ɉ����ւ������̕��e�Ƃ�����A�Ȃ�Ƃ����ڋ��ȁE�E�E���[�c�@���g�́A�N���^�̉��E�C�h���l�I�Ɖ䂪���E���I�|���g������ׂĂ����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@����܂ŁA���y�Ƃ͗�O�Ȃ��{��̂������ł������B���[�c�@���g�́A���j��A���߂Ď��͂Ő��v�𗧂Ă邱�Ƃ��ł������y�Ƃł���B1781�N5��9�������A���̌�̉��y�j��傫���h��ւ���_�@�ƂȂ�������I�ȓ��������̂ł���B
2013.02.10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��6�`�~�����w������E�B�[����
[�C�h���l�I] �@1780�N11��5���A�̋��U���c�u���N�����Ƃɂ������[�c�@���g�̍s����̓~�����w���������B�o�C�G�����I���J�[���E�e�I�h�[���i1724�|1799�j����A�I�y���u�C�h���l�I�v�̍�Ȉ˗������������߂ł���B
�@1780�N11��5���A�̋��U���c�u���N�����Ƃɂ������[�c�@���g�̍s����̓~�����w���������B�o�C�G�����I���J�[���E�e�I�h�[���i1724�|1799�j����A�I�y���u�C�h���l�I�v�̍�Ȉ˗������������߂ł���B�@���[�c�@���g�́A2�N�O�A�����s�̍ہA�}���n�C���ŁA�v�t�@���c�I���̃J�[���E�e�I�h�[���ɉ���Ă���B�����ɂ͔ނ��n�݂����{��I�[�P�X�g��������A���̎��͂̓��[���b�p����Ƃ����Ă����B�y�c������͒g�����}�����A���[�c�@���g�̓}���n�C���Ŋy�������[������5�������߂����i���ʁA�g�I�P�ɋ�Ȃ��Ȃ��h�Ƃ������R�ŏA�E�͊���Ȃ��������j�B�{��̎�A���C�W�A�E�E�F�[�o�[�i��Ɍ�������R���X�^���c�c�F�̎o�j�Ƃ̗����A�[�����ɔ��Ԃ��������B���e�ɂ���Ȏ莆�������Ă���B
�ڂ��͋M���̂悤�ȋ��K�������������͂���܂���B�ڂ��̍Ȃ��K���ɂ������Ƃ͎v���܂����A�ޏ��̍��Y�ōK���ɂȂ낤�Ƃ͎v���܂���B�ڂ���̍��Y�͓��̒��ɂ���̂ł�����B�����āA�ڂ���̓��������Ȃ�������A�N�������D���킯�ɂ͂����܂���B �i1778�D2�D7�}���n�C����蕃�ցj�@ �@����ɑ��镃����̎莆
�����鑧�q��A�ǂ������̎莆���n�ǂ��Ă���I ���������U���c�u���N�Őh���v�������Ă���̂́A�悭�m���Ă���ˁB���܂������X�}�X���鉹�y�ƂƂ��Đ��Ԃ���Y����Ă��܂����A����Ƃ��L���Ȋy���Ƃ��āA�㐢�̐l�����ɂ܂ŏ����̒��œǂ�ł��炦��悤�ɂȂ邩�E�E�E���ɂ������āA�q���������ς��������ĕn�R���A�������̘m�ԂƂ�łЂ�����Ɨ����Ԃ�Ă��邩�A����Ƃ��L���X�g���k�Ƃ��Ċ�т▼�_�����Ɉ�ꂽ�����𑗂������ƁA���O�̉Ƒ��̂��߂ɖ����𐮂��A���Ԃ���͑��h���Ď���ł䂭���́A�Ђ����炨�O�̗����Ɛ������ɂ������Ă���̂ł��B�i1778�D2�D12�U���c�u���N����q�ցj�@���[�c�@���g22�B�A���C�W�A16�B���[�c�@���g�́A���̂Ƃ��A���̍˔\������e�̉̕P�̗�������m������{��C�^���A�Ńf�r���[���������Ɩ{�C�ōl���Ă����B���_�A�K���Ȍ��������B�����m�������I�|���g�A�u���A���ɂ������Ă���Ƃ����A�R�m�B�������炱�����A�ꐶ��_�ɐU�邼�v�Ɛ��ԕ��݂̕��e�̒����ł���B���ʁA���[�c�@���g�́A���̈ӂ�����A�E�����߂ďa�X�p���ւƌ������̂����A����ȕ��e���A���܂�Ă͂��߂đa�܂����v���悤�ɂȂ����A2�N�O�̃}���n�C���ł������B
�@���[�c�@���g��1780�N11��8���A�o�C�G�����̎�s�E�~�����w���ɓ��������B�����ɂ͎������������Ă����J�[���E�e�I�h�[�����o�C�G�����I���Ƃ��ČN�Ղ��Ă���B�O�I���}�N�V�~���A��3���̎����ɔ����A�v�t�@���c�Ƃ̌��C�ƂȂ����̂ł���B�����āA���[���b�p����̃}���n�C���E�I�[�P�X�g�������̂܂܂����Ɉڂ��Ă��邩��A�y�c���݂͂ȋ��m�̊ԕ����B����Ȃ��̏���Ȃ����ŁA�I�y����������̂ł���B�U���c�u���N�ł͏��������Ă������Ȃ��������̃I�y�����E�E�E�E�E���[�c�@���g�̍��g�Ԃ�͂������肾�����낤���B
�@�~�����w���ł̖ړI�͂�����������B����́A3�N�O����̌��Ď����ł���A�E�ł���B���X�I������D�ӂ�y�c���Ƃ̊y�����𗬂́A�����̊y�V�ƃ��[�c�@���g�Ɋm���Ȏ育�����������������ɈႢ�Ȃ��E�E�E�E�E�������̂���ȑ�i���̌��ɋA��Ȃ��Ă����I
�@�C���悭�ȍ��͐i�ށB��{��Ƃ̓U���c�u���N�{��i�Ղ̃W�����E�o�e�B�X�^�E���@���[�X�R�i1736�|1805�j�B���[�c�@���g�͉��x�����x�����Ƃ肵���������B�~�����w���ƃU���c�u���N�B����̓��I�|���g���������B�u���̃I�y���𐬌������Ă����ŕ�炷�B���s�͋�����Ȃ��I�v�C��������̂����R�ł���B�V�˂��C��������Ό��삪���܂��B�m�Â̕]������X���B���n�[�T���ł̃J�[���E�e�I�h�[���̈ꌾ�́A���[�c�@���g��傫���E�C�t����E�E�E�E�E�u���̃I�y���͌������B�N�̖������߂�ɈႢ�Ȃ��v�B
�@�������āA�̌��u�C�h���l�I�v�͊����B1781�N1��29���A���W�f���c����Ŗ����������ꂽ�B
�@�u�C�h���l�I�v�́A���e�̐S�̊�����`�����h���}���B�N���^�̉��C�h���l�I�́A�g���C�Ƃ̐킢�ɏ��������ƊC��ɑ������邪�A�C�_�l�v�`���[���̋~�ς��㎀�Ɉꐶ��B���̌����������i���ʓI�Ɂj���q���тɍ����o���Ƃ������̂������B���͐_�Ƃ̖Ƒ��q�Ƃ̋��ԂŔY�݂ɔY�ށB�ŏI�I�ɐ_�̐M���������āA���f�^�V���f�^�V�ɂȂ�̂����A���̕��e�̎p���A���[�c�@���g�̐S�Ɏc��B�I�y�������̊Ô��Ȋ�тƂƂ��ɁA���ɗ����������^���ȕ��e�̎p���]���ɂ�������ƍ��ݍ��܂��̂ł���B
�@�����āA3��12���A���[�c�@���g�̓~�����w���𗧂��Đ��U�̏Z���ƂȂ�E�B�[���������B�Ƃ������Ƃ́A�~�����w���ł̂����ЂƂ̑傫�ȖړI�A�A�E������Ȃ��������Ƃ��Ӗ�����B���y�ł͍ő���̋����������Ă��ꂽ�I���J�[���E�e�I�h�[�������A�ٗp�ɂ����Ă͓�x�܂ł����[�c�@���g�����ۂ����̂ł���B�ʂɂ͂��܂��܂ȗ��R�����邾�낤���A�ꌾ�Ō����Ύ���̈��A���ꂪ�A���V�����E���W�[���̕ǂƂ������̂��낤�B
[���ꂩ��̃V�J�l�[�_�[]
 �@�V�J�l�[�_�[���A�����Ƀ��[�c�@���g�Ɉ���������Ă������́A���I�|���g�̎莆������M����B�u���܂����������Ƃ��A�Ȃ�Ƃ��̐l�́A���܂��ɂ��悤�Ȃ���������ƁA�X�֔n�Ԃ̂��Ƃ𑖂��Ēǂ������Ă������̂��v�B�܂�ŁA�u�k�̍�����v�̌u�A�u�Ɛ��w�̃~�^�v�̂��������ł���B
�@�V�J�l�[�_�[���A�����Ƀ��[�c�@���g�Ɉ���������Ă������́A���I�|���g�̎莆������M����B�u���܂����������Ƃ��A�Ȃ�Ƃ��̐l�́A���܂��ɂ��悤�Ȃ���������ƁA�X�֔n�Ԃ̂��Ƃ𑖂��Ēǂ������Ă������̂��v�B�܂�ŁA�u�k�̍�����v�̌u�A�u�Ɛ��w�̃~�^�v�̂��������ł���B�@���[�c�@���g�ƕʂꂽ���Ƃ̃V�J�l�[�_�[�́A�U���c�u���N�ɗ��N1781�N2���܂ő؍݁A�ʎZ93��̌������s�����B���̍Ō�̉��ځu�A�O�l�X�E�x���i�E�A�����v�́A4��㉉���ꂽ���A����200�l���̊ϋq����O�Ɉ���قǂ̑�q�b�g�ƂȂ����B���[�c�@���g�́A�V�J�l�[�_�[���u�C�h���l�I�v�̏����ɗU�����A����1��29���́u�x���i�E�A�����v�̑�3��ڂ̌������ɂ�����A��l�̍ĉ�͂Ȃ�Ȃ������B
�@�U���c�u���N�𗷗������V�J�l�[�_�[�́A���C�o�b�n�A�O���[�c���o�ăn���K���[�̃v���X�u���N�ɒH����B���̒n�ł́A���n���E�t���[�f���i1751�|1789�j�Ƃ����[�֔h�̕��w�N������ɍ�������B�t���[�f���͈���Œj�D�̑��ɑ�{���S�������B>
�@1783�N�t�A�V�J�l�[�_�[�̓E�B�[���̃P�����e���匀��Łu�n�����b�g�v�������A��]�����Ƃ�B���̂Ƃ��̔z���́A�n�����b�g���V�J�l�[�_�[�A�N���[�f�B�A�X�����t���[�f���A�I�t�B�[���A�̓V�J�l�[�_�[�̍ȁE�G���I�m�[���������B�܂��A���̃P�����e���匀��́A1824�N5���A�x�[�g�[���F���́u���v���������ꂽ���Ƃł��L�����B
�@�V�J�l�[�_�[��1784�N11��5���A�ēx�P�����e���匀��ɓo�ꂷ��B�o�����̓��[�c�@���g�́u��{����̗U���v�������B�E�B�[���V���́A�u���̈���́A�X�̎��l���Ȃ鋻�s�Ƃ��ẮA�P�����e���匀��ɂĂ������N���̊Ԃ���ꂪ�ό��������̂̒��ōŏ�ł���v�Ə^�����B
�@���āA���̌�̃V�J�l�[�_�[�̓t�@���L�[�ł���B�Ƃ������A�ނ͌��X�����ł���A�܂��ɓ����Ȃ̂��B����̏��D�͂��Ƃ��A�E�B�[���̏����蓖���莟��̑́B����Ȓ���Ɋ��E�܂̏����ꂽ�ȃG���I�m�[���B����ɓ����i���Ƃ͂Ƃ����Δޏ��ړ��Ăɉ�������j�t���[�f���B���������̎O�p�W�̌����́A�V�J�l�[�_�[�̈������̒Ǖ��������B
�@�傪����������̏o�����͎����ƈ������̂��̂ƂȂ�B�V�J�l�[�_�[�������A������o�ꂳ���C���܂Ŕ���đ�O��_�����X�y�N�^�N���E�^�C�v�Ȃ�A�t���[�f���̂͂Ђ�����l�ԃ�������Nj�����^�ʖژH���������B
�@1788�N�A�n���Ȋ����̌��ʁA����͐��ɃE�B�[���E���B�[�f����̖ƐŊقɐݒu���ꂽ����i�t���C�n�E�X����j����ɓ����B�����ŁA3�N��Ɂu���J�v�����������̂ł���B
�@�t���[�f������̌|���́A�ނ̊`���Ƃ��̌��ォ������Ď���B�u���ǂ��̂��ڂɂ����܂���́A�ق�̎G���̉Ԃɉ߂��܂��ʁB�R��Ƃ͐\���ǂ��A��Ђ����ɍb��Ȃ��Ƃ��v���ɂȂ�܂��ʂ悤�A���ɂ��肢�\���グ�邵�����ɂ�����܂��v�B1788�N3��24���A�����Ղ̌��j���������B
�@�Ƃ��낪�A����1�N���1789�N3��31���A�t���[�f���͎��a�̌��j�������������̐��������Ă��܂��̂ł���B���N38�̒Z�����U�������B�⌾�ɂ�����ƌ���������p�����G���I�m�[�������A���Ƃ�肻��ȍˊo�͂Ȃ��B�����ɓo�ꂵ���̂́H ���킸�����Ȃ̃V�J�l�[�_�[�B���̊Ԃɂ��E�B�[���ɕ����߂����ނ́A���H��ʊ�ň���̒��Ɏ��܂��ăt���C�n�E�X�������ɓ��ꂽ�B���Ă̍ȃG���I�m�[���Ɗ���߂����̂͂����܂ł��Ȃ��B�C��R��̒j�ɂƂ��āA����͒��ёO�̏���掖�������B
�Q�l�����F�����u�V�J�l�[�_�[�v�i���}�Ёj
�@�@�@�@�@�@�@���C�i�[�h�E�\���������A�Έ�G��u���[�c�@���g�v�i�V���فj
2013.01.31 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��5�`�V�J�l�[�_�[�Ƃ����j
 �@�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[�i1751�|1812�j�Ƃ����j�������B18���I�㔼�\19���I�����ɂ����āA�h�C�c���I�[�X�g���A�ɐ�������������̍����ł���B�ނ������܂ł��̖����c���Ă���̂́A���[�c�@���g�́u���J�v�̑�{��ƂƂ��Ăł���B��������́A���[�c�@���g���V�J�l�[�_�[�Əo����āu���J�v�����������܂ł̉ߒ���H���Ă䂭�B
�@�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[�i1751�|1812�j�Ƃ����j�������B18���I�㔼�\19���I�����ɂ����āA�h�C�c���I�[�X�g���A�ɐ�������������̍����ł���B�ނ������܂ł��̖����c���Ă���̂́A���[�c�@���g�́u���J�v�̑�{��ƂƂ��Ăł���B��������́A���[�c�@���g���V�J�l�[�_�[�Əo����āu���J�v�����������܂ł̉ߒ���H���Ă䂭�B�m�V�J�l�[�_�[�A�U���c�u���N�Ɍ���n
�@�V�J�l�[�_�[���A�U���c�u���N�Ɍ��ꂽ�̂�1780�N9���A29�̎��ł���B�ނ̈���́A�U���c�u���N���x��i���E�B������A700�����e�j������ɗ��N��2���܂ő؍݂����B���[�c�@���g��ƂƃV�J�l�[�_�[�͂��̊ԁA�e�ʓ��R�̕t������������B��Ƃ́A�V�J�l�[�_�[����^����ꂽ3���̃t���[�p�X�Ŗ����̂悤�Ɍ���ɒʂ��A�V�J�l�[�_�[�̓��[�c�@���g�Ƃɓ���Z�����B
�@���̂Ƃ����[�c�@���g��24�B�U���c�u���N�{��̃I���K���e���Ƃ��āA�܂�ŕs�{�ӂȐ����𑗂��Ă����B3�N�O�A��i���R�����h���痝�s�s�Ȏd�ł����A�|�����A�}���n�C���`�p���֏A�����s�ɍs�������킸�A���̏㓯�s�������S�����ċA���A�����I�|���g����i���ɓ��������āA����ƃI���K���e���̐E�����Ă����Ă����̂ł���B�d���Ƃ����Γ��j���̗�q�p�ɒZ���~�T�Ȃ���艉�t���邱�Ƃ��炢�B�I�y�������������Ă��܂�Ȃ��ނɂƂ��ẮA�������ނ悤�Ȗ����������B
�@�����̃��[�c�@���g�̐S����\�����莆������B
�l�̖��_�ɂ����Đ����Č����܂����A�l�̓U���c�u���N�Ƃ��̏Z�������ɂ����䖝���ł��܂���B�ނ�̌����`�����Ԃ肪�A�܂������ς��������̂ł��B�i1779�D1�D8�j�@�ʂ̎莆�ł́A�u�I�y�������������Ă��A�����ɂ͂܂Ƃ��Ȍ�����Ȃ��v�ƒQ���Ă���B��i���R�����h�ɑ��ĂȂ炢���m�炸�A�Ƃ�����̓U���c�u���N�̒����̂��̂ɋy��ł���B����ȂƂ���ł͎����̍˔\���͊����Ă��܂��E�E�E�E�E ���[�c�@���g�͖{�C�Ŋ�@�����������I�H ����ȃ��[�c�@���g������A�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�V�J�l�[�_�[�ƈӋC���������͎̂��R�̐���s���������B����A�V�J�l�[�_�[���A����̒��Ƃ��āA��Ɏ鉉�ڂ�T���Ă����킯�ŁA�V�ˁI���[�c�@���g�Ƃ̌𗬂͖]�ނƂ��낾�����낤�B
�l�͂�������������邪�䂦�ɂ̂݁A�U���c�u���N�ɂ���̂ł��B�l�͖��_�ɂ����Č����܂����A���̑�i���������Ƃɑς��������Ȃ��Ă��邩��ł��B�i1780�D12�D16�j
�@�V�J�l�[�_�[����́A�U���c�u���N�؍ݒ���5�����Ԃɐ��X�̉��ڂ��㉉�����B�x���_��Ȃ́u�A���A�h�l�v�A�{�[�}���V�F�́u�Z���B���A�̗����t�v�i�u�t�B�K���̌����v�̑O�i�b�ŁA��N���b�V�[�j�̑�\��ɂȂ�j�A�V�J�l�[�_�[�̃I���W�i���u�y�����ߎS�v�u���[�Q���X�u���N�̑D�v�A���@�C�Z�^�q���[�́u�y�����C���v��V�F�C�N�X�s�A�́u�n�����b�g�v�u�������v�ȂǁA�W���O�V���s�[������ŋ�����A�쌀���ߌ����A���ɂ͉���F�i�D������݂����j�܂œo�ꂳ����A��T�[�r�X�̉��|�V���[�Ȃ̂ł���B
�@���[�c�@���g�́A�G�l���M�b�V���ɕ������艉����V�J�l�[�_�[�ɓ������������낤�B�V�J�l�[�_�[�́A���[�c�@���g�Ƃł̑̌�����A�ނ̉��y�I�˔\�ɋ��Q�������Ƃ��낤�B��l�͂������������A�ꏏ�ɕ��䌀����낤����Ȃ������Ƃ����b�ɂȂ�B��������R�̗���ł���B
�@���[�c�@���g��1773�N�A�E�B�[���ɍs�����ہA���y���̍�Ȃ��˗����ꂽ�B�g�r�[�A�X�E�t�H���E�Q�[�u���[��{�́u�G�W�v�g���^�[���X�v�ł���B����̓G�W�v�g�B��l���^�[���X�́A�_�I�V���X�𐒔q����L���̉��Ƃ��ĕ`����Ă���B�G�W�v�g�`�I�V���X�`���A�Ɨ���A�u���J�v�ɂȂ���ƍl����͎̂��R���B��{�̃Q�[�u���[���t���[���C�\���Ȃ̂��[���������B���̉��y���́A1774�N4���E�B�[���ŏ������ꂽ�iK173d�j�B���[�c�@���g�͂�����A�V�J�l�[�_�[�̑O�ɑ؍݂��Ă����x�[������̂��߂ɁA1779�N�Ɏ�������Ă���iK345�j�B�V�J�l�[�_�[�����������㉉�����L�^�͂Ȃ����A��l�̊ԂŘb��ɂȂ����\���͏\������B�u���J�v�̖G��ƍl���Ă������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���[�c�@���g�ƃV�J�l�[�_�[�ɂ�����A��薧�ڂȍ�i������B�����̃I�y���u�c�@�C�[�f�vK344�ł���B
�@�U���c�u���N�{��g�����y�b�g�t�ҁE�A���h���A�X�E�V���n�g�i�[�̑�{�ɁA���[�c�@���g���Ȃ�t�����B�g���R����̎����c�@�C�[�f���A�����̐g�ł���L���X�g���k�S�[�}�b�c�Ɨ��ɗ����A��l�Ō�{���瓦�����邨�b�ł���B�����͖����̂��ߔ���Ȃ��B15�̃i���o�[���f�ГI�Ɏc����Ă���B
�@��Ȃ�1780�N�ɍs���Ă���B�u�c�@�C�[�f�v���x�[�������z�肵�����̂��A�V�J�l�[�_�[�����ΏۂƂ������͏������邪�A�x�[��������V�J�l�[�_�[�������̂�9��������A�u�����̓x�[����z�肵�Ă��ēr������V�J�l�[�_�[�ɐ�ւ����v�ƍl����̂����R���낤�B���c���̋Z�ʂ͈�l�ЂƂ�Ⴄ�̂�����A���̐�ւ��̓��[�c�@���g�Ƃ����ǂ��������͂��ł���B�������A�Ă̏I���ɂ́u�C�h���l�I�v�̍�Ȉ˗�����������ł�������A���[�c�@���g�̋C���͐�炻����ɌX�����B�S�����ɂ��炸�ł���B�u�c�@�C�[�f�v�������ɏI������̂́A�����̎���ɂ����̂��낤�B�Ƃ͂����A�؏����炢���Ă��A1782�N�E�B�[�������̃W���O�V���s�[���u��{����̗U���vK384�ɂȂ����i�ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@1780�N11��5���A���[�c�@���g�́A�ӋC���������V�J�l�[�_�[�ƕʂ�A�~�����w���ւƗ��������B�I�y���ő�q�b�g�����Ƃ������Ɍ������āB�ʂ�ۓ�l�́A���������ƈꏏ�ɃW���O�V���s�[������낤�Ɛ����������ɈႢ�Ȃ��B
�@���̓����A���[�c�@���g�ɂƂ��āA���܂�̋��U���c�u���N�Ƃ̉i���̌��ʂƂȂ����B��l�̃X�e�[�W�́A���N��̃E�B�[���Ɉڂ����B���悢��A�u���J�v�����ւ̃J�E���g�_�E�����n�܂�̂ł���B
2013.01.25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��4�`���[�c�@���g�ƃE�R���h�m�̐ړ_
�@�N��������2013�N�B�u���N���������N�ł���܂��悤�Ɂv�Ɗ肢�Ȃ���A16���A���N�P��A�u�����݂䂫�c�A�[2012�|13�v�i���ۃt�H�[�����j�ɏo�����܂����B��͂�A�����݂䂫�A�������A�����݂䂫�ł����B�@�u����v�|�u�|�̔s�ҕ�����v�|�u����v�̗���̒��ɁA�ޏ��̐^��_�Ԍ����܂����B����ƕs�𗝂��~�ςŌq���I
�@18���̒����V���Ɂu��]�̓���v�̋L���������āA���̎�Ɏ҂̔o�D�E�x�����������u��肻���v���Ƃ̏d�v��������Ă��܂����B������X�����݂䂫�̉̂Ɋ����Ă����̂����ɂ���ł��āA����̃c�A�[�ł͓��ɂ��������܂����B�ŋ��̊��Y���́u����������v�����Ă����̂��A�ޏ��̎v���̕\��ł��傤�B
�ł͖{��ɁB����́A�u���[�c�@���g�A�w�e�B�g�X�E�E�R���h�m�x�Ƒ����v�̊��ł��B
[���[�c�@���g�Ƣ�e�B�g�X�E�E�R���h�m�]
�@���ݎ��g�ݒ��̃e�[�}�́A�u�̌��w���J�x�̖`���Ɂg���{�̎�߂𒅂����q�h�Ƃ����g���������邪�A�Ȃ��킴�킴���{�Ȃ̂��H�v�Ƃ������Ƃł���B���̂��̋^��ɂ��āA���{�̕]�_�Ɛ搶�����́A�u���{���낤���������낤���A�t���J���낤���A����Ȃ��̂ǂ������Ă����B�[���Ӗ��ȂǂȂ��̂�����v�ƍl���Ă�����̂��낤�B���̌��Ɍ��y�����L�q�ɁA����܂ł����̈�x���o��������Ƃ��Ȃ��̂�����B
�@�����A�܂��A���ꂪ�����Ƃ��A�t���J��������A���߂��������낤�B������ɁA�Ȃ�Ƃ����Ă��u���{�v�Ȃ̂ł���B�g�킴�킴����{��Ƃ���ɂ͉��炩�̗��R������͂����h�ƍl����̂́A���{�l���[�c�@���g���D�ƂɂƂ��Ď��ɓ�����O�̔��z�ƕ��ʂɎv���̂ł���B�킪���ɖ{�i�I�ɐ��m���y�������Ă���140�N�B���̊ԁA�ނ���Ȃɂ��Ȃ��������Ƃ̂ق����s�v�c�Ȃ̂ł���B
 �@����Ȏv���̂Ƃ��ɂԂ����������̂����c�r�꒘�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�i�u�k�Ќ���V���j�̌㏑���������B
�@����Ȏv���̂Ƃ��ɂԂ����������̂����c�r�꒘�u�t���[���C�X���ƃ��[�c�@���g�v�i�u�k�Ќ���V���j�̌㏑���������B
���[�c�@���g���g�͉ʂ����ē��{����{�l��m���Ă������ǂ����ƂȂ�ƁA����͐S���Ȃ��B�������Ȃ���A�����ň�����A���̂����₩�Ȍo�����I�����Ă������������B1984�N�A���̓U���c�u���N�ŃU���c�u���N��w���y�w���̃Q�A�n���g�E�N������������A�~�q���G���E�n�C�h���̏@�����u�L���X�g�҂̒����v�̃R�[���X�u�J���^�[�e�E�h�~�m�v���A���̂܂܃��[�c�@���g�̃I���g���I�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�vK118�̏I�Ȃɓ]�p����Ă��邱�Ƃ����ꂽ�B�u�L���X�g�҂̒����v�́A���{�̃L���V�^���喼���R�E�߂���l���ɂ����@�����ŁA�����ɂ́A�e�B�g�X�E�E�R���h�m�i���[�}�̌���e�B�g�X�̖��������Ă���j�A�V���E�O���T�}�Ȃǂ��o�ꂷ��B���̏@������1770�N8��31���A�U���c�u���N�ŏ������ꂽ���A���̂Ƃ����[�c�@���g�͑�1���C�^���A���s�̓r��ŁA�U���c�u���N�ɂ͂��Ȃ������B�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v��1�N���1771�N�āA���[�c�@���g���U���c�u���N�ŏ��������̂ł���B�@�����́u�L���X�g�҂̒����v�̒ʏ̂��u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�ł���B���̂ق����e�[�}�ɑ��������̂ŁA�Ȍ���ď̂́u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�ɓ��ꂷ��B
�@���̋L�q�ɂ��ƁA�g���[�c�@���g�́A���y���u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�Ɂu�e�B�g�D�X�E�E�R���h�m�v�̍����Ȃ̃����f�B�[��]�p�����h�Ƃ������Ƃ��B�����Ŏ��͌��ɓ���B
�@�V���E�x�b�J�[�����瑗��ꂽ�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v���{�������C�uDVD�Ɓu�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�̎s��DVD�i�N���X�g�t�E�|�b�y���w���A2006�N�U���c�u���N�ł̌������C�uDG�Ձj���ƍ��������ʁA�L�ڎ����ɊԈႢ�Ȃ����Ƃ��m�F�ł����B�܂��ɁA�����ŁA���[�c�@���g�ƍ��R�E�߂����т����̂ł���B
 �@�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v��DVD�́A���j�e���E�N���V�JM22�̈�BM22�́A���a250�N�Ɉ��݁A���[�c�@���g�̉̌��E���y���S22��i�����ׂď㉉�����v���W�F�N�g�̖��́B�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�͂��̒��ōł��㉉�p�x�����Ȃ����ڂŁA����ȋ@��Ȃ�������Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����Ȃ��㕨���B
�@�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v��DVD�́A���j�e���E�N���V�JM22�̈�BM22�́A���a250�N�Ɉ��݁A���[�c�@���g�̉̌��E���y���S22��i�����ׂď㉉�����v���W�F�N�g�̖��́B�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�͂��̒��ōł��㉉�p�x�����Ȃ����ڂŁA����ȋ@��Ȃ�������Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����Ȃ��㕨���B�@�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�́A����ɗւ��������j�b�`�ȍ�i�ŁA1770�N�̏����ȗ��̏㉉�L�^�����������Ƃ��Ȃ��B���_���R�[�f�B���O���F���B�V���E�x�b�J�[���̓��{��㉉���ŏ��̍ĉ��������\��������B
�@����ȋɁX��2��i�̉f�������ł����̂ł���B����͂�����ՂƂ��������悤���Ȃ��I
�@��͎��Ă������Ȃ���i�ł���B�Ђ�A�����Ɋ�Â�16�Ȃ��琬�鉹�y���ŁA�Ђ�A���{�̃L���V�^���喼���ނƂ������Ȃ̃V���t�H�j�A��2�Ȃ̍����Ȃ̂ق��͑䎌����̏@�����ł���B�Ƃ��낪�݂��ɓ��������f�B�[�̊y�Ȃ�����R�Ƃ��đ��݂��Ă���B���̐ړ_�̕s�v�c���Ɩʔ����B�u���m�Ƃ̑����v�̊y���݂����ɋɂ܂��ł���B
�@ �m�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v��Ȃ̌o�߂𐄎@����n
�@�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v���������ꂽ1770�N8���A14�̃��[�c�@���g�͑�1��C�^���A���s�̍Œ��������B���̗��s�́A���N���[�c�@���g�ɂƂ��āA�傫�Ȏ��n���������B�Ƃ������A�ނ̐l���̐Ⓒ���������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B7���ɂ̓��[�}���c���u�������ԌM�́v��������A12���ɂ͍ŏ��̃I�y���E�Z���A�u�|���g�̉��~�g���_�[�e�v���~���m�ŏ㉉�A���������߁A1771�N1���ɂ̓��F���[�i�̃A�J�f�~�A�E�t�B�������j�J���疼�_�y���̏̍���^�����Ă���B
�@�����āA�A���r���̃p�h���@�ŁA���[�c�@���g�́A�A���S�[�i����E�W���[�b�y�E�q���l�X���畑�䉹�y�̍�Ȉ˗�����B�U���c�u���N�ɋA�����̂�3�����̂��Ƃł������B
�@1771�N�̉āA���[�c�@���g�́u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�̍�ȂɎ��|����B��{�̓E�B�[���̋{�쎍�l�A�C�^���A�l�̃s�G�g���E���^�X�^�[�W�I�i1698�|1782�j�ł���B���̂Ƃ��A���^�X�^�[�W�I��73�A��������ނ��Ă���B���������Ă��̑�{�̓A�����m�ł���B���[�c�@���g���q�́A�C�^���A���s�̍ۂɁA�C�^���A��̑�{�⎍�𑽐��g�т��Ă����B��l�̒����ɉ�������A���[�c�@���g�������ŋȂ����ăA�s�[�����邽�߂̑f�ނƂ��Ăł���i���̂�����̌��́A���C�i�[�h�E�\���������A�Έ�G��u���[�c�@���g�v�ɏڂ����j�B�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�̑�{���A���[�c�@���g���q�̎蒆�ɂ��������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�A���S�[�i�������˗������Ƃ��A�\�z�͒����ɕ����͂��ł���B
�@�u���āA���̑�{���ǂ��������邩�v���[�c�@���g�͍l�����B�I�y���E�Z���A�̌`���̂邩�A���y���̃X�^�C���ɂ��邩�H 15�̃��[�c�@���g�́A���R�����I�|���g�ɑ��k�������낤�B��������o�i���l�����u���N�A�~�q���G���E�n�C�h���̏@�������w�Ō�����v�Ɓu�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�̏����̘b��������������Ȃ��B������ɂ��Ă��A�ނ́A�����E��́i�U���c�u���N�{��y���j�~�q���G���E�n�C�h���ɑ��k�������������B
�@�u�����ɁA���N�x�l�f�B�N�g�C���@��w�̑��ƋL�O�ɏ㉉�����w�e�B�g�X�E�E�R���h�m�x�̊y��������B�Q�l�ɂȂ�K�����B�����v���ɁA�w�x�g�D�[���A�x�͑�ނ��炢���Ă��w�E�R���h�m�x�̂悤�ȉ��y���������Ǝv����v�E�E�E�E�E���ꂪ�n�C�h���̓����������B
�@�y����ڂɂ������[�c�@���g�́A��̊y�Ȃɒ��ڂ���B�����ȁu�J���^�[�e�E�h�~�m�v�ł���B�u���̋�����@�͎��Ɍh�i�Ŕ������v�ƍl�������[�c�@���g�́A�~�q�F���E�n�C�h���ւ̃I�}�[�W�����܂߁A�u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�̏I�Ȃɓ]�p�����B�����ăn�C�h���̒����ǂ���A���̉�����u���y���v�̌`�ŏ����グ���B
�@1771�N8���A���[�c�@���g�͑�2��C�^���A���s�ɏo������B�����āA�ǂ���A�p�h���@�ʼn��y���u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v���A���S�[�i����Ɍ��悵���B�Ƃ��낪�������̍�i�̏㉉�L�^�͂Ȃ��B�����������́H�Ƃ����^��͎c�邪�A �܂��A����ɂ��Ă͐[���肵�Ȃ����Ƃɂ��悤�B��|���{�P��̂ŁB
�@�ȏ�́g�ߒ��h�͐����̈���o�Ȃ����A���[�c�@���g���A���g�̉��y���u�~��ꂽ�x�g�D�[���A�v�Ƀ~�q���G���E�n�C�h���̏@�����u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v��1�Ȃ�]�p�����͕̂�����Ȃ������ł���B�Ɠ����Ɂu�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�Ƃ����@�����A�����āA���̎�l���E���R�E�߂����炩�̌`�ŋL���ɗ��߂������z���ɓ�Ȃ��̂ł���B
2012.12.25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��3�`�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�Ƃ����@����
�@��O�s�ݏZ�̃h�C�c�l�w�҃f�g���t�E�V���E�x�b�J�[���ɁA�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�ɂ��ēd�b�Ŏ��₳���Ă����������B���l�̗L������̋��n���ł���B���ɂ͎��ɒ��J�ɂ��������������A���̏�A���{�㉉�̍ۂ̑�{�ƃ��C�uDVD�𑗂��Ă����������B�����l�ŁA�قƂ�lj_��͂ނ悤��������i���A��������Ɨ֊s�������Ă��ꂽ�B�@�u�N�����m�v���n�߂�4�N���A����قǂ܂łɐe�ɉ����Ă��ꂽ���͂��Ȃ������B�ɐɊ��ӂł���B�ȉ��̕��͂́A���ׂăV���E�x�b�J�[���̂����ӂ̎����ł���B
��232�N�Ԃ�̏㉉��
 �@2002�N12��1���A���s�{�D��S�i����O�s�j���g���́u�{���̐X�Ђ悵�v�ŁA���C�q�X�V�[�Q����{ �~�q���G���E�n�C�h�����y�̏@�����u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�����{��ŏ㉉���ꂽ�B�v���f���[�X�̓f�g���t�E�V���E�x�b�J�[�A�L���v�ȁB�U���c�u���N������1770�N8��31��������232�N���o�Ă̏㉉�����{�����ł���B�㉉���Ԃ͑S5����2���ԁB�I���W�i����4���Ԃ�Z�k���Ă̏㉉�������B
�@2002�N12��1���A���s�{�D��S�i����O�s�j���g���́u�{���̐X�Ђ悵�v�ŁA���C�q�X�V�[�Q����{ �~�q���G���E�n�C�h�����y�̏@�����u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�����{��ŏ㉉���ꂽ�B�v���f���[�X�̓f�g���t�E�V���E�x�b�J�[�A�L���v�ȁB�U���c�u���N������1770�N8��31��������232�N���o�Ă̏㉉�����{�����ł���B�㉉���Ԃ͑S5����2���ԁB�I���W�i����4���Ԃ�Z�k���Ă̏㉉�������B�@��O�s�́A���s�{�O�g�n���̓암�ɂ���A2006�N�ɂ������̒������������Ďs�ƂȂ����B�l����35,000�l�B�n�}������ƁA�O�g���͍��R�E�߂����߂��ےÍ��Ɨאڂ��Ă���B����ȏ����̒n�ʼnE�߂��h�����B�������h�C�c�l���v�Ȃ̎�ŁB�Ȃ�ƁA��[�����Ƃł͂Ȃ����B
�����炷����
�@����͐퍑����̓��{�B�o��l���̓E�R���h�m�i���R�E�߁j�Ƃ��̉Ƒ��B�ނ��d����V���E�O���T�}�i��j�Ƒ��߂ȂǏ\�����B����̂قƂ�ǂ͑䎌�ɂ���Đi�s���A�nj��y�ɂ�鏘�t�ƌ�t�A�����̍����Ȃ��琬��@�����y���ł���B
�@���R�E�߂͒�ւ̖d�����N��������𐪔�����B���̕��M�ɂ��邩�瑽��̎^������B�u���Ȃ��͎��̍ō��̗F���B�Ɨ��ɂ��炸�B�Ȃ���Ȃ��̂킵�Ɍ����钉�`�ɂ��A�����݂ɂ��A�����ƕ����Ǝv���v�ƁB
�@����ɑ��E�߂́u���M�͎��̎d���Ƃ��ē�����O�̂��ƁB����ꂽ�����͂ЂƂ��Ɉ̑�Ȑ_���玒�������́B���̊肢�̓L���V�^���Ƃ��ēV��Ɏd�����̋�����S�����邱�Ƃ��v�Ǝ���̐M�����q�ׂ�B
�@���������́A�u�V���������i�L���X�g���j�͂킪�_�c��p����Ƃ������ƁB�������Ђ߂�e����悫�肢��\���ׂ��v�ƁA�L���X�g����e�F�ł��Ȃ����Ƃ�`����B
�@�L���X�g���ɑ��A��T�C�h�̏@���͓��{�×��̐_���ł��蕧���ŁA�ً��Ƃ����Ăѕ������Ă���B
�@�ً��̑m�����E�߂Ɂu��͋M�a�̐_�c�ւ̕s�h�͌����Č������Ȃ����v�ƌx�����邪�A�E�߂́u���Ƃ��邪���ɔ���������Ă����̒�ւ̒����͕s�ςł���A���Ō��𗬂��B�����A�V��̂��߂ɂ͂���Ɋ��ŗ������Ƃ��ł���v�ƁA�����܂ŁA�L���X�g���̓V�偁�_���ō��̂��̂Ƃ̈ӎv�������B
�@���̌���E�߂͎����邲�ƂɃL���X�g���ւ̒�����\������B�u���낸�̐_�Ȃǂ��Ȃ��B���킹����̂͗B��̐_�E�V��l�����B�߉ނ∢��ɕ������������́B��a�̍������̐��̑S�Ăł͂Ȃ��A���E��}������͓V��݂̂��v
�@���̂܂܂ł͒�̓{����ƈĂ����`�Z�́u�Ƒ��̂��߂ɂ��S���U��A��a�l�̐M�����킪�M�S�ƌ����v�Ƒ������A�E�߂͕�������Ȃ��B
�@�E�߂̐M�S�̌ł����댯���������߂́u���̂��̂��߂�ׂ��v�ƒ�ɔ���B��͐��Ɂu�����A�������Y�����Ă����@���Ȃ��̂Ȃ�A�z���邵���Ȃ��v�ƈ�����ݍ��ށB
�@�Ƃ��낪�E�߂́u���@���˂Ύ��Ƌ�����̂Ȃ�A���Ŏ���܂��傤�B���Ƃ�肻��͓V��l�����]�݂̂��Ɓv�ƁA�܂��Ƒ����u�V��l�̂��߂Ɋ��ŏ}���̓���I�т܂��v�ƁA�L���V�^���Ƃ��ĉE�߂ƕς��ʊo�傪���邱�Ƃ���������B
�@��̑��߂炪�d������Ă��B�܂����ⓢ���𖽂���ꂽ�E�߂́A�����ɖd������߂��B��́u��x�ɂ킽��E�߂̗E���ȍs���ƒ��`�́A�܂������L���V�^���̋����ƓV��ւ̐M�S�̎����ł���v�Ɨ������A�M����F�߉E�߂��͂��̂ł������B
����i�̔w�i��
�@�����̍��R�E�߁i1552�|1615�j�́A�x�d�Ȃ�א��҂̈����ɂ��������M�S���Ȃ��Ȃ��������A���̂��߁A���ɂ͍��O�Ǖ��𖽂����A�t�B���s���ŖS���Ȃ����B�@�����u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�̉E�߂́A�Ō�ɒ邩��g�M�����������h�Ƃ��낪����Ă���i��̃��f���́A�L�b�G�g�Ɠ���ƍN���낤�j�B
�@����͂�͂�A�J�g���b�N����T�C�h�ō��ꂽ���ꂾ���炾�낤���B�u�s���̐M�S�͍Ō�ɂ͏�������v�Ƃ����X�g�[���[�d���́A�z���̖ړI�ɉ��������̂��낤�B
�@�V���E�x�b�J�[���́A�u���̍�i�́A�x�l�f�B�N�g�C���@��wBenediktiner Universitaet�i���U���c�u���N��w�j�̑��ƋL�O�ɏ㉉���ꂽ���̂ł��v�Ƌ����Ă��ꂽ�B
�@�����́A��w�̌��ւƘL�����g���čs��ꂽ�B�����ł́A���N�A�w���������A���Ǝ��ɃJ�g���b�N�ɓZ���@�������㉉���銵�킵�ɂȂ��Ă����̂ł���B
�@��w�̃��g���b�N�i�C���w�j���t�t���[���A���E���C�q�X�V�[�Q���́A1770�N�̑��Ɖ��ڂɍ��R�E�߂����グ�悤�Ǝv�����B�E�߂̂��Ƃ́u�C�G�Y�X����{�z���j�v�̃h�C�c���i�o�U���g���A17���I �o�Łj�Œm���Ă����B�ނ́A�u�y���ޕ����̉ʂĂɍ��R�E�߂Ƃ����h�i�ȃL���X�g���k�������B�ނ͈א��҂̓x�d�Ȃ鈳���ɂ��������M�����т��ʂ����B���ɃC���p�N�g����b�ł͂Ȃ����B����́A�K����A�L���X�g�҂Ƃ��Ă̊w���̐��_�ɗE�C�Ɗ�]��^������̂��v�ƒ��������B
�@�ނ͏C���@�Ő��X�̎����ɓ�����B�ꍇ�ɂ���Ă͋{��܂ŏo��������������Ȃ��B���ׂ�ɂꕨ�ꂪ�`����Ă䂭�B���ۂ̉E�߂́A���Y�ɏ�����邪�A�����̍�i�ł͒�Ɏ͂���鏟���҂ɂ��悤�B���̂ق����w�������̂��߂ɂȂ�B�����̒����͊m�M�ɕς���Ă������B
�@���y�́A�{��y�c���̃~�q���G���E�n�C�h���i1737�|1806�j�Ɉ˗������B�{��ŏ@�����y�Ɋ���Ă����n�C�h���́A�Z���ԂŌ����ȉ��y�������B�������āA���C�q�X�V�[�Q����{��M.�n�C�h�����y�̏@�����u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�vTitus Ukondonus�́A1770�N8��31���A�U���c�u���N�̃x�l�f�B�N�g�C���@��w�ŏ������ꂽ�B���̂Ƃ����[�c�@���g�̓C�^���A���s�̍Œ��ŁA�U���c�u���N�ɂ͂��Ȃ��B�ނ̖ڂɐG���̂͗��N1771�N�ł���B
 �@�V���E�x�b�J�[�����A���{�㉉�̂��߂Ɏ�����T�������ʁA��{�̓U���c�u���N��w�A�y���͐��y�[�^�[�m�@�i�x�l�f�B�N�g�C���@�j�ɂ������B�Ȃ�ƕʁX�ɕۊǂ���Ă����̂ł���B
�@�V���E�x�b�J�[�����A���{�㉉�̂��߂Ɏ�����T�������ʁA��{�̓U���c�u���N��w�A�y���͐��y�[�^�[�m�@�i�x�l�f�B�N�g�C���@�j�ɂ������B�Ȃ�ƕʁX�ɕۊǂ���Ă����̂ł���B�@�V���E�x�b�J�[���͂�������Ă���B
��{�Ɋւ��ẮA���炷������̃v���O�����ƃI���W�i�����M��{�����y�[�W�����������ł������A������ꂽ��{�����S�Ȍ`�Ŏc���Ă��܂����B����͓����Ƃ������ϒ��������ƂŁA���ɍK�^�ł����B�y���́A�����ȂƃV���t�H�j�A�i�nj��y�ȁj�����ꂼ��Q�ȂÂ���܂����B�����P�ȁA�����o���G�p�̃V���t�H�j�A���n���K���[�ɂ��邱�Ƃ��������܂������A�㉉�ɂ͊Ԃɍ����܂���ł����B����́A�o���G�S���̋��t���n���K���[�l���������߁A�̋��Ɏ����A�������̂Ǝv���܂��B�@���ꂾ���̎������W�߁A���{���{�i��F���c�G�i���j����艹�y�ƂƂ��ɍČ��㉉�����V���E�x�b�J�[���v�Ȃ̏�M�Ɠw�͂Ɋ��t�ł���B
�@�@�����u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�̊y���́A���y�[�^�[�m�@�̎������ɂ������B����́A���炭�A�~�q���G���E�n�C�h�������[�c�@���g�Ɍ������ケ���ɕۊǂ������̂��낤�B�Ȃ��Ȃ�ނ͂������y�[�^�[�m�@����ɖ����Ă��邩��ł���B
�@�Ȃ��A���̊y�������[�c�@���g�������؋��͎���́u�N�����m�v�ŁB
2012.12.10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��2�`���[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h��
���O�����@�ǂ��l�߂�ꂽ��c�����̊R���Ղ����U�ŁA���Ԃ͑I�����[�h�ɓ˓����Ă��܂��܂����B12���̐��}���Ђ��߂��A�O�㖢���̎��ԁB��̂ǂ��ɓ��ꂽ�炢���̂��A�}�X�R�~�������Ή��ɑ哶�ł��B
�@�����^�}�̖���}��CM�Ŗ�c�����́u��N�]������b������ĕ��������Ƃ������܂��B���Ǒ厖�Ȃ��Ƃ͌��߂邱�Ƃł����B���{�̂��Ƃ��l���̂��Ƃ��������̂͌��f�ł��v�Ɣ\�V�C�ɑi���Ă��܂��B�厖�Ȃ͉̂������߂����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł����B�����Ȃ̋؏����ǂ���Ɂu����Ŗ@�āv��ʂ��A���̂܂܂ł͖�c���낵�ɑ����Ď����̑��݂��낤���Ȃ邩����U�����B���������ꂾ���̂��Ƃ��u���f�v�Ȃ�ĈВ����ė~�����Ȃ����A�u�l���v���Ȃ�āA���ꂱ���傫�Ȃ����b�ł��B
�@����������̎����}�́u���{�����߂��v�̘A�āB���߂����āA2009�N�������ȑO�ɂł����H �G�̎����ŕ��������Ă��邾���Ȃ̂ɁA����͉��̔��Ȃ������������v�����Ȃ�����Ȑ��}�ɁA�N��������[�����܂������ȁB
�@��猩�n���ɁA����ɂȂ�̂͂�͂苴���O�ł��傤�B���̓�d�\���̖��������̂��ߕ{�m���ɂȂ����B�s�Ɗ|�����������������Ȃ��̂ŁA���S��m���ɂ��Ď����͎s���ɂȂ��ĉ��v��i�߂Ă���B��̂��ꂾ���̗L�����s�̐����Ƃ��ǂ��ɂ���ł��傤���H �����A��~�̉�̐Ό��T���Y�Ƒg�̂͑厸�s�������H
�@�͂Ă��āA���̖��\�L�̗���͉ʂ����Ăǂ��Ȃ�܂����H ���ƈ�T�ԂŌ��ʂ��o�܂����A����͂��Ă����A�{��ɖ߂�܂��傤�B
�����[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h����
�@1756�N�A�U���c�u���N�ɐ��܂ꂽ���[�c�@���g�i1756�|1791�j�́A�킪�q��V�˂ƌ����������E���I�|���g�i1719�|1787�j�ɂ���ĉp�ˋ�����{����A���̍˔\�ɖ������|���Ă䂭�B13�̂Ƃ��ɂ́A�����Ȃ���U���c�u���N�{��y�c�̃R���T�[�g�}�X�^�[�ɂȂ�B���̂Ƃ����͕��y���ŁA�y���̓~�q���G���E�n�C�h���i1737�|1806�j�������B
 �@�~�q���G���E�n�C�h���́A���[�[�t�E�n�C�h���̎���B26�ŃU���c�u���N�{��y���ɂȂ�A�Ȍ�S���Ȃ�܂ł����ɐ��������B���������āA���[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h���́A1763�N����1781�N�܂ł�18�N�ԁA�����E��̉��y�Ɠ��m�Ƃ����ԕ��ł������B
�@�~�q���G���E�n�C�h���́A���[�[�t�E�n�C�h���̎���B26�ŃU���c�u���N�{��y���ɂȂ�A�Ȍ�S���Ȃ�܂ł����ɐ��������B���������āA���[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h���́A1763�N����1781�N�܂ł�18�N�ԁA�����E��̉��y�Ɠ��m�Ƃ����ԕ��ł������B�@�������A��l�̊W�͎��ɗǍD�������悤���B�P�b�w����444�Ԃ�ł������[�c�@���g�̌����ȑ�37�ԃg�����́A�ߔN�̌����ɂ��A���[�c�@���g����Ȃ����̂͑�1�y�͂̏��t�������ŁA���Ƃ̓~�q���G���E�n�C�h���̂��́A�Ɣ��������B��Ȏ�����1783�N�����c����1784�N�E�B�[���ƒ�������Ă���B���炭�A�E�B�[���ł̗\�t������ŋ}篃V���t�H�j�[���K�v�ɂȂ�A�n�C�h���ɍH�ʂ��Ă�������̂��낤�B�����1783�N�A�~�q���G���E�n�C�h�����A�U���c�u���N�{��Ńs���`�̂Ƃ��ɁA���[�c�@���g����d���t�Ȃ������Č����߂��Ă�������Ԃ��Ƃ������Ă���B�F�D�̏ł���B
���e�B�g�X�E�E�R���h�m��
�@�U���c�u���N�ɂ́A���[�c�@���g�̎ړx�ɂ��A�u���Ȃ��Ƃ�����ƌĂׂ�v�K�͂̂��̂͂Ȃ������i1781�D5�D26�́u�莆�v���j�B�������A�W���O�V���s�[�����㉉������x�̏����͂���������A�n�C�h��������p�ɂ������̍�i�������Ă���B���̒��̈�Ɂu�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v���������B
�@�~�q���G���E�n�C�h����Ȃ́u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�́A���̖��̂Ƃ���L���V�^���喼�E���R�E�߂���l���Ƃ����@�����ŁA����E��{�̓t���[���A���E���C�q�X�V�[�Q���B�����́A1770�N8��31���A�U���c�u���N�ōs��ꂽ�E�E�E�E�E�Ƃ܂��A�m�肤�邱�Ƃ͂��ꂭ�炢�B���ɏ��ʂ����Ȃ����A���_CD��DVD���Ȃ��B
�@�Ƃ��낪���ŋ߁APC�������Ă�����A�u���R�E�߂Ƃ҂������v�i���F�v�ۓc�T�F���j�Ȃ�Site�ɂԂ������B�����ɂ́A�Ȃ�ƁA�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�����{�ŏ㉉���ꂽ�Ƃ̏�f�ڂ���Ă����B
�@2002�N12��1���A���s�{�u�{���̐X�Ђ悵�v�ɂ����āA��K�L�����V���E�x�b�J�[�v�Ȃ̊��Łu�e�B�g�X�E�ߓa�v�̓��{�������s��ꂽ�Ƃ����B����͖]�O�̏��ł���B���҂ɕ����Ώڍׂ����߂邩������Ȃ��B
�@12��8���A������K�L������Ƀ��[���E�E�E�E�E�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�̂P���炷���A2�o��l���A3�\���A�S�㉉���ԁA5�A��{��ƃ��C�q�X�V�[�Q���̂��ƂȂǂ������Ăق����ƁB����ƁA���������A�ԐM���͂����B
�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�́A���̕v�V���E�x�b�J�[���U���c�u���N�̃C�G�Y�X��̎�����T�������ɏo�Ă������̂ł��B2002�N�̓��{�����́A�v���ďC���܂����B�����̓��e����ŁA�̂��Ƀh�C�c���܂������A����������{��ď㉉�����̂ł��B�t���㉉�ɂ�4�C5���Ԃ�����悤�ł����A������2���Ԓ��x�ɒZ�k���ď㉉���܂����B
�����̍����Ȃ����[�c�@���g�͈��u���N�C�G���v�Ɉ��p���Ă��܂��B�܂��A���[�c�@���g���u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v���Ă����Ɖ����œǂ��Ƃ�����܂��B������ɂ��Ă��A���̌��͕v�̕����ڂ����̂ŁA�ł��邾���߂������ɂ܂��A�����܂��B
 �@���ɂ��肪�������Ή����BHP�ɂ��ƁA��K�L������͐��y�Ƃł��苞�s�͒O�g�Ɂu�݂Ƃ����v�Ƃ����h�C�c�E�J�t�F���o�c�A�R���T�[�g�A�S�l���̉�A���|�����Ȃǂ��܂��܂Ȋ�������搄�i���Ă���������B����l�̃f�g���t�E�V���E�x�b�J�[���̓h�C�c�l���{���j�w�ҁB����l�́A�s�̋߂��R������n�ŁA���ƕ����ɍ��������L�Ӌ`�Ȋ�����^���ɑ����Ă�����̂��B
�@���ɂ��肪�������Ή����BHP�ɂ��ƁA��K�L������͐��y�Ƃł��苞�s�͒O�g�Ɂu�݂Ƃ����v�Ƃ����h�C�c�E�J�t�F���o�c�A�R���T�[�g�A�S�l���̉�A���|�����Ȃǂ��܂��܂Ȋ�������搄�i���Ă���������B����l�̃f�g���t�E�V���E�x�b�J�[���̓h�C�c�l���{���j�w�ҁB����l�́A�s�̋߂��R������n�ŁA���ƕ����ɍ��������L�Ӌ`�Ȋ�����^���ɑ����Ă�����̂��B�@����̃e�[�}�ŁA�ő�̓�ւ́A���ʂ̏��Ȃ��u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v���̂��̂ł������B���ꂪ�Ȃ�ƁA���{�ŏ㉉�������ƃ��[���������o�����̂ł���B�Ȃ�Ƃ����F�낤���B�����m�炸�̈ꉹ�y�t�@���̔��M�ɑ����ӂ������Ă�����������������K�L������ɁA�S���犴�Ӑ\���グ�����B
2012.11.25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��1�`�^�~�[�m�͍��R�E�߂��H
�@�u�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v�́A���̂Ƃ��낵�炭�A�{���̃N���V�b�N�E�l�^���牓�������Ă��܂��B�u���m�Ƃ̑����v�Ɩ��ł����ȏ�A�u���m�v�Ȃ���̂̒T���łȂ���Ȃ�Ȃ����炵�Č����݂ȃN���V�b�N�_�ł͊Ŕ|��ɂȂ�A�Ə��������l���Ă��܂��B������l�^��͎d�����Ȃ��I�H�@����́u�w���J�x�ɂ͍��R�E�߂�����ł���H �v�ł��B���[�c�@���g�̌���I�y���ƃL���V�^���喼���ǂ��łǂ����т����B �͂����Ă����ɂ��A�u�N�����m�v���_�͂����Ȃ���H
���u���J�v�̖`����
 �@�u���J�vK620�̓��[�c�@���g�i1756�|1791�j�ŔӔN�̃W���O�V���s�[���B�W���O�V���s�[���͑�O��y���y���̂��ƂŁA���{��ł͈ꗥ�ɉ̌��Ƃ��Ă��邪�A�̌��Ƃ͂��Ȃ����قɂ���B���`�^�e�B�[���H�̑���ɑ䎌���g���A��ނ��y�߂ŁA�ނ���~���[�W�J���ɋ߂��B���ꂪ���[�c�@���g�̎�Ɋ|����ƁA��y�����͂�܂܌|�p��i�ƂȂ�B
�@�u���J�vK620�̓��[�c�@���g�i1756�|1791�j�ŔӔN�̃W���O�V���s�[���B�W���O�V���s�[���͑�O��y���y���̂��ƂŁA���{��ł͈ꗥ�ɉ̌��Ƃ��Ă��邪�A�̌��Ƃ͂��Ȃ����قɂ���B���`�^�e�B�[���H�̑���ɑ䎌���g���A��ނ��y�߂ŁA�ނ���~���[�W�J���ɋ߂��B���ꂪ���[�c�@���g�̎�Ɋ|����ƁA��y�����͂�܂܌|�p��i�ƂȂ�B�@�u���J�v�́A�G�}�k�G���E�V�J�l�[�_�[�i1751�|1812�j�Ƃ����j����̈˗��ŏ����ꂽ�B�ނ͑�O���c�̎�ɎҌ��o�D�B���{�ł����A��{�f������~��x���Y���B�����́A1791�N9��30���A�E�B�[���̃A�E�t�E�f�A�E���B�[�f������ōs��ꂽ�B���̐V��W���O�V���s�[���͑�q�b�g�A������Ō_������Ă�����A���[�c�@���g�̌��ɂ͂��Ȃ�̑�����]���荞��ł����͂��ł��邪�E�E�E�B
�@��l���̒j���̓^�~�[�m�i�e�m�[���j�ƃp�~�[�i�i�\�v���m�j�B�^�~�[�m�̓p�~�[�i�Ɉ�ڂڂꂷ�邪�A�����͎̂p�G�B�܂�͎���G�ŁA���ʂ��肦�Ȃ��b�B�ł����́u�p�G�̃A���A�v�̔������͔�ѐ�ŁA����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悭�Ȃ�B���[�c�@���g�̉��y�ɂ͂��肦�Ȃ��b�����ۂݍ���ł��܂����͂�����̂��B�u���J�v�ɂ͂���ȃ��[�c�@���g�E�}�W�b�N���[�����Ă���B
�@�p�~�[�i�ɂ͖�̏����Ȃ��e�����āA�ޏ����^�~�[�m�Ɂu�킪���p�~�[�i�̓U���X�g���Ƃ����Ɉ��l�Ɏ����Ă���B���ɍ��ꂽ�Ȃ�~�o���Ă���v�ƍ���B�g�`�����Ă�����͗E�Ȃ��Ȃ�h�ƁA�^�~�[�m�̓U���X�g���̊قɌ������B�Ƃ��낪��������r�b�N���V�B�U���X�g���͐��҂ŁA���Ȃ͖̂�̏����Ɣ����B���̂����Ȃ�̋t�]����������̋c�_���ĂԁB
�@�U���X�g���́A���^�ȃp�~�[�i�����ȕ�e����u�����Ă����̂ł���B�����ē�l�́A�U���X�g��������钆�A�����̃X�e�b�v���삯���A���݂ɒB����̂ł���B���f�^�V���f�^�V�Ƃ��������B
�@��{�͌��c��Ɏ҂̃V�J�l�[�_�[�B���[�c�@���g�Ƃ̓U���c�u���N���ォ��̒m�荇���œ����t���[���C�\���̒��Ԃł���B���݂ɁA���݂ɏ��Ƃ̓��C�\���̍��ʂɏ��Ƃ����Ӗ��������B���̃I�y�����@���Ƀt���[���C�\���Ɗւ��Ă��邩�ɂ��ẮA�W���b�N�E�V���C�G���u���J�`�鋳�I�y���v�i�����Ёj�ɏڂ����B
�@���Ď������Ƃ����̂̓��C�\���Ɋւ��Ăł͂Ȃ��B���ɒP���ȂƂ���B�u�Ȃ���l���^�~�[�m�����{�̎���𒅂Ă���̂��v�Ƃ����_�ł���B
�@���Ȃ��I���ƁA���^�~�[�m���o�ꂷ��B���̕����A�I���W�i����{�ɂ́u����т₩�ȓ��{�̎�߂𒅂����q�v�Ƃ����w��������B
�@�Ȃ��A�킴�킴�u���{�́v�Ȃ̂��B����ɂ͂Ȃ�炩�̗��R������͂��ł���B�Ƃ��낪���̕����Ɍ��y�����L�q�Ɏ��͂��ڂɂ����������Ƃ��Ȃ��B����������A�u��{�ɂ͂����w������Ă��邪�A���ۂɂ́i����́j�Ñ�G�W�v�g�ł��邩�疳�Ӗ��ł���v�i���y�V�F�Њ��u���ȉ���S�W�v�j�Ƃ����̂�����B���Ӗ��ƌ����̂͂�������ǁA�Ȃ�A�g���̓��{�Ȃ́H�h�Ƃ����^�₪�����Ȃ��̂��낤���A�Ǝ��Ȃ͎v���̂ł���B
�����R�E�߁�
 �@���R�E���i1552�|1615�j�͐ےÂ̍��̃L���V�^���喼�B���e���L���V�^������������12�̂Ƃ��ɐ�������B���疼�̓��X�g�i���`�̐l�j�B
�@���R�E���i1552�|1615�j�͐ےÂ̍��̃L���V�^���喼�B���e���L���V�^������������12�̂Ƃ��ɐ�������B���疼�̓��X�g�i���`�̐l�j�B�@�C�������h�i�ȃL���X�g���k�ŁA�z���ւ̏�M�������A�̓��̎��Ђ�����ɕς��ĐM�҂𑝂₵���B�X�y�C���l�鋳�t���A�ےÈ�т̃L���X�g���k�̑����Ƀr�b�N�������A�Ƃ����L�q���c���Ă���قǂ��B1587�G�g�̃o�e�����Ǖ��߂ɂ�1614�ƍN�̃L���V�^�����O�Ǖ��߂ɂ����������@�������߁A�y�n���Y�S�Ă������}�j���ɗ�����A�����ŖS���Ȃ����B
�@���R�E�߂́A�ꐶ�U���h�i�ȃL���X�g���k�Ƃ��đS�������B���̌����M�S�́A�V���l�������W���邱�Ƃ͏o���Ȃ������B�X�ɁA�ނ́A��X���l����ȏ�ɃL���X�g���Љ��̐M�C�����������B�Ƃ������ނ���،h�̔O�������Đ��߂�ꂽ�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B��F�@�فA�����s���A�呺�����A�L�n���M�ȂǁA�L���V�^���喼�͐��X����ǁA�E�߂قǐ����L���X�g���Љ�ɂ��̖����Ƃǂ낢�Ă����҂͂��Ȃ��B�ȉ��ɂ��̗���L���B
�@���ꉳ�F���u���R�E�߁v�i�u�k�Ёj�ɂ́A����Ȉ�߂�����B�u�E�E�E�E�E�Ƃ���ŁA��������̕Ԏ��̑���Ƀ��[�}���痈���̂́A���c�V�N�g�D�X5���i1585�|1590�݈ʁj�̃��e����̏��ȂŁA�����Ƃ��Ă̌o�����̂ĐM��������E�߂ɑ���A���������g�ɗ]��^���������A�˂����̂������B�E�߂͂��̏��Ȃɒl���Ȃ��Ƃ��̂���v���A���[�}�ɂ����āA���̂ꂪ�����͖���m��ꂽ�M�҂ł���̂��A���g���L�����v�����v�B
�@���̉ʂĂ̓����̈��̑喼�ɁA�J�g���b�N���{�R�̍ō����Ђ���^���̏��Ȃ��͂����̂ł���B�E�߂̑��݂͋��c�����F�߂�Ƃ��낾�����̂��B
�@��c�W�F���u�������R�E�߁v�i�t�z���Ɂj�ɂ́A�E�߂��t�B���s���E�}�j���ɓ��������Ƃ��̌��n���̌��t������B�u�E�R���h�m�A�M���̉p�Y�I�ȍs�������[���b�p�܂Œm��킽���Ă����A���o�̌h�ӂ�����܂��B������̐l���}�j���Ɍ}���邱�ƂɂȂ����̂͂��̏�Ȃ����h�ł��B�C�X�p�j�������̖��ɂ����đҋ��������܂��v�B�����t�B���s���̓X�y�C���́B�Ȃ�Α��͖{���ł̉E�߂̔F�m�x���n�m���Ă����킯�ł���B
�@���҂��ꂽ�E�߂��������A�}�j��������40����Ɏ��S�����B���̂Ƃ��A�}�j�����̏����ł��炳��A�Ǔ��̃~�T��9���Ԃ��������Ƃ����B
�@������A�����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����������B�Ƃ���̓X�y�C���A�o���Z���i�ߍx�}�����[�T���A���̐��C�O�i�V�I�����ɁA���R�E�߂̃��U�C�N�悪�f�����Ă���Ƃ����B�L���X�g���̕��y�ɐs������50�l�̐��E�҂̈�l�Ƃ��āB�Ȃ����̉�́A�C�G�Y�X��m�}���e�B�E�R���l�X�ɂ��A20���I�����ɕ`���ꂽ���̂ł���B
�@������A���R�E�߂́u���J�v�Ƃǂ��łǂ����т��̂��H �����͎���́u�N�����m�v�ŁB
2012.11.05 (��) ���G���Ō�̑䎌�Ɍ����܂����킯
 �@�f�������O�A�u���Ȃ��ցv�֘A�̃e���r�ԑg�͌G�Ȃ������B������6�N�Ԃ�̉f��ɋC�������g�������炾�B���ł��������߂Ė�����ނ��������Ƃ���NHK�u�v���t�F�b�V���i���v�́A����Ԃɂ킽��͍�ŁA����͂����u���Ȃ��ցv���蒼�O���`���C�L���O���Ԃ̗l���������B���̒��́u�����̐l�����́A������݂ł���ƍ߂��B���Ă���v�Ƃ����i���[�V�������������������B���������A�f����ς����Ƃ����̈Ӗ����悭�͂߂Ȃ������B�O��u���o�Ǐ�̂Ȃ��Y�ꕨ�v�ƌ������̂͂��̂��Ƃ������B
�@�f�������O�A�u���Ȃ��ցv�֘A�̃e���r�ԑg�͌G�Ȃ������B������6�N�Ԃ�̉f��ɋC�������g�������炾�B���ł��������߂Ė�����ނ��������Ƃ���NHK�u�v���t�F�b�V���i���v�́A����Ԃɂ킽��͍�ŁA����͂����u���Ȃ��ցv���蒼�O���`���C�L���O���Ԃ̗l���������B���̒��́u�����̐l�����́A������݂ł���ƍ߂��B���Ă���v�Ƃ����i���[�V�������������������B���������A�f����ς����Ƃ����̈Ӗ����悭�͂߂Ȃ������B�O��u���o�Ǐ�̂Ȃ��Y�ꕨ�v�ƌ������̂͂��̂��Ƃ������B�����G�������̈ꌾ��
�@�u�v���Ԃ�ɂ��ꂢ�ȊC�Ό����v �f��̏I�ՁA���G���������Y��Y��������̑q���p��ɂ��������B�q���̊�]������őD���o���A�����U�����I���ĉ��D��������̑䎌�ł���B
�@�{�Ԍ�A������͑�ꂳ��̉��Z�ɗ܂��Ă����������B�u�Q�����ˁB�w�v���Ԃ�Ɍ����x�Ƃ������Ƃ́A�C�͂������ꂢ�������艸�₩�Ƃ�����Ȃ��Ƃ������ƁB�����ƌ����������苰�낵�������肷��B�ꌩ�����Ɍ����锖���Ƃ��������ȋ������A���͌��������ɂ���Ƃ��������B�����ŕ�炷�l�X�̋C�����B����Ȏ����S�������̑䎌�ɘU���Ă���B��ꂳ��͂�������̂̌����ɕ\�������B�����˂��B���҂��Ă���Ȃ��Ƃ��ł��鏤���ȂB���������Ȃ��ˁB���ꂩ�炠�̋��n�ɍs���邩�ǂ�������Ȃ����ǁA�撣�肽���ˁv�ƁB
�@��ꂳ��̖����͔��[�Ȃ��O�ꂵ�Ă���Ƃ����B�䎌�������O�ɂ��̖��ɐ��肫��B�q�{ ���́u��ꂳ��́A�h���}�w�����̃z���J���x�̂Ƃ��A�B�e�O�̐����ԎD�y�̊X�p�Ōx�@���̎d�������ۂɂ���Ė����������v�ƌ����Ă����B�܂��͖��ɓ�������B���̂��̂ɂȂ�B���Ƃ͎��R�ɑ䎌�����������B�Ȃɂ����K�v�͂Ȃ��B�����������҂������B
�@�u���Ȃ��ցv�ł����̒Z���䎌���������߂ɁA�~���ēƓO�ꂵ�ċl�߂�f�����c���Ă���i8��25�����f�e���r�����u��Ȃ��Ȃ��ց|���q���v�j�B�u�݂�Ȍ��ɂ͏o���Ȃ����ǁA����_�ł͈�v���Ă��ł��ˁv�Ƒ��B�u�����A�ǂ����Ƃ����邽�߂ɂ͈������Ƃ����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ƃ������Ƃł��v�ƊēB�[�����Ė{�ԂɗՂ�ꂳ��̑䎌�Ɍ����܂����E�E�E�E�E�����������ꂾ�����B
�@�ē͖��_���̃V�[���̔w�i�͒͂�ł���B�����ǂ�ł��邩�炾�B�Ƃ��낪�A���Ƃ肩���ꂳ��͓ǂ�ł��Ȃ�����������B������ē��g����܂�������h�����݂��̂ł���B
�@�Ƃ������Ƃ́A�����ǂ�łȂ��ϋq�́A���̏�ʂ̈Ӗ��������悭������Ȃ��B��͂肱��͖�肾�B
����Y��Y�Ɠ쌴�T��̊W��
�@����ɂ����ĉf��ŃJ�b�g���ꂽ�傫�ȃV�`���G�[�V�����̈�́A��Y��Y�Ɠ쌴�T��i�����_�s�j�̊W�ł���B�쌴�͑�Y��Y�̓d�b�ԍ���������������q���ɓn���Ƃ��A��Y�ɂ͐W��Ƃ������q�����邱�Ƃ�b���B�����ɒ��������Ƒq���́u�W��͓쌴�̐e�F�ŁA7�N�O�ɕv�w���X�C�ő�����v���Ƃ�m��B��Y�͑��q�v�w���C�Ŏ������Ă���̂ł���B�u�v���Ԃ�ɂ��ꂢ�ȊC�Ό����v�́A���̂��Ƃ����܂����䎌�������̂��B��Y�̒��ő��q�̎��������ꂽ�̂ł���B
�@�q���̎U���̐\���o���A��Y�͈�x�͒f��B�u�U������Ή�����͋M���̉Ƃ̕�ɂ͓���Ȃ��B���͋���ۂ̕�����Q�肷�邱�ƂɂȂ�B����ł������̂��B���ӂ������l���Ȃ����v���A���̗��R���B�������S�������q���ɑ���Y�͊��őD���o���B���̉ߒ������܂�����Y�̑䎌�������B�u���ꂢ�ȊC�Ό����v�̗��ɂ́u���̂��A�Łv������̂��B���̌o�܂��f��ɂ͂Ȃ��B�ϋq�́A��Y����U�f�����{���̗��R������Ȃ��B����ɂ���g�S���̂₳�����h�ł͂Ȃ��A�f��ł́g��ł��h�����������Ȃ��B������A���̑䎌�̂��[���Ӗ����͂߂Ȃ��B
���쌴�T��5���~�����̂����聄
 �@����ɂ����Ȃ��A�����A�f�悪�J�b�g�����d�v�ȃV�`���G�[�V�����͂��������B����́A�쌴�T�ꂪ4�N�O���疈����������5���~�𑗋����Ă��邭���肾�B�ǂ��ւ��͍Ō�܂ŏ�����Ȃ��B�����A�쌴���_�葽�b�q�i�]�M���q�j�̎��͂��̕v�Ɣ��������Ƃ��A�ǂݎ�́A�����͑��b�q�̂Ƃ���ȊO�ɂ��肦�Ȃ��ƋC�Â��B�����A�G���߂�����Ƃ�����E�ɂ����Ƃ�����A�쌴�͑��b�q�̂��Ƃɑ����������Ă���̂ł���B
�@����ɂ����Ȃ��A�����A�f�悪�J�b�g�����d�v�ȃV�`���G�[�V�����͂��������B����́A�쌴�T�ꂪ4�N�O���疈����������5���~�𑗋����Ă��邭���肾�B�ǂ��ւ��͍Ō�܂ŏ�����Ȃ��B�����A�쌴���_�葽�b�q�i�]�M���q�j�̎��͂��̕v�Ɣ��������Ƃ��A�ǂݎ�́A�����͑��b�q�̂Ƃ���ȊO�ɂ��肦�Ȃ��ƋC�Â��B�����A�G���߂�����Ƃ�����E�ɂ����Ƃ�����A�쌴�͑��b�q�̂��Ƃɑ����������Ă���̂ł���B�@������A���b�q�͓쌴�������Ă��邱�Ƃ͔����Ă���B�������܂��đ������Ă���̂�����A�����������������藧���Ă���ƔF�����Ă���B
�@�쌴�i�������_��j�Ƒ��b�q�́A��l���i�����͂邩�j��3�l�ŁA���₩�Ȑ����𑗂��Ă����B���A�쌴�͕����Ȑ����ɖO������Ȃ������̂��A���߂�ꂽ�����b�ɏ���Ď��s�A�傫�Ȏ؋�������Ă��܂��B�����7�N�O�̂���䕗�̓��ɑD���o�����쌴�́A����A��ʐl�ƂȂ����B�����Ȃ���A����̈ӎv�ʼnƑ��̑O����p�������A�̋����̂Ă��̂ł���i����͐e�F�̐W��v�w������鏭���O�̂��Ƃ������j�B�C��ōs���s���ɂȂ����D���́A3�N�o�Ǝ����I�Ɏ��S���m�肳���B���b�q�͕v�̐����ی�������ɐH�����J�Ƃ��A���Ɠ�l�Ŏ����������₩�ɕ�炵�n�߂��B
�@�܂��Ȃ�5���~���U�荞�܂�Ă���B���b�q�͋����B����������������B���͂��̕v�ɈႢ�Ȃ��Ɗm�M����B�����Ă��邱�ƂA���́g���h�ɂ���č�����H���ł��̂܂܂̐������c�ނ��A�{���̂��Ƃ����\���ĕv�̍s����{�����B���b�q�̐S�͗h�ꓮ�����ɈႢ�Ȃ��B��Y��Y�ɂ����k�������낤�B�����ȋ��������炻��ȉ\���L�܂��Ă���\���͏\���ɂ���B�u5���~�����v�̂�����́A�u������݂Ŕƍ߂��B���Ă���v���Ƃ��������d�v�ȃL�C�Ȃ̂ł���B
�@�����ɐ����؍݂��Ă��̂��Ƃ��@�m�����q���́A���b�q�́u���̐l�Ɍ����邽�߂ɁA���̎ʐ^���C�ɓ����Ă��������v�Ƃ̊肢��ق��Ď~�߁A�߁X�������邱�ƂɂȂ������Ɛe�F�̑��q�̈ߑ����킹�̎ʐ^���A�쌴�ɓ͂���B�i�@�s���Ɍg���l�Ԃ��߂��ʼn߂������ƂɌ��߂��̂ł���B�����̐l�X�����L����߂Ɏ��߁A�u���������v�̂ł���B
�@�q���́A�ߋ��Ɍ��ʂ��A����̐i�ނׂ��������o�����B���ꂱ�����Ȃ��]���Ƃł��������̂��B�Ǘ��߂̈⌾�ɂ́A�f��ł́u���悤�Ȃ�v���������A����ɂ͂����������B
�@�@���̊C�ɎU�����Ă��炦����A���悢�悠�Ȃ��Ƃ��ʂ�ł��B�ǂ����A���Ȃ��́A���Ȃ��̂��ꂩ��̐l�����A���R�ɐS�s���܂Ő����Ă��������B����̗��́A�킽���������ɗU���o���܂������A���ꂩ��̂��Ȃ��ɂ́A���Ȃ������́u����v������Ǝv���̂ł��B���̈���ݏo���āA�ǂ�ǂ�f�G�Ȑl�������ł����Ă��������B�@�f��́A�Ȃ̈⌾�ǂ���V���ȑ����ݏo��������̎p�ŏI���B���C�L���O�̃i���[�V�����u������݂ŁA����ƍ߂��B���Ă���v�A���G���̊m�F�u�݂�Ȍ��ɂ͏o���Ȃ����ǂ���_�ň�v���Ă���v�A�~���ḗu�悢���Ƃ����邽�߂ɂ́A�������Ƃ����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��v�́A���X�g�Ɍq���������Ƃ������̐^������Ă����̂ł���B
 �@���_�����ǂݔw�i��m��s�����Ă��邾�낤�����A�Ƃ��Ƃ�ēƋl�߂�100�����ɂȂ肫�ꂽ���̑䎌�u�v���Ԃ�ɂ��ꂢ�ȊC�Ό����v�Ɋ��ɂ܂����̂́A�����ł���̂ł���B������ɂ́A���̑䎌���A��Y���g�̐g�̏���A�����Ƃ��������ȋ����̎��߂����A���C�����A�߂��B���l�X�̑P�ӂ��A���̕���̊j�S�I�v�f���ׂĂ��������Ă���ƕ��������̂ł���B�g�V���Ȉ�����㉟������́h�܂ł����������Ă��ꂽ�̂ł���B
�@���_�����ǂݔw�i��m��s�����Ă��邾�낤�����A�Ƃ��Ƃ�ēƋl�߂�100�����ɂȂ肫�ꂽ���̑䎌�u�v���Ԃ�ɂ��ꂢ�ȊC�Ό����v�Ɋ��ɂ܂����̂́A�����ł���̂ł���B������ɂ́A���̑䎌���A��Y���g�̐g�̏���A�����Ƃ��������ȋ����̎��߂����A���C�����A�߂��B���l�X�̑P�ӂ��A���̕���̊j�S�I�v�f���ׂĂ��������Ă���ƕ��������̂ł���B�g�V���Ȉ�����㉟������́h�܂ł����������Ă��ꂽ�̂ł���B�@�����A�����ǂ�ŁA�n�߂Ă��������邱�Ƃ��ł����B�u������݂Ŕƍ߂��B���Ă���v�Ƃ����Ӗ��������ł����B�������A�f�悾���ł͋C�Â��Ȃ������B
�@�f������Č����ǂ܂Ȃ��l�̂ق����A�ǂސl�����͂邩�ɏ��Ȃ��͂����B�f��͉f��Ŋ������Ă��Ȃ���Ήf��Ƃ��Ă̊����x�͒Ⴂ�Ƃ��킴��Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�f��u���Ȃ��ցv�́A�u�f����Ƃ͉�����H�v�Ƃ��������[�����𓊂������Ă��ꂽ�B
�@10��2���A��Y��Y���̑��G�����S���Ȃ����B���N87�B�u�v���Ԃ�ɂ��ꂢ�ȊC�Ό����v���Ō�̑䎌�ƂȂ����B������́A���̒��O�܂ő�ꂳ��Ǝ莆�̂��������Ă����Ƃ����B�����������F�肵�܂��B
2012.10.25 (��) ���A���Y����胊���V�Y���`�u���Ȃ��ցv���ςēǂ��
 �@����A���q��6�N�Ԃ�̉f��u���Ȃ��ցv�i�~���N�j�ēj���ς��B�Ȃ�S�������j���A�⏑�ɏ]���U���̂��ߔޏ��̐��܂�̋��������B�s����X�Ŋe�l�e�l�̐l����w�����l�����ɏo��Ȃ��祥�������ȃ��[�h���[�r�[���B
�@����A���q��6�N�Ԃ�̉f��u���Ȃ��ցv�i�~���N�j�ēj���ς��B�Ȃ�S�������j���A�⏑�ɏ]���U���̂��ߔޏ��̐��܂�̋��������B�s����X�Ŋe�l�e�l�̐l����w�����l�����ɏo��Ȃ��祥�������ȃ��[�h���[�r�[���B�@�����̃r�[�g���������u��X���ʂ̔o�D�͂Ȃ�₩��Ƃ��Ȃ��Ƃ����Ȃ����A������͂��邾���ł����l�v�ƌ����Ă������A���̂������ɂ������킹�錒����́A�{���̃X�^�[�Ȃ̂��낤�B�u���Ȃ��ցv�́A�����Ɍ����������! ���������f�悾�����B���A�����������ƁA���o�Ǐ�̂Ȃ��Y�ꕨ�������悤�Ȗ��ȗ��������̂Ȃ����c�����܂܂������B
�@����Ȃ�����A�v�X�Ɂu�����E�����v�u���O��`������A�u���Ȃ��ցv�����グ�Ă���B���͍��N�܂������{�����A�ނ͂��̂ق��Ɂu�V�n���@�v�u����ӂ���v�uALWAYS�O���ڂ̗[�f64�v�u�j�̓��v�ȂǁA���\���Ă���B���}���h�����D�~���͂͌��݁I �ǂ�ő����[���̂���������B�����̃p�^�[���B�ނ́u�����ǂl�́A�s������݂����ł��v�ɒ��ځB���삪����̂Ȃ�ǂ�ł݂悤���B���̒��̃���������������邩���m��Ȃ��B
�@����́A�u���Ȃ��ցv�ɂ����錴��Ɖf����̊֘A���l����B
(1) �����ЂƂ̈⌾
�@�f��̒��ŁA�ł��^��Ɋ������̂́u�Ǘ��߂̈⏑�̓��e�v�������B�q���p��i���q���j�͎��l�ɖ؍H��������x�R�Y�����̎w���Z���B15�N�ԘA��Y�����Ȃ̗m�q�i�c���T�q�j�����ŖS�������A�ޏ��̈⌾��2�ʂ������B�⌾�T�|�[�^�[�Ƃ�炩�������P�ʂɂ́u���̈⍜�͌̋��̊C�ɎT���Ă��������v�Ə����Ă���A����1�ʂ͔����X�Ǘ��Ƃ����w�肾�B�����͔ޏ��̐��܂�̋��A���茧���˂̏����ȋ����ł���B�Ƃ��낪�A�x�R�\����̒����̖��A������⏑�ɂ́u���悤�Ȃ�v�̕��������邾���������B
�@���Ȃ��̍��d�|���̖����������ꌾ�ł́u�ǂ����āH�v�ł���B���̕����A�����g���u���܂��ɂȂ����悭�킩��Ȃ��v��NHK�X�y�V�����̒��Ō���Ă���B ������̋^��́A�����̐H���̏���l�_�葽�b�q�i�]�M���q�j�́u�v�w�Ȃ�Ă���Ȃ��̂ł���B����ŏ\������Ȃ��ł����v�Ƃ������t�ŃP���������Ă���B�q���͂��̑䎌�Ŕ[�����邪�A���͂ł��Ȃ��B����͈ȉ��̂Ƃ���B
����u���Ȃ��ցv�i�X�v�̏����A���~�ɕ��Ɂj�̈⏑�@����ȏ����o���Ŏn�܂钷���̈⌾�́u���Ȃ��Əo������Ƃ́A���̐l���ɂ�����ŗǂ̊�Ղł����B�o����Ă���āA�{���ɂ��肪�Ƃ��B�S����v�Ō����B�u���悤�Ȃ�v�ꌾ�Ƃ͂��炢�Ⴂ���B����Ȃ�⍜�ƈꏏ�ɒ�����𑖂����Ӗ�������B�U���ƌ��т��B�[���ł���B�Ȃ̂ɁA�Ȃ��f��ł͂���Ȋ̐S�v�̕������ȗ������Ă��܂����̂��H �����ɂ��̉f����̌������肻�����B
�l���̂����܂��ɁA����Ȃ���������d�|���Ă��܂��Ă��߂�Ȃ����B�ł����������킽���̂��߂ɍ���Ă��ꂽ�L�����s���O�J�[�ł�����A���߂Ĉ�x���炢�́A���Ȃ��Ɓu�ꏏ�Ɂv�������Ă݂��������̂ł��B���̒��ł͐V�����s�̂���Ȃ�ł���B
(2) ����P�v�̏ꍇ
 �@�q�������̍ŏ��ŏo��̂�����P�v�i�r�[�g�������j�B�����Z���t�őO�Ȉ�Ƃ̎ԏ�r�炵�̒j�ł���B
�@�q�������̍ŏ��ŏo��̂�����P�v�i�r�[�g�������j�B�����Z���t�őO�Ȉ�Ƃ̎ԏ�r�炵�̒j�ł���B�@���삪���Z����ɂȂ����̂͋����q�ɂ����킢���s�ׂ����A���͂��ꂪ㩂������Ƃ����ݒ�B���̂�����A�����ł͏ڍׂȋL�q�����邪�f��ɂ͌��Ђ��Ȃ��B
�@�q���Ɛ���A���͊猩�m��B�q�����A�X�Y��������A�؍H�����������l�̈�l�����삾�����B������f��ł̓J�b�g�B
�@����͋����̕��Ƃ������Ȃ���A���ւ܂őq���ɕt�����肾�B�c�{�C�i�i���g���j�ƍ������ĉG���߂�����̎�`���܂ł��邵�i�f��ł͑q�������j�A�q���̎v���o�̒n�A�|�c�隬�ɂ����s���Ă���B�f��ł͂��ׂăJ�b�g�B�|�c�隬�̂�����́A�q���̖��Ƃ����`�ŕ`�����B
(3) �쌴�T��̏ꍇ
�@�쌴�T��i�����_�s�j�͓c�{�̕����B�킯����̒��N�j�ŁA�Ƃ��̂ĂĂ���7�N�o�Ƃ����B�쌴�́A�q������u�����ŎU������v�ƕ����āA�u�D�̂��ƂȂ�A���̐l��K�˂Ă݂���v�Ɠd�b�ԍ��Ɓu��Y��Y�v�Ƃ������O��������������n���B����ɂ́A�����̎��́g�Ȃ������h�Ƃ��邪�A�f��ł͂������ʁB����ɁA�쌴�̊�ɂ͎Ⴂ���댖�܂ŕt�������Ղ�����A�����ł͂��ꂪ�I�Ր�����̂����A�f��̍����_�s�̊�ɂ͏����Ȃ��B ����ł́A�쌴�͖���5���~�����������������Ă���B������͓��R�c���Ă����Ƒ����낤�Ƒz�������B���̂�����A�f��ɂ͂Ȃ����A���͂��̕���������Ɖf��̊֘A���ł��l�������Ă���邱�ƂɂȂ�B����ɂ͂���ɁA�쌴�Ƒ�Y��Y�̐[���W������B
(4) �m�q�Ƃ̏o��ƕv�w��
 �@�q����15�N�O�A���R�Y�����Ζ��̎���ɗm�q�ɏo��B�m�q�͌Y�����Ԗ�̉̎�B�q���͈�ڂڂꂷ�邪�����������Ȃ��B3�x�ڂ̗����̂Ƃ����������琺���|�����A��₠���āA�v���|�[�Y������������ꂪ����B��r�I�n���B
�@�q����15�N�O�A���R�Y�����Ζ��̎���ɗm�q�ɏo��B�m�q�͌Y�����Ԗ�̉̎�B�q���͈�ڂڂꂷ�邪�����������Ȃ��B3�x�ڂ̗����̂Ƃ����������琺���|�����A��₠���āA�v���|�[�Y������������ꂪ����B��r�I�n���B�@�Ђ�f��ł́A���Ȃ��̍��ݒ�����Ă���B���߂Č��t�����킵�����A�m�q�͈ӊO�Ȃ��Ƃ����ɂ���B�u���݂͂Ȃ���̂��߂ɉ̂��Ă͂��Ȃ��B���̂�������l�̐l�Ԃ̂��߂ɉ̂��Ă���B�݂Ȃ���ɉR�����Ă���̂͂��̂тȂ��̂ŁA�~�߂ɂ���v�ƁB���̌�A��l�̎��l���S���Ȃ��āA���̒j���m�q�̈Ӓ��̐l���������Ƃ�������B
�@�v�w���͂��̕���̒��j�𐬂��e�[�}�B�f��ł͂��Ȃ荎���ɕ`�����B���������ۂ��������炢���i�⌾�̕����������j�B
���~���g�̐���Ӑ}���l���遄
�@�ȏ㌩�Ă����f��ƌ���Ƃ̍��ق���A�f�搧��҂̈Ӑ}��T���Ă݂悤�B
(1) �Ǘ��߂̈⏑���u���悤�Ȃ�v�̈ꌾ�����ɂ���ւ����̂́A�X�^�[��������͂Ƀt�H�[�J�X���邽�߂��B ����ł��`��͎ז��A�Ȃ̑��݂�K�v�ȏ�ɖڗ������܂�������Ƃ���Ӑ}���B�����s�������m�̏�ŁA�����܂ō��q���Ƃ����ދH�ȃX�^�[�̘Ȃ܂���D�悵���Ƃ������Ƃ��낤�B
�@ �������A����͂��̉f��ő�̖��_�B�X�^�[�̃X�^�[����R�����ۗ�������ړI�ŁA�d�v�ȃv���b�g�������ĕύX���邱�Ƃ̐�����A�l���������鎖��ƂȂ����B
(2) �r�[�g�������̏o�Ԃ����Ȃ������̂́A�u������̉f��v���������邽�߂ŁA����͂ނ��듖�R�̑[�u���낤�B���C�L���O�Ō����������u�����Ƃ��Ă���ꂿ�Ⴑ���������Ⴄ��v�͝��������{�������X�H �o�D�E�r�[�g�������̑��݊��������̂ł���B
�@����ɖ؍H���������X�Y�����Ɨm�q�Əo���������R�Y�����͕`�����ɁA�Y�����͕x�R�œ���B������������B
�@���삪�S�������c�R���̋傪���̕���ɐ[�݂�^���Ă���B���݂ɁA�ނ̈��Ǐ��ŕʂ�ۂɑq���ɓn���̂́A����ł́u�R����W�v�Ƃ������ɖ{�����A�f��ł́u���ؓ��v�ɕς��Ă����B���̕����[�݂�����B
(3) �쌴�Ɣ����̐ړ_�����̕���̏d�v�Ȋ́B���̈Ӗ��ŁA�q�����_�葽�b�q�����L���邨�݂��u�쌴�̉ߋ��ƌ��݁v���@�m���邽�߂̏�����́A����̂܂c�����ق����悩�����̂ł́H �쌴�̃����̎����g�Ȃ̋����h���ɂ���B��̏������̂܂ܐ������B���̂ق����A�v���b�g���X���[�Y�ɒH��āA�ϋq�ɂ͐e�������Ǝv���B
�@�Ȃ��A�쌴5���~���������̂�����Ƒ�Y��Y�Ƃ̊W�ɂ��Ă͎���ɉ����B
(4) �f��ɂ����āA��l�̓�ꏉ�߂��������܂ŔώG�ɂ���K�v�����������ǂ����B �m�q�̂ق����琺���|�����K�R�����������邽�߂��낤���A��炸�����Ȃł́H
�@����ł́A�m�q�͓쌴�̓������Ƃ����ݒ�ɂȂ��Ă���B����͗m�q�Ɣ����̌q����̍��ՂƂ��ďI�Ղɕ`����邪�A�f��ł́A�����Âт��ʐ^�قŗm�q�̗c������̎ʐ^���������ʂɒu�������Ă���B�����͉f��ő�̌�����ŁA������Ӑg�́u���肪�Ƃ��v�������Ɗ������ĂԁB�m�q�ƌ̋��̂Ȃ���A�q���̍Ȃւ̑z���Ɣ����ւ̊��ӁA�z���o�A���̗���A�i�F�܂ŁA���ݏグ�邷�ׂĂ��u���肪�Ƃ��v�̂������ꌾ�ɍ��߂��B���ɏG��ȏ�ʂł���o�D�E���q���̐^�������B
�@�f��u���Ȃ��ցv�́A���X�܂Łu������̉f��v�������B�~���g�͂��̖ړI�̂��߂��ғ��H�����ׂĔ���������B����䂦�o������l���̐l����`����Ȃ�������A����̒�����]���ɂ������B���A���Y����胊���V�Y��
��������ꂼ�����~���g�m�M�ƓI�f����ł���A����ɖ�������ϋq������B�������̓��̈�l���B���q��81�A�X�^�[�̏��ł���B
2012.10.20 (�y) ����t���Ɛ�t���ƃm�[�x���܂� �����āA�R������
������t���̏ꍇ���@���N���m�[�x�����w�܂��킵������t���́A����ɐ旧��9��28���A�����V���ɐ�t���Ɋւ��Ċ�e�����B�^�C�g���́u���̉��������铹�v�A�v�|�͈ȉ��̂Ƃ��肾�B
��t��肪�ߔM�����钆�A�����̏��X������{�̏��Ђ��������B����20�N����́A���A�W�A�n��ɂ���������Ƃ�������B���̈�͂����ɌŗL�́u�������v���`������Ă������Ƃ��B���́u���A�W�A�������v�̃}�[�P�b�g�͒����ɐ��n���A�����郁�f�B�A����{�I�ɂ͎��R�ɓ����Ɍ�������A�����̐l�X�̎�Ɏ���A�y���܂�Ă���B���ɑf���炵�����Ƃ��B���̂悤�ȍD�܂������o�������邽�߂ɁA�����N���ɂ킽�葽���̐l�X���S���𒍂��ł����B����̐�t��肪���̂悤�Ȓn���ȒB����傫���j�Ă��܂����Ƃ������͋����B �����������݂���ȏ�̓y���͔����Ēʂ�Ȃ��C�V���[���B����������͎����I�ɉ����\�ȈČ��ł���͂������A�܂������I�ɉ����\�ȈČ��łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl����B�̓y��肪�����I�ۑ���āu��������v�̗̈�ɓ��ݍ���ł���ƁA����͊댯�ȏ��o��������B����͈����̐����Ɏ��Ă���B�����͉�肪�������Ɍ�����点�s����e�\�ɂ�����B �������̍s���ɑ��ĕI�s�����Ƃ�Ȃ��ł������������B�����̐����ŁA�����̐l�X�������N���������Č��̂ɂ��ނ悤�ȓw�͂��d�˂Ă����������������铹���A�ǂ��ł��܂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
 �@�u�̓y���͎����I�ɏ������A�����̎�����s���Ɋ���I�ɂȂ邱�ƂȂ��A�����������グ�����A�W�A���������������낤�ƈێ��������悤�v�Ƃ����Ăт����ł���B���E�̃����J�~���������Ƃ���������͂�����̂��낤���A�}�X�R�~�ł͂��̊�e���^���镗���������B�����̃l�b�g��ł��^�̏������݂����Ă���ƕ����B
�@�u�̓y���͎����I�ɏ������A�����̎�����s���Ɋ���I�ɂȂ邱�ƂȂ��A�����������グ�����A�W�A���������������낤�ƈێ��������悤�v�Ƃ����Ăт����ł���B���E�̃����J�~���������Ƃ���������͂�����̂��낤���A�}�X�R�~�ł͂��̊�e���^���镗���������B�����̃l�b�g��ł��^�̏������݂����Ă���ƕ����B�@�����A10��1���A�����̍�ƃG�������J�����A���܂̕��͂��A�A�����J�́u�C���^�[�i�V���i���E�w�����h�E�g���r���[���v���ɊĂ���i���{�ł́uAERA�v10��15�����ɖ|�f�ځj�B
�@���́A�������A���㎁�̍l�����ɂ͎^�������˂�B������傪���Ԃ����g���Ȃ��B�ϔO�I�ŋ�̐��ɖR�����B�����I�ɉ������ׂ��ƌ��������ŁA���̕�������Ă��Ȃ��B�̓y�����u��������v�̗̈�ɓ��ݍ��܂���ׂ��łȂ��Ƃ������A�̓y���ƍ�������͉ʂ����Đ藣������̂Ȃ̂��B�u��������v�������̐����ɗႦ��̂��s�����ł���B�����ɂ́A���l�s�V�Ȓ������Ă���O���v����鈤��Ȃ��B����ɓZ���Č��ɂ͕��S���Ă��A�����̖{����˂��l�߂�C���Ɍ�����B
�@�Ό��T���Y�s�m�����u�����s�͐�t�������܂��v�ƌ������Ƃ��A14���~���̊�t�����W�܂������Ƃ�ނ͂ǂ��l�������낤���B���̍���������A���㎁�͖�������̂��B���w�Ƃ͂���������������ݎ�邱�Ƃ���n�܂���̂ł͂Ȃ��̂��B���̐���͂Ƃ������Ƃ��āB
�@�̓y���͎����ۑ�Ƃ��ď������ׂ��ƌ������A���ꂪ�\�Ȃ炱�̖��͂Ƃ����ɉ������Ă���͂����B�\�łȂ������J���Ă���̂��B�Ȃ��Ȃ�A����͍�������Ƃ͐藣���Ȃ��Č������炾�B�ނ͂��̖{�����������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�̓y�����������邽�߂ɂ́A�u��������v�Ȃ���̂Ɛ��ʂ�����������ׂ��ł���B���ݍ��ނׂ��ł���B�Ȃɂ��O���̐^��������ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�u��������v�̓K�Ȃ��������ׂ��ƌ����Ă���̂��B���ꂪ�����ڐ��̕����l�̖����ł͂Ȃ����B
�@�u��������v�́u�����S�v�ƒu����������Ǝv���B�ނ͂�����u�����̐����v�ɗႦ�邪�A����Ȉ����ۂ����̂ƕ̂�ł����̂��낤���B���߂āA�u���߂Ă��܂��̉̂� �����ň��݂ق��� ��������D�̃f�b�L�ɗ�������������v�i�����݂䂫�u�̕P�v�j���炢�����Ă���Ȃ����B
�@���͂����v���B�u���{�͗̓y������j���ƔF�����邱�ƁB�������ɗ��j�̐^�������邱�ƁB���ɂ������瓱���o�������j�ς�ɂԂ��邱�ƁB���肪����������A���ې��_�ɖ₤���ƁB�����čŏI�I�ɒI�グ�̌`���`�����邱�Ɓv���B���j�̐^���i���������܂߁j�̔F���́A�u��������v�̗̈�ɗ����I���f�����Ă����͂����B���{�l�͔n������Ȃ��̂�����B
�@���㎁�̊�e���ɂ͗��j�ςƖ����ӎ����������Ă���B����͔ނ̍�i�ɂ��\��Ă���B�ނ͍��N���m�[�x���܂����B�I�l������炩�ɂ���Ă��Ȃ��ȏ�A���I�̗��R�͕s���ł���B�����A�����Č��킹�Ă���������A����͔ނ̕��w�ɂ�������j�ςƖ����ӎ��̋H�����ɋN�����Ă���Ǝv���B
�@�f���Ă������A���̓m�[�x�����w�܂Ƃ������̂ɉ��l�����o���Ă͂��Ȃ����A���㎁�̕��w��ے肷�������Ȃ��B����Ӗ��A�ނ̍�i��]��������̂��B���������O��Ă��܂����A�l�����m�̂���肪�G��ŁA�R���g��Ƃ��y�Ȃ��ʔ����������ɂ���B������̂���ߕ����m�I�ş����Ă���B�����v�f���ڂ̏����ł���B���ʁA�i���_�ނ̑S��i��ǂ킯�ł͂Ȃ����j��l���̐������ɂ͋����ł��镔�������Ȃ��B�N�w�����ݍ���Ȃ��i����Ȃ��̂����݂���̘b�����j�B�ʔ����͂��邪�A�S�͑ł���Ȃ��B
�@���N�̎�ҁE�������̎�ܗ��R�́u���o�������A���Y���ɂ���āA���b�A���j�A�����Z���������B�������Ԃꂵ�Ă��Ȃ����j�[�N�ȍ�ƁB�A�W�A�̏d�v�������܂��Ă��邱�Ƃ̕\��Ƃ�������v�i10��12�������V�����j�ł���B
�@�v��A�u�����Ɨ��j�ɗ��r�����Ǝ����v�Ƃ������ƂɂȂ낤���B�u���m���Ԃꂵ�Ă��Ȃ��v�Ƃ��B����H ����͑��㕶�w�̑ɂł͂Ȃ����B�������ꂪ�X�E�F�[�f����A�J�f�~�[�̑I��R���Z�v�g�Ȃ�A���㎁�̎�܂͉i���ɂȂ����ƂɂȂ�B�앗��ς��Ȃ�����B�����łȂ����Ƃ��F��A���N�ɒ��ڂ������B
�@�}�X�R�~�̑Ή����A�z�炵���Č����Ⴈ��Ȃ��B���\���O�܂Ŏ�����悤�ɐ���オ��B�����ɓo�ꂷ��L���҂̕ق��n���n���������̂���B�u���N�͊ԈႢ�Ȃ��B��[�N����������n�߂�7�N�ڂŊl��������v�u�����V���֊�e�������ʂ͑傫���v�u�D�ꂽ�|�����v�ȂǂȂǁB�_����œ��e�ւ̌��y���F�����B��������Ɂu�Ȃ�����t���͍��N�����Ȃ������̂��H�v���炢�̌���������ǂ����B�ǂ����낭�Ȉӌ��͏o�Ă��Ȃ��Ƃ͎v������ǁB
���R���L�틳���̏ꍇ���@
�@�m�[�x���܃E�B�[�N�ő�̃r�b�O�j���[�X�͎R���L�틳���̈�w�E�����w��܂������B��ܗ��R�́AiPS�זE�iInduced Pluripotent Stem Cell�j�̍쐬�ɐ��E�ŏ��߂Đ����������ƁB�l�����y�Ȃ��������n�זE�̏������ł���B�l�̂̍Đ����\�ɂ���܂��ɖ��̍זE�Ȃ̂ł���B����܂ł̈�w����������邱�Ƃɂ�莡���𑣂����̂��Ƃ���A�n��o���čĐ�����̂�����R�y���j�N�X�I�]���ł���B���ꂼ��w�̊v�������A�����̂������ς���̂�����N�w���ς��Ă��܂����낤�B
 �@��܋L�҉�ŎR�������́u�^���͉������̃��F�[���ŕ����Ă���B���B����ɂ͂��̃��F�[�����ꖇ�ꖇ�͂����Ă䂭��Ƃ��K�v���B���͂��܂��܂��̍Ō�̃��F�[�����͂����������B�ŏ��̈ꖇ�����Ă��ꂽ�̂̓W�����E�K�[�h���������A�ނƈꏏ�Ɏ�܂ł������Ƃ͎��Ɋ�����v�ƌ���Ă����̂���ۓI�������B�����̐l�X�̐ςݏd�˂��i���ނ̂ł���B
�@��܋L�҉�ŎR�������́u�^���͉������̃��F�[���ŕ����Ă���B���B����ɂ͂��̃��F�[�����ꖇ�ꖇ�͂����Ă䂭��Ƃ��K�v���B���͂��܂��܂��̍Ō�̃��F�[�����͂����������B�ŏ��̈ꖇ�����Ă��ꂽ�̂̓W�����E�K�[�h���������A�ނƈꏏ�Ɏ�܂ł������Ƃ͎��Ɋ�����v�ƌ���Ă����̂���ۓI�������B�����̐l�X�̐ςݏd�˂��i���ނ̂ł���B�@�����ɒH����ɂ͒n���Ȏ����̌J��Ԃ����������Ƃ��B�זE�ɒ��������`�q��₪24�����������ŁA�������ɕK�v�Ȉ�`�q�̑g�ݍ��킹����肷��ɂ́A������h�������d�˂邵���Ȃ��B�g�ݍ��킹�͓V���w�I���ɋy�ԁB�����ŏ��肪�u�S������Ĉ�{�������Ă����܂��傤�v�ƑM�����B���ꂪ�R�����u�X�̗��������B���Ă����͍̂����a���u�t�B�R���g�`�[�����[�N�̏����������B
�@���p���ɂ͂���ɑ����̎��ԂƘJ�͂��v��B����ɂ͌������̐g���ۏႪ�������Ȃ��B���͖��ʂȋ����g�킸�ɁA�uiPS�זE�������v�ɏ\���ȗ\�Z�𓊓����ׂ����B�\�h�K��̍ہA��c�����́u3�N�O�����t�����Ă��܂��v�ƎR�����ɘb���Ă����B�����ł���݁B������b�̎d���͌l�I�Ȋ�t�������荑�Ɨ\�Z����邱�Ƃ��낤�B
�@�����c���iPS�זE�Ɋ֘A���āA�������������Ȕy�����ꂽ�B��t�Ƌ��������Ȃ����̃n�[�o�[�h��w�u�t�E�X�����j�Ƃ����l���u���N2����iPS�זE���g�����ڐA��p�ɐ��������v�Ɠǔ��V�����`�����̂��B����͖��炩�ȉR�B�Ȃ�����Ȃ����o����R�����̂��B�����ȁH�s���B�����āA������炸�ɏ����Ă��܂����ǔ��V���ɂ����I���B
�@����Ȕy�͘b�ɂ��Ȃ�Ȃ����AiPS�זE�̎�舵���ɂ͐T�d�ł����ė~�����̂ł���B�R���������������f���炵���͓̂��@�������Ȃ��Ƃ��B�a�C�ɋꂵ�ސl�����������Ƃ�����S���BiPS�זE�͗��n�̌��ł��邱�Ƃ͗e�Ղɑz�������B����𗘗p����l�͂ǂ����ϗ��ς��Ȃ��đΏ����ė~�����B�������ɗ����˂Ȃ�Ȃ��̂Ȃ�A���{�͗��悵�Ė@�����̃��[�_�[����ׂ����B�ނ̐��_���ǂ������݂ɂ���Ȃ��ŗ~�����B
�@�R�������͗Տ�����̓]���g�ł���B��t�Ƃ��Ă͎�悪�s��p�ŁA��p�ł͂��ו��������������B�����w�����u�W���}���v�Ƃ��B�����ނ��Տ���t�Ƃ��Đ������Ă�����iPS�זE�̒a���͂Ȃ������B�s�K�i���K�^���^�̂ł���B���̃G�s�\�[�h�̓`���C�R�t�X�L�[��A�z������B�`���C�R�t�X�L�[�͍ŏ��s�A�j�X�g��ڎw�����A�����̏オ��ǂ���X�e�[�W�ł̓~�X�̘A���A���t�ɂȂ�Ȃ��B�w�{�`���C�H �~�ނȂ���ȉƂɓ]���B���̂��A�ŁA���������͔ނ̐��X�̌���ɂ���Ė�����Ă���B�t�]�̐l���Ƃ����̂���X�ɑ傫�Ȋ�]��^���Ă����B
2012.10.05 (��) ��t���̐^���`����͓c���p�h�̕s�p�ӂȔ�������n�܂���
 �@��3����c���t�����������B�ڋʂ͓c���^�I�q�����Ȋw��b���������B�Ȃɂ��A��������̃~�X�W���b�W�ŏ����������Ƃ̊W�����������ł��D�]���������v�f�����邻���ȁB
�@��3����c���t�����������B�ڋʂ͓c���^�I�q�����Ȋw��b���������B�Ȃɂ��A��������̃~�X�W���b�W�ŏ����������Ƃ̊W�����������ł��D�]���������v�f�����邻���ȁB�@��X����ł́A�c���^�I�q�Ƃ����Ε��e�E�p�h��z���N���͎̂��R�ȗ��ꂾ�B�c���̖��O�͓��������̌��J�҂Ƃ������ƂŒ蒅���Ă���B���A�������A���݂̗����̊W�͍ň��̏�Ԃɂ���B�Ȃ�����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��H �u���̌��_�͓c���p�h�{�l�ɂ���v�Ƃ����̂��A����̖���N���B�c���^�I�q�͉������t�̗��n�̌��Ƃ����Ă��邪�A���e�͂��ł������n�������̂ł���B
�����{�ŗL�̗̓y�Ɍ��܂��Ă��遄
�@�u��t�͓��{�ŗL�̗̓y�ŁA�̓y���͑��݂��Ȃ��v�Ƃ����̂����{���{�̏퓅�傾�B�m���ɗ��j��R�����A���̐��͂����Ƃ��ł���B�٘_�����߂Ȃ��m������̂��B
�@�������{��1895�N�A�u��t�����́A�������͂��߂ق��̂ǂ̍����̗L���Ă��Ȃ��v���Ƃ��m�F���āA���ꌧ�ɑg�ݓ��ꂽ�B���̌ケ���ɂ͐��S�l�̓��{�l����炵�A���ߍH������݁B���\�N�Ԑl���Z�ݎY�Ƃ����t�������̐N�����Ȃ�������Ƃ������{�̗̓y�������B�ғ��̌o�܂�������͂Ȃ��A1940�N�ȍ~���l���Ɖ����Ă������x�z�͑����Ă���B�N�����ƌ������Ɓu���{�ŗL�̗̓y�v�ł��邱�Ƃ͕�����Ȃ������ł���B
�@1968�N�A���A�A�W�A�ɓ��o�ψψ����A�u�C�m�����̌��ʁA���V�i�C�̑嗤�I�ɂ͐Ζ���������������Ă���\��������v�Ƃ̔��\���Ȃ��ꂽ�B����ɐF�C�Â����������̓y���𐁂������Ă����B���ꂪ1972�N�́u�������������v��1978�N�́u�������a�F�D���v�������ɂ͒I�グ����č����Ɏ����Ă���B
�@�ȏオ�A�����A�u��t�������v���j�l�̌��ʂł���B�}�X�R�~�̎����F�����قڂ���ȂƂ��낾�낤�B
�@���́A���ŋ߂܂ŁA�u�����̔r���f���͏�O���킵�Ă���B�����͂���������ȍ��Ȃ̂�����A�C�ꎑ���ɖڂ�����݁A���{�������ɍs�����̗L�����A�푈�̃h�T�N�T�ɕ���ċ��D�����Ƃ̗��j���ɂ���ւ��āA��艻���Ă���B����̓��N�U�̌���������݂����Ȃ��̂ŁA���̍��Ȃ��肩�˂Ȃ��v�ƍl���Ă����B
�@�������ǂ����[���������Ȃ��B���{�̗L���҂͂悭�u�����͖���I�ɖ����n�ȍ��Ƃ��B���n���������`���Ƃł�����{�́A��l�̑Ή������ׂ��ł���v�Ȃ邱�Ƃ������B�͂����Ă������낤���H �����������疢���n������Ƃ����āA���s�s���S����������قǗ��s�s�ȍ��ƂȂ̂��낤���H ���{�ɂ͂Ȃ�̔ۂ��Ȃ��̂��낤���H ����Ȕ��R�Ƃ����^�₪�����痣��Ȃ������B
���Ȃ������͂���قǂ܂łɁ�
�@��t�����͓��{�ŗL�̗̓y�ł���B����͗h�邬�̂Ȃ��������B�ł��Ȃ������͂���قǂ܂łɎ咣����̂��낤���H�咣�ł���̂��낤���H 9��28���A���A�ł̒����O���ƍ��A��g�̔����̂����܂����͂ǂ����B�H���u���{��1895�N�̍b�ߐ푈�i�����푈�j�̏I��育��A�ދ����Ǝ��ӂ̓��i��t�����j�𓐂ݎ�肱���̓���S�ē��{�̂��̂Ƃ����v�B����ɑ�����{�̎��ʍ��A��g�́u���ݎ�����Ƃ����̂͌���������ʼn��̘_�������Ȃ��v�͓��R�̔��_���B
�@���́A���̎��ɓ�����O�̎��ۂ��A���肩��u���ݎ�����v�ƌ����Ă��܂������ɂ���B�����Ȃ�܂łɂ͌o�܂�����͂����B�ߋ��̂ǂ����ɂȂ�炩�̂�������������͂����B�u�C��̐Ζ��v�͒����̓��@�����A�����Ŏ������Ƃ������̂́A������ꂽ�u���������v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A1970�N������܂ŁA�����͐�t���u���{�̗̓y�v�ƔF�߂Ă���؋������邩�炾�B�����1970�N�Œ����̍��苳�ȏ��ɂ���B�����ɂ͐�t�������͂�������{�̗̓y�Ƃ��Čf�ڂ���A�������g��t�h�Ƃ������{��\�L���Ȃ���Ă���̂ł���B
�@���炪�u�����̗̓y�v�ƔF�߂Ă���y�n���A������~�����Ȃ�������Ƃ����āA�����Ȃ�u���̂��̂��v�Ƃ͌����Ȃ��͂��B�ǂ�Ȃɕs���ȍ����Ƃ��Ă��u���������v���Ȃ�������Ȃ�͂����Ȃ��Ǝv���̂ł���B
�����������͓c���p�h��
 �@�u���������͉��H�v�Ɍ��_��^���Ă��ꂽ�̂́A9��30�����f��NHK�X�y�V�����u�����O���͂������Ďn�܂����v�������B�ȉ������������B
�@�u���������͉��H�v�Ɍ��_��^���Ă��ꂽ�̂́A9��30�����f��NHK�X�y�V�����u�����O���͂������Ďn�܂����v�������B�ȉ������������B�@ �@�c���p�h�i1918�|1993�j�́A1971�N�A�����J�̒����}�ڋ߁��j�N�\���E�V���b�N���ɂ݁A�������𐳏퉻���}���ƍl���Ă����B���N�A������b�ɂȂ�ƁA�����̍l�������s�Ɉڂ��B
�@�O����b�啽���F�i1910�|1980�j�́A�����ŁA��������u�������̕����Ɛ�t���������o���Ȃ����Ɓv���m�F�A�c���Ƌ��ɕs�ޓ]�̌��ӂŌ��ɗՂށB
�@�����āA1972�N���j�I��9����5���ԁi25���\29���j���}����B�ӎ`��ł̓c�������̔g��i�g�����f�h�̉��߂��߂����Ắj�A�푈��ԏI���̎����A��p���Ȃǂ̌��Ă����z���āA���Ɂu���������錾�v�����������B9��29���̂��Ƃł������B
�@��������������c���p�h�́A�������𐳏퉻�ɂ�������J�҂Ƃ��ė�������^����悤�ɂȂ�B���_���������ے肷����̂ł͂Ȃ��B���ň��̓����W�Ƃ����鍡�̂��̎����A�k���ōs��ꂽ����63���N�L�O�p�[�e�B�[�ɓc���^�I�q�����҂��ꂽ�̂��A�������̊p�h�ɑ���I�}�[�W�����炾�낤�B
�@�Ƃ��낪�c���͐��ʂƂ͗����ɁA�Ƃ�ł��Ȃ��~�X��Ƃ��Ă����̂��B
�@���������ɍ�����������9��27���A�c���͎������Ɍ������Ă�����o�����B�u��t�����ɂ��Ăǂ��v�����H ���̂Ƃ���ɁA���낢�댾���Ă���l������v�B������Ď������́u��t�������ɂ��ẮA����͘b�������Ȃ��B�Ζ����o�邩�炱�ꂪ���ɂȂ����B�Ζ����o�Ȃ���A��p���A�����J�����ɂ��Ȃ��v�ƕԂ����i�ŋߌ��J���ꂽ�O���Ȃ̊O�����j�B
�@�c���͌y���₢�����̂��肾�����낤�B�ꌩ���̂����́u���i�V�v�Ɖf��B���������A�u��p���A�����J�����ɂ��Ă���v�Ƃ͌����Ă��A�u���������ɂ��Ă���v�Ƃ͈ꌾ�������Ă��Ȃ��B�m���ɂ��̎��_�Œ����́A��Ɏ������l�͐�t���莋���Ă��Ȃ��B����͔ނƓ��{�Ƃ̐M���W������\�����@�ł���B�Ƃ��낪�A���̂��Ƃ肱���A���̎��_�ł͒N���C�Â��Ă��Ȃ��u��t���v�Ƃ��������̉�����������Ύ킾�����̂ł���B
�@����͂��̏،�������M����E�E�E�u��肪�Ȃ�����o���Ȃ�������B�o�Ă�������ɂ͂Ȃɂ�����ƁA�������Ďv���B��́A�c���������Ȃ���o�����̂��A���̂Ƃ�����������Ȃ��v�i�����̊O���Ȓ����ۉے��E���{�����j�B�������炠�Ƃ͎��̐����ł���B
�@�u�����錾�v�̂��ƁA�������Y�}���ł́u�w��t�x�œ��{�ɂ����錄������v�ƔF������悤�ɂȂ�B�ނ�͂����l�����B�u��t�����͓��{�ŗL�̗̓y���Ǝv���Ă����B�ǂ��ɂ������錄���Ȃ��̂�����B�Ƃ��낪�A�Ȃ����c�������̖����o���Ă��ꂽ�B���肪�܂����̖���N�����Ă��ꂽ�̂��B����������ȏ�Ȃ����̏�ŁB���̕ԓ��ɂ́A�g����I�グ���悤�h�Ƃ����j���A���X���܂�ł���B�������������͂Ȃ��B�w�I�グ�x�𗼍��Ԃ̋��ʊm�F�Ƃ��Ă��܂��A���Ƃ͑�������X�Ƀy�[�X�Ɋ�������ł��������v�B�c���̈ꌾ�͒����Ɋi�D�̓˔j����^���Ă��܂����̂ł���B
�@�u�I�グ�v�́A6�N���1978�N�A�u�������a�F�D���v�������A���{�L�҃N���u�ɂ����钆����\�E�������́u��X�ɂ͒m�b���Ȃ��B��t���͎�����̉p�m�Ɉς˂悤�v�́g���䎌�h�Ō���I�ƂȂ����B��������{�l�L�҂̖�킸�����Ȃ̎��₪���������������B
�@�I�グ�̕K�v�Ȃ����Ƃ��I�グ����Ă��܂����B����ŏ����������̂ł���B���{�́u��t���v����������悩�����B100���u���{�̗̓y�v�Ȃ̂�����B�����璆���ł��A����ȓ��{�Ɍ����������t������͂����Ȃ����炾�B���͍Ђ��̌��A���ق͋����B�E�E�E�E�E�����āA���ɂ́u�ދ����͒����̂��́v�ւƕϖe���Ă䂭�B
�@��t���́A���j�I�̋Ƃ𐬂����������{�̑�����b�̈ꌾ��ڕq���������������A�I���Ȏ���Ō��݉����Ă������A���{�ɂƂ��Ď��ɕs�{�ӂȐ������ł���B����́A���{�O���̊Â��ƒ����O���̂�����������@���ɕ����Č��Ȃ̂ł���B
�@���ɂ́A�u�I�グ�͂Ȃ��v�Ƃ��錺�t�O���̔������A�z�ɉf��B��c�����́u�킪���ŗL�̗̓y�v�̘A�Ă͋������f��B�u�������݉������̂͂����炶��Ȃ����B��肪�Ȃ��̂Ȃ�Ȃ�Ő�o�����v�ƓG�͍l���Ă���̂ł���B�o����������͖̂߂�Ȃ��B�Ȃ�����������l���邵���Ȃ��̂��B
�@���{���{�́A�u�w�I�グ�x�̂���������������͓̂��{�v�Ȃ邱�Ƃ�F�����A�u������}�邽�߂ɗ��j�������悤��Ƒ���ɌĂт����邱�Ƃ��B��������A�_���I�ɓ��{�̐�������������S�n�悢���_���o����͂��ł���B����Ă��Ȃ�����ې��_�ɑi��������B��������ԋ���Ă���̂͌��ɂ���Ė��炩�ɂ������j�̐^���Ȃ̂��B
�@�}�X�R�~���A�u�I�グ�����̍����������N�������B���̂Ƃ������ƑΉ����Ă���v�Ƃ��u���͐̂Ɋr�ׂĒ����Ƃ̃p�C�v���Ȃ��̂���肾�v�ȂǂƔ\�V�C�Ȃ��Ƃ������ĂȂ��ŁA�{�������ʂ����{�����ق��������B�N��悵�q�����K���I���B
�@9��27���̍��A����ŁA��c�����́u�̓y�̊C���߂��镴���͍��ۖ@�ɏ]�����a�I�ɉ������ׂ��B���ێi�@�ٔ����iICJ�j�ɒ��ڂ��ׂ����v�Ɖ��������B����͈ꌩ�������������邪�A����Ԃ��Α��l�C���̓��_�B�ޓ��L�̂����ǂ���̖��^�����ł���BICJ�ɑi�����Ƃ���ő���͏o�Ă��₵�Ȃ��B����T������͎��炪�����邵���Ȃ��̂��B���A���{�̎w���҂ɕK�v�Ȃ̂́A����������E�C�Ǝ��含�ƋC�T���B�G�ɂƂ��āA����Ȑ��_�̔��o���Ȃ��������葱���Ă���邱�Ƃ��A��Ԃ̍D�s���Ȃ̂ł���B
2012.09.05 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�E
�m���܂��n�@�O��ŁA���́u�I�����s�b�N����|�[�g�v�͏I���\��ł������A8��15���t�����V���Ɋʼn߂ł��Ȃ��L�����f�ڂ��ꂽ�̂ŁA��������グ�Ē��߂����Ǝv���܂��B����́A�����Ӗ�ҏW�ψ��ɂ��u�L�җL�_�v�ł��B�ł́A�܂��A���̓��e�������Ă��������܂��B
�u���{�ƌܗ� ���_�����ɂ�����肷�����v �����Ӗ��@�F�l�́A���̘_�����ǂ��v����ł��傤���H ���́A��_����Ƃ��^������Ƃ��낪����܂���ł����B�ȉ����̗��R���q�ׂ����Ă��������܂��B
�@�����h���ܗւ����n�Ŏ�ނ��āA���̌ܗւ͐��������̂��ǂ����A���܂��l���悤�Ǝv���B���������Đ����Ƃ���̂��B����͎s���ƑI�肪�y���߂����ǂ��������A���̈Ӗ��ł��̌ܗւ͐����������B�����h���s���͌ܗւ��G���W���C���Ȃ��畁�i�̐����𑗂��Ă����B�������A���Z��ɋl�߂������ϏO�́A�I��Ƀp���[��^����M�C�𑗂��Ă������A����͌����ĔM���I�ł͂Ȃ������B�����ւ̉����́uTGB�i�`�[���E�O���[�g�E�u���e���j�v�B���ځu���v�𐺍��ɋ����`�[���ƑI����������Ă����B����́u�ܗւ͍��ƍ��Ƃ̐킢�ł͂Ȃ��A�`�[���ƃ`�[���A�l�ƌl�̐킢�v�ƋL����Ă����ܗ��͂𐬏n�����s�s���������Ă������炾�Ǝv���B
�@���Ă��̂��Ƃ��A2020�N�̌ܗ֏��v��ڎw�������ɁA�L���ɓ������낤���H ���̓����̓m�[���B���{�Ƃ������͌ܗ��͂��痝�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����Ȋw�Ȃ̓X�|�[�c��{�v��Ƃ��āA�u���E5�ʁv�̋����_���l����ڕW�ɁA15�O���ڎw�����B�����_����7�ɂƂǂ܂������Ƃ���肾�A�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B���_������38�͎j��ő��ŁA�I��͖{���ɗE�C�����ꂽ�B���Ƀ}�C�i�[���Z�Ƃ�����I�肽���̊���ɂ͋���ł��ꂽ�B�������A�����u�����_���ڕW�v���f���邱�Ǝ��̂��i���Z���X�Ȃ̂��B�����Ƃ����s�s����{�����n���Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����낤���B
�i�P�j�����h���s���̉����͔M���I�ł͂Ȃ������̂�
 �@�����ψ��́A8��4���A�I�����s�b�N�E�X�^�W�A���̔M���U���̊����Ȃ������̂ł��傤���B�ނ́A�`���ŏ����Ă���悤�ɁA���n�Ŏ�ނ��Ă��������ł����A��̂ǂ��ʼn�����ނ��Ă����̂ł��傤���H
�@�����ψ��́A8��4���A�I�����s�b�N�E�X�^�W�A���̔M���U���̊����Ȃ������̂ł��傤���B�ނ́A�`���ŏ����Ă���悤�ɁA���n�Ŏ�ނ��Ă��������ł����A��̂ǂ��ʼn�����ނ��Ă����̂ł��傤���H �@���̓��͂܂��A���q7�틣�Z�ŁA�C�M���X�̐��W�F�V�J�E�X�~�X���A6955�_�Ƃ��������_��@���o���ċ����_�����l�����܂����B�Ō�̋��Z800m�����A���X��1�ʁB�X�^�W�A���͕����ɕ����܂����B
�@�قǂȂ����āA�j�q10,000m���X�^�[�g�B�ܗ�3�A�e��ڎw��K.�x�P����i����G�`�I�s�A���A���̓P�j�A�����S�̃��[�X�\�z�̒��A���G�D���C�M���X�̃��n���h�E�t�@���[���W�X�Ƒ����Ă��܂����B
�@���[�X��2000���ɍ��������낤�Ƃ��鎞�A�˔@�t�B�[���h�ɑ劽���������N����܂��B�j�q���蕝���тŁA�C�M���X���O���O����U�t�H�[�h���A���̎��48�N�Ԃ�̋����_�����p���ɂ����炵���̂ł��B�C�M���X����w�A���̓�2�ڂ̋����_���ł����B
 �@10,000���͌㔼�ɓ���܂��B�擪�W�c15�l���߂܂��邵������ւ��B�G�`�I�s�A�A�P�j�A�A�G���g���A�̃A�t���J�������P�ʂŗh���Ԃ���|�������W�J�B����Ȓ��A���n���h��t�@���[��10�\6�\3�Ԏ�ƒ����Ɉʒu�����グ�Ă����B�����āA�c�����A���ɐ擪�ɗ��B�n��̂悤�Ȋ����B�n���̑吺���Ɍ㉟�����ꂽ�t�@���[�̃X�s�[�h�͑S���������A���̂܂܉������ē��X���鏟��������܂����B�X�^�W�A���͂��̓�3�ڂ̋����_���ɑ�M���B�ϋq�̋����̓s�[�N�ɒB���܂����B���ɂ��̐����Ԃ̃X�^�W�A���͐��������B�n���C�M���X���đ�����3�A�������_���ɁA�����ʂ苻���̚��ĂƉ������̂ł��B���̋����̓X�^�W�A���ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A�C�M���X�S�y�������A���̓����g�X�[�p�[�E�`���[�Y�f�[�h�ƌĂԂɎ������̂ł��B
�@10,000���͌㔼�ɓ���܂��B�擪�W�c15�l���߂܂��邵������ւ��B�G�`�I�s�A�A�P�j�A�A�G���g���A�̃A�t���J�������P�ʂŗh���Ԃ���|�������W�J�B����Ȓ��A���n���h��t�@���[��10�\6�\3�Ԏ�ƒ����Ɉʒu�����グ�Ă����B�����āA�c�����A���ɐ擪�ɗ��B�n��̂悤�Ȋ����B�n���̑吺���Ɍ㉟�����ꂽ�t�@���[�̃X�s�[�h�͑S���������A���̂܂܉������ē��X���鏟��������܂����B�X�^�W�A���͂��̓�3�ڂ̋����_���ɑ�M���B�ϋq�̋����̓s�[�N�ɒB���܂����B���ɂ��̐����Ԃ̃X�^�W�A���͐��������B�n���C�M���X���đ�����3�A�������_���ɁA�����ʂ苻���̚��ĂƉ������̂ł��B���̋����̓X�^�W�A���ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A�C�M���X�S�y�������A���̓����g�X�[�p�[�E�`���[�Y�f�[�h�ƌĂԂɎ������̂ł��B�@������A�u�����ĔM���I�ł͂Ȃ������v�Ƃ��鐼���_���͖ؕ��Ε��̗ނł��B�ł��܂��A����͎�ς̖��Ȃ̂ŁA����ȏ�̒Njy�͂�߂Ă����܂��B���͂��ꂩ��ł��B
�i�Q�j�����h���s���́u�I�����s�b�N���́v�𗝉����Ă��āA�����s���͂����ł͂Ȃ��̂��H
�@�����ψ��́A�u�����h���̊ϋq�́A�wTGB�x�Ƃ������������Ď����̑I����������Ă���B����͐��n�����s�s���w�I�����s�b�N���́x�𗝉����Ă��邩�炾�v�Ƃ���������Ă��܂��B�͂�����\���グ�āg����Ȃ̊W�Ȃ��h�Ǝ��͍l���܂��B
�@�uTGB�v�i�`�[���E�O���[�g�E�u���e���j�́A�u�C�M���X�E�I�����s�b�N����vBritish Olympic Association��HP�ɂ��ƁA�p���I�����s�b�N��\�I��̌������̂Ƃ��Ĉ�ʓI�Ɏg���Ă�����̂ł��B�����炻���Ȃ������͒肩�łȂ����̂́A����̐ݗ���1905�N�ł�����A�C�M���X�l�ɂƂ��ČÂ�����̏퓅�傾�������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B �@������ɁA�C�M���X�E�T�b�J�[����́A���N�A�����h���ܗւɑ�\�`�[���𑗂�o���ɂ�����A���̃`�[�������uTGB�v�Ƃ��܂����B�uTGB�v�́A�T�b�J�[��`�[���Ƃ��ẮA����܂ŃA�}�`���A�E�`�[����������������Ƃ̂Ȃ��A����I�Ȍď̂ł����B
�@����炩��A�uTGB�v�́A����̃I�����s�b�N�ɂ����āA�����h���s���̓��ʂȃt���[�Y�ƂȂ����A�ƍl�����܂��B������A�������ɁuTGB�v�����ꂽ�̂͂������R�̐���s���������A�Ǝ��͎v���܂��B�ψ������������g�uTGB�v���u�I�����s�b�N���́v�����̏h�Ȃ�_�@�́A������������I�ɉ߂��܂��B���ؐ��̂Ȃ��Ƃ�悪��̎v�����݂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@����Ɋʼn߂ł��Ȃ��̂́A�ψ����u�����Łw�`�[���E�j�b�|���x�Ƃ���Ȃ����{�́A���n�x���Ⴍ�A�w�I�����s�b�N���́x�𗝉����Ă��Ȃ��v�A�Ǝ�����̂ނ悤�Ș_���ɋy���Ƃł��B
�@�H���A�u�C�M���X�͐��E�̍ł����i���B�����烍���h���s���͐��n���Ă���A�w�I�����s�b�N���́x�𗝉����Ă���B�Ђ�A���n�x�̑���Ȃ������͂���𗝉����Ă��Ȃ��v�B���ꂼ�܂��ɁA�Œ�T�O�ɂƂ��ꂽ�Z���I���_�ł��B
�@�C�M���X�l���uTGB�v�Ƌ��ڂ��Ƌ��Ԃ܂��ƁA���{�l���u�j�b�|���v��A�Ă��悤�Ƃ��܂��ƁA�����Ɂu�I�����s�b�N���́v�̈ӎ��̗L���͂Ȃ��A�ڂ̑O�̑I��̊撣����]���鏃���ȉ����̋C���������邾���ł��B���ꂪ�X�|�[�c���y���ނƂ������Ƃł��B
�@��V���̕ҏW�ψ��̕����A�����Ƃ��������ȍs�ׂɂ������Ȃ������������āA�X�|�[�c�����̊�{���_���킫�܂����A������������ĕΏd��`�ɒЂ����Ă���Ǝv���ƁA��Ȃ����s���ɂȂ�܂��B���̏�A��U�v���������g�̂Ȃ��_���̋ؓ��������̔������ۂŏ؋��t���A�s���Ȏ����͈ӎ��I�ɖ������i����Ƃ����m�j�A�����ɗ\���ǂ���̌��_�������o�����̎�@�A�ŋ߂̌��@�̕s�ˎ�������悤�ŁA�낵�����Ȃ�܂��B
�i�R�j�����_������ڕW�Ƃ��邱�Ƃ͖{���Ƀi���Z���X�Ȃ̂��H
�@�����ψ��͂���ɁA�u���{���A�w�����_���ڕW�x���f���邱�Ǝ��́A�i���Z���X�v�ƒf�肵�Ă��܂��B
�@�I�����s�b�N�ōD���т����߂邽�߂ɂ́A�Z�p�E���_�͂̌���Ə����W�E���͂��������܂���B���̂��߂ɂ͐l���m�܂߂������Ƒ̐���肪�K�{�ł��B����ɂ͂������|����B�g���[�j���O�{�݂̏[����D�G�ȃR�[�`�̔z�u���K�v������ł��B�����͌l�ł͕��S������Ȃ����獑�̉������v��B�����\�Z�𗧂Ă�Ƃ��ɂ͖ڕW�l���K�v�ƂȂ�B�u��Ԃ��Ⴂ���Ȃ��̂ł����v�̂��̘b�ł��B���̖ڕW�l���u�����_�����v�ɒu���������B�i���Z���X�]�X�̎�������Ȃ��A���̒��̏펯�ł��B����Ƃ��A�ψ��̉�Ђ́A�ڕW�i�ړI�j�Ȃ��̗\�Z���܂���ʂ鋏�S�n�̗ǂ���ЂȂ̂ł��傤���H
�@JOC���u�����h���ܗւ̋����_���ڕW��15�v�ƌf���������ŁA�u���_�����ɂ�����肷���v�ƌ����B�������{�́A�C�M���X�ɔ䂵�ẮA�����n�̏Ƃ܂Ō�����B���ꂼ�A�����̓������킫�܂��Ȃ���͂��ŒZ���I�Ȍ����l�ł��B
�@�����\�Z������B�����ɂ́u�ڕW�l�v������B������āA�I��́A�v�X�̃X�^�C���Ŏ��Ȃ��I�����s�b�N�Ƃ�����͂ɓ������Ă䂭�̂ł��B�����_����������O�Ǝv���I�������ł��傤�B���Ō�̎��Ɗ�ԑI�������ł��傤�B����̊��������āA�}�t������B����ł����̂ł��B
�@������A�ψ����ے肷��u�����_���ڕW�v���A�C�M���X�͌f���Ă��Ȃ��̂ł��傤���H ���̓����́A�u�C�M���X�E�I�����s�b�N����v�̌���HP�ɂ���܂��B
Medal and Performance target�@�����ɂ́A�u���_���l�����𐢊E��4�ʁv�ɁA���̂��߂Ɂu�Œ�48��ڕW�Ƃ���v�A�Ɩ��L����Ă��܂��B���݁A�I�����s�b�N�̃��_���E�����N�t���͋����_���D��ɂ��Ă��܂�����A������u���E4�ʂ�ڎw�����߁A��葽���̋����_�����܂ށA�Œ�ł�48�̃��_���l����ڕW�Ƃ���v�ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂��B���{�́u���E5�ʁA15�̋��v�ƂȂ��ς��Ƃ��낪�Ȃ��B����ǂ��납�A�ނ���A���_���̑��������Ă���_�ŁA���{�̖ڕW�����ׂ����Ƃ����܂��B
UK Sport revealed a target of finishing in the top four of the medal table and winning at least 48 medals across at least 12 sports based on an aggregate medal range 40�|70
�@�������ł��傤���A�����ψ��B�M�����h���������n�����C�M���X���A�����_���l���̖ڈ���u���_���ڕW���v�����Ă���̂ł��B �@�ψ��́A�����V���L�҂Ƃ��Č��n�Ń����h���ܗւ���ނ����B���{�̓ǎ҂Ɍ��n�̏𐳊m�ɓ`���������S���āB�Ȃ�A�u�C�M���X�E�I�����s�b�N����v��HP���炢�͔`���Ăق��������B��������A�����Ƃ����Ƃ����L�����������̂ɂƎc�O�ł��B����Ƃ��A�m���Ă��Ȃ��畚�����̂�����B�u���x�̒Ⴂ�ǎ҂ɕ�������̂��v�Ȃ�āB��������A�����Ƌ����Ȃ��I
 �@�V���͂Ȃ��Ȃ��ւ����܂���B���̂�C�A�E�g�ȂǁA���o�I�ȕ������̂ɓ����ł��邩��ł��B�Ȃ̂œ����A�����u�����V���v�����芷���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�@�V���͂Ȃ��Ȃ��ւ����܂���B���̂�C�A�E�g�ȂǁA���o�I�ȕ������̂ɓ����ł��邩��ł��B�Ȃ̂œ����A�����u�����V���v�����芷���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�@����Ȏꏟ�ȓǎ҂�����̂ł�����A���߂ĎА��E�_�����炢�́A�o���邾�����������ؓI�ɏ����Ăق����Ɗ肤����ł��B
�@����̂悤�ɁA���ՂɁu�I�����s�b�N���́v�Ȃ���̂������ς�o���āA���̐��_�������������Ă���悤�ȕ������ŁA���܂��܂Ԃ��������ۂ���Ȑ��_���s���A������̂ނ悤�ȒZ���I�Ȍ��_�C�œ����o���A���ؐ��̂�������Ȃ����ɑe���ł��������ȗނ̋L���́A�ɗ͔����Ă������������B���Ă͓��ɁA�V�V��Ȃ����ɁA�̗͂����Ղ��Ă��܂��܂��䂦�B
2012.08.25 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�D
�@����A�uNumber�v�̃I�����s�b�N���W����ǂƂ���A�g�c���ۗ��Ɋւ��鋻���[���L��������܂����B�O��́u�N�����m�v�ŁA�ޏ��́g�I�����s�b�N��h�̓t�F�C���g�Ȃǃ^�b�N�������ւ̉��P�Ə����܂������A����̓e���r���p�̉���ҁE�g���ˎq���i���q���{��\�`�[����R�[�`�j�̃R�����g���璊�o�������́B�uNumber�v�ɂ������̂́u�g�c�́A�Б��^�b�N����D�悵���v�Ƃ������̂ł����B�g�c�͂���܂ŗ����^�b�N���������B����͐�������Α���ɑ傫�ȃ_���[�W��^���邪�A�Ԃ��Z�ł����댯��������B�Б��ɂ���A�u������f������̂̍������ۂĂ�̂ŁA�J�E���^�[���ɂ������_������v�Ƃ���܂����B�����ŁA�S�����̃r�f�I���`�F�b�N������A�|�C���g�Ȃ���6��̃^�b�N���̂���5�Б��ł����B�Ȃ�قǁA�ޏ��̑�͂ނ��낱�̕��������ƔF����������ł��B���ΐ�厏�A����Ȃ�̂��Ƃ͂���܂��B�ł́A����͑����Ƃ����܂��傤�B[�I���悯����ׂĂ悵]
�@�O��̃��|�[�g�ŁA�{�N�V���O�j�q�~�h�������c�ȑ���44�N�Ԃ�̃��_���l���������܂������A�Ȃ�ƁA���̂���2�����A���������_�����l�����Ă��܂��܂����B����͐������ƁB1964�N�����I�����s�b�N�A�o���^�����E����F�Y�ȗ�48�N�Ԃ��̉����ł��B�������A���{�l�ɂ͖����Ƃ����Ă������d�ʋ��ł̂��́B�V����ł��B
�@���c�I��̃{�N�V���O�́A�ڋߐ킩��ł���Ă��ł��Ԃ��A������u����点�č���f�v�X�^�C���B�����_���́A����̃X�^�C������ȂɊт������ʂł����B����A����F�Y�̂́A�ؗ�ȃt�b�g���[�N����g�����A�E�g�E�{�N�V���O�ŁA�����I���u�Ă�2�̋����_���́A���̃X�^�C���ɂ����Ă��A���ɑΏƓI�Ȃ��̂ł����B�Ȃ��A���䎁�͍��N1��10���A70�ł��̐��������Ă��܂��B
 �@�ŏI����8��12���A�j�q���X�����O�E�t���[�X�^�C��66k���ŁA�Ė��B�O�������_���Œ��߂������Ă���܂����B���͋��ł�����͑f���炵�����e�ŁA���Ɍ����͈����ł����B�����^�b�N������A�����V���������グ�˂����Ƃ�������3�|�C���g�B�������ƂȂ�����R���gchallenge�h���N�\�H�炦�A�L�������킹�Ȃ������ł����B�u�킪���͌�R�ɂ��ꂽ���A���{�ɂ͖��������v�Ȃǂƙꂭ�i�̂Ȃ��ǂ����̍������������̂悤�Ȓɉ��ȏ����ł����B
�@�ŏI����8��12���A�j�q���X�����O�E�t���[�X�^�C��66k���ŁA�Ė��B�O�������_���Œ��߂������Ă���܂����B���͋��ł�����͑f���炵�����e�ŁA���Ɍ����͈����ł����B�����^�b�N������A�����V���������グ�˂����Ƃ�������3�|�C���g�B�������ƂȂ�����R���gchallenge�h���N�\�H�炦�A�L�������킹�Ȃ������ł����B�u�킪���͌�R�ɂ��ꂽ���A���{�ɂ͖��������v�Ȃǂƙꂭ�i�̂Ȃ��ǂ����̍������������̂悤�Ȓɉ��ȏ����ł����B�@���̑N�₩�ȋ����_���́A���X�����O�j�q24�N�Ԃ��̋��ɂ��āA�����h���ܗ�38�ڂ̃��_���ƂȂ�܂����B����́A�A�e�l����37����j��ő��̋L�^�B���]�ˉ�̍������w�̖����ɕ킦�A�u���{�I��c293�l�̃����[�̌��ʁv�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����ɂ��̃��_���́A1920�N�A���g���[�v���e�j�X�ŌF�J��킪��1�����l�����Ă���ē~�ʎZ400�ڂ̂��́B�܂��Ɂu���j��ځv�̑��ɑ�����������ł����B
[���E�V�L�^]
 �@������16�̐��E�V�L�^���a�����܂����B���㋣�Z��4�A���j��7�A�d�ʋ����łS�A�ˌ��łP�Ƃ�������ł��B���̐������������Ȃ����́A�K���Ȏ������Ȃ��̂łȂ�Ƃ������܂��E�E�E�E�E�B�ł͂��̒�����A��ۓI���������̂����������グ�����Ǝv���܂��B
�@������16�̐��E�V�L�^���a�����܂����B���㋣�Z��4�A���j��7�A�d�ʋ����łS�A�ˌ��łP�Ƃ�������ł��B���̐������������Ȃ����́A�K���Ȏ������Ȃ��̂łȂ�Ƃ������܂��E�E�E�E�E�B�ł͂��̒�����A��ۓI���������̂����������グ�����Ǝv���܂��B�@�Ȃ�Ƃ����Ă��A�����́A����u�j�q�S�~100�������[�v�̃W���}�C�J�E�`�[���i�J�[�^�[�`�t���[�^�[�`�u���C�N�`�{���g�j�ł����B36�b84�ƁA�]���̋L�^��0.20����A����36�b��˓��Ƃ����r�b�O�Ȃ��́B��l����9�b21�A�A���J�[���{���g��8�b��ő��蔲���Ă����ł��傤�B�g���b�N���Z�̍ŏI��ڂŁA�{���g�͍ō��̃p�t�H�[�}���X�������Ă��ꂽ�̂ł��B����́A�l���Z�ł͎������Ƃ��Ȃ������悤�Ȑ^�ɖ{�C�̑���ł����B���ɁA���Ă�p���[�̍Ō�̈�H�܂ŐU��i�����悤�ȃS�[���̏u�Ԃ́A�������m�̊����ł����B�{���g�̖쐶�Ƒz�����p�`�ƂȂ��Č���Ă��܂����B�ނ͂���ŁA100���A200���ƍ��킹3���A�������I�����s�b�N����3���2�A�e�Ƃ����O�l�����̈̋Ƃ�B���B�u�`���ɂȂ�v�̊����ł����B
 �@�u���q�S�~100m�����[�v�����_���̃A�����J�E�`�[�������E�V�L�^�ł����B40�b82�B��������A�]���̋L�^�i1985�N�A���h�C�c�E�`�[���j41�b37��j��A40�b��˓��Ƃ������L�^�B�A�����J�E�`�[���̃����o�[�́A�}�f�B�\���`�t�F���b�N�X�`�i�C�g�`�W�[�^�[�B�A���J�[�A�W�[�^�[�̑���͊m���Ɉ����ł������A������ꂽ�̂͑�2���A���\���E�t�F���b�N�X�B�X�����_�[�Ȏ��̂���J��o���t�b�g���[�N�́A�Z�����I����L�̂��������Ȃ��D�낻�̂��́B�����ĉ������A�p���������������̋ɂ݁B���ɂƂ��āA�j��ō��̃`���[�~���O�ȃ����i�[�ł��B�ޏ���200���ł��O��̋����_�����l��A�f���炵�����ɂȂ�܂����B�Ƃ���ŁA���c���l�A�X���[�g�E�t���[�����X��W���C�i�[�̎���100m��200m�̐��E�L�^�͂��j����̂ł��傤���B
�@�u���q�S�~100m�����[�v�����_���̃A�����J�E�`�[�������E�V�L�^�ł����B40�b82�B��������A�]���̋L�^�i1985�N�A���h�C�c�E�`�[���j41�b37��j��A40�b��˓��Ƃ������L�^�B�A�����J�E�`�[���̃����o�[�́A�}�f�B�\���`�t�F���b�N�X�`�i�C�g�`�W�[�^�[�B�A���J�[�A�W�[�^�[�̑���͊m���Ɉ����ł������A������ꂽ�̂͑�2���A���\���E�t�F���b�N�X�B�X�����_�[�Ȏ��̂���J��o���t�b�g���[�N�́A�Z�����I����L�̂��������Ȃ��D�낻�̂��́B�����ĉ������A�p���������������̋ɂ݁B���ɂƂ��āA�j��ō��̃`���[�~���O�ȃ����i�[�ł��B�ޏ���200���ł��O��̋����_�����l��A�f���炵�����ɂȂ�܂����B�Ƃ���ŁA���c���l�A�X���[�g�E�t���[�����X��W���C�i�[�̎���100m��200m�̐��E�L�^�͂��j����̂ł��傤���B�@���j�̐��E�V�L�^�ł́A�u���q400m�l���h���[�v���t�����i�����j���ő�̘b��ɁB�L�^��4��28�b43�ł������A�t���[�X�^�C���̍Ō��50m��28�b93�ŁA�j�q�D���̃��C�A������N�e�̂����0�b17�������Ƃ������́B���̑����A������A�h�[�s���O�H�Ȃ�ĉ\���o���قǂł����B
�@�j�q���j���́A100m�ŃL���������E�t�@���f���o�[�O�i��A�t���J�j���A200m�Ń_�j�G���E�W�����^�i�n���K���[�j�����E�V�L�^�ŋ��B����ł͖k���N����ȃx�X�g���o���Ă��͂��Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B�j�@�ᔽ�̋^�f������Ƃ͂����A�j����˂��l�߂����ʂł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���B�܂��A1992�N�A�o���Z���i�ł����Ƌ��������_�����l��������英�q�́A���Ԓ��Ɏ��ȋL�^��5�b���k�߂�ȂǁA�z��O���N����̂��I�����s�b�N�ł��B���ꂩ��̃��_�����ɂ́A�����W�\���́\��̐��k���ƌ��������A���ȏ�ɋ��߂��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B��ςȂ��Ƃł��B
[�j�㏉�̃p���[�h]
 �@8��20���ɂ́A����Ń��_���X�g�̃p���[�h���s���A�����ɂ͂Ȃ��50���l���W�܂����Ƃ��B������20���Ԃ̊猩�����Ƃł������A�ҏ��Ɏ�������傢�Ɋy���܂��Ă��ꂽ71�l�̃��_���X�g�����Ɋ��t�ł��B
�@8��20���ɂ́A����Ń��_���X�g�̃p���[�h���s���A�����ɂ͂Ȃ��50���l���W�܂����Ƃ��B������20���Ԃ̊猩�����Ƃł������A�ҏ��Ɏ�������傢�Ɋy���܂��Ă��ꂽ71�l�̃��_���X�g�����Ɋ��t�ł��B�@2020�N�̃I�����s�b�N�ɓ���������₵�Ă��܂����A����ō����x�����������Əオ�邱�Ƃł��傤�B���͓����I�����s�b�N���o�����Ă��܂����A�����łȂ�����͂���ς���{�ŃI�����s�b�N���������̂ł́B�C�X�^���u�[���Ƃ̈�R�ł��ɂȂ�ł��傤���A�x������70�����z���D�����ɂȂ肻���ł��i�������x����47���j�B�����h���ܗցA17���Ԃ��肪�Ƃ��A�����ăI�����s�b�N��i���ɁI
2012.08.15 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�C
[�ŋ��̕��q]�@���q���X�����O���I�����s�b�N��ڂƂȂ����̂́A2004�N�A�e�l����ł��B55k���̋g�c���ۗ���63k���̈ɒ��]�́A����`�����s�I���ɂ��ăI�����s�b�N2�A�e���B�����h�����ő�����3�A�e��_���܂����B�����3�A�e�Ƃ����Ă�����͑�ςȂ��ƂŁA���{�l�ł͏_��60k���̖쑺���G�����A���X�����O�ł͗쒷�ލŋ��Ƃ���ꂽ�A���N�T���h���E�J�����������Ƃ������B�Ƃ��낪���̓�l�́A���|�I�ȋ����ŃI�����s�b�N3�A�e�̈̋Ƃ�B�����Ă��܂��܂����B
 �@�g�c���ۗ��͏����̏u�ԁA���E�h���R�[�`�����Ԃ��A�u�ō��̐e�F�s���o���čK���ł��v�Ƙb���Ă��܂������A�h�ē��܂ŃO�V���O�V���������̂���ۓI�ł����B
�@�g�c�́A5���̏��q���[���h�J�b�v�c�̐�ŋv�X�̔s����i���܂����B�s���̓^�b�N�������킳��ẴJ�E���^�[�B���E�����g�c�̍����^�b�N�����������A���̕������߂�}���Ă��܂����B�ܗւ܂ł�3�����A�g�c�Ɖh�ḗA���E�h�����������Ă��̑�����܂����B����́A�g�P���ɔ�э��܂��A�t�F�C���g���g���ȂǑ���̈ӎ�����点�Ă����āA�m���Ƀ^�b�N���Ɉڍs����h��p�ł����B
�@�g�c���ۗ��͏����̏u�ԁA���E�h���R�[�`�����Ԃ��A�u�ō��̐e�F�s���o���čK���ł��v�Ƙb���Ă��܂������A�h�ē��܂ŃO�V���O�V���������̂���ۓI�ł����B
�@�g�c�́A5���̏��q���[���h�J�b�v�c�̐�ŋv�X�̔s����i���܂����B�s���̓^�b�N�������킳��ẴJ�E���^�[�B���E�����g�c�̍����^�b�N�����������A���̕������߂�}���Ă��܂����B�ܗւ܂ł�3�����A�g�c�Ɖh�ḗA���E�h�����������Ă��̑�����܂����B����́A�g�P���ɔ�э��܂��A�t�F�C���g���g���ȂǑ���̈ӎ�����点�Ă����āA�m���Ƀ^�b�N���Ɉڍs����h��p�ł����B�@8��9���A�{�Ԃ̋g�c�͋��������B�g�������сA���|�I�ȋ����ŁA�����Ȃ��Ɋl�����������_���h�ƌ����܂����B
�@�Ƃ��낪�A�ޏ��́A�킢��̃C���^�r���[�ł����������̂ł��B�u�����邩������Ȃ��Ƃ����s���ŁA�O�̔ӂ͖���܂���ł����v�ƁB�����A���̃R�����g�ɂ͂т����肵�܂����B���̈��|�I�ȋ����̗��ɂ���ȕs�����B����Ă����Ƃ́I �܂��ɈӊO���̔����ł����B
�@12�N�Ԃł�����2�s�������Ă��Ȃ��ŋ��̏����ɂ��Ă��̃v���b�V���[�B�����őz�N�����̂́A�̑��̓����q�����u�I�����s�b�N�ɂ͖���������v�Ƃ͌����Ă��A�u�v���b�V���[���������v�Ƃ͒f���Č���Ȃ��������Ƃł����B��D���ŗՂi�{�l�̕فj�͂��̒c�̗\�I�ōŒ�̉��Z�����Ă��܂����̂́A�I�����s�b�N�ɂ͕��i�̗͂��o�����Ȃ����������āA�̂��ӂ̂܂܂ɓ����Ȃ���������ɑ��Ȃ�Ȃ��B������g�v���b�V���[�h�Ƃ����̂ł��B�Ȃ��A�ނ͑f���Ɂg�v���b�V���[�h�Ƃ������t���g��Ȃ��̂��H �ŋ��̏������u�����邩������Ȃ��s���ɖ���Ȃ������v�ƌ����Ă���̂ł��B�q���N���A�����Ƒf���ɂȂ�Ȃ����B��������M���͂����Ƃ����Ƌ����Ȃ�܂��B
�@�ޏ��͂���ɁA�u������m���āA����ɋ����Ȃꂽ�Ǝv���v�Ƙb���܂����B�ޏ��Ɂu�コ���B���Ȃ������v�������܂����B�l�́g������|����m���Ė{���̋�����g�ɂ���h���Ƃ��A�g�c���ۗ��͋����Ă���܂����B
�@����ŃI�����s�b�N3�A�e�Ɠ����ɁA���E�I�茠�ƍ��킹��12�A�e��B���B������J�������ƕ��ԑ�L�^�ł����A�����ɍs����9���̐��E�I�茠�Œ����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
 �@�ɒ��]�̋����́A�g�c�Ƃ͈ꌩ�َ��Ɍ����܂��B���ő�������Ȃ��B��ɕ����Ȃ��`������Ă����āA�������藿������B����Ȉ��芴�������܂��B�U�߂̋g�c�ɑ��Ď��̈ɒ��B���̋g�c�ɏ_�̈ɒ��B�g�c�����˂Ȃ�ɒ��͑�Q�B
�@�ɒ��]�̋����́A�g�c�Ƃ͈ꌩ�َ��Ɍ����܂��B���ő�������Ȃ��B��ɕ����Ȃ��`������Ă����āA�������藿������B����Ȉ��芴�������܂��B�U�߂̋g�c�ɑ��Ď��̈ɒ��B���̋g�c�ɏ_�̈ɒ��B�g�c�����˂Ȃ�ɒ��͑�Q�B�@�Ƃ͂����A��r�͒P�Ȃ��ۏ�̂��ƁB�����ɂ��āA�g�c���{���̉s���U�߂Ɏ��̗v�f��t���A�ɒ��͖{���̎��ɍU�߂̗v�f��t�����āA���X�����O���݂��ɐi�����Ă���A�Ƃ����ق����������������̂悤�Ɏv���܂��B
�@�ɒ��̐��тׂ�ƁA�A�e�l�ܗ֑O����A�������t�����͕̂s��s�����̎���153�A�����B���E���10�e���A�g�c��12��ɋy�Ȃ��̂́A�k���ܗ֏I����A�o�̐�t�̈��ނɔ���2�N�ԋx�{���Ă�������B�����I�ɂ�8�N�ԕ����m�炸�Ƃ��������ŁA�ނ���A�g�c�����芴�͏����Ă���ƍl�����܂��B
�@�g�c�ƈɒ��B�܂��ɍŋ����q�̓�l�B���̓�l���A���q�ł͑O�l�����̃I�����s�b�N4�A�e�Ƃ����̋Ƃ�B������m���͑��������Ǝv���܂��B4�N��̃��I���y���݂ł��ˁB���݂ɁA�I�����s�b�N4�A�e�́A���蕝���т̃J�[���E���C�X�i���T���[���X-�\�E��-�o���Z���i-�A�g�����^�j�Ɖ~�Փ����̃A���E�I�[�^�[�i�����{����-���[�}-����-���L�V�R�j���B�����Ă��邾���ł��B
�@���q���X�����O�ł́A������l�A�����_���X�g���a�����Ă��܂��B48k�����������o��31�B�I�����s�b�N���o��ł̉����ł����B���E�I�茠51k���ł�6�e�̋��҂��Ȃ��H �I�����s�b�N�ɂ�51k�����Ȃ����߁A�o�ꂷ��ɂ�48k����55k���ɈƑւ�����K�v���������B48k���ɂ͖��i��{�^��q�j���������߁A55k����I�Ԃ��A�ŋ������g�c�ɑj�܂ꂽ�B2009�N�A���̎����ނ�48k���ɈƑւ��A���E�I�茠��2�A�e���ă����h���ɗՂ݁A�����ꔭ���D����ʂ������̂ł��B�ޏ��̋������ő�̃h���}��������܂���B
[�]�˂̋w�������h����]
 �@8��10���A�؍��̗������哝�̂��s�ӂɒ|���ɑ��ݓ���܂����B�j�q�T�b�J�[���ؐ�ɐ�삯�āB���̓����_����q�����킢�͊؍��̊����ɏI���A���ɂ���Ȃ��}�ȋC���ɂȂ�܂����B�g�b�v���l�C���̂��߂ɂ����������s�s�ȍs�ׂɏo��̂́A�S�������ė������܂����A�Q�[���I����؍��I�肪�u�Ɠ��i�|���j�͊؍��̗̓y�v�Ə������v���J�[�h���f�����̂ɂ͎��]���܂����B�X�|�[�c�}���V�b�v��`������s�ׂ�����ł��B �����A���̍��Ƃ͂܂Ƃ��ɕt�������Ȃ��Ǝv���܂����B
�@8��10���A�؍��̗������哝�̂��s�ӂɒ|���ɑ��ݓ���܂����B�j�q�T�b�J�[���ؐ�ɐ�삯�āB���̓����_����q�����킢�͊؍��̊����ɏI���A���ɂ���Ȃ��}�ȋC���ɂȂ�܂����B�g�b�v���l�C���̂��߂ɂ����������s�s�ȍs�ׂɏo��̂́A�S�������ė������܂����A�Q�[���I����؍��I�肪�u�Ɠ��i�|���j�͊؍��̗̓y�v�Ə������v���J�[�h���f�����̂ɂ͎��]���܂����B�X�|�[�c�}���V�b�v��`������s�ׂ�����ł��B �����A���̍��Ƃ͂܂Ƃ��ɕt�������Ȃ��Ǝv���܂����B�@����ȕs�����̒��A8��11���A���q�o���[�{�[��3�ʌ���E���ؐ킪�s���܂����B���{���A���X�����ł���܂Ōܗւň�x�����ĂȂ����������ɏ����Ă��̏�ɂ���悤�ɁA�؍��������C�^���A�ɏ����Ă��Ă���B���{�����Ă�28�N�Ԃ��̓����_���Ȃ�A�؍���36�N�Ԃ�ƁA�ǂ���������悤�ȏł����B
�@����ȗ��`�[���ɂƂ��āA�Ō�ɏ��s�����߂�̂͋C�����̋����ł��傤���A���{�́A5���A�����ōs��ꂽ�����h���ܗ֍ŏI�\�I�ŁA�؍��̃G�[�X����i�̋��łɂȂ����ׂȂ��s��Ă������߁A����͋C�����ǂ�����A�u���ĂȂ����낤�v�ƌ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�E�E�E�E�E�E�B
�@�����h���ܗւ��W�听�ƈʒu�Â��Ă����^�琭�`�ḗA�����Ă������_���̃`�����X���ǂ����Ă����m�ɂ����������B5���̓����̓Q�͓��߂Ȃ��B���̂��ߔނ́A�؍���Ɏア�]�����O�����c��攭�ɋN�p�B�T�[�u�Ő�����A����i�Ɋy�ɑł����Ȃ����ɏo�܂����B2008�N�̏A�C�ȗ��f���Ă����uID�o���[�v�̏W�听�Ƃ��āB
�@������݂ƂȂ���iPad�Ў�̐^��єz�������ɓI���A����i�̃X�p�C�N�͂��ɂȂ��~�X���ڗ����A���c�͑S�I���ʂ��ő���23���_���グ�A�^��W���p����3�|0�̃X�g���[�g�Ŋ؍��ɏ������܂����B���ʂ̓X�g���[�g�ł������A�����ꂪ�t�]���Ă����������Ȃ��A���ɋٔ��������e�̃Q�[���ł����B����ȓW�J�̒��A�����̌��ߎ�ƂȂ����̂́A���Ƃ��Ε����ɂȂ��鐣�ˍۂ̃|�C���g�𗎂Ƃ��Ȃ��������ƁB�����A�y�d�ꁁ���ۂ̋����ł����B����́A�������̓������o�Ĕ|��ꂽ���������͂ƒ��߂Ȃ��s���̐��_�͂̎����ł����B�T�b�J�[�̒j�q�Ƃ͂���������Ă��܂����B
�@�������u�ԁA�I��A�X�^�b�t�A�ē��R�[�g�ɓ|�ꍞ�݊�т������܂����B15�N�ԁA���_�I�x���ƂȂ��ă`�[�������������Ă����|���̗܂����Ɉ�ۓI�ł����B���̂���������ÂȒ|�����A�l�ڂ�݂炸�������Ⴍ���Ă���B�`�[���̊�����ے����Ă��܂����B
�@�^��W���p���A�]�˂̋w�������h���ŁA�j�q�̋w�����q�Ő��炵�Ă���āA���肪�Ƃ��I
2012.08.13 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�B
[���ׂĂ̓X�y�C���킩��n�܂����n �@�J��𗂓��ɍT����7��26���A���̂������j���[�X����э���ł��܂����B�j�q�T�b�J�[1�����[�OD�g�\�I�ŁA�킪�֒˃W���p���͗D�����M���̖��G�͑��X�y�C����1�|0�ʼn������̂ł��B�V���ɂ́u�O���X�S�[�̊�Ձv�Ȃ錩�o�������܂������A�Ȃ�̂Ȃ�́A1996�N�A�A�g�����^�ܗւł́u�}�C�A�~�̊�Ձv�Ƃ͑S������قɂ��Ă��܂����B�}�C�A�~�́A�K�^�ȓ��_���Ȃ�Ƃ���肫���������ʂ��ՓI�ȏ����ł������A����͏I�n��������|�����͂ʼn����������X���鏟���ł����B�I�[�o�[�G�C�W�E�g�c�����i�̔ȃo�b�N��w�����A�O���œG�̍U���̉��E�ގ��X�Ȃ܂ł̎���͑�����������A�ނ�ɔނ�̃T�b�J�[�������܂���ł����B�u�S���U���A�S������v�Ƃ����֒˃C�Y���������ɐZ�����������܂����B�����ĉ������A��ɏ��Ƃ����C���ɖ������Ă��܂����B�����f���������̃e�[�}�u�ӊO���v�́A���̎�������n�܂����̂ł��B
�@�J��𗂓��ɍT����7��26���A���̂������j���[�X����э���ł��܂����B�j�q�T�b�J�[1�����[�OD�g�\�I�ŁA�킪�֒˃W���p���͗D�����M���̖��G�͑��X�y�C����1�|0�ʼn������̂ł��B�V���ɂ́u�O���X�S�[�̊�Ձv�Ȃ錩�o�������܂������A�Ȃ�̂Ȃ�́A1996�N�A�A�g�����^�ܗւł́u�}�C�A�~�̊�Ձv�Ƃ͑S������قɂ��Ă��܂����B�}�C�A�~�́A�K�^�ȓ��_���Ȃ�Ƃ���肫���������ʂ��ՓI�ȏ����ł������A����͏I�n��������|�����͂ʼn����������X���鏟���ł����B�I�[�o�[�G�C�W�E�g�c�����i�̔ȃo�b�N��w�����A�O���œG�̍U���̉��E�ގ��X�Ȃ܂ł̎���͑�����������A�ނ�ɔނ�̃T�b�J�[�������܂���ł����B�u�S���U���A�S������v�Ƃ����֒˃C�Y���������ɐZ�����������܂����B�����ĉ������A��ɏ��Ƃ����C���ɖ������Ă��܂����B�����f���������̃e�[�}�u�ӊO���v�́A���̎�������n�܂����̂ł��B�@2��1���ŁA�O���[�v��1�ʒʉ߁B���{�ɕ������X�y�C���́A�C�������ė\�I���[�O�s�ށB���҃X�y�C���Ɉ�����n�����֒˃W���p���́A���j�ɖ����Ƃǂ߂�ɒl���܂��B
�@�����g�[�i�����g�E���X�����̑���̓A���u�̗Y�E�G�W�v�g�B�搧�_�͎����O�̃X�s�[�h�������i��ɂ���Đ��܂�܂����B�������A�����ŕ������đޏ�B���̂���2�_�����A���{��3�|0�ʼn������܂����A���Ƃ���l����ƁA���̉i��̕��������{�̍s�������Î����Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@�x�X�g4�i�o�́A�����_�����l����1968�N�A���L�V�R�V�e�B���ȗ�44�N�Ԃ�A�����ĂΎj�㏉�̋�_���ȏオ�m�肵�܂��B����͒��O�̗��K�}�b�`�ŏ����Ă��郁�L�V�R�B��������{���A����44�N�O�A�����_�������߂��Ƃ��̑���B�V���ɂ��u�J�Ԃ̐�����j�����ށv�u���n�E�F���u���[�ʼnh�����v�Ȃǂ̊��������A�͕���������܂����B
�@����ȕ����ꃀ�[�h�̒��ŁA��l���c�p���������x�����Ă��܂����B�u�ǂ�ȂƂ��ɂ��A���������̃X�^�C�����т��邩�ǂ����B��������͂��ꂪ�|�C���g���v�ƁB
�@�ނ̌x���́A�������̃��L�V�R��ŁA���A�����̂��̂ƂȂ�܂����B�O��11���A������D���E��Â̍��ۋ��̃~�h���E�V���[�g�œ��{���搧�B��D�̃X�^�[�g�ƂȂ�܂������A���L�V�R��30���A�Z�b�g�v���[����̃w�f�B���O�œ��_�B����͂܂��A�փf�B���O�̂����苅�����̑I��Ƀh���s�V���ɓ��������R���̍����S�[���B��Â̐搧�_�ɔ䂷�ׂ����Ȃ����e�Ȃ̂ŁA�����������Ƃ͂Ȃ��̂ɁA�Ȃ������C���Ȃ��A�����������B����͊�Ȃ��Ǝv���Č��Ă�����A�Ă̒�A�㔼19���A�S�[���L�[�p�[���c�̌q���̃X���[��������ɖ��ȃh���u�������ă{�[����D���A���ɂ���3�l�̃f�B�t�F���_�[����R�ƌ���钆�A�G�Ƀt���[�̑̐����狭��ȃ~�h���E�V���[�g��ł���ċt�]�������܂����B���ꂼ�W���͂̌��@�A���ɓ��e�̈������_�ł����B����ł͏�������ł��B
�@�ł����̂̓��L�V�R�̃I�[�o�[�G�C�W�g�����^�B�ނ͂��̌�A�����̃u���W����ł�2���_���������ԗւ̊���B�D���ɑ傢�ɍv�����܂����B��������ɏ��Ƃ��ɂ́A���������q�[���[���K���������̂ł��ˁB
�@�����肾�������{�̗��_�͑傫�������B������̃C���^�r���[�ł́A�u�Ƃɂ�������l���Đ�ւ��܂��v�i��Áj�Ƃ����̂�����t�ł����B
�@���{�̔s���́A�C�������A�u���v����u���Ă�v�ɐ�ւ���Ă��܂������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B遂聕���f�Ƃ܂ł͌����܂��A�������ߐM�݁A�u���������̃T�b�J�[�����Ƃ����v�Ƃ����Ђ��ނ����Ɍ����Ă��܂����B���c�̞X�J�������ƂȂ����̂ł��B
 �@�؍��Ƃ�3�ʌ�����0�|2�̊��s�B�I��Ƀ��_���ւ̎��O�͂������ł��傤���AJ���[�O��m��s�������z���E�~�����{�ē̎����Ȍ����ɂ��J�E���^�[2�{�ɂ���Ă��܂��܂����B���_�A����������Ɏ��H�����؍��C���u���̗͗ʂ͑f���ɔF�߂���܂��B
�@�؍��Ƃ�3�ʌ�����0�|2�̊��s�B�I��Ƀ��_���ւ̎��O�͂������ł��傤���AJ���[�O��m��s�������z���E�~�����{�ē̎����Ȍ����ɂ��J�E���^�[2�{�ɂ���Ă��܂��܂����B���_�A����������Ɏ��H�����؍��C���u���̗͗ʂ͑f���ɔF�߂���܂��B�@�����i�o��j�܂ꂽ���_����\���Ȑ�ւ����ł��Ȃ��������ƁA����Ȃ��J�[�f�B�t�̓�炩�ȃs�b�`�Ɍ˘f�������Ɓi�؍���2�x�ځj�A�B��6�̉���n����������̔�ꂪ�G�ȏ�ɒ~�ς��Ă������ƂȂǁA�s���͂��낢�닓�����܂��B�ł������͕����B������͂�߂܂��傤�B�X�|�[�c�ɍ��̃G�S���������ނ悤�Ȗ�ڂȔy�ɕ������̂͊m���ɉ���������ǁA��X�͍�����t�F�A�v���[�̐��_���т����ł͂���܂��B���ꂪ���{�̃T�b�J�[�ł�����B
�@�֒˃W���p���A���_���͊l��Ȃ���������ǁA�x�X�g�S�i�o�͗��h�ł��B���̒��c�����S�[���f���E�G�C�W�����B�ł��Ȃ����������X�e�[�W�ɋ삯������J�Ԃ̃C���u���ɁA�S����V����ł��B�X�y�C����̏����́A���{�I��c�ɁA�u�S�͂ŗ����������A��������ɂ����Ă�v�Ƃ����E�C�Ǝ��M��^���܂����B�ނ炱���A�{���A���{���i�̌����͂ɂȂ����̂ł��B������A�����ċA���Ă��Ăق����B�����Ă��ꂩ��A�u���������̃X�^�C���v���т��p���A��������l���悤�ł͂���܂��B
[�Ȃł��� ���{�̌ւ�]
 �@�Ȃł����̋�_���͏^�ɒl���܂��B�����_����q�����A�����J���1�|2�ŗ��Ƃ������ƁA���̒m�I�ŗ�ÂȃL���v�e���{�Ԃ��A10�����̊ԁA�l�ڂ��݂炸�������Ⴍ��p�ɁA�u���l��v���{�C���������Ƃ����߂Ďv���m�炳��āA�т����肵���Ɠ����Ɋ������܂����B
�@�Ȃł����̋�_���͏^�ɒl���܂��B�����_����q�����A�����J���1�|2�ŗ��Ƃ������ƁA���̒m�I�ŗ�ÂȃL���v�e���{�Ԃ��A10�����̊ԁA�l�ڂ��݂炸�������Ⴍ��p�ɁA�u���l��v���{�C���������Ƃ����߂Ďv���m�炳��āA�т����肵���Ɠ����Ɋ������܂����B�@�ޏ��قǏ����ɃT�b�J�[���D���Ȑl�͂��Ȃ��B�����v�����̂́A��N���[���h�J�b�v�Ő��E��ɂȂ��āA�A����A�����ɂ͑؍݂����A�����ɏ����N���u�̖{���n���R�ɋA�����Ƃ��ł����B�ޏ��̒��ɂ́u�e���r�ōL����������A�傫�ȑ��ŗD�����邱�Ƃ̂ق����A���q�T�b�J�[���W�̂��߂ɂȂ�v�Ƃ����M�O���������̂ł��B�����āA������p�����L���v�e���Ƃ��Ă̎g�����A�u�����h���ŋ����l�邱�Ɓv�ɒu�����Ǝv���B�ޏ��́u�����_�������l���Ă��܂���v�́A�{���̖{�C�������̂ł��B
�@�����āA�ޏ��͌����Ƀ`�[�������グ�܂Ƃߏグ���B�I��Ƃ��Ă̗͗ʂ�����Ȃ��A��NJςɗ��ł����ꂽ���Q�̃Q�[�������͂Ɠǂ݁A�I����v����蕱����������l���ȂǁA���[�_�[�Ƃ��Ă̑f�{�����ׂďo�����āB�ޏ��́A�܂��A����I�ɉ��x���s�����Ƃ����I��ԃ~�[�e�B���O�ɂ����āA��p�ʐ��_�ʂŔ��Q�̃��[�_�[�V�b�v����������Ƃł��傤�B�܂��ɃL���v�e���ɑ������������������Ǝv���܂��B���炭���̂��Ƃ́A���X�؊ēn�ߑ���܂߂��Ȃł����S�����F�߂Ă���͂��ł��B�ł��u���v��������Ȃ����_�o�ȃ}�X�R�~�␢�Ԃɂ��̂��Ƃ��ؖ�����ɂ́A�����h���ŃA�����J�ɏ����ċ����_�����l��A���[���h�J�b�v�`�ܗ֘A�e�Ƃ����j�㏉�̈̋Ƃ�B�����邱�Ƃ����Ȃ��A�����l���Ă����̂ł��傤�B�A�����J�̎��͂����{�������Ă��邱�Ƃ�m������ŁB
�@�����_����q�����A�����J�Ƃ̌�����B�Ȃł����͌����ɂ��̂炵�����o���Đ킢�������B����́A�u��ɒ��߂Ȃ��v�Ƃ������������̃X�^�C�����т��Ƃ����������Ȑ킢�Ԃ�ł����B
�@�����A�O��26���A���{�̃y�i���e�B�E�G���A���ł̃A�����J�I��̃n���h��R�����������Ȃ������Ȃ�A�����A�O��33���A�{�Ԃ̃~�h���E�V���[�g���A�N���X�o�[�̂ق�̋͂����ɓ����Ă�����A�ȂǁA�v���Ƃ���͂���܂����A�T�b�J�[�̐_�l�́A����̓A�����J��`�[���ɔ��B���[���h�J�b�v�̃��x���W�ɔR���A�œ|���{���f���čŋ��`�[���Ɖ����Ȃ���A�����̃��[�O���x�~���Ƃ����t���̃A�����J�ɔ��B�������ꂾ���̂��ƁB�u�Ȃł�������A���j�����̂͏������葁�������v�Ƃł������Ȃ���B
�@�{�Ԃ̗܂́A�����Ă��Ă����������Ȃ��Q�[���ɃT�b�J�[�̐_�l������ł���Ȃ��������Ƃւ̉������ƁA��肫�������g���A���Ԃ�X�^�b�t�A�����҂ւ̊��ӁA���̃`�[���ƕʂ�邱�Ƃւ̗҂����Ȃǂ��Ȃ������ɂȂ����A���G�Ȃ��̂������̂ł��傤�B
�@�A�����J��̑O�A��́u�ō��̕���ōō��̒��Ԃƍō��̑���Ɛ킦��K���v�Ƃ���������f���܂����B���ׂẴQ�[����ʂ��A�ޏ��̎p�͑f���炵�������B�����Ȃт����ăs�b�`�ɖ�������p�͂܂�ŃT���u���b�g�̂悤�Ȕ������B�G�̍U���̉��E�݁A�@�����čU���ɎQ������c�����s�̓����́A�t�H�A�E�U�E�`�[�����̂��́BOne for all �̌��{�ł����B������ł̗B��̓��_�́A�ޏ��̌��g�̂Ȃ���Ƃł��B
 �@�ޏ��̌����̒��ɁA�S���{��ނ����Ƃ�������������������܂����A���������������B�܂��܂�����ė~�������A�܂��܂�����B�Ȃɂ����A�M���̑��݂͂Ȃł����ɕK�v�Ȃ̂�����B
�@�ޏ��̌����̒��ɁA�S���{��ނ����Ƃ�������������������܂����A���������������B�܂��܂�����ė~�������A�܂��܂�����B�Ȃɂ����A�M���̑��݂͂Ȃł����ɕK�v�Ȃ̂�����B�@�������Ⴍ���Ă����Ȃł������A�\�����ł͑ł��ĕς���ďΊ�œo�ꂵ�܂����B�����Ă����Ă͂��܂�Ȃ��B�����Ă����ᑊ��Ɏ��炾�B�\����ł��ǂ���Ȃł����ɁA���X���������܂����B�u�����ɂ��钇�Ԃƃo�b�N�A�b�v�����o�[�A�X�^�b�t�Ɋ��ӂ��������A�ւ�Ɏv���܂��v�͋{�Ԃ̌��t�B�f���炵����_���B���_�A���{�T�b�J�[�j�㏉�̉����B�����A���͂����܂ł̑P���\�z���Ă��܂���ł����B�Ȃł����͓��{�̌ւ�ł��B
2012.08.10 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�A
�m���������ɏt�n �@8��5���A�������ŃV���K�|�[����j���Č����i�o�A�������A�ΐ�����A���쑁��̎O�l���́A���ɃI�����s�b�N�ߊ�̃��_�����l�����܂����B
�@8��5���A�������ŃV���K�|�[����j���Č����i�o�A�������A�ΐ�����A���쑁��̎O�l���́A���ɃI�����s�b�N�ߊ�̃��_�����l�����܂����B�@���̎����Ɋւ��Ă̎�M�҂́A�����ł��傤�B��1�����̑���́A�V���O���X�l��Őΐ�����̃��_���ւ̖���D�����t�H���E�e�B�G���E�F�C�B�����͂��̑I��Ɉ����B�����̃��x���W���ʂ����Ɠ����Ƀ`�[���ɗ�����Ăэ��݂܂����B���̐����ɏ���ē��{�̓X�g���[�g�����B���̋����������A���_���l���̑单���ɐ��������B�ςݏd�˂��w�͕͂����̂��̂ł͂Ȃ������͂��ł��B������͒����`�[���Ɋ��s�A���_���̐F�͋�ł������A�������Ȃ���3�l���Ɋ��t�ł��I
�@�I�����s�b�N�싅�̗��j�͔�r�I�A1988�N�\�E�����琳����ڂɁB����A�O�l���͒j���ʂ��ď��̃��_�����l�������킯�ł��B����́A�u�j�㏉�v�Ƃ����t���[�Y�����ɂ悭�����܂��B�����_���Ɏ��グ�Ă݂܂��傤�B
[�t�W�J�L]
 �@�o�h�~���g���E���q�_�u���X�Ƃ����A���Ắu�I�O�V�I�v�A2008�k���́u�X�G�}�G�v�A�����č���́u�t�W�J�L�v�ł����B
�@�o�h�~���g���E���q�_�u���X�Ƃ����A���Ắu�I�O�V�I�v�A2008�k���́u�X�G�}�G�v�A�����č���́u�t�W�J�L�v�ł����B�@8��3���A�o�h�~���g���E���q�_�u���X�A���䐐�_��߉��̋�_�������h�̈��B�u�Ȃ��ɁA���C�͎����̂������v�Ƃ�������������܂��傤�B�Ȃɂ��A��������O�ɁA���E�����N1�ʂ��܂�4�y�A�����i�����̂ł�����B
�@�����������A���E�����N2�ʁE�����y�A�Ƃ̌�����ł̑P��́A�ޏ������̋�_�����Ȃ��p���ׂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ���Ă��܂��B���̑�2�Z�b�g14�_�ڂ̊_��̃X�}�b�V��3�A����15�|�C���g�ځE����Ӑg�̌���ł͂��̏ł��B �j�㏉�̃��_���A���߂łƂ��I
[�Ǎ��̌��m�ɒc�̂̋�]
 �@8��5���A�t�F���V���O�E�t���[���c�́B���c�Y�M�́A�O��̖k���͌l�ŋ�B����͒c�̂Ŋl��܂����B�c�̂Ƃ��Ďj�㏉���_���B�����́A�������h�C�c��ŏI�s���I�h�B�c��2�b��1�_�̃r�n�C���h�B���̂܂܂Ȃ�s��Ƃ�����̐▽�̏��A�ʊ��ɔ�э���œ��_�B�����Ɏ�������ŏ������B��������2�b�I ���̏�ʂ͉��x���Ă��������m�B�S�C����Ƃ͂܂��ɂ��̂��ƁB�����ւ̎��O�̌��{�ł��B�����̑��c�́A�����܂Ō����Ė{���q�ł͂Ȃ��A�ނ����y�ɏ������Ă����悤�ł��B�u�����ł��Ȃ��Ⴂ���́v�E�E�E���Ԃւ̑z������Ղ��Ă̂ł��傤�B���̂����肪�c�̐�̂悳�A�ʔ������Ǝv���܂��B���{�Ń}�C�i�[�ȋ��Z���A�����܂ň����グ�����c�N�ɂ͓V����ł��B
�@8��5���A�t�F���V���O�E�t���[���c�́B���c�Y�M�́A�O��̖k���͌l�ŋ�B����͒c�̂Ŋl��܂����B�c�̂Ƃ��Ďj�㏉���_���B�����́A�������h�C�c��ŏI�s���I�h�B�c��2�b��1�_�̃r�n�C���h�B���̂܂܂Ȃ�s��Ƃ�����̐▽�̏��A�ʊ��ɔ�э���œ��_�B�����Ɏ�������ŏ������B��������2�b�I ���̏�ʂ͉��x���Ă��������m�B�S�C����Ƃ͂܂��ɂ��̂��ƁB�����ւ̎��O�̌��{�ł��B�����̑��c�́A�����܂Ō����Ė{���q�ł͂Ȃ��A�ނ����y�ɏ������Ă����悤�ł��B�u�����ł��Ȃ��Ⴂ���́v�E�E�E���Ԃւ̑z������Ղ��Ă̂ł��傤�B���̂����肪�c�̐�̂悳�A�ʔ������Ǝv���܂��B���{�Ń}�C�i�[�ȋ��Z���A�����܂ň����グ�����c�N�ɂ͓V����ł��B[�e�j�X�ƃ{�N�V���O]
 �@�e�j�X���E�����N16�ʂ��ѐD�\�́A�j�q�V���O���X�Ńx�X�g4��ڎw�����A�����N9�ʃA���[���`���̃f���|�g���ɃX�g���[�g�����B�����Ă���A92�N�Ԃ��̏������i�o�ł����B���݂ɂ���1920�N�A���g���[�v���́A�F�J��킪�V���O���X�ƃ_�u���X�iwith��������Y�j�ŋ�B���ꂪ���{�̃I�����s�b�N�����_���ł����B
�@�e�j�X���E�����N16�ʂ��ѐD�\�́A�j�q�V���O���X�Ńx�X�g4��ڎw�����A�����N9�ʃA���[���`���̃f���|�g���ɃX�g���[�g�����B�����Ă���A92�N�Ԃ��̏������i�o�ł����B���݂ɂ���1920�N�A���g���[�v���́A�F�J��킪�V���O���X�ƃ_�u���X�iwith��������Y�j�ŋ�B���ꂪ���{�̃I�����s�b�N�����_���ł����B�@������ł́A�n���C�M���X���A���f�B�[�E�}���[�������L���O1�ʂ̃t�F�f���[��j������_���l���A�E�B���u���h���̐�J���ʂ����܂����B�C�M���X���������̂́A�Ȃ�ƁA1908�N�����h���E�I�����s�b�N�ȗ��A104�N�Ԃ��B���������h���̐V���͈�ʃ}���[�ł����B
�@�{�N�V���O�A�o���^�������������͏������ɐi�o�A�����_���ȏ���m��B2���łȂ�Ƃ��A�z�炵�����S���R���̔���ň�U�͔s��ƂȂ�܂������A���R�̂悤�ɕ���A�����܂ŋ��i�߂܂����B���݂ɂ��̐R���̓I�����s�b�N����Ǖ��ƂȂ�܂����B����͂����ł��傤�A����I�肪3����_�E�������̂Ɉ���J�E���g�����A����̉ʂĂɂ͔��菟����^�����̂ł�����B�ǂ����Ă����āH �d�G�Ƃ����l�����܂���ˁB �~�h�����ł����c�ȑ������X������˔j�A���_�������߂܂����B���d�ʋ��ł͓��{�l���̉����ł��B
�@�{�N�V���O�̃��_����1968�N�A���L�V�R���̃o���^�����E�X���p���ȗ�44�N�Ԃ��B�����Ɠ����I�����s�b�N�̃o���^�����E����F�Y�ȗ�48�N�Ԃ��B������œ�l�̃��_���l���͎j�㏉�ɂȂ�܂��B
[����A���ƌ|]
 �@�_���́A7��30���A���q57k���E���{�O�̊l���������A�j����ʂ��ėB��̋����_���ł����B�ޏ��̓����S�ނ��o���̐킢�Ԃ�́A���Ɋ����I�ł����B����ɁA�f�炪�܂�Ő����̃L�����ɂ��傢�ɍD�������Ă܂����B�O�����A�����x��I
�@�_���́A7��30���A���q57k���E���{�O�̊l���������A�j����ʂ��ėB��̋����_���ł����B�ޏ��̓����S�ނ��o���̐킢�Ԃ�́A���Ɋ����I�ł����B����ɁA�f�炪�܂�Ő����̃L�����ɂ��傢�ɍD�������Ă܂����B�O�����A�����x��I�@�_����������ڂƂȂ���1964�N�����I�����s�b�N�ȗ��A�j�q�̋����_���O�͎j�㏉�̋��J�ƂȂ�܂����B���M���ēɂ́A�u�m�×ʂƐ��_�_�����̌ÏL���w���́H�v�Ȃ�ᔻ���W�܂��Ă���悤�ł��B
�@�ߔN�̏_���́A�ו������ꂽ�|�C���g�ɑΉ����āA���傱�܂��ƃ|�C���g���҂��������A�_���Ȃ��JUDO�̗l����悵�Ă��܂��B
�@�_���̑n�n�҂ɂ��ču���ق̊J�ݎ҂̉Ô[���ܘY�����������_�́u�_�悭���𐧂��v�ł��B�̊i�I�ɗ���Ă��Ă��A����̗͂𗘗p���čŌ�ɂ͋t�]�œ�������A���ꂱ�������{�_���̋ɈӂȂ̂ł��B
�@���ḗA���������2000�N�V�h�j�[�ܗցE100�����������ŁA���S�Ɉ�{�Ǝv�����̂����̊ԁA��ɐ��I�̑��R�Ƃ�����~�X�W���b�W�Ɍ������ċ����_�����킵�Ă��܂��B�ނ͎�����A�u�������ォ���������v�ƈ�،���������܂���ł����B
�@����͎��̐����ł����A����Ȍo���܂����ނ̖ڎw���_���Ƃ́A��R�����Ȃ���������ƈ�{���l��_���A�������{�`���̐��_�ɑ������_�����Ǝv���̂ł��B
�@�_���n�n�̐��_���Ȃ��ăI�����s�b�N��JUDO�𐧂���E�E�E���ꂪ�S���{�ēE���̗��O�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@������ɏ_����JUDO�͍��{�I�ɑ��e��Ȃ����́B��������ƈ�{��_�����A�s�ӂɃ|�C���g��D���ē�����̂�����JUDO�Ȃ̂ł́H �u���Ǝv���Ȏv���Ε�����v�i����Ђ�u�_�v�j�Ƃ��u�Ԃƍ炭��蓥�܂�Đ����� ���̐S�����͍D���v�i���c�p�Y�u�p�O�l�Y�v�j�ȂǏ_�����̂̉̎��̂悤�ɁA�ς��ĔE��ł����畉���Ă��܂��̂��A����JUDO�Ȃ̂ł��B
�@�O���[�o��������JUDO�Ƃ����X�|�[�c�́A���ˍ��̐�����Ă��ꂩ����ϖe��������ł��傤�B���M�ꂱ���A�_����JUDO�̃M���b�v�ɂ������A�f�r���鋁���҂Ȃ̂�������܂���B
�@�I�����s�b�N�ŋ�����邱�Ƃ����{�_���̕����Ƃ����̂Ȃ�A����͂���JUDO�ɍ��킹�邵���Ȃ��B�_�����̂Ă邵���Ȃ��B�g�_����JUDO�Ƃ͕ʃ��m�ł���h�Ƃ����F���ɗ����Ƃ��A�����ւ̑����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�f�l�̓ƒf�Ƃ͎v���A�����l������Ȃ��̂ł��B
2012.08.07 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�@
�@�����h���ܗւ��n�܂�܂����B�����h���́A�����3��ڂ̃I�����s�b�N�B�ŏ��͑�4��A1908�N�B���͑�14��A1948�N�ł����A���{�͔s�퍑�������̂ŕs�Q���B���{�̃I�����s�b�N���Q����1912�N�̃X�g�b�N�z�������Ȃ̂ŁA�����h���͍����߂Ă̎Q���ƂȂ�܂��B�@�J�Í�����̃G���U�x�X�����́A���N�ő���60�N�B����Ȃ���ȂŁA�Ȃɂ����j�̓����������Ă�����A�o��͏o��́u���N�Ԃ�v�Ƃ����t���[�Y�B�܂��Ɂu���j��ځv�B�����B�����g�I�����s�b�N��D���l�ԁh�̎��A���܂��ɖ��̂ЂƎ��^�������ɂ��܂��B ������̃L�C���[�h�́u�ӊO���v�B��{�������q���̏��Ղ̗����B�E�T�C����{���g�̒����s���B�o���̈����}�C�P���E�t�F���v�X�ȂǂȂǁB
�@���đ�30��ܗփ����h�����͂ǂ��W�J����̂��H �I�����s�b�N���Ԓ��́u�N�����m�v�{�،����͍����u���āA���̊ϓ_����A�C�y�Ƀ����h���E�I�����s�b�N��ǂ��Ă݂܂��傤�B
[�悭���J���o�b�N�I �����q��]
 �@�C�M���X�̃u�b�N���[�J�[�̋����_���|�����́A�킪�����q�����A�I�����s�b�N�Q���I�蒆��NO1�������Ƃ��B����قnjł��Ǝv��ꂽ�u�̑��j�q�l�����v�Ɍ������āA7��28���ɍs��ꂽ�u�c�̗\�I�v�ɂ͍������Ă��܂��܂����B�Ȃ�ƍŏ��́u�S�_�v�A����Z�̃R�[���}���ł܂����̗���������������̂ł��B���ꂪ���������Ă��A���̓��͎U�X�̏o���B�l�����̏��ʂ͈ӊO���̋ɒv��9�ʁB�\�I�����˂Ă����u��ڕʁv�́A�u�䂩�v�ŏo�ꌠ���l�����������ł����B���̓��̓��_�͖{�Ԃɂ͈����p���Ȃ��Ƃ͂����A�o���̈����͔��[����Ȃ��B���������Ȃ��킯���Ȃ��Ǝv���܂����B
�@�C�M���X�̃u�b�N���[�J�[�̋����_���|�����́A�킪�����q�����A�I�����s�b�N�Q���I�蒆��NO1�������Ƃ��B����قnjł��Ǝv��ꂽ�u�̑��j�q�l�����v�Ɍ������āA7��28���ɍs��ꂽ�u�c�̗\�I�v�ɂ͍������Ă��܂��܂����B�Ȃ�ƍŏ��́u�S�_�v�A����Z�̃R�[���}���ł܂����̗���������������̂ł��B���ꂪ���������Ă��A���̓��͎U�X�̏o���B�l�����̏��ʂ͈ӊO���̋ɒv��9�ʁB�\�I�����˂Ă����u��ڕʁv�́A�u�䂩�v�ŏo�ꌠ���l�����������ł����B���̓��̓��_�͖{�Ԃɂ͈����p���Ȃ��Ƃ͂����A�o���̈����͔��[����Ȃ��B���������Ȃ��킯���Ȃ��Ǝv���܂����B�@7��30���A�����A���悢��������ł��~�����Ƃ����u�j�q�c�́v�B�ŏI��ځu����n�v���c���āA5��ڂł̓��_��2�Ԏ�B�P�ʂ̒����͗y���ޕ��Ȃ̂ŁA�u�c�O�Ȃ����2�ʑ_���v�Ǝv���Č��Ă�����A�����N�A�Ȃ�ƒ��n�ő厸�s�B�u13.466�A���{���_�������I�v�Ƃ����A�i�E���T�[�̐⋩�����Ƃ��̈��W����C���͍����Y����܂���B�R�[�`�w�R�c�A�R���c�͌����ɁB�҂���15���B���n�O���̓|�����F�߂��ā{0�D6�B�Ȃ�Ƃ���_���Ɋ��荞�̂ł��B���ꂪ�F�߂��Ȃ���A���{�j�q�c�̂͑�4�ʂ������B�u�����������܂łȂɂ�����Ă����̂��낤�v�͔ނ̂��̓��̃V���b�N�Ƌ�Y����Ă��܂����B�������A���̂܂܂������Ǝv���Ƃ����Ƃ��܂��B�������̓����N���A�g���_���Ȃ��h�ł͐�ւ���̂ɑ�ς������ɈႢ�Ȃ�����ł��B
�@���݂ɑ�3�ʂ̓C�M���X�B����̓X�g�b�N�z�������ȗ�100�N�Ԃ��̃��_���ł����B
�@8��2���́u�l�����v�́A���J�I��9�ʔ��i�̂��߁u����n�v����X�^�[�g�B���ꂪ�K�^�ł����B�ŏ��ɂȂ�Ƃ��N���A���Ă��܂��A���Ƃ͗���ɏ���Ɣނ͓ǂB�ژ_���ǂ���ʉ�15.066�B�u��ցv�͂��Ƃ��Ɠ��ӂ���Ȃ����ǎ��s�����Ȃ����Z�A����������ʉ�15.333�B�����͎��́u���n�v�ł����BG��x�V���[�t�F���g���s�^���ƌ��߁A�Ȃ��16.266�B����Ń_���g�c�̃g�b�v�B���̕��s�_����Ȃ��Ȃ�15.325�B���Ƃ́u�S�_�v�ŗ����Ȃ����OK�Ƃ����Ƃ���܂ő��������B���́u�S�_�v�́A�����̊댯������G��x�R�[���}��������A����ɂ܂Ƃ�15.600�B�������菟���ɂ����������ł����B���ӂ́u�䂩�v�͂���ɐT�d�ɂ܂Ƃ߁A15.100�B�g�[�^��92.690��2�ʂ�2.659�̑卷�B ���߂łƂ������B���̈����̃X�^�[�g����Z���Ԃł悭���������Ă���܂����B�������ӊO�ł������A����قǂ܂ł̌����ȗ�������������Ӗ��ňӊO�ł����B���j��R�����A�l�����̋��́A1984�N�A���T���[���X���̋�u���K�i�ȗ�28�N�Ԃ��ł����B
�@8��5���A��ڕʗB��o��́u�䂩�v�͒������z����ꂸ��BG��x�u���E�W�����\���v���͕̂s���ł������A�����̐V����������A�u���Z����1�ԂŁA�̂����߂鎞�Ԃ��Ȃ���������v�Ɣ������Ĕ[�����܂����B
�@�̑��̐^�̋��҂́A�X�y�V�����X�g�ł͂Ȃ��I�[�����E���h�E�v���C���[�ł��B�l�����̓����̎�ڕʃ����N�͂��ׂĈꌅ�B�_���͂��ׂ�15�_�ȏ�B����ȑI��͔ވȊO�ɂ��܂���B���̃����̂Ȃ������A���������E�i���o�[�����ł��邱�Ƃ̏ؖ��Ȃ̂ł��B
�@�����A����2016�N���I��27�B���x�����u�c�́v���u�l�����v��W�������肢���܂��B�c����������������������A���x�͓������݂��y������͂��B���ґ�ł��B
[��͂�����������}�C�P���E�t�F���v�X]
 �@�}�C�P���E�t�F���v�X�̂���܂łɊl�����������_����14�A����17�B�����ȊO�̉��҂ł�����܂���B�Ƃ��낪�A�ŏ��̌l��ځu400m�l���h���[�v�ł́A���{�̍��Z���E��������i���l���j�̌�o��q���ӊO����4���B
�@�}�C�P���E�t�F���v�X�̂���܂łɊl�����������_����14�A����17�B�����ȊO�̉��҂ł�����܂���B�Ƃ��낪�A�ŏ��̌l��ځu400m�l���h���[�v�ł́A���{�̍��Z���E��������i���l���j�̌�o��q���ӊO����4���B�@�g����̃t�F���v�X�͕|���Ȃ��h�Ǝv�����Ƃ���A���X�ɒ��q���グ�Ă��āA���ʁA�u800m�����[�v�u100���o�^�t���C�v�u200m�l���h���[�v�u400�����h���[�E�����[�v�ŋ��A�u200m�o�^�t���C�v�ŋ���l���B�ʎZ��18�A����22�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ��L�^�����������̂ł��B����ɁA�k���N��_���Ă���������3�A�e���u100�o�^�v�Ɓu200�l���h���[�v��W�B���B�X�^�[�g�̈ӊO�����A�I����Ă݂�Ό����ȗ�������B�S���Z�I����A�ނ͈��ނ𐺖����܂������A����قǂ܂ł̑�I��͓�x�ƍĂь���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�@�k���N���̌l��ڃ��_���Ȃ��́A�ӊO���̈ӊO�ł����B�I�����s�b�N�I�l��Ŏ��ȃx�X�g���o���A�{�Ԃւ̃s�[�N���킹�����l���Ȕނ�����A���̗\�z��W���ł����B�����H ���Ȃ�Ɏv���Ƃ���͂���̂ł����E�E�E�E�E�F���͂�߂Ă����܂��B
�@8��5���A���j���Z�Ō�̃��h���[�E�����[�ɂ͊������܂����B���̃��[�X�������̃��x���̏B�܂��A���q�����{�V�L�^�œ��B�����j�q�́A����܂Ń��_���Ȃ��̖k�����u��Ԃ�ł͋A���Ȃ��v�ƊF�������A���g�������ȉj���ŋ�B�f���炵���`�[�����[�N�ŗL�I�̔��B���]�ˉ�������u���h���[�E�����[�́g27�l�S���̃����[�h�B�A���J�[���S�[������܂Ń`�[���̃����[�͏I���Ȃ��v�͖����ł����B
�@���{���j�w�͑匒���B���_��11�͐��ő�B�����O�������͎̂c�O�ł������E�E�E�B���݂ɗ��j��H��ƁA1932�N���T���[���X���ł�12�i����5�j�̃��_�����l�����Ă��܂��B
[�{���g��A���͋�������]
 �@�I�����s�b�N�O�̃W���}�C�J���100m�ŁA�E�T�C����{���g�͗��F���n���E�u���[�N�̌�o��q���܂����B���ӂ�200m�����ʂȂ��S�[���O�Ŏ����B�Ō�̒������[�X�ɗ\�肵�Ă������c�F������������B�����ł̎��̗\�z�́A�g�{���g�{�Ԃ͊낤���h�ł����B��N�̃e�O���E����ł��A�t���C���O���i�ƁA�s�����炯�̃{���g����������ł��B
�@�����������A8��5���A�{���g��100m�����́A9�b64�̃I�����s�b�N�E���R�[�h�ł̋����_���B���ɂƂ��Ă͈ӊO���̈����ł����B�X�[�p�[�X�^�[���X�[�p�[�X�^�[�ł��邱�Ƃ��ؖ������u�Ԃł����B100m�̓�A�e�́A1988�N�A�\�E���̃J�[������C�X�ȗ��B���̂��Ƃ�200m��400m�����[���y���݂ɂ������܂��傤�B
�@�I�����s�b�N�O�̃W���}�C�J���100m�ŁA�E�T�C����{���g�͗��F���n���E�u���[�N�̌�o��q���܂����B���ӂ�200m�����ʂȂ��S�[���O�Ŏ����B�Ō�̒������[�X�ɗ\�肵�Ă������c�F������������B�����ł̎��̗\�z�́A�g�{���g�{�Ԃ͊낤���h�ł����B��N�̃e�O���E����ł��A�t���C���O���i�ƁA�s�����炯�̃{���g����������ł��B
�@�����������A8��5���A�{���g��100m�����́A9�b64�̃I�����s�b�N�E���R�[�h�ł̋����_���B���ɂƂ��Ă͈ӊO���̈����ł����B�X�[�p�[�X�^�[���X�[�p�[�X�^�[�ł��邱�Ƃ��ؖ������u�Ԃł����B100m�̓�A�e�́A1988�N�A�\�E���̃J�[������C�X�ȗ��B���̂��Ƃ�200m��400m�����[���y���݂ɂ������܂��傤�B
2012.07.25 (��) ���̒��̒����݂䂫5�|�����݂䂫�́g���́h�ł���4
�@�I�����s�b�N���߂��B���ڂ͂Ȃ�Ƃ����Ă��E�T�C���E�{���g��100����200���B����W���}�C�J���ł̎����́A�Ȃɂ������Ȃ̂��H �{�ԑO�E�����r��ł̒o�ɂł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�p���Ƃ���Έ�ԋ����Ɍ��܂��Ă���B�����������A���̊ɂ݂Ɉꐡ�ł��u���S�v�������Ă����Ƃ�����H ���̗\���́A�Y�o���A�u�낤���I�{���g�̋��v���B�@�k����3�A�e�́H ����͒B���ł����琦�����ƁA�j�q���j�ł̓I�����s�b�N�j�㏉�̉����ƂȂ�i���q�ł�100m���R�`�̃h���E�t���[�U�[������j�B������100�A200��W�Ȃ�A����͂����s�ł̋��������B�ނȂ炫���Ƃ�邾�낤�B
�@�̑��j�q�E�����q���̖ڕW�͋�5�B�c�́A�j�q�����A���A���n�A�S�_���B�ނ̋��o�͐l�q���Ă���Ƃ����B���i�̗͂��o��Όy���N���A�[�ł���͂����B���Ƃ́A�g�c���ۗ��i�����B�����A���A��t�@���j��3�A�e���F��B
�@�ł͖{��ɓ���܂��傤�B����͒����݂䂫�ŏI��B�c�ƏG�����u33��]�̈��̂������v�ɂ����āA�܂����钘�҂Ƃ̌����̑���ɂ��ďq�ׂ����Ă��������܂��B
�i1�j�u����v�̑������ɂ���
 �@�c�Ƃ���́A�����݂䂫�́u����v�ɂ��āA�u����܂ł����ς�j���^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă����g����h�Ƃ����e�[�}�������̂��悤�ɂȂ����A����͓��{�ɂ�����ƎЉ�Ƃ̊֘A�ō��̂��������o�Ă����Ƃ������Ƃʼn���I�Ȃ��Ƃ��v�Ƌ��Ă��܂������ɂ݂䂫�́u����v�̒��ɏo�Ă���|�ꂽ���l�Ƃ�60�N��̃\���O���C�^�[�����̂��Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ܂ŋ��Ă��܂��
�@�c�Ƃ���́A�����݂䂫�́u����v�ɂ��āA�u����܂ł����ς�j���^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă����g����h�Ƃ����e�[�}�������̂��悤�ɂȂ����A����͓��{�ɂ�����ƎЉ�Ƃ̊֘A�ō��̂��������o�Ă����Ƃ������Ƃʼn���I�Ȃ��Ƃ��v�Ƌ��Ă��܂������ɂ݂䂫�́u����v�̒��ɏo�Ă���|�ꂽ���l�Ƃ�60�N��̃\���O���C�^�[�����̂��Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ܂ŋ��Ă��܂���@�����ɂ́A�݂䂫���̂�����Ƃ���܂ł̒j���\���O���C�^�[�����̑���������Ƃ̓��ꎋ������܂����A����͌����Ⴂ�B����Ύ������H
�@�����݂䂫���u����v�̒��ʼn̂��g����h��60�N��t�H�[�N�̃\���O���C�^�[�������W�I�Ƃ����g�O�I�ȁh����ł͂Ȃ��A���Ȃ̓��ɂ���g���I�ȁh����ł���키����ł��莩���ɍS���Ȃ��ς���Ă䂭����ł͂Ȃ��A�����̂�����ɂ���ĕς���Č����Ă���g����h�Ȃ̂ł��B�g�����͓|�ꂽ���l�������@���܂�ς��ĕ��������h���ʂƂ��āg����͉��@��ш����݂���Ԃ��h�ƋA������B�������ς�邩�玞�オ�ς���Č�����̂ł��2�R�[���X�ڂɂ���g�o��ƕʂ������Ԃ��h���l�A�������B�݂䂫����́A�܂��͎����Ŋ撣��A������ς��ĕ�����Ŕj���悤�Ƃ���B����܂ł́g�����ς��Ă��h�������́g���オ�����h�ƁA�u����v��W�I�ɂ���̂Ƃ͌���I�ɈႤ�̂ł��B
�@�����璆���݂䂫�́u����v�́A���ł��V�N�Ȃ̂ł����肪���Ȃ̂��肩���ɂ���̂�����A����ɍ��E����Ȃ����Ր������B�������A�W�I�Ƃ��Ă̎��オ�e�[�}��������A���̉̂͂Ƃ����ɐF�����Ă����͂��ł��
�@�݂䂫����́u����v�������̂́A�g����h�Ƃ����Љ�I�ȃe�[�}���g���߂ď����h������������ł͂Ȃ��A�����݂䂫�Ƃ����V���K�[�E�\���O���C�^�[���u60�N��̃\���O���C�^�[�����Ƃ͑S���Ⴄ���_�Łg����h�Ƃ������̂𑨂����v���Ƃɂ���̂ł��
�i2�j�����݂䂫�̓W�����k�E�_���N���낤���H
�@�c�Ƃ���́A�33��]�̈��̂�������̒��ŁA���[�~�����N���I�p�g���ɒ����݂䂫���W�����k�E�_���N�ɗႦ�Ă��܂��B���́A���[�~���͂��Ă����A�݂䂫����Ɋւ��ẮA�W�����k�E�_���N�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��
�@�W�����k�E�_���N�́A10��̂�����A�_�̐����A���̐M�����āA�c���t�����X�̂��߂ɐ�����B�����Ĕޏ��͏�������B�����̃t�����X�͊m���ɔޏ���K�v�Ƃ��܂����B
�@�����݂䂫���A�_�̐����Ă����Ƀ��b�Z�[�W�𑗂��Ă���A����ȋC�����܂��B�����āA����̂������܂��A�ޏ���K�v�Ƃ��Ă���B��l�ɂ͊m���ɑ傫�ȋ��ʓ_������܂��B
�@�������Ȃ���A����I�ɈႤ�_������܂������́A�ڐ��̍����ł���W�����k��_���N�̓J���X�}�����Ȃ��ČR�𗦂����B����͕�����Ȃ��g�b�v�E�_�E���I�����ł��B����ɑ��Ă݂䂫����́A�ڐ�����ɉ�X�Ɠ��������ɐݒ肵�Ă���B�����Ă�������i���߂ł͂Ȃ��j�D������܂�����������̂ł�������݂䂫�ƃW�����k�E�_���N�́A�������Ɍ���I�ȈႢ������Ǝ��͎v���܂��B
�@���̖̂{�ɂ��ƕ����`���q���Ɂu�����q�v�Ƃ��������|�\�҂����܂����B�`�o�̗��l�̐Ì�O���L���ł����A�ޏ������́A��ʂ̐l�X�A���ɋC�����̒��l�X�ɉ̂��̂������Ĉꎞ�̈Ԃ߂�^���Ă����Ƃ����Ă��܂�����݂͂䂫����ɂ���ȁu�����q�v�������܂���uMEGAMI�v�u�V���K�[�v�Ȃǂ�������ł��B
�@�����Ă�����A�������u���o�t�v�Ƃ�����m�������B���O�̂Ƃ��肨�o������A���Ȃ킿�A�l�X��ɓ����ړI�ő哹�ŕ��̓�������ĉ�����m���̂��ơ���t�ɗ}�g�����A���ɂ͊y����g���Đ����ĉ��܂�����b�����ʓI�ɐi�߂邽�߂ɁA�b�̑O���ł͂����ɂ��̐��̒�����������b���A��i�ŁA���̓��ɓ���O����������Ɋy��y�ɍs����Ɛ����̂ł�����̃M���b�v�����ʂ����āA���O�̓X���[�Y�ɕ���ɓ����Ă䂭�E�E�E�E�B�����ɂ́g�����̂��܂��h�Ɩ��O�Ɠ��������́g�ڐ��h������܂�������玄�݂͂䂫����Ɂu���o�t�v�������܂������́u�i�v���ԁv�̍\��������̃e�N�j�b�N�ɒʂ�����̂��Ǝv���܂��
�@���_�������݂䂫�̓W�����k�E�_���N�ł͂Ȃ��B����́u�����q�v�ł���u���o�t�v�ł���B
�i�R�j�u�z�[���ɂāv�̉w�͖k�C���ł����H
�@�c�Ƃ���́u�z�[���ɂāv�̃z�[���͖k�C���̉w����������ł��Ȃ��ƌ����܂����B��������͒f���ĈႤ�Ǝv���܂�������ł̃z�[�����k�C���ł͂��̉̂̈Ӗ����킩��Ȃ��Ȃ顂��̉̂́g�]���h�̔O�����������Ȃ���A�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̐S�̒��̖������̂����̂ł��傤��A�肽���C�����Ȃ̂ĂĂ����Ő����Ă䂫�����B�ł��A�肽���B�ł��A��킯�ɂ͂����Ȃ��B������A�₳�����w���̐��i����͎��ۂ̐��ł͂Ȃ��āA�݂䂫�̐S�̒��ɕ�������̋��̉w���̐����Ǝv���܂��j�Ɉ�����āA�g����ו��h�������āA�Ƃ肠�����̓z�[���ɗ����̂ł��傤�B�ł��A��Ȃ��͕̂����Ă��遁���킯�ɂ͂����Ȃ����Ƃ������Ă���A������D�Ԃ��s�����Ă��܂��̂ł��傤�B
�@�g�ӂ邳�Ƃ́@���葱�����z�[���̉ʂāh�ł���A�g�l�I�����C�g�ł́@�R�₹�Ȃ��@�ӂ邳�ƍs���̏�Ԍ��h�����܂��Ă��܂��̂ł��B���ꂪ�ǂ����Ėk�C���̉w�Ȃ̂ł��傤��������́g�l�I�����C�g������h�Ƃ���ŁA�g�z�[���̉ʂĂɂӂ邳�Ƃ�������h�Ƃ��끁�����A�������͓s��łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��
�@����ŁA�u���̒��̒����݂䂫�v���I��点�Ă��������܂��B�W�I�ɂ����c�ƏG�����u33��]�̈��̂������v�́A1984�N�ɏo�ł��ꂽ���́B�����݂䂫�����̂Ƃ��܂łɏo�����A���o����11�^�C�g���B�����ٕ����������̂�2003�N�B���̊ԁA20���̃A���o������ς݂��A�u���v���X�^�[�g�����A�u�n��̐��v��NHK�g���ɏo������ȂǁA�݂䂫����̕ω����i�ɂ͂����܂������̂�����܂����B������A�u����͕s�������v�ƌ����邩������܂���B�������Ȃ���A���̌��19�N���Ȃ��Ƃ��A�A�[�e�B�X�g�̖{���͑�������͂��B�������y�����̂́A�g���̎��_�ő����đR��ׂ��{���I�����h�Ɍ����Ă���Ǝv���Ă��܂��B
�@�Ō�ɓc�Ƃ���͂�������ł��܂��B�u���[�~�����Ђ���z�����������̂��낤�B�݂䂫�͉z�H����̂悤�ȃV���K�[�E�\���O���C�^�[�ɂȂ�̂�������Ȃ��v�ƁB����͏�k��y���łȂ��{�C�̋L�q�B�E�[��������Ƃǂ����ȁH ���Ȃ�g���`���J���I �����~�߂܂��傤�B���ꂩ��́A�����Ƃ܂Ƃ��Ȃ��̂Ɍ��������Ă䂫�����Ǝv���܂��B
2012.07.10 (��) ���̒��̒����݂䂫4�|�����݂䂫��"����"�ł���3
�@�O��܂łŁA�����ȗ����ʼn��̂����n���ɂ������҂ւ̔��_���q�ׂ����Ă��������܂������A����́A�o������������������āu�����݂䂫�͉��̂ł���v�����������Ǝv���܂��B�@����ɐ旧���āA�݂䂫����̉̂̓����������Ă����܂��傤�B���̎��̂��߂ɂ͌������Ȃ��Ǝv���̂ŁB
�@ �l���m��A�O�����A�ǂ�Ȃ炢���������Ă������Ăւ�����Ȃ��B
�u����v��"�����͓|�ꂽ���l���������܂�ς���ĕ���������"
�u�a���v��"�҂��Ă��҂��Ă��߂�ʗ��ł��@���ʂȌ����Ȃ�ĂȂ��ƌ����Ă�"
�u���ɍ~��J�v��"���ɐU��J�̗₽���͐�����Ƌ��ԒN���̐�"
�A �D���������������������Ă����Ȃ��C��������
�u����������Ɂv��"����������Ɉ�l�͂����Ȃ��@�������̂��ɂ�����"
�u�a���v��"�v���o���Ȃ��Ȃ�@�����Ȃ��Ɍ���"
�u��ƌN�̂������Ɂv��"�N�����Ă����Ȃ�@�l�͈��ɂł��Ȃ�"
�B ���ʂ̐l�X�̖�������l��l�̑��݂����������̂Ȃ����̂Ƃ��Ĉʒu�t����
�u�i�v���ԁv��"�F���̏��̒��Ł@�l�͉i�v����"
�u�n��̐��v�ɗ����e�[�}�B
�C �������ł͂Ȃ��A���L����t�B�[���h�̒��ŁA�����ڐ��ŁA��܂��Ă���遁�@�u��������v�ł͂Ȃ��A�u�����������@������ꏏ�Ɋ撣���Ă݂悤��v�ƈꏏ�ɍl����܂��Ă����B����͔ޏ��̊�{�p���ŁA���ׂẲ̂��玩�R�Ɋ����Ƃ����̡
�D �]���̔O���ӂ邳�Ƃ��v���C�����̋���
�u�z�[���ɂāv��"�l�I�����C�g�ł͔R�₹�Ȃ��̋��s���̏�Ԍ�"
�u�C��v��"�C��@���������@������Ȃ�@�����̋��ց@�M���^�ׂ�"�Ȃ�
 �@�ł͏�L�����ɓ��ꂽ��ŁA��̓I�Ȋy�Ȃ��Ƃ�"�݂䂫VS����"�̋��ʍ������������܂���Δ䂳����2�Ȃ̂��������ɒ����݂䂫�̋ȁi�쎌�E��Ȃ͑S�Ē����݂䂫�j�A�E���ɉ��̂̋Ȗ��ƍ쎌�E��ȉƖ��Ɖ̎薼���L���A���ɂQ�̋Ȃ̋��ʍ����ȒP�ɋL�q�����Ă��������܂��
�@�ł͏�L�����ɓ��ꂽ��ŁA��̓I�Ȋy�Ȃ��Ƃ�"�݂䂫VS����"�̋��ʍ������������܂���Δ䂳����2�Ȃ̂��������ɒ����݂䂫�̋ȁi�쎌�E��Ȃ͑S�Ē����݂䂫�j�A�E���ɉ��̂̋Ȗ��ƍ쎌�E��ȉƖ��Ɖ̎薼���L���A���ɂQ�̋Ȃ̋��ʍ����ȒP�ɋL�q�����Ă��������܂��
�@�u�z�[���ɂāv VS �u�A�납�ȁv�i�i�Z��|��������A�k���O�Y�j�@�ȏ�̂悤�ɁA���ʂ���e�[�}�͌��\�����������A�u�݂䂫����̉̂����̂��������{�̑�O���y�Ƃ��ĕ����u�ĂȂ����������Ⴀ��܂��v�Ƃ����̂����̖{�ӂł��茋�_�ł��B
"�l�I�����C�g�ł́@�R�₹�Ȃ��@�ӂ邳�ƍs���̏�Ԍ�" VS "�A�납�ȁ@�A��̂悻������"
�s��Ŋ撣�낤�ƌ��߂��̂�����̋��ւȂA��Ȃ��B�����NjA�肽���Ȃ顂���Ȗ]���̔O�Ǝ��Ȃ̐S�̊����͗��҂ɋ��ʂ̂��̂��B
�A�u���ɑ���v VS �u�J�̕��v�i���v�I�|�l�\��A����I�j
"����������Ȏԁ@�����Ă��܂������̂�" VS "�J�X�ӂ�ӂ�@�����Ƃӂ�@���̂����l�@��ė���"
"�Ԃ������Ă��܂����̐l�Ƃ����ƈꏏ�ɂ�����"�Ƃ����u���ɑ���v�̏����̋C�����ƁA�u�J�̕��v��"�J���ӂ�A�����l������Ă���"�Ƃ������̋C�����͓����B�`���I�ȁu���S�������v�p�^�[��
�B�u����v VS �u��̗���̂悤�Ɂv�i�H���N�|���x�́A����Ђ�j
"�����͓|�ꂽ�@���l�������@���܂�ς��ā@����������" VS "�J�ɍ~���ā@�ʂ�����ł��@�����́@�܂��@�����������邩��"
���͌������Ă��������͕K������Ă���B�u�䂭��̗���͐₦�����āA���������Ƃ̐��ɂ��炸�v�A����L�̖���ςɂ��ʂ��Ă���B
�C�u�C��v VS �u�k���̏t�v�i���ł͂��|�������A�珹�v�j
"�C��@��������������Ȃ�@�����@�̋��ց@�M���^�ׂ�" VS "���̌̋��ց@�A�납�ȁ@�A�납��"
"�̋�"�̈Ӗ��͊e�l�v�X����Ă��Ă����ʂ���₿�������]���̔O�B
�D�u�������v VS �u�V��z���v�i�g�����|���N��A�ΐ삳���j
"�i�C�t�Ȃ�@���Ȃ��������Ȃ���@�܂�Ă��܂������@�K���X�Ȃ�@���Ȃ��̒��ʼn�ꂽ��" VS "�N���Ɂ@�����邭�炢�Ȃ�@���Ȃ����E���Ă����ł����@�����J���Εʂ��Ɓ@�h�������܂�܂̊���K���X"
�|���|�����̏�O�B������̐��E�H
�E�u�Ō�̏��_�v VS �u�ݕǂ̕�v�i���c�܂��Ɓ|����Q���A�e�r�͎q�j
"�����@����͍Ō�̏��_�@�܂�����Ȃ��@�N��҂��Ă�@���Ƃ��Ō�̃��P�b�g���@���݂��c���@�n�����̂ĂĂ�" VS "���Ƃ��F��������߂Ă��@��͍Ō�܂ő҂��Â���"
���l�͂ǂ�����A���������͐�Ɍ��̂ĂȂ��B���_�̈�����̈��������
�F�u����������Ɂv VS �u���ږx�l��v�i��R���ق�|�R�c�N�H�A�V���悵�݁j
"����������Ɂ@��l�͂����Ȃ��@�킽���̂��ɂ�����" VS "�ӂ�ꂽ���炢�ŋ����̂͂��ق�@�������炠����"
��������ł���l������Ă����Ȃ��D�����B
�G�u�T�ɂȂ肽���v VS �u�Q�ԗ�������v�i�����������|����H�A�s�͂�݁�����H�j
"�r�[���͂܂���" VS "�������������Ă���"
����ł�����ł��܂����ݑ���Ȃ������̋g��Ƃ̋q�ƘQ�Ԃ̏t�c���t���͓������̂݁B
�H�uwith�v VS �u���������v�i�g�c���|���R�c�m�A���R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�u�j
"���Ȃ������邩��@�҂����Ƌ������Ƌ^�����@�Y�����" VS "���Ȃ�������@�炭�͂Ȃ���@���̓�������"
�݂䂫���A�O�쐴�̃|�j�[�E�L���j�I���ڐБ�1�e�V���O���u�܁v���������̂�1988�N�B���炭�A���̂Ƃ��Q�l�ɕ��������낤�N�[���E�t�@�C�u�̃q�b�g�ȏW�̒��Ɂu���������v���������ɈႢ�Ȃ��B���̗��Ȃɂ́A"����"���L�C���[�h�ɐ�����x���Ƃ��Ă̑���ɑz������Ƃ������ʓ_������B�uwith�v�́u���������v�����~���ɂ��č��ꂽ�A�Ƃ����̂����̊m�M�B�uwith�v�̓������A���o���u��������v��1990�N�����Ƃ����̂����̏ؖ��H
�I�u��ǂ̏M�v VS �u����ȑD���S�v�i���ԓN�Y�|�R���r�Y�A�O�����q��j
"�킽�������́@��ǂ̏M�@�ЂƂẤ@�����ĂЂƂ�" VS "���킢�����Ȃ́@�݂Ȃ��q���m�@�������@���܂��Ɓ@�Ȃ��M"
�u��ǂ̏M�v�ɂ�����"�����Ȃ��킽�����g�ɍӂ�����ɂ́@�ǂ����ł��܂��̏M���������ɂ����ނ��낤"�́A�M�ɏ����̓��m�̉^���I�ȂȂ����\���B�u����ȑD���S�v��"�݂Ȃ��q���m"�Ƃ������Ƃ̊W�������V�`���G�[�V�����B
�J�u�ޏ��ɂ�낵���v VS �u�����̏h�(�g�����|�s�쏺��A���h��)
"�����������Ȃ��Ă悩������@�����炠�Ȃ���M����ꂽ����" VS "������K���X����Ő@���ā@���Ȃ��@�������@�݂��܂���"
"����"�������Ȃ��Ă悩�����ƁA�����Ȃ��Ă炢�ƁA�S��͂��������`�͓������Ȃ�ʗ��B
�@�����āA���߂Ďv���m�炳�ꂽ�͍̂�ƁE�����݂䂫�̐����ł��B�����Ŕ�r�ΏƂ������̂́A�ł��Â��u�ݕǂ̕�v��1954�N�ŁA�ł��V�����u��̗���̂悤�Ɂv��1989�N�A�Ȃ��35�N�̊u���肪���顂���Ȓ����X�p���̍�i�Q�ɁA�͂���l�̃\���O���C�^�[���ނ��Ă���B���ꂱ���������݂䂫�̔�}���̏ؖ��ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂Ƃ����̂���Ȃ��Ƃ������O�ɁA���̎�������������ƔF������K�v������Ǝv���܂��B
2012.06.27 (��) �b����`�g���X�s�[�J�[�Ȃ�
�@���l�̌��ē�����ł��B�������ŋ�������āA�����Ȃ�ɂȂ��1���~���x�������Ƃ��B�u�₩��叫�̃C���[�W������1���~�Ƃ�"�L���l�͂炢��"�ł��ˁB�@����1���~�ł��A�T�b�J�[�S���{�̒��E���J�����I��̔�Вn�x���͗��h�̈��B�~���I���Z���[���L�^�����ނ̒����u�S���ƂƂ̂���v�̈�őS�z���A�|���Ɨc�t���̍Č��Ɋ�t���������ł��B�̂��I ����1���~���߂��邱�̖��ÁA�T�b�J�[�Ɩ싅�̐����̏ے��̂悤�B
�@�I��̔N�ɐ��܂ꂽ���̏ꍇ�A�q���̂��납��y���݂͂Ȃ�Ƃ����Ă��싅�ł����B����Ȏ��ł��ŋ߂̖싅�͂܂�Ȃ��B�Ȃ��H �Y�o���A������X�^�[�̕s�݁B
�@�{���A�v���싅�I�[���X�^�[�Q�[���̃t�@�����[�I�o�I�肪���肵�܂������A�Ȃ�Ƃ������B���̖�������������͂ł��ˁA���E�̃X�[�p�[�X�^�[ON�͌����ɋy���A����ł́A���c�t�H�[�N�����A�S�r����a�v�A400�����c����A�߉^�̃G�[�X���R���A�����@�B���R�����A��Ղ�26���]�ĖL�A�T�u�}�����R�c�v�u�A�}�T�J�����c�����A��������s�Y�A���ł́A�Ō��̐_�l���N���A�o�b�g�剺�O�A�V���[�g�ł��̌|�p�ƎR����O�A����ۋg�c�`�j�A���c�����������A�m������x�[�u�쑺����A�������{�L�A�S�l�ߊ}�˗Yetc�A�����グ���炫�肪�Ȃ��A���h�X�^�[���Y�����̂��Ƃ��ɋP������B�r�ׂ�������ł��傤���B
�@����Ȃ���ȂŁA�ŋ߂̓T�b�J�[���茩�Ă��܂��B�j�q���[���h�J�b�v�ŏI�\�I�̓��{��\�͎��ɗ��������������A���[���I�茠�����������Ȃ�B�Ȃł����̃����h�����y���݂ł��B�e���r�Œ��{���A����̗��K�����łȂł������A�����J�ɎS�s������A�u�o���G�e�B�ɏo�����B�Ȃ��Ƃ��B���ꂶ���Ȃ���v���ȃR�����g���o���Ă������ǁA���Ȃ��ƌ���Ȃ��ł�I ��ߏ\���N�A����Ƌr���𗁂т��̂ł���B�Ȃɂ�������āA��������Ȃ��ł����B���[���h�J�b�v�ŁA���ꂾ���̊��������ꂽ�̂ł���B�ǂ��Ȃ������ċ���������Ȃ��ł����B���́A���Ƃ��ܗւŃ��_�������Ȃ��Ă��A�Ȃł����͐ӂ߂܂���B���ꂪ���{�l�̗�V�ł��B�ł��A�K���o���Ȃł����I�I
�@�I�����s�b�N�ł�����̘b��Ƃ����A�k���N���3�A�e�B���j�j�q�œ����ڂ�3�A�e�͑O�l�����Ƃ��i���q�ł̓h���E�t���[�U�[��100m���R�`������܂��j�B������2��ڂ�������A����͂����s�ł̋������ł��傤�B�S���Ȃ����_�[���I�[�G���I��̕��܂ŃK���o���k���I�I �ł͑O�u���͂��̂��炢�ɂ��Ė{��ցB
�i�P�j�g���X�s�[�J�[
 �@�����̂悤�ɂ��̃X�s�[�J�[�A�~���`�̎��Ƀ��j�[�N�Ȍ`�����Ă��܂��B��̊y��̂悤�Ȗ��w�����^�C�v�ŁA�����̂ǂ��ɒu���Ă��ǂ��ŕ����Ă��X�e���I����t�ɖ苿���A�Ƃ����̂����蕶��B���̃X�s�[�J�[�A���͐̂��璍�ڂ��Ă����̂ł����A�����C�ɂȂ����̂͂��ŋ߁B���R�A�g�ˎ��́u���y�̕����v�̉��̋߂��ɔ̔����̎������������āA�ł����킹�̋A��ɗ�������Ď������A���������Ƃ����킯�ł��B���ߎ�́A�C�y�ȃi�K�������Ƀs�b�^�����������Ƃł��B
�@�����̂悤�ɂ��̃X�s�[�J�[�A�~���`�̎��Ƀ��j�[�N�Ȍ`�����Ă��܂��B��̊y��̂悤�Ȗ��w�����^�C�v�ŁA�����̂ǂ��ɒu���Ă��ǂ��ŕ����Ă��X�e���I����t�ɖ苿���A�Ƃ����̂����蕶��B���̃X�s�[�J�[�A���͐̂��璍�ڂ��Ă����̂ł����A�����C�ɂȂ����̂͂��ŋ߁B���R�A�g�ˎ��́u���y�̕����v�̉��̋߂��ɔ̔����̎������������āA�ł����킹�̋A��ɗ�������Ď������A���������Ƃ����킯�ł��B���ߎ�́A�C�y�ȃi�K�������Ƀs�b�^�����������Ƃł��B�@�����āA��T�A�ݒu�����BMS-801�Ƃ����^�C�v�ɁA�I���L���[��FR-N9NX�Ƃ���CD�v���C���[�{FM�^AM�`���[�i�[��̌^�A���v��g�ݍ��킹�܂����B
�@�A�R�[�X�e�B�b�N�ȋ����͒����ԕ����Ă����܂���B�o�b�n�̖����t���@�C�I�����Ȃǂ́A�������������ɑt�҂�����悤�ŁA�_�炩�ȐS�n�悢�������g����܂��B�d�C�n�y��̓_���ł��ˁB�ӊO�Ƃ悩�����̂����m�����B�g�X�J�j�[�j�́u���v�͏��N���ォ��̈����ՂŁi1952�N�^���j�A���݂͒���������XRCD�Ŏ����Ă���̂ł����A��͂胂�m�����̓��m�����A����܂ł̃X�s�[�J�[�ł͍d�����ĕ����ꂵ���B�Ƃ��낪�g�����Ǝ��ɏ_��ȉ��ɕϐg����B�Â����������݉����ꂽ�悤�ȋC���Ȃ̂ł��B������ł��ˁA���m�����ɁB���ヂ�m�����̖��Ղ͂��ׂĂ������Œ�������B�W���Y��1950�N�ヂ�m�������D���Ȃ̂ŁA��������y���݂ł��B
�@���ꂩ��́A���y�ƌ��������Ƃ��ɂ̓^���m�C�ŁA�������m�Ȃǂ��i�K���͔g���X�s�[�J�[�ŁA�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�I�[�f�B�I����C�t�̕����L����̂͊��������Ƃł��B
�i�Q�j�u���y�̕����v��2��
�@���D�]��������������1��u���[�c�@���g�̐��U�v�ɑ����āA6��23���ɍs������2��́u���ȉƂ̗����͗l�v�Ƒ肵�āA���[�O�i�[�A�V���p���A�G���K�[�A���i�[�`�F�N�A�x�����I�[�Y�A�x�[�g�[���F���̗�����������グ�܂����B
�@���[�O�i�[�҂̃T�u�^�C�g���́u�݂�Ȃ͈����l���ƌ������A���ɂႢ�������l�������v�ƁA�����a�q�u�ĉ�v�̉̎���������܂����B�ܖ��N�S�́u�����̉��v�Ɂu���[�O�i�[�͐F���t�Ńy�e���t�������v�Ƃ����L�q������悤�ɁA���[�O�i�[���l���͉��y�j��̒���B����ȁA�݂�Ȃ������l�ƌ������[�O�i�[���A�ȃR�W�}�ɂƂ��ẮA�����l�������B�Ȃ��āA�R�W�}���j�̎q���N�̒a�����̒��A�Q���̊O�A�K�i������15�l�Ґ��̃I�[�P�X�g����ҋ@�����A�ޏ��̐Q�o�߂����v����ăI���W�i���Ȃ̐����t�ł��j�����Ă�����̂ł�����A���ꂼ���ɂ̃o�[�X�f�[�E�v���[���g�B�u���ɂႢ���l�v�Ɍ��܂��Ă܂��B���̋Ȃ��u�W�[�N�t���[�g�q�́v�ŁA1870�N12��25���̂��Ƃł����B
�@�V���p���ƃW�����W���E�T���h���L���ł��B���̊W�ɂ��āA�ŋߓǂW���E�T���X�����u�V���p���Ǎ��̑n���ҁv�i�t�H�Ёj�ɂ́A�u����͖{���I�ɂ̓v���g�j�b�N�Ȑ��i��ттĂ����v�Ƃ���܂����B���̓V���p���ɂ͑a���̂ŁA���̐���������V�����͕�����܂��A�ӊO�Ȋ������������͎̂����ł��B
�@�G���K�[�̔N��̏��[�͔ނ̍˔\���J�Ԃ������l���̉��l�B�x�����I�[�Y�̃X�g�[�J�[��������i�[�`�F�N�̘V���炭�̗�������Ȃ��̂�����܂��B�����������i�[�`�F�N�́A����t���u1Q84�v�Łu�V���t�H�j�G�b�^�v���L���ɂȂ�܂����B��l�����������̂��W���[�W�E�Z���̃\�j�[�ՂŁA����CD����Ԃ悤�ɔ��ꂽ�̂��L���ɐV�����B
�@�����A���ƌ����Ă��ʔ����̂̓x�[�g�[���F���u�s�ł̗��l�v�T���ł��B�x�[�g�[���F���̈�i�̒�����A�{���ɐ^����3�ʂ̃��u���^�[���o�Ă����B�����ɂ́A�������ꏊ���N��̋L�ڂ��Ȃ������B�肪����́u7��6���̌��j���v�A�u������v�A�u�X�֔n�Ԃ͂�������K�Ɍ������v�Ƃ����L�q�B1827�N����A���̗��l�T�����n�܂�A���}���E�������n�ߊ����̊w�҂�����̂ł����A100�N�ȏ���������̂܂܂ł����B����ȋ����[�������𖾂����̂́A���ƈ�l�̓��{�l�����������̂ł��B�ޏ��̖��͐��ЁBN���̋@�֎��u�t�B���n�[���j�[�v1959�N8�����Ɍf�ڂ��ꂽ�u�`���̗��l�v�Ƃ����_���ł����B�����ɂ́A����܂Ő�l���܂��������ڂ��ĂȂ��l�̖��O���������̂ł��B���̖���"�A���g�[�j�A�E�u�����^�[�m�v�l"�B���̐��͂��̌�A�����J�̒����ȉ��y�w�҃��C�i�[�h�E�\�������ɂ���ė��t�����܂����B�؎���2009�N�̐l�ƂȂ��܂������A���̐��U�͂܂��Ɂu�s�ł̗��l�v�Ƌ��ɂ���܂����B�����������o�Ă��܂��B���̌ւ�ׂ����{�̈̋Ƃ́A�����ƒ��ڂ���Ă����Ǝv���܂��B
�@����Ȃ���Ȃ̗����͗l�����̓��̃e�[�}�B�Q���̊F�l����́u�ʔ��������B�y�����������B�������C���ɂȂ����v�Ȃǂ̂����t�����������܂����B���肪�Ƃ��������܂��B�܂��̋@��ɐ���I �I����āA�[���̋g�ˎ�������������Ȃ���̂��Âт܂����B�ꌩ���Ē����݂��ς���Č�����͓̂��R�ł����A����ł������ɂ͕s�ς̈�̓�����������A�H�n���ɂ͐̂Ȃ���̏��X�S�����̂܂c���Ă����肵�āA�����̖ʉe���h��B�܂���"�W���E�W�̓I���E�}�C�E�}�C���h"�ł���܂��B
�@�����I�����s�b�N�̔N�Ɉ�N�ԏZ�g�ˎ��B���ꂩ��I�����s�b�N�́A���L�V�R�E�V�e�B�A�~�����w���A�����g���I�[���A���X�N���A���X�A���[���X�A�\�E���A�o���Z���i�A�A�g�����^�A�V�h�j�[�A�A�e�l�A�k�����o�Ă������������h�����n�܂�܂��B�͂Ă��āA���Ɖ���I�����s�b�N��������̂��H �Ȃ�Ă��Ƃ��l����悤�ȍɂȂ��Ă܂���܂����B���N�ɋC�����Đl���傢�Ɋy���݂������̂ł��B
2012.05.31 (��) �b����`���O��G�߂̒���
�i�P�j���y�̕��� �@�g�ˎ��́A�����㋞���ď��߂ďZ���ł���B�̋��𗣂��w���ƂȂ���1964�N�A�����I�����s�b�N�̔N������A����48�N�O�ɂȂ�B���h�́A�k�����珤�X�X��ʂ蔲���A�ܓ��s�X����n���Ă����̂Ƃ���ɂ������B���Z�̗F�l�ƁA�l������Ԃɓ�l�ŏZ�B�ނ̌Z�������̑�Ƃ���������A�ꃖ���̉ƒ��𑊏��������4500�~�Ŏd���Ă�����āB��l���Ȃ��2250�~�I���͐̂ł���B���݂ɍ��d�i����JR�j�̍Œꗿ����10�~�A�w�H�̃��[����30�~�A�J���[���C�X��70�~�̎��ゾ�����B
�@�g�ˎ��́A�����㋞���ď��߂ďZ���ł���B�̋��𗣂��w���ƂȂ���1964�N�A�����I�����s�b�N�̔N������A����48�N�O�ɂȂ�B���h�́A�k�����珤�X�X��ʂ蔲���A�ܓ��s�X����n���Ă����̂Ƃ���ɂ������B���Z�̗F�l�ƁA�l������Ԃɓ�l�ŏZ�B�ނ̌Z�������̑�Ƃ���������A�ꃖ���̉ƒ��𑊏��������4500�~�Ŏd���Ă�����āB��l���Ȃ��2250�~�I���͐̂ł���B���݂ɍ��d�i����JR�j�̍Œꗿ����10�~�A�w�H�̃��[����30�~�A�J���[���C�X��70�~�̎��ゾ�����B�@����ȉ������̋g�ˎ��ŁA���́A����5��26���u���y�̕����v�Ȃ邨�b����������B�ꏊ�͓�������̓������r���ɂ���gallery�V�B���N�O����S���t�����ꏏ�����Ă�����Ă���N���̂��o����̍���ł���B�u�W���E�W�v�͍��Ⓦ���ŏZ�݂�������NO�P�B���̐S�́A�s��߂����c�ɂ������`"�قǂ̂悳"�Ȃ̂��������B
�@���̘b�A���́A��N�A���Ȃ�N���ʑ��ł��o��Ƃ̉�H�̐܁A�b���N���V�b�N�ɓ]�����Ƃ��Ƀt�b�ƕ��������́B�u���A���b���Ă��Ďv�����̂ł����Agallery�ɏW�܂�l�����́A���y�D���̕��������̂ŁA�����Ƃ���ȃN���V�b�N�̂��b����ԂƎv���̂ł��B�u���`���ŔN�ɐ������Ă��������܂��v�Ƃ��o����B�u�Ƃ�ł��Ȃ��A�����Ȃ������A����Ȃ߂��������Ȃ��v�Ɩ��_�ŏ��͂��f��B�Ƃ��낪�A�����ς���M����ƏĒ��̐����̐S�n�悳�ɁA�Ō�́u�����Ƃ��ł�낵����v�ƌ����Ă��܂����̂ł���B
�@�����̂��q�l��17���B�����gallery�͖��t�Ȃ̂��B���ڂ́u�A�C�l�E�N���C�l�ɉB���ꂽ��ƃ��[�c�@���g�̐��U�v�ł���B
�@��w�̋��d�ɗ������o������������Ƃ͂������̂́A���q����̂���ȂɊԋ߂Řb���̂͏��߂ĂȂ̂ŁA���Ȃ�˘f�����B�u���͐��Ƃł͂������܂���B�ł��A��ʂ̐l���A���y�ɂ�����o�����������������Ă��܂��B����ȗ����ʒu�ł��������ɂ��b�����Ă��������܂��̂ŁA�ǂ������C�y�ɂ��������������B�����āA���̉�̂��ƁA�������[�܂��ĉ��y������܂łƈ���ĕ��������肵����A����ȂɊ��������Ƃ͂���܂���v�Ƃ̑O����ŃX�^�[�g�����B
�@�u����2���ԁB��͂�A���[�c�@���g�̐l�������ԓ��Ɏ��߂�͓̂���A�u�t���[���C�\���v�u���̔N1791�N�̌���Q�v�u�A�C�l�E�N���C�l�̓�v�����肪�蔖�ɂȂ��Ă��܂����͎̂c�O�������B�����A�F�l�̔������ƂĂ��ǂ��ėD�����āA�f�l�̎��͑�ϗE�C�Â����A�M�����点�Ă����������B�u�������Ȃ����������������A�b���V�N�Ŋy���߂܂����v�Ƃ̕]�ɁA�ق��Ƌ����Ȃł��낵������ł���B
�@�F����Ɋy����ł����������͉̂���肾�������A��[���l������A��Ԋy���̂͂��̎��ł͂Ȃ����ƋC�������B�������������t���̍Â�������ƁA���₨���Ȃ��Ɋ����܂łɂ܂Ƃ߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��B��̃e�[�}���W�����Ă��Ƃ���܂Œf�ГI�������������n���I�ɂ܂Ƃ܂��Ă���B���[�c�@���g�̉��y�Ɛl�ƂȂ肪�A�����̒��ň�{���ʂ��Ă����B����͗\�����ʁA�����A�傫�Ȏ��n�������B���Ă��ꂽ�F�l�AN�����o��A����������������������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�@����́A6��23���A�u�w�W�[�N�t���[�g�q�́x�Ɍ��郏�[�O�i�[�̈��̌`�Ɨ����͗l�v�Ƒ肵�āA���[�O�i�[�̑P�l���l���肩���ȉƂ̗���������l�@����\�肾�B
�i�Q�j�]��O��
 �@���̂Ƃ���A�N���V�b�N�E�̑�䏊���]���������B5��18���A�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���A�~�����w���ߍx�̎���ŁA������̌��̎胆���A�E���@���f�B�ɊŎ���ĖS���Ȃ����B86�������B���������A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́A�f��u���ȗ[�ȂɁv�̏��D���[�g�E���C���F���b�N�Ƃ��Č������Ă����������������ƋL�����Ă���B�ӊO�ȑg�ݍ��킹�ł���B
�@���̂Ƃ���A�N���V�b�N�E�̑�䏊���]���������B5��18���A�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���A�~�����w���ߍx�̎���ŁA������̌��̎胆���A�E���@���f�B�ɊŎ���ĖS���Ȃ����B86�������B���������A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́A�f��u���ȗ[�ȂɁv�̏��D���[�g�E���C���F���b�N�Ƃ��Č������Ă����������������ƋL�����Ă���B�ӊO�ȑg�ݍ��킹�ł���B�@�ނ��A�h�C�c�̋Ȃɂ�����20���I�ő�̃o���g���̎�ł��邱�ƂɈق�������l�͂��Ȃ����낤�B���Ƃ��ẮA�V���[�x���g�̋Ȃɖڊo�߂�����2�|3�N�A���ɂ悭�ނ̉̏��������A�܂��ɐ��]�ǂ���̑�̎肾�����B����قǃh�C�c�̋Ȃ��A�I�[�\�h�b�N�X�ɁA���݂Ɋ�����R���g���[�����āA�������̂��グ��̎�͑��ɂ͂��Ȃ��B
�@�̋Ȃɂ�����l�ލő�̈�Y�̓V���[�x���g�́u�~�̗��v���Ǝv���Ă��邪�A�ނ́u�~�̗��v�̃X�^�W�I�^����7�c���Ă���B����́A���ׂẲ̎�̍ő��ł���A�ނ̃��p�[�g���[�̍ő��ł�����B�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́u�~�̗��v�̐\���q�Ȃ̂ł���B�����瑼�̉̎�̂͗v��Ȃ��B�ނ��|���[�j�Ƃ����1978�N8��23���A�U���c�u���N���y�Ղł̃��C���͖�CD���̂܂܂����A�����̐����ƕ����B�C���Ղłł���������A�����x�����Ă݂������̂��B
�@�����u�~�̗��v�̍ō��̖����́A��1��^���E1955�N�W�F�����h�E���[�A�Ƃ�EMI�Ղ��B����͎��M�������Ēf���ł���B�����炤��҂̎⛋��������قǂ܂łɌ����ɕ\�o�����̏��͑��ɂȂ��i�������A��11�ȁu�t�̖��v�����́A�u�����f���Ƃ����1985�N�^�� PHILIPS�Ղ��x�X�g���j�B
�@���̘^���́A�ނ�29�̂Ƃ��̂��́B���̎��_�Łu�~�̗��v���ɂ߂�����Ă���̂����琦���B�������A���̔Ղ̓��m���������A���^�̕\���Ɍ����Â�̂��������B���܂ɂ͋C���ɂ߂Ē��������Ƃ�������B����ȂƂ��́A1971�N�W�F�����h�E���[�A�Ƃ�DG�X�e���I�Ղ������B1955�N�Ղ��\��y�߂Ń��m�N���[���Ȕ�����������B
�@����5��25���ANHK-FM�ŁA�t�B�b�V���[=�f�B�[�X�J�E�̒Ǔ��ԑg�Ŋ|�������̂�����1971�N�Ղ������B���̂Ƃ��A�A�i�E���T�[���u�����Ǖ�����̒Ǔ��̌��t�����������������v�ƌ������̂ɂ͋������B�O�̓��ɔ���������]����Ă�������ł���B�u�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�̓h�C�c�̋Ȃɂ�����̑�ȎR���ł����B�ނ̉e�����Ȃ������Ⴂ�̎�͂��Ȃ��ł��傤�B�A�ւ̐_�o�̎g�����͐q��ł͂Ȃ��������A�h�C�c��ɑ��銴�͓��ʂȂ��̂�����܂����B����قǐ[�����n�ɒB�����̎�͂��܂���ł����B���������F�肢�����܂��v�ƒ���ꂽ�B�Ō�ɃA�i�E���T�[�́u�����5��22���Ɏ��^�������̂ł��B��������́A���̓�����5��24����90�ł��S���Ȃ�ɂȂ�܂����v�ƕt���������B
�@��������̑z���o�͂��܂�Ȃ����A�B��A���̍ł��D���ȃ\�v���m�A�t�F���V�e�B�E���b�g�́u�V���[�x���g�̋ȏW�v�̃��R�]����ۂɎc���Ă���B�u�������̂悤�Ȑ����ȃV���[�x���g�����A�V�������c�R�b�v�Ƃ͊i���Ⴄ�v�ƕ]���ꂽ�B�㔼�̕����ɔ������o�����͎̂����ł���B
 �@�����Ƃт����肵���̂́A5��28���̒����V���ŁA�g�c�G�a���̐�����m�炳�ꂽ���Ƃ������B�Ȃ��Ȃ�A���́u�N�����m1��25���t�v�ŏ������Ƃ���A1��22���̃T���g���[�E�z�[���Ō�p�����Ă���̂��B���98�ŁA���q���特�y���ɏo�Ă����Ă���B���ɂ����C���A���̕��Ȃ瓖�������݂��낤�Ǝv�����̂ɁA���ꂩ��4�����ŋA��ʐl�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ́A�l�̖��͎��əR���B
�@�����Ƃт����肵���̂́A5��28���̒����V���ŁA�g�c�G�a���̐�����m�炳�ꂽ���Ƃ������B�Ȃ��Ȃ�A���́u�N�����m1��25���t�v�ŏ������Ƃ���A1��22���̃T���g���[�E�z�[���Ō�p�����Ă���̂��B���98�ŁA���q���特�y���ɏo�Ă����Ă���B���ɂ����C���A���̕��Ȃ瓖�������݂��낤�Ǝv�����̂ɁA���ꂩ��4�����ŋA��ʐl�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ́A�l�̖��͎��əR���B�@���́A���N�O���珑�������Ă���悤�ɁA���̕]�_�X�^�C���ɂ͈�a�����o����҂��B�U�ȓI�����ɂǂ����Ă�����߂Ȃ��̂ł���B�B��A1983�N�A�u�Ђъ��ꂽ�����i�v�ƕ]�����z�����B�b�c���������̒����V���u���y�W�]�v�������āB�u���y�W�]�v�Ƃ����A���Ō�̂���́A��N6��28���́u�t�F���V�e�B�E���b�g�̉̐��v�������B�p���l���b�g�̌|�p�I�y����A�p���̃I�[�f�B�I���O��ʂ��ĉ�͂��Ă��āA���j�[�N�������B
�@3��10���A�u���V����Ɖ��y����������v�Ƃ����h�L�������^���[�����f���ꂽ�B����́A���ڂ̐V�i�`�F���X�g�{�c�傪�A���ˎ����nj��y�c�Ƃ̋�����ʂ��Đ��E�̃I�U���ƐG�ꍇ�������X�̋L�^���B����ɂ͎����������T���g���[�E�z�[�����܂܂�邪�A��ۓI�������̂͂���ɐ旧��1��20���A���ˌ|�p�قł̏o�����������B
�@���̃v���O�����́A1��19����20�������ˁA22���������Ƃ����X�P�W���[���B���V��19���̃R���T�[�g��A�ɓx�ɑ̒�������A20���̏o�����L�����Z�������B���ˌ|�p�ق͂��łɖ����̊ϋq�Ŗ��܂�A���̂قƂ�ǂ����E�̃I�U����ړ��Ăɂ��Ă����B�u���V��������͍���̉��t��̒�����������߁A�o���̓L�����Z�������Ă��������܂��B���������Ė{���̉��t�͎w���҂Ȃ��ōs���܂��v�Ǝ�Îґ��̂����^�̃A�i�E���X�ɁA���O�͂����藧���u����Ȏ���Șb�͂Ȃ��v�ȂǂƓ{������ь����B����͈ٗl�ȋ�C�ɕ�܂ꂽ�B
�@�Ƃ��̂Ƃ��A�����ْ̊��E�g�c�G�a���������オ�����B���͐Â��ɁA�������B�R�Ƃ��������Řb���n�߂��B�u���V����́w�����т�ė����オ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͏��߂Ă��B�\����Ȃ�����Ǎ����̉��t��̓L�����Z�������Ă���Ȃ����x�ƁB����ŁA�l�͉��t�Ƃ̊F����ɂ��̂��Ƃ������āA�w���Ȃ����ǂ����܂����B�L�����Z������Ȃ�L�����Z�����邪�x�Ɛu�����Ƃ���A�ނ�́w���V�����ꂾ���ꐶ��������Ă����̂�����A���̗��K�̐��ʂ��Ȃ��ĉ��t�������x�ƑS�������������܂����B���V�łȂ��Ďc�O�����ǁA���t�Ƃ��������ƌ����Ȃ璮���Ă�낤�A�������l���̕��͂ǂ������c�肭�������v�Ƙb���I�����u�ԁA��ꂪ���̂悤�Ȕ���ɕ�܂ꂽ�̂��B�Ȃ𗧂l�͈�l�����Ȃ������B
�@�����ɂ́A���y���������Ԃ�M�����l�̐l�Ԃ������B�Ȃɂ��B�����떂����������̂܂܂�`���ė���҂Ɍ����ς˂�z�Ƃ����V�l�������B����A���̍�������������Ă��܂������m������������v���������B�g�c�G�a����A���炩�ɁI
2012.05.20 (��) ���̒��̒����݂䂫3�|�����݂䂫��"����"�ł���2
�@�ł͂��������c�Ƃ���̕��͂ɉ����Ď��̍l�����q�ׂ����Ă��������܂��"���������������"�Ǝv����ł��傤���A�����i������Ƃ��������̂ŁE�E�E�����������t���������������B�c�Ƃ��u���̂��D���ȐԂ��傤����̂�������́E�E�E�E�v�Ȃ�Č������炢���Ȃ���ł��� �@�u���ρv�i�A���o���u�����Ă���ƌ����Ă���v�Ɏ��^�j�̉��߂ŁA�����莆�����Ԃ��ɍs���̂�"�������g"��D�҂��ɍs�����Ƃ��A�Ƃ����͎̂��������ł���ł��Е��ŁA�݂䂫����ɂ͂܂�ňႤ��̎����\���O�����邱�Ƃ�F������K�v������܂��B
�@�u���ρv�i�A���o���u�����Ă���ƌ����Ă���v�Ɏ��^�j�̉��߂ŁA�����莆�����Ԃ��ɍs���̂�"�������g"��D�҂��ɍs�����Ƃ��A�Ƃ����͎̂��������ł���ł��Е��ŁA�݂䂫����ɂ͂܂�ňႤ��̎����\���O�����邱�Ƃ�F������K�v������܂��B�@�O�o�u�ЂƂ�v�̏��́A�����������Ƌt��"�莆"���o�����Ƃ��Ă��܂��"�������������璷���莆����������@���͐炸�ɂ������Ă����Ă�@���Ƃ���܂�"�ƁB�����Ƃ����v���o�ɂ������ǂ��t�������������̂ł��傤�B"�莆�����Ԃ��ɍs��"��"�V���ɏ����ďo��"�Ƃ����A�����݂䂫�̒��ɐ����̑Ή�������̂ł�����A���̕Ј�������グ�ĉ��̂Ɣ�ׂ�͕̂Ў藎�����Ǝv���̂ł����������ł��傤���B
�@���ɁA�u���ρv�̒��̉̎�"�o�J����"�ɂ��Ĉꌾ�B�c�Ƃ���͂���Ɠ��\�q�́u�V�h�̏��v��"�o�J����"�͑S���Ⴄ�Ӗ��������Ƌ��Ă��܂�����킭�A�u���ρv��"�o�J����"�͂������}���Ă��邾����"�o�J����"�ł͂Ȃ��A���̂Ȃ炱�̏��͎�����U�����j�̂Ƃ���ɏo�����Ď����̏o�����莆��D�҂��悤�Ƃ��Ă���̂����硈���u�V�h�̏��v��"�o�J����"�͌���Ƃ�����߁A�Q���Ƃ��Ȃ��݁A�s�K�Ɛ�]�Ƀh�b�v���Ђ����Ă��邾���̎��}�I"�o�J����"������B�E�E�E�E�E����͎����قړ����ł�����A������w�E���Ă����������Ƃ�����܂��
�@����͓��\�q��"�o�J����"�͉��̂̐��E�̂��������Ȍv�Z�̎Y���ł���Ƃ������Ƃł��B�u�V�h�̏��v�̍�Ґ�܂����́A�����ɓ��\�q�̃}�l�[�W���[�ł��蔄��o���̎d�|���l�ł�����V�l�̓���o�����߂ɂ��̔��K�����������邽�ߕ�e��ڂ̕s���R�ȗ��|�l�Ɏd���āA�����u���̂̐���w�������h���̏����v�Ƃ��Ĕ���o�����̂ł��������̂̎�l����ڈ�t�s�K�Ɍ����Ȃ��Ă͂����Ȃ������B�]���Đ�]�Ƀh�b�v���Ђ����Ă���ƊŔj�����c�Ƃ���͑S���������ǂ݂������Ǝv���܂��B���A����Ő�܂����̏p���ɂ͂܂��Ă��܂������Ƃ������Ȃ̂ł����������������������̏����͖��͂������܂���ǁB
�@�Ƃ͂������\�q�ɂ́A���ƂɂȂ��āu�l�I���X�̏��v�Ƃ���"�����ă_�������@�����Ă䂱����@�l�I���̊X��"�Ƃ����O�����̉̂�����܂��B�u�_���ȏ������ǎ����ɂ͂��������Ȃ�����A�l�I���X�ňꐶ�����ɐ����Ă䂱���v�Ɖ̂����̋Ȃ̒��̏��ɂ́A�݂䂫����Ɠ����O�����̎p�����������܂��
�@�u����݁E�܂��v(�A���o���u�����Ă��Ă������ł����v�Ɏ��^)�͂��Ȃ肱�킢�ł��ˁA�j�ɂƂ��ġ�ł��A����Ȃ��Ƃ����j�Ȃ獦�܂�ē��R�ł��傤���B����͂��Ă����A�����œc�Ƃ���́A"�݂䂫�̏���l���͎������Ă�����̒j��Y��悤�Ƃ͂��Ȃ������Ȓj���D���ɂȂ���������Y��悤�Ƃ��顖��Ȃ̂̓A�^�V�̕���"�Ƌ��Ă��܂����A���̋ȂɊւ��Ă͂���͈Ⴄ�Ǝv���܂�����Ȃ̂̓A�^�V�Ƃ������Ƃ́A�����̂̓A�^�V�Ƃ������ƂɂȂ�܂�������������Ǝv���Ă��鏗���j���E�������Ȃ��B"�A�^�V�������邩�ǂ����F�B�Ɠq�������ċ߂Â��Ă����A���������̓t���ꂽ���Ƃ��������₷���Ƃ�������"�E�E�E�E�����獦��ł���ˡ�c�Ƃ���̋�"�Y�ꂽ���͎̂����A���̓A�^�V"�Ƃ����͔̂��ŁA"�Y��Ă�肽���̂͑���̒j�A�����̂͒j"�Ƃ����̂��������Ǝv���̂ł����Ⴂ�܂����H
�@����͂��Ă����A�������̉̂̍D���ȕ����́A�㔼��"�h�A�ɒ܂ł����Ă䂭��@�₳��������ėB���ꂵ��������"�̌��ł�����̃t���[�Y�ɕ\��Ă���݂䂫����̊�{�p���ɋ���ł���邩��ł��B����ȏɂ����ĂȂ��A���ꂾ����������ɂ���Ӗ����ӂ��Ă���B���̎v�z�͌�́u�a���v��"�ނȂ������Ȃ�ā@���锤���Ȃ��ƌ����Ă�@���ʂȌ����Ȃ�ā@�Ȃ��ƌ����Ă�"�Ƃ����t���[�Y�ł�肢���������m�ɂȂ�܂�����Ȃ킿�A�ǂ�ȗ����낤���A�ǂ�Ȍ��ʂɂȂ낤���A�������o���������Ƃɖ��ʂȂ��ƂȂ�ĂȂ��A�����͎������ɂ��đ��l�ɂ͎v�����������Ă���Ă��Ă����̂����猋�ʂ����������Ďd�����Ȃ��A�����ꐶ���������Ă������ƂɈӖ�������̂�����A�Ƃ����݂䂫����̎p�����͂�����Ǝ������̂ł��
�@���āA�����܂œc�Ƃ���ւ̕������\���グ�Ă��܂������A�c�Ƃ���̕W�I�ł������u�݂䂫�͉��̂��v�ƌ����Ă���������ɂ������Ă����������Ƃ�����܂��B
�@�ނ炪�����������Ɉ��������ɏo���݂䂫����̋Ȃ́A���܂��āu����݁E�܂��v�ł���u���ρv�ł���A�u���C�ł����v�ł���A�u�킩�ꂤ���v�ł���A�u�ЂƂ���v�ł������肵�܂�����̑��ɂ����낢�날��̂ł��傤���A����ł��݂䂫����̍L�͂ȃ��p�[�g���[�̂ق�̈ꕔ��ΏۂƂ��Ă���ɂ����Ȃ��Ƃ��킴������܂���B���̕ӂ�������"�����݂䂫�͉��̂�"�Ȃ�Ēf�����ė~�����Ȃ��B�c�Ƃ���ɐ\���グ���ƑS�������悤�ɁA�����݂䂫�����̂Ȃ�����ƒ����݂䂫��m���Ă���ɂ��ĉ������Ɛ\���グ���������ł������ċ肽���̂Ȃ�"�����̂��͉̉̂��̃p�^�[���ɛƂ�"���炢�̌������ɂ��Ă����Ă��������������̂ł��B
�@����́A��̓I�Ȏ���������āA�u���́v�Ɓu�݂䂫�́v�̋��ʐ������������Ǝv���܂��B
2012.05.10 (��) ���̒��̒����݂䂫2�|�����݂䂫��"����"�ł���1
�@2003�N�͖����Ă����Ă������݂䂫�������B����Ȑ܂ɓǂu33��]�̈��̂������@���Ȃ��̓��[�~���H����Ƃ��݂䂫�H�v�i�c�ƏG�����A�p��j�Ƃ����{�������[�������B�ǂ����Ƃ����A���̂�n���ɂ��Ă���Ƃ���ł���B�R�m�����[���I ��ԃJ�`���Ƃ��������̏̓^�C�g�����u�݂䂫�̉̂����̂Ȃ�ĒN���������̂��낤�v�������̂ŁA���̏��_�̃^�C�g�����u�����݂䂫��"����"�ł���v�Ɗ����Ă����B���̂��A���ғc�Ǝ��ɑ���莆���ɂ��Ă��邪�A�����ǂ���Ōf�ڂ����Ă��������B���������āu�c�Ƃ���v�Ƃ����Ăт������������A�����͂܂��A�K���ɂ͂�����Ă��ǂ݂���������K���ł���B�E�e��2003�N9��19���ł���B�����݂䂫��"����"�ł���P
�q�[�@�c�ƏG���l
�@���߂Ă��ւ肢�����܂�����̕ւ���������ƂɂȂ�܂����̂́A���Ȃ���1984�N�ɏ�����܂����u33��]�̈��̂������@���Ȃ��̓��[�~���H����Ƃ��݂䂫�H�v���A���ŋߓǂ���ł���܂��
�@���̖{�̒��ŁA���C�J�R���ƒ����݂䂫��l�X�Ȋp�x����▭�ɔ�r���Ȃ��珑���Ă����A�S�̓I�ɂ͊y�����ǂ܂��Ă��������܂�����܂��́A���S�����������ӏ����������Ă��������܂��B
�@ ���̓��e���u�Z���t�v�Ńh���}�̑�{�̂悤�ɏ��������ďq�ׂĂ�����̂͗��Ε�����ƂƂ��Ă̑f�{�B��ϕ�����₷�������B�@�ȏ�̂悤�ɍ��_�ł��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������̂ł����A�ǂ����Ă��[���ł��Ȃ�����������܂����B����́u�݂䂫�̉̂����̂��Ȃ�ĒN���������̂��낤�v�̏͂ł��
�A �u���l���Ȃ�ƌĂт܂����H�v�̖ڂ̕t�����ƁA���[�~���ɂ�"���܂�"�Ƃ����Ăѕ��͈�x���o�Ă��Ȃ��Ȃǂ̌��́A���ɓI���˂Ă��Ċ��S�����
�B �u�w�͂��߂܂��āx���āv���A�s���l�@�B�u�ٍ��v����u�͂��߂܂��āv�̒��́u�l�����̏����ցv�݂̂䂫�ϑJ�̔c���������B
�@�����ł̓c�Ƃ���̋肽�����Ƃ�v��Ɓu���̂ɓo�ꂷ�鏗���͎�������Ǝ��}�ƌ���Ƃ�����߂̒��ɂǂ��Ղ�Ƃ����Ă��܂��B�����đ���̒j��ӂ߂Ȃ��B�����Ȃ����̂́A�j�������̂ł͂Ȃ��A�o�J�Ȏ����������ƐÂ��ɐg�������B�܂������������͏�ɉ������Ǝv���Ă������B�����āA���̂��D���Ȓr�܂̐Ԃ��傤������ŏ��[�̋�s�Ȃnj����Ȃ������ł��邨�₶�����́A�����Ƃ������������D���Ȃ̂��B����ɔ�ׂ݂䂫�̉̂ɏo�Ă��鏗�͈Ⴄ�B�݂䂫�͉̉̂��̂��Ȃ�Ēf���ĈႤ�B����Ȃ��ƈ�̒N���������̂���l�͉��̂͌�������v�ƁA�܂�����Ȏ�|�ɂȂ낤���Ǝv���܂��
�@������ԃJ�`���Ƃ����̂́u�r�܂�����̐Ԃ��傤����ň��ނ�������́A�����Ƃ���ȏ����D���Ȃ̂��v�̌��ł��B���̌������̒��ɂ́A����ȉ��̍D���ȕ��ʂ̐l�Ԃ��A�̂�ł�������܂��B�����́u�������킯�ɂ͂����Ȃ��v�̂ł��B
�@�݂䂫�͉̉̂��̂ł͂Ȃ����Ȃ��Ȃ牉�̂ɓo�ꂷ�鎸�����͂�����߂ɂǂ��Ղ�����Ă��܂��Ă��邩�灨����ȁA�݂䂫�̉̂ƈႤ���E�̏����D�މ��̍D���̒j�͂�����Ȃ����݂��E�E�E�Ƃ����O�i�_�@�������邩��ł��i����ɂ��Ă��A���ꂶ��r�܂̐l�{��܂���j�B
�@�܂��̂��牉�́^�̗w�Ȃ́A���R��Y����W�J�̂�q�����N���V�b�N�̋����������o�̉̎�̕��X����A�����炳�܂Ɍ�������Ă����������������悤�ł����������̂��A���x�͌㔭�̃j���[�~���[�b�W�N���̕��X���猩������Ă���A��������j�͌J��Ԃ��Ƃ������ƂȂ̂��Ȃ��A�Ȃ�Ďv�����肵�Ă���܂��B
�@�����܂߂ĉ��̂��D���Ȓj�����́A�����ɓo�ꂷ�鏗�����A"�]��"��������"���f�|���Ȃ���"��������""�����v��ꂽ���Ƃ����v���Ă���"���Ƃʼn��̂��D���Ȃ̂ł͂���܂���B���̂̎����Ă���L��Ȑ��E���D���Ȃ̂ł�������ɂ͏��S�̈�r���A�����A�W�����S�A���K�̔߈��A�����̏�O�A�j�̐S�ӋC�A�����A�ǓƁA�����A�Ȃǂ��`����A�܂��A����炪���ݍ����Ă̗��A�����A���e�̏�A�F��A�]���̔O�A�s��ւ̓���A�t�̊�ѓ��X�̗l�X�Ȑ��_���E�����o���邩��ł��������A�̋��A�s��A�ٍ��A�R�X�A�C�A�`�A�ՁA�����A����A�����A�s���A���w�A���j�ȂǂȂǁA���ɑ��ʂł��B
�@�܂������ƒ[�I�Ɍ����Ă��܂��A�����g�A���̂��āu�����Ȃ��v�Ɗ�����C�����ƁA�����݂䂫���Ă���������C�����͑S������Ƃ������Ƃł�����͂��̊��o��M���܂�������ēc�Ƃ���̋�悤�ȁu"���̂̏�"���D�������牉�̂��D���Ȃ킯�ł͂Ȃ��v���Ƃ������Ő\���グ�Ă����܂��
 �@���āu�r�܂̐Ԃ��傤����̂�������v�̘b�ɖ߂�܂���c�Ƃ���̕��͂���́A�u���̂悤�Ȑl������"���̂̏�"���D���Ȃ̂�����݂䂫�̉̂ȂǕ���͂��͂Ȃ��v�Ƃ��������܂�������āA"���������ԓx�͂悭�Ȃ��Ȃ�"�Ǝ��͎v���܂��B
�@���āu�r�܂̐Ԃ��傤����̂�������v�̘b�ɖ߂�܂���c�Ƃ���̕��͂���́A�u���̂悤�Ȑl������"���̂̏�"���D���Ȃ̂�����݂䂫�̉̂ȂǕ���͂��͂Ȃ��v�Ƃ��������܂�������āA"���������ԓx�͂悭�Ȃ��Ȃ�"�Ǝ��͎v���܂��B�@�݂䂫����́A�n�ʂ̂���l���Ԃ��傤����̂�������̂悤�ȃt�c�[�̐l�������u�ĂȂ�������Ă���Ă���l�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����B"�����撣���Ă�"���ĉ������Ă����l�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����B����Ȍ������́A�u�i�v���ԁv�i�A���o���u�̂ł��������Ȃ��v�Ɏ��^�j�́u�F���̏��̒� �l�͉i�v���ԁv�Ƃ������ɋ��ɓI�ɕ\��Ă���Ǝv���܂����E�E�E�B
�@���ꂩ��A�r�܂ň���������������Ă��邨������́A�u�T�ɂȂ肽���v��"�r�[���͂܂���"�Ƌ���ł���Z������Ƃǂ����Ⴄ�̂ł����H �r�܂̂�������̂��Ƃ̓o�J�ɂ��āA�u�T�ɂȂ肽���v�̂��Z������ɂ͋�������Ƃ����킯�ł����H�c�Ƃ����āu�w�^�N�V�[�E�h���C�o�[�x��w�T�ɂȂ肽���x������ł̂́A�t�c�[�̐l�������o�ꂷ�邩�炾�v�Ƌ��Ă�ł͂���܂��B�r�܂̂�����������ȃt�c�[�Ȑl�̓T�^�Ȃ͂��ł��B
�@������_���ɂ������̂́A�u�w���̂̏��x�Ɓw�݂䂫�̏��x�͈Ⴄ�v�Ƃ��������ł��B�P�[�X�ɂ���Ă��������}�������邱�Ƃ͔F�߂܂����A���͂��̌��ߕt���ł��B�u�w���̂̏��x���w�V�h�̏��x�T���w�S�̂���x�̏��ł���v�Ƃ������ߕt���ł��
�@���̂ɓo�ꂷ�鏗���͂����Ƃ��낢��ȃ^�C�v�����邵�A�o�ꂷ��̂͏�������ł͂Ȃ����A��������������ł͂Ȃ����A��قǂ��\���グ���悤�ɂ����Ƃ����ƍL�͂ȃe�[�}�������Ă��܂���݂䂫����ɑ��푽�l�ȃe�[�}������悤�ɂł��B
�@�u�l�͉��̂͌������v�Ƌ���͎̂��R�ł��B�ł��u�݂䂫�̉̂͂����"�匙���ȉ���"�Ƃ͈Ⴄ�v�Ƌ�̂Ȃ�A�����Ɖ��̑S�̂����ė~�����Ǝv���̂ł�����Ȃ��̑������⏬�ȉ��̂̐��E����ɒ����݂䂫�̉̂Ɣ�r����ẮA��ɏグ��ꂽ���̂����z�ł���������������܂�������玄�́A���̂ɂ͂����Ƃ����Ƃ��낢��ȉ̂����邵�A���̂悤�ȉ̂̒��ɂ́u�݂䂫����̉̂Ƌ��ʂ�����̂���������v�Ƃ������Ƃ����������Ă����������Ǝv���̂ł��B
 �@�c�Ƃ���́A���̂̎������ɂ͈�̃p�^�[��������Ƌ��Ă��܂���u�j�ɐU���遨�U��ꂽ�����o�J�������Ɛs�����悩����������ł��A���Ȃ����D���v�Ƃ����B
�����Ő\���グ�����̂́A�Ō�́u����ł����Ȃ����D���v�Ƃ������Ȃ��̌����ȉ��̏��p�^�[���Ƃ݂䂫�����u�ēy�Y�v�i�A���o���u�\���v�Ɏ��^�j�́u�m��Ȃ��ӂ肵�Ă����̂� �� �܂����Ȃ����D��������v�̏����͂ǂ����Ⴄ���A�Ƃ������Ƃł��B�U��ꂿ��������Ƃӂ��r��̏��A�Ƃ��������[�x�̈Ⴂ�͂���܂����A�{���I�ɂ͓����ł��B
�@�c�Ƃ���́A���̂̎������ɂ͈�̃p�^�[��������Ƌ��Ă��܂���u�j�ɐU���遨�U��ꂽ�����o�J�������Ɛs�����悩����������ł��A���Ȃ����D���v�Ƃ����B
�����Ő\���グ�����̂́A�Ō�́u����ł����Ȃ����D���v�Ƃ������Ȃ��̌����ȉ��̏��p�^�[���Ƃ݂䂫�����u�ēy�Y�v�i�A���o���u�\���v�Ɏ��^�j�́u�m��Ȃ��ӂ肵�Ă����̂� �� �܂����Ȃ����D��������v�̏����͂ǂ����Ⴄ���A�Ƃ������Ƃł��B�U��ꂿ��������Ƃӂ��r��̏��A�Ƃ��������[�x�̈Ⴂ�͂���܂����A�{���I�ɂ͓����ł��B�@�����ЂƂc�Ƃ���́u���̂̏��͈�l��"��ɂ��킢�����Ǝv��ꂽ��"�Ǝv���Ă���v�Ƌ��Ă��܂����A���̐��̒��ōD���Ȓj�̑O��"���킢���Ǝv��ꂽ���Ȃ�"�������Ă���̂ł��傤���B���ɂ݂䂫�������u�ЂƂ�v�̒���"�o��̌��t��Y��Ȃ��łˁ@���ꂩ�ɂق߂Ă���������ƂȂǁ@���ꂫ��̂��Ƃ�����"�Ɖ̂��Ă���ł͂Ȃ��ł�����������������\���ɂ��C�Â��Ă����������������ɋC�Â����ɂ݂䂫����̃J���X�}�����茩�Ă���ƁA�݂䂫�����������Ă��܂����A�ޏ��Ԃ��ċ��k���Ă��܂���Ȃ��ł����˂��B�u�c�Ƃ���A�������ĉ������Ǝv��ꂽ�����ǃT�E�E�E�v�Ȃ�ĂˁB
2012.04.20 (��) ���̒��̒����݂䂫�P�`���I�ꌳ�I�����݂䂫�_
�@��Ў��ォ��̋��FM�삩�烁�[�����������B�����݂䂫��CD���~�����Ƃ����B�ޏ��̃X�E�F�[�f�����w���ォ��̗F�l�������]�Ȃ̂��������BM��͗��w����{�ɋA�������A�F�l�͂��̂܂܃X�E�F�[�f���Ɏc��A���݂����[�e�{���ɍݏZ�A�j�b�g��ƂƂ��Ċ��Ă���Ƃ̂��Ƃ��B �@���w����A�{���[�X�Ƃ����X�E�F�[�f���̓c�ɒ��ŁAM��ƗF�l�́A������l�̗F�l�����{���玝���������݂䂫�̃J�Z�b�g���A�e�[�v���C����܂Œ����܂������Ƃ����B�u����v�́u�����͓|�ꂽ���l������ ���܂�ς���ĕ����o����v�Ƃ������ɁA�����ƗE�C�t����ꂽ�Ƃ��B�����݂䂫�̉̂́A�ޏ������ɂƂ��āA�܂��ɖ]���̉̂ł���t���̂��̂������B
�@���w����A�{���[�X�Ƃ����X�E�F�[�f���̓c�ɒ��ŁAM��ƗF�l�́A������l�̗F�l�����{���玝���������݂䂫�̃J�Z�b�g���A�e�[�v���C����܂Œ����܂������Ƃ����B�u����v�́u�����͓|�ꂽ���l������ ���܂�ς���ĕ����o����v�Ƃ������ɁA�����ƗE�C�t����ꂽ�Ƃ��B�����݂䂫�̉̂́A�ޏ������ɂƂ��āA�܂��ɖ]���̉̂ł���t���̂��̂������B�@�Ƃ��낪�A���̃J�Z�b�g�e�[�v�̎�́A39�̎��A���������o���ŖS���Ȃ��Ă��܂��B���U�̗F��S������M��́A�ȗ������݂䂫�Ă����B���ꂪ����̂��ƂŁA�u���ւ��悤�v�Ƃ����C�ɂȂ����B�����͗��ꂽ�̂��B
�@���́AM��ɒ����݂䂫��CD-R���g�������B�X�E�F�[�f���Ɠ��{�ɕ����ꂽ�F�l���m���A����L�����u�ĂāA�����݂䂫���Ă���B�S���F�ւ̒����̂Ƃ��āB
 �@���͂����ƒ����݂䂫�̃t�@���ł���B1975�N�A�f�r���[�E�V���O���u�A�U�~��̃����o�C�v�Œ��ڂ�������A�u����v�����������A���E�̗w�ՂŃO�����v�����l�����B���̌�͂��傭���傭�A���o�����悤�ɂȂ邪�A����1979�N�����[�X�́u�e���Ȃ�҂ցv�͋C�ɓ���A���ł��u�^�N�V�[�h���C�o�[�v�ɂ͐S�ꂵ�тꂽ������������Ă��邯�ǖ{���͐Ƃ����̂����炵���ƁA�����āA����ȏ��ɂ��肰�Ȃ�������^�N�V�[�h���C�o�[�̂₳�����ɃW�[���Ƃ����B"�����݂䂫�͉����������̖�����"�Ɗm�M�������̂��B
�@���͂����ƒ����݂䂫�̃t�@���ł���B1975�N�A�f�r���[�E�V���O���u�A�U�~��̃����o�C�v�Œ��ڂ�������A�u����v�����������A���E�̗w�ՂŃO�����v�����l�����B���̌�͂��傭���傭�A���o�����悤�ɂȂ邪�A����1979�N�����[�X�́u�e���Ȃ�҂ցv�͋C�ɓ���A���ł��u�^�N�V�[�h���C�o�[�v�ɂ͐S�ꂵ�тꂽ������������Ă��邯�ǖ{���͐Ƃ����̂����炵���ƁA�����āA����ȏ��ɂ��肰�Ȃ�������^�N�V�[�h���C�o�[�̂₳�����ɃW�[���Ƃ����B"�����݂䂫�͉����������̖�����"�Ɗm�M�������̂��B�@���̌�A���Ԃɂ͗l�X�ȁu�����݂䂫�_�v���o�ꂷ��B1977�N�A�u�킩�ꂤ���v���V���O���E�q�b�g����ȂǁA���̂���ޏ��͂��͂�W���[�ȑ��݂ɂȂ��Ă����B������ɁA�u�݂䂫�_�v�́A�����Ȃׂď��́u��O�v�u�����v�ɃX�|�b�g�ĂĂ���A���Ԃł͒����̉̂́u�Â��v�Ƃ�����ۂɏI�n���Ă����悤�Ɏv���B���̗F�l�ɒ����̘b������ƁA���܂��āu�Â��v�Ƃ����������Ԃ��Ă������̂��B
�@���͗���āu�n��̐��v����u���[�N�B2002�N��NHK�g���̍���ł́A���l�_������̒��p�����ڂ��W�߂��B���̂��낪���́u�����݂䂫���l�T���X�v�������B�S�I���W�i���E�A���o������肵�ĕ����܂���B�����ƋC�ɓ������ȂƂ����ł��Ȃ��ȂɎd��������B�����̃x�X�g����肽���Ȃ�B�����̃p�^�[���ł���B
�@�����ŏo�����̂��uM'S BALLADS�v�BM��ɑ�����1��������ł���BBALLAD�Ɩ��Â����̂́A�I�Ȃ̂قƂ�ǂ� slow & mellow ����������ŁA�����ł��u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�̌X�����o�Ă����H�I �Ȗڂ͈ȉ��̂Ƃ���B
1�C�� 2���ւ� 3�z�[���ɂ� 4������͂悹�� 5�N�̂����ł��Ȃ��J�� 6�ēy�Y 7����ȏ㌾��Ȃ��� 8���Ȃ����C�����Ă��邤���� 9���͗���� 10����������� 11�i�v���� 12�a�� 13���ɍ~��J 14�̕P�@�����CD-R�ɃR�s�[���ĕ����܂������B���̂����F�l�ɂ��z������������B�����Ə��������Ȃ�B�����ŏ������̂��u���I�ꌳ�I�����݂䂫�_�v�B����́A����\�����Ă��������B�������̂�2003�N8���ł���B
M'�r BALLADS�Ǝ��I��ʓI�����݂䂫�_
 �@�����݂䂫�́A�f�r���[�ȗ�28�N�ԋx�ނ��ƂȂ������Ŋ��Â��Ă��邪�A�����ɂ��āA��N��N�g�j�g���̍���ɏo�ꂷ��ȂǑ�u���[�N�B���̂Ƃ��̂����u�n��̐��v�́A"�����N�̉�����"�ȂǂƂ����Љ�ۂɂ܂łȂ����B
�@�����݂䂫�́A�f�r���[�ȗ�28�N�ԋx�ނ��ƂȂ������Ŋ��Â��Ă��邪�A�����ɂ��āA��N��N�g�j�g���̍���ɏo�ꂷ��ȂǑ�u���[�N�B���̂Ƃ��̂����u�n��̐��v�́A"�����N�̉�����"�ȂǂƂ����Љ�ۂɂ܂łȂ����B�@����Ȏ��������炱���A�����݂䂫�̖{���������Ȃ�ɒT���Ă݂����Ȃ����B���̂��߂Ɂu�����݂䂫�`�}�C�E�t�F�o���b�g�v����낤�Ǝv�������A1976�N�̃t�@�[�X�g�E�A���o���u���̐����������܂����v����2002�N�́u���Ƃ��Ȃ��v�܂ŁA30���̃I���W�i���E�A���o���̒�����"�����Ȃ����̉�"�ƒP���ɋ�������i��I��A14�ȂƂȂ����B
�@�����A�ʗ��A�]���A�l���A���A�Ȃǂ̃e�[�}�𒆓��݂䂫�͔ޏ��ɂ����Ȃ������Ō����ɍ��̂��グ�Ă��顂܂�Ŗ��؋��B��������̐��E���
�@�I�قƂ�ǂ̍�i���A���܂��܃X���[���~�f�B�A���E�e���|�̋Ȃ��肾�����̂ŁA�^�C�g�����uM'S BALLADS�v�Ƃ����B
�@��L�̂悤�ɁA�e�[�}�͑���ɓn���Ă��邪�A���̒�ɗ���鋤�ʂ������_�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂��H �A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̓����́H ������T���Ă݂����B
�@�^�C�g����"���I��ʓI"�Ƃ����̂́A���ٕ̐����ޏ��̑��푽�l�c��ȃ��p�[�g���[�S�Ă�Ώۂɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����������Ɗ�����14�Ȃɍi���ď��������_�ł��邱�ƁB�܂����l�Ƃ��Ă̒����݂䂫�͘_���Ă��邪�A��ȉƂƃV���K�[�̕����ɂ͌��y���Ă��Ȃ����Ƃɂ��B�v����Ɏ��I�ň�ʓI�œƒf�I�Ȓ����݂䂫�_�ł���A�P��"�����玩���͒����݂䂫���D���Ȃ̂�"�Ƃ����������ł����Ȃ��
�@�����݂䂫�̉̂̍���ɗ�����т����v�z�́A�ŏ����́u����v�ɂ���悤�Ɂu�����邱�Ƃւ̍m��v���v���X�u�����B"�����͓|�ꂽ���l�������@���܂�ς��ĕ����o����"�Ƃ�������őO�����̐��_�����̂��Ƃ���т��ė���Ă���A�l�����̂����̂͂������A�炢�����̉̂ł��u�������₾�A����ł��܂����v�Ƃ͂Ȃ炸�Ō�̂Ƃ���ł͐�ɂւ�����Ȃ��B
�@���̒��ł͍ł��炢�����̉̂ł���u���͗���āv�ł��A"�����ȂǂȂ��Ɓ@����������@�Ȃ���߂ā@�������܂������Ă����@�l���͂���Ȃ���"�Ƃ��邵�A�u���ɍ~��J�v��"���̐l�Ȃ��ł�1�b�������Ă͂䂯�Ȃ��Ǝv���Ă�"�̂ɁA�₽���J�̒�������Â�������"���ɍ~��J�̗₽���͐�����Ƌ��ԒN���̐��A���������Ɩ��������̐�"�ƂȂ�B
�@����Ɂu�a���v��"�����Ȃ��琶�܂��q���̂悤�Ɂ@������x�����邽�ߋ����Ă����̂�"�A"Remember�@���܂ꂽ���Ɓ@�o���������Ɓ@�ꏏ�ɐ����Ă�����"�͂܂��ɐl���m��̓T�^����"�ЂƂ�ł����͐������邯�ǁ@�ł����ꂩ�ƂȂ�@�l���͂͂邩�ɈႤ"�ɂ̓v���X�u���������ɕ\��Ă���B
�@����ł͔ޏ��̍�i���̎p�����A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̓����͂Ȃ�Ȃ̂��낤�B�꒮���Ċ�������̂́u�����̂��܂��v�A�u�h���}�`�b�N�ȍ\���́v�A�u�n�b�Ƃ�����d�|���v�Ȃ�"���y�n��̖��H"�Ƃ��Ă̒����݂䂫�̍˔\���B
�@���Ƃ��u�i�v���ԁv�B�O���́A"�l�Ԃ̑��݂Ȃǂ����ۂ��Ȃ��̂łǂ�Ȑl�Ԃł��K���Y�ꋎ���Ă��܂�"�ƌ����Ă����āA�Ō�ɁA"�F���͂ЂƂ�ЂƂ�Ɂu�i�v���ԁv�Ƃ������������̂Ȃ����l��^����"�Ɖ̂���O���Ő�]�I�ȋC�����ɂȂ���������͍Ō��"�悩����"�Ƌ~���顂��̃M���b�v���傫�Ȋ������ĂԂ��ƂɂȂ�B
�@�܂��u�ēy�Y�v�ł́A�O�i�Łu�R�v�Ƃ����L�C���[�h�������Ă����āA���Ղł��̍������o����������n���Ƃ����A�I�Ղł͂���ȉR�������j�ɑ���"�m��Ȃ��ӂ肵�Ă����̂́@���@�܂����Ȃ����D��������"�ƐȂ����S���̂�����̕���\���̌������B
�@�u���Ȃ����C�����Ă��邤���Ɂv�̐S���`�ʂƏ�i�`�ʂ��ƂĂ��Ȃ��B"���͗[���@�S���ā@�w�����ā@���Ȃ��A��""���ꂩ�@�Ԃő҂��Ă�݂����ȁ@�����C������@�Â����ǂ�́@���߂čŌ�́@���̂��ŋ�"�ȂǐS����ԂƏ�i������قǂ������蕂����ł���̂͊B�����āA"����ȊC�ӂɁ@�����Ȃ������@����������ȁ@�X�Ȃ�悩����"�̓]�����ĕ��N��ɂ܂�Ȃ���������ɔ�ނ̂Ȃ��|�p�i���
�@����ɁA���M���ׂ��́A���������ڐ���"��ɂ���ꏎ���Ɠ��������ɐݒ肳��Ă���"�Ƃ������Ƃ��B�����Ĕޏ��̂��̖ڐ�����A������"�����Ă����Ȃ��C����"�i���₳���������������j����������̂ł���
�@�Ⴆ�ΑO�o�u�a���v��"�v���o���Ȃ��Ȃ�@�킽���@���ł����Ȃ��Ɍ���"��u����������v��"��l�͂����Ȃ��@�������̂��ɂ�����"���������B�܂��O�o�u�i�v���ԁv��"100���̐l�X���@�Y��Ă��@���̂ĂĂ��@�F���̏��̒��@�l�͉i�v����"�Ƃ����̂��������B
�@�܂��\����i�Ƃ��āA�����Ƃ��납�猩�������ɂ͕ʂ̂��̂ɑ����Ƃ�����@���Ƃ��Ă���Ƃ��낪�����[����u�n��̐��v�̂悤�ɋ�̏ォ�猩�������ɂ̓c�o���ɑ�����̂����ƂŐl�X���Ă�肽���Ƃ����u�̕P�v�ł͎����������Ƃ��납���邱�Ƃ�����������Ɂu�̕P�v�ւ̊�]�Ƃ��Č�点�Ă��顏�ɉ̂���̖̂ڐ��͕�����ł����X�Ɠ����Ȃ̂��
�@������ƈӊO�������̂��u�C�v�Ɋ֘A����̂����\�����������Ƃ�����̒��ɂ�7�ȂɊC���o�Ă��顁u���ւ�v��"���ɐ�����ď��ɂ���@�݂�Ȃ��ꂢ�Ɍ����Ă���"��u�C��v��"���܂��������Ă��Ɂ@�����̋��̉̂��̂���"�ȂǂɊC�ւ̈����������ɕ\��Ă���
�@���ƁA�O�o�́u���Ȃ����C�����Ă��邤���Ɂv��u�ēy�Y�v���C��ɂ������i�ł���B
�@�u�̕P�v��"�X�J�[�g�̐����@�����ɂȂ���"��"��������D�̃f�b�L�ɗ�������������"�ȂǁA�C���݂̕`�ʂł̕\���͂����顒����݂䂫�ɂ͊C���݂̖��Ȃ������
�@�����݂䂫�͏��S��Y��邱�ƂȂ������Â��A�l���𓊂����ɑ������蝈�������肷�邱�ƂȂ��A�ǂ�Ȃɂ炭�Ƃ��ǂ�Ȃɏ������Ƃ�����͂��������̂Ȃ����̂Ȃ̂��������ς��ɐ����čs������ƌĂт����Ă���顂�����������ł͂Ȃ��A�����ڐ��ňꏏ�ɔY�ݍl���Ă݂Ă����B�Ђ��ނ��ɐ����Â���l���̗��l�ł���l�ԥ�����݂䂫���A����ɔ�������ނ܂�Ȃ�|�p�I�\���͂���g���č��o�����X�̍�i���A�D�����g���������̐S�ɋ������R�͐��ɂ����ɂ���Ǝv���������ޏ��̉̂͂܂������u�l��̐l���̉����́v�Ȃ̂��B
2012.04.05 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��D �L�҉�����̐^��
�@�u�N�����m�v�H��܃V���[�Y�͍����7��𐔂���B���w�܂Ȃ���̂ɂقƂ�Nj��������������Ƃ̂Ȃ����������܂ł̂߂荞�̂́A��ɓc���T�펁�̋L�҉�ɂ������B���̕s�@���ȑԓx�͊m���ɏՌ��I���������A�����������������̂͂��̖��悪�^�����Ό��T���Y�Ɍ������Ă��邱�Ƃ������B����͂��̂�����𒆐S�ɁA���߂ċL�҉��U��Ԃ�A���̗��ɂ���c�����̐S���̐^����T���āA�V���[�Y���I�������Ǝv���B�u�m���V���[���[�E�}�N���[���������Ǝv���܂����A�A�J�f�~�[�܂ɉ��x�����ɂȂ������Ǝ�܂����Ƃ��ɁA�w����������ē��R���x�ƌ����������ł����A������������Ȋ����ł��v
 �@���̑䎌�́A�c�����̎�܋L�҉�ł̑�ꐺ�ŁA�u���̂��C�����́H�v�Ƃ��������܂�̎���ɓ��������̂��B
�@���̑䎌�́A�c�����̎�܋L�҉�ł̑�ꐺ�ŁA�u���̂��C�����́H�v�Ƃ��������܂�̎���ɓ��������̂��B�@�V���[���[�E�}�N���[���i1934�|�j�̖��O���o���̂͐��������������B�����B�������̑�̂��ۛ����D�ł���B�u�A�p�[�g�̌��݂��܂��v�i1960�j�Ɓu���Ȃ��������ӂ́v�i1963�j�͓�Ƃ��r���[����C���_�[�i1906�|2002�j�̊ē�i�ŁA�b������ʔ����B2��Ƃ��A�J�f�~�[�剉���D�܃m�~�l�[�g��i���B
�@�u�A�p�[�g�̌��݂��܂��v�́A������̃W���b�N��������i1925�|2001�j���剉�j�D�܂Ƀm�~�l�[�g����Ă����B�ނ���������Ђ̕��T�����[�}���́A�����̃A�p�[�g�̕������̏���̏�̂��߂ɑ݂��Ă���B���̒��̈�g�ɓ�����Ђ̃G���x�[�^�[��̃}�N���[��������B���������v�����鏗�̎q���B������ޏ��̕s�ς̏ꂪ�����̃A�p�[�g�A�ł��A��i�ɂ͋t�炦�Ȃ��B�u�T�����[�}���͂炢��v�ł���B�����Ə�Ȃ��Ə��p�����D�萬���j�̈����B���̕�����܂�Ȃ������B����̓W���b�N�E�������̉f�悾�Ǝv���B
 �@�u���Ȃ��������ӂ́v�ł́A�V���[���[�E�}�N���[���̓p���̉����ŏ�������C���}�Ƃ������̏��w��������B�L���[�g�œV�^ࣖ��A�ł��ǂ����ɉe�ƒm��������B���ꂼ�}�N���[���ꗬ�̃L�������B������͂�͂�W���b�N�E�����������A������͂ǂ��炩�Ƃ����V���[���[�E�}�N���[���̉f�悩�B�Ƃ͂����A�����͑S�Ė������C���_�[���r�̎Y���B�ł��A����͂܂��ʂ̘b���B
�@�u���Ȃ��������ӂ́v�ł́A�V���[���[�E�}�N���[���̓p���̉����ŏ�������C���}�Ƃ������̏��w��������B�L���[�g�œV�^ࣖ��A�ł��ǂ����ɉe�ƒm��������B���ꂼ�}�N���[���ꗬ�̃L�������B������͂�͂�W���b�N�E�����������A������͂ǂ��炩�Ƃ����V���[���[�E�}�N���[���̉f�悩�B�Ƃ͂����A�����͑S�Ė������C���_�[���r�̎Y���B�ł��A����͂܂��ʂ̘b���B�@�������͈�r�ɃC���}�ɍ����x�����B�����܂�͂����q���ɂȂ�A�҂�����͂����A�ϑ����Ė���ޏ��̑��������悤�ɂȂ�B�q����点�Ȃ����߂ɁB����قǃC���}�̂��Ƃ��D���Ȃ̂ł���B��x���������͒������ɖ߂�B���ꂶ��o�ς����Ȃ�����A�[�邩�璩�܂Ŏs��ŘJ���B�u���ꂶ��̂ɂ����킯�Ȃ����v�ł���B�������A��̃������ɃC���}�͕��C�Ɗ��Ⴂ�B�����Ȃ��������Ɉ��z���������C���}�́A�ϑ��C�M���X�a�m�Ƌ삯�����̖B�����͉�����I �ǂ�����W���b�N�E�������B���̓^�������Ɍ����Ȋ����x�B�����āA�����ۂ��������炵���}�N���[���̉��Z�͂܂��Ɏ剉���D�܂��̂������B
�@�V���[���[��}�N���[���́A���̑O�ɂ��u���藈��l�X�v�i1958�j�Ńm�~�l�[�g����Ă���A���̌�u���Ɗ��т̓��X�v�i1977�j���o�āu���ƒlj��̓��X�v�i1983�j�ŁA�O��̎剉���D�܂ɋP�����B5�x�ڂ̐����������B���̂Ƃ��̎�܃X�s�[�`�́u���̌|��͂��̏܂Ɠ������炢�����́B�I�X�J�[�ւ̖���26�N�Ԃ������������Ă���āA���肪�Ƃ��v�������B�c�������������u����������ē��R�v�͂��j���A���X���Ⴄ���A�ޏ��̃E�B�b�g�̗��ɂ���^�ӂ�ނȂ�ɉ��߂����̂��낤�B
�@�c�������u���v�ł̊H���܂͓���5��ڂ������B�ŏ��̃m�~�l�[�g����5�N�ڂ́A�@�V���[���[��}�N���[����26�N�ɔ�ׂ�ΑS�R�Z���B�������A�H��܂̏ꍇ�A"5�N�ȏ�o������V�l�Ƃ݂Ȃ���Ȃ��̂Ŏ�܌�������������"�Ƃ����Öق̗���������i�Ƃ����Ă���j����A�ނƂ��Ă͔w���̐w��������������Ȃ��B
�@�w�����[��t�H���_�́A�剉�j�D�܂̍ŏ��̃m�~�l�[�g��1940�N�u�{��̕����v�ŁA�l�����̂�1981�N�́u�����v���������炻�̊ԂȂ��41�N�A����͋C�̉����Ȃ�悤�ȔN���B���݂ɓ����f��Ŏ剉���D�܂��l�������L���T���[���E�w�v�o�[����4�x�ڂ̎�܂ŁA����̓I�X�J�[�̍ő���܋L�^�ł���B
�u�P��ڂŎ�܂Ƃ����̂���Ԃ�������ǁA5��ڂƂ����̂͊Ԕ����ł��v�@����͎��̏���ȉ��߂����A�u�Ԕ����v�Ƃ����̂͐R�����ɂ��������Ă���悤�ȋC������B�c����5�̃m�~�l�[�g��i�̂����A�ǂ̂́u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�Ɓu��O�I�w�̋��v�Ɓu���v�����Ȃ̂Œf���͂ł��Ȃ����A�����x�Ƃ����ʔ����Ƃ����u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v���f�g�c�̏o�����Ǝv���B�ƒf���Ȃ��H ���̂Ƃ��̎�܍�́A�Ñ��L�v�q�́u�|�g�X���C���̏M�v�ł��邪�A���̍�i�̂��Ƃ�3��1���t�ɏ������Ƃ���A�u���ɂƂ��Ă͂����̃X�J�v�ł���B������ɁA�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�ɋy�Ԃׂ����Ȃ����̍�i�ɁA�I�l�ψ��͏܂�^�����B�c�������u�Ȃ�ĊԔ����Ȑl�������v�Ǝv���Ă��s�v�c�͂Ȃ��H
�@�܂��A���̂Ƃ��݂̂Ȃ炸�A�I�l�ψ��̃R�����g�ɂ͂ǂ����Ǝv�����̂����X����B�����2��15���t�ŏ��������A����̂����ЂƂ�̎�҉~�铃���Ɋւ�����̂͂��̍ł�����̂������B�m���ɓ���ȏ��������A�ݖ�ɂ͕������Ă���l�͂�������̂�����A���������������ɐu���Ȃ肵�ė�������w�͂����ׂ��Ȃ̂ɁA�u����Ȃ����lj������肻���v�Ƃ��u����Ȃ����瑼�̈ψ��ɏ�邱�Ƃɂ����v�ȂǂƂ̂��܂��B����Ȃ̂͑I�l�ψ��Ƃ��Ď��i�������Ƃ���B�܂��A50�N�ȏ���O�ɁA���́u���z�̋G�߁v��I�Ⴄ�悤�ȏW�c������A�u�Ԕ����v�͉������Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ����B
�u�����f�������ĕ����ċC�̏������I�l�ψ����|�ꂽ��Ȃ�����s�����������܂��̂ŁA�s�m���t���Ɠ����s���e�ʂ̂��߂ɂ�����Ƃ��Ă��v
�u�ǂ����Ȃ�~���悩�����B�Ό�����ɖJ�߂���قǃ��L�͉���ĂȂ��Ǝv���܂���A���́v
�u�܂��A�����͂������Ȃ��l�v
�u�Ό�������D���Ȑl���Ă���Ȃɂ��Ȃ��Ǝv�����A������̂����̐l�̎d������Ȃ��ł����v
 �@�����͂��ׂĐΌ��T���Y�Ɍ��������̂ł���B���_��O���́u���݂����ȍ�i�����肾��v�Ȃ�T���Y�����܂��Ă̂��̂����A�c�����̔����͂����ɂ��ߌ��ł���B��������́A�ނ̐Ό��T���Y�ɑ���G�ӂɂ���������ǂݎ���B
�@�����͂��ׂĐΌ��T���Y�Ɍ��������̂ł���B���_��O���́u���݂����ȍ�i�����肾��v�Ȃ�T���Y�����܂��Ă̂��̂����A�c�����̔����͂����ɂ��ߌ��ł���B��������́A�ނ̐Ό��T���Y�ɑ���G�ӂɂ���������ǂݎ���B�@�c�����́A���Z���ƌ㓭���C�͑S���Ȃ��A�Ƃɂ������č�Ƃ�ڎw�����B��ƂƂ��Đ��ɏo��܂łɁu��������v��5����ǂƂ�������A���̓Ǐ��ʂ͑����Ȃ��́B�H��܍�Ƃ̍�i�Ȃǂ́A�قړǔj���Ă����͂����B���R���́u���z�̋G�߁v���B
�@�ނ́A�u����Ȃ��̂��H��܂��B����Ƃ͂����A�Ђǂ��������v�Ǝv�����ɈႢ�Ȃ��B�u����Ȃ��̂��l���Ȃ�A�����̕����܂��܂����v�Ƃ��B�����₱�ꂪ�A5����g���C�ł�����̌����͂ɂȂ����H
�@�c�����̕`���j�����́A�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�̑c���̂悤�ɖ����Ȓj�A���̗l�Ȗ����Ȓj�A�u��O�I�w�̋��v�̑c���̂悤�Ȉ�r�Ȓj�A�u���v�̕��̂悤�ȕϐl�ȂǁA��ؓ�ł͍s���Ȃ��j�������Ђ��߂��Ă���B�u�ł��v�Ɠc�����͌������낤�u�Ό��T���Y�̏��������Ƃ̂悤�Ȕڋ��Ȓj�́A���ɂ͂悤������v�B�u�����������Ȃ��l�v�ƌ������̂͂����������Ƃ��낤�B
�@�܂��A�u���݂����ȍ�i���肾�B�����̐l���f�������A���e�B���Ȃ��B�܂�A�S�g�����������Ȃ��v�̔����ɂ����������ꂽ���Ƃ��낤�B�u���l�̐l���ȂǕ�����͂����Ȃ��̂ɁA�ǂ�����"�l���f"�]�X��������̂��H ����ɁA��i�ɐl�������f����K�v�Ȃ�āA�ǂ��ɂ���I�H�v�ƁB
�@�������R�[�h��Ђ̐�`���ɂ���1980�N����A���y���̎�ނŔ������R���B�Y�̌��t���Y����Ȃ��B�u���y���Đ����l���\�����̂ł����A���Ȃ��̐����l�́H�v�Ƃ�������ɑ��A�u�����l���ĉ��ł����H ���y���l���f����K�v������̂ł����v�Ɣނ͌������B�c�����̏ꍇ�Ɠ������A��⃀���Ƃ��āB�m���ɔނ̉��y�ɐl���͊������Ȃ��B�c�������Ό��T���Y�ɓ������Ƃ��������������̂ł͂Ȃ����B���y�����������낢��Ȍ`�������Ă����̂�����B
�@����ɁA�c�����́u�Ό�����̏ꍇ�͏����ɐl�������f���Ă������A���Ƃ̔ڋ����͔ނ̐l���̔��f�̂͂����v�Ɖ��߂������Ƃ��낤�B�������u�Ό�����ɖJ�߂���قǃ��L�͉���Ă��Ȃ��v�ƌ������̂ł���B
�@�������A����͂����܂ŏ����ƁE�Ό��T���Y�Ɍ��������t�B�����ƁE�Ό��T���Y�͂ǂ���������ɂ��B���ꂪ�u�����������V�}�ɂ�������ł��������v�����ɂȂ����B
�@�c�����́A�u���z�̋G�߁v�̎�l���́u�ڋ��v��m���Ă����B���ꂪ��ܑO���́u���݂����ȍ�i����A�l���f�������A���e�B���Ȃ��v�Ƃ����Ό������ɁA�u���ɂ͌���ꂽ���Ȃ��v�ƃJ�`���Ƃ����B���ꂪ�s�@���L�҉�̐^���ł���B�ɉ��Ȃ邩�ȓc���T�킳��I �u�H��܁v�ɒ��ڂ����Ă���Ă��肪�Ƃ��I�I
2012.03.20 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��C ��ƂƂ��Ă̐Ό��T���Y
 �@�c���T�펁�Ɂu�����������V�}�����ɂ�������ł���������v�ƌ���ꂽ�Ό��T���Y�����ɏo���̂́A1956�N�u���z�̋G�߁v�̊H���܂������B�ނ̃L�����A�̌��_�ł���B
�@�c���T�펁�Ɂu�����������V�}�����ɂ�������ł���������v�ƌ���ꂽ�Ό��T���Y�����ɏo���̂́A1956�N�u���z�̋G�߁v�̊H���܂������B�ނ̃L�����A�̌��_�ł���B�@�Ό��͍������ŊH��ܑI�l�ψ����C�錾���������A���̌������́u���݂����ȍ�i���肾�B�����̐l���f�������A���e�B���Ȃ��B�܂�A�S�g�����������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�����Ⴂ�l���o�Ă��āA������������Ƃ�����ɂ����҂������A�S�R�h���ɂȂ�Ȃ������v�ł������B�����ς�ʐg����Ȍ����l�����A����͂��Ă����A���̌�����u�����͎��Ȃ̔��f�ł���ׂ����v���ނ̎��_�Ɠǂݎ���B������A�Ό��T���Y�̌��_�ɂ��Ď��Ȃ̔��f�ł���u���z�̋G�߁v�������Ă݂����B
�u���z�̋G�߁v�Ƃ�������
�@��l���͒Ð엳�ƁA�����N���u�ɏ��������w���ł���B���b�g�������������Y�K���̂��V�����ŁA�Z�܂��͏Ó�E���q�B����ȖV�₪���ԂƂ��ł��������̐��X��`�����������u���z�̋G�߁v�ł���B
�@�ނƔނ̒��Ԃ͉�����������H �������炻�̂܂�����ʂ��B
 �u���A������A���܁A�����Ɣނ�̈������Nj�������ނ͌��肪�Ȃ��v�B
�u���A������A���܁A�����Ɣނ�̈������Nj�������ނ͌��肪�Ȃ��v�B�@�ł́A�Ȃ�����Ȉ������s���̂��H �u�l�X���ނ�����y��ƂȂ���l�B�̃����������A���͔ނ炪�������������A���ӎ��ɉ��Ƃ��Ă�����̂Ȃ̂��B��l�B���g�����Ǝv�������E�́A���ۂɂ͋t�ɂ��߂��Ă���̂��B�ޓ��͂����ƊJ�����g�������X�������E��v������v�B
����Ȕ�����ȋC�����ŁA���ƂƂ�����w���́A����ŏ����i���p���A�Z��ɔ���A�s�܂��A�ق����ޏ������Ȃ��A�����ň�e�Ƀ��m�𓊂����A�u�n����Y���I�v�Ƌ��ԁB
�@���������̂��V����u��l�ȂɂȂɂ��킩��v�Ƃ������Ȃ���A�������Ė��O���ȍs�������邾���̔j���p�ȎO���������B
�@��l���̍s�ׂ������u���Ă��A�w�h���o�����ȑ䎌��\�������Ȃ��Ȃ��B
�u�m���ɁA���Əꍇ�ɂ���ẮA���͔ޓ��ɂƂ��Č������Ƃ̏o���ʑ��g��ł������v
�u���b�g�Ɗr�ׂ��Ԃň���������Ȃ�Ē��x�̒Ⴂ���Ɍ��܂��Ă炠�v
�u�ł����q�������������܂���n���������ɂ���v�ȂǁB���ɒ�i�ʁB
�@�\���Ȃ�C�������������ōςނ��A���e�I�ɂǂ����Ă��������Ȃ��ӏ��������B��́A���Ƃ��u�o�����q�����Y�܂��邩�낷���ŗh��邪���ǂ͑낷���ƂɌ��߂�v�V�`���G�|�V�����ł���B
�u�ʂɐ��߂Ƃ͌���Ȃ���B�D���Ȃ悤�ɂ����B�q�����o���Ă������Ȃ����Č������������v �B���ȓ����ɉp�q�����炢�炷��̂����Ĕނ͖ʔ��������B���X�A�q�����~�����Ǝv���ނ̐S�́A�ʂ肷����̃E�B���h�ɔ`�����l�N�^�C���}�ɗ~�����Ȃ�C�܂���̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B�@���ނ��낷�����ׂẮu�C�܂���v�B�M�������l�N�^�C�Ɍ����āA�u�n������v�Ƃ�����ڂȌ��t�Ō`�e����B�낷�ƌ��߂����������͂����̐V���̎ʐ^�B�C�܂���ŏ������Ɏ��炵�߂��̂ɁA�t�ɑ���̉�����ʔ�����A����͑��V�̏�Łu�o�J�����[�v���B"�X�|�[�c�}���Ƃ��Ă̖��ȋC���"�Ƃ���\���Ɏ����ẮA�ő��~���悤�̂Ȃ����B�X�|�[�c�}���Ɏ���̖��ߑ���l���̋ɂ݂ł���B
����ȕ��ɂ��āA�ނ͈ꌎ�̊ԉp�q�������ς��Ă������B������V���ŁA�ƒ�Ŏq����������`�����s�I���̎ʐ^�����Ĕނ͊�����߂�Ǝv���������B�O�O���͂��������̑I��́A���炵�Ȃ�������ď��Ă���B���Ƃ͎q�����n�����邱�ƂɌ��S�����B �Ԃ�V�́A�X�|�[�c�}���Ƃ��Ă̔ނ̖��ȋC���̂��߂ɎE���ꂽ�̂��B
�@������͂���ɍ����B���ꂼ�Ό��T���Y�̐��̂ł���B
���̌�����T���Y
�@���Ƃ����ԂƃL���o���[�ŗV��ł���Ƃ��A�����p�q�ƘA�ꗧ���Ă����j�ɏo�����킷�B�o���h�̃g�����y�b�g�������Ƃ����B�Ȃɂ��ʔ����Ȃ����Ƃ́A�������ɁA�_���X�����邻�̒j�̑��݂��Ă�낤�ƃt���A�ɏ��Ɠ��ݍ��ނ��A�͂��݂ŋt�ɂ��̒j�ɑ��܂�Ă��܂��B�j�͖����A���Ƃ͍X�ɓ��Ɍ������B�u������ɂ߂��Ă��v�Ɨ��Ƃ��Ƃ����s�������L�ł���B
�����ɒn���͓����Ă��Ȃ���������������悤�ɖ����Ă���A���̐S�z���Ȃ��ƒm���݂�Ȃ��W�߂Ď蔤�����߂��̂��B��ԏ����łЂ傤����ȓc�{���A�h��ȑ䎌�Œj���Ă�ł���B�w�����䂹�ʂ悤�ɐ����̃o���h���Ɨ��Ƃ͏��ɂ������芪�������B�c�{��l�ƌ��Ēj���ނ��ĐȂ𗧂��K�i�̏�܂ŗ������A�@�����ēc�{���������B�u��O�̂ǂ������ɗ����������Ă�낤���B�����Ă����v�u�����v�u���������A���ꂶ��A���̐l�ɕ����Ă݂ȁv�����Ďv�킸�U��������܂��A�g�����y�b�g�����̐O�ƕ@�̕ӂ�ɑ_�������ė͈�t���Ƃ���������B�j�͑�������Ԃ悤�ɂ��ĉ��̗x���܂ŗ����������̂��B�@���̂��ƁA���Ƃ͖���R�̑���ɃA�b�p�[�J�b�g���������A�u�������瓖���A�y�b�g�̑���Ƀe���|�̍���˂��}���J�X�ł��U���Ă�v�Ɣl��B�����ăG�s�\�[�h���������߂�����B�u�ނɂƂ��đ�Ȃ��Ƃ́A��������Ԃ��������Ƃ��A�������悤�ɍs�������ƌ������Ƃ������B�����������������ۂ��A���̑��̊���͎��ɑ���Ȃ��v�B
�@����ɂ͐����ɑR�Ƃ����B���ꂼ���ɔڋ��̋ɂ݂ł���B�܂��A�x�@�����Ȃ����ǂ����m���߂�����B�����Ă������Ȃ���悵�Ƃ��邳�������������B���������͏��Ƀo���h��������������Ȃ��̐����Ƃ�B����������������B���Ƃ́A��l�̕W�I�ɓ�l�|��őΉ��B��l�ɂ��т������āA�U��������܂��ꔭ�������B�s�ӂ��Ղ��ꂽ����͂ЂƂ��܂���Ȃ��B����Ɏ���Ė���R�ȓG�Ƀ_�������̈ꔭ�B�����Łu�U�}�[�݂₪��v�ƈ��Ԃ����B�����āA�����́u���������Ƃ������������v�ƚ����B
�@��l�𑽐��Œɂ߂��邱�Ƃ�ڋ��ƌ����B�p�ӂ̂Ȃ�����ɕs�ӂ�H��킷���Ƃ��ւ���ƌ����B�����ĂȂ���Ȃɂ�����Ă������͔ڋ��ƌ����B���������Ƃ����邱�Ƃ�g����ƌ����B
�@�{�N�V���O�̐S��������̂�����A�f�l����ɂ́A���ʂɂ���Ă��ԈႢ�Ȃ����Ă���̂��A���������������A�l�����|���A�s�ӂ�H��킷�B����ȕs�����Șb���ǂ��ɂ���B����ȏ�ڋ��ȍs�ׂ���̂ǂ��ɂ���Ƃ����̂��I
�@��҂����̒��ɕs�����������O���ȍs���ɑ��鏬����f��͑��X����B���A�������A�����ɂ͗����ł��镔���������Ȃ�Ƃ����݂�����̂��B�������A�����u���z�̋G�߁v�ɂ͒f���Ă��ꂪ�Ȃ��B�Â����ꂨ�V�����̔ڋ��Ȍ��������邾�����B
�@�Ό��T���Y�͖`���ŏ������悤�Ɂu�����͏������l�Ԃ̐S�g���̔��f�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������������Ă���B�Ȃ���̗��Ƃ̌����́A��҂̐S�ł����҂̕��g�Ƃ������ƂɂȂ�B�ނ́A�����I���u�ĂāA�����ڋ��҂ƔF�߂��̂ł���B
 �@�u���z�̋G�߁v�͑������ׂ������ł���B����ȍ�i�ɊH��܂��^����ꂽ�̂ł���B���ɂ���͓��{���w�j��̒ɍ������낤�B��������ŁA�u���z�̋G�߁v�́A����܂Ő��Ԉ�ʂɂ͂قƂ�ǒ��ڂ���邱�Ƃ̂Ȃ������H��܂Ƃ������w�܂��A��C�Ƀ��W���[�ɉ����グ���Ƃ����]��������B��������́A�������̂��̂̂����ł͂Ȃ��A��������h�������u���z���v�u�[���Ƃ����Љ�ۂ������炵��"����"�ɉ߂��Ȃ��B
�@�u���z�̋G�߁v�͑������ׂ������ł���B����ȍ�i�ɊH��܂��^����ꂽ�̂ł���B���ɂ���͓��{���w�j��̒ɍ������낤�B��������ŁA�u���z�̋G�߁v�́A����܂Ő��Ԉ�ʂɂ͂قƂ�ǒ��ڂ���邱�Ƃ̂Ȃ������H��܂Ƃ������w�܂��A��C�Ƀ��W���[�ɉ����グ���Ƃ����]��������B��������́A�������̂��̂̂����ł͂Ȃ��A��������h�������u���z���v�u�[���Ƃ����Љ�ۂ������炵��"����"�ɉ߂��Ȃ��B�@�f����̃v�������́A����̔ڂ������A�u����Ȃ�܂�������v�M���M���̂Ƃ���܂ŋr�F�����Đ��ɑ���o�����B����͏�L"�ڋ��̃V�[��"������Έ�ڗđR�B����́A�ނ�ɗǎ��������ăv���̋Z���J��o�������ʂł���B�f��͑�q�b�g�B�����f��͌�y�̉��l�B�ϋq�������͔N��11���l�ƌ��݂̖�10�{�A���ړx�͌��ƃX�b�|���ł���B
�@����҂������̑�w���ŊH��܂̍ŔN����ҁi�����j�Ƃ����C���p�N�g���u�[���ɔ��Ԃ����������Ƃ��낤�B����ɂ��̒킪�A���̍�i�ݑ�ɂ��ď��a�̃X�[�p�[�X�^�[�ւ̂�����Ă䂭�̂ł���B����Ȍ��I�Șb�����邾�낤���B�Ό��͂��������̍˔\�Ɗ��Ⴂ�����B�Ό��̃f�r���[�ȗ���т��đ����s���ɂ܂�Ȃ��������A�������_�Ƃ��Ă���͖̂����ł���B�ނ̎��M�͊��Ⴂ�̎Y���Ȃ̂ł���B
�@�u���z�̋G�߁v�͂��܂��܂ȋ��R����d�ɂ��d�Ȃ��Đ��܂ꂽ��ՓI�ȃu�[���������B���̊�_���������������Ƃ͊m�������A������Ƃ����Ă��ꂪ�D�ꂽ��i�ł͒f���ĂȂ��B����ǂ��납����قǒᑭ�ȏ������������B����́A�ǂ҂Ȃ�N��������ȒP�ȗ����ł���B
2012.03.10 (�y) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��B�u���v��ǂ��
�@��146��H���܍�u���v�́A�`���C�ǂ݂܂�ŋC�����̈�����i�ł���B���鎯�҂́u����͒��㌒���̐��E���v�ƌ������A�ǂ��Ƃ��Ȃ����ǂ����Ƃ��v��Ȃ��B�܂��A���ɂƂ��āA���̎�̍�i�ɖƉu���Ȃ��Ƃ����̂͊m���ɂ���B���炷��
 �@���͏��a63�N7���A�Ƃ���͐�ӂƂ����͌��߂��̓c�ɒ��B��l����17�˂̍��Z���E�_���n�B�ނ́A���e�E�~�i50�ΑO�j�ƕ��̏��ō`�ň��݉�������Ă���Վq�i35�j�Ƃ�3�l��炵�B�Վq�͉~�̎q����g�������Ă���B���̕�e�́A�߂��ŋ���������Ă���60�Ύ�O�̐m�q�B�ޏ��͉E����͋`��A���͏オ���Ă���B���n�ɂ͈�ΔN��̏��q�����E��c���Ƃ������F�B�����āA�N����l�͐��s�ׂɒ^���Ă���B
�@���͏��a63�N7���A�Ƃ���͐�ӂƂ����͌��߂��̓c�ɒ��B��l����17�˂̍��Z���E�_���n�B�ނ́A���e�E�~�i50�ΑO�j�ƕ��̏��ō`�ň��݉�������Ă���Վq�i35�j�Ƃ�3�l��炵�B�Վq�͉~�̎q����g�������Ă���B���̕�e�́A�߂��ŋ���������Ă���60�Ύ�O�̐m�q�B�ޏ��͉E����͋`��A���͏オ���Ă���B���n�ɂ͈�ΔN��̏��q�����E��c���Ƃ������F�B�����āA�N����l�͐��s�ׂɒ^���Ă���B�@�����𗬂���ɂ͉�����p���������ꍞ�݊ݕӂɂ̓w�h���A���L�������B����Ȑ�̎p�`������̐_�Ђ��猩���낵�āA�����u����ځv�ƌ`�e�����B���̐_�Ђɂ͒����������āA�u�������̏��͐����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������̌����`��������B
�@���n�́A������̐������ɑ���̎���i�߂Ă���A���Ƃ͑a���ɂȂ��Ă��܂��B���ɂ͂��̂Ƃ�����Ƃ������Ȃ����邱�Ƃ�m�鉓�n�́A�����ɂ�������������Ă��錙������ł��������Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�~�̍Ղ�̓���O�A��l���_�Ђŏo�����킵���Ƃ��A��킪�w���z���Ɂu�������Ă����ő҂��Ă�v�ƌ������������n�̎��Ɏc�����B
�@���̓��́A�삪�×�����قǂ̂Ђǂ���J�������B�Վq�͎q���Ɋ�Q������Ȃ��悤�ɂƉƏo���Ă��܂��B�����m�������́A�ޏ���ǂ��ċ������悤�ɉƂ��яo���Ă������B���n�͂���ȉJ������͗��Ȃ��Əo�����悤�Ƃ͂��Ȃ������B
�@�Վq��T���Đ_�Ђɍs�������́A�J���ɂ������ސ��ɏo��A�~�]�����������ꂸ�ɔƂ��Ă��܂��B�����m������E�m�q�͕��̕��ɋ`����Ԃ����ݎE���B�����A�_�Ђɂ����m�q���x�@���A�s�����Ƃ��A�ޏ��͒��������Ȃ������B
�@9���A�ʉ�����ꂽ���n�͍S�u���ŕ�ɉ�����B�����b���������ƁA�ʂ�ۂɉ��n���u�������ꂷ�����A�Ȃ��H�v�Ɛu�����A��́u�Ȃ�����Ȃ��v�Ɠ�����B�����p�i�͍S�u�����o���Ă����̂��낤�A�Ɖ��n�͎v�����B
�@�ȏオ���炷���ł���B�Ƃɂ����h���h���Ȃ̂ł���B���̌i�F����̎p���L�������Ƃ��̏������̊ւ�����l���̓��̒����B�`���Łu�C�����̈����v�ƌ������̂͂����������Ƃ��B�Ƃ��낪�A�nj㊴���Ȃ����u�₩�Ȃ̂��B����͈�̂ǂ����痈��̂��H
���͓I�ȏ�����
�@�ςȐ��Ȃ����Ȃ炸�҂̕��Ƃ��̌����������ƂɔY�ޑ��q������B���ɔ��C�������j�������B�Ƃ��낪�A��l����芪�����������̗������U�镑���Ɉ�{�̋��ʂ��Ă���B���ꂪ���̏����əz�Ƃ����Ȃ܂���^���Ă���̂��B
�@�܂��́A�Վq����B�ޏ��͐e���̈������������n�Ɂu�ǂꂾ������Ȃ��Ƃ����낤���A�����̐e�̂��ƁA�����Č����́A�悭�Ȃ���v�Ɨ@���B�l�̓�������Ă���B
�@���ɐ��B�J�Ȃ̂ɐ_�Ђɍs�������Ƃ��߂鉓�n�Ɂu�����A�҂��������Č��������v�ƋB�R�Ƃ��Č��������肪�A�u���ĂȂ��B���߂����Ƃ͂Ȃɂ������Ă����̂ł���B�����āA�u�E���v�ƌ����ďo�Ă䂭�m�q�̂��Ƃ�ǂ����Ƃ������n�Ɂu�E���Ă����Ȃ�N�ł�������v�ƌ������B����ɂ̓L�b�p���Ƃ������݂�����B
�@�����͕�E�m�q����ł���B�ߏ��ŕv���ʂ̏��ƕ�炵�Ă��Ă��u����������Ȃ��Ȃ�������v�Ƌ����Ă���B���̌�{�l�Ƃ����ǂ��ߏ��Â����������Ă���B���Ǝq���V�ނ�ŗ������Θ�������Ă��B�M�S�[�������_�Ђɂ��Q�肷��B�܂�Ńw�h���ɍ炢���ω��l���B
�@����Ȑm�q���A���q�̗��l��Ƃ����v���E���̂ł���B�����O�������̂Ɏ��Ƃ������ق�^�����̂ł���B��Ƃ��ď��Ƃ��āB���i�͗D�������A�s���͒f���ċ����Ȃ��B���̎p������i�̐��_�����C�������̂ɂ��Ă���B�u��O�I�w�̋��v�ł����������A�c�����̍�i�ɂ͂�����ւ̃I�}�[�W��������B
�@�m�q����́A�E�������������ۂǂ���_�Ђɂ��Q�肵�A�����Ōx�@�ɕ߂܂�B�����āA�ޏ��͒�������炸�ɘA�s����Ă������B
���������Ȃ�������
�@�オ���Ă���͂��̐m�q���u���������Ȃ������v�B���̃G�s�\�[�h���G�킾�B�����Ă����b�Ƃ������X�g�V�[���̗]�C�Ɏ����B
�@�I�l�ψ����R�c�r�����͂���ɂ��āA�u�ł��A�Ō�̈�s�͂ǂ��Ȃ낤�B���q�̂��O�ɂȂ����p�i�̐S�z�������؍����͂˂��I�i�����̂��ꂳ����ق��Ă݂܂����j�v�ƕ]���Ă���B�Ȃ�Ɛ�ǂ݂ɂ��ĉ��i�Ȍ����l���낤�B
�@�m�q�����������Ȃ������̂́A�u�j���E�����̂�"���Ƃ��Ă�"�l���������v�Ƃ����ӎv�\���Ȃ̂ł���B����O�i�Łu���̒j�́A���肪�����Ƃ������������������v�Ƃ����䎌������B������A�m�q����́A�E�����Ƃ��ɂ́u�����Ƃ������v�łȂ���Ȃ�Ȃ������̂��B
�@���̂Ƃ����̂��̂��{���ɗ��Ă�����������Ȃ����A���Ă��Ȃ�������������Ȃ��B����͔���Ȃ��B���͗��Ă��Ȃ������ƍl����B�w�l�ȓI�m�����Ȃ��̂Ŕ��R�Ƃ��Ȃ����A��U�~�܂������̂�����������Ă悭���邱�ƂȂ̂��낤���H �܂��A����͒u���Ă����Ƃ��āA�厖�Ȃ��Ƃ́A�u�m�q����͒��������Ȃ������ł��肽�������B���̒j���E���������͏��łȂ���Ȃ�Ȃ������B�����ē����ɁA���l�ɂ�������������������v�Ƃ������Ƃł���B
�@������������l���u�������m�q����A��܂�����������A�܂��n�܂�����v�Ǝv���̂��A������������n���u�����p�i����������Ă�낤�v�Ǝv���̂����R�̗��ꂾ�B�����m�q����́A���ہu�Ȃ�����Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���̖{�l�Ƒ��q�Ƒ��l�e�X�Ⴄ�S���̂���悤���A�ŏI�ǖʂ����������]�C�Ŗ������̂ł���B���̎d�|�������A�c���T��̐^�����ł���A�ΎG�ȕ�����|�p�ɏ������Ă���Ǝ��͌���B
�@�R�c�r�����͂����̂Ƃ��낪�����Ă��Ȃ��Ǝv���B�ł́A���̐R���ψ��͂ǂ�ȃR�����g���o���Ă���̂��B
�@����玟�� �u����܍�Ɣ�ׂĂ������ʒu���߂鏬���ł���v
�@����m�q�� �u����ӂꂽ���A�V�N�ȗ͂œǂݎ����������̂́A���e�ł͂Ȃ��A�ޏ������̐����͂��ӂ���ƁA����ꂽ��ƁA�`��Ȃ̂��v
�@���c��F�� �u�j�̖\�͐��Ɍ������������o��l�����������͓I�������v
�@�{�{�P�� �u17�˂̏��N�̉��҂��ւ̟T�������{��̃}�O�}�̈˂��ė��鍪�������Ƌ�̓I�ɂ��Ȃ���A�̐S�ȂƂ��납�獘�������Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��̂��v
�@�Ō�͖����Ό��T���Y�ł���B
�@�u�Е��Ő��������҂Ƃ��āA���̐��A�̂��߂ɂ����w�̎h�������Ȃ�Ɋ��p���Ă������肾���A����̊H��܂Ƃ����V�l�̓o����Ɋւ��d���Ɋ��҂��A���̎���������������悤�ȐV�������w�̌��o�̂����炷��ɂɊ��҂������Ă����B�����Ă��̊��҂͂��Ȃ���ŗ��̒Ⴂ�o�b�^�[�ւ̊��҂̂��Ƃ��قƂ�Ǖ��邱�Ƃ͂Ȃ������B�����Ďc�O�Ȃ��獡��̑I�l���}�ł̗���̈���o�Ȃ��B���낤���Ẳߔ��œ��I�Ƃ͂Ȃ����c���T�펁�́u���v���A���Ԃ��Ȃ��ꖖ�̐����ŗ��s�����w���������~�x�̃V���[�̂悤�Ɏ����玟����ł����Ȃ��o������������i���B�ǂݕ��Ƃ��Ă͓ǂ݂₷���������v�i�u���Y�t�H�v2012�N3�������j
�@���ꂾ���̂��Ƃ������Ă̂���Ό��T���Y�Ƃ͉ʂ����Ăǂ�ȍ�ƂȂ̂��B����A���̂������ނ̊H���܍�u���z�̋G�߁v����T���Ă݂����B
2012.03.01 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�|�g�X���C���̏M�vVS�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v
�@�ߓ��A��146��H��܂̑��掮���������B���ڂ̓c���T�펁�̈��A�́A�������ꌾ�u�ǂ������肪�Ƃ��������܂����v�������B5�x�ڂɂ��Ă̎�܁`�Ռ��̉�`�}�X�R�~���M�`�\��E���`����20�����̃q�b�g�Ƃ������A������1�����̊ԂɋN��������ł���B����܂Ŋ���̏܂͊l���Ă͂��Ă��A���ړx�͌��ƃX�b�|���B�܋���100���~�ŁA20�����̈�ł�2000���~���B�S�z���������ꂳ��Ɂu���肪�Ƃ��v�A�����ł��ꂽ�}�X�R�~�Ɂu���肪�Ƃ��v�A�����Ă��ꂽ�ǎ҂Ɂu���肪�Ƃ��v�ł���B�@���͓c�����Ɂu���肪�Ƃ��v���B���A���܂ŁA����1�����ŁA�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�A�u��O�I�w�̋��v�A�u���v�A�Ñ��L�v�q�u�|�g�X���C���̏M�v�A�����^���q�u�����Ƃ�v�A�~�铃�u�����t�̒��v�A�Ό��T���Y�u���z�̋G�߁v��ǂݏグ���B���X�Ǐ��Ƃł͂Ȃ�����A����ł����X�̉����Ȃ̂��B�ǂ��R�H ��͂�c�����̉�ł���B���̐Ό��T���Y�ɑ���ނ��o���̓G�ӁB��̂����ɂ͂Ȃɂ�����̂����u�N�����m�v�I�ɉ𖾂������Ǝv��������ł���B
 �@�����ŁA������u�|�g�X���C���̏M�v�ł���B���̍�i��2008�N��������140��H���܍�B���̎��̌���i�̈���u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�A�c����3�x�ڂ̒��킾�����B�ʂ����āA���ʂ͏����������̂��A����Ƃ��H ����͒Ñ��L�v�q�u�|�g�X���C���̏M�v��ǂݍ��݁A���؍ς݂��u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�ƑΏƂ����Ă݂����B
�@�����ŁA������u�|�g�X���C���̏M�v�ł���B���̍�i��2008�N��������140��H���܍�B���̎��̌���i�̈���u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�A�c����3�x�ڂ̒��킾�����B�ʂ����āA���ʂ͏����������̂��A����Ƃ��H ����͒Ñ��L�v�q�u�|�g�X���C���̏M�v��ǂݍ��݁A���؍ς݂��u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�ƑΏƂ����Ă݂����B�@�u�|�g�X���C���̏M�v�̎�l���́A��͌_��Ј��A���Ƃ͓�̃A���o�C�g�̊|�����Ő��v�𗧂Ă�29�̏����B��������C���̐E��̌f���Ɂu163���~�Ő��E����N���[�W���O�v�Ƃ����|�X�^�[�����āA���S����E�E�E�u���傤�ǂ����̈�N���̋����ƈꏏ�B���̓�̃A���o�C�g�Ő��v�𗧂āA�����̋����͂��ׂĒ����B��ɂ����ʒ���163���~�ɒB������A���E����̗��ɏo�悤�v�ƁB�����āA���̈�N�Ԃ̔ޏ��̐����Ǝv�����`�����B��ׂ��Ȃ����ɒW�X�ƁB�܂��A���ꂾ���̘b�B�������������ʔ����̂�����Ȃ��B������ɁA���ʂ͊H��܂��B���́u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�������u���āB�ȉ��A�I�l�ψ��̕]�ɉ����āu�_�l�E�E�E�v�Ƃ��Δ䂵�Ȃ��炱�̉������l���Ă݂悤�B
�@�܂����{�{�P���B�Ñ��L�v�q�u�|�g�X���C���̏M�v�ɂ��ẮA�u��d�|���ł͂Ȃ����������ɁA�@���̂��˂�����ʂ����r�̗��ɂ́A�܂��O�\�̍�҂��������鐢�E�̖L������������������Ȃ��B�t�H�ɕx�ލ˔\���Ǝv���v�ƃx�^�J�߂ł���B����A�c���T��u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v���u���ɂ́A���̏����ɂ�����w�_�l�x�Ȃ���̂̑��݂��ǂ��ɂ����o�����Ƃ��ł��Ȃ������B��i�̒��ɂ͂�������̍ޗ���p�ӂ������A�����͕ʁX�̂��̂Ƃ��Ă�T���ꂽ�����ŁA�Z�����ĉ��w�������N�����Ȃ��܂I����Ă��܂����Ƃ�����ۂł���v�ƕ]���Ă���B
�@�u�_�l�v����������Ȃ��Ƃ͂ǂ��ɖڂ����Ă���������̂��I ���{�V���[�Y�Łu�_�l�v�Ƃ����Έ���a�v�A������{�̏펯�B���́u�_�l�v�������N�Ƃ��Ȃ��Ă�������Ղ��N�����N�ɋN�������u�킪�Ƃ̗��j�v��Δ䂵�đ��q�Ɍ���ĕ�������ݒ�̖ʔ������A�킩���Ă��������Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B �����ƂƂ��Ă̋{�{���ɂ́A���āu�h�i�E�̗��l�v�Ŋ����������̂����A�c�O�ł���B�u�|�g�X���C���E�E�E�v�ɂ��Ă͂܂Ƃ߂Č�قǁB
�@����m�q���́A�u�w�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�x�ɂ��܂Ƃ��A���o�����X�ȋC�����̈������A�Ō�܂ŋC�ɂȂ����v�ƌ����Ȃ���u�E�E�E�E�E����炪�A�K�т����i�̂悤�Ɉ��g�ݍ��킳���Ă䂭�ߒ����A���|�����v���œǂv�ƍŏI�I�ɂ͍m�肵�Ă���B�����āA�u�Ñ�����͂��ꂩ��ǂ�ǂ��Ă䂭���낤�B����͊ԈႢ�Ȃ����Ƃł��邵�A��ԑ厖�Ȃ��Ƃł���v�ƁA�Ñ����ɑ��ẮA�f���C�Ȃ����ܒ~������B���̕��͑I�l�ψ��̒��ŏ�Ɉ�ԃ}�g�����Ǝv���B
�@�R�c�r�����́u�_�l�E�E�E�v�ɑ��āA�u�h���}�e�B�b�N�Ȏd�|�����߂��đ厸�s���Ă���B�������A�h�A�̌������Ɏ��͑��q�����Ȃ������Ƃ�����听���������悤�ȋC������v�ƁA�Ƃ�悪��������ĉx�ɓ���B�����̃p�^�[�����B�u�h�A�̌������ɂ��Ȃ����q�ɘb���v�Ƃ����V�`���G�[�V�������Ȃ��听���Ȃ̂��A�}�l�̎��ɂ̓T�b�p������Ȃ��B���̕��u���v�ł��������Ȃ��Ƃ������Ă���B���A����ɂ��Ă͎���ŁB
�@���O�����B�u�_�l�E�E�E�v�ŁA�u���e���A�쒆�̐l�B�͐H�ׂȂ������B�����̂ĂĂ��܂����B���͂����ŁA��҂̖��p����A�͂���Ă��܂��܂����v�ƁB�͂����̂͏���ł����A�����Ⴕ�ēe�͂Ȃ��ł���B�l�ԕ��ʓe�͐H�ׂ܂���B�Ȃ��A�i���j��H�ׂȂ������̂��H ����͖싅�̐_�l�ɑ��鐶�т̋V����������ł���B�c������A���������l����Ŕ���ł��傤�B������߂��ɁA�悭�撣���Ă���܂����B
�@���̕��u�|�g�X���C���E�E�E�v�ɑ��ẮA�u�ǂ�Ȃ��Ƃ��������Ƃ��������A���܂������Ō�܂ŋl�߂čl���A�����\���Ă���v�ƕ]�����Ă���B������A�S�����̂������Ă��Ȃ��ƌ��킴������Ȃ��B���́A�t�ɁA�Ñ����͕�����B���Ȃ܂ܕ��u���ĕ��C�Ȑl���Ǝv�����B�ł͂��̏؋����B
�@�F�l�̓X�Ńo�C�g���Ă̋A�蓹�A���]�Ԃɏ�邪�u���[�L���������ɖ����炪���]�|����V�[��������B���̂��ƂŁu�C�O�N���[�W���O�v�ւ̃X�C�b�`������Ƃ������Ȃ�d�v�ȏ�ʂȂ̂����A�����̕`�ʁE�E�E�E�E�u�Ȃɂ���B�Ȃ�Ȃ�B���ɑ����r���Ȃ��Ă����B�K���[�W�Ŏԗւ̗l�q������ƁA�u���[�L�����������Ƀ^�C���̓����ɖ��C�����邱�Ƃɂ���Ă��̓����𐧌䂷��A�p�b�h�̂悤�ȕ��i���Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩�����B���������A���V�J�̓X�ɂ���ԂɁA�N������������œ������̂��낤�v�B�����ɂ�2�̖��_�����݂���B
�@�m���1�n ���]�ԂŁA�p�b�h�Ńu���[�L���|����̂͑O�ւ����B���ꂪ���܂�Ă��A��ւɉ��炩�̍H���ׂ���Ȃ�����u���[�L�͐�Ɍ����B
�@�m���2�n ���̏ꍇ�A�����Ȃ������̂������ւɂ��H���ׂ��ꂽ�͂��B�����܂ł��̂͂�قǂ̂��ƁA���݂Ƃ������́B�Ȃ�A���̌��͂��Ƃɂ���������͂��Ɠ��̕Ћ��ɓ���Ă������A�Ȃɂ��N���₵�Ȃ����A�������Ȃ��B����A����ς肽���̂������炾�����B�Ƃ���m���1�n�Ɩ�������B���ɞB���B����Łu���܂������A�Ō�܂ŋl�߂čl���Ă���v���Č�����ł��傤���H
�@�r�V�Ď����́A�u�|�g�X���C���E�E�v���u�I�k�ȍ�i�v�ƕ]�������ʂ����Ă������낤���B�m���ɂ��̎�̋N���ɖR�����W�X�Ƃ��������"�I�k"�łȂ��Ă͐��藧���Ȃ��B�ق��ɑi����v�f�����Ȃ�����B���y�ł����N���]���ʼn����x�[�g�[���F���ł͂Ȃ��A�G��I�ȃ����F���̍�i�ɋ߂��Ǝv���B�����Ŏg���镔�i�͐��k�ɑg�ݍ��킳��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��_�̞B�������Ȃ��B�Ƃ��낪���̍�i�͊Â��B�ו��Ń^�K���ɂ�ł���B�O�i�����ɂ��ꂾ���A���̑��ɂ��U�������̂ŁA�Ō�ɂ܂Ƃ߂Ēʂ��ԍ��ŋL���B
�@�m���3�n ���Ă���F�l�̖������Ă̕`�ʁB�u�فX�ƍg��������ł���b�ނ����Ă���ƁA����ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă���B���������Ƃ��܂����Ƃ�����Ȃ��̂ŁA�����������܂������Ȃ��̂��낤�v�B
�@�ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă���̂͂������ł���B���̔N���̎q�͂���Ȃ��Ƃ͂߂�ǂ��������Č���Ȃ������̂��ƁB���ꂩ�A�܂���l���Ɠ����ł��Ȃ�������������Ȃ������B�܂��A�ǂ��ł��������B
�@�m���4�n ��ЋA��A�����ƈꏏ�̃o�X�̒��ŊP�����݈ӎ��������B�C��������Ƃɂ����B�u���c����ɕ��S���Ă�������^�N�V�[��͂ǂ��Ȃ�̂��B�Ԃ��Ȃ���B����ȗ]�v�Ȃ����Ȃ����ǁB��������Ő��E����͖������낤�B�ė������炢�ɂ͒��܂邩������Ȃ����ǁA����͂���ŕ������݂������B1�N�Œ��߂�ƌ��߂Ă����̂Ɂv�B ��匈�S���Ċ撣���Ă邱�Ƃ�����ȍ��ׂȂ��ƂŒ��߂��Ⴄ��ł����B�^�N�V�[����Ă�����Ȃ́B2�����x��Œ��܂��Ȃ�A�o����x�点�čs����������Ȃ��ł����B���A���������̍D������Ȃ��B
�@�m���5�n ���̂��Ɖ�Ђ�9���ԋx�ނ̂����A�M������قǂȂ��P�����������B�v����ɂ����̕��ׁB�����9���Ԃ��x�݂܂����˂��B���a�Ĕ��݂����Șb�Ȃ番���邯�ǁA�����̕��ׂȂ�撣���ďo����ł��傤�A����قǁu���E����v�ɖ����������̂�����B����ł��A���ʁA��Ђ̋Ɛт��ǂ��ă{�[�i�X���o�āA�u��N��163���~�v�͒��܂�̂ł����E�E�E�B�������̋C���Ȃ��Ȃ�����Ă邩��s���Ȃ��Ƃ��������B
�@�����ł��ꐶ�����ł��Ȃ������̂��B �ŏ����炽���Ȃ�ƂȂ��������̂��B����Ȃ��������ȋC�����ň�������Ȃ��ł���������A�ɂ���Ȃ�����B
�@�\����Ȃ����ǁA���̏����A���ɂƂ��Ă͂����̃X�J���B�����ɂ����鎄�̕]����́A�o��l���̖��́A�؏����̖ʔ����A�\���̎|����3�ł���B���쎁���u�Ñ����͊ԈႢ�Ȃ��ǂ�ǂ��Ă䂭���낤�v�Ǝw�E�����Ƃ���A���ɑ����̍�i�����ݏo����Ă���悤�����A���͓ǂ܂Ȃ��B�u�|�g�X���C���̏M�v���A���̃c�{�ɁA3�|�C���g������q�b�g���Ȃ���������ł���B��144���܍�u�����Ƃ�v�́A�ޏ���������Ⴂ�����^���q���̍�i�����A������͑f���炵�������B�u���v�Ƃ������̂��A�Ȋw���𐏏��ɎU��߂����L���ɑ������G��ł���B���͂����܂��g�ݗ��Ă����R�B����Ȃ�킩��̂����A�{�{�����u�t�H�ɕx�ލ˔\�v�ƕ]�����̂͑S�������ė����ɋꂵ�ށB�I�l�ψ��̊F�l�A�����E�_�E�_�Ɨ���ɔC���ĕ�炷�����̂��̎�l���̂ǂ��ɋ����ł���̂ł����H���̞B���ł��������ȏ��������܂����̑㕨�̂ǂ�����܂ɒl����̂ł����H�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v��������Ȃ�čl�����Ȃ������Ȃ��B�c������������ƃK�b�N�������ł��傤�ˁB�u�Ȃ�ł���Ȃ��̂Ɂv���āB�ł����̓G���C�I���̂��ƒj�͖ق��ăg���C�A��x�܂ł��B ����͐��Ɏ�܂����u���v�ɂ��āB
2012.02.20 (��) �T��Łu�����̋L�v
 �@�O��̂肠�����u�����t�̒��v�̉��߂ŁA��ςȊԈႢ�ɋC�Â��܂����B1��17���̓c������̋L�҉���ă`�F�b�N���悤�ƃl�b�g�����Ă�����AYou-Tube�́u��146��H���ҋL�҉�����p�v�i�j�R�j�R����j�Ƃ����̂ɂԂ���܂����B���Ԃɂ��ĂȂ��3���Ԕ��B�܂��A�ɂԂ����������Ǝv���Č��Ă���ƁA������I���T��Y����Ƃ��������A��ܗ\�z�̒��Łu�����t�̒��v�̉�������X�Ƃ���Ă���킯�ł��B���̕��̖{���������̂ł��ˁB�u�R�C�c�͖ʔ����B���̓ǂ݂ƈ�v���邩�ȁv�Ȃ�Ē��C�ɍ\���Č��Ă������̊�́A�݂�݂���߂Ă䂫�܂����B�u�҂Ă�A������������A���̂́H �������̕����S�R���肪�����I�v��������̉��߃~�X�ƔF�߂�܂ł������Ԃ͊|����܂���ł����B�|�C���g�ɂ���2�_�A�u�킽���v�Ƃ�������̓����A.A.�G�C�u�����X���j�E���Ō���邱�Ƃɂ��Ăł��B
�@�O��̂肠�����u�����t�̒��v�̉��߂ŁA��ςȊԈႢ�ɋC�Â��܂����B1��17���̓c������̋L�҉���ă`�F�b�N���悤�ƃl�b�g�����Ă�����AYou-Tube�́u��146��H���ҋL�҉�����p�v�i�j�R�j�R����j�Ƃ����̂ɂԂ���܂����B���Ԃɂ��ĂȂ��3���Ԕ��B�܂��A�ɂԂ����������Ǝv���Č��Ă���ƁA������I���T��Y����Ƃ��������A��ܗ\�z�̒��Łu�����t�̒��v�̉�������X�Ƃ���Ă���킯�ł��B���̕��̖{���������̂ł��ˁB�u�R�C�c�͖ʔ����B���̓ǂ݂ƈ�v���邩�ȁv�Ȃ�Ē��C�ɍ\���Č��Ă������̊�́A�݂�݂���߂Ă䂫�܂����B�u�҂Ă�A������������A���̂́H �������̕����S�R���肪�����I�v��������̉��߃~�X�ƔF�߂�܂ł������Ԃ͊|����܂���ł����B�|�C���g�ɂ���2�_�A�u�킽���v�Ƃ�������̓����A.A.�G�C�u�����X���j�E���Ō���邱�Ƃɂ��Ăł��B�@����́A�f���Ɏ��̊ԈႢ��F�߁A���߂���������Ă��������܂��B
�m�Ԉ�������߂��������n
�i�P�j�u�킽���v�Ƃ�������̓���
�@ �m�ŏ��̉��߁n
�@�@�@�@�m�T�n�F�K�F�K
�@�@�@�@�m�U�n�j�́u�킽���v�i�|��ҁj
�@�@�@�@�m�V�n���́u�킽���v
�@�@�@�@�m�W�n�m�U�n�Ɠ���
�@�@�@�@�m�X�n�m�V�n�Ɠ���
�m���������߁n
�@�@�@�@�m�T�n�F�K�F�K
�@�@�@�@�m�U�n�j�́u�킽���v�i�|��ҁj
�@�@�@�@�m�V�n�F�K�F�K>
�@�@�@�@�m�W�n�m�U�n�Ɠ���
�@�@�@�@�m�X�n�F�K�F�K
�@���̃~�X�̌����͗F�K�F�K��j�ƌ��߂Ă��܂������Ƃł��B�悭�ǂ߂m�V�n�ŁA�t�F�Y�Ɍ���鏗�́u�����A���r�A��ł́A�t�����X��ł́A�X�y�C����ł́A�^�V�����q�[�g��ł́A�^�X�[�X�B�b�c��ł́A�^�A���t�B�[�g��ł́A�A���r�A��E�����b�R�����ł́E�E�E�E�E�v�Ȃǂƌ����Ă���̂�����A����͌���w�҈ȊO�̉��҂ł��Ȃ��ƋC�Â��˂Ȃ�Ȃ��B�F�K�F�K�͏��ł����ƑM���Έꔭ�����������̂ɁI �����ł������I
�i�Q�jA.A.�G�C�u�����X�́m�j�E���n���ɂ���
�@�m�T�n�ŁA�F�K�F�K�́A�����|�V�A�g���Ԃ̔�s�@�̒��ŁA�ׂ荇�킹���j�EA.A.�G�C�u�����X���t�B���O���[�̒����ԂŒ��z��߂܂���̂�����B
�@�m�V�n�ŁA�u�킽���v�́A�V�A�g���|�����Ԃ̔�s�@�̒��ŁA��l�������̂����̈�l���K�^��߂܂���Ƃ����Ď��o�����t�B���O���[�̒��̂�Ԃ�ڌ�����B
�m�ŏ��̉��߁n
�x���ꂽ�̂͂��̕����̕`�ʂł����B�������Ƃ����Ă���̂Ɂm�T�n�ł͒j�EA.A.�G�C�u�����X�ł���m�V�n�ł͏��ł���B�m�V�n�̏���A.A.�G�C�u�����X�Ƃ͌����Ă��Ȃ����A�m�U�n�ŁuA.A.�G�C�u�����X�͎q�{���������Ă���v�Ƃ��邩��A�����������Ă���B������ɂ��Ă��j�ŏ��H ���������ȂƂ͎v���A�����|�V�A�g�����t�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�Â����������ɁA����A.A.�G�C�u�����X�����ɒj�A���ɏ��ɂ����l�ԂƏ���Ɏv������ł��܂����B�悭�l�������Ȑl�ԂȂ�Ă���͂����Ȃ��̂ɁB
�m���������߁n
�F�K�F�K�́m�V�n�Ŏ��̌������܂��A�m�T�n�̒��ɓ����V�`���G�[�V���������A�����u�L�̉��œǂނɌ���v���������B
�@�m�V�n�́u�킽���v���F�K�F�K�Ɠ���ł���A�u�����Ŏ��ۂɏo������������f���ɂ��A�j���������������������v�Ƃ������ꂪ�����Ȃ��ł���̂ł��B�m�T�n�͏����Ȃ̂�����A���Ԃ̗���́m�V�n���m�T�n�ł���͂��A���̓�����O�̂��ƂɋC�����Ă���B �������I
�m�����̋L�n
���́A�F�K�F�K�͒j�ł���Ƃ�������ϔO���甲���o�����A��������̂Ƃ���Łu�����v�����߂܂���ł����B�܂��A��҂̎T�����I����㩁i�Ⴆ�m�T�n�Ɓm�V�n�ɂ����鎞�n����s�@�̏㉺����j�Ə��j�ɛƂ��āu�C���v�̃`�����X���킵�Ă��܂��܂����B
�@����͂܂��ɕ��w�ɑ��鎄�̖��n���ȊO�̉����ł�����܂���B���O���Ȃ߂���A�J���I
�@�u�����t�̒��v���A���̒��x�̗��������Ɂu�����x���Ⴂ�܂�Ȃ���i�v�ƒf�������Ƃ͎��̕s���̒v���Ƃ���ł���A��҉~�铃���ɐ[�����l�ѐ\���グ�܂��B�Ƃ͂����A���������߂�����Ƃ����āA��{�I�ȕ]���ɑ傫�ȍ��ق��������킯�ł͂���܂���B�u�����x���Ⴂ�v�Ɓu�܂�Ȃ��v�͋ނ�œP�A����Ɂu�D���ȍ�i�ł͂Ȃ��v�ƌ������������Ă��������A���l�тƂ����Ă��������܂��B
�@���ɁA�I�l�ψ��̊F�l�ցB���ɐ��O�����ւ́u�m�T�n�́u�킽���v���m�U�n�m�W�n�́w�킽���x�ƍ������Ă���B����Ȃ���2��ʓǂ���ΊȒP�ɉ𖾂ł���̂ɁA�I�l�ψ��̐搶�Ƃ����낤���X���Ȃ��ł��Ȃ��̂ł��傤�v�Ƃ̕s���Ȍ����悤�ɂ��܂��ẮA�Ђꕚ���ēP���Ă��������܂��B��㎁�́u����3�l�قǂ͓����w�킽���x�ɂ�������v�Ƃ����ǂ݂̂ق����A�܂������ɋ߂������̂ł�����B�Ƃ͂����A���Ƃ̕��X�ɑ��Ă͓��ɍۗ����Ē�������K�v�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
 ���������āA�u�����L����āA���̂��͂߂Ȃ��܂܂��グ��������I�l�ψ��v�Ƃ������̊��z�͕ς��܂���B
���������āA�u�����L����āA���̂��͂߂Ȃ��܂܂��グ��������I�l�ψ��v�Ƃ������̊��z�͕ς��܂���B�@����ɂ��Ă��A�ݖ�ɂ͐����l��������̂ł��B�I���T��Y���������ł����A�l�b�g������A�u�����t�̒��E�U���K�C�h�v�Ȃ���̂܂ł���B����������A���̍�i�̓��V�A�̍��������ƃE���W�[�~���E�i�{�R�t�i1899�|1977�j��y��Ƃ��Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂��B�����t�́u���v�̃��f���ʐ^�܂ōڂ��Ă���B���̃K�C�h���������l�Ƃ��A�i�{�R�t�̖|��ҏ���[�`���Ƃ��A�ނ�͂��̏����̃J���N���͂��ׂĂ����ʂ��Ȃ킯�ł��B���̕��������A�������O��́u�N�����m�v��ǂƂ�����A�ꔭ�Ńy�P�A���O�A���ƂƂ����₪��A�ł���܂��B����́A�����Ō��ߕt���邱�Ƃ̕|����͂�����[���v���m�炳�ꂽ�ꖋ�ł����B
2012.02.15 (��) �ً}�Ք��I������̊H��܍�i���l����
 �@����͓c���T�펁�̎�܍�u���v�����グ��\��ł������A2�^10���肵���u���Y�t�H�v3�����Ɍf�ڂ̂�����̎�܍�E�~�铃�u�����t�̒��v��ǂ�A���\�ʔ����������A�I�l�ψ��̌˘f�����X�ɖʔ��������̂ŁA�}篂�����J�b�g�E�C�����邱�Ƃɂ��܂����B
�@����͓c���T�펁�̎�܍�u���v�����グ��\��ł������A2�^10���肵���u���Y�t�H�v3�����Ɍf�ڂ̂�����̎�܍�E�~�铃�u�����t�̒��v��ǂ�A���\�ʔ����������A�I�l�ψ��̌˘f�����X�ɖʔ��������̂ŁA�}篂�����J�b�g�E�C�����邱�Ƃɂ��܂����B�@�I�l�ψ��̈�l����玟���́A�u�~���i��]�����ꂽ�_�����������ڂ����v�Ɩ���A�u�����������邱�Ǝ��̂�����v�Ɠ����Ă��܂����A����ł͍���킯�ł��B�Ό��T���Y�Ȃ́A�u�o�J�݂����ȍ�i�����肾��v�ƌ����ɔے肵�Ă��܂��B�u���̑������d���悤�ȍ�i�ɂ́A���ڂɂ�����Ȃ������v�Ƃ��B�s�m���t���a�A�u���Ȃ��̍�ƂƂ��Ă̑������āA�d���قǂ̂��̂Ȃ̂ł��傤���v�B�u���R�v��������ʂ܂ܑI�ꂽ�u�����t�̒��v�́A�ʂ����Č��삩�H�܂��������H
�u�����t�̒��v��������
 �@�ŏ��A�T�����ƓǂƂ���ł́A�Ȃɂ����{�֓��荞�Ƃ������A�݂͂ǂ���̂Ȃ����o�����B�m���Ɏ��̒m��Ȃ��P�ꂪ�����Ȣf���B�Ⴆ�A�u�~�X�^�X�v�Ƃ������̏ꏊ�B���̐������Ȃ��̂Œ��ׂ�ƁA�u�Q�[����̉ˋE�C���V�F�i�[�̖��l�s�s�v���������B�������ł����B�܂��A�u�w�����p���e����x�́A���w�҃y�A�m���������ꂾ�v�Ƃ�����������B���������画��Ȃ��̂Œ��ׂ�ƁA�W���[�b�y��y�A�m�i1858�|1932�j�A���w�ҁA���R���̌����n�̍l�ĎҁA�l������u�����p���e����v���l�āA�ȂǂƂ������Ƃ�����B�C���^�[�l�b�g�͎��ɕ֗����B���̂�����͗����ł��Ȃ��ɂ��Ă��ǂ�Ȃ��̂����͂߂����ł����B���͂��̐�ł���B
�@�ŏ��A�T�����ƓǂƂ���ł́A�Ȃɂ����{�֓��荞�Ƃ������A�݂͂ǂ���̂Ȃ����o�����B�m���Ɏ��̒m��Ȃ��P�ꂪ�����Ȣf���B�Ⴆ�A�u�~�X�^�X�v�Ƃ������̏ꏊ�B���̐������Ȃ��̂Œ��ׂ�ƁA�u�Q�[����̉ˋE�C���V�F�i�[�̖��l�s�s�v���������B�������ł����B�܂��A�u�w�����p���e����x�́A���w�҃y�A�m���������ꂾ�v�Ƃ�����������B���������画��Ȃ��̂Œ��ׂ�ƁA�W���[�b�y��y�A�m�i1858�|1932�j�A���w�ҁA���R���̌����n�̍l�ĎҁA�l������u�����p���e����v���l�āA�ȂǂƂ������Ƃ�����B�C���^�[�l�b�g�͎��ɕ֗����B���̂�����͗����ł��Ȃ��ɂ��Ă��ǂ�Ȃ��̂����͂߂����ł����B���͂��̐�ł���B�@�u�����t�̒��v��5�̏͂���Ȃ镨��B��ȓo��l���́u�킽���v�ƁuA.A.�G�C�u�����X�v�Ɓu�F�K�F�K�v�Ɓu�V�ڌ����ҁv�ł���B�e�l�̐����͂����������邩��A�ǂ�Ȑl�ԂȂ̂��͔�r�I�ȒP�ɒ͂߂�B�m���Ɋ�ȘA�����肾���A���J���قǂ̂��Ƃ͂Ȃ��B�Ƃ��낪㩂��d�|���Ă���B���ꂪ�����̑��g�ɂȂ��Ă���悤���B
�@��́A�uA.A.�G�C�u�����X�v�͓�l����Ƃ������ƁB�������j�Ə��B�Ȃ��Ȃ�A�m�T�n�Ńn�b�L���Ɓu�j�ł���v�Ə����Ă���̂ɁA�m�U�n�ł͎q�{���������Ă���B�m�X�n�ł́A�u���Ă��̒j�̖��́A�����A�G�C�u�����X���v�ƃn�b�L�������Ă���B��������ƁA������������A���̎��X�Œj�����̂ǂ��炩�ɂȂ鐶�����ƍl����ق������R���Ƃ����C�����Ă���B
�@��ڂ́u�킽���v�Ƃ������肪�e�͂��Ƃɕς�邱�ƁB�����Ȃ�ς��Ō�܂Ő������Ȃ��B������A�����ʼn𖾂��邵���Ȃ��B�m�P�n�ŁA�����|�V�A�g���Ԃ̔�s�@�̒��ŁA�ׂ荇�킹���j�E�G�C�u�����X����F�̕ߒ��ԂŁu���z�v�Ƃ��������̂�̂�ڌ�����u�킽���v�B����́A�F�K�F�K�̖����p���e���ꏬ���u�L�̉��œǂނɌ���v�̑S��Ƃ������������邩��A���́u�킽���v�͗F�K�F�K�̂��ƂŊԈႢ�Ȃ��B�����A�F�K�F�K���u�킽���v�ƌ����ʐl���A������������|��҂́u�킽���v������ɂ��ď����Ă���\�����Ȃ��͂Ȃ��B�����Ȃ̂�����B�m�U�n�́u�킽���v�́A�u�L�̉��œǂނɌ���v�̖|��ҁB�m�V�n�́A�t�F�Y�i�����b�R�̖��{�s�s�j�Ńt�F�Y�h�J���K�����悤�Ƒ؍݂��A���̂��ƁA�V�A�g���|�����Ԃ̔�s�@�̒��ŁA��l�̏����̂����̈�l���K�^��߂܂���Ƃ����Ď��o�����t�B�O���[�̒��̂�Ԃ�ڌ�����u�킽���v�B�m�W�n�ł́A�uA.A.�G�C�u�����X���L�O�فv�ցu�F�K�F�K�Ɋւ��郌�|�[�g�v�����Q�����u�킽���v�B�m�X�n�ŁA���|�[�g��j���������uA.A.�G�C�u�����X���L�O�فv�ɋΖ����鏗�́u�킽���v�ł���B
�@����ɓǂݍ��ނ�5�l�́u�킽���v�̂���2�l������l�Ɣ���B���������āu�킽���v��3�l�B�m�T�n�̗F�K�F�K�A�m�U�n���m�W�n�̒j�́u�킽���v�Ɓm�V�n���m�X�n�̏��́u�킽���v���B�����Ă݂�ΗF�K�F�K�ƒj�́u�킽���v������l���Ƃ����\�����Ȃ��ł͂Ȃ����B�ł��A������[�X]�ŁA���́u�킽���v�������u���Ԃ̒j���c�������e�����̑O�ɍL���Ă���B�F�K�F�K�ł͂Ȃ����̐l���́v�Ƃ����L�q��f���Ɏ�낤�B
�@�������āA���㩂����ɂ߂�Ό������̂͂���قǓ���͂Ȃ��B
�l�u�����t�̒��v
�@�u�����v�ɂ�����O�q�Ƃ͎��ɓ���H�����낤�Ǝv���B�Ⴆ�u���y�v�ɂ�����u�O�q�v�̌ÓT�u4��33�b�v���W������P�[�W�i1912�|1992�j��������̂�1952�N�A60�N�O�̏o�������B�s�A�j�X�g���X�e�[�W�ɏo�Ă��ăs�A�m�̑O�ɍ���B4��33�b�Ԃ����ɂ��ăX�e�[�W���~���B�������ꂾ���̍�i�i�H�j�B����Ȃ��̂ǂ��l���Ă��|�p�Ƃ�����㕨�ł͂Ȃ��̂����A�O�㖢���E����I�ȍ�i�Ƃ��ĉ��y�j��Ɏc���Ă���B�����A����w�ł�낤�Ƃ�����A������433�y�[�W�����u�{�v���낤���B�^�C�g���̓\�m�}�}�u433�Łv�B����Ȃ���N�������H ���ƂقǍ��l�Ɂu���w�v�ɂ�����u�O�q�v���l���̔j��͓���B
�@�~�铃�����ڎw�����̂͐��Ɂu�O�q�v�I�����������낤�B���g�𔒎��ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ�����A���t���g���ēǎ҂����đ̌��������Ƃ̂Ȃ����E�����o�����Ƃ��Ӑ}�����̂��낤�B�����ɂ����ł��Ȃ����̂Ƃ��āB
�@�����Ŏd�|����㩂��A����ŗL�����̓o��l���̒��ɒj�Ə���������������Ƃ������B�u�V���������v�����o�����߂ɁB�X�Ɂu�킽���v�Ƃ���������͂��Ƃɕς��Đݒ肷�邱�Ƃ������B���ꎩ�́A���ɖڐV������@�ł͂Ȃ��������B�������̂͐����Ȃ��ɕς��邱�ƁB����͍��܂ł��܂�Ⴊ�Ȃ��̂ł́A�Ǝv���B�ł��A�ނ͊����Ă��������B�u�V���������v��n�����邽�߂ɁB
�@������ɁA�����̊����x�͎c�O�Ȃ��獂���͂Ȃ��B������s�܂����܂ܕ��u���Ă��邾�����B�S�������āA����ɂ���āu�l���v�̔j��ɐ��������Ƃ��Ă��A���̐�ɂ͉����Ȃ��B����`�������̂����ɂ͉���Ȃ��B��҂���u����Ȃ��̂Ȃ������Ă�������Ȃ��ł����B���߂��̂́A��ƕ��i���̂��̖̂ʔ����ڐV�����Ȃ̂�����v�Ɣ�������邩������Ȃ��B�ł��A����Ȃ��͎̂��ɂƂ��ĉ��̈Ӗ����Ȃ��B�����ƃQ�[����Ԃ̍s�����A�����������玞��̃^�C���J�v�Z���I�����A�����̒��ŁA���ۂ̌������͈�l�ł͂Ȃ����ƁA�����T�O���O�����Ƃ̏d�v���͊m���ɂ��邱�ƁA����Ȃ��Ƃ�\�������������̂��낤���B�܂��I
�@�Ƃ��낪���̍�i�́A��146��H��܂��l�����B����Ȃ܂�Ȃ���i�����́H �����́A8�l�i���㗴�������Ȃ̂��߁j���I�l�ψ����~�鎁�̎d�|����㩂ɂ܂�܂ƛƂ�������ł���B���������Ƃ��v���Ȃ�㩂��𖾂����Ԃ��}���A�܂��A�\�͂Ƃ����̂��������܂����قǂ̔\�͂��玝�����킹�Ȃ����Ƃ�I�悵�āB���͂͂��̏ł���B
�u���Y�t�H�v3�����́u�H��ܑI�]�v��S������
�@ �@�܂��A���N����őI�l�ψ����~�������玟���͂��������B�u��i�̒��ɓ����čs���̂����ɓ����i�������B�������A���̂킩��Ȃ��̐�ɉ���������̂ł͂Ȃ����A�ƍl�������镗���A�I�n�����Ă���̂͊ԈႢ���Ȃ��B���������Ďx������͍̂�����A�S�ے肷��͍̂X�ɓ���A�Ƃ������ɗ��������v�B����͊��S�ɂ���グ�̑́B�킩��Ȃ��Ȃ�]�����Ȃ�������̂ɁA�킩��Ȃ��Ȃ���]�����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă���������B�I�l�ψ��~�͌����Ȍ��f�ł��傤�B
�@���O�����́A�u�ʎq�͊w�v�Ŏ����Ƃ����������ɏo���ĕ]�����Ă���B�H���u���̒��̔L�͐����Ă���Ɠ����Ɏ���ł�����B��̏�Ԃ��d�Ȃ荇�����L������A���ꂪ�܂�ʎq�͊w�I�m�����߁v�B�����āA�u���E�ɂ́A����̌��t�ł͐���������Ȃ����ۂ����݂���v�̂ł��邩��A����������i�������Ă������ƍm�肷��B���ꎩ�̎��͔ے肵�Ȃ��B�����A��������o�������Ⴊ�u��i�v�̂ǂ̕����Ɍĉ����邩�Ƃ�������������������͂��������Ǝv���B�Ⴆ�A�u�G�C�u�����X�̓�ʐ����āA�����������Ƃł́v�I�L�q�B
�@����ɂ���Ȍ��y���B�u�w�����t�̒��x�ɂ͉��l���́w�킽���x�Ƃ������肪�o�ꂵ�܂��B�����́w�킽���x�͈قȂ�l���ł��B����3�l�قǂ͓����w�킽���x�ɂ�������v�B����͐ɂ��������B�u3�l�͓����v�͂�����ƈႤ�B�m�T�n�́u�킽���v���m�U�n�m�W�n�́u�킽���v�ƍ������Ă���B����Ȃ���2��ʓǂ���ΊȒP�ɉ𖾂ł���̂ɁA�I�l�ψ��̐搶�Ƃ����낤���X���Ȃ��ł��Ȃ��̂ł��傤�B�ł����̕��͂܂��}�V�Ȃق��B���̈ψ��͂��̏d�v�|�C���g�ɐG��Ă����Ȃ��B���ꂶ��A�����L����āA���̂��͂߂Ȃ��܂܂��グ������Ă��s�v�c�͂Ȃ����B
�@�����̂Ԏq���́u���S�ł�����A���S�ł��Ȃ����̂ɉ���������ǎ҂����邾�낤���A����͎��ł͂Ȃ��B�ɂ��S�炸�Ō�Ɉ�[�𓊂����̂́A���̌�����x������ψ����A�Ƃ肠�����M�������炾�v�Ƃ��������B����͂����_�O�B�u�����͓��S�ł��Ȃ��������A���̈ψ����x�����邩��A��[�𓊂����v�ł����B �������������͑����~��Ă������������B
�@�R�c�r�����́u���̏����̌������ɒm�I�D��S���h�����鋻���[�����E���L�����Ă���̂��͂�����Ɖ���B����Ȃ̂ɂ��̕��͂Ƀu���b�N����Ă��܂��A����͗e�ՂɌ��J����Ȃ��B�����z��߂���ԁ��������Ɠǎ҂Ɉ����肵�ė~�����v�ƌ����Ă���B�u�����肵�ė~�����v�Ȃ�Ă��������Ȃ��ŁA�u�`�j��w�͂������ł����Ă����������������B��������A�������Ɂu�����[�����E�ȂL�����ĂȂ��v���Ƃ�����܂�����B
�@����m�q���́u�D���オ�����p�b�`���[�N��S�苭�����Ă���ƁA���̗����ɉ������B����Ă���悤�ȋC���ɂȂ��Ă���v�́A���̑O�i�Łu���Ђ��Ȃ����킳��A�ꖇ�̃p�b�`���[�N���D��������A���Ăǂ�Ȗ͗l�������o���Ă������Ɗy���݂Ɍ��߂Ă݂�A�����ɂ͖͗l�Ȃlj�������Ă��Ȃ������v�Ƃ��邩��A�o���オ�������̂�S�苭�����邱�ƂȂǂ����ɖD��������O�ɛ�������㩂̉𖾂�簐i���Ă����������������B��������A���̕��Ȃ猩�����̂ł͂Ȃ����B��x�́u�͗l�Ȃlj�������Ă��Ȃ������v�Ɗj�S�ɔ������̂�����B���u���m�̈����������v�̍�҂ł͂���B
�@�������c��F���B�u���̍�i���̂��̂�����_�ł���v�ƌ����Ă��邪�ǂ����낤���B�m���Ɂu�F�K�F�K�̏������̂́A100�ɔ��錴�����g���Ă���v�Ƃ��u�����p���e����͐��w�҂��l�Ă������̂�����A���w�I�v�f�����邩���m��Ȃ��v�Ƃ�������_�I�L�q�͂���ɂ͂��邪�A����_�������Ƃ��������ł͂Ȃ��Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�u����_�I�L�q�v�ɓ˂��l�߂��[�݂���̐����Ȃ����炾�B�Ⴆ�A���{��I���_�Ƃ��́B�ł��܂��A����͑債�����ł͂Ȃ��B
�@���͂ނ���A�u���������w���߂��x�����}����x�ʂ��Ȃ���A���{���w�ɂ́A�g�ӎG�L�ƃG���^�������c��Ȃ��v�Ƃ������c���̉~�鎁�i��_���낤�B���{���w�̎�ނ́A�z���g�Ɂu�g�ӎG�L�v�Ɓu�G���^���v���������Ȃ��̂ł��傤���B���̌��ߕt���́u��ށv�݂̂�ΏۂƂ��u���@�v�����u���{���w�����\���̓Ǝ����v��Y��Ă���Ǝv���̂ł����A�������ł��傤���B
�@�{�{�P���B�u�ŋ߂̎Ⴂ��Ƃ̊�̒Ⴓ���v���A���Ƃ���͒Ⴍ�Ă��A���̖`���⎎�݂͔���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���A���͎�܂Ɏ^�����鑤�ɉ�����v�B�{�{���́A�肪�Ⴂ�����n�Ƃ����A�u�`���⎎�݁v�Ɉ�[�𓊂����B����́u�`���v�ƌ����������~�鎁�̏������낤���A���Ȃ́A�u�w�`���x�ȂŊH��܂��Ċl�ꂿ�Ⴄ�́v�ƕs�v�c�Ɏv���B
�@�Ό��T���Y���́u�����������t�̈��Ƃ�݂����Ȃł��̈����Q�[���ɕt�����킳���ǎ҂͋C�̓łƂ������Ȃ��B����Ȉ�l�悪��̍�i���ǂ�قǂ̓ǎ҂ɏ����Ȃ�ǂݕ��Ƃ��Ă܂���ʂ邩�͂͂Ȃ͂��^�킵���v�Ǝa��̂Ă�B�����āA�u����ȓz��Ƃ͕t�������Ă����v�Ɠf�����ĂāA�I�l�ψ����~��Ă䂭�B
�@�ł͂����őI�l�ߒ���U��Ԃ��Ă݂悤�B�ŏ��̓��[�Łu���v���ߔ������l��������B���̌���x���̋c�_�̖��u�����t�̒��v�����I�Ƃ������ƂɂȂ����悤���B�I�]���琄�@����ɁA�ŏ�����^�������̂́A���O���A���c��F�A�{�{�P��3���B�����ɍ���玟���ƍ����̂Ԏq���������ߔ����ɒB�����̂��낤�B�ŏ���3�����{����͂�ł���Ƃ͂������A�������2���͕t�a�����B��҂̉~�鎁�ɂ��Ă݂���Ă������ł���B�ނ̖{���𐄑����Ă݂�B
�@�u����͂�A���b�L�[�ł����B��X�̎���ł��B�����āA�I�l�ψ��͒N��l�Ƃ��Ă킩���Ă��Ȃ�������ł�����B��̗v�����{�J���A�o�[�`�����ȒP����g���A����w�I�\���Ŗ��t��������A�v���C�h�̍����I�l�ψ��e�ʂ��A���̎������Ă킩���Ă��Ȃ������Ɍ����Ɉ����������Ă��ꂽ�̂ł��B���f�^�V�A���f�^�V�ł��v
�@���炭����A�}�����Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�u�����t�̒��v�{���ɂ���ȋL�q�����邩��ł���B�u�ؓ����悭�킩��Ȃ����āH �܂��A�������낤�B�킩��悤�ɂł��Ă��Ȃ��̂����瓖�R���B�킽���ɂ����Ă悭�킩��Ȃ��B�킽���ɂ킩��Ȃ��ȏ�A�n��ɂ킩��҂͂��Ȃ��Ǝv�����v����������s�G�ɂ����������Ă���̂��B����Ȋm�M�Ƃ̔y�Ɍ��Ђ���܂�n�����Ⴂ���܂����A�I�l�ψ��̊F�l�I �ł��܂��A��܃C���^�r���[�Łu�����̍�i�́A�����̐l�ɓǂ܂��H��܂ɂ͑���Ȃ��Ǝv���v�ƌ����Ɍ���Ă��邩��A�����͋������Ƃɂ��܂��傤���B�ł��҂Ă�A������܂��Ȏ҂̏Ȃ̂��Ȃ��H
2012.02.10 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��@�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�̖ʔ���
�@�Ȃ��ɂ��炳���؏܂�������Ƃ��ȊO�A���w�܂Ȃ���̂ɊS�����������Ƃ͂Ȃ��������A����̊H���҂ɂ͑傢�ɋ�����������ꂽ�B �@1��17���A�Ռ��̎�܉�B�u4����������Ƃ��ꂽ���Ƃł�����A�����Œf����Ă��̂���V�Ƃ����Η�V�ł����A���͗�V��m��Ȃ��̂ŁE�E�E�B�����f��������ĕ����ċC�̏������I�l�ψ����|�ꂽ��Ȃ�����s�����������܂��̂ŁA�s�m���t���Ɠ����s���e�ʂ̂��߂ɁA������Ƃ��Ă��v�B�ɉ��Ȃ邩�ȓc���T�킳��A���̐Ό��T���Y�ɐ^�����a������s�@��������39�˂Ɋ��т��I
�@1��17���A�Ռ��̎�܉�B�u4����������Ƃ��ꂽ���Ƃł�����A�����Œf����Ă��̂���V�Ƃ����Η�V�ł����A���͗�V��m��Ȃ��̂ŁE�E�E�B�����f��������ĕ����ċC�̏������I�l�ψ����|�ꂽ��Ȃ�����s�����������܂��̂ŁA�s�m���t���Ɠ����s���e�ʂ̂��߂ɁA������Ƃ��Ă��v�B�ɉ��Ȃ邩�ȓc���T�킳��A���̐Ό��T���Y�ɐ^�����a������s�@��������39�˂Ɋ��т��I�@�����A�T���P�C�X�|�[�c�̖����R�����u�Ì��h���v�Ɂu����ȉ�����Ă��܂��ƁA�l�͂ǂ�����M�҂͎�܍��ǂދC�͋N���Ȃ��B�\�����Z�[���X����̂���ƂŁA�����Ƃ��͂��ꂱ�������ɐS���𒍂��̂��낤���A����ׂ�����A�����Ɛ_�o���g��Ȃ��Ƒ�������̂ł͂ƘV�k�S�Ȃ���v���v�Ȃ�R�����g���ڂ����B�������͍̂������Ƃ����L�҂ł���B����ɂ͊J���������ǂ���Ȃ������B�u�V�k�S�Ȃ���v���v�̒����̓}�k�P�����܂��悵�Ƃ��悤�B���z�͌l�̎��R������B���߂����Ȃ��̂́u��܍��ǂދC�͋N���Ȃ��v�̌��ł���B������悤�����܂����A��i��ǂ܂Ȃ��Ƃ́A�V���L�҂Ƃ��Ăǂ��������o�Ȃ̂����b��B������ǂ܂����ď����Ƃ��ǂ��]�����悤�Ƃ����̂��낤�B�����Ă鎖���u�W���[�i���X�g�Ƃ��Ă̒p�N���v�ƋC�Â��ĂȂ��̂��낤���B�u�����Ɛ_�o���g��Ȃ��Ƒ�������v�̂̓A���^����I �T���X�|�Ƃ����Έꗬ�̃X�|�[�c���B�͓̂n�ӖF�q����Ƃ������h�ȋL�҂����܂�������ǂˁi�ޏ��͐V���Ђ����߂āu�k���f�抮�S�K�C�h�v�Ȃ閼�����c���Ă���j�B
�@�����ŁA���́A�c�����̍�i��ǂނ��Ƃɂ����B�u����ȉ������l���ǂ�ȏ����������̂��v�A�W���[�i���X�g�Ȃ炸�Ƃ��������N��������ł���B
 �@�����AAmazon�Ō�������B��146��H���܍�i�u���v��1��27�������ɂ��\���t���Ƃ���B���\�����ƁA���C�Ȃ��ނ̂��̑��̍�i�^�C�g���߂Ă�����A�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�Ƃ����̂ɖڂ��~�܂����B���{�V���[�Y�Ő_�l�Ƃ����A����a�v�������Ȃ��B1958�N�A���̐��S���C�I���Y��Ղ̑�t�]�D���̗����҂ł���B���̒����ΗY���c�̔N�̃V���[�Y�́A���̃X�[�p�[����[�L�[�̊���������ċ��l�����S�ɂ����Ȃ�3�A�������B�u���̓�N�A���S�ɋ�t���r�߂������Ă������l�����ɃV���[�Y�𐧂���̂��I�v�A�R�e�R�e�̋��l�t�@�����������w1�N���̎��͂����L���V�ɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�ł���B��4�퐼�S�̏����A�܂��]�T�B�����A��5��A�w�Z�A��d�C�X�̓X���Ō����A����10�������������T���i���E�z�[�������̏Ռ��I ����ŋ��l��3��2�s�A�É_���������߂�B������A�܂����A�Ɗ������u�Ԃ������B����ȗ\���͓I�������B���̂��Ɛ��S�͈���I��2������ς݂��A���{�V���[�Y�j�㏉��3�A�s4�A���Ƃ�����t�]�D���𐬂��������̂ł���BMVP�́A4�̏���������l�ʼn҂�����������R�̎�܁B���̎����܂ꂽ�̂��u�_�l�E���l�E����l�v�B�������s���܂��������Ȃ�ԈႢ�Ȃ��̃O�����v���������낤�B
�@�����AAmazon�Ō�������B��146��H���܍�i�u���v��1��27�������ɂ��\���t���Ƃ���B���\�����ƁA���C�Ȃ��ނ̂��̑��̍�i�^�C�g���߂Ă�����A�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�Ƃ����̂ɖڂ��~�܂����B���{�V���[�Y�Ő_�l�Ƃ����A����a�v�������Ȃ��B1958�N�A���̐��S���C�I���Y��Ղ̑�t�]�D���̗����҂ł���B���̒����ΗY���c�̔N�̃V���[�Y�́A���̃X�[�p�[����[�L�[�̊���������ċ��l�����S�ɂ����Ȃ�3�A�������B�u���̓�N�A���S�ɋ�t���r�߂������Ă������l�����ɃV���[�Y�𐧂���̂��I�v�A�R�e�R�e�̋��l�t�@�����������w1�N���̎��͂����L���V�ɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�ł���B��4�퐼�S�̏����A�܂��]�T�B�����A��5��A�w�Z�A��d�C�X�̓X���Ō����A����10�������������T���i���E�z�[�������̏Ռ��I ����ŋ��l��3��2�s�A�É_���������߂�B������A�܂����A�Ɗ������u�Ԃ������B����ȗ\���͓I�������B���̂��Ɛ��S�͈���I��2������ς݂��A���{�V���[�Y�j�㏉��3�A�s4�A���Ƃ�����t�]�D���𐬂��������̂ł���BMVP�́A4�̏���������l�ʼn҂�����������R�̎�܁B���̎����܂ꂽ�̂��u�_�l�E���l�E����l�v�B�������s���܂��������Ȃ�ԈႢ�Ȃ��̃O�����v���������낤�B�@�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�́A����Ȏ��ɂƂ��ĖY��悤�ɂ��Y����Ȃ����{�V���[�Y����ނƂȂ��Ă���ɈႢ�Ȃ��B���̃X�|�[�c�Ƃ͉����������̐l���������Ƃ����̂������[�����B���w�����ǔj��������҂ɂ�����ʖʔ����������B
�@���ׂĂ݂�ƁA���̍�i��2008�N�������u�H��܁v�̗��I�삾�����B�Ȃ�A��܍�́u���v�͂����Ɩʔ����͂��H �ۂ����ł����҂����܂�B�Ό��T���Y�́u���݂����ȍ�i�����肾��v����������̊y���݂��B���̑O�ɁA�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v���T�ς��Ă������B
�@ �u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�T�v
�@�u�����A�싅�Ȃ~�߂�v�ƌ����ĕ����Ɉ��������������܂Ƃ������O�̏��w4�N���̑��q���A�h�A�̊O���畃�e����肩����Ƃ��납�畨��͎n�܂�B�u�~�߂�v�ƌ����o�������R�́A6�N���̂����߁B�u���O�͓؎E���̑c������̌��������Ă���v�Ɓu���܂Ȃ�ď��̎q�݂����Ȗ��O���v�Ƃ�����掂������B���̈Ӗ��ɂ��āA�����q�Ɉ�ƎO��̌����ƈ��ʂ�b���ĕ������镨��ł���B�싅�ւ̈،h�̔O�Ƌ��ɁB
�@�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�Ƃ́A1986�N�̃V���[�Y�̂��Ƃ��B���̔N�A�u���v���u������v�͒��w3�N���B���O�́u�ꂳ��v�ƕ����Ղ̉�������搄�i���Ă����B���ڂ́u�ꂳ��v���I�T�~���G���E�x�P�b�g�́u�S�h�[��҂��Ȃ���v�B��{���u�ꂳ��v�̃I���W�i���B�o���҂�3�l�B�S�h�[�i�_�j��҂�l�̍ߐl�Ɂu�ꂳ��v�Ɓu������v���A�S�h�[�̎g�҂Ɂu���܁v�Ƃ������O�̒�1�̏��̎q���������B
�@��l�͑҂B�����Ђ�����S�h�[��҂B�ʂ����ăS�h�[�͌����̂��H �����̌m�Â̗���Ɓu���{�V���[�Y�v�����s���Đi��ł䂭�B
�@�b�͂���28�N�O�A1958�N�ɑk��B���_�u������v�͂܂����܂�Ă��Ȃ�����A����́u������v�̕�e�u��������v���畷�����b���B���̔N�A���O�̑c������A�܂蕃����̕��e�͒��w���B�i�u��������v���u���̒j�v�Ƃ�������Ȃ���������u������v�������ĂԂ��j�u���̒j�v�͉Ƃ��n�R���������獂�Z�i�w����߂��B�i�w�̒f�O�͍D���Ȗ싅�Ƃ̌��ʂ��Ӗ�����B�����싅�ł͎g�����Ƃ̂Ȃ����p�̃o�b�g�Łu���̒j�v�͓��E�����B�u�싅�Ŏg����o�b�g�́A����Ȃ��Ƃɂ������ɗ�����v�Ƃ����C�����������̂��B���S���C�I���Y���ǔ��W���C�A���c��3�A�s�̂���4�A��������Ղ̓��{�V���[�Y�̔N�̏o�����������B�����A"�_�l�̂���"���{�V���[�Y�́B
�@���̌�u���̒j�v�́u��������v�ƌ����B��l�͒j�̎q�����܂�Ă��싅�͂�点�Ȃ��Ɩ��Ă����B�����āA�u������v�����܂ꂽ�B������A�u������v�ɂƂ��Ė싅�͂����̂ł͂Ȃ�������̂������B�����A�u���̒j�v�����x�����o�b�g�̈��������������L���͂��邯��ǁB���̌�A�u���̒j�v�͈����j�����ƕt�������悤�ɂȂ�A�싅�q���Ɏ���o���ĉƂ��o�Ă����Ă��܂����B�o�b�g�������ɒu�����܂܁B
�@�u������v�́A���w�ɓ��鏭���O�A�u��������v����u���̒j�v����Ƃ����S�c�C���ŏ����ꂽ�t����n�����B�u�싅�͂���ĂȂ��̂� ���̃o�b�g�͂܂����邩 ���w�ł͖싅���ɓ���v�Ƃ������ʂ��������A�u�s�K�̌����̖싅�Ȃ�ɂ����v�Ƃ����C�����͕ς��Ȃ������B�����悤�ȕ��ʂ̗t���͓K�x�ȊԊu�œ͂������A�u�Ō�̋@� ���肢�� �싅������Ă���@���߂��Ɋ撣��Ή���������Ă���v�Ƃ�����]�x�������}�ɋ����Ȃ����t�����Ō�ƂȂ����B
�@���炭������������A�Ƃ̂��݃o�P�c�̒�ɁA���������́u�t���v���������B�u�Ȃ�Ŗ싅����낤�Ƃ��Ȃ��� ���肢���싅���v�Ƃ����Ō�̂ق����D���������̎����ɂȂ��Ă���t���B���ԈႦ�悤�̂Ȃ���Ԑg�߂Ȑl�̕M�ՁE�E�E�E�E����܂ł̗t���͂��ׂāu��������v���i�M�Ղ�ς��āj���������̂������̂��B����قNJ������Ă����싅���u��������v�͎��ɂ�点���������B����Ȃɂ܂ł��āA���́H �u���̒j�v�Ƃ̖�j���āu���̒j�v�ɕ��Q�����������̂��낤���B����Ƃ������Ɂu������v�̂��߂ɂ�����������������Ȃ̂��B
�@1986�N�̓��{�V���[�Y�́A�������̂���3�A�s�����������C�I���Y���A���̂��Ɩҗ�Ȑ����Ő���Ԃ��A1958�N�̊�Ղ��Č����悤�Ƃ��Ă����B�u������v�́A��Ղ��N��������A�����Ɓu�S�h�[�v�͗���A�����āA1958�N�ɓ��E�����u���̒j�v������邩������Ȃ��A�Ǝv�����B"�_�l�̂��Ȃ�"���{�V���[�Y�̌��ʂ́H
�@���̉��N����A�u������v�Ɓu�ꂳ��v�͌������Ēj�̎q�����܂ꂽ�B���܂ꂽ�q�����j�ł����ł��A�u���܁v�Ƃ������O������ƌ��߂Ă����B��l�����ѕt���Ă��ꂽ���̕����Ղ̉����Łu�S�h�[�v�̎g�҂ɕ��������̎q�̖��O�B���ꂪ���O���B�������Ă��܁A���O�ɘb�������Ă���B���O���������ꂽ�u�c������̓؎E���v�̌��Ɓu���܂Ƃ������̎q�̂悤�Ȗ��O�v�̗R�����B
�@�c������͂���قǍD���������싅���~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�u������v�͖싅�̉Q�Ɋ������܂�āA��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���O�͂��ܖ싅������Ă���B�싅�́A�ȒP�Ɂu�~�߂�v�Ȃ�Č�����قǐ��Ղ�������Ȃ��B�����炨�O�͖싅�𑱂���B�싅���Đ������̂ȂB
�l�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v
�@����͑�ςȍ�i���B�e�q�O��Ƃ����\���́A���{�×��́u�O��L�v�̓`����A�C�X�L�����X�́u�I���X�e�C�A�O����v�������܂��A���̎O�w�\����J.S.�o�b�n�́u�S�[���g�x���N�ϑt�ȁv���k�������霂Ƃ�����B�e����ɋ��ʂ���싅�Ƃ����L�C���[�h�́A���X�̐l�����f���o���A��ՂƂ���ꂽ��̓��{�V���[�Y�Ƀ����N����B����ɁA1958�N�̐��N���̈��ނƒ����ΗY�̃f�r���[�A1986�N�̎R�{�_��Ɛ����a���̂����Δ䂳���A�����N�x���������Ă�����B
�@�c�����o�E���������������Ɏ̂Ă�A28�N��A���͂��̃o�b�g�������������蓯����Ɏ̂Ă�B��Ղ̃V���[�Y�Ɂu�S�h�[��҂��Ȃ���v�𗍂܂���d�w�\���́A���H�u���[���X�̍�ȋZ�@���Â���B
�@�u�S�h�[�v�̍�҃x�P�b�g�ɂ͑��q�̑�D���ȃ��b�h�\�b�N�X�̃W���V���E�x�P�b�g����q���A1985�N��_�^�C�K�[�X���{��̗����҂��i�|�z�A�o�[�X�ł͂Ȃ��j���c�ƌ��������Ƃ��A�������݂�������Ƃ̐ړ_�̖G��ɂȂ�ȂǁA�싅�ɑ���L���[���m��������̃v���b�g�ɐ▭�ɗ���ł���B�c���̎��H�����Ƃ����싅�q���ɂ́A���炭�A�u�v���싅�����������v�i1969�|71�j���ӎ��I�Ƀ����N�����Ă���͂����B�R�{�_��ƃf���N�E�W�[�^�[�̉E�ł��̈Ⴂ���A�s�����@�͂Ȃ����Ă͏����Ȃ��B�����̐_��Ŗ@�A���d�~�̍\���A���Y�̃_�E���E�X�C���O�A�N���}�e�B�̏o�b�K�X�^�C���A�T�u�}�����R�c�A�}�T�J�����@���c�ȂǁA�싅�t�@���ɂ͂��܂�Ȃ����L���ȑI�肪�`�����z�����ƌ����B�싅��������C�������S�тɈ��Ă���B
�@��Ղ̍Č�����A�S�h�[�͗���A�u���̒j�v���߂��Ă��� �ʂ����āH �Ƃ����I�Ղ̃N���C�}�b�N�X���A���{�V���[�Y�̐��ڂɎ����������g��鉉���̌`���x�������V���N�������āA�ٔ��������錩�����B�t���������Ă����͕̂�e�������ƋC�Â���ʂł̃T�X�y���X�I�X�p�C�X���V���̋Z�B���̐l�A�ɒB�ɒ������Ə������Ⴂ�Ȃ��B
�@���̗���𐔊w�I�k�����ō\�z���闝���Ɩ싅���Ƒ��Ɍ����鈤�Ƃ�����B�\���Ƃ����X�^�e�B�b�N�Ȋ�ƕ���̐��ڂƂ������ݐi�s�`�̃_�C�i�~�Y���B�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�́A����瑽�l�ȗv�f���n���̋Z�ŗZ�����Ɠ��̐F�ʂ��������Ɏ������A�ߔN�H�Ȍ��쏬���ł���E�E�E�E�E�ȁ[��Č�����قǖ{��ǂ�ł���킯�ł͂Ȃ����A���̊������Ŏ˔�������т���ʔ����������������Ƃ����͊m���ł���B
2012.02.05 (��) FM����
�@��N���A������FM�����������Ȃ�܂��āA�u�ʓ|�ł��A���e�i�𗧂Ă悤���v�ȂǂƏ�������̊o������āA�H�t����FM�A���e�i�F�����肵�����̂ł��B����Ȑ܁A�}���V�����̒n�f�W�g�����i�Q�C���j�̌��f�����{����܂����B�P�[�u������TV�d�g���\���ȃ��x���ɂ��邩�ǂ����̌˕ʌ����ł��B���̂Ƃ��������̐l�ɁA�u�܂���TV�P�[�u����FM�g�͓����Ă��܂����ˁv�Ɛu������A�uFM�g�́ANHK�\FM�͂��ߓ����ߍx��8�ǂ��ׂč������Ă��܂��B�ϊ����Ă܂��̂ŁA���̕\���������������v�ƁA����\��FM�����̎��g���ꗗ�\�����ꂽ�B���R�͕�����Ȃ����A�m���Ɏ��g��������Ă���B82.5MHz��NHK�\FM��84.4MHz�Ƃ����悤�ɁB�u�܂����v�ƌ������̂́A2000�N�A���̃}���V�����Ɉ����z�����Ƃ��ɁA�P�[�u���ɂe�l�g�������Ă��Ȃ����Ƃ������A�e�l��f�O�A���������`���[�i�[��p����������������������ł��B1981�N����g���Ă����g���IKT900�Ƃ����_�C�������`���[�i�[�B�F���f�U�C�������C�ɓ��肾�����̂ł����B�@���������Ď��A21���I�ɓ����Ă���Ƃ�������FM�������Ă��Ȃ��̂ł��B����ł���������CD�������ς����������߁A�K�v���������Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�Ƃ��낪�����������ACD����Ɏ��p�x���ɒ[�Ɍ����Ă��܂����B���R�͂ȂɁH �u�N�����m�v�e�[�}���Ȃ����Ă݂�A�u�t�B�K���̌����v�u�J�������v�u���Z���~�T�ȁv�u�V���[�x���g�v�ȂǁA���̓s�x��ɏW������e�[�}������܂����B���ꂪ�A�ُ�ɂ̂߂肱�u�V���[�x���g�v����i�����āA�Ȃɂ��S�Ɍ����J�����悤�ȏ�ԂɂȂ����B
�@���y�͕��������B�ł����������̂������ł��悭������Ȃ��B����݂�CD�͊|����O�ɏo�Ă��鉹��������������ĂăX�����Ȃ��B���������V�����قƂ�ǂȂ��B����ȂƂ��ӂƎv�����̂ł��B�����I�Ɋ|���Ă������̂������B������FM���B���ꂾ�����玩�R�ɉ��y������Ă��Ă����E�E�E�E�E������FM�����������Ȃ����Ƃ����킯�ł��B
�@�d�g�̓P�[�u��������邱�Ƃ����������B���炭�n�f�W��ւ��H���̍ہAFM�g�����ꂽ�̂ł��傤�B�����A���Ƃ̓`���[�i�[�B�o����_�C�������������B�����ŎQ�l�܂łɁu���i�h�b�g�R���v��`���Ă݂܂����B����Ƃǂ��ł��傤�BFM�`���[�i�[�͋͂�5��ނ����ڂ��Ă��܂���B���������ׂĂ��f�W�^�������B�䂪������_�C�������͉e���`���������炸�A�\�z�ʂ�Ƃ͂����₵�����ʂł����B
�@�����ŁA�n�^�ƑM�����B�F�lT���̓I�[�f�B�I�̋S�A���̓J�����ɋÂ��Ă��āA�`���[�i�[�̈���V��ł��邩������Ȃ��B�d�b�}�����A�u���Ă݂悤�B�u���������AT�����A�`���[�i�[�]���ĂȂ��H�v�u�_�C�������ł悯��Γ]�����Ă�̂�����܂���B�����������Ă���������邩�ǂ����v�u���\���\�B���̃_�C���������~���������̂ł��B��Ȃ�������\���}�f��Ƃ������ƂŁB����́H�v�u�V���ŃC�b�p�C�ŏ\���ł��v���b�^�I����ŏ��k�����ł��B
 �@�����������`���[�i�[�́A�p�C�I�j�ASTEREO TURNER P-2030�Ƃ����_�C�������B�f�U�C�������S�ȃA�i���O�����Ō������ƂȂ��ł��B���҂ɋ��c��܂��ATV�A���e�i�����番�g���ă`���[�i�[�̃A���e�i���͂ɐڑ��A�_�C�������B84.4MHz�̂Ƃ����NHK-FM�ɓ����A�Ȃ�ƃ��B���@���f�B�́u�l�G�v����u�t�v������Ă��܂����B���r���O��t�Ɋg����u�₩�Ȓ��ׁI ����͂�A�Ȃ�Ƃ����������t�̂ЂƂƂ��A���Ƃ̏u�Ԃł����BT����肪�Ƃ��I �����ň�� ���t�� �v�����G�t�G�� ���B���@���f�B �m�ʐ^�̓J�Z�b�g�E�f�b�L�ɏ��p�C�I�j�AP-2030�n
�@�����������`���[�i�[�́A�p�C�I�j�ASTEREO TURNER P-2030�Ƃ����_�C�������B�f�U�C�������S�ȃA�i���O�����Ō������ƂȂ��ł��B���҂ɋ��c��܂��ATV�A���e�i�����番�g���ă`���[�i�[�̃A���e�i���͂ɐڑ��A�_�C�������B84.4MHz�̂Ƃ����NHK-FM�ɓ����A�Ȃ�ƃ��B���@���f�B�́u�l�G�v����u�t�v������Ă��܂����B���r���O��t�Ɋg����u�₩�Ȓ��ׁI ����͂�A�Ȃ�Ƃ����������t�̂ЂƂƂ��A���Ƃ̏u�Ԃł����BT����肪�Ƃ��I �����ň�� ���t�� �v�����G�t�G�� ���B���@���f�B �m�ʐ^�̓J�Z�b�g�E�f�b�L�ɏ��p�C�I�j�AP-2030�n�@���āA���ꂩ��Ƃ�������FM�O���̖����B�����A�y�ł����B84.4�ɌŒ肵�Ă����A���Ă����}���̉��y�������I�ɗ���Ă���B��6:00�|�u�Êy�̊y���݁v�A7:20�|�u���܂܂ɃN���V�b�N�vetc�A�ߌ�2:00�|�u�N���V�b�N�E�J�t�F�vetc�A���7:30�|�u�x�X�g�E�I�u�E�N���V�b�N�v�ȂǂȂǁB�����ƁA�Y�ꂿ�Ⴂ���Ȃ� �y�j�����9:00�|�u�g�c�G�a�̖��Ȃ̊y���݁v���B�䂪�h�G�g�c���́A�����V���ł͂��������ł����AFM�ł͖��T���C�Ȍ䐺�����Ă���Ă��܂��B
�@�����X�^�C�����A�������Ȕԑg����DJ�A���N�G�X�g�A�������p�܂ŐF�Ƃ�ǂ�B�N���V�b�N�͊�{�A�S�ȃI���E�G�A����������ǁADJ�`���N�G�X�g�E�X�^�C���̔ԑg�ł͈�y�̓I���E�G�A�^�ŁA����܂��C�y�ł����̂ł��B�܂��A�u���܂܂ɃN���V�b�N�v�ł́u�L�}�N���E�h���v�Ȃ�R�[�i�[�������āA����͐̃e���r�ŗ��s�����C���g���E�N�C�Y�̃N���V�b�N�ŁB������Ȃ��Ȃ��y�����B
�@����Ȃ���ȂŁA���N�͏t����"�y������FM����"���n�܂�܂����B�ł͒��߂�FM���m���ƍs���܂��傤�BFM�Ƃ�Frequency Modulation�̗��œ��{���͎��g���ϒ��B������Ƃ͕�����܂��A���������̂ł��B���݂�AM��Amplitude Modulation�ŐU���ϒ��̂��Ƃ������ŁBNHK-FM�����̊J�ǂ�1957�N�B���N�ɂ�FM���C�������ǂƂ����`�ŊJ�ǁA���̌�1970�N�A��������FM�ǂƂ��ĔF����FM�����ƂȂ�܂����i����ɓ���FM�Ɖ��́j�B���̃I�[�f�B�I�l�������̂����肩��n�܂������ƂɂȂ�܂��B�{���́A�������̃_�C�������`���[�i�[����̊��ł����B
2012.01.25 (��) ���V���� ���{�̕�
�@2012�N�ʏ퍑��E�E�E�s�ޓ]�̌��ӂȂ���̂����v���������炳�Ȃ����Ƃɔ��o���C�Â��Ă��Ȃ��}�f�ȍɑ����A�����Ă����Ȃ����[�_�[�V�b�v����������ɂȂ��Ė������邾�낤���Ԍ��̎n�܂�ł���B�P��ǂ���A�V�c�É����J���錾���ꂽ�B���͎��A�É��ɂ͂��̑O�����ڂɂ������Ă���B���ڂɂ�����Ƃ����Ă���������q�炵�������ł��邪�B�ꏊ�̓T���g���[�z�[���B���ˎ����nj��y�c�̓��������̏�ł���B�@�u���ˎ����nj��y�c�̃R���T�[�g������̂ł����A�������ł����H 1��22���̃T���g���[�z�[���ł��v�Ɨc����̗F�lF������d�b���������B�ނ̓N���V�b�N���y�D���̉��a�Ȑa�m�ɂ��āA���݁A�ꕔ���N��1000���̉�Ђ̉���В������Ă���B���ˎs�o�g�̔ނ́A���ˎ����ǂ̃X�|���T�[�h���s���A�̋��̉��y�������W�ɍv�����Ă�����B�������K�ɐl�̎��́A���肪�������U�����������B
�@�����Ă����ē��ɂ́A���V�����w���A�{�c���̃`�F���A���[�c�@���g�u�f�B���F���e�B�����g�j����K136�v�A�n�C�h���u�`�F�����t�ȑ�1�ԁv�A���[�c�@���g�u�n�t�i�[�����ȁv�Ƃ������B���V�Ƃ�2009�N�A�T�C�g�E�E�L�l���E�t�F�X�e�B�o�����{�ȗ��A�{�c��́u�薼�̂Ȃ����y��v�Ō��Ĉ�ۓI���������`�F���X�g�B�ƂĂ��y���݂��B
 �@�����A�z�[��������Ńv���O���������炤�ƁA�ꖇ�̃v�����g���t���Ă����B�u�{���̌����ɐ旧���čs��ꂽ1��19���̐��ˌ|�p�قł̃R���T�[�g�ŁA�����͖����s���܂������A�I����A�w���҂̏��V�������͂��Čo���������Ƃ̂Ȃ��قǂ̑傫�Ȕ�J�������A�����ɂȂ��Ă��w�����ł���܂ł̗̑͂����܂���ł����B���̌�A�{���Ɍ����Đ×{�𑱂��܂������A�\�肳�ꂽ���ׂẲ��ڂ��w������܂ł̗̑͂����߂��܂łɂ͎����Ă���܂���B�����Ŗ{���̌��������L�̂悤�ɕύX�����Ă��������܂��v�Ƃ��āA�u���[�c�@���g��2�Ȃ��w���҂Ȃ��ōs���A�Ō�Ƀn�C�h���̃R���`�F���g�̂ݏ��V�����w������v�Ƃ������̂������B���[��A���N�̎�p�͐����������̂ɁA�܂��܂��\���ɑ̗͂����ĂȂ��̂��B���̂Ƃ��������̂͂��̃T�C�g�E�E�L�l�����{�ŁA7���Ԃ����w����ɗ��ĂȂ������B�������Ȃ���A�͂�7���̃`���C�R�t�X�L�[�u���y�Z���i�[�h�v��1�y�͂̌������������ƁI �������˂�������ăr�����r���������Ă��������B����ɂ��Ă��A�u���Čo���������Ƃ̂Ȃ��傫�Ȕ�J���v�Ƃ́E�E�E�A���ɐS�z�B
�@�����A�z�[��������Ńv���O���������炤�ƁA�ꖇ�̃v�����g���t���Ă����B�u�{���̌����ɐ旧���čs��ꂽ1��19���̐��ˌ|�p�قł̃R���T�[�g�ŁA�����͖����s���܂������A�I����A�w���҂̏��V�������͂��Čo���������Ƃ̂Ȃ��قǂ̑傫�Ȕ�J�������A�����ɂȂ��Ă��w�����ł���܂ł̗̑͂����܂���ł����B���̌�A�{���Ɍ����Đ×{�𑱂��܂������A�\�肳�ꂽ���ׂẲ��ڂ��w������܂ł̗̑͂����߂��܂łɂ͎����Ă���܂���B�����Ŗ{���̌��������L�̂悤�ɕύX�����Ă��������܂��v�Ƃ��āA�u���[�c�@���g��2�Ȃ��w���҂Ȃ��ōs���A�Ō�Ƀn�C�h���̃R���`�F���g�̂ݏ��V�����w������v�Ƃ������̂������B���[��A���N�̎�p�͐����������̂ɁA�܂��܂��\���ɑ̗͂����ĂȂ��̂��B���̂Ƃ��������̂͂��̃T�C�g�E�E�L�l�����{�ŁA7���Ԃ����w����ɗ��ĂȂ������B�������Ȃ���A�͂�7���̃`���C�R�t�X�L�[�u���y�Z���i�[�h�v��1�y�͂̌������������ƁI �������˂�������ăr�����r���������Ă��������B����ɂ��Ă��A�u���Čo���������Ƃ̂Ȃ��傫�Ȕ�J���v�Ƃ́E�E�E�A���ɐS�z�B�@���ɂ͏d���E�g�c�G�a�����������ɂȂ��Ă����B���̃I�P�̑n�ݎ҂ł���B�����V���u���y�W�]�v�������������Ƃ��������Ȃ̂ŐS�z���Ă������A�����C�����ʼn���肾�����B���t��̂��߂Ɋ��q�̂�����瓌���֏o��������Ȃ�āA�ƂĂ����98�Ƃ͎v���Ȃ��B�Ƃ�����A����ɂƂ��ĕs���Ȃ��̏h�G�i�H�j�Ȃ̂�����A���܂ł������C�ŏ��������Ă������������Ɗ肤�B
�@�w���҂Ȃ��̑O���ŃI�[�P�X�g���������ɂ��_�a�ȕ\��̉��y�����Ă��ꂽ���ƁA30���Ԃ̋x�e������ŏ��V�̓o���҂B�ƁA���̂Ƃ��₩�ɔ��肪�N���N�������B�u�������H�v�Ƌ����Ă��̕����������ƁA��K�Ȃ��V�c�c�@���É����ɂ��₩�ɕ����ė�����̂��������B�Ȃ�ƁA����͓V�������������̂��I ����́A���V�v���Ԃ�̓���������H ����Ƃ��A�É����{�c��̃t�@���H �Ƃ�����A���r�܂������É��̂��p�́A���������{�����ɂƂ��āA�����Ȃ鎞���傫�Ȉ��炬�ƂȂ�B
�@���V���{�c�ƈꏏ�ɃX�e�[�W�Ɍ����B�I�P�̃����o�[�ɉ����b�������Ȃ���A�����̃X�^�C���ł̓o�ꂾ�B�₪�āA�m���^�N�g�̉E�肪��M����B���a�����K���������n�C�h���̑�1��肪�N���o�ł�B�H�т̂悤�Ȍy�₩���B�������K�x�ɒ��܂��Ă���B���炩�ɑO���Ƃ͉����Ⴄ�B�̒��s�\�����J���X�}�����ؖ������H �ނ��A2010�N8��1���A���A�̋L�҉�ŁA�u�ς邩������܂���ˁB�킩��Ȃ����ǁB�������܂��ς���Ă��ꂽ��A�i���y���j�[���Ȃ��Ă��炢�����ł��ˁv��11�b���̒������ق̖����������t���v���o���ꂽ�B���a�łȂɂ����ς�����̂��낤�B���_�I�ȂȂɂ���͂̂��낤�B�c���ꂽ���Ԃ̋M���Ɛ����銽�т̎����ɂ���āA����̉��y���ς��Ɗm�M�����̂ł͂Ȃ����B�����̃n�C�h�����O�q2010�D9�D5�̃`���C�R�t�X�L�[���l�A�m���ɐ[���B���݂����ނƂł����������B
�@�{�c�̃`�F���͐��X���������B�����ƘN�X�Ƃ����͋�������z�����Ă������A����Ă����B���X�g���|�[���B�`�E�R���N�[���̗D���ҁi2009�N�j�Ƃ̂��Ƃ����A�e�C�X�g�̓s�G�[����t���j�G�ɋ߂��B�{�c25�A���V76�B���m����ȉ����ƃe�N�j�b�N�Ŏ��݂ɋ삯����{�c���A�܂�őc���̎����ŗD������������ƕ�ݍ��ޏ��V�B�f���炵���R���{���[�V�����������B�I���Ɨ��̂悤�Ȕ���B�őO��X�^���f�B���O�I�x�[�V�����̔g�B�ӂƓ�K�Ȃɖڂ����ƁA�Ȃ�Ɨ��É����X�^���f�B���O�ł���B����͍������Ⴈ��Ȃ��ƁA������B
�@��~�܂ʔ���ɁA���t�҂͉��x�����x���o������J��Ԃ��B���V�͂��̓s�x�A��K�Ȃ̗��É��ɉE����h�畗�ɂ������ĉ�߂���B���̐l�������������E�𐧂�������Ȃ̂��낤�B
�@���V�����́A24�̂Ƃ��X�N�[�^�[�Ń��[���b�p��l���ɏo�āA�����ŃG���g���[�����u�U���\���w���҃R���N�[���Ō����D���A���E�ɉH�����Ă������B�������w�����������́A���̌��̎�L�u�{�N�̉��y���ҏC�s�v�i�V���Ёj���A����点�ēǂ��̂ł���B���̌�̊���͎��m�̒ʂ�ł���B�������Ȃ���A�̐t�̔ނ̉��y�ɂ͓���߂Ȃ������B���̂��āA�삵�����R�[�f�B���O�́i�S�������킯�ł͂Ȃ����j�Ȃɂ��Ă��������Ȃ������̂�����d�����Ȃ��B
�@������ɁA���V�́A���{�l�Ƃ��Đ��E�ōł������������y�ƂȂ̂ł���B���̎���A�u���{�l�ɉ����o����v�I�ȕ݂̂̒��Ől�m��ʋ��J���C���Ƃ����قǖ��킳�ꂽ�ɈႢ�Ȃ��A����Ȓ��ŁA�Ƃɂ������ɂ����E�ւ̓����Ă������҂Ȃ̂ł���B�L�]�Ȏ��͂��ׂĔނ̔w�������Ĉ�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂��B�����Ƃ����u���V�̉��y�͂ǂ����H�v�Ȃǂƙꂢ���Ƃ���ŁA�ނ͏�Ɂu���E�̃I�U���v�ł��葱���Ă����̂ł���B
�@�����āA���̂Ƃ��ȗ��ނ̉��y�̓K�����ƕς����B2010�N���̎�p����̋A�҂ł���B�O�q�̒ʂ�A���A��ŏ��̃`���C�R�t�X�L�[�u���y�Z���i�[�h�v�͐��܂����Ռ��������B���V�̉��y�ɏ��߂ċ��˂��グ��ꂽ�C�������B�������A��Ȃł͂܂����m���B2010�D12�D14�A�J�[�l�M�[��z�[���ł́u�u���P�v�͌����ĉ����Ƃ͂����Ȃ��������炾�B
�@���V�͍��A�m���ɕς낤�Ƃ��Ă���B���̓����悤�ȋ�������}�[���[�u�����v�����������Č������S�����N���E�f�B�I��A�o�h�̂悤�ɁB�Ƃɂ����A�ł�����蒷������ė~�����B�a���ɕ������ɁI �Ȃ�Ă����������V�����͓��{�̕��ł���A���ꂩ�特�y�������Ƃ����Ɩ{���ɂȂ�A����ȗ\�������邩��ł���B
2012.01.10 (��) �b����`2012�V�N�G��
�@��c�����N���L�҉�́u�l�o�[�E�l�o�[�E�l�o�[�E�E�E�M�u�A�b�v�v�ɂ́A�����Ȃ����ƃE���U���̓�d�t�����܂���܂������A�������s���̐��͓I�����ɂ́A�傢�Ȃ��]�������܂��B�����Ɍ�������I�Ɋ��������Вn�̑ٓ��ƍ��킹�A���{���܂��܂��̂Ă�����Ȃ��Ɗ����邱�̐V�N�A�F�l���������}���ł��傤���B�@�u�N�����m�v2012�N�x��1��́A�N���N�n�̃e���r�E���|�[�g�ƍs���܂��傤�B�܂��́A�N���P��̓�́u���v���t���n�߂����Ǝv���܂��B
�@�ǔ������͐��w�������엳���i1969�|�j�̃^�N�g�B����͈��N�̃T�C�g�E�L�l���E�t�F�X�e�B�o�����{�ŁA���V�����̃s���`�q�b�^�[�Ƃ��āu���z�����ȁv��U����
 ���ڂ��W�߂������͔h�ł��B�r���[�h�̂悤�Ȋ��炩�Ȕ��G��ŁA���y�̗�������R�ōD���x��Ȃ̂ł����A�����ɂ��D�����I�ŃX�������Ȃ��B
���ڂ��W�߂������͔h�ł��B�r���[�h�̂悤�Ȋ��炩�Ȕ��G��ŁA���y�̗�������R�ōD���x��Ȃ̂ł����A�����ɂ��D�����I�ŃX�������Ȃ��B�@����ɑ��m���͌��88���X�^�j�X���t�E�X�N�����@�`�F�t�X�L�i1923�|�j�̎w���B�Z���w���_�œ�����������̂ł����A���o���鉹�ɂ͗͂������Ă���B�������ɗh���Ԃ���悤�Ȋ��o�Ȃ̂ł��B���ɑΏƓI�ȁu���v�ł������A���͒f�R�X�N�����@�`�F�t�X�L�ɌR�z���グ�܂��B2010�N�A�ǔ��������w�������u���b�N�i�[�́u���v�����X���̖����ł����B
�@�@�P��2012�E�B�[���E�t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�́A2006�N�ɑ�����x�ڂ��}���X�E�����\���X�i1943�|�j�̎w���ł����B���N�̓����h���E�I�����s�b�N�J�ÂƂ������ƂŁA�u�A���r�I���E�|���J�v�Ƃ����������Ȃ��̂肠���Ă��܂��B�A���r�I���̓C�M���X�̌ḮA���n���E�V���g���E�X�U�����B�N�g���A�����̕v�N�Ɍ��悵���Ȃ������ł��B�����\���X�A�O��̓��[�c�@���g���a250�N�Ɉ���Łu�t�B�K���̌����v���Ȃ����t���Ă���A�Ȃ��Ȃ��T�[�r�X���_�����Ȑl�B�y�������Ƃ��̏�Ȃ��̂ł����A����܂��D�����߂��ĕ�����Ȃ��B2010�N�̃W�����W���E�v���[�g���ꂳ��̂悤�ȋ���Ȍ������͍D���Ȃ̂ł��B���J���́u��������v���Ȃ͒������ł����B���E�͈Ⴂ�܂����A��N���S���Ȃ�������̗���k�u�́A�{�l�������قǑ債���|�Ƃ͎v���܂��A���̂��䂫�����Ă��܂��B��X���ʐl��"��l�Ƃ͈Ⴄ"�����Ɏ䂩���X�����m���ɂ���̂ł��B�Ƃ��낪�e�F�̓�坎O���v�Ɍ��킹��ƁA�u�����͌��N�I�^�N�������v�Ƃ̂��ƁB�Ƃ������Ƃ́A���̌����������l�����o���������ƂɂȂ�B�ǂ����C�J�T�}�I�ȓ������@���Ȃ������̂͂��̂����肾�����̂����B�ł��܂��A����͂���Ŗʔ����B
�@1��3���́A������P��NHK�I�y���R���T�[�g������܂����B��N�͂������Ēn���������̂ł����A���N�͌����ꂪ�����傢�Ɋy���߂܂����B����h�i�e�m�[���j�́u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv�͒�ԓI���芴�����������A�]���N��i�e�m�[���j�́u�₽����v�i�u�{�G�[���v����j�������悭�L�тĂ��Ă悩�����̂ł����A���̐��E�ł��Ȃł������ہA������ʂ͔ۂ߂��ł����B
 �@�܂����X���G�i�\�v���m�j�B�̂��̓R�����g�D�[���̒�ԁu�֕P�v�́u�����A���͂��̐l���`�Ԃ���Ԃցv�B���̃A���A�́A��l�߂̍ō���Es���|�C���g�B�ʂ̃T�C�g�ł��̃A���A�̃x�X�g�̏���I�肵���Ƃ��A10�l�̃\�v���m����ׂ��̂ł����A���̉����o�������̂�6�l�ŁA���̂���Es�Ɏ���ߒ����y���ǂ��肿���ƒH���Ă����̂�2�l�����B�����A�N���X�Ƃ��܂��傤�B����4�l�͑O�i�ňꑧ����Ă���Əo���Ă���A�����B�B���Ƃ�Es���o�Ă��Ȃ�C�N���X�B���݂�A�N���X�́A�C���A�i�E�R�g���o�X�ƃX�e�t�@�j�A�E�{���t�@�f�b���B�a�N���X�́A�}���A�E�J���X�A�A���i�E���b�t�H�A�G�f�B�^�E�O���x���[���@�A�p�g���c�B�A�E�`���[�t�B�BC�N���X�́A��䏊�e�o���f�B�A���̎�t���[�j�A�����Ƃ��߂��l�g���v�R������A�˂�B���ƂقǍ��l�Ƀ��F���f�B�̈Ӑ}�������l�|�������ɕ\������͓���̂ł��B�킪�X���G�̓N���X�a�������̂ł܂��܂��ł����B�����Ȃ��́A���i����A�N���X������ʂ����ė~�������́B����́A�t�B�M���A�ł����A�t���[�̍Ō�̍Ō�Ńg���v���E�A�N�Z���Ԃ悤�Ȃ��̂ŁA���̃X�^�~�i���̐S�Ȃ̂ł��B���݂Ƀx�X�g�̏��̓R�g���o�X�ł����B
�@�܂����X���G�i�\�v���m�j�B�̂��̓R�����g�D�[���̒�ԁu�֕P�v�́u�����A���͂��̐l���`�Ԃ���Ԃցv�B���̃A���A�́A��l�߂̍ō���Es���|�C���g�B�ʂ̃T�C�g�ł��̃A���A�̃x�X�g�̏���I�肵���Ƃ��A10�l�̃\�v���m����ׂ��̂ł����A���̉����o�������̂�6�l�ŁA���̂���Es�Ɏ���ߒ����y���ǂ��肿���ƒH���Ă����̂�2�l�����B�����A�N���X�Ƃ��܂��傤�B����4�l�͑O�i�ňꑧ����Ă���Əo���Ă���A�����B�B���Ƃ�Es���o�Ă��Ȃ�C�N���X�B���݂�A�N���X�́A�C���A�i�E�R�g���o�X�ƃX�e�t�@�j�A�E�{���t�@�f�b���B�a�N���X�́A�}���A�E�J���X�A�A���i�E���b�t�H�A�G�f�B�^�E�O���x���[���@�A�p�g���c�B�A�E�`���[�t�B�BC�N���X�́A��䏊�e�o���f�B�A���̎�t���[�j�A�����Ƃ��߂��l�g���v�R������A�˂�B���ƂقǍ��l�Ƀ��F���f�B�̈Ӑ}�������l�|�������ɕ\������͓���̂ł��B�킪�X���G�̓N���X�a�������̂ł܂��܂��ł����B�����Ȃ��́A���i����A�N���X������ʂ����ė~�������́B����́A�t�B�M���A�ł����A�t���[�̍Ō�̍Ō�Ńg���v���E�A�N�Z���Ԃ悤�Ȃ��̂ŁA���̃X�^�~�i���̐S�Ȃ̂ł��B���݂Ƀx�X�g�̏��̓R�g���o�X�ł����B �@�v�b�`�[�j�u���E�{�G�[���v����u�����X������v���̂����������q�i�\�v���m�j�͑f���炵�������B����̓N���X�}�X�C�u�̃p���A�T���������߂ċ������̈��l�ɑ��������[�b�^���A�S���c�������l�̑O�ŋ������ĉ̂������c�e���|�̃A���A�B�����L�́u�{�G�[���vDVD7�^�C�g���̒��ł��A�}�������E�`���E�i1982�N�R���F���g�K�[�f���j�ƃ_�i�[�^�E�_�k���c�B�I�i2007�N�v�b�`�[�j���y�Ձj�����肪����Ƌy��ŁA���̎背�i�[�^�E�X�R�b�g�i1982�N���g���|���^���j���C�}�C�`�Ƃ�������ł��B�����́A�d�����i�悭�A���E�̒N�ɂ����������Ȃ������ȃp�t�H�[�}���X���I���܂����B�ޏ��͂܂����H�A�v�����B���w����N������ŁA�u���[���X�u�h�C�c�E���N�C�G���v���̂��Ă���A�|�̕����L���B����ȂɎႭ�͂Ȃ������ł����A����̂���Ȃ���i�����҂ł��܂��B
�@�v�b�`�[�j�u���E�{�G�[���v����u�����X������v���̂����������q�i�\�v���m�j�͑f���炵�������B����̓N���X�}�X�C�u�̃p���A�T���������߂ċ������̈��l�ɑ��������[�b�^���A�S���c�������l�̑O�ŋ������ĉ̂������c�e���|�̃A���A�B�����L�́u�{�G�[���vDVD7�^�C�g���̒��ł��A�}�������E�`���E�i1982�N�R���F���g�K�[�f���j�ƃ_�i�[�^�E�_�k���c�B�I�i2007�N�v�b�`�[�j���y�Ձj�����肪����Ƌy��ŁA���̎背�i�[�^�E�X�R�b�g�i1982�N���g���|���^���j���C�}�C�`�Ƃ�������ł��B�����́A�d�����i�悭�A���E�̒N�ɂ����������Ȃ������ȃp�t�H�[�}���X���I���܂����B�ޏ��͂܂����H�A�v�����B���w����N������ŁA�u���[���X�u�h�C�c�E���N�C�G���v���̂��Ă���A�|�̕����L���B����ȂɎႭ�͂Ȃ������ł����A����̂���Ȃ���i�����҂ł��܂��B�@�Ō�ɔN�n�̉A�����w�`�̎G�������X�B�D���������m��͖{���ɋ��������B�����^�C��10����51��36�b�́A���㐔�N�Ԕj���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B����4�N�ԂŁA�D��3�D���P��Ƃ������т͐��ɓ��m��������̗l���ł����B�����҂͖ܘ_4�N���̎R�̐_�E��������B4�N�ԑS�ċ�ԋL�^�A��3����ԐV�Ƃ������т͕s�ł̋������B�ԈႢ�Ȃ������w�`�j��ő�̖������i�[�Ƃ����܂��B�ނ͕��������킫�s�̏o�g�B�s�K��w�������̋��ɑ傫�ȗE�C��^�����Ǝv���܂��B
 �@���m��D�������̒����V���Ɂu�w�`�ƃ}���\�� �����ȊW�v�Ƃ��������[���L�����ڂ�܂����B�u�w�`�̗������}���\���I��琬�̕��Q�ƂȂ��Ă���v�Ƃ������́B�����A���{�}���\�����̂ɔ�ׂĐ��E�Ƃ̋����������Ȃ��Ă���͉̂��̂��낤�A�����������i�[�̐���D�P�̊�������ɕs�v�c�Ȍ��ۂ��A�ȂǂƂ��˂��ˎv���Ă��܂����B�����w�`�\���ƒc�Ƃ����G���[�g�R�[�X���̂ɖ�肪����Ă���Ƃ��邱�̋L���́A�Ȋw�I�����͕s�m���ł��A���ɖʔ����w�E�ł����B
�@���m��D�������̒����V���Ɂu�w�`�ƃ}���\�� �����ȊW�v�Ƃ��������[���L�����ڂ�܂����B�u�w�`�̗������}���\���I��琬�̕��Q�ƂȂ��Ă���v�Ƃ������́B�����A���{�}���\�����̂ɔ�ׂĐ��E�Ƃ̋����������Ȃ��Ă���͉̂��̂��낤�A�����������i�[�̐���D�P�̊�������ɕs�v�c�Ȍ��ۂ��A�ȂǂƂ��˂��ˎv���Ă��܂����B�����w�`�\���ƒc�Ƃ����G���[�g�R�[�X���̂ɖ�肪����Ă���Ƃ��邱�̋L���́A�Ȋw�I�����͕s�m���ł��A���ɖʔ����w�E�ł����B�@���p�̓��{�e���r�ɋꌾ����B�����w�`�ł����ߔN��ʂɐH�����Í����������������閾����w�A���N�̖ڕW�́u����c����ʂցv�ł����B����͒��p�̒��ł��A�i�E���T�[�����x�������Ă������ƁB�ŏI10��ł́A��ʓ��m��A2�ʋ��Ƃ����`�������܂�����A�����͑���c�Ɩ�����3�ʑ����ɍi���܂����i��N����オ��V�[�h�������́A�J�グ�X�^�[�g�Z�ُ̈�ȑ����Ō����ڂ̖ʔ����͔������Ă��܂����j�B
�@10�撆�p�n�̒ߌ���1��13�b��������Z�̍��́A�����̃A���J�[�Z��̒ǂ��グ�ŁA���c��1��6�b�A�V���c�R���ł͋͂�17�b�A���t�]�Ȃ��Ă����������Ȃ��ł����B�Ƃ��낪���̎��Ԃ��f���o���ꂽ�̂͂ق�̈�u�A�����������A�i�Ɖ���̐��Â���́A�̂�C�ɓ��m��̃A���J�[�ē��̃G�s�\�[�h��b���Ă��܂��B���ꓹ�f�I���̗ނ̘b�͋��Z�N���Ȃ��̎��ԑтł���ė~���������B�₪�ē��m�傪�S�[���B9��2�b����2�ʋ�傪�S�[���B����9���̊Ԃɂ�3�ʑ����̉f���͈�؉f��܂���B����c����ʂցE�E�E��Z�̔ߊ��w���������_�o�ɂ�����Ȃ���������ɑ��閾���̃A���J�[���A�O�N�O���Ƃ�����w�w�`�̒��_���ɂ߂�����c���Ƃ����A�f���I�ɂ͂��̓��ő�̌�����ƂȂ����͂��̏u�Ԃ����Ă��܂��Ă����̂ł��B�����āA���S�[���̂��ƍŏ��ɉf���o���ꂽ�f���́A�Ȃ�ƁA���������ɂȂ��đ��邷�łɔ����ꂽ����c�̃A���J�[�s��̎p�ł����B�A�i�E���T�[�́u4�ʂ̑���c�ł��B�����ɔ�����܂����v�ƋC�̔������A�i�E���X�B3�ʂ��Ђ����閾��E�Z��𑨂����̂͗y�����̂��ƁB�܂�Œ��܂�Ȃ��A���ꂼ���Ԃ̋ɂ݁I���̃Z���X�̌����������ޓǔ��̏ے������B�Ō�ɂ���Ȃ��Ƃ��������w�`���p�ł����B
�@2012�I�y����R���T�[�g�̒��߂�����́A�o�[���X�^�C���̃I�y���u�L�����f�B�[�h�v����u��n�ɑ������āv�iMake our garden grow�j�ł����B�����Ȃ�u���t�̉́v������ɂȂ�̂ł����A���N�͈Ⴂ�܂����B
���l��͏����Ƃ͌����Ȃ����̂����Ȃ������l�ł��Ȃ�������@���̉̂̈Ӗ��������A�n�ɑ������A���������A�l���A�s�����Ă䂫�����Ǝv���܂��B
�@ �m�肽���l���̈Ӗ���
�@ ����t�ł��邾���̂��Ƃ����悤
�@ �Ƃ����Ă܂������蔨���k����
2011.12.25 (��) �b����`2011���N�����s��
�@���N�̗��s���܂́u�Ȃł����W���p���v�A�����ꕶ���́u�J�v�Ɍ��܂�A�e���r���u���N�̏\��j���[�X�v�ő���킢�B������́A�v�����܂܁A�C�̌����܂܁A�ߑ��������Ȃ��̖{�N�x�u�N�����m�v�ŏI��ł��B �@�V���[�x���g��������āA���݂�⋕�E��ԁB�V���[�x���g�Ɍ��炸�A�N���V�b�N���y���C�ɂȂ�Ȃ��B�����̐��E�ł̓X�����v�ɂȂ�Ɓu��痣���v�Ȃ�i������B�X�����v�Ƃ̓`�g�Ⴄ�̂ł����A��S�s���ɏW��������́A�C���]���������Ȃ���̂ł��B���݂̃}�C�E�u�[���̓|�s�����[�E�~���[�W�b�N�B�H���u���ɂ̃|�s�����[���ȃx�X�g�vCD���ł��B�����A�m�y�̗L���ȁA�q�b�g�ȁA�X�^���_�[�h�Ȃ��玩���̍D���ȋȂ�I���2���gCD����낤�Ƃ������́B�Ȑ��́u���ɂ̃V���[�x���g�v�ɍ��킹��40�ȂƂ��܂����B�^�C�g�����uGreat Songs 40�v�B
�@�V���[�x���g��������āA���݂�⋕�E��ԁB�V���[�x���g�Ɍ��炸�A�N���V�b�N���y���C�ɂȂ�Ȃ��B�����̐��E�ł̓X�����v�ɂȂ�Ɓu��痣���v�Ȃ�i������B�X�����v�Ƃ̓`�g�Ⴄ�̂ł����A��S�s���ɏW��������́A�C���]���������Ȃ���̂ł��B���݂̃}�C�E�u�[���̓|�s�����[�E�~���[�W�b�N�B�H���u���ɂ̃|�s�����[���ȃx�X�g�vCD���ł��B�����A�m�y�̗L���ȁA�q�b�g�ȁA�X�^���_�[�h�Ȃ��玩���̍D���ȋȂ�I���2���gCD����낤�Ƃ������́B�Ȑ��́u���ɂ̃V���[�x���g�v�ɍ��킹��40�ȂƂ��܂����B�^�C�g�����uGreat Songs 40�v�B�@���x�Y�N��V�[�Y���������̂ŁA��l���Ɂu���Ȃ��̍D���ȗm�y�q�b�g�ȉ��ł���������5�ȋ����āv�Ƃ��u�v���X���[�ň�ȑI�ԂƂ���Ή��H�v�u�r�[�g���Y�́H�v�ȂǁA�����܂���܂����B�Ƃ͂����ŏI����͎��̍D�������B���������AJ�DD�D�T�E�U�[�u���A�E�I�����[�E�������[�v�ƃM���o�[�g�E�I�T���o���u�A���[���E�A�Q�C���v�͊O���܂����BIceblue�N���فI ������T�����A�u���̐��̉ʂĂ܂Łv�����肪�Ƃ��B
�@�I��̊�{�́A�P�A�[�e�B�X�g1�ȁA�ő�2�ȂɌ���B���ʁA2�ȑI�̂̓T�C�������K�[�t�@���N���ƃr�[�g���Y��2�g�����ł����B���݂ɑO�҂́u�T�E���h�E�I�u�E�T�C�����X�v�Ɓu�����ɉ˂��鋴�v�ŁA����̓X���i���B��҂͑�ςł������A���FY����ƈꔭ���v�����u�A���h�E�A�C�E�����E�n�[�v�Ɓu�U�E�����O�E�A���h�E���C���f�B���O�E���[�h�v�ɗ��������܂����B
�@�ꔭ���i����I�j�A�Ⴆ�v���R���E�n�����́u���e�v�A�X�R�b�g�E�}�b�P���W�[�́u�Ԃ̃T���t�����V�X�R�v�A�s�[�^�[���S�[�h���́u���Ȃ����E�v�Ȃǂ͖��Ȃ��ł����A�啨�͖����܂��B�Ⴆ�A�G�����B�X�E�v���X���[�ƃ��[�����O�E�X�g�[���Y�B���ʁu�D���ɂȂ炸�ɂ����Ȃ��v�Ɓu���r�[�E�`���[�Y�f�C�v�ɂ��܂������A����͂����D�݂ł����Ȃ��ł��ˁB
�@�j�ґ���^������܂��āA���C�E�`���[���X�ł́u�������ɂ͂����Ȃ��v�Ɓu�킪�S�̃W���[�W�A�v�A�f�B�[���E�}�[�e�B���́u�N�����N���������Ă�v�Ɓu���C�t���ƈ��n�v�B�O�҂́u�킪�S�̃W���[�W�A�v�ɂȂ�܂������A����͖��FBrownie���̉e���B��҂͂Ȃ�ƂȂ��u�N���v�Ɍ���B
�@�ł́A�����̖L�x�ȃr�b�O�E�A�[�e�B�X�g�́H �T�b�`���́u���̑f���炵�����E�v�A�i�b�g�E�L���O�E�R�[���́u�g�D�[�E�����O�v�A�W�����E���m���́u�C�}�W���v�A�{�u�E�f�B�����́u���ɐ�����āv�A�r�[�W�[�Y�́u�}�T�`���[�Z�b�c�v�A�J�[�y���^�[�Y�́u�C�G�X�^�f�C�E�����X���A�v�AABBA�́u�_���V���O�E�N�C�[���v�APPM�́u500�}�C��������āv�ŁA���̂�����͈ӊO�ƃX���i���A������Ɩ����ăV�i�g���́u�}�C�E�E�F�C�v�Ƃ�����B
�@���̑��A�ƒf�IFavorite tune�̐��X���L���Ă����܂��E�E�E�E�E�u�J���t�H���j�A�̐���v�i�A���o�[�g�E�n�����h�j�A�u�J�ɂʂ�Ă��v�iB�DJ�D�g�[�}�X�j�A�u�h�b�N�E�I�u�E�U�E�x�C�v�i�I�[�e�B�X�E���f�B���O�j�A�u�j������������Ƃ��v�i�p�[�V�[�E�X���b�W�j�A�u�e�l�V�[�E�����c�v�i�p�e�B�E�y�C�W�j�A�u�A���h�E�A�C�E�����E���[�E�\�[�v�i�y���[�E�R���j�A�u�lj��v�i�o�[�u���E�X�g���C�U���h�j�A�u���[���E���o�[�v�i�A���f�B�E�E�B���A���Y�j�A�u���̃T���t�����V�X�R�v�i�g�j�[�E�x�l�b�g�j�A�u�A���`�F�C���h�E�����f�B�v�i���C�`���X�E�u���U�[�Y�j�A�u������z���v�i�W���I���E�`���N�F�b�e�B�j�A�u�߂����Бz���v�i�w�����E�V���s���j�A�u�߂����J���v�i�J�X�P�[�Y�j�A�u���̋��̂Ƃ��߂����v�i�_�X�e�B�E�X�v�����O�t�B�[���h�jetc�B
�@�������āA�I�y�Ȃ���璭�߂Ă݂�ƁA��͂�\�t�g�������E�n�������A�u���ɃV���[�x���g�v�Ɠ����X�����o�܂����B�N�����|�b�v�������̍D�݂͕ς�Ȃ��Ɖ��߂ĔF����������ł��B
�@20�ȂÂ�2���ɐU�蕪����Ƃ��ACD1�ƂQ��R�^�ɂ��܂����B�r�[�g���Y�u�r�X�g�[���Y�A�v���X���[�u�r�T�b�`���A�V�i�g���u�r�W�����E���m���ȂǂƂ�����ɁB������CD�P��RECTA�ACD2��INVERSA�ƃl�[�~���O�B����͐��Ɣ��Ƃ����h�C�c��ŁA�i�D�r�D�o�b�n�́u�����t�[�K�v�̗p��Ƃ��Ďg���Ă�����́B
�@����Ȃ킯�ŁA�Ȃ��Ȃ����͓I�ȃR���s���[�V���������������Ǝ������Ă��܂��B���v�]�̕��͉����Ȃ����\���t�����������B
 �@12��18���͍P��A�N�Ɉ�x�������݂䂫�w�łɍs���Ă��܂����B�����͐ԍ�ACT�V�A�^�[�A���ڂ́u���^2����2�v�B���ς�炸�݂̂䂫���[���h�S�J�B���N��3.11��k�Ђ�ޏ����ǂ������Ă��邩���C�ɂȂ����̂ł����A�����ł͂Ȃ��A��i�ł��̂������Ă����悤�Ɏv���܂��B�Ⴆ�uGive and Take�v�B�u�{��������̂̋C���v�����S������悤�ȗD�����̎��u�{�����Ă��ꂽ���ƁA���̎������ł��Ԃ��͖���Ă���v�Ȃǂ���ۓI�ł����B���ɂȂ��\�����V���v���ŃX�g���[�g�B�̐������ɗD�����Ƃ��ɗ͋����A�܂��Ɋ����̂ЂƎ��ł����B
�@12��18���͍P��A�N�Ɉ�x�������݂䂫�w�łɍs���Ă��܂����B�����͐ԍ�ACT�V�A�^�[�A���ڂ́u���^2����2�v�B���ς�炸�݂̂䂫���[���h�S�J�B���N��3.11��k�Ђ�ޏ����ǂ������Ă��邩���C�ɂȂ����̂ł����A�����ł͂Ȃ��A��i�ł��̂������Ă����悤�Ɏv���܂��B�Ⴆ�uGive and Take�v�B�u�{��������̂̋C���v�����S������悤�ȗD�����̎��u�{�����Ă��ꂽ���ƁA���̎������ł��Ԃ��͖���Ă���v�Ȃǂ���ۓI�ł����B���ɂȂ��\�����V���v���ŃX�g���[�g�B�̐������ɗD�����Ƃ��ɗ͋����A�܂��Ɋ����̂ЂƎ��ł����B�@����Ɉ��������A���{����c������b�̑Ή��̕s�����������炠��܂���B��Ԃ����Ȃ��̂͌�������Ȃ����ƁB�����āA���O�Ǝ��含�ƈ�ѐ����Ȃ����Ƃł��傤���B
�@12��17���́u�����≷��~��Ԑ錾�v���A�����������D��ŏo���Ă��܂����B�j�R����Z���Ă��鐅�̉��x��391.6�x�i���d�̔��\�j�Ȃ̂ɁA100�x�ȉ��������́u�≷��~�v��"���"�Ƃ������������ăt�@�W�[�������B������A�u�����ɂ�����Ȃ��̂ɂȂ�Ő錾�ł���̂��v�ƌ���ꂿ�Ⴄ�B�h�C�c����́u���̏�Ԃł��������̂̓E�\�Ǝ���d�v�Ƃ܂Ŕᔻ����Ă��܂��B�܂₩���̈��S�́A�t�ɕs������邱�Ƃ�����Ȃ��̂ł��傤���B�悾���Ắu�����A�o�v�̖@�Ă��ʂ��Ă��܂����B���̊��ɋy��ł����E�D��ł����B�펯�l�̎��ɂ͂܂�ŐM�����Ȃ����{�̍s���B�u�����d�����v�Ȃǖ��̂܂����B����Ȃ��Ƃ��ᐛ���l�̂ق����}�V�������ƌ����������Ȃ�B���ނ��炻���v�킹�Ȃ��ł���������A��c�����I
�@12��18���A���؎�]��k�ŏo���u�Ԉ��w���v�ɂ������ƌ��������Ă��Ȃ��B���_�A�������哝�̂̃p�t�H�[�}���X�F���Z�������̂�����ǁA1965�N���؊�{���Ɂu�Ԉ��w���v�����荞�܂�Ă��Ȃ������̂͗��j��̎����Ƃ��Ĕ������Ă���̂�����A�u�@�I�ɂ͌����ς݁v�Ƃ�������ɘA�Ă��Ă��A�Ȃ�̉����ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����Ƃ���������������āA���{�̐l���I�Ή��̎��т��A�s�[�����Ԃ̖������u������A���ꂪ�^���ȊO���p���Ƃ������̂���Ȃ��ł��傤���B���肪�k����Ȃ��؍��Ȃ̂�����B�k�Ƃ����A19���u�����������L���S�v�̃j���[�X������܂����B������@�ɁA���ʂ̍��ɐ��܂�ς���ė~�������̂ł����A�܂��܂����P���ᖳ���ł��傤���ˁH
�@��c�����́A�ڂɂ́u����ŗ��A�b�v�v�������B��������悭�u�łƎЉ�ۏ�̈�̉����v�v�Ȃǂƌ����ւ��Ă��܂����A�����Ȃ̎v�f�œ����Ă���̂͌��������ł��B�s�ޓ]�̌��ӂ����āH ���������厖�Ȍ��ߕ���͕ʂ̂Ƃ���Ŏg���Ă��炢�������́B���{�̏���ŗ�5���͐�i�����x�����猩�ĒႷ����̂͐捏���m�B������A�グ��̂͂�����ł���B���̑O�ɂ�邱�Ƃ�����ł��傤���Ă��ƁB��c�������A�C�����u�ɂ݂�������O�ɁA������g���v�ƌ����Ă�������Ȃ��ł����B�u�c���萔�����ƌ��������^�̍팸�v�B�{���͂����ƃ_�C�i�~�b�N�ȉ��v��]�݂����̂ł����ˁB������㎞�ɂ́A�u�����哱�v�Ƃ������Ċ��Ҏ������Ă���܂�������ˁB�ł������A���^�����ɑ����͖]�܂Ȃ��B�����C���\�͂��Ȃ�����A�y�䖳���Șb�ł��B������A��c����A���̌��������Ƃ��炢�͂���Ă���������B�Ƃ肠�������ꂪ��������^�����܂�����B����ȂɃn�[�h���������Ⴄ�̂��߂����ł����ˁB�M���V���ɂ͂Ȃ肽���Ȃ��ł�����B�{���͌i�C��ƃZ�b�g�ɂ��Ă��炢������ł����A����̓D�Ӎɑ��ɂ͖]�ނ������ʂł��傤�B ����ɂ��Ă��A�u���̖@�Ă������ʂ��āA���{�O�̒i�K�Ŗ��ӂ�₤�B�����ʼn��U���I�����s�������v�����āB ���ӂ�₤�Ȃ�ʂ��O�ɂ��̂��X�W���Ă���Ȃ��ł����B���̕��ǂ��܂Ŕ��[�Ȃ́H�I
�@ �@���V�ԑΉ����q�h�C�b�B�c���Ƃ���������h�q�ǒ������{�̖{�����I�t���R�Ƃ��Œ������Ⴄ�B�i�̂Ȃ��\���ŁB����ɑ������b�̑Ή����V���o�_�o�Ȃ�A����������B�}���͊w�����Ƃ��ł��Ȃ������ŁB�܂��A���V���|���̂��H ���V����͐悾���Ă̕s�M�C���c�G�O���S�̎��_�Ŋ��S�ɏI����Ă�l�ł��傤�H ��́A�����͂ǂ������Ďd�����Ă��ł����B�����ƌ��������B���̖��A���͂Ƃ����Δ��R�R�I�v���̂Ƃ��Ɋi�D���āu�Œ�ł����O�v�Ȃ���������āA�������炿���Ƃ������̂ɁA�I�o�}�哝�̂ɋ��鋰���o���āu�m�[�v�ƌ���ꂽ��A���x�͏��Ԃ��́u�g���X�g�E�~�[�v�B���Ƃ͂����m�h�^�o�^����B�������ŋ߂ɂȂ��āA�u�Ӗ�ÈȊO�̑I�������l����K�v������v�����āB�J���������ǂ���Ȃ��B����ォ�牭�P�ʂł�����������Ă��C�����Ȃ��悤�Ȃ��V����܂͂����\����ɏo�Ă��Ȃ��ł�B�ȑO�u�������ނ���v���Č���������Ȃ��́B����Ȃ��Ƃ��炢���A�R�m�B�ڏ��I
�@����ɂ��Ă��A�Ȃ�œ��{�̑�����b�̓A�����J�哝�̂�O�ɂ���ƁA�������u�C�G�X�v���Č������Ⴄ�̂ł��傤���B���ē����͕��邯�ǁA�����Ǝ匠���Ƃ̌ւ�݂����Ȃ��̂������Ă������Ǝv���B�A�����J�����Ă����ƌ��������l��]��ł����Ȃ��ł��傤���ˁB�I�풼�� �A���{�̎匠����邽�߂ɐg��q�����d��������̃G�s�\�[�h���������Ȃ��̂��ȁB21���I�ł͍ō��]���̏����āA�u�C���N�푈�ɋ��͂��Ă�v���ău�b�V���Ɍ���ꂽ��A�����Ɂu�G�u���V���O�v���Č�����������B�ŋ߁A�Œ�̗��j�]���������ꂽ�C���N�푈�ɖӖړI�ɉ��S����������킯���B����Ȃ�A�Œ�x���������E�X��N�����Ζʂ̃N�����g���哝�̂Ɍ������ĕ������u�t�[�E�A�[�E���[�v�̂ق����A�o�J�����LjӐ}���ʓł���ō����������H
�@�u�[�^���������v�Ȃ��������āA�₩�ɗN���N�������K���x�ӎ��B���{�́u���{�̍K���x����̕��������v�Ɏ��|��������ŁB�A�z���B�K���̗v�����݂�ȂԂ��Ă����Ȃ���A��������肾�ƁB����Ȃ��Ƃ��Ă�ꍇ�ł����B��������@���̂Ȃ����{�B��������B�����ŁAMy2011�N�x���s���܂��u�����Ƃ��I�v�Ɍ��߂��B�����m�A�z������b�̑䎌���������A��������������m������Ȃ�����}�ɂ��āB
�@���̍����̕NJ��B�Ŕj�ł���̂������O�������Ȃ��̂����B���W�I�ŁA�ނƓ��m�������������Ƃ́A�������͂ɑ�����s�{���́uNo�v�̏Ȃ̂ł����A���̎v���A�ő��S����B���낢��ᔻ������悤�ł����A�ނ̖ڕW�B���ɑ���M�O�Ɣ��͂ƍs���͂ƃX�s�[�h���́A���̃{���N������c���ɂ͉���Ȃ����́B�������̐��E�Éꂳ����ĂԂȂǁA�ڂ̕t�������ۗ����Ă�B�����C�ɂȂ�̂͏��V�M�]�Ƌ���_�B�O�҂́A�ޗ��̌v�Z�̓��Ȃ炢������ǁE�E�E�B��҂͂܂��ʂ̋@��ɁB�Ƃ�����A���{�̏����͋����O�ɑ��������Ȃ��H�I �s���܂݂Ȃ��炱�����_���āA�V�����N2012�N���}�������Ǝv���܂��B�ł͊F�l�A�ǂ����N���I
2011.12.05 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����31�|40
�@11��29���t�������V���Ɂu���y�]�_�A���_���ߒ����v�Ƒ肵�āA�ߋ��`���݂̉��y�]�_�̗���ƍ���̍s�����ɂ��Ă̋L�����ڂ����i�g�c���q�L�Ҏ��M�j�B�����Ȃ���Ȃ�ɂ��]�_�͂���킯�ŁA�傢�ɋ����������ēǂB�펞���̉��y�]�_�́u�G���̉��y�Ƃǂ����������ׂ����v�Ƃ������Ƃ̐킢�������Ƃ����B�펞���Ő��m���y��n�ނƂ������������ɑ�ς����������l����������B�@���퐴���́u�s�A�j�X�g���p�_�v����A�u�p�f���E�X�L�[���@���Ă��A�L���������Ă��A�������Ղ���͓����������o�Ȃ��v�Ȃ�ꕶ�����p����Ă���B�O���ǂ܂Ȃ��ƁA���҂̐^�ӂ͒͂߂Ȃ����A���������L���b�`�[�ňА��̂������Ƃ������]�_�Ƃ��펞���ɂ����Ǝv�������ł��y�����B�S���Ȃ�������k�u�݂����ȃL�����������̂�����B
�@���㉹�y�]�_�E�̗Y�E�ЎR�m�G����"����̉��y�]�_�̂����"�I�������Љ��Ă���B�H���A�C���^�[�l�b�g��ŒN������]�����R�ɔ��M�ł���悤�ɂȂ�����������A���y�]�_���u���̃��C�����ō��A�ƒf����̂ł͂Ȃ��A���̒n���̂��̃��C��������������A�Ƃ����O�����]�ɂ������w��Č^�x�ɂȂ炴��Ȃ��v�ƁB�����A���͂��̌����ɂ͑g�݂����Ȃ��B���Ă킪���̋���ψ���ł��o����"��Ƃ苳��"��"�ꓙ�܂����߂Ȃ��^����"�Ɍ����郄���ȋC���Ɠ����Ȃ��̂������邩�炾�B"����������"����͉��ɂ����܂�Ȃ��B�����������ゾ���炱���A�t�ɁA�ԈႢ������Ȃ��u���͂��ꂪ��Ԃ��v���f��I�]�_���K�v�Ȃ̂��B����炪�X�ɂԂ��荇���Ă������߂ĐV�������������܂�A�N���V�b�N�E�̕NJ����Ŕj�ł���A�Ǝ��͐M����B�����ɂ����āu���ߍ���簐i�^�v���������x�����̂��A����łȂ��ᐢ�E�͕ς��Ȃ��Ƃ����s������̔��I�ɈႢ�Ȃ��̂ł���B���͂��ꂩ��������Ȃ�̂��ꂵ���Ȃ��u���Ɂv�����߂Đi��ł䂫�����B
�@�ł́A�Ō�́u���Ɂv�L���v�V�����ɂ��āA�V���[�x���g�̊��S�ŏI��ł��B2010�N8��17���t�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�@�v����n�܂��Ĉȗ�1�N4�����A�Ȃ��56��𐔂��܂����B���Ȃ���悭���������̂��Ǝv���܂��B�Ƃ������A����̓V���[�x���g�Ƃ����H�L�ȓV�˂̑���m��Ȃ����͂̐�����ƂȂ̂ł��B�Ƃɂ����A�����Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B����́A�܂��V���ȁu�N�����m�v�����͂��ł�������ȂƎv���Ă��܂��B������ҁI

31 ���ӂ��� D911-6 1827
�u�~�̗��v��6�ȁB�~�����[�̌����ł͑�7�ȂŁA�ȉ��ŏI�ȁu�҉��y�t�v�̑O�܂ł͂��݂����ׂĈႤ���ԂƂȂ�B�̔M���߂��݂����n���������ƂȂ��ď���ɗ��ꍞ�݁A���̐l�̉Ƃɍs���������낤�@�Ɖ̂��B�����O���I�֑�\���̎��ɁA�����ăV���v���ȗL�߉̋ȂěƂ߂�V���[�x���g�̐E�l�|���������́B���t���t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���W�F�����h�E���[�A71DG�ՂŁB
32 �t�̖� D911-11 �~�����[�@1827
 �u�~�̗��v��11�ȁB�u ���͖������A����Ƃ�ǂ�̉ԁA�̖�A���̂������ȏ����̂���������v�Ƃ����������ƁA�u�{�����Ėڊo�߂錻���v�Ƃ̑Δ�̖��B������Ȃ��D�����s�A�m�̒��ׂ�����łB�R��ƌ������������錆��B�u�~�̗��v�ł́A���̋Ȃ̂��t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���u�����f��86���̂�B���̋Ȃ́A�قڃ��[�A�̃��A���X�e�B�b�N��̃s�A�m�Ŗ��Ȃ��̂����A�����̋Ȃ͂��ꂾ���ł͑���Ȃ��B�s�A�m�Ƀm�X�^���W�b�N�ƃn�[�g�t�������K�v�s���Ȃ̂��B����t�ł�s�A�m����D���������ݏo�āA�������̂̋��ɃW�[���Ɣ���Ȃ��Ɓu�t�̖��v�ł͂Ȃ��̂ł���B���̓_�A�u�����f���͊����ł���B
�u�~�̗��v��11�ȁB�u ���͖������A����Ƃ�ǂ�̉ԁA�̖�A���̂������ȏ����̂���������v�Ƃ����������ƁA�u�{�����Ėڊo�߂錻���v�Ƃ̑Δ�̖��B������Ȃ��D�����s�A�m�̒��ׂ�����łB�R��ƌ������������錆��B�u�~�̗��v�ł́A���̋Ȃ̂��t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���u�����f��86���̂�B���̋Ȃ́A�قڃ��[�A�̃��A���X�e�B�b�N��̃s�A�m�Ŗ��Ȃ��̂����A�����̋Ȃ͂��ꂾ���ł͑���Ȃ��B�s�A�m�Ƀm�X�^���W�b�N�ƃn�[�g�t�������K�v�s���Ȃ̂��B����t�ł�s�A�m����D���������ݏo�āA�������̂̋��ɃW�[���Ɣ���Ȃ��Ɓu�t�̖��v�ł͂Ȃ��̂ł���B���̓_�A�u�����f���͊����ł���B33 �Ō�̊�] D911-16 �~�����[ 1827
�u�~�̗��v��16�ȁB�����h�ꗎ���闎���t��͂��������ȃs�A�m�̋�������ۓI�ȓ���������A�R���[�����@���I�ȃG���f�B���O�ɒB�����t�̃h���}�����A�V���[�x���g�̓V�˂̋Z���B���t���t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�����[�A71DG�Ղ��ŏゾ�i�ȉ�34�A35�������j�B
34 ������� D911-20 �~�����[�@1827
�u�~�̗��v��20�ȁB�����l�����̍s����Wege������Ď����s����StraBen�́A�N�ЂƂ�A���Ă������̂̂Ȃ������B������ׂ������h���̓������͍s�������Ȃ��̂��`�����܂ł��Ă������Љ�Ƃ̑a�O����F�����邵���Ȃ���҂̌��鐣�����S����܂�Ȃ��B�����E�����H��"�u�~�̗��v����̌���"�B
35 �҉��y�t D911-24 �~�����[�@1827
�u�~�̗��v��24�ȁB����̍Ō�Ŏ�҂͗������ɂł���l�ԂƏo��B����͓��������̐��̂Đl���C�A�[�e�����B�V���[�x���g�����U���ߑ������u�́v����Ă��̘V�l�ƐS���ʂ������B�u�́v�������ǂ��܂ł����͗��𑱂��Ă䂭�̂ł���B���C�A�[��͂��t���[�Y�������܂Ŗ��@�I�ɘA�Ȃ������ƁA�Ō�̍Ō�Łu�́v�ƍ��̂���V�˓I�ȍ\���B�V���[�x���g�|�p���ɂ̓��B�_���B
36 �� D939 ���C�g�i�[�@1828
D.F.�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E
��Ȃ�Ɛ������邭���ɋP���Ă��邱�Ƃ� ���͂����Ɨl�X�̈Ԃ߂̋`�����ʂ����Ă���� ���܂������̌����������̏j���ɂ��Ă�����`���ւ̊��ӂƊ肢��Â��ɉ̂��P���ȗL�߉̋ȂŁA�@�����̃����E�����̐��E�ȁB�S�W�����t�B�b�V���[���f�B�|�X�J�E�ŁB
 37 �Z���i�[�f D957-4 �����V���^�[�v�@1828
37 �Z���i�[�f D957-4 �����V���^�[�v�@1828D.F.�f�B�[�X�J�E�AH.�z�b�^�[�AP.�V�����C�A�[
�u�����̉́v��4�ȁB�����V���^�[�v�̃V���v���ȗ��̎��Ɋ��\�̃X�p�C�X���ӂ肩�����V���[�x���g�̓V�˂��A�[���Đe���݂₷���Z���i�[�h��n�肠�����B�u�����̉́v�i37�|39�j�́A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�����[�A72DG�Ղ��x�X�g���B��є����������Ɗ����Ȃ܂łɃR���g���[�����ꂽ�\���́A�V���[�x���g�ŔӔN�̉̐��E�𗝑z�I�ɍ\�z���Ă���B
38 �C�ӂɂ� D957-12 �n�C�l�@1828
�u�����̉́v��12�ȁB�l���̍ŏI�ǖʂŏo�������n�C�l�̎��Ƃ̃R���{���[�V����6�Ȃ͂��ׂĈӖ��[����i�ŁA1�Ȃ�I�Ԃ͓̂�����A�D�݂��܂߂��̋Ȃɂ������B�n�C�l�炵���ł̂��鎍���V���v���ȝR��ƓK�x�Ȍ����ŕ�ݍ��ރV���[�x���g�̂�����V�˂̋Z�Ƃ�����B
39 ���̎g�� D957-14 �U�C�h���@1828
�u�����̉́v��14�ȁB�u�䂪�F�V���[�x���g�ցv�Ȃ�Ǔ����������قǐe���������U�C�h���Ƃ̍���́A�V���[�x���g�Ō�̍�i�ƂȂ����B�u�~�̗��v�Ŏ�҂̑a�O�����Ɍ��܂Œǂ����V���[�x���g���A�Ō�ɍ�����̂��y���ȃr�[�_�[�}�C���[���̂��̉̂������̂́A�ǂ����~��ꂽ�C�����ɂȂ�B�ꂵ�݂ʂ����l�����������A���炩�ɏ�����čs�����Ǝv�������B
 40 ��̏�̗r���� D965 �~�����[�^�t�H���E�V�F�W�@1828
40 ��̏�̗r���� D965 �~�����[�^�t�H���E�V�F�W�@1828E.�}�e�B�X�AB.�w���h���N�X�AK.�o�g���AB.�{�j�[
�����Y���N�����l�b�g�̉��F�B���������D��U�������f�B�[�B�����ɏZ�ޗ��l�ւ̂������ꂪ����A�z���͔M���₪�Ĉ��炩�ɕ��V���āA���ɂ͍����t�̒����y�₩�ɋ삯�߂���B�u�����̉́v�̏I�ȁu���̎g���v�ƂƂ��ɃV���[�x���g�Ō�̍�i�Ƃ����Ă���B�����͂̃o�[�o���E�{�j�[�Ɠ��������L���X���[���E�o�g���͍b���t�����������A�����͐����ȃo�g���̉̐��������炩�ɓV���ɔ�ї��V���[�x���g�ɑ��������B�����@�C���̃s�A�m�����C�X�^�[�̃N�����l�b�g������̃e�C�X�g�Ńo�g�����x���Ă���B
2011.11.25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����21�|30
�@�䂪���ł͓��{�V���[�Y�ƃi�x�c�l���ɕ�����11�����{�ł������A���̃T�C�g�̉Ǝ�ł�����F��K�����g���R�ɍs���Ă��܂����B�̂���Ȃɂ��Ɛe���I�ȍ��Ǝv���Ă��܂������A���ꂪ���ɋN�����Ă���̂��H�E�E�E�E�E �ނ́u�g���R�E���|�[�g�v���u�W���Y�ƃ~�X�e���[�̓��X�v�ŐV�Łi11��19���t���j�ł������������B�ł́A�u���Ɂv�L���v�V������3�e�ł��B 21 �܂̉J �i�u���������ԏ����̖��v���j D795-10 �~�����[ 1823
21 �܂̉J �i�u���������ԏ����̖��v���j D795-10 �~�����[ 1823F.�����_�[���q�AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
�̋ȏW�u���������ԏ����̖��v�́A���E�l�̎�҂��A���������ԏ����̖��ɗ������邪�A��l�ɒD���A��]���Ė����Ƃ�������B��10�ȁu�܂̉J�v�́\�\��҂������閺�Ɩ؉A�ŕ���ŏ���������낵�Ă���B���R�̒��ŏ���ƑΘb�����҂͍K�����ɕ�܂�āA�v�킸�܂���B��ꂽ�܂��������́u����A�J����B����Ȃ�B�ƂɋA��v�ƌ����ė��������Ă��܂��\�\���܂��^��ł������Ɍ��������̗���ɕs�g�ȈÉ_���������߂���u�ł���B���̍ŏI�߂ɂ�����V���[�x���g�̓]���̖��͔�ނȂ��A��t�̃s�A�m���Ȃ肠�鋿���͑�14�ȁu��l�v�̏o���ȍ~�̈Ó]���Î�����B�V���[�x���g�▭�̃e�N�j�b�N�ł���B�����Ȏ�҂̐S����Ƃт���̔����ʼn̂��t���b�c�E�����_�[���q�i�e�m�[���j�̖����ŁB
22 �[�f���̒��� D799 ���b�y 1824/25
E.�V���[�}���A�a.�{�j�[�AC.���[�g���B�q�AA.S.V.�I�b�^�[�AD.�e=�f�B�[�X�J�E�AH.�z�b�^�[
�_�����肽���������̐��̔��������A�Â��Ɍh�i��搂�������B�N���̏��Ȃ��W�X�Ƃ����Ȓ��́A����ړ�������A�̎�̐^�̈Ӗ��ł̎��͂�������Ȃ��B�l���̉A�e��[�����ݍ��悤���N���X�^�E���[�g���B�q�i���b�]�E�\�v���m�j�̊���\���́A���̋Ȃ̓������ō��x�ɔ������Ă���B1994�N4���A�E�B�[�����ʉ��t��ł̃��C�u�^���iRCA�j���A1973�N�̃X�^�W�I�^���iDG�j�ɏ���B���҂̍��ق́A�ɂ���Ĉ�����`�Ő��ݏo�����\���Ƃ������̖̂{����`�킹�Ă����B
23 ��Ɩ� D827 �}�e�[�E�X�E�t�H���E�R���[�� 1823
E.�V���[�}���AT.S=�����_���AK.�o�g���A�a.�{�j�[�@B.�w���h���N�X�AF.���b�g�AP.�V�����C�A�[
��̐Â����Ƃ��ꂪ�^���閲�̐_����A�،h�̔O�����߂ĉ̂��B�P����2�߉̋Ȃ����A��2�߂̓]���̖����Ȃɐ[���A�e��^���Ă���B�咲H���f�ɕς���ē�������2�߂́A�r���g�ɂ��ǂ�A�e����o�čēx�g�ɂ��ǂ��čŏI�s�u�܂�������Ă�����A�₳��������ƁvHolde Traume, kehret wieder!�ɘA�Ȃ�J��Ԃ����B���̌J��Ԃ����������ߍŏI�s�Ɠ��������ƂȂ��ĉ�A���Ă���B���̗���̐_�X�����͕M��ɐs�����������A2009�D10�D17�t�u�N�����m�v�Ŏw�E�����u�����ȑ�8�ԃO���[�g�v��2�y�͂� A1�|B1�ڍs����f�i�Ƃ�������̂�����B���炩�ɒW�X�Ɖ̂��V���e�B�b�q�������_���̐_�X�������A��������e�N�j�b�N�����Ɏ��R�ȃL���X���[���E�o�g�����̂Ă��������A�������A�t�F���V�e�B�E���b�g�Ɏ~�߂������B�o�����̃s�A�j�b�V���̔������͂܂�œV��̐��B�䌨������̂��Ȃ��B�Ă��˂��Ȏ��̉��߂Ǝ����݂̉̏��́A�V���[�x���g�̖{���ł���₳��������ׂȂ��`���āA���Ɋ����I�ł���B�s�A�m�̃O���n���E�W�����\�����A�I�m�ȃe���|�ݒ�Ɖ��₩�ȕ\���ōD�T�|�[�g�B�V���[�x���g����[�g�̗��z���������ɂ���B
 24 �Ⴂ��m D828 �N���C�K�[�E�f�E���P���b�^ 1825
24 �Ⴂ��m D828 �N���C�K�[�E�f�E���P���b�^ 1825E.�V�������c�R�b�v�AE.�A�������N�AG.���m���B�b�c�AL.�|�b�v�AK.�o�g���AB.�w���h���N�X
�����ɗh���S���A�Ō�ɂ͐_�ւ̋A�˂����S����\�\����ȐS�̓������A������̉����[�����s�A�m�̉��̏�ɉ̂���B�̂���ɂ́A���ڂɌĉ����������Ɛ����𒉎��ɍČ�����Z�ʂ��v�������B�B�X���閼�̎肽���Ɍނ��āA�G���[�E�A�������N�͐����h�̃C���[�W���悤�ȃh���}�e�B�b�N�ȉ̏����݂���B�_���Ɛ����Ɍ�������������ꐢ���̖����ł���B
25 �A���F�E�}���A D839 �X�R�b�g�^�V���g���N 1825
T.S=�����_���AE.�A�������N�A�O���h�D���E���m���B�b�c�AB.�w���h���N�X�AB.�{�j�[�AA.S.V.�I�b�^�[
�C�M���X�̗��j�����ƁE�E�H���^�[��X�R�b�g�̏������u�Ώ�̔��l�v���A�V���g���N�����h�C�c�ꎍ�V�тɏ������̂̈�Ȃ����́u�A���F�E�}���A�v�B��₳�����}���A�l �����̊肢���������������� ���̂��߂ɐȂ�F�������邱�̎q�̂��߂Ɂ`�߂�w���������̋������A����}���A�Ɍ���G�����̐Ȃ�F��̉̂ł���B�o�[�o���E�w���h���N�X�̉̏��́A�h�i���əz�Ƃ����X�p�C�X�������B���̖����������̓��e�ƍ��v���āA���̋Ȃ̃x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�������Ă���B
26 ���������m����̂����� D877-4 �Q�[�e 1826
E.�}�e�B�X�AF.���b�g�AB.�{�j�[
���̓Q�[�e�B�u�E�B���w�����E�}�C�X�^�[�̏C�s����v����A���K�̏����~�j�������E�B���w�����ւ̓�����̂���A�́u�~�j�����̉́v����̈�ȂŁA�Ȃ́u�Â��ȍ��ցvD403����̓]�p�ł���B�V���[�x���g���A���̎����A�]�p���Ă܂ŃQ�[�e�̎��ɋȂ������Ӑ}�́H �V���[�x���g�̉̋Ȃ̒��ŁA�Q�[�e�̎��ɏ��������͖̂�70�ȁB���̂قƂ�ǂ�1823�N�ȑO�̍�i���B����ȍ~�͂��́u�~�j�����̉́v���A1826�N�ɐ��ȍ���Ă��邾�����B���̋ɒ[�ȍ�ȔN��̃M���b�v�ɁA�Ȃɂ��Ӗ��͂���̂��낤���H �~�j�����̏ł����悤�ȋ��̂�������ׂȂ��̂��G�f�B�b�g�E�}�e�B�X�i�\�v���m�j�̉̏����A�t�ɐX�Ƌ��ɔ���B
 27 �t�� D882 �V�����c�F�@1826
27 �t�� D882 �V�����c�F�@1826E.�V�������c�R�b�v�AE.�A�������N�AB.�w���h���N�X�AF.���b�g�AA.S.V.�I�b�^�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E�AH.�z�b�^�[
��炭�Ԃ��̖�� ���ׂĂ͂��̎��̂܂܁@���낤�̂� ���� �ЂƂ̂�����`�߂��藈��G�߂ɁA�ЂƂ̂�����̂��낢���̂��B�n���X�E�z�b�^�[�i�o�X�j�̊i�����������ȉ̏��́A���̊����ɂ��ʂ���N�w�I�̐��E��\�����Č������B�W�X�Ƃ��Ȃ�����ނ̐l�������e����Ă���悤�Ȗ����ł���B
28 �j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��� D886-3 �U�C�h��1826
K.�o�g���AB.�w���h���N�X
�R�̐߂��A���j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��̂�@�Ƃ������ʂ̌��Œ��߂�����L�߉̋ȁB��e�ɂ��������āA"���̔ނɌ����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ�"�Ǝv���Ă��������A����ς�ꂳ��̌������Ƃ��肾�����A�ƌ��R�~�J����^�b�`�̉́B"�₭��"�̕����ɂ́Amechant�Ƃ����t�����X�ꂪ�Ƃ��Ă���̂��ʔ����B�t�����X��ɐ��ʂ����]���ɂ��ƁA�u�E�E�E�₭���Ȃ��́v�͂��������Ȃ��Amechant�ɂ�"���������̂Ȃ�"�Ƃ����j���A���X�̖Ó��ł���A�ƌ����B�t�����X�ł́A�q������������������Ƃ��ȂǁA�e��"���������̂Ȃ����Ƃ��Ă̓_���INe sois pas mechant�I"�ƌ����Ď��邻�����B�m���ɁA���̉̂́A�j�̏K���ɂ�����߂������ꂿ����Ă��鏗�̋C�������̂������́B�Ȃ�A���Y���q�����ӂ���e�̋C�����ƕς��Ȃ��B�����ŁA���I�M��̒�ā\�\�u�j���Ă݂�Ȓ���Ȃ����́v�͂������ł��傤���B����3��mechant���A���ꂼ��Ƀj���A���X��ς��ĕ\�������o�[�o����w���h���N�X�̉̏��͂ɒE�X�I���h�D�E���v�[�̖�������
 ���s�A�m���f���炵���B
���s�A�m���f���炵���B29 �V�����B�A�� D891 �V�F�C�N�X�s�A�^�o�E�G�����t�F���g 1826
E.�V�������c�R�b�v�AL.�|�b�v�AB.�w���h���N�X�AA.S.V.�I�b�^�[�AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
�V���₳�����Ɣ�������^�������E�V�����B�A�ւ̎^�́B����J�ɍ��߂i�悭�̂������A���l�E�]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�i���b�]�E�\�v���m�j���A���̖̉̂��͂�]���Ƃ���Ȃ��`���Ă����B
30 ���� D911-5 �~�����[ 1827
�u�~�̗��v��5�ȁB����������l�����A���A�ʂ�߂��čs�����̖T��ɂ͂��ĐS������Ă��ꂽ�����������Ă���B�[���ÈŁA�X�q��������Ԃقǂ̋������A����Ȍ����������ł��A���炢�̂��̏ꏊ����͐₦�ԂȂ��₳�����������������Ă���B�������~�̗��ł̈ꎞ�̈��炬�ł���B�䂪���ł́u��ɓY���� ������v�̉̎��ŋ��ȏ��ɍڂ�A�����Ԑe���܂�Ă����B�u�~�̗��v�̉��t�͊T�ˁA�\�t�g�ȉ̐��̒��Ƀ��}���̍���Ɛt�̂ق�ꂳ���߂��t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�����[�A��DG��7�P���x�X�g�B
���lj�CD��
�̋ȏW�u�~�̗��v
�@�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j
�@�@�N���E�X�E�r�����O�i�s�A�m�j 1948�^��
�@�@�W�F�����h�E���[�A 1955
�@�@�W�F�����h�E���[�A 1962
�@�@�C�G���N�E�f���X 1965
�@�@�W�F�����h�E���[�A 1971
�@�@�_�j�G���E�o�����{�C�� 1979
�@�@�A���t���b�h�E�u�����f�� 1986
�@�@�}���C�E�y���C�A 1990
�@�Q���n���g�E�q���b�V���i�o���g���j�A�n���X�E�E�h�E�~�����[�i�s�A�m�j 1933
�@�s�[�^�[�E�s�A�[�X�i�e�m�[���j�A�x���W���~���E�u���e���i�s�A�m�j 1963
�@�n���X�E�z�b�^�[�i�o�X�j�A�n���X�E�h�R�E�r���i�s�A�m�j 1969
�@�w���}���E�v���C�i�o���g���j�A�t�B���b�v�E�r�A���R�[�j�i�s�A�m�j 1984
�@���[�x���g�E�z���i�o���g���j�A�I���O�E�}�C�Z���x���O�i�s�A�m�j 1987
�@�N���X�g�t�E�v���K���f�B�G���i�e�m�[���j�A�A���h���A�X�E�V���^�C�A�[�i�s�A�m�j 1996
�@�}�e�B�A�X�E�Q���l�i�o���g���j�A�A���t���b�h�E�u�����f���i�s�A�m�j 2003
2011.11.15 (��) �b����`�����E�����̃V���[�x���g���V�˘_
 �@����́A�O��\�������Ă����������悤�ɁA�@�����̃����E�����̃V���[�x���g�_���f�ڂ��܂��B����́u���Ɂv�����̊��z���̈ꕔ�Ƃ��đ����Ă������̂ŁA�V���[�x���g�̓V�ː����̑�ȓ�l�̐�l���[�c�@���g�ƃx�[�g�[���F���Ɣ�r���Ȃ���_�������Ƀ��j�[�N�Ŋ����x�̍����_���ƂȂ��Ă��܂��B
�@����́A�O��\�������Ă����������悤�ɁA�@�����̃����E�����̃V���[�x���g�_���f�ڂ��܂��B����́u���Ɂv�����̊��z���̈ꕔ�Ƃ��đ����Ă������̂ŁA�V���[�x���g�̓V�ː����̑�ȓ�l�̐�l���[�c�@���g�ƃx�[�g�[���F���Ɣ�r���Ȃ���_�������Ƀ��j�[�N�Ŋ����x�̍����_���ƂȂ��Ă��܂��B�@���̃N���V�b�N�j��ɋP��3�l�̈̑�ȍ�ȉƂ��A�l�͈�ʓI�ɂ��ꂼ��A�u�V�˃��[�c�@���g�v�u�y���x�[�g�[���F���v�u�̋ȉ��V���[�x���g�v�ȂǂƌĂт܂��B����ɑ������E�����́A�u�O��҂̌ď̂Ɉ٘_�͂Ȃ����A�V���[�x���g�̂͂����ɂ��y������B�ނ͓�l�̉��ɂ��鑶�݂���Ȃ��B�ނ����l�������V�˂Ȃ̂��v�ƌ����Ă���悤�ɁA���ɂ͕������܂��B�����ɂ́A�V���[�x���g������Ȃ�������ނ̐S����Ă��܂��B
�@����ł́A�����E�����́u�V���[�x���g���V�˘_�v���ǂ����B���A�J�b�g�ʐ^�̓����E����U���̐܂ɎB�����u�@�N����]�ރR�X���X�v�ł��B
�������E�����́u�V���[�x���g���V�˂̏v��
�@�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�̋Ȗڂ߂�ƁA�V���[�x���g�̋����ׂ����n�̓V�˂Ԃ�ɁA���߂Ċ������܂��B�u����a���O���[�g�q�F���v����Ȃ��ꂽ�̂�1814�N�A�V���[�x���g17�̂Ƃ��B���̎��Ԃ�`�ʂ����s�A�m���t���A�O���[�g�q�F���̑z���ɔ����ėl�X�ɕω�����A�����āA�N���C�}�b�N�X�́uUnd ach, Sein Kuss! �v�i�����I�ނ̌��Â��I�j�̂Ƃ���Ŏ��Ԃ̓s�^���Ǝ~�܂��Ă��܂��܂����A�܂��A���܂�������͕��Âɖ߂�A���Ԃ͉������Ȃ������悤�ɉ��n�߂�E�E�E�E�E�̐��ƃs�A�m�̎��݂ŗL�@�I�ȗ��ݍ����A�Q�[�e�̎����̂ɂ���_�̂悤�Ȏ肳���I ���[�c�@���g���x�[�g�[���F�����������Ȃ������Ǝv���鍂�����n�ɁA�͂�17�œ��B�������삾�Ǝv���ĂȂ�܂���B���N�ɂ́u�����v�A�u���v���a���B�V���[�x���g�́A���ɂ��̍�����A�㐢�ɂ܂ň��������u����̐X�v�̎���ɓ����Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@���݂Ƀ��[�c�@���g17�̍��̍�i�Ƃ����A�P�b�փ��ԍ���220�Ԃ�����A�����Ȃ͑�28�ԁA�s�A�m���t�Ȃł͑�5�ԁA�̌���10��ڂ́u�r�����̉��l�v�̎���A�x�[�g�[���F���Ɏ����ẮA�����ȑ�1�Ԃ�30�̍�i������A�܂��C�s���ゾ�����̂ł��ˁB�ȏ�A�̑�Ȑ�l�j�l�Ɣ�r���Ă��A�����ɃV���[�x���g�����n���A�ŏ����犮���x�̍�����i���c���Ă�����ȉƂł����������A�������Ǝv���܂��B
�@�̋ȏW�u���������ԏ����̖��v��1823�N�A26�A�̋ȏW�u�~�̗��v��1827�N�A30�i���̑O�N�j�A����ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�u�����̉́v��1828�N�i31�A���̔N�j�A�u�~�̗��v�̎��ɏ��荇�����̂��A�x�[�g�[���F��������1�����O�i1827�N2���j�B30�̎��̃��[�c�@���g�̎�ȍ�i�������܂��ƁA�����ȑ�38�ԁu�v���n�vK504�A�s�A�m���t�ȑ�23�`25�ԁA�̌��u�t�B�K���̌����vK492������ŁA�悤�₭�㐢�܂Ŏc��u����̐X�v�̓�����i�K�B�x�[�g�[���F����30�́A����ƌ����ȑ�P��Op-21�A�s�A�m�E�\�i�^��14�ԁu�����vOp-27-2������A�܂�������i�ɕ��ނ���鎞��ł��B�܂�A�V���[�x���g30�́u�ӔN�̌���̐X�v�̎���A���[�c�@���g�́u�����̌���̐X�̓�����v�ɓ���������A�x�[�g�[���F���́u�����̎���v�Ɖ]����Ǝv���܂��B
�@���[�c�@���g�A�x�[�g�[���F���́A��ȉƂƂ��ďo���������͐�l�̍앗�P���鎖����n�߂��悤�Ɏv���܂����A�V���[�x���g�́A�����Ȃ�A����܂őS���Ȃ������v�V�I�ȉ��y��@���A�����̉̋Ȃʼn���Ă��܂��܂����B����́A�܂��Ɋv���I�Ƃ�����o�����ŁA����܂ł̃o���b�N�`�ÓT�h���y�ւ̊ɂ₩�ȕϑJ����A�����Ȃ�V���[�x���g�Ƃ������₵���V�˂ɂ���āA���}���h�`�ߑ㉹�y�̖������ė��Ƃ��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�@�����āu1828�N�̊�Ձv�I�I �V���[�x���g31�A���̔N1828�N�̍�i�́A�܂��Ɋ�ՂƂ��������悤�̂Ȃ�����̌Q���B�̋Ȃ������グ�Ă��A�̋ȏW�u�����̉́vD957�ɑ�\�����悤�ɁA�܂��Ɂu�_�ȁv�Ƃ������錆�삪�ڔ������ł��B�u�����̉́v�̍Ō�́u���̎g���v�ƁA�h�C�b�`���ԍ��̍Ō�̍�i�ł���u��̏�̗r�����vD965�́A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v�ɂ��䂷�ׂ���i���Ǝv���Ă��܂��B�������A����i�Ƃ��A�y�����ꂽ���l�ւ̓�����̂����ȂŁA�u�V���[�x���g�̑S��i��"�ޕ��ւ̓���"�ł���v���Ƃ��ے����Ă���悤�Ɏv���܂��B�u��̏�̗r�����v�̓N�����l�b�g�̃I�u���K�[�g���t���Ă��܂��B���̃N�����l�b�g�́A�܂�ʼn̎��ɂ���[���J����̖ؗ�̂悤�ɉ̏��Ɛ▭�ɗ��ݍ����܂��B����Ƃ��A������n�镗�Ȃ̂ł��傤���H
�@�E�E�E�E�E�Ƃ����킯�ŁA�����E�����̃V���[�x���g�_���Љ���Ă��������܂����B�����E�����́A���݁A�u���O�u�����E�����̉������l���v�Łu�E�����v��i���Ă��܂��B�����ɂ́A�O�����ۂ�����Ȃ����{�l�ւ̌x�����l���Ă��܂��B�u���O���C�g�Ƃ̌𗬂̗ւ��L�������悤�ł��B�F���������`���Ă݂Ă��������B
2011.10.31 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����11�|20
�@�@�����̃����E�����́u���z���[�����e�v���͂����B�u�w�\�����X�g�x��36�Ȃ���ꂽ�̂���N�U�����߁A�w���ɂ̃V���[�x���g�̋ȁx��I�肳�ꂽ�̂����N��9�����A���̊ԁA����1�N4�����ɓn��M�Z�̃V���[�x���g�̋Ȃɑ���X�|�Ԃ�̐��܂����ɁA�����̎��Ȃ���A�[�r�Ȍh�ӂ�\�����Ă��������܂��v�Ƃ������J�߂̌��t�Ŏn�܂��Ă���B�h���̔ނ��炱�̗l�Ȏ^�������������̂͌��h�̎���Ƃ������́B�����ނ̑��݂��Ȃ�������A�V���[�x���g�̉̋Ȃ̐X�ɂ���قǂ܂łɐ[���肷�邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�B�ނ͑����āA�u���Ɂv�̍ŏ��̃��X�g�ƍŏI���X�g���r���A�u�����Ȃ炱������v�Ƃ����Ǝ��Ă�W�J���Ă��ꂽ�B�@�ȉ��A�����E����u���Ȃ炸�����w���Ɂx�ɓ���Ȃ��Ă��悢�v�Ǝv���y�ȂƂ���ɑ����āu���ꂽ���v�y�ȂɊւ��Ă̌���]�ڂ����Ă��������B
���u���Ɂv����O���Ă��悢�y�ȁ�
�u�e�̂Ȃ����v�F�f���[�j�b�V���ȏ����̌���ł����A�u�O���[�g�q�F���v�A�u�����v���I�肳��Ă���̂ŁA�����ă`�F�C�X����K�v�͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����H�|�s�������e�B�̓_�ł���肠��B
�u�����v�F�����Ȃł����A���y�����銴�������܂��B
�u�����炢�l�v�F�u�����炢�v�́A�V���[�x���g�́u���������ԏ����̖��v�A�u�~�̗��v�̃e�[�}�ł���A�܂��A�V���[�x���g�̐l�����u�����炢�v�Ƃ��v���A�܂��s�A�m�ȁu�����炢�l���z�ȁv�ɂ��̉̋Ȃ̎����g�p�������Ƃ���A�^�C�g���͗L���ł����A�����́A�V���[�x���g�̋Ȃ̒��ł́A���قnj��삾�Ƃ����������v���܂���B
�u���Ɖ����v�F������u�����炢�l�v�Ɠ����悤�Ȋ��������Ă��܂��B
�u�Ⴂ��m�v�F���̉́A�D���Ȃ̂ł����A�u�e�̂Ȃ����v�Ɠ��l�A�|�s�������e�B�̖ʂŖ�肪����Ǝv���܂��B
���u���Ɂv�ɓ��ꂽ���y�ȁ�
�r�����̒Q���̉� D121b�A��̂قƂ�̎�� D300�A�E���t���[�̋��ނ� D525b�A��ϖ����̗��l D558�A�A�e���X D585�A�G�����t�� D586�A���� ��D771�A���U�����f�̃��}���X D797-3b�A�u���b�N�ɂ� D853�A�����A�����A�Ђ�� D889�A�\���ꂽ����� D902-2�A�A�����f D904�A��l�̈��̉� D909�A�M�l�̕ʂ�̉� D910�A�����̉� D917�A���v�̗��̍K�� D933
�u�O��̋ȏW�v�́A�w�ǍD���ȋȂ���Ȃ̂ł����A���ł����ɍD���Ń|�s�������e�B�̍����Ǝv����Ȃ������܂��B
�u���������ԏ����̖��v�F��2�ȁu���Â��ցH�v�A��7�ȁu�����v�A��9�ȁu���ԏ����̉ԁv�i���̋ȁA�����A��ԃ|�s�������e�B�����肻���ł��j�A��19�ȁu��҂Ə���v�i���̋ȁA�����܂��I�j�A
�u�~�̗��v�F��P�ȁu���₷�݁v�A��9�ȁu�S�v�A��13�ȁu�X�֔n�ԁv�A��15�ȁu���炷�v�A��19�ȁu�܂ڂ낵�v�A
�u�����̉́v�F��P�ȁu���̎g���v�A��2�ȁu���m�̗\���v�A��7�ȁu�ʂ�v�A��9�ȁu�ޏ��̊G�p�v�A��11�ȁu�X�v
�E�E�E�E�E���[��A���ꂶ��O��̋ȏW������40�Ȃ����܂��Ă��܂������ł��i�j
�@�Ƃ܂��A����ȋ�ł���B���O���Ă��悢�y�ȁ�5�Ȃɑ������ꂽ���y�ȁ���30�Ȃɏ��B�{25�Ȃ�CD�������ꖇ�K�v�ɂȂ�B��͂�D�݂͐l���ꂼ��ł���B�����̂قƂ�ǂ͑I�莞�Ƀ����E����琄�E���A�����E���f���Ă��邪�A�u�����A�����A�Ђ���v�Ɓu�X�v�͎��^���Ԃ̊W�ł�ނȂ��O�������̂��B
�@�t�ɁA�����E����E�őI�肵���Ȗڂ������B�����Ƌ����Ă݂�ƁA�u�A���v�X�̎�l�vD524b�A�u�^���^���X�̌Q��vD583�A�u�܂̉J�vD795-10�A�u���������m����̂������vD877-4�A�u�j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��́vD886-3�A�u������ׁvD911-20�A�u���vD939�A�u�C�ӂɂāvD957-12�Ȃǂł���B���ɂ��肪�����A�h���@�C�X�������B
�@�ȏオ�����E�����́u�w���Ɂx�I�ȂɊւ���ӌ��v�ł��邪�A�����̂͂ނ��낱�̂��ƁA�u���̔N1828�N�v�����ɘ_����V���[�x���g�V�˘_�ŁA����̓��j�[�N���O���[�o���Ȏ��Ɍ����ȃV���[�x���g�_�ƂȂ��Ă���B����͎���Ŏ��グ�����Ă������������B��A�����҂ł���B�ł́A�L���v�V����11�|20���B
11 �K�j�����[�g D544 �Q�[�e 1817
E.�V�������c�R�b�v�AE.�A�������N�AB.�{�j�[�AB.�w���h���N�X�AF.���b�g�AJ.�m�[�}���AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
�g���C���g���X�̎q�K�j�����[�g���A��_�[�E�X�ɓV��֘A�ꋎ����C�������̂��B �V������������Ƃ��A���炩�ɔ������̂��グ���o�[�o���E�{�j�[�̉̏����A�M���V���_�b�̔����N���霂Ƃ����đf���炵���B
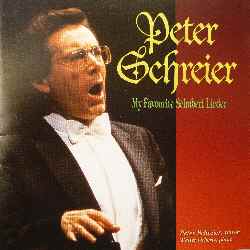 12 ���y�Ɋ� D547 �t�����c�E�t�H���E�V���[�o�[ 1817
12 ���y�Ɋ� D547 �t�����c�E�t�H���E�V���[�o�[ 1817E.�V���[�}���AE.�V�������c�R�b�v�AT.S=�����_���AE.�A�������N�AF.���b�g�AF.�����_�[���q�AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E�AH.�z�b�^�[
���y�ւ̑z���Ɗ��ӁB��ȉƁE�V���[�x���g�̐S��𓊉e�����悤�Ȑe�F�̎��ɁA�e���݂₷�������f�B�[�����B�����܂ŃI�[�\�h�b�N�X�ɐ^���Ɋi�������̂��グ���y�[�^�[�E�V�����C�A�[�ƍ����ȋC�i�����t�F���V�e�B�E���b�g���b�����������������B�V���[�x���g�̋C�������ق���Ƃ����Ӗ�����A�����ł͒j�����̂�B
13 �܂� D550 �V���[�o���g 1817
E.�V���[�}���AT.S=�����_���AE.�A�������N�AL.�|�b�v�AB.�w���h���N�X�AF.���b�g B.�{�j�[�AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
�܂����C�����悭�j���܂��O���ƁA���t�ɕߊl�����㔼�Ƃ����X�g�[���[�\�������A��{�I�ɂ͑O�����[�h�D�悪�������낤�B�T���b�Ɛ��炩�ɉ̂��A�������N�������B
14 �^���^���X�̌Q�� D583 �V���[ 1817
D.F=�f�B�[�X�J�E
�V���[�x���g�̋Ȃ̒��ŁA�V���[��20���ȂƂ����̂́A�Q�[�e�A�}�C�A�[�z�[�t�@�[�Ɏ������B�h�C�c�ÓT��`�̑�\�I�Ȏ��l�ŁA�p�Y��`�A���z��`�ɗ��������ꂽ�j���I�Ȏ��������B�^���^���X�́A�M���V���_�b�ɏo�Ă��閻�E�̈�Ԓ�ɂ���A�_�X�ɔw������ߐl�����Ƃ����Ƃ���B���ł͐_�̗͂��y�����|�Ƌ�s�͂��ʂĂ�Ƃ��m��Ȃ��`�ȑz�͏�ɕs�C���ł��ǂ남�ǂ낵���B�t�B�V���[���f�B�[�X�J�E�ŁB
 15 �t�̑z�� D686 ���[�g���B�q�E�E�[�����g 1820
15 �t�̑z�� D686 ���[�g���B�q�E�E�[�����g 1820E.�V���[�}���AT.S=�����_���AE.�A�������N�AF.�����_�[���q�AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
���Ȃ��̋����Y�݂�Y��邪���� �������Ȃɂ��������ڂ�s���Ƃ��`�f�p�ɏ�L���ɏt�ւ̂�낱�т��̂��B�����Ă����ɂ͑����Ƃ������̃X�p�C�X�������B�t�ւ̊�тƑ����ȋ��̒ɂ݂��o�����X�悭�̂��e���T�E�V���e�B�b�q�������_���i�\�v���m�j�łǂ����B
16 �Y���C�J�T D720 1821
E.�A�������N�AJ.�m�[�}���AB.�w���h���N�X�AB.�{�j�[�AA.S.V.�I�b�^�[
�Q�[�e�̈��l�}���A���l�E���B�����[�}�[�̎��B�����ɑ����āA���l�ւ̂��ƂÂĂ��̂���B���\���ƃG�L�]�e�B�V�Y�������݂���V���[�x���g�Ƃ��Ăِ͈F�̃e�C�X�g�ł���B�u���[���X�͂��̋Ȃ��u���č��ꂽ�ł����������[�g�v�ƕ]�����B���̖����ō��x�ɔ������Ă���̂��o�[�o����w���h���N�X�i�\�v���m�j���B
17 ���̈��A�� D741 �����b�P���g
F.���b�g�AD.F=�f�B�[�X�J�E
�Ǝ��̈��A������������ꂽ�l��@���͂��Ȃ��̂��Ƃ� ���Ȃ��͎��ɂ��Ƃɂ���̂ł��@���̈��A���@���̐ڕ����`���������ꂽ���l�ɑ���ς��ʈ�����̂��B���̐����́A�s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂́u���z�ȁvD934�̑�R���ϑt�Ȃ̎��Ƃ��Ďg���Ă���B���G�ȐS����傫����ݍ��ނ悤���t�F���V�e�B�E���b�g�̉̏����A�e�N�j�b�N����g���ăh���}�e�B�b�N�Ȗ��t��������t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�ɏ���B

18 �~���[�Y�̎q D764 �Q�[�e 1822
E.�V���[�}���AE.�V�������g�R�b�v�AE.�A�������N�AJ.�m�[�}���AB.�w���h���N�X�AF.���b�g�AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
���y�̐�����щ��悤�Ȗ��������S�n�悢�B���������āA����̂悳�ƌy�������|�C���g�ƂȂ�B�G���[�E�A�������N�ƃ��h���t�E�����Z���i�s�A�m�j�̃R���r���x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�������B
19 ���̏�ʼn̂� D774 �V���g���x���N1823
E.�V���[�}���AE.�V�������c�R�b�v�AE.�A�������N�AL.�|�b�v�AF.���b�g�AB.�{�j�[ D.F=�f�B�[�X�J�E
���M�ɂ��Ĕ����������ƌ��肫��߂������Ȃ݂�\���`�ʐ��L���ȃs�A�m�̃}�b�`���O�������B���́A���������R�Ǝ��̗���̒��ɐl���̉A�e�𓊉e����B1988�N�̓��{�f��u�̗��v�ł́AE.�A�������N�̉̏����g���Ęb��ƂȂ����B�ςݏd�˂��l�������R�Ƃɂ��ݏo��悤�ȃV�������c�R�b�v�̖������A�t�F���V�e�B�E���b�g�ɂ͓G��Ȃ��B���M�ɂ��ĉ��[���A�ڂ낤���̉A�e���f���������̉̏��́A�u��̋R�m�v�̃}���V�������̖������z�N������B

20 �N�����͌e�� D776 �����b�P���g 1823
T.S=�����_���AB.�w���h���N�X�AB.�{�j�[�AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
��N�͂킪�₷�炢�@�Â������@��������ɂ��āA�܂��������߂���́`�����C�����ň��̋C�������̂�������B�o�[�o���E�w���h���N�X�̙z�Ƃ����̏��͊����̋ɂ݁B��ɏI�ՁA�u����P���vAllein erhellt�ɂ����銴��ړ��́A���������قǁB�܂��ɖ����ł���B�R��L���ȃ��h�D�E���v�[�̃s�A�m���D�T�|�[�g�B
���O�X�g�ւ̒lj�CD��
�A���F�E�}���A�`�V���[�x���g�̋ȏW DG 1996�^��
�@�@�A���l�E�]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�i���b�]�E�\�v���m�j BENGT FORSBERG�i�s�A�m�j
���`�V���[�x���g�̋ȏW
�@�@�y�[�^�[�E�V�����C�A�[�i�e�m�[���j �����^�[�E�I���x���c�i�s�A�m�j VICTOR 1995
�h�C�c�̋ȏW
�@�@�n���X�E�z�b�^�[�i�o�X�j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j EMI 1957
2011.10.25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����1�|10
�@�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�ɂ́A���̓s�x�����~�߂Ă������L���v�V�����̃X�g�b�N��40�ȕ�����B���e�́A���̑�ӂ�y�ȍ\���ȂNjȂ��̂��̂Ɋւ��邱�ƁA�y�сA�����l�����邻�̋Ȃ̃x�X�g�̏��Ȃǂł���B�O�҂́u���ȉ���S�W�v�i���y�V�F�Њ��j�Ȃǂɏ�����Ă��ĂȂ��ڐV�������̂ł͂Ȃ����A��҂́u�N�����m�v�Ȃ�ł͂̓��e�Ǝ������Ă���B�A���A�L�����A�₩���[�g�E�t�@���̎�ɂȂ���̂䂦�A�����x�Ɏ��M���Ȃ��̂������ȂƂ��낾�B�ł��܂��A���̒m�����A�V���[�x���g�̋Ȉ�Ȃ��Ƃ̒�����ׂɂ��x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�I��K�C�h�Ȃ���̂͐��Ԃɑ��݂��Ȃ��̂�����A���炩�̉��l�͂��邾�낤�B�@�ł́A�J�ɂ���K�C�h�u�b�N�Ƃ͂����Ȃ���̂��H �Ⴆ�ACD�N�W�̒�ԁu21���I�̖��Ȗ��Ձv�i���y�V�F�Ёj�ł́A�u�V���[�x���g�̋ȏW�v�Ƃ��Ĉꊇ���Ĉ����Ă��邾���ł���B���݂ɂ����ł̃x�X�g3�͈ȉ��̂Ƃ���B�S22���g�̃f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j�̏��́u�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�v����1�ʁB�G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v�i�\�v���m�j�ƃG�h�E�B���E�t�B�b�V���[�i�s�A�m�j�ɂ��V���[�x���g�u�̋ȏW�v����2�ʁB�w���}���E�v���C�i�o���g���j�ɂ��u�V���[�̋ȏW�v����3�ʂł���B��1�ʂ�CD22���g"�j���ɂ��V���[�x���g�̉̋ȑS��"�Ƃ������j�I�����Ȃ钴���A��2�ʂ͖������̎�ɂ��X�^���_�[�h�Ȓ�ՁA��3�ʂ̓V���[�̎��ɂ��Ȃ������W�߂����ʓICD���B����ȂɈႤ���i�̃R���e���c���A�]�_�Ɛ搶�͂ǂ�����Ĉꗥ�ɔ�r�ł����̂��낤�H ���̎�̃K�C�h�u�b�N�ň�Ȃ��Ƃ̔�r�������Ȃ͉̂��邪�A���߂Ēj���Ə����A�ʏ�n�Ɗ��n�ɕ�����Ȃǂ̍H�v�������Ă��悩�����̂ł͂Ȃ����B����ł́A�uCD�I�т̗͋����Q�l���v�Ƃ���搂����傪�����Ƃ������̂��B
�@�Ƃ����ꎄ�̏ꍇ�́A40�ȑS�Ăɂ킽��\�Ȍ���َ퉉�t���r�������āA�Ȃ��Ƃ̃x�X�g��I�肷��Ƃ����n���ȍ�Ƃ��s�����B�I��ɂ����čł��d�v��������́A�y�Ȃ̎��u�ŗL�̎p�v�̕\���x���ł���B�p�ɂ͊O���Ɠ��ʂ����邩��A������u�ȑ��v�ƌĂт����B�u�ȑ��v�͌����y�Ȃɔ�����Ă���͂��̂��̂����A�����T��o���͎̂����ł���B�Ⴆ�A�u����a���O���[�g�q�F���v�ɂ�����u�ȑ��v�Ƃ́A�u���ԂȊX���̔�߂�ꂽ��~�ƋC��������r�Ȑ��_�v�Ƃ�����B�����A��Ȃ��ƂɎ����Łu�ȑ��v��ݒ肵�A���t���Ƃɂ��̕\���x�����𑪂�̂ł���B����ȊO�ɂ́A���y�̗���A���̔������A�\���̐[���A���̗ǂ��i��{SP�����Ȃǃ��m�����͏��O�j�Ȃǂ��l�������B�����ɂ����ėL���ғ����l�̈ӌ��͈�ؖ����B���ׂĖ��n�Ȏ��̓ƒf�ōs�����B
�@�ł͈Ȍ�4��ɂ킽��A�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V������10�Ȃ��f�ڂ����Ă��������B�F�l�̖��Ȗ����I�т̏����ł������ɗ��Ă�K���ł���B
�@�Ȃ��A�y�ȃN���W�b�g�̉��i�ɁA������ׂ����t�Җ��Ɩ����ɂ͑S�Ă̎���CD���L�����B�u�����Ɋ܂܂�Ȃ������v�������m�̕��A�u���̃x�X�g�͈Ⴄ�v�Ƃ����������ȂǁA���ӌ��Ղ������Ǝv���܂��B
 1 ����a���O���[�g�q�F�� D118 �Q�[�e 1814
1 ����a���O���[�g�q�F�� D118 �Q�[�e 1814E.�V���[�}���AE.�V�������c�R�b�v�AR.�V���g���C�q�AE.�A�������N�AG.���m���B�b�c�AL.�|�b�v�AJ.�m�[�}���A�a.�w���h���N�X�AF.���b�gB.�{�j�[�AR.�t���~���O�AC.���[�g���B�q
�t�@�E�X�g�̋C���������ꂽ���Ƃ��������O���[�g�q�F���̕s���ȐS��ƁA�܂��c��v��̏���̂��Bkuss(kiss)�ł̏�̍��܂肪����I�����āA���̒���̃s�A�m�̗��ꂪ�S�̗����\���ȂǁA�V���[�x���g�̝R��ƌ����������Ɍ��������L�O��I��i�ŁA���̋Ȃ����������Ƃ����1814�N10��19�����A�h�C�c�E���[�g�a���̓��Ƃ�������������B�t�F���V�e�B�E���b�g�i�\�v���m�j���O���n����W�����\���i�s�A�m�j���f���炵���B�t�@�E�X�g�̂��Ƃ���ڂ���@�̂����̋C�������݁A���h�Ȃ��p�E�E�E�E�E�̌��ŁA�e���|�𗎂Ƃ��ĕ\�����ς�����Ƃ����A�Ō�̌��tschwer�i���ꂵ���j�ɂ�����j���A���X�ɕx�\��͓��M���́B���́u�C�i�Y���F���v�̓Q�[�e�ƃV���[�x���g���n�������O���[�g�q�F������]���Ƃ���Ȃ��\�����Ă���B�O���n���E�W�����\���̃s�A�m���j���A���X�ɕx�݃e���|�ݒ���f���炵���B����Ȃ��̃T�|�[�g���B
2 �e�̂Ȃ��� D138 �Q�[�e 1815
K.�o�g���AJ.�m�[�}���AT.S=�����_���AD.�e=�f�B�[�X�J�E
�͋ꂵ���e���̂Ȃ���т��`�ƌ���I�ɉ̂��B�s�A�m�̉��^�͐S�̕s����\�����̂悤���B�L���X���[����o�g���i�\�v���m�j�́A2���ɖ����Ȃ��Z�����Ԃ̒��ɁA�u���x�Z���\�����Ïk�v�����B�S�̗��ꂪ����ɓ`����Ă���̏����B
 3 ��� D257 �Q�[�e 1815
3 ��� D257 �Q�[�e 1815E.�V���[�}���A�s.�r=�����_���AB.�{�j�[�AB.�w���h���N�X�AF.���b�g�AF.�����_�[���q�A�o.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
�����͌����� �쒆�̂�` �N�ł��m���Ă���e���݂₷���f�p�ȃ����f�B�[�����A���̓��e�͏��N�ɂ����Ȃ��܂��Ă��܂���̂��Ƃ��`����Ă���B����͎Ⴋ���̃Q�[�e�̎��̌����w�i�ɂ���Ƃ����Ă���B��{�I�Ɍy�₩�Ŕ��������A�h���}�e�B�b�N�Ȗ��t����Ԃ��o�[�o���E�{�j�[�i�\�v���m�j�̉̏����ʔ����B������Ƃ�肷���̊������邪�A���̉̂��u���炵�������̉̂ł͂Ȃ��v���Ƃ������ɋ����Ă����B
4 ���� D328 �Q�[�e 1815
Marta Fuchs�AJ.�m�[�}���AG.�X�[�[�AD.F���f�B�[�X�J�E
�s�A�m�͎�������n��͂��A���l�Ȑ����́A���N�A���e�A�����̂��ꂼ��̐��i�`�ʂ��s���B�܂�Łu����̈��ʂ�����悤�ȋٔ����v�������ȍ�i�B�O�҂̈�����L�����N�^�[��I�m�ɕ\���ł���̂́A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j��u���đ��ɂ͂��Ȃ��B���w���̍��A�g�X�J�j�[�j���u100�N�Ɉ�x�̐��v�Ə^�������l�A���g�̎�}���A���E�A���_�[�\����SP�ł悭���������̂����A����CD��������Ă͂��Ȃ��悤���B�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́A�ނɂ��Ă͍r����EMI�Ղ��A�����x����DG�Ղ��H ���D�݂łǂ����B
5 ����߂̘A�� D343 ���R�s 1816
�e.���b�g�AD.�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E
��₷�炩�Ɍe�� ���ׂĂ̗�� �ꂵ�ݖ��키���̂��������I��������̂��@�܂̐��𐔂����ʏ����� �_��ڂ̓�����Ɍ������̂��@���ׂĂ��̐����狎�������� ���ׂĂ̗�͂₷�炩�Ɍe���`���ׂĂ̗�ɋF����������A����߂ɂ�����A���i�i�ՂƉ�O�Ƃ̌��݂̋F��j�̉́B�V���v���ȗL�߉̋ȂɃV���[�x���g�̏������Ƃ₳���������߂��Ă���B���̈����ׂ��̂́A�]�_��KH�����炢���������u�t�F���V�e�B�E���b�g �V���[�x���g���̂��v�ŏ��߂Ēm�����B���̑��ł́A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�̑�S�W�Ɋ܂܂�Ă�����̂��������m��Ȃ��B�����Ƃ������R�[�f�B���O�������Ă������̂ɂƎv���B�t�F���V�e�B�E���b�g�̒W�X�Ƃ������R�ȉ̏��ɂ́A�u���炩�Ȍh�i���v���h���Ă���B
6 ���� D433 �w���e�B�[ 1816
R.�V���g���C�q�AE.�A�������N�AL.�|�b�v�A K.�o�g���AF.���b�g�AP.�V�����C�A�[�AD.�e���f�B�[�X�J�E
���V���ɍs���ĉi���̊�тɐZ��̂��������A���͔ޏ��̔��݂ɕ�܂�Ă��܂ł������ɂ������`�{���͒j�̂����A�Ȓ����珗���������B�u�K�����v���X�g���[�g�ɏo���G���[�E�A�������N�i�\�v���m�j�̖��邭�L�т₩�ȉ̏����������B
7 �����炢�l D489 �����[�x�b�N 1816
�y�[�^�[�E�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
��킽���͂ǂ��֍s���Ă��悻�҂��B�킽���̈����鍑�͂ǂ��ɂ���̂��낤���B�u�ǂ��ɁH�v�Ɩ₦�u�K���͂��܂��̂��Ȃ��Ƃ���ɂ���̂��v�ƁA�����܂ƂȂ��ĕԂ��Ă���\�\�@�V���[�x���g�́A���̐������s�A�m�ȁu�����炢�l���z�ȁvD547�̑�Q�y�́E�ϑt�Ȃ̎��Ɏg���Ă���B�u�o���̂Ȃ���]���v�������ɉ̂��y�[�^�[�E�V�����C�A�[�i�e�m�[���j���x�X�g���B
8 �q��� D498 ��ҕs�� 1816
R.�V���g���C�q�AP.�V�����C�A�[
�����ꖰ���̋��Ɂ@���ꖰ���̎�Ɂ`�Ŏn�܂�A���[�c�@���g�A�u���[���X�Ƌ��ɒm��ʐl�Ȃ��q��̖̂��ȁB�V���[�x���g�̎q��̂́A���̑��Ƀ}�C�A�[�z�[�t�@�[�̎��ɂ��D527�A�e�I�h�[���E�P���i�[D304�A�U�C�h��D867������B�A�������N�̐��炩���Ɂu�ꐫ�̉������v���v���X�����悤�����^�E�V���g���C�q�i�\�v���m�j�łǂ����B
9 �A���v�X�̎�l D524b �}�C�A�[�z�[�t�@�[ 1817
D.F=�f�B�[�X�J�E
�}�C�A�[�z�[�t�@�[�̓V���[�x���e�B�A�[�f�̈���B�V���[�x���g�̉̋Ȃ̒��ŁA50�ȗ]�ɔނ̎����p�����Ă��邪�A����̓Q�[�e�Ɏ������ł���B�㕔�I�[�X�g���A�o�g�����ɁA�A���v�X��G�����t�ȂǁA�Y��Ȏ��R��w�i�ɂ������������B�ŏ��́i�������������j�Ȓ����D�݂���Ȃ��̂ŊO���\�肾�������A�u�V���[�x���g�̗F�l�̒��ł́A�ł����̐����������A�㕔�I�[�X�g���A�̎��R���̂������̂������ׂ��v�Ƃ��������E�����̏����ɂ��I��B���Ȃ������R�̔w�� �����߉��낷�̂��A���v�X�̎�l�̊y���݁A�Î�̒� �ڂ̑O�ɂ��킢�����̖��̎p��������ł���
 �`�u���[���b�p�ŎR�j�̉́v���t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�������Ɖ̂��B
�`�u���[���b�p�ŎR�j�̉́v���t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�������Ɖ̂��B10 ���Ɖ��� D531 �N���E�f�B�E�X 1817
J.�m�[�}���AP.�V�����C�A�[�AD.F=�f�B�[�X�J�E
��P�߂������ő�2�߂����_�̑䎌�Ƃ����ݒ�B���������āA�u��҂̐��i�`�ʁv���|�C���g�B���y�l�d�t��D810�u���Ɖ����v�̑�Q�y�͂́A���̐��������Ƃ���ϑt�Ȃł���B�W�F�V�[�E�m�[�}���i�\�v���m�j�̐��݂�������͂��A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�̕��O�ꂽ�Z�ʂ𗽉킵�Ă���B
������CD��
�G���U�x�[�g�E�V���[�}���̌|�p��1�W�^E.�V���[�}��(S)G.���[�A(P)1936�N�^��*
�V���[�x���g�̋ȏW�^�G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v(S)E.�t�B�b�V���[(P)1952*
�V���[�x���g�̋ȏW�^�G���[�E�A�������N(S)�_���g���E�{�[���h�E�B��(P)���h���t�E�W�����Z��(P)1972�|1984
�V���[�x���g���̂��^���`�A�E�|�b�v�iS)�A�[�E�B���E�Q�C�W�iP�j1983
Schubert Lieder�^�W�F�V�[�E�m�[�}���iS)�t�B���b�v�E����(P)1984
�V���[�x���g�̋ȏW�^�o�[�o���E�{�j�[(S)�W�F�t���[�E�p�[�\���Y(P)1994
Schubert Lieder�^�o�[�o���E�w���h���N�X(S)���h�D�E���v�[(P)1985&1992
�x�X�g�E�I�u�E�V���[�x���g�^���l�E�t���~���O(S)�N���X�g�t�E�G�b�V�F���o�b�n(P)1996
�V���[�x���g�̋ȏW�^�G�f�B�b�g�E�}�e�B�X(S)�J�[���E�G���Q��(P)1988
�V���[�x���g���̂��^�t�F���V�e�B�E���b�g(S)�O���n���E�W�����\��(P)1988
�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�������Ł��O���h�D���E���m���B�b�c(S)�N���X�^�E���[�g���B�q(MS)�A�[�E�B���E�Q�C�W(P)
�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�^�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E(B)G.���[�A(P)
���̉́`�V���[�x���g�̋ȏW�^�L���X���[���E�o�g��(S)�W�F�C���Y�E�����@�C��(P)1986
�V���e�B�b�q�������_���̌|�p�^�e���T�E�V���e�B�b�q�������_��(S)J.�{�m(P)�^���N�s��
�V���[�x���g���̋ȏW�^���^�E�V���g���C�q(S)�G���b�N�E���F���o(P)��
�V���[�x���g�̋ȏW�^�y�[�^�[�E�V�����C�A�[(T)�����^�[�E�I���x���c(P)1995
�U�E�x�X�g�E�I�u�E�V���[�x���g�^�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���jG.���[�A�i�s�A�m�jEMI
�@�@S=�\�v���m MS=���b�]�E�\�v���m T=�e�m�[�� B=�o���g�� P=�s�A�m *���m����
2011.10.13 (��) �u���Ɂv���Ɋ���
 �@��߈�N�]�A���Ɂu���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�����������BPU-CD�Ƃ��Č`�Ɏc�����������̂ŁACD2��160���܂ł̎��^��O���ɒu���Đi�s�����B���̌��ʁA40�Ȏ��^�ɗ����������BPU�Ƃ�private brand��PB�ɑ���private use�̂���ł���B�l�g�p�Ƃ����Ă��A����]�̕��ɂ͍����グ��̂ŁA�ǂ��������Ȃ����\���t�����������B
�@��߈�N�]�A���Ɂu���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�����������BPU-CD�Ƃ��Č`�Ɏc�����������̂ŁACD2��160���܂ł̎��^��O���ɒu���Đi�s�����B���̌��ʁA40�Ȏ��^�ɗ����������BPU�Ƃ�private brand��PB�ɑ���private use�̂���ł���B�l�g�p�Ƃ����Ă��A����]�̕��ɂ͍����グ��̂ŁA�ǂ��������Ȃ����\���t�����������B����ɂ��Ă��ŋ߁ACD�V���b�v�̃h�C�c�E���[�g�i�̋ȁj�̍ɂ͔߂����قǏ��Ȃ��B10�N�قǑO�A�R���s���[�V�����S���̂���A�I���j�o�X�̃N���V�b�NCD�A�Ⴆ�u�N���V�b�N�E�x�X�g100�v6���g3000�~��̂����p�Ղ����肪�ǂ����ꂽ���̂����A���炭������ăN���V�b�N�ɐe�����[�U�[���A���̂܂܃w�r�[�E���[�U�[�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ������B�����Ă��a��"�h�C�c�E���[�g"������̂ɂ܂œ��ݍ���ł���t�@���͂قƂ�NJF���������ɈႢ�Ȃ��B�V���ȃt�@�������܂�Ȃ�����A�h�C�c�E���[�g�̃R�[�i�[�̓X�J�X�J�Ȃ̂��B�������́u�������畷���Ă��������v�Ƃ͌����Ȃ��B�V���[�x���g�D�������F���Ă������ł����A��璮���Ă����̂͌����Ȃ�s�A�m�ȂȂǂ̊�y�ȂŁA�[���ȉ̋Ȃ̐X�ɕ����������̂́u�̋Ȃ�m�炸���ăV���[�x���g�D���Ƃ����邩�I�v�Ƃ����V�̐����Ă���Ȃ̂ŁA�܂�2�N���o���Ă��Ȃ��B
�@���ꂩ��́A�V���[�x���g�̉̋�600�]�Ȃ͐l�ނ̕�ł���Ǝv����悤�ɂȂ����B�����Ė����z�ȋȂ����ł͂Ȃ��B�\���Ă��邩�炱�����������Ă���Ȃ��������B���S�ɉ��ɔ�э��߂A�����ɂ͖����̉F�����L�����Ă���B�����̖��Ȃ�����������ł����B����ł��A�u��͂�Ƃ����ɂ������v�ƌ�������ɂ́A�u�Ȃ���́w���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�x���Ă��������B�����ɂ͒N�����e���߂閼��40�Ȃ��l���Ă��܂��B�������́B�y�����́B�e�މ́B�͋����́B�Â��ȉ́B���炩�ȉ́B���炩�ȉ́B�߂����́B�����I�ȉ́B���z�I�ȉ́B�h�i�ȉ̂ȂǁA�l�Ԃ̗l�X�Ȋ���l�܂��Ă��܂��B���Ȃ��́A���̎��X�̋C���ɍ��킹�ĕ����Ă݂Ă��������B�����Ƒf���炵�����_���E���L����ł��傤�v�Ɛ\���グ�����B
�@����ł͂����ŁA�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�̐���R���Z�v�g��U��Ԃ��Ă����܂��傤�B
�@������R���Z�v�g��
�@�@ �V���[�x���g�̑S�̋Ȃ���s�ӑI��2���gCD�Ƃ���B
�@�A �Ȑ���40�ȑO��Ƃ���B
�@�B �ȏ��͍�ȔN�㏇�ɕ��ׂ�B
�@�C �L���Ȃ͗D��I�ɃZ���N�g����B
�@�D �������D���ȋȂ͉\�Ȍ���I�Ȃ���B
�@�E �I�Ȃɂ����āA���l�̈ӌ��͑��d���邪�A�ŏI�I�ɂ͎����̍D�������Ŕ��f����B
�@�F ��ɓ������̉�������x�X�g���t���Z���N�g����B�����ɂ����Ă͑��l�̈ӌ��͖�������B
�@�G �l�l�������Ċy���߂�悤�ɁA�Ȃ��ƂɃL���v�V�����������B
�@�I�Ȃɂ����ẮA"���l�̈ӌ��d����"�̂ŁA�h�C�c�E���[�g�̐\���q"�@�����̃����E�����"�ɔ��H�̖�𗧂Ă����Ă�������B�����āA���X���~�y�������������i�s�����B�ނ̏����Ńt�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv���w���A�Q�l�ɂ����B�܂��A�ނ̏����u600�]��̉̋Ȃ̒�����40�Ȃɍi��Ȃ�āA���Ƃ��Ɩ��d�ȍs�ׁB����ł����̂Ȃ�A��߂�ߐ��}�ɂȂ�ʂ悤�Ɂv����ۓI�������B����ɂ��ẮA���ʓI�Ɉ�N�ȏ�|�������̂�����悵�Ƃ��Ă����������B�܂��u���Ɂv�Ƃ����������܂����^�C�g�����A�����̐�����ԂɖƂ��ċ����Ă������������B�����̖͗l��2010�N7��7���t�u�@�����̃����E�����P�v����7��ɂ킽���āu�N�����m�v�ɏ����Ă���̂ł��Q�Ƃ��������B�ނɂ͍��A���������u���ɁvCD���Ă�����Ă���̂ōŏI�ӌ����y���݂ł���B������߁X�u�N�����m�v�ŏЉ�����ł��B
�@�����ŁA�D�������D���ȋ� �̊���A����������_�ɂ�╪�͓I�ɏq�ׂ����Ă��������B���̍D�݂̍��W���́A���C���h���������E�A�A�b�v�����X���E�A�r�[�g�����}�C���h���ɂ���B�������y���犴���Ƃ肽�����́A����́A�������������������̋��L�����A���炩������̌h�i���A�_�X��������̑������A�D�������₩������̈��炬�Ƃ������Ƃ��낪�D�悷��B�Ȃ̂ŁA�u���Ɂv�́A�K�R�I�ɁA�����e���|�̒j���I�ȋȂ������₩�ȏ����I�ȋȂ������Ȃ��Ă���B�����F�j���̔䗦��23�F17�i3��̋ȏW��������23�F7�j���B�ꌾ�Ō����Ă��̋ȏW�͏����F�������B
 �@��ɓ���\�Ȍ����CD���r�������ĉ��t�̑I��������B�O�����t�H���́u�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�v�𒆐S�ɁA�u�~�̗��v�̓f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i8��j�A�n���X�E�z�b�^�[�i2��j�A�w���}���E�v���C�A�Q���n���g�E�q���b�V���A�}�e�B�A�X�E�Q���l�A�s�[�^�[�E�s�A�[�X�A���l�E�R���A�N���X�g�t�E�v���K���f�B�G���Ȃǖ�20��A�u���������ԏ����̖��v�u�����̉́v�͏��X�A�̋ȏW�����ł́A�G���U�x�[�g�E�V���[�}���A�G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v�A�e���T�E�V���e�B�b�q�������_���A�G���[�E�A�������N�A�W�F�V�[�E�m�[�}���A�G�f�B�b�g�E�}�e�B�X�A�L���X���[���E�o�g���A�o�[�o���E�w���h���N�X�A�t�F���V�e�B�E���b�g�A�A���l�E�]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�A�o�[�o���E�{�j�[�A�N���X�^�E���[�g���B�q�A�j���ł̓t���b�c�E�����_�[���q�A�y�[�^�[�E�V�����C�A�[�ȂǁA���v80���قǁB�����̂����A���j���߂�u�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�vCD30���g�́A��ɂ���Ğw�R�y�����ɂ��肵���B����܂����ӂ̋ɂ݁I ���̑��̂قƂ�ǂ́A���̂��߂ɐV�����������ꂽ���̂����A�]�_�Ƃ̒��J�쎁���璸�Ղ����u�t�F���V�e�B�E���b�g �V���[�x���g���̂��v�͉��ɂ��ウ��������ʂ̈�i�������B�u���Ɂv�̃x�X�g���t�I��ɔ��Ԃ��|�������̂͂���CD�̂��A�ł���B���̗l�q�́A2010�N8��9���t�u�N�����m�v�ɏ������Ă��������Ă���B
�@��ɓ���\�Ȍ����CD���r�������ĉ��t�̑I��������B�O�����t�H���́u�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�v�𒆐S�ɁA�u�~�̗��v�̓f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i8��j�A�n���X�E�z�b�^�[�i2��j�A�w���}���E�v���C�A�Q���n���g�E�q���b�V���A�}�e�B�A�X�E�Q���l�A�s�[�^�[�E�s�A�[�X�A���l�E�R���A�N���X�g�t�E�v���K���f�B�G���Ȃǖ�20��A�u���������ԏ����̖��v�u�����̉́v�͏��X�A�̋ȏW�����ł́A�G���U�x�[�g�E�V���[�}���A�G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v�A�e���T�E�V���e�B�b�q�������_���A�G���[�E�A�������N�A�W�F�V�[�E�m�[�}���A�G�f�B�b�g�E�}�e�B�X�A�L���X���[���E�o�g���A�o�[�o���E�w���h���N�X�A�t�F���V�e�B�E���b�g�A�A���l�E�]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�A�o�[�o���E�{�j�[�A�N���X�^�E���[�g���B�q�A�j���ł̓t���b�c�E�����_�[���q�A�y�[�^�[�E�V�����C�A�[�ȂǁA���v80���قǁB�����̂����A���j���߂�u�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�vCD30���g�́A��ɂ���Ğw�R�y�����ɂ��肵���B����܂����ӂ̋ɂ݁I ���̑��̂قƂ�ǂ́A���̂��߂ɐV�����������ꂽ���̂����A�]�_�Ƃ̒��J�쎁���璸�Ղ����u�t�F���V�e�B�E���b�g �V���[�x���g���̂��v�͉��ɂ��ウ��������ʂ̈�i�������B�u���Ɂv�̃x�X�g���t�I��ɔ��Ԃ��|�������̂͂���CD�̂��A�ł���B���̗l�q�́A2010�N8��9���t�u�N�����m�v�ɏ������Ă��������Ă���B�@�u�x�X�g���t�v�I��̌o�܂́A�y�ȉ���ƂƂ��ɏ������߂Ă������B����ɂ��Ă͎��珇���f�ڂ����Ă�����������ł���B����́A�ŏI���肵��40�Ȃ̃��X�g�����t�^���f�[�^�Ƃ��Ɍf�ڂ��āA�������Ǝv���B�Ȃ��A�Ȗ��̂��ƂɁA��i�ԍ��A���l�A��ȔN���A���t�҂̂��ƂɃ��[�x���Ƙ^���N���L�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v���t�f�[�^�ŏI��
CD1
1 ����a���O���[�g�q�F�� D118�@�Q�[�e 1814
�@ �t�F���V�e�B�E���b�g�i�\�v���m�j �O���n���E�W�����\���i�s�A�m�j
�@ IMP�^FUNHOUSE 1988
2 �e�̂Ȃ��� D138�@�Q�[�e 1815
�@ �L���X���[���E�o�g���i�\�v���m�j �W�F�C���Y�E�����@�C���i�s�A�m�j
�@ DG 1985
3 ��� D257�@�Q�[�e 1815
�@ �o�[�o���E�{�j�[�i�\�v���m�j �W�F�t���[�E�p�[�\���Y�i�s�A�m�j
�@ TELDEC 1994
4 ���� D328�@�Q�[�e 1815
�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j�W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@ DG 1969
5 ����߂̘A�� D343 ���R�s 1816
�@ �t�F���V�e�B�E���b�g�i�\�v���m�j �O���n���E�W�����\���i�s�A�m�j
�@ IMP�^FUNHOUSE 1988
6 ���� D433�@�w���e�B�[ 1816
�@ �G���[�E�A�������N�i�\�v���m�j �_���g���E�{�[���h�E�B���i�s�A�m�j
�@ PHILIPS 1973
7 �����炢�l D489�@�����[�x�b�N 1816
�@ �y�[�^�[�E�V�����C�A�[�i�e�m�[���j �����^�[�E�I���x���c�i�s�A�m�j
�@ VICTOR 1995
8 �q��� D498�@��ҕs�� 1816
�@ ���^�E�V���g���C�q�i�\�v���m�j �G���b�N�E���F���o�i�s�A�m�j
�@ DG 1959
9 �A���v�X�̎�l D524b�@�}�C�A�[�z�[�t�@�[ 1817
�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@ DG�@�̋ȑ�S�W���
10 ���Ɖ��� D531�@�N���E�f�B�E�X 1817
�@�@ �W�F�V�[�E�m�[�}���i�\�v���m�j �t�B���b�v�E�����i�s�A�m�j
�@�@ PHILIPS 1984
11 �K�j�����[�g D544�@�Q�[�e�@1817
�@�@ �o�[�o���E�{�j�[�i�\�v���m�j �W�F�t���[�E�p�[�\���Y�i�s�A�m�j
�@�@ TELDEC 1994
12 ���y�Ɋ� D547 �t�����c�E�t�H���E�V���[�o�[�@1817
�@�@ �y�[�^�[�E�V�����C�A�[�i�e�m�[���j �����^�[�E�I���x���c�i�s�A�m�j
�@�@ VICTOR 1995
13 �܂� D550�@�V���[�o���g 1817
�@�@ �G���[�E�A�������N�i�\�v���m�j ���h���t�E�����Z���i�s�A�m�j
�@�@ PHILIPS 1984
14 �^���^���X�̌Q�� D583�@�V���[ 1817
�@�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@�@ DG �̋ȑ�S�W���
15 �t�̑z�� D686�@���[�g���B�q�E�E�[�����g 1820
�@�@ �e���T�E�V���e�B�b�q�������_���i�\�v���m�j �W���N���[�k�E�{�m�i�s�A�m�j
�@�@ ACCORD �^���N�s��
16 �Y���C�J�TD720�@���B�����[�}�[ 1821
�@�@ �o�[�o���E�w���h���N�X�i�\�v���m�j ���h�D�E���v�[�i�s�A�m�j
�@�@ EMI 1985
17 ���̈��A�� D741�@�����b�P���g 1822
�@�@ �t�F���V�e�B�E���b�g�i�\�v���m�j �O���n���E�W�����\���i�s�A�m�j
�@�@ IMP�^FUNHOUSE 1988
18 �~���[�Y�̎q D764�@�Q�[�e 1822
�@�@ �G���[�E�A�������N�i�\�v���m�j ���h���t�E�����Z���i�s�A�m�j
�@�@ PHILIPS 1984
19 ���̏�ʼn̂� D774 �V���g���x���N 1823
�@�@ �t�F���V�e�B�E���b�g�i�\�v���m�j �O���n���E�W�����\���i�s�A�m�j
�@�@ IMP�^FUNHOUSE 1988
20 �N�����͌e�� D776 �����b�P���g 1823
�@�@ �o�[�o���E�w���h���N�X�i�\�v���m�j ���h�D�E���v�[�i�s�A�m�j
�@�@ EMI 1985
21 �܂̉J�i�u���������ԏ����̖��v���jD795-10 �~�����[ 1823
�@�@ �t���b�c�E�����_�[���q�i�e�m�[���j �t�[�x���g�E�M�[�[���i�s�A�m�j
�@�@ DG 1966
22 �[�f���̒��� D799�@���b�y 1824/25
�@�@ �N���X�^�E���[�g���B�q�i���b�]�E�\�v���m�j �`���[���Y�E�X�y���T�[�i�s�A�m�j
�@�@ RCA 1994�i���C�u�j
CD2
1 ��Ɩ� D827 �}�e�[�E�X�E�t�H���E�R���[�� 1823
�@ �t�F���V�e�B�E���b�g�i�\�v���m�j �O���n���E�W�����\���i�s�A�m�j
�@ 1MP�^FUNHOUSE 1988
2 �Ⴂ��m D828 �N���C�K�[�E�f�E���P���b�^ 1825
�@ �G���[�E�A�������N�i�\�v���m�j ���h���t�E�����Z���i�s�A�m�j
�@ PHILIPS 1975
3 �A���F�E�}���A D839�@�X�R�b�g�^�V���g���N 1825
�@ �o�[�o���E�w���h���N�X�i�\�v���m�j ���h�D�E���v�[�i�s�A�m�j
�@ EMI 1992
4 ���������m����̂����� D877-4�@�Q�[�e 1826
�@ �G�f�B�b�g�E�}�e�B�X�i�\�v���m�j �J�[���E�G���Q���i�s�A�m�j
�@ NOVARIS 1988
5 �t�� D882 �V�����c�F 1826
�@ �n���X�E�z�b�^�[�i�o�X�j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@ EMI 1957
6 �j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��� D886-3 �@�U�C�h�� 1826
�@ �o�[�o���E�w���h���N�X�i�\�v���m�j ���h�D�E���v�[�i�s�A�m�j
�@ EMI 1992
7 �V�����B�A�� D891 �V�F�C�N�X�s�A�^�o�E�G�����t�F���g 1826
�@ �A���l�E�]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�i���b�]�E�\�v���m�j �x���E�t�H���X�o�[�O�i�s�A�m�j
�@ DG 1996
8 ���� D911-5�@�~�����[ 1827
�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@ DG 1971
9 ���ӂ��� D911-6�@�~�����[ 1827
�@ ����
10 �t�̖� D911-11�@�~�����[ 1827
�@�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j �A���t���b�h�E�u�����f���i�s�A�m�j
�@�@ PHILIPS 1986
11 �Ō�̊�] D911-16�@�~�����[ 1827
�@�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@�@ DG 1971
12 ������� D911-20�@�~�����[ 1827
�@�@ ����
13 �҉��y�t D911-24�@�~�����[ 1827
�@�@ ����
14 �� D939�@���C�g�i�[ 1828
�@�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@�@ DG �̋ȑ�S�W���
15 �Z���i�[�f D957-4�@�����V���^�[�v 1828
�@�@ �f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�i�o���g���j �W�F�����h�E���[�A�i�s�A�m�j
�@�@ DG 1972
16 �C�ӂɂ� D957-12�@�n�C�l 1828
�@�@ ����
17 ���̎g�� D957-14�@�U�C�h�� 1828
�@�@ ����
18 ��̏�̗r���� D965�@�~�����[�^�t�H���E�V�F�W 1828
�@�@ �L���X���[���E�o�g���i�\�v���m�j �W�F�C���Y�E�����@�C���i�s�A�m�j �J�[���E���C�X�^�[�i�N�����l�b�g�j
�@�@ DG 1987
2011.09.30 (��) �u���[�����C�v�́u�t�̖��v���琶�܂ꂽ
�@�O��A�u���[�����C�v�́u�t�̖��v����ɍ��ꂽ�H �ƌy���₢��������A���X�ɂ��ꂪ�m�M�ɋ߂����̂ɂȂ��Ă��܂����B�����ō���́A�}篂��̃e�[�}���J�b�g�C�������Ă��������܂��B�ł́A�������ցB�i1�j�W���q���[�`�n�C�l�`�V���[�x���g�̗�
 �@�u���[�����C�v�́A�n�C�����q�E�n�C�l�i1797�|1860�j�̎��ɁA�t���[�h���q�E�W���q���[�i1789�|1860�j���Ȃ�t�����̋ȁB�䂪���ł́A��Ȃ����͒m��˂� �������т� �Ƃ����ߓ��̖ŕ����ȏ��̂Ƃ��ČÂ�����e���܂�Ă��܂����B��Ȏ҂̃W���q���[�́A�h�C�c�̖���e���[�r���Q����w�ʼn��y�w���҂Ƃ��čō��̒n�ʂɂ���A�I���W�i���̍�Ȃ�h�C�c���w�̕ҋȂȂǁA��ɍ����Ȃ̕���Ō��т��c���Ă��܂��B
�@�u���[�����C�v�́A�n�C�����q�E�n�C�l�i1797�|1860�j�̎��ɁA�t���[�h���q�E�W���q���[�i1789�|1860�j���Ȃ�t�����̋ȁB�䂪���ł́A��Ȃ����͒m��˂� �������т� �Ƃ����ߓ��̖ŕ����ȏ��̂Ƃ��ČÂ�����e���܂�Ă��܂����B��Ȏ҂̃W���q���[�́A�h�C�c�̖���e���[�r���Q����w�ʼn��y�w���҂Ƃ��čō��̒n�ʂɂ���A�I���W�i���̍�Ȃ�h�C�c���w�̕ҋȂȂǁA��ɍ����Ȃ̕���Ō��т��c���Ă��܂��B�@�u���[�����C�v�̌����́A�n�C�l�̎��W�u�̖̂{�v�i1827�N���s�j�́u�A���v�Ƃ����߂ɁA��2�Ԗڂ̎��Ƃ��Ď��^����Ă��܂��B�W���q���[�́A�ǂ����ł��̎��ɑ��������̂ł��傤�B�Ȃ��t����ꂽ�̂�1838�N�̂��Ƃł����B���ꂩ��k�邱��10�N�O�A�V���[�x���g�͂��́u�A���v�̒�����6�т�I�яo���č�Ȃ��Ă��܂��B�����͉̋ȏW�u�����̉́v�Ɏ��߂��A1829�N�ɏo�ł���܂����B�I��6�т͑��X�A��8�ԁA16�ԁA19�ԁA23�ԁA26�ԁA27�Ԃ������̂ŁA��2�ԁu���[�����C�v���V���[�x���g�͒ʂ�z�������ƂɂȂ�܂��B���̓��e���V���[�x���g�̍D�݂ɍ���Ȃ������̂�������܂���B��l�͂��݂��o��������Ƃ͂Ȃ������ł��傤���A�n�C�l�̎��W��ʂ��Ă�������ƌq�����Ă����킯�ŁA���ꂪ���j��R�����y���݂̂ЂƂł�����܂��B���Ȃ킿�A�W���q���[�́A�V���[�x���g���f�ʂ肵���u���[�����C�v��S�ɗ��߂āA���Ȃ����o�����Ƃ����킯�ł��B
�@ �i2�j���F�u���[�����C�v�Ɓu�t�̖��v�̗ގ��_
 �@�ł́A��̊y�Ȃ̗ގ��_�������܂��B��r�ӏ��́A�u���[�����C�v�͍ŏI�s��4���߂ŁA�u�~�̗��v��11���u�t�̖��v��4���߂��琬��s�A�m�̃C���g�������Ƃ��܂��B��r���₷���悤�ɁA��̃p�[�g���n�����Ɉڒ����Ĕ�ׂĂ݂܂����B
�@�ł́A��̊y�Ȃ̗ގ��_�������܂��B��r�ӏ��́A�u���[�����C�v�͍ŏI�s��4���߂ŁA�u�~�̗��v��11���u�t�̖��v��4���߂��琬��s�A�m�̃C���g�������Ƃ��܂��B��r���₷���悤�ɁA��̃p�[�g���n�����Ɉڒ����Ĕ�ׂĂ݂܂����B
�@�`����[�^���^���^�^���n�Ƃ������Y������{�ƂȂ��āA�@�ȏ�A�ގ��|�C���g�͂Ȃ��7���ڂɂ��y�т܂����B�@�A�̗v�f�͌���I�ގ��_�Ƃ�����ł��傤�B�e���|���Ⴄ���ߋC�Â��ɂ����̂ł����A���킹��Α����ɑ����`�̋ȓ��m�Ƃ������Ƃ�����܂��B�B�C������ɗ�炸�傫�ȗގ��_�ŁA�@�|�C�͑����A���Y���ƃ����f�B�[���ʂ���̗ގ��̏ؖ��ł��B���ꂾ���ł��\���Ȃ̂ɁA����ɇD�E����͉���A�F����͉̎��܂ł������̂ł��B���̌o���ł�����قǂ܂ł̎������̓��m�͋H�ł��B
�@ �S�̂��x�z���Ă���
�A���q��8����6���q�œ���
�B�`���̉������m�\�\���\�n�œ���
�C�I����4�����m�V���V�h�n�œ���
�D�Œቹ�̓\�œ����B
�E�ō����̓~�ŁA���̎�O�̉��̓\�Ƃ���܂�����
�F�̎��̉̂��o����Ich�œ���
�@�����ł�����Ɩʔ������������Ă݂܂��傤�B�u���[�����C�v�̓����Q�b�g�i�����₩�Ɂj�̑��x�w��ł���A�u�t�̖��v��bewegt�̓��f���[�g�i���f�̑����Łj�̂��ƂȂ̂ŁA�e���|�����킹�ĂȂ��Ă݂܂��B�����A�u���[�����C�v�̓��Y4���߂̃e���|�����f���[�g�ɏグ�Ă����O�t�Ƃ��āA�u�t�̖��v���̂��o���Ă݂Ă��������B�ǂ��ł����H �S����a���Ȃ��Ȃ������ł��傤�B
�@�ȏ�̔�r������A�u�w���[�����C�x�S16���߂́w�t�̖��x�s�A�m�O�t��f�ނƂ��Ă���v�ƌ������B����ɔ�ׂ���A���̃��f�B�[�E�K�K�̓���^�f�Ȃ�ĉ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�i3�j���_�F�u���[�����C�v�́u�t�̖��v����ɍ��ꂽ
�@��������͎��̐��_�ł��E�E�E�E�E�W���q���[��1838�N�̂�����A�n�C�l�́u�̖̂{�v���߂����Ă��܂����B�����Ƀh�C�c�̓`���u���[�����C�v��f�ނɂ������������܂��B�h�C�c�̖��w�▯�b�����W�������Ă����ނ́A�����ɂ��̎��ɋ����������܂����B�����đ����A�ȍ��Ɏ��g�ނ��ƂɂȂ�܂��B�����ɁA���́u�̖̂{�v����Ȃ��������V���[�x���g�̂��Ƃ����̕Ћ��ɓ���܂��B�h�C�c�̖����w�̉��y�ō��w���҂��Ă�l�ł�����A�V���[�x���g�Ɋւ��Đ[���m���������Ă���͓̂��R�ł��傤�B
�@�W���q���[�́AIch weiss nicht was soll es bedeuten�i�Ȃ����͒m��˂� �������тāj�Ƃ����u���[�����C�v�̎��̖`����ǂ݂Ȃ���A�ӂƑM�����B�v�l�Ɗ��o���L���Ƒ��܂��āA�n�C�l���̖̂{�������̉́��V���[�x���g���~�̗� �Ə����āu�t�̖��vIch traumte von bounten Blumen �i���͖����� ����Ƃ�ǂ�̉Ԃ��j�ɍs�������B
�@�W���q���[�ɂ͕��s���ĕʂ̉�H���������Ǝv���܂��B���[�����C���M�l���M�S��8����6���q�Ƃ������]���C���ƃ��[�����C���`�������w�������D���Ƃ����E�]���C���ł��B����炪�������āA�u�t�̖��v�ɘA�Ȃ�A��������h�����āu���[�����C�v�̈�߂��`�����ꂽ�B�u���[�����C�v�Ƃ��������u�t�̖��v�Ƃ����̋ȂɒH�蒅�������f�B�[�Ƃ����߂𒅂��̂ł��B�����āA�S�̂�A�|A'�|B�|A''�Ƃ����\���ł܂Ƃ߂��̂ł��B
�@���_����͎��̐����ł��B��L���̕��͉����Ȃ���������܂��o�Ă��邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ŁA���̉������ؖ��������͉i���ɗ��Ȃ��ł��傤�B�܂��A�W���q���[���p�N�����̂����ӎ��������̂������l�ł��B�Ƃ͂����A���ʋ��ɂ����܂ł̏؋�������̂ł�����A���Ȃ��Ƃ��A�W���q���[���̈ӂ��ۂ��͕ʂɂ��āA�u���[�����C�v�́u�t�̖��v���琶�܂ꂽ �ƋK�肵�Ă��o�`�͓�����Ȃ��Ǝv���̂ł����A�������ł��傤���B�܂��A�u������Ȃ�Ȃ̂�v�Ƃ������x���ȃe�[�}�ł͂���܂����A�Ƃɂ������Ƃ��Ă͂��̍l�؉ߒ���傢�Ɋy���܂��Ă����������A�Ƃ������Ƃł���܂��B�Ō�ɁA���ꂾ���̂��߂Ɂu���[�����C�v�̊y������z���Ă��ꂽ�����w����w�w�R�y�����ɂ͐S���犴�Ӑ\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
2011.09.20 (��) �u�����̉́v����
�����[�����C�ƃn�C�l���@�h�C�c�̖��w���Ƃ���v���Ă������̉́A���̓n�C�����q�E�n�C�l�i1797�|1856�j�̎��������B�u���[�����C�v�́A���C����̊���ʂ�M�l���ǂ�����Ƃ��Ȃ��������Ă��閭�Ȃ�̐��Ɏ���D���Ă��邤���A�₪�Ĕg�Ԃɒ���ł��܂��Ƃ����������[�����C�`������ɂ������́B���Ƀn�C�l�̓M���V���_�b���܂���ɂ���Ȏ��������Ă���B�Ȃ����͒m��˂ǁ@�������т�
�̂̓`���́@������g�ɂ���
���т������䂭�@���C���̗���
�����ɎR�X�@�������f���
�킵�����́@�ܓ��ɗ�����
�����̋��Ƃ�@���݂̂����
�����@�������މ̂̐���
�����������͂Ɂ@�����܂悤
�����䂭�M�тƁ@�̂ɓ���
�⍪������炸�@���₪��
�Q�Ԃɒ��ނ�@�ЂƂ��M��
�����������́@�w�����[�����C
�@�@�@�@�@�@�@�i�F�ߓ��j
�g�̖A���琶�܂ꂽ���_�̂悤�Ɂ@�����������₭�l�̗��l�@"�g�̖A���琶�܂ꂽ���_�̂悤��"�����̕��������A�ǂ����ŕ��������Ƃ̂���t���[�Y���Ǝv������A"�g�̖A�̂ЂƂ��琶�܂ꂽ����"�`"Oh�������r�[�i�X"�B�����A���R�Y�O1970�N�̃q�b�g�ȁu�������r�[�i�X�v�������B�쎍�̊�J���q���u�A�t���f�B�e�i�r�[�i�X�j�͔g�̖A���琶�܂�Ă����v�Ƃ̃M���V���_�b�ɕ�����̂��낤�i�����������炱�̃n�C�l�̎����炩���m��Ȃ����j�B����ȂȂ����T���o���̂��y�����B
��������̂͂��@�ޏ��͑��̒j��I�ԉłȂ̂�����
�ς��ɑς����炢�S��@���̗�������ނ܂�
���Ԓm�炸�̔n�����̂��邱�Ɓ@�ς��ɑς��Ă�邵�Ă����Ȃ�
�@���āA��т̎��ɋ��ʂ���T�O�́u�����������̏��v�B����͉ʂ����Ăǂ����痈�����̂Ȃ̂��H
�@�f���b�Z���h���t�̃��_���l�ƒ�ɐ��܂ꂽ�n�C�l�́A���l��ڎw���n���u���N�ŋ�s���c�ޏf���̐��b�ɂȂ邪�A�����œ������̂͏��l�Ƃ��Ă̌o���ł͂Ȃ��A���������Ƌꂢ�����̖��������B����͏f���̒����A�}�[���G�Ƃ��������ŁA�n�C�l�͔ޏ��̂��Ƃ��u���s���R�Ȃ��������̗ߏ�ŁA�d�����������Ɣ��ȗ₽�������킹���v�Ə����c���Ă���B��L��̎�����͊m���ɃA�}�[���G�Ƒ��ʂ�����̂����o����B�����Ĕޏ��̖��͂Ǝ����̒Ɏ�́A���U�ɂ킽���ăn�C�l�̍�i�ɉe�𗎂Ƃ����ƂɂȂ�B
�@1827�N�A�n�C�l�͎��W�u�̖̂{�v�\�B���ꂪ�q�b�g��i�ƂȂ����B�u���[�����C�v�́A���̒��̑S100�тقǂ��琬��u�A���v�Ƃ����߂Ɏ��߂��Ă���B����Ɂu�A���v�́A�V���[�x���g�Ƒ�������B1828�N1���̂�����F�l���u�̖̂{�v�������A�����V���[�x���g�́A�u�A���v�̒�����6�т�I�яo���Ȃ�t�����B���Ƃɂ���ɂ����ꂪ�ނ��l�̃R���{�̑S�Ăł���B�����āA����6�Ȃ���Ɂu�����̉́v�Ɏ��߂���B�u�A���v��2�Ԗڂɂ́u���[�����C�v�����邪�A�V���[�x���g�̋Ր��ɂ͐G��Ȃ������̂��낤�A�����f�ʂ肵�āA8�ԁA16�ԁA19�ԁA23�ԁA26�ԁA27�Ԃ�I�̂ł���B�����A�����ŃV���[�x���g���u���[�����C�v��I��ł�����A��X�̒m��t���[�h���q�E�W���q���[��Ȃ̏��́i1838�N��j�͉ʂ����Ēa�����Ă������낤���H �Ȃ�����ȋ^���悵�����Ƃ����A���́u���[�����C�v�̖`���̂S�̉��i�ړ����� �\�\���\�j�́A�V���[�x���g�́u�~�̗��v��11�ȁu�t�̖��v�̂���Ɠ���������ł���B�̎��̎n�܂�� Ich �œ����B����͒P�Ȃ���R���낤���B������A�W���q���[�́u���[�����C�v���u�t�̖��v����ɂ��č�����̂ł́H ���_�t����ɂ͍X�Ȃ錟���K�v���낤���A������y�����z���ł͂���B�Ȃ��n�C�l�̎��ɂ̓^�C�g�����t���Ă��炸�A�ȃ^�C�g���̓V���[�x���g���������̂��B
�@�u�����̉́vD957�́A��1�ȁ\��7�Ȃ������V���^�[�v�A��8�ȁ\��13�Ȃ��n�C�l�A�ŏI��14�Ȃ��U�C�h���̎��Ƃ����\���B��8�ȁu�A�g���X�v�̎�l�����w�������s�s�ȏd�ׂ͊���ʗ��ɒʂ���H ��9�ȁu�ޏ��̏ё��v�͎��������ւ̖����A��10�ȁu���t�̖��v�͋P���������ւ̓��ہA��11�ȁu�s��v�͖��@�I�ȓs�s���i�Ɨ��l�̖ʉe�Ƃ̑Δ�A��12�ȁu�C�ӂɂāv�̈��̗܂����������炻��͓ł������Ƃ����|���A��13�ȁu�e�@�t�v�̌��ʂĂʖ���ǂ����߂�e�@�t�͎������g�������Ƃ����}���E�E�E�E�E�ȂǂȂǗl�X�ȃV�`�F�G�[�V�����̒��A���ʂ���L�C���[�h�͗��̎p�Ǝ����̉e�ł���B
�@��12���u�C�ӂɂāv�ŁA�V���[�x���g�́A�n�C�l�̕`���d�����̉e���A�s�C������s�݂Ȃ�����S�̓I�ɂ͝R��Ƃ����I�u���[�g�ŗD������݂��ށB�K���̑����ł����������̗܂����̐g������Ă䂭�B���̗܂ɓł����͔̂ޏ����g�Ȃ̂�����Ƃ��H �ǂ���ɂ��Ă������ɂ̓A�}�[���G�̉e�������B�ꂷ��B�����ɂ��n�C�l�炵�����ƃV���[�x���g�Z�@�̌����ȗZ���B�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�ւ̑I�Ȃ́u�C�ӂɂāv�Ō��܂�ł���B
���x�[�g�[���F���ƃ����V���^�[�v��
�@���[�g���B�q�E�����V���^�[�v�i1799�|1860�j�́A��]�ƁA�����ƁA�Y�ȍ�ƁA���l�Ƃ����}���`�l�Ԃ������B���i�I�ɂ͂��Ȃ�U���I�ŁA�����̐l�C�I�y����ȉƃK�X�p�[���E�X�|���e�B�[�j�i1774�|1857�j�ւ̔ᔻ�Ŗ����グ���B�n�C�l�����H�n�Ȃ烌���V���^�[�v�͓��H�n�B�Ƃ��낪���Ɋւ��Ă͐^�t�̗l���B�����V���^�[�v�̍�i�́A�n�C�l�I�O�q���̌��Ђ��Ȃ����₩�ȝR����������B�|�͐g�̔��f�Ƃ��������̓�l�ɂ͓��ěƂ܂�Ȃ��B
�@�����V���^�[�v��20�䔼�ŃE�B�[���ɏo�Ă���B�����̃E�B�[���ɂ́u���h�����X�̑��A�v�Ƃ��������l�T�����������āA�x�[�g�[���F���A�E�F�[�o�[�A�T���G���Ȃǒ������y�ƁA�O�����p���c�@�[�A�����b�P���g�Ȃǂ̎��l���o���肵�Ă����B�s���h�̃����V���^�[�v�͂����ɓ���B���O�サ�ăV���[�x���g���F�l�o�E�G�����t�F���g�ƂƂ��ɓ����Ă����B�Ƃ��낪���́u���h�����X�̑��A�v�́A�����댯�v�z�ƓE���ɐ����o���x�@�̌���ɂ����1826�N�ɕ�����Ă��܂����B
�@�啨�H���̃����V���^�[�v�̕W�I�͂����܂ł��Ȃ��d���x�[�g�[���F���ŁA�ނ�7�т̎���������A1827�N3��26���A�x�[�g�[���F���͋Ȃ�t���邱�ƂȂ����E���Ă��܂��B�ނ̎���A����7�т͒�q�̃V���h���[����V���[�x���g�̎�ɓn��Ȃ��t����ꂽ�Ƃ���Ă��邪�A�^�U�̒��͕s���ł���B�m���Ȃ��Ƃ́A�V���[�x���g������7�т��܂߃����V���^�[�v�̎�����9�̉̋Ȃ���������Ƃł���i�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv�ł�10�ȂƂȂ��Ă��邪�A����͑����ނ̊��Ⴂ���낤�j�B
�@���̂����u������́v�͖����ɏI���A�u�H�vD945��1828�N4���ɍ�Ȃ��ꉹ�y���t�ł���n�C�����q�E�p�m�t�J�ɕ�����ꂽ�B�c���7�Ȃ�8���ɍ�Ȃ���A�V���[�x���g�̎���A���y�o�Ŏ҃n�X�����K�[���A�n�C�l��6�ȂƃU�C�h����1�Ȃ����킹�A�S14�Ȃ̉̋ȏW�Ƃ��āA1829�N5���ɏo�ł����B���ꂪ�u�����̉́v�ł���B
�@�����V���^�[�v�́A�u�����̉́v�̒��Ɏ���̎��������Ƃ��A�Ȃ�Ǝv�������낤���B������u�Ȃ�Ńx�[�g�[���F������Ȃ��ăV���[�x���g�ȂB�Ȃ�Ƃ����s�^�v�ƒQ������������Ȃ��B����A�����V���^�[�v����A���Ȃ��̎����V���[�x���g�ɒH������̂͂Ȃ�K�^�I�ł���B���̂��A�ł��Ȃ��̖��͉��y�j��ɉi���Ɏc�邱�ƂɂȂ����̂�����B
�@�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�ւ̃Z���N�g�́A��4���u�Z���i�[�h�v�Ō��܂肾�낤�B�R��I�ȗ��̎��Ɋ��\�Ƃ����X�p�C�X���ӂ肩�����V���[�x���g�̖��@���A���S�̌�����Y�݂������̂��B
�@�Ō�̃Z���N�g�́A��14�ȁA�V���[�x���g�Ō�̍�i�Ƃ������u���̎g���v�i1828�N10����ȁj�ł���B���̓��n���E�K�u���G���E�U�C�h���i1804�|1875�j�B�ނ́A�V���[�x���g�̖����̑O���ɁA�u�䂪�F�t�����c�E�V���[�x���g�ɁI�v�Ƒ肷��Ǔ����������قnj̐l�Ƃ͐e���������B��������N�A�V���[�x���g�̖Âƌ������Ă���B����ȃU�C�h���̎��ɂ��r�[�_�[�}�C���[���̉̂��A�V���[�x���g�̈��ƂȂ����̂́A�Ȃɂ��~��ꂽ�C���ɂȂ�B���яG�Y�͂��̒����u���I�c�@���g�v�Łu���[�c�@���g�̔߂��݂͎������� �܂͒ǂ����Ȃ��v�Ə��������A���́u�w���̎g���x�̉���͌y�₩�ɔ��Ă��� �Q���͗��܂�Ȃ��v�ƌ`�e�������B�V���[�x���g�͈��炩�ɓV��֔�ї����Ă������ƐM�������̂ł���B
2011.09.11 (��) �u�~�̗��v����
 �@����9���B�ҏ�������Ɠ����z�����B�|�p�̏H�A���y�̏H�A�N�X����G�߂̓������I ����A�v�X�Ƀs�A�j�X�g�̊C�V���݂ق���ɂ�������B10��10���̃��T�C�^���̑ł����킹�����˂Ẳ�H�ł���B���̉āA�t�����X�̓{�W�����[�̃V���g�[�ŃR���T�[�g�������ꂽ�����ŁA�C�M���X�l�J���e�b�g�Ƃ̃G���K�[�́u�s�A�m�d�t�ȁv�͎��Ɋy�����Z�b�V�����������Ƃ̂��ƁB�ޏ��̑E�߂ŏ��߂�CD�Œ����Ă݂����A�i�������������Ɉ�ꂽ���Ȃ������B���Ăł̓|�s�����[�Ȑl�C���ւ�Ƃ������������A���{�ł������ƒ�����Ă����Ǝv���B
�@����9���B�ҏ�������Ɠ����z�����B�|�p�̏H�A���y�̏H�A�N�X����G�߂̓������I ����A�v�X�Ƀs�A�j�X�g�̊C�V���݂ق���ɂ�������B10��10���̃��T�C�^���̑ł����킹�����˂Ẳ�H�ł���B���̉āA�t�����X�̓{�W�����[�̃V���g�[�ŃR���T�[�g�������ꂽ�����ŁA�C�M���X�l�J���e�b�g�Ƃ̃G���K�[�́u�s�A�m�d�t�ȁv�͎��Ɋy�����Z�b�V�����������Ƃ̂��ƁB�ޏ��̑E�߂ŏ��߂�CD�Œ����Ă݂����A�i�������������Ɉ�ꂽ���Ȃ������B���Ăł̓|�s�����[�Ȑl�C���ւ�Ƃ������������A���{�ł������ƒ�����Ă����Ǝv���B�@�H�̃��T�C�^���́u���̎��ω��v�Ƃ����T�u�^�C�g�������Ă���B���[�c�@���g�A�x�[�g�[���F���A�V���[�x���g�A���X�g���`���l�X�Ȉ��̌`���ǂ̂悤�ɕ\������邩�A������y���݂ł���B�ڍׂ͊C�V������̌���HP (http://mihoebihara.com/ja/information/index.html) ���������������B
�@���āu�N�����m�v�́A��k�ЂŃV���[�x���g�����f�����܂ܕ��u����Ă���B�u�Ȃ�Ă������ē~�̗��v�́A�u�҉��y�t�v�̒����̓���Ȃ�Ƃ������Ĉꉞ�I�~����łĂ����A�����͂�肩�����u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�ɃP�������˂Ȃ�ʁB
�@��N�̍����A�@�����̃����E������6��̂������o�āA��ʋ�31�ȁi�u���������ԏ����̖��v���܂ށj�͊m�肳�����B�����E�����͓Ɠ��̔��w�i���Ƀh�C�c�E���[�g�ɂ́j�������Ă���A����"�N�����y���߂�"�Ƃ����R���Z�v�g�Ƃ͗��ɂ䂦�A���̃M���b�v���ʔ��������B�ނ̏����őI�Ȃ����������āA���C���A�b�v�Ɍ��݂��o���͎̂����B���������ɂ��t�����������������ӂ��Ă��܂��B���āA�c��͔ӔN�̓�匆��u�~�̗��v�Ɓu�����̉́v����̃Z���N�g���B�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�ցA�܂��́u�~�̗��v������낤�B
�@�V���[�x���g��"�Ō�̉̋ȏW"�́u�����̉́v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���̒��O�܂Ŏ�������Ă����̂́u�~�̗��v�������B����͔ނ̗F�l�̏،���������炩�ł���B�����V���[�x���g�Ɂu���Ȃ���900���܂�̍�i�̒��ŁA��ԍD���Ȋy�Ȃ́H�v�Ɩ₦�A�����Ɂu�~�̗��v�Ƃ����������Ԃ��Ă��邾�낤�B���ꂾ���u�~�̗��v�̓V���[�x���g�ɂƂ��Đ^�Ɉ���������́A�܂��ɕ��g�ƌ����Ă�������i���Ǝv���B
�@������A�u�N�����m�v�ł��u�Ȃ�Ă������ē~�̗��v��14����̑����𐔂����B���́u�~�̗��v�ւ̑z���͑S�Ă����ɕ�������Ă���̂ŁA�Z���N�g�͂���������낤�B
���Ō�̊�]��
�@�u�N�����m�v2010�D12�D25�́A�u�w�Ō�̈�t�x�́w�Ō�̊�]�x���x�[�X�H�v�Ƃ����^�C�g���������B�u�Ō�̈�t�v�̓I�[�E�w�����[�̖���Z�ҁB�s���̕a�ɖ`���ꂽ����l�������O�Ɍ�����̗t���U���Ă䂭�̂����āu���̗t���S���������Ƃ����͎��ʁv�Ǝv�����ނ��A�Ō�Ɏc������t�͂��܂ł��c���Ă����B���̌�a��͊�ՓI�ɉB���́u�Ō�̈�t�v�͊K���ɏZ�ޕ��V�l���ǂɕ`�������̂������E�E�E�E�E�Ƃ����X�g�[���[���A�u�~�̗��v��16�ȁu�Ō�̊�]�v�ƕ��������̂ł���B
�@�����Łu�I�[�E�w�����[�́w�~�̗��x���x�[�X�ɂ��ĒZ�҂��������v�Ƃ��������𗧂Ēǂ�����ł䂭�B��̔ނ͂��ǂ�����āu�~�̗��v�ɏo������̂��H ���������\���ꂽ�̂�1905�N������A�܂����R�[�h�ł͕����Ȃ��B�Ȃ�~�����[�̌����͂ǂ����H �I�[�E�w�����[�̐l���ŁA����ɐG���\���͂����Ȃ���H ���ׂĂ䂭�ƁA1902�N�Ƀ~�����[�́u�\�l�b�g�v��1903�N�ɂ͔ނ́u���L�v��u�莆�v���p���ŏ��߂Ċ��s����A�j���[���[�N�𒆐S�Ƀ~�����[�E�u�[�����N�����Ă������Ƃ��m�F�ł����B�I�[�E�w�����[��1902�N����j���[���[�N�Ɉڂ�Z��ł�������A�����Ń~�����[�̍�i�ɐG�ꂽ�\���͑傢�ɂ��肤��B�܂��A�ނ��Ǐ��ɖ�����ꂽ���N������߂������e�L�T�X�B�I�[�X�e�B���̏Z���̑����́A���y�╶�w�����D����h�C�c�n�A�����J�l�������E�E�E�E�E�Ȃǂ������Ă���B�؋��A���I �������ĉ������j���Œǂ����ݓƑP�I�ɗ�����B���ꂪ�u�N�����m�v�I���y�̊y���ݕ��Ȃ̂ł���܂��B
�@�����u�Ō�̊�]�v�͑I��O���������A�����܂Ŋy���܂��Ă��ꂽ�y�Ȃ��O���킯�ɂ͂����Ȃ��B�Z���N�g�I
���҉��y�t��
 �@�u�~�̗��v�̍ŏI24�ȖځB�~�����[�̌����ł��Ō�ɒu����Ă���B���́u�s�v�c�Ȃ��V�l�@�l�̉̂ɍ��킹�ă��C�A�[���Ă��������܂����v�Ō���邪�A�����ɋÏk����Ă���悤�ɁA�u�҉��y�t�v�̃L�C���[�h�́A�V�l alter�A���C�A�[ leier�A�� liedern�̎O�ł���B
�@�u�~�̗��v�̍ŏI24�ȖځB�~�����[�̌����ł��Ō�ɒu����Ă���B���́u�s�v�c�Ȃ��V�l�@�l�̉̂ɍ��킹�ă��C�A�[���Ă��������܂����v�Ō���邪�A�����ɋÏk����Ă���悤�ɁA�u�҉��y�t�v�̃L�C���[�h�́A�V�l alter�A���C�A�[ leier�A�� liedern�̎O�ł���B�@�u�V�l�v�͗����ŕX�̏���t���t���������C�A�[��e�����N�������X���Ȃ��B��M�͂�����B�N���������ɂ���Ȃ����̂Đl�ł���B�Ƃ��낪�u�~�̗��v�ɏo�Ă���B��̐l�Ԃł�����B����ȑO�A�����Ƃ��̕�i��P�ȁu���₷�݁v���j�A���邭�y�����Ȑl�X�i��12�ȁu�ǓƁv�j�A���l�i��17�ȁu���ɂāv�j�Ȃǂ��o�ꂷ�邪�A�����͑z���o�̒��̐l�X�ł���A�����ɂ��Ă��ւ��̂Ȃ��l�������B�u�҉��y�t�v�̘V�l�����A�u�~�̗��v�̒��ŗB���l�������ݐi�s�`�Ŋւ�����l�ԂȂ̂ł���B
�@�u���C�A�[�v�́A�@�G�� �A��I���K�� �B�n�[�f�B�E�K�[�f�B�i�h���[���C�A�[�j�̑��̂ł���B�̎�����"�Ēe�����t�\�Ȋy��"�ł��邱�Ƃ�����B�@�͉��A�̓I���S�[���Ɠ������������町�t�͏o���Ȃ��B�]���āA�u�҉��y�t�v�̊y��̓n�[�f�B�E�K�[�f�B�Ƃ������ƂɂȂ�B�E��ʼn�2�{�̃h���[�����͏I�n�ʑt�ቹ��t�ő�����B�V���[�x���g�́A������s�A�m�̍���ŋ�5�x�̘a���ŕ\�����B�E��͐�������͂��B
�@�u�́v�Ƃ������t���A�����ŏ��߂ēo�ꂷ��B���U�Nj����������u�́v�Ƃ����������u�~�̗��v�̍Ō�̍Ō�Ō������Ƃ��̃V���[�x���g�̊��S�͂������肾�����낤���B���ɔj�ꐢ�Ԃ���a�O���ꂽ��l���̎�҂ɁA�B��c������]���u�́v�������Ǝ��͎v���B��23�ȁi�~�����[�̌����ł͑�20�сj�u���̑��z�v�ŗB��c�������z�Ƃ́A���p�E���������u�M�A��]�A���v�̂����ꂩ�ł���A�ȂǂƂ����c�_�����邪�A���́A�����"�V���[�x���g�́u�́v�Ɠǂ�"�Ə���Ɏv������ł���B������u���̑��z�v�́u�E�C�v�̂��Ƃɒu�����̂��B
�@����܂Ō���邱�Ƃ̂Ȃ������s�A�m�̉E��Ɖ̂́A�u�l�̉̂ɍ��킹�ă��C�A�[���Ă��������܂����v�̌��ł�������ƍ��̂���B���Ԃ���a�O���ꂽ��҂ƃn�[�f�B�E�K�[�f�B�e���̘V�l�́A�̂�ʂ��ĐS���ʂ������A�A�ꗧ���ĕ����Ă䂭�̂ł���B�ǂ�������Ă݂Ă��u�҉��y�t�v�͐�ɊO���Ȃ��B
�����ӂ��܁�
�@�����̉��y���S���t���Ԃň���ł�����N�̂���ӁA�������V���i�ȉ�N���j���u���Z����̂�����̂��ƁA���j���̐�y���v�[���ɐ������Ă���̂����āA���˂Ɂw�~�̗���7�ԁA���ӂ��܁x�ƌ�������ł���v�Ƙb���ꂽ�B���ԂȂǂƌ����͎̂���ɂ�������y�̖ʁX�ŁA60���̎����ŔN���̏W���ł���BN���͖������J���Z�̐��j�����ŁA�������R�`�Ŗ炵�����I��i���̓S���t���l�̐a�m�ł��邪�j�B�u����𑲋ƌ��OB��Řb������A���x�͕ʂ̂���A�w���ӂ��܁x��6�Ԗڂ���Ȃ����A�ƌ����܂��Ăˁv�Ƒ�����B�����Œ��ԁH�̐Έ�搶���u�w���ӂ��܁x�͑�6�Ȃ���v�Ƃ��������A����Ȃ���肪�������B�����Ă��鎄�͂܂��A�u���ӂ��܁v���u�~�̗��v�̉��Ԗڂ̋ȂȂ̂������ɓ����Ă��Ȃ��������ł���B
�@���ׂĂ݂�ƁA�u���ӂ��܁v�̓V���[�x���g�́u�~�̗��v�ł͑�6�Ԗڂ����A�~�����[�̌����W�ł�7�Ԗڂł��邱�Ƃ��������B�Ȃ�AN���̐�y�̓~�����[�̏��Ԃ��A��y�̓V���[�x���g�̋ȏ����������̂��B�u���ΓV���̖��卂�Z�A�b�̓��e�����x���v�Ɖ��Ő���オ�������̂ł���B
�@�ł́A��̂ǂ����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��N�����̂��낤�H�V���[�x���g�̓~�����[�̏��Ԃǂ���ɍ��Ȃ��������ƂɂȂ�A���́H�E�E�E�E�E���ꂪ�A�����u�~�̗��v�����ɑł����ނ��������ƂȂ����B�����āA�u�Ȃ�Ă������ē~�̗��v��14��𐔂����̂ł���B����܂ł͖����̍������u�~�̗��v���A���̐��藧����d�g�݂����m�ɔc���ł���悤�ɂȂ����B�V���[�x���g�������ɍ��ꍞ��ł�����i���������ł����B���m�Ȃ���̂��D���ɂȂ�A��i��ʂ��č�҂̂��Ƃ����g�߂Ɋ�������悤�ɂȂ����B�����Ȃ�̐������Ȃ��āA�O�l���B�̉��߂��܂���Ȃ�ɂ��\�z���邱�Ƃ��o�����B�u�~�̗��v�̒T�������A���ɂƂ��Ă܂��Ɏ����̑̌��������̂ł���B
�@���̂���������^���Ă����������̂�N���ł���B���ӂ�����Ȃ��قǂ̗L���ł���B����Ƃ����̂��Ȃ�ł��邪�A�N�����m�u�Ȃ�Ă������āw�~�̗��x14�ҁv�͋ނ��N���ɕ��������B�����̂��t�������܂߁A�{���ɂ����b�ɂȂ��Ă��܂��B����Ƃ���낵�����肢�\���グ�܂��B�u���ӂ��܁v�A���R�Z���N�g�B
�@�ł́A�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�u�~�̗��v�̕��ɂ́A��L3�ȂƁA���ȏ��ɂ��ڂ��Ԃ̗L�����u�����v�A���ۂ̐S����ɟ��݂��u�t�̖��v�A�����E����ō�����ƌ������u������ׁv��3�Ȃ������A�S6�Ȃ��Z���N�g����B����́u�����̉́v�B
2011.08.31 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�2
���A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N���u�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�v�B������܂����[�c�@���g�̃Z���i�[�h�ł͍ł��m���Ă����Ȃ��낤�B�����̃v���O�����ł́A���y�l�d�t�ɃR���g���o�X���������d�t�ō\������Ă���B�{���͎l�d�t�̎����y�ȂȂ̂�����ǁA�����40�l�Ґ��ʼn��t���悤�Ƃ����̂��B�@����͖����o�������`�����e�B���y��ɂ�����L�q�ł���B�u�A�C�l�E�N���C�l�v�́A�{���͌��y�l�d�t�̋Ȃ����A�����ł̓R���g���o�X���������d�t�łȂ�����40�l�Ƃ�����Ґ��ł̉��t���B���ꂾ���Ƀr�I���̉������v���Ă��܂��Ȗ{���̂悳���o�Ă��Ȃ��E�E�E�E�E�ȂǂȂǁA��Ґ��䂦�̕��Q��X�Ƃ��Đ����Ă���B
�@���A����͒v���I�ȃ~�X�E�W���b�W�B���̉��y�m���ɂ͐h�����̂�����B
�@�u�{���͎l�d�t�v�͊��S�Ȍ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̋Ȃ͌��X��1���@�C�I�����A��Q���@�C�I�����A�r�I���A�`�F���A�R���g���o�X�Ƃ������y�ܕ��̌`�ŏ�����Ă���̂�����B
�@�ł́A�P�p�[�g��l�̎����y�̌`�ʼn��t���ׂ��Ȃ̂��A����Ƃ������̌��y���t�������̂��H ����ɂ��Ẵ��[�c�@���g�̎w���͂Ȃ����A�����y�̕Ґ��Ƃ����ϓ_���猩��ƁA�R���g���o�X����̌��y�d�t�Ƃ����`�͂��蓾�Ȃ��B���[�c�@���g�Ɍ��炸�A���̕Ґ��ł̎����y�͂��̎��������݂��Ȃ�����ł���B���ɁA�y�ȃ^�C�g��������A�����y�ɂ�鉉�t�͐������������B�Ȃ��Ȃ�A�u�Z���i�[�h�v�͖�O�p�̋@��y�ŁA�I�[�P�X�g���ʼn��t�����̂��ʗႾ���炾�B���������āA�u�A�C�l�E�N���C�l�v�́A������̗��R����A�ܕ��ɂ�錷�y���t�ʼn��t����̂��Ó��Ȃ̂ł���A���R���̂����u�{���͎l�d�t�̎����y�ȁv�͓�d�̃~�X��Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B
 �@���R���̂悤�ȏ����I�Ȋ��Ⴂ�͕ʂɂ��Ă��A�u�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�vK525�͎��ɓ䑽�����ȂȂ̂ł���B���[�c�@���g�̃Z���i�[�h�́A�قƂ�ǂ��Ⴋ���̃U���c�u���N����ɏW�����Ă���A�@��y������A�Ⴆ���ꂻ��̌������̂��߂Ƃ����X�Ƃ̑��q�̓��w�j�p�[�e�B�[BGM�Ƃ��A��Ȃ̖ړI���n�b�L�����Ă���B�Ƃ��낪�A�E�B�[���ŏ����ꂽK525�ɂ͂܂��������ꂪ�Ȃ��B�������Ĕ����҂��ړI�����肳��Ă��Ȃ��̂��B������̓�͊y�͐��ł���B�������鎩�M���͑S�S�y�͂����A���[�c�@���g�̍�i�ژ^�i������{�l�̎��M�j�ɂ́A�T�y�͍\���Ɩ��L����Ă���B��Q�y�͂ɒu���Ă������k�G�b�g���g���I���������Ă���̂ł���B����́A���[�c�@���g�{�l���J�b�g�������̂Ȃ̂��H�P���ɕ��������̂��H ���܂��������A���y�j��̓�̈�Ȃ̂ł���B
�@���R���̂悤�ȏ����I�Ȋ��Ⴂ�͕ʂɂ��Ă��A�u�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�vK525�͎��ɓ䑽�����ȂȂ̂ł���B���[�c�@���g�̃Z���i�[�h�́A�قƂ�ǂ��Ⴋ���̃U���c�u���N����ɏW�����Ă���A�@��y������A�Ⴆ���ꂻ��̌������̂��߂Ƃ����X�Ƃ̑��q�̓��w�j�p�[�e�B�[BGM�Ƃ��A��Ȃ̖ړI���n�b�L�����Ă���B�Ƃ��낪�A�E�B�[���ŏ����ꂽK525�ɂ͂܂��������ꂪ�Ȃ��B�������Ĕ����҂��ړI�����肳��Ă��Ȃ��̂��B������̓�͊y�͐��ł���B�������鎩�M���͑S�S�y�͂����A���[�c�@���g�̍�i�ژ^�i������{�l�̎��M�j�ɂ́A�T�y�͍\���Ɩ��L����Ă���B��Q�y�͂ɒu���Ă������k�G�b�g���g���I���������Ă���̂ł���B����́A���[�c�@���g�{�l���J�b�g�������̂Ȃ̂��H�P���ɕ��������̂��H ���܂��������A���y�j��̓�̈�Ȃ̂ł���B�@��Ɍ������ē˂��i�ނ̂��u�N�����m���_�v�Ȃ�A�����ɔ���邪�A�������g���C���Ă݂悤�ł͂Ȃ����I
�@�u�ڂ���̍ň��̂�������̓ˑR�̎���������߂����m�点���A�ڂ��ɂƂ��Ăǂ�Ȃɐh���������A�e�Ղɑz�����Ă��炦��ł��傤�B���������̂́A�ڂ����l�ɂƂ��ē������̂ł�����v�E�E�E�E�E����́A���e���]���m�������[�c�@���g���A1787�N6��2���A�o�̃i���l���Ɉ��Ăď������莆�ł���B���̎��̃��[�c�@���g�̏́A�E�B�[���ő��I�y���u�h���E�W�����@���j�v����Ȓ��ł������B�Ƃ��낪���̕M����U�~�߂āA�ނ��u���y�̏�k�vK522�Ƃ������i�������B�������t��6��14���B���ꂪ�A�����I�|���g�̎���ɏ������ŏ��̋Ȃł���B����Ɂu���̊y�m�̘Z�d�t�v�Ƃ���悤�ɁA���y�l�d�t�{�z������{�̕Ґ��őS4�y�͍\���B�c�Ɏ҂̍�ȉƂƉ��t�Ƃ𝈝����Ă����i���B������������̒ʂ�A�z�����͋���ɉ����O���A���@�C�I�����͒��ȃ����f�B�[��O���������ɒe�������A�Ō�͂��̂������s���a���ŏI���Ƃ����A�˔��q���Ȃ��y�ȂȂ̂ł���B�ł́A���[�c�@���g�͂��̎����ɂȂ�����ȋȂ�������̂��낤���H ���[�c�@���g�ɑ��w�̐[����ƂȂ��ɂ���́u����̓��[�c�@���g�̕��e�ɑ���`�����B���e���������Ă���̂��v�ƌ����i�Ȃ��ɂ���u���[�c�@���g�E�R���N�V�����v���j�B
�@�������̐��Ɏ^���ł���B�����]���������A���̍�Ȃ̎���~�߂Ă܂ł���ȓ��قȊy�Ȃ��������̂ł���B�V�˂͂Ȃɂ����ł�����������Ȃ��Ƃ͂����A�킴�킴����ȋȂ������͕̂��e�̎��Ɩ��W�ł���͂����Ȃ��B�ނ͕��e�h���Ă����B���̎���������̂��A�i���@���ǂ�����j�����c��������{���Ă��ꂽ�P���̎������Ƃ������Ƃ͎��o�E�������Ă����B�������A���̌セ�̑z�����Ȃ肪������B���[�c�@���g����i�ł���U���c�u���N��i���q�G�����j�X�E�R�����h�̗��s�s�Ȗ��߂ɏ��˂��A�E�B�[���œƗ��������ƌ����������Ƃ��A�����I�|���g�͔݂��Ă͂���Ȃ������B����ǂ��납�A���l�тĎ��ӂ�P��Ǝ莆�ɏ����Ă����̂ł���B����ɑ��A�ނ�1781�N5��19���A���ւ̎莆�ł��������Ă���B�u�����̂Ƃ���A���Ȃ��̎莆�ɂ͈�s���l�̕��e�����o���Ȃ��̂ł��B�����Ǝq���̖��_���C�����A�ŏ�̈���Ɉ�ꂽ���e�ł͂���܂���B�Ђƌ��Ō����A�l�̂�������ł͂���܂���v�i�u���[�c�@���g�̎莆�v�����p�Y��ҁA���w�فj�B����Ȃɋ������q�ŕ��e�����Z���t���A�ނ͂���܂œf�������Ƃ��Ȃ������B�������������Ă����Ǝv���������A����̕ېg�����l���Ă��Ȃ��i���I�|���g���R�����h�̕����Ȃ̂��j�ƒm�蕮�S�����̂ł���B���̂Ƃ��ȗ��A�ނ̕��e�ւ̎v���ɕ��̗v�f����������̂ł���B�u���y�̏�k�v�̓��[�c�@���g�̕��e�ɑ��镉�̃I�}�[�W���Ȃ̂��B
�@�A�����J�̒����ȉ��y�w�҃��C�i�[�h�E�\�������́A�u�ǂ̂悤�Ȏ���ŏ����ꂽ���킩��Ȃ����y�A���Ƃ��A�w�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�xK525��w���y�̏�k�xK522�Ȃǂ́A�W���J���Ƃ̃T�[�N���̂��߂ɏ����ꂽ�ƌ��Ă������̂ł͂Ȃ����v�i�u���[�c�@���g�v�Έ�G��A�V���ي��j�Ə����Ă���B�W���J���Ƃ̃S�b�g�t���[�g�E�t�H���E�W���J���i1767�|1792�j�ƃ��[�c�@���g�͂��݂��F�ߍ����ň��̗F�l���m�������B1787�N6���̂�����A���[�c�@���g�͏o���オ��������́u���y�̏�k�v���W���J���ƂɎ������݉��t�����B���܂�̂��ӂ������[�h�ɁA�W���J���́u�N�����e������ł����͕̂����邪�A���ӂ������߂���B����ŕ��e�ւ̊��ӂ̋C����������̂�����A����ȋȂ���������ǂ����v�ƃ��[�c�@���g�ɏ�������B������ă��[�c�@���g�́A�u�m���ɂ��ꂶ��Ў藎�������B����A���x�͕ʎ����̒Ǔ��Ȃ������Ȃ���v�ƍl�����B
�@���ꂩ�炵�炭�o����1787�N8��10���A�u�h���E�W�����@���j�v����i���������[�c�@���g�́A�W���J���̌��t���v���o����ȂɎ��|����B�u�e���Ƃ̂悫�v���o���c��U���c�u���N������ے�����̂̓Z���i�[�h���v�Ƃ��āA��P�y�̓A���O���A��2�y�̓��k�G�b�g���g���I�A��3�y�̓��}���c�F�A��4�y�̓��k�G�b�g���g���I�A��5�y�̓����h����Ȃ�Z���i�[�h����Ȃ����B���ȁu�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�v�̒a���ł���B�����W���J���ƂɎ�������Ŕ�I����B�u�N������e���܂�郁���f�B�[�Ɍ��l�����X�点��B������������v���A�������q�ɋ��������y�̋Ɉӂ������B�܂��ɂ��̒ʂ�Ɏd�オ�����u�Z���i�[�h�v�̐V��ɁA�����킹���l�����͑傢�ɖ����������Ƃ��낤�B
�@���[�c�@���g�́A�S�����ւ̎v�������߂ē�̑�������y�Ȃ�������B�u���y�̏�k�v�͕ێ�I�ȕ��ɑ��锽�I�}�[�W���Ƃ��āA�u�A�C�l�E�N���C�l�v�͉��y�̊�b��@������ł��ꂽ�L�\�ȕ��ւ̐��̃I�}�[�W���Ƃ��āB�������������ׂ����[�c�@�c�g�́A�ӂƎv�����B���̓�̋Ȃ͑o�q�̌Z�킾�B�Ȃ�u�A�C�l�E�N���C�l�v��4�y�͂ɕύX���悤�B4�y�͐��̃Z���i�[�h�Ƃ����̂��a�V�����A��������A���݂������y�͐��̕����ʂ�\����̂̊W�ɂȂ�B���[�c�@���g�́u�A�C�l�E�N���C�l�v�̓�Ԗڂɒu�������k�G�b�g���g���I�̊y�����O�����B���[�c�@���g���O�������k�G�b�g���g���I�͖����s�����킩��Ȃ����̊y�͂ƂȂ����B�����������������ꂽ��呛���ɂȂ邱�ƕK��ł���B�W���J���Ƃ̖��Ⴊ�����Ă����肵�āH
�@���_�͎��̑z���ł���B�������A�ɂ��Ă͎j���ɒ����ɏ������B��ȂƂ����ꂽ���R�Ɋm�ł��������Ȃ��ȏ�A�u������A���ł́v�ƍl����̂��Ȃ��Ȃ��y�����B
�������V���^�[�v��
�@�Ō�ɍ��ׂȂ��Ƃ����A�ꌾ�t�����������Ă��������B�����A���R���́u�����V���^�[�v�Ƃ������y��]�Ƃ́E�E�E�E�E�v�Ƃ���������������Ă��邪�A���̃��[�g���B�q�E�����V���^�[�v�i1799�|1860�j�̓N���V�b�N���D�ƂɂƂ��ẮA�V���[�x���g�̉̋ȏW�u�����̉́v�̎��l�Ƃ��Ă̂ق�������ݐ[���B���̖��ȁu�Z���i�[�h�v�̍쎍�҂Ȃ̂ł���B�܂��A�x�[�g�[���F���̖��ȁA�s�A�m�E�\�i�^��14�ԁu�����v�̑�1�y�͂��u���c�F�����ɉf���錎���ɕY�����M�̂悤�v�ƌ`�e�������Ƃł��L�����B���y��]�Ƃƌ����ĊԈႢ�ł͂Ȃ��̂����A��X�ɂ͂ނ���A���l�Ƃ��Ă̑��݂̂ق����傫���B�o����Δނ������ƕ��L��������\�����~���������B�u�Ƃ������y��]�Ƃ́v�Ƃ����L�q�ł́A�Z���X�Ƃ��Ă������Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��̂ł���B
2011.08.25 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�1
�@���R�������u����Ȃ�h�r���b�V�[�v�́A�ҏ����A���̒��ꕞ�̐����܂ɂ͂Ȃ����B���y�\���ɋ����[�����̂�����������ł���B�����[���ɂ͍m��Ɣ��_������B����u�s���a���̊��v�Ƃ��āA���̔��_�������������Ă������������B���z�����B�b�c��
�@�s�A�m���t�̖����z�����B�b�c�Ɋւ��Č�邭���肪����B
�z�����B�b�c�Ƃ������s�A�j�X�g��������A���̐l�̔ӔN�̉��t�͂���͂����ɁX�����قǂŒe������3���̂P���~�X�^�b�`�������B�������A���̃~�X���炯�̉��t�̓R���N�[���オ��̎��s�A�j�X�g�̉��t�����y���ɐ��������������B����͔ނ���ȉƂ̈Ӑ}���[���ɗ������A�e�N�j�b�N�̐��������o�ŕ���Ă�������ȂB
 �@�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�i1903�|1989�j�͖��l���F�߂�20���I�ő�̃s�A�j�X�g�̂ЂƂ肾�B���O��̃e�N�j�b�N���瓱���������t���[�Y�͉̐S�Ɉ��y�z�͎��R�z���ɓV����삯��B�ꗱ�ꗱ�̉��͋P���ɖ������̐F�ʂ͎��݂ɕω�����B������͈ꎞ�������E�𗷂���B20���I�������s�A�j�X�g�����́A�o�b�N�n�E�X�A���[�r���V���^�C���A���q�e���A�M�����X�A�u�����f���A�A�V���P�i�A�[�W�A�|���[�j�A�A���Q���b�`�Ȃǐ������邪�A�N��l�Ƃ��ăz�����B�b�c�ɔ䌨����P�������͂Ȃ��B�D�������͕ʂɂ��āA�z�����B�b�c�قǂ̃X�^�[�E�s�A�j�X�g�͑��ɑ��݂��Ȃ��̂ł���B����ȃz�����B�b�c�ɂ��Ă̒��R���̋L�q�͊��S�Ȍ���Ƃ�����B
�@�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�i1903�|1989�j�͖��l���F�߂�20���I�ő�̃s�A�j�X�g�̂ЂƂ肾�B���O��̃e�N�j�b�N���瓱���������t���[�Y�͉̐S�Ɉ��y�z�͎��R�z���ɓV����삯��B�ꗱ�ꗱ�̉��͋P���ɖ������̐F�ʂ͎��݂ɕω�����B������͈ꎞ�������E�𗷂���B20���I�������s�A�j�X�g�����́A�o�b�N�n�E�X�A���[�r���V���^�C���A���q�e���A�M�����X�A�u�����f���A�A�V���P�i�A�[�W�A�|���[�j�A�A���Q���b�`�Ȃǐ������邪�A�N��l�Ƃ��ăz�����B�b�c�ɔ䌨����P�������͂Ȃ��B�D�������͕ʂɂ��āA�z�����B�b�c�قǂ̃X�^�[�E�s�A�j�X�g�͑��ɑ��݂��Ȃ��̂ł���B����ȃz�����B�b�c�ɂ��Ă̒��R���̋L�q�͊��S�Ȍ���Ƃ�����B�@�܂��A3����1���~�X�^�b�`�Ƃ������A�z�����B�b�c�̔ӔN�ɂ���ȉ��t�͑��݂��Ȃ��B���̋L�q�ɍł��߂��̂́A1983�N6��11���A�����������̉��t�����A�~�X��3����1�Ȃ�Ă���Ȃ��B�������ׂċ���ɒ��������A�ƂĂ����y�Ȃ�Ă����㕨����Ȃ��̂ł���B�~�X�^�b�`�]�X�̎�������Ȃ��A�s�A�m�̐��k�����M�Ȃ��I�h�I�h�ƌm�Â����Ă�����Ă���̐}�Ƃ����������肢�������邾�낤���B���ڂ́A�x�[�g�[���F���̃\�i�^��28�ԁA�V���[�}���́u�ӓ��Ձv�A�V���p���́u���z�|���l�[�Y�v���K�ȍ�i10�|�W�A25�|10�A25�|7�A�u�p�Y�|���l�[�Y�v�ŁA�]�_�Ƌg�c�G�a���u�Ђт̓����������i�v�ƓI�m�ɂ��]�������t������B
�@���́A�z�����B�b�c�͂��̎��A�Ȃ�炩�̗��R�Ŗł������Ƃ����Ă���B�m���ɂ����ł��Ȃ���l�����Ȃ����t�Ȃ̂ŁA����͋��炭�������낤�B�A�����J�̊W�҂͔����Ă������낤������{���Ȃ߂�ꂽ���̂ł���B���̂��Ɗ������čė��������̂�86�N�ŁA�����ł͖{���̎p�ɂ��ǂ��Ă����Ƃ����B���̂Ƃ��̉��t�����͒����Ă��Ȃ����A�O��ɘ^�����ꂽCD���Η��������Ă���̂��悭������B1986�N2���A1988�N12���^���́u�z�����B�b�c�E�A�b�g�E�z�[���v�A1986�N4���́u���C�u�E�C���E���X�N���v�A1987�N3���́u�v���C�Y�E���[�c�@���g�v�A1989�N10���́u���X�g�E���R�[�f�B���O�v�Ȃǂł���B�����̉��t�́A�S�����ɂ͉����y�Ȃ����̂́A83�N�������̎��ɐ����������Ȃ�悤�ȉ��t�ɔ�ׂ�Ίi�i�ɗlj����Ă���A�f���āu3����1���~�X�^�b�`�v�ł͂Ȃ��B�����Ō��_�ł���B
�@���R�����q�ׂ��u�z�����B�b�c�ӔN�̉��t��3���̂P���~�X�^�b�`�v�́A���炭1983�N�̏������R���T�[�g�������Ƃ������̂Ǝv���邪�A����͊��S�Ȍ���ł���B���̂悤�ȏ�Ȃ����t�́A�z�����B�b�c�̃s�A�j�X�g�l���̒��ŗB�ꂱ�ꂾ���Ȃ̂�����B��������������Ă���u���̃~�X���炯�̉��t�̓R���N�[���オ��̎��s�A�j�X�g�̉��t�����y���ɐ��������������v����ɂ��肦�Ȃ��B���t��3����1���~�X�^�b�`�ł́A"������"��������͂����Ȃ�����ł���B������"������"��������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��낤���H���ɂ͊F�ڌ��������Ȃ��B
�@���ǎ��́A�u�ӔN�̉��t��3����1���~�X�^�b�`�v�Ɓu���̃~�X���炯�̉��t�͎��s�A�j�X�g�̉��t�������������������v�Ƃ�����d�̃~�X��Ƃ��Ă���̂ł���B���炭�A���͂��̉��t���������ɂȂ��Ă��Ȃ��̂��낤�B
�@����Ɉꌾ�t�����������Ă��������B���R���́u�e�N�j�b�N�̐��������o�ŕ₤�v�Ƃ������A�z�����B�b�c�́u���o�v����^�C�v�̃s�A�j�X�g�ł͂Ȃ��B���o�Œe������Ō|�p�ɂȂ��Ă��܂��A�^�̓V�˃s�A�j�X�g�Ȃ̂��B�������ɂ́A�z�e���Ƀp�C�I�j�A���烌�[�U�[�f�B�X�N�����Ĉ���������������Ă����Ƃ������A�u���X�g�E���}���e�B�b�N�v�Ƃ����e���r�ԑg�ł́A�u�V���[�x���g�͐����I�v�ƌ����āu�Z���i�[�h�v���������݂Ȃ���u�w�A���F�E�}���A�x�A����ȉ��y�̓x�[�g�[���F���͈ꉹ�����ď����₵�Ȃ��v�Ƒ������z�����B�b�c���f���Ă���B�ނ͒�������I�����o�h�̓V�˂Ȃ̂ł���B
����g��
�����畷�����n�[�h�E�F�A�ƃ\�t�g�E�F�A�̘b���v���o���B�y����CD�A���t�҂�CD�v���[���[�B����CD�ł��Đ�����v���[���[�̐��\�ŏo�Ă��鉹�ɂ͉_�D�̍���������B����Ɠ��l�ɁA�����y����ǂ�ł����t�҂̗͗ʂ̈Ⴂ�Ŗa���o����鉹�͐獷���ʂƂȂ�B�����I�[�f�B�I�ƃ��W�J�Z�̈Ⴂ�\�\�c���Ȃ悤�����A����͂����������Ƃ��낤�B�@���R���̂��̔�g�͈���Ō����ƐB����CD�����u�ɂ���ĈႤ��������̂͊m���ł���A���ꂱ�����I�[�f�B�I�̊y���݂ł�����̂����A���̍��͉����I���ʂɌ�����B���t���̂��̂�����ĂłĂ���킯�ł͂Ȃ��B����A�����y�����牉�t�҂ɂ���Đ獷���ʂ̃p�t�H�[�}���X�����܂��͓̂��R�̂��ƁB���F�A�e���|�A�ԁA���o�[�g�A�A�S�[�M�N�Ȃlj��I�v�f�́A�e�N�j�b�N�A���߁i�y���̓ǂ݁j�Ȃlj��t�҂̗͗ʂɂ���ĕς�B�͗ʂ͐l�Ԑ��̔��f������A���t�����Ƃ͑������t�҂̐l�������Ƃ��A�Ǝ��͏�X�v���Ă���B
�@�����I�[�f�B�I���u��ǂ����ނ̂́A���t�҂̐l�������悭�����o�����������߂��B�����ɂ͖��_��Ȏ҂̐l�������e�����B���߂Ƃ����͗ʂɂ͍�Ȏ҂̈Ӑ}�����m����\�͂��܂܂�邩�炾�B�G���W�j�A�̖����́A���܂�o�����t�𒉎��ɕ������߂邽�߂ɍőP�̍���u���邱�Ƃ��B�������Đ��ݏo���ꂽCD�ɂ͂���Ȋ����̐l�X�̋Z�p��v����l���܂ł������ɋl�߂��Ă���̂ł���B
 �@�����I�[�f�B�I�ɋÂ��Ă������̈��Ǐ��́A�ܖ��N�S�́u�I�[�f�B�I���v�i�V�����Ɂj�������B�I�[�f�B�I�ɗ����������ܖ��͂܂�ŋ����ҁB���̃X�g�C�b�N�Ȏp���ɑ傫�Ȋ������o�������̂ł���B���̃X�s�[�J�[���^���m�C�Ȃ̂��ނ̉e���ɂ����̂��B
�f�B�X�N�ɋl���Ă��鉽���̂����������߂ɁA�ܖ��͐l���̂��ׂĂ�q�����B�����ƂƂ��Ă��̂������ړI�́A�I�[�f�B�I���u���M���M���܂Œǂ��l�߂邽�߂ł������B�ނ̃I�[�f�B�I�ɓq���鐦�܂������������͂����p����E�E�E�E�E�u�ȑO�A���邳���_�̂��Ƃ����h���A���̂����ɏ]���ĉ䂪�Ƃɋ���ȃR���N���[�g�E�z�[�������B���ꂪ�ǂ�ȉ��Ŗ��Ă��邩���͒m���Ă���B���̌�e���t���P��S8�^���w�����A��������ׂāA�R���N���[�g�E�z�[�����n���}�[�ŝȂ����킵���v�B���悢�������߂Đl��M���҂������������ނ��A���ł����u�ԝȂ����킵�Ă��܂��B�ƂĂ���l�ł͍l�����Ȃ������ł���B�u�I�[�f�B�I���u�����ݏo�����̖��͂͊m���ɖ��Ӎۂ����A����ȏ�ɂ�����Ȃ��s�����ʖ��͂Ɣ��Ǝv���͂ƁA�b�q�ƁA�@���I�������𑠂��Ă���̂����y���̂����ł���v���ނ̗��O�ł���B���y��������C�������I�[�f�B�I�Nj��ɗD�悵�Ă���B���ꂱ���A�܂Ƃ��ȉ��y���D�Ƃ̃v���C�I���e�B���Ǝv���B
�@�����I�[�f�B�I�ɋÂ��Ă������̈��Ǐ��́A�ܖ��N�S�́u�I�[�f�B�I���v�i�V�����Ɂj�������B�I�[�f�B�I�ɗ����������ܖ��͂܂�ŋ����ҁB���̃X�g�C�b�N�Ȏp���ɑ傫�Ȋ������o�������̂ł���B���̃X�s�[�J�[���^���m�C�Ȃ̂��ނ̉e���ɂ����̂��B
�f�B�X�N�ɋl���Ă��鉽���̂����������߂ɁA�ܖ��͐l���̂��ׂĂ�q�����B�����ƂƂ��Ă��̂������ړI�́A�I�[�f�B�I���u���M���M���܂Œǂ��l�߂邽�߂ł������B�ނ̃I�[�f�B�I�ɓq���鐦�܂������������͂����p����E�E�E�E�E�u�ȑO�A���邳���_�̂��Ƃ����h���A���̂����ɏ]���ĉ䂪�Ƃɋ���ȃR���N���[�g�E�z�[�������B���ꂪ�ǂ�ȉ��Ŗ��Ă��邩���͒m���Ă���B���̌�e���t���P��S8�^���w�����A��������ׂāA�R���N���[�g�E�z�[�����n���}�[�ŝȂ����킵���v�B���悢�������߂Đl��M���҂������������ނ��A���ł����u�ԝȂ����킵�Ă��܂��B�ƂĂ���l�ł͍l�����Ȃ������ł���B�u�I�[�f�B�I���u�����ݏo�����̖��͂͊m���ɖ��Ӎۂ����A����ȏ�ɂ�����Ȃ��s�����ʖ��͂Ɣ��Ǝv���͂ƁA�b�q�ƁA�@���I�������𑠂��Ă���̂����y���̂����ł���v���ނ̗��O�ł���B���y��������C�������I�[�f�B�I�Nj��ɗD�悵�Ă���B���ꂱ���A�܂Ƃ��ȉ��y���D�Ƃ̃v���C�I���e�B���Ǝv���B�@CD�͊y�������t�҂��������Ă���BCD�v���[���[�̓I�[�f�B�I���u�̈�p�[�c�ɉ߂��Ȃ��B������u�y����CD�ʼn��t�҂�CD�v���[���[�v�Ƃ������R���̔�g�͌��X���藧���Ȃ��̂ł���B
�@���R���ւ̕s���a���͑��ɂ��܂�����B�u�ڒ��Ɠ]���v�̍�����u�\���E�s�A�m�ƃJ�f���c�@�v�̞B���ȗ���������ł���B�u�ڒ��v�͋Ȃ����̂܂ܕʂ̒��Ɉڂ����Ƃ������A�u�]���v�͊y�Ȓ��̘A�����闬��ɂ����钲���̕ϊ��������B�s�A�m���t�Ȃɂ����āA�s�A�j�X�g���e�������͂��ׂăs�A�m�E�\���ł���A���̒��Ńs�A�j�X�g�̋Z�ʂ��֎����邽�߂ɓ��ʂɐ݂���ꂽ�p�[�g���J�f���c�A�ł���B�����͊y�T�ɂ����鏉���I�Ȓm���Ȃ̂ŁA���y�֘A�������������Ƃ�����Ƃɂ͍Œ���}���Ă����Ă������������Ƃ���ł���B
2011.08.15 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`���a���̊�
�@�������H�i1926�|1980�j�͍D���ȍ�Ƃł���B���_�����̂������Ă��Ȃ₩���B�悢���u�x���v�Ƃ悭�����B�u���v�ł͂Ȃ����Ȃ₩���������ɂ���B�p�����z�Ƃ��Ĕw���L�тĂ���B���A�u���܂���̐��̒������炱���A���̐l�̋B�R����Ȃ܂������X�����B�@����Ȕނ̐��M�W�u�����̂Ȃ��v�̊����ɁA�u���҂ւ�27�̎���v�Ƃ������ڂ�����B���̎���̈�u�D���ȉ��y�Ƃ́H�v�ɑ��闧���̓������A�u�t�̓o�b�n�A�Ă̓h�r���b�V�[�A�H�̓��[�c�@���g�A�~�̓x�����I�[�Y�v�Ƃ������̂��B�Ă̕�������������u�Ăɂ̓h�r���b�V�[�̉��y���œK���v�Ƃ������ƂɂȂ낤���B���[��A�Ȃ�قǁA�悭�킩��B�h�r���b�V�[�̉��y�͗����Ă�ł����̂��B�ҏ����L�^�I�ɑ������������A���̈����Ȃ̓h�r���b�V�[�u�C�`�R�̌����I�f�`�v�ł���B�W�����[�j�w���t�B���n�[���j�A�nj��y�c�̉��t���ō����B���̖������鐴�����̓N�[���[�ɂ�����A�Ƃ₹�䖝���ߓd�ɗ�ށB
 �@����Ȑ܁A���R�������u����Ȃ�h�r���b�V�[�v�Ƃ����T�㏬����ǂB�������O�A���̃T�C�g�̎劲�A�W���Y���~�X�e���[�̂j���Ɋ��߂��Ă����̂����A����������ɂȂ��Ă������̂��B��k�Ќ�̐����̖����Ɨe�͂Ȃ��ҏ��̘A���ɁA���Ƃ��Ȃ����A�ƕ����Ă�����A���ɂ͗������H�������сA��ɂ́u����Ȃ�h�r���b�V�[�v������Ă����Ƃ����킯�ł���B
�@����Ȑ܁A���R�������u����Ȃ�h�r���b�V�[�v�Ƃ����T�㏬����ǂB�������O�A���̃T�C�g�̎劲�A�W���Y���~�X�e���[�̂j���Ɋ��߂��Ă����̂����A����������ɂȂ��Ă������̂��B��k�Ќ�̐����̖����Ɨe�͂Ȃ��ҏ��̘A���ɁA���Ƃ��Ȃ����A�ƕ����Ă�����A���ɂ͗������H�������сA��ɂ́u����Ȃ�h�r���b�V�[�v������Ă����Ƃ����킯�ł���B�@�u����Ȃ�h�r���b�V�[�v�́A��8��u���̃~�X�e���[���������I��܁v��܍�B���������A�T�㏬���Ƃ��Ă͂ǂ����Ǝv�����B�Ō�ɂǂ�ł�Ԃ��ƂȂ�̂����A�Ɛl�ݒ肪�a�V�H�߂��Ď��ɂ͂ǂ����E�E�E�E�E�B������đO�Ⴀ��ł����H�ד�����Ȃ��ł��傤���H �T���j���ɉ�̂ŁA�u���Ă݂悤�B�����������A���y�`�ʂɂ͋����[�����̂�����B����́A�ނ̉��y�����ɂ��āA�^���ł��镔�����q�ׂĂ݂����Ǝv���B
���u�����v�ɂ͋�����
�@���R���̓h�b�r���b�V�[�ƃ����F���̈Ⴂ�����������Ă���B
�h�r���b�V�[�̋Ȃ́i���������j�e���Ă݂�ƈ�w���y�������炷�悤�ɂł��Ă���B���Ղ�@���Ă���ƁA�v����g�̂��J�������悤�ȉ����ɏP����B�����Ēe���I�����u�ԁA��͂���������E�͊����S�g���ށB�������f�����d�����������F���͒e���Ă݂�Ɗ�ɋ����ŁA�܂�Őg�̂��ׂ����Œ��ߕt�����銴�o������A���̈Ⴂ�͗�R�Ƃ��Ă���B�@�h�r���b�V�[�́u�J�����v�A�����F���́u�����v�B�����ł���B�������˂��˃h�r���b�V�[�ƃ����F���͎��Ĕ�Ȃ���́A�u�h�r���b�V�[�̉����ɂ͏��������邪�����F���͊����Ă���v�Ɗ����Ă����B����͍D�������̖��ł͂��邪�A�����h�r���b�V�[�̂ق����i�f�R�j�D���ł���A���R�����x������B
�@���R���̓s�A�m���t�̕`�ʂ����܂��B�Ⴆ���X�g�́u�}�[�b�p�v��e���搶�̕`�ʁE�E�E�E�E��1���߂���r�X�����������������n�߂��B��������Ƃ��������\�����Ă��钲�q���B������ꂻ���ȑŌ��B�łƂ������͒@���t���Ă���B����͌��Ղ̏��ڂ܂��邵���ړ����A�w��̓����͎c�����c�������Ŗڂɂ����܂�Ȃ��B���x����������r�A�삯����w�Ǝw�B�����͌J��Ԃ��삯�オ��A�Ⴍ����E�E�E�E�E����͂�A�Ȃ��Ȃ��̕`�ʗ́B�s�A�j�X�g�̔��͂��`����Ă���B
�@�܂��A�ʂ̂Ƃ���ŁA���̃R���T�[�g�ɂ��Ă̋L�q�����邪�A������Ȃ��Ȃ����j�[�N�ō��_�������B�u�i�����t�́j������CD���̂Ƃ͎������Ⴄ�B�R���T�[�g�͉����̂ł͂Ȃ����тɗ���ꏊ�ȂȂƎv�����v�E�E�E�E�E"���𗁂т�"�͊������łĂ���B
�����̌���
�@�R���N�[����ڎw����l���̏��q�����̉ۑ�Ȃ��h�r���b�V�[�̖��ȁu���̌��v�ŁA�u�x���K�}�X�N�g�ȁv�̑�3�ȁB���̏����̊j�S�Ȃł���B���̋ȂɊւ��钆�R���̕`�ʁA���ɒ��߂�����̕\���͉��t�̖{����˂��Ă��đf���炵���B
�悸���̘a���̔������ɋ������B�������ꉹ�͂��̂܂܈���̌����B�������ƂȂ��ĐS�̒��Ɏ˂����ށB�v�킸�ڂ���Ă���Ƃ����ɏ�i��������ł���B�h�r���b�V�[�͉��Ɖf���̊W���d�������Ƃ������Ƃ����A���̒ʂ肾�����B�ΖʂɌ��̌����Â��ɍ~�蒍���ł���E�E�E�e���āA���������������̂��Ă���l�ɂ������Ă��������B�@�u�x���K�}�X�N�g�ȁv��4�Ȃ��琬��s�A�m�Ƒt�ȁB�u�x���K�}�X�N�v�Ƃ́u�x���K���́v�Ƃ����Ӗ��ŁA�x���K���͖k�C�^���A�̒n���̖��O�ł���B
�@�N���[�h�E�h�r���b�V�[�i1862�|1918�j�́A�t�����X�̍�ȉƂ̓o����u���[�}��܁v���l���������߁A1885�N����2�N�ԁA�X�|���T�[�ł��郁�f�B�`�Ƃ̂��G���E���[�}�ɑ؍݂����B���������̊ԁA�h�r���b�V�[�̓z�[���V�b�N�Ńp���ɋA��ȂǁA���̗��w�����͐S�������߂Ȃ������悤���B�u���̌��v���܂ނS�Ȃ���Ȃ�s�A�m�g�Ȃ����������̂́A�C�^���A����߂��Ă����1890�N����B�^�C�g���́u�x���K�}�X�N�v�́A���F�����[�k�̎��u���̌��v�̈�� "Que vont charmant masques et bergamasques"�i����ꂽ�鉐�₩�ȉ��ʊ쌀�҂����ƃx���K���̗x��q�����j������p�����Ƃ������Ă��邪�A�ނ����ۂɑ̌������x���K�����֗^���Ă���ƍl����̂����R���낤�B�ȉ��͎��̉����ł���B
 �@2�N�Ԃ̃��[�}�ł̐����́A�h�r���b�V�[�ɂƂ��Č����ĐS�n�悢���̂ł͂Ȃ������Əq�ׂ����A�ނ͋x�ɂ�����Ă͖k�C�^���A�̃x���K���n���ɏo�����Ă������Ƃ����B�ЂƂƂ������̓y�n�ʼn߂������Ƃɂ���āA�ώG�ȓs�������̋C���]����}���Ă����̂��낤�B�k�C�^���A�̐l�X�͉������B�������A�����̓x���K���b�g�̎Y�n�B�x���K���b�g�̓t���[�o�[�e�B�[�E�A�[���O���C�̑f�B���\�͟T�a�̉����B�����A�x���K���͔ނɂƂ��ĐS�n�悢�����̒n�������̂��B�f�p�Ȑl�X�Ɉ͂܂�Ĕ_�Ƃ̌��悠����Ŋ����Ȃ���A�[���O���C��n�ރh�r���b�V�[�̎p��z������ƁA�ق�̂�ƐS���a�ށB
�@2�N�Ԃ̃��[�}�ł̐����́A�h�r���b�V�[�ɂƂ��Č����ĐS�n�悢���̂ł͂Ȃ������Əq�ׂ����A�ނ͋x�ɂ�����Ă͖k�C�^���A�̃x���K���n���ɏo�����Ă������Ƃ����B�ЂƂƂ������̓y�n�ʼn߂������Ƃɂ���āA�ώG�ȓs�������̋C���]����}���Ă����̂��낤�B�k�C�^���A�̐l�X�͉������B�������A�����̓x���K���b�g�̎Y�n�B�x���K���b�g�̓t���[�o�[�e�B�[�E�A�[���O���C�̑f�B���\�͟T�a�̉����B�����A�x���K���͔ނɂƂ��ĐS�n�悢�����̒n�������̂��B�f�p�Ȑl�X�Ɉ͂܂�Ĕ_�Ƃ̌��悠����Ŋ����Ȃ���A�[���O���C��n�ރh�r���b�V�[�̎p��z������ƁA�ق�̂�ƐS���a�ށB�@�t�����X�ɋA��A�s�A�m�g�Ȃ��������A�^�C�g���t�����l�����Ƃ��A�ނ̋L���ɂ��������F�����[�k�̎��Ǝv���o�̓y�n�����т����B��������Ȃ�����2�N�Ԃ̗��w�����ŁA�B��S������Ă��ꂽ�̂̓x���K���̒n�������B�ق����A���₩�ȓc�����i�Ƒf�p�Ȑl�X�̏Ί炪������ł���B�����āA�S�������x���K���b�g�̍���B�����A��S��Ƀx���K���ւ̊��ӂ����߂悤�E�E�E�E�E�������Ă��̏����̌���́u�x���K�}�X�N�g�� Suite bergamasqe�v�Ɩ������ꂽ�B�x���K���ւ̃I�}�[�W�������߂āB�ގ��g�u�[���Ӗ��͂Ȃ��B�����Ȃ�ƂȂ��v�ƌ����Ă͂��邯��ǁB
�@����͂���܂ŁB����͈�]�A���R���́u�l�v�̊Â��ɂ��Č��y�������B
2011.07.31 (��) �b����`�Ƃ�ł��Ȃ��T�b�J�[�_
�@�u�N�����m�v�́A�N���V�b�N���y��f�ނƂ��Ă��܂��B������u�Ȃł����W���p���v���̂́A�O���̓���ɂ����������̂ł����A����܂ő�������Ȃ��Ȃ�܂����B����͂Ƃ�ł��Ȃ��T�b�J�[�L����ڂɂ�������ł��B�@7��26���A�����V���I�s�j�I�����ɁA�@���d�F�������u�������S�[�� �������ɋ����v�Ƒ肳�ꂽ�u�T�b�J�[�_�v���ڂ�܂����B��ɏ悹���͍̂����{�́u�Ȃł����W���p�����E��v�ł��B
�@�]�_�ɂ͗l�X�Ȏ��_�������Ă�����ׂ��ł��B��̎��ۂ�F�X�Ȋp�x����ς邱�Ƃ́A�����̖{���𑨂����Ō������Ȃ��s�ׂł��B�@���������ߔM�C���́u�Ȃł����u�[���v�ɕʎ��_�����𓊂����������̂ł��傤���A�c�O�Ȃ���A���̘_�|�͌����͂���ƌ��킴��܂���ł����B�ǂݐi�ނɂ�Ă��������Ă���"�Ƃ�ł��Ȃ�"�㕨�ł����B���̎��������T�b�J�[���̂𑱂��ď������ƂɂȂ������R�ł����A������́A���肪���喼�_�����ɂ��Č������Ƃ����啨���������Ƃł��B����A�䂪���ō���̓��]�̎�����B�܂��ɁA����ɂƂ��ĕs���Ȃ��I �ł́A���̘_�]�ɉ����āA���̊��z�Ȃǂ��q�ׂ����Ă������������Ƒ����܂��B
 �����s�m�[�`���[�K���̃S�[����������������
�����s�m�[�`���[�K���̃S�[����������������
������Ŏ����Ђ�����ꂽ�̂́A�č��̃~�b�h�t�B�[���_�[�A���s�m�[�̓����ł����B�ޏ������w����O��ɏグ�������c�p�X�Ƀ��[�K�����f�����������A�F�J�����킵�Đ搧�_�����߂��B���̈ӕ\�������{�[���̓����ɁA�u�������B����ȃS�[���������������̂��I�v�Ǝv�킸�������܂����B���̃{�[���̔��������ǂ����v���o���Ă������������B���ꂱ�����T�b�J�[�̑u�����ł��B�@�@�����́A�A�����J�̐搧�_�ƂȂ������s�m�[�`���[�K���̃S�[���ɋ������A�����ɃT�b�J�[�̑u���������Ă��܂��B���ɂ͂��̃S�[���́A�����ɂ��A�����J�炵���͋Z�̃S�[���Ƃ����f��܂���ł����B�������J�E���^�[�ł̃S�[���B�ǂ����Ă��u�₩�Ƃ͊������Ȃ��B�ł��܂�����͊������̖�肾����A����܂łɂ������܂��傤�B
�����{�̃S�[���͔������Ȃ���
����ɔ�ׂ�Ɠ��{�̓��_�͔������Ȃ������B1�_�ڂ͋{�Ԃ����������Ȃ��Ƃ����ꏊ�ɑ��荞�݁A�G�̍�����˂��ă{�[�����Âɗ������݂܂����B�u���̑I��͂����҂ł͂Ȃ��v�Ƌ��Q�������A�u�����͊������܂���ł����B
 �@�����́A�{�Ԃ��u�����҂ł͂Ȃ��v�ƔF�߂Ă���ɂ�������炸�A�u�u�����͊������Ȃ������v�悤�ł��B�ނ͂܂��i���̌�Łj�u�����T�b�J�[������̂́A�I�肽���̎v�������Ȃ������ɋ����A�u�������o����������ł��v�Ƌ��Ă���悤�ɁA�T�b�J�[�ɂЂ�����u�u�����v�����߂Ă���悤�ł��B���͂��̋{�Ԃ̃S�[���ɑ�ϊ������o���܂����B�ăS�[���O�ʼni�����ێR�ɃN���X�𑗂낤�Ƃ����Ƃ��A�{�Ԃ�50m����ɂ����B���̎��_�ŁA�ޏ��͓��̒��ɂ����邱�Ƃ�z�肵�Ȃ���A���̋�������C�ɋ삯����Ă������B�{�[���ɋ߂Â��Ȃ���A�����J�I��̃N���A�̕�����\�m���A��̈ʒu�i�����̌������������Ȃ��Ƃ����ꏊ�j�ɑ��荞�݁A�L�[�p�[�̓������ÂɌ��ɂ߂ăV���[�g�𐬏A�������̂ł��B�I�肪�A���Ȃ��ʂ�z�肵�čŗǂ̈ʒu�����s�����Ƃ́A�T�b�J�[�̏d�v�Ŗ{���I�ȕ������낤�Ǝv���܂��B�����ƃp���[�ŗ����{�́A������ɂ߂Ȃ���A�����J�ɂ͏��ĂȂ������B����������A�ނ�ȏ�ɓ����g��Ȃ���ΐ�ɏ��ĂȂ������̂ł��B������{�Ԃ̃S�[���͎��ɓ��{�炵���ɉ��ȃS�[���ł����B���͂����Ɂu�u�����v���o���܂��B�����̏ꍇ�́A�c�O�Ȃ���A���s�m�[�`���[�K���̗͋Z�̂ق��ɑu�������o������悤�ł��B
�@�����́A�{�Ԃ��u�����҂ł͂Ȃ��v�ƔF�߂Ă���ɂ�������炸�A�u�u�����͊������Ȃ������v�悤�ł��B�ނ͂܂��i���̌�Łj�u�����T�b�J�[������̂́A�I�肽���̎v�������Ȃ������ɋ����A�u�������o����������ł��v�Ƌ��Ă���悤�ɁA�T�b�J�[�ɂЂ�����u�u�����v�����߂Ă���悤�ł��B���͂��̋{�Ԃ̃S�[���ɑ�ϊ������o���܂����B�ăS�[���O�ʼni�����ێR�ɃN���X�𑗂낤�Ƃ����Ƃ��A�{�Ԃ�50m����ɂ����B���̎��_�ŁA�ޏ��͓��̒��ɂ����邱�Ƃ�z�肵�Ȃ���A���̋�������C�ɋ삯����Ă������B�{�[���ɋ߂Â��Ȃ���A�����J�I��̃N���A�̕�����\�m���A��̈ʒu�i�����̌������������Ȃ��Ƃ����ꏊ�j�ɑ��荞�݁A�L�[�p�[�̓������ÂɌ��ɂ߂ăV���[�g�𐬏A�������̂ł��B�I�肪�A���Ȃ��ʂ�z�肵�čŗǂ̈ʒu�����s�����Ƃ́A�T�b�J�[�̏d�v�Ŗ{���I�ȕ������낤�Ǝv���܂��B�����ƃp���[�ŗ����{�́A������ɂ߂Ȃ���A�����J�ɂ͏��ĂȂ������B����������A�ނ�ȏ�ɓ����g��Ȃ���ΐ�ɏ��ĂȂ������̂ł��B������{�Ԃ̃S�[���͎��ɓ��{�炵���ɉ��ȃS�[���ł����B���͂����Ɂu�u�����v���o���܂��B�����̏ꍇ�́A�c�O�Ȃ���A���s�m�[�`���[�K���̗͋Z�̂ق��ɑu�������o������悤�ł��B���V�̃S�[���͂ǂ���������̈ꔭ��
�V��2�_�ڂ��A�����悤�ȓ����̒��ł̃S�[���ł͂Ȃ������B���x�����K�����{�ԂƂ̃T�C���v���[�ł��傤���A�����������Ō��߂��V�͂������Ƃ����ق��͂���܂���B�������A���t�͈�����������܂��A�ǂ����������1�_�݂����Ȋ����ŁA��x�ƋN���Ȃ���Ղł��傤�B�@����͎���ł��B�Ɠ����Ɍ������Ȃ��߂���Ǝv���܂��B�u�����悤�ȓ����̒��ł̃S�[���ł͂Ȃ������v�Ƃ����܂����A�Z�b�g�E�v���[�Ȃ̂����瓖�R�ł��傤�B"�T�C���v���["�Ƃ����܂����A���̂Ƃ��́A�G�̃S�[���L�[�p�[�̃A�N�V�f���g�ɂ���āA�\���ȑł����킹���ł����A�Ƃ��Ƃ�m�F�����������̃V���b�g�ł����B�܂��u���x�����K�����v�Ƃ����܂����A����ł����x���������Ă��܂��i�Ⴆ�Ζk���I�����s�b�N�̃j���[�W�[�����h��j�B����ȊÂ����ȍl�@��y��ɂ��āA�悭���u�ǂ���������́v�Ȃ�Ďv�������`�e���g���܂��ȁI
�@�u�������Ȃ��v�Ɓu�u�������������Ȃ��v�́A�����ł����y����Ă��܂����A���̊���������������̂ł��B�{�Ԃ̕������s���|�C���g�̈ʒu�ɁA�V���f�����삯����Ŏl�����̂�������_�ɍ��킹��B����͌v�Z�ƒ����ƏW���͂ƋC�͂��ׂĂ̗v�f���@�\���ď��߂Đ������鍂��x�̋Z�ŁA�|�p�I�ƌ����Ă������B���͂����ɔ����������܂��B�܂��A4�̗v�f����������ƌ��т���̂͌o���ɑ��Ȃ炸�A���͂������V�̃T�b�J�[�l�������܂��B���ꂾ���̃S�[����"�ǂ���������"�Ƃ��ĕЕt���Ă��܂��_�o���A���͋^�킴��܂���B
�@������A�����Č��킹�Ă��������ƁA�����̓T�b�J�[�̃v���[��_�ł��������Ȃ��悤�ł��B�u���̃S�[���͑u�����v�u���̃S�[���͔������Ȃ��v�ȂǁA����͓_�ł����Ȃ��B�����o�b�N�̃S�[���̂��ƁA�_�����ɂ��������Ȃ��������{�́A�ێR�Ɛ쐟�̃|�W�V���������ւ��A�쐟�̉^���ʂ����č����ʒu����{�[�������ɍs������������B���ꂪ����t�����V�̓��_�S�[���ɂȂ������B�T�b�J�[�ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�Q�[���������ɑg�ݗ��Ă邩�Ƃ������ƁB������A���ő����邱�Ƃ���Ȃ̂ł��B�S�[���͂��̎Y�����Ƃ������Ƃ��A����F�����Ă��������������̂ł��B����ׂ̔h�肳�����ɑ����Ȃ��ŁB
���A�����J��4�|2�ŏ����Ă���������
����4��2���炢�ŕč������Ă������������Ǝv���܂��B�ᒆ���� �����͂��ꂪ�@�\���āA���{�͉��x���U�ߍ��܂�܂������A�č��̃V���[�g�̓o�[��|�X�g�ɂ͂����ꂽ�B���ՂŎ��������߂悤�Əł������ƂŁA�������ă��Y�����������Ă��܂����̂ł��B�@����͂����b�ɂȂ�܂���B�u�������Ă���A��������Ă���Ώ����Ă����v�͂�����X�|�[�c�A������Q�[���ɓ��Ă͂܂�A�������������n���ォ�畉���͂Ȃ��Ȃ�܂��B������A�X�|�[�c�ɂ����āu�^�����o�v�͋�Ȃ̂ł��B��̋����͉������������̂ł��傤���H�u�����O���̃n�[�t�ŁA�č��̃V���[�g���o�[��|�X�g�ɂ͂�����Ă��Ȃ�������A���{�͕����Ă����B��������{�̏����͂����̃��b�L�[�Ȃ̂��v�Ƃł��B�V���̓�����w�����闧��ɂ��������ł�����A�u���{�l��A���̏�����遂�Ȃ���B�Q�[���̒�����������v�Ɛe�g�ɂȂ��Čx����炵�Ă��ꂽ�̂����B�ł������A�ǂ������S�z�Ȃ��B���{�̃T�b�J�[�E�t�@���݂͂�ȕ������Ă��܂��B����́u�t�����N�t���g�̊�Ձv���Ƃ������Ƃ��B�������A��Ղ͔ޏ��������N���������̂ł���A�T�b�J�[�̐_�l�����C�Ɋ撣�����Ȃł��������ɑ������ō��̃v���[���g���������Ă��Ƃ��ł��B�ǂ����A�u�^�����o�v�Ŕޏ������̃T�b�J�[�l���Ɛ��ʂ��Ȃ��Ȃ��ł������������B
��PK��ł̏��s�̓A�N�V�f���g��
PK��ł̏��s�̓A�N�V�f���g�̂悤�Ȃ��́B���{���������Ƃ������A�č������ł��������ł����B�@�m���ɁAPK��̓A�N�V�f���g�Ƃ͂悭�����邱�ƁB��������̂܂�܈��p����A������Ɨ҂������܂���B�A�����J�́A������2�|1�ƃ��[�h�����Ƃ��������m�M�����͂��ł��i����́A7��25�����f��NHK�X�y�V�����u�Ȃł����W���p�����E��ւ̓��v�̒��ŁA�A�����J�̃����o�b�N���،����Ă��܂��j�B���ꂪ�I��3���O�Ɋ�ՓI�ȃS�[���œ��_�ɂ��ꂽ�B����͂�����ӑr���ɋ߂������B�����āAPK�̈�{�ځA�L�[�p�[�C�x�̃X�[�p�[�Z�[�u���o�āA���_���ł���{�������B���ꂪ2�{�ځA3�{�ڂ̃~�X�̘A���Ɍq�������B�Ƃ܂��A�Ȃ�ƂȂ��ł����A���ꂪ�����ł���̂ł��B���_�A�K�R�̏����Ƃ͌����܂��A���{�������̗���ɏ���Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���̂ł��B�ō���̓��]�Ȃ�A���̂��炢�̂��Ƃ͔F�m���Ă���������B
�����̕���Ŏ����������ێR�̓����̑������ɂ͋�������
�����T�b�J�[������̂́A�I�肽���̎v�������Ȃ������ɋ����A�u�������o����������ł��B���X�����̃h�C�c��ł̊ێR�̃S�[���ɂ͂��т�܂����B�V�̕��������p�X��ǂ��Ă��̐����ő��荞�݁A����p�x����E���ŃS�[�������݂ɏR�肱�ށB�N�����u���������`�œ_����肽���v�Ɩ����Ă��Ȃ���j�q�ł����s����v���[���A���̕���Ŏ����������ێR�̓����̑������ɂ͋����܂����B�@�����̓^�C�g���ɂ��Ȃ��Ă���u�������v�̕����B�ǂ������悤�ƌl�̎��R�ł����A���ɂ́u�ێR�̓����̑������v�Ƃ͉f��Ȃ��B�����͂ނ����V�̃p�X�ł���A���ꂱ���u�����ȁv�V���b�g���Ɗ����܂��B�╣�̃g���b�v�E�~�X�̂��ڂꋅ���A�����E�^�b�`�ŁA����f�B�t�F���_�[�̗��A�ێR�̓��z���ɁA�i�ޏ����ǂ����悤�Ɂj�X�s���̗�������⑁���{�[�����A�������B����5�̗v�f����u�̂����ɐ��m�ɍ��̂�����E�E�E�E�E���ꂼ�u�����ȁv�V���b�g�ȊO�̉����ł��Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B�ێR�͂��̃{�[����{�\�̂܂ܒǂ������āA�S�[�����C�����肬�肩��v�����ďR�荞�B����͂ނ��듮���I�S�[���A�����������ΎR���V���b�g�̐F�ʂ������B�ǂ����A�����Ƃ͊������Ⴄ�悤�ŁB
������̃��b�h�J�[�h�ɔߑs�����Ȃ������킯��
����A���{��\�͍����̂ǂ����Łu������C�����Ȃ��v�Ƃ��v�����݂����L�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͂܂�����Ȃ��V�Ƌ{�Ԃ̗͂ł��B�{���Ȃ�ߑs�����Y���͂��̊���̃��b�h�J�[�h�ꔭ�ޏꂪ�A���ɖ��邭�`�[���𗎂����������̂����̂��߂ł��傤�B�����A���{��\���ˏo���������������Ă����킯�ł͂Ȃ��A�D���͏o���������Ǝv���܂��B�@���̘_�|�����������B����̃��b�h�J�[�h�ꔭ�ޏꂪ���ɖ��邭�`�[���𗎂����������̂́u������C�����Ȃ��v�Ƃ����v�����݂̋��L����ł͂Ȃ��B����̃p�t�H�[�}���X�����̏�ʂł́A���{�ɂƂ���"���̏�Ȃ��K�ȍs��"����������ł��B�u������C�����Ȃ��v�Ƃ����C�����̋��L������t����̂́A�̏�ʂɂ����Ăł��B������A���̃R�����g�́A���[�h���ꂽ2�x�̏�ʂłȂ瑊�������B��͂�A������ƃg���`���J���Ȋ����Ǝv�킴��܂���B�����āA�܂��܂��I�}�P�Ɂu�D���͏o���������v�Ȃ�Ăق����Ă���������B�ǂ��������R�ɁA�ł���܂��B
�@�ȏ�A���X�Ə����Ă����킯�́A���́A�@�����_�����̂悤��"�l���������Ɉ̂����Ȍ���������"�l���匙��������Ȃ̂ł��B�����ƁA�f���ɓ��{�̏����Ɋ����ł��Ȃ����̂��A�Ǝv���̂ł��B�������Ől�f����̂͂���Ȃ̂ł����A���̓��喼�_�����ɂ��Č������Ƃ����L�����A���A�{�_�]�̂���悤�ɂ��āA�Ȃ�قǂ�����������̂�����悤�Ɏv����̂ł��B�ȉ��A�Ȃ����̘_�]������ȕ��Ȃ̂��ɂ��āA�u���O�A����͋ɘ_���v�ƌ����邱�Ƃ��o��̏�ŁA�l�@���Ă݂܂��傤�B
�@������w�́A���鍑��w�Ƃ��āA�ېV�ȗ��A�������i�̂��߂̊�������Ă邱�Ƃ�ړI�ɐݗ��ێ�����Ă��܂����B�x���������B�Y���Ƃ́A���̎���A�n�[�h�Ƃ��āi�����I�Ɂj�͊Ԉ���Ă͂��Ȃ������ł��傤���A�����Ƀ\�t�g�Ƃ��Ă̐��_���u������ɂ���Ă��܂����B�g�D�͑�ǂ������d���������B�l�͈�̒��ł̌��v������~������Nj�����悤�ɂȂ����B�ł��ނ�͍���S���Ƃ��������S�����͕ێ����������B�n�������_�Ƀv���C�h�Ƃ����R�[�e�B���O�B����͂��������l�Ԃ�y�o���鋳��@�ւƂ��đ��݂��Ă����̂ł��B
�@�@�������̘_���ɂ́A�u���O��Ƃ͂�����ƈႤ�B�����ɂ͂����Ȍ����������v�ƁA����ȏォ��ڐ���遂肪�����܂��B�Ƃ��낪���̌����ɂ͌���ׂ����̂��Ȃɂ��Ȃ��B�Ƃ�悪��ŁA�x�ɓ����Ă��邾���B��������A�����ƁA�f���Ɋ�Ԃׂ��͊�ׂ����̂ɁA�Ǝ��Ȃ͎v���Ă��܂��B
�@���́u�T�b�J�[�_�v���A������w�̍ō��ӔC�҂��������̎�ɂȂ���̂ƍl����ƁA���w�ɋߑ���{�̗��j���ǂݎ���A���ɂ͂���ȕ��Ɍ�����̂ł����A����́A�܂��A������Ƌ����������ł����ˁB
2011.07.25 (��) �b����`�u�Ȃł����W���p���v�N�����m�I����
 �@2011�N7��18�������A�{�Ԃ����̃R�[�i�[�L�b�N��������ꂽ�{�[���́A�������V����̉E���̊O�R��ɂ���āA�A�����J�E�S�[���ɓ˂��h�������B���̊ԋ͂�2�b�A���{�S�y������ɗh�ꂽ�B�V���痝�z�̒��呜�Ƃ���ꂽ�֍��́A���̃S�[�����u�ق܂�V���[�g�v�Ɩ����B���ꂶ��A���̂܂�܁A������ƃC�[�W�[�H ���͂�����V�́u�~���N���E�r�[���v�ƌĂт����B���ꂼ�A�Ȃł����W���p�����̐▽�̊R���Ղ�����~���o������Ղ̑M���Ȃ̂��B
�@2011�N7��18�������A�{�Ԃ����̃R�[�i�[�L�b�N��������ꂽ�{�[���́A�������V����̉E���̊O�R��ɂ���āA�A�����J�E�S�[���ɓ˂��h�������B���̊ԋ͂�2�b�A���{�S�y������ɗh�ꂽ�B�V���痝�z�̒��呜�Ƃ���ꂽ�֍��́A���̃S�[�����u�ق܂�V���[�g�v�Ɩ����B���ꂶ��A���̂܂�܁A������ƃC�[�W�[�H ���͂�����V�́u�~���N���E�r�[���v�ƌĂт����B���ꂼ�A�Ȃł����W���p�����̐▽�̊R���Ղ�����~���o������Ղ̑M���Ȃ̂��B�@�T�b�J�[�͑f�l�̎������A����̂Ȃł����W���p���ɂ͕���Ȃ��Ɋ��������Ă�������B�u�N�����m�v���u��k�Вf�́v���ЂƂ܂���肪���A���ă\���\���{��ɖ߂낤���Ǝv���Ă������̂��̏Ռ��B����������ɂ͐�ɐi�߂Ȃ��ƁA�܂��܂��v���Ă��܂����B�z���g�ɍ��N�͍l�����Ȃ����������������o����B
�@�Ȃł����������M���A������7��19���A�t�W�e���r�̃X�[�p�[�j���[�X�ŁA�R�����e�[�^�[�̖ؑ����Y���A�u�A�����J�́A�w���{�͂Ȃɂ��Ɍ㉟������Ă����B�A�����J�͂���ȖڂɌ����Ȃ��G�ɂ��ꂽ�x�I�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�������̂͊F����̎��͂ł��v�ƁA�o�����̂Ȃł������^�����B�m���ɂ��̏�ɂ���I��ɑ���^���Ƃ��Ă͓K���Ǝv�����A����ŁA�A�����J�̋C�������悭������̂��B���̓��{�ɕ����Ă��܂����̂��B���肦�Ȃ��I���̓W�J�ŁB���{�Ɉ�̂Ȃɂ��N�����Ă����̂��H �ǂ����Ă��[���ł��Ȃ��B
�@����́A�A�����J������̎��_�������AFIFA���q���[���h�J�b�v�E�h�C�c������ɂ�����u�Ȃł����W���p���v�̋O�Ղ�U��Ԃ��Ă݂����B
�������o�b�N�ƃ��[�K����
�@�A�����J�E�`�[���̃G�[�X�͌����܂ł��Ȃ��A�r�[�E�����o�b�N�A�g��181�Z���`�̋��̓t�H���[�h�ł���B���������I���Ă̑��ʎZ3���_�́A�V�ɂ͈���y�Ȃ����̂́A���e�I�Ɍ����ăq�P�������̂ł͂Ȃ��B���X�����u���W����ł́A�����̃��X�E�^�C���Œl����̓��_�S�[�����A�������̃t�����X��ł͌����S�[����������ȂǁA�~�����Ƃ���œ_������܂��ɗ����G�[�X�ł���B
�@������l�̃L�[�}���A�A���b�N�X�E���[�K����22�C�s�̃t�H���[�h�B�����ǂ���œ��������M�d�Ȑ�͂��B�������ł̓_��������3�_�ڂ������Ă���B
�@�A�����J�E�`�[���́A���[���h�J�b�v��2��A�I�����s�b�N��3��D���B����FIFA�����L���O��1�ʁB���{�Ƃ̑ΐ퐬�т�21��3���Ɖߋ�1��������Ă��Ȃ��B�����͐����ƒm����A�S�̕Ћ��Ɂu���{�ɕ�����͂����Ȃ��v�Ƃ����C�����������Ă��s�v�c�͂Ȃ������B
�@����Ȕw�i�Ŏn�܂���������́A�J�n���X����A�����J�������܂������B���|�I�ȃp���[�ƃX�s�[�h�œ��{�S�[���ɏP��������B���Ȃ��Ƃ��O����3�x�͌���I�ȓ��_�`�����X���������B����28���A�����o�b�N�����������T�C�h����̋���ȃ~�h���E�V���[�g�́A�꒼���ɘg�Ɍ��������͂��ɃN���X�o�[�ɒe���ꂽ�B���_����Ȃ������̂͐_�̉���Ƃ��������悤�̂Ȃ����{�ɂƂ��Ă͎��Ƀ��b�L�[�ȃV���b�g�������B�O���̓X�R�A���X�E�h���[�B�`�����X�炵���`�����X�����Ȃ��������{�ɂƂ��āA���̌o�߂͏�X�������B
�@�㔼�A�A�����J�͏����ɏo���B�攭�`�F�C�j�[�ɑウ�ă��[�K���𓊓�����B������24���A�S�[���O����̒����p�X������ȃX�s�[�h�Œǂ������[�K�����A���̂܂ܓ��ӂ̍����ŃV���[�g�A�搧�_���������B�ēєz�Y�o���I���̊��ł���B���{�͂���12����{�Ԃ����_�S�[����������1�|1�B90���ł͌������t�����Q�[���͉�����ցB
�@�����O����14���A���Ƀ����o�b�N�����_������B���̓��̓����o�b�N�t�̃f�B�t�F���_�[�F�J�ъ��̍D��ɍĎO�`�����X��j�܂�Ă������A���ɔw��Ɉ������t���[�Ȉʒu����A�w�f�B���O�Ō����Ɍ��߂��̂ł���B�A�V�X�g�̓��[�K���B�L�[�}���ɂ��A�V�X�g���G�[�X���Ԃ����I�Ղł̓��_�ɁA�A�����J�͏������m�M�������Ƃ��낤�B�e���r�̑O�̎����A�ő�����܂łƊϔO�����B�G�ɕ`�����悤�ȁu�A�����J�̏����p�^�[���v�Ɖf��������ł���B
�@ ���{�Ԃ��V�Ɗ����
�@�㔼35���ł̋{�Ԃ̓��_�S�[���������������B�S�[���O�A�t�H���[�h���ێR�j�����������Ő荞�ނ���l�̃f�B�t�F���_�[�ɑj�܂��B�����̃f�B�t�F���_�[���E����ɃN���A�[�������̈ʒu�ɁA�w�ォ��X���X���Əオ���Ă����{�Ԃ������B�܂�ŋ�̈�A���Ɍ����ȓǂ݁B�E���Ńg���b�v�������A�E�g�Ŋm���ɏR�肱�ށB���x�ȋZ���Ղ���������{�Ԑ^�����̃e�N�j�b�N�������B
�@���{��1�|2�ƃ��[�h����s�F�Z���̉����㔼�A�c�莞��3���̎��_�Ŋ�Ղ͋N�����B����1��40�b�O�A�V����̃����O�p�X���߉�䂩�����▭�ȃ��[�v�V���[�g�A�ɂ������S�[���͐���Ȃ��������A���̏�ʂŁA�A�����J�̃S�[���L�[�p�[�A�z�[�v�E�\���������I��ƌ����A�����������B���̎��Â��A�R�[�i�[�L�b�N�܂ł̎��Ԃ����ꂽ�B�Ȃł����́A���̓V���^����1���Ƃ������Ԃʂɂ��Ȃ������B���R�[�i�[�Ɍ������{�Ԃ̓��̒��ɂ́A�u�V�̃j�A�Ƀ{�[���𑗂�v�Ƃ����m�ł��鍇�ӂ��\�z����Ă����̂ł���B�R�[�i�[�L�b�N�A�{�Ԃ̉E����������ꂽ�{�[���͒����ǂ���̌ʂ�`���B�f�B�t�F���_�[�̔w�ォ��ĕ^�̂悤�ɔ�яo�����V�́A�G�������o����������Ɏ���̉E�����̂��A�A�E�g�Ɉ�U�B����A�{�[���͑M���Ɖ����ăS�[���ɓ˂��h�������B�ł����V�͓�����Ђ�����Ԃ��Ă����B�����ȑł����킹�Ɛ��k�ȋZ�p�����ċɓx�̏W���͂�����Ղ̃S�[���ɂ��āA�R���Ղ��̓��{���~���������ʂ�N���̈�e�A�L���v�e���V�̃T�b�J�[�l���W�听�̈ꌂ�������B2�|2�̓��_�B��l�̋�����Ƃɂ�鍡���3�x�ڂ̃S�[���́A�V��5�_�ڂƂȂ��ē��_��������Â����B
�@�������m�M���Ă����A�����J�ɂƂ��Ă܂����̓W�J�B�ł��������ɉ��ҁB��ꂽ�̂��ە����Ď��X�ɃS�[���ɔ���B�����ɗ����͂��������̂�������������B
�@��S�̃S�[�������C�o���V�ɒ������ɂ��ꂽ�����o�b�N�́A14���A�E�T�C�h����̐�D�̃N���X�ɃW���X�g�E�^�C�~���O�ʼnE�������킹���B�����b�I�S�[�����H �Ǝv��ꂽ�u�ԁA����̉E���������Ƀ{�[����e���Ă����B����܂ł̃����o�b�N�ԁE�F�J����A���O�ɑ����Ă������̂Ǝv����B
�@���X�^�C���ɓ�����15��2�b�A���x�͓˔j�������[�K�����y�i���e�B�E�G���A�Ɍ������{�[�����^��ł����B�O�ɂ̓L�[�p�[�������Ȃ��B��Ȃ��I���̏u�ԁA�ēx������˂�����Ői����j�B�R���́A���[�K���ɉ����Ԃ��ꂽ����ɑ����b�h�J�[�h�����X�ƌf�����B�l�����̈ꔭ�ޏ�B�t�@�E���n�_�̓y�i���e�B�E�G���A�̒��O�B�A�����J�̃t���[�L�b�N�ƂȂ邪�A�ň��̃y�i���e�B�E�L�b�N�͔�����ꂽ�B����́A������u���̏�ʁA���̂܂܍s��������S�[���̉\���͂��Ȃ荂���Ɣ��f�����B�Ȃɂ����[�K������������B�����疳�䖲���ő̂����v�ƐU��Ԃ����B
�@�����ꂽ�畉���Ƃ������ԑтŁA�A�����J�̃L�[�}����l�̍U�����A�g������đj����̌��g�I�v���C�́A�V��{�Ԃɂ��C�G���鉿�l����p�t�H�[�}���X�������B
�@�t���[�L�b�N����̃A�����J�̍U�����Ȃ�Ƃ��������Ȃł����́A���ɏ�����PK��Ɏ������ށB
�@PK��̓S�[���L�[�p�[�C�x������ɐs����B�A�����J�̈�{�ڂ��~�߂��E���́A���ւ̔�т��������m���ę�l�ɏo�������̂��Ƃ����B���̈�{�ɓ��h�����A�����J�͗��đ�����3�{�̃~�X�B�Ȃł���2�Ԏ�i���̃~�X�̂��Ɠo�ꂵ��3�Ԏ����������́A�l�b�g�����ɃL�b�N�����B�L�[�p�[�͓ǂ݂ǂ���ɔ��Ń{�[���ɐG�����S�[���������B��Ԃ��߂ɒn�ʂ��R���������͐����O�ɒɂ߂��ق��̑��������B�����₱�̏����M���M���̂Ƃ���őj�~�ł��Ȃ�����������������Ȃ��B�A�����J��4�Ԏ胏���o�b�N�͐����B�Ō�͂Ȃł�����4�Ԏ�F�J���S�[������Ɍ��߁A�����������Q�[���ɏI�~����ł����B��l�߂̏C�������y�ɑ������V�̊肢���ʂ��A�T�b�J�[�̐_�l���Ȃł���30�N�̗��j�ɔ��u�Ԃ������B
���f�ГI������
�@�{�Ԃ͎�����A�u�D������̏u�Ԃ̋C�����́H�v�Ƃ����₢�Ɂu�����̓A�����J��\�̑I��ɂ��F�l�������̂ŁA��тƂƂ��ɔނ�Ɍh�ӂ�\���ׂ��Ƃ��������A���\���������Ă��܂����B�܂��A�̂���撣���Ă���ꂽ��y�����ɂ�������������ł��v�ƐÂ��Ȍ����œ������B���ہA�ޏ��͎�����̃s�b�`�ŃA�����J�I��̘J���˂�����Ă����B���̋C���������A�ޏ���������2���_�D�A�V�X�g�ƂƂ��ɋL�������ׂ����낤�B�A������u�������́A�s�b�`�Ō��ʂ��o�����Ƃ���ԑ�Ȃ��Ɓv�ƌ����c���A���`�[���̂��鉪�R�Ɍ������Ă������B���̐l�ɂ͑�NJςƗ��j�ς�����A�n�ɑ��������Ă���B�|�X�g�V�͈��ׂł���B
�@�{�Ԃ��V���A�����J�ŏC�s���Ă���B�k�ЂŃ`�[�����Ȃ��Ȃ����L�������{�X�g���ɈڐЂ��Ċ撣�����B�������đI��͑��X�C�O�ŏC�s���Ă���̂ł���B�ΐ�ɂ͍��N�̑S�p�I�[�v���Ń{���{���̃X�R�A�ŗ\�I�������āA�W�����{����ɏ��������߂��Ƃ����B�W�����{�͗L���ȓ��ٌc�ŊC�O�ł͑ł�����������܂��債�����т��c���Ȃ������l�B����Ȑl�Ԃɑ��k����ɂ��������瑦�C�O�ɏo�����ďC�s���ׂ����B���{�ɋ��_��u���Ȃ���A���̂Ƃ������o�����čs���Ċl���قǃ��W���[�͊Â��Ȃ��B�����i7��25���j�t�����X����A�{�����̕ăc�A�[���G���������`����ꂽ�B��������Ȃł����I�ΐ�̓���������肽���B
�@���́A����ق̒��Łu��s����Ă��ǂ������̂�����߂Ȃ��p���ŁA�������ׂ����Ƃ��������撣���Ă䂫�����v�Ɠ��ق����B���[�A���Ȃ��ɂ͊撣���Ă����Ȃ��Ă�������ł����B
�@�Ό��s�m���́A�s����K�₵�����X�ؑ��v�ēƓ�l�̂Ȃł�����O�ɂ��Ă����Ⴆ���B�u�����o�J�A���{���o�J�A�����s���o�J���B�Ȃ�ŋ�������ł��p���[�h���˂���B����ȃ{�P�i�X�̍��͂Ȃ���B����Ȃ���I�����s�b�N���ĂȂ����B���g�������v���āB����͖T��̓s�E���ɑ��ċ��̂��낤���A���ς�炸����킫�܂��Ȃ��j�ł���B�ȂA�悲�뎫�C�������{�����S����b�́u�����Ƃ��B�m�b���o���Ȃ���ɂ͉������Ă��Ȃ����v��z�N������B�z���g�A���̕��s�^�ȃK�L�叫�B���X�؊ē̐��n�x�����K���ׂ����B
�@�����o�b�N�́u���{�͂��݂���M�����Ō�܂ł�����߂邱�Ƃ͂Ȃ������B����͂����Ƃ͈Ⴄ�������ޏ������̌㉟�������Ă����悤�Ɋ�����v�Ƃ������t�ɁA�A�����J�E�`�[���̖{���������B�ꂵ���B���܂ŁA���̓W�J�ŕ��������Ƃ͐�ɂȂ������B����������̓��{�͉���������Ă����B���͈ȊO�̂��̉����ɂ���ăA�����J�͕������̂��ƁB���̈���ŁA���Ẵ`�[�����[�g�V�ɂ́A�u�V�I�肪�`�[�������������Ă����B���{�͖{���ɋ��������v�Ə̂��A�����I������A�삯����ďj�����邱�Ƃ�Y��Ȃ������B���́A�����ɃX�|�[�c�}���V�b�v�������B�����āA�t�F�A�v���[�̐��_���Q�[���̊�����{�������Ă����̂��������B2006�j�q���[���h�J�b�v�����ł̃W�_���̓��˂������͌����ɋy���A���t�v���[�����s����j�q�T�b�J�[�Ƃ͈Ⴄ�u�₩���������Ă��ꂽ�B
�@�A�����J�ł́A���q�T�b�J�[�͂��Ȃ�̃��W���[�E�X�|�[�c�ŁA�T�b�J�[�l����200���l�Ƃ������Ă���B������{��4���l�B�Ȃł����W���p���̒��Ńv���I���5�l�����B9�`�[�����琬��u�Ȃł������[�O�v�̑I��231�l�̂قƂ�ǂ��A�d���Ƃ�2���̂�炶���Ƃ����B���ϊϋq������900�l��J���[�O��20����1�B�ƂĂ����E��_������ł͂Ȃ��B����ȗȏ������ŁA�ޏ������͐��E��ɂȂ����̂ł���B���������ł����Ȃ��̂ł���B���̎���������A����̉����͊�ՂƌĂ�ނ����Ȃ��̂��B�u�D���������̏��Ȃ�v�u�V���y���ގ҂ɔ@�����v�Ƃ������A�ޏ��������x���Ă�����̂͐��ɂ��́u�T�b�J�[��D���v�Ƃ�����_���낤�B���ꂪ���邩��ǂ�ȋ�J�ɂ��ς����A�����ł��������m�b�����o�����Ƃ��ł����B�Ȃł����́A�X�s�[�h�ƃe�N�j�b�N�ō��グ���p�X�E�T�b�J�[��y��ɁA�`�[�����[�N�Ƃ�����߂Ȃ����_�𒍓����āA���҃A�����J�̍����ƃp���[�ӂ����̂��B��������A�_�������A�n���x���A�オ���𐧂��̐}�́A�^�ɒɉ��������B
�@�{�Ԃ́u�V�����MVP�͓��R�ł����A�S����MVP���Ǝv���܂��v�������ł���B�������X�E�F�[�f���평�攭��2���_���������쐟�ޕ���A���X�����h�C�c��̓y�d��Œl����̃S�[�������߂��ێR�̊���͌����ɋy���A��ɑO�ւ��������A�V�̕Иr�ƂȂ��ăT�|�[�g��������A�������ĊC�x�ɍ�����������y�L�[�p�[�R���̂��������������A�ꖡ�s�����E�A�����_���i���D�G�A�y���ȃT�C�h�o�b�N�L��������h�ɖ������ʂ������B�ēA�R�[�`�A�T���I����܂߂��S���T�b�J�[�̏����������B
�@������f�������̊ۂɂ́u���k�̊F����B�Y�ꂽ���Ƃ͂���܂���B���������ɂł��邱�Ƃ��l���Ă��܂��B����w�ǂ����ʂ�͂���x���̈�S�ł����B���_���������Ă݂Ȃ���̂Ƃ���։�ɍs���܂��B�҂��Ă��Ă��������B�������肪�Ƃ��������܂����v�Ƃ������b�Z�[�W��������Ă����B�����Đ��E�ɂ́uTo Our Friends Around The World Thank You For Your Support�v�Ɣ��M���Ă����B���k�ւ̎v���␢�E�̗F�l�����ւ̊��ӂ��A�Ȃł������㉟�������̂͊m�����낤�B
�@�V�͂��̌�������u�_�l�����ꂽ�`�����X�v�ƕ\�������B���g�̃T�b�J�[�l�������ł��ꂽ�A�����J�ւ̉��Ԃ��̃`�����X�Ƒ������B���������Ƃ̂Ȃ�����ɂ��Ȃ���������C�����Ȃ������Ƃ����B�����Ď��炪�`�[�������������Ďv���`�������ʂ������o�����B���̃S�[���͋�O���̐����������B�����̓ǂ݂Ə����Y�̐ꖡ�����̂����悤�Ȍ����ȋZ�B���߂��V�͂܂�Ō����̕���B�ޏ��������T�����C�E�W���p���i�u���[�j�ł͂Ȃ����B�D���Ɠ��_����MVP�ƃt�F�A�v���[�܁B�I�����s�b�N���q�}���\�������_���̍������q�������h�_�܂Ȃ�A�V���͉i�����_������܂ł���B�A����u�l�ԗ~���o����̂ŁA���x�̓I�����s�b�N�̋����_����_�������v�ƕ�����������B���ɗ��������R�����g�ł���B
�@�ł��A��������ŏ\�����A�Ǝ��͎v���Ă��܂��B���ꂾ���̊����̂��ƁA��̉���ޏ������ɋ��߂�̂��ƁB�����h���ŋ��Ȃ]�܂Ȃ��B���ʂɂ���Ă�������ł����B�����āA����Ȏ����A��x�Əo����킯���Ȃ��̂�����B�c��15���Ń��[�h���ꂽ���ƁA����̕����Ő��܂ꂽ���Ԃ�L���Ɏg���A�L���v�e�����l����q�����V���[�g�����߁A���_�㖢�̌��̃��b�h�J�[�h�Ŏ��_��h���APK��ł͐_������I�Z�[�u��A���ƁA�^�Ɗ�Ղ̃I���p���[�h�ł���B����ȃQ�[�����ǂ�����čČ�����Ƃ����̂��I ���_�A���̌��ʂ��Ăэ��̂́A�Ȃł����������|�����s�f�̓w�͂̎����ł��邱�Ƃ͒N���ے�ł��Ȃ�����ǁA����ł������Č����B����Ȏ����͓�x�Ƃ���킯���Ȃ��B�ꐶ�U������ɂ��ڂɂ�����Ȃ����낤�B������A�Ȃł����W���p���̊F����A�����h���ł͑傢�Ɋy����ł��������B���Ƃ��\�I�����ł����͋����B���Ƃ́u�Ȃł������[�O�v��グ�悤���Ⴀ��܂��B���肪�Ƃ��Ȃł����W���p���I ������������a���q�Ɋ��t�I�I
2011.07.10 (��) �b����`�u�V�F�G���U�[�h�v�ɂ܂��G�g�Z�g��
�@���N�̉Ă͏����I�S���I��6���ɂ�����ҏ������́A�ϑ��j��̋L�^�������������B���̂��Ƃǂꂾ�������Ȃ�̂��낤���H ���̒��́A�Ɉ��ڗ�j��Œᑍ����b�ɂ��̌������錾���̐��X��A�ډ���Ԃ̏d�v�|�X�g�ł���͂��̕����S�����̑�o�J�������C�ȂǁA����ɗǂ��Ȃ�Ȃ��ǂ��납�v�X�n�Ւ������Ă䂭�B�u�����Ƃ��v�̓R�b�`�̃Z���t���R�m�[�I���I �ҏ��Ə�Ȃ��ŕs���w�����オ����ςȂ������A����ȂƂ��ɂ́u�Č����N���V�b�N�v�ł��T���Ă݂悤�B�����͗������Ȃ邩������Ȃ��B�@�ĕ����y�Ƃ����A�|�s�����[�̐��E�ɂ́u�n���C�A���v������AJ-POP�ɂ͉ăo���h�u�`���[�u�v������B������N���V�b�N�́H�ƍl���Ă݂�ɁA��ԓI�ĕ�������킯����Ȃ��B��X����ʓI�ɉĂɕ����C���[�W�́A�C�A�R�A��ɐϗ��_�A�ċx�݁A�ՁA�ԉA���~�A�A�Ȃ����肾�낤���B�N���V�b�N�̏ꍇ�A����ȃL�C���[�h�Ɉ��������鉹�y���Z���N�g���邵���Ȃ��悤�ȁB
�@1970�N��A�������R�[�h��Ђ̉c�ƒS������������A�ď�ɃN���V�b�N�͔���Ȃ��Ƃ������������܂����B�����邩�ȁH �ł��A������܂˂��Ă���肶��\���Ȃ��B�����ŁA�������ȋȂ̃��R�[�h���W�߁A�u�����ĂԃN���V�b�N�v�Ɩ��ł��āA�ẴZ�[����W�J���Ă݂��肵�����̂ł��B�ڋʏ��i�́A���H�[���E�E�C���A���Y�́u��Ɍ����ȁv�u�C�̌����ȁv�A�_���f�B�u�t�����X�R�l�̉̂ɂ������ȁv�A�h�r���b�V�[�̌������u�C�v�A���q�����g�E�V���g���E�X�u�A���v�X�����ȁv������̃��R�[�h�B���܂蔄��Ȃ���������ǁA���X�̐l�Ɓu���Ȃ����͂悩������ˁv�ȂǂƁA�����₩�ɐ���オ�������̂ł���܂��B���ƂȂ��Ă͉��������v���o�A�̂ǂ��ʼn�������ł����B���������A�A���h���E�W�������F�́u�ԓ����t�ȁv�Ȃ�Ă̂�����܂������A���ł͂Ƃ�Ƃ��ڂɂ�����܂���B
�@������A�����g���u�V�F�G���U�[�h�v�͉ĕ����낤���H ���̋��w�̐l�C�nj��y�Ȃ̃x�[�X�̓A���r�A�̐��b�W�u����镨��v�ŁA�V�F�G���U�[�h�́A���l�ɖ�Ȗ�Șb�����鑏���ȉ��܂̖��B��Ȏ҃j�R���C�E�����X�L�[���R���T�R�t�i1844�|1908�j�́A�R�l�M���̉ƒ�ɐ��܂�A�C�R���w�Z���烍�V�A�C�R�ɓ����A�͑��ŊC�O�����̑̌�������ȉƁB������C�̕`�ʂ͂���̂��́B4�̊y�͂ɂ́A�u�C�ƃV���h�o�b�g�̑D�v�Ƃ��u�o�N�_�b�h�̍� �| �C �| �D�̐��̋R�m�̊�ł̓�j�v�ȂǁA�ă��[�h�\���ȕW�肪�t���B�e�L�X�g�́u����镨��v�ٍ̈���ƌ��z�����ēI�Ƃ����������B�����������A���ꂶ��܂����ߎ�ɖR�����B�N���̂��n�t�����~�����I
�@���āA�@�����̃����E������삵��CD�u�Ђ���N���V�b�N�v�iBMG�r�N�^�[1994�N�����j�̉�����ɁA�R�c�m���ē��u�j�͂炢��v�V���[�Y�Ŏg�����N���V�b�N�y�Ȃ͂̂�50�Ȃɂ��y�ԂƂ���B�m���ɁA48���50�ȂƂ����p�x�͔��[����Ȃ��B���̎R�c�ē̃Z���X�Ƌ��{���A�u�j�͂炢��v�ɉ��̐[����^���Ă���ƃ����E�����͎w�E����B�ꌩ�Ђ���ƃN���V�b�N�̓~�X�E�}�b�`�Ɏv���邪�A�ǂ����������țƂ܂��Ȃ̂��B
�@�Ⴆ�A��9��u�Ė����v�i1972�N���J�j�Ŏg��ꂽJ�D�V���g���E�X�̃����c�u�t�̐��v�B�g�i���S��������}�h���i�̎q���A����œЎ��Y�ɏo����ėF�B�ƈꏏ�ɂ͂��Ⴎ��ʂŗ��ꂽ���A�Ȃ̖������ƓЂ���̏o���ň�C�ɐ���オ�����Ⴂ���������̗N�X���������ɃV���N�����Ă����B�R�c�ḗA���̋Ȃ����C�ɓ���Ƃ݂��āA��8��u�Ў��Y���́v�i�r���~�q�j�A��30��u�Ԃ������Ў��Y�v�i�c���T�q�j�ł��g���Ă���B
�@��14��u�Ў��Y�q��S�v�i1974�N���J�j�ł́A�}�h���i���q�i�\��K��j�Ƃ�����A�����ēЂ��i���X�Řb��������ʂŁA���[�c�@���g�́u���z�ȃj�Z��K397�v������Ă����B��l���ʂ������c�ɓЂ����f���|�������Ƃ��C�ɕa�ނ�����̋C�����Ƌȑz�̕ω����A����܂������Ƀ}�b�`���Ă����B�I�[�h���[�E�w�b�v�o�[���̐������u�����ꂴ��ҁv�ŁA�ޏ��̌Z�o�[�g�E�����J�X�^�[���y�Y�ɔ����Ă����s�A�m���e���e����ʂ����邪�A���̋Ȃ������u���z��K397�v�������B���ɂƂ��ĖM�m�f��E�ő�̃A�C�h�����m�ł���Ђ���ƃI�[�h���[�̊ԂɁA��D���ȃ��[�c�@���g�̖���K397����݂��Ă���B���Ɋ�ɂ��Ċ������Ȃ���ł���B
 �@�u�V�F�G���U�[�h�v�́A��11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�i1973�N���J�j�̒��ő�3�y�́u�Ⴋ���q�Ɖ����v���g��ꂽ�B
�@�u�V�F�G���U�[�h�v�́A��11��u�Ў��Y�Y��ȑ��v�i1973�N���J�j�̒��ő�3�y�́u�Ⴋ���q�Ɖ����v���g��ꂽ�B�@�Ђ���́A�^�Ă̖ԑ��Ń��R�[�h�̃o�C�����Ă��鎞�A�h�T���̉̎胊���[�i��u�����q�j�Əo��B�e�L��Ɨ����̉̎�B�����̐���������l�����R�Ɍ��т���B�ޏ����������u�������̑��݂͂��Ԃ��݂����Ȃ��́v�ɋ������邪���Ȃ�����B�����łƂ����s�����n���ȐE�T���B�����ɂ��̋C�ɂȂ邢���̃p�^�[���ł���B���ʁA�ԑ��̔_��ŘJ�����邱�ƂɁB���y�́A�Ђ��ԑ��x�O�̌����_�������������V�[���ŗ����B�L��ł��r���Ƃ��������͂Ă̒n�E�k�C���ԑ��̎��R�ɁA���������R�ȗ���̃����f�B�[�����ɓ����ł����B�N���V�b�N�ʂ̎R�c�ē��Ă̖k�C���ɍ��킹���̂�����A�u�V�F�G���U�[�h�v�͊ԈႢ�Ȃ��ĕ��N���V�b�N�ł���B
�@���̂��ƁA�����ɖ߂��������[���Ė���K�˂ēЂƍĉ�B���Ƃ� fall in love �� broken heart �Ƃ��������܂�̋؏����ɂȂ邪�A�����Ƃ������ލ��Ōq�����l�̊W�́A����܂ł�10�l�̃}�h���i�ɂ͂Ȃ��V�N�ȃp�^�[���������B
�@�������킯�ł͂Ȃ����A�u�j�͂炢��v�̒��ŁA���̑�11��قǑ��푽�l�ȉ��y���g��ꂽ��i�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�N���V�b�N�ł́A�u�V�F�G���U�[�h�v�̑��ɁAJ�DS�D�o�b�n�́u�g�ȑ�R�ԃA���A�v���A�̗w�Ȃł́A�ܖЂ낵�́u���Ȃ��̓��v�A�����[���L���o���[�ʼn̂��u�`��������u�v�u�闈���v�ƕ��i�������ށu�z�㎂�q�̉S�v�A�����В��̂Ƃ���̍H�����̂��u�K���Ȃ������������v�A�]�ː�̓y��ɗ����n�[���j�J�́u�̋��̋�v�œЂ��S�L�Q���ʼn̂��̂̓V���[�x���g�́u���v�Ƃ�������ł���B
�@�]�k�����A�u�`��������u�v�͏��a22�N�̃����[�X�B��������������Ȃ����Ƀ��_���ş�������i�����A���̎����ɍ쎌��Ȃō��ꂽ�Ƃ����̂��������B������͓̂��C�O�B�����r�N�^�[�̎Ј����������������A���q���͍쎌�ƎR��H�v�ł���B
�@�������߂āu�V�F�G���U�[�h�v��m�����̂͒��w���̂��낾�����B�X�e���I�E���R�[�h���������ꂽ�̂�1958�N�B�����A���R�[�h��Ђ͂��̌��ʂ��f���邽�߁A�S���e�n�Ń��R�[�h�E�R���T�[�g���Â����B���_�܂��X�e���I���u�������Ȃ����́A�X�e���I�Ȃ鉹�����������ĉ��̎s���}���ق̏W��ɑ����^���̂ł���B�����Œ������̂��A�r�[�`�����w���F���C�����E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�́u�V�F�G���U�[�h�v�i1957�N�^���j�������B���R�[�h�E�R���T�[�g�ł́A�܂��X�e���I���ʗp���R�[�h���|����B�s���|���ʂ���̃X�s�[�J�[�̊Ԃ����E�ɍs�������B������E�ɗ�Ԃ�����ƁA�����͉E���獶�ɔ�s�@����ы���B�c�����́A�������ꂾ���Łu�X�Q�G��v�Ɗ����������̂��B�����āA�Ō�ɐ^�Łu�V�F�G���U�[�h�v�̓o��Ƒ�����̂ł���B�����A�u�V�F�G���U�[�h�v�Ƃ́A�X�e���I�̃f���E���R�[�h�Ƃ��ďo��������ƂɂȂ�B
�@���R�[�h�E�R���T�[�g�ŃX�e���I�̑f���炵����̌������Ƃ͂����A�䂪�ƂɃX�e���I���u���������͍̂��Z���ɂȂ��Ă���̂��ƁBCEC�̃��|�^�[�ɃO���[�X�̃_�C�i�~�b�N�E�o�����X�^�̃A�[�������t���A���I���̃N���X�^���E�J�[�g���b�W�����킹�����R�[�h�E�v���[���[�ƁA��������X�e���I�E�A���v�ɁA�X�s�[�J�[�̓R�[�����̓����^8�D�Ƃ������C���A�b�b�v�������B���̌�̃O���[�h�E�A�b�v�̗��j�́A�܂��ʂ̋@��ɁB �ŏ��ɔ������X�e���I�E���R�[�h�́A��͂�u�V�F�G���U�[�h�v�������B�������A���R�E�R���Œ������r�[�`�����Ղł͂Ȃ��A�L���O���R�[�h�����̃A���Z�����w���F�X�C�X�E���}���h�nj��y�c�i1960�N�^���j�̃��R�[�h�ł���B���t�̉����邩��������Ȃ��������́A���u���R�[�h�|�p�v�̉��t�E�^���]���Q�l�ɂ��Ă�������A�����ŁA���|�I�ɕ]���̗ǂ������A���Z�����Ղ���킸�������Ƃ����킯���B�m���P��3200�~�������ƋL�����Ă���B
 �@��̃��R�[�h�͍�������CD�Ƃ��Č��݂ł���B�D���ȋȂ͓��Ȉى���ɂ��݂Ȃ��������߂�Ȃ̂��鎄�́A�����܂߁u�V�F�G���U�[�h�v������22�����L���Ă���B�ʂ̃T�C�g�Ɂu���ɂ̃x�X�g���t�v�Ƃ����R��������1���Ă��邪�A7���x�́u�V�F�G���U�[�h�v�����グ���B�S22����CD�����߂Ē����Ȃ��������ʁA�u���ɂ̃x�X�g�v�́A�Ȃ�ƃr�[�`�����ՂɂȂ����B
�@��̃��R�[�h�͍�������CD�Ƃ��Č��݂ł���B�D���ȋȂ͓��Ȉى���ɂ��݂Ȃ��������߂�Ȃ̂��鎄�́A�����܂߁u�V�F�G���U�[�h�v������22�����L���Ă���B�ʂ̃T�C�g�Ɂu���ɂ̃x�X�g���t�v�Ƃ����R��������1���Ă��邪�A7���x�́u�V�F�G���U�[�h�v�����グ���B�S22����CD�����߂Ē����Ȃ��������ʁA�u���ɂ̃x�X�g�v�́A�Ȃ�ƃr�[�`�����ՂɂȂ����B�@�T�[�E�g�[�}�X�E�r�[�`�����i1879�|1961�j�̓C�M���X�̋����B�N��I�ɂ́A�u���[�m�E�����^�[�i1876�|1962�j�Ɠ����ŁA�t���g���F���O���[��N�����y���[�̐�y�i�ɓ�����B�J�������A�o�[���X�^�C���̓K�L�����Ƃ������Ƃ��낾�낤�B�C�M���X�a�m�ł���A���E�ȑ啨�w���҂������B�����l�͏�Ɏ�X�����A���y�͍Ō�܂Ŕ����Ƃ��Ă����B 50�N�ȏ���̂ɒ���s�̐}���قŏo��������t���A�ŏI�I�Ɏ��̃x�X�g�E�p�t�H�[�}���X�ƂȂ����̂͑傫�ȋ����������B���̉��t�A�����̎��ɂ͑S�������ł��Ȃ��������A�������ƁA���y�����R�Ŕ����Ɨ��ꂵ�����������������Ղ�A�ǂ�����Ă��▭�̐߉��������Ă���B���x�����Ă��O�������Ȃ����ɂ̖��l�|�Ȃ̂��B�^�����A�����E��ʂ��m���ŁA���������ƂȂ��Ă͑����̍d����������̂̑��̓I�ɂ͏\���ɔ������B�܂��Ɋ�Ղ̖��Ղ��B
�@�ł͂����A�u�V�F�G���U�[�h�v��3�y�́u�Ⴋ���q�Ɖ����v���r�[�`�����ՂŒ����Ă݂悤�B�ЂƂƂ��A���̗J���������ł��Y��邽�߂ɁB
2011.06.30 (��) ��k�Вf�́m9�n �����̒��� ��
�@��k�Ќ�A�����̃A�[�e�B�X�g�����̎v�������ɔ�Вn�ɏo�������B�S�ꂩ�牉����p�t�H�[�}���X�́A��Ў҂̊F����ɂƂ��ĂȂɂ��̑��蕨�������ɈႢ�Ȃ��B����Ȓ��A���|�I�������̂́A�������������Ǝv���B �@�����A�[�e�B�X�g���� ���ɏ��߂Ē��ڂ����̂́A�Ђ���f���37��u�j�͂炢�� �K���̐����v�i1986�N���J�j�������B�����͉�Ǝu�]�̊Ŕ`���ŁA�}�h���i�u����x�q�Ɨ��l���m�Ƃ����B��ɂ���ēЂ���͎u����ɍ���邪�A��l�̗l�q�����ăG�[���𑗂邱�ƂɂȂ� �Ƃ����ݒ�ł���B�������ł���l�͌����A�X�N���[�������H�����킯���B�����A�u����Ɂu���̋C�������������l�͌����v�ƌ����u����A�����܂����B�ǂ������ȂN�Y�A�˔\�̂ЂƂ����������Ⴕ�Ȃ��v�ȂǂƁA�X�˂Ď�C�ȃZ���t��f���ȂǁA���痂����͂܂��Ȃ��A�ނ��돝���₷���i�C�[�u�ȐN�Ƃ������ǂ��낾�����B
�@�����A�[�e�B�X�g���� ���ɏ��߂Ē��ڂ����̂́A�Ђ���f���37��u�j�͂炢�� �K���̐����v�i1986�N���J�j�������B�����͉�Ǝu�]�̊Ŕ`���ŁA�}�h���i�u����x�q�Ɨ��l���m�Ƃ����B��ɂ���ēЂ���͎u����ɍ���邪�A��l�̗l�q�����ăG�[���𑗂邱�ƂɂȂ� �Ƃ����ݒ�ł���B�������ł���l�͌����A�X�N���[�������H�����킯���B�����A�u����Ɂu���̋C�������������l�͌����v�ƌ����u����A�����܂����B�ǂ������ȂN�Y�A�˔\�̂ЂƂ����������Ⴕ�Ȃ��v�ȂǂƁA�X�˂Ď�C�ȃZ���t��f���ȂǁA���痂����͂܂��Ȃ��A�ނ��돝���₷���i�C�[�u�ȐN�Ƃ������ǂ��낾�����B�@���̂��Ƃ̒����́A1988�N�ɃV���O���u���t�v�ő�q�b�g�����A����TV�h���}�u�Ƃ�ځv�͕���18���̎������������A�o�D�Ƃ��Ă̒n�ʂ��z�����B1990�N�̑�A���ɂ́A�`����NHK�g���x�������̕ǒ��p������A�����āA1991�N��TV�h���}�u����ڂ�ʁv�ŁA�ނ̃A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̌����m�����ꂽ�Ǝv���B�܂��ɔj�|�̉��i���������B���̈�A�̗��������ƁA�ނ̏o���̂���������������̂́u�j�͂炢��v�������Ǝv���Ă���B��͂�A"�Ђ���"�̉e���͂͂����炱����ő�Ȃ̂��B
�@�u����ڂ�ʁv�̕���͍ĊJ���^������̐��V�h�B�����͌��₭���̈�ҁE��S�����������B�n�������҂���͐f�@�������Ȃ��A�܂�ŐV�h�̐ԂЂ��ł���B���͍͂ĊJ���̖��̉��ɁA�y�n��������߂Ă䂭�B�ړI�̂��߂ɂ͎�i��I������ɗL�������킹�Ȃ��B���Љ�I���͂����Ɏg���A��҂��炷�ׂĂ�D�����B��͂���ȕs�𗝂ȈŃp���[�ɑ����`���т��̂�B���ꂼ�����̋ɒv�B���̂����A��҂ɂ͗D�����A���������Ԃ�厖�ɂ���B���������߂��������Ƃ��₦�����E���邩������Ȃ��댯�n�ѐV�h�ł��A�����C�ȂǃT���T���Ȃ��B���������̂Ȃ����Ԃ����邻��ȐV�h����D���Ȃ̂ł���B�₪�āA���̖���͖�̐g�ӂő������A���l��F�l��D�G��炪���X�ɏ�����Ă����B���܂�ɗ��s�s�I ���X�g�E�V�[���A��̂������܂�Ȃ��C�����́A�����ւ̓{��ƂȂ�A�T�ώ҂ւ̕���ƂȂ�A�}�X�R�~�ւ̌x���ƂȂ��Ĕ�������B
�@�Ȃ�ł��������{�l���m�A�����݂���Ȃ��Ⴂ���˂��B�����������荇�������̓��{�l���ǂ����Ă��͍���Ă��Ă��܂����B�����������B�����ɉh���B�M�l��̎�łǂꂾ�������̐l�̖����₽�ꂽ���Ƃ��B���������̔ɉh�ɂ͕����҂��Ă��Ȃ����Ă��ƁA���ɂ͕�����Ȃ��̂��B�@���s�s�Ȃ��Ƃɂ́A���肪�ǂ�Ȃɋ����낤�������������B���Ԃ̃s���`�ɂ͂ǂ�Ȋ댯�����ڂ݂��ɔ�э���ł䂭�B����Ȗ�̕��O�ꂽ���`���ƗD�����Ɩ��S�C���́A���� �����̂��̂Ɠ������āA���́u����ڂ�ʁv�̃����f�B�[�ƂƂƂ��ɋ��ɔ������B���̂���̎��́A�������I�[�o�[���b�v���������Ȃ�̖������C���A�o�u������O��̐V�h�ŁA��Ȗ�Ȓ��Ԃƈ�����A�u����ڂ�ʁv���̂��܂����Ă������̂��B����40��̔��A���������Ď��������Ⴂ�Ȃ��̂ɁE�E�E�E�E�B�u�������[�E�`���b�v�����v�Ńf���G�b�g���Ă��ꂽ�v�������͂ǂ����Ă��邩�Ȃ��B�������̃A�W�g�������N���u�u�W���b�L�[�v�̂Ђ�݂���͌��C���낤���B�����̃}�X�^�[�͐����Ă��܂����B�����ƒ����Q���Ⴄ�q�̂܂��������A�����������Ɋ�������[�������̑叫�����͂������Ȃ��B�v����20�N���̘̂b�ł���B���������I
�@���ꂩ��A�@�����̌������Ń��W���Ă邠�������{������B��������Ă������݂̌�������B�����������Ƃ������A�����������̐ŋ����������̌����Ă邭���ɁA�V�h�ɓs�����Ԃ�������A�������o�b�N�ɊԔ����Ȗʂ��ăJ�����̑O��V�T�C������B���ꂪ���{�������I
�@�}�X�R�~�̊F�����B�ŏ��͂�����^������悤�Ɛ��`���ɋ���Ă����͂����B���ꂪ�A�����o�Ċ��炳��āA�䂪���`���̏�ɂ�����������Ă���B����Ȏ��i�[�������Ђ��ς邾���̓��{�����Ɏd���ďグ���̂́A�Ă߂���}�X�R�~�̃E�W���ǂ������Ă��ƁA�C�������Ⴂ�˂��̂��B
�@2011�N4��16���A�{�錧������n�Ɍ��ꂽ�����́A���q����1500�l�̑O�ɗ����Ă�����o�����B�u������ĉ�����Ă��܂�Ȃ������B���̗L�l�����ē��{�͂������߂��Ǝv�����B����Ȏ��F����̗E�p�������B�����ɓ��{���������B�F����͓��{�̌ւ�ł��B�l�̑厖�Ȍւ�ł��v�B�����Ď�����6�Ȃ��̂��B���Ɂu���t�v�ł́A�S���Ƒ升���ƂȂ����B�����́u�����J��Y��Ȃ��ŗ~�����B���͐�ɖY��Ȃ��v�ƒ��߂��B
�@�����ɂ͖�S���ƕς�ʒ����������B�V�h����D�������{����D���ɒu���������M���ăp���t���ŗD������l�̐l�Ԃ������B���Ԃ����L�������q�����ɂ́A��l�̗�O���Ȃ��A�������̖������Ɗ����̕\�������ł����B�u�ō��ł����B�܂��o�܂����B���C���o�܂����v�u�ŏ����烄�o�������B�������������ł��v�u�S���k���܂����B����������܂��撣�낤�ƁA�S�̒ꂩ��v���܂����v�u�������ł���Ɍ����L���܂����v�E�E�E�E�E�ꓰ�ɉ���ނ�̊|���l�Ȃ��̌��t�ł���B�̂��m���ɔނ�ɗ͂�^�����u�Ԃ������B�A�[�e�B�X�g�ƕ�����̐S���ʂ��A��ΓI���J������Ă����B
�@�������Ď��q�����ɗ͂�^�����������A��Ў҂ւ̑Ή��ɂ͔Y�悤���B�k�В��ォ���Вn�x���̃��W�I�ԑg�𗧂��グ�Ĕ�Ў҂Ƃ̑Θb���s���Ă����B���̒��ŁA�͕̂K�v�Ȃ̂��Ɩ₢�����Ă������B���̂ЂƂ܂��̓������A6��26���Ί��s���a�R�����ł�1000�l�̑升���C���F���g�������Ƃ����B7���ɂ͂��̖͗l���I���G�A�����悤���iNHK�uSONGS�v�j�B�ނ�Ŕq���������Ǝv���B
�@�����́A1991�N�����[�X�̃A���o���uJAPAN�v�̃^�C�g���Ȃł����̂��Ă���B
Japan! Where are you going?�@���S�N�Ɉ�x�̓V�Ђ������B������{�l�Ɍ�����ꂽ�^�̐��ɁA������������ς��邩������Ȃ��Ǝv�����B�ł��A�ꎞ�̖��������B���������ׂĂ��Ԃ����B���{�͂ǂ��֍s���Ă��܂��̂��H�ǂ��֗���Ă����čs���Ă��܂��̂��H �����_�����B���̍��͂����_�����B�ł��A��X���{�l�͂����𗣂�Ȃ��B���{��������߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B���܂��������̍�����D��������B20�N�O�̃y���V���p�̐����݂����ł��A���ׂ̌������ɉ��������������̂��B
�������@���̐�ǂ��ց@����Ă䂭�낤
�����lj������́@���̍��Ő��܂����Ă���
�т��ʂ��Ӓn�́@��ꂽ���̊X��
�������́@�܂�Ł@�ǂ��������ɂ܂݂ꂽ
�y���V���p�̐����݂�����
���₦�����@����ł��@�K���Ɂ@�V����
��ї��Ƃ��Ƃ��Ă�̂�
�x�̌������Ɂ@������������������
2011.06.20 (��) ��k�Вf�́m8�n�͂��I���y�̗́`�C�O�A�[�e�B�X�g��
�@��k�Ђ���R�������o�߂����B�x�@���̔��\�ɂ��ƁA1������̔��Ґ���146,253�l��6��11����88,361�l�������i16���ȍ~�͓��t�{�̔��\�ƂȂ�A���ݏZ����܂߂������ƕς�j�B�������ꂾ���̐l�X�����������������Ă���̂ł���B������Ƃ����āA�������o���l�������K�����Ƃ����Ό����Ă����ł͂Ȃ����낤�B�قƂ�ǂ̐l���A���C�̂Ȃ����ݏZ������e�ʒm�l�𗊂��Ă̋����炵�����X�ŁA���̏ꏊ�ł��Ƃ̕�炵�����Ă���l�͂ق�̈ꈬ��ɉ߂��Ȃ����낤�B�l�Ԃ̐h���͐�Ɋ�]�������邱�Ƃʼn\�ɂȂ�B���A���̂��A���ɂȂ�������Ƃ̐����ɖ߂��̂��A���̌���^����̂������̗͂Ȃ̂����E�E�E�E�E�B�@���y�ɂ͊m���ɐl���ە�������̂�����B�C������a�炰�S������͂�����B�k�Ќ�ɍs��ꂽ���y�s�ׂ�|�\�l�̊������A�����ő������Ă��������B
���Y�[�r���E���[�^��
 �@�C���h�o�g�̖��w���҃Y�[�r���E���[�^�́A3��11���A�t�B�����c�F�̌�������̂��ߓ��{�ɂ������A�˔@�Ƃ��ċN��������k�Ђɗ�����]�V�Ȃ����ꂽ�B���̂��Ƃ��C�Ɋ|���Ă������[�^�́A4��10���A�k�Д�Q�Ҏx���`�����e�B�[�E�R���T�[�g���w�����邽�߁A����������قɖ߂��Ă����B
�@�C���h�o�g�̖��w���҃Y�[�r���E���[�^�́A3��11���A�t�B�����c�F�̌�������̂��ߓ��{�ɂ������A�˔@�Ƃ��ċN��������k�Ђɗ�����]�V�Ȃ����ꂽ�B���̂��Ƃ��C�Ɋ|���Ă������[�^�́A4��10���A�k�Д�Q�Ҏx���`�����e�B�[�E�R���T�[�g���w�����邽�߁A����������قɖ߂��Ă����B�@�R���T�[�g�̓��[�^�̈��A����n�܂����B�u�������J�̍����A���ł��܂������Ă����Вn�̕��X���A��N��A�����Ă���ȍ~�����N�����y���߂�悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��F�����ł��B�������͍��A��Ђ��ꂽ���X�₲�Ƒ��y�b�g�����Ɏv�����F�������܂��v�B�ꕪ�Ԃ̖ٓ��̌�AJ�DS�D�o�b�n�́u�g�ȑ�O�Ԃ��A���A�v���A���������x�[�g�[���F���́u���v�����t���ꂽ�B�������J�̏��̓m�ɁA���[�^�w��NHK�����y�c�ɂ��u���v����Вn�ɓ͂��Ƌ����킽�����B
�@�u���v�͕��a�ƗF���̋Ȃł���B���a��������X�y�C���̋����p�u���E�J�U���X�i1876�|1973�j�̓t�����R�ƍِ��������������̂Ă��B�ނ̐��U�̖��́u���剻�Ȃ����c���Łw���x�����t���邱�Ɓv�������B���́A�������ɂ͊���Ȃ��������A1992�N�o���Z���i�E�I�����s�b�N�̊J��ŁA�ނ̈�u���p�������y�Ƃ����ɂ���Ď��������̂ł���B�܂��A�x�������̕ǂ�����1989�N12���ɂ́A���a�̏ے��Ƃ��āu���v���A�����h�C�c�����I�[�P�X�g���ɂ�艉�t���ꂽ�i�w���̓��i�[�h�E�o�[���X�^�C���j�B
�@����̃`�����e�B�[�Ɂu���v���I�ꂽ�̂́A���a�̓��������Ă̂��̂������낤�B���[�^�́A����ȃ��b�Z�[�W���c���āA���{�������Ă������B�u�n�k�A�Ôg�A�����Ƃ����O�d�̋ꂵ�݁B����ȂЂǂ����Ƃ������Ă����̂��I ���̍���ɑ����{�l�͗E���ɗ����������Ă��܂��B�c�A�[�Ń��[���b�p�A���V�A�A�C���h�Ȃǂ����܂������A�N�������{�l�̍s���h���Ă��܂����B���{�������鎄�Ƃ��Ă��A�ƂĂ��ւ�Ɏv���܂����B�����Ă���Ƃ��A�炢�Ƃ��A���y�͋C�����𖾂邭���A�S�Ɉ��炬��^���Ă������̂ƐM���܂��v�E�E�E�E�E���[�^�������Ă��ꂽ�悤�ɁA��k�Г����̓��{�l�̍s���͊C�O����傢�ɏ^���ꂽ�B������Ԃ��Ă��܂����̂͐����Ƃł���B���ނ���A��Вn�Ɣ�Ў҂݂̂Ȃ���ɖڂ������ė~�����B�C���������ւ��āB�����肤����ł���B
���v���V�h�E�h�~���S��
 �@�v���V�h�E�h�~���S�͎O��e�m�[���̈�l�Ƃ��ėL�������A������Ȃ�20���I�ő�̉̎�̈�l�B�u��k�Ќ�A�����Ă�܂Ȃ����{�ɐS���Ă����B�ꎞ�ł��炳���l�����ɂ��ގ��Ԃ������Ă�����������Ɗ���Ă��܂��v�Ƃ��āA4��11���A�������ŗ�����NHK�z�[���̕���ŃR���T�[�g�ɗՂB�I�P�͓��{�t�B���n�[���j�[�A�p�[�g�i�[�̓��@�[�W�j�A�E�g�[���A�h�~���S�Ƃ͖��قǍ̈Ⴄ�\�v���m�ł���B
�@�v���V�h�E�h�~���S�͎O��e�m�[���̈�l�Ƃ��ėL�������A������Ȃ�20���I�ő�̉̎�̈�l�B�u��k�Ќ�A�����Ă�܂Ȃ����{�ɐS���Ă����B�ꎞ�ł��炳���l�����ɂ��ގ��Ԃ������Ă�����������Ɗ���Ă��܂��v�Ƃ��āA4��11���A�������ŗ�����NHK�z�[���̕���ŃR���T�[�g�ɗՂB�I�P�͓��{�t�B���n�[���j�[�A�p�[�g�i�[�̓��@�[�W�j�A�E�g�[���A�h�~���S�Ƃ͖��قǍ̈Ⴄ�\�v���m�ł���B�@�R���T�[�g�́A���n�[���̊�̌��u�قق��݂̍��v����u�N�͂킪�S�̂��ׂāv�Ŏn�܂�A�u�����[�E�E�B�h�E�v�̒��l�C�f���G�b�g�E�i���o�[�u�O�͖ق��āv�ɑ����B�Â��S�������̂́A��l�̑����s�b�^�������āA�K���C���ɐZ�点�Ă����B�̌��u�g�X�J�v�́u��������ʁv�̓e�m�[���̒�ԋȁB���������ʐ��ʂƐ��̉��́A70�Ƃ͓���v���Ȃ��B�����u�A���h���A�E�V�F�j�G�v�̃A���A�u���𗠐���́v�̓o���g���̎����́B�v���ɂ�荂���n�ʂɒ������V�F�j�G�̗F�l�W�F���[�����A���ĂЂ��ނ��ɗ��z��ǂ����߂Ă���������v�������ׁA���������̎����Ɏ��������߁A���O�̂��߂ɐ����悤�Ɖ��S����A���A���B�u�����ɂ����ċP���������X���������B�����ŁA���S�ŁA�͋����������X���B���A�����͖��Ɩ����ւ̐M�������Ă��܂����B����Ȃ��Ƃł����͂����Ȃ��B���͕ς�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂���̎����ɁB���ꂩ��́A�s����ꂽ�l�X�̗܂��W�߁A���E��_�a�ɕς��悤�B�ڕ��ƕ��i�ŁA���ׂĂ̐l�X��������̂��v�h�~���S���A�킴�킴�o���g���̃A���A��I��ł܂Ō��������������ƁA����͓��{�̃g�b�v�ɑ���x�����H �����������Ƃ͎v���A������Ƃ���ȋC�������B�́A�u�A���h���A�E�V�F�j�G�A�ō��v���Ȃ����Ă͂��Ⴎ��������āA�u���̐l�A�������ĂȂ��ȁv�Ǝv�����L��������܂����̂ŁB
�@���̂��ƁA�u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v�́u���̂��C�ɓ���v�A�u�}�C�E�t�F�A�E���f�B�v����u�N�Z�ފX�Łv�A�u�E�G�X�g�E�T�C�h����v����u�g�D�i�C�g�v�Ȃǃ~���[�W�J���E�i���o�[�������B����ǂ���̌��̂���Ȃ��I�Ȃ��B
�@�h�~���S�̌̋��X�y�C���̉̃T���X�G������3�ȉ̂������ƁA�ނ͂�����o�����B�u���{�݂̂Ȃ���̂炢���X�͒m���Ă��܂��B�l�ޑS�̂��ɂ܂����C�����ł��܂��B�݂Ȃ���Ƃ̂Ȃ�������������Ă��̃R���T�[�g���s���܂����B�K���������͍��݂Ȃ���̐S�ƍ��ɓ͂������ł��܂��B����͓��{�̉̂����͂����邱�Ƃł��B�݂Ȃ���ƈꏏ�ɉ̂��܂��傤�B�w�ӂ邳�Ɓx�v�E�E�E�E�E���̂��������̗͂������B���܂ŕ��������Ƃ̂Ȃ��u�ӂ邳�Ɓv�������B���{��͊m���ɂ��ǂ��ǂ����������A�C�������`����Ă����B�ꐶ�������t���Ȃ���p�ɒN�������������B����������Ȃ����ӂƗD�����ɁA���݂̂�Ȃ��܂��Ĉꏏ�ɉ̂��Ă���B�Ō�͎��R�ɃX�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����ɂȂ����B�����̉Q���z�[�������ς��ɍL�������B
�@���̂��Ɓu�O���i�_�v�Ŗ��ƂȂ������A��͂�u�ӂ邳�Ɓv����ԃW���Ɨ����B�����͓��{�l�Ȃ� �Ɖ��߂Ďv�����B���{�݂̂�Ȃ́u�ӂ邳�Ɓv�ɓ�x�ƍĂт���ȍГ�U�肩����Ȃ��悤�ɁA�����Ĕ�Вn�������������������悤�ɁA���������F�����ł���B���肪�Ƃ��A�h�~���S����I
���V���f�B�E���[�p�[��
 �@80�N����\����A�����J�l�̎�ŁA��̐e���Ƃł���B�k�Ђ̋N����3��11���́A�R���T�[�g�̂��߂ɗ������Ă����B�Ȃ��14��ڂ̗������Ƃ����B�C�O�A�[�e�B�X�g�̃R���T�[�g�����X�ɃL�����Z������钆�A�ޏ��͗\��ʂ�̃X�P�W���[�������ׂĂ�萋�����B
�@80�N����\����A�����J�l�̎�ŁA��̐e���Ƃł���B�k�Ђ̋N����3��11���́A�R���T�[�g�̂��߂ɗ������Ă����B�Ȃ��14��ڂ̗������Ƃ����B�C�O�A�[�e�B�X�g�̃R���T�[�g�����X�ɃL�����Z������钆�A�ޏ��͗\��ʂ�̃X�P�W���[�������ׂĂ�萋�����B�@�������Ԓ��Ɏ��^����NHK�uSONGS�v������B�u���̐S�݂͂Ȃ���Ƌ��ɂ���܂��B���E�����݂Ȃ���̖������F���Ă��܂��v�ƌ�����B���킹�āA�̂���2�Ȃ̉̎�����ۂɎc�����B���̂���̐��Ƌ��ɁB
�@True Colors�u���Ȃ��̖{���̐F�͂ƂĂ��������B������A���������炯�o�����Ƃ�����Ȃ��Łv�@Time After Time�u���Ȃ����|�ꂻ���ɂȂ�����A�����~�߂Ă�����v�E�E�E�E�E�͎̂���"�����ɂ����郁�b�Z�[�W"�ɂȂ�A�ƒɊ������B
����������̃��b�Z�[�W��
�@���̂ق��ɂ��A�C�O���B�X����A�[�e�B�X�g���琔�����̃��b�Z�[�W���͂���ꂽ�B�S���L�^���Ă�����������ǁA���̂܂܃R�s�[���Ă��|���Ȃ��B���{�Ƃ̊ւ��x�����̈Ⴂ����e�͗l�X�ł��A�v���͓����ł���B����́A�T�ˁA��Q�ւ̐S�̒ɂ݁A��Ў҂ւ̌ە��A���{�l�̐��_�ւ̑��h�A�A�ъ��ƋF��ɏW���B�������u�N�����m�I���㕶�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߁A��ꂽ�A�[�e�B�X�g�����L���āA�����������B
�@�������́A���{�ɋN������ЊQ��ڂ̓�����ɂ��āA�S�͂Ђǂ��ɂ�ł��܂��B�ł��A�������͍���ɗ����������F����̗͂�m���Ă��܂��B���̋����ƗE�C�́A�K���₱�̏ɑł������Ă������̂ƐM���Ă��܂��B�W�F�t�E�x�b�N �@�G���b�N�E�N���v�g�� �@�|�[���E�}�b�J�[�g�j�[ �@�U�E���[�����O�X�g�[���Y �@�W�����E�{���E�W�����B �@�|�[���E�T�C���� �@�r���[�E�W���G�� �@�I���r�A�E�~���[�g���E�W���� �@�T���E�u���C�g�}�� �@���f�B�[�E�K�K �@�N�C�[�����@�i4��2�����fNHK�u�f�W�^���E�v���j�A���E���C�u�v���j
�@�������͊F����̃g���_�`�ł��B���E�����x�����Ă��܂��B�������̐S�͏�ɊF����Ƌ��ɂ���܂��B���̑�ςȏ��ꍏ�������I��邱�Ƃ������F���Ă��܂��B
�@�K���o�b�e�I ��������I �����āA�_�̂�������I
2011.06.05 (��) ��k�Вf�́m7�n�Ԏq�̓����ŗx�������
 �@����ANHK-BS�����Ă�����A����YMO���ז쐰�b���A�u3�D11��k�Ќ�A���炭�͂Ȃɂ�����C���N����Ȃ������B�����A�n�}���L���Č����̈ʒu���m�F�����肵�Ăˁv�Ȃǂƌ���Ă����B�ז�Ƃ����A1960�N�ォ����{�̃|�b�v�E�~���[�W�b�N�E�V�[�����������Ă������҂ɂ��ă��[�_�[�I���݁B����䊗m�Ƃ������i�͌��̋��n���犴��������B����Ȕނɂ��āA���̐S���B
�@����ANHK-BS�����Ă�����A����YMO���ז쐰�b���A�u3�D11��k�Ќ�A���炭�͂Ȃɂ�����C���N����Ȃ������B�����A�n�}���L���Č����̈ʒu���m�F�����肵�Ăˁv�Ȃǂƌ���Ă����B�ז�Ƃ����A1960�N�ォ����{�̃|�b�v�E�~���[�W�b�N�E�V�[�����������Ă������҂ɂ��ă��[�_�[�I���݁B����䊗m�Ƃ������i�͌��̋��n���犴��������B����Ȕނɂ��āA���̐S���B�@4��10���A�ז�͑�k�Јȗ����߂ĂƂȂ郉�C�u���s�����B�ߓd�̂��ߊy��͂قƂ�ǃA�R�[�X�e�B�b�N�B�Ɩ��͘X�C�B�̂����̂́uLove me�v�ƁuSmile�v�̓�Ȃ����B���Ƃ͏I�n�k�ЂɓZ���g�[�N�������B���C�u�̌`�Ƃ��Ăُ͈�B�u����ȗ��A���y�ƂƂ��ẴX�^���X���m���ɕς����v�ƌ����Ƃ���̒����������B���Ȃ킿�u��Вn������ȏȂ̂ɁA���͂���Ȃ��Ƃ�����Ă��Ă����̂��v�Ƃ������y�Ƃ̎���ł���B�������������A�������Ƃ����⎩�����閈���������B���������Ȃ�ł����ˁB�ז�������A�v���ƃA�}�A�n���ƌ����̍���������A�u����Ȃ��Ɓv�Ƃ͉��y�ł���B��k�Ђ́u���y���ĂȂv�Ƃ��������I�ȃe�[�}�������Ȃ蓊�����Ă��ꂽ�̂��B
�@���Ď����Ζ����Ă������R�[�h��Ђł́A�����̗Ƃł��郌�R�[�h���u�����K���i�v�Ƃ������t�ŕ\�����Ă����B���R�[�h�i�����y�j���Ȃ��Ă������Ă͂�����B���̈Ӗ��ŁA���y�͐����K���i�ł͂Ȃ��B�u�����v�A�����l�Ԃ炵�����݂��邱�Ƃɂ����ĉ��y�͕K���i�Ȃ̂ł���A�Ƃ����T�O�ł���B�t�Ɍ����A����Ȃ�̐����������ۂ���ď��߂ĉ��y�Ƃ������̂��Ӗ��̂��鑶�݂ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ��B����ɒ��̐g���̂܂܁A�Z����������A�H���Ȃ��A���e����������Ў҂ɁA���y�Ȃ�ĂȂ�̖��ɂ������͂��Ȃ��B���ɂ���Ɖ��������X�`�ƕ��C���~�����B���y�Ȃ�ē�̎����B���y�Ƃ̊������V���b�N�͂����������Ƃ������̂ł͂Ȃ����B���y�̖��͂��̎����B�u���������܂ł���Ă������Ɓv�ւ̋^��B�u��̎����͂Ȃ����̂��B�͂����Ď����Ƃ������݂ɈӖ����������̂��낤���A�����Ă��ꂩ����v���A���₹��������Ȃ������B
�@������͎��R�̋��낵����ڂ̓�����ɂ������ƁB���y�Ǝ��R�͖��ڂɂȂ����Ă���͂��������B���̂悢�F�B���Ǝv���Ă����B�x�[�g�[���F���́u�c���v�A�}�[���[�̌����ȁA�u���b�N�i�[�̌����ȁA���[�O�i�[�̊y���u�W�[�N�t���[�g�v�AR�D�V���g���E�X�́u�A���v�X�����ȁv�A�����X�L�[���R���T�R�t�́u�V�F�G���U�[�h�v�A�O���t�F�́u�O�����h�E�L���j�I���v�Ȃǂ��A���R�Ƃ̑Θb���琶�܂�o����i�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��낤�B���Ƀ}�[���[�Ȃǂ́u���͎��R�̉������y�ɂ��Ă���v�Ƃ܂ł͂����茾���B���̂Ƃ��̎��R�͂܂�����Ȃ��₳�������R�ł���B�Ⴆ�������Ă������Ɏ~��ŕ����������ǂ��B�����ۂ��Ȑl�Ԃ�傫���D�������ł����R����C��X�A������悤�Ȑ���A���������ԁA���C�Ȓ������̂����₫�A�̂ǂ��ȓc�����i�A�������B���ꂪ���̐k�Ђł���BM9���������Ôg�͐l���Ƃ�c�����`����u�̂����Ɉ��ݍ���ł��܂����B�܂�ň����̎d�ł��B����قǒ��ǂ����������R������Ԃ��悤�ɉ�����̂��B���y����҂ɂƂ��Ă��̂��Ƃ��{���ɃV���b�N�������B���y�̌��ɂ����Ď��R�^���Ȃǂł��Ȃ��Ȃ����B
�@ �@�₪�āA���y�Ƃ�|�l�������o�����B�̎�̏ꍇ�A�u�������ɂȂɂ��ł��邩���l������A�̂����Ƃ����ł��܂���B������̂��܂��B�����Ă��������v�B�T�˂���ȑO������p�t�H�[�}���X���n�܂����B�ǂ��Ȃ낤���A���͂�����Ƃ͂��ɍ\���Č��Ă����B�S�łp�t�H�[�}���X������������ǁB
 �@���傤�ǂ���Ȑ܁A4��23���̒����V���Ɂu�Ԏq�̓����ŗx�������v�Ƒ肵�����x�����ԙZ�̕��͂��ڂ����B�ȉ��v�ē]�ڂ���B
�@���傤�ǂ���Ȑ܁A4��23���̒����V���Ɂu�Ԏq�̓����ŗx�������v�Ƒ肵�����x�����ԙZ�̕��͂��ڂ����B�ȉ��v�ē]�ڂ���B
�@�����������Ƃ�ڂ̑O�ɂ���ƁA�l�ԁA�ڂ����Ƃ��邵���Ȃ����Ȃ��Ǝv���B�������������n�k������Ƃ͎v���Ă����B�ł��A�������Ă��܂��ƁA�����̂ق����z�����͂邩�����Ă��܂��Ă����B�@�����ȕ��́A�����āA�����ȐS�̍\���ł���B���x�ɂ܂�őa�����́A���̐l�����҂���S���m��Ȃ������B90�ł܂����C�ȕ�Ɂu�L���ȕ��x�ƂŁA��X����̕��e��B���n�`�ŕ��s��������������o�D�́v�Ƌ�����ꂽ�B
�@���⎩�R�ЊQ�ȂǁA�ǂ����悤���Ȃ����̂ɑ��鋰�|�Ɛ܂荇�������邽�߂ɁA�@����|�p�Ƃ������̂�����B���R�ɑ���l�Ԃ̔��R����Z���T�[�����m�������̂��A���t�ɕϊ����邱�ƂȂ��A���̂܂o���̂��x��≹�y�B�x���͔畆���o�Ő��E�ƃ_�C���N�g�ɂȂ����Ă���B���ʂ܂ŐԎq�ł����邱�Ƃ��������̓����ȂB���̓����ƈ��������ɁA���тƂȂ�A�ڂɌ����ʉ����ɗx������シ��B�傰���Ɍ�����������̉c�݂̈ꕔ�ȂƎv���B
�@�܂�͏����Ȓ����̋C�������A���l���ĕ����ŁA�Ђ傢���ĊȒP�ɉ������ꂿ�Ⴄ�̂��ʔ����˂��B�Ȃ����k�̐l����������ȂɎ���ŃI���������c�����A������������A�킩��Ȃ��A���Ă������������������A�ЂƂ�ЂƂ肪�ȂȂ�̂�����T���̂��u���ށv���Ă�������Ȃ��̂��ȁB
�@���������Ă���ƁA���z�Ɍ������āA�X�̗��Ŕ��ł����C�J���X���v���o���B��ɂ��Ă��܂����֗�������������A�����Ƃ����ƁA�Ɣj�łɎ���܂ŗ~�]���剻�����Ă䂭�B������܂��A�l�Ԃ̋ƂȂ̂��낤���B
�@�k�Ђ͔�Вn�̉����ɂ���l�����̋��ɂ��[�����˂��h�����B���{�l�݂�Ȃŏ\���˂�w�������B�����炱���A�S������Ԃ����߂���B
�@�I�������͒W�X�Ɨx�葱�����B���⎩�R����ċF��A�F�邽�߂ɗx�邵���Ȃ��B
�@���l�H�Ƃ�ł��Ȃ��B���{�l�݂�Ȃŏ\���˂�w�������B�����̂�����T���̂��u�Ǔ��v���Ă��Ƃ��B�W�X�Ɨx�葱�����E�E�E�E�E�Ȃ�Ƃ������́I���Ȃւ̗h�邬�Ȃ��m�M�B�|�p�̖{���ɔ���[�����@�ƕ\���s�ׂւ̉s�����y�B�d��͌����ɂ܂ŋy�ԁB���ꂪ�^�̌|�p�ƂƂ������̂Ȃ̂��B�u�����ꂽ�v�Ɗ������B�����̒��̔���킪�I������B
2011.05.25 (��) ��k�Вf�́m6�n�����}��A���Ɍ�����؍����͂Ȃ�
 �@5��20���A�����d�͂̐������F�В����ޔC���A����r�v�햱���������i�����B�P�W��������Ӗ��ł͕K�v�Ȍ��Ȃ̂��낤���A�^�̃h���ł��鏟���P�v��͗��C�ł���B�����В��́A�ߓ��A�������̔��Ō�����Ў҂���u�����A�y��������v�Ɣl���A���ɕ����Ďӂ����B���͂��̌��i�����Ď��ɕ��G�Ȏv�����������B
�@5��20���A�����d�͂̐������F�В����ޔC���A����r�v�햱���������i�����B�P�W��������Ӗ��ł͕K�v�Ȍ��Ȃ̂��낤���A�^�̃h���ł��鏟���P�v��͗��C�ł���B�����В��́A�ߓ��A�������̔��Ō�����Ў҂���u�����A�y��������v�Ɣl���A���ɕ����Ďӂ����B���͂��̌��i�����Ď��ɕ��G�Ȏv�����������B�@�m���Ɍ�����Ў҂ɂƂ��ē��d�͋����Ȃ����낤�B���̂������܂ŋ��剻���������́A�Ôg�Ƃ������͂ނ��듌�d�̓m��Ȋ�@�Ǘ��̐��ɂ������̂�����B�u��X�̎S�߂Ȑ����̌����͓��d���B�Z�݊��ꂽ�䂪�Ƃɂ��A��邩�̕ۏ��Ȃ��v�ƍl�����Ў҂̑O�ɁA�����В����Ј��������A��Č��ꂽ�B�u�ȂA�����炤��ׂ����Ŏӂ��āA�ЂƂ܂�����ōς܂����Ƃ����̂��B�R�`�g���Ս��Ȋ��̒����ʎv���ŕ�炵�Ă�A�Ȃ̂ɂ��O�����͍����}���V�����łʂ��ʂ��ƁE�E�E�E�E�ӂ�����l�G�I�v ����ȋC�������u�y��������v�����ɂȂ����̂��낤�B���{��"�ӔC�͈�`�I�ɂ͓��d�ɂ���"�ƘA�Ă��Ă���B��Ў҂̊F����̎v�l��H���u�����͓��d�A�����̂̓R�C�c�����v�ƂȂ�̂���������ʂƂ��낾�B
�@����������Ƒ҂��ė~�����B�����𐄐i���Ă����͍̂��Ȃ̂ł���B���S�ӔC���d�͉�ЂƓ����i�ȏ�j�ɂ���͂����B����������Ƃ��Čf���A����ȗ\�Z�𒍂����݁A�d�͉�Ђ�w�҂���荞�݁A�n�������̂�U�����݁A���Ύ҂�r�˂��āA�K���V�����ɐ��i���Ă����̂ł���B����Ȃ�Γd�͉�Ђ��R����͂����Ȃ��B��Έ��S��ۏ����A���n�����̂͑��z�ȏ������ɖڂ�����ށB���̈Ӗ��œ����d�͂��n�������̂��A���v�̋���҂ł���Ɠ����ɔ�Q�҂ł�����̂��B������A�u�y��������v�̐^�̖���͍��ł���A���Y���}�ł��鎩�R����}�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���{���J��Ԃ��u�ӔC�͈�`�I�ɂ͓��d�ɂ���v�́A�u���ɂ���v�Ɗ������ׂ��Ȃ̂��i�u�����}�Ɂv�ƌ���Ȃ��͎̂Љ�l�Ƃ��Ă̐m�`�ł���j�B
�@�����_�ɂ����鐭���̒���́A��ɐ����l�Ƃ���������b�̌��������l�i�ƃ��[�_�[�V�b�v�̌��@�ɋN�����Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ����Ƃł��邪�A�������`����Ă��������}�̃c�P�̑傫���ɂ�镔���������ď������͂Ȃ��B����̌������̂̐ӔC�Njy���ƂĂ��͂��䂢�̂́A�Njy����Ă�����ׂ������}���O��Ȃɂ��邱�Ƃ��B���̂������ł͖ڗ����ʂ悤�ɂ���̂��ނ�̏��������낤���A�����֘A�̐����Ƃ������ŋ߃|�c�|�c�Ƃ��̂������n�߂��B
�@���[���j�������}�Q�c�@�c����5��5����20���A�����V���Ŏ��_���q�ׂĂ���B
�����̌���́A���d�o�g�A������c���Ƃ��ē�d�̐ӔC�������Ă���B�C���^�[�l�b�g��Łw���O�͍i��Y���x�w�`����Ƃ��x�Ə�����Ă炢���A���q�͂�I���������Ƃ͊Ԉ���Ă��Ȃ������B�n���̋����v�]���������ł��A�n��̌ٗp�⏊�����オ�����̂��������B����ʂ̕��ː��́w�ނ���̂ɂ����x�Ǝ咣���錤���҂�����B�Ôg�̑z��Ȃǃ��X�N�Ǘ����Â������Ƃ�����B�x������v�������A���d�⌴�q�͋ƊE�����ŏ���ɑz������߂��̂ł͂Ȃ��A����I�ȋc�_���o�č������S�������A����ɂ��������Č��������݁A�^�]���Ă����̂��B���͍̂��Ɠ��d�A�ƊE�S�̂̋����ӔC���Ǝv���B�@���d�o�g�҂Ƃ������ƂŁA���Ԃ̓��d�����ɐӔC�������t����Ƃ��������ɂ͔��̗���ŁA����͊ԈႢ����Ȃ��B�����͍���Ƃ��Č��������������Ői�߂Ă����̂�����B���̈�́A����䂦���������s���ɓ������ꂽ���Ƃɂ���B�����Ƃ����������A�ւ��l�Ԃ̗ǐS��N�H����Ⴢ����A�P�ǂȎs������]���Ă����̂��B�n���̋����v�]�H ��k����Ȃ��B�����u��Έ��S�v��ۏ��ĎD���Ŕ[�������������ł���B���ڏt�����q�͈��S�ψ���ψ������u2�{�Ń_���Ȃ�5�{10�{�o�������B�Ō�͂��Ȃ炸�܂��v�ƌ������Ĝ݂�Ȃ��ł͂Ȃ����i���S���i��ׂ��g�D�̒������̕���悤�B���̕��͂܂��A3��12��"�C������55���Ԃ̋�"�̌����Ƃ������Ă���A�܂��ɍ������́j�B�z�������I�ȋc�_�̏�ɂȂ��ꂽ�Ƃ������A���Ɏ�荞�܂ꂽ���Ƃ̈ӌ��ɉȊw�ɑa������c�������_�ł���킯���Ȃ��B�����́A�������i�͍��̃S�������ł͂Ȃ�����I�ɐ��s���ꂽ���Ƃɂ��������������̍��ꂽ�_���Ȃ̂ł���B�u���ː����̂ɂ����v�͂��͂�����̈�ł���B�S�������ēK�ʂ̕��ː����̂ɂ����Ƃ��āA��̂��ꂪ���̗ʂ߂��Ă����Ƃ����̂��B����͂�A�Ƃ�ł��Ȃ������Ƃ��������̂ł���B�����Ƃ��������͐l�������܂��Ȃ߂�̂ł��낤���B
�@�������̒����V���ɂ́A�u�����������i�h�͂�n���v�Ƃ������o���ŁA�u���q�͂����v�����c �����������Ƃ������B�ψ����͊×����A�ψ����㗝�ɍדc���V�A���ψ����ɂ͐����N���e��������A�˂�B���̂͌��q�́H �����̐�������Ȃ��ł����H ����3�l�A�}�[�N����K�v�����肻�����B
�@5��20���A�t������Ƃ�ł��Ȃ���������яo�����B�^�Ӗ�]�o�ύ��������S����b�ł���B
�����̎��̂͒N���N���������Ƃ����A�_�l�̎d�ƂƂ��������ł��Ȃ��B�l�Ԃ̒q�b�Ƃ��Ă͍ō��̒q�b�������B�@ �@���x�̑�k�Ђł͐��X�̎������������B�Ⴆ�A�Ό��s�m���́u��k�Ђ͓V���v�����A��������b�́u�����ɂ�10�N�A20�N�Z�߂Ȃ��v�ȂǁB���̒��ł�����͒��W���̐��݂�����B
�@���m�̒ʂ�A���̕��͓V�ˏ����̐l�^�Ӗ쏻�q�̑��ł���B�Ȃ������E��̐����ʂƂ������Ă���i�z���g���̂��낤�l�j�B2010�N4���A�u�œ|����}�v���f���A�����}�𗣓}���āA�������v�i���̐����Ƃ̒��ōł��^���ŋ��ʂ��Ă���̂͂��̐l�ł���j��Ƌ��Ɂu������������{�v�����������B�Ƃ��낪2011�N1���A����������t�̌o�ύ��������S����b�ւƗU��ꂽ��A�z�C�z�C�Ɠ��t���Ă��܂��B��������f���Ĉ�N�������Ȃ������ɁA����}���t�ւ̎Q���ł���B����ł́A���̔�펯�j�i�x�c�l�ɂ܂Łu����Ȗ��ߑ��͋������v�Ƃ�����B���ߑ��l�Ԕ�����������̊��ł���B
�@���̔����̗��ɂ́A�����}����A�ނ����]���N�O�̖剺���Ƃ��Ĉ�т��Č������i�̗��������Ă����L�����A������B�ނ̘_���́u�������i�͐������B���{�̔��W�̂��߂ɂ���ȊO�̑I���������������낤���B��X�͓d�͉�Ђ��܂߈��S��ɂ͖��S�������Ă����B�ō��̒q�b�����āB����̎��̂ł�����͕ς�Ȃ������B������A����Ȃ��ƂɂȂ����̂͐_�l�̎d�Ƃƍl���邵���Ȃ��̂��v�ł���B���ꂪ�ō��̒q�b���������ʂ��Ƃ����̂��낤���B���ݍő�̕s�K�������炵�Ă��鎖�̌����ɂ͖ڂ��Ԃ�A�_�̎d�ƂƂ��ĕЕt����B���ꂪ�܂��Ƃ��Ȑ����Ƃ̔������낤���B�Ƃ������A�l�ԂƂ��Ăǂ����Ǝv���B�������O�̃u���A�����ӔC�̉���A�������������Ƃ͔��������ƂƂ��đ����Ǖ����ׂ����B
�@��������̗^�Ӗ쏻�q�́A���x�����ȃ��}����`���l�ŁA�����ɂ����鐸�_�������т��Ċ����ւ荂���l�Ԃł���B�ޏ��̏�����u�݂��ꔯ�v���\����̂�����B�u��픧�̂��������ɂӂ�����ł��т����炸�⓹������N�v�B���A�ޏ��������Ă����瑷�Ɍ������Ă����r�ނ��낤�B�u�����̎��̌����ɂӂ�����Ő_�̎d�ƂƂ��邼���т����v�B
�@����������ł͐k�Г��ʈψ���s���Ă���B�������̕s����˂������}�̍U���͌��������̂�����B���R���낤�B�ł�����ŁA�u���Ɍ�����؍����ȂȂ��v�Ƃ�������̂ł���B�����}�́A�ϔN�̌����s���̕s���s�������x�S���ŎӍ߂���̂��X�W�ł͂Ȃ����낤���B�U���͂��ꂩ��ł���B
�@���[�����^�Ӗ��b�������̎����}�c�����A�܂����[�ł���B�����͌����������剻�����������͏����Y�����]���N�O�̓�l�Ȃ̂ł���B�����������ނ��������ɂ͂����������Ԃ��~�������A���������Ă�����u�N�����m�v�ł͂Ȃ��Ȃ�̂ŁA�ЂƂ܂��͗��ꂽ���Ǝv���B����͉��y�̗͂ɂ��čl���Ă݂����B
2011.05.20 (��) ��k�Вf�́m5�n�����l��Ղ��s�K
 �@��������b��5��16���A�����{��k�Е�����荞�ޑ��\�Z�Ă̕Ґ���8���ȍ~�ɐ摗�肷��l�������������Ƃ����B��̉����l���Ă���̂��I�W�܂����`�o�������Ă܂���~���x�����Ă��Ȃ����i��_�W�H�̎��ɂ́A2�T�Ԍ�ɂ͏��̔z�����������Ƃ����̂Ɂj�A3�x�J���������\�z��c����o�Ă���b�́u�����Łv�̂��Ƃ���E�E�E�E�E����ȏ��ŕ�\�Z��摗��ł����H 6��22���܂ʼn��������̂�����A���ׂ����Ƃ��h���h���i�߂Ă���������B���������Ƃ��ɗ��搂�͂���̂����[�_�[�̂͂��Ȃ̂ɁA����Ă邱�Ƃ͂܂�ŋt�B�_���͉��������Ȃ̂��H
�@��������b��5��16���A�����{��k�Е�����荞�ޑ��\�Z�Ă̕Ґ���8���ȍ~�ɐ摗�肷��l�������������Ƃ����B��̉����l���Ă���̂��I�W�܂����`�o�������Ă܂���~���x�����Ă��Ȃ����i��_�W�H�̎��ɂ́A2�T�Ԍ�ɂ͏��̔z�����������Ƃ����̂Ɂj�A3�x�J���������\�z��c����o�Ă���b�́u�����Łv�̂��Ƃ���E�E�E�E�E����ȏ��ŕ�\�Z��摗��ł����H 6��22���܂ʼn��������̂�����A���ׂ����Ƃ��h���h���i�߂Ă���������B���������Ƃ��ɗ��搂�͂���̂����[�_�[�̂͂��Ȃ̂ɁA����Ă邱�Ƃ͂܂�ŋt�B�_���͉��������Ȃ̂��H�@����͋��N��11��13���B���lAPEC���A�����Ӌџ���ȂƂ̉�k�ɗՂ킪�����l�̎p�͂Ђǂ������B�O�����݂Ŗڂ����킹���Ɏ�Ɏ�����������ǂݏグ�邾���B ��c�Ȃ�܂������A��Έ�̉�k�ł���B2�����O�ɂ͂��̐�t������肪�������̂�����A�R�c���ׂ��͂�����ł��傤���B����Ȃ̂ɁA�����Ɍ����̂́A�䂪���ō��ӔC�҂̍ō��ɎS�߂Ȏp�B�܂��Ă₱�̉f���͑����S���E�ɔ��M���ꂽ�̂ł��B���Ȓp��������I ���{�͂���Ȃ݂��Ƃ��Ȃ��l�Ԃ��g�b�v�ɑՂ��Ă���Ɛ��E�Ɍ��\�������ƂɂȂ�B�킪���v�Ȃ������̍s�ׂɍR�c���ł����A����Ȏp�𐢊E�ɎN��������Ȓp��������������b���������͕K�v�Ƃ��Ȃ��B
�@���Ƃ��Ƃ��̕��A�������킹�͏㏸�u�������ŁA�����ƂƂ��Ẵr�W�������Ȃ��Ƃ����Ă����B��ɍs�������A�������ꂾ���B�ǂ��������������������A�ǂ�ȍ��Ƃɂ������ł��Ȃ����āB�s��[�]����̉��Ŏs���^�����������Ƃ�ɂ��Ă���݂���������ǁA���O�s�삳��͂����Ĕ����Ă��Ȃ����������ȁB�ނׂȂ邩�ȂƎv���܂���B
�@���������A�u���͎x�������P���ɂȂ��Ă����߂Ȃ��v�Ƃ��u�����������������𗧂Ē������ƁA���ꂪ���̐����ƂƂ��Ă̖{���v�Ȃ�Ă���������Ă��Ȃ��B�M�O�M�����Ȃ�����Ȃ����ɖ{���𐋂����Ă��A���f�Ȃ����Ȃ�ł����ǁB
�@��k�Ђ��N����3��11���̒����V���ŁA�������؍��Ђ̒m�l����104���~�̌������Ă������Ƃ����ꂽ�B�����O�A�O���O���Ă������̊؍��l�������5���~�̌�����莫�C����������������B�����ɖ��\�L�̑�k�Ђ��N����B�����́A���̂��N�������������Ɍ������w���R�v�^�[����A���ݏ����̓d�b����ꂽ�������u�ߋ������݂��������m��Ȃ����Ƃɂ��Ă���B�����Ē����ɓ�����v�����āA�n�Ӑ^�m�q�́u�������v����Ȃ����[�́B�����A�ꍑ�̑�����b���J�����ېg��D��̐}�B������k�Ђ��Ȃ������玫�C�K���̑厖�Ǝv�����̂ł��傤�A���͑��߂Ɂu����ł���2�N�A��������v�Ɖk�炵���Ƃ����B�Ȃ�Ƃ܂��A�ڗ�Ȕ����I ���ꂩ��u �������̑�k�Ђ̂Ƃ��ɍ��̐ӔC�҂ł���͉̂^���ł��v�Ȃ�Ă悭������ˁB�������͂��̉^�����܂��B
�@4��13���A�������̂������������̔��Ώۋ��ɑ��u�������ɂ͂���10�N20�N�Z�߂Ȃ��ˁv�ƌ������������B�����Ɖ�k��̏��{���t���[�Q�^�̘b�B�Ȃ�Ƃ܂��A���n�̐l�̐_�o���t�Ȃł���\�������Ďv�����Ƃ���A���̏��{������������������B��������������߂��Ɍ��܂��Ă܂���B���{���N�����ĕ������Ă�Ȃ����ȁA����Ȏ��B�����A�ڗ�A�����܂ł��Ď�������肽���̂ł��傤���B
�@5��6���A��������b�͋L�҉���J���u�����̈��S���l���A�l�������̉^�]��~�𒆕��d�͂ɗv�����܂����B�v�Ɠ��X�̃��b�Z�[�W�B�l����30�N�ȓ���87���̊m���ŋN����Ƃ���Ă��铌�C�n�k�̗\�z�k����̂ǐ^�ɂ��邩��A�Ƃ������R�ł���B�L�҂́u���̌����́H�v�̎���ɂ́u�~�߂����͂Ȃ��v�B�u���܂ŁH�v�̎���ɂ́u�h���炪�o����2�N��܂Łv�Ɠ������B�����ɂ́A�s������d�͂Ǝ�����ٗp�ւ̔z�����Ȃ���A�G�l���M�[�����S�ʂւ̎w�j���Ȃ��B����"��Ԋ댯�Ƃ����Ă��錴��������~�߂�"�Ƃ�����i�_�@�����邾���B�v�l���x�����w�����݂Ȃ̂��B�l�����댯�Ȃ̂́A�Ôg�����ނ���ϐk�����̂��̂Ȃ̂ɁA����������Ⴆ�Ă���B���Ȃ킿�A�@���n��Ղ��ɂ߂ĐƎ�ł���A�j�R���W���̂̌ŗL�U�������z��n�k�̎��g���ɋ߂����ߒn�k�������ɋ��U���N����₷������ŁA�u�h���炪����������ĉғ��v�͂܂�Ō����Ⴂ�B�����A����ɉz�������Ƃ͂Ȃ�����ǁA�Ôg������O�Ɍ��q�F���Ђ�����Ԃ�������Ă܂���B���ꗈ�Ă������̋��P�����ĊO���d���̑[�u�����u���Ă����Α��v�Ȃ̂��B������A�����́u�l���͌��X���Ă�ׂ��ꏊ�ł͂Ȃ������̂�����i�v�ɒ�~����B�����āA�G�l���M�[����{�I�ɍl���Ȃ����v�������Ȃ́B�����̂͏ꓖ����I�Œ��r���[�A�܂��ɐl�C���A�����p�t�H�[�}���X�ƌ����Ă����傤���Ȃ��B
�@�����͂��̂��ƁA�u30�N��Ɍ����ˑ��x��50���ɂ���Ƃ����G�l���M�[��{����𔒎��ɖ߂��v�ƕ\�������B����͈ꌩ�]���ł����������A�x����Ă͂����܂���B�u�����P��v�ȂN�����Č�����B��Ȃ̂͂ǂ����邩��ł��o�����ƁB�����Ĉˑ��x������40���ɂ���A�P�����ɂ͂Ȃ�̂�����A����͓������̂�����ɂ��������A�Ƃ������ނ���I���Ȍ����l�B���ɐ����l�炵�������Ȃ̂��B�u�����͏��X�ɔp�F�Ƃ��A�ˑ��x�������Ă䂭�B����ɂ��d�͕s���͍Đ��\�G�l���M�[�ŕ₢�A�����I�ɂ͌��������ׂĂȂ����B�n��Ɛ�I�d�͋����̌`�Ԃ����߁A���������ɂ�锭�d�̎��R�����𑣂����Ƃɂ���āA���S�ȃG�l���M�[������}���Ă䂭�B�����Ƀc�P���Ȃ����߂Ɂv�Ƃł������Ă����Ύ��͕]�����邯�ǁA�����ł��傤�ˁB�����Ă��̕��A�R���ł��C���Ȃ�����B�����ɂȂ�͉̂��������B
�@����}�����������̍ő喽��́u�����哱�v�������͂��B�u�����哱�v�̎Q�d�{���́u���Ɛ헪���v�ŁA���̏��㎺���͐����l�������B�ނ͏A�C�ɓ������āu�����哱�ɂ��E�����v�𐺍��炩�ɐ錾�����B��X�́A�悵�A����ŋ��ԈˑR���銯���x�z�������ƒE�p�ł���A�Ɗ��҂������̂ł���B�Ƃ��낪�h�b�R�C�ނ͉����o���Ȃ������B���≽�����Ȃ������Ƃ������ق����������Ă���B�ڂɌ������̂�"�d����"�̘@�u�c���̗E�p�����������B���ɔނ͍�����b�ɂȂ����B���x�͂����ʼn��v�ǂ��납�����Ɏ�荞�܂ꂽ�B�����獡�A����ŗ������グ�_�҂ɐ��艺�����Ă��܂����̂��B
�@�����̑�����b�A�C���̃X���[�K���́u��Ɍٗp�A��Ɍٗp�A�O�Ɍٗp�v�������B�����āu�L�����s���t�v�Ƃ��B�Ȃ�u�l���~�߂Ă��Ԃ�鐔��l�̌ٗp�v�ւ̔z���͂ǂ��Ȃ̂��B����ŗ����グ�Ăǂ����Čٗp������́H�グ����i�C���������ށA��������A�ٗp����������B����ȊȒP�Ȃ��Ə��w���ł�������B�L�����s�H�`�����`�������������B�����炠�͉R�����B��ѐ����Ȃ��B�X�W���ʂ��ĂȂ��B
�@��ѐ��̂Ȃ��͏����Y�ւ̑Ή��ɂ��B2009�N�̂������A�����͏���Â̐V�N��ɗ�̃j�^�j�^��Ōw�łĂ��܂����B���ꂪ��\��ŏ��������Ƃ͈�]���ăI�U����ɁB�@������ɕq�A��F�`���̓V�ˁB���̂Ƃ���̐�Ύ��Ƃ̋������������ہB���ɗ��Ǝv���Έ�x��̂Ă��l���Ăэ��ރV�^�^�J���͎����Ă����ł��ˁB�u�l���v���ނ̏����������ŁB�܂��A���̃J�����I���I�����A�Љ�l�Ȃ�N�ł������͎������킹�Ă���ƌ����Ȃ����Ȃ��̂ł����A�ł��ނ̏ꍇ�͂��܂�ɘI���ō��_���������B������ł��r�V���Ƃ������̂������Ă���A��ڂɌ�����̂ł����A��͂��Ƃ����f��Ȃ��B
�@�����s��̃h���b�J�[������w���҂����ׂ������́u�^���v�u�n�����v�u��M�v�B�����l�������킹�̎����́u�Ƒ��v�u�v�����v�u���C�́v�B
�@�u��v���l�v���]���̍��S�q���V���́A�Â��̑�Ȉא��҂ɂ́u�o��v�u�M�O�v�u�Ŏ��v���������ƌ����B�����l�͑���Ɂu�ېg�v�u����v�u��~�v�����B
�@5��13���̎Q�@�\�Z�ψ���Ő����́A�l����~�v���ɂ��āu�]���͗��j�̔��f�Ɉς˂����v�Ƃ������������ȁB����ɗ��j�I�p�f�Ɗ��Ⴂ���Ă���B�Ȃ�Ƃ����ڏo�x������I ���j�̕]�����H ����Ȃ���A�����̊��S���Ẳ����_�����イ���ƂŃV�����V�����ł���B�n���n�������I �}�g���ɕt�������Ă���R�b�`�̓������������Ȃ��ł����~�߂܂��B
�@������A���Ȃ��u�ŏ��s�K�Љ�̎����v�Ƃ������܂�����ˁB���܉�X���{�����́A�����l�Ƃ����ɑ���Ղ��ő�s�K�Љ�ɘf�킳�ꑱ���Ă���̂ł��B���������Ă������������ނ�ł��肢�\���グ�܂��B
���ǐL��
�@5��19���̒����Ɂu�A�����d�����������v�Ƃ������o����������B����O�i�͂ЂƂ܂��]���������B�ł��A����܂ł̗��ꂩ��A�c�O�Ȃ���ǂ������������ɏI��肻���Ƃ̊뜜�͐@���Ȃ��B���������Ƃ��A��ł�����������s���Ă��炢�������̂ł���B
2011.05.12 (��) ��k�Вf�́m�ԊO�ҁn ���k�ɕ�����A�_�[�W��
�@�f��u�}�[���[ �N�ɕ�����A�_�[�W���v���ς��B�u�o�O�_�b�h�E�J�t�F�v�̃p�[�V�[�E�A�h�����Ƒ��q�t�F���b�N�X�E�A�h�����̋����ē�2010�N�̍�i�ł���B�@���y�̗͂œ��k�����C�ɂƂ������t���悭�����B�m���ɉ��y�ɂ͐l�̐S��������C�Â��鉽��������B���̉f������āA�u��z�^�v��ǂݒ����A�}�[���[�̉��y���ƁA�S���x�܂�B���̎����ɁA�����������獡�̓��{�ɍł������������y���Ƃ����C�������B
 �@���̉f��́u�N�������Ƃ͎j�������A�ǂ��N�������̓t�B�N�V�����ł���v�Ƃ������̂��Ƃ�菑���Ŏn�܂�B����͓`�L���h���}������Ƃ��̂���Ӗ��퓅��i�Ȃ̂ŁA������ƃr�b�N�������B�킴�킴���Ƃ�����ꂽ�̂́A�t�B�N�V�����̓x�����������Ƃ������Ƃ��H
�@���̉f��́u�N�������Ƃ͎j�������A�ǂ��N�������̓t�B�N�V�����ł���v�Ƃ������̂��Ƃ�菑���Ŏn�܂�B����͓`�L���h���}������Ƃ��̂���Ӗ��퓅��i�Ȃ̂ŁA������ƃr�b�N�������B�킴�킴���Ƃ�����ꂽ�̂́A�t�B�N�V�����̓x�����������Ƃ������Ƃ��H�@�}�[���[�̍ȃA���}�͌����ɂ������č�Ȃ��ւ����邪�A���̟T�ςƖ��̎�������ŎႢ���z�ƃO���r�E�X�ɑ���B�����m�����}�[���[���Y�݁A���_���͈�t���C�g�̐f�@����B����͂��̂����̒��ɉߋ��̎��ۂ��t���b�V���o�b�N�����Ȃ���i�ށB���Ԃ̗���ǂ���ł͂Ȃ��A��̊�_������ˏ�ɑO������Ĕ�т܂��߂�B�X�^�C���͕��䌀���B�}�[���[���̃��n�l�X�E�W���o�[�V���i�C�_�[�̓s�b�^���̕��e�ƕ��͋C���B�A���}���̃o�[�o���E���}�[�i�[��19�ΔN���ŎЌ��E�̃~���[�Y�Ƃ����C���[�W����͉��������B�X�^�b�t�́A�j����̌|�p�Ɣ��Ƃ����ʂ����������������̂�������Ȃ��B �f��́u���̑f���炵������������x�Ɗ肢�N�ׂ̗ŋx��ł��������B�������l�您�₷�݁v�Ƃ����}�[���[�̌��`�ŏI���B�ǂ����ł������悤�ȃZ���t���ȂƎv������a���|�b�v�X�̖��ȂȂ���B�u���̑f���炵������������x�v�i�k�R�C�������a�F�j�|�u�V���V�A�v�i�g�c��Y�����܂�Ђ낵�j�|�u�������l��Good Night�v�iBZ�j�������B�܂��A�S���W�Ȃ��ł��傤���B
�@�A���}�̓}�[���[�̎���u��z�^�v�������Ă��邪�A���̒������l�Ɋւ��鋻���[���G�s�\�[�h�����X���������Ă��������i�u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�Έ�G��A�������Ɂj�B
�@�A���}�̓}�[���[�Əo��������u�}�[���[�̉��y�͂قƂ�Ǖ��������Ƃ�����܂���B���������݂̂͂Ȍ����ł��v�ƌ���Ă����B�@�}�[���[�ƃA���}�̌��������͌`�e���������s�v�c���ɖ����Ă���B����́A��X�}�l�ɂ͌v��m��Ȃ��A���I�����ׂ��ŌN�Ղ�����V�ˉ��y�ƂƓV����ȏ��^����ꂽ�~���[�Y�̐\���q���t�ł�ٗl�ȃn�[���j�[�Ƃł������悤���B�V�˂̐��E�I
�@�}�[���[�̎�芪���́A�A���}�ƌ������������Ȃ������̂ŁA�|�p�_�𐁂������ċ�������������Ă䂭���낤�ƍl�����s���邪�A�����Ă������͎̂�芪���̂ق��������B
�@�V�����s�̓y�e���X�u���O�ł̉��t��ɕ֏悵�čs��ꂽ�B�u�g���X�^���v���w������v��̑��Ō����A���}�́u�w���̎��x�̉��y�Ǝw������}�[���[�̎p�̂Ȃ�Ɛ_�X�����������Ƃ��B���́A���ꂩ�炱�̐l�̍s������Ղ����菜�����̐l�̂��߂����ɐ����悤�Ǝv�����v�Əq�ׂĂ���B�Ƃ��낪�A����2�N��ɂ́u�ނ�����ƍ����Â��Ȃ�B�܂�Ńe�[�u���̉��Ɏ��̂�����݂����v�ƕς��B
�@�}�[���[�͎��̒��O�u���܂ł̎��̐l���͂����̎���v�ƌ������B
 �f��ł́A�����ȑ�10�Ԃ̃A�_�[�W�������ɁA�u��5�ԁv�u��S�ԁv�����肪����Ă������A�����ł��D���Ȃ̂́u�����ȑ�3�� �j�Z���v�ł���B�S�ȏ�����1902�N6���B����3������̂��Ƃł���B��́u��z�^�v�ɂ��ƁA�A���}�́u��3�ԁv�̏������āu���߂Ĕނ̍�i�̈̑傳�������ł����v�Ƃ����B�����ɁA�������ď��߂Đ^�̍K�����������Ƃ��B
�f��ł́A�����ȑ�10�Ԃ̃A�_�[�W�������ɁA�u��5�ԁv�u��S�ԁv�����肪����Ă������A�����ł��D���Ȃ̂́u�����ȑ�3�� �j�Z���v�ł���B�S�ȏ�����1902�N6���B����3������̂��Ƃł���B��́u��z�^�v�ɂ��ƁA�A���}�́u��3�ԁv�̏������āu���߂Ĕނ̍�i�̈̑傳�������ł����v�Ƃ����B�����ɁA�������ď��߂Đ^�̍K�����������Ƃ��B�@�S6�y�͂����t�`�ԕʂɘ��Ղ���ƁA��1�y�͂Ƒ�2�y�͂̓I�[�P�X�g���̂݁A��3�y�͂ł̓X�e�[�W��������̃|�X�g�z����������B��4�y�͂ł̓A���g�Ə��A��5�y�͎͂��������Ə��������������A��6�y�͍͂ŏ��ɖ߂��ăI�[�P�X�g���݂̂ƂȂ�B���ɑ��ʂȘg�g�݂��B
�@�����͑�6�y�͂ł���B�ω����J��Ԃ���郍���h��蕔�̂Ȃ�Ƃ������Ȃ��Â����ƈ��炬�B����̓t�H�[���̐������ł͂Ȃ��A�o�b�n�̐������Ƃ��Ⴄ�B�����A��Y�A���D�A���ۂȂǐl�Ԃ̎���X�Ȋ���������炬�ւƏ����A�����ɂ��}�[���[�I�F��̉��y�Ȃ̂��B�F��͂₪�ď����̋����Ɖ����č��݂ւƕ���i�߂�B��P�y�͂̎����Ȃ������Ȃ���i�ނ��̃t�H�����͖`���ւ̉�A���B�i����A�B�����ɂ����ă}�[���[�̓j�[�`�F�ƒ��a����A�Ɗ�����B�ł������́A�}�[���[�̓j�[�`�F�������Ă����B���ɂ͂܂�����͓�ł���B
�@�A���}�͂����Ƀ}�[���[�̈������B�������͓��k�ւ̋F����B
�@����h���Ԃ�Ȃ�����߂Ă����o�[���X�^�C���w���j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�̉��t�����ɂ̃x�X�g�Ղ��B���y�͋�Y���ݍ��ݕ����̒��ׂ���������B�o�[���X�^�C�����F���t�ƂȂ��ă}�[���[���Ăяo�����k�ɓ����̃A�_�[�W���������̂ł���B�Ȃ��A��r��������CD�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�N�[�x���b�N�F�o�C�G����������67
�o���r���[���F�x�������E�t�B��69
�V�����e�B�F�V�J�S��70
�����@�C���F�V�J�S��75
�e���V���e�b�g�F�����h���E�t�B��79
�A�o�h�F�E�B�[���E�t�B��80
���[�O�i�[�F�h�����f���E�t�B��84
�C���o���F�t�����N�t���g������85
�o�[���X�^�C���F�j���[���[�N�E�t�B��87
�u�[���[�Y�F�E�B�[���E�t�B��01
2011.05.09 (��) ��k�Вf�́m4�n �G�l���M�[����̐����������
�@�d�C���ƘA����s�̌��q�̓G�l���M�[�}�ʏW������ƁA40�N�O�ɔ�ד��{�̈�ʉƒ�̓d�͏���ʂ�3�{�ɂȂ��Ă���i�ꐢ�т�����1970�N��119kwh��2009�N��284kwh�j�B�����̐�����U��Ԃ��Ă݂�ƁA40�N�O�ɂ͊��ɓd�C�①�ɂ�����@���e���r���X�e���I���������B�N�[���[�Ɠd�q�����W�͂Ȃ��������A���݃N�[���[�͂قƂ�ǎg���Ă��Ȃ����d�q�����W�͈�u�̂��́BDVD���R�[�_�[��p�\�R�����Ȃ���������Ǐ���d�͂͏������͂��B�ǂ���3�{�̎������N���Ȃ��B�����ŁA�䂪�Ƃ�4�����̗̎��������Ă݂��267kwh�B����͌��݂̈ꐢ�т�����̕��ϒl�ɋ߂��B�Ȃ�قǁA���o�ȏ�Ɏg���Ă���킯���B�o���ς���ΎR�Ƃ��炽�߂Ċ���������ł���B�@�������i�̑�`�����́A�i�P�j�d�͏���g��ւ̑Ή��A�i�Q�j���{�ɂ̓G�l���M�[�������Ȃ��A�i�R�j���d�R�X�g�������A�i�S�j��_���Y�f�̔r�o�ʂ����Ȃ��A�Ȃǂł���B�������f�����S�_�b�����A���͍���Ƃ��Č��q�͔��d�𐄐i���Ă����̂ł���B
�@�i�P�j�i�Q�j�i�S�j�͎����ł��邪�i�R�j�͎��̑Ή������Ă���ƍ��������Ƃ����������Ă��܂����B4��16�A17�������V�����{�̐��_�����ɂ��ƁA�����𑝂₷�ׂ���5���A����ێ�51���A���炷�ׂ���30���A�p�~���ׂ�11���Ƃ������ʁB2007�N�̒����ɔ�ׂĔp�~�����炷�ׂ��̔䗦���オ�����Ƃ͂����A���݁�����ێ����ˑR�Ƃ���50���ȏ������B���̗L�l��ڂ̑O�ɂ��āA���̐����͍������₵�Ȃ����B��@�ӎ��̌��@�Ƒ��l�����o�̌��ʂ��H ����Ƃ��A�l�Ђ�����Ƃ����F�����B�l�ЂȂ�Β�����͂����Ƃ������Ҋ��Ȃ̂��B�ł��ʂ����āH
�@1954�N3���A���]���N�O��4�l�̍���c�������q�͌����J���\�Z��������ɒ�o���āA�䂪���̌��q�͔��d�̗��j���n�܂����B1955�N12���A�u���q�͊�{�@�v�������A����Ɋ�Â�1956�N1���u���q�͈ψ���v�������A����ψ����͓ǔ��V���Ў�̐��͏����Y�������B���͎͂��Ў��ʂ����p���Ȃ��猴���̗L�������������_���`����Ă䂭�B�������S�_�b�̌`���ł���B���͂͌����̕��ƌĂ�Ă���B
�@����A���{���{�́A�������n�����̂ɑ�ʂ̎D�����o���T���B���n�n���t���ƌŒ莑�Y�ł̐ݒ�ł���B����ɂ�茴�����n�����̂ɂ�20�N�ԂŖ�900���~���̍Γ�����������B�ߑa�Ő��ނ��Ă䂭�n�������̂ɂƂ��Ă���͑傫���B��x�֒f�̉ʎ�����ɂ��������̂́A�~�߂��Ȃ��ǂ��납������ێ����邽�߂Ɍ��q�F�̑��݂������B�����͖���Ƃ�����R���ł���B
�@����ƂȂ�����������͗����ƂȂ�B���ƒn�������̂ɓd�͉�ЁA�������[�J�[�A���݉�ЁA�����̉������A�w�҂Ȃǂ��Q���茴���������`������Ă������B���s�����ł���d�͉�ЂɈ��S���w���E�ē���̂��u���q�͈��S�E�ۈ��@�v�ł��邪�A���ꂪ�����G�l���M�[���i�o�ώY�Əȁj�̎P���ɍ����B���i��̂̒��Ƀ`�F�b�N�@�ւ�����̂�����A�ŏ�����@�\�����Ȃ��Ɩ������Ă���悤�Ȃ��̂��B���������ψ���5�l�̂���4�l�����n�������o�g�A�S���̑f�l�Ȃ̂ł���i���݂ɁA���@���̎���M�����̑O�E�͌o�Y�ȏ������ʐR�c���ŁA���͕S�ݓX�̏����R���ł���j�B����ȋ@�ւɂǂ����Đl���Ɋւ��`�F�b�N�@�\���ʂ����悤���B
�@�����������̂́u���q�͈��S�ψ���v���B�����́u���q�͈��S�E�ۈ��@�v���ēw�����闧��ɂ���̂����A���ψ������ڏt�����̌����́A�{���ɂ��̕����q�͎Љ�H�w���������Ă����́H�Ƌ^�������Ȃ���̂���B�u�������ŁA���f�����͐�ɋN���Ȃ��v�u�����H����ȕs�C���Ȃ��̈��S�ł���킯���Ȃ��ł���v�u�����Â̊댯����g�ݍ��킹�Ă������猴���Ȃ�č��܂����B�ǂ����Ŋ���邵���Ȃ��v�u�p���������̕����́A���ǂ͂����ł���B2�{�Ń_���Ȃ�A5�{10�{�ʼn�������v�i�u�T�����t�v4��7������蔲�����j�E�E�E����͂�A�J���������ǂ���Ȃ��B���ƂƂ��Ăǂ����Ƃ��������A�l�ԂƂ��ĕς��B������������"���S"���i���Ă���̂ł��B���ȋ��낵��I
�@�`�F�b�N�@�ւ�����ȕ�������A�����̒��ł͖���}�ȗ����H�������X�ƍs���Ă����B�����I�ȏ�ɂ��킽���āB�����͌�����܂ł��Ȃ��A��������d�͉�Ђւ̓V����A�Â���ݒ�A�e��f�[�^�̋U���A��p�w�҂����̌}���ȂǕ\�ۂ��l�@���邾���ŏ\���ł���B�������i��قƂ�ǂ̎҂͈Ղ��ɗ�����Ă����B���_�A���ɂ͗ǐS�����w�҂�ϗ�������]���҂��������낤���A�ނ�̓����Љ��e�������Ă��܂����B���肵���������p�����邽�߂ɂ͌������ނ̂��������̂ł���B���݂Ɍ��q�͈��S�ψ��̕�V�͔N�z1000���~�ȏ�Ƃ��B���ꂾ�������āA�S���͏T�ꎞ�Ԏ�̊ɂ���c�����Ȃ̂�����A�����肽�����Ȃ邾�낤�B�������Ďc���ꂽ�̂́A���`����r�������l�X����荇����ꍇ���Ƌ\�Ԃɕ���ꂽ�����Љ�����B
�@����̕�����ꌴ�����̂́A����Ȍ��������ւ̌x���ł���B���̂������\�ǂ���ɉ^�Ƃ��Ă��A�n���Z���ɂ͎��Ԃ��̂��Ȃ����킹�Ă��܂����̂�����A�����҂��S���𐬂������Ȃ��B�ł͂ǂ����邩�H�@�܂��͋@�\�̉��ҁ��l�Ђ���̒E�p�ł���B
�@�@�i�P�j �u���q�͈��S�E�ۈ��@�v�̉��
�@�@�i�Q�j �u���q�͈��S�ψ���v�̖����B�o�������܂ł̍��z��V�̕Ԕ[
�@�@�i�R�j ��L��Ɏ���đ�����ƏW�c�ɂ�銮�S�Ɨ��`�F�b�N�@�ւ̐V��
�@�@�i�S�j �u�N���[���G�l���M�[���i���v�̐ݒu
�@�@�i�T�j �u�������_�����v�̐ݒu�Ƒ��������J�n
�@�����Ɍ������G�l���M�[����̂���ׂ��p���������A�����̘g�g�݂��t���ғ������āA�L�Q��p���L�p�ݏo���Ă䂭���Ƃ��̐S�ƂȂ�B
�@���ڈψ����́u�p���������͋��ʼn����v�����́A���������ɔp���������̕�������o�����Ȃ����Ƃ̏ł���B���͍���Ƃ��Č����𐄐i���Ă����̂ɁA�p���������Ƃ����d�v���ɂ͊W�������܂܂������B���x�������悤�ɁA������ꌴ�����̂�10�N�]����������Ƃ��Ă��A�p�����͂ЂƂ܂��Z�������Ɏ̂Ēu�������ŁA���̌�̕���͈�ؖ���̂܂܂Ȃ̂��B����͂Ƃ���Ȃ����������ɔ���ȃc�P�����ƂɂȂ�A���݂����X�̐ӔC�Ƃ��Đ�ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ȃ̂��B������A�����͑Q���k���Ɍ������ׂ��Ȃ̂��B
�@�@�i�P�j �����I�Ɍ����ւ̈ˑ��x���y�����A���X�ɑ�փG�l���M�[�ւ̈ڍs��}��
�@�@�i�Q�j ���L�̌��q�F�𑁊��ɓ_�����A�����Ɉ��S������s����
�@�@�i�R�j ���E�������ȂǓd�͉�Ђ̔��{�I���v��}��B
�@��փG�l���M�[�̈�ɑ��z���A���͂Ȃǂ̃N���[���G�l���M�[������B���z�������͂��A�G�l���M�[���̓N���[���Ŗ��������L���y�n���K�v�ƂȂ�B������p�w�҂͌������낦�āu�N���[���G�l���M�[�ȂǂƂ������A�Ⴆ�Ό������z�����d�Řd�����Ƃ����瓌���h�[���̉��{���̓y�n������B������������������R�X�g��������v�ƌ����B����������肽�������߂ɁB
�@��������������̎�i���i�R�j���E�������A�����A�d�͉�Ђ̋@�\���A���d�Ƒ��d�ɕ������邱�Ƃł���B�����̔��d�ݔ��Ƒ��d�V�X�e���͊����̓d�͉�Ђ��p����������B�V���Ȕ��d�ɂ��ẮA�s����J�����A���Ԃ̐V�K�Q����ϋɓI�ɑ��i����B�s�ꋣ���͐V�K�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ʑ����K����������Ă����͂��ł���B���{�l�̗D�G���ƋΕׂ��������Ă������͌����ē�����Ƃł͂Ȃ��B�����Ă���͌ٗp�̑���ɂ��Ȃ��邩��o�ό��ʂ��傫���B�܂��Ɉ�Γł���B���Ώo����E�E�E�V���[�v���e���r��ʂ̃I�[���t���������f�����Ƃ��A�u�Ȃ�ō��R�X�g�ᐫ�\�ɃV�t�g����̂��v�Ɠ��O�̔��͏������Ȃ������Ƃ����B���ꂪ���A�قƂ�ǂ̃e���r���t���ł͂Ȃ����B�ړI�����ɓK���M�O�Ə�M������ΕK���B�������Ƃ����A����͍D��ł���B���d��Ђ͂܂��A�l���Ƃ̍�鎩�Ɣ��d�d�͂��ϋɓI�ɔ����W�߂�B���̗ʂ������ď������Ȃ��͂����B
 �@�ʐς����E��60�ʒ��x�ł����Ȃ����{�̊C��́A���E��6�ʂ̍L�����ւ�B�C��ɂ͖����̃G�l���M�[�����E���^���n�C�h���[�h����ʂɖ����Ă���A���̎������l��100���~�Ƃ������Ă���B��������Ȃ���͂Ȃ��B���i���ׂ��͌o�Y�ȁE�����G�l���M�[�������肾�낤���A�u���p�܂łɎ��Ԃ��|����v�Ƃ������Ē�S���B��������������̗�������肽�������߂��B��������ʂ̋@�ւŐi�߂�����B���������C�j�V�A�e�B�u�����̂����̃��[�_�[�Ȃ̂�����ǁA���̕��Ɋ��҂��Ă������ł��傤�ˁB
�@�ʐς����E��60�ʒ��x�ł����Ȃ����{�̊C��́A���E��6�ʂ̍L�����ւ�B�C��ɂ͖����̃G�l���M�[�����E���^���n�C�h���[�h����ʂɖ����Ă���A���̎������l��100���~�Ƃ������Ă���B��������Ȃ���͂Ȃ��B���i���ׂ��͌o�Y�ȁE�����G�l���M�[�������肾�낤���A�u���p�܂łɎ��Ԃ��|����v�Ƃ������Ē�S���B��������������̗�������肽�������߂��B��������ʂ̋@�ւŐi�߂�����B���������C�j�V�A�e�B�u�����̂����̃��[�_�[�Ȃ̂�����ǁA���̕��Ɋ��҂��Ă������ł��傤�ˁB�@�����ɕ��̈�Y�������p�����錴���́A����V�݂��Ȃ��B�V�����������q�F�͏����p�F������B����ƕ��s���āA���̓N���[���G�l���M�[���p��W�ԁE���i���A�k�����������q�͔��d�̌����߂������}���Ă䂭�B���������������d��ЂƐV�K�Q����Ƃ͎s�ꋣ���̒��ŃN���[���G�l���M�[��ϋɓI�ɎY�o����B���d��Ђ͂����܂ߖ��Ԃ����o���召�̎��Ɣ��d�d�͂��グ��B���y�X�A���X�X�A�w�\���A�ԗ��A�z�[���A�X�|�[�c�ϐ�{�݁A��ʊ�ƂȂǂ��ߓx�ȓd�͏����T�ށB����A��X�����͂ł������̐ߓd�ɓw�߂�B���ꂱ�����A���{���i�ނׂ����ł���B�����āA�����Ɏ����Ďn�߂āA������ꌴ�����̂̌x�����������ꂽ�Ƃ�����̂ł���B
2011.04.30 (�y) ��k�Вf�́m3�n �������ǂ�����
���l�������̊댯�x�̓n���p����Ȃ���������
�@�É�����O��ɂ��钆���d�͕l�������́A���ł��댯�Ȍ����Ƃ����Ă���B���R���̈�A�����_�ōł��N����m����������n�k�Ƃ����铌�C�n�k�̗\�z�k����̐^��ɗ����Ă��邱�ƁB���R���̓�A�ϐk�����ɂ߂ĐƎ�ł��邱�ƁA�ł���B�����ɁA�J����t���̍�����������B�J�����́A1972�N�����A���ł̎q��Ёu���{���q�͎��Ɓv�̋Z�p�҂Ƃ��ĕl��������2���@�̐v�Ɍg������l�ł���B�����ɂ͋����ׂ��������E�E�E�E�E
1972�N5������A�����ׂ����Ԃ��N����܂����B���傲�Ƃ̐v�҂��W�܂�����c�ŁA�v�Z�S���҂��u���낢��ƌv�Z�����������������B���̐��l�ł͒n�k������ƕl�������͂����Ȃ��v�Ɣ��������̂ł��B�����̑��́A���ݒn�̊�Ղ��ア���ƁB���́A�j�R���W���̂̌ŗL�U�������z��n�k�̎��g���ɋ߂����߁A�n�k�������ɋ��U���N����₷�����Ƃł��B�@�Ȃ�ƁA���n�����ƌ������̂̃_�u���댯�Ƃ����w�E�ł���B�Ȃ�Ή��P��������ł͂Ȃ����E�E�E�Ǝv���̂���ʐl�̔��z�B�Ƃ��낪���������͂����Ȃ�Ȃ��B�J�����͑�����B
��c�ł͂���ɋ����ׂ����ƂɁA�v�Z�S���҂��u�n�k�ɑς�����悤�Ƀf�[�^���U������v�Əq�ׂ܂����B�����A�i�P�j��Ղ͋��������Ƃ��� �i�Q�j�j�R�����ڕ����̎��g���͋Z�p��g��̐����l�Ɠ���ւ��� �i�R�j�����̌��z�ޗ��̔S�������傫�Ȓl�ɕς��Ă��܂� �Ƃ������̂ł��B���͂�����āu����ȁv�Ǝv���A���炭�Y���Ɏ��\���o���܂����B�@�J�����́A�Z�p�҂Ƃ��Ă̗ǐS�̙�ӂɑς���Ȃ��Ȃ��Ď��߂��̂ł���B���̂Ƃ����ꂽ1���@��2���@�́A�K���Ȃ��Ƃ�2009�N1���ɉ^�]���I�����Ă���B�A���A�I����̌��q�F�{�̂Ɗj�R���͐��N�ԗ�p�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A��X�͍���̕����������̂Ŋw��ł���B
�@3�|5���@�͂ǂ����낤�B��������������l�����ō���Ă���Ƃ�����A�����͑傫���B������͉^�]��������ł���B���C�n�k���N���āA�����̓�̕��ƂȂ�����ǂ����B�n���͂��Ƃ��A��s���▼�É��ւ̉e���͂��r��ł���B�����\�����Ԃ�250���������A�l���\������180�����A�l���\���É���120km�Ȃ̂ł���B
�@���������������X���J���ׂ��́A�������Ɍg���l�����̃������̒Ⴓ�ł���B����A�ނ��낻��̓������̂Ȃ��ƌ���������ׂ������m��Ȃ��B�����ɂ͌����Ƃ��������ɍ����Ă��܂����l�Ԃ̔߂������낵��������B����͔w�������Ȃ�悤�ȓ��̂̒m��Ȃ��s�C�����ł���B�f�[�^���n�k�ɑς����Ȃ����Ƃ���������A�{�̂����ǁE��������̂��Z�p�҂̗ǐS�ł���펯�̂͂����B�����ċ\�����Ƃ��A��X�͋U���Ƃ����B����������̋U���ł͂Ȃ��B�l���𑒂荑�v���Ȃ߂�r��Ȃ�U���s�ׂȂ̂��B�����𐄐i���Ă���̂����{�Ƃ������ł���Ȃ�A���̏́A���������E�������g���Ȃ߂Ă���Ƃ����}���Ȃ̂ł���B���ɗR�X�������ƂƂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�l���Ɠ����悤�ɑϐk���ɖ��̂��錴���͑S���ɑ�������Ƃ����Ă���B�n�k�͗\�m�ł��Ȃ��B�������邩������Ȃ��̂��B�Ȃ�A����͓��_�����肶��Ȃ��B���������łׂ��ً}���ԂȂ̂ł���B���{�͍���̑�k�ЂɑΏ����邽�߂ɏ\�����̑��{����������B��}���}�X�R�~���L���҂��ٌ������ɉ�c�͖��Ɲ������ȗ�����������B�m���ɂ��̒ʂ肾���A���͋t�ɑ��݂��Ă���B�u�������_�����v�̐ݒu�ł���B �Ґ��́A�m���[�����A�d�͉�ЋZ�p�����N���X�ƋZ�p�S���ҁA���q�F������Ђ̋Z�p�X�^�b�t�A���������݉�Ђ̃X�^�b�t�A�n�k�w�ҁA�n���w�ҁA���̑��K�v�Ȋw�ҁn�B���悾���̑�����b�Ǝς���Ȃ��d�͉�Ђ̃g�b�v�A�����āA��p�@�ւƐ��艺���������q�͈��S�ψ���ƌ��q�͈��S�E�ۈ��@�͗v��Ȃ��B���[�����́A�s���̗v�Ƃ��Ă��Ȃ��ƍ��邩��B�Z�����Ȃ�Ă���Ȃ��ŁA�L�҉�͕������ɂł��C����ׂ��A�ǂ������厖�����Ď��B�ŁA���̃`�[�������������̂̎ƌ��n�d�͉�ЎЈ��ƍ������A�댯�x���̌������珇�Ԃɉ���āA���G�Ȃ��o���A���S��Ă��쐬�������s����B���ꂱ�����A���̐��{���ŗD��ł��ׂ����Ă��Ǝv�������������낤���B
�@��������A�k�Е�����c������Łu�����ł͂Ȃ�������ڎw���Ăق����v�Ȃ�āA�������悤�ȊϔO�_���Ԃ��グ�Ă���ɂ���������A�u�������_�����v�𑁋}�ɍ���āA�v���ɉĂ��������������̂ł���B
���j�p���������̋���ׂ����ԁ�
�@���䌛�v���̍������u�������ǂ�Ȃ��̂��m���Ăق����v�͐g�̖т��悾�悤�ȓ��e�ɖ����Ă���B���䎁�̂��Ƃ͕��F�E�@�����̃����E����畷���Ēm�����B�ނ̃u���O�u�����E�����̉������l���v�ɂ͓Ǝ��́u���������b�Z�[�W�v���W�J����A�^���̃R�����g�����������Ă���B�ǂ����`���Ă݂Ă��������B
�@���䎁�̍������͌����̌����20�N�ԓ����Ă����Ƃ����l�̎�ɂȂ���̂����ɁA���e���ۗ����ă��A���ł���B�����炱���A���̈���Łu�M�ߐ��ɖR�����v�u80�����R�v�ȂǂƂ����ᔻ�����݂��Ă���̂��낤�B�ł�������Ƒ҂��Ăق����B80�����R�Ȃ��20���͐^�����Ƃ������ƂɂȂ�B����قǂ̑���̍�������20�����^���Ȃ�A����ł����\���ł͂Ȃ����B��X�͂���20����T�蓖�Ă�����̂�����B����Ȕނ̕��͂����p����B
�@��x�����ː��p�����́A�X�̘Z�P�����֎����čs���Ă��܂��B�S����300���{�̃h�����ʂ����ꂩ��300�N�ԊǗ�����ƌ����Ă��܂����A��́A300�N�����h�����ʂ�����̂��A�p�����Ǝ҂�300�N�Ԃ������̂��ǂ����B�@���䎁�́A�u���ː��p�����ɂ́A��x���p�����ƍ����x���p�����A����Ɍ��q�F���̂Ƃ����R�̎�ނ�����B�O��҂͘Z�������ɉ���������Ă��邪�A�i�v�I�ɖ��ߍ��ޏꏊ�͂܂����܂��Ă��Ȃ��B�p�F�����������q�F�̏������@���������̂܂܂��B����ȏ��Ō����̃S�~�͓��ɓ��ɏo�������܂��Ă䂭�B���̂܂܂��Ɠ��{�͕��ː��p�����Ŗ��܂��Ă��܂��v�ƌx�����Ă���̂��B�r�o�ʂȂǐ��ʓI�Ȃ��̂�ʂɂ���A�u���ː��p���������X�o�����邱�Ɓv�Ɓu�p���ꏊ�܂ߏ������@�����m��̂܂܁v�Ƃ����L�q���e��20���̐^���Ɋ܂܂����̂Ǝ��͎v���B
�@������̍����x���p�����A����͎g�p�ς݊j�R�����ď������ăv���g�j�E�������o������Ɏc�������ː��p�����ł��B���{�̓C�M���X�ƃt�����X�̉�Ђɍď����𗊂�ł��܂��B�ǂ�ǂ�̍����x���p�������K���X�ƈꏏ�Ɍł߂āA�����e��ɓ����̂ł��B���̗e��̑��ɓԂ���Ǝ���ł��܂��قǂ̕��ː����o�������ł����A������ꎞ�I�ɘZ�P�����ɒu���āA30�N����50�N�Ԃ��炢��₵�����A���̌�A�ǂ������̏ꏊ�Ɏ����čs���āA�n���[�����߂�\�肾�Ƃ����܂��B�����������\��n�͌��܂��Ă��Ȃ��̂ł��B
�@���q�F���̂ɂ��Ă��A���͎~�߂Ă���T�N��10�N�ԁA���Ǘ����Ă���A���X�ɂ������ăh�����ʂɓ���āA�����̕~�n���ɖ��߂�ȂǂƂ̂Ȃ��Ƃ������Ă��܂����A����ł����Ő����g�����炢�̕��˔\�܂݂�̔p�ނ��o���ł���B�����̃S�~�ł����̂Ă鏊���Ȃ��̂ɁA��̂ǂ����悤�Ƃ�����ł��傤���B�Ƃɂ������{�����j�̃S�~���炯�ɂȂ鎖�͖ڂɌ����Ă��܂��B�����Ȃ�Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ȃ��ł��傤���B
�@������ꌴ���̎����v���O�������v��ʂ�ɐi���10���N��ɔp�F�Ƃ��Ĉ��肵���Ƃ��Ă��A�����Ƃ������͖������̂܂c�����̂ł���B���ꂱ���������ő�̖��_�ł���Ǝ��͍l����B�����āA����͂��ƕ����Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��̂��B���̈�_���������Ă��A�����͓��{�Ƃ������y�ɂƂ��āA�����Ċ��}���ׂ����݂ł͂Ȃ����Ƃ������邾�낤�B�����́A���ƂȂ����ғ����Ă������ɂ����Ă͗D�G�ȓ����҂ł��邪�A��U���Ԃ��������\�ȎE�l�S�Ɖ����A����ł�����̐g�̐U������ԂȂ�Ȃ��A�n���ɏI���Ȃ������Ȃ̂ł���B
�@����ł��������͂���ȉ����ƕt�������Ă����Ȃ�������Ȃ��̂��낤���H
2011.04.25 (��) ��k�Вf�́m2�n �������̂͐l��
 �@4��18���A���d�������ƕ�����ꌴ�������v���O���������\���ꂽ�B�X�e�b�v�P�������p����3�����A�X�e�b�v2���≷��~����3�`6�����Ƃ������̂ł���B�܂��͈���O�i�A�v��ǂ���̎�����Ɋ肢�����B���{�̈АM���������Ă���̂�����B����A����ɓ��t������̂����{�̎d���ŁA���Ӕ��n��E�����v��Ă����}�ɕK�v�ɂȂ��Ă���B������w�����őO���q�͈��S�ψ��̕��c�M�F���́A�u����Ɠ��d��������H���v���O�������o�Ă����̂�����A���͒��������ׂ��B���ɂ��ׂ��́A�n��̏�����Ƃ��B���~�O�ɂ��A�y�̏㕔����邾���ŏ\���_�k�n�Ƃ��čĐ��ł���v�Ǝw�E����B�ʂ����č��͂ǂ������̂��B��������ƌ���肽���B
�@4��18���A���d�������ƕ�����ꌴ�������v���O���������\���ꂽ�B�X�e�b�v�P�������p����3�����A�X�e�b�v2���≷��~����3�`6�����Ƃ������̂ł���B�܂��͈���O�i�A�v��ǂ���̎�����Ɋ肢�����B���{�̈АM���������Ă���̂�����B����A����ɓ��t������̂����{�̎d���ŁA���Ӕ��n��E�����v��Ă����}�ɕK�v�ɂȂ��Ă���B������w�����őO���q�͈��S�ψ��̕��c�M�F���́A�u����Ɠ��d��������H���v���O�������o�Ă����̂�����A���͒��������ׂ��B���ɂ��ׂ��́A�n��̏�����Ƃ��B���~�O�ɂ��A�y�̏㕔����邾���ŏ\���_�k�n�Ƃ��čĐ��ł���v�Ǝw�E����B�ʂ����č��͂ǂ������̂��B��������ƌ���肽���B�@�Ƃ͂����A�k�Ќ�� �������̓����͎��ɐS���ƂȂ����Ҕ��Ƃ��킴��Ȃ��B�����Ⴊ�����\�z��c�ł���B�ݒu�ӔC�҂̐����l�H���u6����t�܂łɂ͍\�z�Ă��o�������v�B����I���Ȃ��Ƃ������Ă�̂��낤���̐l�́B �S����Ў҂̋C�������������Ă��Ȃ��B������A����������Вn��K�₵�Ă��A�u�����A�����Ⴄ�̂ł����v�ƍR�c�̓{���𗁂т�̂��B�s���ɐ��ӂ��Ȃ��ԓx�������I�����炾�B�����Ă܂��A�ܕS�����^�c���̔������u�k�Ђ̔�Q�������S�̂Ŕw�����ׂ������ł��l�������v�̑�ꐺ�����������B�m���ɁA�����m�ۂɐŋ��̌����͕K�v���낤���A�u�����Ɉ�ԑ�Ȃ��Ƃ́A�� �f�U�C���v�̂͂��B���i�n�C�X�N�[���̍���G�搶�ɓ{���܂����B����ɂ��̕��A�ŏ��̉�c�Ŕ�펯�ɂ܂锭���������悤���B�u���I�ňԗ��肽���v�����āB��Вn�̊F����ɂƂ��Ĉꍏ�������Y�ꂽ���͂��̊��܂킵���ЊQ�̍��Ղ��āA��̂ǂ����悤�Ƃ����̂��낤�B�L���̕����������Ƃ����ژ_�݂Ȃ̂����m��Ȃ����A�L�������h�[���Ƃ͖Ⴄ�ƒm��ׂ����B����ȃf���J�V�[�̂Ȃ����_�o���m�ɉ�c�����[�h���������ςȂ��ƂɂȂ�B���c���̈������Y���͗��h�Ȑl�������A���3���̒m���������Ă���̂�����A�ނ璆�S�Ɏ���i�߂Ă��炤�̂����B��l�̔]�V�C�w�b�h�ɂ͑����ސw���Ă��������������̂��B
�@���{�́A������ꌴ���̊댯�x���������ە]���ړx���A���ɍō��l�ł���u���x��7�v�Ɉ����グ���B1986�N�̃`�F���m�u�C���Ɠ����ł���B�`�F���m�u�C���̕��ː��������o�ʂ́A10���Ԃ�520���x�N�����B������40����62���x�N�����œ��X��܂����B�������������w�@�������C�����̎��Z�ɂ��ƁA�����Ƀv���g�j�E�����o�ʂ�g�݂��ނƑO�҂͎���3210���x�N�����ɒB���A�����͂�������x���Ƃ����B�����܂ŗ�R�Ƃ�����������̂ɁA���ۓI�ɂ�"�`�F���m�u�C���Ɠ����x��"�ƕ]������Ă��܂��̂��B�V�Ƃ���������������l�������āB���ꎀ��28�l�ƍb��B���┒���a���҂𑽐��o���A�E�N���C�i�̗Ζ�Ɏ��̊D���T���U�炵�A33���l���ڏZ��]�V�Ȃ����ꂽ�A���̃`�F���m�u�C���Ɠ����Ƃ����]�������E���삯���邱�ƂɂȂ�̂��B�z���g�����̓R���C�̂ł��B ���\�����̂͌��q�͈��S�E�ۈ��@�����A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ������̂�����B����܂ł��݂ǂ���̂Ȃ������ɏI�n���Ă������������߂ăn�b�L�����\�������Ǝv������A���̎n���B�����̕s���v���������A�b�T���ƌ������Ă��܂��Ă������̂��낤���B������k���N�����ꂾ�������������R�������Ă��A���ێЉ�͑�������Ă���ł͂Ȃ����B�ЂƂ܂��U�ɂ��Ă����Ĕ��������邭�炢�̂����������������Ă������̂ł́B����܂��A�������̊O���Z���X���@�̏ؖ����Ǝv�����ǂ����낤�B
�@�댯�x�����x��7�ɒB���Ă��܂��������́A�Ôg�ɂ���Č��q�F�̗�p���u���@�\���Ȃ��Ȃ������Ƃɐs����B����𐭕{�������d�͂����q�͈��S�E�ۈ��@�����q�͈��S�ψ�����������킹�āu�z��O�v�ƌ����B���d������ꌴ���Ƃ��ẮA����5�����̒Ôg��z�肵�Ĉ��S����{���Ă����Ƃ������Ƃ����A3��11���A14�����z���Ôg�Ɍ������A����ɂ����1�|5���@�̌𗬓d�����ׂĂ��r���A���p�f�B�[�[�����d�@��6���@�̈����c�����ׂĎ~�܂��Ă��܂����B���̌���1�|5���@�̗�p���u���@�\���Ȃ��Ȃ�A�F�S�̉��x��g�p�ς݊j�R���̉��x���㏸���A�����E�n�Z�����������B�ƁA���ꂪ�܂����݂Ɏ��钷����̒[���ł���B������u�z��O�v�Ƃ����̂��낤���A�ʂ����Ă���͑z��O�̎��̂������̂��낤���B�ہA�ԈႢ�Ȃ�����͐l�ЂȂ̂ł���B
�@��p���u���@�\���Ȃ������̂́A�d���r�����̃o�b�N�A�b�v�̐����s�����������߂ł���B�n�k����ɑS���q�F��������~�����̂�����A�ЂƂ܂��`�F���m�u�C���͔�����ꂽ�B�Ôg�ɂ���Ď�d���Ɣ��p�d�����r���������̂́A�f�B�[�[�����d�@���쓮����������A���q�F�����Ǝg�p�ς݊j�R�����ɗ�p�ł����\���͍����B���ꂪ�ł��Ȃ������̂́A�d���Ԃ̔z������p�f�B�[�[�����d�@�̐ݒu�����s������������ł���B����͌����ē�����Ƃł͂Ȃ��B�l���Ɋւ���ƂƂ��ē��R�̑[�u�ł���A���ʂɃ����C������ΊȒP�Ȃ��ƁB�Ȃ̂ɕs���̂܂ܐ��ڂ��Ă����̂́A���d�Ƃ�����Ђ̊ɂ݂������̎��̂���͏ؖ��ł���B�Ƃ������ނ���A���̐ӔC�̂ق����傫���H
�@2006�N����A���Y�}�̋g��p���c�����A����o�Y�ψ���ōĎO�ɂ킽���Č����̈��S���𐳂��Ă����B�g��c���̎���͓I�m����̓I�Ȃ��̂ŁA�܂��ɍ����̊�@��\�m���Ă���A���̈Ӗ��ł͎��Ɍ����Ȃ��̂��B�Ƃ��낪�A����ɑ��錴�q�͈��S�ψ���ƈ��S�E�ۈ��@�̉́A�U�b�N���܂Ƃ߂Č����A�u�w�E�͂����Ƃ��ł���A���S�̐��ɖ��͂Ȃ��ƔF�����Ă��邪�A����ɓd�͉�Ђւ̎��m�O���}�肽���v�Ƃ����A�܂�Ŋ�@���̂Ȃ����ӔC�ŋ�̐��̂Ȃ����e�������B�Ƃ���Ŕނ�̑Ή��́H ���̎��_�ŃV�b�J���Ɖ�Б��Ɏw���O�ꂵ�Ă������̎S���͖��R�ɖh�����͂��Ȃ̂ɁA�����͂Ȃ�Ȃ������B���ꂼ�������S���i������̋@�\�s�S�B�f�B�[�[�����쓮���Ȃ��ȑO�ɖ������̏Ⴕ�Ă����̂��B����������قǂ̑�S���������N�����Ă����Ȃ���A�N��l�ӔC����낤�Ƃ��Ȃ��B���S�ψ���̔��ڏt���ψ����ƈ��S�E�ۈ��@�̎���M���@���͑����N�r�őR��ׂ��Ȃ̂ɁA���E�������N�r�ɂ��ł��Ȃ��B���̍��͂�͂肨�������B����Ȗ𗧂����̌��疳�p�ȘA���ɍ��z�ȕ�V���Ă��Ă͍����j�]��������O�Ǝv����B
�@�m����10������Ôg�͑z��O��������������Ȃ��B�������A����ɔ����Ă��ׂ����Ƃ�����Ă����A�S���͂����܂Ŋg����Ȃ������͂��ł���B���ꂪ����Ȃ������̂͊W�҂̐S�ɐ^�������Ȃ��������炾�B�^�����̑����遂�Ɩ��f�Ɠ�ꍇ�������������炾�B�u�z��O�v�̑升���́A�W�Ҏ���̐ӔC����̌�����ł���B�p�ƒm��ׂ����B
�@4��16���t�̒����V���Ɂu�����唼�A���S��ɓ�_�v�Ƃ������o���ŁA�S��17�ӏ�54��̌����̈��S�̋L�����o���B�e�d�͉�Ђ͉s�ӑ��i�߂Ă���悤�ŁA����͂���œ��R�̂��ƁB�����A�Ȃ�ƂȂ��S���ƂȂ��B�Ȃ����낤�ƍl���Ă݂����A�����ɍ��Ƃ̊炪�����Ă��Ȃ����炾�ƋC�������B
�@�h�C�c�̃A���Q���E�����P����3��15���A�������ׂĂ̌��q�F�̉ғ�������3�����ԓ�������Ɣ��\�����B2010�N�A�O�����̒E�����H�����C���A�����̉ғ��N���������j�����\���Ă����ɂ��S�炸���B���_�̉e�����������Ƃ͂����A���{�̌�����肪�N���Ĉ�T�Ԗ����ł̋O���C���͎��ɑN�₩�ɉf��B�܂��ɗE�C����]���ł���B���āu�x�������P���ɂȂ��Ă����߂�C�͂Ȃ��v�ƚ��������{��KY������b�ƂȂ�ƈႤ���Ƃ��B����Ɉ��������A�����P����4��15���ɏ��������������G�l���M�[�����c���s���A�u�����̑����p�~�ƃN���[���G�l���M�[�ւ̈ڍs�v��\�������B���̃L���̗ǂ��Ɛv���Ή��B�����l�̐�S�ېg�ƃ����C�̂Ȃ��Ƃ͐����B�h�C�c���A�܂����I�I
�@�h�C�c�͍��Ǝ哱�ŃG�l���M�[����𐄐i���Ă���B���̈Ӗ��ł́A���{�����Ǝ哱�Ō����𐄐i���Ă����̂ł���B1956�N�A�u���q�͈ψ���v�̐ݒu�B1978�N�A���q�͂̈��S�^�p����̂��߁u���q�͈��S�ψ���v���u���q�͈ψ���v���番�����Ĕ����B2001�N�A�o�ώY�ƏȎ����G�l���M�[���P���Ɂu���q�͈��S�E�ۈ��@�v���ݒu����A���݂Ɏ����Ă���B�����̗���̒��ŁA���{�̌��q�͔��d�͍���Ƃ��Đ��i����A���̌��ʁA���݂ł͑��d�͎��v��30����S�����ƂɂȂ����̂ł���B
�@�O�o�E���c�����́A�u���āA������������A���q�͈��S�E�ۈ��@�Ɍ��q�F���̔z�ǃ~�X���w�E�������Ƃ����������A����Ă��炦�Ȃ������B�����F�߂����̂�����ύX����킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ������R�Łv�Ƙb���B�܂������㎩�q�����t�c���E�u���r�V���́u�k�C����������������A�ً}���Ԃ�z�肵�����P���������̂ɐ\���o����A�w�Ƃ�ł��Ȃ��x�ƒf����܂����B��Έ��S��搂��Ă���̂ɁA�Ȃ�����Ȃ��Ƃ����˂Ȃ�Ȃ��̂��B���ꂶ��A���S���R���ƌ������ƂɂȂ��Ă��܂��ł͂Ȃ����A���������܂�����v�ƃe���r�Řb���Ă����B
�@�����Ō����Ă���̂́A�������S�_�b�`���ێ��̋؏������B�����A���E�d�͉�ЁE�w�҂���̂ƂȂ��āA�����̗L�p��������Ɍf���A�s�s���ɖڂ��Ԃ�A���ΐ��͂����߂Ȃ��琄�i���Ă����Ƃ������Ƃ��B���c�����́u�������i�����Ɍg����Ă��Ċ������̂́A���S�̂��߂͎̒�����Ȃ����[�h�����������ƁB�Ȃɂ���������킸�A�������肫�Ői�߂邵���Ȃ��C���ɂ�������v�ƒQ���B�������g�����̘_���̒��Œe���ꂽ��l�Ƃ�������B���炭�A�܂Ƃ��Ȉӌ���i�������ǎ�����l�����̑������A���̃����Љ��e���o����Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@����́A�����̕l�������̐v�ҒJ����t���A�^�ۗ��_���鍐�����̏�����E���䌛�v����̎咣�������Ȃ���A�m�[�}���Ȉꍑ���i�ł��掄�́j�Ƃ��āA�����̂�������l���Ă݂����B
2011.04.20 (��) ��k�Вf�́m�P�n �z��O�͒p
�@3��11���A���{�Ɉٕς��N�������B�o���������Ƃ̂Ȃ��ЊQ�������B���́A�����P�����ȏソ���������܂���������߂��Ȃ��ł���B���ԂƎ������݂Ȃ���n���b������B�����D���ȉ��y���Ȃ���A�����N���e�[�}�ɂԂ���Ώ������߂�E�E�E����ȓ��킪�ǂ����ɋ����Ă��܂����B�����炱�����U�낤���S�������Ȃ��B���N�܂łƂ͖��炩�ɈႤ�B�ς��ʂĂ����k�Ɩk�֓��̒n�A���R�̋��|�A�������̂Ƃ����ň��̎��ԁA�|�M�����l�X�A�E����������W�ҁA���\��I�悷�鍑�̃��[�_�[�E�E�E�����A�e���r��V���A�T�������痬��Ă��邱���̃j���[�X���A�������������قǂɋC��������ł䂭�B�S���ɁA��Вn�̐l�����ւ̋C����������̂�������Ȃ��\�\�A�џT�A�����A�T�ɂ��ĂȂ��Ⴂ���Ȃ��݂����ȁB�u�����ɉ����o����H�v�Ɩ₤�Ă݂Ă��A�����͐����Ƃ���Ȃ��B�d�������ĉB���̐g���B����ɂ��ł��₵�Ȃ��B���������A�u�h�����������v�Ȃ��ď��x��܂��ӎ��������炢�̂��̂��B�œ����Ă����ĒN���J�߂Ă͂���Ȃ����B�킩���Ă�B����Ȃ��Ƃ͂킩���Ă��邳�B�ł����������̂͂��傤���Ȃ��B�C��������Ȃ��͎̂����Ȃ̂��B�@��Ԃ炢�͍̂D���ȉ��y�ɏW���ł��Ȃ����ƁB����قǂ�������イ�����Ă����u�~�̗��v���ЊQ�ȗ�1�x�������ĂȂ��B���܂ɕ����Ă��W���Y����B���Ƃ����Ȃ��ẮB�u�������Ƃ������O�ɓ��ݏo���v�ƌ������͓̂���ƍN���������B���O�֓��ݏo�����Ƃ��ĉ����H ����́A���̐k�Ђ������̒��Ŏ����Ȃ�ɑ������邱�Ƃ���Ȃ��낤���B����œ��킪�߂��Ă���ۏ͂Ȃ��B�ł��������炸�ɂ͐�ɐi�߂Ȃ����Ƃ��m���Ȃ̂��A�ƍ��������Ă���B
�@1000�N�Ɉ�x�Ƃ����邱�̑�ЊQ���n���I�ɑ����ł���͂����Ȃ��B������A�����ɏ����Ԃ邾�����B���Ȃ͂��A����Ă���j���|�X�����������Ĉ������������L�C���[�h�ɉ����Ēf�͕��ɏ����Ă݂邱�ƁB���ɂ͂��ꂵ���ł��Ȃ��B
���z��O�͒p
�@M9�Ƃ������E�j��4�Ԗڂ̑�n�k���t�̓��{���P�������ƁA�����ɕ������Ă����̂́u�z��O�v�Ƃ����升���������B�u�O�����ł�M�V���x�A�����̐k���n�ŘA�����Ă�M8���x�ɂ����Ȃ�Ȃ��͂��B������M9�͑z��O�v�B���̒n�k�����ψ���i���������ψ����j�̃R�����g�����̒��̈���B���̌����ɑ��A���嗝�w���̃��o�[�g�E�Q���[�����͌������ᔻ����i4��14���t�����V���j�B�u�ߋ�100�N�ȓ��ɋN����M9���̒n�k�A�`����A���X�J�Ȃǂ́A���{�Ɠ��������m�C��ŋN���Ă���B���E�̒n�k�ɖڂ�������A�����͗\���ł��Ȃ��Ă��A�K�͂͑z��ł����͂����v�ƁB
�@����ɁA���j�����Ă݂悤�B���͕�������A869�N�A���k�n���ɑ����̋]���҂��o�����u��ς̑�Ôg�v�̋L�^������B�]�ˎ���ɂ́A�c���O���n�k�i1611�N�j���N���A����l�̋]���҂��o�����B�ߔN�ł́A�����O���Ôg�i1896�N�j�Ə��a�O���Ôg�i1933�N�j�̋L�^������B���ƂɑO�҂ł́A������38�D2���A�]���҂�20,000�l���𐔂����Ƃ����B����قǃn�b�L�������n���I�E���j�I����������̂�����z��ł��Ȃ��͂��͂Ȃ��B����Ȃ��̏��w�������ĕ�����B�u�z��O�v�͐��ƂƂ��Ēp�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ������A�t�Ɂu�Ȃ�M8���x�܂ł����z��ł��Ȃ������̂ł����H�v�Ƃ��u�����������̂��B�Ȃɂ�����覐ΏՓ˂�6500���N�O�܂ł�z�肵��Ƃ͌����܂���B������1000�N�A����A��������100���N���Ȃ��ӂ݂��Ȃ��̂��B
�@ �@���̑̂��炭�ȁu�n�k�����ψ���v�Ȃ���̂�1995�N�A��_�W�H��k�Ќ��߂�ꂽ�u�n�k�h�Б����ʑ[�u�@�v�Ɋ�Â��Đݒu���ꂽ12�l�̐��Ƃɂ�鐭�{�̌��I�@�ւ��B�ψ��̔C�����͑�����b�����B
�@�u�n�k�h�Б����ʑ[�u�@�v�����m�ړI�n�͈̏ȉ��̂Ƃ���B
���̖@���́A�n�k�ɂ��ЊQ���獑���̐����A�g�̋y�э��Y��ی삷�邽�߁A�n�k�h�Ћً}���ƌ܉ӔN�v��̍쐬�y�т���Ɋ�Â����ƂɌW�鍑�̍�����̓��ʑ[�u�ɂ��Ē�߂�ƂƂ��ɁA�n�k�Ɋւ��钲�������̐��i�̂��߂̑̐��̐������ɂ��Ē�߂邱�Ƃɂ��A�n�k�h�Б�̋�����}��A�����ĎЉ�̒����̈ێ��ƌ����̕����̊m�ۂɎ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�@���̖ړI�𐋍s���邽�߂̒����@�ւƂ��Đݒ肳�ꂽ�̂��u�n�k�����ψ���v�Ȃ̂��B�v����ɁA�n�k�ɂ��ЊQ���獑���̐����A�g�̋y�э��Y��ی삷�邽�߂ɒ����������s���]�����A�W�e���ɕE���邱�Ƃ��~�b�V�����Ƃ���@�ւȂ̂ł���B���ʂ͂ǂ����B�n���I�ɂ����j�I�ɂ��@�艺������z������A�N�����������ɑ��ĕ��R�Ɓu�z��O�v�Ƃ̂��܂��B��邾����������ʂ̑z��O�Ȃ�܂������A�@�艺���s�����Ӗ��ɂ��z��O���N�����̂ł���B�����͐E���Ӗ���f���ɔF�ߓy�������邵���Ȃ����낤�B�����Ȃ��蓖�Ă����Ă���̂��낤����B
�@�Q���[�����ɂ��A�u�n�k�����ψ���v�͂܂��A�K�݂͂̂Ȃ炸�A�����n��̐���ɂ����Ă��I���O�����Ƃ����B��_�W�H�ȍ~�A�ő�K�͂ƂȂ����V�������z�i2004�N�j�Ɗ��E�{������i2008�N�j�́A�ψ���s�̗\���n�}���A��r�I�m���̒Ⴂ�Ƃ����n��ŋN���Ă����̂ł���B�K�͂��n����O�����āA��̐^�ʖڂɂ���Ă���̂ł����I�H�\�͂��Ȃ��Ȃ���U���ׂ����B
�@�g�D�I�ɂ݂�ƁA�u�n�k�����ψ���v�͕����Ȋw��b��{�����Ƃ���u�n�k�����������i�{���v�̎P���ɂ���B�����̔C�����͂��ׂđ�����b�ɂ���B���t������b�����l�́A���d�ɏ�荞��Ő����r����O�ɁA�T��ɍ��؋`�������Ȋw��b�ƈ��������n�k�����ψ��������点�āA�u��k�Ђ�E���Ӗ��ɂ��\���ł������ɐ\����܂���ł����v�ƒӂ��ׂ��ł͂Ȃ����B
�@�u�n�k�����ψ���v�̑��Ɂu�����v�u�n�k�\�m�A����v�Ƃ����n�k�֘A�̋@�ւ��������Ă���̂��s�����B�u�����v�͋C�ے������̎��I����@�ւƂ���1979�N�ɔ�������6�l�\���̑g�D�ŁA��͈������̌��C�ł���B�u�n�k�\�m������v��1969�N�ɐݗ����ꂽ30�l����Ȃ�@�ցB�u�n�k�����ψ���v��12�l������A�n�k���͍��v48�l�̃����o�[�ō\������Ă��邱�ƂɂȂ�B�ʂ����Ă��̐l���͖{���ɕK�v�Ȃ̂��H �L�\�Ȃ�Ή��l�������č\��Ȃ����A�T��Í����������悤�ȁu�o�J�{�o�J�{�o�J���o�J�v�ł͍���̂��B�����悤�ȎO�̑g�D���������Ă���̂́A�V���ȑg�D���o���Ă������̑g�D�����ł����Ȃ����߂ɁA�I���ȍ앶�Ŋe�X�̖ړI���ϔO�I�ɕ��U�����Ă��������̏퓅��i�ɂ��Y���Ȃ̂��낤���A�펯�I�ɍl���ĖړI�͈�u�n�k�̔�Q���獑���̐������Y�����v�ɐs����͂��B�Ȃ�Γ����ɂ��g�D�̏ȗ͉��E�������͐}���͂��ł���B�����ɂ��܂��A�������������܂ŕێ����悤�Ƃ��銯�������ς��Ƃ������u���鐭�{�^�}�̊o��̂Ȃ��Ɩ��\�����_�Ԍ�����̂��B
 �@�{�Îs�c�V�n��ɂ͖����̒���Ƃ����w���̑�h���炪����B���̖��̂Ƃ���A����10���̒�h��2433���ɂ킽���ė����͂������Ă���B���������a�O���n�k�̋��P�܂��č��グ�����̂������B�Ƃ��낪�A3�D11����Ôg�ɑ��Ă͖��͂������B���������͑z��O�̌��ʂȂ̂��H ���݂����n�������̂́A�����O���ō���38m�̋���Ôg�������������Ƃ�m���Ă����͂��ł���B�z��͂��Ă����̂��B������100�N�Ɉ�x�̃��m��z�肵��30m���̖h�����2�����ɂ킽���č��킯�ɂ͂����Ȃ��A�o�ϓI�ɂ��i�Ϗ���B���ꂪ�s���Ƃ������̂��B�̐S�Ȃ͍̂������ōň���z�肷�邱�ƂŁA���ꂪ�l�q�Ƃ������̂��B���ɂ́u���ꂾ���̋���ȒÔg�̑O�ɂ͖����̒�������ɗ����Ȃ������ł͂Ȃ����v�ƌ������������邪�A����͈Ⴄ�B���ꂪ�����������Q�͂����ƍL�����Ă����ƍl����ׂ��Ȃ̂��B
�@�{�Îs�c�V�n��ɂ͖����̒���Ƃ����w���̑�h���炪����B���̖��̂Ƃ���A����10���̒�h��2433���ɂ킽���ė����͂������Ă���B���������a�O���n�k�̋��P�܂��č��グ�����̂������B�Ƃ��낪�A3�D11����Ôg�ɑ��Ă͖��͂������B���������͑z��O�̌��ʂȂ̂��H ���݂����n�������̂́A�����O���ō���38m�̋���Ôg�������������Ƃ�m���Ă����͂��ł���B�z��͂��Ă����̂��B������100�N�Ɉ�x�̃��m��z�肵��30m���̖h�����2�����ɂ킽���č��킯�ɂ͂����Ȃ��A�o�ϓI�ɂ��i�Ϗ���B���ꂪ�s���Ƃ������̂��B�̐S�Ȃ͍̂������ōň���z�肷�邱�ƂŁA���ꂪ�l�q�Ƃ������̂��B���ɂ́u���ꂾ���̋���ȒÔg�̑O�ɂ͖����̒�������ɗ����Ȃ������ł͂Ȃ����v�ƌ������������邪�A����͈Ⴄ�B���ꂪ�����������Q�͂����ƍL�����Ă����ƍl����ׂ��Ȃ̂��B�@�ň��̎��Ԃ�z�肵�ĉ\�Ȍ���̔���������B�����̃L���p�V�e�B�������ɑ����čň��̎��ԂƂ̃M���b�v����������Ɣc�����A�M���b�v�߂邽�߂̌P���i������H���Ď��Ԃɔ�����B"�G��m��Ȃ�m��ΕS��낤���炸"�ŁA���ꂪ��@�Ǘ��Ƃ������̂��B
�@���̈Ӗ��ŁA���̋���n�k��͖��S�������̂��H �ۂł���B�{�Îs�c�V�n��ł́A��邾������čŊ��ɐl�q���z�����Ă��܂����B���O�ɂ܂�Ȃ��������낤�B���̒n�k���̌����͏��߂���z����Ă����B�p�ƒm��ׂ����B���O�ʂ��āu�z��O�v�Ȃǂƌ����Ăق����Ȃ��B����͐ӔC����̉����ł��Ȃ����炾�B
�@���̂Ƃ���u������k�Ђ�X�f�C�́H�v�Ȃ錩�o�����|�c�|�c�Əo�n�߂��B�u�z��O�v��A�����鍑�͂�����Ɨ���ɂȂ�Ȃ�����A�����̂��Ƃ͎����Ŏ�邵���Ȃ��̂����B�u���Ƃ��������Ă���邩�ł͂Ȃ��A�����ɉ����ł��邩�v��^���ɍl���悤���Ǝv���B
�@���������ɂ��u�z��O�v���×������B������͂܂��ʂ̋@��ɁB
2011.03.23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X��21 �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v14
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@�ŏI��
�i�W�j���V���[�x���g�Ō��80���Ɓu�~�̗��v���@1828�N9��1���A�V���[�x���g�̓E�B�[���x�O�m�C�G�E���B�[�f��694�Ԓn�ɂ���Z�t�F���f�B�i���g�̉ƂɈ����z�����B����80���O�̂��Ƃł���B����͎厡��G�����X�g�E�����i�E�t�H���E�U�[�����o�b�n���A�a��̈��������ē]�n���]�܂����Ɣ��f�������߂ł���B���a���L�̓��ɂ͖����I�������Ŕނ��ꂵ�߂��B
�@����ȕa��̒��A�ނ͋ȍ��ɗ�ށB�s�A�m�E�\�i�^��19�ԃn�Z��D958�A��20�ԃC����D959�A��21�ԕσ�����D960��3�Ȃ���C�ɏ����グ��B���������̂�9��26���ł������B�Ō�̊�y�ȁu�s�A�m�E�\�i�^��21�ԁv�́A�����I�ɕΓ��ɓI�d�ꂵ���͐���ł�����̂̑S�͎̂���D�������i����B���̘Ȃ܂��͌`�e�����������݂�s�ށB
�@ �@9��25���̃V���[�x���g�̓��L�ɂ́A�u�w�~�̗��x��́A�������łɃn�X�����K�[�ɓn�����v�Ƃ���B��͈���ɉ��߂̌��e���������e�����c���Ă��Ȃ��B���e�͐����e���o�������Ɣj�������̂��낤�B�����e�́A�n�X�����K�[��"�n����"�Ƃ��邩��A�Z�܂���K�˂��n�X�����K�[�ɒ��ڎ�n�������̂Ǝv����B�O�͂ɂ��������悤�ɁA�V���[�x���g���ӔN�ł��M�����Ă����o�Ől�̓n�X�����K�[�ł������B����́A10��2���́u4�Ȃ̑����ȓ��̓n�X�����K�[���o�R���Ĕ��������E�E�E�v�Ƃ����A�ʂ̏o�ŎЂɈ��Ă��莆������ǂݎ���B
�@����A��Ԃ̐e�F���[�[�t�E�t�H���E�V���p�E���i1877�|1865�j�́A�u11��11���ɔނ͏��ɏA����������Ȃ��Ȃ����B�댯�ȕa��ɂȂ��Ă����ɂ�������炸�A�ނ͋�ɂ������邱�Ƃ͂Ȃ��A�������㊴�݂̂�i���Ă����B�₦���ނ͉̂���������ł������A���܂��킲�Ƃ�������ԂɂȂ邱�Ƃ��������B���邢�킸���̎��Ԃ��g���āA�ނ͂܂��w�~�̗��x��̍Z�������Ă����v�Ə����Ă���B
�@11��17���ɓ�l�̗F�l���V���[�x���g���������B�G�[�h�D�A���g�E�t�H���E�o�E�G�����t�F���g�i1802�|1890�j�ƃt�����c�E���b�n�i�[�i1803�|1890�j�ł���B���̂Ƃ��̖͗l�����b�n�i�[�́u�F�l�́A�`�t�X�������ď��ɏA���A�댯�ȏ�Ԃɂ����B�w�l�͂Ђǂ��d�����B�x�b�h���ė��������ȋC������x�Ƃ������t���Y����Ȃ��v�Ə����Ă���B����̃o�E�G�����t�F���g�́u�ނ͋ꂵ�����ɐQ�Ă��āA�̗͂��Ȃ��A���ɔM������A�Ƒi�����B�������ߌ�ɂ͊��S�ɂ������肵�āA���킲�Ƃ̒�����Ȃ��������A�F�l�̏d�ꂵ���C�������̐S�������\���Ŗ��������B���̔ӂɂ͂����a�l�͌��������킲�Ƃ������悤�ɂȂ�A���ꂫ��ӎ��͖߂�Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B�ނ��l���Ō�̖K��҂ƂȂ����B
�@�V���[�x���g��9��25���ɂ́u�~�̗��v��̐����e����U�o�ŎЂ̃n�X�����K�[�ɓn�������A���̌�ǂ����̎��_�Ŏ苖�ɖ߂�A11��17���̖�ӎ��������܂ōZ�������Ă����B�����Đ���19���ɂ͑�������������B������O�̌��e�ł��鐴���e�Ǝ�����������M���M���܂őΛ����Ă����̂ł���B�����ɂ͈�̂ǂ�Ȏ���B����Ă����̂ł��낤���H
�i�X�j�������āA�^����
�@1828�N9��25���A�V���[�x���g����u�~�̗��v��̐����e��������n�X�����K�[�́A�������ł�g�ݎn�߂�B�N���ɏo�ł��邽�߂ɂ͋}���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�V���[�x���g��16�u�Ō�̊�]�v�A17�u���ɂāv�A20�u������ׁv�ōs�����~�����[�̌����̒����Ȃǂ��m�F���Ȃ����Ƃ�i�߂�B�����ɑS�����͂Ȃ��B�����čH�����I�Ղɂ�����������11�����{�A22�u�E�C�v�̏I������A5�̉���������̂ɋC�������B����́A��䏊�t�H�[�O���ɂ��A������o�����̃J�����E�t�H���E�V�F�[���V���^�C���i1794�|1859�j�ɂ��L�c�C�������B���������̉��ɂ́A���ߕ���Ƃ������ׂ��u���������g���_�ɂȂ낤�v�̒��́u���g���vselber�Ƃ����d����傪����Ă���B�������̉̂̌��ߕ����ł���B�����͈ꉹ������ׂ��ӏ����B���ɁA��Ȏ҂ɂ́A�����O�A�j�Z����12�u�ǓƁv�ɂ���A5�����Z���Ɉڒ�����5Fis�ɉ����Ă�����Ă���B����܂ł����̓ƒf�ŕς������ƂȂLj�x�����ĂȂ��B�V���[�x���g�Ƃ̐M���W������Ȏ��̐^�����ŕۂ���Ă���Ǝ������Ă���B������A�����o�����Ĉӌ����������Ƃɂ��悤�E�E�E�E�E�n�X�����K�[�͂��̌��_�������ăV���[�x���g��ɏo�������B1828�N11��16���i�H�j�̂��Ƃł���B
�@�u����ɂ��́A�V���[�x���g�A�������͂ǂ��B����a�����������Ȃ̊y���́A�m���Ƀ}�C���c�̌|�p���ЃV���b�g�ɑ����Ă����܂�����B���āA�����̘b�́w�~�̗��x�̂��ƁB���܁A�����ɂȂ��Ċ��ł�g��ł��܂��B�ǂ����Ă��N�����ɏo�ł������̂łˁB24�Ȃ܂Ƃ߂��`�ŏo�����Ǝv���Ă��܂��B�����ꕔ�����Ȃ������Ă�����Ă��邩��A���̂ق��������ł��傤�B�l�i������܂����ˁB
�@�����ő��k�ł��B22�u�E�C�v�̏I��selber�ɕt����5A�͍������܂��B�t�H�[�O���͍ŁA�������̉��͖����B���܂₠�Ȃ��̉̋ȍō��̉̂���ł���V�F�[���V���^�C���j�݂��A�Ⴂ�Ƃ͂����n�����t�H�[�O�����Ⴂ�̂�����A���G������Ƃł��B�v���ł������̂ł�����A�}�`���A�Ȃ�Ȃ�����̂��ƁB�����͈ꉹ�����ăg�Z���łǂ��ł��傤���B���̕����y�����Ȃ�ڂ������ł��傤���v�ƃn�X�����K�[�B������ăV���[�x���g�́A�u�n�X�����K�[���肪�Ƃ��B����22�Ȗڂ܂ōs�����̂ł����B�o�ł��y���݂ł��B�킩��܂����A�w�E�C�x�̃g�Z���ւ̈ڒ���OK�ł��B����͂����Ɩl�͂ˁA�ŋ�10���Ԉȏ�A�����H�킸�A�������܂��A��ꂫ���ăt���t�����Ȃ���\�t�@�[����x�b�h�֍s�����藈���肵�Ă����ł���B���Ƃ�������H�ׂ��Ƃ��Ă��A�܂������ɓf���o���Ă��܂��B�ł��w�~�̗��x�����͋C������Ȃ�ł��B���̂ق��ɂ��A�܂��A������ƋC�ɂȂ�Ƃ��낪����̂ŁA���̊y����U�u���Ă����Ă���܂��B�����ɕԂ��܂��̂Łv�ƌ����āA�����e��a�������B

�@�n�[�f�B�K�[�f�B�ɂ͐������ƌŒ茷�i�h���[���j������B�Œ茷�͓�{����A�ʏ��C-G��5�x�ɒ�������Ă���B������E��Ńn���h�����ĉ��t����ɉ����o��������̂ł��邪�A�V���[�x���g�͂��̉����s�A�m�̍���Ŗ͂����Ƃɂ����B2�̑������͍ŏ��̂Q���߂����\�\�����n���ɂ������܂�Ȃ�������\�����������̂��B�Ƃ��낪���ꂾ�ƁA�Q�ڂ̑��������牺�~���Ė{�a���ɂȂ����Ă��܂��B����̓n�[�f�B�K�[�f�B�̍\����s���R�ł���B�V���[�x���g�́AE�璼�ږ{�a���ɂȂ���悤�ɁA����������G���O�����ƂɌ��߂��B
�@������̋C������́A�u�҉��y�t�v�̒����ł������B�u�~�̗��v�Ō�Ɉʒu���邱�̋Ȃ́A���Z���ɐݒ肵�Ă���B����͑�ꕔ�ŏI�ȁu�ǓƁv���j�Z�����烍�Z���ɉ������Ƃ��ɁA�݂��̕�����߂�����Ƃ����Ӗ��ō��킹���ɉ߂��Ȃ��B�{���ɂ���ł����̂��낤���B�O���ƌ㔼�ꂵ�Ē��߂邱�ƂɈӖ�������̂��납�B���������A�~�����[�̌����͊����łƂ���24�Ȃ��ꊇ���ďo�ł��Ă���A���̏��ԂƂ͑傫���قȂ��Ă��܂��Ă���B�Ƃ������A�����ȏ����~�����[�̊����łɍ��킹�Ȃ������̂��B���́u�~�̗��v�S24�Ȃ͑O�����㔼���Ȃ��A��A�̗���̒��ɂ�����̂Ȃ̂��B��������A��12�Ȃ�24�Ȃ̒��������킹�邱�ƂɈӖ��͂Ȃ��B
�@�u�҉��y�t�v��S24�Ȃ̒��ߊy�ȂƂ��Č����ꍇ�A����͒f���ă��Z���ł͂Ȃ��B���́u�҉��y�t�v�ɋ~�ς����Ă���B���̃~�����[���Ō�ɓo�ꂳ�����B��̐l�Ԃ����A��҂̈ӎv���~�߂�Ō�̍ԂȂ̂��B���ׂĂ���a�O����A���ׂĂ�ے肵�Ă��ǂ蒅�����I�A�V�X�Ȃ̂��B���ׂĂ��Ȃ����������ɗB��̂������c���āA���̎����̉̂Ƀ��C�A�[�̒��ׂ����킹�Ă��炢�A�ꏏ�ɕ����Ă䂭�̂��B���̐�ɉ����҂��Ă��邩�͕�����Ȃ��B�Ƃɂ������ɂ��s���̂ł���B�������߂��A���ɂ����҂����A�������̂Ƃĉ����Ȃ��B�����A�S�͖��B���ׂĂ͖��Ȃ̂��B�Ȃ�Β��i���j�����ɂ��悤�B���Z������C�Z���ɁB���̂��ׂĂ���D���ȃC�Z���̋����ŏI���B�������A�u�҉��y�t�v�͐�ɃC�Z���łȂ���Ȃ�Ȃ��̂��B
�@���������ɂƂ����邳�̒��ŁA�ނ͂���������B�S�̂������͐�����āA�����N�O����ӎ��̂܂ܐ����������o���ď������Ƃ������A���͂�ނ͎̑̂����̈ӎv������Ă͂���Ȃ������B�ނ͂������܃t�F���f�B�i���g���ĂA�u�Z����A���肢�B�w�҉��y�t�x���E�E�E����G�����������āB���̓C�Z���ɕς��āB�����ăn�X�����K�[�ɁE�E�E�v�ƌ����Ȃ���ނ̈ӎ��͖߂�Ȃ��Ȃ����B11��17���A��̂��Ƃł���B
�@�ނ̍Ō�̍�i�́A�u��̏�̗r�����vD965�Ƃ��u���̎g���vD957-14�Ƃ������Ă��邪�A���͂����ł͂Ȃ��A����́u�~�̗��v�ł���A���̍ŏI�ȁu�҉��y�t�v�������ނ̐^�̈�삾�����̂ł���B
�@19���A�V���[�x���g�͋A��ʐl�ƂȂ����B�t�F���f�B�i���g�́A�₪�ĖK�˂Ă����n�X�����K�[�ɃV���[�x���g�̈ӎv��`�����B�u�����ł����B���������v���ł��B�C�Z���̂ق����݂�ȉ̂��₷���āA��т܂���v �n�X�����K�[�́A�S���Ȃ����̑�ȍ�ȉƂ𓉂݂Ȃ�����A�ɂ�����Ə��āu�҉��y�t�v�̐������̏�ɏ������� in a-mol �ƁB
�@�������āu�҉��y�t�v�͐������̃��Z������C�Z���ɕς��ďo�ł��ꂽ�B�V���[�x���g�̈ӎv�ŁB�����e��́u�C�Z���Łvin a-mol �̕����́A�V���[�x���g�̈ӂ����n�X�����K�[�����������̂������E�E�E�E�E���́A�M�Ղ��n�X�����K�[�̂��̂�����C�Z���ւ̈ڒ��̓n�X�����K�[�̈ӎv�ōs��ꂽ�Ƃ����Z���I���߂ɂ�邱��܂ł̒���́A���̂悤�ɒ��������ׂ��ł���ƍl����B�m���ɂ���ɂ͕��I�؋��͉����Ȃ��B�n�X�����K�[���t�F���f�B�i���g�̉Ƃɍs�����L�^���Ȃ���A�����ŃV���[�x���g�ƈӌ������킵���Ƃ����؋����Ȃ��B�������A�����ɂ����łȂ������Ƃ���؋����Ȃ��̂ł���B�ւ�肤�邷�ׂĂ̐l�X�̎��R�Ȋ����s����f���ɉ��߂��ē����o�������̐��_�̂ق����A����܂ł̒�������A��莩�R�œK���Ȃ��̂Ǝ��͊m�M����B�F�l�͂ǂ��v���邾�낤���H
2011.03.10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևS �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v13
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ ���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����4��
�i�V�j�u��O�̒j�v�@�L�������E���[�h�ē̉f��u��O�̒j�v�́A����E��풼��̃E�B�[��������ł���B����Ȃ��A�����J�l��ƃz���[�E�}�[�`���X�i�W���Z�t�E�R�b�g���j���A���F�n���[�E���C���i�I�[�\���E�E�F���Y�j�̏����ŃE�B�[���ɂ���Ă���Ƃ��납�畨��͎n�܂�B�Ƃ��낪�����������̓��ɁA�����l�̑��V���s���Ă����\�\�����͎��̎��B����͋��F�̗F�l��l�̏،����B�Ƃ��낪���̌���ɂ͂�����l�j�������Ƃ����ڌ��،����B���̂�����l�A�����u��O�̒j�v�������A���͂��̋��F�������B�E�E�E�E�E������ʂŕ`�����I�풼��̃E�B�[���́A�r�����镗��ʼn��y�̓s�̉₩���͔��o���Ȃ��B�����ɁA���͂��̒j�͐����Ă���H ���Ⴂ�����A�Ȃ玀�̂͒N���H �n���n���h�L�h�L�̃V�[�����A������B����A�z���[�̓n���[�̗��l�A���i�i�A���_�E���@���j�ɏ��X�ɐS�䂩��Ă䂭�B�������āA����͋ٔ��������g���Ƀr�^�[�ȗ��̃X�p�C�X�������A���̓`���I�ȃ��X�g�V�[���ɗ��ꍞ��ł䂭�̂ł���B�A���g���E�J���X�̃c�B�^�[�̋�������ۓI�ȁA�T�X�y���X�f����w�̖���ł���B
 �@���āA���x��1828�N�̃E�B�[���ł���B������́u�҉��y�t�v���Z�����C�Z���A�ڒ��̔Ɛl�͈�̂���Ȃ̂��낤���H �O���ŁA��ꍆ�e�^�҃n�X�����K�[�Ƒ��̕��e�t�H�[�O���ɂ͓��@���Ȃ����Ƃ��ؖ������B�ł͈�̒N���H ���́u��O�̒j�v�A�����t�����c�E�y�[�^�[�E�V���[�x���g�������^�Ɛl���ƍl����B����͏����@�Ō��_�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�ڒ��͖{����ȉƂ������ׂ��s�ׂ�����ł���B
�@����ňꌏ�������Ă������̂����A����ł͂܂�Ȃ��B��͂�V���[�x���g�̓��@��T��̂����낤�B���͂���܂ŁA�V���[�x���g�Ɛl�_��������������������Ƃ͂Ȃ��B�J�ɂ���̂́A"�Ɛl�̓n�X�����K�[�ł���"�Ƃ�������������B���̓V���[�x���g�Ɛl�����f��������ؖ����Ă݂����B�܂��Ɂu�N�����m�v�I���Ƃł͂Ȃ����B
�@���āA���x��1828�N�̃E�B�[���ł���B������́u�҉��y�t�v���Z�����C�Z���A�ڒ��̔Ɛl�͈�̂���Ȃ̂��낤���H �O���ŁA��ꍆ�e�^�҃n�X�����K�[�Ƒ��̕��e�t�H�[�O���ɂ͓��@���Ȃ����Ƃ��ؖ������B�ł͈�̒N���H ���́u��O�̒j�v�A�����t�����c�E�y�[�^�[�E�V���[�x���g�������^�Ɛl���ƍl����B����͏����@�Ō��_�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�ڒ��͖{����ȉƂ������ׂ��s�ׂ�����ł���B
�@����ňꌏ�������Ă������̂����A����ł͂܂�Ȃ��B��͂�V���[�x���g�̓��@��T��̂����낤�B���͂���܂ŁA�V���[�x���g�Ɛl�_��������������������Ƃ͂Ȃ��B�J�ɂ���̂́A"�Ɛl�̓n�X�����K�[�ł���"�Ƃ�������������B���̓V���[�x���g�Ɛl�����f��������ؖ����Ă݂����B�܂��Ɂu�N�����m�v�I���Ƃł͂Ȃ����B���V���[�x���g�̓C�Z�����D���H��
�@�V���[�x���g�����������Z���̃s�A�m�E�\�i�^�͑S����5�Ȃ��邪�A�Ȃ�Ƃ��̓���3�Ȃ��C�Z���ł���B���y�w�ҕ��쏺���́A�u�C�Z���̓V���[�x���g�̍ł��D�����ł���v�i���ȉ���S�W�A���y�V�F�Њ��j�ƒf�����Ă���B�V���[�x���g�̃C�Z���y�Ȃɂ͂��̑��ɂ��A���y�l�d�t�ȑ�13�ԁu���U�����f�vD804�A�A���y�W�I�[�l�E�\�i�^D821�Ȃǂ̖��삪����A�˂�B����A���Z���y�Ȃ́A�s�A�m�E�\�i�^�ƌ��y�l�d�t�Ȃɂ͈�Ȃ��Ȃ��A�����Ȋy�ȂƂ��Ă͌����ȑ�7�ԁu�������v������݂̂��B�����́A�V���[�x���g�́u�C�Z�����ł��D��ł����v�Ƃ���������̈ꉞ�̍����ɂȂ肤��Ɠ����ɁA���Ȃ��Ƃ��u���Z���v���͍D���Ȓ����������ƋK�肵�Ă��٘_�͂Ȃ��Ǝv����B
�@�V���[�x���g�̃C�Z���̋Ȃ��Ă݂�B�s�A�m�E�\�i�^��4��D537�̑�P�y�́A��14��D784�̑�P�A3�y�́A��16��D845�̑�P�y�͂ɋ��ʂ��Č�����̂́A�߂��݂̕\������ăh���h�����������ȝR������邱�Ƃ��B���ꂽ�߂��݂ƌ����Ă������B���̓����́A�u�A���y�W�I�[�l�E�\�i�^�v��P�y�͑�P���ɁA��茰���Ɍ���Ă���B���Z���̖��ȁu�������v��1�y�͂̏�O�Ƃ�������Â��Ƃ͖��炩�Ɉَ��ł���B
�@�܂��A���Z���́AJ�DS�D�o�b�n�́u�~�T�ȃ��Z���v�ȍ~�A�u��r�ȏ@���S�v�Ƃ����F�����������Ă���Ƃ����Ă����B�����A�y�ȕ��͂����Ă݂�ƕK�����������Ƃ͌�������Ȃ����Ƃ�������B�u�~�T�ȃ��Z���v��27�Ȃ��琬�邪�A�咲�̃��Z����5�Ȃ����Ȃ��A�j������12�Ȃ��߂�B�u��r�ȏ@���S�v�Ƃ����F�����́A�ނ��땽�s�����ł���j�����̃L�����N�^�[���낤�B�܂��A�x�[�g�[���F�������Z�����u�������v�ƌĂ̂��L���Șb���B
�@���x�́A��������̂ɒu�������Ă݂悤�\�\����Ђ�́u�݂��ꔯ�v�̓C�Z���Őΐ삳���́u�V��z���v�̓��Z���ł���B�O�҂͙R���̒��ɐ����ȝR����h��A��҂̓��������Ɣ߂�����O���Q�����B���̂̐��E�����ʂ̑Δ�𐬂��Ă��Ėʔ����B�܂��A���[�c�@���g�E�C�Z���̖��ȁu�s�A�m�E�\�i�^K310�v�ɂ͍��i�ʂ̔߂��݂���������B
�@ �����ɂ͐F������H��
�@18���I�h�C�c�̉��y�w�҃V���[�o���g�i1739�|1791�j�́u���y���w�̗��O�v�́A�����̎����i�����߂ē����t�������Ƃ����Ă���B�����ɁA����ȓ��e�̕��͂�����B
���͐F�ʂ�������̂��F�ʂ̂Ȃ����̂��̂ǂ��炩�ł���B���^���ƊȌ����͐F�ʂ̂Ȃ����ŕ\�������B�@���̑O��ɂ́A�u�����̑������͐F�ʂ��Z���A���Ȃ����͔����v�Ƃ����x�[�X������B����ɏƍ�����ƁA��i�̕��͂́u���^���ƊȌ����͒����[���̒��ōō��x�ɕ\�������v�ƌ����ւ��邱�Ƃ��ł���B�����[���̒Z���̓C�Z���ł��邩��A�u�߂��݂��ł������肯�Ȃ��\���ł��钲���̓C�Z���ł���v�ƌ��_�ł���B
�@������ȑO�A�����̐��i�t�����������y�Ƃ���l����B��l�̓t�����X�̃}���N���A���g���[�k�E�V�����p���e�B�G�i1643�|1704�j�ŁA���Z�����ǓƂŃ������R���b�N�A�C�Z����D������߂�����\�����ƋK�肵�Ă���B������l�̓h�C�c�̃��n���E�}�b�e�]���i1681�|1764�j�ŁA���Z������قŕs���Ń������R���b�N�A�C�Z����Q���悤�ȕi�ʂ��闎�����������i�̒��ƋK�肵�Ă���B
�@ ���V���[�x���g�͒����ɕq���������H��
�@�����17�|8���I�̒������_���A��̍�ȉƂɂǂ�ȉe����^�������͔���Ȃ��B�����̐F�����ɕq���ȍ�ȉƂ������łȂ��l���������낤�B�����A���̂悤�Ȍ��������݂��Ă���Ƃ������Ƃ́A�X�Ɋ�����F�����͕ʂɂ��āA�����Ƃ������̂���ȉƂ̕\���ɂƂ��ď��Ȃ���ʈӖ������������Ă������Ƃ����͊m�����낤�B
�@�V���[�x���g�ɁA�s�A�m�E�\�i�^��7�ԕσz�����vD568�Ƃ����Ȃ�����B����́AD567�σj�����\�i�^�Ɋy�͂�������A�����ς����s�������̂ł���B���̍��͂������̈ꉹ�B�̋Ȃ���Ȃ�����̂���̉���͊W�Ȃ��B�V���[�x���g�̊����������������̂��B�ނ������ɕq���������Ƃ����A����͈�̏ł͂Ȃ����낤���B
�@�u4�̑����ȁvD899�̑�3�Ԃ͕σg�����ŁA��6������B�o�Ŏ҂̃n�X�����K�[���u�L����ʂ̐l�ɒe���Ă��炢�����̂ŁA��X������Ȃ��悤�Ɂv�ƒ��������ɂ��S�炸���B���ʓI�ɂ́A�n�X�����K�[�̈ӂ�����Ŕ����������̃g�����Ɉڒ����ďo�ł����̂����A���̎��Ⴉ����V���[�x���g�̒����ւ̂�����肪���Ď���B�V���[�x���g�́A�����ɂ͂��Ƃ̂ق��q���ȍ�ȉƂ������Ǝv����B
2011.02.25 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևR �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v12
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ ���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����3��
�i�U�j���n���E�~�q���G���E�t�H�[�O���Ƃ����j�@�ł́A���������n���E�~�q���G���E�t�H�[�O���i1768�|1840�j�ɓo�ꂵ�Ă��炨���B1794�N����1822�N�܂ŁA�E�B�[���{��̌�������̖��̎�Ƃ��ČN�ՁA�I�y���̐��E������ނ������Ƃ́A�ŔӔN�܂ŃR���T�[�g�̎�Ƃ��Ċ���𑱂����B�����̓n�C�E�o���g���B�V���[�x���g�Ƃ�1817�N�ɒm�荇���A�����ɂ��̍˔\��F�ߍ�i�̏Љ�ɐs�͂��A�l�I�ɂ��ɂ߂Đe���ȕt�������������B�t�H�[�O���́A�V���[�x���g�ɂƂ��āA���U��ʂ��Ă̂悫�����҂ł�����̕��e�Ƃ������ׂ����݂������B
�@�ł́A�t�H�[�O���ƃV���[�x���g�Ƃ̊W���A��ɂ���āu�V���[�x���g �F�l�����̉�z�v���炽�ǂ��Ă݂悤�B
���o��A�����ėǂ��p�[�g�i�[�Ɂ�
�@����̃��[�g�����������ʼn̂�Ȃ���Ȃ�Ȃ������V���[�x���g�́A�����Δނ̃��[�g�̂��߂̉̎�����o�������Ƃ����傫�ȗ~����\�����A�{��I�y���̎��t�H�[�O���ƒm�荇�������Ƃ����ނ̐̂���̊�]�͂܂��܂����������̂ƂȂ����B�\�\�����ʼn�X�̃O���[�v�ł͂Ȃ�Ƃ��V���[�x���g�̊�]�ɉ����悤�s�����悤�Ƃ������ƂɂȂ����B�t�H�[�O�����ƂĂ��l�t�������̈����l�������̂ŁA���̉ۑ�͍���Ȃ��̂ł��������A�{�쌀��Ɗ������̓`�肪�������V���[�o�[�����ɓ����A��l�̑Ζʂ����������B�@��l�̏o��́A1817�N�A�V���[�x���g20�t�H�[�O��49�̂Ƃ��ł������B�Ђ�{�쌀��̑�̎�ŁA�Ђ�삯�o���̍�ȉƁB���ΖʂŃt�H�[�O�����ォ��ڐ��������͎̂d���̂Ȃ��Ƃ��낾�낤�B�Ƃ��낪�V���[�x���g�̕��O�ꂽ�˔\���Ɋ��m�����t�H�[�O���́A���T�Ԍ�ɂ́u�����v�u�����炢�l�v�Ȃǐ��Ȃ����̏�ʼn̂��悤�ɂȂ��Ă����B���ꂩ��́A�㕔�I�[�X�g���A�ȂǑ����̔��\�̏��݂��Ȃ���A�V���[�x���g�̍ő�̗����҂ɂ��ĔM��Ȑ��q�҂ƂȂ��Ă������̂ł���B
�@���̓��A�t�H�[�O���͒x��Ă���Ă��āA�ǂ��܂����Ȃ��爥�A�����V���[�x���g�ɑ��A���炩�ɕs���ȑԓx���Ƃ����B�Ƃ��낪�y����n����̂��Ă݂��ނ́A�����ɑԓx��ς���B�����̃��[�g���ނɗ^������ۂ͈��|�I�Ȃ��̂ŁA���x�͑����ꂸ�ɔނ̂ق������X�̃O���[�v�ɋ߂Â��A�V���[�x���g������ɌĂ�ňꏏ�Ƀ��[�g����������悤�ɂȂ����B
�@�ނ̉̏�����X�ƃV���[�x���g���g�ƒ��O�̂�����l�X�ɗ^�����ˑ�Ȉ��|�I�Ȋ�����ڂɂ��āA�ގ��g�����̃��[�g�ɔ��Ɋ������A�ގ��g�V���[�x���g�̍ł��M��Ȑ��q�҂ɂȂ����B
�@���̎Ⴂ���y�ƂɍD�ӂ������l�X�Ȍ`�Ŏx������悤�ɂȂ����t�H�[�O���ɐ����āA�V���[�x���g�́A�V���^�C���[�A�����c�A�U���N�g�E�t���[���A���A�O�����f���A�K�V���^�C���Ȃǂ֍s���A�����̏ꏊ�ł��炵�����[�g�����t���ꂽ�B�i���[�[�t�E�t�H���E�V���p�E���j
�����̕��e��
�t�H�[�O���͈��̏@���I�Ȉ�̔O�������āA�V���[�x���g�̒��̒��a�̐��_�A���t�ɑ���[�����o�A���y�̗͂����m���Ă��܂����B�V���[�x���g�̂��̂��炵���f���������ĉ�Ȃ��������ƁA���R�̍ł����₩�ȓ����������邷�ׂẲ��y���߂����ʂ��ǂ�Ȍy�͂��݂ȕ��ɂ���Ă��������ꂸ�A�܂�Ȃ����h���N�����Ȃ��������Ɓ\�\����͂����炭�{���I�ɃV���[�x���g�̃t�H�[�O���Ƃ̌�F�̌��ʂł���A����̃V���[�x���g�ɂ��ĉ��炩�̋L�q���������ꍇ�A�t�H�[�O���ɏd�v�Ȉʒu���^�����ē��R�Ȃ̂ł��B�t�H�[�O���̓V���[�x���g�̕��̂悤�ȗF�l�ł����B�i�A���g�[���E�V���^�C���r���[�q�F���j�@�t�H�[�O���́A���y�ƂƂ��ėD�G�ł���������łȂ��A�Ñ�M���V����[�}�̌ÓT��@���ȂǍL�͂ɂ킽��m����g�ɂ������{�l�������B����Ȉ̑�Ȑl�Ԃ��V���[�x���g�̂悫�����҂ƂȂ�A���y�ʂ̑��k����ƂȂ�A���{�ʂƌo�ϖʂ����x���Ă��ꂽ�̂ł���B�V���[�x���g�͂ǂ�Ȃɂ��S�����������Ƃ��낤�B�܂������̕��e�ɑ����������݂������B
1819�N�������Ǝv�����A�V���[�x���g�͂���Ɉ�w���R�ʼn��K�Ȑ������o����悤�ɂȂ����B���̂��߂ɑ傫�ȍv�����ʂ������t�H�[�Q���͔ނ̑��̕��e�Ƃ����Ă����ł��낤�B�ނ͌o�ϓI�ɃV���[�x���g�̖ʓ|����������łȂ��A���_�I�|�p�I�ɂ����۔ނ�i���������̂ł���B�i���[�n���E�}�C�A�[�z�[�t�@�[�j
�@ ����l�̉��y�I�W��
1821�N3��7���A�{�쌀��Ńt�H�[�O���ɂ���āu�����v���̂��劅�т��܂������A�����O�̃��n�[�T���ł̂��ƁB�V���[�x���g���t�H�[�O���̗v���ɏ]�����Ƃ���ǂ���s�A�m���t�ɐ����ߑ}�����A�̎肪�x�����Ƃ�@���]�v�Ɏ��Ă�悤�ɂ��܂����B�i�A���[�����E�q�F�b�e���u�����i�[�j�@�ȏ�̋L�q����A�V���[�x���g�́A�̋Ȃ̑n��ɂ����āA�t�H�[�O���̈ӌ��������炸�Ɏ���Ă������Ƃ�����B���̂����ɂ��āA�t�H�[�O���̒�q��"���Ŏ��ꂽ"�Ƃ����A�F�l��"�e�����_��"�Ƃ����A�e�X�̉��x�����ʔ����B�܂��A�j���p�̋Ȃ̍�Ȃɂ����āA�t�H�[�O���̉����z�肵�Ă������낤���Ƃ��e�Ղɑz���ł���B
�V���[�x���g�̉̋ȍ�i�́A�قƂ�ǃt�H�[�O���搶�ɖڂ�ʂ��Ă�����Ă���A�����Ȃ�����ɂƂĂ����Ŏ��ꂽ���̂ł��B�i�J�����E�t�H���E�V�F�[���V���^�C���j�݁j
>
�u�����炢�l�v�u��҃N���m�X�Ɂv�E�E�E�Ȃǂ́A���y�I����̏��i�ł���A�t�H�[�O�����̂����߂ɍ��ꂽ���̂悤�ł������B���̏n�B�����A���ʂ�S�����̎肪�����čs���������ȕύX����͕����I�ɂ���Ȏ҂̓��ӂ��l���������A�e�����_���̎�ƂȂ邱�Ƃ��������͂Ȃ������B�i�G�[�h�D�A���g�E�o�E�G�����t�F���g�j
�V���[�x���g��������̒��A���Ȃ��̃��[�g�������āA���{���Ă��炢�ɁA�t�H�[�O����K��܂����B���̂Ƃ��t�H�[�O���͂ƂĂ��Z�����������߁A�V���[�x���g�͊y����a���ċA��܂����B���̔����قǂ��ƁA�V���[�x���g�͍ēx�t�H�[�O�����K��܂����B���̂Ƃ��A�a�������̈�Ȃ��A�t�H�[�O���������̐���ɍ����悤�ɒႢ���Ɉڒ����������߁A�ʕ��҂̕M�Ղŏ����ʂ�������܂����B����̓t�H�[�O�����g�����Ɍ���Ă��ꂽ���Ƃł��B�i�J�����E�t�H���E�V�F�[���V���^�C���j�݁j�@���̃V�F�[���V���^�C���j�݂̋L�q�͒��ڂɒl����B��������́A�V���[�x���g�̉̋Ȃ��t�H�[�O���������̐���ɍ����悤�Ɉڒ����A�ʕ����ɏ������Ă��������������яオ���Ă���B
�@����ȓ�l�̊W�́A�V���p�E���̏،��ɂ�����Ƃ���A�V���[�x���g�̎�����l���܂ő������̂ł���B
��l�̉��y�Ƃ̌��ѕt���́A�����������܂��܂��܂����ڂɂȂ����ł��������A����͔ނ炪�₦���ꏏ�ɉ���Ă������ʂł������B�i���[�[�t�E�t�H���E�V���p�E���j���u�~�̗��v�ƃt�H�[�O����
�@�V���[�x���g�̐e�F�V���p�E���́A1827�N�̏t�A������������́u�~�̗��v��ꕔ���A�F�l�����Ƌ��ɃV���[�x���g���g�̉S�Œ��������A�]��̈Â��ɓ��f���Ă��܂��B�������ɂƂ��Ă���ނ�������ăV���[�x���g�͌������B�u�l�͂��̃��[�g�W���ǂ�ɂ��܂��ċC�ɓ����Ă���B�����ꂫ�݂����ɂ��C�ɓ����Ă��炦�邾�낤�v�ƁB����ɑ��ăV���p�E���́A�u�ނ͐����������B�����܂���X�́A�t�H�[�O���������ɉ̂����̉A�S�ȃ��[�g�W�̈�ۂɖ����ɂȂ��Ă��܂����̂ł���\�\����ȏシ�炵���h�C�c�ꃊ�[�g�͂����炭�Ȃ����Ƃł��낤�B�����Ă��ꂱ���ނ�"�����̉�"�������̂ł���v�Əq�ׂĂ���B
�@�V���p�E���͕ʂ̒���ł������q�ׂĂ���B�u���̈�N�O�ɂ����̍��M�ȘV�l�́A�{���ږ⊯�G���f���X�@�ł̏W�܂�ŁA����ӘA��̋ȏW�u�~�̗��v�S�Ȃ��܂������̂��A���͋ɂ߂Ď�܂��Ă������A�ꓯ�S�����[�������ɏP��ꂽ�̂ł������B���ꂪ�ނ̍Ō�̉̂ł������v�E�E�E�E�E�t�H�[�O���́A�u�~�̗��v���������A�ȗ��A�S���Ȃ钼�O�܂ʼn̂������Ă������ƂɂȂ�B���̂Ƃ��t�H�[�O����71�B"������܂��Ă���"�͓̂��R�̂��ƁB�}���C�E�y���C�A�Ƌ��������t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�Ō�́u�~�̗��v��65�̂Ƃ��̘^�������A���̂��ƂƔ�r���Ă��A�t�H�[�O��71�̉̏������O�Ɋ�����^�����̂͋��ٓI�ȏo�����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ă��ꂪ�ނ̐l���Ō�̉̂ƂȂ����B�t�H�[�O�������u�~�̗��v�̍ŏ��ɂ��čō��̓`���҂������̂ł���B
�@�t�H�[�O���́A���̗��N1840�N11��19���A���̋P���������U������B���̓��͊�����V���[�x���g�̖����ł������B
���t�H�[�O���Ɓu�҉��y�t�v�̈ڒ���
�@���݁A"�u�҉��y�t�v���ڒ������̂̓n�X�����K�[�̈ӎv�ł���"�Ƃ����̂�����ƂȂ��Ă��邪�A����"�n�X�����K�[�̕M�Ղɂ��u�C�Z���ցv"�Ƃ�����������̕��������ł���B�Ƃ��낪���x�������Ă����悤�ɁA�n�X�����K�[�ɂ͂��̓��@���Ȃ��̂ł���B�ł́A�t�H�[�O���͂ǂ��Ȃ̂��낤���H
�@�V���[�x���g���̋Ȃ̑n��ɂ����ăt�H�[�O���̒���������Ă��������A�t�H�[�O���́u�~�̗��v�ւ̕��O�ꂽ�v������A�ӔN�̐��̐����ɂ�鉹��̏k�����i�V���[�x���g�̗F�l�����ɂ��،������X����j�A�V���[�x���g��i������ʕ����Ɉڒ������Ă��������A�V���[�x���g�̎��܂ő������e���ȊW�E�E�E�E�E�����̎������ӂ݂�A�t�H�[�O�����u�҉��y�t�v�̈ڒ��Ɋւ���Ă���ƍl���Ă��A���Ȃ����s���R�ł͂Ȃ����낤�B���������A�����ł��n�X�����K�[�̏ꍇ�Ɠ������R�œ��@���Ȃ̂��B
�@�̎肪��Ȏ҂̏����������������������Ƃ̗��R��"������������"�Ƃ������Ƃɐs����B�m���Ɂu�҉��y�t�v���Z�����̍ō����f5��60�̃o���g���̎�ɂ͂������낤�B�Ƃ��낪�AG5�Ƃ���ȏ�̍����́u�~�̗��v�ɂ͐��������݂���B�u�����̊��v�u�X���v�u��̏�Łv�u������݂āv�u�S�v�u�x���v�u�X�֔n�ԁv�u�Ō�̊�]�v�u������ׁv�ȂǁA����͌����ď����������ł͂Ȃ��B���Ɂu�X�֔n�ԁv�̃��X�g�ł́AG5��蔼������A��5�̉���2�����������B�����������u���āA�u�҉��y�t�v��G5������������̂͂ǂ��l���Ă��D�ɗ����Ȃ��B��͂�A�t�H�[�O���ɂ��u�҉��y�t�v���ڒ����铮�@�͂Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��̂ł���B
�@�t�H�[�O���Ɋւ���L�q�́A�V���[�x���g�̗F�l�����ɂ���Ă��Ȃ�̗ʂ��c����Ă��邪�A�{�l�̎�ɂȂ���̂͊F���ɓ������B�����ގ��g�̕��͂��c����Ă����Ȃ�A�u�҉��y�t�v�ڒ��̓�Ɋւ��āA���j�S�I�Ȏ����������яオ������������Ȃ��B������v���Ɣ��Ɏc�O�ł���B
2011.02.15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևQ �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v11
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ ���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����2��
�i�T�j�V���[�x���g�ƃn�X�����K�[�@�u�~�̗��v�̍ŏI�ȁu�҉��y�t�v�̒��������Z���ɂȂ����̂́A��ꕔ�̍ŏI�ȁu�ǓƁv���j�Z�����烍�Z���ɕς��A����ɍ��킹�����߂Ƃ����Ă���B�ς����̂̓V���[�x���g���g�Ȃ̂����A�ЂƂ܂��́u�ǓƁv�̒����ύX�̗��R��T���Ă������B�Ȃ������邩�Ƃ����A�������ĉ̂��Â炢����ɐs����B�u�ǓƁv�̃j�Z�����ł̍ō���A5�́A�m���Ƀo���g���ɂ͍�������i�Ȃ��o���g�����Ƃ����A�V���[�x���g���z�肵���̂̓o���g���ɈႢ�Ȃ��Ǝv���邩�炾���A���̌��͎���ȍ~�Ɂj�B���̑��̊y�Ȃ�A5���g���Ă���̂́A��V�ȁu��̏�Łv�̈ꉹ���̂݁B�ł́A�Ȃ��u�ǓƁv���������āu��̏�Łv�̓\�m�}�}�������̂��H�u�ǓƁv�ł́A��x�J��Ԃ����elend�i�S�߂ȁj�Ƃ����d�v�x���̌��t��A5��8���������Ƃ܂��Ă���B����ɑ��A�u��̏�Łv�ł́Aso��o������16�������ŏ���Ă��邾���B����Ȃ瑽�������Ă��̂�����邾�낤�B���炩�Ɂu�ǓƁv��A5�̂ق����Ӗ��͏d���B���������āA�V���[�x���g�́u�ǓƁv��A5���ɔz�����Ĉڒ��������̂Ǝv����B�iA5�Ƃ����̂͌ܐ�����̏�����̉��B����2���オC6�ŁA�����Ƃ���̃n�CC�ł���j
 �@���āA���́u�҉��y�t�v�̃��Z������̈ڒ��ł���B���Z���ł̍ō�����G5�ł���B���̒��x�̍����́u�~�̗��v�̒��ɂ͂����������̂�����A�i�C�Z���Ɂj������ׂ����R�͂Ȃ��͂��ł���B�n�X�����K�[���ς������R�́A"�̂��₷�����Ċy������葽�����邽��"�Ƃ��������ǂ����ŕ������o�������邪�A����ɂ͓���Ȃ����Ƃ��킩�邾�낤�B�������A����ȊO�Ƀn�X�����K�[���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�������Ƃ��Ȃ����A�����g���S���l�����Ȃ��B�����u�n�X�����K�[�ɓ��@�͂Ȃ��v�Ƃ���̂͂��̂��߂ł���B
�ȏ�A���߂āu�n�X�����K�[�����Z������C�Z���Ɉڒ������闝�R���Ȃ��v�ƋK��ł������A���̂��Ƃ́A�n�X�����K�[�ƃV���[�x���g�̊W��H���Ă݂����B���Â������邩�ǂ����A���M�͂Ȃ�����ǁB
�@���āA���́u�҉��y�t�v�̃��Z������̈ڒ��ł���B���Z���ł̍ō�����G5�ł���B���̒��x�̍����́u�~�̗��v�̒��ɂ͂����������̂�����A�i�C�Z���Ɂj������ׂ����R�͂Ȃ��͂��ł���B�n�X�����K�[���ς������R�́A"�̂��₷�����Ċy������葽�����邽��"�Ƃ��������ǂ����ŕ������o�������邪�A����ɂ͓���Ȃ����Ƃ��킩�邾�낤�B�������A����ȊO�Ƀn�X�����K�[���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�������Ƃ��Ȃ����A�����g���S���l�����Ȃ��B�����u�n�X�����K�[�ɓ��@�͂Ȃ��v�Ƃ���̂͂��̂��߂ł���B
�ȏ�A���߂āu�n�X�����K�[�����Z������C�Z���Ɉڒ������闝�R���Ȃ��v�ƋK��ł������A���̂��Ƃ́A�n�X�����K�[�ƃV���[�x���g�̊W��H���Ă݂����B���Â������邩�ǂ����A���M�͂Ȃ�����ǁB�@�g�r�[�A�X�E�n�X�����K�[�i1778�|1842�j�́A�����c�ɐ��܂�A1810�N�ɃE�B�[���ɏo�āA�W�[�N�����g�E�A���g���E�V���^�C�i�[�̌o�c����y���o�ʼn�Ђł��鉻�w�o�ŎЁi���S�DA�D�V���^�C�i�[�ЂƉ����j�ɏA�E�����B���̌�A1826�N�A�V���^�C�i�[���ތ�A�Ж����u�n�X�����K�[�Ёv�ɕύX���A���ׂĂ̋Ɩ��������p�����B �����ŁA�V���[�x���g�ƃn�X�����K�[�Ɋւ���L�q���A�����ǂ��Ĕ��������Ȃ���l�@�������B�����́A�I�b�g�[�E�G�[���q�E�h�C�b�`���Ҏ[�́u�V���[�x���g �F�l�����̉�z�v�i�Έ�s��Y�� �����Ёj�����S�ł���B
���u�����v�̏o�ł������ā�
���́u�����v���g�r�[�A�X�E�n�X�����K�[�ƃA���g�[���E�f�B�A�x�b���Ɍ����܂������A��l�Ƃ���ȉƂ������ł���s�A�m���t������̂ŏ\���Ȑ��������҂ł��Ȃ��Ƃ��āA�o�ł��i��łȂ��Ƃ������Ƃł����j���ۂ��܂����B���̋���ɏ������āA�������̓V���[�x���g���g�̔�p���S�Ƃ����`�ŏo�ł��s�����S�������̂ł��B�i���[�I�|���g�E�t�H���E�]�����C�g�i�[�̎莆���j�@��L2�ʂ�1821�\1822�N�̂��̂ŁA���炭����炪�n�X�����K�[�ɓZ���ŏ��̋L�^���낤�B���̎���̃n�X�����K�[�́A�V���^�C�i�[�̉���10���N�̃L�����A��ς�ł������ł���B�Ώۊy�Ȃ́u�����v�B�V���[�x���g�̗F�l�������A���̑匆����Ȃ�Ƃ����ʂɔ��荞�����Ƃ����ɂ��S�炸�A�o�ŋƎ҂����́A��i�̉��l�������ł����i���邢�͂ł��Ȃ��U������āj�A����ɂ܂�Ȃ��d�ł����������Ƃ��悭�킩��B���ʁA�u�����v�́A(����11�ȂƋ���)��Ȏ҂̌o��S�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ��`�ŏo�ł��ꂽ�̂ł���B�o�ŎЂ̓J�b�s�E�E���g�E�f�B�A�x�b���ЂŁA�n�X�����K�[��S�DA�D�V���^�C�i�[�Ђ͎��Д��s�̐V���ɔ�]���ڂ����Ƃ����W�Ɏ~�܂��Ă���B�������A�n�X�����K�[�̓q���b�e���u�����i�[��n���Ă�肷��ȂǁA�V���[�x���g�w�c�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ��ǍD�ȊW�Ƃ͂����Ȃ������悤���B
�u�����v�́A�܂�1821�N4��2���t�́u�E�B�[���V���v�ɁA�J�b�s�E�E���g�E�f�B�A�x�b���Ђ���o�ł��ꂽ�|�L�����o�Ă��܂��B�L���͎������M�������̂ł��B�܂��A�u�U�����[�v���̐��E�L���������������܂����B�V���[�x���g�ɂ���ă��[�g�ɂ�������̃��[�c�@���g���a�������Ƃ����l�����q�ׂ����ƂŁA���͌������U���𗁂сA�n�X�����K�[�ƃV���^�C�i�[����͔n�����ƌ��ߕt�����܂����B�i���[�[�t�E�q���b�e���u�����i�[�̎莆���j
1822�N�ɂ̓V���[�x���g�̃��[�g�̂��悢�����̂��߂ɗ��h�Ȋ�����ŏ��̔�]���o���B����̓V���^�C�i�[�o�ŎЂ��甭�s����Ă���u��ʉ��y�V���v�̑�6���̂��Ƃł���B�i�ҎҁE�h�C�b�`���̒��j
���n�X�����K�[�̈�{������
�V���[�x���g��1827�N�ɂȂ��āA�V���^�C�i�[�̋��͎҂Ō�p�҂��g�r�[�A�X�E�n�X�����K�[�Ɛe�����ڐG����悤�ɂȂ����B�i�V���h���[�̎莆�ւ̕ҎҒ��j�@�n�X�����K�[�́A1826�N�A�V���^�C�i�[�̈��ނɔ������ׂĂ̋Ɩ��������p�����B�����āA��\�Ƃ��ď��X�ɗ͗ʂ����Ă䂭�B�V���[�x���g�Ƃ̊W���[�܂��āA�����y�Ȃ������Ă������B�n�X�����K�[�͑�Ȋy�����V���[�x���g�ɑ݂��A�V���[�x���g�͎��M�����n�X�����K�[�ɑݗ^���Ă���B�u�����v�̍��̃M�N�V���N�Ƃ����W���A�m���ɍD�]�����l�q���M����B�����Ȃ����̂́A�V���[�x���g�Ƃ͌��X"�l�I�ɂ�"�����Ȃ��ԕ����������炩������Ȃ����A�����łȂ��Ă��A�y�����Ƃ��Ă����܂ł̂��オ���Ă����V�^�^�J�j�ɂƂ��āA���Ԓm�炸�̂��l�D����ȉƂɎ����邱�ƂȂǂ͐Ԏq�̎��P��悤�Ȃ��̂������ƍl���Ă��A�ʒi�����Ȑ��ʂł͂Ȃ����낤�B
�w���f���̃I���g���I�̑����Ƃ����̂́A���炩�ɃT�~���G���E�A�[�m���h��1790�N�������h���ŕҎ[�o�ł����łŁA������x�[�g�[���F�������̒��O�Ɉꑵ��������肵�Ă���B��ɃW���[�R���E�}�C�A�[�x�[�A�̏��L�ɋA�����������g�r�[�A�X�E�n�X�����K�[���V���[�x���g�ɑ݂��Ă����Ƃ������Ƃ��l������B�i����j
�@�n�X�����K�[�ЂɂƂ��ẴV���[�x���g�̏��o�Ŋ�y�Ȃ́A1827�N�́u����ȃ����c�vD969�ŁA�y���͌��\���ꂽ�炵���B���́u�s�A�m�E�\�i�^��18�ԃg�����vD894�ŁA����ɂ́u���z�v�Ƃ������肪�t���Ă��邪�A����̓n�X�����K�[���V���[�x���g�Ɍ����Ă������́B���"�����"�̌`�e�Ƃ����A�w�������Ċy����A�ǂ����Ē��X�̏����l�ł���i���݂Ɂu�~�̗��v�ɑ����u�����̉́v���A�ނ��Ҏ[�E�����������̂ł���j�B �@����ɁA�V���[�x���g�́u�S�̑����ȁvD899�̏o�ł��n�X�����K�[�Ɉ˗�����B�������܂ꂽ�y���������n�X�����K�[�́A�u�`����P���ɁA�Z�I�I�ɂ����ƈՂ����A�����ƍ�荞��Łv�ȂǂƁA�Ȃ��Ƃɂ��Ȃ�˂�������������B���_�A������߂ɁB�����āA�V���[�x���g�͂��̎w���ɏ]���ď��������A���ʁA�l�C�s�A�m�Ȃ��a�������Ƃ����Ă���i���{�G�s����Web-Site���j�B��l�̊Ԃɐe���ȘA�ъ��ƌ����M���W���z���ꂽ���Ƃ��M����G�s�\�[�h���B�����œ��M���ׂ��́A��3�ԕσg�������g�����Ɉڒ�����ďo�ł��ꂽ�����ł���B���̈ꌏ���A�u�҉��y�t�v�̈ڒ��̓n�X�����K�[���s�����Ƃ���鍪���̈���Ƃ��v�����A�ʂ����Ăǂ��Ȃ̂��H �ۂł���B��6�̕σg�����̓n�X�����K�[�̌ڋq�ɂƂ��ē������͖̂��炩�ŁA�����Ⴂ���̃g�����ւ̈ڒ��́A�y���̔��㑝�ɏ��Ȃ��炸�v�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B���̕ύX�͑����A��3�Ԃ���n�ɕς�邱�ƂȂ̂ŁA��n�ł��鑼��3�Ȃ��璲���I�ɗV�����邱�ƂɂȂ�A�V���[�x���g�ɂƂ��Ă͕s�{�ӂ������낤���A�ނ��e�F����C�������\�������ł���̂ł���B�u4�̑����ȁv�̈ڒ��ɂ͓��@�����邪�A�u�҉��y�t�v�ɂ͂Ȃ��̂ł���B
���u�~�̗��v�ƃn�X�����K�[��
�����i1828�N�j�V���[�x���g�Ƃ����ꏏ�ɂ������Ԃ̃t�����c�E���b�n�i�[�����M�҂Ɍ�����Ƃ���ɂ��ƁA�ނ͉̋ȏW�u�~�̗��v�̒���6�Ȃ��n�X�����K�[�̂Ƃ���֎����čs���A�U�O���e�������A�����\�\�����P�O���e����1�t�����̉��l���������B���̐S���҂����Ɏ�芪���ꂽ�ނɉ�ƁA���Ζʂ̐l�ł��ނ̗F�l�������l���f����Ă��܂��̂ł������B�i�T�[�E�W���[�W�E�O���E���̎莆���j�@�T�[�E�W���[�W�E�O���E�����A�莆�̒��ŁA�n�X�����K�[���V���[�x���g�̐S���҂̈�l�Ƃ��Ă���͓̂��M�����B�V���[�x���g����芪���o�ŎЂ́A�����Ȃׂċt���I���͂Ƃ��Ĉ����Ă��邪�A����Ȓ��ɂ����āA����͎��ɋ����[���L�q�ł���B�܂��A�F�l�̃��b�n�i�[���V���[�x���g�̈ӌ����āu�~�̗��v�̊y�Ȃ�蔄�肵�����Ƃɑ��A�Ҏ҂̃h�C�b�`�����A�u����Ȉ������z�Ƃ͐M���������v�Ƃ����Ă���̂������[���B�h�C�b�`���̓n�X�����K�[���A"�V���[�x���g�̍�i�ɓK�ȑΉ����x�����܂Ƃ��ȏo�Ŏ�"�ƌ��Ă���̂ł���B
�g�r�[�A�X�E�n�X�����K�[���u�~�̗��v�̊e���[�g�ɂP�O���e���������x����Ȃ������Ƃ������Ƃ́A�M���������B�ނ͓����N�Ƀt�F���f�B�i���g�i�V���[�x���g�̌Z�j�ɁA������u�����̉́v��13�Ȃ̈�샊�[�g�̑Ή��Ƃ���210�t���[�����x�����Ă���B�i��L�ɑ���ҎҒ��j
�i�V���[�x���g�́j1828�N11��11���ɂ͏��ɂ���������Ȃ��Ȃ����B�댯�ȕa��ɂȂ��Ă����ɂ�������炸�A�ނ͋�ɂ������邱�Ƃ͂Ȃ��A�������E���݂̂�i���Ă����B�₦���ނ͉̂���������ł������A���܂��킲�Ƃ�������ԂɂȂ邱�Ƃ��������B���邢�킸���Ȏ��Ԃ��g���āA�ނ͂܂��u�~�̗��v��̍Z�������Ă����B�i���[�[�t�E�t�H���E�V���p�E���̎莆���j
�@�����āA���Ƃ����Ă��V���p�E���̎莆�ł���B�V���[�x���g���Ō�܂Ō���葱�����^�̗F�l�ł���ނ̏،��ɂ͑傢�ɐ^����������B
�@�V���[�x���g���̔N�A1828�N�ɂ́A�����ȑ�8�ԃn����D944�i���M�����j�A�R�̃s�A�m��D946�A���y�d�t�ȃn����D956�A�~�T�ȑ�6�ԕσz����D950�A�s�A�m�E�\�i�^��19�ԃn�Z��D958�A��20�ԃC����D959�A��21�ԕσ�����D960�A�̋ȏW�u�����̉́vD957�Ȃǚ삵�����̌��삪������Ă���B����Ȓ��ŁA�Ō�̍Ō�܂Ŏ�����Ă����̂��u�~�̗��v�������̂ł���B�V���[�x���g���u�~�̗��v��̐����e���n�X�����K�[�ɓn�����̂�9��25���������B�n�������Ƃ��S���Ȃ�11��19�����肬��܂ŁA�ނ͍Ō�̐��͂����̍Z���ɔ�₵�Ă����̂ł���B�܂�ŁA������킪�q�Ɉ⌾���c���悤�ɁB
2011.02.05 (�y) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևP �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v10
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ ���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����1��
�i�P�j�u�҉��y�t�v�̒����ɂ������� �@�u�~�̗��v��24�ȁu�҉��y�t�v Der Leiermann �́A�ٗl�Ȃ܂łɐ[���A�s�v�c�Ȗ��͂�X�����y�Ȃł���B�u�~�̗��v�̍Ō�Ɉʒu�������̋Ȃ̒��ŁA��l���̎�҂͏��߂Đ��g�̐l�Ԃɏo��B"���y�t"�ȂǂƂ������A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ���H����C�A�[�i�n�[�f�B�K�[�f�B�j�e���ł���B�X�̏�𗇑��ł��߂��悤�ɕ����Ă���B���C�A�[�̉��͖�~�ނ��Ƃ͂Ȃ����A�����Ȗ~�͋�̂܂܂��B�������͖̂�nj������B��҂́A�ނɌ������Ęb��������A�u�s�v�c�Ȍ�V�l �l�̉̂ɍ��킹�ă��C�A�[���Ă��������܂����v�ƁB���̑䎌�����A��]�I�ȁu�~�̗��v�̍Ō�Ɏ�҂����������t�ł���A�݂��ڂ炵���҉��y�t�����A����ʂ��Ċւ�����B��̐l�ԂȂ̂ł���B
�@�u�~�̗��v��24�ȁu�҉��y�t�v Der Leiermann �́A�ٗl�Ȃ܂łɐ[���A�s�v�c�Ȗ��͂�X�����y�Ȃł���B�u�~�̗��v�̍Ō�Ɉʒu�������̋Ȃ̒��ŁA��l���̎�҂͏��߂Đ��g�̐l�Ԃɏo��B"���y�t"�ȂǂƂ������A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ���H����C�A�[�i�n�[�f�B�K�[�f�B�j�e���ł���B�X�̏�𗇑��ł��߂��悤�ɕ����Ă���B���C�A�[�̉��͖�~�ނ��Ƃ͂Ȃ����A�����Ȗ~�͋�̂܂܂��B�������͖̂�nj������B��҂́A�ނɌ������Ęb��������A�u�s�v�c�Ȍ�V�l �l�̉̂ɍ��킹�ă��C�A�[���Ă��������܂����v�ƁB���̑䎌�����A��]�I�ȁu�~�̗��v�̍Ō�Ɏ�҂����������t�ł���A�݂��ڂ炵���҉��y�t�����A����ʂ��Ċւ�����B��̐l�ԂȂ̂ł���B�@�n�Ӕ��ގq���u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v�̒��ɁA�u�҉��y�t�v�̒����Ɋւ��邱��ȋL�q������B
�i�u�҉��y�t�v���j�V���|�x���g�́A���̂悤�Ƀ��Z���ō�Ȃ��A�O�t�ɕ��O�ʼn����g�p���Ă����B�����������̉E��̕��ɁA�o�Ŏ҃n�X�����K�[�̎菑���ŁA�傫���u�C�Z���Ɂvin a-mol�Ə�����Ă���A�o�ŕ��̓C�Z���Ɉڒ����ꂽ�B�O�ʼn��͊e�ŏ��̂P�������L����Ă���B�E�E�E�����E�E�E�u�҉��y�t�v�́A�n�X�����K�[�ɂ��C�Z���ւ̈ڒ������肳�ꂽ�̂ł���B�@����́u�҉��y�t�v�̒����Ɋւ���j�S�I�ȋL�q�ł���B���p�����u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v�͓n�ӎ��̔��m�_���ŁA���̃X�g�C�b�N�Ȃ܂łɍ��x�Ȏ��ؐ��Ɖs�����@�͂́A�i�����镶�͂Ƒ��܂��āA�{����䌨������̂Ȃ����݂ɉ����グ�Ă���B���̕����A���̒��҂̋L�q���A���e�I�ɂ́A�哯���ق��B��̗�Ƃ��āA�~�Î���Ò��u�~�̗��`24�̏ے��̐X�ցv�����p���Ă������B
��Ɍ����悤�ɃG���}�[�E�u�b�f�̌����ɂ���āA��e�����珉�łւ̕ύX���V���[�x���g���g�̎�ɂ����̂��A�o�Ŏ҂̃n�X�����K�[�̎�ɂȂ���̂��A�����ɕ������Ă���B�u�҉��y�t�v���C�Z���ɕύX�����̂̓n�X�����K�[�ł���A�V���[�x���g�̈ӎv�ł͂Ȃ��B�@��l�̋L�q�̒��ɁA�y���Ɋւ��āA"������""�o�ŕ�""��e��""����"�ȂǁA�l�X�ȌĂѕ�������̂ŁA�ЂƂ܂��������Ă��������B
�@�u�~�̗��v�ɂ͊���̊y�������݂���B�܂��A�V���[�x���g���g���������y���ł�������M���ƌĂԁB���M���ɂ͏��e�Ɛ����e������B���e�́A�����ʂ�ŏ��̌��e�ł���ɂ͑����̏������݂��Ȃ���Ă���B�����e�͏o�ŎЂɓn�����߂ɖ{�l�������������e�ł���B���e�Ŏc���Ă�����̂́A1�u���₷�݁v�A8�u������݂āv�A12�u�ǓƁv��������ꕔ�y��9�Ȃ݂̂ŁA���12�Ȃ͐����e�����c���Ă��Ȃ��B���Ƃ͎��ۂɏo�ł��ꂽ�o�ŕ�������A��ꕔ��1828�N1���ɁA��͓��N12�����A��ꕔ�ƍ��킹���`�ŏo�ł���Ă��邪�A��ꕔ��̏o�ŕ��ɂ́A�����܂ߎ�̈Ⴂ������B�E�E�E�Ȍ�A���̌ď̂ɓ��ꂵ�ďq�ׂĂ䂫�����B�i�u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v���Q�Ɓj
�@�ȏ�̍l�@����u�҉��y�t�v�̒����ɂ��Ă̒�����A���̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B
�V���[�x���g���u���Z���v�Ɍ��߂��u�҉��y�t�v�̒����́A�o�Ŏ҂̃n�X�����K�[�ɂ���āu�C�Z���v�ɕς���ꂽ
�@���̐��̍����́A"�����e�Ɂu�C�Z���Ɂv�Ə������M�Ղ̓n�X�����K�[�̂��̂ł���"�Ƃ������Ƃ����ł���B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA"�n�X�����K�[�̓��@"�ɂ��ẮA�[���䂭���̂��������������Ƃ��Ȃ��B�ɂ�������炸�A�Ƃɂ������ɂ��A���ꂪ����ƂȂ��Ă���̂ł���B
�i�Q�j�u�N�����m�v�I�l�@
�@ �@�������̐��ɑS�ʓI�Ɏ^���ł��Ȃ��̂́A�n�X�����K�[�ɓ��@����������Ȃ�����ł���B�����e�ɂ̓V���[�x���g���g�̏������݂ƃn�X�����K�[�̂��̂����݂��Ă���B���҂̎��ʂ͕M�ՊӒ肩��e�Ղɉ\���낤���A���́A���������Ŏ~�܂��Ă��邱�Ƃ��B�V���[�x���g�̎菑���ɂ����͔̂ނ̈ӎv�����A�n�X�����K�[�̎�ɂ����̂̓V���[�x���g�̈ӎv�ł͂Ȃ��A�Ƃ������_���o���āB
�@�m���Ȃ��Ƃ͗B��Ain a-mol�i�C�Z���ցj�̕M�Ղ̓n�X�����K�[�̂��́A�Ƃ������Ƃ����ł���B���ꂾ���̂��ƂŁA"�n�X�����K�[�̈ӎv"�ƌ��ߕt����̂́A�Z���I�߂��͂��Ȃ����H �n�X�����K�[�Ɋm�łƂ������@����������Ȃ��ȏ�A�ύX�̓n�X�����K�[�̈ӎv�ł͂Ȃ��\��������A�Ǝ��͍l����B�ł͒N�̈ӎv�Ȃ̂��H�V���[�x���g���A����Ƃ��E�E�E�B�����A���@�T��̗��ɂ��t�������������������B
�i�R�j�V���[�x���g���A�u�҉��y�t�v���A�܂��̓��Z���Ɍ��肵���o��
�@�V���[�x���g�́A1828�N9��25���A�F�l���n���E�o�v�e�B�X�g�E�C�F���K�[�Ɉ��Ă��莆�̒��Łu�w�~�̗��x�̑�́A�������łɃn�X�����K�[�ɓn�����E�E�E�v�Ə����Ă���B����2�����قǑO�̂��Ƃ��B��ꕔ�̐����e��1827�N10���Ɋ������Ă��邪�A���̍��ɂ͑�̍�Ȃ͏I����Ă����悤���B���������āu��v�����e�̊����ɂ�10�����ȏ����₵�����ƂɂȂ�B�u�҉��y�t�v�̒����͂��̉ߒ��̒��Ō��肵�Ă������̂ł���B
�@�����̕ύX�Ƃ����ϓ_����A��ꕔ�Ŗ��ƂȂ�̂́A10�u�x���v��12�u�ǓƁv�ł���B�����͎��M���ł͗����Ƃ��j�Z���ŏ�����Ă����B�n�Ӕ��ގq���́A������1�u���₷�݁v�i�j�Z���j�Ɠ���ɂ��邱�ƂŁA�u�~�̖�̗������v�u�Y�Ă��l�̉Ƃł̋x���v�u�X���ł̑a�O�ƌǓƁv�Ƃ��������I������e�ɋ������т���^���邽�߁A�Ƃ́i���̎��_�ɂ�����j�����������Ă���B�Ƃ��낪�V���[�x���g�͍ŏI�I�ɁA10�u�x���v���n�Z���ɁA12�u�ǓƁv�����Z���ɕς����B����ɂ��ẮA�n�ӎ��́A�u��ꕔ�̏o�ł�O�ɂ������ɂ́A���ɑ�̍�Ȃ��I����Ă����\��������B24�w�҉��y�t�x�����Z���ɂ������߁A�V���[�x���g�́w�ǓƁx������̖�肩�烍�Z���ɉ����Ă��悢�Ɣ��f�������A���邢�́w�ǓƁx�����Z���ɂȂ������߁A�w�҉��y�t�x�����Z���ɍ��킹���̂�������Ȃ��v�ƁA��Ƃ̊֘A�ɂ����̂Ɛ������Ă���i�u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v���j�B�����A�V���[�x���g�́A�O�㔼�ŏI�Ȃ������ɂ��邱�ƂŁA�u�~�̗��v�̉̋ȏW�Ƃ��Ă̓����}�肽�������A�ƍl������B
�i�S�j�V���[�x���g����芪���o�ŊE�̏�
�@�y���o�ŎЂƍ�ȉƂƂ̊W�ɂ́A���h�Ƒ��������荬�����Ă���B���݂������ɉz�������Ƃ͂Ȃ����A�o�ŎЂ͏����ł�������������A��ȉƂ͏����ł��������肽���̂́A���オ�ς��Ă������͓����ł���B���ƂɃV���[�x���g�̏ꍇ�́A���̍�ȉƂ̂悤�ɉ��t��ʼn҂�����A�M���̂������ɂȂ��ċ��������炤�ȂǂƂ������Ƃ��Ȃ���������A�����̂قƂ�ǂ͊y���̔���グ�ɗ��炴��Ȃ������B���[�c�@���g��x�[�g�[���F���͋q�̌Ăׂ鉉�t�Ƃ��������A�o�b�n��n�C�h���͋���̉��y����M���̂��������y�t�Ƃ��Ĉ��肵�������̕ۏ��������B�ނ�ɔ�ׂ�ƁA�V���[�x���g�̊y���o�ŎЂւ̈ˑ��x�́A��r�ɂȂ�Ȃ����炢���������̂ł���B����ȃV���[�x���g�Ɗy���o�ŎЂ̊W�������L���Ȏ莆������̂ŁA�v�Čf�ڂ��Ă݂悤�B
�M�Ȃ�q�Ď��ɋ����Ă���܂��B���͂������ɁA�ȑO�̂���������A�M�Ђ̂��Ȃ炸���������łȂ��Ӑ}�ɋC�Â��Ă͂���܂������A��͂肱�̂��т̂��Ƃ͂�������Ȃ�Ƃ����ق��͂���܂���B�M�a�́A���̓x�A�I�y���̑����̃R�s�[��Ƃ���150�t���[�����������Ă����܂������A����A�M�a�͌�����100�t���[�����ɂ����Ȃ�Ȃ��Ƃ���������Ă��܂��B�������A�S�������ċL�ڂ̒ʂ肾�Ƃ��Ă��A����܂ł̎��̍�i�̂��̂悤�ɋɂ߂Ĉ����l���݂ƁA���߂́u���z�ȁv��50�t���[�����Ƃ����l�i���l�����킹��A����́A���ɉۂ����Ă���s���ȕ������Ă��܂肠����́A�Ƃ��킴��܂���B���́A�M�a�����̂悤�ɗ]��ɂ��l�ԓI�ȐS�����������킹�łȂ��̂ł͂ƁA��ςɋ^�����̂ł���E�E�E�Ō�ɂ��肢�ł��B�M�a���a�����Ă����鎄�̑S��i�̑��e���A������ꂽ���̂�����Ȃ����̂��A���ׂĕԑ����Ă��������B�h��B�@����͑��o�ŎЃJ�b�s���f�B�A�x���ЂցA1823�N4��10���ɑ������莆�ł���B�u���z�ȁv�Ƃ͖��ȁu�����炢�l���z�ȁv�̂��ƁB�����̂��ߑς��ɑς��Ă����o�ŎЂւ̓{�肪�A���ɔ��������̂ł���B���̈ꌏ����A�o�ŎЂ��A�V���[�x���g���炽�����R�Ŗ��Ȃ��@���A�����̔�p�܂Ő������Ă��鎖���������яオ���Ă���B�������ŏ��͈ϑ��̔����������Ƃ��������Ă���B���̂�����̎���ɂ��āA�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���́u�V���[�x���g���y�I�ё��v�i���^�j�� �����Ёj�̒��ł����q�ׂĂ���B
���S���Ă��d�����Ȃ��B�����͂����߂��ނ����ł���B�V�˂�F�߂邱�Ƃ͂ނ����������A�V���[�x���g�̓V�˂́A�o�Ŏ҂����������ɂ͂ނ��낶��܂ɂȂ����̂ł���B�o�Ŏ҂������ނ���~�������̂́A�����ɂȂ锄��s���̂悢���i�������̂ł���B�������A�ނ̎��̔N�ɏo�ł��ꂽ�u�σz���� �s�A�m�O�d�t�ȁvD929���O�Ƃ���A�ނ̏d�v�Ȋ�y��i�̑�Ȃ�����������Ȃ������Ƃ������Ƃ́A�ނ̂��ׂĂ̍�i��"�s�ꉿ�l"�̔��f�ɉe�������̂ł����āA������悢���Ƃɂ��ďo�Ŏ҂����́A�V���[�x���g�����܂ł��L�]�ȐV�l�̂܂܈����āA��V��Ⴍ�}���Ă����̂ł���B�@�����̍�ȉƂ̃X�e�C�^�X�́A�o�ŋƎ҂ɂƂ��ẮA�y����������y�Ȃ������邩�ǂ����ɂ������Ă����B�V���[�x���g�̊�y�Ȃ͔ނ�̂��Ⴊ�˂ɂ͊���Ȃ��������߁A�ނ͎��ʂ܂�"�L�]��"�V�l�����������̂ł���B���ꂪ�ނ���芪���o�ŊE�̎�������B�A�C���V���^�C�����A�u�����͂����߂��ނ����ł���v�Ə������C�������悭����B����́A�V���[�x���g�ƃn�X�����K�[�Ƃ̊W�Ƀt�H�[�J�X���Ă䂫�����B
2011.01.20 (��) �b����\�\�n�f�W���̌��p
�@��N�H�A�䂪�Ƃ�����ƃe���r���̃f�W�^�������ʂ������B����܂ŁA�uVHS�ʼnߕs���Ȃ�����Ă���̂ɁA�Ȃ�Ėʓ|�ȁv�Ɛ��{���j�ɂ͕s���ƕs�M�̉������ł��邪�A�g���n�߂��炷���Ƀf�W�^���֗̕����ɖڊo�߂Ă��܂����B���ƂȂ��ẮA�u����ȕ֗��Ȃ��̂��Ȃ������Ƒ����E�E�E�v�Ɖ���ގn���A�����Ȃ��̂��B�@����Ȃ킯�ŁA�f�W�^�������N�̔N���N�n�̓u���[���C�E���R�[�_�[�ŗl�X�Ȕԑg���B��܂����Ċy���B�u�E�B�[���E�t�B���E�j���[�C���[�E�R���T�[�g�v�u2009���g���|���^���S��v�uN���̑��v�u���}�W���x�X�^�[�E�R���T�[�g�vNHK�u�j���[�C���[�E�I�y���E�R���T�[�g�v�u�o�[���X�^�C���v��20�N���ԁv�ȂǂȂǁB
�@�u�E�B�[���E�t�B���E�j���[�C���[�v�́A�Ȗڂ��K�i�O�������B�A���R�[���͗�ɂ���āu���������h�i�E�v�`�u���f�c�L�[�s�i�ȁv�Ƃ�����Ԃ̗��ꂾ���A�{���Œm���Ă�Ȃ͊F���B���܂�������̏a���������B�ł��A���͂���ɂ͑�^���B�E�B���i�E�����c�͂ǂ��������͂����̂�����A�u�������ꉽ�H�v�݂����ȏ��߂ĕ����Ȃ̘A���̂ق����h���������Ă����B�w���̃E�F���U�[�����X�g�́A��N�E�B�[�������̌���̉��y�ēɏA�C���������̃z�[�v�B���ʂ̂Ȃ������ƃI�P�̎�������D�悷�鉹�y���͍����x�傾���A�O�N�̃v���[�g���ꂳ��ɔ�ׂ�Ɨ��ɖʔ��݂͂Ȃ��A�ј\�̈Ⴂ�͗�R���B�]�k�����A�ē�����NHK�������q�A�i�͙z�Ƃ��ĕi�������B
�@�u���}�W���x�X�^�[�v�̌Ăѕ��́A�N�z���̖��ȃJ�E���g�_�E���B���N�̓}�[���[�́u�����v�������B���a150�N����v��100�N�ւ̉˂����́A�R�o�P������̎w���Ō����ɃW���X�g�E�����f�B���O���ʂ������B�O�N�͈�㓹�`�w���́u���v�\�f�B�[�E�C���E�u���[�v���������A�m���R�`���̓`���C�Y���������ƋL�����Ă���B���ł͍P��W���j�[�Y�E�J�E���g�_�E�����������ɍs���Ă���܂����B������x�]�k�����A�i�s��TX��]�����q�A�i�͒m�I�Ŗʔ����B���݃}�C�D���x�i���o�[1���q�A�i���B
�@�u�j���[�C���[�E�I�y���v�̎��n�̓\�v���m��������q���炢���B�����悭�L�тĈ��芴���肾�B���Ƃ́A�s�A�j�X�g�A�A���X�E�їǁE�I�b�g���A���X�g���a200�N�Ɉ����ځu���S���b�g�E�p���t���[�Y�v��e���A���т𗁂тĂ����B���߂ĕ������̋ȁA�u���S�̉́v�����������Ƒ҂���тĂ�����A���̂��Ƃ͂Ȃ��A���̂܂I����Ă��܂����B���q�����B�A���X��1988�N���܂ꂾ����܂�22�B���l�ʼn��A�r���m���ȃs�A�j�X�g�Ƃ���ΐl�C���o�ē�����O�A2011�ƃO�����t�H���E�N���V�b�N�E�J�����_�[�̐����͔ޏ��ł���B�Ⴍ�Ĕ������s�A�j�X�g�Ƃ����A2010�V���p���E�R���N�[���̗D���������A���i�E�A���f�[�G����1985���܂�Ȃ̂�25�B�}���^�E�A���Q���b�`�ȗ��̏����D���҂��������BN���Ƃ̃V���p���u�s�A�m���t�ȑ�1�ԁv�������A�̐S�����Đ��X�����B����܂��D���x��B�܂��܂��]�k�����A���̔ԑg�i�s���̏��D�J�R��������������m�I���l�A�Ȃ��Ȃ� good �ł����B
�@��N�̓V���p�����a200�N�Ɉ��l�X�Ȕԑg������ꂽ���A�u�V���p���ɒ���v�Ȃ�A�s�A�m�f�l�|�\�l���ғ��P�ŃV���p����e���Ƃ�������̓��Ԃ�NHK�œ�قǂ������B��͐l�C���˃`���[�g���A���̓���`���ł�����͔o�D�̒��J�쏉�́B���Ȃ݂Ɂu���́v�̓V���p�����������Ă���قǁA���J��̓V���p����D���l�ԂȂ̂��������B���҂̐搶�́A���R�i�H�j�䂪�� No.1 �l�C�����s�A�j�X�g�����������B��l�Ƃ����T�ԂŁi�Â�����j�Ȃ�Ƃ��l�ɂȂ�p�t�H�[�}���X�Ɏd�オ���Ă����B�����Ŏ��������A �ނ�ɏo���Ă��̎��ɏo���Ȃ��킯�͂Ȃ��I�Ȃ�Ă������ăs�A�m�͐̂Ƃ����˂��B"�s�A�m���ăV���p����e����"�ƌ��߂܂����B�s�A�m�Ƃ����Ă��d�q�s�A�m�A�V���p���Ƃ����Ă��u�m�N�^�[���σz������i9�|2�v�ŁA�����͂Ƃ�����5�N��ɁB�Ȃ�5�N�ォ���āH ���́u�N�����m�v�T�����ʔ������Ď肪���Ȃ�����ł���܂��B
�@1��13���́A�P��E�N�Ɉ�x�������݂䂫�w�ł̓��B���̓t�H�[����A�z�[���B�������N�u���v�Ɓu�c�A�[�v�̃e���R�����A���N�̓c�A�[�̔Ԃ������B�u����v�͕ʊi�Ƃ��āA���݂̂䂫�t�F���@���b�g�E�\���OBest�R�́u�a���v�u�̕P�v�u��ǂ̏M�v�ł���܂��B�u�a���v��2007�N�ɁA�u�̕P�v��2005�N�̃c�A�[�ʼn����Ă���̂ŁA����́u��ǂ̏M�v�����������Ǝv���Ă�����A����Ă���܂����B
�@�@�@�@���Ȃ������@�g�ɍӂ�����ɂ�
�@�@�@�@�@ �ǂ����ł��܂��̏M���@�������ɂ����ނ��낤
�@�@�@�@�@ ���ꂾ���̂��ƂŁ@�킽���͊C���䂯���
�@����A�u��ǂ̏M�v�̈�߂����A3�s�ځu���ꂾ���̂��ƂŁv�����܂�Ȃ������̂��B�����悤�Ȃ��Ƃ��W���Y�E�s�A�j�X�g���H�g�q�q�������Ă����B�u�����Ƃ����͈̂�ԑ�Ȃ��Ƃ͉������Ă���Ȃ�����ǁA�����Ă��̂��Ƃ͉������Ă����v�ƁB��ԑ�Ȃ��ƂƂ����̂��u���ꂾ���̂��Ɓv����Ȃ����Ǝv���B�����m�l�Ɍ�������u����A���͂��ׂĂ��������Ă�����v�Ɛ�Ԃ��ꂽ�B�������Ȃ��B�l���ꂼ��I
 �@�݂䂫����̑f���炵���̎��͂��ꂱ���������肷���āA�������������Ă͂����Ȃ����A"���肰�Ȃ�����"�^�C�v�̂�����̋ɂ߂��́A�u�������v�̈�� �̂ˁA�킩��Ȃ��z�����邳���āE�E�E�ł���܂��B��l���i�݂䂫����{�l�j�ɂȂɂ��ʔ����Ȃ����Ƃ��N����ƁA���������j�F�B����v�����悤�ɘA�������āA��l�ŋ������ɍs���A�u���ꂪ�������v�ƌ����Ă����Ȃ��̂ɁA�����T�����ƌ����Ă���邱�̑䎌�B�Ȃ����߂�ł��Ȃ��A�����t���������A�������܂������Ȃ��A��l�̊Ԃɂ͂Ȃ�Ƃ������Ȃ����炩�ȋ�C������Ă��āA���ɂ��������Ȃ̂ł��B
�@�݂䂫����̑f���炵���̎��͂��ꂱ���������肷���āA�������������Ă͂����Ȃ����A"���肰�Ȃ�����"�^�C�v�̂�����̋ɂ߂��́A�u�������v�̈�� �̂ˁA�킩��Ȃ��z�����邳���āE�E�E�ł���܂��B��l���i�݂䂫����{�l�j�ɂȂɂ��ʔ����Ȃ����Ƃ��N����ƁA���������j�F�B����v�����悤�ɘA�������āA��l�ŋ������ɍs���A�u���ꂪ�������v�ƌ����Ă����Ȃ��̂ɁA�����T�����ƌ����Ă���邱�̑䎌�B�Ȃ����߂�ł��Ȃ��A�����t���������A�������܂������Ȃ��A��l�̊Ԃɂ͂Ȃ�Ƃ������Ȃ����炩�ȋ�C������Ă��āA���ɂ��������Ȃ̂ł��B�@�����́A�X�e�[�W�Łu���т���i�o���}�X�j�̃��C���������q�Ȋ��ɏo�Ă�̂̓l�A�����Ď��X�̂��o����Y�ꂿ�Ⴄ�B�o�J������B������ŁA����ȂƂ����ڂŃ`���b�ƍ��}��������悤�ɂ������Ă���́B�F����ɋC�Â���Ȃ��悤�Ƀl�v�Ȃ�Ċ�Ɣ閧�C�Œ���B�ł��ޏ��̂��Ƃ��o�J���Ǝv���Ă���l�́A���Ȃ��Ƃ��t�H�[����5000�l�̒��O�̒��ɂ͈�l�����܂��B�u����̃c�A�[����A�r���ɋx�e�����܂������A����͍���̂��q����̃g�C���E�^�C���̂��߃f�X��v�Ƃ��u�f�B�i�[�V���E�͂��܂���B���q���H�ׂĂ�̂ɁA�������̂��Ă���āA�Ȃɂ���������Ȃ����A�����H�ׂȂ���̂�����V�b�`���J���b�`���J��ˁv�Ȃ�āA�܂�Ŏ��R�ȓ����b�B�ߑ��́A�K���Ȃ����A�C�h���^���̃h�h��ȃh���X�B���ꂪ�̂��n�߂���l�̐S�B�t���̉̂��̂�����B���̃M���b�v�������Ėʔ����B������ޏ��͂������_�Ȃ̂��B�������Ə����Ō��59�Ȃ̂ɁA�����o�邱�Əo�邱�ƁB�{�C�E�g���̐��ʂ��A�Ⴂ�����������ق����o�Ă��邻�����B���̃t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�����āA���̒����Ɠ����N�Ř^�������u�~�̗��v�i�u�����f�����s�A�m�j�ȂA�Ⴂ���̂ɔ�ׂ�Ɓi24�Ȓ��j6�Ȃʼn��������ĉ̂��Ă���̂ɁB����ɁA�ޏ��́A���ꂾ���A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă��l�ԂƂ��Ă������Ƃ��Ă����͓I�Ȃ̂ɁA�\���F���B����������s���B
�@�s���Ƃ����A��N���Ɍ��� NHK-BS�u���[�}���\�z �V�˂�����150�N�̓����`�f���̖��͂Ɏ���ꂽ�l�X�v�́A������������t�@���^�X�e�B�b�N�������B��{�e�[�}�́u�f���v�iPrime Numbers�j�̕��ѕ��B���̂P�Ǝ����ł��������Ȃ������́A2�A3�A5�A7�A11�A13�A17�E�E�E�ƉʂĂ��Ȃ����ԁB�����Ă��̕��тɂ͖������Ȃ��B�����ďo�邱�Ƃ�����A�������Əo�Ȃ������������B�Ⴆ�� 31397 �̎��̑f���� 31469 �ŁA���̋� 72 �ɂ��y�ԁB�����������A����"�ꌩ�Ȃ�̖������Ȃ��f���̕��тɂ́A����@��������͂���"�Ə����鐔�w�҂��o�Ă����B
�@��l�ڂ̓X�C�X�̓V�ː��w�҃��I���n���g�E�I�C���[�i1707�|1783�j���B�ނ̑n�������I�C���[�̓��� ei�� + 1 = 0 �́A�l�ނ̎���Ƃ����鐔�����B���R�ΐ��̒� e �Ɖ~���� �� �Ƌ��� i �A�O�҂̘A���ɍŏ��̐��� �P �������� �O �ɂȂ�Ƃ������̎��́A�Ӗ��͉���Ȃ��܂ł��A���̕��O�ꂽ�Ȃ܂��̔������͎����ł���B�� �� �� ���萔�����A�����_�ȉ������ɐ��������ԁB�� �͎��悷��� �|�P �ɂȂ�Ƃ������̊��Ȑ����B����Ȓ݂͂ǂ���̂Ȃ��R�̐������d�Ȃ荇���čŏ��̐����P�ݏo���Ă���B�Ȃ�Ƃ����s�v�c���A�������B���P�͗����ł����Ƃ����̎p�`�͎��Ƀt�@���^�X�e�B�b�N���B
�@�I�C���[�́A�f���ō��������ς̌`���A���g���Đ��������邱�Ƃɐ��������B�j�㏉�߂đf���̔w��ɂ���_��ɐG�ꂽ�̂ł���B
�@���̓h�C�c�l�J�[���E�t���[�h���q�E�K�E�X�i1777�|1855�j���B�ނ́A�f���̕��т��A�I�C���[�� �� ���g���ĉ𖾂��悤�Ƃ����̂ɑ��A���R�ΐ��ɂ���Ċ֘A�t���悤�Ƃ����B�~�����͏��w�Z�ŏK�����A���R�ΐ����A�����̋N�_����̋����ƒ����̔䂾����A��l�̎��Ă͂Ƃ肠���������\�Ȕ��e�ɂ��邪�A���̓x�����n���g�E���[�}���i1826�|1866�j�ł���B
�@�@�@�@�[�[�^���̔��ȂO�_�͂��ׂĈ꒼����ɂ���͂���
�@���ꂪ���w�j��ő�̓��Ƃ����郊�[�}���\�z The Riemann Hypothesis �ŁA1859�N���[�}���ɂ���ĂȂ��ꂽ�B�[�[�^���́A�f�����g�����ϐ��̎��B�f�� �� �ƘA�����鐮�� n �ŕ\�����B���[�}���͂��̎����瓱�����}�\�̂��ׂĂ� 0 �_�͈꒼����ɕ��ԂƗ\�z�����̂��B���ꂪ�ؖ������A�ꌩ�s�K���Ɍ�����f���̕��тɂ͂����̋K�������F�߂���̂ł���B�\�z���� 150 �N�]��A�����̐��w�҂����킷������ׂĝ��˂����Ă���j��ő�̓��Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�ߔN�A���q�j�G�l���M�[�̊Ԋu�ƃ[�[�^���� 0 �_�̊Ԋu���������ŕ\���ꂽ���Ƃ���A�₩�ɗʎq�����w�Ƒf���Ƃ̊֘A�����ڂ����悤�ɂȂ��Ă����B���̗��ꂩ��A�u����w�v�ɂ���đf���̊Ԋu���𖾂���V���ȓ������o�Ă��Ă���B�����Ȃ��T���̋łɁA���̓������[�}���\�z���������Əؖ����ꂽ�Ȃ�A"�~�N���̐��E����F���ɂ����鎩�R�@���̊�{�͑f���̉��������ɂ���Đ��藧���Ă���"�Ƃ����s��ȊT�O���`������邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��̂��B����ȐX�����ۂ̐_��ɔ��肤�郊�[�}���\�z�Ƃ́A�Ȃ�ăG�L�T�C�e�B���O�Ȏ��ۂȂ̂��낤�B
�@����͂�A����ȕ��ɏ����Ă͂������̂́A�����͔��Ŋ����邾���ŁA����x�͋ɂ߂ĒႢ�Ƃ��킴��Ȃ��B�������������邽�߂ɂ��ꂱ�ꏑ���Ă͂������̂́A���e��F���猩���͂���̋ؗ��ɂȂ��Ă���댯�������肤��B���̂�����A�C�Â������͉����Ȃ����w�E���������B�ł��܂��A����܂ł��͑����ł��������Ɏ��������Ă����悤�ȋC�����Ă���B����x�����ł��A�ʔ����̎����������Ă������Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B������n�f�W���̌��p�H�@�܂��A�ЂƂ܂��͂���ł悵�Ƃ��悤�B
�@�u�~�̗��v�̖��ɂƎv���ď����n�߂�����́u�N�����m�v�ł����A�c��݂����Ė����{���ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ł́A���t���b�V�������Ƃ���ŁA����{��ɖ߂낤���Ǝv���܂��B
2011.01.10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևO �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v9
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������Ȃ��̂����̖{�́I��
�@2010�N�̓V���[�x���g�ɏI�n������N�������B�s�A�m�E�\�i�^�A�����ȑ�8�ԁu�O���[�g�v�A�~�T�ʏ핶�̓�A�̋Ȃ̐X�ƁA���X�̖��m�Ȃ���̂ɑ����ł��āA���ɗL�Ӌ`�Ȉ�N�������Ǝv���B���ɍŌ�A�I�[�E�w�����[�u�Ō�̈�t�v���u�~�̗��v�́u�Ō�̊�]�v�Ɗ֘A�t����ꂽ�̂́A�܂��Ɂu�N�����m�v�I�Ŋ����������B�����A����͂܂��؋�����̐��_�ɉ߂����A��������̓ˍ��݂��s�����Ă���B����̉ۑ�Ƃ��Ďc���Ă����B�@�Ƃ͂����A�u��t�v���u��]�v�̉ߒ��ŁA�Έ�G�搶�̖ƍb��M�炳���Web-Site�ɑ����ł����̂͑傫�Ȏ��n�������B����A�ʔ����{�ɂ����������B����͂��̖{�ɂ��ď������Ă����������A����͐������̏\���ԃW������"���������Ȕy�^�^�L"�ɑ�������̂��B�ł͑����A�l���c��q���w�V���[�x���g �̋Ȃ̐X�x
 �i�d���Ɂj�������Ă䂱���B�^�C�g���́u�V���[�x���g �̋Ȃ̐X�v�́A���u�N�����m�v���݂̃T�u�^�C�g���Ɠ��������A����͖��_�A�S���̋��R�ł���B
�i�d���Ɂj�������Ă䂱���B�^�C�g���́u�V���[�x���g �̋Ȃ̐X�v�́A���u�N�����m�v���݂̃T�u�^�C�g���Ɠ��������A����͖��_�A�S���̋��R�ł���B
���̈ٗl���σz�Z���̍�i�ƁAO.�w�����[�̒Z�ҁw�Ŋ��̈�t�x�Ƃ��A������薼�����ʂ��Ă���̂͋��R�Ȃ̂��H�w�t�̖��x�ł�'�K���X���ɕ`���ꂽ�̗t'�ƃZ�b�g�ōl���o���ꂽ�悤�ɂ��v���邪�A���́A���̏����ɂ���"�߂����q���[�}�j�Y��"������Ă���]�T�͂Ȃ��B�i125�Łj�@�����ƁA�����Ȃ�u�σz�Z���v�����A����́u�σz�����v�̊ԈႢ�ł���B�̏��p�[�g�ŏ��̉����n��ŁA2���ߖڂ̃���� ♮ �ɂ��ā�Ɩ߂��A3���ߖڂŏ��߂Ď咲�̕σz�������o�Ă���E�E�E�Ƃ����������̐����Ȃ̂ŁA������u�Z���v�Ɗ����Ă���������ʂ��Ƃ����m��Ȃ����A����͕�����Ȃ������ȁB�Ō�̘a���m�~��-�\-�V��n�́u�σz�����v�̎�a���A��߂�߂��ԈႦ�̂Ȃ��悤�ɁI �ł��܂��A����̓P�A���X�E�~�X�A��ڂɌ��悤�B�܂��A���������͓���Ă����Ă��������B����͂��Ă����A�I�[�E�w�����[�u�Ō�̈�t�v��"�߂����q���[�}�j�Y��"�ȂǂƂ��������ۂ������ŕЕt��������ɁA�u���]�T�͂Ȃ��v�Ȃǂƕ��u����̂́A�������Ȃ��̂��B���A����������H��킹����ɁA�̂����ȕ������������邱�������^�C�v�̕��̂Ƀ��J�����̂ł���܂��B���������A���̃e�[�}�A�����ȒP�ɉ𖾂ł���킯���Ȃ��A�������܂��A���ق��Ă����܂��傤�B�A���A���͂܂����B���E�ʋ��Ɍ������Ȃ��B�����́u�~�̗��v�̉��t�]�̕����ŁA���X��������ǂ����p�����Ă��������܂��B
���̉̏W�ł͍������̐[�����@�Ɋ�Â����̂̉A�e�����߂���B���̓_�A�n���X�E�z�b�^�[�Ղ��œK�mDG�n�ƌ���ꑱ���Ă������A�ቹ�p���]�������ӏ��������A�I�~�A�njo������������B���̏�e���|���ُ�ɒx���B��1���u���x�݁v�ł́A�q���b�V���ՁmEMI�n��4�����ł���̂ɑ��A6�����߂���v���Ă����A�܂��Ă�ςȏ��ő��p������������ẮA���܂������̂ł͂Ȃ��B�����Ⴂ�̂Ɛ[�݂̂���̂Ƃ͕ʂ̎����̂͂Ȃ��ł���A�����߂���ȁI�܂��A��l���͂���Ԃ�Ă���Ƃ͌����A�܂��N�ł��邱�Ƃ�Y��Ă͍���B����䂦�������Ɋׂ�킯�ł���A�������l�q�ʼn̂���̂́A����疕���L���Ă����Ȃ��B�i133�Łj�@�����ɁI�n���X�E�z�b�^�[����A�{���N�\�ł���B�����z�b�^�[�́u�~�̗��v�͂���قǍD���ł͂Ȃ��̂ŁA���҂̋C�����͕���ʂł͂Ȃ����A���̕��́A�]��ɂ���������B����ł̓z�b�^�[������u�A���^�ɂ͌���ꂽ���Ȃ��I�v�ƍR�c�̑升���K�����낤�B �@�܂��A�u�ቹ�p�ɓ]�������ӏ��������v�͑�ԈႢ�B�]���Ƃ́A�Ȃ̗���̒��Œ�����ς��邱�ƂŁA���̏ꍇ��"�����̂܂܂ł͉̂��Ȃ��̂ŁA�����ڍs����"���Ƃ䂦�A����́u�ڒ��v�ƌ����̂ł��B����Ȋy�T�̏����̏����̗p�����߂�߂��ԈႦ�Ȃ����ȁB�܂��u�ӏ��v�Ƃ͂ǂ����������Ȃ̂��낤���H�܂����A"�Ȓ��̂���ӏ��Œ�����ύX����"�Ȃ�Ă��Ƃ����l���ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��ł��傤�ˁB�ڒ��Ȃ̂Łu�ӏ��v�ł͂Ȃ��u�Ȃ��Ɓv�Ȃ̂ł��B����ɑ����u�I�~�A�njo�������v���ĉ��̂��ƁH �ȏI��肪�njo�ɂȂ���Ă��ƁH ����A�����́u�I�n�v�ł���ˁB�����̌�A�B�����āA��1�Ȃ́u���x�݁v����Ȃ��āu���₷���v�ł��B�L���x�Ɏ擾�𐄐i����J���ۈ����Ⴀ��܂����A�uGood Night�v�̂��Ƃł�����u���₷�݁v�ł��傤�B���A��1�Ȃ������\�L����l�ɏ��߂ďo��܂����B���ꂩ��A�u�Ⴓ�䂦�ɔ������Ɋׂ�v�Ƃ��������l�͂ǂ��ł��傤���B�����A�����Ҕ\�͂Ȃ��ƌ����Ă���悤�ŁA��l���������B���ɂ́A���̎�҂͐�]���Ȃ����������������Ȍ��݂����Ȃ��̂����߂Ă���Ǝv���邵�A�܂��A����Ȏ�҂�邩�ɉ������������Ȃ�̂ł����A����͂܂��A�������̖��䂦����܂łɂ������܂��傤�B�����A�ɂߕt���͂��̂��Ƃł��B
�@���҂́A�u�q���b�V���̉̏���4�����Ȃ̂ɑ��āA�z�b�^�[�̂�6�����߂����|�����Ă���B�E�E�E�����E�E�E���܂�������Ȃ��v�Əq�ׂĂ�����B����̂ǂ������������̂��H����ł͐��������Ă��������܂��B
�@�Q���n���g�E�q���b�V�������́u�~�̗��v��^�������̂�1933�N�ASP���R�[�h�̎���BSP���R�[�h�̕Жʂɂ�4��15�b���炢�܂ł������^�ł��Ȃ��B��1�ȁu���₷�݁v�́A�t���E�R�[���X���̂��ƁA�ǂ��撣���Ă�5�����قNJ|�����Ă��܂��B���ʂɂ܂������ăt���E�R�[���X�Ƃ����I���������������낤���A�ŏI�I�ɁA��2�߂��J�b�g������̖ʂɎ��߂邱�Ƃɂ����̂ł���B�����厖�ɂ����������̂��낤�B���̏コ��ɑS�̂̃e���|���グ��4���\�R�\�R�Ŏd�グ���̂��B�����A��������ł��傤�B���҂́A�t���E�R�[���X���̂��z�b�^�[�Ƒ�2�߂��ȗ������q���b�V���Ƃ����S���ʏ����̉��t���A������l���ɓ��ꂸ�Ƀ\�m�}�}���t���Ԃ��r����Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��߂���Ƃ��Ă��܂����̂ł��B
�@LP���R�[�h�̓o�ꂪ1948�N�B�����Ղ�1951�N�A�����^�[�́u���v�iWL5001�^2�R�����r�A�Ձj�ł����BSP���R�[�h�́ALP�o�ꂩ�炵�炭�̊ԕ�������Ă�������A���Ȃ��Ƃ�1950�N�゠����܂ł͌����Ƃ��đ��݂��Ă����B���҂̌o�𗓂ɂ́A1941�N���܂�Ƃ���܂�����ASP��m��Ȃ��͂��͂Ȃ��B�܂��A���ꗬ�����ɒ����A�q���b�V������2�߂��ȗ����Ă���̂͊ȒP�ɕ�����͂��B�������A���̏��L����EMI�����Ղ̑Ζ�ɂ́A��2�߂̉̎������̂܂�����Ă��āA�e�ɂ��u�����͏ȗ�����Ă��܂��v�Ƃ̒��ӏ������Y�����Ă���B������A���ʂ͊ԈႦ�悤���Ȃ��ł���ˁB��̂ǂ��łǂ����Ⴂ����Ă��܂����̂ł��傤���B�펯�ōl���Ă��A���̒��x�̒����̋ȂŁA�Е���������e���|���x������Ƃ����āA�Q���ȏ���Ⴄ���ƂɁA���̋^��������Ȃ������̂ł����ˁB���ɂ͂܂�ŐM�����܂���B�܂��A�S�������āA�P�ɊԈႦ�������Ȃ�܂�������̂ł����A������x�[�X�Ɂu�����Ⴂ�̂Ɛ[�݂�����̂Ƃ͕ʎ����̂͂Ȃ��v�Ƃ��u��肫���ĉ̂���͖̂����L���Ă����Ȃ��v�Ƃ��u��l�����N�ł��邱�Ƃ�Y��Ă͍���v�ȂǁA��ɂ���Ĉ̂����\���̃I���E�p���[�h�B����̉ʂẮu�����߂���ȁI�v�ł����āB�������Ă�̂͂��Ȃ��̂ق�����Ȃ��ł����I
�@�I�}�P��������B
�u�����A�V���[�x���g���{���e�m�[���̉���ō�����Ă���A�l���̉����邩��m������O�A���c�ɂ��w���Ɏ���a�x�Ȃ�ʁw���Ɍ������ꂽ���C�x�ɑ��Ă���Ɖ�����̂��ӂ��킵���낤�B���̓_�ł́A���z�����B�b�c�iT�j�ƃt�F���_�[�ɂ�閽�����̕ҋȔՁmBMG�n�������Ăق����v�i133�Łj�@���ӂ�������ς����A����͂��Ă����A���́u�{���e�m�[���̉���ō�ȁv�Ƃ������������m�ɂ͐������Ȃ��B���́A�����̕W���s�b�`�iconcert pitch�j�͍��������Ȃ�Ⴉ�����̂��B���݂̂悤��A�̃s�b�`��442Hz�ɓ��ꂳ�ꂽ�̂�1930�N�̃����h����c�ł̂��ƁB����ȑO��1859�N�̃p����c�Ō��߂�ꂽ435Hz�B����ɂ���ȑO�͊e���}�`�}�`�ŁA�h�C�c��415�A�C�^���A��465�A�t�����X��392�������Ƃ����B�i���̂��̂悤�ȕϑJ��H�������ɂ��Ă͖������ɂ�����̉ۑ�Ƃ��������A���̎����͊w�҂̌����ɂ���ďؖ�����Ă���j�B���������ăV���[�x���g�̎���̃E�B�[���̃s�b�`�́A���݂����i442�\415���j27Hz�Ⴉ�����̂ł���B���̐��l�͉����I�ɂǂꂭ�炢�̂��̂��Ƃ����A�P�I�N�^�[�u��220Hz�Ȃ̂ŁA�����́i220��12���j18�D3Hz�ƂȂ�A���������ē����̃s�b�`�͌��݂��������ȏ�Ⴉ�������ƂɂȂ�B�������V���[�x���e�B�A�[�f�ʼn��t����ꍇ�ȂǁA�����p�ɂɃs�A�m�̒����͂ł��Ȃ��������낤����A�����ƒႩ�����\���������B�u�~�̗��v�̏����҂͍�Ȏ҂̐e�F���n���E�~�q���G���E�t�H�[�O���i1768�|1840�j�ŁA�ނ͔������n�C�E�o���g���������Ƃ����B�V���[�x���g�́u�~�̗��v���A�ނ̉����z�肵�č�����킯������A���̃L�C�����݂ɃX���C�h������ƁA�e�m�[���̃L�C�ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B
�@���́A�o���g���̎肪�u�~�̗��v���A�V���[�x���g������������ʼn̂��Ȃ��̂͂Ȃ����낤�H ���Ƃ����Ă��t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E���ō��Ȃ̂ɁE�E�E�ƁA���˂��ˁA�^�������Ă����B���̂��{�l���A���̒����̒��ł��������Ă����B
�����҃t�H�[�O���ȗ����̋ȏW�̓o���g���̂��߂̂��̂Ƃ���Ă������A�ߔN�A�s�[�^�[�E�s�A�[�X���e�m�[�����u�����v�ʼn̂��̂͊��}���ׂ����Ƃł���B�i�u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv���c�ΐ��� �����Њ��j�@�ނ������A�u�~�̗��v�̐[�������ō��ɕ\�����Ă���Ǝv����̂ɁA�u�����v�ʼn̂���̂̓e�m�[�����Əq�ׂĂ���B���炭�A�W���s�b�`���������㏸���Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă��Ȃ��̂��낤�B�u�����v���V���[�x���g���z�肵���L�C�����A���͔ނ̉���Ƀs�b�^���Ȃ��Ƃ�{�l���g�����o���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�V���[�x���g����߂��L�C�́A�W���s�b�`�̏㏸�ɂ��A�����̓o���g����z�肵�Ă������̂��A�i���̂܂܃X���C�h������Ɓj���݂ł̓e�m�[�������̂��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B���̂��Ƃ���A�u�~�̗��v�̓e�m�[���ʼn̂���̂����������ƍl���Ă��鎯�҂������ɑ����悤���B�ނ�́A��������������D�悳���Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ�������B
�@�����́u�����v�ɍ��킹��ɂ́A����̃L�C�����`�ꉹ���x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͂����������肾�낤�B�V���[�x���g���z�肵���L�C�́A��͂�o���g���̂��߂̂��̂������̂ł���B������A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́u�~�̗��v���ō��Ȃ̂́A�����ɍ����Ă���̂ł���B�l���c�����u�{���e�m�[���̉���v�ƌ����Ă���̂͊ԈႢ�ŁA�u�{���o���g���v�A�J���q���Ɍ����u�̂��o���g���A���ł��o���g���v�Ȃ̂ł���B�i�ȏ�A�u�~�̗��v�̃L�C�ɂ��Ă̊�b�m���́A�������̊�����o���g���̎�E�L�����o���c�ӂƂ��鎁���炲�����������������̂��B�j
�@�l���c���ɂ́A�s�b�`�̕ω��ɂ܂ł͂����Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ��A�q���b�V���́u���₷�݁v�ɉ�����߂̏ȗ��ƁA�����I�ȉ��y�p��̎g�������炢�͔c�����Ă��ė~���������B �ނ́A�u�~�̗��v�̏͂�����ȃI���W�i���ȋ�Ō���ł���B
�u�~�̗��v���ꗬ��������������
 �@"���ꗬ��������������"�͂ǂȂ��Ȃ̂ł��傤���H ����ȕ��ɂ́A�A���g���E���[�r���V���^�C���̂���Ȍ��t�������肵�����B
�@"���ꗬ��������������"�͂ǂȂ��Ȃ̂ł��傤���H ����ȕ��ɂ́A�A���g���E���[�r���V���^�C���̂���Ȍ��t�������肵�����B
���Ȃ��̎w�����ɐG���O�ɁA���̋Ȃ��ǂ��e�����A�S�̂Ȃ��ōl���Ă����Ȃ�������Ȃ��B�i�u���y�Ƃ̖����v�w�R�T���ҁE�� ���}�n�E�~���[�W�b�N�E���f�B�A�����j�@���́A������u���̂������O�ɁA���̒��q���ǂ�����̂��A�V�b�J�������������l���Ă����Ȃ�������܂���v�Ɗ������đ��点�Ă��������B�w�R���������ꂽ���̖{�ɂ́A���̂ق��ɂ��A�Í������̑��ȉƁE�����t�Ƃ̊i���E⼌�����������t���Ŏ��^����Ă���B�v���E�A�}��킸�A���悻���y�Ɍg���l�ɂ́A���ɗL�v�Ȓ���ł���B�l���c���ɂ́A���̖{���W�b�N���Ɠǂ�ł����������y�̊�{���V�b�J���Ɛg�ɂ��Ă������������E�E�E�ƐɊ�]������̂ł���B
2010.12.25 (�y) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևN �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v8
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@���u�Ō�̈�t�v�́u�Ō�̊�]�v���ׁ[�X�@�̍�����
�@�I�[�E�w�����[�̖���u�Ō�̈�t�v�ŁA�a�C�̏���l�������O�̖̗t�ɖ��̊�]����� �Ƃ����V�`���G�[�V�����́A�V���[�x���g�u�~�̗��v�̑�16�ȁu�Ō�̊�]�v�ɍ������Ă���B����́A�u�Ō�̊�]�v�̘a��ʂ肠�邱�ƂɋC�Â����̂��L�b�J�P�������B�v���A���́u�N�����m�v�̃X�^�[�g���u�t�B�K���̌����v��ʂ�̉̎��irispetto��dispetto�j�̔����������B���j�͌J��Ԃ��B�@�{�N�x�ŏI��́A�I�[�E�w�����[�͂�����u�~�̗��v�ɐG������ď������̂��H�Ƃ����A���������Z���Z�[�V���i���ȃe�[�}�ɔ����Ă݂����B�A�����J���w�̋S�˂̍ō��̐l�C��i���A�h�C�c�E���[�g�̍ō���ƂȂ����Ă���E�E�E�Ȃ�ƗN�X����e�[�}�ł͂Ȃ����I
�i�P�j��i�̗ގ��_
�@ �e�[�}�̍���
�@�u�Ō�̈�t�v�̕a�C�̏���l���W���[���W�[�́A���O�����Ȃ���u���̗t���ς̍Ō�̈ꖇ��������Ƃ��Ɏ��͎��ʂ́v�Ɠ������Ă��鏗�F�B�X�E�ɘb���B�u�Ō�̊�]�v�̎�l���́u�����A�t����n�ɗ�������@���Ɋ�]���ׂ���̂��v�Ɖr���B���̑O�i�ɂ́u�l�͂��̈ꖇ�̗t�����߁A����ɖl�̊�]��������v�Ƃ��邩��A�V�`���G�[�V�����I�ɂ͑S������Ƃ������ƂɂȂ�B�i���L�u�f�ڎ��v�Q�Ɓj
�A �n���̑���
�@�u�Ō�̈�t�v�ɂ�����"�t����"�̍ŏ��̏Ɋւ��镶�͂͂����Ȃ��Ă���B
�ǂɂ͌͂ꂽ�悤�Ȓӂ���{�A���قǂ܂Ŕ����オ���Ă���B�E�E�E�����E�E�E�W���[���W�[�́u�������������Ȃ��Ă�����B�O���O�ɂ�100�������Ă�������A������̂ɍ����܂ꂽ�̂ɁB�v�ƌ��������A���̐��͂قƂ�Ǖ����Ƃ�Ȃ����炢�ɏ����������B(�Έ�G��)�@����ɑ��āu�Ō�̊�]�v�̖`���́A�u���������̖ؗ��̎}�ɉ������̐F�Â����t�v�ƂȂ��Ă���B�\���́A�Ђ�u100���v�A�Ђ�u�������́v�ł��邪�A�ŏ��͂�������̗t���t���Ă������Ƃɕς��͂Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA����ɂ��ẮA�u��]�v���ɖʔ������ۂ�����B���̕����A�V���[�x���g�̓~�����[�̎���ύX���Ă����̂ł���B�Q�l�̂��߁u�Ō�̊�]�v�S����ēx�f����B
�@�`���́u�������̐F�Â����t�v Manches bunte Blatt�́A�~�����[�̌����ł́u�����c��ꖇ�̗t�v�@Noch ein buntes Blatt�������̂��B���������̖ؗ��̎}�Ɂ@�������̐F�Â����t�������Ă���
�l�͂��̖ؗ��̑O�Ł@���v�����ݗ�������
�l�͂��̈ꖇ�̗t�����߁@����ɖl�̊�]��������
�����l�̗t�ɂ���ނ��@�l�͐k���������k����
�����A�����Ă��̗t���n�ɗ�����Ɓ@����ƈꏏ�Ɋ�]���₦��
�l���n�ʂɂ����ꂨ��ā@�l�̊�]�̕�ɋ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Έ�s��Y��j
�@���̎��̃X�g�[���[��ǂ��ƁA�u���������̖ɕt���Ă��鉽�����̐F�Â����t�̒�����A�ꖇ������I�яo���A���̈�t�Ɂi�����Ȃ��ł���Ɓj�肢��������B���̗t�������Ă��܂��Ζl�̊�]���ׂ���̂��v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@����I�[�E�w�����[�́u��t�v�ł́A�u100���قǂ������t���A���X�ɂ��̐��������āA���ɂ͍Ō�̈ꖇ�ɂȂ��Ă��܂��B���̗t���������Ƃ��Ɏ��͎��ʂ́v�Ə���l���͔��z����̂ł���B100����12���A5���ƒi�X�Ɍ����Ă���Ƃ������A���Ɍ����������ȋٔ�����ł�����B�����A�~�����[���������܂܂ɍŏ�����1�������������Ȃ�A���̓W�J�͂Ȃ��B���_�A�w�����[�́A���́u�~�����[���V���[�x���g�̕ύX�v�܂ł͒m��R���Ȃ��������낤���B�܂��A�V���[�x���g���Ȃ����̕ύX���������ɂ��Ă��A����͂Ȃ��悤���B
�B �x�A�}���ƃ��C�A�[�}��
�@�n�Ӕ��ގq����̃E�F�u�E�T�C�g�u�w�~�̗��x�o�������vNoten zur Winterreise 2008�́u�Ō�̊�]�v�ɂ���ȕ��͂�����E�E�E�u�w�p�J���� II�x�ŁA���̎��͂��傤�ǑO���̍Ō�ɒu����Ă���A���Ǝ��̋��ɂ����Đk���Ă���t�́A�Ō�ɕX�̏�𗇑��ł��߂��Ă���w�҉��y�t�xDer Leiermann�ɒʂ�����̂������܂��v
�@����́A�i�~�����[�̌����ł́j�O���Ō�ɂ�����Ă����12�т�"�h���t"�ƌ㔼�Ō�E��24�т�"���߂��l��"�Ƃ͑��ʂ�����̂�����A�Əq�ׂĂ���̂��B���ɉs���������ɕx�w�E�ł���B�ł́u�Ō�̈�t�v���l�@���Ă݂悤�B
�@�I�[�E�w�����[�u�Ō�̈�t�v�ɂ̓x�A�}���Ƃ����V�l���o�ꂷ��B������l�̊K���ɏZ�݁A��Ƃ�ڎw�������܂��A��������������Ƃ����Ȃ���������N���G�M�������Ă��Ȃ��S�߂ȘV�l�ł���B�N���60���炢���B�ނ̃Z���t���p��̌�������E���Ă݂悤�B�u�W���[���W�[���A��̒ӂ̗t���ς̍Ō�̈ꖇ����������A���ʂ��Č����Ă���́v�ƁA�X�E���獐����ꂽ�Ƃ��ɁA�x�A�}���V�l��������Z���t�̈ꕔ���ł���B
"Vass!"he cried�D"Is dere people in de world mit der foolishness to die because leafs dey drop off from a confounded vine�H I haf not heard of such a thing�D�E�E�E"�@�ꌩ���Ă�������̒ʂ�A�x�A�}���V�l�̉p��͂Ȃɂ��ςł���B�����Ŏ�����V��W �Ad��th�Af��ve���p��Ƃ��Đ����Ȃ̂ł���B���̑��ɂ��Ap��b�Ad��t������ւ���Ă���B�Έ�G�搶�ɂ��ƁA����̓h�C�c�a�̏��Ƃ����B�x�A�}����"�\�\�}��"���A�h�C�c�l�Ƃ��Ă͈�ʓI�Ȑ��̂悤���B�����ŁA���_�E�E�E�x�A�}���̓h�C�c�n�ږ��̈ꐢ�Ƃ��ĕ`����Ă���B�����āA���_�E�E�E�I�[�E�w�����[�́A��ƕ���̗��ގ҃x�A�}���V�l�Ƀh�C�c�a�点�邱�Ƃɂ��A�V���[�x���g�u�~�̗��v�ŏI�͂ɏo�Ă��鐢�̂Đl���y�t�u���C�A�[�}���v�ɋ[�����̂ł͂Ȃ����H
�u�����ƁB���̐��̒��ɁA�͂ꂽ�ӂ̗t�����������炢�Ď��܂��l�Ԃ����邩�B����Ȃ̕��������Ƃ˂����E�E�E�v�i�Έ�G��j
�@�u�Ō�̈�t�v�̃x�A�}��Behrman�́A����̖��ƈ��������ɐl���Ō�̌����`���A�a�C�̏������~���B�u�~�̗��v�́u���C�A�[�vDer Leiermann�́A�͂���҂́u�킽���̉S�Ƀ��C�A�[�̒��ׂ����킹�Ă���Ȃ����v�Ƃ����Ō�̊肢������Ă��B�o���Ƃ�"�l���̗��ގ҂ɂ��l����"�Ƃ������ʍ��B���ׂď؋��ł͂��邪�A"���̕����₢����"�ł���B
�@�Ȃ��A�p��̌����͐Έ�G�搶���炨�݂��������������̂��B���̂Ƃ��ꏏ�ɐ搶�̑S�Ҙa����Y�����Ă����B���ꂪ���Ɍ����Ȃ��̂ŁA�s�̖̂�Ƃ͎����̈Ⴄ��i�Ȃ̂ł���B�����ɂ́A����҂̐l�Ԃ����߂�D�����ڐ��A�o��l���̐������Ƒ��X�̐S�̂Ȃ��肪�I�m�ɕ\������Ă��āA�ǂނ��̂��̃j���[���[�N�����ւƗU���Ă����̂ł���B
�i�Q�j�I�[�E�w�����[�̐l������u�~�̗��v�Ƃ̐ړ_�𐄗ʂ���
�@�I�[�E�w�����[�́A1862�N9��11���A��҂̑��q�Ƃ��āA�A�����J�̓m�[�X�J�����C�i�B�O���[���Y�{���Ő��܂ꂽ�B����҂̏f��̉e���ŁA�{��D���̏������w���N�������Ƃ����B�ނ́A�u����13����19�̊ԂɁA����Ȍ�̂����Ȃ鎞�����������̏�����ǂv�ƌ���Ă���B��҂̕��e�������ɋÂ��Ĉ�Â��ڂ݂Ȃ��Ȃ������߁A���q�͖�t�ɂȂ�ƋƂ��������B
�@���̌�A1882�N�A���̑���ɃO���[���Y�{���ɕ��C�����z�[����t�̊��߂ɂ��A��Ƃ̓e�L�T�X�B�̏B�s�I�[�X�e�B���ɈڏZ�����B�I�[�E�w�����[�̋�P�������������߂ł���B�g�����̂̓z�[����t�̒��j���[���o�c����q�ꂾ�����B
�@�֓������u�w�Ō�̈�t�x�͂������Đ��܂ꂽ�v�i�p��w�|�u�b�N�X�j�ɂ́A�u�e�L�T�X�ɂ́A���đ�ʂ̃h�C�c�ږ������������o�܂�����̂ŁA�I�[�X�e�B���̏Z���̑����͉��y�╶�w�����D����h�C�c�n�A�����J�l�������v�Ƃ����d�v�ȋL�q������B����ɂ́A���[�̒�f�B�b�N�̓h�C�c��̐S��������A�q��ł͉��l���̃h�C�c�l�������Ă��������ł���B�����Ɍ��ꂽ"���y�E���w�E�h�C�c"�Ƃ����L�C�E���[�h�ɂ����A �I�[�E�w�����[�Ɓu�~�̗��v�̐ړ_�̑傢�Ȃ�\���ł͂Ȃ����낤���B
�@���̌�A�w�����[�́A1896�N�A�I�n�C�I��s�Ζ�����Ɍ������̂̍߂őߕ߂����B���@�́A�|�������Ă������h�T�����o�ʼn�Ђ̐Ԏ��̌����߂Ƃ��ꂽ�B
�@1898�N����3�N�Ԃ̕����𑗂邪�A���̊Ԃ͖͔͎��Ƃ��āA�Y�������O�ł̎�ނ⎷�M��������Ă����B1901�N�A�ߕ��B1902�N����͒P�g�j���[���[�N�Ɉڂ�Z�݁A�{�i�I�ɍ�Ɗ������J�n����B��Ȕ��\�̏�́u�j���[���[�N�E���[���h�v���������B
�@�����Đ��ɁA1905�N10��15���A�u�Ō�̈�t�v���u�j���[���[�N�E���[���h�v���j�łɌf�ڂ��ꂽ�B�I�[�E�w�����[���g������������ɂ́A�u�I�[���h�E�j���[���[�N�ɏZ�ޓ�l�̎Ⴂ������ƂƁA���U�̏I���ɔ������킪�g���]���ɂ����V�������ގ҂̕���v�Ƃ������B
�@�����ŁA���ڂ��ׂ�����������B1902�N�A�E�B���w�����E�~�����[�́u�\�l�b�g�v���A1903�N�ɂ́u���L�A�莆�v���A�n�b�g�t�B�[���h�Ђ���o�ł���A�j���[���[�N�𒆐S�Ƀ~�����[�����M�����܂����Ƃ����Ă���B�D��S�������T�����×~�Ȕނ��A�~�����[�ɋ����������A��\��i�u�~�̗��v�ɒH�蒅�����\���͏\������Ǝv���B
�i�R�j�G�s���[�O
�@�I�[�E�w�����[�Ɓu�~�̗��v�̐ړ_��T�闷�����낻��I���ɋ߂Â����B�u�Ō�̊�]�v���t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�����[�A�̃��m�����ՂŒ����E�E�E�s�A�m�̑O�t���A�������ɂЂ�Ђ�ƕ���������͗t��\������B�W�X�Ɖ̂��o���g���̐����A�Ō�ɂ͐����ȋF��ƂȂ��ē˂��h����B�u���C�A�[�v���E�E�E�^�̉����������s����Șa���������I�ɋ������A�����̂Ă����C�A�[�e�����ӂ�ӂ�ƕX�������B����ȔN�V�������̂Đl�ɁA���̒�����a�O���ꂽ�����҂͍Ō�Ɏ����̉S�̔��t���˗�����B�~�����[�̌����W�ł�12�Ԗڂ�24�Ԗڂ̂��̓�Ȃ��Ă���ƁA�I�[�E�w�����[�́u�~�̗��v��m���Ă����Ƃ����v���Ȃ��Ȃ�B�a�C�̏���l����~�̂����炢�l�ɁA��ƕ���̘V�������ގ҂����C�A�[�̘V�l�ɁA�[�����Ƃ����v���Ȃ��̂ł���B
�@ �@�������Ɋ�ȕ����ɋC�������B�u�Ō�̈�t�v�ŁA������l���́A���Ȃ��Ȃ����t���ς��A���ۂɐ����n�߂�B
�W���[���W�[�͑傫�Ȗڂ������Ă����B���̊O�����Ȃ��牽���𐔂��Ă���B���̐������͂ӂ��̋t�������B�u12�v�ƌ����Ă��炵�炭����ƁA�u11�v�ƌ������B�@�Ȃ�ƁA12���琔���Ă���B�~�����[�����߂��u�Ō�̊�]�v�̒ʂ��ԍ�12����I����͒P�Ȃ���R���낤���H���炭���R���낤�B�������A�u12�A11�E�E�E�v�ƕ��ʂɃJ�E���g�E�_�E�������ɁA�u12�ƌ����Ă��炵�炭����Ɓv�E�E�E�ƁA12����ʂȐ����ł����邩�̂悤�Ɋ����Ă���̂ł���B������A�ނ͂���ɈÍ������߂��̂ł͂Ȃ����\�\ �I�[�E�w�����[�E�R�[�h�H
�@����Ȋy�����z�������Ă�����A������A���������������������B�I�[�E�w�����[�̐��܂ꂽ����9��11���B�Ȃ��911�́A�u�~�̗��v�̍�i�ԍ�D�i�h�C�b�`���j911�ƕ��������̂ł���B�I�b�g�[�E�G�[���q�E�h�C�b�`���i1883�|1967�j���u�V���[�x���g�N�㏇��i�\��ژ^�v�����������̂�1951�N�B�^�C�g���ɂ���悤�Ƀh�C�b�`���ԍ�D�͍�i�̊�����������A���ꂱ���P�Ȃ���R�ł���B���������A���̕����́A�^���𖾂Ɍ����ɂȂ��ăg���C�������ւ̐_�l����̃N���X�}�X�E�v���[���g�̂悤�ȋC�����āA�Ȃ�ƂȂ��������Ȃ����B
�@�ł́A�F�l�A�������N���I�N�����܂��V���[�x���g�ł���������܂��傤�B
2010.12.10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևM
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v7 ���V���[�x���g�ƃI�[�E�w�����[��
�@�u�~�̗��v�ɖ������Ă���A����Ɋւ���CD��{�Ȃǂ����\�w�����Ă���A���݂��̃��C�u�����[�́u�~�̗��v��CD��20��A�V���[�x���g�֘A�{��6���قǂɂȂ��Ă���B����Ȑ܁A��16���u�Ō�̊�]�v�̓��{���ʂ肠�邱�ƂɋC�������B
[A]�@[A]�ł͂܂��t�͗����Ă͂��Ȃ����A[�a]�ł͗����Ă��܂��Ă���B���C�u�����[�����ׂČ�������A�Έ�s��Y�A����ΗY�A�b��M��e����A�A�~�Î���ÁA�쑽�����~������B�Ƃ����d�����ɂȂ����B
���������̖ؗ��̎}�Ɂ@�������̐F�Â����t�������Ă���
�l�͂��̖ؗ��̑O�Ł@���v�����ݗ�������
�l�͂��̈ꖇ�̗t�����߁@����ɖl�̊�]��������
�����l�̗t�ɂ���ނ��@�l�͐k���������k����
�����A�����Ă��̗t���n�ɗ�������@����ƈꏏ�Ɋ�]���₦��
�l���n�ʂɂ����ꂨ��ā@�l�̊�]�̕�ɋ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Έ�s��Y�� F�D�f�B�[�X�J�ECD�Ζ���j
[B]
����ق�ƖX�Ɂ@�F�Â��Ă���t��������
����Ȗ؉��ɗ����~�܂�@�悭���v���ɂӂ���
�ꖇ�̗t�����߁@��݂����
�����l�̗t�����Ă����Ԃ���@�̂̐k�����Ƃ܂�Ȃ�
�����A���̗t���n�ɗ������@��݂�������
�l�������ꂨ��@��݂̕�ɋ�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�~�Î���Ö�u�~�̗�24�̏ے��v���j
�@�O��܂łɏ������Ƃ���A�~�����[�͊�]���̂ĂĂ͂��Ȃ��B�V���[�x���g�����Đ��������C�����ɕς��͂Ȃ��B���ꂪ[B]�ł͊��S�Ɋ�]�������Ă��܂��Ă���B���́A�܂������Ɋ�]���c��[A]�ł����ė~�����Ǝv�����B�����Ў�ɉ�ǂ����݂���A�h�C�c��ɂ܂�Ŏア���ɂ͔��ʂ����Ȃ��B�����ŁA�������Ƃ��̐Έ�G�搶�ł���B�����u�搶�A��̂ǂ��炪�������̂ł��傤���H�v�ƕւ�������B���̊ԁA�C���^�[�l�b�g�Łu�~�̗��v�Ɓu�Ō�̊�]�v�����Ă��邤���ɂ��̐����T�C�g�Ǝ��M�҂ɑ��������B
 �@�u�~�u�̋ȉ�فv�Ƃ���Web-Site�������āA�����Ɂu���̎��A�킽���͕��ɖ|�M���ꂽ�͗t���n�ʂɗ������ʂ̕`�ʂƎv������ł����̂ł����A�~�����[�ƃV���[�x���g�̌����ғn�Ӕ��ގq����ɂ��"���@�I�Ɍ��Ė��炩�ɗt�͂܂������Ă��Ȃ�"�Ƃ��������Ɋ�����J���ꂽ�Ƃ���ł��v�Ƃ������͂��������B������������͍̂b��M�炳��B�u�~�u�̋ȉ�فv�̎�Ɏ҂Œ��W���̉̋Ȓʂ��B�����ɂ���n�Ӕ��ގq����ɂ́u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v�Ƃ������m�_���������āA����͍b�コ��̉�Ёu��Ǔ��v�Œ��̂��Ă����B�n�ӂ�������g��HP�������Ă���A���̒��Ɂu�w�~�̗��x�o�������vNoten zur Winterreise2008�Ƃ����R�[�i�[������B�o����ǂ�ł�����A���̂���l�͂��̐������X���Ƃ������Ƃ��������Ă����B�Ƃɂ������ɂ��[���̂ł���B�����\�Ȏ����ɂ͂��܂Ȃ��������Ă��邩��A���̎��ؐ��͌��O��ɍ����B���̓ǂ݂̐[���Ƃ����A�Ȃւ̐荞�݂̉s���Ƃ����A�����̐��k���Ƃ����A�킽���������Ă���u�~�̗��v�{���ׂĂ𗽉킷�鍂�݂ɒB���Ă���B���ꂵ���Ȃ��Ǝ蔏�q�œn�Ӕ��ގq���u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v���w�����Ă��܂����B�喇1���~�I �ł��S�R�����Ȃ��B�~�����[�̑����猩���u�~�̗��v�����j�Ƃ��āA����͐��E�ł��ނ����Ȃ��G��ȕ������Ǝv���B�b�コ��ցA���ׂ̘A���ƂƂ��ɂ��̎������[��������A�u�ԈႢ�Ȃ������ł��傤�v�Ƃ̕ԐM�������������B�������Z�����ēǔj����̂Ɏ��Ԃ͊|���邪�A����u�N�����m�v�̒��Ő܂ɂӂ�ĂƂ�グ�Ă䂫�����Ǝv���Ă���B
�@�u�~�u�̋ȉ�فv�Ƃ���Web-Site�������āA�����Ɂu���̎��A�킽���͕��ɖ|�M���ꂽ�͗t���n�ʂɗ������ʂ̕`�ʂƎv������ł����̂ł����A�~�����[�ƃV���[�x���g�̌����ғn�Ӕ��ގq����ɂ��"���@�I�Ɍ��Ė��炩�ɗt�͂܂������Ă��Ȃ�"�Ƃ��������Ɋ�����J���ꂽ�Ƃ���ł��v�Ƃ������͂��������B������������͍̂b��M�炳��B�u�~�u�̋ȉ�فv�̎�Ɏ҂Œ��W���̉̋Ȓʂ��B�����ɂ���n�Ӕ��ގq����ɂ́u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v�Ƃ������m�_���������āA����͍b�コ��̉�Ёu��Ǔ��v�Œ��̂��Ă����B�n�ӂ�������g��HP�������Ă���A���̒��Ɂu�w�~�̗��x�o�������vNoten zur Winterreise2008�Ƃ����R�[�i�[������B�o����ǂ�ł�����A���̂���l�͂��̐������X���Ƃ������Ƃ��������Ă����B�Ƃɂ������ɂ��[���̂ł���B�����\�Ȏ����ɂ͂��܂Ȃ��������Ă��邩��A���̎��ؐ��͌��O��ɍ����B���̓ǂ݂̐[���Ƃ����A�Ȃւ̐荞�݂̉s���Ƃ����A�����̐��k���Ƃ����A�킽���������Ă���u�~�̗��v�{���ׂĂ𗽉킷�鍂�݂ɒB���Ă���B���ꂵ���Ȃ��Ǝ蔏�q�œn�Ӕ��ގq���u���B���w�����E�~�����[�̎���Ɛ��U�v���w�����Ă��܂����B�喇1���~�I �ł��S�R�����Ȃ��B�~�����[�̑����猩���u�~�̗��v�����j�Ƃ��āA����͐��E�ł��ނ����Ȃ��G��ȕ������Ǝv���B�b�コ��ցA���ׂ̘A���ƂƂ��ɂ��̎������[��������A�u�ԈႢ�Ȃ������ł��傤�v�Ƃ̕ԐM�������������B�������Z�����ēǔj����̂Ɏ��Ԃ͊|���邪�A����u�N�����m�v�̒��Ő܂ɂӂ�ĂƂ�グ�Ă䂫�����Ǝv���Ă���B�@�b�コ��̕��͂͂��������Ă���B�u���āA�~�����[�̌����ł͎c���ꂽ�Ō�̈ꖇ�̗t�ł������A���ꂪ�������ʂ��Ȃ����Ƃ��܂߁A�܂��܂��I�[�E�w�����[�w�Ō�̈�t�x�ɍ������邱�ƂɂȂ�̂������[���Ƃ���ł��B�N�ォ�猩�ăw�����[���w�~�̗��x��m���Ă������Ƃ͏\���l�����܂����A���Ă͖����̍��������~�����[�̎��W��ڂɂ����\�����[���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��v
�@�ւ��A�Z�҂̖���I�[�E�w�����[�i1862�|1919�j�̖���́u�~�̗��v�́u�Ō�̊�]�v���q���g�ɂ����\��������̂��B���ꂼ�܂��Ɂu�N�����m�v�I�I �����ŁA�b�コ��ɂ́A�~�����[���W�ƃI�[�E�w�����[�Ƃ̊֘A�ɂ��āA�n�Ӕ��ގq�����HP�����܂��āA����[����ł����B������Ȃ����Ƃ͒B�l�ɕ����Ɍ���B
�@�����������Ă��邤���ɁA�Έ�搶����Ԏ����͂����B�搶�̓��[�����Ȃ���Ȃ��̂ŗX�ւł���B
�@�u�����́w�����A���̗t����������A���̂Ƃ����̊�]�������Ă��܂��̂��x�̈Ӗ��B�w�������x�Ȃ�ߋ��`�ŏ�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����͌��`�Ȃ̂ŁA�����iwenn�j���ȗ�����Ă���̂ł��B�h�C�c��ł͂悭����\���ł��B�̐l�ł����Έ䎁�͓���ƕ��Ȃ̏������B�Ђ�~�Â���͖����V���̋L�ҁB��͂�Έ䎁�̂ق����������Ă��܂��ˁB�Ƃ���ŃI�[�E�w�����[�Ƃ��������ƂɁw�Ō�̈�t�x�Ƃ����f���炵���Z�҂�����B�ǂ�ł����Ȃ����v
�@�킪�ӂ���A�����āA�܂�����I�[�E�w�����[�A�����鑘���I �Ȃ�����u�Ō�̈�t�v��ǂނ����Ȃ��B���A�p�앶�Ɂu�I�[�E�w�����[����W�@�v�i�ѓ��~�G��j����葦�ǁB���炷���͈ȉ��̒ʂ�B
�@�j���[���[�N�̓O���j�b�`�E���B���b�W�̉�Ƒ��ƌĂ���p�ɁA�X�E�ƃW���[���W�[�Ƃ�����Ǝu�]�̓�l�̏������Z��ł����B���ǂ��̓�l�͎O�K�̕����ŋ������������Ă���B�Ƃ��낪�A���̂����̈�l�W���[���W�[���A�����҈Ђ�U����Ă����x���ɜ���Ă��܂��B��҂̓X�E�Ɂu���������B�C�����œ�������A�����錩���݂͂Ȃ��B�v�Ɛ鍐����B��҂̌���m���Ă��m�炸���A�W���[���W�[�́A���̊O�������u�������Ă�t���S���������Ƃ��Ɏ��͎��ʂ́B���̋���������������ˁB�����������t������12���E�E�E�E�v�ȂǂƁA�F�B�����点���C�Ȕ����B �ޏ������̊K���ɂ́A��X�u��������������Ă��v�ƌ����Ȃ��疢�����̐��ʂ������Ă��Ȃ��x�A�}���Ƃ�����ƕ���̘V�l���Z��ł���B�ނ����̗��s�a�Ɋ|�����Ă����B�X�E���炱�̘b�����x�A�}���́A�u����Ȃ����l���A�w�t���ς��S���������玀�Ⴄ�x�Ȃ�Ă܂�ƌ����Ă�A�����x�x�������Ăv�ƕ���B���̔ӃW���[���W�[���A���ɍŌ�̈ꖇ�ɂȂ����t�����āA�u����͗������B���͎��ʂ́v�ƌ����Ė���ɂ����B���̖�͂��������ɂȂ����B�����A�N�����W���[���W�[�Ɂu�u���C���h���グ�āv�Ƒ����ꂽ�X�E���A���鋰��J�[�e�����J����ƁA�Ȃ�Ƃ܂��t���ώc���Ă���ł͂Ȃ����B��������Ƃ߂��W���[���W�[�́A��R���C���o���̂��낤�A�u�i�|���p��`���ɍs��������v�Ǝ��������Ă��閲�����o������������B���炩�ɋC������������Ă���B���f�ɗ�����҂́u����ŏ�����]�݂͌ܕ��ܕ��ɂȂ����B���Ƃ͂��̊ŕa���悶��v�ƃX�E�Ɏ��ł������B�u�����A�K���̏Z�l�̕��͌����݂��Ȃ��B�������@������v�Ƃ��B�����A��҂̓W���[���W�[��f�āu��@�͒E�����B������������v�Ɗ����������Ă��ꂽ�B���̓��̌ߌ�A�a�@�Ńx�A�}��������������������Ƃ����X�E�́A�W���[���W�[�Ɍ������Ă����������B�u�����x�A�}�����x���ŖS���Ȃ����́B���@���Ă������̓���łˁB���@�������̒����A��Ƃ��A���ԔG��ɂȂ��ĘL���ɂ������܂��Ă����x�A�}�������������ł����āB����ȂЂǂ����̔ӂɈ�̂ǂ��ɍs���Ă����̂��H�E�E�E�N�ɂ�������Ȃ��������ǁA���ɂ͕��������́B��q�͂����̂Ƃ��납��O���Ă����āA�����ɂ́A�܂��̂��������^���Ɖ��F�Ɨ̍��������G�̋�̕t�����p���b�g�����������Ă�������B���Ȃ��A�悭���Ă����Ȃ����B���̗t���ρA���������畗�������Ă������Ƃ��h��Ă��Ȃ��ł���B����͂ˁA�x�A�}�����������G�Ȃ́B���Ȃ����܂����߂ɏ������ނ̍Ō�̌���Ȃ̂�v
�@���Ԃ���͂���Ă��܂�����łȘV�l���A�����̖��ƈ��������ɏ����c�����Ō�̍�i�ŁA�Ⴂ�����̖����~���B�Ȃ�Ƃ������I�ȕ���ł���B��䍂������قǁu�Ō�̊�]�v�̃V�`���G�[�V�����Əd�Ȃ��Ă���B�I�[�E�w�����[�́u�Ō�̊�]�v���x�[�X�Ɂu�Ō�̈�t�v���������A�Ɗm�M�I�Ɏv���Ă���̂��B
2010.11.29 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևL
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v6 ���u�~�̗��v�͖l�̕��g��
�V���[�x���g�̎莆���̎l�u���Ɋ���������v�i1827�N10��31���j�@�e���Ȃ�V���p�E���N�A�u�~�̗��v�����Ɋ��������B�v�����N��1���Ƀ~�����[�̃e�L�X�g�ɏo����Ĉȗ��A��10�������o�߂����ˁB�u��ꕔ�v�i�O�ҁj12�Ȃ͖l�̉S�ŌN�ɂ������Ă�����Ă����ˁB���̂Ƃ��݂͂�ȃ|�J�[���Ƃ��Ă������A���̂��ƃt�H�[�O���ɉ̂��Ă�������肵�Ă��邤���ɁA����ɂ��̋ȏW���D���ɂȂ��Ă��Ă��ꂽ��ˁB�Ƃ��낪�����ɓ����āA�l�́u��v(���)���������B���ꂪ24�т́u�����Łv�Ƃ��Ĕ��\����Ă��đ傢�ɍ��f�������Ƃ́A�O�ɂ��������Ƃ��肾�B����Ȓ��A����Ɩl�̒��Ő��������āA�ȍ��ɏW���ł���悤�ɂȂ����̂͌N�ւ̕ւ�����������������B�����Ȃ���߂����́B�u��v12�Ȃ���������̂ɁA�������鎞�Ԃ͊|����Ȃ�������B�����o����������̂�����A���x�̃e�B�A�[�f������Œ����Ă��炦�����̂�����ǁA�N�ɂ́A�ǂ����Ă����ܘb���Ă��������B�����t�������Ă���Ȃ����A��Z�ɏ�������B
�@�u��v�́u�X�֔n�ԁv����n�܂�B����̓~�����[�̃e�L�X�g�ł�6�Ԗڂ̎����B�܂��A�����̓��C�\�������̒�ԁ�3�̕σz�����ɂ����B���Y����3���q�n��6�^8���q�B����Łu��v�̊J�n�͏��̂悢���邢�Ȓ��ɂȂ����B���_����̓t���[���C�\���A�~�����[�ւ̃I�}�[�W���ł�����B������A���̂��Ƃ̃��C�\���ԍ��̎��ɂ͓��Ɉӎ����ċȂ�t�����B����ɂ��Ă��A�ނ����̎����u�����v�Ɓu���ӂ��܁v�̊Ԃɓ���Ă���̂������Ƃ��́A���炭�˘f������B������̂��ƂȂ̂ɂȂɂ���̂̂悤�ȋC������B
�@���Ȃ郁�C�\���ԍ��Ȃ̓e�L�X�g12�́u�Ō�̊�]�v�i�l��16�j�B"��]"��������Ō�̈�t�́A�܂���̔�ꖇ�łȂ����Ă���B�u�������狃�����v�Ƃ͌����Ă��邪�A�t�������ĂȂ��̂�����܂������Ă͂��Ȃ��B��ꕔ�ł́u�������܁v��u���ӂ��܁v�v�Ȃŋ����܂����Ă���̂ɂˁE�E�E�B�����͍ēx���C�\�������̕σz�����ɂ�������ǁA�������Ɋ낤���������o���Ă݂��B�͗t��������悤�ɂˁB���������āu�Ō�̊�]���������v�Ɗ��Ⴂ����l���o�Ă��邩������Ȃ����A���߂̘a���������łȂ����Ƃ�������Ǝv���B���q��3�^4���q�ō�����B
�@15�u�܂ڂ낵�v�́A�u�X�֔n�ԁv�Ɠ������A�ŏI�i�K�Ń~�����[�����C�\�����ԂɊ��荞�܂��������B"�����Ɋ����Ęf�킳��Ă݂悤"�Ȃ�Ċ��o�́A�܂��Ƀ��C�\���������������ˁB�l�̂ł�19�Ԗڂ̂��̋Ȃ́A6�^8���q�̂������Ɨ����悤�ȃ��Y���ɏ悹�ėD��Ŕ����������f�B��t���Ă݂��B�����l�����������邩�d�C�������邩�͎��R���B�^���I�Ƃ����l�����邩������Ȃ��ˁB�����̓C�����A����́�3�B
�@�~�����[���u���̑��z�v���u�t�̖��v�̑O�Ɋ��荞�܂������߂Ɂu�t�̖��v��21�̃��C�\���ԍ��ɂȂ����B���̗���ɉ�����Ӗ������͑O��̎莆�ɏ��������ǁA����ł��邱�̋Ȃ́�3�̃C������6�^8���q�ŏ����Ă����B������ӎ����������ǁA�Ȃɂ��^���I�Ȃ��̂�������B������l���w�E���Ă��������̂́A13�u���ɂāv�Ń~�����[�́u�킽���͂��ׂĂ̖������ʂĂ��v�Ə����Ă��邱�ƁB������A���̂��ƂɁu�t�̖��v�������Ă��邱�Ƃ́A���炩�ɖ������邱�ƂɂȂ�B���t�ɕq���Ȕނ�����Ȃ��ƂɋC�Â��ʂ킯���Ȃ��B����ł������Ă�����Ƃ����Ȃ�A�ނɂ͂ǂ����Ă����́u���̑��z�v�\�u�t�̖��v����I���܂łɌ��������ꂪ�~���������Ƃ����A����͊m���ȏ؋����Ɩl�͎v���B�O�����u�h�v���u�S�v�̕s���R���Ƌ��ɂˁB
�@�u���̑��z�v�̓e�L�X�g��20�����烁�C�\���ԍ��ł͂Ȃ�����ǁA"3�̑��z"�����ނƂ����e�[�}���B�~�����[������3�Ƃ������C�\���������g���Ă������A�l�������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�����ŁA�����́�3�̃C�����Ŕ��q��3�^4�ɂ����B ���݂ɁA�e�L�X�g9�u������݁v��18�u�S�v�́u��ꕔ�v�̋Ȃ����A���X3�^4��3�^8�ƎO���q�n�ȂB����ŁA6�A9�A12�A15�A18�A21�A24�͂��ׂĎO���q�n�ɂȂ�����B�������͋��R�����ǁA�Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȕ������Ǝv���B
�@��ԋC�ɂȂ����u�E�C�v�́A�ł����C�\���I�Ȏ��Ȃ��A�e�L�X�g�ł�23�ԖځB�l�̋ȏW�ł�22�Ȗڂ��B������A�����ɂ͍S�炸�ɋȒ��ʼn����܂�������B���������t���[���C�\���ւ̓���̊��т��̂��悤�ȗ͋����s�i�ȕ��ɂ����B�o�J�`�����ɂȂ�Ȃ��悤�ɒZ���ɂ͂������ǂˁB���������͍̂l�������Ȃ��ŃX�g���[�g�����������B������܂��A�u���̑��z�v�Ɠ���ւ�������o�������Ƃ����ǁB
�@�����ŁA��������Ƃ��Ă������Ƃ�b���Ă������B�~�����[��4�u�X���v�̎������������Ă����B
�@�@�@�@���̐l�����̘r�ɂ������ā@�̖�����������Ղ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�ꏏ�ɖ��ʂ�@�������������ΎU���@����
�@�~�����[�͂Ȃ����������߂��\���ɕς��Ă���B���̋Ȃ̃|�C���g�́A���̂��Ƃɑ����߂̌㔼�u���̔M���܂� ��ƕX��n�����������v�ɂ����ĂˁB�l�́A���̕��������`�����_�g�����ĔM���C���������߂��B�������������ł͂��̎v���������Ă��Ȃ��B������l�͉����O�̂܂܂ɂ����B��������Ƃ���Ă������������Ƃ����B
�@ �@�����A���悢��24�u���C�A�[�v���B����̓~�����[�̃e�L�X�g���l�̋ȏW�������Ō�ɒu�������ʂ�̏I�ȁB6�Ȗڈȍ~�o���œ����ԍ������̂͂��ꂾ�����B�l�͂��̎����A�u�~�̗��v�Ƃ������\�L�̘A��̋ȏW�̍Ō��������̂ł����āA�{���ɂ悩�����Ǝv���Ă���B���̎��̒��ɁA�� Liedern �Ƃ������t���ŏ��ōŌ�ɏo�Ă������炾�B���̌��t���������Ƃ��̖l�̋C�������Ȃ�Ƃ����ĕ\�������炢���̂��낤�B�u���̑��z�v�ŗB��c�������z�Ƃ́u�́v�������Ɗm�M�����l�̐S�̐k�����A�V���p�E���A�N�Ȃ炫���ƕ������Ă����͂����B���̌��t���������u�ԁA�ȕt���͏I����������R��������B�����͊J�����Z���̃C�Z���ɂ����B�������Ȃ����̐��E����肽���������炾�B�����Ă����Ε����邯�ǁA�s�A�m�̍���͏�ɋܓx[���E�~]�̘a����ł������čŌ�܂Ŏ~�܂邱�Ƃ����Ȃ��B�s�A�m�̉E��Ɖ̂͑�l�߂܂Ō����Č���邱�ƂȂ��i�ށB56���ߖڂ�"���̉̂�"meinen Liedern�̂Ƃ���ŏ��߂ă��C�A�[�Ɖ̂������B�s�A�m�̉E��̓��ƃh�A�̂̓~�łˁB�����A���̋Ȃ̎�a�����h�~�������ŏ��߂Č`�������B�s���ł����Ȃ������ܓx�̘a�����Ō�̍Ō�ʼn������}����̂��B
�@�@�@�@Willst zu meinen Liedern�@Deine Leier dreh'n�H
�@�@�@�@���̉̂� ���O�̃��C�A�[�̂���ׂ����킹�Ă���邾�낤���H
�@����Ŗl�̘b�͏I��肾�B�u�~�̗��v�����������āA���̐����ŌN�Ɏ莆���������B�u��ꕔ�v�͗��N���X�o�ł����܂������A�u��v�͂��ɂȂ邾�낤�B�܂��܂��ׂ����Ƃ�����C������K�v�����肻�������ˁB
�@������ɂ��Ă��A���̋ȏW�͖l�����������܂ł̂ǂ̍�i�����C�ɓ����Ă���B���̓��e�ɂ��^�ɋ��������B�e�L�X�g�Ƃ���ȏo��������āA���̂��A�ł���قǐ����̌`���l��������ꂽ���Ƃ͂Ȃ������B�����āA�g���S�������̂���������𒍓����č������B��Y���������炱���������[���B�����A�u�~�̗��v�͖l�̕��g���B�N���܂߁A�e�B�A�[�f�̒��Ԃɂ͂����ɂ������Ă��炢�����B�����Ɩl�������Ă���Ӗ����������Ă����Ǝv���B�����āA�N�����ȊO�̐l�����ւ��A�L���傫���`����Ă������Ƃ��m�M���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�̐e���ȗF�l �t�����c�E�V���[�x���g
2010.11.19 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևK
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v5 ������ł��ׂĂ��ǂ߂��I��
�V���[�x���g�̎莆���̎O �u�w�E�C�x�̈ʒu��ւ��悤�v�i1827�N10��25���j�@�V���p�E���N�A���C�ł����B���������A���N�̂�����ɁA�݂�ȂŃV���[�o�[�̉Ƃɍs���A�N�������ԂɁu�~�̗��v�O�҂�l�̉S�Œ����Ă���������Ƃ���������ˁB�̂��I�������݂�ȉ����ق�������āA���炭���ăV���[�o�[���u�w�����x�����͋C�ɓ������E�E�E�v�ƈꌾ����ƙꂢ���B������Ėl���u���̋ȏW�͂ǂ̋Ȃɂ������ċC�ɓ����Ă���B�N������������͋C�ɓ����Ă���邾�낤�v�ƌ��������ƁA�����Ă����ˁB���u��ҁv�����ɓ������āA���̋C�����͏������ς���ĂȂ��B
�@���āA�u�E�C�v�̈Ӗ����t���[���C�\�����L�C�ɂ��ĉ������Ƃ��ł����̂́A�O�b�������Ƃ��肾�B�~�����[���t���[���C�\���������͎̂��������A���̊ϓ_����u�����Łv���X�Ɍ������Ă݂����̂ŁA�������炭���t�������肢�����B
�@�u�����Łv����������鏭���O�A�~�����[��10�тő��҂\���Ă����炵���B������2�Ȃ�lj����āA�S24�Ȃ́u�����Łv���ł����킯�����A����2�ȂƂ́u�X�֔n�ԁv�Ɓu�܂ڂ낵�v�������Ƃ����B�l�͂��̎�������A�~�����[���t���[���C�\���Ƃ���12�{12�A���Ȃ킿3�̔{���ł��郁�C�\�������ɍS�������Ƃ��m�M������B�����v���āA�e�L�X�g�̏��Ԃ����߂Ē��߂Ă݂��B�u�X�֔n�ԁv�Ɓu�܂ڂ낵�v��6�Ԗڂ�15�Ԗڂɒu����Ă���B�܂��Ƀ��C�\���ԍ����B���e�����邭���C�\���I�ł͂Ȃ����B����ɂ��̑��̃��C�\���ԍ��ɛƂ܂��Ă���V������Ă݂�ƁE�E�E12�́u�Ō�̊�]�v�ŁA"��]"�̓��C�\���̊�{���O�ɒʂ���B���e�͊m���ɐ�]�I�����A��̔�ꖇ�Ŏ~�܂��Ă���B��]�͎���ł͂��Ȃ��B24�u���C�A�[�v�ɂ́A���߂ēo�ꂷ��"�l��"�ɖ₢������Ƃ������W�B��̃V�`���G�[�V����������B���̂悤�ɁA���C�\���ԍ�6�A12�A15�A24�ɛƂ܂��Ă���V��́A���C�Ƀt���[���C�\���I�ł͂Ȃ����B21�́u�t�̖��v�͋��삾���A���̑O�ɂ킴�킴�V��́u���̑��z�v����ꂽ�̂́A�����I�ȈӖ������̂ق��ɁA�����Ƒ傫�ȗ��R������̂�������Ȃ��H ����₱���ƍl���Ă����Ƃ��A�}�ɖl�̒��ɑM�����̂��������B�������A�~�����[�́u�~�̗��v�Ƃ����Â���邹�Ȃ��悻�҂̔ߌ����A�͂��Ȋ�]�����o���Ȃ���Ȃ�Ƃ����݂Ƃǂ܂��Đ����悤�Ƃ���O�����ȗ���ɕς����������̂ł͂Ȃ����B���҂�����Ă���Œ��ɁA�ނɉ��炩�̕ω��������A�S���ɋ���ȃ��C�\���I�Փ����������̂ł͂Ȃ����낤�����ĂˁB������Ɠǂ݂�����������Ȃ�����ǁB
�@�u�O�ҁv�ł́A�Ђ����玀���݂߂�悻�҂̑a�O�����������Ȃ������l�����A�u�����Łv�ł͂Ȃɂ������]��тт��O�����Ȏp����������̂��B���̃|�C���g�́A20�u���̑��z�v����I���Ɍ���������ɂ���Ɩl�͌����B
�@�u���̑��z�v��"�i�O���鑾�z�̂����j��Ԃ�����͂�������ł��܂����B���̎O�ڂ̓z������ł��������I �ł̒��ɂ���������͂���ۂlj������낤"�ƌ����B�O���鑾�z���S�����ނ̂�����Ă͂��邪�A��͎c���Ă���ˁB���R�Ƃ��Ďc���Ă���B�����ɂ��ẮA���ƂɂȂ��Ă��낢�댾���y���o�Ă��������Ȃ��B�E�[���A�Ⴆ�A�O�Ƃ̓L���X�g�����_�ɑ���u�M�v�u���v�u��]�v���Ƃ��A�c���Ă���͉̂��Ȃ̂��Ƃ��ˁB�l�͂��������c�_�͂��܂�Ӗ����Ȃ��Ǝv���B����͓ǂi�������j�l�����X�����Ƃ������Ȃ����Ȃ��B�ł͖l�͂ǂ����߂��邩�H�c���Ă��鑾�z�Ƃ͉����Ƃ����A����͂��Ƃɑ���21�u�t�̖��v�́u���v��������A22�u�ǓƁv�́u���v��u���v�A23�u�E�C�v�́u�E�C�v���ƒP���ɍl����B ������A�u���̑��z�v��20�ɒu�����ƂŐ����邱�Ƃ������O�����Ȏp����������̂��B�~�����[�͂��̗������肽��������Ȃ����낤���B
�@�l�����߂��u��ҁv�̏��Ԃł́A�I�Ղ�22�u���̑��z�v23�u�E�C�v24�u���C�A�[�v�ƂȂ�B���ꂾ�Ɓu���̑��z�v�Ŏc������̑��z�ɂ́u�E�C�v���܂܂�邱�ƂɂȂ�B����͖l�ɂ͂��܂�Ȃ��B�l�����ėE�C�������Đ������������B�����ǁA�����100���s�\�ȂB�N���m���Ă̒ʂ�ˁB�V���p�E���A������x�u�E�C�v�Ƃ�������ǂ�ł��ꂽ�܂��B���ْ̈[���̂悤�Ȏ������X�O�ɒu���āA�u���C�A�[�v�Ɍq�����邾�낤���H 24�u���C�A�[�v�̍Ō�ŁA��l���͕�����y�t��"���̉̂� ���O�̃��C�A�[�̂���ׂ����킹�Ă���邾�낤���H"�Ɩ₢������B�u�́v�Ƃ������t�����߂ďo�Ă���B�l���Ђ�����̂�Nj����Ă������Ƃ́A�݂�Ȃ��m��Ƃ��肾�B�Ō�Ɏc�������z�́u�́v�ł��肽���B�u�E�C�v�͂���Ȃ��B�Ӗ�������������y�I���ꂩ����A�l�͂ǂ����Ă��u���̑��z�v�Ɓu���C�A�[�v�ڌq�������B����ɂ́u���̑��z�v�Ɓu�E�C�v�̈ʒu�����ւ���K�v������B22�u�E�C�v23�u���̑��z�v24�u���C�A�[�v�Ƃ������Ԃɕς��邱�Ƃ��B
�@���̗���Ȃ�l�̋C�����Ƀs�b�^���ƍ��v����B�~�����[��������t���[���C�\���I�O�����ȗ��ꂪ�A�̂��c���Ă��̐��ɕʂ��������i�Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�l�̗���ɕς��B�������A�u�O�ҁv�Ɓu��ҁv���X�̏��Ԃ́A�e�L�X�g�̂ƕς����ɂ��ށB�u���̑��z�v�Ɓu�E�C�v�����ւ��邾���ŁB
�@�����ЂƂb���Ă����������Ƃ�����B�l�́u������ׁv�̒��̌��t����ς������Ă�������B�u������ׁv�ɂ�straBe(��)�Ƃ����P�ꂪ2��o�Ă���B���������`�ŁE�E�E
Was vermeid ich denn die StraBe�@�~�����[�ɂƂ��āA�ŏ��ɂłĂ��铹�͑��l�̓��ŁA�Ō�̓��͎����̓����B�l�͂��̓�s�߂Ă��ĂӂƎv�����B���ɖl�̂ق����猩��A���̗��l�Ƃ����̂̓~�����[�ŁA�ŏI�߂͎̂�������Ȃ������ĂˁB����ƍŏ��̓����~�����[�̍s�����ŁA�Ō�͎̂����̍s�����Ƃ������ƂɂȂ�BstraBe�͕��ʂ̓��Aweg�ɂ͏����Ƃ����ق��ɐl���̓��Ƃ����Ӗ�������B�~�����[�̓��͔ނ���J���l���̓�������weg�B���̂͏h���Ƃ��Č��߂�ꂽ��������straBe�̂܂܂ł����B���������̓��́u�����l�A���Ă������Ƃ̂Ȃ����v�ȂB��������߂̂ق������������ς����B
�Ȃ��A�킽���͑��̗��l�����̍s����������āE�E�E�i���ߑ��s�j
Eine StraBe muss ich gehen
��̓������͍s���˂Ȃ�Ȃ��i�ŏI�ߍŌォ���s�O�j
Was vermeid ich denn die Wege�@�������邱�Ƃɂ���āA�~�����[�̓�weg�́A�u������ׁv����_�Ɂu�h�v�|�u���̑��z�v�|�u�t�̖��v�|�u�ǓƁv�|�u�E�C�v�|�u���C�A�[�v�ւƘA�Ȃ��Ă䂭���ƂɂȂ�B������Ƃ����ӎu�������āB����A���͏h���Ƃ������߂�ꂽ��straBe����܂˂Ȃ�Ȃ��B����A���ނ����Ȃ��A�u���̑��z�v�|�u���C�A�[�v�Ƃ�������̒����B���߂�straBe����weg�ւ̏��������́A�l�̉̋ȏW�Ƀ~�����[�̈ӎu���悹�邱�ƂɂȂ邵�A�u������ׁv����̃~�����[�̗���Ɩl�̗���Ƃ͌���I�ɈႤ�Ƃ������Ƃ��A�l�̂ق�����ӎv�\�����邱�Ƃɂ��Ȃ�B
�@�����u�h�v�́u������ׁv�Ƃ͐��Ă���Ȃ��W�ɂ���B�u������ׁv�ɂ��������čs���������Ƃ��낪���Ƃ����u�h�v����������ˁB�h�̎�ɏh�������ۂ��ꂽ��l���͂��������u����Ȃ�A����ɗ��𑱂��邱�Ƃɂ��悤�v�ƂˁB�ނ��A���̑䎌�����₢�⌾�����A�O�����Ɍ������H�ǂ�����̂邩�͓ǂސl�̎��R������ǁA�~�����[�̈Ӑ}�͌�҂�������Ȃ����낤���B�����ɂ���ꕔ�Ƃ͈Ⴄ�ނ̎p��������Ă���Ǝv���B������A�l�́A���̕����́A�S�����s����Ɋ�]��������悤�ȃG���f�B���O�ɂ��邩������Ȃ��B�ނ̈ӎv�d���āB�V���p�E���A����Ŗl�Ȃ�ɂ��ׂĂ��ǂ߂��I �����A���Ƃ͋ȍ���簐i���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�̒����ȗF�l �t�����c�E�V���[�x���g
2010.11.10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևJ�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v4 ���V���|�x���g�˘f����
�@�~�����[�́A�u�~�̗��v�O��12�т�1823�N1���ɔ��\�������ƁA���10�т��o��1824�N3���Ɋ�����24�т\�����B�����������������̂́A�u�����Łv���O�т���͂�1�N3������ɔ������ꂽ�Ƃ��������ł���B�V���[�x���g���O�҂�m�����̂�1827�N�����A�����Ŕ�������3�N���o���Ă���̂ł��邩��A�ނ������Ȃ�u�����Łv�ɏo�����킵���Ƃ��Ă��S�R�s�v�c�͂Ȃ��̂ł���B�����V���[�x���g���ŏ��Ɋ����łɏo����Ă����Ȃ�A���̏��Ԃŋȍ��������Ɍ��܂��Ă���B����́A���Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�`�́u�~�̗��v�ɂȂ��Ă������Ƃ��낤�B�Ƃ��낪�~���[�Y�̐_�̈��Y�͂����͂����Ȃ������B���̂��A�ŁA�A��̋ȏW�u�~�̗��v�͍��̋ȏ��Ɏ��܂荡�̋Ȃ��t����ꂽ�B�������́A���̐_�̍єz�ɂ����������ӂ��邵���Ȃ��I�I�@�O��́A�~�����[�����ł̎d�オ��ߒ����������B����͂���ɏo������V���[�x���g���ǂ̂悤�ɂ��Č�҂������������������ǂ��Ă݂悤�B�����͕��ʂɏ������A�ނɌ���Ă��炤�ق����ʔ��������B�����ŁA�E�B�[���̊�h�w�Z���R�����B�N�g���ォ��̐e�F�ŁA�����c�o�g�̊������[�[�t�E�t�H���E�V���p�E���i1788�|1865�j�Ɏ莆�������A�Ƃ����`�œW�J���Ă݂����B�ނ͓����E�B�[���ɂ����̂ŁA���ۂɃV���[�x���g���莆���������Ƃ͂Ȃ���������A�g�g�݂̓t�B�N�V�����ł���B���A���g�͎j�����O�����ɏ����͓̂��R�ł���B
�@�ł͂܂��A����ɐ旧���A�~�����[�^�V���[�x���g�̑Ώƕ\���f�ڂ��Ă������B
| �V���[�x���g | �~�����[ |
| 1 ���₷�� | 1 ���₷�� |
| 2 �����̊� | 2 �����̊� |
| 3 �������� | 3 �������� |
| 4 �X�� | 4 �X�� |
| 5 ���� | 5 ���� |
| 6 ���ӂ��� | 6 �X�֔n�� |
| 7 ��̏�� | 7 ���ӂ��� |
| 8 ������݂� | 8 ��̏�� |
| 9 �S�� | 9 ������݂� |
| 10 �x�� | 10 �������� |
| 11 �t�̖� | 11 ���炷 |
| 12 �Ǔ� | 12 �Ō�̊�] |
| 13 �X�֔n�� | 13 ���ɂ� |
| 14 �������� | 14 ���̒� |
| 15 ���炷 | 15 �܂ڂ낵 |
| 16 �Ō�̊�] | 16 ������� |
| 17 ���ɂ� | 17 �h |
| 18 ���̒� | 18 �S�� |
| 19 �܂ڂ낵 | 19 �x�� |
| 20 ������� | 20 ���̑��z |
| 21 �h | 21 �t�̖� |
| 22 �E�C | 22 �Ǔ� |
| 23 ���̑��z | 23 �E�C |
| 24 ���C�A�[�� | 24 ���C�A�[�� |
�V���[�x���g�̎莆���̈�u�ق�Ƃ��ɂт����肵����v�i1827�N10��10���j
�@�e���Ȃ�V���p�E���N�B���C�ł����B�l�͐������܂�̒��͂悭�Ȃ��B�ł�����Ȃ��Ƃ�������Ԃ��炢�̏o�����ɑ��������B�V���[�o�[����~�����[�́u�~�̗��v���Љ�ꂽ�͍̂��N�̂P���������B�l�͓ǂƂ���ɗ��ɂȂ��C�ɋȂ������グ���B�y���̍Ō�Ɂu�I��vENDE�Ƃ�����������ꂽ���炢������A���̎��W�ɑ���������Ȃ�Ă��̎��͖��ɂ��v��Ȃ�������B�Ƃ��낪���ŋ߁A�l�͔ނ́u������p�J�����̈�e���W�v�̒��ɁA�u�~�̗��v�����łȂ���̂������̂��B����͐V����12�т�������ꂽ�S24�т���Ȃ���̂ŁA���������̏��Ԃ͐V�����ւ����Ă���B���́u�~�̗��v�ɑ��҂��E�E�E�Ƃ��������Ɗ��сA24�҂܂Ƃ߂ď��Ԃ��ς���Ă���Ƃ����˘f�����A�l�̓����Ђǂ����������Ă��ꂽ��B
�@����ɂ��Ă��A���̎��W�Ƃ̈����͂��������Ȃ�Ȃ̂��낤�ˁB�����A�ŏ���12�тɏo������N���̍��ɂ́A������24�т͊��ɏo�ł���Ă����Ƃ����ł͂Ȃ����B�ŏ����炱����ɏo����Ă���A����ȋ�J�����Ȃ��Ă����ނ̂ɂˁB�ł��܂��A���ꂪ�^���Ƃ������̂��낤�B
�@���āA�ǂ��������̂��H�l�͂܂��A���Ԃ߂Ă݂��B����������C�Â����B�ꌩ�o���o���̂悤�ł��āA���̏��Ԃɂ͂����Ƃ������ʂ��Ă�����ĂˁB���������A�\�t�����\�����Ă��ꂽ�܂��B�~�����[�͑O�ҁi�����ȕt�����ς�ł���12�т������Ăڂ��j�̏��Ԃ͈�ؕς��Ă��Ȃ��B�����āA�����ɐV���ɍ����12�т���������ł�������B
�@����Ȃ�A�O�҂̋Ȃ͂��̂܂܂ɂ��āA���̏��Ԃǂ���Ɍ�҂̋ȍ������̂͂���قǓ�����Ƃ���Ȃ��B���ꂪ�������S�Ƀo���o���Ȃ���I���Ă���y�Ȃ��ׂĂ̒�������������������Ȃ����ǁA���̌`�Ȃ�4�ӏ���������������������炾�E�E�E��U�͂����l�����B�ł������ɒf�O������B����́A5�����\6�X�֔n�ԁ\7���ӂ����̂R�Ȃ̗��ꂪ�A����I�Ƀl�b�N���ƕ����������炾�B�����͂ˁA�l�̒����́A5�����E�z�����\6���ӂ��܁E�z�Z���ƕ��ׂĂ���B�̂��������ށu�����v�̓z�����ŁA��a��`���u���ӂ��܁v�̓z�Z���A�����z�̓��咲�Ōq���Ă�B���ꂪ�A�~�����[�́A�Ȃ�Ƃ��̊ԂɁu�X�֔n�ԁv����ꂽ���B�����Ƃ��A�ނ͖l�̋Ȃ��Ă�킯����Ȃ��̂�����A�d�����Ȃ����Ƃ����ǁE�E�E�B���̏�u�X�֔n�ԁv��"�X������X�֔n�Ԃ̃��b�p���������Ă���B�ޏ��̏Z�ޒ����痈���̂�"�Ƃ������e�ŁA�u�����v�Ƃ͓��X���̖���߂̎����B�u�����v�z�����\�u�X�֔n�ԁv�H�|�u���ӂ��܁v�z�Z���ƕ��Ԃ̂��B�u�X�֔n�ԁv���ǂ����H�E�E�E����ɂ͍�������Ȃ���B����ɂ��Ă��~�����[�͂Ȃ��Ă���ȂƂ���Ɂu�X�֔n�ԁv�݂����Ȏ�����ꍞ�낤�H
�@17�u�h�v��18�u�S�v�̌q�����������Ɨ����ł��Ȃ��B�u�h�v�ŕ��ɍs�������Ēf��ꂽ���̂��A����́u�S�v�ŁA�u������͕��ɂ��ǂ���̂��v�Ȃ�Č����Ă���B���ꎩ�̖����͂Ȃ���������Ȃ����A����͂Ȃ���B���̑@�ׂȃ~�����[���A����ȕs���R�ȏ��Ԃɒu�����������A��قǂ̂��Ƃ��B�����܂ł��ă~�����[�����������������̂Ƃ͂��������Ȃ����̂��H
�@�u�t�̖��v���A�V�������ɉ����o�����21�Ԗڂɍs��������Ă�̂��l�b�N�������B���̎��́A"�y������������Ɍ���"�Ƃ������e���B�����疾�邢�C�������咲�ɂ��ċȂ��������B�͂����āA���̋Ȃ��I�ՂɈڂ��ē���ނ̂�����H ����ƁA���̋Ȃ̑O�ɂ��܂��u���̑��z�v�Ƃ����V��������u���Ă���B�l���O��12�Ȃ̒��Œ����ŏ������̂́A�u�����v�Ɓu�t�̖��v�̂Q�Ȃ����B���ꂾ���ɁA�����̑O��̂Ȃ���ɂ͓��ɋC���g���Ē��������߂��B���ꂪ�~�����[�̊����łł́A����2�Ȃ̑O��ɐV�삪�z�u���ꂿ������B���ɂ�����Ă�����2�Ȃ����Ȃ������̋Ȃ̑O��ɂ����B�Ƃ�����A�܂��A����͑�ςȂ��Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�����ł̏����ɏ]���Ƃ���A�قƂ�Ljꂩ�珑���������ƂɂȂ��Ă��܂��̂�����ˁB
�@�����ł�����x���т߂Ă݂��B���������������悤�ɁA�O�҂̕��т��̂��͕̂ς���Ă��Ȃ��B�Ȃ�ЂƂ܂��A���̂܂��o���Ă��܂����B�����Ă����Ɏc������҂�����������ǂ����낤�B���͋ؗ��Ă����A����͐S�z�ɂ͋y�Ȃ��B���̋ȏW�͓����~�����[�Ƃ̑O��u���������ԏ����̖��v�ƈႢ�A�X�g�[���[����������A���̕��тɂ��Ă��������ȂƂ���͉���Ȃ��B�Ƃ������A�ނ���~�����[�̃I���W�i���̂ق��ɖ����������āA�l�̏��Ԃ̂ق��ɐ����������邭�炢�ȂB���_����͋��R�ׂ̈���Ƃ����ǁB�悵�A���ꂾ�B����ł������I
�@�V���p�E���A�����l������l�͂����Ԃ�C�����y�ɂȂ�����B�N���m���Ă̒ʂ�A�l�̑̒��͐��鈫���B�ŋ߂��ˑR���ɂ�f���C���P���Ă��邱�Ƃ������ĂˁB�u�~�̗��v�̂悤�ȃV���A�X�ȍ�i�Ɍg����Ă���ƁA�m���ɑ̗͂����Ղ���B�����l�͂������������͂Ȃ��Ǝv���B������A�Ƃɂ����S���������������ɂ��݂����łق��Ƃ��Ă���B���Ƃ́A��҂̋ȍ��ɏW�������B���̑O�ɁA�O�҂̃e�L�X�g�̒����������邯�ǂˁB�ł́A�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�̗F�l�V���[�x���g
�V���[�x���g�̎莆���̓�u�w�E�C�x�E�E�E�Ȃ����̎��́I�v�i1827�N10��20���j
�@�V���p�E���N�A�N�̌̋������c�͍��A�ǂ�ȗl�q�ł��傤���B�V�����X�x���N�ł͑��ς�炸�����������C�������߂�̂��ȁH ���N�A�N������͂��̃����c��K�ꂽ�Ƃ��A���̕s�݂ɗ��_���A�_����������Ƃ����X�Ȃ���v���o����B����́A�A���i�E�z�F�[�j�q��̂��������ăp�[�e�B�ɏo��\�肾�����̂ł����A�}�ȑ̒��s�ǂɏP���Ēf�O������Ȃ������B����ȑ̒��ł����A�u�~�̗��v�͒��X�Ɛi�߂Ă���B�l������قǂ܂łɓ��ꍞ��i�͑��ɂ͂Ȃ��ƍ��X�Ȃ��炻���v���B
�@�O�̎莆�ɏ������Ƃ���A�O��12�т����Ă݂���B���ʁA�ύX�͐��ӏ��������̂ŁA�ӏ������ɂ��Ėl�̑Ή��������Y���Ă����B
�@ 1�u���₷�݁v�̍ŏI��
�ʂ肷����ɁA�Ƃ̖�Ɂu���₷�݁v�Ə����Ă䂭�A �S�u�X���v��1�A�Ō��2�s
�@�@�@�@�@�@�@��
�o�čs���Ƃ��A�Ƃ̖�Ɂu���₷�݁v�Ƃ��������Ă䂭
���̂ЂƂ����̋��ɕ�������B 9�u�S�v��2�A2�s�ځ@irre Gehen��irregehen
�̖�����܂悢���������̐Ղ�
�@�@�@�@�@�@�@��
�ꏏ�ɖ��ʂ�
�������������ΎU���A����
�C 12�u�ǓƁv��1�A3�s�� wann��wenn
�@�@�́A�ޏ��̉Ƃ�ʂ�߂��邩�o�čs�����ő傫�ȈႢ�͂��邪�A�ύX���Ȃ��B�l�ɂƂ��āA���̃V�`���G�[�V�����̈Ⴂ�͂ǂ��ł��������炾�B�A�́A�Ӗ��͓����Ƃ����Γ���������ǁA�j���A���X���ς���Ă��܂��B�l�͗����̊Â����h�����ŏ��̎����d�����B�����ύX�������B�B�ƇC�̓~�����[�̕ύX�ɏ]���Ă��債�����ق͂Ȃ����炻�����悤�Ǝv���B
�@�O�҂Ɋւ��Ă͈ȏ�Ŏ蒼���͏I���ɂ������B�u�o�ł͗��N1���v�ƃn�X�����K�[�������Ă�������܂��������Ԃɗ]�T�����肻���Ȃ̂ŁA�ق��ɂ��C�Â������Ƃ�����Β������肾�B
�@ �@�����A���Ƃ͌�҂̋ȍ�肾�B���߂ĕ��ׂĂ݂āA�l�͈�̎��ɖڂ��s�����B�u�E�C�v�Ƃ����Ōォ��2�Ԗڂ̎����B�N�ɂ��ǂ�ł��炢�������珑���Ă������B
�Ⴊ���̊�ɐ�������Ȃ��@�ǂ����ˁA�V���p�E���N�B�Ȃ�Ƃ��ѐF�̕ς���������낤�B���̎��ł́A�r���Ƃ����~�i�F�ƂЂ����玀�����߂��҂̐S�������`���Ă���̂ɁA���̍U���I�ȓ��ِ��͂Ȃ�Ȃ낤�B���������X�O�ɒu���āE�E�E�B�l�͂�����A�~�����[�̓t���[���C�\�����Ƃ����b�������Ƃ�����B�Ȃ���̎��͔[���������B�ނ�́A�_�̑��݂������Ĕے�͂��Ȃ����A�_���鍡�̃J�g���b�N�̃N�\�V��ǂ��Ƃ͑��e��Ȃ����낤���ˁB�l�����Ă�����ɂ͑��h�̌��Ђ��Ȃ��̂�����悭�������B
���͂�������Ƃ��Ă�낤
���̒��ŐS��������������Ƃ���
���邭�z�C�ɉ̂��̂��Ă�낤
�S�̌�肩���鐺�͕����܂�
���͎��Ȃ��ɂȂ��Ă��܂���
�S�̒Q�����ɋ��ɂ߂܂�
�Q���͋����Ȏ҂̂��邱��
�E��Ő��̒��ɓ����Ă����Ă�낤
���ƕ��ɐ^��������������āI
���̒n��ɐ_�����܂��ʂȂ�
�����������_�ɂȂ낤����Ȃ���
�@�u�Q���͋����҂̂��邱�Ɓv�Ȃ�āA���̎��Ƃ͐^������Η�����t���[�Y���B�u�~�̗��v�̎�҂͒Q���Ă��肢�����B�u�E��Ő��̒��ɓ����Ă����Ă�낤�v���A����̊k�ɕ��������l���Ƃ͐����̊O�𐫂���B�ɂ߂��́u�����������_�ɂȂ낤�v�̌����ˁB�V�ɐ_�͂���B�n��ɂ͂��Ȃ��B�Ȃ�Ή��������E�E�E���ꂼ�t���[���C�\���łȂ��ĂȂ낤�B
�@�������̎��ɂ́A�ǂ��������̂��ƍ����Ă���B������A���炭�l���Ă݂��B�����������Ԃ��Ȃ�����A�W�����ĂˁB�ނ����̎����������̈ʒu�ɓ��ꂽ�����R���𖾂ł���A�l�͂����ɋȍ��Ɏ��|������肾�B���̓t���[���C�\���B�ł́A�܂��߁X�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�̐����ȗF�l �V���[�x���g
2010.10.28 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևI
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v3 ���~�����[���Ԍ���̐^����
 �@�O��A�u���ǂ��C������v�Ə������W���b�N�E�V���C�G���u�w�~�̗��x�ƃV���[�x���g�̓�v��ǂނ��Ƃ��ł����B����́A�u���y�̎蒟 �V���[�x���g�ҁv�i�y�Њ��j�̒��̈�_���Ƃ��āA���͓����������4�K�̉��y�������ɂ������B�����͉��y�W�̎������L�x�ŁA������Â��B�u�N�����m�v�T���ɂ͊i�D�̊��ɂ���B�W���������Ĕ�ꂽ��A�O�͏��̓m�E�E�E���m���p�فA�����@�A���i���A�싅��A�s�E�r��������U������ƁA�C�������t���b�V���B�������������A�s�������Ƃ̂Ȃ��E�B�[���̐X�ɏd�ˍ��킹�A���[�c�@���g��V���[�x���g�A�x�[�g�[���F���A�}�[���[�ɑz����y���Ȃ��炻��������B�������A�ł�������������ЂƂƂ��ł���B
�@�O��A�u���ǂ��C������v�Ə������W���b�N�E�V���C�G���u�w�~�̗��x�ƃV���[�x���g�̓�v��ǂނ��Ƃ��ł����B����́A�u���y�̎蒟 �V���[�x���g�ҁv�i�y�Њ��j�̒��̈�_���Ƃ��āA���͓����������4�K�̉��y�������ɂ������B�����͉��y�W�̎������L�x�ŁA������Â��B�u�N�����m�v�T���ɂ͊i�D�̊��ɂ���B�W���������Ĕ�ꂽ��A�O�͏��̓m�E�E�E���m���p�فA�����@�A���i���A�싅��A�s�E�r��������U������ƁA�C�������t���b�V���B�������������A�s�������Ƃ̂Ȃ��E�B�[���̐X�ɏd�ˍ��킹�A���[�c�@���g��V���[�x���g�A�x�[�g�[���F���A�}�[���[�ɑz����y���Ȃ��炻��������B�������A�ł�������������ЂƂƂ��ł���B�@�O��́u�N�����m�v�ŁA�u����́w�E�C�x�ɑ���V���[�x���g�̑Ή��ւƘb��i�߂悤�v�Ɨ\���������A�V���C�G�̕��͂����������̂ŁA��蓹���Ă������肠�������B
�@�u�w�~�̗��x�ƃV���[�x���g�̓�v�ɂ��ẮA�~�Î���Ò��u�~�̗��`24�̏ے��̐X�ցv�̒��Ɂu�㔼��12�Ȃ��t���[���C�\���̉��`�ƌ��ѕt���Ă���v�Ƃ����L�q������B�V���C�G�̒���ł́u���J�\�鋳�I�y���v�i�����p�Y������N����A�����Ёj���L���ŁA���[�c�@���g�D���̈��ǎ҂������B���[�c�@���g���t���[���C�\���ŁA�̌��u���J�v�̓��C�\�����`�ɑ������I�y���ł��邱�Ƃ͏O�ڂ̈�v����Ƃ��ł��邩��A����͊��������̉�͖{�Ƃ������Ƃŋ����[���ǂ߂邪�A�u�N�����m�v�I�X�����͂Ȃ��B���ꂪ"�u�~�̗��v�ƃ��C�\���Ƃ̊֘A�₢���ɁH"���e�[�}�ƂȂ�X�������_�E�����ÁX�ł���B���C�\���֘A�t�����l�V���C�G���V���[�x���g�ɂǂ����邩�A���Җ��X�œǂ�ł݂��B
�@���ʂ͎c�O�Ȃ���X�J�������B���ؓI�L�q�͂܂�łȂ��A���ۘ_�ɏI�n���A�B���Ȑ��_����"�V���[�x���g�̓��C�\������������\��������"���Ƃ��������Č���ł���B�Ȃ�قǁA�~�Î����u���̐��͂��܂�d�v������Ă��Ȃ��v�Ƃ����̂�������B
�@�Ƃ��낪�A���n�͑�A���������B�~�����[�̎��̔��\�̎���ڍׂɋL����Ă�������ł���B����̓~�����[�u�����Łv���Ԍ���̐^���ɂȂ���I �u�G�͖{�\���v�A��ނȂ������Ȃ�Ă���͂����Ȃ��i�����݂䂫�u�a���v�j���B
�@�~�����[�́A1823�N1���A�u�E���[�j�A�v�Ɂu�~�̗��v�O��12�т\�������ƁA��1824�N3���ɁA���҂�10�т��G���u�h�C�c ���E���w�E���p�E�������v�̕ʍ��ɔ��\�����B������2�т����������A���12�ёS24�тƂ��A�V���ȏ��Ԃŕ��בւ��u�����Łv�Ƃ��ĊԂ��������ɔ��\�����E�E�E�Ƃ����̂ł���B���݂�10�т̏��Ԃ́A���������|�Ō�̊�]�|���炷�|���ɂā|���̒��|���̑��z�|������ׁ|�h�|�E�C�|���C�A�[�� �ŁA�ォ�珑����2�тƂ́u�X�֔n�ԁv�Ɓu�܂ڂ낵�v�������B�~�����[�͂Ȃ���w�~�̗��x��3��ɕ����Ĕ��\�����̂ł���B���̏��߂ĕ����Ռ��̎������A�ӏ������ł܂Ƃ߂Ă������B
�@�@�@�@ 1823�N1�� �@�O��12�т��u�E���[�j�A�v�ɔ��\
�@�@�@�A 1824�N3�� �@����10�т��u�h�C�c���E���w�E���p�E�������v�����ɔ��\
�@�@�@�B �A�̒��� ������24�т��u������p�J�����̈�e���W�v�ɔ��\
�i�P�j �Ȃ���U��10�т������̂��H
�@�~�����[�́A�ŏI�I�ɂ�12�тƂ����u�~�̗��v����U��10�тŔ��\���Ă����B���̎����͉����̂��낤���H �o�ŎЂ̓s���H���ߐ�ɊԂɍ���Ȃ���������H�E�E�E���j�̐^����"���}������Ȃ��ڋ�"�Ƃ������Ƃ����X�ɂ��Ă��邩�炵�āA��������肾�낤�B�ł��`���b�g�����Ȃ��B�����͏������i�ɍ\���Ă݂悤�B�u�~�����[�́A��U��10�тŔ��\�������̂��A��12�тɕς����̂͂Ȃ����H�v�𐄗�����B
�@�~�����[�́u�~�̗��v�̌�҂������͂��߂��Ƃ��ɂ́A12�тɂ��悤�Ƃ����m�ł���Ӑ}�͂Ȃ������B��҂�12�тł܂Ƃ߂悤�ƍŏ�����l���Ă����Ȃ�A��U10�тŔ��\����͂����Ȃ����炾�B�ł́A�Ȃ��ނ�"10�т\������A�Ԃ��������ɐV����2�т�����������12�тƂ��A���x��24�т̊����łƂ��Ĕ��\����"�Ƃ�����Ȃ�肩���������̂��낤���H ����́A�����I��12�ё����O��҂�24�тłȂ���Ȃ�Ȃ��������������ł���B
�@1821�N�A�M���V���̓g���R�ɑ��ēƗ��푈���N�����B���S�N���̊ԃg���R�̎x�z���ɂ������M���V���̂��̓��������[���b�p�����͐ϋɓI�Ɏx�������B�����镶���l�������A�t�����X�̍�ƃ��B�N�g���E���S�[�A���V�A�̎��l�v�[�V�L���A�C�M���X�̎��l�o�C�����Ȃǂ��A���X�ɃM���V���x���ɖ������グ�Ă������B�~�����[�������ɂ���ɋ��A��1822�N�ɂ́u�M���V���l�̉́v���o�ł���Ȃǂ��Ďx��������ϋɓI�ɍs���悤�ɂȂ�B�w������v���C�Z������^���ɐg�𓊂����悤�ɁA���X�����F�����������l�Ԃ������~�����[�́A��A�̐��������̒��ŁA�t���[���C�\���v�z�ɋ�������悤�ɂȂ��Ă����B���ɂ̐��������Ƃ�������t�����X�v����A�����J�Ɨ��푈�ƃ��C�\���Ƃ̊ւ��Ȃǂɔނ����������������낤���Ƃ͗e�Ղɑz���������炾�B�~�Î��̒����u�~�̗��`24�̏ے��̐X�ցv�ɂ́u�~�����[��1820�N4���Ƀ��C�v�c�B�q�̃t���[���C�\���x���ɓ���̐\�����݂��s���A���N7���ɂ͏W��ɎQ�������v�Ƃ̋L�q������B�~�����[�̓t���[���C�\���������̂ł���B
�@1823�N1���A�u�~�̗��v�O��12�т������E���\�����~�����[�͌�҂̑n��ɓ����Ă䂭�B�t���[���C�\���v�z�̐Z���ɂ���Ĕނ̍앗�͏��X�Ƀ��C�\���F�����߁A�O�҂Ƃ͂��َ��Ȏ��ݏo���悤�ɂȂ�B���̍ł�����̂́u�E�C�v�ł��邪�A�u�Ō�̊�]�v���낤������Ǔ��݂Ƃǂ܂�A�u���������v�����ɋ߂Â������ƌ����Ȃ��炻���Ȃ炸�A�u������ׁv�͂ނ���킪�����s���Ƃ������ӂ��犴�����A�u���̑��z�v���Ō�̑��z�͒��܂��ɃM���M���̐��œ��݂Ƃǂ܂��Ă���A�u���C�A�[�v�ł́A���߂Đl�Ԃ��o��A��l���͔ނɉ̂̔��t�𗊂�ł�����B�O�҂̗��������悫�������z����Ƃ������X�����͎p�������A�r������~�i�F��ł̕s�C�����s�g�����O�ʂɉ����o����Ă����A���̒��O�M���M���̂Ƃ���œ��݂Ƃǂ܂��Ă���̂ł���B�m���ɂ����ɂ͎��E�Ƃ��Ȃ��L���X�g���I���_�̗��Â������邾�낤�B���ƌ��������Ă͂�����̂́A�����o�������Ƃ����M���M���̊���ӎv��ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂ł���B�s������͕���z�肵�Ă��邪�A����͐l�Ԃ̏h���A���l���ʂ̂��ƁB�������A�u�~�̗��v�̎�l���ɂƂ��āA�����́�܂��Ȃ�Ɖ����i�u���������v�j�A���₳���i�u������ׁv�j���̂Ȃ̂��B�~�����[�͂������Č��10�т������グ�u�h�C�c���E���w�E���p�E�������v�ʍ��ɔ��\�����B
�@�����āA���̂��ƃ~�����[�̐g�Ƀ��C�\���I�Ȃ��錀�I�ȕω����N�������̂ł͂Ȃ����B���ꂪ�Ȃ�ł��邩�͕�����Ȃ��B���C�\���̑g�D�́A3����Ƃ���ʊK�ɂ�萬�藧���Ă���B����͏C����ςނ��Ƃɂ���ĈʊK�����i���Ă䂭�B�u���J�v�ɂ�����^�~�[�m�������ł���悤�ɁB������������~�����[�̕ω��Ƃ́A��荂���ʊK�ւ̓��傾������������Ȃ��B�Ȃ���̈ʊK�ɑ����������[�����C�\���ւ̗������������\���͍����B
�@�ނ͑O��12�{���10�Ŋ����E���\���Ă���u�~�̗��v���������B�����đ����ɁA��҂�10�т̂܂܂ł͂����Ȃ����Ƃ��@�m�����B������2�т̒lj������߂�B10�ł͂��߁A���C�\�������R�̔{��12�łȂ���Ȃ�Ȃ������̂��B����őS�̂̐����A24�Ƃ������C�\�������ɐ������̂ł���B
�@�u�~�̗��v��҂���U��10�҂Ŕ��\����Ȃ���A������2�т��lj�����12�тƂȂ����̂́A���̊ԂɃt���[���C�\�������ɂ����鉽�炩�̌��I�ȕω����N�����Ă����E�E�E���ꂪ���̐����ł���B�O��u���������ԏ����̖��v���S20�тȂ̂́A�����������Ƃ���20�̃~�����[�ɂ͂܂����C�\�������ւ̍S�肪�Ȃ���������ł���B
�@ �@�~�����[�̐��U�Ɋւ��镶���͔��ɏ��Ȃ��A�{�_�̃c�{�ł���u10�с�12�т̊ԂɃ��C�\���̈ʊK���オ�����v�Ƃ��镔�������ł���ޗ��͎c�O�Ȃ��猩������Ȃ��B�����͊m���Ɏ��̑z���ł��邪�A����ȊO�̕����͂��ׂė��j�I�����܂��Ă���B��Ȃ̂͂��̉ߒ��ł͂Ȃ��A����12���ƂȂ����A���̂��Ǝ��̂ł���B
�i�Q�j�蒼�����犮���܂ł̌o��
�@ �V����2�Ȃ�����
�@��҂�12�тɂ��邽�߂ɁA�V����2�т̎��������K�v������B�ǂ����Ȃ烁�C�\���F�̋������ɂ��悤�B�Ƃ͂������̎����̃h�C�c�ł̓t���[���C�\���͗e�F����Ă͂��Ȃ��i�h�C�c���I�[�X�g���A�ŗe�F���ꂽ�̂́A18���I�I�Ճ��[�[�t2���݈ʂ̎��ゾ���ł���B���[�c�@���g�̓���͒��x���̎����ɓ��Ă͂܂�j�B������X�g���[�g�ȕ\���́u�E�C�v�����Ɏ~�߂Ă������B�E�E�E�����グ���̂́u�X�֔n�ԁv�Ɓu�܂ڂ낵�v��2�т������B�u�X�֔n�ԁv�́��ʂ肩��X�փ��b�p�������Ă���B�Ȃ�����Ȃɖ�藧�̂��B���̐S��E�E�E�Ŏn�܂�B���ɖ��邢�F���ł���B�u�܂ڂ낵�v�́�ЂƂ����̌����e�����Ɏ��̑O�ŗx��E�E�E�Ŏn�܂�B�u���v�u�e�����v�u���v�A������g�[���͖��邢�B
�@ �A 24�т����Ƃ��ď��Ԃ����߂�
�@���Ȃ��Ƃ͎��̏��Ԍ��߂ł���B�͂��߂ɐS���������ƁA����͎��̗���ւƌ������O�����Ȍ`�ōč\�z���邱�Ƃ������B���̂��߃~�����[�́A���X�O�ɍł����C�\���F�̋������O�����Ȏ��u�E�C�v��u���A�ŏI�ȁu���C�A�[�v�ɂȂ����B�u���C�A�[�v�ɂ́A���Ԃ��犮�S�Ɋu�₳�ꂽ���݂̕�����y�t��o�ꂳ����B�u�~�̗��v�̒��ŁA���ݐi�s�`�œo�ꂷ��l�Ԃ͔ނ����ł���B����܂ŁA���l�A���̕�e�A���̓y�n�̐l�X�Ȃǂ��o�ꂷ�邪�A���ׂĉߋ��̎v���o�̒��B���Ƃ͌��ƃJ���X�A�l�Ԃ͂��Ȃ��B���Ƃ����̂Đl�Ƃ͂������ݐi�s�`�œo�ꂳ���A�u���̉̂Ƀ��C�A�[�̒��ׂ����킹�Ă���邩�H�v�Ǝ�l�����R�~���j�P�[�V�������Ƃ�̂ł���B�܂����u�~�̗��v��"�ꏏ�Ɏ����荇���ė͋��������Ă䂱��"�I�ɒ��߂�킯�ɂ͂����Ȃ����낤�B������~�����[�̒��Ƀ��C�\���I�C���̍V�g���������ɂ��悾�B�ٕ��̂悤�ȁu�E�C�v�̂��ƂŁA�悻�҂̔߈��ɏI�n�������̉̏W����߂�ɂ͂��̂��炢���K���������B���̃��X�O����ŏI�тւ̗��ꂱ���A�~�����[�����C�\�����O�����u���M���M���̕\���������̂ł���B
�@���̂��ƁA���Ԍ���̉ߒ���ǂ����߂ɁA�����Ń~�����[�����`�̋Ȗڃ��X�g���ēx�f�ڂ���B
�@�@ �@ 1 ���₷��
�@�@�@ 2 �����̊�
�@�@�@ 3 ��������
�@�@�@ 4 �X��
�@�@�@ 5 ����
�@�@�@ 6 �X�֔n��
�@�@�@ 7 ���ӂ���
�@�@�@ 8 ��̏��
�@�@�@ 9 ������݂�
�@�@�@ 10 ��������
�@�@�@11 ���炷
�@�@�@12 �Ō�̊�]
�@�@�@13 ���ɂ�
�@�@�@14 ���̒�
�@�@�@15 �܂ڂ낵
�@�@�@16 �������
�@�@�@17 �h
�@�@�@18 �S��
�@�@�@19 �x��
�@�@�@20 ���̑��z
�@�@�@21 �t�̖�
�@�@�@22 �Ǔ�
�@�@�@23 �E�C
�@�@ 24 ���C�A�[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����͑��҂Ƃ��ď��������j
�@��������́A�����`�����Ȃ���A�[�I�ɒH���Ă������B�܂��A23�u�E�C�v��24�u���C�A�[�v�͌��܂����B1�u���₷�݁v�͂��������Ȃ��B2�u�����̊��v�����l�ƕʂꂽ����������A������������낤�B3�|22�͓��ɏ��ԂɍS��K�v�͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����ŕ\���������͎̂�l���̐S�ە��i�Ɠ~�i�F�Ɖ�z�ŁA�u���ԏ����v�̂悤�ȃX�g�[���[���͂قƂ�ǂȂ�����ł���B�Ȃ�ΒP����12�т̑O�҂����̂܂܂ɂ��āA���̂��ƂɐV���ɍ����12�т��Ȃ��Ă��悩�����B�������A�ނ͂������Ȃ������B�Ȃ��H ���j���Ȃ����߂̃J���t���[�W���Ȃ̂��A�P�Ȃ�V�ѐS�Ȃ̂��A�^���͈ł̒��B������Ȃ����̂͂��傤���Ȃ��A�����ł͎�����ǂ��Ă䂭�B
�@�~�����[�́A�O��12�т̏��Ԃ͂��̂܂܂ɂ��āA�����Ɍ��12�т���������ł������̂ł���B����܂ł̒���ł́A�~�����[�͑O��҂��ꏏ�ɂ��V���b�t�����ď��Ԃ����߂��E�E�E�Ƃ������j���A���X�̂��̂��قƂ�ǂ������B���������āu�O�Ҏ��̂̏��Ԃ͂Ȃɂ��ς���Ă��Ȃ��v�Ƃ��邱�̎��̔F���́A�����炭�܂��N�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H �����łJ�Ɍ��߂�Ε�����V���v���Ȏ����Ȃ̂����E�E�E�B �@��҂��������ނƂ����~�����[�̓����烁�C�\������3�͗���Ȃ������̂��낤�B1�|5�܂ł͎���̗�����d���������A3�̔{��6����̓��C�\�����o�ŋ���ł䂭�B6�ɂ͖��邢�ŐV��u�X�֔n�ԁv�A12�ɂ͎̂Ă���Ȃ���]���̂����u�Ō�̊�]�v�A15�ɂ͌����e�����ɖ��u�܂ڂ낵�v�Ƃ�����҂̒��ł����邢�^�b�`��3�̎���ߖڂ̈ʒu�ɑ}�������B
�@10�|17�ɂ͘A�����Č�҂���̎������ށB����ɂ��O�҂́u�t�̖��v���I�ՂɈڂ�B���Ƃ͌�҂́u���̑��z�v�̈ʒu�ɂ���āA�I�Ղ̐F���������܂��Ă���B�����20�ɓ���邱�ƂŁA21�u�t�̖��v����24�u���C�A�[�v�܂ł̗��ꂪ�A�����邱�ƂɌ������O�����̗l����悷��̂ł���B
�@�~�����[�u�~�̗��v�����ł́A�ꌩ�͂���҂̍s���l�܂�I���W�Ɍ����āA���̓t���[���C�\�I���_�x������������ƒʂ��Ă���B����̓t���[���C�\���Ƃ��Ẵ~�����[�����ߍ��B����l�Ȃ̂ł���B
2010.10.18 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևH
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v2 ���u�E�C�v�ɂ�����~�����[�̎��
�@�O��u�~�̗��v�̋ȏ�����ɂ��āA�V���[�x���g�͊��Ɋ������Ă���12�Ȃɂ͎�������ɂ��̂܂ܑO�҂Ƃ��Đ����u���A�V���ɑ�������12�тɂ��Ă͊����ł̏��Ԃǂ���ɔ����o�����̏��Ԃŋȍ����s����҂Ƃ����ƌ��_�t�����B���A���m�ɂ͂���͐������Ȃ��B"��Ȃ�������"�Ƃ������߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���̈�ȂƂ͂Ȃɂ��H�@�܂��́A�O��f�ڂ����V���[�x���g�^�~�����[�̑Ώƕ\���ēx�����������������B
| �V���[�x���g | �~�����[ |
| 1 ���₷�� | 1 ���₷�� |
| 2 �����̊� | 2 �����̊� |
| 3 �������� | 3 �������� |
| 4 �X�� | 4 �X�� |
| 5 ���� | 5 ���� |
| 6 ���ӂ��� | 6 �X�֔n�� |
| 7 ��̏�� | 7 ���ӂ��� |
| 8 ������݂� | 8 ��̏�� |
| 9 �S�� | 9 ������݂� |
| 10 �x�� | 10 �������� |
| 11 �t�̖� | 11 ���炷 |
| 12 �Ǔ� | 12 �Ō�̊�] |
| 13 �X�֔n�� | 13 ���ɂ� |
| 14 �������� | 14 ���̒� |
| 15 ���炷 | 15 �܂ڂ낵 |
| 16 �Ō�̊�] | 16 ������� |
| 17 ���ɂ� | 17 �h |
| 18 ���̒� | 18 �S�� |
| 19 �܂ڂ낵 | 19 �x�� |
| 20 ������� | 20 ���̑��z |
| 21 �h | 21 �t�̖� |
| 22 �E�C | 22 �Ǔ� |
| 23 ���̑��z | 23 �E�C |
| 24 ���C�A�[�� | 24 ���C�A�[�� |
�@��Ȃ��ΏƂ���Ƃ�������̂悤�ɁA�u���̑��z�v�Ɓu�E�C�v�̈ʒu���t�]���Ă���B�V���[�x���g�͑����A�~�����[�����łł�23�Ԗڂɂ������u�E�C�v���22�Ԃɒu���ւ��Ă���̂ł���B��O�̈�ȂƂ́u�E�C�v�Ȃ̂ł���B��X�����ׂĂ݂����A���̗��R�ɂ��Ă̊m�ł��錋�_�͂Ȃ��悤���B����͂������낤�A�c�_���I����Ă���͂��̋ȏ��ɂ��Ă��l�X�ȋL�q�������ɑ��݂��Ă��邭�炢�ł��邩��A����Ȏ}�t���ߓI�ȕ������Ȃ�����ɂȂ��Ă��Ă�����s�v�c�͂Ȃ��B�ł�����͂���A�����́u�N�����m���_�v�Ŕ����Ă݂����B�e�[�}�́u�V���[�x���g�͂Ȃ��w�E�C�x�̈ʒu��ς����̂��H�v�ł���B
���E��Ő��̒��ɓ����Ă����Ă�낤�@����́A�~�����[�����ő�23�сu�E�C�v�̑�3�߂ł���B��ǂ��Ă�������̂悤�ɁA�u�~�̗��v�̒��Ŏ��ɂ���ِ͈F�̎��ł���B���߂Ȃǂ���Ȃ��A�ǂ�ł̂Ƃ��肾�B���̎����A�Ђ����玀����������N�̈Â��S����̂��Ă���̂ɁA����͂ǂ����낤�A�u�E��Ő��̒��ɓ����Ă����Ă�낤�v�u�^������������āv����̉ʂĂɂ́u�_�ɂȂ��Ă�낤�v�ł���B���ɐϋɓI�őO�����A�s���ł��炠��B�܂�Ŋv���̓��m�ł͂Ȃ����B���̂悤�ȁu�`���Ă�낤�v�I�Ȗ��m�Ȉӎv�\���́u�E�C�v�ł͑S����5��o�Ă��邪�A����23�тł͂قƂ�nj�������Ȃ��B�킸���ɁA��P�сu���₷�݁v�́u�����̂̑��Ղ����ǂ��Ă������v�A��4�сu�X���v�́u��ƕX��n�����������v�A��8�сu��̏�Łv�́u�Ƃ������ō��݂��悤�v�A��12�сu�Ō�̊�]�v�́u��]�̕��ŋ������v�̂S���ł���B�������S�Ƃ��������̈ӎv�\���ɉ߂��Ȃ��B�u�E�C�v�̏ꍇ�͂��ׂĂ��O�����Ȃ̂ł���B�ǂ��l���Ă�����ُ͈킾�I��̂���͂Ȃ��H �V���[�x���g�����Ԃ�ւ������Ƃ��l�@����O�ɁA�~�����[�͂Ȃ��u�~�̗��v�ɂ���ȂƂĂ��Ȃ�����}�������̂��H���l���Ă݂�K�v������B
���Ɨ��ɐ^������������āI
���̒n��ɐ_�����܂��ʂȂ�
�����������_�ɂȂ낤����Ȃ���
�@�E�B���w�����E�~�����[�i1794�|1827�j�̓h�C�c�A�f�b�T�E�o�g�̎��l�ł���B���e�͎d�����̐E�l���������A����M�S�ȏ�ɑ����T���������悤�ŁA���̂��߃~�����[�͏\���ȋ������ꂽ�B�x��������w�݊w���́A�t�����X����푈���N����Ɛi��ł��̗���ɐg�𓊂��Ă䂭�B���̌ト�[���b�p�ł́A�����l�𒆐S�ɁA�M���V���̑g���R�Ɨ��^���x���̕��������܂邪�A�~�����[�͂���ɂ����A�ϋɓI�Ɏx���̎��슈�����s�����B���Ȃ萭���F�̋����������ł���B�܂��A���M���ׂ��́A�t���[���C�\���ւ̓����ł���B"�T��""������""�t���[���C�\��"�E�E�E����炪�~�����[�Ƃ������l�̃L�C���[�h�ł���B���U�n�R�Ő��������Ƃ͂قƂ�ǖ����������V���[�x���g�Ƃ́A���炩�ɈႤ�l���̐F����������B�قړ����������l�Ȃ̂ɁB
�@�~�Î���Ò��u�~�̗��`24�̏ے��̐X�ցv�i�������Њ��j�ɂ��ƁA�~�����[���t���[���C�\���ɓ�����̂́A���C�v�c�B�q�Łu�~�̗��v�����M���̂��낾�����Ƃ����B���[�c�@���g�̓t���[���C�\���ɓ����A���C�\���֘A�̋Ȃ𑽐������Ă���B�u�t���[���C�\���̂��߂̑������y�vK477�����ɗL���������̂ق��ɂ��A�̋ȁA�����ȁA�J���^�[�^�ȂǏ��Ȃ��Ƃ�10���Ȃ��c���Ă���B��ƂȂ��ɂ���́u���[�c�@���g�̉��y�́A�t���[���C�\���ɓ����A���I�ɕς�����v�Ƃ��̉e���͂̑傫�����w�E���Ă���B���������āA�~�����[�����C�\������セ�̎v�z�f�������������̂͂����R�Ȑ���s�����������낤�B�u�E�C�v�̊j�S�����u���̒n��ɐ_�����܂��ʂȂ� �����������_�ɂȂ낤����Ȃ����v�̌��́A�܂��Ƀt���[���C�\���̊�{���O�ɒʂ�����̂��B����ɁA�u�_�ɂȂ낤����Ȃ����v�̎�ꂪ"��"�ł͂Ȃ�"������"�ƂȂ��Ă���̂��A"��X���u"�Ƃ������C�\���퓅��ɕ�������B�܂��Ƀ��C�\���v�z�̕\�o�Ȃ̂ł���B
�@�u�E�C�v��2�߂́u�S�̌�肩���鐺�͕����܂��B�S�̒V�����ɋ������߂܂��B�V���͋����҂̂��邱�Ɓv�Ƃ�������Ȍ��t�Ŗ��܂��Ă���B���炽�߂čl���Ă݂�܂ł��Ȃ��A�u�~�̗��v�͑S��"�S�̒V��"�̕\�o�ł���B�Ȃ�Ɓu�E�C�v�̕����Ƃ�������Ă��邱�Ƃ��낤�B������u�E�C�v�̓��ِ��̏ؖ��̂ЂƂł���B
�@�n�쒆�̃e�[�}��"�Љ��͂ݏo�����悻�҂̐S�ە��i�̕`��"�A���C�\���v�z��"����_�ɂ��Ȃ낤�Ƃ���ϋɓI�O�����p��"�B�~�����[�͎��l�Ƃ��āA�t���[���C�\���l�Ƃ��āA���̋��Ԃŗh�ꂽ���Ƃ��낤�B���l�~�����[�Ƃ��Ắu�~�̗��v�̒��Ɂu�E�C�v�̂悤�Ȏ�������ɂ͈�a���������B���܂�ɂ��َ������炾�B�ł́A�������ɂ܂Ƃ߂Ă��܂������B���⎩���̓��C�\���̉�����B�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͂�����������Ȃ��u��������v�ł���B�~�����[�͎��l�Ƃ��Ăł͂Ȃ��t���[���C�\������Ƃ��āu�E�C�v�������A�u�~�̗��v�̑�23�Ԗڂɑ}�������B
�@�ȏオ�u�E�C�v�ɂ����鎄�̌��������A�ł́A���Ђ��鏑���ł͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���H �����̌��ʁA�u�E�C�v�ɂ��Ă̋L�q�͂܂��Ƃɏ��Ȃ������B��������قǑ����̒����ǂ킯�ł͂Ȃ����A����ł��A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�A�쑽�����~�A�~�Î���ÂȂnj��Ђ���V���[�x���g���́A�u�~�̗��v�֘A���͔̂q�ǂ��Ă���B�A�C���V���^�C���́u�V���[�x���g���y�I�ё��v�ł́A��1�߂̎������p���āA�u���������̗z�C���͖�დI�ł����āA������n���K���A���́≼�ʂ����Ă���̂ł���v�Ƃ����L�q�����邾�����B���͂��Z�����A���e���y�Ȃɂ��Ă̋L�q�ł���A�~�����[�̎��ւ̌��y�ł͂Ȃ��B�~�Î��́u�w�~�̗��x�`24�̏ے��̐X�ցv�͋Ȃ��ƂɎ����Ȃ̏ے�������̂����ɓW�J����X�^�C���̂��߁A��22�ȁu�E�C�v�ɂ�����L�q�͑��������Ē����B�u���v���ے�������́A�u�_�v�������`�ł��邱�Ƃ̈Ӗ��A�o�ŎЂ̈ڒ��̖��ȂǁA���e�I�ɂ����ɖL�x���B�����A����ł��Q�l�ɂ��������ł��邪�A"�u�E�C�v�̓ˏo������a��"�Ƃ������{�I�ȕ����ւ̌��y�͂Ȃ��B�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv�Ɗ쑽�����́u�V���[�x���g�v�ɂ́A�u�E�C�v�ɂ��Ă̋L�q�̔j�Ђ��Ȃ��B�V���C�G���u�w�~�̗��x�ƃV���|�x���g�̓�v�́A�u�~�̗��v��҂��t���[���C�\���v�z�ƌ��т������e�Ƃ̂��Ƃ����A���݂ł͂��܂�d�v������Ă��Ȃ��������B�u�E�C�v�����Ȃ炢���m�炸�A12�т��֘A�t����̂ɂ͖���������̂��낤�Ɛ����ł���B�Ƃ͂����A���ǂɂ��@�����Γǂ�ł݂����Ǝv���B
�@�J��Ԃ����u�E�C�v�́u�~�̗��v�̒��ŋɒ[�Ȃ܂łɈِF�̎��ł���B���̎��͂��ׂāu�Љ��a�O���ꂽ�悻�҂̌������̐S�ۂ�`���Ă���v�̂ɑ��u�E�C�v�������ϋɓI�O�����Ȍ��ӂ̉̂Ȃ̂��B�܂��Ɂu�~�̗��v�́u�悻�ҁv�ł���B�����q��łȂ��Ɗ�����͎̂��Ɏ��R�Ȋ����ł͂Ȃ��낤���B���ꂪ�A�L���҂̊��o�������̔@���������̂ɂ́A���Ȃ��炸�ʐH������B
�@�����̕��X�́A���Ƃ̈Ⴂ��������V���[�x���g�̐��Ƃł���B�����炱���A�{�\�I�Ɂu�~�̗��v���ە������Ă��܂��Ă���B�u�E�C�v�Ƃ������ُ̈킳�ɋ^������܂Ȃ��B"�m���ɐq��ł͂Ȃ����A�Ӑ}�͗����ł���"�ȂǂƖ��ӎ��̂����ɐ��������Ă���̂��낤�B�����������炱�̊��o���^�����������Ă���A����ȋC������B ����́u�E�C�v�ɑ���V���[�x���g�̑Ή��ւƘb��i�߂悤�B
2010.10.07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևG�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v�P���ȏ��̓䁄
�u�~�����[�͂����w������p�J�����̈�e���W�x�ł́A�ȑO��12�тƐV����12�тƂ̏�������בւ��A�ЂƂɂ܂Ƃ߂��B�V���[�x���g�͂��łɍ�ȍς݂�12�Ȃ��w��ꕔ�x�Ƃ��Ă��̂܂ܐ����u���A�c���12�Ȃ́w��x�Ƃ��āA�����Ȃ�̍l���ɏ]���Č����W�Ƃ͈قȂ鏇���ɕ��בւ����v�@����̓V���[�x���g�̖����Ƃ����쑽�����~�����u�V���[�x���g�v�i�����I���j�̒��̈�߁B���n���E���[�g���B�q�E�E�B���w�����E�~�����[�i1794�|1827�j�́u������z���������̈�e���W�v�ɂ́A�u�~�̗��vWinterreise�S24�т̊����`���܂܂�Ă���B�Ƒn�I�Ŗ��͂���V���[�x���g�_��W�J����쑽�����ł��邪�A
 ����"�u�~�̗��v�̑�͎����Ȃ�̍l���ɏ]���Č����W�Ƃ͈قȂ鏇���ɕ��בւ���"�Ƃ������́A���S�ȊԈႢ�Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A�j���A���X�I�ɂ��Ȃ�^���Ƃ͈Ⴄ�������ł���B�܂��A���U��8����u�~�̗��v��^�����Ă���20���I�ő�̃o���g���̎�A�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�̒����u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv�i�����Њ��j�ɂ́E�E�E�E�O����12�Ȃ��������ꂽ���ƁA�V���[�x���g�͎��W�̑�Ƃ��Ắu������p�J�����̈�e���W�v�̂Ȃ��ɁA�~�����[�̂��̃`�N���X�̊��S�ȃe�L�X�g�������o�����B�����Ƃ��A�܂���Ȃ���Ă��Ȃ������c���12�̎��́A�����Ƃ��ď����Â����Ă͂��炸�A���X�ɎU����Ă������̂�V�������וς������̂ł���B�V���[�x���g�͂����̎�����肵���ʂ�ɍ�Ȃ��A��������łɂł��Ă������̂ɂ��������̂ŁA�ނ��Ӑ}���ă~�����[�̎��̏����ɕύX���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������A����͂��������X�̃��[�g�̃e�L�X�g�ɂ��Ă����邱�Ƃł���B�E�E�E�E�Ƃ���B���̕��͂͊쑽�����̂��͓K�ȋL�q�ł��邪�A��������ɂ����B�ł́A�V���[�x���g�́u�~�̗��v�S24�т̋ȏ����ǂ̂悤�ɂ��Č��߂��̂������ǂ��Ă݂悤�B
����"�u�~�̗��v�̑�͎����Ȃ�̍l���ɏ]���Č����W�Ƃ͈قȂ鏇���ɕ��בւ���"�Ƃ������́A���S�ȊԈႢ�Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A�j���A���X�I�ɂ��Ȃ�^���Ƃ͈Ⴄ�������ł���B�܂��A���U��8����u�~�̗��v��^�����Ă���20���I�ő�̃o���g���̎�A�f�B�[�g���q�E�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�̒����u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv�i�����Њ��j�ɂ́E�E�E�E�O����12�Ȃ��������ꂽ���ƁA�V���[�x���g�͎��W�̑�Ƃ��Ắu������p�J�����̈�e���W�v�̂Ȃ��ɁA�~�����[�̂��̃`�N���X�̊��S�ȃe�L�X�g�������o�����B�����Ƃ��A�܂���Ȃ���Ă��Ȃ������c���12�̎��́A�����Ƃ��ď����Â����Ă͂��炸�A���X�ɎU����Ă������̂�V�������וς������̂ł���B�V���[�x���g�͂����̎�����肵���ʂ�ɍ�Ȃ��A��������łɂł��Ă������̂ɂ��������̂ŁA�ނ��Ӑ}���ă~�����[�̎��̏����ɕύX���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������A����͂��������X�̃��[�g�̃e�L�X�g�ɂ��Ă����邱�Ƃł���B�E�E�E�E�Ƃ���B���̕��͂͊쑽�����̂��͓K�ȋL�q�ł��邪�A��������ɂ����B�ł́A�V���[�x���g�́u�~�̗��v�S24�т̋ȏ����ǂ̂悤�ɂ��Č��߂��̂������ǂ��Ă݂悤�B�@�~�����[���������u�~�̗��v�̑O��12�т̓��C�v�c�B�q�Ŋ��s���ꂽ�u�E���[�j�A�v�Ƃ����N�ӂɌf�ڂ��ꂽ�B1823�N�̂��Ƃł���B�V���[�x���g�����̋ȕt�������������͎̂��̑O�N1827�N��2���ł������B���̊Ԃ̂ǂ̎����ɔނ��u�~�̗��v�ɑ����������͒肩�ł͂Ȃ����A������ɂ���A���ɂ�����a��w�����Ă��܂����V���[�x���g���A���̎��ɏՌ�����l���Ɏ��Ȃ𓊉e�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�����炢�̗��ɏo�邫�������������������ɂ���A�����n�߂��V�����Љ������͂���A�Љ�I�ɂ����_�I�ɂ��s����������A��O�Ɏ������������Ă��Ȃ���҂̐S��A���̎����̃V���[�x���g�ɂ͒ɂ��قǗ����ł����̂��낤�B�u�~�̗��v�̎�l���́A��O�Ɏ��������Ă��Ȃ��̂ł���B���̂�����̂��Ƃ��t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́u��ȉƃV���[�x���g�����̎d���ɂƂ肩�������Ƃ��̊����̗l�q������ƁA�����̎������̂Ƃ��̔ނ̑n��ӗ~�ɂǂ�قǂ҂�����ł�������������������v�Əq�ׂĂ��邪�A�o�T�͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B���̌��ł́A�V���[�x���g�̓��L��莆�A�F�l�����̋L�^�̒��ɂ����̏��L�������̂͂Ȃ��B���������Ă��̌��A������������ނ̐����Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�O�Ҋ������1827�N�ӉāA�V���[�x���g�́A�~�����[�́u������p�J�����̈�e���W�v�Ƃ����Ҏ[�{�̒��Ɂu�~�̗��v�̊����łƏ̂���24�т̎��W������B���Ȃ킿�~�����[��12�т́u�~�̗��v�O���̊�����A�������o�Ă����12�т̌㔼�̕������������̂ł���B���͂��̔��\�̎d���ł���B�O���͑O���Ŕ��\�������ƁA�㔼�͌㔼�����Ŕ��\���Ȃ������̂��B�O�㔼�����̂����V�������Ԃ���ёւ��A�S24�т̊����łƂ��Ĕ��\�����̂ł���B����V���[�x���g�̑����猩��ƁA�u�~�̗��v�O��12�Ȃ���������������ɁA�S24�т̊����`������A�����Ē����ɑS�҂̊����Ɍ������ȍ����n�߂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ŐS���ׂ���ȃ|�C���g�͓�B��́A�~�����[�̊����ł������Ƃ��A�V���[�x���g�͊��ɑO����12�Ȃ̋ȍ����������Ă������ƁA������̓~�����[�̊����ł��V���ɏ��Ԃ��ς����Ă����Ƃ����_���B
�@���y�j�ケ��قǂ܂łɊ�ȉߒ����o�ďo���オ�����̋ȏW�͑��ɂȂ����낤�B�����āA���̗��ꂪ�A��ȏW�u�~�̗��v�̂���퐫�i������t�����̂ł���B�u�~�̗��v���~�X�e���A�X�Ŗ��͓I�ŁA�l�X�ȉ��߂≯����������v���͐��ɂ��̊�ȉߒ��ɒ[���Ă���̂ł���B
�@ �@�V���[�x���g�́A���̊����`�����āA���炭���R�Ƃ����Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�A�O�q�����悤�ɁA���̊����ł͑O�҂̂��ƂɐV���ɍ����12�т̎���P���ɉ��������̂ł͂Ȃ��A���������S24�т�V�������ёւ������̂���������ł���B�V���[�x���g�́A��x�͂��̊����ł̏��Ԃǂ���ɋȍ����s�����ƍl�������Ƃ��낤�B�������A���ɍ�Ȃ��������Ă���O�ҁi������Ƃ��ɂ͌�҂����낤�Ƃ͎v�������Ȃ������낤���j12�Ȃ́A���̗���ɉ����Ċe�Ȃ̒������L�b�`���ƘA�g�������Ă���B������o�������Ƃ͕s�\�ł���A�����A�����ł̏��Ԃǂ���ɍ�낤�Ƃ���A�S�̂�V���ɍ�蒼���ɓ�������Ƃ����邱�ƂɂȂ�B����͂��蓾�Ȃ��B�|�p�ƂɂƂ��Đ������߂č��グ����i�̂ɂ��邱�ƁA�����āA���̂Ƃ��̃V���[�x���g�̈�������a��͂�����͂���͂����Ȃ��������낤����B
�@���j�[�N�ȁu�~�̗��v�̉�͏��A�~�Î���Î����u�~�̗��`24�̏ے��̐X�ցv�i�������Њ��j�ɂ��A�u���������V���[�x���g�����̋C�ɂȂ�A�O���̓r���ɐV���Ɂw�X�֔n�ԁx��}�����ĉ��y�I�ɉ��̕s���R���Ȃ��Ȃ��邱�ƂȂǁA�ނ̓V�˂������Ă���ł��Ȃ����Ƃł͂Ȃ����낤�v�Ƃ̌������������A����͂��܂�Ɉ�ʓI�Ȍ������B�ύX�_�����̈�_�����Ȃ炢�����炸�A�V���ɍ��������3�т�A�����đO���ɓ���i10�\12�j�A�͂ݏo����4�т̊����̎����㔼�ɁA������͑������ɊԂɐV���Ȏ�������œ����i18�C19�C21�C22�j�A���������Ȃ�I�Ջ߂��ɁE�E�E�Ƃ�����̍��`�Ń~�����[�̓V���b�t�����Ă���̂ł���B���̕��тőS�̂�����������̂́A�V���[�x���̓V�˂������Ă��Ă����݂̘J�͂ł͂Ȃ��Ǝ��͎v���̂��B
�@���āA�V���[�x���g�͂ǂ��������E�E�E���Ɋ������Ă���12�Ȃ͎�������ɂ��̂܂ܑO�҂Ƃ��Ēu���A�V���ɑ�������12�тɂ��Ă͊����ł̏��Ԃǂ���ɔ����o�����̏��Ԃŋȍ����s����҂Ƃ����̂ł���B�����~�����[��́u���������ԏ����̖��vD795�́A�����̂͂�����Ƃ����o��l�������āA�o��|�����|�����|���E�Ƃ�����̓I�ȏo�����ɂ���ăX�g�[���[���W�J����B����A�i���O�I�ȂȂ���ł���B����ɑ��u�~�̗��v�͈�l�̂̎��ŁA���ݐi�s�`�̓o��l���͂قڂ��̎�l����l�����B���Ă̗��l�₻�̕�e�A���̓y�n�̐l�X�Ȃǂ͉�z�̒��ɏo�Ă���ɉ߂����A���̓o��҂Ƃ��Ă݂͂��ڂ炵���X�p�̃I���K���e�����炢�ŁA���Ƃ͌����낪�����������B�N���o�錾�t�͐S�ɉf�镗�i�Ǝ����ւ̖₢��������B�u���������S�v�ɒf���I�Ɂu�ߋ��ւ̓���v���t���b�V���E�o�b�N����"�O�ƂP"�̓�i�@�B�����A�܂�Ńf�W�^���̐��E���Ȃ���Ȃ̂ł���B������ȏ��ɂ́u���ԏ����v�قǂ̕K�R���͂Ȃ��B�V���[�x���g���~�����[�����ł̏����Ɋ����ċȏ������킹��K�v���Ȃ������̂͂��̂��߂ł���B
�@�������ăV���[�x���g�͋ȏ������߂��B����Ӑ}�������Č����̏��Ԃ�ւ����̂ł͂Ȃ��A�ނ���@�B�I�Ɍ��߂��̂ł���B���ꂪ�u�~�̗��v�ȏ�����̐^���ł���B���ɒP���Șb��"��"�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A�^�C�g�������͔ۂ߂Ȃ����E�E�E�B���������A���Ԃɗ��z���Ă���u�~�̗��v�̋ȏ��Ɋւ���B���ȊT�O������Ƃ����_�ɂ����ẮA���ɗ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@ �@�Ō�Ɂu�~�̗��v�ɂ�����V���[�x���g�̋ȏ��ƃ~�����[�̃I���W�i���̏��Ԃ�Δ䂳���Ă����B�~�����[�̕\����A�V���[�x���g����ɓ��ꍞ���i�����\�L�����j�̈ړ���ǂ��A�V���[�x���g�ȏ�����̎��̂��悭������Ǝv���B
| �V���[�x���g | �~�����[ |
| 1 ���₷�� | 1 ���₷�� |
| 2 �����̊� | 2 �����̊� |
| 3 �������� | 3 �������� |
| 4 �X�� | 4 �X�� |
| 5 ���� | 5 ���� |
| 6 ���ӂ��� | 6 �X�֔n�� |
| 7 ��̏�� | 7 ���ӂ��� |
| 8 ������݂� | 8 ��̏�� |
| 9 �S�� | 9 ������݂� |
| 10 �x�� | 10 �������� |
| 11 �t�̖� | 11 ���炷 |
| 12 �Ǔ� | 12 �Ō�̊�] |
| 13 �X�֔n�� | 13 ���ɂ� |
| 14 �������� | 14 ���̒� |
| 15 ���炷 | 15 �܂ڂ낵 |
| 16 �Ō�̊�] | 16 ������� |
| 17 ���ɂ� | 17 �h |
| 18 ���̒� | 18 �S�� |
| 19 �܂ڂ낵 | 19 �x�� |
| 20 ������� | 20 ���̑��z |
| 21 �h | 21 �t�̖� |
| 22 �E�C | 22 �Ǔ� |
| 23 ���̑��z | 23 �E�C |
| 24 ���C�A�[�� | 24 ���C�A�[�� |
2010.09.22 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևF
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�����̃����E�����6�u�����Ɍ��ЂɂȂ�Ȃ��ŁI�v
�i�P�j�����E����[��6�D22�u�����Ɍ��ЂɂȂ�Ȃ��ŁI�v�@�M�Z�́u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�����ł̃��X�g��q�����܂��āA���߂Ċ��������Ƃ��ȉ��ɏ����Ă݂܂��B
�@�u�����炢�l�v�u���Ɖ����v ���̂Q�Ȃ́A��Ńs�A�m�Ȃ⌷�y�l�d�t�Ȃɓ]�p����ă^�C�g�����L���ɂȂ������̂ł����A�����̓I���W�i���̉̋Ȃ͂���ȂɌ��삾�Ƃ�������������܂���B�]���܂��āA�������u���ɂ̃V���[�x���g�v��I�ԂƂ���A�����̋Ȃ͓���Ȃ����낤�Ǝv���܂��B
�A�u�����v�u�Ώ�ɂāv�́A�ǂ�ȋȂ��������A�S���L���ɂ���܂���A�����A�u�����A���ꂪ���̋Ȃ������̂��v�Ǝv���o���̂����m��܂��A����܂ŏ����̐S�̒��ɗ��܂�Ȃ������Ȃł��B
�B�u���̈��A���v�u��Ɩ��v�́A�����̂��Ƃ͎v���܂����A"����"�ɓ����ɂ́A������s���̂悤�ȋC�����܂��B�u�q��́v���A�����̂ɈႢ�Ȃ��ł����A��͂�A����"�y��"�����B������������A�����̉̂ɑւ��āA�u�A���v�X�̎�l�v�A�u���i��j�l�v�A�u�A�`���X�v�Ȃǂ����܂��B�u�A�`���X�v�́A�u�����Ȃ��ȁv�Ƃ�����ۂ��c���Ă���݂̂ŁA���݁A�����̓��̒��ɂ́A��̓I�Ȑ����͕����Ȃ��̂ł����A�Ⴕ������"���ɂ�"���Z���N�g����ۂɂ́A�^����ɍČ����Ă݂����̂ł��B�u���l�v�́A�����A�M�Z����́u�����ۂ��ȁv�Ƃ���ꂻ���ł����A�����A���l�ł��̂ŁA���̋Ȃ�"�D�݂̋�"�Ȃ̂ł��B
�C�f���[�j�b�V���ȋȂƂ��������A���c���q����̂����悤�ɁA"���ɂƂ�߂��ꂽ�悤�ȋ�"�Ƃ����������̂ق����A�V���[�x���g�ɂ͍����܂��ˁB���̂悤�ȋȂ��\����̂��A�����Ƃ��Ắu�M�l�̕ʂ�̎��v�ł��B�����Ƃ��A�u���v�u���̎g���v�Ȃǂ��A�����Ȃ�ʁA"�V�g�ɂƂ�߂��ꂽ�悤�ȋ�"�ł��ˁA�ӔN��"���ɂƂ�߂��ꂽ�悤�ȋ�"���P�Ȃ͓��ꂽ�����������܂��B
�@���́u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȁv�A���R�A�M�Z�́u�N�����m�v�Ŕ��\����邩�Ƃ������܂����A���̂��ƂɊւ��āA�����ӌ����q�ׂ܂��B
�D�I�肳�ꂽ�Ȗڂ�����ƁA�V�����u�N�����m�v�A���Ƃ̂R�����u�N�����m�v�Ƃ������������܂��B���������u�N�����m�v�̕����𑝂₵�A�V���[�x���g�ʂ����X�点��悤�ȃT�v���C�Y���~�����悤�ȋC�����܂��B
�E��ѓ��茴�e�́u���ɂ̃V���p���v�ƈႢ�A�V���[�x���g�́A���N�O���ɋM�Z�������ƒNj�����Ă�����e�[�}�ł��̂ŁA�����������Ԃ������āA����ɂ킽��_�l�̖��ɋȖڂ����肳�ꂽ�ق����ǂ��悤�ȋC�����܂��B
�F��̓I�ɂ����܂��ƁA�����Ǖ�Ȃǂ̐��Ƃ�X�点��悤�Ȑ�����~���������A �u�������ЂɂȂ��Ă��܂��v���Ƃ́A���ƃV���[�x���g�̉̋ȂɊւ��ẮA�֕��ł͂Ȃ����Ɗ뜜���܂��B
�@�ł��A�M�Z�̂̂߂荞�݂̐[���Ƒ����ɂ́A�����A�u���Q�I�v�̈��A�E�X�ł��B
�i�Q�j���������[��6�D22�u���悢��w�~�̗��x�ցv
�@�u�V���[�x���g�E���[�g�̐X�v�͏��̌��������̂ŁA���ɖʔ��������B���Ƀ����E�����Ƃ̂����́A��ϖʔ����Ă��߂ɂȂ�܂����B�ނ�ł���\���グ�܂��B
�@�ł́A�ȉ��M�N�̏����ɂ����������ƂȂǏq�ׂ����Ă��������܂��B�i���ȉ������̃R�����g�ł��j
�@�u�����炢�l�v�u���Ɖ����v���̂Q�Ȃ͌�Ńs�A�m�Ȃ⌷�y�l�d�t�Ȃɓ]�p����ă^�C�g�����L���ɂȂ������̂ł����A�����̓I���W�i���̉̋Ȃ͂���ȂɌ��삾�Ƃ�������������܂���B�]���܂��āA�������u���ɂ̃V���[�x���g�v��I�ԂƂ���A�����̋Ȃ͓���Ȃ����낤�Ǝv���܂��B
����������邱�Ƃ͂悭������܂��B�������A���́A��ɃV���[�x���g����y�Ȃɓ]�p�����̋Ȃ́A�u�ނ̎v�����ꂪ�����悭�m���Ă���ȁv���u�e���݂₷������v�ƒP���ɍl���܂����B���ꂼ�܂��Ɏ���"����"�ł���A�M�N�ƈႤ�R���Z�v�g�Ȃ̂ł��B
�A�u�����v�u�Ώ�ɂāv�́A�ǂ�ȋȂ��������A�S���L���ɂ���܂���A�����A�u�����A���ꂪ���̋Ȃ������̂��v�ƁA�v���o���̂����m��܂��A����܂ŏ����̐S�̒��ɗ��܂�Ȃ������Ȃł��B
 ���u�Ώ�ɂāv�͂Ƃ������i�������X�g����O���Ă܂����j�A�u�����v���L���ɂȂ��Ƃ͂�����ƐM�����܂���B���}�j�A�b�N�̋S�E�����E�����I�@�D�������͕ʂɂ��āA�u�����v�͒��|�s�����[�ȋȂł���B�F����F���Ȃ́A�����u�l����100���v�̒��ŁA�u�l�̓V���[�x���g�́w�����x����D���ŁE�E�E�w�����x�����̂��߂ɂ��̔Ղ��������悤�Ȃ��̂��v�Ɓu�L���X���[���E�o�g�� �V���[�x���g�̋ȏW�v�𐄑E���Ă���̂ł��B�ܘ_�A��������Ȃ��ɍD���ȋȁA���邭�������Ɉ��Ă��Ď��Ƀ`���[�~���O�ȋȂ���Ȃ��ł����B�o�g���̃V���[�x���g�͋M�N�̐��E�Ղł�����̂Ő���m�F���Ă݂Ă��������ȁA5�Ȗڂɓ����Ă��܂�����B
���u�Ώ�ɂāv�͂Ƃ������i�������X�g����O���Ă܂����j�A�u�����v���L���ɂȂ��Ƃ͂�����ƐM�����܂���B���}�j�A�b�N�̋S�E�����E�����I�@�D�������͕ʂɂ��āA�u�����v�͒��|�s�����[�ȋȂł���B�F����F���Ȃ́A�����u�l����100���v�̒��ŁA�u�l�̓V���[�x���g�́w�����x����D���ŁE�E�E�w�����x�����̂��߂ɂ��̔Ղ��������悤�Ȃ��̂��v�Ɓu�L���X���[���E�o�g�� �V���[�x���g�̋ȏW�v�𐄑E���Ă���̂ł��B�ܘ_�A��������Ȃ��ɍD���ȋȁA���邭�������Ɉ��Ă��Ď��Ƀ`���[�~���O�ȋȂ���Ȃ��ł����B�o�g���̃V���[�x���g�͋M�N�̐��E�Ղł�����̂Ő���m�F���Ă݂Ă��������ȁA5�Ȗڂɓ����Ă��܂�����B�B�u���̈��A���v�A�u��Ɩ��v�́A�����̂��Ƃ͎v���܂����A"����"�ɓ����ɂ́A������s���̂悤�ȋC�����܂��B
���u���̈��A���v�͂����Ȃł���B�i�M�N�̑I���ɂ͂Ȃ��j��y�Ȃւ̓]�p���m�ł�����܂����E�E�E�u�s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂̌��z�ȁvD934�̑�R�y�͂ł��B����������Ă݂Ă��������B�Î_���ς��t�̎v���o���S��悤�ŋ����W�[���ƂȂ�܂��B�u��Ɩ��v�̃V���v���Ȕ��������������Ăق����B�t�F���V�e�B�E���b�g���̂��`���A�V���I�ȃs�A�j�b�V���̔��������Ă���������B���ɂȂ邱�Ɛ��������ł��B
�u�q��́v���A�����̂ɈႢ�Ȃ��ł����A��͂�A����"�y��"�����B
������͓���p�Ƃ��Ă͊O���܂���B
������������A�����̉̂ɑւ��āA�u�A���v�X�̎�l�v�A�u���i��j�l�v�A�u�A�`���X�v�Ȃǂ����܂��B�u�A�`���X�v�́A�u�����Ȃ��ȁv�Ƃ�����ۂ��c���Ă���݂̂ŁA���݁A�����̓��̒��ɂ́A��̓I�Ȑ����͕����Ȃ��̂ł����A�Ⴕ�������u���ɂ́A�v���Z���N�g����ۂɂ́A�^����ɍČ����Č������̂ł��B�u���l�v�́A�����A�M�Z����́u�����ۂ��ȁv�Ƃ���ꂻ���ł����A�����A���l�ł��̂ŁA���̋Ȃ�"�D�݂̋�"�Ȃ̂ł��B
�����̂S�O�Ȃ��甲���Ă���������C�̓T���T������܂���B���Ȃ݂ɁA�u���l�v�����Ȃ��̂́A����"�����ۂ�"����ł͂Ȃ��āA���܂Ə��l�̂���肪�A���ɂ͂ǂ����O���e�X�N�Ƃ����������Ȃ�����Ȃ̂ł��B�ł����l���Ă������ł��ˁB�쎍�̃R���[���́A���̐��ɂ����炩�ȁu��Ɩ��v�̍�҂ł�����̂ł�����B
�C�f���[�j�b�V���ȋȂƂ��������A���c���q����̂����悤�ɁA"���ɂƂ�߂��ꂽ�悤�ȋ�"�Ƃ����������̂ق����A�V���[�x���g�ɂ͍����܂��ˁB���̂悤�ȋȂ��\����̂��A�����Ƃ��Ắu�M�l�̕ʂ�̎��v�ł��B�����Ƃ��A�u���v�A�u���̎g���v�Ȃǂ��A�����Ȃ��"�V�g�ɂƂ�߂��ꂽ�悤�ȋ�"�ł��ˁA�ӔN��"���ɂƂ�߂��ꂽ�悤�ȋ�"���P�Ȃ͓��ꂽ�����������܂��B
����͂�u�����������₷���܂Ƃ߂����v�Ƃ����̂�����܂��āA"���ɂƂ�߂���^"�͕ʂ̋@��ɒ��������Ǝv���܂��B�܂��A�������ɒu��������A"���ɂƂ�߂��ꂽ���y"�Ƃ������ƂɂȂ�A���ꂼ�܂��Ɂu�~�̗��v�Ȃ킯�ŁA����ɂ��ẮA���̂��Ƃ�������Ǝ��g�ނ���ł��܂��B
�D�I�肳�ꂽ�Ȗڂ�����ƁA�V�����u�N�����m�v�A���Ƃ��R�����u�N�����m�v�Ƃ������������܂��B���������u�N�����m�v�̕����𑝂₵�A�V���[�x���g�ʂ����X�点��悤�ȃT�v���C�Y���~�����悤�ȋC�����܂��B
�����x�������悤�ɁA"����I����"���傫���̂ŁA�M�N�̂������̔䗦�����āA�t�ɑ听���Ɗm�M�����Ă��������܂����B
�E��ѓ��茴�e�́u���ɂ̃V���p���v�ƈႢ�A�V���[�x���g�́A���N�O���ɋM�Z�������ƒNjy����Ă�����e�[�}�ł��̂ŁA�����������Ԃ������āA����ɂ킽��_�l�̖��ɋȖڂ����肳�ꂽ�ق����ǂ��悤�ȋC�����܂��B
��3��̋ȏW�ȊO�ɂ��ẮA�قڂ���31�ȂŌ��߂����ł��B
�F��̓I�ɂ����܂��ƁA�����Ǖ�Ȃǂ̐��Ƃ�X�点��悤�Ȑ�����~���������A�u�������ЂɂȂ��Ă��܂��v���Ƃ́A���ƃV���[�x���g�̉̋ȂɊւ��ẮA�֕��ł͂Ȃ����Ɗ뜜���܂��B
���u�����Ǖコ���X�点��v�ł����A�E�[���A�����ł��˂��E�E�E�E�ނ́A���R�|1989�N4�����ŁA�t�F���V�e�B�E���b�g�̃V���[�x���g���A�u�V�������c�R�b�v�Ƃ͊i���Ⴄ���A���[�g�Ƃ������̂ւ̌��������p�����܂�ňႤ�v�ƌ����āA�Ȃ��Ă����ł���B����Ȍ�m��X�点�Ă����܂�Ӗ����Ȃ��悤�ȋC������̂ł����A�������Ȃ��̂ł��傤���B�܂��A������������X�点�邽�߂ɖ����ɋÂ����Ȃ�I�ԂƂ����̂��A���̂������Ⴀ��܂��B���ӌ��͂��肪�����̂ł����A����͂��̂܂��̃R���Z�v�g���т����Ă��������܂��B
�@���̂��Ƃ́A���悢��A���c���Ă������u�~�̗��v�̌��ɓ��낤�Ǝv���܂��B���ݑI��ł���̂��u�����v�u�t�̖��v�u������ׁv��3�Ȃł����A�{���ɂ���ł����̂��H�[���ȁu�V���[�x���g�̋Ȃ̐X�v�̒��ł��A��є���������ł��邱�̉̋ȏW�́A����Ӗ��[����ɕ�܂ꂽ��i�ł�����܂��B������ɂ߂Ă������̃V���[�x���g�u���Ɂv�̉̋ȏW������������̂Ǝv���Ă��܂��B���ꂩ����A�h���̂��w�E���Ȃɂ��Ƃ�낵�����肢�������܂��B�����E�����̂��ӌ��͂��ł��Ȃ�ł��劽�}�ł�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v���X�g�����łP
�P ����a���O���[�g�q�F�� D118
�Q �e�̂Ȃ��� D138
�R ��� D257
�S ���� D328
�T ����߂̘A�� D343
�U ���� D433
�V �����炢�l D489
�W �q��� D498
�X ���Ɖ��� D531
10 �Ώ�ɂ� D543
11 �K�j�����[�g D544
12 ���y�Ɋ� D547
13 �܂� D550
14 �^���^���X�̌Q�� D583
15 �t�̑z�� D686
16 �Y���C�J�T D720
17 ���̈��A���@D741
18 �~���[�Y�̎q D764
19 ���̏�ʼn̂� D774
20 �N�����͌e�� D776
21 �܂̉J�@D795-10
22 �[�f���̒��� D799
23 ��Ɩ� D827
24 �Ⴂ��m D828
25 �A���F�E�}���AD839
26 ���������m����̂����� D877-4
27 �t�� D882
28 �j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��� D886-3
29 ���������A�Ђ� D889
30 �V�����B�A�� D891
31 ���� D911-5
32 �t�̖� D911-11
33 ������� D911-20
34 �� D939
35 �Z���i�[�f D957-4
36 �ʂ� D957-7
37 �s�� D957-11
38 �C�ӂɂ� D957-12
39 ���̎g�� D957-14
40 ��̏�̗r���� D965
2010.09.03 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևE�@�����̃����E�����5�u�ّ��͋֕��v
�i�P�j�����E����[��6.20 �u�ّ��͋֕��v�@�V���[�̎��ɂ��̋Ȃ��P�ȓ����Ƃ���A�u�^���^���X�̌Q��vD583�ł��傤���B�u�A���v�X�̎�l�v�Ƃ����^�C�g���̋Ȃ́A�V���[�̂��̂��͂��߉��Ȃ�����܂����AD588�̓}�C�A�[�z�[�t�@�[�̎����������ȁH�I�[�X�g���A�E�A���v�X���߂����Ƃ������āA���̂悤�ȁu�R�v�e�[�}�̋Ȃ��P�Ȃ͓��ꂽ���C�����܂��B�u�G�����t�v�A�u���[�[���R�b�y�̒����ɂāv�Ƃ����Ȃ��u�A���v�X�v�e�[�}�̋Ȃ̂͂��ł��B
�@�V���[�x���g�̓`�L�Ȃǂ́A�S���ǂ��Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ނ̌�F�W�Ȃǂ��悭����܂��A�V���[�x���g����芪���T�����u�V���[�x���e�B�A�[�f�v���琶�܂ꂽ�̂�������ƌ�����K�v�͂��肻���ł��B�F�l�̉̎�t�H�[�O���́A�ǂ�ȉ̂��D��ł����̂��H�}�C�A�[�z�[�t�@�[�̑��̎��l�́A�ǂ�Ȑl�����āA�ǂ�ȉ̂Ɍ��������̂��H�}�C�A�[�z�[�t�@�[�̋Ȃ́A�P�Ȃ͓��ꂽ�����������܂��B
�@�u��l�̈��̉́v�u�M�l�̕ʂ�̉́v�u�\���ꂽ����ҁv�́A��̃t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́u��S�W�v�̍Ō�̃f�B�X�N�Ɏ��^����Ă����ȂŁA���́u��S�W�v�ɂ�菉�߂Ē����A�u�ӔN�̃V���[�x���g�͐����I�v�Ɗ������Ȃł��B�u��l�̈��̉́v�́A�V���[�x���e�B�A�[�f�̃T�������̂Ȃ��炩�ȋȒ��̗L�߉̋Ȃł����A�u���̎g���v�ɒʂ���V���[�x���g�Ȃ�ł͂̍������n�ɒB�����̂��Ǝv���Ă��܂��B�u�M�l�̕ʂ�̉́v�́A�i���̓��e�͂悭�m��܂��j�s��Ńh���}�e�B�b�N�ȋȑz���A"�~�ł̍�p�ŁA�ނ̉��y�\���ُ�ɍ��g�����̂��ȁH"�ƁA�����������A�����܂����B�����������u�X�ɂāv�Ƃ����̂Ɋ������̂ł����A���̑O�A�f�B�[�X�J�E�́u��S�W�v�ŋȖڂ��E���Ă������ɂ́A�����邱�Ƃ��ł��܂���ł������A�����Ƃ������m��܂���B
�@�u���t�̈��̍K���v�́A�G���U�x�[�g�E�V���[�}���̂k�o�̒��ŁA��ԋC�ɓ������Ȃ̈�A�u��̂قƂ�̎�ҁv�A�u�̒��̉́v�����l�ł��B
�@�u�j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��́vD886-3�́A�L���X���[���E�o�g����CD�̒��ň�Ԃ̂��C�ɓ���̋ȁB���̋Ȃ́A�o�g���ȊO�ł͒��������Ƃ�����܂���B���C�g�i�[���u���vD939���A�{���ɃV���[�x���g�炵��"������"�ŁA�����I�ɂ́u���̎g���v�ƕ��Ԗ��Ȃł��B
�@���ߐ�ԋ߂Ƃ̂��Ƃł����A�u���ɂ̃V���[�x���g�v�̑I��͑�ςȍ�ƂȂ̂ŁA�ّ��͋֕��A�V�k�S�Ȃ���A�u���������T�d�Ɂv�Ə��������Ē����܂��B
�i�Q�j���������[��6.20�u�{13�ȁ|9�� ���v40�ȁv
�@�^���Ɍ������Ă����������肪�Ƃ��������܂��B�����[���q�������Ă��������܂����B
�@�V���[�ł��u�^���^���X�̌Q��vD583�ɂ������Ǝv���܂��B�V���[�Ƃ������l�́A�\�����傫�����Ă��܂�D������Ȃ����A�V���[�x���g�Ɏ������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A�厍�l�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��A��͓���Ă����Ă��������ȂƁB����ɓ��X���́u��҃N���m�X�vD369 �i�Q�[�e�j���O���܂��B�Q�[�e�͂�������̂ŁB�u"�R���m"���Ƃ̂��ł����ǂ����܂��傤���B�u�A���v�X�̎�l�v�ł́AD588�̓V���[�ł����A�Z�ҏ������Ȃ���ł��܂�ʔ����Ȃ��B����Ȃ�A�ނ���A�}�C�A�[�z�[�t�@�[�̓�����D524b�̂ق����u�R�j�̉́v���ōD�������Ă܂��B�ł�����܂���A40�ȑO��Ƃ�������������܂����ˁB
�@���ɁA�M�N���E�̔ӔN�̉̂ɂ��Č������܂����B�u��l�̈��̉́vD909�Ɓu�M�l�̕ʂ�̉́vD910�͓����V���[�o�[�̎��ł��ˁB�O�҂͂��܂�ɒP�������ăR�N���Ȃ����A��҂͑�߂��Ď��̍D�݂Ƃ͈Ⴄ�B�c�O�Ȃ��痎�I�ł��B�V���[�o�[�͑匆��u���y�Ɋv������̂ŁA����ɑ�\�����܂��傤�B�u�\���ꂽ����ҁv�́A�����Ȃ��C�^���A��Ƃ������Ƃł͋M�d�ł����A���܂�Ƀ��j�[�N�߂��āA���ɂ̃x�X�g�ɓ����Ȃ���Ȃ��Ǝv���B�u�X�ɂāv�͂Q�����āA�����E��������̂́A�V�F���c�F�̎���1825�N�̍�iD834�̂ق��ł��傤�ˁi�������1820�N�̍�Ȃ̂Łj�B�m���ɁA���c���q�������悤��"���ɜ߂��ꂽ�V���[�x���g"�Ƃ����ʂ͌����邯�ǁA���グ��قǂ̋Ȃ���Ȃ��B���C�g�i�[���u���vD939�́A�����E�����̂��������Ƃ��肢���ȁB����͓��ꂳ���Ă��������܂��B�u�j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��́vD886-3���A�����Ă��ăC���p�N�g����B��������I�B�̏��͒N�ɂ��܂��傤���ˁB�M�N�̓L���X���[���E�o�g���Ƃ������Ⴂ�܂����A���͂�����ƈႢ�܂��B�o�g�����������ǁA�o�[�o���E�w���h���b�N�X�̂ق����\��Z���Ėʔ����B�R��o�Ă���Die Manner sind mechant! �̕\��S���Ⴄ�̂ł���B�������y���^�b�`�̃o�g������������ǁA�������̂ق����f�l�ɂ͕�����₷���B�����ŁA�����L���v�V�����������܂����B���ߕ����mechant���t�����X��Ȃ̂ŁA�t�����X��Ɋ��\�ȏ]���ɈӖ����������肵�āA�܂Ƃ߂Ă݂܂����B
�@�ЂƂ܂��A�����E������œ��ꂳ���Ă�������Ȃ́A�O�蕪�ƍ��킹��ƁA�u�^���^���X�̌Q��v�u���̂��������v�u�܂̉J�v�u���������m����̂������v�u�j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��́v�u���������A�Ђ�v�u������ׁv�u���v�u�ʂ�v�u�C�ӂɂāv��10�ȁB�p�X�����Ă�������Ȃ́A�u�A���v�X�̎�l�v�u�G�����t�v�u���[�[���R�b�y�̒����ɂāv�u��l�̈��̉́v�A�u�M�l�̕ʂ�̉́v�A�u�\���ꂽ����ҁv�ȂǁE�E�E�E�B�j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ���D886-3�@�U�C�h���@1826
�R�̐߂��A��Die Manner sind machant!�i�j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��̂�I�j�Ƃ������ʂ̌��Œ��߂�����L�߉̋ȁB��e�ɂ��������āA"���̔ނɌ����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ�"�Ǝv���Ă��������A����ς�ꂳ��̌������Ƃ��肾�����A�ƌ��R�~�J����^�b�`�̉́B"�₭��"�̕����ɂ́Amechant�Ƃ����t�����X�ꂪ�Ƃ��Ă���̂��ʔ����B�t�����X��ɐ��ʂ����]���ɂ��ƁA�u�E�E�E�₭���Ȃ��́v�͂ǂ������������Ȃ��Amechant�ɂ�"���������̂Ȃ�"�Ƃ����j���A���X�̖Ó��ł���Ƃ����B�t�����X�ł́A�q������������������Ƃ��ȂǁA�e��"���������̂Ȃ����Ƃ��Ă̓_���INe sois pas mechant�I"�ƌ����Ď��邻�����B�m���ɁA���̉̂́A�j�̏K���ɂ�����Ȃ����������߂�����Ă鏗�̋C�������̂������́B�Ȃ�A���Y���q�����ӂ����e�̋C�����ƕς��Ȃ��B�����ŁA���I�M��̒�ā\�\�u�j���Ă݂�Ȓ���Ȃ����́v�͂������ł��傤���E�E�E�B����3��mechant���A���ꂼ��Ƀj���A���X��ς��ĕ\�������o�[�o����w���h���b�N�X�̉̏��͂ɒE�X�I���h�D�E���v�[�̖���������s�A�m���f���炵���B
�@���ƁA���Ǝ��̔��f�ŁA���܂�Ƀ|�s�����[�����Ă�����Y��Ă����u�q��́vD498�A�t�F���V�e�B�E���b�g�̉̏��ł��̔������ɋC�Â����u����߂̘A���vD343�A���������������͂��u�s��vD957-11��3�Ȃ������܂����B
�@�����ŁA�V����13�Ȃ���ꂽ�̂ŁA�u�Q���̉́v�u���Ɋāv�u��҃N���m�X�v�Ȃ�9�Ȃ����O���A���v40�ȂƂ��܂����B���̐V�����u�Ȗڕ\�v��Y�t����̂ŁA�ŏI�`�F�b�N�����肢���܂��B�Ō�ɁA�u�ّ��͋֕��v�Ƃ̃A�h���@�C�X���肪�Ƃ��B���������āA�u���ߐ�A���ߐ�v�ƋM�N���}�������������ȁB�ł��A����������Ƃ��āA�����ł������炢�����傤�ǂ�����ł���B�������炸�B������ɂ��Ă��A�����E�����ɂ͉����Ȃ��Y�o�Y�o�����ė~�����Ǝv���܂��B���̂��Ƃ������V�N�B
���Ō�ɁA�����E�����ɑ��t�����V�����u�Ȗڕ\�v���f�ڂ��āA����́u�N�����m�v����߂܂��傤�B���\�������l���Ă����ȂƂ����������N���Ă��܂��B
�@�@�@�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v���X�g�����łP
1 ����a���O���[�g�q�F�� D118
2 �e�̂Ȃ��� D138
3 ��� D257
4 ���� D328
5 ����߂̘A�� D343
6 ���� D433
7 �����炢�l D489
8 �q��� D498
9 ���Ɖ��� D531
10 �Ώ�ɂ� D543
11 �K�j�����[�g D544
12 ���y�Ɋ� D547
13 �܂� D550
14 �^���^���X�̌Q�� D583
15 �t�̑z�� D686
16 �Y���C�J�T D720
17 ���̈��A�� D741
18 �~���[�Y�̎q D764
19 ���̏�ʼn̂� D774
20 �N�����͌e�� D776
21 �܂̉J D795-10
22 �[�f���̒��� D799
23 ��Ɩ� D827
24 �Ⴂ��m D828
25 �A���F�E�}���A D839
26 ���������m����̂����� D877-4
27 �t�� D882
28 �j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��� D886-3
29 ���������A�Ђ� D889
30 �V�����B�A�� D891
31 ���� D911-5
32 �t�̖� D911-11
33 ������� D911-20
34 �� D939
35 �Z���i�[�fD957-4
36 �ʂ� D957-7
37 �s�� D957-11
38 �C�ӂɂ� D957-12
39 ���̎g�� D957-14
40 ��̏�̗r���� D965
2010.08.23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևD�@�����̃����E�����4�u���v�͓݊��H
�i�P�j�����E����[��6.17 �u�����̉̋ȁv�@�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́u�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�v�́A20��̍��A���}�n���l�X��S�����Ă������ɁA�����炳��k�o25���g�̃T���v���Ղ���A�V�C���`�I�[�v�����[���e�[�v�ɘ^�����A�悭�����Ă��܂����B�A���A�u�O��̋ȏW�v�̂悤�ɁA���ׂĂ̋Ȃ����Â��߂閘�A��������ł͂���܂���B�S�Ȃ�ʂ��Ē������̂͂Q�炢�ł��傤���A���̌�A�a�l�f�{�ЂP�e�Ζ��̎��ɁA�㔼�����̂ݗA���łōw���A���݂��A�O�������͎����Ă��܂��A���̂��A�k�o�̉̎��̓��������C�i�[�m�[�g�����͎����Ă��܂��B
�@�O�����ȂŁA�u�n�K�[���̒Q���v�́A�V���[�x���g�̍ŏ��̉̋ȂƂ����Ӗ��ŋ������̂ŁA�����A�L�`���ƒ����Ă��܂���B�����̍�i�ōD���Ȃ̂́A�Q�[�e�̎��ɂ���u�r�����̒Q���̉́v�ł��B�������u���ɂ̃V���[�x���g�̉́v��I�ԂƂ���A���̋Ȃ��ŏ��̈�ȖڂɂȂ�܂��B
�@�V���[�̎��ɂ�钷��ȃo���[�h�u�����ҁv�i����A20�����炢�v����V���[�x���g�Œ��̋ȁA���������ł݂�A�}�[���[�́u��n�̉́v�Ō�́u���ʁv�ɋ߂����̂ŁA�́A�R�炢�����������ŁA���݁A��̓I�ȉ̂̋L���͂قƂ�ǂ���܂��A�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȁv�ɑI�肵�Ȃ��ɂ��Ă��A���y���Ă����K�v�͂���Ǝv���܂��B
�@�Q�[�e�̎��ɂ���u���v�́A�V���[�x���g�̍ł��L���ȋȂł����A���̎��͔ނ���\�̍��A�V�тɍs��������̖q�t�̖��Ɨ��ɗ����A���̖��̏������u��܂��Ă��܂��v�A���͌�������]�������A����ɔޏ���U���Ă��܂����A�Ƃ����̂ŁA�R�߂��琬�鎍�́A���̌o�܂����f����Ă��܂����A�V���[�x���g�̉��y�͓T�^�I�ȗL�߉̋ȂŁA���̕ω��ɑ��A���y�͑S���݊��Ȃ悤�Ȋ��������܂��B�������́u����a���O���[�g�q�F���v������ȂɎ��̕ω��ɕq���Ȃ̂ɁA�u���v�̓݊����́A�ǂ��l��������̂ł��傤���H
�@�u���ɂ̃V���[�x���g�v��I�肷��ɂ́A��L�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́u��S�W�v�ƁA�������ނ�����CD��DGG�ɘ^���Ǝ��������ď������u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv��ǂޕK�v������Ǝv���܂����A�@���Ȃ��̂ł��傤�H�@�ł́A���҂͋߁X�B
�i�Q�j���������[��6.18 �u���҂����̂��݁v
�@�u���v�͎���ǂ����ŁA���Ȃ����̉̂���Ȃ����Ƃ͊����Ă��܂������A�Q�[�e�̂��������w�i����������ł����B�[�����܂����B���w�u�V���{���ʁv�̔w�i�ɖ���J��̌l�I�ȏ�����Ƃ����Ă��邱�Ƃɋ߂������ł��ˁB�Ƃ͂����A������Ƃ����āA�V���[�x���g���݊����Ƃ���M�N�̐��͓�����Ȃ��Ǝv���܂��B�Q�[�e�̎���͒m��Ȃ������ɂ���A���̎���ǂ�ŁA�����̉��ȉ̂Ɖ��߂���قǔނ͓݊�����Ȃ��Ǝv���B"�V���v�������炱���̈���"�Ƃ����̂͌Í���������킯�ŁA�ނ͊����Ă����I�Ǝ��͎v���̂ł����B������A�̂���͗l�X�ȕ\�����o����B���ł��A�M�N���E�̃o�[�o���E�{�j�[�͎��Ƀh���}�e�B�b�N�B�l�X�Ȑl���̂��Ă��܂����A���̐l�̂��m���Ɉ�Ԗʔ����B�����ŋM�N�̋������Q�l�ɏ������u���v�̃L���v�V�������B
�@�u�f�B�[�X�J�E�̃V���[�x���g�{�v�ł����B�ɂ�����Γǂ�ł݂����Ƃ͎v�����ǁA�ނ̃L�b�`�������̏�����z������ɁA���e�I�ɖʔ����̂��Ȃ��H�@������Ƃ��A�ǂ��ł����B �@�u�����E�����̃V���[�x���g�u���v�A���Ҋ��҂��Ă��܂��B���܂�A�u���O�F�B���Ƃ���肵�Ȃ��ŁA�r�V�o�V�����Ă��Ă��������ȁB�����A�\���\���I�Ȓ��ߐ肽���������̍��ł���܂��B��� D257 �Q�[�e�@1815
�����͌����� �쒆�̂�` �N�ł��m���Ă���e���݂₷���f�p�ȃ����f�B�[�����A���̓��e�́A���N�ɂ����Ȃ��܂��Ă��܂���̂��Ƃ��`����Ă���B����͎Ⴋ���̃Q�[�e�̎��̌����w�i�ɂ���Ƃ����Ă���B��{�I�Ɍy�₩�Ŕ��������A�h���}�e�B�b�N�Ȗ��t����Ԃ̃o�[�o���E�{�j�[�i�\�v���m�j�̉̏����ʔ����B������Ƃ�肷���̊������邪�A���̉̂����炵�������̉̂ł͂Ȃ����Ƃ������ɋ����Ă����B
�����[���ɂ͏����Ȃ��������A�u�r�����̒Q���̉́v�́u���ɂ́E�E�E�v�ɂ͂����킸�I�肵�Ȃ������B�����E����D���Ȃ͕̂����邪�A����͈�ʐl���ΏہB�L���ȁA�L���b�`�[�ȋȁA�����ɉ��̂���ȂƂ����̂��I�Ȋ�̃v���C�I���e�B�Ȃ̂��B
�@�u�����ҁv�ɂ͐����r�b�N�������B�V���[�̎��̓��e�����炭�����A�Ȃ�Ƃ����Ă�24���Ƃ����Ȃ̒����ɁB�ܘ_�A�I��O�����A���݂������Ă��ꂽ�����E�����ɂ͊��ӁB
�@�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�u�V���[�x���g�̉̋Ȃ����ǂ��āv�́A���[���ɂ͂������������A���A�A�}�]���ōw�������B����A���x�����p���邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@�Ȃ��A�����E����[���ɓo�ꂵ�������炳��́A���}�n���l�X�Ζ��̂��ƁA�h�C�c�E�V�����v���b�e���E���[�x���ƌ_�����ԉ��H�ɈڐЁA���݂̓L���O�E���R�[�h�Ŋ������B�S���������[�x���̊W�ŁA���ɋ����h�C�c�n�̉��y����ɏڂ����N���V�b�N�E�̗L�\�Ȑ���}���̈�l���B
�@����ɂ��Ă��A�����E�����A�u�O��̋ȏW�v���ׂĂ��������߂�Ƃ́A���̔N�G���҂ł͂Ȃ��I�I�@
2010.08.09 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևC�`�t�F���V�e�B�E���b�g
 �@�t�F���V�e�B�E���b�g�\�\1947�N5��8���A�C�M���X�A�`�F���g�i�����܂�̃\�v���m�̎�B�����h����w�݊w����1968�N�ɂ́A����ے��̈�Ƃ��āA�t�����X�A�O���m�[�u���̉��y�@�ʼn̂̃��b�X�����Ă���B���ƌ�͏����ɃL�����A��ς݁A�n���̃O���C���h�{�[�����y�ՁA�R���F���g�K�[�f�������̌�����͂��߁A�E�B�[���A�~���m�A�p���A�j���[���[�N�A�h���X�f���A�~�����w���Ȃǐ��E��ꋉ�̃I�y���n�E�X�ɏo���B���ɂq�D�V���g���E�X�u��̋R�m�v�̃}���V�������i�����v�l�j���́A���ɂ̏\���ԂƂ����Ă������B���T�C�^���������[�����Ă���A��w���ォ�瑱���O���n���E�W�����\���i�s�A�m�j�Ƃ̃R���r�́A�Z�p�I�ɂ����y�I�ɂ����z�I�ȃR���{���[�V�����������A���̏́A�u���Ɩ�̈��̉́v�Ƒ肷��p���E�V���g�����ł̃��C�uDVD(2002�N)�Ō��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�f��u�A�}�f�E�X�v�i1983�N�j�ւ́A���̏o��������B
�@�t�F���V�e�B�E���b�g�\�\1947�N5��8���A�C�M���X�A�`�F���g�i�����܂�̃\�v���m�̎�B�����h����w�݊w����1968�N�ɂ́A����ے��̈�Ƃ��āA�t�����X�A�O���m�[�u���̉��y�@�ʼn̂̃��b�X�����Ă���B���ƌ�͏����ɃL�����A��ς݁A�n���̃O���C���h�{�[�����y�ՁA�R���F���g�K�[�f�������̌�����͂��߁A�E�B�[���A�~���m�A�p���A�j���[���[�N�A�h���X�f���A�~�����w���Ȃǐ��E��ꋉ�̃I�y���n�E�X�ɏo���B���ɂq�D�V���g���E�X�u��̋R�m�v�̃}���V�������i�����v�l�j���́A���ɂ̏\���ԂƂ����Ă������B���T�C�^���������[�����Ă���A��w���ォ�瑱���O���n���E�W�����\���i�s�A�m�j�Ƃ̃R���r�́A�Z�p�I�ɂ����y�I�ɂ����z�I�ȃR���{���[�V�����������A���̏́A�u���Ɩ�̈��̉́v�Ƒ肷��p���E�V���g�����ł̃��C�uDVD(2002�N)�Ō��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�f��u�A�}�f�E�X�v�i1983�N�j�ւ́A���̏o��������B�@�����A�t�F���V�e�B�E���b�g�̑f���炵����m�����̂��A1994�N�̃E�B�[�������̌�������u��̋R�m�v��DVD�������B�w���̓J�����X�E�N���C�o�[�A�ޏ��̃}���V�������ɁA�Ⴋ���l�I�N�^���B�A���ɂ̓A���l�E�]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�i���b�]�E�\�v���m�j�A�Ⴂ���]�t�B�[�Ƀo�[�o���E�{�j�[�i�\�v���m�j�Ƃ�������Ȃ��̕z�w�B�����18���I�̃E�B�[���A�����v�l��34�A�Ⴂ���l������B�ޏ����ނɌ��������p�����A�߁X�ޏ��̐e�ʋ̒j�ƌ������邱�ƂɂȂ��Ă���ԉłւ̓`�ߖ��ŁA���ꂪ��̋R�m���B�Ƃ��낪�A�ނ͂��̉ԉłɐS�䂩��Ă��܂��B������@�m�����v�l�́A畏����鈤�l�̔w����������l�����т��A����͐g�������Ă䂭�A�Ƃ����X�g�[���[�B���N�g�əR���������A���̈ڂ낢�ɋ�����������A�z�Ƃ��Đg�������M�w�l�̋C�i�ƈЌ��E�E�E�E�Ȃ�ăI�y���̃p���t���b�g�Ȃǂɂ͏�����Ă��邪�A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�����ɍ���Ȃ��M���̉����A�Ⴂ�c�o���ɑ����̑��肪���ꂽ��ʼnΗV�т���߂�A�Ƃ��������̘b���B������u���������A������̂Ƃ��������Ă܂�34�A�A���t�H�[��O�ł���A�܂��܂��������肶��Ȃ��́B�Ȃɂ����N�g��I�A���̈ڂ낢�əR����������ł����āH ����Ȃɐ[���Ԃ�Ȃ��ł�v�E�E�E�ȂǂƁA�����gOL�����肩��A����^���^���o�܂��肻���ȃV�`���G�[�V�����Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�A�t�F���V�e�B�E���b�g��������ƁA�u�X�~�}�Z���A���Ȃ��̂��������Ƃ���ł��v�Ƒf���Ɏv�킳�ꂿ�Ⴄ���疀�d�s�v�c�A���ꂼ�|�̗́B��3���ŏ����O�l���̂����̂悤�ɔ������O�d��������B�}���V�������́A���ނ̈���ق��̏����Ɉڂ��Ă� ���͍L���S�Ŕނ������Ă䂱���Ɛ����� �ł����̂Ƃ�������Ȃɑ������悤�Ƃ́@�`�Ɖ̂��o���̂����A�������A���낢��ȈӖ��ōő�̌�����Ȃ̂��B�����A�u�Ȃɂ��L���S��A����y�������� �悭�������v�Ƃ��u�Ⴂ���̂ق��������ɂ��܂��Ă�W�����A�j�������ق��������������v�Ƃ����悤�ȁA���鑤�����ʂɎ���������߂�ɑ���S�l�i�I���݊��Ȃ���̂��A���҂ɂ��邩�ۂ��������̕�����ڂƂȂ�̂ł���B�t�F���V�e�B�E���b�g�̏ꍇ�ɂ́A�I�N�^���B�A���������̂����R�Ǝv�킹�鏗�Ƃ��Ă̖��͂ƁA�L���S�ŎႢ��l���ݍ��ދC�����ƕ�e�͂��A���R�ɔ�����Ă���̂ł���B�܂��ɓV����i�A���㐑��A����A�j��ō��̃}���V�������Ƃ����Ă����̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�A�����̗_�ꍂ��1960�N�J�������w���̃U���c�u���N���y�Ռ����̃G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v���G��Ȃ����炾�B�V�������c�R�b�v�́A���b�g���M���Ȃ�A�ޏ��͂ނ���w�Z�̐搶�Ƃ��������B�����A1957�N�̃h�C�c�f��u���ȗ[�ȂɁv�̃��[�g�E���C���F���b�N�����鏗���t�̕��͋C�Ȃ̂ł���B
�@�`���Ɍf�����v���t�B�[������A�C�Â������Ƃ�����B1968�N�ɃO���m�[�u���ŕ����������Ƃ������Ƃ́A���̔N�̓~�G�I�����s�b�N���̒n�ɔޏ��͂������ƂɂȂ�B�ޏ����2�قǔN��̎��͂Ƃ����A�X�L�[�O���̑�w4�N���B�u�ꍂ�����S�R�̉ƂŃA���o�C�g�����Ȃ���A�W�������N���[�h�E�L���[�̃A���y���O�������肢�A�����O���m�[�u���̋�Ɍ������Đ����𑗂��Ă����̂��B�Â��悫����A�Ȃ����A���ɉ��������I�i�債�����Ƃ���Ȃ����H�j �O�����Ƃ����A�k�邱��12�N�O�A1956�N�R���e�B�i�E�_���y�b�c�H�ōs��ꂽ�~�G�ܗւŁA����A���y���O���ɋP�����̂��A�I�[�X�g���A�̃g�j�[�E�U�C���[�������i��]���Z�̋�_���͓��{�̒��J��t�j�B�ނ͂��̌�f��E���肵�A�u����͏�����v�i1959�N�j�ŁA�▋�ł��X�^�[�ɂȂ����B�ނ̉̂������̎��̂���q�b�g�B���� ��Ȃ������� �������Ƃ����肻���ȋC������� �̂Ƃ���̃����f�B�[���A�V���[�x���g�̈��u���̎g���v�̕������ƈ�u�I�[�o�[���b�v����B���ꂼ�A�V���[�x���g���ŏI�ւł悱�������̎g�������H
�@�u�A�}�f�E�X�v�́A���R�[�h��Ђŕ������̍��A�傫�ȏՌ������f�悾�����B���̒��́u�t�B�K���̌����v���ݕv�l�̉̐����ޏ��̐��������Ƃ͒m��Ȃ������B���炽�߂Ċm���߂���A�o�Ԃ͋ɋ͂��A����ł͒��ڂ��W�߂�ɂ͑���Ȃ��������낤�B
�@���āA�t�F���V�e�B�E���b�g�́u�V���[�x���g�̋ȏW�v�ł���B�Ƃɂ�����i�Ȃ̂��B����́A���y�]�_�Ƃ̂j�D�g���ɂ������������̂ŁA���̌��͑O��́u�N�����m�v�ɏ������Ƃ���ł���B������1989�N2��25���A�t�@���n�E�X�E�N���V�b�N�X����B���݂͔p�ՂŁA�J�ł͎�ɓ���Ȃ��M�d�i�ł���B���Ȃ݂ɓ�����CD�]�͂ǂ��������̂��H�u���R�[�h�|�p�v1989�N4�����̈ꕔ�����p����B
�����Ɏ��߂�ꂽ17�Ȃ̃V���[�x���g�́A��������X�^���_�[�h�Ȗ��Ȃ��낢�B�t�F���V�e�B�E���b�g�̓N�Z�̂Ȃ��܂������Ȑ��ŁA�N���X�^���ȃV���[�x���g��͂��Ă����B�����ĒW�ʂȕ\���̒��ɃV���[�x���g�̃i�C�[�u�Ȗʂ͕����яオ���ė��悤�Ƃ������̂��B�����A���̂��ƁA�V�������c�R�b�v�́u�J�[�l�M�[�E�z�[���E���T�C�^���v�����̂����A��������[�g�̏�����̉̂Ƃ́A�u�̂̊i���Ⴄ�ȁv�Ǝv�킴��Ȃ������B���[�g�Ƃ������̂ւ̎p�����܂邫���قȂ�Ƃ��������A�̂̒�����͂ݏo���ė�����̂��A���܂�ɈႢ������̂��B���̈Ӗ��Ń��b�g�̉̂́A�������̂悤�Ȑ������̒��ɂ���V���[�x���g���B�@���]�q�́A��䏊�E�����Ǖ㎁�ł���B����Ō����ƁA�搶��"�u�₩�����ǖ����Ȃ�"�Ƃ���������Ă���B������A���Ă��˂��ɓ�������"����"�G���U�x�[�g�E�V�������c�R�b�v�̐V�������������ɏo���āB�܂��A���ꂪ�A�搶�̊����Ȃ̂�����Ȃɂ��������₾���A������Ɨ҂����C������B�����A�h�C�c�E���[�g�ɂ����āA�j�̓t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�A���̓V�������c�R�b�v���ō��A�Ƃ����������������B��l�Ƃ����ꂾ���̎��͂Ǝ��т�����̂�����A���̂��Ƃɂ��ĕ���͂Ȃ��̂����A�ނ�̉A�ŁA�{���ɑf���炵�����t���s���ɕ]������p�Ղ̗J���ڂ��݂�̂́A����ɂ��̂тȂ����̂��������B���̔Ղ́A�C�M���X��IMP�Ƃ������[�x���̉����ŁA�������{�̐V�����[�J�[�ł���t�@���n�E�X���A�����̔��̃��C�Z���X���l�����Ĕ����������̂��B�t�@���n�E�X�́A���̌�ABMG JAPAN�ƍ����ABMG JAPAN�͍�N�\�j�[�~���[�W�b�N�ɋz�����ꂽ�B���̘͐̂b�ł���B�����炱�̖��Ղ͔p�Ղǂ��납����������Ђ����ł�������Ă���B���Ռ���IMP�͒ʔ̏��i��C�g�ȃN���V�b�N���o���Ă͂��邪�A�N���V�b�N��僌�[�x���ł͂Ȃ����߁A���̖��Ղ�����ՂƂ��ė��ʂ��Ă���\�����قƂ�ǂȂ����낤�B���������āA�����Ղ��A���Ղ�����͐�]�I�Ȃ̂ł���B������A�@�����̃����E�����ɁA�u���v�]����R�s�[�������グ�܂��傤���v�ƌ����Ă���̂ɁA�Ԏ����Ȃ��B�܂��A���A�ނ͑��o�E���v�č��ŖZ�����̂��낤�B�撣���āA�����č���Ă��������ȁI
�@���쒆��PB-CD�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�ɂ́A���̒�����5�Ȃ�������肾�B����CD�ɂ�38�ȑO��̎��^��\�肵�Ă���A���݁A�����E�����ƈӌ����킹�Ȃ���I�Ȓ��Ȃ̂́A�F�l�����m�̒ʂ�ł���B�I�Ȃƕ��s���ăx�X�g�̏��������킹�����Ȃ���s���Ă��āA���܂�ƒ����ɃL���v�V�����������Ă���B���̉ߒ��̒��ŁA�t�F���V�e�B�E���b�g��5�ȑI�Ƃ����킯���B������A�I��5�Ȃ́A���ꂱ����i���̐�i�Ȃ̂ł���B����ł́A�ǂ����ǂ���i�Ȃ̂��H�Ō�ɁA���̃L���v�V�������f�ڂ��āA�������߂����Ǝv���B
����a���O���[�g�q�F�� D118�@�Q�[�e 1814
�@�t�@�E�X�g�̋C���������ꂽ���Ƃ��������O���[�g�q�F���̕s���ȐS��ƁA�܂��c��v��̏���̂��Bkuss(kiss)�ł̏�̍��܂肪����I�����āA���̒���̃s�A�m�̗��ꂪ�A�S�̗����\���ȂǁA�V���[�x���g�̝R��ƌ����������Ɍ��������L�O��I��i�ŁA���̋Ȃ����������Ƃ����1814�N10��19�����A�h�C�c�E���[�g�a���̓��Ƃ����l������B�t�F���V�e�B�E���b�g�i�\�v���m�j���O���n����W�����\���i�s�A�m�j���f���炵���B�t�@�E�X�g�̂��Ƃ���ڂ��� �̂����̋C�������݁A���h�Ȃ��p�E�E�E�`�̌��ŁA�e���|�𗎂Ƃ��ĕ\�����ς�����Ƃ����A�Ō�̌��tschwer�i���ꂵ���j�ɂ�����j���A���X�ɕx�\��͓��M���́B���̊����ŋC�i�Y���\���͌����Ƃ����ق��͂Ȃ��B
����߂̘A�� D343 ���R�s 1816
�@��₷�炩�Ɍe�� ���ׂĂ̗�� �ꂵ�ݖ��키���̂� �������I��������̂� �܂̐��𐔂����ʏ����� �_��ڂ̓�����Ɍ������̂� ���ׂĂ��̐����狎�������� ���ׂĂ̗�͂₷�炩�Ɍe���`���ׂĂ̗�ɋF����������A����߂ɂ�����A���i�i�ՂƉ�O�Ƃ̌��݂̋F��j�̉́B�Ȃ�Ƃ��������������f�B�[�B�V���v���ȗL�߉̋ȂɃV���[�x���g�̏������Ƃ₳���������߂��Ă���B���̈����ׂ��̂́A�u�t�F���V�e�B�E���b�g �V���[�x���g���̂��v�ŏ��߂Ēm�����B���̑��ł́A�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�́u�V���[�x���g�̋ȑ�S�W�v�Ɋ܂܂�Ă�����̂��������m��Ȃ��B�����Ƃ�������̃��R�[�f�B���O�������Ă������̂ɂƎv���B�t�F���V�e�B�E���b�g�̒W�X�Ƃ������R�ȉ̏��ɂ́A���ꂾ���Ő��炩�Ȍh�i�����h���Ă���B
���̈��A�� D741 �����b�P���g 1822
�@�Ǝ��̈��A������������ꂽ�l��@���͂��Ȃ��̂��Ƃ� ���Ȃ��͎��ɂ��Ƃɂ���̂ł��@���̈��A���@���̐ڕ����`���������ꂽ���l�ɑ���ς��ʈ�����̂��B���̐����́A�s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂́u���z�ȁvD934�̑�3���ϑt�Ȃ̎��Ƃ��Ďg���Ă���B���G�ȐS����傫����ݍ��ނ悤�ȃt�F���V�e�B�E���b�g�̉̏����A�e�N�j�b�N����g���ăh���}�e�B�b�N�Ȗ��t��������t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�ɏ���B
���̏�ʼn̂� D774 �V���g���x���N 1823
�@���M�ɂ��Ĕ����������ƌ��肫��߂������Ȃ݂�\���`�ʐ��L���ȃs�A�m�̃}�b�`���O�������B���́A���������R�Ǝ��̗���̒��ɐl���̉A�e�𓊉e���Ă���B�ςݏd�˂��l�������R�Ƃɂ��ݏo��悤�ȃV�������c�R�b�v�̖������A�t�F���V�e�B�E���b�g�ɂ͓G��Ȃ��B���M�ɂ��ĉ��[���A���̈ڂ낢�����������邻�̉̏��́A�u��̋R�m�v�̃}���V�������̖������z�N������B
��Ɩ� D827 �}�e�[�E�X�E�t�H���E�R���[�� 1823
�@��̐Â����Ƃ��ꂪ�^���閲�̐_����A�،h�̔O�����߂ĉ̂��B�P����2�߉̋Ȃ����A��2�߂̓]���̖����Ȃɐ[���A�e��^���Ă���B�咲H���f�ɕς���ē�������2�߂́A�r���g�ɂ��ǂ�A�e����o�čēx�g�ɂ��ǂ��čŏI�s�u�܂�������Ă�����A�₳��������ƁvHolde Traume, kehret wieder!�ɘA�Ȃ�J��Ԃ����B���̌J��Ԃ����������ߍŏI�s�Ɠ��������ƂȂ��ĉ�A���Ă���B���̗���̐_�X�����͕M��ɐs�����������A2009�D10�D17�t�u�N�����m�v�Ŏw�E�����u�����ȑ�8�ԃO���[�g�v��2�y�͂� A1�|B1�ڍs����f�i�Ƃ�������̂�����B���炩�ɒW�X�Ɖ̂��V���e�B�b�q�������_���̐_�X�������A��������e�N�j�b�N�����Ɏ��R�ȃL���X���[���E�o�g�����̂Ă��������A�������A�t�F���V�e�B�E���b�g�Ɏ~�߂������B�o�����̃s�A�j�b�V���̔������͂܂�œV��̐��B�䌨������̂��Ȃ��B�Ă��˂��Ȏ��̉��߂Ǝ����݂̉̏��́A�V���[�x���g�̖{���ł���₳��������ׂȂ��`���āA���Ɋ����I�ł���B�s�A�m�̃O���n���E�W�����\�����A�I�m�ȃe���|�ݒ�Ɖ��₩�ȕ\���ōD�T�|�[�g�B�V���[�x���g����[�g�̗��z���������ɂ���B
2010.07.26 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևB�`�@�����̃����E�����3�u�ЂƂ܂� 3��̋ȏW�ȊO�ցv
�i�P�j �����E����[��6.10 �u3��̋ȏW�ȊO�̋ȁv�@�u3��̋ȏW�v�̘_���́A���炭���ɒu���܂��āA����ȊO�̉̋ȂŋC�ɂ�����̂��U���Ƌ����Ă݂܂����B
�@�n�K�[���̒Q�� D.5�A�����̌��z D.�V�A������ D.77�A�r�����̒Q���̉�D.121�A����Ɋ� D.189�A�C�̐Î� D.216�A�ŏ��̑r�� D.226�A��̂قƂ�̎�� D.300�A����߂̘A�� D.343�A�G�Ւe�� ��� D.478�A�E���t���[�̋��ނ� D.525�A�h�[�i�E��̏�� D.553�A�^���^���X�̌Q�� D.583�A�A�e���X D.585�A�A���v�X�̎�l D.588�A�݂����璾�ݍs�� D.700�A��߂��� D.719�A���̈��A�� D.741�A���l D.771�A�u���b�N�ɂ� D.853�A���������m����̂����� D.877-4�A�j���Ă݂�Ȃ₭���Ȃ��� D886-3�A���������Ђ� D889�A�A�����f D.904�A��l�̈��̉� D.909�A�M�l�̕ʂ�̉� D.910�A�\���ꂽ����� D.902-2 �A�̒��ł̉� D.917�A���t�̗��̍K�� D.933�A���i���C�g�i�[�jD.939
�@�ԐF�ɂ����Ȃ́A�������u���ɂ̃V���[�x���g�v�ɐ���Ƃ����ꂽ���Ȃł����A���Ȃ葽�߂��܂��ˁB�Ȗڂ̓t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E22���g�́u��S�W�v�ƁA���l���̏����̎��CD�̎��^�Ȃ��Q�l�ɂ��܂����B�{���͋Ȗڂ݂̂ɂ��܂��B����ȍ~�ɁA�܂��F�X���������Ǝv���܂��B
�i�Q�j ��������낦�悤
�@�������܂������A�����E�����B�O�̃��[���́u�w�~�̗��x��20�ȁw������ׁx������ł��闝�R�����������肢�����v�Ō��̂ł����A�ЂƂ܂��u���Ă������ł��ˁB��낵���B�u�~�̗��v�̐X�͑����[���������A������ň�ʋȂɓ���̂������͂Ȃ��ł��傤�B
�@����ɂ��Ă��A�m��Ȃ��Ȃ��肪����ł���B�ǂ��Ƃ��ĕ��������Ƃ��Ȃ��B�����������Ă���V���[�x���g�̋ȏW��CD�́A�j���ł́A�t�B�b�V���[=�f�B�[�X�J�E�u�V���[�x���g���̂��v�u�Q�[�e�̋ȏW�v�A�n���X�E�z�b�^�[�u�h�C�c�̋ȏW�v�A�����ł́A�V�������c�R�b�v�A�V���e�B�b�q�������_���A�G���[�E�A�������N�A�o�[�o���E�{�j�[�A�L���X���[���E�o�g���A�o�[�o���E�w���h���N�X�A�W�F�V�[�E�m�[�}��������B������A�����E����E�Ŏ苖�ɂ���̂́A�u�C�̐Î�vD216�A�u�G�Ւe�����vD478�A�u��߂��ƁvD719�A�u���l�vD771�A�u���������m����̂������vD877-4�A�u�j�݂͂�Ȃ₭���Ȃ��́vD886-3�A�u���������Ђ�vD889�A�u�̒��ł̉́vD917 ���炢�̂��́B���Ƃ�20���Ȃ��ǂ����悤�E�E�E�B
�@�O�����悤�ɁA���̃R���Z�v�g��"�|�s�����[�Ȗ��Ȃɖ����Ă͂߂�"�Ƃ������̂��B����A�����E�����́A����Ȃ킽���̎v�f�Ƃ͂��\���Ȃ��Ɏ���̐M�O�Ŕ����Ă���B�ȕւɂ́A20���Ȃ̒�����|�s�����[�Ȗ��Ȃ�I��ł��܂��Ƃ������@�����邪�A����ł́A�܊p���E���Ă��ꂽ�����E�����ɐ\�������Ȃ����A�u�N�����m�v���_�ɂ�������B������20���Ȃ��ׂĂ����Ƃɂ����B
�@�����Ȃ�Ɨ��݂́AN.H�y�������B�����A�A�����Ƃ�B�u�w�V���[�x���g���ɂ̉̋ȏW�x�I�Ȃɂ�����A�S�Ȃ��K�v�ɂȂ����̂ł����A������F=�f�B�[�X�J�E�̑�S�W�͂������ł��傤���v�E�E�E�E���ʁA22���g�́u��S�W�v��8���g�́u�����Əd���̂��߂̉̋ȏW�v������ł��邱�ƂƂȂ����B��͂�ՋS���A����ɂȂ�B
�@�l�l�Ɏ�邾������\����Ȃ��B���͂ł��A�ڂڂ����u�V���[�x���g�̋ȏW�v���W�߂悤�Ǝv�������A2�|3��CD�V���b�v�⒆�ÓX������B���ʁA�j���ł́A�y�[�^�[�E�V�����C�A�[�A�W�F���[���E�X�[�[�A�����ł̓A���l�E�]�t�B�[�E�t�H���E�I�b�^�[�A�G�f�B�b�g�E�}�e�B�X�ADG�̃I���j�o�X�A���N�̖��̎�̑I�W�A�Ȃǂ��w�������B����ŁA�̋ȏW��CD��23���A19�A�[�e�B�X�g�ɂȂ����B����łȂ�Ƃ�����͑������B�ł́A���������E����E�Ȃ�Ԏ����S�Ɍ����Ă䂱���B>
�@�u���̈��A���vD741�́A�ӔN�̖��ȁu�s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂̌��z��D934�v�̑�3���ϑt�Ȃ̎��ɂ��g���Ă��āA�������̂�����ȁB�u���������m����̂������vD877-4�́A�Q�[�e�̎��ŁA�`���C�R�t�X�L�[�ɂ����삪����B�u���������Ђ�vD889�́A�V�F�[�N�X�s�A�̎��Ń|�s�������e�B����B���C�g�i�[���u���vD939�́A���ւ̊��ӂ����₩�ɉ̂��đu�₩�E�E�E�ȏ�4�Ȃ͑I�Ȍ���B�M���V���_�b���̂ŕ��X�����u�A�e���X�v�A�I�y���̃A���A�݂����ȁu�\���ꂽ����ҁv�A�����ĒP���ȁu�̒��ł̉́v�A20����������u�����ҁv�A�Ȃ�10���Ȃ͊O���A�u�^���^���X�̌Q��v�Ȃ�4�Ȃ����������������邱�Ƃɂ���B
�@���s���āA�̂��]�_��K.H���ɂ��A�킪�I�Ȃւ̂��ӌ������ł������A�ނ̓����E�����ƈႢ�A�킽���̃R���Z�v�g�𗝉�������ł̈ӌ�������Ă����B�H���u�I�Ȃ͂قڂ�����Ȃ����B�����A���Ȍ������Ă݂ẮH�v�Ƃ��āA�u�i�C�`���Q�[���ɊāvD497�Ɓu�����炢�l�̌��Ɋ�́vD870�𐄑E���Ă��ꂽ�B�����͌�������Ƃ��āA�v�X�ɉ���Ƃ������ƂɂȂ�A���̂����̒��Łu�������Ƃ��A�t�F���V�e�B�E���b�g�̃V���[�x���g�̋ȏW�����������܂��傤���v�ƌ����B�t�F���V�e�B�E���b�g�͂킽�����ł��D���ȏ����̎�̂ЂƂ�B1994�N�E�B�[�������̌���ł́u��̋R�m�v�̌����v�l���́A�����C�i�ƕ��i�͂���i�ŁA�����̗_�ꍂ���V�������c�R�b�v�̏���䂭�B�ޏ��Ɂu�V���[�x���g�̋ȏW�v�Ȃ�A���o��������Ȃ�Ė��ɂ��v��Ȃ������B�u����A�����V�N�v�Ƃ��肢���āA6��15���A�����̐V�h�̏Ă������ł�������B����������CD�́u�A���F�E�}���A�^�t�F���V�e�B�E���b�g �V���[�x���g���̂��v�Ƃ����^�C�g����1988�N�^���̍����Ղ������B���̉����K.H�����������W�ŁA�P���]���ɏ��L���Ă��i�Ă���āj���̂��B�V���[�x���g�𒆐S�ɉ��y�k�`�ɉԂ��炫�A�ƂɋA��A�����C��������Ԏ����̒��ŁA����CD�����B�����A�����Ők���������B�\�z�ǂ���A����A����ȏ�̑f���炵���I�I
�@����ȋ�������`���āA�����A��T�ԂԂ�Ƀ����E�����Ƀ��[����łB
�i�R�j ���������[��6.16
�@���ɔ~�J����B�ԋI�s�ɂ���ςȋG�߂ɂȂ�܂����ˁi�ނ͎����̃u���O�Ɂu�����E�����̉ԋI�s�v�Ƒ肷��Ԃ߂���G�b�Z�C��A�ڒ��Ȃ̂��j�B�����C�ł����B�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�A�ƒf�ƕΌ��Œ��X�Ƃ���Ă��܂��B
�@�M�N�̈�ʋȃA�h���@�C�X���Q�l�ɂ����Ă��炢�A���̒�����́A�u���̈��A���v�u���v�i���C�g�i�[�j�u���������m����̂̂݁v�u���������Ђ���v��I�肳���Ă��炢�܂��B���̑��ł́A�u�^���^���X�̌Q��v�u��l�̈��̉́v�u�M�l�̕ʂ�̉́v�u���t�̗��̍K���v���������Ƃ����Ƃ���B
�@�Ƃ���ŁA�O��̋ȏW�_���H�ł����A�u�܂̉J�v�͋M�N�̂ق����������ƁA���o�I�ɂ���ȋC�ɂȂ��Ă��܂����B���낢��h�C�c�E���}���h�̎���ǂނƁi�Ƃ����Ă��V���[�x���g�̉̎������łł����j�A�Ȃ�Ƃ������A�s�����ł��\�m�}�}�ɂ��Ă����ق����ʔ������Ă������A���l�߂ʼn����Ă��܂��Ƃ������Ƃ��A�i�X�������Ă��܂��ĂˁB�܂��A���Ƃ͖{�������������̂��ƁA�͂��߂��番�����Ă�����肾�����̂ł����ˁB�v����Ɏ��̔n���ȂƂ���́A�������߂���Ƃ���Ȃ̂ł��B���ۉJ���~�邩�ۂ�����ɂ������Ƃ����A�u�{���̉J���~���Ă����Ȃ��̂Ɂw����A�J����x�Ƃ����̂͂��������v�Ƃ��鎄�̊��o��"���I"����Ȃ������̂ł���B����Ȏ����ɋC�Â��ƁA�M�N�̌|�p�ɑ��銴�o�����X�̂��̂��Ƃ������Ƃ��������Ă���B���₠�A�債������ł��I
�@�ȖڑI���́A�x�X�g�̏��Ă͂߂�̂�����ǁA������ʔ����Ȃ�ł��傤�B����Ȓ��A�M�N�������m�̕]�_��K.H������u�t�F���V�e�B�E���b�g �V���[�x���g���̂��v�Ƃ����t�@���n�E�X��CD�����������܂����B����͐����I�������ʂ��Ē��������ǁA�u��Ɩ��v�u���y�Ɋv�u���̈��A���v�u���̏�ʼn̂��v������͐�i���̐�i���Ɗ����܂����B����CD�A�����E�����͂������ł��傤���H
2010.07.15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևA�`�@�����̃����E�����2�u�܂̉J�v
�i�P�j �����E����[���U�D�U�u�܂̉J�v�@�u���������ԏ����̖��v�̑�P�Ȃ͒P���ȗL�߉̋ȁB�����A�u���ԏ����v���Ƃ��́A���̋Ȃ��O���đ�2�Ȗڂ��璮���n�߂邱�Ƃ������̂ł���܂��B
�@����̃��[���ŋ������Ȃł́A��10�Ȃ��u�܂̉J�v���A���݂��݂Ƃ��������Ȃł��B���߂Ĕޏ��Ɠ�l����Ńf�C�g���������̂��܂�A�v�킸���܂����������āA�ޏ��́u�J���� ����Ȃ� �ƂɋA��v�Ƃ����A�܂��f�p�ȗL�߉̋Ȃł����A�Ō�̔ޏ����u�J���� ����Ȃ� �ƂɋA��v�̕����̂݁A���������f�B�[��ς����̂����Ɍ��ʓI�A�����Č�t�A�ŏ��͉̂̕������������������ł����A�����ɒZ���ɓ]������A���������̋Ȃ̒������A�Â��ɖ������肽�K���̐Ⓒ�̒��ɂ��ꖕ�̕s�����߂���A���̍K���Ⓒ���́A���̑�11�ȁu�l�̂��̂��I�v�Ŋ�т̔����ɂȂ�̂ł����A�ꖕ�̕s���́A��14�ȁu��l�v�̏o���Ŕ߂��������ɂȂ�̂ł��B����Ȏ����ɕx�ށu�܂̉J�v��S20�Ȓ��̑O���̍Ō�ɔz�u�������ƁA�����āA���삪��������㔼�ŏ��̑�11�Ȃ��A�������̊�]���X�g���[�g�ɕ\��������P�ȁu�����炢�v�Ǝ�������邱�ƁA����ȍ\���̖������X�̂��̂ł��B
�@�������A�����E�����A�u�܂̉J�v�𐄑E���A�u���ԏ����v�̍\���̖��ɂ܂Řb���y��Ō����ł���B�����ŁA���߂āu�܂̉J�v���Ă݂�B�t���b�c�E�����_�[���q�i�e�m�[���j���t�[�x���g�E�M�[�[���i�s�A�m�j�ɂ�鉉�t�ł���B�u�܂̉J�v�̃I���W�i���̒����̓C�����ŁA�e�m�[���̃����_�[���q�͂���ɕ���Ă���B���Ȃ݂ɁA�t�B�b�V���[���f�B�[�X�J�E�̓o���g���Ȃ̂ňꉹ�Ⴂ�g�����Ɉڒ����ĉ̂��Ă���B�������̈ꉹ�Ȃ猴�Ȃǂ���ɉ̂���������Ȃ����Ƒf�l�̎��Ȃ͍l����̂����A���炭����"�ꉹ��"�͂ƂĂ��Ȃ��傫���̂��낤�B�V���[�x���g�́A�j���p�̉̋Ȃ����Ƃ��́A���y���Ԃ̉̎胈�n���E�~�q���G���E�t�H�[�O���i1768�|1840�j��z�肵�ď��������낤����A�ނ͍��̃e�m�[������̉̂��肾�����̂��낤�A���̖{�ɂ̓n�C�E�o���g���Ƃ���B���Ȃ݂ɁA�u�~�̗��v���A���̐���ςƂ��āA�o���g���p�̊y�ȂƎv���Ă����̂����A���݁A�I���W�i���̒����ʼn̂��Ă���̂̓e�m�[���̎肾�����B���̂�����́A�u�~�̗��v�̂Ƃ���ŃW�b�N���Ƃ�肽���Ǝv���B
�@�t���b�c�E�����_�[���q�i1930�|1966�j�̐��́A�ƂĂ��Ȃ��Â��������B�������A�z�Ƃ���������������B�������A�i���Ƃ����Ă������B�����邯�Ǖi������A�܂�ŁA������p�B�̃X�C�[�c�Ƃ��������͋C���B�v���N�����A�����ނ̉̂����߂ĕ������̂�30�N�ȏ�O�̂��ƁB�u���l������ǂ����v�ƃ^�C�g�����ꂽ�A�i���O�ՂŁA�����Ă��ꂽ�̂͑�背�R�[�h�X�R�^�j�a�J�X�̓X��T�DK�������B�X���Őj�𗎂Ƃ����u�Ԃ́A���̃^�C�g���Ȃ�����Ă����Ƃ��̏Ռ��͖����ɖY����Ȃ��B�Ȃ�Ƃ��������A�Ȃ�Ƃ����Â��A�Ȃ�Ƃ����i�̂悳�I�I ���̏�Ŕ������߂����̃A���o���ɂ́A���̂ق��ɁA�u�N�͂킪���E�v�u��̂悤�ɐÂ��Ɂv�u�G�X�g�����[�^�v�u�O���i�_�v�ȂǁA�|�s�����[�Ȗ��Ȃ����ځA�Ԋ�������Ȃ���"�����a�݂��ł���"�ł������B���݂��̒��̐��ȂȂ�CD�Ŏ�ɓ��邪�A�̂̐l�Ԃ́A���̂Ƃ��̂܂܂̌`���~�����̂��B�����Ղ���A�ʂP�ȖڂɁu���l�E�E�E�v�����铖���̂܂܂̌`���E�E�E�ł��A����͊���ʖ��Ƃ������̂��낤�B����ȃ����_�[���q�����A1966�N9��17���ɁA�ɂ܂������̂ɂ��S���Ȃ��Ă��܂����B36�̒a������ڂ̑O�ɂ��āB������A�����ނ̑��݂�m�����Ƃ��ɂ͊��ɁA�ނ͂��̐��̐l�ł͂Ȃ������̂ł���B���̔N��7���ɘ^�����ꂽ�u���������ԏ����̖��v���A�ނ̈��ƂȂ����B����́A�����_�[���q�̎��������y�Ȃ̓����ƍō��x�ɍ��v�����f���炵�������ł���B���̑��̎O��̋ȁA�u�~�̗��v���u�����̉́v���A�{���e�m�[���̉���ŏ����ꂽ���̂����珮�X�A�ނ̉̂Œ����Ă݂��������B���Ɂu�~�̗��v�̂��̍r���Ƃ����S���i���ނɂ���Ăǂ��\�������̂��H �ł��A�����A���ꂱ������ʖ��Ȃ̂��B
�@�u�܂̉J�v�������́A�����E�����̌����u�w�J���� ����Ȃ�E�E�E�x�̕����̂ݏ��������f�B�[��ς���̂����Ɍ��ʓI�v�Ƃ��������Ɉ������������B7�߂���Ȃ邱�̋Ȃ̍ŏI�߂��Ⴄ�����f�B�[�ɂȂ��Ă���͎̂������B�����������A�����E��������悤��"�u�J����A����Ȃ�v�̕����̂݃������ς���Ă���"�킯�ł͂Ȃ��B�߂̓��œ]�����Ă���̂��B�ׂ������Ƃ������悤�����A�u�N�����m�v���_����䂭�ƌ��߂����Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ł���B�����ŁA���͎��Ȃ�ԐM�������B
�i�Q�j���������[���U�D�U�u�Ȃ��Ȃ���������A�����E�E�E�v
�@�M�N�̃K�C�h��ǂ݂Ȃ���A�u�܂̉J�v���܂������A�W�X�Ƃ��ăV�b�g���Ƃ��������ׂ��Ȃł��ˁB�m���ɁA��Ƃ���s�A�m�̌�t�͔����B���̕s���Șa����"��14�Ȉȍ~���Î����Ă���"�Ƃ����M�N�̐����ɂ��[���ł��B�������A�V���[�x���g�̐����ł��ˁB�����A�M�N�̉���̒���
�@�@�@�@�\�\�u�J���� ����Ȃ�v�̕����̂݁A���������f�B�[��ς��镔�������Ɍ��ʓI�\�\
�Ƃ���܂����A����̓`�g�Ⴄ�Ǝv���܂��E�E�E���͂���Ƃ����Ȃ�܂��B
�@16���߂���܂Ƃ߂Ƃ��ĕ\���ƁAAB�|AB�|AB�|C�@�Ƃ����`�ƂȂ�AAB���ꊇ��ɂ���3�߂̗L�߉̋Ȃ�16���߂̃R�[�_���t�����ȍ\���Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
�@������A�u�J���� ����Ȃ�v�̕����̂݃����f�B�[��ς���E�E�E�Ƃ����͓̂������Ă��Ȃ��B"32���߂̂P�R�[���X��3��J��Ԃ����L�߉̋Ȃ�A�����Ǝ��Ĕ�Ȃ�▭��16���߂̃R�[�_�������E�E�E�Ƃ����\���������ł���"�ƌ����ׂ��ł��傤�B�m���ɁA����C���������ł��B
�@�Ƃ���ŁA������^�₪�N���Ă��܂����B
�@�@�@�@�\�\�v�킸���܂����������āA�ޏ��́u�J���� ����Ȃ� �ƂɋA��v�\�\
���̂Ƃ���ł����A�O�i�K�Łu�����ɂ͔g���������v�Ƃ��邩��A���ۂɉJ���~�肾�����Ƃ��l�����܂��H�@�i�j���j�����ɔg���������i�悤�Ɍ������j�̂́A�܂̂����E�E�E�Ƃ����̂͂��肤�邯��ǁA��������̗܂��J�ƌ��܂����āu�J���� ����Ȃ�v�Ƃ����̂́A�ǂ����Ă����_���������˂�̂ł���B���̉��߂́A�u�܂��o�����A���ۉJ���~��o�����v�ł��B�܂ƉJ�͘A�����Ă���A�ƍl����ƁA���̏�ʁA�����I�Ȃ̂ł����ˁB�M�N�̂��ӌ������Ă��������B
�i�R�j�����E����[���U�D�W R�F�u�Ȃ��Ȃ���������A�����E�E�E�v
�@�M�Z�́u�����v���̇@�ɂ��ẮA�����̌��t���炸�AC�̖`������m���ɒZ���ɓ]�����Ă��܂��ˁA�������A�u���悤�Ȃ�A���A���ƂɋA���v�̕����͂܂������ɂȂ��Ă���B
�@���������Ƃ�����A���̕ω��ɕq���ȃV���[�x���g�Ȃ�ł͂̉��y���`�͂��Ǝv���܂��B
�@�u�����v���̇A�́A�M�Z�̐��̂Ƃ��肩���m��Ȃ����A���R���ۂƂ��Ắu�J�v�͍~��Ȃ������̂����m��Ȃ��A�����̈ӌ��́A�ˑR�A��҂ł��B
�@���̍����́A�@�Ȃ̌��肪�uTränenregen�v�A����u�܂̉J�v�ł��鎖�B�~�����[�̎��ɂ́A����Ǝ��������ɂ͍l���ɂ����֒����ꂽ�\�������ɂ����邱�ƁA�u�~�̗��v�̑�14�ȁu���������v�A�̎��̓��e�́A�u���������̓��ɂ�����A���������Ȃ�B�V�l�ɂȂ莀���߂��Ȃ����悤���Ɗ�ԁv�Ƃ������̂ł����A�ǂ����������ꂵ���̎��̂悤�Ɏv���܂��B���̎��Ɓu�܂̉J�v�̌������ꂵ����i�`�ʂ́i���܂��]���܂��j���H�ًȂ̂悤�Ȋ��������Ă��܂��B
�@�Y��Ă��܂����B�u���������v�ɑ����u���炷�v�����Ȓ��̖��ȁA���̂�����̋Ȃ́A�F�A�����I�ł��ˁB
�i�S�j���������[���U�D�W�u���̂Ƃ͂������Ȃ��I�v
�@�u���������v�́A�����������ꂵ���b����Ȃ��Ǝv���܂��B�����Ă����̂��h���đ������ɂ����Ǝv���Ă����l�����A���ɍ~�肩���������ɁA�u�����ɂȂ����B���Ƃ����̂��B�������˂�B�������I�v�Ɗ�Ԙb�ł���ˁB�{�l�����ɂ�����]�������Ă���̂�����A�S���I�ɂ́A���ɘ_���I�ȃX�g�[���[���Ǝv���̂ł����E�E�E�B������A"��������"�Ƃ����̂̓`�g�I�O��ł͂Ȃ��ł��傤���B������A�����E�����́A"���̎��������Ɂu�܂̉J�v�Ŏ��ۉJ�͍~��Ȃ�����"�Ƃ���_�l�͐��������Ȃ��Ǝv�����������ł��傤�H �Ƃ͂����A������ɂ��Ă��A�����l�ŁA���܂Ő[���ǂ��ƂȂǂȂ������̎����@�艺���邱�Ƃ��ł��āA���ӂ��Ă��܂��B
�@�u�����v���̇@�ɂ��Ăł����A�u�J���� ����Ȃ�v�̂Ƃ���Œ����ɓ]������Ȃ�Ă��Ƃ́A���͍ŏ�����C�Â��Ă��܂�����B�M�N���A"�w�J���� �E�E�E�x�̕����̂݃�����ς���"�Ƃ�������A�ς��̂̓\�R����Ȃ��āA�b�����S�̂����Č������܂ŁB�v�����"�����̂�"�Ɉ����������������Ȃ̂ł��B�ׂ����Ă��݂܂���B���������͐��i�Ȃ���ŁA���ق��Ă��������ȁB����ɂ��Ă��A�����l�ŁA�V���[�x���g�̐��r�ɋC�Â����Ă��ꂽ���ƂɁA���ӂ��Ă��܂��B
�@�ł́A�����ŁA���݂́u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�̑I��ߒ��ɂ��Ē��ԕE�E�E
�@�M�N�A�h���@�C�X�́u�w���ԏ����x�������ĂȂ��v�ɂ��ẮA���́u�܂̉J�v�����邱�Ƃɂ��܂��B�����ŁA������Ǝ���B��19�ȁu��҂Ə���v���匆��Ƃ��������́H ���́A�ǂ������̎僁���A�V���[�x���g�ɂ��Ă͍�דI�Ȃ��̂������āA���܂�D���ɂȂ�Ȃ��̂ł��B
�@�u�~�̗��v�́A���s�Ăǂ���A�u�����v�Ɓu�t�̖��v�ł��������Ǝv���܂����A�C�ɂȂ�̂͋M�N���ȏW����̌���ƌ����u������ׁv�ł��B���̑匆��Ƃ����R���������������肢�����B�ł́A���X�A��낵�����肢�������܂��B
2010.07.07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�և@�`�@�����̃����E�����P�u�O��̋ȏW�v
�i�P�j �����E����[���U�D�T�@�O��f�ڂ��������烊���E����Ẵ��[���\�\�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȁv���X�g�ɂ��āA�M�N�̂��ӌ����������������\�\�ɕԂ��Ă����A6��5���t�����E�����̃��[�����Љ�܂��B
�M�Z�̃��X�g�ɂ͂��������̈٘_������܂��B�Ȃɂ���V���[�x���g�̉̋Ȃ́A�S����600�]������܂��̂ŁA���������1�^20�ɍi��̂́A������������������Ǝv���܂��B����Ђ�⒆���݂䂫�̋Ȃ�1�^20�ɍi��̂Ɠ����ŁA���Ȃ薳�d�ȍ�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B����͂���Ƃ��āA�u�O��̋ȏW�v����A��̓I�Ɏw�E�����Ă��������܂��B�i�Q�j�����E����[���U�D�T�ւ̍l�@�ƕԐM
�i�P�j�O��̋ȏW�̓��A�u���������ԏ����̖��vD795�̋Ȃ������Ă��Ȃ�
�����̍l����u���ԏ����v�̖��ȁ���Q�ȁu�ǂ��ցH�v�A��T�ȁu�d�����I���āv�A��U�ȁu�m�肽���́v�A��V�ȁu�ő��v�A��X�ȁu���ԉ��̉ԁv�A��10�ȁu�܂̉J�v�A��18�ȁu���ڂ߂�ԁv�A��19�ȁu��҂Ə���v�A���̒�����P�ȑI�ԂƂ���A���[��A����B�����Ƃ��Ă͑�19�Ȃ��匆�삾�ƍl���܂����A��ʓI�ɂ͑�X�Ȃ́u���ԉ��̉ԁv���ȁH
�i�Q�j�u�~�̗��vD911�́u���X�g�v�ȊO�̖���
��P�ȁu���₷�݁v�����Z�̉��y�̋��ȏ��ɍڂ��Ă��āA�̏��e�X�g�ʼn̂������Ƃ�����B
��U�ȁu���ӂ��܁v���́A�uNHK�̂ǎ����v�ł悭�̂�ꂽ�B
��13�ȁu�X�֔n�ԁv���u�����v�u�t�̖��v�ƕ��ԗL���ȁB
��20�ȁu������ׁv�����炭�A�ȏW���̐���̌���A����́u���ɂ̃x�X�g�ȁv�ɐ�����ꂽ���B
�i�R�j�u�����̉́vD957�̖���
��Q�ȁu���m�̗\���v�����́u���m�v�Ƃ́A�V���[�x���g���g�̎����H
��T�ȁu�킪�h�v��������́u�̂ǎ����v�ł悭�̂�ꂽ�i�����́A�ȏW���ł͖}�삾�Ǝv���Ă��܂��j
��V�ȁu�ʂ�v���V���[�x���g�ŔӔN�̑S�����R�Ŗ��邢���A�l���̓��B�_�̍��݂��������悤�ȑ匆��B
�n�C�l�̎��ɂ��̋Ȃ���Ȃ͓��ꂽ���ł��ˁA
��W�ȁu�A�g���X�v�������̓ƒf�ł́A���H���t�́u�v�����e�E�X�v�ɑ傫�ȉe����^�����̂ł͂Ȃ����H�V���[�x���g�́u�v�����e�E�X�v�́i������ƒ����Ă��܂��j�A�܂����I�\�o�͂ɉ����Ē��r���[�Ȃ悤�ȋC�����܂��B
��12�ȁu�C�ӂɂāv���n���Ȑ����ł����A�r������C�ӂ̕`�ʂƁA���l�B�̐�]���̑Δ䂪�����ɕ\�o���ꂽ���삾�Ǝv���܂��B
�u�O��̋ȏW�v�ȊO�͋߁X���[�����܂��B�i�Q�[�e�ƂȂ��ő����̎��ɕt�Ȃ����V���[�����ꂽ�����E�E�E�j
�M�Z���Z���N�g���ꂽ�ȖڂŁA����Ȃ��^���o����Ȃ́B�u����a���O���[�g�q�F���v�u�����v�u�܂��v�u�t�̑z���v�u�Y���C�J�T�v�u�N�����͌e���v�u�~���[�Y�̎q�v�u�[�f���̒��Łv�u���̏�ʼn̂��v�ł��傤���B�u���̏�ʼn̂��v�́A�{���ɑf�G�ȋȂŁA����D946-2�ɑ��ʂ���Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�@�������@�����̃����E�����A���Ɏ����[���ԐM�����ꂽ�B�V���[�x���g�̋Ȃɑ���[�����w���ɂ��݂łĂ���B�ނ���́A���̐́A�u�h�C�c����[�g���ׂ��v�ƌ����A�Ȃ�ƃt�[�S�[�E���H���t�̊y���ƃZ���N�gCD-R���������������Ƃ�����B���_��ɂƂ��Ă��邪�A���������Ƃ͈�x���Ȃ��B�Ȃ��A�����A���E��������"�M�Z"�ƌ����Ă���Ă���̂́A�ނ����a21�N�A�킽�������a20�N���܂�ƁA�͂��Ȃ��玄���N�ゾ����ł���B
�@���āA�V���[�x���g�����A�ނ̂悤�ȃ��[�g�D���ň�ƌ����������j�ɂƂ��āA���̂悤�ȁA����ƈ�T�ԂقǑO�ɃN���V�b�N���j�{��ǂ����őI�悤�ȃh�f�l�̃��X�g�͌����炯�ŁA�����������Ƃ��������邾�낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�����Ȃ�u���d���v�ƌ���ꂿ��������A�K�N���I �ނ̈٘_��ǂ�ŁA�܂��������̂́A���Ƃ̗��r�_�̈Ⴂ�ł���B���̂ق��́A�uCHOPIN SUPREME�v�I�ȁA�|�������[�Ȗ��ȁE�����W����낤�Ƃ������́B�}�d���Ă̕��ł́A���̂����肪���傤�ǂ����Ƃ��낾�낤����B����A�ނ́A�V���[�x���g�̐^�̖��Ȃ�^���ɃZ���N�g���悤�Ƃ���A�m���x�ɂ͊W�Ȃ��B���̒i�K�ł�����̈Ӑ}����������Ɛ����������āA���ɍ��킹���A�h���@�C�X�����炤������邪�A�����͊����Ă��̂܂܂ɂ��Ă������B���̕����A�ނ̎����Ă�����̂���葽�������o���邵�A���ɂ��Ȃ邵�A���̃M���b�v���������Ėʔ����Ǝv������B
�ł́A�����E����[���U�D�T�����Ă������@
�@�u���������ԏ����̖��v����Ȃ������Ă��Ȃ��B�����ׂ��B�ō�����͑�19�ȁu��҂Ə���v�B��ʓI�ɂ͑�9�ȁu���ԉ��̉ԁv�B���̑��ł́A��2�ȁu�ǂ��ցH�v�A��T�ȁu�d�����I���āv�A��U�ȁu�m�肽���́v�A��V�ȁu�ő��v�A��10�ȁu�܂̉J�v�A��18�ȁu���ڂ߂�ԁv
�A�u�~�̗��v�́u�X�֔n�ԁv�u������ׁv���Ȃ��������ׂ�
�B�u�����̉́v���A�����V���^�[�v�ł́u�ʂ�v���~�����B�n�C�l����Ȃ͓����ׂ��B��8�ȁu�A�g���X�v�͂ǂ����B���X�g�́u�v�����e�E�X�v�͓��X���̋Ȃ����A���r���[�Ȃ̂ŊO���ׂ��B��12�ȁu�C�ӂɂāv������B
�@�����ŁA���u3��̋ȏW�v����A�����E�����̐��E�Ȃ������Ă݂��B���ɋ������̂́u���������ԏ����̖��v��10���u�܂̉J�v�Ɓu�����̉́v��12���u�C�ӂɂāv�������B���̚n�D�͂������|�I�Ƀo���[�h�n�ɌX���B���Ƃ��A�����݂䂫�Ȃ�A�D���ȋȂ́u�̕P�v�A�u�z�[���ɂāv�A�u���Ȃ����C�����Ă��邤���Ɂv�A�u���ɍ~��J�v�A�u���z�̏M�v�ȂǃX���[�Ȃ��̂������B�����E�����Ƃ��́A������Ђ̂m�D�x������ԂɁA�悭�����݂䂫�_���킵�����̂��B�ނ̃u���O�u�����E�����̉������l���v�ɂ��ƁA���ŋ߁A���É���ŁA�����O�l�Ɉ͂܂�āA�����݂䂫���J���I�P�����悤���B�������̂ق������݂ʼn����I
�@�u�O��̋ȏW�v�ȊO�Ŏ^�����Ă��ꂽ�̂́u����a���O���[�g�q�F���v�u�����v�ȂNj͂�9�Ȃ����A�u�v�����e�E�X�v��NG�ƂȂ��Ȃ��茵�����B�����ɂ���u���̏�ʼn̂��v����Ȃ��閼�ȂƂ��ċ����Ă���D946-2�Ƃ́A�u3�̃s�A�m��D946�̑�2�v�̂��ƁB����́A�V���[�x���g���̔N�̌���ŁA�ނ̐S�̒�ɐ��ޖ��Ɛl�ɑ���D���������������Ƃт���̋Ȃ��B���͂���������E����狳��������̂��B
�@���āA�b�����X�����ɂ��ꂽ���A���̃��[���ɑ��鎄�̕ԐM���ڂ��āA����́u�N�����m�v����悤�Ǝv���B����̓����E����[����Q�M����X�^�[�g�������B
���������[���U�D�U
�m���ɎO��̋ȏW�̂ЂƂu���������ԏ����̖��v���A�Ȃɂ������Ă��Ȃ��̂͂܂����ł��ˁB�C�ɓ������̂́u�܂̉J�v�B�Â��Ŕ����������f�B�[�B���������̍D���ł��ˁB�u�����̉́v�ł́u�ʂ�v�͓���܂��傤�B�M�N�������ق�"�匆��"�Ƃ́A�����܂��v���܂��E�E�E�B�n�C�l�ł́A�ǂ����Ă��u�A�g���X�v�͍D���ɂȂ�Ȃ��Ȃ��B����Ȃ��ɂ����̂́u�C�ӂɂāv�ł��B�I�`��"���̊��܂킵�������ޏ��̗܂ɓł𒍂�����"���{���ɋ��낵���B����͗��l�����̐�]�Ȃ�Đ��Ղ�������Ȃ��A�����̂ł��B���Ɓu�s��v�̊��������_�j�Y�����̂Ă��������ǁA�ǂ��ł����B����́A�u�~�̗��v�܂ʼn��܂���B������́A�܂��A���炽�߂Ă�肽���Ǝv���܂��B
2010.06.24 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ց`�v�����[�O
�i�P�j�u�N���V�b�N���y�j��n�v�@��N�A�C�V���݂ق���̃s�A�m�E���T�C�^���̂���`���������Ƃ��A���̃v���O�����ɃV���[�x���g�u4�̑�����D899�v�����������Ƃ���A�V���[�x���g�ɋ����������A�u�N�����m�v�ł͂����V���[�x���g��e�[�}����N�߂������Ă���B���܂܂ł��܂�A������ȉƂƂ����t�҂ɋÂ����o�����Ȃ��������ɂƂ��āA����͎��ɒ��������ۂ������B�Ȃ��A�ނƔނ̗F�l���������莆����L�A�ނɊւ��錤������ǂ݁A���y�Ƃ��̐l���̊ւ���_�Ԍ�����l���Ȃǂɐڂ��Ă��邤���ɁA�V���[�x���g�̗��ɂȂ��Ă����̂��B ���Ԉ�ʂɁA�V���[�x���g�̃L���b�`�E�t���[�Y�́u�̋ȉ��v�B�S��i��7�����̋ȂƂ������̗ʂ��A�ʍ�i�V�Ƃ����邻�̎����A�܂��ɂ��̖��ɑ����������̂�����B���͎��̓h�C�c�E���[�g(�̋�)�Ȃ���̂����ŁA���܂܂ŃV���[�x���g�̃��[�g�́A�̋ȏW�u�~�̗��v��u�����v�u�A���F�E�}���A�v�Ȃǂ̒��L���Ȃ��炢�����}�g���ɒ��������Ƃ͂Ȃ��B���t��������Ȃ����Ƃ��ő�̃l�b�N�Ȃ̂����A���ꂾ���ł͂Ȃ��āA�n���łǂ��炩�Ƃ����ΈÂ���ۂ��A����߂Ȃ��������R���Ǝv���B�������A��N���S�̗F�ƂȂ����V���[�x���g��"�̋ȉ�"�Ȃ̂ł���B�̋Ȃ̃����f�B�[���Ďg�p���đ����̊�y�Ȃ������Ă�����B�ނ̍�Ȃ̎����̋ȂȂ̂�����A�̗̂����Ȃ����ăV���[�x���g�͌��Ȃ��͂����B�Ȃ�Ƃ��ނ̉̋Ȃɓ���݂����B�ł��A�ǂ�����āH�@����Ȑ܁A�Έ�G�搶���A�u�q�ɂ̒������Ă�����A����Ȃ��̂��o�Ă�����B�v�邩���v�Ɓu�N���V�b�N���y�j��n�v�Ȃ�V���[�Y�����������B���M�҂͊C�O�̒����ȉ��y�w�҂�]�_�ƁB�ʐ^���ӂ�Ɏg��ꂽ�A�S11���A��ɂ�������Əd�����N���V�b�N���y�j�ł���B�^����ɔ`�����u�V���[�x���g�̃��[�g�v�Ƃ������ڂ́A�̋ȁE�̋ȏW����ȔN�㏇�ɏ���������Ă��āA�w�p�I�Ƃ��������A���Ȗژ^�Ƃ��Ă̈Ӗ�����������Ɋ����Ă��܂����B������A�f�ڂ���Ă���̋Ȃ��ЂƂ܂��S�������Ă�낤�Ǝv���������̂ł���B�K����芵���A�����͂��Ƃ���t��������B
�i�Q�j����J�n�I�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v
�@����݂̂Ȃ��W�������ɁA�����������ĕ�������͂ǂ�������悢���H�ŋ߂̗���̒��Ŏv�����������̂́A�ƒf�ƕΌ��ɂ��uCHOPIN SUPREME�v�B����́A5��10���u�N�����m�v�ɏ������Ƃ���A�m�l�̏�������́u�V���p���̃I�X�X���E�s�A�j�X�g�́H�v�Ƃ������₪���[�ō�����v���C���F�[�gCD�R���s���[�V�����B���ꂼ�V���p���Ƃ������ɂ̖��Ȃ�I�Ȃ��A�����̎��őI�ō��̉��t�Ă͂߂ĂP����CD���쐬����Ƃ������̂��B�I�Ȃ����t�����l�̈ӌ��͈ꉞ��������ǁA�ŏI����͎����������B������Ō��"�ƒf�ƕΌ��ɂ��"�ƂȂ�\�\���͑听���BCD�̐\�����݂��E�����܂����i�������i�Ƃ��Ẵv���C���F�[�g�g�p�ł��j�B
�@����ɕ���āA"�V���[�x���g�̋Ȃ̋��ɂ̃R���s���[�V������A���o��"���쐬���悤�Ƃ����킯�ł���B���{�u�N���V�b�N���y�j��n�v�ɂ́A3��̋ȏW��58�ȁA���̑��̉̋Ȃ�60�Ȃقnjf�ڂ���Ă���B�Ȃɂ͊e�X�Z���L���v�V�������t���Ă���B�Ⴆ�\�\�u����a���O���[�g�w���vD118�́A�����̋����͈��|�I�Ȃ��̂ŁA17�̏��N�̍�Ƃ��Ă͋����ׂ����̂�����\�\�ނ̍ł����炩�ȍ�i�́u�N�����͌e���vD776�ƍł��P���������̂̂ЂƂu���̏�ʼn̂��vD774�\�\�V���[�x���g�̂��ׂẲ̋Ȃ̒��ōł��Â��Ȕ����������u��Ɩ��vD827�\�\�ȂǂȂǁA���͂���ꌾ��������ڂł���B���[�V�A������W�b�N���ǂ݂Ȃ���A��120�Ȃ��đI�Ȃ��I
�@���āA���̑I�Ȃ����A�V���p���̂Ƃ���166�Ȃ���18�Ȃ������B�����600�Ȉȏォ��Ȃ̂�2���g�ɂ��悤�B�P��4���Ƃ��āA2���g�Ȃ�ق�40�ȁB�ł́A120�Ȃ���40�Ȃ����h�ɑI�Ȃɓ���E�E�E�����őM�����I�h�C�c����[�g�f�l�̎��ЂƂ�ł������A�N���ɑ��k���Ȃ����낤����Ȃ����B���l�̈ӌ����Ō�͎����Ō��肷��B�悵�A���ꂪ�����B�Ƃ���ŁA����ȗF�B���邩����B�����������܂����B��l�́u�N�����m�v�ł��Љ���Ă����������@�����̃����E�����B�ނ͍��Z���ォ��h�C�c����[�g���܂����Ă����Ƃ����̋Ȓʂ��B������l�́A����Ђ̌�y�ʼn��y��w�y�����m�g���B�ނ͏��LCD���D��1��������ՋS�B�Ō�́A���l���s�A�j�X�g�Ŏ��g���h�C�c����[�g���̂��]�_�Ƃj�s���B���O���ɂ͂����������[����łB���̒�����A�����E�����ւ�6��2���̃��[�����Љ�Ă����܂��B
�@�Έ�G�搶����A�̍�����{���Ƃ����āu�N���V�b�N���y�j��n�v�Ȃ鍋�ؖ{�V���[�Y�������������B�V���[�x���g��^����ɓǂ�A�̋Ȃ��n���I�ɏ�����Ă���B�����ŁA�uCHOPIN SUPREME�v�Ɉ��������u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v������Ă݂悤�Ǝv���������B�H���A���ɂ̑I�ȂƋ��ɂ̉��t�ɂ��V���[�x���g�̋Ȃ̃R���s���[�V�������B2���g���l���Ă���̂ŁA�Ȑ���40�ȂقǁB�h�C�c����[�g�̌��Ђł���M�N�̂��ӌ���q�����Ȃ���I�Ȃ������Ǝv���܂��B�Ƃ肠�����A�����e��肵���Ȗڕ\��\�t���܂��B�u�N���V�b�N���y�j��n�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�ȂŁA���̎莝��CD�ɂ�����̂�I��A36�ȂقǂɂȂ�܂����B�Ȑ��I�ɂ͂܂��]�T������܂��B���݂̂Ȃ����ӌ����A�����V�N�B�͂Ă��āA���ꂩ��ǂ̂悤�ɓW�J����̂ł��傤���H�����E�����Ƃ̂����𒆐S�Ɂu�V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ցv���������Ă䂱���Ǝv���܂��B�Ō�ɁA���[���ɓ\�t�����Ȗڕ\���f�ڂ��܂��B����A���̕\�����ɘb�͓W�J���Ă䂫�܂��B
�u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v���X�g
1 �Q���̉� D23�@F�D���{���b�c 1812
2 ����a���O���[�g�w�� D118�@�Q�[�e�@1814
3 �e�̂Ȃ��� D138�@�Q�[�e�@1815
4 ��� D257�@�Q�[�e�@1815
5 ���Ɋ� D296�@�Q�[�e�@1815
6 ���� D328�@�Q�[�e�@1815
7 ��҃N���m�X D369�@�Q�[�e�@1816
8 ���� D433�@�w���e�B�[�@1816
9 �����炢�l D493�@�����[�x�b�N 1816
10 ���Ɖ��� D531�@�N���E�f�B�E�X 1817
11 �Ώ�ɂ� D543�@�Q�[�e�@1817
12 �܂� D550�@�V���[�o���g 1817
13 �K�j�����[�g D544�@�Q�[�e�@1817
14 ���y�Ɋ� D547�@�t�����c�E�t�H���E�V���[�o�[�@1817
15 �v�����e�E�X D674�@�Q�[�e�@1819
16 �t�̑z�� D686�@���[�g���B�q�E�E�[�����g 1820
17 �l�Ԃ̌��E D716�@�Q�[�e�@1821
18 �Ђ߂��� D719�@�Q�[�e�@1821
19 �Y���C�J�T D720�@���B�����[�}�[�@1821
20 �~���[�Y�̎q D764�@�Q�[�e�@1822
21 ���̏�ʼn̂� D774�@�V���g���x���N�@1823
22 �N�����킪�e D776�@�����b�P���g�@1823
23 �[�f���̒��� D799�@���b�y�@1824/25
24 �ǓƂȒj D800�@���b�y�@1824/25
25 ��Ɩ� D827�@�}�e�[�E�X�E�t�H���E�R���[���@1823
26 �Ⴂ��m D828 �N���C�K�[�E�f�E���P���b�^�@1825
27 �A���F�E�}���A D839�@�X�R�b�g�^�V���g���N�@1825
28 �v�̉� D881�@�V�����q�^�@1826
29 �t�� D882�@�V�����c�F�@1826
30 �V�����B�A�� D891 �V�F�[�N�X�s�A�^�o�E�G�����t�F���g�@1826
31 ���� D911-5�@�~�����[�@1827
32 �t�̖� D911-11 �~�����[�@1827
33 ��̏�� D943�@�����V���^�[�v�@1828
34 �Z���i�[�f D957-4�@�����V���^�[�u�@1828
35 ��̏�̗r���� D965�@�~�����[�^�t�H���E�V�F�W�@1828
36 ���̎g�� D957-14�@�U�C�h���@1828
2010.06.07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��19�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�A
�i�Q�j�V���[�x���g�̏ꍇ�@�V���[�x���g�́A���̋��|�ɜɂ��Ȃ�����A�L���P�S�[���̂悤�ɕ��̊k�ɕ������邱�ƂȂ��A��ŏ��ėF�l�����Ƃ̎��Ԃ��ɂ����B�y�������ꂸ�ǂ�Ȃɕn�R���Ă��A�L���P�S�[���̂悤�ɐ_�ɐ����̕ۏ�𐿂����Ƃ������A���������A�g������Ĉ�S�ɉ��y�������������B�L���P�S�[���̌����u���ɂ�����a�v�͏@�����u���U���vD689�ŃV���[�x���g�ƂȂ����Ă���B
�@�����u���U���v�̓t���O�����g
�@�u���U���v��1820�N�̍�i�B���n�l��������11�́u���U���̎��ƕ����v�����y���������̂ŁA�K�͂⌀���A�L���X�g�o��̗L���ȂǂɈႢ�͂��邯��ǁAJ�DS�D�o�b�n�u�}�^�C���ȁv�Ɠ����X�^�C���̉��y�ł���B�����ȕW��Ɂu�O���̏@�����v�Ƃ���悤�ɁA�V���[�x���g�͑S�O����z�肵�ċȍ��Ɏ�肩�����B�������A���ʂ͑�2���r���ŏI����Ă���B�V���[�x���g�ɂ悭���関�����Afragment�̂܂܁E�E�E�B
�@��1���́A��l�̖��}���^�ƃ}���A�Ƃ̑Θb��ʂ��āA���ɐ������U���̐S�����`�����B����ȃ��U���̐S�̓����ł��悭����Ă���A���A�̉̎��̈ꕔ���Љ��B
���āA���̞��L�̖؉A�ɉ�������Ă���Ƃ��A���Ƃ����ڂɌ����Ȃ����|���A�̒���k�����������̂������B�@�d���a�ɜ��A���ւ̋��|�ɂ��̂̂����U�����A�L���X�g�̎g�҂̓`���ɂ���ĐS�����₩�ɂȂ�A���ɂ͈��炩�ȋC�����Ŏ����}����l�q���悭������B���y�́A�S�̂ɁA���₩�ɐi�ނ��A���ւ̋��|���̂������Ȃǂ́A���Ȃ�h���}�e�B�b�N�ȋȑz�ɕς��B
�������A���A�S�͈��炬�ɖ����Ă���B�i�����M�������ɖ����Ă���B�ʂ�̐ڕ��̂Ƃ����A����قLj��炩�Ȃ��̂��Ƃ́A�v���Ă��݂Ȃ������B���͏j�����悤�A�߂Â��Ă��鎀�̎g�҂��B
���͎���ł䂭�B�^���Èł̓��������������ł��Ă���B��C�G�X��A�������������������B
�@��2���B�������A���U���̖����𐴂炩�ɉ̂��A�u�ނ́A�_�̌䋖�ɕ�������v�Ɗm�M�������ė͋������ԁB�����āA�}���^�̃��`�^�e�B�[�{�������B�ޏ��́A���U���̎��̂������挊�̑O�ŁA�u�Z����A���͎���ł��Ȃ��ɂ��Ă䂫�����v�ƌ������⋩����B�Ȃ͓��˂ɓr��A�V���[�x���g�������ŋȍ����~�߂����Ƃ��B
�@�����ɂ��ƁA���̂��ƁA�}���^�ƃ}���A�̎o�����C�G�X�ɁA�u���Ȃ��������ɂ��Ă����������Ȃ�A�Z�͎��Ȃ��ɂ��̂Ɂv�ƌ����ƁA�����댃�����C�G�X���A�u���U����A�o�Ă��Ȃ����v�Ƌ���ŁA���U����������̂ł���B�V���[�x���g�͍ł��̐S�ȁu���U�������v�̃V�[�����������ɏI��������ƂɂȂ�B
�@�����̓V���[�x���g�̐ꔄ�����ŁA�ł��L���Ȃ̂́u������ ��7�� ���Z�� D759�w�������x�v���낤�B�����A���̋Ȃ͎c���ꂽ��̊y�͂����Ŋ����i���B���̂��ƂɁA�Ⴆ�X�P���c�H�̑�3�y�́i�`������20���߂܂ł̑������c����Ă���j�`�v���X�g�̏I�y�͂ȂǂƑ����Ă��A�ʂɒ��������Ƃ͎v��Ȃ��B�J�D�ƒ^���B���Y���Λ���������̊y�͂́A�Ȃ܂��̔��������ז����鉽�����v��Ȃ��Ǝv������ł���B�����̌����Ȃɂ�,���̂ق��ɁA�h�C�b�`�����u�V���[�x���g�N��ʍ�i�\��ژ^�v�i1951�N���s�j�ŁAD�ԍ���^��"�����ȑ�7��"�Ƃ����u�z���� D729�v������B����́A�c����Ă���s�A�m�E�X�P�b�`����A�t�F���b�N�X�E���C���K���g�i�[�ƃu���C�A���E�j���[�{�[���h�����X�I�[�P�X�g���[�V�������{���āACD��������Ă���B�A���A���́u������ ��7�� �z���� D729�v�́A���̌㊮����i�Ƃ͌��ꂸ�A"��7��"�Ƃ��������Ȕԍ����O���ꂽ���߁A�u������������D759�v�Ɓu�O���[�gD944�v���J��オ���āA�e�X��7�ԂƑ�8�ԂƂȂ����o�܂�����B�����Ȃł͂��̑��ɂ��AD615�A708a�A936a�Ȃǂ������ł���B���y�l�d�t�Ȃł́A15�Ȓ�3�Ȃ��A�s�A�m�E�\�i�^�ł�23�Ȓ�8�Ȃ��������ł���A�����̐����͂�͂葽���Ƃ����ׂ����낤�B�u���U���v�̕����̏�ʂɊւ��ẮA�������炩�Ȃ茀�I�ȃV�[�����z������邾���ɁA�����i���Ă݂��������Ǝv���B
�@�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���́u�V���[�x���g ���y�I�ё��v�̒��ŁA�u�w���U���x�͎���i�Ƃ��Ă͌����Č���ł͂Ȃ��v�ƌ����Ȃ���A�ʂ̂Ƃ���ł́u���j�I�Ɍ���ƁA�I�y�����特�y���ւ̔��W�Ƃ����Ӗ��ɂ����ẮA�����V���[�x���g�̃t���O�����g�͉��y�I�Ɂw�^���z�C�U�[�x�Ɓw���[�G���O�����x���͂邩�ɗ��킵�Ă����v�Əq�ׂĂ���B����ł͂Ȃ��ƌ����Ȃ���A���[�O�i�[�̌���I�y���𗽉킵�Ă���ƌ����B�ꌩ���������_�l�̂悤�����A�ނ́A�u���U���v�ɂ��������`�^�e�B�[�{�ƃA���A�̍��a���A���[�O�i�[�̓��i���������ɂȂ���Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���̂ł���B�Ȃ�A�u���U���v�́u�����O�v�̐�B�Ƃ�������̂ł͂Ȃ����B
�u���ɂ�����a�v�̌�������
�@�L���P�S�[�����u���ɂ�����a�v�Ƃ������������p�����u���U���v���A�@�����Ƃ��ď�����2�N��A�Ȃ�ƃV���[�x���g�́u���ɂ�����a�v�Ɋ������Ă��܂��B�~�łł���B���ꂩ�炳���2�N��A��a�̎��o�ǏłĂ�������̔ߒɂȎ莆���Љ��B����܂ł����x�����p���Ă���1824�N3��31���A�F�l�N�[�y���E�B�U�[�ɂ��Ă��莆�̑O�������ł���B
�ꌾ�Ō����ƁA�l�́A���������̐��̒��ōł��S�߂Ȑl�Ԃ��A�Ɗ����Ă���̂��B���N��������x�Ɖ��������Ȃ����A���̂��Ƃɐ�]���邠�܂�A������ǂ����悤�Ƃ��邩���ɁA�܂��܂��������Ă����l�Ԃ̂��Ƃ��l���Ă݂Ă���B����A�ł��P��������]�����ɋA���Ă��܂��A���ƗF��̍K�����A����������ɂ̃^�l�ɂ����Ȃ炸�A�i���߂ĐS���ە�����j���ɑ��銴������������낤�Ƃ��Ă���l�Ԃ̂��Ƃ��B����݂͂��߂ŕs�K�Ȑl�Ԃ��Ƃ͎v��Ȃ����ˁH�\�\�u���̂₷�炬�͋������B���̐S�͏d���B���͂�����x�ƁA������x�ƌ��o�����Ƃ͂Ȃ����낤�v�A�l�͍��A���ꂱ�����������̂��������炢���B�Ȃ��Ȃ�A����A���ɏA�����тɁA�l�͂�����x�Ɩڂ��o�߂Ȃ����Ƃ��肢�A�����ڂ��o�߂邽�тɁA����̍��݂�����������邩�炾�B�@�����̌��샊�[�g�u����a���O���[�g�w���vD118�i�Q�[�e���j�����p���āA��Y��Ԃ�V���[�x���g�̐S���͂������肾�����낤���B����ȏ��ł̉��y���A�v��������ߒɂȂ��̂ł����Ă��Ȃ�̕s�v�c���Ȃ��B�m���ɁA�V���[�x���g�̉��y�ɂ͂����������ʂ�����B�������A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�ނ̉��y�́A�ނ�������ɖ����Ă���B�m���ɁA�ߒɂƕ����Ƃ����������銴��́A�V���[�x���g�̉��y�̒��ŋ������Ă���B����́A�����I�ɁA�Ȃ��ƂɁA������x�����E�����Ō����荇���B���₩�ɗ����ȑz���}�ɈÈłɕ�܂ꂽ��A�ߒɂɖ������C���̒��Ƀp�b�ƈ�̌������������肷��B���Ɖe���ό����݂ɏo�v����̂ł���B����ȃX�������V���[�x���g�̖��͂̈������ǁA�{���͂�͂�A�D�����Ɖ��₩���ł͂Ȃ����낤���B�ނ̉��y���Ă����̐S�͈Ԃ߂�ꕽ����B���̔閧�������ׂ��ނ̕��͂��c���Ă���B����́A��̎莆�ɐ旧��1824�N3��27���̓��L�ł���B
���l�̋ꂵ�݂��A�܂����l�̂�낱�т��킩����̂͂�������Ȃ��I��������Ƃ��ɕ���ł���Ǝv���Ă��Ă��A����͂�����������ŕ���ł���ɂ����Ȃ��B�����A�����m����̂̋ꂵ�݁I �ڂ��̑n�����͉��y�ւ̗����Ƃڂ��̋ꂵ�݂��琶�܂ꂽ���̂Ȃ̂��B�ꂵ�݂������琶�܂ꂽ���̂́A���̐�����낱���邱�ƂȂǂȂ��Ǝv�����B�@�u�����͋ꂵ�݂̒����特�y������Ă���B����͎������B����ǂ��A�ꂵ�݂������特�y�ݏo������͂��Ȃ��B����Ȃ��̂͐��̒��̐l�X�������Ă�낱���Ȃ��B�ꂵ�݂����ł͂Ȃ��A���y�ւ̗������特�y�����v�ƁA�V���[�x���g�͌����B������A�l�X�Ɉ��炬��^���邱�Ƃ��ł���̂��B������A�V���[�x���g�̂������y�ւ̗����Ƃ͂Ȃ낤�H���̓����́A�ނ̉̋��u���y�ɊvD547�̉̎����̂��̂ɂ���A�Ǝ��͍l����B���͔ނ̗F�l�t�����c�E�t�H���E�V���[�o�[�i1796�|1882�j�ł���B
���S�₳�������y��A���̐��̂����܂������킪��������̐��m��ʊD�F�̎��ԂɁA���O�͎��̐S�����������ɔR�������点�A���悢���E�ɗU���Ă��ꂽ�̂������I�@�V���[�x���g�̉̋Ȃ��A�ނ����������ɗ����������ď��������A�Ƃ������Ƃ������ɗ����ł��邾�낤�B����������A���ւ̋����Ȃ����ĉ̂͏����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B������ނ̉̋Ȃ̉̎��͔ނ̋C�����Ɠ����B�܂��Ă�u���y�Ɋv�͗F�l�̎��ł���B���ꂪ�ނ̋C�������̂��̂ƌ����Ă����̌�肪���낤���B�u���y�v�Ƃ������̂��A�ǂ�ȂɈÂ����������������ݍ���ł����Ƃ����M�O�ƁA�����������y�ɑ��銴�ӂ̋C�������A�ނ͎����Ă����̂ł���B������A�������g���ǂ�Ȃɐh���ꂵ���Ƃ��A���l�ɂ͈��炩�ȉ��y��͂����������̂��\�\�����A�V���[�x���g�́A���l�ɂ₳�������邱�Ƃ̈Ӗ��������ɋ����Ă����B���́A����ȃV���[�x���g����D�������A���ӂ��،h����B�����āA�������A�C���������ł��A�������肽���Ɗ肤�B���y�͏����Ȃ��̂�����B
�������O�̒G�Ղ��痬��o��f�����A�Â���炩�Șa�����������Ȃ���A���̐��Ȃ�ʐ��E�����̓���ɂЂ炢���\�\�S�D�������y��A�킽���͂��̂��Ƃ����܂��Ɋ��ӂ���I
2010.05.30 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��18�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�@
�@�Z�[�����E�L���P�S�[���i1813�|1855�j�̏��u���ɂ�����a�v�̃^�C�g���́A���n�l��������11�́\4����̂��Ă���B�����ɂ̓L���X�g�����������U���̎��ƕ����̂��Ƃ�������Ă���A�L���X�g���A�u���U�������ɂ������v�Ƃ̕�����Ƃ��ɔ��������t���u���̕a�͎��ɂ����炸�v�������B�L���P�S�[���͂��̌��t���u���ɂ�����a�v�Ƌt���I�ɗp���āA���Ȃ̎v�z�̒��_��z���������̃^�C�g���ɂ����B�V���[�x���g�͓�����ނ��g���āA1820�N�ɁA�@�����u���U���v���������B�ނ͂���2�N��ɁA�u���ɂ�����a�v�Ɋ������Ă��܂��B�~�łł���B�u���U���v�Ɓu���ɂ�����a�v����āA�V�ˍ�ȉƂƁA���c������`�N�w�҂���{�̐��Ō��ꂽ���ƂɂȂ�B�i�P�j�L���P�S�[���̏ꍇ
�@�u���ɂ�����a�v�i�����܊w�|���ɁA���c�[�O�Y��j�̒��ŁA�L���P�S�[���́A���U���̎��ƕ����A�����āA����Ɋւ��C�G�X�E�L���X�g�̂��Ƃ��ǂ̂悤�ɑ����Ă���̂��낤���H ����ǂ�����菜�����ăL���X�g�͋��A�u���U����A�o�ŗ�����v�ƁB����Ǝ����4�����o���ĕ����������U�����A�h���ĕ����o�����B�������A�{���́A"������������"�ł���C�G�X�E�L���X�g���A���̌��t�����ɂ����A��ɕ��݊�邾���ł悩�����̂ł͂Ȃ����H�ƃL���P�S�[���͌����B�\�\���t�����ɂ����̂́A�L���X�g�̗͂��q�����ɕ�����₷���������߂ł���A���̈Ӗ��ł́A���U���̕a���u���ɂ����炸�v�ƋK�肵�A�u���U���͖����Ă��܂����v�Ɗ����Č������Ƃɂ��A��q��������u�������̂Ȃ�A������ł��傤�v�Ƃ̌��������o���āA�u�ނ͎��̂��v�ƌ��̂����̂��߂������B������A�L���X�g�����̏�ɂ���Ƃ������ƂŁA���̕a�͎��ɂ�����a�ł͂Ȃ��B�ہA�L���X�g�����݂���Ƃ������Ƃ����ŁA�����̂��̂ł������ł͂Ȃ��̂ł���B�����i���n�l��������11�́|26�j�ł��A�L���X�g�́u���������ł��薽�Ȃ̂��B����M������̂́A����ł�������v�Ƌ��Ă���B�l�ԓI�ȈӖ��ł́A���͈�̂��̂̍Ō�ł��邪�A�L���X�g���I�ȈӖ��ł́A���͉i���Ȃ鐶���̓����ɂ�����ЂƂ̏����ȏo�����ɉ߂��Ȃ��\�\�L���P�S�[���͂����l����B���̒m�荇���̃J�g���b�N���k�����������Ă���B�u���Ƃ́A�������ăC�G�X�E�L���X�g���_�ƑΖʂł��邱�ƁB������A���͌����ĕ|�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���j�������ׂ����̂Ȃ̂ł��v�ƁB
�@������A�L���P�S�[���́u���ɂ�����a�v���ǂ��K�肵�Ă���̂��낤���H�ނ́u���ɂ�����a�v���A�ꌾ����]�ł���Ƃ���B���_�̎��ł���B�^���ȃL���X�g�҂Ƃ��Đl���ɑ������L���P�S�[���̌��_�́A���R�A�a�͓��̓I�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B�l�Ԃ�"���_"���Ɣނ͌�����̂ł���B
�@�u���ɂ�����a�v�Ƃ́u��]�v�B�u��]�v�ɂ�3��"�ꍇ"������ƃL���P�S�[���͋K�肷��B
���]�R�̏ꍇ���@�l�Ԃ͐��_�ł���\�\���̂��Ɣނ͂���������B�u�������A���_�Ƃ͉��ł��邩�H���_�Ƃ͎��Ȃł���B�������A���ȂƂ͉��ł��邩�H���ȂƂ́A�ЂƂ̊W���ꎩ�g�ɊW����W�ł���B���邢�́A���̊W�ɂ����āA���̊W�����ꎩ�g�ɊW����Ƃ������ƁA���̂��Ƃł���v�B����͂�A��������Ƃ������S�Ɏ��̗�������B�����玄�͏���ɉ��߂����Ⴄ�\�\���ȂƂ͎��g�̓��Ȃ鐸�_�B�����Ƃ������̂̏B����Ƃ����Ƃ����܂ސ��_�̑����̂ł���B�Ƃ͂����A���������Ō`���������̂ł͂Ȃ��B���Ȃ͊O�I�W�ɂ����ĕω����A�������A��荞�ވӎv�͂��̎��_�ł̎��Ȃł���A��荞��ɕω������̂��܂����Ȃł���B�������Ď��Ȃ͕ω����`������Ă䂭�\�\�ƁB�ł́A���Ȃ̌`���x�����f����̂͒N���H ���������l���ŁA�������̂�����Č�����B�Ȃ�A�_���B�E�E�E�����Ȃ�ƁA��L���X�g�҂ł��鎄�͂�������Ȃ��B����Ȃ�������u���Đ�ɐi�ށB�ł́A��]3�̏ꍇ���A��]3��"���"�ɏ��������Ă��܂����B
�@ ��]���āA���Ȃ������Ă��邱�Ƃ����o���Ă��Ȃ��ꍇ
�A ��]���āA���Ȏ��g�ł��낤�Ɨ~���Ȃ��ꍇ
�B ��]���āA���Ȏ��g�ł��낤�Ɨ~����ꍇ
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����̂܂܁j
���]�R�̎�ށ��@���̂ق���������₷���Ȃ����Ǝv�����ǂ����낤�B�����āA����3�̐�]��"���"�́A��l�̐����Ɍ����Ă�ƁA�R�̐����ߒ��ŋN�����]��"�i�K"�ɒu����������̂ł͂Ȃ����B
�@ ���Ȃ����o���Ă��Ȃ���]
�A ���Ȃ�ے肵�����Ȃ��]
�B ���Ȃ��т��������A�ł��Ȃ����Ƃւ̐�]
���]�R�̒i�K���@�ȏオ�A�u���ɂ�����a�v���ҁᎀ�ɂ�����a�Ƃ͐�]�̂��Ƃł����̎��I���߂ł��邪�A�L���P�S�[���́A���҂Ł��]�͍߂ł����ƋK�肷��B�����āA���̏��̑��҂Ƃ����u���{�I�Ȏ��Áv���������B�u���ɂ�����a�v�ʼn�͂�����]���a���A���҂Ŏ��Â���B���ÂƂ͑����A�L���X�g���I�C�����܍��ł���ƌ��_����̂ł���B���̈�A�̗�����l�@����ƁA�����ɂ́\�\�u���ɂ�����a�v�Ƃ͐�]�ł���B��]�͍߂ł���B�߂̓L���X�g���I�C�����܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�\�Ƃ����O�i�_�@�I���@�_��������B�����āA�_�ւ̈،h�ƕ��]���B
�@ ���Ȃ����o���ĂȂ��i�K�ł̐�]�B���I�\�w�I�����������ɁA�P�ɑ��҂Ǝ����Ƃ�Δ䂵�Đ�]����B����͂܂��A���Ȃ̒��ɂ���Ȃ�̉��l�ς��`������Ă��Ȃ��i�K�B���̓��{�̐����͂��̃��x�����B���̂܂ܐ������~�܂��Ă��܂��ΐl���͂܂�Ȃ��B
�A ���Ȋm���r��ł̐�]�B����́A���Ȃ�����Ɍ`��������鎞���ɋN�����]�B�قƂ�ǂ̐l�Ԃ́A�Ⴂ�����ɂ��̎����𖡂키�͂����B
�B ���Ȋm����̐�]�B���Ȃ��m�����ꂽ�Ƃ������o�������Ă���i�K�ŋN�����]�ł���B�ǂ��ɂ��������Ǝv���Ă����̗͂ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���̂܂܂ł������Ă䂭���Ƃ͂ł��邯��ǁA����Ɏ��������߂�ӗ~�����Ă邩�ǂ��������ƂȂ�B
�@���[�O�i�[�̉̌��u�^���z�C�U�[�v�ŁA��l���̃^���z�C�U�[���A���\�̒n���F�[�k�X�x���N�ɓ���Z��F�~�O���̐����𑗂�Ƃ����߂�Ƃ������߁A���[�}�ւ̏�����s���_�ɋ����𐿂��̂����A����Ȃ��A�L���P�S�[���̌���"�L���X�g���I�C��"�Ȃ̂��낤�B�i���Ȃ݂ɁA���[�O�i�[�̃P�[�X�́A"�����̋]���̏�ɐ��藧�~��"�Ƃ������ʂ����邯��ǁA����͂܂��ʂ̋@��Ɂj�B���̂����肪�A�ǂ�����L���X�g�҂̎��ɂ͕�����ɂ����Ƃ���Ȃ̂��B�Ƃ������A���F�[�k�X�x���N�ւ̓���Z�肪�߂ł��邩�ǂ����͕ʂɂ��āA�_�ɋ����𐿂��߂͎͂��ꂿ�Ⴄ�̂��E�E�E�E�Ƃ������ƁB�����A�L���X�g�҂ɂ����ẮA�Ƃ����߂�_�ɍ������č߂��܂����Ƃ́A���ՓI������I�s�ׂȂ̂ł���B
�@�L���P�S�[���N�w�̍���ɂ�"�̏d��"�Ƃ�����{�T�O������B���ꂪ�A������`�̐��Ƃ����R���ł�����̂����A�L���P�S�[���̂��̐��_�́A�ʂ̂Ƃ���ŁA����Ȍ`�Ō����B�\�\�u�킽�������ܐ_�Ɋ��҂��邱�Ƃ́A����҂Ƃ��Ă̂킽���̊��������炩�̕��@�ŏ����Ă�������Ƃ������Ƃł���B���邢�́A�܂��ʂ̕��@�Ŏ��̕�炵�������āA�킽����҂ł��葱�������Ă�������Ƃ������Ƃł���v�\�\�����ǂ�ŁA���́A����Ȃ��Ƃ܂Ő_�ɂ��肢����̂��I������ƁA�Â������ł͂Ȃ��̂��ƁA�s�v�c�ȋC�����ɂȂ����B���Ȃ݂ɁA�V���[�x���g�ɁA����ȊÂ��̓T���T���Ȃ��B�ǂ�Ȃɕn�R���Ă��A����ȃ����Ȍ��t���A�ނ͔����͂��Ȃ������B�L���P�S�[���́A����ɂ܂��A�u�m���ɁA�킽���͐_�̎͂���M���Ă���B�������A���́A�]���Ɠ����悤�ɁA���������[���Ӗ��ő��̐l�X�ƌ��������Ԃǂ��납�A���܂ł����̕����̒ɂ܂����Ƃ肱�ɂȂ��Ă���Ƃ����߂��A�ꐶ�U�A�ɂȂ��Ă��Ȃ���Ȃ�ʂ��Ƃ�m���Ă���v�ƌ����Ď��̊k�ɕ�������B���̓_�Ɋւ��Ă��A�V���[�x���g�͑S�R�Ⴄ�B�ނ̂ق������A�����Ǝ��Ȃ̊k�ɕ������肽�������͂��Ȃ̂ɁA�����Ă܂��A�S�̒��ł́A����A��]�A���|�A���Oetc ����Ƃ����镉�̊���Q�����Ă����͂��Ȃ̂ɁA�ނ́A��ŏ��ĐS�ŋ����āA��������̗F�l�����Ɉ͂܂�Đl�����߂������̂��B
�@���_�̎��Ɠ��̂̎��A���_�̋�ɂƓ��̂̋ꂵ�݁A�V���[�x���g�ƃL���P�S�[���\�\�ǂ��炪�ǂ��ƁA���ȂɌ�����͂����Ȃ��B�����ꌾ"�V���[�x���g�͐���" ���ꂾ���͌�����B�m�M�������āB
�@����́A�u���ɂ�����a�v�Ɓu���U���v���e�[�}�ɁA�V���[�x���g�̐����l�Ƃ��̉��y�N�w�ɓ��ݍ���ł݂����B
2010.05.10 (��) �V���p�����a200�N �ƒf�ƕΌ��ɂ�鋆�ɂ̃R���s���[�V����
�@����A�f���Ђɋ߂�m�荇���̏����s�DH���烁�[���������������B�u���R�K�Y����̃V���p���S166�ȃR���T�[�g�ɍs���Ă��܂����B���߂ăV���p���͂����Ȃ��Ǝv���܂����v�����Ƃ������e�ł���B���R����Ƃ����A�ߔN�A���@���E�N���C�o�[���E�R���N�[���̗D���Ғ҈�L�s����̐搶�Ƃ��Ă��r���𗁂тĂ���s�A�j�X�g�B����ɂ��Ă�166�Ȉ�C���t�Ƃ́A�V���p�����a200�N�Ȃ�ł͂̎v��������悾�B�����A�M�l�X�ɐ\�����Ƃ��B5��4���̒�9������[��1���܂ŁA�Ȃ��16���Ԃ̃}���\����R���T�[�g�B������������������������l�ł����B���A�V���p���͌�������Ȃ�����ǁA��C��166�ȁE16���Ԃ̓`���b�g�����B�����ŁA�n�^�ƑM�����E�E�E�����炪�A��l��166�ȂȂ�A������́A���I�������Ȃ��ɂ߂��̖����t�ł܂Ƃ߂Ă݂悤�A�ܘ_�ƒf�ƕΌ��ŁB�Ȑ��́A�����A�\���ԂɈ����18�Ȃłǂ����낤�B�@�t���f���b�N��t�����\���E�V���p���́A1810�N2��22���A�t�����X�l�̕��ƃ|�[�����h�l�̕�Ƃ̊ԂɁA�����V�����Ő������B1829�N�E�B�[���ōs�������t��听���B��1830�N�A�ēx�E�B�[����K��邪�A���x�͂��܂������Ȃ������B�|�[�����h�^�I�[�X�g���A�Ԃ̐�������������߂ł���B�����ŃV���p���̓p����ڎw�����ƂɂȂ邪�A���ꂪ�ނ̉^����ς����B�p���Ќ��E�ւ̉X�����f�r���[�Ɛ����A�����ăW�����W���E�T���h�Ƃ̏o��́A�ނ̍앗�Ɍ���I�ȉe����^�����̂ł���B
�@�̍��|�[�����h�̏ے�����|���l�[�Y�A�}�Y���J�ɑ�\�����͋����f�p�ȋ��y���I���_�B�����c�A��z�ȂȂǂɏh��D��Ő������ꂽ�p���̍���B�V���p���̉��y�ɂ͂��̓�̗v�f�����݂��Ă���B�܂��A�ނ̓V�˂́A�e���݂₷���T�������y�̒��Ɍ|�p�������R�ɓ�����Ă���B�g�{����������"���ȕ\�o�Ǝw���\�o"�̍I�܂��钲�a�Ƃ����悤���B�����l�X�ȗv�f���A�▭�ɗ��ݍ����n�������āA���͈���V���p����T�E���h���`�����Ă���̂ł���B
�@���������ĉ��t�҂́A�|�[�����h�ƃt�����X�A�f�p�Ɛ����A�͋����ƗD�낳�A���}���ƒm���ȂǁA�V���p���̉��y�������������ʐ�����������Ƒ�������ŁA�e���݂₷���ƌ|�p���̃o�����X�̏�ɁA�����̉��y����肠���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�|�C���g�͍������B�Ƃ͂�������C�܂܂ɉ�������̂܂܃T�}�ɂȂ�l������킯�ŁA���ꂪ�^�̓V�˂������肷��B������A�V���p���̉��y�͉��t�҂ɂ���đ��푽�l�Ȋ�����B���ꂪ������ɂƂ��āA�V���p�����ő�̊y���݂ƂȂ�̂��B
�@�̂���V���p���ӂƂ��閼��͑����B�w������ASP�����Ղ��痬����p�n�}���̗��K�ȁu�����v�́A���Տ������悤�Ȍy���ȉ��t�Ɋ��������o��������B�p�f���t�X�L�[�́u���z�����ȁv�ɂ�����I�g�Ƃ������i�����[�[�t�E�z�t�}���́u�m�N�^�[���v�ł̒[���ȘȂ܂��Ɋ������A�R���g�[�́u�����̃����c�v�ɂ����鎩�R���݂ȕ\���ɁA���}���e�B�V�Y���̋ɒv�������悤�ȋC�ɂȂ������̂ł���B�m���ɂ��̎���A1930�|40�N�゠����̖���̉��t�ɂ́A����ɂ͂Ȃ���������������B�S��㇗��A�\�l�\�F�A�m���ɁA���̑��푽�l�Ȍ��̋P���͔��[�Ȃ����͓I�ŁA���l�ɂ��ウ���������͂������Ă���B�Ƃ͂����A����Ȑ̂���������ł��肢����V�l�̉�z�^�ɂȂ��Ă��܂����ASP�����Ղ̉��͂����ɂ��n�ゾ�B�V���p���̃s�A�m�Ȃ�����̂������ŕ����y�������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B�����ŁA�����̓X�e���I�Ɍ��邱�Ƃɂ���B �ł͎莝����CD���Ȃ���A�V���p��"�ƒf"�R���s���[�V�����E�A���o���̑I��ɂƂ�|���낤�B
�@�܂��́A�z�����B�b�c�i1903�|1989�j����B���R�Ȑ��_���甭���鎩�݂Ȋy�z���Ɍ��̃s�A�j�Y���ƍ��̂��A�j���A���X�ɕx�����E��n������B�܂��ɖ�����V�ˁA����̃��X�g�H �u�p�Y�|���l�[�Y�v�́A�E�s���̒��Ɋ_�Ԍ�����V�ѐS�����܂�Ȃ��B�A�e�[���u�}�Y���J��23�ԁA38�ԁv����i�B
�@�T���\���E�t�����\���i1924�|1970�j�́A�Â����������`���Ă����M�d�ȃs�A�j�X�g�B���̃t�@���^�X�e�B�b�N�Ŏ��I�ȕ\���̓R���g�[�ɂȂ����Ă��邩�̂悤�B���l�|�̋ɒv���郏���c3�_��I�肷��B
�@�A���g�D�[������[�r���V���^�C���i1887�|1982�j�́A���p�[�g���[���|�������ɕ����L���s�A�j�X�g�����A�I�肵���u�����̃����c�v�u���z�����ȁv�u�q��́v�́A���N�I�ȉ��������������B�Z�I���m��������ȑz�Ɉ��芴������B
�@�}���^��A���Q���b�`�i1941�|�j�̉ؗ�ŏ�M�I�ȕ\���́A�����������̂�N�X�����Ă����B�u�M�́v���u�J����v�u�C�����v�O�t�Ȃ��A�₩�ȐF�ʊ����Ɠ��ŁA���Ԃ��o�̂�Y�ꂳ���閂�͂������Ă���B
�@���ɁA�}�E���c�B�I��|���[�j�i1942�|�j�́A���x�ȃe�N�j�b�N�ŃV���p���̐��E��[���ɕ`���o���B��Z�I�Œm������K�ȁu�v���v�u�����v�́A����悭�圤�ȕ\�������́B�܂��A�u�ʂ�̋ȁv�̑u�₩�ȝR����D���x�傾�B
�@�~�G�`�X���t��z���V���t�X�L�[�i1892�|1993�j�́A100�߂��܂Ō����𑱂�����Ղ̃s�A�j�X�g�B���̍��o�����y�͏������C�A�܂�œV��̉��y�B���z�ȁv�̖��i2�_��I�肷�邪�A����قǂ܂łɐ��炩�ȃm�N�^�[���́A���đ��݂��Ȃ��������낤�B
�@�W�������}���N�E���C�T�_�i1958�|�j�́A�R���g�[�`�t�����\���̗�������ރt�����X�̈�ށB�u��z�� ���v��R��L���ɕ`���o���Č������B
�@�ȏ�́A�N�ł������Ƃǂ����ŕ��������Ƃ����閼�Ȃ��낢�BCM�^�C�A�b�v��f��ETV�h���}�ւ̑}���Ȃǂ����������A�������L���Ă݂悤�B
�@�u��z�� �σz���� ��i9�|2�v�́A�f��u�����v�i1955�N�j�̎��ȁu�g�D�E�����E�A�Q�C���v�Ƃ��āA�J�[�����E�L���o�����̉��t�ɂ���đ�q�b�g�����B
�@�u�q��́v�́A���L�m�E���B�X�R���e�B�ē̈��u�C�m�Z���g�v�i1975�N�j�̒��ŁA��ۓI�Ɏg���Ă���B
�@�u�ʂ�̋ȁv�́A�����C���O�}�[����x���C�}���ē̉f��u���тƂ����₫�v�i1972�N�j�̑}���ȂƂ��āA�܂��A���D�x�c���q�̃A�C�h������̃f�r���[�ȁu���т���ڂ��v�i1985�N�����j�́A���̋Ȃɔ����E������t�������́B
�@�u�J����O�t�ȁv�́A���V���ēӔN�̃q�b�g��i�u���v�i1990�N�j��s�A�j�X�g�̃f�C���B�b�h��w���t�S�b�g�����f���ɂ����I�[�X�g�����A�f��u�V���C���v�Ō��ʓI�Ɏg���Ă���B
�@�u�O�t�� ��7�� �C�����v��50�b���炸�̒Z���Ȃ�����ۓx�͔��Q�ŁA"���c�ݎ_ ���[����ł�"�̃o�b�N�ɗ����o���o���̌���CM�Ȃł���B
�@�܂��A�u��z�� �d�n�Z�� ���v���A���D�E���`���ɂƂ��Ă����ƂȂ��Ă��܂���TV�h���}����̃K�[�f����i2008�N�A�q�{����i�j�ŁA�e�[�}�ȂƂ��Č����Ɏg���Ă����̂͋L���ɐV�����B
�@���āA����ŁA�^�C�A�b�v��6�Ȃ��܂ޖ��s�A�j�X�g�̏\���ԉ��t�ɂ��ƒf�I�V���p����R���s���[�V�����S18���ڂ����肵���B�܊p������PB-CD�����܂��傤�B�^�C�g���́A���ɂ̃V���p���Ƃ������ƂŁA�uChopin Supreme�v�͂ǂ����낤�B���������A�W������R���g���[���̖��ՂɁuA Love Supreme�v�Ƃ����̂�����܂��������E�E�E�B�ł͍Ō�ɑS18�Ȃ��f���āA�V���p���E�������A���C���[�ւ̃g���r���[�g�Ƃ����Ă��������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Chopin Supreme
�@�@�@�@�@�@�@�@ �|���l�[�Y ��6�� �σC���� ��i53�u�p�Y�v
�@�@�@�@�@�@�@�A �}�Y���J ��23�� �j���� ��i33�|2
�@�@�@�@�@�@�@�B �}�Y���J ��38�� �d�w�Z�� ��i59�|3
�@�@�@�@�@�@�@�C �����c ��P�� �σz���� ��i18�u�ؗ�Ȃ��~���ȁv
�@�@�@�@�@�@�@�D �����c ��7�� �d�n�Z�� ��i64�|2
�@�@�@�@�@�@�@�E �����c ��9�� �σC���� ��i69�|1�u�ʂ�̃����c�v
�@�@�@�@�@�@�@�F �����c ��6�� �σj���� ��i64�|1�u�����̃����c�v
�@�@�@�@�@�@�@�G ���z������ �d�n�Z�� ��i66
�@�@�@�@�@�@�@�H �q��� �σj���� ��i57
�@�@�@�@�@�@�@�I �M�� �d�w���� ��i60
�@�@�@�@�@�@�@�J �O�t�� �� 7�� �C���� ��i28�|7
�@�@�@�@�@�@�@�K �O�t�� ��15�� �σj���� ��i28�|15�u�J����v
�@�@�@�@�@�@�@�L ���K�� ��12�� �n�Z�� ��i10�|12�u�v���v
�@�@�@�@�@�@�@�M ���K�� �� 5�� �σg���� ��i10�|5�u�����v
�@�@�@�@�@�@�@�N ���K�� �� 3�� �z���� ��i10�|3�u�ʂ�̋ȁv
�@�@�@�@�@�@�@�O ��z�� �σz���� ��i9�|2
�@�@�@�@�@�@�@�P ��z�� �σ��Z�� ��i9�|1
�@�@�@�@�@�@�@�Q ��z�� �d�n�Z�� �����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�A�m�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�B�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c �C�|�E�T���\���E�t�����\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�|�H�A���g�D�[���E���[�r���V���^�C�� �I�|�K�}���^�E�A���Q���b�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�|�N�}�E���c�B�I�E�|���[�j �O�P�~�G�`�X���t�E�z���V���t�X�L�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�W�������}���N�E���C�T�_
2010.04.22 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��17�`�u�����f���ƃ|���[�j3
�i�S�j�u�����f���ƃ|���[�j�ԊO���@�A���t���b�h�E�u�����f����CD�u�t�F�A�E�F���E�R���T�[�g�v�ɂ́A���[�c�@���g�̃s�A�m���t�� ��9�� K271�u�W���m�[���v�A�s�A�m�E�\�i�^ ��18�� K533�^494�A�x�[�g�[���F�� �s�A�m�E�\�i�^ ��13�� ��i27�|1�A�V���[�x���g �s�A�m�E�\�i�^ ��21�� D960�A�Ȃǂ̋Ȗڂ�����ł���B�����h�C�c�^�I�[�X�g���A�n�̉��ڂ́A�ނ̃��p�[�g���[�̒����ŁA����ȊO�ɂ̓V�F�[���x���N�A�E�F�[�x�����ȂNj߁E����ɂ܂ŋy��ł��āA�|���[�j�Ƃ����Ȃ�̕����d������B
�@�}�E���c�B�I�E�|���[�j��1942�N�~���m�̐��܂�B18�ŃV���p�����ۃR���N�[���D���Ƃ����X�����L�����A���ւ�B�������A���̒��ォ���10�N�ԁA�\���䂩��p���������B�[�d���ړI�������Ƃ����Ă���B�u�����f����1931�N�`�F�R�̐��܂�B18�ŏo�ꂵ���u�]�[�j���ۃR���N�[���͑�4�ʂ�����(Wikipedia�₻�̑��̋L�^�y�[�W�ł͂��������A���g�̃C���^�r���[�ɂ��ƗD���ƂȂ��Ă���B�ʂ����Ăǂ��炪�������̂��낤���H)�B�R���N�[����͂��ꂾ���ŁA���̌�̃L�����A���A1970�N39�Ńt�B���b�v�X�ƌ_�Ă��瓪�p�������Ƃ����Ӑ��^�B���e������u�E�b�f�B�E�A�����Ɏ��Ă���v�ƔF�߁A�����ዾ�Ŕ��ԂɃV�����w�����ۂ߂ĕ����A�e���B�T�^�I�Ȋw�Ҕ��̃s�A�j�X�g�̃C���[�W�ŁA�V�˃s�A�j�X�g�̑㖼���̂悤�ȃ|���[�j�Ƃ͑ΏƓI�ȑ��݂ł���B����Ȃ킯������A�l�C�̓|���[�j�̂ق����f�R�����B�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă̌`�e���A�|���[�j�ɂ́A�����ʂ��ꂽ�Z�I�A���邢���m�ȃ^�b�`�A�q�ϓI�A�v���[�`�A�����ȉ��߁A�Ȃǂ̕��������Ԃ��A�u�����f���ɂ́A�^�ʖځA�{���ʁA�w���I�A�Ӑ��ȂǂƂ������ƂɂȂ�B���ʁA�|���[�j������I�ȓV�˃s�A�j�X�g VS �u�����f�����`���I�w�����̃s�A�j�X�g�Ƃ����R�����ł�������B���y�t�@���̑命���́A����Ȑ���ς������Ĕނ�̉��t�����ƂɂȂ�B�����A�ʂ����Ă���͐^���Ȃ̂��낤���B���͂��̂悤�Ȑ���ς����ׂĎ�������āA���y�������悤�ɓw�߂Ă���B��������Ə��X�ɐ^���������Ă���E�E�E�B
�@�ł́A�ނ�ɋ��ʂ̃��p�[�g���[�̒�����A���[�c�@���g�ƃu���[���X�̋��t�Ȃ���ׂĂ݂悤�B
[���[�c�@���g�F�s�A�m���t�� ��12�� �C���� K414]
�@�s�A�m���t��K414�́A���[�c�@���g���E�B�[���ɏo�Ă���2�N�ځA1782�N�̍�i�B�������āA�\�t����O���ɏ��o�����A�ނ̐l���̒��ōł������Ȏ����̊y�Ȃł���B�����N�A�N���X�e�B�A���E�o�b�n���S���Ȃ����B�N���X�e�B�A���E�o�b�n�́A��o�b�n�̖��q�ŁA���[�c�@���g���A���N����A�����h���Ŏn�߂ẴV���t�H�j�[���������Ƃ��ɋ����������t�B���[�c�@���g�́A���̎t�ւ̃I�}�[�W�������߂āA���̋Ȃ̑�2�y�͂ɔނ̐����ߍ���ł���B
�@��2�y��Andante�ɂ������u�����f���ƃ}�b�P���X�w���F�X�R�b�g�����h�����nj��y�c�i2004�N�^���j�̉��t�́A�h�i�ȋF��ɖ����Ă���BABA'�̎O���`���A���̂a�ֈڍs����ۂ̐▭�ȊԂ�A'�ւ̈ڍs�����ɂ�����l�������ꂽ���J�ȕ\���́A�u�����f���̙{���ʂ��̌��ꂾ�B�{���ʁA�������J�������A��i�ƍ�҂ւ̌h���̔O���̂��̂ł���B�|���[�j��2007�N�^���̓E�B�[���E�t�B���Ƃ̒e���U���ł���B�s�A�m�ƃI�P�̗Z�����������͊m���ɔ��������A���y�������ɗ���邾���ŁA�u�����f���̉A�e�ɕx�[���\���Ɋr�ׂ�ƃR�N�ɖR�����B
�@�I�y�͂͌y���ȃ����h�B�I�����B�G�E���V�A���i1908�|1992�j�́u���[�c�@���g�̐������́A�㏸�E���~�̌`�Ԃƃo�����X���▭�ŁA���̃t�H�����̔������͔�ނ��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă��邪�A���̃����h��肱���܂��ɂ��̓T�^�B�����㏸�A�{���~�A�I�N�^�[�u�㏸�A3�x��ɒ��n�A�Ȃ�ƃV���v���Ŕ������`�I �u�����f���͂��̃��[�c�@���g�̓������̂��̂̂悤�Ȏ����A���Ɍy���ɏ_�炩���������N�b�L���ƕ`���o���B���̈Ӗ������m���}�g���\�����B����A�|���[�j�̉��́A�y���_�炩���̂͂����̂����A�c���Ȃ��B�ǂ݂����ɍ��߂��Ă��Ȃ�����A�֊s���ڂ₯���y���_���_���Ɨ���Ă��܂��B������ɁA���̃f�B�X�N�́A���R�[�h�|�p2008�N�x�u���[�_�[�X�E�`���C�X�v�ő�6�ʂƂȂ��Ă���B�O��̃��[�c�@���g(K453&467)��2006�N�x�̓��X�̑�P�ʂ��B��͂�|���[�j�̐l�C�͔��Q�Ȃ̂ł���B�l�C�����ł͂Ȃ��A���Ƃ̕]���������Ԃ�ǂ��A���R�̓��I�Ղł���B����Ȃɍ����]���̉��t���A�����܂��Ȃ��Ă��܂��Ă����̂�����H�ނ炪�ǂ���Ԃ����邩���E�E�E�B
[�u���[���X�F�s�A�m���t�� ��2�� ���� ��i83]
�@�u���[���X�̃s�A�m���t�ȑ�2�Ԃ̃L�[���[�h�̓C�^���A�ł���B1878�N�ŏ��̃C�^���A���s�̂��Ƃ��珑���n�߁A���f�A1881�N�ēx�C�^���A�ɍs���A�A���Ă����C�ɏ����グ��ꂽ�B�d���ŏa���u���[���X�̍�i�̒��ɂ����āA���̋Ȃٍ͈ʂ�����Ă���B���ɏI�y�̓����h�́A�C�^���A�̐��ݐ�����̂悤�ɖ��邢�i�Ƃ͂����Ă��A�u���[���X������A�����f���X�]�[�������ȑ�4�ԁu�C�^���A�v�I�ł���킯���Ȃ����j�B���ȕ��̎�v���͌y���ŁA���ԕ����ɂ�ῂ��ƃZ���`�����^�������n���������悤�ȗz���������B���d�ȑ�P�y�͂��A�d���ŏ�M�I�ȑ�2�y�͂��A�R��I�ȑ�3�y�͂��A���ꂼ��ɖ��͓I�ȉ��y�����A�Ȃ�Ƃ����Ă��|�C���g�͏I�y�͂��B�����ɂ́A�u���[���X���C�^���A�Ɍ����Ȃ�����̓��ۂ�����B
�@�u�����f���́A���̋Ȃ�1974�N�n�C�e�B���N�w�����C�����E�R���Z���g�w�{�E�A1991�N�ɂ̓A�o�h�w���x�������E�t�B���ƁA�|���[�j�́A1976�N�A�o�h�w���E�B�[���E�t�B���A1995�N�������A�o�h�w���Ńx�������E�t�B���Ƙ^�����Ă���B���̋Ȃ̃L�[���[�h"�C�^���A"�ɂ́A�A�o�h�ƃx�������E�t�B�����ō��x�Ƀ}�b�`���O���Ă���B�C�^���A�l�w���҃N���E�f�B�I�E�A�o�h�i1933�|�j�Ƌߑ�I�I�[�P�X�g���̍ō���x�������E�t�B���̃R���r�́A���������ɕ`���o���R��S��Ȃ��A�܂��ɁA�C�^���A���Ȃ̂��B���������ē�l���A�x�X�g�̓A�o�h�F�x�������E�t�B���̕��ɂȂ�B�ł́A�u�����f�����A�o�h�F�x�������E�t�B����91���|���[�j���A�o�h�F�x�������E�t�B����95�̏����₢���ɁE�E�E�E�B
�@�܂����u�����f���B�I�y�͂��n�܂��ăI�[�P�X�g���������������̃s�A�m�E�\���i��17���߁`�j�̃e���|�̗��Ƃ������Ɣ����ȃ^�b�`���f���炵���B����ԈႦ��Ό����ɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ���̃R���g���[�������▭�ł���i���݂�74�N�Ղ̓e���|�̕ϓ��͂Ȃ��j�B�ΏƓI�ɁA45���ߖڂ���̃^�b�`�̋��x���͂ǂ����B�����́A���Ȉى��Ɗr�ׂĂ����炭����̗͋������낤�B���̕����A�|���[�j�̃^�b�`���m���ɋ��x�����A��▾�邭�y���B�|���[�j�̂͋��ɋ������A�u�����f���͂�������ƕ��ɋ����B81���ߖڂ���͑傫���L�т₩�ɉ̂��A97���߂���C�^���A�����ԕ����ɓ����Ă䂭�B���̒��Ԏ��̃u�����f���̒e���l�������Ȃ��́B���т₩�őu�₩�A�����ɃZ���`�����^���ȃX�p�C�X���������ɏ�̃e�C�X�g�ł���B�܂����u���[���X���������C�^���A���̂����Ƃ����C������B���ꂼ���̋Ȑ���̖����A�Ƃ������A���ケ��𗽂����t�͏o�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��� ? �Ǝv����قǂ́A�Ƃ�ɛƂ������ɂ̖����t���B����|���[�j�͂ǂ����B�ȏ�3�̃`�F�b�N�E�|�C���g���ׂĂɂ킽��A�u�����f���ɋy�Ȃ��B�I�[�P�X�g�����������S�R�Ⴄ�B�u�����f���Ղ̃A�o�h�F�x�������E�t�B���́A�\��̗}�g���傫�����s�����[���B�܂�ŁA�u�����f���̑����`���B����Ɋr�ׂ�ƁA�|���[�j�Ղ̃I�P�͕��ʓI�B�O�����Ɠ��̈Ⴂ������B�����R���r�̃I�P�ł��A�\���X�g�ɂ���ĈႤ���y�ɂȂ�Ƃ����A����͍D��ł���B
[�t�L]
�@�u�����f���́u�t�F�A�E�F���E�R���T�[�g�v�����B2008�N12���̈��ދL�O�R���T�[�g�ł���B���ڂ́A�v���O�����̍Ō�ɒu���Ă���V���[�x���g�u�\�i�^��21�ԁv�����A����͒ʎZ4�x�ڂ̘^���ƂȂ�B�S�̎�܂܂̎��Ɏ��R�̂̉��t�������B�u�Ō�Ȃ̂�����v�����Ƃ���ɒe���B�����A���`�Ƃ��m��̃o�����X�Ƃ��͊W�Ȃ��B���́A���S�̎�܂܁A�����Ђ����炻�̔������������̂��������v�Ƃł������悤�ɁB�������Ă��鉹�y�́A�Ȃ�̋C�������Ȃ��A��������p�̎�ꂽ�����݂̉��y�ŁA��Ԃɔ����������������Y���Ă���B���������Ӗ��ł́A�O�R��Ƃ͂܂�Ŏ���قɂ��Ă���B20���N�O�ɁA100�߂��̃z���V���t�X�L�[���c�������R�[�f�B���O��z�N������B�S���c������炬�D�����C�����ɂ��Ă���鉹�y�ł���B�܂��A��1�y�͒��̌J��Ԃ��́A�����ł��s���Ă��Ȃ������B����ɂ��ẮA�O��u�u�����f���ƃ|���[�j�Q�v�ŏq�ׂ��悤�Ɂu�^�₾���A�u�����f���̂�邱�Ƃ�����A�K���Ȃ�炩�̗��R������͂����v�Ǝv���Ă����B
�@�Θb�^�u�����炢�l�v�u�����f���i�}���e�B���E�}�C���[�ҁA���{�a�q��A���y�V�F�Њ��j�Ȃ�{����ɓ������̂œǂ�ł݂���A���̗��R������Ă����̂ŁA���̕��������p����B
�i���̌J��Ԃ��ɂȂ���9���߂̃u���b�W�́j�f�ނ�j�邾���ł͂Ȃ��A���ʂɈ�ѐ��̂��邱�̊y�͂̕��͋C���̂��̂��A�����Ă����\�i�^�S�̂�j�Ă��܂��댯������܂��B���̐����߂͍�i�̂ǂ̕����Ƃ��֘A����������܂���B���@�I�ɁA���邢�͐��_�I�ɉ������������Ă���̂ł���A����͂ق��ł����邱�Ƃł����A�������d����ł��傤�B�������A�����ł͂Ȃ��̂ŁA���͌J��Ԃ���e���܂���B�@�������L����10�����D960�̓��A�J��Ԃ����s���Ă��Ȃ��̂́A�u�����f���ƃN�����E�n�X�L���i1951�N�^���j�����ł������B�J��Ԃ����s��Ȃ��ƁA�V���[�x���g��������9���߂̃u���b�W���Ƃ����ƂɂȂ�B����̓C�R�[���A�V���[�x���g�̎w���ɋt�炤�Ƃ������ƂȂ̂��B"�Ȃ��֘A���Ȃ�����"�Ƃ�"�Ȃ��Ă��܂�����"�Ƃ������R�ł��̎w��������Ƃ́A�����ɂ��u�����f���A���ꂼ�ނ̔��ӎ��Ɗ�ł��̏ؖ��Ƃ����ׂ����낤�B�������������t�Ɛl���̍ŏI�X�e�[�W�̃��X�g�ɒu���قLj����Ă�܂Ȃ��V���[�x���g�̊y�Ȃɂ����Ă�����A�Ȃ�����ł���B
�@�Ƃ͂����A���͂��̌��Ɋւ��Ă͎^�������˂�B�Ƃ������A�ǂ�����������̃u�����f���ƌ��������Ȃ�B�J��Ԃ����A����9���߂̓V���[�x���g�̎w���Ȃ̂ł���B�V���[�x���g�̋C�����A����Ȃ̂ł���B���ꂪ�S�̂�����Ƃ��ČJ��Ԃ������Ȃ��̂́A���t�҂̎v���オ��ł���B�V���[�x���g�͊֘A���̂Ȃ����̂�"�����ē��ꂽ"�̂�������Ȃ��ł͂Ȃ����B�u�����f��������"�֘A���̂Ȃ�9����"�����A2������ɂ͎���ł��܂��M���M���̏̒��Ŕ������V���[�x���g�̐S�̋��тȂ̂�������Ȃ��̂ł���B���ɂ͂�����������B
2010.04.14 (��) �f��u�h���E�W�����@���j�v�`�V�ˌ���Ƃƃ��[�c�@���g�̏o� ���ς�
�@�J�����X�E�T�E���ē̃C�^���A���X�y�C������f��B����ɂ���V�ˌ���ƂƂ́A�u�h���E�W�����@���j�v�̑�{���������E�B�[���{�쎍�l �������c�H�E�_�E�|���e�i1749�|1838�j�̂��Ƃł���B�_�E�|���e�����[�c�@���g�i1756�|1791�j�Ƃ̃R���r��i�ɂ́A�u�t�B�K���̌����v�u�h���E�W�����@���j�v�u�R�V�E�t�@���E�g�D�b�e�v������A�����́A���[�c�@���g�̃_�E�|���e�O����Ƃ��č��ł��p�ɂɏ㉉�����I�y���̌���l�C��i�ł���B�@���y�Ƒ�{�̓I�y���̗��ցB���̈Ӗ��ł́A�_�E�|���e�Ȃ����ĎO����͑��݂��Ȃ������͓̂�����O�����A�ނ̖����͒P�Ȃ��{���������Ɏ~�܂�Ȃ������B����u�t�B�K���̌����v�i1786�N�����j�̓t�����X�̌���ƃs�G�[���E�I�M���X�^���E�J�����E�h�E�{�[�}���V�F�i1732�|1799�j�̋Y�Ȃ�����B����ɖڂ��������[�c�@���g�̓_�E�|���e�ɃI�y�����𑊒k����B�����̃��[�c�@���g�̓E�B�[���ɏo�Ă���5�N�ځB�M���̎q���̃��b�X���Ǝ���̗\�t��̎����łȂ�Ƃ������͐��藧���Ă������A��ȉƂƂ��Ď��炪��������悤�Ȑ��ʂ͂����Ă��Ȃ������B�����A�ꗬ��ȉƂ̏̓I�y���Ă邱�ƁB�u�I�y�����q�b�g�����āA�������ɔF�߂�ꗬ��ȉƂ̒��ԓ�����������v�E�E�E���ꂼ�܂��ɁA���̓V�ˍ�ȉƃ��[�c�@���g�̉R�U�炴��ߊ肾�����̂ł���B����Ȕނ̚k�o�Ɋ|�������̂��u�t�B�K���̌����v�������B"���̑�ނŎ��������y�������ΐ�ɓ�����"�Ɣނ͌ł��M�����B�����ŋ{�쎍�l�_�E�|���e�ɑ��k�����̂ł���B
�@��������_�E�|���e�́u�ʔ����A��낤�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�����҂Ă�B������ʂ����ċ{��͋����邾�낤���B�Ȃ��Ȃ�A���̍�i�A�������M������M����Ƃ����x�z�ґ����猩��ΐr���͂����������e�B�v���O��ŏ����̑䓪���������t�����X�ł���A��҂̓��������܂ŋN���������̊댯�ȋY�Ȃ́A�n�v�X�u���N�Ƃ̌������������Ȃ��E�B�[���ł̏㉉�͋ɂ߂ē���ɂ������̂ł���B�ނ́A�i�ܘ_�A���[�c�@���g�Ƌ��c���Ȃ���j����̉ߌ��ȕ������폜���Z���t��ς���Ȃǂ��Ċp��������B�������āA�_�E�|���e�́A"����̎��G�X�v�������������ƂȂ��A�{��̋���������M���M���̐��ō��"�Ƃ����▭�ȃo�����X�������Ɏ����������B���ꂼ�܂��ɓV�˂̋Z�ł���B�Ƃ��낪����ł��A�T���G���Ƃ���{��ψ���͂��̍�i�̐�����p�������B�����Ń_�E�|���e�͒�����ɑł��ďo��B���[�c�@���g�ɗ����̐[���c�郈�[�[�t2���ڐ������ċ����̂ł���B�������ăI�y���j��̑匆��u�t�B�K���̌����v�͐��ɏo�邱�ƂɂȂ����B1786�N5��1���A�E�B�[���A�u���N����ł̏����͊�Ȃ��̂������炵���B�c��ɒ��k������ĖʖڊۂԂ�̃T���G����h�́A�������Ƀu�[�C���O�𗁂т���B�����A��i�̖ʔ������y�̑f���炵���Ɋ��삵���ϏO�͑劅�сA�������̃A���A�͉��x���A���R�[�����ꂽ�Ƃ����B�܂��ɁA�������钿���ۂ��N�����̂ł���B
�@���̌�A�u�t�B�K���̌����v�̓v���n�ŏ㉉����A��O�̑�q�b�g�ƂȂ����B�v���n����̎x�z�l�|���f�B�[�j�́A�n���Ƀ��[�c�@���g�������B1787�N1���A�v���n�ɒ����u�t�B�K���v�̑�q�b�g��ڂ̓�����ɂ������[�c�@���g�́A�莆�ɂ��������Ă���B�u�����ł́A�l�X�́w�t�B�K���x�̂��Ƃ����b���Ȃ��B�w�t�B�K���x�ȊO�͉������t���Ȃ����A�̂������Ȃ������J�������Ȃ��B�����ł͂��ׂāw�t�B�K���x�B�w�t�B�K���x�ȊO�̂Ȃɂ��Ȃ��v�i1787�N1��15���j�B���ɔO��̑�q�b�g�E�I�y�����蒆�ɂ����ނ̋����U�肪�`����Ă���B�����A���[�c�@���g�����U�ō��̋C���𖡂�����̂͂��̎��������Ƃ����Ă���B
�@�|���f�B�[�j���A����x�z�l�Ƃ��ă��[�c�@���g�Ɏ������˗������͓̂��R�̂��ƁB��{�����_�_�E�|���e���B�����Œa�������̂��O����̑�2�e�u�h���E�W�����@���j�v�������B�������āA�u�h���E�W�����@���j�v��1787�N10��29���v���n����ŏ����B�t�B�K���ɑ����A��q�b�g�����B���̌�A��̉����������āA1788�N5��7���ɃE�B�[���������s��ꂽ�B
�@�ȏオ�A�̌��u�h���E�W�����@���j�v�a���܂ł̌o�܂ł���B�f��́A�_�E�|���e�̏��N���ォ��̌��u�h���E�W�����@���j�v�a���܂ł��`�����B
�@���_���l�Ƃ��āA���F�l�c�B�A�ɐ������������c�H�E�_�E�|���e�i�������c�H�E�o���h�D�b�N�j�́A���N����A��Ƃ��L���X�g���ɉ��@���邪�A�f���Ɏ�����Ȃ��B�����Ő_���͔ނ��_���e�i1265�|1312�j�́u�_�ȁv��ǂނ��Ƃ����߂�B���̂Ƃ��Ɏw����ƂȂ����������A���l�b�^�i�G�~���A�E���F���W�l�b���j�������B�ނ́A�ޏ��Ɓu�_�ȁv��ǂނ��Ƃɂ���āA�L���X�g���𗝉������@�������B���̃A���l�b�^���A�_���e�̉i���̏i���ɂ��āA�u�_�ȁv�ɂ����ẮA�n���ɖ�������l���_���e���w�삵�V���ɓ������Ȃ鏭���Ƃ��ēo�ꂷ���x�A�g���[�`�F��͂��Ă��邾�낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���ŋߕ��f���ꂽ�t�W�e���r�J��50���N�L�O�h���}�O�J�K���i�u�킪�Ƃ̗��j�v�i����͋H�Ɍ���e���r�E�h���}�̌���ł����j�̒��ŁA���c�q�s�������Ƃ̎�̈����̂��A�G�m�P���̏\���ԁu�x�A�g���˂������v�������B���̉̂́A�I�y���̐l�C���ځE��̌��u�{�b�J�`�I�v�i�X�b�y��ȁj�̌����́B�x�A�g���˂������̖{���̓x�A�g���[�`�F�ŁA�I�y���ł́A���C���ŏ����̏��[�Ƃ����ݒ�ł���B�����A�������ǂ�A�_���e�̉i���̏i���ɂȂ���̂ł���B�{�b�J�`�I�i1313�|1375�j�̓_���e�̔M��Ȑ��q�҂��������炾�B�h���}�u�킪�Ƃ̗��j�v�̌����A���e�̓w�}���肵�Ă����Ƒ��ɖ��f�������Ă���B����ȕ��e�̑���ɁA��������킸�Ƒ������������Ă䂭�̂̓V�b�J���҂̒����i�č�R�E�j�ł���B�n���ɖ����������ȕ��e���w�삷��C���������Ƃ����}���́A�_���e�́u�_�ȁv�ɏd�Ȃ荇���B�O�J��i�̉��̐[�����M����B
�@�b�������Ɉ�ꂽ���A���@�����_�E�|���e�́A�m�E�ɂ��������̐��i���������s�����Ĕj�傳��A�������Q�̂��ƁA1781�N�ɃE�B�[���ɂ���Ă���B�����ɂ͓����N�A���e����Ɨ��A�U���c�u���N����ɃE�B�[���ɏo�Ă�������̃��[�c�@���g�i���m�E�O�����`���[���j�������B�ނ�͏o��ӋC�����A�u�t�B�K���̌����v�����A��2�e�u�h���E�W�����@���j�v�ɂƂ肩����B�����ŁA�_�E�|���e�́A���܂��܃��[�c�@���g�̒�q�ƂȂ��Ă����A���l�b�^�ɍĉ�i����͉f��̑n�삾�낤�j�B�I�y������̉ߒ��ɂ��̗������ށB
�@�{��̎�̎哱���������ʔ����B������O���ꂽ�\�v���m�̎肪�_�E�|���e���Ȃ���ƁA���i�̓o��l����V���ɍ�肠���Ă��܂��B���ꂪ�h���i�E�G�����B�[���Ƃ������B���̃G�s�\�[�h�����̂܂������ǂ����͕s�������A����Ȃ��Ƃ�18���I�̃��[���b�p�ł͓��풃�ю��������炵���B�����̓I�y�����B���y�̎���B�Ȃ�Ƃ����Ă��ϋq�̂��ړ��Ă͉̎�Ƃ��̉S�������B�w���ҁA��ȉƂ����A�̎�̈ӌ����ŗD�悳��Ă����̂ł���B���t����̂����C���ŁA�V���t�H�j�[��R���`�F���g�A��y���t�Ȃǂ́A���ޏ��̂̍��Ԃ�BGM�I�����������悤�ł���B���݂̂悤�ɁA�I�[�P�X�g�����y�����ŃR���T�[�g���{�i�I�ɐ��藧�悤�ɂȂ�ɂ̓��X�g�i1811�|1886�j�̏o����҂��˂Ȃ�Ȃ������̂��B
�@���̉f��ɂ͋H��̐F���t�J�T�m���@�i1725�|1798�j���o�ꂷ��B�_�E�|���e�́A���������̊Ԃɒm�荇���e�F�ƂȂ��Ă����J�T�m���@�ɃA�h���@�C�X�𐿂��B�u�J�^���O�̉́v�����āB����̓h���E�W�����@���j�����m�ɂ������̃��X�g��ǂޏ]�҃��|���b�����A���̕����Ԃ��������Q���́B���̃��X�g�ɋL�^����Ă��鏗�̐��́A"�C�^���A��300���l�A�h�C�c��231�l�A�t�����X100�l�A�g���R91�l�A�X�y�C����600���l"�������B��������J�T�m���@�́A�u�������̑c���C�^���A��300�l�͏��Ȃ�����B���ꂶ��C�^���A���ɖ��͂��Ȃ����Ă��ƂɂȂ�B����Ꮈ��疜���B�����͓�{��640�l�ɂ��悤�B�����Ȃ�ƁA�X�y�C���𑝂₳�Ȃ��Ⴂ���Ȃ��ȁB�������ɂ͓G��Ȃ�����1003�l�łǂ����v�ȂǂƏ����B���v2065�l�Ƃ������݂̌`�ɂȂ����̂́A�J�T�m���@�̃A�h���@�C�X�̎����Ƃ����킯�ł���B��������̂܂����Ƃ͎v���Ȃ����A�ʔ������z�ŁA�������B
�@�f��̕���̓E�B�[���Ȃ̂ŁA���������̒n�ōs��ꂽ�Ƃ����`�ɂȂ��Ă���B�ł��A�E�B�[���ő唼�����A�c��Ə��Ȃ̓v���n�Ŏd�グ�ď����A�Ƃ����̂��j���B�E�B�[���㉉�͔��N�ゾ�����B�����̂Ƃ��낪�B���Ȃ̂͂�╨����Ȃ����A�j���ɒ����Ƀv���n���o���g�b�`�����邵�A�f����Ƃ��Ă͂��̒[�܂�͐����Ȃ̂�������Ȃ��B�����A�C�ɂȂ����̂́A�j�S�����ւ̓˂����ݕs���ł���B����́A�_�E�|���e��"�����ɂ��ăE�B�[���{��֓��荞��"�Ƃ����o�܂�"���[�c�@���g�Ƃ̏o�"�̌��A�����āA"�I�y���㉉�̂��߂̋{��ւ̓�������"�̃V�`���G�[�V�������B���_���l��Ƃɐ��܂ꂽ����̕������_�E�|���e���A�̋��̐�y�T���G���Ɏ������ċ{�쎍�l�Ƃ��ēo�p����A���[�c�@���g�̍˔\�ɏo��ӋC�����A�{���G�ɉĂ܂ł��A��l�̍�i�̏㉉��簐i����������́A���n��̍˂ƌ|�p�ƂƂ��Ă̏�M�ƐM�O���A�����������x�Z���`���Ă�����Ǝv�����ǂ����낤�B�m���ɁA���[�c�@���g�ɏo����ċ{��ɔP������i�́A�O��́u�t�B�K���̌����v�ł͂��������A�����͂��܂��ܒ����đ�{���������͂��ł���B�v���n��[�܂��ăE�B�[���ɓ��ꂵ���悤�ɁB
2010.04.09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��16�`�u�����f���ƃ|���[�j2
�i�R�j�V���[�x���g�u�\�i�^��21�ԁv�ɂ�����u�����f���ƃ|���[�j�@�V���[�x���g�Ō�̃s�A�m�E�\�i�^�u��21�� �σ����� D960�v�́A���Ȓ��̖��Ȃł���B�V���[�x���g������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂������ɉ̂�����A������̎p���������ǂ����邩�H�V���[�x���g�̐S����ǂ��\�����邩�H�ŔӔN�̏���ǂ����߂�̂��H �Í��̃s�A�m�E�\�i�^�̍ō���Ƃ������邱�̋Ȃɂ́A����̒���~�������鉽���̂�����߂��Ă���̂��낤�A���̃��R�[�f�B���O�͂��Ȃ�̗ʂɏ��B����Ȓ�����A����̓u�����f���ƃ|���[�j�����グ�Ă݂����B
�@�A���t���b�h�E�u�����f���́A�u��21��D960�v���A1971�N�A1988�N�A1997�N��3��A�t�B���b�v�X�E���[�x���ɘ^�����Ă���B����ȑO�AVOX��VANGUARD�ɂ����邩������Ȃ����A�������ł���B�}�E���c�B�I�E�|���[�j�́A�h�C�c�E�O�����t�H���ɁA1987�N�̘^��������B�u21���I�̖��Ȗ��Ձv�i�u���R�[�h�|�p�v�ҁj�ɂ��ƁA��P�ʂ̓��q�e����21���_�B��2�ʂ��|���[�j��10�_�B�u�����f���́A��3�ʂ�1988�N��(8�_)�A�ȉ�1997�N�i5�_�j�A1971�N�i1�_�j�Ƒ����Ă���B���q�e���ɂ��ẮA�O��q�ׂ����A�_���g�c�̑�1�ʂɂ͑傢�ɋ^�₪�c��B�ꌾ�Ō����ƁA����̓V���[�x���g�ł͂Ȃ��B��Ղ̔N1828�N�̉��y�ɏh��A�߂��݂���i���鎜���݂̏���Ȃ��B���̓V���[�x���g�̉��y�ɂ͂���ȗD�����������B���q�e���́u��21�ԁv��ǂ��Ƃ���l�́A���Ƃ͈Ⴄ"�ʂ̉���"�������ɋ��߂Ă���̂��낤�A����͎��R�ł���B�������͂��̐l�̃V���[�x���g�ɂ͈�a�����o���邵�A������D���Ȑl�Ƃ͉��y�I�ɂ͍���Ȃ��Ƃ����A���ꂾ���̂��Ƃ��B�������A���q�e���́A����ȊO�A�Ⴆ���t�}�j�m�t�̑�2�Ԃ�X�g��2�̋��t�Ȃ̉��t�Ȃǂ͑f���炵�����̂�����B���t�Ƃɂ͓���s���肪����̂ł���B�����玄�́u�ǂ̉��t�Ƃ��D�����H�v�Ƃ�������ɂ͓�����ꂸ�A"���̋Ȃɂ����Ă͂��̉��t�Ƃ��D��"�Ƃ��������������o���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���ꂪ���̒������Ȃ̂ł��B
�@3�̃u�����f���Ղ̒��ł́A�u21���I�̖��Ȗ����v�ōʼn��ʃ����N��1971�N�^�����ł��悢�B�ނ̓������ō��x�ɔ�������Ă��邩�炾�B���������̉��t�́A�u�\�i�^��21�ԁv�ɂ�������c���q�Ƒo���̖����t�ƂȂ��Ă���B������A�A���t���b�h�E�u�����f���̓����Ȃ���̂��A�ނ̃V���[�x���g�u�\�i�^��21�ԁv1971�N�Ղƃ|���[�j1987�N�ՂƂ̔�r�����ɂ���ĒT���Ă������Ǝv���B
�@��P�y�́A�u�����f���́A��̓��c�̎����݂̃A���y�W�I�i��113���߁j�́A���邭�y�������A���q�e���̂悤�ɖ��_�o�ł͂Ȃ��B�y�͑S�̂ɂ킽���āA���y���܌��̕��̂悤�ɑu�₩�ɗ���Ă䂭�B���̗��������N���A���������������������ƕ����яオ��A�\������������ƌ��ʂ���B�������A�N���A�ł���Ȃ���c�����邩��A�\���ɐ����͂����邵�A�e���[���B���ʁA�|���[�j�̃A���y�W�I�̓u�����f�������D�������A���܂肱���ɈӖ��������Ă��Ȃ��悤�Ȓe���Ԃ�ł���B�}�g�̕������Ȃ����̗֊s������قǃn�b�L�����Ȃ��̂ŁA�Q�̎����ۗ����Ȃ��B���������āA�S�̂��ɂ����������悤�ŁA�\�������m�Ɍ����Ă��Ȃ��B�g�c�G�a���́A2008�N�E�B�[���ŕ������|���[�j�ɂ��āA�u�������ꂢ���v�Ƃ�����ɋ��Ă������A����CD���m���ׂ���A�u�����f���̂ق������|�I��"���ꂢ��"�ƁA���͊�����B�܂������A"�L��������̂ɔ�����"�ł���B�������A�u�����f�����A"�����J��Ԃ��Ă��Ȃ�"�͉̂��̂��낤�B�J��Ԃ��Ɏ���9���߂̃u���b�W�́A�S�̓I�ɕ����ɗ�����P�y�͂̒��ŁA�K�x�ȋْ����ݏo���Ă���A���͕K�v���Ǝv���̂����E�E�E�E�B���݂�1988�Ղ�1997�Ղ��A��т��ČJ��Ԃ��͍s���Ă��炸�A����͂Ȃɂ��l����Ƃ��낪����̂��낤�B�����A�m���߂Ă݂������̂ł���B
�@��2�y�́A�u�����f���̉��y�̗���ɂ͂܂��������݂��Ȃ��B���ԕ��̕������ւ̈ڍs�����ŗ��Ƃ����e���|���A2�x�ڂɂ̓C���e���|�œ����Ă���B���̂�����̃R���g���[�����͕������X�点����̂����邪�A�|���[�j�ɂ́A����ȍאS�Ȋ��o�͂܂�łȂ��B�\��͗D�����̂����A�u�����f���ɔ�ׁA���R���͔ۂ߂Ȃ��B�A�e�\���̃u�����f���A�R�����|���[�j�B
�@��3�y�́B�u�����f���̉��͐��������Ɨx���Ă���B�y���Ő����͂Ɉ��Ă���B���ԕ��ł́A�\����v������悤�ɕς��B���̑Δ���N�₩���B�|���[�j�͕��B
�@�I�y�́B"�V���[�x���g�́A�\�i�^�̃t�B�i�[���y�͂̍\���ɋ�Y���������ۑ���A�Ō�܂Ŏc�����܂I����Ă���"�Ƃ�����������B���������������̌������́u�\�i�^�`���������h�`�����n�b�L�������A���m�ȓW�J�����Ȃ�����v�Ƃ������Ƃ̂悤���B�܂��A��������������́A�ނ���ƂɔC���Ă��������B���y�͌`���ŕ������̂ł͂Ȃ�����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������̂����A�t�ɂ��̌`�͑f���炵���A�Ǝ��͎v���B�����u���b�N���͂���ő�P��肪���x���o�Ă���̂́A�m���Ƀ����h�������A�����ɑ�2��肪���ނ̂̓\�i�^�`���I�ł�����B�W�J���Ƃ�����悤�ȃn�b�L���������ԕ��͊m���ɂȂ����A���̕��A�R�[�_�i�I�����j�́A�����Ăяo�����݂ɏ�������Ȃǂ��āA���Ȃ��K�͂ł���B�W�J���������ɂ܂������Ă���ƍl��������̂ł͂Ȃ����B�ނ���A�V���[�x���g�̑z���͂����a�V�Ȍ`���Ƒ������Ȃ����납�B�ނ�1824�N3��29���̓��L�ɂ��������Ă����u�����A���z��I���͐l�ލō��̕�A���͐s���邱�Ƃ̂Ȃ���ł����āA��������|�p�Ƃ��w�҂������悤�Ƀm�h�����邨���������ނ̂��I�v�ƁB���̏I�y�͂����A�ނ��|�p�Ƃ̍ő�̕�ƐM���錶�z���z���͂̎Y���Ȃ̂ł͂Ȃ����E�E�E���ɂ͂����v����B
�@�u�����f���́A��P�����A�Ƃ��ɃX�^�J�[�g�łƂ��Ƀ��K�[�g�ŁA���܃e���|�����炵�Ēe���B��2���́A���ɁA�傫�ȕ\��łނ���N�X�Ɖ̂��B�\��L���ŁA���ꂪ��P���Ƃ̑Δ�����ށB�����āA�Z���W�J���ɂ͏�M������B�����Ō����A���V���R�y�C�e�B�b�h���ꂽ��P���̕\��t�������ɃX�}�[�g�ŁA���q�e���̃��V�A�̔_�����������Ƃ͑�Ⴂ�ŁA�E�B�[�����̕i�̂悳�����܂�Ȃ������B���̏�A�����N���A�Ȃ̂͑�1�y�͂ł��q�ׂ��Ƃ���B������A���̂�╡�G�Ȍ`�����L�b�`�����m�Ɍ��ʂ���B�f���炵���\���ł���B����ɔ䂵�āA�|���[�j�́A�����ł���蓯�m�ł������n�����Ȃ�����A���������ڂ₯�A���ʃt�H�����������Ă��Ȃ��B�e�����Ȃ��u���b�N�ł₯�ɒ���邩��A��������Ԗڗ����Ă��܂��A�̐S�ȕ����̈�ۂ��ڂ���B�u�����f���Ƃ͑�Ⴂ���B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�u�����f���ƃ|���[�j�ł́A�N�G�̈Ⴂ�i�̈Ⴂ�͗�R�ł���B�u�����f���́A2008�N12���ɐɂ��������ނ��Ă��܂������A���̍Ō�̃R���T�[�g�́A�u�t�F�A�E�F���E�R���T�[�g�v�Ƒ肵�A2���gCD�Ŕ�������Ă���B���̒��ŁA�u��21��D960�v�̓��T�C�^���̃��C�����ڂƂȂ��Ă���̂ł���B�����L�����A�̍Ō�ɂ��̋Ȃ�I�Ƃ������Ƃ́A�u�����f���ő�̂��C�ɓ���y�Ȃ̏��B�܂��������ĂȂ����A��P�y�͂̌J��Ԃ��̗L�����܂߂āA�ǂ�ȃp�t�H�[�}���X�Ȃ̂��{���Ɋy���݂ł���B
2010.03.31 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��15�`�u�����f���ƃ|���[�j�P
�i�P�j�u�����f���Ɠ��c���q�̌��t�����@�u���ɂ�����V���[�x���g�́A�����炢�l�ł���B�܂�ŊR��������Ă���悤�����A���̑����ɂ͖��V�a�҂̂悤�ɖ������Ȃ��v�\�\����͖��s�A�j�X�g�A�A���t���b�h�E�u�����f���i1931�|�j�̌��t�ł���B�u�V���[�x���g�̉��y�͎�����i����v�ƌ��������c���q�i1948�|�j�Ƃ����A�ꗬ�̃A�[�e�B�X�g�̌��t�͂����ܒ~���[�����ʔ����B����͎�������������Ă������Ƃł͂��邪�A�Βk�Ƃ�����ɂ����āA���y�]�_�Ƃ͂������Ȃ�Ƃ��ɂ��ނ牉�t�Ƃɂ͓G��Ȃ��B�Ⴆ�A�ߋ��́u���R�[�h�|�p�v���㓙�ł́A���c���q�ƑO�c���Y���A���i�z��Y�ƌ̍��c���ꎁ�ȂǁA������ł���B�]�_�Ə����������炪����Ă����x���̍��͗�R�Ƃ��Ă���B���t�Ƃ͍�Ȏ҂̈ӌ���T�����y����ǂ݁A�Z�p�����y��n������B���̍˔\�Ɠw�͖͂}�l�Ƃ͂������ꂽ���̂�����̂�����A���x��������ē�����O�ł���B�܂��A���y�]�_�ƂȂ���̂́A�����}�l�ƔF�����邱�Ƃ���n�߂�ׂ����i�����F�߂����Ȃ����番�������t��������A������ʔ����Ȃ��̂��j�B�������A�A�[�e�B�X�g�ƑΓ��ɓn�荇���邽�߂̌P���E�w�͂����ׂ����B�A�[�e�B�X�g�Ƃ͕ʎ����ł̓w�͂��B���̈�́A�y�Ȃ̐����ߒ���T������ȉƂ����߂鉹�y�̗��z�`�������Ȃ�ɍ��グ�����Ɓi�����Ɋy�Ȃ̍\����c�����邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����j�B���Ȃ�X�e�b�v�́A�`���������z�`�����t�@�����X�Ƃ��āA�\�Ȍ��葽���̉��t������Ŏd���������邱�ƁB�����_���ɉ������Ă��N�^�̉��t�Ɣ��ʂł��邭�炢�ɁB�����A���ꂾ���͔ނ�ɂ͐�ɏo���Ȃ����ƂȂ̂��B�y���ƑΛ�����Ȏ҂̈Ӑ}���������A�����\�����邽�߂ɋZ�p���l�ԗ͂����߂邱�Ƃ��A�[�e�B�X�g�̎d���Ȃ̂�����A�����Ȃ̕ʉ��t��10��20���ËL����قǒ������ގ��Ԃ����������낤�͂����Ȃ����炾�B
�@���y�͊y�������Ċy���ނ��̂ł͂Ȃ��B�A�[�e�B�X�g�̉��t�s�ׂɂ���ĎY�ݏo����鉹���ď��߂Ċy���ނ��Ƃ��ł���B�A�[�e�B�X�g�͊y����ǂݍ�҂̈Ӑ}�����ݎ���̋Z�p��p���ĉ��t����B����������A���߂ƃe�N�j�b�N��p���āA�ÂȂ�y���ɖ��𐁂����ނ̂��B���߂ɂ͒m���Ɠ��@�͂��A�e�N�j�b�N�ɂ͕s�f�̌��r���s���B������A���t�s�ׂɂ͑S�l�i�����f�����̂��B���t�҂ɂ���ĉ��y���Ⴄ�̂͂��̂��߂��B����������A���t�ɂ���č�ȉƑ�������Č����Ă���̂��B������A�����Ƃ������t����́A��Ȏ҂̐l�ԑ������m�ɓ`����Ă���̂ł���B���ꂪ�N���V�b�N���y�̖{���ł���A���t�̈Ⴂ����邱�ƁA���Ȃ킿�A���t�̒��ɃA�[�e�B�X�g�̐l�ԗ͂�������邱�ƁA�����ē����ɍ�ȉƂ̐l�ԑ������邱�ƁA���ꂪ�N���V�b�N�����Ƃ̑傫�Ȋy���݂̈�Ȃ̂ł���B�u���y�̒��ɐl�Ԃ�����v���B
�@�A�[�e�B�X�g�����X���̂ɂ��ނ悤�ȓw�͂����č��グ�����t�����������ׂ��ĂāA����͂����A����͂����A����͂����A����̓_���E�E�E�ȂǂƏ���ɂق����Ă����X������́A�Ȃ���ґ�Ŏ���ɂ܂�l�ԂȂ̂��낤�B���ɂ����g���Ȃ̂ł���B�����炱���A�w�͂��Đ^���Ɏ��ɓ�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���{�̕]�_�Ə����ɂ́A�����Ȃ�̗��O�������A�\�͂��^���ɉ��y�ɑΛ����Ă��������������������B�R��_���Y���́u�����̎���v�ւ̐[�����w��u�J���V���[�̎�L�v�ɂ�����|��̂��܂��A�쑽�����~���u�V���[�x���g�v�ł̑��p�I���_����̌����ȍl�@�A�ЎR�m�G���̉s�����t�]�A�����r���̔��͂��镶�́A�F����F���̓Ǝ��̔��w���犴�m���閼���]�A�Έ�G���̏_��ʼns�����@�͂��琶�݂��������̐[�����[�c�@���g�_�Ɖ��t�_�A���ы`�����̃o�b�n�l�ɂ�����X�g�C�b�N�Ȃ܂ł̎��ؐ��A�ʐ��E��{�R�I�v�y�����̐��I�m���ՂɌ���Ă����\�́A�̌ܖ��N�S�Ɛ����v�ɋ��ʂȊi��������ł��E�E�E�E�ȂǂȂǁA�F�����đf���炵�����X�ł���B���ʂ����łȂ����X�����Ȃ��炸����������B���́A�����łȂ����X���u���Ȗ����K�C�h�v�Ȃ���̂Ɍg���P�[�X�����X���邱�Ƃ��B�����̓N���V�b�N���D�҂̑啔�����ӖړI�ɃA�e�ɂ�����̂ł��邩��A�]�ҁE�I�҂̕��X���C�����������ƁA���ɍߍ��Ȃ��ƂƂȂ�̂ł���B������A�y�ȒT���Ɖ��t�����r�ׂ̘J��ɂ��܂��ɁA�^���Ɏ��g��ł������������̂��B�����āA"���̎��_����̃��b�Z�[�W"�������ɂ�������͂��Ă������������B��������A���y�L���▼�ՑI���k��A�[�e�B�X�g�E�C���^�r���[���������Ƃ����Ɩʔ����Ȃ�Ǝv���B�܂��A�����Ȃ�Ȃ��Ă��A���Ƃ��ẮA�}�l�Ȃ�ɁA��������X�Nj����Ă䂭���Ƃɕς�肠��܂��B
�@ �@�����ŁA����́A�O��́u�V���[�x���g �\�i�^��21�ԁv�Ŏ��グ���Ȃ������u�����f���ƃ|���[�j�i1942�|�j�ɂ��ď������Ă������������B���R�́A�u21���I�̖��Ȗ����v�́u��21�ԁv�ɂ����āA��2�ʂ��|���[�j�A��3�ʂ��u�����f���i��P�ʂ͑O����グ�����q�e���j�ł��邱�ƁB����ɁA��l���^�����Ă��鋤�ʂ̊y�Ȃ����������邽�߉��t��r�����Ȃ�y���߂���������ł���B
�i�Q�j�g�c�G�a���̒����V���u���y�W�]�v�ɂ����Ĉꌾ
�@�u�����f����2008�N�Ɉ��ނ����B�킪�����y�]�_�E��̏d���E�g�c�G�a���́A2008�D7�D23�t�����V���u���y�W�]�v�ŁA�u�����f���̈��ނɂ��ď����Ă��邪�A���̒��Ń|���[�j�̂��Ƃɂ��G��Ă���̂ŁA����̃e�[�}�ɕ�������B�܂��́A���̃R����������肽���B
�@�E�B�[���ɂ����g�c���́A�؍݂��Ă���z�e�����A���މ��t���s���̃u�����f�����ʂ蔲���A���̔Ӊ��t����s���y�F����z�[���̂ق��ɕ����Ă��������Ƃ�`�������B�u�����ƁA���ԂɃV�����A�C���������Ċy������ꂽ�傫�ȃJ�o��������A�����L�w�̒��g�������߂ĕ����Ă������ɂ������Ȃ��v�Ƃ����`�ʂ�����A�u�����f���͒����Ȃ��������A���̗��X���|���[�j�����Ƃ���B�u�����ސ�p�̊y��炵���s�A�m�̉��̂��ꂢ���������ƁB�O���̓V���p���̖��Ȃ�����B�㔼�̓h�r���b�V�[��O�t�ȏW���P���S���B�ǂ������������������ꂢ�ȉ��̂����ς��l���������ȉ��t����B�A���R�[���̉��Ȃ����ꎅ����ʖ����̘A���v �ǂ�ȉ��t���������m�肽�����ɂƂ��ẮA"�����ȉ��t""�����̘A��"�Ƃ������ۓI�\����"�������ꂢ"�ƒN�ł������N�ł������钮����̂��Ƃ������Ă��邾���ŁA������Ȃ����ƚ삵���B
�@�����āA���{�ɋA���Ă�����A�u�����f���̈��ދL�O8���g�̃T���v��CD���͂��Ă����Ƃ̂��ƁB�����ŁA�E�B�[���Œ����Ă�������̃|���[�j�ƕ����r�ׂāA���҂̉��̔�r�_��W�J���Ă���B�����Ă�������̃|���[�j�ɂ�"�������Ă��Ώ�݂����ɉ����̂��������"�Ə��X�̔�g�I�C�����t�����B�u�����f���́A8���̒�����u�x�[�g�[���F���F�s�A�m���t�ȑ�4�ԁv�����グ�āA�u�A�e�̐[�݁A���n�F�̃p�[�X�y�N�e�B�u�̒��ł̌`�Ԕ���`������̂�����B�x�[�g�[���F���̉��̐[���A���s�������ǂ邤���ɘ����Ɍ����Ă��閾�Â̊��w�ɂ��d�Ȃ������̖��킢�B����͂��������������y�Ȃ̂��B�����͉��y�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���y�͉����Ɏn�܂艹���ɏI�����̂ł͂Ȃ��v�Ə����Ă���B����͈�̂ǂ��������ƂȂ̂��B �܂��A���ɁA�u�����f���́u��4�ԁv�́A���ނ��^�������邪���̂����̂ǂ�Ȃ̂��������ĂȂ��B�������t�҂ł��A���t�͑��X���݂ȈႤ�A�Ƃ���CD�ӏ܂ł͓�����O�̊�{���炢�������Ă����Ăق������̂��B"�A�e�̐[�݁E�E�E���`�Ԕ���`����"���Ăǂ��������ƁH"���̐[���E�E�E�����ǂ邤���Ɍ����Ă��閾�Â̊��w�ɂ��d�Ȃ������̖��킢���A�����������y"���Ăǂ������Ӗ��H�@�T�b�p��������Ȃ��B���_�́A���������������̃|���[�j��艹���������y�����u�����f�����f���炵���Ƃ������Ƃł����H �Ȃ�Ύ��������ӌ��Ȃ̂Ŋ������̂ł����E�E�E�B
�@�����āA�Ō�ɂ͂�������ł���B�u�u�����f���͍̂s�V���ǂ������ł͂Ȃ��A�ނłȂ���Ȃ�Ȃ����̂����Ă����B���́A����ƁA���ɂȂ��ċC�������Ƃ���v ���ɂȂ��ċC�Â��Ă��������̂͌��\�ł����A"�ނłȂ���Ȃ�Ȃ�����"���ĂȂ�Ȃ̂ł��傤���H �c�O�Ȃ���A���̐������Ȃ���Ȃ��܂I����Ă���B���̕��͂����������Ă͂���Ȃ��B����̐S����X�g���[�g�ɘb���Ȃ��B�������́A�����������Ƃ�m�肽���̂ł����E�E�E�B
2010.03.21 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��14�`���c���q�̐����V���[�x���g2
�i�R�j������i���鉹�y�@�O��́A���c���q�̒e���s�A�m�E�\�i�^��19�Ԃ�20�Ԃ̒��ɁA���ɜ߂��ꂽ�V���[�x���g�������B����́u��21�ԁv�̒���"������i���鉹�y"��T�肽���B
�@�u�s�A�m�E�\�i�^ ��21�� �σ����� D960�v�̓V���[�x���g�Ō�̃s�A�m�E�\�i�^�ŁA19�ԁA20�ԂƋ��ɁA���̔N1928�N9���Ɉ�C�ɍ�Ȃ��ꂽ�B�e�X���i�̈Ⴄ���𗧂đ�����3�������グ�Ă��܂��V�˂́A1788�N8���A3������ȁi��39�ԁ\41�ԁj����C�ɏ����グ�����[�c�@���g�ɂ������o���Ȃ��B���c�́u���[�c�@���g�ɂ͓V���̃o�����X���o�����邪�A�V���[�x���g�͉��Ă���v�ƌ������A����͓�l�̋��ʓ_��F��������ł̘b���B����A�X�s�[�h�A�|�p���A�V���̃����f�B�X�g�A��܂ȂǂȂǁA�ނ��l�ɋ��ʓ_�͑����B�V�˂͓V�˂�m��Ƃ������Ƃ��낤�A�V���[�x���g��19�̂Ƃ��ɏ������ŏ��̓��L�ɂ͂���ȕ��͂��x���Ă���B
���邭���ꂽ�A���̔��������́A�l�̐l���̍Ō�̓��܂ł��̂܂c�邾�낤�B�͂邩�������炩�����ɁA�܂�Ŏc���̂悤�ɁA���[�c�@���g�̉��y�̂��̖��@�̂悤�ȉ��F���A�܂��A���̒��ɖ苿���Ă���B�����̔�������ۂ̒f�Ђ́A�l��̍��̒��ɂ��܂ł��c��A�����o���������ς���Ă��A�����Đ@�������邱�ƂȂ��A�l��̓��X�̐����Ɍ���Ȃ����b��^�������邾�낤�B����͂��̐l���Ƃ����Í��̂������ɂ����āA�l�����ɁA�l�������m���Ɋ��߂Ă����̂������ȁA���邢�A�������y���������w�������Ă������̂��B�������[�c�@���g��A�s�ł̃��[�c�@���g��A�������Ƒ����́A�������Ɩ����ɑ����́A���̂悤�ɘ����Ȃ��ǂ����̌b�[���͎ʂ��A���Ȃ��͖l�����̍��̉��[���ɍ��݂��Ă������Ƃ��낤�B�@����́A���[�c�@���g�́u���y�d�t�� ��4�� �g�Z�� K516�v����1816�N6��14���̓��L���B�u���[�c�@���g�̉��y�́A���̉��[���ɍ��ݍ��܂�āA�����o���Ă��@�������邱�Ƃ͂Ȃ��B���̐l���Ƃ����Í��̒��ŁA�y�������̔�������]���w�������Ă����v�ƌ����Ă���̂��B�ނ�19�ŁA���[�c�@���g�̌��Ƌ��ɁA���łɂ��̐��ɈÍ������Ă����̂��I �܂��A���̋ȁA�`���C�R�t�X�L�[�������ė܂������Ƃ��`�����Ă��邵�A���яG�Y�����p�����A�����E�Q�I���́u��������߂��݁vtristesse allante�����̋Ȃ��Ă̂��̂��BK516�͐l�ɋ���Ȉ�ۂ�^����ȂȂ̂��낤�B
�@�ł͖{��ɖ߂��āA���c���q�̒e���u��21��D960�v���Ă݂悤�B�`���A���₩�ȑ�P���̒���A���ቹ���s�C���ɋ����B������V���[�x���g�̖��Ȃ̂��H ���c�̏����o�������ɂ͗]�l�Ƃ͈Ⴄ�[����������B�������A���c�͂��������ȊO�ɖ��͈�������Ȃ��B���̂��Ƃ͒��ւ̃u���b�W���o�Ă̌J��Ԃ��ƍČ����Ō���邾�����B�₪�Ď�X�Δ�̈ӎ��̂Ȃ��D���ȑ�2��肪�����B���͂₻���ɂ̓V���[�x���g�����̕����Ŕ������̐��E�����邾�����B���Ƃ�4�F53�|55�A���y�W�I�i���U�a���j�̗D�����^�b�`�͂ǂ����B���̒��J�ɌJ��o�����ꉹ�ꉹ�����܂��Ɏ����ݍ��ގ����݂̃t���[�Y�ł���B�W�J�������ʂ͑������A�����ɂ͂��͂�D959��2�y�͒��ԕ��Ɍ�����悤�Ȗ��ɜ߂��ꂽ�V���[�x���g�͂��Ȃ��B��2�y��Adagio��������BABA'�̎O���`�������A���̊y�́A����܂ł��ƒ��ԕ�B�Ɍ�����邱�Ƃ��������A�����ɂ͂Ȃ��B��ꂻ���Ɋ낤������Ǘ���͌����đ���Ȃ��B���炩�ȗ܂Ƃ����悤���B�����āAA'�ł͈���̌����������ށB�d�n�Z�����瓯�������ֈڍs����78���ߖڂł���B���c�̂��̕����́A���������m���Ȍ����������ނ̂ł���B�_�X��������̔��������B���c���q�͐l��{�l�������āA�V���[�x���g�̍Ō�ɂ��čő�̌���\�i�^�Ɍ������Ă���B��Ȏ҂ɑ��鈤��ƈ،h���A�����ȒT���S�ƕs�f�̓w�͂�ʂ��āA�������n�̕\�����������Ă���B�����A�����炭�A�ޏ��͂܂��A����̕\���ɖ������Ă��Ȃ����낤�B�Ƃ������A�\���҂Ƃ����̂͏�ɖ������邱�Ƃ̂Ȃ��T���҂ł���A���ꂪ�\���҂Ƃ��Ă̏h���ł��邱�Ƃ�m�o���Ă���ɈႢ�Ȃ��B������A�����A�ޏ����e���V�����u��21�ԁv�������邩������Ȃ��B���Ɋy���݂ł���B��X�͒��C�ɂ��̂Ƃ���҂Ă����B�C�y�Ȃ��̂��B�ł��A����菭���͐������Ă������Ɗ肤�B���ꂪ�A��簂ȉ��t�s�ׂ��������ׂ��A�}�l�̍l���y�Ȃ��r�����Ȃ��w�͂��������Ă���^�̌|�p�Ƃɑ���A���߂Ă��̗�V�ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B
�@�ł́A���̊y�ȁA���̃s�A�j�X�g�͂ǂ�ȉ��t�����Ă���̂��낤���B��2�y�͂𒆐S�ɍl�@���Ă݂�B
�@�܂��A���ՃK�C�h�̃X�^���_�[�h�E�u21���I�̖��Ȗ��Ձv�i���R�[�h�|�p�ҁj�ő�P�ʂɋP�����q�e���i1915�\1997�j���Ă݂悤�B�^����1972�N�B���͂��̉��t��NG���B��2�y��65���߂����A'�����A�������獶��́A��ł��ŃX�^�J�[�g�ɂ��3�A����ł��o�����A���q�e���͂��̉��`����ɑł�������B���ɕ��X�����������B���c������"������i����"�ǂ��납�A�ނ���_�o�ɏ��C������B�����炱��ɑ���78���ߖڂ̈���̌����ɂ̒����B����ȏ�ɍ����̂͑�1�y�͗�̃A���y�W�I�ł���B���q�e���͂���9����җ�Ȑ����Œe������B���ɋP�����͂����邯��ǁA�V���[�x���g�ɂ͑e��ɉ߂���B���c�̑n������@�ׂȉ����E�Ƃ͑ɂɂ��鉹�y�Ƃ���˂Ȃ�܂��B"���ꂪ���̕\�����B���傪���邩�I"�ƌ��������܂ł����A���́A����̓V���[�x���g����Ȃ��ƌ����肽���B���̉��t�����Ђ��閼�ȃK�C�h�œ��X�̑�1�ʂƂ͑S�������ɋꂵ�ށB���y�̊������͐l���ꂼ�ꂾ����Ƃ₩�������C�͂Ȃ�����ǁA����ɂ��Ă��A���q�e���ɕ[�𓊂���8�l�̕]�_�Ə����́A��̂ǂ����������������Ă���̂��낤���A�r���^��ł���B�N�����m�u�i�����ƃ��q�e���v�ɂ����������A���{�̉��y�]�_�Ə����́A�����ƒ����Ă��牉�t�]�������Ă���̂��낤���B����ȃ��V�A�̖�l���͔C���ɒe���Ă��镗�ȉ��t�̂ǂ��������Ƃ����̂��낤���E�E�E�B�f���Ă������A���͉����A���q�e���̑S�Ẳ��t��ے肵�Ă���̂ł͂Ȃ��B���X�g��t�}�j�m�t�̃R���`�F���g�ȂǁA����͑f���炵�������ł���B�����A�ނ̃V���[�x���g�u��21�ԁv�͗e�F�ł��Ȃ��̂ł���B
�@�O�����E�O�[���h���A1957�N�Ƀ\�A�Ń��q�e���́u��21�ԁv���āA�����������������B�u�Ö��p�ɂ��g�����X��ԂƂ����Ⴆ���Ȃ��悤�ȋ��n�Ɏ��͘A�ꋎ��ꂽ�̂ł��v�iWikipedia���j�ƁA�܂��A��������݂̂Ƃ�����Ԃł���B���̂Ƃ��̉��t�Ƃ��ꂩ��15�N���o��CD�Ƃ���ׂ�̂͂��͂�s�\�����A���߂ɂ���قǑ傫�ȈႢ������Ƃ͎v���Ȃ��B������A���̃G�s�\�[�h�͎��ɂƂ��āA���y�̕s�v�c�A�l�ԂƂ������̂̕s���������������Ă���鎖��ł͂���B
�@���I���E�t���C�V���[�i1928�|�j�Ƃ����A�����J�l�s�A�j�X�g������B�Ⴍ���Ė��������A�W�X�g�j�A�������E�肪�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�Ȍ�A���肾���̉��t�𑱂��Ă������A�ߔN�{�g�b�N�X�Ö@�ɂ���ĉE�肪�A2004�N�uTWO HANDS�v�Ƃ����A���o���ŃJ���o�b�N�����B���̃A���o���̃��C���y�Ȃ��u�\�i�^ ��21��D960�v�Ȃ̂ł���B���̉��t�͑f���炵���B���̈ꗱ�ꗱ�����������Ƃ��āA�������[�X�ɗD�������h���Ă���B���y�����т��ȑS�̂ɖ������Ă���B�ނ�1956�N�ɂ����̋Ȃ����R�[�f�B���O���Ă��邪�A����Ɋr�ׂ�ƁA���y���}�g�𑝂��i�i�ɐ[�����Ă���B�����I���u�Ă��A���̐l�������e����Ă���B�������A���̕\���`���u�\�i�^��21�ԁv�ɃW���X�g�E�t�B�b�g���Ă��邩�Ƃ����ƁA�K�����������Ƃ͎v���Ȃ��B���F�͑S�̓I�ɂ�▾�邷���邵�A��1�y�͂̃A���y�W�I�́A���c�̕�ݍ��ނ悤�ȗD�����Ƒ@�ׂ��ɂ͋y�Ԃׂ����Ȃ����炾�B
�@�z�����B�b�c�i1903�|1989�j1986�N3���̘^�����Ă݂�B���������ċg�c�G�a���Ɂuᯂ̓����������i�v�ƕ]���ꂽ3�N��̉��t�ł���B�������ɔ�ׂ�ƁA��������������A���݂Ńs�A�j�X�e�B�b�N�ɉ��y�����Ă���̂͗��z�����B�b�c�Ƃ������������A�t���[�W���O�̗֊s�̊Â��͂�����Ƃ�����A�l�����i���i���j�Ɍ�����͔̂ۂ߂Ȃ��B��������̋Ȃɂ͑��������Ȃ��B�ނ̃V���[�x���g�̃\�i�^�̘^���͑�Ϗ��Ȃ����A�u��21�ԁv�́A���̂ق��ɂ��A1953�N�J�[�l�M�[�E�z�[���ł̃��C�u�^�����c����Ă���̂ŁA���C�ɓ���̋Ȃ������̂��낤�B�ނ͂܂��A��ȉƃV���[�x���g�ɂ��Ă���^���Ă���B�u���X�g�E���}���e�B�b�N�v�Ƒ肳�ꂽ1985�N�̃A�����J�̃e���r�ԑg�̒��Łu�V���[�x���g�̉��y�͓V�g�̉��y���B�x�[�g�[���F���Ȃꉹ�����ď����₵�Ȃ��v�ƌ����Ă���̂��B���������̒��ŁA�u�Z���i�[�h�v���̂��Ȃ���u�w�A���F�E�}���A�x�͂܂��ɓV�g�̉̂��v�Ƃ��A�u�O���[�g�v�̑�2�y�̓��C�������������݂Ȃ���A�u�w�������x���������v�Ȃǂƌ����Ă���̂́A���ΓV�˃z�����B�b�c�Ȃ�ł͂̂����g���B
�@ �@���c���q�́A�V���[�x���g�̉��y�����ɜ߂���Ȃ�������ɂ͎�����i�����Ɏ��������Ƃ����m�����B�����āA���̂��Ƃ̐������킩���Ă���B������ޏ��̃V���[�x���g�ɂ͎����ƈ،h�����R�Ɵ��݂łĂ���̂��B���̔N�̉B�ꂽ�����u3�̃s�A�m�� D946�v�ɂ��A����ȓ��c���������܂܂̃V���[�x���g�̉��y�����R�ɂ����₩�ɗ���Ă���B���2�� �σz�����v�A�����ɂ͋A�藈�ʎႫ���ɓ��������ĐÂ��ɘȂ�31�̃V���[�x���g������B
2010.03.11 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��13�`���c���q�̐����V���[�x���g1
�i�P�j���c���q�V���[�x���g������@�u���ǁA���ɜ߂��ꂿ����Ă��܂�����A���̐l�́I�ŏ�����Ō�܂ŁA������I�v�B����̓��R�[�h�|�p1997�N12�����A��V���[�x���g�Ɖ��y������Ƒ肵���Βk�ŁA�s�A�j�X�g���c���q�����������t�ł���B���̐l�Ƃ̓V���[�x���g�̂��ƁB1997�N�Ƃ����A�V���[�x���g���a200�N���B������͕]�_�Ƃ̑O�c���Y���ł���B
�@���̌��t���o�Ă���O�i�K�̓�l�̂��Ƃ��H��ƁE�E�E�E���c�u�V���[�x���g�ƃx�[�g�[���F���͎d���Ƃ��ē����i�s�ł��邪�A���[�c�@���g�Ƃ͏o���Ȃ��B���[�c�@���g�Ƃ����l�́A�ǂ�ȏꍇ�ɂ������ȃo�����X���o�������Ă����v�B����ɑ��O�c���́u�V���[�x���g���n�Ƀo�����X���o�������Ă����B�x�[�g�[���F���I�_�C�i�~�N�X�Łw�撣�����x���A����ɂ͂�͂���̃o�����X�ɋA���Ă䂭�v�B����ɑ��A���c�́u�ł�����A�o�����X����Ȃ��Ǝv���B���S�ɔj�ꂿ����Ă��܂�����A���̐l�v�ƌ����B�����Ė`���̌��t���o�āA���ɑ����B
�@�u�x�[�g�[���F���́A��������ł���l�������Ă����B���[�c�@���g�̏ꍇ�͂ˁA�ނ͐S���Ƃ��Ă��D�����āA�����Ĕނ͍ߐl�Ȃ́B�������ߐl�ŁA������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ɉ��x�����������Ƃ̂���l������A�w�ӂӂ�I�ق��I�x�ŋ����Ă����B�ŁA�V���[�x���g�͂Ƃ����ƁA�{���ɕs�v�c�ȂقǓ����ȐS���������l���Ǝv���B�Ⴂ�Ƃ�����ނɂ́A���̐��E�Ƃ������A���̐��E�\�\�V������Ȃ��āB���ꂪ���������������ł��B���ꂪ�A���鎞�A�z���͂̐��E����Ȃ��āA�����̂��̂ɂȂ��Ă��܂��A���ꂪ�N�����āB�������N�����Ă���̃V���[�x���g���A�ς��̂ˁB�����A���̋ꂵ�݂ŏI���Ȃ��B���݂ŏI���Ȃ����ƁB���̒��ɓ������Ă�B�������������邱�Ɓ\�\�����čŌ�̍Ō�ɔނ��������邩�Ƃ����Ɓ\�\�ǂ̍�i�łƂ������Ƃ͌����܂��ǂˁ\�\�B�����ƁA����A�F�߂�̂�����ł��������A�����Ƃ��ĔF�߂āA�������y��������i�����悤�ɂȂ�́B���ꂪ�킽�����A�V���[�x���g�̑債�����ƂŁA�ق�Ƃ��ɐS�ɑi���闝�R�́A��ԑ厖�Ȃ��̂���Ȃ����Ǝv���v
�@�{���ɐ������t���B���c���q�́u�V���[�x���g���������ʂȍ�ȉƁv�ƌ������Ă͂���Ȃ����A�����ɂ��A�i�V���[�x���g������Ƃ͂����j���ꂪ�ɂ��ݏo�Ă���B�V���[�x���g�͖ܘ_�A3�l�̊y���̖{����˂��Ă����܂Ō����ɕ`�����������t�𑼂Ɏ��͒m��Ȃ��B
�@���c�́u���ꂪ�N�����āA�V���[�x���g�̉��y���ς�����v�Ƃ����B�u�����v�Ƃ́A�~�łւ̜�a�̂��ƁB���̊��������̓V���[�x���g25�A1822�N�̔N��������Ƃ����Ă���B�����āA���o�Ǐo����A1823�N5��8���A�ނ͂���Ȏ��������B�u����A�łڂ���Đo�̒��ɁA���\�L�̋��̊l���ƂȂ��āA�킪�l���̋]���̓��́A�i���̖v���ւƋ߂Â��Ă䂭�B����f�āA�����Ď����g��łڂ��A���ׂĂ�Y�p�̉͂֓˂����Ƃ��A�������Ĉ�̐����͋������݂��A�����̑�Ȃ���̂�A�i���ɉh����Ƃ������邩��v�ƁB�����āA��1824�N3��27���ɂ́A�u�l�̑n��o������i�́A���y�ɑ��闝��͂ƁA�����Ėl�̋ꂵ�݂ɂ���đ��݂��Ă���B�ꂵ�݂������n��o�������̂́A���̒�������邱�Ƃ��ł��킸�����Ǝv����v�Ɠ��L�ɏ����B
�@�����ɂ́A���Ɏ���a�����o�����V���[�x���g������B����Ȏ�����łڂ��āA�͋����̑�Ȃ��̂�n�����悤�Ƃ���V���[�x���g������B�����Ȃ�������ɂ́A�ꂵ�݂��特�y��n��o�������Ȃ��̂�����ǁA���ꂾ���ł͐l�Ɋ��ł��炦�Ȃ����Ƃ�m���Ă���V���[�x���g������B���ꂪ�A���c���u���ɜ߂��ꂿ����Ă���V���[�x���g���A�Ō�̍Ō�ɁA���Ƃ������̂������Ƃ��ĔF�߁A���y��������i����悤�ɂȂ�v�Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����B�ޏ��́A�u�ǂ̉��y���͌���Ȃ��v�ƌ����B�������낤�A������Ă͂���Ȃ����낤�ȁB�u���Ă��A�u����͂��Ȃ��������邱�Ƃ�v���ĂˁB���ɜ߂��ꂿ����Ă��鉹�y�Ƃ́H������i���鉹�y�Ƃ́H ���c���q�̒e��1828�N�̂R�̃\�i�^ D958�A959�A960���炻����T��邩�E�E�E�i���R�[�f�B���O��1997�N�A��L�Βk�̏����O�ł���j�B
�i�Q�j���ɜ߂��ꂿ����Ă��鉹�y
�@�܂��A�����������̂́A�u�s�A�m�E�\�i�^ ��19�� �n�Z�� D958�v��2�y�� Adagio�B���̋ȂƎ��� D959 �́A�悭�x�[�g�[���F���I�i�x�[�g���F�j�A�[�i�j�ȍ�i�Ƃ�����B��2�y�͕͂σC�����ŁA�咲�n�Z������̕ω��́u�^���v�̂���Ɠ������B�h�i�ȋF��̂悤�ȉ��y�̗��ꂪ�A���s�C���ɕω�����U���ɂ��߂��ꂽ����Ɂu�^�^�^�v�Ƃ����ٗl�Șa���̋��ł��o������B2�F34��2�F40�̓�ӏ��B�����̐S�ꂩ�琁��������悤�ȁA�������˂�������悤�ȏd�����x�ȓ��c�̘a���B���̕������̐l�͂ǂ�Ȓe���������Ă���̂��낤�B�u�����f���ŕ����Ă݂�B�|���[�j�ŕ����Ă݂�B���ʂ̋��ł��B���c�̂͑S�R�Ⴄ�B�d�݂��Ⴄ�B�����������Ă���B���̘a���ɂ͋���L���Ƃ��ăt�H���e���X�t�H���c�@���h ������ ���t���Ă���B����3�A���u�^�^�^�v�́u�^���v�̏ے��ŁA���̂�������x�[�g�[���F���ւ̃I�}�[�W���ƌ���̂��낤���A���c�͊m���ɂ����ɑ��l�ƈႤ���̂����Ă���B�ޏ��͂����ɃV���[�x���g���������Ă���B�I�}�[�W���̌������Ƀx�[�g�[���F���Ƃ̌��ʂ����Ă���B
�@���́u�s�A�m�E�\�i�^ ��20�� �C���� D959�v��2�y�� Andantino �ł���B�����I�Ȏ�肪�������Ƃ��������Ői��ł䂭�B�ǂ����x�[�g�[���F���̑�7�����Ȃ̑�2�y�� Allegretto ��z�N������B�V���[�x���g�� Moderato ���͂���ő��������� Allegretto �Ƒ��Ȃ��x�������� Andantino ��I�̂��B
�@���ԕ��ɓ���Ƃ������Ƃ������݂��A���X�ɏ㏸���~�̌��������`�ɕς���Ă䂭�B���̌����̒��ɂ͊m���ɖ��ɂƂ�߂��ꂽ�V���[�x���g������B�����Č����������_�ɒB��������̐Â����̒��A4�F52�A5�F04�A5�F10�ɍēx�����������B����L���͂܂����� ������ �� �� ���B�K���ɑς��Ă����S�̒ɂ݂��A��C�ɕ��o�������Ă��܂������̂悤���B���̒��ԕ��A�u�����f������͔ߒɂ����`����Ă��Ȃ��B�|���[�j������Ȃ�Ɍ��������A���c�̕\���ɂ͋y�Ȃ��B���c�ɂ͗܂����邪�A�|���[�j�ɂ͂Ȃ����炾�B�啔�̉̂킹�����n�G�̂悤�ȓ��c�̃J���^�[�r���ɋy�Ȃ��B
�@���{�l�̓��c�����[���b�p�̃s�A�j�X�g���V���[�x���g�̐S�̒ɂ݂��������Ă���B���̐l�Ȃ�V���[�x���g�̂��Ƃ�"���̐l"�ƌ����Ă������B����͂܂��ɓ��{�l�̌ւ肾�B����Ȃӂ��Ɏv���B
2010.02.24 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��12�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�C
[�A�C���V���^�C���uin����v���p�̓^��]�@���̂Ƃ��뒷���ɂ킽����グ�Ă��� Credo ���́A�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���uin����v�̊Ԉ�������p�����[�ł����B�x�[�g�[���F���u�����~�T�ȁv��B��̗�O�Ƃ��āA�Í��̃~�T�Ȃ� Credo �͂��ׂāA�u����v�ɑ��Ắuin�i�V�v�ł����B���̔��[�͢�j�P�A�R���X�^���`�m�[�v���M���v�ɂ���Ƃ̌������Ȃ�Ƃ��w�E���邱�Ƃ��ł��܂����B�����A�u��P�R���X�^���`�m�[�v������c�v�J�Â̖ړI����A�̑����ꂽ�u�j�P�R���v�͢����v�O�҂Ɠ���Ɉ������Ƃ�ǂ��Ƃ��Ȃ������B�����Ă��́u�j�P�R���v���u�~�T�ʏ핶�v�� Credo �Ƃ����`�Ŏ��܂����E�E�E�Ƃ����̂����̏o�������_�ł��B�ł́A���̃A�C���V���^�C���́A����܂ň�x���g���邱�Ƃ̂Ȃ�����"�u����v�ɑ��� in"�����p�Ŏg���Ă��܂����̂ł��傤���B����́A���������ĕ�����܂���B�ނ̓��_���l�Ȃ̂ŁA�J�g���b�N�́u�~�T�ʏ핶�v�ɂ͓���݂��Ȃ��������炩���m��܂���B�܂��A���e����ɂ����\���������Ƃł��傤����A�ȑO�l�@�����悤�ɁA���@��uin ����v���K���ł��邱�Ƃ�m���Ă��āA���ӎ���"���@�I�ɐ������`"�ŋL���Ă��܂����̂�������܂���B
�@����Ȑ܁A���C�Ȃ����ы`�����̒��ɂȂ�u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�i�t�H�Ёj��ǂݕԂ��Ă�����A�����Ƌ������߂Ƀu�`������܂����B�����278�y�[�W�ɂ���܂����B
�o�b�n�́E�E�E�EEt in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam �Ƃ����̎����ȗ������A�ނ��뉹�y�I�ɋ������Ă���B�@�Ȃ�ƁA�A�C���V���^�C���ƑS�������uin ����v�̈��p���Ȃ���Ă���ł͂���܂��B����������́A�i�D�r�D�o�b�n�́u�~�T�ȃ��Z���v�Ɋւ���L�q�Ȃ̂ł����犮�S�ȊԈႢ�Ƃ�����B�Ȃ��Ȃ�A�u�~�T�ȃ��Z���v�́uin �i�V�v�ŏ�����Ă��邩��ł��B���ю��Ƃ́A�ȑO�A�o�b�n�Ɋւ���^��_������肵�����Ƃ�����̂ŁA��������ʂŎ��₵�Ă݂܂����B�����͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
���ы`���l����ɑ��āA���ю�����Җ]�̉������Ă��܂����B2��5���̂��Ƃł����B
�C��̕ϓ����������������̍��A�@�����߂����ł��傤���B���́A2�N�قǑO�AJ�DS�D�o�b�n�́u�~�T�ȃ��Z���v�Ɓu�t�[�K�̋Z�@�v�ɂ��܂��āA�₢���킹�����Ă������������̂ł��B���̐߂́A���J�Ȃ邨�Ԏ������������A���ɗL��������܂����B
���̓x���A�搶�̒��ɂȂ�u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�Ɋւ��鎿�₪�����܂����B���萔�Ƃ͑����܂���������낵�����肢�\���グ�܂��B
�Ꮏ���
�搶�̒���ł���u�o�b�n�`���̓��ǂ��v278�y�[�W��
�i�O�j�o�b�n�́E�E�E�EEt in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam �Ƃ����̎����ȗ������A�ނ��뉹�y�I�ɋ������Ă���B
�Ƃ������L�q������܂��B
���̈��p���ꂽ���e����̕����ł����A�u�~�T�ȃ��Z���v�ɂ����܂��Ă� Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam �ƂȂ��Ă���Ain �Ƃ����ꂪ����܂���B����͕������킹������y���ォ����ԈႢ�������܂���B
������@�ɂ��̕��������������ʁA
�E�uCredo�v�̌��ł���u�~�T�ʏ핶�v���uin �i�V�v�ł�����
�E�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C�����A���^�j��i�����Њ��j�u�V���[�x���g���y�I�ё��v��85�y�[�W�ɁA�uin ����v�̈��p���Ȃ���Ă���B
���̂悤�ɐ��̒��ɂ́uin ����v�Ɓuin �i�V�v�̗����̋L�q�����݂��Ă��邱�Ƃ�������܂����B���͌��_�Ƃ��Ắuin �i�V�v���������Ǝv���Ă���܂����A�ÓT�Ƃ����A�C���V���^�C���ƃo�b�n�̖����ł���搶�̒����̈��p���A���Ɂuin ����v�Ȃ͉̂�������������͂����ƍl���Ă���܂��B�搶�����p���ꂽ���̕����̏o�T������������������K���ł��B������낵�����肢�\���グ�܂��B
2010�N1��23��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�W
������̌��ł����A�N���h�̉̎��͍ŏ��̃N���h�i�����͐M���j�ɑ����Ƃ��낪�����A���̂��߂ɍŏ��ɂ��� credo in�E�E�E�� in �ɂȂ��邱�ƂɂȂ�A�Ӗ��̏�ł� in �͂����Ă��Ȃ��Ă������Ƃ������Ƃł��B�ꕶ���o���Ĉ��p����Ƃ��ɂ́Ain �������ق������@�I�ɕ�����₷���Ȃ�Ƃ����z������ in ��t���邱�Ƃ�����܂��B�@���ю�����̕ԐM�����������Ƃ��́A"�Ԏ��Ȃ��̉\��������"�Ǝv���Ă��������ɁA�C�������������܂����B�u�A�C���V���^�C���̈��p�̓���A���ɂ���ʼn������v�ƁB�ł��͐��������Ĕ��q�����̓��e�ł����B���{�l�ł��鏬�ю��́A"�ꕶ�����o���̈��p"�ɂ����āA���T�̈Ӗ����e�������@�I�������i������₷���j��D�悵���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�ł��A���̒��́u�Ӗ��̏�ł́Ain �͂����Ă��Ȃ��Ă��������Ɓv�Ƃ��镔���͒f���Ĕ[���͂ł��܂���B�u�~�T�ȃ��Z���v�͖��炩�Ɂuin �i�V�v�Ȃ̂ł�����A���̎����܂�����ł̉ł����ė~�����������A���́A"�Ӗ��̏�œ����ł͂Ȃ�"���Ƃ𗧏��悤�Ƃ��āA�������Ԃ������Ă����̂ł�����B
2010�N2��5��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ы`��
�@���āA����Ȗ�ŁA�A�C���V���^�C���⏬�ы`�������A�������Ȃ��Ǝv����uin ����v�̈��p�����Ă��闝�R�͂��ɕ����炸���܂��ł����B���i�I�ɂ͂��Ȃ肵�������ł����A���̌��Ɋւ��ẮA��������ȏ�Nj����Ȃ�����ł��B�Ȃ��Ȃ�A���R�����������Ƃ���ŁA���y�̖{���Ƃ͂Ȃ��W���Ȃ�����ł��B���̗��R���A�u���@��̓K�����v�ɂ����̂ł��A�u���p�������T�������Ȃ��Ă����v����ł��A�Ȃ�ł������̂ł��B��������A�A�C���V���^�C����"������2���������������p"�����Ă��ꂽ�������ŁA���y�̘g���щz���āA�J�g���b�N����̗��j�Ƃ������E�j�̖��m�Ȃ�̈�ւƑ��ݓ���邱�Ƃ��ł������Ƃ��A�Ȃ�Ƃ����Ă��L�Ӌ`�ł������A�y���߂܂����B���ɂ��̗��R���O�q�̑z���ǂ��肾�����Ƃ����Ȃ�A�A�C���V���^�C�����J�g���b�N���k�łȂ��������Ƃƃ��e����ɐ��ʂ��Ă������ƂɐS�̒ꂩ�犴�ӂ��āA�uCredo �� in�v�ɑ���l�@�͍���ł����܂��ɂ������Ǝv���܂��B
[�NjL]
���̓x�A�u�����~�T�ȁv��������ɂ�����7��ނ̍�����CD���Q�l�ɂ��܂����B�����͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
�@�g�X�J�j�[�j�w���F NBC�����y�c53�N�^���iBMG�W���p���j
�A�N�����y���[�w���F �j���[�E�t�B���n�[���j�A�nj��y�c65�iEMI MUSIC�j
�B�x�[���w���F �E�B�[���E�t�B���n�[���j�[74�i���j�o�[�T���~���[�W�b�N�j
�C����ޗ��w���F ���t�B���n�[���j�[77�i�r�N�^�[�j
�D�V�����e�B�w���F �V�J�S�����y�c78�i���j�o�[�T���~���[�W�b�N�j
�E�o�[���X�^�C���w���F �A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c78�i�V�j
�F�R�����E�f�C���B�X�w���F �o�C�G�������������y�c92�iBMG�W���p���j
�Ȃ��A����ȃ��X�g�������o�������Ƃ����܂��ƁA����͓��{�̃��R�[�h��Ђ̐���p�������������m��ɂ����邱�Ƃ������Ă���������������ł��B�\���グ�Ă����Ƃ���A�u�����~�T�ȁv�́u�~�T�ʏ핶�v�Ƃ͈قȂ����̎���p���Ă��܂��B�����O��Ɍ����Ă݂܂��傤�B
�@�C�D�F�͐������̎����f�ڂ���Ă��܂��B�������@�̖́A�_�ƃC�G�X�����Ⴆ��ȂǓK�����������Ă��܂��B�C�́u�w�N���h�x�́w�j�P�R���x�����̂܂ܗp���Ă���v�Ƃ������Β��Y���̉�����ԈႢ�B�F�� catholicam ���u�J�g���b�N���k�́v�Ɩ���{�^�Վ��̖�͐r���s�K�B�A�̑Ζ�i�V�͘_�O�B�B�́u�~�T�ʏ핶�v�Ɠ��X�Ə����Čf�ڂ���Ƃ������_�o���B�E���u�~�T�ʏ핶�v���f�ڂ��Ă��܂����A��Ȃ��ƂɁu����v�̕����́uin ����v�ƃA�C���V���^�C���̊ԈႢ���p�Ɠ����B
7W �̓��A�������Ζ���f�ڂ��Ă���̂͂S����܂����A��������{���������Ƃ��Ă����͇̂D�� 1W �����Ƃ���������ƐM�����Ȃ����ʂɂȂ�܂����B�Ζ�i�V�͘_�O�����A�t���Ă��Ă��u�~�T�ʏ핶�v�ǂ���ł͂����ɂ����_�o�B���̏�u�~�T�ʏ핶�v�Ȃ��ڂ܂œ���Ă��܂��ẮA���̋Ȃ𗝉����ĂȂ����Ƃ��������Ă���悤�Ȃ��́B�y���ǂ���̉̎��ɐ������Ζ������Ƃ�����{���̊�{�Ȃ̂ł�����A����b�ł͂���܂���B���R�[�h��Ђ̒S���҂̊F�l�A���ʂɂ����������ė~�����Ǝv���܂��B
2010.02.15 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��11�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�B
[�u�����~�T�ȁv�ɂ�����ϑ����̈Ӗ�]�@�u�~�T�ȁvCredo�ɂ�����A�u�_�v�u�L���X�g�v�u����v�u����v�ɑ���"�M����"�̌`�́A���ԂɁACredo in�AEt in�AEt in�AEt �Ƃ������тł��邱�Ƃ͑O��Ŗ��炩�ɂ����Ƃ���ł��B�u�_�v�u�L���X�g�v�u����v�̐��O�҂��n�b�L���Ɗ��邱�Ƃɂ���ĎO�ʈ�̂m�Ȃ��̂Ƃ��A�u����v��ʂ̌`�Ŏ������Ƃɂ��A���肰�Ȃ����̌��Еt�����s���Ƃ����̂��Ӑ}�ł����B���̌`�́A�ŌẪ~�T�ȂƂ�����M���[���E�h�E�}�V���[����J�DS�D�o�b�n�A���[�c�@���g�܂ŗ�O�͂���܂���B�Ƃ��낪�����ƑS���Ⴄ�`�Ԃ��������u�~�T�ȁv������܂��B������x�[�g�[���F���́u�����~�T�� �j���� ��i123�v�B���т͂����Ȃ��Ă��܂��B
Credo in�@�_
Credo in�@�L���X�g
Credo in�@����
Credo in�@����
�@���ׂċϓ��� Credo in ���t���S�̖ړI���Ɉ����Ă��܂��i�x�[�g�[���F���ɂ͂����P�ȁu�~�T�� �n���� ��i86�v�Ƃ��������̍�i������܂����A���̉̎��́u�~�T�ʏ핶�v�ǂ���ƂȂ��Ă��܂��j�B�x�[�g�[���F���́A�u�����~�T�ȁv�ɂ����āA���̂��̂悤�ȕϑ��I�Ȍ`���Ƃ����̂��H�@����͂��̓�ɔ����Ă݂����Ǝv���܂��B
�i�P�j�x�[�g�[���F���̏@���S
�@���[�g���B�q�E���@���E�x�[�g�[���F���i1770�|1828�j�́A�J�g���b�N�̉ƒ�ɐ��܂�܂������A�M�S�ȃL���X�g���k�Ƃ͂����Ȃ������悤�ł��B�c���̓{���̋{��y���ŁA��Ƃ͂��̗��h�ȑc���ɂ���Ďx�����Ă��܂����B�Ƃ��낪���̑单���̓x�[�g�[���F����2�̂Ƃ��ɖS���Ȃ��Ă��܂��܂��B���Ƃ͕��e���撣��Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł����A���̐l�����������B�ꉞ�{��̎�ł͂���܂������A�ΘJ�ӗ~�̂Ȃ������̑�����݁B���̐e�������Ăɂ����̂��A���Ƃ����낤�ɗc�������特�y�̍˔\�������킪�q�x�[�g�[���F���������B�ǂ��ɂ����Ă��̎q����l�O�̉��y�ƂɈ�Ă����āA�����͊y�����悤�Ɗ�̂ł��B���̓��P�͉ߍ����ɂ߁A�̔��ɂ�鏝�͐₦�邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ̂��ƁB����ȊO�̂Ƃ��ɂ͎��������ŕ�e�ɖ\�͂�U�邤�A�ǂ����悤���Ȃ����e�ł����B�������x�[�g�[���F���͑ς����B���ʁA�����O�̍˔\���J�Ԃ����̂ł��B���@�͂ǂ�����A���̎��Ȓ��e���̃X�p���^���炪����t�������ƂɂȂ�܂��B�c�N��������ȉƒ���ň�����x�[�g�[���F���B�L���X�g���k�̕��e�A���̐l�͈�̉��ȂB�L���X�g�����ĂȂ�ȂႢ�B�M��������͎̂��Ȃ̗͂����ł͂Ȃ����E�E�E�E�B�ނ̃L���X�g�s�M�ƔĐ_�_�I�_�ւ̑����͂��̗c�N���ɉ萶�����ɈႢ����܂���B�₪�ă{����w�ɐi�݁A�����Ŏ��R�Ɛ��`�̋C���ɐG���B���͂܂��Ɏ����{���̎���B�v���̑Ώۂ��J�g���b�N�̋��`�ł͂Ȃ��A�N�w�⎩�R�Ȋw�Ɍ��������͎̂��R�̐���s���ł����B���ɌX�|�����̂́A�M���V���N�w�ł���A�J���g�ł���V���C�N�X�s�A�������B�v���g���̃C�f�A�_��J���g�́u���������ᔻ�v�ɂ݂��闝���d�v���̓N�w�������ނ̎v�l��ՂɂȂ��Ă������̂ł��B������������A�V�F�C�N�X�s�A�̐��E���甽���_���̈ӎ���k��������̂����m��܂���B����炪�ӑR��̂ƂȂ��āu�L���X�g�Ȃǂ��������ɂ��ꂽ���_���l�ɉ߂��Ȃ��v�Ƃ�����N�̉ߌ��Ȕ����ɏW�ꂽ�̂ł��傤�B
�@����ɂ��Ă��A���@���̎��Ȃ́A�@����̏��X�̎��ۂ̒��ɂ͗����ł��Ȃ����̂����\����܂��āE�E�E�E�u��m����v�Ƃ����I�[�h���[�E�w�v�o�[���̉f�悪����܂����A���̒��ŁA�A�t���J�ŕ�d�����������m�����n�l�������Ȃ�o�E����Ƃ������ɏՌ��I�ȃV�`���G�C�V����������܂��B���R�͂܂��Ȃ��t�Ɂu��m���E���Έ������v�Ƃ���ꂽ�Ƃ����̂ł����A���̂Ƃ��w�v�o�[�������铯���̓�m��������ԓx���u�������͎E�l�҂��͂��܂��v�Ȃ̂ł��B�L���X�g���ł͂ǂ�ȍߐl�����͂��Ƃ����̂ł��B����Ȃ��ƕ��ʂ̐l�Ԃɂł���̂ł��傤���B�H�t����r�쉫�w�����ʎE�l�Ƃ����Ɏ͂�����̂ł��傤���B�@���̕s�����B�ǂ����ߑR�Ƃ��Ȃ��B������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�x�[�g�[���F���̋C�����͕�����悤�ȋC������̂ł��B
�i�Q�j�u�����~�T�ȁv Credo�̈Ӗ�����
�@�u�����~�T�� �j���� ��i123�v�́A���h���t����̑�i���A�C�̕���ď����n�߂��܂����B���h���t����́A�x�[�g�[���F�����ł��M������p�g�����ɂ��ĉ��y�F�B�B��i���Ƃ����J�g���b�N����ɂ����ċ��c�����̍��ʐE�B�ő�̔�҂��ō��̒n�ʂɒ����̂ł�����A������h�i�ȃJ�g���b�N���k�łȂ��x�[�g�[���F���ł��A��ȉƂƂ��Ă̈АM��������"�~�T�ȍ��"�ɖv���������Ƃ͑z���ɓ����܂���B���Ȃ�ō��̍�i���Ƃ����ӋC���݂́A���̑��ʎ��ɂ͊Ԃɍ���Ȃ��Ƃ������Ԃ�ł��܂��܂��B����́A�x�[�g�[���F�����A�����܂łɊԂɍ��킹�邱�Ƃ����A���y�Ƃ��Ĕ[���������̂��Y�ݏo�����Ƃ������߂ł��傤�B�悤�₭�������đ���̋��ɓn�����̂͑��ʎ���3�N��A1823�N3���̂��Ƃł����B
�@Credo �́u�킽�����́A�_�A�L���X�g�A�����M���܂��B�����ċ�����v�Ƃ����M�錾�̏͂ł�����A�Í��̃~�T�Ȃ̋ȑz�́A�T�ˌh�i���Ɗm�M�̐F�������Z���B���_�u�����~�T�ȁv�����̗�ɘR��܂��A�ȑz�͂��͋����ӎu�̗͂ɖ����Ă��܂��B���̂ǂ�ȃ~�T�Ȃ������̏����o���p�g�X�͋���ł��B�`���́uCredo�v�ɕt����ꂽ B��-G-C-F �̉��^�͋ȑS�̂��т��āA�܂�Ń��[�O�i�[�̃��C�g���`�[�t�i�������@�j�̂悤�ȓ��������Ă��܂��B��������"�M�錾�̓��@"�Ƃł������܂��傤���B���[�O�i�[�̃��C�g���`�[�t�̌��c�̓x�����I�[�Y�u���z�����ȁv�́u�Œ�ϔO�v�Ƃ����̂����y�j��̒���ł����A���͂��̃x�[�g�[���F���uCredo�̓��@�v��������삯�ł���Ɗm�M����ɂ�����܂����B���̏́A���[�O�i�[�|�p�̏W�听�ł���u�j�[�x�����O�̎w�v�̒��Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B�u�j�[�x�����O�̎w�v�ɂ͗D��100���郉�C�g���`�[�t�����݂���Ƃ����Ă��܂����A���ł��u�w�v�̃��`�[�t�͍ŏd�v���`�[�t�̈�B���̂��s�g�ȉe��тт����^�����P�ƈЌ��ɖ��������`�[�t�ɕό`�����̂��u�����n���̃��`�[�t�v�ł��B���̃��`�[�t���uCredo �̓��@�v�Ɣ��Ɏ��ʂ��Ă���̂ł��ˁB���̉��^��"�\�~�[�h���[�h�h���~�["�i�n�����Ɉڒ����ēǂ�ł��܂��j�B�x�[�g�[���F���uCredo�̓��@�v�͓����`�ɒ����ƁA"�h�[�� ���[�\"�ł�����A�����n���̃��`�[�t�́uCredo �̓��@�v�̉���S���g���ă~���������A�i�O�����Ƃ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B����́A���Ȃ�̃R�W�c�P�Ƃ͊������A���[�O�i�[���u�w�����~�T�x�����ł��_���ȃx�[�g�[���F���I���_���������Ȍ����I��i�v�Ɛ�^���Ă��邱�Ƃ���A���Ƃ��ẮA"���[�O�i�[�̓x�[�g�[���F���ւ̃I�}�[�W���Ƃ��Ă������݂�"�Ǝv�������̂ł��B
�@ �@���}���E���������p�E���E�x�b�J�[�����̈̑�ȃ~�T�Ȃɑ��A�Ǝ��̎^���E�������Ă��܂����A�����[���̂͂�͂胏�[�O�i�[�̌����ŁA�O�q�̃R�����g�ɑ��������ɂ͂�������܂��B
�@�E�E�E�̎��́A���܂��܂����̈̑�ȋ���y��i�ɂ����ẮA�T�O�I�Ӗ��ɂ��������ĉ��߂������̂ł͂Ȃ��A���y�I�|�p��i�̈Ӗ��ɂ����ĂЂ�����̏��p�̑f�ނƂ��Ă̖�ڂ��ʂ������̂ł���E�E�E�@���̃��q�����g�E���[�O�i�[�̌����́A"�x�[�g�[���F���́u�~�T�ʏ핶�v�̉̎���f�ނƂ��čl���Ă���"�Ƃ������Ƃł�����A"���y�ɏ]������`�ŕς���"�Ƃ������̌����ƍ��v���Ă���̂ł͂Ǝv���āA���Ɋ������C���ɂȂ�܂��B
�@�x�[�g�[���F���́u�����~�T�ȁv���@���҂Ƃ��Ăł͂Ȃ���ȉƂƂ��Č����ɏ������B���̌��ʁA�~�T�Ȃ̒��S�����ł��� Credo ���A��̎������ɓW�J��������Ȃ̈�y�͂̂悤�Ȍ`�ɍ��グ�邱�ƂɂȂ����B����ɂ́A���߂������Ȓ��̐ߖڂŌ��ʓI�Ɏg�����Ƃ��K�v�ŁA���̂��߂ɂ́A���̂S�ӏ����ׂẲ̎����uCredo in�v�łȂ���Ȃ�Ȃ������B���ꂪ�u�~�T�ʏ핶�v�̉̎����ς�������R�Ȃ̂ł��B
�@�v���e�X�^���g���k��J�DS�D�o�b�n�́u���Z���~�T�ȁv�ɂ����āA�J�g���b�N�̋K�͂ł���ʏ�̌`���������ς��Ă͂��܂����A���̎O�ʈ�̂̏ے��Ƃ�������"Credo�̕���"��ς��邱�Ƃ͂��܂���ł����B�܂��A�V���[�x���g�́A�����̃J�g���b�N����ւ̕s�M����A�ނ̍�������ׂẴ~�T�Ȃ���A�u����v�Ɋւ��邻�̈ꕶ���폜�����B�����āA�x�[�g�[���F���́A����܂ł�����ς��邱�Ƃ̂Ȃ������u�~�T�ʏ핶�v�̉̎���ς��āA��ȉƂƂ��Ă̐M�O���т����B�s�ςł���ׂ��u�~�T�ʏ핶�v�̉̎���"�̏��p�̑f��"�ƌ��āB
�@�������Ċ������� Credo �́A����Ŋm�M�I�ȁuCredo �̓��@�v���A�����Ȃ̂悤�ɑS�̂��т��A���łȗl�������`�����܂����B�����ɂ͌h�i�ȃL���X�g���k�ł͂Ȃ����ȉƃx�[�g�[���F���̉��y�D��̎p�����͂�����ƌ��Ď��܂��B�܂��A�ނ��u�L���G�v�̊y����ɏ������u�S���o�Ł|�����čĂс|�S�ɂ������v�Ƃ́A"�����̍��́A��U�V��̐_�ɍs�����Ă��A�Ăт܂������̋��ɂ��ǂ��Ăق���"�Ƃ����肢�Ȃ̂��Ǝv���܂��B�����ɂ��A�M���������͎̂��Ȃ̗͂ł��藝���ł���A�Ƃ����ނ̓N�w���ǂݎ��邵�A����������A"�O�ʈ�̂��|�Ƃ���J�g���b�N�̋��`"�Ƃ͑��e��Ȃ��v�z�Ȃ̂ł��B
�@�������Ȃ���A�ނ��A�N���ׂ��炴��u�~�T�ʏ핶�v�̉̎���ς��Ă܂ō��グ�� Credo �̏͂́A���ʁA���O�҂Ƌ����Ɉʒu�Â���Ƃ����`�Ԃ�o���Ă��܂����B���̉����ȃV���[�x���g���A�����̋���ɑ��u����̖V��Ƃ������ɂ́A�V���ڂꂽ�ʔn�݂����ȋU�P�҂ŁA���o�̐e���݂����Ƀo�J�ŁA�����݂����ɃK�T�c�ȘA�����肾�v�ƌ����Ă���̂ł�����A�x�[�g�[���F����������ǂ��`�e���邩�z�������܂���B����Ȕނ̉��y�D��̎p�����A�y��ׂ�����Ɓu�����̃��_���l�v�ƕ̂L���X�g��_�Ɠ��i�Ƃ��Ĉ����A�O�ʈ�̂Ȃ�ʎl�ʈ�̂̌`�Ԃ��`����Ă��܂����̂́A�Ȃ�Ƃ�����Ȍ��ʂƂ�����������܂���B
2010.01.29 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��10�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�A
�@�O��̌��ɂ��A�A�C���V���^�C�������p�����uin ����v�́A�u�~�T�ʏ핶�v�Əƍ��������ʁA�s�����Ƃ̌��_���o�����Ă��������܂����B�~�T�ʏ핶�̂��̕�����Credo �́u�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�i���̃j�P�R���j�ɍs�����܂��B����́A���́u�j�P�R���v��O�ꌟ���āA�Ȃ��uin �i�V�v�������Ȃ̂��A���̓�ɔ��肽���Ǝv���܂��B�i�P�j�u�j�P�R���v�̑��܂�
�@�L���X�g���ŏ��̌���c��325�N�A�j�P�A�ŊJ�Â���܂����B���ꂪ��P�j�P�A����c�ł��B�e�[�}�͋��`�̓���ŁA�_�_��"�L���X�g�̐_��"�B�����A�L���X�g�͐_�Ɠ��ꂩ�ۂ��Ƃ������ł����B���ꂪ�����̃L���X�g���k�̊Ԃň�̑傫�Ș_���ƂȂ��āA�l�X�Ȗ��������N�����Ă��܂����B�����ŁA���̃��[�}�c��R���X�^���e�B�k�X1�����A����珔�����������邽�߂ɉ�c���J�����̂ł��B�ނ�313�N�Ɂu�~���m���߁v�����z�A����܂Ŕ��Q���Ă����L���X�g���k�ɐM���̎��R��^�����B����́A�җ�Ȑ����ōL�܂��Ă䂭�L���X�g�����A����������͎�荞�ނق����A�����㓾��ƍl��������B���̂��߂ɂ́A�L���X�g���k�͈ꖇ��ł��邱�Ƃ��]�܂��������B���`�̓��ꂪ�s���������킯�ł��B��c�̌��ʍ̑����ꂽ�u�j�P�A�M���v��"�L���X�g�͐_�Ɠ����ł͂Ȃ��Ə�������̂���"�Ƃ��������Ō���Ă��܂��B���̂Ƃ��A�r�˂��ꂽ�̂��A���E�X�h�Ƃ�����h�ł����B
�@�Ƃ��낪�A�A���E�X�h�̐��͂͌���c��������Ԑ������ɐ��ڂ����B���̎��Ԃ��d���݂��c��e�I�h�V�E�X�P���́A381�N�ɃR���X�^���`�m�[�v���Ō���c���J���܂����B���ꂪ2��ڂ̌���c�u��P�R���X�^���`�m�[�v������c�v�ł��B��c�̑傫�ȖړI�́A�A���E�X�h�̊��S�r�˂ł����B���̂��߂ɂ́A�u�j�P�A�M���v�{�I�ɕς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����u�L���X�g�̐_���v�Ɓu�O�ʈ�́v����苭�łɑł��o���K�v���������̂ł��B�����āA�̑����ꂽ�̂��u�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�A�ʏ́u�j�P�R���v�ŁA�u�j�P�A�M���v�Ƃ����Βʏ킱����̂��ƁB325�N�̑��̂ق��́u���j�P�A�M���v�Ƃ��ċ�ʂ���̂���ʓI�ł��B
�i�Q�j�u�j�P�R���v��������B
�@�u���j�P�A�M���v�̓M���V����ŏ�����Ă��܂����A�u�j�P�R���v�ɂ̓��e�������t������܂����B���̃��e����̑S�����f�ڂ��܂��B
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.�@�S�̂�3�i�ɕ�����Ă���A�u�_�v�u�L���X�g�v�u����v�̎��̂Ɠ������ڂ����L�q���Ă��܂��B���Ɂu�L���X�g�v�Ɋւ���L�q�͈��|�I�ɑ����B���ꂱ���A"�L���X�g�̐_���̊m��"����c�̑傫�ȖړI�ł������ł��B�����A�u�L���X�g�v�́u�_�v�Ɠ�����̂ł��邱�Ƃ��`���A�u�O�ʈ�́v�������ł��o�����̂ł��B
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre(Filioque) procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
�킽���͐M���܂��B�B��̐_�A�S�\�̕��A�V�ƒn�A��������́A�����Ȃ����́A���ׂĂ̂��̂̑������B
�킽���͐M���܂��B�B��̎�C�G�X�E�L���X�g���B��͐_�̂ЂƂ�q�A���ׂĂɐ旧���ĕ���萶�܂�A�_���̐_�A�����̌��A�܂��Ƃ̐_���̂܂��Ƃ̐_�A�����邱�ƂȂ����܂�A���ƈ�́B���ׂĂ͎�ɂ���đ����܂����B��́A�킽�������l�ނ̂��߁A�킽�������̋~���̂��߂ɓV���炭����A����ɂ���āA���Ƃ߃}���A��肩�炾���A�l�ƂȂ��܂����B�|���e�B�I�E�s���g�̂��ƂŁA�킽�������̂��߂ɏ\���˂ɂ����A�ꂵ�݂��A�����A�����ɂ���Ƃ���O���ڂɕ������A�V�ɏ���A���̉E�̍��ɒ����Ă����܂��B��́A���ҁi��������j�Ǝ��҂��ق����߂ɉh���̂����ɍĂї����܂��B���̍��͏I��邱�Ƃ�����܂���B
�킽���͐M���܂��B��ł���A���̂��̗^����ł��鐹����B����́A���Ǝq����o�āA���Ǝq�ƂƂ��ɗ�q����A�h�����A�܂��a���҂��Ƃ����Č���܂����B�킽���́A���Ȃ�A���Ղ́A�g�k�I�A�B��̋����M���܂��B�߂̂�邵�������炷�B��̐����F�߁A���҂̕����Ɨ����̂��̂���҂��]�݂܂��B�A�[�����B�i���{�i���c���s���F�����j
�@����ɒ��ڂ��ׂ���"����"�Ɋւ���L�q�̂����ł��B�O��́u���j�P�A�M���v�́u"�_�̎q�͈قȂ�{����萬�����"�Ɛ�ׂ�҂���A�����Ȃ�g�k����́A�ׂ��v�Ƃ��Ă����������u�킽���́A���Ȃ�A���Ղ́A�g�k�I�A�B��̋����M����v�ɕς��Ă��܂��B�P�Ɉْ[�̈�h��r�˂���Ƃ����⏬�ے�^�L�q����A�����I�B��̋����M����ׂ��Ƃ�����ǓI�m��^�L�q�ɕς���Ă��܂��B��������ɐ▭�Ȍ`�ԂŁB
�i�R�j�N���҂��d�g�▭�Ȍ`��
[�j�P�R���̌`��]
Credo in unum Deum�@�킽���͐M���܂� �B��̐_��
Et in unum Dominum Jesum Christum�@�킽���͐M���܂� �B��̎�C�G�X�E�L���X�g��
Et in Spiritum Sanctum�@�킽���͐M���܂� �����
Et unam sanctam catholicamu et apostolicam Ecclesiam�@�킽���͐M���܂� �B��̋����
���ꂪ�u�j�P�R���v�̍��q�ł��B�M������̂͂S�B�O�ʈ�̂Ȃ�u�_�v�u�L���X�g�v�u����v�����āu����v�ł��B���F���{����4�ɑ����ׂ�"�킽���͐M���܂�"�Ƃ���������傪����ł��܂��B�Ƃ��낪���e����̌����͕v�X���Ⴄ�`�ŕ���ł��܂��B����₷���悤�ɓ��̕����������ĕ��ׂĂ݂܂��傤�i�ړI��͓��{��ŋL�q�j�B
�@Credo in�@�_
�AEt in�@�L���X�g
�BEt in�@����
�CEt�@����
���ׂĂɎ�ꂪ�ȗ�����Ă��܂����A����́u�M�錾�v�Ȃ̂Łu���v�����ƂȂ�܂��B�@Credo�́u�M����v�Ƃ����������Ain�́u�`���v�Ƃ����ړI��ɑ���O�u���ł�����A�u���͐_��M����v�ł��B�Aet�͉p��� and �ł�����u�܂��v�A���̂��Ƃ� credo ���ȗ�����Ă��܂��B���������āu�܂��A���̓L���X�g��M����v�ł��B�B�������`�Łu�܂��A���͐����M����v�ł��B�Ƃ��낪�C�̌`�Ԃƃj���A���X�͑傫������Ă��܂��B
���F�̓��{���͇C�u�킽���́A���Ȃ�A���Ղ́A�g�k�I�B��̋����M���܂��v�ł�����A��������̂܂܁A���e����ɖ߂��� Et in unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam �ŁA�A�B�Ɠ����`�ɂȂ�͂��ł��B�Ƃ��낪�����͈Ⴄ�B�uin �i�V�v�A���Ȃ킿 Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam�@�Ȃ̂ł��B���������� in �̗L���B����ɂ͈�̂ǂ�Ȕ閧���B����Ă���̂ł��傤���B
[in �����̃P�[�X]�@�����A������ in ����������ǂ��Ȃ邩�H
�@Credo in
�AEt in
�BEt in
�CEt in
�܂��A�u�j�P�R���v�N���҂͂��̌`�ōl�����Ǝv���܂��i���̑O�i�K�ł́A���ׂĂ��uCredo in�v�ɂȂ��Ă����\��������܂��B�u�����~�T�ȁv�̂悤�Ɂj�B�ł��A�ނ͍l���܂��B���ꂾ�ƁA�C�͇A�B�Ɠ����`�A�����@����̕���I���т�����A�u�_�A�C�G�X�E�L���X�g�A����A�����M����v�Ƃ����A4�̖ړI�ꂪ����I�i�t���̃j���A���X�ɂȂ�B�u�j�P�R���v�ő�̖ړI��"�O�ʈ�̖̂��m��"���B����͂܂����B����A��̂Ȃ�u���O�ҁiSaint Trinity�j�v�Ɠ��i�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B�Ȃ�ǂ�����I
[in �i�V�ւ̓]��]
�����炭�N���҂́A���̕��ʂ�O�ɒ��l�������Ƃł��傤�B�O�ʈ�̂Ȃ�u���O�ҁv�ɂ��ẮA�e�X�̓�������������ƋK�肵���B���ɃL���X�g�̐_����h�邬�Ȃ����̂Ƃ��邽�߂Ɂu�L���X�g�͐_�̎q�A�����A�_�Ɠ�����̂ł��邱�ƁB���̂��ׂĂ̂��̂�������ɂȂ������ƁB����ɂ���Đ����A�s���g�ɂ�������Y�ɏ������A�����ĕ������č��͐_�̉E���ɂ����邱�Ɓv�ȂǁA���̐��U�ɂ�����܂ŏڍׂɖ��L�����B���Ƃ́A"�����ȋ���͗B��u�J�g���b�N����v�ł���"���Ƃ�搂��K�v������B�ْ[��r�����邽�߂ɂ��B������Ƃ����āu���O�ҁv�Ɠ��i�ɕ��ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����őM�����A�u�������Ain �i�V�ł������v�B
�@�@�@�@Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam
����Ȃ�A���̓I�Ɂu���O�ҁv�Ƃ͓��i�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�m���ɞB���ȕ\���ł͂��邪�A�Ԃ��Ă���ł����̂ł͂Ȃ����B���i�łȂ��Ƃ������Ƃ́A�u���O�ҁv�̉��ʂɒu�����Ƃ��A�������i�鏈�Ƃ�����B�u�J�g���b�N������B�ꐳ���ȋ���ł���v�Ƃ����Ӗ��̕��������肳����������̂�����B�j���A���X�͂������E�E�E�u�܂��A�B��̐��Ȃ镁�Ղ̂����Ďg�k�p���̋���Ȃ̂��v�����ƁB�����Ɗ��ݍӂ��Ă����u���������ł�v�Ȃ̂��B�܂��ɁA���̓엘���́u�n���V������Ń��[�v�ł���A���E�̉�����́u�X�̎�����낵���v�ł���A�ŋ߂ł͉������j�Y�N�́u�⏕�����I�v�Ȃ̂��B�v����ɁA��i�́u���O�ҁv�́u�J���[�v�ł���u�i�{�i�v�ł���u���Łv�ł����āA����́u�n���V�v�ł���u�X�̎��v�ł���u�⏕���v�Ȃ̂��B��i�Ɠ���ɒu���Ȃ����ɍI���ȕ\����҂ݏo�����̂ł��B���ꂪ�uin �i�V�v�ƂȂ����^���B���̂킸�����̈������A�N���҂��������▭�ȋZ�������B�������āu�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�͍̑�����A�Ȍネ�[�}���c�_�Ƃ���J�g���b�N�̋���ȃq�G�����L�[���`������Ă䂭�̂ł��B�E�E�E���ꂪ���̌����ł����������ł��傤���B���x�Ȃ���̒���Ȃ��ƒf�Ƃ̎��o�͂���܂�����ǁE�E�E�B
�ł͍Ō�ɁA���̕��߂̓��{���������_���ɏE���o���Ă݂܂��傤
�킽���́A���Ȃ�A���Ղ́A�g�k�I�A�B��̋�����M���܂�8�̂���7���u�M����v�Ƃ��������������Ă��܂����A�Ō�̍���I�q����̖�ɂ����u�M����v���Ȃ��B�����炱�̖�̏ꍇ�A����͐��O�҂Ɠ��i�łȂ��B���ꂱ���u�j�P�R���v�^�̎p��ǂݎ�����ł���Ƃ����܂��B������Q�l�ɁA�����l����ɂ߂����{���i�H�j���Ō�ɋL���āA���̏͂��I��肽���Ǝv���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2004�N���c�����F���{�i���c�������j
���́A��E���E���E�g�k�p���̉���M���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1967�N�Łu����c�ɂ�����̃~�T�T�珑�v�j
���M���A��̐��Ȃ���Ȃ�g�k�̋����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���{���n���X�g�X����j
���́\�\�@���E���E�g�k�p���̋�����M���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���R�Ǖv�A�p���X�g���[�i�u���c�}���`�F���X�̃~�T�vCD�j
�܂��A�B�ꐹ���@�g�k�p���Ȃ鋦����M��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�{�萰��A �V�����p���e�B�G�u�^�钆�̃~�T�vCD�j
�܂����́A�B��A���A���A�g�k�`���̋�����M����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����́A���[�c�@���g�u�Պ����~�T�ȁvCD�j
�܂��A���́A�B��A���A���A�g�k�`���̋�����M����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�C�V�V�q�A���[�c�@���g�u�Պ����~�T�ȁvCD�j
�܂��A�B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�̋���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����I�q�AJ�DS�D�o�b�n�u�~�T�ȃ��Z���vCD�j
�@�@�@�@ Et unam sannctam catolicam et apostolicam Eccresiam
�@�@�@�@�܂��A�B��́A���Ȃ�A���Ղɂ��Ďg�k�p���̋���Ȃ̂ł�
2010.01.20 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��9�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�@
�V���[�x���g�́u�~�T�ȑ�6�ԁv�Ŗ��m�Ƃ̑��������܂����B�A���t���[�g��A�C���V���^�C�����u�V���[�x���g���y�I�ё��v�́A�I�b�g�[��G�[���q��h�C�b�`���Ҏ[�́u�V���[�x���g�̎莆�v�u�V���[�x���g�F�l�����̉�z�v�ƕ��ԃV���[�x���g�����̒�ԓI�����Ƃ����Ă��܂��B�������E�ɂ����Ă����Q�l�ɂ��Ă��܂��B�ܘ_�A���^�j��i�����Њ��j�̖|����̂ł����B���āA���̒��ɁA�V���[�x���g�̓~�T�Ȃ́uCredo�v�̂����߂��폜���Ă���Ƃ�����������܂��B����͑O��̃e�[�}�ł������A���͔ނ̈��p�ɂ���܂����B�A�C���V���^�C���́A�V���[�x���g���폜������߂����̂悤�Ɉ��p���Ă��܂��i��͖�҂̓Y�t�j�B�@�@�@Et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
�@�@�@�i�}�^�B��m���A���A�g�k�`���m����j
�����āA��i�Łu�������A��~�T�Ȃ̒��ŁA����8��́E�E�E�E�v��"8��"�ƃn�b�L���Ə����Ă��܂��B
�ʂ����Ă��̉����u���m�Ƃ̑����v�Ȃ̂��H������������O�Ɋ�{�I�m���Ƃ��āA��ʓI�ȁu�~�T�ȁv�̍\���ɂ��ĐG��Ă����܂��傤�B�ʏ�ȉ���5�����琬�藧���Ă���A�S�у��e����ŏ�����Ă��܂��B�Ȃ��u�~�T�v�̓J�g���b�N�̓T��Ȃ̂ŁA�u�~�T�ȁv�Ƃ����J�g���b�N�̓T�特�y�Ƃ������ƂɂȂ�A�v���e�X�^���g�Ɂu�~�T�ȁv�͂���܂���B
��1�� �@�L���GKyrie ���݂��܂�
��2�� �@�O���[���AGloria �h������
��3�� �@�N���hCredo ���͐M��
��4�� �@�T���N�g�D�XSanctus ���Ȃ邩��
�@�@�@�@�@�x�l�f�B�N�g�D�XBenedictus �j������
��5�� �@�_�̏��rAgnus dei �߂������������_�̏��r��
�i�P�jCredo��in�̗L��
Credo�̓��e����Łu���͐M���v�Ƃ����Ӗ��Łu�M�錾�v�̏́B�O�ʈ�̂Ȃ�u�_�v�u�C�G�X�E�L���X�g�v�u����v�A�����āu����v��M����Ƃ������e�ł��B
���̉ӏ��́ACredo�̌�i�Łu�����M����v�Ƃ��������B�`��Credo in unum Deum �u���B��̐_��M���v�Ŏn�܂�AEt in unum Dominum Jesum Christum�u�܂��A���͗B��̎�C�G�X�E�L���X�g���i�M���j�v�Ƃ��āAEt in Spiritum Sanctum�u�܂��A���͐�����i�M���j�v�Ƒ����B�����܂ł͏����u�O�ʈ�́v�_�ɑ����Ă��܂��B���̂��ƂɁAEt in unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam �u�܂��A���͗B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�p���̋�����i�M���j�v�Ƃ�����߂�����̂ł��B
���̕������폜���Ă���̂́A�A�C���V���^�C�����w�E���Ă���Ƃ���A�m���ɃV���[�x���g��6�̃~�T�Ȃ����ł����B�ł́A�V���[�x���g���폜������߂��ǂ��Ȃ��Ă���̂��H���̃~�T�ȂŁA���̕������Ă݂܂����B�Ȃ�J�DS�D�o�b�n�́u�~�T�ȃ��Z���v�B�uCredo�v�̂��̕����͏d���ȃo�X�̃\���B�̎��J�[�h�����Ȃ��畷���Ă��āu����H�v�Ǝv���܂����B���̈�߂̉̎��J�[�h�͂����Ȃ��Ă��܂����B
�@�@�@Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam
�Ȃ�ƁA�A�C���V���^�C���̈��p�ɂ����� in �������Ă��܂��B���������āA�A�C���V���^�C�������p�����W��ł͂Ȃ��A7��Ȃ̂ł��B������A�̎��J�[�h�̌�A���Ǝv���A�ēx�A�C�������ĕ������킹�����Ă݂܂������A�ԈႢ�Ȃ�in���̂��Ă͂��܂���B�Ȃ�A����͒P���ȋL�ڃ~�X�ł͂Ȃ��A�y�Ȃ��̂��̂��uin�i�V�v�Ȃ̂ł��B"�V���[�x���g���폜�������̂��Ă݂���A����Ǝv���Ă�����傪�폜����Ă���"�Ƃ����Ȃ�Ƃ���Ȍ����ɂԂ������̂ł����B�܂��A��⍱�ׂȂ��Ƃł����A����ecclesiam�̓����������啶���ɂȂ��Ă��܂��B�����Ȃ�Ɖ\�Ȍ��茟�������Ȃ�̂����̏�ł���܂��āA�F�l�̕]�_�Ǝ������CD�����肵�ĢCredo�����~�T�Ȃ��̈�߂̌��ɓ���܂����B���̑O�Ƀ~�T�i�~�T�ȁj�Ƃ͂Ȃ�H�Ƃ������Ƃ������Ɣc�����Ă����܂��傤�B
�~�T�imass�j�͐��̍ՋV�Ƃ����āA�J�g���b�N���k������ɏW�܂��čs���d�v�ȓT��V���̈�B������i��i�Ղ��A�I���Ƃ��Ɂumass�i����ɂĂ��J���j�v�ƌ��������Ƃ���A�T�炻�̂��̖̂��̂ɓ]�������̂Ƃ���Ă��܂��B�����́u�}�^�C�������v���ɂ́A�C�G�X�E�L���X�g���A�u���Ȃ��������_�̎q�ł��v�ƍ���������q�y�g���Ɍ������u���̊�i�y�g���j�̏�Ɏ��̋�������Ă�v�Ɛ錾�������Ƃ�������Ă��܂��B���ꂪ����̔��˂ŁA�Ȍ�A���[�}���c�_�Ƃ��鋐��ȃ��[�}��J�g���b�N�̃q�G�����L�[���`������Ă䂭�̂ł��B�L���X�g�ɐM������u�V�̍��̌��v�����������y�g���B���̃y�g�������㋳�c�Ƃ��郍�[�}�E�J�g���b�N��������A�L���X�g�̋����ɓ`����B�ꐳ���ȑ��݂ł���Ƃ����킯�ł��B�Ȃ��J�g���b�N�icatholicam�j�Ƃ̓��e�����"���Ղ�"�Ƃ����Ӗ��̌`�e���B
�~�T�Ȃ́u�~�T�ʏ핶�v�ɋȂ��������́B�u�~�T�ʏ핶�v�Ƃ̓J�g���b�N����ɂ����čs����~�T�̂��߂̎����̂��ƂŁA�����̓��e����ŏ�����Ă��܂��B���i�̃~�T�ł́A�����i���j���j�ɐM�҂�����ɏW�܂��āA�����Ɋ�Â��i�Ղ̐������A�Ō���u�M�錾�v���s���܂��B���̐M�錾���u�~�T�ʏ핶�v�̒����uCredo�v�Ȃ̂ł��B���������āA�uCredo�v�����A�~�T�Ȃ̒��j���Ȃ��͂Ƃ����܂��B
����ł́A�u�~�T�ȁv���� Credo"���̈�߂� in �̗L��"�������܂��B�ΏۂƂ����~�T�Ȃ͈ȉ��̂Ƃ���B�f�ނ�CD�Ƃ��̉̎��J�[�h�y�ъy���ł��B
[�������~�T��]
�@ �M���[���E�h�E�}�V���[�i1300�|1377�j�u�m�[�g���_����~�T�ȁv
�A �M���[����f���t�@�C1397�|1474�j�u�p�h���@�̐��A���g�j�E�X�̂��߂̃~�T�ȁv
�B �V�����p���e�B�G�i1643�|1704�j�u�^�钆�̃~�T�v
�C J�DS�D�o�b�n(1785�|1750)�u���Z���~�T�ȁv
�D ���[�c�@���g(1756�|1791)�u�Պ����~�T�ȁv
�E �x�[�g�[���F���i1770�|1827�j�́u�����~�T�ȁv
�@�͓T�當�S�̂���l�̍�ȉƂŘd�����ŌẪ~�T�ȂƂ����Ă��� �A��15���I�ő�̍�ȉƂŁA�������烋�l�b�T���X�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ������M���[���E�f���t�@�C�̍�� �B�̓C�G�Y�X��̊y���V�����p���e�B�G���������~�T�ȂŁA�m�G���i���́j���Ԃɋ��ތ`���Ƃ����N���X�}�X�p�̃~�T�� �C�̓v���e�X�^���g���kJ�DS�D�o�b�n���l���̍Ō�ɏ��������ՓI�i�J�g���b�N�j�ȃ~�T�� �D�̓��[�c�@���g�̃U���c�u���N�i�����̓��[�}���c�̒����n�j����̍�i �E�̓x�[�g�[���F�����ӔN�ɍ�����~�T��
[���،���]
�@�M���[���E�h�E�}�V���[�́u�m�[�g���_���~�T�ȁv���烂�[�c�@���g�u�Պ����~�T�ȁv�܂ł́A�����e�L�X�g���g���Ă���A���ׂĂ��uin�i�V�v�ł������B �A�x�[�g�[���F���́u�����~�T�ȁv�́A�̎��i�T�當�j������Ă���AEt���g�킸��Credo in�Ƃ��Ă���B
�i�Q�j���@�I�l�@
�ł́A���@�I���n����ACredo�S�̗̂����ǂ��Ȃ���A���̈�߂������Ă݂܂��傤�BCredo�̓��e�����"�M����"�Ƃ����Ӗ��̓����̈�l�̒P���`�ł�����u���͐M����v�ƂȂ�܂��B�܂��A�`����Credo in unum Deum�ł�����A�u���͗B��̐_��M����v�ł��B����Et in unum Dominum Jesum Christum�Ȃ̂ŁA��܂��A���͗B��̎�C�G�X��L���X�g���i�M����j��ł��B����Et in Spiritum Sanctum�Łu�܂��A���͐�����i�M����j�v�ł��B�����܂ł��u�O�ʈ�́v�̊e�X��M����Ƃ��������B���Ă̂Ƃ���AEt�̂��Ƃ�Credo���ȗ�����Ă��܂��B������A���̌�ɑ������̈�߂����REt in unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam�u�܂��A���͗B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�p���̋�����i�M����j�v�łȂ���Ȃ�܂���BCredo�͎������ł�����ړI�������Ƃ��́Ain �����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���������ĕ��@�I�ɂ����̗��ꂩ����uin����v�������ƍl����̂����R�ł��傤�B
�i�R�j�����́u�~�T�ʏ핶�v�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂�
�@�@�@Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam
�@�@�@�킽���́A���Ȃ�A���Ղ́A�g�k�I�A�B��̋����M���܂�
��̕��͂́A���{�J�g���b�N�i���c�T��ψ���s�u�~�T�ʏ핶�v�́uCredo�v���瓖�Y�������R�s�[�������̂ł��B���{�J�g���b�N�i���c�̓��[�}���c������A�Ȃ鐳���ȋ@�ւȂ̂ŁA���̓T�當�͌����̂��́B���2004�N�ɋ��c������F���ꂽ�ŐV�����L���܂����B�����̂Ƃ���A�O�f�u���Z���~�T�ȁv��"�̎��J�[�h�Ɠ���"�ŁA�����ɂ�in������܂���B���@�I�ɂ����̗͂��ꂩ����uin����v���������Ƃ��ꂽ�̂ɁA�uin�i�V�v�ƂȂ��Ă���B��̂��̎������ǂ����߂����炢���̂ł��傤���B���̂��߂ɂ́uCredo�v�̐����ɂ܂ők��K�v������܂��B
�i�S�j�uCredo�v�i�M�錾�j�̐���
���[�}�c��R���X�^���e�B�k�X1���i272�|337�j�́A313�N�A�~���m���߂z�B����ɂ��L���X�g���k�ɑ���M���̎��R���ۏႳ��܂����B���肵�������̂��߂ɂ͐��͂𑝂��������L���X�g���k���X���[�Y�������悭��荞�ޕK�v���������B���̂��߂ɂ̓L���X�g���k���ꖇ��ɂȂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�Ƃ��낪���k���ł̋��`�͂�������Ɠ��ꂳ��Ă��炸�A����"�_�ƃL���X�g�͓�����̂ł͂Ȃ�"�Ɓu���E�O�ʈ�́v�̗�����Ƃ�A���E�X�h�̑䓪�̓L���X�g���k����̊�@�����s��ł����̂ł��B�����ōc���325�N�A��P�j�P�A����c���J�Â��܂��B��c�́A�_�ƃC�G�X�E�L���X�g�Ɛ���͓�����̂ł���Ƃ����u�O�ʈ�́v�����`�Ƃ��Č��F�A�u�j�P�A�M���v���̑����܂��B�S���̓M���V����ŏ�����A�Ō�ɂ́u"�_�̎q�͈قȂ�{����萬�����"�Ɛ�ׂ�҂���A�����Ȃ�g�k����́A�ׂ��v�Ƃ������t�Ō���ł��܂��B�����ɃA���E�X�h�͔r�˂���A�ْ[�r�˂�ړI�Ƃ������c�̌��`�́A�����Ɍ`�����ꂽ�̂ł��B
�e�I�h�V�E�X�P���i347�|395�j�́A381�N�ɁA�R���X�^���`�m�[�v������c���J�Â��܂��B���̉�c�ł́A�O����c�ō̑����ꂽ�u�j�P�A�M���v�����ƂɁA�M�Ƃ������̂����[���@�艺���A�u�O�ʈ�́v����薾�m�ɑł��o���A�ْ[�r�˕��̑���ɁA�u�i���[�}�E�J�g���b�N����j"�B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�p���̋���"�ł���v�Ƃ̕�������ꂽ�M�錾�����̑����܂����B���̍Ō�̕��������A�{�͂̃e�[�}�ł��� Et unam sanctam cathoricam et apostolicam Eecclesiam �ŁA�����Ő����ɍ̑����ꂽ�u�M�錾�v���u�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�ł����B����̓M���V����ƃ��e����ŏ�����Ă��܂����A���e���ꕶ����{�J�g���b�N�i���c�T��ψ���s�́u�~�T�ʏ핶�v�́uCredo�v�Əƍ�����ƁA�s�^���ƍ��v���܂��B���������āA�u�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�́A�̑��ȗ�1600�N�ȏ���̊ԁA�ς�邱�ƂȂ�����܂Ōp������A���̂܂܂̌`�Łu�~�T�ʏ핶�v�́uCredo�v�Ƃ��Č������Ă���B �Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���݁A�u�j�P�A�M���v�Ƃ����A��ʓI�Ɂu�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�̂��Ƃ��w���܂��B���ɁAJ�DS�D�o�b�n�u�~�T�ȃ��Z���v��Q���̕\���ɂ́A�uNo�D�U SYMBOLUM NICENUM�v�Ə�����Ă���A����́u�j�P�A�M���v�Ƃ������e����B���̓��e���u�j�P�A��R���X�^���`�m�[�v���M���v�Ȃ̂͏ƍ�����Έ�ڗđR�B���̂��߁A�M���V����ŏ����ꂽ�I���W�i��325�N�̑��́u�j�P�A�M���v���u���j�P�A�M���v�Ƃ��ċ�ʂ��Ă��܂��B
�����"�V���[�x���g���폜�������"�̔��˂ɍs�������܂����B�u�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�̍̑��͐���381�N�B�u�~�T�ȁv�͍ŌÂ̂��̂ł�14���I�̍�i�B�Ƃ������Ƃ́A���ׂẴ~�T�Ȃ́uCredo�v���̈�߂��uin�i�V�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��H ���ݓ���́u�~�T�v�ɂ�����u�M�錾�v�iCredo�j�͍����Ƃ̌��t�ŏ�����Ƃ��������ɂȂ��Ă���ƕ����܂��B�������{�ł��A2004�N�ɍ̑����ꂽ���������ɂ���u�M�錾�v�����サ�Ă��܂��B�܂��A�����Ɠ����̕����ɂ��u�M�錾�v���̂��̂̈Ⴂ������悤�ł��B���������āA�u�M�錾�v�́A���ۏ�l�X�Ȍ`�ő��݂���̂ŁA�u�~�T�ȁv�̉̎����e�ɂ��Ă͌y�X�����f��ł��Ȃ��A�Ƃ����������܂��B�Ƃ͂����A�u�M�錾�v�i�u�~�T�ʏ핶�v��Credo�j���u�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�ł���Ƃ��������͓������������A���������āA�A�C���V���^�C�����������悤�ɁA�~�T�Ȃ̒��Łuin����v�ɂȂ��������͂��肦�Ȃ��Ǝ��͍l���܂��B����́A�Ȃ��uin�i�V�v�Ȃ̂��H �u�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���v�i�ʏ́F�j�P�R���j����̓�ɔ���܂��B
2010.01.11 (��) �i�����ƃ��q�e��
�@��N��A���ɍs��ꂽ��60��NHK�g���̍���ɁA���炪�i����Ɩ��i�g���T�v���C�Y�E�Q�X�g�Ƃ��ēo�ꂵ�܂����B�������啨�̍g�����o��́A���㐏��̐l�C�O���[�v���̉̏���g�[�N�̍Œ��ɁANHK�z�[���̊y����������ւ܂���ʂ铹�����ׂĂ��J�������ǂ��Ƃ���VIP�X�^�C���B�̂��͍ő�̃q�b�g�ȁu���Ԃ�~�܂�v�B�Ƃ��낪�̂̏o�����ŁA"�߂Ȃ�� A�� PACIFIC �܂Ԃ����悤"�Ƃ���Ă��܂����B�I�C�I�C�����Ȃ�܂Ԃ������Ⴄ�̂���B"�܂Ԃ����悤"�̓����E�R�[���X�ŏI�s�̉̎��B������"�ɂ��R����C"���X������Ă��܂����̂ł��B�����Ă鎄�͓��Ɍ�����薬�����ł��̖{�l���Ȃ���̕����オ��B�����t���[�Y��"�ǂ���� ����̕�������"�͖����ʉ߁A"�܂Ԃ����悤"���J��Ԃ��`�Œ��߂Ĉꉞ���Ȃ������Ɍ����܂����B�Ƃ��낪�A�i�����A���h�͎��܂��Ă��Ȃ������A�Q�R�[���X�ڂ̓����ӏ�"�₦���W�����"��"�����̒j��"�ƁA�������Ƃ܂����������ԈႢ�����ł����Ă��܂����B�����A�����Ȃ���������V���o�_�o�BNHK�͍Q�Ăăe���b�v�������đΉ�������A"���锧�̍��肪"���ǂ��g�`��������"���̎�ɍ��肪 ����𐌂킹��"����킯���킩��Ȃ��B�Ō�"���Ԃ�~�܂� ���̖�ῂ̒���"�ƂȂ�Ƃ����n���܂������A����Ă��ꂿ������i�����A��ῂ������̂͂������̂ق��ł����B�@�e���b�v���������g���Ƃ����A2003�N�̒����݂䂫����B���̔NNHK�u�v���W�F�N�gX�v�̎��́u�n��̐��v����q�b�g�A�g�����o��̑啨��NHK���p�ӂ����X�e�[�W�́A���l�_���̒n���g���l���ł����B2�R�[���X�ڂ̑�2��"����������̂�ǂ��� �P�����̂�ǂ���"���܂������o���Ƀ������[�[�B�����ʼn̎��e���b�v�������܂����B
�@�i�����̑�g�`���ł�����v���o�����̂́A�s�A�m�̋����X���@�g�X���t�E���q�e���i1915�|1997�j��1965�N6��16���I�[���h�o�����y�Ղōs�������C�u�^���ł��B���̉��y�Ղ́A��ȉƁE�s�A�j�X�g�E�w���҂ł���C�M���X�̎���E�x���W���~���E�u���e���i1913�|1976�j����ɂ���R������C���F���g�B�u���e���́A��ȉƂƂ��ẮA�̌��u�s�[�^�[�E�O���C���Y�v��u�푈���N�C�G���v�ȂǂŗL���ł����A�w���҂Ƃ��Ă��A���Ƀ��[�c�@���g�ӂƂ��Ă���A���ł��A�����ȑ�40��K550�A��38��K504��v���n�v��N���t�H�[�h�E�J�[�]���i�s�A�m�j���\���X�g�Ɍ}���Ẵs�A�m���t�ȑ�20��K466�A��27��K595�i��������I�P�̓C�M���X�����nj��y�c�j�Ȃǂ͖����̗_�ꍂ�����́B���āA����1965�N�̃I�[���h�o�����y�ՂŁA���q�e���̓u���e���w���C�M���X�����nj��y�c�ƃ��[�c�@���g�̃s�A�m���t�ȑ�27�ԕσ�����K595���������܂����B�Ƃ��낪�A���ꂪ�ƂĂ��Ȃ��㕨�Ȃ̂ł��B
�@��P�y�͖`���A�I�[�P�X�g���̏��t��2��30�b���������ƁA�s�A�m��\����������4���ߒe���āA�NJy��̍����̎肪��^�[�^�b�^�^�[�^�Ɠ���B���̂��Ƃ�"���Ȃ鍇���̎肠�Ƃ̃t���[�Y"��e���Ă��܂����B�v����ɍŏ��ɒe���ׂ��t���[�Y���X������Ă��܂����̂ł��B�r�b�N�������I�P�͍Q�Ăč����̎������B�s�A�m�͒e��������̃t���[�Y������B�������t�̊ԉ����l�����ł����Ă����̂ł��傤���H��A���̉i�����̃p�^�[���ƑS���������Ԃ���������������̂ł��B
�@���̋Ȃ̓��[�c�@���g�Ō�̃s�A�m���t�ȂŁA���̔N1791�N�̍�i�B���̔N�ɋ��ʂ̏��ꂽ�������������A��Ƃ��Ė��ʂȉ��̂Ȃ����k���ɂ܂閼�Ȓ��̖��ȁB����Ȑ����̉��̂悤�ȏ����ȋȂ̃h���ŁA�������t���[�Y���X���������t���[�Y���J��Ԃ�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������t�s�ׂ́A���Ԃ��̂��Ȃ��厸�ԃp�t�H�[�}���X�Ƃ�����������܂���B�o�@���������ꂽ�w���҃u���e���́A���̏����̂悤�ȑ@�ׂȐ_�o���Y�^�Y�^�Ɉ�����A���̌�̃s�A�m�E�\���Ƃ̊|���������S�����ɂ��炸�̋��B�܂��ɃV���o�_�o�̉��t�ƂȂ��Ă��܂����̂ł����B
�@������A�i�����A�g���̃~�X�ȂC�ɂ��邱�Ƃ͂���܂���B���E�̋���������Ȏ��Ԃ������Ă���̂ł�����B�������i�����́A���̋ȁu�R�o���g�̋�v�ł́A�������悭�����ɉ̂�����������Ȃ��ł����B���q�e�������t�S�̂�䖳���ɂ������Ƃ��v���Η��h�Ȃ��̂ł��B���A���E�ň�ԗ�������ł���̂̓^�C�K�[�E�E�b�Y�Ƃ����̂�����Ȃ�A������A�i�����͓�Ԗڂ����ƈꎞ�͐S�z���܂������A�ǂ��Ƃ������Ƃ͂���܂����B�����ǂ�ő����ł��C����a�炰�Ă���������K���ł��B
�@���̉��t��CD�Ƃ��Đ��ɏo�Ă���̂ŁA�����̂�����͂������ɂȂ��Ă݂Ă��������B����A�J�g���b�N�̃~�T�Ȃ̂��ƂׂɁA���̉��y�������ɍs�����Ƃ��A�Ђ���Ƃ��Ă���CD�̉��t�]�͂ǂ��������̂��ȂƁA�y���C�����Łu���R�[�h�|�p�v�̃o�b�N�i���o�[���{�����Ă݂܂����B2000�N2���V���̂���CD�́A�u���R�|�v���N3�����̋��t�ȗ��Ŏ�肠�����Ă��܂����B��������Ď��͖ڂ��^�����̂ł��B�Ȃ�ƁA���̒��Ղ��u���I�Ձv�ɂȂ��Ă���ł͂���܂��I�I�u���R�[�h�|�p�v�̃��R�]�́A���CD���l�̌��]�q���]�����A��l�����āu���E�Ձv�ɂ������̂��u���I�Ձv�Ƃ��āA���̌��̐V���̍ō��]��CD�ƂȂ�̂ł��B���̂Ƃ��̕]�҂͉̍�a�F�A���q���u�̗����B�܂��͔ނ�̕]�����܂��B
[�̍莁�]]�@�Ƃ܂��A������Ƃ��x�^�J�ߑ各�E�ł���܂��B�ނ炪�����������̂ł�����A�ǂ��������R�ɂōς܂����Ǝv�����̂ł����A�����������킹�Ă��炢�����Ȃ�܂����B�����l�Ƃ��A"���q�e�����̃X������s��"�ɂ͑S���G��Ă����܂���B�N�������Ă������ɔ���~�X�v���C�Ȃ̂ɂł��B����͂ǂ��������Ƃł��傤���B������"�S���C�Â��Ȃ�����"��"�C�Â��Ă������Ȃ�����"�̂ǂ��炩��������܂���B�O�҂̏ꍇ�́A���肦�Ȃ����Ƃ��������悤���Ȃ��̂ł����A�����{���ɂ����Ȃ�A������ɂ͑�ώ���Ȃ���A�h�����郌�R�|���]�q�ǂ��납�]�_�ƂƂ��Ď��i�������Ƃ��킴��܂���ˁB��҂̏ꍇ�́A����ȃ~�X�͑債����������Ȃ��Ǝv��ꂽ�̂��A����Ƃ��A�����������o���I�[������������ė]�肠��Ɗ�����ꂽ�̂��A�ǂ��炩�Ȃ̂ł��傤�B��������ɂ͗���s�\�B�O�q�����Ƃ���A���̖`���̃~�X�v���C�́A���k����܂�Ȃ�K595�Ƃ�����i�ɂ����Ă͒v�����ł���A������@�m�������t�҂�䩑R�����A���̂��ƁA�I�P�̓s�A�m�Ƃ̎n�����k�����������A�z�����͓�x�̃~�X�u���E�����A�s�A�m�͓x�X�w�̘C�������Ȃ��Ȃ�B��ɋC�ɂȂ����̂͑�3�y�͂̃����h���̃t���[�W���O�ŁA���̍���ɔ߂��݂�X���������悤�ȃ����f�B�[���A�ςɕȂ̂���̂��܂킵�Ńu�`�Ă���B����Ȗ����ȕ\���͂�����Ƃ���ŎU������A�Ȃ̖{���ƗV�����邱�Ɛr���������t�Ȃ̂ł��B
�u���e������ɂ����I�[���h�o�����y�Ղ̘^���W�ŁA���ڂ����̂́A��͂胊�q�e�����\���X�g�Ɍ}�������[�c�@���g�́�s�A�m���t�ȑ�27�ԁ₾�낤�B50�ƂȂ��ĊԂ��Ȃ����q�e���́A���̋����Ȃ�ł̖͂����ʂ��ꂽ���x�ȉ����_�炩���@�ׂɐ������āA���������킢�[�����t�������Ă���B��P�y�͂͏����}�����݂��ȂƎv���邪�A����Ɋ����������Ă䂭���t�́A�_�炩�����������ƂƂ��ɁA��i�ւ̐[�������ɗ��ł����ꂽ�e���������Ȃ��Ă���A�����L���ł���B�u���e���ƃC�M���X�����nj��y�c���A�����L���ȕ\���ɂ���āA�����������q�e���̃\�����d��I�݂ɃT�|�[�g���Ă���B
[���q���]]
BBC�����̉����ɂ���A�̃V���[�Y�Ƃ��āA���t�ƂƂ��Ẵu���e�������[�c�@���g�����t�����ۂ̃��C�����W�߂��ꖇ���o�ꂵ���B�w���҂Ƃ��Ẵu���e���́A�����ɂ���ȉƂ炵���k���ȕ��ǂ݂ŁA�Ȃ̂Ȃ����U�@�̉��y��������Ƃ��Ă���B�܂��A��ɁA���t�̌���Ɋւ���Ă������Ƃ������āA���������`�̓Ƃ�悪��ȃA���o�����X�Ƃ͖������B���̃u���e���̖_���������߂ɕ~���߂��O�~�̏�ŁA���q�e���̓t���[�Y�P�ʂ̎��݂ȐL�k��K�x�ɐD������Ȃ���A�����O�̖��x�̍������y���J��L����B���ʊ��̂���^�b�`�ƁA����I�Ȍ����ɂ�郂�[�c�@���g���߂̌��{�̂悤�ȏG�����B
�@�����Ȃ��A�N���t�H�[�h�E�J�[�]���i�s�A�m�j�������u���e���w���C�M���X�����nj��y�c�Ƌ�������1970�N�̘^��������܂��B����͐��k�ɂ��Ċ��������Ƃ����f���炵�������ł��B����Ɣ�ׂ�A�i�����҂������ł��j�����Ƀ��q�e���Ղ����������꒮�đR�ŕ�����̂ɁA������́A�]�_���A����Ȋ�{�I�Ȓ�����ׂ����ĂȂ������̂ł��傤���B���Ƃ������͑Ӗ��B���܂�̉䂪���N���V�b�N�]�_�̎��̒Ⴓ�ɕ�������ł��B������ɂ��Ă��A�����Ȃ�CD���^���Ă��܂��悤�ȗ���s�\�Ȏ��������y�]�_�Ƃ���l�ƁA�ނ�����F���]�q�Ƃ������{�̃N���V�b�N���D�Ƃ̎w�j����ׂ��|�W�V�����ɐ����Ă������y�V�F�Ђ́A10�N�O�̂��ƂƂ͂����A�ҏȂ��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B���̌エ����̃��R�]���ǂ��ς�����̂��͑����グ�܂�������C������܂��A�����q���́u�nj��y����v�̌��]�ɉ��A�̍莁�͌��]�q�����~�肽���̂́A�u���R�[�h�A�J�f�~�[�܁v�I��ψ��Ƃ��Ă��������ł��B
�@��A���ANHK�z�[���Ŗ��i��������オ���Ă��ꂽ�������ŁA�V�N��������ʔ����������������̂ł��B�����͏t���牏�N�������H���N���u�N�����m�v�ɁA�ǂ��������҂��������B
2009.12.25 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��8�`�~�T�ȑ�6��
����A�����݂䂫�́u���VOL.16�v���ς܂����B����͋ߔN�̑�ȔN���s���B����́u�{�ƁE���Ӊ��v�B�f�ނ́u�����Ɛ~�q���v�`���B�ꐶ�͏I����Ă��܂����Z�b�g����āA���́A�܂�����ȂƂ��납���蒼����Ƃ����ӂ��ɁA���̂��납�炩�A���̍��ł͌������Ă��邩������Ȃ��B����̏�������B�Q�[����������B��������ł����̂��낤���B�{���́A�߂����߂��݂����ׂė����Ɉ����p���ł䂭���̂ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B���܂ꂽ�q���̏��ɂ͑O�������܂�Ă���ׂ��ł͂Ȃ��̂��B�ꂵ�݂Ɛ킢�A�ς��Ȃ��琶���ʂ����Ƃ������A�����ւ̖ƍߕ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�Ȃ�ł�����ł��ȒP�Ƀ��Z�b�g���Ă��܂��Ė{���ɂ����̂��낤���H���ꂪ�ޏ��̋^��B��Ղ̔N�̍�i���u�~�T�� ��6�� �σz����D950�v������܂��B���̋Ȃ̓V���[�x���g�Ō�̏@�����y�ŁA1828�N�̉ĂɊ������Ă��܂��B
�i�P�j�_�̏��r
�u�~�T�ȑ�6�ԁv���āA�ł��S�ɐZ�݂镔���́A���ɂƂ��Ắu�_�̏��rAgnus Dei�v�ł��B�u�_�̏��r�v�́A���ׂĂ̍߂�w�����ď\���˂ɉ˂���ꂽ�C�G�X�E�L���X�g�𐒂߁A����݂��������B�ʏ�̃~�T�Ȃł́A���߂�C�������h�i�Ő����ȋȑz�ɏ悹�A����݂���Ƃ���Ō��I�v�f������������̂�����܂��BJ�DS�D�o�b�n�u�~�T�� ���Z���v�̂���͐����̋ɂ݁B�t�H�[���́u���N�C�G���v�͓����Ȕ������̒��Ɍ���������o���܂��B���F���f�B�́u���N�C�G���v�́A�o�������A�J�y���ɂ��āA��ւ̌h�i�ȋC�������������Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�~�T�ȑ�6�Ԃ́u�_�̏��r�v�ł́i�u��������݂��܂��v�ň�u�h�i��������o�����̂́j�I�n��єߒɂȋ������[�����Ă��܂��B�܂�ŃV���[�x���g�̜ԚL�̂悤�ȁB����ȁu�_�̏��r�v�͕��������Ƃ�����܂���B
�V���[�x���g��6�̃~�T�Ȃ������Ă��܂����A��A�̗���̒��Łu�_�̏��r�v�������Ă݂܂��B�̎��͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�@�@�@�@Agnus Dei�Cqui tollis peccata mundi miserere nobis�I
�@�@�@�@�_�̏��r�@���̍߂��������������@��������݂��܂�
��P�Ԃ֒���D105�i1814�N�̍�i�j�́u�_�̏��r�v�ɂ͐����Ő����ȋ���������܂��B��2�ԃg����D167�i1815�N�j�ł́A�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���i1880�|1952�j�ɂ��A"�u�_�̏��r�v�͍ł��@�ׂōł�������������������Ă���y��"�i�����Њ��u�V���[�x���g���y�I�ё��v���j�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��3�ԕσ�����D324�i1815�N�j�Ƒ�4�ԃn����D452�i1816�N�j�́A�R��I�Ŕ������ȑz�̑O�����A���ǂƑŊy�킪������ăL���X�g�]�̂̎���o���㔼�Ɏ���đ���Ƃ����A���ʂ�������������܂��B��5�ԕσC����D678�i1819�N�j�́A�����������Ȓ��̒��Ɍh�i�ȋF��̋C������\�o���Ă��܂��B
���̂悤�ɑ�P�Ԃ����5�Ԃ܂ł́u�_�̏��r�v�ɂ́A�e�X�̓����͂���܂����A��6�Ԃɂ݂���悤�Ȕߒɂȋ����͂Ȃ��B�����đ�6�Ԃ̏�ɋ߂����̂𑼂̍�ȉƂ̍�i�ɋ��߂�ƁA���[�c�@���g�����̑��u�n�Z���~�T�ȁv�ɂȂ�ł��傤�B���̍�i�́A�����̍ȃR���X�^���c�F�Ƃ̌������肤���[�c�@���g���A�ޏ��Ƀ\���E�p�[�g���̂킹�ĉƑ��ɏЉ�邱�Ƃ�ژ_��ō�邱�Ƃ��v���������Ƃ����Ă��܂��B���ۂ̍�Ȃ͌����̗��N�ɍs���܂������A�ޏ��s�����U���c�u���N�ւ̗��ɂ͊Ԃɍ��킸�A���Ɋ������݂邱�Ƃ͂���܂���ł����B���������Ă��̋ȂɁu�_�̏��r�v�͑��݂��܂���B�������J�g���b�N�̃~�T�Ȃ́u��ɉh������Gloria�v�̒��ɂ́A��LAgnus Dei�ȉ���qui tollis����̕��߂��܂܂�Ă��܂��B���[�c�@���g�̂��̕������ƁA�����̏ɍ�����Ƃ����ژ_�݂Ƃ͗����ɁA���ɕ��߂��������ɖ����Ă��܂��i���[�c�@���g���Ȃ�����ȋȑz��I�̂��Ƃ����l�͂��̍ےu���Ă����܂��j�B�Ƃ͂����A����͔ߜƊ��Ƃ������ׂ���ŁA�V���[�x���g�̔ߒɂ��Ƃ͔����ɈႤ�B�V���[�x���g�́u�~�T�ȑ�6�ԁv�ɂ�����u�_�̏��r�v�ƃO���[���A�u���̍߂�����������́E�E�E�v�ɐ��ޔߒɂȋ����́A���ꂱ���ٗl�Ƃ����ׂ��ł��B���͂����ɃV���[�x���g�̉e�����܂��B
�i�Q�j�T��ɂ͎g���Ȃ��~�T��
�V���[�x���g�̃~�T�Ȃ͓T��ɂ͎g���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B����̓~�T�Ȃ́u���͐M��Credo�v�ɒʏ�܂܂���s���폜����Ă��邩��ł��B�ʏ�̃~�T�Ȃ͂����Ȃ��Ă��܂��B
�@�@�@�@���͐M���A��Ȃ鐸��A�����̗^���傽����̂�
�@�@�@�@���́A���Ǝq��肢�ŁA���Ǝq�ƂƂ��ɔq����A�����߂��
�@�@�@�@�a���҂ɂ��Č�肽�܂������́B
�@�@�@ *�܂��A�B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�̋���Ȃ�B
�@�@�@�@�iEt in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam�j
�V���[�x���g�́A���̍Ō�̍s *�u�܂��A�B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�̋���Ȃ�v���Ȃ��Ă��܂��B����́u��6�ԁv�Ɍ��炸�ނ̑S�Ẵ~�T�Ȃɋ��ʂ��Ă��錻�ۂł��B�ł́A�Ȃ��ނ͂��̕��߂��Ȃ����̂ł��傤���H����ɂ��ẮA�V���[�x���g�̐M�Ɋւ����Ƃ��āA�̂��珔��������܂����A�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���́u�V���[�x���g���y�I�ё��v�̒��Łu�~�T�ȂƃV���[�x���g�̐M�v�Ƃ������ڂ�݂��A���������Ă��܂��B
��V���[�x���g�̓��ِ����ǂ�����������悢�ł��낤���H�V���[�x���g�͎����̂����ł��̌��͂ɂЂ����ɍR�c�����̂��H �w�m���K���̏��ł������́x�Ƃ��w�����C�����L���X�g��A�Ȃ�Ƒ����̈��s�Ɍ�g�͂��̎p��݂��^������˂Ȃ�Ȃ��������x�Ƃ����������܂킵�i1825�N9��12���\21���t�F���f�B�i���g���Ă̎莆�j�́A�����ċ���ɑ���h�ӂ�\���Ă͂��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�V���[�x���g�̈Ӑ}�A�R�c���\�����Ă݂�̂͊ԈႢ�ł��낤�B�������̏ȗ�����N�̃~�T�Ȃ����ɂ���Ȃ炻����ł��悤���A17��18�̏��N�̏ꍇ�ɂ͂���͂ł��Ȃ��B�ł��P���ōł����肫����̐����́A�ނ��~�T�̃e�N�X�g�̎ʂ�������āA�������肠��8������A�~�T��Ȃ̂Ƃ��ɂ͂������̓����ʂ����g�����Ƃ������Ƃ��낤��V���[�x���g��1818�N10��29���A�Z���ɏ������莆�̒��ɂ���Ȍ�������܂��B
�u�V��Ƃ����푰�ɑ���Ë���m��Ȃ������͌Z����̖��_���B�ł��A����ȌZ����ɂ��z�������Ȃ����낤�ȁA�����̖V��Ƃ������ɂ́A�V���ڂꂽ�ʔn�݂����ȋU�P�҂ŁA���o�̐e���݂����Ƀo�J�ŁA�����݂����ɃK�T�c�ȘA������Ȃ̂��B���������Ă���ƁA���̈����ɍ��܂Ő��܂����l�|���c�F�[�l�_���ł��܂�������F�Ƃ������炢�q�h�C���̂��v����͂����炭�A�A�C���V���^�C�������p�����u�m���K���̏��ł������́v�Ƃ��������ɑ���������̂Ǝv���܂��B���̎莆���������̂�21�ł�����A�ނ������u17�A8�̏��N�ɂ͂���͂ł��Ȃ��v�͂��������Ǝv���܂��B�ނ̂悤�ȓV�˂�18��21�ɁA���̊�{�I�v�l��Ղ̍��قȂǁA�͂����Ă���̂ł��傤���B�܂��A�ނ͓��L�̒��Łu�M�S�́A���ʂƂ��m���Ȃ��A�͂邩�ɑ������������̂��v�Ƃ������Ă���̂ł��B���́A�f���ɁA���ꂱ���A�l���̑�����������萶���Ă����V���[�x���g�̑m��������ւ̕s�M�̏ƌ��܂��B���������āA���߂̍폜�́A�A�C���V���^�C���������u�e�L�X�g�̎ʂ��Ⴂ�v�Ƃ͎v���܂���B�Ⴆ���̃L�b�J�P���ʂ��Ⴂ�������Ƃ��Ă��A����u�B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�v�Ƃ͎v����͂����Ȃ������ł��傤�B���͂�����O�����̂̓V���[�x���g�̈ӎv�ɈႢ�Ȃ��Ɗm�M���܂��B
�i�R�j�V���[�x���g�̐M�S
����ȁA����s�M�����V���[�x���g�̐M�S�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂������̂ł��傤���B�O���ł��ꕔ��肠�����ނ̓��L�̑S���Ǝ莆�����p���܂��B
�u�M�ƂƂ��ɁA�l�Ԃ͐��̒��ւ̑����ݏo���B�M�́A���ʂƂ��m���Ƃ��A�����������̂����A�͂邩�ɑ������������̂��B�Ȃ��Ȃ�A�����𗝉����邽�߂ɂ́A���͂��̑O�ɁA������M���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B�M�͂�荂���n�Ղł����āA���̏�ɁA��X�����m�������̍ŏ��̏ؖ��̍Y��ł����ނ̂��B�m���Ƃ́A��̕��͂��ꂽ�M�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��v�i1824�N3��28���̓��L�j�����Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�V���[�x���g�̐M�S�ɂ͗h�邬�Ȃ����̂�����܂��B�͂�����ƁA�M�����m���ɗD�悷����̂ƈʒu�Â��Ă��܂��B�������ւ̎]�̂Ƃ͂����m�u�A���F�E�}���A�v�̂��Ƃł����A�����ł́A�h�i���Ƃ������̂��A�����ɂƂ��Ă͗�������Ȃ��A"���₨���Ȃ��Ɉ��|��������"�ł����āA���ꂱ�����^���̌`�ł���ƒf�����Ă��܂��B����͔ނ̊m�ł���M�S�̕\��ł��B�g�k�Ƃ��Ă̋���͐M�p���Ă��Ȃ���������ǁA�B���̐_�̂��Ƃ͐M���Ă����B
�u�l�X���������̂́A�܂��A�ڂ����������ւ̈�̎]�̂ɂ����ĕ\�������l�̐M�S�[���ɑ��Ăł���܂����B���̋Ȃ͂����Ƃ��ׂĂ̐l�̂�����𑨂��āA�h�i�ȋC�����ɂ����邱�Ƃł��傤�B�ڂ��͎v���̂ł����A����́A�ڂ�����x���������������Čh�i�ɂȂ낤�Ƃ������Ƃ��Ȃ��A���₨���Ȃ��Ɍh�i���Ɉ��|�����ȊO�́A�����Ă��̂悤�Ȑ���]�̂�F��̉̂���Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��炫�Ă��܂��B�ł��A���ʂ͂��ꂱ���������^���Ȍh�i���Ȃ̂ł��v�i1825�N7��25���A���e�ƌp��Ɉ��Ă��莆�j
�����炱���A�~�T�̃e�L�X�g����u�܂��A�B��̐��ɂ��Č��Ȃ�g�k�̋���Ȃ�v���폜���āA�B���̐_�ڐM�����B���̍߂�w���������Y�ɏ�����ꂽ�C�G�X�̌�S�ɒ��ɐG�ꂽ�B�����āA�u�_�̏��r�v�Ɏ����𓊉e�����B�s���̕a�ɐN���ꂽ�ꂵ�݂��C�G�X�̋ꂵ�݂ɏd�˂��̂ł��B�ނ́A�L���X�g�ɑ��A1824�N9��21���̎莆�̒��Łu���Ȃ����g���܂��ɁA�l�ԂƂ������̂̍߂̐[����������ł��S�܂����L�O�肾�����E�E�E�v�Ƃ��q�ׂĂ���B����قǃC�G�X�E�L���X�g�̋ꂵ�݂𗝉��������y�Ƃ������ł��傤���B�u�_�̏��r�v�̔ߒɂ��̓V���[�x���g�̃C�G�X�E�L���X�g�Ƃ̓����ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�V���[�x���g���s���̕a�ɐN���ꂽ�̂́A1822�N�̏I��育��Ƃ����Ă��܂��B��P�Ԃ����5�Ԃ܂ł̃~�T�Ȃ́A1819�N�܂łɏ�����Ă��܂��B���̂��Ɯ�a�B�Ō�̑�6�Ԃ͎��̔N1828�N�̍�B��͂�A���̍�i�ɂ͕a�̉e�����ĂƂ�܂��B���K��邩������Ȃ����̉e�ɋ����Ȃ��l�ԂȂ��Ȃ��ł��傤�B�V���[�x���g�����ė�O�ł͂Ȃ������͂��ł��B�������C���Ȃ��Ȃ������ĕs�v�c����Ȃ��B�ł��ނ͂ւ�����Ȃ������B��葱�����B�V���[�x���g�͍ł����ʂȍ�ȉƂƂ����Ĝ݂�Ȃ����c���q�͂��������܂��B�u�V���[�x���g�ɂ͎Ⴂ�Ƃ�����A���̐��E�Ƃ������A���̐��E���A���������������ł��B���ꂪ���鎞�A�z���͂̐��E����Ȃ��āA�����̂��̂ɂȂ��Ă��܂��A���ꂪ�N�����āB���ꂪ�N�����Ă���̃V���[�x���g���A�ς��̂ˁB�������̋ꂵ�݂ŏI���Ȃ��B���݂ŏI���Ȃ��v�i���R�[�h�|�p1997�N10�����̑Βk���j�E�E�E"���ꂪ�N������"�Ƃ����͖̂ܘ_�~�łւ̜�a�̂��ƁB�ޏ��́A���ꂪ�N�����Ă���V���[�x���g�̉��y���ς�����A�����A�u�ꂵ�݂ŏI��炸�ɁA���y��[���������v�Ƃ����̂ł��B����ɂ͎��������ł��B�s�^���߂������Ƃ��ĎƂ߁A�����w�����Ċ撣��ʂ��B���ĔƂ����߂��͉����̔O���ĂыN�����A���̋ꂵ�݂͓��X�����邱�Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B���Z�b�g��]���N���N�����͂��ł��B�ł��ނ̓��Z�b�g���Ȃ��l�����������B�������A�߉^�Ƃ����g��[���Ƃ����d�ɕς��Đ[���ȑn�������Y�ݏo�����̂ł��B���̋��ɂ��A��Ղ̔N1828�N�̌���Q�Ȃ̂ł��B�u�~�T�ȑ�6�ԁv�́u�_�̏��r�v�ɏh�鋿���͂��̈�̏ł͂Ȃ��ł��傤���B
����ɂ��Ă��A�V���[�x���g�̂ǂ��ɂ���ȗ͂��������̂ł��傤���H �Ȃ��A�ނ͂���ȑ傻���Ȃ��Ƃ�����Ă̂���ꂽ�̂ł��傤���H ������ł�����ςȉۑ�Ȃ̂ŁA�����Ƃ��ɕ����낤�͂��͂Ȃ��Ɗ����Ȃ�����A�𖾂Ɍ������ĂȂ�Ƃ��撣���Ă䂫�����Ǝv���������̍��ł���܂��B
2009.12.09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂV�`���͂Ȃ��
�V���[�x���g�̕a�C�Ɖ��y�Ƃ̊֘A�����l���Ă�����A���̒����g�b�`�������Ă��܂��āA�l�������͂��S�R�܂Ƃ܂�܂���B�f�����e�[�}�́u�V���[�x���g�͕s���̕a�ɜ�����ɂ��S�炸�A�Ȃ�����Ȃɂ��f���炵����i�����������邱�Ƃ��ł����̂��H�v�Ƃ����܂��Ɂu�N�����m�v�ɑ����������̂Ȃ̂ł����E�E�E�B�����̐��E�ɁA��������u���͂Ȃ��v�Ƃ����i��������̂ŁA�������Ă݂悤�E�E�E����Ă݂���A�ӂƐ̂��v���o���܂����B �������߂Č̋�����𗣂�㋞�����̂�1964�N�����I�����s�b�N�̔N�B����45�N���̂̂��Ƃł��B�������Z�̓������̗F�l�ƁA�g�ˎ��̎l�����������Ŏ�āA�Ԃ̓����������X�^�[�g�����܂����B�ƒ��͈��1,000�~����Ȃ̂ŁA�ꕔ��4,500�~�͈�l�����茎�X2,250�~�̏o��ŁA���݂Ƃ͊u���̊�����ł��B��l2�D25���Ȃ��o�J������Ԃł��A�����ɒy�������̓t���t���Ɗm���ɕY���Ă��܂����B���̍��A���ӂ̂悤�ɑ��_���畷�����ꂽ�Ȃ��A�W�����[�E�����h�����̂��u���̐��̉ʂĂ܂Łv"The End of The World"�ł����B�o���F�̖�����"The End of The World"�̎�荇�킹�͖��ł����A�������̂͂��� �ł����B���̋ȁA�I���W�i���̓X�L�[�^�[�E�f�C���B�X��C���v�̃q�b�g�E�i���o�[�ł����A�����V���O���E�q�b�g���Ă����̂̓u�����_�E���[�B�ޏ����p���`���������ĉ̂��̂ɑ��A�W�����[�E�����h���͂����Ƃ�Ɨ��������đ�l�̉̂����Ă��܂����B�����X�b�J���ޏ��ɖ������āA�x�X�g�E�A���o���uAll about Julie�v�����݁A�Â�悤�ɒ��������̂ł��B�u���̐��̉ʂĂ܂Łv�̂ق��ɂ́A�u�����E���^�[�Y�v�u�z���o�̃T���t�����V�X�R�v�u���Ȃ��Ɩ�Ɖ��y�Ɓv�u���@�C���E�R���f�B�I�X�v�Ȃǂ�����LP�ɓ����Ă��܂����B�T�˃~�f�B�A����X���[�̊y�Ȃ��悩�����̂ł����A�ō��ɋC�ɓ������̂̓A�b�v�E�e���|�́u�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���v�ł����B���ʂ́A�Ⴆ�t�����N�E�V�i�g���Ȃ��A�X���[���~�f�B�A���ʼn̂��Ă��܂����A�W�����[�̓{�T�m���@���̃A�b�v�E�e���|�ł̉̏��B���̃s�c�B�J�[�g�����Q�ɃS�L�Q���ŁA�v���œ���s�A�m�������Ă��܂��B����Ȗ������郊�Y���̏���A�W�����[�̋C���邢�n�X�L�[�E���H�C�X���X���[�Y�ɏ���Ă䂭�B���̃~�X�}�b�`�������ɑu�₩�ŐS�n�悢�B���t���Ԃ�2�����ƒZ���ĔZ���B
�������߂Č̋�����𗣂�㋞�����̂�1964�N�����I�����s�b�N�̔N�B����45�N���̂̂��Ƃł��B�������Z�̓������̗F�l�ƁA�g�ˎ��̎l�����������Ŏ�āA�Ԃ̓����������X�^�[�g�����܂����B�ƒ��͈��1,000�~����Ȃ̂ŁA�ꕔ��4,500�~�͈�l�����茎�X2,250�~�̏o��ŁA���݂Ƃ͊u���̊�����ł��B��l2�D25���Ȃ��o�J������Ԃł��A�����ɒy�������̓t���t���Ɗm���ɕY���Ă��܂����B���̍��A���ӂ̂悤�ɑ��_���畷�����ꂽ�Ȃ��A�W�����[�E�����h�����̂��u���̐��̉ʂĂ܂Łv"The End of The World"�ł����B�o���F�̖�����"The End of The World"�̎�荇�킹�͖��ł����A�������̂͂��� �ł����B���̋ȁA�I���W�i���̓X�L�[�^�[�E�f�C���B�X��C���v�̃q�b�g�E�i���o�[�ł����A�����V���O���E�q�b�g���Ă����̂̓u�����_�E���[�B�ޏ����p���`���������ĉ̂��̂ɑ��A�W�����[�E�����h���͂����Ƃ�Ɨ��������đ�l�̉̂����Ă��܂����B�����X�b�J���ޏ��ɖ������āA�x�X�g�E�A���o���uAll about Julie�v�����݁A�Â�悤�ɒ��������̂ł��B�u���̐��̉ʂĂ܂Łv�̂ق��ɂ́A�u�����E���^�[�Y�v�u�z���o�̃T���t�����V�X�R�v�u���Ȃ��Ɩ�Ɖ��y�Ɓv�u���@�C���E�R���f�B�I�X�v�Ȃǂ�����LP�ɓ����Ă��܂����B�T�˃~�f�B�A����X���[�̊y�Ȃ��悩�����̂ł����A�ō��ɋC�ɓ������̂̓A�b�v�E�e���|�́u�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���v�ł����B���ʂ́A�Ⴆ�t�����N�E�V�i�g���Ȃ��A�X���[���~�f�B�A���ʼn̂��Ă��܂����A�W�����[�̓{�T�m���@���̃A�b�v�E�e���|�ł̉̏��B���̃s�c�B�J�[�g�����Q�ɃS�L�Q���ŁA�v���œ���s�A�m�������Ă��܂��B����Ȗ������郊�Y���̏���A�W�����[�̋C���邢�n�X�L�[�E���H�C�X���X���[�Y�ɏ���Ă䂭�B���̃~�X�}�b�`�������ɑu�₩�ŐS�n�悢�B���t���Ԃ�2�����ƒZ���ĔZ���B �̂�z���o���āA���̂���A����ȃW�����[�E�����h����CD���Ă�����A�e���rCM����T���E���H�[���́u�����@�[�Y�E�R���`�F���g�v������Ă��܂����B����CM���͊m�F�ł��܂���ł������A�����60�N��̉��������q�b�g�E�i���o�[�B���Ȃ�J�DS�D�o�b�n�u�A���i�E�}�O�_���[�i�̉��y���v�Ɏ��^����Ă���g�����̃��k�G�b�g�ŁA����͓�����̍�ȉƃN���X�e�B�A���E�y�c�H�[���g�i1677�|1733�j�̍�i���o�b�n���ғ��������́B�W�����[�E�����h���̉̂́A�قƂ�ǂ��X�g�����O�X����ŁA���ꂪ���ɂ����̂ł����A�T���E���H�[���́u�����@�[�Y�E�R���`�F���g�v�������B�ŏ��ƍŌ�����ŕ�݁A�����̓W�����[�Ƃ͑ΏƓI�ɂ�⑾�߂̒j���ۂ����Ō����Ȃ��T�����Ɖ̂��Ă��܂��B�T���E���H�[���́A�G���E�t�B�b�c�W�F�����h�A�J�[�����E�}�N���G�ȂǂƋ��ɁA�������l�W���Y�E���H�[�J���X�g�̍ō���B�^���̂قƂ�ǂ̓V���A�X�ȃW���Y�E�A���o���ł����A���������Ă���u�����@�[�Y�E�R���`�F���g�v�����CD�́A�|�s�����[�ȃq�b�g�Ȃ�X�^���_�[�h�E�i���o�[���A�y�߂̃A�����W��20�Ȏ��^�����|�b�v�X�n�x�X�g�E�A���o���B���̂����X�g�����O�X����̊y�Ȃ͖��ŁA���Ƃ̓r�b�O�E�o���h�ƃR���{���t���o�b�N�ł��B�ʂ��ĕ����Ă݂�ƁA���t�̃T�E���h���Ȃ��ƂɈႤ�̂ŁA���̓s�x�Ȃɂ���a�����c��B���ɁA�W�����[�E�����h���Ƃ̋��ʋȂ�2�`3�Ȃ����āA���R�ƕ�����ׂĂ݂�������āB�Ⴆ�A�u�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���v�̓R���{���t�ŃX���[�A����̓X�g�����O�X����ŃA�b�v�E�e���|�̃W�����[�̂ق����f�R�����B�u�~�X�e�B�v�̓W���W�[�ȃt�B�[�����O���▭�̃T���̂ق��Ɉ���̒�����A�X�g�����O�X����ł����邵�E�E�E�ȂǂȂǁB
�̂�z���o���āA���̂���A����ȃW�����[�E�����h����CD���Ă�����A�e���rCM����T���E���H�[���́u�����@�[�Y�E�R���`�F���g�v������Ă��܂����B����CM���͊m�F�ł��܂���ł������A�����60�N��̉��������q�b�g�E�i���o�[�B���Ȃ�J�DS�D�o�b�n�u�A���i�E�}�O�_���[�i�̉��y���v�Ɏ��^����Ă���g�����̃��k�G�b�g�ŁA����͓�����̍�ȉƃN���X�e�B�A���E�y�c�H�[���g�i1677�|1733�j�̍�i���o�b�n���ғ��������́B�W�����[�E�����h���̉̂́A�قƂ�ǂ��X�g�����O�X����ŁA���ꂪ���ɂ����̂ł����A�T���E���H�[���́u�����@�[�Y�E�R���`�F���g�v�������B�ŏ��ƍŌ�����ŕ�݁A�����̓W�����[�Ƃ͑ΏƓI�ɂ�⑾�߂̒j���ۂ����Ō����Ȃ��T�����Ɖ̂��Ă��܂��B�T���E���H�[���́A�G���E�t�B�b�c�W�F�����h�A�J�[�����E�}�N���G�ȂǂƋ��ɁA�������l�W���Y�E���H�[�J���X�g�̍ō���B�^���̂قƂ�ǂ̓V���A�X�ȃW���Y�E�A���o���ł����A���������Ă���u�����@�[�Y�E�R���`�F���g�v�����CD�́A�|�s�����[�ȃq�b�g�Ȃ�X�^���_�[�h�E�i���o�[���A�y�߂̃A�����W��20�Ȏ��^�����|�b�v�X�n�x�X�g�E�A���o���B���̂����X�g�����O�X����̊y�Ȃ͖��ŁA���Ƃ̓r�b�O�E�o���h�ƃR���{���t���o�b�N�ł��B�ʂ��ĕ����Ă݂�ƁA���t�̃T�E���h���Ȃ��ƂɈႤ�̂ŁA���̓s�x�Ȃɂ���a�����c��B���ɁA�W�����[�E�����h���Ƃ̋��ʋȂ�2�`3�Ȃ����āA���R�ƕ�����ׂĂ݂�������āB�Ⴆ�A�u�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���v�̓R���{���t�ŃX���[�A����̓X�g�����O�X����ŃA�b�v�E�e���|�̃W�����[�̂ق����f�R�����B�u�~�X�e�B�v�̓W���W�[�ȃt�B�[�����O���▭�̃T���̂ق��Ɉ���̒�����A�X�g�����O�X����ł����邵�E�E�E�ȂǂȂǁB���Ƃ��Ǝ��́A�X�g�����O�X����̃W���Y����D���ŁA�Â��́A�`���[���[�E�p�[�J�[�u�E�B�Y�E�X�g�����O�X�v�A�N���t�H�[�h�E�u���E���u�E�B�Y�E�X�g�����O�X�v����60�N���MJQ�u�T�[�h�E�X�g���[���E�~���[�W�b�N�v�A�E�F�X�E�����S�����[�uFUSION�I�v�u�A�E�f�C�E�C���E�U�E���C�t�v�AK&JJ�u�C�X���G���v������܂ŁA���ꂼ�ꂪ�A�c����C�����x�܂�㎿�Ȗ����n���y�ł��B
�����������Ă��邤���ɑM�����̂��A�W�����[�E�����h���ƃT���E���H�[���̃X�g�����O�X����v���C���F�[�g�E�R���s���[�V�����ł����B�悵�A��l�̏����̎��l�̉̏������݂ɕ��ׂāA���E��only one�̃A���o��������Ă݂悤�I
���肵���u�W�����[���T���v�̂����Ƃ����E�v���C���F�[�gCD�̐���R���Z�v�g�͈ȉ��̒ʂ�B�@�K���X�g�����O�X����ł��邱�ƇA�I�Ȃ̓X���[�ƃ~�f�B�A�����d�_�Ƃ��邱�ƇB���ꂵ���A�����W�Ƃ��������@�͔r�����邱�ƇC��l�̔䗦�̓W�����[�E�����h���Q�ɑ��T���E���H�[���P�ɂ��邱�ƁB�����ŏo���オ�����̂��v���C���F�[�gCD�u�W�����[���T�� LOVE SONGS�v�B�W���P�b�g�̓N�����g�́u�ڕ��v�B�Ȗڂ͈ȉ��B
�u�W�����[���T�� LOVE SONGS�v�u�ڕ��v�̃W���P�b�g�����Ȃ��炱��CD���܂��B�W�����[�E�����h�����Ă���ƃT���E���H�[�������������Ȃ�B�T���������ƃW�����[�����������Ȃ�B�꒮���Đ��͈Ⴄ���W���Y�I�t�B�[�����O�����������Ⴄ��l�Ȃ̂ɁA�Ȃ����s�v�c�ȃu�����h���������ɂ���܂��B�e�X���ۗ����Ă���̂ɗn�������Ă���B����Ȑ▭�ȃv���C���F�[�g�E�R���s���ł�������܂����i���`��c������O���X�Ȃ��Ƃ͏��m���Ă���܂��j�B���Ĕ�Ȃ���́A��Ŏ�������̂Ȃ̂ł��傤���B�Ȃɂ�����A�V���[�x���g�ƃ��[�c�@���g�̊W�Ɏ��Ă��邩�� �Ȃ�Ă��Ƃ��v�����点�Ȃ���A�y���������Ă��܂��B����ȁA������Ƌ��͂Ȃꂽ�������̍��ł����A���C���X�g���[���ʼn������M���ł��傤���H ����A���������ė~�������̂ł��B
�@ �z���o�̃T���t�����V�X�RJ
�A �t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[��J
�B �����@�[�Y�E�R���`�F���gS
�C �����E���^�[�YJ
�D ���ƃo���̓��XJ
�E �C�G�X�^�f�CS
�F ���E���h�E�~�b�h�i�C�gJ
�G ���f�̃����cJ
�H �V���h�E�E�I�u�E���A�E�X�}�C��S
�I �h���[��J
�J ���ɗ������Ƃ�J
�K �}�C�E�t�@�j�[�E���@�����^�C��S
�L ���̂����䂭�܂�J
�M �~�X�e�BS
�N ���̐��̉ʂĂ܂�J
�@�@�@�@�@�@�mJ=�W�����[�E�����h���AS=�T���E���H�[���̏��n
2009.11.26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��6�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�E
�i11�j�u�O���[�g�v�^���̎p����܂�5��ɂ킽���āA�u�O���[�g�v�̖��͂���ɓZ���G�s�\�[�h�ɂ��āA���f�ГI�ɒԂ��Ă܂���܂������A�܂��������̕������c���Ă��܂��B���̌����̈�͎����s���ł����B��������j�I�ɉ𖾂���ɂ͐M���ɑ��鎑�����s���ł��B�V���[�x���g�𖾂̃��t�@�����X�����́u�V���[�x���g�̎莆�v�Ɓu�F�l�����̉�z�v�i��Ƃ��P�X�P�S�N�����j�ŁA�����̓I�b�g�[�E�G�[���q�E�h�C�b�`�����Ҏ[�������́B���͂���܂Łu�V���[�x���g�̎莆�v�����𗊂�ɂ���Ă��܂������A�J�Ԍ����Ă��邱�Ƃ�"�{�l�̎莆�ɂȂ�"�Ƃ������Ƃ����X����܂����B�ő�̊S���u�O�����f���E�K�V���^�C���Ō����Ȃ��������v�Ƃ������j��̒������O�ł͂���܂���ł����B���͂���A�u�F�l�����̉�z�v�ɏ�����Ă���̂ł��B�ŋ߂��������Ǝ�ɓ��ꂽ�̂œ���͑����܂����B����́A�u���Y�ꂽ���������������������̐����������A�����Ȃ�Ɂu�O���[�g�v�^���̎p��`���A�����������Ǝv���܂��B
[����������1�n �V���[�x���g�̓O�����f���E�K�V���^�C���n���ő傫�Ȍ����Ȃ������
����ɂ��Ă͗��j�I�����Ƃ��Ē蒅���Ă���ɂ��W��炸�A���́A�u1825�N�́w�V���[�x���g�̎莆�x��9�ʂ��邪�A���̒��ɂ�"�����Ȃ������Ă���"�Ƃ��������͂����̈�s���o�Ă��Ȃ��v�Ə�����������܂���ł����i�N�����m�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȇ@�v�j�B���̂Ƃ��́A�u�F�l�����̉�z�v���V�b�J���ǂ�ł��Ȃ������̂ŁA"����Ȃɑ�Ȃ��Ƃ��A�V���[�x���g���莆�ɏ����Ȃ��킯�͂Ȃ�"�Ǝv�����̂ł��ˁB���ہA���̒��ɂ́u�V���[�x���g�̓O�����f���E�K�V���^�C���n���Ō����Ȃ��������"�莆�ɏ����Ă���"�v�Ƃ����Ԉ�����L�q�����\���݂��Ă��܂��B
�u�V���[�x���g �F�l�����̉�z�v�i�I�b�g�[�E�G�[���q�E�h�C�b�`���ҁA�Έ�s��Y�� �����Њ��j�ɂ́A�ނ̎��𓉂�ŗF�l�������������Ǔ����������ڂ��Ă��܂��B���̒��̈�l�ŁA�����c�o�g�̖�l�A���[�[�t�E�t�H���E�V���p�E���i1788�|1865�j�̒Ǔ����̒��ɁA����͂���܂����B�u1825�N�ĂɁA�V���[�x���g�̓K�V���^�C���ň�Ȃ̑�����Ȃ������グ�����A�ނ͂��̋ȂɑS�����ʂ̈������Ă����v�ƁB
�쌀��Ƃɂ��Ė�l�̃G�h�D�A���g�E�t�H���E�o�E�G�����t�F���g�i1813�|1890�j�́u�E�B�[���̌|�p�A���w�A�����A���s�̂��߂̎G���v1829�N6�����ɂ��������Ă��܂��B�u�ӔN�̑��̒��ɂ́A1825�N�ɃK�V���^�C���ŏ�����A���̍�҂����ʋC�ɓ����Ă��������ȂƁA�ނ̍Ō�̍�i�ł���1828�N�̃~�T�Ȃ���������v�ƁB������u�F�l�����̉�z�v�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
�u�O�����f���E�K�V���^�C���Ō����Ȃ��������v�Ƃ����L�q�́u�F�l�����̉�z�v�̒��̂��̓������������܂���B���������āu1825�N�ɃO�����f���E�K�V���^�C���n���Ō����Ȃ��������v�Ƃ������j��̏،��́A"�V���[�x���g���g�̎莆�ɂ͂Ȃ��A�ނ̓�l�̗F�l�̋L�q�ɂ����̂����ׂĂł���"�Ƃ������Ƃł��B�����āA�����Ă����ׂ���"�V���[�x���g�͂��̋Ȃɓ��ʂȈ�����Ă���"�Ƃ����_�ł��B
�m����������2�n �V���[�x���g�́u�O���[�g�v���x����֒�o����
1826�N10���A�y�F������ǂɈ��Ă��u�V���[�x���g�̎莆�v�ɂ͂�������܂��B
�u�I�[�X�g���A���y����́A�|�p��ڎw���ǂ̂悤�ȓw�͂��x������Ƃ������M�ȈӐ}���m�M���A�c���̌|�p�Ƃ̈�l�Ƃ��āA���͎v�����Ă��̎��̃V���t�H�j�[���A�M����Ɍ��悵�āA���x�������������Ȃ�����ׂ��A�������Ă������������ƂƂ������܂��B�����鑸�h�̔O�����߂āA�t�����c�E�V���[�x���g�h���v������"�v������"���悵���V���t�H�j�[�́u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�ŊԈႢ����܂���B����̓h�C�b�`���Ҏ[�́u�V���[�x���g �F�l�����̉�z�v�̒��߂ł����炩�ł��B�����ɂ́A�u�w������ȁx�Ƃ����̂́A1826�N�Ɏӗ炪�V���[�x���g�Ɏx�����Ă��邩��A���������w�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁx�̂��Ƃł������ɂ������Ȃ��B�E�B�[���y�F����i�I�[�X�g���A���y����j�Ɏc���Ă���n�����̑�����Ȃ�1828�N�̍�ł���v�Ƃ��邩��ł��B�܂��A���̋L�q����́A���̎����ɂ͂܂�"�u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�́u�O���[�g�v�Ɠ���ł���"�Ƃ����}���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ�������܂��B
�V���[�x���g�����Ɍ������Ȃ�������̏��́A�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���́u�V���[�x���g ���y�I�ё��v�i1948�N���s�j�ł��B���̒��ɂ͂���ȋL�q������܂��B�u�V���[�x���g���g�́A���́w�n�����̑�V���t�H�j�[�x�̊�����܂��Ȃ��A������E�B�[���y�F����ɒ�o�����̂����A��������"���܂�ɂȂ����A���܂�ɂނ�������"�Ƃ��ċ��ۂ����Ƃ��ɁA���̑���ɑO��̃n�����V���t�H�j�[�i��6��D589�j������B�v
���́u������܂��Ȃ��v�Ƃ����̂�1828�N�̂��ƂȂ̂ŁA"�u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�́u�O���[�g�v�Ɠ���ł���"�Ƃ��������ɂ���āA���Ȃ錋�_�������o����܂��i����炪����y�Ȃł��邱�Ƃ́A�O�f�N�����m�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȇ@�v�Ŏ��؍ς݂ł��j�B
�V���[�x���g�́u�O���[�g�v��1826�N��1828�N�̓�x�ɂ킽���Ċy�F����ɒ�o�������A����������t�����ۂ���Ă����B
�ȏ�̌��_���������Ȃ���A����u�O���[�g�v�̐����ߒ����A�����ɂ܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���܂��B
[�������āu�O���[�g�v�͒a������]
1824�N5��7���A�x�[�g�[���F���L��̑��u�����ȑ�9�ԃj�Z���w�����x�v���E�B�[���̃P�����g�l���匀��ŏ�������A����23���ɂ̓��h�D�[�e���U�[���ōĉ����ꂽ�B�V���[�x���g�͂��̃j���[�X�����������@�m���A1824�N3��31���F�l���̎莆�Ɂu�E�B�[���̈�ԐV�����j���[�X�̓x�[�g�[���F�����R���T�[�g���J���āA�V���������Ȃ��I����Ƃ����������v�Ə����Ă���B�����莆�̒��Ɂu�̋Ȃ͂��܂���Ȃ��������A���̑���A��y�̍�i���������삵�Ă݂���B�����������ɂ��āA�Ƃ������A�l�́A�傫�ȃV���t�H�j�[�ւ̓����J���Ă䂱���Ǝv���Ă���v�Ƃ��B�����̓��e����A�u���v�����̃j���[�X��m�����V���[�x���g��"�傫�ȃV���t�H�j�["�n��ւ̈ӗ~���ނ��ނ��ƗN���Ă������Ƃ��n�b�L���ƉM����B�ނ͋��炭�x�[�g�[���F���́u���v�̉��t��5��7����23���̗����Ƃ������ɂ������̂ł͂Ȃ����낤���B�ނ��A�n���K���[�̋M���G�X�e���n�[�W�Ɨߏ�̉��y���t�Ƃ����D�����̏A�E�Ɍ��������������̂�5��25���ŁA�ĉ���2����ł���B���̎����ƁA���ꂾ���S�҂��ɂ��Ă������t��̏����ɍs���Ȃ��͂��͂Ȃ��Ǝv���邱�Ƃ���A"�����Ƃ������ɂ�����"�Ɛ������Ă����Ȃ����I�O��Ƃ͂����Ȃ����낤�B�V���[�x���g�́A�ǂ�ȋȂł�����������Ŋo���Ă��܂��������ł��邪�A����ȃV���[�x���g���u���v�ɓ�x�������^�Ƃ���A����́A���̍ŐV�삩����Ռ������O��đ傫���������ƂƁA���̋K�͂̑傫�����ă`�F�b�N��K�v�Ƃ������炾�낤�B�������ăV���[�x���g�́u���v���V�b�J���Ƌ��ɍ��ݍ��̂ł���B
1825�N5������10���̊ԁA�V���[�x���g�͏㕔�i�k���j�I�[�X�g���A�ւ̗������Ă���B���ł��A�O�����f���ƃK�V���^�C���n���ɂ͒����ɂ킽��؍݂������A�����̓n�v�X�u���N�ƈ��p�̕������Z�ȉ���n�ł���B���̖ړI�̓V���[�x���g�̓]�n�×{�ƁA���s�����̎�t�H�[�N���Ƃ̌��n�ɂ�����R���T�[�g�J�Âł������B�V���[�x���g��1822�N�̏I��荠�ɓ����s���̕a�������~�łɜ�a���̒��Ɉٕς��������Ă����B���̂̒m��Ȃ��a�ւ̋��|�Ƒ̒��s�ǂɔY�ޓs��ł̐����́A�O�����f���E�K�V���^�C���̑厩�R�ɂ���āA���̊Ԃ̕�����^����ꂽ�̂��낤�B�Ƒ���F�l�ɑ������莆�ɂ́A���R�Ɛڂ����тɖ������Ă���B�H���u�K�V���^�C���́A���̒n���ł����Ƃ��L���ȉ���n�̈�ŁE�E�E�E���̗��s��l�͂��Ƃ̂ق��y���݂ɂ��Ă��܂��B�����āA�����ł��ł��������n���������˂邱�Ƃ��o����̂ł�����v�u�_�X�����R���߂Ă݂���A�����Ƃ��̂����ۂ��Ȑl�Ԃ̈ꐶ�ȂǂƂ������̂��A����قǕK���ł����݂����l�̂���ΏۂƂ͎v��Ȃ��Ȃ�ł��傤�Ɂv�u���̋��J�̈��炵�����������R�g�o�Ő�������̂͂قƂ�ǎ���̋Ƃ��B���a�����}�C���������ɁA�����̏��_�����X�����Ă܂Ȃ����������Ă���p�B��ϖ������Ȃ���̂�����������A�����������̐F�̂��イ�����~���߂��悤�Ȗ쌴�┨�A����Ȏ��Ɉ͂܂ꂽ���ؓ��A����炷�ׂĂ��A�[�܂ł͂ƂĂ����n�����Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȍ��������R�̗�ɂ����Ǝ��͂܂�āA�܂�ŁA�V���̒J�̔ԕ��Ɍ������Ă��銴���v�u�����邩����ň�ԍ����R�́A�L���L���Ƃ���߂��Ȃ���M��������A����̎R�X���]���āA���z�ƕ���œ��X�Ƃ��т��Ă���B�O�̎莆�ŏ������J���A�܂�œV����ʂ蔲����݂����ɐi�B����ȉ��K�Ȏv���̓A�_���ƃC�u�ɂ͂Ƃ��Ă����킦�Ȃ��������낤�v�ȂǂȂǁB
����Ȓ��ŁA�ނ͈�̌����Ȃ������������̂ł���B�c��������u�x�[�g�[���F���̂��Ƃł������������ł���Ƃ����̂��v�Ǝv�������A�u���v���ĐG�����ꂽ������Ȃւ̑z�����A�O�����f���E�K�V���^�C���̑厩�R�̒��ő��B���A�y�����Ƃ点��C�萬�Ɋ����ւƌ��������̂��B
�厩�R�ɕ����ꂽ�s��ŐS�n�悢�C���ɖ��������̌����Ȃ��A�V���[�x���g�͎�̊O�C�ɓ����Ă����B�^�̉�S�삾�����ɈႢ�Ȃ��B�����āA��1826�N�H����A��������Ċ������A���M�������ăE�B�[���y�F����Ɍ��悵���B�Ƃ��낪�Ăɑ��Ⴕ�āA�͂��Ȏӗ���������̂̉��t�͂���Ȃ������B�Ȃ�ƁA�ЂƂ܂��y���͈���������̂��낤�B����������悤�Ƃ��āB�������V���[�x���g�͂��̍�Ƃ����炭�̊Ԃ��̂܂܂ɂ��Ă������B�����̍�i����u���邱�Ƃ��������Ȃ������V���[�x���g�ł��邩��A�قƂ�NJ���������i���Ƃ肠�������̂܂܂ɂ��Ă������Ƃ͏\���ɍl�����邵�A�܂����̎����́A�A��̋ȏW�u�~�̗��v�ɂ���肩����˂Ȃ�Ȃ������͂��ł���B
������1828�N������Ă���B�V���[�x���g�͂��̔N��11���ɖS���Ȃ�̂ł��邪�A���ڂ̌����͒��`�t�X�ł����Ă��A�s���̕a�������Ă����̂ł��邩��A���炩�̎��̗\���͂������ɈႢ�Ȃ��B����Ȓ��A�ނ͐S����C�ɓ����Ă���u�O���[�g�v�̊y�������o���āA�蒼�����n�߂��B�����Ă��Ɋ��S�Ȍ`�ŏ����I�����V���[�x���g�͊y���̍Ō�Ɂu1828�N3���v�Ə������B�V���[�x���g�͏�ɁA�y�Ȃ̊����N������������ł�������ł���B�������āA1825�N�ɂ͂قƂ�Ǐ����グ���Ă����u�n���������ȃO���[�g�v�́A1828�N3���������Ă��ׂĂ̎蒼�����I���A�^�̊����𐋂����̂ł���B���̎��M���́A1825�N�Ɏg��ꂽ�ܐ����̏�ɁA���������̍��Ղ��c���Č������Ă���B
�V���[�x���g�͒����ɂ�����ēx�y�F����Ɏ��������A�u�������ē���v�Ƃ̗��R�ʼn��t����Ȃ������B�ނƂ��ẮA��S�̎��M����x�܂ł����ۂ��ꂽ�̂ł���B�d���Ȃ����������ɕ��u�����V���[�x���g�́A11��19���ɂ͋A��ʐl�ƂȂ��Ă��܂��B�ꏏ�ɏZ��ł����Z�̃t�F���f�B�i���g�͂����ۊǂ����܂�10�N���o�B
1839�N1��1���A�O�N�H����E�B�[���Ɉڂ�Z��ł������[�x���g�E�V���[�}�����t�F���f�B�i���g��K�˂��B�ނ̓V���[�x���g�Z��ɑ���h���̔O���A��������特�y�G�����Ɍf�ڂ��Ă�������A�t�F���f�B�i���g�����}���Ă��ꂽ�͎̂��R�̐���s�����������낤�B�b���e�݁A���₩�ȂƂ�������A���낻��Ɍ�����悤���Ǝv���Ă����Ƃ��A�t�F���f�B�i���g�͌������u�����ɂ��関�o�ł̍�i�����Ă���Ă��������v�B�����ɂ͂��������ς܂ꂽ�y���̎R���������B�V���[�}���͐H������悤�Ɍ����Â�悤�ɓǂ݂ӂ������B����͂܂��ɕ�̎R�������B���ł������ś����Ƃ����ނ��Ă����̂��u�n����������ȁv�������̂ł���B���̍�i�̑f���炵�����Ɋ��m�����V���[�}���̊����͂������肾�������낤���B�ނ́A���̏�Ńt�F���f�B�i���g�̋������A�e�F�̃����f���X�]�[���ɂȂ��A�����̎�����簐i����B��������1839�N3��21���A�u�O���[�g�v�̓����f���X�]�[���w���̃��C�v�c�B�q�E�Q���@���g�n�E�X�E�I�[�P�X�g���ɂ����j�I�ȏ������s��ꂽ�̂ł���B
�ȏオ�A�u�O���[�g�v�����̐��ɐ��܂�o�������o�܂ł��B��ɓ���\�Ȍ���̏�����g���đ������Ă݂܂����B�����I�ɂ͂��Ȃ萸�x�͍����Ǝv���Ă��܂��B�u�O���[�g�v���A���̌�u7�ԁv���u9�ԁv���u8�ԁv�ƁA�����ȘA�Ԃ��ς�����������ɂ��ẮA�����10��7���t�N�����m�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȇ@�v�����Q�Ƃ��������B
���Q�l������
�u�V���[�x���g�̎莆�v�h�C�b�`���ҁA���g���v��E����i���^�����o�Łj
�u�V���[�x���g �F�l�����̉�z�v�h�C�b�`���ҁA�Έ�s��Y��i�����Ёj
�u�V���[�x���g ���y�I�ё��v�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C�����A���^�j��i�����Ёj
�u���y�Ɖ��y�Ɓv�V���[�}�����A�g�c�G�a��i��g�V���j
�u�V���[�x���g�v�쑽�����~���i�����I���j
�u�N���V�b�N���Ȗ����_�v�c���a�I�v���i�A���t�@�x�[�^�Ёj
2009.11.16 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��5�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�D
�i10�j�u�O���[�g�v�Ҏ�����̂���Ȃ���_�O��́u�N�����m�v�ŁA���Ђ������{�u�ŐV���ȉ���S�W�v�ɂ�����u�O���[�g�v�̊ԈႢ�L�q�ɂ��Ă��b�����Ă��������܂����B�����́A�����N�x��莆�������ꂽ�N��̎��Ⴆ�ȂǂŁA�j���Əƍ�����Ε�����A����ΒP���~�X�ł��B�Ƃ��낪���̒Ҏ��̕��͂́A���ꂾ���ł͂Ȃ��A���e�I�Ɍ��߂����Ȃ��������Ă���̂ł��B���̎g�p���܂߂āB�ܘ_�A����͎�ς̖��Ȃ̂ŁA��̂��ӌ��Ƃ��ĂЂƂ܂����d���悤���Ǝv�����̂ł����A�ǂ߂Γǂނقǂ��������Ǝv�킴��������A�����Ō��y���Ă������ق����x�^�[�ƍl���܂����B�������t���������������B
�m�s�����̂P�n �V���[�x���g�͂���ɍ���ʂ��Ƃ�����
�Ґ搶�́A�u�ŐV���ȉ���S�W�v�̒��ŁA�u�������A�C�̒Z������l�ɑ��ẮA�������ɂ��̋Ȃ͒����ɂ����邱�Ƃ͎����ł���v�Əq�ׂĂ����܂��B�����ł��傤���B�V���[�}�����u�O���[�g�v��"�V���I�Ȓ���"�ƕ]�������Ƃ͗��j��̎����ł����A�����"�S�n�悢�u�₩�������邩�炢�܂ł��I����Ăق����Ȃ�"�Ƃ����D�ӓI�Ӗ��������������Ƃ́A�O�͂ŏq�ׂ��Ƃ���ł��B�u�O���[�g�v�ȍ~�̃u���b�N�i�[��}�[���[�̌����Ȃɂ́A�͂邩�ɒ����y�Ȃ���������܂��B���������āA�C���Z�����ǂ����͕ʂɂ��āA�����Ȃ͌���̉�X�̂ق��������Ȃ�Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B�搶��"�����ɂ�����"�Ƃ����\���ɂ́A�V���[�}���Ƃ͈Ⴂ�A�ے�I�ȃj���A���X���F�Z���������܂��B����́A���̌�i�ł����q�ׂĂ����邱�Ƃ�������炩�ł��B
�u���̋Ȃ́A��1�y�͂����̂����݂Ȍ����ɂ���Ċ��S�Ȃ܂Ƃ܂���݂��A��4�y�͂�����ɂ��܂Ƃ܂���݂��邪�A���̂܂Ƃ܂肩���́w�������x�̑�1�y�͂ɂ���ׂ�Ƌٖ����������Ă���B�V���[�x���g�͂���Ύ��g�̂���ɍ���ʂ��Ƃ����݂�����ł���B�v�����ł̖��_�͓����܂��B��́A�u�O���[�g�v��̊y�͂��u�������v�ٖ̋����ɗ��ƕ]���ꂽ���Ƃł��B���̂悤�ȑf�l�ɂٖ͋��������邩��������Ȃ��B���y���Ă��āu���̋Ȃٖ͋����B���̋Ȃٖ͋��łȂ��v�Ȃ�Ċ��������Ƃ��l�������Ƃ�����܂���̂ŁB��ڂ́A�ٖ����ɂ����ė���4�y�͂́A����ł�"��Ԗڂɂ܂Ƃ܂肪�悢"�Ƃ���������Ă���_�ł��B�Ȃ�A��2�y�͂Ƒ�3�y�͂͂����Ƃ܂Ƃ܂肪�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���́A��2�y��Andante con moto�����A���ɃV���[�x���g�炵���f���炵�����y���Ɗ����Ă��܂��B��v��A�ƕ���B�����݂Ɍ���镡���I�O���`���ł����A��̕����͏������ω����Ȃ���i�W���A�����̌q���̕�������Ƃ��ē������̂͂���܂���B���̕ϖe�͗\�����ʃX�����ɕx�݁A���l���ʂȕ\��͖����I���X���O���邱�Ƃ�����܂���B�����������ɂ͈�{�̋��ʂ�S�̂ɉ̐S�����Ă��܂��B���}�����ƌÓT���̌����ȃo�����X�������ɂ���܂��B
�Ґ搶�́A���̑�2�y�͂�"��1�y�͂Ɏ����܂Ƃ܂�̑�4�y�͈ȉ�"�Ȃ̂�����A�{���ł͐G��Ă�������Ⴂ�܂���B���������|�C���g�͂܂Ƃ܂����B�܂Ƃ܂肪����Ȃɑ厖�Ȃ̂ł��傤���H���͂܂Ƃ܂�Ȃǂ��ł������B����Ȃ��̂́A���y���Ƃ��Ɉӎ��������Ƃ�����܂���B������[�߂邽�߂Ɍ`�����m�F���邱�Ƃ͂���܂����B
���y�����Ƃ̈Ӗ��B����́A������"�S�����������̂����炮�̂�"�ɐs����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ґ搶�́u�ŐV���ȉ���S�W�v�ɂ́A���������v�f�̕����͊F���ł��B�o�Ă�����́A�u�Ă������v�u�܂Ƃ܂�v�u�ٖ����v�̂悤�Ȗ��@�I�ȕ��܂̂��Ƃ���B�����p�g�X���������镶���͈����܂���B�����Ăǂ������邩�Ƃ�����I���ʂɂ͑S�����y���Ă��Ȃ��̂ł��B�Ȃ̂ɁA����łƂ₩�������̂͊Ԉ���Ă��܂��B���E�̐l�X��������V���[�x���g���u����ɍ���Ȃ��v�Ȃ�ĕs���Ȍ��t�Ō��ߕt����̂Ȃ�A�����Ƃ����_���������Ă��Ăق����B����ȑ�w�Ȃ��Ƃ�������ɂ́A����̉p�m�Ɗ����������Ď�肩����ׂ��ł���A�V���[�x���g�̊���̔��I��`���Ƃ̊i����S�Ĕc��������Ŕ�����ׂ����Ǝv���̂ł��B����������̕n�������ܓI�����������Œf�肷��Ȃ́A�V���[�x���g�ɑ��Ď���疜�Șb�B�����ɗႦ��Ȃ�A�������M��������Ċ̐S�̗�������炸�Ƃ���������B����Ƃ��A�搶�́A�܂Ƃ܂�𑪂镨�������������āA�����ǂݎ��Z���T�[���������ł͂Ȃ��̂ł��傤���B�܂��A����Ƃ��A�A�C���V���^�C���u�V���[�x���g���y�I�ё��v�̈Ђ���āA"�u�O���[�g�v�́u�������v�ɗ��"�ƌ��_���ꂽ�̂ł��傤���B�A�C���V���^�C���͂��������Ă��܂��B
�u�l�X���V���[�}�����炠��Ȃɂ����Έ��p���āA�n�����s��t�V���t�H�j�[�Ɍ������w�V���I�����x�Ƃ��������A�w�������x�V���t�H�j�[�̓�y�͂Ɍ�������̂͂ЂƂ�����Ȃ������B�V���[�x���g�́A�ɓx�ْ̋������A���h�ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�\�i�^�`���̊y�͂����������A�W���x�̓_�ł���ɔ�r������̂́A�x�[�g�[���F���̑�܃V���t�H�j�[�̑�P�y�͂����ł��낤�v�i�����Њ��A���^�j��j �E�E�E�F�l�͂ǂ��v���܂����B�m�s�����̂Q�n �u�������v�̐��E���ق艺����ׂ��ł�����
�Ґ搶�́A����ɂ��̒��ŁA�V���[�x���g�̍�ȉƂƂ��Ă̕������ɂ��āA��_�ŗE�C���锭�������Ă�������Ⴂ�܂��B�ŏ��ɂ��̕�����]�L�������܂��B
�u�ނ̓x�[�g�[���F���̑s��Ȍ����Ȃ����������Ƃ���߂ċ����A�Ȃ�Ƃ����Ă��̈╗�������̂���肾�������Ǝv���Ă����ɑ���Ȃ��B�������A���̖]�݂́A�ނ̐��܂���̐����ɂ͕s�������Ȃ��̂ł���B�ނ���A�ނ͂V�N�O�́w�����������ȁx�̐��E���ق艺����ׂ��ł������B���̈Ӗ��ɂ����āA���̋Ȃ̓V���[�x���g�̂���̂܂܂̂�����������킷�Ȃł͂Ȃ��B�v�܂��͖`���̃x�[�g�[���F���Ɋւ��镔���ł��B�V���[�x���g�́A20�ΑO��̍��A�u�x�[�g�[���F���̂��ƂŁA�������������ł���̂��v�ƔY��ł����͎̂����ł��B�x�[�g�[���F���́A���̂Ƃ����ł�40��㔼�B�����Ȃł́u�p�Y�v�u�^���v�u�c���v�A�s�A�m���t�ȁu�c��v�A���@�C�I�������t�ȁA�s�A�m�E�\�i�^�u�����v�u�M��v�ȂǂȂǁA�㐢�Ɏc�閼�Ȃ̐��X�ݏo���Ă���A������������ʑ�ƂƂ��ČN�Ղ��Ă��܂����B����ȃx�[�g�[���F���̐��Ȗ������A�����E�B�[���ɏZ�ރV���[�x���g�́A���ɐg�߂œ���I�ȏo�����Ƃ��Ċ��m���Ă������Ƃł��傤�B���������āA�ނ�"��ȉƂƂ��Ă̂����"�ɂ����āA�x�[�g�[���F���ɓ��������Ă������낤���Ƃ͑z���ɓ����܂���B�ł�����́A"�앗�ɓ���Ă���"�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�Ȃ��Ȃ玄�́A�V���[�x���g���A���̂悤�ȈӖ��̂��Ƃ��A�����Ă���̂������Ă���̂��������Ƃ��Ȃ�����ł��B���̈Ӗ��ł́A�ނ���A���[�c�@���g�̉��y�Ɏ䂩��Ă����ӂ�������܂��B1816�N6��14���t���̓��L�ɂ͂�������܂��B�u�������[�c�@���g��A�s�ł̃��[�c�@���g��A�������Ƒ����́A�����Ȃ�Ɩ����ɑ����́A���̂悤�Ș����Ȃ��ǂ����̌b�ݐ[���͎ʂ��A���Ȃ��͖l�����̍��̉��[���ɍ��ݕt���Ă������Ƃ��낤�E�E�E�E�v�ƁB����́A���[�c�@���g�́u���y�d�t�ȃg�Z��K516�v���Ă̊�����Ԃ������̂ŁA�����ɂ̓��[�c�@���g��^�̌��t���x���Ă��܂��B
�����炱�́u�x�[�g�[���F���̑s��Ȍ����Ȃ����������Ƃ���߂ċ����v�Ƃ����A�搶��"�Ȃ�������"�Ƃ����Ӗ������ɂ́A�^���ł����˂܂��B�������R�ŁA�u�V���[�x���g�̓x�[�g�[���F���̈╗�������̂����o�������Ǝv���Ă����ɑ��Ⴂ�Ȃ��v�Ƃ̐搶�̌����ɂ��ًc�����������Ă��������܂��B���̂��Ƃɑ����u���̖]�݂́v�ɂ��ẮA�ނ͖]�Ⴂ�Ȃ��͂����Ǝv���܂����A���ɂ���u�ނ̐��܂���̐����ɂ͕s�������v�́A�܂��A�������Ă��邩�ȂƁB�ł��A���������炱�����A�u�V���[�x���g�̚n�D�̓x�[�g�[���F���I�ȑs�傳���u�����Ă͂��Ȃ������v�Ƃ����Ă��������܂�����ǁB
���āA�ނ�����͂��̂��Ƃł��B�搶�͂��������Ă����܂��u�ނ́A7�N�O�́w�����������ȁx�̐��E���ق艺����ׂ��ł������v�E�E�E�����������̌�������͉��Ȃ̂ł��傤�B���̒��ǂ����߂�������̂ł��傤���B�u�O���[�g�v�Ȃ�Ă�������ɂ��Ȃ����̂���炸�Ɂu�������v�̂悤�ȈÂ���O�̐��E�ɐ�O���ׂ��Ƃ�������肽���̂ł��傤���B���������̂�傫�Ȃ����b�Ƃ����̂ł��B�m���ɁA�u�������v�ɂ����鎩�ȍ����I��O�̐��E���V���[�x���g�̂��̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ��ł��傤�B�u�w�������x�����Ȃ̓V���[�x���g�̐��I�Փ��̕\���ł���v�Ƃ����l�����邭�炢�ł�����B�������A����ł͎��R��������V���[�x���g�����܂��B�ނ̐e�����F�l�̈�l���[�[�t�E�t�H���E�V���p�E���́A1829�N�̒Ǔ����̒��ł��������Ă��܂��B
�u���R�̔������ɑ��Ĕނ͔��Ɋ����₷���A�ނ����N�������ĉĂ̐������ԃt�H�[�O���ƈꏏ�ɖK��Ă����㕔�I�[�X�g���A��U���c�u���N�̂��炵���n���̂��Ƃ��v���o���̂���D���������̂��A���̈Ӗ��ɂ����Ă������v�i�I�b�g�[�E�G�[���q�E�h�C�b�`���ҁA�Έ�s��Y��u�V���[�x���g �F�l�����̉�z�v������ ���j�㕔�I�[�X�g���A�Ƃ̓O�����f���E�K�V���^�C���n���̂��ƂŁA�܂��Ɂu�O���[�g�v�a���̒n�B���R������Ȃ�������V���[�x���g���A��D���Ȏ��R�Ɉ͂܂�č�����u�O���[�g�v���A����"�V���[�x���g�̂���̂܂܂̎p������킷�Ȃł͂Ȃ�"�̂ł��傤���B���́u�������v�͂���ɍ������ǁu�O���[�g�v�͍���Ȃ��̂ł��傤���B�Ґ搶�̂��l���́A���܂�ɂ���ʓI�ŁA�S���Ȃ��Đ��F���邱�Ƃ͏o���܂���B�F�l�͂ǂ��v����ł��傤���B
�i�t�j ��͂�X�x���Ă��܂����Ζ،���Y�搶
������A�]�w�ҁE�Ζ،���Y���̏����\���R��̃j���[�X����э���ł܂���܂����B�Ζ؎��́A�{�N6���́u�N�����m�v��3��ɂ킽���Ē@�����Ă�����������������ɂ��A�Ō�ɂ�����Ƃ������̖��ɐG�ꂳ���Ă��������܂��B���͑��Z�����āA����3�N�Ԃɂ��킽��\���R��Ƃ����߂���Ƃ��Ă��܂��������ł��B���̓��]�����Ȕ]�w�҂����Y��ɂȂ�ꂽ�̂ł�����A���̂����Z�Ԃ�͐q��ł͂Ȃ������̂ł��傤�ˁB������A���������Ȃ��I���̂Ƃ��A���́u�e���r��W�I�Ő��O�̉��y���������A���E�t�H���E�W�����l�̃A���o�T�_�[�Ȃ�����Ă���ɂ���������A�^���ɖ{�Ƃɑł�����ł��������B�������Ȃ��Ɛ搶�̂��߂ɂȂ�܂���v�ƃA�h���@�C�X�\���������͂��ł��B
����Ȑ܁A�V���[�x���g�Ɋւ�����͉̂��ł��C�ɂȂ��Ă��鎄�̎��E�ɁA���́u���ׂĂ͉��y���琶�܂��v�iPHP�V���j�Ȃ�{����э���ł��܂����B���肪"�]�ƃV���[�x���g"�Ȃ̂ŁA�V���[�x���g�̉��y�̖��͂��ǂ�Ȃɂ������������Ă��邩�Ɗy���݂ɓǂ܂��Ă��������܂����B�Ƃ��낪�A�o�ꂷ��y�Ȃ́u�������v�Ɓu�����v�Ɓu���l�̖�̉́v�Ɓu�~�̗��v��4�Ȃ����B�܂��Ă�ނ̐S�̒ɂ݂�D�����ɂ͂܂��������y����Ă��܂���ł����B�K�b�J���I����͎��������ɃV���[�x���g�ɓ���݂��Ȃ����̏ł��B�u�������v�̌��ł́A�V�m�[�|���w���̃E�B�[���E�t�B���̃R���T�[�g�̌�������Ă��āA�u�w���߂̔g�x�Ƃł��ĂԂׂ����̂��R���T�[�g�E�z�[���S�̂ɗ���Ă����v�Ȃ�ăg���`���J���Ȃ��Ƃ������Ă���܂��B�ǂ�ȉ��߂������Ƃ������t�̒����Ɋւ���L�q�͈�Ȃ��A�u���̏o�������炵�������̂��B�w�S���k�����x�Ȃǂƌ����Ă��܂��ƁA�}�f��������Ȃ��B�����A�w�����x�Ɓw��Ɂx�͓������ł���̂͋��R���낤���v�E�E�E����ȕ\�ʓI�ł܂�Ȃ���C���킹�̎��傪����ł��邾���B���̒��x�̊����������ł��Ȃ��f�l��"����"�Ȃ�Čy�X���������Ăق����Ȃ��B���߉]�X�́A�قȂ�^�C�v�̉��t���܂���Ⴂ�𗝉�������ł͂��߂Č�������̂Ȃ̂ł�����B�ق�ƁA���߂����m����̂͑�ςȂ�ł���B�������z�[���S�̂Ɂu���߂̔g�v���������Ăǂ��������Ƃł��傤�H �w���҂̉��߂��A���̏�ɋ����킹�����O�S�������������L���Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B����ȉ��y�I�ɍ��x�ȕ�������肪����R���T�[�g�Ȃ�Đ�ɂ��肦�܂���ǁE�E�E�B���̂��Ƃɂ̓o�b�n�ɂ��b���y�т܂��B�u�_�ւ̎������w�}�^�C���ȁx�ɁA�s��ւ̂܂Ȃ������w�R�[�q�[�E�J���^�[�^�x�ƂȂ����v�ȂǂƂ���������Ă��܂����A������\�w�I�d�����ɉ߂��܂���B�u�}�^�C���ȁv��71�Ȃ́u�G���A�G���A���}�A�A�T�u�^�j�v�i�_��A�Ȃ�����̂ċ������j�Ƃ����l�ԃL���X�g�̔ߒɂȋ��т������m�Ȃ��̂ł��傤���B���̏u�ԁA�_���̏ے��Ƃ��Ă̌��y���s�^���Ǝ~�܂鋰�낵�����E�E�E�Ȃ̖{�����m�炸���Đ_�ւ̎����Ȃ�Čy�X���������Ăق����Ȃ��B�ނ���u�}�^�C�v�͐l�ԃh���}�Ȃ̂ł�����B���̂悤�ɐ搶�̕��͂́A��т��ēI�O��Ŕ�����ȕ\���ɏI�n���Ă��܂��B
�����āA�Ō�ɁA�Ȃ�ƃ��E�t�H���E�W�����l�̎�Î҂Ƃ̑Βk�����X40���y�[�W�ɂ킽���Čf�ڂ���Ă��܂����B����Ŕ[���B���̖{�́u2008���E�t�H���E�W�����l�v�̃��C�V���{�Ƃ������Ƃ�����������B�܂��A�A���o�T�_�[�Ȃ̂ł�����A���y�Ղ̍L��s�ׂ��s���͓̂��R�ł��傤�ˁB�ł��ǂ��ł��傤���A��Îґ��́A��ȍL�����A���e�̂Ȃ������̐l�C�҂ɔC���Ȃ��ŁA�����ƃ}�V�Ȑl�ɂ��肢�����ق��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����̉��y�Ղ̔��W�̂��߂ɂ��B
�Ζؐ搶�͖{���̒��ł����q�ׂĂ����܂��B�u�E�E�E�����ƕς�邱�Ƃ̂Ȃ��l�Ԃ̌��_�Ƃ����ׂ����̂�����B�������A�߂܂��邵�����������鐢�E�ɂ����āA��������������O�̂��Ƃ́A���Y�ꂪ���ɂȂ�A�ӓ_�ƂȂ�B���̖Y����Ă��܂�����Ȃ��̂������A�V���[�x���g�̉��y���t�łĂ�����̂Ȃ̂��B����܂ł̎��ɂƂ��āA�V���[�x���g�͖ӓ_�������̂��v�B�����Ƃ��Z���������̒��ŏ����̐\�����ӓ_�ƂȂ��Ă��܂�ꂽ�̂ł��傤�B
2009.11.06 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��4�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�C
�i9�j�u�O���[�g�v����� �W�c�~�X�����̐^�Ɛl�͂��ꂾ�H�O��́u�N�����m�v�ŁA�u�O���[�g�v������CD�̉���������������ʁA���ʂ̃~�X�L�q���������U�����ꂽ���Ƃ���A"�Ȃɂ������"�Ƃ�����a���A���Ȃ킿�A�ǂ����ɕK���Ɛl������͂����Ƃ������R�Ƃ����m�M���N���Ă��܂����B����́A������Ɗ�蓹���āA���̔Ɛl�T�������Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�m�X�e�b�v1�n �莝��CD�����Ղ̋��ʃ~�X�L�q���m�F����
�P�[�X�@
�u�O���[�g�v�̏����N�́A1839�N�ł���̂ɁA1838�N�ƂȂ��Ă������
�n�ӌ쎁 �i�J�[���E�x�[���w���F�x�������E�t�B���A������UM�j��CD���
��{�^�Վ� �i�n�C���c�E���[�O�i�[�w���F�x���������A�R�����r�A�j
�F����F�� �i�J�[���E�V���[���q�g�w���F��h�C�c�������A�R�����r�A�j
���ђ��Ǝ� �i�t�����c�E�R�����B�`���j�[�w���F�`�F�R�E�t�B���A�R�����r�A�j
�x���C�� �i�w���}���E�A�[�x���g���[�g�w���F���C�v�c�B�q�������A���ԁj
�ēc���ꎁ �i�J�[���E�x�[���w���F�E�B�[���E�t�B��75�������C�u�AUM�j
�P�[�X�A
�V���[�x���g���u�Ƃɂ����l�͑傫�ȃV���t�H�j�[�ւ̓����Ă䂱���Ǝv���Ă���v�Ƃ����̂́A1824�N3��31���A�N�[�y���E�B�U�[���Ă̎莆�ɏ��������̂Ȃ̂ɁA"1828�N"�������́A"�F�l�Ɍ����"�ƂȂ��Ă�����́B
���ђ��Ǝ�
�u�ނ������Ȃ������ӎ������̂�1828�N�A���̔N�ł������B���̎��A�ނ͗F�l�Ɉ��ĂĂ��������Ă���B�w�����̋Ȃ͂�߂��B���ꂩ��͌����Ȃ����������x�v
�F����F��
�u����9���̍�ȔN���1828�N�A���Ȃ킿�A�V���[�x���g�̎��̔N�ł��邪�A�����̔ނ͂܂��܂��x�[�g�[���F���ɐS�����A�w�̂͂�����߂��B����̓I�y���ƃV���t�H�j�[�����������x�ƌ����āE�E�E�E�v
��{�^�Վ�
�u���̌����Ȃ���Ȃ��ꂽ�̂́A�V���[�x���g�̎��̔N�ł���B���̂���ނ́A�w���͑傫�Ȍ����Ȃ����������B�̂́A������߂��x�ƗF�l�ɉk�炵�Ă���B�v
�|�㐽���� �i���h���t�E�P���y�w���F�~�����w���E�t�B���ASony�j
�u�V���[�x���g���F�l�ɂ��炵���Ɠ`������w�̂͂�����߂��B���ꂩ��̓I�y���ƌ����Ȃ����ɂ���x�Ƃ����ł��ӎu�́E�E�E�v
�ȏオ�A���̏��L����u�O���[�g�v������CD26�^�C�g�������������ʂł��B�P�[�X�@�̃~�X�͂U�^�C�g���A�P�[�X�A�̃~�X�͂S�^�C�g���A�L�q�]�_�Ƃ�7���B����͂��Ȃ�̏W�c�����Ƃ�����ł��傤�B
�m�X�e�b�v2�n �Ɛl�̖ڐ�������
���ʂ̃~�X���W�c�I�ɔ��������Ƃ��ɂ́A�K����̌��������܂��B�������~�X�L�q��Ƃ���7�l�̖ʁX�́A���V���璆���ɂ�����B�X������X����B���������Ă��̌����́A�N���V�b�N�E�ɂ����āA�X�^���_�[�h�Ƃ��ĔF�m���ꂽ���Ђ�����̂łȂ���Ȃ�܂���B�ʂ����āA�^�Ɛl�̖ڐ��́E�E�E�ȒP�ɂ��܂����B����͉��y�V�F�Њ��s�u�ŐV���ȉ���S�W�v��������܂���B���̌o���ł��A���R�[�h��ЍݐЎ���A�y�ȉ���̈˗������Ƃ��ɂ́A�܂��A�N���V�b�N���̐}���P�[�X�ɐ��R�ƕ���ł���u�ŐV���ȉ���S�W�v����o���Ă��Ďg�������̂ł��B
�u�ŐV���ȉ���S�W�v�́A1959�N���s�́u���ȉ���S�W�v���ł����肵���R���������{�B�Í��̖��Ȃ��A�����ȁA�nj��y�ȁA���t�ȁA�����y�A��y�ȁA���y�ȁA�̌��̃W�������ɕ����A���y�w�ҁE�]�_�ƁE��ȉƂ̐搶�������ӕ���S���Ď��M����20��������Ȃ���̂ŁA���M�҂ɂ́A����`�N���i�ȉ��h�̗��j�A�E�R��A�C�V�V�q�A��ؐ����A��{�^�ՁA�ēc��Y�A�p�q��N�A����ەv�A���슰�C�A��n�����A���䐽�A�F��B�v�A�n�ӌ�ȂǁA�䂪���N���V�b�N�E���B�X����d��������A�˂Ă��܂��B�o�ł͉��y�V�F�ЂŁA����܂��䂪�����y�E�̌��Ђ����M���B1979�N�̊��s�ł��B
�m�X�e�b�v3�n �ڐ��������Ɛl�Əƍ�����
�����ŁA�m�X�e�b�v�P�n�Ŋm�F����7���̉�����̓��e�ƁA�~�X�̌����Ƃ��Ėڐ��������u�ŐV���ȉ���S�W��P�������ȇT�v�i338�Ł|343�Łj�̒ґ��ꎁ���ɂȂ�V���[�x���g�u�����ȑ�9�ԃn���� �O���[�g�i��j�vD944�̍����A�ƍ����܂��B
�܂��͔Ɛl�ڐ��{�u�ŐV���ȉ���S�W�v����A�Ҏ��̌�����]�L�������܂��B
�P�[�X�@
�u��Ȃ��炿�傤��10�N�̂̂��A"1838�N3��21��"�Ƀ����f���X�]�[���̎w���ŒZ�k�����`�ŁA���C�v�c�B�q�̃Q���@���g�n�E�X���t��ŏ������ꂽ�v
�P�[�X�A
�u1828�N3���|����͔ނ̎���9�����O�ł���|�ނ͑傫�ȕ����������āA�������������������Ȃ��ŁA���̑�����Ȃ��������낵���B"�F�l�ɂނ����āw�̂͂�����߂��B�I�y���ƌ����Ȃ����ɂ���x�ƌ�����"�Ƃ�������قǁA���̋Ȃɖ����ɂȂ��Ă����v
����́A�m�X�e�b�v1�n�Ŋm�F����CD������Ƃقڊ��S�ɍ��v���܂��B�����"��������M�҂́u�ŐV���ȉ���S�W�v���Q�l�ɂ���"�Ƃ������Ȃ�m���ȗ\�������藧���܂��B
�m�X�e�b�v4�n �u�ŐV���ȉ���S�W�v�̓��e���ԈႢ�ł��邱�Ƃ��ؖ�����
�����ł́A�Ɛl�ڐ��{�u�ŐV���ȉ���S�W�v�̓��e�̊ԈႢ�����E�ؖ��������܂��B���ꂪ�ؖ������A�ڐ��{�͐^�Ɛl�ł���ƒf��ł���ł��傤�B�Ȃ��Ȃ�A���ʂ̃~�X���W�c�I�ɔ��������Ƃ��́A����Ώۂ�͕킵�Ă�����̂Ƒ���͌��܂��Ă��邩��ł��B
����܂Łu�N�����m�v��ǂ܂ꂽ�F�l�ɂ́A�����ɁA�����ґ��ꎁ�̕��͂̃~�X�ɋC�����͂��ł��B�P�[�X�@ ������1838�N�͊ԈႢ�ŁA������1839�N�B���̕����̓V���[�}���̎�L�������̓A�C���V���^�C���́u�V���[�x���g���y�I�ё��v����̈��p�ł��傤���A�u�V���[�}�����A1838�N10���ɃE�B�[���Ɉڂ�Z�݁A���N1839�N1���P���ɃV���[�x���g�̌Z�t�F���f�B�i���g��K�ˁA�����Łw�O���[�g�x�̎�e���A���̑f���炵���ɋ��Q���A�����f���X�]�[���Ɍv���āA���ʁA���̔N1839�N3��21�����C�v�c�B�q�ŏ������ꂽ�v�Ƃ����̂��j���ł��B�����ɂ�1838�N��10������1839�N��3���܂ł̎��n���邽�߁A�Ҏ��̕߂炦���ɍ������������̂ł��傤�B���̏؋��ɁA��i�ŁA�u�V���[�}���͂��́w������ȁx�̊y�����A1839�N1��1���A�̐l�̒�̉ƂŌ����o���āA�����f���X�]�[���ɂ����߂ĉ��t���������Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���v�Ƃ����L�q�����邩��ł��B1839�N�Ɍ��������̂�1838�N�ɉ��t���邱�Ƃ͏o���܂���B���ƒ��ł��������������Ă����ɁA�����J�ɂ��A�Z���Ǝ��Ⴆ�Ă��܂��B�܂��ɃV���o�_�o��Ԃł��ˁB
�P�[�X�A�͂�╡�G�Ȃ̂ŁA�ȉ�������ǂ��Đ����������܂��B���͑O����1828�N��Ȑ��͎~�ނ���Ƃ��������̂ŁA�����ł͒u���Ă����܂��傤�B����ɑ���"������������������炸�ɏ������낵��"���A��ϓI�ɂ����Ă��Ȃ�̖�蕔���ł͂���܂����A�ώG�ɂȂ�̂ŁA�������Njy�͂������܂���B�����ōł����ɂ��ׂ��́A�u�w�̂͂�����߂��B�I�y���ƌ����Ȃ����ɂ���x�Ɓi1828�N3������Ɂj�F�l�ɂނ����Č������v�Ƃ����㔼�̕����ł��B�Ҏ��͂�����ǂ���������ς肾���Ă����̂ł��傤���H1828�N�ɃV���[�x���g�́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�F�l�ɘb�������Ƃ��A�莆�ɏ��������Ƃ������܂���B�{�l�̎莆�ɂ��A�F�l�̒��q�ɂ��A�h�C�b�`����A�C���V���^�C���̒���ɂ��A����ȋL�^�͌������炸�A����ɗނ���L�^�́A�B��A"1824�N3��31��"�ɃN�[�y���E�B�U�[�Ɉ��Ă��{�l�̎莆�����Ȃ̂ł��B���e�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
�u�E�E�E����ȕ�������A�l�͂܂����Ă��A�I�y�������ʂɍ�Ȃ��Ă��܂������ƂɂȂ�B���[�g�̂ق��ł́A���܂�V�������͍̂��Ȃ��������A���̑���A��y�̍�i���������삵�Ă݂���B���@�C�I�����A�r�I���A�`�F���̂��߂̎l�d�t�Ȃ��ȁA���d�t�Ȃ���ȁA����Ɏl�d�t��������ȍ�낤�Ǝv���Ă���B�����������ɂ��āA�Ƃ������l�́A�傫�ȃV���t�H�j�[�ւ̓����Ă������Ǝv���Ă���v�i���g���v��E����u�V���[�x���g�̎莆�v�����Њ����j�Ҏ��̃P�[�X�A�̕��͂́A���̎莆�����ɏ������Ƃ����l�����܂���B�Ȃ��Ȃ�A�O�q�̂悤�ɁA�����悤�ȓ��e�̋L�^�����ɂ͈�Ȃ�����ł��B�Ȃ�A����͂��܂�̐�ǂ݂Ƃ���Ȃ���Ȃ�܂���B���ł��A1824�N��1828�N�Ƃ��Ă��܂����͍̂ő�̃~�X�ŁA����͂������Ԃ��̂��Ȃ��v�����ł��B�u���ꂩ��͌����Ȃ����ɂ���v�ƌ��������āA���̌����Ȃ�1825�|6�N�ɂ͊������ꂿ����Ă���̂ł�����B�u�莆�ɏ������v�Ƃ����������u�F�l�Ɍ�����v�Ƃ����̂��A�吨�ɉe���Ȃ��Ƃ͂����A�~�X�ɂ͈Ⴂ����܂���B����Ɏ��̎������e�̓ǂݎ������~�X�̏�h������Ă��܂��B�u�V���t�H�j�[�ւ̓������v�Ɓu�����Ȃ����ɂ���v�̕��������́A�i�N������Ⴆ�����Ƃ�ʂɂ���j�h���������ƕ������Ă��܂����A�u���[�g�̂ق��ł́A�V�������͍̂��Ȃ������B�I�y�������ʂɂ����v�Ƃ����������A�u�̂͂�����߂��B�I�y���i�ƌ����ȁj�����ɂ���v�ɂȂ��Ă��܂����̂́A���܂�ɍ����ȉ��Ƃ����ׂ��ŁA���͂�~���悤������܂���B��́A�펯�I�ɍl���Ă݂Ă��A1828�N�Ƃ��������Ɂu�̂͂�����߂��v�Ȃ�ăV���[�x���g�������킯������܂���B���̎��̔N�ɁA�V���[�x���g�́A�̋ȏW�u�����̉́v�i�S14�ȁj���͂��߁A20���Ȃ��̃��[�g������Ă���̂ł��i����1824�N�ɂ͋͂�6�Ȃ܂ł�������Ă��炸�A�莆�̐M�ߐ��𗠕t���Ă��܂��j�B�������A�����̉̋Ȃ́A�ނ̓��B�����ō��̋��n���������삼�낢�B�u�̂͂�����߂��v�ƌ������l���A��̍��������Ȃ����̌�̐������ԂŁA���ʋ��ɂ��ꂾ���̉̋Ȃ����ł��傤���B�Ȃ�A�V���[�x���g�Ƃ����l�͑�R���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B���̖��őP�ǂł��l�悵�̃V���[�x���g���ł��B�{���ɁA���̐搶�́A�V���[�x���g�̂��Ƃ������m�Ȃ̂ł��傤���B����ȓ�����O�Ȃ��Ƃɉ��̋^��������Ȃ������̂ł��傤���B
�ȏオ�u�ŐV���ȉ���S�W�v�Ҏ��L�q�́u�O���[�g�v���̏ؖ��ł����A��������p�����]�_�Ə����ɂ��ꌾ�\���グ�܂��B�F�l�͒Ҏ��̕��͂�"�قڂ������肻�̂܂�"���p����Ă��܂����A���̈��Ղ��ɂ��Ă͑傢�ɔ��Ȃ��Ă������������Ƃ������Ƃł��B�ԈႢ���������p�����Ƃ������Ƃ́A�����Ō����Ă��Ȃ��؋��ł��B"���p�͎���̎����ׂ�"�Ƃ�������̊�{��Y��Ȃ��ł��������������̂ł��B
�m�X�e�b�v5�n �^�Ɛl�̑f���𖾂炩�ɂ���
�Ƃ���ŁA���̒ґ��ꎁ�Ƃ͂ǂ�ȕ��Ȃ̂ł��傤�B1895�N���ɐ��܂�A�����鍑��w�𑲋ƁA������w�A�������y��w���_�������C���A���{���y�w������߁A1987�N�A91�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B���{���y�w��Ƃ́A�䂪�����y�]�_�̑��{�R�I���݂�1952�N�ɐݗ��A�����͉������V���B�Ҏ��̂��Ƃ́A�������O�A�C�V�V�q�A�p�q��N��e��������A�ˁA������E�R�뎁�ł��B���Ђ���w��̐ݗ��ɐs�͂����߂�ꂽ�ґ��ꎁ�́A�܂��ɁA���y�]�_�E�̍Œ��V�ɂ��đ�䏊�I���݂������̂ł��B
���������āA�u�O���[�g�v�̉���ɂ����ẮA���y�V�F�Д����u�ŐV���ȉ���S�W�v�̒��́A�d���E�ґ���搶�̒��ɂȂ�y�ȉ�������A�{�Ɩ{���ō����Ђ̒���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B������A���e���˗����ꂽ������́A�^����ɂ��������̂ł��B�܂�������ɊԈႢ�Ȃǂ��낤�͂��͂Ȃ��Ƃ��āB�����Ɍ���I�ȃ~�X�����݂���̂ł�����A���̉e���͂͐r��ō߂͔���ł��B�������A�삯�o���̃��C�^�[�Ȃ炢���m�炸�A���y�]�_�E�̌��Ђ�D�G�Ȓ����Ƃ�������X���ێʂ��ɂ��Ă���̂ł�����A���̉e���̑傫�����M���m��܂��B�����������̂͂��܂��苖�ɂ�����26�_��CD��������ł������A���̒��ɂ͂܂��܂������́u�O���[�g�v�̉�������݂��Ă��邵�A�ԈႢ�Ȃ�������V���ɏ����������邾�낤���炵�āA�u�ŐV���ȉ���S�W�v�����̂܂܂ł���Ȃ�A�~�X�L�q�͂���ɑ����Ă䂭�\��������܂��B���́A�~�X�������炤���ƂƂ���҂ł͂���܂���̂ŁA����Ȃ錟�Ȃǂ������܂��A���̎��_�ɂ����āA�x������K�v�͂��낤���Ǝv���Ă���܂��B
�m���X�g�E�X�e�b�v�n�`�J���ꂽ�N���V�b�N�ƊE�̂��߂�
���y�V�F�Ђ��A���̂悤��"�ԈႢ���炯�̖��ȉ��"������Ă��܂������Ƃ́A�`������䂪���N���V�b�N���y��M�̒����Ƃ��āA���ɒp���ׂ����Ƃł���A����ɁA���̉e���͂��l����ƁA���Ԃ͑����[���ł���Ƃ��킴��܂���B�����Ȃ��́A�u�V���[�x���g��� ������ ��9�ԁw�O���[�g�x�v�̍��̑��}�Ȃ�������A�܂��͊�]�������܂��B�����āA����Ɏ��͒������B����͎������܂��܋C�Â������Ƃł��邩�炵�āA�u�ŐV���ȉ���S�W�v�ɂ́A���ɂ����������̒����K�v�ӏ�������̂ł͂Ɗ뜜������̂ł��B�j���I�ɂ����e�I�ɂ��B�܂��A���������͒���ł��������̂��A�N�����o�ĕ���P�[�X�������͂���͂��ł��B���N�Ŕ���30�N�B���y�V�F�Ђ��A������@��ɁA���Ђ���u�ŐV���ȉ���S�W�v�̑��_�����s�����Ƃ�ɂ��肢������̂ł���܂��B
�����āA�Ō�Ɉꌾ�B���Ђ����̊ԈႢ���A�������̌������������Y�ݏo����������ł������肢���������Ǝv���܂��B�ܘ_���̑唼�͏����ꂽ���X�ɂ���̂ł����A���앨�Ƃ������͕̂ҏW�҂̎���o�Đ��ɏo����̂Ȃ̂ŁA�ނ炪�����̃~�X�ɋC�����A���̒i�K�Œ������邱�Ƃ��o����킯�ł��B�o�ŎЂ̕ҏW��R�[�h��Ђ̕Ґ��Ɍg���F����ɂ́A���̂悤�ȃ~�X�𖢑R�ɖh����悤�A���Ȍ��r���^���ɋƖ��Ɏ��g��ł����������Ƃ�������]�������܂��B�N���V�b�N�ƊE�ł́A"���Ђ��鎷�M�҂̒��q�́A���Ƃ��ԈႢ�Ɖ����Ă��w�E���ɂ�������������"�Ƃ����b�������Ƃ�����܂����A����Ȕn���Șb�͂���܂���B�ԈႢ�͊ԈႢ�ł��B�w�E�E��������̂�������O�ł͂���܂��B���̂悤�ȕ������A�킪���̃N���V�b�N�E����I���Ў�`�I�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̋ƊE�ɐg�������Ⴂ�l�����ɂ́A�E�C�ƐM�O�������Ďd���ɓ�����A����ȓy������v���Ă����Ă��炢�����B�����āA���{�̃N���V�b�N�E���^�Ɏ��R�ŊJ���ꂽ���E�ɂȂ�悤�肢�������̂ł��B
2009.10.26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��3�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�B
�i�V�j�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C��������̗\���H�V���[�x���g���y�F����ցu�I�[�X�g���A�y�F����́A�|�p��ڎw���ǂ̂悤�ȓw�͂��x������Ƃ������M�ȈӐ}���m�M���A�c���̌|�p�Ƃ̈�l�Ƃ��āA���͎v�����Ă��̎��̃V���t�H�j�[���A�M����Ɍ��悵�āA���x�����������Ȃ�����ׂ��A�������Č䐄�܂������Ƃƒv���܂��B�����鑸�h�̔O�����߂āB �t�����c�E�V���[�x���g�h���v�i���^�����o�Ŋ� ���g���v��E����j���̎莆�́A�V���[�x���g���E�B�[���y�F����ɑ�����1826�N10���ɏ������莆�ł��B��ҁE���g���́A�{�����ŁA���̎莆�ɂ��āu���̃V���t�H�j�[�Ƃ́A����܂�"���̃V���t�H�j�["�Ƃ����Ă����w�O�����f���E�K�V���^�C���x�V���t�H�j�[���w���A�Ƃ���邪�A���̋Ȃ͐�̒����̗��s�L�ɕ`�����㕔�I�[�X�g���A�ۗ̕{�n�O�����f���y�уK�V���^�C���n���Ŋ������ꂽ�炵���i1825�N7���`8���j�v�Ɖ�����Ă��܂��B
����͑����u�V���[�x���g��1825�N7���`8���ɂ����đ؍݂����O�����f���y�уK�V���^�C���n���ň�̃V���t�H�j�[�������グ�A������A1826�N10���E�B�[���y�F����ɒ�o�����v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�u���Ƃ̓��[�c�@���g����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��v�E�E�E����͂��̃A���x���g�E�A�C���V���^�C���i1879�|1955�j�̗L���Ȍ��t�ł����A�����肠����A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���i1880�|1952�j�͔ނ̏]��ł��B�ނ̒��킵���u�V���[�x���g���y�I�ё��v�i�����Њ� ���^�j��j�́A�V���[�x���g�����̌ÓT�Ƃ����閼���B�Ƃ��낪����A���̒��́u�O���[�g�v�Ɋւ��鍀�ڂ�ǂ�ł�����A�u����H�v�Ǝv���ӏ��ɂԂ���܂����B����͂��̕����ł��B
�u�n�����V���t�H�j�[�iD944�j�ɂ��Ă̘b�͎��m�̂��Ƃł���B1838�N�H�Ƀ��[�x���g�E�V���[�}�����A�����Ǝ����̌|�p�̂��߂Ɍ̋���������L���ȓy�n�����o�������Ƃ����f�p�Ȋ�]������ăE�B�[���ɈڏZ�����Ƃ��A�ނ̓V���[�x���g�̕����łȂ��A�V���[�x���g�̌Z�t�F���f�B�i���g�̉Ƃ����K��āA1839�N�̂͂��߁\�\���m�Ɍ�����1���P���\�\�ɁA��e��"�R�ς݂�������"�̂Ȃ����炱�̃V���t�H�j�[�������̂ł���B�E�E�E�����E�E�E�V���[�x���g���g�́A���̃V���t�H�j�[�̊�����܂��Ȃ��A������E�B�[���y�F����ɒ�o�������A��������"���܂�ɒ����A���܂�ɂނ�������"�Ƃ��ċ��ۂ����Ƃ��ɁA���̑���ɑO��̃n�����V���t�H�j�[�i��6��D589�j������B�E�E�E�����E�E�E�����f���X�]�[���͂��̍�i�������āA1839�N3��21���̏�����ɂ��A����ɓ�t�����v�O�q�����u�V���[�x���g�̎莆�v�ɂ́u�w�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁx��1826�N10���ɃE�B�[���y�F����ɒ�o�����v�Ƃ���܂����A�A�C���V���^�C���́u�w�O���[�g�x������܂��Ȃ��y�F����ɒ�o�����v�Ƃ��Ă��܂��B�A�C���V���^�C�����u�V���[�x���g���y�I�ё��v���������̂�1948�N�Ȃ̂ŁA���̍��ɂ͂܂��u�O���[�g�v���u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�Ɠ���ł���Ƃ������Ƃ͎�����Ă��܂���B���������āu�O���[�g�v������܂��Ȃ��Ƃ����̂́A�A�C���V���^�C���̒��ł́A1828�N3���ȍ~�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�A�C���V���^�C���̂��̋L�q���������Ƃ���ƁA�i���ƂȂ��Ắu�O�����f���E�K�V���^�C���v�́u�O���[�g�v�Ɠ���Ǝ����ꂽ�̂ł�����j�V���[�x���g�͈�x���ۂ��ꂽ������i��2�N��ɍēx����ɒ�o�������ƂɂȂ�܂��B�V���[�x���g�͖{���ɂ���Ȃ��Ƃ������̂ł��傤���H���Ƃ��ẮA�܂��A�펯�I�ɍl�����Ȃ��̂ł����E�E�E�B
1828�N3���ȍ~�Ɂu�O���[�g�v������ɒ�o�����Ƃ����L�^�́A�V���[�x���g���g�̎莆�ɂ͑��݂��܂���B�ł̓A�C���V���^�C���͉��������ɂ����������̂��H�����1826�N10���� ���Ⴂ�ł͂Ȃ��̂��H ������ނ̓��̒��ł́A���ӎ��̂����ɁA�u�O���[�g�v���u�O�����f���E�K�V���^�C���v�Ƃ����}�����\�z����Ă����̂ł͂Ȃ����B����̓A�C���V���^�C���̊�ՓI�ȗ\���Ȃ̂ł͂Ȃ����H ����A"����Ɂu��6�ԃn�����v���o��������"�Ƃ�����̓I�L�q������̂�����A�����Ɖ��炩�̍���������ɈႢ�Ȃ��B�ȂǂȂǁA����₱���ƁA�����ϑz�����点�Ă��܂����H�̖钷�̉ɂԂ��ł����B
�i�W�j�u�O���[�g�v��CD�������������
���ЁE�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���̖����ɁA����قǂ܂łɍl����������L�q������̂ł�����A�䂪���̕]�_�Ɛ搶�����ꂱ��ƍ������Ă���������ʂ��Ƃ�������܂���B�����ł͎莝���́u�O���[�g�vCD�̉������A�����[�����͂������āA������Ɛ��]�����������Ă��������܂��B�v�������~�X�L�q�������āA���\�y���߂܂����i����I�j�B�ł́A�u�O���[�g�v�̐������p���ӏ������ɂ��āA�����X�^�[�g�B�F�l������6���ڂƏƂ炵���킹�Ă��y���݂��������B
�@ �u�O���[�g�v��"���̌�����"�Ƃ����Ă����u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�Ɠ����i����{�^�Վ��̉���i�n�C���c�E���[�O�i�[�w���F�x���������������y�c��CD�j
�@ �@����B
�A 1825�N7���`8���ɍs�����O�����f���`�K�V���^�C���n�����s���ɏ����n�߂��A10���ɂ͂�
�@ �@�Ƃ�ǂ̊������݂��B
�B 1826�N10���A�V���[�x���g�͂��̍�i���A�E�B�[���y�F����ɒ�o���Ă���B
�C 1838�N12���ɁA�E�B�[���ŃV���[�x���g�̕�����Q�肵���V���[�}���́A���N1���P���ɃV���[
�@�@�x���g�̌Z�t�F���f�B�i���g��K�ˁA�u�O���[�g�v�̎�e�y���������B
�D �����ɂ��̍�i�̐^����F�߂��V���[�}���́A�����f���X�]�[���Ɋy���𑗂艉�t�𑣂����B��
�@�@�̌���1839�N3��21���A�����f���X�]�[���̎w���ɂ�胉�C�v�c�B�q�ɂď������ꂽ�B
�E �u�Ƃɂ����l�́A�傫�ȃV���t�H�j�[�ւ̓���ؑĂ������Ǝv���Ă���v�Ƃ���1824�N3��31
�@�@���N�[�y���E�B�U�[�Ɉ��Ă��莆���u�O���[�g�v��Ȃ̏o���_�Ƃ����Ă���B
�u���̌����Ȃ���Ȃ��ꂽ�̂́A�V���[�x���g�̎��̔N�ł���B���̂���ނ�"���͑傫�Ȍ����Ȃ����������B�̂͂�����߂�"�ƗF�l�ɉk�炵�Ă���v
�u�O���[�g�v���u�O�����f���E�K�V���^�C���v�ł���Ƃ����}���́A�q�ϓI��100���������ƔF�m���ꂽ�킯�ł͂Ȃ����炵�āA�]�_�Ƃ̊F�l�ɂ͊e�X�̌����������Ă�����ׂ��ł��傤���A�����Ă�̏����ꂽ����Ȃ�A1828�N����ȔN�Ƃ���̂͂�ނ����Ȃ��Ǝv���܂��B�������A���͂��̐}���͐������ƐM������̂Ȃ̂ŁA�����Ă��̌������Ȃ��Đ��]�����Ă��������܂��B�F����F���i�J�[���E�V���[���q�g�w���F��h�C�c���������y�c�j
��{���͑�䏊�ł����A��ȔN��ȊO�ɂ��A2�_�̌�肪����܂��B"�傫�Ȍ����Ȃ���������"�Ƃ����̂́A���̔N�ł͂Ȃ�1824�N�̂��ƁB"�F�l�ɉk�炵��"�̂ł͂Ȃ��A�莆�ɏ����Ă���̂ł��B
�u�����1838�N�����̂��Ƃł���B�E�B�[����K�ꂽ���ȉƃV���[�}���́E�E�E�����E�E�E�����ē��N3��21���ɃQ���@���g�n�E�X�̃R���T�[�g�ɂ����āA�����f���X�]�[���̎w�����ɗ��j�I�ȏ������s��ꂽ�B�v
����͉F��搶�炵����ʃ~�X�B�V���[�}�����E�B�[����K�˂��̂�1838�N��10���ŁA�����Ƃ����Ȃ�1839�N�������ł��B���������ď����N��1838�N�ł͂���܂���B������94�N�ɏ����ꂽ�u�W�����[�j�w���F�o�C�G�������������y�c�v��CD����ł́A�S�Ă̍��ڂ��������C������Ă��܂��B�������E�F��搶�ł��B���ђ��Ǝ��i�t�����c�E�R�����B�`���j�[�w���F�`�F�R�E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�j
�u�ނ������Ȃ������ӎ����Ă����̂�1828�N�A���̔N�ł������B���̎��A�ނ͗F�l�Ɉ��ĂĂ��������Ă���B�w�����̋Ȃ͂�߂��B���ꂩ��͌����Ȃ����������x�B�����������ӂ̂��Ƃɏ����ꂽ���̃n�����̌����Ȃ́A�ǂ���Ɋy�F����ɑ���ꂽ�B�v
����͔ՋS�E���ю��炵����ʃ~�X�B��ȔN�Ǝ莆�̎������ԈႢ�B���̎莆�������ꂽ�͇̂E�ɂ���悤�ɁA1824�N�̂��Ƃł��B2003�N2���Ƃ������q���t������܂����A���̎����Ȃ�O�f�́u6���ځv�͂��͂�펯�̂͂��ł��B�Ɨ��a�v���i�I�b�g�[�E�N�����y���[�w���F�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�j
�u�V���[�x���g�ɂ��Ō�̌����Ȃł���A�S���Ȃ�8�����O�ɍ�Ȃ��ꂽ�B�i��Ȃ́j���ڂ̓��@�́A�ނ����h����x�[�g�[���F���̎��ɐڂ������Ƃł���A���̈̑�Ȃ��y�ɕC�G��������Ȃ��������Ƃ����������S���ނ����̌����ȂɌ����킹��B�������āA1828�N3���ɍ�ȂɎ�肩����A�X�P�b�`���Ƃ炸�ɒ����ɃX�R�A���������낵�A��C�萬�Ɏd�グ�邱�ƂɂȂ�B�v
���쎞���͂��Ȃ�ȑO�Ǝv����̂ŁA��Ȃ��ꂽ�̂�1828�N�Ƃ����̂͑�ڂɌ��܂��傤�B�������A��ȓ��@��"�x�[�g�[���F���̎��ɐڂ�������"�ƒf�肵�Ă���̂͒P�Ȃ鉯���ɉ߂��Ȃ����A���ʓI�ɂ͊ԈႢ�ł��B"�X�P�b�`�Ȃ��̒������ň�C�ɏ����グ��"�́A�u�O���[�g�v�������̕��ʂł����c���ĂȂ��������ƂƁA1828�N3���Ƃ����������l�����Ĉ����o���ꂽ����Ȃ̂ł��傤���A���p����Ƃ��͎����Ȃ�̍l�@�����ė~���������Ǝv���܂��B��O���ꂽ���Ƃł͂��ׂĂ����������ʂɂȂ��Ă��܂��̂ŁB�x���C���i�w���}���E�A�[�x���g���[�g�w���F���C�v�c�B�q���������y�c�j
�u�V���[�x���g��1828�N��3���A���̑�Ȃ������������B�������ꂽ�����Ȃ́A1838�N�Ƀ��C�v�c�B�q�ŏ������ꂽ�B�v
"1838�N�ɏ������ꂽ"�͊ԈႢ�B���̂����̃~�X�͐������U������܂��B�ēc���ꎁ�i�J�[���E�x�[���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[75�N�������C�u�j
�u�����́A�����f���X�]�[���̎w�����郉�C�v�c�B�q�E�Q���@���g�n�E�X�nj��y�c�ɂ����1838�N3��21���ɍs���Ă���B�v
"�����N1838�N"�͓���̃~�X�B�����i�G�[�h���A���E�{�[���g�w���F�����h���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�j
�u1828�N3���A�V���[�x���g�͔ނ̍Ō�̌����Ȃ������������B�E�E�E�����E�E�E1838�N�̏����A�E�B�[����K�ꂽR�D�V���[�}���́E�E�E�v
���̒�����t2006�N11�����_�Łu6���ځv�͏펯�B�V���[�}�����E�B�[����K�ꂽ�̂�1838�N�̏����ł͂Ȃ�10���ł��B�n�ӌ쎁�i�I�b�g�[�E�N�����y���[�w���t�B���n�[���j�A�nj��y�c�AEMI�����1300�j
�u�V���[�x���g�����N�A1828�N�ɍ�Ȃ��ꂽ�B�ނ͂��̍�i���E�B�[���̊y�F����ɒ�o�������A����͂��܂�ɏd�ꂵ������ł���Ƃ̗��R�ł����ԋp�����̂ł���B�v
����CD��2005�N�̔����ł����A"�����1965�N�̂��̂�]�p����"�Ƃ���܂��B�咷�V�E�n�ӎ������̎����ɏ��������̂Ȃ�A"���̔N1828�N�̍�i"�Ƃ���͎̂d�����Ȃ��ł��傤�B�܂��A"������y�F����ɒ�o�������ԋp���ꂽ"�̕����́A�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���̋L�q�����̂܂܈��p���Ă���ƍl�����܂��B����́A�u�V���[�x���g���y�I�ё��v��1962�N�ɓ��{��o����A�����ɃV���[�x���g�����̃o�C�u���Ƃ��Ē蒅�������Ƃ�������@����܂��B�ȏ�A�d���̋��c�c�L���肵�Ă��܂����̂ŁA�����̔O�����߂āA�Ō�ɍō��ɑf���炵����������������Ă��������A���̃R�[�i�[����߂����Ǝv���܂��B����́A���쏺���̉���ł��i�I�g�}�[���E�X�E�B�g�i�[�w���F�x�������E�V���^�[�c�E�J�y���ɂ��u�V���[�x���g�F�����ȑS�W�v�j�B�u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�̑��݂Ɓu�O���[�g�v�Ƃ̊W���A�c����Ă��镶���ƐM���ł��錤�����ʂ݂̂������ɂ��Ę_�������̂ŁA��_�̞B�������Ȃ��^�Ɏ��ؓI�ȕ��͂ƂȂ��Ă��܂��B�ڍׂɂ��Ă͎���G��邱�ƂɂȂ낤���Ǝv���܂��B
����ɂ��Ă��A���R�[�h�E���[�J�[���A2005�N�̎��_��1965�N�̉�������̂܂ܓ]�p����̂͂������Ȃ��̂ł��傤���B40�N�̊ԂɐV���Ȍ������Ȃ���͑傢�ɕς���Ă���̂ł�����A����͉����Ƃ����Ă��d�����Ȃ��Ǝv���܂��B
2009.10.17 (�y) �V���[�x���g1828�N�̊��2�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�A
�i�S�j�V���I�Ȓ����u�O���[�g�v�����������Ȃ̑㖼���ɂȂ����̂́A���@�҃V���[�}���̃R�����g�ɗR�����Ă��܂��B�H���u�W�����E�p�E���̎l���̑啔�̏����ɗ�炸�A�V���̂悤�ɒ����v�ƁB�����ň��������ɏo�����W�����E�p�E���i1763�|1825�j�̓h�C�c�E���}���h�̏����ƁB�}�[���[�̌����ȑ�P�Ԃ̃^�C�g���u���l�v�́A�W�����E�p�E���̓�����������̈��p�ł��B�V���[�}���̐^�ӂ�"��������ǎ��Ԃ��o�̂�Y���قǖʔ���"�ɂ���܂����B
�V���[�x���g�́A��������N1826�N10���ɁA���̋Ȃ��E�B�[���y�F����ɒ�o���Ă��܂��B���������̂���u�O���[�g�v�����t���ꂽ�`�Ղ͂���܂���B���̌�A�V���[�}����������1839�N�Ƀ��C�v�c�B�q�ŏ������ꂽ����A�����h����p���̃I�[�P�X�g���́A��P�y�͂����̉��t�ŏI����Ă��܂��B�u�����ē���v�Ƃ������R�ŁB���������āA�������̋Ȃ𗝉������̂́A�V���[�}���ƃ����f���X�]�[���ƃ��C�v�c�B�q�̎s�������������Ƃ����邩������܂���B
�M�l�X�u�b�N�ɍڂ��Ă��鐢�E�Œ��̌����Ȃ́A�n���@�[�K���E�u���C�A���i1876�|1972�j�Ƃ����l�������������ȑ�P�ԁu�S�V�b�N�v�ŁA������110���Ƃ̂��Ɓi���́u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v�Ȃǂ̃~���[�W�J����ƃ��`���[�h�E���W���[�X��������uThe Symphony Victory At Sea�v�Ƃ���13���Ԃɂ��y�Ԍ����Ȃ����邻���ł����A����͘g�O�Ƃ���̂��Ó��Ȃ悤�ł��j�B����ɔ�ׂ���u�O���[�g�v��50�����������Ƃ����̂́A�����ɂ������Ȃ����A�u���v��1824�N�ɂ͊������Ă��Ė�70���A���N��̍�i�x�����I�[�Y�́u���z�����ȁv��5�y�͂Ƃ͂����u�O���[�g�v����Ⓑ���B�ł��܂��A�����̐l�X�������̂͗����ł���Ƃ��āA���݂̋ȉ�����A���ꂱ���n���̈�o���̂悤�Ɂu�V���I�Ȓ����v�Ƃ��茾�������Ă���̂͂������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�V���[�}�����{���Ɍ������������͎̂��͂����ł͂Ȃ��A���̑O��̕����Ȃ̂ł��B�v��ƁB
�u�����ɂ����āA���̌����Ȃ�m��Ȃ��l�͂܂��V���[�x���g���悭�m��Ȃ��B���̌����Ȃɂ͂����̔������̂Ƃ��A���܂ʼn��y�����S��ƂȂ��\���Ă�������ӂꂽ��y�Ƃ��������̈ȏ�̂��̂���߂��Ă��āA�����l�����܂ł��������Ƃ��v���o���Ȃ��悤�Ȃ��鍑�֘A��Ă䂭�B���̂Ȃ��ɂ́A���X���鉹�y��̍�ȋZ�p�ȊO�ɁA���푽�l���ʂ��ɂ߂��������ł������Ȓi�K�Ɏ���܂ŕ\��Ă����ɁA������Ƃ���ɐ[���Ӌ`������A�ꉹ�ꉹ���s�����ɂ߂��\���������A�������čŌ�ɑS�Ȃ̏�ɂ͍��܂ł̂��ׂẴt�����c�E�V���[�x���g�̋Ȃɂ���ĂȂ��݂��[�����}�������܂����炳��Ă���B��������Ɖ���ɂ����̂ł����A�V���[�}�����������������̂�"�܂�����Ȃ����}���e�B�V�Y������V���[�x���g�̋Ȃ����A���ĕ��������Ƃ̂Ȃ��悤�ȌQ������i�ł���B���ʂĂ�Ƃ��m��Ȃ����A���܂ł��g���ς˂Ă������قǁA�L���őu�₩�ȋȂł���B�x�[�g�[���F���̉e������E������A��Ȏ҂̒j���I���ʂ������ɔ�������Ă���"�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�����b���A"�����đދ�"�ł͂Ȃ�"���܂ł��I����ė~�����Ȃ��قǑ�z���Ă���"�Ƃ��������̂ł��ˁB������^�E��^�̗��Ȃ̂ł����A���̋C�������܂����������A�����������Ȃ��ł���܂��B
�p�E���̏��������̃n�����̌����Ȃ��A�ǂ���������ďI���Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��ẮA���ɂ����Ƃ��ȗ��R������̂ŁA��Ƃ��ǎҁi������j�ɁA���̌���A���ꂩ�炻��ւƐS�䂭����l�����������̂�����A�ǂ����Ă��I��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B�S�Ȃɂ݂Ȃ���L���Ȋ������A�ǂ�قǐl�̐S������₩�ɂ��邾�낤�B�ق��̋Ȃł͂������I��邩���I��邩��S�z���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂����̋Ȃ́A�x�[�g�[���F���̌����Ȃɑ��Ċ��S�ɓƗ����Ă���Ƃ����_���A���̗Y�X������ȉƂ̖ʖڂ��⊶�Ȃ��\���Ă���v�i��g���ɃV���[�}�����u���y�Ɖ��y�Ɓv�g�c�G�a����j
�i�T�j�u���v���ӎ��H
�u�O���[�g�v�̓V���[�x���g���g"���M��A��D���ȋ�"�ƌ����Ă��܂��B������D���Ȃ̂ŃV���[�x���g�̊����Ƃ܂��ɍ��v���āA����������B�Ƃ���Ŕނ́A���̋Ȃ����ɂ�����A�u���v���ӎ����Ă����̂ł��傤���H�c���a�I�v����́u�N���V�b�N���Ȗ����_�v�ɖ��X�����[���l�@������܂��B
�u��4�y�́A�W�J���ɓ���A���̂���߂��͂₪�ĕσz�����ɗ��������B����ƃN�����l�b�g�̓�d�t�����̂悤�Ȑ����������̂ł���i��385���߈ȉ��j�B����͉����H����̓x�[�g�[���F���́w���x����̎�肻�̂��̂ł͂Ȃ����v���̕����́i�ړ����Łj�A�u�\�[�t�@�~���t�@�~���h�[���~�~�[�����[�v�Ȃ̂ŁA�u���v��"����̎��"�u�~�[�t�@�\�\�t�@�~���h�h���~�~�[�����[�v�ɍ������Ă��܂��B�ŏ���4���́A�Ђ�u�\�[�t�@�~���v�A�Ђ�u�~�[�t�@�\�\�v�ŁA3�x���ꂽ��P�����A��2���Ō������āA��3����3�x�A��4����4�x�����Ƃ����V�����g���[���^�B��5�����炠�Ƃ͑S�������ł��B�c������́u����̓V���[�x���g���Ӑ}�������̂ŁA�x�[�g�[���F���ւ́A�w���x�ւ̃I�}�[�W���ɑ��Ȃ�Ȃ��v�ƌ����Ă��܂����A�������̐��Ɏ^�����܂��B�������V���[�x���g�͎��ɍI���Ȏ�@���g���Ă���B���̉��^���t���ɏo��܂ŁA�u�\�[�t�@�~���t�@�~���v�Ƃ����O������������o�������Ă��܂��B����͂������Ɉ�ەt����̂��ړI�ŁA���������ł͑S��"����̎��"�Ƃ̑������͔F�m�ł��܂���B�����āA���������đS�̂��o���B���̂Ƃ�������́A��ەt����ꂽ�O�����̂��ƂɌ㔼���u�h�[���~�~�[�����[�v���t�����Ă���Ƃ����`�ŕ����B�ʕ��ƔF�m���Ă���O���Ɂu�h�[���~�~�[�����[�v���t���Ă��A"����̎��"�Ƃ͊��m�ł��Ȃ��B���̏�A�u���v��4����4���q�ɑ��u�O���[�g�v��4����2���q�Ȃ̂ʼn�������F�m���ɂ������ʂ�����܂��i���_����̓V���[�x���g���Ӑ}�������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���ʓI�ɂ̓J���t���[�W���̖�ڂ��ʂ����Ă���j�B�c������́u���^�T���Ɍ���ɂȂ��Ă���l�������ǂ����ċC�Â��Ȃ��̂������ł��Ȃ��v�Ƃ���������Ă��܂����A�ނ�͂��̃V���[�x���g�̍I����㩂Ɋ|�����Ċ��m�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�I�}�[�W���̖��ߍ��݂͊��m����Ȃ��悤�ɂ���̂��v���̋Z�ł�����B�Ԃ��Ă����ɃV���[�x���g�̈Ӑ}��������A�Ǝ��͎v���܂��B�����āA����ɋC�Â����c������̊����͑f���炵���B���_�B��͂�V���[�x���g�́u���v�ɐG������āu�O���[�g�v���������I�u�Ƃ������A�傫�ȃV���t�H�j�[�ւ̓����Ă䂱���Ǝv���Ă���v�Ƃ���1824�N3��31���̎莆���A�u���v�̃j���[�X���Ă̂��̂��������Ƃɕ������܂��B
�Ƃ��낪����A�Ȃ�Ƌ����ׂ����ƂɁA9�D16�u�N�����m�v�̒��ł����p�����u�l�͂��̐��ōł��s�K�ōł��S�߂Ȑl�Ԃ��v�Ŏn�܂�A�V���[�x���g�̐��U�̒��ł���ȏ�Ȃ���]�I�Ȏ莆�̌�i�̕����Ȃ̂ł��B�o������"����]�I"��i��"�V���Ȓ���"�܂��ɐ�]�Ɗ�]���������Ă��܂��B���͂��ꂾ���������銴�������莆��ǂ��Ƃ�����܂���B�ꌩ���[�c�@���g�̃p������̎莆�Ƒ��ʂ���悤�ȋC�����܂����A�{���I�ɂ͈قȂ�܂��B�����ɁA������������V���[�x���g�̐��_�̔閧���B����Ă���̂����B���̂�����͂܂�����ȍ~�ŁB
�i�U�j�u�O���[�g�v�ő�̊�����
�V���[�}���͂��������Ă��܂��B�u���̋Ȃ̖͗l�������ł��m�点�悤�Ǝv������A�����ȑS�̂̋������ł������悤�ɏ����Ȃ���Ȃ�܂��B�����A����Ȋ����I�ȑ�2�y�͂ɂ��ẮA���Јꌾ���Ȃ���C�����܂Ȃ��B���̒��Ńz��������������ĂԐ��̂悤�ɕ������Ă���Ƃ��낪����B������ƁA�l�͂��̐��Ȃ�ʐ����悤�ȋC������B�������ēV�̊��e�̔E�ё��Œʂ��Ă䂭�����A�X�����邩�̔@���S�y��͂͂��Ǝ~��Ŏ������܂��B�v
�����́A�z�������g����A�����Đ���Â��ɑt�ł�Ƃ���ŁA�V���[�}���������邽�����ЂƂ̊����̋�̗�Ƃ����܂��B�m���ɂ���̓��j�[�N�ň�ۓI�ȉӏ��ł����A���ɂƂ��Ă̂���͓�����2�y�͂̑�P�̂Ȃ����玟�̎��ւ̗���̕����Ȃ̂ł��B�����V���[�}���ɂȂ���āA���̈�ӏ���������̗�Ƃ��ċ��������Ă��������܂��B
��2�y�͂́AA1�|B1�|A2�|B2�|A1�Ƃ����K�͂̑傫�ȎO���`���ō\������鉸���y�͂ł����A����A1����B1�ւ̂Ȃ��̕�������B1�̎�������o��܂ł̊y�z�̕ω������ɂƂ��Ă̍ő�̊������ł��B�n��������ڍs�����C���������炭��������A�剹�C�����Ƀg�����y�b�g�ƃt�@�S�b�g�t���ጷ���㉹�őt�ŁA�ǂ����s�C���ȕ��͋C�������o���܂� �i89���߂���j�B�������ŃN�����l�b�g�������Ƃ�┖�������������ށB�܂������������ɖ؊Ǎ��t�Ɉڂ�Ƃ���ɖ��邳�𑝂��A���ɂ͌����܂��܂������C�����ꉹ�Ƃ���D�������炩�Ȑ������w�����ʼn̂��o���B���̕\��̂Ȃ�Ɛ_�X�������Ƃł��傤�B���̐����ߊԂ́A��т��ăC����Ƃ��Ă���A�����ɘa���̕ω�����`���āA���푽�l���ʂȕ\������o���B���������R�ȗ���̒��ŁB���ꂼ�V���[�x���g�̋H�L�Ȃ�˔\�̂Ȃ���Z�Ƃ����܂��B���������ނ̐S�g��������K�V���^�C���̑厩�R����O�Ɍ��o�������̂悤�B�����ɂ̓V���[�x���g�Ɖ�X�̈�̊�������܂��B�����Ă��銽�т��������鎊���̏u�Ԃ�����܂��B
�Ȃ�����̃^�C�g���A�u1828�N�̊�Ձv�́A�䂪�F�E�@�����̃����E�����̃��[������q�������́B�ނ̉��y�ɑ��鑢�w�͔��[���Ⴀ��܂���B���Ƀh�C�c�E���[�g�ƃi�c�����Ɋւ��ẮB����V���[�x���g�������ɂ�����A���[�g�͖ܘ_�A�s�A�m�Ȃɂ��Ă����낢�낲�������������܂����B���ӂ̔O�����߂āA�ނ����N�n�߂��u���O�u�����E�����̉������l���v���Љ�܂��BGoogle�Ɂu�����E�����̃i�c�����v�Ɠ����Əo�܂��B�}�j�A�b�N�ɂ��Ċy���������A���y���݂��������B
2009.10.07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂP�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�@
�V���[�x���g��1828�N11��19���A�E�B�[���ł��̐��U����܂����B���N�͂�31�ł����B���̔N�ɂ́A3�Ȃ̃s�A�m�E�\�i�^�A�R�̃s�A�m�ȁA�s�A�m�O�d�t�ȑ�1�ԁA�����ȑ�8�ԃn�����u�O���[�g�v�A�~�T�ȑ�6�ԁA���y�d�t�ȁA�̋ȏW�u�����̉́v�Ȃǂ����đ����ɒa�����Ă��܂��B�������A�S�Ă̋Ȃ́A���������Ƃ��Đ[���A�����ꂽ�������ɖ����Ă���A�^�̌��삼�낢�B���ʋ��ɂ܂��Ɋ�Ղ̔N�Ƃ��������悤������܂���B���y�j��A����ɔ䌨����̂̓��[�c�@���g�̃P�[�X�����ł��B����A�V���[�x���g��Ղ̔N1828�N�ɐ荞��ł䂫�����Ǝv���܂��B�܂��́A�����ȑ�8�ԁu�O���[�g�v����B
�m�P�n�u�O���[�g�v�A���̈̑�Ȍ�����
�i�P�j�u�O���[�g�v��"��8��"�ɗ������܂�
�u�O���|�g�v����Ղ̔N�̍�i�Ƃ����Ă����̂́A���M����"1828�D3"�Ƃ����������݂�����������ł��B�����āA�ŋ߂܂ő�9�ԁA����ȑO�͑�7�ԂƌĂ�Ă��܂������A���݂ł͑�8�Ԃɗ������܂����B�܂��͂��̌o�܂���B
�V���[�x���g�̍�i�ԍ��ɂ́A����D���t���Ă��܂����A����̓h�C�b�`���ԍ��Ƃ����āA�I�b�g�[�E�G�[���q�E�h�C�b�`���i1883�|1967�j�̓������B�h�C�b�`���́A�c��ȗʂ̃V���[�x���g�̍�i���A��ȏ��ɐ����Ҏ[�����I�[�X�g���A�̉��y�w�҂ł��B�ژ^��1951�N�Ɋ������܂������A�ނ͂��̒��ŁA�����Ȃ��ȉ��̂悤�ɋK�肵�Ă��܂��B
��1�Ԃ����6�Ԃ܂ł͊�����i�Ƃ��Ċm�肵�Ă���̂Ŗ��͂Ȃ��B1821�N�̃z�����̓X�P�b�`�Ƃ͂����S�y�͂��������Ă���̂Łu��7��D729�v�Ƃ��A1822�N�̃��Z����2�y�͂܂ł����Ȃ���������i�Ƃ݂Ȃ��u��8��D759�v�Ƃ���i���ꂪ�u�����������ȁv�j�B�y����1828�N3���̃T�C��������n�����́A�Ō�̍�i�Ȃ̂Łu��9��D944�v�Ƃ���i���ꂪ�u�O���[�g�v�j�B�����҃V���[�}������7�Ԗڂ̌����ȁi�����u�����������ȁv�͖������j�Ə����Ĉȗ���7�ԂƌĂ�Ă����u�n�����v���A�����ő�9�Ԃɕς�邱�ƂɂȂ����̂ł��B���̑��̖�������i��莆�����ɓo�ꂷ��u���̌����ȁv�ɂ́AD�ԍ��̂ݗ^���ď���ԍ��͑ł��Ȃ��B�ȏオ�h�C�b�`�����s���������Ȃ̋K��ł��B
�h�C�c�̊y���o�ł̑��x�[�������C�^�[�Ђ�1978�N�Ɍ��������A���ۃV���[�x���g����Łu�V�V���[�x���g�S�W�v�ɂ��ƁA��7��D729�͌����Ȃ̘A�Ԃ���O����܂����B���̋Ȃ́A�E�B�[���̖��w���҃t�F���b�N�X�E���C���K���g�i�[��ɂ���ăI�[�P�X�g���[�V�������Ȃ���A���R�[�f�B���O������܂����A�s�A�m�E�X�P�b�`�����c����Ă��Ȃ������̂ł�����A���̑[�u�͓��R�ł��傤�B���������āA���̂��Ƃ�2�Ȃ��J��オ��A��7�Ԃ��u�������v�A��8�Ԃ��u�O���[�g�v�ƂȂ�܂����B���҂̊Ԃł́A�����ԓ���ԍ��͕ς���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����l�����܂��B�m���ɁA���Ȃ��A�u�������v�Ƃ����Α�8�ԂƂ����̂��̂ɐ��݂���ł���̂ň�a���͑傫���̂ł����A���̃��C���E�A�b�v�͗��j�I�ɗ����ꂽ�Ó��Ȃ��̂Ȃ̂ŁA����ɏ]���ׂ����Ǝv���܂��B10�N������Β蒅����ł��傤����B
�i�Q�j�u���̌����ȁv
�V���[�x���g��1824�N3��31���̎莆�ŁA�u�̋Ȃł͐V�������̂͂Ȃ��A���̑���A��y���������삵���B�����������ɂ��āA�Ƃ������傫�ȃV���t�H�j�[�ւ̓����Ă������Ǝv���Ă���B�E�B�[���̈�ԐV�����j���[�X�́A�x�[�g�[���F�����R���T�[�g���J���āA�ނ̐V�����V���t�H�j�[�A�V�����~�T����3�ȁA����ɐV�������Ȃ����I����Ƃ����������v�Ə����Ă��܂��B���̂Ȃ��̃V���t�H�j�[�Ƃ́A�������炢���āu������ ��9�� �j�Z�� ��i125��i�u���v�j�ŊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�u���v�́A1824�N5��7���A�E�B�[���A�P�����g�l���匀��ŏ�������Ă��܂��B�Ȃ��A"�V�����~�T"�Ƃ����̂́u�����~�T�� ��i123�v�̂��Ƃł��B�V���[�x���g�́u���v�ɐG�������"�傫�ȃV���t�H�j�["�����Փ��ɋ��ꂽ�ƍl���Ă��s���R�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�ł́A�V���[�x���g�́u���v�����ۂɕ������̂ł��傤���B�c���a�I�v�������ꂽ�u�N���V�b�N���Ȗ����_�v�i�A���t�@�x�[�^�Ёj�́u�O���[�g�v�̍��ɋ����[���l�@������̂ň��p�����Ă��������܂��B
�u�x�[�g�[���F����2�Ȃ̏�����5��7���A�ĉ���23���B��������25���ɃV���[�x���g�̓n���K���[�Ɍ����E�B�[���𗧂��Ă���v����́A�G�X�e���n�[�W���݂���A�ߏ�̉��y���t�ɂƏ����ꂽ�������ł����B��Ȏd���ւ̗��������u���v�ĉ���2����B�V���[�x���g�͔O��̉��t���A�S�u���Ȃ��n���K���[�ɗ��������̂�������܂���B�Ƃ͂������̏؋��͂Ȃ��A���яG�Y�̌����u���j�͌��������������v����������܂��B������ʔ����̂ł����E�E�E�E�B
�V���[�x���g�́A���̗��N1825�N�̉āA�k�I�[�X�g���A�ۗ̕{�n�O�����f���A�K�V���^�C���n���ɗ��s�ɏo�����܂��B�n�v�X�u���N�Ƃ����p�������̉�����ۗ{�n�ŁA�a�g�̃V���[�x���g�͑��̊Ԃ̕����i�����̂ł��傤�B���̂Ƃ��̎莆����́A����ȐS�̈��炬�Ƒ̒��̂悳���������܂��B
���̒��ŁA�u���V���������ȂɎ��g��ł���v�Ƃ����L�q�����邱�Ƃ��A�����̕����ɏ�����Ă��܂��B���Ƃ��A�V���[�x���g�����̌ÓT�A���t���[�g�E�A�C���V���^�C���́u�V���[�x���g���y�I�ё��v�i1948�N���j�̒��ɂ́A�u6���̌㔼��7���̑O���̓O�����f����"����߂ċC�����悭"�߂������B�����Ă����ŁA���̕��������V���t�H�j�[�������n�߂�ꂽ�̂ł���v�ƁB�܂��A�C���^�[�l�b�g�ɂ��u�V���[�x���g�̎莆�Ɍ��y��������̂̊y���̑��݂��Ȃ��E�E�E�v�iWikipedia�j�Ƃ��1825�N�̉āA�O�����f���n���ւ̗��s���̎莆�̒��ŁA�����Ȃ���Ȓ��ł���Əq�ׂĂ���v�Ȃǂ̋L�ڂ�����܂��B�v����Ɂu�V���������Ȃ������Ă���v�Ƃ����V���[�x���g�̎莆������Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB���͂��̏o�T��T�����̂ł����A�����Ɍ������Ă��܂���B
�V���[�x���g�̍ō����ЂƂ����h�C�b�`���������đ��ɂ��܂���B�ނ�1914�N���s�́u�h�L�������g�|�V���[�x���g�̐��U�v�́A�{�l�̎莆�𒆐S�ɂ��āA���̐��U��Ԃ������́B1825�N�ɂ�9�ʂ̎莆���f�ڂ���Ă��܂����A���̂����A���s��̃O�����f���E�K�V���^�C���n���Ȃǂ���́A7�^21�V���p�E�����A7�^25���e���A9�^12�Z�t�F���f�B�i���g���A9�����A���V���^�C�����A9�^18��������19�o�E�G�����t�F���g���A9�^21�Z�t�F���f�B�i���g����6�ʂ̎莆����肠�����Ă��܂��B���{���ō��v300�s����c��ȗʂł��B�Ƃ��낪���̒��ɂ́u�����Ȃ������Ă���v�ȂǂƂ��������͂����̈�s���o�Ă��܂���B�h�C�b�`���͂��̌�u�V���[�x���g��i�ژ^�v�����������āA�����Łu�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv��D�ԍ���^����̂ł�����A���̂��Ƃ��L�����莆������̂Ȃ�A������O���͂��͂���܂����ˁB��́A����͂ǂ��������ƂȂ̂��B�u�莆�ɂ���]�X�v�Ə����Ă���F����͉��������ɂ��Ă���̂��A�u���Ă݂������̂ł��B���̈ꌏ�A��Ƃ��Ďc��܂����A�����́A����̉ۑ�Ƃ��Ď��߂Ă����܂��B
����͂��Ă����A"�V���[�x���g���莆�ŏ����Ă���"�����ȂƂ����̂́A�h�C�b�`����1951�N�����̍�i�ژ^��D849�̔ԍ���^��������̌����ȁv�ŁA�u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȣ�ƌĂ�Ă������̂Ȃ̂ł��B"�莆�ɂ���̂ɁA�y�����Ȃ�"�A�����A���͂���ǂ��p�͌�������Ԃ������Ƒ����Ă����킯�ł��ˁi�����݂̎��ɂƂ��ẮA�莆�̑��݂�������߂Ă��Ȃ��u���̌����ȁv�Ȃ̂ł����j�B�����@�C�I���j�X�g�A���[�[�t�E���A�q���́A"�s�A�m�E�f���I�ȁu�O�����E�f���I�vD812�����̌����Ȃ̌��Ȃł���"�Ƃ̐��ɑ����āA�I�[�P�X�g���[�V�����܂ōs���Ă��܂����A����͊ԈႢ�ł��B�ł́u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�͂ǂ��ɍs���Ă��܂����̂ł��傤���H
20���I�㔼�A�A�����E�^�C�\���i1926�|2001�j�Ƃ����C�M���X�̊w�҂��A����I���@�ɂ���āA����܂Ŗ��m�肾�������X�̃��[�c�@���g��i�̐����������m�肵�܂����B��������I���Ƃ����ƁA�ނ̕��@�͑S�������ĉȊw�I����������ł��B�Ⴆ�ΐ��������s����A�Ƃ����y�Ȃ�����Ƃ��܂��BA�������ꂽ���M���Ƀx�[�^���ː��āAX�������t�B�����Ɏ��́u�������v�iWatermark�j���Ă��t���܂��B�ܐ����ɂ́A���[�J�[�ʁA���������ʂɁA�e�X�قȂ�"������"�������Ă���̂ł��B����A�����������m�肵�Ă���S���[�c�@���g��i�̎��M�������āA�u�������v�ʂɌܐ����̎g�p�����ނ����\�����܂��B���Ƃ�A�́u�������v��\�Əƍ�����ΐ����������m�肷��A�Ƃ������́B�����Ƃ��A��l�̍�ȉƂ����U�S�������^�C�v�̌ܐ������g�������Ă�����A���̕��@�͒ʗp���Ȃ��̂ł����A�K���Ȃ��ƂɁA���[�c�@���g��V���[�x���g�͎����ɂ���ĈقȂ鎆���g���Ă��܂����B�^�C�\���̔����ŗL���Ȃ̂́A1782�N�̍�i�Ǝv���Ă������[�c�@���g�́u�z�������t�ȑ�P�ԃj�����v���A�u���N�C�G��K626�v�Ɠ����������̈��ŁA�����͎����1792�N���������Ƃ��m�肵�����ƁA�Ȃǂ�����܂��B���̌��́A�Έ�G���u�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv�i�w���l���Ɂj�ɏڂ����̂ł����A�܂�ŁA���������̂悤�Ȗʔ����ł��B
�u������ �n���� D944 �O���[�g�v�̎��M���ɂ́A1828�N3���Ə�����Ă��邻���ł����A�^�C�\�������ŕ��͂������ʁA1825�N�Ɏg���Ă����ܐ����ɏ�����Ă������Ƃ��������܂����B�����ŁA�������_����܂���"�u�O���[�g�v��1825�N�ɂ͂قڊ������Ă������Ƃ���A����͂��̔N�̎莆�ɂ���u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�̂��Ƃł���B���̌�o�ł����t�@����Ȃ��܂܁A1839�N�܂Ŋ��̒��Ŗ��葱���Ă����B"�E�E�E�����ł��A���́u�O�����f���E�K�V���^�C�������ȁv�������u�O���[�g�v�������̂ł��B�Ȃ�A�u�O���[�g�v�͊�Ղ̔N1828�N�̍�i�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�܂����A�����܂ł��Ă��܂����̂����瑱�������Ă��������B������������A���̔N�ɉ��M�����\�������Ă��邩������܂��B����ɂ��Ă��A�V���[�x���g�̎莆���̂��̂��ǂ݂����Ȃ��E�E�E�E�B
�i�R�j�V���[�}���̌v��m��Ȃ�����
�u�O���[�g�v�̖�����o�܂����̂̓V���[�}���ł����B�ނ́A1839�N1��1���A�E�B�[���ɃV���[�x���g�̌Z�t�F���f�B�i���g��K�˂Ă��̋Ȃ����܂��B�V���[�}���͂��̂Ƃ��̊����������q�ׂĂ��܂��B
�u�t�F���f�B�i���g���́A�t�����c�E�V���[�x���g�̍�i�̂����ŁA�܂��ނ̎苖�ɂ��������l�Ɍ����Ă��ꂽ�B�����ɂ��������ς�ł�������i�����Ėl�͊�тɂӂ邦���B�����Ȃ̃X�R�A�������������Ă����������ǂ��A���̑����͂܂���x�����t���ꂽ���Ƃ̂Ȃ����̂ŁA���X�������l���������A�ނ�����������Ƃ��֒����Ђǂ��Ƃ������Ď̂Ă�ꂽ���̂������B���̌����Ȃɂ��Ă��A�����l���A���C�v�c�B�q�̃Q���@���g�n�E�X�̎w���҂Ɍ��Ă��炤�悤���v���Ȃ������Ȃ�A�܂��ǂ�قǒ����Ԛ��ɂ܂݂ꂽ�܂܁A�Ћ��ɕ���o����Ă������킩��Ȃ��̂ł���B���������͂��̖]�݂����������B���C�v�c�B�q�ɑ���ꂽ�����Ȃ͂��������㉉����āA�݂�Ȃɗ������ꂽ�B�ĉ��ɓ������ẮA��ςȊ��}���A�قƂ�ǑS�s�̏^���v�i��g���ɃV���[�}�����u���y�Ɖ��y�Ɓv�g�c�G�a����j�V���[�x���g�̌Z�t�F���f�B�i���g����A�苖�ɂ���y���������Ă��炢�A���̒��ɕ��u����Ă����u�n���� �����ȁw�O���[�g�x�v���B���̍�i�𐢂ɏo�����߂ɁA���C�v�c�B�q�E�Q���@���g�n�E�X�nj��y�c�Ƃ��̎w���҃����f���X�]�[���ɓ��������A���E�����ɂ������A�ĉ��Ŋm�ł���]�������Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B������1839�N3��21���ł����B���̌����Ȃ@���A�^�������ɂ߁A�����ɂ��������V���[�}���̊�͂ƔM�ӂƍs���͂́A������^���Ă����������̂ł͂���܂���B�Ȃ��Ȃ�u�O���[�g�v�͂��̌�̉��y�V�[���ɑ���ȉe����^�����^�Ɉ̑�ȍ�i������ł��B
2009.09.29 (��) Romance�ւ̗U���G�u�u���[���X�̓����c���D���H�v
�i1�j�u���[���X�͂��D���u�u���[���X�͂��D���v�Ƃ����t�����\���[�Y�E�T�K���̏���������܂��B��l�̗��Ƀi�C�[�u�Ȏ�҂����ރp��������̂ق�ꂢ���u�E�X�g�[���[�ŁA1961�N�ɂ͉f�扻������܂����B���N�j���ɃC���E�����^���ƃC���O���b�h�E�o�[�O�}���A��Җ��ɃA���\�j�[�E�p�[�L���X��z�����A�i�g�[���E���g���@�N�ē̃A�����J�f��B�A���\�j�[�E�p�[�L���X������A�����J�N�t�B���b�v���A�o�[�O�}��������N�㏗���|�[�����R���T�[�g�֗U���Ƃ��̌��ߕ��傪�u�u���[���X�͂��D���v�ł����B�N�㏗���ւ̓���́A�܂��Ƀu���[���X�̃N�����E�V���[�}���ւ̗��S�ƃI�[�o�[���b�v�B���������ݒ肪�x�X�g�Z���[��ƃT�K���̐^�����Ȃ�ł��傤�ˁB�f��^�C�g��"Goodbye Again"�u����Ȃ��������x�v���▭�ł��B�S�҂ɗ���鉹�y�̓u���[���X�u�����ȑ�3�ԁv��3�y�́B���y�S���̓W�����W���E�I�[���b�N�B�I�l�Q���A�~���[�A�v�[�����N��Ƌ��Ƀt�����X6�l�g�̈�l�ŁA������Ƃ����N���V�b�N�̍�ȉƂɂ��ĉf�批�y�̑�ƁB�u���[�}�̋x���v�̉��y���f�G�ł����B
�i2�j�V���[�}���͉��l
���n�l�X�E�u���[���X�i1833�|1897�j�����ɏo�邫��������������̂̓��[�x���g�E�V���[�}���ł����B�u���[���X�͒��ǂ��̃��@�C�I���j�X�g�A���[�[�t�E���A�q���̏Љ�Ń��X�g�ɉ�܂����A�g��������Ȃ��ĕs���B�Ȃ�ƍ��x�̓V���[�}���ɏЉ�B���ΖʂŒe�����s�A�m�ɃV���[�}���͒ɂ��������܂��B����Ή��y�ƃu���[���X�Ɉ�ڍ��ꂵ���킯�ł��B�Ƃ��낪�u���[���X�͈ꏏ�ɕ����Ă����V���[�}���̍ȃN�����Ɉ�ڍ���B���̒��l�X�A�l�����낢��ł����A���̂�����̌��͏�f���̉f��u�N�����E�V���[�}���`���̋��t�ȁv�ł��m���߂��������B���āA���������V���[�}���́A��ɂ���u���y�V��v�ɐ�^�̏Љ�������܂��B�肵�āu�V�������v
�u���̏\�N�A�m���ɐV�������y�̂�������������悤�ɂȂ��Ă����B�L�]�ȐV�l���吨���ꂽ�B�ł��M������܂łɂ͂�����Ȃ������B�����āA���͂��������v���Ă����B��i���܂����Ԃɒm���Ă��Ȃ��Ă��A�i�X�ɒE�炵�đ�ƂɂȂ�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���łɊ������ꂽ�A�����S���g�����������l���A���R�Əo������͂����ƁB�܂��o�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁB����ƁA�ʂ����āA�ނ͂����B�d���̂Ƃ�����D��̏��_�Ɖp�Y�Ɍ�����Ă�����҂��B���̐l�̖��́A���n�l�X�E�u���[���X�E�E�E�����E�E�E���̃n���u���N���܂�̎�҂́A���ɗ��h�ȕ��e�������Ă��āA�݂邩��ɁA���ꂱ�������ꂽ�l���ƍm������l�������B�s�A�m�ɍ���ƁA���������s�v�c�ȍ��̔����J���n�߂����A�������͂��łĂ܂��܂��ӂ����Ȗ��͂̍Ⴆ�ɁA��������Ђ����肱�܂�Ă��܂����B�ނ̉��t�Ԃ�͑S���V�˓I�ŁA�߂��݂Ɗ�т̐����c���Ɍ��������āA�s�A�m���I�[�P�X�g���̂悤�ɂЂ����Ȃ����B�ނ̓�����l�Ƃ��āA�������͐��E�ւ̖�o�ɓ������ĔނɌh�炷��v�i��g���ɃV���[�}�����u���y�Ɖ��y�Ɓv�g�c�G�a����j�ނ͂��̒��ŁA�u���[���X���e��������̃\�i�^��"��i�Ƃ��Ă̑f���炵��"����^���Ă���A���t�Ƃƍ�ȉƂ̗��ʂ���x�^�J�߂������ƂɂȂ�܂��B�u���[���X�͂��̂Ƃ�20�B��������������Ƃ��ĉ��y�E�ɗY�X�����H�����Ă䂫�܂��B
�i3�j�u���[���X�ƃE�B�[���A�����ăV���[�x���g
�u���[���X���E�B�[���ɈڏZ�����̂�1862�N�̂��ƁB�ނ́A���̍��̂��Ƃ��A��N�A�V���[�x���g�̌����ȑS�W�̊y�����o�ł��ꂽ�܂�A�����q�ׂĂ��܂��B�u����ȎႢ���̍�i����������Ȃ�āA����������Ȃ����B�l��20�N�O�ɑS���ʕ�������B���ꂪ�E�B�[���ɂ��čŏ��̎d���������B����Ȃ��Ƃ����Ȃ���A�����ȍ�i��������̂��v�A���Ȃ킿�E�B�[���ɂ��čŏ��̎d���́A�V���[�x���g�̎��M�����ʕ����邱�Ƃł��肻�̍�i���������邱�Ƃ������̂ł��B����ɓ������ɁA����Ȏ莆�������Ă��܂��B
�u���̃V���[�x���g�ɑ��鈤��͔��ɐ^�ʖڂȎ�ނ̂��̂ł��B�ł��̑�Ȑl�Ԃ��c�ʂɂ������Ă���̂�������ɁA���̂悤�ȑ�_���Ɗm�����������Ĕ��Ă���ނ̓V�˂̂悤�ȓV�˂��A�ق��̂ǂ��ɂ���ł��傤���B�ނ̓W���s�^�[�̗��ƗV�сA�Ƃ��ɂُ͈�Ȏd���ł������舵���_�X�̎q���̂悤�ɁA������ۂÂ��܂��B�������ނ͑��̐l���ǂ����Ă��B���邱�Ƃ̏o���Ȃ��̈�ŁA�܂������ɂ����āA�����������̂ł��v�i1863�N6���A�F�l�A�h���t�E�V���[�u�����O�ւ̎莆�j"�c�ʂɂ������Ă���ł��̑�Ȑl��"�Ƃ͖��_�x�[�g�[���F���̂��ƁB�m���ɁA�ނ́A�x�[�g�[���F���̂��Ƃ͑��h���Ă������A�V���[�}���ɂ͉��������Ă����ł��傤�B�ł��ނ���ԍD���ȍ�ȉƂ̓V���[�x���g�������A������̓V�˂Ɉ،h�̔O���������ŁE�E�E���̎莆�͂�������Ă��܂��B����ȗ��ނ̍�i����������Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B����́u�����c�W ��i39�v�B
�i4�j�u���[���X�̓����c���D���H
�u���[���X���A16�Ȃ���Ȃ�u�����c�W�v���������̂�1865�N�A�E�B�[���ɏo�Ă��Ă���3�N�ڂ̓~�̂��Ƃł����B���̋Ȃ����悳�ꂽ�����̗L���Ȕ�]�ƃn���X���b�N�͂��������܂����B�u�^�ʖڂŖ����ȃu���[���X�A�k�h�C�c���ŁA�v���e�X�^���g�ŁA�V���[�}���̂悤�Ȕ��I�Ȓj�������c���������v�ƁB���̔�]�́A"�k�h�C�c�̓c�ɕ��Ő^�ʖڂȒj���A���E�̑�s��E�B�[���ő嗬�s���Ă��郏���c��������"�Ƃ����~�X�}�b�`�̖������������́B�����E�B�[���̓����c�V���B�c���Â̋{�앑����͉₩�ȃE�B���i�E�����c��F�B���̎w���҂����̃��n���E�V���g���E�X�U�i1825�|1899�j�ŁA���̈���A����̊y�c�𗦂��ă��V�A�A�A�����J�ɂ�����L���A���E���܂��Ɏ���̃����c�����t����Ƃ����c�����s�̊�������Ă������ł����B
���̂���A����p�[�e�B�[�ŁA���n���E�V���g���E�X�v�l�ɃT�C���𗊂܂ꂽ�u���[���X�́A�����o���ꂽ��q�ɁA�u���������h�i�E�v�̉����������A�u�c�O�Ȃ��烈�n�l�X�E�u���[���X�̍�ɂ��炸�v�Ə����Y�����Ƃ����G�s�\�[�h���c���Ă��܂��B�d���ȍ앗�̃u���[���X���ؗ�ȃ����c�ɓ���Ă������Ƃ���Ă��܂��B
�Ƃ͂����A�u���[���X�́u�����c�W ��i39�v�́A�ؗ�ȃE�B���i�E�����c�Ƃ��������A�����Ɠy���I�Ƃ������ׂ��f�p�ȃe�C�X�g�������Ă��܂��B���̂����A��葽�ʂȎ����܂��B�����ł��A�ނ͂��̋ȏW�ɂ��āu���x�A�V���[�x���g�ӂ��Ȍ`�̖��C�ȏ����������c��������v�Əq�ׂĂ���̂ł��B�u�����A�V���[�x���g���H�V���[�x���g�������c���H�v�����v���Ē��ׂĂ݂�ƁA�ӊO�Ȃ��Ƃ��������Ă��܂����B
�i5�j�u���[���X�ƃV���[�x���g�A���̍��̃����[
�V���[�x���g�̓s�A�m���t�p�̃����c���Ȃ��98�Ȃ�����Ă��܂����B�V���[�x���g�ɂ͑����̗F�B�����āA���y�����t������A�_���X�ɋ�������A�c�_������̊y�����W��������܂����B������V���[�x���e�B�A�[�f�ƌĂ�ł��܂����A�ނ́A�����ōs����y�����_���X�E�^�C���̂��߂Ƀ����c���������̂ł��B���̖ړI�͗x�邽�߂Ƃ����̂�����̂悤�ł����A���͂����ƍL���A�H���⊽�k����BGM�Ƃ��Ă��L���Ɏg��ꂽ�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B�Ȃ�A�����Ă悵�x���Ă悵�̃V���[�x���g�̃����c�́A�T�����ŕ������邽�߂̂��̃V���p���̌��샏���c�W�ɂ��A�{��̑啑����ŗp������ؗ�ȃE�B���i�E�����c�ɂ��A���ʂ��Čq������I��i�������A�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̓V���[�x���g�́u12�̃����c�WD145�v�Ƃ����s�A�m��i���Ă݂܂����B���ʁA��Ȃ��P���قǂ̘g�g�݂̒��œW�J����鑽�ʂȕ\��ɁA���������Ă��܂��܂����B�����e���|�̖������A���X�Ƃ����͋����A���₩���ƗD�낳�A�����悤�Ȑ������A���v���ɒ^��悤�Ȉ����A�f�p�Ȗ������A�����̂悤�Ȍy�₩���A���������������ȗ܁A�₩�ȉ������t�@���t�@�[���A�ȂǂȂǁA���ɑ��푽�l�Ȋ���E��i�������ɂ���܂����B�E�B�[���ɏo�Ă�������̃u���[���X���A�V���[�x���g�̎��M�����ʕ������Ȃ��ɁA���̂悤�ȃ����c���������������Ƃ͑z���ɓ����܂���B�����ɂ��̖L���ȉ��y�ɐG��āA�ނ͂����Ƌӊ쐝���͂��ł��B�����Ă��̈�ۂ�ނ͂����ƒg�߂Ă����E�E�E�����āA�V���[�x���g�̂悤�ɗl�X�Ȋ���𒍓�����16�Ȃ̃����c���������B������͂�����Ɓu�V���[�x���g�ӂ��Ȍ`�Łv�ƌ������̂ł��B���͂����m�M���܂��B
�C�V������́A���H�̃��T�C�^���Ńu���[���X�́u�����c�W ��i39�v���Ƃ肠���Ă��܂��B�����ƃV���[�x���g����u���[���X�ւ̍��̃����[���������Ă��邱�Ƃł��傤�B�ł͍Ō�ɁA�u���[���X������c�W��̋Ȗ��R�����g���v���O�����E�m�[�c������p���āA�i���ɂ킽��܂����Romance�ւ̗U������I��点�Ă��������܂��B
�@���邭�y���Ȗ������A���₩�ȗ������B���̊Ԃ̎₵���C�J���Ɖ₩���̂���W�v�V�[���D�D���Ȃ�����芴�E���C�Ōy�₩�F�Ô��ŃZ���`�����^���G�T��ȕ���H�����悤�Ȉ��D�I�f�p�Ȏ�J���Y�~�J���Ŕ߂����ȇK�̐S����L�ؗ�ɒ��郊�Y���M��M�I�W�v�V�[�_���X�N���}���e�B�b�N�ʼn��Ȏq��̇O���D��U�����₩�ł������Ƃ����I�ȁ@�����͂��ׂĐ�ڂȂ����t�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@
�C�V���݂� �s�A�m�E���T�C�^���`Romance�ւ̗U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��F 2009�N11��14��(�y) 15�F00�J���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ���F �i�s�A�[�g�z�[�� �A�t�B�j�X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�D�X�J�����b�e�B�@�@�\�i�^ �n���� K�D159
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �\�i�^ �j�Z�� K�D9
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�D�V���[�x���g�@�@�@4�̑����� D�D899 Op�D90
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�D�u���[���X�@�@�@�@�����cOp�D39
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�D�t�����N�@�@�@�@�@ �O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K
���₢���킹�F memusicoffice@mihoebihara.com
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
2009.09.21 (��) Romance�ւ̗U���F�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����5
�i�V�j�ŏI�́`�\�i�^�ł͂Ȃ�1827�N�̃s�A�m���V���[�x���g�͌�����"�\�i�^�����"�ł͂Ȃ���������ǁA����ꓬ�������Ƃ͎����B����Ɉ��������A�`���ɑ����Ȃ��u�����ȁv�u���z�ȁv�Ȃǂ͋C�y�ɏ������̂ł��傤�A�Ƃ肠�����̓����b�N�X���Ċy���ނ��Ƃ��ł��܂��B
�u�s�A�m�ƃ��@�C�I�����̂��߂̌��z�ȁv�iD934�j�Ƃ����Ȃ�����܂��B���́A���̋Ȃ��A�ܖ��N�S���u���y����v�i�V���Ёj�Œm��܂����B�ނ͂��̒��ŁA���y���ɂ��Ă͉��������`�ʂ𑱂������ƁA�u�V���[�x���g�́w���z�ȁx���ƁA�����A���ꂪ���Ƃ��悤���Ȃ��Ô��Ő��炩�Ȕޏ��ւ̑z���o�ɕς��B�Â܂�Ƃ��낫���Ȃ��v���o�͍�i159�́w���z�ȁx�ŏ���Ă���B�V���[�x���g��"�₳����"�̈��ɂ����ȉƂ��Ǝ��͎v���Ă��邪�A�₳�����̗��łǂ�قǎS�߂ȉ�����ς��Ă��������������ƁA�w���z�ȁx�̉ؗ킳�͈ꂻ���悭��ۂɎc��v�Ə����Ă��܂��B�V���[�x���g�̉��y�͔������̉��ɑς���߂��݂��߂Ă���A�����畷�����������͏����B���������ܖ�����̃V���[�x���g���͗����ł��܂��B"�����Ȃ��v���o���A�V���[�x���g�����Ƃɂ���ď����g���肳"�͑��������͂��܂����B
�������̋ȂɊ�����̂�"���D"�ł��B��A�ւ�"����"�Ƃ����Ă������B�u�A���F�E�}���A�v��z�N������F��̂悤�Ȗ`���̐������u�A���_���e�B�[�m�v���͂���ʼn�A���Ă���B�Ȃ͉ؗ�ɏI���̂ł����A�S�Ɏc��̂͂Ȃ�Ƃ����Ă��R��I�ȁu�A���_���e�B�[�m�v�̕����B���N����̉����������Î_���ς����i����A���Ă��܂��B�Â��Ȃ�܂Ŗ싅�ɋ������H�ƍ��Z�̃O���E���h����H�̌������ɍL����[�Ă���B�����Ƃ��������`�����o���ő����������R�ȂǁB�V���[�x���g�������Ƃ���������Ȃ���A�y���������R�����B�N�g�ł̊�h�����Ȃǂ��v�������Ă����ɈႢ�Ȃ��A�ȂǂƏ���Ɏ����œ�������������Ă��܂��B
�u���z�ȁv�Ɠ���1827�N�̍�i�ɁA�s�A�m�ɂ��u�����ȏW�v������܂��B�u4�̑����ȁv�Ƃ���D899��D935�����đ����ɍ���܂����BD935�ɂ��āA�V���[�}���͂��������Ă��܂��B�u����w�����ȁx�Ɩ��Â����Ƃ͐M���������B��1�Ԃ̓\�i�^�̑��y�͂ł���A�������B��2�Ԃ�������ȑz���猩�ē����\�i�^�̑��y�͂��B�I���̓�̊y�͂��ǂ��֍s���Ă��܂������́A�V���[�x���g�̗F�l�Ȃ�m���Ă��邾�낤�B��3�Ԃ͕ʂ̋ȂŁA��4�Ԃ͂�����������\�i�^�̃t�B�i�[����������Ȃ��v�ƁB�V���[�x���g�̏o�ł̓n�Y�����K�[�Ƃ����E�B�[���̊y���o�ʼn������s���Ă��āA����܂ŁA"�\�i�^"�Ƃ������O�ł͔���Ȃ��Ƃ����āA�s�A�m�E�\�i�^D894��"���z��"�Ɩ��Â����肵�Ă�������A�V���[�}���́u�����ȁv�����̎肾�Ǝv�����̂ł��傤�ˁB��������قړ����ɍ��ꂽD899�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B�uD935�̑�3�Ԃ͕ʕ��ŁA3�C4�y�͂͂ǂ����֍s����������v���Ⴝ���̑z���A�Ȃ�Ǝ��ؐ��ɖR�������Ƃł��傤�B�����̋C�Â������Ƃ͖������M�����܂��A���Ă͂܂�Ȃ������͞B���Ȃ�܂܂ɕ��u����B�����炱�̐l�͐M�p�ł��Ȃ��E�E�E�Ȃ�Ă����Ƃ܂��V���[�}���E�t�@���̕�����{��ꂻ���ł����B
�ނ��뎄�̋����̓n�Y�����K�[�Ƃ����l�ɂ���܂��B�u�\�i�^���ᔄ��Ȃ�����w���z�ȁx���A����w�����ȁx�ɂ��悤�v�Ƃ����͔̂�����߂̍��ŁA���ɖʔ������ނ��ł��B���̗L���ȁu�O���[�����y���T�v��Ҏ[�������y�w�҃W���[�W�E�O���[�����u����͏��l�̋C�܂���A���������v�ƌ����������ł����A�܂��j�ł��ȁA���̐l�́B�����Ȃ���葽���̐l�ɒ����Ă��炦��H�v�����邱�Ƃ��u���l�̋C�܂���v�ł����B"�������"���Ȃ������B������V���[�x���g�݂����Ȑl���n�R�����Ⴄ�B������N���V�b�N�͍L����Ȃ��B�܂��A�n�Y�����K�[�́A�V���[�x���g�̍Ō�̔N�̉̋Ȃ�14�ȏW�߁A�u�����̉́v�Ɩ��Â��ďo�ł����l�ł�����܂��B�����V���^�[�v�i���̃x�[�g�[���F���u�����̋ȁv�̖��t���e�j�̎���7�ȁA�n�C�l��6�ȁA�����čŌ�ɃU�C�h�����u���̎g���v�����������B���̋Ȃ��V���[�x���g�Ō�̉̂Ƃ����Ă���̂ł����A���̂܂Ƃߕ��Ɩ����̏�肳�͓��M���ł��B�����ނ�����ɐ����Ă�����剹�y�v���f���[�T�[�ɂȂ��Ă������Ƃł��傤�B
�C�V���݂ق���́A���̏H�̃��T�C�^���Łu�S������D899�v����肠���܂��B���̋Ȃɂ��ẮA�����グ������̃v���O�����E�m�[�c���������������B����������āu�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v���I��点�Ă��������܂��B
�m�V���[�x���g��ȁF4�̑����� D�D899 op�D90�n
�@�t�����c��V���[�x���g�i1797�|1828�j�́A����31�N�Ƃ����Z�����U�̒��ŁA800�Ȉȏ�ɂ��̂ڂ��i���c���Ă���B�u�̋ȉ��v�ƌĂ�Ă���悤�ɁA���̑唼�͉̋Ȃł��邪�A�s�A�m�Ȃ��d�v�ȃ��p�[�g���[�ƂȂ��Ă���B��i90�́u4�̑����ȁv�i4 Impromptus�j�́A�S���Ȃ�O�N1827�N�ɍ��ꂽ�s�A�m�ȏW�ŁA���̔N�ɂ͉̋ȏW�̌���u�~�̗��v�����܂�Ă���B
�@"impromptu"��"�����̏o���Ă��Ȃ�"�Ƃ����Ӗ��̃��e����ɗR�����錾�t�B�u�����ȁv�Ƃ������{���ɂӂ��킵���A�ȑz�̓A�h���u�I�Ȏ��R���ɖ����Ă���A"�`���ɑ����Ȃ��A�C�y�Ŏ��R�ȏ��i"�ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B
�@�x�[�g�[���F���̂悤�ɁA�����ȑf�ނ��`���̒����k���ɓW�J���Ă䂭���Ƃ����A�����̎�܂ܔ�����������a���������ƂӂƂ����V���[�x���g�ɂƂ��āA���́u�����ȁv�Ƃ����`�́A�\�i�^�ȏ�ɔނ̉��y���ɍ����Ă����Ƃ����邾�낤�B4�Ȃ��ׂĂ������������f�B�[�ɍʂ��Ă���A��ʂ̖��ȂƂ��Đe���܂�Ă���B�݂̂Ȃ炸�A���̋ȏW�́A�V���[�}���A�V���p���A�u���[���X�ȂǂɂȂ���A���}���h�̐��i���i�i�L�����N�^�[�E�s�[�X�j�ւ̐��I��i�Ƃ��āA���y�j�I�ɂ��d�v�ȈӖ��������Ă���B
��1�ԁ@�A���O���E�����g�E���f���[�g �n�Z�� �l���̎l���q ���R�ȕϑt�Ȍ`��
�n�Z���Ŏ��������͊Ô��Ń������R���b�N�B���ɗ���ŗD�����A���ɗ͋����������A�����ċٔ������܂�Ŗ����I�ɁA5�̕ϑt�͗l�X�ȕ\��������Ă����B�R�[�_�̍Ō�̓n�����ƂȂ��āA�Î�̂����ɋȂ����B
��2�ԁ@�A���O�� �σz���� �l���̎O���q �����O���`��
��v�e�[�}�́A3�A�������㏸���~���J��Ԃ��X�s�[�h��������́B���̉��̘A���͊��炩�őu�����ɖ����Ă���B���ԕ��͈�]���āA�Z���Ȃ��畑�ȕ��̗͋�����ɕς��B�Ō�ɕ��ȕ���肪�ω����Ȃ����z����邪�A���̂�����ɂ������Ȃ炵�����R������������B
��3�ԁ@�A���_���e �σg�Z���@�̓q�@�O���`��
���^�ŝR��Y���̋Ȃ̂悤�ȁA�����ɂ��V���[�x���g�炵���y�ȁB���ԕ��͕σz�Z���ƂȂ��āA���̋Ȃɏ���������Ȃ��^���Ă���B���܂ł��g���ς˂Ă������Ȃ�悤�ȉ��₩�ň��炬�ɖ��������y�ł���B
��4�� �A���O���b�g �σC�Z�� �l���̎O���q�@�O���`��
�`���ő����e���|�̒Z����肪��ۓI�ɓo�ꂷ�邪�A���x���]�����d�˂����ƁA�͂�����Ƃ���������肪����Ɍ����B�g���I�����ł́A���₩�ȃ��[�h���x�z���A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA���d����������Ă䂭�B���̂��Ƒ�ꕔ�̒Z����肪�Ăь���ė͋����Ȃ���邪�A������g���I�������A�\�i�^�I�ȃX�P�[���������̋Ȃɗ^���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@
�C�V���݂� �s�A�m�E���T�C�^���`Romance�ւ̗U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��F 2009�N11��14��(�y) 15�F00�J���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ���F �i�s�A�[�g�z�[�� �A�t�B�j�X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�D�X�J�����b�e�B�@�@�\�i�^ �n���� K�D159
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �\�i�^ �j�Z�� K�D9
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�D�V���[�x���g�@�@�@4�̑����� D�D899 Op�D90
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�D�u���[���X�@�@�@�@�����cOp�D39
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�D�t�����N�@�@�@�@�@ �O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K
���₢���킹�F memusicoffice@mihoebihara.com
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
2009.09.16 (��) Romance�ւ̗U���E�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����4
�i�U�j�s�A�m�E�\�i�^�̖��Ȃ��̂Q�u���O�\�i�^�v�l���u�s�A�m�E�\�i�^ ��19�� �n�Z�� D958�v�́A�x�[�g�[���F���I�ȍ�i�Ƃ����Ă��܂��B�V���[�x���g�́A�s�A�m�E�\�i�^�̍�Ȃɂ�����A��Ƀx�[�g�[���F�����ӎ�������Ȃ�����I���n���I���ɂ��������Ƃ́u����1�v�ŏq�ׂ��Ƃ���ł��B���̐��T�ԑO�A���đ�����3�Ȃ̃\�i�^�����܂������A���̑��Ȗڂ��A�x�[�g�[���F���I�F�����̏W�听�ł����Ă��A�Ȃ��s�v�c�͂���܂���B��������́A��1�y�͂������ŏ\�������ł���ł��傤�B�Z�����߂���Ȃ�E�s�ȑ�1���Ə_�a�ȑ�2���̑Δ�Ȃǂ͂܂��Ƀx�[�g�[���F���I�B�t�ɁA��������̓V���[�x���g���L�̗����悤�ȉ̐S�͂��܂芴�m����܂���B�V���[�}����������i�ƌ���肻���ɂȂ����̂��\���ɍm���܂��BD575������Ɠ���ɕ��������̂�������܂���B����́A�x�[�g�[���F���̃\�i�^���������s�����Ď���̊y�ȂɎ�����Ă������V���[�}�������炱���A�I�m�ɓǂݎ�ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͂����ƁA���閼�ȉ���Ɂu���̋Ȃ̃n�Z���Ƃ��������́A���Ƃ��ƃx�[�g�[���F���̂��̂ł������v�Ƃ������ꂽ����������܂����B"�x�[�g�[���F���I�ł���"�Ȃ狖���܂����A"�x�[�g�[���F���̂��̂ł�����"�͂Ȃ��Ǝv���܂��B�������N�^�̎������Ȃ�ă~���[�Y�̐_�͋����Ă���Ȃ��̂ł́H �V���[�x���g���n�Z���ŏ������̂̓x�[�g�[���F���Ƃ͉��̊W���Ȃ��A�ނ̉����o���I���ʂɈႢ����܂���B�m���Ɂu�n�Z���̓x�[�g�[���F���̏h���̒����ł���v�Ƃ͐̂���悭�����Ă��邱�Ƃł����A���������N�����߂��̂ł��傤���H ���ƃo�b�n�́u���Z���v�ƃ��[�c�@���g�́u�g�Z���v�ł��������B�������������̂Ȃ��ތ^�I�Ȍ��ߕt���A���ɂ͂ǂ�������߂܂���B
�u��20�� �C���� D959�v�ɂȂ�ƁA�̂����L���Ɉ��o���Ă��܂��B��1�y�́A��2���ƂȂ��̕����Ɋ��������Ȃ��̗w���B��2�y�͂͂��ꂼ�V���[�x���g�̉̂��̂��́B���̒W�X�Ƃ��Ă�∣����тт������f�B�́A�܂�řR���ĐȂ��ނ̐l���̂悤�B�������A�����Ȃ茻��钆�ԕ��̌���ɂ̓r�b�N�����܂����B��3�y�̓X�P���c�H�̌y�������Ɠ��̃Z���X�B��4�y�́A���x������郍���h���́A�I�e�Ƃ��ĉ��₩�A�܂��ɃV���[�x���g�̉̂�t�łĂ��܂��B
���āA���悢��Ō�̃\�i�^�u��21�� �σ����� D960�v�ɒH����܂����B������1828�N9��26���ł��B
��P�y�͖`������V���[�x���g�̉̂���X�Ɨ���o���܂��B�Ȃ�ƈ��炬�ɖ����������A�Ǝv�����u�ԁA�s�C���Ȓቹ�̃g����������B�㐟�݉t�̂悤�ɏ��ꂽ�����̒�ɂ����߂��ǂ��������a���B���ꂱ���V���[�x���g�̜ԚL�B�ӂ�����Ȃ̎v���ɑ��Ȃ�Ȃ��Ǝ��ɂ͕������܂��B���̂Ƃ��V���[�x���g�܂�31�A�������A���͋͂����T�Ԍ�ɔ����Ă����̂ł��B�����͒��`�t�X�ł������A25�̎��ɂ͔~�ła���Ă��܂����B�s���̕a�̒��ŁA�ǂ�Ȃɕs���ł�邹�Ȃ����X�𑗂��Ă������Ƃł��傤�B�ނ̐S��Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă��邱��Ȏ莆������܂��B
�u�ЂƂ��ƂŌ����ƁA�l�͂��̐��ł�����s�K�ŁA������Ȑl�Ԃ̂悤�ȋC�����܂��B�l���Ă��݂Ă��������B�����������Č��N�����߂����Ƃ��]�߂��A����ɐ�]���邠�܂�A���Ԃ͂悭�Ȃ�ǂ��납�����Ȃ����Ƃ�������Ȓj�̂��Ƃ��B�l���Ă��݂Ă��������B�P��������]�����������A��Y�ȊO�Ȃɂ������炳���A���ɑ���슴���A���Ȃ��Ƃ��S�����悤�Ȃ��̂͏��������Ă��܂�������Ȓj�̂��Ƃ��B���ꂪ����ŕs�K�Ȓj�łȂ��Ƃ����̂ł��傤���H �w���̐S�͏d���A���͂₯�����Ĉ��炬�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��x �l�͂��܁A���������̂��Ă������̂ł��B��A����ɂ��Ƃ��́A���̂܂ܖڂ��o�߂Ȃ����Ƃ�]�ނ���ǁA���N����Ƃ����A����̋ꂵ�݂������v���o�����̂ł��B�v�i1824�N3��31���A�F�l�N�[�y�����B�U�[���j�Ȃ�Ɣߒɂȕ��ʂȂ̂ł��傤���B�ނ͔w���Ⴍ���т��オ��Ȃ��D����������Ȓj�������Ƃ����܂��B�F�l�ɂ͌b�܂ꂽ����Ǐ����Ƃ̕t�������͂܂������Ȃ������Ƃ��B����Ȑl�Ԃɐ_�l���^�������̂́A���O�ꂽ���y�̍˔\�ƕn�R��31�N�̎����ł����B�ނ́A���̕n�������Z�����U�̒���800�Ȉȏ���̊y�Ȃ������グ�܂����B����ȃW�������ɂ킽��l�X�Ȑ��i�̉��y���B����Ȕނ̉��y�̖{���͗D�����ɂ���܂��B���̂���ɂ��^���̂ł��Ȃ��������D�������y�������ɂ���܂��B�������X�ɖ����������炵�Ă����B���E��s�K�Ȑl�Ԃ����E���̐l�X�Ɉ��炬��^���Ă���Ă���B����ȊԎڂɍ���Ȃ��b������ł��傤���B�ނ͏�Ɏ��̐��E�ƌ��������Đ����Ă����B�Ў����S���痣��邱�Ƃ̂Ȃ����̋��|�ɋ����Ȃ���A���̂���ȗD�����ɖ��������y�����������������邱�Ƃ��ł����̂ł��傤���H�����A�����ɒu����������A�������������Ȃ�ǂ��E�E�E�~�߂܂��傤�A�}�l�ɒu�������Ă݂����Ă��傤���Ȃ��E�E�E�B����́A�ނ̌����Ȃ��c�̋����������̂��B�n�������ȗD���������ׂĂz�������ʂ������̂��B�_�̉���䂦�Ȃ̂��B�Ƃ�����A�m���ɂ����邱�ƁA����́A���������V���[�x���g���Ƃ������Ƃ͑����A���炪�^�ɗD�����Ȃ邱�Ƃł���_�Ɋ��ӂ���Ƃ������ƁA�Ȃ̂ł��B�������a�������Ă�����܂��B�S�̒��忂���������u�T���ڂɕ\�o�������Ă悢�ł͂���܂��B�����āA���̂��Ƃ͂����V��̋����̂悤�ȗD�����̂��Ƃ߂ǂȂ����o���Ă���B�V���[�}�����u�������������玟�ւƗ��ނ��Ƃ�m��ʂ��Ƃ��A���炳��Ɨ���Ă䂭�v�ƌ������悤�ɁB�z�����B�b�c���u�V���[�x���g�̉��y�͂��ׂĂ��́B�x�[�g�[���F���ɂ͈ꉹ�����ď����₵�Ȃ��v�ƌ������悤�ɁB����Ƃ��͐t�̋P�����������݁A�܂�����Ƃ��͎Ⴋ���̌�������N���Ȃ���B
��2�y�͂́A�K���X�H�̂悤�ɑ@�ׂȎ���Ɛt�ւ̋��D���D��Ȃ��n�[���j�[�B��3�y�͂̓V���[�x���g�Ȃ�ł͂̌y���ȃX�P���c�H�B
�ŏI�y�́B���y�̗F�Њ��u���ȉ�����C�u�����[�v�̒��ŁA���ҕ��쏺���́u540���߂ɋy�ԃt�B�i�[���́A���m�ȓW�J���������A�Ō�܂ł��̍\���ɋ�Y���������V���[�x���g�̉ۑ���c�����܂I���Ă���v�Ƃ��Ă��܂��B�m���ɂ�����\�i�^�`���Ƒ�����A�W�J���͖��m�ł͂Ȃ��̂ł��傤�B�ł����̊y�͂��A�����h�����̑�1���Ɖ��₩�őf����2�����啔�Ƃ��āA����I�a���̋��ł��u���b�W�ɂ��Ẵ����h�`���iA�|B�|A'�|C�|A�|B�|A''�R�[�_�j�Ƒ������Ȃ����Ȃ����낤���A�C���͂ނ��냍���h�ł��B�V���[�x���g�͉ۑ���c���ďI�����̂ł͂Ȃ��A�\�i�^�`���ł������h�`���ł��Ȃ��Ǝ��̌`���ɓ��B���čŌ���������̂��A�Ƃ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�ł��A����Ȍ`���_�͂ǂ��ł���낵���B�����́A�����A�V���[�x���g�̉̂��܂��傤�B����ɉʂĂ��Ȃ��ꂵ�݂��߂Ȃ���A���C�ɐ��������C�Ȓj�̗D�����S�̋��т��A�������͑f���ȋC�����ŕ��������B
�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����v�������̂ł��傤���H �m���ɁA�肪����20�ȏ�̍�i�����������̂�15�Ȃł��邱�ƁB��Ƀx�[�g�[���F�����ӎ����Ă����ł��낤���ƁB�\�i�^�ւ̒��肪�����Ȃ��x�ꂽ���ƁB�܊y�͐���S�y�̓\�i�^�`���Ȃǂ̕ϑ��I�Ȍ`���ɒ��킵�����ƁB���R�Ȍ`���̃s�A�m�Ȃ̂ق��ɁA�V���[�x���g�炵�������Z���łĂ��邱�ƁB�Ȃǂ���A����Ȓ�����ł����������̂��Ǝv���܂��B�ł��A�����������͂͐��Ƃ̕��X�ɔC���Ă����܂��傤�B��X�͂����S�ŃV���[�x���g�̃\�i�^�������B�����ɂ͏�ɉ̂�����A�܂�����Ȃ��V���[�x���g���̐l������B�u���y�͏�ɂ���̂܂܂̎��̐S�ł��v�Ƃ����ЂƂ�̉��y�Ƃ�����̂ł�����B���肪�Ƃ��A�V���[�x���g�B
2009.08.31 (��) Romance�ւ̗U���D�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����3
�i�T�j���O�\�i�^�̃V���[�}���]���l�@�����V���[�x���g�́A1828�N9����3�̃s�A�m�E�\�i�^�iD958�AD959�AD960�j�����������Ă��܂��B�S���Ȃ鐔�T�ԑO�̂��Ƃł��B���������ׂĂ����B����͐����n��͂ł��B�����3�Ȃ́A�ނ̎��サ�炭���ɏo���ɂ��܂������A1837�N�ɂȂ��Ďn�߂ďo�ł���܂����B�V���[�x���g�̈�u�ɂ��t�������Ɍ��悳���͂��ł������A�o�ł̒��O�ɖS���Ȃ������߁A�i�o�ŎЂ̈ӌ��Łj�V���[�}���ɕ������Ă��܂��B�V���[�}���́u���y�Ɖ��y�Ɓv�i��g���� �g�c�G�a��j�̒��ł����q�ׂĂ��܂��B����x�̃\�i�^�́A���̌|�p�Ƃ̏����̍�i�Ǝ��Ⴆ���˂Ȃ������B�V���[�x���g�̂悤�ɁA����قǑ����̍�i���������l�́A�I�n���サ�i�����Ă䂭�Ƃ����̂͐l�Ԃ킴�ł͍l�����Ȃ�����A����3�Ȃ��A���邢�͖{���ɍŌ�̍�i�������̂�������Ȃ��v�ƁB���̋L�q�ɂ͎��ɋ����[�����̂�����܂��B�u����o�Ă�������Ƃ����Ă��Ō�̍�i�Ƃ����킯����Ȃ��B�@����ɁA���̏o�����炢���āA�����⏉����i��������Ȃ��v�ƁA��x�͋^�����̂ł��ˁB�ł��悭��������i�ǂ�A���́A�e���Ă݂���A�����m��܂��j��͂�"�Ō�̍�i"�ƌ��_�����Ƃ����킯�ł��B�����A�V���[�}���́A�����3�Ȃ���U�͏�����i��������Ȃ��Ƌ^�������炢�A�]���͒Ⴉ�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����Ă��������܂��B�u���x�̋Ȃ͔ނ̂ق��̃\�i�^�ɂ���ׂāA�����̑f�p���ƁA���܂Ŕނ�����Ȃɍ����v�����Ă����ڂ��܂����V�����������I�ɂ�����߂Ă��邱�ƁA���܂łȂ�Ίy�i����y�i�ւƐV�������Ōp���ł����̂ɂ��镽�}�ȉ��y�I�y�z�X�ƕ~���i�ӂ���j���Ă��� �Ƃ����O�_�œ��ɍۗ����Ă���悤���B�v�ƁA�a�V�����܂������Ȃ��璷�ȍ�i�ƌ��ߕt���Ă��܂��B����ɂ��������܂��B�u�����������܂ł��s���邱�Ƃ�m��ʂ��Ƃ��A�������������玟�ւƗ��ނ��Ƃ�m��ʂ��Ƃ��A�������y�I�̂ɕx��ł��邱�̋Ȃ́A�ł���łւƂ��炳��Ɨ���Ă䂭�v�ƁB�����́A"���̋�"�ƒP���i��j�ɂȂ��Ă���̂ŁA�i���肳��Ă͂��܂��jD960�̂��Ƃ��w���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������ł��B��҂̕������̂������������Ă����Ƃ��肪���������̂ł����A����͂��Ă����A���̕����́u��21��D960�v�̓���������Ӗ��������ĂĂ���Ǝv���܂��B
�V���[�}���̕��͂����p�������łɁA���̂܂ܘb��E�������āA�������������V���[�}���ɓ˂�����ł݂܂��傤�B���x�̈��p�͌ܖ��N�S���u�����̉��v�i�V���Њ��j����u���y�ɍ݂鎀�v�̈ꕔ�ł��B
�u�V���[�}����"���z��"�n�����i��i17�j�̑�P�y�͂��A�x�[�g�[���F���̃\�i�^���Ȃ����ď������B���̃V���[�}�����g�̃s�A�m�E�\�i�^��1�ԉd�֒Z���i��i11�j�́A���낢��\�i�^�`���̒��ŐV�N�����o�����Ƃ͂��Ă��邪�A��M�ƌ��z���肪��s���A"�Â肷���č���"���A�������ɂ�����Ƃ͌�������A��3�Ԃ֒Z���i��i14�j�̒��S�ƂȂ���́A���ăN���������������̂̈��p�ł���B�E�E�E�����E�E�E���@�C�I�������t�Ȃ̓��A�q�������t���郁���f���X�]�[���̂�����ċ}�Ɋ����������Ȃ������̂ł���B�����ɂ��x�[�g�[���F���I�ȏd���������o���オ��ŁA�V���[�}���͑������M���������炵�����A�����ꂽ���A�q���͈�ڂ��ɂ��ꂸ�A����Ԃ��A���t��ɍ̏グ�Ȃ������B�V���[�}���������Ȃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂�͂���߂đ�����̉e���ɐ��܂�₷�������������A����̈ӎu�ł͂Ȃ��A����Ȋ����̔����ōs�����Ă��܂������������y�Ƃł��������Ƃ��A�����Ă���܂ł��v�ܖ������"�V���[�}�����Ȃ��Ă���킯�ł͂Ȃ�"�Əq�ׂĂ��܂����A�����͂ɂ���ȋL�q������܂��B
�u�厖�Ȃ��Ƃ�Y���Ƃ��낾�����B�V���[�}���́A�N�����Ƃ̌������ٔ��ɂ���ď�������Ă���B���e���B�[�N��ǂ�A���i���Ă͂��߂Ĕޏ����Ȃɂ����B����Ԃ��܂ł��Ȃ������B�[�N�̓V���[�}���ɂ͐搶�ł���B���e�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�t�Ƃ��ă��B�[�N�͂��̌����ɔ������̂łȂ��ƁA�N�Ɍ�����̂��B����ł͐����ł����A���y�̓V���ł͂܂��Ă�����Ȃ������A�ٔ��Ƃ����A��O�҂̗e�[��҂��˂N�����������̂��̂ɏo���Ȃ������Ƃ������̂��Ƃ����ŁA�V���[�}�������͐M�p���Ȃ��v���́A�ܖ�����̈ӌ��ɋ���������Δ�����������̂ł����A���̃V���[�}���Ɋւ��Ă͓����ł��B�ň��̐l�ɏo����Đ��U�����ɂ��悤�Ǝv���A�e�̏����悤�Ƃ���Ȃ�A������C�������̂��̂Ǝ���̍˔\���Ȃ��ĂԂ���ׂ��Ȃ̂ɁA���ʓI�ɂ͍ٔ��Ƃ�����O�҂̎�A����������A���Ђ̎P�ɂ���Ă����B���ł��Ȃ������B������ܖ�����̓V���[�}����M�p���Ă��Ȃ��̂ł��B�V���[�}���̉��y��M�p���Ă��Ȃ��̂ł��B����Ȓj����鉹�y�����l��������������킯���Ȃ��Ƃ܂ŋ��܂��B���́A�����܂ł͌����܂���B��ȉƂ��ǂ�Ȑl���𑗂낤����{�I�ɂ͒m�������Ƃ���Ȃ����A�l���͉��y�ɓ��e������̂Ƒ��ꂪ���܂��Ă���킯����Ȃ��B"���y���̂���"���������̐S�ɋ������ǂ��������̖��Ȃ̂ł�����B�ł��ܖ�����̋邱�Ƃ͂悭������܂��B
���y���������ɗ^���Ă������́A����͊����Ɩ����ł��B����������A���y���Ƃ����s�ׂ͊������邱�Ƃł��������邱�Ƃł���A�Ƃ�������B�������A�g�����A�������A�������A�Ȃ��A�������A�͋����A���ɂ͔߂����A�������A��邹�Ȃ��ȂǁA���y���\������l�X�ȏ�ɐS�������ꂽ��A�̎��̓��e�╨��̖ʔ����ɋ������邱�ƁB�D�������₩�ȃT�E���h�ɐS������邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B���킩������ւ̔��ĂƂ����Ă������ł��傤�B
���y�͓��Œ������̂ł͂Ȃ��S�Ŋ�������̂Ȃ̂ŁA���̃V���[�}�������ɗ��R�͂���܂���B�V���[�}�����āA���܂�S������Ȃ����A���炬�������Ȃ��Ƃ����A�������ꂾ���̂��ƁB�������A����Ȏ����ܖ�����̕��͂�ǂ�ō��_���������̂��m���ł��B�|�p�ɂ�����n���Ƃ́A�{���A��ނɎ~�܂�ʐS�̏Փ��ɂ���ĂȂ����_���ȍs�ׂ̂͂��ł��B���X�̕K�v�ɉ����Ď��R�ɉ��y���N���Ă����i�Ƃ����Ă���j�^�̓V�˃��[�c�@���g�̏ꍇ�ł������A�ŏI�I�ɎY�ݏo���ꂽ��i�͐S�̏Փ��̒��ڂ̎Y���̂͂��ł��B�������ȉƂ́A�S�̒ꂩ��˂��グ��Փ���f���ɕ\�����ׂ��Ȃ̂ł��B�V���[�}���ɂ͂��̑f�������Ȃ��B���g�̋C�����ƍ�i�Ƃ̊ԂɂȂɂ��ٕ������܂��Ă���i�悤�Ɏ��ɂ͕�������j�B����͑��ւ̉ߏ�ӎ��ƁA���Ёi�����j�ɂ����鎩�M�̂Ȃ��ɋN�����Ă���̂ł͂Ȃ����B������A�V���[�}���̉��y�́A���̐S�ɑf���ɋ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�ܖ�����̕��͂Ŏ��̃V���[�}�����������_�t�����ꂽ�悤�Ɋ����Ă��܂��B
�ł���Ȃ�����̊y�Ȃ�����܂��B����́u�g���C�����C�v�ł��B���ꂾ���͕���Ȃ��ɂ����Ȃł��B�Ȃ�����Ȃɖ��C�őf���Ŕ������Ȃ��V���[�}���͍�ꂽ�̂ł��傤���H�i���̋Ȃ��܂ށu�q���̏�i�v�S�̂ɂ�������̂ł����j�B���y�͕��ϒl�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�g���C�����C�v��Ȃ����ŃV���[�}���͑f���炵����ȉƂȂ̂ł��B��������̍l�����ł��B
����͏�������V���[�}���ɒE�����܂������A����̓V���[�x���g�ɖ߂������Ǝv���܂��B
2009.08.24 (��) Romance�ւ̗U���C�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����2
�i�R�j�s�A�m�E�\�i�^�ɓZ����ȃX�^�C���̔�r�V���[�x���g���s�A�m�E�\�i�^���肪�����̂́A1815�N�A18�̂Ƃ��B����A�����ȂɊւ��ẮA1813�N16�Łu��1�ԃj�����v�������Ă��܂��B����́A�V���[�x���g��11�̂Ƃ��ɏ��w���Ƃ��ē��w�����R�����B�N�g�i��h���_�w�Z�j�ł̐����Ɗ֘A������܂��B�����̓E�B�[���{��̒����@�ւŁA�y���̓T���G���B���̉f��u�A�}�f�E�X�v�̎�l���̈�l�ŁA���[�c�@���g�̓G���̂��ꂳ�y�Ƃł��B���k�݂͂ȗ�q���̃R�[���X�����ƂȂ�܂����A���ꂪ���݂̃E�B�[�����N�����c�ŁA��y�ɂ̓n�C�h���A��y�ɂ̓u���b�N�i�[�����܂��B�V���[�x���g�́A1813�N16�܂ł�5�N�Ԃ������ʼn߂����A���y�̊�b���w�сA�s�A�m�ȁA�̋ȁA�������́A���y�l�d�t�ȂȂǐ��X�̊y�Ȃ����܂����B�����ɂ͏������Ȃ�����{�i�I�Ȋw���I�[�P�X�g��������A�ܘ_�V���[�x���g�����̈���Ƃ��āA�n�C�h���A���[�c�@���g�A�x�[�g�[���F���̃V���t�H�j�[�����I�ɉ��t���Ă����悤�ł��B�ŏ��̌����Ȃ́A���Ƃ̔N�ɁA���̃I�[�P�X�g���̂��߂ɏ��������̂ł��B
���ꂪ�x�[�g�[���F���ɂȂ�ƁA�u�s�A�m�E�\�i�^��1�ԁv��1793�N23�A�u�����ȑ�1�ԁv��1800�N30�ō�ȁA�Ƃ����t�̌��ۂƂȂ�܂��B�u���[���X�̏ꍇ�́A�����Ɛr�������A�Ō�̃s�A�m�E�\�i�^�u��3�ԁv���������̂��㊥20�ŁA�ŏ��̌����ȁu��1�ԁv�����������̂��ő��s�N����43�̂Ƃ��B���̎���́A������l�̍�ȉƂƂ��Ẵ^�C�v��@���ɕ�����Ă��܂��B�����A�ނ�ɂƂ��āA�����Ȃ�����y�Ȃ̍ō��̌`�ł���A���̂��߂ɂ͎����ȏ������K�v�������Ƃ������Ƃł��B����ɂ͎���w�i������܂����A��l�̐��i�ɂ��Ƃ��낪�傫���ł��傤�B�����A�x�[�g�[���F�����u���[���X���A�v�搫��ŐT�d���ςݏグ�^�̐��i�������B���Ƀu���[���X��"����@���Ă��n��Ȃ�"�قǂ̐T�d���m�������悤�ł��B�ނ����̐�y�ɂ�"����@�������ĉ��Ⴄ"�Ƃ����l�����܂�������ǁB
���[�c�@���g�̏ꍇ�́A�ŏ��̃s�A�m�E�\�i�^�������Ȃ����N����ɍ���Ă��܂��B��������ŏ��̃s�A�m�E�\�i�^�i��1��K279�j��18�̂Ƃ��̍�i�ł����A����ȑO�A���N����ɁA4�g�̃\�i�^������Ă��܂��B�����̂���3�g�̓��@�C�I�����ƃ`�F�������́iK6�\K9�j�A�c��P�g�̓\���ł����y���͕������Ďc���Ă��܂���B�ŏ��̌�����K16�́A����̃����h���ŁA�o�b�n�̖����q�N���X�e�B�A���E�o�b�n�̋������Ȃ��珑���グ�A���t��ɂ����Ă��܂��B���ꂪ8�̂Ƃ��B���[�c�@���g�́A���N����ɁA���[���b�p�������t���s�ʼn���Ă��܂��B���̂Ƃ��Ɏ���̊y�Ȃ��K�v�ł����B���������Ă��̎����̃��[�c�@���g�̊y�Ȃ͂��̎��X�̕K�v�̎Y���ł����B�����I�M���^�Ƃ�����ł��傤�B�V���[�x���g�̍�ȃX�^�C���́A�x�[�g�[���F�����u���[���X�^�ł͂Ȃ��A�����Č������[�c�@���g�^�ɋ߂��Ƃ����邩������܂���B
�V���[�x���g�́A���������Ă��܂��B�u�S�̒�ł͎������A���炩�̐l���ɂȂ�邩�Ɗ��҂͂��Ă���̂ł����A�������x�[�g�[���F���̌�ł܂����������N�ɁA���炩�̐l���ɂȂ�邱�Ƃ��ł���ł��傤���H�v�ƁB��������́A�x�[�g�|���F���ɑ���،h�̔O�Ɠ����ɁA�ނ̌����Ȑ��i�����Ď��܂��B���۔ނ̐��i�́A�o������^�ł͂Ȃ��������ݎv�Č^�������B�����ėF�B�z���ŗD�������i�A�ł��s���Ȕy�ɂ͓��X�ƈӌ����������`�����������킹���A����Ō����A���ɂ������c�������̂ł��B����Ȕނ��A25�A6�̍��A�s���̕a��w��������ł��܂��̂ł�����A�_�l�̈��Y�����ɋɂ܂��I
�i�S�j�s�A�m�E�\�i�^�̖��� ���̂P
�u��13�� �C���� D664�v��1819�N�̍�i�B�O�͂ŐG�ꂽD575�i1817�N�����j�̂��Ƃ́AD613�A625�A655��3�ȗ��đ����ɖ����ɏI����Ă���A���̎����A�s�A�m�E�\�i�^�ɂ�����V���[�x���g�̈���ꓬ�Ԃ肪�M���܂��B���������Ă���͋v�X�̊�����i�ŁA�R��I�Ŕ������܂Ƃ܂�̂悢���ȂɎd�オ���Ă��܂��B
��13��D664�̂��ƁA���̍�i��14�� �C�Z�� D784�i1823�N�����j�܂ł́A�܂���3�N�Ԃ��Ă��܂��B����������1817�|1822�N�i�V���[�x���g20�|25�j�̂T�N�Ԃ̓s�A�m�E�\�i�^�Ƃ̋ꓬ�̎���Ƃ����邩������܂���B�Ƃ��낪�A���̊Ԃ�1822�N�ɁA���ڂ��ׂ��s�A�m�Ȃ����܂�Ă��܂��B�u�����炢�l���z�ȁv�ł��B���̍�i�̓V���[�x���g��19�̂Ƃ��ɏ������̋ȁu�����炢�l�v�̃����f�B���e�[�}�ɂ���4�̊y�͂���Ȃ錶�z�ȂŁA���B���g�D�I�[�]�I�s�A�j�Y����O�ʂɉ����o�������t���ʔ��Q�̋ȁB�Ƃ͂����A���R�̂��ƂȂ���V���[�x���g���L�̝R���̐S�Ɉ��Ă���A���w�̐l�C�ȂƂȂ��Ă��܂��B�\�i�^�Ƃ����`���I���肩��J�����ꂽ���R�Ȑ��_�̔��Ă��A���̋Ȃɂ��������̂Ȃ����͂�^���Ă���̂ł��傤�B���������āA���̍�i�Ő����ꂽ�̂��A�Ȍ�\�i�^�̖��Ȃ��ڔ������ɕ��т܂��B
�u��16�� D845 �C�Z���v�i1825�N�����j�͉���I�ȍ�i�B�����ɕ�����鋽�D���inostalgia�j�ƈٍ��(exoticism)�͂���܂ł̍�i�ɂ͂Ȃ����������Ƃ����܂��B��1�y�͂̑�1���ɂ͙R�Ȃ����D���������A���y�͓W�J���̓���ɕY���G�L�]�`�b�N�ȃ��[�h�ɂ̓n�b�Ƃ���������̂�����܂��B�����̊��o�́A�܂��A��3�y�̓X�P���c�H�̃g���I�����ɂ��������܂��B��2�y�͂��ϑt�ȂŁA��4�y�͂������h�`���ō���Ă���̂����̋Ȃ̓����B����܂ŁA�s�A�m�E�\�i�^����Ȃ��o�ł��ĂȂ������V���[�x���g�ł����A����D845�́A�����シ���ɏo�ł��Ă��܂��B����͔ނ̂��̋Ȃɑ��鎩�M�̕\���ł��傤�B
"���z��"�Ƌw���������u��18�� �g���� D894�v�i1826�N�����j�ɂ��āA���}���h�̋����ɂ��Ę_�q�̃V���[�}���́A1836�N�Ɂu�`���Ƃ������_�Ƃ����A�V���[�x���g�̍�i�̒��ł��������ɂ߂����̂ł���v�i�V���[�}�����u���y�Ɖ��y�Ɓv��g���ɂ��j�ƕ]���Ă��܂��B�܂��ɍō����̎^���ł��B���̂Ƃ��A���3��\�i�^�i��19�ԁ\21�ԁj�́A�܂��V���[�x���g�̈����o���̒��Ŗ������܂܂ł������A���N�o�ł��ꂽ�܁A�V���[�}���͂�����]���Ă��������Ă��܂��B�u3�Ȃ̃s�A�m�E�\�i�^�͂���܂ł̍�i�ƍۗ����Ĉ���Ă���B���Ȃ킿�A�����̑f�p���Ɩڊo�����V��������߁A�y�i����y�i�Ɍq����V�������̌q�����Ȃ��A���}�ȉ��y�I�y�z�Œ��X�ƕ~�����Ă���v�ƁB������͎��ɔے�I�Ȍ����ł��B�v�����"�V���[�}�����]������V���[�x���g�̃\�i�^�̍ō�����́w��18��D894�x�ł���"�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB����ł͂��̎^����O���ɒu���āA�Ȃ��Ă݂܂��傤�B
��1�y�́B�F��ɂ��������������A�ǂ����x�[�g�[���F���́u�g���� �s�A�m���t�ȁv�̏o�����Ɏ��Ă��܂��B�����āA���̂��ƁA�̂��悤�ȑ��̒����������J��o����Ă䂫�܂��B�Ȃ�قǁA�o�ŎЂ��u���z�ȁv�Ɩ��Â����̂�������ȑz�ł��B��2�y�́A�啔�͓]���ɂ��ȑz�̕ω����▭�ŁA���ԕ��ɂ͂��ĂȂ����I�ȋ���������܂��B��3�y�͂̃��k�G�b�g�̂Ȃ�Ɨ͋����j���I�Ȃ��ƁB�I�y�͂̓����h�`���B�����h���iA�j�ƌq���̕���(B,C,D)�̍\������{�^�Ƃ͏�������Ă��܂��B��{�^��A�|B�|A�|C�|A�|D�|A�Ƃ���A���̋Ȃ�A�|B�|A�|C�|A��D�ȗ��`�ƂȂ��Ă��܂����A���̑���C�̕������O���`���ɃX�P�[���A�b�v���Ă��܂��B����C�����̒��ԕ��́A�R��ƌ��z�������킹�������f���炵�����������h���A����ɁA�������Փ��I�ȃt���[�Y�Ɛ����ȗZ���������܂��B�����ĐÂ��ɉ��₩�ɁA�Ō�͎�v���`�[�t����z���ċȂ���܂��B���������郍�}�����A���R�ɏ_��ɕω��������`���̒��Ō����ɏ����������A���_�ƌ`���̐▭�ȃo�����X�������ɂ���܂��B���ꂼ�V�˂̋Z�B�V���[�}�����u�`���I�ɂ����_�I�ɂ��������ɂ߂���i�v�ƌ������̂́A�܂��ɂ��̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�V���[�}���̕]�_�ɂ͓Ɠ��̕Ȃ�����悤�ł��B����Ƃ��A�V���p���̋ȁu�h���E�W�����@���j�̓�d���̃e�[�}�ɂ��ϑt�ȁv���Ċ��������V���[�}���́A�u�M���͓V�˂��B����قǂ̈Ӑ}�荞�߂�Ȃ�āI�v�Ƃ��āA��Ȏ҂ɂȂ�����Ď��ׂ��ɕ��͂����ȉ��߂��V���p���{�l�ɑ������B�����ǂV���p���͗F�l�ɂ����R�炵�Ă��܂��B�u�l�̋ȂɊ��������h�C�c�l��10�y�[�W�ɂ��y�ԕ��͂𐔓��O�ɑ����Ă����Ȃ�āA�N�ɑz���ł��邩���B���̐l�͋Ȃ��قƂ�Ljꏬ�߂��Ƃɕ��͂��Ă���B�l�̍�i�������̕ϑt�Ȃł͂Ȃ��āA���z�I�ȕ`�ʂɂȂ��Ă���Ƃ����̂���B���̐l�̑z���͖͂ʔ�������ǁA�l�ɗ���Łw�����F�E�~���[�W�J���x�i�t�����X�̉��y�]�_���j�ɍڂ�悤��Ă���͍̂��������̂��B�v�i�Έ�G���u�����y�j�v�V���Њ����j�ƁB���̃G�s�\�[�h����́A���Ȃ̐M�����ɏ]���ēƎ��i����j�ɉ��߂���V���[�}���ɑ��āA�u�ʂɂ���Ȃ���ŏ�������Ȃ�����ǁv�ƁA���f����V���p���̎p�������Ă��܂��B���y�������y�Ƃ��đ�����V���p���ƃ��}���I�ɉ��߂���V���[�}���B�����Č����A�����D��E�]�h�̃V���p���Η����D�捶�]�h�̃V���[�}���A�Ƃ������}���ł��傤���B����́A����Ȏv�l�X���̃V���[�}�����A���܂蔃���Ă��Ȃ������V���[�x���g�u�Ō�̂R�̃\�i�^�v�ɔ��肽���Ǝv���܂��B
2009.08.17 (��) Romance�ւ̗U���B�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v���̂P
�O��̃h���j�R�E�X�J�����b�e�B�̓\�i�^�̐E�l�B����̃V���[�x���g�̓\�i�^�����H�t�����c�E�y�[�^�[�E�V���[�x���g�i1797�|1828�j�́A���̒Z�����U�ŁA23�Ȃ��̃s�A�m��\�i�^���肪���Ă��܂��B���̂���������i��15�ȁB���̒��ŁA�\���ʂ��猩��ƒʏ�Ȃ炴����̂�2�Ȃ���܂��B��3�ԃz����D459�Ƒ�9�ԃ�����D575�ł��B����ɍ�ȉߒ�����́AD567��D568�̊W�ɂ������[�����̂������܂��B
�i�P�j�ʏ�Ȃ炴��`�Ȃ�
�V���[�x���g�̢�s�A�m�E�\�i�^ ��3�� �z���� D459�v�́A5�̊y�͂��琬�藧���Ă��܂��B����14�Ȃ͑S��3�T��4�y�͍\���Ȃ̂ɂł��B���̑��̍�ȉƂ̗�A���Ƃ����[�c�@���g�̃s�A�m�E�\�i�^�́A18�Ȃ��ׂĂ�3�y�͍\���B�x�[�g�[���F���́A32�Ȓ��A2�y�͍\����6�ȁA3�y�͂�4�y�͍\�����e�X13�ȂÂƂ�������B����炩�猩�Ă�5�y�͍\���Ƃ����̂͂����ɂ����قȊ��������܂��B�O��̃h���j�R�E�X�J�����b�e�B�̏ꍇ�́A555�Ȃ��ׂĂ��P��y�́A����������ł����A���オ�Ⴄ�̂Ŕ�r�̑Ώۂ���͊O���܂��傤�B
���̍�i�́A��P�y�͂����5�y�͂܂ŁAAllegro moderato�|Scherzo�|Adagio�|Scherzo�|Allegro patetico�Ƃ������тɂȂ��Ă��܂��B5�y�͂ɂȂ��Ă���̂�Scherzo�i�X�P���c�H�j���ʏ�����������ł��B����ׂ�ƁA��2�y�͎͂��ɉ��₩�ȋȒ��ŁA�ʏ�̃X�P���c�H�Ƃ͎���قɂ��Ă��܂��B�V���[�x���g�͉��̂����ɂ���Ȃ��̂�u�����̂ł��傤���H ������������AAdagio�i�A�_�[�W���j�����ރV�����g���[�ɍ\�����Ă݂����������炩������܂���i�Ӗ��Ȃ����j�B���[�y�͂͂ǂ�����\�i�^�`���B��P�y�͂́A��1���Ƒ�2��肪�Ƃ��ɉ̗w�������f�B�[�œ����Ȓ��A�W�J���͂��Ȃ�Ȍ��ł��B����A��5�y�͂̂ق��́A��1��肪�Z�����`�[�t�n�ŁA��2���͑ΏƓI�ɗ���Ȑ����B����2�̎��̑Δ�ƁA���̂��Ƃ̓W�J�͂܂��Ƀx�[�g�[���F���I�B�����\�i�^�`���ł��A���[�y�͂͂��Ȃ�Ⴄ��ۂ���X�ɗ^���܂��B���̍�i�́A1816�N�A�V���[�x���g19�̂Ƃ��ɍ���Ă��܂��B�o�łɂ������ČZ�̃t�F���f�B�i���g���u5�̃s�A�m�ȁv�Ɩ��ł������Ƃ���A"�\�i�^�ł͂Ȃ�"�Ƃ����������悤�ł����A���[�y�͂��\�i�^�`���ł��邱�ƁA�A�_�[�W���͂ǂ��݂Ă��Ɨ������ȂƂ͂����Ȃ����ƁA��������̊y�ȂƂ��Ă̕��тɂȂ��Ă��邱�ƁA�Ȃǂ���A��̃\�i�^�Ƃ��Ĉ����̂��Ó��ł��傤�B
�u�s�A�m�E�\�i�^��9�ԃ�����D575�v�́A1817�N�̍�i�B�S�l�y�͂����ׂă\�i�^�`���ŏ�����Ă���Ƃ����Ă��܂��B������ʏ�Ȃ炴��`�Ƃ�����ł��傤�B��P�y�́A�`��������1���̓V���[�x���g�ɂ��Ă͒Z�����`�[�t�n�̂��́B����"�^���^�^�[��"�̃��Y���������Ɍ���āA�y�͑S�̂ɓK�x�ȋٔ�����^���Ă��܂��B�܂��A���̎��̓x�[�g�[���F���u�M��\�i�^�v��P�y�͑�1���ɍ������Ă��܂��B���Ƃ��猻����2���́A����Ƃ͑ΏƓI�ɉ��₩�Ȃ��́B�����ɂ��x�[�g�[���F���I�Δ䂪�����܂��B��2�y�͂�Andante�B�O���`���Ƃ����������܂����A���ԕ��ւ̓]�����Ă̈ڍs��A��3���ł̍���̃��Y������1���ƈႤ�_�Ȃǂ���A��͂�m�\�W�J�\�Č��n�܂����\�i�^�`���Ƃ݂�̂��Ó��ł��傤�B��3�y��Scherzo�͖ʔ����B�����̌`�� ABABA�\C�\ABA�ƂȂ��Ă��܂��B�\�i�^�`���Ƃ����Ȃ�Č������ɉ��炩�̕ω��������đR��ׂ��ł����AAB�Ƃ����p�[�c�͓����ł��B�������m�ɓ����Ƃ͂������A���������Ă���͕ϑ��O���`���܂��̓����h�`���Ƃ���̂��Ó��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ł��ɂ�����AC�Ƃ����W�J��������ŁA���iABABA�j�Ək�������Č����iABA�j����Ȃ�\�i�^�`���Ƃ����Ȃ�������܂���B��4�y�͂́A�j���I�ȑ�1���ƃ������R���b�N�Ŕ�������2��肪�Δ䂵�Ă��܂��B�W�J���͏��K�͂ł����m�łƂ����\�i�^�`���̑̍ق��Ȃ��Ă��܂��B
��ȉߒ��ɂ����ċ����[���̂�D567��D568�̊W�ł��B1817�N�A�V���[�x���g�́A7�Ԗڂ̃\�i�^��3�y�͐��ō��܂����B���ꂪD567�σj�����ł��B�Ƃ��낪����Ƀ��k�G�b�g�������A�ꉹ�ڒ����ĂS�y�͐��ɍ��ς��Ă��܂��B���ꂪD568�σz�����ł��B��P�y�͂́A�֊s�̂͂����肵����P���Ɖ̗w���̑�2��肪�Δ�A����ɑ�3�̎����o�ꂷ��\�i�^�`���ƂȂ��Ă���A���ȁiD567�j����͒����啝�ɃX�P�[���E�A�b�v����Ă��܂��B�ʔ����̂͑�2�y�́B���Ȃ̑�2�y�͉͂d�n�Z���ŁA�咲�i�σj�����j�Ƃ͓����ى����i�G���n�[���j�b�N���j�ƂȂ��Ă��܂��B���̗��ꂩ��͉d�j�Z���Ƃ���̂����R�ł����A���ۂ̓g�Z���Ɉڒ����Ă��܂��B�����ɂ��V���[�x���g�̎��s����̂��Ƃ������܂��B��3�y�͂́A�V���ɉ��������₩�ȋȒ��̃��k�G�b�g�B��4�y�͂́A��̎�肪�Ƃ��ɉ̗w���̒����ƒZ���A�e���|���A���O�����f���[�g�A���Y��������̂悢8����6���q�ƁA�V���[�x���g�炵�����l�������y�B�W�J���ɂ�������ď[�������Ă��܂��B
�V���[�x���g�́A���炩�̗��R�ŁA�o��������̋Ȃ��A�S���V������i�ɍ��ς��Ă��܂����B�t�@�̖��Ȃ̂��A����������ΓI�����̖��Ȃ̂��B���̗��R�́A�}�l�ɂ͕�����Ȃ��V�˂̒����Ȃ̂ł��傤�B�����m���Ȃ��Ƃ́A�����ɂ��V���[�x���g�̃\�i�^�ɑ���ꓬ�Ԃ肪�M����Ƃ������Ƃł��B
�i�Q�j�\�i�^�`�����ĉ��H
�\�i�^�`���Ƃ́A�C�^���A�́u�_�E�J�[�|�v�A���A���甭�W���A�h�C�c�Ŋ������ꂽ���y�̌`���ŁA�����ȁA���t�ȁA���y�l�d�t�ȁA�\�i�^�Ȃǂ̂ǂꂩ�̊y�͂ɗp�����A��̎��𒆐S�Ƃ��ām���\�W�J���\�Č����n�̎O�����琬���y�Ȃ̌`���E�E�E�E�E�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
�h�C�c�̉��y�w�҃p�E���E�x�b�J�[�́u���m���y�j�v�ɂ͂�������܂��B�u�����ɉ��y�j�I�ȗ��ꂩ�炢���A�������y�`���̊����̉ߒ����猩��A�����̉��y�`���ł���\�i�^�`����������n�C�h���́A���[�c�@���g�����d�v�Ȑl���ł���v�ƁB���̂悤�Ƀh�C�c�̉��y�j�ς́A�u�\�i�^�`�������ō��̉��y�`���ł���A���̑n�n�҂ł���n�C�h���̓��[�c�@���g�������y�j�I�ɂ͏d�v���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�n�C�h�����n�n�����Ƃ����̂����Ȃ̂ł����A���̗��j�ς̍ő�̌��ׂ͌`���D��̎v�z�ł��B������"���y�`���̊����̉ߒ����猩���"�Ƃ����f�菑�����t���Ă���ɂ���A�u�n�C�h�������[�c�@���g�����d�v���v�Ƃ�����j�ς��������营�F����킯�ɂ͂����܂���B�ł����ꂪ�h�C�c���y�j�ς̃o�b�N�{�[���ɂ��邱�Ƃ͎����Ȃ̂ł��B�n�C�h�����烂�[�c�@���g���o�Ĉ琬���W�����u�\�i�^�`���v�̓x�[�g�[���F���Ō������܂��B�ł�����A�i�h�C�c���y�j�ς���݂Ắj�j��ō��̍�ȉƂ́A�\�i�^�`�����ɂ߂��x�[�g�[���F���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�x�[�g�[���F���̃\�i�^�`���̓����̂ЂƂɁA��̎��̐��i�̑Δ䐫������܂��B��1��肪�E�s�Ȃ��̂Ȃ��2���͗D���Ȃ��̂Ƃ����悤�ɁB����́A�w�[�Q���ُؖ̕@�ƌ��т��m�ł�����j�ςƂȂ�܂��B��1�����e�[�[�i�喽��j�ɁA��2�����A���`�e�[�[�i�Η�����j�ɏy���A���Œ��ꂽ��̎��́A�W�J���Ŋ������s���A�Č����ʼn�������~�g�����ƁB
�V���[�x���g���A�i�P�j�Ō������\�i�^��������1817�N���܂łɁA�x�[�g�[���F���͑�28�Ԃ܂ł̃s�A�m�E�\�i�^�������グ�Ă��܂����B���̒��ɂ͎O��\�i�^�Ƃ�����u�ߜƁv�u�����v�u�M��v���͂��߁u�e���y�X�g�v�����g�V���^�C���v�u���ʁv�Ȃǂ̖��Ȃ����łɊ܂܂�Ă���̂ł��B�x�[�g�[���F���́A1792�N�ɃE�B�[���ɏo�Ă��āA�S���Ȃ�1827�N�܂ŏZ��ł����̂ł�����A1797�N�E�B�[���ɐ��܂�A�̋��𗣂�邱�ƂȂ�1828�N�ɖS���Ȃ����V���[�x���g�́A���U�A�y���x�[�g�[���F���Ɠ�����̉��ŕ�炵�����ƂɂȂ�܂��B�V���[�x���g�́A���U�A�j��ō��̍�ȉƂ��ӎ�������Ȃ����ɂ������B��3��D459�́u5�y�͍\���v����9��D575�́u�S�y�̓\�i�^�`���v���AD567����D568�ւ̏����������V���[�x���g�̎��s����̏ł��B����͑����A�x�[�g�[���F���ƃ\�i�^�`���ւ̒��킾�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ł��A�V���[�x���g�ɂƂ��āA�s�A�m�E�\�i�^����Ȃ���Ƃ����s�ׂ́A�̑�Ȑ�y�ƌ`���Ƃ�����������d���ɑ��铬���̗��j�������̂�������܂���B
�uRomance�ւ̗U���`�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v�͂������炭���������Ă��������܂��B���̂Q�́A�X�ɖ��ȃ\�i�^�iD845�A894�Ȃǁj�̖��͂ɓ��ݍ���ł݂����Ǝv���܂��B
2009.08.03 (��) Romance�ւ̗U���A�u�h���j�R�E�X�J�����b�e�B��J�DS�D�o�b�n�͓����̍��v
�O����グ���t�����N�́A�H�̊C�V���݂ق��T�C�^���E�v���O�����̃G���f�B���O�ȁB����̃h���j�R�E�X�J�����b�e�B�̓X�^�[�g�ȁB�Ȃ����J�DS�D�o�b�n�ł��B�t�����N��J�DS�D�o�b�n���h�����A����I�ȃs�A�m�ȁu�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v�̖`������BACH�̃e�[�}���g���Ă��܂��BBACH�̃e�[�}�����A���u�t�[�K�̋Z�@�v�̍ŏI�ȁE�����́u�l�d�t�[�K�v�̃��`�[�t�B�J�[���E�t�B���b�v�E�G�}�k�G���E�o�b�n�͂��̊y���ɁuB�|A�|C�|H�Ƃ������O�������Ƃ��ĐD�荞�܂��A���̃t�[�K�̐��쒆�ɁA���̍�Ȏ҂͖S���Ȃ����v�Ə������B�J�[����t�B���b�v��J�DS�D�o�b�n�̓�j�ŕ�̓}���A�E�o���o���B�o�b�n�̎q��R�͗L���ŁA���̃}���A�E�o���o���Ƃ̊Ԃɂ�7�l�A��l�ڂ̍ȃA���i�E�}�O�_���[�i�Ƃ̊Ԃɂ�13�l���̎q�������܂����B���A�h���j�R�E�X�J�����b�e�B�������Ă͂��Ȃ��B�ŏ��̍Ȃ��Ȃ��������N�A57�ŁA�Ⴂ�X�y�C�����ƍč��A�����5�l���̎q����ׂ��Ă���B�Ȃ�Ƃ����͓I�ł��B
�h���j�R�E�X�J�����b�e�B�i1685�|1757�j�́A1685�N10��26���A�i�|���Ő��܂�܂����B���̔N��3��21���ɂ�J�DS�D�o�b�n�i1685�|1750�j�����܂�Ă���A��l�͓����̍��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�h���j�R�̕��̓i�|���y�h�̋����A���b�T���h���E�X�J�����b�e�B�ł��B
�A���b�T���h���E�X�J�����b�e�B�i1660�|1725�j�̓I�y���̐��E�ő傫�ȋƐт��c���Ă��܂��B�ނ�����17���I�㔼�A�C�^���A�ɂ����ăI�y���͂��łɏ����̌�y�Ƃ��č��Â��A�i�|���ł�4�������̃I�y���n�E�X������܂����B���������̓h���}�̋ؗ��ėD��̌`�ł������A���X�ɉ̏��͂����������X���������Ȃ�A���̍��ɂ́A��̏o�����̒��ɁA�Ȃ��50�Ȃ��̃A���A�����ꍞ�܂��悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̃n�`�����`���ȏ����āA�㐢�Ɍq����I�y���l���̃X�^���_�[�h�ȃ��f����������̂��A�A���b�T���h���ł����B���v�̋�̍�͓�B��͋�������郌�`�^�e�B�[���H�Ɖ̏��͂��֎�����A���A�̊������K�肷�邱�ƁB������̓A���A�̌`���A�u�_�E�J�[�|�E�A���A�v�ɓ������邱�Ƃł����B"�_�E�J�[�|"�Ƃ͓�����̈Ӗ��B�`�a�Ƃ��āA�a�̍Ō��D�DC�D�ƑłA����Ɠ��ɖ߂��Ă`���J��Ԃ��ďI���B�����`�a�`�Ƃ����O���`���ɂȂ�B���ꂪ��Ƀh�C�c�Ŋ��������u�\�i�^�`���v�̑b�ɂȂ�̂ł��B�\�i�^�`���́m���\�W�J���|�Č����n�Ƃ���3�̕������琬�藧���Ă��āA���炩�ɂ��́u�_�E�J�[�|�E�A���A�v�̌`���W���������́B�������h�C�c�l�́A"���̌ւ�ׂ��`���̓C�^���A�Ɍ���������"�ȂǂƂ́A�����Ă�����Ȃ��B���̕ӂ̌��́A�킪�h������Έ�G�搶�́u�����y�j�v�i�V���Ёj�ɏڂ����̂ŁA�悩������ǂ�ł݂Ă��������B�D�G�Ř_���I�ł͂��邪�r���I�ȃh�C�c�l�̊�{�I�Ȑ��_�\���������Ă��܂��B�����_����`�ƃQ���}�������ŗD�ʂ�W�Ԃ��ē˂��������i�`�X�̖\�����A���̂�����ɉ���������̂ł́A�Ƃ����C�ɂ������܂��B
�h���j�R�́A���A���b�T���h�����特�y�̎�قǂ����A���X�Ɏ��͂�~���Ă䂫�܂��B1701�N�A16�̂Ƃ��ɂ͒n���i�|���̉��{�I���K���t�ҥ��ȉƂɔ��F����A�E�Ɖ��y�ƂƂ��Ė{�i�I�ȃX�^�[�g���܂����B����AJ�DS�D�o�b�n��1703�N7���ɂ̓A�����V���^�b�g�̐V����̃I���K�j�X�g�ɏA�C���Ă��܂��B������܂��Ƀo�b�n�̃v���Ƃ��Ă̏o���_�i����Ɉ���ŁA���̋���́u�o�b�n����v�ƌĂ�Ă��܂��j�B��l�Ƃ��L�����A�̃X�^�[�g�͋���̃I���K���t�҂������̂ł��ˁB
�h���j�R�́A���̌�1709�N�A���|�[�����h���܃}���A�E�J�V�~�[���̔���ă��[�}�Ŋ������܂��B���̎����ނ́A�i�|���y�h�̍�ȉƂƂ��āA���X�̃I�y�����㉉���Ă��܂��B�������i1708�N�j�AJ�DS�D�o�b�n���A�ŏ��̒������C�n���C�}�[���Ɉڂ��Ă��܂��B�̂����ă}���A�E�J�V�~�[�������[�}������Ƃ��A�p�g�����������p�����̂��A�|���g�K���̃f�E�t�H���e�X���݁B�h���j�R�́A1719�N�A34�̂Ƃ��A�t�H���e�X���̈����Ń��X�{���̑�i��������̊y���ɏA�C�A�����Ƀ|���g�K�������}���A�E�o���o���̉��y���t�ƂȂ�܂����B���̃}���A�E�o���o���Ƃ̏o������A�h���j�R�̈Ȍ�̐l��������t�����^���̏o��ł����B�}���A�E�o���o���Ƃ����AJ�DS�D�o�b�n�̍ŏ��̉�����̖��O�B�ǂ��܂ł����̂��铯���̓�l�ł��ˁB�h���j�R�́A1728�N�A�����43�ōŏ��̍ȃ}���A�E�J�e���[�i�ƌ������܂��B
1729�N�A�����}���A�E�o���o�����X�y�C���c���q�t�F���i���h�ƌ�������ƁA�A���b�T���h�������s���ăX�y�C���E�}�h���[�h�ɈڏZ�A�I�����̒n�ʼn߂����܂����B�c�܂̉��y���t�Ƃ��āB����́A�c�܂����t�Ƃ��Ẵh���j�R�h���A���̉��y���������ł��傤�B�i�|���ɐ��܂�A���[�}�A���X�{���A�}�h���[�h��3�̒n�ɕ��C�����h���j�R�E�X�J�����b�e�B�B�A�C�[�i�n�ɐ��܂�A���C�}�[���A�P�[�e���A���C�v�c�B�q�Ƃ�͂�3���������_�Ɋ�������J�DS�D�o�b�n�B�C�^���A�l�ƃh�C�c�l�̈Ⴂ��������A���N���܂�̂ӂ���̐��U��H���Ă݂�ƁA�����ɂ��ӊO�ȋ��ʓ_�����o�����Ƃ��o���܂��B
�}�h���[�h�Ɉڂ�Z��ł���̃h���j�R�̐l���́A�}���A�E�o���o���̐�C���y���t�Ƃ��Ă̐F���������Z���Ȃ��Ă䂫�܂��B�����̋{�쉹�y�Ƃ͕K���I�y�������������̂ł����A�h���j�R�����Ƃ��ď����Ă��Ȃ��̂��A����𗠕t���Ă��܂��B�ޏ��Ƀ`�F���o���������A�\�i�^�������̂��ނ̐����̂��ׂĂł����B�u�\�i�^�v�isonata�j�̌ꌹ�̓C�^���A��� sonare�ŁA�����"�y��őt�ł�"�Ƃ����Ӗ��B���������ăX�J�����b�e�B�̃\�i�^�́A�h�C�c�ÓT�h�Ō�����K�͂Ȍ`���ɂ��u�\�i�^�v�ł͂Ȃ��A"�y��i�`�F���o���j�őt�ł鉹�y"�Ƃ����y���Ӗ������Ȃ̂ł��B���݂ɁA���Ό�́u�J���^�[�^�v(cantata)�B"�̂�"�Ƃ����Ӗ���cantare���ꌹ�ł��B
�h���j�R�́A���ď��N����ɁA���ɘA����ăt�B�����c�F�Ƀ��f�B�`�Ƃ�K�₵�Ă��܂��B���f�B�`�Ƃ́A���킸�ƒm�ꂽ�A���l�T���X�̒��j�ƂȂ����C�^���A�̖���B�ړI�̓��f�B�`�Ƃւ̏A�E�ŁA����͊����܂���ł������A�ނ͂����ŋM�d�ȑ̌������܂����B�����ɂ̓`�F���o�����̖��E�l�o���g�����[�I�E�N���X�g�t�H�[�������܂����B�ނ̍�����ŐV�̃`�F���o����17�̃h���j�R�𖣗����A��̃\�i�^�̍�Ȃɑ傫�ȉe����^�����̂ł��B�܂��A�N���X�g�t�H�[���͂��ꂩ�琔�N��A�`�F���o�������ǂ��āu�s�A�m�E�t�H���e�v���B���ꂪ�����̃s�A�m�̎n�c�ƂȂ�܂����B
�h���j�R�́A���U��555�Ȃ��̃\�i�^������Ă��܂����A�����͂��ׂă}���A�E�o���o���̂��߂ɍ�Ȃ������̂Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�ޏ����e�����߂ɁA�ޏ��ɕ������邽�߂ɁA�ޏ���������߂ɁA�������ƃ\�i�^���������̂ł����B���U��������l�̏����̂��߂����ɁA����̍˔\�̑S�Ă��Ԃ��āA�삵�����̃\�i�^�������グ���A����Ȏ���͉��y�j�̂ǂ��ɂ���������܂���B���ꂼ�E�l�̈�O���Ƃ��킸���ĉ��ƌ`�e��������̂ł��傤�B�}���A��o���o���ɏo�����34�Έȍ~�́A���̐l�̂��߂Ƀ\�i�^���������Ƃ��A�����̂ɂ��ς���������т������B�����āA����ȏ�̂��Ƃ͑S�����߂��ɁA���̋������y���̂ł��B
�����Ȃ����b�p�����̎q���ɐ��܂�A��Ɋ��Ɛ킢�Ȃ���A�l�X�ȃW�������ɂ킽������̖��Ȃ𐢂ɑ���o����J�DS�D�o�b�n�B�i�|���y�h�̋����Ɏ����A�}���A�E�o���o���Ɖ^���̏o������Ă���́A�ꐶ�U�ޏ��Ɋ��Y���A�\�i�^�Ƃ����B�ꖳ��̃W�������Ɍ��肵�āA�D��ɐl���𑗂����h���j�R�E�X�J�����b�e�B�B�����N�̓�l�́A���ʍ����������邯��ǁA���̐l���̐F�����͎��ɑΏƓI�ł��B
�h���j�R��X�J�����b�e�B�̃\�i�^�́A�S�Ă��P��y�͂̍�i�ŁA�`���I�ɂ͂قƂ�ǂ��`���A���t���Ԃ���Ȃق�2�|5�����x�ƒZ�����̂ł��B����Ȏ��Ԃ̒��ŁA�R��I�Ȑ����A���т₩�Șa���A��_�ȕs���a���A�]���̖��A���������Y���Ȃǂ��A���ꂼ��e�y�ȂɎU��߂��A�L���ő��ʂȍ�i�Q���`�����Ă��܂��B�R��I�����̓C�^���A���A���Ɍ���錃�������Y���̓X�y�C�������������A�X�J�����b�e�B�̐��U�𓊉e���Ă��邩�̂悤�ł��B
�C�V������́A���T�C�^���̃v���O�����ɁA�X�J�����b�e�B�̃\�i�^��2�ȓ���Ă��܂��B�A�b�v�E�e���|�̃n�����ƃX���[�ȃj�Z���B�ΏƓI��2�Ȃ̓��e���A�v���O�����E�m�[�c������p���Ă݂܂��傤�B
(1)�\�i�^ �n���� K�D159����́A�\�i�^�����i�H�j�ȃV���[�x���g���A�ӔN���̘g���͂����ď���������u4�̑����ȍ�i90�v�Ƀ����[���܂��B
�@�\���͓`���B�`���ɏo��y���őN���Ȏ�肪�A�ω����Ȃ���Ō�܂œ����e���|�ŋ삯�����܂��B��2���ɓ���ƁA�Z����肪�o�ꂵ�܂����A�܂������ɓ]���A�Ȃ���܂��B���т₩�ő����e���|�̃p�b�Z�[�W�ɁA�]���ɂ�鈣�����▭�Ƀu�����h����āA�ȂɓƓ��̉A�e��^���Ă��܂��B
(2)�\�i�^ �j�Z�� K�D9
�@���V�ȒZ����肪�A�܂�ŏM�̂̂悤�ɗ���A���ɂ��т��тƂ�������������Ȃ���A�J��Ԃ���܂��B�㔼�́A�����œ���܂����A�߂܂��邵���]�����d�ˁA�Â��ȗ���ŋȂ���܂��B�u�p�X�g���[���v�̈��̂�����悤�ɁA���₩�ȐÂ������S�̂���ł��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@
�C�V���݂� �s�A�m�E���T�C�^���`Romance�ւ̗U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��F 2009�N11��14��(�y) 15�F00�J���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ���F �i�s�A�[�g�z�[�� �A�t�B�j�X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�D�X�J�����b�e�B�@�@�\�i�^ �n���� K�D159
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �\�i�^ �j�Z�� K�D9
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�D�V���[�x���g�@�@�@4�̑����� D�D899 Op�D90
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�D�u���[���X�@�@�@�@�����cOp�D39
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�D�t�����N�@�@�@�@�@ �O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K
���₢���킹�F memusicoffice@mihoebihara.com
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
2009.07.20 (��) Romance�ւ̗U���@�u�Z�U�[���E�t�����N��̊�v
��������A�t�����N�����グ���̂́A���m�̃s�A�j�X�g�C�V���݂ق��A���H�̃��T�C�^���ŁA�ނ̍�i�u�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v��e����邩��ł��B�C�V������̓\���Ɏ����y�ɁA�����݂̂Ȃ炸�A�����J�E�C�M���X�ȂǁA���ۓI�ɕ��L����������Ă��܂��B����Ă�킸�y�Ȃɐ^���ʂ�����g�ސ^���ȃs�A�j�X�g�B���x�ȃ^�b�`�Ɩ��������ꂽ�e�N�j�b�N�ŁA�X�P�[���̑傫���u�₩�ȉ��y�����o���Ă䂫�܂��B���T�C�^�������y���݂ɁB�ڍׂ͊��������Q�Ƃ��������B�u�勶���ȁv�u�ؗ�Ȃ�ϑt�ȁv�u�p�����̂ɂ��ƂÂ��l��A�e�ȁv�u�G�N�X�E���E�V���y���̑z���o�v�E�E�E�����͂����ȉƂ̊y�ȃ^�C�g���ł��B�����ɂ��A�h��ȃe�N�j�b�N�ʼn��t���ʂ�_�����ȁA�ƌ����܂����E�E�E�B���͂���A����̃e�[�}�A�Z�U�[���E�t�����N���Ⴉ�肵���ɍ�����s�A�m�Ȃ̃^�C�g���Ȃ̂ł��B
�Z�U�[����I�[�M���X�g��W�����E�M���[������x�[���E�t�����N�́A�h�i�ȃJ�g���b�N���k�Ƃ��āA����̃I���K�j�X�g���߂Ȃ���A�l���̍Ō�ł��̍˔\���J�Ԃ��A���Ȃ��c������ȉƁB���̃C���[�W�́A�n���A�����A���ȓI�A�֗~�I�A�@���I�A�Ӑ��^�A�w�͌^�A�ȂǂȂǁB����ɑ��A�`���̃^�C�g������́A�h��A�O�ʓI�A����Z�I�A������̃C���[�W�������A����̓��X�g���v�킹��L�����B�����ł��A�t�����N�͂܂����X�g�̂悤�ȃs�A�j�X�g��ڎw�������y�Ƃ������̂ł��B
�i�P�j �j�R�����W���Z�t�̖�]
�t�����N�̕��j�R�����W���Z�t�́A�x���M�[�̓����[�W���̕n�������s���ł����i�s�A�m�̘r�O�͂Ȃ��Ȃ��������悤�ł��j�B1822�N�ɐ��܂ꂽ�Z�U�[�������y�I�˔\�������ƁA�R���T�[�g�E�s�A�j�X�g�Ɉ�Ă悤�Ƃ��܂��A���X�g�̂悤�ȁB���X�g�́A1819�N8�̎��ɂ͌��J�̉��t����J���A�t�����N�����܂��O������ɐ_���Ɛ��߂��Ă��܂����B�����̃��@�C�I�����e���ƈ���ꂽ���̃p�K�j�[�j���A�E�B�[���ň�T�ԃR���T�[�g����������̉҂��́A�V���[�x���g���ꐶ�������ē����������y�Ȃ������قǂƂ����Ă��܂��i�N���ǂ��v�Z�������͒m��܂��j�B���ƂقǍ��l�Ƀ��B���g�D�I�[�\�i����Z�I���t�Ɓj�̉҂��͍�ȉƂƂ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǂł����B�܂��Ă�X�g�ł�����A���̉҂��͂ƂĂ��Ȃ����̂������ɈႢ����܂���B���̗l�q��ڂ̓�����ɂ��Ă����n�R��s���̕��e���A�˔\���鑧�q�����X�g�̂悤�ȃs�A�j�X�g�Ɉ�ĂĈ�ׂ��������A�Ɗ�ނ͖̂�������ʂ��Ƃł����B�ł́A����ɑ��Ďq���͂ǂ������������H
���[�c�@���g�́A5�̂Ƃ��ɂ͂��łɁA���e�ɘA����ă��[���b�p�e�n�ɏo�����Ă���̂ŁA���ꂪ������O�̐����Ǝv���Ă����B�{��̎�̕���������̖������������x�[�g�[���F���́A���ʋ��t�Ƃ��āA10�̍��ɂ͂�����Ƃ̑单���Ƃ��Ċ撣���Ă����B����}�������X�[�p�[�X�^�[�A�}�C�P���E�W���N�\���̏ꍇ�́A���Y���^�ŕ��e�����邱�ƂŁA�c�N����Ɏ��s�҂̕������B�l�����낢��A���q���F�X�ł��B
�Z�U�[���͂Ƃ肠���������q�������B�n���ł��ƂȂ������i�ł������A���e�̊��҂���g�ɎĊ撣�����B���X�˔\�L�����������N�́A1833�N�A11�̂Ƃ��ɂ̓s�A�j�X�g�Ƃ��č������t���s���s���܂łɂȂ�܂����B34�N�n���̉��y�@�𑲋Ƃ����35�N�ɂ͈�Ƃ������ăp���ɈڏZ�i��Ƃ̊��҂̑傫�����`���܂��j�A37�N�ɂ̓p�����y�@�ɓ��w�B38�N�̃s�A�m�����ł͖��_�Ώۂ���܁A40�N�ɂ̓t�[�K�ő�ꓙ�܂��l���B�����̗���͂��ׂĕ��e�̍єz�ɂ����́B�Ƃ��낪���ꂪ���̌�Z���Y�ނ̂ł��B
�i�Q�j ���Ƃ̌��ʂ��猆��̔ӔN��
�Ԃ̓s�p���ʼn��y���w�Ԃ����A�ނ̋����͂ǂ�ǂ��ȂɌX���Ă䂫�܂��B�ڎw���́u���[�}�܁v�B���̏܂́A1663�N���C14�����n�݂����|�p�Ƃ̗��ɑ��鏧�w���x�ŁA���y�܂�1803�N�ɒlj�����A�p�~�����1968�N�܂ŁA�t�����X�l��ȉƂ̓o����ƂȂ��Ă������Ђ���܂ł��i��҂ɂ́A�x�����I�[�Y�A�r�[�[�A�h�r���b�V�[�ȂǁA�B�X����l���������܂����A�T�����T�[���X�A�t�H�[���A�����F���Ȃǖ�킸�ɑ听������ȉƂ����܂��j�B���āA���q���u���[�}�܁v��ڎw���Ă���ƒm�������e�͑匃�{�B�u��ƂňڏZ�܂ł��Ă��O���p�����y�@�ɓ���Ă�����͉̂��̂��߂��Ǝv���Ƃ��B���ɂȂ���ȂȂǂƂ��ƂƎ~�߂āA�R���T�[�g��s�A�j�X�g�ɐ�O�����v�ƌ����āA�����Ɋw�Z�����߂����A�x���M�[�ɘA��A���Ă��܂��̂ł��B�t�����N20�A1842�N�̂��Ƃł����B���W���Z�t�̓x���M�[�����Ŏ����̂Ă𗊂�ɃR���T�[�g��g�݁A������葧�q���X�e�[�W�ɗ������܂��B���炭�͊����𑱂��܂����A�������C�ō�ȉƎu�]�ɕς���Ă����Z�U�[���̃X�e�[�W�́A�s�A�m�̐\���q���X�g�̖��͂ɂ���Ԃׂ����Ȃ��A�q�͐���オ�炸���e�̖��͏��X�Ɉނ�ł䂫�܂��B������44�N�A�Z�U�[���͉��y�@�ɖ߂�A48�N�ɂ͌����A�����ŕ��e�Ɛ����Ɍ��ʂ��Ă��܂��̂ł��i�������@�ɕ����ꂷ��̂́A���[�c�@���g�̃P�[�X�ɂ悭���Ă��܂��j�B��͂�A�q����e�̃G�S�ʼn���������̂͂悭�Ȃ��̂ł��ˁB
���̌�Z�U�[���́A����̃I���K�j�X�g�Ƃ��Đ��v�𗧂ĂȂ���A�D���ȍ�ȂɏW�����܂��B����Ƃ��̓I�y���������܂����A�I�y���n�E�X�͎��グ�Ă���Ȃ��B�܂�����Ƃ��͍Ȃ̊��߂ŋ���y�������܂����A�����Ƃ͌�����o���B�u���[�}�܁v�̎��i����N��30���߂��Ă䂫�܂��B�ʔ����̂̓s�A�m��i�B1845�N�́u�R�̂Ȃ����݂��Ɓv�ȗ��v�b�c���Ə����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B���炭���������������e�Ƃ̂�����݂��L�b�p���ƒf���肽�������̂ł��傤�B������53�N�ɂ͉ߘJ�̂��ߍ�Ȃ𒆒f���Ă��܂��܂��B
1858�N�A�p���̓T���E�N���e�B���h����̍������ɂȂ��č�Ȃ��ĊJ�B�u�U�̏��i�v�Ȃǂ̃I���K���ȁA�u3���̃~�T�v�A�u�V�g�̗Ɓv�A�u����n���v�Ȃǂ̋���y�A�u�o�x���̓��v�u�W�̍K���v�Ȃǂ̃I���g���I�ȂǁA���̎����́A�E�Ƃf������i������ł��܂��B1866�N�A�u�U�̏��i�v�̃I���K�����t�������X�g���u�o�b�n�ȊO�ɕ��Ԃ̂��Ȃ���i�v�ƌ��܂��������ł����A����͓����̑傫�Ȍւ肾�������Ƃł��傤�B�ł��܂��㐢�Ɏc�閼��͒a�����Ă��܂���B
��Ȃō˔\���J�Ԃ����͔̂ӔN�̂��ƁB�u�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v(1884)�A�u�����I�ϑt�ȁv(1885)�A�u�O�t�ȁA�A���A�ƏI�ȁv�i1886)�A�u���@�C�I�����E�\�i�^ �C�����v(1886)�A�u������ �j�Z���v(1888)�A�u���y�l�d�t�� �j�����v(1890)�A�u3�̃R���[���v(1890)�Ȃǂ̌���́A���ׂ�60���߂��Ă���̍�i�ł��B���ł��u���@�C�I�����E�\�i�^�v�́A��ނ̂Ȃ��������ƝR��ƋC�����Ƃ��ӑR��̂ƂȂ����A�Í��̃��@�C�I�����E�\�i�^���̍ō���ł����A�u������ �j�Z���v�̓h�C�c�I�d�����ƃt�����X���F�ʊ����A���U�Nj������z�`���̒��ŁA�ō��̊����x�������Č��������t�����N���ɂ̍�i�ł��B�������A�������ڂ������̂́u�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v�ł��B���̋Ȃ���1845�N�ȗ��قƂ�Ǐ������Ƃ̂Ȃ������s�A�m�Ȃ̑��Ȃ̂ł��B
�i�R�j�u�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v�ƊC�V���݂كv���O����
�t�����N�v�X�̖{�i�I�s�A�m�ȁu�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v�́A1884�N�A62�̂Ƃ��ɍ���܂����B1845�N�ȗ��ł�����Ȃ�Ɩ�40�N�Ԃ�ƂȂ�܂��B�s�A�m�ɑ���g���E�}�������ɋ��������̏ł��傤�B�[���ł��Ȃ����B���g�D�I�[�\�ւ̓��ɂǂ��܂ł��Ŏ��������e�ւ̑����������܂ŁA���̐^�ʖڂŕs��p�ȉ��y�Ƃ́A�ŔӔN�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂�������܂���B�܂��A�s�{�ӂȋȂ��������Ă��Ȃ������s�A�m�Ȃ������ő������Ă������������̂�������܂���B������ɂ��Ă����̋Ȉȍ~�A�t�����N�͌���̐X�ɕ��������Ă䂭���ƂɂȂ�̂ł��B
�Ȃ�3�̕����ō\������Ă���A�x�݂Ȃ����t����܂��B�u�O�t�ȁv�ł́A�A���y�W�I���čŏ��Ɍ���铮�@�iJ�DS�D�o�b�n�u�����̃t�[�K�v��"BACH"���@�ɍ������Ă��܂��j�𒆐S�ɁA�t�[�K���������āA�]�����Ȃ���y�z������オ��A�N���C�}�b�N�X���}���܂��B�u�R���[���v�ł́A�h�i�ȃR���[���������Z����3�x�o�Ă��܂����A���̊Ԃɓ������}���傪����"�R���[�����z��"�̗l����悵�Ă��܂��B�����u�t�[�K�v�͂��Ȃ蒷��Ȃ��́B�������ƔM���ۂ��A���₩���Ɨ͋����A�߂܂��邵���Ɨ������ȂǁA�������銴����R�ȗ���̒��ő��Â��Ă��܂��B���x���Ăяo�����R���[�������́A�Ō�ɂ͒����ɓ]���A���X�ƋȂ���܂��B���̋����̓I���K���ɁA���̐��_�͌h������o�b�n�ւƌq�����Ă���悤�ł��B�܂��A�u�O�t�ȁv��u�R���[���v�̒��Łu�t�[�K�v�̎����Î�������A�u�t�[�K�v�ɂ����āA�R���[���������O�t�Ȃ̃��`�[�t�ɗ���Ō����ȂǁA�t�����N�ӔN�̌���ɋ��ʂ����u�z�`���v�̎�@�������B�ꂵ�Ă��܂��B
�t�����N�ɂ͓�̊炪����܂����B��͎Ⴂ���냔�B���g�D�I�[�\��ڎw���Ċ���Ȃ��R���T�[�g�ɖ������Ă����Ƃ��̕s�{�ӂȊ�B������́A�ӔN�A�S�Ă�������Đ^�̍�ȉƂƂ��Č�����c�����{���̊�ł��B���̋��ڂƂȂ����̂��s�A�m�Ȃ̌���u�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v�Ȃ̂ł��B�t�����X�̖��s�A�j�X�g �A���t���b�h��R���g�[�́A�u�w�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�x�����A���l���Ɏ����Ă䂫���������Ȃ��y���̈�v�ƌ����Ă��܂��B
�C�V������͂��̋Ȃ����T�C�^���̍Ō�ɒu���Ă��܂��B���T�C�^���̃T�u��^�C�g���́uRomance�ւ̗U���v�B���{��Łu���}���X�v�Ə����Ƃ��ʑ��I�ȓ��������܂����A�p��̢Romance��ɂ͓��ۂƂ������o���t������āA�v���O�����Ƀs�b�^���ƛƂ�܂��BD�D�X�J�����b�e�B�Ɏn�܂��āA�V���[�x���g�A�u���[���X���o�ăt�����N�Œ��߂�Ƃ����v���O���������ɖ��͓I�ł��B�Ȃ��Ȃ�e�X�̊y�Ȃ������Ȃ����łȂ����Ă��邩��ł��B�Ⴆ�A�t�����N���h�����A�u�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v�̑�1�y�͂Ńe�[�}�Ɏg����J�DS�D�o�b�n��D�D�X�J�����b�e�B�Ɠ��N���܂�Ƃ��A�ȂǂȂǁB���T����A�����Ȃ�������J��Ȃ���A�����[�����Ţ�C�V���݂� Romance�ւ̗U���v�V���[�Y��A�ڂ��܂��B����́A�u�h���j�R�E�X�J�����b�e�B��J�DS�D�o�b�n�͓����̍��v�ł��B�ǂ������y���݂ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@
�C�V���݂� �s�A�m�E���T�C�^���`Romance�ւ̗U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��F 2009�N11��14��(�y) 15�F00�J���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ���F �i�s�A�[�g�z�[�� �A�t�B�j�X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�D�X�J�����b�e�B�@�@�\�i�^ �n���� K�D159
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �\�i�^ �j�Z�� K�D9
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�D�V���[�x���g�@�@�@4�̑����� D�D899 Op�D90
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�D�u���[���X�@�@�@�@�����cOp�D39
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�D�t�����N�@�@�@�@�@ �O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K
���₢���킹�F memusicoffice@mihoebihara.com
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
�C�V���ٌ݂����T�C�g�@http://mihoebihara.com/ja/blog/index.html
2009.06.29 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�R
���������āA���A���������͗g�������L�����Ȃ̂��A�ߋ����D�]�������������̂́u���яG�Y���a��v�u�g�c�G�a���a��v�ȂǁA���|�I��"�l�a�胂�m"�ł����B���ݘA�ڒ��́u�Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��v�����̃W�������ɓ���̂ŊT�ˍD�]�Ȃ̂ł����A���ʁA�u������Ɛ��ʂ邢��Ȃ��́A�����ƓO��I�Ɏa���Ă�v�Ƃ����������Ȃ��炸�����Ă���܂��B�ʂɎ���ɂ߂Ă������͂Ȃ��̂ł����A�ނ͉��y�I�ɂ͑f�l�Ȃ̂ŁA���сA�g�c���搶�ɑ���قǔR���ĂȂ��̂������ł��B�Ƃ͂����A�Ζؐ搶�̂��̂Ƃ���̏o�����l�́A��ڂɗ]��̂ŁA�ŏI��̍���͑����h���ɓ]���Ă݂܂��傤���E�E�E�B�i�T�j���g�[�}�X����
�o�b�n�́A1723�N����S���Ȃ�1750�N�܂ł̊ԁA���C�v�c�B�q���g�[�}�X�����14��̃J���g���Ƃ��Ċ��܂����B�J���g���͕���"������"�Ɩ�܂����A������̎s�̉��y�ēł���A���T�����ɏ]���ăJ���^�[�^�̍�ȁE���t���s���Ȃǂ��̔C���͑��Z���ɂ߁A����y�𒆐S�ɕ��L�����y�������s���܂����B�o�b�n��^�҂́A�u�o�b�n�͂��̐M�S����ӔN�̕��C�n�����C�v�c�B�q�ɒ�߁A�_�̌�S�ɏ]���ď@�����y�̍�Ȃɐ�O�����v�Ɣ������܂Ƃ߂悤�Ƃ��܂����A���ۂ̎���͂��Ȃ�Ⴄ�悤�ł��B���̕ӂ̌��͍���̎�|����O��܂��̂ŏȂ����Ă��������܂��B
���āA�Ζؐ搶�́A�����I���ɋ߂Â���������A���g�[�}�X����̑O�ɘȂ�ŁA�����q�ׂĂ����܂��B
�u�����̎�v���̐Α���̕������́A����Ƃ������̂��S�ɂǂ̂悤�ȍ�����c�����Ƃ����������̊ϔO�ɂ��ꂢ�ɓK�����Ă���B����A���𒆐S�Ƃ������������́A�u�ތ��v���́u�n���v�A�u�s�ʁv���́u���i�v���|�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ŁA��X���������I�Ȉ�ۂ�^�����B���̃R���g���X�g�B�܂�ŐΏ�̓s��𗣂�ė��ӂ��x�O�̋u�ɗV��ł��邩�̂悤�ȁA����Ȃ��������Ƃ����S�̓����������N�������B�o�b�n�͂��܂��܂Ȋ�����l�������B����ł́w�}�^�C���ȁx��w���Z���~�T�ȁx�̂悤�ȍ\���̑傫���@���Ȃ����A�����ł́w�R�[�q�[�E�J���^�[�^�x�̂悤�ȋY��ɖ����������Ȃ��c�����o�b�n�B���̓��X�̎d���̏�Ƃ��āA�ڂ̑O�Ɍ����g�[�}�X����͂����ɂ��ӂ��킵�������B�v�搶���A���g�[�}�X����̐����̐Α���Ɠ��̃N���[���F�̃R���g���X�g�����m���āA"�s��"��"���i"�Ƃ�������������̂Ɏv����y�����̂́A�܂��A����悤�ȋC�����܂��i�ʐ^�����������ł����j�B�������A������A�o�b�n��i�̑��l���Ƀ����N�������̂́A�������Ȃ��̂ł��傤���B���ꂪ�o�b�n���L�̂��̂���������͂���܂���B�ł��A����́A�o�b�n�Ɍ��炸�Í��̑��ȉƂȂ�N�ł������Ă�������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�Ⴆ�A�u�G���[�[�̂��߂Ɂv�Ɓu���v�̃x�[�g�[���F���A�u�X�J�g���W�[�E�J�m���v�Ɓu�h���E�W�����@���j�v�̃��[�c�@���g�A�u�q��́v�Ɓu�h�C�c�E���N�C�G���v�̃u���[���X�A�u�W�[�N�t���[�g�q�́v�Ɓu�w�v�̃��[�O�i�[�ȂǁA���ꂼ��ɑΔ�ۗ��D�Ⴊ���т܂��B�u�R�[�q�[�E�J���^�[�^�v�Ɓu�}�^�C���ȁv�̑Δ�Ɋ��Q���Ă���悤�ł́A������Ɖ��y�j�̕�������Ȃ��̂ł͂ƐS�z�ɂȂ�܂��B
���j�Ƃ����A�}���e�B������^�[��1539�N5��25���A����~�Ր߁i�y���e�R�X�e�j�ɁA���̐��g�[�}�X����ŗ��j�I�ȉ����������̂�搶�͂����m�ł��傤���B
���^�[�ƃ��C�v�c�B�q�̊W�ɂ͐[�����̂�����܂��B1521�N�A���H�����X�鍑�c��Ń��^�[���ْ[�҂Ƃ��ꂽ���Ɠ�����̂́A�U�N�Z���E���C�v�c�B�q�̃��@���g�u���N��B���̌�����^�[�̓U�N�Z���I��狭�͂Ȕ���A���v�𐄂��i�߂Ă䂫�܂����B���̐^�����ōs�����̂��u�g�[�}�X����̐����v�ł��B���v�Ɏ艞���������Ă������^�[�́A����̐M�O�Ɋ�Â��A���[�}�E�J�g���b�N�x�����A�v���e�X�^���g�̗��O��͋��������܂����B���̉����ɂ���ă��C�v�c�B�q�̓��^�[�������̉p�Y�Ƃ��ĔM���I�Ɍ}�����ꂽ�̂ł��B
�u���̃����[�v�����̗��̎�v�e�[�}�Ȃ�A���̃��C�v�c�B�q�ł̃��^�[�ƃo�b�n�̌���I�Ȍq����������Ƃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���̂ł��B�o�b�n���̋���ɘȂ�ŁA���y�j�I�펯����X���ʎ����āA"�����ɂ��ӂ��킵������"�Ȃ�Ē��C�Ȋ��S�ɒ^���Ă���ɂ���������A���̎j������������Ɣc�����Ă��ė~���������B�����������n�ɍs���Đ^�������悤�Ƃ���Ă���̂ł�����B
�i�U�j�u���Ƃ����v���C�ɂȂ���
�Ō�ɂ�����A�C�ɂȂ�ӏ����u���Ƃ����v�ɂ���܂����B�搶�͂����q�ׂ��Ă��܂��B
�u�������A����Ȃ��Ƃ��������B�����ɖ߂��Ă��炭���Ă���A�o�b�n�́w�S�[���h�x���N�ϑt�ȁx�����B�����X���钆�ŁA�S�̒��ł̉��y�̋��������A����̃h�C�c�̓~�̗��̑O�Ƃ͂�������قȂ��Ă��邱�Ƃɖڂ��[�����ꂽ�̂ł���v�搶�́A����"�h�C�c���s�̌�ł́u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�̋���������������قȂ��Ă���"�Əq�ׂ��Ă��܂��B���̋L�q�Ɏ��́u�ǂ�����ĕ����������v���C�ɂȂ�A���҂ŋ��͍���܂����B�Ƃ��낪�A�搶�̋L�q�͂��̂܂܂ŏI����Ă��܂��B"�Ⴂ"�ɂ͂܂������G�ꂸ���܂��ŁB����ɂ͐S�ꂪ�����肵�܂����B����ĕ��������Ȃ�A�ǂ�����Ă����̂���b���Ă���đR��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�S����M�҂�������A�����܂ŏ����ΕK��"��̓I�ɂ́E�E�E"�Ƒ����ď����Ă������̂ł��B�Ȃ������Ȃ����H����͏����Ȃ�����Ȃ̂ł��B�搶�قǕ����̐����ɒ����Ă�������Ȃ�A���m�������Ƃ͕K���������Ă����͂��ł���ˁB���ꂪ�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A"����Ċ�����"�̂�"�����Ȃ�ƂȂ�"�ł����Ȃ������̂ł��傤�B��������������ӂ�����āu�قȂ��Ă��邱�Ƃɖڂ��[�����ꂽ�v�Ȃ�Ĉ̂����ɏ����Ăق����Ȃ��B����ȑԓx�́A�^���Ƀo�b�n���A�u�S�[���h�x���N�v�������������悤�Ƃ��Ă���^�̉��y���D�Ƃɑ�����ł��B
�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�͕s�v�c�Ȗ��͂��߂��Ȃł��B�����̓�͂��Ă����Ă��A�����s���邱�Ƃ͂���܂���B���̍\���͐��k���ɂ߁A���̘Ȃ܂��͉F�����v�킹��[���ȋK�����Ɏx�z����Ă��܂��B�A���A�ɋ��܂ꂽ30�̕ϑt�B���́A1�E4�E7�E�E�E28�A2�E5�E8�E�E�E29�A3�E6�E9�E�E�E30��10�ȂÂ̊e��̎p�B��1��͗l���̕ϑJ�B��2��̓e�N�j�b�N�̓�Փx�B�����đ�3��́A2���̃J�m���̊Ԋu���K��������1�x�Â㏸���鐮�R���B������9�x�܂łŃs���I�h��ł��A10�Ȗڂœ����̂͂��̗l���́u�N�I�h���x�b�g�v��}�����ăA���A�ɂȂ��閭���B���̒���3�ȋ��ɂ��Ȃ���A��̈ӎ��������āA���Ӑ[�������Ȃ��ƁA�o�b�n�̈Ӑ}�������Ă��Ȃ��B�������āA�Ō�ɂȂ�A�F����f�r���Ĕ��ʂĂ�"�]"�ɁA��30�ϑt���}�ɉ����b�ŏ����I�Ȑ����������ė���o���B���̋����A�������g���B�Ȃ��o�b�n�͂����ɂ���Ȃ��̂��H�����ăA���A���A�o�����ƑS�������`�Ō����A���A�^�̈����������ɐ��܂��B�K���I�ɐ��R�ƕω����Ȃ���A�Ȃɂ��ٕ����������āA�f�r��������܂����ɖ߂�i�����B���́A�ŋ߁A���ڂ낰�Ȃ��番�����Ă����悤�ȋC�����Ă��܂��B
�i�V�j�����ꂽ�Βk
�t�������Y�Ƃ������@�C�I���j�X�g�����܂��B���܂苻���̂��鑶�݂ł͂���܂��A����l�b�g�����Ă�����A�ނ����M�����[�ŏo�����Ă���J�|WAVE�̔ԑg�ŁA�Ȃ�ƖΖ،���Y�搶�ƑΒk���Ă��܂����B�������搶�B�e���r��������Ȃ����W�I�ɂ܂Ői�o�Ƃ́B
�t�����u�o�b�n�ɑ��鑢�w�͂����납�炨�����Ȃ̂ł����H�v����ȂA���������m��Ȃ�����Ǝv���āA���������ŞB���ȕ\���ɏI�n���Ă��܂��ˁB������ƃ��J���܂��B�Q�[�f���̂͢��`�����Ȃ��āu�藝�v�ł��B�܂��A����Ȃ��Ƃ��A�������������Ǝv�����̂́A�搶�������"���w����ɓǂ�"�Ƃ������B�z�t�X�^�b�^�[�́u�Q�[�f���E�G�b�V���[�E�o�b�n�`���邢�͕s�v�c�̊v��1979�N�̊��s�B�搶��1962�N���܂�ł�����A17�̂Ƃ��ł���ˁB�A�����J�Ŋ��s����āA�ǂ�Ȃɑ������Ă��A���w����ɂ͊Ԃɍ����܂��ǁB���]�����Ȑ搶���A���w�����Z�����A�Y���͂����Ȃ��ł��傤���B���̌��h�����肪�I �܂��A���Z�ƒ�������Ă������̂ł����A����ɂ��Ă�����œǂ܂ꂽ�̂ł��傤�ˁA���ΐ搶�A������Ȃ��I ��ʂ̓��{�l�����̏��ɒ��ڂ��Ĕ邩�ȃu�[���ƂȂ����̂́A�a���g�Ђ��犧�s���ꂽ1985�N�ȍ~�̂��ƁB�搶�͂��͂��w�@�Ō��s���̂���ł��傤���B�܂��A����œǂ܂ꂽ�搶�ɘa��͕K�v�Ȃ������ł��傤���B
�Ζu���w���炢�̎��Ƀz�t�X�^�b�^�[�̏������w�Q�[�f���E�G�b�V���[�E�o�b�n�x��ǂ�ŁB�Q�[�f���͐��w�Łw�s���S����`�x���ؖ������l�ŁA�G�b�V���[�͗L���ȁw�����K�i�x�̃G�b�V���[�B������o�b�n�̃t�[�K�Ƃ����ɁA�����͐��w�I�Ɏ����\�����Ɓv
�Ƃ͂����A����͐����{�ł��B�}�l�̎��ɂ́A�r�b�N�����邭�炢����Œ���Ȗ{�ł��B���{������ɂƂ��Ă݂܂������A�a�T�T�C�Y��700�y�[�W���z���钴�d�ʋ��B����Ȗ{���A���w�i���Z�j���̂Ƃ��ɁA����������ŁA�搶�͖{���ɓǂ܂ꂽ�̂ł����H
����Ȗ{���A������������̟����ꏬ�m������œǂ�ŁA�ʂ����ė����ł���̂ł��傤���B���҃z�t�X�^�b�^�[���u15�̓��̂����A���ɓǂ�ł��炢�����v�ƌ����Ă���̂͂قƂ�ǟ������A�A�C���V���^�C����z�[�L���X���m�N���X�̎q����Ώۂɂ��Ă���̂��Ǝv���܂���B���������̖{�́A�o�b�n�̓��发�Ȃ���Ȃ��B�����܂ŃQ�[�f���̒藝��v�Z�@�Ȋw��l�H�m�\�����肪���ł����āA�o�b�n�̉��y�́A��������������i�i�q���j�Ƃ��Ă̈�������Ȃ��ł����B�m���Ɂu���y�̕������́v�̃J�m�����A�u�s���S���藝�v��u�����K�i�v�Ɠ����������̏ے��Ƃ��Ď�肠�����Ă͂��܂����A���S�ł͂Ȃ��i�������搶�A�u�t�[�K�v�ł͂Ȃ��u�J�m���v�ł�����A�O�̂��߁j�B���������{����o�b�n�ւ̋����������n�߂�ꂽ�̂ł�����A������Ȃ��B���ȂA���N�������E�̓`�L�u���y�̕��o�b�n�v����ł����̂ˁB�G���[�g�͂���ς�Ⴂ�܂��ȁB
�Βk�͂܂������܂��B
�Ζu����Ɩ����̐l�C�̍��́A���t�̉��y���̍��ɂ���̂ł͂Ȃ����B����̌��t�͉��y�Ƃ��ė͂������āA����Ŏx�����ɍ����o��̂ł���A�����Ƃ݂�ȉ��y���w�ق��������v�ȂႱ���B���l�C��������̂́u�f��I�L���b�`�E�R�s�[�b�@�Ŕ����n�b�L�������b���������āA�n���ȃ}�X�R�~������ɏ��A�o�J�ȑ�O����ꂽ�v�����B�����̐l�C���Ȃ��̂́u�o�J�Ȃ����v�ł��B�搶�A�����Ȃ炢�����ǁA�}�W��������z���g�A�����^���܂����I
���ꂩ��A�t��������A�u���C�v�c�B�q�͖l�s�������Ȃ��āB������o�b�n�����܂ꂽ���ł����A�ǂ�ȂƂ���ł����H�v�͂Ȃ��ł��傤�B�o�b�n�����܂ꂽ�̂̓��C�v�c�B�q����Ȃ��ăA�C�[�i�n�ł���B���E�I���@�C�I���j�X�g�i�H�j���A�o�b�n�̐��n�Ɩv�n�����Ⴆ�Ă͍���܂��B�Ζؐ搶���A�s���Ă�������Ȃ���A�������炢���Ȃ�����B�Q�X�g���Q�X�g������Ǖ������������B�����Ɛ^�ʖڂɂ�ꂥ�[�B���{������j�ď�����B
���̂��Ƃ́A���[�O�i�[�ƃu���[���X�̘b�����ݍ��킸�A�Ζؐ搶�̃R�����g���S�����e�Ȃ������܂����������̕ӂŎ~�߂܂��傤�B�n���n�������̂ŁB�����̂�����́AJ�|WAVE�uANA WORLD AIR CURRENT�v�z�[���E�y�[�W���������������B�E���U�����邱�Ɛ��������ł��B
�ł́A�Ō�Ɉꌾ�B�Ζؐ搶�A�������������A���y�̘b�͎~�߂ɂ��Ă��������܂���ł��傤���B�e���r�����W�I���{���B�����G�ꂽ���̉���}�g���Ȃ��̂͂���܂���ł����B�����ɂ͎��ؐ��_�̌��Ђ��Ȃ��A���̕\���͞B���Ńi���V�X�g�I�M�v�ŏ[�����Ă��܂��B������������A���̂悢���V�����Ƃ��āA�X�N�X�N�ƈ���Ă���ꂽ�̂ł��傤�B�����āA�ǂ�����"�܂₩���^�n�b�^���b�@"��g�ɂ���ꂽ�̂ł��傤�B�u������U��߂Đ����悭�����Ă���A���l�l��"����"�Ƃ������đ��h���Ă������́B�Ⴆ�������������Ă��Ȃ��Ă��v���ĂˁB����Ȓ��q�Ő搶�́A�f�l���y�t�@�����[�ւ��Ă�����肩������܂��A���̂悤�Ȍy����͂��ȃR�����g�ɏI�n����Ă��ẮA�|�p�̖{������������Ɍ���点�錋�ʂ��邾���B���������y���D�҂̑����猩��A�S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��Ȃ̂ł��B��������������A����ȕ��Ƃ��������Ă炵�āA�����́u�]�Ȋw�v�����̎��Ԃ͂���̂ł��傤���B���͂�����̂ق����S�z�ɂȂ�܂��B
���E�t�H���E�W�����l�̃A���o�T�_�[�����̂��A�~�̃h�C�c�ɗ����ĉ��y�̖{�������̂��A�t�������Y�Ƃe�l�ł����肷��̂��A�u�薼�̂Ȃ����y��v�ōu�ߏq�ׂ�̂��A�u���ȒT��A�}�f�E�X�v���D�~�X����̂��A�S�������Ă悵�Ƃ��܂����B�Ȃ�܂��A�{�Ƃ������������Ă���ɂ��Ă������������B��n�߂ɁA�֓��搶�ɕԐM�𑗂��Ă͂������ł��傤���B�����Ƃ�����t�Ɛ��ʂ���ӌ����킹�邱�Ƃɂ���āA�{�Ƃɂ����鎩��̗͗ʂ�����邱�Ƃł��傤�B���ׂĂ͂�������n�܂�܂��B�Ȃ�m�邱�Ƃ���B���̖��ߑ��\����Ԃ́A�搶�̖����ɑ������Č����������炷���̂ł͂Ȃ����Ƃ��A�͂�����Ɛ\���グ�Ă����܂��B�^���ɖ{�Ƃɑł�����ł����A���͊J�����̂ł��B�搶�̂����������F��\���グ�܂��B
2009.06.22 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�Q
�i�R�j�Ζ؎��́u���̃����[�v�̎��ؐ��Ζ،���Y�搶�̒����u���y�̕������́v�ɂ��A�u���^�[����o�b�n�ւ̍��̃����[�v�����m�����̂́A�A�����V���^�b�g�̃o�b�n��������悤�ł��B�����Ńo�b�n�̃I���K���Ȃɐg���ς˂Ă���Ƃ��A�u���̃����[�v�Ɏv���������Ƃ̂��ƁB����̋�Ԃ����o�b�n�̑����ȋ������A���`�̉��v�҃��^�[�̃R���[���i�]���́j�Əd�Ȃ荇�����̂ł��傤�B���ɑA�܂����̌��ł��B���̏�ɂ����Đ搶�̔]���͐����ȃN�I���A�ɖ������Ă������Ƃł��傤�B�搶�́u���̃����[�v�ɂ��Ă̋L�q�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�u�o�b�n����̒��ŁA����̖���ɂ��p�C�v��I���K���̉��t���B�����ԕ�����ɏ�̎��Ԃ̗���̒��ŁA���̋����Ɏ����X���Ă��鎞�Ɉ�̃C���X�s���[�V�������K�ꂽ�B"�����ғI�ȋΕ�""���j�I�ȁu��v""�M�S�̏��Ȃ�䂦""���̋�"������"���̃����["�ȂǁA�Ӗ����肰�Ŏ��G��̂��������������ς�����ł��܂��B�T�����Ɠǂ߂Δ��������͂Ȃ̂�������܂��A�����ۓI�Ŏ��ؐ��ɖR�����B�u���̃����[�v�́A����Ńp�C�v��I���K���̋������Ȃ���M�����悤�ł����A����͒P�Ȃ钼���ł��i�搶��"�C���X�s���[�V����"�Ƌ��Ă܂����ˁj�B�����Ȃ��āu���̃����[�v�Ƃ����̂����T�b�p�������Ȃ��B���c���j�ɂ��A�����̗��Â��̂Ȃ��z������z�Ƃ��������ł����A�搶�́u���̃����[�v�����̋�z�ɋ߂����̂�����B
�l�ނ̐��_�j�̒��ɐ��������V�Ȃ镗�̂悤�ȃ��^�[�h�̐M�B���̂悤�Ȏ���́w�㉟���x�����������炱���A���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�́A���y��ʂ��āw�_�̉h���x�Ɍ��������Ƃ������_�^���ɐ^���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł����B�o�b�n�̋����ғI�ȋΈׂA���j�I�ȁw��x�̉��ł������藧�����B���̉��y������قǂ܂łɉ����ւƎ������̍����^��ł����͂����̂́A���̔w�i�ƂȂ�M�S�̏��Ȃ�䂦�ł���B
�}���e�B���E���^�[�́A����̋V���ɂ����鉹�y�̖������d�������l�ł������B���^�[���g���A��O�ɂ���ĉ̂���w�R���[���x����Ȃ��Ă���B
���^�[����o�b�n�ցB���́w���̃����[�x�ɁA�A�����V���^�b�g�̃o�b�n����̒��Ŏv���������B��l�̓V�˂̊Ԃ��Ȃ����̋��B�t�ł���b�݂ɖ��������ׂ��A�������͍����������Ă���v
���͒����Ƃ����Ƃ��̓�����ے肷����̂ł͂���܂���B�l�Ԃɔ�������L�p�Ȕ\�͂̈���Ǝv���Ă��܂��B������ɂ���������Ƃ��́A�����d�˂��Ō�̎��_�ł���ׂ��ł��B���l�������ɔ[�����邩�ۂ��͎��̋q�ϐ��ɂ������Ă��܂��B��������������̗L���ł��B�搶�́u���̃����[�v���ł͂��̕��������S�Ɍ������Ă���B������A�搶��D���̃t�@���ɂ͂�����������Ȃ����A��ʓI�ɂ͂����ɂ������͂ɖR�����Ƃ��킴��܂���B
�u���̃����[�v�͂��̖{�̊j�S�����ł��B�����炱���A���Ȃ��Ƃ����̕������炢�ɂ͋q�ϓI�����������ė~���������B�搶�قǂ̓��]�̎�����Ȃ�A������Ƃ��̋C�ɂȂ�ł���͂��Ȃ̂ɁA�c�O�ł��B���Z��������̂ł��傤�B���������A���^�[��"�u�V���v�ɂ����ĉ��y���d�R���[��������Ă���"�Ƃ���܂ő����������̂ł�����A��������˂�����ł����������������Ǝv���͎̂������ł��傤���B
�i�S�j�u���̃����[�v�̎��I�l�@
����ł͂��́u���̃����[�v�ɂ��āA���Z�����Ζؐ搶�ɂȂ�����āA�ɂȎ����������Ă��������܂��B�L�C�E���[�h�̓��^�[�̃R���[���ƃo�b�n�̃J���^�[�^�ł��B
����J���^�[�^�̓h�C�c�̃v���e�X�^���g����̗�q���ɉ��t����鉹�y�ł��B��q�ɏW�܂�����O�́A�q�t�̐����ƂƂ��ɃJ���^�[�^�̉��t���܂��B�����͋����Ɋ�Â��čs���܂�����A�J���^�[�^������ɑ��������e�̂��̂ƂȂ�܂��B�Ⴆ�A�~�a���i�N���X�}�X�j�ɂ̓L���X�g�̒a�����A�����߁i�C�[�X�^�[�j�ł̓L���X�g�̕������A�Ƃ�����ɁB�y�Ȃ́A�I�[�P�X�g���ȁA���`�^�e�B�[���H�A�A���A�A����ɍ����ȁA�R���[���i�v���e�X�^���g����̎]���́j�ō\������Ă���̂���ʓI�ł��B
�o�b�n�͋���J���^�[�^��300�Ȉȏ������悤�ł����A���ݎc���Ă���̂�200�Ȃ��܂�B���ł����U�Ō�̕��C�n���C�v�c�B�q�̐��g�[�}�X����J���g���i�������j�̎���ɂ́A�T��Ȃ̃y�[�X�ŏ����Ă�������������܂����B
���^�[�̏@�����v�ɂ�����傫�ȖړI�̈�ɁA"�J�g���b�N����̕��s�𐳂����O�ɐ^�̏@���s�ׂ����߂�"���Ƃ�����܂����B������ܗG��i�ƍߕ��j�̔p�~�Ɨ�q�̉��v�Ɍ���܂��B"�_�̂��ƂŐl�݂͂ȕ���"�Ƃ�����v���O�Ɋ�Â�"���l���J"�̍l���́A��O�̗�q�ł̐ϋɓI�Q���𑣂��A�������킹�Ď]���̂��̂����Ƃ����サ�܂��B���^�[�����y���d�����R���[������Ȃ����̂͂��̂��߂ł��B
���^�[�́A��O�݂�Ȃ��̂���h�C�c��ɂ��R���[����36�ȂقǍ�Ȃ��Ă��܂����A���ł��u�_�͂킪�E�v�iEin feste Burg�j�͍ł��L���ȋȂ̈�B�u�_�͂킪�E�A�킪�������A�ꂵ�߂�Ƃ��̋��������v�Ɛ_�̉h����͋���搂������邱�̃R���[���́A�����̎��ё�46�͂̎��Ƀ��^�[���Ȃ��������́B���̐����̓V���v���ɂ��ė͋����A�܂��ɐ��`�̊v���҃��^�[�̐��_��\�ۂ��Ă��܂��B�o�b�n�͂��́u�_�͂킪�E�v����ɂ��ăJ���^�[�^��80�ԁu���炪�_�͌����ԁv����Ȃ��܂����B
�J���^�[�^�u���炪�_�͌����ԁv��8�ȍ\���B�R���[���u�_�͂킪�E�v�͂��̑�1�ȁA2�ȁA5�ȁA8�ȂɎg���Ă��܂��B��1�Ȃ͍����ő�K�͂ȃR���[�����z�Ȃ̑́B��������t�[�K�̒��Ƀ��^�[�̐��������݂Ȍ`���Ƃ�Ȃ��猻�o���܂��B��2�Ȃ̓\�v���m�ƃo�X�̓�d���B�R���[�������̓\�v���m�E�\���ɂ͂����肵���`�Ō���܂��B��5�Ȃ́u�R���[���v�B�����̃��j�]�����u�������ɖ����ā@�悵�⋺���Ƃ��@���͋��ꂶ�@�_�͖����Ȃ�v�ƃ��^�[��R���[����3�߂�s���̓��u�������ĔM���̂������܂��B�܂��ɋ����ɗ������������v�҃��^�[�s���̐��_�������Ă��܂��B��8�ȁi�I�ȁj�̓R���[����4�߁u�_�͌�S�ƌ�b�Ƃ����ā@��ɂ���ɖ������������v�����炩�ɉ̂��đS�Ȃ����т܂��B
�o�b�n�̓J���^�[�^�u���炪�_�͌����ԁv��10��31�����v�L�O���̂��߂ɍ�Ȃ��܂����B1517�N10��31���A���^�[�̓��B�b�e���u���N�鋳��̕ǂɁu95�����̒v��ł��t���ď@�����v�̈ӎv�������A���ꂪ�S�ẴX�^�[�g�ƂȂ����̂ł��B�o�b�n���A���̃v���e�X�^���g����ŏd�v�L�O���̂��߂ɍ�����J���^�[�^�ɁA���^�[�̃R���[�����g�����͕̂K�R�ł���h�ӂɑ��Ȃ�܂���B
���^�[�u95�����̒v�֘A�̂�����̗�Ƃ��āA�J���^�[�^��79�ԁu��Ȃ�_�͓��Ȃ�A���Ȃ�v����肠�������Ǝv���܂��B���̋Ȃ���͂�@�����v�L�O���̂��߂ɍ��ꂽ��i�ŁA1725�N10��31�����C�v�c�B�q�ŏ�������Ă��܂��B
���̃J���^�[�^��6�ȍ\���B���̑�P�Ȃ͎���84�̑�11�́u��Ȃ�_�͓��Ȃ�A���Ȃ�@��͌b�݂Ɖh���������āA���������ގ҂ɗǂ����̂����݂��������ƂȂ��v��p���Ă��܂��B �P�����������d�ȃI�[�P�X�g���̑S�t���n�܂�Ɠ����ɁA�e�B���p�j�[��8������������ł䂫�܂��B���̑ʼn��͑�P�ȑS�̂ɂ킽���Ė葱���A���̐���300�ł��܂��B���ꂱ�����^�[�����B�b�e���u���N�鋳��̕ǂɁu95�����̒v��ł������Ƃ̉����[���Ă���Ƃ����Ă��܂��B����͑�3�ȂōĂь��ꂽ���ƁA�I�Ȃł�4�������ƂȂ�A�u�v�̌f�����m�M�ւƕς���ċȂ���܂��B
�J���^�[�^��79�ԂƑ�80�ԁB�o�b�n�́A���^�[�̐_�ւ̃L���X�g�ւ̖��O�ւ̏��Ȃ�v�������N���Ȃ���A�������������̂ł��傤�B���^�[�ւ̌h���ƔM���z���B����2�Ȃ̃J���^�[�^���Ă���Ƃ���ȃo�b�n�̋��̓����Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă��܂��B200�N�̎�����āA���^�[�̐��_���o�b�n�ɍ~�Ղ����A���ꂱ���u���̃����[�v�̗�ł��B
����ɂ�����A����͕L���̑��u�~�T�ȃ��Z���v�Ƃ̊֘A�ł��B
����܂ł̐l����ʂ��Ċ����Ă����l�X�Ȋ���A�_�̉h���A�C�G�X�E�L���X�g�ւ̊��ӁA�l�Ԉ��Ȃǂ��A�K�������S�Ă̋Z�@����g���ď����������u���Z���~�T�ȁv�����A�o�b�n���y�̏W�听�ł���ō��̌��삾�Ǝ��͎v���Ă��܂��B
���̖`���u������݂��܂��v�̂Ȃ�Ƃ������悤�̂Ȃ������B�n�̒ꂩ�牽����i����悤�Ȉٗl�ȋ����B�������͂��̏u�ԁA�����ɐ[���ȃo�b�n�̐��E�Ɉ������܂�Ă䂭�̂ł����A���̐������������^�[�́u�h�C�c��~�T�v�̃R���[�������Ɋ�Â����̂Ȃ̂ł��B�u�h�C�c��~�T�v�́A1526�N�A���^�[���l�����q�̂���ׂ��p�����߂Č`�Ɏ��������̂ŁA����ɂ���Ĕނ̏������q���v�̑̍ق������܂����B�܂��Ɂu�h�C�c��~�T�v�����A���^�[�̓T��ɂ����鐸�_��ՂƂ������ׂ����́B�o�b�n�́A���̃��^�[���_�̌���Ƃ������ׂ��R���[���������A�l���Ō�̍�i�Ɉ��p�����̂ł��B
�������́A�����̋Ȃ��Ă���ƁA���^�[����o�b�n�q����C����������{�̎����������܂��B���^�[�̃R���[������o�b�n�̃J���^�[�^�ցA�����ĉ�O�ւƁB�u���C���o�� �_�͂����������v�Ƃ��������������Ă���悤�ł��B���ꂱ�����u���̃����[�v�̕��Ղ̏Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ζؐ搶��"�����̖{���͌���ɍs���Ȃ��ƌ����Ȃ�"�Ƃ���������Ă��܂����A���̑O�ɂ����Ɠ��{�Ŋ�{����������������ė~���������A�����Ƃ�����Ɖ��y���̂��̂��Ăق��������A�������͎v���܂��B���E�t�H���E�W�����l2009�̃A���o�T�_�[�Ȃ̂ł�����B
2009.06.15 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�P
�́A��J������Łu���[�]�v�Ƃ����Ȃ�����܂����B�~�łɂ������Ĕ]�ɃL�^�Ƃ��������Ȃ��̂ł������A���݁u�]�v�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����Ă��]�w�ҖΖ،���Y�搶�ł��B���̊����U��͐��ɖڊo�������̂�����܂����A��ʏT�����t�ɋC�ɂȂ�L�����ڂ��Ă��܂����B�u�Ζ،���Y����̓��̒����S�z�ł��v�Ƃ̃^�C�g���ŁA�֓�����Ƃ������_�ȗՏ��オ���������́B�ł́A���̋L���Ɏ��̍l�@�������āA�ȉ��B�i�P�j�Ζ،���Y�֓���
�Ζ؎��́u�N�I���A�_�v�ɂ���"�l�Ԃ̔F���ƍs���́A�]�̓����ɂ���Ďx�z�����B�����ɂ́u�N�I���A�v�Ƃ������̂̑��݂�����"�Ƃ����B�Ƃ���Łu�N�I���A�v���ĉ��Hqualia�́u���o���v�Ɩ��B�����"�]�����m���鎿��"�̂��Ƃ炵���B�Ⴆ�A�o�b�n�̉��y�����Ƃ��Ɋ�����u�o�b�n�̃o�b�n�炵�����郂�m�v�Ƃ����Ε�����₷���ł��傤���B����ɂ��Ă����o�I�����I
����A�֓����̊w��I���r�_�̓��J���I�v�z�Ƃ��B�W���b�N����J���̓t�����X�̐��_���͊w�҂Łu�l�Ԃ͋�"����"�iMR�DCHILDREN�̃q�b�g�Ȃɂ���܂����ˁj�̏�ɑ��l�Ƃ̊ւ��ɂ����ď��X�Ɏ��Ȃ��m�����Ă䂭���́v����������u���@������̂̎���ɍ\�z���ꂽ���z�̈��v�Ƃ����l�����̎�����B�������҂ɂ���Ċm������鎩�ȁB
�Ζ؎��́u�N�I���A�ɂ���ĉ��l�����܂�B�N�I���A�͐挱�I�Ɍ��肳��Ă���B�v�ƌ����Ă���悤�ł��B�����挱�I���Ȉ��^��̂��肫�̐��E�B
�u�l�Ԃ̉��l�́A�挱�I�Ɍ`�����ꂽ�N�I���A�̏������ɋ���v�Ƃ���Ζ؎��̊T�O�ƁA�u�l�ԂƂ͌��@������̂̎���ɍ\�����ꂽ���z�v�Ƃ���ē����̂���́A�^��������Η�������̂ƌ��Ď��܂��B
�����܂��āA�ē����͖Ζ؎��ɂ����ł��Ăł܂��B
�u�]�Ȋw�v���u���_���́v�����J�̕���ŁA���i�K�ł͉����Ɖ��߂̏W�ςɉ߂����A���͍̏���50�N�͑������낤�B����������A���݂́u�]�Ȋw�v�S�Ă����Ă݂Ă��A�l�Ԃ̎Љ�I�s���ړI�ɐ������邱�Ƃ͏o���Ȃ��͂��ł���B
�Ƃ��낪�A�����̖Ζ؎��̊���Ԃ��f��I�ȕ������́A�܂��܂������n�Ȃ��̕���ɉߏ�Ō�����F����^�����˂Ȃ������B������A���_�Ȉ�̗���Ŕ]�w�ҖΖ،���Y�ɖ₢�����u�]�Ȋw�͐l�Ԃ̎Љ�I�s��������ł���̂��v�ƁB�Βk�`���ł́u���_�摗��̉��₩���n�v�ɂȂ肻���Ȃ̂ňӖ����Ȃ��Ȃ��B�����Ɋw��I�ȋc�_�ɂ���������B�܂��A���̋c�_���A�ŏI�I�Ƀp���_�C���̋���s�\���ɒ��ʂ����Ƃ��Ă��A����͂���ňӋ`�����낤�B������l�b�g��ł̉������Ȃ̌`�͂ǂ����E�E�E�Ɛē�������āB�������瑦�A�Ζ؎�����u�����v�Ƃ̕Ԏ��������B�Ȃ�Ɛē����́u�]�͐S���L�q�ł���̂��v�Ƃ�����ڂŃl�b�g�Ɍf�ڂ���B���ꂪ2007�N6��1�����������A�����ɕԓ��͂Ȃ��B�����Łu��U���m���Ȃ���2�N�ԂȂ��̂ԂĂƂ́A�Ζ���̔]�̒����S�z�ł��v�ƂȂ�������Ȃ̂ł��B
�֓��搶�͂��̕����u���܂ł��A�莆�̕Ԏ������҂����Ă��܂��B�ܖڂŁv�Ɖ��₩�ɒ��߂Ă��܂����A�{���́u��UOK���Ă����Ȃ���A2�N���̊ԉ����������Ƃ͂������Ȃ��̂��A������q�]�w�Ґ搶�B����͖����ł��傤���A����Ƃ��G�O���S�H�v�Ɠ{���䩈ӂ������Ă��u���ɂȂ肽���S���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i���̍֓����̏��Ȃ́u�o���ɁvHP�o��������2007�N6��1���t�Ōf�ڂ���Ă��܂��B��掩�͖̂Ζ؎��̖����̂��ߏI����Ă��܂����悤�Ȃ̂ł����j
�������Ɍ��݂̔]�u�[���͐��܂������̂�����܂��B"�E�]"��"���]"��"�N�I���A"��"�h�[�p�~��"���B������Ζؐ搶�̌��сH �ɂ߂��̓L���^�N���]�w�҂ɕ�����V�h���}�uMR�DBRAIN�v�B����ȃh���}���o�����̂��]�u�[���̂����ł��傤�B�ł�����ڂ̓��e�͂�����Ƃ��e���ł����ˁB�Ɛl�̎咣����A���o�C��]�����f�����ŕ������Ⴄ�̂ł�����A���ꂶ��A�Y���͌���֍s���Ȃ��Ȃ����Ⴄ���B
����Ȑ܁A�ޗǂɏZ�މ��y���Ԃ̂ЂƂ肩��u�Ζ،���Y�Ȃ�]�w�҂��w���y�̕������́`���^�[����o�b�n�ցx�Ƃ�����w�ȃ^�C�g���̖{���������݂������B�ŋߖ�O�����ςȂ��̂������ĕs�����ɂ܂�Ȃ��B���O����̂������ƓŐ�Ő���@���Ă���Ȃ����v�ƃ��[�������܂����B������q�]�w�҂�@���Ȃ�āA�C�̎ア���ɂł���������܂��A���̕������y�D���������ƁA���ȋߐe�����o���A�������e�[�}���o�b�n�Ȃ�ŁA�����������̖{���ēǂ�ł݂܂����B����������E�E�E�H
�i�Q�j�Ζ،���Y���̍ŐV����u���y�̕������́v
���̖{�̃J�o�[���ɂ͂�������܂��`���ȉƂi�D�r�D�o�b�n�̑f������߂āA�^�~�̃h�C�c�ցB�����Ō��o�����̂́A���y�̕��̒m��ꂴ��p�B�Y�ꂩ���Ă����Ⴉ�肵��M�B�����ď@�����v�𐬂����������^�[�����S�N�̎����Ďp���ꂽ�u���̃����[�v�������B
�o�b�n�̒m��ꂴ��f�炩�A�E�[���y���݁B�Ζؐ搶�̖Y�ꂩ���Ă����Ⴉ�肵��M�A����͂ǂ��ł�������B���^�[�ƃo�b�n�u���̃����[�v�A�Ȃ�Ɣ������I���ɋ����ÁX�B
���̖{�ɂ̓h�C�c�̒n�}���ڂ��Ă��āA5�̓s�s�����t���Ă��܂��B����Ɩ{�����ƍ�����ƁA�Ζؐ搶�����̓~�A�����̓s�s���K���ꂽ���Ƃ�������܂��B�i�����j�킸����T�ԑ��炸�ŁB�A�C�[�i�n�A���C�}�[���A���C�v�c�B�q�A�G�A�t���g�A���F�q�}�[���A�A�����V���^�b�g�A���ׂăo�b�n���̒n�B���Đ搶�͂����ʼn���������ꂽ�̂ł��傤���B
��s��J�DS�D�o�b�n���a�̒n�E�A�C�[�i�n�ցB�����ɂ̓��^�[���؍݂��Ă����Ƃ����u���^�[�n�E�X�v������������u�Q�I���N����v������܂��B�u�Q�I���N����v�̓o�b�n����������Ƃ���ł�����A�h�C�c���_�j��ދH�ȓ�l�̈̐l���A200�N�̂Ƃ����u�ĂČ��������n�_�ł��B"�����̖{���͌��n�֍s���Ȃ���Ό����Ȃ�"�Ƃ����搶�̓N�w���^������ттĂ��܂��B
�A�C�[�i�n�ɐ��܂ꂽ�o�b�n�ł������A10�̍����e�ɑ������Ő旧����A�I�[���h���t�ɏZ�ތZ���n���E�N���X�g�t�Ɉ����Ƃ��܂��B�o�b�n�͂����̍����w�Z�Ń��^�[�����h�̐_�w���w�т܂����B���N�o�b�n�̃i�C�[�u�ȐS�ɍ�簂ȃ��^�[�̐��_�����߂ē��^���ꂽ�̂ł��B������������u���̃����[�v�Ƃ����e�[�}�ɍł����������s�s�͂��̃I�[���h���t��������܂���B�ł�������͊O���Ăق����Ȃ������I �����炿����Ƒ���L���s����̂ɂƁA�c�O�ł͂���܂����A����͂܂��A���ׂȂ��Ƃł��B
�������̖{��ǂ�ŁA����̓}�Y�C�Ɗ��������ƁA�����"���s�̃h�C�c�l������f�B���N�^�[���Ȃǂ̋L�q�͂₽�瑽���̂ɁA�̐S�v�̉��y�̘b�����܂�ɔ�������"�Ƃ������Ƃł����B�܊p"�������̓o�b�n��������Ă͂Ȃ�Ȃ�"�ȂǂƑ��i�ɐU�肩�Ԃ��Ă���������̂ł�����A���y�I���ʂ�������Ɠ˂�����ŗ~���������B
�Ⴆ�A�ŔӔN�̌���u���Z���~�T�v�͂Q�|�R�ӏ��ŐG����Ă��܂����A���̓��e����₨�����̈ꌾ�Ƃ��킴��܂���B��͑�3�͂ŁA�u�w�����t�`�F���g�ȁx��A�w�u�����f���u���N���t�ȁx�A�w���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�x�A�w�S�[���h�x���N�ϑt�ȁx�A�w�}�^�C���ȁx�w���Z���~�T�ȁx�Ȃǐ��X�̌�����c�����o�b�n�v�Ƃ����ӏ��B���̂��Ɓu���̑n�����͂܂��Ɂw��Ձx�ł���B�ǂ����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��\�ł������̂��B�ǂ�قǍl���Ă݂Ă��A���̓����͗e�Ղɓ���ꂻ�����Ȃ��B�v�ƁA���ɒ��Ȋ��Q�������������B������͑�4�́A�u�o�b�n�Ɋւ��鎑�����W�߂��w�o�b�n�E�A�[�J�C���x�Łw���Z���~�T�ȁx�Ɋւ���~�X�e���[�����v�Ƃ��������B�X���b�I���Ɍ��n�Ȃ�ł̖͂ʔ����b�������������A�Ɛg�\���܂������A�L�q�͂����܂ŁB�q�h����搶�A�`�������Ă����Ĉ������߂��Ⴄ�B���ꂶ��ǎ҂͔߂����A�e�n�B
���̑��̃o�b�n�̊y�Ȃɂ��Ă͂ǂ��ł��傤���B
�u�}�^�C���ȁv�́A�o�b�n�ĕ]���̓���������Â���
�ˑR�A���̒��Ƀo�b�n�́u�g�b�J�[�^�ƃt�[�K�v������n�߂�
���y��w�̐��k�O�l���A���y�p�ɕҋȂ��ꂽ�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv��e��
�o�b�n�̌���u�R�[�q�[�E�J���^�[�^�v�̃A���A�����̒��ɕ�����
����̒��ŁA�o�b�n����Ȃ������e�b�g��R���[������
��l�����y�h���̓��ʂ�`�����u�}�^�C���ȁv�̒��̔������A���A
�t�H���E�P�b�Z������̉��t�ŁA�o�b�n�̃v�������[�h����
�ȏ�A���ꂪ"�o�b�n�̉��y�Ɋւ���L�q"�̑S�Ăł��B�y�ȂɊւ������L�q���A���肫����̊��Q�R�����g���A�u�������v�Ƃ��u���̒��ɕ����ԁv�Ƃ��u���̒��ɗ���n�߂��v�Ƃ������A�����̊��o�ƍs�ׂ̗���A�����B�����ɂ͎v�l�E���̗v�f�̂�������Ȃ��B"���y�̕��̐^�̎p�����߂��u�~�̗��v"�ɂ��Ă͎��ɂ���������ł��B�Ō�́u�v�������[�h�����v�ɂ��Ă����́A���̂Ƃ��̊��������Ȃ蒷�����ƒԂ��Ă͂��܂����A����͉��y�Ƃ��������A�吹���̕��͋C��p�C�v�E�I���K���̋������̂��̂ւ̊����Ɠǂ݂Ƃ�܂��B
�l�Ԃ̓��]�ɂ͊����邾���łȂ��v�l����\�͂�����͂��B�O�҂��u�E�]�v��҂��u���]�v�ł��������A�搶�B�Ȃ�ΐ搶�́u���]�v�̓����������ƌ����ė~���������B���̖{��J�DS�D�o�b�n�̑f������߂闷�ł���Ȃ�A���̐l����������y�ɂ����ƌ��y���ė~���������B�������������ł�������[���@�艺���ė~���������B�Ȃ��ăo�b�n�͍�ȉƂȂ̂ł�����B���ꂾ�����特�y���Ȃ��搂킸�ɁA���̎ʐ^�W�ɂł������ق����}�V�������̂ł́H �ł����ꂶ��}�Y�C�ł���ˁA���E�t�H���E�W�����l��I��W���|���̃A���o�T�_�[�Ƃ��ẮB
�挎�搶�́AGW�P��̉��y�Ձu���E�t�H���E�W�����l2009�`�o�b�n�ƃ��[���b�p�v�̃A���o�T�_�[�Ƃ��āA���ʘZ�]�̂��������Ƃ��B5��4���ɂ͗�؉떾���ƑΒk�܂łȂ������悤�ł��B��؉떾���Ƃ����A���݃o�b�n���t�̑��l�҂Ƃ����Ă���A�܂��ɉ��y�̕���������ē��{�ɑ��荞��"�o�b�n���y�̐����Ȏg��"�Ƃ������鍑�̉��y�ƁB�z���g�A�Ζؐ搶�͂����x�����Ă܂���B�������邵������܂���B�܂�����؎��Ɍ������āu�o�b�n��������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ȃ�ċ�Ȃ������ł��傤�ˁB
�b�͂�≡���ɂ���Ă��܂��܂������A�Ζؐ搶�̖{�́A���̂悤�ɁA�����Ȃׂēˍ��݂�����܂���B���ؐ����Ȃ��B���������L���b�`�[�ŐS�n�悳���Ȍ�傪����ł��邾���B�o�b�n�̑f���K�˂闷�Ȃ�A���E�t�H���E�W�����l�̃A���o�T�_�[�Ȃ�A�����Ɛ^���ɉ��y�ƌ��������ė~���������Ǝv���̂ł���܂��E�E�E�Ƃ܂��A����Ȃ��Ƃ�\���グ��ƁA�搶�{��̈ꌂ�����̔]�V���������u�����ɂ̓N�I���A�����ɏG�ł����l�������B�Ȃ��傠�����B�v�Ȃ�ĂˁB�b�������ɂȂ��Ă����Ƃ���ō���͂���܂ŁB����́A�j�S�����u���̃����[�v�ւ̌��y�𒆐S�ɁA�Ƃ߂ǂȂ��������Ă������������Ǝv���Ă���܂��B
2009.06.01 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�ŏI��
��2���u�j�P�A�M���v��9�ȍ\���Ƃ��ăV�����g���[��B�������o�b�n�́A�u�O���[���A�v�ɂ��V�����g���[�������Ă��邱�ƂɋC�Â��A�S�̂��V�����g���[�ɍ\�����邱�Ƃ��v�����B22�u�T���N�g�D�X�v��1724�N�̊����y�Ȃ����Ă͂ߏ������������B������3���Ƃ��Ċ������͎̂��ɑ���23�u�z�U���i�v���͂�����ƕ������邽�߂ł���A�v���e�X�^���g�̋K�͂ɂ����v����B����2�̍�����4�C5�̍����ƑΉ������B����1�|3[�����A�\���A����]�Ƃ̑Ή����B�c��y�Ȃ�24�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v��25�u�_�̏��r�v��26�u�I�ȁv�ł���B
�ł��ȒP�ȕ��@�́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�������A�u�_�̏��r�v���\���A�u�I�ȁv�������Ƃ���A1�|3�Ƀs�^���ƈ�v����B�Ƃ��낪�����Ŗ�肪������B���������22�A23�A24�Ɓu�����v���R�������ƂɂȂ�A������4������23��24�������u���ĕ����܂���22��23�̍��������邱�Ƃ͕s���R�ł���B22��23��̍������ЂƂ܂Ƃ߂ɂ���ɂ�24�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v���\���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɂÂ��u�z�U���i�v�́u�����v�Ȃ̂ő�24�Ȃ�24���\���A24�������Ƃ������ƂɂȂ�B����ɉ�����24�|26�̌`�Ԃ��܂Ƃ߂�ƁA[24���\���A24�������A25�\���A26����]�ƂȂ�B1�|3�m�����A�\���A�����n�ƑΉ�������ɂ̓\����������B�Ȃ�Έ�����������B����Ȃ�������ɂ͂ǂ������炢�����B�����Ă��Ă������Ă��ԁB�ǂ�����āH�@
�����ŃW���[�J�[�̔��z�������ԁB���w�҃o�b�n�̐^�����ł���B24���̓\���Ƃ���2�̍������������������������Ȃ��B�ł�25�\���u�_�̏��r�v���������B�ǂ�����āH�@�����Ɂ�n�̒����ĂăW���[�J�[�Ƃ���Ȃ�"���݂��Ă��đ��݂��Ă��Ȃ�"���ƂɂȂ�B��n�̉d�֒Z���ɂ��ׂ��Ƃ�������������̃g�Z���ɂ��悤�B��������A���̑��̋Ȃ͑S�ā�n������25�\���͗��h�ȃW���[�J�[�ƂȂ�B�����Ȃ�Q�T�\���͏�����B������24�|26��[�\���A�����A����]�ƂȂ�1�|3�ɑΉ�����B���ɂ����Ō����ɑS�̂̃V�����g���[�����������̂ł���B
���Ƃ͂��̗���ɏ]���Ď��ۂɋȂĂ͂߂Ă䂯�����B24���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̓e�m�[���E�\���̌h�i�ȋȂƂ��悤�B���Ɂu�z�U���i�v���J��Ԃ��̌`�Œu���B25�u�_�̏��r�v�̓W���[�J�[�Ƃ��邽�߂ɁA1735�N�̃C�Z���̃J���^�[�^��"��n�̃g�Z��"�Ɉڒ����č�蒼�����B���Ă��悢��u�I�ȁv�ł���B
�u�I�ȁv�̉̎��͐S�̕����Ɛ��E���a�ւ̊肢�����߂āuDona�@nobis�@pacem�v�Ƃ����B���Ă���ɂӂ��킵���Ȃ��ǂ�����ē��Ă͂߂悤���B���̉e���E�ъ�钆�o�b�n�͎v������B�V�Ȃ���鎞�Ԃ͂Ȃ��B�Ȃ�ǂ���������p���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ǂ����ǂ����炩�����ς��Ă���Ȃ�A���̊y�Ȃ̒�������p����Ώz�ɂ�铝�ꊴ���B���ł���B�ł͂ǂ̋Ȃ������������H�V�����g���[���������邽�߂ɂ͌`�Ԃ͍����ȂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�̎��̓��e����A��]�������ďI���Ȓ����~�����B�z�̈Ӗ����������邽�߂ɂ͋Ȃ͑O���ɂ���K�v������B����ȏ��������Ȃ��o�b�n�͌�����B�z�`���ł̏퓅��i�Ƃ��Ă�3�͍����Ƃ����`�Ԃ͖��������A�����̓��Z���Ŗ����Ɍ��������邳���o�Ȃ��B�����̍�����4��12���Ȓ�������Ȃ���5�͂�₹�킵�Ȃ��B�����͑�7�ȁu��̑傢�Ȃ�h���̂䂦�ɂ����Ɋ��ӂ��Ă܂�v�����Ȃ��ł͂Ȃ����B����Ȃ�Ή̎��Ɖ��y���҂�����Ɠ��Ă͂܂�B�y�z�͐Â��Ȋ肢����₪�ĉ���������悤�ɕς��A�S�̓��Ȃ镽�����S���E�̕��a�ւ̋F��ɏ����Ă䂭�B�������āA�o�b�n�͏I�Ȃɑ�7�Ȃ̉��y��I�сA���̒���ŕ��ՓI�ȃ~�T�Ȃ������������B�����ɂ͊w�I�V�����g���[�ɉ����A�_�̌��ɂ�蒲���̃V�����g���[���������Ă����B����1749�N10���A���͗��N�ɔ����Ă����B
���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�́A�l���̍Ō�Ō㐢�ւ̈�剹�y��Y����u���Z���~�T�v�������������B����̓J�g���b�N�̘g�g�݂̒��Ƀv���e�X�^���g�̐��_�𐁂����S����I�ȍ�i�������B�܂����Ȃ̋Z�@�̑S�Ă𓊓����ċ��ɂ̉��y�I���݂ɓ��B�������삾�����B�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̘g���A�S�l�ނɌ������ĕ������^�ɕ��ՓI�ȍ�i�������B�����āA���̍�i�S�̂̊w�I�V�����g���[�̌`���𐬂������邱�Ƃɂ���ē��ꊴ�������炷���Ƃɐ��������B�Ȓ��ɈÍ���BC�ߍ���ŁE�E�E�B����ɁA�����ɂ͐_�̉���ɂ�蒲���̃V�����g���[���`������Ă����B�u���̎��܂ŁA���̍�i��"�P�Ȃ�W�߂̍�i"�Ƃ����s���_�ɊÂȂ���Ȃ�Ȃ���������Ȃ��B�������A���̍�i�ɖ��ߍ��Í��ɋC�Â����̈ӎv�������Ƃ����Ȃ�A�����Ƃ��̍�i���S�l�ދ��ʂ̐^�ɕ��ՓI�ȍ�i�ł��邱�Ƃ���������邾�낤�B���̎��͂����Ƃ���B���͂����M���Ă���v�E�E�E�o�b�n�͂��̍Ō�̍�i�̓�������㐢�ɑ����A1750�N7��28���A���̐��U������̂ł���B
2009.05.25 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�W
���G�s���[�O�F��z�̃V�����g���[������1�i�D�r�D�o�b�n�̓��[�c�@���g�ƈႢ�莆���c�����Ƃ��Ȃ��A�d������ɂ܂�镶�������܂�c����Ă��Ȃ����߁A�ނ̍�Ȃ̐��ڂ�S�̂�����T�邱�Ƃ͑�ϓ�������̕������ǂ����Ă������Ȃ�B�Ƃ͂����Ō�ɁA�\�Ȍ���A�u���Z���~�T�v����Ȃ��V�����g���[�������������o�܂�ނ̐l�������ǂ�Ȃ����z���Ă��������B
��3���u�T���N�g�D�X�v����Ȃ��ꂽ1724�N�A�o�b�n�̓h�C�c�̎��R�s�s���C�v�c�B�q�̐��g�[�}�X����̃J���g���i���y�ēj�̐E�ɂ������B���C�v�c�B�q�̓��^�[�����h�v���e�X�^���g�̒��B�o�b�n��5�̋���A��w�Ȃǂ̎����I���y�w���҂ƂȂ��Ă��������A�e�X�̑������₦���A����Ɋ������܂�ċC��J�̑������X���߂����Ă����B����ȏ�Ŕj���邽�߁A�o�b�n�̓��C�v�c�B�q�ɑ傫�ȉe�������U�N�Z���̋{��ƊW�������Ƃ�����Ă����B���Z���̑�P���Ɏg�����u�L���G�v�Ɓu�O���[���A�v����Ȃ��ꂽ�̂�1733�N�̂���Ȏ����̂��Ƃł���B�����Ă����̋Ȃ̓J�g���b�N�̐M�҃U�N�Z���I���t���[�h���q�E�A�E�O�X�g2���Ɍ��悳��A1736�N�ɂ͔O�肩�Ȃ��đI���t���{�쉹�y�Ƃ̏̍���^������̂ł���B���̌��ʂ͂����Ɍ����w������̎G���͏��Ȃ��Ȃ�A�ꎞ�I�ɂ̓o�b�n�̖ړI�͒B�������B�o�b�n�͂����Ƀv���e�X�^���g�n�̃J���g���A�J�g���b�N�n�̋{�쉹�y�ƂƂ����̑��܂𗚂����ƂɂȂ����B���Ȃ����납��A�h�C�c��̃J���^�[�^�̔��W���ɋ^��������n�߂Ă����o�b�n�͕��ՓI�ȃ��e����ɂ���i�𑽂������悤�ɂȂ��Ă䂭�B�v���e�X�^���g���k�̃o�b�n�̐��_���J�g���b�N�ɑ����X�Ɋ��e�ɂȂ��Ă䂭�̂ł���B���ꂩ��N���͗��ꂢ�����l���̏I����\�������o�b�n�͎��Ȃ̏W�听�����i���c�����Ǝv�����B����͌㐢�Ɏc�����y��Y�Ƃ��Đ^�ɕ��ՓI�Ŏ����Ȃ��̂ł��肽���B����ȑz�������R�Ƃ������₪�Ċm���Ɍ`������Ă������̂ł���B���̋Ȃ����u���U�ŏK�����������鉹�y�Z�@��p�����J�g���b�N�̘g�g�݂ɂ��~�T�ȁv���u���Z���~�T�ȁv�ł������B
�o�b�n��1748�N8���A�u�L���G�v�Ɓu�O���[���A�v�����Ƃɂ��Đ��Ɋ����Ɍ����Ē��肵���B�����Łu�L���G�v�̖`����������������B���̈�x��������Y����Ȃ��n�̕�����N���������Ă���悤�Ȕ߂��݂̋����ł���B�����đ�Q���u�j�P�[�A�M�o�v�������B�W�Ȃ������グ���o�b�n�́A���̑�2���Ƀv���e�X�^���g�̐��_�𐁂����ނ��ƂƃV�����g���[�\���ɂ��邱�Ƃ��v���������B3�Ȗڂ�"���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g���B����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾�����܂������̂�"��藣���A��3�ȁu���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g���v�Ƒ�4�ȁu����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾�����܂������̂��v�Ƃ����B���̂��߁u�j�P�[�A�M�o�v�͑S9�ȂƂȂ�A17�u����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����v���Ȃ̒��S�ɂ�������B����ɂ���āu�j�P�[�A�M�o�v�S9�Ȃ̃V�����g���[���ƁA�u���Y�v���u�����v�i18�u���͐M���A�O���ڂɂ�݂�����v�j���d�郋�^�[�����h�̍l�����̋�����B�����ꂽ�̂ł���B
�����ŁA�u�O���[���A�v�ɖڂ�]�����o�b�n�͂���9�Ȃɂ��V�����g���[�������Ă��邱�ƂɋC�Â��B���Ȃ킿4�����C5������ʂɂ�����Ƃ̂V�ȂŃV�����g���[���`�����Ă��邱�Ƃ��B������A����ꂽ2�Ȃ̍�����1�|3�̃L���G���A���̂��ƍ��u�T���N�g�D�X�v�ȍ~�ƑΏ̂���ΑS�̂̑傫�ȃV�����g���[����������B���ꂱ���S�̓���̏A�܂��ɂ��̋Ȃɂӂ��킵���V�����g���[�̊����ƍl�����̂ł���B
2009.05.18 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�V
����V�́F�o�b�n����������k�ɂ܂�Ȃ��g�g�݁����ڂ����̂�"�u���Z���~�T�v�̘g�g�݂��̂���"�������B�u���Z���~�T�ȁv�o�b�n���M�̊y���������������������B�L�C�́u�z�U���i�v�ł���B�J�g���b�N�̋K�͂ł́u�T���N�g�D�X�v�ɕt�����ׂ��u�z�U���i�v���A��3���Ƃ��Ċ��S�ɓƗ����Ă���B����u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̌�ɑ����u�z�U���i�v�͑�4���̕\���ɂ͏�����Ă��Ȃ��B���Ȃ킿�\�L��u�T���N�g�D�X�v�ł͕������Ă��邪�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł͓���Ă���B�u�T���N�g�D�X�v�ł̕����̓o�b�n�̈Ӑ}�������̂ł��������A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł̓���͂����ł͂Ȃ����낤�B����͒P�Ȃ�\�L�̖��Ȃ̂ŁA�o�b�n�̈Ӑ}�Ƃ���ɂ͖���������Ǝv������ł���B���������̈Ӑ}������\�L���_�̌��ɂȂ����Ă䂭�̂ł���B
�o�b�n�͌��ʓI�Ɂu�z�U���i�v�̕������ɕs���ꊴ�����������B������Đ_���������Ɂu"�ꍇ�ɂ���Ă͕����������́A�ꍇ�ɂ���Ă͓��������"�ƍl����A�ړI�͗B��V�����g���[�̌`���̂��߂��v�Ƌ����Ă���Ă���̂ł͂Ȃ����B �O�q�����悤�ɃV�����g���[�ɂ͊w�I�V�����g���[�ƒ����I�V�����g���[�������āA����R�́��ł͊w�I�V�����g���[�̑��݂��ؖ����ꂽ�B���̂Ƃ��u�z�U���i�v�͂Q�Ƃ��Ɨ������y�ȂƂ����B�V���ɏؖ��������̂͒����̃V�����g���[�ł���B�ڂɌ�����w�I�`�Ԃł́A�u�z�U���i�v��"������������"�Ƃ����Ȃ�A�����Ƃ����ڂɌ����Ȃ����̂ɑ��ẮA�u�z�U���i�v��"��������"�Ƃ���ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ����B
������22�u�T���N�g�D�X�v��23�u�z�U���i�v���ʂ��猟����ƁA��2�͓����j�����ł������邱�ƂɂȂ���a���͂Ȃ��B�����24���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v��24���u�z�U���i�v��������ƁA�O�҂̓��Z���Ō�҂̓j�����A����͂��݂������ƒZ���̕��s���ŁA�������Q���m�œ���邱�Ƃɉ��̈�a�����Ȃ��B���y�I�ɂ͂ނ��낱������ق������R���ƍl������B������22�{23����Ȃƈ�����̐��͂Q�A24���{24������ȂƂ���̐���2�ƂȂ����B�����Ă���܂��āA�O�͂ł�����悤�Ɂ�̐��������Ă݂悤�B
�O�����A��7�Ȃ����19�Ȃ܂ł́�̐��́A���Ԃ�2�C1�C2�C2�C2�C2�C3�C2�C1�C2�C1�C2�C3�ō��v25�B�㔼����20�Ȃ����6�Ȃ܂ł́A3�C2�C2�C2�C2�C2�C2�C3�C2�C2�C3��25�B�����őO���㕔�́�̐������Ɉ�v�����̂ł���B����̓o�b�n���d�����̂ł͂Ȃ����낤�B�ł��_�̎肪�����ăo�b�n���Ӑ}���ĂȂ����������̃V�����g���[���������Ă��܂����̂��B�����Ɂu���Z���~�T�ȁv�́A�w�I�Œ����I�ȓ�d�̃V�����g���[�ɂ�铝�ꊴ��B�������̂ł���B�_�̌�肪�����āB
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�o�b�n�F�~�T�ȃ��Z���̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́��̐�
����P����
�i�L���G�j�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j
�@�P �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@������݂��܂�
�@�Q ��d���@ �j�����@ �@�Q�@�L���X�g��A����݂��܂�
�@�R �����@�@�d�֒Z�� �@ �R�@���A����݂��܂�
�i�O���[���A�j
�@�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���ƍ����Ƃ���ɂ͐_�ɉh������Ƃ�
�@�T �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@�n�ɂ͑P�ӂ̐l�X�ɕ��a����
�@�U �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@�������ق�
�@�V �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@��̂������Ȃ�h���̂䂦�ɂ����Ɋ��ӂ��Ă܂�
�@�W ��d���@�@�g�����@ �@�P�@��Ȃ�_�A�V�̉�
�@�X �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@���̍߂��̂��������҂�
�P�O �A���A�@�@���Z���@ �@�Q�@���̉E�ɍ����������̂�
�P�P �A���A�@�@�j�����@ �@�Q�@���̂ݐ��Ȃ�
�P�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@����ƂƂ���
����Q�����i�j�P�[�A�M�o�j
�P�R �����@�@�@�C�����@�@ �R�@���M���A�B��Ȃ�_���i�~�N�\���f�B�A�����������C�����j
�P�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�B��Ȃ�_���B�S�\�̕�
�P�T ��d���@�@�g�����@ �@�P�@���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g��
�P�U �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾����
�P�V �����@�@�@�z�Z���@ �@�P�@����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����
�P�W �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�����ɂ��肵���Ƃ��A�O���ڂɂ�݂�����
�P�X �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@���͐M���A��Ȃ鐹���A�����̗^���傽��҂�
�Q�O �����@�@�d�֒Z���@ �R�@�߂̎͂��̂��߂Ȃ�B��̐����F��
�Q�P �����@�@�@�j�����@�@ �Q�@���҂̂�݂�����Ɨ����̐����Ƃ�҂��]��
����R�����i�T���N�g�D�X�j
�Q�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���Ȃ邩��
����S����
�Q�R �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�S�� �A���A�@���Z���@ �@ �Q�@ ��̌䖼�ɂ��ė���҂͍K���Ȃ�i�x�l�f�B�N�g�D�X�j
�@�@�� �����@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�T �A���A�@�@�g�Z���@ ��Q �@�_�̏��r
�Q�U �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ɕ�����^�����܂�
�@�@�@�@���o�b�n�̃I���W�i���y����S���\���ɂ͑�Q�S�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��Ƃ̢�z�U���i��̋L�ڂ͂Ȃ�
�@�@�@�@���C���ۂɂ͊y�����ɁuOsanna�@repetatur�v�Ƃ���̂ŁA�����͢�x�l�f�B�N�g�D�X��� �Q�S���C�u�z�U���i�v��
�@�@�@�@�Q�S���ƕ\�L����
2009.05.11 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�U
����T�́F�����ЂƂ̃V�����g���[�����̏͂͂��������ė~�����Ǝv�����̊肢�ł����āA�o�b�n�̈Ӑ}�������̂ł͂Ȃ��B����͂�����̃V�����g���[�̌`���ł���B�������ꂪ��������Ă���A�o�b�n�̈Ӑ}������"�_�̌��ɂ��"�ʂ̃V�����g���[���`������邱�ƂɂȂ�B�����A���t�������肢�����Ǝv���܂��B
�O�͂Ŋm���Ɋw�I�ȃV�����g���[�͏ؖ����ꂽ���A�W���[�J�[���K�肵�����̂͒����������B�����������璲���ɂ��V�����g���[������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă݂��B�ł͒����̃V�����g���[�Ƃ͂Ȃ낤�H����͑S26�Ȃ������I�ȋύt�������Ƃł���B�����̋ύt�A�����"��̐�"�̋ύt�ł͂Ȃ����B�o�b�n���y�Ȃ̌`�Ԃ��V�����g���[�Ɠ����ɒ����̃V�����g���[���B�����Ă�����ǂ����낤�A�ł�����̓o�b�n���ӎ��I�ɂ������ƂƂ͎v���Ȃ�����ǁE�E�E����Ȍy���C�����Œ��ׂĂ݂��B
�܂���25�Ȃ̓W���[�J�[�Ȃ̂ŏ����A��̐����Ȃ̑O���ƌ㔼�Ŕ�ׂĂ݂�i�����̕\���Q�Ɓj�B�O����1�|13�Ɋ܂܂����2�C2�C3�C2�C2�C3�C2�C1�C2�C2�C2�C2�C3�ō��v��28�A�㔼14�|26��2�C1�C2�C1�C2�C3�C3�C2�C2�C2�C2�C2�C2��26�ł���B
�����ŁA13�u���͐M���A�B��Ȃ�_���v�́��̐���3�Ƃ������R��������Ă��������B����͋�����@�̂ЂƂ~�N�\���f�B�A���ŏ�����Ă���A�y����ɂ��钲���L���́�2�ł���B�������o�������炵�炭�̓g���Ɂ������Ă���A���Ԃ̓g���̓i�`�������ɖ߂邪�A�Ō�̓C�����̎�a���ŏI����Ă���B���̃��[�h�͒��Ԃ��i�`�������g���Ȃ̂ŁA��{���́�2�ɂ��Ă����ĕK�v�ȏꍇ�Ƀg���Ɂ�������Ƃ������@���Ƃ��Ă͂��邪�����̓C�����Ȃ̂ł���B����������"���̐�"�Ƃ��Ă�3���Ó��ƍl������i���̌��Ɋւ��ẮA�u�o�b�n�`���̓��ǂ��v�̒��ҏ��ы`���搶�Ɋm�F�ς݂ł���j�B
�ł͖{��ɖ߂낤�B��̐��͑O��26�㔼28�B�c�O�Ȃ��瓯���ł͂Ȃ��B�����Ŋϓ_��ς��Ă݂�B�w�I���o�I�����������Ȃ������̋ύt���l����ꍇ�A�����̋N�_����P�Ȃł���K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�ʂ̂Ƃ���ɕK�R�I�ȋN�_�������������Ƃɕ�����悢�̂ł͂Ȃ����B�Ȃ�ǂ����ɋN�_�������L�C�E���[�h���B����Ă͂��Ȃ����낤���H�@�����Œ��ڂ����̂���26�ȁu���ɕ�����^�����܂��v�ł���B�o�b�n�͐��U�̏W�听�����i�����ԁu�I�ȁv�ɂȂ�Ƒ�7�ȁu��̑傢�Ȃ�h���̂䂦�ɁA�����Ɋ��ӂ��Ă܂�v�����p���Ă���B�~�T�Ȃ́u�I�ȁv�ɂ�������p�͒ʏ�`�������́u�L���G�v���炳�����́B����͏z�Ƃ����`�ɂ���đS�̂̓��ꊴ���o�����Ƃ��_���Ȃ̂��B�Ȃ�Ȃ��u�L���G�v�ł͂Ȃ���V�ȂȂ̂��A���͂ōl���Ă݂�B
����U�́F��V�ȁ�
�~�T�Ȃł́u�I�ȁv�ɖ`���́u�L���G�v�����̉��y�������Ă��邱�Ƃ��������Ȃ��B���[�c�@���g�̃��N�C�G���i���ۏI�Ȃ̓W���X�}�C���[���������������̂����j���I�ȁu�R���[�j�I�i���̔q�́j�v�͑�1�ȁu���N�C�G���v�̉��y�����̂܂g���Ă���B�܂������̃~�T�Ȃɂ��A�u�I�ȁv�Ɂu�L���G�v�̑�2���̉��y���J��Ԃ��A�z�I�`�Ԃ����o�����Ƃ͋H�ł͂Ȃ������B�o�b�n�́u���Z���v���A�u�I�ȁv�ւ͑�7�Ȃ����A�u��2�L���G�v�̉��y�����p����ق������������Ǝ咣����ӌ�������B�X�����h�́u�ׂ荇���w�_�̏��r�x�ƏI�ȁw���ɕ�����^�����܂��x�͓��e�I�ɖ��ڂȊW������B���̂��߂ɉ��y�͑�7�Ȃ���2�w�L���G�x�̂ق������������B���̏�z�I���i�����������v�ƌ����Ă���B
������Ƀo�b�n�͏I�ȁu���ɕ�����^�����܂��iDona�@nobis�@pacem�j�v�̉��y�ɑ�7�ȁu��̑傢�Ȃ�h���̂䂦�ɁA�����Ɋ��ӂ��Ă܂�v�����p�����i��7�Ȃ̓J���^�[�^BWV29�̑�2�y�́u�_��A������Ɋ��ӂ��v�̃p���f�B�[�ŁA����u�I�ȁv�͓�d�̃p���f�B�[�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���j�B������A�V�����g���[�����̋N�_����7�Ȃɂ��邱�Ƃ������������̂Ɖ��߂��Ă݂�B�����Ă������N�_�ɂ��������̃V�����g���[�������Ă݂�B�ł͗�ɂ���Ċ����̍\���}�����Ȃ��炨�ǂ݂������������B ��7�Ȃ��N�_�Ƃ���ƑO������7�|19�A�㔼����20�|6�Ƃ������ƂɂȂ�B���Ă��̂Ƃ��́�̐��͂ǂ����낤���B�O������25�Ō㔼����29�A�����ł͂Ȃ��B��͂肱��Ȃ��Ƃ͐������Ȃ��̂��B�ł�������鉽��������͂����B����͂Ȃ낤�H����4�����������̂��ǂ����ɐ���ł������ȋC������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�o�b�n�F�~�T�ȃ��Z���̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́��̐�
����P����
�i�L���G�j�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j
�@�P �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@������݂��܂�
�@�Q ��d���@ �j�����@ �@�Q�@�L���X�g��A����݂��܂�
�@�R �����@�@�d�֒Z�� �@ �R�@���A����݂��܂�
�i�O���[���A�j
�@�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���ƍ����Ƃ���ɂ͐_�ɉh������Ƃ�
�@�T �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@�n�ɂ͑P�ӂ̐l�X�ɕ��a����
�@�U �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@�������ق�
�@�V �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@��̂������Ȃ�h���̂䂦�ɂ����Ɋ��ӂ��Ă܂�
�@�W ��d���@�@�g�����@ �@�P�@��Ȃ�_�A�V�̉�
�@�X �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@���̍߂��̂��������҂�
�P�O �A���A�@�@���Z���@ �@�Q�@���̉E�ɍ����������̂�
�P�P �A���A�@�@�j�����@ �@�Q�@���̂ݐ��Ȃ�
�P�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@����ƂƂ���
����Q�����i�j�P�[�A�M�o�j
�P�R �����@�@�@�C�����@�@ �R�@���M���A�B��Ȃ�_���i�~�N�\���f�B�A�����������C�����j
�P�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�B��Ȃ�_���B�S�\�̕�
�P�T ��d���@�@�g�����@ �@�P�@���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g��
�P�U �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾����
�P�V �����@�@�@�z�Z���@ �@�P�@����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����
�P�W �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�����ɂ��肵���Ƃ��A�O���ڂɂ�݂�����
�P�X �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@���͐M���A��Ȃ鐹���A�����̗^���傽��҂�
�Q�O �����@�@�d�֒Z���@ �R�@�߂̎͂��̂��߂Ȃ�B��̐����F��
�Q�P �����@�@�@�j�����@�@ �Q�@���҂̂�݂�����Ɨ����̐����Ƃ�҂��]��
����R�����i�T���N�g�D�X�j
�Q�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���Ȃ邩��
����S����
�Q�R �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�S�� �A���A�@���Z���@ �@ �Q�@ ��̌䖼�ɂ��ė���҂͍K���Ȃ�i�x�l�f�B�N�g�D�X�j
�@�@�� �����@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�T �A���A�@�@�g�Z���@ ��Q �@�_�̏��r
�Q�U �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ɕ�����^�����܂�
�@�@�@�@���o�b�n�̃I���W�i���y����S���\���ɂ͑�Q�S�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��Ƃ̢�z�U���i��̋L�ڂ͂Ȃ�
�@�@�@�@���C���ۂɂ͊y�����ɁuOsanna�@repetatur�v�Ƃ���̂ŁA�����͢�x�l�f�B�N�g�D�X��� �Q�S���C�u�z�U���i�v��
�@�@�@�@�Q�S���ƕ\�L����
2009.04.27 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�T
����S�́F�W���[�J�[�����C�Ȃ��y�����߂����Ă�����A��25�ȁu�_�̏��r�v�iAgnnus Dei�j�̌ܐ����Ɂ�2����ł���̂ɋC���t�����B�g�Z���������B�u������H�v�Ǝv�����B�u���Z���~�T�v�̊�̓��Z���Ȃ̂ŁA���̋Ȃ̊y���̏�ɂ͑S�ā���ł���B�S26�Ȃ̒���"��25�Ȃ݂̂���n�̒���"�Ȃ̂ł���B��������Ȃ����A����͊�قł���B�Ȃ��o�b�n�͂����Ɂ�n�̊y�Ȃ�u�����̂��낤���B�g�Z���̋ߕӂ̒����Ƃ��Ă͔����������Ȃ��d�֒Z��������B����Ȃ��n�̒Z���Ƃ��ċȂ̗���ɂ��}�b�`����B���ɉd�֒Z���́A��3�ȁu�L���G�v�A20�ȁu�B��̐����F�߁v�̒����Ƃ��đ��݂��Ă���B2�x���g���Ă���̂͂�����̕������R�����炾�B�g�Z���͂�����Ȃ�ł����˂ŕs���R���B�Ȃ�����ȕs���R�Ȃ��Ƃ��o�b�n�͂����̂��낤���B�ނ�"�ʏ�Ȃ炴�邱��"������Ƃ��A�����ɂ͕K�������̈Ӑ}������B�ނ̈ӎu������B�o�b�n���u�������̑S�ĂƈႤ��ȁ��u�_�̏��r�v�̓W���[�J�[�Ȃ̂ł͂Ȃ����H�Ǝ��͑M�����B�����A��25�ȁu�_�̏��r�v�̓o�b�n��������2��BC�ŁA����̓W���[�J�[�������̂ł���B�u�_�̏��r�v�Ƃ�"���̍߂�w�����Đ_�ɕ������鐶�тł���A�\���˂ɂ�����ꂽ�C�G�X�E�L���X�g"�̂��Ƃ��B���Ȃ킿�V�����g���[�`���̂��߂Ƀo�b�n���w���������т���25�u�_�̏��r�v�������̂ł͂Ȃ����B�Ƃ͂������̃W���[�J�[�̍ۗ����������������������Ȃ�ƌ`�e�����炢���̂��낤���B�ʑt�ቹ�ƌ��y�ɂ��V���v���ȍ��t�̏l�X������݂̒����A�A���g��"���̍߂������������_�̏��r��A�������݂��܂�"�ƐÂ��Ɍh�i�ɉ̂������Ă䂭�B�����"�g�Z��"�̂Ȃ���ƂȂ̂��B
�u�_�̏��r�v�̌��Ȃ�1735�N�����̃J���^�[�^�u���̌䍑�ɂĐ_��_�߂��Ă܂�vBWV11�̑�4�ȁu���܂肽�܂��킪���v�i�����̓C�Z���j���Ƃ����Ă���B�u�_�̏��r�v�͌����A�_�̏��r���L���X�g���\���˂ɂ�����ꂽ���ƂɔF�߂���_�̔ډ����ے����邽�ߒႢ�����ŏ������̂����킵�Ƃ���Ă���B����܂��Ē��������߂�Ƃ��A�C�Z���̌��Ȃ����Ⴂ�g�Z���Ɉڒ�����̂͗����ł���B�������A�u���Z���~�T�v�̎咲�̓��Z���ŁA��n�̋Ȃł���B�Ȃ�g�Z�����X�ɔ����Ⴍ��n�̉d�֒Z���Ɉڒ�����ق�����莩�R�ł����Ƒ��������͂��B����Ȃ̂ɁA�����Ă������"����������n�̒���"��I�̂́A"25�u�_�̏��r�v���W���[�J�[�ɂ��Ȃ�������Ȃ�"�Ƃ����o�b�n�̕K�R������������ł͂Ȃ����낤���B
�����ŁA��3�͂ւ��ǂ낤�B24�|26��[24���\���A24�������A25�\���A26����]�Ƃ��Ă���B�W���[�J�[�͔����̃J�[�h�A���̑��݂͖��E�E�E25�u�_�̏��r�v���W���[�J�[�Ȃ�A25�̃\����������B����Ƃ����̃u���b�N��[�\���A�����A����]�ƂȂ�A1�|3[�����A�\���A����]�ƌ����ɑΉ����v����̂ł���B���ɁA�����ɂ����āu���Z���~�T�v�͑S�̂Ō����ȃV�����g���[�������`�������̂ł���I
�V�����g���[���������邽�߂ɃW���[�J�[��p����Ƃ����̂͂����ɂ��s���R���Ƃ��������������Ă������ł���B�m���ɂ���Ȃ��Ƃ������Ƃ��ړI���B�������Ȃ�A����Ȗʓ|�Ȏ�i���g���K�v�͂Ȃ��B�����ł́A"�W���[�J�[���g�킸��"�V�����g���[���`���ł���i24�|26��[�\���A�����A����]�Ƃ���j������\���𒊏o���āA���̌`���̉ۂ������Ă݂�B�l��������@�͎O����B
��P�̕��@�́A24�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v���u�z�U���i�v���܂߂���̍����Ȃɂ��邱�Ƃł���B��������A24�|26��[�����A�\���A����]�ƂȂ��ĂP�|�R�Ƀs�^���Ή�����B�W���[�J�[�ȂǓ��ꍞ�܂Ȃ��Ă��P���Ɍ`�������B�������A��������ƂQ�Q�u�T���N�g�D�X�v����Q�S�܂ō������R�������ƂɂȂ�A������S���ɓ����Ă���Q�R�ƂQ�S�����炸�ɕ����܂���22��23������͕̂s���R�ł���B����������23�����̌�ɂ̓\�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B���̂��߂��̕��@�͐������Ȃ��B ��Q�̕��@�́A�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��Ƃ́u�z�U���i�v����������25�u�_�̏��r�v�������ȂƂ��邱�Ƃł���B����Ȃ��24�|26��[�\���A�����A����]�ƂȂ��ĂP�|�R�ɑΉ�����B�������A�o�b�n�͂��̕��@���Ƃ�Ȃ������B���w�҃o�b�n�́u�T���N�g�D�X�v�̂��Ƃɑ������u�z�U���i�v���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ŏ������Ƃ̖����������Ȃ��������A���y�ƃo�b�n�́u�_�̏��r�v�������ȂƂ��邱�ƂɑË��ł��Ȃ������̂��Ǝv���B ��R�̕��@�́A24���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v��24���u�z�U���i�v����̍����ȂƂ�����ŁA1�|5��22�|26��5�ȂÂ����Ɍ���l�����ł���B���������22�|26��[�����A�����A�����A�\���A����]�ƂȂ�1�|5��[�����A�\���A�����A�����A����]�ƃs�^���Ή�����B�ł�����͉��y�I�ɂ݂Ăǂ����낤���H��͂�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̓\���������������A�u�T���N�g�D�X�v���番�����đ������u�z�U���i�v�́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł��������������ׂ����낤�B�V�����g���[�`���̂��߂ɉ��y�����������`�ɂ��邱�Ƃ͖{���]�|�ł���o�b�n�͂���������킯�ɂ͂����Ȃ������Ǝv���B
����ȊO��"�W���[�J�[���g�킸��"24�|26��[�\���A�����A����]�Ƃ�����@�͂Ȃ��B���������ăW���[�J�[���g�������@���B��ł��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ�̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�o�b�n�F�~�T�ȃ��Z���̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́��̐�
����P����
�i�L���G�j�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j
�@�P �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@������݂��܂�
�@�Q ��d���@ �j�����@ �@�Q�@�L���X�g��A����݂��܂�
�@�R �����@�@�d�֒Z�� �@ �R�@���A����݂��܂�
�i�O���[���A�j
�@�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���ƍ����Ƃ���ɂ͐_�ɉh������Ƃ�
�@�T �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@�n�ɂ͑P�ӂ̐l�X�ɕ��a����
�@�U �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@�������ق�
�@�V �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@��̂������Ȃ�h���̂䂦�ɂ����Ɋ��ӂ��Ă܂�
�@�W ��d���@�@�g�����@ �@�P�@��Ȃ�_�A�V�̉�
�@�X �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@���̍߂��̂��������҂�
�P�O �A���A�@�@���Z���@ �@�Q�@���̉E�ɍ����������̂�
�P�P �A���A�@�@�j�����@ �@�Q�@���̂ݐ��Ȃ�
�P�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@����ƂƂ���
����Q�����i�j�P�[�A�M�o�j
�P�R �����@�@�@�C�����@�@ �R�@���M���A�B��Ȃ�_���i�~�N�\���f�B�A�����������C�����j
�P�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�B��Ȃ�_���B�S�\�̕�
�P�T ��d���@�@�g�����@ �@�P�@���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g��
�P�U �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾����
�P�V �����@�@�@�z�Z���@ �@�P�@����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����
�P�W �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�����ɂ��肵���Ƃ��A�O���ڂɂ�݂�����
�P�X �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@���͐M���A��Ȃ鐹���A�����̗^���傽��҂�
�Q�O �����@�@�d�֒Z���@ �R�@�߂̎͂��̂��߂Ȃ�B��̐����F��
�Q�P �����@�@�@�j�����@�@ �Q�@���҂̂�݂�����Ɨ����̐����Ƃ�҂��]��
����R�����i�T���N�g�D�X�j
�Q�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���Ȃ邩��
����S����
�Q�R �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�S�� �A���A�@���Z���@ �@ �Q�@ ��̌䖼�ɂ��ė���҂͍K���Ȃ�i�x�l�f�B�N�g�D�X�j
�@�@�� �����@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�T �A���A�@�@�g�Z���@ ��Q �@�_�̏��r
�Q�U �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ɕ�����^�����܂�
�@�@�@�@���o�b�n�̃I���W�i���y����S���\���ɂ͑�Q�S�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��Ƃ̢�z�U���i��̋L�ڂ͂Ȃ�
�@�@�@�@���C���ۂɂ͊y�����ɁuOsanna�@repetatur�v�Ƃ���̂ŁA�����͢�x�l�f�B�N�g�D�X��� �Q�S���C�u�z�U���i�v��
�@�@�@�@�Q�S���ƕ\�L����
2009.04.13 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�S
����R�́F�z�U���i�������A�u���Z���v�̃V�����g���[�ɋC�Â��������������u�z�U���i�v���������Ƃ͑�P�͂ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B�u�z�U���i�v�̓J�g���b�N�̋K�͂ɂ��ƒʏ�u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɕt�����镔���ł���B����͑�P�͂ɏ������悤�ɂ��̑��̃J�g���b�N�n�~�T�̌��ɂ���Ė��炩���B�����Ƀo�b�n�̓v���e�X�^���g�I�v�f�荞��Łu�T���N�g�D�X�v�Ɓu�z�U���i�v��藣���A�������u�T���N�g�D�X�v�P�Ȃɑ�R���Ƃ��������^�����B���t���ԂŌ��Ă��A��1���͖�60���A��2���͖�35���A��4������20���ɑ��āA��3���u�T���N�g�D�X�v��6����Ƃ����̂͂����ɂ��o�����X�������B
�u���Z���v�̑��̓I�g�g�݂ł���J�g���b�N�̋K�͂ɂ��A�����I�ɐ��_�𒍓������v���e�X�^���g�̋K�͂ɂ����̂悤�ȂS���ɂ��d�����͋H�ł���B�V�삠��p���f�B�[����̕s����Ȋy�ȌQ�A�J�g���b�N�ʏ핶�ɉ����Ȃ�����v���e�X�^���g�̋K�͂����荞�ނȂǂ̉e���ŁA���ʎ��Ƀ��j�[�N�Ȍ`�̎d�����ƂȂ��Ă���̂ł���B�o�b�n�͂������������ɔC���Ďd�����������ł��낤���H���₻���ł͂Ȃ��͂����B�ނ����̂悤�Ȏd�����������͉̂��炩�̈Ӑ}���������͂��ł���B�^���ř{���ʂŐ��w�ғI���y�Ƃł������o�b�n�̍Ō�̋Ȃ����炱���A�����ɂ͔ނ̈Ӑ}������܂ňȏ�ɍ��߂��Ă���ƍl���邱�Ƃɉ��̕s���R�������낤���B�o�b�n�́u�T���N�g�D�X�v���3���Ƃ��Ċ��邱�Ƃɂ��u�z�U���i�v��Ɨ�������̊y�ȂƂ��Ė��m�ɂ������������̂ł͂Ȃ����낤���B���Ȃ킿�{���u�T���N�g�D�X�v�ɕt������u�z�U���i�v��Ɨ�������̊y�ȂƂ݂Ȃ����E�E�E���ꂪ�ނ̑�P�̈Í����o�b�n�E�R�[�h(BC)�P�Ȃ̂ł���B�ł͂��̃R�[�h�ɏ]���V�����g���[�̍\�}�������������Ă䂱���B���悢�悱�ꂩ��{�҂̊j�S�ɓ����Ă䂭�B�i�\���}�����Ȃ��炨�ǂ݂������������j
����Q�́F�V�����g���[���Ŗ��炩�ȂƂ���A�V�����g���[���������Ă����2��9�ȁi13�|21�j�Ƒ�1����7�ȁi6�|12�j�������őΉ����Ă���ƂȂ�ƁA�e�X�̊O������1�|5��20�|26���Ή�����ΑS�̂̃V�����g���[����������Ƃ������Ƃ͂��łɏq�ׂ��Ƃ���ł���B���Ȃ킿����܂ŕ��u����Ă����O���[���A��2�Ȃ̍����S�A5�́A�u�z�U���i�v���������Ƃɂ���āA�u�T���N�g�D�X�v�̍����i22�j�Ɓu�z�U���i�v�̍����i23�j�ɑΉ�����B���ꂱ���o�b�n���Ӑ}�������Ƃ������̂��B�J�g���b�N�̗l���ǂ���u�z�U���i�v���u�T���N�g�D�X�v�ɕt���������̂Ƃ���Ƃ��̑Ή��͕s�\�ɂȂ邩��ł���B
�c���1�|3��24�|26�̑Ή��ł���B1�|3��[�����A�\���A����]�A24�|26��[�\���A�\���A����]�ł���B����ł͑Ή����Ă���Ƃ͌����Ȃ��B���̉����������܂ł��I�҂Ă�A24�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�͂P�ȂŊ����Ă��邪�A�e�m�[���E�\�����O���A�u�z�U���i�v���㔼�̎���2�Ȃł͂Ȃ����B�������u�z�U���i�v�͑�S���`���œƗ����Ă���23�u�z�U���i�v�ƑS������̂��̂ł���B�������炱����́u�z�U���i�v���Ɨ����������ȂƂ��Đ藣���čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂����B������24�|26�̕������@[24���\���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�A24�������u�z�U���i�v�A25�\���u�_�̏��r�v�A26�����u���ɕ��������������܂��v]��4�Ȃɂ���B����������ł͑Ή���������1�|3�ƋȐ�������Ȃ��B�܂��܂��Ïʂɏ��グ��B���͂₱��܂ł��Ǝv���A���C�Ȃ��e�Ȃ��Ƃ̒����߂Ă������A�V�[�̂悤�ȑM���������N�������B���̂S�Ȃ̒��ɃW���[�J�[�������̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�o�b�n�F�~�T�ȃ��Z���̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́��̐�
����P����
�i�L���G�j�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j
�@�P �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@������݂��܂�
�@�Q ��d���@ �j�����@ �@�Q�@�L���X�g��A����݂��܂�
�@�R �����@�@�d�֒Z�� �@ �R�@���A����݂��܂�
�i�O���[���A�j
�@�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���ƍ����Ƃ���ɂ͐_�ɉh������Ƃ�
�@�T �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@�n�ɂ͑P�ӂ̐l�X�ɕ��a����
�@�U �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@�������ق�
�@�V �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@��̂������Ȃ�h���̂䂦�ɂ����Ɋ��ӂ��Ă܂�
�@�W ��d���@�@�g�����@ �@�P�@��Ȃ�_�A�V�̉�
�@�X �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@���̍߂��̂��������҂�
�P�O �A���A�@�@���Z���@ �@�Q�@���̉E�ɍ����������̂�
�P�P �A���A�@�@�j�����@ �@�Q�@���̂ݐ��Ȃ�
�P�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@����ƂƂ���
����Q�����i�j�P�[�A�M�o�j
�P�R �����@�@�@�C�����@�@ �R�@���M���A�B��Ȃ�_���i�~�N�\���f�B�A�����������C�����j
�P�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�B��Ȃ�_���B�S�\�̕�
�P�T ��d���@�@�g�����@ �@�P�@���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g��
�P�U �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾����
�P�V �����@�@�@�z�Z���@ �@�P�@����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����
�P�W �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�����ɂ��肵���Ƃ��A�O���ڂɂ�݂�����
�P�X �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@���͐M���A��Ȃ鐹���A�����̗^���傽��҂�
�Q�O �����@�@�d�֒Z���@ �R�@�߂̎͂��̂��߂Ȃ�B��̐����F��
�Q�P �����@�@�@�j�����@�@ �Q�@���҂̂�݂�����Ɨ����̐����Ƃ�҂��]��
����R�����i�T���N�g�D�X�j
�Q�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���Ȃ邩��
����S����
�Q�R �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�S�� �A���A�@���Z���@ �@ �Q�@ ��̌䖼�ɂ��ė���҂͍K���Ȃ�i�x�l�f�B�N�g�D�X�j
�@�@�� �����@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�T �A���A�@�@�g�Z���@ ��Q �@�_�̏��r
�Q�U �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ɕ�����^�����܂�
�@�@�@�@���o�b�n�̃I���W�i���y����S���\���ɂ͑�Q�S�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��Ƃ̢�z�U���i��̋L�ڂ͂Ȃ�
�@�@�@�@���C���ۂɂ͊y�����ɁuOsanna�@repetatur�v�Ƃ���̂ŁA�����͢�x�l�f�B�N�g�D�X��� �Q�S���C�u�z�U���i�v��
�@�@�@�@�Q�S���ƕ\�L����
2009.04.06 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�R
����Q�́F�V�����g���[���@���@���^�[�E�t�F�b�^�[�̌���"��̓��ꂵ����i"�Ƃ͉����H���������ē���Ƃ����̂��H���̈̑�ő��l�Œ���Ō^�j��ȑ��ꂷ�邽�߂Ƀo�b�n������ƂƂ͈�̉��������̂��H�����́u�V�����g���[�v�ł���B���̍Ō�̍�i�ɉ��y�ƂƂ��Ă̑����Z��ژ_�o�b�n���A�|���Ă������y�Z�@�̑S�Ă𒍂����݁A�����̍�i���܂�"�W�߂�"���Ƃ͑O�͂Ŏ������Ƃ���ł���B���Ƃ͂����"��̓��ꂳ�ꂽ�y��"�Ƃ��Ă܂Ƃ߂����邱�ƁA���Ȃ킿���ꂵ���`���������邱�ƁA���ꂪ�o�b�n�̉ۑ�ł������B�o�b�n�͂܂��̑�Ȃ鐔�w�҂Ƃ������Ă���B�ނ̍�i���̓����̈�ɁA�e�Ȃ̑g�ݍ��킹�⏇�ԂȂǂ�����@�����������Đ��R�ƕ���ł���A�Ƃ����̂�����B���̍ł���`�A�S�̂���Ղ��čł����ꐫ����������`�A���ꂪ�u�V�����g���[�v�Ȃ̂��B�l���̑����Z�I��i���c�����Ƃ���Ƃ��A�ނ��S�̂��V�����g���[�ɍ\�����悤�ƍl���邱�Ƃɕs���R���͂Ȃɂ��Ȃ��B"�o�b�n�͊W�߂́u���Z���~�T�v�ɓ��ꐫ���������邽�߂ɑS�̂��V�����g���[�ō\������"�E�E�E�E�E���ꂪ���̉����ł���B
�@ �@��2���u�j�P�A�M���v���V�����g���[�̌`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B�����́u�\���}�v���Q�Ƃ��Ȃ��炲�m�F���������������A����9�ȁi��13�Ȃ����21�Ȃ܂Łj��16�|18��3�̍��������ɂ��āA�����O����15��19���\���i�ȉ��A��d���������ȊO�Ƃ�������ŕX�I�Ƀ\���ƌĂԁj�y�ȂƂ��đΏ́A���̊O��13�{14��20�{21�������Ƃ��đΏ̌`�𐬂��Ă���̂ł���B�����Ńo�b�n��3�̎��i16�|18�j����邽�߂ɃJ�g���b�N�l���ł͂ЂƂ̊y�Ȃ�[15��16]��������ɂȂ��ĂQ�ɕ��f�A15���\����16�������ȂƂ��Ă���B�������邱�Ƃɂ���Č���8�̊y�ȍ\����9�ɂȂ�3�̍����Ƃ������ɂ��V�����g���[���`�����ꂽ�̂ł���B�ł́A�ʂ����ăV�����g���[���`�����邾���̂��߂�"���X��̂���"�f���邱�Ƃ�������邾�낤���B�����ɂ͂���K�R���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�{���ʂȃo�b�n���Ō�̍Ō�ł��������Ȏ�i���u����͂��͂Ȃ��B�ł̓o�b�n�͂ǂ��������A�ǂ��l�����̂��B�ނ̓J�g���b�N�̗l���Ƀv���e�X�^���g�̗l���E���_�𒍓����邱�Ƃł�����ʂ����A���f���邱�Ƃ̑�`�������ʂ������̂ł���B�o���オ�����R�̍������̒��S�i�S9�Ȃ̒��S�ł�����j�ł���5�Ȗڂɂ�17�u����̂��߂Ƀs���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����v�����邱�ƂɂȂ�B�J�g���b�N�̋��`�ł̓L���X�g�̕����ɏd����u�����A�v���e�X�^���g�ł����Y���d������Ƃ����B���̃��^�[�̒��S�v�z�Ƃ������ׂ����Y�҃C�G�X�E�L���X�g���̂��y��17�𒆐S�ɐ����邱�Ƃ̓v���e�X�^���g���k�o�b�n�̐��_�ɂ����v����B�����ł͏\���˂̓��@���t�ł��邪�A���͂��̘a���́u�L���G�v�`���̔ߒɂȋ��тɂ��Ȃ����Ă���̂��B
�@ �u���Z���v�ɂ͂��̂悤�Ƀo�b�n���v���e�X�^���g�̐��_�荞�i�J�g���b�N�̋K�͂����E����j�ӏ������ɂ��U�������B�����ł������܂Ƃ߂Ă������B
�@��W�ȁu��Ȃ�_�A�V�̉��v�̉̎����ADomine�@Fili�@Jesu�@Christe�̂��ƂɁu�Caltissime�v�Ƃ��@�����̎�������A�u���Z���v�̓J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̋K�͂�Z�������G�L�����j�J���i�S����I�j�ȍ�i�Ƃ��Ĉʒu�Â����邱�Ƃ�����B�����Ă��ꂪ���̍�i�̎����Ր��̏ے��ł�����̂��B���Ƀo�b�n���Ӑ}����"�l���̍Ō�ɑS�l�ނւ̕��ՓI���y��Y���c��"���ƂɂȂ����̂ł���B�����Ă��̉e�Ƀo�b�n��������Ӑ}�������́�"�V�����g���["�ɂȂ��鎖�ۂ������B�ꂷ��̂��B
�@������t�����Ă���B�ł������Ƃ����Ӗ��̂��̌��t�̓v���e�X�^���g�̒n���C�v�c�B�q�ł̊�
�@��ɏ]���ĕt���������̂ł���B
�A��22�ȁu���Ȃ邩�ȁv�̉̎����APleni�@sunt�@coeli�@et�@terra�@glonia�@eius�́ueius�v�̓J�g���b
�@�N�̋K�͂ł�tua�ƂȂ��Ă��邪�A�o�b�n�̓��^�[�̐����Ɩ�ɏ]���Ă����ς��Ă���B
�B�Ȃ̂S���\���A���Ȃ킿��P���u�L���G�v�u�O���[���A�v�A��Q���u�j�P�A�M���v�A��R���u�T���N�g�D
�@�X�v�A��S���u�z�U���i�v����u���ɕ�����^�����܂��v�܂Ł@�Ƃ����\���̓J�g���b�N�̃~�T�ł�
�@�ʏ킠�肦�Ȃ��B�܂��u�T���N�g�D�X�v�Ɓu�z�U���i�v����������Ă���̂́A�v���e�X�^���g�̐�
�@�̖{�u������̑I�W�v�ɂ��̗Ⴊ����B����"�ʏ�Ȃ炴�����"�ƍŏ��Ɋ��������̃z�U��
�@�i�̕����́A�o�b�n�̈Ӑ}�ł͂�����������ɂ����������̂ł͂Ȃ��A�v���e�X�^���g�̋K�͂�
�@���������̂������̂ł���B
�C�u�j�P�A�M���v�ɂ����ď\���˂̏͂𒆐S�ɒu�����߂ɁA������̏͂��Q�ɕ��f����
�@�i�O�q�j�B
�@�����I�V�����g���[�̑��݂���P���㔼�u�O���[���A�v�S9�ȁi4�|12�j�̒��ɂ�������Ƃ�����������B����������́u�\���\�v�������������������B�܂��`��4�C5��2�Ȃ̍�����ʊ���Ƃ��ď��O����B[8�\���C9�����C10�\��]�����Ƃ���ƁA���T�C�h6�{7��11�{12���Ώ̂�7�Ȃ̃V�����g���[���\�������Ƃ������̂��B�ł͏��O���ꂽ4�{5�̍����͂ǂ��Ȃ�̂��H�������u�����܂܂ŏ]���̍l�@�͎~�܂��Ă���B���Ȃ킿�u���Z���v�ɂ�����V�����g���[�̍\���͕����I�w�E�ŏI����Ă���̂ł���B���͂���W�����đS�̓I�V�����g���[���ؖ��������B�o�b�n���B�����Í��ɏ]���ĒO�O�ɂق����Ă䂯����͕K���������������ɈႢ�Ȃ��̂��B
�@�ł́A�o�b�n������"�V�����g���[�őS�̂��\������"���Ƃ��v���������̂͂����������̂��낤���B�u���Z���~�T�v���\�z���A��2���u�j�P�A�M���v�̍�Ȃɒ��肵���̂�1746�N�̂��ƁB�O�q�̂悤�ɂ�������8�Ȃ��������邪�A�o�b�n�͂����Ƀv���e�X�^���g�̐��_�𒍓����邱�ƂƑ�2�����V�����g���[�ō\�����邱�Ƃ��v�����B�\���˂�^�Ɉʒu�����邽��3�Ԗڂ̋Ȃ�2�ɕ����S9�ȂƂ���ƁA�^��3�̍��������Ƃ���V�����g���[�����������B���̂��ƃo�b�n�̓O���[���A��9�Ȃɖڂ��ڂ�B�����ɂ��V�����g���[�������Ă����B�A���`��2�Ȃ̍����������āB���̏��O���ꂽ2�̍����Ɓu�L���G�v��3�Ȃ���3���ȍ~�̊y�ȂƑΉ��ł���ΑS�̂̃V�����g���[����������̂ł͂Ȃ����B���ꂱ���ꌩ�A���o�����X�ŊW�߂Ɍ����邱�̋ȂɊm�ł��铝�ꊴ��^������̂ɂȂ�͂��Ȃ����E�E�E�ނ��S�̂̃V�����g���[���\�z�����̂͐��ɂ��̏u�Ԃ������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�o�b�n�F�~�T�ȃ��Z���̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́��̐�
����P����
�i�L���G�j�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j
�@�P �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@������݂��܂�
�@�Q ��d���@ �j�����@ �@�Q�@�L���X�g��A����݂��܂�
�@�R �����@�@�d�֒Z�� �@ �R�@���A����݂��܂�
�i�O���[���A�j
�@�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���ƍ����Ƃ���ɂ͐_�ɉh������Ƃ�
�@�T �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@�n�ɂ͑P�ӂ̐l�X�ɕ��a����
�@�U �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@�������ق�
�@�V �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@��̂������Ȃ�h���̂䂦�ɂ����Ɋ��ӂ��Ă܂�
�@�W ��d���@�@�g�����@ �@�P�@��Ȃ�_�A�V�̉�
�@�X �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@���̍߂��̂��������҂�
�P�O �A���A�@�@���Z���@ �@�Q�@���̉E�ɍ����������̂�
�P�P �A���A�@�@�j�����@ �@�Q�@���̂ݐ��Ȃ�
�P�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@����ƂƂ���
����Q�����i�j�P�[�A�M�o�j
�P�R �����@�@�@�C�����@�@ �R�@���M���A�B��Ȃ�_���i�~�N�\���f�B�A�����������C�����j
�P�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�B��Ȃ�_���B�S�\�̕�
�P�T ��d���@�@�g�����@ �@�P�@���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g��
�P�U �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾����
�P�V �����@�@�@�z�Z���@ �@�P�@����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����
�P�W �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�����ɂ��肵���Ƃ��A�O���ڂɂ�݂�����>
�P�X �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@���͐M���A��Ȃ鐹���A�����̗^���傽��҂�
�Q�O �����@�@�d�֒Z���@ �R�@�߂̎͂��̂��߂Ȃ�B��̐����F��
�Q�P �����@�@�@�j�����@�@ �Q�@���҂̂�݂�����Ɨ����̐����Ƃ�҂��]��
����R�����i�T���N�g�D�X�j
�Q�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���Ȃ邩��
����S����
�Q�R �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�S�� �A���A�@���Z���@ �@ �Q�@ ��̌䖼�ɂ��ė���҂͍K���Ȃ�i�x�l�f�B�N�g�D�X�j
�@�@�� �����@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�T �A���A�@�@�g�Z���@ ��Q �@�_�̏��r
�Q�U �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ɕ�����^�����܂�
�@�@�@�@���o�b�n�̃I���W�i���y����S���\���ɂ͑�Q�S�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��Ƃ̢�z�U���i��̋L�ڂ͂Ȃ�
�@�@�@�@���C���ۂɂ͊y�����ɁuOsanna�@repetatur�v�Ƃ���̂ŁA�����͢�x�l�f�B�N�g�D�X��� �Q�S���C�u�z�U���i�v��
�@�@�@�@�Q�S���ƕ\�L����
2009.03.30 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�Q
����P�́F�ʏ�Ȃ炴����́������A���̋Ȃ�"���̃~�T�ȂƈႤ"�A�Ǝv�����ŏ��̂��������͑�23�ȁu�z�U���i�v�ł���B�����́u�\���}�v�������������������B�����ŕ�����悤�Ɂu�z�U���i�v�͈�̍����ȂƂ��ēƗ����Ă���B�u�z�U���i�v�́i���̂���܂ł̒m���ł́j�u�T���N�g�D�X�v�܂��́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɕt�������Ȃł���Ɨ������y�ȂƂ��đ��݂��Ă����͂Ȃ��B�����������͎��ԓI�ɂ��Z���A���́u���Z���v�̂悤�ɂR���ɋy��Ƃ����K�͂Ȃ��̂͊F���ł���B�u�T���N�g�D�X�v�͖`���Łu���Ȃ邩�ȂƂ����Ӗ���Sanctus�v���R��J��Ԃ��ꂽ��A�u���R�̎�Ȃ�_�A��̉h���A�V�ƒn�ɖ��Ă�v�ŏI���B�u�z�U���i�v�́u���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�v�ƊԂ����ɂ���ɑ����i���݂Ɂu�z�U���i�v�Ƃ́A�C�G�X�E�L���X�g���C�G���T�����ɓ��邵���ۂɌQ�W�����������Ă̋��тł���j�B
���́u�z�U���i�v���܂ށu�T���N�g�D�X��Sanctus�v�̉̎��͈ȉ��̂Ƃ���ł���B"Sanctus�CSanctus�CSanctus�@Dominus�@Deus�@Sabaoth�DPleni�@Sunt�@Coeri�@et�@terra�@gloria�@ejus�DOsanns�@in�@excelsis"�B�Ȃ��u�T���N�g�D�X�v�̍Ō�̌�� ejus �́A�J�g���b�N�ʏ핶�ł�tua�ł��邪�o�b�n�͂��̕������v���e�X�^���g���ɒu���ウ�Ă���B�����̗�͑��ɂ����X����̂ł܂Ƃ߂Č�q�������B
��S���ɒu���ꂽ��24�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�͈�ȂŊ����Ă��邪�A�y���Ŋm�F���Ă݂�ƁA�e�m�[���E�\���ʼn̂��郍�Z���̊ɏ������i24���j�̂��Ƃ�"�u�z�U���i�vrepetatur"�Ə�����Ă���B�����23�u�z�U���i�v�����̂܂܌J��Ԃ��i24���j�Ƃ������ƂȂ̂Łu�z�U���i�v�͑�S�����ɂ�2�Ȋ܂܂��킯���B�Ƃ��낪�o�b�n�̎��M���̑�S��������\���́A�ォ��uOsanna�v�uBenedictus�v�uAgnus�@Dei�v�uDona�@nobiis�@pacem�v�i���ۂ̕\�L�ɂ́u�v�͂Ȃ��j�Ə�����Ă��ĂS�Ȃ����\�L����Ă��Ȃ��B����5�ȁA�\�L4�Ȃł���B
���Ȃ킿�u���Z���~�T�v�ɂ�����u�z�U���i�v�͑�K�͂ŁA�u�T���N�g�D�X�v��u�x�l�f�B�N�g�N�X�v���番���Ɨ����Ă���B���̂悤�ȗ�͑��̃~�T�Ȃɂ���̂��낤���H�@�����Ă݂�B
�V�����p���e�B�G�F�^�钆�̃~�T�@�T���N�g�D�X�i�ȉ��r�j�{�z�U���i�i�ȉ��g�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�l�f�B�N�g�D�X�i�ȉ��a�j�{�g
�x�[�g�[���F���F�����~�T�@�@�@�@�@ �r�g�C�a�g
�V���[�x���g�F�~�T�ȑ�U�ԁ@�@�@�@�r�g�C�a�g
�x�����I�[�Y�F���N�C�G���@�@�@�@�@�r�g
�V���[�}���F���N�C�G���@�@�@�@�@�@ �r�g
���F���f�B�G���N�C�G���@�@�@�@�@�@�@�r�g�C�a�g
�h���H���U�[�N�F���N�C�G���@�@�@�@ �r�g�C�a�g
�t�H�[���F���N�C�G���@�@�@�@�@�@�@ �@�r�g
�u�z�U���i�v�͗�O�Ȃ��u�T���N�g�D�X�v���u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ɕt��������̂Ƃ��Ďg���Ă���A�u���Z���v�̂悤�ɒP�Ƃň�̊y�ȂƂ��Ĉ����Ă���̂͊F���ł���B�ܘ_�u�T���N�g�D�X�v�ł̕����Ɓu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł̓���Ƃ����Ⴄ�\�L���������Ă������܂������Ȃ��B
�ȏ�A�����u���Z���v�̒���"�ʏ�Ȃ炴�����"�Ƃ��čŏ��Ɋ������u�z�U���i�v�̌`�ł���A���̌`�����o�b�n��"�Ȃꂷ��Ƃ����ӎu"��������Í����o�b�n�E�R�[�h�iBC�j�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƒ��������킯�ł���B��������������ɐ����ƌ����d�˂邱�Ƃɂ��ABC�͑S���łS���݂��邱�Ƃ����������B�����Ă��̂S��BC�ɂ�荡�܂ŒN��l�Ƃ��ċC�Â��Ȃ������A�o�b�n�����̊y�Ȃɂ��߂��ӎu�A���Ȃ킿��������ؔ������̒��Łu����̉��y�ƂƂ��Ă̏W�听���鉹�y��Y��"���ꂵ����̊y��"�Ƃ��Č㐢�Ɏc���v���Ƃ��A�ǂ�����ĒB�������̂��Ƃ����閧���𖾂����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�o�b�n�F�~�T�ȃ��Z���̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́��̐�
����P����
�i�L���G�j�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j
�@�P �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@������݂��܂�
�@�Q ��d���@ �j�����@ �@�Q�@�L���X�g��A����݂��܂�
�@�R �����@�@�d�֒Z�� �@ �R�@���A����݂��܂�
�i�O���[���A�j
�@�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���ƍ����Ƃ���ɂ͐_�ɉh������Ƃ�
�@�T �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@�n�ɂ͑P�ӂ̐l�X�ɕ��a����
�@�U �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@�������ق�
�@�V �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@��̂������Ȃ�h���̂䂦�ɂ����Ɋ��ӂ��Ă܂�
�@�W ��d���@�@�g�����@ �@�P�@��Ȃ�_�A�V�̉�
�@�X �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@���̍߂��̂��������҂�
�P�O �A���A�@�@���Z���@ �@�Q�@���̉E�ɍ����������̂�
�P�P �A���A�@�@�j�����@ �@�Q�@���̂ݐ��Ȃ�
�P�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@����ƂƂ���
����Q�����i�j�P�[�A�M�o�j
�P�R �����@�@�@�C�����@�@ �R�@���M���A�B��Ȃ�_���i�~�N�\���f�B�A�����������C�����j
�P�S �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�B��Ȃ�_���B�S�\�̕�
�P�T ��d���@�@�g�����@ �@�P�@���͐M���A�B��̎�A�C�G�X�E�L���X�g��
�P�U �����@�@�@���Z���@ �@�Q�@����ɂ��āA�����}���A���䂩�炾����
�P�V �����@�@�@�z�Z���@ �@�P�@����̂��߂Ƀ|���e�B�I�E�s���g�̂��Ƃɏ\���˂ɂ����
�P�W �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���͐M���A�����ɂ��肵���Ƃ��A�O���ڂɂ�݂�����>
�P�X �A���A�@�@�C�����@ �@�R�@���͐M���A��Ȃ鐹���A�����̗^���傽��҂�
�Q�O �����@�@�d�֒Z���@ �R�@�߂̎͂��̂��߂Ȃ�B��̐����F��
�Q�P �����@�@�@�j�����@�@ �Q�@���҂̂�݂�����Ɨ����̐����Ƃ�҂��]��
����R�����i�T���N�g�D�X�j
�Q�Q �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@���Ȃ邩��
����S����
�Q�R �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�S�� �A���A�@���Z���@ �@ �Q�@ ��̌䖼�ɂ��ė���҂͍K���Ȃ�i�x�l�f�B�N�g�D�X�j
�@�@�� �����@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ƍ����Ƃ���Ƀz�U���i�i�z�U���i�j
�Q�T �A���A�@�@�g�Z���@ ��Q �@�_�̏��r
�Q�U �����@�@�@�j�����@ �@�Q�@ ���ɕ�����^�����܂�
���o�b�n�̃I���W�i���y����S���\���ɂ͑�Q�S�ȁu�x�l�f�B�N�g�D�X�v�̂��Ƃ̢�z�U���i��̋L�ڂ͂Ȃ����C���ۂɂ͊y�����ɁuOsanna�@repetatur�v�Ƃ���̂ŁA�����͢�x�l�f�B�N�g�D�X��� �Q�S���C�u�z�U���i�v�� �Q�S���ƕ\�L����
2009.03.21 (�y) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�P
�@���̓o�b�n�́u���Z���~�T�v�̊y�����߂����Ă����B�����I���ɋ߂���25�ȁu�_�̏��r�v�̏�ŁA�ˑR���̖ڂ͓B�t���ƂȂ����B�����ɂ́����ł���`�g�Z���B���̑���25�Ȃɂ͑S�ā������Ă���̂ɂ���͗B��t���b�g�n�̋ȁB�Ȃ������ɁH�Ȃ��o�b�n�͑�25�Ȃɂ��̒�����I�̂��H�E�E�E����͂����Ɖ����̈Í��ɈႢ�Ȃ��B�����o�b�n�E�R�[�h�I�@�ނ͂����Ƀ��b�Z�[�W�𑗂��Ă���B���͂����m�M�����B�����́�
�@���n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�i1685�|1750�j�́u�~�T�ȃ��Z���v�́A�v���e�X�^���g���k�̃o�b�n���J�g���b�N�̃~�T�̘g�g�݂̒��ɁA���y�ƂƂ��Ă̑S�\���X���Đl���̍Ō�Ɋ���������i�ł���B���̒��ɂ͐V���ɍ�Ȃ����Ȃ�����A�����̊y�ȂĂ͂߂��p���f�B�[������B���̋K�͂͂S��26�Ȃ���Ȃ�A���t���Ԃ�2���Ԃ��z����Ƃ��������ł���B���̒����A�K�͂̑傫���͎��ۂ̃~�T�Ɏg����͂����Ȃ��A�܂����̋L�^���Ȃ��B�ł́A�o�b�n�͂Ȃ��l���̍Ō�̍Ō�ɂ���ȋȂ������������̂��낤���H�v���e�X�^���g���k�̃o�b�n���Ȃ��J�g���b�N�l���̃~�T���������̂��낤���A�ȂǂȂǐ̂��特�y�w�҂̊Ԃł��܂��܂ȋ^���ӌ�����ь����A���y�j��ő�̖���ɂȂ��Ă�����B�Ⴆ�A�o�b�n�����ƂƂ��Ė������t���[�h���q�E�X�����h�́u��ȂƂ��ē��ꂳ�ꂽ�w���Z���~�T�x�Ƃ������̂͑��݂����A�݂��Ɋ֘A�̂Ȃ�4�̕������������Ă���ɉ߂��Ȃ��v�Ǝ咣���Ă���B�܂��A19���I�o�b�n�����̑n�n�҂Ƃ�������t�B���b�v�E�V���s�b�^�́u�Ȃ̌㔼�́A�啔�����p���f�B�[�ł���J�͂��g���Ă��Ȃ��B�o�b�n�͍�i���d�グ�邽�߂ɁA�}�����悤�Ɏv����v�Ɛ������Ă���B��ȉƂ̍Ō�̍�i�ł́A���N��Ԃ̈����P�[�X�������B���[�c�@���g������A�V���[�x���g������A�o�b�n����O�ł͂Ȃ������낤�B���肭�鎀���ӎ�����A�������}���C�����������Ȃ�͓̂��R�ł���B�����ɂ���Ȉӌ����o�Ă���w�i������킯���B
�@ �@�ł͂����ł��̋Ȃ̐��藧���ƍ\����͂�ł��������B��3���u�T���N�g�D�X�v��1724�N�̍�i���̊y���͓����{�w�~�A�̃V�F�{���t�������L���Ă������A���݂̓x�����������}���ُ����j�B��1���u�L���G�v�u�O���[���A�v��1733�N�ɍ�ȁA�J�g���b�N�l���ɂ���ă��e����ŏ�����Ă���A�U�N�Z���I���t���[�h���q�E�A�E�O�X�g2���Ɍ��悳��Ă���B�u�T���N�g�D�X�v�ɑ����u�z�U���i�v��1734�N�̍�ɂȂ鐢���J���^�[�^�u���̂��K���]����vBWV215�̖`������]�p�i�p���f�B�[���j���Ă���i���̋Ȃ����������J���^�[�^�w�����Ȃ鉤��A���xBWV�D�`����11����̓]�p�j�B��Q���u�j�P�A�M���v��1747�N����1748�N�ɂ����āA��4���́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�u�_�̏��r�v�u���ɕ�����^�����܂��v��1748�N����1749�N�ɂ����č��ꂽ�B���̍\���́A��1�����u�L���G�v�Ɓu�O���[���A�v�i12�ȁj�A��2�����u�j�P�A�M���v�i9�ȁj�A��3���u�T���N�g�D�X�v�i1�ȁj�A��4���́u�z�U���i�v�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�u�_�̎q�r�v�u���ɕ�����^�����܂��v�i4�ȁj��4��26�Ȃ���Ȃ�B
�@ �@��P���`���́u�L���G�v�B���̐l�Ԃ̋Ɍ��̋�Y��\�o����悤�Ȉٗl�ȋ����ɏՌ����Ȃ��l�͂��Ȃ��B���̏��t�ɑ����啔�͌ܐ��̃t�[�K���s��ɓW�J���A������2�Ȃ̓\�v���m�ƃA���g�̓�d�����u�L���X�g���������v�Ɛ����ɔ������̂��グ�A��3�ȑ�2�́u�L���G�v�ł͑��d�ȌÂ��l���̃t�[�K���t�ł���B�S�ĒZ���ō\�����ꂽ�u�L���G�v�̂��ƁA�u�O���[���A�v�͖��邭�͋����������_�̉h�������t�ȕ��ɑ�炩�ɑt�łĎn�܂�B��9�C10�Ȃ͒Z���ł͂��邪�A�u�L���G�v�ɂ�����ߌ����͂Ȃ��B��2���u�j�P�A�M���v�͗B���Ȃ�_�A�B��Ȃ��C�G�X�E�L���X�g�ɕs�ς̐M�S��\���p�[�g�Łu�N���h�v�Ƃ������B�����Ńo�b�n�̓v���e�X�^���g�̐��_���������߂̗��Z��p���Ă��邪�A�ڍׂ͌�قǁB��3���́u�T���N�g�D�X�v�P�Ȃ̂݁B�u�T���N�g�D�X�v�͐��Ȃ邩�ȂƂ����_�ւ̊��ӂ̎]�̂ł���B��4���͖{���u�T���N�g�D�X�v�Ɋ܂܂��u�z�U���i�v���藣����Ė`���ɒu����L���X�g�ւ̊��Ă��̂��グ��i�o�b�n�͒ʏ��Hosanna�Ƃ����\�L��Osanna�Ƃ��Ă��邪�A�����ł͒ʏ�ʂ�u�z�U���i�v�ƕ\�L����j�B�u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�ł͐_�̌䖼��艺�苋�����L���X�g�ւ̏j�����e�m�[���ɂ��̂���B���������u���ꂽ�u�z�U���i�v�͖`���ƑS���������̂��������ł́u�x�l�f�B�N�g�D�X�v�Ɋ܂܂��`���Ƃ��Ă���i�y���ɂ�Osanna�@repetatur�Ƃ���j�B�u�_�̏��r�v�͏d���Ōh�i�ȃA���g�̃A���A�B�I�Ȃ͍������u����ɕ�����^�����܂��v�Ɖ̂��B
�@�����A�\���A��d���Ȃǂ̌`�ԁB���t�ȁA�t�[�K�A�J�m���Ȃǂ̗l���B�]���A�y��Ґ��A�����≹�^�Ȃǂ̍�ȋZ�@�B����炪���푽�l�ɑg�ݍ��킳��剾�����`�������B����܂łɔ|���Ă������y�Z�@�̑S�Ă𒍓��������y�ƃo�b�n�̐��ɏW�听�I��i�Ȃ̂ł���B
�@������ɐ�q�����悤�Ɂu�w���Z���x�͒P�Ȃ�W�߂̍�i�A���ɑ�4���͔��藈�鎀��\�����ăA�����m�ŊԂɍ��킹�Ē��K�����킹���v�ȂǂƂ��������I���������݂���B�͂����Ă������낤���B�o�b�n������Ȃ��������ȍ��������邾�낤���B����̎���\�������A���Ȃ̉��y�ƂƂ��Ă̏W�听�Ƃ��Č㐢�ւ̈̑�ȉ��y�I��Y���c�����Ƃ��Ă��邠�̑�o�b�n��"�P�Ȃ�W��"�̂܂ܑn����~�߂Ă��܂����낤���B���₱�̋Ȃ��W�听�Ƃ��Ďc�����Ǝv�����������ɂ́A���łɂ��̍�i��"��̓��ꂵ����i�Ƃ��Ċ�������"�Ƃ������m�Ȉӎu����ɂ������͂��ł���B����́u�o�b�n�͂قƂ�ǂ̑��ɂ����āA�Η�������̂��ЂƂɂ܂Ƃ߁A�����ɒ[�Ȋ��o�I�܂��͎u���I�ΏƂ�"���ꂷ��"���Ƃɐ������Ă���B���̑����́A�S�̂̑n��ɂ����Đ��U�A�\�������̂ł���v�Ƃ������@���^�[�E�t�F�b�^�[�̐��ɂ���Ă����Â�����邾�낤�B���̐��̒��œ��ɒ��ڂ������̂�"���U"�Ƃ��������ł���B�o�b�n��"���ꂷ��"�Ƃ����u���͐��U�������Ƃ������Ƃł���A����͐��U�Ō�̍�i�ƂȂ����u���Z���~�T�v�ɂ��y��ł���Ƃ������Ƃ��B
�@�ł͔ނ͂ǂ�ȕ��@�ł���"�̑�ő��l�Œ���Ō^�j��ȑ��"��"���ꐫ"���������悤�Ƃ����̂��낤���H������������͂���̂��낤���H�E�E�E��ɂ���B�u�o�b�n�͎���̈ӎu���������̈Í��ɑ����Ă��̋Ȃɖ��ߍ��v�Ƃ����̂����̉����ł���B���̃o�b�n�E�R�[�h�����̑�Ȃ钴���u�~�T�ȃ��Z���v�ɔ�߂�ꂽ����������ƂȂ�̂ł���B�X�����h���V���s�b�^�����̈Í��ɋC�Â��Ă��Ȃ��B�t�F�b�^�[���������̐��̒��Łu���Z���v�̓��ꐫ��������̓I�Ȏw�E�͂��Ă��Ȃ��B�������̂��̉������������ؖ������Ȃ�A�o�b�n�����̋Ȃɑ������S�l�ނւ̎v�����N���Ȍ`�ƂȂ��Č����͂��ł���B
2009.03.09 (��) �b����\�\�`���C5
�����O�A�`���C�R�t�X�L�[�́u������ ��5�� �z�Z�� ��i64�v�ŗ��đ����ɕ����@�����܂����B�ܘ_�m��Ȃ��Ȃł͂Ȃ������̂ł����A�}�ɐe���݂��N���Ă��āA���̋Ȃ��ɂ߂Ă݂����Ƃ����~���ɋ���܂����B�u�ɂ߂悤�v�Ǝv���Ă������肢����̂́ACD���P�ʂ̏��L�Җ����L�����p�X���Ԃ�H�y�����B�ނɗ��ނƂ��́A�܂������̎莝��CD�ƕ����������t�҂���A�u���̂ق��ɐ��E�Ղ�����ΐ���v�ƌ����Ă��肵�܂��B���̂Ƃ����́u�`���C5�v�̎莝���́A�����g�D�[58�A�Z��59�A�������B���X�L�[60&77�A���[�g���B�q60�A�X�g�R�t�X�L�[65�A�J������84�A�o�[���X�^�C��88�A���X�g���|�[���B�`91�A�Q���M�G�t98�ł����B�ނ���肽�̂́A�P���y��51�A�V�����F�X�g��57�A�N�����y���[63�A�����g�D�[63�A�������B���X�L�[73&78�A�x�[��80�A���[�e�B81&91�A�����82&01�@�ȂǁB���[�e�B��2���肽�̂́A����u�`���C5�v���ɂ߂����Ǝv�����L�b�J�P�̈��2008�N9��14���~���[�U���ł̃��[�e�B&�E�B�[���E�t�B�����t���������ł��B�w���҂̓����̉��I�P�S�̂����_�I�Ɋ��S�Ɉ�̂ƂȂ��Ă���l���A���o�I�ɂ����o�I�ɂ����m�ł����f���炵���̌��ł����B���肵��2���̃��[�e�B�̂����A81�N�̂ق��̓U���c�u���N���y�Ղł̃��C�u�B���̏I�y�̖͂\�������܂�Ɉُ�Ńr�b�N�����܂����B�P���y���͏��N����`���C5�̒�Ԃ��������̂��ēx���̋@��ɂƂ����v���ŁB����͓����Ƃ��Ă͉����悭���t���������肵�����́B�����01�͔ނ̃��X�g�E�R���T�[�g�̖��É��̃��C�u�Ŕi�B�h�C�c���y�̌����E����ލŌ�̋Ȃ��u�`���C5�v�������͈̂ӊO�ł����B���t�B���̃����o�[�������Ȃ��牉�t���Ă����Ɠ`�����Ă��܂����A�m���ɃI�P�̋����ɂ͚T�苃�����h���Ă��܂��B�����܂ł͂����̂Ƃ���ł����B���������̂́A�y�������u�N�X���Ƃ����T�C�g�Ƀ`���C5�̃R�[�i�[������B�ʔ����ł���v�Ƌ����Ă��ꂽ���Ƃł����B�����`���Ă݂܂����B�Ȃ�ƁA�����ɂ́A�M�����Ȃ��悤�ȃ`���C5�̃f�B�X�R�O���t�B�[������܂����B1921�N�^���X�g�R�t�X�L�[�w���F�t�B���f���t�B�A�ǂ���n�܂��āA�قڂ��ׂẴf�B�X�N���Ƃ肠�����Ă��܂��B���̐���370�_�B��������v�ȃ��R�[�h�ɂ͂���l�̃R�����g�܂ŕt���āB����l�̖��O�͓c����������B�����Ă��̃R�����g����┼�[����Ȃ��B���̋Ȃ�"�c�{"�ɉ����Ă̌����ȉ��t���͂��W�J����Ă���B���̃c�{�̐������A�Ȃ��33�ӏ��I
�Ⴆ�u�c�{10�v�i��2�y�͖`���ƃz�����E�\���j�ɂ͂�������܂��B
�E �`���ጷ�ɂ�铱�����̃j���A���X�́H�@�Ƃ�������B�������y������ŁB�ł͂���ɉ����ēc�����ǂ�ȃR�����g�����Ă��邩�H���̕��������̑�D���ȁu�V�����e�B�w���F�p�����y�@�nj��y�c56�v���ɉ��L�B
�E 9���ߖڂ���̃z������\���ydolce con molto espress������߂ď_�炩���L�Ɂz�Ƃ����w������
�@����������Ă��邩�H
�E �z������\���̗͗ʁA�Z���X�́H
�E �N�����l�b�g�Ƃ̗���́H
�E ���̌�A24���߂���I�[�{�G���������������ycon moto=�����������āz�Ƃ̃R���g���X�g�́H
�`���̒ጷ�́A���ꎩ�̂��e�[�}�ł��邩�̂悤�ɋ��͂Ɏ咣�B�A�[�e�B�L�����[�V�����������B�Z���ȃ��B�u���[�g�������I�ȃe�[���F�̃z��������i�B���o�I�Ɉَ��ɕ������邪�A�Ƃ낯������ƍׂ₩�ȃt���[�W���O�ɜ����I���ꂪ�����邾���ł����̃`���C5�̖��͂͑傫���B���ރN�����l�b�g�ƃI�[�{�G���j��ō��N���X�̍I���B�ݒ肵���u�c�{�v��S�ĉ������������ȕ��͂ł��B���͈��Ղ�"�j��ō�"�Ȃ��ƌ�����Ɣ����������Ȃ鐫�i�ł����A���̕��ɂ͕��傪�����܂���B�Ȃɂ��A���̒��q��33�ӏ��������̂ł��B���������ł�100�_���鉉�t�ɂ��̍�Ƃ��{���Ă���̂ł�����B�������Č��������t�Ŕނ̂��ዾ�ɂ��Ȃ����f�B�X�N�ɂ�
"excellent"�}�[�N�������Ă��܂��B���ꂪ�܂������B���������Ƃ��Ȃ��悤�Ȏw���҂���{�̒n���I�P�̉��t�ɂ��̃}�[�N���t���Ă��܂��B�����ɔ����ĕ����Ă݂�Ƃ��ꂪ�����ɑf���炵���̂ł��B��������`���C5�Ɠc������̗��ɂȂ������́Aexcellent�}�[�N�𗊂�ɔ��������A10�������Ȃ������`���C5CD���P������50�����z���Ă��܂��܂����B�܂��Ɂu�`���C5 ���m�Ƃ̑����v�ł����B
�`���C5���L�b�J�P�ɂ��܂�Ɋ����������́A�c������Ƀ��[����ł��܂����B�u���Ȃ��̂悤�ȕ��������ɐi�o���Ă����獡�̕]�_�Ƃ͑��ɂȂ��Ă��G��Ȃ��ł��傤�v�ƁB���̌㉽�x�����[���̂����������Ă��������Ă��܂��B���݂Ɂu�g�c�G�a���a��V�v�łƂ肠�����I���o�[�E�V���j�[�_�[���c�����狳��������̂ł��B�c�����ꂩ�����낵�����肢�������܂��B�F���������u�N�X���v�T�C�g��`���Ă݂Ă��������B�f���炵�����E���J���邱�Ɛ��������ł��B
�Ō�Ɂu�}�C�E�`���C5�x�X�g5�v�����������Ă��������u�b����v����悤�Ǝv���܂��B�@�|�C�͓c�������excellent�}�[�N�t�i�D�͕]���̂��̂��܂�����܂���j�B�����ł̃R�����g�͕s�ю��ł��B�������炸�B
�@ �m�[�}���E�f���E�}�[�w���F�����h���E�t�B���n�[���j�[79����A�u�w�o�b�n�E�R�[�h�x�`�~�T�ȃ��Z���ɉB���ꂽ��v�����͂����܂��B�ߔN�̌����ŁA�i�D�r�D�o�b�n�̍Ō�̍�i�́u�t�[�K�̋Z�@�v�ł͂Ȃ��u�~�T�ȃ��Z���v�Ƃ������Ƃ��͂����肵�܂����B���ȉƂ̍Ō�̍�i�ɂ͓�̃^�C�v������܂��B����́u�Ō�Ƃ������Ƃ��ӎ����ď��������ۂ��v��������ڂƂȂ�̂ł����A�o�b�n�̏ꍇ�͊ԈႢ�Ȃ�"�Ō�̍�i"���ӎ����ď����Ă��܂��B����ȁu�~�T�ȃ��Z���v�ɑ��āA�u�ʂ̎����ɏo�����l�X�Ȋy�Ȃ��W�߂������̍�i�Ȃ̂ŁA���ꊴ���S���Ȃ��v�ȂǂƂ��������I�]�����m���ɑ��݂��Ă��܂��B���͂��˂��ˁA���̑�o�b�n�́u�~�T�ȃ��Z���v���P�Ȃ�W�߂ł���킯���Ȃ��A�Ō�̍�i�ɑ����������ꊴ���`�����邽�߂ɁA�o�b�n�͕K���������{���Ă���͂����A�Ƃ����m�M�������Ă��܂����B����ȉ����ɑ��A������ˑR�M�������̂�����܂����B����͂�������n�܂�܂��B
�A�[�e�B�L�����[�V�����i�y�z�̕ω��Â��j�������܂ő����ɂ��Ȃ���A����قǎ��R�ɕ������鉉�t���H�ł��B�ǂ��W�J���邩�\�������Ȃ����A����Ă炤�Ɏ~�܂�Ȃ������x�̍��������B���̍����C�M���X���������̖��́B
�A ���h���t�E�P���y�w���F�x�������E�t�B���n�[���j�[59
������肵���e���|�ŔZ����搂����������A�����ȃe���|�̗h������́B�m�M����߉ɂ͗L�������킹�������������܂��B�����Ȃ��ƕ������Ă��Ă��Ƃ��Ă��܂������̖��͂Ƃ��������͋C�ł��傤���B
�B ���h���t�E�A���x���g�w���F�Z���g�E�\���nj��y�c59
�����ȋ����̒��ɃL�����Ƃ����R����Y���A�i�������������d�オ��B��2�y�͂̃z�����E�\���̃t�����X�I���F�ƃ��j�[�N�Ȑ߉͗d�����܂łɔ�������i�̎����܂��B
�C �W�����W����v���[�g���w���F�j���[��t�B���n�[���j�A�nj��y�c64
���y���ɏ��H�͂Ȃ����݂͗I�R�Ƃ��Ă��܂��B���������m�Ȃ̂ŗ֊s����������ƕ����o�ăe�N�X�`���A����������ƌ��ʂ��܂��B�t���[�Y�ׂ͂Ƃ����ƂȂ���ۂ͗���B�m�Ə�̃o�����X����̖��l�|�B
�D �G�t�Q�j�E�X���F�g���[�m�t�w���F�\���B�G�g�����nj��y�c90
�傫�ȍ\���ƖL��ȋ����̓��V�A�̑�n���霂Ƃ����Ă���܂��B�Ƃ͂�������̓��V�A�I�������R���[�̐��E�ł͂Ȃ��A�ނ��낻���ɂ͖��邭�D������ݍ��ނ悤�ȉ��y�̗��ꂪ����܂��B���Ă���Ƃ��ȂǁA�����l���������ɐg���ς˂����Ƃ��ɍœK�ł��B
2009.03.02 (��) �b����\�\�u�t�B�K���̌����v�^���̎p ����k
�u�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v���n�܂����̂���N5���B�ŏ��́u�t�B�K���̌����v�{���̔��A���ł����B���N���߂Ă����͍쎩�M��H�͂��߂ăl�b�g�ɍڂ�̂��������āA�F�l�m�l�ɒm�点�܂���܂������A�����̓C�}�C�`�ł����B�c�O���[�[��B�u�}�j�A�b�N������v�Ƃ����]�����������ł��ˁB�u�̎��Ƌȏ�����ʂ�Â���A�ǂ��������������v�Ƃ������ɒP���Șb���Ǝ��͎v���Ă���̂ł����B����Ƃ��A�F�l�̒m�l�Ńv���̃s�A�j�X�g�̕������z���Ă��������܂����B�u���[�c�@���g�Ɍ��炸�A�I�y���̋ȏ��Ȃ��㉉�̂��тɕς���͑����̂�����A���܂�C�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ���Ȃ��́B�̎��������Ƃ�������ǁA�ǂ��炪���y�I�ɗ��ꂪ�悢���������Ȃ��ƈӖ����Ȃ��̂ł́v�Ƃ������́B�l�n���ɂ��Ă���Ǝv���܂������A���_�͂�߂Ă����܂����B���̊��z�ɑ��Ďv�������Ƃ́A"���̕��^���ɓǂ�ł���ĂȂ���"�Ƃ������Ƃł����B��͂�A�����̑f�l�͑���ɂ���Ȃ��E�E�E�B�ł�������ł���B�u�N�����m�v�͑��l�l�ɓǂ�ł����������Ƃ��A�����̎v�����������߂邱�ƂɈӋ`������̂ł�����B����Ȓ��A�ŋ߁AYAHOO������"�J�������ƃA�E��"�Ƃ�"�P�l�f�B�ƌܖ��N�S"�Ƃ������Ɓu�N���V�b�N���m�Ƃ̑����v��������܂��B���l�l�ɒm���ĂȂ��Ă��������{�b�g�ɂ͔F�m����Ă���H
�u�t�B�K���v�A�ڂ��I�������N6�����̂��ƁB"���������V���̃��[�c�@���g�̂��߂ɔނ̖{�ӂ��������̂ł�����A���ꂩ��́u�t�B�K���v�͂��������Ăق���"�Ƃ����肢�����߂āu���ۃ��[�c�@���e�E�����c�v�ɓ��������܂����B��Ђ̑��y��ʂ��āA���c�B��̓��{�l�����ł�����C�V�V�q�搶�ɕ����������肵�܂����B�ȉ����̎莆�̑S�����f�ڂ��܂��B
�C�V�V�q�搶�c�O�Ȃ���A�搶��������[�c�@���e�E�����c������A����܂őS������������܂���B����Ă��ꂽ��y�����x���A���������グ�Ă���悤�Ȃ̂ł����B�����A�Ȃ̂ł��傤���H
�@���߂Ă��ւ肳���Ă��������܂��B���̓��[�c�@���g�ɌX�|����ꉹ�y���D�Ƃł��B�ŋ߁A�ӂƂ������R����̌��u�t�B�K���̌����v�̋����[���ǖʂɂԂ���܂����B��́A��4����13��ɂ�����t�B�K���̃Z���t���̏��ɂ���ē�ʂ肠�邱�ƁB������͑�3���u�ٔ��̏�v�����ɂ����y�ȏ�����ʂ肠�邱�Ƃł����B��҂̓��E�o���[�����C�o�[�����Ƃ��Č��\�m���Ă��鎖���ł����A�O�҂�"dispetto"��"rispetto"�̕����ɂ��܂��Ă͂��܂茾�y����Ă��Ȃ��悤�ł��B
�@���������Ȃ�ɒNj������̂��ʎ��Y�t�����Ă��������܂����u�w�t�B�K���̌����x�^���̎p�v�Ƃ��������_���ł��B���̌��_�́A�u�V���[�c�@�c�g�S�W�v�́u�t�B�K���̌����v�̓��[�c�@���g���Ӑ}�����`�ɂȂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B�u�V�S�W�v��Ҏ[�����͍̂��ۃ��[�c�@���e�E�����c�ł�����i���̂��Ƃ͐搶�̋ߒ��u���[�c�@���g�̉��L�v�ŋ����Ă��������܂����j�u���c�v��2�ӏ��̒�����������Ƃ������Ƃł������܂��B
�@���ۃ��[�c�@���e�E�����c�������I���̔N���������A���Ẳb�q����g���ĕҎ[�����u�V�S�W�v�ɁA���m�̈�f�l���y���D�҂��C�Â��悤�ȊԈႢ�����݂���Ȃ�ĐM�����Ȃ��Ƃ��v���ɂȂ�͓̂��R�̂��Ƃł��傤�B�����u�V�S�W�v���ԈႢ�ł���Ƃ̌��_���o�����Ƃ��͐����т����肢�����܂����B���������̌��_�ɂ͎��M�������Ă���܂��B�Ȃ���c�ɂ͒������Ă��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
�@�����Ő搶�ɂ��肢�ł������܂��B���ʓ|�ł��܂��ٕ������ǂ݂��������A�������ӂ����������Ȃ�A���̎|���u���ۃ��[�c�@���e�E�����c�v�֒��Ă������������̂ł��B�����́u�t�B�K���̌����v�̐������㉉�̂��߂ɁA�������{���甭�M���邱�Ƃ̈Ӌ`�͔��ɑ傫�����̂ł���ƐM���Ă���܂��B�ȂɂƂ���낵�����肢�\���グ�܂��B
�@ �@�@�@�@2008�N6��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�W
���������ށ�
�P�A ���ۃ��[�c�@���e�E�����c�ւ̗v�]��
�Q�A �u�t�B�K���̌����v�^���̎p
�莆�ɂ́u�����́w�t�B�K���̌����x�̐������㉉�̂��߁E�E�E�v�ȂǂƑ�ɏ����܂������A���̐^�ӂ͂����ƌy�����́B���c�哱�̊y���u�V���[�c�@���g�S�W�v�ɕύX�_���������̂ł�����A�Ȃ�炩�̈Ӗ�������͂��ł��B�u���S�W�v�ł́urispetto�v���������̂��A�����I���̎��Ԃ������čs������v���W�F�N�g�̖��Ɂudispetto�v�ɕς���Ă��܂����̂́A�Ȃ����H�Ɛu���Ă��邾���Ȃ̂ł��B���E�̉b�q���W�߂Č��������̌��_�Ȃ̂��A����Ƃ��ꕶ���̃~�X�v�����g�ɉ߂��Ȃ��̂��H�@�����m�肽���̂͂������ꂾ���ł��B���Ƃ��Ȃ�Ȃ��ł��傤���A�搶�B���߂Ȃ�A�ʂ̕��@��T���Ă݂邵���Ȃ��Ǝv���������̍��ł���܂��B
2009.02.23 (��) �b����\�\������x�g�c�G�a���a��
��N������J��������CD���蒮���Ă����̂ŁA���X���܂����B���͂i�D�r�D�o�b�n��������ł����A��������B������A������ł��傢�ƈ�x�݁A�u�N�����m�v�ւ̔����ȂNjC�y�ɏ����Ă݂悤���Ǝv���܂��B�^�C�g�����Ȃ��Ȃ��v�����Ȃ������̂ŁA��ɋ����Łu�b����v�Ƃ��܂����B��N9��17������7��A�ڂ����u�g�c�G�a���a��v�͓��X�ł͌��\����������܂����B��䏊�Ƃ��L���l�ɂ͕K���A���`��������̂ł����A�g�c�搶����O�ł͂Ȃ������悤�ł��B�u�����ǂ��낪�Ȃ��Ǝv���Ă����グ�����悭�������Ă��ꂽ�v�Ƃ������ь^����u����Ȃɂ���đ��v�H�v�Ƃ����S�z�^�܂ŗl�X�ł����B���A�P�`������͎̂�ł͂���܂��A�ς͕ςƂ����ׂ����Ǝv���̂ł��B�������Ώۂ���䏊�Ƃ�����l�ŁA�����Ƃ��̑f�l�����������Ă��h�邪�Ȃ��l�Ȃ�A������Ȃ��낤���Ǝv���킯�ł��B
���Ƃ��A2008�N11��10���f�ځu�g�c�G�a���a��v�ɒm�荇���̉��y�]�_�Ƃ̕�����u���o�b�N�n�E�X�ƃM�[�[�L���O����ǂ܂��Ă��������܂����B�w����Ȉ��������ł��Ȃ��̂Ȃ�"�M������"�Ȃ�Čy�X���������ė~�����Ȃ��x�܂��ɂ��̒ʂ�B�܂��܂������������邱�Ƃ��ł��܂����v�ƁA�^���̃��[�������������܂����B���̕��͂����M�S�ɓǂ�ł��������Ă���A�{���ɗ�݂ɂȂ��Ă��܂��B
�u�N�����m�v�ɂ͕ԐM�����Ȃ����߁A�m�荇���ȊO����͂قƂ�Ǔ��������܂���B����Ȓ����������A�f�ڃT�C�g�u�J�v���l�b�g�E���R�[�h�v�ɂ���ȏ������݂��͂��܂����B�u���܂��܁A�l�b�g���������Ă�����w�g�c�G�a�̈��]�x�̋L���ɂԂ���܂����B�������̐l�̕��͂ɂ͋����������Ƃ��Ȃ��̂œ����ł����A���܂ł��U����̂͂悭����܂���B�����v��ǂ炢�����ł��傤���v�Ƃ��e�ȃA�h�o�C�X�ł����B���肪�Ƃ��������܂����B�ł������ĐU���Ă���킯�ł͂���܂���B�O��I�ɂ��̂������Ȃ����ł��āB�����č������������u�g�c�G�a���a��v�̑��������܂��B
����́A��N9��29���f�ڂ́A�N�����m�u�g�c�G�a���a��|3�v�̌���k�Ƃ��������̂ł����A�܂��A�������ɂ����A���R�[�h�|�p2007�N2�����g�c�G�a�u�V���y���ގ҂ɔ@�����v���m�F���Ă����܂��B
�u���̊ԁA�������v���g�j���t�������Ǝv���i�łȂ��Ă��ǂ��ł������̂����j���A�����̂ǂ����̃I�[�P�X�g�����w�����ăx�[�g�[���F���́w�������ȁx��������B���̉��t�]��ЎR�m�G�������āw�����V���x�ɍڂ��Ă����B�ǂ�ȉ��t�����ǂݎ�ɂ悭�`����Ă���A�͂����肵���A�ǂ�ł��ċC�����̗ǂ��A�܂�w�Ȃ�قǁx�Ǝv����L���������B�ЎR����̂͂������Ă����ŁA���͂قƂ�ǂ������S���ēǂ�ł���B�ŁA���̔�]�Ō����ƁA�v���g�j���t�́w���x�͏o�������狭��̑ΏƂ��ɂ߂ċ�������Ă��āA���̕\��t���ł��A�x�[�g�[���F���Ƃ������ނ���V���X�^�R�[���B�`�ɂӂ��킵�����̂������炵���̂ł���B�����Ɍ���������A�v����Ƀx�[�g�[���F�������V���X�^�R�[���B�`�����ꂽ�悤�Ȃ��̂��Ƃ����킯�ł���B�ЎR����́A������A�ǂ����܂ł͏����ĂȂ������悤�Ɋo���Ă��邪�A�����ǂ߂A���������㕨����������āA�ނ������ē������ɂӂ��Ă���Ƃ����l�q�����������ɕ����Ԃ悤�ɏ�����Ă����]�������B�ŁA�w�Ȃ�قǁx�Ǝ��͎v���A�ǂ���]���A�������āA�����������낤�ȂƐ����������̂������B�v�������ɂ����̂́A�g�c�搶�͂��̉��t������ۂɕ����Ă����Ȃ��̂Ɂu�������������낤�v�Ƃ�������������Ƃł��B�����Ă����Ȃ����t���A������̕��͂Ɋ��S��������Ƃ����āA�u�������Ă����������낤�ȁv�Ǝv���̂ł��傤���H����͐�ɂ��������B���肦�Ȃ��B�܂��A���炽�߂ċC�ɂȂ����̂ł����A"�i�łȂ��Ă��ǂ��ł������̂����j"�͍����B�v���g�j���t�ɑ��Ď���ł��B���ꂪ���t�Ƃ�������l�̂������t�ł��傤���E�E�E�B���ɂƂ��āA�N�����m�u�g�c�G�a���a��|3�v�͐ꖡ�悭�܂Ƃ܂����Ǝv���Ă͂��܂������A�B��C�����肾�����̂́A�ЎR���̒����V���̃R���T�[�g�]���̂��̂�ǂ�łȂ��������Ƃł��B�{���㔼�ł��������Ă��܂��B
�u���̕��͂������ɂ������āA���͕ЎR���́w�����V���x�̕]��ǂނׂ����Ǝv���A�o�������̎��s���������A����Ȃ������B��앶�����4�K�́u���y�������v��2006�N�|2007�N�ɂ����Ă̑S�Ă̐V���蔲���L���ׂ������t����Ȃ������B�܂����@������̂�������Ȃ����A�ǂƂ���Ŏ��̎�|���_�����ς��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�ЂƂ܂��u���Ă������Ƃɂ��Ă���B�v�Ƃ��낪�ߓ����ɔ����I ���̃R���T�[�g���A2006�N12��17���T���g���[�z�[���ōs��ꂽ�~�n�C���E�v���g�j���t�w���F�����t�B���n�[���j�[�����y�c�́u���v�ł��邱�Ƃ��m�肵�āA�ēx���y�������Œ��ׂ����ʂł����B�ȉ��A�����V��2006�N12��28���f�ځA�ЎR�m�G���̃R���T�[�g�]�A�肵�āu�v���g�j���t�������t�B���́w���x�`����ɐZ��ʌ���l�ɕ����v�i�̈ꕔ�j�ł���܂��B
�u�x�[�g�[���F���̌����ȑ�9�Ԃ͖���s�މ����B��1�y�͂́A�K�X�_�̂����߂��̂悤�ȏ��t�́A���܂�Ȃ��x���B�x�[�g�[���F���炵���A�����s�����Ƃ����ْ������Ȃ��B�Ƃ��낪�A��ȑ�1��肪�o��ƁA�r�[�ɂ����܂������肫��B���̐������ۂ��ꂽ���Ǝv���ƁA�����ŁA�n�����N�����ē|���悤�ɒE�͂���B��2�y�͂̃X�P���c�H�́A�֓]�@���P���ȉ��Ɏ����X���ăC���C�����Ă��銴���B�Ô��ɘa�߂�͂��̑�3�y�͂̃A�_�[�W���́A�ł�܂����āA�����܂��I���B�����ăt�B�i�[���B���t���͑�1�y�͂Ɠ��������ɂ��낾�B�������w����̉́x�ɂȂ�ƒ��˖Ґi�B�Ə��҂����͂��Ă䂭�̂�����Ƃ��B�܂艹�y�����ɒ[�ɕ��Ă���B�T�X�Ƃ��������ƈٗl�ɒ���镔���̗��ɒ[�Œ��Ԃ��Ȃ��B�������肷�邩�Ǝv���ƁA���˂ɐ⋩�A���̌J��Ԃ����B �@�����������y��i�́A���̒����_�o�ǓI�ɂȂ肾���A20���I�Ȍ�ɑ�����B���Ƃ��V���X�^�R�[���B�`���������B���̓��́w���x�́A�܂�ŃV���X�^�R�[���B�`�I�ȉ��߂������B�S�ꂩ�畽�a�⊽��ɐZ��Ȃ�����l�ɕ�����ꂽ�w���x�Ǝv���ƁA�傢�ɔ[���ł���B�N���ɗJ������Y��悤�Əo��������A�Ԃ蓢���ɂ��ꂽ�B�����������t������v�ł͂����Ő搶�̕��͂Ɣ�r�����Ă݂܂��傤�B
�g�c�搶�́u�o�������狭��̑ΏƂ��ɂ߂ċ�������Ă��āA���̕\��t���ł��A�x�[�g�[���F���Ƃ������ނ���V���X�^�R�[���B�`�ɂӂ��킵�����̂������炵���̂ł���B�����Ɍ���������A�v����Ƀx�[�g�[���F�������V���X�^�R�[���B�`�����ꂽ�悤�Ȃ��̂��Ƃ����킯�ł���B�v�Ƃ���������Ă��܂����A�ЎR���́u�T�̕����ƈٗl�ɒ��肫�镔���̗��ɒ[�Œ��Ԃ��Ȃ��v�ƌ����Ă���̂ł����āA����̑ΏƂȂǂƂ����\�����Ȃ���Ή��̋�����Ӗ����镶���������܂���B"�ْ����ƒE�͊��̓��˂Ȃ�ϊ�"�ƌ����Ă���̂ł����āA"���̋���̑ΏƂ̋���"�ȂǂƂ������Ղňꌳ�I�Ȍ��t�ɒu��������ꂽ��A���̈Ӗ����`���͂�������܂���B�܂��u�V���X�^�R�[���B�`�����ꂽ�悤�Ȃ��́v�Ƃ��������������A"�I�ȉ���"�Ƃ����ЎR���̈Ӗ���������̓j���A���X�̓x�������������ꂷ���Ă��܂��B�搶�̊����͋ɓx�ɓK�����������Ƃ��킴��܂���B����ɐ搶�́u������A�ǂ����܂ł͏����ĂȂ������v�Ƃ���������Ă��܂����A�ЎR���́u����l�ɕ�����ꂽ�w���x�ŁA�J������Y��邽�߂ɏo��������A�Ԃ蓢���ɂ������B����ȉ��t������v�ƁA������"�ǂ�ȉ��t�������"�������Ă���܂��B
����́A�g�c�搶������������ǂ肵�Ă��̂��������ꍇ�A�L�����B���ɂȂ��Ă��ēx�������m�F����J���Ƃ�Ȃ����ƂɌ���������Ǝv���܂��B2008�N10�����u�V���y���ގ҂ɔ@�����v�ł́A�A���Q���b�`��DVD��Ώۂɘ_�|��i�߂Ă����܂����A�u���͖Y��Ă��܂����B������x���߂āADVD��������C�͂��Ȃ��̂ŁA�Ԉ���Ă��邩������Ȃ����v�Ƃ��u�������������悤�ɁA���͂���DVD��������x�����Ċm���߂�C�����Ȃ��̂Łv�ȂǂƂ����������ĎO�o�Ă��܂��B���C��"�ēx����C�����Ȃ�"�Ə�����Ă���̂ł��B�Ԉ���Ă��邩������Ȃ��̂Ȃ�A�܂����������Ċm�F���������������Ȃ��ł����B�B�������c�����܂ܕ��u���Ă����āA�悭���C�ł����܂��ˁB���ɂ͂��̑ԓx�͓��ꗝ���ł��܂���B�ǂݎ��n���ɂ��Ă��܂��B�����������Ƃ�����A�ЎR���̃R���T�[�g�]���ȉ������܂������Ă��܂�ꂽ�̂ł��傤�B
���̂��т̕ЎR���́u�R���T�[�g�]�v�����ŁA�g�c�搶�̞B��������������ɂ��ꂽ�`�ɂȂ�܂����B�ނ�Ŕ��Ȃ��Ă������������ƐɊ肤���̂ł���܂��B
2009.02.09 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�ŏI��
�@�J�������Ɂu���y�I�A�E���v�͂Ȃ��̂��H �u�J���������N���V�b�N���E�����v�̒��ҁE�{�������́u�J�������̉��y�͎���Ƀq�b�g���Đ��E��Ȋ��������A�㏞�Ƃ��ăA�E�����������v�ƌ����B�O��̓P�[�Q���Ƃ̔�r�ɂ����āA�A�E���̗L�����������B���ʂ͂��Ă����A����͂���ɑ����̎w���҂��Ȃ���l���Ă݂����B�i�P�j �u�c�������ȁv�̏I�y��
�@�Ώۂ̓x�[�g�[���F����Ȍ����ȑ�6�ԁu�c���v�̑�5�y�́i�I�y�́j�ɂ��悤�B�O�̋Ȃ��Ƃ肠�����̂͒P�Ȃ���R���������A�u�A�E���v�T���ɂ͂Ȃ�Ƒ����������y�������낤�B�x�[�g�[���F���́u�c�������ȁv�Ɏ��R���_�ւ̊��ӂ����߂��B��1�y�́u�c�ɂɒ������Ƃ��̖������C���̂߂��߁v����A�l�X�ȓc�����i���o�āA�u�q�l�̉́B���̂��Ƃ̊�тƊ��ӂ̋C�����v�Ƃ����ŏI�y�͂ɒH����B���N�O�A�⏑�܂ŏ������n�C���Q���V���^�b�g�̎��R�̒��ŁA���x�͖�����Ȃ��炻�̓c�����i���i�S���I�Ɂj�Ԃ����B�x�[�g�[���F���̎��R�ւ̊��ӂ͐_�ւ̊��ӂɂȂ����āA�ŏI�y�͂ɏW�ꂽ�̂ł���B�A�E���������Ƃ�ɂ͐��ɍœK�ȉ��y�ł͂Ȃ��낤���B
�@�y�͂̏I��237���ߖځApp�@sotto voce�i�����Ђ��߂āj�����8���߂ɁA���͐_�́i�_�ւ́j�����B�����ł́A����܂ł̑S�t�͎~���y�킾���ɂȂ�BJ�DS�D�o�b�n���u�}�^�C���ȁv�ŃC�G�X��L���X�g�_���̏ے��Ƃ��ėp�������̌��y���t�ł���B���̋Ȃ́A�����̂��ƃ����f���X�]�[�����h������܂ŁA100�N���̊ԉ��t����Ȃ������̂�����A�x�[�g�[���F���͒m��R���Ȃ��������낤���A���̕����͂����Ƃ����v���Ȃ��B������ăo�b�n���~��Ă����Ƃ����v���Ȃ��̂ł���B
�@�ł́A���̕����i�ȉ�BB�ƌĂԁj�𒆐S�ɁA�u�c���v�I�y�͂�������B
�i�Q�j �J�������ȊO�̎w���҂ɂ��u�c���v�I�y�͂���������
�@�����̃|�C���g�́ABB�����ɍ��߂�C�����Ɓu�A�E���v�̎����ł���B
�@�@�@ �N�����y���[�F�t�B���n�[���j�A58
�@�@�@�@�@7�F40�̋��ǂ̗h��ɃA�E���i�ȉ�A�j��������
�@�@�@�@�@BB�@���ɐ_�X���������B���R�̌b�݂Ɛ_�ւ̊��ӂ������Ƃ��
�@�@�A �P�[�Q���F�h���X�f���E�t�B��89
�@�@�@�@�@�o���̃N�����l�b�g�ƃz�����̔����ȃj���A���X��A
�@�@�@�@�@1�F44����̃g�����y�b�g�̋�����A
�@�@�@�@�@BB ���J�ɂ����Ղ�Ɛ_�ւ̊��ӂ��̂��B
�@�@�@�@�@����ɑ���245���߂� ���� ���D����
�@�@�B �X�E�B�g�i�[�F�x�������E�V���^�[�c�J�y��80
�@�@�@�@�@BB�@���J�ŏ����Ő��ݐ�����������������
�@�@�C �t���g���F���O���[�F�E�B�[���E�t�B��52
�@�@�@�@�@BB �ӊO�Ƃ������肵�Ă��邪�C�����͂������Ă���
�@�@�@�@�@8�F58�@�R�[�_�E���̉̂킹����A
�@�@�D �����^�[�F�R�����r�A��58
�@�@�@�@�@2�F12�@�������^�������h���ăN�����l�b�g�`�z�����������1���ւȂ���▭�Ȍċz��A
�@�@�@�@�@BB�@���̏�Ȃ����J�ŗD�������߂ɖ����Ă���
�i�R�j �J�������́u�c���v�ɂ̓A�E�������������H
�@���������̂͑O��Ɠ���2���B�I�[�P�X�g���͗��҂Ƃ��x�������E�t�B���n�[���j�[�ŁA�^���N��͑��X63�N��76�N�ł���B�I�y�͂̃^�C���́A63�N�Ղ�8�F46��76�N�Ղ�8�F35�ŁA���܂荷�͂Ȃ��A��������������قǕω��͂Ȃ��B�����Ă����A�O�҂��L�r�L�r�Ǝ�X�������t�Ȃ̂ɑ��A��҂͒�d�S�ŋ������Z���ŗ��튴�������Ă���Ƃ����悤���B�������P�y�͂̈�ۂƑ卷�Ȃ��B
BB�ɂ����܂芴��̓��ꍞ�݂͊�����ꂸ�A���ɃA�b�T���Ɨ����B����76�N�Ղɂ��̌X�����������B
�@�����A�A�E���L���̃|�C���g�Ƃ��ĒT�蓖�Ă�BB�|�C���g�ɂ����āA�ł���������Ȃ��X���i���Ɨ��ꋎ���Ă䂭�̂̓J�������̉��t�������B�����������o�Ă��̌X���͂���ɋ��܂��Ă��Ă���B�J�������̉��y��"����̋N����r���A������������������邱�Ƃ����Ƃ���"�X���������ł������Ɍ���Ă���Ƃ�����B
�@�A�E����������ׂ��ȂɃA�E�������������Ȃ��J�������̉��t�B��͂�J�������ɂ̓A�E�����Ȃ��H
�@�����́A���t��r�̏�ł͂Ȃ��̂ő�T�ɂ��邪�A�N�����y���[�ƃX�E�B�g�i�[���o�����B�I�R���鑫�ǂ�ŒW�X�Ɖ^�сA�Ō�Ő_�ւ̊��ӂ��h�i�ɉ̂�������N�����y���[�B���R�ȗ���Ƃ��Ȃ₩�ȕ\����������ɐS�n�悳�ƈ��炬��^����X�E�B�g�i�[�B���ɖ��͂��ӂ���́u�c���v�ł���B�����ă����^�[�B���͂��̔ՂŁu�c���v��m�����B���w�P�N���̂Ƃ��ł���B�v�X�ɂ������蒮�������A��͂�f���炵�������B���e�ɖ������D���ȉ��y�͔ނ̗D�������₩�Ȑl�����̂��̂��B����͎��ɂƂ��ĕʊi�́u�c���v�ł���B
�i�S�j���т�
�@�{�����������������u�A�E���v�̑��݂́A�撣���Ē͂����Ƃ������A�����������̂�������Ȃ��B��͂�"�Ȃ��킯�ł͂Ȃ������ȁA���킭������A�_��I�ȁu����������́v"�Ȃ̂��B
�@����́u���m�̈����������v�i����m�q���j�ɂ���悤�ȁA"�i���̐^���͖ڂɌ����Ȃ��B�S�Ō������"�Ȃ̂�������Ȃ��B���m���������u�I�C���[�̓����v�́A�����邩�͉�͂ł���킯���Ȃ����A�������͊��o�I�ɂȂ�ƂȂ�������B�l�C�s�A���Ɖ~�����Ƃ��������萔���A�����Ƃ����o�[�`�����ȑ��݂Ɓu�P�v�Ƃ����ŏ��̌Ƒ��܂��Ė��ɋA����Ƃ����A�v��m��Ȃ��_��́A�����̔�������X���Ă���B�n�肾�����ƂȂǂł���͂����Ȃ����A�V�˂̑n�����ɔ��������Ƃ邱�ƂȂ�A��X�}�l�ɂ����Ăł���B
�@���y�ɂ�����u�A�E���v��"�����Č��t�ł͌��Ȃ��A�������������"�Ȃ̂��낤�B���y�����͓̂���B�ł����t�ɂ��Ȃ���Α��l�ɂ͓`���Ȃ��B�������͈�l�ЂƂ�Ⴄ���́B�\���̎d�����݂ȈႤ�B����Ȓ��ŁA���y�����`���������Ƃ́A����Ɍ��܂��Ă���B�u�A�E���v�𑨂����͓̂�����A���̗L���������Ƃ邱�ƂȂ�ł��邾�낤�B����ł����̂��B�u�I�C���[�̓����v�ɔ���������悤�ɁB
�@�N���܂����ŘA�ڂ����J������������ŏI���ɂ��܂��B�킪���y�l���̂���������^���Ă��ꂽ�J���������A���a100�N�ɂ�����A�l�X�ɒNj��ł����̂͑�ϗL�Ӌ`�ł����B
�@"50�|60�N��̔e�C���A70�|80�N��ɑr�����A�ŔӔN�őh��"�Ƃ�����܂��ȗ�����A�Ȃ�ƂȂ�������ꂽ�悤�ȋC�����Ă��܂��B�����čŏI�̓y�d��ŁA�Ȃ�ƂȂ��ł͂Ȃ��{���̖����t�i�Ȃ�ӂ�\�킸���y�ɂԂ������j�u�u��1�����h��88�v�ɏo����Ƃ��ł��܂����B����͑�ςȎ��n�ł����B�������J�������B���肪�Ƃ��B�V����ł��I
2009.02.02 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�V
�O��́A�x�����~�����ʐ^�ɂ����ċK�肵���u�A�E���v�̊T�O���u���y�I�A�E���v�ɓK�p���A�{����������"�J�������̉��y�ɂ̓A�E�����Ȃ�"�Ɋ֘A�t���Ă݂��B�����E�E�E�u���y�I�A�E���v�Ƃ́u����̒��ŁA���R�Ȋ���̓����ɂ���ċN������鉹�y�̗h�炬�v�ł���B�J�������̉��y�͊���ړ���r�������̂��B���������ăA�E���̂Ȃ����y���B���x���t���Ă��������y�����܂��B�����Ɏ���̓��R�[�h�Ƃ������y�̕����Z�p�B�������B�A�E���̂Ȃ��������y���ی��Ȃ��������ꂽ�E�E�E���ꂪ���y�ɂ�����A�E���r���̎p�ł���A�J���������Ƃ����ő�̍߂̂ЂƂł���B����́A"�J�������̉��y�ɂ́u�A�E���v���Ȃ��̂��H"�ɂ��Č�����B
�i�P�j���������̓P�[�Q��
�{�����̓J�������̑ɂɂ���w���҂Ƃ��ăN�����y���[�ƃP�[�Q���������Ă���B"�J�������Ɂu�A�E���v���Ȃ��̂Ȃ�A�P�[�Q���ɂ͂���Ƃ������Ƃ��H"�Ȃǂƍl���Ă���Ƃ��A���钆��CD�V���b�v�ŃP�[�Q���^�h���X�f���E�t�B���n�[���j�[�̃x�[�g�[���F�������ȑ�6�ԁu�c���v���������B�l�i�͂Ȃ��200�~�B���������ĕ����Ă݂��B
���́u�c���v�̃e���|�͑��������B�ł����R�Ȋ����͂��Ȃ������B��1�y�͒��̃^�C���́i�J�Ԃ��Ȃ��Łj2�F17�������B�g�c�G�a�搶���u�������H���X�|�[�c�J�[�ő����Ă���悤�ȁv�ƌ`�e�����J�������^�x�������E�t�B��63��2�F22�A�P�[�Q���̂ق���5�b�����B����͂ƂĂ��Ȃ������Ƃ����Ă����B�ł�������̓J�������̂ق�������������B����͉��́H�����Ɂu�A�E���v�𖾂̃q���g��މB����Ă���̂ł͂Ȃ����H�Ǝv�����B ���x��������ׂďo�����_�́u�h�炬�v�̍��������B�u�h�炬�v�͕ω��ɂ���Ĉ����N�������B�ω��ɂ̓e���|�ƃ_�C�i�~�N�X�i���̋���j��2��ނ�����B�����͒P�ƂɁA���ɂ͏d�Ȃ��āA�y�z�ɕω��������炷�B���ꂪ���y�̗���i���ԁj�̒��Ŏ��R�Ɂi����̎�܂܂Ɂj�������Ƃ��A���y�I�u�h�炬�v��������B���ꂪ�����u�A�E���v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�J�������̉��t���A�����I�ɑ����P�[�Q���̉��t��葬��������̂́u�A�E���v���Ȃ�����Ȃ̂ł͂Ȃ����H
�i�Q�j�P�[�Q���ƃJ������
�w���x���g�E�P�[�Q���i1920�|1990�j�̓h���X�f�����܂ꋌ���h�C�c�̎w���ҁB62�N�\77�N�̓��C�v�c�B�q�������̉��y���ēƂ��āA77�N����86�N�܂ł̓h���X�f���E�t�B���n�[���j�[�̎�Ȏw���҂Ƃ��Ċ���A���̊ԂقƂ�Nj����h�C�c���o�Ă��Ȃ��B
89�N�x�������̕ǂ����A���N�h�C�c�͓���B�����h�C�c�ɂ��������瑽���̉��y�Ƃ����ꂽ�B�����P�[�Q���̊���̏�͂��߂��A�Љ��`�҂ł��������ނ͟T��Ԃ������A���ɂ�1990�N11��20���s�X�g�����E��}��҂�ʐl�ƂȂ��Ă��܂��B
�P�[�Q���ƃJ�������B���Ɛ��A�A�Ɨz�A�������ƌ������B"�m��l���m��"��"�m��ʂ��̂Ȃ����E�̒鉤"�B�����w���x���g�ł������Ⴄ���A�܂��ɑΏƋɂ܂��l�ł���B
���́u�J�������l�R�v�ɏ������悤�Ɂu�����L�����p�X�v�ŃN���V�b�N������������Ă���B���������Ĉꉹ�ꉹ�����܂߂ɕ�����ׂ�����K��������B�������Ȃ���"�A�E���̑���"�̗L������ׂ�͎̂���̋Z�������B�J�������͕��R�ɗ���A�P�[�Q���͗h�炬�����Ȃ��痬��Ă���A�Ɗ��o�I�ɂ����̂��ւ̎R���B�Ȃ�ƂȂ�������Ƃ��������悤���Ȃ��̂����A�����Ĉ�ӏ�������������Ă݂�B
�u�c�������ȁv��1�y��98���ߖڂ�103���ߖڂ̎�a���̃g�D�b�e�B�i�S�t�j�̕����B�����Ƃ���f�i�����j���t���Ă���B�J�������i1�F39�A1�F46�j�͑f���C�Ȃ����������o���B�u���͍�Ȏ҂̎w���ǂ������Ă���A���傠�邩�v�݂����ȁB�P�[�Q��(1�F35�A1�F42)�͕�ݍ��ނ悤�ɉ����o���B�t�@���e�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����ǂ��ƂȂ��D�����B�Ȃɂ�"���y�ɗh�ꂪ����"�悤�ȁB������ǂ��Ȃ̂�ƌ���ꂻ�������A���͂����Ɂu�A�E���v�̗L���������Ƃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B�J�����������R���f���C�Ȃ�������̂Ȃ����A�E���Ȃ��B�P�[�Q�����}�g���v�����ꁁ����̔��I���A�E���B
�Ƃ͂�������͎��ɞB���B�F���������ĂȂ�قǂƎv�����낤���B�v���Ă����������Ƃ���ł���́u�A�E���v�Ȃ���̂Ȃ̂��H����͂ނ�����߂Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂��H�����͏o�������Ȃ�����ǁA�Ȃ�Ƃ���T��Ői��ł݂悤�B�ł͎��ɗ��҂̕ʎ��_�ł̉��t���r���Ă݂�B
�܂��̓J�������B����13�N��1976�N�ɁA�����x�������E�t�B���Ƃ̍Ę^��������B�u�c���v��1�y�͒��̃^�C����2�F25�Ȃ̂�63�N�Ղ��3�b�x�������B�\���́A���d�S���Ⴍ���K�[�g�������S�̓I�ɂ��\�t�g�Ŏ�����肪�ǂ��Ȃ��Ă��邪�A���{�I�ɉ��y���ς���Ă͂��Ȃ��B
���ɃP�[�Q���B1989�N10��18���A�T���g���[�z�[���ɂ�����h���X�f���E�t�B���Ƃ̗������t��̃��C�u�^��������B�^�C����2�F44�ƂȂ��27�b���x���B�\�����ʕ����B
�܂��́A��3���ߖڂ̋ɒ[�ȃ��^�������h�B����͊y���ɂ��Ȃ��B��15���ߖڂ�p�̕\����Z���B37���ߑ����̈����Â���A�����`��42�A47���߂ł��`����B���Ɍ��L�ȉ��`�������Ă���B�����ʂ����Ă��ꂪ�u�A�E���v���Ƃ����u�H�v���B���R�Ȋ���̔��I�Ȃ̂��Ӑ}�I�Ȃ���Ȃ̂��H �ł��A�m���ɂ��܂芴��̉�����������Ȃ��J���������́u�A�E���v�A���Ƃ����邩������Ȃ��B�܂���̊ϓ_���猩�Ă��A�ȑO�̃X�^�W�I�^������܂�ŕʐl�̂��Ƃ��̃��C�u���t�����邱�Ǝ��́A�u�A�E���v�I�Ƃ����邩������Ȃ��i���̊y�́A���ɏI�y�͂Ȃǂ͕ω��̓x��������茰���ł���j�B
�K�肵���܂ł͈А����悩�������A������ƂȂ�Ƃ��̗L�l�ł���B����Ȓ��x�ł���B��͂�ʐ^���琶�܂ꂽ�T�O�����y�Ɍ��т��邱�Ƃ͎n�߂��疳���Ȃ̂��낤���H ���y���炻��������Ƃ邱�Ƃ͓���̂��A����Ƃ����X�Ȃ����̂Ȃ̂��B���y�͂ŕ\�����Ƃ̓������`���āA����͎���̋ƂƂ��������ł���B�v�X���H�Ɋׂ肻���ȗ\��������B�ł��܂��A�h���E�L�z�[�e�ōs�����B�ˌ�����̂݁B�������͉̂����Ȃ��B����͂��̞B���͌ЂƂ����u�A�E���v�Ȃ���̂��A��葽���́u�c�������ȁv���Ȃ���l���Ă݂����B
2009.01.26 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�U
�{�������̒����u�J���������N���V�b�N���E�����v�i�����АV���j�́A���̂ɂ͈�a�������邪�A���p�Ǝv�l�̈ꕔ�ɂ͋������o�����Ə������B����́A�ނ����p�����u���y�I�A�E���v�ƃJ�������̉��y�Ƃ̊֘A�ɂ��čl�@���Ă݂����B�i�P�j�u�A�E���v���������J������
�{�����͖{�����́u�����^�̔��w�v�́u���y�I�A�E���v�̒��ł����q�ׂĂ���B
�u�J�������̉��y�́A�Ȃ�قlĵɖ����A�Ƃ��ɂ͖\�͓I�ł��炠�������A�����͑��������I�ł�����͌v�Z�Â��ł������B���[���b�p�͕ς�肽�������B����A�ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ߋ��𐴎Z���V�������[���b�p����ł����Ă�K�v���������̂��B��̌R�ɂ���Ă����炳�ꂽ�A�����J�̉��l�ς̐V�����A���R�ȕ��͋C�A�����̕��Ր��B�����ۏ�������]�V�C�Ŋy�ϓI�ȁu�V���E�v�̐��E�ς������ȃ��[���b�p�̐��E�ςӂ����B���̂悤�ȕ��ՓI�A�Đ��E�I���l�ςɃJ�������̉��y�͌����Ƀq�b�g�����̂��B���Ȃ킿�ނ̉��y�I�˔\�ƃR�X���|���^���I�������A����̗v���ƃ}�b�`���鉹�y���`����Ă������v�ނ̌����J�������̉��y�́A�ܖ��N�S���������u�C�y�ɕ��������Ă���A�����ɂ�����l�D�݂ȃr�[�g�����������t�����A�܂Ƃ��ɒ����o���A���̐Ȃ��ƁA�����ςȂ��ƁA�T�[�r�X�ߏ�ŁA�i���̂Ȃ����ƁA�܂��ɃA�����J�l�����Ƃ����C������v�ɂ��̂܂ܕ������������B�܂��u�����I�ł�����v�Z�Â��ł������v�́u�J�������l�\�\�P�v�C�k "�J�������͂ǂ�ȐU������ł���B��ɒ��O���ӎ����Ă���" �ɂȂ���B
�u���̑㏞�Ƃ��ăJ���������������̂́A���Ẵ��[���b�p�A���Ƀh�C�c�ꌗ�ɕՍ݂��Ă����ϔO�_�I�`���Ƃ���ɑ���h�ӂƈؕ|�ł������B"�ڂɌ����Ȃ������������"�ւ̈،h�̔O�ƌ����Ă��������Ƃ��B"���邱��"���ؖ����邱�Ƃ͓���s�\�����A�����ĂȂ��킯�ł�"�Ȃ�������"�A�_��I��"�����������"�ł���A�x�����~���������Z�p����ɂ͎����邱�Ƃ�\�������w�A�E���i�I�[���j�x�ł������v
�{�����̓J�������̉��y�����������̂́u�A�E���v�ł���ƌ����B�����"���邱��"�i���݁j���ؖ��ł��Ȃ��Ƃ������B�ł����������j�S�I�ȗv�f�ɍs���������̂�����A�ؖ��ł��Ȃ��ܑ͖̂̂Ȃ��B�Ȃ�Ύ�������Ƀg���C���Ă݂悤�B�������ȁH
�肪����͂R�B�ЂƂ̓��@���^�[�E�x�����~���̌����u�A�E���̊T�O�v�A��ڂ́u�A�E���̂Ȃ��J�������̉��y�v�A�O�ڂ́u�A�E�������ϔO�_�I�h�C�c�`���̉��y�v�ł���B
�i�Q�j�x�����~���̋K�肷��u�A�E���v�Ƃ����T�O���l�@����
���@���^�[�E�x�����~���i1892�|1940�j�̓x�������̗T���ȃ��_���l���p���̉Ƃɐ��܂�Ă���B���������Ĕނ̕����_�͔��p�Ǝʐ^�ɍ��������̂��B���ҋ{�����͐��m���p�j�����Ȃ̂ő����т����̂��낤���A�����s���̊��͔ۂ߂Ȃ��B������������J�������̉��y�ƃx�����~���̗\�������u����A�E���v�����т��邱�Ƃ̓���͐捏�����m�������̂ł͂Ȃ����B����Łu"���邱��"���ؖ����邱�Ƃ͓���s�\�v�Ɠ����Ă��܂����̂����m��Ȃ��B�ł������������ꂽ�e�[�}�Ȃ̂������ɂ��悤�B
�u�A�E���̊T�O�v�̓x�����~���̒����u�ʐ^���j�v�Ɓu�����Z�p����̌|�p��i�v�ɏ�����Ă��邪�A�����𑽖؍_�u�x�����~���w�����Z�p����̌|�p��i�x���ǁv�i��g�V���j������p���Ă݂�B
�u���������A�E���Ƃ͂Ȃɂ��B��ԂƎ��Ԃ̐D��Ȃ��s�v�c�ȐD���ł���B���Ȃ킿�ǂ�قNj߂��ɂł���A���鉓�������I�Ɍ���Ă�����̂ł���B�Ă̐^���A�Â��Ɍe���Ȃ���A�n���ɘA�Ȃ�R�Ȃ݂��A���邢�͒��߂Ă�����̂̏�ɉe�𓊂������Ă���̎}���A�u�Ԃ��邢�͎��Ԃ������̌�����ɂ�������Ă���܂ŁA�ڂŒǂ����Ɓ\�\���ꂪ���̎R�X�̃A�E�����A���̖̎}�̃A�E�����ċz���邱�Ƃł���B�v�i�u�ʐ^���j�v���j�x�����~���̓A�E�������̂悤�ɋK�肵�����ƁA�l�K�^�|�W�����̎ʐ^�Z�p�̔��W�̒��A�E�W�F�[�k�E�A�W�F�i1854�|1927�j�Ƃ����V�ˎʐ^�Ƃ��u�Ώۂ��A�E������J�������v�Ɛ������B�ނ̎B�����ʐ^�͊���ړ���r�����p���̊X���݂������B����͎��Ԃɂ��ω�����Ԃɂ��ω����Ȃ��B�Ώۂ͂������Ȃ�Ƃ������ł���B����������͎ʐ^�̕����Z�p�B�����Ă���B�A�E���̂Ȃ������I�u�W�F���ی��Ȃ��������ꂽ�E�E�E���ꂪ�A�E���r���̐^�̎p�ł���A�ߑ�ʐ^���h�ɂ����т̒��ŁA�ő�̂��̂��ƃx�����~���͋K�肵���B
�u���������A�E���Ƃ͉����H���ԂƋ�ԂƂ��Ɠ���あꂠ���ĂЂƂɂȂ������̂ł����āA�ǂ�Ȃɋ߂��ɂ����Ă��͂邩�ȁA������̌��ۂł���B�v�i�u�����Z�p����̌|�p��i�v���j
�{�����́A����ɕ���āA�J�������̉��y�ƃ��R�[�h����������K�肷��B�J�������̉��y�͊���ړ���r�������̂��B���������ăA�E���̂Ȃ����y���B���x���t���Ă��������y�����܂��B�����Ɏ���̓��R�[�h�Ƃ������y�̕����Z�p�B�������B�A�E���̂Ȃ��������y���ی��Ȃ��������ꂽ�E�E�E���ꂪ���y�ɂ�����A�E���r���̎p�ł���A����̎w���ҁE�J���������Ƃ����ő�̍߂ł���ƁB
���҂̍ő�̈Ⴂ�́A�x�����~���̓A�E���̑r����"����"�ƌ����Ă���̂ɑ��A�{������"��"�Ƃ����Ă���_���B�Ȃ�A�{�����̈��p�͂������������s���Ƃ��킴��Ȃ��̂ŁA�������ݍ���ł݂悤�B
�A�E���Ƃ����͉̂�X�����ʂɌ����I�[���̂��ƂŁA�ꌹ�̓��e�����aura�ł���B�����ɂ���aura�́u���v�Ƃ��u�V�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�����u�V�v�����ԂƋ�Ԃ̒��Ŏi��A�u���A���A��C�v�ȂǁA������������Ă���傢�Ȃ���̂��Ӗ�����B�u���R�v�ƒu�������Ă������B
���������āu�A�E���v�Ƃ́u���ԂƋ�Ԃ��D��Ȃ����R�̗h�炬�v�̂悤�Ȃ��̂ƋK��ł���B������X�ɉ��y���Ɍ���������ǂ��Ȃ邾�낤���B�L�C���[�h�́A���R�A���ԁA��ԁA��A����ł���B
�H���u���y�I�A�E���v�Ƃ́u����̒��ŁA���R�Ȋ���̓����ɂ���ċN������鉹�y�̗h�炬�v�Ƃ������Ƃ��ł��邾�낤�B
���������āA�A�E���́A�Ώۂ����ԂƋ�Ԃ̒��������u�ʐ^�v�ɂ����Ă͎ז��ŁA��Ԃ̒������ԂƂƂ��ɗ����u���y�v�ɂ����Ă͗L�p�Ȃ̂��B�t�Ɍ�����"�A�E���̑r��"�́u�ʐ^�v�ł�"����"�ł���A�u���y�v�ł�"��"�Ȃ̂��B
����́u�J�������̉��y�ɂ̓A�E�����Ȃ��̂��ǂ����v���A���ۂ�CD���Ȃ��猟����B
2009.01.19 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�T
�i�P�j�u�u���[���X�F�����ȑ�1�ԁv�ɂ�����J������ ���̂Q���u�u��1�v�����U�v���O��́u�u��1�v�@�|�C�܂ł��������āA�B���ň��C���ō��Ƃ������ʂ��o���B������A�u�ߜƁv�u�V�x���E�X��2�ԁv�u�f���v�ƍ��킹�A�V���v���ɕ��ނ��Ă݂�B
�@ �E�B�[���E�t�B��59�iDECCA�j
�A �x�������E�t�B��63�iDG�j
�B �x�������E�t�B��77�iDG�j
�C �x�������E�t�B��87�iDG�j
�D �x�������E�t�B��88�D5�D5�T���g���[�E�z�[���E���C�u�iDG�j
�E �x�������E�t�B��88�D10�D5�����h���E���C�u�iTESTAMENT�j
���ǂ����t���ȏ�������
�u�V�x���E�X��2�ԁv�t�B���n�[���j�A60
�u�f���v�E�B�[���E�t�B��61
�u�ߜƁv�E�B�[���E�t�B��84
�u�u���[���X��1�ԁv�x�������E�t�B��87
�u�ߜƁv�x�������E�t�B��88
���ǂ��Ȃ����t��
�u�u���[���X��1�ԁv�x�������E�t�B��77
�u�V�x���E�X��2�ԁv�x�������E�t�B��80
�u�f���v�x�������E�t�B��81
�@�@�@ 70�㔼�\80�O���̃x�������E�t�B���̉��t�ɗǂ��Ȃ����̂�����
�@�@�A ����60�N�O��ƔӔN80�N��㔼�ɗǂ����̂��ł܂��Ă���
�Ƃ����X�����M����B
�����A"�J��������60�N��܂ł͗ǂ��������A70�N��㔼����80�N��O���܂ł͈����A�ӔN�ɂȂ��čĂїǂ��Ȃ���"�Ƃ������Ƃ��B����͂܂�"�J��������70�N��ɂȂ��đ�����"�Ƃ̍J�̕��]�ɂ����Ă͂܂�B�Ƃ͂����A���������ꂾ���̃T���v���ŁA�̑�ȃJ�������̋ƐтɃP�`��������A���t�̗ǂ������̕ϑJ���X���Â��邱�Ƃ͏o���Ȃ����낤�B���̂��߂ɂ͍X�ɑ����̃T���v�����K�v�ŁA�c��Ȏ��ԂƉ����������̎������������Ȃ����낤���A���ꂩ������X�ƃJ�������̉��t��������̂�"�����������"�ł���A�f�l�̎����Ƃ�����������̂�"�������܂���"�̂ŁA����Ɏ~�߂Ď��ɐi�݂����Ǝv���B
�i�Q�j���ٓI�����t�̏o��
��N�́A�J���������a100�N���L�O���āA���ڂ��ׂ�CD�������������ڌ��������B�u�R���T�[�g�E�C���E�x������1957�v�iSONY�A�O�����E�O�[���h�����j�A�u���X�g�E�R���T�[�g1988�v�R�v�iDG�A�Ō�̓��{�����A�u�ߜƁv�u�u���P�v�u�W����̊G�v�u�x�[�g�[���F��4�ԁv�u���[�c�@���g29�ԁA39�ԁv�Ȃǁj�ȂǁA�����͂��ׂċ����[��CD����ŃJ�������E�t�@���Ȃ炸�Ƃ��y���߂����A�Ō�ɂ��Ē��W���̖����t���o�������B�x�������E�t�B���Ƃ́u�u���[���X�F�����ȑ�1�ԁv�A88�N�����h���������C�u�iTESTAMENT�j�ł���B
����͐����B�����Ȃ�Ă�������Ȃ��B�ƂĂ��Ȃ����t�Ƃ͂��̂��Ƃ��B�C�������킷����ٓI�Ȗ����t�ł���B1988�N10��5���A�����h���A���C�����E�t�F�X�e�B�o���E�z�[���ł̃��C�u�B���̓��A���܂ł���9�����B
��1�y�͂̏o����������ɋS�C����ْ���������B�e�B���p�j�[�̋��łɍ��߂�ꂽ�p���[���낵���B�`��9���ߖڃe�B���p�j�[�̍Ō�̈�łւ�"��"�̐▭�Ȃ��ƁB���C�u�Ȃ�ł͂̃A�E�������U���Ă���B�������Ƃ́A�R�[�_�O�̉��̍��݂ɂ������āA����قǃ����n���̂���ȑz�͑��ɕ��������Ƃ��Ȃ��i�N�i�b�p�[�c�u�b�V������肻���ȁB�ł��ނ́u�u��1�v�͂��Ȃ��j�B�y�͑S�̂�ʂ��āA�܂�ʼn������ΑN������юU��悤�ȔM�����B
��]�A��Q�y�͂̓��}���e�B�b�N�ȕ����ɕ�܂��B�������炩�����ł͂Ȃ��A�傫�Ȃ��˂�̂Ȃ��ɕY���S�̈��炬�Ƃ����Γ������Ă��悤���B�����݂䂫�u���z�̏M�v�̂悤�ȁE�E�E�B�z�Ƃ����I�[�{�G�̋�������i���B��R�y�͂͘A�����郌�K�[�g���N�b�L���Ƃ��ĝR��̓x�g���Ȃ��B����C�̂Ȃ��ȑf�Ȕ��������ۗ��B
�����āA�I�y�́|�����h���̏H�̗�C���悤�Ȑc�̋����x�������̌����A�S�̐[����h���Ԃ�悤�ȏo���B�N�X�Ɩ�킽��A���y���E�z�����̋������A�����ȃt���[�g���瑑�d�ȋ��ǂ��o�āA�܂��߂��Ă���ǂ̃����[�́A���ĂȂ��j���A���X�������o���B�����ă��@�C�I�����ɂ���P���́A�h�i�ȋF��ɂ������_�X������X���Ĕ�ނȂ��B���Ƃ́A�����̒��ɕ������_�Ԍ��āA�J�����ꂽ���тւƐ��_������������Ă䂭�B�I�P�S�̂̋����́A���̂悤�ɋ���ŗʊ�����e�B���p�j�[�Ƃ�������悤�ȉs�����Ɏx�����Ă���B�����A�x�������E�t�B���̋��͂Ȍ��y��Q�ƓV�˃I�Y���@���g�E�t�H�[�O�i�[�̃e�B���p�j�[�B"�w���ҁ^�R���T�[�g�}�X�^�[�^�e�B���p�j�[���I�[�P�X�g���̍�����"�Ƃ͂悭������b�����A���ꂼ���ɃJ���������x�������E�t�B�������B�������ɂ̋��n�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�������H�J���������A�l���̍ŔӔN�Ɏ����Đ��������A����͑z����₷�閼���t�ł���B
���̉��t�́A�y�킪�Ԃɍ���Ȃ��������ߊJ�����Ԃ������āA���n�[�T���Ȃ��ŗՂꔭ�����������Ƃ����B���̐�������J�������̓x�������E�t�B����Ȏw���҂̃|�X�g��ǂ��邪�A����Ȏw���҂ƃI�P�Ƃ̊W�̉��A���ꂾ���̖����t�����������̂͊�ՂƂ��������悤���Ȃ��B�������ꂪ�A���̓˔����̂̂����������Ƃ����Ȃ�A��X�͂��̐_�̈��Y�Ɋ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�i�R�j�u�u���P�v�����J�������̃V���{����
�J�������̃L�����A��H���Ă݂�Ɓu�u���[���X�̑�1�ԁv�͔ނɂƂ��ē��ʂȊy�Ȃł��邱�Ƃ��킩��B�ߖڂł͕K�����t���Ă���v������i���o�[�E�����y�Ȃ��B���̈Ӗ��ł́u�ߜƁv���G��Ȃ��B�ȉ��u�u���P�v�����t���ꂽ�@����L���Ă݂�B
�@ 1935�N�A�[�w���̌��ꎞ��A�̌���I�[�P�X�g���ł̏��R���T�[�g�@�@�@�́A�̌���w���Ҏ���̏��R���T�[�g�ŁA�A�[�w���s������M���I���т𗁂т��Ƃ���
�A 1946�N1���@�E�B�[���E�t�B���Ƃ̐�㏉�̃R���T�[�g
�B 1954�N�@������NHK�����y�c�Ƃ̌���
�C 1955�N�@�x�������E�t�B���Ƃ̏��̃A�����J�E�c�A�[
�D 1957�N�@�x�������E�t�B���Ƃ̏������R���T�[�g�E�c�A�[
�E 1958�N�@�x�������E�t�B���Ƃ̏��̃��[���b�p�E�c�A�[
�F 1963�N10���@�x�������A�t�B���n�[���j�[�E�U�[�������L�O����
�G 1988�N5���@�x�������E�t�B���Ō�̗�������
�H 1988�N10���@�x�������E�t�B���Ō�̃C�M���X����
�@�@�A�́A�i�`�X�}�����������߁A���R���T�[�g�������֎~����Ă�����̉�����
�@�@�C�D�E�́A�I�g��Ȏw���҂Ƃ��ăx�������E�t�B���𗦂��čs�������̊O���c�@�[
�@�@�F�́A�V�z�Ȃ����t�B���n�[���j�[�E�U�[���ł̂���I�ڌ����i�����́u���v�j
�@�@�G�H�́A�S���Ȃ�O�N�A���̒n�ł̃��X�g�E�R���T�[�g
�J�������Ɓu�u��1�v�Ƃ̊W�B���͂⑽����v���Ȃ����낤�B����́A�J�������ƃA�E���Ȃ���̂ɂ��čl���Ă݂����B
2009.01.12 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�S
�i�P�j�u�J�������{�v�̐V��2008�N�̓J���������a100�N�Ƃ��ŁA�������́u�J�������{�v���V�K�ɔ������ꂽ�B�ǂ̂�3���B����E��u�t���g���F���O���[�ƃJ�������v�́A1955�N�A�J���������x�������E�t�B���̏I�g��Ȏw���҂ɂȂ�܂ł̃h�L�������^���[�B����}�[���b�����u�،��E�t���g���F���O���[���J���������v�́A���҂�m��x�������E�t�B���̃����o�[�ւ̃C���^�r���[���́B�{�������u�J���������N���V�b�N���E�����v�́A"���݂̃N���V�b�N���y�E�̍��ׂ̓J�������̂�����"�ƒf����ߌ��ȉ��y�����_�B���́A���̖{�ɂ́A��a���Ƌ������o�����B��a���͔ނ̕��̂ŋ����͈��p�Ǝv�l�̈ꕔ���B
�u�J���������N���V�b�N���E�����v�́A1988�N5��5���̃T���g���[�E�z�[������b���n�܂�B���̓��̓J�������Ō�̗����R���T�[�g�ŁA�I�[�P�X�g���̓x�������E�t�B���A�v���O�����́u���[�c�@���g�����ȑ�39�ԁv�Ɓu�u���[���X�����ȑ�1�ԁv�������B���̉��t�́A��N�A��CD������A��������Ă���B
���҂͂��̓��́u�u��1�v�̉��t�ɂ��āA�u�ŏ��͊����������A���̂̒m��Ȃ����Ȃ��̂ɐG�ꂽ�悤�Ȍ㖡�̈������c�����v�ƌ����Ă���B���̂�����ɃJ�������̉��t�̔閧���B����Ă������ł��邪�A�ЂƂ܂�����͒u���āA�u�u��1�v���t��r�ɓ��낤�B
�i�Q�j�u�u���[���X�F�����ȑ�1�ԁv�ɂ�����J������ ���̂P
�J�������́u�u��1�v�͑S����8�v�𐔂���i09�N1�����݁A���K�Ղ̂݁j�B���Ԃ́A1943�N�̃R���Z���g�w�{�E�Ղ���A1988�N10��5���x�������E�t�B���A�����h�������܂ł̎���45�N�ԁA����́u�ߜƁv�ɕC�G����J���������C�ɓ���y�Ȃ̏ؖ����B
���u�u��1�v�����U�v��������ǂ��ƁA�J�������̃L�����A���j���[�E���f�B�A�Ƃ̊W���͂�����ƌ����Ă���B3�e�ڂƂȂ�@�́A58�N�Ɏ��p���������X�e���I�E���R�[�h�̂��߂̘^���B�����E�B�[���E�t�B����DECCA�A�x�������E�t�B����DG�A�J���������g��EMI�̐ꑮ���������߁A���R�[�h��DECCA����̔����ƂȂ����B���̃R���r�ł̘^����65�N�܂ő����B�A�͓����u�J������DG���S�ꑮ�v��搂��Ă̔����B�x�������E�t�B�����J������������ē���DG�ꑮ�ƂȂ��Ă̏��^���B�B�́A�O�^������14�N�A�x�������̃t�B���n�[���j�[�E�U�[�������Ƃ��āi63�N�Ղ̓C�G�X�E�L���X�g����j�V�Z�p�ɂ��^�����c�����������̂��낤�i�Ō�̃A�i���O�^���j�B�C�͂��̋ȏ��̃f�W�^���^���A�f���Ɠ������^�B�D�͍Ō�̓��{�����̃��C�u�^���B�E�͍Ō�̃����h�������̃��C�u�^���E�E�E�E�Ƃ���������B
�@�@�E�B�[���E�t�B��59�iDECCA�j
�A�@�x�������E�t�B��63�iDG�j
�B�@�x�������E�t�B��77�iDG�j
�C�@�x�������E�t�B��87�iDG�j
�D�@�x�������E�t�B��88�D5�D5�T���g���[�E�z�[���E���C�u�iDG�j
�E�@�x�������E�t�B��88�D10�D5�����h���E���C�u�iTESTAMENT�j
�܂��̓��R�[�h�|�p78�N12�����A��ؐ������̐V�����]����B�x�������E�t�B��77�����Ă݂悤�B�u�Ƃ���ʼn��t�����A���ꂪ�d���M�S�ƒO�O�������R�[�h�̏�Ōւ�J�������ɂ��ẮA�ǂ����B�̈�{�������������ɂ������炸�̔��[�Ȃ��̂ł���B�t�_�����X�^�b�J�[�g�����ׂĂڂ��������y�֎q�ɍ������悤�ȋC���ɉ^�ы����Ă���v�E�E�E���ꂱ���܂��ɁA�O��u�f��80�x�������E�t�B���v�Ŏ���������"�^�K�͊ɂݗ֊s�͂ڂ��A�C���̂Ȃ����ƚ삵��"�ɍ��v����B����Ɏ��͂��������Ă���u�w���҂ƃI�[�P�X�g���̊y���Ƃ́A�ŏI�I�Ȏd���̏�ł͑Λ�����ʂ̗̈���߂���̂��B�Ƃ��낪�J�������́A���ł̓I�[�P�X�g���E�T�C�h�Ɉ������܂�A�e�������y���݂̊J���̂ق��ɑË����Ă���v�ƁB������u�V�x���E�X��2��81�x�������E�t�B���v�ł�"�w���҂��I�[�P�X�g������ꍇ���̋ɒv�ŁA�����ɂ͉��y��n��o�����т��ٔ����������������Ȃ�"�Əq�ׂ����Ƃƕ�������B
�m���ɁA����77�N�̘^����"�����ɂ킽��I�P�Ƃ̕t���������A��ꍇ���ɂ��ٔ����̌��@��ŁA���C�̖R�������t�ƂȂ��Ă���"�Ɗ�����B��͂�A�J������70�N��㔼�\80�N��O����"��"�͖{���Ȃ̂��H
���̇B�����ɁA�܂�����ɐ旧�@�A�������E�l���Ă݂�B��������B�ɔ�ו\�����L�����ƒ��܂��Ă���̂���������B�@�E�B�[���E�t�B���Ղ́A��X�����\���͖��͂����A�\����d���I�P�̖���C�}�C�`���B�܂��w���҂̓O��x���ア�Ƃ������ƂɂȂ낤���B���̂Ƃ��J��������50�B�����E�B�[���E�t�B����v�N43�̂Ƃ��ɐU�����C�V���g���@���E�P���e�X�́u�u��1�v73�́A���ʓI�͋����Ə�M�Ɉ��A�I�P�̔�����������A���̉~�n�x�͗y���J�������̏���䂭�i�ܘ_�A���R�[�f�B���O�Z�p�̌���Ƃ������ʂ������ł��Ȃ����j�B���������̐l�������Ă�����A�J�������̖���������قǂ܂łɂ͏オ��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�{���ɐɂ����l��S���������̂��B�A�x�������E�t�B��63�́A�������ؗ�ɃI�[�P�X�g�����苿���A�J���������D�u����E�p��������ł���������B
��������ɂB�̂��ƁA�C�x�������E�t�B��87�͐M�����Ȃ��悤�Ȗ����ƂȂ��Ă���B�Ȃ�ƌ����Ă��������[�����Ă���B�L�����Ƃ����֊s�̒��ɖL���ʼnؗ�ȋ����������Ă���B�����ĉ��������ɋC�����U���Ă���B�\���ɐ��C���h���Ă���B��P�y�͂̑��d���A��2�y�̗͂D�����A��3�y�̘͂Ȃ܂��̔������A�I�y�̗͂E�s���ȂǁA���ꂼ��̐��i���A�����𗦒��ɏo���邱�ƂŗY�قɕ����B�����Ƃ���ꂽ�J�������̂ЂƂ̋��ɂ̃p�t�H�[�}���X�������ɂ���B
70�N��㔼����80�N��O��������܂ł̃J���������x�������E�t�B���ɂ͊m���ɖ}�����U������邪�A�����Ŏv���o�����̂��L���ȃU�r�[�l�E�}�C���[�������B
�r��������������������N�����l�b�g�t�҃U�r�[�l�E�}�C���[���C�ɓ������J�������́A�ޏ����x�������E�t�B���ɓ��c�����悤�Ƃ��邪�A�c���̔��ɂ����ċ��ۂ����i�x�������E�t�B���͒c���̓��[�ɂ���Ė���I�Ƀ����o�[�����߂�`��������A�����͂܂������c����F�߂Ă��Ȃ������j�B1982�N�̂��Ƃł���B�J�������͂�������āA�ޏ��������c�����邪�A�c���̈ӎu�͌ł��A�ŏI���[�ł����ہB����ł��܂������点�邪�A����1984�N�ޏ����g�����Â炭�Ȃ��đޒc�A�����̓I�P���̏����Ƃ������Ƃňꉞ�̌����������B���̎����ŁA�J�������ƒc���Ƃ̕s���͌���I�ƂȂ邪�A�m���̉�͊���70�N�ォ��萶���Ă����Ƃ����B����́A�J�������̋��ƌ��͂ւ̎����������炷�I�[�P�X�g���̎������u���������B���̎����ɂ�����x�������E�t�B���Ƃ̖}���͂��̕ӂ�ɂ�����������̂��낤�B
����A���̎����̖��������ĂȂ��͂Ȃ��B���[�O�i�[�̕���ՓT���u�p���V�t�@���v�i79�N�^���j�̓J���������̃f�W�^���^���Ŗ����̗_�ꍂ�����̂����A�ʔ����̂́u�}�[���[�̌����ȑ�9�ԁv�ŁA79�N�̃A�i���O�Ō�̘^����82�N�̃f�W�^���E���C�u�E���R�[�f�B���O��2��ނ�����B79�N�Ղ̘^�����Ԃ́A11�����痂�N��9���܂ŁA�Ȃ��10�����̒����ɓn���Ă���B����́A�J�n���O79�N10���A���i�[�h�E�o�[���X�^�C���̃x�������E�t�B�������ڌ������ӎ����Ă̂��̂ɈႢ�Ȃ��B�o�[���X�^�C���͂����Łu�}�[���[�̑�9�ԁv�����t�B���̃��C�u�E���R�[�f�B���O�͈�����̖����Ƃ̕]�����Ƃ����B���C�o���Ɏ蕺���g���Ă��̗L�l�A�J�������͖ق��Ă��Ȃ������B���ォ��̒����ɂ킽��O����ȃ��R�[�f�B���O�́A���̑R�ӎ��̕\�ꂾ�낤�B������3�N�����ɐV�^���A�������f�W�^���E���C�u�E���R�[�f�B���O�ł���B���C�u�Ƃ��������������ŐV�Z�p�ł̘^���B�������Ă�����"�o�[���X�^�C���͂��������ɂ͒ǂ����Ȃ�"�ƍl�����̂��낤���B�}�[���[�͋��Ƃ�����J���������A2����^�������Ȃ͂��ꂾ�����B�����܂������O�B����ȑR�ӎ��B�j���[�E���f�B�A������ŁA���ꂼ�܂��ɃJ�������^�����̃G�s�\�[�h�ł���B
���݂�79�N�Ղ�82�N�Ղ̃^�C���͊y�͂��ƂɊe�X�A29�F04�|16�F41�|12�F44�|26�F41��28�F10�|16�F38�|12�F45�|26�F49�ŁA�قƂ�Ǎ��ق��Ȃ��B�Ђ�X�^�W�I�Ђ�C�u�A3�N�o���Ă��قړ����^�C���ʼn��t���Ă���B�^�C�������邱�ƂȂ���A���t���̂��قƂ�Ǎ��ق͊������Ȃ��B������J�������炵���B���낢��ȈӖ��ŋ����[���Q�́u�}��9�v�����A�c�O�Ȃ���79�N�Ղ͔p�Ղ̂܂܂��B
�A���T���u���̗�������̂Ƃ������C�����œ˂��i�ރG���[�V���i���ȃo�[���X�^�C���B�ו��܂Ŗ����ʂ��l�H���̋ɒv���鐢�E�����グ���J�������B20���I���\�����l�̋������A�x�������E�t�B��������Ďc�������̑ΏƓI�Ȗ����́A���R�[�h���y�j����w�̖������̂ЂƂ��B�ǂ�����̂邩�̓��X�i�[�̎��R�B���̓}�[���[�̖{�����앗�ւ̍��v�x����o�[���X�^�C�����̂邯��ǁB
�J������84�N�u�ߜƁv�̖����̓E�B�[���E�t�B���Ƃ̂��́B����́A�����^�����̃x�������𗣂�A�E�B�[���ʼn��y�����ɏW���ł������ʂȂ̂��B87�N�u�u��1�v�x�������E�t�B���Ƃ̖����́A�}�C���[��������3�N�̎����o�ė��҂̊Ԃɐ������A�����Ӗ��łْ̋����̎������H
����́A�D�E�ŔӔN�́u�u��1�v2����l����B
2008.12.29 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�R
�i�P�j�����L�����p�X�ƃJ������3�N�قǑO����A�N���V�b�N���D�̎u���W�܂��āu�����L�����p�X�v�Ȃ�[�~�i�[�����Â��Ă���B�f�U�C�i�[�������ǂ���̃A�g���G�ɁA���y��w�y�����A���R�[�h��ЕҐ��}���A�����ǃN���V�b�N�ԑg����X�^�b�t�Ȃ�"���̂悢"�i�H�j�����o�[���A�����W�܂��āA���Ȉ10�_�̉��t�҂�ډB�����ĕ������Ă�Ƃ����A����"�N���V�b�N������"�̉�ł���B
�菇�͂����ł���B
�@ ���̌��̉ۑ�y�Ȃ����߁A���莝����CD�������o�[��"�ՋS"��l�i�e�X1�����A2�����̃R�Ƃ�������ł���B
�@�@���N�^�[�j�ɕ���B
�A �ǂ������A�ނ珊�L��CD�����̎茳�ɏW�܂�i���̐����悻10�|30���j�B
�B ����炷�ׂĂ��������āA10���̃m�~�l�[�g�Ղ����߂�B
�C �������i4�A5���̓��ꕔ���j��ݒ肵�A10�̉��t��������CD�|R���쐬����B
�D �[�~�i�[�������A���������s����CD�|R�������A�ډB�����������o�[�ʼn��t�҂č�
�@�@���B�����o�[�̒N�����S�_�������Ă�܂ŕ������ށB
�E �Ō�Ƀx�X�g���t�����߂�B
������n�߂����@�́A�u���t�̈Ⴂ�������Ȃ�A�ډB�����ĕ����ĉ��t�҂�������܂ŁA�������݂��ɂ߂�ׂ��ł͂Ȃ����B���̕]�_�Ɛ搶����"�ډB���e�X�g"�����āA���ꂪ�I�m�ɂ��̈Ⴂ���������Ă邱�Ƃ��o����̂��B�x�X�g���t�����߂�Ƃ��ȂǁA�������������̉��t����ׂĂ���̂��낤���B���t�]���A���\����ςłȂ���Ă���P�[�X�������̂ł͂Ȃ��낤���B�Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ����v���Ȃ��悤�Ȗ��ӔC�ȃx�X�g�ՑI�т����s���Ă��邩�炾�B�Ȃ�Ή�X���A�����̉��t����ׁA�ډB���ʼn��t�҂����ʂł���܂ŕ�������ŁA"�^�̖���"�����߂悤�ł͂Ȃ����v�Ǝv������������ł���B
�m�~�l�[�g�́A���̓ƒf�ŁA�ǂ��Ǝv�����t�A�������鉉�t��10�_���߂�킯�ł��邪�A�����ɂ́A���ԂŖ��ՂƂ����Ă�����̂��i���y�V�F�Њ��F�u21���I�̖��Ȗ��Ձv�Ȃǂ��ړx�Ƃ��āj�K������邱�Ƃɂ��Ă���B����́A���̃[�~�i�[�����A�J�Œ�]���閼���t���A��]���������͖Y�ꋎ��ꂽ���t�ŕ����A"�v�������ʖ����t"�@���邱�Ƃ��햡�Ƃ��Ă��邩��ł���B30�������Ă���Ƃ���ȃP�[�X�͂�����ł��o�Ă��Ď��Ɋy�����B
���Ƃ��A��25��u���t�}�j�m�t�̃s�A�m���t�ȑ�2�ԁv�Ńx�X�g�ɑI�肵�����N���C�o�[���^���C�i�[���ՁB����͒�]���閼�Ձ����q�e���^���B�X���b�L���Ձi�u21���I�̖��Ȗ��Ձv�̃_���g�c�̑�1�ʁj���f�R�����Ƃ������ƂɂȂ����B"�^�b�`�̋��x���͌݊p�����A���X�����ł͏���䂭�B���C�i�[�̎w�����ق��̒N�����f���炵���B���ꂱ������Ȏ҂̐S����ł��悭�\���Ă��鉉�t���B"�Ƃ����̂��I�藝�R���i�ڂ����́u�����f�U�C�����v��HP���������������j�B
���@���E�N���C�o�[���́A1958�N�A��P��`���C�R�t�X�L�[���ۃR���N�[���E�s�A�m����Ō����D�����ʂ������A�����J�̃s�A�j�X�g�B�������̂����A�\�A�̈АM���|�������ɁA23�A�e�L�T�X�o�g�̎Ⴋ�A�����J�l���D�����������̂ł���B�A�����J�̋����͂����܂����A�ނ͈�C�ɉp�Y�ɍՂ�グ����B�f�r���[�Ղ́A�R���N�[���̉ۑ�ȁu�`���C�R�t�X�L�[�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁv�i�R���h���V���w���j�ŁA����̓N���V�b�N�E�ٗ�̃r�b�O�E�q�b�g�ƂȂ����B�Ƃ��낪���̌�A�X���������f�r���[�̔������炩�A������ɓ���B�����[�X����A���o��������ɔ���Ȃ��Ȃ�A"�����̃s�A�j�X�g"�ƂȂ��Ă��܂��B���݂ł́A���͂⊮�S�ɖY���ꂽ���݂��E�E�E������"���N���C�o�[���̃��t�}�j�m�t�̑�2�ԁi1964�^���j���̓��q�e���Ղ��z���閼����"�Ə�����A���ɑ傫�ȃC���p�N�g�ƂȂ�킯���B�ł����ۂ����Ȃ̂�����d�����Ȃ��B�ډB���e�X�g�ŕ�������͈꒮�đR�ȂɁA���̔Ղ��]�_�̘�ɂ��o��Ȃ��i�����u21���I�̖��Ȗ��Ձv�ł̓m�[�}�[�N�j�̂́A�]�_�ƃZ���Z�C��"���̃N���C�o�[���̉��t������"�Ƃ�������ςŕ����Ă��邩��ɈႢ�Ȃ��B�����łȂ���A�ނ炪�������������Ă��Ȃ����A���̎��������������A�ǂ��炩���낤�B
���ƁA�u�u���[���X�̃s�A�m���t�ȑ�1�ԁv�ɂ����遃�J�[�]���^�Z�����Ձi���u�����f���^�A�o�h���Ղɑ��āj�A�u���z�����ȁv�́��u�[���[�Y�^�N���[�������h�ǁ��Ձi���~�����V���^�p���ǁ��Ղɑ��āj�ȂǂȂǁB�A���A����͑�햡�����A�����ĖړI�ł͂Ȃ��B�V���v���ɕ�����ׂăx�X�g��I�肵�Ă���킯�ł��邩��A�����Œ�]���閼�Ղ��x�X�g�Ƃ������ƂɂȂ�A���̌��ʂ͑f���Ɏ���A������蕢�����Ƃ͂��Ȃ��B
30��قǂ���Ă���̂ŁA�u�����L�����p�X�v�I��x�X�g���t�͓�������������킯�ł��邪�A���̒��ŃJ�������́A�V�x���E�X�̌����ȑ�2�ԁi�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�j�ƃu���[���X�̌����ȑ�1�ԁi�x�������E�t�B��87�j�Ńx�X�g�E�������l�����Ă���B
�i�Q�j�V�x���E�X�F�����ȑ�2�ԂƃJ������
�V�x���E�X��2�Ԃ́A��23��J�Ẩۑ�ȂŁA�o���r���[���A�x���O�����h�A�U���f�������N�A�����g�D�[���ɍ������āA�J�������ł́A�t�B���n�[���j�A��60�ƃx�������E�t�B��80��2�_���m�~�l�[�g�����B������ׂ̌��ʁA�Â��ق��̃t�B���n�[���j�A�ǂ����|�I�ɂ悩�����B�����C���̓����������Ⴄ�B���ʂ̓X�^�J�[�g�œ����P�y�̖͂`�����A�e�k�[�g�C���Ȃ̂ɂ͂���a�������������A�S�̓I�ɂ�����ƒ��܂����R��ƃ��}���̍���̃o�����X�������Ȗ����ŁA���ɑ�4�y�̖͂z���̂悤�ȏ�M�̕\�o�̓r�����r�����Ƌ��ɔ���B�������A�J�������Ɋ���Ȃ��Ȃ�āA�N���v��Ȃ����낤�B����ɔ�ׂăx�������E�t�B��80�́A���������Ă��邾���A�w���҂��I�[�P�X�g������ꍇ���̋ɒv�ŁA�����ɂ͉��y��n��o�����т��ٔ����������������Ȃ��B�����J�������ł���Ȃɂ��Ⴄ�A�Ɗ������̂͂��̎������߂Ă������B���̈ӊO�Ȍ��ʂ��`�Ŏc�����߁A�x�X�g�P�̓J���������ՂɌ��߂��B
���̐́A�J�������̎蔲���G�s�\�[�h���Q���蕷�������Ƃ�����B�ЂƂ́A1974�N�A�g�����y�b�g�̖��胂�[���X�E�A���h���ƃo���b�N�̃R���`�F���g�����R�[�f�B���O�����Ƃ��̘b�B���R�[�f�B���O�E�X�P�W���[���҂��̃A���h���ɓ͂����̂́A�Ȃ�ƃJ�������ƃx�������E�t�B�����t�̃J���I�P�E�e�[�v�������B��ނȂ��A���h���́A���l�̃X�^�W�I�ŁA�J���I�P���o�b�N�ɘ^�������Ƃ����B�Ђǂ��b�ł���B���E��̃g�����y�b�g�̖���̋C���͂ǂ�Ȃ������̂��낤�B
�ӂ��ڂ́A����ō��̃��@�C�I�����t�҃L�h���E�N���[�����̘b�B�u���[���X�̃��@�C�I�������t�Ȃ��J�������̃x�������E�t�B���ƃ��R�[�f�B���O����Ƃ������ƂɂȂ����C�s�̃��@�C�I���j�X�g�A�N���[�����́A���n�[�T���ɗՂ݁A��ʂ�e���I�����B�����{�Ԃ��ƈӋC����ŏo�������X�^�W�I�ɁA�J�������̎p�͂Ȃ������B�Ȃ�ƃJ�������́u���n�[�T���̃e�C�N��OK�v�ƌ����c���ăX�^�W�I�����������Ƃ������Ƃ����B�����1976�N�A�N���[����29�̂Ƃ��̂��ƁA�Ȍ�ނ̓J�������Ƃ͎d�������Ă��Ȃ��B
�����̃G�s�\�[�h����́A���y�ɑ���^�������،h�̔O���܂�œ`����Ă��Ȃ��B�鉤�ƂȂ����J�������́A�|�p�ɑ���A���������ŕs���ȑԓx�������Ă��邾�����B�����70�N�㔼����80�N�㔼���炢�܂ł̃J�������ɂ́A�I�P�Ɠ�ꍇ������̂Ȃ��}�����A�m���ɎU�������B
�i�R�j�z���X�g�F�g�ȁu�f���v�ƃJ������
�z���X�g��ȁE�g�ȁu�f���v���A�J��������2�R�[�f�B���O���Ă���B�ŏ���1961�N�E�B�[���E�t�B���A����1981�N�x�������E�t�B���ł���B�����ł́A��4�ȁu�W���s�^�[�v����A�`�������ƕ��������ő�q�b�g�����L���ȃR���[�������Ă݂悤�B���_���[�����Ĉ������܂�A�͋����N�X�Ɖ̂��グ��61�E�B�[���E�t�B���Ղɑ��A81�x�������E�t�B���Ղ́A�^�K�͊ɂݗ֊s�͂ڂ₯�A�C���̂Ȃ����ƚ삵���B���̍��͈꒮����Η�R�Ɖ���B�Ƃ��낪�u21���I�̖��Ȗ��Ձv�ł́A81�N�Ղ�10�_�l���ő�2�ʁA61�N�Ղ�3�_�̑�7�ʂƂ������d�s�v�c�Ȍ��ۂ��N�����Ă���B10�l�A���̕]�_�Ƃ̒��ł܂Ƃ��Ȃ̂́A"61�N�Ղ̂ق����f�R����"�ƌ���������O�搶�ƁA��2�ʂɓ���Ă���g�䈟�F�搶�������B�Ƃ��낪���̂�������ʂ̊y�Ȃł̓~�X�E�W���b�W��Ƃ��Ă���B���������Ă��̘A����10�l�̐搶�́A�u�����L�����p�X�v�I�Ɍ���A�c�O�Ȃ���S���s���i�ƌ��킴��Ȃ��B���̂�����͂܂��ʊ��ň����Ă݂����Ǝv���B
���Ȃ݂ɂ��̋Ȃ́A�u�����L�����p�X�v�ł́A��27��Ŏ��グ�Ă��āA�x�X�g���t�̓{�[���g�w���j���[�E�t�B���n�[���j�A�nj��y�c1966�ɋP���A�J�������F�E�B�[���E�t�B���Ղ͎��_�������B���̃J�������F�E�B�[���E�t�B���Ղ́A����܂Ń}�C�i�[�������u�f���v����C�ɐl�C�y�Ȃɉ����グ���������A���ՂƂ��Ă��������B���̋Ȃ̏����ҁE�C�M���X�̖��w���҃G�[�h���A���E�{�[���g�́A�J�������Ղ̏o���ɐG�����ꂽ�̂��A����66�N4�x�ڂ̘^���ł́A�����҂̈АM���������Ӑg�̖����t���s���Ă���B�P�������������܂��������ɂ���đt�ł��錄���Ȃ��i�������\���́A�z���X�g���z�肵���F���̐_��������ɕ`�������Ă���B���t�̃e�C�X�g�͐��ɃC�M���X���A���̕����ŃJ�������F�E�B�[���E�t�B���Ղ������Ă���B������ɁA���̖����t�A���݂͔p�ՂŎ�ɓ���Ȃ��B���R�[�h��Ђ́A����12�N��A�a�C�×{��89�̃{�[���g���A��������������o���č����5�x�ڂ̘^���i�I�P�͏����Ɠ��������h���E�t�B���j���A��ՂƂ��ăJ�^���O�Ɏc���Ă��邪�A���ꂼ�܂��ɋC�̔������r�[���A�V����������Ƃ�������Ȃ��A����͓T�^���B66�N�j���[�E�t�B���n�[���j�A�Ղ��uEMI�N���V�b�N�X�E�x�X�g100�v�ɓ����Ƃ͌���Ȃ����A���̖�����p�Ղ̂܂܂ɂ��Ă�����͂Ȃ��B���R�[�h��Ђɕ����������]�݂����B
�u���[���X�̌����ȑ�P�Ԃ́A��8��u�����L�����p�X�v�ۑ�ȁB�J�������F�x�������E�t�B��87�Ղ��A�x�[���F�x�������E�t�B���A�o�[���X�^�C���F�E�B�[���E�t�B���A�����^�[�F�R�����r�A���A���@���g�F�k�h�C�c���A�~�����V���F�p���ǂȂǂɌނ��A���X�̃x�X�g�P���l�����Ă���B
����́A������܂ރJ������4�̃u���[���X�����ȑ�1�Ԃ���ׂ�B
2008.12.22 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�Q
���J�������̑������N�A���a100�N���}�����J�������B�̂͂悩���������鎞������_���ɂȂ����Ƃ͂悭�����b���B���̈�̋�̗�Ƃ��ĐΈ�G���u�J�������͂������đ������v�i�w��M���Ɂu�鉤���特�y�}�t�B�A�܂Łv���j�����p���Ă݂�B
�u60�N��̏��߂ɘ^�������u���[���X��x�[�g�[���F���̌����ȂƂ��ꂩ��15�N�����Ę^�������������̂���ׂĂ݂�A���Ђւ̈��Z�Ƃ������̂��l�Ԃ��ӂ₯��������ʂ��͂�����ƌ��邱�Ƃ��o���邾�낤�v�j���[�E���f�B�A�̏o���ɂ���ĉ��y���v�����I�ɑ��債���@���3�x����B1948�N��LP�A1958�N�̃X�e���I�A1982�N��CD�̏o���A�ł���B����́A1908�N���܂�̃J��������40����74�܂łɂ�����A�܂��ɔނ̎w���҂Ƃ��Ă̐Ⓒ���ƕ�������B�����������ŁA�Z�p�̐i���A����̕ω��ɂ���߂ĕq���Ȍ|�p�Ƃ��J�������������B�j���[�E���f�B�A�͑�ʏ���݁A�J�������̉��ɂ͔���ȋ����]���荞�B����͕ʂɈ������Ƃł͂Ȃ��B���Ƃ�"���ɂȂ邩�特�y�������"�Ƃ��Ă��E�E�E�B���͂��̂��߂�"���y�����������ǂ���"�����ł���B
�u�J�������́A�O���I�܂łɂ͌����Ȃ������^�C�v�̉��y�Ƃł������B�����̈̑�ȓ��������y�n���Ƃ��Ĉ�̓�����ޒ��ŁA�ނ͂��������A�䓪���Ă������_�����s���{�Ǝ������A�|�p�����Ƃɕς��A���y�����Ɋ�����B���p���o���ALP���R�[�h����ɁA�X�e���I�A�f��A�e���r�A�r�f�I�ACD�Ǝ��X�Əo�Ă���j���[�E���f�B�A����荞��Ń}���`�l�ԂԂ���������B���y�Ƃɂ��Ă����̂͂��������Ȃ��قǂ�"������"�ł������v
�Ƃ͂����A�f�l�̎��Ɂu�J�������̉��y�����������ǂ����v�ȂǂƂ����e�[�}�͑s��ɂ�����B�ł��܂��A�Ȃ�Ƃ��g���C���Ă݂悤�A�~���������ɁB�J�������̓��Ȉ�������_���ɒ�����ׂ邱�Ƃɂ���āA�����ł��𖾂ł���Ɗ��҂��B
���`���C�R�t�X�L�[��ȁF�����ȑ�6�ԁu�ߜƁv�̉��t��r��
�܂��̓`���C�R�t�X�L�[�́u�ߜƁv���������낤�B���̋Ȃ́A1939�N�A�J���������ŏ��Ƀ��R�[�f�B���O���������Ȃł���A1988�N�A�Ō�̓��{�����̃��C���y�Ȃł��������B���N�ɂȂ��Ă��̃��C�uCD���������ꐳ�K�^����8�_�ɂ��Ȃ����B�܂��ɃJ�������̉��y�l���ƂƂ��ɕ����̊y�Ȃ������B���̒�����e�N����\����4�_��I�ђ�����ׂĂ݂�B
�@�@�@�@�x�������E�t�B��64DG�i�h�C�c�E�O�����t�H���j
�@�@�@�A�x�������E�t�B��71EMI
�@�@�@�B�E�B�[���E�t�B��84DG
�@�@�@�C�x�������E�t�B��88���{���C�uDG
���̋Ȃ̊y�z�̓��}���e�B�b�N�ƃ������R���b�N�����ւ��B���̂Q�v�f���@���ɖȁX�Ɣ����������o����邪�|�C���g�ƂȂ�B
[�|�C���g�P] ��P�y��2�x�ڂ̑�2��聨���}���e�B�b�N�v�f�̌���
�@�@�@�@�x�������E�t�B��64�i7�F26�`�j
�@�@�@�@ �L�����Ƃ����قǂ悢�R���������
�@�@�@�A�x�������E�t�B��71�i7�F01�`�j
�@�@�@�@ �������ʂ̉̂킹���B�S�ɐZ�݂���̂��H
�@�@�@�B�E�B�[���E�t�B��84�i7�F16�`�j
�@�@�@�@ ���F���̂��̂����ɒ^���I�Ŗ��͓I�B�O�����ƐS��h���Ԃ鋿��������B
�@�@�@�C�x�������E�t�B��88�i7�F22�`�j
�@�@�@�@ �B�Ƃ͈Ⴄ���F�ŁA�����L���Ŋ����I�ȋ����������o���B�\����Z���B
�m�|�C���g�Q�n��4�y�͖`�����������R���b�N�v�f�̌���
�@�@�@�@�x�������E�t�B��64
�@�@�@ �@�T�����Ƃ������Ĕ߂��݂������Ă��Ȃ�
�@�@�@�A�x�������E�t�B��71
�@�@�@ �@�l�H�I�ɔ�������������ł���Ƃ������
�@�@�@�B�E�B�[���E�t�B��84
�@�@�@ �@�`���̌����{���ɂ����苃���Ă���B�߂��݂��S�ɐZ�݂���ł���
�@�@�@�C�x�������E�t�B��88
�@�@�@ �@�B�ɂ��������Ԃ���悤�ȕ\���B�����苃���ɑ��Ă���͜ԚL���B
�u�ߜƁv�̓E�B�[���E�t�B��84�ƃx�������E�t�B��88���o���̑f���炵�����B88�N�Ղ́A�Ō�̗����R���T�[�g�A1988�N5��2���T���g���[�z�[���ł̋L�^�ł���B���C�u�E���R�[�f�B���O�Ƃ������Ƃ������āA�\���Ɉ�����̎����A���ꂪ�������ĂԁB�t���[�W���O�����݂��߂�悤�ɒO�O�œ��Ȃ�v���������i�������Ă���B��R�y�͂̋��ǂ̋��t��e�B���p�j�[�̋��łȂǂ��q��ł͂Ȃ��B���̊y�͂͂܂��A�e���|���x���A�s�i�ȂƂ��Ă̌y�������A���d�����������Ă���B�S�̂̃o�����X�Ȃǂ��\���Ȃ��̈ꔭ�������B����ɑ��A84�E�B�[���E�t�B���́A���F���e���|�����y���A����ׂ��ŏI�y�͂Ƃ̑ΏƂ��ۗ��B��Q�y�͂��A�d���X�e�b�v��88�N�Ղɑ��܂�ŃE�B���i�����c�̂悤�Ȍy�₩�����B
�J��������"�����Ȃ��Y�̕\����������\�����Ă��܂��|�p��"���ƒN���������Ă����B����������������R���[����ɏ���������w���҂Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ�A����قǁu�ߜƁv�ɓK�����w���҂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B���̈Ӗ��ŃE�B�[���E�t�B���Ղ̕����A���u�ߜƁv�̖{���Ƀ}�b�`���Ă���Ƃ�����������Ȃ��B���̓Ɠ��̉��F�����}���e�B�b�N�Ń������R���b�N�Ȋy�z�Ƀs�^���ƍ��v���Ĕ��ɏ����Ă���B
�J���������ŏ��ɘ^�����������ȁu�ߜƁv�B���̎v�����ꂠ��Ȃ̍Ō�̂Q�́A�ނƍł����̐[��2�̃I�[�P�X�g���ɂ��ΏƓI�Ȗ����t�ƂȂ����B�`���̉��F�ŁA�������R���[����ɂ܂ŏ������A�^���̋ɂ݂Ƃ������ׂ��E�B�[���E�t�B���̉��t�B�����L���ȋ����̒��A瞂銴����B�����Ƃ������A�v���������i��������x�������E�t�B���̉��t�B�������ɗ܂��邩�A�߂��݂ɗ܂��邩�B�Ō�ɓ��B��������2���́u�ߜƁv�̓J�������̕��݂��ے�����M�d�Ȉ�Y�ƂȂ����B�����Ɏ���"����������"�Ȃǂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̒��ɁA�ނ̔ӔN�̋��̓��������Ă���悤�ȋC������B
�ł́A�J�������̋��̓��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��H�ނ͔ӔN�A���̎�N���X�^�E���[�g���B�q�Ɂu�����������ʂ悤�Ȃ��Ƃ�����A���Ԃł悭������w�ނ͒�����Y�̖��ɖS���Ȃ����x�Ƃ������t���҂����肾�v�Ƃ��݂�������Ƃ����B����͒f�����������ւ̎����Ȃ̂��A�l���͋ꂵ�݂���Ƃ��������Ȃ̂��B�w���҂̃|�X�g�ɂ����Ă͒��_���ɂ߁A���y�r�W�l�X�ł͖��\�L�̐��������߂��鉤�J���������A�l���̍Ō�ɂ��Ă����q�����Ă���̂ł���B���̃J�������ɂ��Ă������킵�߂��l���Ƃ́A�l�Ԃ̍K���Ƃ͂����������Ȃ̂��낤���H �Ȃ�ƂȂ�����Ȃ��Ƃ��l����������G�s�\�[�h�ł͂���B
�I�[�\���E�E�F���Y�̖���u�s���P�[���v�i1941�N�āj�̖`���A��l���`���[���X�E�t�H�X�^�[�E�P�[�����ՏI�̏��ŁuROSEBUD�v�i�K�N���Q�j�Ƃ������t��ꂭ�B�f��͂��̂��ƁA���̌��t�̓��ǂ��ēW�J���邪�A�N�ЂƂ肱�̈Ӗ���������Ȃ��B���͂╪����ʂ܂I���̂��Ǝv�����Ō�̏u�ԁA�����"���N����ɗV���ɋL����Ă������t������"�Ƃ������Ƃ���ʂɎ������B�����̕x��z���V�����Ə̂���ꂽ�j���Ō�ɕ��������t�A�S�̒��Ɉꐶ�������������̂����ꂾ�����B�l�Ԃ������ɂ܂Ŏ����Ă䂫�������́A����͌��͂Ȃ���Ȃ��A�����̕x�ł��Ȃ��B�S�̒��̂������Ȃ��́A�l���ꂼ��Ⴄ�����B���ꂪ�A�V�����P�[���ɂƂ��Ắu�K�N���Q�v�������B���ɏ���ėV���N����̉��������v���o�������B�鉤�J�������ɂƂ��āA����͂Ȃ����̂��낤���B
2008.12.15 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�P
�@���ɂƂ��ăw���x���g�E�t�H���E�J�������i1908�|1989�j�͓��ʂȉ��y�Ƃł���B1957�N�x�������E�t�B���n�[���j�[�𗦂��ė����A�u�^���v�u�V���E�v�u�u���[���X��1�v�Ȃ�"�{��"���[���b�p�̃N���V�b�N���y�����Ă��ꂽ�ŏ��̎w���҂������B���y�]�X�ȂǕ�����Ȃ����w6�N���̎��́A�����e���r�ɉf��J�������̊i�D�����w���p���A�����E�b�g���ƒ��߂Ă��������B���̃N���V�b�N�l���́A�܂��ɃJ�������̊G�p�ŃN���b�V�F���h�����������Ƃ����邾�낤�B�@�Ƃ��낪�A���̌�J�������̃��R�[�h�Ɋ��������Ƃ����L�����Ȃ��B�k�o�ł́A�x�������E�t�B���Ƃ̃��[�c�@���g�̌���V���t�H�j�[�iEMI�j���āA���܂�̃��K�[�g�t�@��"�C��������"�Ɗ��������炢�̂��̂ŁA���̃J�������̌��́A���N����̎p�������̊i�D�ǂ��Ɏ䂩�ꂽ�����̎��ɒ��g�̂Ȃ����̂������B�����玄�ɃJ����������鎑�i�͂܂������Ȃ��B�Ƃ͂������N�͐��a100�N�Ƃ��ŁA���R�[�h��Ђ�30���~�̑�Z�b�g��o������A������Ă������C�u�^���@������A1��25���~������K���XCD���J�������̉��t�i62�N�́u���v�j��������A�����Η��N�͖v��20�N�Ƃ��ł܂��Z�[����W�J����炵���B����Ȏ������͂�������A�����i�v�ɃJ���������l���邱�Ƃ͂Ȃ���������Ȃ��B�����v���ăJ�����������グ�邱�Ƃɂ����B����Ȏ���ɂ��A���炭�f�ГI�ł܂Ƃ܂�̂Ȃ����̂ɂȂ肻���ł����A�����ق������������Ǝv���܂��B
���G���I�J�������f�́�
�@���҂̖��O�͖Y�ꂽ����ǁA�̂��閼�ȃK�C�h�Łu���t�҂�I�ԕK�v�͂Ȃ��B�J������������Ζ��킸�J��������I�ׂ悢�v�Ƃ����̂��������B�l�̌܂̌��킸�ɂ܂��J�������B�Ƃɂ������h�Ȃ̂̓J�������Ƃ������Ƃł����B��q����1957�N�̃J�����������R���T�[�g�]�ŁA�����悤�Ȍ꒲�Ȃ̂��������B�u����ŁA�s�A�j�b�V������t�H���e�܂Ŕ��ɕ����L���Ă݂�ȗ��h�ł����B���y�̑i�������Ă���ꏊ���A���̐悩��ܐ�܂ŁA�܂蓪���狹����A�����������̕��܂ŁA�S���ɕ������Ă���A���h�Ȃ��̂��Ǝv���܂����v�B�ȂႱ���I �S�g�}�b�T�[�W���H ����͒N�ł��傤�H ������������ł��ˁB�g�c�G�a�搶44�Ύ��̃R���T�[�g�k�ł����B
�@�ܖ��N�S�搶�̃��[�c�@���g�u���N�C�G���v�̃J�������]�\�\�u�J�������̃h�C�c�E�O�����t�H���́w���N�C�G���x�̉��t�͂Ђǂ��B�w���N�C�G���x�������ɉ��y�Ƃ��Ċӏ܂���l�ɂ͂ǂ����m��ʂ��A���̎��ɂ́A�����������炢�q���w���N�C�G���x�������v�i�u�����̉��v���j�Ƃ����܂������]�B�������t�ɂ��āA��Ƃ̂Ȃ��ɂ���搶�͂����q�ׂĂ���\�\�u���̉��t�͍ō��ł��B���E����ō��̍˔\���W�߂ăJ�������̃p���[�Ɨ��B�̘r�Œ�o���Ă���B�U���c�u���N���C�^���A���t�����X���A�����J���Ȃɂ��Ȃ��A����ΐ��E�̑僌�N�C�G����n�낤�Ƃ����B���ꂱ�����E�l���[�c�@���g�ɑ������������t���v�i�u�Ȃ��ɂ��烂�[�c�@���g�E�R���N�V�����vBMG JAPAN���j�B�Ђ⍓�]�A�Ђ��^�B�ł��A���搶�ɂ͓����悤�ɕ������Ă���悤�ȋC������B�\���͐����ɏo�Ă��B���ꂪ�J�������̐����Ȃ̂�������܂���B
�@�ܖ��搶�͂܂��A�J�������͗�������50�N��܂ł͂�����60�N��ɓ����Ă���̃O�����t�H���Ղ̓_�����Ƃ���������Ă���B�u�C�y�ɕ��������Ă���A�����ɂ�����l�D�݂ȃr�[�g�����������t�����A�܂Ƃ��ɒ����o���A���̐Ȃ��ƁA�����ςȂ��ƁA�T�[�r�X�ߏ�ŁA�i���̂Ȃ����ƁA�܂��ɃA�����J�l�����Ƃ����C������v�ƃ{���N�\�ł���B
�@1948�N����x�������E�t�B���ɍݐЁA�t���g���F���O���[�ƃJ��������l�̋����̌��ʼn��t�����e�B���p�j�[�t�҃e�[���q�F���̏،��B
�u�J�������͖ڂ��҂��āA����������Ă����B�����������A�����v�����Ȃ������B������A�I�[�P�X�g���̓t���g���F���O���[�̈�Y�P���A�Ǝ��̔\�͂ʼn��t���Ă䂯���B�����y�I�\�͂̂���c���������Ă�������A���̊y��̉��Ɏ��܂��Ȃ��牉�t����ȂǁA�킯���Ȃ������B�܂�A�J�������ɂ��Ă݂�A�ŏ��̘J�͂ŁA�ő�̌��ʂ��グ�����ƂɂȂ�B�����āA���ꂪ"���p�t�J������"�Ȃǂƌ���ꂽ���A���̂��Ƃ͂Ȃ��A�J�������Ȃǂ��Ȃ��Ă��A��X�͓����悤�ɂł����ł��傤�ˁB���ꂪ"���p�t�J������"�̎햾�����v�@�����Ă�����������B
�u�J�������̎w���Ɍ����Ă�����̂́A����ł��B�J������������Ȃ��Ŏw��������ƁA�I�[�P�X�g��������Ȃ��ʼn��t����B���������A�ŏ�����Ō�܂Ŗڂ��҂��Ďw��������A�I�[�P�X�g���Ƃ̌�M�͂Ȃ������R�ł��B���y�ɂ����āA��ԑ�Ȃ̂͊����\�����邱�Ƃł��B����̂Ȃ����y�́A���y�ł͂Ȃ��B�J�������̉��y�ł́A����͗����~�܂����܂ܓ����Ȃ��v�i�V���I���F����}�[���b�����u�،��E�t���g���F���O���[���J���������v���j�@�ɓx�ɔᔻ�I�ȏ،��ł���B�e�[���q�F����"�ŏ�����Ō�܂Ŗڂ��҂��Ďw��������I�[�P�X�g���Ɋ���͓`���Ȃ�"�ƌ����Ă��邪�i�܂��J���������ڂ��J���Ďw���������̂�80�N��ȍ~�Ƃ����̂���������j�A1957�N�J�������������t��̃��C�u�f���iNHK�G���^�[�v���C�Y���sDVD�j������ƁA"�ŏ�����Ō�܂�"�͊ԈႢ�ŁA�|�C���g�̏u�Ԃɂ͉��x���ڂ����J���ăI�[�P�X�g�����������Ă���B�e�[���q�F�����g�����̉f���Ƀn�b�L���Ǝʂ��Ă���̂�����A���̏،��i2007�N11���j�́A���������Ó����������Ƃ��킴��Ȃ��B����ɂ��ẮA�����x�������E�t�B�����ɂ̓t���g���F���O���[�M�]�҂����Ȃ�̐��������Ƃ̏A�Ƃ��đ������ق��������悤���B
�@���E�̃I�U��������Ȃ��Ƃ������Ă����B�u����Ƃ��A�����w���������t��ɃJ�������搶�����Ă��ꂽ�B���t���I����āA�y���ɗ����J�������ɋ��鋰��w�������ł������x�ƕ����Ă݂��B����������J�������́A�ŏ��̉�����A�����͂ǂ��������A�ǂ��͂ǂ��������A�������͂��������������������ق����������X�A���X�Ō�܂ŁA���ɂ���ׂɂ���A�I�m�Ȕ��f�����ꂽ�B�I���������̎��̎w���E���t�����ׂċL�����Ă����B�Ȃ�Ƃ����L���́I�Ȃ�Ƃ����˔\�I�v�Ƌ��Q���Ă����B�Ȃ������Ă����݂̍˔\�ł͂Ȃ��̂��B
�@�u���R�[�h�|�p�v1957�N11�����ɁA�J�������w���x�������E�t�B���n�[���j�[�̗����������ẮA���c���Y�A�u���h���Y�A���G�V�̓C�k������B��������X�s�b�N�A�b�v���Ă݂悤�B
���c�@�u�E�B�[���ɂ����Ă��A�J���������܂�Ő_�l�̂悤�ɍl����l�X�ƁA�����ł͂Ȃ��ăJ�������͐����͂̐l���ƌ����l�ɋɒ[�ɕ�����Ă���Ƃ������Ƃł��v�@�t���g���F���O���[�A�g�X�J�j�[�j�A�����^�[�ȂǓ����̋����w���҂Ƃ͈�����悵���A�V����̎w���҂Ƃ������������B�Ƃ�����艹�y���������߂Ď��g�ވ̑�ȃ}�G�X�g���ł͂Ȃ��A��ɒ��O�ɖڂ������A�ړI�ɉ����Ď��������킹�Ă䂭��p�ȐE�l�I�w���҂ƁA�����݂̂̕������Č��Ă���B�Ȃ�قǂ��̓C�k�̃^�C�g�����u�w����̖��p�t�J�����������v�ł���B�܂����������ł͔��f�̂��Ȃ����̂悤�ȏ��S�ȏ��N���A�J�������̃��R�[�h��Ȃ������̂͂��̕ӂɌ������������̂��낤�B�e���r�ł��̊i�D�ǂ��Ɋ������Ă��A�N�Ԑ���~�Ƃ������Ȃ��������䂦�A�O�O�Ƀ��R�[�h�G����ǂ݁A������L�ۂ݂ɂ��ă��R�[�h���w�����Ă�������ł���B�t���g���F���O���[�̃x�[�g�[���F���u�p�Y�v�u��7�ԁv�A�g�X�J�j�[�j�́u�V���E�v�u�x�[�g�[���F�����v�A�����^�[�́u�c���v���[�c�@���g�u�S�O�ԃV���t�H�j�[�v�Ȃǂ����̂���̈����ՂŁA���p�b�e�B�i�s�A�m�j�Ƃ́u�V���[�}���̃s�A�m���t�ȁv�����������Ă����B��̃J�������E�R���N�V�����������B����ɂ��Ă��A��N�u�J��������"���y�͋��ɂȂ�"�ƌ���Ă���������v�Ȃǂ̌������ɂ��A�m���ɃL�����A��ς�ł���̉��t�ɂ͋C���̓����ĂȂ����̂�����ƋC�Â�����͂������̂́A�܂����A1957�N�A�x�������E�t�B���Ƃ̗����̎��_�ŁA���łɌ|�p�ƂƂ������E�l�I�Ƃ�����ۂ���{�̉��y�E�ɗ^���Ă����Ƃ͋����������B
�u���@�u�J�������́A�t���g���F���O���[�̂悤�Ɉ�{��ʂ��ăO�C�O�C�����Ă���悤�Ȃ����ł͂Ȃ��āA���̋ȂɎ��������킹�Ă䂭�v
����@�u�J�������Ƃ����l�͂ǂ̂悤�Ȃӂ��������炵���ł��B����̓I�[�P�X�g���̎��ɉ����Ďg����������A���O�̎��ɉ����Ďg���킯���肵�āB�����牽�����Ԃ�������Ȃ��B���ɂ������w���҂Ƃ��v�����A�����Ȃ���Ȃ����Ǝv�����肷��v
�u���@�u�݂͂ǂ��낪�Ȃ��v
���c�@�u��ɒ��O���ӎ����Ďw�����Ă���v
2008.12.01 (��) �P�l�f�B�Ǔ� ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɓZ���Έ�G�ƌܖ��N�S
�@1963�N11��22���A�A�����J�哝�̃W�����EF�D�P�l�f�B���ÎE���ꂽ�B���E���߂��݂ɂ��ꂽ���N�A�ނ�Ǔ�����~�T���s��ꂽ�B���̏�ʼn��t���ꂽ�̂����[�c�@���g�́u���N�C�G���v�ł���B�P�l�f�B�́A�A�����J�j�㏉�̃J�g���b�N���k�ɂ��哝�̂������B���̓T��ɁA�J�g���b�N�l���́u���N�C�G���v�����t���ꂽ�̂ɂ́A����ȕK�R�����������킯�ł���B�@����́A���̃��R�[�f�B���O���߂���Έ�G�A�ܖ��N�S�̌��������ɘb��i�߂Ă݂����B
�i�P�j �Έ�G�́u���̈ꖇ���I�v
�@�Έ�搶�́u�~�T�ȁv�ɂ��Ă̍l������"�T��̒��ł����̂��悢"�ƈ�т��Ă���B�u�Έ�G�̂��̈ꖇ���I�v�i�V���فF�u���[�c�@���g �x�X�g101�v���j�́u���N�C�G���v�̍��ɂ͂�������B
�u���Ȃ����ɁA�V���X�^�C�������藐��āi�ł����藐��āj���܂��܂ȉ��t������B�������w�Պ��~�T�x�̍��ł��������悤�ɁA����̓T��̉��y�͓T��̒��ŕ����ׂ��ł���B���̐́A�P�l�f�B�哝�̂̑��V�̃��C���^��������A���̉��y�����̋Ȃ������B���̃��R�[�h�����ʂ���T��̖͗l�́A���̈ٗl�ȉ��y�ƂƂ��ɋ���ł��̂����������A���ł͎�ɓ���Ȃ��v�@�����Ŏ��グ��ꂽ���R�[�h�́A1964�N1��19���A�{�X�g�����\���ˑ吹���ɂ�����A�����J�哝�̃W�����E�e�E�P�l�f�B�̒Ǔ��~�T�̖͗l�����^�������C���Ղł���B���t�̓G�[���q�E���C���X�h���t�w���{�X�g�������y�c�A���B���̃��R�[�h�́u���[�c�@���g �x�X�g101�v���������ꂽ2004�N�̎��_�ł͔p�Ւ����������A���[�c�@���g�E�C���[��2006�N�ɂȂ���CD�����ꂽ�B
�@���̉��t�́A�ŏ�����ٗl�Ȃ܂ł̔M�C�ɕ�܂�A�I�n��сA�Ō�܂ł��ْ̋������r��邱�Ƃ͂Ȃ��B���e�ɓ|�ꂽ�̑�ȑ哝�̂̎��𓉂ށA�A�����J�����́A���E�̐l�X�́A�߂��݂����ڂ������̂悤�ȋ���Ȋ���̔��I�������ɂ͂���B���Տ��u���N�C�G���v�́A�h�i�ȃ\�v���m�E�\������̍����uexaudi orationem meam�v�i�킪�F������܂��j���A����قǐ؎��ɋ������̂͑��ɂȂ��B�u�L���G�v�u�݂��̑剤�v�u���ꂵ���́v�̂�����݂�ʂނ��o���̊���͂ǂ����B���҂̍���V��ֈ��炩�ɑ���̂��u���N�C�G���v��������Ȃ����A�n��Ɏc���ꂽ�l�Ԃ̜ԚL���肪�������郌�N�C�G�������������Ă����B����قǂ��́u���N�C�G���v�́A�ߒQ�Ƃ�������������ɖ����Ă���B
�@�Ƃ��낪�A���̃��R�[�f�B���O��l�������B�̌ܖ��N�S�ł���B
�i�Q�j �ܖ��N�S�̃A�����J�ᔻ
�@�ܖ��N�S�i1921�|1980�j�́u�����̉��v�i�V����1969���j�́A���y�ƃI�[�f�B�I�ɑ���A��҂̐q��Ȃ炴��v����f�I�����A���j�[�N�ȑ̌��I�G�b�Z�C�ł���B�Ώۂւ̓��ۂɂ������M���v���́A�ǂގ҂����₨���Ȃ���҂̐��E�ֈ������荞��ł䂭�B���́A���̂قƂ�ǂɋ���������̂����A���̒��ň�����[���ł��Ȃ��͂�����B�肵�āu���Ɖ��y�v�B�����ŁA�ܖ����́A���̃P�l�f�B�Ǔ��̂��߂̃��[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɂ��Ă����q�ׂĂ���B
�u�P�l�f�B�����Ƃ��A���V�����[�c�@���g�́w���N�C�G���x�ŏI�n�����̂͒m��ꂽ�b�����A���̂Ƃ��̎������R�[�h���r�N�^�[����o�Ă���B�P�l�f�B���ÎE���ꂽ���Ƃ̈Â��́A���̃~�T�̑������̒��ŁA���̂��Ɛ���Ă����B�������v��r�����ȃW���N���[�k�̜ԚL�ƒQ���́A�V���̂ǂ�ȑ������ɂ����ꋎ�邱�Ƃ͂Ȃ��B�����̑��V�ɂ͐���l�̎Q�q�҂��W�܂������������A�[���߂��݂ő��V�ɗA�V��������d���Ă����̂̓W���N���[�k�Ƃ�������������l���B����́A�P�l�f�B�̂��߂̃��N�C�G���ł͂Ȃ��A�ޏ��̂��߂̒����Ȃ������B�@�ܖ��N�S�͐l��l��瀂��E���Ă��܂����o�������B���̎����́A�E���Ă��܂����l�Ԃƈ⑰�ɑ�������Ǝ��ӂ̔O�ɋ���A���[�c�@���g�́u���N�C�G���v���Â蕷�������p���Ȃ������Ƃ����B������P�l�f�B�̃��R�[�h�̂��Ƃ����̂܂����ɍ~�肩�����Ă���̂��B�u���N�C�G���v���đ��������̂���߂邵���Ȃ��������X�̎������A�ۂ����ł����e���Ă��܂��̂��B�{���̋ꂵ�݂͓����҂ɂ���������Ȃ��ƁB������v���ƁA�ނ̎v�l���⑰�ł���W���N���[�k���S�l�Ɂi�����j�������̂͗����ł���B�ޏ����߂��ނ͓̂��R�����A���ꂪ�ޏ��̂��߂̃~�T�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����낤�B������ɁA�P�l�f�B�͌��l�ł���B�������A�A�����J�����͂��Ƃ�萢�E�����爤���ꂽ�A�����J�哝�̂Ȃ̂ł���B�����炱���"�ޏ��̂��߂���"�̃~�T�ł͂Ȃ��̂��B
�@����ǁA�������N�C�G�������Ƃ߂˂Ȃ�ʗ���ɂȂ��Č�������Ƃ́A���̎����^���̃��R�[�h�͍ȃW���N���[�k�̂��߂����̂��̂ł���A��������i�����A����o�����Ƃ̖`���ɂ��Ăł���B���N�C�G����ɍs���^�����Ē����L�O����̂͂����B�������A�Ȃɂ����E�Ɍ������Ĕ���o�����Ƃ͂Ȃ��B���҂��Ƃ́A�̂����ꂽ�Ȃ̂��Ȃ��݂ɓ���̗܂𗬂����ƂȂǂł���킯�͂Ȃ����A���̋Ɛт�J�ߏ̂��邱�Ƃ��A���S�l�ւ̂������ɂȂ�̂Ȃ�A�����L�Ɏ��Ȃꂽ�ЂƂɁA����͂��킢���L�ł����ƖJ�߂�悤�Ȃ悻�悻�����ƁA�ǂꂾ���Ⴄ���B�������A���̈⑰�ւ̎v�����������ȊO�̒������Ȃǖ{���͂���킯�͂Ȃ��̂ł���B
�@�������傭�A�A�����J�l�̓P�l�f�B���ÎE�������ƂŊԈႢ�A���S�l��������邱�Ƃł�����ɑ傫�Ȍ���Ƃ����B�A�����J�Ƃ������́A���[�c�@���g�̂��́w���N�C�G���x�ꖇ���Ƃ��Ă݂Ă���T�̏��˂������Ă��邱�Ƃ��킩��v
�@�ܖ��搶�͂܂��A�u�̐l�̋Ɛт�J�ߏ̂��邱�Ƃ́A�����L���Ȃ������ЂƂɁA�L�͂��킢�������Ƃ����A�悻�悻�����ƈ��Ȃ��v�ƌ������A������Ԉ���Ă���B�̐l��ɂ���Łu�ނ͗��h�ȋƐт��c�����v�Ƃ��A�܂��A�S���Ȃ����L���u�Ȃ�Ă��킢���L�������̂ł��傤�v�Ɖ������ނ��Ƃ́A�ʂ����Ăǂ����悻�悻�����̂��낤���B�����ɂ͌̐l���̂��������ޏ����ȋC���������邾���ł���A�܂��Ă�P�l�f�B�ł͂Ȃ����B
�@�L���O�q�t���~���A�L���[�o��@��������A�R�k��}��A���a���������x�����X�g�哝�̂��ˑR���̕s���̋��e�ɓ|�ꂽ�̂ł���B�A�����J�������A���E�̐l�X���߂��ނ͓̂��R�ł͂Ȃ����B���̐l���~�T�̃��R�[�h�ɗ܂��ĉ��������̂��B�W���N���[�k�����ɂ����܂͋�����Ȃ��Ƃ����̂��B�ނ̎��𓉂ށA�n�[�����̍��l�Ɣޏ��̔߂��݂Ƃ̊ԂɁA�ǂ�قǂ̍�������Ƃ����̂��B�f���Ă��̃��R�[�h�̓W���N���[�k�����̂��̂ł͂Ȃ��B
�@�ܖ��搶�͎����̗��V�ł��̃��N�C�G�������B�A�����J�l�̓A�����J�l�̕������ł�������B���͎��ł��̃��N�C�G�����B����ł����ł͂Ȃ����B���������@���^���Ă��ꂽ�̂́A�A�����J�����̉��t�𐢊E�Ɍ����Ĕ������Ă��ꂽ���炾�B����̂ǂ��������Ƃ����̂��B�����`���Ƃ����̂́A�Պ�т����������n�̂��Ƃ��A���Ȓ��Œ����I�Ȍ����ł����Ȃ��B�A���A�A�����J����T�̘H���˂������Ă������Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ����Ƃ����B
2008.11.17 (��) �Έ�G�̂��̈ꖇ���I
�@�Έ�G�i1930�|�j�́u���̈ꖇ���I�v�i�V���فu���[�c�@���g �x�X�g101�v���j�͖��Ղ̕�ɂ��B���̃K�C�h�������̂́A���Ԉ�ʂɗ��z���Ă���"����"�Ə̂�����̂��قƂ�Ǔo�ꂵ�Ȃ����Ƃ��B����́A������͂Ȃɂ����E����Ȃ��搶�Ǝ��̑I��ł��邱�Ƃ̏ł���A�����Ă��ꂪ���ɂƂ��đf���炵�����y����Ȃ̂́A����Ă�����Ƃ�悪��̑I��łȂ��ؖ����낤�B�����̒�����Ƃ��Ă����̃��[�c�@���g�����Љ�����B�g�c�搶�ւ̃A���`�E�e�[�[�Ƃ����Ӗ������߂āB�����Ă�����A�u�g�c�G�a���a��v�̍ŏI�͂ɑウ�����Ǝv���B�@�V�����h�[���E���F�[�O�w���U���c�u���N�E�J�����[�^�E�A�J�f�~�J�@�u�Z���i�[�h�A�f�B���F���e�B�����g�W�v�i10���gCD�ACapriccio�j
�u�����A���[�c�@���g�̃Z���i�[�h��f�B���F���e�B�����g���~�����Ƃ����l������Ƃ���A���͂��߂炤���ƂȂ����̃Z�b�g���������̂ł���B���Ƃ��̃W�������Ɋւ��Ă͉E�ڍ�ᾂ���K�v�͂܂������Ȃ��B���킸���̃Z�b�g���悢�̂ł���v�@2�N�قǑO�A���̓f�B���F���e�B�����g �j���� K136�̗ǂ�CD��T���Ă����B�A�i���O����̃o�E���K���g�i�[�i�I�C���f�B�X�N�Ձj�ȗ��A�C�ɓ��������t�ɏo����Ă��Ȃ��������炾�B�����ŁA���y�V�F�Ёu21���I�̖��Ȗ��Ձv��ǂ�ŁA��1�ʂ̃g���E�R�[�v�}���w���A���X�e���_���E�o���b�N�E�I�[�P�X�g�����Ă݂����A�s���I�h�y����L�̃M�X�M�X�������t�ŁA�S�R�C�ɓ���Ȃ������B
�@�搶�́u���̈ꖇ���I�v��ǂ̂́A���傤�ǂ���ȍ��ł���B�Ȃ�Ƃ������������ȃK�C�h���낤�B�������M�O�������Ă���B���͒����ɂ��̃Z�b�g�����߂��B�j136��P�y�͖`���A��P��肪����o�����u�ԁA�̂��k�����B���t���̒����삯�߂������B�����Ɩj�͍g�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B�Ȃ�Ƃ������������Ƃ������y�Ȃ̂��낤�B���̉����ɐ������������܂�A�������ƂȂ��Ď��R�ɓ�������Ă���B�C�^���A���s����A��������̏��N���[�c�@���g�̊�тƋ����������ɓ`����Ă���B���킸�����Ė{���ɗǂ������I ���^����Ă��邻�̑��̊y�ȁAK137�A138�A251�u�i���l���v�A334�u���k�G�b�g���v�A525�u�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�v�A�����ɂ́A�ǂ�ЂƂƂ��Ċ����̂Ȃ����y�͂Ȃ������B
�A�N���t�H�[�h�E�J�[�]���i�s�A�m�j�A�x���W���~���E�u���e���w���C�M���X�����nj��y�c�@�u�s�A�m���t�� ��27�� ���� K595�v�iDECCA�j
�u���[�c�@���g�̍Ō�̃s�A�m���t�Ȃُ͈�ȋȂł���B�قƂ�Ǒ����~�߂��悤�Ȑ�捂ȋ�Ԃ݂̂������Ď��Ԃ��Ȃ��悤�ȁE�E�E�B���̐��E�����̂̌����ɒe���o���Ă���̂��A�N���t�H�[�h�E�J�[�]���̎���A�Ǔ��ՂƂ��Ĕ������ꂽ���̃f�B�X�N�ł���B���̗\�������鉹�y�B�����Ď��̗\���̂��鉉�t�B�I�[�P�X�g���̎w���̓x���W���~���E�u���e���A���̏�Ȃ��f���炵���v�@���̋Ȃ̏�����1791�N3��14���B���[�c�@���g���J�̐Ȃł̍Ō�̉��t�������B���肭�鎀�̗\���̒��Ŕނ͂ǂ�ȋC�����ł��̋Ȃ����t�����̂��낤���B����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���J�[�]���^�u���e���Ղ��ƁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��C���ɂȂ��Ă���B���͒ɂނ��A�߂����킯����Ȃ��B�Ȃ�����ǁA���������킯����Ȃ��B�����ɂ͐����̂悤�ɏ����ȉ��y�����Ă��邾�����B���ݐ������[�c�@���g�̍����Y���Ă��邾�����B
�@�o�b�N�n�E�X�ƃx�[���w���E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�̉��t�́A������Ӗ��őf���炵���B�����ȃo�b�N�n�E�X�́A�I�y�͂̏I�Ղň�u����鑕�����ɁA�ނ̟������C���_�Ԍ�����B�������C�ȃ��[�c�@���g�̉��y�ɁA�l�ԃo�b�N�n�E�X�Ƃ����X�p�C�X���قǂ悭���������A���̂����������▭�Ȃ̂��B
�@�g�c�搶���A���̋Ȃ̃J�T�h�V���̉��t�ɂ��Ă��������Ă���i�������Ɂu���R�[�h�̃��[�c�@���g�v�j�B
�u���̎�i�̊Ȍ��Ɛ^��̏����Ƃ�����������ʂ��A��̌ǓƂ�\�����Ă��܂�����ՓI�ȍ�i�ɂ��ẮA�J�T�h�V���ł́A���܂�ɋq�ϓI�ɒ��߂����A�����̐��E�ɓ��邱�Ƃ��x����������C���������āA���̂���Ȃ��B�Ƃ����̂��A���̂���܂ł̍l���������B�����A���̂���ɂȂ��āA�����Ă���Œ��A�����ł́A��̌ǓƁA�܂�œ��������A�o���̂Ȃ������̒��ɂƂ����߂��Ă��܂����V�˂̎p���A�����������ɋq�ϓI�ɂЂ���Ă�������A�������āA���т����`�ŕ����オ���Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����u�Ԃ�����悤�ɂȂ��Ă����B�Ƃ����Ă��A����ł́A�ْ��x�����R�����悤�ȋC�����āA�J�T�h�V���̌��E���������̂��ȂƂ����l���������Ԃ̂������ł���B���̎v�����������ǂ����A���̐�́A�ЂƂǎҏ����ɔ��f���Ă����������v�@���͂��������]�_��F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ƃ�����莄�Ƃ͂܂������Ⴄ�������Ǝv���������B�J�T�h�V���������ɒe���Ă��悤�����܂����ǂ��ł������B�J�T�h�V���Ɍ��E�����낤���Ȃ��낤���ǂ������Ă����B�����m�肽���̂́A�搶�͂��̉��t���āu���������̂��ǂ����v�u�������y���Ǝv�����̂��ǂ����v�Ƃ������Ƃ������B�������炸���āu�ǎҏ����ɔ��f���Ă����������v�ł����B�搶�́A�v�����������ǂ����̔��f���A�f�l�̂����Ɋۓ����ł����B�]�_�Ƃ��ǎ҂ɔ��f���ς˂悤�Ƃ����̂Ȃ�A"���ꂩ���ꂩ"�ł͂Ȃ���"���͂ǂ������Ǝv��"���炢�̈ӎv�\���͂��Ă���Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�N�C�Y�̏o��҂��Ⴀ��܂����B�搶�͊m���u���Ƃ��Č����A�w���̓X�̂Ƃ͂��������x�ƁA�͂����茾���̂��{���̔�]�v�Ƃ���������Ă��܂����ˁB����ł͂܂�ŁA���s�s��v���̂��̂ł��B�Έ�搶�́A�����Œj�炵���]�_�Ƃ́A��ׂ�ׂ�������܂���B
�@�ł́A���������u���̈ꖇ���I�v�����i�̂T�����Љ�āA�{�e����߂����Ǝv���B�搶�̈ꔭ�R�����g�t�ŁB�������܂��Ɏv�������Ȃ��I�����ł���B
�B�e���T�E�V���e�B�b�q�������_���i�\�v���m�j���W���N���[�k�E�{�m�i�s�A�m�j�@�u���[�c�@���g���V���[�x���g�̋ȏW�v�i�u�[�ׂ̑z���v�u�N���[�G�Ɂv�u�t�ւ̓���v�u���݂�v�� Accord�j
�u���[�c�@���g�̉̋ȂƂ����ƁA�w�G���[�U�x�g�E�V�������c�R�b�v�x�Ȃ�Ă��l���ɂȂ�̂͂ǂȂ��ł����B�����A�m���Ƀs�A�m�̃M�[�[�L���O�͂��炵���ł��ˁB�ł��A���̌��h��̃��C�N�p�̂悤�ȉ̂������ق�Ƃɂ���قǐ邵�����̂ł����B�x���ꂽ�Ǝv���ăV���e�B�b�q�������_���ƒ�����ׂĂ݂Ă��������v�C�W�m�E�t�����`�F�X�J�b�e�B�i���@�C�I�����j�A�u���[�m�E�����^�[�w���R�����r�A�����y�c�@�u���@�C�I�������t�� ��3�� �g���� K216�v�iSony�j
�u"���������̖��������A�����ȂĂ���ɉ�����"�ƃC�G�X�͌������B���@�C�I���������̊��\�I�Ȕ�������������A�����ȂĂ���ɑウ���悤���B���@�C�I�����̋�������͏I���A�n�̐K���̉��������Ȃ��Ȃ������A���̍Ō�̈�l���t�����`�F�X�J�b�e�B�������B�u���[�m�E�����^�[�Ƃ̂��̋��t�Ȃ̘^���B�܂��ɔ����v�D�W�����A�[�h���y�l�d�t�c�@�u���y�l�d�t�� ��14�� �g���� K387�v�iSony�j
�u�l�d�t�c�Ƃ������̂́A�l�l���ύt�������̂ł���A��l�̃��[�_�[�ƎO�l�̐����ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��������܂��Ƃ��₩�ɚ����ꂽ�������������B���ۂɂ���Ă݂�킩�邪�A����I�ȃA���T���u���ȂǂƂ����̂͋�z�̎Y���ł���A�����ꂽ�`�[���͂����ꂽ���[�_�[���琶�܂����̂Ȃ̂ł���B���Ƃ��A���̃��o�[�g�E�}���̂悤�Ɂv�E�f���B�b�h�E�I�b�y���n�C���i�N�����l�b�g�j���u�_�y�X�g���y�l�d�t�c�@�u�N�����l�b�g�d�t�� K581�v�iSony�j
�u���㐏��̃N�����l�b�g�̖���̓��`���[�h�E�X�g���c�}���B���̔ނ����i����̂��I�b�y���n�C���ŁA�ނ͍����t�̍�����}�E�X�s�[�X���g���Ă���B�ނ̓j���[���[�N�ɏo�Ă��ď��߂ăI�b�y���n�C�������Ƃ��̊����͖Y����Ȃ��Ƃ����B����́A�u�_�y�X�g�l�d�t�c�Ƃ������̏�Ȃ��p�[�g�i�[�������ǂ���̗��j�I�Ȗ��Ղł���v�F�~�G�`�X���t�E�z���V���t�X�L�[�i�s�A�m�j�@�u���z�� �j�Z�� K397�v�iNonesuch�j
�u�z���V���t�X�L�[��95�̂Ƃ��A������x���{��K��A�J�U���X�E�z�[���Ń��T�C�^�������Ă��ꂽ�B�o�b�n�A���[�c�@���g�A�V���p���A�V���[�}�������ă��B�������{�X�Ȃǂ�e�������Ă݂����̂����A������������̉��y���玩�R�ɔ�����悤�ȉ��F�ɂȂ��Ă���A�s�A�m�������̈�F�ł����e�����Ƃ����ł��Ȃ��s�A�j�X�g�����ɂƂ��Ă͖����̂ł����Ƃ������B���̃z���V���t�X�L�[�̍ŔӔN�̔��������[�c�@���g������v�@�ȏ�͂�������101����7�B
2008.11.10 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�V���G�s���[�O
�m�o�b�N�n�E�X�ƃM�[�[�L���O�n�g�c�G�a�搶�̒����u���E�̃s�A�j�X�g�v�o�b�N�n�E�X�̍��ɂ���ȋL�q������B
�u���͂�������ȏ�A�����Ɏ��߂�ꂽ�Ȃɂ��Ă͂ӂ�Ȃ��B���ɍŌ�́w�C�Z�������h�x�iK511�j�́A���̔M������Ȃł���A�o�b�N�n�E�X�̉��t�́A���̋Ȃ̍ŏ�̂��̂̂ЂƂ��ƍl���邯��ǂ��v����̓o�b�N�n�E�X�́u���[�c�@���g�E���T�C�^���v�Ƃ����A���o���̂��Ƃɂ��Č��ꂽ�Ō�̕����ł���B���̃A���o���̓^�C�g���ǂ���AK331�i�g���R�s�i�Ȃ��j��K332�Ȃ�4�̃\�i�^�ƁA��ʂ̏��i�u�����h �C�Z�� K511�v�����^����Ă���I�[���E���[�c�@���g�E�v���O�����̃A���o���ł���B���̑O�i��K332�Ȃǂɂ��Ă͏ڍׂɘ_�����Ă���̂ɁA"�M�������"�ɑ��Ă͍Ō�ɐ\������x�ɐG��Ă��邾�����B�{���ɔM������̂Ȃ�A���̋Ȃ̑f���炵�����A�܂��A�ŏ�̉��t���o�b�N�n�E�X�Ȃ�A�Ȃɂ��ŏ�Ȃ̂���_����̂��ł͂Ȃ����B�V������Ȃ��̂����炢����ł����ʂ͂���͂����B�����������r���[�������ɂ͉䖝�Ȃ�Ȃ��BK511������Ȉ��������ł��Ȃ��̂Ȃ�A"�M������"�Ȃ�Čy�X���������Ăق����Ȃ��B
�Έ�G�搶���ӔC�ҏW�����u���[�c�@���g �x�X�g101�v�i�V���فj�Ƃ����{������B����͐搶���A���[�c�@���g�̑S�y�Ȃ̒�����x�X�g�Ǝv����101�Ȃ�I��ʼn�����A���̃x�X�g���t���u�Έ�G�́w����1�����I�x�v�Ƃ������ڂ̒��őI�肵�����[�c�@���g�̖��ȁE�����K�C�h�ł���B���ȁE�����K�C�h�͐��X���邪�A���͂���قǂ܂łɌ��I�������I�ȃK�C�h��m��Ȃ��B
"���̃��[�c�@���g"�̓��[�c�@���g���D�҂̐���������B���������"�q�ϓI��"��낤�Ƃ������N�҂��Ă������܂��Ƃ��������ʂɂȂ邾�낤�B�����玄�́A�����Ђ����ɂ���ϓI�I�����s����101�Ȃ�I��ł݂��B�Ȑ������̒��ŁA�����ėL���Ȃ��O���āA��������"������"�Ȃ��������̂ɂ́A���[�c�@���g�̑S�̑��𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ����_�����������E�E�E�E�搶�͂��̖{�́u�܂������v�ł����q�ׂ��Ă���B�����Ђ������Ȃ���S�̑������ށA���Ȃ킿��ϓI�ŋq�ϓI�ȁA�����ȃo�����X�ŏ�����Ă���̂ł���B
�ł́A���̒��́u�����h �C�Z�� K511�v�̍������Ă݂悤�B
���ȏЉ�u�����h �C�Z�� K511�v���A�s�A�m�ȗ��s�̕ϑJ�̒��ő����A�Ȃ̐��i���牉�t�̓���ɋy��Ńx�X�g���t�����ߋ����錩���ȃX�g�[���[�W�J�ł���B�Έ�搶�̏ꍇ�͂����������B���������͂͊i�������ɕ�����₷���B������[�����Ē����ɂ��̉��t�������Ȃ�B�C�����������ח��āA�B���ȕ\���ɏI�n���A�D�����Ƃ����Ȃ��璆�r���[�ł��I���ɂ��ĕ��R�Ƃ��Ă���A�ǂ����̑�搶�Ƃ͑�Ⴂ�Ȃ̂ł���B
�s�A�m�̏��i����́A���́u�����h �C�Z�� K511�v�����グ�����A������"���i"�Ȃ��甒���̔������������Ă���i�}�f�̒e��������Ȃ��j�B19���I�ɂȂ�ƁA�s�A�m�Ȃ͏��i����ŁA�\�i�^�̐��͏��Ȃ��Ȃ�B���X�g��V���p����擪�ɁA�s�A�j�X�g�̓T�����̏���������邽�߂ɁA�m�N�^�[���A�����c�A�}�Y���J�Ȃǂ̏��i���������Ə������B���[�c�@���g�̂���͂��傤�ǂ��̉ߓn���ɂ���A�㗬�̏����������e�����蕷�����肷��Ȃ́u�\�i�^�v�i��y�ȁj�Ƃ��������z�ȃ^�C�g�������Ă����B���[�c�@�c�g�����������i�̑����̓\�i�^�����Ăł����ЂƂ̊y�͂Ɠ����ŁA�A���O���Ƃ��A�A���_���e�A���邢�͂��̋Ȃ̂悤�Ƀ����h�Ƃ������肪���Ă���B���́u�����h �C�Z�� K511�v�́A1787�N3��11���Ɋ������Ă����ɏo�ł��ꂽ���Ƃ���A�ŏ����犷�����ړI�ŏ����ꂽ�͖̂��炩�ł��邪�A�����K�̎�肩�炵�āA�㗬�̉��l�����̂��Ղ������y�Ƃ͌������˂�l�ɍ���Ă���B
���Έ�G�́u����1�����I�v��
���̋Ȃ̎�����Ȃ��T��Ȏ�A�����ď����o�����J�D�̉e�A����炪�s�A�j�X�g�����ɁA���t���Ă݂����Ƃ����~�]���N��������B�������A�����Ă��͂��̋Ȃ̏p���ɂ͂܂��Ă��܂��A�����炮����Ƃ킯�̕�����Ȃ����t�ɂȂ��Ă��܂��B���[�����C�̂悤�ȍ�i�Ȃ̂��B����o�b�N�n�E�X�ɂ��Ă��������Ă���Ƃ͌�����B
�B�ꂱ�̋Ȃ����Ƃ������Ƃ��ł��A�Đ����邱�Ƃ��ł����̂́A��Ȏ҂̍ė��M�[�[�L���O���B
�E�B���w�����E�o�b�N�n�E�X�i1884�|1969�j�̓��C�v�c�B�q���܂�h�C�c�̃s�A�j�X�g�B�h�C�c�ÓT�h�A���}���h�̋����Ƃ��ČN�ՁA�u���Ղ̎��q���v�ƌĂꂽ�B
�����^�[�E�M�[�[�L���O�i1895�|1956�j�̓t�����X�̃��������܂�h�C�c�̃s�A�j�X�g�B�V�˔��ŁA����y����ǂ����ł����Ȃ�Õ��Œe�����Ȃ����Ƃ����Ă���B���p�[�g���[�̓��[�c�@���g�A�x�[�g�[���F���Ȃǃh�C�c�ÓT�h����h�r���b�V�[�A�����F���Ȃǃt�����X���y�܂ŕ��L���B
�g�c�搶���������Έ�搶�͐����Ƃ͂�����ƌ��������o�b�N�n�E�X�B�Έ�搶���B�ꐬ�������Ƃ����V�˃M�[�[�L���O�B���̓�l�́u�����h �C�Z�� K511�v����ׂĂ݂悤�B
�M�[�[�L���O�́A�y���Ƃ����f�ނ����܂肢���炸�ɒW�X�ƒe���B�f�ނ��̂��̂��f���炵���̂�����A�Ȃɂ������������H���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ�������ɁB������Ƃ����ĂȂɂ����ĂȂ��킯����Ȃ��B�L�b�`���ƍ��ꂽ�����h�`���iA�|B�|A�|C�|A�j�Ƃ����`������ɂ��邱�Ƃɕ��S����B���`���i�Ȃ܂��̔������j�̃A�s�[���ł���B����́A3����v��蕔��A���N�b�L���ƕ����������Ă��邱�Ƃ�����M����B���Ȃ킿�A�M�[�[�L���O�́A3��Ƃ������e���|�E�����ȑz��A��e���B����ɁABC�����̃e���|�����R�Ȋ����ő��߁A���ʂ̋N��������A�ɂȂ��Ă���BA���ۗ������邽�߂ɁB���̂ق��ł͂�������Ƀe���|�����悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B�܂��ɐ▭�Ȃ��������ł��̋Ȃ̐��k�Ȕ������������o���Ă���̂ł���B�Έ�搶�������A��Ȏ҂̍ė����V�˂̋Z�Ƃ́A�����������Ƃł͂Ȃ����B
�M�[�[�L���O�ɔ�ׂ�ƁA�o�b�N�n�E�X�̉��t�́A�e���|�����ӏ�����葽���B���Ƃ���`��������������悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�y�_�������p���āA�܂�őS�̂����}���h�̌��z�Ȃ̂悤�ɕ�������B������ЂƂ̕\�����낤���A�M�[�[�L���O���������k�Ŕ��������̋Ȃ̘Ȃ܂��͌����Ă��Ȃ��B�o�b�N�n�E�X���A�x�[�g�[���F���̃\�i�^�Ō�����A�����̑��`���������Ă��Ȃ��B�Έ�搶��"�Ȃ̏p���ɂ͂܂�"�ƌ������̂͂����������Ƃ������̂ł͂Ȃ����B
����́A�M�[�[�L���O�ƃo�b�N�n�E�X�̋Z�ʂ̍���������Ȃ����A�����łȂ���������Ȃ��B���܂����́AK511�ɂ����āA��l�̉��y���Ȃ̘Ȃ܂��ɏƂ炵���킹�Č��������̂��Ƃł���B
�ŋ߁A�X�C�X�̎��I���o�[�E�V���i�C�_�[�Ƃ����s�A�j�X�g��K511�������A����͑f���炵�������B�V�g�̉H�т̂悤�Ɋ��炩�ł��������̂悢�^�b�`���������݂ȉ��y��t�ŁA���������ꂽ���R�Ȑ��_����������K�����ŕ�ݍ��ށB���݂ɕ\�����Ă��Ȃ���A���̋Ȃ̗J�D���܂��k�ȘȂ܂�����������B�����o����鐐�X�����R������܂�Ȃ������B����ȉ��t���B����͗N�X���̓c�������狳���Ă����������i���̕��͐����l�ł��I�j�B���̃s�A�m�𗼐搶���ǂ��]�����邩�������[���B
�Ƃ�����A������܂��A�g�c�搶�����Έ�搶���x�����邱�ƂɂȂ����B����͕ʂɐ���ςł������Ă���̂ł͂Ȃ��A�f���ɉ��t���Ƃ���������̂�����d�����Ȃ��B���̏ꍇ�A���y���g�c�搶�Ƃ͈���ĕ������A�Έ�搶�Ƃ͓����ɕ�������̂��낤�B
����́A�g�c�G�a�搶�ւ̃A���`�E�e�[�[�Ƃ��āA�Έ�G�搶�u���̈ꖇ���I�v���炳��ɉ��Ȃ��Љ���Ă��������Ȃ���A�����ɓn�������̘A�ڂ���߂����Ǝv���B
2008.10.27 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�U
�i�P�j�ܖ��N�S�ƃ����h�t�X�J�@�ܖ��N�S�̖����u�����̉��v�i�V���Њ��j�̒��ɁA�����_�E�����h�t�X�J���s�A�m�Œe�������[�c�@���g�́u�����h�@�C�Z��K511�v�̂��Ƃ������Ă���B�ܖ����̎���ɐ����t��������ȃR���N���[�g�E�z�[���̉������P���悤�ƁA���̌㕔�ɍ�������ʕ����̋�Ԃ��A�g���b�N�P�䕪�̏��ЂŖ��ߐs�����Ƃ������܂������Ƃ����āA���o���������Ƃ��̌��ł���B���̃R���N���[�g�E�z�[���͏c���Q���[�g���A�����̃I�[�f�B�I�E�̏d���A����d�����v�̃X�s�[�J�[�ŁA�㕔���������ЂŖ��߂�Ƃ����̂����̃A�h�o�C�X�ɂ����̂������B
�@�u�������A�I�P�͂������A���@�C�I�����E�\�i�^�⌷�y�l�d�t�Ȃ͂������낵���Ȃ��B�J�[�N�p�g���b�N�̃o�b�n�̃p���e�B�[�^���r���@�̃^���m�C�̑����Ƃɂ��y�Ȃ��B�����h�t�X�J�̃s�A�m�ɂ�郂�[�c�@���g�́w�����h�x�\�\���̐_�i�Ƃ��̂��ׂ������t�\�\����낵���Ȃ��v�E�E�E���njܖ����͍��鎁�Ɏ��]���Ă��̃R���N���[�g�E�z�[����@������̂ł���B
�@���́A�ܖ��N�S�̍����Œf��I�ȕ��́i�g�c�G�a�搶�̖͌ЂƂ��ď_�a�ȕ��̂Ƃ͑ɂ́j�Ɖ��y���I�[�f�B�I�ɂ����鋶�C�Ƃ��������M�ɁA�L�������킹�����|����M�Ă����B���̃X�s�[�J�[���^���m�C�Ȃ̂��ܖ��搶�̉e���ł���B"Stirling"�Ƃ����A�V���[�Y�ŏ��̂��̂�����A�搶�̃I���W�i���E�I�[�g�O���t�ɂ͔䌨���ׂ����Ȃ����낤���A���\�������Ŗ��Ă���\���������Ă���B ���āA���̒���"�_�i�Ƃ��̂��ׂ������t"�Ƃ������t���C�ɂȂ��āA��X�����Ă݂����Ǝv���Ă��������h�t�X�J�̂j511���������A2006�N���[�c�@���g�E�C���[�ɐ��E��CD������Ă���B���炽�߂Ē����Ă݂����A���ɕs�v�c�ȉ��t�������B
�@���̋Ȃ́A�V�V���[���A���_���e�̃e���|�ɏ���đt�ł��郍���h�`���ɂ��s�A�m�̏��i�ł���B��v��蕔����A�Ƃ���ƁAA�|B�|A�|C�|A�Ƃ������������h�`���Ő��藧���Ă���B�����Ă��̎�v���́A�܂��ƂɃ��j�[�N�ȃ����f�B�[�E���C���������Ă���̂ł���B�S8���ߒ��ɁA��������������Ɓi�L�������ꂽ������"�^�[��"���܂߁j53�̉��������邪�A�Ȃ�Ƃ��̂�����18�ɔ����L���i��or��j�ƃi�`�������L�����t���Ƃ������ɃN���}�e�B�b�N�i�����K�I�j�Ȏ��Ȃ̂��B���W���[�ƃ}�C�i�[���s�ӂɌ���Ă͏����A����������ɂ͑S����ǂ݂��Ȃ��B����������1���߂Ƒ�5���߂ɃL�b�`���ƐU�蕪�����A�S�̂̉������т͊����Ɏ��܂�A���̊����x�͈ꉹ�̏o�������������Ȃ��قǂ̌��������B�Ƃ��낪���̊m�ł��鉹������o����鉹�y�́A�������ĕ��������Ƃ��Ȃ��悤�ȁA�����ƊÔ����̃o�����X���Ƃꂽ�A�����̃����V�Y���ɖ����Ă���B�܂��ɐ�i�̃s�A�m���i���B���[�c�@���g�̉��y�́A�����ȗ���̒��ɕs�ӂɕs��������o������A�߂��݂̒�����}�Ɍ����������肷��B�����������͂������R�Ɍ��������y�̗���������~�߂邱�Ƃ͌����ĂȂ��B�Ƃ͂��������̕ω��͗����y�z�̒��ōs����̂����ʂ��B�Ƃ��낪K511�̎��́A������8���߂̎����ł����ω��̌������s���Ă���̂ł���B�Ȃ�Ƃ����s�v�c�Ȏ�肾�낤�B
�@�����h�t�X�J�́A���̋Ȃ����t����ɂ������Ă̐S�\���ɂ��āA��������Ă���B�u���[�c�@���g���g�͊ɏ��y�\�\�����͑����y�͂��������̑�������K�v�Ƃ���\�\���A�����X�P�b�`�����ɂƂǂ߂Ă����킯�ł͂Ȃ��B�ׂ₩�Ȓ��ӂŎ�̂悢�������{�����Ƃ����Ȃ��炸�������B���̍ł������ȗ��K511�ł���B�����牉�t�҂́AK333�I�y�͂̃J�f���c�@�ł͎��R�ɑ������t���{���Ă悢�̂����A�u�����h�@�C�Z���v�͂��̂����Ȃ��]���ȔM�����g�������ĉ��t���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�i�u�v�{�S�q�E�F�u�T�C�g�v�����p�j�E�E�E ���Ȃ킿�ꉹ����邪���ɏo���Ȃ������x������K511�ɑ��ẮA�Ƃɂ������[�c�@���g���y���ɏ����L�����Ƃ��蒉���ɒe���ׂ��ƌ����Ă���̂ł���B
�@�͂����ă����h�t�X�J��K511�͂ǂ��Ȃ̂��낤���B�ޏ���3���ߖڂ�7���ߖڂł��Ȃ�͂�����ƃe���|�𗎂Ƃ��ȂǁA���̉��t�͖{�l�������Ă���قǏ]���Ō��g�I�Ƃ͎v���Ȃ��B�ł����̃A�S�[�M�N�͎��Ɏ��R�ɉ��y�ɏ���ĉ��t�҂̌ċz��f���ɔ��f���Ă���B���܂肢�����Ă͂����Ȃ��Ȃ��������Ă��T�}�ɂȂ�E�E�E������ܖ��搶�͐_�i�Ə̂����̂ł͂Ȃ����B�ł������������̂͂ނ�����������ɏo���ꂽK333�̂ق��ł������B
�@�����h�t�X�J�͓���CD�̒��ŁA�u�\�i�^�@�σ�����K333�v���e���Ă���B���߂��ɒ����Ă݂���A���ꂪ�����B�ŏ�����x�̂����B��1�y�͂͑u�₩�ȑ�1��肩��n�܂邪�A�����Ȃ肻�̑�5����6���̊Ԃɑ傫�ȊԂ�u���B�������ɂƂ�ꂽ������́A����ɂ���J��Ԃ����`�����̈ٗl�Ȃ܂ł̈Ӗ��Â��ɁA����ɋ��������B�����ɂ͊J�����ꂽ���_�̎��R������A���ꂪ�T�}�ɂȂ��Ă��鐦����������B�����Ɛ����̂͑�3�y�͂̃J�f���c�@���B�قƂ�ǂ̑t�҂̓��[�c�@���g���c�������̂����̂܂ܒe���Ă��āA����̓M�[�[�L���O�ł��A�����[�E�N���E�X�ł��A�s���X�A�O���_�A���c���q�A�{�q�A�݂ȓ����ŁA���Ԃɂ���1���\�R�\�R�̂��̂��B
�@�����h�t�X�J�̃J�f���c�@�͑S���Ⴄ�B���Ԃ�����ׂĂ�2��13�b�ƁA�ق��̒N���������̂����A����������Ⴄ�B�����h�t�X�J�����݂ɍ��ς��Ă���̂ł���B���V���R�t�X�L�Ɏt��������Ȃ̘r���Ⴆ�Ă���B�C�}�W�l�[�V�����Ɉ��A�L���Ȋ������瓱���ꂽ�y�z�͋�Ԃ����݂ɔg�ł����V����B������̐S�͎��R�ȉ��y���_�����m����тɖ��������B�M���ɂ͓G���܂���ƂЂꕚ�������Ȃ��B���ꂱ�����ޏ����g����郂�[�c�@���g���t�ɂ�����"���R�Ɏ{���Ă悢����"�̋ɒv�ł��낤�B�B��R�ł���̂�1������v����O�[���h�ł��邪�A����ƂĂ����`��傫���ς��Ă���킯�ł͂Ȃ��B��ȉƂł�����O�[���h�ł������܂łȂ̂�����A�����h�t�X�J�̕\���҂Ƃ��Ă̎��R�z�����͗]�l�̋y�ԂƂ���ł͂Ȃ��B�������A�O�[���h�ȑO�ɔޏ����s�A�m�Łu�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv��e���Ă�����E�E�E�z�����邾���ł����N���N���鉼�肾�B
�i�Q�j�g�c�G�a�ƃO���_��K545��K333�Ȃ�
�@�����h�t�X�J������"���[�c�@���g�̎{���Ă悢����"�́A�t���[�h���q�E�O���_�̒e���u�\�i�^�@�n����K545�v�ɂ����ĂƂ��B����ɂ��Ă͂킪�g�c�G�a�搶���A�����u���E�̃s�A�j�X�g�v�̒��Łi�u���[�c�@���g�ɒ����v�Ƃ����T�u�^�C�g�������āj��^����Ă�����̂ŁA���̕�����v�Ă݂�B
�@�u�O���_�͂��̋Ȃɂ�������̑����������Ēe���Ă���B��������錎�]�q�����������Ƃ����ē{���Ă���̂��ǂB�������A���̉��t�͎��ɉ��y�I�ŏ����̖������Ȃ��B�����ł͊y���ɋL�ڂ��ꂽ�Ƃ���̌J��Ԃ����s���Ă��邪�A�ŏ��̎��ɑ��������������āA�J��Ԃ��ł܂��ʂ̑����ɏo��ƁA�Ăы������^������B�Ɠ����ɁA����͂��������ɂƂǂ܂炸�A��������ȉ��y�̎����̎��R�Ȑ��_�̂͂����ɂӂꂽ��тƂȂ�B���̉��t�����[�c�@���g�ɒ����łȂ��̂��ǂ����B������������̓��[�c�@���g�̊y���ɑ���l�����ɂ���B���[�c�@���g�́A���y�͂��̂��ׂĂ��y���ɏ����\������̂ł͂Ȃ��A�܂��A���ׂ��ł��Ȃ��ƍl���Ă����̂ł���v
�@�������̍l�����ɂ͑�^���ł���B���͏�X�A"�y���ɒ����ȉ��t�Ƃ����̂̓i���Z���X�ł���A��ȉƂɒ����Ƃ����Ȃ�Ӗ�������"�ƍl���Ă�����̂ł���B�y���͉��t���邽�߂ɍ�Ȏ҂������Ƃ߂��w�W�ɉ߂����A��Ȏ҂̈Ӑ}���邷�ׂĂ̗v�f�荞�ނȂ�Ă������Ƃ́A�n�߂���s�\�Ȃ��ƂȂ̂��B���t�s�ׂƂ́A�y�������Ȏ҂̈Ӑ}��ǂݎ���āA�������ƂȂ������Ƃ����L���ɐ����𐁂����݁A���y�Ƃ����������ɕς����Ƃ̂��Ƃ��ƍl���Ă���B
�@�Ƃ܂��A�l�����Ƃ��Ă͋g�c�搶�Ɏ^���Ȃ̂����A�͂����ăO���_�̂��̉��t����Ȏ҂̕`�������y�ɂȂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA���͂����v��Ȃ��B���̉��t�A�ǂ������Ă��S�n�悭�Ȃ��B�����ƌ����Ă��܂��A���̃A�h���u�͂��邳�������܂�i�D�悭�Ȃ��B����ȃW���Y�s�A�j�X�g���ތ^�I�ȃA�h���u��e���Ă���悤�Ɏ��ɂ͕�������B�������A��2�y�͒��Ԃ̒Z�����������͑f���炵���A����͂������₨���Ȃ��ɖ�������B�Ȃ�ƁA��������ȃs�A�j�X�g���낤�B������A�A�h���u�͂��������ɂ���悩�����̂��i�o�b�N�n�E�X���AK595��3�y�͂Ō������悤�Ɂj�B����"�߂�����͋y���邪�@��"�������Ƃ������Ƃ��B�����搶��"����ŐS�n�悢"�Ƃ�������������āA����͂��������̈Ⴂ�����A���ꂱ�����y������ĕ�������̂����牽���������Ƃ͂Ȃ��B�F����͂��̑����������ǂ��������邾�낤���B
�@���̉��t��1965�N�O���_34�̂Ƃ��̘^���ł���B����CD�ɂ�K333�������Ă���B��̑�3�y�̓J�f���c�@���Ă݂�ƁA�����ł͉�������Ă��Ȃ��B���[�c�@���g���c�������ʂɏ]���Ēe���Ă��邾�����B�����h�t�X�J��i�̃A�h���u�Ɣ�ׂĂ݂��������̂ɁA���Ɏc�O�ł���B
�@�u�Պ����v�Ƃ���K537�̃s�A�m���t�Ȃ�����B���[�c�@���g�͂��̋Ȃ̊y���ɍ���̃p�[�g���قƂ�Ǐ�������ł��Ȃ��i���ɑ�2�y�́j�B���̊y���͌�ɑ��l���������������̂ł���B���ꂱ�����t�҂���Ȏ҂̈Ӑ}��ǂ�ő����I���t�����ׂ������Ȃ̂����A1983�N�^���̃O���_�i�A�[�m���N�[���w���j�́u�Պ����v���c�O�Ȃ���قڊy���ǂ���ɒe���Ă��邾�����B����ł́A���㏗�����[�c�@���g�e���̑��l�҃s���X�i�A�o�h�w���j�́A�Z���X�悢�������������ς��ɐU��T���������ȉ��t������̂����B
�@�쑺���炦�т����u���Ȍ���Ձv�i�������Ɂj�̃s�A�j�X�g�E�����h�t�X�J�̍��Ɂu�����܂ł��Ȃ��N���u�T���̃����h�t�X�J�����A�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă��m���ŁA�s�A�m���t�ȁw�Պ����x�j�����i���[�c�@���g�j���r�N�^�[JD1076�|9���͖����t�Ƃ���Ă���v�Ƃ����L�q������B����͂܂����������A�����炭��Q�y�͂Ȃǂł́A�i�s���X�ȏ�ɁH�j�v���葕���������ĉ��t���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B��ɓ���Ă��ЂƂ��m���߂Ă݂������̂ł���B
�@���̃W���Y�ɂ����\�ȃO���_�����炱���AK545�̃\�i�^���A�\�i�^K333��u�Պ����v�̂ق��ŁA���̃A�h���u�̖������ė~���������B���ꂱ�����[�c�@���g�̉��y�ɒ����ȉ��t�s�ׂ��낤�Ǝv���B�����ȃO���_�ɂ���Ȃ��Ƃ�������ʂ͂��͂Ȃ��̂����E�E�E������Ⴋ����K545�̎��s���g���E�}�ƂȂ��Ă���̂��낤���H
2008.10.13 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�T
[�O�����E�O�[���h�̃o�b�n]����2�O�[���h�́u�t�[�K�̋Z�@�v�͕s���ȑ㕨
�@�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�̑f���炵���ɔ����A�O�[���h�́u�t�[�K�̋Z�@�v�͎��ɕs���ȑ㕨���B���̋Ȃ́A20�ȑO��i�Ȑ��̒�����Ȃ����ߓ��肵�ď������Ƃ͏o���Ȃ��j�̋Ȃ��W�܂��č\�������J�DS�D�o�b�n�ŔӔN�̖��삾���A�����̏�ɔގ��g���ȏ����y��w��������ɖS���Ȃ��Ă��܂������߁A������"��Ȏ҂̈Ӑ}"���m�肳��Ă��Ȃ��䑽����i�ł���B���������ĉ��t����ɂ������ẮA�t�҂͍l���z���͂��������Ď����Ȃ�̌`�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�u�t�[�K�̋Z�@�v�́A�o�b�n�̎��̗��N�i1751�N�j�ɏ��ŕ����o�ł��ꂽ�B�\���͈ȉ��̒ʂ�ł��邪�A���t�҂͂�������ƂɁA�Ȃ�I�����ȏ������ߊy���I�Ԃ��ƂɂȂ�B
�@�@�@�t�[�K���R���g���v���N�g�D�X(Contrapunctus)�i�ȉ�C�j�Ƃ����ď̂�11�ȕ��ԁBC�P�|C11
�@�@�A�����t�[�K�i�݂��ɑΏ̌`���Ȃ��t�[�K�j��2�g�BC12�CC13
�@�@�BC10�̉������i���炩�Ȍf�ڃ~�X�̂��߁A���ʂ͊O���j
�@�@�C�J�m����4��
�@�@�DC13��2��̃N�����B�[�A�p�ɕҋȂ������́i�Ȃ����Ƃ������j
�@�@�E�����̃t�[�K�BC14
�@�ߔN�̌����ɂ��ƁA�@�A�iC1�|C13�j�܂ł́A��o�b�n�̈ӌ������f����Ă���ƌ����Ă���i�A��C12�C13�ɂ����鋾��[recta�Cinversa]�̏��Ԃ͖��m��j�B
�@1962�N�^���̃O�[���h�̃��R�[�h�ł́A���ŕ�����9�Ȃ̃t�[�K�iC1�|C9�j�������I���K���ʼn��t���Ă���B��L�\���\�����Ă��A�t�[�K��11�ȔT��13�ȉ��t����Ȃ�܂������A9�Ȃ����Ƃ����̂͂����ɂ����r���[�ŁA�����ɂ͂Ȃ��Ӗ������o���Ȃ��B�������A�����J���o�Ղ̃��C�i�[�m�[�c�ɂ́A�f�C���B�b�h�E�W�����\���Ƃ����l�̓�������̂Ȃ��y�ȉ���ƁA�O�[���h���I���K���Œe�����Ƃ̐�������\������x�ɏ��������͂��ڂ��Ă��邾�����B���̒��̃I���K���Ɋւ���ꕔ�����Љ�悤�B
�@�u���̘^���Ɏg�p���ꂽ�I���K���́A�g�����g�s�L���O�Y�E�F�C�̃I�[���Z�C���c����̂��̂ŁA65�n���̃X�g�b�v�A3900�{�̃p�C�v������A�l�I�E�o���b�N�I�ȑf���炵�������������Ă���B���ɃO�[���h�̃o�b�n���t�ɂ͂����Ă��̂��̂ł���B "���̐��\�N�̊Ԃɖk�đ嗤�ɏo�����������Ƃ��f���炵���s�A�j�X�g"�ƌ�����O�����E�O�[���h���A���x�̓I���K�j�X�g�Ƃ��ĐV���ȉh������ɂ��悤�Ƃ��Ă���B�ނ͎q�����ォ��I���K�����w�сA14�̎��ɂ́A���Ђ���I���K���E�R���e�X�g�ł���J�T���@���E�V���[�Y�ɏo�����Ă���B���݁A���t�ƃO�����E�O�[���h�̎�v�y��̓s�A�m�ł��邪�A�ނ��I���K���̖���ł��邱�Ƃ́A���́w�t�[�K�̋Z�@�x������͂�����ƌ��ĂƂ��v
�@���ɓ��e�̖R�������͂ł���B�������A���̎��Ȍ����~�̋����O�[���h���A���g�������Ă��Ȃ��̂ł���B����ł�"�O�[���h�l�C�ɕ֏悵�Ă���y�ɍ���������ړ��Ẵ��R�[�h"�ƌ����Ă����傤���Ȃ����낤�B
�@�ЂƂ܂��ŏ��͂���Ȍ`�Ŕ������ꂽ�O�[���h�́u�t�[�K�̋Z�@�v�����A���ɍŌ�܂œ��ꂵ���`�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������B��9�Ȃ܂łŒ��f�������R�́A��Ɂu�I���K���̗��K��������ɖ{�Ԃɓ��������Ƃɂ�茨�ɏ�Q���N�����Ă��܂������߁v�Ɩ{�l������Ă���B����ȏ㑱������{�Ƃ̃s�A�m�ւ̉e�����o�邩��~�߂��Ƃ����킯�ł���B���̎��g�ݕ��͂������Ȃ��̂��Ǝv���B���ꂾ���Ȗ��Ɍ����A�����ɏ��������u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�̃O�[���h�͂ǂ��ւ����Ă��܂����̂��낤���B����͓V�˂̋C�܂���Ȃ̂��H
�@�O�[���h�͂��̂��ƁA1967�NCBS�̃��W�I������C9�A11�A13�irecta�j���A1981�NCBS�e���r��C1�A2�A4��C14�u�����̃t�[�K�v�����t���^�����c���Ă���B���x�̓s�A�m���g���āB1967�N��3�Ȃ̓��W�I�p�̃��m���������Ȃ̂ŁA�ƂĂ����l�ȃO�[���h�̃s�A�j�Y���𑨂��Ă���Ƃ͌����������A����̓{�[�i�X�g���b�N�Ƃł������ׂ����̂��낤�B���̔���1981�N��4�Ȃ́A�A�e���鎩�݂ȋȑz�́A�O�[���h�{���̐��E����Ă����B �O�[���h���u�t�[�K�̋Z�@�v�Ŏc�����^���́A�ȏ�́A�Ȃ�疬���̂Ȃ����v16�Ȃ����ł���B�Ƃ͂����A81�N��4�Ȃ͎��ɑf���炵���B����C14�u�����̃t�[�K�v�ɕY���Ɠ��̎�͂Ȃ�ƌ`�e�����炢���̂��낤�B��̋�����F�ʂ�r���������m�N���[���̐��E�B�����ɂ͂����A�o�b�n�����āA�O�[���h�����邾�����B����A�o�b�n���O�[���h�����Ȃ��B���C�ȉ�������ł��邾���B��捂��閳���B�Ȃɂ��͉���ʂ������ƂĂ��Ȃ��������B����͂܂�ŁA�F����f�r�����̂悤�ŁA���̕��i�������u�t�[�K�̋Z�@�v�̏h�����f���Ă���A�Ƃł��������肾�B������ɂ��A�Ȃ��O�[���h���A�s�A�m�ŁA�܂Ƃ��ɁA�܂Ƃ߂āA����Ă���Ȃ������̂��A�ۂɌ������Ē��q���ς���̃}�[���[���̂��Ă���ɂ���������A�u�t�[�K�̋Z�@�v�������Ƃ���ė~���������I ������v���Ǝc�O�łȂ�Ȃ��B
�@�u�o�b�n �`���̓��ǂ��v�i���ы`�����A�t�H�Ёj�Ƃ����o�b�n�����̖{������B����́A�u�~�T�ȃ��Z���v��u�t�[�K�̋Z�@�v�̐�����d�g�݂Ɋւ��A���ɖ����ȉ���Ă���f���炵���{�ł���B�B��������ؔr���������ؐ����o�b�n���y�̐^�̎p�������ɉ����������Ă����B���N�̏t�A�����ǂ�Ŋ����������́A���҂̏��ы`���搶�Ɏ莆���������B���̒��ŁA�O�[���h�́u�t�[�K�̋Z�@�v�Ɋ֘A��������Ȏ�������Ă݂��B�u�w�t�[�K�̋Z�@�x�̉��t�𑽐������܂������A�搶���K�肳�ꂽ�`�ɉ����Ă�����̂���������łȂ����̂�����B���Ƀ}�`�}�`�ł��B���ɃO�����E�O�[���h62�N�̃I���K���ɂ��w�t�[�K�̋Z�@�x�́A�t�[�K��9�ȑI��ł���ł��I���Ƃ������̂ŁA�����ɂ͂����Ȃ�Ӑ}��������ꂸ�A�o�b�n�ɑ���`���Ƃ����v�����A�搶�͂ǂ��v���܂����v�ƁB����ɑ��搶�́A�u���t�Ƃ̕��X�́A�K�������ŐV�̊w����ǂ�Ō������Ȃ��牉�t���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���ꂪ���f����Ă��Ȃ��Ƃ����͂�����Ƃ���Ɍ����܂��B�O�����E�O�[���h�����̗�O�ł͂���܂���B���������O�[���h�ɂ͍�i�̃I�[�Z���e�B�V�e�B���d������ԓx�͌����܂���A����C�܂܂Ƃ��������悤������܂���B�悭�����Ό|�p�Ƃ̎��R�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���v�Ǝ��ɏl�X���邨�Ԏ������������B���ꂱ�����^���ȉ��y�w�҂̖ڂ��猩���O�[���h�ςȂ̂��낤�B��͂�O�[���h�́u�t�[�K�̋Z�@�v�͂܂Ƃ��ł͂Ȃ��B���́u�����̃t�[�K�v�̔������Ƃ͗����ɁB
�@�g�c�搶�̃O�[���h�u�t�[�K�̋Z�@�v�̕]�_�͓ǂ��Ƃ͂Ȃ��̂ŁA����Ƃ��搶�̂��ӌ������������Ă݂������̂ł���B
2008.10.06 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�S
[�O�����E�O�[���h�̃o�b�n]�\�\����1�i�P�j�O�[���h��^�̐���
�@�g�c�G�a�搶�́A�킪���ł��������O�����E�O�[���h(1932�|1982)��]�������]�_�ƂƂ����Ă���B�搶�̒����u���E�̃s�A�j�X�g�v�ɂ́A�u1958�N�Ƀ��[���b�p�ŃO�[���h�ŕ���2�x�̃`�����X���������������Ă��܂����B��ώc�O���������A������Ă������{�̃s�A�j�X�g���c���O�Ə��Y�L������"�O�[���h���^����b"�͕������Ƃ��ł����B�Ƃ��낪�A�A��������A���{�̕]�_�E�̑吨�̓O�[���h�ɔے�I�������B�O�[���h�́w�S�[���h�x���N�ϑt�ȁx��w�p���e�B�[�^�x���ė�W�ł�����̂́A���ɂ͂Ƃ��Ă��l�����Ȃ����Ƃ������B"���炭����"�A�R�����r�A����˗�����āA�V�������w�S�[���h�x���N�ϑt�ȁx�̃W���P�b�g�Ɂw�O�[���h�]�x�Ƃ����ꕶ���������߂��v�Ə�����Ă���B"���炭����"���������ׂĂ݂���A1963�N3���̂��Ƃ������B��������u�|�p�V���v�ɂ�������Ă���B���̂����肪�A�ǂ����A�킪���ł̃O�[���h�]���̐��Ƃ������ƂɂȂ����悤���B�������ł���A�f�r���[����V�N�ȏ���o�������̍��ɂ́A�C�O�ł̃O�[���h�]���͂��͂⊮�S�ɒ蒅���Ă��邵���̃A�[�e�B�X�g�������^�̐����������Ă���B�O�[���h��]�����邱�Ƃ��`���ł��Ȃ�ł��Ȃ������Ȃ̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A���̂͂邩�O�A1956�N���R�[�h�|�p10�����́u�߂���������郌�R�[�h�v���ɁA���r�Y�搶���u�O�����E�O�[���h���t�̃S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�Ƒ肷�镶�͂��ڂ��Ă���̂ŁA���̈ꕔ�����Љ��B
�@�u�܂�24�ɂȂ�������̃J�i�_�̃s�A�j�X�g�A�O�����E�O�[���h�́w�S�[���h�x���N�ϑt�ȁx�������V���Ŕ����ɂȂ�B�����ł́A�w�S�[���h�x���N�ϑt�ȁx�͐������y�ǂ��납�A���C���ǂ����ւӂ��Ƃ�ł��܂��悤�ȉ��y�ƂȂ��Ă���B�O�[���h�̉��t���o���o���Ƃ��ă_�C�i�~�b�N���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�����������i���m���ɂ��邪�A����ȏ�ɖ����ŁA���̂����A�V�N�����������Ă��鉉�t�Ȃ̂��B����̓o�b�n�̉��߂Ƃ��Ă͂܂��ƂɈِF�ł���B�������Ƃ����Ĕނ͌����Ď��R�z���Ƀo�b�n��e���������Ă���Ƃ����̂ł��Ȃ��B�����ƒm���̃o�����X�̂Ƃꂽ���t�ɂȂ��Ă���̂��B�E�E�E�����E�E�E�Ƃ�����A�O�����E�O�[���h�͋ߍ��ł̌����ł���A�w�S�[���h�x���N�ϑt�ȁx�́A���̂��ǂ낭�ׂ��s�A�j�X�g�̃f�r���[�����閼�Ղł��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��v
�@���̎����́A�u�O�[���h�̃S�[���h�x���N�ϑt�ȁv���{�������̂P�����O�ł���B���搶�͂�����O���[�J�[����鎎���Ղ��ď����ꂽ�Ƃ����B�{�Ղɂ̓O�[���h�{�l���������ڍׂȉ��t�m�[�g���f�ڂ��ꂽ���A�����Ղɂ͕t���Ă��Ȃ������������B����Ȑ^���T���ȏ��ŁA�u�o�b�n�̉��߂Ƃ��Ăِ͈F�����A�m��̃o�����X�̎�ꂽ�V�N�Ŋy�������t�ŁA���ꂪ���Ղł��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��v�ƓI�m�ɔ��f����^�̕]����������Ă���̂ł���B���ꂱ���܂��ɂ킪��"�O�[���h�]"�̐��ł͂Ȃ����B
�@���搶�ɂ́A������20�N�قǑO�A���̖�LD�u�_�j�[�E�P�C�ƃj���[���[�N�E�t�B���̗[�ׁv�̓��{�������[�X�̂Ƃ��A����������Ă����������o��������B���₩�Ȑl���̑f���炵�����������B���ƂȂ��Ă͉��������z���o�ł���i�����ł����j�B
�i�Q�j�S�[���h�x���N�ϑt�Ȃ͂Ȃ������̂�
�@�O�����E�O�[���h���AJ�DS�D�o�b�n�ӔN�̍�i�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv��^�������̂�1955�N�㊥22�̂Ƃ��ł���B���̋Ȃ��f�r���[��ɑI�̂̓O�[���h���g�����A�������CBS�̏�w���́u����Ȃ������߂Ă����B�w�S�[���h�x���N�x�Ȃ�Ă��̂̓����h�t�X�J������Ώ\�����B�������s�A�m�łȂ�Ă��肦�Ȃ��v�ƌ������������B�����u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�́A1933�N�ɖ����������_�E�����h�t�X�J���`�F���o���Ř^���������̂���ނȂ�����ՂƂ���A�s�A�m�ʼn��t���ꂽ���̂͂Ȃ��ɓ����������B
�@����ȋt���̒��A���̍�i�Ńf�r���[���ʂ������̂́A�O�[���h�́A�O�ꂵ���y�Ȍ����ɗ��Â����ꂽ���Ȃ̕\���ւ̗h���Ȃ����M�ƁA�m�ł���M�O�������ɈႢ�Ȃ��B�o�b�n�����̋Ȃ�������Ƃ��̓`�F���o�������Ȃ������̂�����A�`�F���o���ʼn��t����̂��������Ƃ���̂͊m���ɂ܂��Ƃ��ȍl�������낤���A�o�b�n�̉��y�͉F���̂悤�ɑ傫���āA���Ƃ��ƃ`�F���o���̕\���͂ɓ��肫��悤�ȉ��y�ł͂Ȃ��̂��B
�@�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�́A�Q�̃A���A�Ƃ���ɋ��܂��30�̕ϑt�Ȃ��琬�藧���Ă���B����������30�Ȃ́A3�ȂÂ�10�̃u���b�N�ɕ������K������������ł���B���̂����|�l������Ă���R�̔{������"1,2, �R, 4,5, �U�E�E�E"�ł���i������ƁA�o�b�n�Ɏ��炩�j�B �c���e�X�̕��т̐��w�I�K�����͉F�������A�z������s��ȃt�H�������`������B
�@�`�F���o���͉��̋���������Ȃ����A�s�A�m�͂ł���B��������芊�炩�ɒe�����肷��̂��s�A�m�̂ق����D��Ă���B�y�_���Ƃ������������B�v����ɕ\���͂��`�F���o���Ɋr�ׂČ��Ⴂ�ɑ傫���̂��B������o�b�n�̉��y�̓s�A�m�ʼn��t���ׂ����y�Ȃ̂��B�o�b�n���g���z�肷�ׂ����Ȃ���������ǁA�ނ̉��y�́A���܂���`�F���o���̋@�\���z���āA�����̊y��̉��҂���s�A�m���u�����Ă����̂ł���B����͍�������ȒP�Ɍ����邱�Ƃ��������Ƃ��Ă͎v�������ʘb�ŁA���ꂱ���R�����u�X�̗��������̂��B����Ȕ����I���́A20���������̃O�[���h�͂��̂��ƂɋC�Â��A���̂��߂ɋZ�p���A����̍l���鉹�y�����������̂ł���B�t�Ɍ����A�[���s��ȃo�b�n�̉��y�����̐^�̎p���������߂ɂ́A�O�����E�O�[���h�Ƃ����s�A�j�X�g�̏o����҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B����͕��̐l�Ԃɏo���邱�Ƃł͂Ȃ��B������ނ͐��҂ł���V�˂Ȃ̂ł���B
�@�f�r���[��͔����I�Ȕ����������N�����A�O�[���h�͈��X�^�[�_���ɂ̂��オ�����B�Ȃ����ꂪ��q�b�g�����̂��H�o�b�n���s�A�m�ł�������Ƃ̎a�V�������̒��ɋ���ȃC���p�N�g��^�������炩�B����͂���ŊԈႢ�Ȃ����Ƃ��B�������ꂾ���ł̓Q�e���m�ŏI����Ă��܂��B�O�[���h�́u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�́A����ɉ����A����Ă炤�Ɏ~�܂�Ȃ����y�Ƃ��Ă̊����x�������Ă�������ł���B���ꂪ���������y�Ƃ��đ��Â��Ă�������Ȃ̂��B
�@�O�[���h�́A���̌�o�b�n�̍�i�𒆐S�Ƀ��[�c�@���g�A�x�[�g�[���F���A�u���[���X�A�V�F�[���x���N�Ȃǐ��X�̃��R�[�f�B���O���s���A�S���Ȃ���20���N�����������݂ł������͂Ȃ��x�X�g�������O�Z���[�𑱂��Ă���B�Ō�̍�i�ƂȂ����̂�1981�N�́u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�̍Ę^���������B�����55�N�Ղ��͂邩�ɗ��킷�錩���ȉ��t�ŁA�\��Â��͂��[���A�ϑt���Ƃ̐��i�t���͂�薾�m�ƂȂ�A�M�O�ɗ��ł����ꂽ���R�Ȑ��_�����������Ɵ����Ă���B�܂��Ƀt�@���^�X�e�B�b�N�ȉ��t�ł���B���m��������X�e���I�ɕς�������̗lj����傫���B�o�b�n�̍�i�ɂ���Ȃ鐶���𐁂����Ƃ�����B�ނ͂��̘^����1�N��A�A��ʐl�ƂȂ����B
�@���͂���81�N�Łu�S�[���h�x���N�v����D���ł悭�����B55�N�łɊr�ɒ[�ɒx���e���|�Ŏn�܂�A���A�ɂ͘����Ȉ������Y���B��1�ϑt�����12�ϑt�܂ł́A���K�[�g�����������`�F���o���I������D�悵�A�قڃC���e���|�Łi�e���|��������܂܁j���y�͐i�ށB�o�b�n�̕`���|���t�H�j�b�N�ȉ��`���w�I�Ȑ��ƂȂ��Ă�������Ɠ��ɏĂ����B��13�C14�ϑt�����肩�獶��̃��C���̋�����K�[�g�̗v�f���������Ă���B�`�F���o���ɂ͂ł��Ȃ��s�A�m�Ȃ�ł͂̕\���ł���B�㔼�ւ̕z�Ƃ����邩������Ȃ��B�Â��ȌΖʂ�Y���悤�ȑ�15�ϑt�őO�����I���B��16�ϑt����̌㔼�́A��]���āA�e���|�͓����A�_�C�i�~�N�X�͋�������A���K�[�g�����p�����B�C���e���|�ƃm���E���K�[�g�̊�ɂ���炪�����\���̕����啝�ɍL����B�s�A�m�ɂ�鑽�ʂȕ\���́A���C�ƐÎ�A���x�Ɗ����A�D���Əs���A�s��Ɗȑf�ȂǁA�Η�����l�Ԃ̗l�X�Ȋ����\�o����B�Ȃ��Ƃ̑Δ�ƑO�㔼�ł̑Δ�͓�d�̑ΏƂ��`�����ăo�b�n�̐��_�����ʂ��A�[���Ń��}���e�B�b�N�ȃO�[���h�̐��E���剾���ƂȂ��Č��o����B���ꂼ���ɐl�ނɈ₳�ꂽ�ł���B
2008.09.29 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�R
[�����Ă����Ȃ����t�ւ̕]�_]�@���R�[�h�|�p2007�N2�����́u�V���y���ގ҂ɔ@�����v�ŁA�g�c�搶�͎��Ɋ�ȉ��t�]��W�J����Ă���B�ʂ̕]�_�Ƃ̉��t�]��ǂ�ł̕��͂Ȃ̂����A�搶�͌��ɂȂ������t�������Ă��̉��t�̊j�S�ɋy�т������甭�W���Č����Ȃ܂ł̎��_��W�J�����̂ł���B���͂��������ނ̉��y�]�_�ɏo��������Ƃ��Ȃ������̂ŐS��т����肵�Ă��܂����B�ł͂��̕��͂�ǂ��Ȃ���l�@����B
�i�P�j�v���g�j���t�́u���v�̓V���X�^�R�[���B�`�H
�@�u���̊ԁA�������v���g�j���t�������Ǝv���i�łȂ��Ă��ǂ��ł������̂����j���A�����̂ǂ����̃I�[�P�X�g�����w�����ăx�[�g�[���F���́w�������ȁx��������B���̉��t�]��ЎR�m�G�������āw�����V���x�ɍڂ��Ă����B�ǂ�ȉ��t�����ǂݎ�ɂ悭�`����Ă���A�͂����肵���A�ǂ�ł��ċC�����̗ǂ��A�܂�w�Ȃ�قǁx�Ǝv����L���������B�ЎR����̂͂������Ă����ŁA���͂قƂ�ǂ������S���ēǂ�ł���B�ŁA���̔�]�Ō����ƁA�v���g�j���t�́w���x�͏o�������狭��̑ΏƂ��ɂ߂ċ�������Ă��āA���̕\��t���ł��A�x�[�g�[���F���Ƃ������ނ���V���X�^�R�[���B�`�ɂӂ��킵�����̂������炵���̂ł���B�����Ɍ���������A�v����Ƀx�[�g�[���F�������V���X�^�R�[���B�`�����ꂽ�悤�Ȃ��̂��Ƃ����킯�ł���B�ЎR����́A������A�ǂ����܂ł͏����ĂȂ������悤�Ɋo���Ă��邪�A�����ǂ߂A���������㕨����������āA�ނ������ē������ɂӂ��Ă���Ƃ����l�q�����������ɕ����Ԃ悤�ɏ�����Ă����]�������B�ŁA�w�Ȃ�قǁx�Ǝ��͎v���A�ǂ���]���A�������āA�����������낤�ȂƐ����������̂������B�ȑO�������炱��ł��I���������낤�v
�@�F����͂�������ǂ݂ɂȂ��Ăǂ��v���܂����H "�łȂ��Ă��ǂ��ł�����"�Ƃ�"�����̂ǂ����̃I�[�P�X�g��"�Ƃ������t�g�����l�����̂����A����͂��Ă����Ƃ��āE�E�E�B���l�̔�]��]�_����̂͂��肤�邱�Ƃ�����A���̂��Ǝ��̂ɕ������������͂Ȃ��B�ł����̏ꍇ�A���܂��Ȃ�������Ȃ����Ƃ́A��]�̑Ώہi���̏ꍇ�Ȃ�v���g�j���t�w���́u���v�̉��t�j���������̌����Ă��邱�ƁA���́A�����łȂ�������A�]�_�����̑Ώۂ��̂��̂ɋy�Ȃ����ƁA�Ⴆ�A���̐l�̕��͂̂��܂��ȂǂɌ����Ă̂��́A�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA���͎v���B
�@�搶�͂��̑ΏۂƂȂ������t�͕����Ă����Ȃ��B����͕��͂̒[�X�Łi�Ⴆ��"�x�[�g�[���F�����ނ���V���X�^�R�[���B�`�ɂӂ��킵�����̂������炵��"��"�炵��"�Ƃ����\���ȂǂŁj��R���B�����Ă����Ȃ��̂ɁA�ǂ����āu�Ȃ�قǁv�Ȃǂƌ�����̂��낤���B������"�����Ɍ���������"������B���ɂ����J�Șb�ł���B����������"��������"����₠�܂���I�O��B"�\��V���X�^�R�[���B�`��"��"�܂�ŃV���X�^�R�[���B�`�����ꂽ�悤�Ȃ���"�Ƃ͈Ӗ����S�R�Ⴄ�i�����A�����ЎR���̕]�_�͓ǂ�łȂ��̂�����{���͔�r�Ȃǂł��Ȃ��̂����j�B����ɂ͕ЎR�����т����肾�������Ƃ��낤�B���āA�����ł���Ɂu�������āA�������������낤�v�ł���I�@�ق�Ƃ��̕����C�Ȃ̂��낤���H�@�ΏۂƂȂ��Ă��鉉�t���Ă����Ȃ��ŁA�ǂ������"����������"�̂��낤���B
�@�搶�͂����܂ł��A�u�ȑO�������炱��ł��I���������낤�v�ƁA���������P�[�X�͐搶�ɂƂ��Ă͈ȑO���璿�����Ȃ����Ƃł���ƔF�߂Ă���������B�����܂łł��r�b�N���V�Ȃ̂ɁA�搶�̕]�_�͂��̂��Ƃ���ɋ����ׂ��[�݂ւƓ��荞��ł䂭�B
�i�Q�j�V���͂Ȃ��N���V�b�N�ɂ����Ǝ��ʂ������Ȃ��̂��H
�@�u�Ƃ��낪�A���́A���̂��ƂŁA�v���g�j���t�͂Ȃ�����Ȃ��Ƃ������̂��낤�H�ƍl�����B�ނ́A�x�[�g�[���F���̖є�����ăV���X�^�R�[���B�`���������ɏo���Ă݂����������A���邢�͌���̐l�ԂƂ��Ď����̖�ڂ̓x�[�g�[���F���̓V���X�^�R�[���B�`�Ƃ����킹���`�Œ���ɂ���ƍl�����̂��B�ނ̏ꍇ�͐M�O�Ƃł������ׂ����̂������Ă̂��Ƃƍl����ق������R�ł���B����������ȐM�O�i���R�j���������Ƃ��āA�\�A�����ċv�������A�������邱�Ƃɂǂ�Ȉ�ʐ�������Ƃ����̂��H�@�ǂ�ȋq�ϓI�Ó���������Ƃ����̂��H�@�����������Ƃ��l���_����̂��A���͕]�_�Ȃ̂��v�B�܂����╷���Ă����Ȃ����t�ɑ��āu�Ȃ�����Ȃ��Ƃ������̂��낤���ƍl�����v�̂ł���B���͂₱�̕]�_�g�c�ۂ͖����̊ς�悵�Ă����B����Ɍ���Ƃ�������w�i�̒��ŁA�i�����Ă����Ȃ��j���̉��t�̈Ӗ�������_����̂��^�̈Ӗ��ł̕]�_�Ȃ̂��ƒf���Ă���������B�����Đ搶�́A�Ō�ɁA���ɋ����ׂ����_�ł��̘_����߂�������̂��B
�@�u�ЎR���Ȃ炻�ꂪ�ł����ł��낤�ƁA���͗\�������҂���B�Ƃ��낪�A�����Ȃ�Ȃ������B�Ȃ��H ���{�̐V���ɂ͂��������X�y�[�X���Ȃ����炾�B�Ȃ�Ƃ܂�Ȃ����Ƃ��낤�I�@�����A�Ȃ����{�̐V���͉��y��]�ɃX�y�[�X������܂肳���Ȃ��̂��H�v
�@�Ȃ�Ƌ����ׂ����ɁA"�ЎR���̘_�]�����r���[�ŏI������̂́A�V�����N���V�b�N�Ƃ����i�����ŕ����I�ȁj�W�������ɁA����ɑ��������X�y�[�X��^���Ă���Ă��Ȃ����炾"�ƌ��_����̂ł���B
�@�ЎR�����A����ȏ�_��������A�܂Ƃ߂Ăǂ����̉��y���ɏ��������̂ł���B�g�c�G�a�܂���܂����قǂ̕��Ȃ̂����特�y���ɍڂ��Ă��炤���ƂȂǂ��₷�����낤���A�ǂ����Ă��V������ŏ���������A����������f�ڂ��Ă��炤���Ƃ��s�\�ł͂Ȃ����낤�B�搶�͕ЎR���ɂȂ肩����ĐV���ɍR�c���Ă���Ă���B�ЎR����"���̂��߂ɂȂ�Ƃ����������ł��肪��������"�Ƌ��k���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B������ɐV���͌����̃X�y�[�X�ł���B����́A�����A�o�ρA�X�|�[�c�A�|�\�ȂǁA�����ɖ����������̂���G���^�e�C�������g�ɂ�����܂ŕ��L������ɂ���ԁB���y�͂��̈ꕔ���ɉ߂��Ȃ����A�������N���V�b�N�Ȃ�Ă������͉̂��y�S�̂�5���ɂ������Ȃ��̂ł���B����ȃ}�C�i�[�Ȃ��̂ɐV���͍��ȏ�̃X�y�[�X�������킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B���̂܂܂ł��A"�����ŕ����I��"���삾���炵�āA�V���̃X�e�C�^�X�Ƃ��Đ���t�����Ă���Ă���ق����Ǝ��Ȃ͎v���B�u�Ȃ����{�̐V���͂����Ɗ����Ȃ��̂��H�v�Ƃ���������Ă��A���܂̃X�y�[�X�̂܂܂ŏ\���ȏ�Ȃ̂ł���A�搶�A�Ǝ��͐\���グ�����B������u�����Ɓv�ƌ����̂̓N���V�b�N����遂�ł���A��C��ǂ߂Ȃ�"��̒��̊^"�ƌ����Ă����������Ȃ����낤�B��Ȃɂ��̂����ɁA�����킫�܂��Ȃ�����Ƃ����肪���ł��邾�낤�B���������N���V�b�N�E�T�[�N���̓ƑP�I���r���I�̎������̍��̃N���V�b�N���y����I�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B遂�Ȃ���N���V�b�N�ł���B
�@�ǂ����N���V�b�N�̐��ƂƂ����Ă���l�B�ɂ́A�̂����ɂ��Ă���l�������i�ܘ_���ɂ͌����Ȏ��͎҂����邯��ǁj�B���̑ԓx�A���ɕ@�����Ȃ�Ȃ��B"�������N���V�b�N�A�Ȃ�ڂ̂��Ⴂ"�ƌ����Ă��ꂽ�ق����]���e���݂��킭�̂ɂƎv���B�Ȃɂ����͔ډ���������ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�ւ�����̂͑���B�ł��A�ւ��遂�͈Ⴄ�B�ւ�͎����������Ȃ��B��������ɂ����ꂪ�厖�Ȃ̂ł���B����Ȓ��A���̃A�[�e�B�X�g�̒��Ɂu���������y����Ȃ��ł����B�������ɂǂꂾ���̂��Ƃ��o����̂ł��傤�v�Ƃ��u���@�C�I���j�X�g�ɂƂǂ܂�Ȃ�Ă܂�Ȃ��v�ȂǂƔ�������ꗬ�̐l�������o�Ă��Ă���B�_���^�R�q��ܓ�����ł���B����͎��Ɋ�����X�����B ������A�N���V�b�N�E�̑�䏊����g�c�搶�ɂ͐��̂��������������ƔF�����Ă��������A"���y�̊y�����l��"�Ƃ����搶�̃��b�g�[�ɑ����ċƊE�����[�h���Ă����Ă������������̂ł���B"�f�l�ɂ͕�����₷���A���Ƃ�����������"�M�v�������āB
�i�R�j�v���g�j���t�u���v��CD
�@�������p�����̂͐搶�̕��͂̈ꕔ���ł���B���̉�̐搶�̃e�[�}��"�����g�E�_�E��"�Ƃ̂��ƂŁA�ȑO�͎����̒��ł͂�����Ƌ�ʂ���Ă������̂��A���͂��̋��E���n�������悤�ɞB���ɂȂ��Ă��Ă���A�Ȃ�������Ȏ��Ⴊ�����Ȃ��Ă���A�Ƃ������̂������B���̈�̋�̗�Ƃ���"�v���g�j���t�́u���v�̉��t"���������Ă�����킯�ł���B�����玄�����グ���̂͊j�S�����ł͂Ȃ����炵�āA��������Ȃɗ͂܂Ȃ��Ă��H�Ȃ�Č����邩������Ȃ��B�ł�����́A�j�S�������낤�����ӕ������낤���A�u���������ĕ]�_�v�Ƃ����A�����Ă͂Ȃ�Ȃ��s�ׂɂ��A�������Ă����������܂ł��B
�@���̕��͂������ɂ������āA���͕ЎR���́u�����V���v�̕]��ǂނׂ����Ǝv���A�o�������̎��s���������A����Ȃ������B��앶�����4�K�́u���y�������v��2006�N�|2007�N�ɂ����Ă̑S�Ă̐V���蔲���L���ׂ������t����Ȃ������B�܂����@������̂�������Ȃ����A�ǂƂ���Ŏ��̎�|���_�����ς��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�ЂƂ܂��u���Ă������Ƃɂ��Ă���B
�@����ȏ�Ƀv���g�j���t�́u���v���t��͕����Ă݂��������Ǝv�����B�u�ЎR����"�V���X�^�R�[���B�`�̕\��"�ƌ������v�Ƌg�c�搶����������������̉��t���B �߂��������R���T�[�g�̓I���G�A���Ȃ���Α̌����邱�Ƃ͏o���Ȃ����A���ׂĂ݂���K���Ȃ��Ƃ�CD����������Ă����B�~�n�C���E�v���g�j���t�w���F���V�A�E�i�V���i���nj��y�c�́u�x�[�g�[���F�������ȑS�W�v�ŁA�^����2006�N6�|7���A���X�N���Ƃ���B�ЎR���������ꂽ���{�ł̃R���T�[�g�́A�g�c�搶�̋L���̃^�C�~���O���炢���āA���炭2006�N�̔N��������Ɛ��@�ł���B�Ƃ������Ƃ́A���{�̉��t��̔��N�O�̃��R�[�f�B���O�ł���B���������Ă��̉��t�l���͊�{�I�ɂ͓����Ɍ��܂��Ă���B�Ȃ����CD�̉��t�͌��̉��t��Ƒ卷�Ȃ��͂����B���͂�������CD����ɓ���E��ŕ����Ă݂��B�搶�́u�o�������狭��̑ΏƂ��ɂ߂ċ�������Ă��āv�Ɓi�ЎR����������Ă���Ɓj������Ă���̂ŁA�莝���́u���v32�����������o���ăv���g�j���t�̂ƕ�����ׂĂ݂��B�v���g�j���t�́u���v�́A�����߂̃e���|�i��32��̂ǂ���������t���g���F���O���[�u�o�C���C�g�v�Ƃ͑S�̂�13�����̍����������j�ƃs���I�h�y�핗�ȃA�N�Z���g�̕t�����ƃ|���t�H�j�b�N�ȋ��������ɓ���������A�m���ɂ���܂ł̓`���I�X�^�C���Ƃ͈�����悵�����t�ɂ͈Ⴂ�Ȃ������B���̂������ЎR���́A"�V���X�^�R�[���B�`�̕\��t��"�ƕ]���ꂽ�̂�������Ȃ��Ǝv�����B�ł��A���Ȃ��Ƃ����ɂ́A�g�c�搶�������C�g���ꂽ�悤��"�V���X�^�R�[���B�`�����ꂽ�悤�Ȃ���"�Ƃ܂ł͊������Ȃ������B
�@���������܂ł�����̂�����A�搶�ɂ͐���Ƃ��v���g�j���t��CD���Ă��������āA�{����"�V���X�^�R�[���B�`�����ꂽ�悤�Ȃ���"�Ɗ������邩�ǂ������܂߁A���z�����������肦��K���ł���B������u����̓x�[�g�[���F���I�ł͂Ȃ����D���ł���v�ȂǂƂ���������Ȃ��ł��傤�ˁB
2008.09.22 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�Q
�@����͋g�c�G�a���u���R�[�h�̃��[�c�@���g�v�i�����V���j����A�搶�̃��[�c�@���g���t�_�ɔ����Ă݂����B�Ⴊ�h������F����F�A�Έ�G���搶�ƑΔ䂵�āB�i�P�j�J�������ƃZ���̃��[�c�@���g
�@�g�c�G�a�搶�ɂ��ƃJ�������̃��[�c�@���g�͂����������ƂɂȂ�B
�@�u�J�������̍l���Ă��邱�Ƃ͉̂̍ŗD��ł���B���K�[�g���d�����Ă��邱�Ƃ��^�����Ȃ����m���œ`����Ă���B������ɂ߂������̐��̎����̂������y��Nj����ׂ��ō��̉��l�����p�ł���ƁA���炩�ɍ������Ă���悤���v�ƁA�ނ̉��t����V���t�H�j�[�̉��t�Ɋւ��āA���ς�炸�̋g�c�߂Ō���Ă���B�����āA�u���͂��̃��[�c�@���g���D�����B���������ꂪ���[�c�@���g�̂��ׂĂłȂ����Ƃ́A���ꂪ�ЂƂ̂����ꂽ���[�c�@���g�����Ƃ����̂Ɠ������炢�͂�����Ƃ��Ă���B�ނ���~���̃��B�[�i�X���̖L��Ȕ����̃^�C�v�͕K���������[�c�@���g�̖��������Ƃ͏����������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������v�ƌ���Ă���B
�@���Ȃ݂Ɏ��͂����������[�c�@���g�������ł���B����͍D�������̖�肾����c�_�ɂȂ�Ȃ��B
�@����W���[�W�E�Z���́u��40�ԃg�Z���V���t�H�j�[�v��u�|�X�g�z�����E�Z���i�[�h�v���Ɋւ��ẮA�����{�̒��ł����q�ׂ��Ă���B
�@�u�w�|�X�g�z�����E�Z���i�[�h�x�̓��[�c�@���g�ł͏����ދ��ȋȂ����ɁA�����Ȗ��ɐ��m�ɗ��V�ɂ������������낭���悤�Ɗ���H���قƂ�ǎ{�����ɉ��t���Ă���Ƃ������Ƃ��A�������Ă������낭�v���Ă���B�Ȃ��Ȃ����ɉ����������l�̉��y������Ă���悤�ȋC�����Ă���B����܂胂�[�c�@���g�炵���Ȃ����t�ł���A�\�\�Ƃ������\�\���������[�c�@���g�炵����낤�Ƃ��ĂȂ����t���B�w�g�Z���̃V���t�H�j�[�x�̉��t���Ă������ł���B���[�c�@���g�炵�������[�c�@���g�炵���Ȃ����B��������A�����A�ڂ̑O�̋ؓ����́A�f���炵�����C�ɖ��������y������A�������A�����ɂ͂ق��ɗނ̂Ȃ������̐V�N���ƋC�i��������Ă���Ƃ�����A��������Ȃ��͂�낱��ł����Ȃ����낤���H�v
�@�v�͂�����搶�͗_�߂Ă���������B�Ƃ���Ő搶�����������"���[�c�@���g�炵��"�Ƃ͂ǂ��������t�Ȃ̂��낤���H ���ɂ͌����Ă��Ȃ��B �֑��Ȃ��玄���g���̃W���[�W�E�Z���́u40�ԃV���t�H�j�[�v�́A�ł����[�c�@���g�炵���Ƃ������A���̋Ȃɑ�������������ł������t���Ǝv���Ă��܂��B
�@ �@�U�b�N���ƌ����A�搶��"�J���������Z�������[�c�@���g�炵���͂Ȃ����A�����Ƃ��D����"�Ƃ���������Ă���B�Ђ�L���Ȕ����^�C�v�A�Ђ�ؓ����Ŋ��������Ƃ������y�B�����Ƃ����[�c�@���g�I�ł͂Ȃ��B�ł������Ƃ��ɍD�����B�E�[���A��͂�s���E�s���āB�����Ă�����x�u�������Ȃ�A�u�搶�����[�c�@���g�I�Ƃ����̂͂ǂ��������t�̂��ƂȂ̂ł����H�v�ƁB
�@�u��40�ԃg�Z���V���t�H�j�[�v�ɂ��āA�F����F�搶�̓u���[�m�E�����^�[�w���F�E�B�[���E�t�B���i52�N�^���j�Ղ���ɐ��E����Ă����邪�A�u���߂ă����^�[�F�j���[���[�N�E�t�B���Ղɐڂ����Ƃ��́A�����̂��ǂ��ɂ��Ȃ��Ă��܂��قǂ̍K�����ɕ�܂ꂽ�B�Ƃ��낪�����ƌ�ɂȂ��āA�����^�[�F�E�B�[���E�t�B���Ղɐڂ����Ƃ��͂���ȏゾ�����B���̂k�o�͖l�̗��l�ɂȂ�A���t�]�̓��u���^�[�ƂȂ����v�i���y�̗F�Њ��u�N���V�b�N�l����100���v�j�Ə�����Ă���B����͎��ɔM���ۂ��ĕ�����₷���B�搶�̔M���v������Ɏ��悤�ɓ`����Ă���B����قǂ܂łɐ搶�𖣗��������R�[�h���Ă݂����Ƃ����C�ɂȂ�B
�@ �@�g�c�搶�͑O�o2006�N12��25���̓ǔ��V���̒��ŁA�u�Ⴆ��w���̓X�̃g���J�c�͂��������x�ƁA�����̊���ɂ��������āA�����������̂����������Ə����̂��{���̔�]�ł���v�Ƃ̎��_���q�ׂ��Ă�����B�Ƃ��낪�ǂ����낤�A�J�������ƃZ���̃��[�c�@���g�Ɋւ��āA�搶�̔�g�ɂ��������ă����C�g����ƁA�u���̓X�̃g���J�c�Ƃ��̓X�̃g���J�c�͖��͑S�R���������������������v�Ƃ������ƂɂȂ�B���������Ƃ��������̂͂����̂����A�ǂ����̓X�̃g���J�c��H�ׂĂ����̂�������Ȃ��B�J�������ƃZ���͖����S�R�Ⴄ�̂Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��u�����͂������̂ق��������������Ǝv���v���炢�̂��Ƃ͌����Ăق��������Ǝv���B�ł��܂��A���ꂱ�����搶�̐^�����ŁA����ΑS���ʓI������`�Ƃ������̂Ȃ̂�������Ȃ�����ǁB������͂�A���Ƃ��Ă͂��̃^�C�v�͂�����ƍ���B"�����������������Ȃ��Ȃ�"�ł́A���R�[�h���C�ɂȂ�Ȃ��̂��B�ł���ǂ��炪�D�������炢�̎��͌����Ăق����Ǝv���B
�@ �i�Q�j�n�X�L�����O�����~�I�[�̃\�i�^
�@����ɓ����{�̒��ŁA���@�C�I�����E�\�i�^�̍�������B���̃O�����~�I�[�i���@�C�I�����j���n�X�L���i�s�A�m�j�ՂɊւ��镔����v�Ă݂悤�B �u���[�c�@���g�̃��@�C�I�����E�\�i�^�̃��R�[�h�ł́A�������͈ȑO�O�����~�I�[�ƃn�X�L���̑g�ݍ��킹�ɂ����̂������Ă����B����͒P�ɖ����Ƃ��������łȂ��A�{���ɋC�����̂悢�����ƌĂԂق��Ȃ��悤�ȁA�f���炵�����R�[�h�ł������B���̒��ŁA�������A��������̌��_�\�\�Ƃ������A�L�Y�A�Ƃ������A�Ƃ���ǂ���Ńn�X�L���̃s�A�m���傫�����肷���Ă��āA���@�C�I������K�v�ȏ�ɑނ��Ă��܂��C���̂��邱�Ƃ������v
�@���̃��R�[�h�ɂ��Ă͂킪�h������Έ�G�搶�̉��t�]��R�Ƃ��Ă����Ă݂����B �u���[���@���g�̃��@�C�I�����E�\�i�^�́A�ގ��g"���@�C�I�������t�t�̃s�A�m�E�\�i�^"�ƌĂ�ł���Ƃ���A�����̃\�i�^�̓s�A�j�X�g�̒����ŏ����ꂽ���̂ł���A�s�A�m�哱�̍�i�Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪���R�[�h��Ђ̓��@�C�I�����E�\�i�^�ƕ\�L���A���@�C�I�����ɏd�����������^��������B�n�C�t�F�b�c���X�~�X�̉��t�͂��̓T�^�ŁA�����̔��t���`��e�����@�C�I�����̉��ʂ��A�s�A�m���t�ł����������������������Ă��܂��Ă���B���m�����쌀�Ƃ����ׂ����B�������A���R�ɂ��܂������Ă��܂����Ƃ����ꖇ������B����͔ӔN�̃N�����E�n�X�L��(63��)���Ⴋ�O�����~�I�[(37��)�Ƙ^���������̂ł���B�^���������O�����~�I�[�������o�������A�n�X�L���������Ă��鐢�E�̂ق����f���炵���A���@�C�I�����̉��̖��͂������Ă���̂ł���v�B
�@����͑ΏƓI�ȕ]�_�ł���B���҂Ƃ��f���炵�����t�Ƃ��Ȃ�����A�g�c�搶�́A�n�X�L���̃s�A�m�̉����傫�����肷���Ă���̂����_�Ƃ��������A�Έ�搶�́A�n�X�L���̑f���炵�������[�c�@���g�̉��t�l���Ƀs�^�����v���Ă���ƌ����Ă���B�����I��"���̑傫��"�Ɋւ��ẮA�g�c�搶�̓n�X�L�����傫���Ƃ��������̂ɑ��A�Έ�搶��"�^�����O�����~�I�[�̉��������o������"�Ɛ^�������̊������Ȃ̂��ʔ����B�������A�n�X�L���̉��y�����A�����傫�߂ȃO�����~�I�[�̉����ē`����Ă���Ƃ������������a���B
�@���͈��|�I�卷�ŐΈ�搶���x������B���[�c�@���g�������̃\�i�^���������ړI���牉�t�l���̂��肤�ׂ��p������A���R�[�h��Ђ̗��j�F���̖��n������n�C�t�F�b�c�̃��R�[�f�B���O�ɂ܂Řb���y�сA�n�X�L�����O�����~�I�[�E�R���r�̖��Ղ͑g�ݍ��킹�̋��R�ɂ��Y���ł���ƌ��_�����B���ؓI�ŋ�̓I�ȁA���Ɍ����ȃX�g�[���[�ł���B���������ɂ́A���̉��t�͐Έ�搶�̂��������悤�ɕ�������B�n�X�L���̃s�A�m�̉����傫������悤�ɂ͕������Ȃ����A�n�X�L�������y�I�ɂ����_�I�ɂ���т��ăO�����~�I�[�����[�h���Ă���͖̂��炩�ɕ�����B
�@�ǔ��V���C���^�r���[�L���ŋg�c�搶�́u�킴�Ɛl�ƈႤ���Ƃ������Ă���킯����Ȃ��B���y���l�Ƃ͈���Ē�������v�Ƃ���������Ă��邪�A�܂��ɋg�c�搶�ƐΈ�搶�Ƃ͓������t������ĕ������Ă���̂ł��낤�B
�@���������y�t�@���͖����o�Ă���V��CD��S�ĕ����킯�ɂ͂����Ȃ��B���Ȃ��������Ŏ����ɍ��������R�[�h�������悭�W�߂����Ǝv���Ă���B������M�p�ł���]�_�Ƃ�T���B�������N�������čs���������̂��A�F��A�Έ䗼�搶�ł���B
�@�F��搶�͎���̊�������M���Ēf�������B���l�̕]���͈ӂɉ�Ȃ��B�����́u����͂����v�Ƃ������ϗ͂�����M���Ă���B������M�p�ł���A���ɍ�������Ȃ��͕ʂɂ��āB���̗͂͗슴�I�ł��炠���X�Ɏv�������Ȃ����t�𐄑E���Ă����B���ꂪ�f���炵���B�搶�̐��E�Ŏ�ɓ��ꋤ���������̂����_�������Ă����B
�@�t���g���F���O���[�w���x�������E�t�B���̃V���[�x���g�F�����ȑ�8�ԁu�O���[�g�v�i42�N�^���j�A�t���b�`���C�w���x�������������̃`���C�R�t�X�L�[�F�����ȑ�6�ԁu�ߜƁv�A�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���x�������E�t�B���̃u���[���X�F�����ȑ�3�ԁi50�N�^���j�A�����[�E�N���E�X�̃��[�c�@���g�E�s�A�m���y�S�W�iEMI�Ձj�A���c���q�̃��[�c�@���g�F�s�A�m���t�ȑ�15��K450�ȂǂȂǁB�����͐��ɒ��W���̖����t�Ƃ����ׂ����̂����A�����ɂ͂��܂葼�̕]�_�Ƃ̐搶�����������Ă��Ȃ����t���܂܂��B���Ύ��Ȃ̒���������M����F��搶�Ȃ�ł͂̐��E�ł���B�搶�̑�D���ȕ\���ł��鐳��"�����|����"���E�Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�A�F��搶�ɗւ������Đ����̂��Έ�G�搶���B�搶�̐��E�Ղɂ��Ă͂܂�������B�@
2008.09.15 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�P
�i�P�j�Ђт̓����������i�@���A���̕����ɂ̓z�����B�b�c���e���V���p���́u���K�� ��i10�|8 �֒����v������Ă���B�z�����B�b�c������1983�N6��11���m�g�j�z�[���ł̉��t�ł���B�w�͓��������͔�у��Y���̓M�N�V���N�֊s�͂ڂ₯�A���悻�l�l�ɕ��������鉉�t�ł͂Ȃ��B�ł��e���Ă���͕̂�����Ȃ�20���I�ő�̃s�A�j�X�g�̈�l�z�����B�b�c�Ȃ̂ł���B���̂Ƃ��z�����B�b�c��79�B�`���̃s�A�j�X�g�̃R���T�[�g�ɑ喇5���~�𓊂��ďW�܂������O�͊��Ẵu�����H�[�Ɛɂ��݂Ȃ���������B�ނ炾���Ă��̉��t���Ђǂ��㕨���������Ƃ͕S�����m�������낤�B�ł��e���Ă���̂͂܂������z�����B�b�c���̐l�B���O�͂����Ƀz�����B�b�c�����邾���Ŗ��������̂��낤�B���������̉��t�Ɋ��R�Ɛ��_�������������]�_�Ƃ������B�u�z�����B�b�c�͂Ђт������������i�������v�ƁB�ނ̖��͋g�c�G�a�i1913�`�j�B����قǓI���˂��\���͂Ȃ��A�킪�����y�]�_�j��ɂ����Ă�����قǂ܂łɃZ���Z�[�V���i���ȕ]�_�͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����B6��17���t�A�����V�����y�W�]�Ɋ��搶�̃R���T�[�g�]���f���炵�����̂������B�u�����͒x�������Ƃ��킴��Ȃ��B�ڂ̑O�ɂ���z�����B�b�c�͂��͂⍜���i���B�����ł���ȏ�A����l�͐ɂ������Ȃ������𓊂��邪�A����l�͈�ڂ��ɂ��Ȃ��B����͂���ł����A�����c�O�Ȃ��玄�͂�����t�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ�قǁA���̌|�p�́A���Ă͖��ނ̖��i�������낤���A���́\�\�ł��T���ڂɂ����Ă��\�\�Ђт������Ă���B����Ȃ��Ƃ������̂��A�����̘V��Ƃɑ��A�ǂ�Ȃɔ��ŏ�m�炸�̎d�ł����A�����낦�ĂȂ��킯�ł͂Ȃ��B�����A��ƂɌ������āA���܂���Ќ����߂ł��Ȃ����낤�E�E�E�v�B�ڂ̑O�ŌJ��L����ꂽ���t�ɑ���I�m�Ȕ��f�ƌ����Ȕ�g�B���ۂ�����q�ϓI�Ȏ��_�B�B�R�Ƃ��Ċi���������́B���̏㉓���̑�Ƃɑ��郊�X�y�N�g���Y��Ă��Ȃ��B�����ɉ��y�]�_�̗��z�̌`������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��قǂ́A����͎j��Ɏc�閼�]�_�������B
�@�搶�͈��N�A�����M�͂����M���Ă���킪�����y�]�_�E�̑�䏊�ł���B���94�Ȃ���A�����V���̉��y���]�A���R�[�h�|�p�ł̘A�ڃG�b�Z�C�ȂǁA�����ʂ�V���ĉv�X����Ȋ���Ԃ肾�B��������������A�Ɠ��̔�g�╶�w�I�\�����瑽���̃t�@���������Ă���B�����ŋ߂̐搶�̕]�_�ɂ͂��Ă̍Ⴆ�������Ȃ��B����̂̂��̂��悭�ǂނƃs���Ƃ�����̂����Ȃ��B��g�Ƃ����p�Ɋւ��Ă��A���̗��ɂ���^���̈Ӗ����������Ă�����̂��ǂ����^�������Ȃ�悤�ȕ\�����U�������B����������ׂ邱�Ƃ�D�悵�āA���t�̐^�̈Ӗ��ւ̓��@������Ȃ��B�����Ȃ�Ό��t����������Ǝg���Ă���B���́u�Ђт̓����������i�v�͌��������̂��H����Ƃ�������̓ˑR�ψق������̂��H�O�яG�Y���a�������ō���͏d���g�c�G�a�ɔ����Ă݂����B��������͂��A���{�����g�������̗l����悷�邱�ƂɂȂ肻�����B����͉��g���ُ�C�ۂ̂����Ƃ��������������������B
�i�Q�j�V���y���ގ҂ɔ@����
�@�搶�́u���R�[�h�|�p�v��2006�N4��������u�V���y���ގ҂ɔ@�����v�Ƒ肷��G�b�Z�C���n�߂�ꂽ�B����́u�_��v�̌��t�����A�搶�͗]�����D���Ȃ̂��낤�A���̍��ł��u�_��v�����p����Ă���B�u��i���X�y�ɂ�����͖�l��B��i���X�y�ɂ�����͌N�q�Ȃ�B�Ⴕ�V��p���Α�����͐�i�ɏ]���v�i�X�y�i���j������̂ɐ̂̐l�͖�l�I�ŁA���̐l�͌N�q�I�ł���B���͐̂̐l�̂����������j�ł���B���̋��������p���Đ搶�͂��������Ă���B�u���̐��l�N�q�̊ӂ݂����ȍE�q�\�\�����J���Η�Ƃ����Ƃ��̐��������Ă����悤�Ȉ�ۂ�^���Ă�l���A�w�X�y�łǂ������Ƃ邩�Ƃ����A�ڂ��͖�l�I�̂ق����ˁx�Ƃ����Ă���̂ł���v�ƁA�����ɂ�"�E�q���`��������d��̂��ӊO��"�Ƃ��������������Ă���B����͂������F���s���Ƃ������̂��낤�B�E�q�͌��X�̐����̍��M�ȉƕ��ɐ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�ŖS���ł���u�̌��������������m�̂������썇�̎q�Ƃ��Đ��܂�A���Ƃɂ͎����ꂸ�ɋ���̓�����l�ԂȂ̂��B�����̍��{�́u�m�v�������ł���A�搶��������悤��"���l�N�q�ŗ�Ƃ����Ƃ��̐��������Ă��������I�ł������א���"�Ƃ����C���[�W�̐l�ł͂Ȃ��B�̊�{���O�Ƃ�����ܓ����u�m�v�u�`�v�u��v�u�m�v�u�M�v�̏��ԂŁA����������A�K��������D�悷�邱�Ƃ̕\�ꂾ�낤�B��i�ɏ]���͈̂ӊO�ł��Ȃ�ł��Ȃ��āA�ނ��듖�R�Ȃ̂ł���B"�����J���Η�Ƃ����Ƃ��̐��������Ă��邨�����E�q"�Ƃ����̂͐搶�̐���ςł���B�����̐���ς���ʘ_�ɒu�������Ȃ��ł������������B
�@���R�|�G�b�Z�C�J�n���ł͂���ȋL�q������B�u�̂͂悭�w���[�c�@���g�͑�l���Ђ��ɂ͂₳�������A�q�����Ђ��ɂ͂ނ�����������x�Ȃ�Č���ꂽ���̂ł���v�ƁB����Ȃ�����܂��̘b�����ɂȂ�܂����H���ۂ�"���[�c�@���g�̃s�A�m�E�\�i�^�͋Z�p�I�ɂ͊ȒP�Ŏq���ɂ��e�Ղɒe�����Ƃ��ł��邪�A�V���v���Ȃ����ɉ��y�Ƃ��Ē�������ɂ͎��ɓ��"�Ƃ����Ӗ��ŁA�u���[�c�@���g�͎q�����Ђ��ɂ͂₳�������A��l���Ђ��ɂ͂ނ��������v���������̂ɁA���������X�Ɛ^���ɊԈ���Ă��܂���Ƃ�������ǂ��Ή����Ă悢��������Ȃ��Ȃ�B���̍��ł́A�܂��o�C���C�g�̃V�F���[���o�̏㉉�N����Ԉ���Ă��āA�����Ŏߖ�����Ă������A��������Ȃ炱����̕��ł͂Ȃ��ł����H�@���㌿�Ȃǂ����p�����ꍇ�͏d�X���ӂ��Ă���ɂ��Ă������������Ǝv���B
�i�R�j�i�C�A�K���̑�
�@�ł͂����Ő搶�̕��͂��Ȃ������s���Ƃ��Ȃ��̂��������Ă݂����B���R�͕��͂���肭�ǂ�����Ȃ̂����A��Ƃ��Ă͉��ł������̂�����ǁA�`���Ƃ̊֘A�ŁA�����u���E�̃s�A�j�X�g�v�i�V�����Ɂj����u�z�����B�b�c�v�̍��̈ꕔ�������p�����Ă��������i�ܘ_����́u�����i�v�]�_�̂͂邩�ȑO�ɏ����ꂽ���̂ł��j�B
�@�����ł́A��z�����B�b�c��"�z�����B�b�c�̋���"�Ƃ������ׂ��Ɠ��̋����������Ă���E�E�E�v�Ƃ������͂��Ă��������Ă���B�u�����l���Ă���ƁA�z�����B�b�c�����Ӓ��̓��ӂƂ��鉹�y�A���Ƃ��V���p���Ƃ����X�g�A���邢�̓V���[�}���Ƃ��X�N�����[�r����̍�i���Ђ����̔ނ́A�����S�Ɛg�̂Ɗy��̎O�����S�Ɉ�̂ƂȂ��Ă��āA�ނ��s�^�b�ƃs�A�m�̑O�ɍ����ĂЂ��o���ƁA�ŏ��̉��A����A���ɂȂ�O�̔ނ̌ċz�A�ނ̌��Ƙr�Ǝw�̓�������A�Ō�̉��ɂ�����܂ŁA���X�܂Ŋ�������A�b�B���ꂫ���Ă��āA�����ɂ́A���܂��牽��V�����H�v����K�v���Ȃ���A���A�������Ă��ǂ��Ƃ����ĕς��]�n���Ȃ��قǂ��E�E�E�E�E�ƁA�����Ȃ��Ă��Ă��s�v�c�͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă���B�@�Ƃ��낪�A�ǂ����A�����ł͂Ȃ��炵���̂��v�B�Ȃ�R�����[�I�@���̎��̂��A�u�Ƃ��v�u���邢�́v�u����v�u���v�Ȃǂ������ɂȂ��Ă������̂ɂƂ�������ŎU����Ă���A��Ǔ_�������Ȍ������܂������Ȃ��̂����A����ȏ�ɃY�b�R�P���͕̂��̗͂���ł���B�O�����܂�ɔ��ׂȕ`�ʂ��Ȃ����Ă��邩����ۃ��C�u�������ɂȂ��Ă���̂��Ǝv�����₻���ł��Ȃ��炵���A�u�s�v�c�͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă���v�Ƃ���B�����Č��т́u�����ł͂Ȃ��炵���̂��v���I�@����̓K�N�b�Ɨ��܂���A�搶�B����́A�Ⴆ�A�j������O�ɂ��āu�M���́A�m�I�Ŕ������A�C���Ă������A���X�܂Ŋ�������Ă��闝�z�̏����̂悤�ȋC�����Ă���B�Ƃ��낪�����ł��Ȃ��Ȃ��v�ƌ����Ă�悤�Ȃ��̂ŁA�܂Ƃ��ɘb���Ă����l�Ԃ͂��܂�Ȃ��B���Ă������Ƃ��Ȃ����Ƃ����Ă������Ƃ̂悤�ɕ`�ʂ��āA�����f�肹���A����ɂ܂Ƃ߂Čy���ے������B����ł͓ǂ�ł�ق��͉������������̂�������Ȃ��B�g�c�l���̓T�^�I�p�������ɂ���B
�@����ȕ��̘͂A�������炱�́u�z�����B�b�c�v�̍��Ɂi���ɖ{�Łj15�y�[�W���������Ⴄ�̂ł��ˁB��������肽���̂́u�z�����B�b�c�͎��������̋������������f���炵���s�A�j�X�g�����A�オ��ǂȂ̂����x���R���T�[�g�����𒆒f���Ă���B�ނ��̑�Ȃ̂͑��̃s�A�j�X�g�ɂ͂Ȃ��u�J�T�v�������Ă��邱�Ƃ��B�ܘ_�ނ̃e�N�j�b�N�͑f���炵�����̂����u��������i���Ȃ�v�����̓O���e�X�N�ł��������Ȃ��B����ȗ͂̌֎����ߔN�i70�N�ォ�j�͂����}�����y�Ȃ̓��ʂ��o�����X�悭������悤�ɂȂ��Ă����B���͂������ƌĂт����v�Ƃ������Ƃ��Ǝv�����A���ꂾ���̂��Ƃɉ��X15�y�[�W����₵�Ă���B�����ᐳ�����܂��B�u�~���V�e�C����z�^�v�ɂ͂���ȉӏ�������E�E�E����A�����J�̔�]�Ƃ����i�~���V�e�C���j�Ƀz�����B�b�c�Ɋւ���R�����g�����߂Ă��Ă����������A�u�z�����B�b�c�͉��t��Ŏ��X��U���ɒe���Ƃ͎v���܂��H�@�ނ̉��t�ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ���������Ƃ͎v���܂��H�v�B���͂���{���̔�]�Ƃɂ��������Ă�����A�u����Ȃ����ۂ��ȏ����͂�߂Ȃ����I�@�z�����B�b�c�͂����̈̑�ȃs�A�j�X�g�ł͂Ȃ��A���R�̐����قȂ̂ł��B�N�͐����������邩��Ƃ����āA�i�C�A�K���̑��ᔻ�ł��邩���H�v�ƁB���ɂ͂��̐��s�̂ق����g�c�搶��15�y�[�W��������ۂǓI�m�Ŗʔ����Ǝv���܂��B
�@ �i�S�j�ւ炵����
�@2006�N12��25���ǔ��V���ɁA���̔N�b��̕����l�Ƃ��āA�����M�͂����M�����g�c�G�a�搶�����グ���Ă���B�����Ă��̋L���́u���[�c�@���g�͕��e���Ă̎莆�Łw�l�̉��y�͑f�l�ł����Ƃł��y���߂���̂ł��x�ƌւ炵���ɏ������B�w�Í������A���y�ɂ��ď����҂���ԐS������ׂ��́A���̂��Ƃł��傤�x�Ɓi�g�c�G�a���́j�قق��v�ƌ���Ă���B�C���^�r���[���Ă���搶�̖����C�Ȋ炪������悤�ł���B����̓C���^�r���[�̒��߂Ȃ̂�����A�搶����Ԍ��������������ƂȂ̂��낤�B�u��������ԐS�����Ă��邱�Ƃ͑f�l�ɂ����Ƃɂ��y���߂���̂��������Ɓv�ł���ƁB�����҂Ă�A�Ǝ��͎v���B�搶�͂��̃��[�c�@���g�̎莆�̖{���̈Ӗ�������������ň��p���ꂽ�̂��ǂ����E�E�E���ɂ͂ǂ����Ă�����������̂ł��B"�ւ炵����"�Ƃ������t�ɁB
�@�搶�����p���ꂽ���̎莆�́A1782�N12��28���A���[�c�@���g�V��̃s�A�m���t�ȁiK413�C414�C415�j�̊����̂Ƃ��̂��̂ŁA�u�����̋Ȃ͂ނ��������Ȃ��A�₳�������Ȃ������炢�̂��̂ŁA��������̂悢�ƂĂ��h��Ȃ��̂ł��B�\�\�Ƃ����ċȂ��̂ł͂Ȃ��A���R�ł��B�\�\������Ƃ���ɐ��Ƃ�������������Ƃ��낪����܂����A�\�\����ł�����A���S�҂ł��Ȃ�ƂȂ���������Ƃ��낪����Ǝv���܂��v�ƕ��e�ɏ��������̂ɊԈႢ�Ȃ����낤�B���Ƃ����"�ւ炵���ɏ�����"�͎����Ƃ͈Ⴄ�Ǝ��͎v���B"�ւ炵����"�Ƃ����ƁA���H���t�K���O�������I�|���g�Ɂu������͒m��Ȃ��ł��傤���A�l�����x�������Ȃ͂��ꂱ�ꂱ���Ȃ̂ł��E�E�E�v�Ǝ������ɏ����Ă���Ƃ����j���A���X�ƂȂ낤���A����͂܂������Ⴄ�B"�f�l�ł����Ƃł��y���߂鉹�y"�͕����I�|���g���A���y�ƂƂ��č��݂ɏ�邽�߂ɋꂵ���C�s����ɐg�ɒ�������Ȃ̋Ɉӂł���A�킪�q���H���t�K���O�ɗc��������O��I�ɒ@�������[�c�@���g�Ƃ̍�Ȃɂ��������ΉƌP�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B���������Ă����͕��e��"�ւ炵��"�ł͂Ȃ�"���������܂ŕ���ɂ��������Ă����ʂ�̉��y�������܂���"�Ƃ����ނ��늴�ӂ̕Ȃ̂ł���B"�ւ炵��"�ƌ���ꂽ�g�c�搶�����̎��������Ă��炵���̂��ǂ����H�@��������������Ə������̂͂��������Ӗ��������̂ł��B
�@�ł́A���̍������o���č������߂����Ǝv���܂��B�Έ�G���u�V�˂̕����I�|���g�E���[�c�@���g�̐t�v�i�V���Њ��j131�y�[�W�B�E�E�E�u���I�|���g����Ȃɂ����ĐS�������̂́A�����̗��z��"��Ή��y"�ł͂Ȃ��A���s�̃X�^�C���̂���ɂ��킩��₷�����p�I�ŕ����ȉ��y���������Ƃł������B����ɂ́A�����ɂȂɂ��C�̗������d�|�����A�ق�̏��������A�X�p�C�X�̂悤�ɐU�肩����B�����ȕւȉ��y�͒�R�Ȃ���ʂɎ�����A�d�|���͎��̂悢���Ƃ��������邱�Ƃ��ł���B���ꂪ�ނ̍�Ȃɂ�����N�w�ł������v�E�E�E�B����ȕ��e�ɑ����[�c�@���g��"�ւ炵����"������킯�͂Ȃ��̂ł���B
2008.09.01 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�Q
�@�X���̐����đ啪���̂��₷���Ȃ��Ă��܂����B���̂��ߑO��قǓ��̓J�b�J���Ă��Ȃ��̂ŁA�^�b�`�͏��X�_�炩���Ȃ肻���ł����A�܂��A���������ď��яG�Y���a���Ă����܂��傤�B�@���яG�Y�̖����u���I�c�@���g�v�ɂ͂܂��܂������Ȃ��L�q������B�u�Ⴆ�A�l�́A�n�����N�����e�b�g�iK465�j�̑�2�y�͂��Ă��āA���I�c�@���g�̎����Ă����\������Ƃ���ӎu�̋����ׂ�������������Ă���l���A���̍��f���o���Ȃ��璭�߂�̂ł���B�Ⴕ�A���ꂪ�^���Ȑl�Ԃ̃J���^�A�r���Ȃ�A�������̐扽���ɍs���������낤���B�Ⴆ�`���C�R�t�X�L�C�̃J���^�A�r���܂ő�����K�v�������ɂ������̂��낤�B�v�i��10�́j�E�E�E�����Ŏ��͉��y�j�������o���Ĕ��_�������͂Ȃ��B����Ȃ��Ƃ�������_������o���Ă��܂��B����͂�����"��"�͂Ȃ��Ǝv���B�`���C�R�t�X�L�[���ėD�����ċC���キ�Ė{���ɂ����l���������ĊF�����Ă�B�s�A�m�����ʂقǂ��܂������̂ɐl�O�ʼn��t����x�����Ȃ���ō�ȉƂɂȂ������Ă������B�ł��悩�����A�C���������ėD�����������A�ł���Ȃ�������̖��Ȃ�������̂�����B����ȋC��ȃ`���C�R�t�X�L�[�Ȃ̂ŁA�搶����"��"���Ȃ���ꂽ�玩�E�����Ⴄ�����m��Ȃ��B�����Ƃ��ߔN�A�����͎��E���Ă��ƂɂȂ��Ă�悤�����ǁB�����@�C�I���j�X�g�A�i�^���E�~���V�e�C���̉�z�^�ɂ���ȋL�q������B�u�`���C�R�t�X�L�[���D�l���ł��������Ƃł͗F�l�ƈӌ�����v�����B�ނ��ǂꂾ�����[�c�@���g�������Ă������H �R���T�[�g�Ńg�Z���d�t��K515���ǂ����������B���ăp�g�����̃}�_���E�t�H���E���b�N�ɂ������������Ă���\�\�܂��j��`���A�l�X�ɋC�Â���Ȃ��悤�ɐȂ𗧂��˂Ȃ�܂���ł����A�ƁB�ނ̓R���T�[�g�̎c��𒌂̉e�ɉB��Ē������̂ł���B���̓`���C�R�t�X�L�[�̉��y��"�ǂ��"���āA���Ă���قǖ��m�ɒm�I�ɂ����ėD��ɉ��y����������ȉƂ͂��Ȃ��Ǝv�����v�i�t�H�Њ��u���V�A���琼���ցv�`�~���V�e�C����z�^�A������c��[��]���j�B���яG�Y���u���Ȃ����͎�������A�܂͒ǂ����Ȃ��v�Ƃ���������f�����g�Z���d�t�ȂŁA�`���C�R�t�X�L�[�͗܂𗬂��āA�l�ɋC�Â��ꂽ���Ȃ��āA�����ƐȂ𗧂����̉e�ŋ����Ȃ��璮���Ă����̂ł���B�����Ă��̙R��������������ȉƂ�"���m�ɒm�I�ɗD���"���y���������̂ł��B���[�c�@���g����D���ł��̍�i���ė܂𗬂����ȉƂ��������J���^�[�r���̂ǂ���"��"�������̂Ȃ̂ł����B���ꂶ��`���C�R�t�X�L�[��������܂���B�����͐�ɏC�����ė~�����B
�@���яG�Y���Ō�Ɉ��p���Ă���̂����[�c�@���g1787�N4��4���̎莆�B�u��N���A���͐l�ԒB�̍ŏ�̐^���ȗF�B�Ƃ����l���ɂ������芵��Ă���܂��B�\�\�l�͂܂��Ⴂ���A���炭�����͂������̐��ɂ͂��܂��ƍl�����ɏ��ɔ����������͂���܂��ʁB�����A�l��m���Ă�����̂́A�N���A�l���t�������̏�ŁA�A�C���Ƃ��߂��C���Ƃ���������̂͂Ȃ����ł��B�l�͂��̍K����_�Ɋ��ӂ��Ă���܂��v(��11��)�ł���B����͕�����₷�����͂��B�Ƃ��낪���̌�ɑ������т̕��͂̂Ȃ�Ɠ���Ȃ��Ƃ��B�Ⴆ�u�����Ō���Ă���̂́A���͂�I�c�@���g�Ƃ����l�Ԃł͂Ȃ��A�J�뉹�y�Ƃ�����ł͂���܂����B�E�E�E�ނ͂��̉��y�ɌŗL�Ȏ��Ԃ̂����ɁA�����v���ɖ��݁A�l��̓���̎��Ԃ��A����Ƌt�ɐi�s����l�߂�B�E�E�E�E�E��͉����Ă͂����Ȃ����A��������͓̂�ł͂Ȃ��B���R�͔ނ̕��ɐG���قNj߂��A�T�ɍ݂邪�A���������͂��Ȃ��B�ٖ�͂��łɐ��藧���Ă���A���R�́A�����̎��݂Ȗ��̊m���ȗh�Ղ��鎖���~�߂Ȃ��A�ƁB�E�E�E�ނ̉��y�́A�ߋƂ̎v�z�ɐZ����ʈ��̗։�������Ă���l�Ɍ�����B�l��̐l���͉߂��čs���B�������ɑ��ĉ߂��čs���ƌ����̂��B�߂��čs���҂ɉ߂��čs�����������悤���B���́A�ʂ����Đ���m��ł��낤���v���X����ɂ܂������ׂ���A�u���I�c�@���g�̌����ق����������v�ƒf�����āA�u�₪�ĉ��y�̗�͔ނ�H���E���ł��낤�A���炩�Ȃ��Ƃł���v�Ǝ��M�������Č������Ă���B���������镔���͗B��u�l��̐l���͉߂��čs���v�������A�g�z�z�B
�@���͉��x�ǂ�ł��悭������Ȃ��̂Œ��߂邯�ǁA�ЂƂ͂����肵�Ă���̂́A���т������Ă���̂̓��H���t�K���O�Ɋւ��邱�Ƃ������Ƃ������Ƃ��B����łق�Ƃɂ����̂ł����H�Ǝ��͖₢�����B���̎莆�́A���H���t�K���O��"�����I�|���g�͂��������͂Ȃ�"�Ƃ̕���ĕ��e�Ɉ��Ăď������莆�Ȃ̂ł���i���яG�Y��"����͢�h���E�W�����@���j����\�z����O�ɁA���e�ɑ������莆�̈�߂ł���"�Ƃ��������Ă��Ȃ��B�̈ӂ����m���͒m��Ȃ���"���̗e��"�ɂ͐G��Ă͂��Ȃ��̂ł���j�B���y�̎�قǂ������Ă��ꂽ�ň��̕������̂��Ƃ��Ă���i���ە��͂��̈ꌎ����5��28���ɖS���Ȃ��Ă��܂��j�A����Ȏ��Ƀ��H���t�K���O�͎����̂��Ƃ��������Ȃ����낤���B��ɂ��肦�Ȃ��Ǝ��͎v���B����������n���Ȃ�ɂȂ�Ƃ�������Ԃ߂悤�Ǝv���B����ȏ܂�����������C�g�����"���͓�N���A���͐l�ԂɂƂ��čŏ�̗F�B�Ǝv����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����疾���͂������̐��ɂ��Ȃ��Ǝv���Ă������ɓ����Ă���̂ł����A�����ĈÂ��Ȃ��Ă͂��܂���B���͂���ȐS���ɂȂꂽ���Ƃ�_�Ɋ��ӂ��Ă��܂��B������A���ɂ����Ă����l������悤�ɂȂ����̂ł�����A���Ȃ��������悤�ɍl�����Ȃ��͂��͂���܂����ˁB�ꏏ�Ƀ��C�\���Ŋw�̂ł�����B"�Ƃ����Ȃ邾�낤�B�ނ͂₪�Ď��ɐ������̕s���ȐS��𗶂��ĈԂ߂Ă���̂ł���B����͕��ւ̎v�����̎莆�Ȃ̂ł���B������킴�Ǝ�������Ȃ��U������Ă���Ƃ�������̂ł���B����ȐS�D�������[�c�@���g�����͑�D�����B���̎莆����́A���H���t�K���O�̕��e�v���̗D�����^���ǂݎ���Ă��ׂ��ł͂Ȃ����A�Ǝ��͍l����B
�@�����A�V�˃��[�c�@���g�̐��i����X�}�l�������낤�͂��͂Ȃ��̂������B�肪����͎c���ꂽ�莆�����Ȃ����A���̓��e����⒴�^�ʖ�(��)�Ȃ��̂���x���ŗ�Ȃ��̂܂ŗl�X���B1778�N12��23���A�]���̃x�[�Y���ɏ������莆�͎x���ŗ�̓T�^�ŁA�N�\���炦�A���K�ɕ��A�\�����e���ˁA�O�������납����A����I�i���l�̓V�g���X�A���ꂱ����C���킹�A�ʟ����A�X�J�g���W�[�Ȃ������ɍʐF�G�����ł���B�܂��A�p�����牡�ɕ�e�̈�̂�u���ď������Q�ʂ̎莆���L���B���e�ւ̓V���b�N��^���܂��Ɩ�����ď�ԂƏ����B��������ŗF�l�ɂ͂����S���Ȃ����Ƃ���������b���A���e���Ԃ߂Ă���Ə����B���ւ̎莆�͂��̂��Ɓu���āA�b���ς��܂��B����Ȕ߂����l���͂悵�Ċ�]�������܂��傤�v�Ɛ�ւ��āA�����̐V��̃V���t�H�j�[���劅�т𗁂т����Ƃ��ւ炵���ɏ����Ă���B���̓V�ߖ��D���͂܂�Ŕނ̉��y�ɂ�����]���̂悤�ł���B���̓��[�c�A���g�A�p���ł͏A�E�����Ȃǎ����̂��ƂŎ��t�ŕ�A���i�E�}���A��������炩���ɂ��Ă����悤�Ȃ̂��B�u������A�ЂƂ肫��ŁA�Â������̒��ɍ����Ă��܂����A�܂�ŘS���ɂł�������Ă���悤�ł��B������A���̎q�ɂ͉�܂���v�Ƃ����ꂩ�畃�ւ̎莆���c���Ă���B�Ȃ�Ƃ����̂����B�Ȃ�Ƃ����Ȃ��B��͂��̂R������ɂ͎���ł��܂��̂ł���B�������炩���ɂ��Ă����ꂪ����Łu�F��A�l�ƂƂ��ɔ߂���ł���A�����͖l�̐��U�ōł��߂������������v�ƕ��R�Ǝ莆�������B����Ȃɔ߂��ނ̂Ȃ�����Ɩʓ|���Ƃ��Ă���ƌ��������Ȃ邵�A�ǂ��܂Ŗ{�C�Ȃ̂�������������Ȃ��B�����ό����݂ȃ��[�c�@���g�̊y�z�ɂȂ��炦�Ă��s�v�c�͂Ȃ��A�����珬�яG�Y����Ă̕��ւ̎莆�Ɂu���y�Ƃ����삪����Ă���v�ƌ����Ă��A���̂��Ƃɕ������������͂���܂���B�ł����͂���Ȓ��ɂȂ�Ƃ����[�c�@���g�̐^����������B
�@���e�ւ̎v���ɂ͏��������āA�u�c�������烈�[���b�p������������A���q�𗘗p���ċ��ׂ�������e�v�����[�c�@���g�͍��ݕ̂�ł����A�ƌ��ߕt���鎯�҂�����B�����烂�[�c�@���g�͕���������ɢ���y�̏�k�K522���������A���̂̔O�����߂āA�ȂǂƁB�m���ɏ��N���[�c�@���g�̗���H���������肩�ȂƂ͎v���B�ł�����Łu�������Ȃ��l�Ԃ͑S������Ȑl�Ԃł��B�}�f�Ȑl�Ԃ͗������悤�Ƃ��܂��Ɠ����ł����A�D�ꂽ�˔\�̐l�Ԃ͓����ꏊ�ɂ���ƑʖڂɂȂ�܂��v�Ǝ莆�i1778�D9�D11�j�ɂ������Ă���Ƃ���A�����ɂ͎����̍˔\���J�Ԃ����Ă��ꂽ���A�Ђ��Ă͗��ɘA��o���Ă��ꂽ���e�ւ̊��ӂ̋C�����͐�ɂ���͂����Ǝ��͎v���B�����āA5����킪�q�����[���b�p�������Ă��ꂽ�e���Ȃ�ĉ��y�j�㑼�Ɉ�l�����Ȃ��̂�����B���тɂ͂��ꂪ�����Ȃ��B����Ⴛ�����낤�A�ʂ̉ӏ��Łu���[�c�@���g�̂قƂ�Nj��Ƃ��]���������U�v�Ȃ�Ă����ɓx�ɕ\�ʓI�ȋL�q�_�o�ɂ��Ă��܂��l�ł���A�Ƃ������Ƃ͑����ƒf�I�Ɉ�̊p�x���炵�������Ȃ��l�Ȃ̂��B�ނ͂܂������������Ă���B�u�N�ł������̊��ʂ��Ă����l�������₵�Ȃ��B�����������^�����蕎�̂����肵�����̂Ȃ��l�ɁA�ǂ����Đl�����^�����蕎�̂����肷�鎖���ł������낤���v�i��X�́j�ƁB���͂����ނɂ��̂܂ܕԂ��Ă�肽���B�u���яG�Y�͎����̊��ʂ��Ă������[�c�@���g�̎莆��ǂ�ł��Ȃ��B���l�ɑ��Ĉ������v���������������Ƃ̂Ȃ��l�ɁA�ǂ����ă��[�c�@���g�̎v����肪�����邾�낤���v�ƁB����͂�����ƌ����������H�����ǂ܂��A�l�͂���������Ƃ��炵�����Ƃ������Ă����t�̒[�X�ɖ{���͏o���Ⴄ���̂Ȃ̂ł��B������R��Y�Ɂu���O�̔�]�́A������ނ�̂ł͂Ȃ��A�ނ��t���������邾���A�����炨�O����ɂ͍˔\���Ȃ��v�ƌ���ꂿ�Ⴄ�B�V�˂ɂ͏��т�"�{���̌����Ȃ�����"��������̂��B�v�����Ɍ����鍂��Ԑl�Ԃɂ͕����̖{���������Ă��Ȃ����Ƃ�ނ͂����ʂ��Ȃ̂ł���B�R�̂��Ƃ����т́u�l�����͏G�˂������������͓V�˂��v�ƕ]�����Ƃ������A�V�˂͂��̒ʂ肾����ԈႢ�Ȃ����A�����Ŏ����̂��Ƃ��G�˂��Č����̂͂ǂ��ł��傤���B����͐l�l�������Ă���邱�ƂȂ�Ȃ��ł����B ���яG�Y�́u���I�c�@���g�v���Ă���ȂɌ���Ȃ̂ł����H
�@����X�̓C���^�[�l�b�g��������[�c�@���g�̑S�Ă̊y�����{���ł��A�ŐV�̃��f�B�A�̓��[�c�@���g���������قƂ�ǑS�Ă̊y�Ȃ����i���̉��ʼnf���Œ��Ă����B�R���T�[�g�͐��m�ꂸ�A�C�O�ɂ����Ă������ōs����B�u���I�c�@���g�v�������ꂽ�̂͏��a21�N�I�풼��̂��Ƃ��B���̎����ʂ����݂Ƃ͉_�D�̍����������B���яG�Y�̓��[�c�@���g�̉��y���قƂ��78��]�r�o���R�[�h�Œ��������Ȃ��������A���͂��ׂėm�����瓾�邵���Ȃ������낤�B����Ȏ���ɔނ͂��ꂾ���̂��̂��������̂ł���B����͊ԈႢ�Ȃ����яG�Y�̍˔\�̏ؖ��ł���A�����̐l�X�����̓���Ř����ȕ��̂ɂ�鐼�m�̉b�q���U��߂���i�ɋ��Q�����͓̂��R�̂��Ƃ������B�u���I�c�@���g�v�͂܂��Ɋ�Ղ̍�i�������̂ł���B������ƌ����āA������Ȃ����͕̂�����Ȃ����A�Ⴄ�Ǝv�����Ƃ��Ⴄ�ƌ����Ă����Ȃ��킯���Ȃ��B�搶�������Ă����琥��u���Ă݂����Ǝv�����B���Ɂu���s�̂����v�Ɓu�`���C�R�t�X�L�[�̑��v�̌��ɂ��ẮB����V�Ԃ��Ă̔��͉Ă̏����̂����Ƃ������������������B
2008.08.25 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�P
�@�Ƃɂ��������B�������������ᎄ�̓���������������Ă�B����ȂƂ��͂Ȃɂ��l�����ɓk�R�Ȃ�܂܂ɏ��������Ȃ��B�^�[�Q�b�g�͌��ЁB�X�^�C���͎x���ŗ����ςȂ��B�\�������珋���̂����ɂ����Ⴂ�܂��傤�B����ł����ƋC���u���B�������u�b��ԁB�������}�l�A���i�͋C�B�����܂����Đ����Ă��炽�܂ɂႱ�������̂���������Ȃ�������B�����A�^�u�[�ɒ��킾�B�@���ЂƂ����Ε]�_�̐_�l�Ƃ���ꂽ���яG�Y(1902�|1983)�B���{�̉Ă͂��~���Ƃ��I��L�O�������邹�����̂��v���o�������Ȃ����肷�����ŁA�v�X�ɔނ̖����Ƃ�����u���I�c�@���g�v���Ă̂�ǂݕԂ��Ă݂��B���y�]�_�̌ÓT�I����Ȃ���������ĒN�����̖{�̈��������Ă�̕��������ƂȂ��̂Ŏ�������Ă�낤�Ǝv���Ă��B�ǂނ��тɎv���̂͂���ȓ�����́A�F�ق�Ƃɕ������Ă�̂��Ȃ��Ď��B���͐��������Ă悭������܂���B�搶�̌������B�Ⴆ�Α�X�͂ɂ���ȂƂ��낪����B�u���I�c�@���g�̌ǓƂ́A�ނ̐[�����C�����A���̏�ɍ��邠��[�������m���ȕ��ł������B�ނ͗��e�̗���ɗV��ł���q���̗l�ɌǓƂł������v�B�ȂႱ���I�悭�������ǔn���ȓ��Ђ˂��ă����C�g���Ă݂��"���[�c�@���g�̌ǓƂ̏�ɂ͐[�����C���������Ă���B������[�������m���Ȃ��̂��B���������̌ǓƂ͗��e������̂Ƃ��ɗV��ł���q���̂��ꂾ���炻��قǐ[���Ȃ���Ȃ�"�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�ƌ����Ă��A"���C���������Ă���Ǔ�"���ǂ�����"�m���ȏ[����������"�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��T�b�p���������A���S��ǂ�ł��ˁB����ȓ���ȕ��̓��U���U�����Ƃ��ĂȂɂ��������������Ă��Ɓu���[�c�@���g�̌ǓƁv���H���l�̌ǓƂ��Ȃ邩�Ȃ�ĕ�����̂ł����ˁA���ۂ̂Ƃ���B
�@���̏����O�ł͂��������ߕt���Ă�B�u������A���I�c�@���g�ɂ́A�S�̒��f�I����悤�ȗF�͈�l���Ȃ������̂͊m�����낤���A�Ⴕ�A�S�̒�ȂǂƂ������̂��A�����������I�c�@���g�ɂȂ������Ƃ�����A�ǂ��������ƂɂȂ邩�v�B����͎���Ȍ����������B�l�ɐS�̒�͂����A���l�ɂ͕�����Ȃ������ŁB�ʂ̂Ƃ���Łu���I�c�@���g�͐l�ɐS�̉���͌����Ĕ`�����Ȃ������v�Ƃ��邪�A"����"���Č����Ă�ł͂���܂��B����͖������Ă܂��B����������ȗF�l�͂��Ȃ��������āH������O���낤���B�S�̉����f�I����F�l�Ȃ�Ă��Ȃ��ق������ʂ����āB"����"����A����Ȃ��������ĕ�����Ⴕ�Ȃ�����B��������Ȃ��P��_�o�Ɏg����Ȃ����āB�ł����Ȃ蒇�ǂ��Ȃ̂͂����Ǝv���B���̖��̓N�����l�b�g�̖���V���^�[�h���[�B���[�c�@���g�ӔN�̕n�R�͔��ł��������Ă����������邪�A�J���ɂ��Ĉ�l�Ŋ����グ�Ă��̂��V���^�[�h���[���������Č����Ă���B�����Ă������Ă��܂��o�����čs���Ă��B���������Ȃ�������ނ������ƁB�ǓƂ�������߂��������ǂ������ɂ͕�����Ȃ�����Ǘ҂������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�u���I�c�@���g�̌ǓƂ́A�ނ̐[�����C�����A���̏�ɍ���E�E�E�v�Ȃ�Ė�̕�����ƌ����ĂȂ���"�҂�����₾����"���đf���ɏ����Ă����A�������}�l�ɂ��悭������Ǝv�����ǂȁB����ł����Ă��̈��F�ɖ���u�N�����l�b�g���t�ȁv�������Ă���Ă�B�؋��̂����������̂�������Ȃ����ǁA����ł���������Ȃ��ł����B�����Ă���悤�Ȃ��̊W�A���F�����ǐe�F�������Ǝv���B���ꂱ������"�����ȗF��"���Ǝv�����ǂȁB�搶�ƐR��Y�̊ԕ��Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ���ǂˁB
�@���Ɓu�s��p���͉B���Ƃ������ł͂���܂��v���悭������Ȃ��t���[�Y���B����́u���[�c�@���g���c�����莆���A�S�̒��f�I����悤�ȗF�l�������Ƃ��Ă��A���̓��e���ς�邱�Ƃ͂Ȃ��B�ނ́A�莆�̒��ŁA���炭����B���Ă͂��܂��v�ɑ��������Ȃ̂��B"�ނ͕s��p������S�̓����B�����Ƃ��o���Ȃ��B����ł����̂�"�i�Ⴄ�̂��ȁH�j�݂����ɏ����Ă����Ε�����₷�����ǂȁB�����ł��܂����̐l���[�c�@���g�̐S�̉��ꂪ�������Ă���Č����Ă�A����B���ĂȂ����Ƃ����������B�ق�ƁA���������̂��l�ɂ͕�����̂��Ȃ��B�ł��܂�������"���炭"���Č`�e���t���Ă��ŁB
�@�ɂ߂��͂���A�u���I�c�@���g�̉��y�ɖ����ɂȂ��Ă������̍��A�l�ɂ͊��ɉ������������Ă��Ȃ������̂��B�Ⴕ�����łȂ���A���ł��܂�����m�炸�ɂ���Ƃ������ɂȂ�B�ǂ��炩�ł���B�v�i��2�͂̏I�Ձj����͑T�ⓚ���H ���ꂱ�����̓��ł͗����̌��x���Ă���B�ł��������ĉ��߂��Ă݂悤�E�E�E"���̍��͎Ⴍ�ĂقƂ�lj��������Ă͂��Ȃ������̂��낤���B�Ⴕ�����Ă����̂Ȃ�A���ł���������ĂȂ��Ƃ������Ƃ��B�ǂ��炩��"�E�E�E����ς薳�����B�Ȃ�Ƃ����낪�����͍̂ŏ��̃Z���e���X�����ł��Ƃ͑S���Ӗ��s���B���Ɂu���Ɂv��"����"�Łu�����łȂ���v��"�����ł����"�Ȃ�Ӗ��͒ʂ�E�E�E"���̍��͎Ⴍ�ĂقƂ�lj��������Ă͂��Ȃ������̂��낤�i���j�B���������ł���Ȃ�A���ł��܂���������Ă��Ȃ����ɂȂ�B�ǂ��炩�ł���B"�E�E�E�Ƃ܂������Ȃ�̂ŁB�ł�����ȓ�����O�̕��͂�]�_�̐_�l�������͂��Ȃ���ȁB������u�ǂ��炩�ł���v���ǂ����Ă�����܂���B"�ǂ��炩"�ƌ����Ă�̂�����A��B��̑Ώۂ��Ȃ�������Ȃ��̂����A�Ȃɂ�A�łȂɂ��a�Ȃ̂��H�����A���̓��͉�ꂻ���B�F�l�������狳���Ă��������B
�@����ɐ搶�̌��ߕt������B�Ȃ̖����u�ނ͂����@�����悩�����B�d�������Ȃ���A�S�����̎��ɋC���Ƃ��Ă���Ă��ŁA�h���悤�Ȗڕt���ł����Ɗ�𐘂��Ă��Ȃ���A�ǂ�Ȏ��ɂ��ނ̌��͂�����Ɖ�������̂ł���B�H��ɂ��ƁA�i�v�L���̒[�����݁A�M���M���P���āA�@�̉����s�����藈���肳����̂����A�l���������Ă��邩��A���l�͉������Ă��邩�����ĂȂ��l�q�B����Ȏ������Ȃ���A�����l��n���ɂ����悤�Ȃ��Ƃ������B�v�Əq�����Ă��邱�ƂƁA�Ȃ̎o�̒U�߃����Q�́u�ނ͂ǂ����Ă���l���Ƃ͌����Ȃ��������A���ɑ厖�Ȏd���ɖv�����Ă���Ƃ��̌��s�͂Ђǂ����̂ł������B�������ނ̏�k�������B�ӂ���������@�ȑԓx������B�v�Ƃ�����̘b�ɁA���I�c�@���g�̓`�L�͗v���Ǝv����i��7�́j�E�E�E�Ɛ搶�͌���������Ă�B�g���̌����Ă�b������ԈႢ�Ȃ����낤���i�����Q�ɂ͕��G�Ȏv���͂��邯��ǁj�A���[�c�@���g�̐��i�⌾�s�����������m���͎̂����B����͂����Ƃ��āA"�`�L�͂��̓�ɗv���"�͂���܂肶��Ȃ��ł����B���ꂶ�Ⴢ�[�c�@���g��"�ʂ̂��Ƃ����Ȃ����Ȃł����Ⴄ�V�˂����A�������������Ȃ��Ĕn���ȏ�k���茾���Ă��閳��@�ȏ���"�Ƃ������ƂŏI������Ⴄ�B�搶�͔ނ̋`�������������Ƃ��Ă邺�B����͖S���Ȃ����N�̍�i���ώ@�������������̂ɁB����������̂������āu���N�C�G���v�̊������}���ł����̂͒N�ł��m���Ă邵�A���ɂ��Ȃ邩��Ȃ̃R���X�^���c�F���K���ɏ��������낤���炻��͒u���Ƃ��āE�E�E�u�A���F�E���F�����E�R���v�X�v�͂ǂ����H����͍Ȃ������b�ɂȂ��Ă��铒����̍������ɑO���痊�܂�Ă������̂��������A�u���J�v�Ȃ^�_���R�C���Z���e�B�u�Ȃ��ŋ��m�̂����˂����̈������̈˗��ŏ��������́A���Ƃ͑O�o�u�N�����l�b�g���t�ȁv�ƁA�قƂ�ǂ����ɂȂ�Ȃ��`���ʂ����̂��d������B�ɂ߂��́u�z�������t�ȑ�P�ԁv���B���[�c�@���g�ɂ͂����ЂƂ胍�C�g�Q�v�Ƃ����z�������l�̐e�F�������B�Q�S�ΔN��Ől�̂����I�b�T���B���ʂ܂ōs�������Ă������Ƃ͎莆��ǂ߂Ε�����i���[�c�@���g�����̐l�ɂ�"�S�̒�"��ł������Ă����Ǝv�����ǁA����͒u���Ƃ��āj�B�ނ������Ñ����Ȃ�����Y�ꂿ����Ă�����ǁA����������肩���́u�z�������t�ȁv�����������Ƃ����[�c�@���g�͎v���o���B���������͔����Ă���B�{���͈ꍏ�ł������u���N�C�G���v���d�グ�Ȃ��Ⴂ���Ȃ����ɁA�ނ̓��C�g�Q�v�ɏ����Ă��̂ł��ȁA��K�ɂ��Ȃ�Ȃ��R���`�F���g�̑������B�ق�Ɣނ͋`�������B����ȃ��[�c�@���g���͑�D���ł��B�ł����������Ɏ���ł��܂��B���[�c�@���g�̈��́u���N�C�G���v�̑��ɂ�����Ȃ������̂ł���B�ł��ǂ����Ĉ�삪�u��P�ԁv�Ȃ́H�u�z�������t�ȁv�͂S�Ȃ���̂ɁA�Ǝv����ł��傤�ˁB����̓P�b�w���̂��������ȍl�̎Y���i���̕����Ɋւ��Ă͂ł��B�g�[�^���ł̔ނ̌��т͌v��m��Ȃ����̂�����܂��j�B���̌�̌�������A�ނ������ԍ�����ȔN�㏇�ɕ��ׂ�ƂQ�C�S�C�R�C�P�ƂȂ�̂ł��B���̂�����͂܂��ʂ̋@��ɁB
�@�u������\�N���̂̂��Ƃ��A�ǂ��������Ɏv���o������悢���킩��Ȃ��̂ł��邪�A�l�̗����ȕ��Q����̈���~�̖�A���̓��ږx��������Ă����Ƃ��A�ˑR�A���̃g�Z���V���t�H�j�C�̗L���ȃe�G�}�����̒��Ŗ����̂ł���B�v�Ƃ������L���ȕ`�ʂ�����B����͂����ł��ʂɁA����Ȃ��Ƃ͒N�ɂ����Ă��邱�Ƃ�����A��Ȃ��Ⴄ�����ŁB���͂��̏������Ɓu���ӂ��Ēu���������A���x���̍��́A���̊X�́A�l�I���T�C���ƃW���Y�Ƃŏ[�����A���ȗ��s���̂́A�d�g�̂悤�ɖ��𑖂�A�������̎Ⴂ���̂̎�_�Ƃ�����_���h�����āA�l�͒f���̎v�������Ă����̂ł���v�Ƃ��������ł���B���ȉ��y������Ă���G���̒��ŁA�[���̂悤�Ƀ��[�c�@���g���������Č�������ł���B"���ӂ��Ă��u��������"���ƁA�̂����ɁB��������͂܂������Ă������B���A"�l�I���T�C���ƃW���Y�Ƃŏ[�����A�������̎Ⴋ���̂̎�_���h�����āA�l�͒f���̎v�������Ă���"������ǂ���������ɂ��B�����A��ɋ����Ȃ��̂�"���ȗ��s���S"�Ƃ�����������B�����̗��s�̂ɂ͂ǂ�Ȃ��̂��������̂��A���a�̏��߂��Ƃ���Ɓu�o�D�̍`�v�u�N�����v�u�g���̍`�v�����肾�낤���B�Ȃ͂Ȃ�ł��������B�Ƃɂ������s�̂��������ĂȂ�̐S�̒ɂ݂��������ɕ��R��"����"�ƌ��ߕt����ԓx�͒f���ċ������Ƃ͏o���Ȃ����B��̍J�ł��������͂������Ĉ�������ŗJ�����炵�Ė���������邩�Ȃ����Đ���t�����Ă�����B������Ȃ��Ƃ́I�������`���I�Ɍ�������Ȃ����āB����ςŌ��ߕt�����Ȃ����āB���������̂_�o���Č�����B���݂����Ȕy�Ƀ��[�c�@���g���������Ă��܂邩�B���[�c�@���g�̔߂������������Ă��܂邩�B�ӂ�����Ȃ�����[�́A���̑����I���W���B�g�Z�����ƁH�������Ƃ܂��Ă�˂��B���q�����Ă�˂����[�́B������x�����B���ȂɃ��[�c�@���g�͕�����Ȃ��B���������Ȃ�Č��킹�Ȃ��B
�@���яG�Y�̖����u���I�c�@���g�v�͂��̂悤�ɓ���ŁA���܂ɕ�����Ε������A���ɂ̓X�g���X��t�̖����ł��B���ꂾ���ł͂܂�����Ȃ��̂Ŏ��������t�������������B
2008.08.11 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̃G�s���[�O
�i�P�j���ѐ��ւ̔��_�@�u���R�[�h�|�p�v�ŐV���i2008�N8�����j�V�������Ȍ��]���ŁAORFEO�����Ձu�o�C���C�g�̑��v�Ɋւ��F����F�����u�Ƃɂ������̂܂܂ł́A�݂Ȃ������ɂ��̂��͂��܂����悤�ȋC���������Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ�����J���锭�������Ă��邪�A�����C�ɂȂ����̂́u��������M�̕��ьN�́A���̃o�C�G�����Ձi�Z���^�[�Ձj�������n�[�T���ł͂Ȃ����Ə����Ă���v�Ƃ��������̂ق��������B�Ȃ�Ǝ��Ɠ����ӌ��ł͂Ȃ����B����ORFEO�����Ղ��L���O���R�[�h�̗F�l�Ɏ�z���Ă��炢���ђ��Ǝ��̉����ǂ�ł݂��B�u���̌��Ɋւ��A���R�[�h�|�p2007�N9�����ł�4���̈ӌ����f�ڂ����Ƃ����ُ펖�ԂƂȂ������A���q���u���́w�Z���^�[�Ձx���n�[�T�����A����3���͖{�Ԑ��ł���B���͋��q�����x������v�Ƃ������̂ł������B�S�����������i�y�͊Ԃ̉��̗L���Ƃ����Ⴂ�͂��邪�j�̓��CD�̂����A�t���g���F���O���[�E�Z���^�[�ЕzCD�̉���͈�т��āu�Z���^�[�Ձv�{�Ԑ��ŁAORFEO�Ղ́uEMI�Ձv�{�Ԑ��ŏ�����Ă���B���������ɐ^�����Ⴄ��̉���B�����������ُ̈펖�ԂƂ�����̂�������Ȃ��B���ю����̍����̓Z���^�[�Ղ́u�s�����鍂�g���v�ł���A�u�Ȃ�ƂȂ��y�������Ă���v�Ƃ�����ۂ������Ƃ����B���ю��̊��o�͐������Ǝ����v���B�������A���̕\���͂ǂ��݂Ă���I�ɉ߂��͂��Ȃ����B����ł͊����̎�L���Ă��鑽���̃Z���^�[�����[�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�ނ�̓��e����琔�_�s�b�N�A�b�v���Ă݂悤�B
�E�uWFHC-013�i�Z���^�[�Ղ�CD�ԍ��j�������܂����B�������ꂽEMI�^���Ƃ͊m���ɈႤ�Ƃ���͑����ł��B�I�y�̓R�[�_�̍Ō�̂Ƃ���A�{�Ԃ͑S������Ȃ��s�V�b�ƌ��܂��Ă���A��͂�{�ԉ��t�̂ق�����ѐ��������Ă悢�ł��v
�E�u�w���x�������܂����B�I�y�͂̃N���C�}�b�N�X�͂����ƃI�P�͉������߂Ă���ł͂Ȃ��ł����I�F����F���]�_��"���܂�̉����ɃI�[�P�X�g���͂��Ă��Ă��Ȃ�"�Ƃ�����|�̂����肪����܂������A��������������Ȃ���Ȃ�܂���v
�E�u�{���́w�o�C���C�g�x�����Ă��܂��B�c�O�Ȃ����3�y�͂̃z�����E�\���O�̖؊ǂ͉����͓����ł������i�^�Ẵz�����͖{���ɑ�ρj�A�y�͑S�̂�ʂ��Ă݂�����炪�f�R�D��Ă���B4�y�͂̍����̍����̎肪�x��Ȃ��̂��{���ɏՌ��I�I�I���C�u�͂�͂�ҏW���Ă͂��߂Ȃ̂ł��ˁv
�E�u�o�C���C�g�̖{���̑��̘^�������܂����B3���Ē������̂ł����A3��ڂɂ͋�������J������Ċ������܂��~�܂�Ȃ��Ȃ�܂����B���̘^���������̐��E��Y�ɂӂ��킵���Ǝv���܂��v
�@���ǂ݂ɂȂ��Ă�������̂悤�ɉ���̊F�l�̓��e�͂����ȂׂāA�u�Z���^�[�Ձv�������{�ԉ����ŁA�����Ȃꂽ�uEMI�Ձv�Ɗr�ׂ�Ƈ@�I�y�͂̃R�[�_�̍Ōオ����Ȃ��A��3�y�͂��S�̓I�ɂ�����̂ق����D��Ă���B��4�y�͂̍��t�̍����̎肪�x��Ă��Ȃ��E�E�E�ȂǁA���t�I�ɂ��Z���^�[�Ղ��f�R�D��Ă���A�Ƃ����_�|�Ŋт���Ă���B����ɋ����킹�Ȃ������ނ�́A����ǂ݃Z���^�[��CD�����ǂ��"�u�Z���^�[�գ�{�Ԑ�"�ɐ��]����Ă���킯�ł��邩��A�҂��ɑ҂���"�{�ԉ��t"�́u�Z���^�[�Ձv���A�꒮���ĈႤ�uEMI�Ձv�ւ̋^�f�͐[�܂�Ɍ��܂��Ă���B����ȁu�Z���^�[�Ձv���Ċ������Ă������̕��X�ɂƂ��āA�u�Ȃ�ƂȂ��y�������Ă���v�Ƃ͉������Ƃ������ƂɂȂ낤�B�C���Ŕ��f���Ȃ��ł���ƌ����邾�낤�B���������ߕt����Ƃ��͏�I�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u���͂����͊����܂���v�ƌ���ꂽ��c�_�͂����ŏI����Ă��܂�����ł���B
�@��������ނ�̓��e��ǂ�ʼn��߂Ċm�F�ł����̂́A�O���������uEMI�Ձv�R�̔j�]������"�������N���������ɕ�����قǑ傫�����r�����Ȃ̂�"�Ƃ������Ƃł������B1951�N7��29���o�C���C�g�j�Ռ���ɂ����l���uEMI�Ձv���āA�������̌��������C�u�ƈ���Ă����Ȃ�A����͂����ǂ���Ɋ��m����Ă��܂����낤�Ƃ������Ƃ��B�t�ɔނ炪�u�Z���^�[�Ձv���u����͖{�ԉ��t�Ƃ͈Ⴄ�v�Ƒ����Ɍ��������ƂɂȂ邾�낤�B
�@���ю��͂���ɑ�����B�u�w�Z���^�[�Ձx�̉���ł́A"vor Gott"�t�F���}�[�^�����̃N���b�V�F���h��EMI�̐���҂������������̂Ƃ��Ă��邪�A���͂���͂��蓾�Ȃ��Ǝv���B�I�[�P�X�g���ȂŒ����L���ďI���Ƃ��ɂ́A��Ȃ菬�Ȃ�u�ԓI�ɃN���b�V�F���h���ďI��邱�Ƃ��������炾�B������w�Z���^�[�Ձx�̃��n�[�T���ł͌y�������{�Ԃ́wEMI�Ձx�ł̓N���b�V�F���h�����ƍl���Ă��s���R�ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���B�T�E���h�I�ȍl��S��������"���肦�Ȃ��Ǝv��"�Ƃ́A��������I�ɉ߂���B�����ꂽ�����Ɛ��_�ɂȂ��q�ϐ����Ȃ����ꂱ�����肦�Ȃ��B���ю��͂���Ɂu�Z���^�[�ږ�O�R�_����A�t���g���F���O���[�̑��́s���t�^���ɂ��̃N���b�V�F���h�̗Ⴊ�F�߂��Ȃ����Ƃ�"�wEMI�Ձx�̐l�דI����"�̍����Ƃ��Ă��邪�A���t�̈���l������ƁA���̃N���b�V�F���h�͑���i�V�̂��̂ƍl���Ă����������Ȃ��͂����v�Ƒ����Ă��邪�A�킽����"�o�C���C�g�ȊO�ł͂���Ă��Ȃ�����"�Ƃ���O�R���̂ق���"��̂��̂�����"�Ƃ�������镽�ѐ�������ۂljȊw�I�Ő����͂�����Ǝv�������������낤���i���̌��Ɋւ��Ắj�B
�i�Q�j���їѐ��ւ̎^��
�@�u�wEMI�Ձx�����C�u�ƃ��n�[�T���̃~�b�N�X�ՂƎw�E���鐺�͑����̂ɁA��̓I�ɂǂ̕����Ƀn�T�~����ꂽ�̂��̋L�q����������Ȃ��̂͋^�₾�v�Ƃ̂��w�E�ɂ͎����S�������ł���B"�n�T�~�����Ă���"�Ƃ��������F����ɂ͐����̓I�ȉӏ����w�E���ė~�����B�O�R�������R�[�f�B���O�E�v���f���[�T�[��㎁�������肾�B�Ƃ͂����A�c�M�n�M�ӏ������������Ƃ���ŁA���̌��������ۂ����Ă��ĕ����Ȃ���Ε�����Ȃ��悤�Ȕ����Ȃ��̂������炻�ꂪ���R�[�h�ɂƂ��Ĉ�̉����Ƃ����̂��낤���I�ƍߍs�ׂƂł������̂��낤���B�����������R�[�h�Ȃ�Ă���Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��B�u�Z���^�[�Ձv�ɂ����āA��4�y�́u����̉́v�̃e�[�}���O�A��̃t�����F���́u�ԁv�����ɖ��炩�ȉ��ʃA�b�v�̍��Ղ�����ł͂Ȃ����B�uEMI�Ձv�ɂ��ẮA�f�l�̎��ɂ͍��̂Ƃ����2�y��2��50�b������������������c�i�M���ȂƎv������x�ŁA���̑��͑S���F�m�ł��Ă��Ȃ��B�A���T�����ׂ��^���ɕ����܂������邩������Ȃ����A�Ӗ����Ȃ��̂ł��Ȃ������̂͂Ȃ��ł���B
�@���ю��͂��̂��ƁuEMI����LP�v�ɂ܂��p������̂�����ւƐi�ށB�u�A�����J���o��LP�̉���ɂ́A���̉��t�̓n�C�t�@�C�^���ł͂Ȃ������̂ł���܂Ŕ�������邱�Ƃ͂Ȃ������ƋL����Ă���B���̕��͂ł͏ڂ����o�܂͕s���ł�����̂́A�����A�����ɂ������I�Ɏ��^�����悤�ȕ��͋C����������B�܂肱��EMI�����͎��^��Ɏ������A������NG�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��낤���B�����l����ƁA���́wEMI�Ձx�����S���̎�����̃��C�u�ł���̂�������Ȃ��v�B���̎��ؐ��͑f���炵���B�m���ȕ����猩���Ȑ��_�������o���Ă���B�����͗��ΔՋS���тł���B
�@�ނ������悤�ɁA�u�Z���^�[�Ձv�̉����͂����Ȃ闝�R�Ŏ��^�ۊǂ��ꂽ���̂Ȃ̂��ȂǕs���ȓ_�͂܂������c���Ă͂���B���̑��ɂ��Ⴆ�A�u�Z���^�[�Ձv�{�Ԑ��̉F��搶���u���n�[�T���ł͏o�x��Ă��������̍����̎�́A�{�Ԃ́u�Z���^�[�Ձv�ł́A�w���҂̑����݉��炵�����}�ɂ���Ă����Əo�Ă���v�Ƃ������R�|�ŐV���ł̂��w�E��������ƌ�����K�v�����邾�낤�i���͑S���t�̌����ł��邪�j�B�܂��l�b�g��ɂ́A���Ղ̊P�̗L���������ɏƍ����Ă��郌�|�[�g���������肵�āA�������}�j�A�͐����ȂƎv���B�����̏�����A�u���̖��͂܂��܂��n�܂�������v�Ƃ��u�c�_�͂܂��܂����������v�Ƃ��錩�����ނׂȂ邩�ȂƎv�킹��B�����������̖����������͎}�t�ł����Ċ��ł͂Ȃ��B�}�t�̂��Ƃ̓}�j�A�̕��X�ɂ��C�����悤�Ǝv���B�܂��[���ł����ɂǂ����Ă��^����m���߂����Ƃ����l�́A�����ɂȂ��ē������ɂ����l��T���o�������̂ł���B�����������Ȃ��͎̂��̒��ł͂��łɌ��_���o�Ă��邩�炾�B�uEMI�Ձv����1951�N7��29���u�o�C���C�g�̑��v�{�Ԃ̂��܂�����ςłȂ��f��̉����ł���B���R�͂���܂ŏq�ׂĂ����Ƃ���ł���B
�@�ȏ�Łu�o�C���C�g�̑��v�͏I���ɂ��܂��B�Ō�ɁA�l�X�Ȏ�������Ă��������������w����w�̞w�R�y�����A�L���O���R�[�h�̌�������A���̎������傤�ǃo�C���C�g�ɂ��ėL�͂ȏ��������������命�䂳��A���y�]�_�Ƃ̒��J�쏟�p����ɂ͖{���ɂ����b�ɂȂ�܂����B���̏�����肵�Ă����\���グ�܂��B
�@���č���͂��łɁu���v�ɓZ��鎄��"�v����"����������Ă������������Ǝv���܂��B����͂���Ƃ��ӂƑM�������̂ŁA�����ׂ����̂��ƐF�X�g���C�����̂ł������Ǐo���Ȃ��������̂ł��B������v�����ǂ܂�Ȃ̂ł����A���̊��ł͐�ɊԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă��鎖���Ȃ̂ł��B�����炭����͐��E���̌����ł��傤�B���܂ŒN�������Ă���̂������Ƃ�����܂���B���āA�F����͂ǂ��v����ł��傤���B�^�Ă̖�̉ɂԂ��ɂ������t���������������B
�i�R�j�����F���́u���v���q���g�ɂ��Ė���u�{�����v����Ȃ����H
�@�t�����X�ߑ���\�����ȉƃ��[���X�E�����F���i1875�|1937�j�̓o���G���y��5�ȏ����Ă���A���̗L���ȁu�{�����v�͂��̍Ō�̍�i�ł��B�����m�̂悤�ɂ��̋Ȃ́A16���߂Â�2�̃����f�B�[���I�n�ϑt���]�������ꂸ�ɓ����e���|��9�肩������A�ω�����̂͊y��̑g�ݍ��킹�Ɖ��̃_�C�i�~�N�X�݂̂Ƃ������y�ł��B�t���[�g�̃s�A�j�b�V���Ŏn�܂�N�����l�b�g�A�t�@�S�b�g�A�T�L�\�t�H�[���ȂǂɎp����g�ݍ��킳��N���b�V�F���h����čŌ�ɂ̓I�[�P�X�g���S�t�̃t�H���e�V���ŏI���Ƃ����\���ł��B
�@1928�N11���A�p���E�I�y�����ŏ�������Ĉȗ��A�u�{�����v��"���̍\��"�ɂ���Ďj��ނ����Ȃ��a�V�Ŋv���I�ȍ�i�Ƃ���A���̐F�ʓI�ȃI�[�P�X�g���[�V�����̖��͂Ƃ����܂��āA�����F���̑�\��Ƃ��Đl�X�ɐe���܂�Ă��܂��B
�@�����҂Ă�I�Ǝ��͎v���̂ł��B�����̐l�X�ɐe���܂�Ă��閼�ȂƂ������ƂɈق����������͂���܂��A�ʂ����Ė{����"�j��ނ����Ȃ�"�ȂȂ̂ł��傤���B�u���������f�B�[���A�e���|�����Y�������`���ς����A��������B�ς��̂͊y��̑g�ݍ��킹�Ɖ��ʂ����B�s�A�j�V������n�܂��ăt�H���e�V���ŏI���v�A����ȋȂǂ����ŕ��������Ƃ�����܂��H
�@1928�N�̂�����A���x�ƃC�_�E�����r���X�^�C���v�l���A�������x��o���G�ȂƂ��āA�A���x�j�X�́u�C�x���A�v�̕ҋȂ������F���ɈϏ����Ă��܂������A�ʂ̍�ȉƂ����łɍs���Ă��邱�Ƃ��킩��A�I���W�i������邱�Ƃɂ��܂����B�Ƃ��낪�\�z�̒i�K�ŁA�\�肳��Ă����A�����J���t���s�̎���������Ă��Ă��܂��B�����F���͂��̂܂܃A�����J�ɍs���ĉ��t���s���s���听�������߂܂��B�����̋Ȃ͋A������6������10���ɂ����Ă���Ɗ��������܂����B�u�{������̒a���ł��B�������Ă���A�����J���t���s�ɍs���A�����Ă��炵�炭���Ċ��������킯�ł����A���̊ԂȂ��Ȃ��肪���肪���߂Ȃ����������F���͂��Ȃ�Y�ݏł��Ă����͂��ł��B
�@�Ƃ��낪���鎞�t�b�ƑM�����B���ꂪ�u���v�������̂ł͂Ȃ����E�E�E�Ƃ����̂����̍l���ł��B�����F���̓A�����J�Ŏ��ۂɁu���v�����̂��A�����A��̑D�̏�őM�����̂��A����Ƃ��A�����č�Ȃɐ�O�����T���W�����h�����c�ł������̂��E�E�E����͕�����܂��A�v�����郉���F����"�u���v�̗l��"�Ƃ����V�[���ˑR�M�����̂͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���̂ł��B
�@�ł͢��㣂̂ǂ̕������M�����̂ł��傤���B����́u���v�̏I�y�́A�I�[�P�X�g��������̃e�[�}��t�Ŏn�߂�93���ߖڂ���188���߂ɂ����Ă�96���߂ł��B���̕����������炢���Ă݂܂��傤�B�܂��ŏ��̃����E�R�[���X�͒ጷ�����ʼn��t����܂��A�Â�2�R�[���X�ڂŃ��B�I���ƃt�@�S�b�g�������A�R�R�[���X�ڂɂ͂���Ƀ��@�C�I������������Č㔼�N���b�V�F���h�����Ȃ���S�R�[���X�ڂɂȂ���A�Ō�̓I�[�P�X�g���̗͋����S�t�ŏI���܂��B1�R�[���X�͂�������24���߂Â̍��v96���߁A���̊ԃ��Y�����e���|���S���ς�炸�ɁA���ʂ��s�A�m����t�H���e�ɑ�������ē��������f�B�[�����肩�����B�u���v��4��A�u�{�����v��9��Ɖ͈Ⴂ�܂�����@�͑S���ꏏ�ł͂���܂��B
�@�����F���̎�L����ǂ�ł݂Ă��u�{�����v�́u���v���Q�l�ɂ����ȂǂƂ����L�q�͂ǂ��ɂ���������܂���B�|�p�Ƃ͎햾�����͂�������Ȃ����̂����A�����F���̐S�̒��ŋN���������Ƃ䂦����͉i���ɏؖ�����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�ł����͊m�M�������Ēf���ł��܂��B"�����F���́u���v���q���g�ɂ��āu�{�����v�������"�ƁB
�@��{�I�ɂ͓����\���́u�{�����v�Ɓu���v�ł�����̈Ⴂ������܂��B���������āA���̕������u���v�Ɉ���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂��B����1�A�u���v�͈�̃e�[�}�̌J��Ԃ��ł����u�{�����v��2�̐����������Ă��܂��B����́u���v�̑�3�y�͂Ɠ����ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B��3�y�͕͂ϑt�Ȍ`���ł��B���ʕϑt�Ȃ̃e�[�}�͈�Ƒ���͌��܂��Ă��܂����A�x�[�g�[���F���́u���v��3�y�͂ɓ�̃e�[�}��p���܂����B�����F�����u�{�����v���Q�����f�B�[�X�^�C���ɂ����̂͑�3�y�͂��q���g�������̂ł͂Ȃ����H ����2�A�u���v�͋ȓr���ł����A�u�{�����v�͒P��y�ȂȂ̂ŏI��点�Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��ߏI�������t���Ă��܂��B���̏I�����͂܂�ʼn�������������悤�ɕs���a���I�ɓ]�����ďI���̂ł����A���̋����A�u���v�I�y�͖`���̃U���U�������s���a���I�����ƃR�[�_�̋����I�A�b�`�F�����h�ɒʂ��Ă���悤�Ɏv����̂ł��B����قǂ܂łɁu�{�����v�Ɓu���v�͎��ʂ��Ă���B�������������{�\�������ł͂Ȃ��l�X�ȃA�C�f�B�A���u���v����q���Ė��ȁu�{�����v��n��o�����̂�������܂���B
�@���y�͗��j�ƂƂ��ɗ���Ă��܂��B�݂��Ɋ֘A�������Ȃ��玟�̎���Ɉ����p����Ă䂫�܂��B���Ȃ͖��Ȃ݁A���ȂƖ��Ȃ͌����Ȃ����Ōq�����Ă���̂ł��B���̂悤�Ȍ����Ȃ����������Ȃ�ɒT�������̂��N���V�b�N���y�̊y���݂̂ЂƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�z���ɉ߂��Ȃ���v�ƌ����悤�Ƃ��B
2008.08.04 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂Q
�i�P�j�Z���^�[�Ձu�o�C���C�g�̑��v�@�u�t���g���F���O���[�E�Z���^�[�v�͐��I�̑�w���҃E�B���w�����E�t���g���F���O���[�̌|�p��������l�����ō\�����ꂽ���{�ɂ�����I�t�B�V�����ȉ���g�D�ł���i�t���g���F���O���[���S�l�����_��j�B�����ɂ��̉�ł��钆�����s�������R�[�h�|�p2007�N9�����Ɋ���L������B�������͂��̒��ŁA�u1951�N7��29���w�o�C���C�g�̑��x����������o�C�G���������ǂɁA�{�������̂��̂����^�����e�[�v�����݂��Ă����B������m�F�������Z���^�[�́A�����̌��̖��ɂ��̉�����CD��������������Еz���\�Ƃ����B���t�͂���܂ŗB��Ƃ���Ă����wEMI�Ձx�Ƃ͖��炩�Ɉ���Ă���A�o�C���C�g���y�Ղ̋L�O��I�ȍĊJ�ɂӂ��킵���t���g���F���O���[�̑�㉉�t�j�̒��ł��ŏ�̂��̂ł���v�Əq�ׂĂ���B�����čŌ�Ɂu���e�[�v�̔��ɂ�"1951�N�o�C���C�g���y�ՍĊJ�����̋L�^�A�^����29�D7�D51"�Ɩ��L����Ă���B�܂��A���̕ʂ̉ӏ��ɂ�"���Ƃ������I�ɂł������Ɏg�p���邱�Ƃ͋֎~"�Ƃ�������������v�ƋL�q���Ă���B"�����g�p�֎~"�̈Ӗ��͓�Ƃ��Ȃ���A�ŏI�I�ɁA���ꂱ���u�o�C���C�g�̑��v�{�����̐^�����C�u�����ł���ƌ��_���Ă���B����Ɂu���肪�������ƂɁA�y�͊Ԃ��ꕔ�^������Ă���A��3�y�͊J�n�O�ɉ̎肽���̓��ꂷ�鑫������������v�Ƃ����A������u�Z���^�[�Ձv���{�ԃ��C�u�����̏ł���Ƃ��镶�������邪�A�{���ɂ����Ă��ꂪ�^���𖾂̃L�C�|�C���g�ƂȂ�̂ł�������Ƃ��L���肢�����B
�@���������R�[�h�|�p9�����ɂ̓Z���^�[�ږ�E�O�R�_��̕��͂��f�ڂ���Ă���B����͒������̌�����O��Ƃ���2�̔Ղ̑���_�����ׂ����q�ׂ��Ă���A�u�Z���^�[�Ձv�����{�ԉ����ł���Ɗm�M�������Č������Ă���B�u�꒮���ĕʉ��t�Ȃ͖̂��炩�ŁA�wEMI�Ձx�ɂ����4�y�͍����̏o�̕s�����́w�Z���^�[�Ձx�ɂ͂Ȃ��B�wEMI�Ձx�́A�����ɋꂵ�ރ_�C�i�~�b�N�����W�̕ϓ��i"vor Gott"�����j�A��R�Ƃ����e�[�v�ҏW�̍��Ձi�M�Ғ��F��̓I�ɂ͎�����Ă��Ȃ��j�A���t��̔��肪�p�Ռn�ƓƔՌn�ňႤ���ƁA�Ȃǂ���wEMI�Ձx�͖{�����ƃ��n�[�T���E�e�[�v���Ȃ������ɂ����n�C�u���b�g�Ղł���ƍl������B�o�C���C�g���y�Ղ̐�㕜���̎��Ӗ��A�����ĉ������t���g���F���O���[���g�����̍ĊJ�̃X�e�[�W�őS������߂��ł��낤�S���E�Ɍ��������b�Z�[�W�A�����̑S�Ă��ō��x�ɋÏk���ꂽ�̂��w�o�C���C�g�̑��x�ł���A���̐^�̎p��`������̂����Ȃ�ʁw�Z���^�[�Ձx���Ƃ�����B����w�Z���^�[�Ձx���w�o�C���C�g�̑��x���w���A�Ƃ����_�ł͑���̓��ӂ���������̂Ɗm�M���鎟�悾�v�Əq�ׂĂ���B
�@����ɍd�h�̃N���V�b�N��厏�u�N���V�b�N�W���[�i��027���v�ɎR��_���Y����CD�]������B�����ɂ́u�w�Z���^�[�Ձx�́A��3�y�͂̑�3���ߖڂŏo���1���@�C�I�����������o�Ă��܂����A�wEMI�Ձx�͐������o�Ă���B��4�y�͂�"vor Gott"�̍Ō�ɁwEMI�Ձx�̓N���b�V�F���h��������Ȃǂ���A�wEMI�Ձx�͓����̖{�Ԃ��̂܂܂ł͂Ȃ����n�[�T���ȂǕʉ�����}���ҏW����"�����ϔ�"���ƍl������v�Ƃ���B
�@�ȏ�3�̕��͂�"�u�Z���^�[�Ձv�����{�ԉ����ł���"�Ƃ����O��ŏ�����Ă���B�u�����炱��Ɩ��炩�ɈႤ�wEMI�Ձx�͉\�ǂ���̃n�C�u���b�h�Ղ������B�ق畷���Ă����A���̕����͓��������ǂ��̕����͖��炩�ɈႤ�ł���v����ȁuEMI�Ձv�̂���{���I�l����悵�Ă���̂ł���B�߂������ȁuEMI�Ձv�ł���B�����ʂ����Ă����Ȃ̂��낤���H
�@�Z���^�[���̘_���́A�u�w�Z���^�[�Ձx�����o�C�G�������������ۂɕ����Ɏg�����{�ԃ��C�u�̉����ł���B�Ȃ��Ȃ甭�����ꂽ�e�[�v�ɂ́�1951�N�o�C���C�g���y�ՍĊJ�����̋L�^�A�^����7��29�����Ɩ��L����Ă��邩��ł���v�Ƃ����Œ�ϔO����o�����Ă���B�Z���^�[��CD�̉�����ɂ́A���̃e�[�v�̑��݂�˂��~�߂��o�C�G�����B���ǂ̃`�F���X�g�A�o�C�G���������̃A�[�J�C�u�S���ҁA�t���g���F���O���[�E�Z���^�[�3���̕��͂��ڂ��Ă���B�S�āu�Z���^�[�Ձv�����{�ԃ��C�u�ŁuEMI�Ձv�͉\�ǂ����"�����ϔ�"�Ƃ����_���ň�т��Ă���B�����̕��͂�ǂl�͏\�����ケ�ꂱ���{�ԃ��C�u�����ł���Ɛ��]����Ă��܂����낤�i���͎��������ł����j�B�������o�C�G���������A�[�J�C�u�ɖ����Ă��������́A1951�N7��29���̓��������p���ꂽ�{�ԉ������Ƃ����m�͂ǂ��ɂ��Ȃ����A���̂��O���͂��̓��o�C���C�g�j�Ռ���̌���ɂ����킯�ł͂Ȃ��A���̃��W�I���p�����킯�ł��Ȃ��̂��B
�@�ނ�̍����́A�o�C�G�����������u�o�C���C�g�̑��v���t�𒆌p�����Ƃ��������Ɓu�e�[�v�ɋL�ڂ��ꂽ�����v�̓�ł���B�������������ɏ����Ă���"�����g�p�֎~"�Ƃ��������͕s��ɕt���Ă���B�����́A���x���̕����̐M�т傤�����m���߂�ׂ������Ɠ˂����ނׂ��ł͂Ȃ��������B���ʂ����Ŋ����̉��l�ς����ꂩ��ς��悤�Ƃ����̂͂����������Չ߂��͂��Ȃ����B����͗��j�ɑ��Ď���Ƃ��킴��Ȃ��B�Ȃ�Ύ������́u�Z���^�[�Ղ����{�ԉ����ł���v�Ƃ����ނ�̎咣��O��I�ɕ����Ă�낤�Ǝv���̂ł���B�ȉ��͂��̏ؖ��ł��邪�A����ɂ̓��R�[�h�|�p9�������q���u���̊�e���u�o�C���C�g�́s��9�t�V�����������������V���ȋ^��v���傢�ɎQ�l�ƂȂ������Ƃ����f�肵�Ă��������B
�i�Q�j�ǂ��炪�u�{�ԁv�Ȃ̂�
�@�{�ԃ��C�u�������ۂ�������Â�����@�͈�����Ȃ��B����́A1951�N7��29���ߌ�8������2���Ԃقǂ̊ԁA�h�C�c�A�o�C�G�����B�o�C���C�g�ɂ���o�C���C�g�j�Ռ���ŁA�E�B���w�����E�t���g���F���O���[�w���F�o�C���C�g�j�Պnj��y�c�������c�A�G���[�U�x�g�E�V�������c�R�b�v�i�\�v���m�j�A�G���[�U�x�g�E�w���Q���i�A���g�j�A�n���X�E�z�b�v�i�e�m�[���j�A�I�b�g�[�E�G�[�f���}���i�o�X�j�̏��ɂ��A���[�g���B�q�E���@���E�x�[�g�[���F����ȁF�����ȑ�X�ԃj�Z���u�����v���t�̏�ɋ����킹���l�Ⴕ���͉��t�ғ��l�ɁA�uEMI�Ձv�Ɓu�Z���^�[�Ձv���Ă��炢�A�ǂ��炪���̓��̃��C�u���t�Ȃ̂��肵�Ă��炤���Ƃł���B��̉��������ʂ��Ă���Ȃ�Ƃ������A�uEMI�Ձv�ɂ͗�R����j�]���������Ȃ��Ƃ��R�ӏ��͂����āA�u�Z���^�[�Ձv�Ƃ̎��ʂ��������ėe�Ղł��邽�߁A����炢�͊m���ɏƍ��ł���͂��ł���B�����ł��́uEMI�Ձv�̔j�]�������m�F���Ă������B
�@�@��4�y�̓R�[�_�̍Ō�ŁA�I�[�P�X�g������������w���҂̃e���|�ɂ��Ă䂯���A�A���T���u���𗐂����������ɂȂ��Ē��n����
�A�@��3�y��83���߁\98���߂̃z�������f�l�݂����Ƀ��������ɗ���Ă���
�B�@��4�y�́A�o���g���Ɍĉ����ďo�鍇���̉̂��o��"Freude"�����S�ɒx����Ƃ��Ă���
�@�������̏�ɋ����킹���l�≉�t�ғ��l���A�����ɂ��̏�Ɉ�������o�����Ƃ͕s�\�Ȃ̂ŁA"�ނ炪�uEMI�Ձv������ǂ��������邩"�𐄑����邱�Ƃŏؖ��ɑウ�����Ǝv���B
�@�uEMI�Ձv��1955�N�ɑS���E�Ń��R�[�h�������ꂽ�B���̋L�O��I���t��ɎQ�������قƂ�ǂ̉��t�҂⒮�O�͊ԈႢ�Ȃ����̃��R�[�h�ɊS������͂��ł���B���̂����̑命���̐l�����̢EMI�գ�������낤���Ƃ͋^��̗]�n���Ȃ��B���C�u����܂�4�N�����o���Ă��Ȃ��̂�����L��������邱�Ƃ��Ȃ����낤�B����3�ӏ����j�]�̂Ȃ��u�Z���^�[�Ձv���{�ԃ��C�u�������Ƃ����Ȃ�A�������ꂽ�uEMI�Ձv�����Q���҂͂ǂ������������������낤���B
�@�H���A�@�I�y�͍Ō�̂��̃��`���N�`���ȗ�����͂ȂI�A��3�y�͂̃z�����̊O�������͂܂�łǑf�l�݂������B�����̉̂��o��"Freude"�̏o�x��͂ǂ�����������́E�E�E���ꂪ���t�҂�������u�������͖{�Ԃł���ȕ��ɉ������Ⴂ�Ȃ��v�A���O��������u���̎��̉��t�͂���ȂЂǂ�����Ȃ������v�ƌ������낤�B3�ӏ��S���łȂ��Ƃ��A���Ȃ��Ƃ��P�ӏ����炢�͊ԈႢ�Ȃ��o���Ă���͂����B�o�C���C�g�j�Ռ���̃L���p��1925�l�ł���B�Ȃ���̎��ɂ͊ԈႢ�Ȃ�2000�l����l�X�������̂ł���B���̏ケ��͂��傻����̃��C�u�ł͂Ȃ��B�Ȃ�Ƃ��������āuEMI�Ձv�͐��E�̉��y�t�@�����҂��]�L�O��I���t��̃��R�[�f�B���O�Ȃ̂ł���B�^�����₳���ɖS���Ȃ��Ă��܂����Ǝv���Ă����t�����F���E�t�@�����҂��ɑ҂����u���v�Ȃ̂ł���B�N�����o�Ă����̕]���͗�����ǂ��납�~�܂邱�Ƃ�m��Ȃ����ՂȂ̂ł���B������R�[�h�j������߂��B�ꖳ��̋������Ȃ̂ł���B����ȒN�����m���Ă���N�����S�̂���uEMI�Ձv���A���������ۂ̃��C�u���t�ƈ���Ă����Ƃ����Ȃ�A����܂łɊe���ʂ��狊�e�̐����������Ă��Ȃ�����������̂ł���B�uEMI�Ձv�����r���炯�̂��̂����ɁB
�i�R�j�����E�H���^�[�E���b�O�͉��������̂�
�@�E�H���^�[�E���b�O�̓N���V�b�N�E���R�[�h�E�Ɍ��ꂽ�^�̈Ӗ��ōŏ��̃��R�[�f�B���O�E�v���f���[�T�[�ł���B����܂ł͒P�Ȃ錻��̗���l�ł����Ȃ��������̒n�ʂ���ς������l���ł���B���t�͏o���Ȃ��Ƃ����y�̉����邩�����Ă����ނ́A�������R�[�h���EMI�̒��S�I�v���f���[�T�[�Ƃ��Ęr��U������B���y�ɑ���s�����@�͂Ǝ��M���琶�܂�鉟���̋����͂��̃g�X�J�j�[�j�̐M�����l������قǂ������B�ނ��v���f���[�X�����V���i�[�x���̃x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^�S�W�A�J�U���X�̂i�D�r�D�o�b�n�F�����t�`�F���g�ȑS�ȁA�d�E�t�B�b�V���[�̂i�D�r�D�o�b�n�F���ϗ��N�����B�[�A�ȏW�S�ȁA�M�[�[�L���O�̃��[�c�@���g�E�s�A�m���y�S�W�A�t���g���F���O���[�̃x�[�g�[���F���A���[�O�i�[�A�u���[���X�A�N�����y���[�ӔN�̃Z�b�V�����A�}���A�E�J���X�A�N���C�X���[�A�f�B�k�E���p�b�e�B�Ȃǂ̃��R�[�f�B���O�́A���݂��s�ł̖��ՂƂ��Ă��̉��l�������Ă͂��Ȃ��B���ɃJ�������Ƃ̐e���͌����A�i�`�X�}���������J����������ト�[���b�p�S�y�ʼn��t�������ł��Ȃ����������ɁA����n�݂����t�B���n�[���j�A�nj��y�c�����Ă����Ċ����̃��R�[�f�B���O�@�����Ă���B���݂ɖ��\�v���m�A�G���[�U�x�g�E�V�������c�R�b�v�͔ނ̉�����ł���B
�@����ȃ��b�O������d�l�h���R�[�f�B���O�E�`�[�������́u�o�C���C�g�̑��v�����R�[�f�B���O���A����4�N��Ƀ��R�[�h���������̂ł���B���̉ߒ��𐧍�҂̐S���ʂ���l�@���Ă݂�B�܂�EMI���b�O�E�`�[���������̉����������Ă���A���͂�����"�����ϔ�"�����Ɖ��肷��B�����Ɂu�{�ԉ����v�Ɓu���n�[�T�������v������Ƃ���B�t�@�[�X�g�E�`���C�X��"�j�]�̂Ȃ��{�ԉ���"�Ɍ��܂��Ă���B����"�j�]�����{�ԉ���"��"�j�]�̂Ȃ����n�[�T������"������ŁA��Ƀ`���C�X���Ȃ��̂�"�j�]�������n�[�T������"�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B�ł́A���ۂ̔j�]�����@�I�[�P�X�g�������������ɂȂ��Ē��n�����4�y�̓R�[�_�̍Ō�����͂�����Ƃ��悤�B�����j�]�̂Ȃ��u�Z���^�[�����v���{�ԉ����ŁA���������́uEMI�����v�����n�[�T���̂��̂��Ƃ����Ȃ�A�v���f���[�T�[�͂ǂ����I�Ԃ��낤���B"�j�]�̂Ȃ��{�ԉ���"��I�ԂɌ��܂��Ă���B���ۂɑI�̂̓��������̉����Ȃ̂�����A�j�]�̂Ȃ��u�Z���^�[�����v�͖{�ԉ����ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���b�O�͔j�]���Ă��Ă��{�ԉ�����I�̂ł���B�Ȃ�"�j�]�̂Ȃ����n�[�T������"�i�u�Z���^�[�����v�j��I�Ȃ������̂��B����̓Z���^�[�����������Ă��Ȃ��������A���C���Ȃ��������A�Z�p�I�ɕs�\���������A�ǂ�����r�����낤���{�ԉ�����D�悷�ׂ��Ƃ����|���V�[�������Ă������̂����ꂩ���낤�i������������S����������������Ȃ����j�B����Ȃ��Ƃ𐄎@���Ă����܂�Ӗ��͂Ȃ��Ǝv�����A���́u���C���Ȃ��������v���Ƃ�B
�@���R�́A���b�O�͂��̉��t���Ă��Ȃ������߂����邩��ł���B�u�J�������ƃt���g���F���O���[�v�i����E��A���~�ɐV���j�ɂ��ƁA�R���T�[�g���I����Ċy����K�ꂽ���b�O�̓t���g���F���O���[�Ɍ������āu�悢���t�ł������A���҂����قǂł͂���܂���ł����v�ƌ������Ƃ����B�����Ɍ������āu���҂����قǂł͂Ȃ������v�Ƃ́A�����̃��b�O�̐�������Ă��邪�A�{�S�łȂ���Ώo��͂����Ȃ��Z���t�ł���B���Ȃ��Ƃ����b�O�͂��̉��t���C�ɓ����Ă͂��Ȃ������B���������X�o�C���C�g�̓t���g���F���O���[���E�B�[���E�t�B���Ői�s���������X�^�W�I�^���̌����ȑS�W�̂��߂̎����^�肭�炢�ɂ����l���Ă��Ȃ������Ƃ������Ă���B�Ƃ��낪1954�N11���w���҂̎��ɂ���đS�W�͊��������ɏI����Ă��܂��i���̎��_�Ř^�����I�����Ă����̂͂P�C�R�|�V�Ԃ�6�Ȃ����ł���j�B�u�o�C���C�g�̑��v�����R�[�h�����Ă������ȑS�W�͊������Ȃ����A�t�@���̗v�]�ɉ����ĂƂ肠�����o���Ă������ƍl�����̂��낤�B�����烌�R�[�f�B���O����4�N�A�������S���Ȃ��Ă����1�N�������Ă���ƃ����[�X����Ă���̂��B�����ケ��Ȃɔ������ĂԂƂ͖��ɂ��v�킸�ɁB
�@����J�������Ƃ̑S�W��1952�N�ɃX�^�[�g�������Ɋ����Ɍ������Đi��ł����B������1955�N7���ɂ́u���v�����R�[�f�B���O���ꂽ�B���t��EMI�̃G�[�X�E�I�P�ł���t�B���n�[���j�A�nj��y�c�A�Ə��҂̓V�������c�R�b�v�i�\�v���m�j�A�w�t�Q���i�A���g�j�A�w�t���K�[�i�e�m�[���j�A�G�[�f���}���i�o�X�j�Ƃ��������C���E�A�b�v�ł���B�w���҂�����ł��܂����u�o�C���C�g�̑��v�Ǝ���̒S����J�������ŐV�^���́u���v�A���b�O���ǂ���́u���v�ւ̎v�����ꂪ�����������ȂǁA�����܂ł��Ȃ����Ƃ��B�t���g���F���O���[�̌���ăx�������E�t�B���̉��y�ēɂȂ����J�������̃x�������E�t�B���Ƃ̃��R�[�f�B���O�̓h�C�c�E�O�����t�H���̌����ł��邽�߁AEMI�ꑮ�ō��̉̎�w��z���āu���v���܂ރx�[�g�[���F���̌����ȑS�W�̌���Ղ��c���Ă��������Ƃ����C���������������ɈႢ�Ȃ��B������ɂ��Ă��S�̒���"�J�������ŐV�^���̑��"�ň�t�������낤�B�����̏���A�����ς��ׂ����̎����ɁA���b�O�́u�o�C���C�g�̑��v�ȂNJᒆ�ɂȂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�ނ̉�z�^�u���R�[�h����E�����āv�ɂ́u�o�C���C�g�̑��v�Ɋւ���L�q���قƂ�ǂȂ��̂����̗��Â��ƂȂ낤�B�������Ƃ���A"�uEMI�Ձv�͂��͂����������ϔ�"�Ȃ��ƍJ�Ԃ�����悤�Ȗʓ|�ȍ�Ƃ�ނ͖{���ɂ����̂��낤���B���ɂ�����Ƃ��Ă��A�N�����꒮���ĕ����邱�̔j�]�ӏ��@�|�B�����̂܂܂ɂ��Ă����đ��̕����������ς���ȂǂƂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��̂ł���B����ȏ�̔j�]���������ɂ���Ƃ͂ǂ����Ă��v���Ȃ��̂ł���B����قǂ��̔j�]�x�����͑傫���̂��B�����玄��"�uEMI�Ձv�����ϔՐ�"�ɂ����ӂ��Ȃ��B��ӏ��������āB
�@���̈�ӏ��Ƃ͑�4�y��330���ߖ�" Gott"�̃t�F���}�[�^�Ō���̋}���ȃN���b�V�F���h�̂��Ƃł���B���̕����A�g�����y�b�g�ƍ����������X�e�b�v�ő�������Ă���悤�ɕ�������B2�ȏ�̊y��i���j���N���b�V�F���h����ꍇ�A���ʓI�ɓ����x�����ő��������P�[�X�͋H�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�l�Ԃ���邱�ƂȂ̂�����e�X�̓x�����ɔ����ȍ��ق��ł�ق������R�Ƃ������̂��낤�B�Ƃ��낪�uEMI�Ձv�̂��̕����́A�S�Ẳ��������x������"�@�B�I��"��������Ă䂭�悤�ɕ�������B���x�����Ă�������������B������20��ދ߂�����t�����F���́u���v�ɂ����āA���̕����ɃN���b�V�F���h�������鉉�t��́uEMI�Ձv�������đ��ɂ͂Ȃ��B���������āA�����̓��b�O���d�C�I�ɏ������{�����ƍl����̂��������낤�B9�D09�b�̃t�F���}�[�^�̍Ō�̕����Ń{�����[���܂݂����Ƃ����l�����Ȃ��̂ł���B
�@�u�o�C���C�g�̑��v��債�ĕ]�������A���͂���Ƃ��ʓ|���������Ă����i�Ǝv����j���b�O���Ȃ�����ȗ]�v�Ȃ��Ƃ������̂��낤���B��Ƃ��������悤���Ȃ��B���������̃N���b�V�F���h�́A�������낤�ɔ�����A�����I�Ȗ����t�̏Ƃ��Č��p����邱�ƂɂȂ�̂ł���B��䏊�F����F�����u"vor Gott"�̃t�F���}�[�^��EMI�Ղ͍Ō�ɃN���b�V�F���h�������邪�A������l�͍D�����v�Əq�ׂĂ����邵�A���q���u���͍��Z���̂Ƃ��ɕ��������̕������u"vor Gott"�̉i���ɑ����Ƃ��Ƃ��v����t�F���}�[�^�͏Ռ��I�������v�ƖY�ꂦ�ʈ�ۂƂ��Č���Ă���B�ߍ��Ȃ邩�ȃ��b�O�ł���B�����������q���u���̓��R�[�h�|�p2007�N10�����ł��������Ă���u�wEMI�Ձx330���߃t�F���}�[�^�������p�\�R������ȂǂŃN���b�V�F���h�̓d�C�t���I��������菜�����Ƃ��Ă��A�g�����y�b�g�̋��x�Ȑ��t�����Ƃ������ʂ͑S�Ă̊��o�Ղɗ����̂ł͂Ȃ��v�B����Ȑl�דI�ȃN���b�V�F���h���Ȃ������āA����Ȃ��ق����Ȃ�����A�w���҂̈Ӑ}����g�����y�b�^�[�̋��x�ȓ��肪���Ȋ������ĂыN�������͂��Ȃ̂��Ɣނ͌����Ă���̂ł���B���b�O����A���Ȃ��͈�̉��̂��߂Ƀ{�����[���܂݂���������̂ł����A�㐢�̐l�����ɂ���Ȗʓ|�Ȃ��Ƃ��l�������Ȃ��ł��������ȂƎ��͌��������B
�i�S�j����ɂ�����́u�o�C���C�g�̑��v
�@�����čŌ�ɂƂ��Ă����̏؋������o�����Ă������������B����A�����������4�K�ɂ��鉹�y�������Ő̂̎��������Ă����Ƃ��̂��ƁB���R�[�h�|�p1955�N2�����ɁA�C�O���y���@���s����A��������̋g�c�G�a���i����41�j�Ƒ��c���Y���Ƃ̑Βk���������B����33�`35�ł̈ꕔ�����Ă݂�B
���c�@�ł̓t���g���F���O���[�́u���v�̂��b�����Ă�������
�g�c�@�u���v�̓o�C���C�g�Œ����܂���
���c�@�\���͂��ꂪ���܂�����
�g�c�@�����ƁA�e�i�[�̓��B���g�K�b�Z���A�o���g���̓��[�h���B�q�E�E�F�[�o�[�Ƃ����l�ŁA�\�v���m�̓O���E�u���[�E�F���X�e�C���Ƃ����I�����_�l�A�A���g�̓C���E�}���j�E�N�ł�
���c�@����Ŋy�͂̒u�����A��ڂ́A���{�Ɠ����悤�ɂ��̂ł���
�g�c�@2�y�͂�3�y�͂̊Ԃ͏������������ł��ˁB���̂ق��͂���Ȃɒ����x�܂Ȃ�
���c�@�����ł����B����ƓƏ��҂��������S�����߂���o�����ł���
�g�c�@�����A���߂���ł�
�@����͋g�c���̘b����A1954�N8��9���o�C���C�g�j�Ռ���ōs��ꂽ���t��ł���Ɠ���ł���B���Ȃ킿���́u�o�C���C�g�̑��v����3�N��A�����o�C���C�g�j�Ռ���ōs��ꂽ�u���v�Ȃ̂ł���i���̉��t��MUSIC&ARTS����CD��������Ă���A�O���̃��n�[�T�����i�̓t���g���F���O���[�E�Z���^�[����Еz�A�C�e���Ƃ���CD������Ă���j�B����ɂ�����́u�o�C���C�g�̑��v���������̂ł���B�������C�Â����낤�A���̘b����A���̃X�e�\�W�ł͓Ə��҂��������n�߂���X�e�[�W�ɏo�������Ȃ̂ł���B3�N�O�Ń\���X�g���Ⴄ�Ƃ͂����A�ŔӔN�̃t���g���F���O���[�������V�`�F�[�V�����ɂ����āA����\����̏d�v������ύX����Ƃ͂܂��l�����Ȃ��B����������1951�N7��29���̃o�C���C�g�ł�"�Ə��҂ƍ����͎n�߂���o������������"�ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B�����Ŗ{���`���̃t���g���F���O���[�E�Z���^�[��������s���̕��͂��v���o���Ă������������B�u���肪�������ƂɁA�y�͊Ԃ��ꕔ�^������Ă���A��3�y�͊J�n�O�ɉ̎肽���̓��ꂷ�鑫������������v�Ƃ������e�̕��͂ł���B�����u�Z���^�[�Ձv�ł͑�3�y�͊J�n�O�ɁA"�̎肽���������Ă���"�̂ł���B����Ȣ�Z���^�[�գ�́A���߂���o�������ł���͂��̖{�Ԃł͂Ȃ����ƂɂȂ�B�r����������Ă����̂����烊�n�[�T���������̓Q�l�v�����Ƃ������ƂɂȂ�B��݂�����̌��ł��邱��"���肪��������"���A����ɂ�"�u�Z���^�[�Ձv�͖{�Ԃɂ��炸"���ؖ����Ă��܂����̂ł���B�Ȃ���ʔ������ꂽORFEO�Ղɂ͂��̑�3�y�͑O�́u�ԁv�͍폜����Ă���B�܂��u�Z���^�[�Ձv�ɂ͔��肪�����Ă��Ȃ��B���炭���e�[�v�ɂ������Ă��Ȃ��̂��낤�B�{�ԃ��C�u�̕��������Ȃ畁�ʔ���̓J�b�g�����ɕ�������Ǝv���邪�ǂ����낤���B
�@���_��\���グ��B�u�Z���^�[�Ձv�́u�o�C���C�g�̑��v�{�ԉ����ł͂Ȃ��B�Q�l�v�������n�[�T���̉����ł���B�����̂Ƃ��̂��߂Ɏ��^�E�ۊǂ��Ă������o�b�N�E�A�b�v�����Ȃ̂��낤�B�e�[�v���ɏ����ꂽ"���Ƃ������I�ɂł������Ɏg�p���邱�Ƃ͋֎~"�̈Ӗ��͂����������Ƃ������̂ł͂Ȃ����B���肪�Ȃ��̂��s���ȍޗ��ł���B2007�N9�����s�́��t���g���F���O���[�E�Z���^�[����P�T�����ɁuEMI�Ղ��{�ԂŃZ���^�[�Ղ̓��n�[�T���Ǝv����Ƃ���"����"�܂Ŕ�яo���Ă��Ă��܂����E�E�E�v�Ƃ��邪�A����͒����ł͂Ȃ���"�^��"�������̂ł���B
�@�uEMI�Ձv�������㐔�X�̋^�f���Ă̂́A���̗��j�I���C�u�̃��R�[�f�B���O�����b�O������EMI�^���`�[���̂��̎��̃v���C�I���e�B�Ɩ��ł͂Ȃ��������ƂƉ��t�ɂ͋Z�p�I�Ȕj�]���������Ȃ��炸���������ƂȂǂ���A���R�[�f�B���O��4�N�ȏ���������Ȃ��������ƁA��4�y��329�|330���߂�"vor Gott"�ɂȂ����d�C�I�l�דI�ȃN���b�V�F���h��t�����Ă��܂������ƁA�Տꊴ���o�����߂��o���Δ����ɂȂ��Ă��܂������߂��͂��Ă����A����⑫���Ȃǂ�SE�I�T�E���h��t�����Ċg����}�������ƁA�Ȃǂɂ��̂��낤�B�uEMI�Ձv�́A"�����ϔ�"��������Ȃ����A�قƂ�ǂ̕�����{�ԉ����ō��グ�����K�̃��R�[�h�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł���B
�@�u��̃o�C���C�g�̑��v�͂���ŏI���\��ł������A���T������x��点�Ă����������Ƃɂ������܂��B���R�̓��R�[�h�|�p�ŐV���ɁA�u���ђ��Ǝ���"ORFEO�����Ղ̉��"�̒��ŁA�w�Z���^�[�Ձx���n�[�T�����������Ă���v�Ƃ��������������ł��BORFEO�Ղ͗A���Ղ��������Ă��炸�A�����Ղ̉���͓ǂ�ł��Ȃ��������߁A�ނ̘_�|��m�炸���Ă��̂܂��̘b���I���ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��Ǝv��������ł���܂��B����ł͗��T�A�u��̃o�C���C�g�̑��v�G�s���[�O�Ƒ肵�A���ѐ��̌��𒆐S�ɏ������Ă��������܂��B�ł͎���8��11�����ǂ������y���݂ɁB
2008.07.29 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂P
�i�P�j�����I ������́u�o�C���C�g�̑��v�@��N�āA���̗��j�I����EMI�̃t���g���F���O���[�u�o�C���C�g�̑��v�ɑ�"���ꂱ�����^���̃��C�u����"�Ƃ����ʃe�C�N�������h�C�c�̃o�C�G���������ǂŔ������ꂽ�Ƃ����j���[�X�����ꂽ�B�E�B���w�����E�t���g���F���O���[�i1886�|1954�j��20���I���\���閼�w���҂̂ЂƂ�B���Ƀx�[�g�[���F���A���[�O�i�[�A�u���[���X�A���q�����g�E�V���g���E�X�Ȃǃh�C�c�{���̉��t�ɂ����Ă͉E�ɏo����̂͂��Ȃ��Ƃ����A����50�N�ȏ�o���������ł������Ȃ��l�C���ێ���������H�L�Ȃ��w���҂ł���B�u�o�C���C�g�̑��v�Ƃ����̂́A1951�N7��29���Ƀt���g���F���O���[�����[�O�i�[�̐��n�o�C���C�g�Ŏw�������x�[�g�[���F�������ȑ�X�Ԃ̉��t�̒ʏ́B���̃��C�u�E���R�[�f�B���O��1955�N11���A�d�l�h���烌�R�[�h���������Ɣ����I�l�C���ĂсA�ȗ����j�I�����t�Ƃ��Ė��Ղ̖����ق����܂܂ɂ��Ă���B���������āA���̢�o�C���C�g�̑�㣂ɑ������炱�����{�ԂƂ����꒮���ĕʃe�C�N�ƕ����鉹�����������ꂽ�Ƃ����̂�����A�N���V�b�N���D�ƂɂƂ��ďՌ��I�łȂ��킯���Ȃ��B���̉����͍ŏ��t���g���F���O���[�E�Z���^�[�̉������CD�Ƃ��ĔЕz���ꂽ���A���N�ɂȂ���ORFEO�������ʔ�������A�N�ł�����ł���悤�ɂȂ����B���̎��_�Ő��Ԃɂ͂Q�́u�o�C���C�g�̑��v�����݂��邱�ƂɂȂ����̂ł������ʂ��ČĂԕK�v�����������B�J�ԁA�]���̔Ղ��uEMI�Ձv�A�V���ɔ��@���ꂽ�������u�Z���^�[�Ձv�ƌĂ�ł���̂ł����ł�����ɏ]�����B
�@2007�N7��26���A�����V���[���Ɂu�Z���^�[�Ձv�̏Љ�L�����f�ڂ����ƁA8��3���ɓ��{�o�ϐV���A���̌ヌ�R�[�h�|�p9�C10�C11�����A�N���V�b�N�W���[�i��027���Ȃǂł����X�Ǝ��グ���A�₪�ăN���V�b�N���D�Ƃ̊Ԃő唽���������N�������B�t���g���F���O���[�E�Z���^�[�́u�Z���^�[�Ղ����^���̃��C�u�v�ƌ����A�u����A�Z���^�[�Ղ̓��n�[�T���̉����v�Ƃ������_���������肵�ĂP�N���o�߁A�����ł����̌��Ɋւ������Ƃ������_���o�Ă��Ȃ��悤���B���Ƀ��R�[�h�|�p�ŐV���i2008�N8�����j�ł��A�V�������Ȍ��]����ORFEO�����Ձu�o�C���C�g�̑��v�Ɋւ��A���Β��j�����܂��u���������A�ǂ������{���Ȃ̂��A���\�Ɠ����ɐ^��푈�������N���������A�^���͖����ɕs���ł���v�ƌ����Ă���̂ł���B
�@����͖��̃��C�u���s��ꂽ7��29���Ɉ��݁A�����Ɋւ��l�X�ȈČ�������"�ǂ��炪�{���̃��C�u�����Ȃ̂�"�����Ȃ�ɋ����E���肵�����Ǝv���B�Q�T�A�ڂ̗\��ł��邪�A��1��ڂ̍���́A�a�����獡���܂ŁA�s���̖��ՂƂ��Ă̒n�ʂ���т��ĕۂ��Ă���uEMI�Ձv�̗����ǂ����Ƃɂ���B
�i�Q�j�o�C���C�g1951�N7��29��
�@���q�����g�E���[�O�i�[�i1813�|1883�j�͎���̌|�p�𗝑z�I�Ȍ`�ŏ㉉���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����p����̌��݂�i�߂Ă������A����1876�N�Ɋ����A8��13���A�L���̑��u�j�[�x�����O�̎w�v�́i�ʂ��㉉�Ƃ��Ắj���������̊`���Ƃ��ƂȂ����B���ꂪ�o�C���C�g���y�Ղ̎n�܂�ł���B���y�Ղ͈Ȍ㎑����ɂ�郏�[�O�i�[�̗��z�ƌ����Ƃ̃M���b�v�A��I�ȃi�`�X�E�h�C�c�̉^�c�ȂǂɔY�݂Ȃ�����Ȃ�Ƃ��p������邪�A�I��̔N1945�N�ɒ��f����ƁA���̂��ƃh�C�c��6�N�̒����ɂ킽�肱�̉��y�Ղ��J�Âł��Ȃ��ł����B���̊ԏj�Ռ���͒����ČR�̃L���o���[�Ɖ����ȂǁA�h�C�c�͔s�퍑�̔߈�������Ƃ����قǖ����킳��邱�ƂɂȂ�B�����Đ���1951�N�̉āA�҂��ɑ҂�����㏉�߂Ẵo�C���C�g���y�Ղ��J�Â��ꂽ�̂ł���B���̊J���������鉉�t���A�t���g���F���O���[�w���̃o�C���C�g�j�Պnj��y�c�������c�ɂ��x�[�g�[���F���̌����ȑ�X�Ԃ������B���́u���v�Ȃ̂��H ����͂�������v�����Ȃ��̂ł���B���[�O�i�[�ɂƂ��āu���v�ȏ�ɈӖ��̂���ًȂ͑��ɂȂ�����ł���B�u���v�̓��[�O�i�[��15�̂Ƃ��ɒ����Ċ����A��ȉƂ��u���悤�ɂȂ������������̋Ȃł���A1872�N5��22���A��59�̒a�����ɗF�l���W�߁A���ꌚ�݂ւ̋����ӎu���������ߎ���̎w���ɂ�艉�t�����Ȃł��������B
�@1951�N7��29���A�j�Ռ���q���铹�͖�8���̊J����҂���т鑽���̒��O�Ŗ��ߐs������A���̓��̉��t�̓��W�I��ʂ��Đ��E�̉��y�t�@���ɂ�����͂���ꂽ�B�t�F�X�e�B���@���̍ĊJ�͐��E���̉��y�t�@�����҂��]���̂ł���A���̕�����������u���v�̉��t�͐��ɋL�O��I�Ӌ`�������̂������̂ł���B����ɂ���㏉�̊J����������ꂽ1951�N�̃o�C���C�g���y�Ղ́A�n���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V���ƃw���x���g�E�t�H���E�J�������̎w���ɂ�胏�[�O�i�[�̊y�����㉉���ꂽ�B���ڂ́u�j�[�x�����O�̎w�v�u�j�������x���N�̃}�C�X�^�[�W���K�[�v�u�p���V�t�@���v�ł���B���̂����N�i�b�p�[�c�u�b�V���́u�_�X�̉����v�u�p���V�t�@���v�A�J�������́u�j�������x���N�̃}�C�X�^�[�W���K�[�v�u�����L���[���v�͌���CD������Ă��蓖���̗l�q���M���m�邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��t���g���F���O���[�͂��̔N�����̂��Ƃ��o�C���C�g�ł̓I�y�����w�����Ă��Ȃ��B
�i�R�j�`���́u�o�C���C�gEMI�Ձv�a��
�@�E�H���^�[�E���b�O������EMI���R�[�f�B���O�E�`�[���͓�������o�����̃J������(����43��)�w���̃��C�u�����߂邱�Ƃ���ړI�Ƃ��Ă������A7��29���̃t���g���F���O���[�i����65�j�́u���v�����^�����B������EMI�͂Ȃ������̘^�������炭���������ɂ����B�������Ă��邤���Ƀt���g���F���O���[��1954�N11���A68�ł��̐��������Ă��܂��B�o�C���C�g�E���R�[�f�B���O�̑��݂��\�ł����Ȃ��������E�̉��y�E�́A�ނ��u���v�̘^�����c�����ɖS���Ȃ��Ă��܂������Ƃ�S�����̂ł���B����ȏ̒��A1955�N11���i���{�ł�12���j�A���Ɂu�o�C���C�g�̑��v�����������B���y�E�������Ɋ���������Ă�����}�������͑z���ɓ�Ȃ��B���ꂼ�҂��ɑ҂����t�����F���́u���v�ł���A���j�I���������^�����L�O��I���C�u�ł���A�l�ނ̉i���̈�Y���郌�R�[�h�j�ɋP�������t�Ƃ����`���I���R�[�f�B���O�ɍՂ肠������̂ł���B
�@�������Đ��ɏo��EMI�Ղ́A�Ȍ�l�X�Ȍ`�ōĔ�������A�i���O����CD�ɂȂ��Ă����f�B�A���Đ��ɏo�܂����Ă���B2007�N�f�B�X�N���j�I���̓��T�Ƃ��Ċ��s���ꂽ[�t���g���F���O���[���S�f�B�X�R�O���t�B�[]�ɂ��ƁA�u�t�����F���E�o�C���C�g�̑��v�̃����[�X��LP�ACD�e�X80�_�ȏ�𐔂��A���e�I�ɂ�"��������"��"�������"�Ȃǂ��������A�h�C�c�A�C�M���X�A�t�����X�A�A�����J�A���{�͂��Ƃ��C�^���A�A�X�y�C���A�I�����_�A�f���}�[�N�A�M���V���A��A�t���J�A�A���[���`���A�E���O�@�C�A�I�[�X�g�����A�A�����A��p�A�؍��Ȃǐ��E���ŗl�X�Ȍ`�ŏo����Ă���B����͑�ςȐ��ł���B�ނ̗��j�I�����Ƃ����u�V���[�}���̌�����4�ԁv�i1953�N�^���̃h�C�c�E�O���t�H���Ձj��LP24�_�ACD45�_�A�܂��t���g���F���O���[���x���������o��Ƃ��Ċ��Ă������Č}����ꂽ1947�N5��27���̃��C�u�Ձu�x�[�g�[���F�������ȑ�5�ԁv�i������DG�Ձj��LP23�_�ACD28�_�Ƃ��������Ɣ�ׂĂ݂Ă����̍��͗�R���B
�@����ɖ��ՃK�C�h�Ȃ���̂������_���Ɍ��Ă݂悤�B�܂��A[���R�[�h�|�p�ʍ����Ȗ��ՃR���N�V����2001]�i1978�N���j�ɂ́u���܂���܂��A�ƌ����悤���w�t�����F���A�o�C���C�g�x�������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���̉��t�ɂ͂��ƂɂÂ����̂��ǂ����Ă����킷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����̕ǂƂ�������Ќ�������B��゠������̂��Q���Ă�������ɂ������܂ꂽ�l�Ԃ̋��x�Ȏ����̂悤�Ȃ��̂������Ƃ邱�Ƃ��ł���v�Ƃ����]�ƂƂ��ɓ��R�̑�1�ʂɃ����N����Ă���B[���R�[�h�|�p�ҁE���Ȗ���300]�i1997�j�ł͐��O�����u�t���g���F���O���[�̐���̃��C�u�^���̒��ł��Ƃ�킯�w�o�C���C�g�ł̉��t�x�������I�Ȃ̂́A��i�ɑ����������Ə��A�����Đl������ɂ������Ȃ��B�v�ƕ]��22�_���l���A2�ʂ�7�_�Ƃ����_���g�c�̑�1�ʁB[���R�[�h�|�p�ҁE21���I�̖��Ȗ���]�i2002�j�ł́A�u�w�o�C���C�g�̑��x�͕s���̂P���B����͕ʊi�A�o�C���C�g�Ƃ����V�`���G�[�V�����͓��ʁv�Ƃ��āA10�l��9�l��1�ʂɋ����l���_��27�_�͑��̑S�Ă̖��Ղ����|�I�Ɉ��������Ă���B[�w���E�N���V�b�NCD�G�b�Z���V�����E�K�C�h150]�i2002�j�͕��쏺�����u�w�o�C���C�g�̑��x��20���I�㔼�ɐ�����Ȃ��قǂ̏^���ɂ���Č�������Ă����B�̎�w���������B���t���߂̐��ۂ������y���̐^���̎p��������Č���̒�����̋Ր�����������v�Ƃ��đ�1�ʁB[���R�|�E�N���V�b�N�s�ł̖���1000]�i2007�j�ł́A���{�������u���̓��[���b�p�ł͓��ʂ̋@��ɉ��t�����ʊi�̐��i�����B���悤�₭�ĊJ���ꂽ�o�C���C�g���y�Ղ̊J����������w�t�����F���̑��x�͂��̒[�I�ȗ�B���X�܂ňُ�Ƃ�������ْ������͂���I�ɂ��������o���㊊�肷�邱�ƂȂ��i�s����B���y�����͂��̋Ɍ��̎p�������ɂ���v�ƕ]�����ɂ̖���100�I�g�ɓ����Ă���B�ȂǂȂǂ�����u���Ȗ��ՃK�C�h�v�̗ނ͏�Ɂu�o�C���C�g�̑��v�����ɂ̃t�@�[�X�g�E�`���C�X�ƂȂ��Ă���̂ł���B
�@�����̎^�����悭�ǂނƉ��t���e�������t���ꂽ�V�`���G�[�V�����ɏd�����u����Ă���̂��悭������B�s�퍑�h�C�c�̉��y�I�ے��ł���o�C���C�g���y�Ղ̕����ł���A���[�O�i�[���́u���v�ł���A�h�C�c���y���_�̌�������t���g���F���O���[�Ɠ��カ���Ă̖��̎�B�̉��t�ƁA��������قNJ����I�ȃV�`���G�[�V�����͂Ȃ������̂ł���B���⍡������y�E�ɂ���ɕC�G����悤�ȗ��j�I���Ԃ��N���邱�ƂȂǍl�����Ȃ��قǂ̋ɂ߂ē��ʂȃV�`���G�[�V�����������̂ł���B������u�o�C���C�g�̑��v�̓��R�[�h���y�j��̋L�O��ł���l�ނɈ₳�ꂽ�i���̉��y��Y�Ȃ̂ł���B�������ł���A�L�O��I�Ӌ`�Ɩ����t�͕ʖ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����������͖������ۂ����l�����ł͂Ȃ��̂ŁA�l�I�����͍����T�����t���̂��̂��ł��������q�ϓI�ȃ^�b�`�ő����Ă��������B
�@EMI�Ղ͊m���Ɋ����I�ȉ��t�Ȃ̂��낤�B�t���g���F���O���[�������o���A���˂�悤�Ȍ��̋����A��������̋��ǂ̋��t�A�y��e�B���p�j�[�̋��ŁA�\���̎�w�̑f���炵���̏��Ȃǂ́A1951�N�̕n���EMI�̘^����ʂ��Ċm���ɓ`����Ă��āA�������̂�����������͂������Ă���B�t���[�Y�̈��ɉ��y�������тƐV��������Ɍ������ē˂��i�ދ����ӎu�̗͂������Ă��邩�̂悤�ł���B�X�Ɂu�o�C���C�g�̑��v�̖����̏Ƃ��āA��4�y�̓I�[�P�X�g�����u����̉́v���̂��������O�̈ٗl�ɒ����x�~��329�|330���߂�"vor Gott"�i�_�̑O�Ɂj�Ɖ̂��t�F���}�[�^�����̋}���ȃN���b�V�F���h�͐��q�҂̊Ԃł͊O���Ȃ��|�C���g�ƂȂ��Ă���悤�ł���B
�@����A�j�]���������Ȃ��炸���݂���B�����ł͒N�������Ă������ɕ�����j�]������3�w�E���Ă��������B�����̕����͐^��l�@�̍ŏd�v�|�C���g�ɂ��Ȃ�̂ŕ�����₷���ӏ������ŏ������߂Ă����B
�@��4�y�̓R�[�_�̍Ō�ŁA�I�[�P�X�g������������w���҂̃e���|�ɂ��Ă䂯���A�A���T���u���𗐂����������ɂȂ��Ē��n����
�A��3�y��83���߁\98���߂̃z�������f�l�݂����Ƀ��������ɗ���Ă���
�B��4�y�́A�o���g���Ɍĉ����ďo�鍇���̉̂��o��"Freude"�����S�ɒx����Ƃ��Ă���
�@�u�o�C���C�g�̑��vEMI�Ղ́A���X�̔j�]�������܂݂Ȃ�����A�傫�ȗ��j�I�Ӌ`�����L�O��I�����t�Ƃ��āA�����܂ŕς�邱�ƂȂ����̕s���̒n�ʂ�ۂ������Ă���̂ł���B
�@����8��4���͘b��́u�Z���^�[�Ձv�����グ��"�ǂ��炪�^����"�̐^���ɔ��肽���Ǝv���B������ҁB
2008.07.14 (��) ���E�n�C�t�F�b�c�̍ė�
�@�_���^�R�q�T���g���[�z�[���E�R���T�[�g��2�Ȗڂ̓v�[�����N�̃��@�C�I�����E�\�i�^�ł���B���_���ş��������Y���i�s�Ɏ����萟�ݐ����R���V�A�I�������R���[������o����1�y�́B�����Ƃ�Ƃ�����̒��Ɏ���̕s�������_�Ԍ����钆�Ԋy�́B�����߂���M�Ń��C���h�ɓ˂��i�ޏI�y�́B�W���Y�E�X�p�C�X���������̖��͂���\�i�^�͉��t�҂ɑ��ʂȕ\���͂�v�����邪�A�旧���đ�Ȃ̂͊m���ȋZ�p�Ƌ������ł���B���̋Ȃ�1943�N�W�l�b�g�E�k���[�ɂ���ď������ꂽ�B�k���[�Ƃ�����1935�N�A15�Ń��B�G�j���t�X�L���ۃR���N�[���Ŗ����̋���27�̃_���B�b�h�E�I�C�X�g���b�t��2�ʂɑނ��ėD�������V�ˏ������@�C�I���j�X�g�ł���B���̌㍑�ە���ő劈���1949�N��s�@���̂Őɂ����������������B�ޏ��̉��y�ɂ͒j����̋������ƌ���������ړ����琶�܂�鋭��Ȏ��Ȏ咣������B���̑O�N1948�N�̃��C�u�^���u�u���[���X�̃��@�C�I�������t�ȁv�͂��̍D��ŁA���X�̃~�X�����̂Ƃ�������簐i����k���[�̃p�g�X�̓��}���̖z���Ɖ����ĕ������̂����|����B�@NHK���W�u���������`���@�C�I���j�X�g�_���^�R�q21�v�̒��ŏ������̎t���c�K��Y�͊��Q�̖ʎ����Łu�ޏ��͋������ݏo����b�܂ꂽ�̊i���������Ă���v�ƌ���Ă���B�܂���ʂɂ̓��b�N���Ȃ���铹���W���M���O����_���̎p���f���o�����B�u�W���M���O�͂Ȃ�̂��߂ɁH�v�Ƃ̎���ɁA�u�̗͂Â���ł����ˁB�V���X�^�R�[���B�`�̋��t�ȂȂ̗͑͂��Ȃ��Ƌ|�𗎂Ƃ����Ⴄ��ł���v�B�ޏ��͔��݂Ȃ��炻���������B�悢���y��n�����邽�߂ɕK�v�Ȃ͍̂��x�ȉ��y���ƃe�N�j�b�N�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ����A���łɂ��Ȃ�̍����x���Ŏ������킹�Ă���ޏ��Ȃ̂ɓ��X���r��ӂ�Ȃ��B����̗͑͂̐�Βl���e�N�j�b�N�̐��x�����߂邱�Ƃ�ޏ��͒m���Ă��邩�炾�B"�܂��͋���"�������S�Ă̕\���̊�b�ƂȂ邱�Ƃ�m���Ă��邩��Ȃ̂��B�����y��ɌJ��o�����"��������"�̓k���[�ɒʂ�����̂�����B
�@ �@�x�e�����̓V�}�m�t�X�L�́u�_�b�v�Ŏn�܂����B����́u�v�����v�ɂ����^����Ă���B�u���@�C�I�����ƃs�A�m�̂��߂̂R�̎��v�Ƃ̕��肪����悤��3�ȂŃZ�b�g�̋Ȃ����A�܂Ƃ܂��Ă̘^���͈ӊO�ɏ��Ȃ��Ƃ����i��P�ȁu�A���g�D�[�U�̐�v���P�Ƃʼn��t����邱�Ƃ������j�B����Ȓ��A�`���C�R�t�X�L�[�E�R���N�[���D���҂̐�y�z�K�����q�����̑S3�Ȃ�2���ڂ̃A���o���Ŏ��グ�Ă���B
�@�u�_�b�v�͋ߑ�|�[�����h�̍�ȉƃJ�����E�V�}�m�t�X�L��1915�N�ɏ��������@�C�I�����̖��i�B���̎����V�}�m�t�X�L�͌Ñ�M���V���ɓ���y���V���̐_���`���l�W�����[���E�E�b�f�B�[���E���[�~�[�ɌX�|���Ă����B�Ñ�ւ̓���Ɛ_���`�I�e�C�X�g�͊y�ȑS�̂�d���������������B
�@�z�K���͎��Ƀ��}���e�B�b�N�Ɍ�肩���Ă���B�܂�ŗd���Ȕ����q����������悤�ɁB����A�_���̃��@�C�I�����́A���Â̐_���A���R���A���̂܂܌�肩����悤�Ȍ���������炩�ȋ����������B�I�ȂŌ��ʓI�Ɏg����t���W�I���b�g�͔��o�̑�����Ȃ��圤�ȝR���t�ŁA�n���̂悤�ȉs�����F�͐_��̃��F�[�����B���̗圤�ȉs���̓n�C�t�F�b�c���霂Ƃ�������̂�����B����C�c�@�[�N�E�p�[���}����DVD�u�A�[�g�E�I�u�E���@�C�I�����v�̒��Łu�n�C�t�F�b�c�̉��̉s���̔閧�͕��O�ꂽ�^�|�̑����ɂ���v�Ǝw�E���Ă��邪�A�_���̐g�̔\�͂�����ɕC�G����̂ł͂Ȃ����B�ʂ̘b�����A����DVD�̒��Ŏ�菗�����@�C�I���j�X�g�̊���q�����[�E�n�[���́A�n�C�t�F�b�c�ɂ��Ă���Ȃ��Ƃ������Ă���B�u�悭�����ƃn�C�t�F�b�c�͉������Ă��܂����A�����ɕ������܂��v�ƁB��������_���́u�n�C�t�F�b�c�͉������Ă��Ă����������S�����܂����e���Ă���悤�ɕ������Ă��܂��B���̃e�N�j�b�N�͊������̂ł��v�ƁA���˂����������������Ă���B�O�o��NHK���W�u���������`�v�̒��ŁA�`���C�R�t�X�L�[�̃��@�C�I�������t�ȑ�1�y�͂̊y���Ɂu�����Ƃ��v�Ƃ����ޏ����g�̏������݂��f���o����Ă����B����͂��悢�\���̂��߂ɉ����킴�Ɣ���Ēe���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝ��͐��@���邪�ǂ����낤���B���̃��@�C�I���j�X�g�������w�E���邾���̎��ۂ��A�\���̃e�N�j�b�N�Ƃ��ĐϋɓI�Ɏ�����Ă���B����ׂ��_���^�R�q�ł���B
�@�q�����[�E�n�[����28�A���ݍł����ڂ���Ă����胔�@�C�I���j�X�g�̈�l�ł���B���Ƀ��R�[�h�|�p7�����u���㖼�ՊӒ�c�v�ł́A�ޏ��́u�V�x���E�X�̃��@�C�I�������t�ȁv���t�B�[�`���[�b�c�Ƃ��Ď��グ����^���Ă���B���͂�������N3���̔������ɒ����������܂��ۂɎc���Ă��Ȃ������B���߂ĉ��x�������Ȃ����Ă݂Ă��A�m�I�ł͂��邪������h�������A��Âł͂��邪�S��~�����ĂȂ����܂�ɂ��ÓI�ȉ��t�Ƃ�����ۂ͕ς��Ȃ������B�Ƃ��낪�����œC�k������]�_�Ɛ搶�����͗l�X�Ȍ`�e�ł��̉��t�����܂��Ă���B�H���u�M���ۂ��A����ł��ăN�[���Ȓe���Ԃ�v�A�u���܂ł̊�{�I�Șg�g�݂���蕥�����Ƃ���ł̓O�ꂵ���\���B�Ȃ�����p�[�X�y�N�e�B�����傫���A���̒��ŌX�̃t���[�Y���L�@�I�ɈӖ��������ĂȂ���v�ȂǁA���ɂ͂Ȃ�̂��Ƃ��T�b�p��������Ȃ��\������ь����Ă���B���ꂾ���Ȃ�܂������A�u�k���[������n�C�t�F�b�c�悳��ł����v�ȂǁA�����قǂقǂɂƂ��������悤�̂Ȃ������C�ł��Ă���B������k���[�Ƃ͂����n�C�t�F�b�c�������u���ĂƂ́A���肦�Ȃ����[�̂��B���y���牽�������悤���l���ꂼ�ꂾ���A���t�̍D���������l���������ē��R�A���l���ǂ������������R�ł���B������F����͂��������Ƃ͌���Ȃ��A���͂����͎v���܂���ƌ��������ł���B����ɁA�����ɂ͎�v�^���ՂƂ���51�_���̃��R�[�f�B���O�����X�g�A�b�v����Ă���B�搶���͂��̒�����e�X�̒��ڔՂ��ɏ悹�Č���Ă���킯�ł��邪�A���łɂ���������������킹�Ă��������ƁA�f���炵���Ƒt������N���X�e�B�A���E�t�F���X�^�J�������Ղ��m�[�}�[�N�Ȃ̂͂������Ȃ��̂��Ǝv���B�t�F���X�Ղ�1965�N�̔��������u����̓J���������ׂ����R�[�h�ŁA�t�F���X�̓J�������̈Ӑ}�𒉎��ɂȂ����Ă���ɉ߂��Ȃ��v�ȂǂƂ������ł����]�_�Ƃ��������̂��B�Ƃ��낪�悭�����Ă݂�ƑS�R����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�t�F���X�̗͋�������瞂��M�́A�����l�̐S��M���������h���Ԃ��đf���炵�����̂�����B����Ȃ͕̂��ʂɒ����Β����ɂ킩��B�C�k�̐搶�����͐�B�̖S��𖢂��ɐU�肫��Ȃ��ł���̂��낤���B�������m�[�}�[�N�̐z�K���^�I�����Ձi02�j�����Ĉ����Ȃ��B�ޏ����t�ł�n�C�t�F�b�c�̈���h���t�B���̋����͌����Ȑ����͂�����A�����l�ɖ��͂���̐S��͂��Ă����B�ǂ�������ɂƂ��Ă̓n�[�����͂����Ƌ��ɔ���B
�@�Ƃ��낪�����ɐ_���^�R�q2007�N10��21���̃T���g���[�z�[���ł̃��C�u���t������B�����͉��t���c�K��Y�w�����{�t�B���n�[���j�[�B�����ł̐_���̃\���͂��łɂ��ăn�[�����z�K�����t�F���X���������Ă���B��{�I�ɋ������������Ă��邩��㉹��������B�{�E�C���O���f��������אg�ʼns�����Ƒ����L���ȉ����͂�����ƑΔ䂳���B�e�N�j�b�N�E�����W�����O��čL���̂ł���B�y�Ȕc���͐X�����Ď}�t��͂ށA��NJςƍׂ₩������������B�ǂ�����Ƃ������芴�̒��łЂƂЂƂ̃t���[�Y�ɍׂ₩�Ȋ���ړ�����A�����\������e�N�j�b�N�̕��͕��O��čL���B������ޏ��̋Ȃɍ��߂�����͂����̐S�ɃX�g���[�g�ɓ`���B���������D�����������������₩������т��߂��݂��B���ʂŐS�ł��y�����܂��̂ł���B�q�����[�E�n�[���ł͋����Ȃ����_���̃��@�C�I�����Ől�͋����B���K�^���ł̃V�x���E�X�𑁂������Ă݂������̂��B
�@�v���O�����̍Ō�̓t�����N�̃��@�C�I�����E�\�i�^�ł���B�u�t�����N���A�e�F�C�U�C�̌����̂��j���ɍ�����Ȃł�����A���܂�ߌ��I�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��v�Ɛ_���͌����B��������ƍ�Ȃ��ꂽ�w�i��c�����Ă���B�Ƃ��낪�l�ɂ���Ắu�ȍ��̔w�i�Ȃ�ĊW�Ȃ��B�y���������B���̐^���Ȃ̂�����A����ȊO�̏��͉��y�\����ނ���ז��ɂȂ�B��ȉƂ̐S���i�ɂ����������f����Ă���Ƃ͌���Ȃ����v�Ƃ����l����������B���[�c�@���g�́A���ȕt���������������F�V���^�[�h���[�̂��߂ɁA�V���I�ɔ������N�����l�b�g���t��K622���������B�܂��A�u����Ȕn���ɉ�̂͋v���Ԃ肾�v�Ǝ莆�ɂ܂ŏ����ĕ��������r�j�q�Ƃ���̒����ō�����̂��A���̃M�������g�ŗD��Ȗ���f�B���F���e�B�����g��17��K334�������肷��B�w�i�Ɖ��y�����W�ł���T�^���B�Ƃ��낪�t�ɁA�\�i�^�z�Z��K304�ɏh�鈣���̓p���Ŏ��₽���d�ł��Ɩ��W���Ƃ͌�����Ȃ����A�u���N�C�G���v�������ߒɂȋ��т͔E�ъ�鎀�ɜɂ����[�c�@���g�̍��̜ԚL�ɑ��Ȃ�Ȃ����낤�B�x�[�g�[���F���́u�c���v������A�u���[���X�̃s�A�m���t�ȑ�1�ԁA�`���C�R�t�X�L�[�́u�ߜƁv�A�h���H���U�[�N�́u�V���E���v�A���t�}�j�m�t�̃s�A�m���t�ȑ�2�Ԃ�����ł���B�����̖��ȂɁA��Ȏ҂̐l���₻�̂Ƃ��ǂ��̏����f���Ă��Ȃ��ȂǂƒN���f�����悤���B�u���ꂱ�����̂ɂ��ނ悤�ȋ�J�����ċȂ�����Ă��ꂽ�̂ł�����A�Ȃ�Ƃ���ȉƂ̋C�����ɋ߂Â��������A���̐l���ɋ߂Â����炢���ȂƎv���܂��B�v���ꂪ�_���̐^��ł���B������ޏ��͐ϋɓI�ɏ������W����B�}�f�Ȑl�ԂȂ���ߑ����ז��ɂȂ邱�Ƃ����邾�낤���A�_���͎����̒����h�ߑ��u�������Ă���B������ދH�Ȃ�˔\�Ȃ̂��B���݂̎t���U�n�[���E�u�����͌����u����Ƃ��A�������b�X�����Ɏw���������Ƃ�ޏ��̓X�e�[�W�ł��̂Ƃ���ɂ͂��܂���ł����B�����̒��ŏ������ĐV���Ȍ`�ŕ\�����Ă����̂ł��B���̂Ƃ����͔ޏ��ɂ͋����ׂ��˔\��������Ă���Ɗ����܂����v�B������ޏ��ɂƂ��Ă͏��͂������قǂ����B�h�߂��A�K�v�Ȃ����̏���I��������ŁA����̕\����n�肾�����Ƃ��ł��邩��ł���B
�@�t�����N�̃��@�C�I�����E�\�i�^�͔ޏ��̔�r�I�V�������p�[�g���[�̂悤���B�`���C�R�t�X�L�[�D����Ɏ��g�Ƃ������Ƃ͂܂���N�قǂ����o���Ă��Ȃ��BNHK�u�������̋����v�̒��ŁA�X�C�X�̃��]�[�g�n���F���r�G�ōs��ꂽ�t�����N�̃R���T�[�g�f�����������B���̂��ƃu�����搶�����̋Ȃ����b�X�����Ă����B�u���F���r�G�ł̔ޏ��̉��t�͖��ߌ����ɂȂ��Ă����v�Ɛ搶�͕]�����B�͂��ċȂ��̂��̂̔������������o���A����ȃe�[�}�̃��b�X�����i���W�J���Ă����B
�@��4�y�́B�_���͋C�����Ɣ������̋ɂ݂Ƃ������ׂ����̊y�͂�S�̂̔����ƈʒu�Â��Ă�Ƃ����B��P�y�͖`���̎�肩��h�������i�������e�[�}���s�A�m�ɂ���đt�ł���ƁA�P���ߒx��ă��@�C�I�������ǂ�������A�܂��ɃJ�m���ł���B53���ߖڂ���͋t�Ƀ��@�C�I��������s���s�A�m���ǂ�������A���̃V�����g���[�́u�����t�[�K�v�����A�z������B�o�b�n���h�������t�����N�̐S�����_�Ԍ�����B�y�z���ω����Ȃ��炻��܂ł̎�肪���X�Ɋ���o���Ă���B�t�����N�Ǝ��̏z�`�����ɂ܂�B�����ĉ��y�͌������̋N���������R�[�_�ւƂȂ����Ă䂭�B
�@�T���g���[�z�[���ł̐_���̓��F���r�G�E�Z���^�[�Ƃ͖��炩�ɈႤ�t�����N��t�łĂ����B���b�X���ɂ���Č����ɏC������Ă����̂ł���B����I�Ȏp������A�͂܂��Ɏ��R�ɉ̂��グ������ɉ��y���ς���Ă����B�r���[�h�̂悤�ɏ_�炩���A�������c�̂���A�C�����������ޏ������̋��������R�ȉ��y�̗���ɏ���ċ�Ԃ�Y���Ă����B21�ΐ_���^�R�q�̑f���炵�����t�������B�Ō��21���߁Apoco animato�i�������C�Ɂj�Ƃ����w����poco�i�����j ���A�ق�̋͂�assai�i����߂āj���ɂȂ��Ă��܂������Ƃ������ẮB
�@���̉��t��ޏ����g�͂ǂ��l���Ă���̂��낤���B�ޏ��͍����݂̉��t���O���u21�ł��鍡�̎������o���邱�Ƃ����܂ł��B�x�X�g��s�����āv�ƍl���Ă���B���̊ϓ_����݂���̖�̃t�����N�͂��Ȃ薞���̂䂭�o���f���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���b�X���̐��ʂ��\���ɏo�Ă������B��������ł͌����Ė������ĂȂ��ޏ�������B�����Ƃ������y���n���͂����Ɗ����Ă���ޏ�������B�ł��}�����Ƃ͂Ȃ��B���y�͐l�Ԃ��̂��̂𓊉e������̂Ȃ̂�����A�o���̐ςݏd�˂ɂ���Ď��R�ɕς���Ă䂯�����̂ł���B���̂��Ƃ��ޏ��͂����ƕ������Ă���B�u���y�͌o���ɂ���Đ��n������̂ł�����A���Ƃ�ɂ�ĉ��y���悢�����Ɍ������Ă���������ȂƎv���Ă��܂��B�܂�21�N���������Ă��Ȃ���ł�����A���Ȃ�Ă܂��܂��ł���B���͂܂��S�R�������ĂȂ��Ǝv���Ă��܂��v�E�E�E��������10�N�A15�N��A�_���^�R�q�͂ǂ�ȉ��y�ƂɂȂ��Ă���̂��낤�B�܂�������Ƃɕς�����Ƃ��ޏ��͂ǂ�ȃt�����N�����Ă����̂��낤���B�_�����킵�����̋H�L�Ȃ�V�˂͂��������ǂ̂悤�Ȑi���𐋂��Ă䂭�̂��낤���B�{���ɋ����͐s���Ȃ��B
2008.07.07 (��) �n�C�t�F�b�c�̍ė�
�@�挎�T���g���[�z�[���Ő_���^�R�q�̃��T�C�^�������B��N�x�̃`���C�R�t�X�L�[���ۃR���N�[���A���@�C�I��������̗D���҂ł���B�`���C�R�t�X�L�[�E�R���N�[���Ƃ����A�z�K�����q���j��ŔN�������{�l���Ƃ����Z���Z�[�V���i���ȗD�����������̂�1990�N�Ȃ̂ŁA�������ꂱ��20�N�߂����O�ɂȂ�B���̂Ƃ�4�������_���͍��N6���Ƀ\�j�[BMG����CD�f�r���[���������B�f�r���[�Ȃ̂�����V�l�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A7�N�Ԃ̃R���T�[�g�E�L�����A�i2001�N�ɃA�����J�ŃR���T�[�g�E�f�r���[���ʂ����Ă���j�A�`���C�R�t�X�L�[��R���N�[���̗D���A��x�ɂ킽��NHK���ԂȂǂɂ�蒍�ړx�͕��݂̐V�l�̔�ł͂Ȃ��B�@����̃R���T�[�g�E�c�A�[�͂P�������炸�̊ԂɑS��16�ӏ��A�v���O������5���14�y�Ȃ𐔂���B�t�����N�A���[�c�@���g�z�Z���A�v�[�����N�AR�D�V���g���E�X�̃\�i�^�A�V���[�\���u���ȁv�A�����F���u�c�B�K�[�k�v�A�T�����T�[���X����t�ƃ����h�E�J�v���c�B�I�[�\��A�t�H�[�e�B���u�t�H�[�����E���C�g�v�i���E�����j���̑��A�`���C�R�t�X�L�[�A�X�g�����B���X�L�[�A�V�}�m�t�X�L�A�V���[�x���g�Ǝ��ɑ��ʂȑI�Ȃł���B���Ƀt�����N�𒆎��ɐ����Ă���̂����݂���Ȃ��B
�@�t�����N�Ƃ����ΌÍ��̃��@�C�I�����E�\�i�^�̒��ł����w�̖���ŁA���̔������͔�ނȂ����̋C�����͌���Ȃ��B���������ă��@�C�I���j�X�g�̋��ɂ̃��p�[�g���[�Ƃ��ě����Ǎ��̍�i�Ȃ̂ł���B���Ղ̗_�ꍂ���e�B�{�[&�R���g�[�Ղ̃W���b�N�E�e�B�{�[��49�A�n�C�t�F�b�c�����[�r���V���^�C���̃n�C�t�F�b�c��37�A���^�[32�A�t�F���X32�A�`����29�ȂǁA�T���ĔN����L�����A���ς�ł��烌�R�[�f�B���O������̂Ƒ��ꂪ���܂��Ă���B����͂��̋Ȃ����t�҂̋Z�ʂƐl�����f���o�����̂悤�ȍ�i�����炾�B�㊥21�̐_������̂ǂ�ȃt�����N�����Ă����̂��낤���B
�@�e�B�{�[�ƃR���g�[�̃t�����N�͌Í��̖��ՂƂ��Ĕ��Γ`�������Ă���B����1929�N�^����SP�����������ɂ��̋Ȃ̍ō��̖����Ƃ����]���Ă���̂͂�����ƕs�v�c�ȋC������B���R�[�h�t�����ɑ�䏊�쑺���炦�т����u�t�����N���w�̖���\�i�^�ɁA�e�B�{�[�ƃR���g�[�͟ӑR�V�ߖ��D�I�Ȏ��|���������v�Ɛ�^�������A���ꂪ����ƂȂ��č��������Ă���̂ł͂Ȃ����B���̉��t�ɂ̓e�B�{�[���L�̓T�낳�Ɵ��E�����܂��Ă���̂͊m�������A�������Ă��鉹�y�̓e�B�{�[�ł����ăt�����N�ł͂Ȃ��B���|�͕������邪�Ȃ̘Ȃ܂��͌����Ă��Ȃ��B�t�����N�ɂ͂����Ɨ圤�ȝR����~�����B�����ƂЂ��ނ��ȋC�������~�����B
�@�n�C�t�F�b�c�ƃ��[�r���V���^�C����1937�N�̘^��������B��ݍ��ނ悤�ȃ��[�r���V���^�C���̃s�A�m��D���āA�X�g�C�b�N�ŏ����ł܂�Ő����̂悤�ȃn�C�t�F�b�c�̃��@�C�I�������Y���̂��B�������ƋC�����������ɗZ�����t�����N�ƈꌳ������B���ꂱ���t�����N�̃��@�C�I�����E�\�i�^�̐^�̖����ł͂Ȃ����낤���B
�@CD�f�r���[�ɐ�삯�ăI���G�A���ꂽNHK�n�C�r�W�������W�u�������̋����v�̒��ŁA�ڕW�ɂ��郔�@�C�I���j�X�g�́H �Ƃ�������ɑ��Đ_���́A�u���܂���A�D���Ȑl�͂��܂����ǁv�Ɠ����Ă���B����f�r���[CD�u�v�����iPRIMO�j�v�̃��C�i�[�m�[�c�ɂ́A"�����̉��t�͕����Ȃ����A���̃��@�C�I���j�X�g�̉��t���͍̂D���ŁA���Ƀn�C�t�F�b�c�ɂ͖������Ă���"�Ƃ���B������q�����킹��Ɓu�ڕW�ɂ��郔�@�C�I���j�X�g�͂��Ȃ����A�n�C�t�F�b�c�͑�D�����v�Ƃ������ƂɂȂ�B"�ڕW�̓n�C�t�F�b�c"�ƌ���Ȃ��Ƃ��낪�_���炵���B�܂������ԑg�̒��ŁA�ł͖ڕW�ɂ��Ă��邱�Ƃ͂ȂɁH�Ƃ�������ɂ́A�u�����郔�@�C�I���j�X�g�ɂȂ肽���ł��v�ƁA�ł͌����Ăǂ�ȁH�ɂ́A�����Ԃ������āu������܂���A���̎���̓p�X�ł��v�ƒ��߂��i�u����͎��̉��t���Ă��炦��Ε�����܂��v�ƌ������������̂��낤���ǁj�B�ʂ̂Ƃ���ł͂����������Ă���A�u���I�ȉ��t���������Ǝv���Ă��܂��B�����ΒN�i���j�ƕ�����悤�ȁB�ł�����͊���Ă炤���Ƃł͂Ȃ���ł��B��������͍̂D������Ȃ��v�ƁB �ȑO�A���̑��h���邠��]�_�Ƃ̕����A�˗��������e�̒��ŁA�q�b�g����y�Ȃ͂����Ȃׂāu"�Ƒn���ƃC���p�N�g�̋���"������ "����Ă炤�Ɏ~�܂�Ȃ������x�̍���"�������Ă���v�Ƃ������͂��������B���y�|�p�̂���悤�Ɋւ��W���������Ă���قǓI�������͂Ȃ��ƁA�ȗ���������̕]���̕������ɂ����Ă�����Ă���i�����l�ɂ͒f�������Ă��܂��j�B����ɏƂ炵�Đ_���̋��߂���́i�ڕW�j������������Ɓu����Ă炤�Ɏ~�܂�Ȃ����������x���������ɂ����ł��Ȃ�������p�t�H�[�}���X�v�Ƃ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����B������ō��x�Ɏ������Ă���̂��n�C�t�F�b�c���Ɣޏ��͔F�����Ă���̂��낤�B�ڕW�̓n�C�t�F�b�c����Ȃ��ăn�C�t�F�b�c�����B�����������n�ł���A�D���Ȃ͔̂ނ̃e�C�X�g�Ȃ̂��Ǝv���B����́u�ŋ߂̈��Ǐ��́H�v�Ƃ̎���ɁA�J�~���́u�y�X�g�v���f���Ȃ���u���̔��������������镶�̂��ƂĂ��D���ł��B���܂�ׂƂׂƂ����͍̂D������Ȃ��B�v�Ƃ������t�ɂ��\��Ă���B����̓n�C�t�F�b�c�̌|���ɂ��ʂ���B
�@"�n�C�t�F�b�c�̍ė�"�Ƃ������R�[�h��Ђ̐�`���傪����B������n�C�t�F�b�c�����@�C�I���j�X�g���̃��@�C�I���j�X�g�ł��邱�Ƃ̏ؖ����낤�B�̃}�C�P���E���r���Ƃ������@�C�I���j�X�g�������B1936�N�A�����J���܂�A���̓j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N�̃��@�C�I���j�X�g�ŕ�̓W�����A�[�h���y�w�Z�̃s�A�m���t�Ƃ����T���u���b�h�B9�ŃR���T�[�g�E�f�r���[���ʂ����A12�ōŏ��̃��R�[�f�B���O���s���Ƃ����_���Ԃ���������B���q����̂̓n�C�t�F�b�c�A������݂ȃn�C�t�F�b�c�̍ė��ƚ������āA�܂��͏��������̉��y�l������݂����B�Ƃ��낪60�N��ɂȂ��"20�Ή߂�������̐l"�ɂȂ��Ă䂭�B�ڕW�͉_�̔ޕ��ɉ�������A�~�߂�킯�ɂ͂����Ȃ����t�����̌p�����X�g���X��ŁA�ނ͖�ɓM���悤�ɂȂ��Ă��܂��A�����Đ���32�̎Ⴓ�ł��̐����������̂ł���B���̂��납��n�C�t�F�b�c�E�V���h���[���Ȃ錾�t�����܂��B���B�ł���͂����Ȃ����݂Ƀn�C�t�F�b�c�͂���B�ނ�ڎw���Ă������ꎩ���̗͂̂Ȃ����v���m�炳��邾�����B���@�C�I���j�X�g�Ƃ��Đ����Ă䂭���߂ɂ́A�ނ̌��e�������̒�����ǂ��o�������Ȃ��B�E�E�E�قƂ�ǂ̃��@�C�I���j�X�g�͂����������̂ł���B
�@����ȃn�C�t�F�b�c�Ƃ����G���F���X�g�ɑ��_���́u�ڕW�ł͂Ȃ����D���ȃ��@�C�I���j�X�g�v�ƕ��R�ƌ����B�Ȃ�Ƒ�_�ŋ����m��Ȃ������Ȃ̂��낤�B���M�Ƃ������Â����Ȃ���Ώo�Ă���͂����Ȃ��B�������A�������͔ޏ��̉������u�ԂɁA����͂Ȃ�̂Ă炢���Ȃ��ޏ��̐^��̂��̂ł��邱�Ƃ��v���m�炳���̂ł���B�n�C�t�F�b�c�ɂ��䌨�����鍂�������x�Ƒ��Ɗu�₽�鎩�������̋����A�����炱���ޏ��͂܂�����Ȃ�"�n�C�t�F�b�c�̍ė�"�Ȃ̂ł���B
�@�v���O�����̓��[�c�@���g�̃\�i�^�z�Z���j304����n�܂����B�����A���߂ĕ����_���̐������z�[���ɋ������u�ԁA�̂���������B�����D�����ꂽ�B�Ȃ�Ƃ����������B�Ȃ�Ƃ������X�����B�A�R�[�X�e�B�b�N�̋ɂ݂Ƃ������ׂ��ɏ�̋����������BNHK�u�������̋����v�̒��ŁA���R�[�f�B���O�����ɏ��߂Ď����̘^�������������j�^�[�E�X�s�[�J�[���痬��o���u�Ԃ̐_���̉��b�����ȕ\��Ɓu���̉����Ă���Ȋ����Ȃ́H�ȂS���ۂ��v�ƌ��������t���v���o���ꂽ�B�u�v�����v���Ă������́A�ǂ����Ă���CD�̉�������ȕ��Ɍ����̂��悭������Ȃ������B����͂���ŏ\���ɔ������\���ɃA�R�[�X�e�B�b�N�ł͂Ȃ����B���̑��u�̓A�L���t�F�[�Y(DP57�^C200�{P300)�`�^���m�C�iStirling�j�ŁA���ꂱ��"�S���ۂ��Ȃ���"�����߂č\���������̂��B�����玩���̑��u�ŕ����Ă����u�v�����v�̉��͏\���A�R�[�X�e�B�b�N�Ō����ēS���ۂ��͂Ȃ������B�Ƃ��낪�T���g���[�z�[���ŕ����_���̉��͊m����CD�Ƃ͂������ꂽ���������̂��B����͌��̂悤�ɂ��炩���r���[�h�̂悤�ɂ����������A����ł��Đc�̂���A�C�����������V��̋����E�E�E�u�������̋����v�������B
�@�u���Ă̂��q����Č��\�悻�悻������ł����A�R���T�[�g���I���Ɗ������ď\�N���̗F�l�̂悤�Ɋ��ł���Ē��ɂ͗܂𗬂��Ă����l������B������݂ɂ���Ă��܂��v�ƍT���߂Ȍ����Řb�������t�������Ƃ��ė����ł����B�����āA�j���[���[�N�E�^�C���Y��"�����������r���[�h�̉��F"�Ƃ����\�����B
�@���y�̓z�����̒��ԕ��ł́A�����̉H�т��V����Ă���悤�Ȍy�����Ȃ₩�ȋ����������̋�Ԃ��`������B�ޏ��̃��@�C�I�����͉������Ől��������������D�����p���[�������Ă���B���ꂱ�����܂��Ƀ��@�C�I�������{�������Ă��閂�͂Ȃ̂ł���B
�@�p��Ń��@�C�I�����̂��Ƃ��t�B�h���Ƃ������A���̌ꌹ�̓��e�����vitulor�Łu�Ղ������A��낱�ԁv�Ƃ����Ӗ��������������ے����Ă���B����Łu�l�����Ԃ炩���v�Ƃ����Ӗ�������A����̓Q�[�e�́u�t�@�E�X�g�v�ɂȂ���ăj�R���E�X�E���[�i�E�������������u�t�@�E�X�g�v�ł́A�������t�B�X�g�t�F���X�����@�C�I������e���Đl�X�����킹���ʂɏے������B�܂����@�C�I�����̋S�_�Ƃ���ꂽ���̃p�K�j�[�j�́u�����ɍ����ăe�N�j�b�N����ɓ��ꂽ�v�Ɖ\���ꋳ��͔ނ̖��������ۂ����Ƃ�����b���c���Ă���B����₱���ŁA�̂��烔�@�C�I�����́A���������ڂ�Ƃ��A����D���Ƃ��A����ȉ��������肪�[�����閂�@�̊y��Ƒ��ꂪ���܂��Ă���̂ł���B�u�Ƃ��낪����̃��@�C�I���j�X�g�͂���ȉ���t�łȂ��B�M�X�M�X�Ɩ�A�l�̐S�Ɋ�т⏁����^���Ȃ��B����Ŋ��т𗁂тĂ��邪����̓A�X���b�e�B�b�N�Ȗ��Z�A�y�Ƃ݂����Ȃ��̂��v�A����͉䂪�h������Έ�G�搶�̖����u�N�����@�C�I�������E�������v�̈�߂ł���B�搶�ɂ͐���_�����Ă��炢�������̂��B�����l�̍���D���_���̃��@�C�I�������Ă������������Ǝv���B
�@�v���O�����͂��̂��ƃv�[�����N�̃\�i�^�Ɍq���邪�A���ꍞ�݂����Ď��ʃI�[�o�[�ɂȂ��Ă��܂����B�����͎���ŁB
2008.06.30 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�ŏI��
���I�́� ���ۃ��[�c�@���e�E�����c�ւ̗v�]���q�[�@���ۃ��[�c�@���e�E�����c�a
���̓��[�c�@���g����D���ȓ��{�̈ꉹ�y�t�@���ł��B���ւ肵���̂͋M���c�ɂ��肢�����邩��ł��B����͋M���c�Ҏ[�u�V���[�c�@���g�S�W�v�̉̌��u�t�B�K���̌����v�̒��Ƀ��[�c�@���g�̈ӎv�ɔ������ԈႢ��2�܂܂�Ă��邽�߁A����������ė~�����A�����āA�����[�������������璼���ɒ������ė~�����Ƃ������Ƃł���܂��B�Ȃ�����2�̉ӏ��ɂ��܂��Ă͋M���c�̃f�W�^���Łu�V���[�c�@���g�S�W�v�Ŋm�F���邱�Ƃ��o���܂��B
�i�P�j��4���̑䎌�� ���������������� �ɒ����ė~����
�u�V�S�W�v555�y�[�W�̃t�B�K���̑䎌���A�r���������������������@�����@"����������������"�ƂȂ��Ă��܂����A��������"����������������"�ł��B���̂Ȃ�{�[�}���V�F�̌���Y�Ȃ����̕��� �������������@�������@�����@�������������� �ƂȂ��Ă��邩��ł��B�u���S�W�v�ł�"����������������"�ł�����̂��u�V�S�W�v��"����������������"�ɕς�����̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B�P�Ȃ��A�ł��傤���A����Ƃ��ʂ̗��R�ɂ����̂Ȃ̂ł��傤���B�������������������Ƒ����܂��B
�i�Q�j��3���̋ȏ��� N20�|N19�|N21 �ɒ����ė~����
�u�V�S�W�v375�y�[�W����� N19�|N20�|N21 �Ƃ����ȏ��́A�������̎~�ނ����Ȃ�����ɂ���ĕύX���ꂽ���̂ł���A���X���[�c�@���g���Ӑ}�����ȏ��� N20�\N19�\N21 �ł��������Ƃ����E�o���[�ƃ��C�o�[���ɂ���ďؖ�����Ă��܂��B�m���Ɂu�V�S�W�v���s�̏��Ԃ́A������������Ȃ����[�c�@���g���������Ԃł���킯�ł����A���̓��E�o���[�^���C�o�[�������x��������̂���܂��B����Ƃ��\���ɂ������������������ɂ��肢�\���グ�܂��B
�ȏ�2�ӏ��̍����͕ʎ��ɂĐ��������Ă��������܂��B��������ǂ݂���������A����炪���[�c�@���g�̈ӎv�ł��邱�Ƃ��������肢������������̂Ɗm�M�������܂��B�������̓��[�c�@���g���Ӑ}�����^���̌`�����߂Ă��܂��B����̓��[�c�@���g�̉��y������Ȃ������邩��ł���܂��B�M���c���A���X���[�c�@���g�̐l�ƍ�i�̐^�̎p�����߂Ċ�������Ă��邱�Ƃł��傤�B���݂��^�������߂�C�����͓������Ǝv���܂��B�ǂ������̋��ʂȐ��_�ŏ�L2�ӏ��̌������肢�������܂��B�����Ă��̒�Ăɔ[�����ꂽ�łɂ́A����Ƃ����̒������s���Ă������������Ƒ����܂��B2�ӏ��̊ԈႢ������u�V�S�W�v�����̂܂܂ł́A�u�t�B�K���̌����v�̐������`�ł̏㉉�͉i�v�ɖ]�߂܂���B����́u�V�S�W�v�����E���ő傫�Ȍ��Ђ������M���Ă��邩��ł���܂��B���ɂ��̐M������u�V�S�W�v�������������A���E�́u�t�B�K���̌����v�͐������`�ɕς��܂��B�����Ȃ�A�V��̃��[�c�@���g���ǂ�Ȃɂ����ł���邱�Ƃł��傤�B���ꂪ�ނ̈Ӑ}�Ȃ̂ł�����B
�M���c�̌��f�Ǝ��s�ɑ傢�Ɋ��҂�����̂ł���܂��B
�Q�O�O�W�N�U��
���{�̈ꉹ�y�t�@��
���݁A���̗v�]���́u���[�c�@���e�E�����c�v�ɑ���悤�i��肵�Ă���܂��B��̂ǂ�Ȕ����������̂��ƂĂ��y���݂ł��B���́A"���c�哱�́u�V���[�c�@���g�S�W�v�ɂ͊ԈႢ�������"�Ƃ����ɒ[�Ȍ������ŁA���̃e�[�}�������ăV���v���ɓW�J���Ă܂���܂����B���������̒��P���ɉ^�Ԃ��Ƃ̂ق����������킯�ŁA�������������낤�ɒN�����m���Ă����l�C�̖���I�y���̌��Ђ���y���ɁA�h�f�l���l���Ă�������悤�ȒP���ȃ~�X�����\�N���̊Ԃ��̂܂ܕ��u����Ă���Ȃ�āA���̂ق�������ۂǕs���R�ł��B�܂��{�������킹�Ă���������A���[�c�@���g�^�_�E�|���e�ɂ́A�����^�ʖڂ� ���������������� �����T�r�̌����� ���������������� �̂ق����������Ɗ����Ă���܂��B�����炱���^����m�肽���̂ł��B���������͂܂�"����ł��w�V�S�W�x�͊Ԉ���Ă���"�ƍl���Ă��邱�Ƃɕς��͂���܂���ǁB
��6�͂ɂ������܂����Ƃ���A1973�N�ȑO�ɂ� ���������������� ��"�y���̏��"���݂��Ă��܂����B�����ĉߓ��A�e�������t�����������Ă��������Ă��鉹�y�]�_�Ƃ̂���ŁA���̌�����ɐ���オ���Ă����Ƃ��̂��ƁA�₨��ނ��Ƃ�o���Ă����R���N�V�����̒��ɓ����悤�Ȏ��ۂ����܂����B�����1964�N�^���̃I�g�}�[���E�X�C�g�i�[�w���V���^�[�c�J�y���E�h���X�f���A�v���C�A�M���[�f���A���[�e���x���K�[��ɂ��h�C�c��Łu�t�B�K���̌����v�ł��B������̌��A���̔Ղ� �q�������� �ƂȂ��Ă���C�����"���Q"�Ƃ����Ӗ��ł����� ���������������� �ł��B���Ȃ킿1973�N�ȑO�ɁA"�h�C�c���" ���������������� ���������̂ł��B�ƂȂ�Ɓu�V���[�c�@���g�S�W�v�� ���������������� �ւ̕ύX�́A��A�ł͂Ȃ�������������o���ꂽ���́A�����Ƃ���������������́A�ƍl����ׂ���������܂���B
�Ƃɂ���������_�@�ɂ��ׂĂ����炩�ɂȂ��ė~�����B����ꂪ�m�肽���̂͐^���ł��胂�[�c�@���g���]���ƁA�������ꂾ���Ȃ̂ł�����B
�@ 2�����Ԃɂ킽��٘_�u�w�t�B�K���̌����x�^���̎p�v�ɂ��t�����������������肪�Ƃ��������܂����B���̂���7�����́A�G�b�Z�C�Ȃǂ��Q�`�R�菑�����Ă��������܂��B����"�v�������Ȃ����_����"�����͖̂����ł��A�Ȃ�ׂ��f���Ă��܂����ŔɋU��Ȃ��悤�撣�肽���Ǝv���܂��B�����7��7���A�u�n�C�t�F�b�c�̍ė��v�Ƒ肵�āA��N�`���C�R�t�X�L�[�R���N�[���ɗD�����A����CD�f�r���[���ʂ�����50�N�ɂЂƂ�̈�ށA���@�C�I���j�X�g�_���^�R�q�̓V�˂̔閧�ɔ���܂��B
2008.06.23 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�U
����U�́����ۃ��[�c�@���e�E�����c�u�V���[�c�@���g�S�W�v�̕Ҏ[��1955�N�Ɏn�܂�܂����B�U���c�u���N�́u���ۃ��[�c�@���e�E�����c�v�����S�ƂȂ��āA���[�c�@���g�̑S��i���������Ƃ����c��ȃv���W�F�N�g�ł����B�ړI�́A�u���C�g�R�b�v�Њ��s�̏����u���[�c�@���g���S�W�v�i1905�N�Ɋ����j���������C�����Ă��^���̌`�ɋ߂Â��邱�Ƃł����B�����Ă��̍�Ƃ��Ƃ肠�������������̂�1991�N���[�c�@���g�v��200�N�̂��ƁB�y���̊��s�̓h�C�c�̏o�ŎЃx�[�������C�^�[�Ђ������A�u�t�B�K���̌����v��1973�N�Ɋ��s����Ă��܂��B�ЂƂ܂��Ҏ[����������1991�N����������͐����s���2007�N�ɂ͕⊮�C����Ƃ��قڊ��������Ƃ����Ă��܂��B
���ۃ��[�c�@���e�E�����c�̗��j�͌Â��A���̕�̂ł��郂�[�c�@���e�E����1841�N�ɔ�����1880�N�A�g�D�̈�Ƃ��č��ۃ��[�c�@���e�E�����c���ݗ�����܂����B�Ȍ㌻�݂Ɏ���܂ŁA���M�y���A���ȂȂǃ��[�c�@���g�E�R���N�V�����̎��W�Ǘ��A�Q�g���C�f�K�b�Z�̐��Ƌy�у}�J���g�L��̏Z���̈ێ��Ǘ��A���ۃ��[�c�@���g�T�Ԃ̊J�ÂȂǁA���[�c�@���g�ɂ܂��l�X�Ȍ����������s��������[�c�@���g�����̑��{�R�I�c�̂ł��B
�O�͂܂ł͊ԈႢ�̒��{�l�̓x�[�������C�^�[�ЂƐ\���グ�Ă��܂������A�����Ŗ��炩�Ȃ悤�ɂ��̍����́u���ۃ��[�c�@���e�E�����c�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Ȃ킿1955�N�ȗ��u���ۃ��[�c�@���e�E�����c�v�͐V�������[�c�@���g�̑S��i�̌������Ҏ[���s���A���̈ӂ����x�[�������C�^�[�Ђ��u�V���[�c�@���g�S�W�v�����s���Ă����Ƃ����킯�ł��B����Ήƌ����`�̍ŐV�ł��x�[�������C�^�[�Łu�V���[�c�@���g�S�W�v�Ƃ������ƂɂȂ�A���������Đ��E�̉��y�E��������X�^���_�[�h�ƌ��͎̂����̗��Ȃ̂ł��B1973�N�ȍ~�������������������吨���߂��̂��ނׂȂ邩�ȂƂ����܂��傤�B���̍�Ƃ͌��݂قڂ��ׂĂ��������A�S�y���̓f�W�^��������Đ��E�̒N�����C���^�[�l�b�g��ʂ��Č��邱�Ƃ��ł���܂łɂȂ�܂����B����͎��ɉ���I�ō��c�̑傫�Ȍ��тł��B
���̍��ۃ��[�c�@���e�E�����c�����J���Ă���"NMA-PUBLIKATIONEN"�Łu�V���[�c�@���g�V�S�W�v�́u�t�B�K���̌����v�����Ă݂܂��傤�B�u�t�B�K���̌����v�͂r���������U���ꉹ�y��32�ȂƂ��Čf�ڂ���Ă���A����555�y�[�W�ɂ�"����������������"���A375�y�[�W����͑�3���ȏ������Ď��A[2�ӏ��ԈႢ�^]���m�F�ł���ł��傤�B
�ł��A�ǂ����Ă��̂悤�Ȏ��ۂ������ɑ����Ă���̂ł��傤���H ����2�ӏ��Ɋւ��Ă̌��͖����Ȃ̂ɂȂ��Ȃ̂ł��傤���H �u�V���[�c�@���g�S�W�v�͗��j������c�������I�ȏ�������Ă��̉b�q�̌����s�����č��グ�Ă����ł��M���ɂ���X�^���_�[�h�Ȃ̂ł��B�����Č��݂����X�����⊮����Ă���̂ł��B�Ȃ̂ɂȂ�����ȒP���Ȃ��ƂɋC�Â��Ȃ��̂ł��傤���H ����ɓ�����ΊȒP�ɕ����邱�Ƃ��ǂ����ĒN���������悤�Ƃ��Ȃ��̂ł��傤���H �������ꂽ���m�̕Ћ��ɂ����Ǒf�l���y�t�@�����C�Â��悤�ȒP���Ȃ��ƂɁA�Ȃ����E�͋C�Â��Ȃ��̂ł��傤���H �������͕s���ɂȂ��Ă��܂��܂��A�����Ԉ���Ă���̂���Ȃ����ƁB
�ŋ߁A���y�ƊE�̐�y�̈�l���u���O����̍S���Ă��還���������������^�����������������Ɋւ��Ėʔ������Ⴊ���邼�v�Ƃ����āA1959�N���}�Њ��s�́u�Ζ�I�y���S�W�v�Ȃ�{�������Ă���܂����B�����ɂ͂�����̕������Ȃ�Ƃ����������������ƂȂ��Ă���ł͂���܂��B�u�V�S�W�v���s��14�N���O�ɂ����������������̎��Ⴊ�������̂ł��B�Ⴄ�Ƃ���œ�����A������m���͏������̂ŁA�����������������͍�������ύX�������̂�������܂���A���̓��ۂ͕ʂɂ��āB�Ȃ���̏o�T��������m�肽���Ȃ�܂��B��̎肪����Ƃ��āu�Ζ�I�y���S�W�v�̌��T��T�邱�Ƃł����A���҂̋{��c�ꎁ�͂��͂�̐l�ł���A�o�łɊւ�������X��T���̂��e�Ղł͂Ȃ��ł��傤�B�Ƃ͂����Ⴆ���̏o�T�����炩�ɂȂ����Ƃ��Ă��A�{�[�}���V�F�̌��삪"��������������"�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��A���̐���������̂ł͂���܂��B
�傫�Ȋm�M�Ƃ�����Ƃ����s���B�����Ȃ��́A���{�l�́u���[�c�@���e�E�����c�v�ɒ��ڊm���߂邵������܂���B�u���E���́w�t�B�K���̌����x�̏㉉���������`�ōs���邽�߂ɁA���s2�ӏ��̊ԈႢ��������ė~�����v�ƒ�Ă��邵������܂���B�u���c�v�̓��[�c�@���g�̍��Y����胂�[�c�@���g�ɌW��邷�ׂĂ̎������������`�ʼn^�p����邱�ƂƂ��Ă���A�u�V�S�W�v�̕Ҏ[���܂��ɂ��̖ړI�̂��߂ɍs��ꂽ�̂ł��傤����A�����Ɛ^���ȑΉ������Ă����͂��ł��B�����āA���̒�Ă��������i�����[�c�@���g���Ӑ}�������́j�ƔF�߂�ꂽ�Ȃ�A�����ɒ������Ă����ł��傤�B�����������Ȃ��Ƃ����Ȃ�A���̗��R�������Ă���邱�Ƃł��傤�B�������̗��R���[���ł�����̂�������A���͂�������ȏ�̒Njy�͂�߂ɂ��悤�Ǝv���܂��B
2008.06.16 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�T
����T�́��@�U���c�u���N2006�����̖��_�̌��u�t�B�K���̌����v�̑�\�I�ȃ\�t�g16�_�̂����A�Q�ӏ��Ƃ����������t��������Ȃ������̂͑傫�ȋ����ł����B����������炪���ꂽ�̂�1973�N��1980�N�ł�����A�������ꂱ��30�N�߂����������`�̃v���_�N�V���������݂��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�������͑�ςȖ��Ȃ̂ł����A����ȏ�ɏd�v�Ȃ̂̓U���c�u���N���y��2006������"2�ӏ��ԈႢ�^"�ł��邱�Ƃł��B
���݃I�y�����o�ɂ����ēǂݑւ��Ȃ�V�@�������𗘂����Ă���悤�ł����A�u����Ȃ��Ƃ��l����ɂ���������A��i�̖{���ɒ��ڊւ���{�����������Ɨ}���Ă��������v�ƌ��������B�u�P���r�[�m�̉��g��n�����Ă���ɂ���������A�ȏ���̎��𐳂������܂��Ă���ɂ��Ă��������ȁv�ƌ��������̂ł��B
�i�P�j���o��̎��s
"�Q�ӏ��ԈႦ�^"�̃U���c�u���N2006�v���_�N�V�����ɂ́A���s�Ƃ������鉉�o��������ӏ�����܂��̂ŁA�܂��͂�����w�E�������Ǝv���܂��B�{���̎�|�Ƃ͎����܂����A�I�y�����o�̍����Ɋւ��d�v�Ȗ��ł��̂Ŋ����ĐG�ꂳ���Ă��������܂��B�J�ł͂��̃v���_�N�V�������A�u�V�����o��l����n�����a�V�ȉ��߂��{��������I�ȏ㉉�B���Ƀ��[�c�@���g�E�I�y���̐^�����������v�ȂǂƑ����ł��āA������Ƃǂ����Ǝv���̂ł����A����ɂ��Ă͂����Č��y�������܂���A�����͉��߂��c�_�����ł͂���܂���̂ŁB�����������ɂ͐�ɓ��݊O���Ă͂����Ȃ��Œ���̖��Ƃ������̂������āA�O�[�g���o�͂��̕����Ɋւ���Ă���̂ňꌾ�\���グ�����̂ł��B
�@��R���`���A���ݕv�l�ƃX�U���i�̖��k����X�U���i�����݂�U�f�����ʂł̕v�l�̓���
���ݕv�l�̓X�U���i�Ɂu���݂Ɉ����̖������Ȃ����B���̌v��͋M���̘r�ɂ������Ă���̂�v�ƌ����܂߂Č��������Ă��B�S�O���Ă����X�U���i�͂���ňӂ������Ĕ��݂Ɍ������ĕ����o���B�v�l�͂�������͂����炷���ɂ��̏�𗧂�����Ƃ����̂��ʏ�̃p�^�[���B���̏�ʁA�O�[�g���o�ł́A��������ׂ��v�l�����������ɁA�K�i�̏ォ���l�̗l�q���M���Ă���̂ł��A�����������Ԃɂ킽���āE�E�E����͐�ɊԈႢ�Ƃ���Ȃ���Ȃ�܂���B�Ȃ��Ȃ�A�v�l�͂��̂��Ƃ̃��`�^�e�B�[���H�Łu�X�U���i�͒x���̂ˁB���̎q�̐\���o�ɔ��݂͂Ȃ�ē������̂�����E�E�E�v�Ǝ���̐��ۂ��Ă��ēƔ������ʂ����邩��ł��B�����ł��u���C�o�[�����v�̃|�C���g�ɂȂ�����̃��`�^�e�B�[���H�ł��B���݂ƃX�U���i�̏���d���Ō�̕����A���݂́u���ꂵ���A�킽���͊�тł����ς����v�Ƃ������t�܂ł�������ƕ����Ă���l���A�u�Ȃ�ē������̂�����v�͂Ȃ��ł��傤�B���A�����b�̂��������Ƃ��Ģ�˂��A�ǂ��������H��Ɛu���̂ł͂Ȃ��A�Ɣ��Ȃ̂ł�����B���o��A��l�̂����ڊ_�Ԍ���v�l�̐S���i���̕\��̂Ȃ�ƕs�����Ȃ��Ɓj��P��o�����������̂�������܂��A����͎��s�ł����B�����ɂ͔Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���������̂ł��B
�A��4���A�X�U���i�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�u����̐l�̘r�̒��Łv�`�u���������ŁA�f���炵����т�v�̏�ʂł̃X�U���i�̕���
�t�B�K�����Ď��ɂ���Ă���ƒm�����X�U���i���A�킴��"���݂Ƃ̈�����҂���тĂ���"�U������āA�t�B�K��������ʂł��B���̏�ʂ̃X�U���i�̕����ɂ́A�X�U���i�̕����̂܂܂ƕv�l�ɕϑ��ς݂Ƃ�����̃p�^�[��������܂��B�O�[�g���o�̓X�U���i�����^�ł��B�Ƃ��낪���̕����A���̂��ƕv�l�ɕϑ������Ƃ��̂Ǝ��ɋ�ʂ����ɂ����B�F�͓������n���A�Ⴂ�͋��̊J��������Ȃ̂ł�����C�Â��Ȃ��l�����\�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��l������ւ��Ƃ����̂���S���̃L�C�E�|�C���g�Ȃ̂���������Ƌ�ʂ̂��₷�����������ė~���������B�Ⴆ�A�G�v�����𒅗p�����邾���ł��悩�����̂ɂƎv���܂����A���ӎ�������������Ȃ������̂ł��傤���B����Ƃ����̕����A�O�[�g�́u����Ȃɐ_�o���ɂȂ�Ȃ���ȁv�Ǝv���Ă���������̂ł��傤���B�������Ƃ�����A���͂�����Ƃ��̕��ƗF�B�ɂ͂Ȃ�܂���B
���̕����͌Í��̉��o�Ƃ̏����ǂ���̈�Ȃ̂ł��傤�A����܂ŗl�X�Ȏ�����{����Ă��܂��B�Ⴆ�A�x�[��76�c�u�c�ł̃|�l���́A�u���łɓ�l�͕ϑ����Ă���A�X�U���i�����̕v�l���t�B�K���̌�����ʒu�ɒu���A�����Ȃ��Ƃ���ŃX�U���i�ɉ̂킹��v�Ƃ����Â������o�����Ă��܂����B
�܂����[�^03�ł̃W���i�T���E�~���[�́A���F�ƍ��Ƃ������ʂ��₷���F�Ⴂ�̃}���g��������Ɏg���āA��ڂł���ƕ�����ϑ����{���Ă��܂����B
�����ЂƂA�ŋߓ��M���ׂ����o�����܂����B���[�R�v�X04�V�����[���[����A�W���������C�E�}���e�B�m�e�B���o�̃��C�u�c�u�c�ł��B�t�B�K�����猩����ʒu��"�X�U���i�ɕϑ��ς݂�"�v�l�𗧂�����"���p�N"�������A�A�ŃX�U���i���̂��Ƃ������̂ł����B�|�l���^������ɐi���������X�^�C���ł��B�ߑ������䑕�u���F�ʓI�ŕi�������āA���m�g�[���̃O�[�g���o�Ƃ͎��o�I�ɑɂɂ���A���Ă��Ď��Ɋy�����㉉�ł����B���ꂪ������������������������Ǝc�O�łȂ�܂���B
�i�Q�j2�ӏ��ԈႦ�^�̐ӔC�Ƌ`��
�U���c�u���N2006�v���_�N�V�����́A������������������[�P]�|[�Q]�\[�R]���т�[�Q�ӏ��ԈႦ�^]�Ȃ̂ł��B����͏d��Ȗ��ł��B�Ȃ��Ȃ�A�U���c�u���N���y�Ղ̓��[�c�@���g�E�I�y���㉉�ɂ����鐢�E�̃��[�_�[�ł���A���E�͂�����K�͂Ƃ���ƍl����Ƃ����}�������邩��ł��B���[�_�[������̂́A���̉e���̑傫�����\���ɔF�����Ă��������Ȃ��Ă͍���܂��B���[�_�[������ł͍��㐳�����`�ł̏㉉�͂܂��܂��]�߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�U���c�u���N���y�Ղ̃X�^�b�t�́A�g�p���Ă����{�������Ă������������B�����ĊԈႢ��F�������璼���ɐ��E�ɔ��M���Ă������������Ǝv���܂��B�u�t�B�K���v�㉉���퉻�̂��߂ɁB
2008.06.09 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�S
����R�́��Q�ӏ��Ƃ��������`�̉��t�͓�����Ȃ������i�P�j�Q�̗v�f�̏ƍ�
���悢�悱�ꂩ��A�S�P�U�^�C�g���̂���"�������`"�ł̉��t�͂ǂꂩ�H�̌��ɓ���܂��B
����P�́����瓖�Y�ӏ��̉̎��͂�����������������[�p�^�[���a]�𐳂����Ƃ���
����Q�́������R���̋ȏ���[�Q]�|[�P]�\[�R]��[�p�^�[���a]�𐳂����Ƃ���
�����Q���ڂƂ�[�p�^�[���a]�ɂ�鉉�t��"�������`"�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ƍ������₷�����邽�߂Ɂm�p�^�[���a�n�ɂ�鉉�t���������ڕʂɗ�L���Ă݂܂��傤�B
[�p�^�[���a]�ɂ�鉉�t
���P���@�����������������^
�@�J�������T�O�b�c
�A�d�E�N���C�o�[�T�T�b�c
�B�W�����[�j�T�X�b�c
�C�x�[���U�U�U���c�u���N���y�Ղc�u�c
�D�x�[���U�W�b�c
�E�v���b�`���[�h�V�R�O���C���h�{�[�����y�Ղc�u�c
�F�x�[���W�O����������قc�u�c
�G�f�C���B�X�X�O�b�c
���Q���@[�Q]�|[�P]�|[�R]�^
�@�v���b�`���[�h�V�R�O���C���h�{�[�����y�Ղc�u�c
�A�x�[���V�U�c�u�c
�B�J�������V�W�b�c
�C�x�[���W�O����������قc�u�c
�D�A�o�h�X�P�A���E�f�A�E�E�B�[������k�c
�E�n�C�e�B���N�X�S�O���C���h�{�[�����y�Ղc�u�c
�F���[�^�O�R�t�B�����c�F�܌��Ղc�u�c
�G���[�R�v�X�O�S�V�����[���[����c�u�c
���P�����Q���ɋ��ʂȉ��t�́\�\
�E�v���b�`���[�h�w���A�s�[�^�[�E�z�[�����o�A�O���C���h�{�[��1973�c�u�c
�E�J�[���E�x�[���w���A�w���Q�E�g�[�}���o�A�����������1980�c�u�c
�P�U�^�C�g���̂����������Q�^�C�g���Ƃ������ʂƂȂ�܂����B
���M���ׂ��̓v���b�`���[�h�^�s�[�^�[�E�z�[���Ղł��B���̂c�u�c�͌��ݔp�ՁA�u���C�N���O�̃L���E�e�E�J�i���A�t�f�����J�E�t�H���E�V���^�[�f�A�C���A�i�E�R�g���o�X���ꓯ�Ɋ�����낦�����M�d�ՂƂ��Ă��������̂ł����A����"���[�c�@���g���Ӑ}�����������`�ł̉��t"�Ƃ����V���ȌM�͂�����������ƂɂȂ�܂��B�ȏ��Ɋւ��ẮA�{���̐����������Ƃ͂����A����܂Œ��N���s����Ă���������ɂ͗E�C�Ɗm�M���Ȃ���ł��Ȃ����ƁB�����炭����́A����Łu�A�}�f�E�X�v�̉��o������Ă���C�M���X�����E�̏d���s�[�^�[�E�z�[���̌d��ł��傤�i���̎莝���̃R���N�V�����ł͂��ꂪ�ŏ���[�p�^�[���a]�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����ȑO��[�p�^�[���a]�̗p�̃v���_�N�V���������݂��Ă���\���͂��肦�܂��A���C�o�[��������7�N�������Ă���̂ł�����B�����m�̂����͋����Ă��������j�B�����������������Ɋւ��ẮA�x�[�������C�^�[�ł̉e�������ɂ��M���M���̎����������͍̂K�^�ł����B
�x�[���^�w���Q�E�g�[�}�Ղc�u�c�͖����̗_�ꍂ�����́B�t�B�K���̓w���}���E�v���C�A�X�U���i�̓��`�A�E�|�b�v�A���ݕv�l�̓O���h�D���E���m���B�b�c�A�P���r�[�m���A�O�l�X�E���@���c�@�Ƃ����B�X����̎�w�Ƀx�[���w���F�E�B�[�������̌���nj��y�c�������c�Ƃ����܂��ɖ{��́u�t�B�K���v���ɂ̃X�e�[�W�����{�ŏ㉉���ꂽ�̂ł��B�X�^�b�t�E�N���W�b�g�ɂ́A�����o�ƃW�����E�s�G�[���E�|�l�����ߑ��S���A�w���Q�E�g�[�}�����o�ƂȂ��Ă��܂����A�g�[�}��"���̃c�@�[������"���o�S���ł����B���������āA���X�̘g�g�݂̓|�l���̂��̂ƍl���Ă����ł��傤�B���|�l���A�x�[���V�U�c�u�c�ł�[�p�^�[���a]�ȏ����̗p���Ă��܂����B����ɂ��āA���y�]�_�Ɛ��O���̓l�b�g��Łu�|�l���́A�v�l�̃n�����̃A���A��Z�d���i�u�ٔ��̏�v�j�̑O�ɒu���A���I���ʂ����߂Ă���v�i�r�c�������̃T�C�g���j�Əq�ׂ��Ă��܂����A���I���ʂ����߂Ă���̂̓|�l���ł͂Ȃ����[�c�@���g�Ȃ̂ł��B
�����������������Ɋւ��Ă͑��������Ȗ����͂��ł��܂��B�m���Ƀt�B�K���̃w���}���E�v���C��"����������������"�Ɖ̂��Ă��܂����A���{�ꎚ���́u���J��^���Ă��܂��傤�v�ł����i�Ɍꎚ���͂Ȃ��j�A�x�[���V�U�c�u�c�̈Ɍꎚ���������������������ƂȂ��Ă��܂��B����炩��A���̃v���_�N�V�����̎g�p��{�������������������^�������\���͏\�����肦�܂��B
�i�Q�j�ƍ����ʂ��l�@����@
�@��������������������肾�B
��R���ȏ��Ɋւ��āA�ŏ��Ɍ��ꂽ�V�R�N�ȍ~��������ƁA[�p�^�[���a]�̂W��ɑ�[�p�^�[���`]�͂R��ł��B���̂��Ƃ��烌�C�o�[�����͂��Ȃ�Z�����Ă��邱�Ƃ�������܂��B
���́A������̌��Ɋւ��Ăł��B�ŏ��͐������p�^�[�����������������������Ȃ��������̂��A�y���o�ł̃x�[�������C�^�[�Ђ������������������ɂ��Ă��܂������߁A���s���ꂽ�V�R�N�ȍ~�A�����������������Ƃ�������������������������悤�ɂȂ�܂����B�������A�����������������̂R��ɑ������������������͂W��𐔂��A�ԈႢ�p�^�[���̕��������Ƃ��������o���Ă��܂��B����̓x�[�������C�^�[�̉e���͂̑傫���������܂��B
�Q�̗v�f�̂����A��R���ȏ��̓��C�o�[�����̐Z���x�͍����A�����������Ɍ������Ă��āA����͑�ϊ�������Ƃł��B������ɂ��Ă͂����������������g�p�̌X���������A����͈����������Ƃ��킴��܂���B
�A�y�ς͋�����Ȃ�
�����ŕʊp�x����"�������`"�ł���Q�^�C�g�����l�@���Ă݂܂��傤�B���Ȃ킿���̂Q�^�C�g����"�Ȃ��������`�Ɏ��܂����̂�"�Ƃ������Ƃ��B
�v���b�`���[�h�V�R�O���C���h�{�[���Ղ́A�u���C�o�[�����v��E�C�Ɗm�M�������Ď��グ�����Ƃ������ł��B�g�p���Ɋւ��ẮA���������������������z����邬�肬��̎������������߁A���������ł��邒�����������������g�p���ꂽ�B����͍K�^�ł����B
�x�[���W�O����������ٔՂ́A���o�̃|�l���͋ȏ��ɂ��Ắu���C�o�[�����v���̗p�������A�g�p���Ɋւ��ẮA�����������������ɂ��Ă����A���Ȃ킿�x�[�������C�^�[���g�p���Ă����\��������B����͓��{�ꎚ����������������������ł��邱�ƁA�V�U�|�l�����o�̈Ɍꎚ������͂肄���������������ł��邱�Ƃ���̐����ł��B�����ł���Ȃ�A���̃v���_�N�V�������������`�Ɏ��܂����̂́A�w���}���E�v���C��"�o���㎩��I��"���������ł��邒�����������������̂������Ƃɂ��B����͐���҂̈Ӑ}�ł͂Ȃ��B
���������Ă������Q�����Ȃ�"�������`"�̃v���_�N�V�������A�ЂƂ͎����I�ȉ^�ɂ���āA�����ЂƂ͉̎�̌o���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���R�̎Y����������������Ȃ��̂ł��B���Ȃ킿"�������`���Ӑ}����"���삳�ꂽ�v���_�N�V�����́A������������܂����݂��Ă��Ȃ��̂�������܂���B�ƂȂ����"�������`"�̃v���_�N�V���������ݏo�����\���͋ɂ߂ď������Ƃ��킴������܂���B����1980�N�ȍ~"�������`"�͊F���Ȃ̂ł�����B
�ȏ�̌��_�͂����܂Ŏ������ł���16�_�͈͓̔��ł̂��Ƃł��B�u�t�B�K���̌����v�̏㉉�����i������Ă���p�b�P�[�W���삵�����ɏ���Ă���̂ŁA�����100��������͕̂s�\�ł����A����\�Ȍ��肵�Ă䂱���Ǝv���Ă��܂��B
����Ȓ��A�r�c�������́u�t�B�K���̌��������f�[�^�v�Ƃ����A�u�t�B�K���v�̉f���R���e���c���W�߂����ڂ��ׂ��T�C�g�ɏo����Ƃ��ł��܂����B�S����33�^�C�g�����Љ��Ă���A����������10�^�C�g���̉f�����i�͑S�Ċ܂܂�Ă��܂��B�����ɂ͊e�v���_�N�V�����̃f�[�^�͌����ɋy���A���t����o�̍ו��ɂ܂Ō��y�A���O�̎��҂̕]�_�E�R�����g���j���[�g�����Ɏ����ꂽ�܂��Ƃɑf���炵�����e�ł��B���o����̒��ő�3���ȏ��ɂ��G����Ă��܂��̂ŁA�����Ƃ�グ��10�_�ȊO�̒�����[�p�^�[���a]�̂��̂��������Ă��������܂��B
�G�X�}���w���A�h���b�g�j���O�z����1981
�K�[�f�B�i�[�w���A�V���g������1994
�A�[�m���N�[���w���A�`���[���b�q�̌���2002
�p�b�p�[�m�w���A�R���F���g�K�[�f��2006
���Ȃ��Ƃ�����4�_�Ɋւ��ẮA�������������������ǂ����������Ă݂����Ǝv���܂��B�A���A���ɂ��̒��ɂ����������������^���������Ƃ��Ă��A�U���c�u���N2006���ς��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���̐������{���畢�邱�Ƃ͂���܂���B���̂��Ƃ͑�5�͂ŏڂ����q�ׂ����Ă��������܂��B
����S�́����{���̍���
�����Řb�͂�����Ɖ����ɔ���܂����A"���{���"�̊ϓ_�����l���Ă݂����Ǝv���܂��B��҂̔C����"�̎肪�̂��Ă���̎�"�𒉎��ɖ��Ƃɂ���܂����A�x�[�������C�^�[�u�V���[�c�@���g�S�W�v�����s���ꂽ�V�R�N�ȍ~�ɂ����āA���{���̍����������������܂��B
�i�P�j�̎肪�����������������Ɖ̂��Ă���̂ɂ���������������������Ă���P�[�X
�E�A�o�h�A�A���E�f�A�E�E�B�[������X�P�k�c
�u���h���������܂��v�i���Ήp�v��j
�E�n�C�e�B���N�A�O���C���h�{�[���X�S
�u���h���������܂��v�i���Ήp�v��j
�i�Q�j�̎肪�����������������Ɖ̂��Ă���̂ɂ���������������������Ă���P�[�X
�E�x�[���A�U���c�u���N�U�U�c�u�c
�u�����������̑���v�i��ҕs���j
�E�x�[���A����������قW�O�c�u�c
�u���J��^���Ă��܂��傤�v�i���Ήp�v��j
�����Ɠ��{������Ă��Ȃ����͈̂ȏ�ł��B���Ήp�v�������悤�ł��B������Ȃ�"�������`"�ł̌����̈�x�[���W�O�c�u�c�̓��{��Ԉ���Ă���̂͂�����Ǝc�O�ł��B�����Ղ̔����ȉ��_�Ƃ����邩���m��܂���B
�x�[���E�U���c�u���N�U�U�c�u�c��������������������ɂȂ��Ă���͍̂����Ձi�s�c�j�j��2003�N�������������߂ł��B�U�U�N�̏㉉�Ȃ̂ʼn̎�͓��R�����������������Ƃ����̂��܂���B�Ƃ��낪���������Ƃ́i2003�N�ɂ͑��݂��Ă���j�x�[�������C�^�[�ł��g�����̂ł��傤�A���̂��߂�����������������ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����A����͍����̏ے��I����ł��B
2008.06.02 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�R
�i�R�j���C�o�[�����̊T�v1965�N�A�I�[�X�g���A�̉��y�w�҃}�C�P���E���C�o�[���ƃ��o�[�g�E���E�o���[���u�w�t�B�K���̌����x��R���̍\���v�\���܂����B���̃��C�o�[�����̑��݂͐Έ�G�搶�ɋ����Ă��������܂����B���C�o�[���^���E�o���[�����͓��{�ł͂قƂ�Ǐo����Ă��Ȃ����߁A�搶�̂��b�����ɍ\�z���Ă��܂��B�]�k�ł����}�C�P���̌Z�N���X�g�t�@�[�̓f�b�J�̃v���f���[�T�[�Ƃ��Ċ���A���X�̖��Ղ�����Ă��܂��B
�u�t�B�K���̌����v��1786�N5��1���A�E�B�[���̃u���N����ŏ������ꂽ�Ƃ��̋ȏ���[�p�^�[���`]��[�P]�\[�Q]�\[�R]�������B����܂ł��̋ȏ��ŌŒ肳��Ă������A�����I�Ƀ��[�c�@���g�̒ʏ�̕��тł͂Ȃ��B�����Ń��C�o�[���́A���[�c�@���g���{���Ӑ}�����`��[�p�^�[���a][�Q]�\[�P]�\[�R]�������̂ł͂Ȃ����Ƃ̉����𗧂Ă܂��B�ȉ��A���C�o�[���̐�����ǂ��Ă݂܂��傤�B
�������̔z����
�t�B�K���F�t�����`�F�X�R�E�x�k�b�`
�X�U���i�F�i���V�[�E�X�g�[���X
�A���}���B�[���@���݁F�X�e�[�t�@�m�E�}���f�B�[�j
���ݕv�l�F���C�[�U�E���X�L
�P���r�[�m�F�h���e�[�A�E�u�b�T�[�j
�o���g�����A���g�[�j�I�F�t�����`�F�X�R�E�u�b�T�[�j
�}���`�F���[�i�F�}���[�A�E�}���f�B�[�j
�o���o���[�i�F�A���i�E�S�b�g���[�v
�o�W���I���h���E�N���c�B�I�F�}�C�P���E�P���[
�������ɃE�B�[���̋{��ōs��ꂽ�������������āA�������B�X�����Ԃꂪ����ł���悤�ł��B���ł��X�U���i���̃i���V�[�E�X�g�[���X�͍c�郈�[�[�t2���̂��C�ɓ���Ń��[�c�@���g���v�����Ă����`���[�~���O�ȃ\�v���m�̎�B�t�B�K���������I����ăC�M���X�ɋA��ޏ��ɑ������Ȃ��A�R���T�[�g�E�A���A�̌���A�V�F�[�i�u�ǂ����Ă��Ȃ���Y����悤�v�`�����h�u����Ȃ��ň�����l��v�j�T�O�T�ŁA���ʉ��t��ł̓s�A�m�E�p�[�g�����[�c�@���g���g���e���Ĉ�����i���V�[�Ƃ̕ʂ��ɂ��̂ł����B�E�B�[���؍ݒ��������ޏ��̌Z�ō�ȉƂ̃X�e�t�@���E�X�g�[���X�ƃo�W���I���h���E�N���c�B�I����̃}�C�P���E�P���[�́C��̂ق����[�c�@���g�ƋC�������āA�̋��C�M���X�ɏ������Ƃ�{�C�ōl���Ă��������ł��B�����̃����h���́A���Y�K���̑䓪�ɂ���ăI�y�����s���E�B�[���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂ̊�����悵�Ă����悤�ŁA�������̘b���������Ă�����A���[�c�@���g�̃I�y���͂����Ƃ����Ƒ����Ă�����������܂���B
���������ԋ߂ɔ���A���Ȃ������đS�Ȃ����I�������[�c�@���g�̎��Ȃ��Ƃ͋ȏ��ԍ��t���ł����B��P�W�Ȃ܂ŏ����ɂ������[�c�@���g�̎肪�A�u�ٔ��̏�v�Ɓu���敗�̓�d���v�ɂ������������Ƃ���Ŏ~�܂��Ă��܂��܂��B��R���́u�ٔ��̏�v�́A�t�B�K���Ƃ̌������咣����}���`�F���[�i�����̓t�B�K���̕�e�ŁA�o���g�������e���������Ƃ�������V��ʁB���́u�Z�d���v�̂��Ƃ́A�t�B�K���A�X�U���i�A�}���`�F���[�i�A"�o���g��"�̃��`�^�e�B�[���H�ƂȂ�A�����Ȃ�e�q�Ƒ�������4�l�͍~���ėN�����K���ɑ傢�ɐ���オ��ޏꂷ��̂ł����A���̒���"�A���g�[�j�I"�Ɣ��݂̊|�������̃��`�^�e�B�[���H�������āu���敗�̓�d���v�ɂȂ����Ă䂫�܂��B�Ƃ��낪�A�o���g���ƃA���g�[�j�I�͈�l����A���̕��т̂܂܂ł͒��ւ��Ă��鎞�Ԃ��Ȃ��B���Ăǂ�����H �����ōl�������̂��A��̏�ʂ̊ԂɁA�u�ٔ��̏�v�̑O�ɂ����Ă������ݕv�l�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�u�X�U���i�͗��Ȃ��v�u�Â��y���������K���Ȏ��́v��}������Ƃ����A�C�f�B�A�ł����B�������邱�Ƃɂ���āA���ւ��鎞�Ԃ����܂��l������\�ɂȂ����̂ł��B�����Ă��̏��ԂŔԍ����ł���܂����B��P�X�ȁu�Z�d���v�A��Q�O�ȁu���ݕv�l�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�v�A��Q�P�ȁu���敗�̓�d���v�Ƃ����ӂ��ɁB���ꂪ[�p�^�[���`]�ŁA�������̑䏊����ɂ�����̑[�u�������킯�ł��B�Ȍケ�̌`�������Ƒ����Ă��Ă��܂��܂����B�N���^������܂Ȃ��܂܂ɁB�����Đ���1960�N��ɁA�}�C�P���E���C�o�[���ƃ��o�[�g�E���E�o���[�����̎����ɋC�Â��A���[�c�@���g�����Ƃ��ƈӐ}���Ă����I���W�i���̋ȏ���[�p�^�[���a]�ł������Ɗm�肵���̂ł��B�Ȃ�Ə�������180�N���o�߂��Ă��܂����B
�i�S�j�����ʂ���̌���
���C�o�[�������̂��ƂɋC�Â������������͒����̕��тł����B�ނ��ڂ������̂͂ǂ��������̂��A2�̃p�^�[���������Ă݂܂��傤�B
�܂��́A�R�̃u���b�N�̒����L���ăp�^�[�����Ƃɕ��ׂĂ݂܂��B
[�u���b�N�P]�|�@���b�@ �i���_�͏o���E�E�E�j
[�u���b�N�P]�|�A���e�@ �i��19�ȁu�Z�d���v�j
[�u���b�N�P]�\�B���a��i�����A�������l�E�E�E�o���g���܂ގl�d���j
[�u���b�N�Q]�|�@���b�@ �i�����ő��́E�E�E�j
[�u���b�N�Q]�|�A���b�@ �i��20�ȁu���ݕv�l�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�v�j
[�u���b�N�R]�|�@���e�@ �i�a�l�A�P���r�[�m�͂܂��E�E�E�A���g�[�j�I�Ɣ��݁j
���p�^�[���`���̂Ȃ����
[�b�|�e�|�a��]�\�b�\�e
���p�^�[���a���̂Ȃ����
�b�|[�b�\�e�|�a��]�\�e
�|�C���g�́A[�u���b�N�P]��P�X�Ȃ����ޑO��̃��`�^�e�B�[���H�ł��B�@�̂b���A��P�X�Ȃe���o�ćB�̌����ł͂a��ɕς���Ă��܂��B���̂���[�p�^�[���a]�ł͑����̂e�ɂȂ���܂��B�b�ɂȂ���[�p�^�[���`]�ł͂킴�킴�a��ɕς����Ӗ��������ł��B�������X��[�p�^�[���a]���������ƂɂȂ�A���C�o�[���͂����l�����̂ł��B
������܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B
���p�^�[���`���́A�a��b���o�Ăe�ɂȂ���B
���p�^�[���a���́A�b����b�ɂȂ���A����u���b�N���łe���o�Ăa��ɕς���Ă��瑮���̂e�ɂȂ���B
���p�^�[���a�������R�Ȃ��Ƃ͈꒮�đR�ł��B
�i�T�j�����ʏ؋�
����܂ł�[�p�^�[���a]���{���̌`�ł���Ƃ̊m������ꂽ�Ǝv���܂����A���̍��ł͍X�ɕ���̐i�s�Ƃ������_���猟���Ă݂܂��傤�B
�u�ٔ��̏�v�̑O���ɂ̓X�U���i�̎p�͌����܂���B�}���`�F���[�i���t�B�K���̕�e���ƕ���������A���_����ȏ͂������Ȃ��X�U���i�����z����ɂ��Ė@��ɓo�ꂵ�Ă��������܂��A�u���ݗl�A���҂��������B2000�M�j�[�p�ӂ������܂����B�t�B�K���ɑ����Ă��x�����������܂��v�ƁB�����ł��A�X�U���i�̓t�B�K���̎؋����H�ʂ��Ď����Ă����̂ł��B��̂ǂ��̒N�ɗp���ĂĂ�������̂��H����͔��ݕv�l����ł����B���̕����I�y���ł͐���������܂��A�{�[�}���V�F�̌���ł́A�X�U���i���u���ݗl�A���҂��������B�����l��蒸�Ղ��܂������̎��Q�������x�����������܂��v�Ƃ͂�����ƌ����Ă��܂��B���̊ԃX�U���i��"���ݕv�l�ɉ���Ă���"�̂ł��B
�Ȃ�Α�20�ȕv�l�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�u�X�U���i�͂܂����Ȃ��v�͐�Ɂu�ٔ��̏�v�̑O�A����[�p�^�[���a]�łȂ��Ă͂Ȃ�܂���B[�p�^�[���`]���Ƃ���ƁA�����O�ɉ��������Ă���l�Ԃɑ��āA�u�܂����Ȃ��v�͖������܂��B���ꂱ��[�p�^�[���a]�����������Ƃ̓����ʏ؋��ł͂���܂��B
�X�ɉ��y�ʂ��猩�Ă��A�u�ٔ��̏�v�`�u�\�v���m�E�\���v�`�u�\�v���m�E�f���G�b�g�v�ƕ���[�p�^�[���`]�����A���I�ȁu�ٔ��̏�v���͂��ތ`�ŁA2�Ȃ̔����������y�Ȃ��O��ɔz�u����Ă���[�p�^�[���a]�̂ق�����艹�y�I�ł���A���[�c�@���g�I�Ȃ܂��ł���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��������C�o�[�����̐������̏ؖ��ł��B
�i�U�j�y���̌���
�E�u���C�g�R�b�v�ł�[�p�^�[���`]
�E�x�[�������C�^�[�Łu���[�c�@���g�V�S�W�v�i�V�R���j��[�p�^�[���`]
�u���C�g�R�b�v�ł�[�p�^�[���`]�Ȃ͓̂��R�ł��傤�B�����I�ɂ͏\���`�����X���������x�[�������C�^�[��[�a]���̗p���܂���ł����B�V���̃x�[�������C�^�[��������̗p���Ȃ������̂ɂ͉������R�ł�����̂ł��傤���B�����ɋꂵ�݂܂��B
�i�V�j���_
�@�������A�䏊����ɂ���ām�p�^�[���`�n�ŏ㉉�A���̌`�̂܂�20���I�㔼�܂ł��Ă��܂����B����ɋ^������������E�o���[�^���C�o�[�����A1965�N�ɐ������`���@��N�������B
�A���C�o�[���́A�m�p�^�[���a�n�����[�c�@���g���Ӑ}�����������`�ł���ƋK�肵���B �@�������A73�N���x�[�������C�^�[�u���[�c�@���g�V�S�W�v�͂��̐����̗p�����A�����Ɏ����Ă���B
�@ ��"[�p�^�[���a]���������͕̂����邪�A[�p�^�[���`]�͏����̌`�Ȃ̂�����A�����ے肷��͍̂s���߂��ł͂Ȃ���" �Ƃ̔��_���������Ă������ł���B�m���ɂ�����ꗝ���邾�낤�B�������玄�͂������������A[�p�^�[���`]���̗p����Ȃ�o���g���ƃA���g�[�j�I�̈�l����ɂ��ׂ����ƁB����Ȃ珉���̒����ȍČ��Ƃ��ė��ɂ��Ȃ��Ă���B�Ƃ��낪�c�O�Ȃ���A���̃X�^�C���ł̃v���_�N�V�����͎��̒m����葶�݂��Ă��Ȃ��B���̃I�y���W�҂̊F�l�́A���̃X�^�C�����̗p���Ă݂Ă͂��������낤���H
�u�w�t�B�K���̌����x�����X�^�C���ł̌����v�A�Ȃ��Ȃ��C���p�N�g����̂�����ł͂Ȃ����B
����I�ȃ��C�o�[�����̂������ŁA��R���̏��Ԃ��������K�肳��܂����B�������`�ł���[�p�^�[���a]�́A1973�N�A�v���b�`���[�h�w���̃O���C���h�{�[�������ŏ��߂Ď������Ă��܂��i���̎莝���\�t�g�ł́j�B�Ȍ�[�p�^�[���a]�̗̍p�͑����̌X���ɂ���܂��B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E[���_�Q]���[�c�@���g���Ӑ}�����������ȏ���[�p�^�[���a]�ł���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
2008.05.26 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�Q
����Q�́���3���̋ȏ��ȑO����e���r�ʔ̃`�����l���ŁA�I�y���c�u�c���b�c���ďC�������Ƃ�����܂��B�u�t�B�K���̌����v�u�֕P�v�u�J�������v�u�g�D�[�����h�b�g�v���S���g�̃Z�b�g�ɂ����̂ł����A���́u�ӏ܂̎�����v��������Ƃ��̂��Ƃł����B
�u�t�B�K���̌����v�́A�T�[�E�R�����E�f�C���B�X�w���o�C�G�����������X�O�N�̃n�C���C�g�b�c��I�т܂����B��R���ɂ́A�Z�d���u���̕��i�ŕ�e�ƕ������Ă�����v�`���ݕv�l�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�u�X�U���i�͗��Ȃ��v�u�Â��y���������K���Ȏ��́v�`�u���敗�̓�d���v�����̏��ԂŎ��^����Ă��܂����B�����"�����Ⴄ"�ƈ�a�����o���܂����B���܂ł̎����̋L���Ƃ͈Ⴄ�̂ł��B�}���Ńx�[���V�U�c�u�c�Ɣ�ׂĂ݂܂����B�Ȃ�ƁA�ŏ��̋ȂƂQ�Ԗڂ̋Ȃ�����ւ���Ă��܂��B���̕����A���̒��ɂ͓�ʂ�̋ȏ������݂��Ă��邱�ƂɋC�Â����u�Ԃł����B
�ł͑�R���̋ȏ��ɂ��Č��������܂��B�u�Z�d���v�u���ݕv�l�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�v�u���敗�̓�d���v�A�y�ȃi���o�[�ł����܂��ƁA��P�X�ȁA��Q�O�ȁA��Q�P�ȁi���̃i���o�����O�̓x�[���V�U�c�u�c�ɏ]���Ă��܂��B���̔ł͑�W�ȁu��������A��т̂����ɉԂ��܂��v����X�Ȃɂ��J��Ԃ���Ă��܂��B�����łȂ��ł͂��̕�����P�W�ȁA��P�X�ȁA��Q�O�ȂƂȂ��Ă�����A�����ƎႢ�ԍ��̂��̂�����܂��j�̕����̋ȏ�����ʂ葶�݂��Ă���̂ł��B�����ł́A�ǂ����Ă����������ۂ��N�������̂��H ���[�c�@���g���{���Ӑ}�����̂͂ǂ����������̂��H �����܂��B
�i�P�j�u���b�N�Ŋ���
���Y�y�Ȃ̑O��ɂ̓��`�^�e�B�[���H���t�т��Ă��܂����A�����͈�̃u���b�N�Ƃ��Đ藣�����Ƃ͂ł��܂���B���������Ċy�Ȃ��ړ��������肷��ꍇ�͈�̂܂Ƃ܂����u���b�N�Ƃ��ē��������ƂɂȂ�܂��B�܂��̓u���b�N�ʓ��e��\�L���܂��B
[�u���b�N1]�i�ٔ��̏�j
�@���`�^�e�B�[���H�u���_�͏o���v�i�h���E�N���e�B�I�A�}���`�F���[�i�A�t�B�K���A���݁j
�A��P�X�ȘZ�d���u���̕��i�ŕ�e�ƕ������Ă�����v�i�}���`�F���[�i�A�t�B�K���A �o���g���A�h���E�N���e�B�I�A���݁A�r������X�U���i�j
�B���`�^�e�B�[���H�u�����A�������l�v�i�}���`�F���[�i�A�o���g���A�X�U���i�A�t�B�K���j
[�u���b�N�Q]�i���ݕv�l�̃��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�j
�@���`�^�e�B�[���H�u�����ő��̔������������Ă���v�i�o���o���[�i�A�P���r�[�m�j
�A��Q�O�ȃ��`�^�e�B�[���H�ƃA���A�u�X�U���i�͗��Ȃ��v�u�Â��y���������K���Ȏ��́v�i���ݕv�l�j
[�u���b�N�R]�i���敗�̓�d���j
�@���`�^�e�B�[���H�u�a�l�A�P���r�[�m�͂܂���ɂ��܂��v�i�A���g�[�j�I�A���݁j
�A���`�^�e�B�[���H�u�b���āA���݂͉��ƌ���ꂽ�H�v�i���ݕv�l�A�X�U���i�j
�B��Q�P�ȏ���d���u���敗�Ɋ�E�E�E�v�|�u�Â��������v�i���ݕv�l�A�X�U���i�j
�i�Q�j�Q�̃p�^�[���ɕ��ނ���
���Ԃ͓�ʂ葶�݂��Ă��܂��B[�P]�|[�Q]�|[�R] �� [�Q]�|[�P]�|[�R]�ł��B
[�p�^�[���`]���u���b�N[�P]�|[�Q]�|[�R]�̏�
�@�J�������w���T�O�N�b�c
�A�G�[���q�E�N���C�o�[�w���T�T�N�b�c
�B�W�����[�j�w���T�X�N�b�c
�C�x�[���w���U���c�u���N�U�U�N�c�u�c�A�M�����^�[�E�����l���g���o
�D�x�[���w���U�W�N�b�c
�E�V�����e�B�w���p���E�I�y�����W�O�N�c�u�c�A�W�����W���E�X�g���[�������o
�F�f�C���B�X�w���X�O�N�b�c
�G�A�[�m���N�[���w���U���c�u���N�O�U�N�c�u�c�A�N���E�X�E�O�[�g���o
[�p�^�[���a]���u���b�N[�Q]�\[�P]�\[�R]�̏�
�@�v���b�`���[�h�w���O���C���h�{�[���V�R�N�c�u�c�A�s�[�^�[�E�z�[�����o
�A�x�[���w���V�U�N�c�u�c�A�W�����E�s�G�[���E�|�l�����o
�B�J�������w���V�W�N�b�c
�C�x�[���w�� ����������قW�O�N�c�u�c�A�w���Q�E�g�[�}���o
�D�A�o�h�w���A���E�f�A�E�E�B�[������X�P�N�c�u�c�A�W���i�T���E�~���[���o
�E�n�C�e�B���N�w���O���C���h�{�[���X�S�N�c�u�c�A�X�e�B�[�����E���h�J�E���o
�F���[�^�w���t�B�����c�F�܌��ՂO�R�N�c�u�c�A�W���i�T���E�~���[���o
�G���[�R�v�X�w���A�V�����[���[����O�S�N�c�u�c�A�W���������C�E�}���e�B�m�e�B���o
������S�P�U�_�̂������x���X�ÂƂ������ʂƂȂ�܂����B�܂������ŕ����邱�Ƃ�[�p�^�[���a]�����߂ēo�ꂷ��̂��P�X�V�R�N�ŁA����ȑO�͑S��[�p�^�[���`]�ł��邱�ƁB�V�R�N�ȍ~��[�p�^�[���a]���D���ł���A�Ƃ������Ƃł��B��̋ȏ��A����͈�̂ǂ��������ƂȂ̂��A�ǂ��炪�������̂��H����͂P�X�U�T�N�ɏo���ꂽ�}�C�P���E���C�o�[���̊w���ɋN�����Ă��܂��B
����̓��C�o�[�����ɂ��Ă��b���������܂��B
2008.05.21 (��) �u�t�B�K���̌����v�`3�l�̕��_�����Y��Ղ̌���
����P�́�3�l�̕��_�����[�c�@���g�̉̌��u�t�B�K���̌����v�̌���́A�t�����X�l�s�G�[�����I�M���X�^���E�J�����E�h�E�{�[�}���V�F�i�P�V�R�Q�|�P�V�X�X�j�������A�P�V�W�S�N�ɏ������ꂽ�Y�ȁu�@�O�Ȉ���A���邢�̓t�B�K���̌����v�ł��B�{�[�}���V�F�̓p���̂����Ȃ����v�E�l�̎q���ɐ��܂�܂������A���O�ꂽ�˔\�ƓV�˓I�Ȑ��n��̏p�ŁA���C�P�T���`�|���p�h�[���v�l�̂��C�ɓ���ƂȂ��ċM���ɂ܂łȂ��Ă��܂��܂��B����Ȕނ��i�t�����X���{�̈ӌ��Łj�A�����J�Ɨ��푈�ɉ��S���Ȃ��珑�����������M����`�̋Y�Ȃ����̢�t�B�K���̌�����Ȃ̂ł��B�ނ̎v�z���ł��悭����Ă���A�����t�B�K�����A���}���B�[���@���݂Ɍ������Č����Z���t�����p���Ă݂܂��傤�B�u�M���A���Y�A�g���A�K���E�E�E�����������������ɓ���邽�߂ɁA���Ȃ��͉����Ȃ����܂����H���܂�Ă����A�������ꂾ���̂��Ƃ��Ⴀ��܂��B���ꂾ���̂��Ƃł����܂ł̂��̂���ɂ�����ɂȂ����E�E�E�Ƃ��낪���̉��Ȃ́E�E�E���������Ă������Ƃ����̂��߂ɂ��A����Ƃ�����m�b�A�ˊo���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ�������ł���v�i�Έ�@�G��j�B���̃t�B�K���̃Z���t�����K���Љ�ւ̋���Ȕᔻ�ł���{�[�}���V�F���g�̃��b�Z�[�W�ɑ��Ȃ�܂���B�ŋߊ��s���ꂽ�A�����J�̖{�Ɂu�{�[�}���V�F�͎q���̂���"���������@����������"�ƌĂ�Ă����v�Ƃ��邻���ł��B�����"�J�����Ƃ���̑��q"�Ƃ����Ӗ��ł����A�������Ă݂Ă��������B"�t�B�X�E�J����"�E�E�E�����ł�"�t�B�K��"�Ȃ̂ł��B�ނ͂��łɎq���̂��납��u�t�B�K���v�������킯�ł��B���̃t�B�K�����{�[�}���V�F�̏�L�Z���t�͓��{���{�łU�y�[�W�ɋy�Ԓ���Ȃ��̂ŁA�ނ��u�t�B�K���̌����v�ɍ��߂��v���̊j�S�����Ȃ̂ł����A������ꂱ�������̈א��ҁ��M���K�w�ɂƂ��čł������v�z�������̂ł��傤�A�I�y���ł͊��S�ɃJ�b�g����Ă��܂��B
���č��x�̓��[�c�@���g�i�P�V�T�U�|�P�V�X�P�j�ł��B�ނ��c�ɒ��U���c�u���N�̋{��y�m�̉Ƃɐ��܂ꂽ�����̎q�B��i�ƃP���J���ĂQ�T�ŃE�B�[���ɏo�Ă��ēƂ藧�����܂��B�s�A�m���t�Ɨ\�t��Ŕ�����q�ɂȂ�܂����A�ނ̖��̓I�y���Ńq�b�g�������Ƃł����B������C�^���A��́B�����łԂ����������̂��t�����X�ŕ]���ɂȂ��Ă���u�t�B�K���̌����v�ł����B�Ƃ��낪���N��Ɋv�����T���Ă���i�M���̗͂���܂��Ă����j�t�����X�ł͂Ȃ�Ƃ��㉉�������ꂽ���̂́A�܂��܂��n�v�X�u���N�Ƃ̌����������I�[�X�g���A�ł͏㉉�֎~�ƂȂ��Ă����i�ł��B�i�n�v�X�u���N�Ƃ�����̂͂P�X�P�W�N�ł��j�B����Ȋ댯�v�z�����ς��̖���̃I�y�����́A�܂Ƃ��ɂ�������͋����Ȃ��Ɍ��܂��Ă��܂��B�ł����[�c�@���g�͂��̍�i�̃I�y�������ǂ����Ă����������������B���̌���i�ɏh�銈�������Ƃ�������̑����݂����Ȃ��̂������Ƃ��Ă����̂ł��傤�B�����Đ��N��̂P�V�W�X�N�Ƀt�����X�v�����T�����ؔ��������k������Ă����̂ł��傤�B�v�����N���Ă��܂����炱��"�������M���𝈝����镨��"�͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��B�Ƃɂ����ނ͂��̃^�C�~���O�������͂Ȃ������B���[�c�A���g�����̃I�y�������v���������̂͂P�V�W�T�N���ƌ����Ă��܂��̂ł��̃`�����X�͋͂��S�N�Ԃ����Ȃ�������ł��B���̋͂��ȃ^�C�~���O������Ō�����c�������[�c�@���g�̃Z���X�ƍ˔\�͈�̂Ȃ�ƌ`�e���Ă悢�̂�������܂���B���y����邾���łȂ������ǂޖڂ��V�˓I�������̂ł��B���̂������Ŏ������͐l�ނ̕�Ƃ������ׂ���i��������ł���̂ł�����B
�ł͂����ő�R�̒j�ɓo�ꂵ�Ă��炢�܂��傤�A�ނ̖��̓������c�H�E�_�E�|���e(�P�V�S�X�|�P�W�R�W)�A�C�^���A���܂�̃��_���l�B�ނ������[�c�@���g�̈ӂ��̌��u�t�B�K���̌����v�����Ɉ����������������傢�Ȃ闧���҂̈�l�Ȃ̂ł��B�ނ̏��N����A��Ƃ̓��_��������L���X�g���ɉ��@���܂��B������Ĕނ̓��F�l�c�B�A�Ő��E�҂ƂȂ�܂����A�����̎��R�Ŏ��R���I�C�����炨���������ɂ͂Ȃ��߂��ɕ��������𑗂�悤�ɂȂ�A�����Ǖ�����Ă��܂��܂��B�H��̏����炵�J�T�m���@�ɏo������̂����̍��ł��B���ꒅ�����E�B�[���ŋ{��y���̃T���G���ɔ\�͂��A�{�쎍�l�Ƃ��č̗p����܂����B���[�c�@���g�ɂƂ��ċ{����ɔނ��������Ƃ��ǂ�Ȃɂ��肪�����������m��܂���B���[�c�@���g����u�t�B�K���v�̑��k�����ނ͑�{���������B�M�����h�����镔�����J�b�g�����艸�₩�ȕ\���ɕς���Ȃǂ��đ�{�������A�X�ɋ{����̃l�S�V�G�[�V�����������ďo�܂��B�����āA��i�R�c���ʂ����ɒ��ڍc�郈�[�[�t�Q�����������Ƃ����E���g���b���̋Ƃ��g���āA���ɏ㉉�������t�����̂ł����B
�������ĉ̌��u�t�B�K���̌����v�́A�P�V�W�U�N�T���P���A�E�B�[���̃u���N����ŏ�������܂��B�t�����X�v���ɐ旧�킸���R�N�O�̂��Ƃł����B
�̌��u�t�B�K���̌����v�́A���̂悤�Ɍ���҃{�[�}���V�F�A��Ȏ҃��[�c�@���g�A�r�F�҃_�E�|���e�Ƃ�������̕��_���̍˔\����̂ƂȂ萳�ɂ��̎����O���Ă͂ł����Ȃ������^�C�~���O�Ő��ݏo���ꂽ��O���̌���ƌ������Ƃ��ł���̂ł��B�������͂��̂R�l�����̎����A���̐��̒��ɑ��荞��ł��ꂽ�_�l�̍ٗʂɂ����犴�ӂ��Ă����ӂ��������̂ł͂���܂���B
�{�[�}���V�F�̓t�����X�l�A���[�c�@���g�̓I�[�X�g���A�A�_�E�|���e�̓C�^���A���܂�A����̓X�y�C���Ō���̓C�^���A��E�E�E�E�ȂǂȂǍl����Ɓu�t�B�K���v�͐^�ɍ��ۓI�ȍ�i���Ƃ������Ƃ�������܂��B���[���b�p�̉p�m�����W���s���K��������ɖ��o�鎞��̐�삯�ƂȂ�����Ղ̍�i�E�E�E�ƌ��������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
����2�́�����̓W�J�Ƃ��̖ʔ���
�ȏ�A�u�t�B�K���v�̎v�z�I���ʂɍi���Ă��b���Ă��܂������A�����I�ɂ����ɗǂ��ł����ʔ�����i�ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B���[�c�@���g�����̌���ɐڂ��ăI�y�������v���������̂́A���̎v�z�ɋ�����������Ƃ����̂͏q�ׂĂ����Ƃ���ł����A������̉����Ƃ��Ă̖ʔ����Ɗ����x�̍����ɍ�ȉƂƂ��Ă̚k�o�����������Ƃ��������Ȃ��ł��傤�B�C�^���A��̃I�y�����E�B�[���Ńq�b�g������Ƃ������U�̖���������ɂ͂��̍�i�������Ăق��ɂȂ������̍�i�Ɏ��������y�������Α�q�b�g�ԈႢ�Ȃ��A�Ƃ̋����m�M���������̂��Ǝv���܂��B�ނ���"�v�z�ɋ���"��������"��ȉƂƂ��Ă̚k�o"�̂ق������������̂�������܂���B����ł͂��炷���ƌ������E�E�E�E
�@ �S��鏘�Ȃ��I���ƁA�t�B�K�����ǂ��Ƀx�b�h��u�����ƕ����̒��Ő��@�𑪂��Ă���B�Ȃɂ����Ă���̂ƕ����X�U���i�Ɂu�a�l���ׂ̂��̕��������������B�֗�������ȁv�B��������X�U���i�u���͂���A�����ēa�l�͂���"�̎匠"�i�̓��̏�������������O�ɏ�������������M���̌����̂��Ɓj�������Č����O�̎����˂���Ă����ł����́v�E�E�E���̃X�^�[�g�̉�b���猋�����T������l�̏Ƃ��ꂩ�牽���N���낤�Ƃ��Ă���̂����ꔭ�ł킩��܂��B���Ȃ킿�t�B�K���͂���Ȃ��Ƃ�ژ_�ގ�l�i���݁j�ɑ��������߂��点�ĂȂ�Ƃ����������̌��������ς܂��Ă��܂����Ƃ���킯�ł��B
���Ă��̍��́E�E�E�E�E
�@"���ݕv�l������������"�Ƃ����U�莆�������o�W���I�i�̓��̉��y���t�j���g���Ĕ��݂ɓ͂���"���i�[��"���݂�����������
�A�X�U���i��"�D�F��"���݂�U�f�����A�X�U���i�ɕϑ��������P���r�[�m�Ƃ����v�t���^�������̏�����҂����Ĕ��݂��\��
�B���l���g���Ĕ��݂��قߎE���ɂ��Č���������������߂�����
�E�E�E�E�E���̍����̌���˂��Č������������Ă��܂��Ƃ����؏����B
�Ƃ��낪�A�X�U���i�Ɣ��ݕv�l���P���r�[�m�ɏ��������Ă��鎞�ɕs�ӂɔ��݂�����Ă��̌v�悪�o���ď��ŁB�i���̑�Q���A���������g�����l�̓���ւ��ɂ���x�������ƃX�����̖ʔ����I�j
�Ȃ���x�́E�E�E�E�E"�X�U���i�����݂�U�f���A�X�U���i�ƕv�l���ϑ��œ���ւ���Ĕ��݂炵�߂�"�E�E�E�E�E�Ƃ����V�K�v���v�l���l�āA�X�U���i�ɒ�Ă����s�Ɉڂ��i���̓R���C�I�j�B�����A�v�l�͂��Ă���قǂ܂łɐ��ӂƏ�M�������Ď������������Ă��ꂽ�i���̂�����̂��b�͑O�i�b���b�V�[�j�u�Z���B���A�̗����t�v�ł����������j���݂����������ɖO���ĕ��C�����ł���̂�Q���Ȃ�Ƃ��ނ̖ڂ������Ɍ��������悤�Ƃ��Ă���̂ł��B�|�C���g��"���̐V�K�v����t�B�K���͒m��Ȃ�"�Ƃ������ƂŁA���ꂪ��S���̖ʔ����ɂȂ���܂��B
����t�B�K�������˂ɏ��������āA���͏����ȑO�������̃}���`�F���[�i�Ƃ����N�����ɋ�����āA���̎��u�Ԃ��Ȃ��ꍇ�͌�������v�Ƃ����ؕ��������Ă��܂��Ă���B���͂܂��Ԃ��ĂȂ����Ԃ��邠�Ă��Ȃ��B�����m�������݂͂ق����݃X�U���i�Ƃ̌����͔F�߂Ȃ��Ƌt�P�ɂł�B�ٔ��B�Ƃ��낪�т�����V�̌����B�Ȃ�ƃ}���`�F���[�i�̓t�B�K���̂��ꂳ��ŁA���ăt�B�K���ɋ�`���r�߂������ĕ��Q��ژ_��ł�����t�o���g�������e�������B����ň�]���ďj�����[�h�ɁB���ꂪ��R���B ��S���͔��ݕv�l�̌v����s�̏�B�Èł̒��ŃX�U���i�ɕϑ������v�l�݂͂���ƒm�炸�ɖ{�C�Ō������B���̍���m��Ȃ��t�B�K�����A�X�U���i�����݂ƈ�������Ƃ����\���Č���A�����`�����ĒQ���߂��ށB�Ƃ��낪�I�Ղ��̂��炭������j�����t�B�K���A�C�Â��ʐU������ĕv�l�ɕϑ������X�U���i���������ƁA���x�̓X�U���i���{��S���E�E�E�E���X�V�`���G�[�V�������߂܂��邵���ς��ʔ����A�������B�Ō�͔��݂��v�l�Ɏӂ�v�l�����݂������A�t�B�K���ƃX�U���i���߂ł��������A�����Ă�����g�A�o���g���ƃ}���`�F���[�i������ă��f�^�V���f�^�V�Ŗ��Ƒ�����܂��B
���ǐL�� �����5��26���A�{��ɖ߂��āu�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�Q�����͂����܂��B
2008.05.19 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�P
����P�́������������������Ƃ�����������������N��������A�u����Ȃɖʔ�����Ό�����ǂ�ł����v�A�̌��u�t�B�K���̌����v�ɂ��ĐF�X���������Ă������̂��ƁA�Έ�G�搶�ɂ��������āA�{�[�}���V�F��u�@�O�Ȉ���A�܂��̓t�B�K���̌����v�i�V���فj��ǂ�ł݂܂����B�搶�Ƃ͂b�c�|�a�n�w�u�Ȃ��ɂ��烂�[�c�@���g�E�R���N�V�����v�i�a�l�f�@�i�`�o�`�m�j�̐��쎞�A�y�ȉ�������肢���Ĉȗ��e�������t�����������Ă��������Ă��܂��B���̖{�͐搶�̖�ł����A���̖{�������邱�ƂȂ���A������ō��ɖʔ����B�p���̂����Ȃ����v���̑��q�ɐ��܂ꂽ�{�[�}���V�F���A����̍ˊo�����𗊂�ɁA�M���̏̍�����ɓ���Ď��̌��͂̒����ɓ����đ劈�������A����Ȏ���̕��_���̐l���ɂ͋����s���Ȃ����̂�����܂��B�����āA���[�c�@���g�Ƌ{�쎍�l�_�E�|���e�����̋Y�Ȃɏo�����킵�ĉ̌��u�t�B�K���̌����v���a������킯�Ȃ̂ł����A���̂�����̂�����͎���ŁB
���āA�{�[�}���V�F�Łu�t�B�K���̌����v��ǂ�ł̓I�y���c�u�c������Ƃ���"���݊ӏ�"�����Ă���������A"�����"�Ƃ����Z���t�ɂԂ���܂����B����{�Q�Q�X�y�[�W�̂Q�s�ځA��4���̃t�B�K���̃Z���t�u�����l�̖ڂɂ͌����Ȃ����ɂ��A�����h�\���グ��C����������ł���Ƃ��l���������v���A�����ӏ��A�V�U�N����x�[���̂c�u�c�ł́A�u���J�̔O������ɑウ�āv�Ƃ������{�ꎚ���ɂȂ��Ă���B���炩�ɈႤ�Ӗ����e�ł��B�����Ŏ莝���̃t�B�K���̂c�u�c�Ƃb�c�ŁA���̕����̃C�^���A�ꂪ�ǂ��Ȃ��Ă��邩�ׂĂ݂܂����B���̌��ʋ����ׂ����������������̂ł��B���̉ӏ���"����������������"�Ɖ̂��Ă�����̂�"����������������"�Ɖ̂��Ă�����̂��������Ă����̂ł��B����͈�̂ǂ������킯���낤�H�@�Ȃ����̂悤�Ȋ�Ȃ��Ƃ��N�����̂��낤���H�@�ǂ��炩���������āA�ǂ��炩���ԈႢ�Ȃ̂��H�@�ȉ������̒ǐՋL�^�ł���܂��B
�̌��u�t�B�K���̌����v��S���P�R��t�B�i�[���A�t�B�K���́u���ׂĂ͐Â��ʼn��₩���v����n�܂镔���A���ݕv�l�ɕϑ������X�U���i������ƌ��j�����t�B�K�����������Ă��炩����ʂ�����܂��B�t�B�K�����u�����قNjM���̂���l�����̐V�ȂƂ����܂�Ɏp�������܂����v�ƍ�����Ɓu�d�Ԃ����Ă�肽����v�Ɓi�v�l�ɕϑ����Ă���j�X�U���i�B�t�B�K�����u���Y�ꂭ�������܂��A����ȗ���҂̂��Ƃ́v�ƃW���u��ł��āu���l�ɔR����S������܂��v�Ə�ݍ��ށB�����ŃX�U���i�́u������Ȃ��ɁH�v�Ɩ₢�����邪�A������ăt�B�K���������Z���t���A�u�r���������������������@�����@�����������������v�̂��̂Ɓu�r���������������������@�����@�����������������v�̓�ʂ肠��̂ł��B
���Ƃ��A�������ꕶ���̈Ⴂ�ł����A�����������������͕������A�����������������͑��h�Ƃ����S���Ⴄ�Ӗ��̒P��ɂȂ�܂��B���S�̂̈Ӗ��́A�O�҂�"���݂��X�U���i�ɕ��C���Ă���u�������v�ɑウ�Ď��ƕ��C���܂��傤"�ŁA��҂�"����̑���ɉ��l�ɑ���u���h�v������܂����琥��"�ƂȂ�܂��B�Ώۂ�ς��ĉ��߂���ΈӖ��͒ʂ��Ă��܂��Ƃ͂����Ă��A��̌`�����݂��Ă���̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤�B
�i�P�j�Q�̃p�^�[���ɕ��ނ���
�܂��͑�\�I�ȁu�t�B�K���̌����v�̂c�u�c�A�b�c�P�U�^�C�g�����ǂ���̌��t�ʼn̂��Ă��邩���ʁE���ނ��܂��B���@�́A���Y�����̃q�A�����O�ɂ���čs���܂����B���͉s���꒲�^���͊�����̂��߁A���ʂ͔�r�I�e�ՂŁA���ʑS16�_�̂���14�_�͊��S�Ɏ��ʂ��ł��܂����B�x�[���V�U�c�u�c�̃w���}���E�v���C�ƃJ�������V�W�b�c�̃W���Z�E���@���E�_���A2�_�̔��ʂ����ɂ��������̂ŁA�����͕t���̈Ɍꎚ�����Q�l�ɂ��܂����B
[�p�^�[���`]��"����������������"�Ɖ̂��Ă������
�@�x�[���w���V�U�N�f��łc�u�c�A�w���}���E�v���C�i�t�B�K���j�A�W�����E�s�G�[���E�|�l�����o
�i�ǂ���Ƃ������Ȃ������Ȕ������A�Ɍꎚ���͂����������������Ȃ̂ł�����ɕ��ށj
�A�J�������w���V�W�N�b�c�A�W���[�E���@���E�_��
�i������ǂ���Ƃ������Ȃ��̂ňɌ�Ζ��������������ɏ]���j
�B�V�����e�B�w���p���E�I�y�����W�O�N�c�u�c�A�W���[�E���@���E�_���A�W�����W���E�X�g���[�������o
�C�A�o�h�w���A���E�f�A�E�E�B�[������X�P�N�k�c�A���`�I�E�K�b���A�W���i�T���E�~���[���o�@
�D�n�C�e�B���N�w���O���C���h�{�[���X�S�N�c�u�c�A�W�F�����h�E�t�B�����[�A�X�e�B�[�����E���h�J�t���o
�i�Ɍꎚ���������������������j
�E���[�^�w���t�B�����c�F�܌��ՂO�R�N�c�u�c�A�W�����W���E�X�[���A���A�W���i�T���E�~���[���o
�F���[�R�v�X�w���V�����[���[����O�S�N�c�u�c�A���J�E�s�T���[��
�i�Ɍꎚ���������������������j
�G�A�[�m���N�[���w���U���c�u���N���y�ՂO�U�N�c�u�c�A�C���f�v�����h�E�_���J���W�F���A�N���E�X�E�O�[�g���o
�i�Ɍꎚ���������������������j
[�p�^�[���a]��"����������������"�Ɖ̂��Ă������
�@�J�������w���T�O�N�b�c�A�G�[���q�E�N���c�i�t�B�K���j
�A�G�[���q�E�N���C�o�[�w���T�T�N�b�c�A�`�F�[�U���E�V�F�s
�B�W�����[�j�w���T�X�N�b�c�A�W�F�[�b�y�E�^�f�B
�C�x�[���w���U���c�u���N���y�ՂU�U�N�c�u�c�A�����^�[�E�x���[�A�M�����^�[�E�����l���g���o
�D�x�[���w���U�W�N�b�c�A�w���}���E�v���C
�E�v���b�`���[�h�w���A�O���C���h�{�[�����y�ՂV�R�N�c�u�c�A�N�k�[�g�E�X�N�����A�s�[�^�[�E�z�[�����o
�F�x�[���w�� ����������قW�O�N�c�u�c�A�w���}���E�v���C�A�w���Q�E�g�[�}���o
�G�f�C���B�X�w���X�O�N�b�c�A�A�����E�^�C�^�X
�S�P�U�_�̂������x�����ÂŁA�����������������͂V�O�N��ȑO�ɑ����A�����������������͂V�U�N�ȍ~�Ɍ����Ă��܂��B���������Č��X�͂������������������������̂��V�O�N�㔼������ɂ���������������������āA���݂ł͂������������������g�p���邱�Ƃ������Ȃ��Ă���A�Ƃ����̂����̐��ڂł��B
�����ׂ��͂Q�_�A���[�c�@���g�̃I���W�i����{�͂ǂ��炾�������H �I���W�i���ƈႤ���ɕς����Ɛl�͒N���H �Ƃ������Ƃł��B
�i�Q�j�y���̌���
�E�u���C�g�R�b�v�ł͂���������������
�E�x�[�������C�^�[�ŁE���[�c�@���g�V�S�W�i�V�R���j�͂���������������
�i�R�j����̌���
���̕����A�I�y���̌���P�V�W�S�N�㉉�̃{�[�}���V�F��̋Y�Ȃ̑�{�i�t�����X��j�͂����Ȃ��Ă���\�\
�u�������������@�������@�����@���������������v�i�����Ȃ��Ƃ���ɂ��A�����h�\���グ��C����������ł���Ƃ��l���������j
�i�S�j���_
�@����{�E�{�[�}���V�F��u�@�O�Ȉ���A�܂��̓t�B�K���̌����v�����������������i�t�����X��j�Ȃ̂ŁA���[�c�@���g�̃I���W�i����{�͂����������������ŊԈႢ�Ȃ��B ���[�c�@���g�^�_�E�|���e���I�y�����̍ۂɂ��̕������i�̈ӂł����A�ł���j�����������������Ƃ���\�����Ȃ��ł͂Ȃ����A�����������������ł̏㉉��R�[�f�B���O���P�X�V�O�N��ȑO�ɂ͂P�_�����݂��Ă��Ȃ��Ƃ�����������A���̉\���͊F���ƒf��ł���B
�A�V�R�N���s�̃x�[�������C�^�[�Łu���[�c�@���g�V�S�W�v�ŁA�����������������Ƃ����B ����ȑO�ɂ͑S���Ȃ��������̂��A����ȍ~��R�����������������̎g�p�������Ȃ��Ă䂭�B"���Ђ���"�x�[�������C�^�[�ł̉e���̑傫����������B�������A�ǂ����Ă����������������ɂȂ������͕s���B���������Ă̂��ƂȂ̂��P�Ȃ��A�Ȃ̂��H����ɂ��Ă͓����҂ɐ��������Ȃ����A���i�K�ł͕s�v�B���̃X�e�b�v�Ŏ��R�Ɖ𖾂���邾�낤����B
�ȏォ��A�I���W�i�����������`�͂����������������ł���ƌ��_�ł��܂����B�����Ă����������������Ȃ�I���W�i���ƈႤ�̎����̗p���Ă��܂����Ɛl�̓x�[�������C�^�[���낤�Ƃ������Ƃł��B�Ȃ��Ȃ炻��ȑO�ɂ����������������Ȃ�y�����Ȃ���v���_�N�V���������݂��Ă��Ȃ�����ł��B
�����̌��_�͐Έ�搶�̂��ӌ������������Ċm�����̂ł��B
�@�@ �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E[���_�P]�@�������`�͂����������������ł���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
���ǐL�� �u�w�t�B�K���̌����x�^���̎p�v�͖��T���j���ɍX�V���Ă��܂��B�����ǂݎn�߂Ă������������̒��ɂ̓N���V�b�N�Ɋւ��Ă悭�����m�̕��������łȂ���������������Ǝv���܂��B��҂ł��̘b�ɋ����������Ă������������̂��߂ɁA"�u�t�B�K���̌����v�ӏ܂̎����"�����T���j��5��21���Ɍf�ڂ������܂��B���I�Ȏ���̒��Ő��܂ꂽ��Ղ̎Y���Ƃ����ϓ_����A�^�C�g�����u3�l�̕��_�����Y��Ղ̌���v�Ƃ��܂����B�ܘ_�I�y���Ƃ��Ă̌������킩��₷�������������܂��B
2008.05.12 (��) �N���V�b�N ���m�Ƃ̑����\�\�v�����[�O
���͏I��̔N�P�X�S�T�N�̐��܂�ł���܂��B1950�N��́A����̏��w���ł����B��Ɋ��߂��ďK���n�߂��s�A�m�Ɖ��y�̎��Ƃŕ������u�^���v�ŃN���V�b�N�ɖڊo�߂�����A57�N�ɂ̓J�������^�x�������E�t�B���̏������A59�N�ɂ̓f���E���i�R��i����C�^���A�̌��c�̌����ȂǂɃe���r�ő����A�N���V�b�N���y�̖��͂ɂƂ�߂���Ă䂫�܂����B���w���̏������͔N1000�~�B����œ������s��n�߂��R�����r�A�E�_�C�������h�E�V���[�Y25�Z���`1000�~�Ղ������̂ł��B���u�̓r�N�^�[�̖ƐŃv���[���[5980�~�B�����5���X�[�p�[�ɂȂ��Ŗ������������Ղ���N�������Ă��܂����B�I�[�}���f�B�F�t�B���f���t�B�A�ǂ́u�^���v�A�I�C�X�g���b�t�̃����f���X�]�[���u���@�C�I�������t�ȁv�A�J�U���X�^�[���L���̃x�[�g�[���F���u�`�F���E�\�i�^��R�ԁv�ȂǁB���w���ɂȂ�Ə����͏�������������30�Z���`�Ղ�������悤�ɂȂ�܂����B�����^�[�F�j���[���[�N�E�t�B���́u�W���s�^�[�v�u40�ԁv�A�t���g���F���O���[�́u�G���C�J�v�u7�ԁv�A�g�X�J�j�[�j�́u���v�u���[�}3����v�A�~�����V���F�{�X�g�����́u���z�����ȁv�A�������B���X�L�[�̃`���C�R�t�X�L�[��ߜƣ�A���C�i�[�F�V�J�S���́u�V���E���v�A�M�����X�́u�c��v�A�N���C�X���[�i�o���r���[���w���j�̃x�[�g�[���F���u���@�C�I�������t�ȁv�A�u�����V�������̃`���C�R�t�X�L�[�u�s�A�m���t�ȑ�1�ԁv�ȂǂȂǁA���ł����̉���߉͂�������Ɣ]���ɍ��ݍ��܂�Ă��܂��B���Z����͎����S���������߁A��w�ɓ�������I�[�P�X�g���ɓ��낤�ƌ��߂Ă��܂����B1964�N�����I�����s�b�N�̔N�A�ꋴ��w�ɓ����đ��I�[�P�X�g�����ɓ����A�g�����y�b�g�������4�N�ԁA�y�������[��������w�����𑗂邱�Ƃ��ł��܂����B���̊ԁA��������q����Ƃ́u�Պ����v���A�C��`�Y����Ƃ̓`���C�R�t�X�L�[�������A�g�ɗ]��M�d�ȑ̌��ł����B���ƃs�A�j�X�g�̈����q�q����ƃx�[�g�[���F����4�Ԃ�����܂����B���̂��������l�s�A�j�X�g�ŁA���͊y���������Ɋ���蒭�߂Ă��܂����B�����ǂ����Ă���������ł��傤���B�����̃I�[�{�G�ɋ{��h�Y�����āA���ނ�50���߂��ăf�r���[�����x�炫�̎w���҂Ƃ��đ劈�����ł��B
���Ƃ��āA�����������O�̂悤�ɓ��{�r�N�^�[�ɓ��ЁA�c�ƁA��`���o�Č��݂�BMG JAPAN�_�C���N�g�E�}�[�P�e�B���O���ŁA�l�X�ȃW�������̐���Ɍg����Ă��܂��B
�D���ȃN���V�b�N�͂��Ă����A���R�[�h��Ђł̓W�������ɂ�����邱�ƂȂ��A�c�ƁA��`�A����Ɨl�X�ȋƖ��Ɍg����Ă��܂����B����Ɗҗ���߂���3�N���炢�O����A����ς�̂Ƃ����n���A�N���V�b�N�ɗ����Ԃ��Ċy����ł��܂��B�W�����Ă��낢��ȋȂ����߂Ē����Ă݂�ƁA�ʔ������ƂɂԂ�������悤�ɂȂ�܂����B���Ƃ����[�c�@���g�u�t�B�K���̌����v��3���̋ȏ�����ʂ肠�邱�ƂɋC��������A�X�ɂ��鎞�A��4���̂���Z���t������܂���ʂ肠�邱�ƂɋC�������肵�܂����B����͂Ȃ��H ��������H ���[�c�@���g���Ӑ}�����̂͂ǂ����H ���o�Ă���\�t�g�͂ǂ��Ȃ��Ă���H ���̕ӂ��g�R�g���Nj����Ă䂭�ƁA���܂Ō����ĂȂ��������̂������Ă���̂ł��ˁB�����A�܂��Ɂu���m�Ƃ̑����v�ł��B�����������ق����Ă䂭�ߒ��͂܂�Ő��������̓�����̂悤�ŁA����Ă��Ă���ȂɊy�������Ƃ͂���܂���B�����������琢�E�ŒN���C�Â��Ă��Ȃ���Ȃ��낤���ȂǂƎv�����肵�Ȃ���E�E�E�B���[�c�@���g�u�t�B�K���̌����v�̌����ߒ��ł��鍂���ȉ��y�w�҂ɂ��b�����Ƃ���A�u�����m��Ȃ������A�悭�C�������ˁv�ƌ����܂����B������A���̒��z�܂�ł͂Ȃ��ȂƎ������Ă���܂��BJ.S.�o�b�n�́u�t�[�K�̋Z�@�v���䂪���������͂��܂���B���̋ȏ��ɂ��Ă����邱�ƂɋC�����܂����B�܂��u�~�T�ȃ��Z���v�ɂ���Ȏ��ۂ����X�����āA����������ꂱ�̏�����肵�Ă��b�ł���Ǝv���Ă���܂��B����ȁw�N���V�b�N ���m�Ƃ̑����x�ɂ������t�������������B
�܂��́u�t�B�K���̌����v����n�߂����Ă��������܂��B
�u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�͂��߂�
����̒����V���[���ɁA���m���|�p����ōs��ꂽ2006�U���c�u���N���y�Ռ����A�N���E�X�E�O�[�g���o�u�t�B�K���̌����v�̃X�e�[�W�]���ڂ��Ă��܂����B���c�Ő�����Ƃ������y�w�҂̕��̕]�ł����B�u�o��l���̉��߂͎a�V�����������A���ǂ��ǒ��߂���ł��܂�Ȃ��B�����܂œǂݑւ���Ȃ�A���y���������ɃA�����W��������v�Ƃ�����|�ł����B�������̕���A�����Ō��܂������A�搶�Ɠ������T�˔ᔻ�I�ł��B�A�����̗��R�͈Ⴂ�܂����ǁB�t�ɁA�搶�]��"���y������"�̕����͂��܂�ɋ���߂��č��������Ă��܂��܂����B
�����\���グ�����̂́A���o��̂��Ƃł͂Ȃ��A�u���̍ł�"�V�����Č��Ђ̂���"�U���c�u���N�̃v���_�N�V�����ɂ́A��{��̊ԈႢ����܂܂�Ă���A���ꂪ��肾�v�Ƃ������Ƃł��B
�����܂ł��Ȃ��A�u�t�B�K���̌����v�́A�V�˃��[�c�@���g�̑�\��ł���Ɠ����ɌÍ��̃I�y����i�̒��ł��Q��������ł���l�C���ڂł��B�O�q�U���c�u���N2006�N���E�X�E�O�[�g���o���b��ɂȂ��Ă��܂����A����܂łɂ��A�W�����E�s�G�[���E�|�l���A�W���i�T���E�~���[�A�s�[�^�[�E�z�[���Ȃ��B�X���鉉�o�Ƃɂ��삵�����̃v���_�N�V���������݂��Ă��܂��B�������Ȃ���A�����̒��Ń��[�c�@���g���Ӑ}�����u�t�B�K���̌����v��"�^���̎p"��`���Ă�����̂���̂ǂ̂��炢����̂ł��傤���B����������A���̌��ʂ𐢊E�֔��M����̂����̖ړI�ł��B�����炭���̎w�E�͐��E�Ŏn�߂Ă̂��̂ɂȂ�ł��傤�B�����ċ߂������A�u�t�B�K���̌����v�̏㉉�́A���ׂĎ��̎w�E�ǂ���̌`�ɂȂ�͂��ł��B�Ȃ��Ȃ炻��̓��[�c�@���g�{�l���Ӑ}�������̂ł��邩��ł��B