古楽という名の迷宮へ! 2009年1月~2016年12月
2016/11/05 (土) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅶ)
2016/07/14 (木) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅵ)
2016/04/03 (日) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅴ)
2015/12/16 (水) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅳ)
2015/08/30 (日) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅲ)
2015/06/12 (金) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅱ)
2015/04/05 (火) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅰ)
2014/12/02 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(27)
2014/08/30 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(26)
2014/06/08 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(25)
2014/04/18 (土) 佐村河内問題について
2014/02/13 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(24)
2013/11/11 (月) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(23)
2013/08/22 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(22)
2013/06/02 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(21)
2013/03/19 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑳
2013/01/15 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑲
2012/11/22 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑱
2012/09/16 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑰
2012/06/29 (金) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑯
2012/05/07 (月) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑮
2012/02/24 (金) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑭
2011/11/24 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑬
2011/09/25 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑫
2011/08/07 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑪
2011/06/04 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑩
2011/04/26 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑨
2011/03/08 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑧
2011/02/01 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑦
2010/10/23 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑥
2010/10/05 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑤
2010/09/14 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬④
2010/08/08 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬③
2010/07/11 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬②
2010/06/12 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬①
2010/05/27 (木) ある組合の解散に思う~「古楽」の再開を前に
2009/12/20 (日) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――3
2009/12/07 (月) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――2
2009/11/16 (月) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――1
2009/10/26 (月) 服部幸三先生の思い出
2009/10/16 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――15
2009/09/25 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――14
2009/09/05 (土) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――13
2009/08/17 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――12
2009/07/27 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――11
2009/07/06 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――10
2009/06/15 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――9
2009/05/25 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――8
2009/05/15 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――7
2009/04/28 (火) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――6
2009/04/14 (火) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――5
2009/04/06 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――4
2009/04/01 (水) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――3
2009/03/23 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――2
2009/03/16 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――1
2009/03/09 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――3
2009/03/02 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――2
2009/02/23 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――1
2009/02/16 (月) Ⅱ. トーマスカントルの系譜と音楽――2
2009/02/09 (月) Ⅱ. トーマスカントルの系譜と音楽――1
2009/02/02 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――4
2009/01/26 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――3
2009/01/19 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――2
2009/01/12 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――1
2009/01/08 (木) ようこそ古楽の花園へ!
2016/07/14 (木) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅵ)
2016/04/03 (日) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅴ)
2015/12/16 (水) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅳ)
2015/08/30 (日) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅲ)
2015/06/12 (金) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅱ)
2015/04/05 (火) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅰ)
2014/12/02 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(27)
2014/08/30 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(26)
2014/06/08 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(25)
2014/04/18 (土) 佐村河内問題について
2014/02/13 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(24)
2013/11/11 (月) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(23)
2013/08/22 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(22)
2013/06/02 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(21)
2013/03/19 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑳
2013/01/15 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑲
2012/11/22 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑱
2012/09/16 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑰
2012/06/29 (金) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑯
2012/05/07 (月) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑮
2012/02/24 (金) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑭
2011/11/24 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑬
2011/09/25 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑫
2011/08/07 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑪
2011/06/04 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑩
2011/04/26 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑨
2011/03/08 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑧
2011/02/01 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑦
2010/10/23 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑥
2010/10/05 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑤
2010/09/14 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬④
2010/08/08 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬③
2010/07/11 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬②
2010/06/12 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬①
2010/05/27 (木) ある組合の解散に思う~「古楽」の再開を前に
2009/12/20 (日) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――3
2009/12/07 (月) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――2
2009/11/16 (月) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――1
2009/10/26 (月) 服部幸三先生の思い出
2009/10/16 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――15
2009/09/25 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――14
2009/09/05 (土) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――13
2009/08/17 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――12
2009/07/27 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――11
2009/07/06 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――10
2009/06/15 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――9
2009/05/25 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――8
2009/05/15 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――7
2009/04/28 (火) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――6
2009/04/14 (火) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――5
2009/04/06 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――4
2009/04/01 (水) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――3
2009/03/23 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――2
2009/03/16 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――1
2009/03/09 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――3
2009/03/02 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――2
2009/02/23 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――1
2009/02/16 (月) Ⅱ. トーマスカントルの系譜と音楽――2
2009/02/09 (月) Ⅱ. トーマスカントルの系譜と音楽――1
2009/02/02 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――4
2009/01/26 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――3
2009/01/19 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――2
2009/01/12 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――1
2009/01/08 (木) ようこそ古楽の花園へ!
2016.11.05 (土) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅶ)
7. シャルパンティエ:死者のためのミサ曲今回のテーマは一応前回のCD紹介で終了したことになりますが、ここまでいろいろ前期ヴェルサイユ楽派の音楽を調べたり、聴いたりしているうちに気になったことや、その他に素晴らしいCDもいっぱいありましたのでそれらを少しご紹介したいと思います。はじめにミシェル・コルボが指揮したエラート盤のシャルパンティエの「死者のためのミサ曲(レクイエム)」をとりあげたいと思います。これはずっと以前から私がヴェルサイユ楽派の中で最も気に入っていた録音の一つです。
この音楽の素晴らしさは言葉で言い表せないほど美しく感動的であり、他のヴェルサイユ楽派の作曲家からは聴くことができません。講談社の学術文庫に礒山雅氏が書いた「バロック音楽名曲鑑賞事典」(2007)という本があります。このなかにヴェルサイユ楽派の音楽(CD)もかなり紹介されているのですが、不思議なことにこの名曲はとりあげられていません。同時代の他の作曲家のレクイエムはいくつか紹介されていますが、それらよりはるかに名曲だと私は思っています。
シャルパンティエの「死者のためのミサ曲 Messe pour les trepasses」はニュー・グローヴによると3曲あります。H(ヒッチコック)番号でいうと、H2、H.7そしてH.10になります。このうちH.7だけは以前よりNAXOSから発売されていたと思います。初期ヴェルサイユ楽派の作曲家は国王ルイ14世がモテットを好んだことからミサ曲を書かなかったことは以前にも触れましたが、シャルパンティエはリュリによって宮廷から遠ざけられていたこともあって、ミサ曲を書いています。また生まれはシャルパンティエより30年ほどあとになりますが若くして亡くなった同時代のフランスの作曲家にジャン・ジル(Jean Gilles 1668-1705)という人がおり、彼も有名な「死者のためのミサ曲(レクイエム)」を残しています。これについては後でまた触れますが、ジルは広い意味でヴェルサイユ楽派の1人とされることはあるものの、彼自身パリとは全く縁がなく南仏のトゥールーズで一生を終えています。ヴェルサイユの中央で活躍した作曲家で「レクイエム」を残しているのはアンドレ・カンプラ(Andre Campra1660-1744)で、この作品もよく知られていますが、彼の活躍した時代はヴェルサイユ楽派の中期で、彼ももともと南フランスの生まれで若い頃はエクサン=プロヴァンスやトゥールーズで活躍し、後にパリに出てルイ15世の宮廷礼拝堂の副楽長に就任しました。彼のレクイエムがいつ頃書かれたのかははっきりしませんが、パリ以前の南フランス時代に書かれた、という説が有力です。ですから中央の楽壇にあってレクイエムを作曲したのはこのシャルパンティエだけ(?)ということになるのかもしれません。またシャルパンティエの作品には「レクイエム・エテルナム」で始まる入祭唱(イントロイトゥス)がありません。これは当時入祭唱の固有文はグレゴリオ聖歌で歌うのが習慣だったためとされています。
さて3曲あるシャルパンティエの「死者のためのミサ曲」のうちH.7は既にエルヴェ・ニケ指揮コンセール・スピリテュエルの演奏(NAXOS 8.553173)のCDがあることは触れました。最近になってこれにルイ・ドゥヴォ指揮によるエラート盤(WPCS-16174)が加わり、これにはH.10も収録されています。ドゥヴォ盤は1979年の録音で以前LPで発売されたことがあるようですが、記憶に残っていません。この2曲はどちらも1690年代、シャルパンティエの後年に書かれた作品で4声の合唱からなり、その規模は小さいもので、曲の長さも20分から30分程度の短いものです。H.7は通奏低音の伴奏でどちらかというとプティ・モテを思わせるミサ曲で、曲の最後には「深き淵よりDe Profundis」の詩篇(H.213)が加えられており、これがこの曲の核心部分ともいえます。とても美しいハーモニーによる音楽で、古い時代のポリフォニーを思わせますが、曲としてはやや単調です。H.10はオーケストラの伴奏で木管や弦が加わり、H.7よりは変化にとんだ音楽が繰り広げられます。特に第2曲の「怒りの日Dies irae」で「くすしきラッパの音Tuba mirum」の個所ではオーボエがトランペットのファンファーレのように響き、それを受ける合唱のフーガは力強くダイナミックで時に二重合唱のように聴こえ、H.7よりははるかに変化に富んでおり、レクイエムに対していい表現とは言えませんが、より音楽としては楽しめます。
さて残るはH.2で、これがコルボ盤の「死者のためのミサ曲」なのですが、この曲にはその成立に複雑な事情があるようです。このCD(現在は廃盤)は1972年の録音で、当初エラート・レーベルのライセンスが日本コロムビアからせビクターのRCAに移って間もない頃確か2枚組のLPとして発売しました。おそらく1973年か74年頃のことと思います。当時まだシャルパンティエの研究もそれほど進んでいなく、当然ヒッチコック番号なども存在していませんでした。作品目録(H番号)が整備されたのは1982年であり、また30巻からなる自筆譜のファクシミリ版の刊行が始まったのは1990年代になってからになります。「ニュー・グローヴ世界音楽大辞典」が本国で刊行されたのが1980年、その日本版が講談社から発売されたのが1993年のことになります。そんな状況の中でこの楽曲がいつ頃作曲され、どんな作品なのか知る手掛かりは掴めず、フランスから楽譜を送ってもらったりもしました。その楽譜には1945年2月27日付で校訂者ギィ・ランベールの署名があり、出版はエラートの本体であるコスタラ出版(Editions Costallat)が刊行していました。原盤には歌詞が添付されていなかったため、楽譜から歌詞を読み取ろうとしましたが手書きのラテン語で、通常文とはことなることからこれも難しく、結局原盤に付された解説の翻訳のみを掲載して発売しました。
この作品は演奏に60分以上を要する前2曲とは較べ物にならない大曲で、8人のソリスト(コルボ盤は5人)の他、合唱は4声部ではなく8声の二重合唱を必要としており、オーケストラも二群に分けられます。編成はフルート、オーボエ、弦、通奏低音からなり、その規模からいってもシャルパンティエの作品中最大級ではないでしょうか。ただこの曲は後からいくつかの部分が継ぎ足され、それらが全体で一つの楽曲になっています。H.7やH.10でもごく一部にこうしたことが行われていますが、この曲ではそれが大規模に行われていて、ちょっとバッハのロ短調ミサを思い起こします。曲の素晴らしさ、規模の大きさという点でもロ短調ミサにひけをとらないのではないでしょうか。この作品LPでは(後に発売されたCDでも)、音楽学者ハリー・ハルプライヒ氏(Harry Halbreich 1931-2016 ベルギーの音楽学者で現代音楽に功績のあった人ですが、古典音楽にも造詣が深い。解説書ではアルブレッシュと表記)が詳細な解説文を寄せています。彼はこの作品を「雄大な規模と円熟したスタイルを示す」としてシャルパンティエがサント・シャペルの楽長時代(1698~1704)であった晩年の作ではないか、としています。ところがH.2という目録番号からもわかるように、最近では彼の初期1670年代初め頃の作品ではないかとするのが有力です。その理由はシャルパンティエが生涯にわたって書き綴った28冊からなる自作のスコア帖の3冊目にこれが登場していることから推論されているようです(1990年に刊行された手稿譜ファクシミリ版の全集ではその第1巻に収録―“MARC-ANTOINE CHARPENTIER OEUVRES COMPLETES ⅠMESLANGES AUTOGRAPHES Volume 1” MINKOFF FRANCE EDITEUR PARIS)。この1670年代の初めというのはシャルパンティエがギーズ家のマリ・ド・ロレーヌに仕えるようになって間もない頃で彼が30歳になるかならない頃の若い時期ということになります。
さてこの曲ですが、ランベール校訂版では下記のような曲の配列になっています。
Ⅰ. キリエ一見してわかるのは一般のレクイエムと違い「死者のためのモテット」が挿入されていることです。入祭唱については前述のとおりグレゴリア聖歌で歌われるのが当時の習慣でしたが、ハルプライヒ氏によるとこのモテットも“Plainte des armes du Purgatoire(煉獄における霊魂の嘆き)”(旧約聖書のヨブ記からとられている)という副題をもち、17世紀フランスの典礼では「グラドゥアーレ(昇階唱)」と「オフェルトリウム(奉献唱)」の代わりに歌われることがよく行われており、更にルイ14世時代のフランスではサンクトゥスとベネディクトゥスの間にピエ・イエスを挿入するなど、現在の典礼とは少し異なっていたとか。金澤正剛氏の「キリスト教と音楽」(音楽之友社 2007年)によれば、フランスは元来ローマ教皇庁の決定には従わず独自の伝統による礼拝を行っており、レクイエムの昇階唱では「永遠の安息を」の代わりに「死の暗闇をさまよえども Si Ambulem」が歌われたとか(1610年アンリ4世の葬儀の際に歌われ、以後フランスにおけるレクイエムの規範になったウスタシュ・デュ・コロワのレクイエムにみられるように)。
Ⅱ. ディエス・イレ(怒りの日)(続唱―セクエンツィア)
Ⅲ. 死者のためのモテット
Ⅳ. サンクトゥス
Ⅴ. ピエ・イエス
Ⅵ. ベネディクトゥス
Ⅶ. アニュス・デイ
このレコードを発売する際、ハルプライヒ氏による解説以外に作品を知る手がかりがなく、これを一つの楽曲として発売したのですが、最近の研究によるとこれは元来一つの楽曲ではなく、いくつか別々に書かれたものを集めたものといわれています。上記の構成の中で、H.2の作品番号を持つ「死者のためのミサ曲」はⅠ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶの4曲のみで、レクイエムを補完させる目的から校訂者ランベールが後に書かれた作品を集めて一つのレクイエムを完成させた、というのが正しいのかもしれません。ただシャルパンティエは他の作品でも後に曲を補完するために曲の一部を作曲したりしていますし(前述したレクイエム2曲も)、ここではすべて二重合唱に基づいている(編成もすべて同じ)ことから、作曲者が何かの機会(葬儀)のためにこうした構成で曲を演奏したのかもしれません。ただランベール氏の解説もないためそれはわかりません。このレクイエムの中で現在H.12の番号を与えられ、この作品中もっとも大きな部分を占める「ディエス・イレ」は恐らく規模の大きさからしてもこれは単独で演奏できるように考えられたものでしょう(リュリにも同様なグラン・モテがあり、パイヤールの演奏で聴ける)。Ⅲの「死者のためのモテット」はH.311の、またⅤはH.234のそれぞれ分類委番号を持っています。いずれにしろこれらはすべて1670年代初期に書かれたと考えられていますが、Ⅴを除きこれらがH.2を補完するために作曲されたのかどうかは不明で、謎を含んでいます。
「ミサ」というのはそもそもキリストの「最後の晩餐」を記念する感謝の儀式で、「パン=キリストの体」と「ブドウ酒=キリストの血」の恵みを受けることでキリストと一体になり信仰を捧げるもので、キリスト教の中では「聖務日課」とともにその中核をなすものです。すべてのミサに共通する通常文とその日の祭式によって異なる固有文があり、ミサ曲では「キリエ(憐れみの言葉)」「グローリア(栄光の賛歌)」「クレド(信仰告白)」「サンクトゥス(感謝の言葉)」「アニュス・デイ(平和の言葉)」が通常文となり、「イントロイトゥス(Requim aeternam-入祭唱)」「グラドゥアーレ(Requiem aeternam-昇階唱)」「セクエンツィア(Dies irae-続唱)」「オフェルトリウム(Domine Jesu Christe-奉納唱)」「コンムニオ(Lux aeterna-聖体拝領唱)」などが固有文となります。これを頭においてH.2をみてみるとすべて通常文だけでレクイエムを構成する固有文がないことがわかります。従って「死者のためのミサ曲(レクイエム)」となっている以上、そこには固有文があったと考えるのが普通では。シャルパンティエがこの作品を演奏しない作品として残すためだけに作ったのであれば別ですが、おそらく何らかの機会に演奏した筈なので、ランベール版のような構成は十分に考えられると思います。特に編成がまったく同じなので、このように演奏されたと考えても不思議ではないと思います。
さて最近になって上記のコルボ盤に加えて、ウィリアム・クリスティ指揮によるCDが国内発売されました。古楽演奏による待望の録音です。以前からこのCDの存在(2004年9月のライヴ録音)は知っていたのですが、輸入盤もなかなか手に入らず最近ようやく入手することができましたので、これも含めてもう少しこの曲に触れることにします。クリスティ盤はランベール版ではなく、新たに出版されたジョン・パウエル校訂の楽譜によっています。このパウエル版も曲を構成する典礼文は同じなのですが、その配列他いくつか異なっています。
パウエル校訂版では、上記ランベール版Ⅲの「死者のためのモテット」(H.311)がⅣ~Ⅵのあと、Ⅶのアニュス・デイの前に置かれています。ただこれについてはハルプライヒ氏や金澤氏がいうようにこのモテットが昇階唱や奉献唱の代わりとすれば、サンクトゥスの前に置くのが自然なのでは。パウエル氏も解説文でその点について「キリエのあとに演奏されるかたちになっているが、歌詞の内容からアニュス・デイの前にもってくるのがふさわしい」として、曲順を変えています。この点については今一つ解説文からはわかりにくくもう少しわかりやすい説明が欲しかったと思います。このジョン・パウエルという人は私も初めて聴く名前でしたが、アメリカのトゥルサ大学(オクラホマ州)の教授で17世紀フランス音楽に関する著作の出版や、楽譜の校訂を多く行っているようです。彼の校訂による楽譜はインターネットの「john-powell @utulsa.edu」を開きその「Web-Projects」のサイトをクリックすると見ることができるようです(私のPCではソフトが足りなくて見られませんでしたが)。また彼の解説の中で一つ気になったのは、彼が「この録音が現代における復原の試みにすぎない」としていてあたかもこれが初めての試みのように読めてしまうのですが、すでにランベールよる校訂版が半世紀も前にあったことについては全く触れられていません。彼はまた「この曲がシャルパンティエ生存中にこのようなかたちで演奏されたことはおそらくなかったに違いない」とも述べています。
曲はたいへん美しい「キリエ」で始まります。A→H→C→D→E(イ短調)の上行音によるサンフォニーがひとしきり演奏されたのち、それをやや変化させた音形により独唱者たち(プティ・クール)に受け継がれます。そして合唱(グラン・クール)が加わってくるのですがこれがサンフォニーの開始上行音とは対称的にE→D→C→H→Aの下行音で、コルボ盤はf(ランベールの指定はSempre f )で歌われこれがあたかも天から降ってくるように聴こえ、とても印象的です。一方クリスティ盤では出だしからずっと同じような静かな音量で歌われていて、合唱に入ってもあまり変わらずこれはこれでとてもきれいです。ただキリエ・エレイソンのプティ・クールとグラン・クールによる掛け合い部分ではコルボ盤が見事です。その他大きな違いは、コルボ盤ではChriste eleisonのあとダ・カーポして冒頭のサンフォニーに戻りキリエが歌われるのに対し、クリスティ盤ではChristeが歌われた後、再びChristeの前奏(サンフォニー)を間奏曲風に奏しそのあとにキリエが歌われ、しかもソリストではなく合唱で始まる点が大きく違っています。この点については好みの問題ですが、冒頭のサンフォニーがとても美しいだけにランベール版の構成の方が私は好きです。モダン楽器と古楽器の違いもありますが、コルボ盤のオーケストラはやや弦楽器の編成も大きく、音色も含めその点ではクリスティ盤の方が古楽のつつましさを保っています。装飾音についてもしかり。また最後の終結音を転調して終わらせるなどこの「キリエ」の美しさは際立っています。
「怒りの日」のテーマは有名なグレゴリオ聖歌の旋律(ベルリオーズ「幻想交響曲」の第5楽章を思い起こせばおわかりでしょう)を基にしており、ランベール版では冒頭から力強い男声合唱で始まるのに対して、パウエル版のクリスティの演奏はオーケストラの前奏で始まります。この後者の前奏は38小節あり(ワン・コーラス分)、元の楽譜にはない(?)トロンボ-ンが加えられているようです。この前奏がもともとシャルパンティ自身の書いたものだったのかどうかは確認できませんでした。この楽章での聴きものの一つに二重合唱による掛け合いがあげられます。まさにイタリアで学んできた成果がここに見事な合唱音楽となって結実しています。人数の多いコルボ盤ではことのほかダイナミックな合唱が聴かれます。一方少人数(といっても古楽の中では比較的多い人数)のクリスティ盤でも、この二重合唱の掛け合いの前で一旦音量をpに落とし、fの合唱との強弱を際立たせるなど工夫してダイナミックな表現を聴かせてくれます。「くすしきラッパの音Tuba mirum」の個所になると木管楽器も加わって軽快な音楽に変わり、第1ソプラノと第2ソプラノの二重唱による掛け合いからバス二人(ランベール版の指定ではバス・ターユとバス・コントル)の掛け合いに変わり、更に合唱が加わって音楽が展開されていきますが、このあたりとても変化に富んでいて楽しめます。
こうして二つの版を比較しながらもっと曲の紹介をしていきたいところですが、そうでなくともここまで長い話が、更に長くなってしまうのでこのあたりでやめます。ただもう一つ大きな違いを挙げておきますと、サンクトゥスとアニュス・デイには冒頭にそれぞれサンフォニー(前奏曲)がおかれていて、これらは自筆譜集Meslanges Autographesにも含まれています。ランベール版のコルボはすべてこれらも演奏しているのに対し、パウエル版ではこれがカットされています。カットした理由をパウエルは明確にしていませんが、おそらく文中でこれらのサンフォニーが楽譜の余白に書かれていて、後に続く声楽部分とあまり関連がみられないことを指摘しているのでそうした理由からだと思います(注:サンクトゥスのサンフォニーは明らかに合唱と関連性がある)。クリスティ盤では従って演奏時間もやや短く、そのおかげで同日コンサートで演奏された「テ・デウム」(仏HM盤とは別の録音)も一枚のCDに収録されています。
少し長くなってしまいましたが、シャルパンティエの「死者のためのミサ曲」を紹介してきました。H.2を中心としたこの作品がどのようにして生まれたのかはわかりませんが、とても素晴らしい曲であることにかわりはありません。もっと多くの人に聴かれていいと思います。コルボ盤とクリスティ盤、どちらも素晴らしい演奏です。昨今の古楽ブームでは、オーセンティックな演奏ばかりがもてはやされ、そうしたCDしか発売されなくなりましたが、おそらくはそれ以上のファンがいる合唱愛好家にとってはコルボのようなモダン楽器による演奏もまた捨てがたいものでしょう。古楽をしっとりとあじわいたい人にはクリスティ盤、合唱の醍醐味をたっぷり味わいたい人にはコルボ盤、という聴き方もできるかもしれません。コルボ盤の復活を望みたいところです。
それぞれのCDは以下のとおりです。
その他のヴェルサイユ楽派のCDは次回まとめて紹介したいと思います。①ミシェル・コルボ指揮
リスボン・グルベンキアン管弦楽団&合唱団
カリーヌ・ロザ(S)、ジェニファー・スミス(S)
ハンナ・シャウアー(A)、ジョン・エルウィス(T)
フェルナンド・セラフィム(T)、フィリップ・フッテンロッハー(Br)
ミシェル・ブロダール(B)
(録音:1972年7月 Erato R20E-1002)
②ウィリアム・クリスティ指揮
レザール・フロリサン
オルガ・ビタルク(S)、オルランダ・ヴェレス・イシドロ(S)
ポール・アグニュー(Ct)、ジェフリー・トンプスン(Ct)
トピ・レティプー(T)、マルク・モイヨン(T)
ベルトラン・ボントゥー(B)、ホアン・フェルナンデス(B)
(録音:2004年9月ライヴ Erato WPCS-16254)
2016.07.14 (木) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅵ)
6. テ・デウムとCDはじめに「テ・デウム」について少し触れておきますと、これはローマ・カトリック教会の典礼の際に歌われる「神への賛美」の賛歌で、“Te Deum laudamus(私たちは神であるあなたを讃えます)”の言葉で始まります。歌詞は初期キリスト教時代に多くの賛歌を作り「西方教会音楽の父」とも呼ばれたミラノ大司教聖アンブロシウス(339-97)の作、もしくは彼と聖アウグスティヌス(354-430)との合作と伝えられており、グローリアと共にキリスト教賛歌の最も古い形式とされています。真偽の程は別にして面白い逸話が残されています。それによるとミラノの教会でアウグスティヌスがアンブロシウスによって洗礼を受けたとき、二人は霊感に包まれ、即興的に一句ずつ交互に歌い、それによってこの詩が生まれたとか。もともとは主日(日曜日)や祝日の聖務日課で歌われる歌ですが、歌詞の内容から祝典的な音楽にも使用されるようになり、特に17世紀以降この傾向は強くなります。国家的な祝賀行事や戦勝記念の際に多くの作曲家によって作品が生まれています。またこのテ・デウムはカトリックだけでなく、プロテスタントやイギリス国教会でも歌われています。今回とりあげているリュリやシャルパンティエの他にもパーセル、ヘンデル、ベルリオーズ、ブルックナー、ヴェルディなどがよく知られています。ドイツではルターによってドイツ語“Herr Gott, dich loben wir”と訳され、バッハはカンタータBWV16の冒頭の合唱にこの「テ・デウム」のドイツ語訳を使用しています。またメンデルスゾーンは1832年にイギリス国教会の礼拝のために合唱とオルガン伴奏による英語の「テ・デウム」を作曲しています(後にオーケストラ伴奏によるドイツ語作品に改訂。但しルターのドイツ語訳とは異なる)。
さてリュリとシャルパンティエのテ・デウムですが、CDの話に入る前に楽譜についても触れておきましょう。今回私が参考にした楽譜は以下のものです。
まずシャルパンティエですが、この曲はオイレンブルク社から小型のスコアが出版されており、これにはNew Urtext Editionと書かれています。つまり最新の原典版であることを示しています。校訂者はジャン=ポール・モンタニエ(Jean-Paul Montagnier)で1996年に出版されています(Edition Eurenburg No.8042)。小型といってもいわゆるポケット版よりは少し大き目なスコアなのでとても見やすい楽譜です。
次にリュリのテ・デウムですが、これについては残念ながら音大の図書館などで全集版(Oeuvres completes de J.-B. Lully/publiees sous la direction de Henry Prenieres) に入っている大型スコアを閲覧させてもらう以外には手がありません。 この全集版はロマン・ロランの弟子でもあったアンリ・プリュニエール(1886-1942)によって1935年頃に出版されたもので、通奏低音の解釈をオルガニストで作曲家でもあったアンリ・ルトカール(Henry Letocart 1866-1945)が行っています。ただ1976年にパイヤール指揮によるLPをエラート・レーベルから発売する際、私が参考用にフランスから送ってもらったスコアのコピー(以下「パイヤール版」)がまだ手元にあり、これが今回大いに役立つことになりました。このパイヤール版は基本的に全集版の楽譜を実際の演奏に即して手書きで修正したものと思われ、随所に注意書なども書かれていますが、手書きのフランス語なのでその判読はちょっと私には荷が重すぎます。また表紙にはClavecinと書かれていることからおそらく通奏低音を担当したクラヴサン奏者(クレジットがないので誰かは不明)が使用した楽譜のコピーと思われます。この楽譜についてはCDの紹介の中でも触れます。
現在私が所有している両曲のCDは以下のもので、録音順に並べてみます。
[リュリ:テ・デウム]
① ジャン=フランソワ・パイヤール指揮 パイヤール室内管弦楽団
ジェニファー・スミス(S) フランシーヌ・ベサック(S) ツェーガー・ヴァンデルシュテーン(Ct) ルイ・デヴォー(T)
フィリップ・フッテンロッハー(B) ヴァランス“ア・クール・ジョワ”合唱団
(エラート WPCS-22063 同時収録“ディエス・イレ”) (録音:1975年頃)
② ヴァンサン・デュメストル指揮 ル・ポエム・アルモニーク
アメル・ブライム=ジェルイ(S) オロール・ビュシェ(S) レイナート・ファン・メヘレン(Ct) ジェフリー・トンプスン
(T) ブノワ・アルヌー(B) カペラ・クラコヴィエンシス
(マーキュリー Alpha 952) (録音:2013年)
[シャルパンティエ:テ・デウム]
③ ルイ・マルティーニ指揮 パイヤール管弦楽団
マルタ・アンジェリシ(S) ジョスリーヌ・シャモナン(S) アンドレ・マラブレラ(Ct) レミイ・コラッツァ(T) ジョル
ジュ・アブドゥーン(Br) ジャック・マルス(B) フランス音楽青少年合唱団 モーリス・アンドレ(Tp) マリー・
クレール=アラン(Org)
(エラート R20E-1003) (録音:1963年)
④ ミシェル・コルボ指揮 リスボン・グルベンキアン管弦楽団・合唱団
エルザ・サーク(S) ジョアナ・シルヴァ(S) ジョン・ウィリアムス(Ct) フェルナンド・セラフィム(T) フィリップ・
フッテンロッハー(Br) ホセ・オリヴェイラ・ロペス(B)
(エラートR25E-1034) (録音年は不明ですがおそらく1970年代後半?)
⑤ ウィリアム・クリスティ指揮 レ・ザール・フロリサン
(harmonia mundi FRANCE-King International KKCC-5) (録音:1988年)
⑥ マルク・ミンコフスキ指揮 レ・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブル
アニック・マシス(S) マグダレーナ・コッチェニャ(Ms) エリック・ヒュエ(T) パトリック・ヘンケン(T) ラッセル・
スミス(Br) ジャン=ルイ・バンディ(B)
(アルヒーフ POCA-1153) (録音:1997年)
② ヴァンサン・デュメストル指揮 ル・ポエム・アルモニーク
アメル・ブライム=ジェルイ(S) オロール・ビュシェ(S) レイナート・ファン・メヘレン(Ct) ジェフリー・トンプスン
(T) ブノワ・アルヌー(B) カペラ・クラコヴィエンシス
(マーキュリー Alpha 952) (録音:2013年)
以上の内、①③④はモダン楽器を使用しており、それ以外はピリオド楽器による古楽奏者たちによる演奏です。そして当然ながらそれぞれに特徴を備えており、その違いが面白くもあります。
それぞれの簡単な印象について書いてみますと、
 ①はモダン楽器による演奏で、この曲が初めて国内盤でリリースされた記念すべき
録音です。録音データが当時付されていなかったの
で詳しいことは不明ですが、パイヤールが当時よく
使用していたフランス東部ドローム県の中心にある
ヴァランスの教会で録音されたものと思われます。
とても響のいい教会です。フランスは伝統的に管楽
器の名手が多く、ここでもトランペットの輝かしい
音色と木管の妙技が音楽に華を添え、ソリストや合唱も申し分なく、モダン・ピッチを使用していることもあってヴェルサイユ楽派らしい輝かしい音楽がたっぷり楽しめるものになっています。
①はモダン楽器による演奏で、この曲が初めて国内盤でリリースされた記念すべき
録音です。録音データが当時付されていなかったの
で詳しいことは不明ですが、パイヤールが当時よく
使用していたフランス東部ドローム県の中心にある
ヴァランスの教会で録音されたものと思われます。
とても響のいい教会です。フランスは伝統的に管楽
器の名手が多く、ここでもトランペットの輝かしい
音色と木管の妙技が音楽に華を添え、ソリストや合唱も申し分なく、モダン・ピッチを使用していることもあってヴェルサイユ楽派らしい輝かしい音楽がたっぷり楽しめるものになっています。②はもっとも新しい録音で、しかも300年以上前にまさにここで演奏されたヴェルサイユの王室礼拝堂で録音されています。もちろんピリオド楽器を使用した演奏で、リュリが興奮して足を指揮杖で突いてしまった事件を思わず想像してしまいます。ピッチはパイヤール盤のモダン・ピッチに比べると半音低くなっており、記載がないので正確なことはわかりませんがa=415という通常のカンマートーンを採用していて、a=392のヴェルサイユ・ピッチ(モダン・ピッチよりほぼ全音低い)にはなっていません。ということは礼拝堂のオルガンは使用しなかったのでしょうか?せっかく王室礼拝堂で録音したのですから、そこまで合わせてもらえると申し分ないと思うのですが、おそらくはポジティヴ・オルガンを持ち込んで録音したのかもしれません。それとここでフランス・バロックのちょっとやっかいな問題に触れておかねばなりません。イタリアやドイツと違い、フランス・バロックには独特の演奏法が存在します。それは主に「リズム」と「装飾」についてで、これら古楽演奏の約束事は、私のような素人にとってそれを理解するのはとても難しいものです。私がバロック音楽に興味をもった20代の頃、サーストン・ダート(1921-71)の「音楽の解釈」(1953)やアーノルド・ドルメッチ(1858-1940)の「17・8世紀の演奏解釈」(1916)などを読み漁って理解しようと思いましたが、なかなか難しいものでした。これらの理論は現在ではもう古くてそれを鵜呑みにするのは危険とも言われていますが、その後出版されたコープマンの「バロック音楽講義」(1985)などを読んでも、同様なことが書かれています。ここでそのリズムについて触れてみたいと思います。バロック時代の音楽は多くの場合、様々に舞曲の影響を受けています。ですから楽譜通りに演奏すればいいというものではなく、リズミカルな演奏が求められます。特にフランスの古楽においては一般的に「イネガル(不均等)奏法notes inegales」と呼ばれる演奏法で、早いテンポの曲では均等に記された8分音符の扱いが問題となります。つまり「均等な音価を不均等に演奏すること」が要求されるのです。もちろんすべてに対して適用されるわけではなく、同様な音型が連続するような場合で4/4拍子であれば4分音符を分割する8分音符がその対象となります。これはクープランが「クラヴサン奏法」の中で述べていることで、「フランス人は順次進行の8分音符を付点なしで記譜するが、どちらかというと付点音符のように演奏する」(コープマン前掲書、風間芳之訳 音楽之友社より)という記述に基づいています。テ・デウムの冒頭の部分でそれをちょっと考えてみましょう。

上記の譜例はテ・デウム冒頭で、上段が全集版に記されたスコアのリズムであり、下段がイネガル奏法を採り入れたリズムになります。その違いがはっきりわかると思います。ではこの2種類の演奏ではどうなっているでしょう。古楽器集団による演奏の②が当然そうした奏法になっていると思われるのですが、実はまったく逆になっています。①がイネガルを採用した古楽奏法で②は8部音符を記譜通り(冒頭小節のみ付点付きのリズムに変更)に演奏しています。さすがバロック音楽を得意としていたパイヤールだけのことはあります。パイヤールが使用したスコアにはそうした書き込みが随所にみられとても興味深いものです。ただそのパイヤールもイネガルは器楽部分だけに適用していて、声楽部分は記譜通りに歌っています。②の指揮者デュメストルはフランスのリュート奏者で、1998年に古楽アンサンブル「ル・ポエム・アルモニーク」を組織して最近注目されており、2009年にはともに来日し日本公演を行っています。合唱は名前からもおわかりのようにポーランドの古楽系の合唱団。解説には制作ノートも付されており、トランペットにこだわったようですが、こうしたリズムの問題には一切触れていません。尚このイネガル奏法は8部音符を必ずしも付点8部音符で演奏しなければならないというものでもなく、延ばす音符の長さは演奏者の解釈に任されているともいわれます。ただソロの場合はともかくアンサンブルとなると、はっきり付点音符のように決めたうえで演奏しないと統率はとれないでしょう。当時の作曲家はなぜこんな曖昧なことをしたのでしょう?サーストン・ダートによれば「作曲家たちがそのような長い間にわたって不正確な記譜法を用い続けたことは、はじめは驚異に思われるかもしれないが、その方が記譜がはるかに早く行えるうえ手数が省けたし、それの正しい演奏法は、練習の際の説明にまかせたほうが克明に紙に書きつけて表示するよりは、むしろはるかに容易に解明できる性質のものだった」(前掲書、奥田恵二訳 音楽之友社)と述べています。このイネガルについて詳しく知りたい方は、橋本英二著「バロックから初期古典派までの音楽の奏法」(音楽之友社)やハワード・ファーガソン編「初期フランスの鍵盤音楽選集」(橋本英二訳、全音楽譜出版社)の序文などに、イネガルを適用してはいけない記譜上の注意なども含め詳述されています。
シャルパンティエの「テ・デウム」に移りましょう。③のマルティーニ盤は私にとって思い出深い録音で、名手モーリス・アンドレの輝かしいトランペットが聴けるのがうれしいのですが、さすがに半世紀以上も前の録音でその古さは否めません。でもこの曲を初めて世に知らしめた先駆者としての栄光は永遠のものです。不朽の名盤といっても過言ではないでしょう。他に二重合唱を伴うグラン・モテの「大マニフィカト」(10曲あるマニフィカトのうち最大規模の作品で、自筆譜の第11巻に所蔵され、1680年代初期に書かれたといわれるH.74)を収録しています。
④もまたモダン楽器によるもので、派手さという点ではこれが一番ではないでし ょうか。第1トランペットはパリ・オペラ座管のベルナール・ガベルが吹いていま す。やや遅めのテンポで実に堂々としています。歌の冒頭はフッテンロッハーのバ リトンでこれも素晴らしい歌声です。ただこの演奏でまず特筆すべきなのは合唱の素晴らしさです。この合唱団、バロックものを得意としているわけではなく、以前ブラームスの合唱曲などでも素晴らしいハーモニーをきかせてくれていました。大編成の合唱ながらそのハーモニーの良さは絶品で、さすが合唱指揮者コルボに率いられているだけのことはあります。これを聴いているとかつて訪れた眩いばかりに装飾されたヴェルサイユ宮殿を思い出します。あまり古楽的とは言えませんが。尚このCDにはオラトリオ「最後の審判」(1680年代初期、H.401)と二重合唱による美しい作品の詩篇111番「ベアトゥス・ヴィル(いかに幸いなことか、主を畏れる人)」(1690年代中期?H.224)を収録しています。
さて⑤からは古楽団体による演奏となります。ウィリアム・クリスティ(1944~)はもともとアメリカ生まれのチェンバロ奏者でしたが、1970年代にヨーロッパに活動拠点を移し、79年には器楽と声楽のアンサンブル「レ・ザール・フロリサン(「花咲ける芸術」の意味で、シャルパンティエの同名オ ペラから引用)」を組織して主にフランスのバロック
 音楽を精力的に録音しています。シャルパンティエ
の録音もかなりあります。この「テ・デウム」は80年
代後期の録音で、もうそれ程新しいものとは言えま
せんが、器楽や合唱も安定しており今なおこの演奏
が最も安心して聴けるCDではないでしょうか?リ
ュリのところで触れた「イネガル」の奏法もしっかりとここでは生かされています。さすが古楽の大ベテランというべきか。ただ難を言えば独唱者は合唱団のメンバーから選ばれているようでちょっと弱いようにも感じます。でもそれがかえってアット・ホームに感じたりもするのですが。それとこの作品が戦勝記念のために書かれた(?)ことを想定してか、曲の冒頭にジャック・ダニカン・フィリドール(1657-1708、よく知られたアンドレ・ダニカンの弟でやはりグランド・エキュリーの音楽家)が作ったティンパニー・ソロの行進曲がおかれていて、これがちょっと長く感じます(といっても1分半ほどですが)。おまけにそのあと、テ・デウムの有名なプレリュードの冒頭にも短いながらもティンパニーの即興を加えていてちょっとくどいように思います。またこの演奏も通常のバロック・ピッチで演奏しており、できればヴェルサイユ・ピッチで演奏してほしかったと思います。更にティンパニーと重ねて使用されるバス・トランペットをここではトロンボーンに変更しています。同時収録の作品は、テ・デウムの華やかさとは打って変わっって静かで美しい「聖母被昇天のミサH.11」と「聖母マリアへの連?H.83」の2曲です。華やかな曲と対照的なのでその対比が鮮やかであり、特にH.11は晩年に書かれ、音楽も感動的です。
音楽を精力的に録音しています。シャルパンティエ
の録音もかなりあります。この「テ・デウム」は80年
代後期の録音で、もうそれ程新しいものとは言えま
せんが、器楽や合唱も安定しており今なおこの演奏
が最も安心して聴けるCDではないでしょうか?リ
ュリのところで触れた「イネガル」の奏法もしっかりとここでは生かされています。さすが古楽の大ベテランというべきか。ただ難を言えば独唱者は合唱団のメンバーから選ばれているようでちょっと弱いようにも感じます。でもそれがかえってアット・ホームに感じたりもするのですが。それとこの作品が戦勝記念のために書かれた(?)ことを想定してか、曲の冒頭にジャック・ダニカン・フィリドール(1657-1708、よく知られたアンドレ・ダニカンの弟でやはりグランド・エキュリーの音楽家)が作ったティンパニー・ソロの行進曲がおかれていて、これがちょっと長く感じます(といっても1分半ほどですが)。おまけにそのあと、テ・デウムの有名なプレリュードの冒頭にも短いながらもティンパニーの即興を加えていてちょっとくどいように思います。またこの演奏も通常のバロック・ピッチで演奏しており、できればヴェルサイユ・ピッチで演奏してほしかったと思います。更にティンパニーと重ねて使用されるバス・トランペットをここではトロンボーンに変更しています。同時収録の作品は、テ・デウムの華やかさとは打って変わっって静かで美しい「聖母被昇天のミサH.11」と「聖母マリアへの連?H.83」の2曲です。華やかな曲と対照的なのでその対比が鮮やかであり、特にH.11は晩年に書かれ、音楽も感動的です。⑥のマルク・ミンコフスキー(1962~)はフランス生まれのファゴット奏者で、1982年にこのル・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブルを設立。やはりフランスのバロック音楽をレパートリーの中心に据えていますが、古典派やロマン派の音楽なども演奏しています。この盤の特徴は何といってもヴェルサイユ・ピッチを採用し、低いピッチでありながらも実に絢爛とした音楽でこれぞヴェルサイユ楽派の教会音楽という醍醐味を聴かせてくれることです。テンポも溌剌としていて、多少乱暴なようにも感じますが第3曲や終曲など合唱がついていくのも大変そうです。それとここでは通奏低音にバロック・ギターとテオルボが使用され(奏者は今村泰典氏)、それがとても効果的です。ただ残念ながらどうしたことかそこまでやっておきながら、イネガルなどのリズムは無視してしまいました。このCDには有名な「真夜中のミサ曲 H.9」を収録していますので、シャルパンティエの教会音楽を初めて聴きたいという人にはお勧めです。
最後の②はリュリのところでもふれたように王室礼拝堂における録音です。ただライヴではありませんが、2曲をたった1日で録音するというハード・スケジュールで、通常はあまりかんがえられない強行日程です。おそらく1日しか借りられなかったのでしょう(あるいは予算がなかったのか)。でもだからといって演奏が雑になることもなく、むしろよく1日でここまで録音できたな、と思わせる内容です。この演奏もまた冒頭に短いティンパニーの即興を加えています。ただあまりマイクセティングの調整などに時間がとれなかったのか、全体にやたらティンパニーがふやけたようなドローンとした音で、ちょっと興をそがれます。バス・トランペットを重複して使用していないことも影響しているかもしれません。それを除けばとてもいい演奏だと思います。リュリのところでもふれたようにイネガルのリズムは採用されていません。それとこの作品は10の楽章からなっていて(この盤のトラック割りは9)本来切れ目なく演奏されるのですが、ここでは曲によって少し長めの休止をとっているところもあります。この盤の最大の特徴はヴェルサイユ楽派前期の代表的なテ・デウムが2曲聴けることです。
以上ざっと御紹介しましたが、どれが一番いいかなどというつもりはありません。私自身はその時の気分でその中から選んで聴いています。
2016.04.03 (日) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅴ)
5. マルカントワーヌ・シャルパンティエ1643年パリに生まれた(注1)マルカントワーヌ・シャルパンティエは多くの点でリュリとは正反対の生涯を送りましたが、フランス・バロックの黄金期を共に築いた大作曲家の一人であることに変わりはありません。現代の評価という点ではリュリをはるかに凌いでいる、といっても過言ではないでしょう。フランス音楽史の中でリュリがオペラという分野で金字塔を打ち立てたのに対し、シャルパンティエは宗教音楽の分野で輝かしい成果を残し、20世紀の後半からはシャルパンティエ・ルネサンスともいえるほど、彼の評価は高まりました。フィレンツェ生まれのリュリがパリで本格的に音楽を学んで成功したのに対し、シャルパンティエはローマに出て、そこで音楽を学び、その成果をパリに持ち帰ったのでした。
シャルパンティエの若い頃についてはいよくわかってはいませんが、ローマに留学したのは1662年から67年の間と推定され、そこで3年間オラトリオの祖と言われるジャコモ・カリッシミ(Giacomo Carissimi 1605-1674)について音楽を学びました(注2)。かつては彼が画家になるため、絵の勉強にローマに行ったとされていましたが、<ニュー・グローヴ>などではこの説を否定しています。同姓の人と間違えたのだとか。ただ彼の先祖には二人の画家がいたとも言われています。
ここで少しカリッシミに触れておきますと、この作曲家はイタリア中部のマルケ州サンタンジェロ村にワインの樽作り職人の息子として生まれますが、聖歌隊の歌手を経て10代にして既に教会のオルガニストになるなど才能に恵まれ、ティヴォリやアッシジの教会で楽長を務めた後、1629年25歳でローマに移り、そこでイエズス会の名門として知られる教育施設コレギウム・ゲルマニクム(ドイツ寄宿学校)の教師とその付属教会であるアポッリナーレ教会の楽長に就任します。1643年にはモンテヴェルディの後任としてサンマルコ大聖堂の楽長職を得る機会に恵まれたにもかかわらず、それも断わり、以後彼はこの職を離れることなく、生涯を終えています。ここで彼は代表作ともいえる「イェフタ」をはじめ数々の名作を生みだし、聖書の物語を題材とした「オラトリオ」という形式の音楽を確立します。ドラマティックなアリアやアリオーソ、レチタティーヴォ、それらにうまく合唱をからめてオペラのような演劇を伴わなくても十分人をひきつけることができる音楽を造りだしたのでした。「イェフタ」はオラトリオの古典とされ、フランスをはじめヨーロッパの国々に楽譜のコピーが多数出回っていた、といわれます。カリッシミのオラトリオは旧約聖書の物語を題材としてラテン語で歌われますが、「イェフタ」以外にも「ソロモンの裁き」や「エゼキア物語」などがよく知られています。彼の弟子としてはこのシャルパンティエの他、ドイツのカスパール・フェルスター(Caspar Forster 1616-73)やボローニャ楽派のジョヴァンニ・パオロ・コロンナ(Giovanni Paolo Colonna 1637-95)などがいます。
20代半ばに留学を終えて帰国したシャルパンティエは、当時パリでイタリア音楽を愛好する少数のグループに加わり曲を提供するなどし 」
 ていたようですが、1670年には名門貴族ギーズ家の公
爵令嬢マリ・ド・ロレーヌ(1615-88)に仕えるようにな
ります(注3)。このギーズ家はフランス貴族の名門で、
ユグノー戦争による内戦の際ギーズ公アンリ(1550-88)
は一時的にパリを占拠して事実上の王になったりもしま
すが、アンリ3世に暗殺されその野望は果たせませんで
した。その曾孫にあたるのがこのマリ・ド・ロレーヌで
す。彼女の一家は1631年リシュリーによって追放され
フィレンツェに亡命していたのですが、1645年に許され彼女はパリに戻ってきました。そんなわけで彼女は王家とは直接かかわりを持たず、もっぱら教会や修道院を訪れる日々を送っていたとか。パリの右岸マレ地区にあった彼女の館(現在パリ国立古文書館)にはフランスで当時最大と言われた私的な音楽サロンがあったといわれています。ここには夫人お抱えの歌手や器楽奏者達がおり、シャルパンティエは彼らのために世俗的な劇作品やオラトリオ、モテットなどの宗教曲を書いています。またシャルパンティエ自身もオート・コントル(カウンター・テナー)の歌手であったと言われています。シャルパンティエが彼女のお抱え音楽家になったのは、彼女がフィレンツェで過ごしていたこともあってイタリア音楽を愛好していた背景があるのでは。彼は彼女の依頼で「花の冠」という牧歌劇を作りますが、これは12人の弦楽器奏者を必要としたため、リュリの禁止令に抵触して演奏中止に追い込まれてしまいます。
ていたようですが、1670年には名門貴族ギーズ家の公
爵令嬢マリ・ド・ロレーヌ(1615-88)に仕えるようにな
ります(注3)。このギーズ家はフランス貴族の名門で、
ユグノー戦争による内戦の際ギーズ公アンリ(1550-88)
は一時的にパリを占拠して事実上の王になったりもしま
すが、アンリ3世に暗殺されその野望は果たせませんで
した。その曾孫にあたるのがこのマリ・ド・ロレーヌで
す。彼女の一家は1631年リシュリーによって追放され
フィレンツェに亡命していたのですが、1645年に許され彼女はパリに戻ってきました。そんなわけで彼女は王家とは直接かかわりを持たず、もっぱら教会や修道院を訪れる日々を送っていたとか。パリの右岸マレ地区にあった彼女の館(現在パリ国立古文書館)にはフランスで当時最大と言われた私的な音楽サロンがあったといわれています。ここには夫人お抱えの歌手や器楽奏者達がおり、シャルパンティエは彼らのために世俗的な劇作品やオラトリオ、モテットなどの宗教曲を書いています。またシャルパンティエ自身もオート・コントル(カウンター・テナー)の歌手であったと言われています。シャルパンティエが彼女のお抱え音楽家になったのは、彼女がフィレンツェで過ごしていたこともあってイタリア音楽を愛好していた背景があるのでは。彼は彼女の依頼で「花の冠」という牧歌劇を作りますが、これは12人の弦楽器奏者を必要としたため、リュリの禁止令に抵触して演奏中止に追い込まれてしまいます。1672年シャルパンティに大きな転機が訪れます。リュリと仲たがいしたモリエールが今度はシャルパンティエと組んで劇作品をつくることになったのです。こうして二人のコンビによる「強制結婚」が上演されますが音楽の編成はごく簡素化されたものになっています。更に「気で病む男」を上演しますが、その成功をねたんだリュリの横やり(国王の勅令による楽器編成の制限)により、何度も改変を余儀なくされます。この間にモリエールは死去(1673年2月)してしまい、二人の共同作業は長く続きませんでした。ただモリエール一座とは1680年に一座が「コメディ・フランセーズ」と改名した後もしばらくその関係は続き、コルネーユの作品などを上演しています。
シャルパンティエはリュリの存命中に国王と直接関係を持つことはありませんでしたが、国王は彼を少なからず評価していたと思われます。1679年から王太子に使えるようになり、その楽長としてミサの音楽を任されるようになります。そこで彼は多くのモテットを作曲し、それらのいくつかは国王も気に入っていたといわれています。それがきっかけで1683年王室礼拝堂の副楽長候補に立候補することになったのですが、前述したようにこれは最終選考を彼が病気のため欠席したことで実現しませんでした。しかしながら王はシャルパンティエが王太子に尽くしたことへの感謝のしるしとして年金を与えています。こののちシャルパンティエはシャルトル公(後にルイ15世の摂政を務めるオルレアン公)の音楽教師になり、更にはパリのイエズス会修道院の作曲家および楽長に就任しています。このイエズス会修道院において彼の本領はいかんなく発揮され、創作活動の絶頂期を迎えます。当時王室礼拝堂では国王がもっぱら詩篇によるモテットを好んだため、ミサ曲などの演奏は行われなかったのですが、幸か不幸かシャルパンティエは王室礼拝堂とは関係を持たなかったため、詩篇やモテットの他ミサ曲、オラトリオ、カンタータなどあらゆるジャンルの宗教音楽を残しています。それに比べると器楽曲はほんの一握りほどしか書いていません。その器楽曲も多くは宗教的色彩を持っています。
1687年リュリが他界するとシャルパンティエの頭上にようやく光が差し込んできます(王の名のもとに出されていた勅令も廃止される)。国王が臨席する劇のための音楽に協力を求められ、「殉教者ケルソス」(1687)や「ダヴィデとヨナタン」(1688)などが書かれます。後者は現在CDでも聴くことができます(ウィリアム・クリスティ指揮 HMX-2901289)。これらの劇音楽は宗教曲とちがってラテン語ではなくフランス語で歌われ、舞曲がふんだんに使われ、宮廷の趣味を反映したヴェルサイユ楽派らしい華やかな音楽が繰り広げられます。こうした宗教劇の作品を経て彼の唯一のオペラといわれる抒情悲劇「メディア」が生まれ、1693年にパリ・オペラ座で初演されています。尚一般的には「ダヴィデとヨナタン」も歌劇と呼ばれていますが、<ニュー・グローヴ>ではこれを宗教劇として区別しており、CDなどには“Tragedie biblique”(オペラはTragedie lyrique)と表記されています。
1698年シャルパンティエはサント=シャペルの楽長という更に大きな職を得ますが、これにはシャルトル公の力添えがあったといわれています。このサント=シャペルの楽長職はヴェルサイユ宮王室礼拝堂の音楽監督に次ぐ高い地位とフランスでは考えられています。ここで晩年を過ごしたシャルパンティエは「ルソン・ド・テネーブル」やグラン・モテ「サロモンの審判」などの名曲を生み出します。1704年に他界するまで、彼はこの地位にとどまりました。リュリより少し長生きしたことが彼に幸運をもたらしたのです。
シャルパンティエの作品は圧倒的に宗教音楽が多く、また優れた音楽もそこから生まれています。彼は劇音楽もかなり残してはいますが、シャルパンティエの作品として面白いかと問われれば、その点ではリュリの方に分があるように思います。あくまでも彼の本領は宗教音楽です。二重合唱をふんだんに取り入れ、小合唱と大合唱との対話、あるいは器楽と声楽との対話など、イタリアで学んだコンチェルタート様式の見事さはフランスにおける同時代の他の作曲家の作品をはるかに凌いでいます。心に染み入るような旋律の美しさや、また民謡を取り入れて親しみやすいミサ曲にしたりするなど、多様な音楽的趣味が彼の宗教音楽には反映されています。彼の多くの宗教音楽を聴いていて、個人的に感じるのは、そのオーケストレーション特にフルート(トラヴェルソやリコーダー)の使い方が巧みなことです。現在彼の音楽はかなり録音されていて、私たちもCDでそれらを聴くことができるようになりました。現在の評価という点ではリュリをはるかに凌駕しでいるといっても過言ではないでしょう。
リュリのオペラとシャルパンティエの宗教音楽、この時代を黄金時代へと築き上げた二人の功績は大きく、フランス・バロックを飾る金字塔と言えるでしょう。しかしながら17世紀のフランスでは人々の趣味はオペラに注がれたことから、時代はリュリに勝利を与えたのです。もしシャルパンティエがリュリと異なる時代に生きていたら、彼の運命も大きく変わっていたことでしょう。
シャルパンティエの作品で生前に出版されたものは非常に少なく、オペラ「メディア」他わずかな劇作品と少数のモテットを数えるだけです。ただ彼の自筆譜の大半が王室図書館に残されており、長らく未整理のままだったのですが1982年にヒュー・ウィリアム・ヒッチコック(Hugh Wiley Hitchcock 1923-2007)によって作品目録として整理され、現在ではヒッチコック番号(H)で表記されるようになりました。ただ彼の宗教音楽は膨大な量があり、LP時代に発売された作品にはこの番号がないため特定するのにちょっと苦労します。また彼の音楽が20世紀後半になってようやく脚光を浴びるようになり、再評価されるようになったきっかけが実はこの「テ・デウム」(H.146)の音楽にありました。1953年にのちのステレオ録音とは別にルイ・マルティーニがこのテ・デウムを録音し(オーケストラ、合唱は同じ)、その冒頭に置かれたトランペットの輝かしいプレリュードが、ヨーロッパ放送連合内でニュースを流す国際ネットワークとして1954年に創設されたユーロビジョンのテーマ音楽として使われたことから、一気にこの作品が知られるようになったのです。当時まだこの作品のスコアは出版されておらず、1943年にギィ・ランベールによって出版されたヴォーカル・スコアのみがあった時代でした(フル・スコアの出版は1957年)。そんな時代に録音されたこのプレリュードの響きが視聴者に大きなインパクトを与えたのです。このH.146の「テ・デウム」は1692年「ステンケルクの戦い」でフランス軍がオランダ軍に勝利しそれを記念した祝賀行事の際に初演され、彼が当時楽長を務めていたイエズス会のサン=ルイ教会(現サン=ポール=サン=ルイ教会)の委託を受けて作曲したものといわれています。曲は作曲者自身が「喜びと勇敢さ(joyeux et tres guerrier)の象徴」としているニ長調で書かれ、4声部の合唱と8人の独唱者、そしてオーケストラはフルート(リコーダー)2、オーボエ2、トランペット3(内2本はユニゾンで奏され、もう1本はバス・トランペットでティンパニーと重ねて使用)、ティンパニー、弦4部と通奏低音(バソン2とオルガンを含む)からなっています。二重合唱は使われていませんが、独唱者たちによる小合唱と大合唱のかけあいというグラン・モテの伝統や二重唱、三重唱などがからみあって、大規模で華やかな音楽を繰り広げています。
シャルパンティエはテ・デウムを6曲書いたといわれていますが、現存しているのはH.146を含め4曲だけです(H.145,147,148)。このうちトランペットを使用しているのはこのH.146のみで、この「テ・デウム」の音楽にトランペットを使用するようになったのはリュリが最初といわれ、以後フランス・バロック期に書かれた「テ・デウム」の伝統的な編成となっています。またH.145はヒッチコックによると初期の作品ですが二重合唱を用いています。デュメストル盤の解説(カトリーヌ・セサック)によると、1687年1月に国王の快気祝でリュリのテ・デウムが演奏されましたが、この祝いの行事は更に続き、同月末にパオロ・ロレンツァーニによるテ・デウム(作品は消失)が、そして更に2月8日にシャルパンティエの二重合唱によるテ・デウムが演奏された、といいます。このとき演奏されたテ・デウムがどれかはわかっていませんが、おそらく消失したものではとセサックは述べています。「テ・デウム」には様々な作曲家による名曲が数多く残されていますが、このシャルパンティエの作品ほどきらびやかで祝典的な音楽は他にはないと思います。
(注1) かつてはシャルパンティエの生年について1634年とか36年とかと表記されていましたが、最近の研究では1643年と推定されており、現在ではほとんどそう表記されています。
(注2) デュフルクの「音楽史」では1634年に生まれ、15歳でローマに留学し、3年間カリッシミについて学んだとされています。これだと1649年にはローマに赴いていたことになり、現在の説とはかなり食い違ってきます。かつてのレコードの解説などではこちらの説にしたがって書かれているものが多かったのですが、現在ではかなり修正されています。
(注3) シャルパンティエの若い頃については不明な点が多いのですが、1987年に発表されたパトリシア・レイナムの論文で「注1」に記載した彼の生年を含めわかってきたことがあります。このあたりについては、マルゴワール盤「シャルパンティエ『四つの合唱のためのミサ曲 H.4』(WPCC-4254)」の今谷和徳氏の解説に詳しく紹介されています。それによると、シャルパンティエ家は代々ギーズ家に仕えていたので(父親はマリ・ド・ロレーヌの書記官を務めていた)、彼はローマに留学する以前からかかわりをもっていて、留学そのものもギーズ嬢の援助があったからでは、と今谷氏は推測しています。
2015.12.16 (水) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅳ)
4. ジャン=バティスト・リュリ船山信子氏によるパイヤール盤「リュリ:テ・デウム」の解説書冒頭にはロマン・ ロランによる文章が引用され、そこには「<餓鬼><強欲者><憎たらしい幇間><追従者><腹黒い輩><低能><ペテン師><独裁者><がさつ者><放らつ者>・・・」とかなりひどい表現でその人となりが紹介されています。またそれ以外にもデュフルクのフランス音楽史では「調停者で天才的な日和見主義者」
 「情熱の人、自由奔放な放蕩者、巨万の富を残した山師」
など、ともかくリュリにはいい表現が見当たらないほどの
悪評ばかりです。確かに彼が王から与えられた権威を利用
して、周囲の才能ある音楽家を次々と追い落として権力の
頂点に上り詰めていく様を見ていくと、それも十分頷ける
もので、その追いやられた作曲家の中にシャルパンティエ
も含まれていました。
「情熱の人、自由奔放な放蕩者、巨万の富を残した山師」
など、ともかくリュリにはいい表現が見当たらないほどの
悪評ばかりです。確かに彼が王から与えられた権威を利用
して、周囲の才能ある音楽家を次々と追い落として権力の
頂点に上り詰めていく様を見ていくと、それも十分頷ける
もので、その追いやられた作曲家の中にシャルパンティエ
も含まれていました。リュリとシャルパンティエ、ともにヴェルサイユ楽派を代表する作曲家ですが、この二人まったく好対照ともいえる存在で、リュリはイタリア生まれでありながらフランスで頂点を極め、シャルパンティエはフランス生まれでありながらイタリアに出て音楽を学びその才能を開花させました。まずリュリについて少し詳しく見ていきたいと思いますが、その前にイタリア音楽とパリの宮廷との関係にもう少し触れておきたいと思います。
フランスで通奏低音が使用されるようになったことについては、2回目の「黄金時代」のところで触れていますが、1600前後に起こったフィレンツェにおけるカメラータ達のモノディの様式は意外と早くパリの宮廷に伝えられています。というのもアンリ4世が1600年に再婚したマリ・ド・メディシスはフィレンツェで権勢を誇ったメディチ家(フランス風に言うとメディシス)の娘であり、自身もモノディ様式の歌曲を作曲していたといわれています。メディチ家の宮廷楽長でカメラータの中心人物であったヤコポ・ペーリ(Jacopo Peri 1561-1633)が主に作曲した現存する最古のオペラ「エウリディーチェ」はこの二人の結婚祝賀のためにフィレンツェの宮殿で上演されたものでした。彼女は1604年に「アマリリ麗し」などの歌曲や、前述のオペラの作曲にも加わっていたジュリオ・カッチーニ(Giulio Caccini 1545頃-1618)をパリの宮廷に招き、彼は半年ほどそこに滞在したことからパリの音楽界にも影響を与えたと思われますが、フランスでは当時「エール・ド・クール」と呼ばれるリュート伴奏による宮廷歌曲が流行していてこうしたイタリア歌曲が入り込む余地はなかったようです。
時代はやや下り1643年にルイ13世が亡くなりルイ14世へと王位が受け継がれますが、新王はこのときまだ4才であり、したがって政治の実権は宰相マザラン(1602-61)に握られることになります。彼はもともとイタリア人でローマで育ったことからオペラにも造詣が深く、そのためフランスにもイタリア・オペラを根付かせようとします。こうして1645年にパリで史上初めてイタリア・オペラが上演され、この前後から多くのイタリア人音楽家がパリにやってきます。マザランは彼らを使って次々にイタリア・オペラをパリで上演し、その普及を図りますが、バレ好きのパリ人の心はつかめなかったようです。何しろあのヴァーグナーでさえバレーのシーンを加えないとパリではオペラを上演できなかったほどの国ですから。ただこうしたオペラの上演が1669年に音楽アカデミー(1672年に王立となる)の設立に結び着いたのです。ちょっと回り道をしましたが、こうした背景があってリュリがパリへとやってくるのです。
1632年フィレンツェで製粉業者の息子として生まれたリュリのイタリア時代についてはよく知られていませんが、幼少期に修道士から音楽の手ほどきを受け、ギターを習っていたといわれ、その他ヴァイオリンも弾いていたようです。どうも自分の過去にコンプレックスを持っていたようで、1661年にフランスに帰化する際名前をルッリ(Lulli)からリュリ(Lully)に改め、「貴族の息子」と偽ったりもしています。リュリがパリにやってくるきっかけは、ルイ14世の従姉妹にあたるモンパンシェ公女がイタリア語会話の相手を探していて、彼女の甥にあたる騎士のロレーヌが1646年イタリア旅行の際に彼女のために連れてきたのがそもそもの始まりです。彼女の料理人として雇われたという説もあるようです。こうして彼は20歳まで公女のもとで働く傍らギタリスト、ヴァイオリニストそして舞踏家としての才能に磨きをかけ、更に作曲とクラヴサンもこの頃学んだとされています。公女の住まいチュイルリー宮殿で催される王室の音楽界やバレも彼がフランス音楽を吸収するうえで大いに役立った筈です。この頃パリでは宰相マザランに反対する貴族や民衆によるフロンドの乱が起こり(1648-53)、公女はそれに加担したことから追放され、リュリは公女の元を離れます。舞踏家や喜劇役者として既にルイ14世(当時まだ15歳)に知られていたリュリは前述の「夜のバレ」で国王と初めて共演し(1653)、更に国王の信頼を勝ち取ることに成功します。このとき彼は羊飼い、兵士、浮浪者など五つの役を演じたといわれています。このあたりの変わり身の早さはさすがで、その後すぐに王室シャンブルの器楽作曲家に任命され、以後バレ・ド・クールの音楽を次々に書いていきます。このバレ・ド・クール(宮廷バレー)は舞踊に音楽や詩、パントマイムなどを取り混ぜた独特のもので、王が成人するとますます宮廷で盛んとなり、その伴奏のためにリュリによってプティット・バンドが組織されます。1661年マザランが死去すると、いよいよ王による親政が開始され、絶対王政が確立されます。この中央集権による絶対権力は文学や芸術の世界にも浸透していき、王の威光の名のもとに様々なジャンルで主導的な人物やグループが形成されていきます。音楽でその主導者となったのがリュリでした。リュリはこの年シャンブル付き楽団の総監督及び作曲家に任命され(J.B.ポエセと兼務)、その力は強大なものになり、彼によって作られたルールに従わない者は宮廷にとどまることは許されなくなります。更にリュリは翌年フランスに帰化し「王室音楽教師」に就任しその地位をゆるぎないものとします。ただこうした中央集権的な動きの中からこの時期フランスにおける様々なジャンルの新しい音楽が生まれていくのです。
音楽における絶対権力者となったリュリは1664年の5月、まだ建築中であったヴェルサイユ宮殿で開かれた祭典で、その音楽の中心的役割を果たし、当時フランスにおける最大の喜劇作家モリエール(本名ジャン・バティスト・ポクランJean-Baptiste Poquelin1622-73)と組んでコメディ・バレを上演します。このコメディ・バレは最初に器楽のプロローグがおかれ、喜劇の各幕のあとにバレがおかれるというフランスでは全く新しい形式の舞台芸術でした。ここからリュリの創作はバレ・ド・クールからコメディ・バレへと移っていき、モリエールと組んで10曲ほどの作品を残しています。その後期には現在でもよく知られる「町人貴族」(1670)があります。
リュリの功績は何といってもフランス・オペラの確立にありますが、彼の舞台芸術に対する野心と権謀術数はここでいかんなく発揮されます。マザランによってフランスにイタリア・オペラがもたらされましたが、結局フランスには根付かず、彼の政策は失敗に終わりますが、このとき同時に北イタリアから「パストラル」と呼ばれる牧歌劇も入ってきます。当初これには音楽部分は少なく、台詞が多かったのですが、やがてそのセリフはすべて歌われるようになり、ここにフランス・オペラの前身ともいえる音楽が誕生したのです。その立役者は詩人のピエール・ペランとオルガニストのロベール・カンベールで、彼らはマザランの助言もあってこのパストラルをいくつか作曲・上演し、この活動が国王の目にとまり、ここに以前にも少し触れた音楽アカデミーが創設されることになったのです(1669)。彼らは12年間パリでオペラを上演することができる特権を国王から与えられました。新しい劇場もできあがり1671年二人のコンビによるパストラル「ポモーヌ」が上演されますが。これがフランス・オペラの記念すべき最初の作品となります。これは8ヶ月間延べ100回以上も上演され、記録的な大ヒットとなりました。当然リュリはこれを苦々しく思っていたことでしょう。フランス語はオペラには向かないと批判する側に立っていたのです。ところがこの二人がオペラの上演を仕切っていたマネージャーに騙され、多額の借金を背負い、ペランは裁判にも負けて投獄されてしまいます。野心家のリュリがこの機会を見逃す筈がありません。彼はペランの借金を肩代わりする代わりにペランからオペラ上演に関する国王からの特権を買い取ってしまったのです。王室の後ろ盾が役立ったことは言うまでもありませんが、柴田南雄著「西洋音楽の歴史(中)」の中にリュリが副業に不動産業を営んでいてそこから莫大な富を得ていた、ということが真偽のほどはともかく紹介されており、そうした財力からこんなことができたのかもしれません。オペラ上演の特権を入手したリュリは更に国王からこのアカデミーに「王立」という称号を手に入れます(1672)。こうした動きにモリエールは反発し、結局二人は仲たがいし、モリエールはその後シャルパンティエとコンビを組むことになります。リュリは報復的にモリエールの劇団の本拠地(パレ・ロワイヤル)まで入手し、彼らを追い出してしまいます。更にリュリは、リュリの許可なくして全編歌われる音楽(オペラ)の上演を禁止し、王立音楽アカデミー以外では歌手6名、器楽奏者12名を超える編成による音楽の上演を禁止してしまったのです。更に翌年にはシャルパンティエがモリエールと組んでコメディ・バレを上演したのをきっかけに歌手2名、器楽奏者6名までに制限してしまい、77年には人形芝居による音楽まで禁止するという徹底ぶりでした。こうして彼はオペラを独占し、年に1作ずつ新しい劇場(ジュ・ド・ポム、翌年パレ・ロワイヤルに移転)で上演するようになったのです。
リュリのオペラは、主に神話を題材としていてプロローグと5幕から構成され、初めに英雄(「国王」を想定)を賛美し、あとは豪華な衣装や機械仕掛けの大規模な舞台装置などで観客の目を楽しませ、バレや合唱も随所に挿入してドラマを盛り上げるという手法をとっています。また彼の音楽は言葉を重視してフランス語の抑揚を十分生かしたものと評価されています。バッハをはじめドイツの作曲家にも大きな影響を与えた「フランス風序曲」もリュリによって始められたものです。私はバロック期のオペラを普段あまり聴くことがないので、彼のオペラ(「抒情悲劇 Tragedie lyrique」と呼ばれる)を評価することなどできませんが、今回いくつか聴いてみて、晩年に作曲された「アルミード」はとても素晴らしいオペラだと思いました。中でも第5幕のパッサカーユ(パッサカリア)など、どうしたらこんな素晴らしい音楽が書けるのか、と思えるほどです。オーケストラ、ソロ、合唱が一体となって生みだされる音楽は彼の人間性からは想像もできないような美しいものです。この曲は器楽の序奏が長いこともあって、ここだけ器楽曲として単独で取り上げられることもあります。
リュリは70年代の終わりごろから様々な批判や争いに巻き込まれます。オペラを独占していながら年に一作しか発表しないことへの風当たりや、王立音楽アカデミー取得の際の一部権利者との裁判沙汰、また彼の性的私行(同性愛)に対する国王からのひんしゅく等々が彼を大いに悩ませたようですが、それでも国王の信頼を失うほどには至らず、1681年彼は「貴族」の称号を手に入れます。1683年ルイ14世が再婚を機に次第に宗教心を強く抱くようになってオペラへの興味を失うと、リュリは今度は教会音楽の作曲に力を注ぐようになります。翌年デュ・モンやロベールの作品とともに「王の礼拝堂付き楽団のための二重合唱によるモテット(全50曲)」として6曲のグラン・モテが出版されています。ただそのうちの3曲はそれ以前に書かれたもので、その1曲が今回取り上げている「テ・デウム」となります。彼の後期の宗教作品はプティ・モテの方が多かったようです。彼は生涯に少なくとも25曲以上の宗教曲(グラン・モテは11曲)を作曲していますが、その数はシャルパンティエや他の礼拝堂付き作曲家に比べるとさほど多くありません。彼が教会音楽を書くようになったのは1664年以降と思われており、その最初期のグラン・モテ「ミゼレーレ(憐れみたまえ)」は国王が最も好んだ作品と言われています。彼は王室礼拝堂に関しては要職に就きませんでしたが、当然のことながら彼の力は礼拝堂にも及んでいたことでしょう。シャルパンティエが病気のため欠席した王室礼拝堂副楽長のイスをめぐるコンクールも陰でリュリが暗躍していたという説もあるようです。彼のグラン・モテの中で最大規模の「テ・デウム」は1677年9月9日国王ルイ14世臨席のもとフォンテンブロウで行われた長男ルイ(1664年生まれ)の公式の洗礼式のために作曲されました。彼はその2年後にも王族関係者の結婚式でこれを演奏しており、そのときパリの新聞に「100人のスイス人傭兵、太鼓、横笛、トランペットが特別席の下に陣取り、音楽隊は円天井まで届いている、特別席正面の階段式桟敷席に並んでいました。室内楽団はむかって右、聖歌隊は左です。<24人の弦楽合奏隊>に加えてオーボエ、フルート、トランペット、ティンパニーなどの楽器、120人にのぼる人々が歌いかつそれらの楽器を奏しました・・・」(パイヤール盤レコードの船山信子氏解説より)と紹介されており、当時としてはきわめて大掛かりな演奏だったことがわかります。さて私が今回のテーマを始めるにあたって、まだ聴いたこともなかったこの曲に関心を持ったのはある事件がきっかけだった、と述べました。その事件について触れておきましょう。1687年1月8日(パイヤール盤の解説では6日、デュメストル盤では9日となっていますがニュー・グローブの日付に従っておきます)、国王が病から癒えてその快気祝いの礼拝がパリ市内の教会で催され、そのときリュリはこの「テ・デウム」を指揮して国王を祝ったのですが、興奮のあまりか彼は指揮杖(当時は杖を上下に動かして指揮した)で自らの足を突いてしまいました。そこから傷口が悪化して膿毒症となり、更には彼が手術を拒んだことで壊疽を発症し、その事故から2か月後の3月22日、その波乱にとんだ生涯に幕を閉じたのでした。今でこそ有名なこの逸話も50年近くも前、まだ学生だった頃読んだ音楽史の本で初めて知り、そんなに興奮するような曲っていったいどんなものだったのかぜひ聴いてみたい、とずっと頭の隅に残っていたのでした。その願いがパイヤールの演奏で1976年にようやくかなったのでした。思っていた通りの絢爛豪華な音楽でした。リュリの宗教音楽は最近CDでも何曲か聴くことができるようですが、シャルパンティエに比べるとずっと少なく、私自身はこの「テ・デウム」の他やはりパイヤール指揮による演奏で、「ディエス・イレ」を聴いたにすぎません。この「ディエス・イレ」も1684年に出版された6曲のグラン・モテの内の1曲で、こちらの方は弦楽オーケストラと5人の独唱者、5声部の合唱という構成で、トランペット他管楽器は使用されていません。ディエス・イレは通常レクイエムの中の続唱にあたる部分で、「Tuba mirum(くすしきラッパの音)」の節を含むことから後世の作曲家はこぞって大規模な管弦楽を使用したりしていますが、この時代では他の作曲家の作品も含めてそうした大掛かりな音楽にはなっていないようです。とはいえ二重合唱の壮麗さなどグラン・モテの魅力は十分発揮されています。デュフルクはこの作品について「感動的な表現で、人間の苦悩を呼び起こしている」と評しています。ただ、シャルパンティエやドラランドの宗教音楽と比較してしまうと、どこか音楽的に物足りなさを私は感じてしまいます。彼はやはりオペラの作曲家なのでしょう。
今回少し長くなってしまいましたが、最後にリュリの音楽を端的に表現しているデュフルクの言葉を上げておきます。
「彼は節度のある繊細な感情の描写には秀でている。しかし、人間、あるいは物語のなかの主人公を揺さぶる戦慄や情熱を、リュリはめったにわれわれに送り返してくれることがない。彼は自分の名声を保つことには熱心だったとしても、自分の選んだ主題に感動したことが一度でもあったかどうかは疑わしい。リュリは、聴衆の好みに応じて、自分の手法、様式、音楽を、つねに単純化しようと望んでいたといわれる。装飾や母音唱法やメリスマを抑え、旋律の過度に耳ざわりな音程を捨て去り、ディミニュシオンとドゥブル[いずれも演奏家の即興的なフィギュレーションや変奏をさす]への門戸を閉ざしている。彼はシラビックやレシタティフをまもり、合唱の声部の垂直な書法を重んじて、観客に言葉がすべてわかるようにしている。彼は協和的な和音を用い、フーガ風の対位法や凝った書法は放棄する。・・国王と聴衆にたいする成功というはっきりした意図のもとに、イタリアの美学とは対蹠的な美学を守っている」(「フランス音楽史」遠山一行、平島正郎、戸口幸策訳 白水社)
2015.08.30 (日) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅲ)
3. 17世紀後半のフランス王室をとりまく音楽事情ヴェルサイユ楽派とはいうまでもなく、17世紀後半にパリ郊外に建立されたヴェルサイユ宮殿を中心に活躍した作曲家たちの総称ですが、その定義はやや曖昧なもので広義には直接ヴェルサイユとは関係のない作曲家(ジャン・ジルなど)も含めてそう呼ばれたりします。ここではあまり範囲を広げず、17世紀中頃からパリを中心に活躍していた作曲家も含めフランス王室に関連した作曲家を主にとりあげています。それでは当時フランスの王室をとりまく音楽的な状況について主に教会音楽との関連から少し触れてみたいと思います。
(1) 王宮
ルイ14世が自らの絶対権力を誇示するために作ったのがヴェルサイユ宮殿ですが、この宮殿は1678年から本格的に建設工事が行われ、王が移住したのは1682年になります。したがってデュ・モンにしてもまたリュリにしてもこの宮殿とかかわるのは晩年のごくわずかな期間にしか過ぎません。ですから彼らが活躍していたのはもっぱらルーブル宮殿を中心としたパリ市内の王宮ということになります。フランス王室の宮殿は中世以来パリのセーヌ川に浮かぶシテ島にありましたが(現在のパレ・ド・ジュスティスに名残をとどめる)、ヴァロア朝の賢王と謳われたシャルル5世(在:1364-80)が、12世紀に国土防衛のために造られその後牢獄などとして使用されていたルーブル城を国王の住居として豪華に改築し、以来学問や文化の中心地となったのです。このとき礼拝堂も城内に造られています。ただ王宮として国王の正式な居城となったのはフランソワ1世(同:1515-47)の時代になります。このルーブル宮殿はその後フランス国内を二分して争われた宗教戦争の際(ユグノー戦争1562-98)アンリ3世(在位:1574‐89)によっていったん放棄され荒廃してしまいますが、3世が暗殺され王位を継いだ賢王アンリ4世(在位:1589-1610、ブルボン朝の創始者)が宮殿を一層豪華な建物に改築し、芸術家を宮殿内に住まわせるなどして文化の中心地としての華やかさを取り戻します。しかしアンリ4世もまた暗殺され、改築は未完のままのちのルイ13世(同:1610-43)、そしてルイ14世に受け継がれ更に豪華な建物へと改築されていきますが、1666年ルイ14世は母親の死を契機にチュイルリー宮殿に移ってしまい、以後ここが王宮として使用されることはなくなりました。ルイ14世は更に豪華な王宮を造るにはルーブルでは手狭で、そのためにルイ13世が狩りの際の城館として使用していたヴェルサイユの地に大規模な宮殿を建設しようと考えたのでした。その間彼はフォンテンブロウ、チュイルリー、サン=ジェルマンといった離宮を渡り歩いていたようです。王がルーブル宮を去ったのちそこには様々な学術や芸術のためのアカデミーが国王によって設置され、1669年には王立音楽アカデミーも開設されますがこれはルーブル内ではなく宮殿に近いパリ市内で、正式には「公衆の前で、オペラと音楽並びにフランス語による公演を行い、歌唱するためのアカデミー」で、つまりここに現在のパリ・オペラ座の前身が誕生したのです。またこのアカデミーはパリ市内における公開演奏に関する独占権も持っていました。少し時代は下って1725年、このアカデミーが年にある特定の35日間だけ休みになることに目をつけたフィリドールという音楽家が、そのときだけ演奏会を開く許可を得て定期演奏会を始めました。これがコンセール・スピリテュエルでその名前が示すように当初は管弦楽と合唱による宗教音楽(ドラランドやカンプラのグラン・モテ)の演奏会でしたが、次第に他のジャンルの作品もとりあげるようになり、定期的な演奏会として定着するようになります。こうしてルイ14世の死後音楽の中心はヴェルサイユから再びパリへと移っていくことになります。
(2) 王室礼拝堂
上記で触れたようにシャルル5世によりルーブル宮殿内に礼拝堂が作られたのですが、これが王室礼拝堂としてどのように使用されていたのかについては、いろいろ文献を調べても定かではありません。この礼拝堂のある円塔の古い建物は1664年王室建築家ルイ・ル=ヴォーによって大きなパヴィリオンに改築されるまで中世の姿のまま取り残されていたようです。アンリ4世の統治下ではウスタシュ・デュ・コロワ(Eustache du Caurroy 1549 ? 1609)が礼拝堂の副楽長を務めていましたが、アンリ4世が暗殺されそのあとを継いだルイ13世は、新たに礼拝堂を造ろうとし、現在の美術館「時計のパヴィリオン(シュリー・パヴィリオン)」の2階に未完のまま残された礼拝堂が残されています。ルイ13世の時代にはニコラ・フォルメ(Nicolas Forme1567-1638)が王室礼拝堂の副楽長を務めていましたが、結局礼拝堂は1623年にルーブル宮殿のすぐ北に隣接して作られたオラトワール・デュ・ルーブル教会(Oratoire du Louvre 1811年にプロテスタントに改宗)に移されました。ルイ14世はというともっぱら宮殿の東に隣接するサン・ジェルマン・ロクセロワ教会に通い、大きな祝祭日の時にはノートルダム寺院やサント・シャペルを利用していたとか。つまり王室礼拝堂は一つではなくパリ市内にいくつかあったことになります。そして親政と呼ばれる絶対王政の確立を機に、自らの権力を誇示するためヴェルサイユ宮殿の建設を開始したのです。
ヴェルサイユ宮殿の造営は親政の開始と同時に始まり、その工事期間中にも演劇や、バレエ、音楽のための大規模な祭典が開かれるようになります。大規模な拡張工事は1678からになりますが、1674年には王室礼拝堂が現在の「ヘラクレスの間」につくられており、ここでデュ・モンやリュリ、ドラランド、クープランがヴェルサイユ・デビューを果たしています。ルイ14世は更に建築家マンサールに依頼して1699年からより豪華な宮廷礼拝堂の建設に乗り出し、それは彼の生涯最期の大事業だったのかもしれませんが、1710年に完成し現在に至っています。ここにはカヴァイエ・コルと並ぶフランスの名工ロベール・クリコ製のオルガンが正面2階に設置されており、その周囲には大規模なオーケストラや合唱をおくことのできるスペースがあります。国王は毎朝ここでおこなわれるミサに出席しましたが、王は一般的なミサ曲を好まなかったためここでは最初に絢爛豪華なグラン・モテが演奏され、そのあとには小規模なプティ・モテが、そして最後には聖歌隊全員によって「ドミネ・サルヴム(Domine salvum fac regem 主よ、王に救いを)」が歌われました。 礼拝堂の楽長職についても少し触れておきましょう。当時王室礼拝堂における「楽長」は聖職者が務めることになっており、そのため音楽家としては副楽長がその最高位のポストとなり、実質的な楽長を意味しました。したがってデュ・モンやロベール他ここに登場する多くの作曲家は副楽長という役職になっています。またこの副楽長はルイ14世の時代4人(13世の時代は二人、また一時的に二人になったこともある)いて、それぞれはコンクールで選ばれ春・夏・秋・冬と交代でその任にあたっていました。1683年デュ・モンとP. ロベールが礼拝堂楽団に何人かヴィオール奏者と女性歌手を強引に任命したという理由で引責辞任し、一時的にリュリがその職を代行していましたが、王はすぐにコンクールを開きます。そのときシャルパンティエが国王の注目を集めながら、病気のため欠席し、とうとう副楽長にはなれなかったのは有名な話です。このとき副楽長の職に就き、後にあらゆる分野でリュリのあと要職を占めていくのがドラランドです。
(3)王宮の音楽家たち
アンリ4世は1592年王室における音楽総監督の職を定め、同時に「24人の大弦楽合奏団 Les Vingt-quatre Violons du Roi(ラ・グラン・バンド)」を王室内に組織しました。以来この楽団は宮廷で演じられるバレエ(「バレ・ド・クール」と呼ばれる)の伴奏をし、パリのもっとも優れた弦楽器奏者の中からコンクールで選ばれました。弦楽器と言ってもこの時代、ヴァイオリンはまだ世俗の楽器で、王室内ではヴィオールを意味しています。ドゥシュ6(dessus、ソプラノ)、バス6(Basses)、オート=コントル4(Haute-Contre、アルト)、タイユ4(Taille、テノール)、カント4(Quintes 「第5」、次中音)の24人からなり、5種類の音域を持つヴィオールで構成され、現在一般的な4種の弦楽器編成より、中音部に厚みを持たせているのが特徴です。このバレの伴奏からクーラント、ブランル、サラバンドの舞曲で組曲が構成され、更にメヌエットとブレーがのちに加わり、冒頭にアルマンドがおかれるなどして管弦楽組曲ができあがっていきます。現代のオーケストラで当たり前になっているボウイング(弓使い)の統一もこの合奏団から生まれたといわれています。1656年アンサンブルの精度を更に高めるため、リュリは国王に請願して16人のオーケストラをつくりました(ラ・プティット・バンド)。
ヴェルサイユ宮殿ができあがると、音楽の中心もパリからヴェルサイユへと移っていきます。ヴェルサイユには音楽家の数だけでも200人がいた、といわれています。その200人は皆、シャペル(王室礼拝堂)、シャンブル(室内楽団)そしてエキュリー(大厩舎)と呼ばれる三つの組織のいずれかに所属していました。この組織そのものはかなり古くから存在していたようです。「シャペル」は楽長、副楽長をはじめ専属の作曲家、歌手(ドゥシュからバスまで)、オルガニスト(副楽長同様4人)などで構成されていました。オルガニストにはニコラ・ルベーグ(Nicolas Lebegue 1631-1702)やギョーム=ガブリエル・ニヴェール(Guillaume=Gabriel Nivers 1632-1714)などフランス・バロックのオルガン音楽を代表する奏者がおり、後にフランソワ・クープランも加わります。1708年ニヴェールの後任にはドレスデンであの大バッハとオルガンの腕前を競う(1717年)ことになって直前に逃げ出したといわれるルイ・マルシャン(Louis Marchand 1669-1732)が就任しています。歌手の中には楽器を演奏する人もあったようですが、グラン・モテなどの演奏にはシャンブルの弦楽器奏者や、エキュリーの管楽器奏者が駆り出されていました。デュフルクの記述によれば、オルガンの両側の階段席にヴィオールで伴奏される90人の歌手たち(合唱)、オルガンと手すりの間に副楽長(おそらくは指揮者として)、独唱者、更にクラヴサンを囲んでヴァイオリン、フルート、オーボエなど19人の器楽奏者が配置されていました。尚礼拝堂にヴァイオリンを持ち込んだのはリュリが最初であり、物議をかもしたとのことです。この記述に従えばゆうに100人以上の大編成となります。
「シャンブル」は国王や、王妃が宮殿内で室内楽を楽しんだり、舞踏会が催される際の音楽の伴奏などをするために組織されました。その頂点には音楽監督がおり、ルイ14世の親政開始(ルーブル時代の1661)以後はリュリとJ.B.ポエセの二人が半年交代でその任にあたっていました。そして音楽監督を補佐する楽長や、更には専属作曲家もそれぞれ二人ずつおり、それらにはリュリとゴベールやデュ・モン、P.ロベールらがあたっていました。王宮のヴェルサイユ移転後間もなくしてポエセもリュリもほぼ同時期に亡くなってしまい、それらのポストはリュリの一族に受け継がれますが、やがて台頭してきたドラランドにすべてが集約されていきます。このシャンブルには声楽や器楽の演奏者が20人ほどおり、その他に前述の「王の24の大弦楽合奏団」や、「プティット・バンド」などがありました。アンサンブルだけでなく、クラヴサンのソロによるコンサートも数多く行われ、ダングルベール(Jean Henri d’Anglebert 1629-91)が活躍しました。またヴィオールのマラン・マレ(Marin Marais 1656-1728)やテオルボ、バロック・ギターの名手ヴィゼ(Robert de Visee生没年不祥)もシャンブル付きの王室奏者として人気を博していました。このシャンブルの音楽家たちのもう一つ重要な仕事として、王の晩餐の際に食卓を飾る音楽を提供することも含まれていました。ドラランドはそのために多くの「王の晩餐のためのサンフォニー」を残しています。またルイ14世はしばしば「太陽王」という名前でよばれることがありますが、これは王自身がバレの踊り手の名手であり、1653年に宮殿で催されたバレ・ド・クール「夜のバレ」上演の際に、輝かしく世界に夜明けを告げる太陽の象徴としてアポロンに扮して登場し、それ以来この名前で呼ばれるようになりました。このバレは当時シャンブルの音楽監督であったカンブフォール(Jean de Cambefort 1605頃‐61)を中心に何人かのシャンブル付作曲家の共作で作られたものですが、このときにやはり踊り手として登場していたのがリュリで、王の注目を集めたリュリは瞬く間に栄光への階段を昇っていくことになります。
「エキュリー」は、ヴェルサイユ宮の野外で行われる音楽を受け持ち、正式には「大厩舎の音楽 musique de la ecurie」と言います。野外で行われる馬術の催しで演奏したり、また最大の目的は狩りの際の音楽でホルン(12本)やトランペット(同数)、ティンパニを含む太鼓による豪壮な音楽で、それにはオーボエやフルート、ファゴットなどの管楽器も響きを補強するために加わっていました。ですからこのエキュリーは管楽器による演奏集団と言っていいでしょう。かつてはヴァイオリンも所属していたようですが、それらはフランソワ1世の時代にシャンブルに移されたといいます。またこの楽団にはちょっと変わった楽器もありました。フランスの民族楽器でバグ・パイプの一種である「ミュゼット」や「海のトランペット」と呼ばれる長い棹のようなものに一本の弓を張って弦でこすって音を出す「トロンバ・マリーナ」(フラジオレット奏法でトランペットに似た音を出す)などの楽器もありました。現代、木管楽器(特にフルート)の歴史や奏法を語るうえで極めて重要な作曲家ジャック・オトテール(Jacques Martin Hotteterre 1680頃-1761)はミュゼットの名手でもありその楽器のための教則本なども出版していますが、彼は1692年にはこの楽団に入団しファゴット奏者、同時にシャンブルのフルート奏者(トラヴェルソ)になったといわれています。
以上がかなり足早にみてきた17世紀後半から18世紀初頭にかけてのフランスの音楽事情になります。次回からリュリやシャルパンティエについてもう少し詳しくみてみたいと思います。
2015.06.12 (金) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅱ)
2. フランス音楽の黄金時代音楽史家ノルベール・デュフルクによれば、フランスには音楽史上四つの黄金時代が あったとされています。第一期はカペー王朝の聖王と呼ばれたルイ9世の時代(在位1226年~1270)で、この時代は1163年に着工されたノートル=ダム大聖堂を中心としたノートル=ダム楽派が活躍し、レオナン(Leonin レオニヌスともいう。12世紀後半、生没年不明)やペロタン(Perotin ペロティヌスともいう。1183?-1236)などを輩出したアルス・アンティークヮの時代と呼ばれています。単旋律の音楽から多声音楽へと変わりますが、この時代の多声音楽は一つの主旋律に三度や四度で並行して和声がつけられたもので、オルガヌム(語源はオルガン)と呼ばれ、後のポリフォニー(多声音楽)と区別して「多旋音楽」などという人もあります。第二の黄金期はルイ11世(1461~83)の時代から16世紀までで、ブルゴーニュ楽派の大作曲家ギョーム・デュファイ(Guillaum Dufay c.1400-74)やそれに続くフランドル楽派最大の作曲家で「音楽の父」などとも呼ばれるジョスカン・デ・プレ(Josquin des Prez c.1440-1521)などが現れ、ポリフォニーの黄金時代を築き上げ、ヨーロッパ中に大きな影響を及ぼしました。第三の黄金時代は1660年から1760年までで、そして第4の黄金期は1860年から1940年までとされています。今回スポットを当てているシャルパンティエとリュリは、この第三期黄金時代に属しています。
デュフルクによれば100年続いたこの第三期黄金時代は更に三つの世代に区分されます。最初の世代がジャン=バティスト・リュリ(Jean-Baptist Lully 1632-87)とマルカントワーヌ・シャルパンティエ(Marc-Antoine Charpentier 1643-1704)に代表される時代で、二番目の世代はミシェル=リシャール・ドラランド(Michel-Richard Delalande 1657-1726)とフランソワ・クープラン (Francois Couperin 1668-1733) 、そして第三の世代がジャン=フィリップ・ラモー(Jean-Philippe Rameau 1683-1764)とジャン=マリー・ルクレール(Jean-Marie Leclair 1697-1764)となります。この第三期の開始が1660年と明確にされているのは、ルイ14世が絶対王政を確立したいわゆる「親政」の開始と時を同じくしていることによります(正確には1661年)。今回のテーマはこの第三期黄金時代で、フランス・バロック(デュフルクはバロックという語は使わず「前古典主義」という表現を用いています)の輝かしい頂点を築いた第一世代の代表的作曲家二人になりますが、この第一世代によってフランス・バロック期の音楽がどのように形成されていったのかもう少しく詳しくみてみましょう。尚第二期黄金時代と、第三期黄金時代の間(ルネサンス後期)にはジョスカンの弟子で非常に美しいポリフォニーを書いたニコラ・ゴンベール(Nicolas Gombert 1500頃-57)や、よく知られたオルランドゥス・ラッスス(Orlandus Lassus イタリア語表記ではオルランド・ディ・ラッソ 1532頃-94)等がいましたが、彼らはフランドルを出て主にドイツやスペイン、イタリアなどで活躍していました。その他にはクロダン・ド・セルミジ(Claudin de Sermisy 1490頃-1562)やシャンソンで知られるクレマン・ジャヌカン(Clement Jannequin 1485頃-1558)、そして変わったところではカルヴァン派のプロテスタントでサン・バルテルミの虐殺で犠牲となったクロード・グディメル(Claude Goudimel 1510頃-72)等がいました。
バロック音楽の大きな特徴として、通奏低音とコンチェルタート様式に見られる対比の芸術があげられることは今までにも何度か触れてきました。これらの様式は1600年前後に始まったイタリアのオペラや宗教曲によって確立され、全ヨーロッパに波及していきます。保守的なフランスでもイタリアの影響をさまざまに受け始め、ジョスカン以来のア・カペラによるポリフォニーを良しとする教会音楽の世界も器楽や世俗の音楽とぶつかりながらイタリアの様式を受け入れ、あるいは反発しながら発展していきます。教会音楽のポリフォニーにフランスではじめて通奏低音を導入したのはジャン=バティスト・ボエセ(Jean-Baptiste Boesset 1614-85)だといわれています(注)。更にそうした教会音楽にイタリアの複合唱によるコンチェルタート様式を導入したのは、後に王室礼拝堂作曲家にもなったトマ・ゴベール(Thomas Gobert 1600頃‐1672)になります。ゴベールは合唱を大合唱(グラン・クール Grand choeur)と小合唱(プティ・クール Petit choeur)に分け、プティ・クールは独唱者たちによってのみ歌われる形式を作りました。こうした彼らの音楽はやがて1663年にパリ王室の宮廷礼拝堂副楽長になったアンリ・デュ・モン(Henry Du Mont 本名アンリ・ド・ティエ 1610-84)やピエール・ロベール(Pierre Robert 1618頃-1699)によって更に進化され、以後長らくフランスの宗教音楽の特徴を決定づける二つの様式が生まれます。一つは小規模な合唱や重唱に通奏低音を加えたプティ・モテ(Petit motet)で、もう一つは大規模な合唱や独唱にオーケストラを伴うグラン・モテ(Grand motet)と呼ばれる形式です。プティ・モテには小編成の弦が加わることもあります。そしてグラン・モテは器楽、合唱、独唱や重唱などがお互いにかけあいながら壮麗な音楽を作り出します。その壮麗さにおいてはヴェネツィア楽派をも凌ぐほどです。中でもアンリ・デュ・モンがフランス宗教音楽に果たした功績は大きく、<ニュー・グローヴ>のモテットの項では「交響曲と弦楽四重奏におけるハイドンの地位に匹敵する」と紹介されています。時代遅れとなっていたア・カペラのポリフォニーを捨てて新しい音楽を作り出したのでした。彼はベルギーのリエージュ近郊に生まれ、1638年からパリに移って活躍し、1663年ルイ14世の王室礼拝堂副楽長となって頂点を極めます。彼は生涯に69曲のグラン・モテと130曲のプティ・モテを作曲しましたが、かなりの作品が失われてしまい、現在ではそれぞれ26曲と19曲しか残っていないといわれています。そして通奏低音に関しても、数字付きの独立した声部として楽譜に書かれるようになったのは、このデュ・モンによる作品が最初だともされています(1652“聖歌集Cantica sacra”。ボエセの作品は部分的で、しかも声の最低声部と重複)。したがってしばしば「フランスにおける通奏低音の開始はこのデュ・モンが最初である」と書かれることがあります。また彼は作曲技法に優れ、グラン・モテには当時フランスで使われていたすべての音楽形式が盛り込まれている、といわれています。ポリフォニー、レシタティーフ、エールド・クール(宮廷で歌われていた世俗的な有節歌曲)、そして二重唱のカノンなどを巧みにつなぎ合わせて礼拝の間に演奏したのでした。このデュ・モンの教会音楽はいくつかのCDで聴くことができます。グラン・モテに関しては古い録音しか私は持っていないので、あまり参考にはならないかもしれませんが、ルイ・フレモー指揮による演奏(フィリップ・カイヤール合唱団、パイヤール管弦楽団、ジョスリーヌ・シャモナンのソプラノ他 エラート R20E-1015)で、マニフィカト他3曲のグラン・モテを収録したものがあります。これらはすべて王室礼拝堂のために書かれ、彼の死後1686年に出版されたもので、大合唱と複数のソリスト(小合唱も兼ねる)および管弦楽によって演奏されます。私の個人的な感想としては、これらの作品はのちに続くシャルパンティエやドラランドなどのグラン・モテと比較するとまだ発展途上なのかなと思います。ただその中ではメインの「マニフィカト」より最後におかれた少し短い「ベネディクトゥス」の方が楽しめるように思います。終曲のプティ・クールとグラン・クールの掛け合いによる対比の音楽は聴きごたえがあります。このCDだけでデュ・モンのグラン・モテを評価することはできませんが、現在輸入盤などではカタログに何枚かリストがあるものの入手できなかったので他の演奏で比較することはできませんでした。一方プティ・モテに関してはアンサンブル・ピエール・ロベールによる演奏で「王室礼拝堂のためのモテット集」(マーキュリー Alpha021)があり、
 これは素晴らしいCDです。1681年に出版された「2声、3声および4声の
モテット集」から選曲されたもの、と解説書には書かれてい
ますが、いくつか調べているうちに気がついたことがありま
す。1681年出版となっていますが、<ニュー・グローヴ>に
はその年号に出版されたものがなく、1671年に同じタイトル
の作品群が出版されたことになっています。デュフルクの本
では71年の記載がなく、CDと同じ81年の出版に同タイトル
のものが見出されます。どちらかが間違っているのか、あるいは両方とも正しくてそれぞれに出版されているのか、ちょっとわかりませんが、いずれにしろこれらのプティ・モテに聴く表情豊かな音楽は素晴らしく、この様な作品がバッハが生まれる以前に既にフランスに存在していたことはちょっと驚きです。
これは素晴らしいCDです。1681年に出版された「2声、3声および4声の
モテット集」から選曲されたもの、と解説書には書かれてい
ますが、いくつか調べているうちに気がついたことがありま
す。1681年出版となっていますが、<ニュー・グローヴ>に
はその年号に出版されたものがなく、1671年に同じタイトル
の作品群が出版されたことになっています。デュフルクの本
では71年の記載がなく、CDと同じ81年の出版に同タイトル
のものが見出されます。どちらかが間違っているのか、あるいは両方とも正しくてそれぞれに出版されているのか、ちょっとわかりませんが、いずれにしろこれらのプティ・モテに聴く表情豊かな音楽は素晴らしく、この様な作品がバッハが生まれる以前に既にフランスに存在していたことはちょっと驚きです。こうした宗教音楽の発展の背後でイタリアからやってきた粉屋の息子リュリが着々とその地盤を固めていき、絶大な権力を握っていくのです。
(注) ニュー・グローヴ音楽事典では、出版された作品としてフランスで通奏低音が導 入された最古の教会音楽はコンスタンティン・ホイエンス(Constantijn Huygens 1596-1687)の「パトディア・サクラ・エト・プロファーナ Pathodia sacra et Profana」(1647)だとしています。ただホイエンスは名前からもわかるようにオラ ンダ人で、そのためかデュフルクのフランス音楽史には名前すら登場しません。 いずれにしろ、だれが最初に通奏低音を導入したのかについては、解釈も含め議 論があるようです。
2015.04.05 (日) Ⅶ. シャルパンティエとリュリのテ・デウム: ヴェルサイユ楽派の宗教音楽 (Ⅰ)
昨年でバッハのカンタータについては一先ず区切りをつけ、新たなテーマで始めますが、今回はちょっと趣向を変えて、一枚のCDから話を発展させてみようと思います。タイトルにもあるように、最近下記のCDを聴いたのですが、この2曲については私にとってたいへん思い出深いものでしたので、そんな話を交えながら話を進めてみたいと思います。
マルカントワーヌ・シャルパンティエ:テ・デウム H 1461. 出会い
ジャン=バティスト・リュリ:テ・デウム LWV 55
ヴァンサン・デュメストル指揮 ル・ポエム・アルモニーク
カペラ・クラコヴィエンシス
(マーキュリー Alpha 952)
私が高校生の頃朝のFM放送「バロック音楽のたのしみ」を毎日聴いていたことは今までにも何度か触れてきましたが、ヴェルサイユ楽派の音楽に初めて触れたのもこの時期でした。ちょうどクリスマスの頃だったと思いますが、服部幸三先生の解説でシャルパンティエの「真夜中のミサ曲」がとりあげられました。この作品は当時のフランスではよく知られていたノエル(クリスマス・キャロル)の旋律からとられているだけあってとても親しみやすいもので、私もすぐにこの曲が気に入りました。当時我が家には兄が買ったテープ・レコーダーがあって、この番組で紹介される音楽はほとんどそれに録音して気に入った曲は何度も繰り返し聴いていたものです。話が少しそれますが、このテープ・レコーダーについて触れておくと、コロムビア製のオンボロなレコーダーでしたが、なかなかのすぐれものでした。ヘッドは2トラックになっていて録音は片チャンネルのモノラル(往復録音)ながら、再生だけはステレオ再生ができたのです(といってもあくまでも家庭用の機械なので、速度は19cm/sec.が最高速)。購入後しばらくして兄はアメリカへ行ってしまったので私が独占して使用することになりました。貧しい我が家ではなかなか生テープを買う小遣いもなく、少しずつ貯め込んだお金で秋葉原まで行き、ツギハギだらけの屑テープを購入するのがやっとでした。いざコピーを始めると、つなぎ目で音がプルッとなり、いつもひやひやしながらコピーをしていたことを懐かしく思い出します。レコード会社に入ってスタジオで仕事をするようになったとき、もはや時効なので告白しますが、仕事が終わってから時間があると倉庫からマスター・テープを取り出し、こっそり余ったテープを継ぎ足してそれにコピーして我が家でもちょっぴり楽しませてもらいました。このときこのテレコは大いに威力を発揮しました。何しろ2トラックのテープ・レコーダーなど家庭用ではこの機種ぐらいしかなかったのでは(高価なものではRebox)。もちろんいくらテープの扱いには慣れていたとはいえ、こんなことをしてはいけませんね。こうして私はこの「真夜中のミサ曲」を繰り返し聴く内に、ヴェルサイユ楽派の音楽に興味を持ったのです。因みにこの「真夜中のミサ曲」、日本でもその後かなり人気があったのか、1972年にはヒュー・ウィリー・ヒチコック版(H. Wiley Hitchcock、シャルパンティエの曲は近年彼の作品目録H番号であらわされる)によるヴォーカル・スコアが日本でも全曲出版されています(基督教音楽出版「コンコルディア大カンタタ・ブック」―「カンタータ」ではなく「カンタタ」などという言葉に時代を感じますね)。
大学に入って、アルバイトをしながら少し余裕が出てくると、当時中古レコードを扱っていた数寄屋橋のハンターや、数寄屋橋から新橋に向かうアーケードの中にあった輸入盤専門店ハルモニアなどに足しげく通うようになりました。そんなある日、いつものようにハルモニアに行くと、美しい唐草模様の統一ジャケットに収められたシャルパンティエのテ・デウムのレコードを見つけました。アメリカ・ヴァンガードの輸入盤で演奏はルイ・
 マルティーニ指揮の演奏でした。このヴァンガード
のレーベルはすべて同じような統一ジャケットでとても美しく、
またバロック音楽のレパートリーもノンサッチやミュージカル・
ヘリテージ・ソサエティなどのレーベル同様当時としてはかな
り充実していたように思います。フェリックス・プロハスカ指
揮によるバッハのカンタータ・シリーズなどもこのレーベルだ
ったと記憶しています。どんな音楽かはわからなかったものの
「真夜中のミサ曲」で親しんでいた作曲家の作品で、興味があったのですぐに購入しました。この当時お金もないくせにけっこうこうした衝動買いのようなことがありました。今のようにネットで買う時代と違って実際にレコードを手に取って、隅々まで眺めると、どうしてもほしくなってしまうことがあるのです(この習性は今も変わらず、時間があってレコード店にブラッと立ち寄ると、CDを手に取ってみては衝動的に買ってしまうことがよくあります)。だからこうして購入したレコードは一枚一枚が私にとっては大事な宝物なのです。そして帰宅後レコードに針を落とすと、そこから溢れ出てきたまさに洪水のような音楽に圧倒されました。世の中にこんなに壮麗な音楽があったのかと。「真夜中のミサ曲」とは正反対のとてつもなく派手な音楽です。この二つの作品で私はヴェルサイユ楽派の音楽の虜となったのです。そして学生時代、大学オーケストラの活動に勤しみながらも、ロマン派の音楽同様、バロック音楽への興味も尽きることなく続き、音楽史の本なども読みふけるようになりました。こうして古楽への興味はどんどん時代をさかのぼり、ついには中世やルネサンスの作品にまで手をだすハメになってしまったのです。それもこれもすべてはNHK/FMの朝の番組「バロック音楽の楽しみ」がきっかけを与えてくれたのです。そしてその当時この番組で楽しいお話をいっぱいしてくださった、皆川達夫先生や今は亡き服部幸三先生と、レコード会社に入ってまたお世話になろうとは当時全く思いもしませんでした。
マルティーニ指揮の演奏でした。このヴァンガード
のレーベルはすべて同じような統一ジャケットでとても美しく、
またバロック音楽のレパートリーもノンサッチやミュージカル・
ヘリテージ・ソサエティなどのレーベル同様当時としてはかな
り充実していたように思います。フェリックス・プロハスカ指
揮によるバッハのカンタータ・シリーズなどもこのレーベルだ
ったと記憶しています。どんな音楽かはわからなかったものの
「真夜中のミサ曲」で親しんでいた作曲家の作品で、興味があったのですぐに購入しました。この当時お金もないくせにけっこうこうした衝動買いのようなことがありました。今のようにネットで買う時代と違って実際にレコードを手に取って、隅々まで眺めると、どうしてもほしくなってしまうことがあるのです(この習性は今も変わらず、時間があってレコード店にブラッと立ち寄ると、CDを手に取ってみては衝動的に買ってしまうことがよくあります)。だからこうして購入したレコードは一枚一枚が私にとっては大事な宝物なのです。そして帰宅後レコードに針を落とすと、そこから溢れ出てきたまさに洪水のような音楽に圧倒されました。世の中にこんなに壮麗な音楽があったのかと。「真夜中のミサ曲」とは正反対のとてつもなく派手な音楽です。この二つの作品で私はヴェルサイユ楽派の音楽の虜となったのです。そして学生時代、大学オーケストラの活動に勤しみながらも、ロマン派の音楽同様、バロック音楽への興味も尽きることなく続き、音楽史の本なども読みふけるようになりました。こうして古楽への興味はどんどん時代をさかのぼり、ついには中世やルネサンスの作品にまで手をだすハメになってしまったのです。それもこれもすべてはNHK/FMの朝の番組「バロック音楽の楽しみ」がきっかけを与えてくれたのです。そしてその当時この番組で楽しいお話をいっぱいしてくださった、皆川達夫先生や今は亡き服部幸三先生と、レコード会社に入ってまたお世話になろうとは当時全く思いもしませんでした。それから先程シャルパンティエの「テ・デウム」について、ルイ・マルティーニ指揮のヴァンガード盤とご紹介しましたが、詳しい方ならおやっと思われた方もあるかと思います。そう、この演奏は日本ではエラート原盤としてよく知られているものです。ですから私も、これはおそらくヴァンガードがアメリカでライセンスを受けて発売していたものと最近まで思っていたのですが、この原稿のために古いLPを引っ張り出して裏を眺めると、どうやらバッハ・ギルドとの共同制作のようです。このバッハ・ギルドはヴァンガード傘下のレーベルで、ニューヨーク大学の教授マーティン・バーンスタインの助言の元”Historical Anthology of Music”という古楽のシリーズ(レパートリーは中世から古典派まで)を発売していました。その中には前述したウィーンにおけるプロハスカによるバッハのカンタータ・シリーズやデラー・コンソートによるマショーの”ノートルダム・ミサ”(古くはドイツのテープ・メーカーとして知られていたBASFのレーベルで発売されていて現在はdeutsche harmonia mundiとなったレーベルのものと同録音?)、ヴィルヘルム・エーマン指揮ヴェストファーレン・カントライによるシュッツの”クリスマス・オラトリオ”(Cantate原盤?)などの録音も含まれていました。このレコードはそうしたシリーズの一枚として発売されていたのです。その他の演奏者もご紹介しておきましょう。
M.-A.シャルパンティエ: テ・デウム&マニフィカトそして「真夜中のミサ曲」同様、後にこれらの録音に私自身が仕事でもかかわることになろうとはゆめゆめ思いませんでした。現在上記の演奏は我が家ではR20E-1003という番号のCDで今なおよく聴いているものの一枚です。
ルイ・マルティーニ指揮 パイヤール管弦楽団 フランス音楽青少年合唱団
マルタ・アンジェリシ(S)、ジョスゥリーヌ・シャモナン(S)、アンドレ・マラブレラ(C-t) 他
モーリス・アンドレ(Tp)、マリー=クレール・アラン(Og)
またもう一方のリュリの「テ・デウム」ですが、この曲はかつて私が読んでいた音楽史の本の中で、ちょっとした事件とのかかわりで、これはいったいどんな曲だったのだろうか?とずっと頭の中に残っていた曲だったのです。何しろこの曲については当時録音が手に入らず、やはりエラート・レーベルから1970年代半ばにジャン=フランソワ・パイヤール指揮による録音が発売されて、ようやく聴くことができるようになったものでした(これが世界初録音だったわけではなく、ずっと以前に古いモノラル盤がヨ-ロッパなどでは発売されていたことがあったようです)。その事件についてはこの曲のより詳しい紹介の中で後述することにします。
2014.12.02 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(27)
26. カンタータ第82番「我は満ち足れり」BWV82―Ⅷさて最後にCDのご紹介ですが、私の好きな曲だけにかなり枚数も多いので、独断と偏見により相応しいと思われるものいくつかにしぼってリスト・アップします。
この曲がバス、ソプラノ、アルトのためにそれぞれ書かれていることはこれまでにもご紹介した通りです。またバスのソロにも第1稿と第4稿の2種類あることも前回触れたとおりです。まずそのバスのソロによるCDから始めますが、こうしたソロによる演奏となるとどうしても歌手の力量によるところが大きくなり、その意味では古楽系はちょっと苦戦を強いられます。またこのカンタータに関する第1回目の原稿の冒頭で既に私の気に入っている演奏については触れており、基本的にはその演奏を聴くことがほとんどで、他の演
 奏はそのときの気分によって時々聴くという程度
にすぎません。ただこのカンタータで一般的に一番いいと言われ
ているのが、カール・リヒター指揮によるフィッシャー=ディー
スカウのアルヒーフ盤(1968年録音 POCA-2031)であることは知
っています。私もフィッシャー=ディースカウは大好きな歌手な
ので、これが一番いいと言いたいところですが、ゲルネの歌を聴
いてしまうとどうもいろいろなところが気になってしまいます。第1曲目は何とも間延びしたような歌い方でその楽天的とも思える歌い方が気になります。また第3曲では歌いだしから2小節目の”ihr matten(疲れた)“をちょっと強調し、これが何度も出てくるので辟易とさせられます。第4曲ではアウフタクトで始まる「と」音が低い声で苦しいのかその音だけオクターヴあげて歌ったりもしています。ただ全体的に歌いまわしはさすがと思わせるものがあり、特に中間部の劇的な変化は他の歌手からは感じられないものです。また特筆すべきは歌ではなく通奏低音のオルガンです。これ程多彩とも思えるオルガンの扱いはさすがにリヒターの指揮ならではと思います。私はフィッシャー=ディースカウの歌ならもう一種別の録音の方がまだ好きです。これはカール・リステンパルト指揮の室内管
奏はそのときの気分によって時々聴くという程度
にすぎません。ただこのカンタータで一般的に一番いいと言われ
ているのが、カール・リヒター指揮によるフィッシャー=ディー
スカウのアルヒーフ盤(1968年録音 POCA-2031)であることは知
っています。私もフィッシャー=ディースカウは大好きな歌手な
ので、これが一番いいと言いたいところですが、ゲルネの歌を聴
いてしまうとどうもいろいろなところが気になってしまいます。第1曲目は何とも間延びしたような歌い方でその楽天的とも思える歌い方が気になります。また第3曲では歌いだしから2小節目の”ihr matten(疲れた)“をちょっと強調し、これが何度も出てくるので辟易とさせられます。第4曲ではアウフタクトで始まる「と」音が低い声で苦しいのかその音だけオクターヴあげて歌ったりもしています。ただ全体的に歌いまわしはさすがと思わせるものがあり、特に中間部の劇的な変化は他の歌手からは感じられないものです。また特筆すべきは歌ではなく通奏低音のオルガンです。これ程多彩とも思えるオルガンの扱いはさすがにリヒターの指揮ならではと思います。私はフィッシャー=ディースカウの歌ならもう一種別の録音の方がまだ好きです。これはカール・リステンパルト指揮の室内管
 弦楽団と共演した演奏で1951年に録音した
やはりアルヒーフ盤(POCA-2603)です。モノラル録音ながら音
質も思ったほど悪くありません。まだ20代半ばの頃で、声も
若々しく張りがあり、音楽も情感にとんでいます。ただ一部ピ
ッチが不安定なところがあり、またオクターヴあげて歌うとこ
ろはこれも同じで、この録音では更に第1曲の最後のところで
も急にオクターヴあげています。ただこちらは声が出ないというより劇的な効果をねらったものでしょう。バロック音楽ではこうした即興的な演奏はよく行われることですが、バッハはアーティキュレーションなど厳格に従うことを要求し、細かく楽譜に指示するなどしてシャイベから批判され、それが論争となったりしたくらいなので、少なくともバッハ自身は変更されることを望んでいないのではないでしょうか。こうしたことをしているのはフィッシャー=ディースカウだけです。
弦楽団と共演した演奏で1951年に録音した
やはりアルヒーフ盤(POCA-2603)です。モノラル録音ながら音
質も思ったほど悪くありません。まだ20代半ばの頃で、声も
若々しく張りがあり、音楽も情感にとんでいます。ただ一部ピ
ッチが不安定なところがあり、またオクターヴあげて歌うとこ
ろはこれも同じで、この録音では更に第1曲の最後のところで
も急にオクターヴあげています。ただこちらは声が出ないというより劇的な効果をねらったものでしょう。バロック音楽ではこうした即興的な演奏はよく行われることですが、バッハはアーティキュレーションなど厳格に従うことを要求し、細かく楽譜に指示するなどしてシャイベから批判され、それが論争となったりしたくらいなので、少なくともバッハ自身は変更されることを望んでいないのではないでしょうか。こうしたことをしているのはフィッシャー=ディースカウだけです。もう一枚やはりモダン楽器によるオーケストラと共演しているトーマス・クヴァストホフのCD(独グラモフォン UCCG-1219)についても触れておきましょう。彼の歌は全体的にソフトな歌い方で、ところどころやさしく語り掛けるように歌うppが特に美しいと思いま
 す。声にもう少し深みがあるとさらにいいのですが。
またこの演奏ではオーボエのソロをベルリン・フィル主席のアル
ブレヒト・マイヤーが吹いています。オーボエがでたついでに、
録音はやや古いですがバリー・マクダニエルが歌うEratoのフ
リッツ・ヴェルナー盤では名手ピエール・ピエルロのオーボエが
聴けます。ただ彼のオーボエはちょっとチャルメラ的な音色で好
き嫌いが分かれるでしょう。
す。声にもう少し深みがあるとさらにいいのですが。
またこの演奏ではオーボエのソロをベルリン・フィル主席のアル
ブレヒト・マイヤーが吹いています。オーボエがでたついでに、
録音はやや古いですがバリー・マクダニエルが歌うEratoのフ
リッツ・ヴェルナー盤では名手ピエール・ピエルロのオーボエが
聴けます。ただ彼のオーボエはちょっとチャルメラ的な音色で好
き嫌いが分かれるでしょう。私がゲルネの演奏がいいと思っている理由は、まず声に深みがあり気高く、また十分張りがありながら抑制がきいていて、言葉の一つ一つにも気を配りながら情感に満ちていることです。これには胸を打たれます。気持ちが疲れていた り、病に苦しんでいたりするときなど、心の底から癒されます。
 オーケストラは1997年から常任を務めるロジャー・ノリントン
指揮のカメラータ・アカデミカ・ザルツブルクです。話がそれま
すがこの指揮者ベートーヴェンやブラームスの交響曲全集を別
のオケと録音しているのですが、これが全くつまらない演奏で、
私の嫌いな指揮者の一人です。古楽奏法などを取り入れているそうですが、全く面白味のない凡庸な演奏です。以前N響を振りに来て、そのリハーサルの一部がTVで放映されましたが、どこかスノビッシュで、第九に至ってはひどいものでした。よくあんな滅茶苦茶な棒で演奏できるなと思ったものですが、オケの団員も彼の指揮は見ずに演奏したとかいう話も。ところがこのCDでは好演でゲルネをよくサポートしています。素晴らしい歌手との出会いが生んだ奇跡なのかもしれません。またここでもマイヤーのオーボエが聴けるのですが、クヴァストホフ盤(2004年録音)とは全く違った演奏です。こちらは1999年の録音で後に録音されたものより控えめに奏され、非常に豊かな音楽性を感じさせてくれます。ゲルネの歌にとてもよくマッチしています。上記にご紹介した演奏はすべてモダン楽器による現代のピッチで演奏されており、すべて第1稿によっています。
オーケストラは1997年から常任を務めるロジャー・ノリントン
指揮のカメラータ・アカデミカ・ザルツブルクです。話がそれま
すがこの指揮者ベートーヴェンやブラームスの交響曲全集を別
のオケと録音しているのですが、これが全くつまらない演奏で、
私の嫌いな指揮者の一人です。古楽奏法などを取り入れているそうですが、全く面白味のない凡庸な演奏です。以前N響を振りに来て、そのリハーサルの一部がTVで放映されましたが、どこかスノビッシュで、第九に至ってはひどいものでした。よくあんな滅茶苦茶な棒で演奏できるなと思ったものですが、オケの団員も彼の指揮は見ずに演奏したとかいう話も。ところがこのCDでは好演でゲルネをよくサポートしています。素晴らしい歌手との出会いが生んだ奇跡なのかもしれません。またここでもマイヤーのオーボエが聴けるのですが、クヴァストホフ盤(2004年録音)とは全く違った演奏です。こちらは1999年の録音で後に録音されたものより控えめに奏され、非常に豊かな音楽性を感じさせてくれます。ゲルネの歌にとてもよくマッチしています。上記にご紹介した演奏はすべてモダン楽器による現代のピッチで演奏されており、すべて第1稿によっています。 これが古楽系では一番かなとも思います。フッテンロッハーはコ
ンサートなどで聴くと声量こそあまりありませんが、声に深みと張
りもあり、そのためか録音ではけっこう重宝されています。コルボ
と組んでエラート・レーベルにもかなり名演を残しています。これ
ら古楽系の演奏はすべて第4稿による版を採用しており、ピッチも
当然ながらカンマートーンで演奏していますので現代のピッチより半音低くなっています。第4稿の特徴は前回にも触れましたがアーティキュレーションの違いと、それと最も大きな違いは第3曲にオーボエ・ダ・カッチャを加えていて、これがオーケストラにとてもやわらかい響きを与えていることです。
これが古楽系では一番かなとも思います。フッテンロッハーはコ
ンサートなどで聴くと声量こそあまりありませんが、声に深みと張
りもあり、そのためか録音ではけっこう重宝されています。コルボ
と組んでエラート・レーベルにもかなり名演を残しています。これ
ら古楽系の演奏はすべて第4稿による版を採用しており、ピッチも
当然ながらカンマートーンで演奏していますので現代のピッチより半音低くなっています。第4稿の特徴は前回にも触れましたがアーティキュレーションの違いと、それと最も大きな違いは第3曲にオーボエ・ダ・カッチャを加えていて、これがオーケストラにとてもやわらかい響きを与えていることです。次にソプラノによる第2稿についてですが、これが音高を3度あげたホ短調であることは前回にも触れました。音高が上げられたことにより、オーボエでは高音域が演奏不能になる(当時の楽器では)ため、オブリガート楽器がフラウト・トラヴェルソに変更されています。ソプラノ版の録音はバス版に比べるとずっと少なくなり、私も2種類しか持っていま
 せん。どちらも古楽団体によるものですが、一枚目は現代の歌姫ナタリー・デセイの歌とエマニュエル・アイム指揮による演奏です。「死
へのあこがれ」をうたった音楽としては、私にはちょっと華や
かすぎるように思えます。ただこれはブックレットにデセイや
アイムの容姿(写真で見る限り二人とも美人ではある)が強調
されていることからくる先入観がそう思わせているのかもしれ
ません。素晴らしい声ですが、やや甘ったるく聴こえます。指
揮者のアイムは最近ベルリン・フィルなども指揮していて注目
されています。もう一枚は鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)によるもので、彼らはバス版の他にこのソプラノ版も別に録音しています。ソプラノはイギリス出身のキ
せん。どちらも古楽団体によるものですが、一枚目は現代の歌姫ナタリー・デセイの歌とエマニュエル・アイム指揮による演奏です。「死
へのあこがれ」をうたった音楽としては、私にはちょっと華や
かすぎるように思えます。ただこれはブックレットにデセイや
アイムの容姿(写真で見る限り二人とも美人ではある)が強調
されていることからくる先入観がそう思わせているのかもしれ
ません。素晴らしい声ですが、やや甘ったるく聴こえます。指
揮者のアイムは最近ベルリン・フィルなども指揮していて注目
されています。もう一枚は鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)によるもので、彼らはバス版の他にこのソプラノ版も別に録音しています。ソプラノはイギリス出身のキ ャロリン・サンプソンで、彼女は主にバロックからモーツァルトあたりまでを得意にしていてこれ以外にもBCJとのカンタータ・シリーズに何
曲か登場しているほか、ヘレヴェッヘによる録音でも歌ってい
ます。透き通るような声で私にはこちらの方が合っているようで
す。ただサンプソンの声もやや艶のある声で、ソプラノであれば
曲の内容からするともっと無垢なボーイ・ソプラノのような声で
聴いてみたいとも思うのですが。それと終曲ではほんのごくわず
かながらピッチやオーケストラとのずれを感じます(気になるほどのことではありませんが)。そう思って他にCDがないか我が家の棚を探していたらもう一枚ありました。エマ・
ャロリン・サンプソンで、彼女は主にバロックからモーツァルトあたりまでを得意にしていてこれ以外にもBCJとのカンタータ・シリーズに何
曲か登場しているほか、ヘレヴェッヘによる録音でも歌ってい
ます。透き通るような声で私にはこちらの方が合っているようで
す。ただサンプソンの声もやや艶のある声で、ソプラノであれば
曲の内容からするともっと無垢なボーイ・ソプラノのような声で
聴いてみたいとも思うのですが。それと終曲ではほんのごくわず
かながらピッチやオーケストラとのずれを感じます(気になるほどのことではありませんが)。そう思って他にCDがないか我が家の棚を探していたらもう一枚ありました。エマ・
 カークビーによる歌で、こちらの方がいいと思いましたが、
残念ながらこれは全曲ではなく第2曲と第3曲のみを2曲ある結
婚カンタータの余白に収録したものです。しかもオーケストラで
はなく通奏低音による伴奏で前奏や間奏なども省かれていますの
で、これはつまりカンタータとしての録音ではなく、「アンナ・
マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集(A.M.B.1725)」中の作品としての録音になっています。解説書の曲目表示にはカンタータとして記載されていますが、これはあくまで「レチタティーヴォとアリア」として表示すべきで、カンタータについては( )内に補足して記載するのが正しいと思います(解説にはそうした説明はされていますが。ただこの解説、中世やルネサンスの音楽に詳しい今谷和徳氏が書いていますが、その中で「この2曲のみがソプラノ用に編曲されて」と書かれており、この記述が正確でないことはもう説明するまでもないでしょう)。そのことは別にして彼女の声は本当に清楚な美しい声で、彼女の歌うバロックの声楽曲はいつ聴いても心が洗われるようです。ただ彼女も何か所かで即興的にメロディーに変更を加えています。
カークビーによる歌で、こちらの方がいいと思いましたが、
残念ながらこれは全曲ではなく第2曲と第3曲のみを2曲ある結
婚カンタータの余白に収録したものです。しかもオーケストラで
はなく通奏低音による伴奏で前奏や間奏なども省かれていますの
で、これはつまりカンタータとしての録音ではなく、「アンナ・
マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集(A.M.B.1725)」中の作品としての録音になっています。解説書の曲目表示にはカンタータとして記載されていますが、これはあくまで「レチタティーヴォとアリア」として表示すべきで、カンタータについては( )内に補足して記載するのが正しいと思います(解説にはそうした説明はされていますが。ただこの解説、中世やルネサンスの音楽に詳しい今谷和徳氏が書いていますが、その中で「この2曲のみがソプラノ用に編曲されて」と書かれており、この記述が正確でないことはもう説明するまでもないでしょう)。そのことは別にして彼女の声は本当に清楚な美しい声で、彼女の歌うバロックの声楽曲はいつ聴いても心が洗われるようです。ただ彼女も何か所かで即興的にメロディーに変更を加えています。最後にもう一つ残されているアルトの版ですが、これも2種ご紹介しておきましょう。最初はルネ・ヤコブスによる歌です。古楽のアルトといえば
 カウンターテナーが担当する、というのが本来のありかたで
しょう。ルネ・ヤコブス(1946~)は現在主に古楽演奏の指揮者
として数々の名演奏を残していますが、元々はアルフレッド・
デラーの弟子で、かつてはこの分野で活躍していた歌手です。
1980年代に録音したものが多く、アーノンクールやレオンハ
ルトによるバッハ・カンタータ全集の中でも歌っています。あのレオンハルト指揮の「マタイ受難曲(独harmonia mundi BVCD-38121~3)」における「憐れみたまえ」やクイケン指揮の「ヨハネ受難曲(同 BVCD-38124~5)」の「こと果たされぬ」の名唱も忘れられないものでした。このCDもほぼそれらと同時期の録音で、彼の全盛期を代表するものと言えるかもしれません。ただ曲中の短いアリアを担当するのとは違ってこれだけ長いカンタータの全曲を歌うとなると、ちょっと難しい問題も出てくるようです。カウンターテナーとして素晴らしい声を聴かせてくれますが、全体としてやや冗長な感じがします。特に後に紹介するシュトゥッツマンの歌と比べてしまうと、その歌唱力の差は歴然としてしまいます。そのナタリー・シュトゥッツマンですが、彼女が古楽アンサンブルのハノーヴァー・バンドと
カウンターテナーが担当する、というのが本来のありかたで
しょう。ルネ・ヤコブス(1946~)は現在主に古楽演奏の指揮者
として数々の名演奏を残していますが、元々はアルフレッド・
デラーの弟子で、かつてはこの分野で活躍していた歌手です。
1980年代に録音したものが多く、アーノンクールやレオンハ
ルトによるバッハ・カンタータ全集の中でも歌っています。あのレオンハルト指揮の「マタイ受難曲(独harmonia mundi BVCD-38121~3)」における「憐れみたまえ」やクイケン指揮の「ヨハネ受難曲(同 BVCD-38124~5)」の「こと果たされぬ」の名唱も忘れられないものでした。このCDもほぼそれらと同時期の録音で、彼の全盛期を代表するものと言えるかもしれません。ただ曲中の短いアリアを担当するのとは違ってこれだけ長いカンタータの全曲を歌うとなると、ちょっと難しい問題も出てくるようです。カウンターテナーとして素晴らしい声を聴かせてくれますが、全体としてやや冗長な感じがします。特に後に紹介するシュトゥッツマンの歌と比べてしまうと、その歌唱力の差は歴然としてしまいます。そのナタリー・シュトゥッツマンですが、彼女が古楽アンサンブルのハノーヴァー・バンドと
 テノールによる歌については触れませんでしたが、私の所蔵CDにもテノール版はありません。ただ前記カークビーと同様、「A.M.B.1725」(全45曲)の中から24曲を収録したイギリスの古楽団体トラジコメディアのCD(DAS ALTE WERK)で、ジョン・ポッターという歌手によりやはり2曲だけこれを聴くことができ
ます。男性的というよりはやわらかい女性的なちょっと頼りない
声のテノールですが、この曲にはこうした歌い方の方がテノールの
場合あっているように思えます。この団体はルイジ・ロッシやカリ
ッシミ他の作品を集めた「反宗教改革の新しい歌」(WPCS-4906)
など素晴らしい録音を残している注目すべき団体です。
テノールによる歌については触れませんでしたが、私の所蔵CDにもテノール版はありません。ただ前記カークビーと同様、「A.M.B.1725」(全45曲)の中から24曲を収録したイギリスの古楽団体トラジコメディアのCD(DAS ALTE WERK)で、ジョン・ポッターという歌手によりやはり2曲だけこれを聴くことができ
ます。男性的というよりはやわらかい女性的なちょっと頼りない
声のテノールですが、この曲にはこうした歌い方の方がテノールの
場合あっているように思えます。この団体はルイジ・ロッシやカリ
ッシミ他の作品を集めた「反宗教改革の新しい歌」(WPCS-4906)
など素晴らしい録音を残している注目すべき団体です。以上がこの曲のCDに関する私の感想であり、末尾にパート別、録音年代順にその一覧を掲載しておきます。ところでこのテーマの連載を終えるにあたり、バッハは一体どんな死生観を持っていたのでしょうか。もちろんそんなことはどこにも書かれていないのでわかりません。こうしたカンタータを他にもたくさん残していることから自身も若いころから「死」に憧れを持っていたのでしょうか?敬虔なルター派の信者として「死=永遠の命の獲得」と思っていたかもしれません。そんな「死」に関する音楽の中に面白いものを見つけましたので、長くなりましたがそれを最後にご紹介しておきます。それは「A.M.B.1725」の中に収められた1曲です。この曲集はバッハが妻へのささやかな贈り物として書いたものの第2巻にあたるもので、今回のカンタータのソプラノ版に基づくアリアもここに収録されていることはすでに触れたとおりですが、それとは別に曲集中の第20曲にタバコのアリアとして知られる「パイプに煙草を」というとても短かい曲があります。新バッハ全集版には、その曲のクラヴィーアのための楽譜(ニ短調BWV515)と歌詞付きのアリア(ト短調BWV515a)が掲載されており、更にそれに続いて「煙草好きの教訓」と題する詩が掲載されています。この曲は詩と共にかつてはバッハが書いたものと思われていたようですが、現在では彼の作品でないことがはっきりしており、通説ではバッハとアンナ・マグダレーナとの間に生まれた最初の男子ヨハン・ゴットフリート・ハインリヒ・バッハ(1724~63)ではないかといわれています。彼は幼いころ才能に恵まれながらも精神障害を発症し、不遇の生涯を送りました。新全集版の解説(ゲオルク・フォン・ダーデルセン、訳角倉一郎 全音楽譜出版社)によると、この詩は当時ヨーロッパに広く流布していたもので、この詩をもとにまだ幼いヨハン・ゴット・フリートが習作として書いたものだそうです(1735年以降、上声の旋律のみ?)。タバコの歴史を論じるほどの能力もスペースもありませんが、これがコロンブスによる新大陸発見の副産物であることはご存知でしょう。当時は「癒しや疲れをとる効果がある」などの迷信により瞬く間に全世界に広まったのです。当時流行した「ペストに対する予防効果もある」などと言われ、年寄りから子供までタバコ(パイプ喫煙)を吸ったそうです。一方でキリスト教会はタバコに批判的で、ドイツでは1848年まで街頭や公の場所で喫煙は禁じられていたほどです。そうした背景を持ちながらこの曲が生まれているのですが、敬虔なクリスチャンのバッハもタバコの魅力には勝てなかったようです。この曲は幼いバッハの子供(おそらくはまだ10代半ば?)がそのタバコの詩に基づいてクラヴィーアのための曲を書き(No.20a BWV515)、それを母親が歌いやすい高さに移調して歌詞を添え、それに更にバッハが通奏低音を加えた(No.20b BWV515a)、とされています。ただ私が一つ疑問に思うのは、いくら当時子供がタバコを吸う時代であったとしても、このような詩に幼い子供が影響を受けて曲を作るでしょうか(もちろん現代の常識が通用する時代ではありませんが)?曲を作ったのは事実としても、その詩とは関係なく、後に両親(それもタバコ好きのバッハ自身)が歌詞をあてはめたと考える方が自然であり、そしてその歌詞を楽譜に書き込んだのがアンナ・マグダレーナだったのではないでしょうか?ですからこの詩はバッハが好んでいたもの、と考えることもできます。なお楽譜に書かれている歌詞は第1節のみで、「No.20c」の詩全節はバッハの死後に書き加えられたとされています。でも短い曲なので、バッハ家の団欒の場で歌われる際にはその中の何節かが歌われていたのではないでしょうか?では最後にその詩をご紹介しておきましょう。
「タバコ好きの信心
パイプにおいしいタバコを詰めて
楽しみと気晴らし得んと
それを手にとるそのたびに
わが心には死の姿が浮かび出て
こう教え訓してくれるのだ、
お前もパイプと同じなのだと。
パイプのもとは粘土と土くれ、
私も同じ土くれからできて
やがては土と化さねばならぬ。
思わず知らずパイプは落ちて
わが手のうちで二つに割れる、
わが運命もそれと同じさ。
パイプは色が塗られずに
いつも白くあるように、
いずれ私も死んだとき
肉体(からだ)の色は褪せ果てん。
使い古したパイプのように
墓でこの身も黒ずまん。
パイプにいったん火がつくと
みるみる煙が立ちのぼり
たちまち空に消え失せて
あとに残るは灰ばかり。
人の栄誉も燃え尽きて
肉体(からだ)は塵に帰るのみ。
タバコを喫うときよくあるように
タバコ押えが手元にないと
とかく指を使いがち。
指を焦がして思うのだ。
灰がこんなに熱いなら
地獄の業火はいかばかりかと。
いつもタバコを吸うときは
こうしたことを考えながら
信仰心を高めるのだ。
それゆえ旅でも家にあっても
信心深く一服やって
そのすえ心は満ち足りるのだ。」
(ベーレンライター原典版―10「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」
全音楽譜出版社 角倉一郎訳 歌詞大意より転載)
[CD一覧]
<バス独唱―第1稿>
① デートリヒ・フィッシャーディースカウ
カール・リステンパルト指揮 室内管弦楽団
(録音:1951年 ARCHV POCA-2603)
② デートリヒ・フィッシャーディースカウ
カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団
(録音:1968年 ARCHIV POCA-2031)
③ マティアス・ゲルネ
サー・ロジャー・ノリントン指揮 カメラータ・アカデミカ・ザルツブルク
(録音:1999年 DECCA POCL-1914)
④ トーマス・クヴァストホフ
ライナー・クスマウル指揮 ベルリン・バロック・ゾリステン
(録音:2004年 Deutsche Grammophon UCCG-1219)
<ソプラノ独唱―第2稿>
① キャロリン・サンプソン
鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン
(録音:2007年 BIS KKC-5253)
② ナタリー・デセイ
エマニュエル・アイム指揮 ル・コンセール・ダストレ
(録音:2008年 Virgin Classics TOCE-56151)
<アルト独唱―第3稿>
① ルネ・ヤコブス
キアラ・バンキーニ指揮 アンサンブル415
(録音:1987年 harmonia mundi FRANCE HMA-1951273)
② ナタリー・シュトゥッツマン
ロイ・グッドマン指揮 ザ・ハノーヴァー・バンド
(録音:1994年 RCA Red Seal BVCC-736)
<バス独唱―第4稿>
① フィリップ・フッテンロッハー
ニコラウス・アーノンクール指揮 ウィーン・コンチェントゥス・ムジクス
(録音:1978年 TELDEC SBZ-25)
② ピーター・ハーヴェイ
ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 イングリッシュ・バロック・ソロイスツ
(録音:2000年 ARCHIV UCCA-1005)
③ ペーター・コーイ
鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン
(録音:2006年 BIS SACD-1631)
<A.M.B.1725>
① エマ・カークビー(S)
クリストファー・ホグウッド指揮 エンシェント室内管弦楽団
(録音:1997年 DECCA POCL-1906)
② ジョン・ポッター(T)
トラジコメディア (録音:1991年 TELDEC WPCS-4095)
2014.08.30 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(26)
25. カンタータ第82番「我は満ち足れり」BWV82―Ⅶさて五つの楽章からなるこのカンタータもまたシンメトリックな構成になっています。中央と両端にアリアをおき、その間がレチタティーヴォという内容です。
第1曲のアリアはやさしく波打つ弦のゆらめくような動きに乗せてオーボエ(ソプラノ稿ではフラウト・トラヴェルソ)による嘆きの旋律が奏でられます。冒頭の音型は嘆きのフィグール(修辞音型)と呼ばれるもので、マタイ受難曲の有名なアルトのアリア”Erbarme dich, mein Gott(憐れみたまえ、わが神)”で聴かれるヴァイオリン・ソロと同様な音型になっています。そしてそのオーボエの旋律を受け継いで”Ich habe genug 私は満ち足りています”とソロが歌いだします。ところでこの曲は今日”Ich habe genug”と表記されることがほとんどですが、礒山氏によると”genug”は古くは”genung”と表記されていたとか。つまりgenungはgenugの古語ということになるのですが、これについては少し調べてみましたが私の見た何冊かの辞書には載っていませんでした。この表記を採用している著作物は、見た限りクリストフ・ヴォルフの「ヨハン・セバスティアン・バッハ 学識ある音楽家」(秋元里予訳 春秋社 2004)とマルティン・ゲックの「ヨハン・セバスティアン・バッハ」(小林義武他訳 東京書籍2001)、そして礒山氏の著作や彼が関係している書籍で前記「バッハ カンタータの森を歩む 第1巻」(東京書籍)の他小学館の「バッハ全集」、「バッハ事典」(東京書籍 1996)など比較的新しい著作で、他の著作はすべて「genug」の表記を使っています。手元にあるCDではバッハ・コレギウム・ジャパンの2種(バリトン版とソプラノ版)(注)それと第3稿(アルト)によるルネ・ヤコブス盤のみとなっています。些細な問題かもしれませんが、表記が違っているとちょっと考え込んでしまいます。歌詞の内容から考えるとここで歌っている主人公はシメオンであり、彼が幼子イエスに会い、胸に抱き、やっと死を迎えることができる喜びを表しています。
第2曲(レチタティーヴォ)の歌いだしもまた“Ich habe genug 私は満ち足りています”で始まりますが、ここでの歌い手はシメオンではなく「私」になります。つまりキリスト教を信仰するすべての人にあてはまるのですが、バッハ自身と考えることも可能でしょう。「私」がイエスのものとなり、イエスが「私」のものとなり、シメオンと共にあの世の喜びをかいま見よう、たとえそれが今生の別れとなったとしても、自分は満ち足りている、と歌います。
第3曲はこのカンタータの核心であり、バッハの作品の中でももっとも美しいアリアの一つと言えるでしょう。これほど優しく心に訴えかけてくる音楽は他にありません(少なくとも私にとっては)。病を抱えて苦しんでいるとき、この音楽にどれほど癒されたか。それはおそらく経験したことのない人にはわからないかもしれません。少し長くなり、またきわめて個人的なことではありますが、病で悩んだり苦しんでいる人があったらと思い、私が体験したことについて書いておこうと思います。
私は小さいころから股関節に持病を持っていて、それが年齢を重ねるごとに悪化していき、60歳を越えたころひどい痛みを伴うようになってきました。それで退職を機に思い切って人工関節に代えることを決断しました。こうした手術に定評のある新宿の大病院に通い、やがて手術の日取りも決まりました。ところがその間に別の機関で検査した人間ドックで担当医がおかしなことを言いだしたのです。「ほんのわずかだが、膵管に拡張がみられる」と。医者はそこでかなり考え込みました。とても細い筋のような線で私が見てもわからないほどです。「このまま来年の検査まで様子を見るか、大きな病院で精密検査をするか」と。彼はその場では結論を保留し、後日検査結果を送る、といって別れました。そのときの様子から私はまだ楽観的に考えていたのですが、検査結果は「要精密検査」となり、病院宛に紹介状が同封されていました。周囲からは癌ではないかといわれ、このときはじめてその深刻さに気付いたのです。焦りました。早く病院で診てもらわないと、と思ったものの、運悪く病院はもう年末年始の休みにかかっていました。そんなわけでこのときは非常に不安な正月を過ごすことになったのです。ようやく正月もあけ、私は股関節でかかっている病院を訪ねたのです。すぐにMRIを撮り、詳しい画像による診断を受けたのですが、そのときの若い医師の言葉は私を更に不安にさせました。「癌かどうかはグレーゾーンでわからない」と。そしてその説明はかなり悲観的なものだったのです。私は友人を膵臓癌で何人か亡くしており、そこから生還したという事例を全く知りません。つまり私の中では「膵臓癌=死」という図式ができあがっていたのです。奈落の底に突き落とされたような気分となり、やがて医師はその上司となるベテラン医師に代わり、様々な検査を受けることになったのです。その間周囲には平静を装ってはいたものの、私の心の内は「死」への恐怖でいっぱいでした。よくTVドラマなどで「余命何か月」などという話を聞きますが、それが実感となって自分に降りかかってきたのです。もちろんまだ「癌」と決まったわけではないにしても。そんなときこの音楽に巡り合ったのです。もちろんこの曲を聴いたのはこれが初めてというわけではありませんが、それ以前にはあまり自分の心の中に入って来ませんでした。またこの時には他にも多くの音楽に慰められました。特に「心と口と行いと生活で」BWV147の有名なコラール「主よ、人の望みの喜びよ」などもその優しさに心を打たれました。そんなこともあって、私の股関節の手術は延期され、まずは検査の結果を見ることになりました。検査には一か月以上かかり、結果は「膵嚢胞」とよばれるものでした。ただ粘液性の質の悪いもので放っておくと癌に転化するものだ、ということがわかりました。また場所が悪く(膵頭部)、それを除去するのは大手術になりこの病院でもそれはできないのでもう少し様子を見よう、ということになったのです。ここでさしあたっての危機は去り、私の不安は軽減されたのです。この結果ようやく股関節の手術にたどりついたのですが、ここでも大きな選択をしなければなりませんでした。人工関節の素材をどうするかという問題です。現在一般的に行われている素材はセラミックによるもので、この手術は比較的簡単で傷口も小さくてすみます。ただこれだと割れたり、脱臼したりする危険性があるので、今後の生活に大きな制約が生じてきます。何よりも好きな山歩きができなくなります。その不安を解消するにはメタルと呼ばれる素材でゴツイ、頑丈なものにしなければなりません。これなら山歩きもできるし、走ったりすることも可能になります。ただこれは日本ではまだ新しい素材でデータも少なく、癌を発症する可能性があると主張する医師もいるそうです。手術痕も大きくなります。またしても「癌」という言葉が出てきました。摩擦で生じる金属イオンが血中に溶け込み、癌を誘発するのだとか。そんなこともあってここでも大いに悩まされたのですが、今後癌については十分な検査もしていくだろうし、何よりもアメリカでは今このメタルによる人工関節が普及しているという話を聞き、私はこちらの素材を選択することにしたのです。こうして手術を終え、リハビリを経て少し不自由はあるものの以前のように歩くこともできるようになりました。ところが新しい仕事もみつかり、ようやく働き始めた矢先、夜中に激しい腹痛に見舞われ、緊急入院する羽目になったのです。急性膵炎という診断でしたが膵臓癌というのはおそらくこうした痛みがずっと続くのでしょう。膵管が詰まり、行き場のなくなった膵液(もっとも強い消化液)が自らの膵臓を溶かし始めたのです。“嚢胞が癌化したのか?”という疑念が生じましたが、ここまで短期間に多くの経験をしてきたせいかこのときはもう恐怖はあまりありませんでした。幸いこれも10日ほどの入院で済みましたが、このことがあって医者からは手遅れにならないうちに早く手術をするよう勧められました。そこで私はインターネットでこの病気に関して徹底的に調べあげ、ある一人の医師の説明を読んでその人に手術をお願いすることにしたのです。手術は無事成功し、術後医師からは「あと半年遅かったら危なかった」と言われ、腫瘍の一部が癌化していたそうです。健康な人には本来あるべき一部の臓器は切り取られてしまいましたが、幸い他部位への転移もなく今こうして生きていられるわけです。ほんのわずかな変化を発見してくれた人間ドックの医師や、その後検査や手術をしてくれた医師にもただただ感謝するばかりです。あれから間もなく4年が過ぎようとしています。この先どうなるかは「神のみぞ知る」といったところでしょうか。同じように病気で悩んでいる方があれば、何かのお役にたてればと思い、自ら経験したことを書いてみました。
さて曲に戻りましょう。この第3曲のアリアは「子守唄」とよくいわれます(シュヴァイツァーは「死の子守唄」と言っています)が、どうしたらこんな曲が書けるのかというほど優しさに満ちています。「眠りなさい、疲れた目よ 穏やかな安らぎの中で 目を閉じなさい」という言葉で始まり、途中いくつか変化はありますが、この言葉が何度も繰り返されます。ただここでは「眠りなさい」という言葉はまだ永遠の眠りを意味しているわけではありません。”Schulummert”という言葉が使われていますので、「まどろみ」とか「うたたね」を意味しています。曲が変ホ長調からト短調に転調すると、音楽は少し動きが激しくなり「この世は苦しみばかりで、自分の居場所はもうここにはない」と歌いますが、やがて再びまた「眠りなさい」という優しい音楽に戻ります。そして再び今度はハ短調に転ずると、「来世では平安と安らぎを見ることができるだろう」と歌い、またダ・カーポで最初の音楽に戻るというように、これが繰り返されていきます。オーケストラは弦楽と通奏低音だけですが、第2稿(ソプラノ版)ではトラヴェルソが、また第3稿(アルト稿)と最終稿(第4稿)ではオーボエ・ダ・カッチャが付加されます。このアリアは長く、カンタータは全体で約20分とちょっとなのですが、この曲だけで10分近い長さを持っています。この楽章のためにこの曲はある、といっても過言ではないでしょう。
第4曲(レチタティーヴォ)では第3曲で夢見た穏やかな来世がいつ来るのかと問い、そしてそれはやって来た、この世よおやすみなさい、と別れを告げます。
第5曲のアリアですが、私はこのカンタータで唯一この部分だけ少し違和感があります。再びオーボエ(ソプラノ稿はトラヴェルソ)が活躍し、3/8拍子の舞曲風の早いテンポで奏され、それにのってバスが快活に歌い始めます。「死が待ち遠しい、早くその時が来ないか。そのとき私はあらゆる苦難から解放される」と。これが第4曲のレチタティーヴォの前ならわかるのですが、すでにこの世に別れを告げたあとに、いつその時が来るのかというのは順序が逆のように思います。このカンタータの台本作者が誰なのかはわかっていませんが、明らかにおかしな流れになります。もちろんバッハのカンタータにすべて物語性があるわけではないので、目くじらを立てることではないのでしょうが、あまりに大きな矛盾にちょっと戸惑います。それと言葉の矛盾はおくとして、この喜びに満ちた音楽は一体どうとらえていいものか(シュヴァイツァーは「突如として爆発する恍惚たる歓喜」と表現)。シメオン老人がやっと死を迎えることができる喜びはわかりますが、ここまで喜ぶというのは?この言葉の問題についてはキリスト教に対する私の理解力のなさからくるものかもしれません。これについて礒山氏は「カンタータの森・・」(第1巻)の中で、第4曲までは「別れ」という言葉で表現されていて、これは「肉体の鎖からの解放」や「平安の内に逝くこと」で、第5曲になって初めて「死Tod」という言葉を使い、「死の死」を描いたのではないかと。とても難しい表現なので、あとに続く言葉をそのまま引用しますと「シメオンとともに満ち足りて眠りについた今、魂は肉体を抜け出して死と戦い、死を揶揄し、とげを抜いて死を倒し、勝利して歓呼する。それはすなわち、新たに獲得された、霊的な生命の謳歌にほかならない。」と。そしてパウロやルターの言葉を引用しながら「シメオンの喜びは、死を克服し生を獲得したという確信にこそよっているというのが、ルターの考えである。第82番の最後のアリアは、まぎれもなくルターのこの精神を鼓吹しているように、私には思われる。」と解説しています。でもここまでくるともう私の頭では理解を越えていてとても難しい問題です。
注) 鈴木雅明氏は「我が魂の安息 おおバッハよ」(音楽之友社 2004)の中でBWV60「おお 永遠、そは雷の言葉」の終曲コラール”Es ist genug, so nimm, Herr, meinen Geist”に触れて次のように書いています。
「“genung”という単語は、現在用いられない”genug”の古い形であり、これは有名なバスのソロ・カンタータBWV82など、バッハのカンタータにはしばしば用いられている。通常ドイツ語の発音の原則からは、この単語の末尾ngは、少し鼻に抜けるように[genuŋ]と発音されることになるが、これについては常に議論がある。(このBWV60においては、バッハ当時の賛美歌集はすべて”genug”と記しており、バッハがそれを”genung”と書き写している)。
2014.06.08 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(25)
24. カンタータ第82番 「我は満ち足れり」 BWV82―Ⅵバッハが5年分の教会カンタータを残そうとしていたことは既に触れたとおりです。したがってこの「マリアの清めの日」のためのカンタータもこの1曲だけではありません。1723年の5月にトーマス教会のカントルに就任してその第一年巻にあたる教会カンタータの創作に着手しますが、翌1724年にはライプツィヒにおける初めての「マリアの清めの祝日」を迎えます。このときバッハはBWVでは次の番号となるBWV83「新しき契約の嬉しき時」を作曲、初演しています。冒頭から2本の狩猟ホルンが豪壮に鳴り響く音楽はいかにも祝日にふさわしい喜びに満ちており、それにオブリガートの独奏ヴァイオリンも絡んでアルトのソロが「新しい契約の・・・」と歌います。この曲にシメオンの名前は登場しませんが、第2曲でシメオンがイエスと出会い、やっと死の時を迎えることのできる喜びの独白(ルカ、第2章29~31節)が歌われます。このカンタータでは第3曲のテノールのアリアが印象的で、ここでも独創ヴァイオリンが終始活躍します。終曲ではルター作詞のシメオンの讃歌によるコラール「平安と歓喜もてわれはいく」の最終節「主は救いにして、聖なる光」が歌われています。そして第二年巻の1725年2月2日には前記ルターのコラールに基づくコラール・カンタータBWV125が初演されています。このカンタータでちょっと面白いのは、冒頭の合唱でパッヘルベルのモテットのスタイルに似た手法をとっていて、ソプラノに息の長いコラールの旋律を歌わせ、あとの3声による合唱がポリフォニックに絡み合っていきます。更にソプラノのコラールだけに旋律を補強させるためホルンを一本重複させています。聴いているとあまり目立たないのでそれだけにホルンを使用するというのは、ちょっと贅沢な編成のようにも思います。ここで活躍する楽器は各1本ずつのフラウト・トラヴェルソとオーボエ・ダ・モーレになっています。ただバッハは1730年代の後半にこれを再演する際第1曲目のみをオーボエ・ダ・モーレからオーボエに変更している他装飾音などにもかなり手を加えています。またここにはシメオンは登場せず、ルターのシメオンの讃歌によるコラールが冒頭の合唱と終曲のコラールで歌われるだけです。BWV82を含めこの3曲が「マリアの清めの祝日」のために書かれたカンタータとなります。最後のBWV125はその中ではもっとも地味な作品と言えるかもしれません。
ここで再三登場するシメオン老人について少し触れて起きますと、彼の名前は聖書の中でわずかにしか記述されていませんが(「ルカによる福音書」に数行登場するだけで、マタイ他の3福音書には全く記載がない)、この老人の登場はキリスト教においてかなり重要な意味を持っていると思います。それがキリスト教の「死」という概念の本質をあらわしているように思えるからです。つまりキリスト教において「死への憧れ」は「安らかな死」であると同時に「永遠の生命」を得ることへの憧れを意味しているのではないでしょうか。これは何もバッハに始まったことではありませんが、16世紀末に繰り広げられた宗派の争い(カトリックの反宗教改革による巻き返しや、ルター派とカルヴァン派との抗争など)に始まり、30年戦争(1618~48)やペストの流行などもあってドイツ国内の人口は激減し(約半分になったといわれています)、人々が「安らかな死」に対して強く憧れるようになったことが背景にあると考えられます。教会歌のコラールがそうした背景から生まれたことは以前にも触れたとおりです。
さてバッハが1727年に作曲したこのBWV82は、バス独唱のためのソロ・カンタータですが、バッハは当初これをアルト独唱のための作品として書き始め、途中でバス用に書き改めた、といわれています。それは自筆譜のスコアにそれらしい書き込みと訂正が見られるからですが、私はこの曲を聴くとやはりバスで歌われるのがもっともふさわしいように思います。ただバッハはこの曲を1727年以降の「マリアの清めの日」にも何度か再演し、それに伴っていくつか変更を加えています。最初の再演は1730年頃とされそのときには変更がなく、翌年の再演の際にソプラノ用に編曲しています。このソプラノ版(第2稿 BWV82a)では管楽器のオブリガートがオーボエからフラウト・トラヴェルソに変更され、調性もハ短調からホ短調に移調されています。ただしバッハ・コレギウム・ジャパンのCDの解説書によると、このオブリガート楽器の変更は更にその後の1735年頃の再演の際に行われたもの、と書かれています。ということは最初に改変されたソプラノ版は当初オーボエのままだったことになるのですが、それだとオーボエの音域としては非常に難しくなります。第一曲のアリアでは2オクターヴ上のC(3点ハ音)が何度か出てきますが、これを3度上げるということは当時の楽器で演奏可能だったのでしょうか?やはり最初の再演のときに既にフルートに変更されていたと考える方が自然です。
そして更に1735年以降に再演された際、バッハは当初考えたアルト独唱用に編曲し、調性も元のハ短調に、そしてオブリガート楽器もオーボエに戻すという作業を行っています。これが第3稿と呼ばれるものです。こうしてこのカンタータはテノールを除く三つの声部で歌うことが可能になったのですが、ソプラノの声部をオクターヴ下げてテノールで歌うことも可能なため、すべての声部で歌うことができる、というちょっと珍しい作品になったのです。そしていわゆる新バッハ全集版というのは1747年に再演されたオリジナル・パート譜を基に作成された第4稿と呼ばれるものとなります。
このカンタータをめぐる成立事情は礒山雅氏の「バッハ カンタータの森を歩む」第1巻(東京書籍 全3巻 2004)に詳しく掲載されており、私の記述もそれを基にしていますがなかなか複雑です。その原因は初演の際の自筆スコア(パート譜はない)といくつか存在する再演の際のパート譜が違っていたりするためと考えられます。礒山氏の記述も小学館のバッハ全集の解説ではソプラノ版を第3稿とし、新バッハ全集版を第2稿とするなど、前記の著作との食い違いを見せていますが、それだけ音楽学の研究も日進月歩で変わってきているということでしょう。
また前述のとおりこのカンタータの第2曲のレチタティーヴォと第3曲のアリアは「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」に組み込まれていますが、これは妻アンナ・マグダレーナ(1701~60)お気に入りの歌曲として彼女が書き取ったもので、1731年のソプラノ稿(第2稿)を基にしています。アンナ・マグダレーナは音楽一家に生まれプロの歌手として活動していたことが知られており、バッハ自身1730年に友人のエルトマンに当てた手紙で「二度目の結婚で生まれた子供たちは、まだみな幼く、頭の息子が六歳であります。しかしいずれもみな生まれついての音楽家でございまして、もうすでにわが家族にて声楽や器楽の音楽会が組めるのではないかと自負しております。ことに現在の妻[アンナ・マグダレーナ]は、きれいなソプラノを歌いますし、長女もまた捨てたものではありません。」(白水社「バッハ叢書」第10巻:資料集 酒田健一 訳)と書いているように、バッハ自身彼女の才能を高く評価していたことがわかります。ですからこのソプラノ編曲そのものも彼女の存在があったからではと私には思えるのですが、それはともかくとしてここに選ばれた2曲は、彼女が何か特別な機会に歌うために書き取った(1730~33頃)と言われています。こうした歌曲やクラヴィーア作品がバッハの家庭内で子供たちとともに団欒の場でよく演奏されていたのではないかと思うと、あのいかめしい肖像画からは想像もできないほど優しい家庭人としてのバッハ像が浮かび上がり、とても微笑ましく思われます。
尚礒山氏によれば「マリアの清めの日」に演奏されたカンタータとしては今回触れた作品以外にもBWV157「汝われを祝せずば」があり、それ以外にも今は消失してしまったカンタータで、一部転用したり、転用されたりした作品としてBWV158「平安 汝にあれ」(終曲のコラールは有名なBWV4「キリストは死の縄目につながれたり」の第5節)やBWV161「来たれ、汝甘き死の時よ」が関係していること、そして断片として残されているBWV200のアリア「われはその御名を言い表さん」などがあることを付記しておきます。
2014.04.18 (土) 佐村河内問題について
前回からの続きを書く前に、かつて私自身レコード会社に在籍しクラシック音楽の制作に携わってきた人間として、佐村河内問題に一言触れておきたいと思います。この問題については当カプリネットのサイト内にある「クラシック未知との遭遇」に詳述されていますので、その経緯や問題点などはそちらをお読みください。とても面白い内容です。さて結論から言うと、少なくとも「私個人にとって」はこの問題はさほど大きな問題ではありません。私もNHKスペシャル「魂の旋律」は興味をもって見させていただきました。クラシックに携わったものとして放置できる番組ではなかったからです。当然のことながら音楽にも大きな関心をもっていました。ただゲーム音楽しか(?)作ってこなかった人間に交響曲など書けるのか、という思いもありました。結果的に番組から流れてきた音楽には大いに失望させられました。たとえ彼が被爆2世という不幸な境遇に生まれ、重度の障害に苦しみながら作曲したということがあったとしても、番組から流れてきた音楽は、ある部分ワーグナー風であったり、マーラー風であったり、またラフマニノフ風であったりと、さまざまな大作曲家の作風をいたずらに模倣しただけの、まがい物の音楽にしか私には聴こえませんでした。この時点で私の頭の中から佐村河内という名前は消えました。よくこの音楽に感動して涙を流す人が多かったということを耳にしますが、それはそうした過去の作曲家からそれらしい部分を模倣して聴かせれば、人々は彼の境遇や震災による惨状を重ね合わせ、涙することは当然考えられます。映画のバックで流れる音楽を聴きながら涙するのと同じ構図です。もしクラシック音楽に詳しく、普段から様々な音楽をよく聴いている人が「この音楽は素晴らしい!」と純粋に思ったとすれば、それはそうした周囲の事情を斟酌するあまり、正常な判断ができなくなっていたからだと思います。そうではなくて、本当にこの音楽が素晴らしい、ともし思ったのならその人の音楽的感性を私は疑いたくなります。でも人は誰しもそれぞれ固有の感性を持っていますので、そうした人がいたとしても不思議ではありません。ただもしそうならこの場合、その人はこの曲が誰に作られたかは問題ではなく、いいと思ったその気持ちをずっと持ち続けるべきだと思います。音楽そのものに罪はないのですから、騙された、裏切られたと言って、態度を変えたり、怒ったりするのは筋違いです。だいたいNHKのこうした特番でよかったと思うことが私には一度もなかったように思います。いつもがっかりさせられます。もちろんそんな私の感情とは逆にその音楽CDは飛ぶように売れるので、日頃ポップスのように売れないクラシックにとっては大きな社会現象になったりします。フジコ・ヘミングも辻井伸行もそうでした。確かに話題性はあるのでしょうけれど、音楽の中身がそれに追いついていけない。番組の制作者は、たとえつまらない番組になったとしてももっと彼らの音楽と真剣に向き合うべきでしょう。だから今回、このような音楽を誰が作ったかなど、少なくとも私にはどうでもいいことだったのです。だいたい障害者とか被爆を売り物にするような行為、もうそろそろ止めたほうがいいでしょう。私もかつてそうしたことがあるので偉そうななことは言えませんが、軽度とはいえ自分が障害者になって初めて思ったのは、障害が言い訳にならないこと。障害者はそのことを言い訳にするようなことを、むしろ恥ずかしいと思うでしょう。だから決してそれを売り物などにして欲しくないと思います。ヘルムート・ヴァルヒャのオルガンは彼が盲目であることなど関係なく素晴らしいものでした。また日本でも和波孝禧という優れた盲目のヴァイオリニストがいて、彼らは決して障害を売り物などにはしていません(自伝や、母親の手記「母と子のシンフォニー」などの本はありますが)。和波さんがかつて英RCAに録音したバッハの協奏曲など素晴らしい演奏だったと記憶しています。今回前代未聞ともいえるこんな事件が起こり、障害者や震災で惨事に遭われた方々が一番迷惑しているのではないでしょうか?こんな騒ぎを起こした張本人たち、一応謝罪の姿勢を見せてはいますが、結局儲けるだけ儲けて裏で高笑いをしているような気もします。損をしたのはひどく傷つけられた人達や、騙されて本やCDを買った人たちだけ、ということかもしれません。真の作曲者新垣氏は周囲の慰留にもかかわらず桐朋音大を去ったということで、彼もそれなりの罰を自分に課したということなのでしょう。
ところで今回の事件でいくつか思うところをもう少し書いてみたいと思います。まずゴーストライターの件ですが、このことは確かに以前からさまざまな噂がありました。著名な作曲家の「XXさんはゴーストラーターを使っている」というような噂は私がクラシックに在籍していた当時にもありました。ただこんな大それた話ではなく、主に映画やTVの劇伴などを頼まれたときの音楽だったと記憶しています。今回そんな作曲家の一人がもっともらしいコメントをしているのをTVで見て、思わず笑ってしまいました。でもそれはあくまでも噂の話しで確たる証拠があったわけではありません。そうした裏の伝統のようなものが今回の事件につながったのではないか?とも思っています。そういえば新垣氏もこの曲が「交響曲などではなく、ゲーム音楽の延長上の作品と思って書いた」と手記にありましたね。
また今回この作品におけるクラシック関係者のちょうちん持ちとして、許光俊、野本由紀夫、三枝成彰の三人がまるで「三匹の悪玉」のようにバッシングを受けています。批判することは簡単で、褒めるという行為はなかなか難しいことなので、その意味では本来称賛したいところですが、今回ばかりはそうはいきません。ごくありふれた音楽を音楽史上最高の音楽だと持ち上げ、世間をたぶらかせた罪は大きいといわざるを得ません。彼らの称賛の言葉が好意からでたものなのか、下心があってのものなのか、あるいはビジネスつまり報酬の引き換えとして行われたものなのか私にはわかりませんが、そのしっぺ返しは相当なものです。許光俊という男、かなりの数にのぼる本を出版し、一部のクラシック・ファンからはカリスマのように思われている評論家だそうです。私も何冊か読んだことがあり、いくつか共感するところもあるのですが、内容は独善的で、不遜であり高慢な態度に満ちています。言葉も汚く、およそ大学の教授とは思えない文章です。改めて今回彼の本に目を通してみると、こうした失敗を犯す下地が十分に見て取れます。つまり彼はそこに何らかの音楽以外の物差しがないと音楽の良し悪しを判断できないのです。汚い本の代表的なものとして彼が2005年に出した「オレのクラシック」(青弓社)とい本がありますが、この中で「指揮姿が醜い。オレの知っている限り、指揮姿が醜いにもかかわらず音楽がすばらしいという指揮者は、誰もいない」などといってルネ・ヤコブスやヘレヴェッヘを切り捨てています。つまり外見からしか音楽を理解できない人間なのです。ヤコブスの「フィガロ」はひどいといっていますが、私はいい演奏だと思っています。彼の「ロ短調ミサ」なども素晴らしい演奏です。このような記述はあちこちに散見されます。そんな自らも認める古楽嫌いの彼がアーノンクールの著書「古楽とは何か」を翻訳・出版しているのはどういう神経なのでしょう。私はクラシック部門に在籍中、何人かの若手の評論家を育てたこともあります。中には今も立派に活躍している人もいて、あるときシリーズ企画で大量のCDを一度に発売しなければならず、解説文を書いてくれるライターが不足してしまい、そのとき彼からこの許君を紹介してもらい、クラシックの世界に引っ張り込んでしまったことを覚えています。でもそのときはおとなしそうないい青年だったのですが、いつからこんなにエラくなってしまったのでしょう。彼は本の中でこんなことも書いています。「『現場』の幸福感に当てられてしまって、ある時点から現場の人たちの代弁者のようになり果ててしまう評論家やジャーナリストがいる。私にしてみれば、そのような人間は最初から物書きに生まれついていない。鑑賞者として誠実を尽くす、鑑賞者の幸福を極め尽くす、それを心がけるべきであり、安易に実作者と馴れ合ってはならないのだ」(「クラシックがしみる」青弓社2012年)と。この文章からは音楽家に対するかなりのコンプレックスを感じ取ることができますが、自らの言葉を戒めとしてもっと謙虚になってもらいたいものです。野本由紀夫氏については私はあまり知りません。最後の三枝氏ですが、彼が作曲家であることは私も知っています。でも私は不勉強といわれるかも知れなませんが、彼の作品を聴いたことがありません。むしろタレントとしての方が有名なのでは。現代曲の録音も少なからず経験し、武満さんや吉松さんなどは私が敬愛する作曲家です。そんな私でも聴いたことがないのですから、おそらく一般の人はほとんど聴いたことがないのでは。それでも「有名な作曲家(?)」の人が推薦すれば、知らない人はいい作品だと思ってしまうでしょう。今回の事件はこうした三人や、NHK取材班の古賀淳也氏(彼の出版した本「魂の旋律」など、事実を知った後では滑稽にしか思えず、被災者や少女に対してどう言い訳するのでしょう)他、今回の一件で大儲けをした日本コロムビア、講談社、コンサートの企画運営会社など、彼らも被害者なのかもしれませんが、それ以上に加害者として与えた罪の方がはるかに大きいでしょう。今後彼らがどのようにこの事件と向き合っていくのか見守っていきたいと思います。
陶山 義則
2014.02.13 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(24)
23. カンタータ第82番「我は満ち足れり」BWV82―Ⅴ前置きが大変長くなってしまいました。ようやく本題に入りますが、最初にも述べたようにこれはあくまで教会カンタータであり、その意味ではドイツ歌曲ということはできません。でもこのあとにも触れるようにバッハ自身このカンタータがかなり気に入っていたのでしょう。このカンタータの第2曲と第3曲を妻アンナ・マグダレーナ・バッハのクラヴィーア小曲集にチェンバロ伴奏による歌曲として組み込み、おそらくは彼の家庭でもよく歌われていたものと思います。そうしたこともあって私はドイツ歌曲について少し長々と寄り道をしてしまいました。
まずはじめにこのカンタータ作曲の背景についてみてみることにします。バッハはトーマスカントルに就任後、毎週日曜日と祝日に教会カンタータを演奏することが義務付けられていたため、その教会暦に従うと1年間に60曲近いカンタータを用意しなければなりませんでした。もちろんそれ以前に作曲したカンタータを改作して使いまわしたりもしています。バッハの死後息子のカール・フィリップ・エマヌエルと弟子のヨハン・フリードリヒ・アグリーコラによって1754年に発表された「故人略伝」には5年分のカンタータが書かれたことになっており、それが正しければ300曲近い作品が残されている筈ですが、ご承知のように現存する教会カンタータはおよそ200曲ほどです。これとて膨大な数には違いありませんが、父から最も才能を期待されながら不安定な性格から極貧の生活を送った息子のヴィルヘルム・フリーデマンが、相続したカンタータの楽譜を売却するなどしたため失われたものも相当数あるのでは、ともいわれています。
バッハが1723年5月トーマスカントルに就任してから、その翌年の6月4日までをカンタータの第一年巻(教会暦1年分)としていますが、クリストフ・ヴォルフによればその間に演奏されたカンタータは全部で64曲で、そのうち旧作をそのままもしくは改作するなどして演奏したのが24曲(世俗カンタータからの転用も含む)になっています(同じ日に2曲演奏していることも何度かあります)。ですから新しい作品としては40曲になります。そして次の第二年巻(1724年6月11日~25年5月27日)では52曲で旧作の再演はわずか1曲しかありません。この第二年巻のカンタータは「コラール・カンタータ」という画期的な試みで書かれていることは以前にもご紹介しました。尚両年ともこれらの演奏に加えてマニフィカトや受難曲、オラトリオなどの演奏が加わります。第三年巻(1725年7月29日~27年4月11日)になると再演を除き37曲と、今までのペースに比べるとずっと少なくなり、カンタータ創作のピークは過ぎ、作曲のペースは衰えていきます。しかもシリーズの完結にはここで約2年と倍の期間がかかっています。その理由はよくわかっていませんが、他人の作品を演奏したり、失われてしまったものもあったりするようです。ただこの第三年巻のカンタータには今までにないいくつかの新しい特徴が指摘されています。一つはソロや対話形式によるカンタータで、もう一つはシンフォニアに自身の管弦楽作品からの編曲やBWV35「霊と心は驚き惑う」に代表されるようなオルガン・パートの充実です。1726年11月24日に初演されたBWV52「偽りの世よ、われは汝に頼まじ」のシンフォニアではブランデンブルク協奏曲第1番の第一楽章が、またBWV110「笑いは、われらの口に満ち」(1725年のクリスマスに初演)の冒頭は管弦楽組曲第4番の第一楽章が使われています。そして独奏オルガンについてヴォルフはその背景として、バッハがそれまで指揮者に専念していたことをやめ、オルガン奏者としてその技術の高さを証明したかったのでは、と推測しています。今回とりあげているBWV82は1727年2月2日というこの第三年巻のほぼ終盤に初演されたカンタータです。ちなみにこの第三年巻の最後を飾る聖金曜日(4月11日)には「マタイ受難曲」が初演された、というのが現在一般的な説(確証はないものの)ですので、それが正しければおそらくこのカンタータの作曲と同時並行的に「マタイ」の作曲が行われていたと考えられるのではないでしょうか?
さてキリスト教では2月2日を「マリアの清めの祝日」と定めています。マリアは言うまでもなくキリストの母で一般的には「聖母マリア」として知られています。面白いことに聖書にはこのマリアの記述はあまり登場しません。私も細かく全部読んだわけではないので詳しいことは言えませんが、キリストの生誕に関わる記述(マタイ、ルカ)や招待されたカナでの婚礼の場面(ヨハネ)、処刑された際にその足元にいた(ヨハネ)、などで全体からすればほんのわずかに過ぎません。そして「マルコ」にいたっては手の萎えた人を癒す場面でわずかに登場するだけで、マリアという名前さえ登場しません。「ヨハネ」にも名前は登場しませんが、このマルコとヨハネの両福音書にはキリスト生誕にまつわる物語そのものがありません。しかるに「聖母マリア」と崇拝されているのは何故でしょうか?もちろん母親という存在はとても大きいのですが、やはり処女懐胎という特殊な事情(わたしのような俗人にはとても信じがたいことですが)によるのでしょうか。当時のユダヤでは婚約=結婚とみなされ、一年間は婚約期間を置かなければならず、その間他人とはもちろんのこと婚約者との性的交渉すら持つことは禁じられる、という厳しい戒律(旧約聖書)があり、それを破ったもの、特に他人との性的関係は石打ちによる死罪とされていたので、ユダヤ教徒として信仰心の厚い二人はそれを忠実に守ったに違いありません。ですから処女懐胎という現在の科学でも証明できそうにないそうした事象もありえたのかな、とは思ったりもしますが。それに比べ父親(ヨセフ)の存在の何と薄いことか。尚ヨセフは当然のことながらユダヤの律法に基づいて離婚を考えましたが、そこに夢で天使ガブリエルのお告げがあったりして話しはややこしくなり、結局イエスを授かることになるのです。このマリア崇拝は東方に起源をもち431年のエフェソスの公会議や、681年のコンスタンティノープルの公会議で「神の母」と宣言されるなどして西方のカトリック教会でも一般的になったとされています。プロテスタントでは信仰の対象はあくまでもキリストであり、行き過ぎた「マリア崇拝」に警鐘をならしているとか。
では「マリアの清めの日」とは何でしょうか?名前からすると、何かものすごく美しくきれいなことを想像してしまいますが、そういうことではありません。またマリアを崇拝することでもありません。出産にかかわる事柄なので確かに崇高な行為には違いないのですが、むしろ不浄な内容にかかわってきます。再び旧約聖書に戻りますが、旧約とは神との契約ですので、ここにはさまざまな律法が書かれています。特にレビ記や申命記には厳しい掟が定められています。レビ記の第12章に以下のような出産についての記述があります。
「主はモーセに仰せになった。さてこれをキリストの誕生に当てはめてみましょう。言うまでもなくその誕生はクリスマス、つまり12月25日です。したがってその八日目の1月1日には割礼の手術が施されているはずです。この割礼も旧約聖書の創世記17章に神との契約の証としてそうしなければならないと書かれており、この割礼によってここにイエスという名前がつけられたのです。この割礼、現在でもユダヤ教やイスラム教の世界では行われているようで、またアジアでも韓国などにはその風習があるようです。余談ですが私が小学校にあがるかあがらないかの頃、近所に韓国人の子供がいてよくいっしょに遊んでいました。あるとき二人で藪に入り立小便をしたら、その子供の皮がきれいに剥けており、彼に何故そんなになっているかたずねたら、「家の風習だ」といっていたのを今でも覚えています。韓国にもそんな習慣があったということはあまり知られていないようです。また初期キリスト教徒たちはこの割礼を拒んだ、とされています。
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。妊娠して男児を出産したとき、産婦は月経による汚れの日数と同じ七日間汚れている。八日目にはその子の包皮に割礼を施す。産婦は出血の汚れが清まるのに必要な三十三日の間、家にとどまる。その清めの期間が完了するまでは、聖なるものに触れたり、聖所にもうでたりしてはならない。
女児を出産したとき、産婦は月経による汚れの場合に準じて、十四日間汚れている。産婦は出血の汚れが清まるのに必要な六十六日の間、家にとどまる。
男児もしくは女児を出産した産婦の清めの期間が完了したならば、産婦は一歳の雄羊一匹を焼き尽くす捧げ物とし、家鳩または山鳩一羽を贖罪の捧げ物として臨在の幕屋の入り口に携えて行き、祭司に渡す。祭司がそれを主の御前にささげて、産婦のために贖いの儀式を行うと、彼女は出血の汚れから清められる。これが男児もしくは女児を出産した産婦についての指示である。」(新共同訳)
そして1月1日から数えて33日目がこの2月2日となり、これが「清めの日」ということになります。女性のこの種の血を不浄なものとする考え方は日本にも古来からあったようです。25年ほど前京都に旅行した際、ガイドをしてくれたタクシーの運転手が興味深い話しをいろいろしてくれたのですが、そのなかに「昔京都では生理中の女性は鳥居の下をくぐってはならなかった」のだそうです。また地方によっては村の祭に女性の参加を拒むようなところもあったとか。これらは平安の頃からの古い因習だと思いますが、室町時代に伝わったとされる経典「血盆経」に至って仏教における女性差別は頂点に達したようです。女性のこの種の血が大地の神を汚すというような経典で、これもそうした血が不浄であるという考え方から生まれたもともとは中国から入った思想ですが、ここまでくるともう滑稽というより他ありません。この経典、現代の女性が読んだら激怒するに違いありません。宗教というものはすべからく女性蔑視にできているのでしょうか?ユダヤの場合は女性の産後の回復のためにこうした律法が作られたという説もあるようですが、男児と女児とで大きく日数が異なるのは意味がわかりませんし、男女差別といわれても仕方がないでしょう。というよりこんなことを不浄と考えること自体がおかしいといわざるをえません。
話しが脱線してしまいましたが、マリアとヨセフはこの「清めの日」を迎え、晴れて外出できるようになり、彼らは山鳩一つがいか、家鳩の雛二羽を捧げるためイエスを連れてエルサレムの神殿に向かったのでした。これは日本で言う「お宮参り」のようなものでしょう。そしてエルサレムに着いた彼らはそこでシメオンという老人に会うことになります。このあたりは「ルカによる福音書」によく描かれており、礼拝ではそのくだりが朗読されます。そのシメオンとイエスとのかかわりから、「安らかな死」への憧れを歌っているのがこのカンタータなのです。尚「マリアの清めの祝日」はイエスのために生贄を捧げたことから、現在では「主の奉献の祝日」とか「聖燭蔡(キャンドルマス)」といわれ、一部のカトリック圏では蝋燭の儀式(人々が蝋燭を手にシメオンの讃歌[Nunc Dimittis「主よ、今こそあなたはこの僕を安らかに去らせてください」]を歌いながら行列してミサに行ったり、安産を祈願する女性たちが祭壇に蝋燭を捧げる)が今でも行われているそうです。
2013.11.11 (月) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(23)
22. カンタータ第82番「我は満ち足れり」BWV82-Ⅳバロック時代に入ると、イタリアやフランスではオペラが人々の関心を集め音楽の中心的存在となりますが、ドイツでは30年戦争(1618~48)やペストの流行により国土は荒廃し人口も激減するなど大きな痛手をこうむります。そんななかで人々の関心は教会音楽へと向かい、礼拝で皆が口ずさめるコラールがもてはやされ、モテットや教会コンチェルト、受難曲を含むオラトリオなどへ慰めを求めるようになります。
一方歌曲はというと、そんな状況下にあっても脈々と受け継がれていきますが、この時代のドイツ歌曲に関しては音楽史の本でもあまり触れられることがありません。ハスラーのあと、ドイツ歌曲の開拓者としてまずあげられるのはヨハン・ヘルマン・シャイン(Johann Hermann Schein 1586-1630で、この頃になるとようやく多声の歌曲から独唱の歌曲が多く書かれるようになります。彼はハインリヒ・シュッツ(Heinrich Schutz 1585-1672)、ザムエル・シャイト(Samuel Scheidt 1587-1654)とともにドイツ3大Sと称される大作曲家で、数多くの宗教曲、器楽曲そして世俗の歌曲などを残していますが、彼はバッハの5代前のトーマスカントルとしても知られています。彼の歌曲はハスラー風のマドリガルやヴィラネルラから出発していますが、やがてシュッツやシャイトとの親交を通じてヴェネツィアのスタイルを学び、ドイツ歌曲に初めて通奏低音の手法を採り入れたのです。彼はシュッツのようにヴェネツィア留学などは行っていません。彼の歌曲集としてはまずライプツヒ大学の学生時代に出版された「ヴェヌスの花環」(1609年)があり、これはまだハスラーの影響を大きく留めているといわれています。その後「森の音楽」(1621年、1626年、1628年の3巻からなる)や「田園の楽しみ」(1624年)などを出版し、これらで通奏低音歌曲の様式を開拓したのです。またちょっと面白いのは彼が「学生の宴」という歌曲集を1626年という人生の終盤になって出版しており、ここには酒宴の歌を納めていることです。話がそれますが、ここでドイツにしか見られない(?)特徴的な現象に少し触れておきたいと思います。といってもけっこうこれがその後のドイツ音楽には重要な役割を果たしたのです。
ドイツは根っからの酒好き、歌好きという国民性からどこでも集まってはすぐに音楽を演奏することを好んだといわれます。こうした音楽は「ゲゼルシャフトムジーク(社交のための音楽)」と言われていますが、そういえばドイツのビヤホールに行くと必ず歌が聞こえてきますね。日本でも一時流行しました。また歌だけでなく器楽の伴奏も好んでいました。イタリアやフランスでは器楽はオペラや宮廷、教会のなかで主に使われたのに対し、ドイツでは一般の市民の中に浸透していったのです。そのため小さな器楽のアンサンブルが組織されるようになりますが、これに大きな役割を果たしたのが大学でした。大学では音楽好きの学生たちによって「コレギウム・ムジクム(音楽同業組合)」という演奏団体が各地に作られていきます。これがいつ頃から組織されるようになったのかははっきりしませんが、16世紀後半には誕生していたようです。そして17世紀になるとドイツ各地に広がり、これが学内の単なるサークルという枠を飛び越えて、町の音楽活動の中心的な役割を担っていくのです。公開演奏会としては1660年にマティーアス・ヴェックマン(Matthias Weckmann 1619頃-74)がハンブルグで行ったものが最初とされています。またバッハがライプツィヒ時代ツィマーマンのコーヒーハウスで、コレギウム・ムジクムを指揮して定期的にコンサートを行っていたことはよく知られています。正木光江氏によるシャインの「オペラ・ノーヴァ第2巻」のCD (deutsche harmonia mundi BVCD-6) の解説書には、シャインが既にライプツィヒのコレギウム・ムジクムの指導も行っていた、と書かれていますので、既に同市には存在していたことになるのですが、これについてはまた後ほど触れます。もう一つドイツには「学生歌」と呼ばれる独特のジャンルがあります。ガウデアームスやムシデン、更にはあのブラームスの大学祝典序曲に使われた「狐狩りの歌」(古くから大学の新入生の歓迎歌として歌われ、わが国でもラジオの受験番組のテーマ音楽で知っている人も多いでしょう。「狐」は「新入生」のこと)などがよく知られていますが、これらはおよそ18世紀に作られたと言われていますが、その多くは古くからあった民謡などを素材にしています。学生歌の多くは酒や愛、友情、さすらい、そして愛国心などを歌っていて、これらはドイツ歌曲の歴史と密接に結びついています。シャインのみならず多くの作曲家が学生のための歌や音楽を書いています。ライプツィヒに限っただけでもパウリ・リヴァンダー(Paul Rivander 1570頃~1621?)の「Studenten-Frewd(学生の喜び)(1621)」やヨハン・エラスムス・キンダーマン(Johann Erasmus Kindermann 1616-55)の「Deliciae studiosorum(愛好者たちの楽しみ)」などがありますが、以前ご紹介したローゼンミュラーの「学生音楽Studenten-Musdik」(1654)は器楽の組曲集で、後のコレッリによって確立される室内ソナタ(前奏曲といくつかの舞曲から構成される)の先駆ともなったものです。
シャインの歌曲(多声)を収録したCDも僅かながらあるようですが、残念ながら私の手元には宗教曲しかなく、前記「オペラ・ノーヴァ第2巻 Opella Nova Ⅱ」(1626)とフィリップ・ヘレヴェッヘ指揮 シャペル・ロワイヤルによる「イスラエルの泉 Israelis Brunnlein」(1623)(harmonia mundi FRANCE KKCC-204)しか聴けませんでした。前者はブラス・アンサンブルを加えた壮麗な音楽ですが、私自身はもう少しこじんまりとした後者の音楽の方が奥の深さを感じて好ましいように思います。また器楽は「音楽の饗宴 Banchetto Musicale」(1617)から組曲第4~6番をフリッツ・ノイマイヤー指揮 コレギウム・テレプシコーレの実に楽しい演奏(Archiv UCCG-3193~4)で聴くことができます。
さてシャインの手法を受け継いで、通奏低音歌曲の様式をドイツに確立した作曲家としてハインリヒ・アルベルト(Heinrich Albert 1604-51)をあげておかなければなりません。彼はシュッツの従弟にあたり、若い頃ドレスデンでシュッツから音楽の手ほどきを受けた、といわれていますが、本格的には彼がライプツィヒ大学に入学し(1623年)そこでシャインに師事して作曲を学んだのです。学生時代から既に歌曲を作曲しており、生涯に8巻からなる「アリア集Arien」を出版しています。これらの歌曲を通じて彼は「通奏低音歌曲」と呼ばれる様式をドイツに確立したのです。それらの歌曲は独唱もありますが、多くは多声によって書かれています。ただ曲中でソロになったり合唱になったり、また器楽によるリトルネロを挿入したり、と変化をつけています。1641年の第4巻に収められている「秋の歌Herbtslied」では、2声の声楽に通奏低音という編成ですが、旋律を支える低声部はad libitumと書かれており、歌わなくてもいいようになっています。こうしたことは昔ながらの伝統なのでしょうが、彼の音楽はどちらかといえば古臭く、ドイツ・ルネサンスのポリフォニーをまだひきずっているように思います。また詩については自作のものもありますが、多くは当時の人気作家で友人でもあったシモン・ダッハ(SimonDach 1605-59)の詩によっています。彼の歌曲は「ハインリヒ・アルベルト 愛と死の歌」というCD(コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン deutsche harmonia muindi BVCD-45)で聴くことができます。ここには彼の8巻からなるアリア集から17曲の歌が集められています。
 「朝の歌」(第5巻)や「悲しきものの魂に何を訴えるのか」
(第7巻)他素朴な旋律でそのままコラールになってもお
かしくないような作品もあり、事実彼の歌曲のなかから
少なくとも25曲がコラールに転用されています。また
「老人を崇める者は」(第8巻)では比較的長い器楽の前奏
や中間にリトルネロおくなど、器楽伴奏の充実も図られ
ています。それ以前の器楽は歌と並行するようにつけられ
たいわば歌っても器楽で演奏してもよいような補完的な役割でしたが、このあたりから歌の伴奏としての役割が明確になってきます。アルベルトは1626年にはライプツィヒからケーニヒスベルクの大学に移り、法学を学んだ後音楽の道に進み、同地の大聖堂オルガニストに就任しています。その間30年戦争に自らかかわり、スウェーデンで捕らえられて投獄されたりもしています。またケーニヒスベルクではコレギウム・ムジクムの指導にも携わっています。彼の歌曲は当時たいへんな人気を博したといわれています。ただ先にも触れましたが、彼の音楽は少し古臭く、あまり楽しめるものとは言いがたいように思います。こうした不満を解消してくれるのが、次に登場する17世紀ドイツ・バロックにおける最大の歌曲作曲家アダム・クリーガーですが、彼に入る前に一枚ご紹介しておきたいCDがあります。
「朝の歌」(第5巻)や「悲しきものの魂に何を訴えるのか」
(第7巻)他素朴な旋律でそのままコラールになってもお
かしくないような作品もあり、事実彼の歌曲のなかから
少なくとも25曲がコラールに転用されています。また
「老人を崇める者は」(第8巻)では比較的長い器楽の前奏
や中間にリトルネロおくなど、器楽伴奏の充実も図られ
ています。それ以前の器楽は歌と並行するようにつけられ
たいわば歌っても器楽で演奏してもよいような補完的な役割でしたが、このあたりから歌の伴奏としての役割が明確になってきます。アルベルトは1626年にはライプツィヒからケーニヒスベルクの大学に移り、法学を学んだ後音楽の道に進み、同地の大聖堂オルガニストに就任しています。その間30年戦争に自らかかわり、スウェーデンで捕らえられて投獄されたりもしています。またケーニヒスベルクではコレギウム・ムジクムの指導にも携わっています。彼の歌曲は当時たいへんな人気を博したといわれています。ただ先にも触れましたが、彼の音楽は少し古臭く、あまり楽しめるものとは言いがたいように思います。こうした不満を解消してくれるのが、次に登場する17世紀ドイツ・バロックにおける最大の歌曲作曲家アダム・クリーガーですが、彼に入る前に一枚ご紹介しておきたいCDがあります。30年戦争がドイツに壊滅的な打撃を与えたことは既に触れましたが、この時代に書かれた歌曲だけを集めたCDがあります。それは最近オペラやリートの世界で活躍するドイツのソプラノ歌手アネッテ・ダッシュが歌う「ドイツ・バロック歌曲集」というCD(harmonia mundi s.a. HMG 501835 伴奏はベルリン古楽アカデミー団員)で、この30年戦争にスポットをあて、「愛」「無常」「平和」「自然」そして「運命」という五つのテーマに分けて独唱曲を選曲し、アルベルトやアダム・クリーガーはもちろんですが、他に アンドレアス・ハンマーシュミット(Andreas Hammerschumidt 1611-75)、ヨハン・エラスムス・キンダーマン、 ヨハン・クリスティアン・デーデキント(Johann Christian Dedekind 1628-1715)、ヨハン・クリーガー(Johann Krieger 1649-1725)、そしてフィリップ・ハインリヒ・エルバッハ(1657-1714)といった当時を代表する歌曲作家の作品を18曲(内2曲は器楽曲)集めています。これがとてもいいCDなのです。通奏低音歌曲あり、器楽のリトルネロ伴奏ありとヴァラエティも持
 たせています。中でも「無常」というテーマに入っている
エルバッハの“Unser Leben ist mit viel Not umgeben”
という曲には胸を打たれます。ドイツ語の歌詞を理解で
きるほどの能力は私にはありませんが、歌を聴いている
だけでその意味するところは伝わってきます。まるで悲
劇的なオペラのドラマチックなアリアを聴いているよう
です。「私をこの大きな苦しみから救ってください!」とい
う悲痛な叫びの歌のように聴こえてきます。その他ではコラール作家として知られるJ.クリーガーの“Abend-Andacht(夕べの祈り)”も素朴な旋律の中に情感がこもっていて美しい曲です。アルバム全体として感じるのはかなり器楽伴奏が充実してきており、バロックもいよいよ成熟期を迎えつつあるのかな、という印象です。ただこうした歌曲がもともとすべてソプラノ用にかかれたものなのか、というのはCDの解説にも書かれていないのでよくわかりません(曲ごとの解説もありません)。たいへん立派な声でいいのですが、できれば男性の声で聴いてみたい、と思うのは私の偏見でしょうか?またこのCD、外から見ただけでは誰が書いた曲なのかまったくわかりません。唯一わかるのは「30年戦争時代の歌を集めた」ものというだけで、安かったからいいようなものですが、まるでギャンブルように開けてみて初めて作曲者がわかるという、豪華な装丁ながらちょっと不親切なCDではあります。それとデーデキントという作曲家はほとんど音楽史の本などにも紹介されていませんが、私の所蔵する本の中では唯一パウル・ヘンリー・ラング著「西洋文化と音楽」(ノートン音楽史シリーズ、音楽之友社)の中で数行触れられている(当時最も人気のあった歌曲作家だったとのこと)のと、楽譜「Alte Meister des Deutschen Liedes: 46 Gesange des 17. und 18. Jahrhunderts-Hans Joachim Moser編 EDITION PETERS」の中に登場するだけです。ただそのどちらにも名前はKonstantin Christian Dedekindとなっており、生没年が同じなので、おそらくこちらの表記の方が正しいように思うのですが。
たせています。中でも「無常」というテーマに入っている
エルバッハの“Unser Leben ist mit viel Not umgeben”
という曲には胸を打たれます。ドイツ語の歌詞を理解で
きるほどの能力は私にはありませんが、歌を聴いている
だけでその意味するところは伝わってきます。まるで悲
劇的なオペラのドラマチックなアリアを聴いているよう
です。「私をこの大きな苦しみから救ってください!」とい
う悲痛な叫びの歌のように聴こえてきます。その他ではコラール作家として知られるJ.クリーガーの“Abend-Andacht(夕べの祈り)”も素朴な旋律の中に情感がこもっていて美しい曲です。アルバム全体として感じるのはかなり器楽伴奏が充実してきており、バロックもいよいよ成熟期を迎えつつあるのかな、という印象です。ただこうした歌曲がもともとすべてソプラノ用にかかれたものなのか、というのはCDの解説にも書かれていないのでよくわかりません(曲ごとの解説もありません)。たいへん立派な声でいいのですが、できれば男性の声で聴いてみたい、と思うのは私の偏見でしょうか?またこのCD、外から見ただけでは誰が書いた曲なのかまったくわかりません。唯一わかるのは「30年戦争時代の歌を集めた」ものというだけで、安かったからいいようなものですが、まるでギャンブルように開けてみて初めて作曲者がわかるという、豪華な装丁ながらちょっと不親切なCDではあります。それとデーデキントという作曲家はほとんど音楽史の本などにも紹介されていませんが、私の所蔵する本の中では唯一パウル・ヘンリー・ラング著「西洋文化と音楽」(ノートン音楽史シリーズ、音楽之友社)の中で数行触れられている(当時最も人気のあった歌曲作家だったとのこと)のと、楽譜「Alte Meister des Deutschen Liedes: 46 Gesange des 17. und 18. Jahrhunderts-Hans Joachim Moser編 EDITION PETERS」の中に登場するだけです。ただそのどちらにも名前はKonstantin Christian Dedekindとなっており、生没年が同じなので、おそらくこちらの表記の方が正しいように思うのですが。さてアダム・クリーガー(Adam Krieger 1634-66)はドイツ歌曲の歴史を紹介する本には必ず登場する、ドイツ・バロック期最大の歌曲作家です。彼はポーランドとの国境に近い中部ドイツの都市フランクフルト(オーデル)に程近い
 町ドリーセンに生まれ、1650年頃にはライプツィヒに出
て大学に入り、正規の学生ではなかったようですが学生達
のために歌を書き、彼らの間ではかなり人気を博していた
といわれます。アメリカの学者ジョシュア・リフキンによ
れば、彼は「1650年代(もしくはそれ以前)にライプツィヒ
大学にコレギウム・ムジクムを組織しその最初の指導者」
とされていますが、これについてはいささか古い記述なの
で前述のようにどうやらシャインが最初の指導者ではないでしょうか?このコレギウム・ムジクムですが、バッハがライプツィヒに着任し、聖トーマス、聖ニコライ、新教会そして聖パウロという四つの教会の音楽を任されたとき、その器楽演奏を受け持ったのは前2教会についてはトーマス学校の生徒達(何人かはエキストラも入っていたと思いますが)が、そして聖パウロ教会ではこのコレギウム・ムジクムが担当していました。クリストフ・ヴォルフによれば「聖パウロ教会では、主要な祝祭日と定期市の時の通常の礼拝の蔡、コレギウム・ムジクムを形成する大学生たちによって、教会の音楽監督の指揮で行われる声楽・器楽合奏が呼び物となっていた」(ヨハン・セバスティアン・バッハ―学識ある音楽家)となっていますので、この教会でもバッハの指揮する音楽が当時市民の間で人気を博していたことがわかります。そして残る新教会ですが、こちらは1704年にテレマンが創設した新しいコレギウム・ムジクムによって演奏されていました。バッハが後にコーヒーハウスで定期的に器楽のコンサートを開くようになるのはこの新しい方のコレギウム・ムジクムとです。またややこしい話しですが、1708年にはヨハン・フリードリヒ・ファッシュ(Johann Friedrich Fasch 1688-1758)が更に別のコレギウム・ムジクムをライプツィヒ大学に組織しています。ということはバッハの時代、同じ大学内に少なくとも三つのコレギウム・ムジクムが存在していたことになります。いずれにせよ彼らがライプツィヒにおいて器楽演奏の中心的な役割を果たしていたことは間違いありません。彼らは事あるごとに裕福な市民層や貴族のために音楽を提供し、教会においても演奏することでその活動を支えてきたのです。クリーガーは1655年投獄されたローゼンミュラーの後任として聖ニコライ教会のオルガニストに就任するとともに、こうした学生たちのために器楽伴奏による後奏付き(リトルネロ)の歌曲を数多く書き、1657年に「アリア集Arien」を出版してその名声を築き上げたのです。同年ザクセン選帝侯の招きでドレスデンに移り、更にはトビーアス・ミヒャエルの後任としてトーマスカントルへの就任を勧められるも条件が折り合わずこれを拒み、結局58年に選帝侯の宮廷オルガニストに就任することになります。歌曲作家として名声を築きながらも1566年32歳という若さで世を去りました。
町ドリーセンに生まれ、1650年頃にはライプツィヒに出
て大学に入り、正規の学生ではなかったようですが学生達
のために歌を書き、彼らの間ではかなり人気を博していた
といわれます。アメリカの学者ジョシュア・リフキンによ
れば、彼は「1650年代(もしくはそれ以前)にライプツィヒ
大学にコレギウム・ムジクムを組織しその最初の指導者」
とされていますが、これについてはいささか古い記述なの
で前述のようにどうやらシャインが最初の指導者ではないでしょうか?このコレギウム・ムジクムですが、バッハがライプツィヒに着任し、聖トーマス、聖ニコライ、新教会そして聖パウロという四つの教会の音楽を任されたとき、その器楽演奏を受け持ったのは前2教会についてはトーマス学校の生徒達(何人かはエキストラも入っていたと思いますが)が、そして聖パウロ教会ではこのコレギウム・ムジクムが担当していました。クリストフ・ヴォルフによれば「聖パウロ教会では、主要な祝祭日と定期市の時の通常の礼拝の蔡、コレギウム・ムジクムを形成する大学生たちによって、教会の音楽監督の指揮で行われる声楽・器楽合奏が呼び物となっていた」(ヨハン・セバスティアン・バッハ―学識ある音楽家)となっていますので、この教会でもバッハの指揮する音楽が当時市民の間で人気を博していたことがわかります。そして残る新教会ですが、こちらは1704年にテレマンが創設した新しいコレギウム・ムジクムによって演奏されていました。バッハが後にコーヒーハウスで定期的に器楽のコンサートを開くようになるのはこの新しい方のコレギウム・ムジクムとです。またややこしい話しですが、1708年にはヨハン・フリードリヒ・ファッシュ(Johann Friedrich Fasch 1688-1758)が更に別のコレギウム・ムジクムをライプツィヒ大学に組織しています。ということはバッハの時代、同じ大学内に少なくとも三つのコレギウム・ムジクムが存在していたことになります。いずれにせよ彼らがライプツィヒにおいて器楽演奏の中心的な役割を果たしていたことは間違いありません。彼らは事あるごとに裕福な市民層や貴族のために音楽を提供し、教会においても演奏することでその活動を支えてきたのです。クリーガーは1655年投獄されたローゼンミュラーの後任として聖ニコライ教会のオルガニストに就任するとともに、こうした学生たちのために器楽伴奏による後奏付き(リトルネロ)の歌曲を数多く書き、1657年に「アリア集Arien」を出版してその名声を築き上げたのです。同年ザクセン選帝侯の招きでドレスデンに移り、更にはトビーアス・ミヒャエルの後任としてトーマスカントルへの就任を勧められるも条件が折り合わずこれを拒み、結局58年に選帝侯の宮廷オルガニストに就任することになります。歌曲作家として名声を築きながらも1566年32歳という若さで世を去りました。クリーガーは生前に50曲ほどからなる1巻の歌曲集を出版しただけで、それも現在完全な形では残されていません。よく知られているのは彼の死の翌年仲間たちが編纂したやはり50曲ほどからなる「新アリア集Neue Arien」で、これは更にその10年後ドレスデン宮廷のヴァイオリン奏者ヨハン・ヴィルヘルム・フルヒハイム(Johann Wilhelm Furchheim 1635頃-1682)が器楽のリトルネロに少し手を加えたり、書き加えたりして出版しています。彼の歌曲は多くが詩の各節を同じ旋律で繰り返す有節歌曲で、通奏低音歌曲というドイツの伝統に従いながらもドイツ語の語感を生かした詩を自ら創作し、リトルネロを更に充実させ、またイタリアの影響を受けて旋律もより美しく、そして何よりも表現力が豊かになっています。私がこのクリーガーを知るようになったきっかけは、前回のハスラーと全く同じです。番組では故服部幸三氏がとても楽しそうにクリーガーの歌曲を紹介され、それを聴いた私は後にやはりレコードを捜し求めたのでした。そのレコードは「Student Music in 17th Century Leipzig」(Nonesuch H-71204)というLPで、演奏はジョシュア・リフキン指揮及びハープシコード、ロンドン小オーケストラ団員で、歌手はサリー・ル・サージュ(S)、クリスティナ・クラーク(S)、ナイジェル・ロジャース(T)、ジェフリー・ショウ(Br)という布陣で、重唱あり、独唱ありという内容です。この中にはクリーガーの歌曲が10曲収められ、そのほかにはローゼンミュラーの「学生音楽」から組曲第2番と、ライプツィヒのシュタットプファイファー(町のラッパ吹き)として知られるヨハン・クリストフ・ペーツェル(Johann Christoph Pezel 1639-94)の器楽曲2曲が収録されています。購入以来私はこのレコードが好きで何度となく聴いてきたので、今これを聴くことはできないのですがそのうちの何曲かははっきりと口ずさめるほど覚えています。中でも酒宴の歌「Der Rheinsche Wein tanzt gar zu fein(ラインワインはグラスに踊る)」は、いかにもドイツ
 の学生歌らしい実に楽しい曲です。これは前記の楽譜にも
載っていて、冒頭“Frisch(元気に)”という指示が書かれ
ています。曲はバリトンによる単純なメロディで各節の最
後に男声合唱の合いの手が入り、弦のリトルネロがそれに
続きます。この曲は彼の歌曲の中ではもっとも知られてい
るものかもしれません。ただ私が一番好きなのは
「Es fehlet ihr nur einer Zier(娘よ、ただひとつ一つお前
に欠けているものは)」という同じくバリトンのソロで歌われる曲です。これを学生の音楽とするのはちょっと乱暴なような気もしますが、父親が成長した我が娘をしげしげと眺めながら情感たっぷりに歌います。単純なメロディですがその旋律の美しさはそれ以前の作曲家には見られないものです。このLP残念ながらCDにはなっていないようです。現在私がもっているCDの中でA. クリーガーの歌曲は前記ダッシュ盤に入っている「Fleug, Psyche, Fleug(飛べ、プシュケー、飛べ)」という曲だけです。この歌も素晴らしい曲ですが、彼の作品に多い単純な有節歌曲ではなく、一節ごとに旋律が変化していき、最後にダ・カーポで冒頭の旋律に戻るという手法で、明らかにイタリアの影響が感じられます。軽快な恋の歌で、神話の中の田園的な愛の情景を描いており、テンポや旋律など変化に富んでいて、これがとてもバロック中期の作品とは思えない、聴けば聴くほど味わいのある歌です。彼の作品には歌曲のほかに5曲ほどのカンタータも残されており、もしもう少し長生きしていれば間違いなくドイツ三大Sの後継者になったであろうと言う人もいます。シューベルト以前のドイツ歌曲最大の作曲であったことは間違いないでしょう。32歳という若さで亡くなったことが本当に惜しまれます。尚彼の歌が収録されているCDは他に2枚ほどあります。一つはアンドレス・ショルが歌う「ドイツ・バロック歌曲集」(Harmonia Mundi Gold HMG-501505)で内容的にはダッシュ盤と似ていますが、こちらにはA.クリーガーの歌曲が4曲収録されており、これには「ラインワインは・・・」も収録されています。またもう一枚はスペインの古楽レーベルGlossa Cabinetから発売されているクラウディオ・カヴィーナ他の歌(Laments, Cantatas & Arias German Broque GCDC-80901)によるもので、こちらには6曲ほど収録されています。両盤ともカウンターテナーによる歌で、これらも聴きたかったのですが、私の乏しい資力ではそうそう次から次へと購入することもできず、あきらめました。A.クリーガーの歌曲のうちいくつかは定旋律としてコラールに転用されていて、バッハの死後に編纂された「4声のコラール集」のBWV396「いまぞこの日は終わり Nun sich der Tag geendet hat」もその一つです。
の学生歌らしい実に楽しい曲です。これは前記の楽譜にも
載っていて、冒頭“Frisch(元気に)”という指示が書かれ
ています。曲はバリトンによる単純なメロディで各節の最
後に男声合唱の合いの手が入り、弦のリトルネロがそれに
続きます。この曲は彼の歌曲の中ではもっとも知られてい
るものかもしれません。ただ私が一番好きなのは
「Es fehlet ihr nur einer Zier(娘よ、ただひとつ一つお前
に欠けているものは)」という同じくバリトンのソロで歌われる曲です。これを学生の音楽とするのはちょっと乱暴なような気もしますが、父親が成長した我が娘をしげしげと眺めながら情感たっぷりに歌います。単純なメロディですがその旋律の美しさはそれ以前の作曲家には見られないものです。このLP残念ながらCDにはなっていないようです。現在私がもっているCDの中でA. クリーガーの歌曲は前記ダッシュ盤に入っている「Fleug, Psyche, Fleug(飛べ、プシュケー、飛べ)」という曲だけです。この歌も素晴らしい曲ですが、彼の作品に多い単純な有節歌曲ではなく、一節ごとに旋律が変化していき、最後にダ・カーポで冒頭の旋律に戻るという手法で、明らかにイタリアの影響が感じられます。軽快な恋の歌で、神話の中の田園的な愛の情景を描いており、テンポや旋律など変化に富んでいて、これがとてもバロック中期の作品とは思えない、聴けば聴くほど味わいのある歌です。彼の作品には歌曲のほかに5曲ほどのカンタータも残されており、もしもう少し長生きしていれば間違いなくドイツ三大Sの後継者になったであろうと言う人もいます。シューベルト以前のドイツ歌曲最大の作曲であったことは間違いないでしょう。32歳という若さで亡くなったことが本当に惜しまれます。尚彼の歌が収録されているCDは他に2枚ほどあります。一つはアンドレス・ショルが歌う「ドイツ・バロック歌曲集」(Harmonia Mundi Gold HMG-501505)で内容的にはダッシュ盤と似ていますが、こちらにはA.クリーガーの歌曲が4曲収録されており、これには「ラインワインは・・・」も収録されています。またもう一枚はスペインの古楽レーベルGlossa Cabinetから発売されているクラウディオ・カヴィーナ他の歌(Laments, Cantatas & Arias German Broque GCDC-80901)によるもので、こちらには6曲ほど収録されています。両盤ともカウンターテナーによる歌で、これらも聴きたかったのですが、私の乏しい資力ではそうそう次から次へと購入することもできず、あきらめました。A.クリーガーの歌曲のうちいくつかは定旋律としてコラールに転用されていて、バッハの死後に編纂された「4声のコラール集」のBWV396「いまぞこの日は終わり Nun sich der Tag geendet hat」もその一つです。アダム・クリーガーのあとドイツにおける歌曲の創作は急速に衰えていき、オペラやカンタータに吸収され姿を消してしまいます。そうした中で中部ドイツ、テューリンゲンの森の都に一人の偉大な作曲家が産声をあげるのです。
2013.08.22 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(22)
21. カンタータ第82番「我は満ち足れり」BWV82-Ⅲ前回はドイツ歌曲の過去を遡ってその起源と歴史について話を進め、その中でイザークの「インスブルックよ、さようなら」の歌をとりあげました。レヒナーの替え歌にも触れ、インスブルックが「愛」に置き換わったことや、更にこの歌が後にパウル・ゲルハルトによってコラールに編曲されたこと、またそれがバッハの受難曲やカンタータに様々に使用されていることもご紹介しました。ただこのコラールにはもう一つ別の作者不詳の同じ旋律(リズムが少し異なる)によるものがあり、それは「愛」を更に「この世O Welt」という語に変え、葬式用のコラールにしてしまったものですが、これが讃美歌21の第569番「今やこの世に わかれを告げて」として知られているものです。ゲルハルトのコラール“O Welt, sieh hier dein Leben”とこちらの“O Welt, ich muss dich lassenn”の微妙な違いがおわかりいただけると思いますが、後者の方がイザークの原詩に近く、ゲルハルトのコラールが1648年に作られたのに対し、こちらの方は1555年頃と推定される印刷譜による(「讃美歌21略解」)とされていますので、この方が古いことになります。前述したように、コラールの多くは当時流行っていた流行歌や民謡など既存の旋律(定旋律)を借用しており、こうした手法は「コントラファクトゥム」と呼ばれています。つまり「パロディ」になるわけで、これは13世紀ごろ盛んに用いられた手法で、それが16世紀に復活してこれらのコラールや「パロディ・ミサ」と呼ばれる宗教曲などにも用いられるようになったのです。後にバッハやヘンデルが自作の旋律を盛んに転用したのは、こうした伝統があったからではないでしょうか?
さてルネサンスの末期になると、ドイツ歌曲の重要な作曲家としてハンス・レオ・ハスラー(Hans Leo Hassler 1564~1612)が登場します。彼はルネサンスからバロックへと大きく変わる変革の時代を生きたシュッツ以前におけるドイツ最大の作曲家と言っても過言ではありません。ニュルンベルクに生まれ、はじめオルガニストの父親から音楽教育を受け、更にラッソの弟子で同地の教師をしていたレオンハルト・レヒナーから大きな影響を受けた(直接の関係があったかどうかは不明)といわれています。彼は二十歳になったばかりの1584年、ヴェネツィアに留学します。この留学はその後バロック時代に入ってシュッツをはじめドイツから多くの作曲家がヴェネツィア詣でをする先駆けとなります。ハスラーのヴェネツィア留学は18ヶ月という短いものでしたが、そこでアンドレア・ガブリエリ(1510頃~86)に師事しその甥のジョヴァンニとともにヴェネツィア楽派の音楽を学んだのでした。ジョヴァンニとはかなり親しかったようで、二人の共作になるモテットなども作曲しています。
1586年ドイツに戻ると、彼はアウグスブルクのフッガー家に雇われその室内礼拝堂オルガニストの地位に就きます。このフッガー家は、鉱山経営と銀行業から得た莫大な富を背景に、神聖ローマ帝国皇帝の選挙やローマ教皇の選出などにも大きくかかわり、政治や経済、宗教などさまざまな分野でヨーロッパを支配した大富豪で、一方では芸術家を庇護するなど、イタリアのメディチ家にも似たような家系ですが、その財力はメディチ家の5倍と言われています。ルターによる宗教改革の発端となった免罪符も、教皇庁がフッガー家に対する借金の返済のために発行した、とされています。ただフッガー家がメディチ家などと異なるのは、繁栄の祖となったヤコプ・フッガー(2世)(1459~1525)が富を社会に還元することも義務と考え、福祉にも重点を置いていたことです。
少し話が横道にそれてしまいますが、このアウグスブルクという町はドイツ・ロマンティック街道の中ほどに位置し、街道中最大の(といっても小さな町)、そして最古の都市でもあります。紀元前15年ローマ帝国の属州として要塞が置かれ、時の皇帝アウグストゥス(初代ローマ皇帝)によって「アウグスタ・ヴィンデリコルム」と名づけられたのが起源といわれています。私も今からもう四半世紀も前になってしまいますが、この地を訪れたことがあります。ミュンヘンから列車で30分ほどの古都で、そこは観光客の人並みで溢れたミュンヘンの町とはまったく違い、静かで落ちついた町並みが広がり、ルネサンスの面影を色濃く残した古き時代のドイツを味わうことができます。町の中心部を過ぎて更に歩いていくと「フッゲライFuggerei(フッガー長屋)」と呼ばれる大規模な集合住宅があります。この住宅こそがヤコプが社会福祉のために建てた住宅で、世界最古の福祉施設といわれています。今もそこは施設として利用され、家賃も当時のままに据え置かれていると聞きましたが、あれから25年ほどたちどうなっているでしょうか。またこのフッゲライにはモーツァルトの曾祖父であるフランツ・モーツァルト(1649~94 石大工の親方)も住んでいて、そのことを示すプレートが博物館の隣の住居に掲げられています。アマデウスの父レオポルト(フランツの孫にあたる)がこの町の出身であることはご存知の方もあると思いますが、彼の生まれた家は旧市街の北のはずれにあり、そこは今モーツァルトハウスとして記念館になっています。
さて、このフッガー家が芸術を庇護していたことは既に述べましたが(よく知られているのは画家アルブレヒト・デューラーのパトロン)、彼らはオルガンを教会に寄贈したり、楽譜印刷の援助を行ったりもしています。そしてオクタヴィアン2世(1549-1600)の代になって彼は一族のための豪華な礼拝堂を建設します。彼は歴代のフッガー家の中でももっとも音楽好きだったと言われており、アンドレア・ガブリエリとも親しく、その彼からの推薦でハスラーはフッガー家に雇われるようになった、といわれています。このアウグスブルク時代にハスラーの創作活動はもっとも活発になり、彼の名声は広く知れ渡るようになりますが、その名声に比してアウグスブルクにおける彼の評価は低かったようで、そのせいかオクタヴィアン2世が没すると、1601年彼は市当局からの音楽監督の要請を断って、15年という長きにわたったアウグスブルクを去り、生まれ故郷ニュルンベルクに戻って同市の音楽監督となります。彼の評価が低かった理由は、ハスラーがプロテスタントであり、カトリックの町アウグスブルクでは人間関係がうまく保てなかったのでは、といわれています。オクタヴィアン2世も最後彼を一族の分家に左遷してしまったのです。
ニュルンベルクでも精力的に作曲活動を行いますが、その期間は4年という短いもので、その後アウグスブルクの西方約70kmにある町ウルムに移り、ここで遅まきながら結婚しています。1608年にはザクセン選帝侯クリスティアン2世の要請により、破格の高給を得てドレスデンに移り、そこでオルガニスト、更には宮廷礼拝堂楽長となりますが、ドレスデンに移ってすぐに結核を発病し、それがもとで1612年に亡くなりました。彼のドレスデンにおける仕事はその後ミヒャエル・プレトリウス、更にはハインリヒ・シュッツへと引き継がれていきます。
ハスラーの音楽はドイツの重厚な響きに加え、イタリア・ヴェネツィア楽派の壮麗さを加えたもので、宗教曲においては後のシュッツによる「ダヴィデ詩篇集」のような派手さはありませんが、実に奥深い感動的な作品であり、また歌曲においては「私の心は思い悩んでいる(「わが心は千々に乱れ」という訳でも知られる」)に代表されるように、後世に計り知れない影響を及ぼしたのです。CDをいくつかとりあげながら、彼の音楽に触れてみたいと思います。
はじめにご紹介するのは、「ルネサンスの名歌の花束~フッガー家の音楽」(アントニー・ルーリー指揮 コンソート・オブ・ミュージック バロック・ブラス・オブ・ロンドン deutsche harmonia mundi BVCD-38174 録音:1985年)というCDです。フッガー家の
 ために書かれた音楽ばかりを集めていますが、こ
こには今回の主人公ハンス・レオ・ハスラーのみならず、
同時代の大作曲家が軒並み名を連ねており、いかにヨーロ
ッパにおけるフッガー家の影響が強かったかがわかります。
アンドレア、ジョヴァンニの両ガブリエリ、ラッソ、ハ
ンスの弟ヤコプ・ハスラー(1569-1622)、そしてオラツィ
オ・ヴェッキ(Orazio Vecchi 1550-1605)などなどの作品で、
他にも珍しい作曲家によるマドリガーレやカンツォネッタを収録しています。ハスラー(兄)の作品は1590年に出版され、クリストフ・フッガー(左遷先の分家)に捧げられた曲集から4声のカンツォネッタ「明るく輝く星よChiara e lucente stella」と同じく4声のマドリガーレ「羊飼いたちはいつも Vivan sempre i pastori」の2曲が選ばれています。短い曲ですが透き通るように美しいハーモニーが心に沁みます。なおここにはドイツ語による歌は1曲もなく、また器楽だけの演奏も2曲含まれています。ブラス・アンサンブルの名曲、ジョヴァンニ・ガブリエリの「ピアノとフォルテのためのソナタ」も収録されており、8声によるステレオ効果満点の作品で、音楽史上最初に強弱が指示されたことでも知られています。音の対比が鮮やかで、これこそがバロックへの道を拓いた記念すべき作品といえるでしょう。1597年に出版された「サクラ・シンフォニア集」という曲集に含まれていますが、この曲集がフッガー家に捧げられたとは私も今まで知りませんでした。それと短い作品ですが、ヴェッキの「モ、モ・マガーリ」(「ヴェネツィア方言で書かれた意味のない言葉」だそうです)という3声の合唱曲はとても愉快な曲です。
ために書かれた音楽ばかりを集めていますが、こ
こには今回の主人公ハンス・レオ・ハスラーのみならず、
同時代の大作曲家が軒並み名を連ねており、いかにヨーロ
ッパにおけるフッガー家の影響が強かったかがわかります。
アンドレア、ジョヴァンニの両ガブリエリ、ラッソ、ハ
ンスの弟ヤコプ・ハスラー(1569-1622)、そしてオラツィ
オ・ヴェッキ(Orazio Vecchi 1550-1605)などなどの作品で、
他にも珍しい作曲家によるマドリガーレやカンツォネッタを収録しています。ハスラー(兄)の作品は1590年に出版され、クリストフ・フッガー(左遷先の分家)に捧げられた曲集から4声のカンツォネッタ「明るく輝く星よChiara e lucente stella」と同じく4声のマドリガーレ「羊飼いたちはいつも Vivan sempre i pastori」の2曲が選ばれています。短い曲ですが透き通るように美しいハーモニーが心に沁みます。なおここにはドイツ語による歌は1曲もなく、また器楽だけの演奏も2曲含まれています。ブラス・アンサンブルの名曲、ジョヴァンニ・ガブリエリの「ピアノとフォルテのためのソナタ」も収録されており、8声によるステレオ効果満点の作品で、音楽史上最初に強弱が指示されたことでも知られています。音の対比が鮮やかで、これこそがバロックへの道を拓いた記念すべき作品といえるでしょう。1597年に出版された「サクラ・シンフォニア集」という曲集に含まれていますが、この曲集がフッガー家に捧げられたとは私も今まで知りませんでした。それと短い作品ですが、ヴェッキの「モ、モ・マガーリ」(「ヴェネツィア方言で書かれた意味のない言葉」だそうです)という3声の合唱曲はとても愉快な曲です。次に、今回宗教曲はとりあげないつもりでしたがあまりに素晴らしい作品なので、簡単にご紹介したいと思うCDがあります。それは「ミサ・デキシット・マリア Missa super Dixit Maria(マリアは言われた)」という作品で、フィリップ・ヘレヴェッヘ指揮のシャペル・ロワイヤルによる演奏です(harminia mundi FRANCE-King International KKCC-204)。
 このミサ曲は1599年に出版
された4声のア・カペラによる作品で、これを聴くとハス
ラーの才能がいかに素晴らしいものだったかがよくわかり
ます。プロテスタントの作曲家がラテン語のミサ曲を書く
のはバッハの例をみてもわかるようによくあること。この
ミサ曲はグレゴリアン風の導入に始まり、そこから旋律を
発展させるような方法で展開する、まさにポリフォニー芸
術の最高峰といっても過言ではないでしょう。何という美しさでしょう。「純粋ポリフォニーによるア・カペラ洋式」という点で、プロテスタントでありながらあのカトリックのトリエント公会議(1545~63)で推奨された反宗教改革の新しい波をも感じさせます。パレストリーナの美しさも格別ですが、旋律の動きが緩慢でややもすると退屈に感じることがありますが、この作品には力強さや躍動感すら感じられます。そしてヴェネツィア楽派の影響もはっきりみてとれ、声部間の掛け合いによる対比の綾(特に「グローリア」)などの新しさも加わり、既にバロックへの移行が感じられます。このCDには他に4曲のモテットとルターのコラール「主の祈り」(有名な「天におられる私たちの父よ」で始まる祈り)を合唱に編曲した作品、更には彼の師と言われるレヒナーのモテット「もし主の御手から恵みを得るならば Si bona suscepimus」も1曲収録しています。
このミサ曲は1599年に出版
された4声のア・カペラによる作品で、これを聴くとハス
ラーの才能がいかに素晴らしいものだったかがよくわかり
ます。プロテスタントの作曲家がラテン語のミサ曲を書く
のはバッハの例をみてもわかるようによくあること。この
ミサ曲はグレゴリアン風の導入に始まり、そこから旋律を
発展させるような方法で展開する、まさにポリフォニー芸
術の最高峰といっても過言ではないでしょう。何という美しさでしょう。「純粋ポリフォニーによるア・カペラ洋式」という点で、プロテスタントでありながらあのカトリックのトリエント公会議(1545~63)で推奨された反宗教改革の新しい波をも感じさせます。パレストリーナの美しさも格別ですが、旋律の動きが緩慢でややもすると退屈に感じることがありますが、この作品には力強さや躍動感すら感じられます。そしてヴェネツィア楽派の影響もはっきりみてとれ、声部間の掛け合いによる対比の綾(特に「グローリア」)などの新しさも加わり、既にバロックへの移行が感じられます。このCDには他に4曲のモテットとルターのコラール「主の祈り」(有名な「天におられる私たちの父よ」で始まる祈り)を合唱に編曲した作品、更には彼の師と言われるレヒナーのモテット「もし主の御手から恵みを得るならば Si bona suscepimus」も1曲収録しています。最後にご紹介するのは、私が受験に失敗して浪人生活を送っていた頃だったと思いますがNHK FMの「バロック音楽のたのしみ」で皆川達夫氏によって紹介され、どうしてもそのLPが欲しくなって大学に入学後アルバイトでお金を貯め、神田や新橋の中古レコード店を探し回ってようやく手に入れた1枚のレコードにまつわる話しです。そのレコードは「第6研究部門:ドイツのバロック音楽 ハンス・レオ・ハスラー作曲《新しいドイツ歌曲の喜びの園》より」(Archiv 2533 041)というものでした。この曲集の正式なタイトルは「Lustgarten Neuer Teutscher Gesang, Balletti, Gaglliarden und Intraden mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen: Componiert durch Hans Leo Hassler von Nurnberg 1601」と書かれてい
 るように、新しいドイツ歌
曲と舞曲やイントラーダ(導入曲)などの器楽曲を集めたも
ので、アウグスブルグ時代に書いた作品をニュルンベルク
に移ってすぐに出版したものです。内訳は声楽曲が39曲、
器楽曲が11曲となっていて、このレコードにはその中か
ら10曲の声楽作品と6曲の器楽曲が収録されていました。
器楽作品については、アンドレア、ジョヴァンニ両ガブリ
エリの模倣の域を出ないと言われますが、声楽作品につい
てはその後のドイツ歌曲の発展に及ぼした影響の大きさは
計り知れない、といわれています。それはレコードの3曲目に収録されている愛の歌「わたしの心は思い悩んでいる Mein Gmuth ist mir verwirret」がその後たどった歴史を見ればあきらかでしょう。この曲は1613年には「わが心の切なる願い Herzlich tut mich verlangenn」という歌詞をつけられて「Harmoniae sacrae」という宗教曲集に組み入れられ、更に1647年ヨハン・クリューガー(Johann Cruger 1598-1662)がパウル・ゲルハルトの「血潮したたる主のみかしら O Haupt voll Blut und Wunden」という詩にこの旋律を使用して讃美歌集「Praxis pietatis melica(美しい旋律による敬虔の実践)」に収録しています。これが後にバッハの「マタイ受難曲」のパッション・コラールに編曲され今やクラシック・ファンならだれもが知る名曲となったのです。「血潮したたる」は讃美歌21の310番と311番としても知られていますが、その2曲はリズムが異なっており、ハスラーの原曲に近いのは前者の方です。ハスラーのこの歌曲はもともと若い娘に恋焦がれる男の愛の苦しみを歌った5声の合唱曲として作られたものですが、このLPではテノールリートの形式で上声部の旋律のみをかつて名エヴァンゲリストとして活躍し、1972年から91年まで聖トーマス教会のカントルを勤めたハンス=ヨアヒム・ロッチュのソロで歌われています。伴奏はペーター・クルグによるバス・ガンバのみです。まさにドイツ・リートの原点といってもいい、素晴らしい歌曲です。LP全体の演奏者の紹介がまだでしたが、これはライプイツィヒ放送合唱団などを第一級の合唱団に育てあげた名合唱指揮者として知られるディートリヒ・クノーテ指揮によるライプツィヒ合奏団(Capella Lipsiensis)によるもので、声楽陣には前記ロッチュの他、ソプラノのアデーレ・シュトルテ、バスのヘルマン・クリスティアン・ポルスターなどが加わっています。その後何度か引っ越したりしているうちに我が家ではLPが聴ける環境ではなくなってしまい、このLPもレコード棚の奥にしまいこまれたままになってしまいました。そんなことから何とかこの曲が収録されているCDがないものかと探し回っていたところ、BERLIN ClassicsのETERNAレーベルにこの曲の入ったCD(番号:0031272BC)があることがわかり、レコード店に行くと「品切れで今すぐには入手できない」といわれ、それでも一応注文だけはしておいたところ、半年以上たって私もすっかり忘れていた頃「CDが届いた」と店から連絡がありました。演奏者は同じクノーテ指揮によるものであることは知っていたのですが、詳しい情報が記載されていなくてそれ以上のことは何もわかりませんでした。しかしながら聴いてみてびっくり、このCDはあのアルヒーフ盤とまったく同じだったのです。アルヒーフ盤の懇切丁寧なクレジットとは対照的にこのCDには簡単な曲目表示しかなく、詳細な演奏者のクレジットもありません。でも内容がまったく同じであることはすぐにわかりました。アルヒーフ盤には録音が1963年3月18~22日と書かれており、CDにはコピーライト表示が 「1963 “edel” Gesellschaft fur Produktmarketing mbH」となっています。思わぬ形で懐かしい録音のCDが手に入ったの
るように、新しいドイツ歌
曲と舞曲やイントラーダ(導入曲)などの器楽曲を集めたも
ので、アウグスブルグ時代に書いた作品をニュルンベルク
に移ってすぐに出版したものです。内訳は声楽曲が39曲、
器楽曲が11曲となっていて、このレコードにはその中か
ら10曲の声楽作品と6曲の器楽曲が収録されていました。
器楽作品については、アンドレア、ジョヴァンニ両ガブリ
エリの模倣の域を出ないと言われますが、声楽作品につい
てはその後のドイツ歌曲の発展に及ぼした影響の大きさは
計り知れない、といわれています。それはレコードの3曲目に収録されている愛の歌「わたしの心は思い悩んでいる Mein Gmuth ist mir verwirret」がその後たどった歴史を見ればあきらかでしょう。この曲は1613年には「わが心の切なる願い Herzlich tut mich verlangenn」という歌詞をつけられて「Harmoniae sacrae」という宗教曲集に組み入れられ、更に1647年ヨハン・クリューガー(Johann Cruger 1598-1662)がパウル・ゲルハルトの「血潮したたる主のみかしら O Haupt voll Blut und Wunden」という詩にこの旋律を使用して讃美歌集「Praxis pietatis melica(美しい旋律による敬虔の実践)」に収録しています。これが後にバッハの「マタイ受難曲」のパッション・コラールに編曲され今やクラシック・ファンならだれもが知る名曲となったのです。「血潮したたる」は讃美歌21の310番と311番としても知られていますが、その2曲はリズムが異なっており、ハスラーの原曲に近いのは前者の方です。ハスラーのこの歌曲はもともと若い娘に恋焦がれる男の愛の苦しみを歌った5声の合唱曲として作られたものですが、このLPではテノールリートの形式で上声部の旋律のみをかつて名エヴァンゲリストとして活躍し、1972年から91年まで聖トーマス教会のカントルを勤めたハンス=ヨアヒム・ロッチュのソロで歌われています。伴奏はペーター・クルグによるバス・ガンバのみです。まさにドイツ・リートの原点といってもいい、素晴らしい歌曲です。LP全体の演奏者の紹介がまだでしたが、これはライプイツィヒ放送合唱団などを第一級の合唱団に育てあげた名合唱指揮者として知られるディートリヒ・クノーテ指揮によるライプツィヒ合奏団(Capella Lipsiensis)によるもので、声楽陣には前記ロッチュの他、ソプラノのアデーレ・シュトルテ、バスのヘルマン・クリスティアン・ポルスターなどが加わっています。その後何度か引っ越したりしているうちに我が家ではLPが聴ける環境ではなくなってしまい、このLPもレコード棚の奥にしまいこまれたままになってしまいました。そんなことから何とかこの曲が収録されているCDがないものかと探し回っていたところ、BERLIN ClassicsのETERNAレーベルにこの曲の入ったCD(番号:0031272BC)があることがわかり、レコード店に行くと「品切れで今すぐには入手できない」といわれ、それでも一応注文だけはしておいたところ、半年以上たって私もすっかり忘れていた頃「CDが届いた」と店から連絡がありました。演奏者は同じクノーテ指揮によるものであることは知っていたのですが、詳しい情報が記載されていなくてそれ以上のことは何もわかりませんでした。しかしながら聴いてみてびっくり、このCDはあのアルヒーフ盤とまったく同じだったのです。アルヒーフ盤の懇切丁寧なクレジットとは対照的にこのCDには簡単な曲目表示しかなく、詳細な演奏者のクレジットもありません。でも内容がまったく同じであることはすぐにわかりました。アルヒーフ盤には録音が1963年3月18~22日と書かれており、CDにはコピーライト表示が 「1963 “edel” Gesellschaft fur Produktmarketing mbH」となっています。思わぬ形で懐かしい録音のCDが手に入ったの
 です。おそらく旧東
ドイツの団体による演奏なので、もともとアルヒーフがラ
イセンスで発売したLPだったのではないでしょうか?他
の曲にも少し触れておきましょう。CDの冒頭にはイント
ラーダ第6番が置かれこれはブラス・アンサンブルで演奏
されますが、まさに導入の音楽を飾るに相応しい古式豊か
なファンファーレです。2曲目のガイヤルダ「さあ踊ろう、
跳びまわろう Tantzen und springen」は舞曲のリズムにのって「ファ・ラ・ラ・・」という言葉が何度もでてくるように、酒宴の際に歌われた音楽ではないかといわれています。ワインで饒舌になった若者が陽気に歌う恋の歌(5重唱)で、この曲だけは合唱の名曲としていくつか他のCDでも聴くことができます(ウィンズバッハ少年合唱団他)。そのほか第7曲の「うまい冷やりとしたワインで Nun lasst uns frolich sein」では酒を飲んで人生を楽しもうと歌ったり、第11曲「ああ、愛らしいひと Ach Fraulein zart」や第14曲「あらゆる快楽あらゆる喜び All lust und freud」では激しい愛の歌を歌っています。また第6曲「さわやかな五月に Im kulen mayen」は8声の二重合唱用に作られた作品で、ヴェネツィア楽派の影響がはっきりみてとれます。面白い(?)のは第15曲の連作歌曲で「a) 花嫁が寝室に行きたがらなかった」「b) 花婿が運を天にまかせて」「c)そして熱烈にこう言った」「d) このことで彼は全く笑いものだった」という4つの部分からなるドラマ仕立てになっており、新婚初夜の花婿の緊張から来る不安を生々しく描き、ちょっと滑稽で卑猥な内容の歌です。アルバム全体は独唱あり、重唱あり、ブラスや木管、ヴィオールのアンサンブルありと、とても変化に富んでいて楽しめるものです。使用楽器もすべて古楽器によっています。ルネサンスからバロックへと時代の潮流が大きく変わる時期に活躍し、ドイツ歌曲の発展に大きな貢献を果たしたハスラーの音楽を代表するアルバムとして是非お薦めしたいCDです。なお本アルバムの曲目表示はすべて皆川達夫氏によるレコード解説から引用させていただきました。このハスラー以降ドイツ歌曲は衰退期に入り、歌の主役は宗教的なコラールへと移っていきます。
です。おそらく旧東
ドイツの団体による演奏なので、もともとアルヒーフがラ
イセンスで発売したLPだったのではないでしょうか?他
の曲にも少し触れておきましょう。CDの冒頭にはイント
ラーダ第6番が置かれこれはブラス・アンサンブルで演奏
されますが、まさに導入の音楽を飾るに相応しい古式豊か
なファンファーレです。2曲目のガイヤルダ「さあ踊ろう、
跳びまわろう Tantzen und springen」は舞曲のリズムにのって「ファ・ラ・ラ・・」という言葉が何度もでてくるように、酒宴の際に歌われた音楽ではないかといわれています。ワインで饒舌になった若者が陽気に歌う恋の歌(5重唱)で、この曲だけは合唱の名曲としていくつか他のCDでも聴くことができます(ウィンズバッハ少年合唱団他)。そのほか第7曲の「うまい冷やりとしたワインで Nun lasst uns frolich sein」では酒を飲んで人生を楽しもうと歌ったり、第11曲「ああ、愛らしいひと Ach Fraulein zart」や第14曲「あらゆる快楽あらゆる喜び All lust und freud」では激しい愛の歌を歌っています。また第6曲「さわやかな五月に Im kulen mayen」は8声の二重合唱用に作られた作品で、ヴェネツィア楽派の影響がはっきりみてとれます。面白い(?)のは第15曲の連作歌曲で「a) 花嫁が寝室に行きたがらなかった」「b) 花婿が運を天にまかせて」「c)そして熱烈にこう言った」「d) このことで彼は全く笑いものだった」という4つの部分からなるドラマ仕立てになっており、新婚初夜の花婿の緊張から来る不安を生々しく描き、ちょっと滑稽で卑猥な内容の歌です。アルバム全体は独唱あり、重唱あり、ブラスや木管、ヴィオールのアンサンブルありと、とても変化に富んでいて楽しめるものです。使用楽器もすべて古楽器によっています。ルネサンスからバロックへと時代の潮流が大きく変わる時期に活躍し、ドイツ歌曲の発展に大きな貢献を果たしたハスラーの音楽を代表するアルバムとして是非お薦めしたいCDです。なお本アルバムの曲目表示はすべて皆川達夫氏によるレコード解説から引用させていただきました。このハスラー以降ドイツ歌曲は衰退期に入り、歌の主役は宗教的なコラールへと移っていきます。
2013.06.02 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬(21)
20. カンタータ第82番「我は満ち足れり」BWV82-Ⅱ前回ヴォルフガング・サヴァリッシュと小林義武両氏の訃報についてお伝えしましたが、そのすぐ後にマリー=クレール・アランさんが亡くなられた、というニュースが届きました。以前にも少し触れましたが、私はクラシックの仕事をしていた頃LPで70枚以上になる「バロック・オルガン大全集」というのを企画したことがあり、その演奏の中核を占めていたのが、このアランさんでした。北ドイツ楽派のブクステフーデとゲオルク・ベームの全曲録音、中部・南ドイツ楽派ではパッヘルベルとヨハン・ゴットフリート・ヴァルターの大半にわたる作品、そして母国フランスからはニコラ・ルベーグ、フランソワ・クープラン、ルイ・マルシャン、ギラン、ニコラ・ド・グリニー他、さらにはイタリアのパスクィーニやスペインのアントニオ・ソレルといったヨーロッパ各国のバロックを代表するオルガン音楽が含まれていました。もちろん大バッハの全集もそこには加えられています。特にバッハに関して言うと、彼女はその全集を3回録音しています。「大全集」には2度目の録音が使用されましたが、そのあとのデジタル時代になって3度目の録音が行われ、その録音ではバロック時代の歴史的名オルガンが使用されていました。私はこちらの全集はその一部しか聴いていませんが、ともかくこれだけの録音を残したオルガニストは過去に例がなく、またこれからも現れないでしょう。オルガンという楽器を身近なものに感じさせてくれたのは彼女の功績がとても大きいと思います。この楽器はピアノと同じ鍵盤楽器でありながら、一方は叩いて音を出し、こちらは鍵盤を押すことで、パイプに空気を送って音を出す(1本1本はリコーダーのような原理)という、まったく性質の違う楽器であり、しかも歴史は古代にまで遡り全盛期はバッハの時代で、ピアノはそれ以降、とまったく異質な楽器なのです。来日公演のとき一緒に食事をする機会があり、彼女にいろいろなお話をうかがいましたが、彼女が「オルガンの演奏はとにかくとても疲れるの!1回の公演を終えるともうぐったり」といった言葉が今でも耳に残っています。もちろんどんな楽器でも演奏に全身・全霊で臨めば、疲れは同じかもしれません。でもオルガンという楽器、両手・両足を使って演奏するのです。まさに楽器との格闘に近いものがあります。こんな楽器、他にはないでしょう。あの小さな体のどこにそんなエネルギーがあったのでしょう。彼女が亡くなり、とてもさびしい気持ちです。このところ巨匠と呼ばれる音楽家の訃報が相次いでいます。何か大きく歴史が動いている、そんな印象を彼女の死は与えてくれました。ご冥福をお祈りいたします。
ドイツ歌曲の歴史を遡っていくと、ミンネゼンガー(ミンネジンガーともいう)に突きあたります。もちろんそれ以前にもドイツ語の歌曲はあったと思いますが、そこから先は資料がなく、またあったとしても判読できずそれ以上には遡れません。このミンネゼンガーMinnnesangerとは、1150年代の中世ドイツに現れた貴族階級の詩人・音楽家達のことで、「吟遊詩人」などとも呼ばれますが、ドイツ語の辞書をひくとミンネMinneとは「中世特に12,3世紀に騎士が身分の高い多くは既婚の婦人に捧げた崇拝的・奉仕的な恋愛感情」(郁文堂 独和辞典)とあるとおり、「愛の歌い手」を意味していました。ドイツ音楽というと今でこそバッハやベートーヴェンをはじめクラシック音楽の中心的な存在で先進国のように見えますが、バッハ以前となるとむしろ後進国であり、このミンネゼンガーによる単旋律歌曲なども他国の歌を模倣しながら生まれたものでした。特に十字軍による交流が大きな契機となり、南フランス(フランドル)のトルバドゥール(ラング・ドック語を言語とする歌)や北フランスのトルヴェール(現在のフランス語に近いラング・ドイル語を言語とする歌)の歌を模倣しながら発展していきます。
 こうしたミンネゼンガーによる恋愛歌(ミンネザング)の創作では何人かが一同に会してお互いの歌の優劣を競い合う歌会(歌合戦)が行
われていました。これを題材にしたのが有名なヴァーグナーの歌劇「タンホイザー」です。
このオペラに登
場するミンネゼンガー達のうちヴァルター・フォン・デア・
フォーゲルヴァイデ(Walter von der Vogelweide 1170頃
~1230頃)は実在したもっとも有名な人物であり、そのほ
かヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハやタンホイザ
ー自身も実在のミンネゼンガーとして知られています。ヴ
ァルターは1205年から11年までヴァルトブルクに滞在し、
そこでヴォルフラムらとともに1207年のヴァルトブルク
城の歌合戦に参加したことがわかっています。またタンホ
イザーには6作のミンネザングが残されており、そのうち楽譜の残されている「今日は喜ばしい日Es ist hiute eyn wunnychlicher tac」は、神への祈りとともに死への憧憬を歌った作品と言われています。ヴァルターにはかなりの数の作品が残されていますが、ほとん
どが詩のみで唯一「パレスチナの歌 Palastinalied」
こうしたミンネゼンガーによる恋愛歌(ミンネザング)の創作では何人かが一同に会してお互いの歌の優劣を競い合う歌会(歌合戦)が行
われていました。これを題材にしたのが有名なヴァーグナーの歌劇「タンホイザー」です。
このオペラに登
場するミンネゼンガー達のうちヴァルター・フォン・デア・
フォーゲルヴァイデ(Walter von der Vogelweide 1170頃
~1230頃)は実在したもっとも有名な人物であり、そのほ
かヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハやタンホイザ
ー自身も実在のミンネゼンガーとして知られています。ヴ
ァルターは1205年から11年までヴァルトブルクに滞在し、
そこでヴォルフラムらとともに1207年のヴァルトブルク
城の歌合戦に参加したことがわかっています。またタンホ
イザーには6作のミンネザングが残されており、そのうち楽譜の残されている「今日は喜ばしい日Es ist hiute eyn wunnychlicher tac」は、神への祈りとともに死への憧憬を歌った作品と言われています。ヴァルターにはかなりの数の作品が残されていますが、ほとん
どが詩のみで唯一「パレスチナの歌 Palastinalied」
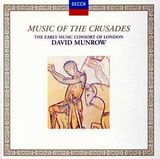 だけがオリジナルの旋律とともに完全な形で残されていま
す。この歌は「十字軍の音楽」(デイヴィッド・マンロー
指揮ロンドン古楽コンソート London UCCD-3257)という
CDで聴くことが出来ます。リュートの伴奏にのって朗々
と歌われ、まさに吟遊詩人という言葉にふさわしい雅な世
界へと誘ってくれます。歌の内容は、彼が十字軍の一員と
して聖地エルサレムに入場したときの感動と聖母マリアへの賛美を表したものです。
だけがオリジナルの旋律とともに完全な形で残されていま
す。この歌は「十字軍の音楽」(デイヴィッド・マンロー
指揮ロンドン古楽コンソート London UCCD-3257)という
CDで聴くことが出来ます。リュートの伴奏にのって朗々
と歌われ、まさに吟遊詩人という言葉にふさわしい雅な世
界へと誘ってくれます。歌の内容は、彼が十字軍の一員と
して聖地エルサレムに入場したときの感動と聖母マリアへの賛美を表したものです。このミンネゼンガーは、14世紀に入るとその担い手が次第に貴族から市民階級へと移っていき、15世紀には職人を中心とするマイスタージンガーにとって変わられます。両者とも歌の形式はAABという形(バール形式と呼ばれる)で、一つの詩節A(シュトッレン)を二度繰り返した後(二度目の終わりは少し変化させる)、新しい旋律B(アップゲザング=歌い納め)を加えるという方法で、これは同じくヴァーグナーの楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の中でハンス・ザックスによって詳しく語られています(第3幕、第2場)。ミンネザングも後期に入ると歌は多声化され、そして時代はルネサンス期へと移っていきます。
ドイツではルネサンスの時代、多声化された歌曲のなかでテノールに主旋律(多くは当時流行していた民謡などを基にした既存の旋律=定旋律)を置くいわゆる「テノールリート」と呼ばれる形式が表れます。それまでは各パートの音域がバラバラで上になったり、下になったりと入り混じっていたのですが、パートごとの役割をはっきりさせたことにより、美しいハーモニーが得られるようになったのです。このテノールリートの代表的な作曲家にハインリヒ・イザーク(Heinrich Isaac 1450頃~1517)とその弟子ルートヴィヒ・ゼンフル(Ludwig Senfl 1486頃~1543)がいます。ほとんどの楽曲は4声で書かれ、旋律はテノールにゆだねられ、他の声部はハーモニーを構成しますが、テノール以外は器楽で演奏されることもあります(バロック以前の声楽曲においては器楽のパートを別に記すという習慣がなかったため、実際に演奏する場合は演奏者にその解釈が委ねられます)。ここではイザークをとりあげてみたいと思います。
ネーデルラント楽派のイザークはフランドル(今日のオランダ、ベルギー、北フランスにまたがる地方)の生まれで、盛期ルネサンスといわれる同時代最大の作曲家ジョスカン・デ・プレ(Josquin des Prez 1440頃-1521)にも比肩する作曲家といわれています。彼の若い頃の記録がないため、どのような方法で音楽を学んだのかはわかっていません。彼が記録に現れるのは、1484年9月彼がメディチ家に仕えるためフィレンツェに向かう途中で立ち寄ったインスブルックが最初といわれ、翌年の7月からフィレンツェの聖ジョヴァンニ洗礼堂(「花の聖母」を意味する名高いサンダ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂付属の施設)の聖歌隊で活動を始めています。この聖歌隊は洗礼堂だけでなく、大聖堂や他の教会でも歌うことを義務付けられていました。彼はメディチ家の黄金時代を築き、ボッティチェリやミケランジェロのパトロンとしても知られるロレンツォ・イル・マニフィコの手厚い庇護を受け、ここでイタリア歌曲やミサ曲、モテットなどを書いています。しかしながら1492年にロレンツォが早逝しメディチ家の独裁や腐敗を糾弾していたジローラモ・サヴォナローラが支配するようになると、イザークもまたフィレンツェにはいられなくなり、1496年彼はウィーンに移り、翌年神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアンⅠ世の招きで今度はハプスブルグ家に仕えることとなり、その宮廷作曲家に就任しました。1515年に再びフィレンツェに戻るまでここで充実した作曲活動を行い、多くの名作が生まれています。
イザークはフランドルに生まれ、おそらくそこで音楽の勉強や素養を身につけたと思います。彼の音楽には宗教曲はもちろんですが、世俗曲の分野でもフランスのシャンソン、イタリアのフロットラ(当時流行した上声部に旋律を置く3~4声部の世俗歌の総称)、そしてドイツのリートというようにヨーロッパの中心的な国々の異なる文化を吸収しており、そのことが多様な音楽を生み出し、時の権力者からも慕われたのではないでしょうか。特に後進的なドイツの音楽に、当時中心的な役割を果たしていたネーデルラント(フランドル)楽派の新風やイタリア・ルネサンスの息吹を吹き込んだことはこの後大きな影響をド
 イツにもたらしたのです。彼の世俗音楽を集め
た「インスブルックよさらば~ハインリヒ・イザーク、シャ
ンソン・フロットラ・リート集」(ロンドン中世アンサンブル、
オワゾリール、UCCD-3259)というCDで彼のその多才な
音楽を聴くことが出来ます。ここにはフランス語のシャンソ
ン、イタリア語のフロットラ、そしてドイツ語によるリート
と、彼の世俗歌曲のすべてのスタイルが収められています。
なかでもタイトル曲にもなっている名曲「インスブルックよさようなら」の美しさは格別です。この曲がいつ頃書かれたのか正確には知りませんが、記録上彼がインスブルックを訪れたことがわかっているのは、1484年9月、1500年2月、そして1501年12月の3回で、おそらくこのいずれかのときで、ドイツ語の歌曲であることを考えれば後者の時期だと思われますが、ただこの地には1490年以来皇帝の館も置かれていたので、それ以外にもしばしば訪れていた可能性があります。また一つ付け加えておくと、この曲そのものはソプラノ―ご紹介したCDではカウンターテノール―に主旋律が置かれていて、ここで触れてきた「テノールリート」とは異なっています。またその旋律もイザーク自身のものではなく、15世紀半ばから歌われていた民謡を素材にしたものと言われています。この曲は後にパウル・ゲルハルト(Paul Gerhardt 1607 - 76)によってコラール「おお世よ、ここに汝の生命を見よO Welt, sieh hier dein Leben」に編曲され、マタイ受難曲やヨハネ受難曲などに使用されていることはこれまでにもご紹介しました。「讃美歌21」の295番や569番でご存知の方もあるかと思います。
イツにもたらしたのです。彼の世俗音楽を集め
た「インスブルックよさらば~ハインリヒ・イザーク、シャ
ンソン・フロットラ・リート集」(ロンドン中世アンサンブル、
オワゾリール、UCCD-3259)というCDで彼のその多才な
音楽を聴くことが出来ます。ここにはフランス語のシャンソ
ン、イタリア語のフロットラ、そしてドイツ語によるリート
と、彼の世俗歌曲のすべてのスタイルが収められています。
なかでもタイトル曲にもなっている名曲「インスブルックよさようなら」の美しさは格別です。この曲がいつ頃書かれたのか正確には知りませんが、記録上彼がインスブルックを訪れたことがわかっているのは、1484年9月、1500年2月、そして1501年12月の3回で、おそらくこのいずれかのときで、ドイツ語の歌曲であることを考えれば後者の時期だと思われますが、ただこの地には1490年以来皇帝の館も置かれていたので、それ以外にもしばしば訪れていた可能性があります。また一つ付け加えておくと、この曲そのものはソプラノ―ご紹介したCDではカウンターテノール―に主旋律が置かれていて、ここで触れてきた「テノールリート」とは異なっています。またその旋律もイザーク自身のものではなく、15世紀半ばから歌われていた民謡を素材にしたものと言われています。この曲は後にパウル・ゲルハルト(Paul Gerhardt 1607 - 76)によってコラール「おお世よ、ここに汝の生命を見よO Welt, sieh hier dein Leben」に編曲され、マタイ受難曲やヨハネ受難曲などに使用されていることはこれまでにもご紹介しました。「讃美歌21」の295番や569番でご存知の方もあるかと思います。ここでこの時代のドイツ歌曲を語る場合、もういくつか触れておかなければならないことがあります。時代は少しイザークの前に遡りますが、1460年頃ニュルンベルクで写された44曲からなる「ロッハマー歌曲集」や、ヘルマン・シェーデルという人が集めた128曲からなる「シェーデル歌曲集」(1460年頃)、グローガウ(現ポーランド領)で作られた224曲(70曲のドイツ歌曲を含む)からなる「グローガウアー歌曲集」(1488年)などの歌曲集があり、これらは規模の大きなものとしてはもっとも古いドイツの歌曲本と言われています。ほとんどが作者不詳で多声のテノールリートの様式で書かれていますが、テノール以外のパートには歌詞がつけられていなかったりで、演奏する際テノールの定旋律以外は楽器で奏されたのでは、ともいわれています。ミンネゼンガーが衰退し、貴族階級から職人によるマイスタージンガーへと移行していくことは前に触れましたが、マイスタージンガーそのものは音楽的にも時代遅れでそれほどの価値はなく、むしろこれらの歌曲が重要といわれています。自由都市の発展とともに音楽の作り手も、台頭してきた市民階級へと変わり、歌の内容も恋愛歌が多いとはいえもっと市民的な叙情歌曲へと変わっていきます。後にブラームスなどもこうした歌曲から旋律を引用したとも言われています。またグローガウアー歌曲集には、同時に二つ以上の旋律や歌詞(多くは当時流行していた音楽)を絡ませながら歌う「クオドリベット」(言葉の意味は「お気に召すまま」)が何曲か含まれ、こうした音楽はゼンフルによってさらに発展し、これが後のバッハのゴルトベルク変奏曲(第30変奏)へと受け継がれていくのです。
こうしてテノールリートはドイツにおいて音楽ジャンルの主要な位置を占めるようになり、15世紀後半イザークの同時代人で多くのドイツ歌曲を残した盲目のオルガニスト、パウル・ホーフハイマー(Paul Hofhaimer 1459-1537)やトマス・シュトルツァーThomas Stolzer ? -1526)らによって4声の多声リートが確立されます。これらの音楽は東ヨーロッパにまで影響を及ぼしたといわれています。特にホーフハイマーの音楽は単純ながらその情感と力強さにおいて、「ゲルマン魂」などと形容されたりします。こうした中でネーデルラントのイザークによって新しい風が吹き込まれてくるのです。
テノールリートはイザークの弟子ゼンフルによって上記の二つの流れが統合され、発展します。特に16世紀になって楽譜の印刷技術が確立されると多くの歌曲集が出版され、一般の家庭にも浸透していきます。ゲゼルシャフトリートと呼ばれる仲間が集まったときに歌う歌曲が生まれたのもこの頃です。ゼンフルの時代テノールリートはその最盛期を迎えますが、16世紀の半ば、ネーデルラント楽派による侵略を激しく受けるようになりその終焉を迎えます。そのネーデルラント楽派最大の作曲家がバイエルン宮廷大聖堂楽長のオルランド・ディ・ラッソ(オルランドゥス・ラッスス Orlando di Lasso 又はOrlandus Lassus 1532-94)です。彼はイタリアのパレストリーナと並ぶルネサンス末期を飾る大作曲家として知られ、宗教曲のほか多くのリート作品も残しています。ただその音楽自体は既にイタリアからの影響(自由詩に基づくマドリガーレや「田舎の歌」を意味する陽気なヴィラネッラ等の歌)を色濃く反映しているのです。さらにその音楽はラッソの弟子たちを通じてドイツの音楽に深く浸透していきます。そうした弟子たちにレオンハルト・レヒナーやヨハン・エッカルトなどがおり、さらに弟子たちを通じてハンス・レオ・ハスラーやミヒャエル・プレトリウスといった重要な作曲家に影響を及ぼしていくのです。
廃れてしまったテノールリートはというと、そのスタイルはドイツに新しく誕生した「コラール」に受け継がれていきます。コラールもまた成立当初こそ単旋律のユニゾンで歌われていましたが、多声化されるとその定旋律はテノールに置かれるようになりました。現在のようにソプラノでそれが歌われるようになるのは16世紀末になってからのことです。
ちょっと駆け足で歌曲の歴史を振り返ってきましたが、短い文章でその全体像を捉えるのはちょっと無理があるかもしれません。いろいろ間違いや説明不足があるかもしれませんがなにとぞご容赦下さい。またルネサンス後期からについては次回にしたいと思います。
なおイザークの「インスブルックよさようなら」の歌は名曲だけに数多くのCDに収録されています。ここにご紹介したCD以外では「マクシミリアンⅠ世の宮廷音楽」(アーノンクール指揮ウィーン少年合唱団他 Archiv POCA-3048)もあり、これにはジョスカンやゼンフルの音楽も収録されています。ただ合唱の素晴らしさと言う点では、ちょっと人数が多そうなのが難点ですが、ウィンズバッハ少年合唱団によるアカペラの合唱(カメラータ・トウキョウ 25CM-397)が素晴らしいハーモニーを聴かせてくれます。更に変わったところ
 ではあのミュージカル映画「サウンド・
オブ・ミュージック」で知られるトラップ・ファミリーに
よる歌唱(BMG BVCF-35016)もあります。録音は1940年
頃と古く、歌もどことなく素人っぽいところもありますが、
ここには他に民謡やドイツ・ルネサンス期の歌、そして我
が家のCDコレクションでは唯一ホーフハイマーの歌曲(
解説書には英文、邦文ともホトハイマーと記されているが
誤り)も収録されており、当時の歌がいかに家庭に浸透し、そして歌い継がれてきたのかを知ることが出来るとても興味深いCDです。またこの旋律がゲルハルトのコラールに使用されたことはすでに触れたとおりですが、そのちょうど中間に位置するようにレオンハルト・レヒナー(Leonhard Lechner 1510頃-1606)がこの定旋律を使用して「ああ愛よ、おまえとわかれねばならぬ Ach Lieb, ich muss dich lassen」を書いており、イザークのタイトルと比較していただければわかるように、インスブルックを「愛」に置き換えた替え歌になっています。deutsche harmonia mundiの「クラシックの世紀~耳による西洋史 Vol.3」(BVCD-7320 ユングヘーネル指揮カントゥス・ケルン)というCDに収録されており、リュートの伴奏で歌われるとても味わい深い歌です。ただ歌詞も、曲目解説も付されていないためそれ以上詳しいことはわかりません。「讃美歌21略解」(日本基督教団出版局)によると、この旋律は1505年には讃美歌として使用されていた(ルターの宗教改革以前になる)そうなので、かなり古くから定旋律としてさまざまな人によってつくられていたのかもしれません。
ではあのミュージカル映画「サウンド・
オブ・ミュージック」で知られるトラップ・ファミリーに
よる歌唱(BMG BVCF-35016)もあります。録音は1940年
頃と古く、歌もどことなく素人っぽいところもありますが、
ここには他に民謡やドイツ・ルネサンス期の歌、そして我
が家のCDコレクションでは唯一ホーフハイマーの歌曲(
解説書には英文、邦文ともホトハイマーと記されているが
誤り)も収録されており、当時の歌がいかに家庭に浸透し、そして歌い継がれてきたのかを知ることが出来るとても興味深いCDです。またこの旋律がゲルハルトのコラールに使用されたことはすでに触れたとおりですが、そのちょうど中間に位置するようにレオンハルト・レヒナー(Leonhard Lechner 1510頃-1606)がこの定旋律を使用して「ああ愛よ、おまえとわかれねばならぬ Ach Lieb, ich muss dich lassen」を書いており、イザークのタイトルと比較していただければわかるように、インスブルックを「愛」に置き換えた替え歌になっています。deutsche harmonia mundiの「クラシックの世紀~耳による西洋史 Vol.3」(BVCD-7320 ユングヘーネル指揮カントゥス・ケルン)というCDに収録されており、リュートの伴奏で歌われるとても味わい深い歌です。ただ歌詞も、曲目解説も付されていないためそれ以上詳しいことはわかりません。「讃美歌21略解」(日本基督教団出版局)によると、この旋律は1505年には讃美歌として使用されていた(ルターの宗教改革以前になる)そうなので、かなり古くから定旋律としてさまざまな人によってつくられていたのかもしれません。
2013.03.19 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑳
19. カンタータ第82番「我は満ち足れり」BWV82-Ⅰつい先日新聞を読んでいたら、名指揮者ヴォルフガング・サヴァリッシュ氏が亡くなられたという訃報が掲載されていました。彼にはシューマンの交響曲全集などとびきりの名演奏があり、またもうかれこれ30年以上前のことになりますが、彼の指揮によるベートーヴェンの交響曲の録音に携わったこともあり、悲しみとともにその当時のことがとても懐かしく思い出されました。そしてその記事の横に少し小さな扱いでしたが、バッハ研究家小林義武氏の訃報が合わせて掲載されていたことに気づかれた方もあると思います。私は残念ながら直接小林氏にお会いしたり、お話ししたりといった機会には恵まれませんでした。私がクラシックの仕事にかかわっていた頃、氏はまだドイツで仕事をされていて、バッハの生誕300年記念に沸き返る当時でさえ、失礼ながら日本ではまったくといっていいほど知られていなかったと思います。1987年に発売されその年のレコード・アカデミー賞にも輝いたレオンハルト指揮による「バッハ:ロ短調ミサ(deutsche harmonia mundi BVCD-38119/20)」の解説書で私は初めて氏の名前を目にしたのですが、解説(著者はワルター・ブランケンブルク)にはバッハが死の直前に没頭していたのが「フーガの技法」ではなく「ロ短調ミサ」の作曲であったという新しい研究成果が紹介されており、そこには「(ゲッティンゲンのコバヤシ・ヨシタケ氏の、最近の発見による)」と書かれていました。つまり翻訳者(古学評論家として知られた故佐々木節夫氏)でさえ名前の表記を知らなかったのです。氏が日本に帰国して活動を始めたのが1991年ということで、それからの活躍は目覚しいものがあります。というよりドイツ時代にゲッティンゲンの「ヨハン・セバスティアン・バッハ研究所 Johann Sebastian Bach-Institut Gottingenn」の研究員としてすでに輝かしい業績を残されていて、バッハ関係の本を読んでいると、多くの書物の中に彼の論文や発言(講演)が引用されているのを目にします。わが国の数あるバッハ研究者の中でももっとも国際的な貢献をした学者ではないでしょうか?いくつか例をあげることもできますが、それらは私がここでとりあげるよりも今後音楽雑誌などで紹介されるでしょうから、それらをお読みいただけるとより正確に彼の業績を知ることができると思います。またもっと関心のある方は辻壮一賞を受賞した「バッハ伝承の謎を追う」(春秋社 1995)や、「バッハ復活―19世紀市民社会の音楽活動」(春秋社 1997)などを読まれるといいでしょう。興味深い記事が満載されています。著書「バッハとの対話~バッハ研究の最前線」(小学館 2002)の中では有名なオルガン曲「トッカータとフーガ ニ短調BWV565」の偽作説なども紹介されており、とても面白く読ませて頂きました。日本にとってかけがえのない研究者を失ったことは残念でなりません。心よりご冥福をお祈りいたします。
さて私がこのテーマでカンタータをとりあげてからもう2年半が経過してしまいました。その間わずか4曲のカンタータしかとりあげることができませんでした。私の書くスピードが遅いことがその一番の原因ですが、一介の古楽ファンにしかすぎない私が、できるだけ多くの情報を盛り込もうと様々なことを調べながら書いていくのはとても骨の折れる作業です。ただそれは同時に大きな楽しみでもありました。バッハの教会カンタータは何しろおよそ200曲もあるわけで、今回の内容に即した作品もまだまだたくさんあります。しかしながら同じテーマで書いていると次第にマンネリ化してくることに気がつき、そんなわけでこのテーマについてはこの作品を最後にしようと思います。特にこのタイトルともなったBWV161「来たれ、甘き死のときよ」をとりあげられなかったのは残念ですが、またの機会にしたいと思います。
このBWV82「我は満ち足れりIch habe genug」ですが、そもそもはこのカンタータのために今回のテーマを考えたといっても過言ではありません。私がバッハのカンタータの中で一番好きな作品です。3年前にお腹に怪しい影が見つかり、検査を重ねているとき、場所が悪かったこともあり、つとめて平静を装ってはいたもののその不安と恐怖に対するおののきはとても尋常なものとは言えず、それは経験したことのない人にはわからないと思います。そんななかで私はバッハのカンタータにのめりこんでいき、多くの作品を聴いていくうちにこの作品に出会いました。このカンタータの中心に置かれた第3曲「まどろめ、疲れた目よ」を聴くと、どうしてバッハはこんなに優しい音楽が書けるのだろうと思い、この作品の虜になりました。この第3曲を「子守唄」という人がありますが、確かにこれは人を眠りに誘う音楽です。でもそれはただの眠りではなく永遠の眠りです。こんなことを言うと不謹慎と、またあるいはナルシストともいわれるかもしれませんが、私がこの世と別れるときにはこんな曲に包まれながら逝きたい、と思ったほどです。そしてさまざまな歌手による演奏を聴きましたが、結論から言うとマティアス・ゲルネによるものがその情感・歌唱力ともに図抜けて素晴らしいものでした。
このカンタータには合唱もなければ、コラールもありません。あるのはバスのソロだけです。つまりいわゆるソロ・カンタータと呼ばれるものですが、私はこれは最上級の「ドイツ・リート」だと思っています。確かに宗教的な内容であり、またオーケストラ伴奏なので、これをリートという人はいません。厳格なドイツ・リート愛好者は「リートとはシューベルト以降のドイツ歌曲」をいい、なおかつその誕生は1814年10月19日(シューベルトが「糸を紡ぐグレートヒェン」を作曲した日付)である、とさえ言います。彼らにとってはベートーヴェンの歌曲でさえリートではないのです。確かにリートを特定のジャンルとして扱うような場合はこうした考えもわからなくはありません。でもリートLiedはそもそもドイツ語による歌曲であり、その名称はずっと古くから使われてきたのです。ピアノの伴奏でなければならない、ということもないと思います。このバッハのカンタータはれっきとしたリートであると思います。ただ用語の混乱を避ける意味で、ここでは以後「ドイツ歌曲」と表記することにします。
よくバッハやヘンデルが生きた18世紀前半は歌曲にとって「不毛の時代」などとも言われます。確かにバッハを例にとっても歌曲として知られているのは「シェメッリ歌曲集」ぐらいで、おまけにその歌曲集もどこまでがバッハの真作なのか議論のあるところです(注)。またこれも詩は宗教的な内容によっています。あと歌曲というと、5曲からなる宗教歌曲集(BWV519~523)があり、さらに「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集第2巻」に収められたいくつかの歌曲(これもほとんどは他人の作った曲)もあります。
バッハはこのカンタータをとても気に入っていたと思われ、このバスのためのソロ・カンタータをソプラノ用、さらにはアルト用にも編曲しています。そしてさらにこの作品の中核でもある第3曲を、その前におかれたレチタティーヴォとともに上記「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集第2巻」(1725~)に第34番と第38番と2度にわたって収録しており、通奏低音の伴奏だけで家庭でも簡単に歌えるように編曲もしています。これほど優れたドイツ歌曲を他に探すことは私にはちょっと難しいことのように思います。是非多くの人に聴いていただきたいカンタータです。次回バッハにいたるまでのドイツ歌曲の歴史について簡単に触れてみたいと思います。
注) ライプツィヒ近郊の小村ツァイツのカントルだったゲオルク・クリスティアン・シェメッリ(Georg Christian Schemelli 1680-1762)がバッハの協力を得て1736年に出版した954編からなる通奏低音つき宗教歌曲集ですが、多くは歌詞のみで楽譜が付されているのは69曲のみ。そのうちバッハの真作として現在判明しているのはBWV452「Dir, dir Jehovah, will ich singen(エホバよ、汝に向かって歌わん)」、BWV478「Komm, susser Tod, komm, sel’ge Ruh’!(来たれ、甘き死よ、来たれ、至福の安らぎよ)」 そしてBWV505「Vergiss mein nicht, vergiss meinn nicht(我を忘れたもうな、我汝を忘れまじ)」の3曲のみで、多くは通奏低音をバッハが手直しした、とされている。
2013.01.15 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑲
18. カンタータ第4番「キリストは死の縄目につながれたり」BWV4―ⅢここからはCDとその演奏について触れたいと思いますが、前回ご紹介した作品についてのさまざまな学説は比較的新しいものがほとんどで、古い有名な著作からの引用がまったくなかったことに気づかれた方もおられると思います。今から100年以上も前に書かれたシュヴァイツアーの本なども、古くなったとはいえいまだにその価値を失ってはいない、と私は思っています。でもそのシュヴァイツアーにしても、また20世紀後半に入って書かれたガイリンガーの本にしても、このカンタータに関する言及は他の初期のカンタータと比べると非常に少ないのです。コラール変奏の様式という他のカンタータとはまったく違う楽曲で、比較対照すべきものもなく、また資料そのものも少なかったのでしょう。演奏者にとってもそれは同じ状況だったようです。 このカンタータは昔からよく知られた名曲で、CDもかなり多くの団体が録音しています。それに比べると我が家のコレクションは非常に貧弱で頼りないものですが、それでも一応演奏スタイルの変遷は辿ることができるように思います。例によって録音年代順に列挙します。
①フリッツ・レーマン指揮 バッハ祝祭管弦楽団以上ですが、ここに掲げたほとんどのCDは既に他のカンタータのところでもご紹介しておりその傾向は同じなので、ここでは重複を避けるためこのカンタータ特有の問題に絞って話を進めていきたいと思います。
ヘルムート・クレプス(S)、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(B)、
フランクフルト国立音楽大学合唱団
ARCHIV POCA-2603 (録音:1950年)
②フリッツ・ヴェルナー指揮 プフォルツハイム室内管弦楽団
ハイルブロン・ハインリヒ・シュッツ合唱団
ERATO WPCS-11771 (録音:1961年)
③カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ合唱団&管弦楽団
ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(B)
ARCHIV F20A-20067 (録音:1968年)
④ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 イングリッシュ・バロック・ソロイスツ
モンテヴェルディ合唱団
deutsche harmonia mundi(日本原盤) BVCD-38129 (録音:1980年)
⑤アンドルー・パロット指揮 タヴァナー・コンソート・アンド・プレーヤーズ
エミリー・ヴァン・エヴェラ(S)、キャロライン・トレヴァー(A)、
チャールズ・ダニエルズ(T)、デヴィッド・トーマス(B)
Virgin Classics 7243 5 61647 2 7 (2枚組) (録音:1993年)
⑥トン・コープマン指揮 アムステルダム・バロック管弦楽団&合唱団
バルバラ・シュリック(S)、カイ・ヴェスル(A)、ギ・ドゥ・メ(T)、クラウス・メルテンス(B)
Erato WPCS-4717 (3枚組) (録音:1994年)
⑦鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン、コンチェルト・パラティーノ
栗栖由美子(S)、太刀川昭(A)、片野耕喜(T)、ペーター・コーイ(B)
BIS (King International) KKCC-2195 (録音:1995年)
⑧コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン
ヨハンナ・コズロウスキー(S)、エリーザベト・パピエン(A)、ゲルト・テュルク(T)、
シュテファン・シュレッケンベルガー(B)
harmonia mundi FRANCE HMC-901694 (録音:1999年)
(1)合唱か、ソロか
前回書いたように、この曲でバッハは合唱で歌うべきか、ソロで歌うべきか、楽譜に指定していないため、それは指揮者の判断に委ねられることになります。
 上記のうちパロット盤⑤とユングヘーネル盤⑧は、各パートすべて一人の演奏なので、
4声の合唱部分も単声による部分も違いが問題になること
はありません。私はこの方法を好みませんが、18世紀初
期には行われていたという記述もあってバッハ初期のカ
ンタータには当然こうした選択はありうると思います。
ただそうした歌唱形態の是非は別にしてこのパロット
盤、実に素晴しいのです。声のアンサンブルの愉しみ
が聴き手にダイレクトに伝わってきます。歌好きの4人が集まって、すぐその場でこんなアンサンブルができたらさぞ素敵なことだろうと思います。そんなことを感じさせてくれる演奏には滅多に出会えません。
上記のうちパロット盤⑤とユングヘーネル盤⑧は、各パートすべて一人の演奏なので、
4声の合唱部分も単声による部分も違いが問題になること
はありません。私はこの方法を好みませんが、18世紀初
期には行われていたという記述もあってバッハ初期のカ
ンタータには当然こうした選択はありうると思います。
ただそうした歌唱形態の是非は別にしてこのパロット
盤、実に素晴しいのです。声のアンサンブルの愉しみ
が聴き手にダイレクトに伝わってきます。歌好きの4人が集まって、すぐその場でこんなアンサンブルができたらさぞ素敵なことだろうと思います。そんなことを感じさせてくれる演奏には滅多に出会えません。 ヴェルナー盤②とガーディナー盤④は、すべて合唱による演奏です。したがって単声に
よる歌も斉唱によって歌われています。ガーディナー
盤の解説書に、中央に置かれた合唱(第5曲)のみ
Soloquartettという表記があり、これはここだけ4人で
歌われていることを意味していると思われますが、聴いた
限りそういう風には聴こえません。おそらく各声部とも
3~4人で歌われているように思います。
ヴェルナー盤②とガーディナー盤④は、すべて合唱による演奏です。したがって単声に
よる歌も斉唱によって歌われています。ガーディナー
盤の解説書に、中央に置かれた合唱(第5曲)のみ
Soloquartettという表記があり、これはここだけ4人で
歌われていることを意味していると思われますが、聴いた
限りそういう風には聴こえません。おそらく各声部とも
3~4人で歌われているように思います。レーマン盤①、コープマン盤⑥、そしてBCJ盤⑦は、 第2、第5そして終曲の第8曲が合唱で歌われ、他の楽 章はソロや二重唱で歌われます。これがもっともオーソドックスな方法で、序奏のあと、合唱―二重唱―独唱―合唱―独唱―二重唱―合唱というきれいなシンメトリー構造を形作ります。ただコープマン盤とBCJ盤が二重唱もソリストによるデュエットを採用しているのに対して、レーマン盤は合唱による二重唱になっています。このあたりは時代の流れを感じます。
最後にリヒター盤②が残ってしまいましたが、この演奏については少し問題があります。
 基本的にはヴェルナー盤同様合唱によっていますが、第6曲(第5節)のみバスのソロにしているのです。何が問題かというと、もうお分かりかと思いますがこれではバッハ初期カンタータの基本的な特徴であるシンメトリー構造
が失われているからです。もちろん演奏の方法とその質は
別ですが、「バッハ演奏の大家」と言われるリヒターも、稀
有のバス歌手(バス・バリトン)を前にその形容詞をはずさな
ければならなかったのか、或いははじめからそんなことに
配慮するつもりはなかったのか知る由もありません。ちな
みにフィッシャー=ディースカウのソロについて言うと、
私はモノラル録音ながらレーマン盤の方が好きです。まだ20代半ばの録音で、多少ピッチが不安定に感じるところもありますが、微妙なニュアンスに富み、溌剌とした輝きを感じます。
基本的にはヴェルナー盤同様合唱によっていますが、第6曲(第5節)のみバスのソロにしているのです。何が問題かというと、もうお分かりかと思いますがこれではバッハ初期カンタータの基本的な特徴であるシンメトリー構造
が失われているからです。もちろん演奏の方法とその質は
別ですが、「バッハ演奏の大家」と言われるリヒターも、稀
有のバス歌手(バス・バリトン)を前にその形容詞をはずさな
ければならなかったのか、或いははじめからそんなことに
配慮するつもりはなかったのか知る由もありません。ちな
みにフィッシャー=ディースカウのソロについて言うと、
私はモノラル録音ながらレーマン盤の方が好きです。まだ20代半ばの録音で、多少ピッチが不安定に感じるところもありますが、微妙なニュアンスに富み、溌剌とした輝きを感じます。(2) オーケストラの編成とピッチは
古い録音(①~③)に共通しているのは、管楽器を追加した1725年のライプツィヒ再々演版を使用していることです。そして古楽器を使用しているわけではありませんのでツィンクは音色的に近いトランペットで代用していますが、ヴェルナー盤のみ解説書の曲目表にはツィンクと記されています。当然ピッチは現代の標準ピッチによっています。
すべてのパートを一人で演奏しているパロット盤とユングヘーネル盤は当然ながら初期のスタイルに従って管楽器の補強を排除しています。その分ポジティブ・オルガンが効果的に使用されています。ただしピッチという点からみてみると、パロット盤は現代の標準ピッチを採用しており、ユングヘーネル盤は半音低いカンマートーンで演奏しています。これら両者のピッチレベルでは当然初期カンタータのスタイルとは異なったものとなり、矛盾が生じます。そうであればバッハの嘆願書に従って合唱は複数のほうが望ましい、ということにもなるのでは。
次にガーディナー盤ですが、こちらもピッチはカンマートーンを採用していて現代より半音低くなります。オーケストラの編成については解説書に記載がないので正確なことはわかりませんが、聴感上からトロンボーンが追加されているのがはっきりわかります。そうなると1725年の再々演版に符合し、これはこれで整合性が保たれています。いつもながら合唱のすばらしさは特筆ものです。
残るコープマン盤とBCJ盤ですが、
 当然ながら両者ともコアトーンによる現在より半音高いピッチで演奏しています。つまり初期カンタータとして本来採用するべきピッチで演
奏していることになります。私の手持ちの8種類の
CDのなかでコアトーンを採用しているのはこの2種類だ
けでした。では楽器編成は?というと両者で違いが生じま
す。コープマンはこの曲の演奏にあたって、クリストフ・
ヴォルフとの共著「バッハ=カンタータの世界 第1巻」
(礒山雅訳 東京書籍)の中で「BWV4、150、196などの場
合、これらが一本ずつの弦楽器編成で演奏されることは、
音楽的な理由から明白である。作曲の仕方が独奏楽器的なのだ。」と書いているとおり、すべてのパートを1本(挺)の楽器で演奏しています。これに対しBCJ盤では1パート2~3人の弦楽器編成でオーケストラを構成しています。そしてさらにコープマンは第3曲の二重唱だけコルネットとトロンボーンを加えて声楽を補強しています。聴感上ではほとんど目立たないので部分的に使用したのかとも思いますが、これに関する説明は一切ありません。
当然ながら両者ともコアトーンによる現在より半音高いピッチで演奏しています。つまり初期カンタータとして本来採用するべきピッチで演
奏していることになります。私の手持ちの8種類の
CDのなかでコアトーンを採用しているのはこの2種類だ
けでした。では楽器編成は?というと両者で違いが生じま
す。コープマンはこの曲の演奏にあたって、クリストフ・
ヴォルフとの共著「バッハ=カンタータの世界 第1巻」
(礒山雅訳 東京書籍)の中で「BWV4、150、196などの場
合、これらが一本ずつの弦楽器編成で演奏されることは、
音楽的な理由から明白である。作曲の仕方が独奏楽器的なのだ。」と書いているとおり、すべてのパートを1本(挺)の楽器で演奏しています。これに対しBCJ盤では1パート2~3人の弦楽器編成でオーケストラを構成しています。そしてさらにコープマンは第3曲の二重唱だけコルネットとトロンボーンを加えて声楽を補強しています。聴感上ではほとんど目立たないので部分的に使用したのかとも思いますが、これに関する説明は一切ありません。 一方BCJ盤は、コアトーンで初期のスタイ
ルを採っていながら、第2、3、8曲でコルネット、トロン
ボーン3本による補強を行っており、つまり1725年の再々
演版によるオーケストラ編成となっているのです。このBCJ
盤は彼らのバッハ=カンタータ全曲録音の第一弾で最初に
録音されたものだったため、まだ解説書の編集方針も定まっ
ていなかったのか鈴木雅明氏による制作ノートなども掲載
されていません。またその後に出版された鈴木氏の本などにもBWV4に関する記述はわずかしか見られません。それどころか「わが魂の安息、おおバッハよ!」(2004年 音楽之友社)には「トロンボーンが加えられたのは1723年と24年の再演のとき」と明らかに間違った記述をしているほどです。年号の間違いは別にして、トロンボーンの追加がライプツィヒ時代だとわかっていて何故初期カンタータとしての録音にこれを加えたのか、その説明は欲しいところです。ちなみにコープマンは異稿としてツィンクと3本のトロンボーンを加えた1725年版の編成による演奏(第1、2、3&8曲のみ)も追加で同じCDに収録しています。但し、こちらは本来カンマートーンを採用すべきところ、同じコアトーンの演奏になってしまっています(でもこれは同じCDに収録しているため、コアトーン用に合わせた弦楽器の弦の張替えなど、困難を伴うので致し方ないことかと思います)。おまけに解説書には「3本のトロンボーン」とすべきところを、「3本のトランペット」と記載するなど、明らかにミス・プリントだとは思いますがいろいろ混乱しているようです。混乱ついでに楽譜のことにも触れておきますと、BWV4の新バッハ全集版のコピーライト表示が1985年になっていますので、そのときに出版されたものだと思いますが、前回書いたように私のポケット・スコア(Study Scores)には、デュルによる序文の日付が1995年9月と書かれています。もっとも信頼すべき楽譜の出版社がミスということは考えられないので、ポケット・スコアが遅れて出版され、その際書かれた序文なのか、あるいはそのときに改訂されたものなのか判然としません。このあたり一度学者の方にはっきりさせていただけるとありがたいと思います。
一方BCJ盤は、コアトーンで初期のスタイ
ルを採っていながら、第2、3、8曲でコルネット、トロン
ボーン3本による補強を行っており、つまり1725年の再々
演版によるオーケストラ編成となっているのです。このBCJ
盤は彼らのバッハ=カンタータ全曲録音の第一弾で最初に
録音されたものだったため、まだ解説書の編集方針も定まっ
ていなかったのか鈴木雅明氏による制作ノートなども掲載
されていません。またその後に出版された鈴木氏の本などにもBWV4に関する記述はわずかしか見られません。それどころか「わが魂の安息、おおバッハよ!」(2004年 音楽之友社)には「トロンボーンが加えられたのは1723年と24年の再演のとき」と明らかに間違った記述をしているほどです。年号の間違いは別にして、トロンボーンの追加がライプツィヒ時代だとわかっていて何故初期カンタータとしての録音にこれを加えたのか、その説明は欲しいところです。ちなみにコープマンは異稿としてツィンクと3本のトロンボーンを加えた1725年版の編成による演奏(第1、2、3&8曲のみ)も追加で同じCDに収録しています。但し、こちらは本来カンマートーンを採用すべきところ、同じコアトーンの演奏になってしまっています(でもこれは同じCDに収録しているため、コアトーン用に合わせた弦楽器の弦の張替えなど、困難を伴うので致し方ないことかと思います)。おまけに解説書には「3本のトロンボーン」とすべきところを、「3本のトランペット」と記載するなど、明らかにミス・プリントだとは思いますがいろいろ混乱しているようです。混乱ついでに楽譜のことにも触れておきますと、BWV4の新バッハ全集版のコピーライト表示が1985年になっていますので、そのときに出版されたものだと思いますが、前回書いたように私のポケット・スコア(Study Scores)には、デュルによる序文の日付が1995年9月と書かれています。もっとも信頼すべき楽譜の出版社がミスということは考えられないので、ポケット・スコアが遅れて出版され、その際書かれた序文なのか、あるいはそのときに改訂されたものなのか判然としません。このあたり一度学者の方にはっきりさせていただけるとありがたいと思います。(3) 終曲の合唱とまとめ
終曲の合唱は、1725年の再々演のときに簡潔な4声のコラールに差し替えられたものだということは、
 前回触れたようにデュルをはじめ多くの学者が指摘している事柄です。もとの姿がどんなものだったのかはもはや不明なので、
現在の出版された楽譜どおりに歌うのがもっとも一般的で
す。ただこれも前回ご紹介したように、何人かの学者は第
2曲の合唱の音楽がそっくりそのまま歌詞を変えて使用さ
れていた可能性についても言及していました。私の手持ち
のCDの中に、この学説に準拠して演奏しているものがひ
とつだけありました。それは⑧のユングヘーネル盤です。
この演奏を聴いていると、まったく違和感を感じません。それどころか完璧なシンメトリーとなるので、確かにこれも演奏上の一つの解決法だと思います。
前回触れたようにデュルをはじめ多くの学者が指摘している事柄です。もとの姿がどんなものだったのかはもはや不明なので、
現在の出版された楽譜どおりに歌うのがもっとも一般的で
す。ただこれも前回ご紹介したように、何人かの学者は第
2曲の合唱の音楽がそっくりそのまま歌詞を変えて使用さ
れていた可能性についても言及していました。私の手持ち
のCDの中に、この学説に準拠して演奏しているものがひ
とつだけありました。それは⑧のユングヘーネル盤です。
この演奏を聴いていると、まったく違和感を感じません。それどころか完璧なシンメトリーとなるので、確かにこれも演奏上の一つの解決法だと思います。さていろいろ形式的な細かい事柄にこだわってCDの演奏についてみてきましたが、もちろん「こうでなければいけない」などと言うつもりはありません。むしろいろいろな違いについて今回は楽しませていただいた、というのが本音です。演奏という点では、古いものを除きどれもすばらしいものです。古楽団体による演奏は、合唱ハーモニーの完璧さ、オーケストラの響きの美しさ、などどれもすばらしいと思います。ただそれと同時に今回は「オーセンティシティAuthenticity」とはいったい何なのか?ということも考えさせられました。
「オーセンティシティ」という言葉は「確実性」とか「信憑性」と訳されますが、古楽でこの言葉を使う場合、一般的には「作曲された当時の楽器や楽譜、演奏様式に従って音楽を解釈し表現すること」をいうと思います。しかしながらあらゆる条件が異なる現代において、バッハが演奏したであろう音楽と同じものものを求めることが不可能なのは自明のことであり、また同じことが「オーセンティシティ」だとも思いません。真の音楽愛好家もそんなものは求めていないと思います。音楽は「絶対的」なものではなく、あくまで「相対的」なものであり、だからこそそこにさまざまな解釈や演奏が生まれてくるのです。ただそうだからといって何でも許されるわけではなく、そこには時代考証や作曲者に関するさまざまな知識の習得、そして可能な限り原典に近づけようと努力する姿勢などがなくてはなりません。そして不可欠とはいいませんが、できればその過程を私たちにも知らせてくるとありがたいと思います。そうした努力に立って演奏者が私たちに生きた音楽を聴かせてくれること、これが真の「オーセンティシティ」なのでは、と今回痛切に感じました。このカンタータ第4番ほど、演奏者によって解釈の違いが表れる作品も少ないのではないでしょうか?これを書くまではそんなこともまったくわかりませんでした。それぞれが、いい意味で良さをもっています。
2012.11.22 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑱
17. カンタータ第4番「キリストは死の縄目につながれたり」BWV4―Ⅱこのカンタータ、「死への憧憬」というテーマからすると少し違っていますが、「神(=人間)の死と復活」をテーマとする初期の代表的名曲であることから、ここにとりあげました。今回は数字や記号に隠された意味(「数の象徴」と言われる)などにも少し触れながらこの作品をご紹介したいと思いますが、この曲は調べれば調べるほど複雑な背景を持つ作品で、演奏についてもいろいろと問題を孕んでいるように思います。
この作品はルターが1524年に書いた7節からなる同名のコラールを全節使用して作曲されています。全曲が一つのコラールからできているカンタータとしてはもう1曲BWV137の「主よ頌めまつれ、勢威強き栄光の主を」(1725)があるのみで、他には例がありません。ルターはブルゴーニュ出身で中世の聖職者・詩人として知られるヴィグベルト(Wigbert通称ヴィーポWipo ca.955-ca.1050)が作った復活祭のためのセクエンツィア(グレゴリオ聖歌の一つで「続誦」とも訳される)「ヴィクティメ・パスカリVictimae pascali(過ぎ越しの生贄の讃歌)」を真似てこのコラールを書いたといわれています。ただ真の作者はルターではなく、彼の協力者であったヨハン・ヴァルター(Johann Walter 1496-1570)が書いたもの、という説もあります。また旋律はヴィーポの死後、1090年頃に作られた復活祭劇用の音楽に基づいています。この復活祭のためのコラールは古くから親しまれてきた有名なもので、バッハ以前にも多くの作曲家が作品を残しています。オルガンのためのコラール編曲が多く、ゲオルク・ベームの2曲やパッヘルベルの作品などはCDでも聴くことができます。またパッヘルベルはこのコラールに基づく宗教コンチェルトも作曲しており、バッハがコラール全節を使用して作曲したのはこのパッヘルベルの作品(注1)に倣ったのでは、という説もあります。
バッハがこのカンタータを作曲したのはミュールハウゼン時代(1707年6月~1708年6月)といわれており、その間の復活祭となると、1708年しかありません。ところが近年学者の間ではアルンシュタット時代に作曲されたという説が浮上しています。樋口隆一著「バッハ カンタータ研究」(1987 音楽之友社)によれば、そもそもはアルフレード・デュルが1977年の論文で発表した提言が発端のようですが、クリストフ・ヴォルフやアンドレアス・グレックナーなどもこれを支持しています。バッハが1707年の復活祭の日(4月24日)に、亡くなったヨハン・ゲオルク・アーレ(Johann Georg Ahle 1650-1706)の後任としてミュールハウゼンの聖ブラジウス教会オルガニストの登用試験を受け、その際自らの能力を誇示するためオルガン曲だけではなくこのカンタータも演奏した、というものです(注2)。そうなるとこの曲はアルンシュタット時代に作曲されたことになり、BWV150に次ぐバッハ2番目のカンタータということになります。当然これには反論もあります。マルティン・ゲックも大著「ヨハン・セバスティアン・バッハ」(2000 東京書籍)の中でこの説を支持しているように思えますが、彼はこれに条件をつけていて「オルガニストの職務に声楽曲の作曲と上演が付随していればの話」としています。ミュールハウゼンのオルガニストの職務に、特別の機会のために依頼された場合を除きカンタータの作曲が含まれていないことは多くの学者も一致していることなので、どうもこれはありそうにないのですが、ゲックも言っているように「推測と大胆な仮説なしでは、バッハの初期作品を論じることはできない」ということで、なかなか面白い議論ではあります。因みに我が国の学者礒山雅氏は、第5曲の合唱と1708年2月4日に初演されたBWV71「神はいにしえよりわが王なり」の合唱とを比較して、前者はより作曲技法が手馴れているので、BWV71より後に作られたと考えるのが妥当、としています。
ところでこのカンタータは様々な根拠から初期の作品(注3)と位置付けられていますが、今日残されている楽譜はライプツィヒで再演された際のパート譜から作られたものなので、そのオリジナルがどのようなものだったかは正確にはわかっていません。再演の際、ライプツィヒの教会は初演時より大きな教会になったことから、声楽を補強するために管楽器が加えられたり、その他にも大きな変更が行われたりしています。アルフレート・デュルによる新バッハ全集スコアの序文(1995 B arenreiter)を読むと、次のように書かれています。パート譜は1724年と、1725年の2種類の日付のものがあり、現在のような終曲の合唱(単純な4声の合唱によるコラール)は1724年にはまだなく、1725年に組み入れられた(注4)。1724年の演奏で最終節が歌われなかったというようなことは考えられないので、デュルは以下のような可能性を指摘しています。
①現在は失われてしまった他の音楽を転用して演奏したか、シンフォニアに続く第2曲(コラール第1節)の音楽を最終節の歌詞に変えて繰り返し使用した。そして、更に1725年の再演時に管楽器による補強が行われ、ツィンクと3本のトロンボーンのパートが加えられた、としています。従って、バッハはもともと管楽器を加える構想はなかったので新全集版のスコアには管楽器のパートを“ad libitum”としたのだと。
②他に例を見つけることはできないが、最終節は会衆によって歌われた。
③1724年に再演の準備は行われたが、何らかの理由により演奏されず、翌年に延期された。
このことからわかるように、このカンタータの終曲の元の姿がどんなものだったのか、今となっては知る手がかりがありません。確かにバッハのカンタータにほとんど見られる簡潔な4声による終結コラールは、現存する作品の中では1714年(4月22日)のBWV12以降になりますので、現在歌われているようなものでなかったことは確かでしょう。因みに1724年の復活祭第1日は4月9日、1725年は4月1日になります。
 ここで1725年に追加された管楽器のツィンクのことに少し触れておきます。ツィンクは一般的にはコルネット(イタリア語)と呼ばれたりしますが、現代のトランペットのような形状のコルネットとはまったく別の楽器です。ですからここでは誤解を避けるためドイツ語のツィンクという名称を使用します。もともとは「小さな角笛」という意味で、金管楽器同様マウスピースに唇を当て、唇を震わせる
(リップリード)ことによって音を出します。但し素材
は木製で、スライドやヴァルブを持たないため細長い
管に指孔を開け、木管楽器と同じような方法で演奏す
る、非常に原始的な楽器です。ちょっと乱暴ですが、
リコーダーにマウスピースがついた楽器、と思えばだ
いたい想像できると思います。参考までに右に
Wikipediaに掲載されている写真を掲載しておきます。
ルネサンス時代に主に使用されましたが、音は小さく、
また技術的にも難しいため、バロック時代に入ると木
管楽器にとって代わられるようになり、廃れていきました。でも音量は小さくてもとても柔らかな音を出す、いぶし銀のような味わいのある音色です。イタリア・ヴェネツイア楽派の金管アンサンブルや、シュッツの作品でよく使用されています。
ここで1725年に追加された管楽器のツィンクのことに少し触れておきます。ツィンクは一般的にはコルネット(イタリア語)と呼ばれたりしますが、現代のトランペットのような形状のコルネットとはまったく別の楽器です。ですからここでは誤解を避けるためドイツ語のツィンクという名称を使用します。もともとは「小さな角笛」という意味で、金管楽器同様マウスピースに唇を当て、唇を震わせる
(リップリード)ことによって音を出します。但し素材
は木製で、スライドやヴァルブを持たないため細長い
管に指孔を開け、木管楽器と同じような方法で演奏す
る、非常に原始的な楽器です。ちょっと乱暴ですが、
リコーダーにマウスピースがついた楽器、と思えばだ
いたい想像できると思います。参考までに右に
Wikipediaに掲載されている写真を掲載しておきます。
ルネサンス時代に主に使用されましたが、音は小さく、
また技術的にも難しいため、バロック時代に入ると木
管楽器にとって代わられるようになり、廃れていきました。でも音量は小さくてもとても柔らかな音を出す、いぶし銀のような味わいのある音色です。イタリア・ヴェネツイア楽派の金管アンサンブルや、シュッツの作品でよく使用されています。さてここからは楽曲の内容に入っていきたいと思いますが、まず既に述べたようにこのカンタータは全編ルターのコラールを使用しており、これは17世紀からの伝統的なコラール変奏の手法に従っています。ですから冒頭の器楽のみによるシンフォニアも含め、その定旋律はすべてルターによるコラールの旋律がベースとなっています。歌詞もルターの言葉を一字一句違えることなく使用しています。ただバッハはここでとても大胆なことをやっています。これはゲックの指摘によるものですが、ハッハはこのコラールを引用する際、冒頭の2音で本来長二度下降するところの音型を短二度の半音階的な進行の音型に変えてしまいました。「長い伝統を誇るルターのコラール(不可侵の旋律)」に手を加えるなどということは、おそらく当時の人々にしてみれば驚天動地の出来事であったかもしれません。バッハはこの短二度下降の音型を全曲にわたって使用しています。「バッハは教会音楽創作の開始において、まさにバッハ的な個性を示した。彼は伝統に従うが、同時に伝統に手を加えるのである」(ゲック前掲書、小林義武監修、鳴海史生訳)と。ゲックによればこの短二度の下降音型は「激しい情念」を喚起するフィグール(修辞音型)であり、そればかりかこのことは多くの意味を示している、と言います。まずバッハは短二度を含め曲中に♯を多用しており、これは以前にも触れましたが、♯はドイツ語でKreuzであり、これはいうまでもなく十字架を意味します。バッハは「聴覚だけでなく、視覚にも訴えた」のです。キリストの受難と復活を歌うこのカンタータにとってこれほど格好の仕掛けが他にあるでしょうか?すばらしいアイデアです。さらにゲックはこの短二度の下降は、バッハの名前そのものでもある、と指摘します。B→A/C→H、まさに短二度なのです。これは「偶然」で片付けられるでしょうか?私は以前から確信しているのですが、もしバッハが作曲家にならなかったら、おそらく偉大な数学者になっていたのではないでしょうか?ただ、これも以前から言ってきたことですが、過度なこじつけは厳に慎むべきで、何でもかんでも数字や意味のありそうな言葉に置き換えて結論を導き出すような考えには賛成できません。でもこの程度の仕掛けは十分考えたのではないでしょうか。バッハ一族は、昔から親戚中が集まって音楽遊びに興じたり(クオドリベットなど)しており、そうした若い頃から培われた遊び心が、その後の作品にもところどころ顔をのぞかせているのではないでしょうか?
全曲は既に触れたように八つの楽章で構成されており、冒頭のシンフォニアを除きシンメトリックな構造になっていて、これは他の初期の作品とも共通しています。つまり、第5曲の合唱を中心に両端に合唱、そして二重唱(第3&7曲)、ソロ(第4&6曲)という順番になっています。但し声楽パートについては合唱で歌うべきなのかソロで歌うべきなのか楽譜には書かれていませんので、これは演奏者が判断することになります。また全体がホ短調という♯一つの調性で統一されており、まさに「Kreuz=十字架」をカンタータ全体で表現しています。
第1曲のシンフォニアは、コラールの旋律をモチーフにしつつも、そのメロディーを追うような構成にはなっていません。ですから他の楽章に比べると非常に自由な印象を受けます。全体は14小節からなっており、この14という数字は「バッハの数」と言われます。つまりB(2)+A(1)+C(3)+H(8)=14という意味で、確かに彼が14という数字を好んでいたことはよく知られています(注5)。これもバッハが意図したものかもしれません。
第2曲(コラール第1節)合唱は早めのテンポ(アレグロ)で進みますが、コラールの主旋律は長い音価を持つソプラノによって息の長いフレーズで歌われます。他の声部はそれらを模倣しながら忙しくソプラノの周囲を駆け巡るように歌います。この手法はまさにパッヘルベルを想起させます(有名なコラール「われらが神は堅き砦」を使用したモテット「わたしたちの避けどころGott ist unser Zuversicht」などがいい例)。歌詞は、人の罪を背負って十字架に架けられたキリストの復活を祝い神に感謝する、という内容です。最後はコラールの旋律を離れ、合唱が一体となって自由に、そして力強くハレルヤ(神をほめたたえよ)を歌います。
第3曲(コラール第2節)はソプラノとアルトの二重唱で、このカンタータの中でもっとも美しい(但しハーモニーが完璧であれば)楽章であり、私が一番好きな部分です。ゆったりしたテンポでしっとりと「人の死が必然である」ことが歌われます。伴奏は通奏低音が「死の歩み」を表すように同じパターンで執拗に繰り返されます(バッソ・オスティナート Basso Ostinato)。
第4曲(コラール第3節)は早いパッセージによるヴァイオリンの旋律にのって「死はすべてを失い、形を残すのみ」と歌われるテノールのアリアで、「死の形 Tods Gestalt」という箇所で突然曲はアダージョとなり、すぐに元のテンポに戻ります。バッハはこの言葉を強調したかったのでしょう。
第5曲(コラール第4節)は、このカンタータの中心におかれた4声の合唱で、バッハはここで生と死の激しい戦いを描写します。ここもパッヘルベルのモテットの手法で、アルトによるコラールの旋律に他の声部が激しく絡んできます。バッハはここで元の調性であるホ短調を維持しつつ、アルトのコラールは嬰ヘ短調に転調させるという手の込んだことをやっています。まさに戦いの音楽を思わせる激しさですが、当然ここでは生が死に打ち克つことになります。
第6曲(コラール第5節)はバスのアリアで、信仰の証を死にかざすとき、もはや死は自らを滅ぼすものではない、と歌います。
第7曲(コラール第6節)は、付点リズムを伴うバッソ・オスティナートにのって、ソプラノとテノールの二重唱により「復活の喜び」が歌われます。コラールはソプラノとテノールの間をカノンのように行きかいます。
第8曲(コラール第7節)の終曲のコラールについては、既にご紹介したとおり1725年の再演(再々演?)の際に変更された4声の簡潔なコラールが一般的に使用されており、「キリストこそが命の糧」と歌われます。この終曲の元の形がどんなものだったかは今となってはわかりません。デュルも序文の中で触れていましたが、ヴォルフは第2曲の音楽をそのまま歌詞を変えて使用したのではないか、としています。確かにこれだと完全なシンメトリー構造になりますが、ちょっと安易にすぎるようにも思います。
次回CD紹介で演奏上の問題について触れたいと思います。
注1) ゲックによると、バッハのモテット的な作風に比べ、パッヘルベルの作品の方がよりコンチェルト的であり、進歩的な音楽だったと。
注2) クリストフ・ヴォルフはコープマン盤の解説の中で、ミュールハウゼンにおける登用試験の際、「声楽曲の上演を求められた」と書いていますが、他の記述にはそこまでの表現はありません。
注3) デュルは新全集版スコアへの序文で次のような点をあげて初期の作品としています。
①1715年頃までのバッハの記譜法の癖(♯を取り消す際、通常ナチュラル記号?を使用するところを、♭記号を使う)
②ヴィオラの分割使用は1715年の復活祭以降、ごく簡単に説明がつく明らかなケースを除いて見られなくなった。
③声楽パートの音域が比較的低く(特に第6曲の第65~67小節など)、これはコアトーンでの演奏を想定していた。
注4) この点について、ヴォルフは著書「バッハ=カンタータの世界 第1巻」(1995 東京書籍)やコープマン盤の解説で、1724年の再演の際、当時のライプツィヒの習慣に合わせて4声のコラールに差し換えた、としていますが、ほとんどの学者は1725年のデュル説を採っています。
注5) 1747年、バッハは音楽評論家ミツラーが主催する音楽学術交流協会の会員になりますが、これもわざわざ14番目になるまで待っていた、という有名な逸話が残されています。
2012.09.16 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑰
16. カンタータ第4番「キリストは死の縄目につながれたり」BWV4―Ⅰまたまた初期の作品になりますが、今回はこの曲にまつわる私の思い出話しから始めたいと思います。
私がそもそもクラシック音楽を好きになった理由は様々考えられますが、大きくは二つあったように思います。第一のきっかけは、小学校の高学年か中学のはじめか記憶は定かではありませんが、学校でオーケストラによる移動音楽教室に行ったことです。今でも場所ははっきり覚えていて、南新宿にあったヤマノホール(現「山野美容学校」のホールで、よく歌謡ショウなどが行われていた)でしたが、そこでプロのオーケストラ(どこのオケかは忘れました)による生の演奏を初めて聴きました。曲は「軽騎兵序曲」や「天国と地獄」などありふれたものでしたが、その迫力や音の拡がりに圧倒され、クラシック音楽の魅力にとり憑かれてしまったのです。以来我が家にあった電蓄で、クラシックのEP盤(45回転のシングル盤)を聴いていました。プレーヤーを古い白黒テレビの小さなスピーカーにつなげただけの粗末な装置でモノラルだったため、とても迫力とか音の拡がりなどというものはありませんでした。それでもルービンシュタインのピアノやトスカニーニ指揮のモノラルLPをかけて楽しんでいました。
そんな状態が何年か続いていましたが、とうとう我が家にも最新式のステレオ装置が導入されたのです。やはりクラシック好きだった兄が購入したものでした。1960年代の初め頃だったと思います。日本ビクター製のいわゆるアンサンブル型ステレオと呼ばれるもので、プレーヤー、アンプ、スピーカーがすべて一体になっているものです。これにはエコー装置(スプリング・エコー)がついていて、ボリュームで量をコントロールできるようになっていました。エコーの量をコンサートホールの位置に設定すると、狭い我が家の部屋がまるでカーネギー・ホール (カーネギー・ホールなどというものは知る筈もなく、当時TVで見た映画から勝手にイメージしていただけですが) のように音楽で一杯に満たされました。ステレオと一緒に兄が購入したレコードがハイフェッツのメンチャイでした。チャイコフスキーのコンチェルトでヴァイオリンのソロが終わりブラスのファンファーレによる壮麗なトゥッティが始まると、その大音量と音の拡がりに圧倒され、それは今でも耳にこびりついていて忘れることがありません。あの映画「カーネギー・ホール」で演奏していたハイフェッツが瞼に浮かんでくるようでした。この曲を聴くたびに今でもそれを思い起こします。これが私を更にクラシック好きにさせた第2の要因でした。余談ですがこのステレオ装置、プレーヤーが確か「パーフェクトアーム(?)」とかいって、「45度まで傾けても音を忠実に再現する」とかいうことも売り文句になっていて、当時ビクターの大ヒット商品になったものでした。今考えると、45度傾けてもなどというのは、ぞっとします。それだけ針圧が高く、レコードを激しくこすっているわけですから。
その後中古のレコードなどを購入したりして少しずつ我が家のカタログも増えていきましたが、あるときやはり兄が新譜のレコードを購入してきました。当時のステレオLPは2,500円から2,800円で、非情に高価なものでした。何しろ私が昭和45年にレコード会社に入社した時の初任給が34,500円だったわけですから、この当時の初任給はおそらく15,000円とか18,000円くらいではなかったでしょうか。ですから2,500円というのは非情に高価な商品といえるのです。このレコードこそがフリッツ・ヴェルナーが指揮するところのバッハのカンタータ第4番だったのです。B面には同じくバッハのカンタータ第21番「わがうちに憂いは満ちぬ」がカップリングされていました。4番が1961年、そして21番が1962年の録音ですので、その翌年に発売されたとして、私はちょうど中学3年か高校1年生の頃の話になります。私にとってこれが記念すべきバッハの音楽との最初の出会いだったのです。
さてこのレコードには一つ大きな問題があって、このことでも私は生涯忘れることのできないものになっています。新品で購入した筈のレコードなのですが、レコードが1回転するたびに「ジャリッ」というノイズを発したのです。私は元来あまりノイズを気にするほうではありません。ジリッとかパチッというのは針でこするレコードにはつきもので、それをいちいち気にしていたら音楽を楽しむことはできません。音楽にだけ耳を傾けていれば、少々のノイズは気にならなかったのです。でも1回転ごとに決まって発する周期ノイズだけはどうにもなりません。音楽をすべて台無しにしてしまいます。これは私に限らずすべての人がそうだと思います。したがってこれは当然発売元にクレームとして返品することになったのです。誤解のないように言っておきますが、我が家は決してタチの悪いクレーマーなどではありません。兄は極めて紳士的に苦情として発売元の日本コロムビアに連絡し商品の交換をお願いしたのです。このときのレコード会社の対応にも驚かされました。
苦情を受けたコロムビアでは、すぐに交換用のレコードを持って我が家にかけつけてくれました。しかも菓子折りまで持参して丁寧に謝罪し、その場でレコードを交換したのです。レコードを交換するのは当然としても、この種の苦情で菓子折りまで持参するというのは正直驚きました。それだけレコードはこの時代高価な商品だったということでしょう。苦情処理の仕方としては顧客を大切にする素晴しい対応だったと思いますが、そうした対応とは対照的に、レコードそのものは交換してもノイズは改善されませんでした。この種のノイズは盤面につけられた傷から生じるものではなく、スタンパー(レコードをプレスするための凸状の金属盤)そのものに起因するので、これを解決するにはレコードの製造工程をはじめからやり直さなければなりません。残念ながらそこまではしてくれなかったのです。当時のレコード製造の技術は発展途上で、まだたくさんこうした問題をかかえていたのかもしれません。ですからこの第4番のカンタータの音楽はノイズつきで私の記憶に残ることになってしまったのです。音楽そのものは、4番の全曲を通して金太郎飴のように使用されているルターのコラールと、21番終曲のハレルヤ・コーラスのフーガが高校生の耳に深く刻まれ、以後忘れられない音楽となったのです。私が宗教音楽を特に好んで聴くようになったのはおそらくこの時期のこうした体験からきているのだと思います。
2012.06.29 (金) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑯
15. カンタータ第131番「深き淵より われ汝に呼ばわる、主よ」BWV131―Ⅲ最後にCDについて触れておきましょう。この作品も名曲だけにかなりCDは発売されています。それにくらべると私のコレクションは貧弱なものといわざるを得ず、従って優れた録音がまだほかにもあるだろうということをまずお断りしておきます。私の手元にあるCDは下記の7種類で、これも録音年代順に並べてみましょう。
①フリッツ・ヴェルナー指揮 ハイルブロン・ハインリヒ・シュッツ合唱団(66年)
ゲオルク・イェルデン(T)、ヤコブ・シュテンプフリ(B) プフォルツハイム室内管弦楽団 ピエール・ピエルロ(Ob)
ERATO WPCS-11789
②ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 モンテヴェルディ合唱団(80年)
ウィリアム・ケンドル(T)、スティーヴン・ヴァーコー(B) イングリッシュ・バロック・ソロイスツ
deutsche harmonia mundi BVCD-38129 (現米エラート盤 2292.45988)
③リチェルカール・コンソート (91年)
グレタ・ド・レジェル(S)、ジェイムズ・ボウマン(A)、ギィ・ドゥ・メ(T)、マックス・ファン・エグモント(B)
Mercury MRIC 295
④トン・コープマン指揮 アムステルダム・バロック管弦楽団&合唱団(94年)
ギィ・ドゥ・メ(T)、クラウス・メルテンス(B)
ERATO WPCS-4715~17 (現Challenge Classics CC72201)
⑤鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン(95年)
ゲルト・テュルク(T)、ペーター・コーイ(B)
BIS(King International) CD-781
⑥トーマス・ヘンゲルブロック指揮 (07年)
バルダサール=ノイマン=アンサンブル&合唱団
deutsche harmonia mundi BVCD-31015
⑦トーマス・グロッパー指揮 ミュンヘン・アルチス=ヴォーカリステン(10年)
マキシミリアン・キーナ(T)、フランツ・シュレヒト(B) アルパ・フェスタンテ・バロック管弦楽団
OEHMS Classics OC 783
([現・・]の表記は国内盤が廃盤で入手できないものの輸入盤の番号です)
フリッツ・ヴェルナー指揮による演奏はエラート・レーベルの黄金時代を代表するなつかしいものですが、さすがに古臭くなってしまいました。
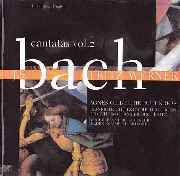 当時としては合唱やオーケストラもこじんまりとしていて、その点では現代にも通用す
るところがありますが、演奏スタイルはその規模の小ささを
逆に大きく聴かせようとするかのようにちょっと大げさに聴
こえます。多めの残響を利用して合唱もオーケストラもゆっ
たりとたっぷり聴かせます。でも当時はリヒターの演奏も含
めこうした演奏が主流だったのです。ピエルロのオーボエ(こ
れも懐かしい)の上手さには舌を巻くばかり。チャルメラのような彼の音色は決して好きではないのですが、バロック音楽で聴かせる彼の上手さはやはり格別。ヴェルナーによるカンタータのCDは各10枚組2巻に分けて発売されたもので、この131番は第2巻の方に含まれています。多分現在は廃盤になっているかもしれませんが、再発売される機会もあるかと思います。ピッチは現代の標準的なピッチによっています。
当時としては合唱やオーケストラもこじんまりとしていて、その点では現代にも通用す
るところがありますが、演奏スタイルはその規模の小ささを
逆に大きく聴かせようとするかのようにちょっと大げさに聴
こえます。多めの残響を利用して合唱もオーケストラもゆっ
たりとたっぷり聴かせます。でも当時はリヒターの演奏も含
めこうした演奏が主流だったのです。ピエルロのオーボエ(こ
れも懐かしい)の上手さには舌を巻くばかり。チャルメラのような彼の音色は決して好きではないのですが、バロック音楽で聴かせる彼の上手さはやはり格別。ヴェルナーによるカンタータのCDは各10枚組2巻に分けて発売されたもので、この131番は第2巻の方に含まれています。多分現在は廃盤になっているかもしれませんが、再発売される機会もあるかと思います。ピッチは現代の標準的なピッチによっています。ガーディナー盤ですが、ここにかかげたCDは彼が最初に録音したバッハのカンタータ演奏です。というより、初めてバッハの作品に取り組んだもの、といった方がいいかもしれません。この録音にはちょっとしたエピソードがあり
 ますので、それをご紹介しておきましょう。当時ようやく古
楽演奏が脚光を浴びるようになり、古楽の旗手として彼の名
声も次第に高まっていきましたが、これが録音された1980
年頃ではバロック音楽に古楽器を使用する是非について演
奏家や音楽ジャーナリストのあいだでも激論が交わされる
など、まだ「古楽器」が現在のような市民権を得るには至っ
ていませんでした。そして当時彼が所属していたフランスのレコード会社「エラート」もミシェル・コルボやパイヤールによるバッハやバロック音楽の録音に力を注いでいたため、彼にバッハのカンタータ録音を許可しませんでした。ヘンデルやパーセルで名演を聴かせてはいましたが、バッハとなると躊躇したのだと思います。当時バッハのカンタータ録音といえば古楽器を使用したものではアーノンクールとレオンハルトによるテレフンケンのプロジェクトがあるくらいで、そうした録音が活発になるにはもう少し待たなければなりませんでした(注1)。でもバッハ・カンタータ録音への挑戦という新たな目標をガーディナーは捨て去ることができず、彼は当時エラートとレーバル契約をし、共同制作なども積極的に行っていた日本のレコード会社「RVC(RCA Victor Corporationの頭文字をとってできた日本ビクター(JVC)と米RCA Recordsの合弁会社)」にこの企画を売り込んだのです。こうしてできあがった録音がこのCDで、ですからこの録音は海外のレコード会社などではなく、日本のレコ-ド会社の制作によるものなのです(私の記憶が正しければ仏エラートとの共同制作ではなく100%日本の原盤)。録音は1980年の11月で、この録音のためにJVCが開発したばかりの16ビット、デジタル・レコーディング・システムDAS-90が日本から持ち込まれました。ガーディナーによるアルヒーフへの全曲録音の開始は、この録音から更に10年近くたってからのことです。
ますので、それをご紹介しておきましょう。当時ようやく古
楽演奏が脚光を浴びるようになり、古楽の旗手として彼の名
声も次第に高まっていきましたが、これが録音された1980
年頃ではバロック音楽に古楽器を使用する是非について演
奏家や音楽ジャーナリストのあいだでも激論が交わされる
など、まだ「古楽器」が現在のような市民権を得るには至っ
ていませんでした。そして当時彼が所属していたフランスのレコード会社「エラート」もミシェル・コルボやパイヤールによるバッハやバロック音楽の録音に力を注いでいたため、彼にバッハのカンタータ録音を許可しませんでした。ヘンデルやパーセルで名演を聴かせてはいましたが、バッハとなると躊躇したのだと思います。当時バッハのカンタータ録音といえば古楽器を使用したものではアーノンクールとレオンハルトによるテレフンケンのプロジェクトがあるくらいで、そうした録音が活発になるにはもう少し待たなければなりませんでした(注1)。でもバッハ・カンタータ録音への挑戦という新たな目標をガーディナーは捨て去ることができず、彼は当時エラートとレーバル契約をし、共同制作なども積極的に行っていた日本のレコード会社「RVC(RCA Victor Corporationの頭文字をとってできた日本ビクター(JVC)と米RCA Recordsの合弁会社)」にこの企画を売り込んだのです。こうしてできあがった録音がこのCDで、ですからこの録音は海外のレコード会社などではなく、日本のレコ-ド会社の制作によるものなのです(私の記憶が正しければ仏エラートとの共同制作ではなく100%日本の原盤)。録音は1980年の11月で、この録音のためにJVCが開発したばかりの16ビット、デジタル・レコーディング・システムDAS-90が日本から持ち込まれました。ガーディナーによるアルヒーフへの全曲録音の開始は、この録音から更に10年近くたってからのことです。演奏はところどころアクセントをつけてマルカートで歌うなど(特に第3曲合唱冒頭の「私は主に望みをおき」という言葉を強調)他の演奏にはない解釈が聴かれます。終曲の合唱は力強く、ぐいぐいと前に進む推進力が感じられます。合唱の醍醐味という点ではこれが一番ではないでしょうか。ただこれがこの作品に相応しいかどうかは聴く人の好みによってくるでしょう。合唱やオーケストラの規模などは当時まだ記載する習慣がなかったので正確にはわかりませんが、おそらく合唱は各パート4~6人にソプラノを少し加えた程度ではないでしょうか。そして今回あらためて聴いて驚いたのは、この時点で既にコアトーンを採用しており現代の標準ピッチより半音高く演奏されていることです。楽器に関する議論は行われていましたが、ピッチに関してはそれほどまだ注目されていない時代だったと思います。というより、「古楽器=低いピッチ(カンマートーンのa≒415)」というのが定説とされていた時代です。コアトーンによる演奏といえば北ドイツのバロック・オルガンではありましたが、それ以外まだ珍しい時代ではなかったでしょうか。尚このCDには同じくバッハ初期の名曲、第4番がカップリングされています。またガーディナーによるアルヒーフへのカンタータ全曲録音というプロジェクトは何枚か録音された後打ち切りになってしまい、その後彼は自身のレーベルSDGを立ち上げ、そこで全集を録音しておりこの131番も再録音しています。それがどんな演奏か興味のあるところですが、そちらの方までは聴いていません。
リチェルカール・コンソートの演奏は「深き淵より」と題されたCDで、グラウプナーなど他の作曲家の作品と一緒に収録されており、既に1回目のところでもご紹介しました。合唱は各パート1人というリフキン方式によっています。アメリカの音楽学者ジョシュア・リフキンがこの方式を学会で発表したのが1981年末のことで、リフキン本人の指揮による演奏は別にして、それが他の演奏家にも浸透するには少し時間がかかったのではないでしょうか?アンドルー・パロット指揮による録音も含め1990年ごろからこうしたCDが現れるようになってきます。このCDもその一つです。18世紀の始めにはそうした方法も一般的に行われていたという記述もあるので、バッハの初期のカンタータについてはこうした演奏法も納得できるものですが、演奏については再三指摘しているように、こうした方式をとる場合ちょっとしたヴィブラートもハーモニーを壊してしまうので禁物です。この演奏でもヴィブラートは控えめに歌われていますが、それでも聴いていると冒頭からちょっと違和感を感じます。それに比べると器楽陣はとても素晴しく、ヴィオラの代わりにガンバを使用していることもあって、中声部がとても豊かに聴こえます。ただここまで古楽に徹していながらピッチは現代の標準ピッチで演奏するというちぐはぐさが感じられます。
トン・コープマンのCDは、カンタータ全集の第1巻に収録されています。もちろん古楽器によるコアトーンを採用した演奏であることはいうまでもありません。この全集、全部で66枚のCDという途方もない枚数になりますが、それ
 だけバッハはたくさんのカンタータを作曲したということです。
ただ第1巻の3枚は、初期といってもヴァイマル時代の作品と
並べられており、この131番も21番のカンタータ(初演1714
年6月17日)の次に収録されています。コアトーンで共通する
同じ初期のカンタータとはいっても、ヴァイマル時代の作品と
なるとイタリアの影響を反映してその作風も異なることから、このミュールハウゼン時代の作品とは別にした方がよかったように私自身は思いますが、そうした問題は別にしてこの演奏とても素晴しいものです。実に生き生きとしており、この作品からこれほどの生命力を引き出すとは。最初の録音ということで満を持して演奏されたものでしょう。その意気込みが聴き手にも充分伝わってきます。合唱のハーモニーの素晴しさも特筆されます。難を言えばテノール・ソロの素人っぽい歌い方にちょっと興をそがれるくらいです。合唱の編成は7、4、4、4という布陣で、ソプラノが多く、アルトはすべてカウンターテノールで歌われています。オルガンの通奏低音も他の盤より雄弁で、そうしたところ(第4曲)はコープマン自身の演奏によるものかもしれません。クリストフ・ヴォルフによる解説も読み応えがあります。
だけバッハはたくさんのカンタータを作曲したということです。
ただ第1巻の3枚は、初期といってもヴァイマル時代の作品と
並べられており、この131番も21番のカンタータ(初演1714
年6月17日)の次に収録されています。コアトーンで共通する
同じ初期のカンタータとはいっても、ヴァイマル時代の作品と
なるとイタリアの影響を反映してその作風も異なることから、このミュールハウゼン時代の作品とは別にした方がよかったように私自身は思いますが、そうした問題は別にしてこの演奏とても素晴しいものです。実に生き生きとしており、この作品からこれほどの生命力を引き出すとは。最初の録音ということで満を持して演奏されたものでしょう。その意気込みが聴き手にも充分伝わってきます。合唱のハーモニーの素晴しさも特筆されます。難を言えばテノール・ソロの素人っぽい歌い方にちょっと興をそがれるくらいです。合唱の編成は7、4、4、4という布陣で、ソプラノが多く、アルトはすべてカウンターテノールで歌われています。オルガンの通奏低音も他の盤より雄弁で、そうしたところ(第4曲)はコープマン自身の演奏によるものかもしれません。クリストフ・ヴォルフによる解説も読み応えがあります。鈴木雅明とBCJのCDはカンタータ全曲シリーズの第2集で、106番「神の時こそ いと良き時」と71番「神はいにしえよりわが王なり」と共に収録されています。106番では少し固さも感じられた演奏でしたが、ここでは全くそんなこ
 ともなく素晴しい演奏を聴かせてくれます。再三指摘してきた
ように彼らの演奏は「日本人による」という枠を超えて、世界
のトップ水準にあるバッハ演奏であり、これは同じ日本人とし
てとても誇りに思います。鈴木雅明氏が先ごろライプツィヒ市
から「バッハ・メダル」を贈られたというのは充分納得できるも
のです。むしろ遅すぎたくらいです。このメダルの授与は2003年から始まったもので、過去受賞したアーティストにはグスタフ・レオンハルト(初年度)、ヘルムート・リリング(04)、ジョン・エリオット・ガーディナー(05)、トン・コープマン(06)、ニコラウス・アーノンクール(07)、ヘルマン・マックス(08)、フリーダー・ベルニウス(09)、フィリップ・ヘレヴェッヘ(10)、ヘルベルト・ブロムシュテット(11)と錚々たる演奏家が名を連ねています。ブロムシュテットだけがちょっと異質に思えますが、ゲヴァントハウス管の常任だった頃、ロ短調ミサをはじめバッハの作品も多くとりあげてそれが認められたのでしょう。話が横にそれましたが、このCD、ともかく素晴しいので是非多くの人に聴いていただきたいと思います。解説書にも「a=465」と記されているとおりコアトーンで演奏されています。合唱は5、5、4、5という布陣で、コープマンのようにソプラノだけ多くする、という方法はとっていません。オーケストラは通奏低音を除き各パート2~3人で演奏されています。面白いのはアルトのパートを、男性2人(カウンターテナー)、女性3人という混声にしていることです(注2)。また私の耳では第2曲バスのソロとソプラノによるコラールの掛け合いで、ソプラノはソロで歌っているように聴こえます。もしこれがソロではなく複数ならば、これほど完璧なユニゾンはないでしょう。一方第4曲のテノールのソロとアルトのコラールの掛け合いでは、アルトは少ない人数(恐らく2人くらい?)ながら斉唱で歌われているようです。ここで聴くテノールのテュルクもなかなかの名唱です。それからここに収録されている71番のカンタータがとびきりの名演であることを付け加えておきたいと思います。
ともなく素晴しい演奏を聴かせてくれます。再三指摘してきた
ように彼らの演奏は「日本人による」という枠を超えて、世界
のトップ水準にあるバッハ演奏であり、これは同じ日本人とし
てとても誇りに思います。鈴木雅明氏が先ごろライプツィヒ市
から「バッハ・メダル」を贈られたというのは充分納得できるも
のです。むしろ遅すぎたくらいです。このメダルの授与は2003年から始まったもので、過去受賞したアーティストにはグスタフ・レオンハルト(初年度)、ヘルムート・リリング(04)、ジョン・エリオット・ガーディナー(05)、トン・コープマン(06)、ニコラウス・アーノンクール(07)、ヘルマン・マックス(08)、フリーダー・ベルニウス(09)、フィリップ・ヘレヴェッヘ(10)、ヘルベルト・ブロムシュテット(11)と錚々たる演奏家が名を連ねています。ブロムシュテットだけがちょっと異質に思えますが、ゲヴァントハウス管の常任だった頃、ロ短調ミサをはじめバッハの作品も多くとりあげてそれが認められたのでしょう。話が横にそれましたが、このCD、ともかく素晴しいので是非多くの人に聴いていただきたいと思います。解説書にも「a=465」と記されているとおりコアトーンで演奏されています。合唱は5、5、4、5という布陣で、コープマンのようにソプラノだけ多くする、という方法はとっていません。オーケストラは通奏低音を除き各パート2~3人で演奏されています。面白いのはアルトのパートを、男性2人(カウンターテナー)、女性3人という混声にしていることです(注2)。また私の耳では第2曲バスのソロとソプラノによるコラールの掛け合いで、ソプラノはソロで歌っているように聴こえます。もしこれがソロではなく複数ならば、これほど完璧なユニゾンはないでしょう。一方第4曲のテノールのソロとアルトのコラールの掛け合いでは、アルトは少ない人数(恐らく2人くらい?)ながら斉唱で歌われているようです。ここで聴くテノールのテュルクもなかなかの名唱です。それからここに収録されている71番のカンタータがとびきりの名演であることを付け加えておきたいと思います。トーマス・ヘンゲルブロックは先ごろ常任指揮者となった北ドイツ放送交響楽団を率いて日本デビューを果たしました。古楽の指揮者が現代オーケストラを指揮するのは最近では珍しくなくなりました。ガーディナーやブリュッヘンは
 古くから振っていましたし、最近では鈴木雅明もそこに加わっ
ています。ただそれがすべて成功しているかというと、難しい
ところがあります。好き嫌いは別にして文句なく成功したと言
えるのはアーノンクールでしょう。ヘンゲルブロックは実際に
私も聴いていませんのでなんとも言えませんが、少なくとも新
聞評などを読むかぎりかなり厳しかったのではないでしょうか?一方彼の古楽演奏に関して言えば、ロ短調ミサ(DHM BVCD-1912~3)など私はベストにあげたいくらいの素晴しい名演ですし、バッハが編曲したペルゴレージの「スターバト・マーテル」(BWV1083)の演奏も心に沁みる素晴しいものでした。このCD、「生の喜び・死の芸術」というタイトルがつけられ、パーセルの短いアンセムや「メアリー女王の葬送のための音楽」、ヨハン・ルートヴィヒ・バッハ(1677-1731)のモテット、そしてセバスティアン・バッハのBWV150とともに収録されています。文字通り「生と死」というテーマに相応しい作品を集めています。ライナーノーツもドイツの哲学者による文章が寄せられるなど、哲学的内容で難しく、その宗教的奥深さを理解できるほど私の頭脳は哲学的ではありません。でもそんなことは別にして、この演奏もまた素晴しく、私が一番よく聴いている演奏です。第3曲の合唱で聴かれる安らかな音楽は天国的といってもいいでしょう。第4曲の通奏低音で使用されるポジティブ・オルガンの演奏もコープマンとは違った室内楽的な響が心地よいものになっています。合唱は6、4、5、4という全部で19人からなるちょっと変則的な編成で、オーケストラはすべて各パート1人による演奏です。ここでもアルトは男性と女性の混声で歌われています。BCJもそうですが、優れたカウンターテナーの歌手を全部揃えるというのは少し難しいのかもしれません。この演奏も当然ながら現代のピッチより半音高いコアトーンによるものです。
古くから振っていましたし、最近では鈴木雅明もそこに加わっ
ています。ただそれがすべて成功しているかというと、難しい
ところがあります。好き嫌いは別にして文句なく成功したと言
えるのはアーノンクールでしょう。ヘンゲルブロックは実際に
私も聴いていませんのでなんとも言えませんが、少なくとも新
聞評などを読むかぎりかなり厳しかったのではないでしょうか?一方彼の古楽演奏に関して言えば、ロ短調ミサ(DHM BVCD-1912~3)など私はベストにあげたいくらいの素晴しい名演ですし、バッハが編曲したペルゴレージの「スターバト・マーテル」(BWV1083)の演奏も心に沁みる素晴しいものでした。このCD、「生の喜び・死の芸術」というタイトルがつけられ、パーセルの短いアンセムや「メアリー女王の葬送のための音楽」、ヨハン・ルートヴィヒ・バッハ(1677-1731)のモテット、そしてセバスティアン・バッハのBWV150とともに収録されています。文字通り「生と死」というテーマに相応しい作品を集めています。ライナーノーツもドイツの哲学者による文章が寄せられるなど、哲学的内容で難しく、その宗教的奥深さを理解できるほど私の頭脳は哲学的ではありません。でもそんなことは別にして、この演奏もまた素晴しく、私が一番よく聴いている演奏です。第3曲の合唱で聴かれる安らかな音楽は天国的といってもいいでしょう。第4曲の通奏低音で使用されるポジティブ・オルガンの演奏もコープマンとは違った室内楽的な響が心地よいものになっています。合唱は6、4、5、4という全部で19人からなるちょっと変則的な編成で、オーケストラはすべて各パート1人による演奏です。ここでもアルトは男性と女性の混声で歌われています。BCJもそうですが、優れたカウンターテナーの歌手を全部揃えるというのは少し難しいのかもしれません。この演奏も当然ながら現代のピッチより半音高いコアトーンによるものです。私の所蔵CD中一番新しい録音が⑦の団体による演奏ですが、この団体を私はこのCDで初めて知りました。ミュンヘン・アルチス・ヴォーカリステンという合唱団は古楽専門の団体ではありません。2005年にロッシーニの小荘厳ミ
 サ曲を演奏するために結成されたまだ新しい合唱団です。バロッ
クからロマン派まで幅広いレパートリーを持ち、メンバーは50
人ほどで構成されています。ただこのCDではもう少し人数は少
なくしているように思います。一方バックで演奏しているアルパ・
フェスタンテ・バロックオーケストラ(注3)は完全な古楽の団体
で、創立が1983年といいますから、古楽器による演奏団体としては比較的古いほうの部類に入ると思います。現代的な合唱団と古楽アンサンブルの共演で、ピッチはコアトーンが採用されています。ただ人数が多く、そのせいかハーモニーはやや濁って聴こえるところもあります。ソリストも今ひとつ物足りなく、やはり古楽系の団体による演奏と比べると、少し聴き劣りします。指揮者のトーマス・グロッパーはかつてミュンヘン・バッハ合唱団にも参加し、そこのトレーナーなども勤めていた声楽家ですが、古楽を専門としているわけではないようです。ただこうした演奏は、日本のアマチュア合唱団がバッハのカンタータなどを採り上げる際参考にするには一番いいのかもしれません。3曲目の合唱の歌いだしをマルカートで歌ったり、終曲合唱冒頭の「イスラエルよ」の叫びを少しクレッシェンドさせたり、といった工夫もみられます。このCDにはヴァイマル時代のカンタータ第182番「天の王よ、汝を迎えまつらん」(初演1714年3月25日)がいっしょに収録されています。ここにはもうミュールハウゼン時代の暗い死の面影はありません。
サ曲を演奏するために結成されたまだ新しい合唱団です。バロッ
クからロマン派まで幅広いレパートリーを持ち、メンバーは50
人ほどで構成されています。ただこのCDではもう少し人数は少
なくしているように思います。一方バックで演奏しているアルパ・
フェスタンテ・バロックオーケストラ(注3)は完全な古楽の団体
で、創立が1983年といいますから、古楽器による演奏団体としては比較的古いほうの部類に入ると思います。現代的な合唱団と古楽アンサンブルの共演で、ピッチはコアトーンが採用されています。ただ人数が多く、そのせいかハーモニーはやや濁って聴こえるところもあります。ソリストも今ひとつ物足りなく、やはり古楽系の団体による演奏と比べると、少し聴き劣りします。指揮者のトーマス・グロッパーはかつてミュンヘン・バッハ合唱団にも参加し、そこのトレーナーなども勤めていた声楽家ですが、古楽を専門としているわけではないようです。ただこうした演奏は、日本のアマチュア合唱団がバッハのカンタータなどを採り上げる際参考にするには一番いいのかもしれません。3曲目の合唱の歌いだしをマルカートで歌ったり、終曲合唱冒頭の「イスラエルよ」の叫びを少しクレッシェンドさせたり、といった工夫もみられます。このCDにはヴァイマル時代のカンタータ第182番「天の王よ、汝を迎えまつらん」(初演1714年3月25日)がいっしょに収録されています。ここにはもうミュールハウゼン時代の暗い死の面影はありません。以上、BWV131のCDについて私なりの感想を述べてきましたが、冒頭でもお断りしたように、このカンタータはまだまだ様々な団体による演奏が発売されています。もっとたくさん聴きたかったのですが、ここまでしか聴けませんでした。特にヘレヴェッヘのCDが廃盤になっていて入手できなかったのが残念です。
注1)トン・コープマンが頭角を現してくるのは1980年代半ばで、バッハ・カンタータ全曲録音の開始は1994年11月からのことです。ガーディナーによるアルヒーフへの録音は、受難曲やミサ、オラトリオが先行して1985年(ロ短調ミサ)から始まっていますが、カンタータの録音は1989年9月からになります。
注2) この曲に限ったことではなく、BCJでは常にこうした方法がとられているようです。
注3) ライナーノーツによると、「アルパ・フェスタンテ」というのは1653年ミュンヘン・オペラ(宮廷歌劇場で現在のヘルクレスザール)のオープニングで上演されたマッチオーニ(G.B. Maccioni)のオペラのタイトルに由来しています
2012.05.07 (月) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑮
14. カンタータ第131番「深き淵より われ汝に呼ばわる、主よ」BWV131―Ⅱさてバッハの131番のカンタータですが、ここでもう一度初期の作品について触れておきましょう。
バッハの最初に書いた曲が何であったのか、というようなことはもちろんわかりませんが、ヨハン・セバスティアンの父ヨハン・アンブロージウスが死去して長兄の元に引き取られて過ごしたオールドルフ時代(1699年まで)に恐らくクラヴィーアのための習作を書いているのではないか、と思います。月明かりのもとで兄の所蔵する楽譜を夜ごと写しとっていたという有名な逸話から、そうしたことが想像されます。現存する作品のなかではリューネブルク時代(1700~03)に書いたと思われるオルガンのための4曲のコラール・パルティータ(BWV766、767、768、770)と、クラヴィーアのための「最愛の兄の旅立ちによせて」BWV992がもっとも若い頃の作品と考えられています。
カンタータはそこまで古くはありませんが、一番古いものは最近の著作などでは第150番「主よ、われ汝を仰ぎ望む」でアルンシュタット時代(1703~07)に書かれた、といわれています。アルンシュタット時代といえばまだ20歳前後という若さで、そんな青年があのような深遠な作品を書くとは驚くほかありません。このカンタータが後にブラームスによって脚光を浴びることになったことは既に述べたとおりですが、もう一つ余談になりますがこのカンタータにまつわる興味深い話をご紹介しておきましょう。1705年8月4日、バッハは町の中心部にあるマルクト広場でガイエルスバッハという聖歌隊のメンバーと喧嘩騒ぎを起こし、お互い剣を抜きあうという大事件に発展しました。バッハは聖職者会議に喚問され、以後聖歌隊との仕事から全く手を引くことになってしまいます。このガイエルスバッハという人物はバッハより年長のファゴット奏者でしたが、相当下手だったようで、バッハから口汚く罵られ、そうしたお互いの不満が爆発して起った事件でした。150番のカンタータはファゴットが重要なパートを占めており、高い技術が必要とされるそうです。ですから学者の中には、前述の事件はこのカンタータが原因ではなかったのか、という人もいるのです。もちろんことの真偽はわかりません。でももしこれが真実であれば、このカンタータはこの騒動以前に書かれたことになり、作曲年代の特定にも結びついてきます (注1)。
この150番やこれからとりあげる131番、そしてこの欄で最初にとりあげた106番のカンタータはバッハがまだ20代前半(アルンシュタットからミュールハウゼン時代)という若い時代に書かれており、しかもそうした作品がバッハの全作品の中でも極めて重要な位置を占めていることから考えると、やはりバッハは「宗教音楽の作曲家」という表現がもっとも相応しいのではないでしょうか。もちろん管弦楽曲や協奏曲、室内楽作品、そして世俗の声楽曲なども素晴しいのですが、オルガン曲も含めた彼の宗教音楽がその中核にあることは誰しも否定できない事実だと思います。
初期のカンタータ作品の特徴についてはBWV106でもふれましたが、もう一度ここでその様式的な特徴を簡単にまとめておきたいと思います。もちろん個々に例外はありますが。
①歌詞(台本)はすべて聖書の言葉とコラールのみからなっていて、自由詩はない。こうした初期カンタータの特徴を念頭において、このBWV131についてみてみたいと思います。
②全体の構造が通作的で各楽章間の区切りが後の作品ほど明確でない。
③声部間に対話を持たせるため、独唱にコラール旋律(歌もしくは楽器による)を絡めたりする。
④BWV106の「イン・パラディス」のように特定の言葉を何度も強調したりする。
⑤冒頭の短い器楽による前奏のあとは、合唱で始まり、中央と最後に再び合唱をおくシンメトリックな構造をとる。終曲はフーガ形式をとることが多く、後世のカンタータのような終結コラールはない(例外BWV4)。
⑥オーケストラの楽器編成は概ね小さく(例外BWV71)、ガンバやリコーダーなど素朴な響きによる渋味のある音楽で派手さがない。ただ6曲はすべて編成が異なっていて、変化をもたせている。また中声部を厚くする傾向がある。
6曲の初期カンタータのうち、作曲年代をはっきり特定できるのは2曲だけで、あとの4曲は上記のような様式上の特徴などから初期の作品と推定されているにすぎません。BWV71の「神はいにしえよりわが王なり」はライプツィヒ時代を含めバッハの生存中にスコアが出版された唯一のカンタータ(注2)で、1708年2月8日ミュールハウゼン市の参事会員交代式用に書かれたことがはっきりしています。年代が特定できる2曲のうちのもう1曲が、このBWV131になります。バッハ自筆のスコアが残されていて、その最後に「尊師ゲーオルク・クリスティアン・アイルマル神学博士の所望により作曲に附す。ミュールハウゼン市オルガニスト、ヨーハン・セバスティアン・バッハ」(アルベルト・シュヴァイツアー「バッハ」杉山好 他訳 白水社)と書かれていることからミュールハウゼン時代の作であることがはっきりわかります。彼がミュールハウゼンのオルガニスト(聖ブラジウス教会)に就任したのが1707年6月14日(22歳)で、ヴァイマルに移転するため同市に辞表を提出したのが1708年6月25日ですので、その間に作曲されたことになります。何のために書かれたのかを示す根拠はないのですが、詩篇130番は悔い改めの詩篇として知られていますので、そうした礼拝のための作品と考えられています。アルフレート・デュルは当時ミュールハウゼンで発生した大火災に伴う悔い改め式のためにか書かれたのではないか、としています。この火災、バッハがミュールハウゼン聖ブラジウス教会のオルガニストに応募した直後の5月に発生し、市の中心部のほとんどが崩壊した、と言われています。その火災による悔い改めの礼拝は7月に行われましたので、その際に演奏された、と考えるのが一般的です。BWV106が伯父のトビーアス・レンマーヒルトの葬儀のための音楽だったとすれば、それは1707年8月14日に演奏されたことになりますので、このBWV131はそれより以前で、バッハがミュールハウゼンに着任後最初に作曲したカンタータということになります。
このカンタータの台本は依頼者のアイルマル牧師(Georg Christian Eilmar 1665-1715)と言われており、ルターによるドイツ語訳詩篇130番全文に、途中リングヴァルトのコラールを絡めた内容になっています。このアイルマルはそもそも同じ市内でも他の教会(聖マリーエン教会)の牧師で、バッハの直接の上司ブラジウス教会のフローネ牧師(Johann Adolf Frohne 1652-1713)とは対立関係にありました。アイルマルはルター派の正統主義者で、教会の礼拝に音楽は欠かせないという立場であり、一方のフローネはいわゆる敬虔主義に属し、礼拝に過度な音楽を持ち込むことを否定する考えの持ち主でした。若きバッハは当然厳格な正統主義者でしたのでフローネと良好な関係を維持することは難しく、アイルマルと親交を深めるようになり、後のBWV71では台本をアイルマルが担当しています。こうした複雑な関係は当然バッハの頭を悩ませ、彼が一年という短い期間でミュールハウゼンを去ることになった一因にもなっています(直接的な動機は金銭問題?)。
成立にまつわる話はこれくらいにして、曲の内容には入っていきましょう。既に触れたようにこの曲は聖書の詩篇130番とコラールのみからなっており、初期作品の典型的な特徴であるシンメトリックな構造をとっています。編成は合唱4部、オーケストラはヴァイオリン1、ヴィオラ2、オーボエ1、ファゴット1、通奏低音となっており、独唱はテノールとバスのみとなっています。第2ヴァイオリンがなく、ヴィオラが2声部となっていて、ここでもバッハは中声部を厚くしています(106番ではヴァイオリンがなく弦はガンバと通奏低音のみ)。
冒頭23小節からなる短いシンフォニア(アダージョ、ト短調)が置かれ、あとに続く合唱の動機が「ため息」の音型として弦楽器とオーボエで奏され、そのまま合唱に受け継がれます。いかにも「深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます」という呼びかけに相応しい哀調を帯びた旋律で詩篇の第1節が切々と歌われた後、曲はヴィヴァーチェに転じ「主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈るわたしの声に耳を傾けてください。」の第2節が歌われます。「主よ、この声を・・・」は執拗に繰り返され、そのあと「嘆き祈る・・・」の小規模なフーガに転じます。そして曲の後半では合唱の合間にオーケストラは冒頭の「ため息」の音型を模倣し、曲はそのまま切れ目なく第2曲へと続きます。第1曲で聴かれるこれらのフーガに至る音楽の対比はオルガンの「前奏曲とフーガ」の形式が持ち込まれたものです。
第2曲(アンダンテ、ト短調)はバスのアリオーソで、詩篇の第3、4節「主よ、あなたが罪をすべての心に留められるなら・・・」が歌われると、そこにソプラノ(合唱)が呼応してバルトロメウス・リングヴァルト(Bartholom?us Ringwald c.1532-1600)が1588年に書いたコラール「Herr Jesu Christ, du h?chstes Gut 主イエス・キリスト、至高の宝よ」の第2節「このことを思い悩む私を憐れんでください。私の心からこの重荷を取り外してください。あなたはこの罪を贖われたのですから、十字架上の死の苦痛によって。だから私は大きな悲しみとともに、わがもろもろの罪に破滅することも、永遠に意気消沈することもないでしょう」(礒山雅氏 訳)が絶妙に絡み合いながら歌われていきます。バスのアリオーソは死への恐怖を、コラールはそこからの救いを歌います。オーボエのオブリガートも二つの声の間を縫うように効果的に響きます。
このカンタータの中心におかれた第3曲の合唱は詩篇の第5節「わたしは主に望みをおき」の短い句による変ホ長調のアダージョで始まりますが、すぐに「わたしの魂は・・・御言葉を待ち望みます」でヘ短調のラルゴとなります。「わたしの魂は望みをおき、待ち望みます」が緩やかなフーガの調べにのって何度も繰り返されバス、テノール、アルト、ソプラノの順に、歌い継がれていきます。ここでは神への希望が歌われます。
第4曲は12/8拍子のリズミカルな通奏低音のオスティナートにのってテノールのアリオーソが歌いだされます(ハ短調)。ここは詩篇の第6節となり「見張り(夜番)」が夜明けを待つ、つまり希望を待ち望む姿が歌われますが、前半部では「マイネ・ジーレ(わが魂は)」という悲痛な叫びが執拗に繰り返され、この言葉はBWV106の「イン・パラディス」同様、全曲を通じてもっとも耳に残る印象的な言葉です。この言葉に、第2曲同様、同じリングヴァルトのコラールの第5節(注3)がアルトの合唱(斉唱)によって被ってきます。コラールは「あなたの血によって罪を洗い流してください」と歌います。
終曲の合唱は、まず「イスラエルよ」という短い呼びかけが3度アダージョ(ト短調)によって力強く歌いだされますが、響としてはとても古臭く、伝統的なモテットを思い起こさせます。しかしそれはすぐに「主を待ち望め」という言葉でウン・ポコ・アレグロに転じ、これも何度か歌われた後再びアダージョとなって「悲しみは主のもとに」となり、最後は「主は、イスラエルを すべての罪から贖ってくださる」というフーガ(アレグロ)になります。つまり詩節の行ごとにバッハはテンポを変えて変化をもたせています。最後のフーガの部分は、スコアを見ていると始め合唱の伴奏は通奏低音のみだったのが、しだいにヴァイオリン、オーボエ、ヴィオラと加わっていき、最後は全楽器が加わって大きなクライマックスを築き上げていくのがわかります。ここでもまた「前奏曲とフーガ」の技法が使われています。
このカンタータのテーマは「生と死」である、といわれています。宗教的にその意味が考えられるほどの信仰や知識を私は持ち合わせていませんので、そのことはよくわかりません。でも歌詞を追い、音楽に耳を傾けていればこれが「絶望の淵から希望を見出す」、そんな音楽である、ということはわかります。傷ついた人の心や、何よりも大きな災害に遭われた人々の心を癒すことができる、これはそんな音楽ではないでしょうか。
注1) ブラームスも使用した終曲の主題がパッヘルベルの作品からの借用ではないかと考えられ、そうだとすると1706年3月に死んだパッヘルベルへのオマージュとしてバッハが作曲したのでは、という説もあり、これが近年一般的になっているようです。
注2) クリストフ・ヴォルフは著書「ヨハン・セバスティアン・バッハ~学識ある音楽家」(秋元里予訳 春秋社)の中でミュールハウゼン時代に出版されながら紛失してしまった作品として、このBWV131のカンタータとクォドリベットBWV524をあげています。
注3) 解説書によっては第3節としているものがありますが、第5節が正しい。
2012.02.24 (金) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑭
13. カンタータ第131番「深き淵より われ汝に呼ばわる、主よ」BWV131―Ⅰ再び初期の作品に戻り、今回は第131番のカンタータをとりあげてみたいと思います。BWV106同様ミュールハウゼン時代の若い頃の作ですが、これは聖書の詩篇第130番に基づいて作曲されています。この第130番の詩篇「深き淵より」はその優れた詩の内容からバッハ以前にも多くの作曲家の創作意欲をかきたて、多くの名曲が生まれています。バッハのカンタータに入る前にこのあたりのことを少しご紹介しておきたいと思います。
まず詩篇(最近では新共同訳聖書に従って「詩編」と表記される)ですが、これは旧約聖書に書かれた150編からなる宗教詩で、その内容は神への讃歌、王の歌、嘆願、巡礼歌などとなっています。そしてこれらは毎日ユダヤの神殿で読み上げられるというよりは、礼拝の音楽として器楽の伴奏つきで歌われてきたものでした。詩篇はラテン語でPsalmus、英語ではPsalmと書きますが、これはギリシャ語のプサルモスを語源としており、プサルモスは「弦楽器を伴奏に歌う歌」を意味しています。またプサルモスという言葉も「弦をつまむ」という意味のプサロからきています。つまり詩篇はその起源から音楽とは不可分の関係にあったのです。そんなことから古くから多くの作曲家がこぞって詩篇の音楽を作曲してきました。ではこれらの詩はいつ頃誰によって作られたのでしょう。一般的にはその大部分がダヴィデの作といわれています。このダヴィデとは言うまでもなく紀元前1012年頃に成立したイスラエル王国の第2代国王(在位BC1010~971)で石を投げてゴリアテを倒した逸話で知られています。詩篇の作者としては他にソロモンやアサフ、モーセなどの名もあげられていますが、これらはそれぞれの詩篇の冒頭に詩の目的や状況を説明するために書き記されたもので、必ずしも作者を表したものではないとする説が有力で、それ以前のメソポタミアや小アジアで栄えたシュメールやアッカド、ウガリット、エジプトなどの民族の間に伝承された讃歌や詩を集めたもの、というのが正しいようです。
もう一つ、最近のCDではあまり見られなくなりましたが、以前ラテン語を歌詞とする詩篇では番号が二つ併記されていました。これは「ヴルガタ聖書」と呼ばれるローマ教会公認のラテン語訳と、各国語に訳されているヘブライ語訳(マソラ本)とで詩篇に付された番号が少し違っていることから生じたものです。ですから例えば「詩篇第130番(129番)」とか「第129番(現:130番)」と表記されたりしていました。日本の新共同訳聖書はマソラ本に従っています。
前置きが長くなりましたが、詩篇第130番の話に戻りましょう。この130番の詩篇は類型的には嘆願詩篇もしくは悔悛詩篇に属し、ラテン語では
ジョスカン・デプレ(2曲)、ルター、ゼンフル、パレストリーナ、ラッスス、シュッツ、ゼレ、ローゼンミュラー、リュリ、M.-A.シャルパンティエ、シェレ、ドラランド、フックス、ブルーンス、グラウプナー、J.S.バッハ、グルック、メンデルスゾーン、リスト、グノー、シェーンベルク、オネゲル、ミヨー、ペンデレツキ、アルヴォ・ペルト 等々 これらはほんの一例で、調べ上げれば相当な数にのぼるでしょう。この中からいくつかの作品についてCDでご紹介しておきましょう。
①ジョスカン・デプレ:深き淵より
ポール・ヒリヤー指揮 ヒリヤード・アンサンブル
EMI Classics 7492092
まずはフランドル楽派最大の巨匠、いやルネサンス期最高の作曲家といっても過言ではないジョスカン・デプレ(Josquin des Prez c1440-1521)の作品です。ジョスカンはモテ
 ットと呼ばれる声楽曲のスタイルを確立したこと
でも知られています。ミサ曲よりは短く、詩篇などを歌
詞とするモテットはグレゴリオ聖歌から発展したもので
すが、彼はそれまで一つの声部(テノール)だけが受け
持っていた旋律に対して4~6声のすべての声部を独立
させて均等に扱い、ポリフォニー(多声音楽)の黄金時代
を築き上げました。このCD(ジョスカン・デプレ作品
集)に収録された「深き淵より」は2曲あるうちの4声で作曲された方の曲ですが、両作品ともジョスカン晩年の作とされています。ルネサンス、ポリフォニー芸術の最高峰ともいえる素晴しい作品で、このモテット自体は10分にも満たない短い曲ですが、その果てしなく奥深い響きには胸を打たれます。ヒリヤード・アンサンブルの合唱も完璧なハーモニーで、盛期ルネサンスのまさしく頂点を極めた音楽といえるでしょう。是非一聴されることをお勧めします。なお、この4声の「深き淵より」は音楽辞典などによってはジョスカンの真作かどうか不明な作品として分類されています。でもその素晴しさには変わりありません。またこのモテットの最後には、詩篇にはない「願わくば、父と子と聖霊とに栄えあらんことを」という栄唱(ドクソロジア)が付け加えられています。
ットと呼ばれる声楽曲のスタイルを確立したこと
でも知られています。ミサ曲よりは短く、詩篇などを歌
詞とするモテットはグレゴリオ聖歌から発展したもので
すが、彼はそれまで一つの声部(テノール)だけが受け
持っていた旋律に対して4~6声のすべての声部を独立
させて均等に扱い、ポリフォニー(多声音楽)の黄金時代
を築き上げました。このCD(ジョスカン・デプレ作品
集)に収録された「深き淵より」は2曲あるうちの4声で作曲された方の曲ですが、両作品ともジョスカン晩年の作とされています。ルネサンス、ポリフォニー芸術の最高峰ともいえる素晴しい作品で、このモテット自体は10分にも満たない短い曲ですが、その果てしなく奥深い響きには胸を打たれます。ヒリヤード・アンサンブルの合唱も完璧なハーモニーで、盛期ルネサンスのまさしく頂点を極めた音楽といえるでしょう。是非一聴されることをお勧めします。なお、この4声の「深き淵より」は音楽辞典などによってはジョスカンの真作かどうか不明な作品として分類されています。でもその素晴しさには変わりありません。またこのモテットの最後には、詩篇にはない「願わくば、父と子と聖霊とに栄えあらんことを」という栄唱(ドクソロジア)が付け加えられています。②シュッツ:深き淵より SWV25~ダヴィデの詩篇歌集作品2より
コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン
コンチェルト・パラティーノ
harmonia mundi 901652/53
時代は16世紀から一気に100年ほど飛んでハインリッヒ・シュッツ(Heinrich Sch?tz1585-1672)のドイツ語によるモテットになります。シュッツはバッハのちょうど100年前に生まれた「ドイツ音楽の父」と呼ばれる大作曲家で、数多くの宗教音楽を残しています。こ
 の「ダヴィデの詩篇歌集」は彼の2
番目に出版(1619年)された26曲からなるモテット&教会
コンチェルト集で、「ダヴィデの詩篇曲集ならびに数曲の
モテットとコンチェルト集。8声あるいはそれ以上の声
部のための作品で、さらに二つのカペッラ(注:合唱を補
強するための楽団)を加えて三ないし四つの合唱団によっ
て演奏することも可能・・・」という正式なタイトルか
らもわかるように、二重合唱(もしくはそれ以上)と、それを更に補強するブラスや木管楽器を加えた管弦楽による壮麗な音楽を聴くことができます。ここには明らかにヴェネツイアで修業をしてきた影響がみてとれます。曲集全体はヴェネツィア楽派の音楽かと思えるほどステレオ効果満点の壮麗さで、彼の作品の中でもその絢爛さは群を抜いています。そうした中にあって8声(二つの合唱)で歌われるこの作品は他の作品ほどの華やかさはなく、地の底から湧き上がってくる様な響きで、5分にも満たない短い曲ながら名前の通り深遠な世界を味わうことができます。いきなり半音階で上昇する音楽にも驚かされます。シュッツも詩篇の最後に栄唱を加えています。この2枚組のCDはダヴィデ詩篇曲集の全曲を収録しています。カントゥス・ケルンの合唱とコンチェルト・パラティーノの器楽による音の対比(コンチェルト)も見事です。なおカントゥス・ケルンはここでもバッハのカンンタータ同様各声部一人による合唱になっています。ただし重唱で変にヴィブラートをかけてハーモニーを乱すようなことはなく、素晴しいハーモニーを聴かせてくれます。バッハ以前の合唱では各声部一人という歌い方は行われていたようです。合唱ももっと大きな編成で聴きたいという人は、全曲盤ではなく、この「深き淵より」も入っていませんが、ケンブリッジ・トリニティ・カレッジ合唱団によるCD(Conifer Records CDCF-190)もあります。シュッツの音楽にしてはちょっと響きが洗練されすぎているように思いますが、ステレオ効果は抜群です。
の「ダヴィデの詩篇歌集」は彼の2
番目に出版(1619年)された26曲からなるモテット&教会
コンチェルト集で、「ダヴィデの詩篇曲集ならびに数曲の
モテットとコンチェルト集。8声あるいはそれ以上の声
部のための作品で、さらに二つのカペッラ(注:合唱を補
強するための楽団)を加えて三ないし四つの合唱団によっ
て演奏することも可能・・・」という正式なタイトルか
らもわかるように、二重合唱(もしくはそれ以上)と、それを更に補強するブラスや木管楽器を加えた管弦楽による壮麗な音楽を聴くことができます。ここには明らかにヴェネツイアで修業をしてきた影響がみてとれます。曲集全体はヴェネツィア楽派の音楽かと思えるほどステレオ効果満点の壮麗さで、彼の作品の中でもその絢爛さは群を抜いています。そうした中にあって8声(二つの合唱)で歌われるこの作品は他の作品ほどの華やかさはなく、地の底から湧き上がってくる様な響きで、5分にも満たない短い曲ながら名前の通り深遠な世界を味わうことができます。いきなり半音階で上昇する音楽にも驚かされます。シュッツも詩篇の最後に栄唱を加えています。この2枚組のCDはダヴィデ詩篇曲集の全曲を収録しています。カントゥス・ケルンの合唱とコンチェルト・パラティーノの器楽による音の対比(コンチェルト)も見事です。なおカントゥス・ケルンはここでもバッハのカンンタータ同様各声部一人による合唱になっています。ただし重唱で変にヴィブラートをかけてハーモニーを乱すようなことはなく、素晴しいハーモニーを聴かせてくれます。バッハ以前の合唱では各声部一人という歌い方は行われていたようです。合唱ももっと大きな編成で聴きたいという人は、全曲盤ではなく、この「深き淵より」も入っていませんが、ケンブリッジ・トリニティ・カレッジ合唱団によるCD(Conifer Records CDCF-190)もあります。シュッツの音楽にしてはちょっと響きが洗練されすぎているように思いますが、ステレオ効果は抜群です。③・トマス・ゼレ:深き淵より
・クリストフ・ベルンハルト:深き淵より
・ヨハン・フィリップ・フェルチュ:深き淵より
・クリストフ・グラウプナー:カンタータ「深き淵より」
グレタ・ド・レジェル(S)、ジェイムズ・ボウマン(A)、ギィ・ド・メ(T)、マックス・ヴァン・エグモント(B)
リチェルカール・コンソート
Mercury MRIC-295
これら4人の作曲家の作品は文字通り「Aus der Tiefe」というタイトルのCDにバッハのカンタータとともに収録されており、すべてドイツ語の歌詞によるものです。
トマス・ゼレ(Thomas Selle 1599-1663)についてですが、不思議なことにこのCDの解説書にはこの作品についてはおろか、作曲者についても全く触れられていません。まるで収
 録されていないかのような扱いなのです。したがっ
てこの作品に関してはよくわかりません。ゼレはライプツ
ィヒで音楽を学んだ後、北西ドイツの諸都市でカントルや
指揮者を歴任し、1641年ハンブルクに移りそこで一生を終
えています。ハンブルクではヨハネウムというラテン語学
校のカントルとなり、聖マリア教会の司祭なども務め市の
教会音楽の発展に貢献しました。彼はモテットや教会コンチ
ェルト、リートなど多くの作品を残していますが、何といっても彼の作品の中で重要なのは「マタイ」「ヨハネ」の両受難曲で、バッハへとつながる「オラトリオ受難曲」の先駆的役割を果たしています(詳しくは以前連載した「ヨハネ受難曲をめぐって」の「8. バッハへの道」をご参照ください)。このモテット「深き淵より」はソプラノ2、アルト、テノール、バス、という5声部の合唱と通奏低音による5分ほどの短い作品です。曲想に相応しく静かな美しいハーモニーを聴くことができます。
録されていないかのような扱いなのです。したがっ
てこの作品に関してはよくわかりません。ゼレはライプツ
ィヒで音楽を学んだ後、北西ドイツの諸都市でカントルや
指揮者を歴任し、1641年ハンブルクに移りそこで一生を終
えています。ハンブルクではヨハネウムというラテン語学
校のカントルとなり、聖マリア教会の司祭なども務め市の
教会音楽の発展に貢献しました。彼はモテットや教会コンチ
ェルト、リートなど多くの作品を残していますが、何といっても彼の作品の中で重要なのは「マタイ」「ヨハネ」の両受難曲で、バッハへとつながる「オラトリオ受難曲」の先駆的役割を果たしています(詳しくは以前連載した「ヨハネ受難曲をめぐって」の「8. バッハへの道」をご参照ください)。このモテット「深き淵より」はソプラノ2、アルト、テノール、バス、という5声部の合唱と通奏低音による5分ほどの短い作品です。曲想に相応しく静かな美しいハーモニーを聴くことができます。クリストフ・ベルンハルト(Christoph Bernhardt 1628-92)はダンツィヒで音楽を学んだ後、ドレスデン宮廷の合唱隊に入りシュッツに師事し、そこで副楽長となります。その後ローマに留学し、帰国後ハンブルクに移ってゼレの後任として当市のカントルに就任。同時に主要な教会の音楽監督として活躍します。10年後、シュッツの後継者としてドレスデンに呼び戻され宮廷の副楽長、さらには楽長となり、当地で没しました。ミサやモテットなど多くの作品を残しています。シュッツの高弟でもあったことから、彼の葬送の音楽なども作曲しています。この「深き淵より」はソプラノ独唱とヴァイオリン、通奏低音のための7分ほどの長さの曲で、「深い淵の底から・・・」の言葉どおり、ソプラノとしてはかなり低い音域から天に向って上昇するように歌われます。技巧的な曲ではありませんが、歌手にとっては幅広い音域が要求されそうです。
ヨハン・フィリップ・フェルチュ(Johann Philipp F?rtsch 1652-1732)という作曲家は音楽辞典などにもあまり掲載されていません。解説書によるとフェルチュは医者、物理学者として活躍し、歌手として舞台に立っていたとも。作曲家としてはオペラや教会音楽を残しているそうですが、音楽は元々数学とも密接に関係しているので物理学とも通じるところがあるのかもしれません。この「深き淵より」もそうした理論家らしい一面が反映されていて、とても整った音楽というのが第一印象で、「ため息の音型」をはじめ随所に修辞学的な技法(聴き手の感情に、より強く訴えるために言葉に合わせて考案されたライトモチーフのような音型の使用)が用いられています。曲は8分ほどの長さで、これもソプラノ・ソロのために書かれていて、器楽はヴァイオリンとガンバ、通奏低音となっています。憂いに満ちたとても美しい作品です。
クリストフ・グラウプナー(Christoph Graupner 1683-1760)はバッハとほぼ同世代の作曲家で、彼については既に何度かここで紹介してきましたので今更記載することもないと思いますが、彼はクーナウが死んでトーマスカントルが空席になった際、市当局からテレマンの次に白羽の矢が立てられた作曲家でした。つまり当時はバッハよりも上位にランクされた作曲家だったのです。彼に断られたことで、市はいやいやバッハを任命したわけです。彼がそのままトーマスカントルに就任していたら、バッハの運命も大きく変わっていたことでしょう。グラウプナーは生涯に教会カンタータを1,418曲書いており、そのほかオペラ、協奏曲、管弦楽曲を多数残しており、カンタータだけとってもたいへんな多作家でした。多作家なのでこれはつまらない作品かと思いきや、なかなかに聴かせてくれます。3楽章からなる14分ほどの曲で、中央にレチタティーヴォ、両脇に合唱、という構造になっています。彼はダルムシュタットの宮廷に慰留されて残ったのですが、そこの礼拝堂では合唱は各パート一人で歌われていたそうで、ここでもそのように歌われています。この曲、彼がライプツィヒ市からカントル職を依頼されて出むいた際にも当地で演奏された作品、と解説書には書かれています。既にホモフォニーへの移行が感じられ、バッハよりも新しさを感じます。と言ってもやはりバッハほどの感動は望むべくもありません。レチタティーヴォもアリオーソに近く、伴奏もただ和音を連ねているだけではありません。終曲の合唱も躍動感があり、この詩篇の内容に相応しいかどうかは別にしてとても楽しめます。
このCDの演奏について触れておきますと、フィリップ・ピエルロを中心とするベルギーの古楽団体による器楽の演奏はその音色といい、古楽に相応しく、素晴しいものです。ただ少し声楽に不満を感じます。原因はやはりヴィブラートです。途中でも触れましたが、このCDの声楽は合唱もすべて各パート一人によっています。つまりソリストが合唱もかねています。合唱の部分で声を震わせると、どうしてもハーモニーは乱れます。ここではそれほど大きくヴィブラートをかけてはいませんが、それでも僅かとはいえハーモニーは乱れます。一人で合唱を歌うことを否定するつもりはありませんが、重唱ではせめて声を震わせることは止めて欲しいものだと思います。
④ブルーンス:「深き淵より」
ハリー・ヴァン・デル・カンプ(B)
ピリオド・インストゥルメント・アンサンブル
SONY CLASSICAL SICR-1886
北ドイツ・オルガン楽派の作曲家ニコラウス・ブルーンス(Nicolaus Bruhns 1665-97)はブクステフーデの弟子で、才能に恵まれオルガンとヴァイオリンの名手として活躍しましたが、32歳という若さで世を去りました。彼は一人でオルガンとヴァイオリンを同時に弾いて聴衆を唖然とさせた、という逸話が残されています。つまりオルガンのペダルでバスを弾き、二本の腕でヴァイオリンを弾いた(しかも重音奏法で)わけです。彼はブクステフーデの推薦で若くしてシュレスヴィヒ地方フーズムの市立教会のオルガニストとなり、
 オルガン曲や宗教曲を数多く作曲しました
が、そのほとんどは散逸してしまい教会コンチェルト12
曲とオルガン作品が5曲残されているだけです。「前奏曲と
フーガ」などブクステフーデの作品に劣らず重厚で実に堂
々としており、これらはいずれもバッハへとつながる重要
な作品とされています。この教会コンチェルト(カンター
タ)「深き淵より」はプロテスタントの音楽でありながら
ラテン語の歌詞によっています。以前にも書きましたが、バッハもラテン語のミサ・ブレヴィスを書いているように、この時代はプロテスタントの教会でも一部ラテン語による礼拝が行われていましたので不自然なことではありません。この作品、彼が過ごした北海沿岸の町フーズムを象徴するように冷たい、暗い響きを持っています。しかしそこには内に秘められた意思の強さのようなものを感じます。単一楽章ながら14分ほどのやや長い曲ですが、暗い前奏の後レチタティーヴォ風のアリオーソ、アレグロによる早いパッセージをはさんで、再びゆるやかなアリア、アレグロ、と緩・急・緩が交互に現れるように進みます。冒頭の通奏低音に聴かれるオルガンや、アレグロ部分のヴァイオリンの使い方が巧みで、彼のオルガニスト&ヴァイオリニストとしての才能の豊かさがいかんなく発揮されています。古楽を得意とするヴァン・デル・カンプの名唱も光ります。オーケストラはピリオド・インストルメント・アンサンブルというちょっと安直な名称の団体で、おそらくはこの録音のために集められた寄せ集めのメンバーかと思いますが、名プロデューサー、ヴォルフ・エリクソンによるものだけあって名手揃いで、とくにルーシー・ファン・ダールのヴァイオリン(1643年製ニコロ・アマティ)が光ります。このCDはバスのために書かれたカンタータを集めていて、シュッツやブクステフーデ、ローゼンミュラーの他にやはり北ドイツ楽派のトゥンダー(Franz Tunder 1614-67)、マティアス・ヴェックマン(Matthias Weckmann c1619-74)といった珍しい作曲家の作品も収めています。
オルガン曲や宗教曲を数多く作曲しました
が、そのほとんどは散逸してしまい教会コンチェルト12
曲とオルガン作品が5曲残されているだけです。「前奏曲と
フーガ」などブクステフーデの作品に劣らず重厚で実に堂
々としており、これらはいずれもバッハへとつながる重要
な作品とされています。この教会コンチェルト(カンター
タ)「深き淵より」はプロテスタントの音楽でありながら
ラテン語の歌詞によっています。以前にも書きましたが、バッハもラテン語のミサ・ブレヴィスを書いているように、この時代はプロテスタントの教会でも一部ラテン語による礼拝が行われていましたので不自然なことではありません。この作品、彼が過ごした北海沿岸の町フーズムを象徴するように冷たい、暗い響きを持っています。しかしそこには内に秘められた意思の強さのようなものを感じます。単一楽章ながら14分ほどのやや長い曲ですが、暗い前奏の後レチタティーヴォ風のアリオーソ、アレグロによる早いパッセージをはさんで、再びゆるやかなアリア、アレグロ、と緩・急・緩が交互に現れるように進みます。冒頭の通奏低音に聴かれるオルガンや、アレグロ部分のヴァイオリンの使い方が巧みで、彼のオルガニスト&ヴァイオリニストとしての才能の豊かさがいかんなく発揮されています。古楽を得意とするヴァン・デル・カンプの名唱も光ります。オーケストラはピリオド・インストルメント・アンサンブルというちょっと安直な名称の団体で、おそらくはこの録音のために集められた寄せ集めのメンバーかと思いますが、名プロデューサー、ヴォルフ・エリクソンによるものだけあって名手揃いで、とくにルーシー・ファン・ダールのヴァイオリン(1643年製ニコロ・アマティ)が光ります。このCDはバスのために書かれたカンタータを集めていて、シュッツやブクステフーデ、ローゼンミュラーの他にやはり北ドイツ楽派のトゥンダー(Franz Tunder 1614-67)、マティアス・ヴェックマン(Matthias Weckmann c1619-74)といった珍しい作曲家の作品も収めています。これ以外にもまだありますが、これ以上触れていくと長くなりますので最後にまとめて書いておきます。あと私の手元にある「深き淵より」のCDではローゼンミュラー(Johann Rosenm?ller c.1619-84)のラテン語による教会コンチェルト(カトリックのヴェネツィア時代の作品。カントゥス・ケルン、deutsche harmonia mundi BVCD-605 「宗教コンチェルト集」)、シェレ(Johann Schelle 1648-1701)のドイツ語歌詞によるカンタータ(カントゥス・ケルン deutsche harmonia mundi 88697 281822/28 「バッハ以前のトーマスカントル達」)、フックス(Johann Joseph Fux 1660-1741)のモテットK54(クレマンシック・コンソート ARTE NOVA CLASSICS BVCE-38107 「皇帝レクイエム~フックス作品集」)などがあります。ローゼンミュラーの作品は彼の他の作品と比べると華やかさはありませんが、それでも冒頭部分を除くとあまり暗さは感じられません。器楽、声楽、合唱の掛け合いの妙(コンチェルト)を楽しむ作品といえるでしょう。これも最後に栄唱の言葉が添えられています。シェレはバッハの2代前のトーマスカントルで、彼の功績は、何と言ってもドイツ語の教会カンタータを始めてトーマス教会の礼拝に導入したことです。この「深き淵より」もその一つで、これを聴いているとバッハの初期のカンタータと共通する響きを感じます。詩に関しても聖書の詩篇に宗教的自由詩を既に加えており、こうしたことは後にコラールなども含んだカンタータの成立に大きな影響を与えることとなります。フックスはウィーンの宮廷楽長やシュテファン大聖堂の楽長を務めたオ-ストリアの作曲家で、約80曲のミサ曲や詩篇など多くの教会音楽のほかオペラやシンフォニア、ソナタなどの器楽曲も残しています。また彼の名は対位法の理論と実践を書いて後のウィーン古典派の音楽に大きな影響を与えた音楽理論書「グラドゥス・アド・パルナッスム(1725)」の著者としても知られています。この「深き淵より」はアカペラで歌われる4分ほどの短い曲で、いかにもカトリックの音楽らしい保守的な作風で、バロックというよりはルネサンス後期のポリフォニーを聴いているようです。
以上ざっとご紹介してきましたが、フランスの作品をとりあげることができませんでした。フランスではヴェルサイユ楽派による壮麗なモテット(管弦楽伴奏による「グラン・モテ」やオルガンもしくは通奏低音のみの伴奏による「プチ・モテ」)が作曲され、詩篇に基づく作品も多くあります。「深き淵より」でよく知られているのはドラランド(Michel-Richard de Lalande 1657-1726)のグラン・モテで、これはかつてステファヌ・カイヤ指揮・合唱団(パイヤール室内管)によるCDがエラートから発売されたことがあり(R20E-1009)私も持っているのですが、今回どうしてもそれが見つからずご紹介できませんでした。この曲は現在全くCDで発売されていませんのでそれ以外で聴くことができませんが、とても素晴しい作品だったことを覚えています。ノルベール・デュフルクの「フランス音楽史」には次のように記されています。
「すべての偉大な頁の中で、いまのところ最も有名なものとしては『デ・プロフンディス』がある。冒頭の合唱は・・(中略)・・ただちに感動的な調子を生みだす五重の対位法のなかで一つにまとまる。・・(中略)・・こうした頁のすべてが、フランスとイタリアの二様式の結合を実現することのできたドラランドの驚くべき手腕を物語っている。つまりドラランドのなかでは、H・デュ・モンとM=A・シャルパンティエが重なり合い一つになって、あのバッハとヘンデルという、驚くべき名前を予告しているのである。」(白水社、遠山一行・平島正郎・戸口幸策 訳)それともう一つ、ルターの「深き淵より」について触れませんでしたが、ルターは1523~24年にかけて聖書のドイツ語訳と平行していくつかの詩篇をコラールとして作曲しており、それにはこの「深き淵より」も含まれています。現在讃美歌21の第160番「深き悩みより」として親しまれていますが、これは聖書詩篇のドイツ語訳と少し異なっています。詩篇は"Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir"で、これに対しコラールは"Aus tiefer Not schrei ich zu dir"となっています。バッハはこのコラールに基づいたカンタータも1724年に作曲しており、それはカンタータ第38番「深き悩みの淵より、われ汝に呼ばわる」(BWV38)というタイトルで知られているものです。
最後に参考までに「新共同訳聖書」による詩篇130番の詩を掲載しておきます。
都に上る歌
深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。
主よ、この声を聞き取ってください。
嘆き祈るわたしの声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら
主よ、誰が耐ええましょう。
しかし、赦しはあなたのもとにあり
人はあなたを畏れ敬うのです。
わたしは主に望みをおき
わたしの魂は望みをおき
御言葉を待ち望みます。
わたしの魂は主を待ち望みます。
見張りが朝を待つにもまして
見張りが朝を待つにもまして。
イスラエルよ、主を待ち望め。
慈しみは主のもとに
豊かな贖い主のもとに。
主は、イスラエルを
すべての罪から贖ってくださる。
2011.11.24 (木) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑬
12. 願わくば一条の光を―Ⅲ: CDの話-カンタータBWV198「侯妃よ、願わくばなお一条の光を」
このカンタータの項を終わらせるにあたって、CDについてごく簡単にご紹介しておきましょう。
このカンタータのCDは第106番ほど多く録音されていません。また前回も触れたようにルスト版によるCDは見当たりません。私が持っているCDも3種類しかなく、それは以下のとおりです(録音順)。
① フィリップ・ヘレヴェッヘ指揮 シャペル・ロワイヤル管弦楽団&合唱団
イングリッド・シュミットフューゼン(S)、チャールズ・ブレット(A)、ハワード・クルック(T)、ペーター・コーイ(B)
仏harmonia mundi HMG 501270
② ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 イングリッシュ・バロック・ソロイスツ モンテヴェルディ合唱団
ナンシー・アルジェンタ(S)、マイケル・チャンス(A)、アントニー・ロルフ・ジョンソン(T)、スティーヴン・ヴァルコー(B)
Archiv POCA-1025
③ トン・コープマン指揮 アムステルダム・バロック管弦楽団&合唱団
リサ・ラーション(S)、エリーザベト・フォン・マグヌス(A)、ポール・アグニュー(T)、クラウス・メルテンス(B)
ERATO WPCS-5705~07
この3種類の録音は当たり前のことですが、三者三様でそれぞれに良さがあり、どれがベストとはちょっと決められません。そのときどきの私の気分で選択して聴いています。三種とも古楽器による演奏で、この作品に関してはコアトーンなどの問題も存在しないため、同じカンマートーンによって演奏されています。つまり現代のピッチより半音低い a=415になっています。
 ヘレヴェッヘ盤の特徴は、ちょっと表現が難しいの
ですが響きが何とも典雅で心地よいのです。特に第5
曲のアルトのソロで聴かれるガンバの響きや柔らかな
リュートの音色など他の盤ではちょっと聴けません。
ちょっとリュートが目立ちすぎ、といえなくもありま
せんが。またチャールズ・ブレットのカウンターテナ
ーも名演といえます。合唱は各パート4人で構成されていますが、ブックレットの記載が正しいとすれば、この合唱には4人のアルトに加えて4人のカウンターテナーが補強されています。オーケストラの弦楽器は、4,3,2,2,1で、これにトラヴェルソ2、オーボエ&オーボエ・ダモーレ各2の管楽器とガンバ2、リュート2そして通奏低音としてポジティブ・オルガンが加わっています。「記載が正しいとすれば」と書いたのは、このCDのブックレット、とんでもない間違いがあったからです。このCDにはもう1曲有名なBWV78の「イエスよ、汝はわが魂を」というカンタータが収録されているのですが、その作曲者の表示が何とフォーレ/メサジェとなっていて(恐らく二人の共作になる「小ミサ曲」と間違えたもの)、こんなこと日本だったら回収ものになるようなミスなので(ジャケット本体にはない)、今一つ記載内容に不安があるのです。とても豪華な装丁の別冊ブックレットなのにこんな間違いがあるとは、いかにもラテン国らしい大らかさといえるでしょう。合唱にカウンターテナーが加わっているかどうかは、私の耳では区別できませんでした。ただここに聴かれる合唱のやわらかい響きは素晴しく、それはカウンターテナーの補強、つまり内声部を厚くしている結果かもしれません。部分的に補強していることも考えられます。そうしたことによるものかどうかは別にして、こと合唱については三種類の中ではこれが一番いい、と私は思っています。ただこの盤には欠点も二つあります。最大の欠点はソプラノ・ソロのピッチが不安定でちょっと自分の耳がおかしくなります。特に第2曲のレチタティーヴォに顕著で、アリアでもその傾向が見られます。更にオーケストラの木管のピッチなどもごく僅かですが不揃いになるところがあります(第6曲テノールのレチタティーヴォの最後の和音など)。1987年というまだ古楽演奏に課題をかかえていた頃の録音で、特に管楽器などは技術的に現代の水準とは隔たりのあった時代です。それと一点補足しておきたいのは、ブックレットにチェンバロ(通奏低音)の記載がありません。初演の際に「チェンバロをバッハが弾いた」という記事があったことは以前ご紹介したとおりなので、当然使用している筈と思い、よく聴いてみるとやはりチェンバロは使用しています。ブックレットの記載から漏れたようです。いろいろありますが先にも触れたように、合唱が素晴しいこと、そして響き全体がとても優しくそれらの欠点を補って余りある演奏だと思います。私にとっては一番聴く機会の多いCDです。
ヘレヴェッヘ盤の特徴は、ちょっと表現が難しいの
ですが響きが何とも典雅で心地よいのです。特に第5
曲のアルトのソロで聴かれるガンバの響きや柔らかな
リュートの音色など他の盤ではちょっと聴けません。
ちょっとリュートが目立ちすぎ、といえなくもありま
せんが。またチャールズ・ブレットのカウンターテナ
ーも名演といえます。合唱は各パート4人で構成されていますが、ブックレットの記載が正しいとすれば、この合唱には4人のアルトに加えて4人のカウンターテナーが補強されています。オーケストラの弦楽器は、4,3,2,2,1で、これにトラヴェルソ2、オーボエ&オーボエ・ダモーレ各2の管楽器とガンバ2、リュート2そして通奏低音としてポジティブ・オルガンが加わっています。「記載が正しいとすれば」と書いたのは、このCDのブックレット、とんでもない間違いがあったからです。このCDにはもう1曲有名なBWV78の「イエスよ、汝はわが魂を」というカンタータが収録されているのですが、その作曲者の表示が何とフォーレ/メサジェとなっていて(恐らく二人の共作になる「小ミサ曲」と間違えたもの)、こんなこと日本だったら回収ものになるようなミスなので(ジャケット本体にはない)、今一つ記載内容に不安があるのです。とても豪華な装丁の別冊ブックレットなのにこんな間違いがあるとは、いかにもラテン国らしい大らかさといえるでしょう。合唱にカウンターテナーが加わっているかどうかは、私の耳では区別できませんでした。ただここに聴かれる合唱のやわらかい響きは素晴しく、それはカウンターテナーの補強、つまり内声部を厚くしている結果かもしれません。部分的に補強していることも考えられます。そうしたことによるものかどうかは別にして、こと合唱については三種類の中ではこれが一番いい、と私は思っています。ただこの盤には欠点も二つあります。最大の欠点はソプラノ・ソロのピッチが不安定でちょっと自分の耳がおかしくなります。特に第2曲のレチタティーヴォに顕著で、アリアでもその傾向が見られます。更にオーケストラの木管のピッチなどもごく僅かですが不揃いになるところがあります(第6曲テノールのレチタティーヴォの最後の和音など)。1987年というまだ古楽演奏に課題をかかえていた頃の録音で、特に管楽器などは技術的に現代の水準とは隔たりのあった時代です。それと一点補足しておきたいのは、ブックレットにチェンバロ(通奏低音)の記載がありません。初演の際に「チェンバロをバッハが弾いた」という記事があったことは以前ご紹介したとおりなので、当然使用している筈と思い、よく聴いてみるとやはりチェンバロは使用しています。ブックレットの記載から漏れたようです。いろいろありますが先にも触れたように、合唱が素晴しいこと、そして響き全体がとても優しくそれらの欠点を補って余りある演奏だと思います。私にとっては一番聴く機会の多いCDです。 ②のガーディナー盤は、前回とりあげたBWV106とカップリングされていますので、これからこの二つのカンタータを聴いてみたいという人にはこれがいいかもしれません。これもとてもいい演奏です。3種類のなかではテン
ポはこれが一番早く、その分引き締まった演奏になって
います。ただ残響が多いことと、全体的にややレガート
な奏法のためか古楽特有の鋭角的な響きには少し欠けま
す。この演奏の最大の利点はソリストの粒が揃っていて、
もっとも安定した歌唱が聴けることです。テノールのア
リアで聴かれるロルフ・ジョンソンの名唱は聴きものと
いえるでしょう。またテンポの速さは特に終曲などに生かされ、合唱の力強さが目立ちます。私の好きなカウターテナーのチャンスはここでもいい声を聴かせてくれるのですが、低音域がちょっと苦しそうに聴こえます。このCD、バッハの葬儀に関連したカンタータを3曲(もう1曲はモテットと呼ばれるBWV118の「おお、イエス・キリスト、わが生命の光」)収録していて、企画としてはたいへん面白いものですが、初期のカンタータといっしょに録音するとなると、コアトーンの問題が生じてちょっと無理がでてくるのではないでしょうか。合唱の規模はやや大きく、8,6,6,6という編成になっています。オーケストラの弦楽器はヘレヴェッヘ同様4,3,2,2,1で、これにトラヴェルソ2、オーボエ&オーボエ・ダモーレ2の管楽器とガンバ2とリュート2、そして通奏低音としてチェンバロ、オルガンが加わっています。
②のガーディナー盤は、前回とりあげたBWV106とカップリングされていますので、これからこの二つのカンタータを聴いてみたいという人にはこれがいいかもしれません。これもとてもいい演奏です。3種類のなかではテン
ポはこれが一番早く、その分引き締まった演奏になって
います。ただ残響が多いことと、全体的にややレガート
な奏法のためか古楽特有の鋭角的な響きには少し欠けま
す。この演奏の最大の利点はソリストの粒が揃っていて、
もっとも安定した歌唱が聴けることです。テノールのア
リアで聴かれるロルフ・ジョンソンの名唱は聴きものと
いえるでしょう。またテンポの速さは特に終曲などに生かされ、合唱の力強さが目立ちます。私の好きなカウターテナーのチャンスはここでもいい声を聴かせてくれるのですが、低音域がちょっと苦しそうに聴こえます。このCD、バッハの葬儀に関連したカンタータを3曲(もう1曲はモテットと呼ばれるBWV118の「おお、イエス・キリスト、わが生命の光」)収録していて、企画としてはたいへん面白いものですが、初期のカンタータといっしょに録音するとなると、コアトーンの問題が生じてちょっと無理がでてくるのではないでしょうか。合唱の規模はやや大きく、8,6,6,6という編成になっています。オーケストラの弦楽器はヘレヴェッヘ同様4,3,2,2,1で、これにトラヴェルソ2、オーボエ&オーボエ・ダモーレ2の管楽器とガンバ2とリュート2、そして通奏低音としてチェンバロ、オルガンが加わっています。 ③のコープマン盤ですが、この中ではもっともテンポ
が遅く、その意味では葬儀の音楽にもっとも相応しいと
いえるかもしれません。冒頭の合唱からゆっくりと、ま
るで足を引きずりながら歩くように重く沈痛な響きに満
ちており、これはあたかも当日ニコライ教会からパウリー
ナ教会まで繰り広げられた葬列がそのまま教会に持ち込
まれたかのような印象を覚えます。合唱の規模は解説書
の記載によれば9,6,8,6で、これも三種の中ではもっとも大きなものになっています。ただこのCD「ライプツィヒ時代の世俗カンタータⅠ」という3枚組の中の1曲で、個別の曲に関しては触れていませんので、全員が歌ったものなのかどうかまで、ちょっとわかりません。でも聴感上も合唱の規模は大きく聴こえます。世俗カンタータの中に組み込むというのは少し無理があると思いますが、確かにこの曲は分類上の難しさを抱えていてどのカンタータと組み合わせて録音するかは難しい問題かもしれません。このCDではこのあとにBWV215の世俗カンタータ「おのが幸を讃えよ、祝されしザクセン」が続いており、がらっと曲調が変わってしまうのでとてもアンバランスに感じます(冒頭の曲がロ短調ミサのホサンナに転用されたものだとはいえ)。合唱の規模が大きいのも世俗作品と捉えたからかもしれません。またここではアルトのソロも、カウンターテナーではなく女性によるアルトで歌われています(理由はわかりませんがコープマンは他のカンタータでも曲によってアルト歌手を女性と男性で使い分けています)。ソリストもガーディナー盤と遜色のない歌唱を聴かせてくれます。ソプラノもしっかりしていて、アリアの歌唱では力強さが光ります。その「黙りなさい!」というたしなめの言葉を受けつぐアルトのレチタティーヴォ「震える鐘の響よ」では、全体が遅いテンポの中、ここだけとても速いテンポで歌われており、それが劇的な効果を生んでいます。第二部冒頭のテノールのアリアもしっとりと情感たっぷりに歌われ、悲しみに満ちています。終曲の合唱は、これだけテンポが遅いとちょっと間延びした印象を受け、私はもう少し早いほうが好きですが、テンポが遅い分表情豊かに歌われています。後半部分の繰り返しでは一回目よりやや強く歌われるなど劇的な表現も見られます。その他では全体的にチェンバロの即興性(コープマン自身が弾いている)や、合唱でも装飾音を随所に聴かせるなど、コープマンの古楽研究家としての顔があちこちで散見されます。オーケストラの規模はヴァイオリン8(第1、第2の区別不明)、ヴィオラ以下2,2,1で、これにトラヴェウソなどの管楽器、ガンバ、リュ-トなどが加わり、通奏低音にはオルガンとチェンバロも使用されています。これもとてもいい演奏だと思います。私の持っているCDはかつてエラート・レーベルから発売されたものですが、全集録音のプロジェクトをエラートが放棄してしまいましたので、現在ではこの録音Challenge Classicsというレーベルから発売されていることを付記しておきます。
③のコープマン盤ですが、この中ではもっともテンポ
が遅く、その意味では葬儀の音楽にもっとも相応しいと
いえるかもしれません。冒頭の合唱からゆっくりと、ま
るで足を引きずりながら歩くように重く沈痛な響きに満
ちており、これはあたかも当日ニコライ教会からパウリー
ナ教会まで繰り広げられた葬列がそのまま教会に持ち込
まれたかのような印象を覚えます。合唱の規模は解説書
の記載によれば9,6,8,6で、これも三種の中ではもっとも大きなものになっています。ただこのCD「ライプツィヒ時代の世俗カンタータⅠ」という3枚組の中の1曲で、個別の曲に関しては触れていませんので、全員が歌ったものなのかどうかまで、ちょっとわかりません。でも聴感上も合唱の規模は大きく聴こえます。世俗カンタータの中に組み込むというのは少し無理があると思いますが、確かにこの曲は分類上の難しさを抱えていてどのカンタータと組み合わせて録音するかは難しい問題かもしれません。このCDではこのあとにBWV215の世俗カンタータ「おのが幸を讃えよ、祝されしザクセン」が続いており、がらっと曲調が変わってしまうのでとてもアンバランスに感じます(冒頭の曲がロ短調ミサのホサンナに転用されたものだとはいえ)。合唱の規模が大きいのも世俗作品と捉えたからかもしれません。またここではアルトのソロも、カウンターテナーではなく女性によるアルトで歌われています(理由はわかりませんがコープマンは他のカンタータでも曲によってアルト歌手を女性と男性で使い分けています)。ソリストもガーディナー盤と遜色のない歌唱を聴かせてくれます。ソプラノもしっかりしていて、アリアの歌唱では力強さが光ります。その「黙りなさい!」というたしなめの言葉を受けつぐアルトのレチタティーヴォ「震える鐘の響よ」では、全体が遅いテンポの中、ここだけとても速いテンポで歌われており、それが劇的な効果を生んでいます。第二部冒頭のテノールのアリアもしっとりと情感たっぷりに歌われ、悲しみに満ちています。終曲の合唱は、これだけテンポが遅いとちょっと間延びした印象を受け、私はもう少し早いほうが好きですが、テンポが遅い分表情豊かに歌われています。後半部分の繰り返しでは一回目よりやや強く歌われるなど劇的な表現も見られます。その他では全体的にチェンバロの即興性(コープマン自身が弾いている)や、合唱でも装飾音を随所に聴かせるなど、コープマンの古楽研究家としての顔があちこちで散見されます。オーケストラの規模はヴァイオリン8(第1、第2の区別不明)、ヴィオラ以下2,2,1で、これにトラヴェウソなどの管楽器、ガンバ、リュ-トなどが加わり、通奏低音にはオルガンとチェンバロも使用されています。これもとてもいい演奏だと思います。私の持っているCDはかつてエラート・レーベルから発売されたものですが、全集録音のプロジェクトをエラートが放棄してしまいましたので、現在ではこの録音Challenge Classicsというレーベルから発売されていることを付記しておきます。このカンタータBWV198は録音が少ないと始めに書きましたが、この項を書き終える直前友人が調べてリストを送ってくれました。もちろん私もそのうちのいくつかは知っていましたが、それによるとこれまで全部で15種類の録音があるそうです。古いものではヘルマン・シェルヘンのウェストミンスター盤があり、その他ハンス=ヨアヒム・ロッチュ指揮によるものやヘルムート・リリング指揮のものなどがあります。ただほとんどが廃盤になっていて大型レコード店に行ってもなかなかこれらを入手するのは難しく、時々見かけるのはアーノンクール=レオンハルトによるテルデックの全集からレオンハルト指揮によるものと、比較的新しい録音になるフィリップ・ピエルロ指揮リチェルカーレ・コンソートによるCDくらいしか見当たりません。後者はいわゆる「リフキン方式」によるもので、合唱パートは一人で歌われています。素晴しい作品なのでいろいろな録音がもっと手に入りやすいといいのですが。
2011.09.25 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑫
11. 願わくば一条の光を―Ⅱ: 忘れ去られた版をめぐって―カンタータBWV198「侯妃よ、願わくばなお一条の光を」
1731年の聖金曜日には「マルコ受難曲」が上演されたことが知られています。この受難曲の楽譜がすべて失われてしまったことから今ではバッハの幻の受難曲になってしまいましたが、その歌詞だけは残されています。1732年に出版されたピカンダー(本名 Christian Friedrich Henrici 1700-64)の詩集にその台本が含まれていたからです。その台本をもとにその復元への道が開かれました。そしていくつかのことがわかってきます。例えば歌詞からどこでどんなコラールが使用されたかは比較的容易にたどることができます。そしてその他のアリアや合唱曲は韻律をもとに過去の作品と照らし合わせながらどんな曲であったかを検証していったのです。ご存知のとおり、 バッハは受難曲で過去の作品からの転用(「パロディ」といわれる)を盛んに行っています。そんなことからこの方法による検証でかなりのことがわかってきたのです。といってもこれは気の遠くなるような困難な作業だったと思います。また転用があるとはいえすべてではありませんので完全に復元することは不可能でしょう。レチタティーヴォは過去の作品とは関係ありませんし。ガイリンガーはこの曲が全部で132曲から成り立っていると書いていますが、現在入手可能な同曲のCDにはせいぜい40~60曲前後しか収録されていません。この曲については機会がありましたら別にとりあげてみたいと思いますのでこれ以上深入りしませんが、ひとつだけ触れておきたいと思います。19世紀半ばから始まった旧バッハ全集の刊行とともにその主幹でもあったヴィルヘルム・ルスト(Wilhelm Rust 1822-92)やシェリング(Arnold Schering 1877-1941)、スメント(Friedrich Smend 1893-1980)といった学者の研究により、マルコ受難曲はこのカンタータからの転用を中心に作曲されたということが指摘されたのです。具体的には10曲あるうちの第1,3,5,8,そして第10曲が転用されています。つまりレチタティーヴォを除くと第一部終曲の合唱を除きその全てが再使用されていることになります。しかも冒頭と終曲の合唱はそのまま歌詞を変えて使用されています(コープマンはそれに異を唱えているようですが)。更に第1曲と終曲の合唱は1729年の3月に演奏された「ケーテン公レオポルトのための葬送音楽」BWV244aにも使用されているのです(この作品も残念ながら歌詞しか残されていません)。それだけこのカンタータに対するバッハの思い入れは深く、たった一度の機会だけの音楽で終わらせたくなかったのでしょう。
ところでこのカンタータにはもう一つ版が存在します。この版については現在顧みられることもなく、解説などでもまったく触れられることがありません。私も知らなかったのですが、今回この作品について調べているうちにその存在を知った次第です。もちろんCDなどもないと思います(ひょっとして古いレコードにはあるかもしれませんが)。シュヴァイツァーの「バッハ」第3巻の一節に次のような記述があります。
「ルストはバッハ協会版全集にみずからの手になる万霊節用の改作歌詞を添えることによって、バッハのこのすばらしい作品のために大きな功績を挙げた。『哀悼頌』の演奏のたびごとにそれをいつもクリスティアーネ・エーバーハルディーネのための記念祭にするというわけにもいかないから、現今の演奏は一般にルストの改作歌詞によるのである。」(浅井真男、内垣啓一、杉山好訳 白水社)この記述からいくつかわかることがあります。まずヴィルヘルム・ルストによって改作された歌詞が存在すること。そしてそれは、ザクセン侯妃クリスティアーネ・エーバーハルディーネのための歌詞ではなく、万霊節のための詞に変えられていること、そしてそれがかつて実際に演奏されていたこと、等々です。ヴィルヘルム・ルストは1880年から92年までトーマスカントルの地位にあり、そしてバッハの没後100年を記念して1850年から始められた旧バッハ全集版の刊行に中心的役割を果たした音楽学者でした。その彼が万霊節用に歌詞を改めたのですが、この万霊節とはキリスト教における「死者の日」で、カトリックでは11月2日と決められています(日曜日と重なる場合はその翌日)。クラシック・ファンならリヒャルト・シュトラウスの歌曲でこの名前だけは知っているかと思います。余談ながらその前日の11月1日は「万聖節(諸聖人の日Hallowmas)」で、さらにその前日は最近日本でも子供たちに人気のある「ハロウィン("Hallow Eve"が語源)」になります。これらはすべて死者を偲ぶ(というより死者の魂を年に一度この世に迎える)ための一連の行事なのです。日本の「お盆」に似ていますね。この万霊節、プロテスタントでは特に日にちは決められていないようですが、それでも同じような時期に「昇天者記念日」として礼拝が行われたりします。万霊節のための音楽、つまりそれは死者のための音楽であり、形式上の問題からは同一視できませんが、まさにレクイエムそのものといっていいのではないでしょうか。ドイツ語の歌詞ですから「ドイツ・レクイエム」ということになります。ルストによる改作がいつ頃行われたものかはわかりませんが、彼は1862年から74年までベルリン・バッハ連盟の指揮者として盛んにバッハの宗教曲を演奏しその普及に努めていましたので、おそらくその時代に改作したものではないでしょうか。そしてシュヴァイツアーの「バッハ」が出版されたのが1908年ですので、その当時はこの版によって演奏されていたことがわかります。では日本ではどうでしょうか?もちろんこれを調べるのはちょっとたいへんな作業です。バッハのカンタータを歌う合唱団の数はアマチュアを含めると今やものすごい数になっています(プロは少ない)。樋口隆一著「バッハから広がる世界」(春秋社)の一章に「日本のバッハ受容」という項があり、わが国の歴史的なバッハ演奏について触れられていますが、もちろんここにこの曲は登場しません。そこでいくつかの合唱団に絞って調べてみると、1985年に設立されたバッハ研究会合唱団が2001年の7月に定期公演でこのカンタータをとりあげていました(もちろん原曲の歌詞による)。そのほかバッハ・コレギウム・ジャパンも、芸大の「カンタータクラブ」や「東京バッハ合唱団」などもこの作品を演奏したという記録は見つかりません。いずれにしても日本におけるバッハ・カンタータの演奏はまだ歴史も浅く最近のことなので、まずは原曲どおり歌うことに主眼がおかれるのは致し方ないことでしょう。ですからおそらくこのルスト版が日本で演奏されたことはないと思います。最後に原曲とルスト版の歌詞を比較できるように載せておきましたので、ご参照ください。原曲のタイトルが"Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl"で「侯妃よ、願わくばなお一条の光を」と一般に訳されていますが、これが"Lass, Höchster, lass der Hoffnung Strahl"に変わっていますので、「主よ、希望の光をお与えください」とでも訳せましょうか。この版の存在を知り、私のルスト版探しが始まりました。
いろいろ調べた結果何とかこの版を見つけることができました。ブライトコップフから出版されていて、そのヴォーカル・スコアを入手することができたのです。ところが私が入手したスコアもどうやらルストのオリジナルではないようです。というよりルストは恐らく歌詞だけ変えて、楽譜までは出版しなかったのかもしれません。シュヴァイツアーが書いているように旧全集版の出版の際にこの改作された歌詞が添えられていたのかもしれません。このカンタータのルスト校訂による旧全集版は第13巻に含まれており、その出版は1865年になります。このヴォーカル・スコアはルストの歌詞に基づき、更にコラールが5曲追加されています。楽譜の表紙には"Bearbeitung von Philipp Wolfrum"という表記があります。Bearbeitungつまり編曲者の表示です。編曲とは言っても楽器編成も調性もそのままなのでおそらくはコラールを追加しただけなのでしょう。具体的には第3曲ソプラノのアリア、第4曲アルトのレチタティーヴォ、第一部終曲の合唱(第7曲)、第二部冒頭のテノールのアリア(第8曲)、そして終曲の合唱(第10曲)のそれぞれのあとにコラールがおかれています。このフィリップ・ヴォルフルム(1854-1919)はオルガニストや指揮者(ブラームス派からヴァーグナー派に転向)としても知られたドイツの作曲家で、ハイデルベルクに活動拠点をおき1885年ハイデルベルク大学の音楽部長に就任すると、当地にハイデルベルク・バッハ協会及やアカデミー合唱協会を設立してバッハの声楽作品の普及に努めました。ルストより30歳ほど若く、彼がバッハのカンタータを積極的にとりあげたのが恐らく1885年以降と思われますので、この編曲はその頃に行われたのではないでしょうか。
ドイツ語の歌詞を翻訳できるほどの能力は私にはありませんので、正確な意味をお伝えすることはできませんがルスト版ではFörstin(侯妃)という言葉はH?chster(主)やFreunde(友)という言葉に置き換えられ、またKönigin(王妃)という言葉もGottessohn(神の子)やMenschenkind(人)に換えられています。そして原曲の歌詞を生かせるところはそのまま使用し、変更した歌詞の部分もなるべく元の韻を生かすよう気配りされています。
ヴォルフルムが追加したコラールについても触れておきましょう。まず第3曲ソプラノのアリアのあとにくるコラールは、バッハ晩年の弟子であったキルンベルガー(Johann Philipp Kirnberger 1721-83)と息子のカール・フィリップ・アマヌエルが共同でバッハの死後に編纂した4巻からなる「4声のライプツィヒ・コラール集17784-87」から"Es ist geweisslich an der Zeit(まことに時は迫りたまえり)BWV307"の旋律を使用しています。これはクリスマス・オラトリオの第59曲のコラール"Ich steh an deiner Krippen hier(わたしはあなたの秣桶のそばにたたずむ)"(パウル・ゲルハルト作詞)とも同じ旋律です。ここで歌われるコラールの歌詞はガルヴェ(Karl Bernhard Garve 1763 - 1841)作の6節からなるコラールの第1節"Der ersten Unschuld reines Glöck"が使用されています。
2番目に追加されたコラールはカンタータBWV179「心せよ、汝の敬神の偽りならざるかを」の第6曲コラール"Ich armer Mensch, ich armer Sönder (わたしは哀れな人間、哀れな罪人として) "を転用したものでクリストフ・ティーツェ(Christoph Tietze 1641-1703)の作によるものです。そして第一部を締めくくるコラールはカンタータBWV92「われは神の御胸の思いに」の第9曲のコラールと同一で、有名なゲルハルトのコラールの第9節"Soll ich denn auch des Todes Weg (たとえ死の道、暗い通りを辿ったとしても) "となります。この旋律はバッハがマタイ受難曲の中(第25曲)でも使用しており、そちらはプロイセン公アルブレヒト作の"Was mein Gott will, das g'schen' allzeit(わが神の御心のままに)"というコラールです。その他にもBWV72、103、111そして144でも同じメロディを聴くことができます。バッハお気に入りの旋律だったのでしょう。そもそもこの旋律はフランス・ルネサンス期の作曲家クローダン・ド・セルミジ(Claudin de Sermisy c.1490-1562)のシャンソンがもとになっています。ヴォルフルムは楽譜に「できればア・カペラ(無伴奏)が望ましい!」と記しています。第一部を締めくくるには相応しいコラールといえるでしょう。
第二部冒頭のテノールのアリアに続くコラールはやはり「ライプツィヒ・コラール」から転用され、"O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen (ああいかに幸いなるかな、汝ら信仰の厚き者たちよ) "BWV406と同一でジーモン・ダッハ(Simon Dach 1605-59)作のコラール第1節になります。そして終曲のコラールですが、これはカンタータBWV145の第1曲のコラールをもってきています。しかしながらこのコラール、新バッハ全集版ではカットされています。理由はこのコラールがテレマンの合唱曲といっしょにバッハの死後にこのカンタータに付け加えられたものだと解釈されたからです。旧全集版ではこのカンタータ、ア・カペラでまずこのコラールが歌われ、そのあとにテレマンの作と判明した合唱曲が続き冒頭に置かれていました。そのコラールがこの"Auf mein Herz! des Herren Tag(立て我が心よ、主の日なり)"で、カンタータのタイトルは冒頭の句がそのまま曲のタイトルになりますので、旧全集版では「立てわが心よ・・・」だったのですが、新全集版になってそれがなくなってしまいましたので、今のタイトルはそのあとに続くソプラノとテノールの二重唱"Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen(われは生く、わが心よ、汝を喜び楽しませんため)"になってしまいました。ですから詳しく調べてみないとわかりませんが、このバッハの手になるコラールはルスト=ヴォルフルム版のBWV198でしか聴けなくなってしまったのかもしれません。詞の作者はカスパール・ノイマン(Kaspar Neumann 1648-1715)です。あのすばらしい終曲のあとにコラールを持ってくるのは私自身としてはあまり賛成出来ないのですが、ヨハネ受難曲の例もあるので何とも言えません。ただいずれにせよ、これらコラールの追加までルストは想定していなかったのではないでしょうか。
このルスト版はもう忘れ去られてしまったのかと思っていたのですが、アメリカでは最近演奏されたようで、現在バッハ・カンタータの全曲演奏を続けているボストンのエマニュエル教会の団体(1970年創立)のホームページでそれを知ることができます。そこにはルスト版の歌詞とその英訳が公開されていますので、そのURLを下に掲載しておきます。歌詞の意味を知る上で参考になると思います。因みにここではコラールも含めて演奏されたようです(http://www.emmanuelmusic.org/notes_translations/translations_cantata/t_bwv198_rust.htm)。
さて、つい先日私はかつての職場の仲間達との会合がありそれに出席してきました。いつもは他愛のない昔話に終止する会合なのですが、この日久しぶりに仙台からかつての同僚が駆けつけてくれました。そこで私たちは彼から3.11のドキュメントともいうべき生々しい、そして悲しい話を次々に聞かされました。新聞やテレビでは報道されない、そこに暮らしたもっと身近な人々が遭遇した悲惨な実態です。それを目の当たりに体験してきた人間から直接聞く話は、どんなニュースよりも激しく人の心を打つものがあります。泣きながら聞いた人もありました。でも悲惨なだけではなく、そこから希望というものも感じられました。改めてあの悲惨な出来事を思い起こし、わたし達一人一人が何をできるのか私も考え続けていきたいと思います。そして私は今回この作品について調べているうち、この作品を復興のシンボルとして演奏してみては、と思うようになりました。東北は日本で初めてバッハの名前を冠したコンサートホールを作った地でもあります。今年で30周年を迎えたあのバッハホールも震災の影響を受けたと聞いていますが、この夏「ロ短調ミサ」でその復興への道を歩き始めたようです。わが国では追悼というとすぐにモーツァルトやフォーレのレクイエムが演奏されますが、東北にはまさにバッハが相応しいのではないでしょうか?おそらく来年の3月には東北に限らず、各地で追悼の催しが行われると思いますが、合唱関係者の方でもしこの記事をごらんになるようなことがありましたら、是非このルスト版のカンタータ演奏を検討してみてはいかがでしょうか?
長くなりましたが、最後に原曲の歌詞とルスト版の歌詞を並列したものを添付しておきます。興味のある方はご覧ください。
| Original | Rust | |
| Erster Teil 1. Coro Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl Aus Salems Sterngewölben schiessen, Und sieh, mit wieviel Tränengüssen Umringen wir dein Ehrenmal. |
Erster Teil 1. Coro Lass, Höchster, lass der Hoffnung Strahl Aus Himmelshöhen sich ergiessen, Und Sieh, wie bitt're Thränen fliessen, Uns'rer Todten Trauermal. | |
| 2. Recitativo(Soprano) Dein Sachsen, dein bestütrztes Meissen Erstarrt bei deiner Königsgruft; Das Auge tränt, die Zunge ruft: Mein Schmerz kann unbeschreiblich heissen! Hier klagt August und Prinz und Land, Der Adel ächzt, der Bürger trauert, Wie hat dich nicht das Volk bedauert, sobald es deinen Fall empfand! |
2. Recitativo(Soprano) Ach wehe, weh uns Menschen allen, Erstarrt sinkt Jeder einst zur Gruft; Die Liebe weint, die Klage ruft: O herbes Loos, dem wir verfallen! Es kennt der Tod kein theures Band, Er rafft dahin, was fleischgeboren: Mit Adams Fall ging auch verloren Die Seligkeit, das Heimathland! | |
| 3. Aria(Soprano) Verstummt, ihr holden Saiten! Kein Ton vermag der Länder Not Bei ihrer teuren Mutter Tod, O Schmerzenswort!―recht anzudeuten. |
3. Aria(Soprano) Hinweg, entflohn ist Edens Friede! Das Leben beut nur Kampf und Noth, Nach Müh' und Sorge schliesst der Tod, O Schmerzenswort! Die Augen müde. (Choral) Der ersten Unschuld reines Glück, Wohin bist du geschieden? Du flohst, und kehrest nicht zurück Mit deinem süssen Frieden. Dein Edensgarten blüht nicht mehr, Verwelkt durch Sündenhauch ist er, Durch Menschenschuld verloren. | |
| 4. Recitativo(Alto) Der Glocken bebendes Getön Soll unsrer trüben Seelen Schrecken Durch ihr geschwungnes Erze wecken Und uns durch Mark und Adern gehn, O, könnte nur dies bange Klingen, Davon das Ohr uns täglich gellt, Der ganzen Europäerwelt Ein Zeugnis unsres Jammers bringen! |
4. Recitativo(Alto) Der Glocken bebendes Getön Soll unsrer trüben Seelen Schrecken Durch ihr geschwungnes Erze wecken Und uns durch Mark und Adern gehn, O, möchte doch dies bange Klingen, Das über Gräber täglich gellt, Allmächt'ger Schöpfer dieser Welt Dir Zeugniss unsres Jammers bringen. (Choral) Ich armer Mensch, ich armer Sünder Steh' hier vor Gottes Angesicht, Ach Gott, ach Gott, verhahr' gelinder Und geh' nicht mit mir in's Gericht. Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich! | |
| 5. Aria(Alto) Wie starb die Heldin so vergn?gt! Wie mutig hat ihr Geist gerungen, Da sie des Todes Arm bezwungen, Noch eh er ihre Brust besiegt. |
5. Aria(Alto) Getrost! Erbarmen kam von Gott, Wie mächtig hat sein Christ gerungen, Da erdes Todes Arm bezwungen, Zu tilgen aller Sünden Noth. | |
| 6. Recitativo(Tenor) Ihr Leben liess die Kunst zu sterben In unverrückter Übung sehn; Unmöglich konnt es denn geschehn, Sich vor dem Tode zu entfärben. Ach selig! wessen grosser Geist Sich über die Natur erhebet, vor Gruft und Särgen nicht erbebet, wenn ihn sein Schöpfer scheiden heist. |
6. Recitativo(Tenor) Im Leben fromm, getreu im Sterben Soll fest der Christ zu Christo stehn; dann wird dem Tod in's Aug' er sehn, Die Furcht kann ihn nicht mehr entfärben, Ja selig, der in Christi Geist Sich über die Natur erhebet, vor Gruft und Särgen nicht erbebet, wenn ihn sein Schöpfer scheiden heist. | |
| 7.Coro An dir, du Fürbild grosser Frauen, An dir, erhabne Königin, An dir, du Glaubenspflegerin, War dieser Grossmut Bild zu schauen. |
7.Coro Von dir, du Vorbild aller Frommen, Von dir, erhab'ner Gottessohn, Von dir, o Lamm im Himmelsthron, Ist ew'ges Leben wieder kommen. (Choral) Soll ich denn auch des Todes Weg Und finstre Strassen reisen, Wohlan! so tret' ich Bahn und Steg, Den mir dein Augen weisen. Du bist mein Hirt, der Alles wird Zu solchem Ende kehren, dass ich einmal in deinem Saal dich ewig möge ehren. | |
| Zweiter Teil 8. Aria(Tenore) Der Ewigkeit saphirnes Haus Zieht, Fürstin, deine heitern Blicke Von unsrer Niedrigkeit zurücke Und tilgt der Erden Denkbild aus. Ein starker Glanz von hundert Sonnen. Der unsern Tag zur Mitternacht Und unsre Sonne finster macht, Hat dein verklärtes Haupt umsponnen. |
Zweiter Teil 8. Aria(Tenore) Des ewgen Gottes Vaterhaus Zieht, Freunde, die gehob'nen Blicke Von ird'scher Niedrigkeit zurücke, Und tilget Gram und Kummer aus. Es strahlt im Glanz, der Sonnen, Der grosse Tag verscheucht die Nacht. Der Geist, er spricht: Es ist vollbracht, was Liebe wob, was Gnad'gesponnen. (Choral) O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen, Dir ihr durch den Tod zu Gott gekommen, Ihr seid entgangen Aller Noth, die uns noch hält gefangen. | |
| 9. Recitativo-Arioso(Basso) Was Wunder ists? Du bist es wert, du Fürbild aller Königinnen! Du musstest allen Schmuck gewinnen, Der deine Scheitel itzt verklärt. Nun trägst du vor des Lammes Throne Anstatt des Purpurs Eitelkeit Ein perlenreines Unschuldskleid Und spottest der verlassnen Krone. Soweit der volle Weichselstrand, Der Niester und die Warthe fliesset, Soweit sich Elb' und Muld' ergiesset, Erhebt dich beides, Stadt und Land. Dein Torgau geht im Trauerkleide, Dein Pretzsch wird kraftlos, starr und matt; Denn da es dich verloren hat, verliert es seiner Augen Weide. |
9. Recitativo-Arioso(Basso) O grosse Lieb'! Es hält uns werth Der König Himmels und der Erde; Er will, dass uns das Heil auch werde, Das unsre Todten schon verklärt. Dort stehn sie vor des Lammes Throne Entrückt der Erde Eitelkeit; Im perlenreinen Unschuldskleid Empfingen sie des Lebens Krone. So weit der Himmel spannt sein Zelt, Das Meer das Erdenrund umfliesset, So weit die Sonn' ihr Licht ergiesset, Preist selig sie die ganze Welt. Doch wir, wir gehn im Pilgerkleide Noch eine Zeit nach Gottes Wahl Und wandeln hier im dunkeln Thal: Dann kommt des Wiedersehens Freude. | |
| 10. Coro Doch Königin! du stirbest nicht, Man weiss, was man an dir besessen; Die Nachwelt wird dich nicht vergessen, Bis dieser Weltbau einst zerbricht. Ihr Dichter, schreibt! wir wollen's lesen: Sie ist der Tugend Eigentum. Der Untertanen Lust und Ruhm, Der Königinnen Preis gewesen. |
10. Coro O Menschenkind, du stirbest nicht, Du weisst, dass dein Erlöser lebet, Der dich erweckt und hoch erhebet, Ob dieser Weltbau auch zerbricht, Herr Jesu Christ, nach deinem Worte, Ist dein das Reich und dein die Kraft, Die Leben wirkt, die Welten schafft: Erschliess auch uns des Himmels Pforte! (Choral) Auf, mein Herz! des Herren Tag Hat die Nacht der Furcht vertrieben; Christus, der begraben lag, Ist im Tode nicht geblieben. Nunmehr bin ich recht getröst't: Jesus hat die Welt erlöst. |
2011.08.07 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑪
10. 願わくば一条の光を――Ⅰ――カンタータBWV198「侯妃よ、願わくばなお一条の光を」
私は当初今回のテーマでこの作品をとりあげる予定はありませんでした。このカンタータは確かに「死」を扱ったものですが、それはあくまで特定のある個人を偲び、讃える音楽だからです。しかしながら私たちはこの度とてつもなく大きな災害に見舞われ、多くの人々の尊い命が失われ、今もって行方の知れない方々がたくさんおられます。更にいまだ先行き不透明な原発事故におびえながら日々私たちは暮らしています。そうしたことへのやり場のない怒りを感じるとき、この音楽がとても私の心を癒してくれました。そんなことからどうしてもこの音楽をとりあげたい、と思ったのです。
この作品は礼拝を目的とした教会カンタータとは違います。聖句やコラールもここにはありません。従って一般的には世俗カンタータに分類されていますが(ハンス・ヨアヒム・シュルツェとクリストフ・ヴォルフが編纂した新しい作品番号による「バッハ便覧」でもそのように扱われている)、教会で行われる追悼式(これも「礼拝」ではある)を目的とした音楽が世俗カンタータというのはどう考えても不自然です。これも宗教的行事に違いないのですから。といって教会カンタータでもないので、ちょっと変わった作品ということになりますが、一般的には「追悼頌歌」と呼ばれています。
このカンタータは先にも触れたとおり歌詞の上からはある特定の人物の死の悲しみを歌ったものですが、その音楽の力は言葉を超えて普遍的な死者への悲しみと、慈しみに満ちており、多くの人々に感動を与える名曲中の名曲といっていいと思います。こんな素晴しい音楽が、過去の特定の機会のためだけの音楽として今日あまり演奏されないとしたらとても残念なことだと思います。バッハは、ミサ・ブレヴィスやロ短調ミサ曲などを除き、カトリックのラテン語によるミサ曲などは書いていません。もちろんレクイエム(死者のためのミサ曲)も。しかしながらもしこのカンタータが聖書の言葉などをもって神を讃え死者へのいたわりを歌っていたら、これは素晴しい「ドイツ・レクイエム」となっていたでしょう。否私はこのままでもそれに匹敵する「バッハのレクイエム」である、とさえ思っています。
この作品の成立についてはかなり詳しいことがわかっています。1727年9月7日、ザクセン公国の侯妃クリスティアーネ・エーバーハルディーネ(・フォン・ブランデンブルク=バイロイト)が急逝し、国民は4ヶ月間喪に服することになります。享年55歳でした。「強
 王」として知られた夫の選帝侯フリードリ
ヒ・アウグスト1世(ポーランド国王としては2世)は
ポーランド国王の資格を得るため1697年にルター派
からカトリックに改宗しており、そのため彼女も改宗
するよう宮廷から圧力を受けていました。しかしなが
ら彼女はそれを断固として拒み、夫の戴冠式にも出席
せずヴィッテンベルク近郊のエルベ川沿いに立つプレ
ッチュ(Pretzch)城に引きこもってしまったのです。以
来彼女は公衆の前からほとんど姿を消してしまいまし
たが、慈善事業や文化の振興には力を注ぎ、生涯ルター
派の信仰を貫いたことで国民から広く慕われていました。こうしたことから彼女を偲ぶ追悼式をライプツィヒ大学付属のパウリーナ(聖パウロ)教会で行うことが計画されました。一般的に知られている事実は、ハンス・カール・フォン・キルヒバッハという貴族出身の大学生が企画し、大学当局や市を説得し自らの費用負担によりこの追悼式を実行したことになっています。彼はその追悼礼拝を実行するにあたり、その音楽の作詞を当時ライプツィヒ・ドイツ協会(Leipzig Deutsche Gesellschaft、文学者の同好会)の会長を務めていた有名なヨハン・クリストフ・ゴットシェート(Johann Christoph Gottshed 1700~66)に、そして作曲をバッハに依頼したのでした。
王」として知られた夫の選帝侯フリードリ
ヒ・アウグスト1世(ポーランド国王としては2世)は
ポーランド国王の資格を得るため1697年にルター派
からカトリックに改宗しており、そのため彼女も改宗
するよう宮廷から圧力を受けていました。しかしなが
ら彼女はそれを断固として拒み、夫の戴冠式にも出席
せずヴィッテンベルク近郊のエルベ川沿いに立つプレ
ッチュ(Pretzch)城に引きこもってしまったのです。以
来彼女は公衆の前からほとんど姿を消してしまいまし
たが、慈善事業や文化の振興には力を注ぎ、生涯ルター
派の信仰を貫いたことで国民から広く慕われていました。こうしたことから彼女を偲ぶ追悼式をライプツィヒ大学付属のパウリーナ(聖パウロ)教会で行うことが計画されました。一般的に知られている事実は、ハンス・カール・フォン・キルヒバッハという貴族出身の大学生が企画し、大学当局や市を説得し自らの費用負担によりこの追悼式を実行したことになっています。彼はその追悼礼拝を実行するにあたり、その音楽の作詞を当時ライプツィヒ・ドイツ協会(Leipzig Deutsche Gesellschaft、文学者の同好会)の会長を務めていた有名なヨハン・クリストフ・ゴットシェート(Johann Christoph Gottshed 1700~66)に、そして作曲をバッハに依頼したのでした。キルヒバッハが大学当局に式典の申請をすると、ここで一騒動おきます。今までにも何度かご紹介してきましたが、バッハはライプツィヒ市や大学とは良好な関係にあるとは言えませんでした。大学はバッハが大学教育を受けていないことを理由に、市の音楽監督でもあるバッハを大学の音楽監督としては認めずヨハン・ゴットリープ・ゲルナー(Johann Gottlieb G?rner 1697~1778)をその地位に任命していました(注)。したがってゲルナーはこの計画を知るや直ちに大学に抗議し、教授達も大学の教会であるパウリーナ教会で行う追悼式の音楽はゲルナーに依頼すべきだ、と主張したのです。これに対しキルヒバッハがとった行動は、「それならすべての計画を中止する!」と逆に大学側を脅したのです。結局この騒動はキルヒバッハがゲルナーにお金を支払うことで決着しました。バッハにも当局は今後大学側の行事にかかわらないよう「今回は特別の計らいで、これを前例としない」という文書にサインするよう求めたのですが、バッハはこれを拒否しました。
このようにこの作品の成立にはキルヒバッハという貴族出身の学生が大きくかかわっていますが、一説では「ゴットシェートがそもそも企画したものの宮廷の威光を恐れ、彼のサークルに所属していたキルヒバッハに肩代わりさせたのだ」とする人もあり、どれが真相かはわかりません。何しろこれだけの追悼式を貴族出身とはいえ一介の学生がすべてとりしきるのは少し無理があるように思います。
バッハは自筆スコアの最後に10月15日という日付を書いており、このことからこの作品は追悼式の2日前に完成されたことがわかります。パート譜が大急ぎで写譜されましたが、
 残念ながらこのパート譜は失われてしまい、今では判読するのも難しいような殴り
書きのスコアが残されているだけです。追悼式
は午前9時、ニコライ教会からパウリーナ教会
へと向かう市の参事会員や大学教授による荘厳
な葬列とともに始まり、教会における追悼式の
中心はもちろんこのカンタータの演奏でした。
曲は10曲からなり、キルヒバッハの悼辞を挟
んで2部構成となっています。この追悼式の模
様については次のような記録が残されています
残念ながらこのパート譜は失われてしまい、今では判読するのも難しいような殴り
書きのスコアが残されているだけです。追悼式
は午前9時、ニコライ教会からパウリーナ教会
へと向かう市の参事会員や大学教授による荘厳
な葬列とともに始まり、教会における追悼式の
中心はもちろんこのカンタータの演奏でした。
曲は10曲からなり、キルヒバッハの悼辞を挟
んで2部構成となっています。この追悼式の模
様については次のような記録が残されています
「今月17日、当地大学のパウロ教会において、宮廷よりのいとも恵み深き特別の許可に基づき、ザクセンの騎士ハンス・カール・フォン・キルヒバッハにより、亡き王妃を偲んで名文のドイツ語による追悼ならびに顕彰演説がおこなわれ、絶賛を博した。しかも葬儀場の舞台は創意に富んだもので、あらゆる種類の碑銘、年代文(クロノグラム)、浮彫で飾られていた。また、ここで演奏された追悼音楽は、バッハ氏の作曲になるものであった。そしてこのたびのミサに参列した侯家のかたがた、大臣、騎士、その他外国人たちはみな、多数の貴婦人たちとともに、そしてまた尊敬すべき大学ならびに高貴にして賢明なる市参事会の全職員とともに、この追悼式に連なったのである」(『ホルシュタイン通信』の報告-ライプツィヒ、1727年10月24日)この記録からもわかるとおりかなり大掛かりな追悼式で、これはキルヒバッハ個人の企画を越えて、すでに市全体のイベントと言っていい大きな式典になっています。文中の「イタリアの流儀」というのはレチタティーヴォとアリアで音楽が構成されていることからそう表現されたものです。またオルガンの前奏は(後奏も)ヴォルフによれば、バッハ自身によって演奏された可能性が高い、とされています。楽器編成はフラウトトラヴェルソ2、オーボエ2(というよりほとんどはオーボエ・ダモーレ2)、ヴァイオリン、ヴィオラ、ヴィオラ・ダ・ガンバ2、リュート2、通奏低音という構成で、中でもリュート2挺というのが目をひきます。それだけ通奏低音が豊かになるという点でバッハの中でも特異な作品と言えるでしょう。前記ジークルの記事中で「縦笛」とあるのは、オーボエ(ダモーレ)と間違えたものかもしれませんが、スコア完成後パート筆で付け加えられたとか、演奏される際にトラヴェルソがリコーダーに変更されたのでは、等々の説などがあります。そしてこの音楽は「ロ短調」というバッハが特に重要な作品に好んで使用した調性が選ばれています。
「全員が席につくまでオルガンによる前奏曲がかなでられ、そしてマリア学寮の同僚である学士ヨーハン・クリストフ・ゴットシェート氏の筆になる追悼頌歌が校僕らによって参列者に配られると、いよいよ、このたび楽長ヨーハン・セバスティアン・バッハ氏がイタリアの流儀にならって作曲した追悼音楽が、バッハ氏みずから受けもつチェンバロ、それにオルガン、ヴィオラ・ダ・ガンバ、リュート、ヴァイオリン、縦笛、横笛などによって演奏された。ただし、その前半は頌=悼辞の前に、後半はそのあとに演奏されたのであった。」(C.E.ジークル『涙するライプツィヒ』-ライプツィヒ、1727年)
(両資料とも「バッハ叢書第10巻 - バッハ資料集(酒田健一訳)」より)
10曲の構成は合唱が3曲、アリアが3曲、レチタティーヴォ4曲となっていますが、第2部のレチタティーヴォには途中アリオーソが含まれます。そして第1部が7曲、第2部が3曲で、演奏時間としては35分前後のバッハのカンタータとしては大曲の部類に入ります。
第1曲の合唱は、終止付点音符の音型によるオーケストラの伴奏がリズムを厳格に刻み、「侯妃よ、願わくばなお一条の光を投げかけてください。そしてどれほどの人々が涙しているかご覧ください」と悲しみの中にも力強く歌われます。
第2曲から3曲のソプラノのレチタティーヴォとアリアでは、16部音符の弦が「ため息」や「すすり泣き」を表現しますが、ソプラノのアリアがそれを「黙りなさい!」とたしなめ「どんな音楽もその悲しみを正しく伝えることはできない」と歌います。
第4曲のレチタティーヴォでフルートが小さな鐘の音を鳴らすと、アルトが「震える鐘の響よ」と歌いだし、それに呼応してオーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、ガンバ、リュートがどんどん加わっていき通奏低音による大きな鐘の響へと発展して、「全ヨーロッパにその悲しみの響が伝わるとよいが」と結びます。バッハはこれをわずか11小節の音楽で表現しています。そして第5曲のアルトのアリア(このカンタータの中では一番長い)へと続き、勇敢な最期だったことを告げそれを讃えます。たいへん美しいアリアで、ここではそれぞれ2挺のガンバとリュートが伴奏を務めますが、こうしたいぶし銀のような渋い響はあの106番のカンタータを想起させます。
第6曲はオーボエ・ダモーレの二重奏と通奏低音の伴奏によるテノールのレチタティーヴォですが、歌われる内容は前曲同様彼女の勇敢さを讃えるものです。そして第1部終曲の合唱へと続きますが、ここでも「偉大な女性達の模範」「気高い王妃」と彼女を讃美する言葉が続きます。合唱は比較的短いものですが、合唱、器楽とも小規模ながらフーガの書法が際立っており、いかにも侯妃を讃える音楽に相応しい堂々とした内容です。
悼辞のあと、この音楽のクライマックスともいうべき第2部がテノールのアリアによって開始されます。トラヴェルソとオーボエ・ダモーレの二重奏によって序奏が始まりますが、そのメロディーはテノールへと受け継がれ、「永遠のサファイア色の住まいがあなたの晴れやかな眼差しを卑しい私たちから引き戻し、地上の汚れを拭い去ります」と歌います。何と美しいアリアでしょうか?まさに天国のような響きです。歌だけでなくトラヴェルソも、オーボエ・ダモーレも、ガンバも、そしてリュートも典雅な響きを奏でます。
第9曲はバスのレチタティーヴォで、まず通奏低音のみの伴奏でこれでもかと思うほど様々な言葉を並べて彼女を讃美します。そしてこの国の美しさを歌うところにきて曲はアリオーソへと変わります。心憎い演出といえるでしょう。再びレチタティーヴォに戻ると、今度はトラヴェルソ、オーボエが2管ずつ加わりいよいよクライマックスともいうべき終曲の合唱に向っていきます。
終曲は「侯妃よ、あなたは死んではいません。私たちはあなたの元で得たものを知っています。後の世にあっても、この世の終りがくるまであなたのことは忘れないでしょう」と歌います。8分の12拍子でちょっと舞曲風のリズムの音楽ですが、この合唱の優しさは一体どこからくるのでしょうか?いつ聴いても感動します。この曲に限らずマタイの終曲や、ヨハネの第39曲の合唱ほかバッハには心から感動できる音楽がたくさんあります。まさに名曲中の名曲といえるでしょう。曲は三つの部分すなわち序奏(A)、合唱第一部(B)、合唱第二部(C)で構成されており、Aの後BとCはそれぞれ繰り返して演奏され、最後ダ・カーポで再び序奏部分に戻り、全曲を終えます。
この作品はバッハにとって大きな転換点にもなりました。彼と大学との冷えた関係はその後も続きますが、バッハはこの作品で大きな財産を得ることになります。それは共に演奏した大学生達がバッハの音楽に大きな共感を示し(これまでにも教会でエキストラとして加わってはいたが)、以後バッハは大学生の演奏団体「コレギウム・ムジクム(1701年テレマンによって創設)」と親密な関係を築いていくのです。教会カンタータの作曲もこのあたりから少なくなっています。もちろんかなり紛失してしまったとも言われていますので正確なところはわかりませんが、それでも制作意欲が衰えていったことは充分考えられます。活動の中心がトーマスカントルからコレギウム・ムジクムの指導者へと移っていったのです。1729年の3月、バッハは正式にこの団体の指揮者に就任し、コーヒーハウスを中心に毎週1回定期的に管弦楽曲、協奏曲そして世俗カンタータなどを演奏したのです。
さてこのBWV198のカンタータは、その後1731年、今は失われ幻となってしまったバッハの「マルコ受難曲」の中心的な楽曲として転用(パロディ)されました。この作品がなくなってしまった(歌詞だけが残っている)のはかえすがえすも残念ですが、バッハ自身とても気に入っていたのでしょう、そのほとんどの楽曲が受難曲に含まれていたようです。これらの点もご紹介しながら次回もう少しこの作品をみてみたいと思います。
注)前任者のクーナウはすべてを監督する立場にありました。この件についてバッハはトーマスカントル就任後アウグスト1世に抗議文を送りましたが、却下されています。以来バッハはパウリーナ教会における職務に興味を失い、「旧礼拝」の音楽(大きな祝祭日や年4回の宗教式典の礼拝のみトーマスカントルが行うこととされていた。これに対し主日の礼拝を「新礼拝」といい、こちらはゲルナーが監督)もその指揮を助手に任せるようになってしまいました。ゲルナー自身は1721年からニコライ教会の、そして1729年からはトーマス教会のオルガニストを務めており、バッハとも良好な関係を保っていたようです。
2011.06.04 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑩
9. カンタータ第106番「神の時こそ いと良き時」BWV106―ⅢCDの紹介ですが、この曲は名曲だけにかなり多くの種類が発売されています。もちろん私はそれらをすべて聴いているわけではありませんので、ここにご紹介するCD以外にもいい演奏があると思います。
私の手元には現在以下の8種類のCDがあります。録音の古いものから並べてみます。
①フリッツ・ヴェルナー指揮 プフォルツハイム室内管弦楽団 (1964年)こうして録音順に並べてみますと、面白いことにバッハ・カンタータの演奏スタイルの変遷を知ることができます。そうした点についても触れながら個々の演奏について少し気がついたことなどをご紹介していきたいと思いますが、その前に楽譜のことに触れておきましょう。旧バッハ全集のスコアはまず変ホ長調(リコーダーはヘ長調)のシンフォニアで開始されますが、新バッハ全集版ではそれはすべてヘ長調で書かれています。つまり単純に言えばスコア上新バッハ全集版は全音高いことになります。これについてはまたあとで触れます。
エディト・ゼーリヒ(S) クラウディア・ヘルマン(A) ゲオルク・イェルデン(T) ヤコブ・シュテンプフリ(B)
ハイルブロン・ハインリヒ・シュッツ合唱団 アウグスト・ヴェンツィンガー(Viole da gamba)
(Erato WPCS-4716)
②ヴォルフガング・ゲンネンヴァイン指揮 コンソルティウム・ムジクム (1965年)
エディト・マティス(S) シビル・ミシュロウ(A) テオ・アルトマイヤー(T) フランツ・クラス(B)
南ドイツ・マドリガル合唱団 (EMI 7243 5 68756 2 7)
③カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ合唱団&管弦楽団 (1966年)
ヘルタ・テッパー(A) エルンスト・ヘフリガー(T) テオ・アダム(B) ハンス=マルティン・リンデ(Bl-fl)
(Archiv F20A-20067)
④グスタフ・レオンハルト指揮 レオンハルト・コンソート(1980年)
ハノーファー少年合唱団員(S)(A) マリウス・ヴァン・アルテナ(T) マックス・ヴァン・エグモント(B)
ハノーファー少年合唱団 コレギウム・ヴォカーレ (Teldec 4509 91760)
⑤ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 イングリッシュ・バロック・ソロイスツ(1989年)
ナンシー・アルジェンタ(S) マイケル・チャンス(A) アントニー・ロルフ・ジョンソン(T) スティーヴン・ヴァルコー(B)
モンテヴェルディ合唱団 (Archiv POCA-1025)(現463581)
⑥トン・コープマン指揮 アムステルダム・バロック管弦楽団&合唱団 (1994年)
バルバラ・シュリック(S) ガイ・ヴェスル(A) ギ・ドゥ・メ(T) クラウス・メルテンス(B)
(Erato WPCS-4716) (現Challenge Classics CC72289)
⑦鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン (1995年)
柳沢亜紀(S) 米良美一(A) ゲルト・テュルク(T) ペーター・コーイ(B) (BIS CD 781)
⑧コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン (1999年)
ヨハンナ・コスロウスキー(S) エリザベス・ポピエン(A) ゲルト・テュルク(T) シュテファン・シュレッケンベルガー(B)
(harmonia mundi FRANCE HMC-901694)
①フリッツ・ヴェルナーのカンタータ演奏はとても懐かしいもので、私がエラートの日本発売の仕事に携わる以前からずっと親しんできたものです。ドイツ人の演奏とはいってもリヒターのような厳しさはなく、むしろラテン的な明るさまで感じられ、それが良くも悪くも彼のカンタータ演奏の特徴でした。この演奏も例外ではなく、哀悼行事という音楽の中にもどこか楽天的な明るさを持っています。合唱やオーケストラの人数は聴感上から判断するとさほど大きなものではなく、これは現代のスタイルに近いといえます。名手アウグスト・ヴェンツィンガーのガンバ演奏が聴けるのはうれしい限りです。
②ゲンネンヴァインの名前も懐かしいものです。彼の手兵ともいえるコンソルティウム・ムジクムは確かすでに古楽器を使用していたと思います。この曲に使用されるリコーダーもヴィオラ・ダ・ガンバももともと今の楽器にはないのですからおかしな表現ですが、ただ当時の古楽器は今よく用いられる「オリジナル楽器」とは違い、ピッチも現代のa=440を基準にしていました。この演奏でも通奏低音にリュート(テオルボ?)を使用するなど、その当時の演奏としては新しい試みが聴かれます。
③リヒター盤は、いかにもドイツ的といっていいような厳しさを持っています。リンデやフィンクといった器楽に名手を揃え、合唱も「素晴しい!」の一語につきます。特に終曲の力強さは群を抜いています。ただいかんせん合唱の規模が大きく、音楽が肥大しています。またテンポをやたら動かしたり、強弱の幅を意図的に大きくしたり、とロマン的な傾向が強く出ています。かつてはこうした演奏がもてはやされたのでしょうが、古楽器による演奏が定着した今では、あまりにその差が大きすぎます。それとこの演奏で一番問題になるのは第2曲dの部分で、最初に掲げた演奏者のリストをごらん頂いてもわかるように、ここにはソプラノのソロがありません。この部分はこのカンタータの核心ともいえる箇所で、合唱とソプラノ・ソロの掛け合いが重要な意味を持っています。リヒター盤ではそれが合唱とソプラノの多人数による斉唱となっているのです。新バッハ全集版のスコア(Bärenreiter-Study scores)では合唱部分は各声部ともはっきりTuttiと、そしてソプラノの部分はSoloと書かれています。この盤が録音された当時の旧全集版では確かにスコア上に合唱とかSoloを指定する文字は見られず、目次に第1曲(Chor)、終曲Chorと書かれているだけです。ですからこうした解釈も成り立つのかもしれませんが、やはり合唱とSoloで歌うべきではないでしょうか。特に最後ソプラノが息絶えて歌い終えるところはソロでなければ表現し得ないと思います。
④レオンハルト盤は、アーノンクールとの共同作業によるTeldecの「バッハ:カンタータ全集」中の録音で、女性歌手を起用しないバッハ時代の演奏様式に従ったものです。ソプラノやアルトのソロは少年合唱団の中の優秀な団員に歌わせています。以前この全集録音についてはあまり評価できないと書きましたが、この106番はまだいい方です。とはいえやはり当時の少年合唱団員では少し荷が重すぎたのでしょう。ピッチがふらついたりして感心できない部分があります。でも一番ひどいのは大人の歌うバスで、あの「イン・パラディス」の何と情けない声。ただバッハ自身もミュールハウゼンにおける辞職願いのなかで、その演奏の質を嘆いていたように、とても満足できるような演奏ではなかったようなので、その意味ではバッハ時代の演奏にもっとも忠実なのかもしれません。ここでは当然ながら古楽器が使用されており、こうした楽器によるバロック音楽の演奏が本格化するのはこの頃からだったと思います。レオンハルトは後にフィリップス・レーベルにエイジ・オブ・インライトメント管弦楽団と合唱団を指揮してバッハのカンタータを何曲か録音していますが(106番はない)、これは素晴しい演奏です。ここまでがいわゆるLP時代の録音になります。
CDが登場しデジタル時代になると、古楽演奏は古楽器、それも当時のピッチにしたがったオーセンティックな楽器によるものが当たり前のようになり、1970年代までの現代楽器による演奏とはちょうどその地位を逆転するような状況になります。古楽器の演奏技術も格段に進歩します。こうした中から生まれてきたのがガーディナーやコープマンなどで、彼らはバロック音楽を以前の博物館的な古楽演奏から、現代的な生き生きとした古楽演奏へと甦らせました。
⑤のガーディナー盤は現在彼がすすめているSdgレーベル(Sdgはバッハがカンタータの自筆譜の最後に書き添えた文字でSoli Deo Gloria「ただ神にのみ栄光あれ!」の略)への全集録音に先立ってアルヒーフ・レーベルに
 録音したもので、ソリスト、合唱、器楽、そしてテンポ感などすべてにわたって素晴しい演奏です。合唱の規模は4,3,3,3で、ライプツィヒ時代にバッハ書いた上申書の規模にほぼ従っています。ソプラノのアルジェンタの声質もボーイ・ソプラノのような透明感があり、またアルト(カウンター・テナー)のチャンスも素晴しい声を聴かせてくれます。それとこの盤では、アルトのアリオーソの部分(3a)で通常チェロとオルガンで演奏される通奏低音がオルガンのみで演奏されます。この通奏低音の動きは後半バスのアリオーソとコラールになるとそのままガンバの旋律に受け継がれますのでやはりチェロで演奏した方がいいように思いますが、「深遠さ」という意味ではこれも納得できるものです(この問題についてはこのあとのコープマンのところでも触れます)。私もこの演奏が気に入っていてこれがベストといいたいところですが、一つだけ問題があってこれは最後に触れたいと思います。
録音したもので、ソリスト、合唱、器楽、そしてテンポ感などすべてにわたって素晴しい演奏です。合唱の規模は4,3,3,3で、ライプツィヒ時代にバッハ書いた上申書の規模にほぼ従っています。ソプラノのアルジェンタの声質もボーイ・ソプラノのような透明感があり、またアルト(カウンター・テナー)のチャンスも素晴しい声を聴かせてくれます。それとこの盤では、アルトのアリオーソの部分(3a)で通常チェロとオルガンで演奏される通奏低音がオルガンのみで演奏されます。この通奏低音の動きは後半バスのアリオーソとコラールになるとそのままガンバの旋律に受け継がれますのでやはりチェロで演奏した方がいいように思いますが、「深遠さ」という意味ではこれも納得できるものです(この問題についてはこのあとのコープマンのところでも触れます)。私もこの演奏が気に入っていてこれがベストといいたいところですが、一つだけ問題があってこれは最後に触れたいと思います。コープマンのCD(⑦)も全集中の1枚です。この全集録音は著名な音楽学者でハーバ-ド大学の教授でもあるクリストフ・ヴォルフのサポートを得て開始されたもので、そのライナーノーツもヴォルフ自身が書いていて読み応えがあります。このCD全集は「バッハ=カンタータの世界」という3巻からなる本の副
 産物を生み、その中にはコープマン自身による演奏論も含まれています。ここに聴かれる演奏はすべての点で古楽の模範といってもいいようなものだと思います。ただその分少し面白みに欠けます。合唱の人数はガ-ディナー盤より多く、7,4,4,4となっています。彼の演奏論からこれがどのように録音されたかみてみましょう。まず合唱のソプラノとアルトは純粋に音楽的な見地から少年合唱ではなく、女声合唱を起用しています。そしてもっとも大きな問題のピッチについて次のように言っています。「18世紀後半のこの手書き譜は、この作品について現存する唯一の手書き資料である。この総譜に従えば、リコーダーは弦楽器と同じ調で演奏するが、そうするとリコーダーにはない音で演奏しなければならないことになる。・・(中略)・・この問題は、リコーダーに全音低く演奏させることによって解決できる。つまりa=約415Hzというピッチをリコーダーに使うのであるが、他はすべてa=約465Hzのピッチで演奏するため、全体が一致するのである。」と(礒山雅 他訳、東京書籍)。この主張に対してデュルが書評で「『唯一の手書き資料』ではない」とか、「スコアにはリコーダーと弦楽器が同じ調では書かれていない」などと批判したのですが、ちょっとこの批判は言葉尻を捉えたような発言で本質からはずれています。それはさておき、ここに初めてコアトーンを採用した演奏が出てきたのです(これ以前にもあったかもしれませんが少なくともこの曲に関する限り)。続けて彼はガーディナーのところでも触れた第3曲aの通奏低音についても言及し「BWV106にはチェロ・パートは存在しなかった」と言っています。ところが実際に聴いてみると、チェロ(?)の音が聴こえます。これはどうしたことかと更に読み続けると、彼によれば「1723年以前に使われていたコントラバスは一オクターヴ高く響いた」そうで、それを「八フィート・ヴィオローネ」と呼び(オクターヴ低い通常のコントラバスは「十六フィート・ヴィオローネ」)、ここではフレット付きのその楽器で演奏した、と書いています。このフレットつきのヴィオローネは確かに楽器図鑑などで見ることができますが、それが1オクターヴ高かった、ということは知りませんでした。コープマンによる全集録音も結局はガーディナー同様、メジャー・レーベルが最後まで継続できず途中で放り出す形で終わってしまい、これはChallenge Classicsというオランダのマイナー・レーベルに引き継がれて完成されました。
産物を生み、その中にはコープマン自身による演奏論も含まれています。ここに聴かれる演奏はすべての点で古楽の模範といってもいいようなものだと思います。ただその分少し面白みに欠けます。合唱の人数はガ-ディナー盤より多く、7,4,4,4となっています。彼の演奏論からこれがどのように録音されたかみてみましょう。まず合唱のソプラノとアルトは純粋に音楽的な見地から少年合唱ではなく、女声合唱を起用しています。そしてもっとも大きな問題のピッチについて次のように言っています。「18世紀後半のこの手書き譜は、この作品について現存する唯一の手書き資料である。この総譜に従えば、リコーダーは弦楽器と同じ調で演奏するが、そうするとリコーダーにはない音で演奏しなければならないことになる。・・(中略)・・この問題は、リコーダーに全音低く演奏させることによって解決できる。つまりa=約415Hzというピッチをリコーダーに使うのであるが、他はすべてa=約465Hzのピッチで演奏するため、全体が一致するのである。」と(礒山雅 他訳、東京書籍)。この主張に対してデュルが書評で「『唯一の手書き資料』ではない」とか、「スコアにはリコーダーと弦楽器が同じ調では書かれていない」などと批判したのですが、ちょっとこの批判は言葉尻を捉えたような発言で本質からはずれています。それはさておき、ここに初めてコアトーンを採用した演奏が出てきたのです(これ以前にもあったかもしれませんが少なくともこの曲に関する限り)。続けて彼はガーディナーのところでも触れた第3曲aの通奏低音についても言及し「BWV106にはチェロ・パートは存在しなかった」と言っています。ところが実際に聴いてみると、チェロ(?)の音が聴こえます。これはどうしたことかと更に読み続けると、彼によれば「1723年以前に使われていたコントラバスは一オクターヴ高く響いた」そうで、それを「八フィート・ヴィオローネ」と呼び(オクターヴ低い通常のコントラバスは「十六フィート・ヴィオローネ」)、ここではフレット付きのその楽器で演奏した、と書いています。このフレットつきのヴィオローネは確かに楽器図鑑などで見ることができますが、それが1オクターヴ高かった、ということは知りませんでした。コープマンによる全集録音も結局はガーディナー同様、メジャー・レーベルが最後まで継続できず途中で放り出す形で終わってしまい、これはChallenge Classicsというオランダのマイナー・レーベルに引き継がれて完成されました。途中でメジャー・レーベルが制作を続けられなくなったガーディナーやコープマンのケースと違い、一つのレーベルで着々と今なお全集録音を進行させているのがスウェーデンのBISレーベルによる、鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)のプロジェクトです。現在48巻まで発売されていますので2/3以上終わったことになりま
 す。これらはすべて日本で録音されており、このことはバッハの音楽がわが国の音楽文化にそれだけ深く浸透していることを物語っています。ただ録音しているというだけでなく、その演奏水準が極めて高く、ガーディナーやコープマンの演奏に勝るとも劣らない偉業ともいえる素晴しいプロジェクトです。同じ日本人として誇りに思います。彼らの全集録音もまた非常に充実した内容のあるライナーノーツで、内外の研究者による詳細な解説の他、鈴木氏自身による制作ノートがCDごとに付されています。ただ残念ながらこの106番については彼らの2枚目の録音で、まだそうした構想がまとまらなかったのか、制作メモがつけられるようになるのは3枚目のCDからです。この曲の制作ノートは彼の著書「わが魂の安息、おおバッハよ」(音楽之友社)にはっきり書かれています。この部分は非常に難しいところなので、少し長くなりますが全文をご紹介しておきます。
す。これらはすべて日本で録音されており、このことはバッハの音楽がわが国の音楽文化にそれだけ深く浸透していることを物語っています。ただ録音しているというだけでなく、その演奏水準が極めて高く、ガーディナーやコープマンの演奏に勝るとも劣らない偉業ともいえる素晴しいプロジェクトです。同じ日本人として誇りに思います。彼らの全集録音もまた非常に充実した内容のあるライナーノーツで、内外の研究者による詳細な解説の他、鈴木氏自身による制作ノートがCDごとに付されています。ただ残念ながらこの106番については彼らの2枚目の録音で、まだそうした構想がまとまらなかったのか、制作メモがつけられるようになるのは3枚目のCDからです。この曲の制作ノートは彼の著書「わが魂の安息、おおバッハよ」(音楽之友社)にはっきり書かれています。この部分は非常に難しいところなので、少し長くなりますが全文をご紹介しておきます。
「この作品は、残されている資料ではヴィオラ・ダ・ガンバと声楽、コンティヌオのパートは変ホ長調、リコーダー・パートのみヘ長調(フランス風ヴァイオリン記号)で書かれている。このことは、リコーダーのピッチが弦楽器より全音低かったことを意味しており、他のミュールハウゼン時代のカンタータと共通である。当然弦楽器(とコンティヌオ)がコーアトーンで奏され、リコーダーがカンマートーンで奏されたはずだが、絶対的なピッチについては、必ずしも定かではない。現在通常考えられているコーアトーン(a'≒465)とカンマートーン(a'≒415)を想定すると、声楽パートはかなり高くなる(特にバス・パートが明らかに高すぎる)。リコーダーを最も低いピッチのもの(いわゆるD管のヴォイス・フルート)を採用し、ガンバとオルガンは低いフレンチ・ピッチ(a'≒392)の変ホ長調で演奏する方法もありうるだろう。なお新バッハ全集ではこれをヘ長調に統一して出版しているが、もしガンバをヘ長調として演奏すると、楽器の音色が大きく変化するので、どのピッチであれ、これはヘ長調ではなく変ホ長調として演奏すべきである。これを読めば演奏上のすべての問題が明確になります。言い方は違っていますが、コープマンと同様の解決法で両者ともコアトーンを採用した高いピッチで演奏しています。他の演奏と比べると明らかに音色が明るくなっています。哀悼音楽は暗い方がいいと思うかも知れませんが、それはあくまでも比較してしまうからであり、これが本来のピッチなのです。BCJの演奏では合唱の規模は5,4,4,5というやはりコープマンに近いものですが、私はこの合唱が一番いいと思っています。全体の感想としては、まだ彼らにとって2枚目の録音だったためか少し固さも感じられ、特にソプラノの最後の「息絶える」部分の音楽表現などは、もう少し演出的な歌い方(過度な演出は謹むべきだが)でもよかったのでは。彼らにはいつかもう一度これを録音して欲しい、と願っています。
また、コンティヌオについては、当時オルガンのみで演奏した可能性が高いが、今日用いる楽器が大きなオルガンではなく、閉管のみを持つポジティフオルガンであり、低音が著しく不足するので、チェロを重ねることとする。」(第56回定期演奏会(仙台公演)制作ノート 2002年9月)
最後のユングヘーネル盤(⑧)ですが、これもまた熱演で素晴しい演奏です。微妙な言葉のニュアンスに沿った強弱など、他の演奏からは聴くことのできないものです。この輸入盤には簡単な曲目解説しかつけられて
 おらず、彼らがどうやって演奏したのかは書かれていません。ただピッチレベルはコープマン、BCJ盤と同じa≒465Hzのコアトーンを採用しています。つまり変ホ長調では現在のピッチより半音高く、また新バッハ全集版のヘ長調とすれば半音低くなります。また3aの通奏低音にはヴィオローネを使用しているように思います(音色からしてチェロとは違う?)。この演奏のもっとも大きな特徴はリフキン方式を採用していることです。つまり合唱は各パートに一人ということになります。この方式については私の意見も含め既にご紹介しましたので、詳しくはそちらをお読みください(5回目「演奏者は何人が適切か」)。ただ初期のカンタータだけに限って言えば、この当時はワンパート一人の合唱というのは普通に行われていたという記述もあり、その意味では充分説得力を持っています。このCDではちょっと早めのテンポですが、あの「イン・パラディス」の力強さが光ります。
おらず、彼らがどうやって演奏したのかは書かれていません。ただピッチレベルはコープマン、BCJ盤と同じa≒465Hzのコアトーンを採用しています。つまり変ホ長調では現在のピッチより半音高く、また新バッハ全集版のヘ長調とすれば半音低くなります。また3aの通奏低音にはヴィオローネを使用しているように思います(音色からしてチェロとは違う?)。この演奏のもっとも大きな特徴はリフキン方式を採用していることです。つまり合唱は各パートに一人ということになります。この方式については私の意見も含め既にご紹介しましたので、詳しくはそちらをお読みください(5回目「演奏者は何人が適切か」)。ただ初期のカンタータだけに限って言えば、この当時はワンパート一人の合唱というのは普通に行われていたという記述もあり、その意味では充分説得力を持っています。このCDではちょっと早めのテンポですが、あの「イン・パラディス」の力強さが光ります。以上手持ちのCDに関して特長をあげてきましたが、大別するとガーディナー盤の⑤までがa=440の現代のピッチに基づく変ホ長調で開始される演奏であり、コープマン以降の盤が同じ変ホ長調でもコアトーンを採用した演奏ということになります。古楽演奏の第一人者ともいうべきガーディナーがコアトーンを採用しなかったのは何故なのでしょう?彼が録音した当時には既に新バッハ全集によるスコアは刊行されています(1986年)。「ヘ長調」という問題があった故でしょうか?いつもラーナーノーツでは多弁な彼が、この盤では自身の演奏にまったく何も触れていない(少なくとも私の持っている盤では)のも気になります。演奏自体はとても素晴しいのに唯一この点だけが疑問です。もちろんピッチがすべてではありませんが。
また新バッハ全集版がなぜヘ長調で開始されるのか?このスコアの校訂の主管にはわが国のバッハ学者として名高い樋口隆一氏があたっています。これも素晴しいことだと思います。その彼の書いたスコアの序文にはコンサート・ピッチ(カンマートーン)のリコーダーの音域に合わせるため、ヘ長調に変更したと書かれています。つまりa=415のピッチとし、それをヘ長調で演奏するように改めたのだと思います(彼がリヒター盤に書いている解説にもその様なことが書かれています)。ただコアトーンによる演奏が現れてくると、ちょっとこの変の事情は変わってくると思いますが。
以上が私のカンタータ第106番をめぐるCDの感想です。まだまだこの曲をめぐるベスト盤探しは続きます。
2011.04.26 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑨
8. カンタータ第106番「神の時こそ いと良き時」BWV106―Ⅱバッハの初期のカンタータに共通する様式的な古さの特徴として、短い器楽の序奏とアリオーソがあげられますが、この106番については楽器編成の上でも古さが指摘されています。
器楽の序奏ですが、バッハは初期の作品(全部ではない)では「ソナタ」とか「シンフォニア」「ソナティナ」という名前で非常に簡素な器楽による序奏を置いており、それらはすべて20小節前後で書かれています。ライプツィヒ時代の規模の大きな序奏とは対照的です。そしてそれらはその後に続くカンタータのテーマを暗示するような手法で書かれており、この106番のシンフォニアも暗く静かに始まり、いかにも哀悼行事にふさわしい音楽で、ここで聴かれるモチーフがこの曲全体を支配しています。後年のカンタータでは、自身の器楽作品を転用しながらそこにコンチェルトや管弦楽組曲風の大規模な序奏として独立した楽曲をおくなど、その作風はまったくことなっています。
初期のカンタータはよく「モテット的」といわれ、合唱の占める比重が高くなっています。この106番のカンタータもモテット的であり、宗教コンチェルトとしての特徴は器楽と声楽の対比以上にソロと合唱などによる声楽同士の対比にあらわれています。合唱の比重が高い点は、アリオーソとの関連でも指摘されます。アリオーソは簡潔に表現すれば「旋律的なレチタティーヴォ」であり、アリアでもレチタティーヴォでもないその中間的な楽曲ですが、聖句を用いることにより物語を進行させる役割も持っていました。そのアリオーソが合唱やアリアとうまく融合しながら楽曲全体を有機的に結び付けています。 ヴァイマル時代、バッハにはいくつか大きな変化が訪れます。その一つは宮廷礼拝のために定期的にカンタータの作曲が義務付けられたこと。そしてもう一つはイタリア音楽の様式を採り入れた事です。後者でもっとも顕著な例は、バッハが親戚でもあり、友人でもあったヨハン・ゴットフリート・ヴァルターと共に主君の命により作曲した「オルガン協奏曲」(協奏曲とはいってもこれはオルガンのソロ作品)で、これはヴィヴァルディの協奏曲集「調和の霊感作品3」の数曲を編曲したものでした(ヴァルターはトレッリやアルビノーニの協奏曲を編曲)。こうした作品を通じて彼はイタリア様式を吸収し、深くイタリア音楽に傾倒していったのです。もちろんイタリア・オペラの手法にも。
これらのことがバッハの声楽作品にどんな影響を与えたのでしょうか。まずアリオーソはレチタティーヴォ(通奏低音による伴奏のみのレチタティーヴォ・セッコ)とアリア(多くの場合ダ・カーポ・アリア)に分解されます。物語の進行はもっぱら非旋律的なレチタティーヴォとなり、これは聖句が引用されます。そしてアリアは自由詩となり、宗教的とはいえ言葉は貧弱化し物語の信仰も妨げる結果になります。ただその分言葉の制約から離れて自由な表現が可能となります。ソプラノからバスまで各々のソリスト(コンチェルティスト)が一曲のアリアを歌うとすれば4曲のアリアが挿入され、その結果時間的な制約(カンタータは礼拝の一部分でおよそ20分前後、長い場合は説教を間に挟み二部構成となる)もあって合唱の比重は少なくなり、もっぱら最初と最後を飾る音楽としてしか歌われないようになります。これがヴァイマル以降のバッハのカンタータの特徴でもあります。シュヴァイツァーなどは、これ以降のバッハのカンタータをあまり評価していません。確かに初期のカンタータに共通する深遠な世界は、以降の作品から失われてしまったように私も思います。ではそれ以降の作品が悪いか、というとそれもまた違うと思います。確かにヴァイマル以降その作曲技法がややパターン化していることは否めないように思います。ライプツィヒ時代のカンタータは特にそうした傾向が強いと思いますが(ライプツィヒ二年目のコラール・カンタータという壮大の計画があったにせよ-注1)、考えてみれば毎週一曲のカンタータを上演しなければならないのですから、それは並大抵の苦労ではなかったと思います。作曲だけならまだしも、演奏まで自分で仕上げなければならないのですから、ある程度パターン化するのはやむを得ないように思います。それでいて、ではそうした作品が駄作か、というとまったくそうではないのですから驚くほかありません。私はライプツィヒ時代のカンタータにも好きなものがたくさんあります。
楽器編成上の古さとして、リコーダーとヴィオラ・ダ・ガンバそれに通奏低音という組み合わせがあげられます。非情に渋みのある音色で、「哀悼行事」という曲想に相応しいものですが、このような楽器の使用はバッハ以前のトーマスマントルや、ブクステフーデ、ゲオルク・ベームなどの音楽に共通するものです。またこの曲ではヴィオラ・ダ・ガンバのパートは二つに分割されて使用されますが、こうしたヴィオール・パートの分割使用という手法も17世紀によく行われていたものです。
以上106番のカンタータとバッハの初期の作品における特徴について触れてきましたが、ここからは19世紀におけるバッハ・ルネサンスのなかでこの作品がどのような役割を果たしてきたのかをみてみたいと思います。
今日における評価とは違い、バッハの生前における評価は三流の作曲家としてのそれしかありませんでした。一流はテレマンであり、二流がヘンデルで、バッハはそれ以下だったのです。ですからバッハの死後、彼の音楽は一部の器楽作品を除き急速に忘れ去られていきます。バッハの音楽がある種古臭さを持っていたこともあるでしょう。バッハの音楽に変わってもてはやされた宗教音楽はグラウン(Carl Heinrich Graun 1704-59)の受難カンタータ「イエスの死 Der Tod Jesu」(注2)でした。オペラチックな華やかさとセンチメンタリズムをもった音楽で、この作品は18世紀後半、今日のヘンデルのメサイアのように頻繁にドイツで演奏されていたといわれています。人々の趣味はこうした華やかなものへと移っていったのです。テレマンやヘンデルのファンからは怒られそうですが、バロック音楽はバッハの死とともに終焉し、時代は前古典派の音楽へと大きく移っていったのです。
しかしながらまったくバッハのカンタータが忘れられたわけではなく、細々と演奏もおこなわれていました。特にカール・フィリップ・エマヌエルとヴィルヘルム・フリーデマンの二人の息子たちは自身の務める教会(ハンブルクとハレ)でバッハのカンタータをとりあげていましたし、またトーマス教会でも演奏されていました。もう一つ大きな役割を果たしていたのがウィーンのスヴィーテン男爵(Gottfried van Swieten 1734 - 1803)で、彼は自身の館で定期的に演奏会を開き、ここではヘンデルとバッハだけが取り上げられていました。モーツァルトもその演奏に加わっていたといわれます。モーツァルトが1789年トーマス教会でバッハのモテット「主に向って新しい歌をうたえ」BWV225の実演を聴いていたく感動し、その筆写譜を取り寄せて勉強し、それがジュピター交響曲(終楽章の壮大なフーガ)やレクイエムの傑作につながった、というのは有名な話です。
更に19世紀に始まるバッハ・ルネサンスに大きな役割を果たしたと思われるのは、18世紀後半に始まる出版社ブライトコプフによる楽譜の販売です。作曲家はこぞってこれらの楽譜を手に入れ、バッハの対位法を勉強したのです。もっとも熱心だったのがメンデルスゾーンで、彼は師のツェルター(Carl Friedrich Zelter 1758-1832)を通じてバッハの偉大さを知りその音楽を勉強したのです。彼にはコラールを用いたオラトリオや詩篇が多数残されています。そして1829年3月11日メンデルスゾーンはその上演100年を記念して「マタイ受難曲」の復活上演を果たしたのです(当時マタイの初演は1729年とされていた)。ここからバッハ・ルネサンスは始まりそれが今日まで続いているのですが、ではこの106番のカンタータはその中でどのような役割を果たしたのでしょうか?
「マタイ」の復活上演以降バッハの声楽作品は教会で歌われるものから、コンサート・ホールで演奏されるものへと変質していきますが、バッハのカンタータが今日のように演奏されるようになったのは、旧バッハ全集版の楽譜が出版されるようになってからのことです。バッハのカンタータで生前出版されたものは初期の作品であるBWV71「神はいにしえよりわが王なり」しかありません。メンデルスゾーンやシューマンらの熱心な提唱によってバッハの没後100年にあたる1850年にバッハ協会が設立され、その全作品が次々に出版されていきますが、その全作品の刊行までには実に50年の歳月を要しました。したがってバッハのカンタータがコンサートで演奏されるようになるのは19世紀後半になってからのことです。
そうしたなかでこの106番は古くからバッハ崇拝者達により愛好され、1830年には楽譜も出版され、1833年の5月にはフランクフルトでヨハン・ネポムク・シェルブレ(Johann Nepomuk Schelble 1789-1837)の指揮のもと公開演奏がおこなわれました。それ以後この作品の再演を希望する声は高まり、ドイツ各地で演奏されるようになります。およそ50年の間に少なくとも28回以上の公開演奏が行われ、これは他のカンタータとは比べものにならないほどの公演回数といわれています。このあたりの事情は樋口隆一著「バッハ カンタータ研究」(音楽之友社)に詳述されていますので、興味のある方はそちらをお読みになるといいでしょう。また19世紀後半にブラームスが果たした役割にも触れておかなければなりません。彼は1872年ウィーン楽友協会の総監督に就任すると、コンサート・プログラムに新しい作品だけでなく、古い作品も積極的にとりあげるようになり、バッハのカンタータもとりあげたのです。当時使用されたパート譜が今も楽友協会に残されています。ブラームスがバッハの作品を研究し、その結果が交響曲第4番の終楽章に発展したことは以前にも述べましたが、彼とこの106番のカンタータとのかかわりを示す証拠は見られないものの、彼の友人であった当時の高名なバリトン歌手ユリウス・シュトックハウゼン(Julius Christian Stockhausen 1826-1906、ブラームスの歌曲を積極的にとりあげた)が愛好したカンタータであったことから、ブラームスも当然知っていたと思われます。ドイツの音楽学者ガイリンガー(Karl Geiringer)は著書「バッハ-その生涯と音楽」の中でこの106番のカンタータは「内容においても構成においても、ブラームスの『ドイツ・レクイエム』との類似がきわめて著しい」としています(注3)。いずれにしろ、この作品がバッハのカンタータの中でもっとも高く評価され、そしてもっとも多くの人達から愛されてきた作品であることはおわかりいただけたかと思います。
CDの紹介を続けたいところですが、長くなりますのでこれは次回(なるべく早く書きます)にしたいと思います。尚今回この原稿を書いている最中に巨大地震というとてつもなく大きな災害に私たちは見舞われ、多くの方々が亡くなられました。このカンタータは「哀悼行事」という名が示すとおり死者を追悼する音楽です。そこには「安らかな死」と、そこから生まれる「希望」あるいは「救い」が歌われています。死者に対する安息の祈りは、同時に今地上に生きる私達への安らぎと希望への祈りでなければなりません。まだ原発の恐怖という大きな問題を抱えていますが、私たちに早く「希望」が訪れますよう願って止みません。このカンタータを聴きつつ、亡くなられた多くの方々のご冥福を心からお祈りいたします。
注1)以前書いた「バッハとネアンデルタール人」の「バッハのカンタータ」の項をご参照ください。
注2) グラウンはフリードリヒ大王の宮廷で楽長を務めた人物。現在のベルリン国立歌劇場(Staatsoper Unter den Linden)の創設者(1742年)としても知られる。この「イエスの死」は、1755年3月26日に初演され、以来再びバッハの受難曲が復活する19世紀末までの100年以上ものあいだ、聖金曜日に繰り返し演奏されてきました。曲はいきなりあの有名なパッション・コラール「血しおしたたる」のメロディによる合唱で始まるもので、以下のCDで聴くことができます。
ウータ・シュワーベ(S)、インゲ・ヴァン・デ・ケルクホーヴェ(S)、クリストフ・ゲンツ(T)、シュテファン・ゲンツ(B)、エクス・テンポーレ シギスヴァルト・クイケン指揮 ラ・プティット・バンド hyperion CDA67446=2枚組
注3) ガイリンガーの著書「ブラームス その生涯と芸術」(山根銀二訳 芸術現代社)によると、ドイツ語によるテキストの作成や、楽曲のシンメトリックな構成など多くの類似点が見られるという。
2011.03.08 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑧
7. カンタータ第106番「神の時こそ いと良き時」BWV106― Ⅰバッハのカンタータというと、一般的には第140番「目覚めよ、とわれらに呼ばわる物見らの声」やコラール「主よ、人の望みの喜びよ」で知られる第147番「心と口と行いと生きざまもて」の2曲がよく知られていますが、バッハ好きの人がどれか一曲だけ選ぶとしたら、まずこの第106番「神のときこそ いと良き時」をあげる人が多いのではないかと思います。「死」への憧れともとれるこのカンタータは、私たち日本人の感性からすると少し違和感のようなものを感じますが、その音楽の世界は果てしなく深淵で感動的なものです。
人間、年をとると死は身近なものとなり、避けては通れないテーマになります。ところがこのカンタータはバッハがまだ若いミュールハウゼン時代(1707~08)に作ったもので、彼はかなり若い頃から「死」と向き合っていたことになります。幼いうちに両親をあいついで亡くしたことなどが影響していると思われますが、彼が若い頃に作ったカンタータにはこうした「死」への憧れを強く感じるものがあります。
現存するバッハのカンタータのなかで、ミュールハウゼン時代に作られたと思われるカンタータが6曲あります。BWV150「主よ、われ汝を仰ぎ望む」、BWV131「深き淵よりわれ汝に呼ばわる、主よ」、BWV71「神はいにしえよりわが王なり」、BWV106、BWV196「主はわれらを御心に留めたまえり」とBWV4「キリストは死の縄目につながれたり」の6曲で(注1)、このうち作曲年代がはっきり特定されているのはBWV131と71の2曲だけです。他の4曲は様式的な観点などからこの時代の作と推定されているだけです。これら6曲のカンタータはどれも素晴しい作品ばかりですが、後のライプツィヒ時代の円熟した手法によるカンタータとはその傾向を全く異にしています。
第106番のカンタータは自筆のスコアやパート譜はなく、バッハの死後に作成された筆写譜でしか残されていません。1768年にライプツィヒで作られた筆写譜に"Actus tragicus"と記されていたことから「哀悼行事」(アクトゥス・トラギクス)という別名でも呼ばれています。誰のために、いつ演奏されたのかはわかっていませんが、一般的には1707年8月10日にエルフルトで亡くなったバッハの母方の伯父にあたるトビーアス・レンマーヒルト(Tobias L?mmerhilt)のために書かれたといわれています(注2)。またミュールハウゼンで親しい関係にあった聖マリーエン教会の牧師ゲオルク・クリスティアン・アイルマルの妹で1708年6月3日に亡くなったドロテア・スザンナ・ティレジウスのために書かれたという説もあります。バッハが最初の妻マリア・バルバラと結婚したのが1707年10月ですので、いずれにしろ彼にとってはもっとも希望に燃えた時期の前後に書かれたことになります。シュヴァイツアーは作品中に表れるシメオン老人の讃美に触れ、この作品はかなり年をとった人の死に対して書かれたのではないかとしています。
歌詞はバッハ自身によって書かれたものと推定されていますが、旧約聖書と新約聖書を対照的に巧く繋ぎ合わせていて、これはルター派の神学者ヨハン・オレアリスが書いた「キリスト教の祈りの学校」に似たようなところがあることから、それを参考にしたのではないか、と言われています。皮肉にも、出来の悪さで知られるバッハのカンタータの歌詞にあって、この作品だけは例外で、もっとも優れたものとして評価されています。
この作品の内容を細かく書こうとするとどうしてもキリスト教の教義や聖書の内容に立ち入らざるを得なくなり、それはとても私の手に負える範疇ではありませんので行いませんが、この背景には「人の生死は神によって決められており、すべての人は死すべき定めを負っている(旧約)。しかしキリストを信じるものは救われ永遠の命と安らぎを得る(新約)」というキリスト教の「死」に対する根本思想があります。シュヴァイツアーの「バッハ」に簡潔に記述されていますので以下にご紹介してきます。
「歌詞も音楽と同様に完成したものである。それは、旧約的な死への怖れと新約的 な死への喜ばしさとの対照が、その効果を充分に発揮するような聖句から成っている。預言者イザヤの命ずる『家を整えておきなさい。なぜなら、お前は死に、生きながらえることはないのだから』の言葉に和して、合唱が『古い契約にこうある。人よ、汝は死ぬ定めなり、と』と歌う。しかしたちまちにして、まるで異なった世界から飛んで来るようにソプラノの声がヨハネ黙示録の結びの希求『わかりました、主イエスよ、来てください』を歌いはじめ、管弦楽はそれにあわせてコラール『私は私のことを神に委ねます』を奏するのである。ゴルゴタ丘上の十字架が姿を現わす。魂はイエスの最期の言葉『御手に、私の魂をゆだねます』を、そのまま自分の祈りとして捧げる。するとあの盗賊に与えられたイエスの『今日、お前は私とともに天国にいるであろう』という約束の言葉を聞くのである。死にゆく魂はこうして『安らかに、喜びつつ私は逝く』を雄々しく歌う。そして終結のコラール『栄光、讃美、誉と栄華が』が『われ汝に依り頼む、主よ』のメロディーによって響き出すのである。最後の行の『イエス・キリストによって、アーメン』は輝かしい幻想曲にまで拡大されてゆき、やがて器楽が主題を拡大して奏することによって終結にもたらされる」シュヴァイツアーも言っているようにこの曲でもっとも劇的な部分は、曲の中央に置かれた合唱とソプラノ(独唱)のアリオーソ(新バッハ全集版2d)で、合唱が旧約聖書の聖句を歌い、そこに曲を中断させるかのように入り込んでくるソプラノのコロラトゥーラによる新約聖書の言葉「わかりました、・・・来てください」というアリオーソの掛け合いです。これは「死」への葛藤を表しているといわれますが、全体はこの曲を中心にシンメトリックな構造(冒頭の器楽によるソナティナを除いて)になっています。この劇的な音楽もさることながら、私が一番好きな部分はそのあとに歌われるバスのアリオーソ「今日、お前は・・・天国にいるであろう」(3b及び3c)という部分です。これは死を前にして、十字架上でイエスが同時に処刑された盗賊達に向って話した言葉 (ルカによる福音書-以下「ルカ伝」) ですが、ここではもっと普遍的な意味を持っていると思います。これも合唱(コラール)の合間を縫うように歌われますが、その何度となく繰り返される「イン・パラディス」という言葉がいつまでも耳に残ります。まさに天国的な美しさで、これを聴いているとフォーレのレクイエムのあの美しい「イン・パラディスム(楽園にて)」を思い出さずにはいられません。フォーレのレクイエムとバッハのこの作品との関連性が論じられたことは私も聞いたことがありませんが、19世紀の半ばに起きたバッハ・ルネサンスについてはフォーレも知っていたでしょうから(彼の師であったサン=サーンスは熱心なバッハの信奉者でもあった)、あながちそれを否定することもできないように思います。言葉も音楽の質も全く異なりますが、少なくともその根底にある「死」に対する考え方は同じだったと思います。この「イン・パラディス」のバックで歌われるコラールはシメオンの讃歌をもとにルターが作詞したもので、バッハはこの作品以外にもシメオンを讃美するカンタータをいくつか残していますので、このシメオン老人について触れておきたいと思います。
(アルベルト・シュヴァイツァー著「バッハ」 浅井真男、内垣啓一、杉山好 共訳 白水社)(尚『』内の表記は原文では文語体になっていますが、わかりやすくするためここではその部分だけ礒山雅訳の口語体に変更しました)
シメオンは「ルカ伝」の中でキリストの生誕にまつわる話として出てきます。イエスが生まれたのち、両親(マリアとヨセフ)がイエスをつれてお宮参り(モーセの律法により生贄―鳩―を捧げるため)にエルサレムに出かけます。そこで彼らはこのシメオンという老人に会います。シメオンは聖霊を宿しており、メシアに会うまでは死ぬことができなかったのですが、ここで彼らに出会い、両親にイエスが救世主であることを告げ、祝福し、そこでやっと死を迎えることができるようになり、ルターのコラール「安らかに、喜びつつ私は逝く、神の御旨により」となるのです。バッハはBWV83のカンタータ「喜び満ちし新しき契約の時」でも同じコラールの最終節を用いてシメオンを讃美しています。
このカンタータの終曲(新バッハ全集版4)はアダム・ロイスナー(Adam Reusner 1496-1575)のコラール「主よ、あなたの内に私は望みをおいてきました」の第7節が器楽のリトルネロをはさみながら明るく、そして荘厳に歌われ、そのまま二重フーガ「イエス・キリストによってアーメン」の合唱に入っていきます。最後は合唱が弱く「アーメン」と歌い、それにエコーのようにリコーダーが答えて静かに曲を終えます。
この曲の素晴しさをシュヴァイツァーは次のように表現しています。
「バッハ崇拝者の中で、二百の教会カンタータを「哀悼の式(アクトゥス・トラギクス)」(第百六番)の方法で書かれた百の作品と取替えても惜しくないと思ったことのない人はおそらく皆無であろう」(前掲書)次回、様式的な問題や後世への影響、そしてCDのことなどについて触れてみたいと思います。
(注1)ガイリンガー(Karl Geiringer 1899-1989)の「バッハ-その生涯と音楽(1967)」及び樋口隆一「カンタータ研究(1987)」ではBWV150に関して、初期の作品として扱ってはいません。樋口氏のこの本ではミュールハウゼン後期からヴァイマル初期の作品とされています。但し彼が後に出版した「バッハの風景(2008)」では初期の作品として6曲に組み入れており、また2001年に出版されたマルティン・ゲックの大著「ヨハン・セバスティアン・バッハ」でも初期の作品(この本ではもっとも早い時期のアルンシュタット時代に書かれたのでは、と大胆な推定をしている)でも初期の作品として扱っていることから、ここでは6曲としました。更にマルティン・ペッツォルトの論文(C.ヴォルフ編「バッハ=カンタータの世界」に収録)では断片としてしか残されていないBWV223を所期のカンタータ作品に加えています。
(注2)これについてマルティン・ゲックは著書「ヨハン・セバスティアン・バッハ」の中でちょっとした逸話を紹介しています。「レンマーヒルトの子孫の一人は、『牧人』的なリコーダーをともなう編成が、故人の名前[レンマーは『小羊』の複数形、ヒルトは『牧人』の意]をほのめかしているという」と。確かに様々な仕掛けをすることの好きなバッハにはありうる話か、とも思わせます。
2011.02.01 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑦
番外編―ピッチの変遷しばらく中断してしまいましたが、体のほうも何とか以前の状態に戻ってきましたので、再開したいと思います。ただ中断前はほぼ一ヶ月に一度記事を書いてきましたが、なかなか重いテーマで、今後もそのペースを続けられるかどうか自信がありません。何とか続けたいと思いますが、不定期になってしまうこともあるかと思います。その節はなにとぞご容赦ください。
さて前回、バッハ・カンタータの演奏上の問題としてピッチのことを採り上げましたが、その後友人から「どのような経緯で今のa=440になったのか教えて欲しい」というご質問を頂き、調べてみるとこれがけっこう面白いので、個々のカンタータに入る前に番外編としてここで採り上げてみました。
この問題についてはニュー・グローヴ音楽辞典にかなり詳細に記述されていますが、この記事、前半がわかりにくくとても不親切な書き方といわざるをえません。そこで他の資料なども参考にして現在までの変遷について書いてみたいと思います。
1700年前後のヨーロッパは、早くから絶対王政を確立していたフランスを除いて、まとまりのない小国家が群立していた時代であり、音楽の先進国であったイタリアでさえ10以上の国に分かれており、ドイツに至っては300近い国が乱立していたといわれます。そんな状態ですから、ピッチが統一されるなどということはありえなかったのです。
まず前回ご紹介したコアトーン(教会ピッチ)ですが、これも地域によってかなり違っていました。以下に17~18世紀初め頃における例をいくつかあげておきますが、今日の標準ピッチ(一点a=440Hz)に対しての比較で高い方から並べました。
①北ドイツ、北東ドイツ(ポーランド・シュレジア地方) ・・・ +短三度~全音
②南ドイツ、中部ドイツ ・・・ +半音
③イギリス ・・・ +半音
④ヴェネツィア、北イタリア ・・・・ +半音
(但しサン・マルコ寺院だけは例外でこれより半音低かった、つまり今日と同じ)
⑤南西ドイツ(ライン川流域) ・・・ 今日と同じ
⑥ローマ、スペイン、オランダ ・・・ -半音
⑦フランス ・・・ -全音
というような状況で、これらはオルガンのピッチによっています。記録上もっとも高いピッチはドイツ中部の美しい古都市ハルバーシュタット(ザクセン・アンハルト州)にある大聖堂のオルガン(1361年建造)でa=505.8(現在より短三度以上高い)となっています。またイギリスではピッチの変動が激しく、16世紀にはa=360と全音以上低かったのが17世紀にはa≒475で全音近く高くなり、18世紀になって半音上に下がっています。更に1751年にヘンデルがロンドンでメサイアを上演した際はa=422.5という音叉が使用されています。こうした高いピッチのコアトーンはルネサンス時代、管楽器のピッチが高かった(「ルネサンス・ピッチ」 a≒440~470)ためとも言われています。
一方カンマートーン(宮廷ピッチ、もしくは室内ピッチ)は、コアトーンがオルガンを基にしているのに比べてそのよりどころとなる基準があいまいなのですが、ルネサンス以来の世俗音楽に用いられた楽器や、宮廷での食卓を飾る音楽、そして家庭内で使用された鍵盤楽器のピッチがそもそもの起こりだと思われます。バロック期のイギリスではコアトーンが現在のピッチより高かったのに比べ、家庭で使用されたヴァージナルは逆に今より半音低く、その理由はこの方が一般の家庭では歌いやすかったため、と言われます。それとは逆に前述のとおりルネサンス時代の管楽器はピッチが高く、そのため後のコアトーンとカンマートーンの高さはバロック初期においては逆転しており、特にドイツで使用された金管楽器のピッチはコルネットトーンと呼ばれ、後にコアトーンと同義語になっていきます。いずれにしろ地域や楽器によってかなり幅があり、幾つかの例は最後の一覧を参考にしていただきたいと思いますが、当時はアンサンブルをする際、移調などの方法がごく当たり前に行われていたようです。
こうしたピッチについて歴史上初めて言及したのはでミヒャエル・プレトリウス(Michael Praetorius 1571-1621)で、3巻からなる音楽史上最初の百科辞典「音楽大全 Syntagma musicum」の第2巻(1619)に書かれています。彼は標準ピッチを15℃でa≒425(現在の440より五分の三音低い)としました。もちろんこの当時にHzなどという数値ガ存在する筈はありません。彼の本に書かれたオルガンのパイプの図解から割り出されたもので、これには経年変化による本の縮みまで計算されているとか。彼はこのピッチを基にヨーロッパ各地のオルガンについてパイプの長さや聴感によりその高低を実測したのです。そして彼は基準ピッチより高いものも、また低いものも否定し、今後作られる楽器には自身の標準ピッチ採用するよう提唱したのです。一つにはこの時期に飛躍的に発展したヴァイオリンという楽器の影響があります(注)。これ以上高いピッチはE線を切る恐れが生じ、また低いと充分な音の強さが表現できないと考えたからです。しかし彼の提唱も1618年に始まったドイツ30年戦争で国内は壊滅的とも言える打撃を受けて混乱し、結局はその後も高いピッチのオルガンが建造されていったのです。その後のコアトーンとカンマ-トーンについては前回述べたとおりです。バロック・ピッチといわれるカンマートーンのa=415が18世紀半ばまでのオーケストラ・ピッチになったのです。
ではバッハ以降のピッチがどうなったのかをみてみますが、19世紀に入るまでの間についてはあまり記述がありません。ただオーケストラのピッチはしだいに高くなっていきます。始めのほうでご紹介した1751年のヘンデルのメサイアではa=422.5でしたし、モーツァルトは自身のクラヴィーアをa=421.6で調律したと言われていますので18世紀後半から19世紀初頭にかけてはこのあたりが標準だったと考えられます。奇しくもプレトリウスが提唱したピッチ・レベルになったわけです。但しフランスだけは相変わらずやや低く、1760~80年頃のヴェルサイユ宮廷室内楽団で使用された音叉のピッチはa=409でした。しかしそれも19世紀に入ると、パリのオペラ座でa=423というのが確認されており、ここに至ってようやくドイツ、イギリス、フランスがほぼ同じピッチで統一されたのです。
19世紀も進むとピッチは更に高くなっていきます。こうなった背景の一つにヴァイオリンのガット弦の改良が挙げられていますが、それ以上に大きな音や輝かしい音を人々が求めたためと言われています。この結果弦楽器には手が加えられ(ネックの強化や指板の角度の変更他)、管楽器も大きな音が出るよう改良されていきます。しかしながらピッチが高くなるということは歌手たちにそれだけ負担をかけることになり、当然不満がでてきます。したがって以後高くなったり、反動でそれを少し下げたり、ということが続きます。それでも1830年パリのオペラ座ではa=430.8となり、ドイツでは1834年シュトゥットガルトの会議でa=440が提唱されています。ただシュトゥットガルトのピッチは当時一般化されることはありませんでした。そして1846年にはとうとうロンドンのフィルハーモニー協会がa=452.5という極めて高いピッチを採用しました。この頃のイタリアも同様で1856年のスカラ座ではa=451を超えていたといわれ、この事実はヴェルディの一部のオペラが極めて高いピッチで初演されたことを物語っています。
こうした高いピッチに歯止めをかけるため1859年フランス政府は委員会を開き、a=435という標準ピッチを定め法的効力を持たせました。これがディアパソン・ノルマルといわれるもので、しだいにヨーロッパ各地に浸透していき1885年のウィーン会議でもこれが採用され、やがてヨーロッパやアメリカのピアノ・メーカーがこれに追従します。ただ19世紀末イギリスではこれよりやや高いNew Philharmonic Pitchと呼ばれるa=439(気温68°F-20℃に相当-の下で)が採用されており、アメリカでもa=440がコンサート・ピッチとして使われていました。そんな状況下で、1938年英国規格協会はディアパソン・ノルマルが温度に関する変動要因を無視しているとしてa=440を標準ピッチとして提唱し、翌年のロンドンの国際会議でこれが決定されたのです(おそらくは68°Fの下で。またこのあたりニュー・グローヴの記述はわかりにくい)。BBCやアメリカのスミソニアン協会がこれを積極的に推進したことから、これが世界的に採用されるようになり、1955年ISO(国際標準化機構)もこれにしたがって勧告を行い、現在に至っています。日本では1948年文部省がa=440を標準音として定め(それ以前は435)、これを基準にすべて楽器が作られるようになりました。ただ実際のコンサートなどではほぼ世界的にこれより高いピッチが採用されていることは皆さんもご承知のとおりです。ベルリン・フィルやウィーン・フィルの445は高すぎるとしても、日本ではN響も442以上でチューニングされているそうです。私もピアノの録音では442で調律してもらっていました。現在ではチューニング用の電子機器もあり、温度の変化によるピッチの変動もなくなりましたが、管楽器などは演奏前に充分温めておく必要があります。
以上駆け足でピッチの変遷についてみてきましたが、私は「すべての演奏が当時のピッチで演奏されるべきだ」などと言うつもりは毛頭ありません。ただ少なくともバロック音楽などは当時のピッチで演奏されることが望ましいと思っています。またモーツァルトの音楽をもし現代のオーケストラがベルリンやウィーンのオケのように高いピッチで演奏するとすれば(ベーム、カラヤン然り)、それは作曲者が意図した音楽とは少し違ったもの(少なくとも半音は高い)である、と認識した上で聴くべきかと思います。ではベートーヴェンは?などといろいろあげていくと際限がなくなりますのでやめますが、ベートーヴェンの管弦楽曲も現代のような大編成ではなく、当時の規模(弦は4,4,2,3,3プルトの32人+2管編成の管楽器-ボン時代)で聴きたいと私は思います。
最後に文中では触れられなかった歴史的なピッチについていくつかあげておきます。
1611年 約360 イングランド中部ウースターに建造されたオルガン
1708年 475 セント・ジェームズ宮殿礼拝堂に建造されたオルガン
1762年 407.9 ハンブルクにおいてヨハン・マッテゾンが採用したピッチ
1783年 409 パスカル・タスカン(仏の有名なクラブサン製作者)の音叉
1813年 423.7 初期のロンドン・フィルハーモニー協会のピッチ
1815-21年 423.2 ドレスデン歌劇場の音叉
1846-54年 452.5 ロンドン・フィル(オケ)のピッチ
1849年 445.9 ロンドン、ブロードウッド社(ピアノ・フォルテ)のピッチ
1856年 445.8 パリ・オペラ座
1857年 451.7 ミラノ・スカラ座の音叉
1874年 454.7 高くなったロンドン・フィルハーモニー協会のピッチ
(1879年作られた英スタインウェイ社のピアノも同じ)
1879年 457.2 ニューヨーク・スタインウェイのピッチ
(年号のあとの数字がピッチになります。また本文中で触れたものは記載していませんので、あわせて参考にしてください。)
(注) 16世紀後半にガスパーロ・ダ・サロ(Gasparo da Salo、本名Gasparo di Bertorotti 1540-1609)やクレモナの名匠アマティ一門(もっとも有名なのは Niccolo Amati 1596-1684)によるヴァイオリンの製作が始まっています。
2010.10.23 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑥
6. 教会カンタータ演奏上の諸問題――(2) ピッチのこと「古楽器が嫌いだ」という人の中に、「ピッチが低いから」という人がいます。そう主張する人達に絶対音感があるかどうか知りませんが、音楽が沈んだように響くということはあり、そのせいで「嫌いだ」と思うことはあるかもしれません。古楽器のピッチが低いということはある部分正しいのですが、バッハのカンタータに限ってみてみると、ことはそう単純ではないのです。
私は1981年の5月、会議でヨーロッパに行った帰途ドイツのハンブルクに立ち寄りました。大きな目的は私が録音したギターのアルバム(展覧会の絵/山下和仁)を売り込むことでした。編集を終えたばかりのマスターからコピーしたカセット・テープを持参し、ドイツの社長に聴いてもらったところすぐにその場で発売を約束してくれました。このレコードはその後ドイツ・レコード賞を受賞し全世界でも発売されました。当時日本の録音が海外で発売されることは極めて稀だったのです。話が脱線しましたが売り込みを終え、帰りの飛行機が日曜日の夕方だったため、土・日に市内を少し散策しました。国際的な港町として栄えたハンブルクはヨーロッパでも有数の歓楽街をかかえ猥雑で華やかな一面を持っていますが、そうした一部の地域を除くと、アルスター湖を中心とした美しい風景と、南ドイツとは違った落ち着いた雰囲気に支配され、私はすっかりこの街が気に入りました。土地の人の生真面目さや頑固さも感じられます。湖畔できちっとしたスーツに身を包んだ老人が釣り糸を垂れている姿にも驚かされました。さてこのハンブルクで私はどうしても行きたいところがありました。帰国する日の日曜日、私は教会に出かけました。そこは天に尖塔を突き立てたような教会で建物自体には歴史を感じないものでした。中に入ると、ちょうど礼拝を行っておりオルガンの荘厳な響きが教会内に鳴り渡っていました。私は静かに歩を進め礼拝堂の奥へと進んでいきます。やがて背後のオルガンの見えるところまで
 行って振返ると、その薄暗がりの中にラッパを吹く天使が二人左右に立ちその背後に巨大なオルガンのパイプが林立しているのをはっきりと見ることができました。そう、このオルガンこそザンクト・ヤコービ(聖ヤコブ)教会の名匠アルプ・シュニットガー(Arp Schnitger 1648-1720)製作のオルガンだったのです(右写真-GNU Free Documentation License)。それを目にしたときの感動は今でも忘れることができません。1720年の秋バッハはこの教会のオルガニストを志願して老匠ラインケンの前でこのオルガンを弾いたのでした。ただよく聴いてみると、どうもオルガンはその楽器からではないように思え、周囲を見回すとその横の壁に新しく設置された現代的なオルガンから流れてくるものでした。どうしてこんなことが、と疑問を持ちつつハンブルクを後にしたのです。それからしばらくして来日したフランスのオルガニスト、マリー=クレール・アランさんと食事をする機会があって、私はそのことを彼女に尋ねてみました。すると彼女は小声で「これは内緒の話ですが、あのオルガンは今は弾くことができないのです」と教えてくれたのです。そんなことからいろいろ調べてみると、教会は第二次世界大戦で爆撃にあって破壊され、戦後に建て直されたものであること、ではどうしてオルガンが残っているか?それは市民が戦時中オルガンが爆撃で破壊されることを恐れてそれを疎開させていたこと、などがわかりました。それほどハンブルクの市民にとってこのオルガンは大事なものだったのです。ですから戦後その姿だけは元通りになったのですが、音が出る状態までにはならなかったのです。このオルガンは1993年ユルゲン・アーレントにより当時の状態に復元され、現代に甦りました。今ではいくつかここで録音されたCDも発売されています。
行って振返ると、その薄暗がりの中にラッパを吹く天使が二人左右に立ちその背後に巨大なオルガンのパイプが林立しているのをはっきりと見ることができました。そう、このオルガンこそザンクト・ヤコービ(聖ヤコブ)教会の名匠アルプ・シュニットガー(Arp Schnitger 1648-1720)製作のオルガンだったのです(右写真-GNU Free Documentation License)。それを目にしたときの感動は今でも忘れることができません。1720年の秋バッハはこの教会のオルガニストを志願して老匠ラインケンの前でこのオルガンを弾いたのでした。ただよく聴いてみると、どうもオルガンはその楽器からではないように思え、周囲を見回すとその横の壁に新しく設置された現代的なオルガンから流れてくるものでした。どうしてこんなことが、と疑問を持ちつつハンブルクを後にしたのです。それからしばらくして来日したフランスのオルガニスト、マリー=クレール・アランさんと食事をする機会があって、私はそのことを彼女に尋ねてみました。すると彼女は小声で「これは内緒の話ですが、あのオルガンは今は弾くことができないのです」と教えてくれたのです。そんなことからいろいろ調べてみると、教会は第二次世界大戦で爆撃にあって破壊され、戦後に建て直されたものであること、ではどうしてオルガンが残っているか?それは市民が戦時中オルガンが爆撃で破壊されることを恐れてそれを疎開させていたこと、などがわかりました。それほどハンブルクの市民にとってこのオルガンは大事なものだったのです。ですから戦後その姿だけは元通りになったのですが、音が出る状態までにはならなかったのです。このオルガンは1993年ユルゲン・アーレントにより当時の状態に復元され、現代に甦りました。今ではいくつかここで録音されたCDも発売されています。何故このオルガンの話をしたかというと、このオルガンのピッチは一点a=489.2Hz(以下略記)という非常に高いもので、現在のピッチa=440と比べてもほぼ全音高くなります。つまりh(493.88)に近いのです。当時のピッチは一般的にa≒415(現在のA♭に相当)と言われていますので、それに比べると短三度も高くなります。これがいわゆるコアトーンChortonと呼ばれる北ドイツを中心とした音楽圏のピッチになります。ただこのコアトーンも2種類あって当時一般的だったのはこれほど高くはなくだいたいa≒465(現在のb、つまり半音高い)くらいだったようです。コアトーンは「教会ピッチ」とも言われますが、バロック時代においては現在のように決まったピッチはなく、国や楽器によっても様々に違っていました。ピッチが統一されるようになったのは1859年、フランスの国際会議でa=435と定められてからです。
バロック時代様々なピッチがあったとはいえ、大きな柱としては上記のコアトーンがあり、またもう一つの大きな柱としてはカンマートーンKammertonと呼ばれる「宮廷ピッチ」がありました。このカンマートーンはもともと世俗の音楽に使用され、フランスのオルガンに使われていた低いピッチa≒392がもとになったといわれていますが、柴田南雄氏の「西洋音楽の歴史(中)」(音楽之友社)によると、ドイツではもともと(17世紀バッハ以前)カンマートーンの方がコアトーンよりピッチが高く、それが18世紀になってフランスで改良されたオットテール(Jacques-Martin Hotteterre 1674-1763)の管楽器に取り替えられたため(注1)、そこで逆転が起きたのだとされています。おそらくこのフランス型の低いピッチはツェレの宮廷からドイツに持ち込まれたのでしょう。ツェレはリューネブルクとハノーファーの中間に位置していて北ドイツ圏にありますが、この宮廷には当時名高いフランスの楽団があって、ここから様々なフランス様式がドイツに持ち込まれています。フランス風序曲、組曲(パルティータ)などがすぐに思い浮かびますが、バッハも若い頃リューネブルクで過ごした日々、ツェレを訪ねてそれらの様式を直接吸収している筈です。G.ベームがフランス様式を取り入れたのもお互いに近い都市関係があった故でしょう。この低いピッチの管楽器がトーマス教会に導入されたのはクーナウの時代の1702年といわれます。この管楽器のピッチ(カンマートーン)がa≒415で、現在の古楽器(オリジナル楽器)の標準的なピッチ(a=415)になっています。前記ヤコービ教会の高いピッチのシュニットガー・オルガンは同時にカンマートーンにも対応できるようにa=411.4の通奏低音用のレジスターを持っていました。北ドイツのオルガンの名匠がシュニットガーであれば、南ドイツの名匠はジルバーマン(Gottfried Silbermann 1678-1753)になります。彼はザクセンに生まれ、若い頃イタリアやフランスでオルガン製作を学んだ関係から北ドイツとはまた違ったスタイルのオルガンを作りました。彼が最後に設計した(建設中に死亡)ドレスデンの教会のオルガンがa=415.5(現在のA♭に近い)でした。従ってこれらの事実や残された古い楽器から当時のカンマートーンのピッチがa≒415だったと考えられているのです。
ではカンタータを上演する際の障害について考えてみましょう。バッハが活躍の場としたテュービンゲン地方は地理的には中部ドイツに属していますが、宗教的にはプロテスタントになり、そのオルガンは北ドイツ圏と同じコアトーンで調律されています。一方管楽器は伝統的にカンマートーンで作られていますので、これらがアンサンブルをするには当然困難が伴います。バッハやまた現在の古楽演奏団体はそれをどうやって解決しているのでしょうか?
すぐに思いつくのは移調という方法です。そのほか弦楽器であれば調弦を変えることもできます。ただ後者の場合、当時の弦楽器は今ほどネックも丈夫ではなく、また弦はスチールではなくガットでしたので、高くするのは容易ではなかったと思います(注2)。また低くするのは可能でしょうが、力のある音が出るかどうか。管楽器の場合は移調して高くしたり低くしたりしたときの高音や低音で演奏不可能な音がでてこないかどうか?また楽器によっては運指がやたら難しくなったり、その逆になったりといろいろ問題はでてきそうです。いずれにしろどのピッチにあわせるのかで変わってきます。
結論から言いますと、ちょっとややこしいですがヴァイマール時代までのカンタータはコアトーンのオルガンのピッチに合わせて管楽器が高く移調して演奏し、ライプツィヒ時代のカンタータはカンマートーンの管楽器にオルガンを低く移調して演奏する、ということになります。何故こんなことをするのかというと、残された楽譜からバッハが当時そうやって演奏したことがわかっているからです。ライプツィヒではクーナウがトーマス教会に採り入れた伝統的な方法にバッハは従ったのです。
ミュールハウゼンやヴァイマールのオルガンはコアトーンのa≒465でしたので、管楽器のパート譜は全音もしくは短三度高く書かれていたことになります。アーノンクールは弦楽器をコアトーンで調弦する方法を試み、鈴木雅明氏やコープマンなどはこの方法を採っています。この場合同じ弦は使えず、鈴木雅明氏は通常より細い弦で対応しているそうです。バッハはライプツィヒで初期のカンタータを再演する際、移調する方法をとっていたようです。
ここでもう一つ面白いことが指摘されてます。鈴木氏やコープマンも書いているのですが、ファゴットの問題です。バッハの最初期のカンタータが4曲あり、中でも現存する最古の曲でアルンシュタット以前に書かれたと推定されるBWV150「主よ、われ汝を仰ぎ望む」ではファゴットは弦楽器より短3度高く記譜されており(下の譜例―シンフォニアの冒頭スコアの一部―を参照ください)、このことは何を意味するかというと、同じカンマートーンの管楽

以上、ピッチについての問題をご紹介しましたが、曲によって更にいろいろ検討する必要があるようです。特にリコーダーの扱いは少々ややこしく、コープマンの解釈は明らかに間違っている(BWV106に関して)とデュル(Alfred Dürr)に指摘されるなど、問題は非常に複雑です。また現代の楽器で楽譜どおり(管楽器はスコア上の弦の調性にあわせる)にこれらコアトーンで書かれたカンタータを演奏した場合、実際にはバッハが意図した音よりも半音低く響くことになり、上記ファゴットの問題に限らず声楽なども大きな影響を受けます。バスは更に低くなり、ソプラノは高い輝かしい声が失われてしまいます。それでもかつてはこうして演奏されていたのです。これ以上この問題に深入りしますとまさしく「迷宮」に入っていきますので、ここまでの記述にとどめます。あくまでもイントロダクションとしてお読みください。もっと詳しくお知りなりたい方は本文中にご紹介した本などをご参照ください。
<お断り>(注1) 改良がどのようなものだったかというと、当時一般的に使われていたフルート(フラウト・トラヴェルソ)は軍隊が使っていた切れ目のない一本の楽器だったのですが、これを歌口のある頭部、指穴を開けた胴部、一つのキーがついた足部の三つの部分に分け、利便性を高めたのです。このフルートはさらに1720年ごろ胴部を二つに分けてその上のほうの部分に幾つかの長さの異なるスペアを用意し、他の楽器とピッチを合わせられるように変えられたのです。こうすることで半音高くしたり、また半音低くしたりできたそうです。(クヴァンツ「フルート奏法」荒川恒子訳 全音楽譜出版社より)
(注2) ヴァイオリンは18世紀後半以降楽器に手を加え、音域を広げたりより大きな音を出すために、指板を胴の中央まで長くしたり、そして駒や指板の位置を高く(ネックの傾斜を深くする)して弦の張力を増したりしています。弦はE線を除き現在でもガット(羊の腸)弦が使われたりしますが現在のガット弦はその上にスチール線が巻かれています。その他にも様々な改良が施されています。こうした改良が施される前の楽器をバロック・ヴァイオリンと呼んでいます。他の弦楽器も同様です。
ここで再び中断を余儀なくされてしまいました。あと1回、楽器に関する問題に触れてから休載できればと思っていましたが、時間がなくなってしまいました。来年個々のカンタータから再開しようと思いますが、3ヶ月ほどお休みさせていただきます。それではそのときまで。
2010.10.05 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬⑤
5. 教会カンタータ演奏上の諸問題――(1) 演奏者は何人が適切か前述のとおり、教会カンタータは本来教会内の礼拝で演奏されることを目的としてかかれましたが、今日では多くの団体がそうしたこととはかかわりなくコンサート・ホールで演奏し、またCDなどにも録音しています。現代楽器によるもの、古楽器によるものなど様々に演奏されています。現代楽器による演奏は最近ではかなり少なくなっていますが、かつてはそれが主流を占めていました。カール・リヒター、フリッツ・ヴェルナー、そしてヘルムート・リリングらの指揮によるものがその代表的なもので、これらは合唱の人数も多く、歌唱法や奏法も現代的なのが特徴です。一方トン・コープマン、ジョン・エリオット・ガーディナー、そして日本が世界に誇る鈴木雅明らの指揮による演奏は古楽器(オリジナル楽器)を使用し、様々な時代考証や研究の成果に基づいてバッハ本来の響きを取り戻そうと工夫を凝らし、演奏しています。演奏者の数も少人数によっています。
少しテーマからそれますが、皆さんは現代楽器、古楽器、どちらの演奏を好みますか? 私は断然古楽器を選択します。もちろん古楽器なら何でも良いという訳ではなく、技術的に劣るものは話になりません。私はかつて古楽が嫌いだった時期があります。1980年代頃だったでしょうか?いわゆるバロック・ブームの中で古楽器による演奏が台頭し始めた頃になります。何故嫌いになったのか?それは明らかに技術的に劣っていたからです。いくら古楽器を使用しそこに新しい響きが生まれたとしても、へたくそだったら興ざめです。厳しいようですがデレフンケン(Das Alte Werk)のアーノンクールやレオンハルトによるバッハのカンタータ全曲録音などいい例です。初期のガーディナーの録音なども器楽に欠点をかかえていました。それでいてこうした「古楽器による演奏こそがバロック音楽本来の響だ」という主張が行われるようになり、それに嫌気がさしたのでした。そんな時期があり、私は古楽鑑賞から離れてしまいました。ところがどうでしょう、現在の古楽演奏の水準は現代楽器とまったく変わらないどころか、少なくともロマン派より前の音楽については凌駕しているといって過言ではないでしょう。声楽を含めハーモニーの良さは古学の団体からしか聴くことができないと思えるほどです。ロマン派の音楽でさえ最近はオリジナル楽器で演奏しようという団体が現れています。この8月にも仲道郁代さんが弾くショパンの1番のコンチェルトを1841年製のプレイエル・ピアノで弾く演奏会がありました。19世紀のピアノについてはそれ以前にも神谷郁代さんがシューベルトのアルバムの中で1曲だけ録音していたので、それ以来その響きの良さには驚いていたのですが、当日のコンサートで生の音を聴き、そのビロードの輝きにも似た美しいピアノの響きに改めてオリジナル楽器のよさを再認識した次第です(ただオーケストラ――クラシカル・プレイヤーズ東京――にはまだ技術的な課題が多く残されました)。言葉の響きからすると、現代楽器は新しく、古楽器は古いというイメージがありますが、まったく逆です。古楽器による演奏は常に新しく、私たちに新鮮な驚きを与えてくれます。私のまわりにも「古楽器は嫌いだ!」という人が何人かいますが、私からすると彼らは自らの手で音楽を聴く喜びに蓋をしているだけのように思えてなりません。
話がそれてしまいましたが、バッハの教会カンタータの演奏について同じ古楽の団体でも何人で演奏すべきかという点はまちまちです。そこにも彼ら独自の解釈が現れています。通常何げなく聞いていると気がつきませんが、こうした点も新しい響きにつながっていて、それぞれの個性を感じることができるのです。では何人で演奏すべきかという点について考えてみましょう。
これについても実はバッハが1730年の8月23日に書いた、ライプツィヒ市の参事会にあてた上申書から推察することができます。少し抜粋して以下に掲載しますと、
整備された教会音楽には歌手と楽器演奏者とが必要であります。歌手は、当地においてはトーマス学校の生徒たちによって編成され、その内訳はディスカウント(ソプラノ)、アルト、テノール、バスの四種となります。以上がバッハの考えている声楽陣の数になります。つまり単一合唱では各パート3人が最低必要で、理想は4名(この場合1名は病気などで欠員がでた場合の補充要員)であることがわかります。独唱者はその中から優秀な人がコンチェルティストとして歌っていました。 バッハは続けて器楽に必要な人数もあげています。
教会作品のための合唱団がそれにふさわしい体裁を整えるには、歌手たちは更に二種類の群に、すなわち独唱者(コンチェルティスト)と合唱者(リピエニスト)に区分されねばなりません。
独唱者は普通四名ですが、ときには五名、六名、七名、あるいは八名にまでなることがあります。すなわち複数の合唱隊によって(ペル・コーロス)演奏をおこなおうとする場合です。
合唱者は少なくとも八名は必要です。つまり各声部に二名必要だということであります。
楽器奏者もまた数種類に区分されます。・・・・・(略)
トーマス学校の寄宿生の数は55名です。この55名が四つの合唱隊に分けられて、四つの教会に配属され、そこで一部はカンタータを、一部はモテットを、一部はコラールを歌わねばなりません。聖トーマス、聖ニコライおよび新教会の三教会に配属される生徒たちはみな、音楽的才能をもったものでなければなりません。ペテロ教会にまわされるものは屑ばかり、つまり、まるで音楽がわからず、かろうじてコラールが歌える程度といった連中であります。
さきの音楽的合唱隊にはそれぞれに少なくとも三名のソプラノ、三名のアルト、三名のテノール、および同数のバスが必要です。・・・・(略)・・・(ただし、各声部あてに四名の人員を配置でき、したがって各合唱隊が16名の編成をもてるような集団がつくれますなら、これに越したことはありません)
というわけで、音楽がわかっていなければならない人員の数は、計36名ということになります。
(白水社 バッハ叢書第10巻「バッハ資料集」 酒田健一訳)
 第1ヴァイオリン・・・2ないし3名
第1ヴァイオリン・・・2ないし3名第2ヴァイオリン・・・2ないし3名
第1ヴィオラ・・・・・・2名
第2ヴィオラ・・・・・・2名
チェロ・・・・・・・・・・2名
ヴィオローネ・・・・・1名
・・・・・ (同 資料集)
弦楽器以下は管楽器が続き、それは曲の編成次第で変わりますが、フル編成(オーボエ、ファゴット、トランペット、ティンパニですが場合によってフルートも加わる)の場合で人数は「最低20人は欲しい」としています。こうした記述から考えると編成にもよりますが、カンタータの上演には合唱12名、器楽奏者20名つまり全部で32名が必要だったことになります。ただここには当然ながら必要とされる通奏低音のオルガンが省かれていますので、もう一人追加されることになります。上の図版はバッハのいとこであり、オルガン作品の分野でバッハにも大きな影響を与えたJ.G.ヴァルター(Johann Gottfried Walter 1684-1748)が著した「音楽辞典」の表紙で、当時のライプツィヒにおけるカンタータの演奏風景を描いたものですが、1732年という年号がわかっていますので、となると中央で丸めた楽譜を持って指揮している人物はバッハその人と考えられます。この図版からわかることは一部に思われているようにバッハがオルガンを弾きながら指揮したということはなく、彼は指揮者に専念していたと思われます。いずれにしろこのバッハの上申書はカンタータの演奏に当たって声楽も器楽も優秀な人員が不足しており、市に対してもっと報酬を増やすなどして人員を確保できるようにして欲しい、という趣旨で書かれたものです。優秀な器楽奏者(町の楽師や大学生)が確保できず、トーマス学校の下手な奏者を使わざるを得ないことを嘆いています。
バッハが意図していたカンタータ演奏上の編成規模は上述のとおりですが、現在では多くの古楽演奏の団体も、曲によって多少変わるものの、合唱は概ねそれに従うか、やや多い人数になっています(各パート3~6名)。但し、コープマンは声のバランスを考慮してか、ソプラノを少し増やす傾向にあります。これら古楽の団体によるCDのライナー・ノーツもたいへん読み応えがあり、特にコープマンやBCJによるCDでは著名なバッハ研究家による解説や演奏者自身の言葉による解釈などが書かれていてとても面白い読み物になっています。
ところでこうしたバッハ自身の編成に関する記述があるにもかかわらず、最近これに異を唱えて「合唱は各パート1人で歌うべき」という注目すべき主張が表れています。もっともこの異論は最近と言ってももう30年近く前のことになります。1981年の11月にアメリカの音楽学会で発表され、翌1982年The Musical Timesに「バッハの合唱団――予備報告」として掲載されました。もうかなり時間は経っているのですが、時間の経過とともにこの考え方に基づく演奏が最近増えているので、あえて最近とさせていただきました。この論文はアメリカの音楽学者(チェンバリスト・指揮者でもある)ジョシュア・リフキン(Joshua Rifkin)によるもので、彼はマタイ受難曲の初演について、従来の1729年説を覆して1727の4月11日であったと訂正し、注目を浴びた学者です。彼の主張するこの方式を採用する指揮者には、リフキン本人のほか、アンドルー・パロットとタヴァナー・コンソート、シギスヴァルド・クイケン(但し後年になって)、そしてポール・マクーリッシュなどが名を連ねています。
この考え方の根拠は大きく二つあります。詳細な記述はしませんが、まず一つは、バッハの上申書の中にも出てくるように不足する器楽奏者をトーマス学校の生徒が補わなければならなかったため、1パート3人の合唱を確保できず、計算していくとパートに1人しか歌手はいなかった、というものです。バッハの記述では第2ヴァイオリンからヴィオローネまでの弦楽器を一時的に、また楽器によっては常時トーマス学校の生徒が担当していた、ことになっています。四つのグループで各12人とすれば48人となり、55人の生徒だと7人余るので、彼らが器楽を担当していたのでは?という考え方も成り立ちますが、バッハは病気で演奏できなくなる生徒のことも考えて常に余分な人員が必要だと言っていますので、器楽専門の寄宿生はいなかったと考えてよさそうです。これについてコープマンは「寄宿生は確かに55人だったが、市内在住の通学生で音楽的素質のあったものもたくさんいたので、人数の確保は十分できた筈」という説を打ち出して反論していますが、それなら前述の上申書に多少なりともそれをうかがわせる記述があってもいいように思います。
もう一つの根拠は現存するパート譜から推察されたことです。バッハのカンタータのパート譜はその後再演する時のためにかなりの作品が保存されています。そしてそれらの大半は1部ずつ残されていて、ソロの部分が書かれているソリスト(コンチェルティスト)用のパート譜となっています。「大半は」と言ったのは、曲によって合唱(リピエニスト)用の別のパート譜が残されているものがあるからです(BWV21、23、29、63、71、76、110、195の9曲)。この合唱用の楽譜が存在することから、それ以外(上記の9曲を除く)のカンタータはすべてソリストだけで、つまり4人だけで歌われていたのだ、という考えです。かつてバッハのカンタータは1部のパート譜を3人が見て歌っていた(真ん中にソリスト、その両脇に合唱に参加する人を置く)とする説が有力でしたが、これはその説をまっこうから否定するものです。ソリストのパート譜にソロと合唱の区別が書かれていないこともその根拠となっています。更にこの考えを裏付けるものとしていくつかのソロ・カンタータの例をあげています。バッハのソロ・カンタータで最後にコラールの登場する曲がいくつかあります。そのうちBWV55、56、84、169の4曲は自筆のスコアに「テノール独唱と3リピエーノのための」とか「ソプラノ、アルト、テノールとバス・コンチェルティーノのための」と書かれており、もしソリスト以外のリピエニストが1パート複数の人間によって歌われると、合唱部分でコンチェルティストしかいないパートとのバランスを明らかに欠いてしまう、という主張が成り立つのです。これらの理由からバッハのカンタータは一部の例外を除き当時「1パート1人の歌手によって歌われたものである」とリフキンは主張したのです。
リフキンの主張した説には当然反論がいろいろ存在しますが、それにはまたそれを正当化する反論も出てきたりして、机上の議論としてはたいへん面白いものだとは思います。現在でも多くの学者がこれをとりあげ、なかなか出口の見えない議論が続けられています。しかしながら実際の演奏がどうだったかは別にして、バッハ自身が書いた上申書に理想的な演奏規模が記されている以上、その人数で演奏すべきだと私は思います。当時のトーマス教会とは違って今では優秀な歌手をそろえることはそんなに難しいことではないでしょうから。それとCDで聴いたりする分には演奏がよければリフキン方式でも十分楽しめます。それは録音という電気的な処理が入るのでバランスや残響などが簡単に調整できるからです。でももしライブで聴くとすると、まずはすべての演奏者が歌手として優れていて、かつ古楽の素養を十分持っていること、そして何より余程条件のいい教会かホールでないと鑑賞に耐えないのではないかと思います。素朴といえば聞こえはいいですが、貧弱な演奏を聴かされるのではたまりません。残念ながら私はまだリフキン方式のライブを聴いたことがありません。いつかチャンスがあったら聴いてみるのも一興かもしれません。もう一つこうした演奏が出てきた背景にはレコーディング・コストの高騰や演奏者の分け前が増えるといった理由など、ちょっとうがった見方もしてみたくなります。
最後にリフキン方式による演奏でいいと思ったCDを下記にあげておきます。
 ①マニフィカトBWV243
①マニフィカトBWV243②カンタータBWV11「神をそのもろもろの国にて頌めよ」(昇天祭オラトリオ
BWV249b)
③カンタータBWV50「いまや、われらの神の救いと力と」(断片)(二重合唱)
④カンタータBWV4「キリストは死の縄目につながれたり」
⑤復活祭オラトリオBWV249
エマ・カークビー(S)、ペーター・コーイ(Br)他
アンドルー・パロット指揮 タヴァナー・コンソート&プレーヤーズ
Virgin Classics 7243 5 61647 2 7(2枚組)
尚リフキン自身が指揮した「ロ短調ミサ」のCD(Nonesuch 79036-2)もいいのですが、声楽陣の僅かなヴィブラートがハーモニーを損なっていて気になります。ただそのライナー・ノーツはリフキン説を知る上でとてもいい読み物になっています。
2010.09.14 (火) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ-死への憧憬④
4. 教会カンタータと礼拝バッハには現在200曲ほどの教会カンタータが残されていますが、息子のカール・ フィリップ・エマヌエルと弟子のアグリーコラによる「故人略伝」によれば5年分のカン タータを作曲したことになっていますので300曲程書いたことになります。また中に はグラウプナーのように1400曲という途方もない数の作品を残した人もいます。バッ ハの300曲の真偽はともかく何故こんなに必要だったのでしょうか?それにはカンタ ータと教会における礼拝の関係をみてみる必要がありそうです。
今日わが国のプロテスタントの教会では主日(日曜日)の礼拝はおおむね次のように行われています。
①前奏(オルガンによる) ②招詞(神による招きのことば) ③讃美歌(招詞にこたえて会衆が歌う) ④交読詩篇(牧師と会衆の応答形式による詩篇の朗読) ⑤聖書朗読(その日のテーマに沿って牧師により旧約と新約聖書の一説が読まれる) ⑥祈祷 ⑦説教(牧師によるお話し) ⑧讃美歌 ⑨献金 ⑩主の祈(「天にまします我らの父よ」で始まる有名な祈りの言葉) ⑪頌栄(三位一体を讃える歌) ⑫祝祷(牧師による祝福の祈りで手を上方にかざして唱えられ、会衆はアーメンで答える) ⑬後奏(オルガン) ⑭報告上記の式の順序と内容は私が時々行く教会で行われているもので、教会によっては順序や内容も異なっているかもしれません。
礼拝はもともと日曜日の朝に信者が集まって聖書を読み、祈り、歌い、話を聞き、そして聖餐と呼ばれるパンとぶどう酒を分け合う儀式に始まりましたが、それは次第にミサ(注1)と呼ばれる礼拝式に発展しました。しかし発展に伴いローマ教皇は絶対権力を持つようになって教会は堕落し、そこから宗教改革が生まれました。
では宗教改革以降ドイツの教会で礼拝はどのように行われていたのでしょうか。まず当事者であるルターはどう言っているでしょう。彼は1525年10月29日に自身の主張に基づいて初めてドイツ語による礼拝をヴィッテンベルクで行い、それを更にまとめる形で翌年の1月「ドイツ・ミサの礼拝と順序」を出版しました(青山四郎訳 聖文社 ルター著作集第1集 第6巻に収録)。それを読みますと、その中の「信徒のための日曜日」に次のような順序が書かれています。
①讃美歌(詩篇34の第2節から23節までを第一旋法で歌う)(下記はその楽譜)以上がルターの書いた主日礼拝の順序です。これをみてわかるように、彼はラテン語の礼拝をすべて排除しようとは思っていません。また文中に出てくる第1旋法とか第5、第8旋法とかは中世グレゴリオ聖歌のいわゆる教会旋法です。この教会旋法は19世紀後半ドビュッシーなど印象派の音楽や20世紀後半にはモダン・ジャズの世界で再び脚光を浴び、意外なところで今も聴かれる旋法です。ここには紹介しきれませんでしたが、各項目には細かい解説や具体的な聖句が書かれており、さらに使徒書の朗読にはコンマ、コロン、ピリオドそして質問について各々メロディーの規則と楽譜までも示しています。ただルターは同時に自分が書いたこれら礼拝式の順序に従う必要はなく、弊害が生じればそれを改め、形式ではなくすべては信仰のためにあるのだ、とも述べています。ここで面白いのは彼がオルガンについて全く言及していないことです。前奏もなければ後奏もありません。シュヴァイツァーによればルターはオルガンが好きではなかったのでは、ということですが(彼自身はリュートを弾く)、「バッハ叢書第7巻 バッハとライプツィヒの教会生活」(ギュンター・シュティラー著 杉山好・清水正訳 白水社)によれば「典礼上不可欠のものとしてルターは評価していた」と書いてありこれは判然としません。オルガンは教会には不可欠であり、バロック期の教会音楽には欠かせない楽器ですが、まだこの当時は機能的に不完全(調性や平均律の問題など)だった為礼拝の中で言及するほど重要ではなかったのでしょう。この楽器が教会音楽(とりわけコラール)に欠かせない存在となるのは17世紀半ばのことです。②キリエ・エレイソン(同じ音調で3回、キリエ・エレイソン、クリステ・エレイソンキリエ・エレイソン)(主よ、憐み給え。キリストよ、憐み給え。)
③集祷(「コレクタ」と呼ばれる短い祈りの言葉で「特祷」と書かれることも。旋律ではなく「ヘ音」で唱える)
④使徒書の朗読(第8旋法で=集祷と同じ高さのまま)
⑤讃美歌(ドイツ語。"今われらは聖霊を祈るNu bitten wir den heyligen geyst"かそれに類するもの)
⑥福音書朗読(第5旋法で)
⑦ニカイア信条(いわゆる「クレド」ですが、ルターがドイツ語の讃美歌にしたもの―「私たちはみな唯一の神を信じます Wyr gleuben all an eynen gott」-を歌う。「信徒による信仰告白」として重要な部分。)
⑧説教(年間の「説教集」の中からその日に適したものを選んで読む)
⑨「主の祈」の解説と洗礼や聖餐を求める会衆への訓戒
⑩聖餐式と聖別(「最後の晩餐」に由来する儀式。カトリックの「聖体拝領」に相当。パンとブドウ酒をキリストの肉と血として分け与える。その間ドイツ語の「サンクトゥス」もしくは讃美歌"神はたたえらるGott sey gelobet"などを歌う。その後、前の讃美歌の残りもしくは「アニュス・デイ」のドイツ語訳を歌う)
⑪集祷と祝福
ライプツィヒの状況はどうだったでしょうか。トーマス・カントルであったシャイン(Johann Hermann Schein 1586-1630)は1627年に出版した「カンティオレーナ」というコラール曲集でオルガンを伴奏に用いたことが知られています。これは会衆によるコラールの歌唱を歌いやすくするためでした。ルター派正統主義の牙城でもあったライプツィヒにはトーマスとニコライという二つの大きな教会があり、これらの教会に礼拝用の音楽を提供する義務を負っていたのがトーマスカントルでした。そしてこれらの教会では午前7時の教会の鐘の音とともに日曜日の礼拝が始まり、聖歌隊(カントライ)によってその開始時にはモテット(ラテン語)がアカペラで歌われ、そして福音書朗読のあとにはその聖書の内容に沿った歌詞に基づくカンタータが歌われました。そして聖餐式の最中にも合唱曲が歌われますが、これは同じカンタータの第2部か、それがなければ別の作品が歌われたのです。バッハ叢書第7巻によると、18世紀初頭に行われていた礼拝の順序は以下のとおりです。
①前奏(オルガンによる)以上はあくまで通常の日曜日の礼拝式の内容で、それもかなり簡単にまとめた内容です。実際は祝祭日や教会暦にもとづく特別の日などによって内容は異なってきます。大きな違いは聖餐式で単声のラテン語による序誦とそれに続く多声によるサンクトゥス(ラテン語もしくはドイツ語)とアニュス・デイ(ドイツ語)が歌われたりします。また上記で「キリエ」「グローリア」の第1・第2聖歌隊は、当時ライプツィヒでは1週間ごとに聖トーマス、聖ニコライの受け持ちが入れ替わったためで、その二者間には技術的な差があり第2聖歌隊の場合ラテン語では歌えなかったためです。全体の礼拝にかかる所要時間は3~4時間だったといわれています。
②入祭唱(聖歌隊による)
③オルガン演奏
④キリエ(第1聖歌隊の場合はラテン語で聖歌隊だけで、第2聖歌隊の場合はドイツ語 "Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit"で会衆と共に歌う)
④グローリア(祭壇の前に出た司祭者の先導で歌われる。キリエに準じてラテン語とドイツ語。但し18世紀前半にドイツ語のみで歌われる方向に傾斜)
⑤挨拶と集祷(ラテン語)
⑥使徒書朗読
⑦讃美歌
⑧福音書朗読
⑨ニカイア信条(Credo-特別の日を除きラテン語の冒頭句のみ)とカンタータ演奏。それに続いて使徒信条"Wir glauben all en einen Gott"を歌う。終わりに説教者が歩み出て語りかけ、それに会衆が応えてその日によって定められた讃美歌を歌う。
⑩主の祈り(ここまでで約1時間)
⑪説教(1時間)
⑫祈祷
⑬讃美歌もしくはカンタータ第二部
⑭聖餐式(聖餐拝領)(式の間定められた音楽やドイツ語の讃美歌を歌う)
⑮集祷と祝祷
⑯讃美歌「神われらに恵みと憐みを施し "Gott sei uns gnädig und barherzig"」
ルターの礼拝と比べて大きな違いは「グローリア」の存在です。ルターはグローリアを礼拝式には入れませんでしたが(注2)、彼の友人で協力者でもあったヨハネス・ブーゲンハーゲン(Johannes Bugenhagen 1485-1558)は「グローリア」を含めた教会規則を定め、これをルターが認めたため、以後ルター派の教会ではこのグローリアも礼拝の中でラテン語で歌うようになったのです。バッハがラテン語の歌詞でミサ・ブレヴィス(「キリエ」と「グローリア」からなる)を作曲しているのもこうした事情から来ています。
ドイツ語による教会コンチェルトを礼拝の中で歌うことはドレスデンなどではシュッツの時代(1620年代)から行われていましたが、保守色の強いライプツィヒでは認められていませんでした。1683年のクリスマス、この習慣に果敢に戦いを挑んだのはバッハの2代前のトーマスカントル、 ヨハン・シェレ(Johann Schelle 1648-1701)でした。彼は市長に反旗を翻し、ラテン語ではなくドイツ語のカンタータを歌うべしと、市の参事会に訴え、これが認められたのです。これにより礼拝の中でドイツ語のカンタータが初めて歌われることとなったのです。シェレは同時にコラール・カンタータも導入しました。その日の説教のテーマに関連するコラールに基づくカンタータを作曲したのです。私は以前「シェレのカンタータは古臭く、あまり好きになれない」という趣旨のことを書きましたが、改めて彼の作品を聴くと、「深き淵より、われ汝に呼ばわる、主よ」など、バッハの初期のカンタータを髣髴とさせるような素晴しい作品である、と思うようになりました(注3)。
さてこうした状況の中1723年5月22日、バッハはライプツィヒに着任します。彼の仕事はトーマスカントル兼ライプツィヒの音楽監督であり、カントルとしてトーマス学校の生徒達の教育のみならず、聖トーマス、聖ニコライ他市内の主な4教会に音楽を提供することが義務付けられました。特に前記2教会ではカンタータの演奏が義務付けられ、このため教会暦に則って日曜・祝日のために年間60曲あまりのカンタータを用意しなければならなかったのです。それはカンタータが、福音書朗読のあとに続く信仰告白を会衆者すべてが表現するための手段として、また説教に先立つ「神の言葉」として演奏されたので、何よりもその福音書の内容(予め教会暦よって定められている)に沿った歌詞でなければならなかったからです。ですからカンタータはある特定の日のために作曲され、いつ演奏してもよい、というものではなかったのです。したがって日曜・祝日のために年間60曲ほどのカンタータが必要だったわけです。カンタータの歌詞は1700年頃から事前に会衆に配られるようになりました。
では礼拝の中でバッハのカンタータはどのように演奏されたのでしょうか?これを知る手がかりはバッハ自身によって書きとめられています。1723年11月28日(11月30日にもっとも近い日曜日から始まる待降節の第1主日)、バッハはヴァイマル時代の自作のカンタータ「いざ来ませ、異邦人の救い主」BWV61を再演する際その自筆スコアの表紙の裏に礼拝式の要点を記したメモを残しています。こうしたメモがあるということは恐らくその前に何か失敗したことがあったのか、あるいはライプツィヒ着任後最初の待降節で、間違えないように書き留めておいたのでしょうね。それには以下のとおり記されています。
①前奏 ②モテット ③キリエへの前奏。キリエは全曲演奏 ④祭壇の前の発唱(イントナツィオ) ⑤使徒書簡の朗読 ⑥連祷(リタナイ)の詠誦 ⑦コラールへの前奏 ⑧福音書の朗読 ⑨主要音楽[カンタータ]への前奏 ⑩信経の歌 ⑪説教 ⑫説後、慣例どおり讃美歌の数節をうたう ⑬聖餐設定の言葉(ヴェルバ・インステイトウテイオニス) ⑭音楽[カンタータ]への前奏。この音楽のあと、前奏とコラール合唱とが交互に繰り返されながら、聖体拝領の終了まで続く。等々。わかりにくいところがあったり、一部メモの必要がない式順のところは省かれたりしていますので少し補足して整理しておきますと以下のようになります。
(白水社 バッハ叢書第10巻「バッハ資料集」 酒田健一訳)
①オルガンによる前奏そしてこの日(待降節第一主日)読まれた使徒書簡は「ローマの信徒への手紙第13章11節から14節で「救いは近づいている」というものと、福音書朗読は「マタイによる福音書」第21章1節から9節「イエスのエルサレム入場」でした。こうしたその日に読まれる聖句のことを「ペリコーペ」と言うことについては以前にも書いたとおりです。バッハは第1曲のルターのコラール「いざ来ませ、異邦人の救い主」をフランス風序曲の付点リズムで始め、荘厳な雰囲気とともに救世主の到来を告げています。また終曲のコラールでもフィリップ・ニコライ(Philipp Nicolai 1556-1608)の有名な「輝く暁の明星のいと美わしきかな」の第3節を使用し、「おいでください、わたしは心からあなたをお待ちしています」と歌いペリコーペの内容を音楽で表現しています。
②聖歌隊によるモテットの演奏
③キリエ(主よ、憐みたまえ)(オルガンの前奏に続いて聖歌隊によって歌われます。メモからはわかりませんが、第2聖歌隊の場合は慣習に従ってドイツ語で会衆とともに歌われたと推察します)
④グローリア(牧師がラテン語の最初の句Gloria in excelsisを先唱し、聖歌隊と会衆がそのあとを歌う。尚ドイツ語のグローリアは「いと高きところには、神にのみ栄光あれAllein Gott in der Höh sei Her」。)
⑤使徒書簡の朗読(牧師による)
⑥連祷(会衆によって歌われる)
⑦(オルガニストによる)コラール前奏曲とそれに続く会衆による讃美歌(その日に歌うべきコラール。オルガンの伴奏付)
⑧福音書の朗読(牧師による)
⑨カンタータの演奏
⑩使徒信条(聖歌隊と会衆による「私たちはみな唯一の神を信じます Wir glauben all an einen gott」)
⑪説教(牧師)
⑫讃美歌(会衆)
⑬聖餐開始の言葉(牧師)
⑭聖餐式と音楽(カンタータの第二部もしくは別の曲。このあと何曲かのコラールをオルガニスト、聖歌隊、会衆が交互に演奏する)
⑮感謝の祈りと祝祷(牧師)
⑯オルガンによる後奏
以上がルター派のプロテスタント教会における日曜礼拝と音楽の関係ですが、本文中でも触れたように日曜以外の礼拝や祝祭日、受難節他そのときどきによって礼拝の内容は変わります。ここではあくまで一般的なものとして記載しました。またライプツィヒ以外のバッハ縁の地の礼拝については、「バッハ=カンタータの世界Ⅰ~クリストフ・ヴォルフ、トン・コープマン編 東京書籍」をご参照ください。次回からはバッハのカンタータにおける演奏上の問題について考えてみたいと思います。
(注1) ミサMissaはラテン語で、もともとの意味は「解散」という意味。初期の教会では礼拝が終わると司祭が "Ite, missa est(行きなさい、解散!)"と唱え、それに会衆が "Deo gratias(神に感謝)"と答えたことから始まった言葉といわれます。
(注2) 1523年に書いた「ミサと聖餐の原則」では省いてもよいとしつつ、保持することが書かれています。
(注3)この曲が含まれているCDは以前にもご紹介しましたが「バッハ以前のトーマスカントル Die Thomaskantoren vor Bach」(deutsche harmonia mundi 88697 281844/28)というCDで、演奏はユングヘーネル指揮カントゥス・ケルン。セットものの1枚になります。クニュプファー(2曲)、シェレ(4曲)そしてクーナウ(2曲)の作品が収録されています。
2010.08.08 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ-死への憧憬③
3. ここまでの音楽(CD紹介)ここまでのところのCDをご紹介しておきましょう。
①サン・ロッコの饗宴―ヴェネツィア1608年 ローランド・ウィルソン指揮 ラ・カペラ・ドゥカーレ ムジカ・フィアタ・ケルン
 (Sony Classical SOCR-1586/7)
(Sony Classical SOCR-1586/7)このCDは1608年ヴェネツィアで聖ロッコの祝典がとり行われた際、当時の旅行者の日記からこんな曲が演奏されたであろうと推定される作品を集めてそれを再現した「空想の音楽会」で、ここにはガブリエリの器楽作品やモテットを始めとするヴェネツイア楽派の壮麗な音楽が集められています。演奏も素晴しく、その華々しい音楽からは往時の栄華がしのばれます。G.ガブリエリの音楽はこれ以外にも「サクラ・シンフォニア第2巻/A.パロット指揮タヴァナー・コンソート オワゾリール POCL-3299」他かなり多くのCDが発売されています。
②シュッツ: ダヴィデ詩篇曲集 SWV22~47 コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン コンチェルト・パラティーノ
 (仏Harmonia mundi HMC 901652/3)
(仏Harmonia mundi HMC 901652/3)シュッツはドイツ音楽の父とされるだけあって、かなりの作品をCDで聴くことができます。この「ダヴィデ詩篇集」も様々な団体が演奏していまが、全曲盤となると私の知る限り2種類しかなく、私はこちらしか聴いたことがないのですが、素晴しい演奏です。ヴェネツイア楽派を髣髴とさせる豪華さと明るさに満ちた音楽ですが、やはりそこにはドイツ的な重厚さも見られます。
③ミヒャエル・プレトリウス:使者たるポリヒムニア ローランド・ウィルソン指揮 ラ・カペラ・ドゥカーレ ムジカ・フィアタ
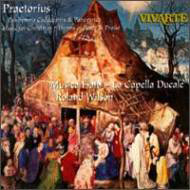 (Sony Classical SOCR-2344/5)
(Sony Classical SOCR-2344/5)1613年から17年にかけて作曲された40曲からなる曲集で、このCDにはそのうちの18曲が収録されています。出版(1619)の際「平和と歓喜の祝祭コンチェルト」という副題がつけられたように、ドイツ30年戦争の勃発に対する平和の祈りともいうべき曲集です。このCDでは1枚目にクリスマスの音楽を、そして2枚目には平和と歓喜の讃歌を集めています。クリスマスの作品には有名な「目覚めよ、とわれらに呼ばわる物見らの声」や「高きみ空より」「輝く暁の明星のいと美わしきかな」といったコラールに基づくコンチェルトが含まれています。中でも古くからドイツに伝わるクリスマスの歌で、讃美歌としても有名な「甘き喜びのうちにIn dulci jubilo」は単純な旋律の繰り返しですが、そこに聴かれる音楽の巨大さには圧倒されます。音の大きさだけならマーラーには及びませんが、空間そのものを巨大な音の拡がりに変えているこの音楽の大きさはとてつもなく巨大です。尚「ポリヒムニア」とはギリシャ神話の女神「ポリュヒュムニア」のラテン語です。
④バッハ以前のドイツ・カンタータ集 フィリップ・ヘレヴェッヘ指揮 コレギウム・ヴォカーレ
 (仏harmonia mundi→King International KKCC-452)
(仏harmonia mundi→King International KKCC-452)このCDは以前にもご紹介しましたが改めて掲載します。ここにはトゥンダーの「われらが神は堅き砦」他、クーナウ、ブルーンス、グラウプナーの作品が収録されていまが、それらはすべて素晴しい作品ばかりです。このうちクーナウとグラウプナーの曲はレチタティーヴォ、アリアそして合唱から構成されており、明らかに教会カンタータの形態をとっています。クーナウについて本文で触れることができませんでしたが、彼はバッハの前任のトーマスカントルだっただけに、その作品はもうかなりバッハに近いといってもいいでしょう。ここに収められた詩篇第51番「神よ、御慈しみをもって」はバッハの初期のカンタータを彷彿とさせる佳作です。1705年の四旬節直後(復活祭の46日前からの最初の日曜日)にトーマス教会で初演されています。尚ドイツ語によるカンタータを礼拝に取り入れたのはクーナウの前任者シェレでした。ブルーンスのコンチェルト「身を横たえて眠りいかん」は音楽的に少し古さを感じますが、曲の中央にデュエットを置き、両端にシンフォニアと合唱を、そしてその間にアリアと器楽のリトルネッロを挟む完全なシンメトリー構造を作っています。グラウプナーの「主よ、湖の波が高まり」(1734)はもうバッハと同時期に書かれたカンタータで、終曲のコラールなどしっとりとした美しさをもっていますが、5曲目のソプラノのアリアなどはオペラチックな華やかさをもっています。ただ彼は何しろ1,400曲以上カンタータを作った多作家なので、これが本当に彼の代表的な曲なのかどうか?
⑤パッヘルベル:モテット集 コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン
 (deutsche harmonia mundi BVCD-35008)
(deutsche harmonia mundi BVCD-35008)パッヘルベルといえばすぐに「カノン」を思い浮かべますが、彼はオルガン音楽の巨匠であり、また教会音楽も数多く残しています。パッヘルベルはニュルンベルクに生まれ、同地で没していますが、このCDに収録されているのはコンチェルトではなくすべてモテットで、2重合唱のために書かれています。それらはすべて彼のエルフルト時代(1678-90)の作品になります。エルフルトといえばテューリンゲン地方(中部ドイツ)の中心地であり、バッハ一族縁の地として知られています。彼自身バッハ一族と親交が深かったのですが、彼はエルフルトに着任する前年アイゼナハの宮廷オルガニストとなり、ここでヨハン・クリストフ・バッハ(Johann Christoph Bach 1642-1703、聖ゲオルク教会オルガニスト)やそのいとこになるヨハン・アンブロジウス・バッハ(JohannAmbrosius Bach 1645-1695)と親交を深めるようになります。彼のバッハ一族との関係はここから始まっているのです。そしてこのアンブロジウスがヨハン・セバスティアンの父であることは言うまでもありません。彼のオルガン音楽がバッハに与えた影響はとても大きく、そのコラール前奏曲を聴いていると、中にはまるでバッハの曲を聴いているのではないかと思うことがあります。それに比べ彼のモテットは少し古臭さを感じますが、それでもバッハが登場する以前のこの地方を代表する音楽だったといわれます。このCDにはパッヘルベルの現存する二重合唱のためのモテット全曲(10曲+マニフィカト1曲)が収録されていますが、そのほとんどが詩篇に基づいています。その中の1曲「わたしたちの避けどころ」(詩篇46番)について少し触れておきます。音楽自体は前述のとおり少し古臭いのですが、軽快な二重合唱で始まり、第五節でいったんテンポを落としてますが、すぐにもとのテンポにもどります。楽譜が手元にないので正確なところはわからないのですが、ここから音楽は4声の合唱になります。今までの軽快な合唱はソプラノを除く3声の合唱に引き継がれ、そこにその合唱に絡むように長い音価の単旋律コラールが現れソプラノによって歌われます。このコラールの旋律はルターの有名な「われらが神は堅き砦」ですが、歌詞はまったく違っています。一行目だけ同詩篇の第9節を引用しているものの、あとは出典も書かれていないので正確にはわかりませんが、恐らくパッヘルベル自身の歌詞によるものと思われます。こうした合唱に単旋律コラールの絡む音楽を聴いていると、あのバッハのマタイ受難曲冒頭の二重合唱を思い浮かべます。パッヘルベルにはモテットのほかオーケストラ伴奏による教会コンチェルトもあり、中には編成の大きなものもあるのでこちらも聴いてみたいと思っていますが、まだ未聴のためちょっとわかりません。でもカンタータという意味ではこちらの曲のほうが重要かもしれません。その他このCDにはヨハン・クリストフ・バッハのモテットが3曲、そしてヨハン・ミヒャエル(Johann Michael Bach 1648-94、ヨハン・クリストフの弟)のモテットが2曲収められています。バッハ直前のテューリンゲン地方の教会音楽を知るうえで貴重なCDといえるでしょう。
⑥ベーム:カンタータ集 ラルフ・ポプケン指揮 カペッラ・サンクティ・ゲオルギ ムジカ・アルタ・リパ
 (Deutsche harmonia mundi 88697405442)
(Deutsche harmonia mundi 88697405442)ベームはブクステフーデと並ぶ北ドイツ・オルガン楽派の巨匠で、そのオルガン音楽はバッハに大きな影響を与えました。彼もまた中部ドイツ、テューリンゲン地方のオールドルフ近郊に生まれ、バッハ一族とは浅からぬ縁を持っています。彼はコラール変奏曲を発展させて「パルティータ」という形式に高め、重厚な北ドイツの音楽にフランス趣味を取り入れたのです。一方彼の教会コンチェルト(カンタータ)は大半が失われ、現在ニュー・グローヴをみても10曲しか載っていません。このCDはそのうちの5曲を集めています。これらは以前ローゼンミュラーの項でもご紹介したボーケマイアー・コレクションに含まれているものです。バッハは15歳になる直前、 オールドルフの長兄の元を離れリューネブルク の教会の付属学校に入り聖歌隊の一員になりました。この地で彼はもっとも多感な時期 の3年間を過ごすことになり、ここで多くのことを学びます。当時同市のヨハネス教会 でオルガニストをしていたのがこのベームです。ベームとバッハが直接関係あったかど うか長いこと議論されてきましたが、最近の発見でベームがバッハに音楽の手ほどきを していたことがはっきりしています。彼は若いバッハにオルガンや合唱音楽を教えてい たのです。ですからバッハがリューネブルクに行ったのも偶然ではなく、実は一族との つながりからむしろベームの元へ派遣された、という考え方も成り立つのです。ここに 収められた詩篇第2番「なにゆえ、国々は騒ぎたち」はレチタティーヴォ、アリア、合唱 からなる教会カンタータであり、また「いざ来ませ、異邦人の救い主」はルターのコラー ルに基づくコラール・カンタータ(変奏曲と言ってもいい)になっています。ベームの音 楽はオルガン音楽を除き今まであまり録音されなかっただけに、これは貴重なCDとい えるでしょう。ただこれらのカンタータは楽器編成も規模が大きいのですが、様式的に 古く、どの程度バッハに影響を与えたのかはわかりません。しかしながら、バッハがご く初期のカンタータでコラール変奏の形式を用いている(BWV4)ことを考えると、それ はベームの直接的な影響なのかもしれません。尚ここに収録されているラテン語の歌詞 による「サンクトゥス」とヨハネ黙示録に基づく「サタンとその血」はニュー・グローヴで はF.N.ブルーンス(1637-1718)の作ではないかとされていますが、もう少し詳しく検証 してみる必要がありそうです。いつかこの点も明確にしたいと思います。
⑦ブクステフーデ:カンタータ集 コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン
 (harmonia mundi France 901629)
(harmonia mundi France 901629)ブクステフーデのカンタータを集めたCDはかなり出ています。私は以前コープマン指揮による3枚組のCD(WPCC-4237~39)を聴いていましたが、最近ではこちらをよく聴いています。その理由は、ブクステフーデのコンチェルトは数が多くそれら全部を聴いても楽しめないので、むしろその中のえりすぐりの曲だけを聴いたほうが楽しめるからです。その点このユングヘーネル盤は収録曲は6曲と少ないですが、コンチェルトあり、アリアあり、コラール編曲ありとバラエティに富んでいて演奏も優れています。特にBuxWV79の「さあ、万物の神をほめたたえよ」は大規模な管弦楽による輝かしい作品で、ブクステフーデの数ある作品の中でも特に楽しめます。またBuxWV41の「心からわたしはあなたを愛する、おお主よ」はマルティン・シャリング(Martin Schalling ?-1608)のコラールを編曲したもので、変奏曲のようなスタイルをとっています。このコラールは後年バッハがその第3節をヨハネ受難曲終曲のコラールに使用していることでも知られています。尚コープマンは以前録音した盤(3枚組、1987年録音)が気に入らなかったのか、2000年以降過去録音した作品も含めて再録音を開始し、今度はどうやら全集をめざしているのかすでにかなり発売されています(輸入盤)。
⑧ブクステフーデ:わたしたちのイエスの四肢 鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン
 (BIS CD-871)
(BIS CD-871)感動的な名曲です。本文中ブクステフーデの教会コンチェルトについてあまり評価しないようなことをいいましたが、これだけは別格です。7曲からなる連作カンタータですが、これはカンタータというより受難曲といった方がいいかもしれません。十字架にかけられたイエスの体を愛しむかのように、切々と歌い上げる感動的な音楽です。特に3作目の「手について」に聴かれる合唱(「汝の手にあるこの傷は」)は悲しみに満ちていますが、その歌はどこか甘美的ですらあります。ブクステフーデはルター派の正統主義とは異なり敬虔派 に属するプロテスタントといわれ、そうした敬虔主義の精神がこれだけの美しい音楽を 生んだのかもしれません。歌詞は、中世の時代からキリスト教文化に大きな影響を与え たといわれる「ウルガタ聖書」とクレルヴォーのベルナール作の中世の詩「リュトミカ・ オラツィオ」(すべてのアリア)から採られていて、ラテン語で歌われます。名曲だけに 多くの団体によるCDがありますが、私は日本が生んだ最高の古楽団体であるバッハ・ コレギウム・ジャパンの演奏をとりたいと思います。透明感のある美しい声と完璧なハ ーモニーが更に感動的な高みへと聴き手を導いてくれます。
2010.07.11 (日) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ-死への憧憬②
2. バッハへの道ヴェネツィアに留学し、G.ガブリエリのもとでイタリアのモテットを学んできたシュッツは、その壮麗な複合唱の手法をドイツ・プロテスタントの教会音楽に持ち込みます。彼がドイツで最初に出版した作品集「ダビデ詩篇集」
 (1619)は、まさしくヴェネツィア楽派の音楽そのものといってもいいほど、規模が大きく壮麗な音楽です。そして更にシュッツは2度目のヴェネツィア留学(1628)でモンテヴェルディに教えを受け、ここでオペラにみられる劇的な歌唱法を習得します。これにより先に触れたヴィアダーナの通奏低音を用いた教会コンチェルトの様式による「小教会コンチェルト kleine geistliche Conzerte」(1636)を出版し、ソロもしくは重唱の歌(ごく一部合唱も使われる)によるコンチェルトを50曲以上残しています。シュッツはさらにシンフォニア・サクレ第二集(1647)、第三集(1650)と重要な曲集を出版し、ここに宗教音楽の舞台は完全にイタリアからドイツへと移ったのです。晩年(1664)シュッツはクリスマス・オラトリオ(「イエス・キリストの喜ばしき降誕の物語」SWV435)を作曲していますが、この曲はレチタティーヴォ、アリア、そして合唱で構成されており、初期の教会カンタータの形式といってもいいと思います(もちろん礼拝で使用される音楽ではなくあくまでもオラトリオですが)。シュッツは500曲ほどの作品を残しましたが、その大半は宗教曲でした〔写真: 晩年のシュッツ〕。
(1619)は、まさしくヴェネツィア楽派の音楽そのものといってもいいほど、規模が大きく壮麗な音楽です。そして更にシュッツは2度目のヴェネツィア留学(1628)でモンテヴェルディに教えを受け、ここでオペラにみられる劇的な歌唱法を習得します。これにより先に触れたヴィアダーナの通奏低音を用いた教会コンチェルトの様式による「小教会コンチェルト kleine geistliche Conzerte」(1636)を出版し、ソロもしくは重唱の歌(ごく一部合唱も使われる)によるコンチェルトを50曲以上残しています。シュッツはさらにシンフォニア・サクレ第二集(1647)、第三集(1650)と重要な曲集を出版し、ここに宗教音楽の舞台は完全にイタリアからドイツへと移ったのです。晩年(1664)シュッツはクリスマス・オラトリオ(「イエス・キリストの喜ばしき降誕の物語」SWV435)を作曲していますが、この曲はレチタティーヴォ、アリア、そして合唱で構成されており、初期の教会カンタータの形式といってもいいと思います(もちろん礼拝で使用される音楽ではなくあくまでもオラトリオですが)。シュッツは500曲ほどの作品を残しましたが、その大半は宗教曲でした〔写真: 晩年のシュッツ〕。 この時期シュッツ以外に注目すべき作曲家としてミヒャエル・.プレトリウス(Michael Praetorius 1571-1621)をあげておきたいと思います。シュッツがプロテスタントであるにもかかわらずコラールをあまり使用しなかったのに対し、彼はコラールを多用してガブリエリやシュッツ以上に大胆で壮大な複合唱によるコンチェルト集「使者たるポリヒムニア」 (1619)を発表しています。彼はヴェネツイアで学んだことはありませんが、自身が仕えるヴォルフェンビュッテル宮廷からドレスデンの宮廷に出向き、そこで学んだといわれています。M.プレトリウスは最古の音楽辞典「音楽大全Syntagma musicum」を著し、その中で当時の楽器について詳述しているだけに、ここでも多彩な楽器が使用されています。ドイツとイタリアの音楽が見事に融合した素晴しい曲集です〔写真: M.プレトリウス〕。
この時期シュッツ以外に注目すべき作曲家としてミヒャエル・.プレトリウス(Michael Praetorius 1571-1621)をあげておきたいと思います。シュッツがプロテスタントであるにもかかわらずコラールをあまり使用しなかったのに対し、彼はコラールを多用してガブリエリやシュッツ以上に大胆で壮大な複合唱によるコンチェルト集「使者たるポリヒムニア」 (1619)を発表しています。彼はヴェネツイアで学んだことはありませんが、自身が仕えるヴォルフェンビュッテル宮廷からドレスデンの宮廷に出向き、そこで学んだといわれています。M.プレトリウスは最古の音楽辞典「音楽大全Syntagma musicum」を著し、その中で当時の楽器について詳述しているだけに、ここでも多彩な楽器が使用されています。ドイツとイタリアの音楽が見事に融合した素晴しい曲集です〔写真: M.プレトリウス〕。シュッツ達によるこれら教会コンチェルトは更に多くの作曲家によって受け継がれ、発展していきます。ハンブルクやリューベックなどの北ドイツではゼレ(Thomas Selle 1599-1663)、ヴェックマン(Matthias Weckmann 1619頃-1707)、トゥンダー(Franz Tunder 1614-67)、ブクステフーデ(Dietrich Buxtehude 1637-1707)、ブルーンス(Nicolaus Bruhns 1665-97)、そしてベーム(Georg Böhm 1661-1733)達に、またニュルンベルクを中心とする南ドイツではケルル(Johann Kaspar Kerr 1627-93)、パッヘルベル(Johann Pachelbel 1653-1706)、フックス(Johann Joseph Fux 1660-1741) そしてグラウプナー(Christoph Graupner 1683-1760)達に、更にドイツ・プロテスタント最大の中心地である中部ドイツではドレスデンのベルンハルト(Christoph Bernhard 1627-92)やハレのフィリップ・クリーガー(Johann Philipp Krieger 1649-1725)とツァホウ(Friedrich Wilhelm Zachow1663-1712)、そしてシェレ(Johann Schelle 1648-1701)やクーナウ(Johann Kuhnau 1660-1722)をはじめとするライプツィヒ・トーマス教会のカントル達に受け継がれていき、そしてこれら全てが大きな大河のうねりとなってバロック最大の巨匠バッハへと注がれていくのです。シュヴァイツアーはバッハ伝のなかで「十二世紀から十八世紀に至る間に教会歌が作り出した壮麗なものはことごとく、バッハのカンタータと受難曲の飾りとなっている。・・・・(中略)・・・・かくのごとくバッハは一つの終局である。・・・一切が彼のみを目ざして進んできたのである。」(白水社 浅井真男、内垣啓一、杉山好 共訳)と言っています。
こうしてドイツの教会コンチェルトは大いに興隆を極めていきますが、ではそれらのなかでバッハの作品を想起させるようなものがあったのかという点について少し触れてみたいと思います。もちろんバッハの作品に匹敵するようなものはないのですが、それでもバッハの初期のカンタータに通じるものはあります。私が様々に聴いてきてそう思える作品を書いた作曲家というとトゥンダー、クーナウそしてブクステフーデがあげられると思います。ベームやパッヘルベルの作品にもすばらしいものがありますが、それでもバッハとの隔たりは大きいと言わざるを得ません(バッハに与えた影響という点で、この二人は重要な位置を占めています)。そうした中で一般的にはブクステフーデの作品がバッハ以前のカンタータの中では重要と位置付けられています。ブクステフーデは元々ドイツ人ではなく、デンマーク人なのでディートリヒという名前の表記はおかしく、本来はディデリクDiderikと表すべきですが、活躍の場が北ドイツだった為かディートリヒが定着してしまいました。彼は120曲のカンタータを残しておりそのうちのいくつかはCDでも聴くことができます。各々はだいたい5分から長くて15分くらいの曲で、それらは概ねいくつかの部分(楽章)から構成され、ソロあり、重唱あり、そして時には合唱でも歌われます。ただブクステフーデの場合大半は教会コンチェルトであり、それらをすべて「カンタータ」と呼ぶのは厳密な意味からすると少し違っています。ブクステフーデに限らずバッハ以前のこの種のコンチェルトは、習慣的に「カンタータ」と呼ばれることがほとんどです。「コンチェルト」とすると「協奏曲」という今日の概念とダブってしまうことによるのだと思いますが、「教会(宗教)コンチェルト」としたほうが歴史的な流れの中では理解しやすいと思います。ブクステフーデの場合コンチェルトが大半といいましたが、それでもこれらの作品はいくつかの分類に分けられます。ほとんどの場合「教会コンチェルト」ですが、いくつかはコラール編曲であり、またいくつかは宗教詞に基づくアリアに分類されるものもあります。ただし中には「わたしたちのイエスの四肢BuxWV75」に代表されるようにカンタータと呼んでもいい作品がいくつかあります。この「イエスの四肢」は7曲からなる連作カンタータで各曲は十字架にかけられたイエスの身体の各部分(足、膝、手、脇腹、胸、心そして顔)を歌っています。それぞれの曲とも器楽合奏によるソナタで始まり、あとはアリアと重唱及び合唱で歌われるコンチェルトからなっていて、これは初期のカンタータと呼んでもいいように思います。ただ私はこれらブクステフーデの作品を聴いていて、確かにそれ以前の作曲家のものに比べて完成度も高く、素晴しいと思うのですが、それでもバッハの作品との距離を感じずにはいられません。むしろ曲は少ないのですが、トゥンダーの作品の方がバッハの初期のカンタータに通じるものを感じます。ブクステフーデは北ドイツの都市リューベックの聖マリーエン教会のオルガニストを1668年から務めていますが、それ以前にこの教会のオルガニストだったのがトゥンダーで、ブクステフーデはトゥンダーの死後当時の習慣に従い彼の娘と結婚することによってこの教会オルガニストの地位を得たのでした〔注1〕。ブクステフーデの時代、リューベックの名物として栄えた「夕べの音楽Abendmusik」は当初「アーベントシュピールAbendspiel」と呼ばれ、このトゥンダーによって始められました。彼が着任した1641頃には始まり(記録上は1646年)、そもそもは毎木曜日の午後証券取引を待つ商人達のために行われたコンサートと言われています。初めはオルガン演奏会だけのようでしたが、その後声楽と器楽による「教会コンチェルト(カンタータ)」の演奏会として定着し、最終的には年5回の開催(クリスマス前の11月と12月の日曜日)に変更されました。トゥンダーの作品として残されている声楽曲は17曲と多くありません。そのうち6曲ほどが今私の手元にあるCDで聴くことができますが、それらは実に味わい深い音楽で心に沁みてきます。彼の「われらが神は堅き砦 Ein fest Burg ist unser Gott」はコラール・コンチェルト(カンタータ)で、シュヴァイツアーも「力と精気に溢れた作品」として「ブクステフーデ以上に重要である」としています。彼は会衆にとって馴染み深いコラールの旋律と詞の両方をモテットに採り入れた先駆者であり、その後の教会カンタータの形成に重要な役割を果たしています。こうしたトゥンダーやブクステフーデを始めとする教会音楽が当時リューベックで盛んに演奏され、「夕べの音楽」〔注2〕はドイツ全土に知れわたることとなり、1705年の10月末はるばる400キロ以上を徒歩で旅してこの「夕べの音楽」を聴きに来た青年がいました。この青年こそ若きヨハン・セバスティアン・バッハその人に他なりません。
ここまでの記述で「教会カンタータ」がどういう音楽なのかはだいたいお解かりいただけたと思いますが、少し整理しておきましょう。教会カンタータを簡潔に表すとすれば「イタリアの教会コンチェルト(モテット)と、オペラに始まる通奏低音に支えられた歌(レチタティーヴォとアリア)とが次第に融合され、バッハの時代その頂点に達した教会音楽」ということができると思います。ただどこまでがコンチェルトでどこからがカンタータなのかを厳格に区分するのはちょっと難しいと思います。ルター派のキリスト教が礼拝で音楽を重んじたことは以前にも述べましたが、そこからコラールが生まれ、更に17世紀後半には聖書の言葉や儀式の式文さえ音楽にとりこもうとし、そこからカンタータが生まれたのです。1700年、ハンブルクの神学者で詩人でもあったノイマイスター(Erdmann Neumeister 1671-1756)は新しい形の宗教詩をレチタティーヴォやアリアなどにあてはめて作り、これをイタリアにもともとあった音楽の形式「カンタータ」と呼んだのでした。特にレチタティーヴォは今迄の詞とは根本的に異なる (脚韻も不規則で行の長さも不揃いな自由詩) ため、礼拝に訪れた会衆にはより強い言葉となって心に刻まれ、また作曲家にとっても自由な発想が広がることから、これが作詞・作曲の両面で主流になっていきます。ここに至って今まで多様なスタイル(作曲家がオルガニストであるかカントルであるかによってもその音楽のスタイルは違う)だったコンチェルトやカンタータが一つの方向に集約されていきます。ノイマイスターは教会暦5年分(1年分は約60曲)の詞を作りましたし、それ以外にも多くの彼の追従者達が詞を書いています。ですからそれらをもとに、テレマン(Georg Philipp Telemann 1681-1767)は少なくとも12年分のカンタータとモテット〔注3〕を作曲(全部でおよそ3,000曲といわれる)していますし、グラウプナーも1,400曲以上のカンタータを作曲しています。ただ、この「カンタータ」という言葉はバッハ自身もごく一部の例外を除いて使用しなかったように、当時一般的な用語ではなく、この言葉が使われるようになったのは19世紀に入ってからで、旧バッハ全集の校訂に伴って使われるようになったのです。
最後に1700年ノイマイスターによるテキスト集(第1年分)の序文に書かれた「カンタータ」の簡潔な定義をもう一度ご紹介しておきましょう。
「簡単にいうなら、カンタータとは、レチタティーヴォのスタイルと幾つかのアリアをひとまとめにした、あるオペラの部分のようなものである」(服部幸三著「バロック音楽のたのしみ」より)
かなり駆け足でバッハ以前のカンタータの歴史について述べてきましたが、本来ここまでの話をこんなに端折ってしまうのは、とても乱暴なことのように思います。いつか個々の作曲家と作品についてもっと詳しく触れてみたいと思います。また次回CDの紹介の中でも少し補足したいと思います。
(注1) これについてはバッハにも面白いエピソードが残されています。ブクステフーデは訪ねてきたバッハの才能を高く評価し、自分の娘と結婚させて彼をマリーエン教会オルガニストの後継者にしようとしたのですが、この娘はそれ以前にヘンデルやマッテゾン(Johannes Mattheson 1681-1764,作曲家というより理論家として名を馳せた)にも断られ、年齢も高かった(30歳)ことから当時20歳のバッハは当然これを断ったのでした。おそらく容姿も?
(注2) ブクステフーデの時代の「夕べの音楽」の礼拝はかなり長かったようで、劇に近かった催し、といわれています。アリア、ディアローグ(二重唱ですが、イエスと魂との対話を意味し、通例バスとソプラノで歌われる)、コラール、ポリフォニーによる合唱、オルガンそしてオーケストラの演奏と、これらが全体としてオラトリオのように演奏されたといわれています。
(注3) ややこしいのですが、この時代「教会コンチェルト(カンタータを含む)」と「モテット」を区別して分類することがあります。バッハの作品(6曲)でもそうですが、独立した器楽のパートを持たない教会合唱曲を「モテット」として区別しています。伝統的なポリフォニー合唱音楽で、一般的に無伴奏(アカペラ)かバスの声部に重複する通奏低音のみで歌われます。
2010.06.12 (土) Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬①
「古楽という名の迷宮へ」の再開にあたって病気治療などがあって半年間古楽に関するコラムを中断してしまい、申し訳ありませんでした。今月から再開したいと思いますが、そのテーマについてもう一度考えた結果「バッハのカンタータ」にすることにしました。中断するときにジェズアルドと対になるその続編を書くと、予告したのですが、入院中様々なCDを聴いていてバッハの素晴しさを改めて認識したこと、またこの半年の間に身に降りかかってきたことで不安に駆られたり、落ち込んだりしましたが、そんなときベッドの上で「生きる」こととは何か、「死」とは何か、などと大げさなことを考えているうちこのテーマに行きついてしまったのです。
Ⅵ. 来たれ、甘き死のときよ――死への憧憬
人は誰しも「死」というものを一度は考えたことがあるのではないでしょうか。私も若い頃、「死」に対して強い恐怖心を持っていました。存在そのものがこの世からなくなり、自己の意識は目覚めることのない永遠の眠りにつく、そんなことへの計り知れない恐怖だったのだと思います。こんなことを書くと、では「今はないのか?」と問われそうですが、確かに今はかつてのような恐怖心を抱いてはいません。子供達も育ち、仕事にも一区切りがつき、新たな目標を見つけることにも苦労し、そうして知らないうちに身体のあちこちにガタがきてつらくなる、等々で「生」への執着心がかつてほどなくなってきたからかもしれません。いや「そんなことではいけない!」と自分を奮い立たせ、「新たな目標を立てなければ!」などとベッドの上ではいろいろ考えます。時間がありすぎるからかもしれません。そんなときバッハのある種のカンタータを聴くととても心が癒されました。バッハがどうしてそうなったのかはわかりませんが、彼は若い頃から生涯を通じて「死」への憧れともとれるカンタータをいくつも書いています。それらはみなすばらしい曲ばかりです。バッハの教会カンタータはキリスト教と密接に結びついていますので、「死」をテーマとするのは当然ですが、ただ自ら進んで「死」に対して憧れを抱くというのは尋常ではないように思います。熱心なクリスチャンであったバッハにしてみれば、信仰を深めれば深めるほどそうした心境になっていったのでしょうか。今回はそんなカンタータのなかからいくつか代表的な曲にスポットを当ててみようと思いますが、まずはその前段の話をいくつか。
1. カンタータの起源
まず数あるバッハの作品のかなで何故カンタータなのかという点ですが、バッハのカンタータには彼のすべての音楽の要素がそこに集約されているといっても過言ではないからです。カンタータには彼の受難曲はもちろんですが、管弦楽曲、協奏曲、器楽曲(特にオルガン)など、すべてにわたる音楽のスタイルが凝縮されています。例えばカンタータBWV35「霊と心は驚き惑う」にはオルガン・コンチェルトが出てきますし、BWV110「笑いはわれらの口に満ち」では管弦楽組曲が、さらにBWV174「われ いと高き者を心を尽して愛しまつる」ではブランデンブルク協奏曲(第3番そのもの)などが登場します。でもそれらはほんの一例でそれ以外の曲にも様々なスタイルの音楽がちりばめられていて、カンタータを聴けばバッハのすべてがわかる、といっても大げさではないでしょう。
バッハには現在世俗カンタータを含めておよそ220曲ほどのカンタータが残されていますが、これらを全部聴こうとすればCDでは70枚ほどになり、これはワーグナーのリングでさえも遠く及ばない数になります。私も全部の曲に耳を通すには相当の期間が必要でした。「カンタータとは?」については以前にも簡単に触れましたが、今回歴史的な流れを見ながらもう少し詳しくみてみたいと思います。
16世紀イタリアではモテットが全盛を極めていました。このモテット(ラテン語で「モテトゥス」)という音楽の定義は優しいようでいてちょっと厄介です。大きなくくりとしては「多声による宗教的合唱曲」と言っていいと思いますが、一部世俗の曲もあるようで、また時代によって様式も異なることからその定義はなかなか難しいようです。その語源についてはウィキペディアなどにも書かれているのでそちらをご参照ください。ただ起源について触れておきますと、このモテットの起源は13世紀ノートルダム楽派のぺロタン(「ペロティヌス」とも言う、Perotin 1160頃~1220頃、パリのノートル・ダム大聖堂で活躍)にまで遡り、彼らの多声宗教作品がミサ曲にかわる新しい曲種として生まれたものとされています。15世紀の音楽理論家ティンクトーリス(Johannes Tinctoris 1436頃~1511)によれば彼が書いた最古の音楽辞典「音楽用語定義集」で「ミサ曲は大規模な歌」、そして「モテットは中規模な歌でどんな歌詞でもかまわないが、多くの場合宗教的内容をもつ」と定義されています。
 このモテットはルネサンス後期、パレストリーナ(Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525~94)に至って完成の域に達し、当時のイタリアで栄え同時代のジョヴァンニ・ガブリエリ達のヴェネツイア楽派によって壮麗な複合唱(「コーリ・スペッツァーティ cori
spezzati」といわれる)のモテットがたくさん作られました。教会(サン・マルコ大聖堂)の構造を生かして、ステレオ効果満点の輝かしい音の饗宴が繰り広げられたのです〔写真上:サン・マルコ寺院に残るパレストリーナの肖像画、写真下:17世紀初頭のサン・マルコ寺院の風景〕。歌詞は多くの場合新約聖書の語句や旧約聖書の詩篇(150編からなる宗教詩)からとられています。またヴェネツィア楽派の音楽は、器楽を著しく発展させました。それまで教会音楽の世界では器楽は声楽パートと重複して使用され補完的な役割をするだけで、楽器の指
このモテットはルネサンス後期、パレストリーナ(Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525~94)に至って完成の域に達し、当時のイタリアで栄え同時代のジョヴァンニ・ガブリエリ達のヴェネツイア楽派によって壮麗な複合唱(「コーリ・スペッツァーティ cori
spezzati」といわれる)のモテットがたくさん作られました。教会(サン・マルコ大聖堂)の構造を生かして、ステレオ効果満点の輝かしい音の饗宴が繰り広げられたのです〔写真上:サン・マルコ寺院に残るパレストリーナの肖像画、写真下:17世紀初頭のサン・マルコ寺院の風景〕。歌詞は多くの場合新約聖書の語句や旧約聖書の詩篇(150編からなる宗教詩)からとられています。またヴェネツィア楽派の音楽は、器楽を著しく発展させました。それまで教会音楽の世界では器楽は声楽パートと重複して使用され補完的な役割をするだけで、楽器の指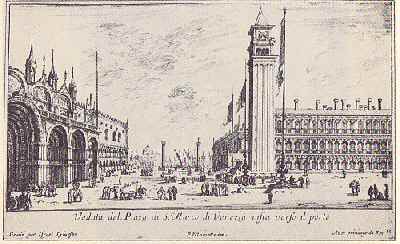 定も行われていませんでした。G.ガブリエリに至って器楽は充実し、声楽から独立して、お互いが応答しあうようになります。ここにコンチェルタートの様式が生まれるのです。更に器楽合奏だけの音楽も作られるようになり、ここから「ソナタ」という言葉(語源は「ソナーレsonare」で「響く」という意味)も生まれました。そしてこのジョヴァンニ・ガブリエリ(Giovanni Gabrieli 1557~1612)達の壮麗な音楽を学ぼうと多くの名だたる作曲家がヴェネツイアを訪れています。よく知られているのはドイツ音楽の父と言われ、バッハのちょうど100年前に生まれたハインリヒ・シュッツ(Heinrich Schütz 1585-1672)ですが、それ以外にもハスラー(Hans Leo Hassler 1564~1612、マタイ受難曲の有名なコラール旋律の作者)やH. プレトリウス(Hieronymus Praetorius 1560-1629)、更にこのコラムの最初にとりあげたローゼンミュラーなどがいます。
定も行われていませんでした。G.ガブリエリに至って器楽は充実し、声楽から独立して、お互いが応答しあうようになります。ここにコンチェルタートの様式が生まれるのです。更に器楽合奏だけの音楽も作られるようになり、ここから「ソナタ」という言葉(語源は「ソナーレsonare」で「響く」という意味)も生まれました。そしてこのジョヴァンニ・ガブリエリ(Giovanni Gabrieli 1557~1612)達の壮麗な音楽を学ぼうと多くの名だたる作曲家がヴェネツイアを訪れています。よく知られているのはドイツ音楽の父と言われ、バッハのちょうど100年前に生まれたハインリヒ・シュッツ(Heinrich Schütz 1585-1672)ですが、それ以外にもハスラー(Hans Leo Hassler 1564~1612、マタイ受難曲の有名なコラール旋律の作者)やH. プレトリウス(Hieronymus Praetorius 1560-1629)、更にこのコラムの最初にとりあげたローゼンミュラーなどがいます。複合唱のモテットは編成が大きいため、ソリストもまた多くの人数が必要とされました。ただこうした音楽はどこでも演奏できるわけではないため、狭い空間における演奏ではソリストや合唱の数を減らし、代わってそれらは通奏低音に支えられた器楽で演奏されるようになり、ここに少規模なコンチェルト様式が生まれます。この分野で功績のあったのがヴィアダーナ(Lodovico Grossi da Viadana 1564-1645)でモテットに初めて通奏低音を用い、1602年「100の教会コンチェルト」を出版しました。この通奏低音の記譜には数字が付されていて、以後通奏低音にはこの記譜法が一般的になっていきます。これらのモテットは声と器楽による対比の芸術となりやがてコンチェルトと呼ばれるようになります。
さて16世紀末イタリアでオペラが誕生しますが、オペラではより歌詞をはっきり聴衆に伝えるために今までのポリフォニー(多声合唱)ではなく、器楽伴奏にのった単声の歌が登場します。これがモノディと呼ばれるもので、これが音楽におけるバロックの始まりで、このスタイルは一気に開花します。なかでもカッチーニ(Giulio Caccini 1550頃~1618)やペーリ(Jacopo Peri 1561~1633)たちフィレンツェのカメラータのメンバーは通奏低音の伴奏による歌曲をたくさん書きました。この世俗の歌曲がカンタータと呼ばれる音楽でした。このカンタータはもちろんイタリア語のcantare(歌う)からきています。やがてこのカンタータはレチタティーヴォ(叙唱)とアリアで構成されるようになり、カリッシミ(Giacomo Carissimi 1604~74、オラトリオ作家の最初の巨匠)の時代になって全盛となり、ダ・カーポ・アリア(A→Bの後再びAに戻って終わる)の形式が登場します。17世紀後半A.スカルラッティ(Alessandro Scarlatti 1660-7125、ドメニコの父)はこのカンタータを500曲以上作曲しています。
次回これらのモテットやカンタータがどのようにしてバッハに受け継がれていったのかをみてみましょう。
2010.05.27 (木) ある組合の解散に思う~「古楽」の再開を前に
病気治療などがあって半年間「古楽という名の迷宮へ」を中断してしまい、申し訳ありませんでした。おかげさまで病気も回復し、日常生活にも支障のないほどになりましたので、そろそろまたこのコラムを始めたいと思います。さて古楽のテーマに入る前に、いささか個人的なことにもなるのですが、最近ちょっとしたできごとがあり、このことについて触れておきたいと思います。古楽の記事は6月から再開します。
今月(5月)末にある労働組合が解散しました。ここにとりあげることもないほどの、本当に小さな組合の解散でした。ただこの組合にかかわった人間として、おそらくこれを解散した人たちも今ではほとんど知らない、ちょっとした歴史をその秘話も含めて話しておきたいと思います。労働組合が形骸化してしまったいま、今後の労働組合というものを考える上で何がしか参考になれば、とも思います。
この組合はその母体となる会社が昨年大手レコード会社に吸収されてなくなってしまったことにより、解散の決議をし、今月になって正式に解散となったようです。
そもそもこの組合の設立は1977年の9月に遡ります。おそらく解散を決めた人たちは、1987年に一度会社の実態が変わったのでそのときにできたと思っているかもしれません。確かにその時点で会社を離れた人たちも多くいたので組合も一度清算したことは事実です。ただそれはあくまで会計的な問題であり、その後の組合といっても全ての人間や労働条件はそこから引き継がれたわけで、実態としては全く変わっていないのです。ですからその起源という点では1977年が正しいと思います。1977年以前はある電機メーカーの一支部として活動していました。
1975年、当時大手レコード会社の一事業部だった部署が外国資本との関係で独立し、そこに新しい合弁会社が生まれました。社員は当面全員出向になりました。そして出向のまま2年が経過し、1977年に全員移籍というときを迎えたのです。
この移籍の前年(76年)、私は多くの社員に推されるかたちで組合の支部長という大役を任されました。そしてここから私の苦難の時が始まったのです。まず私も含め本社の大半の人は組合も独立すべきだ、と考えました。ところが営業所ではどんな組合になるのか、また労働条件が維持できるのかという不安もあり、そのまま親会社の組合の一支部のまま残るべきだという考えが大半でした。そんななか親会社の組合幹部も自分達の支配下に置いておきたいと考え、組合の独立には激しい妨害を行ってきました(私の思想的なことへの不安も持っていた?)。そのため私は渋谷の労政事務所に相談に行ったりもしました。またあるとき彼らは私を熱海の旅館に軟禁し、「独立を撤回するまで帰さない!」とまで言ったのです。夜を徹して話し合う中で、何とか彼らには健全な組合として独立するのだということをわかってもらい、逆に協力してもらう合意をとりつけました。営業所に対しては親会社と同等以上の労働条件を守るために全力をあげることを約束し、こうした曲折があって私たちは独立した組合を発足させることができたのです。それが1977年の9月のことでした。
ただ発足直後から順風満帆というわけにはいきませんでした。最初の一時金交渉では親会社の妥結金額+αを獲得することができたのですが、これはもう時効だから言いますと、非公式な場とはいえ最初の交渉で会社は私たちの要求に満額回答を出してきました。ところが社長が親会社にその結果を報告に行ったところ一蹴され、「この間の回答はなかったことにして欲しい」といってきたのです。私たちも要求はしてみたものの満額が出るとは思っていなかったので、ここは引き下がったのです。したがってその+αはかなり減額されてしまいました。このことは当時執行部の人間しか知りませんでした。それでも親会社以上には勝ち取ることができスタートとしては順調だったと思います。しかしその後思うように会社の業績が伸びず、「親会社以上の労働条件」という約束を守ることが難しくなってきました。そんなことからそれ以後毎年のようにストライキを繰り返すような状態に陥りました。小さな組合で潤沢な資金があったわけでもありませんので、ストライキは当然組合員にも負担がかかってきます。そんなことから私たちがとった戦術は、会社が止められると困る特定の部門を無期限でストップさせるという、今考えるととても過激な方法による部分ストライキでした。一番長く止めたのは3日ぐらいだったと記憶しています。もちろん全面的なストライキも何度かうったことがあります。そうして私たちは労働条件の維持と雇用を守ってきたのです。
業績は相変わらずいいときもあれば悪い時もあり、特に悪い時私たちは苦しい立場に追い込まれました。社長が交代し、新社長との賃金交渉でどうしてもあとほんの少しのところでお互い歩み寄ることができず、結局私自身の首をかけて最後はまとめるということになり、これがあって私は委員長を辞めました。
私の在任期間は5年ほどだったと思いますが、その間他のレコード会社に先駆けて残業カウントを廃止して職種別の手当を導入したり、勤務地の違いによる地域手当を新設したり、更に切り捨てられる有給休暇をプールして病気等による休業期間に組み込む(つまりその期間有給保証が増えることになり、これを認めていない健保組合には内緒で行った)など新しい制度をつくったりもしました。今はやりの事業仕分けではありませんが、無駄な制度を廃止したりして賃金の再配分を行ったのです。これは限られた原資をいかに配分するかという苦肉の策でもあったわけで、こうしたことがではよかったかどうかは議論のあるところでしょう。手当制の導入に対して組合員(特に残業の多い部署)からの反発は並大抵のものではありませんでした。ただこうした新しい試みは世間的には評価され週刊誌に採り上げられたりもしたのです。そしてこれらの制度はつい最近までずっと生き続けたのです。
それ以外にも個人的にはたくさん思い出があります。組合設立後間もなく、同じ業界の組合が集まって組織する協議会に私たちも参加しましたが、その翌年協議会の議長になって欲しいと頼まれたこと。もちろんそんな余裕はないのでこれは固辞しました。またあるとき会社の業績が落ち込み、アメリカ本社の人事担当者が極秘に来日して私に面会を求め、組合員を含む社員の解雇に組合が同意するよう迫ってきたこと(もちろんこんなことは認めませんでした)。更に深夜に及ぶ交渉で家に帰れなくなり、皆(会社の人事担当も含めて)近くの連れ込み旅館に泊まったり(何度もある)、膠着した交渉を打開しようと深夜激しく雪の降るなか人事部長の家まで押しかけて行って話し合ったこと等々、様々に思い出されます。今ではどれもいい思い出です。かつて私は人前で話すことも苦手だったのですが、こうした経験によりそれが苦痛ではなくなりしました。その意味では周囲の人たちに育ててもらった、といえるでしょう。
私が委員長を辞めて後任に引き継ぐ時、とにかく「これからはストライキはしないように!」と言ったことを今でも覚えています。時代の変化もありますが、これはそれ以後守られてきました。ストライキは会社に大きなダメージを与えますが、決断する側の人間も神経を著しくすり減らします。ともあれ、そんな組合でしたがそれもとうとう完全に消滅ました。
最後に苦言を一つ。今の組合執行部の人たちや組合員がどんな考えで解散したのかは私にはわかりません。もちろん今の時代、労働組合そのものの意義が問われていることも確かでしょう。新しい会社に組合がな
かったことで、それを継続させる難しさもあったと思います。ただそれ以上に今の執行部の人たちにどれだけの熱意があったかも疑問です。今の人たちにとっては会社に入った時当たり前のように組合が存在していて、む
しろそんなものはウザッたい、と思う人もあったかもしれません。でも組合というのはそんなに簡単にできるものではありません。私は後年会社の経営側に入って見てきましたが、組合員が思っている以上に経営者は組合
に神経を使ってきました。その証拠に会社は何度か早期退職勧告を社員に行ってきましたが、組合員にそれが及ぶことはありませんでした(自発的に辞める人は除き)。昨年会社が吸収される際もそれは有効に作用しました。ただ会社がいて欲しくない人間には嫌がらせをしてきたことも事実ですが、それを守れるかどうかも組合次
第です。
解散にあたって私のところにもそのパーティの案内状が送られてきました。もちろん出席という返事を出しましたが、2週間ほど前になって「あなたは管理職だった(1987年の時点)ので対象外で、出席できなくなりました」と電話がかかってきました。そんなことは調べてから案内状を出すべきで極めて失礼な話ですが、その失礼さは置くとして、そのときの電話の内容がとても気になりました。「会社からその当時管理職だった人は除外するようにきつく言われているので」と言うのです。これを聴いて私は唖然とさせられました。執行部の人間(?)ともあろうものが「会社から言われて」とはどういうことでしょう?会社が組合のすることに介入し、それを許すことってありうるでしょうか?私の知らない事情もあるのかもしれませんが、どんな事情であれそんなことは論外で、こんな執行部なら組合員に迷惑をかけるだけなので解散した方がマシでしょう。また私も書いてきたように、この組合にはこれまでたくさんの人が設立から運営に至るまでかかわってきました。1987年以前のことなど関係ないので知らないと決め込んでいるのなら仕方がありませんが、もしそうでないという気持ちがあれば、かかわった人たちに解散に至る経緯など説明する案内があってもいいと思うのですが、これは年寄りの僻みでしょうか?組合の存在意義が問われる今、解散する組合はこれからも増えていくかもしれません。でも本当にそれでいいのか今一度考えてみる必要があると私は思います。組合は強い人のためでなく、弱い仲間達のためにあるのだということを。
最後にきついことを書きましたが、これも後輩を思う気持ちとしてご容赦ください。ともあれ終身雇用という制度が崩れた今、組合という防波堤をも捨て、これからは働く人個人々々が自分で自分を守っていかなければなりません。今後も皆さんが頑張っていい仕事ができますよう心からお祈りしてこの話を終わります。
2009.12.20 (日) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――3
4. ジェズアルドの音楽とCDカルロ・ジェズアルドはその生涯からもわかるように、いわゆるプロの音楽家ではありません。ですからその作品のジャンルもかなり偏っています。彼の作品の中心をなすのはマドリガーレ(注)と呼ばれる世俗の歌曲です。それに宗教作品が少し加わります。器楽曲はほんの数えるほどしかありません。また彼自身が貴族であったため、誰かのために作曲する必要もなく、すべてが自らの感情表現のために書かれたという点でも同時代の他の作曲家とはちょっと違っていました。死後に出版された作品まで含めるとかなりの数にのぼりますが、ここでは生前に出版されたものを中心に主なものだけとりあげてみたいと思います。
彼は例の猟奇事件を起こした後、すぐにジェズアルドの城に逃げ帰り、引きこもってしまいましたが、この間にマドリガーレを集中的に作曲したと思われます。この時期のマドリガーレが第1巻(16曲)及び第2巻(14曲)として出版されています。ただいつ出版されたのかは正確にはわかっていません。しかも彼はこれを自分の名前ではなく、ジョゼッペ・ピローニ(Gioseppe Pilonij)という他人の名前で出版していたのです。1594年に彼がフェラーラに着いたとき、その二巻のマドリガーレ集を持参していたことが知られていますので、それ以前に作られたことになります。そして彼はフェラーラで再度これら二巻のマドリガーレを今度は自分の名前で出版したのです。ですから一般的にはこれらの作品集は1594年の出版とされています。
フェラーラ滞在中の1595年及び96年に第3巻(17曲)及び第4巻(15曲)のマドリガーレ集を続けて出版し、ここで彼の名声は一気に高まります。そして何よりも注目すべきはここに前衛音楽といってもいい大胆な半音階や無調の手法が持ち込まれたことです。これが音楽におけるマニエリスムともいうべきもので、これらを聴いていると我々が現代音楽とかアヴァンギャルドなどと呼んでいる無調や半音階の音楽などは、既にこの時代にあったことがわかります。こうした手法がまさにフェラーラを中心に行われていたわけです。
ここで前章の注でも簡単にご紹介ましたが、このマニエリスムについて、もう少し触れておきたいと思います。マニエリスムがマニエラ(様式・手法)を語源とすることは既に述べましたが、絵画の世界でまず起こり、自然の模倣から脱却し、「高度の芸術的手法(マニエラ)」により自然を超越した美を追求する表現様式、とちょっと乱暴ですが定義づけられると思います。音楽の世界では、ルネサンス時代ポリフォニー芸術が高度に発展し、均整のとれた美しい音楽が全盛を極めますが、そこに世俗のマドリガーレが登場し、詩の内容をより感情に即して表現するために半音階や無調などの手法が生み出されたのです。先の注でも紹介したヴィチェンティーノなどは「古代音楽の現代技法への応用L'antica musica ridotta alla moderna prattica」(1555)という理論書を著し、ギリシャの音階理論に基づいてオクターヴを31に分割するアルキチェンバロという楽器を作ったりもしています。これが音楽におけるマニエリスムの手法で、そのもっとも代表的な作曲家がこのカルロ・ジェズアルドなのです。彼の音楽は特にその傾向が著しく、愛や死に対する憧れを大胆な半音階や、無調を用いて表現しています。それはあたかも精神の病に冒された殺人者の心の叫びのように聴こえてきます。このマニエリスムに属する作曲家としてその他、オルランド・ディ・ラッソ(Orlando di Lasso 1532-94、 Orlandus Lassusuオルランドゥス・ラッススと表記されることも)やルカ・マレンツィオ(Luca Marenzio 1553頃-1599)などが名を連ねています。またモンテヴェルディ(Claudio Monteverdi 1567-1643)を加える人もあります。このマニエリスムは後に絵画の世界で同じような傾向の作品ばかりが書かれるようになり「マンネリズム」と蔑称されるようになります。やがてヨーロッパを襲った宗教改革の混乱も収まり、絶対主義権力が確立するにつれ、世の中は安定に向い、時代はルネサンスからバロックへと移っていきます。マニエリスムもそれと共に消えていきます。尚この時代、半音階といっても現代のように不協和音を伴うことはありませんでした。音楽を縦に割ってみると、その一つ一つの和音は協和音でできています。ただそれらが無調的に自由に組み合わされるので聴いていると現代音楽のように聴こえてくるのです。
フェラーラからジェズアルドの館に戻った後、カルロの鬱病は更に悪化し、息子の死をきっかけにますます城にこもるようになります。そうした中で彼の創作の対象は宗教作品へと向けられ、1603年二巻の宗教声楽曲集(五声用と六・七声用)を出版します。そしてやや年月を隔てた1611年にマドリガーレの第五巻(20曲)、第六巻(23曲)そして「聖週間のためのレスポンソリウム集」という彼の最も重要な作品群が次々に出版されます。恐らくこの頃には彼の健康状態は最悪の状態だったと思います。曲の内容も暗く「愛に対する絶望」や「死へのあこがれ」を激しく歌ったもので、そのせいかその前衛的手法は更に強められています。
ここからはCDの紹介をかねてもう少し個々の音楽をみてみたいと思います。
①五声のためのマドリガーレ集第4巻
フランチェスコ・チェーラ指揮 アンサンブル・アルテ・ムジカ
Brilliant Classics 93652
②五声のためのマドリガーレ集第5巻
アントニー・ルーリー指揮 コンソート・オブ・ミュージック
L'OISEAU-LYRE 475 9110
③わが美しのニンフ~16/17世紀ヨーロッパのマドリガル集
アンドレ-アス・ゲップフェルト指揮 ハレ・マドリガリステン
Deutsche Schallplatten TKCC-30227
④テネブレ~聖週間のためのレスポンソリウム集(全曲)
ポール・ヒリアー指揮 ヒリヤード・アンサンブル
ECM Records POCC-1525~6(2枚組)
⑤テネブレ~聖金曜日のレスポンソリウム
アンドリュー・パロット指揮 タヴァナー・コンソート
SONY Classical CR-2517
ジェズアルドの作品はかなりCD化されています。特にマドリガーレは生前に出版されたものはすべてCDで聴くことができます。ただほとんどが輸入盤です。上にあげたリストはその中で私が普段聴いているCDで、彼の全作品中に占める割合からすれば僅かにしかすぎません。ただ重要なものはほとんど含まれていると思います。
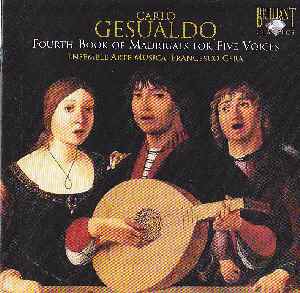 まず①の第4巻のマドリガーレですが、これはフェラーラに移って2番目に出版された曲集で、第3巻ではその半音階手法もまだわずか程度だったものが、ここに至ってより明確に示されているという点で注目される曲集です。なかでも第12曲の「ここにわたしは死
んでいく Ecco, moriro dunque」はよく知られており、世をはかなんで死を待つ気持ちを歌ったものです。この第4巻には二部構成からなる作品が6曲あり、この作品もその一つで第二部では「ああ、すでに私は息とだえ Ahi, gia mi discoloro」と歌われます。なおこのCDには途中彼の唯一の鍵盤楽曲「(プリンチペの)カンツォン・フランチェーゼ」が挿入されています。これは1620年ごろのナポリの写本に含まれていたもので、いつ頃作曲されたのかは不明です。穏やかな部分と技巧的な部分とが対照的に描かれた佳作です。半音階は使用していません。この団体の演奏(すべて五重唱)はとてもしっかりしていていいのですが、ときおりヴィブラートが耳につきます。アカペラが中心ですが、曲によってリュート、ポシティブ・オルガン、チェンバロなどがごく控えめですが伴奏で使用されています。録音はややデッドです。
まず①の第4巻のマドリガーレですが、これはフェラーラに移って2番目に出版された曲集で、第3巻ではその半音階手法もまだわずか程度だったものが、ここに至ってより明確に示されているという点で注目される曲集です。なかでも第12曲の「ここにわたしは死
んでいく Ecco, moriro dunque」はよく知られており、世をはかなんで死を待つ気持ちを歌ったものです。この第4巻には二部構成からなる作品が6曲あり、この作品もその一つで第二部では「ああ、すでに私は息とだえ Ahi, gia mi discoloro」と歌われます。なおこのCDには途中彼の唯一の鍵盤楽曲「(プリンチペの)カンツォン・フランチェーゼ」が挿入されています。これは1620年ごろのナポリの写本に含まれていたもので、いつ頃作曲されたのかは不明です。穏やかな部分と技巧的な部分とが対照的に描かれた佳作です。半音階は使用していません。この団体の演奏(すべて五重唱)はとてもしっかりしていていいのですが、ときおりヴィブラートが耳につきます。アカペラが中心ですが、曲によってリュート、ポシティブ・オルガン、チェンバロなどがごく控えめですが伴奏で使用されています。録音はややデッドです。 ②の第5巻は第6巻と共にジェズアルド絶頂期(?)の作品です。フェラーラから自身の城に戻って書かれたもので、病状は既に最悪な状態(これを絶頂期というのはおかしいですが、彼の作品としては)だったことが妻エレオノーラが兄に送った手紙などから明かにされています。マドリガーレの出版も第4巻から実に15年が経過していました。半音階と無調は更に徹底され、ここに彼の集大成とも言えるマドリガーレ集ができあがったのです。この第5巻の中では「この上なく優しいわたしの命である人よ Dolcissima mia vita」や「お願いだ、と私は泣いて叫ぶ Merce grido piangendo」は特に良く知られた名曲です。前者は「燃える想いを受け入れてもらえないのなら死を!」と激しい恋を歌ったもので、また後者は「自分の願いを聞いてくれる人が誰もいないので死にたい!」と叫ぶ絶望的な歌です。曲集中の半分が「死」という言葉を扱った暗いもので、それだけに大胆な半音階と無調が際立っています。演奏はソプラノのエマ・カークビーを中心とする五重唱で、すべてアカペラです。この演奏をきれいすぎるという人もいますが、きれいで悪いことはないと思います。特に半音階や無調というとある種の聴きにくさがありますので、私はこのくらいきれいに整っている方が聴きやすくて楽しめます。その分激しさみたいなものは薄れますが。
②の第5巻は第6巻と共にジェズアルド絶頂期(?)の作品です。フェラーラから自身の城に戻って書かれたもので、病状は既に最悪な状態(これを絶頂期というのはおかしいですが、彼の作品としては)だったことが妻エレオノーラが兄に送った手紙などから明かにされています。マドリガーレの出版も第4巻から実に15年が経過していました。半音階と無調は更に徹底され、ここに彼の集大成とも言えるマドリガーレ集ができあがったのです。この第5巻の中では「この上なく優しいわたしの命である人よ Dolcissima mia vita」や「お願いだ、と私は泣いて叫ぶ Merce grido piangendo」は特に良く知られた名曲です。前者は「燃える想いを受け入れてもらえないのなら死を!」と激しい恋を歌ったもので、また後者は「自分の願いを聞いてくれる人が誰もいないので死にたい!」と叫ぶ絶望的な歌です。曲集中の半分が「死」という言葉を扱った暗いもので、それだけに大胆な半音階と無調が際立っています。演奏はソプラノのエマ・カークビーを中心とする五重唱で、すべてアカペラです。この演奏をきれいすぎるという人もいますが、きれいで悪いことはないと思います。特に半音階や無調というとある種の聴きにくさがありますので、私はこのくらいきれいに整っている方が聴きやすくて楽しめます。その分激しさみたいなものは薄れますが。③はヨーロッパ各国のマドリガルを集めたもので、イタリアからはジェズアルドの他、マレンツィオ(2曲)、パレストリーナ、アルカデルト、モンテヴェルデイ(2曲)、シュッツ、ラッソ等のマドリガーレが選ばれています。イタリアにおけるマドリガーレの流れを俯瞰するには便利なCDといえるでしょう。マレンツィオの作品(「わが美わしのニンフ」他)は思ったほど半音階は使用されておらず、むしろモンテヴェルディの「アリアンナの嘆き」の方がマニエリスムの傾向は強く出ています。ジェズアルドの作品は2曲だけですが、そのうちの1曲「悲しやわたしは死ぬ、苦しみゆえに Moro, lasso, al mio duolo」は第6巻のマドリガーレ集に収録されている曲で、ジェズアルドのマドリガーレ中もっとも有名ものです。「自分は苦悩に疲れて死んでいくが、愛する人は助けようともしてくれない!」というこれも暗く絶望的な歌です。もう一曲は先に触れた第5巻の「この上なく優しいわたしの命である人よ」です。この演奏は五重唱ではなくすべてアカペラの合唱で歌われています。といってもそれほど人数は多くなく、ヴィッテンベルク大学の合唱団から選らばれた人たちで、素晴しいハーモニーを聴かせてくれます。このCDにはそのほかイギリス、ドイツのマドリガルやフランスのシャンソンなどが納められています。尚ジェズアルドの第6巻のマドリガーレは内容としては第5巻とほぼ同じ傾向といわれます。また今回のリストには入れませんでしたが、「マニエリスト革命 The Mannerist Revolution」(演奏:ポメリウム)(DORIAN DOR-90154)というCDがあり、これはイタリアのマニエリスムの作曲家達の作品だけを集めていて、ここでは第6巻から「美しい人よ、心を持ち去るのなら Belta, poi che t'assenti」を聴くことができます。これも大胆な半音階の音楽で、後にストラヴィンスキーがオーケストラに編曲した作品として知られています。
ジェズアルドのマドリガーレは死後ほどなくして全6巻がまとめられてジェノヴァで出版されていますが、現在CDでもこの全曲を聴くことができます。私は持っていませんが、オランダのカシオペア・クインテットという団体が録音しています(東京エムプラス、全6枚)。ただ死後に出版されたものや、他の作曲家といっしょに出版された作品までも含めるとジェズアルドのマドリガーレはかなりの作品数にのぼり、それらはまだ録音されていないようです。
さてカルロ・ジェズアルドはマドリガーレのほかに宗教曲もいくつか残しています。数はそれほど多くありませんが、やはり特異な作品として以前から様々な団体が録音しており、今回のテーマで冒頭にご紹介したデラー・コンソートもその一つでした。それは「聖週間のためのレスポンソリウム集」で私個人としてはこちらのほうが好きで、是非皆さんにも一聴されることをお勧めします。
聖週間については、前回の「ヨハネ受難曲」の話のなかでもふれましたが、復活祭(イースター)の前1週間のキリスト教最大の行事で、「棕櫚の日曜日」から始まり、聖木曜日、聖金曜日、聖土曜日の三日間は「過越しの三日間」と呼ばれ特に重要とされること、などをご紹介しました。そしてこの三日間の朝課(夜中のミサ)のための音楽を様々な作曲家が残していることなどもお話しましたが、このジェズアルドの作品もその一つです。
「過越しの三日間」の朝課では、日没と共に聖堂内の特別な燭代に24本のロウソクを立て(パロット盤のライナーノーツには15本となっていますが間違いでは?)、まず「エレミアの哀歌」の朗読が行われます。そして各アンティフォナとレスポンソリウムの歌いだしと共に1本ずつロウソクを消していきます。こうして明かりはどんどん消されていき、最後の一本のみ残るのですが、これは祭壇の後ろにあって会衆からは見えないため聖堂内は暗闇となります。この暗闇を意味する言葉がラテン語でTenebraeのため、これらの三日間の朝課を「テネブレ」と呼んでいます。アンティフォナとは「対唱」で「二つの合唱が交互に歌うこと」であり、またレスポンソリウムとは「応唱」で「先唱者に続いて合唱が答える」歌を意味します。
テネブレの典礼はそれぞれ三つの夜課(ノクトゥルノ)に分けられ、それぞれの夜課はまず三つの詩篇とアンティフォナによって導かれ、更に三つの朗読(レクツィオ)に続くレスポンソリウムがそれぞれ歌われます。もう少しわかりやすく書くと「アンティフォナ、詩篇」、「レクツィオ1、レスポンソリウム1」「レクツィオ2、レスポンソリウム2」「レクツィオ3、レスポンソリウム3」の順番で、これが「第1ノクトゥルノ」を形成し、これが三つあるということです。そしてこれが三日間、つまりすべてが3という数字になります。これは「三位一体」とキリストが埋葬されていた日数の3を表しています。前置きが長くなってしまいましたが、ジェズアルドの「聖週間のためのレスポンソリウム」を理解する上で重要と思われますので書いておきました。
 そこでまず④のヒリヤード盤ですが、これは全曲盤(聖木曜日、聖金曜日、聖土曜日の朝課で歌われるレスポンソリウムを全て収録)ということになっており、素晴しいハーモニーでたいへん評価の高い演奏です。このCD確かに全曲で間違いないのですが、実際に教会で演奏される場合、テネブレの典礼で触れたように、そのレスポンソリウムの前には詩篇やレクツィオが置かれますので、このレスポンソリウムだけを取り出してしまうとちょっと違和感があります。例えはあまりよくありませんが、何か「あんこのたくさん詰まったお菓子のあんこ」だけ食べているようで、長く聴いていると正直疲れます。これはヒリヤード盤に限らず他のほとんどの演奏もそうしているのだと思うのですが、一つだけ実際に典礼で行われたであろう演奏に近いCDがあります。それが⑤のタヴァナー・コンソート盤です。
そこでまず④のヒリヤード盤ですが、これは全曲盤(聖木曜日、聖金曜日、聖土曜日の朝課で歌われるレスポンソリウムを全て収録)ということになっており、素晴しいハーモニーでたいへん評価の高い演奏です。このCD確かに全曲で間違いないのですが、実際に教会で演奏される場合、テネブレの典礼で触れたように、そのレスポンソリウムの前には詩篇やレクツィオが置かれますので、このレスポンソリウムだけを取り出してしまうとちょっと違和感があります。例えはあまりよくありませんが、何か「あんこのたくさん詰まったお菓子のあんこ」だけ食べているようで、長く聴いていると正直疲れます。これはヒリヤード盤に限らず他のほとんどの演奏もそうしているのだと思うのですが、一つだけ実際に典礼で行われたであろう演奏に近いCDがあります。それが⑤のタヴァナー・コンソート盤です。 このタヴァナー・コンソートによる演奏は「聖金曜日のレスポンソリウム」だけですが、これは三日間の典礼でもっとも重要な日の朝課であり、それだけで十分音楽の素晴しさは理解できます。まずその朝課の構成は各夜課の冒頭にアンティフォナと詩篇を置き、朗
読(聖歌)1、レスポンソリウム1、朗読2、レスポンソリウム2、という具合に本来の朝課に近いスタイルで演奏されます。ですからとても聴きやすく、雰囲気も満点です。もちろんハーモニーも素晴しく、聴いていると静寂な、そして暗黒の世界へと思わず引き込まれていくようです。ただしこの盤も一部省略があります。つまり各夜課が三つの詩篇で始まるところ、ここでは一曲だけしか収録されていないのです。しかしながらこれは適切なカットだと思います。三つの詩篇ではかえって冗長となり、聴くほうもつらくなるかもしれません。それに何より更に長くなります。ヒリヤード盤が三日間のレスポンソリウムをCD2枚に収録しているのに対し、こちらは聖金曜日一日だけでもCD1枚の収録時間いっぱいなのですから、そこまで録音すると1枚のCDでは入らなくなってしまうでしょう。尚ジェズアルドはこのレスポンソリウムを作曲している間中、1610年に聖者の列に加えられた彼の母方の伯父にあたる聖カルロ・ボロメオ (Carlo Borromeo 1538-184) に異常とも言える執着を示し、彼の遺骨を手に入れようとフェデリコ・ボロメオ枢機卿に執拗に手紙で要求していたということで、ここでもその錯乱した精神状態が伝わってきます。
このタヴァナー・コンソートによる演奏は「聖金曜日のレスポンソリウム」だけですが、これは三日間の典礼でもっとも重要な日の朝課であり、それだけで十分音楽の素晴しさは理解できます。まずその朝課の構成は各夜課の冒頭にアンティフォナと詩篇を置き、朗
読(聖歌)1、レスポンソリウム1、朗読2、レスポンソリウム2、という具合に本来の朝課に近いスタイルで演奏されます。ですからとても聴きやすく、雰囲気も満点です。もちろんハーモニーも素晴しく、聴いていると静寂な、そして暗黒の世界へと思わず引き込まれていくようです。ただしこの盤も一部省略があります。つまり各夜課が三つの詩篇で始まるところ、ここでは一曲だけしか収録されていないのです。しかしながらこれは適切なカットだと思います。三つの詩篇ではかえって冗長となり、聴くほうもつらくなるかもしれません。それに何より更に長くなります。ヒリヤード盤が三日間のレスポンソリウムをCD2枚に収録しているのに対し、こちらは聖金曜日一日だけでもCD1枚の収録時間いっぱいなのですから、そこまで録音すると1枚のCDでは入らなくなってしまうでしょう。尚ジェズアルドはこのレスポンソリウムを作曲している間中、1610年に聖者の列に加えられた彼の母方の伯父にあたる聖カルロ・ボロメオ (Carlo Borromeo 1538-184) に異常とも言える執着を示し、彼の遺骨を手に入れようとフェデリコ・ボロメオ枢機卿に執拗に手紙で要求していたということで、ここでもその錯乱した精神状態が伝わってきます。この曲集では半音階や無調はマドリガーレよりは抑制されており、その意味ではより聴きやすいと思います。しかしこの静寂な音楽は何よりもジェズアルドの暗黒の心の叫びのように私には聴こえてきます。
カルロ・ジェズアルドの音楽は半音階や無調など、ちょっと聴きにくいと思われる方があるかもしれませんが、その分とても現代的で、私たちにも身近に感じられるものです。彼のマドリガーレの詩は初期においてはタッソやグァリーニ他の作者の詩を使っていますが、3巻以降はごく一部の作品を除きその詩の作者はわかっていません。ほとんどが短い詩なのですが、それは彼が音楽にあわせて自由に詩を作り変えたかったからだ、ともいわれています。いずれにしろカルロ・ジェズアルドはイタリア・ルネサンス末期にあってその猟奇事件もさることながら音楽的にもきわめて特異な存在であり、後世(特に20世紀の音楽)に及ぼした影響も大きく、ストラヴィンスキーが彼を崇拝・絶賛し、マドリガーレをオーケストラに編曲したのは前述のとおりです。しかしほぼ同時期に起こったバロック音楽の興隆とともに、彼のような半音階や無調の手法を受け継ぎ、発展させる次代の担い手は現れず、ここにルネサンスは終焉を迎えるのです。
<お詫び>(注) 15~16世紀にかけてフロットーラと呼ばれる世俗合唱曲が盛んになりますが、これは最上声部のメロディにただハーモニーを添えただけの三ないし四声の単純な声楽曲でした。それを更に芸術的に高めようと、メロディ以外のパートをもう少し独立させてポリフォニック(多声的)なスタイルにして生まれたのがマドリガーレと呼ばれる曲種です。14世紀にもマドリガーレという曲種がありましたが、それは詩の形式を意味していて16世紀以降のものとは異なります。
今回のカルロ・ジェズアルドのあと、もう一つ対のテーマがあり、そこまで終えてからと思っていたのですが、途中で中断することになりそうですので、とりあえず「古楽」については事情により2月一杯まで休止させていただきます。あしからずご了承ください。 尚その間まったく関係ないテーマですが、昔書き溜めておいた私の「山」に関するお話しを、毎週お届けしたいと思います。ご興味のある方はおつきあいください。「古楽」は3月に再開したいと思います。
2009.12.07 (月) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――2
3. カルロ・ジェズアルドの生涯ジェズアルド家は、ナポリ王国の名門貴族の一つで、ドン・カルロは1561年頃その次男として生まれました。ただしこの生年については諸説あり、最近発見された母親ジローラマ(ローマ法王ピウス4世の姪にあたる)からの手紙で1566年説が有力になっています。ジェズアルドの町はナポリから東方の内陸部に70キロほど入ったところに位置しており、アヴェリーノ州にある小さな山の頂に今も城跡が残っています。カルロの祖父の時代の1560年、ジェズアルド家はスペイン王フェリペ2世(当時ナポリ王国はスペイン領)からヴェノーサ公の地位を授与され、この町の支配者にもなりました。このヴェノーサはジェズアルドから更に東方の、イタリア半島のほぼ中央部に位置しています。
 ドン・カルロの父ファブリツィオ(1591没)は音楽好きで、自らアカデミーを設立して音楽の擁護にも力を注ぎ、そのためジェズアルド家の周りには多くの音楽家が集まっていたといわれています。そうした環境に育ったカルロが音楽の道に進もうとしたのは当然の成
り行きといえるでしょう。彼自身リュートの名手で、また類稀な美声の持ち主であったといわれています。ところが1585年長男ルイジの急死をきっかけに彼の一生は大きく狂い始め、悲劇的な人生へと転がっていきます。
ドン・カルロの父ファブリツィオ(1591没)は音楽好きで、自らアカデミーを設立して音楽の擁護にも力を注ぎ、そのためジェズアルド家の周りには多くの音楽家が集まっていたといわれています。そうした環境に育ったカルロが音楽の道に進もうとしたのは当然の成
り行きといえるでしょう。彼自身リュートの名手で、また類稀な美声の持ち主であったといわれています。ところが1585年長男ルイジの急死をきっかけに彼の一生は大きく狂い始め、悲劇的な人生へと転がっていきます。次男として気ままに音楽に親しんでいたカルロは、長男の死によりヴェノーサ公の継承者となりました。本人の意思に反して政治の世界に飛び込んだカルロは、更に政略結婚を強いられることになり、こうして1586年同じナポリの名門ダヴァロス家の娘で、いとこにも当たるマリア・ダヴァロス(Donna Maria d'Avalos)とナポリで結婚することになったのです。このマリア・ダヴァロスは絶世の美人だったそうですが、二十歳という若さにもかかわらず既に二度の結婚歴があり、淫乱で男癖の悪さでも知られていたのです。
結婚当初こそつつましく見えたマリアですが、夫への不満もあったのかやがて浮気の虫が眼を覚まし、やはりナポリの名家のアンドリア公ファブリツィオ・カラーファと情交を重ねるようになります。1588年ごろにはナポリ中の噂にもなり、当然それはカルロの耳にも入ります。彼は2年もの間その屈辱的な状況に耐えてきたのですが、とうとう堪忍袋の緒が切れたのです。耐えに耐えて解き放された感情の反動は強いものでした。こうして1590年10月16日事件は起きました。
事件の顛末は既にブラントームの記述でご紹介したとおりです。ただこの事件は証人による宣誓証言がすべて残されていることから、今でもその詳細を知ることができます。そこでいくつか補足しておきますと、まず彼は狩り出かける振りをして二人を欺き油断させ、あらかじめ部下に命じてドアの鍵を開けさせておきました。急ぎ宮殿にとってかえし、二人の濡れ場を押さえます。そして部下に命じて二人をベッドの上で殺害させたのです。おまけに残酷にも死体をすべてばらばらにし宮殿の前で人目に晒したのです。
更に証言からは次のようなことがわかっています。殺人のほとんどは部下達が実行した(させられた)のですが、しかしカルロ自身「彼女はまだ死んでいない!」と狂気の叫びをあげながら妻を何度も刺し、切り刻んだこと。情夫のアンドリア公は夥しい剣による深い刺し傷や頭部への一撃によって虐殺され、死体にはマリアのナイト・ドレスが着せられ、自分の服は全く血の付いていない状態でベッドの脇に積まれていたこと、等々です。カルロはまず始めにマリアを殺し、そして次に情夫を殺し、彼を辱めるために愛人の服を着せたのでした。
この殺人事件は当時タッソの詩をはじめナポリの多くの詩人たちによって広く宣伝され、センセーションを巻き起こしました。殺人事件の淫らな詳細が活字となって広まりますが、カルロは貴族なので罪に問われることはなかったのです。また当時のイタリアでは妻の浮気を夫が成敗することは認められていたといいます(注1)。それでも部下の手を借りたことは大いに世間の反感を買ったのでした。更に相手のカラーファ家は名門であったため、逆に復讐の矛先として命を狙われることになったのです。そのため彼はすぐにジェズアルドにある自分の城に逃げ帰り、そこにおよそ2年の間閉じこもってしまったのです。以後彼の周りには常に武装した兵士がいたといわれています。
警察の報告書は400年以上たった今でも人びとに衝撃を与えています。事件後更に詳細が補足され、それらによると、カルロはマリアとの間にできた2番目の子供まで殺害したといいます。まだ生後間もない幼児でしたが、子供の眼を見て自分が父親であることを疑ったのだと。そしてその際彼は息が止まるまで子供を振り回して殺した、という説まであらわれているとか。また復讐しようと城にやってきた義理の父親も殺してしまった、という別の記事もあるそうです。ただこれら二つの殺人は公文書には記載されていないので事実かどうかはわかりません。いずれにしろかなりの猟奇事件であったことは事実です。皮肉にも彼が城に逃げ帰り閉じこもっている間、彼は作曲に専念することができたのです。ただ同時にこの頃から彼の鬱病が始まりました。
しばらく自分の領地内に引きこもっていたカルロですが、1593年になって新しい人生が開けます。この年伯父のアルフォンソ・ジェズアルド枢機卿の勧めでエレオノーラ・デステ(Eleonora d'Este 1551-1637)と婚約します。エレオノーラは北イタリアのフェラーラ公国の君主アルフォンソ二世のいとこで、やはり名門エステ家の娘でした。アルフォンソ二世は歴代のフェラーラ公国の君主にあってもっとも芸術の振興に力を注いだ人物として知られ、そこには多くの優れた音楽家が集っていました。マニエリスム(注2)といわれる美術の手法が音楽に持ち込まれたのもこの宮廷だといわれます。そんなフェラーラにカルロが感心を示したのは当然でした。この婚約を期に彼はフェラーラに向かいます。ただこの婚約もまた政略結婚だったのです。
1594年2月21日フェラーラで二人の婚儀が執り行われました。様々な音楽家や詩人達がこの祝宴のために作品を捧げ、音楽劇や舞踏会が夜通し行われたといいます。カルロは結婚後もしばらくフェラーラに残りここで新しい音楽を吸収していきます。この宮廷で彼はマニエリトとして知られる宮廷オルガニストでマドリガル作家のルッツァスコ・ルッツァスキ(Luzzasco Luzzaschi 1545-1607)から大きな影響を受けたと言われ、これが後に彼の音楽を特異なものとする決定的な要因になっています。フェラーラ滞在中にも何度か旅をし、ヴェネツィアではジョヴァンニ・ガブリエリらヴェネツイア楽派の壮麗な音楽にも触れますが、彼は気に入らなかったようです。
1596年彼はフェラーラを離れてジェズアルドの自分の領地にもどります。ところが妻のエレオノーレはこのとき同行せず、どうやらあまり夫婦仲がよくなかったことがわかります。多分カルロの暗い性格が気にいらなかったのでしょう。1597年の終わりになってようやく彼の元にやってきたものの、しばしば出かけては長い間外で過ごすような状態でした。どうもジェズアルドの城になじめず、また隠遁生活を送るカルロとはウマが合わなかったのでしょう。カルロの鬱病は次第に悪化し、妻を虐待するようにもなり、エステ家ではエレオノーラに離婚を勧め、それは訴訟になったとも言われています。
一方でカルロはフェラーラの宮廷を真似て自身の館を音楽の中心にしたいと考え、お抱えの楽師(フェラーラには当時名高い「貴婦人達のコンチェルト」と呼ばれた声楽アンサンブルがあった)や自分の曲を歌ってくれる歌手達を集めたのですが、生まれつきの孤独癖が災いしてうまくいきませんでした。
1600年の10月に二人の間の息子アルフォンシーノが幼くして亡くなると、彼はジェズアルドにあるカプチン派の教会のために大きな絵の制作を依頼しました。そこには天使のような一群の人物の下にジェズアルド本人、彼の叔父のカルロ・ボローメオ、妻のエレオノーラそして亡くなった息子の魂が書かれているそうです。このことがあって彼はさらに音楽に没頭するようになります。そして殺人への畏れも加わったのか鬱病も悪化の一途をたどり、「一人では用足しもできず、またその世話をしてもらうために手を打って召使を呼ぶこともできなかった」と言われるほどでした。一説では召使に自らを鞭打たせ、マゾヒストのような異常な生活を送っていた、ともいわれています。1613年、彼の唯一の後継者でジェズアルド家の財産を管理していたエマヌエレ(最初の妻マリア・ダヴァロスとの間にできた息子)が亡くなると、その3週間後の9月8日、カルロ・ジェズアルドは孤独のうちにその波乱に満ちた生涯を閉じたのでした。
彼はナポリにあるジェズ・ヌオヴォ教会の聖イグナチウス礼拝堂に埋葬されましたが、1688年の地震で墓は壊されてしまいました。教会が再建されたとき墓は覆い隠されてしまい、今は教会の石畳の下で、わずかに埋められた場所を示す飾り板だけが残されているそうです。
(注1) ジェズアルド以外にも音楽の世界で知られている事件としては、バルトロメオ・トロンボンチーノ(Bartolomeo Tromboncino 1470?~1535?)による事件があります。1499年やはり妻の浮気に怒り、殺害しています。ただ彼の場合は情夫まで殺さなかった、と言われています。
(注2) 16世紀イタリアで起こった美術様式で、「様式」とか「手法」を意味するイタリア語のManieraに由来しています。奇怪ともいえる非現実的表現が特徴でミケランジェロの「最後の審判」はその先駆的作品といわれます。音楽もその影響を受けて大胆な表現が求められ、半音階や無調の音楽が生まれました。フェラーラの宮廷ではこの前衛的な音楽がヴィチェンティーノ(Nicola Vicemtino 1511-72)やデ・ローレ(Cipriano de Rore 1516-65)達によって盛んに作られたのです。
2009.11.16 (月) Ⅴ. 妻を寝取られ逆上の末・・・その狂気の叫び!――1
さてバッハから話はルネサンス後期のイタリアへと移ります。16世紀末、ナポリで音楽史上名高いある猟奇事件が発生しました。事件の顛末は後に記すとして、少し遠回りしますが私とその作曲家の出会いから話を進めてみたいと思います。1. アルフレッド・デラーのこと
私がクラシック部門に異動して最初に任された仕事は、「デラー・レコーディングス」というレーベルを日本で発売することでした。これはハルモニア・ムンディの1レーベルで、カタログとしてそれほど枚数は多くありませんでした。全部で30枚(LP)ちょっとだったと記憶していますが、イギリスのルネサンスからバロック期の音楽が中心でした。ただ、そのなかにモンテヴェルディ(Claudio Monteverdi 1567-1643)他イタリア・ルネサンス期の作曲家のものが何点か含まれており、なかでも今回採り上げる作曲家のレコードは5枚もあり、一人の作曲家の録音という点では全体のなかで大きな位置を占めていました。
この「デラー・レコーディングス」というのは当時カウンター・テナーの第一人者であったアルフレッド・デラー(Alfred Deller 1912-79)によって組織された声楽アンサンブル「デラー・コンソート」による一連のレコーディングで、ウィリアム・バード(William Byrd 1542/3-1623)のミサ曲や、パーセルの歌劇「妖精の女王」などの名盤がありました。1970年代中頃のことで、現在の古楽ブームに先鞭をつけた、といっても過言ではありません。そのアルフレッド・デラーについて、今回のテーマとは直接関係はないのですが、面白い逸話が残されていますのでちょっとご紹介しておきます。といってもこれは当時ある高名な音楽学者の先生から聞いた話なので、真偽の程は定かではありません。
前述のとおりアルフレッド・デラーはカウンター・テナーの歌手です。このカウンター・テナー、古楽全盛の今となっては履いて捨てるほどたくさんの歌手がいますが、デラーはその先駆的な存在だったことから、その当時はまだ珍しく、そのためかなりひどい偏見の目で見られていました。言うまでもなく、カウンター・テナーは女性のアルトに変わって男性がそれを受け持つものです。
このデラー・レコーディングスはアルフレッド・デラー60歳前後の録音でしたので、彼の全盛期はもう過ぎていたかもしれませんが、全盛期、彼はたいへん女性に人気があったそうで、彼のコンサートにはオペラ・グラスを片手に多くの淑女達が押しかけてきたといいます。ところがそのご婦人方の興味は音楽などではなく、彼の身体の一部に向けられていたのです。デラー氏が舞台に登場すると、ご婦人方はいっせいにオペラ・グラスをかざし、彼のただ一点を凝視するのです。つまりもっぱらご婦人達の興味の中心は、彼には男としてあるべきものがついているのかいないのか、ということだったのです。
この逸話の真偽はわかりませんが、この話の意味するところは要するに、当時カウンター・テナーに対してとんでもない偏見を持っていた、ということです。カウンター・テナーをカストラート(注)と混同していた訳です。同様な話がインターネットのWikipediaにも掲載されていますので、あながちオーバーな話ではないと思います。
カウンター・テナーは男性がファルセット(裏声)でアルトの音域を歌うのに対し、カストラートは少年時代、変声期を迎える前にソプラノの音域を確保するため去勢手術により睾丸を除去してしまうものです。そうすることで喉の咽頭部の成長を止めてしまいソプラノの音域を大人になっても歌えるようにするのです。誤解している人があるかもしれませんが、男性器全部を除去してしまうものではありません。ですから余談ですが、彼らにはセックスの能力もありました。そのおかげでカストラート全盛期(17~8世紀)には、彼らは貴族のご婦人達の浮気相手としてもっとも重宝されていた、ともいわれています。なにしろこれほど安全な?浮気相手はなかったでしょうから。したがって、カウンター・テナーにしてもカストラートにしてもオペラ・グラスでわかるようなものではなかったと思いますが、話としてはなかなか面白いものでした。
ちょっと思わせぶりに書いてしまいましたが、これらの件と今回のテーマは下半身の話としては共通しますが、直接関係はありません。そしてそのアルフレッド・デラーを中心とするデラー・コンソートが精力的に録音していたのが、イタリア後期ルネサンスの作曲家カルロ・ジェズアルド(Don Carlo Gesualdo da Venosa 1561頃-1613)の音楽だったのです。ジェズアルドはその猟奇的な事件や数奇な生涯と作品により、音楽史上きわめて特異な存在、といえるでしょう。
2. 1590年10月16日(注) 使徒パウロが聖書のなかで「婦人たちは、教会では黙っていなさい。」(コリントの信徒への手紙、第14章34節)と述べたことが発端となって男性のファルセット歌手が生まれましたが、声も小さく下手だったこともあって10世紀には去勢歌手が誕生し、15世紀に入ると盛んになった、といわれます。映画にもなったファリネリ(本名Carlo Broschi 1705-82)に代表されるように17~18世紀にかけて全盛を極めました。手術はかなり危険を伴い多くの幼い命が失われたといいますが、成功したカストラートには世界的な名声と富がもたらされました。ソプラノだけでなくアルトの歌手もいましたが、19世紀にはやがて廃れ、20世紀初頭まで存在したカストラート歌手、アレッサンドロ・モレスキ(Alessandro Moreschi 1858-1922)を最後に歴史から姿を消しました。ただイギリスでは19世紀を通じて男性のファルセットによるアルト歌手、つまりカウンター・テナーがずっと男声合唱で使われており、アルフレッド・デラーはそうした伝統の中から生まれたのです。なおモレスキには録音が残っており、聴くことができます。バッハ~グノー編のアヴェ・マリア(DG POCG-30033 Recording Pioneers、1904年録音)ですが、なかなか感動ものです。
事件は1590年10月16日に起きました。歴史上名高い事件であったことから過去に詩人のタッソ(Torquato Tasso 1544-95)やアナトール・フランス(Anatole France 1844- 1924)他多くの人がこれを題材に詩や小説を書いています。ここで私が事件の内容について述べるより、まずそうした記事のなかで面白いものをご紹介したいと思います。それはフランス・ルネサンス期にヨーロッパ中を放蕩してまわり、貴族社会の性態をこれでもか!というほど万集して書かれたブラントーム (本名ピエール・ドゥ・ブルドゥイユ Pierre de Bourdeuille 1539?-1614 )の「ダーム・ギャラント Les Dames Galantes」(鈴木豊 訳「好色女傑伝」 講談社 上・中・下)という本で、その記述を以下にご紹介します。
「ごく近年のことであるが、ナポリ王国でこれと全く違った事件が起きた。というのは、ナポリ王家の一族のうちでも、美貌第一の聞え高く、ヴェヌーズ(注:「ヴェノーサ」のこと)の公子のもとへ嫁いだ、ドナ・マリア・ダヴァロスが、これまたナポリ王の連枝で、並ぶものなき美男の大子といわれたアンドリア伯に横恋慕のはて、ある日二人で恋の戯れにうつつを抜かしているのを、夫君に感づかれた。その結果は、夫君に買収された刺客に、ベッドの中で××××××××の現場へ踏み込まれて、二人ながら惨殺されるという事件である(二人の不義を夫君が知ったいきさつを話してもよいが、はなしが永くなりそうなので、ここでは割愛いたすとしよう)。この記事に登場する夫君こそ、カルロ・ジェズアルドその人に他なりません。次回、彼の生涯と作品について見てみたいと思います。かくしてその翌日、この家の門前の石だたみの上に、今はまったく息絶えて、すでに冷たくなった二人の相愛の美男美女の死体が横たえられて、通行人の眼にさらされるという、見るも無残なありさま。通りすがりの者ひとしく、恋人たちのために涙にくれて、彼らの悲劇の境涯を嘆いたものだった。
この憂目にあった奥方の親戚の者たちはこの惨事に呆 然として、次には大いに憤慨して、ナポリ王家の法の定めの許す限り、下手人を裁きにかけて、死者の怨みを晴らそうとしたところが、当の奥方は、かくも美しくもまた高貴な手を、血でけがす値打すらないようなならず者の下男奴隷の手にかかって果てられたのだから、この問題をのみ表立てて、犯人たる夫君を法の裁きによって追求するのが唯一の方法で、もちろんこれがもし、夫君が自分で手を下したならば、ことは全く違ってくる。夫君みずから手を下した場合は、いかなる法律も追求の手は及ばぬことになるという定めだ。
亭主みずから手を下して女房を殺害に及んだら、法の手が及ばないなどとは、愚かもここにきわまる、まったく奇妙キテレツな意見であり、形式主義の権化ともいうべきはなしだが、かつてはかくもいとしんだおのれの女房を、われとわが手で殺すのと、ならず者の下男の手を借りるのと、その罪科はどちらが重いかについては、弁論法曹界の大家がたにお任せするとしよう。・・・(中略)・・・
ひとづてに聴いたはなしだが、副王ペスカイル侯は、この惨事に先立って、不義密通の男女を殺害するという計画を小耳にはさむや、この事を情夫ばかりでなく、当の奥方にまで警告してやったのだが、悲恋の幕がこんな惨事に終わったのも、二人が背負った運命の星のせいだろうか。
この女性はペスカイル侯爵の次男、ドン・カルロス・ダヴァロスの息女であるが、このご仁たるやその道の達人で、流した浮名のかずかずは、筆者もとくと存じているが、このご仁にして、もしこんな陰謀にはめられたとしたら、とっくの昔に、冥途に向って、長い草鞋をはいていたに違いない。」
(注:「×××・・・」はちょっと下品な言葉なのでカットしました)
2009.10.26 (月) 服部幸三先生の思い出
今月8日、服部先生が亡くなられたとの訃報を新聞で知りました。以前からおからだを悪くされていいて、何年か前から賀状の音信もままならなくなり心配していたのですが、とうとう帰らぬ人となってしまいました。私が先生を最初に知ったのは、このコラムを始めたときにも書いたように高校生の頃で、NHK・FM放送の「バロック音楽のたのしみ」を通じてでした。優しい語り口で、バロック音楽の面白さを教えてくださり、それは今でも私の宝物になっています。そのとき聴かせて頂いたたくさんの音楽やお話が今の私を支えている、といっても過言ではありません。
大学卒業後レコード会社に入って、クラシック音楽の企画や制作に携わるようになり、私はエラート・レーベル他を通じて直接先生とお会いする機会にも恵まれました。月に1回テスト盤を持って浦和のお宅に伺うことが楽しみになってもいました。その間先生とは直接バロック音楽の魅力についてお話しをすることができ、また一緒にたくさんの企画を考え、レコードとして発売もしてきました。中でも一番大きな企画は「バロック・オルガン大全集」というものでした。当時エラートにはマリー=クレール・アランをはじめ何人かのオルガニストがバッハやブクステフーデをはじめとするバロック期の作曲家の全集を録音していましたので、何とかこれを体系的にまとめることはできないかと先生に相談させていただいたところ、監修者としてご協力いただくことを快く承諾してくださったのです。こうしてLPで70数枚規模の、かつてない大きな全集が誕生することになりました。
全集としてまとめるため先生のお宅に何度となく足を運び、あるとき失礼をも省みず先生が風邪で横になられているときも枕元まで押しかけ、編成の相談などさせていただいたことが懐かしく思い出されます。この企画はその年のレコード・アカデミー賞にも選ばれました。先生の訃報に接し、悲しみと共に感謝の気持ちで一杯です。
先生ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。
2009.10.16 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――15
16. 「ヨハネ受難曲」のCD「ヨハネ受難曲」は「マタイ受難曲」に比べると合唱の比重が大きいこともあって、よほど訓練された合唱団によるものでないと、鑑賞に耐えません。そうしたことからいわゆるコンサート指揮者が演奏するにはかなり困難が伴うと思います。現在カタログを見回してもそうした団体によるものとしてはヨッフム指揮によるものくらいしか見当たりません。カラヤンやクレンペラー、ショルティ他大指揮者と呼ばれるかなりの人たちが録音している「マタイ」と比べてもその違いは歴然です。
さて現在私の手元には17種類の「ヨハネ」があり、大体のものは聴いているつもりですが、それでも前記ヨッフム盤を含めまだまだ聴いていないものはかなりあります。そうした未聴のCDの中にもいい演奏はあるかもしれません。その点おことわりしておきます。以下に私が好んで聴いているCDをご紹介します。
[新バッハ全集版]
①エーノホ・ツー・グッテンベルク指揮 ミュンヘン・バッハ・コレギウム
クラース・アーカン・アーンシェ(福音史家) アントン・シャリンガー(イエス) ナタリー・シュトゥッツマン(アルト) トーマス・クヴァストホフ(ピラト) 他 コーアゲマインシャフト・ノイボイエルン
RCA BVCC-3025/6 (1991年録音)
②ヘルムート・リリング指揮 バッハ・コレギウム・シュトゥットガルト
1. ペーター・シュライアー(福音史家) フィリップ・フッテンロッハー(イエス) ユリア・ハマリ(アルト) アンドレアス・シュミット(ピラト) 他 ゲヒンゲン・カントライ・シュトゥットガルト
SONY 72DC-628/9 (1984年録音)
2. ミヒャエル・シャーデ(福音史家) マティーアス・ゲルネ(イエス) インゲボルク・ダンツ(アルト) アンドレアス・シュミット(ピラト) 他 ゲヒンゲン・カントライ・シュトゥットガルト
hänsler COCO-80734/6 (1996年録音)
③フランス・ブリュッヘン指揮 18世紀オーケストラ
ニコ・ファン・デル・メール(福音史家) クリスティン・ジグムンドソン(イエス) ジェイムズ・ボウマン(アルト) イェッレ・ドライヤー(ピラト) 他 オランダ室内合唱団
PHILIPS PHCP-5136/7 (1992年録音)
[第4稿]
④鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン
ゲルト・テュルク(福音史家) 浦野智行(イエス) 米良美一(アルト) ペーター・コーイ(ピラト)
BIS(キング・インターナショナル) KKCC-2279/80 (1998年録音)
⑤アンドルー・パロット指揮 タヴァナー・コンソート・アンド・プレーヤーズ
ロジャース・コンヴェイ=クランプ(福音史家) デイヴィド・トーマス(イエス) クリスティアン・ギュンター(アルト) スティーヴン・チャールズワース(ピラト) 他
Virgin Classics 7243 5 62019 2 7 (1990年録音)
[第2稿](参考)
フィリップ・ヘレヴェッヘ指揮 コレギウム・ヴォカーレ
マーク・パドモア(福音史家) ミヒャエル・フォレ(イエス) アンドレアス・ショル(アルト) セバスティアン・ノアク(ピラト) 他
harmonia mundi 901748/49 (2001年録音)
このリストを見て「おや?」と思われた方も多いでしょう。そう、ここにはカール・リヒター盤が入っていません。音楽雑誌には必ずといっていいほど、この演奏が第一に採り上げられます。私がこの曲を好きになったきっかけもこのアルヒーフ盤でしたが、今回あえてこの演奏をあげませんでした。理由はいくつかありますが、リヒター盤でこの曲が好きになって以来、他の演奏を耳にするにつれ私は逆にこの演奏を否定していくようになったのです(マタイも含め)。その大きな理由は二つあります。第一は合唱です。ミュンヘン・バッハ合唱団の実力はすばらしく、この演奏でもそれはいかんなく発揮されているのですが、リヒターの歌わせ方に問題があるように思います。今主流を占めている古学演奏団体のものと比較すれば明らかなように、かなりロマン的性格が強く、禁欲的な演奏を好む私の趣味からは遠い存在となってしまいました。テンポをわずかながら不自然に動かしたりフェルマータをやたらのばしすぎるのは考え物です。本来コラールのフェルマータは会衆によって歌われるとき、「ずれたコーラスをそこでまた息を整えてあわせるために書かれた記号」であり、一般的な意味で使われる音をのばすための記号ではないということです。もちろんいくつかの部分で音楽的な解釈として伸ばすことは他の指揮者でも行われていますが、リヒターは過度にそれを行う傾向があります。第二にエヴァンゲリスト(福音史家)のエルンスト・ヘフリガーです。かつて彼のエヴァンゲリストは神様のように言われ、今でも崇拝する人が多いことは私も知っています。でもときおりピッチは不安定で、何より高音部の苦しそうな声は聴いていると、こちらまで首を絞めつけられているようで聴くに耐えません。どこがいいのでしょう?ギュンター・ラミン指揮による1952年の録音(edel CLASSICS 002312CCC)でも傾向は同じです。イエスのヘルマン・プライは立派です。もはやこのリヒター盤は先駆者としての歴史的役割を終えたと思います。
 さて私が好んで聴くCDを5点とりあげましたが、それらについて簡単ですが少し感想を述べたいと思います。まず①のグッテンベルク盤ですが、この演奏が前回の章で述べた第11曲のコラール演奏に該当するCDです。グッテンベルクといっても知らない人が多いと思いますが、マタイ受難曲(2種)をはじめブラームスのドイツ・レクイエムなど素晴しい録音を残しており、合唱音楽のスペシャリストともいえる指揮者です(最近ブルックナーの交響曲などにも活動の幅を広げている)。同じRCAに録音したマタイ受難曲も名演です。ノイボイエルンの合唱団は彼によって1967年に組織されておりそれほど古い団体ではありませんが、その実力の高さはマタイ、ヨハネの両受難曲を聴くと十分理解できます。古楽の団体ではないので合唱の人数は多く、聴感上から判断するとミュンヘン・バッハ合唱団とほぼ同規模かと思います。彼らの合唱はミュンヘン・バッハほど洗練されてはいません。ただそこに聴く力強い歌声は、大地から湧きあがるように生き生きとしていて、まさに「生命」を感じます。土の匂いさえしてくるようです。冒頭におけるオーケストラと合唱のバランスがあまりよくないので、第一印象は良くないかもしれませんが、曲が進むにつれその素晴しさに引き込まれていきます。各コラールをはじめ最後の二つの合唱も素晴しいのですが、彼らの実力をいかんなく発揮しているのが第二部冒頭の合唱です。これほど歯切れのいい合唱を聴いたことはありません。また福音史家のアーンシェやアルトのシュトゥッツマンを始めソリストの好演も光ります。
さて私が好んで聴くCDを5点とりあげましたが、それらについて簡単ですが少し感想を述べたいと思います。まず①のグッテンベルク盤ですが、この演奏が前回の章で述べた第11曲のコラール演奏に該当するCDです。グッテンベルクといっても知らない人が多いと思いますが、マタイ受難曲(2種)をはじめブラームスのドイツ・レクイエムなど素晴しい録音を残しており、合唱音楽のスペシャリストともいえる指揮者です(最近ブルックナーの交響曲などにも活動の幅を広げている)。同じRCAに録音したマタイ受難曲も名演です。ノイボイエルンの合唱団は彼によって1967年に組織されておりそれほど古い団体ではありませんが、その実力の高さはマタイ、ヨハネの両受難曲を聴くと十分理解できます。古楽の団体ではないので合唱の人数は多く、聴感上から判断するとミュンヘン・バッハ合唱団とほぼ同規模かと思います。彼らの合唱はミュンヘン・バッハほど洗練されてはいません。ただそこに聴く力強い歌声は、大地から湧きあがるように生き生きとしていて、まさに「生命」を感じます。土の匂いさえしてくるようです。冒頭におけるオーケストラと合唱のバランスがあまりよくないので、第一印象は良くないかもしれませんが、曲が進むにつれその素晴しさに引き込まれていきます。各コラールをはじめ最後の二つの合唱も素晴しいのですが、彼らの実力をいかんなく発揮しているのが第二部冒頭の合唱です。これほど歯切れのいい合唱を聴いたことはありません。また福音史家のアーンシェやアルトのシュトゥッツマンを始めソリストの好演も光ります。問題の第11曲のコラールですが、彼らはまず第3節の「誰があなたをかくも打つのですか」という問いを、天の高みからそっと問いかけるように優しく歌います。そして第4節に入り一転してフォルテで力強く「私です、私とその罪なのです」と歌います。こうした歌い方をしている演奏は私が知る限り2種類しかありません。ほとんどの場合逆です。最初に強く歌い、2度目には弱く歌う、という方法です。本来の演奏法からするとこちらの方が正しいので、ほとんどそうしているのだと思います。中には同じ音量で歌っているものもあります。しかし言葉の意味を考えた場合、グッテンベルクの解釈が正しいことは明らかだと思います。ここは「ヨハネ」の中でも特に重要な部分です。このCDを聴いているとこの前後、彼らの演奏はあたかも絵画の遠近法を採りいれたかの様に、深い奥行きと大きな拡がりを感じさせてくれます。残念ながら現在廃盤のようですが、前記マタイやシュライアー指揮によるロ短調ミサと一緒になったBox Setの輸入盤が格安で買えるようです。
 ②のリリング盤ですが、2種類あります。どちらか一方をと思いましたが一長一短なので、両方あげておきました。まず1984年盤ですが、こちらの聴きものは何と言ってもペーター・シュライアーのエヴァンゲリストです。これほど格調高く、またドラマチックな歌唱は他にありません。間違いなく最高のエヴァンゲリストで、これを聴くだけでも十分にこのCDは価値があります。シュライアーには他にハンス・ヨアヒム・ロッチュ指揮、ゲヴァントハウス管弦楽団&トーマス教会合唱団のCD (KICC-9508/9)がありますが、これほどの歌唱は聴かせてくれません。また第11曲のコラールでは、この演奏もグッテンベルク盤ほど力強くはありませんが、初めは弱く、そして繰り返しで強く歌う、という方法をとっています。ただアーリン・オジェーのソプラノが今一つだったり、合唱も含め全体的には96年録音盤の方が優れているように思います。
②のリリング盤ですが、2種類あります。どちらか一方をと思いましたが一長一短なので、両方あげておきました。まず1984年盤ですが、こちらの聴きものは何と言ってもペーター・シュライアーのエヴァンゲリストです。これほど格調高く、またドラマチックな歌唱は他にありません。間違いなく最高のエヴァンゲリストで、これを聴くだけでも十分にこのCDは価値があります。シュライアーには他にハンス・ヨアヒム・ロッチュ指揮、ゲヴァントハウス管弦楽団&トーマス教会合唱団のCD (KICC-9508/9)がありますが、これほどの歌唱は聴かせてくれません。また第11曲のコラールでは、この演奏もグッテンベルク盤ほど力強くはありませんが、初めは弱く、そして繰り返しで強く歌う、という方法をとっています。ただアーリン・オジェーのソプラノが今一つだったり、合唱も含め全体的には96年録音盤の方が優れているように思います。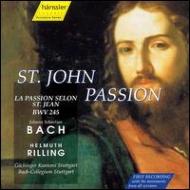 96年盤は厳密に言うと一般的な新バッハ全集版とは違います。このCDは1724年の初稿をもとに、失われた楽譜については他の稿を参考にしながらそれらを補完するような形で録音しています。一例をあげると、コラールを含む合唱では第4稿をもとに通奏低音にコントラファゴットを加えたり、一部のアリアにはコントラバスを補強させたりしています。このセットは3枚組で、3枚目にすべての異稿による演奏も収録しています。アンドレアス・グレックナーの楽曲解説も読み応えがあり、また異稿やこのCDの録音に関する指揮者リリングによる詳細な解説もついていてこれらは大いに参考になります。
96年盤は厳密に言うと一般的な新バッハ全集版とは違います。このCDは1724年の初稿をもとに、失われた楽譜については他の稿を参考にしながらそれらを補完するような形で録音しています。一例をあげると、コラールを含む合唱では第4稿をもとに通奏低音にコントラファゴットを加えたり、一部のアリアにはコントラバスを補強させたりしています。このセットは3枚組で、3枚目にすべての異稿による演奏も収録しています。アンドレアス・グレックナーの楽曲解説も読み応えがあり、また異稿やこのCDの録音に関する指揮者リリングによる詳細な解説もついていてこれらは大いに参考になります。この演奏の良さは次の二つにあると思います。まず冒頭の合唱からいきなり速めのテンポでぐいぐいと聴き手を音楽に引き込んで生きます。聴き手は構える間もなくいきなり劇的な世界へと引きずり込まれてしまいます。これは84年盤でも同様な傾向がありましたが、こちらの方が更にそれを徹底しています。途中からテンポは落着きますが、そうした印象もあって、かなり劇的表現の強い演奏になっています。もう一つの良さは福音史家のミヒャエル・シャーデです。彼はここでシャライアーに勝るとも劣らない歌唱を聴かせてくれます。彼は現在こうした宗教曲はもちろんオペラの世界でも幅広く活躍し、1965年生まれといいますから今油の乗り切ったテノールでしょう。シュライアーの後を継ぐ、現代最高のエヴァンゲリストと言っても過言ではないと思います。シュライアーとは声質も違い、もう少し乾いたハリのある声で、何より高音部にも余裕があります(グッテンベルグ盤のアーンシェもこちらに近い)。これに更にドラマチックな歌唱が加われば最高なのですが。ただこのCDで疑問に思ったのは第11曲のコラールで、84年盤とは逆の演奏法を採ってしまったことです。つまり一般的な歌い方で始めを強く、そして二度目に弱く歌うという方法です。何故変えてしまったのか、疑問です。
③のブリュッヘン盤は古楽器による演奏です。ですからオーケストラや合唱のハーモニーは素晴しく、また柔らかな響きがします。合唱の人数も各パート6人ほどで、編成としてはオーケストラも含め中規模なものといえるでしょう。この演奏の特徴としては強弱の使い方のうまさでしょうか。全体にイエスの受難物語りを優しく丁寧に歌っていき、誇張のないとてもオーソドックスな演奏といえるでしょう。ソリストなどにも派手さはありません。冒頭合唱の序奏では弦のうねるような動きを極力抑え、ファゴットを含む通奏低音による「歩みの音型」を際立たせ、重い足を引きずるようにゴルゴタの丘へと進むイエスを強く暗示しているようです。また合唱の入りも音量を抑え、次第にクレシェンドしていきますが、何よりその不安な表情がキリストの受難を予感させます。こうした演奏は他のCDには見られない特徴です。その後も強弱の使い方が巧みで音楽に変化をもたらしています。あの「マタイ」の凡演が嘘のようです。一つ残念なのは、ジェイムズ・ボウマンです。私はかつてパリで彼の出演するバロック・オペラを観たとき(残念ながら演目が思い出せません)、その恰幅の良さと、惚れ惚れするほどの美声に驚かされたのですが、ここではピッチも少し不安定でやや精彩にかけます。ライブのせいもあるでしょうが、残念です。
 ④と⑤はどちらも第4稿による演奏です。鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)には1995年にライヴで収録された一般的な新バッハ全集版の録音(KICC-168/9、彼らの最初の録音?)もありますが、こちらは98年にセッションで録音されたものです。そのライヴ盤もいいのですが、こちらは更に完成度を高めています。合唱は各パート5人で、ブリュッヘン盤と同じような規模です。この演奏は古楽特有の合唱におけるハーモニーの美しさがあげられます。あまり訓練されていない合唱団は各々が勝手にヴィブラートをかけて歌うので、その濁ったハーモニーを聴かされる方は気持ちが悪くなってきます。古楽の団体にはほとんどそういうことはありません。この演奏は世界のどこに出しても恥ずかしくない、第一級の演奏です。難を言えばエヴァンゲリストをはじめソリスト陣がややひ弱に思えますが、その中にあって米良さんの"Es ist Vollbracht"などは感動的です。第4稿は以前にも触れたように歌詞の変更やヴィオラ・ダモーレがヴァイオリンに変わったり、また通奏低音が強化されていますので音に厚みがあります。このCDには最後に追加として第2稿のアリアが3曲収録されています。
④と⑤はどちらも第4稿による演奏です。鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)には1995年にライヴで収録された一般的な新バッハ全集版の録音(KICC-168/9、彼らの最初の録音?)もありますが、こちらは98年にセッションで録音されたものです。そのライヴ盤もいいのですが、こちらは更に完成度を高めています。合唱は各パート5人で、ブリュッヘン盤と同じような規模です。この演奏は古楽特有の合唱におけるハーモニーの美しさがあげられます。あまり訓練されていない合唱団は各々が勝手にヴィブラートをかけて歌うので、その濁ったハーモニーを聴かされる方は気持ちが悪くなってきます。古楽の団体にはほとんどそういうことはありません。この演奏は世界のどこに出しても恥ずかしくない、第一級の演奏です。難を言えばエヴァンゲリストをはじめソリスト陣がややひ弱に思えますが、その中にあって米良さんの"Es ist Vollbracht"などは感動的です。第4稿は以前にも触れたように歌詞の変更やヴィオラ・ダモーレがヴァイオリンに変わったり、また通奏低音が強化されていますので音に厚みがあります。このCDには最後に追加として第2稿のアリアが3曲収録されています。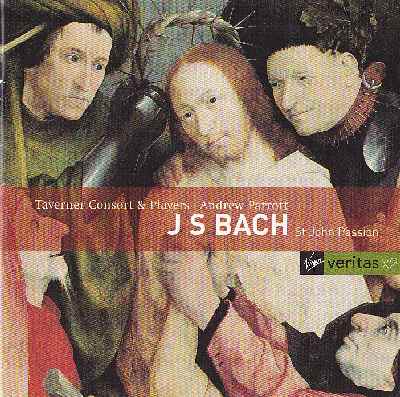 アンドルー・パロットのCDは同じ第4稿でもちょっと変わっているので採り上げました。パロットはカンタータの演奏などでリフキン方式と呼ばれる演奏法の熱心な推進者です。リフキン方式とはアメリカの音楽学者・指揮者として知られるジョシュア・リフキン(Joshua Rifkin)が1981年に提唱したもので、バッハの合唱曲は「各パート1人で歌うべき」というものです。ですから独唱者が合唱もすべて兼ねるということになります。この方式による演奏で知られたものとしてはポール・マクーリッシュ指揮のマタイ受難曲や日本のバッハ・コンチェルティーノ大阪のカンタータ演奏などがあります。でもそれらは成功しているとは思えません。原因は先にあげたヴィブラートです。ソリストが歌うので、合唱部でも過度なヴィブラートをかけてしまい、ハーモニーがだいなしです。アイデアはいいのですが、もっと古楽における歌唱法を学ぶべきでしょう。さてこのパロット盤ですが、さすがに彼はこの「ヨハネ」で各パート1人という選択を採りませんでした。彼は各パート2人で歌う方法を採り、それは見事に成功しています。オーケストラも実際にバッハが演奏していたと思われる編成に即した小規模なものにしています。BCJ盤同様ソリストがややひ弱ですが、このCDを聴いていると、そうしたことも忘れ、時を超えて自分がどこか小さな教会に引き込まれたかのような錯覚さえ覚えてきます。素朴な響きが心に沁みます。アビーロードのスタジオで録音されていますが、どこか片田舎の小さな教会で録音されたら、もっと雰囲気がでたでしょうね。
アンドルー・パロットのCDは同じ第4稿でもちょっと変わっているので採り上げました。パロットはカンタータの演奏などでリフキン方式と呼ばれる演奏法の熱心な推進者です。リフキン方式とはアメリカの音楽学者・指揮者として知られるジョシュア・リフキン(Joshua Rifkin)が1981年に提唱したもので、バッハの合唱曲は「各パート1人で歌うべき」というものです。ですから独唱者が合唱もすべて兼ねるということになります。この方式による演奏で知られたものとしてはポール・マクーリッシュ指揮のマタイ受難曲や日本のバッハ・コンチェルティーノ大阪のカンタータ演奏などがあります。でもそれらは成功しているとは思えません。原因は先にあげたヴィブラートです。ソリストが歌うので、合唱部でも過度なヴィブラートをかけてしまい、ハーモニーがだいなしです。アイデアはいいのですが、もっと古楽における歌唱法を学ぶべきでしょう。さてこのパロット盤ですが、さすがに彼はこの「ヨハネ」で各パート1人という選択を採りませんでした。彼は各パート2人で歌う方法を採り、それは見事に成功しています。オーケストラも実際にバッハが演奏していたと思われる編成に即した小規模なものにしています。BCJ盤同様ソリストがややひ弱ですが、このCDを聴いていると、そうしたことも忘れ、時を超えて自分がどこか小さな教会に引き込まれたかのような錯覚さえ覚えてきます。素朴な響きが心に沁みます。アビーロードのスタジオで録音されていますが、どこか片田舎の小さな教会で録音されたら、もっと雰囲気がでたでしょうね。 <参考>としてあげた第2稿によるヘレヴェッヘ盤ですが、これも演奏はたいへん素晴しく、No.39の「子守歌」など本当に泣けてくるほど感動します。ただ問題は稿にあります。異稿について述べたところでも触れたように、これは全く別といってもいいほど違う音楽が含まれています。そうした興味からこれを聴くのはいいと思いますが、これをもって「ヨハネ受難曲」である、とするのはやはり問題だと思います。最大の問題は終曲の合唱です。第2稿では、最後に再び長い合唱曲(アニュス・デイ-神の子羊-をドイツ語訳にしたコラール)を置いています。前回にも言いましたが、本来曲の両端に合唱曲を置くのが当時の習慣で、最後に合唱を2曲続けるのは異例だったのです。そこにもってきて長い合唱のあとに、更にまた長い合唱を続けるというのは、シンメトリックな構造を好むバッハが何故そうしたのかちょっと疑問のあるところではないでしょうか。聴感上も大変疲れます。優れた演奏だけにこれはこれとして新全集版もしくは第4稿で今一度彼らの演奏を聴いてみたいと思います。第2稿の演奏は他に我が国のバッハ研究家・指揮者として知られる樋口隆一氏も録音しており、彼は著書「バッハから広がる世界」の中で、第2稿こそが資料的かつ芸術的に優れているのだ、として自己の演奏をPRしていますが、芸術的というには無理があるように思います。これはやはり急場しのぎの稿と解すべきではないでしょうか。
<参考>としてあげた第2稿によるヘレヴェッヘ盤ですが、これも演奏はたいへん素晴しく、No.39の「子守歌」など本当に泣けてくるほど感動します。ただ問題は稿にあります。異稿について述べたところでも触れたように、これは全く別といってもいいほど違う音楽が含まれています。そうした興味からこれを聴くのはいいと思いますが、これをもって「ヨハネ受難曲」である、とするのはやはり問題だと思います。最大の問題は終曲の合唱です。第2稿では、最後に再び長い合唱曲(アニュス・デイ-神の子羊-をドイツ語訳にしたコラール)を置いています。前回にも言いましたが、本来曲の両端に合唱曲を置くのが当時の習慣で、最後に合唱を2曲続けるのは異例だったのです。そこにもってきて長い合唱のあとに、更にまた長い合唱を続けるというのは、シンメトリックな構造を好むバッハが何故そうしたのかちょっと疑問のあるところではないでしょうか。聴感上も大変疲れます。優れた演奏だけにこれはこれとして新全集版もしくは第4稿で今一度彼らの演奏を聴いてみたいと思います。第2稿の演奏は他に我が国のバッハ研究家・指揮者として知られる樋口隆一氏も録音しており、彼は著書「バッハから広がる世界」の中で、第2稿こそが資料的かつ芸術的に優れているのだ、として自己の演奏をPRしていますが、芸術的というには無理があるように思います。これはやはり急場しのぎの稿と解すべきではないでしょうか。ここには採り上げませんでしたが、ガーディナー(POCA-2134/5)やコープマン(WPCS-10293/4)による演奏もとてもいい演奏です。ただ今ひとつ訴えかけてくるものに欠けているようで、それが残念です。
17. エピローグ
今夏、「意志の勝利」という映画を見ました。小さな劇場でしたがそれでも入りきれないほどの人で溢れ、中には上映中倒れてしまう人まで現れて、ちょっと異様な雰囲気でした。私はこんな映画私と同世代か、それ以上の人しか見ないだろうと思っていたのですが、若い人が多いのにびっくりしました。それも女性同士で来ている人も多く見かけました。この映画は説明するまでもないかもしれませんが、1934年9月、ニュルンベルクで開催された第6回国家社会主義ドイツ労働者党(いわゆる「ナチス」)の党大会の記録映画です。レニー・リーフェンシュタール(ベルリン・オリンピックの記録映画「オリンピア『民族の祭典』」の映画監督として知られる)による映像美もさることながら、ドイツがあのおぞましい戦争へと駆り立てられていくファナティックな有様が克明に記録されています。日本では1942年に一度公開されたきりで、実に67年ぶりに再び上映されたのですが、何故今の時期なのか、ちょっと考えさせられます。今や戦後世代が多くなり、戦争に対する見方も変化してきているのかもしれません。「憲法改正」などという言葉が安易に口をついて出るようになったり、「核」という言葉も以前ほどの重みがなくなってきたように思います。少し前に漫画「わが闘争」が予想以上の売れ行きを示している、という新聞報道もありました。この映画はそうした社会の風潮に対する警鐘と考えるべきでしょう。
今回何故このテーマにしたのかという問題について少し書いておきたいと思います。現在はちょっと小康状態になっていますが、ちょうどこれを書き始める前イスラエルによるパレスチナへの無差別攻撃があり、多くの市民が犠牲になりました。こうした光景は何度となく繰り返されています。かつてユダヤ人は虐殺された苦い経験を持っているはずなのに、今はパレスチナに対してその正反対の行為を行っています。もちろん言い分はあると思います。またパレスチナ人によるテロへの報復だ、というかもしれません。でも関係のない市民まで無差別に殺害する行為は「ナチによるユダヤ人虐殺」と同じと言われても仕方ないのではないでしょうか?背後に聖地をめぐる根深い宗教的対立があることはわかりますが、ユダヤ教(キリスト教も)とイスラム教、どちらも先祖はアバラハムを父とする兄弟同士(だから余計に仲が悪いのかも)なのですから、過去の歴史を教訓としてお互い平和への道を模索して欲しいと思います。そんな思いから反ユダヤ主義の音楽といわれる「ヨハネ受難曲」について考えてみました。
復活祭を間近に控えた3月中ごろからこのテーマを書き始め、早いものであれからもう半年以上が過ぎてしまいました。長くなるとは思いつつ、でもこれほど長くなるとは思いませんでした。その間体調を崩したり、また会社もとうとう退職し、その前後は忙しかったこともあって、遅々として筆が進まなくなりました。難しいテーマでしたが、漸くここに終わらせることができました。それにしても思うのは、バッハの音楽の底の深さです。受難曲に限らず、彼の様々な曲を聴けば聴くほどいろいろな興味がわいてきます。また違うテーマに取り組みたいと思いますが、それまで充電のため少しお休みをいただきたく。
<補足>
9章「バッハの受難曲誕生前夜」の項で、ラインハルト・カイザーの「マルコ受難曲」についてご紹介しましたが、作者について少し補足しておきます。
ほとんどの本でカイザー作としていますので私もそれに従いましたが、正確には「伝ラインハルト・カイザー作」とするのが正しいようです。クリストフ・ヴォルフの説によれば作者はフリードリヒ・ニコラウス・ブラウンスで1707年ハンブルクで作曲者自身の指揮により初演されている、としています。
2009.09.25 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――14
15. 「ヨハネ受難曲」に思う「ヨハネ受難曲」(以下「ヨハネ」と略記します)にまつわる話についてはほとんど書いてきたつもりですが、音楽そのものについてはあまり触れてきませんでした。そこでここでは私なりにいくつかこの曲から感じられる点を今回のテーマへの答えも含めて書いてみたいと思います。
既に触れてきたように、これほど大規模な受難曲はそれ以前には存在しませんでした。冒頭合唱を聴くだけで、それは十分理解できるでしょう。かつてシューマンは「《ヨハネ受難曲》を《マタイ受難曲》よりも『はるかに大胆で激しく、また詩的である』とし、こう述べた。『[ヨハネ受難曲は]なんと密度の濃い、なんと独創的な作品だろうか。とくに合唱曲といったら!』(マルティン・ゲック「ヨハン・セバスティアン・バッハ」鳴海史生訳 東京書籍)と言ったそうですが、まさにその言葉どおりだと思います。
では新バッハ全集版に沿って話を進めてみましょう。まず冒頭合唱におけるオーケストラの導入部ですがこれは大きく三つの部分に分けられます。通奏低音の保続音とそれに乗って奏される弦の波のような動き、そして協和音と不協和音が交互に現れる管楽器群の三つですが、これは何を表しているのでしょう。私は以前にも申し上げたとおりこじつけのような「数の象徴論」(注)には賛成しかねるのですが、それでもいくつかの真実はあると思っています。その一つが「三」という数字です。多くの人が指摘するようにこの「三」は「三位一体(父と子と聖霊)」を表わしていることになります。そして通奏低音の保続音は、修辞学に従えば「歩みの音型」であり、これはゴルゴタの丘へと導かれるイエスを象徴しているとみることができるでしょう。協和音と不協和音が交錯する管楽器は受難を予告するような不安な音に満ちています。また音の動きが交差するいわゆる十字音型(最初と最後の音を結ぶ線と中に位置する二つの音を結ぶ線が交差する)をも示しています。この冒頭導入部についてゲックは次のように言います。まず低音部は「父なる神」を表わし、木管楽器は「痛ましい音程」によって「神の御子の受難」を表現し、そして弦のうねるような動きは「聖霊の去来するさま」を表わしているのだ、と。合唱が入ってくるとまたしても「Herr(主よ)」が三度叫ばれます。ここでも「三」です。また冒頭合唱の調性がg-moll (ト短調)であることにも着目すべきかと。GはいうまでもなくGott (神)もしくはGeist (聖霊)を表わしていることになります。バッハは当然これらのことを念頭におきながら作曲したと思います。
第2曲に入り、いよいよヨハネ福音書による受難物語が始まります。マタイ受難曲ではイエスが捕らえられるまで「最後の晩餐」他いくつかのシーンがありますが、この「ヨハネ」では、いきなりイエスの「捕縛」のシーンから始まります。そしてユダに手引きされた兵士達にイエスが「誰を探しているのか?」と尋ね、彼らが「Jesum von Nazareth!(ナザレのイエスを)」(No.2b及びd)と叫ぶにいたり、ここで音楽は一気に劇的な高まりをみせます。この合唱が生ぬるいと、概して演奏は平凡なものになってしまいます。この「ナザレのイエスを」も三度歌われます。そしてこの音型は、言葉を変えて全曲中に何度か現れますので、それだけ重要なモティーフということができるでしょう。
最初に歌われるコラール(No.3)はヨハン・クリューガー(Johann Cr?ger 1598-1662)作のメロディーにヨハン・ヘールマン(Johann Heermann 1585-1647)が詞をつけたもので、讃美歌21の第313番「愛するイェス」としても知られるものです。「おお、大いなる愛よ」と歌われ、高まった緊張を一瞬ほぐしてくれます。これはコラールの第7節を歌ったものですが、この曲は第二部に入ってその第8及び9節(「ああ、大いなる王」)がもう一度歌われます(No.17)。またこれは「マタイ受難曲」でもやはり最初に現れるコラール(第1節が歌われる)として知られています。
このコラールのあと、イエスを捕らえようとした兵士に、弟子のペテロが剣を抜いて襲いかかりその耳を切り落とすという事件が起こります。イエスがそれを諌めたのち再びコラール(No.5)が挿入されます。これはルターの作った"Vater unser im Himmelreich"というコラールで、讃美歌21の第63番「天にいます父よ」として知られています。ここではその第4節が「神の御旨が実現しますように」と歌われます。
捕われ人となったイエスはまずユダヤ人による裁判を受けます。ここでアリアが2曲挿入されます(No.7&9)。最初のアルトのアリアは「自分達の身代わりとなってイエスが縄に繋がれていくのだ」と歌い、その次のテノールのアリアでは「私もあなたについていきます」という信仰告白が行われます。
アリアのあと再び聖書の記述に戻り、ここでいわゆる「ペテロの否認」と呼ばれるシーンとなります。イエスのあとに従ったペテロに対し、「あなたもあの人の弟子ではないのか」と尋ねられたペテロが「違う!」と否定する場面です。3度尋ねられて否認したところでバッハは「マタイ伝」からの聖句を挿入します。つまりペテロはイエスの言葉(『鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないというだろう』)を思い出し、「外に出て、激しく泣いた。」という句で、「マタイ受難曲」ではここで有名なアルトのアリア(ヴァイオリンのオブリガート付き)が歌われます。そして「ヨハネ」ではこの否認の場面でとても重要なコラール(No.11)が歌われます。最初の否認の後、イエスが下役から平手打ちを食らわせられる場面で歌われます。私はこのコラールこそバッハがこの「ヨハネ」でもっとも人々に伝えたかった言葉ではなかったのかと、思っています。そう思ったきっかけはあるCDの演奏にありました。彼らはここでどうしてこういう演奏をするのか?と考え込んでいくうちに、次第に思いは広がっていき、今回のテーマを書くきっかけにもなったのでした。演奏の内容については次回CD紹介の章でご紹介したいと思いますので、ここでは触れませんが、このコラールの詞がとても重要だと思います。これはパウル・ゲルハルトがハインリヒ・イザークの有名な「インスブルックよ、さようなら」の旋律に詞をつけたもので、讃美歌21の第295番「見よ、十字架を」でも知られています。このコラールの第5節は「マタイ受難曲」でも歌われていますが、ここではその第3及び4節が歌われます。以下がその詞になります。
[第3節]この詞のそれぞれ一行目に注目してください。「誰があなたを打つのか?」という問いに対し「私です。私の罪なのです。」と答えるようになっています。このことばはそのまま「誰があなたを十字架にかけたのですか?(あるいは『誰があなたを殺したのですか?』)」「それは私です。」と置き換えることができます。「私」はすべての人間を表わします。つまり、イエス・キリストを殺したのは「すべての人の罪」なのだ、と。ですから決してユダヤ人などではありえない、という結論になります。これが「ヨハネ受難曲」と反ユダヤ主義に対する私の結論ですが、これと同じことを指摘している人がいました。私はあるCDの演奏からこの結論を導き出したのですが、キリスト者の視点から川端純四郎氏は次のように言っています。
「誰があなたをかくも打つのですか。
私の救いよ、誰があなたに責め苦を
こんなにも酷く負わせるのですか。
あなたは、罪びとではありません。
私たちや、私たちの子らとは違って。
あなたは悪事など、思いもよられぬ方なのです」
[第4節]
「私です、私とその罪なのです。
その多いこと、
浜の砂子のようなこの罪が
あなたを追いやるのです、
あなたを襲う悲惨へと、
また、いまわしい責め苦の数々へと」 (礒山 雅訳)
「《ヨハネ受難曲》の中心メッセージは第11曲のコラール『だれがあなたにこんな責め苦を負わせたのですか。私です。私とその罪です』というところにあります。「十字架につけろ」と叫ぶ『ユダヤ人』は『私』なのです。だからこそ、バッハは、これらの『ユダヤ人』の合唱にあれほど恐ろしい真実性を歌いこめたのです。そこには単純な『反ユダヤ主義』はありません。」
氏は同時に「ヨハネ伝」が「ユダヤ人」を「罪」の代名詞として使用している点に、疑問を持たなかったバッハにも多少の罪があるともしていますが、音楽の力がそれを超えている、と結んでいます。
再び曲に戻りましょう。「ペテロの否認」後半部でペテロが「外に出て激しく泣いた」という部分、通奏低音に半音階の上昇音型と下降音型が現れますが、これは修辞学による「ラメント・バス(嘆きの低音)」の音型といわれます。そしてこの「否認」のあとに続くテノールのアリア(No.13)とコラール(No.14)ではペテロが自らの罪を悔い、慟哭し、第一部を閉じるのですが、この2曲は調性が嬰ヘ短調となっていてこれは♯が三つになります。そして嬰記号(♯)のドイツ語はKreuzであり、十字架と同じことばになります。したがって「十字架」と「三位一体」を重ね合わせて表わしている、ということにもなります。最後のコラールはパウル・シュトックマン作の"Jesu Leiden, Pein und Tod"で、その第10節が歌われます。このコラールは第二部のNo.28及び32曲でもその第20節及び第33節がそれぞれ歌われます。
第二部にはいると、ユダヤ人の裁判では死刑を求めることができないため、ユダヤ人達はイエスをローマ総督であるピラトの元へ連れて行き、いよいよその審問が開始されます。その導入部は力強いコラールで、これはルターの宗教改革に先立って改革の烽火をあげ、闘いに破れて火刑に散ったヤン・フスの急進的な流れを汲む、ルターと同世代の作家ミヒャエル・ヴァイセ(Michael Weisse 1488?-1534)がボヘミア兄弟団の歌に詞をつけものです。讃美歌21の第293番「救いのぬしは罪もなしに」としても知られています。ここではその第1節が歌われますが、後半のNo.37でももう一度現れ、その第8節が歌われます。
ピラトへ引き渡す際の群衆の合唱(No.16b)も、かつてこれほど激しい合唱があったでしょうか?ここからしばらくピラトとイエスの間で禅問答のような会話が続きます。この間、No.3で歌われたヘールマンのコラール第8及び9節が「ああ、大いなる王」と歌われます。そして曲は以前スメントの説としてご紹介したこの第二部の核心部ともいえるシンメトリックな楽曲構造部に入っていきます。
No.17 コラール「ああ、大いなる王」少し解りやすくするため上記のように列記してみましたが、この一連のなかで殺人の罪を犯したバラバは過越祭の恩赦により解放され、イエスはユダヤ人らの激しい訴えを受け入れたピラトにより鞭打たれることになります。ここでバスのアリオーソ(No.19)とテノールのアリア(No.20)が歌われますが、ヴイオラ・ダモーレとリュートの通奏低音により甘味といってもいいほど、この受難曲中で最も美しい音楽になっています。前後に激しい音楽を配しているため、それはより際立って聴こえます。鞭で打たれた背中の傷を虹にたとえるなど、これが後に物議をかもし、演奏中止に追い込まれ第4稿へとつながったのでした。
No.18b 合唱「あの男ではなく、バラバを!」
No.19&20 独唱「見つめるがよい」
No.21b 合唱「万歳、ユダヤ人の王様」
No.21d 合唱「十字架につけろ」
No.21f 合唱「私たちには律法があります」
No.22 コラール「あなたが捕われたからこそ」
No.23b 合唱「あなたがこの男を釈放するなら」
No.23d 合唱「十字架につけろ」
No.23f 合唱「私たちには、皇帝のほかに王はいません」
No.24 独唱「急げ、悩める魂よ」
No.25b 合唱「『ユダヤ人の王』と書かずに」
No.26 コラール「私の心の奥底には」
真ん中に置かれたコラール(No.22)はC.H.ポステルという人が書いた受難曲台本のアリア自由詩をもとに、バッハがヨハン・ヘルマン・シャインのコラールに節をつけたもので「あなた(イエス)が私達の身代わりとなってくれたことで、私たちは自由になれたのです」と優しく歌います。それも束の間音楽は一転して激しさを取り戻し、ここからいよいよイエスのゴルゴタの丘への道行きと磔の場面へと進みます。ピラトへの恫喝ともいえる激しい言葉(No.23b)が群衆によるフーガ形式の合唱で歌われ、これによりピラトはイエスを十字架にかけることになります。このあたりのたたみかけるような音楽の進行は劇的で、見事というほかありません。そしてこの激しい音楽の一連の流れは終り、シンメトリック構造の最後におかれるコラールへと導かれていきます。
ここまでは激しい音楽が続き、聴く方にもかなり緊張感がもとめられますが、そこにこのコラールが現れ、ほっとすることができます。力強く歌われる、私も大好きなコラールで、これはヴァレリウス・ヘルベルガー(Valerius Herberger 1562-1627)が1613年死者のために書いた「われ汝に別れを告げん」という詩に翌年メルヒオール・テシュナー(Melchior Teschner 1584-1635)が作曲したものです。讃美歌21の第571番「いつわりの世に」としても知られています。ここではその第3節が「わたしの心の中では、あなたの名前と十字架だけがいつも光を放っています」と歌われます。これは変ホ長調で♭が三つ。ここでも「三位一体」が表されます。
No.26のコラールのあと、いよいよ「死」の場面へと移っていきますが、その前に十字架にかけられたイエスが残した衣服を、兵士達が奪い合うシーンがあります(No.27)。これが何とも軽妙で4声部の合唱の掛け合いが見事です。これは「くじ引きで決めよう」と言い争っているのですが、その描写のうまさには舌を巻きます。それにしてもこれからイエスの最期が描かれるというのに、この軽妙な音楽は場違いのような気もしますが、これも対比の見事さなのでしょう。このあとイエスの母やマグダラのマリアらが登場し、そして死の前に再びコラール(No.28)が歌われます。これは第一部の最後に歌われたコラールと同じですがその第20節で、イエスが母マリアを弟子に引き取らせた後「いまわのときに、彼はすべて準備を終わらせた」と歌います。この音楽の調性はイ長調、ここでも♯(十字架)が三つになります。
いよいよ「死」の場面です。ここでイエスは喉の渇きを訴え、葡萄酒で口を拭ってもらい、そして有名な言葉"Es ist vollbracht!(成し遂げられた)"とつぶやきます。これは「マタイ受難曲」の「エリ・エリ・ラマ・サバクタニ(わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか)」に相当する言葉ですが、それよりはるかに奥深い言葉といえるでしょう。この言葉を受けてアルトのアリア"Es ist vollbracht"(No.30)が歌われます。ヴィオラ・ダ・ガンバの伴奏で静かに悲しみをかみしめるようにしみじみと歌われるこの曲は「ヨハネ」のなかでもっとも有名なアリアです。「マタイ」のアルトのアリアと双璧をなす名曲中の名曲といっても過言ではないでしょう。後半音楽はVivaceに転じ激しい音の動きを見せますが、これは戦いを表わしていて「ユダ族の勇士(イエスのこと)、ここに勝って戦いを終わらせる」という歌詞によるものです。そして最後に再び静かに "Es ist vollbracht"と歌って終わります。このあと福音史家によりイエスの死が静かに告げられます。
イエスの死を受けて歌われるバスのアリアとコラール(No.32)はとても穏やかな気持ちにさせてくれるもので、バスが「あなたが成し遂げられたというからには、私たちは死から解放されたのでしょうか」「天国をさずかることができるのでしょうか」「救いはなったのでしょうか」と問いかけていく合間に、静かにコラールが流れていきます。ぼんやり聴いているとわかりませんが、第一部終曲(No.14)のコラールと同じ(歌詞は第33節)ものです。
このコラールのあと、もう一度「マタイ伝」からの引用があり、「そのとき、神殿の垂れ幕が真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて多くの聖なる者たちが甦った」と福音史家が告げますが、「マタイ受難曲」同様激しい弦の動きがその異常な様を描写しています。この言葉はそのまま次のアリオーソ(No.34)に受け継がれ、美しいソプラノのアリア「溶けて流れよ、私の心よ、溢れる涙の潮に乗って」(No.36)へと続いていきます。このアリアも情感に富み、アルトの"Es ist vollbracht"ととともに有名なものです。
次の福音史家の言葉では、ユダヤ教の習慣により安息日に死人を十字架に置いたままにはできないことから、彼らをそこから降ろす際のちょっと残酷な場面が語られます(No.36)。イエス以外の二人の罪人は兵士たちにその足を折られ、またイエスは既に死んでいたのがわかったので足は折らず、その代わり槍で腹を突いた、といいます。ということは足を折られた罪人はまだ生きていた、ということでしょうか?いずれにしろこうした記述は他の福音書には見られません。このあとコラール(No.37)が歌われますが、これは第二部冒頭のものと同じで、その第8節「あなたのつらい受難を通じて、どうか私達に力をお与えください」と歌います。
さていよいよこの受難曲も大詰めとなり、まず福音史家が「亡骸がピラトの許しを得てヨセフに引き取られたこと」「十字架にかけられた場所に園があり、そこに新しい墓があったのでそこに埋葬したこと」を報告し、この受難物語はそこで終わります。したがって復活の話しは「マタイ受難曲」同様でてきません。ただ音楽はまだ2曲続きます。
ここからの2曲がまた素晴しい音楽です。No.39の合唱は「マタイ受難曲」の終曲に相当する大曲ですが、その素晴しさは例えようがありません。最近歳をとって涙腺が弱くなったせいか、このすすり泣くようなオーケストラの序奏が始まったとたん私は涙を止めることができなくなってしまいます。礒山さんはこの曲を「子守唄」と評しましたが、そうした言葉では言い尽くせない程素晴しい音楽です。
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine何と優しく、そして慈愛に満ちた音楽でしょうか?深い感動に包まれる名曲です。この曲はc-moll(ハ短調)で、このCはChristus(キリスト)もしくはCreuz(十字架。バッハの時代KreuzはCreuzと書いた)を象徴しているといえます。
Die ich nun weiter nicht beweine;
Ruht wohl, und bringt auch mich zur Ruh!
安らかに憩え、聖なるむくろよ
私はもうこれ以上、嘆き悲しみますまい
安らかに憩い、私をも憩わせてください (礒山 雅 訳)
No.39の合唱で本来終わるべきところですが、バッハはもう一曲簡潔なコラールを最後に置きました。このコラールはマルティン・シャリングが1569年に作ったもので、ここではその第3節が歌われますが、この曲も変ホ長調で、つまり♭が三つになります。最後に再び「三位一体」があらわれます。この時代の宗教曲では両端に合唱を置くのが普通で、最後に合唱を2曲続けるというのはとても異例なことだと思います。バッハも一度第3稿ではこの合唱を削除しています。ですから本人も悩んだ末のことだったと推察しますが、どうして2曲続けたのでしょう。ゲックはライプツィヒ当局の要請に従ったのだろう、としています。もちろん本当のところは知る由もありませんので私なりに考えてみますと、「安らかにお休みなさい」と歌って終わるのもいいですが、それより最後に神に感謝することばで終わりたかったのではないでしょうか。その結果この終結コラールは未来に向けた力強いメッセージのように私には聞こえてくるのです。以前私はコンサートで「安らかにお休みなさい」の合唱で深く感動するあまり、このまま曲が終わってしまったら、しばらく椅子から立ちあがることさえできないような状態になってしまいました。でも続いてこのコラールを聴いたとき、晴れ晴れとした気持ちで家路につくことができたのです。それほど「私達に生きる力を与えてくれる」そんな素晴しい讃美歌です。
最後にこれは意外に知られていませんが、バッハの受難曲は1988年までイスラエルでは上演が禁止されていた、といいます。もちろん今ではこのようなことはありません。私はこの素晴しい音楽を聴いていると、これが反ユダヤ的などとはどうしても思えないのです。
「私はあなたを、永遠に讃えます!」と力強く歌ってこの曲は終わります。
(注) 主にスメントらによって主張されたもので、バッハの音楽を数字の組み立てから分析しようとするものです。日本でも丸山桂介氏や杉山好氏らがこの方法論を採っています。一例をあげると杉山好氏は著書「聖書の音楽家バッハ」のなかで、「マタイ受難曲」のユダのアリア(No.42)について次のようにいいます。「このアリアが全部で六十五小節なんです。これを分解すると、5×13になる。五というのはバッハにおいては神人イエスを象徴する数なんです。なぜかというと、5=3+2で、三は神、二は人を表わしますから。・・・その主イエスが十三で象徴されるユダに最後までかかわりを持っておられた。ユダをイエスは最後まで見放さない・・・」という具合ですが、本当にそこまで考えて作ったのでしょうか?丸山氏になるともっと複雑な数字を持ち出し、読んでいるこちらの方が頭が痛くなってしまいます。
2009.09.05 (土) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――13
14. ヨハネ受難曲の初演と再演 ―― その異稿をめぐって1724年の聖金曜日(4月7日)にヨハネ受難曲が初演されたことは既に触れましたが、このときのちょっとしたエピソードをご紹介しておきましょう。
バッハがライプツィヒに着任したのが、1723年の5月だったことも前述のとおりですが、もう一度当時のライプツィヒにおける受難曲の演奏についておさらいをしておきましょう。
ライプツィヒでようやく受難曲の演奏が認められたのが1721年で、このとき聖トーマス教会でクーナウの「マルコ受難曲」が演奏されました。そして翌年にはライプツィヒのもう一つの主要教会である聖ニコライ教会で同じ曲が再演されました。ここに聖トーマスと聖ニコライの二つの教会で受難曲が毎年交互に演奏される習慣が出来上がりました。バッハがライプツィヒに着任する直前(1723)の聖金曜日には、やはりクーナウの同じ受難曲が聖トーマス教会で再々演されています。したがってバッハの最初の受難曲上演は、順番からいうとニコライ教会で演奏されることになります。バッハがこの習慣を知らなかったのか、あるいは確信犯的にそうしたのかはわかりませんが、バッハはトーマス教会で演奏するべく勝手に自らチラシを作成して配ってしまったのです。背景にはトーマス教会の方が大きいので、大規模な作品の演奏にはより適していたこと、また当然集まる聴衆の数も多いことがあります。これを知った市参事会は直ちにバッハに対し演奏会場を変更するよう命令し、4月3日バッハもこれを受け入れ、参事会に対し「自分が当地の習慣に通じていない他郷人であることに免じて許してもらいたい」(バッハ叢書10巻)と詫びて落着したのでした。ただ同時にいくつかの要望(壊れたチェンバロの修理や演奏スペースを広げることなど)も出し、市側もこれを受け入れ、また市の費用でチラシの再印刷も行われました。こうしてかつて類をみない大規模な受難曲がニコライ教会の聖金曜日の晩課の礼拝で初演されたのでした。このエピソードは後にバッハが市参事会と対立していく、最初の小さな事件と見ることができるでしょう。このときの演奏が「第1稿(もしくは初稿)」と呼ばれるものですが、残念ながらスコアは紛失してしまい、不完全なかたちで残されているだけです。
初演が行われたときの評判や市民の反応についてはわかっていませんが、これだけの大規模な作品を初めて聴いた聴衆はさぞ驚かれたことと思います。バッハは翌年(1725)の聖金曜日(3月30日)におけるトーマス教会での受難曲演奏に、この「ヨハネ受難曲」を再演することにしました。新曲を用意する余裕がなかった、ということもあったかもしれません。ただ再演にあたって、彼は大胆にこれを改編することにします。その理由はいくつか挙げられており、市当局からの圧力説や新曲が用意できなかったので改編してお茶を濁したのでは、などと推測されています。私は後者の理由がもっともらしく思えますが、それと同時にこれだけの大規模な作品はバッハにとっても初めてのものだっただけに気にいらなかったところも直したい、と思ったのではないでしょうか。改編されたこの「ヨハネ受難曲」は、まったく別の曲と言ってもいいほどに変更されました。これが「第2稿」と呼ばれるものです。詳細に記すと長くなりますので書きませんが、合唱やアリアをそっくり入れ替えたり、新しい楽曲を加えたりもしています。聴いてすぐに驚くのは冒頭の合唱が、後に「マタイ受難曲」第一部の終曲に使用される合唱「人よ、汝の大いなる罪を泣き悲しめ」(調性は違う)に変更されていることです。ですから最初からまったく違った作品に聴こえます。また注目すべきは近年の研究により、これらの変更された合唱やアリアが、実は以前触れた「ヴァイマール受難曲」からの転用ではないか、という点です(もちろんそれを否定する意見も多い)。もしそうだとすると、今後この失われた受難曲の全容を知るうえで、何らかの手がかりになってくるのではないでしょうか。それともう一つ大きな変更は、終曲で通常歌われる簡素なコラールが、カンタータ第23番終曲の長大なコラールに変更されている点です。
バッハは1725年の再演以降も2度この作品を演奏しています。1732年(推定)と最晩年の1749年(4月4日)ですが、これらは現在それぞれ第3稿、第4稿といわれているものです。二つの稿とも第2稿の変更を破棄して、再び第1稿に立ち返っています。何故元のスタイルに戻ったのかはわかりませんが、一部研究者によると「2稿で新たに挿入されたアリアの演奏が困難だった」からではないかとしていますが、そうであればその曲だけ直せば済むことと思います。勝手な推測を許していただけるなら、「同じ曲を2年続けて演奏するのは気がひけたが(バッハの受難曲演奏史上2年続けて同じ曲が演奏されている例は他にない)、さりとて新曲を用意する時間もない。仕方なく曲を大幅に改編して演奏したが、やはり気に入らなかった」ということなのかもしれません。こうして変更された第3稿はもちろん第1稿と全く同じという訳ではなく、ここではNo.33から35のレチタティーヴォとアリア(「マタイ伝」からの引用となる「すると神殿が裂け」からの部分)は器楽のシンフォニアにとってかわり、終曲のコラールも削除されるなど、他にも細かい変更があります。ただこの第3稿の変更部分も楽譜が消失してしまったため、その詳細はわからなくなってしまいました。 そして第4稿ですが、これはほとんど第1稿と変わりません。変更はそれまで使われてきたパート譜を補充する形で行われました。No.9、No.19そしてNo.20の歌詞部分と通奏低音の補強が図られるなど楽器編成が変更されています。変更された歌詞は当然ながらいずれもアリアやアリオーソの自由詩による部分で、変更の理由は小林義武氏によると「その表現があまりにどぎつかったことによる」のではないかということで、特に「19曲と20曲においては、イエスの刺す茨の上に花が咲くという表現や、鞭打たれて血に染まったイエスの背をこの上なく美しい虹に譬えるといった描写が見られ、・・・(中略)・・・どぎつい芸術表現を好んだバロックの人間にとっても度の過ぎたものだった」(小学館バッハ全集第7巻「バッハによる受難曲上演について」)ということになります。
以上少し整理しますと、第1稿、第3稿そして第4稿は細部においては違っているものの大筋ではほぼ同じ形態ということができます。ところが第2稿だけはかなり異質であり、これは別の曲といってもいいほどに改編されています。それではどれがバッハが最終的に意図した決定稿なのか?という問題がおきます。基本的には最後に演奏された第4稿ということになるのでしょうが、歌詞の変更が後述するように本人の意思に反して行われたとすれば、それを決定稿とするのは問題があるように思います。では第3稿か?といえば、変更された部分の資料が残っていないのでこれは除外されなければなりません。つまりそうして考えていくと、結論としてこの「ヨハネ受難曲」には決定稿が存在しない、ということになるのです。
ただ実は第3稿と第4稿の間の1739年に、もう一度バッハはこの曲を上演しようとしたことがわかっています。そのとき後世に保存することを考え自筆の浄書譜を書き始めたのですが、バッハはこれを途中で止めてしまったのです。それは歌詞に関して問題があるとの理由で市の参事会から上演中止の命令が下されたからです。このときバッハは第10曲の途中までスコアの浄書を終えていました。3月17日付(上演の10日前)の市書記官の記録には次のように書かれています。
「いと高貴にして賢明なる市議会の命令について、本官がバッハ氏のもとに赴き、同氏にいつもの許可が下りるまで、同氏が来る聖大金曜日に演奏予定の音楽を演奏できない旨、伝えた。それに対し同氏は以下のように答えた。『恒例のことだったのに。まあ、あれをやっても何の得にもならず、重荷でしかなかったので、こちらとしてはどうでもよい。教会総監督に、演奏を禁じられたことを伝える。歌詞に、問題があったのだとしたら、もう何度も演奏したのに、いまさら何故』[と彼は述べた]」この記録はかなり重要な内容を含んでいると思います。もちろん演奏中止の理由がはっきりしたことはもちろんですが、それ以上にこの文書からは、バッハが既にトーマスカントルとして完全に「ヤル気」をなくしていることが読み取れます。この年バッハは「ヨハネ受難曲」に代わってテレマンの「ブロッケス受難曲」を演奏したのでは?と言われますが(不確定としつつもヴォルフが言及、またグレックナーはテレマンの「至福なる考量」としています)、小林氏はこれはありえないこととしています。理由は以前述べたようにライプツィヒの主要教会で受難オラトリオが演奏されることは考えられないからです。こうして1739年の版は10曲目で終わってしまいましたが、後に残りの部分を弟子が初稿を元に完成させた、といわれています。しかしこれが第○版というように扱われて演奏されることはありません。
(クリストフ・ヴォルフ:「ヨハン・セバスティアン・バッハ ― 学識ある音楽家」
春秋社、秋元里予訳)
「ヨハネ受難曲」において決定稿が存在しないということは上述のとおりですが、それでは「新バッハ全集版」とは何をさすのでしょうか?ここで新バッハ全集版のスコアに書かれたアーサー・メンデルの序文を読んでみます。ところがこの序文を読んでみてもどうしてそうなったのかよくわからないのです。この点についてはわが国のバッハ研究者樋口隆一氏も著書(下記参照)で「実用的ではない」と批判しています。そこで様々な本や資料からどうしてこうなったのか私なりに推論してみました。
まず再び第4稿を考えてみます。4稿において大きな改訂は歌詞にあったわけですが、上述したとおり歌詞はバッハの意思に反して変更されたので、元の歌詞にもどすのが正しいと思わざるを得ません。
次にバッハは上述のように1739年の改訂を途中で止めてしまいましたが、少なくとも10曲目の途中までは本人自筆のスコアが残っているわけです。そして1749年の第4稿ですが、この稿には1739年第10曲までの改訂がパート譜に反映されていなかったので、実際の演奏は細かい部分で1739年稿とは違っていた、とされています。したがって現在一般的に新バッハ全集版といわれる場合、この一度も演奏されることのなかった第10曲までと、それ以降は第4稿のパート譜から作成されたスコアを基にしたものを使用し、第9、19、そして20曲については元の歌詞の方に戻し、そしてスコアの最後に、付録として第1稿、第2稿そして第4稿(変更された歌詞による)の変更された曲を掲載する、という方法をとったのではないかと思います。ですから一般的な演奏は付録を除いた全曲スコアで行われ、特に他の稿を取り入れる場合には「第2稿版」とか「第4稿版」とかと記載することが行われています。また一部楽器の変更について、例えば第19及び20曲では、両方の楽器を併記して演奏者が選択(ヴィオラ・ダモーレか弱音器つきヴァイオリン)できるようにしているのでは。もちろんこのスコアの成立過程について、樋口氏はメンデルの長大な校訂報告書を読まないとわからないとしていますので、私の推論がいかに乱暴なものであるかはわかっていますが。
以上、「ヨハネ受難曲」の初演から再演に至る各稿について書いてきましたが、間違った部分があるかも知れません。またかなり凝縮して書いていますので、理解しにくいところもあると思いますが、ご容赦ください。これらの点についてもっと詳しくお知りになりたい方は、以下の文献を参照されるとよいでしょう。
・樋口隆一:「バッハから広がる世界」(春秋社)
・小林義武:「バッハによる受難曲上演について」(小学館バッハ全集第7巻)
(「バッハとの対話-バッハ研究の最前線」-小学館-にも収録)
・鈴木雅明:「わが魂の安息、おおバッハよ!」(音楽之友社)
2009.08.17 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――12
13. 「ヨハネによる福音書」のこと新約聖書には「マタイによる福音書」、「マルコによる福音書」、「ルカによる福音書」そして「ヨハネによる福音書」の四福音書(以下それぞれ「マタイ伝」「マルコ伝」「ルカ伝」「ヨハネ伝」と記します)があることは、クリスチャンでなくても知っていると思います。ただそれぞれが書かれた順番や、また誰が書いたのか?ということまで知っている人となるとかなり少なくなるでしょう。中にはこれらの福音書は12使徒(注1)の一人が書いたものと思っている方もあるかもしれません。確かに12弟子の中にはマタイもヨハネもいました。しかしながらマルコとかルカという名前はありません。いずれにしろ現在の通説ではこれらはイエスの直接の弟子が書いたものではない、といわれています。また福音書が何故書かれたのか?これも難しい問題です。ここでは神学的な問題を扱う訳ではありませんので詳しく述べませんが、いくつか読んだ本の中から加藤隆さんが書いた「福音書=四つの物語」及び「『新約聖書』の誕生」(講談社選書メチエ)を中心に、他の資料からの記述も含めてごく簡単にご紹介したいと思います。
福音書が何故書かれたのか?加藤氏によれば、まず「イエスが自身の記録を残すことを否定した」ので弟子達もその意思に従って記録は残さなかった、ということになります。イエスは字が書けなかったからだ、という説もあるそうですが、加藤氏はそれは本質的なことではない、としています。ですから新約聖書自体、イエスの意思に反してできた書物ということになります。そしてイエスや弟子達が記録を残さなかったことが、結果として弟子達の権威を高める(直接見、知っているということから)ことになり、イエスの情報を独占することになってしまった、と。こうしたことから「イエスの弟子達を批判して、イエスについての情報を彼らの独占から開放」するために生まれたのが最初の福音書、「マルコ伝」なのです。およそイエスの死後(紀元30年頃)40年が経過しており、書いたのが誰かは不明ですが12弟子の中の更にその弟子にあたる人物ではないか?といわれています。
「マルコ伝」ができると、今度はそれに対する批判が生まれます。そうして次にできたのが「マタイ伝」で、更に「ルカ伝」も同様な理由から生まれました。これら福音書の成立年代は諸説ありますが、自由国民社版「聖書の世界」によると「マルコ伝」が西暦70年頃で、「マタイ伝」「ルカ伝」の両福音書が80年代に書かれた、とされています。12弟子達への批判で思い起こすのは「マタイ受難曲」の「ゲッセマネの祈り」の場面(新バッハ全集版No.16~26)で、弟子達が居眠りをしていてイエスに二度もしかられるシーンがありますが、何とも間の抜けた話で、こうした弟子達へのイエスの怒りは受難の場面だけでなく他の福音書などにも時々見られます。いずれにしろこの三つの福音書は共通点も多く、そのためひとくくりに「共観福音書」と呼ばれています。
一方「ヨハネ伝」(注2)ですが、こちらは「マタイ伝」や「ルカ伝」より更に10年程経過した紀元90年から100年の間に書かれ、「共観福音書」とは内容をかなり異にしています。その違いを一つ一つここで明らかにするには、かなり聖書の解釈に踏み込んでいかなければならず話題がそれてしまいますので、ここでは「反ユダヤ主義」との関連に絞ってお話ししたいと思います。
「マタイ伝」や「ルカ伝」が成立する少し前、パレスチナの地では大きな事件が起きていました。西暦66年、ユダヤ人が殺害されたことが発端となり、ユダヤ過激派が一斉蜂起し、暴動へと発展したのです。ユダヤ属州の総督により首謀者が逮捕・処刑されるに及んで、反乱はパレスチナ地方全土に広がりました。シリアから派遣されたローマ側の軍団も反乱軍によって逆に滅ぼされてしまいます。これを重く見た時の皇帝ネロは、ローマから大挙軍団を派遣し鎮圧に向かわせます。ローマ軍はエルサレム周辺の都市を次々に攻略し、エルサレムは完全に孤立し陥落寸前に陥りました。ところが今度はガリア(ローマの北方)でも反乱が起き、これが引き金となって各地で暴動が発生し、とうとうネロは元老院からも見離され自殺してしまいます(68年)。混乱に陥ったローマは翌年の12月ようやく平定され、皇帝に即位したウェスパシアヌスは息子ティトゥスを司令官として再びエルサレム攻撃を開始します。ユダヤ人も激しい抵抗を見せますが、圧倒的なローマ軍の攻撃の前に、エルサレムは炎上・陥落します。この司令官ティトゥスこそ、後に皇帝となりモーツァルトのオペラに登場することになるのです。エルサレムが陥落した後も各地で散発的に暴動は続きました。最後の砦となったマサダも激しい抵抗を続けましたが、73年ついに陥落、ここにユダヤ戦争(注3)は終結したのでした。ではこのユダヤ戦争がキリスト教にどのような影響を及ぼしたのでしょうか。
ユダヤ教徒がイエスを危険分子として処刑したことは以前触れましたが、それでもその後のキリスト教に対しては寛大で、彼らもキリスト教はユダヤ教の一分派として考えていました。ところがユダヤ戦争の直前、ローマでネロによる史上名高いキリスト教徒迫害事件(西暦64)が起きるに及んでキリスト教徒はユダヤ教徒とは明確に区別され、ユダヤ共同体から分離・独立するようになります。そしてこのユダヤ戦争によりキリスト教も壊滅的な打撃を受けエルサレム教会は完全に消滅してしまったのです。「共観福音書(特に「マタイ伝」と「ルカ伝」)はこうしたユダヤ戦争後の混乱の中でユダヤ教に対するキリスト教の優位を主張するために書かれたといわれています。しかしながら戦後、ユダヤ社会の復興が本格的に始まると、その担い手の中心となったファリサイ派は保守色を強め、公然とキリスト教徒に対する迫害を始めます。その迫害と対立の中で生まれたのがこの「ヨハネによる福音書」なのです。ですからキリスト教は本来「救い」をテーマとした普遍的な広がりを持つ宗教の筈ですが、この「ヨハネ伝」に限って言えば、かなり排他的でユダヤ人に対する敵意を持った記述になっているのです。
ここにもう一つ変った本があります。「主の祈りのユダヤ的背景」(ミルトス出版)という本で、著者はブラッド・ヤングとダヴィッド・ビヴィンという二人のユダヤ人です。エルサレム楽派と呼ばれるグループに属する学者で、一般的な考え方とは違ったユダヤ人という視点からキリスト教を論じています。その第二部「福音書の『ユダヤ人』とは誰のことか」の項を読むと、興味深いデータが載せられています。福音書の記述には「ユダヤ人」という単語が88回出てくるそうですが、その大半がこの「ヨハネ伝」で71回になるそうです。因みに「マタイ伝」では5回しか出てこない、と。では「ヨハネ受難曲」と「マタイ受難曲」ではどうでしょう。皆さんもお手元に両方の対訳をお持ちでしたら比べてみてください。その違いはすぐにわかると思います。「ヨハネ受難曲」では21回出てくるのに対して、「マタイ受難曲」では「ユダヤ人の王」という表現が3回でてくるだけです。本の著者によると、どうしてそうなったのかは、ある言葉を「ユダヤ人」と誤訳してしまったからだ、というのです。本来同じ出来事を書いているのだから、「ヨハネ伝」だけこうした記述になるのはおかしい、と主張します。「ヨハネ伝」は他の福音書と違ってイスラエル(パレスチナ)の地から遠く離れた小アジアで書かれ、そのとき誤って作者がファリサイ人と「ユダイオイ(「ユダ地方の出身者」という意味だそうです)」という言葉を入れ替えてしまい、おまけに後の翻訳者が「ユダイオイ」(ギリシャ語)という語を「ユダヤ人」と誤訳してしまったため、それが後の反ユダヤ主義につながったのだ、というのです。この説の真偽はともかく、すでに2000年近く世界中の人から読まれ現在の聖書が定着してしまっている以上、今更「本当は違うのだ」と言われてみてもどうにもならないように思います。
もう一つ「ヨハネ伝」が他の福音書の記述と違う点は、やや生々しい残酷な表現が見られるところです。これはそのままバッハの受難曲の中にも現れます。福音書第19章31~34節(受難曲ではNo.36)のイエスが息を引き取った後、ユダヤ人の要請で兵士が彼のわき腹を槍で突き刺すシーンです。「マタイ伝」も含め他の福音書にはこのような記述はまったくありません。聖書には以下のように書かれています。
「その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは、安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り降ろすように、ピラトに願い出た。そこで、兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、既に死んでおられたので、足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスのわき腹を刺した。すると、すぐに血と水が流れ出た。・・・」(新共同訳)
この記述はすべてそのまま「ヨハネ受難曲」の中で歌われています。
この章の最後に、それでは「マタイ伝」には「反ユダヤ主義」は存在しないのか?という点について触れておきたいと思います。以前「受難劇」の章で、「マタイ伝」における「血の誓約」と呼ばれる記述についてご紹介しました。それが故にオーバーアマガウの受難劇はユダヤ人からの抗議により変更を余儀なくされたこともご紹介しました。とすれば「マタイ伝」も当然「反ユダヤ的」といわれてしかるべきでしょう。でもこの点についてはかなり議論があるようです。「血の誓約」の記述には「民衆」とか「我々」という言葉はあってもはっきり「ユダヤ人」とは書いていません。この問題についても前回ご紹介した川端純四郎氏がその著書「J.S.バッハ~時代を超えたカントール」の中で、聖書学者ウルリヒ・ルッツ(Ulrich Luz)の説を採り上げて解説しています。それによると、「マタイ伝」はユダヤ人キリスト者の集団(加藤隆氏によれば、「ヘレニスト」(ギリシャ語を母国語とするユダヤ人で、ユダヤ系ギリシャ人とも言われる)と呼ばれるキリスト教徒)から生まれたもので、ファリサイ派との争いによるあくまでもユダヤ教内部の兄弟喧嘩にすぎず、したがってユダヤ人に対する非難も内からのものであった、と。キリスト教が異邦人に広まるにつれ、それが外側からのユダヤ人全体に対する人種的非難へと発展したのだ、というのです。つまりあくまでもその後発展した異邦人キリスト教会が「反ユダヤ主義」を生んだ、という論旨になっています。従って福音書成立当時は別にして、「マタイ伝」もまた「反ユダヤ主義」的性格を持っている、ということになると思います。「ヨハネ伝」ほどではないにしろ。
ではバッハの「ヨハネ受難曲」や「マタイ受難曲」は本当に反ユダヤ的なのでしょうか?これについては次回以降の楽曲にまつわる説明の中で、私自身の考えも含めてお話したいと思います。
(注1) 12使徒の名前は以下のとおりです。
シモン・ペトロとその兄弟アンデレ、ゼベタイの子ヤコブ(大ヤコブ)とその弟ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ(小ヤコブ)、タダイ(「ヤコブの子ユダ」とも呼ばれる)、熱心党のシモン、イスカリオテのユダ(自殺後マティアに代わる)
(注2) 聖書を読んだことのない人でも、「はじめに言葉ありき」という句については知っていると思いますが、その言葉で始まるのがこの「ヨハネによる福音書」です。余談ですが、前掲の「聖書の世界」によると最初に日本語に翻訳された聖書はこの「ヨハネ伝」で、これはキリシタンと呼ばれる時代、日本への布教を目的にシンガポールで刊行(1830~40)されたそうです。そのときの訳は「ハジマリニ カシコイモノゴザル、コノカシコイモノ ゴクラクトトモニゴザル、コノカシコイモノワガゴクラク」だったそうで、何とも愉快な訳です。因みに現在の日本語訳の「言葉」は、もともとギリシャ語ではLogosで、もっと哲学的で深い意味を持っています。
(注3) このときの戦争は「第一次ユダヤ戦争」と呼ばれるもので、その後勢力を盛り返したユダヤ人たちは西暦132年、再び反乱を起こします。これが第二次ユダヤ戦争で、反乱は一時成功し2年半の間エルサレムを中心とする地域はユダヤ人の支配下に置かれました。しかしこれも長つづきせず結局は135年ローマ軍によって鎮圧されてしまいます。その結果、ユダヤ教及びユダヤ社会は徹底的に破壊され、彼らの地は「パレスチナ(ユダヤ人と対立した『ペリシテ人』に因む)」と命名され、同時にユダヤ人たちは世界各地に散っていくことになるのです。ここに「流浪の民」が誕生したのです。
2009.07.27 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――11
12. ヨハネ受難曲と反ユダヤ主義キリストの受難をテーマとする物語が「反ユダヤ主義」につながる危険性については既に今までに述べてきた事柄で十分お解かりいただけていると思いますが、その問題の最大の原因は福音書の記述(これについては次回触れます)にあります。しかし福音書の問題であればすべての受難曲に共通する問題なのですが、特にバッハのヨハネ受難曲との関連で近年この問題をとりあげる学者が出てきています(注1)ので、それについて今回ご紹介したいと思います。
残念ながら日本の音楽学者はこの点について一切口を閉ざしています。「ただ純粋に音楽のことだけ考えていればいいのだ」ということなのかもしれませんが、音楽も常に社会との結びつきの上に成り立っているのですから、それを無視することはできない筈です。是非日本のバッハ研究者と呼ばれる方々からもこの点についての見解を聞いてみたいと思いますが、一人だけ音楽学の立場からではなくキリスト者の立場からこの点について意見を述べている人がいます。川端純四郎さん(注2)という方で、この方はオルガニストでもあり、またバッハ研究や教会音楽についても詳しく、彼の著書「J.S.バッハ~時代を超えたカントール」(日本キリスト教団出版局 2006)は音楽学者とは違った視点からバッハを見つめていて、とてもユニークで面白い本です(バッハの出発点を一人の音楽職人「マイスター」として位置付ける)。その中で彼は「ヨハネ受難曲と反ユダヤ主義」の問題を採り上げています。
まず氏の著作から少し引用させてもらいます。
「近年しきりに論じられている深刻な問題は『反ユダヤ主義』の問題です。《ヨハネ受難曲》は『イエス殺し』の罪をユダヤ人になすりつけることによって『反ユダヤ主義』を増大させて、ついにその道はヒトラーに至った、というのです。『反ユダヤ主義』はキリスト教会最大の汚点です。・・・・中略・・・・当然のことですが、この通念(注:「イエスを殺したのはユダヤ人だ」という)は、毎年の『受難週』に、繰り返し新しく再生産されることになります。聖職者たちが、主イエスを神の子と認めないユダヤ人の『かたくなさ』を説教壇から非難すると、それを聞いて激高した民衆は、シナゴグを襲撃し、ユダヤ人の家に放火し、その財産を奪いました。まことに『受難週』はユダヤ人の受難の時でもあったのです。そして『受難劇』や『受難曲』が、このような『反ユダヤ感情』を増幅することに大きな役割を担ったことも否定できない事実です。」
こう述べたあと、氏は音楽史家ホフマン・アクストヘルム(D. Hoffmann-Axthelm)が指摘する「ヨハネ受難曲」の音楽に見られる反ユダヤ主義について話を進めます。
「ヨハネ受難曲」が論じられる際、必ずといっていいほど「第二部裁判」の場面のシンメトリックな構造が引き合いに出されます。新バッハ全集版第22曲のコラール「汝の捕われにより、神の御子よ」を中心として両端(No.17とNo.26)にコラールを置き、その間に合唱とアリアを前後対称に配置して、なおかつ合唱(トゥルバ)は相対する音楽がそれぞれ同じような音型で作曲されていることから、スメントがそのシンメトリックな構造に着目し、その構造の見事さと、そこに込められた意味について意見を述べたのです(F.スメント:バッハのカンタータ、白水社―バッハ叢書6)。ここで詳しくその内容を述べることはしませんが、そこにはXという文字が隠され、それはキリストというギリシャ名の最初の文字(ChristmasをXmasと書くように)と十字架を意味している、というのです。アクストヘルムはルネサンスからバロックの時代に盛んに用いられた音楽修辞学(注3) を持ち出して、このシンメトリックな構造を「かたくなさ」の音型である、としたのです。「ユダヤ人群衆の合唱に同じ音楽が三組も繰り返されることによって、イエスを神の子として認めないユダヤ人の『かたくなさ』が示されているのだ」と。そして川端氏は言います。「『十字架につけよ』という合唱の恐ろしさに戦慄を覚えたことのある人なら、誰でも納得のいく解釈です。ユダヤ人の『かたくなさ』を、こんなにも強烈に歌うことによって《ヨハネ受難曲》は『反ユダヤ主義』に貢献したのだとアクストヘルムは言います。」と。
そして氏は、「ヨハネ受難曲」中聖句以外に彼が選んだ言葉(レチタティーヴォやアリア)には一切「反ユダヤ」的な語句はないとしつつも、当時のライプツィヒのユダヤ政策に影響され、証拠はないがバッハの心の中にどこか反ユダヤ的意識があったのでは、と推察してもいます。ただライプツィヒに移って一年もしないうちにそうした意識が生まれるのかどうか私は怪しいと思いますが、確かに当時の知識人と呼ばれる多くの人達のなかにも反ユダヤ主義が浸透していたことを考えると、それは十分考えられることではあります。その場合、ライプツィヒのというより、バッハが心の拠りどころとしたルターの影響が大きいでしょう。川端氏は別の箇所でバッハが唯一示した反ユダヤ的感情の具体例をあげています。それはカンタータ第46番「考え見よ、われを襲いしこの痛みに」で、その部分を以下に引用しておきます。
「一回だけセバスチァンは自分の選んだ歌詞で『反ユダヤ主義』をうたったことがあります。それは《カンタータ第46番》です。1723年8月1日の三位一体後第10主日のカンタータです。・・・略・・・この日はルター派教会では「イスラエルの日」として守られ、夕拝ではヨセフスの「エルサレム滅亡」の物語が朗読されてユダヤ人の罪とその罰について説教が行われました。・・・略・・・そしてこの説教が終わると、しばしば会衆によるユダヤ人虐殺が行われたのです。セバスチァンはこの日のカンタータを3曲作っていますが(46番、101番、102番)、エルサレム滅亡を主題にしたのはこの46番だけです。このカンタータの2曲目のテノールアリアには『お前は完全に破壊された方がよかった。お前の中でキリストの敵が今も神を冒涜しているのを耳にするよりは』という歌詞があります。つまり、『昔、キリストを信じなかった罰としてエルサレムは滅びたが、今もエルサレムではユダヤ人たちが神を冒涜している』と言うのです。歌詞作者はヘルビヒという人ですが、それを選んだのはセバスチァンです。ここには過去の出来事との『同時性』が現在のユダヤ人に対する非難として示されています。」
もう一人マルティン・ゲック(Martin Geck 1936-)の指摘もご紹介しておきましょう。彼が2000年のバッハ没後250年を記念して出版した大著「ヨハン・セバスティアン・バッハ」(鳴海史生訳 東京書籍)の中でやはりこの問題に少しですが触れています。彼もまた合唱「十字架につけよ(No.21d)」をとりあげます。彼はこの強い情念に支配されたポリフォニーの傑作をバッハが作るうえで、どこから刺激を得たのか?という疑問から次のように言います。
「ただひとついえるのは、課題の重大さが、バッハのインスピレーションを大いに刺激した、ということである。そうして彼は『十字架につけよ』という一語から、ドラマの中心、さらに《ヨハネ受難曲》の神学上のクライマックスを作り上げた。フーガ形式に近い、すなわち精巧なポリフォニー技法によるものの、決して型どおりではない対位法の中で、受難曲のキーワードが、密集したリズムと鋭い不協和音によってうなり声を発し、感情を煽り、互いに入り乱れ、荒々しい身振りをもって提示される。激しい憎悪をこれほど音楽で生き生きと表現した例は、音楽的にもまれである。もちろんこの書法にも、神学史的背景がないわけではない。バッハの存命中に流布した、ロストックの神学者ハインリヒ・ミュラーによる受難物語の注釈本(注:「福音主義の心の鍵・・・」 1705)を、その代表的なものとして挙げることができる。そこでは『十字架につけよ、の叫び』が『ユダヤ人たちの殺人の歌』とみなされ、こう説明されている。『この世は今日もなお、福音書のユダヤ人と同じように、殺害への凶暴な欲にとりつかれている』。 音楽的に見ると、『十字架につけよ』の合唱は、おそらく反ユダヤ主義的な意味合いを持つ『騒々しい音楽Charivari』の一種とみなすことができよう。」
そして更にここでもシンメトリックな合唱の音型について、バッハは「不誠実さPerfidia」(前記アクストヘルムのところではこれを「かたくなさ」とした)の伝統的音楽表現(修辞学)に立ち返ったのでは、としています。
以上バッハの「ヨハネ受難曲」における反ユダヤ主義との音楽的なかかわりについて書いてきましたが、冒頭にも申し上げたとおりこの問題の最大の原因は「ヨハネ福音書」の記述にありますので、次回その福音書について考察してみたいと思います。
(注1) 本文中に出てくる文献以外にも比較的知られたものとして以下の本があります。
Michael Marissen: Lutheranism, Anti-Judaism, and Bach's St. John Passion:
with an annotated literal translation of the libretto
Oxford University Press(1998) ISBN: 0-19-511471-X
とても英文の本までは余裕がなく今回読むことはできませんでしたが、いずれ読んでみて、必要があればいつかご紹介したいとも思います。
(注2) 川端純四郎
1934年生まれ。東北大学文学部博士課程終了後ドイツのマールブルク大学に留学し、1999年まで東北学院大学文学部でキリスト教学を教える。現在は日本キリスト教団仙台北教会のオルガニストで、また「平和をつくり出す宗教者ネットinみやぎ」の事務局長もつとめ、平和や人権のための運動にも積極的に参加されています。日本キリスト教団讃美歌委員でもあり、著書には本文で紹介した以外に「CD案内 キリスト教音楽の歴史」や「讃美歌21略解」他があります。
(注3) 音楽における修辞学(フィグール)というのは、音楽の表現する内容を聴き手に伝えるために用いる特別な音の使い方や音型のことをいいます。古典派以降こうした作曲技法が廃れてしまったため我々現代人にはちょっとわかりにくい手法です。
2009.07.06 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――10
11. バッハの受難曲1723年5月22日、バッハは家族と共に馬車でライプツィヒに着任しました。彼に課せられた任務は聖トーマス学校のカントル兼4つの教会(聖ニコライ、聖トーマス、新教会-後に聖マタイ教会に改名、そして聖ペテロ教会の四つで後の二教会は現存しません)の音楽監督を務めることですが、これはつまりライプツィヒ市の音楽監督を意味します。その翌週の日曜日(30日)には就任後最初のカンタータ(BWV75)を聖ニコライ教会で演奏しライプツィヒでのデビューを果たしたのです。ここから56曲に及ぶカンタータの第一年巻が始まりました。
バッハはほとんど日曜毎に演奏する礼拝用カンタータの作曲と準備に追われ、最初の一年はそれに忙殺されていたようですが、それでもその合間に最初の大規模な声楽曲マニフィカト(7月の聖母マリアの祝日のために書かれた?)を書いたりもしています。これはその年の降誕祭にクリスマスの讃美歌4曲を挿入して再演されてもいます。そして年が明けて受難週を向かえ、いよいよ聖週間最大のイベント聖金曜日の礼拝のための受難曲を準備します。こうして1724年4月7日ヨハネ受難曲が演奏されたのですが、ヨハネの話に入る前にバッハの受難曲について少し触れておきたいと思います。
私達が現在耳にするバッハの受難曲はマタイとヨハネの2曲だけです。しかしながら以前別のコラムでもご紹介したとおり、息子のカール・フィリップ・エマヌエルと弟子のアグリーコラが記したごく短いものですが最初のバッハ伝ともいえる「故人略伝」には次のような記述があります。
「故バッハの出版されていない作品には、およそ以下のようなものがある。以上の記述から長らく音楽学者の間で論争が交わされているのが「五つの受難曲」という問題です。バッハには受難曲が五曲あったというのです。
(1) 五年分の日曜=祭日用教会作品[カンタータ]
(2) 多数のオラトーリオ、ミサ曲、マニフィカト。若干のサンクトゥス、音楽劇、セレナーデ、誕生日、
命名日、葬儀のための音楽、婚礼ミサ曲、それにいくつかの滑稽な歌曲。
(3) 五つの受難曲。うち一曲は二重合唱のためのもの。
(4) 若干の二重合唱用のモテット。
・・・・・・・」 (バッハ叢書第10巻:資料集―酒田健一訳 白水社より)
先にも触れたように一般的に私達が知っているバッハの受難曲はヨハネとマタイの2曲だけですが、もう一曲譜面が消失してしまって歌詞だけ残されている受難曲があります。それはマルコ受難曲(BWV247)です。そしてこれは1731年の聖金曜日(3月23日)にトーマス教会で演奏されたこともわかっています。その初演時の楽譜は失われてしまい、いくつか他の人が筆写した不完全な楽譜があったようですが、それも1945年の大戦の戦火の中で焼失してしまい、今や残された楽譜は全くなくなってしまったのです。ピカンダーによる残されたテキストを頼りに、何人かのバッハ研究家がコラールやアリアをパロディの手法から手がかりを得てかなりの部分復元したりもしています。CDも何種類か出ていますので、いずれこのマルコ受難曲もとりあげて見たいとおもいますが、ここではここまでにしておきます。
マルコ受難曲を含めると、ここにバッハの受難曲としては3曲が存在したことになります。ではあとの2作品はどうでしょう。ヨハネ、マタイ、マルコとくれば当然ルカ受難曲があってもおかしくありません。1730年の聖金曜日(4月7日)にニコライ教会でルカ受難曲(注1)が演奏されたと推定されていますが、実はこのルカ受難曲(BWV246)の作者は不明とされています。このルカ受難曲は、19世紀の音楽学者でバッハ研究家として名高いフィリップ・シュピッタ (Philipp Spitta 1841-1894)がバッハの若い頃の真作であるとして旧全集に含めたことでバッハの作品とかつてはされましたが、それ以前からメンデルスゾーンは偽作として位置付けていましたし、ブラームスも同様にバッハの作品ではないと主張していました。20世紀以降、受難曲スコアの前半をバッハが、そして後半を息子のカール・フィリップ・エマヌエルが筆写したことが判明したことから、「筆写した人間が数え間違えることはない」という理由で五受難曲中の一曲とすることはありえないということになりました。したがってもし5曲が正しければこれ以外の作品を指していたことになります。偽作とされるルカ受難曲にもしご興味のある方は(注)にあげたCDを聴いてみて下さい。コラールなどいかにもバッハ風の装いをしてはいますが、感動とは程遠い音楽です。現在では同時代人の誰か、あるいはバッハ一族の誰か、の作品ではと言われています。ただこのルカ受難曲で面白い事実を一つご紹介しておきましょう。
1966年、わが国の音楽学者服部幸三と角倉一朗の両氏が、鎌倉にある前田利建氏の邸宅で未発見のバッハ自筆譜を発見し、大きな話題となりました。それは第二次大戦前にロンドンに外交官として赴任していた前田利為公爵が同地で入手して日本に持ち帰り、前田育徳会のコレクションに収められていたものです。この自筆譜こそバッハが1743~46年の間に再演したルカ受難曲(BWV246)の中の1曲(第一部終曲)で、そのときバッハが書き直したものだったのです。作者不詳の原曲は繰り返しを含む12小節からなるテノール(ペトロ)によるコラールAus der Tiefe rufe ich(深き淵より、我汝に呼ばわる)と通奏低音の曲ですが、バッハはそれに弦楽伴奏を加え15小節の曲に編曲しています。この楽譜も以前カイザーのマルコ受難曲でご紹介した新バッハ全集のスコアにBWV246/40aとして掲載されています。それにしてもバッハの自筆譜が日本で発見されるというのは、日本人のバッハ好きが世界に証明されたようなものですが、喜ぶべきか悲しむべきか、ちょっと複雑な気持ちにさせられます。
もうひとつ近年様々に議論されているものに「ヴァイマール受難曲」もしくは「ゴータ受難曲」と呼ばれる受難曲があります。これはバッハの没後百年(1850)に出版されたヒルゲンフェルト(Carl Ludwig Hilgenfeldt)の「バッハ伝」に、1717年(ヴァイマール最後の年)にバッハが受難曲を作曲したという記述があること、またヴァイマール近郊の町ゴータ宮廷から受難曲の作曲に対する謝礼と思われる報酬がバッハに支払われていること、更にはヨハネ受難曲やマタイ受難曲の一部の曲の起源がヴァイマール時代に遡ること、などから現在ではその受難曲が存在した可能性は極めて高い、と思われています。前章でご紹介したように、バッハはカイザーのマルコ受難曲をすでに演奏していた事実があり、その意味からすればこれは十分考えられることです。
ではそれがどんな受難曲だったのか、音楽学者の意見を少しご紹介しておきましょう。 まずフリードリヒ・スメント(Friedrich Smend 1893-1980)はその古典的著書「バッハの教会カンタータ(白水社 バッハ叢書第6巻)(1947/48)」第2章で「単一合唱のためのマタイ受難曲」であったと推定しています。その根拠は、バッハの自筆譜の数箇所にわざわざ「福音書記者マタイによる・・・二つの合唱のための受難曲」と書いている(注2)ことから、それは単一合唱のための受難曲と区別しようとしたのだ、というものです。学者というものはちょっとした言葉の使い方からとてつもない仮説を膨らませるものだ、と感心しますが、いずれにしろこの説が今まで有力で、わが国の礒山氏もこの説をとっています。 次にアンドレアス・グレックナー(Andreas Glöckner)は「小学館バッハ全集第8巻」に寄せた論文「バッハの失われた受難曲について」のなかで、この受難曲は「受難オラトリオ」であった可能性が高いと述べています。その根拠として、バッハはライプツィヒで受難曲を何度か再演するのに、この曲については再演せず、個々の曲を他の受難曲やカンタータに転用しているだけなので、これはライプツィヒの教会では演奏できない形態だったのではないか?というものです。演奏できない形態とは、それは聖句をもたない自由詩による受難オラトリオ、ということになります。クリストフ・ヴォルフは「受難オラトリオ」とは限定していませんが、ゴータの宮廷教会で音楽による受難劇を上演するように求められ、聖金曜日に上演した、としています。その際「上演予定の受難劇のための、製本された歌詞の小冊子が20冊用意されていた」とされていますが、現存していないためその歌詞についての手掛かりはありません。ただもしそうだとすると、その部数から考えてごく限られた宮廷貴族のために書かれたものではないでしょうか?その他にもこのヴァイマール受難曲が受難オラトリオだった、とする説をとる学者が最近多いようで、近年ではこちらの方が説得力を持っているように思います。
一方、最初から五曲の受難曲など存在しなかった、という人もいます。シュヴァイツァーは彼の歴史的名著「バッハ」(1908)の中で、「バッハの受難曲は五曲ではなく、もともと4曲しか存在しなかったのだ」としています。しかも面白いのはその4曲目の受難曲は、1725年ピカンダー(ヘンリーツィ)が刊行した「聖木曜日および聖金曜日用にオラトリオとして作れる、受難し給うイエスについての教化的なる想い」という詩に、バッハが作曲した受難オラトリオだ、というものです。シュヴァイツァーは次のように言っています。「ピカンダーの公にした他の教会音楽用歌詞は、ほとんどすべてバッハのために書いたものであるから、バッハがこの受難オラトリオをピカンダーに注文し、当然作曲もしたということは確実と見ていい」(白水社。中巻。浅井真男、内垣啓一、杉山好 共訳) と。同時にシュヴァイツアーはこの歌詞を「考えられる限りもっともひどいもの」とも書いています。ただ現代の研究成果からするとこれはちょっとおかしなことになります。1725年に演奏された受難曲はヨハネ受難曲(第2稿)ですし、前述したようにこの時期ライプツィヒの主要教会(ニコライ、トーマス)で受難オラトリオが演奏されることは考えられないからです。シュヴァイツァーはヨハネの再演を1727年としていますが、これは現在ではマタイ受難曲の初演が行われた年とされています。いずれにしろこのシュヴァイツアーの説は20世紀の初めに書かれたもので、今となっては古く、現代においてこれが論じられることはないようです。
もう一人反対論者をご紹介しておきましょう。わが国の学者杉山好氏は著書「聖書の音楽家 バッハ」(音楽之友社 2000)の中で、カンタータ五年分とか受難曲五曲というのは、「故人略伝」の筆者達がつじつまあわせのために大まかな記述をしたのではないか、というものです。杉山氏は著書の中でいわゆる「数の象徴」論を展開しており、ここでも5=3(三位一体)+2(人)で、これは「神にして人なるキリスト」の象徴数でバッハが大切に意義付けていた数なので、著者達が「5の数でまとめた」のだと。「バッハと数」の問題はよく好んでとりあげられますが、私自身は好きになれません。確かにいくつかの真実はあると思いますが、何でも数学的にバッハの曲を分析するのはこじつけが過ぎるかと。
以上バッハの受難曲について考察してきましたが、私自身はいつか5曲目の受難曲が発見されることを願いたいと思います。学者でもない人間が偉そうなことはいえませんが、ヴァイマール受難曲は恐らくヴォルフ説が正しいのだろうと、そして5曲目の受難曲は?と問われれば全く根拠はありませんが、ヨハネ、マタイ、マルコがあるのですから、それはやはり「ルカ受難曲」(BWV246とは別の)なのではないか?と。
(注1) ルカ受難曲のCDは以下のとおり。
福音史家:クルト・エクイルツ イエス: フランツ・ヴィマー クリスティアーネ・ソレル(ソプラノ)
マウラ・モレイラ(アルト) アカデミー室内合唱団
ゲオルゲ・バラティ指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団
Sarx records SXAM 2026-2(2枚組)
このCDいつ頃録音されたのかデータが書いてありませんが、録音状態からみて1960年前後のように思われます。ともかく演奏、録音共によくありません。当然ながら第一部最後のコラールは旧全集版によっています。
ところでもう一枚ルカ受難曲の珍品中の珍品をご紹介しておきましょう。それはカール・オルフが編曲したといわれるものです。もっともオルフが編曲した楽譜は大戦で焼失してしまったため、彼がバッハのヴォーカル・スコアに書き込みを入れたメモをもとにヤン・イラーセクという作曲家が再作曲したものです。BWV246からはコラールやアリアをかなりカットし、全体にコンパクトにしたものになっています。ただ曲調はオルフ風に大幅に書きかえられ、編成も金管楽器を含む2管編成に通奏低音、多彩な打楽器となり、ちょっと驚かされます。CDは以下のとおりです。
福音史家:マーク・クリアー イエス:フリオ・ザナージ ピラト:ウルリク・コルド
ペトロ:スティーヴン・クロナウァー ボニ・プエリ児童合唱団
ダグラス・ボストック指揮 ミュンヘン交響楽団&オラトリオ合唱団
キング・インターナショナル KKCC-4304
(注2) これはマタイ受難曲のアーノンクール盤CD(2000年録音のWPCS-10652/4)で確かめることができます。このCDの3枚目はCDエクストラになっていてバッハの自筆譜が全曲データとして収められていますので、その扉の部分にはっきり "für Zwei Chore"と、また第二部冒頭にも"a due cori"と書かれているのがわかります。
2009.06.15 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――9
10. ルター以後のドイツにおける反ユダヤ主義とライプツィヒ第7章でルターの罪に触れ、彼がユダヤ人への対処法について提唱した言葉がその後のドイツ・ルター派正統主義に浸透していった、と書きましたが、事実彼らは住み慣れた町から追い出されていくのです。ここで再びレオン・ポリアコフの本に戻ってみたいと思います。
彼の「反ユダヤ主義の歴史第1巻」(前掲)によると、農民戦争(1524~25)の時再びユダヤ人の虐殺が行われるのですが、そのとき一部財力にものを言わせて権力にすりよって彼らの支援者となった「宮廷ユダヤ人」と呼ばれる特権的な上層階級が生まれ、彼らがユダヤ人社会の規律を自ら作ったり、またドイツ自身30年戦争の痛手から貴族社会に強大な権力がなくなったこともあって、反ユダヤ主義は一時的に以前よりひどいものではなくなった、というようなことが書かれています(追放運動も1614年のフランクフルトにおけるゲットー襲撃が最後)。この穏やかな状態は20世紀のヒトラーの前まで続いたそうですが、ただそれはあからさまな追放や虐殺がなかったという意味にすぎず、一方ではより陰湿なものになっていったとも書かれています。いくつかの例が記されていますので、ここで少しだけご紹介しておきましょう。
まず、フランクフルトでは「①ユダヤ人章の着用 ②キリスト教徒の下僕を雇うことの禁止 ③目的もなく街中をぶらつかないこと ③二人連れで歩かない ④一部の場所への立ち入り禁止 ⑤市場で買い物をする場合はキリスト教徒が終わってから・・」などが定められ、これは後にヒトラーが模倣することになります。同様なものはハンブルクでも行われ、ウイーンでは1726年に法律により「結婚できるのは長男のみ」といった制度まででき、これはその後ボヘミア、モラヴィア、プロイセン、アルザスなどへどんどん拡大されていったのです。こうしたことからユダヤ人の多く(特に若い人)はハンガリーやポーランドなどの東欧圏に流れていきました。時代は少し下りますが、童話作家で知られるグリム兄弟(19世紀)は著書「ドイツ語辞典」のなかでユダヤ人を次の様に定義しました。「彼らの数々の好ましからざる特性のなかでも強調されるのは、利得ずくであること、あらゆる面で暴利を貪ることに加えて、その身の不潔さである。・・・・」などと書いており、その先はここに紹介するのも憚るほどの汚い罵倒が続きます。それでもこの時代はユダヤ人にとって平和な時代だった?のでしょうか。ではバッハが移り住むライプツィヒはどうだったのでしょう。
以前トーマスカントルのコラムを書いたとき、ライプツィヒの成り立ちと発展について少し触れました。ライプツィヒがヨーロッパの交通の要衝にあったこと、そして書籍文化が栄えたこと、などをご紹介しましたが、実はライプツィヒにおけるもっとも大きな産業は交易上の地の利を生かした見本市だったのです。この見本市のおかげで、あの壊滅的な打撃を受けた30年戦争(1618~48)後もライプツィヒはいち早く復興することができたのです。
ライプツィヒにおける見本市は新年、復活祭そして9月のミカエル祭の年3回、それぞれ約3週間にわたって開かれ、その間この都市には世界中から商人が集まり、国際都市として大いに賑わっていました。ゲヴァントハウス・オーケストラとして知られる「ゲヴァントハウス」はこうした見本市から生まれた「織物商の館」を意味する言葉ですし、そのほか毛皮、貴金属、絹をはじめタバコやコーヒー、そして変わった(?)ものではトルコ人の干し首まで売られたといいます。もちろん商人以外にも楽士や大道芸人も集まり、華やかな国際見本市が開かれたのでした。こうした中で、商人といえばすぐに思いつくのがシェイクスピアの「ヴェニスの商人」でも知られるユダヤ人です。
見本市が開かれると、ユダヤ人は主にポーランドやウクライナ、ロシアなどの東欧圏から続々と集まってくるようになり、年々その数を増していきました。当然地元の商人との間で諍いも起きるようになり、1682年ザクセン選帝侯のヨハン・ゲオルク3世(1647~91)は「ユダヤ人規程」を制定し、ユダヤ人の流入や商業権を制限することにしました。それにより市の参事会は以後ユダヤ商人に対して長期滞在権を制限したりしたのですが、商業活動が活発になるにつれ高額の税と引き換えに市内の割り当てられた地域(ゲットー)に住むことを許されるユダヤ人も増えてきたのです。そうするとそこにユダヤ共同体ができ、ユダヤ教徒のためのシナゴーグ(集会所)も作られるようになったのです。
さてここで話題をライプツィヒの聖週間の音楽へと移しましょう。前章で18世紀初頭北ドイツを中心に受難オラトリオが盛んに演奏されるようになったことをご紹介しましたが、ここライプツィヒは同じプロテスタントの中でもかなり保守的な町で、復活祭の46日前から始まる四旬節に入ると断食が始まり、宴席や合奏などは禁止され、教会では晩課の礼拝で受難記事の朗誦が行われ、伝統的に棕櫚の日曜(復活祭の1週間前)の朝の礼拝ではルターの友人でコラール作者としても知られるヨハン・ヴァルター(Johann Walter 1496-1570)が作曲した時代遅れの応唱風受難曲「マタイ受難曲」が、そして聖金曜日には「ヨハネ受難曲」が朗誦されていました。トーマス学校の生徒の一人が福音史家を、助祭がイエスを、そして他の人物は別の生徒がそれぞれ担当して朗誦し、トゥルバ(民衆)のみが合唱で歌われたのです。すでに他の都市ではもっと新しいスタイルの受難曲が演奏されていたこともあって、ザクセン公国のドレスデン宮廷はライプツィヒに対し新しい受難曲をとりいれるよう、圧力をかけていたといいます。これにより市の参事会はしぶしぶそれを受け入れ、市の公式な教会ではない「新教会」で演奏することを許可したのです。こうして1717年聖金曜日の朝の礼拝で演奏されたのが、テレマンの「ブロッケス受難曲」でした。これには大勢の市民が押し寄せたことから、当時のトーマスカントル、クーナウ(バッハの前任者)は何としてもトーマス教会でもこの新しいスタイルの受難曲を演奏したいと考え、当局に訴え、市会議員の後押しも得てその説得に成功したのでした。しかし保守的な教会会議は朝の礼拝には頑としてそれを認めず、晩課の礼拝のみに許可したのでした。かくして1721年の聖金曜日、クーナウの「マルコ受難曲」がトーマス教会で演奏されたのでした。この曲は現在断片しか残されていませんが、クリストフ・ヴォルフは「バッハにとって価値ある模範を確立した」と述べています。バッハの受難曲同様牧師の説教をはさんでその前後に演奏する二部構成からなっていますが、バッハの曲に比べるととても質素な作品だったといわれています。この受難曲は翌年聖ニコライ教会で、またその次の年には聖トーマス教会で演奏され、こうして一年ごとに二つの教会で交互に演奏する習慣が出来上がり、同時に聖週間のクライマックスを飾る礼拝にもなったのでした。以前から健康に不安を抱えていたクーナウは1722年6月5日亡くなりました。そしてそのトーマスカントルの後任として最終的に選ばれたのがヨハン・セバスティアン・バッハでした。1723年4月22日、テレマンとグラウプナーの獲得に失敗した市の参事会はやむなくバッハを後任として選んだのです。ここからバッハのライプツィヒにおける輝かしい経歴が始まり、受難曲やカンタータをはじめとする素晴らしい音楽が次々に生まれてくるのですが、バッハが受難曲を書くにあたって、何故新しいスタイルの「受難オラトリオ」ではなく、一昔前の「オラトリオ受難曲」を書いたのか、というのはこうした市の古い体質によるところが大きかったのだと思います。オペラ的なオラトリオを嫌っていたライプツィヒ市は、聖書の語句によらない受難オラトリオではトーマス教会やニコライ教会での演奏を認めなかったでしょう。
2009.05.25 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――8
9. バッハの受難曲誕生前夜前章でバッハの時代へと続く受難曲の歴史について簡単に記しましたが、今回は18世紀、いよいよバッハの受難曲が生まれるあたりのことを書いてみたいと思います。
バッハは1685年3月21日、中部ドイツのアイゼナハに生まれましたが、父ヨハン・アンブロージウスが亡くなった1695年、長兄ヨハン・クリストフに引き取られてオールドルフに移住します。その少年時代、貧しい中月明かりの下、兄に隠れてこっそり巨匠たちの鍵盤音楽を写譜していて叱られた逸話は有名ですが、当時から音楽へのなみなみならぬ関心を示していた証拠でしょう。1700年15歳のとき生涯の友となるエールトマン(Georg Erdmann 1682-1732)を連れ立って北ドイツのハンザ都市リューネブルクへと旅立ったのです。彼はその地の聖ミヒャエル教会の聖歌隊に採用されたのでした。もちろんまだ15歳ですから教会付属の学校に通いながらの音楽生活でしたが、多感な時期でもあり彼はここで計り知れないほどの音楽を吸収したのではないでしょうか。リューネブルクの聖ヨハネ教会には北ドイツ・オルガン楽派の巨匠ゲオルク・ベーム(Georg Böhm 1661-1733)がおり、直接彼から音楽を学んだという記録はない(注1)ようですが、当然彼からオルガンや教会音楽について多くを学び取ったと思います。バッハはこのリューネブルクで17歳まで3年ほど過ごしますがその間ハンブルクにも何度か足を運び、当時オルガン音楽の大家といわれたカタリーナ教会のヤン・アダムス・ラインケン(Jan Adams Reinken 1623-1722)のオルガンを聴いたりもしていたのです。アルンシュタットに職を得た後も、はるばるリューベックに旅(1705)して北ドイツ・オルガン楽派最大の巨匠ブクステフーデ(Dietrich Buxtehude 1637頃-1707)の音楽や彼が聖マリア教会でクリスマス前に主催する「夕べの音楽Abendmusiken」を聴いたりしています。こうして彼は人生の多感な時期、様々な教会音楽に接し貪欲にそれらを吸収していきますが、中には当然受難曲も入っていたと思います。
さてオラトリオ受難曲が成立しドイツで多くの作品が生まれるようになると、そこに今度は新しいタイプの受難曲が誕生します。それは聖書の言葉をそのまま引用するのではなく、少し当世風にアレンジした語句に基づくレチタティーヴォやアリア、合唱で構成される受難物語の台本が登場するようになります。そうしたもののなかでよく知られているのがフーノルト(Christian Friedrich Hunold 1681-1721)とブロッケス(Barthold Heinrich Brockes 1680-1747)の作詞による受難物語で、前者は「血にまみれて死にゆくイエス」、そして後者は「世の罪のために苦しみ、死にゆくイエス」の二作品で、こうした台本に基づく受難曲をオラトリオ受難曲と区別して「受難オラトリオ」と呼んでいます。ちょっとややこしいですが、要は聖書の原文を使っているかいないかの違いです。受難オラトリオの方が自由に音楽が書ける、という利点があります。フーノルトの詩に曲をつけた作曲家としてはラインハルト・カイザー(Reinhard Keiser 1674-1739)がおり、またブロッケスの詩に作曲したのは前記カイザーのほか、テレマン(Georg Philipp Telemann 1681-1767)、ヘンデル(Georg Friedrich Händel 1685-1759)、マッテゾン(Johann Mattheson 1681-1764)そしてファッシュ(Johann Friedrich Fasch 1688-1758)らがいます。ここで少しヘンデルの「ブロッケス受難曲」のCDをご紹介しておきましょう。
ヘンデル:ブロッケス受難曲
福音史家: エルンスト・エフリガー イエス: テオ・アダム(バス) ピラト: ヤコブ・シュテンプフリ ユダ: ポール・エスウッド
シオン: マリア・シュターダー マリア: エッダ・モーザー 他
アウグスト・ヴェンツィンガー指揮 バーゼル・スコラ・カントールム レーゲンスブルク大聖堂合唱団
ARCHIV 463 644-2(3枚組)
この曲が作られたのは1716年で、カイザーやテレマンの同じ作品もほぼ同時期に作られ、彼らはお互いよく知っていたこともあって、マッテゾン(1718)の作品も含め競作したのではないか、とも言われています。ヘンデルはこの作品をロンドンで仕上げ郵便でハンブルクに送ったことが知られています。但し初演は1719年まで待たなければなりませんでした。ヘンデルの数多いオラトリオ作品の中で唯一ドイツ的なオラトリオ作品とされており、彼がドイツ語で書いた最後の作品でもあります。ヘンデルの作品には珍しくコラールも使用されています。冒頭のシンフォニアは作品3-2の合奏協奏曲第3楽章の異稿ですが、受難曲で書いたものを後に流用したのでしょう。17世紀の教会音楽に比べるといかにも盛期バロックといった華やかさが感じられ、随所に美しい旋律(特に第34、35曲のアリア)もありますが、それでもこの曲調で3時間を超える長さを一気に聴くのは、正直ちょっとつらいところもあります。1722年にテレマンがこの曲を再演していますが、何といっても注目すべきはバッハの再演でしょう。バッハは晩年になって妻のアンナ・マグダレーナの協力を得てこの作品をすべて書き写し、1749年頃これを演奏しています(注2)。但し、聖書の語句によらない作品だったためトーマス、ニコライの両教会以外の場所で行われたのでは、と小林義武氏は推論しています(小学館「バッハ全集7」)。またバッハは彼の最初の受難曲(残されたものの中では)となるヨハネ受難曲について、聖書の語句以外の自由詩にあたる部分ではこのブロッケスの詩を基に書き直したものを使用したとされています。
この「受難オラトリオ」というジャンルはその後大いにドイツで流行しますが、この流れに逆らったのがバッハだったという訳です。ですからバッハの受難曲そのものは当時の流行からすればもはや時代遅れになっていたのですが、では現代においてどちらが優れているのか、いや音楽として私たちが楽しむことができるのか、というと答えは明白だと思います。受難オラトリオはバッハの死後も大いに流行し、舞台を教会から劇場へと移します。特にグラウン (Carl Heinrich Graun 1704-59)の「イエスの死 Der Tod Jesu 1755」(注3)など現在ではほとんど知られていませんが、18世紀後半から19世紀にかけて今の「ヘンデル:メサイア」と同じような状況で盛んに演奏された、といわれています。
さてもう一方の古いといわれる「オラトリオ受難曲」ですが、こちらにもバッハの受難曲へとつながる重要な作品が生まれています。それは受難オラトリオでも触れたラインハルト・カイザーによる「マルコ受難曲」です。これもCDで聴くことができますので、それをご紹介しながら話を進めます。
ラインハルト・カイザー: マルコ受難曲
福音史家: ゲオルク・イェルデン イエス: ウルリヒ・ギルゲン ジュリエット・ビーゼ(ソプラノ) マルグリット・コンラート(アルト)
シャルル・ヴュイシャール(カウンターテナー) トーニ・クラウザー(テノール)
イェルク・エーヴァルト・デーラー指揮ベルン合奏団 ラングナウ教会合唱団 ツヴァイジメン混声合唱団
Claves Records(キング・インターナショナル) CD 50-9223/24
カイザーはバッハの少し前に主にハンブルクで活躍したドイツの重要な作曲家の一人です。特にオペラの分野での活躍は目覚しく生涯に100曲以上の作品を残しています。同時にオラトリオや受難曲などの宗教作品もかなり作曲しています。このマルコ受難曲は二部構成で全50曲からなりますが、福音史家をはじめとするレチタティ-ヴォ、アリアそして合唱から構成され、ヘンデルの作品のような華やかさはありませんが、いかにもドイツ的といっていいような格調ある劇的な音楽となっています。コラールの使用は5曲(終曲の途中に挿入されるコラールも含む)しかありませんが、第5曲のゲッセマネの祈りの場面で歌われるアルブレヒト作のコラール「Was mein Gott will, das gscheh allzeit(神の御心がつねに成就しますように-礒山 雅訳)」(旋律はクローダン・ド・セルミジ)は後にバッハがマタイ受難曲の第25曲(新全集版)で使用しており、同じく第一部終曲(裁判の場面)のヴァイス作のコラール第8節「O hilf, Christe, Gottes Sohn (おお助けてください、キリストよ、神の御子よ-同氏訳)」はヨハネ受難曲の第二部37曲で、またその第1節をヨハネ第二部の冒頭合唱に使用しています(ただこれは第二部の第26曲とともに後にバッハが挿入したコラールです)。面白いのはマタイの代名詞とも言われるゲルハルトのコラール「血潮したたる、主のみかしら」の第9節「Wenn ich einmal soll scheiden (いつか私が世を去るとき-同)」(第10節も歌われる)で、カイザーはイエスが「エリ、エリ、ラマ、サバクタニ」と言って息絶えたあとにこの曲を挿入しており、バッハもマタイ受難曲でこれとまったく同じことをしているのです。ただカイザーはこのコラールを合唱ではなくアルトのソロで歌わせています。この作品がいつ作曲されたか正確なデータがないのですが、フランツ・キーンベルガーという人のライナーノーツによれば1717年頃ということですが、あとにご紹介する事実からこれは明らかに間違っています。こう書かれた原因はどうやらニューグローブにありそうです。ニューグローブのカイザーの項の作品表に「マルコ受難曲 17年?」という表記があり、原文をあたらないとわかりませんが、こんな表記がそう書かせたのかも知れません(またこれを受難オラトリオとしているのも?)。いろいろ調べてみるとどうやら1707年以前とするのが正しいようですが、判然としません。
この受難曲、バッハは2度演奏しています。最初の演奏はヴァイマール時代で、小林氏の説に従えば1713年頃となります。小林氏も紹介しているように、バッハはこれを演奏する際コラールを2曲追加していますが、どうやらそれはバッハの作ではないそうです。新バッハ全集版のスコア(Neue Bach AusgabeⅡ, 9-Lateinische Kirchenmusik, Passionen-Zweifelhaftes, Bearbeitungen)に収録されており、そこには"Weimar vor 1712"と書かれています。つまり1712年以前ということになります。どこで何のために演奏されたのかはわかっていません。そして2度目にこれをとりあげたのはライプツィヒ時代の1726年、聖ニコライ教会における聖金曜日の礼拝においてでした。このときヴァイマール時代に追加した2曲のコラールを改編して演奏したのですが、この2曲のうちの第一部終曲はどうやらバッハの作らしく同スコアにはBWV1084の作品番号が与えられています。またこのとき同時にもう一曲「So gehst du nun, mein Jesu, hin(かくして、わがイエスよ、汝は今や行きぬ-小林義武訳)、BWV500a」というコラールを作曲して追加しています。このCDでは新たに追加されたコラールは含まれていませんが、この改編された2曲のコラールを含むライプツィヒでのヴァージョンに基づいて演奏されています。そのほかオーケストラの使用法などでもバッハとの類似性が指摘されており、この作品がバッハに大きな影響を与えたことは間違いないでしょう。
バッハはヴァイマール時代に受難曲を1曲書いたのではといわれていますが、こうした事実からも十分それは考えられることではないでしょうか?ここまで来るともうバッハの受難曲が誕生するのは時間の問題だったのです。長くなってしまいましたので今週はここまでにしておきます。
(注1) キリスト者で教会音楽やバッハの研究でも知られる川端純四郎氏の「J.S.バッハ~時代を超えたカントール」を読みますと、近年の研究でバッハとベームが直接師弟関係にあったことを示すバッハの筆写譜が見つかった、と紹介されています。
(注2) 1749年ごろというのは小林義武氏の説。礒山氏は1746~47年頃としています。
(注3) グラウンの「イエスの死」は以下のCDで聴くことができます。
シギスヴァルト・クイケン指揮 ラ・プティット・バンド エクス・テンポーレ
ウータ・シュワーベ(ソプラノ) インゲ・ヴァン・デ・ケルクホーヴェ(ソプラノ) クリストフ・ゲンツ(テノール) 他
hyperion CDA67446
2009.05.15 (金) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――7
8. バッハへの道ここでひとまずユダヤ問題から離れて、バッハに至る受難曲の道のりについて手元にあるCDを交えて簡単にご紹介したいと思います。
第4章で「モノフォニー受難曲」が生まれるまでを記しましたが、ルネサンスの時代に入るとやがてポリフォニー(多声音楽)による受難曲が現れます。そのもっとも古い例(1430~40頃、ルカ、マタイ受難曲-断片)がイギリスに見られ、写本が今も大英博物館に保管されているそうです。イタリアやフランドルでなくイギリスというのがちょっと面白いですが、ルネサンスの巨匠ギョーム・デュファイ(Guillaume Dufay 1400頃~74)が現れる以前、大陸はちょうど音楽史の谷間ともいえる時代で、その当時はダンスタブル(John Dunstable 1380頃~1453)やジョン・ベネット(John Benet 15世紀初)などによりイギリスの教会音楽が興隆を極めていましたので、そうした影響かもしれません。ただその受難曲も結局大陸には全く影響を及ぼさず、そこで途切れてしまったようです。またその少し後の時代と思われますが、南ドイツ(フュッセンの教会)でも群衆などトゥルバの部分を3声の合唱で歌う楽譜(理論書)が見つかっています。
15世紀も後半になると受難曲の舞台はイタリアに移ります。北イタリア、フェラーラの宮廷礼拝堂にマタイ受難曲とヨハネ受難曲の2曲の楽譜が残されていて、これらは多声と単声(福音史家やイエスなど)が交互に現れることから「応唱風受難曲(「コラール受難曲」とも呼ばれる)」と呼ばれています。このタイプの受難曲はその後ネーデルランド楽派最後の巨匠オルランド・ディ・ラッソ (Orlando di Lasso 1532-94)(オルランドゥス・ラッスス Orlandus Lassus とも呼ばれる)やスペインの大作曲家トマス・ルイス・デ・ビクトリア(Thomas Luis de Victoria 1548-1611)のマタイ受難曲へと受け継がれていきます。
16世紀にはいってポリフォニー全盛になると、エヴァンゲリストの朗唱を含めて多声化するものまで現れ、これは「通作受難曲(注1)」(または「モテット風受難曲」)と呼ばれます。その最も古い作品がパリの作曲家ロングヴァル(Antoine de Longueval 1507-22宮廷礼拝堂、生没年不詳)の「マタイ受難曲」とされていますが、これはかつてヴィッテンベルクのゲオルク・ラウ(初代トーマスカントルでもあった)が誤ってヤコプ・オブレヒト(Jacob Obrecht 1457頃-1505)の作品として出版し、そのため古い音楽史の本にはオブレヒトの作品として紹介されています。通作受難曲ですが、他の福音書からの記述も採り入れていることから後に述べる「調和受難曲」の要素も含んでいます。多声部分は定旋律に和音をつけただけですべてが同じリズム(譜割り)で進行するファルソボルドーネと呼ばれる様式で書かれています。ロングヴァルの受難曲がヴィッテンベルクで出版されたことからこの通作受難曲はその後主にドイツで発展しますが、イタリアでもいくつか作られ、その代表的なものがチプリアーノ・デ・ローレ(Cypriano de Rore 1516-65)の「ヨハネ受難曲」です。この曲はパウル・ファン・ネーヴェル指揮ウェルガス・アンサンブルの演奏(CD: deutsche harmonia mundi BVCD-12)で聴くことができます。当時イタリアではトリエント公会議に代表される反宗教改革の新しい波が押し寄せており、そのため世俗的な要素や華美な様式を避け純粋なポリフォニーを追求することが求められ、この作品もその例外ではありません。全体的に禁欲的な厳しいスタイルに貫かれ、そのなかに美しいポリフォニーがちりばめられている、といった印象です。
やがて受難曲の舞台は主にイタリアからドイツへと移り、宗教改革と相まって大いに発展します。通作受難曲の代表的なものとしてシュトゥットガルトの楽長レヒナー(Leonhard Lechner 1553頃-1606、ラッソの弟子)のドイツ語による「ヨハネ受難曲」(1594)があり、これはラインハルト・カンムラー指揮アウグスブルク・ドムジングクナーベン室内合唱団の演奏(CD: deutsche harmonia mundi 05472 77472 2)で聴くことができます。但し輸入CDの限定盤で"BAROQUE ESPRIT"と題されたBox Set中の一枚です。30分にも満たない短い曲で、全編アカペラによる四声の合唱で歌われます。そのほかやがてマルコ、マタイ、ルカそしてヨハネの四福音書を混ぜ合わせたストーリーで構成する「調和受難曲」と呼ばれるものまで現れ、後にバッハもヨハネ受難曲で一部この手法を採り入れています。
17世紀バロックの時代になると、受難曲はほとんどドイツでしか見られなくなります。1631年デマンツィウス (Johannes Christoph Demantius 1567-1643)が書いたヨハネ受難曲以降、通作受難曲は劇的表現を好む大衆から支持されなくなり急速に姿を消していきます。そこに登場するのが「ドイツ音楽の父」と謳われるハインリヒ・シュッツ晩年の作品ルカ(1653頃)、ヨハネ(1666頃)そしてマタイ(1666)の三受難曲です。これらは形式的に「応唱風受難曲」に属し、冒頭は伝統的な導入句による「これは聖なる福音史家○○○による主イエス・キリスト受難の物語」という合唱(上述したCDもすべてこの合唱で始まる)で始まり、合唱はもちろんエヴァンゲリストやイエスもすべてアカペラで歌われます。アカペラであるが故に古いスタイルという印象を与えますが、前にも述べたように「聖週間中は器楽演奏を慎むべし」という厳格な宗教上の理由(特にシュッツの仕えたドレスデン宮廷では)によるもので、その音楽は決して古いものではなく、地味ながら味わい深く、まさに「ドイツ音楽の父」の名に相応しい素晴しい音楽です。シュッツは上記三作品の他に1645年頃に「十字架上の七つの言葉」という受難曲を書いており、これは聖書の4福音書の言葉から構成される「調和受難曲」で、音楽も器楽による伴奏はもちろん単独のシンフォニア(五声)も2曲挿入されています。マタイ受難曲のCDについては第3章で触れましたので、そちらをご参照ください。ここでは「ルカ受難曲」と「十字架上の七つの言葉」の2曲が収録されているCDをご紹介しておきましょう。
「十字架上の七つの言葉(SWV478)/ルカ受難曲(SWV480)」
イルムガルト・ヤコバイト(ソプラノ)、ベルト・ヴァン・トホフ(テノール)、マックス・ヴァン・エグモント&クリストフ・ルンゲ(バリトン)、ジャック・ヴィリ
ゼク(バス) ハンブルク・モンテヴェルディ合唱団
ユルゲン・ユルゲンス指揮 レオンハルト合奏団 TELDEC WPCS-22031
「十字架上の七つの言葉」とはよく知られた「エリ、エリ、ラマ、サバクタニ(わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか)」や「渇く」「成し遂げられたEs ist vollbracht」他、文字通りイエスが十字架上で発した七つの言葉を題材とした受難物語で、後にハイドンもオラトリオを作曲しています。全体にもの静かで悲しげな音楽ですが、ヴィオールの合奏やオルガンをはじめとする通奏低音にのって歌われる美しい歌声がとても感動的です。器楽を伴うことからこの作品はドレスデン宮廷の礼拝では使用されなかったと考えられています。このCDでは2曲のシンフォニアもヴィオールの合奏によって演奏されますが、フランスの音楽学者ロジェ・テラールはこの作品について、正確な楽器編成が記載されていなく、この二つのシンフォニアは本来「当時の習慣に従って金管楽器による五重奏で演奏すべき」と言っています。短い作品の中に素晴らしい音楽が凝縮されていて、シュッツの受難曲に興味を持たれた方はまずこれを聴いてみるといいでしょう。ルカ受難曲はマタイ受難曲ほどの大曲ではありませんが、シュッツの受難曲の中ではもっとも優しさに満ちた曲と言われています。そしてこの応唱風受難曲からやがてバッハの作品へと連なる「オラトリオ受難曲」が生まれます。
17世紀半ばになると、北ドイツ、ハンザ都市の作曲家達により受難曲の新時代が開かれます。彼らは声楽だけでなく器楽による演奏も交え、また聖書による言葉だけでなく自由詩やコラール(讃美歌)を受難曲に挿入しました。これが「オラトリオ受難曲」と呼ばれるものです。レチタティーヴォを含むソロ、合唱、器楽がそれぞれ重要な要素を構成して対比(コンチェルタート様式)し、劇的な表現を伴って様式的にオラトリオ(注2)に近いものになったのです。その最初の作品はハンブルクのトマス・ゼレ(Thomas Selle 1599-1663)が1640年代に書いた「マタイ」「ヨハネ」の両受難曲とされています。1642年の「マタイ」では弦と通奏低音が、また翌年の「ヨハネ」ではさらに管楽器のファゴットが加えられるなど、器楽パートの充実が図られます。コラールや大規模な編成(ソロ、二重合唱、器楽)による「インテルメディウム」なども置き、オラトリオへの接近を示しています。その後、ヨハン・タイレ(Johann Theile 1646-1724、シュッツの弟子でローゼンミュラー亡き後ヴォルフェンビュッテルの宮廷楽長となる)のマタイ受難曲(1673)、ツェレのキューンハウゼン(Johannes Georg K?hnhausen ?-1714)の同じマタイ受難曲(1700頃)などが続き、いよいよ18世紀バッハの時代へと移っていきます。
この章を閉じる前に、一言だけイタリアについても触れておきます。受難曲の作曲がほとんどドイツを中心に行われたことは確かですが、ではイタリアでは全く忘れられてしまったのか?というとそうでもないのです。確かに数は少ないのですが、何曲かは作曲されており、なかでもアレッサンドロ・スカルラッティ(Alessandro Scarlatti 1660-1725)の「ヨハネ受難曲(ヨハネによる我らが主イエス・キリストの受難の物語)」は比較的よく知られており、これはCD(注3)でも聴くことができます。これも独立した器楽パートを持ち、オラトリオ受難曲に分類される作品です。ライナーノーツによればスカルラッティのごく初期の作品とされていますが、ニューグローブでは1700年頃と書かれています。演奏にはおよそ1時間を要する大曲ですが、器楽の独立したパートは主に合唱のときに用いられ、福音史家や他のレチタティーヴォはほとんど通奏低音のみで演奏されます。そしてアリアは1曲もなく、また自由詩なども一切使われず聖書の言葉だけによるきわめて珍しい作品になっています。福音史家もここではテノールではなくアルト(カウンターテナー)で歌われます。カトリック圏の作品なので同時代のドイツの受難曲ほどの劇的な音楽ではありませんが、これはこれでしっとりとしたいい作品だと思います。
この章で書いた受難曲の歴史についてはかなり途中を省略して書いていますので、詳しくお知りになりたい方は、礒山 雅さんの「マタイ受難曲」(東京書籍)や金澤正剛さんの「キリスト教と音楽~ヨーロッパ音楽の源流を訪ねて」(音楽之友社)などをお読みになるといいでしょう。
(注1) 「通作」とは、聖書からの歌詞が全曲を通じてアカペラの合唱で作曲されていることを意味しています。
(注2) 「オラトリオ」とは?と始めますと、これまた長く、迷宮に陥ってしまいますので止めますが、ごく簡単に記しておきますと、そもそも「オラトリオ」とは「小さな祈祷所」を意味するところから始まり、それが集会所となって発展し、さらにそこで賛歌が歌われるようになり、そこで歌われる音楽を「オラトリオ」と呼ぶようになった、と言われています(異論もある)。バロックのモノディやコンチェルト様式と結びつき、更にカリッシミやスタラデッラなどの作品により発展し、最終的に次のような要素を伴った音楽を「オラトリオ」と呼んでいます。
①宗教的な題材をもとにした物語性のある叙事的な音楽。
②アリア、レチタティーヴォ、合唱などによる複数の音楽で構成される。
となりますが、乱暴な言い方をすると「演技や衣装を伴わない宗教的な題材によるオペラ」といってもいいかもしれません。カンタータとの違いはオラトリオの方が規模が大きい、ということでしょうか。オラトリオはいつか別のテーマで触れてみたいと思います。
(注3) アレッサンドロ・スカルラッティ: ヨハネ受難曲
エヴァンゲリスト:ルネ・ヤコブス、 イエス:クルト・ヴィトマー、 ピラト:グラハム・プシー、
バーゼル・マドリガリステン、バーゼル・スコラ・カントールム弦楽合奏団
deutsche harmonia mundi BVCD-38189
2009.04.28 (火) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――6
7. キリスト教による反ユダヤ主義とルターの罪前章でヒトラーとナチスによるホロコーストについて触れましたが、実はそうしたユダヤ人に対する迫害は何も彼らの専売特許ではなく、実に長い時代にわたってヨーロッパで脈々と受け継がれてきた歴史の果てだった、ということを最近になって知りました。それは一番はじめに書いたトーマスカントルの物語でルターの宗教改革について調べていたことがきっかけでした。
受難劇の話から時代は更に遡ります。キリスト教がユダヤ教から分離する形で成立する頃(紀元1世紀)、当初はイエスのようにキリスト教徒がユダヤ人から迫害されていました。しかしその迫害の主役がユダヤ人からローマ皇帝へと代わって激しさを増すに従い、逆に信徒の数を増やし、やがて313年皇帝コンスタンティヌスによって公認され、これによってキリスト教は世界宗教への道を一挙に加速させることになります。こうなると今度はユダヤ人を「神殺しの下手人」として迫害するようになるのです。
ここにレオン・ポリアコフ(Leon Poliakov)という人が書いた「反ユダヤ主義の歴史」(筑摩書房、菅野堅治訳)という本があります。全5巻からなり各々が5~600ページにも及ぶ膨大な著作で、とてもこれを全部読破する程の余裕はありませんが、その第1巻が古代から17世紀頃までのヨーロッパにおける反ユダヤ主義を扱っています。ここに書かれている内容は恐らく過去に、そして現在でもタブーとされているような事柄かもしれません。今回はその本を中心にいかにヨーロッパでユダヤ人が虐待されてきたか、という点について触れてみたいと思います。
ポリアコフによると、歴史上最初の大規模なユダヤ人虐殺は十字軍の遠征の際に起こった、とされています。十字軍について私たちが教えられたことは、「イスラム(セルジュク・トルコ)に占領された聖地イェルサレムを奪還するために11世紀から13世紀にわたってキリスト教国によって組織された遠征軍」、ということでした。しかしそうした表の史実とは裏腹に、歴史の本には載っていませんが、彼らは行く先々で異教徒を虐殺していったのです。もちろん全部隊がそうだったという訳ではありません。中にはまともな軍隊もあったようですが、特にひどかったのがフランス王国のギョウム・ル・シャルパンティエとドイツ(当時は神聖ローマ帝国)のエーミヒョによってそれぞれ組織された軍隊だったそうで、なかでもエーミヒョによる残虐な行為が克明に記されています。
1096年(第1回遠征)5月3日、エーミヒョによって組織された遠征軍はマンハイム近郊の村シュパイアー(古い町並みが今も残る美しい町でかつて私も一度訪れたことがあります)に入り、ユダヤ人に改宗を迫ります。改宗に応じないと見るや虐殺の行動に出ますが、ここは村の司教の計らいで11人が殺されただけで終わりました。しかしこれが全て事の発端だったのです。彼らは奇妙なことにイェルサレムとは正反対の方角、つまりライン川を下って北に進みます。そして5月25日ヴォルムスに入りここでもユダヤ人に「洗礼か死か」と迫ります。ここでまず800人のユダヤ人が虐殺されます。事件はその二日後マインツに移りますが、その様子について本には次のように書かれています。
「エーミヒョとその一味は、謀議の末、日の出ととともに、つるはしと槍をもってユダヤ人たちに襲撃をかけた。[・・・]錠をこじ開け、門を突き破って押し入り、七百人もの人々を殺害した。ユダヤ人たちの方でも防御を試みたが、武力で彼らをはるかに凌ぐ敵勢を前にしてはすべてが無駄だった。女たちも同じようにして虐殺された。子どもたちも男女に関わりなく、みな剣の刃にかけられた。ユダヤ人たちは、キリスト教徒の一群が敵として武装し、自分たちと、そして年端のゆかぬ子供たちにも襲いかかってくるのを見るにおよんで、剣先を自分たち自身に向けた。つまり、同宗の仲間、妻、子供、姉妹に剣をふるい、自分たちのあいだで殺し合ったのである。言語に絶する光景である。母親たちは、割礼を受けていない者の手にかかって殺されるぐらいなら、身内で殺し合った方がましであると考え、みずから剣を抜き、乳飲み子の喉を掻き切った。この残虐きわまりない虐殺を免れたユダヤ人は数えるほどしかいなかった。何人かは洗礼を受け入れたが、それはキリスト信仰への愛のためであるよりは、死に対する恐怖によるものであった。」以後、ケルンやモーゼル河畔の町トリアーなどでもこうした事件が報告されています。そして十字軍は約200年のあいだに8回の遠征が行われましたが、その度にこのような事件が繰り返されたのです。ポリアコフは次のように結論付けています。
「中世ヨーロッパが大いなる信仰の動きに煽られるたびに、また、キリスト教徒が神への愛をかかげて未知なるものとの対面を迫られるたびに、ユダヤ人に対する憎悪の火があちらこちらで燃え上がるのであった。キリスト教徒の敬虔心が飛翔し、行動のうちに渇きを癒そうとする際に、決まってユダヤ人の境遇が悪化するという図式が出来上がってしまったのである。」この本ではその後の反ユダヤ主義について延々と様々な角度から実例が紹介されていきますが、このあたりで止めておきましょう。いずれにしろキリスト教によるユダヤ迫害は歴史の裏側で続けられていくのです。
16世紀になって、ローマ・カトリックのキリスト教支配に敢然と立ち向かったのがマルティン・ルターであった(注1)ことは以前にも書いたとおりです。彼はこのユダヤ人問題についても彼らを擁護してローマ・カトリックと対立します。1521年ローマ教皇から破門されたルターを神聖ローマ帝国皇帝カール5世がヴォルムスに喚問し、世に名高い「ヴォルムス国会」が開かれます。この内容については触れませんがご興味のある方は「ルターと宗教改革」(成瀬 治、盛文堂新光社)他の本をお読みください。ちょっとしたサスペンスのように緊迫感が伝わってきます。そのヴォルムス国会の期間中ルターは宿に訪ねてきたユダヤ人と討論し、それを基に「イエスはユダヤ人として生まれた」という小冊子を書きます。その中で彼は次のように言います。
「われらが愚者、すなわち教皇党と司教たち、ソフィストと聖職者たちが、ユダヤ人に対してあまりといえばあまりの振る舞いをしてきたため、心正しきキリスト者の方ではいっそのことみずからユダヤ人になってしまいたいと思うほどである。私がユダヤ人であったとしても、みずからキリスト教徒になるぐらいならばいっそ豚になったほうがましだと考えたにちがいない。ほかでもない、これらの愚か者とうすのろのロバどもがキリスト信仰を牛耳り、それを教え諭そうとしているからである。彼らはユダヤ人を人間ではなく犬のように扱い、迫害を加え続けてきた。ユダヤ人とは、われらの主が血を分けた縁者、兄弟であったにもかかわらずである。」これで終わっていれば彼は真に英雄になれたかもしれません。しかし彼がユダヤ人を擁護した理由は、彼が彼らを容易に改宗できる、と考えていたからであり、その後改宗させることがいかに困難であるかを悟った時、ルターは一転して反ユダヤ主義の先頭に立つことになるのです。ルターが晩年に書いた反ユダヤ主義に関する著作は、ヒトラーに利用されたりした結果今日では出版されることがないようですが、前記ポリアコフの本に少し紹介されています。ルターは晩年「ユダヤ人とその虚言について」(1542)「聖なるみ名とキリストの血筋について」「シェム・ハメホラス(口にするまでもない名前)について」といった反ユダヤの小冊子(注2)をたてつづけに出版しますが、これらの中でヒトラー顔負けの罵詈雑言をユダヤ人に対して浴びせます。
「というのも、ユダヤ人を改宗させることは悪魔を改宗させるのと同じくらい困難な業だからである。ユダヤ人とその心は、棒のように、石のように、鉄のように、悪魔の心と同じぐらい固く強ばっている。要するに、彼らは地獄の火を運命づけられた悪魔の末裔なのである。・・・中略・・・彼らの目からすれば呪われた異教徒(ゴイ)にすぎないこの私は、彼らがいかにしてこのような巧妙な議論を展開する力を手にしたのか理解しかねている。もちろんその理由として以下のようないきさつが考えられないわけではない。イスカリオテのユダが首吊り自殺をした時、そのはらわたが破れ、中身がすっかり外にぶち撒かれてしまった。その時、ユダヤ人どもは、使いの者に銀の大皿と金の水差しを持たせて現場に走らせ、ほかの金品と同時にユダの小便を採取させたのかもしれない。そしてこの糞尿を飲み食いし、それによって現在のような鋭い眼力を得るにいたったのではないか・・・・」彼のユダヤ人に対する汚い言葉はまだまだ続きますが、最終的に彼は「ユダヤ人のシナゴーグを焼き払うこと、彼らの書物を押収すること、彼らの様式に則った神への祈祷を禁じること、彼らを労働に従事させること、あるいは、より望ましいこととして、諸侯が自領から彼らを追放すること・・・」等々を提唱するのです。私がこうした問題を今回敢えてご紹介したのは、何も興味本位からではなく、これがその後のドイツにおけるルター派正統主義教会内部に深く浸透していくことになるからです。
(注1) 宗教改革というとルターばかりがクローズアップされますが、その約100年前にボヘミアのヤン・フス(Jan Hus 1369-1415)がそもそも起こした運動であることを忘れてはなりません。ルターはヴォルムス国会の論戦に負けて命からがらヴァルトブルク城に逃げ込んで難を逃れましたが、フスはカトリック教会によって破門され異端者として火刑に処されます。そのときの反乱軍の様子をスメタナは連作交響詩「わが祖国」の中で描いています。
(注2) これらの冊子はルターの存命中に2~3版増刷されますが、ほどなくして廃棄処分とされ、以後長らく陽の目をみることはなかったようです。19世紀になってルターの全集が刊行される際収録され、そして20世紀ヒトラー政権になっていくつか出版されるようになり、一般の人の目に触れるようになった、と言われています。日本で全訳があるか図書館などでも探してみましたが、今のところ見つかっていません。1994年アメリカのルーテル教会は公式にこの文書を拒絶し、更にその世界連盟もこれを破棄しています。
2009.04.14 (火) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――5
6. ヴァルプルギスの夜 (注1)1934年このオーバーアマガウは、受難劇の上演からちょうど300年という記念の年にあたり、その祝いの行事で沸き立っていました。入場料を安くし、鉄道運賃も割引されるなどし、この300周年の上演(第33回)では観客数44万人、上演回数84回という記録的な公演となったのです。しかしそれ以上に注目すべきは、時代を反映してまさにファナティックといえるほど異様な受難劇になっていたことです。
当時のドイツを考えてみましょう。第一次世界大戦(1914-18)に破れたドイツは多額の賠償金負担を求められ、おまけに世界恐慌も重なって失業者が溢れ、国内は疲弊しきっていました。国民の不満は高まり、その不満を肥やしにするかのようにどんどん大きくなっていったのがナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)です。1932年の大統領選でヒトラーはヒンデンブルクと争って敗れますが、37%という高い得票を得ました。さらにその直後の選挙でナチスはとうとう比較第一党になったのです。これによりますます勢いを得たヒトラーとナチスは倒閣運動を起こし、1933年1月とうとう首相に就任してヒトラー内閣を誕生させたのです。新政府は当時すでに人気のあったこの受難劇のポスターに「ドイツはあなたを呼んでいる」と刷り込ませ反ユダヤ主義の宣伝に利用します。
1934年8月2日、大統領ヒンデンブルクが死去するとヒトラーは自ら法律を制定し大統領と首相の職務を合体させ、その承認を得るべく国民投票を呼びかけます。そして直ちにこのオーバーアマガウに乗り込みます。劇場に入るや観客は総立ちになり、「ハイル!ハイル!」の歓呼の大合唱で迎えられたのです。その直後の国民投票では90%近い得票を得て信任され、ここに「総統」が誕生したのです。
その年に演じられた受難劇の様子は、カール・クラウス(Karl Kraus 1874-1936)が晩年に書いた「第三のワルプルギスの夜」という本に少し紹介されています。
「・・・すでにバイロイトは、政府が招待券を買い集めるといった奇妙な開幕式を必要としているのに、オーバーアマガウの受難劇のほうは一体どうなるのだろう?ここでは観光と、よりよき信念のあいだに、ある悲劇的な矛盾葛藤が口を開けてしまっていた。使徒に変装する民宿の主人達は国家社会主義者になったということだが、かれらはユダヤタイプの役を演じなくてはならないために、良心の呵責に耐えねばならぬ (注2) 。・・・中略・・・演ずるものたちに関しては、《キリストは青い目のブロンドの男で上衣にハーケンクロイツをつけていればよい》こと、またキリストに忠実な使徒たちはアーリア的ゲルマン的タイプでなくてはならぬこと、一方ユダは《はっきりとユダヤタイプ》としての演技をしなくてはならぬことが指示された。それはゲッペルス宣伝相が自己犠牲の精神をもってそのための労苦を引き受けたところの、ひとつの改革であった。・・・」(佐藤康彦、武田昌一、高木久雄 訳 法政大学出版局)ヒトラーとナチスが以後ホロコーストと呼ばれるユダヤ人大量虐殺への道に進んでいったことは今更説明するまでもありません。
ここでようやく問題が明らかになったと思いますが、聖書の受難の物語の背景には常にこうした危うさを孕んでいる、ということなのです。「イエス・キリストはユダヤ人に殺された」、これは動かしがたい事実です。しかしながらイエス・キリストもまたユダヤ人なのです。クリスチャンでない人から見れば、これはユダヤ人という一つの民族の中で起きた不幸な出来事(ユダヤ教を批判し社会不安を煽る政治犯としてイエスは殺された)でしかないのですが、そこに宗教が入ってきて問題を複雑にしてしまった、と言ったらちょっと乱暴でしょうか?このあたりは次章で更に検証してみたいと思います。
さて終戦を迎えたオーバーアマガウでは村人の半数近くがナチ党員だったとも言われ、この受難劇は存亡の危機に立たされます。しかし村人の熱意と努力により復活し、1950年、あの1934年以来となる34回目の上演が行われました。このときも首相のアデナウアーやアイゼンハワーをはじめとする連合国代表団などが列席しています。またデドラーの音楽は一部オイゲン・パプストによって書き直されています。ただ戦後ここに新たな問題が生じることになったのです。
第二次世界大戦後、列強の後押しを得てユダヤ民族にとって悲願であったイスラエルがパレスチナの地に建国されます。やがて彼らの発言力も強さを増し、これにアメリカのユダヤ人団体なども加わって20世紀後半になると、彼らはこの受難劇に反撃を加えたのです。彼らは台本に書かれている「その血の責任は我々と子孫にある」(いわゆる「血の誓約」)という台詞を問題視し、「これを削れ!」と言い出したのです。これはマタイ受難曲にもでてくる有名な言葉で、「マタイによる福音書」には次のように書かれています(第27章)。
23節 ピラトは、「いったいどんな悪事を働いたというのか」と言ったが、群衆はますます激しく、「十こうなると事は「一地方の受難劇対ユダヤ」という構図ではもはやなくなり、キリスト教(この地方はカトリック)全体にかかわる問題としてクローズアップされてきたのです。上記の台詞をめぐってオーバーアマガウ自身でもまたヴァチカンでも真剣な取り組みが行われ、受難劇の新しいあり方も模索されるようになりました。確かに問題となった台詞 (注3) はマタイによる福音書にしか書かれておらず、他のマルコ、ルカ、そしてヨハネによる福音書には同じ場面でもこうした言葉は使われていません。この受難劇事態が「マタイ受難劇」ではないのですから、台詞の変更は可能な筈です(バッハの「マタイ」ではそういう訳にいきませんが)。でも問題は台詞だけではないでしょう。台詞をヤリ玉にあげたのは単なる口実に過ぎません。
字架につけろ」と叫び続けた。
24節 ピラトは、それ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持
って来させ、群衆の前で手を洗って言った。「この人の血について、わたしには責任がない。
お前達の問題だ。」
25節 民はこぞって答えた。「その血の責任は、我々と子孫にある。」
26節 そこで、ピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから、十字架につけるために引き渡した。
(「新約聖書」新共同訳より)
その後幾度か改革されてきましたが、2000年に行われた前回の上演でとうとう彼らはこの台詞を削除しました。しかしながらユダヤ人団体(この上演に招待されていた)はそれにも満足せず、今度は「ユダヤ教の聖職者が悪役に描かれている」と言い出したとか。このあたり、今でも戦後処理をめぐって日本が近隣の諸国からたたかれる構図と何やらダブって見えてきます。また実はこうした状況を2000年の8月NHKが特集番組として放送していました。タイトルは「NHKスペシャル11 アルプス山麓 祈りの大舞台~360年守り続けた村の誓い~ドイツ オーバーアマガウ村」というもので、番組の紹介文は次のように書いています。
「ドイツ・バイエルン州にあるアルプス山麓の村オーバーアマガウ。今年この村に、世界中から50万人が、10年に一度のキリスト受難劇を見に訪れる。360年以上の伝統を持つ受難劇は、すべて村人の手で行われてきた。しかし、村人が大切にしてきたこの受難劇は、ヒトラーによってユダヤ人迫害に利用されていたため、今日までユダヤの人々から激しい批判を浴び、戦後存続の危機にひんしていた。受難劇の改革に向け奮闘する村の人びとの姿と、戦後初めて果たされた村人とユダヤ人との対話を描く。」残念ながらこの番組BS Hiで放送されたので私は見ていません。何人かご覧になった方々の感想がインターネットで公開されており、それを読みますと明らかにユダヤ人グループの態度に不快感を覚えているようです。
こうした人種や宗教に絡む問題をたやすく解決することは難しいでしょう。しかしどんな宗教も本来「平等」とか「博愛」を求めているのですから、ゆっくり話し合いを重ねていけば解決の糸口をみつけることは可能なのではないでしょうか。この受難劇についてはまだまだいろいろ書きたいことはありますが、話が別の方向にいってしまいますのでこのあたりで終わりにします。そしてこの熱い受難劇のシーズンがいよいよ来年(2010)に迫ってきました。次回はどんな上演になるのでしょう。チケットの前売りが始まったとのニユースも届いています。私も一度観てみたい、と今思っています。
(注1) 「ヴァルプルギスの夜」はゲーテの「ファウスト」に登場する魔女達の春を待つ祭りで4月30日から5月1日にかけて繰り広げられる馬鹿騒ぎ。南ドイツには実際にこうした悪ふざけの風習が残っているとか。更にヒトラーは意図的にこの日(4月30日)を選んで自殺したとも言われています。また魔女達の祭りはブロッケン山で行われたそうで、この山は日本でもアルプスなどの高山で時折見られる「ブロッケン現象」発祥の山としても知られています。
(注2) この受難劇の上演では出演者のメーキャップが許されないそうで、そのために出演者は何年も前から役作りに励み、ユダヤ人を演じる人はその人物になりきる必要があり、あごひげを伸ばしたりしなければならないとか。そうした背景を知るとここに書かれた様子はより理解しやすいでしょう。ですから今でもその時期に町を歩くと、イエス風の人、ユダ風の人、使徒のような風貌の人など、様々な人物に会えるそうです。
(注3) この「血の誓約」の言葉に関して、富山鹿島町教会の藤掛牧師の旅行記(インターネット上に公開されている)の中で次のような一文が書かれていますのでそれをご紹介しておきます。
「出版されている『台本』の『後書き』として、著名な新約聖書学者ルドルフ・ペシュが短い論説を書いている。ペシュは、この言葉(その血の責任は我々と子孫とにある)は、キリストの受難の責任をユダヤ人に帰し、反ユダヤ主義を正当化するようなものではなくて、むしろ、キリストの受難によって罪のゆるしをうけ、救いにあずかる全ての者、即ちキリスト者、教会こそが、イエスの死に対する責任を負っているのだ、と語る。そして、キリスト教会がそのことを正しく理解せず、ユダヤ人を迫害してきたことは、教会の最大の罪であったと語る。そして、その罪と、それによって引き起こされたユダヤ人虐殺の事実を、おおい隠してしまうのではなく、しっかりと見つめていくために、あの言葉を残しておく意味があるのだ、と語るのである。」
2009.04.06 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――4
5. オーバーアマガウの受難劇1987年の7月、私はあるピアニストの録音で南ドイツに向かいました。ミュンヘンに到着してすぐに彼女とカメラマンにおちあい、プロモーション写真やアートワークの撮影などのため一路ミュンヘンからノイシュヴァンシュタイン城へと車を走らせました。針路を南にとりミュンヘン郊外を抜けると、すぐにあの狂王ルートヴィヒ2世が謎の死を遂げたことで知られるシュタルンベルク湖畔に出ます。更に南下を続け一時間ほども走ったでしょうか、車は小さな町に入りました。するとGasthofと書かれた建物が目に飛び込んできました。ホテルというよりは民宿あるいはペンションとでもいったほうが適切だと思いますが、何故今でもそれをよく覚えているのかというとその壁に大きくきれいな宗教的なフレスコ画が書かれていたからです。そんな家がいくつかあったように記憶していますが、車はあっという間に通り過ぎてしまい、特にそれ以外町の印象は残っていませんでした。その町がオーバーアマガウだったということを知ったのはつい最近のことです。このオーバーアマガウで今ではドイツ最古のイヴェントといわれる受難劇が10年に一度約半年間にわたって盛大に上演され、世界中から多くの見物客を集めているのです。
この受難劇の成り立ちは、様々な読み物から要約するとざっと以下のようなものです。1632年、あのドイツ30年戦争の最中、オーバーバイエルンと呼ばれるこの一帯はスウェーデン軍に蹂躙されて荒廃し、彼らが去った後付近一帯にペストが猛威をふるいます。オーバーアマガウの村ではこの疫病から村人を守るため、村の入口に見張りを立てるなどして外部からの侵入を厳しく防いできました。ところが翌年(1633)のある日、外に出稼ぎに出ていた村人の一人(名をカスパール・シスラーという)が、家族のことが心配になり暗闇に紛れて山の方から侵入し、帰ってきてしまったのです。彼は翌日ペストで死んでしまい、とうとうこの村は瞬く間にペストの猛威にさらされることになったのです。記録によると半年の間に村人の20%の人が亡くなった、と言われています。村人達はどうしたらこの災いから逃れることができるのか考え、そこで出した結論がこの受難劇の上演だったのです。
村人は「これから未来永劫、10年に一度受難劇の上演をする」という誓いを神に立てたのです。つまりこれは村人が神と交わした契約ということになります。この約束があって後この村からペストの脅威はなくなった、といわれています。そして1634年のペンテコステ(聖霊降臨祭)の日、彼らはペストで亡くなった人たちの墓のある墓地にしつらえた舞台でこの受難劇を上演しました。
こうしてそれ以後オーバーアマガウで受難劇が上演されることになったのですが、ただこの受難劇も突然現れたわけではなく、おそらく中世の時代から細々と行われてきた典礼劇が背景にあったと考えるのが自然だと思います。そしてこの受難劇も最初の墓地での上演は別にして、それからしばらくは教会内で行われていたことが推察されます。
オーバーアマガウの受難劇の上演は周辺の町や村にも影響を及ぼし、以後バイエルンからオーストリア地方の各地で流行するようになりました。ただ18世紀の後半にこれらの地方では受難劇の上演が禁止される事態が起きます。おそらくはキリストの受難を劇で演じることに対する批判から禁止されたのでしょう。このオーバーアマガウでも一時的に中断があった(1770)ようですが、1780年にはこの地の受難劇だけが特別に許可され、以後現在まで彼らの約束は守られているのです。そしてその上演は会を重ねるごとに観客の数を増し、そうなると場所は教会から野外へと移り、しかも上演回数もどんどん増えていくようになります。こうして現在では専用の野外劇場を持ち、出演者も2,000人(すべて村人)、オーケストラに合唱(注)、上演期間は5月から9月までの日曜日を除くほぼ毎日、観客数延べ50万人(一回の上演の収容人数は約5千人、ですから100回上演される)という巨大なイベントへと発展したのです。
しかしこの受難劇を今日有名にしているのは、実はそんなイベントの巨大さとかいうようなことではありません。かつてこの受難劇を見物に来た人の中には、ルートヴィヒ2世をはじめとする各国の王室はもちろん、ワーグナー、ブルックナー、リスト、トマス・マン、トルストイといった錚々たる著名人が連なりますが、この受難劇を今日的にした、あるいはもっとも重大な問題へと発展させた張本人が別にいるのです。今回のテーマの核心ともなり、長くなりますので今週はここまでにしておきます。次回その核心部分について考えてみたいと思います。
(注) 現在この受難劇で演奏される音楽は1815年オーバーアマガウの教師であったロッフス・デドラー (Rochus Dedler 1779-1822)によって書かれたものです。劇そのものは午前9時半に始まり、正午から3時間の休憩を挟んで再び午後3時から6時まで、の5時間半かけて上演されます。
2009.04.01 (水) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――3
4. 受難曲と受難劇の誕生聖週間に新約聖書(注1)の受難に関する箇所を朗読する習慣が現れるようになりますが、それは4世紀ごろにはすでに行われていたといいます。それはやがて「枝の主日(日曜日)」にはマタイによる福音書、聖水曜日にはルカ、聖木曜日にはマルコそして聖金曜日にはヨハネのそれぞれ福音書を朗誦する習慣に発展していきます。
中世の時代になって、教会で聖週間の説教が行われる際、キリストの受難に関する朗誦が3人の聖職者の対話で行われるようになります。つまり一人(助祭)が中声を受け持つ福音史家、もう一人(司祭)が低声のキリスト、そして三人目の副助祭が高声でピラトやペトロさらには群衆(「トゥルバ turba」と呼ばれる)の言葉を担当して朗誦し、対話が進められたのです。このような対話は劇的な要素も多分に含んでいましたので、それはやがて言葉に抑揚が生まれ音楽的な発展を見せます。こうして14世紀頃には単旋律の「モノフォニー受難曲」が生まれた、といわれています。
受難曲はあとでまた触れるとして、この聖週間で演奏される音楽についてもう少し触れておきますと、聖週間の中で特に重要とされる最後の三日間は「過越しの三日間」(もしくは「聖なる三日間」)と呼ばれていて、カトリック教会ではその祈りのために優れた音楽がたくさん作られています。その代表的なものが「エレミアの哀歌」で、これはその三日間の各朝課(夜中に行われるミサ)(注2)の際に朗読される聖書の言葉を音楽にしたもので、ルネサンスからバロックにかけて偉大な作曲家達が素晴しい作品を残しています。イギリスではトマス・タリス (Thomas Tallis 1505頃-85)やウィリアム・バード (William Byrd 1543-1623)が、スペインではトマス・ルイス・デ・ビクトリア (Thomas Luis de Victoria 1548頃-1611)が、またイタリアではパレストリーナ(Giovanni Pierluiji da Palestrina 1525頃-94)、カリッシミ(Giacomo Carissimi 1604-74)、A. スカルラッティ(Alessandro Scarlatti 1660-1725)他で、あげればまだまだあります。そういえばドイツでは唯一ローゼンミュラーが書いていましたが、これは以前トーマスカントルのコラムで紹介させていただきました。ただ私としては「エレミアの哀歌」で何が一番かと問われると、エミリオ・デ・カヴァリエリ(Emilio de' Cavalieri 1550-1602)をあげたいと思います(注3)。これを聴いていると時のたつのを忘れてしまうほど素晴しく、ポリフォニー芸術の極地といってもいいほどです。それからこの「エレミアの哀歌」はフランスにいくと「ルソン・ド・テネーブル(暗闇の聖書朗読)」と呼ばれる音楽となります。クープラン(François Couperin1668-1733)の名曲他、シャルパンティエ(Marc-Antoine Charpentier 1634-1704)やドラランド (Michel-Richard Delalande 1657-1726)などの作品があります。「哀歌」は大切な人の死を悲しむ歌ですが、「エレミアの哀歌」は旧約聖書(注4)の中で預言者エレミアが、紀元前609年敬愛したユダ王国の賢王ヨシヤの死を悼んで作った(注5)ものといわれていましたが、最近の説はそれに否定的です。
また受難曲が生まれる過程で、もう一つ見過ごせないものがあります。それは当時(中世)古代ギリシャ悲劇や喜劇に変って民衆の中に浸透していた宗教劇との関係です。受難曲同様教会内で司祭が礼拝式を行う際その一部をドラマティックにするため、受難曲ではそれが抑揚をもった旋律になったわけですが、もう一方ではそれは演じられる劇へと発展し、「典礼劇」が生まれます。はじめは主にキリストの復活をテーマとした劇だったようですが、後に「生誕」や様々なエピソードが加わり、ついには「受難」の物語が加わることになります。ここに「受難劇」が誕生し、やがてこちらは教会から離れて舞台は街の広場へと移り、演じる人も司祭から市民へと代わり、言葉も自分達の言葉で演じるようになっていったのです。ただこの受難劇にも器楽や合唱他音楽が加わっていました。
今回のテーマ「ヨハネ受難曲」との関連で、その本題に入る前にどうしてもこの「受難劇」について触れておかなければなりません。次回、あるドイツの小さな町で今も行われている「受難劇」について少し考えてみたいと思います。
(注1) 新約聖書とは「神の御子イエス・キリストを通じて信者が神と契約を結んだ新しい約束について書かれた書」というような意味でしょうが、内容は要するにキリストが生まれた以降の話でマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書、使徒行伝、弟子達の書簡集、そしてヨハネ黙示録から成っています。
(注2) カトリック教会ではかつてイエスの弟子達がしたと同じように、決まった時間に祈りを捧げる習慣がありこれを聖務日課といいます。日没前の「晩課」、寝る前の「終課」、夜中過ぎの早朝に行う「朝課」、日出に祈る「賛課」、午前7時の「第一時課」、午前9時の「第三時課」、正午の「第六時課」、午後三時の「第九時課」の八つの日課です。
(注3) カヴァリエリ:「エレミアの哀歌」のCD
ジェズアルド・コンソート・アムステルダム
音楽監督:ハリー・ヴァン・デル・カンプ SONY Classical SICC-118/19
カヴァリエリはフィレンツェのカメラータの運動にも加わっており、彼らとともにモノディ様式(トーマスカントルの項参照)を確立したことでも知られています。この「エレミアの哀歌」でも常に通奏低音に支えられて音楽は進み、ソロと合唱が交互に現れます。合唱のポリフォニーは極度に洗練され、ゆるやかなウネリの中に激しいドラマを感じます。尚カヴァリエリはかつて「魂と肉体の劇」(1600、ローマ)で最初のオラトリオ作者とされていましたが、現在ではこれはオペラと言われています。ということは音楽史上最初のオペラといわれるヤコポ・ペーリ(Jacopo Peri 1561-1633)の「エウリディーチェ」(1600)と同じ年にオペラを作ったことになります。
(注4) 旧約聖書とは「ユダヤ人の先祖である預言者アブラハムやモーセなどを通じて人間が神と結んだ古い約束について書かれた書」となりますが、内容は神話、信仰、神を奉る方法、日常生活で守るべき規則、等々を集めた膨大な書物です。ユダヤ教はイエス・キリストを救世主とは認めませんので、この旧約聖書がユダヤ教の聖書となります。 宗教とは離れますが、近年この旧約聖書に書かれた様々な逸話、例えばバベルの塔、ノアの箱舟(洪水伝説)、エリコの城砦等々について、聖書の記述はオーバーとしてもその存在が明らかにされ、聖書考古学として注目されるところです。
(注5) ヨシアの死後王国の指導者は堕落し、それを嘆いたエレミアはイェルサレムの崩壊を予告します。当時世界の覇権を握りつつあった新バビロニア帝国の王ネブガドネザル2世は紀元前605年及び597年の二度にわたってイェルサレムを陥落させ、大量の捕虜をバビロンに連れ去ります。これが世に名高い「バビロン捕囚」です。前586年ゼデキヤによる反乱軍鎮圧のため再びイェルサレムは破壊され、エレミアも捕虜となります。この哀歌は、このバビロン捕囚の頃にまとめられたので、その作者がエレミアと考えられてきたのです。因みに私たちは極東の地にあってなかなか感じることはできませんが、ネブガドネザル2世とユダヤの対立は、そのまま現代の中東(パレスチナ)問題にまで引き継がれており、問題の根深さを痛感します。
2009.03.23 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――2
3. 聖週間と復活祭(イースター)イエス・キリストが十字架にかけられたのは、ユダヤ教の過越祭(注1)の始まった翌日の金曜日でした。ですからキリスト教ではその週を聖週間といい、西方教会(カトリック、プロテスタント、イギリス国教会)ではそれは春分の日の後、最初に訪れる満月の週と決められています(注2)。従ってその週の金曜日は「聖金曜日」であり、その三日後の日曜日が「復活祭」となります。今年は4月12日が復活祭にあたります。因みに昨年は3月23日でした。それ程年によって違ってしまいます。余談ですが、ヨーロッパではこの復活祭の日を基点として定められる祝日がいくつかあり、それを知っていないと美術館や店に行っても閉まっていた、などということになってしまうので旅行の際は注意が必要です。
そしてこの復活祭の1週間前の日曜日は、キリストが処刑を覚悟のうえで(注3)イェルサレムに入場したことからそれを記念して「棕櫚の日曜日(プロテスタント)」と呼んでいますが、その由来はガリラヤで数々の奇跡を起こしたイエスを「群衆がナツメヤシの枝を持って出迎えた」という聖書の記述を日本語に訳す時、「ナツメヤシ」を「棕櫚」と誤訳し、それがそのまま「棕櫚の日曜日(カトリックでは「枝の日曜日」)と呼ばれるようになってしまったとか。ヨーロッパではこの日家々をオリーブの枝(ナツメヤシはなかなか手に入らないので)で飾ったり、また教会ではその枝で人々が祝福を受けたりするそうです。そしてこの日から始まる聖週間にはさまざまな行事が行われます。よくテレビなどでも紹介されるカトリックの十字架にかけられたキリスト像や聖母マリア像を持った行列などもこの週に行われます。なかでも最後の三日間は特に重要な日とされ、聖木曜日(最後の晩餐の日)、聖金曜日(処刑された日)、聖土曜日(墓で過ごした日)などと呼ばれています。バッハの受難曲演奏はその聖金曜日に行われました。
またその更に1週間前、つまり復活祭の二週間前から、「受難節」と呼ばれる期間に入り、そして更に更に復活祭から数えること46日前から四旬節と呼ばれる期間に入ります。これはキリストがイスラエル入場前に荒野で修行(断食)をしたことにちなんでいるので、この日から信者は肉を食べることを禁じられ、禁欲と節制の生活に入ります。一般的には音楽や宴席は禁止され、結婚式なども行われず、町には静寂なときが訪れる、といいます。そういえばシュッツに「マタイ」「ルカ」「ヨハネ」の各受難曲(注4)がありますが、それらはすべてアカペラで書かれており、それは当時この聖週間には器楽演奏が禁じられていたからだとか、何かで読んだ記憶があります。そんなこともあってこの四旬節の始まる前に、ヨーロッパではカーニバルが行われ、思い切り飲み食いし馬鹿騒ぎをするのだとか。
さて聖週間についてはこのあとにもまたふれますので、ここで復活祭にちょっと触れておきたいと思います。私が小さい頃よく教会に行っていたのは、前回のテーマで書きましたが、そのときイースターで思い出すのは教会で貰ったタマゴ(イースターエッグ)です。このタマゴは金色に塗られ、そこに様々な美しい刺繍のような絵柄が書かれていました。何故こんなタマゴを貰うのかそのときは全くわかりませんでしたが、これは「雛がかえる」ということから「復活」を象徴するのだ、ということを大きくなってから知りました。インターネットの記述などを読みますと、ゆでタマゴで作るなどと記載しているものもありますが、私の記憶では生タマゴでした。それにしてもきれいな絵柄で、どこかで売っているのだと思っていたのですが、これも教会員が手作りで作ったものだと後で知り、驚きました。今でもまだ教会では続けられているのでしょうか?ちょっと懐かしい気がします。また何故イースターと呼ぶのかについては、紅山雪夫氏の著書「ヨーロッパの旅とキリスト教」によると、民衆にこの祭日を説明する際「過越しの祭り」を例に出してもわからないので、ゲルマンに昔から馴染みのあった「光と春の女神」の祭りエアストレEastreを引き合いに出し、それと同じようなものだ、と説明したとか。それがEasterになったのだ、と。ですからこれは春の祭りなのです。
(注1) ユダヤ教の祭りで、もともとは春先の収穫(麦など)を祝う祭りであったのが、その後神がイスラエルの民をエジプトから救い出したことを祝う祭りとなったもの。子羊を生贄として神に捧げる神事が行われ、その祭りの際にキリストが復活したのでイエス自身を「神の子羊」と呼ぶようになったとか。
(注2) 紀元325年のニケア公会議で定められた。
(注3) 私も含め信者以外にはなかなか理解しにくいのですが、受難曲を理解するにはキリスト教の考え方も多少知っておいた方がいいと思います。キリスト教では、神が人間を救うために地上に御子イエス・キリストをつかわしたとし、イエスをメシア(救世主)と考えます。そして人類の究極的な救いは、イエスが十字架にかけられて死んだことにより、初めて成し遂げられたのだ、と。ですから十字架による死は必然だったのです。
(注4) シュッツの受難曲はアカペラのせいもあって、様式的に古いという印象がありますが、人間の声だけで訴えてくる音楽には、思わず引き込まれてしまう不思議な力があります。3曲とも晩年に書かれただけあって、ドイツ音楽の父シュッツの最高芸術といっても過言ではありません。マタイ受難曲のCDをあげておきます。
シュッツ:マタイ受難曲 SWV479
福音史家: ペーター・シュライアー(テノール) イエス: ヘルマン=クリスティアン・ポルスター(バス)
マルティン・フレーミヒ指揮 ドレスデン聖十字架合唱団
Deutsche Schallplatten KICC-9633
当然ながら福音史家もイエスも、すべてアカペラです。またコラールも使用していませんので、親しみにく
いかもしれませんが、逆に声がストレートに心に沁みてきます。
2009.03.16 (月) Ⅳ. ヨハネ受難曲をめぐって――1
あるとき友人から、「世の中で好きな曲を1曲だけ選ぶとしたら何を選びますか?」と聞かれたことがあります。こんな難しいことを聞かれると答えに窮してしまうのが普通ですが、そのとき私は即座に「(バッハの)ヨハネ(受難曲)」と答えました。それほど私はこの曲が好きです。マタイよりはるかに音楽は劇的緊張感に富み、それでいて優しさに満ちています。しかしこの曲にのめり込めば込むほど、またいろいろ考えさせられることが多いことも事実です。今回はそのヨハネ受難曲について書いてみたいと思います。1. 日本人の宗教観
だいぶ昔まだLP時代のことですが、あるレコード会社が「マタイ受難曲」を年末に発売し、その際レコードのタスキに「クリスマスに聴く最高の贈り物!」(正確な文言は忘れましたが、内容はそういうこと)と書いて発売したことがあります。これが音楽誌の月評で評論家の先生からこっぴどく叩かれました。賢明な読者の方はどこが間違っているかすぐにおわかりになると思いますが、あまり笑えないミスです。
言うまでもなくクリスマスというのはイエス・キリストの「降誕」(注)をお祝いするものであって、受難とはまったく関係なく、またそれを祝うなどということはありえないのです。とはいえ、かくいう私も年末になるとヘンデルのメサイアやバッハのクリスマス・オラトリオとともに、受難曲も聴いてしまうことが度々あります。誕生のコラールと受難のそれとはまったく意味が違うのですが、クリスチャンでもない限り言葉の意味を考えずに、賛美歌のメロディーによる雰囲気だけで聴いてしまうのでこんな現象が起こるのでしょう。またヘンデルのメサイアも、日本ではクリスマスの音楽と思われていますが、これも本来三部構成になっていてクリスマスに関係あるのは第一部の「予言と降誕」だけで、あとは「受難」「復活と永遠の生命」がテーマになっています。昔からこの曲は日本では年末に慈善コンサートとしてよく演奏されたりしてきたので、いつの間にかクリスマスの音楽と思われるようになってしまったのかもしれませんが、ダブリンで初演されたのも4月で、本来は復活祭前後に聴く音楽でしょう。ともかく年末というと宗教音楽の録音をどっと出すレコード会社の習慣も考えものですが、その時期にならないと聴く気になれないという音楽ファンももう少し考えた方がいいかもしれません。
2. ヨーロッパの春(注)キリストの誕生は一般的に西暦元年12月25日とされていますが、マタイ福音書にはヘロデ王の時代にベツレヘムで生まれた、となっていて、そのヘロデ王は紀元前4年に死んだことが確かだそうなので、そうするとキリストの誕生は紀元前4年以前ということになります。キリストとヘロデ王の物語は、クラシック・ファンならベルリオーズの「キリストの幼児」を思い起こせばよく理解できるのでは。
3月になると日本ではようやく暖かい日差しとともに、春が訪れます。野山にはスプリング・エフェメラル(春の妖精)と呼ばれる小さな花々が一斉に花開き、行き交う人々の目を楽しませてくれます。ではヨーロッパの春はどうでしょう?
私たちは地中海というとすぐに「光溢れる暖かい地」というイメージが浮かびます。でもナポリでさえ北緯41度あり、これは青森の北緯約40.5度にくらべても更に北に位置します。かつて私たちの年代には懐かしいコマーシャルですが「ミュンヘン、札幌、ミルウォーキー」というキャッチコピーがありました。これはビール会社のコマーシャルで、この3都市が「ほぼ同じ緯度に位置していて、だからそこで作られるビールは美味い(ミルウォーキーのビールが美味いとは思えませんが)」のだ、という意味で使われたのでした。ミュンヘンは南ドイツ・バイエルンの州都、南ドイツという言葉からは暖かいというイメージが浮かびます。でも厳密に言えば札幌より緯度は高いのです。というより稚内よりも上に位置するのです。ましてやバッハの住んだ街、ライプツィヒは更にそこよりも緯度は高くなります。海流の影響により「極寒の地」とはなりませんが、春の訪れは日本よりかなり遅いと思わなければいけないでしょう。
そのヨーロッパの暗く、長い冬が終わり、春の足音が聞こえてくる頃キリスト教圏では待望の春の祭り、復活祭(イースター)が盛大に行われます。この復活祭、ヨーロッパではクリスマス以上に大きなお祭り、といいます。それだけ春の訪れが待ち遠しい、ということなのでしょう。
2009.03.09 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――3
ネアンデルタールに触れたついでに、このタールから生まれたもう一つの興味深い物語りをご紹介しましょう。4.タール(谷).から生まれたもう一つの物語
バッハのカンタータに第67番「死人の中より甦りしイエス・キリストを覚えよ Halt im Gedächtnis Jesum Christ BWV67」、そして第145番「われは生く、わが心よ、汝を喜び楽しませんため Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen BWV145」という作品があります。前者は第4曲に、そして後者は終曲にそれぞれ「栄光の日は現れた Erschienen ist der herrlich」というコラールを使用しています。またカンタータ第151番「甘き慰めなるかな、わがイエスは来ませり Susser trost, mein Jesus kömmt BWV151」でもコラール「キリスト者たちよ、ともに神を讃えよ Lobt Gott, ihr Christen alle gleich」の第8節を使用していますが、この二つのコラール作者はニコラウス・ヘルマン (Nikolaus Herman 1500-61)といいます。
ヘルマンはニュルンベルク近郊のアルトドルフという町に生まれましたが、経歴はあまりよくわかっていません。一説ではワーグナーのあの「マイスタージンガー」のモデルとなったハンス・ザックスから影響を受けたとも言われますが、確証はありません。1518年18歳のときに町の教会のカントル、ラテン語学校の教師そしてオルガニストとして(ザンクト)ヨアヒムスタールにやってきます。彼はここで終生暮らし、教師という立場から子供たちのためにコラールを作りました。先にあげた2曲のコラールは「讃美歌21」に第319番「輝きのこの日」、第250番「主にある人々」というタイトルでそれぞれ収められています。
さてここでご紹介するのはヘルマンではなく、この地名に由来する事柄です。このザンクトヨアヒムスタールは日本語にすると「聖ヨアヒムの谷」となりますが、ここはもうドイツの国境に近い現在のチェコ領(チェコ名ではヤーヒモフ)に位置します。古くから鉱山として知られ、18世紀後半からはウラン化合物が採掘され今でも高価な品とされるボヘミアングラスの着色技術に使用されたり、また1898年には、女性として最初のノーベル賞を受賞(1903)したキューリー夫人が、夫と共同してその谷で採掘したウラン化合物からラジウムを抽出したことでも知られる地です。
ヘルマンが暮らしていた時代は、良質な銀が採れることで知られていました。かつての日本もそうでしたが、ここヨアヒムスタールでも鉱山労働者は過酷な労働を強いられ、ヘルマンはそうした鉱山労働者のためのコラールも作っています。良質な銀が採れることから、銀貨が鋳造されそれは(ヨアヒムス)ターラー(ターレルとも)と呼ばれる通貨となりました。
バッハの伝記を読んでいると、彼はお金に細かく、また人一倍執着心が強かったようで年俸の少なさをぼやいたり、より高い給料を求めてすぐに仕事を変わったりする様子が描かれています(当たり前かもしれませんが)。そのとき決まって登場してくるのがこのターラーとその下の単位グロッシェンです。アイゼナッハ時代の73ターラーに始まり、ミュールハウゼン、ヴァイマルの各時代を経て、ケーテン時代の終わりごろには年俸は400ターラーになっていました。ライプツィヒでは市から支払われる年俸は100ターラー程だったようですが、その何倍もの副収入があり本人は700ターラーだった、と友人エールトマンに書き送っています(天候のよい年には葬式が少なく収入が減るとぼやいてもいます)。この額について、人間の一般的な心理で「少し見栄を張った額では?」という人もいますが、バッハの生真面目な性格を考えると案外本当の数字では、と私は思っています。また比較の参考までに記載すると当時のライプツィヒ市長の年俸が1,500ターラーだったそうです。ではこのターラーという通貨、今だとどのくらいの価値があるのでしょう?クリストフ・ヴォルフが書いた「ヨハン・セバスティアン・バッハ~学識ある音楽家」(春秋社)にその試算が載っており、それによると1ターラー=72$となっています。それで計算するとライプツィヒ時代の彼の年収は$50,400ということになります。これが多いか少ないかは皆さんでご判断ください。尚礒山雅氏が書いた講談社新書「J.S.バッハ」にも別の人が試算した額が掲載されていますが、これではちょっとバッハがかわいそうな気がします。
さてこのターラー、ドイツでは1871年のドイツ帝国誕生の翌年マルク(ゴルトマルク)に切り替えられ、そこで通貨としての役目を終えたのですが、それは海を越えてアメリカに渡り、今や世界の通貨doller($)となって生き続けているのです。
5. この稿のCD(音楽)について
(1)バッハ: カンタータ第137番「主を頌めまつれ、力つよき栄光の王をば」BWV137
エディット・マティス(ソプラノ)、ユリア・ハマリ(アルト)、ペーター・シュライアー(テノール)、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(B)
カール・リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管弦楽団&合唱団 Archiv POCA-2045
このカンタータの録音は上記以外にもあります。コープマン、バッハ・コレギウム・ジャパン他カンタータ全曲録音を行っている(進行中も含め)団体がいくつかあり、その中からも聴くことができます。リヒターとミュンヘン・バッハの演奏は中にはあまり好きになれないものもありますが、ここでは何といってもシュライアー、フィッシャー=ディスカウの歌が素晴らしく、お勧めです。
(2) ハンス・レオ・ハスラー: わたしの心は思い悩んでいる
「新しいドイツ歌曲の喜びの園」中の一曲
(LP) ハンス=ヨアヒム・ロッチュ(テノール) ペーター・クルグ(gamba) ARCHIV 2533 041
(CD) Eterna Classics BC31272
「血潮したたる」の原曲はかつてロッチュの歌うLPで親しんでいました。これを聴いていると、こうしたリートがその後アダム・クリーガー(Adam Krieger 1634-66)に引き継がれ、やがてドイツ・リートの最高峰シューベルトへと繋がっていくことが耳で実感されます。CDはエテルナ・クラシックスから歌曲集が出ていて、注文しているのですが残念ながら未だに入荷されません。
(3) ハインリヒ・イザーク: インスブルックよ、さようなら
イザーク:シャンソン、フロットラ、リート集
(CD) L'OISEAU-LYRE POCL-5205
「インスブルックよ、さようなら」は上記イザークの作品集に収録されているほか、名曲だけに様々な演奏によるものが出ています。変わったところでは、以前「Original Trapp Family Singers」というCDが出ていてそれにも入っていました。これはあの映画「サウンド・オブ・ミュージック」のモデルとなったトラップ・ファミリーによる演奏で(BMG BVCF-35016)録音は当然モノラルで1940年前後と古いのですが、思った以上にいい音質です。このCDにはその他「血潮したたる」や「高きみ空より」などのコラールも収録されています。
(4)バッハ:カンタータ第67番「死人の中より甦りしイエス・キリストを覚えよ」
第145番「われは生く、わが心よ、汝を喜び楽しませんため」
バッハのカンタータは(1)で触れたように、全集がいくつか出ていてそれらで聴くことができます。ただ両曲ともカンタータの中では録音が少ないほうかもしれません。145番はかなり後期の創作(1729年4月19日?)に属しますのでバッハ・コレギウム・ジャパンもまだここまで録音が進んでいません。私はアーノンクール指揮によるTELDEC盤しか持っていませんが、TELDECによる全集録音は古楽器と少年合唱団を起用していて当時の演奏に近いことはわかるのですが、ピッチが不安定だったり、ソプラノ・ソロ(少年合唱団員)がテンポに乗れなかったりと、古楽演奏初期によく見られた欠点が多く、あまりお勧めできません(137番は比較的いい演奏ですが)。又復活祭後の第1日曜日(主日)に演奏される67番にはちょっと厄介な問題があります。このカンタータはライプツィヒに移ってバッハが最初にフラウト・トラヴェルソ(横笛)を使用した曲といわれていますが、問題なのはcorno da tirarsiというわけのわからない楽器が指定されていることです。この楽器日本語にすると「スライド・ホルン」となるのですが、こんな楽器は聞いたことがありません。スライド式の金管楽器といえばトロンボーンが有名ですが、その他このバッハの時代にも既にスライド・トランペットというのはありました。でもホルンというのは?そこで2種類の演奏をあげておきます。
①ロビン・ブレイズ(アルト)、櫻田亮(テノール)、ペーター・コーイ(バス)
鈴木雅明指揮 バッハ・コレギウム・ジャパン BIS CD-1251
②アムステルダム・バロック・コア・ソロイスツ&コーラス
トン・コープマン指揮 アムステルダム・バロック・オーケストラ ERATO
両者の違いは①はこの楽団のトランペット奏者島田俊雄氏がこの録音のために様々な資料をもとに開発したスライド・ホルンで演奏していること、また②はホルンではなくトランペットを使用していることです。私は楽器の真偽はともかくとして断然①をお勧めします。またTELDECのレオンハルト盤は通常のホルンを使用しています。 バッハのカンタータをこれから少し聴いてみたいと思われる方がいらしたら、聴き方として番号順に聴くのではなく、バッハの場合かなりの作品の演奏記録がわかっていますので、演奏された順に聴いていくことをお勧めします。そうすることで作風がわかってきますが、特に初期のカンタータは味わい深いので是非聴いてみてください。初期のカンタータはいつかこのコラムでも採りあげてみたいと思います。
2009.03.02 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――2
3.バッハのカンタータバッハは200曲以上のカンタータを残しており、そのうち20曲ほどが世俗カンタータで、あとは全て教会カンタータ(注1)です。カンタータの作曲を求められなかったケーテン時代(1717-23)を除き、ほぼ全期間にわたって彼はカンタ-タを作っていますが、特にヴァイマル時代の後半(1714以降)には毎月1曲、そしてライプツィヒ時代(前期)にはほぼ毎週1曲のカンタータ作曲(過去に作った作品の再演や改編も含む)が義務付けられたため、これだけでも相当な数の作品になります。それ以外に受難曲やオラトリオを書いているのですからもはや超人的というほかありません。もっとも1,518曲のカンタータを作曲したテレマンや、バッハとトーマスカントルの地位を争って勝利し辞退したグラウプナー(Christoph Graupner 1683-1760)の1,418曲などという例もありますが、たくさん書けばいいというものではなく、バッハの場合そのほとんどがきわめて価値の高い芸術作品なのですから、驚きという以外ありません。バッハの次男カール・フィリップ・エマヌエル(Carl Philipp Emanuel Bach 1614-1788)と、バッハの弟子アグリーコラ(Johann Friedrich Agricola 1720-74)がセバスティアンの死後発表した「故人略伝」という短い伝記には、「5年分の日曜=祭日用教会作品を残した」と書かれており、これが事実だとすれば300曲程のカンタータがなければなりません。したがってかなりの数の作品が失われたことになります。
バッハの教会カンタータでよく知られている曲と言えば、「主よ、人の望みの喜びよ」のコラールが入った147番「心と口と行いと生きざまもて」、そして「目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ」(140番)、「われらが神は堅き砦」(前述のルターのコラール)(80番)などで、これらのコラールは今日様々に編曲されて私たちにも身近な作品になっています。こうしたバッハの教会カンタータの中で特に「コラール・カンタータ」と呼ばれる作品群があります。少し難しくなりますが、バッハはライプツィヒに移って2年目(1724年)の6月11日(三位一体節後最初の日曜日)(注2)から始まる「コラールの第2年巻」に壮大な試みを始めます。それが「コラール・カンタータ」と呼ばれるものですが、これは翌年の3月まで一貫した技法でおよそ40曲が作られたのです。「ひとつのコラールの歌詞と旋律を曲全体の基礎に置いたカンタータ」のことをそう呼んでいます。曲の構成は冒頭にコラール(定旋律 Cantus firmus)をもとに編曲した大規模な合唱を、そして終曲に4声によるコラールそのものを置いたカンタータなのですが、真ん中にもコラールを定旋律とした合唱を置いたり、その前後にレチタティーヴォ(「叙唱」などと訳されるが、通奏低音にのせて物語や聖書の語句を語るように歌う)やアリアを置いて全体を構成しています。またこれらの「コラール・カンタータ」とは別に更にもっと「厳格なコラール・カンタータ」があります。これはすべての楽章にわたって一つのコラールを基礎におき、いわばコラール変奏曲とでもいえる形になっていて、それは第4番と第137番の2曲しかありません。4番のカンタータは有名な「キリストは死の縄目につながれたり」というバッハのごく初期のカンタータですが、1724年の3月に台本作者の急死により突如停止してしまった「コラール・カンタータ」創作(注3)の代わりとして4月に再演されました。この再演がきっかけになったかどうかはわかりませんが、その年の8月にまったく同じ手法(この手法自体はシェレやブクステフーデなどにも見られる古い手法ですが、バッハはそれを更に完成度の高い音楽に仕上げています)で第137番のカンタータを作曲したのです。このカンタータのタイトルは「主を頌めまつれ、勢威強き栄光の主を Lobe den Herren, den mächtigen König」でコラールの作者はヨアヒム・ネアンダー(Joachim Neander 1650-1680)といいます。
4. 自然をこよなく愛した薄幸の詩人ネアンダー(注1) 樋口隆一氏の「カンタータ研究」(音楽之友社)によれば、バッハ自身は教会カンタータとは呼ばず「コンチェルト」としていたといいます。つまり前回のテーマでも述べた「器楽伴奏つきの声楽曲」ですが、明らかにその間には大きな発展があり、ここでは教会カンタータと呼ばれます。カンタータ自体はもともとイタリアで起こった通奏低音にのせて歌う世俗の歌曲ですが、その影響を受けてドイツで盛んになったのが教会カンタータです。乱暴な言い方ですがレチタティーヴォとアリア、コラール(ない場合もある)によって構成される教会音楽と思えばいいでしょう。カンタータの台本作者として知られるエルトマン・ノイマイスター(Erdmann Neumeister 1671~1756)の言葉がよく引き合いに出されます。「簡単に言うなら、カンタータとは、レチタティーヴォのスタイルといくつかのアリアをひとまとめにした、あるオペラの一部分のようなものである」(服部幸三「西洋音楽の歴史(バロック)」より)
また教会カンタータで注意しなければならないのは、カンタータは教会の説教と密接に結びついていて、牧師によってその日に読まれる聖句の内容(教会暦のなかであらかじめ決められていて「ペリコーぺ」と呼ばれる)を補完する役割があることです。ですから曲ができなかったからといって数週間前に演奏したものをまたもってくる、という訳にはいかないのです。但し何年か前の同じ日に演奏したものを再利用することはできました。
(注2) クリスチャン以外にはわかりにくいのですが、キリスト教には三つの大きな祭日があります。つまりクリスマス、イースター(復活際)、ペンテコステと呼ばれる聖霊降臨祭の三つです。聖霊降臨祭はイースターから数えて50日目の日曜日に行われ、そしてその次の日曜日が三位一体節主日(日曜日のこと)となります。そしてこの三位一体節は、11月30日に一番近い日曜日から始まる待降節(キリストの誕生-いわゆるクリスマス-を待ちわびる期間)の前まで約半年間続きます。それぞれの由来や意味まで触れていると長くなりますので、インターネット他で調べてください。
(注3) これはクリストフ・ヴォルフの説。高名な音楽学者アルフレ-ト・デュル(Alfred Dürr 1918~)は教会における「ペリコーペ」といわれる聖句の内容が変わってしまったためではないかと推察しています。
ネアンダーはあの音楽隊の童話で知られる北ドイツのブレーメンに生まれ、その地の大学で神学を学びました。卒業後ハイデルベルクで家庭教師をしながら更に神学を学び、その後フランクフルトの教会に入ります。彼はここで後に「敬虔主義の父」とされるシュペーナー(Philipp Jacob Spener 1635-1705)に出会い、大きな衝撃を受けたといわれます。 「敬虔主義」について話し出すと、難しくまた長くなってしまいます。ですからここではちょっと乱暴ですが、「敬虔主義とはルター派正統主義教会内に起こった改革運動」としておきます。ルター派のプロテスタントも時間の経過とともに教条化してきます。そうしたことに反発してもっと本来の個人の信仰を重視しようとして起きた運動ですが、教会とは別に同志で集会を開いたりしたので危険分子とみなされたりしました。また彼らは純粋な信仰に相応しくないとの理由から大げさな音楽を教会に持ち込むことにも反対していました。
フランクフルトで勉強を終えたネアンダーは、24歳(1674)のときデュッセルドルフの改革派(カルヴァン主義)付属のラテン語学校の校長に赴任します。しかし既に純粋な敬虔主義者であったネアンダーは教会(彼の就任後にできたカルヴァン派の教会)に隠れて周囲に敬虔主義を説き、時には郊外の美しい自然に囲まれた渓谷で秘密集会を開いたりしました。次第に教会にも行かなくなりとうとう彼は査問にかけられ、今後敬虔主義の集会には参加しないという調書にサインさせられます。更に教会は最終的に彼の校長職をも剥奪し、彼は失意のどん底に陥ります。そんなネアンダーにかつて彼を教えた師(敬虔派の牧師テオドール・ウンデライク)が救いの手を伸ばし、1679年彼を故郷ブレーメンの教会に呼び戻しますが、ただ彼はもう生きる気力をなくしたのか、その10ヵ月後30歳という若さでこの世を去ったのでした(ペストが死因だったという説もあります)。
ネアンダーは自然をこよなく愛し、しばしば郊外の美しい渓谷に出向き、そこで詩を作ったと言われています。彼の死後出版されたコラール集のタイトルがそれをよく表しています。少々長いのですが次のようなものです。「ヨアヒム・ネアンダーの信仰と愛の練習曲集――単純な契約歌曲と感謝の詩篇歌に刺激され、周知の歌い方あるいはまだ知られていない歌い方で新たに作曲されたもの・・・旅行中に、あるいは家庭で、また緑の自然の中でのキリスト教徒の楽しみのときに読み、歌うために」(ニューグローブ音楽辞典)と。"Lobe den Herren"ももちろんそこに含まれており、これは日本でも讃美歌21の第7番「ほめたたえよ、力強き主を」でよく知られていますが、今や世界中の教会で歌われている名曲なのです。讃美歌21では
ほめたたえよ、力強き主をと歌います。
わが心よ、今しも目覚めて
たてごと かきならしつつ
み名をほめまつれ
ネアンダーの死後、彼と一緒に行動していたかつての仲間や支持者たちはその美しい渓谷を、彼を偲んで「ネアンダーの谷」、つまりドイツ語で「ネアンデルタール(Tar=谷)」と名づけたのでした。
彼が亡くなってから4年後、彼が教えていた学校の庭にデュッセルドルフで初めてのプロテスタント教会が建てられ、1916年にこの教会は「ネアンダー教会」と改名されたといいます。
バッハが何故ネアンダーのコラールを使用したのか?これもちょっと難しい問題です。バッハはルター派正統主義の立場に立っており、彼と敬虔主義とのかかわりを論じ始めると今回のテーマから著しく外れてしまいますのでここでは止めますが、彼の遺品となった蔵書に敬虔主義者の書いた書物が何冊かあったり、ネアンダー以外の敬虔派のコラールをいくつか使用してもいますので、少なからぬシンパシーはもっていたのではないかと推察されます(注1)。
カンタータ第137番は15分程の短い曲ですが、トランペット3、オーボエ2、ティンパニ、弦、通奏低音(オルガン)という編成としてはかなり大掛かりなものです。5楽章からなり、そのすべてにこの「主を頌めまつれ、勢威強き栄光の主を」のコラールが使用されます。第1曲は合唱のソプラノに、第2曲はアルトのアリアに、第3曲はソプラノとバスの二重唱に、第4曲はトランペットのソロに、そして終曲のコラールにと言う具合で、歌詞もネアンダーの1節から5節までのすべてが使われます(注2)。たいへん輝かしい曲で、私は今これを聴くと、かつてこの緑豊かな渓谷に生きた古代人へのバッハのオマージュのようにも聞こえてくるのです。
この場所はいま、かつての緑溢れる景観を取り戻そうと公園として市民の憩いの場になっているそうですが、写真で見る限り雑木林の間を流れる小川と遊歩道があるだけでとてもそんなに美しい場所とは思えません。「覆水盆に返らず」一度破壊されたものをもとにもどすのは容易ではありません。日本も開発と言う名の自然破壊をいつまで続けるのかもう考え直す時期にきていると思うのですが。
今回の原稿を終えようとしていましたら、何というタイミングか今日(2月28日付)の朝日新聞夕刊「かがくるアドベンチャー冒険マル秘ノート」という欄で「ネアンデルタール人はなぜ滅んだ」というごく短いコラムが載っていました。それによるとどうやら私たち人間(ホモ・サピエンス)が彼らの生活圏をどんどん侵し、絶滅に追いやったのでは?ということでした。何と言ったらいいのか?彼らを称えて今日もカンタータ137番を聴くことにします。(注1) バッハはミュールハウゼンを去るに当たって、その一因として敬虔主義者との抗争に嫌気がさしたためとも言われていますが(主たる要因は金銭問題?)、アルフレート・デュルは「バッハ=カンタータの世界」(クルストフ・ヴォルフ編)への書評の中で、「バッハは後期に至って、敬虔主義に開眼した可能性があるのでは」とも言っています。
(注2) バッハはこのコラールの第4、5節を1729年頃に書いた結婚カンタータBWV120a「主なる神、万物の支配者よ Herr Gott, Beherrscher aller Dinge」の終曲コラールにも使用しています。スコアで見る限り2部構成の比較的規模の大きい作品ですが、残念ながら不完全な形でしか残っていないため、今日演奏されることはないようです。また旋律だけ少し変形させてカンタータ第57番「試練に耐うる人は幸いなり Selig ist der Mann」の終曲コラールにも使用しています。
2009.02.23 (月) Ⅲ. バッハとネアンデルタール人――1
この突拍子もないタイトルを見て驚かれた方も多いと思います。もちろんこの両者には直接何の関係もありません。ただある人物を介するとこの二つが結びついてくるのです。1. ネアンデルタール人
1856年ドイツのデュッセルドルフ郊外にある渓谷の洞窟から人類の祖先と思われる骨が発見されました。20万年くらい前から2万数千年前まで生存していた人類の祖先とされ、発見された地名にちなんでネアンデルタール人と名づけられました。現在では直接人類の祖先ではなく、人類に近い祖先といわれています。
ヨーロッパの列強の中にあって、ドイツは国家の統一が遅れたため工業の発展も他国に比べ遅れをとっていました。鉄血宰相ビスマルク率いるプロイセン王国によりドイツ帝国が統一誕生するのは1871年ですが、それに先立ってナポレオン戦争終結後ウィーン議定書(1815)により「ドイツ連邦」が誕生します。そんななかドイツは遅れまじ、と1830年代からすさまじい開発ラッシュが始まります。ネアンデルタールと呼ばれた渓谷は豊かな石灰岩の産地だったことから徹底的に掘りつくされ、かつての美しい渓谷は無残な姿になってしまいます。そんな採掘作業の副産物としてネアンデルタール人は発掘されたのです。
2. コラールの誕生
バッハの受難曲やカンタータでなじみ深いコラールですが、それらのいくつかは日本のプロテスタント教会でもよく歌われる讃美歌として親しまれています。私はクリスチャンではありませんが、家がプロテスタントだったこともあり、小さい頃両親や兄弟に手をひかれて教会の日曜学校なるものに行き、よく讃美歌を歌ったものでした。ですからこれらの歌はとても懐かしく、今でもよく覚えています。こうした小さい頃の音楽体験がわたしをクラシック好きにさせたのかもしれません。
このコラールはもちろんルターの宗教改革の一環として生まれたものです。カトリックの教会では典礼の際聖歌隊によってラテン語のミサや詩篇が歌われますが、ルターはもっと民衆と一体となれる礼拝(プロテスタントでは一般に「典礼」とは言わず「礼拝」という)のあり方を模索し、讃美歌を教会に集う会衆全員で歌おう、と考えたのでした。そしてルター自身で聖書の語句をもとにドイツ語の会衆歌を作曲しました。これがコラールの始まりです。これは当時の印刷技術と相まって紙に刷られ瞬く間に民衆の間に広がっていったのです。シュヴァイツァーの言を借りれば「芸術的な音楽を神のもっとも完全な啓示の一つとみなしていた」ルターは自身リュートがたいへん巧く、音楽的素養にも恵まれていたと言われています。彼が作ったコラールに有名な「神はわが砦」(Ein feste Burg ist unser Gott 讃美歌21、第377番。メンデルスゾーンの交響曲第5番他様々な作曲家がこれを利用しています)がありますし、その他クリスマスによく歌われる「天のかなたから」(Vom Himmel hoch, da komm ich her同第246番)もその一つです。
こうしてコラールはその後様々な人によりたくさん作られるようになっていきますが、その過程で面白い現象が現れます。それは民衆の間によく知られている曲に詞をつける、いわば替え歌のような手法が登場してきます。それは民謡であったり、グレゴリアンの旋律であったり、また時には世俗の歌曲であったりしたのです。そうしたコラールから有名な作品が生まれました。ルター以降最大のコラール作家といわれたパウル・ゲルハルト(Paul Gerhardt 1607-1676)の曲に「血しおしたたる O Haupt voll Blut und Wunden」(讃美歌21、第310,311番)と「見よ、十字架を O Welt, sieh hier dein Leben」(同第295番)の2曲があります。両方とも「マタイ受難曲」の中で何度も現れてくる有名なコラールですが、前者はハンス・レオ・ハスラー(Hans Leo Hassler 1564-1612)の「わたしの心は思い悩んでいる、それはやさしい若い娘のためなのだ・・」と恋の悩みを歌う3拍子系のドイツ・リートが、また後者は1976年の冬季オリンピックなどにも歌われたハインリヒ・イザーク(Heirich Isaac 1450?-1517)の「インスブルックよ、さようなら」という歌がそれぞれ原曲です。とても素晴しいコラールですが、その背景には過酷なドイツ30年戦争(1618-48)が影を落としています。新旧の宗教対立から起きた戦争ですが、途中からは周辺国が入り乱れてドイツ国内で戦を繰り広げ、おまけにペストの流行も重なって、ドイツはこの戦争で人口が3分の1にまで減ってしまった、といわれています。ゲルハルトはまさにその渦中で成長し、その悲惨な状況を目の当たりにしてこうした美しいコラールをたくさん作ったのです。現在プロテスタント教会が使用している「讃美歌21(注)」という曲集には彼の讃美歌が9曲含まれています。
横道にそれてしまいましたが、これからの物語に関係してくるコラールについての予備知識としてお話ししました。
(注) 讃美歌は1954年に出版された日本基督教団の「讃美歌集」(567曲+追加259曲)が一般的でしたが、1999年に来るべき21世紀を迎えて新しい讃美歌集が発行され、それが「讃美歌21」(全580曲で新しく追加されたものも入っています)と呼ばれるもので現在ではこちらの方がよく使われているようです。もちろん曲はかなり重複していますが、付されている番号はまったく違います。私の番号とタイトルは「讃美歌21」に従っています。
2009.02.16 (月) Ⅱ. トーマスカントルの系譜と音楽――2
2. バッハ以前のトーマスカントルの音楽これについては単独でいつか扱おうとも思いましたが、それほど量も多くないのでここで触れておきます。
(1)ゲオルク・ラウ:
現在CDでは入手できないようですが、以前「1460年から1560年までのドイツの歌曲と舞曲」と題されたアルヒーフのLP盤(2533 066)にゲオルク・ラウの歌曲が3曲(美しい小麦色の娘 Mir ist ein feins brauns Maidelein 他)、ヴォルフ・ラインホルトのテノールとディートリヒ・クノーテ指揮ライプツィヒ合奏団他の演奏で聴くことができました。
(2)ヨハン・ヘルマン・シャイン:<オペッラ・ノーヴァ> 第2巻
ハリー・ヴァン・デア・カンプ(バス) 他 ライン・カントライ ムジカ・フィアタ・ケルン 指揮:ローランド・ウィルソン
deutsche harmonia mundi BVCD-6
シャインはシュッツ、ザムエル・シャイト(Samuel Scheidt 1587-1654)と共にドイツ3大Sと呼ばれた大作曲家の一人で、ザクセン地方のグリューンハインという地に生まれ44歳という比較的若い時期にライプツィヒでなくなりました。臨終の際には親しい友人であったシュッツが見舞い、シャインが選んだ詩に歌詞をつけた合唱曲「それは確かな誠」(6声の葬儀モテット)を奥さんと二人の息子のために作曲したといわれています。この曲は後にシュッツの宗教的合唱曲集作品11の第20曲(SWV388)として出版されています(1648)。
彼の作品は今までもなかなか録音に恵まれずちょっと地味な感じがしますが、ここにこうしてCD一枚分の作品集が発売されたのは素晴らしいことです。このCDにはドイツ語の歌詞による全部で12曲の宗教コンチェルト(この場合のコンチェルトは前にも言いましたように、器楽伴奏つきの声楽曲をいいます)が収められていますが、正木さんの解説には「(この曲集で)イタリアのコンチェルタート様式とドイツのコラール編曲の技法を見事に融和させた」と書かれています。二重合唱(第6曲「ダビデの歌」)もいいですが、なぜこうした合唱曲を「コンチェルト」と呼ぶのかその意味がこれを聴くとよくわかると思います。それとシャインの合唱曲は器楽伴奏が特に優れているように思います。
(3)シャイン:挽歌(Motette "Threnus" 1617)
シュッツ・アカデミー 指揮:ハワード・アーマン ドイツ・シャルプラッテン TKCC-15092
とても美しい曲です。1617年ザクセン選帝侯婦人のドロテア・マリーアの葬送音楽として作曲されています。シャインはトーマスカントルになる直前ヴァイマールでヨハン・エルンスト侯の宮廷楽長を務めており(1615-16)、婦人はその母にあたる人でした。尚これは「17世紀葬儀の音楽」というタイトルのCDに収録されており、ここにはシュッツのムジカーリッシェ・エクゼクヴィーエン(Musikalische Exequien)(「ドイツ・レクイエム」という別名で親しまれている)や前記「それは確かな誠」も収録されているとてもいいアルバムです。
(4)シャイン:<音楽の饗宴(1617)> から
①組曲第3番イ長調 ②組曲第4番ニ長調 ③組曲第5番ト長調
テルプシコーレ合奏団 Archiv UCCG-3193/4
「音楽の饗宴」はシャインの器楽曲の代表作で、20の組曲からなり最古の弦楽合奏曲集のひとつといわれています。このCDには他にミヒャエル・プレトリウス (Michael Praetorius 1571-1621)のテルプシコーレが収録され、かつてLP時代の名盤といわれていたものの復活です。まるでジャズのような感覚で当時の舞曲が即興的に演奏される心の底から楽しめる愉快な演奏でした。現在のCDタイトルは「ダンス・オブ・ルネサンス」です。
(5)Thomaskantoren vor Bach
カントゥス・ケルン 指揮:コンラート・ユングヘーネル deutsche harmonia mundi 88697 281822-28
文字通り「バッハ以前のトーマスカントル」というタイトルのCDですが、残念ながら輸入盤で、しかも50枚組のなかの28枚目にあたるCDです。昨年ドイツ・ハルモニア・ムンディの50周年記念のCD Boxとして限定発売されたもので、何と50枚で5,000円もしない(タワーレコード)格安のセットでした。この中にはヘンゲルブロックによるバッハのロ短調ミサなど素晴らしい名演がたくさん詰まっています。まだあまり古楽のCDを持っていない人で、これから聴きたいと思っている人にはぜひとも勧めたいセットです。多分まだ売られていると思いますがなくなっていたらごめんなさい。ただ格安であったためかちょっと誤植があったり(ご愛嬌というべきか)、また少なくともこのCDに関する欧文の解説も一切ついていません。
このCDにはバッハ以前のカントルであるクニュプファー(2曲)、シェレ(4曲)そしてクーナウ(2曲)の宗教曲計8曲が以下の通り収録されています。
① クニュプファー:Ach Herr, strafe mich nicht (ああ主よ、わたしを責めないで下さい)
② シェレ:Das ist mir lieb (わたしは主を愛する)
③ クーナウ:Gott, sei mir gnaedig nach deiner Güte (神よ、御慈しみによりて)
④ シェレ:Ach, mein herzliebes Jesulein (ああ、わが心より尊びまつる嬰児イエスよ)
⑤ シェレ:Barmherzig und gnädig ist der Herr (主は憐れみ深く、恵みに富み)
⑥ クニュプファー:Es haben mir die Hoffärtigen
⑦ シェレ:Aus der Tieffen rufe lich, Herr zu dir (深き淵よりわれ汝に呼ばわる、主よ)
⑧ クーナウ:O heilige Zeit (ああ聖なるとき)
( )内の邦題は知っている範囲で私が載せたものです。
ここでまずクニュプファーですが、彼こそ本来就任する筈であったローゼンミュラーの代わりにカントルになった人です。そして彼の時代にトーマスカントルは<ライプツィヒ市の音楽監督>にまでその範囲が拡大されたといわれます。①の音楽を聴くと、けっこう編成の大きな器楽を伴う宗教コンチェルトですが、作風はかなり保守的でまだまだバッハとの距離を感じます。ここに収録されたものが彼の代表的な音楽だとすれば「ローゼンミュラーの足元にも及ばない」といったら言いすぎでしょうか?
次にシェレですが、彼はトーマス教会に初めてドイツ語の典礼カンタータを導入した点で重要な役割を果たしています。宗教改革で母国語が使われるようになったとはいっても、周辺の都市に比べライプツィヒは保守的で礼拝にはラテン語が使用されていたのです(バッハもラテン語のミサ・ブレヴィス-小ミサ曲-をいくつか書いているほどです)。そうしたなかシェレはクニュプファーの弟子で彼の推薦でカントルに就任しましたが、当時のライプツィヒ市長はこれに反対していたためこれを機に激しい対立が両者の間に生まれます。参事会はシェレの側に立って擁護したため彼は守られました。後にバッハがライプツィヒ市との軋轢で苦しめられますが、その根はこの頃からあったのかもしれません。シェレは更に教会にコラール・カンタータ(次回のテーマで触れます)を持ち込み、これを定着させました。これが後のバッハの教会カンタータへとつながっていくのです。印刷されたコラールの歌詞を会衆に配布する習慣もこの頃から始まったといわれます。さてここに収録された作品で聴く限り、かなりしっとりとした作品で、特に②はちょっとシャルパンティエのミサ曲を聴いているのかと錯覚するほどです。ただ彼の作品はかなりの数消失したといわれていますので、これらをもって代表作というのは難しいかもしれません。彼の音楽としてはいくつかの書物にも紹介されているカンタータ「主をたたえよLobe den Herrn」を是非聴いてみたいものです。
最後のクーナウですが彼はバッハの前任者で、さすがに彼の音楽を聴いているともうそこまでバッハが来ている、ということが実感できます。彼はまずシェレが他界して荒廃したトーマス学校を建て直すことに尽力します。就任当初はすべてがうまく運び、新たにニコライ教会の音楽監督にもなります。しかしまたもや市長、参事会との摩擦が生じそれは彼の任期中には解決されずそのままバッハへと引き継がれていくのです。クーナウのカンタータはシェレの様式を引き継いでいるといいますが、それとは比較にならないほど素晴らしい音楽です。ただ演奏そのものは次にあげるCDの方が素晴らしいと思います(クーナウまでくるとCDの種類も少し多くなります)。
(6)クーナウ:神よ、御慈しみによりて(上記②)
コレギウム・ヴォカーレ 指揮:フィリップ・ヘレヴェッヘ harmonia mundi FRANCE KKCC-452
(5)のCDに収録されている曲と同じ楽曲で、こちらは「バッハ以前のドイツ・カンタータ集」というタイトルのアルバムに収録されています。ヘレヴェッヘとコレギウム・ヴォカーレの演奏はいつもながら「素晴らしい」の一語につきます。このCD、クーナウ以外トーマスカントルとは関係ありませんが、かのシュヴァイツァーが絶賛したトゥンダーのカンタータ「神は堅き砦Ein feste Burg ist unser Gott」他、ニコラウス・ブルーンス(Nicolaus Bruhns 1665-1697)の作品などバッハへとつながっていく重要な作品が収められています。是非ご一聴されることをお勧めします。
(7)クーナウ:マニフィカト
バッハ・コレギウム・ジャパン 指揮:鈴木雅明 BIS CD-1011
クーナウの現存する作品の中ではもっとも大規模な作品。マニフィカトとは「わが魂は主をあがめ」という歌いだしで始まる賛歌で、聖母マリアが受胎告知を受けて神に感謝する歌です。ですからバッハをはじめ輝かしい作品が多く、これも例外ではなくヴェルサイユ楽派顔負けの壮麗な音楽です。このCDでうれしいのは、日本の古楽演奏水準の高さです。バッハの受難曲やカンタータ(全曲録音を進行中)もそうですが、彼らの水準はすでに世界のトップレベルにあるといっても過言ではありません。同じ日本人としてとても誇らしく思います。彼らの演奏するバッハの受難曲など是非一度聴いてみてください。このCDにはバッハとゼレンカ(Johann Dismas Zelenka 1679-1745 チェコの作曲家でドレスデン宮廷教会付き)のマニフィカトが収録されています。
(8)クーナウ:聖書ソナタ
①第1番「ダヴィデとゴリアテの戦い」
②第2番「ダヴィデの音楽により癒されたサウル」
③第3番「ヤコブの結婚」
④第4番「瀕死の重病を患い、恢復したヒゼキア王」
⑤第5番「イスラエルを救える者ギデオン」
⑥第6番「ヤコブの死と埋葬」
グスタフ・レオンハルト(オルガン、チェンバロ、語り)
クーナウを語るときどうしても外せないのが鍵盤音楽でこれは彼の代名詞ともいえる作品です。旧約聖書の物語を題材にしたソナタ集ですが、いくつかの楽章に基づくこうした鍵盤楽器のためのソナタはドイツではこれが最初と言われています。それだけにバッハに与えた影響はとても大きなものがあります。しかもそれを標題音楽的にまとめているとてもユニークな作品です。各曲の冒頭には長い物語の解説が作曲者自身によって付され、ここではレオンハルトがその朗読をおこなっています。第2番の前奏曲とフーガや第6番終曲のメロディーなどバッハのチェンバロ曲にも匹敵する素晴しい作品です。ここでは1番と4番がオルガンで演奏されており、中でも4番はあのバッハのパッションコラールで有名な「血潮したたる主のみかしら」のコラール変奏曲になっています。
少し長くなってしまいましたが、以上バッハ以前のトーマスカントルの音楽をご紹介しました。もちろんこれらはわたしが聴いたもののなかからあげたものにすぎず、これら以外にも輸入盤のCDはいくつか出ていますので、ご興味のある方は聴いてみてください。
2009.02.09 (月) Ⅱ. トーマスカントルの系譜と音楽――1
前回までの内容を補足するもので、興味のある方だけご覧ください。系譜とバッハ以前のカントルの音楽を2週に分けてお届けします。1. 歴代のトーマスカントル
歴代のトーマスカントルについて記載している資料はほとんどなく、私が目にできたのはただ一つしかないので正確なところは難しいのですが、まずその唯一掲載されていた前述標準音楽辞典の内容から始めます。
(1) ゲオルク・ラウ(1519-20)以上が音楽辞典に記された内容で、( )内のカタカナ名は後に記された欧文から私が補足したもので、欧文の後の年代は辞典に記された任期を示していますが、この中には明らかな間違いがいくつかあります。気が付いた方もあるかもしれませんが、一番大きな間違いは最後のマウエルスベルガーです。ルドルフはドレスデン聖十字架教会のカントルでトーマス教会のカントルは弟のエアハルトのほうです。それから(17)のアダム・ヒラーは1804年に亡くなっているので1810年までカントルを務めることは不可能です。又(15)のハラーの名前はGeorgではなくJohann Gottlobが正しい名前です。そのほかにもちょっとわからないものがありますが、その点はあとで。いずれにしろこの辞書ではバッハのカントルは第14代ということになります(但しローゼンミュラーをいれると15代になってしまいますが)。
(2) ヨハン・ヘルマン(Johann Hermann 1531-36)
(3) (ヴォルフガング・)ユンガー(Wolfgang Jünger)
(4) (ウルリヒ・)ランゲ(Ulrich Lange)
(5) ヴォルフガング・フィグルス(Wolfgang Figulus 1549-51)
(6) ハイヤー(M. Heyer 1553-64)
(7) (ヴァーレンティン・)オットー(V. Otto 1564-94)
(8) (ゼトゥス・)カルヴィジウス(Sethus Calvisius 1594-1615)
(9) (ヨハン・ヘルマン・)シャイン(Johann Hermann Schein 1615-30)
(10) (トビーアス・)ミヒャエルとローゼンミュラー(1631-57)
(11) (セバスティアン・)クニュプファー(Sebastian Knüpfer 1657-76)
(12) (ヨハン・)シェレ(Johann Schelle 1677-1701)
(13) (ヨハン・)クーナウ(Johann Kuhnau 1701-22)
(14) ヨハン・セバスティアン・バッハ(Johann Sebastian Bach 1723-50)
(15) (ゲオルク・)ハラー(Georg Harrer1750-55)
(16) ヨハン・フリードリヒ・ドーレス(Johann Friedrich Doles 1756-89)
(17) (ヨハン・アダム・)ヒラー(Johann Adam Hiller 1789-1810)
(18) (ヨハン・ゴットフリート・)シヒト(Johann Gottfried Schicht 1810-23)
(19) (クリスティアン・テオドール・)ヴァインリヒ(Chr. T. Weinlig 1823-42)
(20) (モーリツ・)ハウプトマン(Moritz Hauptmann1842-68)
(21) (エルンスト・フリードリヒ・)リヒター(Ernst Friedrich Richter 1868-79)
(22) (ヴィルヘルム・)ルスト(Wilhelm Rust 1880-92)
(23) (グスタフ・)シュレック(Gustav Schreck 1893-1918)
(24) (カール・)シュトラウベ(1918-39)
(25) (ギュンター・)ラミン(Günther Ramin 1939-56)
(26) クルト・トーマス(Kurt Thomas 1956-61)
(27) (ルドルフ・)マウエルスベルガー(Rudolf Mauersberger 1961- )
上記を見てそのほかに気がつかれた方もあると思いますが、書いてある年代が飛んでいるところがいくつかあります。年代のわからないものは別にして、はっきり空白期間とわかるものは次の期間です。①1520~31 ②1551~53 それに③アダム・ヒラーが亡くなった後の1804~10も加えておかなければなりません。ではこの間カントルは不在だったのでしょうか?①については本文中でも触れたようにラウのあとしばらく続いたカトリック時代のカントルということになります。ニュー・グローブ音楽辞典のライプツィヒの項を見ますと、ラウのあとに登場するカントルの名前として「J. ブリュックナー」という表記があります。これは上記のリストには見られない名前です。そんなことを調べていたら一つ面白いサイトにぶつかりました。
ライプツィヒ在住のアンドレ・ロー=クリーシュ(Andre Loh-Kliesch)という人がLeipzig-Lexikon(ライプツィヒ辞典)というホームページを開設していてそこにトーマスカントルの全リストが掲載されていました。そこには氏名と在任期間、生没年などが記されています。もちろんこのリストが正しいという保証はないのですが、私が上記で見つけた音楽辞典のミスなどもなく、これは信頼できる資料ではないかと思うに至りました。ホームページのURLを載せておきましょう。ご興味のある方はご覧になってください。
http://www.leipzig-lexikon.de/KULTBETR/thomkant.htm
ここでわかるのはラウのあとのカトリック時代にはヨハネス・ガリクルス(Johannes Galliculus 1520-25)(注)、ヴァレリアン・ヒュッフェラー(Valerian Hüffeler 1526-30)の二人が続き、ヘルマン(標準音楽辞典ではヨハンと表記されていますが正確にはヨハネスJohannes)、ユンガーを挟んでヨハネス・ブリュックナー(Johannes Bruckner 1539-40)が登場します。1539年ということですからあのトーマス教会でのルターの説教後プロテスタントに改宗し、その最初のカントルということになります。その意味では非情に重要なカントルだと思いますが、これが抜けてしまうというのはちょっと辞書としての権威にも?というよりおそらくこの辞書が出版された頃にはまだわからなかったのだと思います。音楽学も日進月歩でどんどん新しい事実が発表されているのです。因みに現行の標準音楽辞典(1991年改訂版)ではこの項(トーマスカントル)は削除されています。
さて①の空欄は埋まりました。②はというとここだけはlexikonのリストも飛んでいます。不在だったと考えるべきなのでしょう。③はアウグスト・エバーハルト・ミュラー(August Eberhard Müller 1801-1810)でぴったり埋まります。アダム・ヒラーは1801年には退任していたことになります。それから(6)のハイヤーですが、このリストではHeyerではなくMelchior Hegerになっています。多分こちらの方が正しいでしょうね。またシャインのトーマスカントルの就任は次回にも触れますが1616年です。
こうして疑問点を整理したうえで考えてみますと、ではバッハは何代目のカントルだったのでしょうか? lexikonに従えば第17代というのが正解になります。但し、もしラウ以降のカトリックのカントルまで排除するとなると第13代ということになります(ローゼンミュラーを数えると14代)。ちなみにマウエルスベルガー以降のカントルは(32)ハンス=ヨアヒム・ロッチュ(Hans-Joachim Rotzch 1972-91)、そして現在の(33)ゲオルク・クリストフ・ビラー(Georg Christoph Biller 1992- )へと続きます。
このほかにトーマス教会が配布しているパンフレットなどにもまた違った表記があるようですが、私は行ったこともないのでそうした資料は持っていません。またそれが正しいかどうかはまた検証しないとわからないでしょう。いずれにしろ彼が何代目であったかということで地球がひっくり返るような話ではないので、そうしたいろいろな資料がある、ということがわかればいいのでは?というのが私の結論です。なおロー=クリーシュ氏ホームページの文責欄に書かれた自己紹介を読むとpostalischと書かれています。何やらバッハのカンタータや受難曲に数多くのテキストを提供したあの郵便官吏ピカンダー(本名クリスティアン・フリードリヒ・ヘンリーツィ Christian Friedrich Henrici 1700-64)がふと頭の中に浮かんできました。
(注)ニュー・グローブ音楽辞典にはラウと親しかった人物とされ、いくつかのミサ曲をラウが出版しているといいます。ラテン語の歌詞による宗教曲ですがプロテスタント教会のために書かれたそうです。トーマスカントルとしての記載はありません。こうしたことから考えると、カトリック時代とはいってももうかなりプロテスタントの色彩が濃かったのではないでしょうか?
2009.02.02 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――4
6. エピローグ前回までがローゼンミュラーの生涯と作品の簡単な紹介ですが、彼は器楽曲も重要ながら作品としては圧倒的に数の多い声楽曲(教会音楽)が更に重要な位置を占めている、と近年言われています。事件を起こす前のドイツ時代はシュッツの影響を強く受けてドイツ語の歌詞による宗教的コンチェルトを書いています。その中には後にバッハが教会カンタータにそのまま使用したものもあります(BWV27)。ヴェネツィアに移ってからはラテン語による典礼用の作品を数多く残しており、それらはローゼンミュラーの創作活動における頂点をなすもの、といっても過言ではありません。それにしても、もし彼が脱獄していなかったらどうなっていたでしょう。我々がいまこうして彼の音楽を楽しむ事はできなかったでしょうね。歴史というのは面白いものです。ちょっと意味がちがうかもしれませんが「災い(?)転じて福となす!」といういい見本かもしれません。
ローゼンミュラーについてはまだまだ謎の多い作曲家で、今後更に録音が増えてその全貌が明らかになることを期待します。
以上でローゼンミュラーの話はおしまいですが、彼のことを書いていて一つ思い出したことがあります。音楽とはまったく関係ありませんし、時代はそこから200年ほど下って、舞台もこの日本になります。興味のある方だけもう少しおつきあいください。
私には音楽の他にもいくつか趣味があり、そのうちの一つに山歩きがあります。齡50を過ぎてから始めた山ですが、歩き始めて間もないころ山梨県のある山に行ったときのことです。それは扇山という1,000㍍ちょっとの山で、富士山がきれいに見えることからハイカーに人気のあるところです。中央高速の談合坂サービスエリアの道を挟んで反対側の山塊といえばわかりやすいかもしれません。
この山からの帰り道、山頂からは1時間ほどで民家のあるところまで来てしまい、下りついたところに君恋温泉などというちょっと洒落た名前の温泉があるのですが、名前とは裏腹に民宿のような小さな建物が一軒あるだけで、何かだまされたような気分になります。そしてここからは延々中央線の四方津駅まで長い舗道歩きを強いられるので、これがちょっとうんざりします。道は県道30号と書かれていますが要するに旧甲州街道です。気を取り直して歩き始め、山間の道をくねくね歩いていきますと、20分くらい歩いたでしょうか、そこにバス停がありました。変わった名前で「犬目」と書かれています。時刻表を眺めると1日1本しかありません。これでは役に立たないのでなおも歩いていくと、このあたり少し開けていてどうやらかつての宿場町のようです。やがて一軒の立派な民家の前に出ます。そしてここに何やら曰くありげな看板が立てられており、そこにこの町、いやこの民家とそれにまつわる歴史が書かれていました。話の内容は概ね以下のようなものです。
江戸時代に飢饉(二度目の天保の飢饉)があった際一揆が起こり、その首謀者犬目村の兵助がこの家で生まれ、その一揆は現在の大月を中心に甲州一帯に広がり一時は甲府城を占拠するなど勢いもあったが、結局は幕府に鎮圧されてしまった。死罪から逃れるため彼は家に絶縁状を残して日本中を逃げ回る旅に出ますが、死の直前30年ぶりにこっそりと故郷に舞い戻って、静かに70歳の生涯を終えたそうです。この生家にはそのときの絶縁状や旅日記が今も残されているといいます。
その後少し調べてみたことを補足しますと、この甲府一揆が起きたのは1836年のことでそもそもは米屋に米を売ってくれるよう集団で頼んだのが聞き入れられず、それが一揆に発展したのでした。笹子峠に集結した民衆はその後ならず者も加わって暴徒化し、甲府城(明治になって廃城となり、現在は舞鶴公園となっている)を占拠するなど一時は幕府を脅かすほどの勢いがあったそうですが、結局は鎮圧され、兵助は家族が処罰されるのを懼れ、家に絶縁状を残して全国へ逃亡生活に出ます(以前現代語による彼の「逃亡記」が出版されていたといいます)。最終的には木更津の地に隠れながら望郷の念たまらず帰郷の機会をうかがっていたようです。念願かなってこっそりと帰郷しますが役人の目を逃れて隠れるように暮らし、故郷の地で波瀾に富んだ71歳の生涯を終えたのでした。明治維新を翌年に控えた慶応3年のことでした(注)。
ローゼンミュラーと犬目兵助、まったく関係はありませんが、長い逃亡生活の果て、新しい時代の到来を前にひっそりと終えたその生涯に何か共通するものを感じたのでした。
文中でお約束したとおり<参考>として「トーマスカントルの系譜」について記載しますが、今回一緒にすると大変長くなってしまいますので、これについては来週掲載します。(注) 彼の死については維新後と書かれているものが多いのですが、慶応3年は維新より前になると思います。ただこの維新前後はちょっと年号の複雑さもあってよくわかりません。
2009.01.26 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――3
5. ローゼンミュラーの音楽ここでCDで聴くことのできる彼の音楽と彼の果たした功績などについて少しご紹介しておきましょう。
(1) 「学生の音楽」から: 組曲ハ長調 アルマンド~クーラント、アダージョ~アルマンド~サラバンド
デイヴィッド・ダグラス指揮 キングズ・ノイズ
CD "Sachsen~Leipzig, Halle, Dresden a l'epoque baroque"
邦題「ヨーロッパ音楽夢街道 ドレスデン」 に収録
harmonia mundi FRANCE KHM 100006
彼の音楽の中ではもっとも聴きやすい作品でしょう。多分放送で聴いたのもこの曲集中の1曲だったと思います。「学生の音楽 Studenten-Music」は1654年、つまり彼が例の事件を起こす前年にライプツィヒで出版された舞曲による組曲集です。おそらくトーマス学校の生徒達のために書いたものでしょう。全部で10組曲あり、順に高い調性に移っていくように配列されています。昔"Student Music in 17th Century Leipzig"(ジョシュア・リフキン指揮)と題されたNonesuchのレコードで楽しんでいましたが、そこに収録されていたのは第2番のニ短調組曲でした。曲調はバロックというより、ルネサンス時代の舞曲を少し洗練させたような音楽で、その意味では少し面白みに欠けます。ルネサンス時代の舞曲のほうがもっと活力があって楽しめます。これは彼の習作的な曲集なのかもしれません。
(2) ①二つのヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ホ短調
CD 「ドイツ盛期バロックの弦楽器のための室内楽曲集」
アラリウス・アンサンブル・ブリュッセル
deutsche harmonia mundi BVCD-38204
②二つのヴァイオリン、ヴィオラと通奏低音のためのソナタ
CD「グスタフ・レオンハルト・エディション Vol.11」
グスタフ・レオンハルト指揮 レオンハルト・コンソート
TELDEC DAS ALTE WERK WPCS-6296
この2曲は1682年ニュルンベルクで出版された「2つ、3つ、4つ、5つの弓奏弦楽器あるいはその他の楽器と通奏低音のための12のソナタ集」の中のそれぞれ第2番と第7番になります。このソナタ集は彼がドイツに帰るきっかけとなったアントン・ウルリッヒ公に献呈されたものです。どちらも演奏時間10分に満たない短い曲ですが、緩―急―緩―急を組み合わせた荘重な音楽による典型的な教会ソナタの形式をとっています。官能的な和声と、明かるいイタリア的な旋律の美しさが際立っており、声楽が苦手、という人はこれらを聴くといいでしょう。特に第7番冒頭の半音階的進行の音楽にはハッとさせられます。どちらのアルバムにもビーバーやシャイト、ブクステフーデといったドイツ・バロック中期を代表する作曲家の作品が収録されていますが、これらの作品と聴き較べても、彼の才能がいかに高かったかわかると思います。彼の器楽曲はそのほかまとまったものとしては1667年ヴェネツィアで出版された11曲からなる室内ソナタ集Sonate da cameraがあり、これは前にも触れたようにヨハン・フリードリヒ公がヴェネツィアを訪れた際、公に献呈されています。この曲集のCDが現在入手できなくて残念なのですが、これは冒頭にシンフォニアを置いていて、この手法が後のバロック後期の組曲(教会ソナタに対し舞曲のリズムで構成される「室内ソナタ」)の形成につながっていったという点で音楽史上とても重要な作品集といわれています。
(3) レクイエム
アンサンブル・カンティクム ラ・カペラ・ドゥカーレ ムジカ・フィアタ・ケルン 指揮: ローランド・ウィルソン
Sony Classical SICC-49/50 (2枚組)
後世のレクイエムのように1曲としてまとまったものではなく、レクイエム(死者のためのミサ)を構成する「キリエ(主よ、彼らに永遠の安息を与えたまえ)」「ディエス・イーレ(怒りの日)」「アニュス・デイ(神の小羊)」を軸におき、そこにいくつかのモテットや器楽のシンフォニアを加え、更にそれぞれの曲の前にグレゴリオ聖歌を配置してレクイエムとしてまとめたものになっています。1612年メディチ家のために行われた「死者のためのミサ」を参考にウィルソンが曲を構成したそうです。ローゼンミュラーはヴェネツィアにいても自分の曲はそこで出版せず、ほとんど手書きの楽譜としてドイツに送っていたそうです。それが幸いして彼の作品は主にドイツ中部の各地の教会や聖歌隊に写本として伝えられ、今に残ることになったのです。このレクイエムに収められた作品もヴェネツイア時代の作品で、1690年代になってゲオルク・エスターライヒという人が写譜して集めた「ボーケマイヤー・コレクション」にすべて収められているそうですが、このボーケマイヤー(Heinrich Bokemeyer 1679-1751)〔注2〕という人、バッハと同時代の作曲家ですが作家というより楽譜の収集家として知られています。エスターライヒから受け継いだのでしょうが、彼はこの他にも様々な作曲家の曲を集めておりそのコレクションは膨大な量にのぼるそうです。特にローゼンミュラーについては彼の終焉の地となったヴォルヘンビュッテルのカントルを1717年から務めていたこともあって彼がかなりの数の曲を集めていた(116曲)ようです。
音楽は大胆な和声進行で、とても同時代の他の作曲家からは感じられない官能的な響きがしますが、単旋律のグレゴリオ聖歌と合わさるとどこか異次元の音楽のような妙な気分にさせられます。この時代の音楽を初めて聴く人には全曲を通して聴くのはちょっと辛いかもしれませんが、1曲目だけでも充分にその深遠な世界を味わうことはできます。
(4) 「宗教コンチェルト集~詩篇曲、マニフィカト、グローリア」(注2)ボーケマイヤーの膨大なコレクションはその後、バッハの死後始めての本格的な伝記を書いたあのフォルケル (Johann Nikolaus Forkel 1749-1818) のコレクションとなり、そこから更にベルリンの図書館に売却されています。
コンラート・ユングヘーネル指揮 カントゥス・ケルン
deutsche harmonia mundi BVCD-605
このCDには以下の曲が収録されています。
①主を恐るる者は幸いなり(Beatus vir)
②マニフィカト(Magnificat)
③われ主をたたえん(Benedicam Dominum)
④深き淵より(De Profundis)
⑤主よ、われは心をあげて(Confitebor tibi)
⑥グローリア(Gloria)
ここにはヴェネツィア時代に作られた膨大な数の詩篇曲から6曲が選ばれていますが、これらがどのコレクションから選ばれたのかなどジャケットやライナーノーツにも記載がないのでわかりません。ただ上記レクイエムの音楽とはまたかなり違った曲調で、全体にコンチェルタート様式(声と器楽の対比)が鮮明なのでよりバロック的といっていいでしょう。その意味ではとても聴きやすいCDです。ローゼンミュラーが器楽の分野で組曲(室内ソナタ)の形成に貢献したのと同様、この声楽の分野でもこれらの詩篇曲中に聴かれるコンチェルタート様式がすでにコンチェルト・グロッソのスタイルを示しているなど、注目すべき点がとても多いのです。更にこれらの音楽はシュッツとバッハの谷間を埋めるものとしてドイツの教会コンチェルト(この時代にはまだ現在のような「協奏曲」という意味ではなく器楽を伴う声楽曲を「コンチェルト」と言っていました)や教会カンタータの発展史に欠かせない重要な作品といわれています。このCDはそうした意味でもとても重要なものといえるでしょう。ぜひご一聴されることをお勧めします。
その他手元にあるCDの中では「預言者エレミアの哀歌」から聖木曜日と聖金曜日の音楽を収録した「バスのためのカンタータ集」(バス:ハリー・ヴァン・デル・カンプ Sony Classical CR-1886)がありますが、エレミアの哀歌はカヴァリエリやタリスなどもっといい作品があるのでここではとりあげませんでした。ただローゼンミュラーではありませんが、このCDに収録されているシュッツのカンタータ「わが子、アブサロン」にはちょっと驚きました。何箇所かまるでワーグナーかと思わせるようなブラスの響きが聴かれ、さすが「ドイツ音楽の父」であります。その他このCDにはバッハへとつながっていく重要な作曲家たちヴェックマン(Matthias Weckmann 1619頃-1674)やトゥンダー(Franz Tunder 1614-1667)、ブルーンス(Nicolaus Bruhns 1665-1697)といったあまり聴くことのできない珍しいカンタータが収録されています。
以上が私の手元にあるCDから聴くことのできる彼の音楽です。今後このコラムでなるべくCDをとりあげていこうと思いますが、最近はCDの発売されている期間がどんどん短くなっているので、廃盤になっていたりするかもしれません。その際はあしからずご了承ください。ただ番号が変ったり、廉価版となって再発されたりすることもあるので、日常的に広告などに目を通しておかれるといいと思います。
2009.01.19 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――2
3. ローゼンミュラーとトーマスカントルさて前置きが長くなりましたが話を本題のヨハン・ローゼンミュラーに戻しましょう。彼の正確な生年月日はわかっていませんが、1619年ごろ、中部ドイツ、もうチェコとの国境にも近いツヴィツカウ近郊のエルスニッツに生まれ、1640年にライプツィヒ大学の神学部に入学しています。そして当時トーマス教会のカントルを務めていたトビーアス・ミヒャエルTobias Michael(1592-1657)(カントル在任期1631-1657)のもとで音楽の勉強をしたと言われています。才能に恵まれ、1642年にはトーマス学校の助手となり、低学年に音楽を教えたとされています。1645年には最初の曲集「パドゥアーナPaduanen」という舞曲集が出版されますが、そのとき今では「ドイツ音楽の父」と呼ばれる大作曲家ハインリヒ・シュッツHeinrich Schütz(1585-1672)が「貴君の名前は、またたく間に、全ドイツに知れ渡るだろう」と祝辞を送ったそうです。その後宗教コンチェルト集「格言歌Kern-Sprüche」(1648)も出版されて名声は更に高まり、1650年にはトーマス学校の第一助手に抜擢され、翌年、トーマス教会よりは小さいですがライプツィッヒのもう一方の主要教会である聖ニコライ教会(バッハが「ヨハネ受難曲」を初演した教会)のオルガニストに任命されました。1653年にはライプツィッヒ市の参事会がとうとう彼に栄えある次期トーマスカントルの地位を与えることを約束したのです。こうして彼は第11代トーマスカントル(ちなみにバッハは第14代)になる筈でした。ところが事件は起きました。
1655年の春、彼は同性愛が発覚しトーマス学校の数人の生徒たちとともに逮捕、投獄されてしまったのです。生徒たちがどのくらいの年齢だったのか、それはわかりません。でも生徒(12~23歳)である以上年齢はかなり若いと思わなければなりません。一説では少年聖歌隊員(わが国でも「トマーナー」などという愛称で親しまれている)とされていますので、これはもう重大事件といっていいでしょう。少し前にアメリカのロック歌手がこんな事件を起こして騒がせ世界を揺るがす大きな裁判になったのはまだ記憶に新しいところですし、わが国の芸能界や海外の音楽界でも――某有名指揮者――そんな噂をときに耳にしたりしますが。ともあれこうして彼は就任前(注1)とはいえトーマスカントルという栄光の座を一度は手にしながら、その輝かしい将来を棒に振った(?)のでした。
ところが話しはこれで終わりません。彼はまんまと脱獄に成功し逃れてしまうのです。一説では脱獄後ハンブルクに向かったと言われていますが、確証はなく、ともかく最終的にイタリアのヴェネツィアに逃れ着いたのです。もしハンブルクからイタリアに向かったとすれば海路で渡ったのでしょうね。でも人生何が起こるかわかりません。将来を棒に振った筈の人生なのに、ヴェネツィアに渡ったことで思わぬ運が開けてくるのです。
4. 音楽の都ヴェネツィアとローゼンミュラー(注1) 昭和41年に発行された音楽の友社の標準音楽辞典(第一版)「トーマスカントル」の項には、トビーアス・ミヒャエルと並んでローゼンミュラーの名前もカントルとして掲載されており、その他古い音楽史の本にも同様の記載がありますのでひょっとすると事件当時すでに就任していた、とも考えられますが。
バロック時代、ヨーロッパの音楽の中心地といえばこのイタリア半島をおいて他にはありません。当時のイタリアはスペインやオーストリアに領有され、そこにいくつかの小国も加わって統一とは程遠い状態にありましたが、こと音楽や美術に関しては16世紀後半から18世紀にかけて空前の興隆を見せました。バロック芸術そのものがここイタリアの地で起こったのですから。
「バロック音楽」を語る際、その意味についてよく「いびつな真珠」(ポルトガル語のbaroccoに由来)という表現が使われたりしますが、いったい何がいびつだったのでしょう?この問題に踏み込んでいくととんでもない迷路に入っていきかねませんので詳しくは述べませんが、一つにはルネサンス時代の最高度に成熟したポリフォニー音楽(複数の声部が絡み合って高度に均整のとれた音楽)から抜け出して、もう少し人間的な音楽に立ち返ろうとして起こった運動だったのだと思います。ですからそうした均整よりもっと人間的な感情表現や生活の営みを音楽にとりいれようとしたのでしょう。これは音楽に限らず当時のイタリアの芸術全体にいえたことです。そうした中で16世紀後半から17世紀前半にかけて活発に活動したカメラータCamerata(「仲間たち」といった意味)と呼ばれるフィレンツェのグループから生まれた通奏低音を伴う音楽の様式(モノディー)や、ソロと総奏(トゥッティtutti)による対比の芸術ともいうべきコンチェルト様式(声楽の場合はコンチェルタート様式)などが、その代表的な特徴として生まれたと言っていいでしょう。これ以上は踏み込みませんがともかくイタリア、中でもヴェネツィアにおける音楽の状況は類を見ないほど華やかなものでした。ルネサンスからバロックにかけてヴェネツィア楽派と呼ばれる、そうそうたる作曲家がここに輩出します。アンドレア、ジョヴァンニの両ガブリエリ(伯父、甥の間柄)は壮麗な音楽を聞かせてくれますが、特にジョヴァンニは史上初めて音楽に強弱を採り入れたといわれるソナタ「ピアンネ・フォルテSonata pian'e forte」(現在ブラス・アンサンブルの重要なレパートリー)がよく知られています。またヴェネツィア楽派は有名なサン・マルコ寺院を中心に活動しますが、この寺院の建物の構造を生かして、二重合唱や合奏などステレオ効果満点の音楽を作曲しています。この技法はシュッツによってアルプスを越えてドイツにもたらされ、後のバッハの不朽の名作「マタイ受難曲」へとつながっていきます。両ガブリエリの後にはモンテヴェルディClaudio Monteverdi(1567-1643)、そしてバッハと並ぶバロックの巨匠ヴィヴァルディAntonio Vivardi(1678-1741)までその栄光は引き継がれていきます。
こうした華やかな音楽の都に逃れ着いたローゼンミュラーにとってその環境は願ってもないものでした。というよりヴェネツィアという地は彼にとって必然ではなかったのでしょうか。おそらく彼はシュッツに対して大きな憧れと尊敬を抱いていたでしょう。1645年以降にもシュッツは何度かライプツィッヒを訪れていますし、何しろ彼の最初の曲集にシュッツは祝辞を寄せており、またローゼンミュラーはというとシュッツが1647年に出版した「宗教的シンフォニア(シンフォニア・サクレ)集 第2巻」のライプツィッヒでの販売代理人になっているのです。ですから当然親交はあったと思います。シュッツは若い頃ヴェネツィアに留学(1回目1609-13)し、あのジョヴァンニ・ガブリエリの弟子となって壮麗な二重合唱やイタリアのコンチェルト、そしてモノディーといった様式をドイツにもたらし、その後のドイツ音楽に大きな発展をもたらした(そんなことから「ドイツ音楽の父」と呼ばれる)ことは先にも触れたとおりです。ですから誰もが当時シュッツに対して尊敬の念を抱いていたと思いますし、彼のたどった道を自分も歩きたい、と思って不思議はありません。したがってローゼンミュラーがヴェネツィアに憧れを持っていたことは間違いないでしょう。ですから彼の逃亡先がヴェネツィアであったことは偶然ではないと思います。ひょっとして逃亡の際シュッツを頼ってドレスデンに行き、彼の手配でヴェネツィアに向かった、なんていうとちょっと話は面白くなるのですが。何しろライプツィッヒからシュッツの住むドレスデンまでは近く、またそこからハンブルグへはエルベ川を下っていけば行きつくのです。でもこれは冗談です。
さてローゼンミュラーがヴェネツィアに着いたのがいつ頃なのか正確にはわかりませんが、1658年のはじめに彼はサン・マルコ寺院のトロンボーン(この時代は「サックバットSackbut」といった)奏者になっています。もともとドイツでしっかりとした音楽教育を受け作曲家としての才能も発揮していただけに、イタリア音楽に接するとその優れたところをどんどん吸収してここヴェネツィアでも作曲家として頭角を現していきます。彼の名声は高まり、それは母国ドイツにも知れ渡るようになりました。1660年ヴァイマール宮廷は使者をヴェネツィアに送って彼の楽譜を購入させたといいます。そして1673年から74年にかけてドイツの作曲家ヨハン・フイリップ・クリーガー(Johann Philipp Krieger 1649-1725)が彼に弟子入りするためにヴェネツィアにやってきています。更に1678年から1782年まで彼はピエタ養育院付属音楽院の作曲の教師にもなっているのです。その約20年後にあの「赤毛の司祭」と呼ばれたヴィヴァルディがヴァイオリン教師としてここに赴任してくることになるのです。
ローゼンミュラーはドイツから追放された状態でしたので、祖国に戻ることができませんでしたが、ブラウンシュヴァイク-リューネブルク家(ハノーファー近郊)は、ヨーハン・フリードリヒ公(1625-1679)が1667年にヴェネツイアを訪れた際ローゼンミュラーから最初のソナタ集を献呈されていたことをきっかけに親交を深めていました。そして1682年に公のいとこにあたるアントン・ウルリヒAnton Ulrich (1633-1714)がヴェネツィアに外遊した際、彼を引き連れてとうとうドイツに連れ戻してしまったのです。かくして彼は再び祖国ドイツの地を踏むことができ、ヴォルフェンビュッテル宮廷の楽長になったのでした。彼がどれくらい望郷の念を抱いていたかなどは知る由もありませんが、帰国して平穏を取り戻したのか、その2年後の1684年、彼はその波乱に富んだ人生に幕を閉じ、ヴォルフェンビュッテルに埋葬されました。それはバロック最大のそして最後の巨匠ヨハン・セバスティアン・バッハが生まれる一年前のことでした。
以上がローゼンミュラーの生涯です。次回はCDの紹介を含め、彼がその後の音楽史に及ぼした影響などについて触れてみたいとおもいます。
2009.01.12 (月) トーマスカントルのスキャンダル?――1
1. 事件との出合い遠い昔、わたしが高校生の頃、団塊世代の真っ只中にあって「受験戦争」などと呼ばれた時代のことです。私は学校から帰ってくるなり、すぐに寝ることにして、勉強と言えば夜、世の中が静まり返った頃起きだして、朝まで勉強するという習慣を繰り返していました。このほうが集中でき、知識を詰め込むことができたのでした。いやそう思っていただけのことかもしれませんが。ともあれそんな習慣は浪人生活まで続きました。
その頃私の唯一の楽しみといえば、朝6時のニュースのあとから始まる「バロック音楽の楽しみ」というFM放送でした。それまでクラシックと言えば、ベートーヴェンやモーツァルトなどごくありふれた音楽ばかりしか知らなかったので、この番組は私にとても新鮮で大きな喜びを与えてくれたのでした。番組を構成していたのは音楽学者で当時東京芸術大学教授の服部幸三先生と、立教大学教授の皆川達夫先生でした。このお二人が週代わりで交代しながら巧みなお話しと素晴らしい音楽を届けてくれたのです。どちらかというと服部先生はバロック期の、また皆川先生はルネサンス期の音楽が中心になっていたと思いますが、もちろんお互いにそれらはオーバーラップしながら、ともかくも珍しい楽しい音楽を次から次へと聴かせてくれたのです。
めでたく大学に入って時間ができると、オーケストラに入部しながらその当時に聴いたバロックやルネサンス時代のレコードを片っ端から集めて聴くようになりました。とはいえ貧乏学生のこと、カネもなく、仕方なく新橋や有楽町、神田などの輸入盤やセコハンを扱っている店にばかり通っていました。アルバイトで稼いだカネも何はともあれこうしたレコードに消えていきました。そんなわけで当時のArchivやNonesuch、Vanguardといったレーベルのレコードには愛着があり今でも大切に保管しています。
さてそんなある朝の番組内でのこと、その日は服部先生のご担当で、あるドイツの作曲家の作品が紹介されたのですが、そのときの解説があまりに当時の私には強烈で、ですからその話の内容だけが頭に残り、何の曲がかけられたのかさえ全く覚えていないのです。それはドイツ・バロック中期の作曲家なのですがそのときのお話しは「男色の罪により投獄された」と言う内容で、そのことをわざわざ「ちゃんと権威ある音楽辞典にも載っている事実」としてすごく強調されていたので、それがとてもおかしかったのと同時に、「そんな昔にそんなことってあったのだろうか?」と当時くそまじめな一高校生は思ったのでした。いま考えればそんなこと何も今に始まったことではなく、大昔からあったことでデカメロンやカルミナ・ブラーナの世界と較べればむしろまだかわいい方なのかもしれません。そんなわけで私はその作曲家の名前を終生忘れることができなくなってしまったのです。
さてもう古学ファンなら当然ご存知ですよね。その作曲家はヨハン・ローゼンミュラーJohann Rosenmüllerといいます。最近そのローゼンミュラーのCDをいくつか聴き、昔のことが懐かしく思い出だされてきたのです。そんなわけで彼をとりあげてみました。これがまたなかなかにドラマチックな生涯をおくっています。
2. トーマス教会とトーマスカントル
彼の話に入る前にここで簡単にライプツィヒの街とトーマス教会について触れておきます。
ライプツィヒは紀元900年ごろプライセ川、パルテ川そしてヴァイセエルスター川という三つの川の合流する地点にできた村Lipzyk(スラヴ語で「菩提樹」の意味)がその発祥となり、ここは神聖ローマ帝国時代(962~1806)北イタリアからバルト海へ南北に抜ける「皇帝の道」と、ライン川からロシアへ東西に走る「王の道」が交差する地にあり、帝国の東端として異教徒スラヴを監視する前線にもなっていました。そうした交通の要衝、戦略上の拠点としてこの地は発展していきました。ドイツ最古の大学の一つといわれるライプツィヒ大学が15世紀(1409)には誕生し、そのせいか古くから印刷業が盛んで書籍文化が栄えました。現在楽譜出版で有名なペータースやブライトコプフ(Breitkopf & Härtel)もこのライプツィヒで起こっています。
トーマス教会は12世紀に町の教会として建てられたのがその始まりですが、1212年に修道院に改められここにアウグスチノ修道会聖トーマス教会が誕生したのです。ですからその歴史は中世に遡ります。話しが横にそれますが、これもかつて番組内で服部先生から教えていただいた話しで、中世に立てられた教会は「その町の大きさを現す」ことになります。戦争が起きて街が攻められても、市民は教会に逃げ込めば命は助かったのです(異教徒との戦でない限り)。ですから教会はそれだけの大きさを持っていなければなりません。パリのノートルダム寺院(1225年)やシャルトル大聖堂(1220年)など、あの巨大な建物にどれだけ人間が収容できたか、それがわかれば当時の街の人口もわかる、ということになります。最大の大聖堂といわれるフランスのランスの大聖堂はゆうに1万人を収容できた、と言われています。このトーマス教会は15世紀後半にゴシック様式の教会に建て替えられたので作られた当時の大きさはわかりませんが、それほど大きなものではなかったと思います。
トーマス教会という名前の由来ですが、これにはちょっとした逸話が残されています。「1220年、吟遊詩人ハインリヒ・フォン・モルンゲンが十字軍に従軍した帰途インドに行き、イエス・キリストの十二使徒聖トマスの遺骨をこの地に持ち帰った」ところからこの名前がつけられたというのです。しかしながら上述のように、トーマス教会という名前はその8年前にすでにつけられていたのですから、この話には矛盾があります。その他にもいくつか説がありますが、逸話というのは所詮そんなものでしょう。ただこの聖トマスに少し触れておきますと、確かに彼はペルシャやインドを布教活動の地としていたそうで、現在南インドの大都市マドラス(1996年チェンナイに改名)にあるサン・トーマ大聖堂は彼の墓の上に建てられたといわれています。また彼には英語でdoubting Thomasなどとありがたくないあだ名がつけられていますが、その由来はイエスが復活して弟子達の前に現れたとき彼だけその場にいなかったので、「自分は実際に(イエスの)手足の釘痕やわき腹の槍痕があるかどうか、確かめるまでは信じない」と言ったことからそんな名前がつけられ、物語としてはその八日後に再びイエスが現れてそうさせたとか。そのせいか絵画に描かれるトマスはいつも指をイエスのわき腹に突っ込んでいるそうです。
話が脱線してごめんなさい。さてそのトーマスカントルですが、初代のカントルはゲオルク・ラウ(Georg Rhaw1488-1548)という人です。このラウ以前にもトーマスカントルと言われた人は存在します。15世紀半ばにヨハネス・ステッファニ(ステッファニ・フォン・オルパともいう)というカントルがいたことが知られており、その他ルートヴィヒ・ゲッツェなどの名前も他の資料で見ることができます。ではなぜゲオルク・ラウなのか、しかも彼はほんの2年ほどしかその地位にいなかったのに? それはラウ以前のカントルの記録があまりはっきりしないことと、最初の方でも述べましたが、カトリック時代のカントルはその性格が異なり、現在のプロテスタントのカントルとしてはラウが最初ということになるからです。
1488年生まれのラウは1512年ヴィッテンベルグ大学に入学し、卒業後その地で出版社に勤めました。ヴィッテンベルクといえばすぐにある人物の名前が浮かんできますね。そうマルティン・ルター(Martin Luther1483-1546)です。1517年、ルターは「95箇条の提言」をヴィッテンベルク城教会の扉に打ち付け、ここに宗教改革の口火が切られたのでした。ラウがそのときどんな立場にいたのかはわかりませんが、その事件については当然知っていたでしょう(ドイツの音楽学者クリストフ・ヴォルフは彼が「改革運動に加わっていた」としています)。翌1518年彼はヴィッテンベルクを離れ、このトーマス教会のカントルに就任します。そしてトーマス教会にも宗教改革の波が押し寄せます。1519年6月トーマス教会でルターとカトリックの論客として知られるヨハン・エック(Johann Eck)との間で公開討論会が開かれます。ラウはそのとき開始前の礼拝用ミサを作曲しています。そして彼は翌年自らプロテスタントに改宗し、またトーマス学校も改宗させてしまった、といいます(前掲ヴォルフによる)。それが原因でラウは学校当局から解任され、わずか2年というトーマスカントルとしての短い任期を終えたのでした。その後ラウは再び出版の世界に戻り、以後プロテスタント音楽の普及に大きな影響を与えました。1539年5月25日(聖霊降臨祭)トーマス教会でマルティン・ルターによる歴史的な説教が行われ、この日をもってトーマス教会とライプツィヒ市は正式にプロテスタントに改宗することとなり、同時にカントルは市の職員としての身分になりました。以後ライプツィヒはルター派の強固な牙城となっていきます。
ラウ以降のカントルもですから当初はカトリックの時代がしばらく続いていたわけですが、どの音楽史の本でもこのラウをもって初代トーマスカントルとしています。このあとの記述でバッハを第14代カントルと表記しますが、実はこれも諸説あり、私は服部先生の「バロック音楽のたのしみ」(1979、共同通信社刊)、及び正木光江氏によるシャインのCD「オペッラ・ノーヴァ第2巻」(ドイツ・ハルモニア・ムンディBVCD-6)のライナーノーツに記載された表記にしたがって第14代としました。このあたりの事情は最後に<参考>として掲載しますので、興味のある方はお読みください。
2009.01.08 (木) ようこそ古楽の花園へ!
今年から新たにクラシック音楽のページを投稿させていただくことになりました。簡単に自己紹介をさせていただきますと、私はいわゆる団塊の世代に属する人間で、会社に入ってからは音楽の仕事に携わり、クラシック音楽の企画や制作を行ってきました。会社での人生もほぼ終えようとしている今、もう一度ちょっと過去を振り返り、そして少しでもクラシック音楽の楽しさを皆さんにわかってもらえたら、と思い筆をとった次第です。このサイトをご覧になる方はジャズやポピュラー音楽のファンが多いと思いますので、そうした方々にもなるべくわかりやすく書いていこうと思います。ただクラシック音楽と言っても長い歴史と、膨大な量の音楽があります。古典派以降の音楽は同じサイトにある岡村さんにおまかせすることにして、私はそのなかでとくにバロック音楽、それもバッハを中心としたその周辺を書いていきたいと思いますが、時には脱線してしまうこともあるかもしれません。その節はご容赦ください。何しろこの種の音楽は底なし沼のように深く、ちょっと話しがそれるだけでどこまでいってしまうかわからないところがあります。なるべくそうした迷路には入らないようにしたいと思います。また仕事も終わりに近いとはいえまだ宮使いの身、書いたり調べたりするのはとても時間を必要とします。それだけの時間はまだ作れませんので、定期的に話題を提供するのはちょっと難しいかもしれません。がんばって書いていこうと思いますが、あらかじめご了承ください。
本来こうした文章は実名を公表して書くのが正しいと思うのですが、今後音楽制作の裏話しなどにも触れたいと思っていて、そんなとき実名で書いてしまうと人に思わぬ迷惑をかけてしまうとも限りませんので名前は伏せさせてください。ですから筆名として、わが敬愛するバッハの音楽にあやかり「たそがれのフェーブス」とでもしておきます。
今なぜ古楽なのでしょう?
ここ10年ほど古楽ブームとも言われ、かつてないほどこの世界は活況を見せています。そもそもは古楽器から出発してバロックや古典派の音楽が中心になっていた古楽ですが、今やロマン派の世界にまで拡大したため、最近では古楽器とはいわずピリオド楽器などと呼んだりしています。そしてその演奏はというとそれが実に素晴らしいのです。ガーディナーやヘレヴェッヘによるベート-ヴェンの交響曲やミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)、ブラームスのドイツ・レクイエム、そしてフォーレのレクイエムなどどれも第一級の演奏だと思います。ブルックナーの交響曲までもありますね。一方現代楽器の方はというとかつての巨匠たちが他界してちょっと沈滞しているように思えます。それでも少し前に聴いたデヴィッド・ジンマンによるベートーヴェンの交響曲全集などはちょっとした衝撃でした。でもこれも一部ピリオド楽器を使用したり、また古楽奏法をとりいれたり、と結局は現代楽器の側からの古楽へのアプローチから生まれた演奏でした。これは今後現代楽器が進む一つの方向性を示したものと私は思っています。現にそれ以後ほかのオーケストラからもこうした取り組みが出てきています。そんなわけで古楽が今ちょっとした流行のようにも感じられますが、実は私が学生の頃も似たような現象があり、バロック・ブームなどといわれていました。その代名詞のように言われたのがイ・ムジチによる四季でした。今の古楽ファンからすると笑われてしまいそうですが、でもこれが空前の大ヒットになったのでした。まずはそんな時代のトーマスカントルにちなんだお話しから始めたいと思います。
Ⅰ. トーマスカントルのスキャンダル?
トーマスカントルといえばすぐに私たちは大バッハ(ヨハン・セバスティアン)を思い起こします。このトーマスはいうまでもなくドイツ中部、かつては東ドイツの主要都市であったライプツィッヒの聖トーマス教会のことをいいます。そしてカントルとは、ドイツ語の辞書によれば「教会(聖歌隊)の合唱指揮者」ということになります。カトリックの場合はそれでいいのですが、プロテスタントの場合もっと範囲は広くなり教会内の音楽監督やその付属の学校(音楽学校ではない)ひいては市全体の音楽監督にもなっていたわけでその任務を全うするのはたいへんな労力が必要とされたでしょう。でもそれは同時にそれだけの権力と名声をも得ることをも意味します。そのトーマスカントルに危うく大スキャンダルとなる事件がありました。
