ブルーバイユーからの手紙 2009年7月~2013年12月
2013/11/29 (金) Blue Brain vs Pink Brain
2013/10/30 (水) Grand Illusion
2013/09/21 (土) Men in the Kitchen
2013/07/23 (火) Southern Soul
2013/01/17 (木) How Can You Sleep at Night
2012/11/13 (火) 高揚の秋
2012/09/29 (土) Ain't No Mountain High Enough
2012/06/22 (金) If You Can
2012/03/18 (日) Nickname
2011/12/20 (火) jealousy と envy
2011/09/25 (日) ダズンズ
2011/07/17 (日) Raw & Odor
2011/04/17 (日) Little Boy
2011/01/15 (土) 男はBBQ、女はパイ
2010/12/04 (土) Saturday Night Live
2010/10/31 (日) Mississippi Burning
2010/09/04 (土) Six Feet Under
2010/07/01 (木) Knock the Door
2010/04/23 (日) Friend Before Lover
2010/04/11 (日) 女性にモテる職業
2010/03/06 (土) 南部のミスコン
2010/01/18 (月) ハイチの友人
2009/12/20 (日) ニューオーリンズのクリスマス
2009/11/23 (月) サザン・ホスピタリティ 1
2009/10/30 (金) ポンチャントレイン・レイク・コーズウエイ
2009/10/12 (月) ヴードゥーの女神たち
2009/09/16 (水) 理想郷という名の裏通り II
2009/08/25 (火) 理想郷という名の裏通り Ⅰ
2009/08/13 (木) ニューオーリンズのB級グルメ
2009/07/22 (水) Scent of New Orleans
2013/10/30 (水) Grand Illusion
2013/09/21 (土) Men in the Kitchen
2013/07/23 (火) Southern Soul
2013/01/17 (木) How Can You Sleep at Night
2012/11/13 (火) 高揚の秋
2012/09/29 (土) Ain't No Mountain High Enough
2012/06/22 (金) If You Can
2012/03/18 (日) Nickname
2011/12/20 (火) jealousy と envy
2011/09/25 (日) ダズンズ
2011/07/17 (日) Raw & Odor
2011/04/17 (日) Little Boy
2011/01/15 (土) 男はBBQ、女はパイ
2010/12/04 (土) Saturday Night Live
2010/10/31 (日) Mississippi Burning
2010/09/04 (土) Six Feet Under
2010/07/01 (木) Knock the Door
2010/04/23 (日) Friend Before Lover
2010/04/11 (日) 女性にモテる職業
2010/03/06 (土) 南部のミスコン
2010/01/18 (月) ハイチの友人
2009/12/20 (日) ニューオーリンズのクリスマス
2009/11/23 (月) サザン・ホスピタリティ 1
2009/10/30 (金) ポンチャントレイン・レイク・コーズウエイ
2009/10/12 (月) ヴードゥーの女神たち
2009/09/16 (水) 理想郷という名の裏通り II
2009/08/25 (火) 理想郷という名の裏通り Ⅰ
2009/08/13 (木) ニューオーリンズのB級グルメ
2009/07/22 (水) Scent of New Orleans
2013.11.29 (金) Blue Brain vs Pink Brain
男と女の違いは脳なのか、環境なのか?そんな男女脳の違いを示すという簡単な脳テストをやってみた。その結果、私の脳は8:2で、男寄りという結果が出た。なるほど、昔から男顔だといわれ、性格も男っぽいといわれてきたのは、自分の脳が男寄りなのだと納得した。こう書くと、いかにも性格がサバサバしていて、男性が得意とする空間認知にも長け、理論的に考えられる、なかなかデキた女みたいな良い誤解を受けそうだが、ただ、女性が得意とすることの点数が低く、男性が得意とすることの半数ほどがそこそこだったというだけの、なんとも中途半端な脳のジェンダーが判明しただけであった。最近はそんなどっちつかずの脳をもった人も多いのではないかと思える。
しかし、確かに男と女の違いを感じるときはある。
私は男性には男っぽさと少年ぽさが共存すると思う。男っぽい人ほど子どもっぽい。男気があって、女性を守ろうと一途になったり、リーダーシップを見せ、男同士でガッツリとハグし合い、行動力も決断力もある男性が、じつは、物語に感動して涙したり、幼児のようなわがままを言ったり、女性に対して母親にするように、あるいは、母親にもできなかったように甘える場面にたびたび遭遇する。子どもっぽいなあ、と思いながらも微笑ましい。
ところが、女っぽい女性は、少女のようだろうか?一見そうみえるが、私には、かなり大人のように思える。女性としての役割、立ち位置、幸せをしっかり理解し、追及し、手に入れる強さを持っていると思う。したたかととらえられるかもしれないが、私は、そんな女性は逆に清々しくさえ思える。あのケネディの嫁、ジャクリーン夫人はそんな女の代表であろうかと思うが、彼女のおかげでケネディもオナシスも幸せだったに違いない。私自身は、8割男脳で女性としての魅力が全く足りないので、羨ましくてもジャクリーンのようには生きられない。そんな自分でも、世の中の男らしい男性達にはずいぶんと助けられてきた。そのおかげで私も、2割の女らしさを失わないで過ごせたのだろう。
 サンクス・ギビングが終わると、街はクリスマス一色になる。私も毎日、ルーサー・ヴァンドロスの、テンプテーションズの、テイク6のソウルフルなクリスマス・ソングを聴いて、気持ちが高まっている。そんなとき、男と女の感じ方の違いを描いた、ずいぶん前の映画の一場面を思い出した。「About Last Night」という、初々しいロブ・ロウとデミ・ムーア共演の映画である。80年代のアメリカは、若い男女がかたっくるしくなく愛し合おうよ、という風潮だった。好きだったら将来のことは考えず、とにかく一緒に暮らそう、その代わり、束縛、嫉妬はなし、のようなカジュアルなスタイルの恋愛が流行っていた。映画のタイトルはつまり、「昨夜のことは聞くな」という意味があるのだと思う。映画でも、プレイボーイのロブ・ロウが、デミ・ムーアにほだされる感じで同棲生活を始めるのだが、そのなかでだんだんと、二人の関係がギクシャクしてくる。お決まりの、女は嫉妬し、束縛したがり、男は自由と刺激を求め、という感じである。そんな二人が、同棲して初めてのクリスマスを迎えるとき、その料理でもめる。男性は「クリスマスなんだから、ターキーに決まっているだろう」、女は「二人なんだからターキーは余る。ハムでしょう」となる。そんなどうでもいいことから、ついに二人は同棲を解消する。せいせいした感のロブ・ロウと傷つくデミ・ムーアだが、次第にロブ・ロウは同棲生活が懐かしくなり、デミ・ムーアの大切さに気づき後悔し、その頃はデミ・ムーアの方はしっかり立ち直って新しい人生をスタートしている、というオチだったように覚えている。
サンクス・ギビングが終わると、街はクリスマス一色になる。私も毎日、ルーサー・ヴァンドロスの、テンプテーションズの、テイク6のソウルフルなクリスマス・ソングを聴いて、気持ちが高まっている。そんなとき、男と女の感じ方の違いを描いた、ずいぶん前の映画の一場面を思い出した。「About Last Night」という、初々しいロブ・ロウとデミ・ムーア共演の映画である。80年代のアメリカは、若い男女がかたっくるしくなく愛し合おうよ、という風潮だった。好きだったら将来のことは考えず、とにかく一緒に暮らそう、その代わり、束縛、嫉妬はなし、のようなカジュアルなスタイルの恋愛が流行っていた。映画のタイトルはつまり、「昨夜のことは聞くな」という意味があるのだと思う。映画でも、プレイボーイのロブ・ロウが、デミ・ムーアにほだされる感じで同棲生活を始めるのだが、そのなかでだんだんと、二人の関係がギクシャクしてくる。お決まりの、女は嫉妬し、束縛したがり、男は自由と刺激を求め、という感じである。そんな二人が、同棲して初めてのクリスマスを迎えるとき、その料理でもめる。男性は「クリスマスなんだから、ターキーに決まっているだろう」、女は「二人なんだからターキーは余る。ハムでしょう」となる。そんなどうでもいいことから、ついに二人は同棲を解消する。せいせいした感のロブ・ロウと傷つくデミ・ムーアだが、次第にロブ・ロウは同棲生活が懐かしくなり、デミ・ムーアの大切さに気づき後悔し、その頃はデミ・ムーアの方はしっかり立ち直って新しい人生をスタートしている、というオチだったように覚えている。私もアメリカ時代、恋していた男性からアパートをシェアしよう、といわれたとき(アメリカでは男女がルームメイトになることも普通だった)、心が動いたものの断ったのは、やはり、アメリカに来て、本分である黒人文化の勉強もしっかりしていない志半ばで、恋愛に浮かれたくなかったからだ。その彼のことは、最高に最高級に大好きだったのにも関わらず、意地を通した。そして、一人前になって初めて恋愛も堂々とできると考えていた。そのことをシスターの友人に話したら「マッチョなんだから!」と、私以上に惜しがられた。そんなときでも、私の8割の男脳が女としての幸せを邪魔していたのである。
今年のクリスマスのディナーは、何を作ろう。
うちも息子と二人だ。大きなターキーなんてもってのほか。ビーフは高いしハムはつまらない。お財布にシビアな女性脳と、お祭り感を大事にする男脳が検討した結果、安上がりでおいしいロースト・ポークにしようかと思っている。ケーキは、自分はアンリシャルパンテイエのノエルに惹かれるが、ここはクリスマス、息子の大好きなデメルのザッハトルテにしょうか、と考えるのも楽しい。こういうときは、男脳でも女脳でもなく、母親脳になっていて、とても幸せを感じるときである。
2013.10.30 (水) Grand Illusion
ラスベガス、ニューオーリンズ、ニューヨーク……私が行ったことのあるアメリカのエンターテインメントの3大都市である。ニューヨークは経済の中心都市でもあるし、街ごとにそれぞれ趣は異なるが、ラスベガスなどは、作り物めいたまがまがしさが感じられる独特の雰囲気に、空港へ降り立ったとたんに取り囲まれてしまう。ニューヨークはそれこそ、一流のミュージカル、プレイが安心してブロードウエイで見られる。そして、オフ、あるいは、オフオフのブロードウエイでも、珠玉の作品に出会えることがたびたびある。
クリスマス・イブの日、私はハイチの友人、ショーン、ウノ、ワノと過ごすためニューヨークへ行った。ニューヨークへ着くとその日のマチネのプレイをチェックした。そこで、目に留まったのが、オフオフでの黒人男女4人による舞台劇だった。一枚ならまん中のいい席が取れるというので、早速購入し、劇場へ行くと、なんと斜め前にエディ・マーフィーが座っていた。観客は全員黒人である。他の観客も気がついていたに違いないが、だれもサインを求めて駆け寄ったりしない。幕間にも何も起こらなかったが、舞台が終わりカーテンが下りたとたんに、観客が口々に「メリー・クリスマス、エディ!」と声を上げ、それに答えて、エディ・マーフィーも立ち上がり、「メリー・クリスマス、エヴリボディ!」とあの魅力的な笑顔を振りまいた。なんとも素敵なイブの幕開けとなった。
ニューオーリンズは街全体がライブ会場である。ストリートは音楽とリズムに溢れている。八十過ぎのおじいさんがブルース・ギターを爪弾き、10代の少年達が和になってステップ・ダンスを披露し、ドアが半分開いた店の奥では、美しいストリッパーたちが、ハリケーン(ニューオーリンズの強いカクテル)片手の観光客を誘っている。
ラスベガスは一番、嘘っぽい作り物めいた街だった。ラスベガスで過ごすなら、ギャンブルとエンターテインメントしかない。私が行ったとき、息子はまだ未成年だったので、ギャンブルはできない。しかし、息子はくじ運がすごくいい。少し息子に稼いでもらおうと思い、こっそりと息子とスロット・マシーンに近づいたら、警備員が飛んできて叱られてしまい、すごすごと引き下がった。というわけで、ショウを見まくった。ブルーマンで笑い、シルク・ドゥ・ソレイユの“O”で水をかぶり、どれも素晴らしかった。ある夜のショウでグラディス・ナイトのライブがあるということを知った。ソウルファンとしては、行かないわけには行かない……のだが、その日は私がラスベガスにいく一番の目的だったショウと重なっていた。デイビッド・カッパーフィールドのイリュージョンである。彼はロン毛をなびかせ、シャツのボタンをへそ近くまで外し、バイクに乗ってステージに登場する元祖ビジュアル系イリュージョニストである。当時はもう落ち着いた中年であったが、ショウのスタンスは変わっていなかった。早速、「Who want to pregnant my baby?(誰か、僕の子どもが欲しくない?)」と、女性客を騒がせる。多くの女性観客がきゃあきゃあと手をあげ、「私!私!」と、隣のツレの男性を忘れさって欲望丸出しである。そのイリュージョンの肝心なオチは忘れてしまったが、赤ちゃんの名前を当てたり、女性が瞬間移動したり、もちろん、舞台に上がった女性客も仕込みであろう。そうわかっていても、楽しい。最後は、デイビッド・カッパーフィールドが消えるというイリュージョンで、それも何人かの観客を舞台にあげ、そのタネ明かしをするという。音楽を流しながら観客席にシルバーの大玉を何個か回し、音楽が止まったところでボールを手にした観客数人が舞台に上がれるという説明があった。デイビッド・カッパーフィールドの子どもは妊娠したくないが、消えるところは見てみたい。なんだか、いけそうな気がして、大玉が来るのを今か今かと待ち、まさに、音楽が止まろうとするそのとき、私のところへ玉が転がり、「やった!」と、大玉を受け止めようと手を広げた瞬間である。隣のオジサンに、がつっととられてしまった。私と息子は「え?」と顔を見合わせたが、オジサンは「ワーォ!」と、大玉を持ちあげて大喜びである。そこでもすごすごと引き下がったが、あとで考えると、タネ明かしなんて見なくて良かった。夢を見るのが楽しくてイリュージョンを見ているのだから、と納得した。
 私はフーディーニに始まり、イリュージョニストが大好きだ。先日公開された映画「Grand Illusion」は、トレイラー版を見たときから、見たくてたまらず楽しみにしていた。なんといっても大好きな俳優、マーク・ラファロがでる。彼はサポーティング・アクターで出ることが多い役者だが、その人間性をたっぷりと滲ませる多くの演技を見て大ファンになった。映画の内容は、4人のイリュージョニストが、ラスベガスの舞台で320万ユーロの大金を一瞬にして持ち去り、さらに、ニューオーリンズで、ニューヨークで、大掛かりなマジックを仕掛けるというものである。それを追うFBI捜査官の役がマーク・ラファロだ。物語の冒頭から、ワクワク、ドキドキ、まさに最後まで興奮のし通しだった。音もいい、映像も最高、役者も素晴らしい、展開も演出もさすがハリウッドと唸らせる最高級のエンターテインメントだった。
私はフーディーニに始まり、イリュージョニストが大好きだ。先日公開された映画「Grand Illusion」は、トレイラー版を見たときから、見たくてたまらず楽しみにしていた。なんといっても大好きな俳優、マーク・ラファロがでる。彼はサポーティング・アクターで出ることが多い役者だが、その人間性をたっぷりと滲ませる多くの演技を見て大ファンになった。映画の内容は、4人のイリュージョニストが、ラスベガスの舞台で320万ユーロの大金を一瞬にして持ち去り、さらに、ニューオーリンズで、ニューヨークで、大掛かりなマジックを仕掛けるというものである。それを追うFBI捜査官の役がマーク・ラファロだ。物語の冒頭から、ワクワク、ドキドキ、まさに最後まで興奮のし通しだった。音もいい、映像も最高、役者も素晴らしい、展開も演出もさすがハリウッドと唸らせる最高級のエンターテインメントだった。 マジシャンのリーダー役には「ソーシャル・ネットワーク」でナードな主役を演じたジェシー・アイゼンバーグが、がらっと変わりかっこいい男を演じている。一番歳若のマジシャン役のディヴ・フランコは、甘いマスクがどこかファミリアな感じがしたが、あの女性キラー俳優、ジェームス・フランコの弟だそうである。甘いマスクだけでなく、ラスト間近にみせるアクションは素晴らしかった。しかし、なんといってもマーク・ラファロがいい。一匹狼で影がある不精ひげのFBIエージェント。そんな役もマーク・ラファロが演じると、どこか暖かい。
マジシャンのリーダー役には「ソーシャル・ネットワーク」でナードな主役を演じたジェシー・アイゼンバーグが、がらっと変わりかっこいい男を演じている。一番歳若のマジシャン役のディヴ・フランコは、甘いマスクがどこかファミリアな感じがしたが、あの女性キラー俳優、ジェームス・フランコの弟だそうである。甘いマスクだけでなく、ラスト間近にみせるアクションは素晴らしかった。しかし、なんといってもマーク・ラファロがいい。一匹狼で影がある不精ひげのFBIエージェント。そんな役もマーク・ラファロが演じると、どこか暖かい。マジックシーンもさることながら、ニューオーリンズのマルディグラの真っ最中に、バーボン・ストリートでロケをしたシーンなど、見所が満載である。そのほか、モーガン・フリーマン、ウディ・ハレルソンなど素晴らしい役者が名演技を見せてくれる。とにかく、爽快、痛快、見終えたあと晴れ晴れとする、最高のエンターテインメント映画であった。まさに、イリュージョンに魅せられた2時間だった。
ニューヨークの劇場でエディ・マーフィーを見たクリスマス・イヴの日。芝居が終わりひとりで通りを歩いていると、真っ黒の長いリムジンがすうっと寄って来て、窓が静かに開いた。中から黒人男性が、「失礼ですがせっかくのクリスマスなので、パーティーにいらっしゃいませんか?」と、私に声をかけた。クリスマス・イヴに、ひとりでトボトボ歩く東洋人に同情したのだろう。窓から覗くと、座席の奥にはエディ・マーフィーが……いた!私の頭の中で、ゴージャスなペントハウス、ライトで煌くジャグージー、勢いよく開けられるクリュッグのロゼ、水着姿の美しいシスター達……が駆け巡った。魅力的だ。しかし、私にはハイチの友人たちとのクリスマスが待っていた。そこはぐっと理性的になり、「ありがとう。でも約束がありますので。皆様も良いクリスマスを」と辞退した。ハリウッドスターを乗せたリムジンは、何事もなかったかのように静かに走り去っていった。
ホテルに帰ると、すぐにショーンが大きな花束を抱えて迎えに来てくれた。そこで、ウノ、ワノの双子が待つ家へ行き、ハイチからの大勢の移民たちと、ハイチ産のラム酒をのみ、温かい料理を囲んで、夜が更けるまで喋り捲った。ハリウッド・セレヴたちと過ごす幻想的な一夜も魅力的だ。でも、日を重ねて信頼を積み重ねてきた友人たちと過ごす、等身大のクリスマスは何にも代えがたい宝物だ。それでも、また、夢見るような、胸がすくような爽快なイリュージョンの世界には、騙されたいと思う。
2013.09.21 (土) Men in the Kitchen
アメリカ映画では、男性が朝食を銀のトレイにいれ女性のもとへ運んでくれる、というシーンを良く見る。カリカリに焼いたベーコン、全粒子のトースト、サニーサイド・アップの卵、絞りたてのオレンジ・ジュースに淹れたての香りよいコーヒー。おまけに一輪挿しにさした美しいバラまでトレイに乗っていることがある。こんなことを本当に欧米人の男性はやってくれるのだろうか?答え、やる。時にはフルーツ・カクテルのデザートまで添えて。私の友人のアメリカ黒人男性は、料理を厭わない人が多かった。その理由として、彼らの母親たちが料理好きであり、家計のことも考え、外食は特別な日のみという認識を持っていた、ということがあると思う。バレンタイン・デーもクリスマスも、教会でのイベントの後でも、家食が主だった。彼女たちは、一日の多くの時間をキッチンで過ごしたのだろうと思う。私は彼女たちとキッチンに立つのが大好きだった。キッチンで一緒に料理をして楽しい人とは、歳の差も性差も人種も関係なく、相性が良い証拠で素敵な友達になれると思う。私の学友の黒人の母親たちは、コーン・ブレッドを焼くために、生のトウモロコシの粒をはがし、すりつぶす作業から始める。キャセロールの上に乗せるクリスピーなビスケットも手作りだ。そんな作業を、女達が集まり、ぺちゃくちゃと、「私の大学卒業式の写真、帽子からアフロが爆発してるの!」とか「ベンソン牧師が6人目の養子をもらったって」と、たわいもないことを話しながら手の動きは止めない。そこへ、彼らの息子が来て、「あ、おいしそう!」などと言い、ロースト・ポークをつまもうものなら、ピシャッと手を叩かれ、「祈る前に食べるなんて、ケダモノ!」と、おしかりを受ける。そんな母親に育てられた息子たちは、キッチンは楽しい社交の場、という感覚で気負うことなく料理する習慣が身についたようだった。
歌手のノーマンの得意料理、スパイシー・ブロイルド・フィッシュは隠し味にソイ・ソースがほんの少し入っており、絶品だった。エリックの作ってくれた、フライド・キャット・フィッシュにバーベキュー・ソースをつけて食べるのも、スナック感覚で美味しく、ウォーレンのポークチョップス・アンド・ビーンズなどは、甘い付け合せの豆もとろけるようで、いまだに私も日本でよく作る。バハマ出身のデイルがつくるコンク・フリッターは、今思い出しても頬が緩むほどの美味しさだった。そのなかでも、モア・ハウスのアキーヤは、毎日のように気軽に料理をし、盛り付けも美しく、こんな人が奥さんだったら……などと思わせるほどだった。アキーヤは筋骨たくましい男性で空手の師範でもある。私がお返しにつくる他愛もない春巻きや、シュウマイ、日本式のカレーなども、彼がひと手間加えると、エキゾチックでオシャレな一品に様変わりして、まるでマジックのようだった。そして、カラード・グリーンやオクラなどの野菜の付け合せも欠かさなかった。
昔からアメリカでは$0.99でハンバーガーが買えた。その反面、ブロッコリーが一房で$1.29くらいしていたと思う。主婦だったら家族に健康的で美味しいものを食卓に並べたい、と思うだろう。でも、お腹を減らした子どもを三人抱えていたら、自分は生活費のために、仕事を2つも掛け持ちしていて夕食を作る時間もなかったら、夫が腰を悪くしてその鎮痛剤に月100ドルもかかるとしたら……。つまり家計にまるでゆとりがなかったら、 $0.99のバーガーに手が伸びるだろう。そこから悪循環が生まれ、ファスト・フードで育った子どもの四人に一人は若年性の糖尿病になり、家計や国の医療財政を圧迫していく。 先日経済破綻したデトロイトは、毎年全米の肥満人口率の上位に名を連ねる。アメリカでは貧困と肥満が切っても切れない関係だ。多くの豊かではない層の人たちが、糖尿病や心臓病を抱え、不安な日々を送っている。
母親がゆったりと料理できる時代は良かった。しかし、彼女達だって決して暇だったわけではない。カイルの母親は教師で毎日くたくたになるまで働いていたし、エリックの母親もシングル・マザーで決して豊かではない家計から、少しでも質のよい食事を子どもたちに与えていたのだと思う。
 私は食べることも料理することも大好きだ。決して上手ではないけれど。キッチンではスピナーズの“Love Trippin’”を歌いながら、お玉を振り回し、ボビー・ブラウン風に腰を揺らしノリノリで料理する。息子がまだ幼稚園に入る前、そんな母親を見て「おかんが宇宙人と交信している!」と思い、青ざめていたこともあったが、今ではしっかり自分のものは料理できるほどに育ってくれた。料理は楽しく、が一番美味しくできる秘訣のように思う。
私は食べることも料理することも大好きだ。決して上手ではないけれど。キッチンではスピナーズの“Love Trippin’”を歌いながら、お玉を振り回し、ボビー・ブラウン風に腰を揺らしノリノリで料理する。息子がまだ幼稚園に入る前、そんな母親を見て「おかんが宇宙人と交信している!」と思い、青ざめていたこともあったが、今ではしっかり自分のものは料理できるほどに育ってくれた。料理は楽しく、が一番美味しくできる秘訣のように思う。また、アメリカ人男性の料理上手を書き連ねたが、私は日本人男性のダイナミックな料理も大好きだ。特にチャーハンと焼きそばは、男性には敵わない。そんな飾らない料理を美味しくできるのが、日本人男性の素晴らしいところだと思う。女性は男性の気持ちのこもった料理を食べれば幸せになり、たとえ、男性が料理のあとのキッチンをグタグタにしていても、喜んで皿洗いはやってくれるだろう……と、思う。
2013.07.23 (火) Southern Soul
アメリカ南部人の特徴といって、すぐ思い浮かべることは何だろう。料理ではとにかく揚げ物が好き。鶏でもオクラでもなまずでも何でも揚げて食べる。とくにフライド・チキンには誇りがあり、母から娘に作り方を伝授するとき、うっとりとした顔で言う。
「フライド・チキンほど人を幸せにする食べ物はないよ」
アメリカは肉大国で、しょっちゅうビーフ・ステーキを食べているイメージがあるが、牛肉より鶏肉の方が俄然消費量が多いということだ。
アメリカ人がトマト・ケチャップをドボドボかけて食べるということは、前にも書いたが、南部人はタバスコを、水道の蛇口をひねるようにして何にでもぶちまける。なんといってもルイジアナはタバスコ発祥の州。南北戦争で破産した銀行家が一発奮起して立ち上げた田舎の小さな工場で、現在は世界中どこへ行っても見ないことはないという大ヒット商品を生みだした。今では当たり前のTVニュース24時間放送だってアトランタのCNNが始めたし、コカコーラも、日本で行列のできるドーナツ屋さんも南部からやってきた。
それにサザン・ベルといわれる喋りかた。
私は日本に帰国して、アメリカのエリート白人に、「あなたの英語は南部人のアクセントがあるね」といわれた。ようは、「なまってる」ということである。南部が舞台の映画を観ていると、Tシャツからパンパンの太い腕をだし、キャップからロン毛をはみ出させ、オーバーオールを着ている日焼けした登場人物が、語尾を延ばしゆったりとしたリズムで、「I cock nice meal for you」という台詞は、字幕では「おれっちがよー、オメーにうまいもん食わせてやっからよー」なんてことになってしまう。
モーリス・ブラウン大学に在籍していたとき、キャンパスでラップ・コンテストが開かれることとなった。優勝者には100ドル贈呈。これは学生にとっては大変美味しい額だ。このあいだキャンパスにとめておいた車からタイヤホイールを盗まれたから(よくあることだった)、それを補充して、今度のリサイタルで歌う楽譜の新品を買って(多くの学生は、教科書などは節約のため中古を買っていた)、モールでみんなとフライド・チキンをお腹一杯食べてもお釣りが来る・・・。
 そう思った学生は私だけではなかったはずだ。同じ声楽科の男子生徒3人に誘われて、私も出場することになった。3人の男子学生がリズミカルにハモったあと、私が一言ラップする、という段取りが決まった。私は振り付けも、当時流行っていた女性ラップ・グループ、Salt’ N’ Pepa風にキメ、練習を聖歌隊のメンバー監修のもと行ったのだが、私のたわいもない一言のラップ、「So, why don’t ya, baby?」という場面で、みな腹を抱えて笑い転げるのだ。私はウケたのは嬉しかったのだが、その理由がわからない。どうして?ときくと、「キミのラップ、モロ南部黒人訛りで、チョーおもしれえ!」ということらしい。一部のナイーブな男子からは、「キミは他の黒人女性とは違うと思っていたのに・・ガッカリした・・・。」と肩を落とされたが、そんなヤワな男より賞金100ドルの方が魅力的だ。私はスカーレット・オハラのように全ての非難はホメ言葉だと解釈し、そのまま意気揚々とコンテストに臨んだ。会場では、やはり、私のラップ部分で大爆笑がおこり、優勝は逃したものの、準優勝を得て、マダム・ウィリーのフライド・チキンの無料券を頂いた。コンテストが終わったその足で仲間と店にいき、バケツ一杯はいったドラム・チキン・ダーク・ミートを、指を脂でギトギトにしながら、皆で分け合い平らげた。そこでやっぱり、「南部はフライド・チキンだよねえ。」と、幸福感に浸ったのである。
そう思った学生は私だけではなかったはずだ。同じ声楽科の男子生徒3人に誘われて、私も出場することになった。3人の男子学生がリズミカルにハモったあと、私が一言ラップする、という段取りが決まった。私は振り付けも、当時流行っていた女性ラップ・グループ、Salt’ N’ Pepa風にキメ、練習を聖歌隊のメンバー監修のもと行ったのだが、私のたわいもない一言のラップ、「So, why don’t ya, baby?」という場面で、みな腹を抱えて笑い転げるのだ。私はウケたのは嬉しかったのだが、その理由がわからない。どうして?ときくと、「キミのラップ、モロ南部黒人訛りで、チョーおもしれえ!」ということらしい。一部のナイーブな男子からは、「キミは他の黒人女性とは違うと思っていたのに・・ガッカリした・・・。」と肩を落とされたが、そんなヤワな男より賞金100ドルの方が魅力的だ。私はスカーレット・オハラのように全ての非難はホメ言葉だと解釈し、そのまま意気揚々とコンテストに臨んだ。会場では、やはり、私のラップ部分で大爆笑がおこり、優勝は逃したものの、準優勝を得て、マダム・ウィリーのフライド・チキンの無料券を頂いた。コンテストが終わったその足で仲間と店にいき、バケツ一杯はいったドラム・チキン・ダーク・ミートを、指を脂でギトギトにしながら、皆で分け合い平らげた。そこでやっぱり、「南部はフライド・チキンだよねえ。」と、幸福感に浸ったのである。南部人は、その訛りを「教養がなさそう」などといわれ、「脂っこいものばっか食べて」と眉をひそめられて、「近所づきあいがうっとおしい」とウザったく思われて、「教会しか楽しみがないくせに」と、つまらなそうに囁かれ、それでも笑い飛ばしてしまうたくましさがある。南北戦争でたくさんの命や家畜、農作物を失っても、希望を失わず、知恵と力を振り絞り、再び立ち上がってきた南部人の歴史。ハリケーン・カトリーナという災害とあっても、立ち直るエネルギーを持った魂。私もスカーレット・オハラには遠く及ばないが、自分の南部訛りをネタにチキン無料券を勝ち取るくらいのたくましさは、しっかり身につけて帰ってきたと思う。
ジョージアの州のシンボルは桃。
今まさに、いろいろな桃のフェステイバルが執り行われているころだ。スパゲテイ・ジャンクションとよばれる入り組んだ州道も混んでいることだろう。そんななか、かわいいピンクの桃のナンバー・プレートを車につけて、ゆったりと運転し、「ドライビング・ミス・デイジーか?!」とクラクションを鳴らされても、「So, why don’t you?」(だからなんなのさ?)と動じないジョージア人が懐かしい。
2013.01.17 (木) How Can You Sleep at Night
「How can you sleep at night?」これは、映画などでよく耳にする台詞だ。ちょっと読むと、「どのようにお休みになっていますか?」のような感じにとらえられるが、そういう意味で使うことは滅多にない。ダイアナ妃がパパラッチに追われ、車の事故で亡くなったとき、ジョージー・クルーニーがメディアに向かって発した言葉でもある。江戸っ子風に訳せば、「オマエ、そんなアコギなことして、よくすやすやと眠ってられるな、このヤロー!」くらいの強い非難を含み、ぬけぬけと罪悪感を感じない人間に向けられる言葉だ。
人はしばしば眠れなくなる。その原因は不安だったり、罪悪感だったり、強い興奮だったりするものだと思う。眠れなくなると辛い。羊の数が1000匹になっても、2000匹になっても、頭が冴えるばかりで一向に眠気がやってこない。自分は、アメリカでスパンキーとあだ名をつけられ、意気揚々とキャンバスを闊歩していたとき、いきなり眠れなくなった。授業のあとクワイアの練習をしてアパートに帰るのが9時近く。それからが長かった。大体毎日、朝一番の授業をとっていたので、7時には30分かけて大学に向かわなければならないのに、一睡もできぬまま朝を向かえ、車を運転し授業を受け、クラスの合間に車の中で仮眠をとったりしていた。このままじゃいけないと思い、そのとき不眠の原因がわからなかったので、精神科医に相談をしに行った。そして、不眠症という英語は「insomnia(インソムニア)」と頭に叩き込み、ドクターにしっかりと伝えたとたん、その若いドクターはうろたえ、「ど、どんなときにそうなりますか?」とたずね、それは夜に決まっているだろう、と思いながら「夜から朝までずっとなんです。そのまま翌日まで丸2日以上症状が続くこともあります。」というと、「それはそれは・・・」と、今度は頬を赤らめるのである。なんかヘン、いくら経験不足の若い医師だとしてもいちいち、驚きすぎる。そこで私は「I cannot sleep, なんですけど・・・?」というと、その若い医師はしまった!という顔をし、「nymphomania(ニンフォメニア・色情症)だと、聞き違えた、あっはっは・・・」と、から笑いをし、私も「やーだ、先生!」と、その場を明るく濁し、重厚なカウンセリングルームが場末のスナックみたいになってしまった。だいたい、いくら経験不足とはいえ、ニンフォメニアひとりにいちいち照れていたら仕事にならないだろう、まったく・・・、と思いながら自分の英語の発音もまだまだだ、などと反省をし、薬局に売っている軽い入眠剤の処方箋をもらい、クリニックをあとにした。
私の不眠症の原因は、「不安」だったように思う。
 当時、私のアパートに真夜中、日中を問わず、不気味な電話が続き、留守電にも暗い男の声で、毎日のように不穏なメッセージが残されていた。キャンパスでは女子学生に、「あんたは、黒人の男を盗んだ!」といきなりどつかれ、遊びに行ったクラブでは銃撃戦に巻き込まれ、学友のアレックスは車の中で試験勉強をしているときに、たった5ドルのために撃ち殺された。入学式のとき、モーリスブラウンの学長の挨拶で、「去年、キャンパス界隈で12人、殺されました。皆さんも気をつけるように。」といわれたことが、現実味を増してきたのだ。本来は臆病な私は、それを隠すために、元気に振舞っていたのが「不眠」という体の不調になって現れたのだと思う。
当時、私のアパートに真夜中、日中を問わず、不気味な電話が続き、留守電にも暗い男の声で、毎日のように不穏なメッセージが残されていた。キャンパスでは女子学生に、「あんたは、黒人の男を盗んだ!」といきなりどつかれ、遊びに行ったクラブでは銃撃戦に巻き込まれ、学友のアレックスは車の中で試験勉強をしているときに、たった5ドルのために撃ち殺された。入学式のとき、モーリスブラウンの学長の挨拶で、「去年、キャンパス界隈で12人、殺されました。皆さんも気をつけるように。」といわれたことが、現実味を増してきたのだ。本来は臆病な私は、それを隠すために、元気に振舞っていたのが「不眠」という体の不調になって現れたのだと思う。「マシニスト」という映画では、クリスチャン・ベイルが極限まで痩せ、
 眠れない機械工の役を鬼気迫る演技で体当たりしていた。眠れないことも、ガリガリに痩せることも、私にはその主人公の気持ちが理解できた。つまり・・・と、ここで書くと、それこそ、結末を吹聴するアコギなヤツになってしまうので伏せておく。
眠れない機械工の役を鬼気迫る演技で体当たりしていた。眠れないことも、ガリガリに痩せることも、私にはその主人公の気持ちが理解できた。つまり・・・と、ここで書くと、それこそ、結末を吹聴するアコギなヤツになってしまうので伏せておく。今でも、救急車のサイレンを聞けば息子ではないかと不安になり、過去におこした過ちでウジウジと罪悪感に浸り、少し褒められればハイになる、まるで肝の据わってない自分は、たまに眠れなくなるときがある。そのときは絶大な信頼を寄せているK氏から頂いたコルトレーンのバラードを枕元で小さくかける。そうすると、一枚が終わる頃には安らかな眠りについていることが多い。朝の目覚めも良い。そして、今度眠れないときは何を枕元で聴こう、と考える楽しみもできて、音楽の幅も広まりそうだ。悪事を働いてもすやすやと眠れる悪人が少し羨ましいときもあったが、今では厳しい寒さの冬の夜長を、あったか湯たんぽと音楽で乗り切っている。
2012.11.13(火) 高揚の秋
渡米して1~2年は、勉強も忙しく、あらゆるものを新鮮に感じていたが、勉強に疲れたときや、ふと時間が空いたときなど、「芸術・文化」的なものが恋しくなるときがあった。不思議なもので、木々の葉が色づきはじめ、風にも秋の気配が感じられる頃になると、特にそう思った。たかだか建国400年のアメリカ、それもアトランタで歴史的な建造物といえば、南北戦争前のプランテーション、近代ではコカ・コーラ博物館などの軽い観光地が多く、美術館の所蔵もピンと来ず、日本では銀座の画廊に勤めていたので、ただ、「良い絵画」が見たい、と思っていた。日本にいる今でも、衝動的に見たくなる絵画作品がある。それは、そのときの気分、状況によって違うし、また、部屋に飾りたい絵画と、作家の魂まで掴みたい、と思うような絵画は別。くつろぎの場である居間に飾っているのは、見ているだけで楽しくなる、
 色彩もあでやかなギャラリー・マーゴットのミロのポスターと、バブリーだった東京を自嘲的に思わせるカシニョールの版画。私の場合、本当に好きな絵とは、ザワザワと胸をかきむしられる様な、落ち着かない気持ちにさせてくれる絵画だ。ダントツに好きな作家は、ルドン。木炭で描かれた黒の世界は素晴らしい。ルドンは、なぜ、黒をたくさん使うのか、と聞かれて、「黒は汚されないから。」といったそうだ。彼の描く世界は、不気味でせつない。木炭の黒だけで、なぜ、いまにも語りかけてくるような瞳の表情を描けるのか、それは、作家の技術ではなく魂を生きうつしたからだと思う。また、色彩を使い出したルドンの有名な「キュプロークス」もせつない。美しい女神ガラテイアに恋をし、岩陰からそっと彼女を見つめる一つ目の怪人、キュプロークス。その哀しい視線は、中学のとき、バレー部のエースに叶わぬ恋をして、物影からそっとバレーコートをみていた、メガネのイケテない私のそれと同じだ。
色彩もあでやかなギャラリー・マーゴットのミロのポスターと、バブリーだった東京を自嘲的に思わせるカシニョールの版画。私の場合、本当に好きな絵とは、ザワザワと胸をかきむしられる様な、落ち着かない気持ちにさせてくれる絵画だ。ダントツに好きな作家は、ルドン。木炭で描かれた黒の世界は素晴らしい。ルドンは、なぜ、黒をたくさん使うのか、と聞かれて、「黒は汚されないから。」といったそうだ。彼の描く世界は、不気味でせつない。木炭の黒だけで、なぜ、いまにも語りかけてくるような瞳の表情を描けるのか、それは、作家の技術ではなく魂を生きうつしたからだと思う。また、色彩を使い出したルドンの有名な「キュプロークス」もせつない。美しい女神ガラテイアに恋をし、岩陰からそっと彼女を見つめる一つ目の怪人、キュプロークス。その哀しい視線は、中学のとき、バレー部のエースに叶わぬ恋をして、物影からそっとバレーコートをみていた、メガネのイケテない私のそれと同じだ。アメリカのことを冒頭で、文化的につまらないというようなことを書いたけど、実は美術館の数は、世界一だそうである。また、南北戦争後の観光地には興味深いものもある。例えば、アトランタで有名なのはストーン・マウンテン。
 縦27メートル、横58メートルという世界最大の御影石の岸壁に、南軍3大将軍、リー、ジャクソン、ジョンソンの彫刻が施されている。アトランタでは、キング牧師のお墓は真っ先に訪れたけれど、ストーン・マウンテンにはいったことがなかった。ある日、モアハウス大学の教授と歴史学専攻の学生数人が、私をストーン・マウンテンに連れて行こう、という話になった。とはいえ、みな、「ストーン・マウンテンかあ・・・、まあ、いいけどさ。」と、あまり乗り気じゃなさそうなのである。それでも、せっかくだからアトランタ最大の観光地に行こうということになり、夜のレーザーショウの時間に合わせて、出発した。岸壁に刻まれた彫刻は、壮大な眺めだった。観光地としては、広大な自然と歴史を調和させて、なるほど、と思わせるものだった。しかし、レーザーショウが始まって、みなが乗り気じゃなかった謎が解けた。南北戦争を物語るレーザーショウなのだが、いかにも、「偉大なるリー将軍様が、ヤンキーに負けてやりましたよ・・・。奴隷を解放して差しあげましたよ・・・。」と、押し付けがましく、上から目線なのである。潔くない。私が、「なるほど、こういうわけだったのね。」というと、「だろ?」と、みなが頷き、私達はお口直しじゃないけど、大学に隣接したミセス・ウィリーという、黒人料理の店へ繰り出し、歴史話に花を咲かせた。歴史は視点を変えると七変化する。だから難しいし、楽しい。
縦27メートル、横58メートルという世界最大の御影石の岸壁に、南軍3大将軍、リー、ジャクソン、ジョンソンの彫刻が施されている。アトランタでは、キング牧師のお墓は真っ先に訪れたけれど、ストーン・マウンテンにはいったことがなかった。ある日、モアハウス大学の教授と歴史学専攻の学生数人が、私をストーン・マウンテンに連れて行こう、という話になった。とはいえ、みな、「ストーン・マウンテンかあ・・・、まあ、いいけどさ。」と、あまり乗り気じゃなさそうなのである。それでも、せっかくだからアトランタ最大の観光地に行こうということになり、夜のレーザーショウの時間に合わせて、出発した。岸壁に刻まれた彫刻は、壮大な眺めだった。観光地としては、広大な自然と歴史を調和させて、なるほど、と思わせるものだった。しかし、レーザーショウが始まって、みなが乗り気じゃなかった謎が解けた。南北戦争を物語るレーザーショウなのだが、いかにも、「偉大なるリー将軍様が、ヤンキーに負けてやりましたよ・・・。奴隷を解放して差しあげましたよ・・・。」と、押し付けがましく、上から目線なのである。潔くない。私が、「なるほど、こういうわけだったのね。」というと、「だろ?」と、みなが頷き、私達はお口直しじゃないけど、大学に隣接したミセス・ウィリーという、黒人料理の店へ繰り出し、歴史話に花を咲かせた。歴史は視点を変えると七変化する。だから難しいし、楽しい。私が仕事部屋に飾る絵画は、先に述べたが、モアハウスの学生が寮の部屋に飾るポスターは、一番がキング牧師の写真ではなく、マルコムの写真だった。マルコムが命を狙われ、家族を守るために銃を抱え、窓のブラインドの隙間から外をうかがっている緊張感が伝わってくるポスターだ。どの部屋にもといっていいほど、そのポスターが飾られていた。これは、やはりみなが、非暴力のキング牧師も尊敬するけど、自分のことは自分で守らなければならないという危機感をもっていたからだと思う。
私は、絵画でも音楽でも文学でも、作家の魂がこめられている、気持ちを高揚させてくれる作品が好きだ。「さあ、やるぞ!」という気持ちになる。秋も深まり、冬の到来の一歩手前のこの時期、オバマ大統領じゃないけれど、Go Forwardするためにも、上質の芸術に触れたいと思う。
2012.09.29(土) Ain't No Mountain High Enough
私がアメリカで乗っていたダッジはよく故障した。ある雨の日、まだ四ヶ月ほどの乳児だった息子を、南部では優秀なエモリー大学病院に連れて行く途中、突然車が動かなくなった。外はザンザン降りの大雨、診察予約時間は迫っている。ちょうど都合のいい事に、向かい側に公衆電話があるので、ディーラーに電話ができるのだけど、アメリカでは少しの時間でも子どもを一人で車に残していくのは法律違反。しかたなく、傘を差し、子どもをだきかかえて公衆電話に向かったが、番号をプッシュしようとすると、子どもが大泣きを始め、傘もさせない、電話もできなく、困っていた。すると、「Can I hold your baby? (赤ちゃんを抱っこしていてあげようか?)」と、救いの声が。「Thank you・・・」と、振り返ると、そこには、強面の、歯に金歯を光らせ、ぬっと出たマッチョな腕には、ドクロのタトウー、首からはラン・DMCみたいな大きな金の鎖を下げている、ギャングにしか見えない黒人男性が立っていた。私はこの男性に、大事な我が息子を預けていいものか、一瞬迷った。頭の中には、「人種差別・・・公民権運動・・・キング牧師・・・」などの単語が駆け巡っていた。私は決めた。仮にも公民権運動を学びにスペルマン大学に入学した自分、ここで黒人青年を疑っては同胞達に顔向けができない・・・。「助かります。」と私が息子を手渡すと、その青年は、いかつい顔をふわっとほころばせ、息子を、はれ物に触るような、ちょっとおびえたような優しい目で見つめた。その黒人青年の瞳を見たとき、私の選択は正しかったと思った。その後、無事に電話を終え、青年は「Take care. (気をつけてね。)」といって去っていった。 科学者に言わせると、瞳が何かを語るということはないそうである。せつなそうな瞳も、愛しい瞳も、科学的な根拠はないらしい。目の周りや、顔全体の筋肉で表情を読み取るという。
科学者に言わせると、瞳が何かを語るということはないそうである。せつなそうな瞳も、愛しい瞳も、科学的な根拠はないらしい。目の周りや、顔全体の筋肉で表情を読み取るという。私がマービン・ゲイの歌で一番好きなのは、タミー・テレルとデュエットした「エイント・ノウ・マウンテン・ハイ・イナフ」である。その頃、所属のモータウンの社長の娘と結婚していながら、可憐なタミーに恋をしていたマービン・ゲイ。その後、タミー・テレルが若くして脳腫瘍で他界すると、マービン・ゲイは魂を抜かれたように再起不能になってしまった。二人が見詰め合って、「どんな高い山も、深い谷も私達を遮らない・・・」と歌う瞳には、深く熱い愛情が感じられて、そのビデオを見るたびに胸がキュンとしたものだった。
ところが、アメリカに来て、ある友人から「あれは、モータウンの宣伝で創り出したものだよ。二人は恋なんかしていなかった。」ときいて、ガックリとした。
 ある日、いつものように私のアパートに、カイルとデイルが遊びに来ていて、BET(ブラック・エンターテインメント・チャンネル)をつけていたら、そのマービン&タミーのミュージック・ビデオを流していた。私が、「二人は恋してたわけじゃないんだってね・・・。」といったら、科学専攻のカイルが「なに言っているの?恋しあっていたに決まってるじゃん。二人の瞳をみてみろよ。」といったのである。私はその瞬間、やっぱり、と思った。瞳が科学に勝った!いつもは、洒落たことなどいえないカイルがそのときだけは、ちょっとクールに見えた。
ある日、いつものように私のアパートに、カイルとデイルが遊びに来ていて、BET(ブラック・エンターテインメント・チャンネル)をつけていたら、そのマービン&タミーのミュージック・ビデオを流していた。私が、「二人は恋してたわけじゃないんだってね・・・。」といったら、科学専攻のカイルが「なに言っているの?恋しあっていたに決まってるじゃん。二人の瞳をみてみろよ。」といったのである。私はその瞬間、やっぱり、と思った。瞳が科学に勝った!いつもは、洒落たことなどいえないカイルがそのときだけは、ちょっとクールに見えた。日本に帰国して何年かたち、とてもニューオーリンズが恋しくなって、一人で旅したことがある。そのとき、バーボン・ストリートをぶらぶらしていて、路上で似顔絵描きのおじいさんが、ちっちゃな椅子にシャンと背筋を伸ばして座っている前を通りがかった。私はなんとなく、描いてもらうことにした。その絵描きさんは、筆を走らせながら、「あなたの瞳には力がある。その瞳は、一生懸命生きている証だ。」と、いっていた。当時、ちょっと疲れていた私は、絵描きさんの言葉に元気づけられたのを覚えている。出来上がった絵は、「プリティー・ベイビー」のときのスーザン・サランドンのようで、実物より何百倍も美人に仕上がっていた。絵描きのおじいさんは「あなたは、タフな女性だ。また、ニューオーリンズに帰っておいで。」といって、灰色がかった瞳を、無数の皺の中に埋めるように細めて微笑んだ。
たまに弱気になったとき、その似顔絵を出してみることがある。鉛筆でかかれた私の黒い瞳は確かに力強く、私自身に「あなたはタフ!」と、語りかけているような気がして元気づけられる。
2012.06.22(金) If You Can
If you can't fly…人生の教訓本など、著名人の一言をまとめたありがたい著書は、いつの時代でも確実な読者がいるのだろう。私も、キング牧師のスピーチに啓発されてアメリカまで行ったのだから、かなりそういうものにのせられやすい方なのかもしれない。ただ、あまりにも、前向き、善人過ぎる言葉などには、素直になれないときがある。
とても辛くて辛くて、人生のどん底だ、なんていうときに、「神様はその人に乗り越えられない試練は与えない。」なんていわれると、「じゃあ、あなた、私の人生を生きてみる?!だいたいワガママで怒りっぽい神様なんて嫌いだし。」と、言い返したくなる。その人が、親切心で言ってくれたのがわかるので、グッと黙り込んでしまうけれど。
そんなときは、オスカー・ワイルドの「我々は皆どん底にいるが、星を見ている人もいる。」くらいの逃げ場のある言葉の方が、ふっと肩の力を抜かせてくれる。
キング牧師は非暴力運動を訴え、「右の頬を打たれれば、左の頬を差し出せ。」の言葉を大事にしていたけれど、マルコムXの「右の頬を打たれたら、殴りかえせ!」の方が、胸に迫った場面もいくつか経験した。
それでもやはり、キング牧師の言葉は苦しいときに支えてくれる。
If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.わが身に置き換えれば、20代のときに意気揚々とアメリカへ飛んでいき、大学生活を突っ走り、子育ての期間はゆっくりと歩き、今はまさに、地を這っている時代だけれど、それも自分には必要なことだと思える。オスカー・ワイルドのように星を見上げることも忘れず。
(飛べないときは走りなさい、走れないときは歩きなさい、歩けないときは這いなさい、前進
し続けなければならない。)
 そんな地を這うような人生でも、生き抜かなければならないことを、アカデミー賞助演男優賞を獲得したハビエル・バルテムが見事に演じている映画が「ビューティフル」。移民の父親が壮絶に家族を守る話だ。余りにも辛くて、歯を食いしばって鑑賞していたので、奥歯が痛んだほど。そこまでして生き抜かなければならない、生きていくことこそに意味がある、とそんじょそこらの教訓本より、よっぽどずっしりと勇気が湧いてくる。
そんな地を這うような人生でも、生き抜かなければならないことを、アカデミー賞助演男優賞を獲得したハビエル・バルテムが見事に演じている映画が「ビューティフル」。移民の父親が壮絶に家族を守る話だ。余りにも辛くて、歯を食いしばって鑑賞していたので、奥歯が痛んだほど。そこまでして生き抜かなければならない、生きていくことこそに意味がある、とそんじょそこらの教訓本より、よっぽどずっしりと勇気が湧いてくる。私が抗いきれないアメリカの言葉がもう一つ。「明日できることは、明日にしよう。」である。これとならんで、オスカー・ワイルドの「誘惑には負けろ。」という言葉がひらめいたときは、もう心の赴くまま、食べたいものを食べ、好きな音楽を聞き、見たい映画を見る。地を這っている時代だからこそ、見えてくるものもたくさんあり、ささやかなことに幸せを感じられる。半日のグータラくらいは、神様だって許してくれるだろう。
2012.03.18(日) Nickname
私がアメリカに留学した目的は、黒人音楽を学ぶため、キング牧師の公民権運動の魂を継承するため・・・、などとかっこいいこと並べており、それはもちろん事実なのだが、ミーハー的な理由もたくさんあった。例えば、サム・クックが歌うように「スイート・ハート」と呼ばれてみたい・・・、「マイ・ベイビー」というものになってみたい・・・、などとソウル音楽の世界に憧れていた。親だったら許せない留学理由である。 実際、アメリカで生活していると、そうそう「スイート・ハート」などとは呼んでもらえなかった。わたしのファースト・ネームはアメリカ人にも発音しやすく、そのまま覚えてもらっていた。それでも、クワイヤのメンバーが、私になにか、黒人らしいミドル・ネームをつけようということになり、みんなが頭をひねったあげく、黒人音楽に欠かせない「JAM」を学んでいるのだから、「Jamise」(ジャミース)はどうだろうということになり、はれて、K・Jamise・M となったのである。ルイ・アームストロングの「サッチモ」やビリー・ホリデイの「レディ・デイ」ならカッコイイが、ジャムの欠片も持ち合わせていない私にジャミースの名称は似つかわしくなく、ゴスペル・クワイヤ科の教授に「ヘン!」といわれ、浸透しなかった。ちなみにその教授の名前はプリンである。
実際、アメリカで生活していると、そうそう「スイート・ハート」などとは呼んでもらえなかった。わたしのファースト・ネームはアメリカ人にも発音しやすく、そのまま覚えてもらっていた。それでも、クワイヤのメンバーが、私になにか、黒人らしいミドル・ネームをつけようということになり、みんなが頭をひねったあげく、黒人音楽に欠かせない「JAM」を学んでいるのだから、「Jamise」(ジャミース)はどうだろうということになり、はれて、K・Jamise・M となったのである。ルイ・アームストロングの「サッチモ」やビリー・ホリデイの「レディ・デイ」ならカッコイイが、ジャムの欠片も持ち合わせていない私にジャミースの名称は似つかわしくなく、ゴスペル・クワイヤ科の教授に「ヘン!」といわれ、浸透しなかった。ちなみにその教授の名前はプリンである。ニューオーリンズのチューレーン大学についた初日は、ポツポツと雨が降っていた。その緑のキャンパスで、雨に濡れるのも気にせず、ベンチに座ってリチャード・ライトを読んでいる黒人学生がいた。肌の色は夜のように深い漆黒で瞳は切れ長、体はマッチョ。これこそ、自分が思い描いていた理想の黒人と色めき立ち、私から声をかけて友人となった。彼には間もなくあだ名をつけられた。「Spunky」、スパンキーである。黒人文化を学びにアメリカに渡り、黒人街を歩き回り、黒人ライブハウスや黒人教会にひとりで乗り込む私は、勇気があって元気、ちっちゃいけど向こう見ずな犬みたいという理由からである。女性として魅力的であるというニックネームではないけれど、スイート・ハートと呼ばれるより気に入っていた。
その黒人青年エリックは、非白人率が5%以下という白人の金持ちの子息が集まるチューレーン大学で、白人のGFと付き合い、スポーツシューズメーカーの専属モデルをこなし、勉学でもスポーツも優秀で一目置かれているスター学生だった。そのせいか、自信家で辛らつ、俺サマで少々いけ好かないところもあった。それでも常に正直で、私のことを強くあれと精神的に鍛え、夢を支えてくれる、なくてはならない友人だった。
当時、たまに金曜日の夜はオン・キャンパスで巨大なスクリーンを掲げ、野外映画会をやっていた。その日は、「ロッキー・ホラーショー」。エリックは、芝生にねっころがりながら、映画のストーリーとは関係なく、高校まで過ごしたミシシッピー州ジャクソン市での話をいつになく淡々と語ってくれた。アメリカン・エアーに努めていた父親は彼が幼い頃家を出て、たくましい母親に育てられたこと、貧乏な家庭出身の自分はアメリカンフットボールの奨学金でチューレーンに来たが、膝の故障で退部、モデルをしながら学費を稼いでいる、卒業したらロー・スクールに入って弁護士になり、黒人社会に貢献したい・・・。日頃どちらかというと白人に融合しているエリート意識の高い黒人のイメージだった彼の意外な一面だった。そして、にこっと笑いながら、「僕のミシシッピーでのあだ名は、チャコールだったんだよ。炭みたいに真っ黒だから!」といったのである。その瞬間、私は彼の肉厚で漆黒の手を握り締めていた。
そのエリックは、現在サンフランシスコの検事局で活躍している。先日彼が最高裁で闘った、黒人青年が隣人夫婦を殺害した裁判記録を見た。どんなサスペンス小悦を読むよりスリリングで、犯罪者も被害者も確かに存在していて、読み応えのある記録だった。なによりも、スタックアップ(うぬぼれや)で自信家の彼が、自分の夢を実現し、篤い心を持った法律家として生きている証明が嬉しかった。海を隔ててもう何年もあっていないけど、かつて私をスパンキーと呼び、彼の友人として恥じないように信念を貫こうと勇気を与えてくれる、大切なソウル・メイトの存在に感謝する。
2011.12.20(火) jealousy と envy
"男はBBQ, 女はパイ"に登場したウォーレンの姉、タニヤにはせっかくキーラム・パイの作り方を伝授してもらったのに、ウォーレンともタニヤとも別れてしまった。アメリカで、その家のパイの作り方を伝授するということは、日本でいえば、正月のお雑煮の味を引き継ぐ、というようなお嫁さん候補ナンバーワンということ。ウォーレンよりタニヤのほうが乗り気だった。タニヤは高校を出てすぐ、地元の女性ばかりの会社でオペレーターをしていた。そこへ、私がルームメイトとして、弟の大切な友人として、やってきたわけで、心配もあってか、私の出かける先には必ずついてきた。ある日、聖歌隊のリサイタルにやってきたタニヤに私はその頃密かに憧れていたコンサート・マスターのダリルを紹介した。ダリルが私達からはなれたあと、私は軽い気持で、「彼にはローラという彼女がいるの。I am jealous.(妬けちゃうわ)」といったら、タニヤが血相を変えて「No!ダメよ!嫉妬なんて!」といったのである。私はだんだんとアメリカで暮らすうちに嫉妬を嫌う気質というものが分かってきた。日本なら、例えば、ホメ言葉として素敵な旦那さんのいる奥さんに、「あなたの旦那さん、素敵ねえ、羨ましいわ。」といっても、相手はあらそう?と微笑んでちょっと誇らしげな気分になるものだが、アメリカで「I envy you.」と旦那のことを言ったら、言われた奥さんは「コイツ、私の亭主を盗むつもりね!」と、頭に血が上るだろう。自分を他者とくらべて、「羨む」などということは、「弱く」「恥」という考えかたで、日本語の「妬む」「ひがむ」の意味合いの方が強いと思う。また、キリスト教徒として、七つの大罪のなかに、「嫉妬」があるのも理由のひとつだろう。
タニヤは私とモアハウス男子大学生のカイル、デイルがつるむときもやってきた。だんだんと、タニヤがカイルに惹かれて行くのを、私は迂闊にも気がつかなかった。ある夕方、デイルがスペルマンのGF、トニを伴い、カイルと私達のアパートメントを訪ねて来た。仕事から帰ってきたタニヤのテンションがとても高くなり、カイル達の黒人名門大学「Morehouse(モアハウス)」を、シャレのつもりかモジって、「Whore House(ホアハウス・娼館)」といって、ゲラゲラ笑い始めたのである。それを聞いた誇りだけは一人前のカイルは、むっとして舌打ちをした。モアハウス男子大学の学生は、当大学の出身者、映画監督のスパイク・リーが「モアハウス・ドッグ」と呼ぶほど、女好き、見境がないので、当たってなくもないけれど・・・。そんなカイルの不機嫌に気がつかないタニヤは、おアツいデイルとトニに刺激を受けて、いきなりカイルに「あなたと付き合いたいわ。」と告白したのである。私は、「なぜこのタイミングで・・・!?」と、驚いてカイルを見ると、案の定不機嫌そうに「それは無理」と言い放った。部屋の空気が一気に張り詰めた。そうしたら、何を思ったかタニヤは、「どうせ、アンタたちモアハウス・ドッグは私達みたいなのを相手にしないんでしょ!スペルマン・ビッチ(メス犬!)がいいんでしょ(このときはまだ私はモーリスブラウン大学在学・同じ黒人大学でもひとつ下に見られていた)、トニなんてお尻はペッタンコ、本物の女とは言えない!」(黒人男性には女性のバストよりもヒップが重要・タニヤのヒップは見事だった) と、怒りの矛先をトニに向けたのである。これを聞いたカイルが怒って、「下品な言葉を僕らの前で言うな。」といったら、なんと、タニヤがカイルに殴りかかった。デイルも「タニヤ、落ち着け!」と、止めに入ったものの、カイルは怒りより、女に殴りかかられたことにびっくり仰天、タニヤは興奮状態、収まりがつかない。なんとか、タニヤを寝室に連れて行き、危険を察知したみんなは私の荷物をまとめて、トニの寮に泊まるよう勧めた。それがきっかけで私は、タニヤと別れて一人暮らしを始め、タニヤ、ウォーレンとは疎遠になってしまった。
タニヤは何に怒っていたのだろう・・・。私に「嫉妬はするな。」と忠告した彼女は、実はトニみたいな才色兼備の女性に嫉妬していたのかもしれない。でもそれは、本当は思うように仕事も恋もダイエットもうまく行かない、自分に対する怒りだったと思う。今も思
 えば、タニヤの気持ちに気づかずに無神経にもチャラチャラしていたことは申し訳なかったと思っている。
えば、タニヤの気持ちに気づかずに無神経にもチャラチャラしていたことは申し訳なかったと思っている。先日、モーツアルトの才能に嫉妬したサリエリを描いた映画「アマデウス」を見た。嫉妬の余り狂ってしまうサリエリ・・・。哀しいけど、判るような気がする。何かを成し遂げようとしたとき、それはライバルとの闘いではなく、自分との闘いになる。嫉妬には相手がいるけれど、それは思ったような自分になれない自身への怒りとなり、身を滅ぼすことになってしまう。逆に、ほどほどの成功に満足せず、嫉妬の余り狂ってしまうサリエリを私は美しいと思った。それにしても、嫉妬は男性の方がどろどろしているかもしれない・・・。
2011.09.25(日) ダズンズ
「おまえのかあちゃん、でーべそ!」と、相手をはやすのは、日本だと幼児か、せいぜい小学校低学年。これをアメリカの黒人達は大人になってもやるのである。それはちゃんと、「ダズンズ」という名前までつき、「でべそ」なんて単語一つだけじゃなく、はやし言葉のバリエーションも格段に豊富で、酷いものばかり。例えば、モアハウス大学の学生達が数人集まって、車で出かけようということになると、だいたい女の話しかダズンズが始まる。(ダズンズをやるのは男性のみ)ギュウギュウ詰めの車の中で、「おまえのかあちゃん、色が真っ黒けで、夜になると歯しか見えないんだってな!」「おまえのかあちゃんこそ、太りすぎで、丸太と間違えられて、犬にション便ひっかけられたんだって!?」と、全く大人気ない。それで、怒った人が負け。それをわかっているから、仲の良いブラザー同志は、一番おかしなはやし言葉に笑い出し、みんなで和気藹々なのである。仲間同士ならまだいい。私が見たのは、プロジェクト(低所得者住居)の空き地で、いかにもギャングのメンバーっぽい、10代の男子が、顔をお互いのツバがかかるほどくっつけ、母親の悪口を言い合っていた。「おまえのかあちゃん、今日も客をとるのに忙しいか?」 「おまえのかあちゃんこそ、頭にカーラーつけたままで、不細工な顔してふらふらしてたぜ!」 これはヤバイ。ここまできたら行き過ぎだし、なんせ敵対してるギャング(らしい)である。一発触発、緊張の空気。ジーンズの腰のところに膨らみがあるし、銃でも入っていて撃ち合いになったらどうしよう・・・。モアハウスの学生とビラ配りに来ていた私は、すぐに警察署に通報しようと、公衆電話を探していた。そこで、片方のギャングが、プッと吹き出したのである。そして、悪口を言っていたもう片方に、「Yo, men! おまえには負けたよ。見事だ。リーダーはおまえに譲るぜ!」と、握手をしハグしあっているのである。私は、え?と、目が点状態。仮にもギャング、リーダーという重要なポストを、こんな口げんかに毛の生えたようなゲームで決めちゃっていいのか?! 一緒にいたモアハウスの学生は落ち着き払っていた。「ダズンズはみんな小さい頃からやっているから、こんなもんさ。」ダズンズという遊びが成立するのは、黒人男性の母親崇拝が大きいから、早く言えばマザコンだからである。私は、全世界の男性のほとんどがマザコンだと思うし、世の若い女性が「マザコン男はいや」というのがわからない。逆にマザコンでない男の方が信用できない。それでも、黒人男性の母親崇拝は他民族の群を抜いていると思う。それは、彼らの奴隷としてアメリカに連れてこられた歴史が背景にある。プランテーションで運よく結婚できた奴隷の夫婦は、自分の妻が農園主にレイプされても、夫は逆らえない。しかし、悔しいし妻を守れない自分が情けない・・・。男としての自信、誇りがどんどん奪われていく。自分の妻が陵辱されていてもじっと堪える。我慢することしか生き残る術はなかった。農園主も子供をたくさん産む女性奴隷を、最大限に利用していた。そして、その妻たちはたくましく、子供を育て、家庭を守っていた。それを見て育った子供たちは、母親の強さ、母性を一番の安心できるものとして、敬愛するようになり、また男の子達は自分の愛する人が侮辱されてもじっと耐えるという哀しい習性を生きるために学んだのだと思う。それが、現代はダズンズという遊びに形を変えたのだと思う。
たびたび登場するカイルもマザコン。母親のミセス・モーズレイは、夫を早くに亡くし、小学校の教師をして、二人の子を育て上げた。カイルが、「お袋は毎日、仕事から帰ってくると疲れ果てていてソファーにぐったりしていた。それでも家をきれいにし、美味しいご飯を作って、僕を大学まで出してくれたんだ。」といっていた。そんなスーパーウーマンには逆らえっこない。いつか、大学の春休みにアトランタから帰ったとき、私もミセス・モーズレイの家に泊まらせてもらった。そして、カイルが一度、ミセス・モーズレイと言い争いになって、ドアをバタン!と閉めた時があった。すかさず、ミセス・モーズレイが「私の家で! 二度と扉を音を立てて閉めるんじゃありません!」と強い口調でいった。カイルはそのとたん「イエス、マム・・・。」とうなだれた。大学では、モアハウスのラボで研究員をしていたスタックアップ(自信過剰)のカイルも母の前ではドアの開け閉めで撃沈。かわいいものだ。
ダズンズは奴隷の歴史という哀しい背景を持っているけれど、黒人男性の母親崇拝は、尊いと思う。たとえマザコン男と呼ばれても。
2011.07.17(日) Raw & Odor
 飛行機で空港に降り立った瞬間、その街の匂いで体を包まれる。一番ワクワクする時だ。ニューオーリンズ空港では、ペカンパーラインの甘ったるい匂い、サンフランシスコではサワードウのすっぱい匂い・・・。でも自国成田空港ではどんな匂いがするかは余り感じない。自国や自分自身の匂いなどには余り敏感ではないのかもしれない。
飛行機で空港に降り立った瞬間、その街の匂いで体を包まれる。一番ワクワクする時だ。ニューオーリンズ空港では、ペカンパーラインの甘ったるい匂い、サンフランシスコではサワードウのすっぱい匂い・・・。でも自国成田空港ではどんな匂いがするかは余り感じない。自国や自分自身の匂いなどには余り敏感ではないのかもしれない。チューレーン大学には、スイス人、コロンビア人、スペイン人といろいろな国からの留学生がいた。ある日彼らが、話題にしていたのはおトイレの匂いで、アメリカ人の入ったあとのトイレは肉臭く、スイス人のあとはチーズ臭く、日本人のあとは醤油臭く生臭い、とのことだった。そうなのかな、自分では全く気がつかない。ただ、トイレの後の笑い話くらいならいいけど、自分たちの国が臭いとか、お料理とかをけなされると、文化を否定されたように気分が悪くなってしまうと思う。いまでこそ、寿司はアメリカ人に浸透した食べ物だけれど、当時は日本食レストランといえば、「ショーグン」だの「サムライ」などという名前がつき、料理人はアフリカ人や他のアジア人ばかりだった。寿司は妊娠中は食べてはいけない、などと医師が言う時代。今では生魚は当たり前だけれども、先日アメリカ人に「明日、ふぐを食べに行く。」といったら、「勇気があるわね!」と、驚かれてしまった。まだまだ毒のイメージが強いのかもしれない。
スペルマン大学時代、授業と聖歌隊におわれ、家で日本食を調理する時間などなかった。でもある日、たまたま明太子の瓶詰めがあったので、よっしゃ、今日はご飯たいてお味噌汁も作って明太子でディナーにしようかな、と思っていたら、ドンドン、とドアをノックする音。いつものように、カイルとデイルが「チキンを食べに行こう!」ときたのである。毎日こんな調子で、全くなんで彼らはチキンばかり、とその日はすっかり明太子モードだった私は、「いま、夕食作ってるから食べてみる?」と誘ってみた。カイルは明太子を見たとたん、「う~っ!なんだそりゃ?生の魚の卵だって?僕は食べれない。」と顔をしかめた。自分たちは生のブロッコリーやカリフラワーをサラダで食べるのに。そこで、バハマからの留学生のデイルは、「美味しそうじゃない!」と、スプーンでペロリと明太子を食べた。そして、「これ、クラッカーに載せてもおいしそう、チーズともあいそうだね。」と、ご満悦なのである。ここで、私のデイルのポイントが上がった。女性は未知の食べ物をぱくりと口にする男性に男らしさを感じるもの。モテること間違いなし。
何を食べていくかで、体臭も違ってくると思うのだが、ここでカミングアウトすると、私は欧米人の体臭も大好き。あの松脂のようなにおいにぴったり合ったコロンを身につけている男性は、カッコイイな、セクシーだな、と思う。肉食系のたくましさを感じるから。 アメリカ人の友人は10代の頃、父親に、「You, odor! 匂うぞ、立派な女性になったな!」と、喜ばれたそうである。女性も匂って一人前。男性がたも、肉をモリモリ食べて、未知の食べ物もどんどん食べて、匂う男になってほしい。
数年前、カイルが日本に旅行にやってきた。着いた日に、何を食べたいかと聞いたら、任せる、といったので、カニ料理屋に入った。そこで、大学も卒業して、大会社の役員にもなっていたカイルは、蟹の刺身や蟹味噌を、躊躇なく食べる一人前の男になっていた。そしてしんみりと、「I could marry you.(きみと結婚しても良かったのにな)。」といったのである。冗談じゃない、明太子も食べられない男と結婚できるか!といいたいのをじっと堪えて、友達でよかったね、といった。私も少しは大人になったのである。
2011.04.17(日) Little Boy
日本を覆っていた厚い雲が1週間ぶりに取り払われた晴天の日、トムはリトル・ボーイとともに、日本へ向けて飛行した。リトル・ボーイは4000キログラム、広島に投下された原子爆弾の通称。トムとは、そのスイッチを押した28歳の米軍爆撃手である。その若いアメリカ空軍兵は、リトル・ボーイの投下スイッチを押したことを、死ぬまで背負っていたのだろうと想像する。上官が言ったように、「クラーク・ゲーブルより有名になった。」などと本当に思っただろうか。そして、彼は核爆弾を積んだその軍機に、正義感の強い自分の母親の名前をつけたことを悔やんだろうか。爆弾投下の空軍チームの面々はいずれも二十代の若者ばかりだった。司令塔で指揮を執るのは老巧な将軍。最高司令官であるトルーマン大統領は、爆弾投下成功の知らせを受け、「歴史上偉大なできごとだ。」といった。ナチス・ドイツと争うようにして開発された歴史上最大最悪のパワー、原子力。その開発をアメリカはマンハッタン計画と呼び、それに関わった研究者も大学院生などの若者が多かった。
チェルノブイリ原発の街は、平均年齢27歳の若い街だった。病院も消防署も原発に勤務する人々のためにあり、若い夫婦や子供達が多く、公園には家族連れの笑い声が絶えない眩しいほどの街だったのだろう。原発が爆発し、駆けつけた消防署員も医師も二十代の若者が多く、命を落としたり一生障害を背負って生きなくてはならない体になった人たち、妊娠中の赤ちゃんを死産で迎えた若い妻・・・未来の希望に溢れた若々しい街は一挙に悲しみの廃墟となった。
自分は通訳失格、と思ったときがある。仕事としての通訳ではないが、アメリカ人ビジネスマンと日本人ビジネスマンの飲食の席で、軽い気持ちで頼まれた通訳をしたとき、第二次世界大戦の話から原爆に話が及んだ。そのとき、アメリカ人が、「日本だってパール・ハーバーの襲撃があるじゃないか。」といったとき、言い返さない日本人ビジネスマンにシビレを切らし、「その議論を原爆と同じテーブルに乗せるな。」と割って入ってしまった。仕事の通訳だったら、ギャラをもらい損ねたことだろう。そのとき私が気に入らなかったことの一つに、そのアメリカ人ビジネスマンが第二次世界大戦も経験していない若い人だったことがある。きっとおじいちゃんの話、テレビからの知識で原爆を語ったのだろう。
私はアトランタの黒人大学で歴史を専攻した。歴史なんてビジネス戦力にもならず、薄給の教師か、良くて大学の勤務講師だろう、などとビジネス系学部生からは冷ややかな目で見られていたと思う。歴史を学ぶものはロマンチストが多い。歴史上のヒーロー、ヒロインに憧れ、自分の生き方に投影し、大きな大きな思考の旅をする。私はその時間が大好きだった。それと、もう一つ、かっこいい理由づけをすれば、物事を正しく次世代の人たちに伝える役目がある、と思ったからである。悪も善も、偏らずに正しく伝えなくては、人はたくさんの過ちを繰り返すもの、世界の中のちっぽけな自分という一個人でさえ、繰り返した過ちの愚かさを思い知り、苦さを味あうのである。それが、大きな国や世界のレベルになったら、取り返しがつかないことは・・・・歴史が物語っている。
世界で唯一の被爆国日本は、世界最大級の被曝レベル7という事態に陥ってしまった。歴史史上最悪の事態である。そして、今また若い作業員、消防士、自衛官などが被曝の危険を顧みず、最前線で頑張っている。また歴史マニアっぽいが、かつての指導者は、ウォーリア(戦士)だった。 前線に立ち、後ろに部下を従えて、盾になり闘ったものである。形ばかりの作業服の戦士なんてありえない。私たち個人はやるべきことをひたすらやるしかない。これ以上、日本の歴史に悲劇を記すことのないように、指導者たるものは立ち向かってほしい。
2011.01.15(土) 男はBBQ、女はパイ
アメリカ人は食べ物にドボドボとソースをかけて食べるのが好きだ。それは、フランス料理みたいにバターや生クリーム主体のオシャレなソースではなく液状調味料と呼ぶほうがぴったりくる。ケチャップが日本人の醤油みたいなものだと思う。私もすっかりその食べ方に染まり、日本に帰国したとき、マクドナルドのフライド・ポテトのあの小さいケチャップでは全く満足できなかった。ホットドックにもマスタードとケチャップを大量にかけるし、サラダにはサザンアイランドやランチドレッシングを野菜が隠れるくらいかけるので、ヘルシーであるはずのサラダにも油がたっぷり乗っていることになる。サラダ・ドレッシングでは俳優のポール・ニューマンが開発したドレッシングがとても美味しく、またその収益金を全て寄付していたというポール・ニューマンはアメリカのヒーローだ。男性が俄然、生き生きとして食べ物を語るときはバックヤードで行うBBQパーティーのとき。普段味音痴な男性もBBQソースや焼き方にはこだわりをみせる。しかし、自家製のソースを使うことなく、売られている中でどれが一番美味しいか、というだけ。当時はA1ソースが人気で、有名歌手の歌詞の中にも出てきたくらいだ。BBQが始まるとそこのホストが、グリルの前にたち、巨大なリブやらビーフ100%のパテを焼き始める。その周りを招待客の男性陣が囲むように座り、ビール片手にグリルを見守る。白人達には"ジュネイン・ミラー"、黒人達には"ミケロブ"というビールが人気だった。そうやって、グリルの火を眺めながら、デイズカバリーチャンネルの人気番組、"ウイング"という戦闘機のドキュメンタリーについて、「昨日のチョッパー(ヘリコプター)の特集は納得できない、あれはウイング(翼)じゃない!」などと、どうでもいい話題に興じる。そうやって焼きあがったBBQは、ダイナミックで美味しく、その焼き手のホストは、妻や女性客から絶賛され株を上げる。お手ごろな家庭用のBBQグリルが普及したことが、アメリカの家族団らんに一役買ったことは間違いないと思う。
 アトランタの大学に通っていた頃、私は黒人人口が多い郡のシダーパインというアパートメントに住んでいた。ルームメイトは東京で知り合った黒人ウォーレンの姉、タニヤ。ウォーレンはそのときロンドンの大学に留学していて、黒人大学に進む私を心配し、タニヤと住むことを勧めてくれた。タニヤはオープラ・ウィンフリー似の世話やきの女性だった。アメリカで知り合った黒人女性は世話やきがとても多く、ビッグ・ママみたいに頼れる存在だった。その年のサンクス・ギビングの日、ウォーレンが一時帰国するという知らせを受けた。ウォーレンと私が結婚することを強く願っていたタニヤは、「ウォーレンが夢中になるレシピを教えてあげる。」といって、あるパイの作り方を伝授してくれた。キーライムパイである。アメリカには数多くのパイがあって、ホームメイドのデザートといえば、パイ。チョコレート・パイ、チェリー・パイ、ペカン・パイ・・・・。そのキーライムパイはシンプルでさっぱりしていて、私にも間単にマスターできた。そして、ウォーレンが大きなぬいぐるみをプレゼントにアトランタに帰ってきたとき、私がパイを差し出すと、ウォーレンは、飛び上がらんばかりに感激し、美味しい、美味しいといって食べてくれた。そして、私をサウス・カロライナに連れて行き、そこに住む、ウォーレンの父親、ステップ・マザー、母親に、私のことを大切な人、と紹介するまでに至ったのだから、タニヤの「パイでメロメロ作戦」は成功したといえるのだろう。その後、いろいろあり、タニヤとも別れて住み、ウォーレンと結婚はしなかったのだが、キーライムパイはいまだによく作る。それを味わうたびに、ウォーレンの兄弟姉妹、家族に温かく迎えられたことを思い出し、ウォーレンと結婚していたら、どうなっていたのかな、などと思うのは歳をとった証拠かもしれない。しかし、とにもかくにもアメリカ人男性を落とすなら、美味しいパイを作ることが必須だ。
アトランタの大学に通っていた頃、私は黒人人口が多い郡のシダーパインというアパートメントに住んでいた。ルームメイトは東京で知り合った黒人ウォーレンの姉、タニヤ。ウォーレンはそのときロンドンの大学に留学していて、黒人大学に進む私を心配し、タニヤと住むことを勧めてくれた。タニヤはオープラ・ウィンフリー似の世話やきの女性だった。アメリカで知り合った黒人女性は世話やきがとても多く、ビッグ・ママみたいに頼れる存在だった。その年のサンクス・ギビングの日、ウォーレンが一時帰国するという知らせを受けた。ウォーレンと私が結婚することを強く願っていたタニヤは、「ウォーレンが夢中になるレシピを教えてあげる。」といって、あるパイの作り方を伝授してくれた。キーライムパイである。アメリカには数多くのパイがあって、ホームメイドのデザートといえば、パイ。チョコレート・パイ、チェリー・パイ、ペカン・パイ・・・・。そのキーライムパイはシンプルでさっぱりしていて、私にも間単にマスターできた。そして、ウォーレンが大きなぬいぐるみをプレゼントにアトランタに帰ってきたとき、私がパイを差し出すと、ウォーレンは、飛び上がらんばかりに感激し、美味しい、美味しいといって食べてくれた。そして、私をサウス・カロライナに連れて行き、そこに住む、ウォーレンの父親、ステップ・マザー、母親に、私のことを大切な人、と紹介するまでに至ったのだから、タニヤの「パイでメロメロ作戦」は成功したといえるのだろう。その後、いろいろあり、タニヤとも別れて住み、ウォーレンと結婚はしなかったのだが、キーライムパイはいまだによく作る。それを味わうたびに、ウォーレンの兄弟姉妹、家族に温かく迎えられたことを思い出し、ウォーレンと結婚していたら、どうなっていたのかな、などと思うのは歳をとった証拠かもしれない。しかし、とにもかくにもアメリカ人男性を落とすなら、美味しいパイを作ることが必須だ。BBQ達人の夫、パイ名人の妻、というのがアメリカの理想の円満家庭だろう。日本で言えば、鍋奉行の夫に肉じゃが上手の妻、というところか。美味しいものを家族に食べさせたい、と尽力することは思いやりの原点だし、愛情の現われだと思う。
今日、私はパン生地を腕が痛くなるほど必死でこねながら、焼きたてのパンを美味しそうに食べる息子の顔が浮かび、幸せな気持になった。大切な人のために料理をすることは、大きな喜びでいっぱいになる。母親でよかったな、と思う。
2010.12.04(土) Saturday Night Live
土曜の夜は伝説のコメディ番組、「サタデイ・ナイト・ライブ」を見るのが楽しみで、コーンチップスとチーズディップ、コークを抱えてウキウキとテレビのチャンネルを合わせていた。今、日本で見られない番組で何が一番みたいかといえば、「サタデイ・ナイト・ライブ」だ。多くの売れっ子コメディアンが出演し、エディ・マーフィーもこの番組出身である。内容は、コメディアンたちの寸劇、そのネタが、人種・宗教・政治、とタブーの世界で、一般的に口に出せないものを笑い飛ばしてしまうもの。大統領などは格好の笑いネタだった。また、コメディアンたちの扮装が本当に巧みで、ブッシュパパ役、その妻バーバラ役、サダム・フセイン役など、そっくりでそれを見ているだけでも笑いを誘う。番組にはミュージック・ゲストと俳優ゲストが出演し、それらも充実していた。俳優ゲストは、ソープ・オペラの主役だったり、ハリウッド・スターだったりするが、大体が自虐ネタを披露する。「Xファイル」で主役をしていたデイビッド・ドゥカヴニーが、「俺を映画にも出してくれ!」と哀願したり、10年以上も続いているソープ・オペラの主人公が「私はトニー賞がほしいんだってば!」と叫んだり、なりふり構わない。ロスアンゼルスで、スタンダップ・コメディの舞台を黒人男性と見に行ったときは、舞台上からコメディアンに散々絡まれた。インターレイシャル・カップルへのからかい、非難である。これが、街を歩いていて通りすがりの誰かに言われたら、「ちょっと待てよ。」と、穏やかには済ませられないところが、コメディアンの毒を笑いで包んだ言葉だと、こっちも「そうだよね。」と笑い返せるのである。心の奥底では、みな思っていることだから。例えば、バーバラ・ブッシュはブッシュパパのお母さんにしか見えないくらい老け顔だよね・・・、黒人と付き合っているアジアの女って・・・コメディアンはさらに強烈な毒を吐くのだが、小心者の私はここには書けない・・。
 サタデイ・ナイト・ライブで印象に残っているのは、エディ・マーフィーが、顔に白いファンデーションを塗り、白人になりすまして一日を過ごすというもの。名前はなぜかホワイト氏となり、銀行にいけば、「住宅ローンは何億でもじゃんじゃん組んでくれ!」と銀行員に笑顔で迎えられ、スタンドで新聞を買ってお金を払おうとすると、「お金なんかいいから、好きなだけもっていってくれ、チョコ・バーもどうだ?」といわれ、バスにのれば、「ぜひ隣に座ってくれ、なんだったら僕の膝にでも・・・」と超フレンドリーに迎えられ・・・という寸劇なのだが、エディ・マーフィーの、「白人ってこんなにいいもんなんだ。」という戸惑いの表情が面白かった。
サタデイ・ナイト・ライブで印象に残っているのは、エディ・マーフィーが、顔に白いファンデーションを塗り、白人になりすまして一日を過ごすというもの。名前はなぜかホワイト氏となり、銀行にいけば、「住宅ローンは何億でもじゃんじゃん組んでくれ!」と銀行員に笑顔で迎えられ、スタンドで新聞を買ってお金を払おうとすると、「お金なんかいいから、好きなだけもっていってくれ、チョコ・バーもどうだ?」といわれ、バスにのれば、「ぜひ隣に座ってくれ、なんだったら僕の膝にでも・・・」と超フレンドリーに迎えられ・・・という寸劇なのだが、エディ・マーフィーの、「白人ってこんなにいいもんなんだ。」という戸惑いの表情が面白かった。毒と笑いは背中合わせだと思う。当時のアメリカのコメディアンの毒を含んだ笑いが、視聴者に受け入れられていたのは、人間はそんなにきれいなもんじゃない、俺たちを非難するならヒポ(偽善者)をこそ非難しろ、という自分たちの言葉に対する強い責任感があったからだと思う。ディズニー映画みたいに、「Love conquer everything(愛は全てを乗り越える)」などということは、うそっぱちだ、現実を見てみろ、というメッセージは、自分たちにも跳ね返ってくる。彼らコメディアンには、それらを見据える強さがあったと思う。
話は少し変わるが、先日、アメリカか英国か忘れてしまったが新聞社のアンケートで、「見て気が滅入る映画ベスト30」がランキングされていた。1位は、私が最近観た映画の中では一番好きな「レクイエム・フォー・ドリーム」。30位にはこれまた、心に残った映画で「縞模様のパジャマの少年」。両方とも、ハッピーエンドからかけ離れているし、救いもない。アメリカ人の好きな愛国心も家族愛も全て砕け散ってしまうようなストーリーだ。でも、私はそれらの映画の、現実は生易しくない、という事実を真っ向から捉えた内容に清々しさを感じる。
人は誰でも醜さや弱さと無縁ではいられないと思う。毒を含んだ笑いや気が滅入る映画は、それを人に突きつけるが、それを受け止めることはしっかり生きている証しなのだ、と教えてくれるような気がしている。
2010.10.31(日) Mississippi Burning
 アトランタ、ジョージア。バーミンハム、アラバマ・・・と聞いて胸が騒ぐようにミシシッピー、ジャクソンの地名も心を熱くする。どの地も公民権運動でburning(燃えた)街である。
アトランタ、ジョージア。バーミンハム、アラバマ・・・と聞いて胸が騒ぐようにミシシッピー、ジャクソンの地名も心を熱くする。どの地も公民権運動でburning(燃えた)街である。アメリカでは良く映画を見た。映画チャンネルが豊富だったので、どこかにチャンネルを合わせれば、何かしら興味のある映画が放映されていた。ある日、モアハウス大学の友人、カイル(ミセス・モーズレイの息子)とデイル・・・彼らとは本当によくつるんで遊んでいた仲間だが、私のアパートメントでHBOを見ていたとき、「ミシシッピー・バーニング」をやっていた。ジーン・ハックマンがたたき上げの刑事、ウィレム・デフォーが青臭い新進気鋭のFBI捜査官に扮し、ミシシッピーで起こった殺人事件を追うというストーリーである。その殺人事件とは、公民権運動家の黒人青年二人と白人青年一人が自動車ごと行方不明になり、その後死体があがるというものである。私はそれを見て、黒人社会の中に入り込んで事件を解決しようとする二人の白人捜査官にいたく感動したのであるが、カイルとデイルは、ドッチラケなのである。「60年代の南部で、黒人が死んだからって、FBIが動くはずないじゃないか、ヒポ(偽善)だ。」と、辛らつなのである。 このように、白人が作った映画で黒人が出演するもので評判の悪いものはたくさんある。その頂点はなんといっても、「アンクル・トムの小屋」だろう。これは小説の映画化だが、それを見たときは私もかなりのモアハウス・シスターだったので、あまりのばかばかしさに胸が悪くなった。黒人奴隷が忠実に白人のお嬢様に仕え、二人の間に友情が生まれるというものであるが、そんなもの友情なもんか、死ぬまでマスター(ご主人様)とスレイブ(奴隷)じゃないか、と、その寒々としたきれいごとに腹が立った。黒人の間では、白人におべんちゃらをいい、へつらう黒人を「アイツはアンクル・トムだ。」といい、軽蔑するくらいである。
マーク・トウエインの小説、「ハックルベリ・フィンの冒険」にもひどい描写が出てくる。船が沈没したことをハック(白人)がサリーおばさん(白人)に報告する場面である。けが人が出なかったのかと聞くサリーおばさんにハックが「いえ、黒ん坊が一人死んだだけです。」と答え、サリーが「そうかい、そりゃあよかった。」と答えるのである。こういうことを聞いて、「そんなに目くじら立てなくても、仲良くやっていこうや。」というのは、差別されたことがない鈍感な人間である。
しかし、アンクル・トムの部屋からは長い年月がたった。今ではラッパーが自分たちの事をニガーと呼び、年寄り連中はひっくり返りそうになっている。
先ごろカイルが日本を訪ねてきたときだ。やんちゃでいい加減な大学生だったカイルは今は、投資会社のCEOである。それでも、彼がホテルにチェックインするとき、ホテル側が私を部屋に入れてくれなかった・・・!私は普通のワンピースを着た一般人にしか見えなかったと思うのだが、どうも商売人と間違えられたらしい。カイルは怒りながらも必死になって、私とカイルが写った大学の卒業式の写真や、私と彼の母親であるミセス・モーズレイの写真をフロントにみせて、「彼女は家族同様なんだ!」と説明していた。本当にばかばかしい。これは、黒人差別というより、おばさん差別じゃないの・・・。
先日、そのカイルからメールを受け取った。このコラムにもたびたび登場する母親のミセス・モーズレイが亡くなったという。マージョリー・モーズレイは、私の母親であり、師であり、かけがえのない親友だった。ミセス・モーズレイの死は皆にとっての great loss である。彼女は優しい息子、嫁、孫に看取られて穏やかに死を迎えたという。もう一度あって、ありがとう、と伝えられなかったのがとても悲しい。
2010.09.04(土) Six Feet Under
アメリカの学生にとって、一番お手軽な娯楽、デート・コースは映画鑑賞だと思う。日本に比べて格段に安いのも理由の一つであるし、映画の楽しみ方がいかにもfree country、自由の国アメリカなのである。アメリカの映画館は騒がしい。日本のそれのように、映画の始まる前に「静かに、前の人の椅子を蹴らない・・・」などと、いちいちスクリーンに出てこない。彼らは面白ければ大声で笑うし、エキサイトすれば前の椅子を叩くし、気に入らない場面では、「Boo!」と声を上げて騒ぐ。ニューオーリンズで、「マイティー・クイン」という、デンゼル・ワシントン主演の映画を見た。ジャマイカが舞台でデンゼル・ワシントンはそこの警察官の役だ。音楽プロデューサーとしても評判の高いコメディアン、ロバート・タウンゼントも出演している。細かいストーリーは忘れてしまったが、ミミ・ロジャース扮する未亡人が、デンゼル・ワシントンと見つめあい、もう少しでキス・・・、というシーンで、映画館会場の黒人女性たちが一斉に立ち上がり、「ノー!やめろ!」と叫びだしたのである。スクリーンでは、デンゼル・ワシントンは、ミミ・ロジャーズの誘惑を振り切り、その場を立ち去った。そこでまた拍手喝采なのである。
映画館は地区のショッピング・モールの中にあり、よって、黒人が多く住む地区、白人の多い高級住宅街のある地区と分かれており、私が行く映画館は黒人ばかりが集う場所だった。そんな地区だったので、黒人女性みんなの恋人、デンゼル・ワシントンが白人のミミ・ロジャーズとキスをするなど、許せなかったのだろう。
 アメリカにいて英語や文化を学んでよかった、と思うことの一つに映画のささやかな楽しみ方がある。英語での独特の言いまわし、時事ネタなど、生活しているからこそわかり面白みが増すことがある。
アメリカにいて英語や文化を学んでよかった、と思うことの一つに映画のささやかな楽しみ方がある。英語での独特の言いまわし、時事ネタなど、生活しているからこそわかり面白みが増すことがある。「クリムゾン・タイド」というこれもデンゼル・ワシントン主演の潜水艦映画では、アラバマ号という潜水艦の出陣式で、隊員皆が、「ゴー!バマ!ゴー!バマ!」とアラバマ号をもじって声をそろえ意気を上げる。そのとき艦長役のジーン・ハックマンの隣でデンゼル・ワシントンが、ちょっと戸惑ったような意味深な笑顔をチラッと見せるのである。
アメリカの黒人の中で、アラバマは「ダサい」の代名詞なのである。失礼だが日本でもちょっと前によく言われた、「ダサイタマ」と同じノリで使う。例えば車を運転していて、前の車がノロノロしていたりすると、「チッ!バマが・・・!」と舌打ちし、モールにイケてないファッションで登場すると、「バマみたいだぞ。」とからかうのである。そんな背景があって、映画の中で多くの白人隊員がバマを連呼する場面でデンゼル・ワシントンがクスッと笑ったのだと思う。
また、映画や会話などで、「さあ、これからどうしようか。」という問いかけに、「Go west.」とこたえた場合、「西へ行こう。」といってるわけではなく、西部の開拓史からとって、「開拓しに行こう。」の意味なのである。この場合の開拓も状況によっては、「ガール・ハント」だったり、警官の「パトロール」だったりする。
「最近、彼どうしちゃったのかしら?」と聞かれ、「Six feet underかもね。」と答えたら、それは、シックス・フィート地下、つまり埋葬、墓の下、亡くなっているということだったり。
こうやって鑑賞すると、映画もひときわ面白い。
私が感じるアメリカ映画のおもしろさは、台詞の良さが大きい。心に残る台詞は数多くあるのだが、これは「プラクティス」という弁護士ドラマでの一言。
交通事故にあい、怪我もしていないのに偽りを述べ、ちゃっかり相手から賠償金をせしめた若い女性に対し、新進の弁護士が「You think you got big money without injury, so lucky . But your heart was injured already.(君は怪我もしないで大金を掴んでラッキー、と思っているだろうが、その時点で君の心は蝕まれて(怪我して)いるんだよ。)」と、述べる。
そうだ、法に問われなくても、誰も知らなくても、ズルをすれば、知らず知らず心は病み、傷を負っているのだ・・・。世の中、罪を逃れてのうのうと暮らしている輩たちも、無意識下の心が蝕まれ、人間性が傷を負っていくのだろう。自分は正しいことをして生きていこう!などと、ブルース・リーの映画を見たすぐ後で「アチョー!」と騒ぐ観客さながら、鼻息も荒く正義感に燃えられるのも、私が映画から得る快感である。
2010.07.01(木) Knock the Door
アメリカにいって夢を叶えようと、その地を踏む人はいまだに多いと思う。アメリカへ渡ったはいいが、夢に押しつぶされてしまったり、ずっと夢を叶えられないまま埋もれてしまった人も、失意のまま自国へ帰った人も数え切れないくらいいると思う。しかし、私はアメリカへ渡り教育を受け、人にもまれているうちに、明らかに日本でいた頃とは違った「スピリッツ」が生まれてきたことは実感した。日本にいた頃は、楽器といえばバイオリンを少々幼少のときに習っただけで音楽の素養など全くなかった私が、アメリカの黒人大学で声楽科に入学できたことは、それだけでも驚きだと思う。試験の日、私はどうしようかと焦りまくっていた。ずらっと並ぶ黒人音楽教授たちの前で、他の素質ある黒人学生のあとに、歌はなくてはならないのである。当時私は人前で歌ったことなどなく、カラオケも嫌いだったくらいのど素人だった。いざ、自分の番が来た。黒人大学に日本人が受けに来るだけでも当時は皆興味津々だったので、教授たちの鋭い視線が一点に私に向けられている。私は意を決して、
「サム・クックの<チェンジ・イズ・ゴナ・カム>を歌います。」というと、おお、というような歓声が教授達から漏れ聞こえてきた。
I was born by the river in a little tent・・・・私は震える声で少し歌うと、ワン・コーラスでやめ、
「お聞きの通り、私はヘタです。でも、アフリカン・アメリカンの優秀な生徒に混じってソウルフルな音楽を学びたいのです。どうか、私にソウル・シスターになるチャンスをください!」
 と、演説をぶったのである。ソウル・シスターなんて今思うと恥ずかしいが、そのときは必死だった。そうすると、まず、グリーン教授(デンゼル・ワシントン並みのハンサムだった)が席を立ち、大きな拍手をしてくれた。それにつられて、他の教授たちも暖かく拍手をしてくれ、
と、演説をぶったのである。ソウル・シスターなんて今思うと恥ずかしいが、そのときは必死だった。そうすると、まず、グリーン教授(デンゼル・ワシントン並みのハンサムだった)が席を立ち、大きな拍手をしてくれた。それにつられて、他の教授たちも暖かく拍手をしてくれ、
「素晴らしい!あなたは確かに未熟です。でも、この学校を選んでくれたことを光栄に思います。声楽科はあなたを歓迎します。」と、言ってくれたのである。その日は、必要な書類をとりに一睡もせずに6時間ぶっ続け130マイルで運転し興奮のままニューオーリンズへ帰った。
入学してからも、生まれながらのシンガーである彼らに混じって、リサイタルをしたり、日々の訓練に明け暮れた。声楽の時間では、みんなの前でソロで歌い、評価を受けなければならない。私は優秀な彼らの前で、黒人霊歌「I am going home」を歌ったことがある。そのとき、男子学生が私の歌を聴いて、涙を一つ、落とした。
「カナの歌には、ソウルがあるよ、テクニックなんて関係ないよ。」と、言ってくれた。謙遜ではなく、私は本当にヘタなのに、である。しかし、そのホメ上手な学生や教授に囲まれ、努力した以上の成果が得られたのは事実だと思う。
1年後、私はステップ・アップを望んだ。同じアトランタ黒人大学群にあるスペルマン大学に転入しようと思った。キング牧師の母校であるモアハウス大学の姉妹校、スペルマン女子大学に入り学ぶことが私の「夢」だったのである。スペルマン大学は名門中の名門、黒人大学の最高峰である。勉強ができることももちろんだが、「黒人のリーダー、黒人のなかの黒人」の大学なので、果たして日本人の自分が受け入れてもらえるかどうか。案の定、面接のときに、つりあがっためがねをかけたディオンヌ・ワーウィックのような怖そうな教授が私を睨むように、
「なんで日本人のあなたが黒人の大学に入りたいの?興味本位はお断りよ。」と言い放ったのである。私はそこでまた、
「自分は、キング牧師の"I have a dream"のスピーチに魂を揺さぶられた1人です。その黒人の魂を学ぶため、受け継ぐためやってきました。キング牧師の思いを継承したいのです!」と、偉そうに言った。そうしたら、ディオンヌ・ワーウィック教授の顔が、ほころんだ。
「あなた、私はマーティンの妹なの。」キング牧師の妹である教授は入学を許可してくれ、私のために英語の個人授業を設けてくれたり、教会に連れて行ってくれたりと、とても親切にしてくれた。
スペルマン大学のキャンパスの一日目、大学長を見かけた。彼女は女性学、黒人学の権威であり著書も多数あるスーパー・ウーマンである。その雲の上の存在のひとが、
「カナ!スペルマンへようこそ!」と、声をかけてくれた。私は名前を知っていてくれただけでも嬉しくて、そこでもまた、
「ソウル・シスターになるために来ました!」と、やってしまたのである。本当に恥ずかしい。これは、日本に来て「サムライになりたい」といってるヘンな外人そのものである。それなのに、学長は、
「あなたはすでに、ソウル・シスターよ。」と抱きしめてくれたのである。
そうやって、英語がつたなくても、歌が下手でも温かく受け入れてくれたアメリカの教育現場には本当に感謝している。
ニューオーリンズにいたとき、スペルマン大学で学ぶ夢を熱く語った私に、友人のエリックが言ってくれた。
「あなたはもう扉をノックしている。あとは自分の力で扉を開くだけだ。」そのアメリカでの黒人大学での経験があるから、今でも重い扉を開けることに努力することが自分のキマリみたいになっているのだと思う。
2010.04.23(日) Friend Before Lover
六本木でナンパしているアメリカ人や、映画のなかでバーで女性を口説いている場面ばかり見ていると、アメリカ人男性は“軽い”というイメージに捉われてしまうが、実際アメリカで生活してみると、その男性像というものが見事に覆された。もちろん、バーで会ってそのまま部屋に行ってしまうような人たちもいることはいる。でも、私が出会った大半のアメリカ人は男女の付き合いに関してとても真面目なのである。例えば、チューレーン大学で知り合った黒人学生は、学費稼ぎにリーバイスのモデルをしているほどカッコイイので、きっとGFなんてとっかえひっかえだと思っていたら、大学のフレッシュマン(1年生)のときから付き合っている女性一筋なのである。彼曰く、「僕たちは“関係”を築くのに時間をかける。まだ、GFには "I love you" とは言っていない」というのである。つまり、付き合いには段階があって、I think I like you → I know I like you → I think I love you → I know I love you
まで、数年もの時間をかけることなど普通であり、自分の中にある愛情を確信するまで、軽々しく "I love you" などとは決して言わないということらしい。だからまず、友達になろう、ということからスタートして、何年もかけて恋人同士になるということはざらなのである。有名スポーツ選手でもハリウッドスターでもハイスクール・スイートハート(またはカレッジ)と結婚した人は多い。私は“一目ぼれ派”だったが、今ではその気持ちが理解できる。初めに「友達」なのだから、相手がハゲようと、お腹が出ようと、しわが増えようと、気持ちには変わりないのである。ハゲたから友達と絶交した、という話はないのだから。深い信頼関係で結ばれているから、「過ち」なども許せる。元MBL選手のマジック・ジョンソンは、大学時代の恋人と結婚したが、たくさんの女性と遊びまわり、HIVに感染してしまった。それでも、大学時代からの恋人の妻クッキーは、そんなマジックを受け入れ、今でも幸せな結婚生活を続けている。そこに至るまでのクッキーの苦悩は計り知れないと思うが。
 アトランタのモーリス・ブラウン大学で1年だけ、音楽を専攻した。黒人音楽がたまらなく好きだったので、歴史科を専攻するまでどうしても黒人学生に混ざって声楽をやりたかったからである。全くの素人の私が、才能溢れる黒人学生達のなかにぽんと入れてもらったのはいいが、朝の8時から夜の8時まで、昼休みも週末もどっぷり音楽づけの毎日だった。どんな授業風景かというと、声楽科の学生の誕生日にはレッスンの前に「ハッピー・バースデイ」を皆で歌うのだが、そのありきたりなお誕生日ソングが、彼らが歌うと、ホールを揺るがす迫力あるゴスペルになるのである。声楽科の学生ひとりひとりが、ホイットニー・ヒューストンやジョニー・ギルばりの実力者だった。私は彼らの後をついていくのに必死だった。そんな私に昼休みも放課後も時間を割いてレッスンしてくれたのが、コンサート・クワイアのマスターで、ダリルという名のナット・キング・コールに似た4年生だった。聖歌隊のレッスンのときはいつも隣に立って私のパーツをバックアップし、私が不安になるとそっと手を握ってくれる、優しいダリルのピアノで毎日練習していくうちに、私は彼にほのかな恋心を抱くようになった。しかし、彼にはフレッシュマンのときから付き合っているローラという心優しいキュートなGFがすでにいた。それでも私の心のどこかでは、自分にも望みがあるのかも、と密かに思っていた。ある日、聖歌隊のレッスンが終わり、またダリルと私だけ居残りをしていたとき、ピアノの前に座っていたダリルが私のそんな気持ちに気づいていたのであろう、真剣な面持ちで言った。
アトランタのモーリス・ブラウン大学で1年だけ、音楽を専攻した。黒人音楽がたまらなく好きだったので、歴史科を専攻するまでどうしても黒人学生に混ざって声楽をやりたかったからである。全くの素人の私が、才能溢れる黒人学生達のなかにぽんと入れてもらったのはいいが、朝の8時から夜の8時まで、昼休みも週末もどっぷり音楽づけの毎日だった。どんな授業風景かというと、声楽科の学生の誕生日にはレッスンの前に「ハッピー・バースデイ」を皆で歌うのだが、そのありきたりなお誕生日ソングが、彼らが歌うと、ホールを揺るがす迫力あるゴスペルになるのである。声楽科の学生ひとりひとりが、ホイットニー・ヒューストンやジョニー・ギルばりの実力者だった。私は彼らの後をついていくのに必死だった。そんな私に昼休みも放課後も時間を割いてレッスンしてくれたのが、コンサート・クワイアのマスターで、ダリルという名のナット・キング・コールに似た4年生だった。聖歌隊のレッスンのときはいつも隣に立って私のパーツをバックアップし、私が不安になるとそっと手を握ってくれる、優しいダリルのピアノで毎日練習していくうちに、私は彼にほのかな恋心を抱くようになった。しかし、彼にはフレッシュマンのときから付き合っているローラという心優しいキュートなGFがすでにいた。それでも私の心のどこかでは、自分にも望みがあるのかも、と密かに思っていた。ある日、聖歌隊のレッスンが終わり、またダリルと私だけ居残りをしていたとき、ピアノの前に座っていたダリルが私のそんな気持ちに気づいていたのであろう、真剣な面持ちで言った。「僕はあなたのことが大好きで大切だけど、ローラと築き上げてきた4年間を捨てるわけにはいかない。
彼女はかけがえのない女性なんだ。」
見事にふられてしまった。その後、ダリルとローラは結婚し、私は結婚式でローラのブライズ・メイドを務めさせてもらった。私のアトランタでの大切な思い出の一つである。
そんなアメリカ人の理想の恋人像は、“親友であり、兄弟のようなセクシーな恋人”という。素晴らしい。ただ、そんな相手は滅多にいないのが現実。出会ったらそれだけでも、ラッキーな人生だと思う。
2010.04.11(日) 女性にモテる職業
アメリカ女性に人気の高い男性の職業というと、なにが頭に浮かぶだろうか。 敏腕弁護士、スマートな医師、ウォール街のエリート・・・。 いや、なんと言っても消防士の人気にはかなわない。毎年のカレンダーの売り上げでも、消防士の12ヶ月は飛ぶような売れ行きだし、その月のページを飾る消防士は、ミスター・セプテンバー、ミスター・マーチ、などと呼ばれ映画スター並みの人気だ。警官たちは、「ハンサムな警官と不細工な消防士だったら、女は迷わず不細工な消防士を選ぶ。」などとぼやいている。消防士人気の理由のひとつは映画「バックドラフト」の影響があると思われるが、私はやはり消防士のイメージが、「ヒーロー」「清廉潔白」であるからだと思う。コップ(警官の俗称)のイメージの中には賄賂や、ロドニー・キング氏への暴行事件などのように権力をかさに着る、というものがクローズ・アップされがちなのに比べ、消防士は賄賂など全く関係なく火事が起きれば直ちに出動するし、人命救助というのが第一の任務になっているので、市民の味方、ヒーローのイメージが強いのだと思う。
いや、なんと言っても消防士の人気にはかなわない。毎年のカレンダーの売り上げでも、消防士の12ヶ月は飛ぶような売れ行きだし、その月のページを飾る消防士は、ミスター・セプテンバー、ミスター・マーチ、などと呼ばれ映画スター並みの人気だ。警官たちは、「ハンサムな警官と不細工な消防士だったら、女は迷わず不細工な消防士を選ぶ。」などとぼやいている。消防士人気の理由のひとつは映画「バックドラフト」の影響があると思われるが、私はやはり消防士のイメージが、「ヒーロー」「清廉潔白」であるからだと思う。コップ(警官の俗称)のイメージの中には賄賂や、ロドニー・キング氏への暴行事件などのように権力をかさに着る、というものがクローズ・アップされがちなのに比べ、消防士は賄賂など全く関係なく火事が起きれば直ちに出動するし、人命救助というのが第一の任務になっているので、市民の味方、ヒーローのイメージが強いのだと思う。アメリカの女性は合理的で、社会的地位や収入の高い男性を好むと思われがちだが、それは大恐慌時代を経た、ずっと昔の話。今のアメリカ女性は本当に男性と変わりなく得るものは得ているので、わざわざ相手に経済力や社会的地位を求めなくてもいいわけである。いま、アメリカで増えつつあるカップルの形に、女性が弁護士、医師、会計士などの頭脳労働者、男性が工事現場の職人、農業などの肉体労働者というものがある。つまり、タイトルと内容が異なってしまうが、「女性にモテる職業」というものの定義が存在しない時代なのだと思う。
しかし、アメリカ女性が一番嫌う男性像というものは明白だ。それはずばり、コントロール・フリーク。あたりさわりない日本語に訳すと支配欲の強い男ということだが、フリークという言葉を使っているので、もっと強く、軽蔑の意味がこめられている。つまり、なんでもかんでも思ったように、女性をコントロールする男、自分の持っている「女はこうあるべき」像を押し付ける男、である。たとえば、妻や恋人の友人や家族をさりげなくソフトに非難し、自分の交友関係のみに引き入れる。相手のキャリアをこれまたソフトに貶め、自分のほうがはるかに立派な人間なのだ、と思わせる。このソフトに、というところが重要で、あくまでも表面的には、「君を愛しているから、君のためを思って。」というスタンスで攻めてくる。やなヤツである。そしてひとたび女性が反抗すると、手厳しく攻撃してくる。こういう男がアメリカでは増えてきているという。もともと、マッチョな男性像というものを自分に課してきたアメリカ男が、現代は女性にかなわなくなってきたので、何とか沽券を保とうとジタバタもがいているのだと思う。
じゃあ、どんな男性がモテるのか。アメリカ女性が(多分日本女性も)口を揃えて言うのは、「あるがままの自分を受け止めてくれるひと。」職業も、趣味も、自分のルーツも、欠点も、そのまま認めてくれる人、ということ。「Just be yourself」と、言ってくれる男性なのである。これは、簡単なのか容易いのか・・・それは心の広さと愛情の深さにかかっていると私は思うのだが・・・。
もちろん、女性の方にも同じことがいえる。相手のあるがままを受け止めるというのは、夫や恋人がアルコール依存症だったり、浮気性だったとしても、一緒に乗り越え解決の道を見つけるということだ。これに関しては、私は多くのアメリカ女性に拍手を送りたい。実際、私の周りにも相手がどんな問題を抱えていても共にカウンセリングにかかり、とことん話し合い、乗り越えていった女性がたくさんいる。相手を支えるという点では、優しく、しかしタフでもあるハードボイルドなアメリカ女性からたくさん学んだと思う。
2010.03.06(土) 南部のミスコン
 南部の女性には「サザン・ベル」と呼ばれるような、女性らしく美しい人が多い。州ごとのミス・コンテストも盛んだが、私が見た、アトランタの黒人大学のミスキャンパス・コンテストもとても楽しいものだった。アトランタにはアトランタ・ユニバーシティーセンターといって、黒人大学が5つ集結した学区がある。男子校のモアハウスの姉妹校として、アリス・ウォーカー、キング夫人を輩出したのがスペルマン女子大学だ。そこのスペルマン大学のミスコン優勝者は、ミス・モアハウスとなる。大会はセンター内にあるキング・ホールで行われた。舞台で5人の出場者たちが、様々な芸を披露してくれる。バレエを美しく踊るもの、オペラを歌うもの、詩を読むもの・・・皆美しい。比較的肌の色が薄く、髪の毛もこてをあててカールを伸ばしたストレートヘアにしている者ばかりだ。友人と見に行ったのだが、皆美しいのは美しいのだが、ちょっと退屈し、「皆似たタイプの女性なので、これなら誰がなってもおかしくないね。」と話していた。
南部の女性には「サザン・ベル」と呼ばれるような、女性らしく美しい人が多い。州ごとのミス・コンテストも盛んだが、私が見た、アトランタの黒人大学のミスキャンパス・コンテストもとても楽しいものだった。アトランタにはアトランタ・ユニバーシティーセンターといって、黒人大学が5つ集結した学区がある。男子校のモアハウスの姉妹校として、アリス・ウォーカー、キング夫人を輩出したのがスペルマン女子大学だ。そこのスペルマン大学のミスコン優勝者は、ミス・モアハウスとなる。大会はセンター内にあるキング・ホールで行われた。舞台で5人の出場者たちが、様々な芸を披露してくれる。バレエを美しく踊るもの、オペラを歌うもの、詩を読むもの・・・皆美しい。比較的肌の色が薄く、髪の毛もこてをあててカールを伸ばしたストレートヘアにしている者ばかりだ。友人と見に行ったのだが、皆美しいのは美しいのだが、ちょっと退屈し、「皆似たタイプの女性なので、これなら誰がなってもおかしくないね。」と話していた。そこで最後の女性のパフォーマンスになって、観客があっと驚いた。ホームレスの汚い格好をしてショッピング・カートを引き登場したのである。そしてゴミ箱を漁っている。「これって、ミスコンだよね?」と、友人と顔を見合わせた。失礼だがその最後の女性は格好もさることながら、体格もでっぷりとしていて、肌の色も濃く、髪の毛もナチュラルなアフロのままなのである。そのホームレス姿の女性が、ゴミ箱の中から空き缶を見つけ、それを拾い上げすすり、口を拭い大きく「げええっぷ・・・!」とやったので会場から「Oh, no!」とかブーイングが聞こえ始めた。その時である。その女性が薄汚いホームレスの服を脱ぎすてローブになり、高らかにゴスペルをうたいだしたのである。その歌声といったら、アレサ・フランクリンもぶっ飛ぶような迫力なのである。会場はそのとたんに歓声で溢れ、皆総立ちである。帽子を投げるもの、ジャケットを振り回すもの、踊りだすもの・・・。キング・ホールが熱狂のゴスペル会場となった。私も彼女の迫力ある歌声に鳥肌が立ち、声援をおくっていた。もちろん、ミスコン優勝者のティアラはホームレスに扮した彼女が持っていった。決してお人形さんのように美しくはなく、綺麗な曲線美を見せたわけでもない、ナチュラルな黒人の姿のままのソウルフルな彼女の圧勝である。
 あの頃の黒人社会では、髪の毛にこてをあて白人のようなストレートヘアーにするのが流行り、肌の色もライトな方がいい、という風潮だった。しかし、ミスコンの会場の熱気はそれを覆す勢いだった。60年代にブラック・パンサー党がたからかに提唱した「ブラック・イズ・ビューティフル」がいつまでも人々の心に深く存在していることを見た瞬間だった。
あの頃の黒人社会では、髪の毛にこてをあて白人のようなストレートヘアーにするのが流行り、肌の色もライトな方がいい、という風潮だった。しかし、ミスコンの会場の熱気はそれを覆す勢いだった。60年代にブラック・パンサー党がたからかに提唱した「ブラック・イズ・ビューティフル」がいつまでも人々の心に深く存在していることを見た瞬間だった。ミスコンといえば、ニューオーリンズのジムによく通っていた頃、「ミス・ニューオーリンズ・コンテストにでないか?」といわれ、なぜ自分が、とどぎまぎしちょっと喜んだのだが、それは実は、ミスはミスでもボディビルダーの筋肉モリモリコンテストのことだった。当時のミスター・ニューオーリンズをそのジムから出していて、彼が小柄なので、背も小さい東洋人の私が目に留まっただけだった。やっぱり、自分はサザン・ベルには程遠いのだ、と、あらためて実感した。
2010.01.18(月) ハイチの友人
ニューオーリンズでの長い夏休み、私は1週間をニューヨークで過ごした。日本にいる頃、絵画の仕事をしていたときの知人が学生生活を送っている私にバイトとして、簡単な仕事をニューヨークでくれたのである。ニューオーリンズの夏は、暑く、湿気でじっとりとしていて、長い。そんな体にまとわりつくような湿気を私は大好きだったが、たまに違った空気を吸うのもいい、そう思い、ニューヨークへ向かった。ニューヨークの街で、久々にビジネススーツだの、ハイヒールだの、着飾っている人々を見た。ニューオーリンズでは、夏はみな、思いっきり肌を露出させたラフな格好で湿気対策をするので、男性はその頃はやっていた、「マッスルズ・Tシャツ」という、ほとんど体を隠さないランニング・シャツが定番だったし、ジャケットなど、考えるだけで暑さで頭に血が上ってしまいそうだった。そんなニューヨークで私を待っていた仕事は、きらびやかで贅沢なものだった。自家用ジェットでアメリカを縦断する画商、一晩3000ドルもする娼婦をただ食事のためだけに呼ぶイタリア人の画商、売れっ子のフランス人作家・・・。そのような面々とウオルドフ・アストリアでミーテイングをし、大きなリムジンで移動をし、夜は高級レストランでクリュッグのロゼをあける。チューレーン大学の芝生に、裸足で寝っころがり、勉強する生活と180度違う日々は、3日もすればうんざりしてしまった。そこで私は、皆の群れを離れ、ひとりで街へ繰り出すことにした。
ソウルフルな音楽と黒人達の汗が恋しくなっていた私は、タクシーにのり、運転手さんに、「黒人音楽の聞けるクラブへ連れて行ってください。」と頼んだのだ。運転手さんは、「オーケー。一つ、いいところを知っているんだけどなあ、そこは会員制だから、メンバーのエスコートがなければ、店に入れないんだよ。」と、残念そうに言う。そのとき、ちょうど信号待ちで止まった私の乗っているタクシーの隣に、一台の車が並び、こちらを見て何か言っていた。その車には黒い肌の男性が3人乗っていた。それを見た運転手さんと彼らはフランス語で何かしゃべっている。運転手さんが振り向いて私に言った。「僕が言った会員制のクラブ、ネイルズに、彼らはちょうど行くところらしい。あなたを連れていってくれるというんだけど。」 海外旅行か留学を考えている女性には決して、決して薦めないが、そのとき私は、彼らと一緒にクラブにいくことにした。タクシーがネイルズにつくと、運転手さんも降りて、「彼女を頼む!」と、彼らに念を押している。車から出てきた、3人の黒人男性は、皆、オシャレなスーツを着こなし、インテリジェンスな顔つきで、20代前半のように見えた。そのうちの一番背が高く、ひょろりとした男性が、私のエスコート役を買って出てくれ、クラブに入った。他の2人も、にこやかに微笑みながら、私の周りを取り囲んだ。
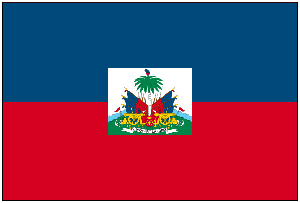 クラブはむっとするような汗と熱気で、ガンガンとソウル・ミュージックが鳴り響き、黒人魂に餓えていた私はご機嫌だった。3人の男性達も紳士的で和やかだった。話す英語はフランス語のアクセントがあり、とてもきちんとした綺麗なものだった。私をエスコートしてくれた青年は、「僕はショーン、彼らが僕の従兄弟で双子のウノ、ワノ。」と紹介し、自分たちはハイチからの移民で、今、ニューヨーク大学で建築学を学んでいることを話してくれた。ハイチから来た家族は、ニューヨークでブティックとレストランを経営しているという。そこでショーンは、「今日は、声をかけたのが僕たちだからいいけど、絶対、こんなことはしないほうがいい。」と、自分たちのことを棚に上げて言うのだった。ショーンたちは終始私を気遣い、紳士的だった。
クラブはむっとするような汗と熱気で、ガンガンとソウル・ミュージックが鳴り響き、黒人魂に餓えていた私はご機嫌だった。3人の男性達も紳士的で和やかだった。話す英語はフランス語のアクセントがあり、とてもきちんとした綺麗なものだった。私をエスコートしてくれた青年は、「僕はショーン、彼らが僕の従兄弟で双子のウノ、ワノ。」と紹介し、自分たちはハイチからの移民で、今、ニューヨーク大学で建築学を学んでいることを話してくれた。ハイチから来た家族は、ニューヨークでブティックとレストランを経営しているという。そこでショーンは、「今日は、声をかけたのが僕たちだからいいけど、絶対、こんなことはしないほうがいい。」と、自分たちのことを棚に上げて言うのだった。ショーンたちは終始私を気遣い、紳士的だった。その日は、黒人音楽に満足し、ホテルに帰り、翌日からは仕事を終えると、スノッブな画商たちとわかれ、ショーン、ウノ、ワノと、彼らの家族が経営するレストランで、ハイチからの大家族とワイワイとビーンズと肉中心の食事を楽しんだり、彼らの通うニューヨーク大学の図書館で、ハイチの歴史を学んだり、とても楽しい時間を過ごした。私がニューオーリンズに帰るときもショーンたちは空港まで送ってくれて、「アメリカは怖いところだから、むやみに人を信じないように。」と忠告するので、「私はあなた達と出会ったからラッキーだったのね。」というと、「タクシーの運転手さんが、あなたの事を本当によろしく頼む、僕らのことを信頼している、と言ったんだよ。僕らヘイシャンは、人の信頼を裏切ることはとても恥ずべきことだと思っている。」と、真面目な面持ちで言ったのだった。
その後も、しばらくはニューヨークへ行く度にショーンたちと会ったり、連絡のやり取りをしていたのだが、私がアトランタへ行ってそのうち、連絡も取らなくなってしまった。ショーンと、ウノ、ワノは、自分たちの民族、国家に誇りを持った、ニューヨークの王子様だった。ニューヨークにいるときは、いつも私を紳士的にエスコートし、家族の一員ように守ってくれた。彼らは今、どうしているのだろう・・・。
ハイチは多くの問題を抱えた、経済的に困窮している国だ。今回の地震でも多大な被害がでている。私にはとても他人事とは思えない。ショーンと、ウノ、ワノが、ニューヨークで私を守ってくれたように、ハイチの人々を守れたら、と思う。今の私にできることは限られていて、本当にもどかしい。ハイチの一日も早い復興を心から願う。
2009.12.20(日) ニューオーリンズのクリスマス
12月の声を聞くと私は、自分で「ソウル・クリスマス」と名づけたMDを毎日聴く。クリスマスが過ぎても聴き続けるそのMDでは、ルーサー・ヴァンドロスやテンプテーションズのクリスマスソングとともに、テイク6の美しいアカペラが聖夜を称えている。クリスマスの思い出はそれが、楽しい思い出であっても悲しいものであっても、過去になってしまえば全てせつなく感じてしまう。クリスマスが終わればニューオーリンズを発つことは、夏には友人達には言っていたが、わたしがなぜ、そこまでアトランタの黒人大学にこだわるのか、ニューオーリンズで唯一白人の友人、メリールゥには、理解できないでいた。
 メリールゥに連れられて、スーパードームに、ニューオーリンズ・セインツのフットボールの試合にいったときのこと、ヘッド・コーチのジム・ムーア(当時、NFLの監督の中で一番ハンサムとされていた名将)と懇意にしていたメリールゥは、試合後私を選手の更衣室へ続く廊下に連れて行って、ジム・ムーアを紹介してくれた。そこで、ジム・ムーアは試合のない週末に私達を自宅に招待してくれた。選手やコーチたちも来るという。私は飛び上がらんばかりに嬉しかったのだが、その話をしている最中、周りは、試合後の野獣の熱気ムンムンで、上半身裸で腰にタオルを巻いただけの筋肉隆々のライン・バッカーがのしのし歩いていたり、2メートルもあろうかと思うワイド・レシーバーがGFと熱いキスを交わしていたりと、目のやり場に困っていた。メリールゥは、「誰が気に入った?」と私に聞くので、私が返答に困っていると、なんと私をニューオーリンズに引き止めるには、ニューオーリンズの男性と結婚するのがいいと思い、セインツの選手とのマッチ・メイクをたくらんでいたのだ。ジム・ムーア氏も賛同していて、「クオーター・バックのコーチはナイス・ガイだよ。」などと薦めるのである。帰りに、メリールゥに、アトランタへはどうしても行かなければならない、というと、下を向いて、「クリスマスまでは、いるのね・・・。」と、ぽつりと言った。
メリールゥに連れられて、スーパードームに、ニューオーリンズ・セインツのフットボールの試合にいったときのこと、ヘッド・コーチのジム・ムーア(当時、NFLの監督の中で一番ハンサムとされていた名将)と懇意にしていたメリールゥは、試合後私を選手の更衣室へ続く廊下に連れて行って、ジム・ムーアを紹介してくれた。そこで、ジム・ムーアは試合のない週末に私達を自宅に招待してくれた。選手やコーチたちも来るという。私は飛び上がらんばかりに嬉しかったのだが、その話をしている最中、周りは、試合後の野獣の熱気ムンムンで、上半身裸で腰にタオルを巻いただけの筋肉隆々のライン・バッカーがのしのし歩いていたり、2メートルもあろうかと思うワイド・レシーバーがGFと熱いキスを交わしていたりと、目のやり場に困っていた。メリールゥは、「誰が気に入った?」と私に聞くので、私が返答に困っていると、なんと私をニューオーリンズに引き止めるには、ニューオーリンズの男性と結婚するのがいいと思い、セインツの選手とのマッチ・メイクをたくらんでいたのだ。ジム・ムーア氏も賛同していて、「クオーター・バックのコーチはナイス・ガイだよ。」などと薦めるのである。帰りに、メリールゥに、アトランタへはどうしても行かなければならない、というと、下を向いて、「クリスマスまでは、いるのね・・・。」と、ぽつりと言った。メリールゥは、8歳になる息子と、豪邸に住んでいた。夫は、やり手の実業家で経済的には成功者だったが、会社の若い秘書と恋に落ち、家を出てもう数年になる。当時のルイジアナの法律では別居して何年かたつと一方的に離婚が認められてしまうのである。そのタイム・リミットがクリスマス・イブの前夜だった。私は、その日はメリールゥの家で過ごした。メリールゥは、私に結婚式の写真や家族旅行など、結婚生活が幸せだったアルバムを見せ、「まだ、彼を愛してる。」といいながら、目じりに涙をため、微笑むのである。その脇では息子が無邪気にクリスマス・ツリーの飾りに目を輝かせている。そのとき、ドアベルがなり、フェデラル・エクスプレスの職員が、封書を持って立っていた。それは、夫からの離婚届だった。それを受け取った瞬間、メリールゥが泣き崩れ、何も知らない息子は、「ダディから?サンタさんから?」と、走り回ってる。
その日、一晩彼女の家で過ごした私は、悲しみに沈んでいるメリールゥを残してクリスマス後にニューオーリンズを発つことが、ますます辛くなってきた。翌朝、クリスマス・イブ、メリールゥの家を心配で出られない私に、メリールゥは、泣き明かして腫れた目で、笑顔を作りながら、「行きなさい。自分の信じたことを貫いて。」と、送り出してくれたのである。私をニューオーリンズに引き止めていたエリージャン・フィールズの教会のメンバーも、イブのサービスのとき、力強いゴスペルで、私の新しい出発を祝ってくれた。チューレーン大学のBFも、その最後の夜、オートバイでポンチャントレイン湖に連れて行ってくれ、コーズウエイをドライブしたあと、リチャード・ライトの「ブラック・ボーイ」を私に手渡し、「きみを誇りに思う。頑張れ。」と、拳を合わせてくれた。
ニューオーリンズで最初で最後のクリスマスは、優しくて力強いニューオーリンズっ子の心意気を実感した思い出深いものとなった。いまでも、クリスマスになると、ニューオーリンズのソウル・メイトたちの、可憐ながらもしっかり実をつけるドッグウッドの花のような笑顔を思い出し、私に人生に立ち向かう勇気を与えてくれている。
2009.11.23(月) サザン・ホスピタリティ 1
The door is always open for you."いつでもあなたを歓迎する"という意味のこの言葉を私はニューオーリンズでよく耳にした。南部人の情の深さ、暖かさを感じさせる言葉だ。実際、私もずいぶんニューオーリンズの人々の優しさにふれた。
大学のキャンパス内にある寮を出て、エリージャン・フィールズ・アヴェニュー近くのアパートにひとり住まいをすることに決め、必要にかられて車を購入することにした。その車選びにも歌手のノーマンやらGFのグゥエンやら、皆がゾロゾロ一緒にきてくれて、ああでもない、こうでもない、もっと安くしろ、などと私に代わって交渉してくれる。中古車のデイーラーも驚いたことと思う。ちっちゃい東洋人の女が、筋骨隆々たる黒人男性やら、牧師やら、10代の母とその赤ちゃんやら、謎の美女を従えて、車を物色しているのだから。
そうして、ダッジの車を購入し、喜び勇んでアパートの駐車場をぐるりと回ったとき、なんと初日で駐車場内にある隣人の車にコツン、とやってしまった。その車のバンパーがぼっこりとへこんでいる。私は青くなって、初めて会うその隣人のドアを叩き、車をぶつけてしまったことをわびた。その持ち主は、まさにニューオーリンズ美人、という感じの褐色の肌が美しいセクシーな女性だった。彼女は、悠長に「あら、そう。」と、車のダメージをチェックすると、「大丈夫、こんなの。従兄弟に直してもらうから。」と、微笑んでいる。しぐさがやけに色っぽい。「でも・・・」と、私が戸惑っていると、「Take it easy.(気にしないで) それよりあなた、今度一緒にのみに行かない?」と、誘うのである。東京で長年過ごし、村上龍を愛読していた私は、「コレは罠ではないか? のこのこ飲みにいったら、実は彼女はギャングのボスの情婦で、私はコロンビアあたりに売られてしまうのでは・・・?」などと、本当に失礼なことを想像してしまった。もちろん、彼女はギャングの情婦ではなく、銀行の秘書で、本当に気のいいニューオーリンズ人だったのである。その日から、彼女とはよくクラブに一緒に出かける友人となった。
 ブラック・ヘリテージ・フェステイバルという音楽の祭典が5月に開催される。その期間中はニューオーリンズ中のホテルは満員でレンタカーも借りられない。ニューオーリンズのシティパークを中心にあちらこちらで、ジャズやゴスペル、ソウル・ミュージックの野外ライブをやっている。その周りの芝生にはたくさんの屋台が立ち並び、クロウ・フィッシュ(ザリガニ)とコーンとジャガイモをスパイシーなスープで煮詰めた郷土料理や、アンドウイェ(固くて塩味の強いソーセージ)、レッド・ビーンズ・アンド・ライス(インゲン豆やソーセージと米を煮込んだもの)などが、いい匂いをさせているのである。1週間以上続くお祭りだと思ったが、私は毎日のように学校が終わると、その頃は寮に住んでいて車がなかったので、大学の友人と行くか、一人でもタクシーを使って通っていた。
ブラック・ヘリテージ・フェステイバルという音楽の祭典が5月に開催される。その期間中はニューオーリンズ中のホテルは満員でレンタカーも借りられない。ニューオーリンズのシティパークを中心にあちらこちらで、ジャズやゴスペル、ソウル・ミュージックの野外ライブをやっている。その周りの芝生にはたくさんの屋台が立ち並び、クロウ・フィッシュ(ザリガニ)とコーンとジャガイモをスパイシーなスープで煮詰めた郷土料理や、アンドウイェ(固くて塩味の強いソーセージ)、レッド・ビーンズ・アンド・ライス(インゲン豆やソーセージと米を煮込んだもの)などが、いい匂いをさせているのである。1週間以上続くお祭りだと思ったが、私は毎日のように学校が終わると、その頃は寮に住んでいて車がなかったので、大学の友人と行くか、一人でもタクシーを使って通っていた。ある日、ひとりでタクシーを捕まえると、運転手さんが気のいい(大体みな陽気で親切な運転手さんばかり)かたで、いろいろとおしゃべりをしながら向かった。彼はカリブ諸国からの移民で、タクシーの運転手と沖仲士をしながら、家族を養っているという。その彼が、「アリゲーター(ワニ)は食べたか?」と聞くので、まだ食べていない、というと、フェステイバルで屋台が出ているから、ぜひ食べなさい、という。とても美味しいし、元気になるから、と。「わかった、食べますね。」と、返事して、シティパークに着き、5ドルあまりの料金を払おうとすると、いらない、という。「せっかく、遠くからニューオーリンズに勉強に来ているのだから、美味しいものを食べて、楽しい思いをしてほしい。
 その5ドルでアリゲーターを食べてくれ」と、かたくなにお金を受け取ろうとしない。私は、代わりに何か日本のお土産でもと思ったが、あいにく何も持ち合わせていなかった。押し問答の末、私は彼の好意に甘え、固い握手をさせてもらい、車を降りた。
その5ドルでアリゲーターを食べてくれ」と、かたくなにお金を受け取ろうとしない。私は、代わりに何か日本のお土産でもと思ったが、あいにく何も持ち合わせていなかった。押し問答の末、私は彼の好意に甘え、固い握手をさせてもらい、車を降りた。車を降りると、野外ステージから、ゴスペルの力強い歌声が聞こえてくる。私はさっそく、人波を掻き分け、アリゲーター料理の屋台を見つけ、4ドル99セントの小皿料理を買った。プラスチック製のフォークですくって食べるスパイシーな味付けのアリゲーターは鶏肉のようにさっぱりしていて、運転手さんの言うとおり、腹の底から力が沸いてくる味だった。
いまでも、ゴスペルを聴き、草の匂いが立ちのぼる5月になると、あのアリゲーターの味と親切な運転手さんのことを思い、昨今の厳しいアメリカの移民政策を憂える。アメリカを土台から作り上げたのは、他でもない、彼らの力なのだから。"あなたをいつでも歓迎する"という言葉通り、懐の大きいアメリカであって欲しいと思う。
2009.10.30(金) ポンチャントレイン・レイク・コーズウエイ
アメリカ最長の大河が流れ、メキシコ湾に大きく扉を開いているニューオーリンズ。フランス領だったかつては、街の振興のため、パリの貧民達や囚人達が労働力としてかき集められ、奴隷の最大の市場だった。それらの民を祖先に持つ街は、退廃的で逸楽的であり、他の保守的な南部の都市にはない魅力があるのだと思う。そんなニューオーリンズに憧れる、ミシシッピーやアラバマの住人も多かったはずだ。どんな不況でも国が荒れていても、ニューオーリンズにさえ行けば、美味しい酒も食べ物も女性も手に入るだろう、あのポンチャントレイン湖にかかる橋を渡りきれば。24マイル(約38km)の橋を渡るときの胸の高まりは、それを渡る人々それぞれの特別な思いがあっただろう。心躍るジャズのリズムだったり、石畳を踏み鳴らす美しい女の足音だったり、刺激的なスパイスがフライパンの上で弾けるメロデイーだったり。ポンチャントレイン湖は最深部で3mと浅く、いつも白い静かなさざ波がたっている。夏の日の夜は、ワイン片手に湖岸に腰掛けると、そのグラスに蛍が留まり、手元をぼうっと照らしてくれる。橋をドライブしているときウインドウから見える風景は、南部の強い陽の光がそのさざ波を照らし、湖面全体にダイヤを撒き散らしたようにキラキラと眩しい。
 私がポンチャントレインコーズウエイを渡るときは、ニューオーリンズを出発してミシシッピーをぬけ、アラバマを通り、目的地であるアトランタへ行くためだった。もともと、アトランタの黒人大学に入学するのが目的で留学したが、その前に英語力を上げるため、たまたま選んだのがニューオーリンズで、私は早くアトランタへ行きたくてしょうがなかった。ポンチャントレインコーズウエイは、アトランタへと続き、私とキング牧師を繋ぐ夢の架け橋だった。ところが、ニューオーリンズで暮らしているうちに、その魅力にとりつかれ、去りがたくなってしまった。そういう人は多いのではないかと思う。港にふらりと降り立ち、そのまま居ついてしまったり、アムトラックで途中下車してしまったり。ニューオーリンズは自分の夢も惑わせてしまうほどの強い磁力を持っていた。「ニューオーリンズにもディラードという黒人大学があるじゃないか、そこで学べばいい。」と、ミシシッピー出身、チューレーン大学4年生のBFにもいわれ、正直心がぐらついたこともあった。しかし、そのたびに私は、「アトランタでなければ、キング牧師が卒業したモアハウス大学でなければ意味がない。」と、自分の意思を強く持たせていた。
私がポンチャントレインコーズウエイを渡るときは、ニューオーリンズを出発してミシシッピーをぬけ、アラバマを通り、目的地であるアトランタへ行くためだった。もともと、アトランタの黒人大学に入学するのが目的で留学したが、その前に英語力を上げるため、たまたま選んだのがニューオーリンズで、私は早くアトランタへ行きたくてしょうがなかった。ポンチャントレインコーズウエイは、アトランタへと続き、私とキング牧師を繋ぐ夢の架け橋だった。ところが、ニューオーリンズで暮らしているうちに、その魅力にとりつかれ、去りがたくなってしまった。そういう人は多いのではないかと思う。港にふらりと降り立ち、そのまま居ついてしまったり、アムトラックで途中下車してしまったり。ニューオーリンズは自分の夢も惑わせてしまうほどの強い磁力を持っていた。「ニューオーリンズにもディラードという黒人大学があるじゃないか、そこで学べばいい。」と、ミシシッピー出身、チューレーン大学4年生のBFにもいわれ、正直心がぐらついたこともあった。しかし、そのたびに私は、「アトランタでなければ、キング牧師が卒業したモアハウス大学でなければ意味がない。」と、自分の意思を強く持たせていた。いよいよ、アトランタ大学群(黒人大学が5つ集まったユニバーシティー・センター)の一つに入学が許可されたのは、ニューオーリンズで迎える初めてのクリスマス間近の日だった。私はクリスマス後にニューオーリンズを発つことに決めた。アパートの荷物は全て引き払い、がらんどうになった部屋で、最後のニューオーリンズの夜を過ごし、夜明けとともに、最後の一つのバックを車のトランクに載せ、BFからもらったリチャード・ライトのペーパーバック「ブラックボーイ」を助手席に置き、ポンチャントレインコーズウエイに続く国道を走った。「ブラックボーイ」の表紙、オーバーオールを来た黒人青年の強い瞳が私をじっと見つめている気がした。
ポンチャントレインコーズウエイに乗ったときは、太陽も頭上に上がり、湖面の輝きがいつもにも増しして煌びやかに感じ、いよいよニューオーリンズとお別れだ、と思うと涙で目が曇った。24マイルの道のりを私は時速75マイルで走った。半時間足らずでポンチャントレイン湖の向こう側についてしまう。運転している前方には果てしなく続く橋のほか、何も見えない。カーラジオから聞こえてくるニューオーリンズ黒人局のDJの声がだんだんと途切れてくる。これでよかったのだろうか、ニューオーリンズの黒人大学で学び、エリージャンの黒人教会で歌い、ノーマンやミセス・モーズレイ、チューレーン大学のBFと黒人社会に根付いて暮らしていけばそれはそれでよかったのでないか、との思いが駆け廻った。しかし橋にのってしまった以上、途中で引き返すことは物理上無理で、とにかく湖の向こう岸までたどり着かなくてはならない。ハンドルを握る手に力が入っていた。
そんなとき、電波が悪くなり途切れ途切れのカーラジオから、マービン・ゲイとタミー・テレルの「エイント・ノウ・マウンテン・ハイ・イナフ」が聴こえてきた。"どんな高い山も深い谷も広い河も、私達を阻まない・・・"その歌声が終わる頃には、私は、ちゃっかりと涙も乾き、橋の先、アトランタへ続く道がはっきりと見えてきた。ポンチャントレインコーズウエイの24マイルの間に、心の中がニューオーリンズの思い出から、アトランタの黒人大学で始める新しい生活の喜びへと移り変っていった。現金なようだがそんな効力も世界一長い橋、ポンチャントレインコーズウエイの魔力の一つかもしれない。
2009.10.12(月) ヴードゥーの女神たち
 ニューオーリンズという街のイメージは、フレンチ・クオーターのバルコニーに施された繊細なアイアン・ワーク、ミシシッピー河を行く蒸気船、バーボン・ストリートの喧騒、ディキシーランド・ジャズ、マルディグラのビーズ、セントルイス・セメタリーの白い墓標・・・などでそれぞれが独自のオーラを放ち、旅行者を魅了していると思う。私はそこにもうひとつ、ニューオーリンズの街が持つ「妖しさ」に、とても惹かれる。アメリカの中で最もヴードゥー信仰が栄えた街。ハイチなどカリブ海からの奴隷が自由黒人となって、広めたといわれている。そのヴードゥーの女王としてニューオーリンズで君臨していたのが、"マリー・ラヴォー"である。父親が白人で黒人の母を持つ、飛びぬけた美人だったといわれている。ヴードゥー・クイーンがなにをするか、といえば、
ニューオーリンズという街のイメージは、フレンチ・クオーターのバルコニーに施された繊細なアイアン・ワーク、ミシシッピー河を行く蒸気船、バーボン・ストリートの喧騒、ディキシーランド・ジャズ、マルディグラのビーズ、セントルイス・セメタリーの白い墓標・・・などでそれぞれが独自のオーラを放ち、旅行者を魅了していると思う。私はそこにもうひとつ、ニューオーリンズの街が持つ「妖しさ」に、とても惹かれる。アメリカの中で最もヴードゥー信仰が栄えた街。ハイチなどカリブ海からの奴隷が自由黒人となって、広めたといわれている。そのヴードゥーの女王としてニューオーリンズで君臨していたのが、"マリー・ラヴォー"である。父親が白人で黒人の母を持つ、飛びぬけた美人だったといわれている。ヴードゥー・クイーンがなにをするか、といえば、"占い""まじない"の類である。マリー・ラヴォーはその魔術と巧みな社交術で、ニューオーリンズの黒人だけでなく、白人層も虜にしていったという。いまでも、ニューオーリンズを訪れたら、マリー・ラヴォーの墓に参らないと不幸が降りかかる、などといわれるほど、彼女の魔術は健在である。そんな民間伝承をすんなりと信じてしまえるところにニューオーリンズの妖しい魅力があるのだと思う。
そんな魔女とまで言わなくても、ニューオーリンズには魅力的でパワーを持った女性がたくさん存在した。前回名前がでた、理想郷通りのミセス・モーズレイもその一人。彼女は早くに夫を亡くし、小学校の教師をしながら、二人の息子を育て上げた。当時、次男はアトランタのモアハウス大学に在学しており、後に私がモアハウス大学の姉妹校(モアハウスは男子大学)のスペルマン大学に編入したときには、試験休みのたびに、息子と、彼女の親戚など7人で私の車にギュウギュウ詰めで乗り込み、ニューオーリンズに帰ったものだった。大体、夜の10時ごろアトランタを発ち、朝の6時過ぎにニューオーリンズのミセス・モーズレイ宅に着く。一晩中運転してクタクタの私達を見るなり彼女は、「シャワーより何より、コレを食べなさい!ニューオーリンズっ子たち。」といって、温かいガンボ・スープをたっぷりよそってくれた。彼女の作るガンボ・スープはレストランのものよりさらさらでオクラと鶏の首筋肉がたっぷり入った、まさに元気の出るソウル・フードだった。
ミセス・モーズレイは私の母と同年代だと思うが、私達は一晩中でもいろいろな話をした。私がスペルマン大学という、黒人女性にとっては最高に誇り高い大学に入ったとき、人種的なことなども相談にのってもらった。私が必死に黒人社会に溶け込もうと努力をして、ガチガチになっていたときも彼女は、「You are already soul sister, so just be yourself.(あなたはすでに私達の同胞なのだから、あなたらしくいなさい。)」と、私の肩を優しくさすり、心を解きほぐしてくれた。また、恋の悩みで、「カレシに、ジュリーという女が(ミセス・モーズレイも何度か会ったことのある黒人女性)言い寄っている!」と、私が泣き言を言うと、「あんなウイッグをつけたニセ黒人がいいって言う男なら、尻を蹴っ飛ばして、くれてやりなさい!」と、私の目を覚まさしてくれたり。そうやって、試験休みの間中、一緒にキッチンに立って、コーン・ブレッド用のトウモロコシの実をほぐしたり、ペカン・パイを焼いたりしながら、しゃべり続けるのが楽しかった。試験休みが終わり、アトランタの大学へ戻る前、必ずミセス・モーズレイは、「You have me.(あなたには私がいるから)」といって、私の肩を優しくさすってくれた。そのミセス・モーズレイの手の温もりが、ヴォードゥーのどの魔術よりも、私を元気づけ目標へと進ませてくれたのである。
2009.09.16(水) 理想郷という名の裏通り II
《承前》 その頃、南部ではまだまだ異人種間のカップルは、目に見えないところで差別されていた。歌手ノーマンのGFの固い表情は、白人として黒人教会に来ている緊張なのだと私は思った。 「彼女はグゥエン。彼女の家族もみんなこの教会のメンバーなんだよ。」ノーマンはそういってGFを紹介した。私は、あれ?と思った。その教会のどこを見回しても白人はいない。戸惑った私の表情をみて、グゥエンは固い表情を崩すことなく言った。
「I am black.(私は黒人よ)」
グゥエンはただ肌が白いのではない。顔の造作も白人のそれなのだ。ノーマンがとりなすようにいった。
「グゥエンの両親も祖父母も曾祖父母もみな、黒人だよ。ただね、僕らのアメリカでの奴隷としての歴史の中では、白人にレイプされて白人の血が混じった子孫をたくさん残しているんだ。そのずっと昔の白人の血がそれだけ受け継がれて、グゥエンのように全く白人の姿の黒人が生まれることがあるんだ。グゥエンの兄弟もみな、全くの黒人だというのにね。」
家族写真を撮っても、黒人だけの小学校に通っても、グゥエン一人だけ白人の姿。しかし、彼女の中身は、ソウルは、黒人そのもの、ということを、その後時間をかけて彼女を知るほどにそう実感した。白人の姿に生まれてしまった苦しみも。
彼女のように白人と変わらぬ姿の黒人は存在する。そのうちの何人かは、「パッシング」といって、黒人としての自分のルーツを捨て、家族も友人も、思い出も捨て、白人として生きていく道を選ぶという。知り合いに会わないように、遠くに引越し、家族と手紙や電話のやり取りもせず、きっぱりと自分の歴史を捨て、白人社会の中で生きていく。その生き方も、グゥエンのように黒人の中で生きて行く道もそれぞれ苦難の日々だと思う。ノーマンとグゥエンはまだ結婚していなかったが娘が一人いた。彼女は父親にそっくりのルックスだった。その娘もまだ、母親の姿と自分の姿の違いに戸惑っているという。
グゥエンとの初対面のあと、ノーマンのリードで聖歌隊で歌っている彼女をみていると、力強く、誇らしげで、一体、肌の色とは何なのであろうと思う。
初めて会ったときのグゥエンの固い表情は、私のことを人気者のノーマンを狙っている油断のならない女の登場だと誤解したらしい。その誤解もとけて、グゥエンは逆に、黄色人種でありながら黒人の文化に飛び込んだ私に親近感を持ってくれたようだった。私のニューオーリンズでの初めての黒人女性の友人は、肌の白いソウルフルなグゥエンとなった。
そのエリージャン通りの教会では、心底ソウルフルなビック・ママ、ミセス・モーズレイという、親子ほども歳が離れていたが親友のようにお付き合いをさせてもらった女性もいた。後にアトランタの黒人大学に転入し、街を離れた私にいつも、帰る家と温かいソウル・フードを与えてくれた彼女がエリージャン通りに住んでいたということだけでも、その通りは私にとって第二の故郷であり理想郷だった。
2009.08.25(火) 理想郷という名の裏通り Ⅰ
ニューオーリンズに、Elysian Avenue という名の裏通りがある。裕福な白人層の象徴のようなセント・チャールズ・アヴェニューとは違い、ストリートカーは通らないし、舗装されていないがたがたの砂利道には、ドラッグで使った注射器が散乱している。白目が黄色く濁った中毒者たちがたむろし、数少ないドラッグストアーの扉は、がっちりと強盗防止の鉄格子で覆われている。初めてその通りにバスで降り立ったとき、パトロール・カーから警官に呼び止められ、危険だから大学の寮へ送るのですぐ乗るように、といわれたくらい治安の悪い通りである。だが、その犯罪と貧困の通りがまさに私にとっては、名の通りエリージャン(理想郷)となった。その地域で見つけた黒人料理と音楽の店で、ニューオーリンズを代表する歌手と出会った。彼は"ルイジアナ・パーチェス"というソウル・バンドのリード・ボーカルで、テンプテーションズとの共演もあり、TV出演多数、コンサートも毎回満員の実力派だ。彼自身はテンプテーションズのかつてのボーカリスト、アリオリにルックスも声質も似ていた。そんな彼はニューオーリンズのスターで女性ファンも多く、彼のコンサートでは興奮した女性客が舞台に上がったり、失神したり、いつかは私と彼が街を歩いているときに、女性ファンに私が殴りかかられたこともあるくらいだ。そんな人気者の彼は、決して浮ついたところのない真面目なクリスチャンの青年だった。私の黒人音楽と文化に対する熱意を聞いて、"Stick with me.(僕についていなよ。)"と、その言葉通り、私を自分の通う黒人教会に連れていってくれたのである。その黒人教会ももちろん、エリージャン通りにある
大学では白人ばかりの環境で、自分が南部に来たという実感がなかったので、その黒人教会に初めて足を踏み入れ、聖歌隊の歌声を聴いたときは魂がぶっ飛んだ。質素な木造の建物が大きく揺さぶられている感じだった。その教会は、初めての非黒人である訪問者の私を温かく迎えてくれた。牧師夫妻は5人もの養子を育てていて、慎ましやかな暮らしをしており、メンバーたちは、まさにビッグ・ママと呼ばれるようなたくましい黒人女性が7割を占め、あとはその彼女達の連れ合いやら子供達が参加していた。聖歌隊が歌い始めると、映画「ブルース・ブラザーズ」でジェイムズ・ブラウンが説教師の役で歌い踊り、バック転までしてしまうシーンがあったが、本当にその通りの光景が見られた。なんせ、聖歌隊のリード・シンガーはニューオーリンズきっての実力派歌手。メンバーはモアハウス大学(キング牧師の出身大学)のグリークラブ員やら、産声を上げたときから、ゴスペルを聴いて育った面々である。教会がゴスペルのコンサート会場になるのだ。そんな真の黒人教会に連れてきてくれたその歌手には本当に感謝していた。彼こそまさに、黒人としての誇りを持ったソウル・ブラザーだった。
その彼が、次の教会の集まりで、自分のGFを連れてきて紹介してくれるという。彼の選んだ恋人なら、とことんソウルフルなシスターだろう。私もそんな女性と友人になりたいと願っていたので、次回の教会のサービスの日が待ち遠しかった。その日、ワクワクして教会の扉を開けると、彼がGFと紹介してくれた彼女がいた。輝くような金髪、真っ白い肌、青い目の美しい女性が固い表情で私を見つめていた。 《続く》
2009.08.13(木) ニューオーリンズのB級グルメ
ニューオーリンズで有名なのは、フランスやアフリカの影響を受けた地元の味、ガンボやザリガニなどのケイジャン料理だろう。私もそれらは大好きだが、それ以外に日本へ帰国しても恋しかった料理はたくさんある。 例えば、POボーイ。フランスパンにシュリンプや、レタス、トマト、たまねぎをはさんだ普通のサンドイッチなのだが、ソースがピリリとしていて、後を引く。ランチ・ドレッシング(この場合の"ランチ"は牧場の意味)という野菜の刻んだものやアボガド、マヨネーズが主体のソースにチリが混ざっていて、ニューオーリンズの湿気を一気に取り払ってくれるような、引き締まった味。勉強の合間に、ドライブをしながら、とながら族にはもってこいの一品だと思う。私は二十歳すぎまで日本で暮らし、両親からは人並みのしつけを受けたと思うが、アメリカに来てとたんに、行儀が悪くなった。試験用の資料を読みながら、何かを食べるなんてもってのほかだったのだが、ニューオーリンズに来てからは、POボーイが勉強の友になっていた。
例えば、POボーイ。フランスパンにシュリンプや、レタス、トマト、たまねぎをはさんだ普通のサンドイッチなのだが、ソースがピリリとしていて、後を引く。ランチ・ドレッシング(この場合の"ランチ"は牧場の意味)という野菜の刻んだものやアボガド、マヨネーズが主体のソースにチリが混ざっていて、ニューオーリンズの湿気を一気に取り払ってくれるような、引き締まった味。勉強の合間に、ドライブをしながら、とながら族にはもってこいの一品だと思う。私は二十歳すぎまで日本で暮らし、両親からは人並みのしつけを受けたと思うが、アメリカに来てとたんに、行儀が悪くなった。試験用の資料を読みながら、何かを食べるなんてもってのほかだったのだが、ニューオーリンズに来てからは、POボーイが勉強の友になっていた。それに合うのが、チコリ・コーヒー。コーヒー豆をひいたものにチコリというハーブ野菜の刻んだものを混ぜて、独特の苦味を出した、ニューオーリンズっ子が愛してやまない一品。たっぷりのミルクを注いでカフェオレにするのが一番のお勧めだ。ディック・ロクティのミステリー小説にニューオーリンズを舞台にしたものがあって、登場人物のみんながみんな、チコリ・コーヒーを飲んでいる。その小説で主人公の私立探偵が、チコリ・コーヒーの淹れ方にとてもこだわっている描写がある。ペーパー・フィルターのコーヒー豆にお湯を注ぐとき、大さじ一杯ずつ、ゆっくりと淹れていく。マグナム銃をぶっ放したり、殺人犯をジリジリと追いつめるハード・ボイルドな男だって、チコリ・コーヒーを淹れるときは、チマチマと大さじのスプーンを用意するのだ。元々、チコリ・コーヒーは白人家庭に奴隷として使えていた黒人達が、白人の残り物を少しでも美味しくしようと捨てられた屑野菜を加えて飲んでいたものだ。差別される側の食卓には、差別する側が思いもよらぬような、工夫と知恵が潜んでいる。その奴隷食だったチコリ・コーヒーは、現代では人種を超えて親しまれている。
もう一つが"ポパイ"のフライド・チキン。ニューオーリンズ人(南部人)は、ケンタッキー・フライド・チキンなんて食べない。スタンダードで激辛のポパイ・チキンのさらに辛いものをわざわざオーダーする。そのオーダーをするとき、辛さの度合いとともに、「ホワイト・ミートか?ダーク・ミートか?」と店員に訊ねられる。もちろん、黒人はダーク・ミートを注文する。白いものが美味しいなんて、白人の作った自分達に都合のいい幻想だ、白砂糖より黒砂糖、白米より玄米、白い食パンより全粒子のパン・・・それらの方が栄養もあって、美味しい、というのが黒人達の意見だ。肌の色の人種問題になれていない日本人からすると、言いがかりのように聞こえるかもしれないが、南部アメリカという奴隷制度で栄えた州に暮らしていると、肌の色がどれだけ繊細な問題であるかを痛感する場面によく出くわしたものだった。
それと、食ではないがニューオーリンズ独特の音楽について、ニック・ロクティのミステリーのなかで、チンピラが、「俺はザイデゴを聴きたくなかったから、家を出たんだ。」という場面が有るが、私もそのチンピラに同感である。
2009.07.22(水) Scent of New Orleans
南部アメリカに位置するニューオーリンズは、通りごとに、様々な匂いが湿気の多い空気の中に溢れている。セント・チャールズ・ストリートカーを終点で降り、カナル・ストリートを歩いていると、どこからともなく高級なフランス製の香水の香りが漂ってくる。そこからバーボン・ストリートに入ると、開け放したバーの扉の中からは、ガヤガヤと演奏されている観光客向けのジャズに混じって、強烈なカクテル、"ハリケーン"のラム酒とフルーツ、ミントがミックスされた刺激的な匂い。一本裏のバーガンディ・ストリートには、ニューオーリンズの伝統的なスイーツ、キャラメルをナッツと絡めた、脳天を突き刺すような甘ったるい匂い。ミシシッピー河沿いのジャクソン・スクエアに向かい、ロイヤル・ストリートに入ると、河に浮かぶ藻や、レストランからの、チリで煮詰めたザリガニの匂いに混じって、昼間から男性客を誘うストリップ・バーのお香の香りが鼻腔に入り込んでくる。そのニューオーリンズの街の様々な匂いというのは、多民族の生命の匂いのように思う。スペインの植民地となり、その後フランスに買われ、またナポレオンが政策のためにアメリカに押し売りし、それからは大きな奴隷市場の港町として、アフリカから黒人を拉致し、そしてクレオール人、ケイジャン人などが生まれた。様々な先祖を持つ地元の女性はエキゾチックで、目を奪われそうな美人が多い。そんなニューオーリンズを舞台にした映画は数々ある。そのなかで私がニューオーリンズという街の魅力を一番感じて好きなのは、"ソニー"、今は名も知られてきた、ジェームス・フランコが男娼を演じる作品である。母親がニューオーリンズで娼館を営んでいたから、必然的に男娼になった青年。一度兵役に付き、男娼を辞めて本屋になろうとするがうまくいかず、また男娼に戻ってしまう。母の使っている新人の娼婦に愛されるが、お互い男娼・娼婦以外に生きる方法を知らない。ジェームス・フランコ演ずる男娼が客に会うとき、金で買われた偽りの愛人を演じる哀しげな顔が、ニューオーリンズという街の裏通りを表しているように思えた。表通りが裕福な白人層が通う、きらびやかな十字架を掲げたカソリック教会なら、裏通りは鶏の干からびた足をお守りにするヴードゥー。また、その裏通りが妖しいほど生き生きしているのがニューオーリンズの魅力だと思う。
そして、雨が体に叩きつけるように降り注ぐのがニューオーリンズである。その激しい雨は、芝生や木々のむせ返るような緑の生命の匂いも、すえた酒の匂いも、レストランで捨てられた魚のはらわたの匂いも、娼婦がつける淫靡な香水の匂いも、ザリガニ漁の男達の体臭も、全て混ぜ合わせニューオーリンズで生きる人々の匂いを作っていく。
今、日本で梅雨の季節、雨上がりの公園を歩いていると、たまにニューオーリンズの匂いがふっと鼻をかすめたように思うときがある。そういうときは、エリージャン・アベニューの黒人教会でよく歌っていた「I 'm going home」を思いながら帰路につき、ハリケーン・カクテルならぬミケロブ・ビールの栓を抜くことにしている。