僕儍僘偲儈僗僥儕乕偺擔乆丂丂2006擭9寧乣2023擭6寧
2023擭6寧朸擔 旛朰榐249丂峚岥寬擇偺塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺1丗僒僀儗儞僩塮夋
2023擭6寧朸擔 旛朰榐248丂偐偮偰尒偨夰偐偟偄尨愡巕弌墘塮夋
2023擭6寧朸擔 旛朰榐247丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘偺塮夋丂偦偺2
2023擭6寧朸擔 旛朰榐246丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘偺塮夋丂偦偺1
2023擭6寧朸擔 旛朰榐245丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺4
2023擭6寧朸擔 旛朰榐244丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺3
2023擭6寧朸擔 旛朰榐243丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺2
2023擭6寧朸擔 旛朰榐242丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺1
2023擭6寧朸擔 旛朰榐241丂僷僂僄儖仌僾儗僗僶乕僈乕偺寍弍塮夋
2023擭5寧朸擔 旛朰榐240丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺6
2023擭5寧朸擔 旛朰榐239丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺5
2023擭5寧朸擔 旛朰榐238丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺4
2023擭5寧朸擔 旛朰榐237丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺3
2023擭5寧朸擔 旛朰榐236丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺9丗懕乆儘僢僙儕乕僯
2023擭4寧朸擔 旛朰榐235丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺2
2023擭4寧朸擔 旛朰榐234丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺1
2023擭3寧朸擔 旛朰榐233丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺8丗懕乆儀儖僀儅儞
2023擭3寧朸擔 旛朰榐232丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺7丗懕儀儖僀儅儞
2023擭3寧朸擔 旛朰榐231丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺6丗儕僠儍乕僪僜儞
2023擭3寧朸擔 旛朰榐230丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺5丗暓仌攇
2023擭3寧朸擔 旛朰榐229丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺4丗儀儖僀儅儞
2023擭3寧朸擔 旛朰榐228丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺3丗懕儘僢僙儕乕僯
2023擭3寧朸擔 旛朰榐227丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺2丗儘僢僙儕乕僯
2023擭3寧朸擔 旛朰榐226丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺1丗僀僞儕傾塮夋
2023擭3寧朸擔 旛朰榐225丂彈偺惗偒偞傑傪昤偔媑懞岞嶰榊偺塮夋
2023擭3寧朸擔 旛朰榐224丂壀揷帪旻偑弌墘偡傞彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丂偦偺2
2023擭3寧朸擔 旛朰榐223丂壀揷帪旻偑弌墘偡傞彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丂偦偺1
2023擭3寧朸擔 旛朰榐222丂怱傪懪偮僜楢偺暥寍塮夋
2023擭2寧朸擔 旛朰榐221丂栰懞峗彨偺愴慜偺僐儊僨傿塮夋
2023擭2寧朸擔 旛朰榐220丂堫奯峗丒嶰慏晀榊僐儞價偺帪戙寑
2023擭2寧朸擔 旛朰榐219丂僎僥儌僲丒僇儖僩塮夋
2023擭2寧朸擔 旛朰榐218丂徏抾僰乕償僃儖償傽乕僌偺偦偺屻
2023擭2寧朸擔 旛朰榐217丂棝崄棖乗乗枮塮帪戙偺捒昳
2023擭2寧朸擔 旛朰榐216丂尨愡巕傪尒傞帄暉乗乗1940擭
2023擭2寧朸擔 旛朰榐215丂嶳岥廼巕傪尒傞桖墄乗乗1950擭戙
2023擭2寧朸擔 旛朰榐214丂1952擭偺搶曮塮夋
2023擭2寧朸擔 旛朰榐213丂愴憟捈屻偺栘壓宐夘塮夋
2023擭2寧朸擔 旛朰榐212丂尨愡巕傪尒傞帄暉乗乗1940擭戙拞婜
2023擭1寧朸擔 旛朰榐211丂巌梩巕偲曮揷柧嫟墘偺搒夛塮夋
2023擭1寧朸擔 旛朰榐210丂乬掅柪婜乭偺惉悾枻婌抝嶌昳丂偦偺2
2023擭1寧朸擔 旛朰榐209丂乬掅柪婜乭偺惉悾枻婌抝嶌昳丂偦偺1
2023擭1寧朸擔 旛朰榐208丂攕愴捈屻偺擔杮塮夋
2023擭1寧朸擔 旛朰榐207丂50擭戙屻敿偺暷傾僋僔儑儞塮夋
2023擭1寧朸擔 旛朰榐206丂60擭慜屻偺儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉庡墘塮夋
2022擭12寧朸擔 2022擭奀奜儈僗僥儕彫愢儀僗僩丒僥儞
2022擭10寧朸擔 旛朰榐205丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖棊偪曚廍偄丂偦偺3
2022擭10寧朸擔 旛朰榐204丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖棊偪曚廍偄丂偦偺2
2022擭10寧朸擔 旛朰榐203丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖棊偪曚廍偄丂偦偺1
2022擭9寧朸擔 旛朰榐202丂僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕庡墘偺愴憟僗僷僀塮夋
2022擭9寧朸擔 旛朰榐201丂暷崙30擭戙偺堎怓僊儍儞僌塮夋
2022擭9寧朸擔 旛朰榐200丂壛摗懽偺償傽僀僆儗儞僗塮夋
2022擭9寧朸擔 旛朰榐199丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺儅僀僫乕側塮夋丂偦偺3
2022擭9寧朸擔 旛朰榐198丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺儅僀僫乕側塮夋丂偦偺2
2022擭8寧朸擔 旛朰榐197丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺儅僀僫乕側塮夋丂偦偺1
2022擭8寧朸擔 旛朰榐196丂僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕庡墘偺暥寍塮夋丂偦偺2
2022擭8寧朸擔 旛朰榐195丂僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕庡墘偺暥寍塮夋丂偦偺1
2022擭8寧朸擔 旛朰榐194丂僇僂儕僗儅僉偺攕幰3晹嶌丂偦偺2
2022擭8寧朸擔 旛朰榐193丂僇僂儕僗儅僉偺攕幰3晹嶌丂偦偺1
2022擭8寧朸擔 旛朰榐192丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑庡墘偟偨愴屻偺惣晹寑丂偦偺3
2022擭8寧朸擔 旛朰榐191丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑庡墘偟偨愴屻偺惣晹寑丂偦偺2
2022擭8寧朸擔 旛朰榐190丂60擭慜屻偺傾儊儕僇壒妝塮夋
2022擭8寧朸擔 旛朰榐189丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑庡墘偟偨愴屻偺惣晹寑丂偦偺1
2022擭8寧朸擔 旛朰榐188丂30擭戙偺傾儊儕僇塮夋
2022擭7寧朸擔 旛朰榐187丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偺塮夋丂偦偺2
2022擭7寧朸擔 旛朰榐186丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偺塮夋丂偦偺1
2022擭7寧朸擔 旛朰榐185丂嵟嬤偺塮夋
2022擭7寧朸擔 旛朰榐184丂儀僥傿丒僨僀償傿僗偺弶婜庡墘塮夋
2022擭7寧朸擔 旛朰榐183丂儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偺庡墘塮夋
2022擭7寧朸擔 旛朰榐182丂2杮偺堎怓僼傿儖儉丒僲儚乕儖
2022擭6寧朸擔 旛朰榐181丂惉悾枻婌抝偑庤偑偗偨2杮偺僆儉僯僶僗塮夋
2022擭6寧朸擔 旛朰榐180丂尨愡巕偺庡墘塮夋丂偦偺2
2022擭6寧朸擔 旛朰榐179丂尨愡巕偺庡墘塮夋丂偦偺1
2022擭6寧25擔 梋択丗儈僗僥儕乕彫愢撉屻姶憐
丂丂丂丂丂丂丂丂怱偵怗傟傞傾僀儖儔儞僪偺晽宨丄弶榁偺抝偲巕嫙偺怱偺岎棳
2022擭6寧朸擔 旛朰榐178丂愳搰梇嶰偺塮夋丂偦偺2
2022擭6寧朸擔 旛朰榐177丂愳搰梇嶰偺塮夋丂偦偺1
2022擭5寧朸擔 旛朰榐176丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺塮夋丂偦偺3
2022擭5寧朸擔 旛朰榐175丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺塮夋丂偦偺2
2022擭5寧朸擔 旛朰榐174丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺塮夋丂偦偺1
2022擭5寧朸擔 旛朰榐173丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕偺塮夋丂偦偺3
2022擭5寧朸擔 旛朰榐172丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕偺塮夋丂偦偺2
2022擭5寧朸擔 旛朰榐171丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕偺塮夋丂偦偺1
2022擭5寧朸擔 旛朰榐170丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺4
2022擭5寧朸擔 旛朰榐169丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺3
2022擭5寧朸擔 旛朰榐168丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺2
2022擭5寧朸擔 旛朰榐167丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺1
2022擭5寧8擔 梋択丗亀彮擭墹幰戞10廤 夦廱夊屨曆亁傪撉傫偩
2022擭2寧朸擔 旛朰榐161丂夰偐偟偺擔杮塮夋丗戝妛偺嶳懐偨偪丄抧崠偺掙傑偱偮偒崌偆偤
2022擭2寧朸擔 旛朰榐160丂夰偐偟偺僀僞儕傾塮夋丗寖偟偄婫愡丄傢傜偺抝
2022擭1寧朸擔 旛朰榐159丂嶰慏晀榊偺庒偒擔偺抦傜傟偞傞塮夋
2022擭1寧朸擔 旛朰榐158丂僽儗僢僜儞偺揙掙偟偰棟夝傪嫅傓塮夋
2022擭1寧朸擔 旛朰榐157丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩偺塮夋丂偦偺2
2022擭1寧朸擔 旛朰榐156丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩偺塮夋丂偦偺1
2022擭1寧朸擔 旛朰榐155丂50擭戙偺惣晹寑丂偦偺2丗僴僒僂僃僀偲儅僥
2022擭1寧朸擔 旛朰榐154丂50擭戙偺惣晹寑丂偦偺1丗僽儖僢僋僗偲儘乕儔儞僪
2021擭12寧朸擔 2021擭奀奜儈僗僥儕乕彫愢儀僗僩丒僥儞
2021擭12寧朸擔 旛朰榐153丂榁彈桪偑嫟墘偟偨帬枴偵晉傓堩昳
2021擭12寧朸擔 旛朰榐152丂僫僠僗偲愴偆愴憟杁棯塮夋
2021擭12寧朸擔 旛朰榐151丂戝愳宐巕偑弌墘偟偨2杮偺塮夋
2021擭12寧朸擔 旛朰榐150丂僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖
2021擭11寧朸擔 旛朰榐149丂50擭戙慜婜偺堎怓擔杮塮夋
2021擭11寧朸擔 旛朰榐148丂僄儕傾丒僇僓儞偺拞屻婜嶌昳
2021擭11寧朸擔 旛朰榐147丂僄儕傾丒僇僓儞偺弶婜嶌昳
2021擭11寧朸擔 旛朰榐146丂戝塮偺屸妝帪戙寑
2021擭11寧朸擔 旛朰榐145丂嵟嬤偺塮夋偐傜
2021擭10寧朸擔 旛朰榐144丂愴慜愴屻偺壒妝塮夋
2021擭10寧朸擔 旛朰榐143丂巗愳棆憼偺戙昞嶌2杮
2021擭10寧朸擔 旛朰榐142丂擔暷偺廏堩側孯帠嵸敾塮夋
2021擭10寧朸擔 旛朰榐141丂僪儞丒僔乕僎儖偺弶婜塮夋丂偦偺2
2021擭10寧朸擔 旛朰榐140丂僪儞丒僔乕僎儖偺弶婜塮夋丂偦偺1
2021擭10寧朸擔 旛朰榐139丂徏杮惔挘尨嶌塮夋丂偦偺2
2021擭10寧朸擔 旛朰榐138丂徏杮惔挘尨嶌塮夋丂偦偺1
2021擭10寧朸擔 旛朰榐137丂嶳揷梞師偺2杮偺弶婜塮夋
2021擭9寧朸擔 旛朰榐136丂嵟嬤偺塮夋偐傜
2021擭9寧朸擔 旛朰榐135丂僴儕僂僢僪50擭戙弶婜偺柤嶌
2021擭9寧朸擔 旛朰榐134丂塸崙偺媨掛寑偲壠掚寑
2021擭9寧朸擔 旛朰榐133丂僴儕僂僢僪40擭戙屻婜偺柤嶌
2021擭8寧朸擔 旛朰榐132丂戝塮偺棆憼帪戙寑
2021擭7寧朸擔 旛朰榐131丂墿崹婜偺惣晹寑
2021擭7寧朸擔 旛朰榐130丂墿嬥帪戙偺惣晹寑
2021擭6寧朸擔 旛朰榐129丂愴慜丒愴屻偺捒昳擔杮塮夋
2021擭6寧朸擔 旛朰榐128丂儖儖乕僔儏偺償傽儞僠儏儔庡墘塮夋
2021擭6寧朸擔 旛朰榐127丂僩儕儏僼僅乕偺傾僀儕僢僔儏尨嶌塮夋
2021擭5寧朸擔 旛朰榐126丂嵟嬤偺塮夋偐傜
2021擭5寧朸擔 旛朰榐125丂嫄彔儉儖僫僂偺屆揟揑僒僀儗儞僩塮夋
2021擭5寧朸擔 旛朰榐124丂傾儊儕僇偺屆偄僗儕儔乕塮夋
2021擭5寧朸擔 旛朰榐123丂僠僃僐偺怱偵嬁偔壒妝塮夋
2021擭5寧朸擔 旛朰榐122丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺4
2021擭5寧朸擔 旛朰榐121丂儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偵枺偣傜傟偰丂偦偺2
2021擭5寧朸擔 旛朰榐120丂儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偵枺偣傜傟偰丂偦偺1
2021擭5寧朸擔 旛朰榐119丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪偝傜偵孈傝婲偙偡丂偦偺3
2021擭5寧朸擔 旛朰榐118丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪偝傜偵孈傝婲偙偡丂偦偺2
2021擭5寧朸擔 旛朰榐117丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪偝傜偵孈傝婲偙偡丂偦偺1
2021擭4寧朸擔 旛朰榐116丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺3
2021擭4寧朸擔 旛朰榐115丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺2
2021擭4寧朸擔 旛朰榐114丂僗僥傿乕償丒儕乕償僗庡墘僀僞儕傾惢乻寱偲杺朄乼塮夋
2021擭3寧朸擔 旛朰榐113丂僪僀僣愴慜攈偺嫄彔僷僽僗僩偺2嶌
2021擭3寧朸擔 旛朰榐112丂尨愡巕偑庡墘偟偨乽抭宐巕彺乿
2021擭2寧朸擔 旛朰榐111丂僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩偲僕儍僢僋丒儗儌儞
2021擭2寧朸擔 旛朰榐110丂僕儑儞丒僸儏乕僗僩儞偺2杮偺堎怓嶌
2021擭2寧朸擔 旛朰榐109丂拞尨傂偲傒偲傾儞僫丒僇儕乕僫
2021擭2寧朸擔 旛朰榐108丂僒僀儗儞僩帪戙偺僪僀僣偺嫄彔儉儖僫僂傪娤傞
2021擭2寧朸擔 旛朰榐107丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺1
2021擭2寧朸擔 旛朰榐106丂90擭戙偺怴姶妎僪僀僣塮夋
2021擭1寧朸擔 旛朰榐105丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺4
2021擭1寧朸擔 旛朰榐104丂嶰慏晀榊偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒價僨僆
2021擭1寧朸擔 旛朰榐103丂儗僗僞乕偲僷僂僄儖偺儗傾側僪僉儏儊儞僞儕乕塮憸
2020擭12寧朸擔 2020擭奀奜儈僗僥儕乕彫愢儀僗僩丒僥儞
2020擭12寧朸擔 旛朰榐102丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺3
2020擭12寧朸擔 旛朰榐102丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺2
2020擭12寧朸擔 旛朰榐101丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺1
2020擭12寧朸擔 旛朰榐100丂妋偐側榬偺怑恖娔撀愮梩懽庽偺塮夋3嶌
2020擭12寧朸擔 旛朰榐99丂朙揷巐榊娔撀偺暥寍塮夋2嶌
2020擭12寧朸擔 旛朰榐98丂惉悾枻婌抝偺屻婜偺巀斲傪屇傇壠懓塮夋2杮
2020擭12寧朸擔 旛朰榐97丂惉悾枻婌抝偺晇晈傕偺3晹嶌傪峔惉偡傞2杮
2020擭12寧朸擔 旛朰榐96丂僉儍僌僯乕偑恀壙傪敪婗偟偨傾僋僔儑儞塮夋
2020擭12寧朸擔 旛朰榐95丂岲娍僕僃乕儉僘丒僉儍僌僯乕偺僊儍儞僌塮夋戙昞嶌
2020擭11寧朸擔 旛朰榐94丂偝偭傁傝椙偝偑暘偐傜側偄僑僟乕儖塮夋
2020擭11寧朸擔 旛朰榐93丂婏柇偩偑峈偟偑偨偄枺椡傪曻偮僇僂儕僗儅僉偺塮夋
2020擭11寧朸擔 旛朰榐92丂榁偄偰側偍晽奿傪昚傢偣傞僕儍儞丒僊儍僶儞偺2嶌
2020擭11寧朸擔 旛朰榐91丂50擭戙屻婜丄惉悾枻婌抝偲尨愡巕偺堎怓嶌
2020擭11寧朸擔 旛朰榐90丂50擭戙敿偽丄崟郪柧媟杮偺堩昳2嶌
2020擭11寧朸擔 旛朰榐89丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺柤昳2嶌
2020擭10寧朸擔 旛朰榐88丂僼僃僨乕偲僇儖僱偺屆揟揑柤嶌
2020擭10寧朸擔 旛朰榐87丂僨儏償傿償傿僄偺愴慜偺戙昞嶌2杮
2020擭9寧朸擔 旛朰榐86丂僋儖乕僝乕偺弶婜偲屻婜偺2杮偺塮夋
2020擭9寧朸擔 旛朰榐85丂僕儍儞丒僊儍僶儞偺儊僌儗寈帇傕偺2杮
2020擭9寧朸擔 旛朰榐84丂僕儍儞丒僊儍僶儞50擭戙偺斊嵾塮夋2杮
2020擭9寧朸擔 旛朰榐83丂僽儗僢僜儞偺敆恀揑側扙崠塮夋
2020擭9寧朸擔 旛朰榐82丂僼儔儞僕儏偺峳搨柍宮側妶寑塮夋乽僕儏僨僢僋僗乿
2020擭9寧朸擔 旛朰榐81丂僕儑儖僕儏丒僼儔儞僕儏偺徴寕嶌乽婄偺側偄娽乿
2020擭9寧朸擔 旛朰榐80丂僩儕儏僼僅乕偵傛傞2杮偺塮夋
2020擭9寧朸擔 旛朰榐79丂僕儍僢僋丒僼僃僨乕偺屆揟揑柤嶌
2020擭9寧朸擔 旛朰榐78丂僔儍僽儘儖偺弶婜偺塮夋3杮
2020擭9寧朸擔 旛朰榐77丂僽儗僢僜儞偺撈帺惈偑敪婗偝傟偨拞婜偺塮夋
2020擭9寧朸擔 旛朰榐76丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偺弶婜塮夋2杮
2020擭9寧朸擔 旛朰榐75丂儕僲丒償傽儞僠儏儔偺傾僋僔儑儞塮夋乣偦偺2
2020擭9寧朸擔 旛朰榐74丂儕僲丒償傽儞僠儏儔偺傾僋僔儑儞塮夋乣偦偺1
2020擭9寧朸擔 旛朰榐73丂儌僟儞丒僕儍僘傪巊偭偨僼儔儞僗墲擭偺斊嵾塮夋
2020擭8寧朸擔 旛朰榐72丂儘儀乕儖丒傾儞儕僐斢擭偺2嶌昳
2020擭8寧朸擔 旛朰榐71丂40擭戙屻婜偺僊儍僶儞偺庡墘嶌2杮
2020擭8寧朸擔 旛朰榐70丂僕僃儔乕儖丒僼傿儕僢僾庡墘偺2嶌昳
2020擭8寧朸擔 旛朰榐69丂僇儖僱仌僊儍僶儞丒僐儞價偺戙昞嶌乽柖偺攇巭応乿
2020擭8寧朸擔 旛朰榐68丂償傿僗僐儞僥傿偺乽堎朚恖乿
2020擭7寧朸擔 旛朰榐67丂僕儍僢僋丒儀僢働儖屻婜偺柤昳2嶌
2020擭7寧朸擔 旛朰榐66丂僕儍僢僋丒儀僢働儖弶婜偺杴嶌2杮
2020擭7寧朸擔 旛朰榐65丂儖僱丒僋儗儅儞偲傾儔儞丒僪儘儞偺僐儞價偵傛傞2嶌
2020擭7寧朸擔 旛朰榐64丂儖僀僗丒僽僯儏僄儖偺捒嶌偲柤嶌
2020擭7寧朸擔 旛朰榐63丂僔儌乕僰丒僔僯儑儗偲僔儍儖儖丒傾僘僫僽乕儖
2020擭7寧朸擔 旛朰榐62丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺4
2020擭7寧朸擔 旛朰榐61丂僺傾丒傾儞僕僃儕偺弶庡墘嶌
2020擭7寧朸擔 旛朰榐60丂乬搟傟傞庒幰偨偪乭偺塮夋
2020擭7寧朸擔 旛朰榐59丂40擭戙偺2杮偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖
2020擭7寧朸擔 旛朰榐58丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺3
2020擭7寧朸擔 旛朰榐57丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺2
2020擭7寧朸擔 旛朰榐56丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺1
2020擭6寧朸擔 旛朰榐55丂愴屻偺僨儏償傿償傿僄偺斊嵾僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺2
2020擭6寧朸擔 旛朰榐54丂愴屻偺僨儏償傿償傿僄偺斊嵾僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺1
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂摼傞傕偺偑傎偲傫偳側偐偭偨2嶜偺塮夋杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂僼儕僢僣丒儔儞僌偺弶婜偺捒嶌偲斢擭偺夦嶌
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂50擭戙弶婜僼儕僢僣丒儔儞僌偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂乽僨僨偲偄偆彥晈乿僔儌乕僰丒僔僯儑儗偺埫偄忣擮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐52丂儊儖償傿儖偺擔杮枹岞奐嶌昳2嶌
2020擭6寧朸擔 旛朰榐51丂40擭戙屻敿偺懳徠揑側僼儔儞僗塮夋2杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐50丂擔暓偺嫽枴怺偄塮夋僪僉儏儊儞僞儕乕2杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐49丂50擭戙偺抧枴側僼儔儞僗塮夋
2020擭6寧朸擔 旛朰榐48丂儖僱丒僋儗儅儞偺弶婜嶌昳2杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐47丂愴屻柉庡庡媊偺嫵忦塮夋
2020擭6寧朸擔 旛朰榐46丂埳扥枩嶌偺僐儊僨傿2杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐45丂僌儗傾儉丒僌儕乕儞尨嶌偺2杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐44丂儘僶乕僩丒傾儖僪儕僢僠偺塀傟偨堩昳2杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐43丂僲儚乕儖晽枴偺嶌昳2杮
2020擭6寧朸擔 旛朰榐42丂巗愳浝偺50擭戙晽巋塮夋
2020擭6寧朸擔 旛朰榐41丂愴慜偺帪戙寑2嶌
2020擭5寧朸擔 旛朰榐40丂尒摝偟偰偄偨儖僲儚乕儖偲僨儏償傿償傿僄
2020擭5寧朸擔 旛朰榐39丂尨愡巕偺愴慜嶌偲埌愳偄偯傒偺弶婜嶌
2020擭5寧朸擔 旛朰榐38丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺6
2020擭5寧朸擔 旛朰榐37丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺5
2020擭5寧朸擔 旛朰榐36丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺4
2020擭5寧朸擔 旛朰榐35丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺3
2020擭5寧朸擔 旛朰榐34丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺2
2020擭5寧朸擔 旛朰榐33丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺1
2020擭5寧朸擔 旛朰榐32丂惉悾枻婌抝偺愴慜枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺3
2020擭5寧朸擔 旛朰榐32丂惉悾枻婌抝偺愴慜枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺2
2020擭5寧朸擔 旛朰榐31丂惉悾枻婌抝偺愴慜枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺1
2020擭5寧朸擔 旛朰榐30丂僩儕儏僼僅乕偵傛傞屻婜偺2嶌
2020擭5寧朸擔 旛朰榐29丂怱偵巆偭偨嵟嬤偺2杮偺塮夋
2020擭5寧朸擔 旛朰榐28丂僌乕儖僨傿儞僌偺庤榬偑岝傞40擭戙偺2嶌
2020擭5寧朸擔 旛朰榐27丂僪僀僣帪戙偺僼儕僢僣丒儔儞僌偺2嶌
2020擭5寧朸擔 旛朰榐26丂僪僀僣偺昞尰庡媊偲塮夋恖偺朣柦傪捛偆2杮偺僪僉儏儊儞僞儕乕
2020擭5寧朸擔 旛朰榐25丂媣徏惷帣偺戙昞嶌2杮
2020擭5寧朸擔 旛朰榐24丂儀僥傿僇乕偺乽幍恖偺柍棅娍乿傪傛偆傗偔娪徿
2020擭5寧朸擔 旛朰榐23丂僕僃乕儞丒僼僅儞僟偲僼僃僀丒僟僫僂僃僀
2020擭5寧朸擔 旛朰榐22丂70擭戙暷崙偺榖戣嶌2杮傪嵞尒
2020擭5寧朸擔 旛朰榐21丂峚岥偺僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋偲僪僀僣偺楌巎揑塮夋
2020擭5寧朸擔 旛朰榐20丂惉悾枻婌抝偺柍柤偺嶌昳3杮
2020擭5寧朸擔 旛朰榐19丂乽僇僢僐乕偺憙偺忋偱乿
2020擭5寧朸擔 旛朰榐18丂栘壓宐夘偺2嶌丄乽梉傗偗塤乿偲乽徰憸乿
2020擭5寧朸擔 旛朰榐17丂庒偒僺傾丒傾儞僕僃儕偑旤偟偄乽The Light Touch乿
2020擭5寧朸擔 旛朰榐16丂僆僼儏儖僗偺棳楉側僇儊儔乽偨偦偑傟偺彈怱乿
2020擭5寧朸擔 旛朰榐15丂50擭戙偺抦傜傟偞傞擔杮塮夋
2020擭5寧朸擔 旛朰榐14丂60擭戙偲70擭戙偺堩昳暷塮夋
2020擭5寧朸擔 旛朰榐13丂惉悾枻婌抝偺2嶌丄柤昳乽廐棫偪偸乿偵椳偡傞
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 12丂僔僆僪儅僋偲儀僥傿僇乕偺弶婜嶌昳
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 11丂弶婜偺儅儞僉僂傿僢僣嶌昳2杮
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 10丂塀傟偨柤嶌丄嶳揷偲嶰慏偺乽壓挰乿
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 9丂僕儑僙僼丒儘乕僕乕70擭戙
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 8丂僕儑僙僼丒儘乕僕乕60擭戙
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 7丂3杮偺堎怓擔杮塮夋
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 6丂廰偄僼傿儖儉丒僲儚乕儖3杮
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 5丂乽梸朷偺嵒敊乿偲乽戝偄側傞栭乿
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 4丂峚岥寬擇偺2嶌
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 3丂償傿僗僐儞僥傿偺2嶌
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 2丂埌愳偄偯傒偺2嶌偲傕偆1杮
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐 1丂尨愡巕偺2嶌
2019/12/26 (栘) 2019擭儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
2019/04/03 (悈) 怴尦崋偵偮偄偰巚偆
2019/01/11 (嬥) 2018擭儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
2018/06/16 (搚) 億乕儔儞僪偲偄偆崙
2017/12/30 (搚) 2017擭儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
2017/10/24 (壩) 廜堾慖嫇嶨姶
2017/01/10 (壩) 擭巒嶨姶
2016/12/26 (寧) 2016擭奀奜塮夋儀僗僩10
2016/12/22 (栘) 2016擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
2016/10/10 (寧) 5寧偺僶儖僩3崙偱偼僶乕僪丒僠僃儕乕偑壴奐偄偰偄偨
2016/09/03 (搚) 庒偒僒僢僠儌偑妶桇偡傞堎怓僕儍僘丒儈僗僥儕乕
2016/08/20 (搚) 儕僆屲椫偱媑揷嵐曐棦慖庤偑棳偟偨椳
2016/08/09 (壩) 揤峜偺乽偍婥帩偪昞柧乿傪暦偄偰姶偠偨偙偲
2016/08/06 (搚) 杒挬慛偺儈僒僀儖峌寕
2016/08/03 (悈) 揤峜偺惗慜戅埵昞柧
2016/07/28 (栘) 僋乕僨僞乕枹悑帠審屻偺僩儖僐偺峴偔枛
2016/06/25 (搚) 塸崙偺EU棧扙偲僫僔儑僫儕僘儉偺戜摢
2016/05/29 (搚) 僆僶儅戝摑椞偺峀搰偱偺墘愢偵巚偆
2016/04/16 (搚) 偁偺儕僗儀僢僩偑婣偭偰偒偨丄亀儈儗僯傾儉4亁偲偲傕偵
2016/04/02 (搚) 旈榖偑柧偐偝傟傞僽儔僂僯乕偺僪僉儏儊儞僞儕乕DVD
2016/02/28 (擔) 嶐擭岞奐偺奜崙塮夋儀僗僩僥儞
2016/02/14 (擔) 乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿傪傔偖偭偰
2016/01/30 (搚) 儀儖儕儞偺暻偲椻愴
2016/01/16 (搚) 擭巒嶨姶
2015/12/28 (寧) 2015擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
2015/12/16 (悈) 嵟戝偺晄惓偲媆嵩傪惗傒弌偟偰偄傞偺偼埨攞惌尃偩
2015/11/29 (擔) 捛憐偺尨愡巕
2015/02/15 (擔) 2014擭奀奜儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
2014/11/20 (栘) 寬偝傫偑巰傫偱偟傑偭偨
2014/06/22 (擔) 6寧偺儕僗儃儞偱偼僕儍僇儔儞僟偺壴偑嶇偔
2014/05/26 (寧) 擔杮偑婋側偄
2014/05/18 (擔) 2013擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
2014/05/10 (搚) 弔傪庻偖僕儍僘
2013/09/12 (栘) 摗孿巕偑惱偭偰偟傑偭偨
2013/07/26 (嬥) 僕儍僘丒償僅乕僇儖丒儀僗僩3
2013/07/14 (擔) 僯僐儔僗丒W丒儗僼儞偺乽僪儔僀償乿偼惁偄塮夋偩
2013/07/07 (擔) 埫嶦幰偺惓媊
2013/06/28 (嬥) 嶗堜儐僞僇偝傫偺巚偄弌
2013/01/18 (嬥) 2012擭奀奜塮夋儀僗僩10
2012/12/16 (擔) 2012擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
2012/12/08 (搚) 塮夋乽傾儖僑乿偲僀儔儞暷戝巊娰堳恖幙帠審偺恀幚
2012/11/29 (栘) 傾儊儕僇偺棤偺悽奅傪僥乕儅偵偟偨2嶜偺儈僗僥儕彫愢
2012/11/15 (栘) 堐怴偺夛偺偍慹枛偝偲堐怴敧嶔偺嬻嫊側拞恎
2012/11/01 (栘) 搒抦帠傪帿怑偟偰変幏偲榁廥傪偝傜偡愇尨怲懢榊
2012/10/24 (悈) 廡姧挬擔偺乽僴僔僔僞乿曬摴傪傔偖偭偰
2012/10/22 (寧) 栰揷惌尃偺枛婜揑徢忬
2012/09/22 (搚) 婋婡揑側擔拞娭學偵庤傪偙傑偹偔偩偗偺柍擻側栰揷惌尃
2012/09/10 (寧) 亀壴偐偘亁 偦偺2
2012/09/09 (擔) 亀壴偐偘亁 偦偺1
2012/08/31 (嬥) 僆僗僾儗僀攝旛斀懳塣摦偼側偤惙傝忋偑傜側偄偺偐
2012/08/22 (壩) 椞搚栤戣偲擔杮偺偲傞傋偒摴
2012/07/31 (壩) 媣偟傇傝偵偡偖傟偨朻尟彫愢偺彂偒庤偑搊応偟偨
2012/07/14 (搚) 嵅乆晹惔娔撀偲摨惾偟偨帄暉偺5帪娫
2012/06/28 (栘) 彫戲堦榊傛暠婲偺帪偩丄柉庡搣偼帺柵偣傛
2012/02/17 (嬥) 儂僀僢僩僯乕丒僸儏乕僗僩儞偑巰傫偩
2012/02/08 (悈) 嫶壓揙怣幰偨偪偺堎忢側峴摦
2012/01/31 (壩) 嫶壓揙戝嶃巗挿偺尵摦傊偺堘榓姶
2012/01/11 (悈) 婣偭偰棃偨僫僠僗丒僪僀僣偺扵掋儀儖儞僴儖僩丒僌儞僞乕
2011/12/27 (壩) 擭枛嶨姶乣偝傜偽柉庡搣
2011/12/17 (搚) 2011擭奀奜塮夋儀僗僩10
2011/12/10 (搚) 2011擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
2011/11/19 (搚) 僩儖僐偲偄偆崙
2011/10/29 (搚) 偩偗偳丒丒丒旤偟偄
2011/06/14 (壩) 塱尒旉懢榊偺帠審曤
2011/06/02 (栘) 亀恖惗晥亁
2011/05/16 (寧) 斵傜偼偨偩嫀偭偰偄偔丄儉乕儞儔僀僩丒儅僀儖偺斵曽偵
2011/05/01 (擔) 扙尨敪偺婥塣偑惙傝忋偑傜側偄偺偼側偤偐
2011/04/23 (搚) 亀壗恖偵懳偟偰傕埆堄傪書偐偢亁
2011/04/16 (搚) 愇尨搒抦帠4慖偵巚偆
2011/04/14 (栘) 尨敪帠屘偵娭偡傞奀奜偱偺晽昡偲傾儊儕僇棅傒偺暅媽懳嶔
2011/04/02 (搚) 搶揹偲桙拝偟偨尨巕椡埨慡埾堳夛偺庤敳偒娗棟偑尨敪帠屘傪惗傫偩
2011/03/29 (壩) 恔嵭偵傑偮傢傞尵摦偱廥埆偝傪業掓偟偨3恖
2011/03/21 (寧) 尨敪帠屘偺恀偺尨場偼丄偢偝傫側尨敪惌嶔偵偁傞
2011/03/19 (搚) 戝抧恔旐嵭抧媬墖偺抶傟偼嫋偟偑偨偄
2010/12/29 (悈) 2010擭奀奜塮夋儀僗僩10
2010/12/26 (擔) 2010擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
2010/12/22 (悈) 僕儍僐偺嵃偵怗傟傞
2010/12/19 (擔) 僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偵弔偼棃傞偺偐
2010/11/07 (擔) 姫偒崬傑傟宆僒僗儁儞僗丒儈僗僥儕乕偺柺敀偝
2010/10/31 (擔) 儕僗儀僢僩偺埑搢揑側懚嵼姶偺慜偱偼偡傋偰偑夃傫偱偟傑偆
2010/10/24 (擔) 姶椳傪桿偆僽儔僂僯乕庒偒擔偺攋揤峳側墘憈
2010/10/17 (擔) 嵞朘丄墿崹偺戝塸掗崙
2010/10/10 (擔) 嫢埆側彮彈攧攦慻怐傪焤柵偟丄傾僥傿僇僗偼嫀偭偰峴偭偨
2010/10/03 (擔) 晲壠幮夛偵惗偒傞抝偨偪偺愴偄偑嫻傪擬偔偡傞
2010/09/26 (擔) 儅乕僇僗丒儈儔乕偲岎嬁妝抍偺嫟墘傪姮擻偟偨堦擔
2010/09/19 (擔) 彮擭偲孻帠偺曵夡偟偨壠掚偵媬偄偼朘傟傞偺偐
2010/09/12 (擔) 挿嶈偺巐奀極偱懢査嶮偆偳傫傪怘傋偨
2010/07/25 (擔) 憡杘奅墭愼曬摴偺塭偱偺偝偽傞嫄埆
2010/07/19 (寧) 崿柪偡傞惌帯偵懪奐偺庤棫偰偼偁傞偺偐
2010/06/29 (壩) 揤栘捈恖挊亀偝傜偽擔暷摨柨亁偑巜偟帵偡擔杮偺偲傞傋偒摴
2010/06/21 (寧) 崙柉傪棤愗傞悰怴庱憡偺業崪側尰幚楬慄
2010/06/12 (搚) 儐僟儎偲僀僗儔儉偺懳棫偵傎偺尒偊傞丄偐偡偐側婓朷
2010/06/02 (悈) 儅僗僐儈偑栙嶦偡傞2偮偺媈榝乗乗偦偺2乽姱朳婡枾旓偺巊搑乿
2010/06/01 (壩) 儅僗僐儈偑栙嶦偡傞2偮偺媈榝乗乗偦偺1乽憂壙妛夛偲屻摗慻乿
2010/05/25 (壩) 壂撽婎抧栤戣偱曻抲偝傟傞擔暷摨柨偵娭偡傞榑媍
2010/05/24 (寧) 暷孯僋儔僗僞乕抏搳壓孭楙偲娯崙娡捑杤帠審
2010/05/17 (寧) 僄僐乕丒僷乕僋偵桯偐偵嬁偔儌儞僋偲僐儖僩儗乕儞
2010/03/22 (寧) 傂偨偡傜摝偘傞乬慶崙側偒抝乭偺偨偳傞摴偼
2010/03/11 (栘) 梞妝嬋柤偁傟偙傟乗乗偦偺3乽僕儍僘丒僗僞儞僟乕僪乿
2010/03/04 (栘) 2偮偺椳
2010/03/01 (寧) 梞妝嬋柤偁傟偙傟乗乗偦偺2
2010/02/22 (寧) 梞妝嬋柤偁傟偙傟
2010/02/16 (壩) 懴偊傞抝偺旤偟偝傪昤偒懕偗偨僨傿僢僋丒僼儔儞僔僗
2009/12/26 (搚) 2009擭塮夋儀僗僩10
2009/12/20 (擔) 2009擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
2009/12/11 (嬥) 乽彮擭墹幰乿乗乗尪偺乽夦廱夊屨曆乿
2009/11/29 (擔) 塱墦偺僗僞乕丄拞懞嬔擵彆
2009/11/15 (擔) 嶳愳憏帯偺乽彮擭墹幰乿偑垽偲桬婥傪嫵偊偰偔傟偨
2009/10/19 (寧) 旤嬻傂偽傝峫
2009/10/08 (栘) 乬將偺椡乭偵撍偒摦偐偝傟偨恖乆偑偨偳傞塣柦偼
2009/09/18 (嬥) 墿崹偺戝塸掗崙
2009/08/31 (寧) 憤慖嫇偱埑彑偟偨柉庡搣偵婜懸偡傞
2009/08/28 (嬥) 僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺2枃偺儗傾CD
2009/08/07 (嬥) 僕儍儞僑偺煭扙偲僼儗僨傿偺擬婥
2009/07/30 (栘) 乽栰朷乿偲乽暅廞乿傪僥乕儅偵偟偨2嶜偺杮
2009/07/24 (嬥) 怉憪堦廏巵偺抯娍檒嵾帠審偲嵟崅嵸偺晄摉敾寛
2009/07/16 (栘) 廥偝傪偝傜偗弌偡枛楬偺帺柉搣
2009/07/09 (栘) 僕僃僼傽乕僜儞丒儃僩儖傪傔偖傞撲偲憶摦
2009/07/02 (栘) 懞忋弔庽偵偮偄偰巚偆偙偲
2009/02/18 (悈) 屲椫彽抳丄抸抧堏揮偲偄偆愇尨偺嬸嫇偵搟儕偺惡傪
2009/02/16 (寧) 彫愹敪尵傪夁戝曬摴偡傞儅僗僐儈偺峳攑偲懧棊
2009/01/31 (搚) 僼儗僨傿丒僴僶乕僪偺巚偄弌乗乗偦偺俀
2009/01/29 (栘) 僼儗僨傿丒僴僶乕僪偺巚偄弌乗乗偦偺侾
2009/01/25 (擔) 僀僗儔僄儖偺僈僓峌寕偲僆僶儅怴惌尃
2009/01/23 (嬥) 僆僶儅偺戝摑椞廇擟偵巚偆
2009/01/21 (悈) 姱椈傕惌帯傕儊僨傿傾傕傒傫側楎壔偟偰偄傞乗乗偦偺俀
2009/01/20 (壩) 姱椈傕惌帯傕儊僨傿傾傕傒傫側楎壔偟偰偄傞乗乗偦偺侾
2008/12/30 (壩) 撉傒摝偟偰偄偨媣乆偺寙嶌朻尟彫愢
2008/12/26 (嬥) 塮夋儀僗僩丒僥儞2008
2008/12/22 (寧) 僕儍僘丒儀僗僩丒僥儞2008
2008/12/20 (搚) 崱擭丄怱傪摦偐偝傟偨2嶜偺僲儞僼傿僋僔儑儞
2008/12/18 (栘) 儈僗僥儕乕丒儀僗僩丒僥儞2008
2008/11/27 (栘) 儃僨僀僈乕僪偐傜堩扙偟偨傾僥傿僇僗偼偳偙偵峴偔偺偐
2008/11/18 (壩) 揷曣恄榑暥偐傜尒偊偰偔傞堎忢側晽宨
2008/11/15 (搚) 媼晅嬥栤戣偱杻惗庱憡偺尒幆偺側偝偑偝傜偗弌偝傟偨
2008/11/09 (擔) B媺傾僋僔儑儞偺柺敀偝傪枮媔偱偒傞2杮偺梞夋
2008/10/30 (栘) 嬧峴僊儍儞僌偲僇儞僒僗丒僔僥傿丒僕儍僘
2008/10/22 (寧) 攋柵偵岦偭偰撍偒恑傓孼掜乗乗儖儊僢僩偺埑搢揑側怴嶌塮夋
2008/10/06 (寧) 7擭傇傝偺僼儘僗僩寈晹僔儕乕僘偺怴嶌傪姮擻
2008/09/30 (壩) 億乕儖丒僯儏乕儅儞偺巚偄弌
2008/09/19 (嬥) 怱庝偐傟傞僋儔僂僗丒僆僈乕儅儞偺僯儏乕丒傾儖僶儉
2008/09/04 (栘) 擔杮傪晳戜偵偟偨僴儞僞乕偺怴嶌偵偑偭偔傝
2008/08/01 (嬥) 僿儗儞丒儈傾乕僘乽傾儊儕僇偺嬀丒擔杮乿偑夝偒柧偐偡恀幚
2008/07/23 (悈) 9.11僥儘偼傾儊儕僇偺堿杁偩偭偨偺偐
2008/07/16 (悈) 帒杮庡媊偺枛婜揑徢忬偑業掓偟偰偄傞
2008/07/10 (栘) 柉庡搣偺傾僉儗僗銯丄慜尨惤巌
2008/07/04 (嬥) 姱椈偲帺岞惌帯壠偺楎埆偝壛尭
2008/06/30 (寧) 捝晽敪徢揯枛婰
2008/05/19 (寧) 乽挿偄偍暿傟乿偲乽儘儞僌丒僌僢僪僶僀乿
2008/05/12 (寧) 償傽僱僢僒丒儗僢僪僌儗僀償偺2杮偺怴嶌塮夋
2008/05/05 (寧) 堘寷敾寛偼側偤壓偣側偄偺偐乗乗擔杮偺嵸敾惂搙乮偦偺3乯
2008/04/27 (擔) 嵸敾姱偺夁偪偼扤偑嵸偔偺偐乗乗擔杮偺嵸敾惂搙乮偦偺2乯
2008/04/25 (嬥) 偄傑偺擔杮偺嵸敾惂搙偼偙傟偱偄偄偺偐乮偦偺1乯
2008/03/29 (搚) 僕儍僘丒僐儞億乕僓乕丄僼傽儞僞僕乕彫愢丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖
2008/03/17 (寧) 怴嬧峴搶嫗丂愑擟摝傟偵廔巒偡傞愇尨搒抦帠偺廥偝
2008/03/14 (嬥) 屒撈偲栂幏偺嶌壠丄僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏
2008/01/24 (栘) 抍夠僆儎僕偺僸乕儘乕偼價乕僩儖僘側傫偐偠傖側偄
2008/01/19 (搚) 儁儕乕丒僐儌偺巚偄弌
2007/12/26 (悈) 崱擭偺儈僗僥儕乕偼乽僉儏乕僶丒僐僱僋僔儑儞乿偑1埵偩
2007/12/10 (寧) 懢査嶮偆偳傫偵偼傑傞
2007/12/06 (栘) W.C.僼傿乕儖僘岅榐
2007/11/25 (擔) 怴偨偵敪孈偝傟偨僕儍僐偺嬃偔傋偒墘憈
2007/11/05 (寧) 僊儕僔儍偱尒偨擑偼戝偒偐偭偨
2007/11/03 (搚) 彈埫嶦幰僞儔丒僠僃僀僗偼傾儔僽偵岦偐偆
2007/11/01 (栘) 栚傪偔偓晅偗偵偡傞敆椡枮揰偺僐儖僩儗乕儞偺DVD
2007/10/06 (搚) 孻帠偵暅怑偟偨僴儕乕丒儃僢僔儏傪懸偭偰偄偨帠審偼
2007/10/04 (栘) 儀儔乗乗擔杮偵傕杮暔偺儗僨傿丒僜僂儖偑偄偨
2007/09/29 (搚) 埫偄儀儖儕儞偲柧傞偄僾儘償傽儞僗
2007/09/17 (寧) 朰傟傜傟偨嶌壠 W.P.儅僢僊償傽乕儞
2007/09/14 (嬥) 僴乕僪儃僀儖僪偺愴屻巎
2007/09/11 (壩) 傕偆傂偲偮偺乽僇僒僽儔儞僇乿
2007/07/31 (壩) 暷崙僱僆僐儞偺堿杁傪恾彂娰堳偼慾巭偱偒傞偐
2007/07/18 (悈) 悓梋偺壥偰偺僕儍僘丒僩乕僋
2007/07/16 (寧) 傓偐偟僶僯乕丒儀儕僈儞偲偄偆僩儔儞儁僢僞乕偑偄偨乗乗偦偺2
2007/07/15 (擔) 傓偐偟僶僯乕丒儀儕僈儞偲偄偆僩儔儞儁僢僞乕偑偄偨乗乗偦偺1
2007/07/12 (栘) 僕儍僘偲僄儘僥傿僔僘儉
2007/07/08 (擔) 崱擭偺東栿儈僗僥儕乕偼晄嶌丄偱傕孈傝弌偟暔傕偁傞偧
2007/07/07 (搚) 僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺僾儔僀償僃乕僩斦
2007/07/06 (嬥) 嵟嬤偺傾僋僔儑儞塮夋偼偗偭偙偆偍傕偟傠偄
2007/06/07 (栘) 儘僀丒僿僀儞僘偺僪儔儈儞僌偵悓偭偨堦栭
2007/05/20 (擔) 偙偺崙偺備偔偊
2007/05/15 (壩) 崟郪柧偺嬻敀偺5擭娫
2007/01/08 (寧) 僨傿僢僋丒僼儔儞僔僗6擭傇傝偺怴嶌偵攺庤
2006/12/17 (擔) 儈僗僥儕乕丒儔儞僉儞僌偺岲傑偟偐傜偸晽挭偵妳両
2006/12/03 (擔) 嵟嬤偺償僅乕僇儖丒傾儖僶儉乗乗僌儔僨傿僗丒僫僀僩偲悈椦巎
2006/11/12 (擔) 摗戲廃暯偺塮夋壔嶌昳傪傔偖偭偰
2006/11/11 (搚) 僶儖僙儘僫傪悂偔晽偵偼塭偑偁偭偨偐
2006/11/10 (嬥) 僒儞僙僢僩77偺儘僕儍乕丒僗儈僗偼镈憉偲偟偰偄偨
2006/11/05 (擔) 儔僢僔儏丒儔僀僼偵崬傔傜傟偨僗僩儗僀儂乕儞偺斶捝側巚偄
2006/10/15 (擔) 僠儞僪儞偲僶儖僇儞偑梈偗崌偆偲偒
2006/10/14 (搚) TWA800曋捘棊偺恀憡偼媶柧偝傟偨偐
2006/10/10 (壩) 僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞抐復
2006/10/09 (寧) 僇儕僼僅儖僯傾丒儚僀儞偲償傽乕僕僯傾丒儅僪僙儞
2006/09/22 (嬥) 僈儖償僃僗僩儞偺嶦偟壆偺寣偼偄偮捔傑傞偺偐
2006/09/21 (栘) 恀偺僐僗儌億儕僞儞丄僓償傿僰儖
2006/09/09 (搚) 儈儏儞僿儞峴偒栭峴楍幵偺忔傝怱抧偼
2006/09/03 (擔) 僽僈僢僥傿偼愯椞壓偺僷儕傪幘憱偟偨偐
2006/09/02 (搚) 僐儖僩儗乕儞堎榑
2006/09/01 (嬥) 僴儕乕丒儃僢僔儏偼偳偙偵峴偔偺偐
2023擭6寧
2023擭6寧朸擔 旛朰榐250丂峚岥寬擇偺塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺2丗愴慜偺僩乕僉乕塮夋
1935戞堦塮夋丂峚岥寬擇丂昡揰亂D亃
壞栚燍愇偺彫愢偺塮夋壔丅儔僗僩丒僔乕儞偑寚棊偟偰偄傞丅夋幙偼偲傕偐偔丄壒偑楎埆偱丄傛偔挳偒庢傟側偄丅塸岅帤枊偱傛偆傗偔嬝傪捛偄偐偗傞偙偲偑偱偒偨丅堦庬偺孮憸寑偱丄庡墘偑扤側偺偐偑偼偭偒傝偟側偄偑丄榖偼抝傪庤嬍偵庢傞嫊塰怱偺嫮偄彈丄摗旜亖嶰戭朚巕偲丄斵彈傪垽偡傞擇恖偺惵擭丄壞愳戝擇榊偲寧揷堦榊偺嶰妏娭學傪幉偵揥奐偡傞丅慡懱偵昤偒曽偑愺偄偟丄惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅寧揷堦榊偼嶳揷屲廫楅偲寢崶偟偨攐桪偱丄弶傔偰尒傞偑丄墴偟弌偟偼傗傗抧枴側偑傜丄側偐側偐偺僴儞僒儉偩丅
柤搧旤彈娵
1945徏抾丂峚岥寬擇丂昡揰亂B亃
搧抌栬傪庡恖岞偲偡傞堦庬偺寍摴傕偺丅峚岥偺娔撀嶌昳偵偟偰偼捒偟偔丄壗儠強偐寱寔偺応柺偑怐傝崬傑傟偰偄傞丅壴桍復懢榊偲嶳揷屲廫楅偺庡墘丄傎偐偵壴桍堦栧偺怴攈偺栶幰偑弌墘偡傞丅偦偺婄傇傟偼偙傟傛傝2擭慜偺惉悾枻婌抝偺塮夋乽壧峴摃乿偲傎傏摨偠偩丅塮夋偲偟偰偼乽壧峴摃乿偺傎偆偑偼傞偐偵桪傟偰偄傞偗傟偳丄偙偺乽柤搧旤彈娵乿傕悽昡偼掅偄偑偦傟傎偳埆偄弌棃偱偼側偄丅側傑偔傜搧傪專擺偟偨偣偄偱壎恖傪巰側偣偰偟傑偭偰嬯擸偡傞庒偄搧抌栬偑壎恖偺柡偺媤摙偪偺偨傔偵惛嵃崬傔偰柤搧傪嶌傞偲偄偆榖丅嶳揷屲廫楅偺彈寱巑偼巔惃偑椙偔樔傑偄偑旤偟偄丅峚岥偼挿夞偟偲堷偒嶣傝偱嬞挘姶傪尒帠偵帩懕偝偣傞丅拞斦偺庡恖岞偺擇恖偑嵞夛偡傞栭偺僔乕僋僄儞僗丄僄儞僨傿儞僌偺廙椃偺僔乕僋僄儞僗側偳丄報徾怺偄応柺傕懡偄丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐249丂峚岥寬擇偺塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺1丗僒僀儗儞僩塮夋
1933擖峕僾儘丂峚岥寬擇丂昡揰亂B亃
愹嬀壴尨嶌偺怴攈斶寑丅擖峕偨偐巕偲壀揷帪旻偺庡墘偺僒僀儗儞僩塮夋丅恖婥偺崅偄彈悈寍恖丄戨偺敀巺偼丄忔崌攏幵偺屼幰偺庒幰偲恊偟偔側傞丅庒幰偑昻偟偄偨傔妛栤傪抐擮偟偨偙偲傪抦偭偨斵彈偼丄斵傪搶嫗偵憲傝弌偟丄巇憲傝傪偟偰惗妶傪墖彆偡傞丅傗偑偰恖婥偑棊偪丄巇帠偑掅柪偟偨斵彈偼丄崅棙戄偟偐傜嬥傪庁傝傛偆偲偡傞偑丄懱傪媮傔傜傟岆偭偰斵傪巋嶦偡傞丅妛嬈傪廔偊偰専帠偵側偭偨庒幰偼斵彈傪崘敪偣偞傞傪摼側偄塇栚偵娮傞丒丒丒丅傂偲偮傂偲偮偺憓榖偑挌擩偵堿塭怺偔昤偐傟偰偍傝丄偲傝傢偗丄偍傏傠寧偺栭丄嫶偺壓偱戨偺敀巺偲庒幰偑嵞夛偟丄尵梩傪岎傢偡僔乕儞偼報徾偵巆傞丅擖峕偨偐巕偼摉帪21嵨丄恖婥偺愨捀婜偱丄偠偮偵偒傟偄偵嶣傟偰偄傞丅埆鐓側崅棙戄偟偵悰堜堦榊丄嬥傪庁傝偰塤塀傟偡傞彈寍恖偵塝曈孒巕偑暞偟偰偄傞丅
愜掃偍愮
1935戞堦塮夋丂峚岥寬擇丂昡揰亂A亃
偙傟傕愹嬀壴偺彫愢乽攧怓姏撿斬乿傪尨嶌偲偡傞僒僀儗儞僩塮夋丅戝妛偺偙傠偺桭偩偪偺傂偲傝偑愹嬀壴偺僼傽儞偱丄岲偒側彫愢偼乽攧怓姏撿斬乿偲尵偭偰偄偨偺傪巚偄弌偡丅榖偺嬝偼乽戨偺敀巺乿偲摨岺堎嬋丅庡墘偼嶳揷屲廫楅偲壞愳戝擇榊丅怱側傜偢傕崪摕壆堦枴偺埆摽彜攧傪庤揱偭偰偄傞偍愮偼丄帺嶦偟傛偆偲偟偰偄傞昻偟偄堛妛惗傪彆偗丄斵傪巟偊椼傑偟偰丄曌嫮傪懕偗偝偣傞丅傗偑偰斵偼堛幰偵側傞丅偍愮偼戇曔偝傟丄楇棊偡傞丅嵟屻偼堛幰偺斵偑惛恄偵堎忢傪棃偨偟偨偍愮傪昦堾偵尒晳偆僔乕儞偱廔傞丅怴攈斶寑偩偑丄揑妋側嶣塭偵傛傝揨柸偨傞忣弿傪昚傢偣偰偄傞丅偲偔偵戇曔偝傟偨偍愮偑嫻尦偺愜掃傪岥偵偔傢偊丄尒憲傞庒幰偵搳偘憲傞僔乕儞偺旤偟偝偼奿暿丅摉帪17嵨偺嶳揷屲廫楅偼偡偱偵鋎挿偗偰偍傝丄愻楙偝傟偨旤偟偝傪敪嶶偟偰偄傞丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐248丂偐偮偰尒偨夰偐偟偄尨愡巕弌墘塮夋
1955怴搶曮丂憅揷暥恖丂昡揰亂C亃
偙傟偼岞奐擭偐傜偡傞偲彫惗偑彫妛2擭惗偺偲偒偵尒偨偙偲偵側傞丅曣恊偵桿傢傟偰堦弿偵尒偨偲婰壇偡傞丅彫妛掅妛擭偺彈偺巕偑栘偐傜抮偵棊偪丄昦彴偱堄幆晄柧偵娮偭偰偄傞偁偄偩偵丄塤偺忋偱愬恖偵恎偺忋榖傪偡傞柌傪尒傞丄偲偄偆僼傽儞僞僕乕晽枴偺帣摱岦偗暥晹徣慖掕塮夋丅庡墘偺榢暎惏巕偼摉帪10嵨丄偦偺晝曣傪尨愡巕偲摗揷恑偑墘偠偰偄傞丅斵傜偺壠偵偼偪傖傇戜偑偁傝丄晽楥偼暟偒偮偗偱暒偐偟丄曣偼朌偄暔偵惛傪弌偟丄孼偲枀偼嵄嵶側偙偲偱寲壾偟丄榬敀側孼偼晝偵墸傜傟傞丄偲偄偆摉帪偺擔杮偺偛偔晛捠偺壠掚偺晽宨偑塮偟弌偝傟傞偺偑夰偐偟偄丅尨愡巕偼敀撪忈偺庤弍傪偟偰1擭敿傇傝偺塮夋弌墘偩偭偨丅尨愡巕偑曣恊栶傪傗傞偺偼偙傟偑弶傔偰偱偼側偄偩傠偆偐丄怱帩偪杍偑傆偭偔傜偟偰偍傝丄旤偟偔桪偟偄偍曣偝傫傪偟偭偲傝墘偠偰偄傞丅尨偲摗揷偼愴慜偐傜愴屻偵偐偗偰偨偔偝傫偺塮夋偱僇僢僾儖傪墘偠偨丅摉帪10嵨偺榢暎惏巕偼柌偺側偐偱償傽僀僆儕儞傗僶儗僄偺榬慜傪斺業偡傞丅偙偺壜楓側旤彮彈偑丄偺偪偵惵弔僗僞乕傪宱偰梔墣側弉彈偵側傝丄僰乕僪幨恀廤傪弌斉偟丄抝偲晜柤傪棳偡偵帄傞偲偼丄偘偵彈偼嫲傠偟偒偐側丅
擔杮抋惗
1959搶曮丂堫奯峗丂昡揰亂C亃
偙傟傪尒偨偺偼拞妛2擭偺偙傠偩偭偨偩傠偆偐丅朻摢偵弌偰偔傞敿棁偺抝彈丄僀僓僫僊偲僀僓僫儈偺巔偵嫻偑僪僉僪僉偟偨偙偲傪妎偊偰偄傞丅偄傑尒傟偽偳偆偭偰偙偲側偄僔乕儞偩偑丅婰婭傪傕偲偵偟偨恄榖帪戙偺擔杮偺暔岅偱3帪娫偺戝嶌丅挬掛偵攈尛偝傟偰擔杮晲懜偑晪偔惇惣偲搶惇傪拞怱偵昤偐傟傞丅偦偺娫偵揤徠戝恄偺揤娾屗塀傟傗恵嵅擵抝柦偵傛傞敧婒戝幹戅帯偺憓榖偑怐傝崬傑傟傞丅庡墘偺嶰慏晀榊偼擔杮晲懜偲恵嵅擵抝柦偺擇栶丅搶曮偺僗僞乕偑憤弌墘偡傞偑丄側偤偐怷斏媣淺偑偄側偄丅攐桪僋儗僕僢僩偺僩儕傪忺傞尨愡巕偼丄揤徠戝恄傪墘偠偰恄乆偟偄旤偟偝傪曻偮丅嶰慏偺憡庤栶傪柋傔傞彈桪偼擺摼偺巌梩巕偲崄愳嫗巕丅嶰栘偺傝暯丄彫椦宩庽丄壛搶戝夘丄桳搰堦榊側偳偺婌寑僗僞乕偼揤娾屗偺憓榖偱搊応偡傞丅娾屗傪偙偠奐偗傞庤椡抝柦傪挬幀懢榊偑墘偠偰偄傞偺偑夰偐偟偄丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐247丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘偺塮夋丂偦偺2
1966惣丒暓丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘丂昡揰亂B亃
僔僃乕僋僗僺傾偺偄偔偮偐嶌昳偵榚栶偱搊応偡傞戝暫旍枮偺榁婻巑僼僅儖僗僞僢僼傪庡恖岞偲偡傞暔岅丅庡偵乽僿儞儕乕4悽乿偑壓晘偒偵側偭偰偄傞丅嗦嘞偱岲怓丄戝庰堸傒偱嫮梸偩偑憺傔側偄惈奿偺僼僅儖僗僞僢僼傪僂僃儖僘偼悈傪摼偨嫑偺傛偆偵墘偠傞丅塸崙墹偺忛娰傗応枛偺埨廻偺僙僢僩偑尒帠偱丄嬻娫傪惗偐偟偨僇儊儔儚乕僋傕慺惏傜偟偄丅僼僅儖僗僞僢僼偼曻摖岲偒偺墹巕偲偮傞傫偱埆傆偞偗傪妝偟傓偑丄晝墹偑巰偵懄埵偟偨偲偨傫丄墹巕偼偙偺媽桭傪墦偞偗丄捛曻張暘偵偡傞丅尒廔傢偭偰乽偍傕偟傠偆偰丄傗偑偰斶偟偒丒丒丒乿偲偄偆攎徳偺嬪偑巚偄晜偐傇丅僼僅儖僗僞僢僼偲婥偺崌偆埨廻偺彥晈偵暞偡傞僕儍儞僰丒儌儘乕偑偄偄丅
僼僃僀僋
1975僀儔儞丒暓丒惣撈丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘丂昡揰亂D亃
僆乕僜儞丒僂僃儖僘偑姰惉偝偣偨嵟屻偺娔撀嶌昳丅僫儗乕僞乕寭恑峴栶傪僂僃儖僘帺恎偑柋傔傞丄婁嶌夋壠僄儖儈傾丒僨儂乕儕乕偲婁嶌嶌壠僋儕僼僅乕僪丒傾乕償傿儞僌傊偺僀儞僞償儏乕偑拞怱偲側偭偨僪僉儏儊儞僞儕乕晽偺塮夋丅偟偐偟丄僂僃儖僘偑乽偙偺塮夋偺敿暘偼杮摉偱敿暘偼塕乿偲尵偆偲偍傝丄僺僇僜傗僴儚乕僪丒僸儏乕僘偺堩榖丄帺傜偺棃楌傪岅傞偆偪偵丄偟偩偄偵嫊幚偑濨枂偵側偭偰偄偔丅僺僇僜偺乽寍弍偼傂偲偮偺塕偩乿偲偄偆尵梩傪徯夘偟偰偙偺塮夋偼廔傞丅僂僃儖僘傜偟偄塮夋偲尵偊傞偩傠偆偑丄撪梕偲偟偰偼偁傑傝柺敀偝傪姶偠傜傟側偄丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐246丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘偺塮夋丂偦偺1
1951儌儘僢僐丒埳丒暷丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘丂昡揰亂C亃
僂僃儖僘偑乽儅僋儀僗乿偵懕偄偰嶌偭偨僔僃乕僋僗僺傾偺斶寑丅婔搙偐偺惢嶌拞抐傪宱偰丄4擭傪偐偗偰儌儘僢僐偱姰惉偝偣偨偲偄偆丅儉乕傾恖偺彨孯僆僙儘偑汙恇僀儎乕僑偺妲尵傪怣偠偰掑愡側嵢僨僘僨儌乕僫傪嶦偡偲偄偆桳柤側榖丅僂僃儖僘偑惢嶌丒娔撀丒媟杮丒庡墘傪柋傔傞丅乽儅僋儀僗乿傎偳柺敀偔偼側偄偑丄朻摢偲枛旜偱塮偟弌偝傟傞僆僙儘偲僨僘僨儌乕僫偺憭楍偺丄屆戙偺堎嫵偺媀幃傪巚傢偣傞堎條側岝宨丄僉僾儘僗搰偺嫃忛偺婏娤丄堿塭偵晉傓嶣塭丄墱峴偒傪姶偠偝偣傞峔恾丄慺憗偄応柺揥奐側偳丄尒偳偙傠偼懡偄丅僨僘僨儌乕僫栶偺僗僓儞僰丒僋儖乕僥傿僄偼柍柤偩偑側偐側偐昳奿偺偁傞旤宍偺彈桪偩丅
旈傔傜傟偨夁嫀
1955暓丒惣丒悙丂僆乕僜儞丒僂僃儖僘丂昡揰亂D亃
僼傿儖儉丒僲儚乕儖晽偺僗儕儔乕塮夋丅偙傟傕惂嶌丒娔撀丒媟杮丒庡墘偼僂僃儖僘丅夞憐宍幃偱傂偲傝偺抝偺夁嫀偑朶偐傟傞偲偄偆嬝棫偰偼乽巗柉働乕儞乿傪巚傢偣側偄偱傕側偄丅尦悈暫偺抝偑丄攇巭応偱嶦偝傟偨抝偐傜傾乕僇僨傿儞偲偄偆柤慜傪傪暦偒丄嬥偺擋偄傪歬偓偮偗偰丄偦偺傾乕僇僨傿儞偲偄偆戝晉崑偵愙怗偡傞丅傾乕僇僨傿儞偐傜婰壇偵側偄帺暘偺夁嫀傪挷傋偰傎偟偄偲埶棅偝傟偨斵偼丄傾乕僇僨傿儞備偐傝偺恖乆偵夛偭偰榖傪暦偒丄夁嫀傪扵傞偆偪偵丄偦傟傜偺恖乆偑晄怰巰傪悑偘丄偦偺塭偵傾乕僇僨傿儞偑偄傞偙偲偵婥偑偮偔丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅摫擖晹偼慛傗偐偱丄嶣塭傕堿塭偵晉傫偱偄傞丅偟偐偟丄偦偺偁偲偺揥奐偑暯斅偱惙傝忋偑傝偵朢偟偄偟丄慡懱偺僾儘僢僩傕晄帺慠偩丅傾乕僇僨傿儞傪墘偠傞僂僃儖僘偼崟儅儞僩偵摿堎側晽杄偱側偐側偐懚嵼姶偑偁傞丅斵偺尵摦偼偡傋偰撲傔偄偰偄偰丄壗偑杮摉側偺偐敾慠偲偟側偄丅僂僃儖僘偼偙偺塮夋偱尦悈暫偲楒拠偵側傞傾乕僇僨傿儞偺柡傪墘偠偨僷僆儔丒儌儕僗偲寢崶偟偨丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐245丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺4
1934徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂B亃
婌敧傕偺偺戞2嶌偱丄彫捗偑愴屻偵儕儊僀僋偟偨柤嶌乽晜憪乿偺僆儕僕僫儖斉丅偁傜偡偠傗榖偺棳傟偼乽晜憪乿偲傎傏摨堦偩丅婌敧傕偺偲偼偄偊丄嶁杮晲墘偢傞椃幣嫃堦嵗偺嵗挿丄婌敧偺僉儍儔僋僞乕偼戞1嶌偲偼偐側傝堎側傞丅乽晜憪乿偱偼悪懞弔巕偑墘偠偨嵗挿偺愄偺垽恖偱偁傞堸傒壆偺彈彨偵偼斞揷挶巕偑暞偡傞丅愴慜偺彫捗塮夋偵偍偄偰丄斞揷挶巕偼愴屻偵悪懞弔巕偑扴偭偨栶妱傪壥偨偟偰偄傞偲尵偊傞丅嶁杮偲斞揷偺塀偟巕傪墘偠傞嶰堜峅師偼儕儊僀僋斉偱嵗堳偺傂偲傝偵暞偟偰偄偨丅彫捗偼嶁杮偲嶰堜偺恊巕偑愳偱掁傝傪偡傞僔乕儞偱娖偺摦偒傪僔儞僋儘偝偣偰偄傞偑丄偙傟偼乽晝偁傝偒乿偱偺妢抭廜偲嵅栰廃擇偵傛傞掁傝偺僔乕儞偺尨宆偲尵偊傞丅塮夋偲偟偰偼傛偔弌棃偰偄傞偑丄慡懱揑偵怴攈墘寑晽偺幣嫃偑偐偭偨挷巕偑嫮偔丄傗傗嫽偞傔偡傞丅惉悾枻婌抝偑1940擭偵嶣偭偨丄摨偠偔椃幣嫃堦嵗偺擔忢傪僥乕儅偲偡傞乽椃栶幰乿偲斾妑偟偰傒傞偺傕柺敀偄偩傠偆丅
搶嫗偺廻
1935徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂C亃
嶁杮晲偑庡墘偡傞婌敧傕偺偺嵟廔嶌丅僒僀儗儞僩塮夋偩偑僒僂儞僪斉偱壒妝偑晅悘偟偰偄傞丅婌敧僔儕乕僘偼偩傫偩傫埫偄撪梕偵側傞丅偙偺晄嫷壓偱嬯偟傓壓憌弾柉偑昤偐傟傞嵟廔嶌偑偄偪偽傫埫偔丄愗側偄丅婌敧偼擇恖偺梒偄抝偺巕傪楢傟偰丄拫娫偼怑傪媮傔偰偝傑傛偄曕偒丄栭偼栘捓廻偵攽傑傞偲偄偆擔乆傪夁偛偟偰偄傞丅怑偼尒偮偐傜偢丄嬥偑側偔側傝搑曽偵曢傟偰偄傞偲偙傠偵丄愄側偠傒偺斞壆偺彈彨亖斞揷挶巕偲憳嬾偟丄斵彈偺彆偗偱摥偒岥偑尒偮偐傝丄傑偲傕側惗妶偑偱偒傞傛偆偵側傞丅偦傟傕懇偺娫丄斵偼彈偺巕傪楢傟偨偦偺擔曢傜偟偺彈亖壀揷壝巕偵摨忣偟丄彈偺巕偑昦婥偱擖堾偟偨帯椕旓偵偁偰傞偨傔嫮搻傪摥偔丅嵟屻偼丄婌敧偑巕嫙傪斞揷挶巕偵戸偟丄斵彈偵尒憲傜傟偰寈嶡偵弌摢偡傞僔乕儞偱廔傞丅塮夋偲偟偰偼傛偔弌棃偰偍傝丄巕嫙偺昤偒曽傕岻柇偩偑丄偙傟傕慜嶌偲摨偠偔屻敿偼怴攈幣嫃偠傒偰偔傞丅斞揷挶巕偼偙偺偙傠30戙敿偽偩偑丄偡偱偵擭憹偺娧榎傪昚傢偣偰偍傝丄偦偺懚嵼姶偼愨戝丅柇側怓婥傪敪嶶偡傞壀揷壝巕偼丄偙偺塮夋岞奐偺2擭屻丄尩姦偺姃懢傪挻偊偰僜楢偵朣柦偟偨丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐244丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺3
1933徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂A亃
嶁杮晲偑庡墘偡傞乽婌敧傕偺乿偺戞1嶌偵偁偨傞恖忣婌寑丅岺応楯摥幰偺嶁杮晲亖婌敧偼丄憡朹偺戝擔曽揱傗嬤強偺斞壆偺斞揷挶巕偵彆偗傜傟側偑傜懅巕偺撍娧彫憁傪堢偰偰偄傞丅嶁杮偼峴偒応偺側偄柡丄暁尒怣巕偵摨忣偟丄斞壆偵棅傫偱摥偒岥傪悽榖偡傞丅嶁杮偼偙偺柡偵崨傟傞偑丄柡偼憡朹偺戝擔曽偵婥偑偁傞丅榖偼斵傜偺擔乆偺惗妶丄嶰妏娭學丄恊巕偺忣側偳傪昤偒側偑傜揥奐偡傞丅媟杮偑桪傟偰偍傝丄弌墘幰偨偪傕傒側払幰偵墘偠偰偄傞丅偲偔偵撍娧彫憁偺揤堖柍朌側墘媄偼摿昅偵抣偡傞丅偙傟偼僒僀儗儞僩帪戙偺彫捗偺戙昞嶌偺傂偲偮偩傠偆丅彫捗撈摿偺嶣塭媄朄偼偡偱偵掕拝偟偰偄傞丅柍妛偱偗傫偐偭憗偄偑偍恖岲偟偱忣偵傕傠偄婌敧偺僉儍儔僋僞乕偼傑偓傟傕側偔嶳揷梞師偺僼乕僥儞偺撔偺尨宆偱偁傠偆丅
曣傪楒傢偢傗
1934徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂C亃
曣巕垽偲孼掜垽傪昤偄偨僼傽儈儕乕塮夋丅慡9姫偺僼傿儖儉偺偆偪嵟弶偲嵟屻偑寚偗偨晄姰慡斉偟偐巆偭偰偄側偄丅晇偑媫巰偟丄嵢偺媑愳枮巕偼丄挿抝亖戝擔曽揱偲師抝亖嶰堜峅師傪寽柦偵堢偰忋偘傞丅挿抝偼晇偺愭嵢偺巕偱偁傝丄偦傟傪抦偭偨挿抝偼堦帪傂偹偔傟傞偑丄媊曣偺垽偑暘偐偭偰怱傪擖傟懼偊傞丅偟偐偟戝妛偵擖偭偨挿抝偼曣偺垽偑曃偭偰偄傞偲巚偄崬傫偱壠弌偟丄曣偲師抝偼嫻傪捝傔傞丅嵟屻偼尦偺忊偵廂偭偰偟偁傢偣偵廔傞丅師抝偺妛桭偵妢抭廜丄妛峑偺梡柋堳偵嶁杮晲丄僠儍僽壆偺憒彍晈偵斞揷挶巕偲偄偆忢楢偺栶幰偑弌墘偟偰偄傞丅偲傝傢偗壠弌偟偨挿抝傪桜偡憒彍晈偺斞揷挶巕偑報徾怺偄丅偙偙偵傕彫捗偺摦嶌偺僔儞僋儘傊偺偙偩傢傝偑尒傜傟傞偑丄慡懱偲偟偰嬝棫偰偵柍棟偑偁傝丄姶彎惈偵棳傟偰娫墑傃偟偨揥奐偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐243丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺2
1932徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂C亃
庒幰偺惗懺傪捠偟偰摉帪偺悽憡傪昤偄偨婌寑丅夛幮幮挿偺懅巕丄峕愳塅楃梇偼丄惸摗払梇側偳3恖偺拠偺偄偄桭恖傗丄儀乕僇儕乕偺娕斅柡丄揷拞對戙偲偺岎桭傪妝偟傒側偑傜妛惗惗妶傪憲偭偰偄偨偑丄晝恊偑媫巰偟偨偨傔戅妛偟偰夛幮傪宲偖丅桭恖偨偪偐傜擖幮偟偨偄偲尵傢傟偨峕愳偼嶔傪楙偭偰擖幮偝偣偰傗傞丅峕愳偼揷拞偲寢崶偟傛偆偲偡傞偑丄惸摗偑揷拞偲崶栺偟偰偄偨偺偵棫応傪峫椂偟偰栙偭偰偄偨偙偲傪抦傝丄惸摗傪墸傞丅嵟屻偵斵傜偼拠捈傝偟丄惸摗偲揷拞偺栧弌傪廽偆丒丒丒丅桭恖偺傂偲傝偵妢抭廜丄惸摗偺曣偵斞揷挶巕丄妛峑偺梡柋堳偵嶁杮晲偑暞偡傞丅懠垽側偄榖偩偑丄斾妑揑岻偔傑偲傑偭偰偍傝丄悘強偵儐乕儌傾偲晽巋偑偪傝偽傔傜傟偰偄傞丅怴崶椃峴偵弌偐偗傞惸摗偲揷拞偑忔偭偨楍幵偵岦偐偭偰丄桭恖偨偪偑暲傫偱價儖偺壆忋偐傜庤傪怳傞僄儞僨傿儞僌偺峔恾偼丄愴屻偺彫捗塮夋偱傕巊傢傟偰偄偨丅
搶嫗偺彈
1933徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂E亃
偙傟傕壓憌幮夛偺堦抐柺傪昤偄偨塮夋偩偑丄撪梕偼埫偄丅50暘庛偺彫昳丅妛惗偺峕愳塅楃梇偼夛幮嬑傔偺巓丄壀揷壝巕偲擇恖曢傜偟丄嬤強偺柡丄揷拞對戙偲偼憡垽偺拠偩偑丄巓偑惗妶旓傪壱偖偨傔偵悈彜攧偺傾儖僶僀僩傪偟偰偄傞偙偲傪抦傝丄巓傪墸偭偰壠弌偟偰帺嶦偡傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅偙偙偱偼儘僂丒億僕僔儑儞偺僇儊儔丒傾儞僌儖偑懡梡偝傟偰偍傝丄彫捗撈帺偺媄朄偑姰惉偝傟偮偮偁傞偲偺姶傪書偔偑丄彫捗塮夋偺側偐偱偼乽搶嫗曢怓乿偲暲傫偱屻枴偺埆偄嶌昳偩丅帺嶦偼偁傑傝偵搨撍偱偁傝丄側偤偙傫側晄帺慠偐偮嫮堷側嬝棫偰偺塮夋傪嶌偭偨偺偐棟夝偵嬯偟傓丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐242丂彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丄巆傝傪慡晹尒傞丂偦偺1
1929徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂D亃
尰懚偡傞彫捗埨擇榊娔撀塮夋偺側偐偱偄偪偽傫屆偄嶌昳丅戝妛惗偺桭恖2恖偵傛傞彈傪弰傞楒偺偝傗摉偰偲丄僗僉乕椃峴偵弌偐偗偨妛惗偨偪偺峴摦傪昤偄偨僐儊僨傿丅暷崙偺僐儊僨傿塮夋偺塭嬁偑尠挊偱丄彫捗傜偟偝偼偄傑偩敪婗偝傟偰偄側偄丅庡墘偼寢忛堦榊偲惸摗払梇丅彫捗塮夋偺忢楢丄斞揷挶巕偲妢抭廜偑憗偔傕榚栶偱婄傪弌偟偰偄傞丅
楴傜偐偵曕傔
1930徏抾丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂C亃
崅揷柅偲愳嶈峅巕偺庡墘丅僠儞僺儔偺傗偔偞偑庒偄柡偵堦栚崨傟偟丄傗偔偞壱嬈偐傜懌傪愻偭偰惓嬈偵偵廇偔榖丅傾儊儕僇塮夋偺塭嬁偑擹岤偱丄梞晽偺晽懎偑昿斏偵塮偟弌偝傟傞丅偺偪偺彫捗塮夋偺摿挜偺傂偲偮偱偁傞丄暋悢偺搊応恖暔偺摦嶌傪僔儞僋儘偝偣傞庤朄偑壗搙傕巊傢傟偰偄傞偟丄傗偐傫偺傾僢僾傕弌偰偔傞偺偑嫽枴怺偄丅
2023擭6寧朸擔 旛朰榐241丂僷僂僄儖仌僾儗僗僶乕僈乕偺寍弍塮夋
1948塸丂僷僂僄儖仌僾儗僗僶乕僈乕丂昡揰亂B亃
偝傜偵塸崙偮側偑傝偱丄僷僂僄儖仌僾儗僗僶乕僈乕偺2杮偺塮夋傪尒偨丅偙傟偼傾儞僨儖僙儞偺摱榖乽愒偄孋乿傪儌僥傿乕僼偵偟偨栰怱揑側僶儗僄塮夋丅桳柤僶儗僄抍傪棪偄傞寍弍僾儘僨儏乕僒乕偼庒偄柍柤偺僶儗儕乕僫傪敳揊偟偰怴嶌僶儗僄乽愒偄孋乿傪忋墘偟丄戝惉岟傪廂傔傞丅僶儗儕乕僫偼堦桇恖婥僗僞乕偵側傞偑丄僶儗僄抍偺嶌嬋壠偲楒拠偵側傝丄楒垽傪庢傞偐丄僶儗僄傪庢傞偐偱嬯擸偡傞丅愒偄孋傪棜偄偨彮彈偑巰偸傑偱梮傝懕偗傞偲偄偆乽愒偄孋乿偺僗僩乕儕乕偦偺傑傑偵丄塮夋偼斶寑揑側寢枛傪寎偊傞丅庡墘偺僶儗儕乕僫偵暞偡傞儌僀傾丒僔傾儔乕偼旤恖偱偼側偄偑垽沢偺偁傞婄棫偪偱丄懱偺慄傕旤偟偄丅寑拞偱忋墘偝傟傞10悢暘偵媦傇僶儗僄偺僔乕儞偼敆椡枮揰丄僥僋僯僇儔乕偺塮憸偑慛傗偐偩丅僶儗僄抍偺抍挿偼僶儗僄丒儕儏僗偺僨傿傾僊儗僼偑儌僨儖傜偟偄丅柤崅偄怳晅巘儗僆僯乕僪丒儅僔乕儞偑僟儞僒乕偲偟偰弌墘偟偰偄傞偺傕嫽枴傪屇傇丅
儂僼儅儞暔岅
1951塸丂僷僂僄儖仌僾儗僗僶乕僈乕丂昡揰亂D亃
偙傟偼僆僢僼僃儞僶僢僋嶌嬋偺僆儁儔乽儂僼儅儞暔岅乿偺塮夋壔丅僷僂僄儖仌僾儗僗僶乕僈乕偵傛傞慜嶌偵懕偔僥僋僯僇儔乕寍弍塮夋偩偑丄側偵偟傠慡曇偑僆儁儔側偺偱丄僆儁儔岲偒側傜偲傕偐偔丄偁傑傝娭怱偺側偄幰偵偲偭偰偼尒偰偄傞偲戅孅偡傞丅
2023擭5寧
2023擭5寧朸擔 旛朰榐240丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺6
1949塸丂傾儖僼儗僢僪丒僸僢僠僐僢僋丂昡揰亂C亃
偮偄偱偵丄偙傟傑偱枹尒偩偭偨拞婜僸僢僠僐僢僋偺掅昡壙偝傟偰偄傞2杮偺塮夋傪尒偨丅偙傟偼19悽婭枛偺僆乕僗僩儔儕傾傪晳戜偵偟偨楒垽僪儔儅丅僑僔僢僋丒儘儅儞晽偺嬝棫偰偰丄乽棐偑媢乿偲乽儗儀僢僇乿傪懌偟偰2偱妱偭偨傛偆側嶌昳丅塸崙憤撀偺墮儅僀働儖丒儚僀儖僨傿儞僌偑僔僪僯乕偵傗偭偰棃偰丄尦偼庴孻幰偺桳椡幚嬈壠僕儑僙僼丒僐僢僩儞偲抦傝崌偄丄斵偺壆晘傪朘傟丄惛恄忬懺偑堎忢側嵢僀儞僌儕僢僪丒僶乕僌儅儞偲弌夛偭偰楒偵棊偪傞丅塮夋偼偙偺嶰妏娭學偲塸崙帪戙偺晇晈偺旈枾傪弰偭偰揥奐偡傞丅壆晘偺椻崜側彈幏帠偼乽儗儀僢僇乿偺僟儞僶乕僗晇恖傪巚傢偣傞丅僸僢僠僐僢僋偑僶乕僌儅儞偵乽偨偐偑塮夋偠傖側偄偐乿偲尵偭偨偺偼丄偨偟偐偙偺塮夋偺嶣塭拞偩偭偨丅尨戣偺乽capricorn乿偲偼乽嶳梤嵗乿偱偼側偔乽撿夞婣慄乿傪堄枴偟偰偄傞偱偁傠偆丅
僗儈僗晇嵢
1941暷丂傾儖僼儗僢僪丒僸僢僠僐僢僋丂昡揰亂C亃
偙傟偼僸僢僠僐僢僋偵偼捒偟偔丄僗儕儔乕偺梫慺偑傑偭偨偔側偄弮慠偨傞僐儊僨傿塮夋丅庡墘偼僉儍儘儖丒儘儞僶乕僪偲儘僶乕僩丒儌儞僑儊儕乕丅垽偟崌偭偰偄傞偺偵寲壾偑愨偊側偄晇晈偑丄帺暘偨偪偺寢崶偑柍岠偩偭偨偙偲傪抦傜偝傟偰姫偒婲偙傞憶摦偑昤偐傟傞丅儘儞僶乕僪偺僐儊僨傿僄儞僰偲偟偰偺岻偝偑嵺棫偮丅壓昳側彈傪楢傟偰儗僗僩儔儞偵棃偨晇偑丄暿偺惾偵偄傞嵢偲栚偑崌偄丄椬偵偄傞尒偢抦傜偢偺旤彈偵丄偝傕楢傟偺傛偆偵榖偟偐偗傞僔乕儞偑書暊傕偺丅
2023擭5寧朸擔 旛朰榐239丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺5
1934塸丂傾儖僼儗僢僪丒僸僢僠僐僢僋丂昡揰亂C亃
塸崙僒僗儁儞僗塮夋偺尮棳偼僸僢僠僐僢僋丅偲偄偆偙偲偱丄塸崙帪戙偺僸僢僠僐僢僋偺枹尒偩偭偨3杮偺塮夋傪尒偨丅偙傟偼尵傢偢偲抦傟偨愴屻偺儕儊僀僋斉乽抦傝偡偓偰偄偨抝乿偺僆儕僕僫儖丒償傽乕僕儑儞丅崙嵺堿杁抍偵桿夳偝傟偨柡傪晇晈偑昁巰偵庢傝曉偦偆偲偡傞榖丅堿杁抍偺傾僕僩傪抦偭偰偄傞偑丄嫼敆偝傟偰偄傞偨傔寈嶡偵尵偊側偄晇偼丄桭恖偲偲傕偵帺椡偱傾僕僩傪扵傞丅堿杁抍偺庱椞僺乕僞乕丒儘乕儗偺嫮楏側僉儍儔僋僞乕偑嵺棫偭偰偄傞偑丄庡栶偺晇晈偺報徾偑敄偔丄摉慠側偑傜儕儊僀僋斉傎偳弌棃偼椙偔側偄丅
娫挸嵟屻偺擔
1936塸丂傾儖僼儗僢僪丒僸僢僠僐僢僋丂昡揰亂C亃
僒儅僙僢僩丒儌乕儉嶌偺僗僷僀彫愢偺塮夋壔丅僪僀僣偺僗僷僀傪揈敪偡傞偨傔塸崙挸曬堳僕儑儞丒僊乕儖僌僢僪偑僗僀僗偵攈尛偝傟傞丅斵偼旤恖偺彈娫挸儅僨儕乕儞丒僉儍儘儖丄摼懱偺抦傟側偄彈岲偒偺彆庤僺乕僞乕丒儘乕儗偲偲傕偵擟柋偵廇偔丅僐儈僇儖巇棫偰偱丄僸僢僠僐僢僋傜偟偝偼悘強偵偁傞偑丄慡懱揑偵偼娚偄報徾傪梌偊傞丅
僒儃僞乕僕儏
1936塸丂傾儖僼儗僢僪丒僸僢僠僐僢僋丂昡揰亂B亃
僕儑僙僼丒僐儞儔僢僪偺彫愢乽枾巊乿偺塮夋壔丅儘儞僪儞傪晳戜偵攋夡岺嶌偺堦枴偲寈嶡偲偺峌杊偑昤偐傟傞丅晇偲傕偵塮夋娰傪塩傓庒嵢偵僔儖償傽僀傾丒僔僪僯乕丄嬥傎偟偝偵攋夡妶摦偵廬帠偡傞偦偺晇偵僆僗僇乕丒儂儌儖僇偑暞偡傞丅孻帠偑椬偺敧昐壆偺揦堳偵側傝偡傑偟偰斵傪娔帇偟偰偄傞丅塮夋偼慡懱偲偟偰僒僗儁儞僗偵枮偪偰偍傝丄塸崙帪戙偺僸僢僠僐僢僋偺戙昞嶌偺傂偲偮偲尵偊傞偩傠偆偑丄桞堦偺嚓圊偼敋抏偺塣傃壆偵偝偣傜傟偨僔僪僯乕偺掜偺柍幾婥側彮擭偑敋巰偟偰偟傑偆愝掕偵偟偨偙偲丅偦偺偨傔偙傟偼屻枴偺埆偄嶌昳偵側偭偨丅僸僢僠僐僢僋帺恎傕偦偆偡傋偒偱偼側偐偭偨偲岅偭偰偄傞丅
2023擭5寧朸擔 旛朰榐238丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺4
1959塸丂儅僀働儖丒儅僢僇乕僔乕丂昡揰亂D亃
戞2師戝愴拞偺塸崙偺旈枾嶌愴傪昤偄偨塮夋丅僆儔儞僟偵怤峌偟偨僪僀僣孯偑傾儉僗僥儖僟儉偵岦偗偰恑寕偟偰偄傞嵟拞丄傾儉僗偵偁傞戝検偺僟僀儎儌儞僪傪塸崙偵堏憲偡傞偨傔丄曮愇彜僺乕僞乕丒僼傿儞僠偼拠娫偺2恖偲偲傕偵傾儉僗偵愽擖偡傞丅斵傜偼棨孯徣偵柋傔傞彈僄償傽丒僶儖僩乕僋偺彆偗傪庁傝丄僫僠僗戞5楍偺峌寕偵憳偄側偑傜丄曮愇彜偨偪偐傜僟僀儎傪廤傔丄偝傜偵嬧峴偵偁傞僟僀儎傪敋攋偟偰庢傝弌偦偆偲偡傞丒丒丒丅僸儘僀僘儉偲偛搒崌庡媊偑栚棫偪丄撪梕揑偵偼惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅
抧崠偺僈僀僪僽僢僋
1964塸丂儔儖僼丒僩乕儅僗丂昡揰亂B亃
搶惣椻愴偺嵟拞丄僗僷僀偵巇棫偰傜傟偨抝偺昁巰偺摝憱寑傪昤偔僐儈僇儖側僗僷僀塮夋丅塸崙偺攧傟側偄嶌壠僟乕僋丒儃僈乕僪偼偦傟偲抦傜偢偵僗僷僀偵巇棫偰傜傟丄僠僃僐偺僾儔僴傪朘傟偰忣曬傪帩偪婣傠偆偲偡傞偑丄僗僷僀偱偁傞偙偲偑敪妎偟丄旈枾寈嶡挿姱偺柡偱塣揮庤偲偟偰摨峴偡傞偆偪偵斵偲楒偵棊偪偨僔儖償傽丒僐僔僫偺彆偗傪摼偰丄捛偄偐偗傞旈枾寈嶡偺庤傪摝傟偰塸崙戝巊娰偵摝偘崬傕偆偲偡傞丅偙傟偼孈傝弌偟傕偺偺塮夋偩丅儂僥儖儅儞丄楯摥幰丄柉懓堖憰偺寍恖丄媿擕攝払堳側偳丄偄傠傫側奿岲偵曄憰偟偰僾儔僴偺奨傪摝偘夞傞儃僈乕僪偺摝憱寑偼丄僐儊僨傿偲偼偄偊丄側偐側偐嬞敆姶偵偁傆傟偰偄傞丅巰傫偩挸曬堳偺堚昳偑惍棟偝傟丄乽007乿偺柤嶥偑奜偝傟傞朻摢偺僔乕儞偑煭棊偰偍傝丄徫偄傪桿偆丅儃僈乕僪偺岻偝傕偝傞偙偲側偑傜丄僔儖償傽丒僐僔僫偺僌儔儅儔僗側旤彈傇傝傕嵺棫偮丅僐僔僫偼僿儔僋儗僗塮夋偱僗僥傿乕償丒儕乕償僗偲嫟墘偟偨偙傠偲偼報徾偑堎側傝丄梔墣枴偑憹偟偰偄傞丅
2023擭5寧朸擔 旛朰榐237丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺3
1949塸丂儘僫儖僪丒僯乕儉丂昡揰亂B亃
晳戜偼杒傾僼儕僇偺彫偝側挰丅敪孈偝傟偨屆戙偺堚昳傪挷嵏偡傞偨傔偵傗偭偰棃偨塸崙偺峫屆妛幰僩儗償傽乕丒僴儚乕僪偑姫偒崬傑傟傞晲婍枾桝堦枴偲偺憟偄傪昤偄偨塮夋丅斵偼搳廻偡傞儂僥儖偺柡傾僰乕僋丒僄乕儊偲楒偵棊偪傞丅堎崙忣弿偲楒垽傪棈傑偣偨僗儕儔乕偩偑丄弌棃偼埆偔側偄丅栭丄崑塉偺拞丄僴儚乕僪偑幵傪塣揮偟偰儂僥儖傪栚巜偡朻摢偺僔乕儞偑報徾偵巆傞丅奟曵傟偱摴偑搑愗傟偨偨傔丄斵偼嶳偺拞傪曕偄偰儂僥儖傪栚巜偡偑丄偦偺搑拞偵晲婍枾桝偺尰応傪栚寕偡傞丅僴儚乕僪偑奀拞偱僄乕儊偺孼偺巰懱傪尒偮偗傞僔乕儞傗丄僀僲僔僔庪傝偺側偐傪僴儚乕僪偲僄乕儊偑摝偘榝偆儔僗僩丒僔乕儞傕嬞敆姶偵晉傫偱偄傞丅僄乕儊偺悙乆偟偝偑愨昳偩偟丄揋栶偺僴乕僶乕僩丒儘儉傕岲墘偟偰偄傞丅
僉儍儞儀儖宬扟偺寖摤
1957塸丂儔儖僼丒僩乕儅僗丂昡揰亂C亃
僴儌儞僪丒僀僱僗偺朻尟彫愢偺塮夋壔丅媫巰偟偨慶晝偺堚巙傪宲偓丄愇桘敪孈偺偨傔儘僢僉乕嶳拞偵傗偭偰棃偨塸崙惵擭僟乕僋丒儃僈乕僪偼丄偦偙偵僟儉傪寶愝偟傛偆偲偡傞僗僞儞儕乕丒儀僀僇乕堦枴偺朩奞偵憳偄側偑傜丄晄帯偺昦偵朻偝傟偰偄傞恎偵傓偪懪偪丄慶晝偺桭恖偺柡傗應検媄巘偺彆偗傪摼偰敪孈嶌嬈傪巒傔傞丒丒丒丅儃僈乕僩偺庛乆偟偝偺側偐偵嫮枵側堄巙傪偆偐偑傢偣傞晽忣偑偄偄丅傑偨儘僢僉乕偺戝帺慠偺旤偟偝丄廔斦偺僟儉偑寛夡偡傞僔乕儞偺敆椡傕側偐側偐偺傕偺丅
2023擭5寧朸擔 旛朰榐236丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺9丗懕乆儘僢僙儕乕僯
1949埳丒暷丂儘儀儖僩丒儘僢僙儕乕僯丂昡揰亂C亃
儘僢僙儕乕僯偑僀儞僌儕僢僪丒僶乕僌儅儞傪婲梡偟偰嶌偭偨悢杮偺塮夋偺戞1嶌丅偙偺塮夋嶣塭拞偵擇恖偼晄椣娭學偵娮傝丄僶乕僌儅儞偼傾儊儕僇偺僼傽儞偐傜斀姶傪攦偆偙偲偵側傞丅偙傟偼僱僆儗傾儕僗儌偱昤偔恄偲帺慠傪庡戣偲偟偨塮夋丅戞2師戝愴廔愴捈屻丄儕僩傾僯傾弌恎偺彈僶乕僌儅儞偼擄柉僉儍儞僾偐傜敳偗弌偡偨傔丄僉儍儞僾偱抦傝崌偭偨僀僞儕傾偺嫏巘偺庒幰偲寢崶偟丄斵偺屘嫿偱偁傞僥傿儗僯傾奀偺壩嶳搰僗僩儘儞儃儕偵峴偔丅偩偑丄搰偺昻偟偄惗妶丄廧柉偑傛偦幰偵岦偗傞椻偨偄帇慄偵懴偊偒傟偢丄壩嶳偺暚壩偵忔偠偰扙弌偟傛偆偲偡傞偑丄暚壩岥晅嬤偱椡恠偒搢傟丄恄偵彆偗傪媮傔傞丅僶乕僌儅儞偑壩岥傪偝傑傛偆巔偼丄乽怴偟偒搚乿偺儔僗僩偺尨愡巕傪渇渋偲偝偣傞丅摉帪33嵨偺僶乕僌儅儞偑偲偰傕偒傟偄偵嶣傟偰偄傞偺偼偄偄偑丄偦傟偩偗偵丄楎埆側嫬嬾偵恎傪棊偲偡彈惈傪墘偠傞偺偵偼堘榓姶傪妎偊傞丅愨奀偺屒搰偺峳椓偨傞晽宨丄嫏巘偨偪偑椼傓儅僌儘嫏偺昤幨偑報徾偵巆傞丅
僀僞儕傾椃峴
1954埳丒暓丂儘儀儖僩丒儘僢僙儕乕僯丂昡揰亂C亃
儘僢僙儕乕僯偲僶乕僌儅儞偺僐儞價偵傛傞寫懹婜偺晇晈偑弌偐偗偨僀僞儕傾椃峴偺揯枛傪昤偄偨塮夋丅僀儞僌儕僢僪丒僶乕僌儅儞偲僕儑乕僕丒僒儞僟乕僗偑庡墘偺晇晈傪墘偠傞丅堚嶻偱憡懕偟偨暿憫傪張暘偡傞偨傔僫億儕傪朘傟偨塸崙恖晇嵢丄晇晈拠偼椻偊愗偭偰偍傝丄偍屳偄偵棧崶傪峫偊偰偄傞丅嵢偼僫億儕嬤曈偺攷暔娰丄抧壓曟強丄儀僗價僆嶳側偳偺柤強媽愓傪娤岝偟丄晇偼僇僾儕搰偱彈桭偩偪偲梀傇丅億儞儁僀偺堚愓偱書偒崌偭偨傑傑巰傫偩抝彈偺堚懱偺敪孈傪尒偨擇恖偼丄婣搑丄惞曣憸偺嵳傝偱暒偒曉傞孮廜偺側偐丄傛傝傪栠偦偆偲寛堄偡傞丅寫懹婜偺晇晈偺椃傪昤偔偙偺塮夋偼僽儗僀僋丒僄僪儚乕僘偺儘乕僪丒儉乕償傿乽偄偮傕擇恖偱乿傪憐婲偝偣傞丅儘僢僙儕乕僯偼懄嫽揑側墘弌傪偟偨偲偄偆偙偲偩偑丄塮夋傪尒傞偐偓傝丄僔儞僾儖偱傑偲傑偭偰偍傝丄偦傫側暤埻婥偼姶偠傜傟側偄丅僶乕僌儅儞偑尒偰曕偔攷暔娰偺僔乕僋僄儞僗偑弌怓偩丅偟偐偟丄偙傟偼僑僟乕儖側偳偺僰乕儀儖僶乕僌嶌壠傗僗僐僙僢僔側偳偺娔撀偵崅偔昡壙偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄偦傟傎偳偺寙嶌偲傕巚偊側偄丅偙偙偵傕恄偵傛傞媬嵪偲偄偆僥乕儅偑奯娫尒偊傞偟丄儔僗僩偼傗傗庢偭偰晅偗偨傛偆側報徾傪庴偗傞丅
2023擭4寧
2023擭4寧朸擔 旛朰榐235丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺2
1951塸丂僉儍儘儖丒儕乕僪丂昡揰亂B亃
撿奀偺搰傪晳戜偵丄栰斬偲暥柧偺憡崕傪昤偄偨塮夋丅娔撀偼僉儍儘儖丒儕乕僪丄慜嶌偺乽戞3偺抝乿偲偼懪偭偰曄傢偭偨晳戜愝掕偱丄堦尒丄旈嫬朻尟塮夋偺傛偆偩偑丄幚懱偼彈偵擖傟崬傫偱攋柵偡傞僟儊抝傪昤偄偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖偩偲尵偊傞丅尨嶌偼僕儑僙僼丒僐儞儔僢僪丅僔儞僈億乕儖偱摥偔僩儗償傽乕丒僴儚乕僪偼夛幮偺嬥傪巊偄崬傫偱庰偲搎攷偵擖傟偁偘丄僋價偵側傞偑丄媽抦偺岎堈慏偺慏挿儔儖僼丒儕僠儍乕僪僜儞偵彆偗傜傟丄旈枾偺峲楬傪捠偭偰慏挿偑暔帒傪巇擖傟傞旈嫬偺搰偵峴偔丅柍堊側擔乆傪夁偛偡偆偪偵尨廧柉偺廢挿偺柡偺夦偟偄枺椡偺偲傝偙偵側偭偨僴儚乕僪偼丄斵彈傪傕偺偵偡傞偨傔丄壎恖偺儕僠儍乕僪僜儞傪棤愗傝丄廢挿偲寢戸偡傞傾儔僽偺彜恖偵旈枾偺峲楬傪柧偐偡丅偦傟傪抦偭偨儕僠儍乕僪僜儞偼曬暅偡傞偨傔晲婍傪庤偵偟丄墱抧偵愽傓僴儚乕僪偺傕偲偵岦偐偆丒丒丒丅撿奀偺搰偲僩儗償傽乕丒僴儚乕僪庡墘偲偄偆偙偲偐傜偟偰丄僴儚乕僪偑椻崜側慏挿傪墘偠偨1962擭偺塮夋乽慏娡僶僂儞僥傿乿傪楢憐偟偰偟傑偆丅搊応偡傞恖暔偼傒側暔梸偲怓梸偵廁傢傟偰偍傝丄扤偵傕尐擖傟偡傞偙偲偑偱偒側偄丅悈忋偱惗妶偡傞尨廧柉偨偪偺帇慄丄庡恖岞偺廃傝偵孮偑傞巕嫙偨偪偑僒僗儁儞僗傪彆挿偡傞丅僴儚乕僪偑怓崄偵揗傟傞廢挿偺柡偼僼傽儉丒僼傽僞乕儖偱偁傝丄擇恖偑栭丄枾夛偡傞応柺偼岝偲塭偺僐儞僩儔僗僩偵傛偭偰擹岤側僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺怓崌偄傪懷傃傞丅
嫝抏
1949塸丂儀僀僕儖丒僨傿傾僨儞丂昡揰亂C亃
儘儞僪儞寈帇挕偺寈姱傗孻帠偺憑嵏傪僪僉儏儊儞僞儕乕丒僞僢僠偱昤偄偨寈嶡塮夋丅僠儞僺儔偺晄椙惵擭偑嫮搻偺嵺丄儀僥儔儞寈姱傪寕偭偰巰朣偝偣傞丅儀僥儔儞寈姱傪曠偭偰偄偨怴暷寈姱偼昁巰偺憑嵏偱庤偑偐傝傪尒偮偗丄斊恖傪捛偄媗傔傞丅寈嶡偺抧摴側憑嵏偲寈姱偨偪偺桭忣丄柍婳摴側晄椙惵擭偺惗懺偑岎屳偵僥儞億傛偔昤偐傟傞丅慜擭偵嶌傜傟偨僕儏乕儖僗丒僟僢僔儞偺乽棁偺挰乿偵塭嬁傪庴偗偰偄傞偙偲偼柧傜偐偩丅弌墘偟偰偄傞偺偼傎傏柍柤偺攐桪偽偐傝偩偑丄斊恖偵偼僨價儏乕偟偰娫傕側偄庒偒僟乕僋丒儃僈乕僪偑暞偟偰偄傞丅
2023擭4寧朸擔 旛朰榐234丂塸崙偺僗儕儔乕仌僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺1
1958塸丂J丒儕乕丒僩儞僾僜儞丂昡揰亂B亃
塸岅帤枊偱娪徿丅戞2師戝愴拞偺傾僼儕僇愴慄丅塸孯拞堁偺僕儑儞丒儈儖僘偼憘挿偲偲傕偵栰愴昦堾幵偱2恖偺廬孯娕岇晈傪慜慄偺僩僽儖僋偐傜屻曽偺傾儗僉僒儞僪儕傾傑偱憲傝撏偗傞擟柋傪堷偒庴偗傞丅娕岇晈偺傂偲傝偑僔儖償傿傾丒僔儉僘丅儈儖僘偼傾儖拞偱丄惛恄偑晄埨掕偲偄偆愝掕丅斵傜偼抧棆尨傪墶抐偟偨傝丄僪僀僣孯偺捛寕傪庴偗偨傝丄夦偟偘側撿傾孯彨峑傾儞僜僯乕丒僋僃僀儖傪廍偭偨傝偟側偑傜丄擬嵒偺嵒敊傪幵偱憱傝栚揑抧傪栚巜偡丅嫤椡偟偰嬯擄傪忔傝墇偊傞斵傜偺偁偄偩偵偼桭忣偑夎惗偊傞丒丒丒丅側偐側偐傛偔弌棃偨椙幙偺塮夋偩丅偙傟偼愴憟塮夋偩偑岎愴僔乕儞偼偁傑傝側偔丄嵒敊偲偄偆壵崜側帺慠偲偺愴偄傗恖娫摨巑偺怱偺岎棳傗偑昤偐傟偍傝丄偦偺揰偱偼朻尟塮夋偵嬤偄丅弌墘幰偺側偐偱偼抝偨偪偵岎偠偭偰暠摤偡傞暷崙偺僕儍僘壧庤偲摨惄摨柤偺僔儖償傿傾丒僔儉僘偑偄偄丅偦傟傎偳桳柤側彈桪偱偼側偄偑丄崟栚偑偪偺弮杙側婄棫偪偑岲報徾傪梌偊傞丅搑拞偱憳嬾偡傞僪僀僣孯偺彨峑偑偙偲偝傜埆栶偱偼側偔晛捠偺孯恖偲偟偰昤偐傟偰偄傞偺傕岲傑偟偄丅戣柤偺乽Ice Cold in Alex乿偼偳偆偄偆堄枴偐暘偐傜側偐偭偨偑丄塮夋傪尒偰撲偑夝偗偨丅偙傟偼乽Ice Cold (Lager) in Alex(andria)乿偺棯偱偁傝丄儈儖僘偑椃偺搑拞偱乽傾儗僋僒儞僪儕傾偵偨偳傝拝偗偨傜椻偊偨價乕儖傪傒傫側偵偍偛傞乿偲尵偆壢敀偵偪側傫偩尵梩偩丅
The Criminal 乮僐儞僋儕乕僩丒僕儍儞僌儖乯
1960塸丂僕儑僙僼丒儘乕僕乕丂昡揰亂B亃
塸岅帤枊偱娪徿丅崅峑惗偺偙傠偵塮夋娰偱尒偰丄嬝偼朰傟偰偟傑偭偨偑嫮偔婰壇偵崗傒崬傑傟偰偄偨丄僗僞儞儕乕丒儀僀僇乕庡墘偺斊嵾塮夋丅娔撀偺儘乕僕乕偼偙偺偁偲儀僀僇乕偲慻傫偱僱僆丒僲儚乕儖偺寙嶌乽僄償傽偺擋偄乿傪嶣傞丅偙傟偼嫞攏応偐傜嫮扗偟偨攧忋嬥傪傔偖傞拠娫摨巑偺憟偄傪昤偄偨塮夋偱丄敿暘偼儀僀僇乕偑擖崠偡傞孻柋強偺応柺偵妱偐傟偰偄傞丅朻摢丄孻柋強偐傜弌強偟偨儀僀僇乕偼丄堦枴偲偲傕偵嬥傪嫮扗偟偨偁偲丄幪偰偨忣晈偵枾崘偝傟偰嵞傃孻柋強偵擖傞丅嬥偺偁傝偐偼儀僀僇乕偟偐抦傜側偄偺偱丄拠娫偼斵傪扙崠偝偣偰塀偟応強傪暦偒弌偦偆偲偡傞丒丒丒丅僗僞儞儕乕丒儀僀僇乕偺晄揋側柺峔偊偲慡懱偵昚偆姦乆偲偟偨旕忣側暤埻婥偑報徾偵巆傞丅孻柋強偺撪晹傗搤偺儘儞僪儞傪嶣傞儘僶乕僩丒僋儔僗僇乕偺僇儊儔偑偄偄丅愥偵暍傢傟偨栰尨傪儘儞僌偱嶣塭偟偨僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞偑朰傟偑偨偄丅壒妝偼僕儑儞丒僟儞僋儚乕僗偺儌僟儞丒僕儍僘丅悘強偱棳傟傞僟儞僋儚乕僗晇恖僋儗僆丒儗乕儞偑壧偆僼僅乕僋僜儞僌晽偺嬋乽Thieving Boy乿偑帹偵從偒晅偔丅
2023擭3寧
2023擭3寧朸擔 旛朰榐233丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺8丗懕乆儀儖僀儅儞
1973悙丂僀儞僌儅乕儖丒儀儖僀儅儞丂昡揰亂D亃
忋棳奒媺偺3巓枀偲彚巊偄偺彈拞偺4恖偑庡側搊応恖暔丅昦偵傛傝巰偺彴偵偮偔師彈丄斵彈傪娕庢傞偨傔偵幚壠偺娰傪朘傟傞挿彈偲3彈丄傗偑偰師彈偼巰偵丄挿彈偲3彈偼壠傪惍棟偟偰婣楬偵廇偔丅僇儊儔偼傎偲傫偳廔巒丄壠偺側偐偐傜奜偵弌側偄丅朻摢偲夞憐僔乕儞偱塮偟弌偝傟傞廐偺擔偑嵎偟崬傓怷偺晽宨偼奊夋偺傛偆偵旤偟偄丅壠偺側偐偼暻傕彴傕僇乕僥儞傕偡傋偰愒堦怓丄偦偙偵慜敿偼敀堖丄屻敿偼崟堖偺彈偨偪偑摦偒夞傞丅帪寁傗壠嬶傗恖宍偑堄枴偁傝偘偵塮偟弌偝傟傞丅恌嶡偵棃偨堛幰偲娭學傪寢傏偆偲偡傞3彈丄妱傟偨僈儔僗偱堿晹傪彎偮偗丄儀僢僪偱懸偮晇偺慜偱堿晹偺寣傪岥偺廃傝偵側偡傝偮偗傞挿彈丄帺傜偺暊傪僫僀僼偱巋偡3彈偺晇丄棁偱揧偄怮偟偰師彈傪娕昦偡傞彈拞丄巰傫偱偄傞偺偵尵梩傪敪偟偰巓枀傪屇傇師彈側偳丄栿偺暘偐傜側偄僔乕僋僄儞僗偑懕偔丅垽偺抐愨傪昤偄偨偺偱偁傠偆偑丄儂儔乕塮夋偺傛偆側妸宮偝傪姶偠傞塮夋偩丅僼儕乕僪僉儞偺乽僄僋僜僔僗僩乿偼偙偺塮夋偵塭嬁傪庴偗偨偲偄偆丅3巓枀傪墘偠傞僀儞僌儕僢僪丒僠儏乕儕儞丄僴儕僄僢僩丒傾儞僨儖僙儞丄儕償丒僂儖儅儞偼丄偦傟偧傟偑偳偙偐偺帪婜偵娔撀儀儖僀儅儞偺垽恖偩偭偨偲偄偆偐傜嫲傟擖傞丅
廐偺僜僫僞
1978悙丂僀儞僌儅乕儖丒儀儖僀儅儞丂昡揰亂D亃
戣柤偑忴偡僀儊乕僕偲偼棤暊偵丄恊巕偺抐愨傪昤偄偨憇愨側僪儔儅丅僀儞僌儕僢僪丒僶乕僌儅儞偲儕償丒僂儖儅儞偑曣偲柡傪墘偠傞丅僶乕僌儅儞偵偲偭偰丄偙傟偑堚嶌偵側偭偨丅柡偺僂儖儅儞偼曣恊僶乕僌儅儞傪帺戭偵彽偔丅僶乕僌儅儞偼偄傑傕昿斏偵岞墘椃峴偡傞挊柤側僺傾僯僗僩丅僂儖儅儞偺晇偼怱桪偟偄壏岤側杚巘丄斵彈偼忈奞幰偺枀傪堷偒庢偭偰柺搢傪尒偰偄傞丅曣偲柡偑夛偆偺偼7擭傇傝丅柡偼傗偭偰棃偨曣恊傪娊懸偡傞偑丄偦偺栭丄曣恊偲夛榖偟偰偄傞偆偪偵丄巕嫙偺偙傠傪巚偄弌偟丄曣偑偄偐偵壠掚傪側偄偑偟傠偵偟偰偄偨偐丄恎彑庤側帺暘杮埵偺怳傞傑偄偵傛偭偰偄偐偵怱偵彎傪晧偭偨偐傪岅傝丄暜滎傪傇偪傑偗傞丒丒丒丅乽嫨傃偲偝偝傗偒乿偲摨偠偔丄偙偺塮夋傕朻摢偲嵟屻偲夞憐僔乕儞傪彍偗偽丄僇儊儔偼傎偲傫偳揷幧偺杚巘娰偺側偐偩偗偵尷掕偝傟偰偄傞丅搊応恖暔偼4恖偩偗丄婄偺僋儘乕僗傾僢僾偑懡梡偝傟丄壢敀偑傗偨傜偵懡偔丄偦偺偨傔偄偮傕埲忋偵晳戜寑偺傛偆側報徾傪庴偗傞丅偊傫偊傫偲懕偔曣偲柡偺攍傝崌偄偑偡偛偄丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐232丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺7丗懕儀儖僀儅儞
1957悙丂僀儞僌儅乕儖丒儀儖僀儅儞丂昡揰亂B亃
儀儖僀儅儞偺塮夋偺側偐偱傕傕偭偲傕娤擮揑丄宍帶忋揑側嶌昳偺傂偲偮丅庡墘偼儅僢僋僗丒僼僅儞丒僔僪乕丅帪偼拞悽丄廫帤孯偺墦惇偐傜婣娨偟偨婻巑偲廬幰偑攏偵忔偭偰帺戭偺忛傪栚巜偡丅婻巑偺慜偵巰恄偑尰傟傞偑丄巰恄偼婻巑偐傜僠僃僗偺彑晧傪挧傑傟丄摨堄偡傞丅椃偺搑拞偱丄斵傜偼崟巰昦偺枲墑偵偍偺偺偔懞恖偨偪丄斊嵾幰偵惉傝壓偑偭偨杚巘丄杺彈偲偟偰壩偁傇傝偵偝傟傞彈丄帺傜傪曏懪偮嫸怣揑側廆搆偺堦抍側偳傪栚寕偡傞丅婻巑偼壠懓傪幐偭偨彈傗嵢偑嬱偗棊偪偟偨抌栬壆傗椃寍恖偺堦嵗側偳傪堷偒楢傟偰椃傪懕偗傞丅婻巑偼壗搙偐峴傢傟偨巰恄偲偺僠僃僗偺彑晧偵晧偗傞丅椃寍恖偼巰恄傪尒偰摝朣偡傞丅堦峴偲偲傕偵忛偵婣偭偨婻巑偺慜偵丄嵢偲嵞夛偟偨偺傕偮偐偺娫丄巰恄偑巔傪尰偡丒丒丒丅奀曈偱栚妎傔偨婻巑偺慜偵巰恄偑尰傟丄攇偑懪偪婑偣傞堥偱擇恖偑僠僃僗傪巒傔傞朻摢嬤偔偺僔乕儞偲丄媢偺忋偱巰恄傪愭摢偵傒傫側偑庤傪偮側偄偱梮傝側偑傜嬱偗偰偄偔偺傪挻儘儞僌偱嶣偭偨嵟屻偺僔乕儞偑報徾偵巆傞丅偙傟偼堦庬偺廔枛榑傪庢傝忋偘偨塮夋偱偁傠偆偐丅惗偑枮偪偁傆傟偰偄傞偺偼愒傫朧傪楢傟偨椃寍恖晇晈偺廃埻偩偗偱丄偦傟埲奜偼偡傋偰巰偺僀儊乕僕偵曪傑傟偰偄傞丅
張彈偺愹
1960悙丂僀儞僌儅乕儖丒儀儖僀儅儞丂昡揰亂B亃
偼傞偐愄丄梞夋傪尒巒傔偨偙傠丄偙偺塮夋偼乽斊偝傟偨彮彈偺巰懱偐傜愹偑桸偒弌傞丄栿偺暘偐傜側偄嶌昳乿偲偟偰幆幰偺偁偄偩偱榖戣偵側偭偰偄偨丅偙傟傕庡墘偼儅僢僋僗丒僼僅儞丒僔僪乕丅拞悽僗僂僃乕僨儞偺嶳墱丄宧錳側擾晇晇嵢偺柡偑嫵夛偵儘僂僜僋傪曺偘偵偄偔搑拞丄昻偟偄梤帞偄偺3恖孼掜偵朶峴偝傟嶦偝傟傞丅3孼掜偼偦傟偲偟傜偢偵擾晇偺壠傪朘傟偰廻傪岊偆丅斵傜偑柡偐傜攳偓庢偭偨堖暈傪攧傝偮偗傛偆偲偟偨偙偲偱柡偺堎曄傪抦偭偨擾晇偼暅廞偺偨傔恎傪惔傔偰3恖傪嶦偡丅柡偺巰懱傪尒偮偗偨擾晇偼恄偺捑栙傪庺偆丅巰懱傪書偒忋偘傞偲偦偺壓偐傜愹偑偙傫偙傫偲桸偒弌傞丒丒丒丅弮恀柍岰側彮彈偑椝怞偝傟傞僔乕儞偼丄岞奐摉帪偲偟偰偼僔儑僢僉儞僌偩偭偨偱偁傠偆丅嶳偺拞偱偺朶峴僔乕儞偼乽梾惗栧乿傪憐婲偝偣傞丅偙傟偼怣嬄偲恄偺捑栙傑偨偼恄偺晄嵼傪僥乕儅偵偟偨塮夋側偺偱偁傠偆偑丄愹偑壗傪堄枴偡傞偺偐偼棟夝偟偑偨偄丅偟偐偟丄帺慠岝偲帺慠壒偩偗偱嵶晹偵傢偨偭偰偨傫偨傫偲塮偟弌偝傟傞擾晇堦壠偺惗妶偺昤幨偵偼怱庝偐傟傞偟丄屛偺娸曈傗嶳偺椗慄傪攏偵忔偭偰峴偔彮彈偺岝宨偼塮憸偲偟偰偙傛側偔旤偟偄丅塮憸偐傜曻偨傟傞敆恀惈偵偼僽儗僢僜儞偲摨幙側傕偺傪姶偠傞丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐231丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺6丗儕僠儍乕僪僜儞
1961塸丂僩僯乕丒儕僠儍乕僪僜儞丂昡揰亂B亃
儘儞僪儞峹奜偺掙曈憌偱曢傜偡彮彈偺惗妶傪儕傾儖偵昤偄偨塸崙僯儏乕丒僔僱儅偺堦嶌丅庡墘偺儕僞丒僩僁僔儞僴儉傪弶傔偰尒偨偺偼乽僪僋僩儖丒僕僶僑乿偩偭偨偑丄摿堎側晽杄偱婰壇偵巆偭偨丅僩僁僔儞僴儉偼抝偵傕壠帠偵傕偩傜偟側偄曣恊偲擇恖曢傜偟偺彈巕崅惗丅斵彈偼崟恖慏堳偲恊偟偔側傝丄垽傪岎傢偡偑丄慏堳偼慏偱弌峘偡傞丅曣恊偼庒偄抝偑偱偒偰壠傪弌傞丅孋壆偱摥偒巒傔傞偨斵彈偼僎僀偺惵擭偲抦傝崌偄丄嫟摨惗妶傪偡傞傛偆偵側傞丅怱桪偟偄斵偼擠怭偟偨斵彈傪悽榖偟丄椼傑偡偑丄偦偙偵抝偵幪偰傜傟偨曣恊偑婣偭偰偒偰斵傪捛偄弌偡丅挰偑寲殑偵曪傑傟傞僈僀丒僼僅乕僋僗偺栭丄惵擭偼惷偐偵壠傪嫀傞丒丒丒丅僎僀偺惵擭傪墘偠傞偺偼儅儕乕丒儊儖償傿儞丅60擭戙偺塸崙塮夋偱傛偔庛乆偟偄撪岦揑側抝傪墘偠偰偄偨撈摿偺婄棫偪偺攐桪偩丅偙偺塮夋偱偼丄偳偪傜傕屒撈側怱傪帩偮僩僁僔儞僴儉偲儊儖償傿儞偺偁偄偩偵丄彊乆偵垽偑夎惗偊傞夁掱偑忋庤偔昤偐傟偰偄傞丅傑偨丄曣偲柡偼偄偮傕偄偑傒崌偭偰偄傞偑丄擇恖偺偁偄偩偵偼偳偆偟傛偆傕側偄擏恊垽偑奯娫尒偊傞丅偦傟傪偙偺塮夋偼岻傒偵昞尰偟偰偄傞丅帺懧棊側曣恊傪墘偠傞僪儔丒僽儔僀傾儞傕抝偵擖傟偁偘偰偼怳傜傟傞拞擭彈偺斶垼傪姶偠偝偣偰愨昳丅偆傜庘傟偨塣壨偺岝宨傗丄昻柉奨偱梀傃夞傞巕嫙偨偪偺忣宨偑朰傟偑偨偄丅
儔償僪丒儚儞
1965暷丂僩僯乕丒儕僠儍乕僪僜儞丂昡揰亂B亃
塸崙僯儏乕丒僔僱儅偺婻庤儕僠儍乕僪僜儞偑暷崙偵彽偐傟偰嶣偭偨丄暷崙偺嬥栕偗庡媊傪捝楏偵潏潐偡傞僽儔僢僋丒僐儊僨傿丅僀乕償儕儞丒僂僅乕偺彫愢乽殤偒偺楈墍乿偺塮夋壔丅塸崙偐傜僴儕僂僢僪偵傗偭偰棃偨攧傟側偄帊恖偼丄夋壠偺攲晝偑塮夋夛幮傪僋價偵側偭偰帺嶦偟偨偺傪宊婡偵丄憭媀夛幮偑宱塩偡傞楈墍偱摥偒巒傔傞丅塮夋偱偼僄儞僶乕儈儞僌張棟偵傛偭偰巰幰傪彜昳偲偟偰埖偆楈墍偺巇帠偑僌儘僥僗僋偵昤偐傟傞丅僇儖僩嫵夛偺怣幰偺傛偆偵宱塩庡傪悞傔傞廬嬈堳偨偪丄巰幰偵彜昳偲偟偰儊僀僋傪巤偡壔徬巘丄嫸偭偨傛偆偵寋擏傪杍挘傞懢偭偨攌偝傫丄寶愝嬛巭嬫堟偵寶偮寶暔偱惗妶偡傞彈惈丄儘働僢僩偵柌拞偺揤嵥彮擭丄娀偐傜弌偰偔傞僐乕儖僈乕儖側偳丄傾僽僲乕儅儖偱婏夦側僽儔僢僋丒儐乕儌傾偑師乆偵塮偟弌偝傟傞丅庡墘偺儘僶乕僩丒儌乕僗偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偑丄僕儑儞丒僊乕儖僌僢僪丄僕僃乕儉僗丒僐僶乕儞丄僟僫丒傾儞僪儕儏乕僗丄儈儖僩儞丒僶乕儖側偳偺払幰側栶幰偑榚傪屌傔傞丅側偐偱傕儅僓僐儞偺巰懱壔徬巘傪墘偠傞儘僢僪丒僗僞僀僈乕偼僴僠儍儊僠儍偺夦墘丅僐儅乕僔儍儕僘儉偵巟攝偝傟偨尰戙暥柧傊偺撆偺偁傞晽巋偲偄偆揰偱僉儏乕僽儕僢僋偺乽攷巑偺堎忢側垽忣乿偲廳側傞丅戣柤偺乽The Loved One乿偲偼巰幰偺偙偲傪堄枴偡傞
2023擭3寧朸擔 旛朰榐230丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺5丗暓仌攇
1952暓丂傾儞儕丒償僃儖僰僀儐丂昡揰亂B亃
攏傛傝傕挿偄婄偺抝丄僼儔儞僗偺埳摗梇擵彆偲傕偄偆傋偒婌寑攐桪僼僃儖僫儞僨儖偺庡墘偲偄偆偙偲偱丄戣柤偲傕憡樦偭偰丄偰偭偒傝僐儊僨傿偩偲巚偭偰偄偨偑丄偙傟偼庒偄柡偵東楳偝傟傞拞擭抝偺斶垼傪昤偄偨塮夋丅婥埵偺崅偄嵢偵摢偑忋偑傜側偄恀柺栚側堛巘僼僃儖僫儞僨儖偼丄傆偲偟偨偒偭偐偗偱忣帠傪帩偭偨庒偄柡僼儔儞僜儚乕僘丒傾儖僰乕儖偺偲傝偙偵側傝丄斵彈偲堦弿偵挰傪弌傛偆偲偡傞偲偡傞偑丄斵彈偐傜偦偱偵偝傟丄偡偛偡偛偲壠偵婣傞丅傛偔偁傞榖偩偑丄攏柺偺婌寑攐桪僼僃儖僫儞僨儖偲彫埆杺揑彈桪傾儖僰乕儖偑墘偠偰偄傞偩偗偵丄恀幚枴偲斶垼姶偑偮偺傞丅娔撀偺償僃儖僰僀儐偼偙偺偁偲丄傾儖僰乕儖傪棫偰懕偗偵婲梡偟偰乽夁嫀傪帩偮垽忣乿傗乽僿僢僪儔僀僩乿傪嶣偭偨丅傾儖僰乕儖偼偙傟傜偺塮夋偵傛偭偰桳柤偵側傝丄摉帪偺擔杮偱傕塮夋僼傽儞偺偁偄偩偱愨戝側恖婥傪攷偟偨偲偄偆丅偙偺塮夋偱偺傾儖僰乕儖偼丄抝傪閤偟偰庤嬍偵庢傞埆彈偲偄偆傛傝傕丄抝偑帺慠偵偐偟偢偔揤恀啵枱偱僐働僥傿僢僔儏側彈偱偁傝丄偦偺揰偱偼僽儕僕僢僪丒僶儖僪乕偺愭嬱偗偲尵偊傞丅捠忢丄偙偺庤偺塮夋偱偼丄嵟屻偵抝偑楇棊偟棊偪傇傟壥偰傞偺偩偑丄偙偙偱偼擬偑椻傔偨僼僃儖僫儞僨儖偑壠偵婣傞偲嵢偑懸偭偰偍傝丄晇晈偺傛傝偑栠偭偰僄儞僪偲側傞丅
塭
1956億乕儔儞僪丂僀僃乕僕乕丒僇儚儗儘償傿僢僠丂昡揰亂B亃
偙偺塮夋偼埲慜偵尒偰偄傞偼偢偩偑丄撪梕傪妎偊偰偄側偄偺偱嵞尒偡傞丅億乕儔儞僪偺暋嶨側惌帯幮夛忬嫷傪攚宨偵偟偨儈僗僥儕乕巇棫偰偺嶌昳丅3偮偺憓榖偐傜側偭偰偄傞偑丄偦傟偧傟偺榖偼棈傒崌偭偰偄傞丅朻摢丄婦幵偐傜抝偑旘傃崀傝偰巰朣偡傞丅偦偺屻丄愴帪拞偺懳撈儗僕僗僞儞僗丒僌儖乕僾偑帒嬥挷払偺偨傔忇傪嫮扗偟傛偆偲偟偨揦偱暿偺僌儖乕僾偲摨巑摙偪偡傞榖丄愴屻娫傕側偔偺崰偺惌晎孯暫巑偑斀惌晎僎儕儔偺恊嬍埫嶦偺偨傔愽擖偡傞偡傞榖乮偙偺恊嬍偼庒偄崰偺僾乕僠儞偵偦偭偔傝偩乯丄尰戙偺扽岯敋攋帠審偱柍幚偺庒幰偑斊恖偵巇棫偰忋偘傜傟傞榖偑暔岅傜傟丄戞3榖偺嵟屻偱朻摢偺僔乕儞偵寢傃偮偒丄偙偺3榖偵嫟捠偟偰搊応偡傞偁傞抝偑堿偱偙傟傜偺帠審傪巇慻傫偱偒偨偙偲偑柧傜偐偵側傞丅偙偺塮夋傪棟夝偡傞偨傔偵偼丄廔愴捈屻偺億乕儔儞僪偱偼丄嫟嶻搣惌尃偵斀婙傪東偡柉懓攈偺斀惌晎僌儖乕僾偑僥儘妶摦傪峴偭偰偄偨偙偲傪抦偭偰偄側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偼傾儞僕僃僀丒儚僀僟偺乽奃偲僟僀傾儌儞僪乿偺庡戣偱傕偁偭偨丅儚僀僟偼斀惌晎僥儘儕僗僩傪摨忣揑偵昤偄偰偄偨偑丄僇儚儗儘償傿僢僠偼傑偭偨偔偺埆偲偟偰昤偄偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄偙偙偵偼儚僀僟偺傛偆側僪儔儅僥傿僢僋側忣擮偼朢偟偄偑丄僒僗儁儞僗塮夋偲偟偰偼傛偔弌棃偰偄傞偲尵偊傞
2023擭3寧朸擔 旛朰榐229丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺4丗儀儖僀儅儞
1955悙丂僀儞僌儅乕儖丒儀儖僀儅儞丂昡揰亂D亃
忋棳奒媺偺抝彈偺楒偺偝傗摉偰傪昤偄偨丄僼儔儞僗塮夋傪巚傢偣傞墣徫鏉丅曎岇巑晇晈丄孯恖婱懓晇晈丄晳戜彈桪丄曎岇巑堦壠偺懅巕偲彈拞側偳偑岲偒偩寵偄偩偲嬻憶偓偡傞丅屻敿偺慡堳偑廤偆崑壺側暿憫偱偺堦栭偼丄偍偦傜偔僔僃乕僋僗僺傾偺乽恀壞偺栭偺柌乿傪壓晘偒偵偟偰偄傞偱偁傠偆丅嵟屻偼偡傋偰偑廂傞傋偒偲偙傠偵廂偭偰挬傪寎偊傞丅僐儊僨傿側偺偵徫偊側偄偟丄柺敀偔側偄丅
栰偄偪偛
1957悙丂僀儞僌儅乕儖丒儀儖僀儅儞丂昡揰亂A亃
岟惉傝柤悑偘偨榁嫬偺堛巘偑庡恖岞丅柤梍攷巑崋庼梌幃偺偨傔丄懅巕偺壟偲偲傕偵丄帺戭偺僗僩僢僋儂儖儉偐傜儖儞僪偵幵偱岦偐偆斵偺堦擔傪昤偄偨儘乕僪儉乕償傿乕晽偺嶌昳丅幵偵偼庒偄梲婥側抝彈3恖慻偺僸僢僠僴僀僇乕傗寲壾傪孞傝曉偡晇晈偑摨忔偡傞丅斵傜偼搑拞偱斵偑巕嫙偺崰偵夁偛偟偨暿憫傗斵偺曣恊偑廧傓壠偵棫偪婑傞丅偦傫側椃偺僄僺僜乕僪偺側偐偵丄偲偒偍傝榁恖偑尒傞巰傪梊姶偝偣傞埆柌傗怱傪嫀棃偡傞庒偒擔偺巚偄弌偑憓擖偝傟傞丅嵟屻偵榁恖偼愜傝崌偄偑埆偔側偭偰偄偨懅巕晇晈偲傛傝傪栠偟丄摨忔偟偨庒幰偨偪偐傜廽暉偝傟丄枮偪懌傝偨婥暘偱柊傝偵偮偔丅朻摢偺埆柌偺僔乕儞偼僟儕傗僉儕僐側偳偺僔儏儖儗傾儕僗儉奊夋傪巚傢偣傞丅庡恖岞偺夞憐偼帊揑側僀儊乕僕偵嵤傜傟偰偍傝丄偁傞庬偺怱徾晽宨偲尵偊傞偩傠偆丅乽僂儞儀儖僩D乿偲摨偠偔榁恖偑庡恖岞偩偑丄偙偙偵偼幮夛揑丄宱嵪揑側帇揰偼偄偭偝偄側偄丅偦傟傪偳偆昡壙偡傞偐偼尒傞懁偺峫偊曽偟偩偄偩丅僼僃儕乕僯偼偙偺塮夋偐傜拝憐偟偰乽8 1/2乿傪嶌偭偨丅偦偟偰儀儖僀儅儞偼偙偺塮夋傪嶌傞偵偁偨傝丄崟郪柧偺乽惗偒傞乿偵僸儞僩傪摼偨偲偄偆丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐228丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺3丗懕儘僢僙儕乕僯
1959埳丂儘儀儖僩丒儘僢僙儕乕僯丂昡揰亂B亃
戞2師戝愴枛婜丄杒僀僞儕傾偺僕僃僲償傽丅攷懪岲偒偱彈偨傜偟偺偪傫偗側拞擭嵓媆巘偑挀棷僪僀僣孯偺僎僔儏僞億偵戇曔偝傟丄柍嵾曻柶偡傞戙傢傝偵丄岆偭偰幩嶦偝傟偨儗僕僗僞儞僗偺巜摫幰儘儀儗彨孯偵側傝偡傑偟丄僗僷僀偲偟偰孻柋強偵擖傝僷儖僠僓儞偺儕乕僟乕傪尒偮偗傞傛偆柦椷偝傟傞丅孻柋強偵擖偭偨斵偼丄庴孻幰偨偪偺桬婥傗怣擮傪栚寕偟丄儘儀儗彨孯晇恖偐傜偺垽忣偁傆傟傞庤巻傪撉傒丄垽崙怱偵栚妎傔偰丄僎僔儏僞億偺柦椷偵媡傜偄丄懠偺庴孻幰偨偪偲偲傕偵儘儀儗彨孯偲偟偰廵嶦偝傟傞丅庡墘偼償傿僢僩儕僆丒僨僔乕僇丅幚榖偵婎偯偔塮夋偩偲偄偆偑丄側偐側偐椙偔弌棃偰偄傞丅傗傗忕枱側偲偙傠傕偁傞偑丄偙傟偼乽柍杊旛搒巗乿偲暲傇儘僢僙儕乕僯偺柤嶌偲尵偊傞偩傠偆丅働僠側嵓媆巘偑崠拞偱偟偩偄偵恖娫惈偵栚妎傔偰偄偔條巕偑岻傒偵昤偐傟偰偄傞丅廵嶦捈慜偵婾儘儀儗彨孯偑暻偵巻傪偁偰偰儘儀儗晇恖埗偰偵乽巰傪慜偵巚偆偺偼孨偺偙偲偩丅僀僞儕傾枩嵨乿偲儊僢僙乕僕傪彂偔僔乕儞偑報徾偵巆傞丅
償傽僯僫丒償傽僯僯
1961埳丂儘儀儖僩丒儘僢僙儕乕僯丂昡揰亂C亃
僗僞儞僟乕儖偺抁曇彫愢傪塮夋壔偟偨楌巎楒垽斶寑丅僱僆儕傾儕僗儌偐傜弌敪偟偨儘僢僙儕乕僯偼丄10悢擭傪宱偰偙偺傛偆側暥寍嶌昳傪嶣傞娔撀偵曄梕偟偨丅庡墘偼僒儞僪儔丒儈乕儘丅19悽婭弶摢丄儘乕儅婱懓償傽僯僯壠偺柡償傽僯僫偼晝恊偑摻偭偰偄傞斀懱惂妚柦攈僌儖乕僾偺儕乕僟乕偲弌夛偄丄彎傪晧偭偨斵傪夘書偟偰偄傞偆偪偵楒偵棊偪傞丅偙偆偟偰丄垽偵惗偒傞彈偲妚柦偵忣擬傪擱傗偡抝偺恎暘堘偄偺楒偺揯枛偑偨傫偨傫偲昤偐傟傞丅塮夋偼峣庱戜偵忋傞抝偲廋摴堾偵擖傞彈偑儘儞僌偱嶣傜傟偰僄儞僪偲側傞丅僒儞僪儔丒儈乕儘偼椻偨偄旤偟偝偺側偐偵彈偺怓婥傪姶偠偝偣傞偑丄慡懱偲偟偰怱偵敆傞傕偺偑偁傑傝姶偠傜傟側偄丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐227丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺2丗儘僢僙儕乕僯
1948埳丂儘儀儖僩丒儘僢僙儕乕僯丂昡揰亂C亃
僱僆儕傾儕僗儌偺嫄彔儘僢僙儕乕僯偺愴憟3晹嶌偺嵟廔嶌丅戞2師戝愴捈屻丄攑毿偲壔偟偨儀儖儕儞偱丄傾僷乕僩偱懠偺壠懓偲嫟摨惗妶傪憲傞昻偟偄堦壠偺枛偭巕丄12嵨偺彮擭傪庡恖岞偵偟偨塮夋丅彮擭偼壠寁傪彆偗傞偨傔暔傪攧偭偨傝擭楊傪婾偭偰摥偄偨傝偟偰偄傞丅壠偵偼廳昦偺晝丄桪偟偄巓丄塀傟廧傓尦僫僠搣堳偺孼偑偄傞丅彮擭偼偐偮偰偺彫妛峑偺嫵巘偵嵈偝傟偰昦偵暁偡晝傪撆栻偱嶦偟丄嵟屻偵價儖偐傜旘傃崀傝偰巰偸丅傑偭偨偔媬偄偺側偄榖偩丅尦僫僠傜偟偄晄婥枴側榁恖傗丄揇朹偱惗妶旓傪壱偖彮擭僌儖乕僾偑搊応偡傞丅姠釯偩傜偗偺儀儖儕儞偺奨暲傒偑捝乆偟偄丅僩儕儏僼僅乕偺乽戝恖偼傢偐偭偰偔傟側偄乿偼偙偺塮夋偵塭嬁傪庴偗偨偲尵傢傟偰偄傞偑丄彮擭偺昤偒曽偐傜偟偰丄側傞傎偳偲巚傢偣傞丅
儓乕儘僢僷1951擭
1952埳丂儘儀儖僩丒儘僢僙儕乕僯丂昡揰亂D亃
婏柇側塮夋偩丅僀儞僌儕僢僪丒僶乕僌儅儞庡墘丄尰戙儓乕儘僢僷偵惗偒傞彈惈偺嬯擸傪昤偄偨塮夋丅晇偲懅巕傪帩偮忋棳奒媺偺彈惈僶乕僌儅儞偼丄曣恊偵峔偭偰傕傜偊側偄偺傪嬯偵懅巕偑帺嶦偟偰愨朷偡傞丅斵彈偼嵍梼巚憐偵姶壔偝傟丄壠弌偟偰岺応偱偼摥偒巒傔丄昻偟偄恖乆偲偲傕偵惗妶偟傛偆偲偡傞偡傞偑丄斊嵾幰傪摝偑偟偨偨傔惛恄昦堾偵擖傟傜傟傞丅幮夛偺恖乆偼扤傕斵彈偺峴摦傪棟夝偟傛偆偲偟側偄丅斵彈偼壠偵婣傞偺傪嫅傒丄惛恄昦姵幰傊偺垽偵栚妎傔丄斵傜偲偲傕偵惗偒傛偆偲寛堄偡傞丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡恖岞偺彈惈偼僉儕僗僩偵側偧傜偊傜傟偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅40擭戙屻敿偺僱僆儕傾儕僗儉偲偼傑偭偨偔偐偗棧傟偨嬽榖揑側嶌昳偩丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐226丂墲擭偺墷廈柤夋丄棊偪曚廍偄丂偦偺1丗僀僞儕傾塮夋
1952埳丂償傿僢僩儕僆丒僨丒僔乕僇丂昡揰亂C亃
僨僔乕僇偺僱僆儗傾儕僗儌偺摓払揰偲傕尵偆傋偒丄榁恖偑嫮偄傜傟傞尩偟偄尰幚傪椻揙偵昤偄偨塮夋丅愴屻偺僀儞僼儗偵尒晳傢傟晄嫷偵偁偊偖僀僞儕傾幮夛偑昤偐傟傞偑丄崅楊壔幮夛偺尰戙傪愭庢傝偟偰偄傞偲傕尵偊傞丅帞偄將偩偗傪桭偲偡傞堷戅偟偨榁擭偺岞柋堳偑壠捓枹擺偺偨傔晹壆偐傜捛偄弌偝傟傞丅擭嬥堷偒忋偘傪媮傔傞榁恖偨偪偺奨摢僨儌偑寈嶡偵傛偭偰廟嶶傜偝傟傞朻摢偺僔乕儞偐傜丄壠傪弌偨峴偔摉偰偺側偄榁恖偲將偑岞墍偱梀傇僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞傑偱丄壗偲傕傗傝偒傟側偄榖偑懕偔丅庡墘偺榁恖偼慺恖偱丄戝妛偺尵岅妛嫵庼偩偲偄偆丅
姄傪帩偭偨彈
1961埳丂償傽儗儕僆丒僘儖儕乕僯丂昡揰亂B亃
擭忋偺彈偲崅峑惗偺彮擭偺弌夛偄偲暿傟傪昤偔楒垽塮夋丅僉儍僶儗乕丒僶儞僪偺壧庤偱抝偵閤偝傟傗偡偄揤恀啵枱側彈偵僋儔僂僨傿傾丒僇儖僨傿僫乕儗丄傆偲偟偨偒偭偐偗偱斵彈偲抦傝崌偄丄楒怱傪書偔曣偺偄側偄嬥帩偪偺壠偺恀柺栚側彮擭偵僕儍僢僋丒儁儔儞偑暞偡傞丅偙偺塮夋偱偺僇儖僨傿僫乕儗偼偠偮偵旤偟偔丄帩偪枴傪偄偐傫側偔敪婗偟偰偄傞丅怺栭丄墂偐傜弌偰棃偨僇儖僨傿僫乕儗偑堦恖偱埫偄曕摴傪曕偒嫀傞僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞偑朰傟偑偨偄丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐225丂彈偺惗偒偞傑傪昤偔媑懞岞嶰榊偺塮夋
1956戝塮丂媑懞岞嶰榊丂昡揰亂A亃
嶳杮晉巑巕庡墘丄嫗愼偺悽奅傪戣嵽偲偟偰丄愼暔偵忣擬傪擱傗偡彈偺巇帠偲楒偺惉傝峴偒傪昤偄偨塮夋丅媑懞岞嶰榊娔撀偺嫗搒傪晳戜偵偟偨塮夋偵偼嫗儅僠巕庡墘偺乽婾傟傞惙憰乿偲偄偆寙嶌偑偁偭偨偑丄偙傟傕偦傟偵楎傜偸桪傟偨嶌昳偩丅惉岟嶌偨傝偊偨梫場偺懡偔偼媨愳堦晇偺嶣塭偵婣偡傞偲巚偆丅晝偑宱塩偡傞嫗搒偺榁曑愼暔壆偱嶌昳嶌傝偵椼傓柡丄嶳杮晉巑巕偼丄巃怴側愼暔傪奐戱偟偰昡敾傪屇傃丄斕楬傪峀偘傛偆偲偟偰偄傞嵟拞丄嶃戝嫵庼偱昦偵暁偡嵢偲柡偑偄傞忋尨尓偲抦傝崌偆丅擇恖偼壗搙偐婄傪崌傢偣傞偆偪偵偍屳偄偵庝偐傟崌偄丄娭學傪寢傇偑丄嵢偵娭偡傞斵偺尵摦偵抝偺恎彑庤偝傪姶偠偨嶳杮偼丄嵢偑昦巰偟偨偁偲丄斵偺寢崶怽偟崬傒傪嫅傒丄愼暔傂偲偡偠偵惗偒傛偆偲偡傞丅榖偺棳傟偼摨偠娔撀偺尨愡巕丄嵅暘棙怣庡墘乽桿榝乿傪憐婲偝偣傞丅乽桿榝乿偱偼抝偺嵢偺巰屻丄擇恖偼寢偽傟傞偑丄乽栭偺壨乿偱偼彈偑抝傪怳傞丅偙偺塮夋偺嵟戝偺枺椡偼媨愳堦晇偺嶣塭偲怓嵤偵偁傞丅橂嵴偱嶣傜傟偨屆偄奨暲傒傗帥堾偺岝宨偼丄峔恾偑尒帠偱丄偠偮偵旤偟偄丅怘摪幵偺憢偵幨傞嶳杮偺巔傕朰傟偑偨偄丅擇恖偑塉廻傝偺偨傔擖偭偨椃娰偱偺忣帠偺僔乕儞偱塮偝傟傞丄埫偄晹壆偵嵎偟崬傓愒偄梉擔偼丄偲傝傢偗報徾偵巆傞丅愼暔丄壴丄岝丄儊乕僨乕偺婙丄悘強偱巊傢傟傞愒偄怓偑慛楏偩丅攳偄偨備偱棏偺傛偆側婄棫偪偺嶳杮晉巑巕偼丄偙偺偙傠旤偟偝偺愨捀偩傠偆偐丄傑偝偵戝椫偺壴偺傛偆偩丅忋尨尓偼憡曄傢傜偢桪偟偄偑桪廮晄抐側抝傪墘偠偰岻偄丅嶳杮偺婃屌側晝恊傪搶栰塸帯榊丄偄偮傕側偑傜岲怓偱嗦尗偄愼暔彜偺恊晝傪彫戲塰懢榊偑墘偠傞丅朻摢偲僄儞僨傿儞僌偱塮偝傟傞儊乕僨乕偺僨儌峴恑偑幮夛揑側嵤傝傪揧偊傞丅桞堦偺嚓圊偼愳嶈宧嶰暞偡傞嶳杮傪曠偆庒偄夋壠偵傑偮傢傞僔乕僋僄儞僗偱偁傝丄偙傟偼梋寁側憓榖偱偁傠偆丅
栭偺挶
1957戝塮丂媑懞岞嶰榊丂昡揰亂C亃
偙傟偼嫗儅僠巕偲嶳杮晉巑巕庡墘偵傛傞丄嬧嵗偺僋儔僽傪晳戜偵丄彈偳偆偟偺妋幏偲憟偄傪昤偄偨塮夋丅桳柤恖偑捠偆嬧嵗偺堦棳僋儔僽偺傗傝庤儅僟儉丄嫗儅僠巕偼丄嫗搒偺寍媁忋偑傝偺恖婥儅僟儉丄嶳杮晉巑巕偑嬧嵗偵忔傝崬傒丄揦傪奐偔偙偲偵側偭偨偺偱丄揋溈怱傪曞傜偣傞丅斵彈偨偪偺娫偵偼偐偮偰抝傪弰傞妋幏偑偁偭偨丅嶳杮偺怴揦偵媞傪庢傜傟巒傔傞偲丄嫗偼嶳杮偺僷僩儘儞偱偁傞娭惣偺僨僷乕僩偺幮挿丄嶳懞汔傪偨傜偟崬傓丅恎傕怱傕曺偘偨堛妛惗丄奌愳斾楥巙偵怳傜傟丄僷僩儘儞傕庢傜傟偨嶳杮偼丄媡忋偟偰丄悓偭偨惃偄偱壏愹偵岦偐偆嫗偲嶳懞偑忔傞幵傪丄帺暘偺幵傪塣揮偟偰捛偄偐偗傞丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅嵙愜偟偨壒妝壠偱偄偮傕娛僺乕僗傪帩偪曕偔彈媼埓慁嬈幰偺慏墇塸擇偑嫸尵夞偟傪柋傔傞丅戝塮2戝彈桪偺嫞墘偼敆椡廫暘丄嫗儅僠巕偼偝偡偑偵払幰側墘媄偩偟丄嶳杮晉巑巕傕岻偄丅搟傝傪擱偊偨偨偣偨嶳杮偑尒偣傞婼偺傛偆側宍憡偑朰傟偑偨偄丅尨嶌偼丄偦偺偙傠嬧嵗偵幚嵼偟偰攅傪嫞偭偰偄偨僋儔僽偲儅僟儉傪儌僨儖偲偟偰愳岥徏懢榊偑彂偄偨彫愢偱偁傝丄嶳懞偑墘偠傞娭惣偺僨僷乕僩偺幮挿偼敀廎師榊偑儌僨儖偩偲偄偆丅嶣塭偺媨愳堦晇偼丄搶嫗偺娊妝奨偑晳戜側偺偱丄偄傑偄偪椡傪敪婗偟愗傟偰偄側偄偑丄偦傟偱傕奌愳斾楥巙偑嶳杮晉巑巕偵暿傟傪崘偘傞僔乕儞偺丄儘儞僌偱嶣傜傟偨丄憢墇偟偵晹壆傪塮偡僔儑僢僩側偳偼丄懅傪撣傓傎偳慛傗偐偩丅偙偺塮夋丄柺敀偄偙偲偼偨偟偐偩偑丄偨偲偊偽摨偠嬧嵗偺僋儔僽傪戣嵽偵偟偨惉悾偺乽彈偑奒抜傪忋傞偲偒乿偺傛偆側墱怺偝偼姶偠傜傟側偄丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐224丂壀揷帪旻偑弌墘偡傞彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丂偦偺2
1931徏抾乮僒僀儗儞僩乯丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂B亃
僐儈僇儖側僫儞僙儞僗婌寑丅壀揷帪旻偺婌寑栶幰偲偟偰偺岻偝偑帵偝傟偰偄傞丅旹傕偠傖偱寱摴偵廏偱偨僶儞僇儔妛惗偺壀揷偼丄帪戙嶖岆側尵摦偱彈偨偪偐傜椟鏓傪攦偭偰偄傞丅廇怑偺偨傔闄傪掍傞偲旤抝巕偵側傝丄梌懢幰偵棈傑傟偰偄傞偺傪彆偗偨僞僀僺僗僩偺柡丄抝庉壠偺桭恖偺枀丄晄椙偺儌僟儞僈乕儖偲偄偆3恖偺彈偵崨傟傜傟傞偑丄寢嬊僞僀僺僗僩偺柡偲寢偽傟傞丅偙偺柡偵暞偡傞偺偑愳嶈峅巕丄揷拞對戙偵帡偨榓晽旤恖偱丄偺偪偵暉揷棖摱偲寢崶偟偨丅傎偐偵斞揷挶巕丄媑愳枮巕丄嶁杮晲丄惸摗払梇側偳丄彫捗慻偺忢楢偑婄傪懙偊偰偄傞丅壀揷偑桭恖偺枀偺抋惗夛偱寱晳傪梮傞僔乕儞偼寙嶌丅壀揷偺墭偄晹壆偺暻偵揬偭偰偁傞梞夋偺億僗僞乕偑栚傪堷偔丅偙偺塮夋偵傕暷崙塮夋晽偺儌僟儞側枴傢偄偑墶堨偟偰偄傞丅
搶嫗偺崌彞
1931徏抾乮僒僀儗儞僩乯丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂B亃
昻崲偲廇怑擄傪攚宨偲偡傞壠懓僪儔儅偱丄傑偨偄偮傕偲摨偠僥乕儅偐丄偲偄偝偝偐鐒堈偡傞偑丄儐乕儌傾偲壠懓垽偑傑傇偟偰偁傞偺偱柺敀偔尒傞偙偲偑偱偒傞丅乽偦偺栭偺嵢乿偲摨偠偔壀揷帪旻偲敧塤宐旤巕偑晇晈傪墘偠傞丅拞妛惗偺壀揷偑峑掚偱懱堢嫵巘乮惸摗払梇乯偵偟偛偐傟傞僔乕僋僄儞僗偱巒傑傝丄堦揮偟偰嵢偲3恖偺巕傪帩偮僒儔儕乕儅儞偵側偭偨尰戙偺壀揷偺惗妶偵堏峴偡傞丅壀揷偼屆嶲幮堳乮嶁杮晲乯偑棟晄恠偵戅怑偝偣傜傟偨偺傪幮挿偵峈媍偟偰夝屬偝傟傞丅斵偼廇怑岥偑尒偮偐傜偢擸傫偱偄傞偲偒偵偐偮偰偺懱堢嫵巘偲嵞夛偟丄廇怑傪悽榖偟偰傗傞偙偲偺尒曉傝偵丄懱堢嫵巘偑巒傔偨梞怘壆偺愰揱偺偨傔偵價儔攝傝傪庤揱偆偼傔偵側傞丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅壀揷帪旻偼岲墘偟偰偄傞偑丄怱側偟偐憠偣偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅敧塤宐旤巕偑墘偠傞怱桪偟偄偟偭偐傝幰偺嵢傕尒帠丅彫妛惗偺挿抝偑帺揮幵傪攦偭偰偔傟側偄晝恊偵斀峈偡傞僄僺僜乕僪偼丄梻擭偺彫捗偺乽惗傟偰偼傒偨偗傟偳乿傗愴屻偺乽偍憗傛偆乿傪憐婲偝偣傞丅惔悈岹偩偗偱側偔丄彫捗傕巕嫙偺昤偒曽偑岻偐偭偨丅偙偺挿抝傕偦偺枀傕尵摦偵偼傢偞偲傜偟偝偑側偔丄惗偒惗偒偟偰偄傞丅枀偼丄偳偙偐偱尒偨婄偩偲巚偭偰偄偨偑丄偁偲偱崅曯廏巕偩偲暘偐偭偨丅摉帪偺崅曯偼側傫偲7嵨両 傎偐偵斞揷挶巕偑懱堢嫵巘偺嵢傪墘偠傞丅壀揷偺壠偺側偐偺僇儊儔丒儚乕僋偵偼偺偪偵掕拝偟偨彫捗僗僞僀儖偺朑夎偑姶偠傜傟傞丅戣柤偼丄懱堢嫵巘偺揦偺奐揦廽偄偵偐偮偰偺惗搆偨偪偑廤傑傝丄傒傫側偱椌壧傪崌彞偡傞僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞偵桼棃偡傞傕偺偱偁傠偆丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐223丂壀揷帪旻偑弌墘偡傞彫捗埨擇榊偺僒僀儗儞僩塮夋丂偦偺1
1930徏抾乮僒僀儗儞僩乯丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂C亃
偙傟偼壀揷帪旻偱偼側偔惸摗払梇庡墘偺丄懖嬈傪峊偊偨戝妛惗偺惗懺傪昤偄偨僐儊僨傿丅妛惗偨偪偼懖嬈帋尡偱岺晇傪嬅傜偟偰僇儞僯儞僌偟傛偆偲偡傞偑幐攕丅偩偑丄堦恖傪彍偄偰慡堳偑崌奿偡傞丅斵傜偼棊偪崬傓棊戞偟偨妛惗傪堅傔傞偑丄廇怑帋尡偵偙偲偛偲偔幐攕偟丄偙傟側傜棊戞偟偨曽偑椙偐偭偨偲巚偆丅廇怑擄偺幮夛忬嫷傊偺晽巋偑崬傔傜傟偰偄傞丅棊戞偡傞妛惗傪惸摗払梇丄斵傪曠偆儈儖僋儂乕儖偺彈媼傪揷拞對戙偑墘偠傞丅妛惗偺傂偲傝偵妢抭廜偑暞偟偰偄傞偑丄偙傟偼妢偑彫捗偵婲梡偝傟偨嵟弶偺塮夋偩傠偆偐丅
偦偺栭偺嵢
1930徏抾乮僒僀儗儞僩乯丂彫捗埨擇榊丂昡揰亂C亃
斊嵾傪棈傔偨恖忣僪儔儅丅彫捗偑庴偗偨僴儕僂僢僪塮夋偺塭嬁偑尠挊偩丅庡墘偼壀揷帪旻丅僶僞廘偄擇枃栚偱偁傝丄柍惡塮夋帪戙偺嵅揷孾擇偲尵偊傛偆偐丅昻朢側壀揷偼昦婥偵暁偡梒偄柡偺帯椕旓傪岺柺偡傞偨傔対廵嫮搻傪偡傞丅寈姱戉偐傜摝傟偨斵偼婣戭偟偰嵢偲嫟偵柡傪娕昦偡傞丅懌愓傪歬偓偮偗偨孻帠偑偦偺壠傪朘傟丄斵傪戇曔偟傛偆偲偡傞偑丄幚忣傪抦傝丄怮偨傆傝傪偟偰斵傪摝偑偦偆偲偡傞丅偩偑斵偼夵怱偟偰帺傜戇曔偝傟傞丅壀揷偺嵢傪墘偠傞敧塤宐旤巕偼弶傔偰尒傞彈桪偩偑丄側偐側偐婥昳偺偁傞婄棫偪偩丅斵彈偑対廵傪峔偊偰孻帠傪埿奷偡傞僔乕儞偼乽旕忢慄偺彈乿偺揷拞對戙傛傝偝傑偵側偭偰偄傞丅
2023擭3寧朸擔 旛朰榐222丂怱傪懪偮僜楢偺暥寍塮夋
1959僜楢丂儓僔僼丒僿僀僼傿僢僣丂昡揰亂B亃
僠僃乕儂僼偺桳柤側抁曇彫愢偺塮夋壔丅娔撀傕弌墘幰乮僀儎丒僒乕償傿僫丄傾儗僋僙僀丒僶僞乕儘僼乯傕撻愼傒偑側偄偑丄岲姶偺帩偰傞楒垽塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅暔岅偺慜敿偼儘僔傾偺崟奀増娸偺曐梴抧儎儖僞偑晳戜丅悁棷媞偺拞擭偺嬧峴堳偼偄偮傕巕將傪楢傟偰嶶曕偡傞晈恖偲恊偟偔側傞丅儌僗僋儚偐傜棃偨嬧峴堳偵偼嵢巕偑偁傝丄儁僥儖僽儖僋偐傜棃偨晈恖傕庒嵢偩偑丄擇恖偼楒拠偵側傝丄堦栭偺宊傝傪寢傇丅斵傜偼偦傟偧傟偺壠掚偵栠傞偑丄抝偼斵彈偑朰傟傜傟偢丄儁僥儖僽儖僋偵峴偒丄寑応偱斵彈偲夛偆丅斵彈傕斵傪曠偭偰偍傝丄儌僗僋儚偵傗偭偰棃偰斵偲枾夛偟傛偆偲偡傞丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅傛偔偁傞晄椣偺榖偩偑丄傢偞偲傜偟偝偺側偄丄棊偪拝偄偨岅傝岥偱丄忣姶朙偐偵昤偐傟偰偄傞丅慡懱偺棳傟偼僨償傿僢僪丒儕乕儞偺乽埀傃偒乿傪憐婲偝偣傞丅庒嵢偵暞偡傞僀儎丒僒乕償傿僫偼旤恖偲偄偆傛傝梒偝傪偨偨偊偨壜垽偄婄棫偪偱丄岲傑偟偝傪姶偠傞丅愥偑愊傕傞奨楬偱抝偑儂僥儖偺憢曈偐傜庤傪怳傞彈傪尒忋偘傞僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞偑報徾偵巆傞丅
僆僽儘乕儌僼偺惗奤傛傝
1979僜楢丂僯僉乕僞丒儈僴儖僐僼丂昡揰亂C亃
19悽婭偺儘僔傾嶌壠僑儞僠儍儘僼偺彫愢乽僆僽儘乕儌僼乿偺塮夋壔丅懹懩偱柍婥椡側撈恎婱懓傪庡恖岞偲偡傞偙偺彫愢偼昡敾傪屇傃丄乬僆僽儘乕儌僼乭偼幮夛偵婑惗偡傞柍堊搆怘偺梋寁幰偺戙柤帉偵側偭偨丅巕嫙偺崰偐傜晝曣偵揗垽偝傟丄彚巊偄偵偐偟偢偐傟偰堢偭偨婱懓偺僆僽儘乕儌僼偼柍婥椡側懹偗幰偵戝恖偵惉挿偟丄妶摦揑側帠嬈壠偵側偭偨梒側偠傒偺恊桭偺桭忣偵墳偊傞偙偲偑弌棃偢丄斵偵徯夘偝傟偰恊偟偔側偭偨旤彈偲偺垽傕惉廇偝偣傞偙偲偑偱偒側偄丅斵偑梒偄崰偺曣恊偲夁偛偟偨妝偟偘側擔乆偺岝宨偑悘強偵巚偄弌偲偟偰憓擖偝傟傞丅愜乆偵塮偟弌偝傟傞儘僔傾偺揷幧偺弔壞廐搤偺旤偟偄宨怓偑報徾偵巆傞丅抝2恖偲彈1恖偺僩儕僆偺桭忣偼丄帺揮幵傪忔傝夞偡憓榖偲憡樦偭偰乽柧擔偵岦偐偭偰寕偰乿傪巚偄婲偙偝偣傞丅
2023擭2寧
2023擭2寧朸擔 旛朰榐221丂栰懞峗彨偺愴慜偺僐儊僨傿塮夋
1940徏抾丂栰懞峗彨丂昡揰亂B亃
乽垽愼偐偮傜乿偱抦傜傟傞栰懞峗彨偼儊儘僪儔儅偺娔撀偩偲巚偭偰偄偨偑丄偙偺塮夋傪尒偰僐儊僨傿傕岻偔嶣傟傞恖偩偲偄偆偙偲傪擣幆偟偨丅揷拞對戙丄忋尨尓偲偄偆乽垽愼偐偮傜乿偺墿嬥僐儞價偺庡墘丅忋尨尓偼懌戃壆偺斣摢偱偟偭偐傝幰偺寴暔抝丄揷拞對戙偼懌戃壆偺庡恖偺彑婥側堦恖柡丅撪怱偱偼岲偒崌偭偰偄傞偺偵丄夛偊偽寲壾偽偐傝偡傞偙偺擇恖偑丄恻梋嬋愜偺偡偊寢偽傟傞傑偱偺榖偑丄偺傫傃傝偟偨挷巕偱昤偐傟傞丅彜攧偦偭偪偺偗偱婑惾偵捠偆偺傫偒側庡恖丄懌戃壆偺庡恖偲椬偺儃乕僩壆偺庡恖乮惸摗払梇乯偲偺偄偑傒偁偄丄儔僀僞乕傪彫摴嬶偵偟偨徫偄丄晽幾偱怮崬傫偩忋尨偑晍抍傪壗枃傕偐偗傜傟偰栥偊傞僔乕儞側偳丄書暊僔乕儞偑悘強偵嶶傝偽傔傜傟偰偄傞丅庤楙傟偺僗僞僢僼偲僉儍僗僩偵傛傞怑恖媄偺旝徫傑偟偄塮夋偩偲尵偊傞丅傎偐偵嶰戭朚巕丄壨懞阾媑偑弌墘丅
尦婥偱峴偐偆傛
1941徏抾丂栰懞峗彨丂昡揰亂C亃
偙傟傕栰懞峗彨偺娔撀偱丄嵅栰廃擇丄忋尨尓丄嵅暘棙怣偲偄偆徏抾嶰塇塆偵丄揷拞對戙丄崅曯嶰巬巕丄孠栰捠巕偲偄偆恖婥嶰恖柡傪攝偟偨崑壺側僉儍僗僩偵傛傞嶌昳丅暔岅偼嵅栰廃擇偲揷拞對戙偺僇僢僾儖偺楒偺偝傗摉偰傪幉偵恑傓丅嵅栰廃擇偲忋尨尓偼抧幙挷嵏夛幮偱摥偔摨椈幮堳丅嵅暘棙怣偼偦偺忋巌丅揷拞對戙偼嵅栰偑壜垽偑偭偰偄傞夛幮媼巇偺彮擭偺巓偱杮壆偺揦堳丅崅曯嶰巬巕偼嵅栰廃擇偺枀偱忋尨尓偲楒拠丅孠栰捠巕偼嵅暘棙怣偺嵢偲偄偆攝栶丅揷拞對戙偺晝偼嶳巘偱丄偄偮傕嬥傪柍怱偡傞栵夘幰丅斵彈偼晝偺嶳巘壱嬈傪巭傔偝偣傞偨傔丄掜傪捠偠偰抦傝崌偭偨嵅栰偵憡択偡傞丄偲偄偆嬝棫偰偱僗僩乕儕乕偑揥奐偡傞丅儐乕儌傾巇棫偰偱偁傝丄懢暯梞愴憟撍擖捈慜偲偼巚偊側偄挿娬側塮夋偩偑丄婲暁偵朢偟偔娫墑傃偟偨姶偠偱丄偁傑傝柺敀偔側偄丅揷拞偺晝偺嶳巘偵壨懞阾媑丄墶朶側尰応娔撀偵妢抭廜偑暞偡傞丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐220丂堫奯峗丒嶰慏晀榊僐儞價偺帪戙寑
1952搶曮丂堫奯峗丂昡揰亂C亃
愴崙帪戙偺棊晲幰偨偪偺惗偒條傪昤偄偨嶰慏晀榊偺庡墘嶌昳丅堜忋桋偺尨嶌丄娔撀偺堫奯峗偲崟郪柧偺嫟摨媟杮偩偑丄屸妝傕偺側偺偐暥寍傕偺側偺偐拞搑敿抂偱丄弌棃偼椙偔側偄丅怐揷孯偵敆傜傟偰棊忛悺慜偺愺堜挿惌恮塩丅摝偘偢偵愴偆偑妶楬傪尒偄偩偡偮傕傝偺帢偵嶰慏晀榊丄扙弌偟偰惗偒側偑傜偊傛偆偲偡傞嗦尗偄帢偵嶰崙楢懢榊丄庡孨偺壎偵曬偄偰摙偪巰偵傪妎屽偡傞帢偵巗愳抜巐榊偑暞偡傞丅斵傜偼側傫偲偐惗偒墑傃丄棊晲幰偲側偭偰嶰幰嶰條偺惗偒曽偱恖惗傪曕傓丅嶰慏偼儌僥抝偱丄栰搻摢栚偺柡偺嶳岥廼巕丄愺堜壠偺崢尦偺愺姖偟偺傇偺椉曽偐傜崨傟傜傟傞偲偄偆愝掕丅3恖偺抝偨偪偺惈奿晅偗偑偁偄傑偄偱丄嬝偺棳傟傕偛搒崌庡媊偑栚棫偪丄慡懱偲偟偰惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅
戝嶁忛暔岅
1961搶曮丂堫奯峗丂昡揰亂B亃
偙傟傕堫奯峗偲嶰慏晀榊偺僐儞價偵傛傞堦嶌丅懞忋尦嶰偺彫愢偺塮夋壔偩偑丄屸妝塮夋偺崪朄偵懃偭偨柺敀偄嶌昳偵巇忋偑偭偰偄傞丅戝嶁搤偺恮傪戣嵽偵丄朙恇曽丄摽愳曽擖傝棎傟偰偺杁棯傗棎摤偑昤偐傟傞丅堦婙偁偘傞偨傔偵戝嶁偵弌偰棃偨捈忣宎峴偺楺恖丄嶰慏晀榊偑丄摉弶偼愴傪慾巭偟傛偆偲偡傞廤抍偵壛傢偭偰摥偔偑丄愴偄偑旔偗傜傟側偔側傞偲丄朙恇曽偵枴曽偟偰億儖僩僈儖偺晲婍抏栻傪戝嶁忛偵塣傃擖傟傛偆偲偡傞丅廤抍偺儕乕僟乕偵暯揷徍旻丄嶰慏傪彆偗傞擡幰丄柖塀嵥憼偵巗愳抍巕偑暞偡傞丅帪戙寑偵偼捒偟偔彈桪恮偑崑壺偱丄梽孨傪嶳揷屲廫楅丄愮昉傪惎桼棦巕丄壛摗壠偺昉傪媣変旤巕丄愴慾巭廤抍偱摥偔撲偺彈傪崄愳嫗巕偑墘偠傞丅嶰慏偼奜崙慏偵桿夳偝傟偨崄愳傪彆偗丄擇恖偼楒拠偵側傝丄嵟屻偼僴僢僺乕丒僄儞僪偱廔傞丅墌扟塸擇偺摿嶣偑慺惏傜偟偔丄塮偟弌偝傟傞戝嶁忛偼嫄戝側儈僯僠儏傾偩偲偄偆偑丄尒墳偊廫暘丅曽峀帥偺戝暓傗戝嶁偺挰偺僙僢僩傕傛偔弌棃偰偄傞丅忛偺旈枾偺敳偗寠偑偁偭偨傝丄夦偟偘側彜恖偑埫桇偟偨傝丄撲偺廋尡幰堦枴偑尰傟偨傝偲丄揱婏揑側嫽庯傕惙傝崬傑傟偰偄傞丅曅嬎妿尦傪巙懞嫪偑墘偠丄偄偮傕偼埆栶偺忋揷媑師榊偑恖偺偄偄晲嬶壆偺庡恖傪墘偠偰丄懚嵼姶傪帵偟偰偄傞丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐219丂僎僥儌僲丒僇儖僩塮夋
1966搶塮丂彫戲栁峅丂昡揰亂B亃
僞僀僩儖偳偍傝丄庡墘偺掃揷峗擇埲壓丄7恖偺攷搆偑妶桇偡傞乽幍恖偺帢乿傪柾偟偨傗偔偞塮夋偩偑丄儈僜偼斵傜慡堳偑恎懱忈奞幰偱偁傞偙偲丅庡墘偺掃揷偼曅栚丄嫟墘偺摗嶳姲旤偼曅榬丄懸揷嫗夘偼慡栍丄嶳杮椨堦偼曅懌丄彫徏曽惓偼橕機丄嶳忛怴屴偼榃垹丄戝栘幚偼婄柺壩彎偲偄偆恎忈幰丅偩偑斵傜偼擔堿幰偲偄偆堄幆偼傒偠傫傕側偔丄傒側対廵丄廮弍丄搧丄嵔姍側偳偺昁嶦媄傪恎偵偮偗偰偄傞丅暔岅偼棧傟彫搰傪晳戜偵丄嵦愇応偺棙尃憟偄傪弰偭偰揥奐偟丄嵟屻偼掕愇偳偍傝丄斵傜偑埆鐓側嬈幰偺杮嫆抧偵墸傝崬傓丅岅傝岥偼僐儊僨傿丒僞僢僠偱丄斶憇姶傕偍椳捀懻傕側偔丄寉夣偵榖偑恑傓丅巚偄偺傎偐柺敀偄丅偍撻愼傒偺惣懞峎傗嬥巕怣梇傕弌墘偟偰帩偪枴傪弌偟偰偄傞丅弌墘幰偺側偐偱偼懸揷偲嶳杮偺慡栍丒惽媟僐儞價偑嵟崅丅
峕屗愳棎曕慡廤丂嫲晐婏宍恖娫
1969搶塮丂愇堜婸抝丂昡揰亂D亃
峕屗愳棎曕偺乽僷僲儔儅搰婏択乿傪棎曕岲偒偺愇堜婸抝偑塮夋壔偟偨傕偺偩偑丄幚嵺偵偼棎曕偺條乆側彫愢偑楙傝崌傢偝傟偰偄傞傛偆偩丅庡墘偼媑揷婸梇丄媑揷偺晝偵埫崟晳梮偺搚曽扚丄柧抭彫屲榊偵戝栘幚偑暞偡傞丅堛妛惗偺媑揷偼晉崑偺晝偑棟憐嫿傪嶌偭偰偄傞偲偄偆柍恖搰偵峴偔偑丄晝偼偦偙偱帺暘偑憿傞婏宍恖娫偲偲傕偵曢傜偟偰偄偨丄偲偄偆榖丅偄傠偄傠弌偰偔傞婏宍恖娫偼丄儊僀僋偟偨敿棁偺抝彈偑偆偛傔偄偰偄傞偩偗偱丄傑偭偨偔柺敀偔側偄丅媑揷偑惛恄昦堾偵暵偠崬傔傜傟偨傝丄帺暘偲偦偭偔傝偺巰傫偩孼偲擖傟懼傢偭偨傝偡傞憓榖偵傛偭偰丄夦婏側暤埻婥傪忴偟弌偦偆偲偟偰偄傞偑丄夦婏尪憐偲偄偆傛傝丄摉帪偺搶塮偺僄儘丒僌儘楬慄偵忔偭偨偩偗偺塮夋偲偄偆姶偑嫮偄丅嵟屻偺柧抭彫屲榊偺庬柧偐偟傕庢偭偰晅偗偨傛偆側報徾丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐218丂徏抾僰乕償僃儖償傽乕僌偺偦偺屻
1962徏抾丂媑揷婌廳丂昡揰亂C亃
摗尨怰帰尨嶌丅壀揷錆浠巕偑100杮栚偺弌墘塮夋偲偟偰塮夋壔傪婇夋偟丄媑揷婌廳偵娔撀傪埶棅偟偨嶌昳丅媑揷偺塮夋偲偟偰偼桞堦傑偲傕偵嶌傜傟偨儊儘僪儔儅偩偲尵偊傞丅愴憟枛婜丄嬻廝偱壠傪從偐傟丄寢妀傪昦傓惵擭丄挿栧桾擵偑壏愹偺椃娰偵偐偮偓偙傑傟傞丅斵偼椃娰偺彈彨偺柡丄壀揷錆浠巕偺娕昦偵傛傝丄惗偒傞堄梸傪庢傝栠偡丅擇恖偼庝偐傟崌偆偑丄抝偼側偤偐椃娰傪嫀偭偰挰偵栠傞丅抝偼嶌壠巙朷偩偑惉岟偣偢丄庰偵偲彈偵揗傟丄寢崶偟偰夛幮嬑傔傪偡傞偑柍婥椡側惗妶傪憲傞丅抝偼悢擭偵堦搙丄廐捗壏愹偵栠傝丄彈偲悢擔娫夁偛偟偰嫀偭偰峴偔丅2恖偑拞擭偵側傝丄媣偟傇傝偵壏愹偵棃偨抝偲堦栭傪夁偛偟偨彈偼暿傟嵺偵帺嶦偡傞丅帪戙偵庢傝巆偝傟偨傛偆側壏愹偺忣宨偲丄偦偙偵廧傫偱抝偵恀忣傪曺偘懕偗傞彈偑偠偭偔傝偲昤偐傟傞丅愳抂峃惉偺乽愥崙乿偲惉悾枻婌抝偺乽晜塤乿傪儈僢僋僗偟偨傛偆側嶌昳丅桪廮晄抐側娒偭偨傟偺抝偲丄偦傫側抝偵垽傪拲偖彈偵偼丄壵棫偨偟偝偟偐姶偠側偄丅悘強偱巊傢傟傞壒妝偼傒側摨偠慁棩偱丄偦偺壒検偼側偤偐僶儔儞僗揑偵堎條偵戝偒偔丄嫽偑嶍偑傟傞丅壀揷錆浠巕偼惛嵤偵晉傫偱偄傞偑丄挿栧桾擵偼儈僗僉儍僗僩偱偁傠偆丅
姡偄偨壴
1964徏抾丂幝揷惓峗丂昡揰亂B亃
抮晹椙庡墘偺尰戙傗偔偞塮夋丅尨嶌偼愇尨怲懢榊偺偮傑傜側偄嶰暥捠懎彫愢偩偑丄塮夋偺傎偆偼嬞挘姶傪偨偨偊偨僪儔僀側暤埻婥偺柺敀偄塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅抮晹椙偺嫊柍揑側傗偔偞幰偑偄偄丅斵偑偙偺塮夋偱傗偔偞幰傪岲墘偟偨偺偑乽徍榓巆嫚揱乿偺晽娫廳媑偵寢傃偮偄偨偺偐傕偟傟側偄丅慡懱偵栭偺僔乕儞偑懡偔丄岝偲塭偺岠壥偑岻偔敪婗偝傟偰偍傝丄榓惢僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺姶偑偁傞丅撲偺彈丄壛夑傑傝偙偼堦庬偺僼傽儉丒僼傽僞乕儖偩丅峈憟偱恖傪嶦偟偨抮晹椙偼丄孻婜傪廔偊偰弌崠偟丄尦偺慻偵栠偭偨偑丄嫊柍姶傪書偄偰偄傞丅斵偼偨傑偨傑婄傪弌偟偨搎応偱戝抇偵搎偗傞庒偄彈丄壛夑傑傝偙傪尒偐偗丄嫽枴傪書偔丅斵偼傕偭偲戝偒側搎偗傪偟偨偄偲偄偆斵彈偺棅傒傪暦偒擖傟丄懠偺慻偑巇愗傞婋尟側搎応偵楢傟偰峴偔丅傗偑偰慻摨巑偺峈憟偑嵞敪偟丄斵偼斵彈傪屇傃弌偟偰丄揋懳偡傞慻挿傪帺暘偑巋嶦偡傞偺傪栚寕偝偣傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅晄婥枴側庒偄嶦偟壆丄摗栘岶偺憓榖偼側偄傎偆偑偡偭偒傝偡傞偟丄僄儞僨傿儞僌偺孻柋強撪偱偺嵟屻偺僔乕僋僄儞僗傕梋寁偩偲巚偆丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐217丂棝崄棖乗乗枮塮帪戙偺捒昳
1939搶曮丒枮塮丂戝扟弐晇丂昡揰亂C亃
搶曮偲枮塮偺採実戞1夞嶌昳丅1939擭偵拞崙偱丄梻擭偵擔杮偱岞奐偝傟偨丅攐桪僋儗僕僢僩偱偼棝崄棖偑僩僢僾偩偑丄帠幚忋偺庡墘偼拞崙恖偺庒幰2恖偱丄枮廈偐傜摨嫿偺桭恖偵夛偆偨傔擔杮偵傗偭偰棃偨旍枮抁嬰偲挿恎憠嬰偺撌墯僐儞價偑捒摴拞傪孞傝峀偘傞僐儊僨傿丅壢敀偺敿暘偼拞崙岅偱擔杮岅帤枊偑擖傞丅枮廈偺揷幧偵廧傓2恖偑擔杮偵峴偙偆偲寛傔丄楍幵偵忔傞偲丄師偺僔乕儞偱偼擔杮偺楍幵偺嵗惾偵嵗偭偰偄傞丄偲偄偆憗偄僥儞億偵屗榝偆丅斵傜偼愗晞傪側偔偟偨偨傔敔崻偱崀傠偝傟丄晉巑嶳傪攚宨偵丄廫崙摶傪偲傏偲傏曕偔丅偙偺僔乕儞偼乽塀偟嵲乿偺摗尨姌懌偲愮廐幚傪憐婲偝偣傞丅2恖偼塮夋嶣塭偺儘働戉偵憳嬾偟丄僗僞僢僼傗弌墘幰偨偪偲恊偟偔側偭偰丄儘働戉偺僶僗偵摨忔偟偰搶嫗偵岦偐偆丅弌墘幰偺傂偲傝偑尨愡巕偱丄斵彈偺弌斣偼偙偺僔乕僋僄儞僗偩偗丅偲偄偆傢偗偱丄偙偺塮夋偱偼尨愡巕偲棝崄棖偑嫟偵弌墘偟偰偄傞偑丄巆擮側偑傜偙偺2恖偑棈傓僔乕儞偼側偄丅枮廈偺撌墯僐儞價偑擔杮偱弌夛偆恖乆偼傒側恊愗偱桪偟偄偑丄朘偹傞桭恖偺嫃応強傪尒偮偗傞偙偲偑偱偒側偄丅擔斾扟丄恄揷丄擔杮嫶側偳丄摉帪偺搶嫗偺晽宨偑憓擖偝傟偰嫽枴怺偄偑丄慡懱揑偵娤岝塮夋偺姶偑偁傞丅斵傜偼傂傚傫側偙偲偐傜儅僗僐儈偵庢傝忋偘傜傟丄帟僽儔僔夛幮偺峀崘偵婲梡偝傟偰恖婥幰偵側傞丅偙偺夛幮偺愰揱晹挿偑丄側傫偲摗尨姌懌偩丅斵傜偼傗偭偲拞壺椏棟壆傪塩傓桭恖偲嵞夛偟偰婌傇丅偙偺桭恖偺媊枀偱帟僽儔僔夛幮偺僞僀僺僗僩偱偁傝丄捠栿傪柋傔傞偺偑棝崄棖丅庒偄棝崄棖偼彮彈偭傐偄柺塭傪廻偟偰偍傝丄屻擭偲偼彮偟婄棫偪偑堎側傞丅拞斦偵斵彈偑庡戣壧乽梲弔彫塖乿傪壧偆僔乕儞偑憓擖偝傟傞丅廔斦偵斺業偝傟傞擔寑僟儞僔儞僌丒僠乕儉偺僗僥乕僕偼側偐側偐偺憇娤丅斵傜偼傒傫側偱戝棨偵栠傠偆偲寛傔傞丅嵟屻偼枮廈偺峀偄暯栰偱妝偟偦偆偵揷敤傪奐崵偡傞斵傜偑塮偟弌偝傟偰廔傞丅偙傟偼屲懓嫤榓丄墹摴妝搚傪鎼偄丄拞崙岦偗偵擔杮偺椙偝傪抦傜偟傔傞偲摨帪偵丄擔杮岦偗偵枮栔奐戱傊偺嶲壛傪懀偡崙嶔塮夋偲尵偊傞丅懢暯梞愴憟撍擖慜偺丄偺傫傃傝偟偨妝揤揑側嬻婥婥偑昚偭偰偄傞丅
巹偺轵
1944搶曮丒枮塮丂搰捗曐師榊丂昡揰亂C亃
搶曮偲枮塮偺嫟摨惂嶌偵傛傞棝崄棖庡墘偺壒妝塮夋偱偁傝丄1944擭偵姰惉偟偨偑丄岞奐偝傟偨偺偼拞崙偺傒偱丄擔杮偱偼岞奐偝傟側偐偭偨丅専墈偱擃庛偩偲尒側偝傟偨偐傜偩傠偆偐丅戝樑師榊尨嶌丄壒妝偼暈晹椙堦丅僴儖僺儞偱儘働偝傟丄尰抧嵼廧偺儘僔傾恖壒妝壠偨偪偑嶣塭偵嫤椡偟偨偲偄偆丅弌墘幰偺懡偔偼儘僔傾恖偱丄戜帉傕戝敿偼儘僔傾岅丄媽壖柤尛偄偺擔杮岅帤枊偑晅偄偰偄傞丅捒昳塮夋偲尵偊傞偩傠偆丅儘僔傾妚柦偱枮廈偵朣柦偟偨敀宯儘僔傾偺僆儁儔壧庤偨偪偼丄擔杮恖偺彜幮堳偵媬傢傟傞偑丄孯敶偺愴摤偵姫偒崬傑傟傞丅彜幮堳偼嵢偲梒偄柡偲嫟偵壧庤偨偪傪楢傟偰攏幵偱摝偘傞搑拞丄旐抏偟偰棊攏偟丄棧傟偽側傟偵側傞丅彎偑桙偊偨彜幮堳偼昁巰偱嵢偲柡傪扵偡偑尒偮偐傜偢丄桭恖偵偁偲傪戸偡偟偰撿曽偵晪擟偡傞丅偦傟偐傜10悢擭丄嵢偼昦巰偟丄柡偼惉挿偟偰儘僔傾丒僆儁儔壧庤抍偺儕乕僟乕偺梴彈偲側傝丄僴儖僺儞偵廧傫偱丄梴晝偐傜惡妝傪妛傫偱偄傞丅桭恖偑斵傜傪尒偮偗丄彜幮堳偵抦傜偣傞丅愜傝偐傜枮廈帠曄偑杣敪偟丄奨偼崿棎傪嬌傔偰偄傞乧乧偲偄偆僗僩乕儕乕丅惉挿偟偨柡偵暞偡傞偺偑棝崄棖丅斵彈偼幚嵺偵枮廈偵廧傫偱偄偨崰丄儘僔傾恖壒妝壠偺傕偲偱惡妝傪妛傫偱偍傝丄偙偺塮夋偱尒帠側僆儁儔晽壧彞傪斺業偟偰偄傞丅傎偐偵傕僆儁儔偺僗僥乕僕偑抐曅揑偵憓擖偝傟傞丅晝偺彜幮堳傪墘偠傞偺偼擇杮桍姲傜偟偄偑丄憠偣偰崪挘偭偰偍傝丄愴屻偺塮夋偱尒傞斵偲偼傑偭偨偔婄偮偒偑堎側偭偰偄傞丅慡懱揑偵丄嬝偺棳傟傗丄搊応恖暔丄尵梩側偳偺偣偄偐丄墷暷偺塮夋傪尒偰偄傞傛偆側嶖妎偵娮傞丅崙嶔揑側梫慺偼偁傑傝側偄偑丄弌墘幰偺傂偲傝偺乽擔杮孯偑僴儖僺儞偵恑挀偟偨偍偐偘偰崿棎偑廂傝丄暯榓偑栠偭偨乿偲偄偆壢敀傗丄梴晝偑崱嵺偺嵺偵柡偵尵偆乽杮摉偺偍晝偝傫偲擔杮偵婣傝側偝偄丄擔杮偼懜偔旤偟偄丄恄偺崙偩乿偲偄偆尵梩側偳偵丄愴帪壓偺塮夋傜偟偝偑昞傟偰偄傞丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐216丂尨愡巕傪尒傞帄暉乗乗1940擭
1940搶曮丂崱堜惓丂昡揰亂C亃
尨愡巕偑庡墘偡傞擔忢惗妶偺垼娊傪昤偄偨彫巗柉僪儔儅丅梞暈怑恖偺晇偑墳彚偟偨偁偲丄嵢偺偄偹巕偼偍偱傫壆傪奐偔丅揦偼斏惙偡傞偑丄嵟弶偼墳墖偟偰偄偨嬤強偺偲傫偐偮壆偺彈彨偐傜偼媞傪庢傜傟偲暥嬪傪尵傢傟丄媊巓偐傜偼悽娫懱偑埆偄偐傜巭傔傠偲尵傢傟丄媞偲偺娫偵椙偐傜偸塡偑棫偪丄懡帠懡擄丅偟偐偟丄偄偹巕偼偦傟偵傔偘偢婥忎偵揦傪懕偗傞丅傗偑偰彍戉偟偰婣娨偟偨晇偼嵢偺峴忬傪媈偆偑丄岆夝偑夝偗丄揦偼傕偲偺梞暈揦偵栠傝丄擔忢傪庢傝栠偡丅懠垽側偄僗僩乕儕乕偺彫昳偩偑丄尨愡巕偑偲偰傕偒傟偄偵嶣傟偰偍傝丄庒嵢偄偹巕栶傪惗偒惗偒偲墘偠偰偄偰丄旝徫傑偟偄丅偲傫偐偮壆偺彈彨栶偺惔愳嬍巬丄媊巓栶偺戲懞掑巕傕帩偪枴傪敪婗偟偰偄傞丅
壟偖擔傑偱
1940搶曮丂搰捗曐師榊丂昡揰亂B亃
偙傟傕乽彈偺奨乿偲摨偠偔丄拞棳壠掚偺惗妶傪偨傫偨傫偲昤偄偨壠掚僪儔儅丅尨愡巕偺庡墘丄戲懞掑巕丄惔愳嬍巬丄戝愳暯敧榊偺彆墘偲丄僉儍僗僩傕崜帡偟偰偄傞丅尨愡巕偼堦壠偺挿彈丅昦杤偟偨曣偵戙傢偭偰壠掚傪愗傝惙傝偟丄僒儔儕乕儅儞偺晝乮屼嫶岞乯傗彈妛惗偺枀乮栴岥梲巕乯傪悽榖偟偰偄傞丅晝偼嵞崶偡傞偑丄幚偺曣偑朰傟傜傟側偄枀偼媊棟偺曣偵側偮偐偢丄斀峈揑側懺搙傪庢傝丄尨偼怱傪捝傔傞丅傗偑偰尨偼寢崶偟偰壠傪弌傞偑丄偦偺慜偵媊棟偺曣偲拠椙偔偡傞傛偆枀傪桜偡丅塮夋偼尨偑壴壟巔偱幵偵忔傝丄枀偑偦傟傪尒憲傞僔乕儞偱廔傞丅惛恄惈傗墱怺偝偼暿偲偟偰丄榖偺棳傟偼愴屻偵彫捗埨擇榊偑尨愡巕傪婲梡偟偰嶌偭偨堦楢偺塮夋偺僥乕儅偲嫟捠偟偰偄傞丅20嵨偺尨愡巕偼丄僉儞僉儞惡偺挐傝曽偼憡曄傢傜偢嫽偞傔偡傞偑丄杍偑傆偭偔傜偟偰丄偙傛側偔旤偟偄丅枀栶偺栴岥梲巕偼愴屻丄崟郪柧偲寢崶偟偨丅妛峑偺嫵巘栶偱悪懞弔巕偺庒偄巔傪尒傞偙偲偑偱偒傞丅栭丄壠弌偟偨枀傪扵偡尨愡巕偺僔乕僋僄儞僗偺攚屻偵丄側偤偐儀僯乕丒僌僢僪儅儞妝抍偺1939擭偺僸僢僩嬋乽揤巊偼壧偆乿偺墘憈偑棳傟傞丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐215丂嶳岥廼巕傪尒傞桖墄乗乗1950擭戙
1950徏抾丂廰扟幚丂昡揰亂C亃
嶳岥廼巕庡墘偺僐儊僨傿塮夋丅壓廻恖丄崅棙戄偟丄廻壆偺恊晝側偳丄曄側抝彈偑孞傝峀偘傞偳偨偽偨憶偓傪昤偄偨嶌昳偱丄摨偠娔撀偺乽偰傫傗傢傫傗乿傗乽帺桼妛峑乿傪憐婲偝偣傞丅揷幧偱椃娰傪宱塩偡傞嶳岥廼巕偑彈拞偺朷寧桪巕傪楢傟偰丄昦婥偺枀傪尒晳偄偵搶嫗偵弌偰偔傞丅斵彈偼枀偺庁嬥偺尐戙傢傝偵彈拞曭岞傪偝偣傜傟丄杻悵嫸偄偺壓廻恖偺嵅暘棙怣丄崅棙戄偟偺斣摢偺嵅栰廃擇偲抦傝崌偄丄揷幧偐傜媽抦偺塅嵅旤撝偑忋嫗偟丄偦偺3恖偵尵偄婑傜傟偰崲榝偡傞傕桳捀揤偵側傞丅嬝棫偰偼嫮堷偱偄偄壛尭偩偑丄慡懱揑側報徾偲偟偰偼柺敀偔側偔偼側偄丅
搶嫗偺媥擔
1958搶曮丂嶳杮壝師榊丂昡揰亂B亃
 嶳岥廼巕偺堷戅婰擮塮夋丅僐儊僨傿巇棫偰偺僀乕僗僩儅儞丒僇儔乕寑塮夋偩偑丄壧偲梮傝偺僗僥乕僕丒僔儑僂偑怐傝崬傑傟偰偄傞丅搶曮強懏偺摉帪偺僗僞乕偨偪偑憤弌墘偡傞丅怷斏媣淺丄抮晹椙丄嶰慏晀榊丄曮揷柧丄彫椦宩庽丄尨愡巕丄巌梩巕丄敧愮憪孫丄崄愳嫗巕丄媣帨偁偝傒側偳偑丄嬝偵偐傜傓栶傗儚儞丒僔乕儞偩偗偺偪傚偄栶偱懕乆偲弌偰偔傞丅搊応偡傞攐桪偨偪偺柤慜偼懡偡偓偰丄偲偰傕彂偒愗傟側偄丅僉儍僗僩偵嵹偭偰偄傞巙懞嫪丄怴媴嶰愮戙丄庒嶳僙僣巕側偳偼丄偳偙偵弌偰偄偨偺偐丄婥偑偮偐側偐偭偨丅庡墘偺嶳岥廼巕偼傾儊儕僇偵搉偭偰惉岟偟偨僼傽僢僔儑儞丒僨僓僀僫乕偺栶丅斵彈偑擔宯堏柉偺娤岝抍懱偵傑偠偭偰擔杮偵棦婣傝偟丄偝傑偞傑側宱堒傪宱偰僼傽僢僔儑儞丒僔儑乕傪奐偔丄偲偄偆懠垽側偄僗僩乕儕乕偩偑丄師乆偵搊応偡傞僗僞乕偨偪傪尒偰偄傞偩偗偱妝偟偄丅庒庤彈桪傗墇楬悂愥側偳偺壧庤偨偪偑梮傝傗壧傪斺業偟丄嶳岥廼巕帺恎傕偐偮偰偺僸僢僩嬋乽栭樢崄乿傪壧偆丅曮揷柧偲巌梩巕偺僇僢僾儖偑拞壺椏棟揦偵峴偔偲丄揦庡偼捒柇側擔杮岅偱榖偡怷斏媣淺偱丄揦柤偑乽棝崄棖乿偲偄偆妝壆棊偪僊儍僌偑徫偊傞丅嶰慏晀榊偼廔斦偵嶳岥廼巕偑堢偭偨揷幧偺梒側偠傒偱偁傞傂偘柺偺杙鎐側惵擭偲偟偰搊応丅尨愡巕偼擔杮偺暈忺嫤夛偺棟帠挿栶偱丄僼傽僢僔儑儞丒僔儑乕偺朻摢偺垾嶢傪偟丄嶳岥廼巕傪徯夘偡傞丅尨偲嶳岥偼1920擭惗傑傟偺摨偄擭丅偙傟偼偙偺2恖偺戝彈桪偑嫟墘偟偨桞堦偺塮夋偩偲巚偆丅
嶳岥廼巕偺堷戅婰擮塮夋丅僐儊僨傿巇棫偰偺僀乕僗僩儅儞丒僇儔乕寑塮夋偩偑丄壧偲梮傝偺僗僥乕僕丒僔儑僂偑怐傝崬傑傟偰偄傞丅搶曮強懏偺摉帪偺僗僞乕偨偪偑憤弌墘偡傞丅怷斏媣淺丄抮晹椙丄嶰慏晀榊丄曮揷柧丄彫椦宩庽丄尨愡巕丄巌梩巕丄敧愮憪孫丄崄愳嫗巕丄媣帨偁偝傒側偳偑丄嬝偵偐傜傓栶傗儚儞丒僔乕儞偩偗偺偪傚偄栶偱懕乆偲弌偰偔傞丅搊応偡傞攐桪偨偪偺柤慜偼懡偡偓偰丄偲偰傕彂偒愗傟側偄丅僉儍僗僩偵嵹偭偰偄傞巙懞嫪丄怴媴嶰愮戙丄庒嶳僙僣巕側偳偼丄偳偙偵弌偰偄偨偺偐丄婥偑偮偐側偐偭偨丅庡墘偺嶳岥廼巕偼傾儊儕僇偵搉偭偰惉岟偟偨僼傽僢僔儑儞丒僨僓僀僫乕偺栶丅斵彈偑擔宯堏柉偺娤岝抍懱偵傑偠偭偰擔杮偵棦婣傝偟丄偝傑偞傑側宱堒傪宱偰僼傽僢僔儑儞丒僔儑乕傪奐偔丄偲偄偆懠垽側偄僗僩乕儕乕偩偑丄師乆偵搊応偡傞僗僞乕偨偪傪尒偰偄傞偩偗偱妝偟偄丅庒庤彈桪傗墇楬悂愥側偳偺壧庤偨偪偑梮傝傗壧傪斺業偟丄嶳岥廼巕帺恎傕偐偮偰偺僸僢僩嬋乽栭樢崄乿傪壧偆丅曮揷柧偲巌梩巕偺僇僢僾儖偑拞壺椏棟揦偵峴偔偲丄揦庡偼捒柇側擔杮岅偱榖偡怷斏媣淺偱丄揦柤偑乽棝崄棖乿偲偄偆妝壆棊偪僊儍僌偑徫偊傞丅嶰慏晀榊偼廔斦偵嶳岥廼巕偑堢偭偨揷幧偺梒側偠傒偱偁傞傂偘柺偺杙鎐側惵擭偲偟偰搊応丅尨愡巕偼擔杮偺暈忺嫤夛偺棟帠挿栶偱丄僼傽僢僔儑儞丒僔儑乕偺朻摢偺垾嶢傪偟丄嶳岥廼巕傪徯夘偡傞丅尨偲嶳岥偼1920擭惗傑傟偺摨偄擭丅偙傟偼偙偺2恖偺戝彈桪偑嫟墘偟偨桞堦偺塮夋偩偲巚偆丅2023擭2寧朸擔 旛朰榐214丂1952擭偺搶曮塮夋
1952搶曮丂扟岥愮媑丂昡揰亂C亃
庡墘偼嶳岥廼巕偲嶰慏晀榊丅柧帯弶擭偺墶昹丅埆摽姱寷傪嶦偟偰摝朣拞偺嶳岥偼僆儔儞僟恖偺杅堈彜偵彆偗傜傟偰摻傢傟丄斵偺彣偵側傞丅嶰慏偼偙偺杅堈彜偺攏挌丅嶳岥偼嶰慏偲庝偐傟崌偆傛偆偵側傝丄嶰慏偺姪傔偱杅堈彜偺壠傪弌偰帺庱偟傛偆偲偡傞偑丄偦傟傪抦偭偨杅堈彜偼斵彈傪慏偵暵偠崬傔丄嶰慏偼斵彈傪彆偗弌偦偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅戝樑師榊偺怴暦彫愢偑尨嶌偩偑丄杅堈彜偺恖奿愝掕偑偁偄傑偄偩偟丄傾僋僔儑儞傕拞搑敿抂偱丄偁傑傝柺敀偔側偄丅偲偼偄偊丄偙偺塮夋偱偺嶳岥廼巕偼偠偮偵旤偟偔嶣傜傟偰偄傞丅嶰慏偼乽幍恖偺帢乿偺媏愮戙僞僀僾偺捈忣宎峴丄弮恀慺杙側抝傪抧偱墘偠偰偄傞丅巙懞嫪偑埆鐓側恖懌尦掲傔偲偟偰弌墘丅
挬偺攇栦
1952怴搶曮丂屲強暯擵彆丂昡揰亂B亃
崅曯廏巕偑庡墘偟偨僉儍儕傾丒僂乕儅儞塮夋丅堄奜側孈傝弌偟暔偱屻枴偑偄偄丅桳擻側杅堈夛幮偺幮堳丄崅曯偺巇帠傇傝偲楒柾條偑昤偐傟傞丅崅曯偺摨椈幮堳偵壀揷塸師丄嫞崌偡傞彜帠夛幮偺幮堳偵抮晹椙偑暞偡傞丅崅曯偼傗傞婥枮乆偺壀揷偲拠偑椙偄偑丄偟偩偄偵椙壠偺朧偪傖傫偱恖偑椙偄偍偭偲傝偟偨惈奿偺抮晹偵庝偐傟偰偄偔丅攕愴偐傜6擭屻偺搶嫗丄搒夛偺昞捠傝偼壺傗偐偱暅嫽挊偟偄偑丄廧戭抧偵偼傑偩姠釯偑嶶棎偟偰偍傝丄愺憪奅孏偵偼晜楺幰傗晜楺帣偑曕偒夞偭偰偄傞岝宨傕塮偟弌偝傟傞丅愴憟偺塭偼偄傑偩偵擹岤偱丄懅巕傪崅曯壠偵梐偗偰敔崻偺椃娰偱摥偔嶰戭朚巕偺晇偼愴巰偟偰偄傞丅崅曯偲偲傕偵幣惗偱怮揮偑傞抮晹偼乽偙偺嬻偼價儖儅偱尒偨嬻偲摨偠偩乿偲偮傇傗偔丅抮晹帺恎偑撿曽偱暫栶偵廇偄偰偄偨丅榚栶偱偼抮晹壠偺帹偺墦偄彈拞偵暞偡傞塝曈孒巕偑弌怓丅抮晹偺戝妛儃乕僩晹偺愭攜栶偱忋尨尓丄晜楺帣廂梕巤愝偺僔僗僞乕栶偱崄愳嫗巕偑偪傜偭偲婄傪弌偡丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐213丂愴憟捈屻偺栘壓宐夘塮夋
1946徏抾丂栘壓宐夘丂昡揰亂C亃
栘壓宐夘偺愴屻戞1嶌丅悪懞弔巕庡墘丅桾暉側忋棳奒媺偺壠懓偺徍榓18擭偐傜攕愴傑偱偺愴帪壓偵偍偗傞庴擄暔岅丅枹朣恖丄悪懞偺堦壠偼丄挿抝偑巚憐斊偲偟偰専嫇偝傟丄柡丄嶰塝岝巕偺寢崶偼攋択偵側傝丄師抝偼墳彚丄嶰抝偼摿峌戉偵巙婅偟偰愴巰偡傞丅朣晇偺掜偱偁傞婃柪側崙悎庡媊幰偺孯恖丄彫戲塰懢榊偺晇晈偑悪懞偺壠偵堏傝廧傒丄変偑暔婄偵怳傞晳偆丅悪懞偼嬯擄偵懴偊懕偗傞偑丄攕愴屻丄摿尃傪棙偟偰暔帒傪塀摻偡傞彫戲偵搟傝傪敋敪偝偣丄弌偰偄偗偲偄偆丅偙偆偟偰帺桼庡媊偲孯崙庡媊偺懳棫偑恾幃揑偵昤偐傟傞丅応柺偼堦娧偟偰戝慮崻壠偺壆晘偺側偐偵廔巒偡傞偑丄僄儞僨傿儞僌偩偗丄孻柋強偺栧偱曣偲枀偑庍曻偝傟傞挿抝傪寎偊傞僔乕儞偵側傝丄摨峴偟偰偄偨夋壠丄搶栰塸帯榊偑乽戝慮崻壠偺挬偩乿偲尵偄丄栭柧偗偺岝宨偑塮偟弌偝傟偰廔傞丅偙偺僄儞僪丒僔乕儞偼丄偄偐偵傕庢偭偰晅偗偨傛偆側報徾偱丄嶌昳偲偟偰攋抅偟偰偄傞丅偙傟偼GHQ偺巜帵偵傛偭偰晅偗懌偝傟偨傕偺傜偟偄丅悪懞弔巕偺梷偊偨墘媄偑尒帠丄彫戲塰懢榊偼憺乆偟偄揋栶傪墘偠偰偝偡偑偺娧榎丅偟偐偟堦壠傪廝偆晄岾偺昤偒曽偑僙儞僠儊儞僞儖偵棳傟偡偓偰偄傞偟丄恖暔偺昤偒曽偑偁傑傝偵傕昞柺揑偱敄偭傌傜偄丅
寢崶
1947徏抾丂栘壓宐夘丂昡揰亂E亃
栘壓宐夘偺愴屻戞3嶌丅庡墘偼揷拞對戙偲忋尨尓丅愴屻偺晄嫷偱嬯偟偄惗妶偵懴偊傞楒恖偨偪偑嬯擄傪忔傝墇偊偰寢崶偵帄傞傑偱偑昤偐傟傞丅揷拞傕忋尨傕丄揷拞偺壠懓丄幐嬈拞偺晝偲壠掚傪庣傞曣乮搶栰塸帯榊偲搶嶳愮塰巕乯傕丄忋尨偺壓廻愭偺庡晈傕丄奃廯偑嫮偄搶栰偺尦晹壓乮彫戲塰懢榊乯傕丄傒側慞恖偩偑丄惗妶嬯偺偨傔巚偆傛偆偵側傜側偄丅栘壓宐夘偼乽戝慮崻壠偺挬乿偱擔杮偺婸偗傞枹棃傪梊姶偝偣偨偑丄幚嵺偵偼尩偟偄尰幚偑懸偭偰偄偨丄偲偄偆偙偲傪尵偄偨偐偭偨偺偩傠偆偐丅塮夋偼慡懱偵幣嫃偑偐偭偰偄偰丄廌扱応偑懡偔丄偁傑傝偵僙儞僠儊儞僞儖偱丄尒偰偄偰鐒堈偡傞丅娤媞偺椳傪桿偆偨傔偵偙偠偮偗偨偲巚傢傟傞榖偺揥奐傕懡偔丄怴摗寭恖偺媟杮偲偼巚偊側偄丅寢崶傪峊偊偨柡偺栶傪傗傞偵偼丄揷拞偼擭傪庢偭偰偄偰柍棟偑偁傞丅
2023擭2寧朸擔 旛朰榐212丂尨愡巕傪尒傞帄暉乗乗1940擭戙拞婜
1943搶曮丂嶳杮嶧晇丂昡揰亂D亃
懢暯梞愴憟偨偗側傢偺偙傠偺崙嶔塮夋丅孯旛憹嫮偺偨傔憹嶻偵搘傔傞惢揝強偑晳戜丅梟峼楩偺傂偲偮偑晄挷偱岠棪偑埆偔丄帠屘傕昿敪偡傞丅夛幮偺忋栶傕岺堳傕偍崙偺偨傔堦娵偲側偭偰惓忢壱摥偵庢傝慻傓丄偲偄偆榖丅尨愡巕偼怴擖傝偺帠柋堳丄岺堳偺儕乕僟乕偵摗揷恑偑暞偡傞丅尨偼婃屌堦揙側摗揷偵摉弶丄斀姶傪妎偊傞偑丄偟偩偄偵岲堄傪書偔丅摗揷偼壓廻愭偺柡偱尨偲婘傪暲傋傞壴堜棖巕偵庝偐傟偰偄傞丅嵟屻偼梟峼楩偺惓忢壔偵惉岟偟丄慡堳偱枩嵨嶰彞丄尨偑摗揷偵幐楒偟偰廔傞丅榖偺棳傟偼嫮堷偱柆棈側偔丄傑傞偱妛寍夛偺傛偆側塮夋偩丅傆偭偔傜偟偰旤偟偄丄庒偄尨愡巕偑尒傜傟傞偺偑桞堦偺旤揰丅傎偐偵徖嶈孧丄悰堜堦榊偑弌墘偟偰偄傞丅
杒偺嶰恖
1945搶曮丂嵅攲惔丂昡揰亂D亃
1945擭8寧5擔偺晻愗傝偱偁傝丄攕愴帪偵桞堦忋塮偝傟偰偄偨塮夋偩偲偄偆丅偦傫側帪婜偵塮夋偑忋塮偝傟偰偄偨偙偲偵嬃偔丅3恖偺彈惈捠怣巑偺妶桇傪庡幉偵偟偨嶌昳偱偁傝丄愴堄崅梘丄彈惈偺愴憟嶲壛傪懀偡栚揑偱嶌傜傟偨傕偺偱偁傠偆丅夋幙偼偐側傝埆偄偑尒傟側偔偼側偄丅嵟埆側偺偼壒幙偱丄戜帉偑椙偔暦偒庢傟側偄丅惵怷旘峴応偺捠怣巑偵尨愡巕丄愮搰旘峴応偵晪擟偡傞捠怣巑偵崅曯廏巕丄戰懆偺杒奀旘峴応捠怣巑偵嶳崻庻巕偑暞偡傞丅斵彈傜偼傒側摨偠捠怣妛峑偺摨婜惗偩丅尨偲崅曯偼乽垻曅愴憟乿偱巓枀偺栶傪墘偠偰埲棃偺嫟墘丅塮夋偼丄偙偺3恖偺彈惈捠怣巑偺妶桇偵傛傝丄埆揤岓偱帇奅晄椙偺側偐丄桝憲婡偑揋婡偺峌寕傪偐偄偔偖偭偰惵怷偐傜戰懆偵暔帒傪塣傇偙偲偵惉岟偡傞丄偲偄偆榖丅桝憲婡偺婡挿傪摗揷恑丄嶳崻偺楒恖偺娤應堳傪嵅暘棙怣偑墘偠傞丅
2023擭1寧
2023擭1寧朸擔 旛朰榐211丂巌梩巕偲曮揷柧嫟墘偺搒夛塮夋
1962搶曮丂楅栘塸晇丂昡揰亂B亃
巌梩巕庡墘丅惗偒攏偺栚傪敳偔傛偆側峀崘嬈奅偱摥偔僉儍儕傾丒僂乕儅儞偺惗懺傪昤偄偨塮夋丅弌棃偼側偐側偐椙偄丅巌梩巕偑偒傟偄偵嶣傟偰偍傝丄抝偵晧偗偢偟偐偨偐偵巇帠偡傞偑丄偲偒偍傝惼偝傪奯娫尒偣傞彈傪岲墘偟偰偄傞丅搶曮傜偟偄柧楴夣妶側塮夋偩偲巚偭偰偄偨傜丄偐側傝埫偄撪梕偱丄偟偐傕儌僲僋儘丄搊応恖暔偼扤傕岾偣偦偆偵偼尒偊側偄丅夛幮偱彈偨偪偑抝偺傛偆側尵梩偯偐偄偱夛榖偡傞偺偵嬃偐偝傟傞丅巌梩巕偼峀崘戙棟揦偺塩嬈僂乕儅儞丄僞僶僐傪僗僷僗僷媧偄丄杻悵傪傗傝丄帺戭傾僷乕僩偱傗偗庰傪偁偍傞丅憡庤栶偺曮揷柧偼儔僀僶儖夛幮偺傗傝庤偺幮堳丅巌偼曮揷偲楒拠偵側傞偑丄巇帠偱斵偵棤愗傜傟傞丅嶳嶈搘丄悈栰媣旤丄惣懞峎側偳偑榚傪屌傔偰偄傞丅
垽忣偺搒
1958搶曮丂悪峕晀抝丂昡揰亂C亃
巌梩巕偼揷幧偐傜搶嫗偵弌偰棃偨惔弮慺杙側柡丄媊巓偑宱塩偡傞僗僫僢僋丒僶乕偱摥偔丅曮揷柧偼彈梀傃偵惛傪弌偡夛幮幮挿偺偳傜懅巕丅曮揷偼巌偵堦栚崨傟偟丄夵怱偟偰恀柺栚偵惗偒傛偆偲寛怱偟丄巌傕曮揷傪垽偡傞傛偆偵側傞偑丄曮揷偺栚晅栶傗垽恖偑擇恖偺拠傪堷偒楐偙偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅揟宆揑側儊儘僪儔儅偩偑弌棃偼埆偔側偔丄戅孅偣偢偵尒傜傟傞丅僨價儏乕偟偰3擭偺巌梩巕偼杍偑傆偭偔傜偟偰庒乆偟偔丄慜敿偺弮杙側柡丄屻敿偺楇棊偟偨彈傪岻偔墘偠偰偄傞丅巌偺媊巓偺憪揓岝巕丄曮揷偺夛幮摨椈偺彫愹攷傕岲傑偟偄丅偄偮傕側偑傜娭惣曎偱寵枴傪鄖楐偝偣傞楺壴愮塰巕丄恄揷僯僐儔僀摪偺晽宨昤幨傕尒墳偊偑偁傞丅
2023擭1寧朸擔 旛朰榐210丂乬掅柪婜乭偺惉悾枻婌抝嶌昳丂偦偺2
1950搶曮丂惉悾枻婌抝丂昡揰亂D亃
僟儞僗儂乕儖偵弌杤偟丄嬥帩偪偺彈傪閤偟偰嬥傪姫偒忋偘傞擇恖偺晄椙妛惗傪拞怱偵丄愴屻偺晽懎傪昤偄偨塮夋丅庡墘偼塅栰廳媑偲尨曐旤丅偳偪傜傕尒偨栚偼偍偠偝傫偱丄妛惗暈傪拝偰偄偰傕傑偭偨偔妛惗偵偼尒偊側偄丅塅栰偼搑拞偱夵怱偟丄嵓媆傪巭傔傛偆偲偡傞偑丄尨偼傑偡傑偡偺傔傝崬傫偱偄偔丅巙懞嫪丄搶嶳愮塰巕丄庒嶳僙僣巕丄媣変旤巕偐傜榚傪屌傔傞丅搊応恖暔偼椶宆揑偱丄嶌昳偲偟偰偼柺敀偔側偄偑丄壆奜偺儘働丒僔乕儞偑懡偔丄塅栰偲庒嶳偑曕偒側偑傜搑拞偱懌傪巭傔偨傝怳傝曉偭偨傝偟偰夛榖偡傞僔乕儞偵偼丄惉悾撈摿偺僗僞僀儖偑尒傜傟傞丅嬍堜惓晇偺嶣塭偑尒帠偩丅惉悾塮夋偵偟偰偼捒偟偔丄嫞攏応偺僔乕儞偑弌偰偔傞丅
敀偄栰廱
1950搶曮丂惉悾枻婌抝丂昡揰亂D亃
彥晈偨偪偺峏惗巤愝傪晳戜偵丄椌挿傗彈堛偲廂梕偝傟偰偄傞彈偨偪偲偺岎棳傪昤偄偨塮夋丅峚岥偺乽栭偺彈偨偪乿傪渇渋偲偝偣傞丅愴屻偺悽憡傪攚宨偲偡傞幮夛攈嶌昳偩偑丄孈傝偑愺偔暯斅偱丄柧傜偐側幐攕嶌偩丅棟夝偁傞慞椙側椌挿乮嶳懞汔丄庒偄両乯偲怱傗偝偟偄彈堛乮斞栰岞巕丄撻愼傒側偄彈桪偩偑榓晽偺惔慯側婄棫偪偩乯偑棟憐壔偝傟偡偓偰偄偰尰幚姶偵朢偟偄丅廂梕幰偺堦恖偱丄崶栺幰偱偁傞壀揷塸師偲偺娭學偵擸傓彈偵丄愴屻偺惉悾塮夋傪巟偊偨榚栶彈桪丄拞杒愮巬巕偑暞偡傞丅偙傟偼拞杒偺惉悾塮夋傊偺弶弌墘嶌偱偼側偄偩傠偆偐丅
2023擭1寧朸擔 旛朰榐209丂乬掅柪婜乭偺惉悾枻婌抝嶌昳丂偦偺1
1942搶曮丂惉悾枻婌抝丂昡揰亂C亃
懢暯梞愴憟恀偭扅拞偺塮夋丅惗妶嬯偵偁偊偓側偑傜抝庤傂偲偮偱懅巕傪堢偰傞晝恊偺暔岅丅晝恊偵悰堜堦榊丄昦嬯偱帺嶦偡傞嵢偵擖峕偨偐巕偑暞偡傞丅慡懱偺棳傟偼彫捗偺乽晝偁傝偒乿傪憐婲偝偣傞丅慜敿偼昻朢惗妶傪偨傫偨傫偲昤偔壠掚寑丅廔斦偼丄惉悾偵偟偰偼捒偟偔愴憟傗弌惇偺婰榐塮憸偑憓擖偝傟丄愴堄崅梘塮夋偺庯傪掓偡傞丅搶嫗壓挰偺儘働丒僔乕儞傗丄嵢偺帺嶦偺捈愙昤幨傪旔偗傞墘弌側偳偵惉悾傜偟偝偑偆偐偑偊傞丅恊愗側嬤強偺晇晈丄摗尨姌懌偲戲懞掑巕偑偄偄丅斵傜偺柡偵暞偡傞庒偒擔偺崒梉婲巕傪尒偰丄栚旲棫偪傗挐傝惡偑尨愡巕偵帡偰偄傞偺偵婥偯偄偨丅
弔偺栚偞傔
1947搶曮丂惉悾枻婌抝丂昡揰亂C亃
媣変旤巕庡墘丅抧曽偺彫偝側挰偱曢傜偡抝彈偺拞崅峑惗偨偪偺岎梀丄巚弔婜偺擸傒傪昤偄偨塮夋丅惉悾偺掅柪婜偲尵傢傟傞帪婜偵偟偰偼弌棃偺偄偄嶌昳偩偲巚偆丅惉悾偼搒夛傪昤偔偺偑岻偄娔撀偩偭偨偑丄乽幵彾偝傫乿傗乽愇拞愭惗乿傗乽傑偛偙傠乿偺傛偆偵丄揷幧傪晳戜偵偟偨塮夋偱傕庤榬傪敪婗偟偨丅偙偺嶌昳傕偦偆偱丄傎偺傏偺偲偟偨憉傗偐側暤埻婥偵曪傑傟偰偄傞丅壆奜儘働偵傛傞帺慠偺晽宨偑偺偳偐偱旤偟偄丄弌偰偔傞恖暔偑傒側恀柺栚側岲恖暔偽偐傝側偺偑旕尰幚揑偩偑丅塮夋偺屻敿偼惈嫵堢偺庡戣偑晜偐傃忋偑傞偑丄偙偺帪戙偲偟偰偼夋婜揑偩偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅僨價儏乕偟偰娫傕側偄媣変旤巕偼弶乆偟偄偑丄傏偔偼愄偐傜偙偺彈桪偑嬯庤偱偁傑傝枺椡傪姶偠側偄丅晝孼偲偟偰巙懞嫪傗斞揷挶巕偑弌墘偟丄偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅
2023擭1寧朸擔 旛朰榐208丂攕愴捈屻偺擔杮塮夋
1945戝塮丂娵崻巀懢榊丂昡揰亂B亃
攕愴偺擭偵岞奐偝傟偨嶃搶嵢嶰榊庡墘偺恖忣婌寑丅僠儍僢僾儕儞偺乽僉僢僪乿偺擔杮斉儕儊僀僋丅峕屗帪戙偺戝堜愳傋傝偺挰丄愳墇恖懌偺棎朶幰丄嶃嵢偼幪偰巕傪廍偄丄巇曽側偔帺暘偱嬯楯偟偰堢偰丄幚偺恊巕偺傛偆偵曢傜偡偑丄戝柤壠偑偦偺巕偼愓庢傝側偺偱堷偒庢傝偨偄偲怽偟弌傞丅寲壾偟傑偔傝丄憱傝夞傝丄揮偘夞傞嶃嵢偺墘媄偑慺惏傜偟偔丄偙傟偼柍朄徏偲暲傇斵偺戙昞嶌偲尵偊傞偩傠偆丅恊巕偺忣垽傗恖懌拠娫偲偺桭忣偑幖偭傐偔側偔昤偐傟偰偍傝丄儔僗僩傕憉傗偐偱屻枴偑椙偄丅
塝搰懢榊偺屻遽
1946搶曮丂惉悾枻婌抝丂昡揰亂D亃
惉悾枻婌抝偺愴屻戞1嶌偩偑丄傑偛偆偐偨側偄幐攕嶌丅柉庡庡媊偺庡挘傗埆摽惌帯偺媻抏偼惉悾偵崌傢側偄丅GHQ偺専墈偵攝椂偟偨夛幮偐傜偺偍巇拝偣婇夋偱偁傠偆丅偙偺塮夋偑僉儍僾儔偺乽孮廜乿傪壓晘偒偵偟偰偄傞偙偲偼柧傜偐偩丅摉帪偼暷崙塮夋偵僸儞僩傪摼偨塮夋偑棳峴偭偨偺偩傠偆偐丅儔僕僆偱斺業偟偨乽晄岾偺嫨傃乿偱拲栚偝傟傞旹傕偠傖偺暅堳暫偵摗揷恑丄怴暦婰帠偵偡傞偨傔斵傪棙梡偡傞怴暦婰幰偵崅曯廏巕偑暞偡傞丅斵傪庢傝崬傫偱搣惃奼戝傪恾傞惌搣偑尰傟丄崅曯偐傜恀憡傪懪偪柧偗傜傟偨摗揷偼僯僙柉庡庡媊傪崘敪偡傞丅捖晠側嬝棫偰偲戝偘偝側墘媄偱丄尒偰偄偰戅孅偡傞丅報徾怺偄偺偼攕愴娫傕側偄搶嫗偺儘働丒僔乕儞偩丅姠釯偺嶳偲壔偟偨崙夛媍帠摪偺廃曈偑捝乆偟偄丅摉帪21嵨偺崅曯廏巕偑偒傟偄偵嶣傟偰偄傞偺傕廍偄傕偺丅傎偐偵悪懞弔巕傗拞懞怢榊偑嫟墘偟偰偄傞丅
2023擭1寧朸擔 旛朰榐207丂50擭戙屻敿偺暷傾僋僔儑儞塮夋
1959暷丂僲乕儅儞丒僷僫儅丂昡揰亂D亃
壠懓偺妋幏傪棈傔偨丄儅僼傿傾偺儃僗偺摝朣偵傑偮傢傞傾僋僔儑儞塮夋丅晳戜偼僇儕僼僅儖僯傾偺揷幧挰偱丄惣晹寑偺傛偆側巇忋偑傝偵側偭偰偍傝丄攈庤側廵寕愴傗僇乕丒僠僃僀僗偑偁傞偑丄婜懸偵斀偟偰偁傑傝柺敀偔側偄丅儅僼傿傾偺偨傔偵摥偔曎岇巑偵儕僠儍乕僪丒僂傿僪儅乕僋丄儃僗偵儕乕丒J丒僐僢僽偑暞偡傞丅僂傿僪儅乕僋偼曐埨姱偺晝恊偑嶦偝傟偨偨傔丄儃僗偺摝朣傪慾巭偟偰寈嶡偵堷偒搉偦偆偲偡傞丅僂傿僪儅乕僋偺尦楒恖傪墘偠傞僥傿僫丒儖僀乕僘偼梔墣側旤彈丅壧庤偱傕偁傝丄偐偮偰尪偺柤斦偲偝傟偨僕儍僘丒償僅乕僇儖丒傾儖僶儉傪嶌偭偰偄傞丅
桿夳 Ransom
1956暷丂傾儗僢僋僗丒僔乕僈儖丂昡揰亂C亃
桿夳傪僥乕儅偵偟偨斊嵾僒僗儁儞僗塮夋偩偑丄斊恖偺憑嵏傛傝旐奞幰壠懓偺嬯擸傗妺摗偑拞怱偵昤偐傟偰偍傝丄斊恖偼晄柧偺傑傑廔傞丅懅巕傪桿夳偝傟偨夛幮幮挿偼丄恎戙嬥偺堷偒搉偟傪嫅斲丄TV傪捠偠偰斊恖偨偪偵挧愴忬傪撍偒偮偗傞丅晝恊偺夛幮幮挿偵僌儗儞丒僼僅乕僪丄偦偺嵢偵僪僫丒儕乕僪偑暞偡傞丅僪僫丒儕乕僪偼摉帪35嵨偩偑丄傑偙偲偵旤偟偔枺椡揑偩丅壠掚偱偺怳晳偼斵彈庡墘偺儂乕儉丒僪儔儅乽偆偪偺儅儅偼悽奅堦乿傪渇渋偲偝偣傞丅傎偐偵怴暦婰幰栶偱偺偪偺婌寑栶幰儗僗儕乕丒僯乕儖僙儞偑弌偰偄傞丅90擭戙偵儕儊僀僋偝傟偨丅
2023擭1寧朸擔 旛朰榐206丂60擭慜屻偺儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉庡墘塮夋
1960暷丂僼儗僢僪丒僕儞僱儅儞丂昡揰亂B亃
杚梤偺巇帠傪媮傔偰僆乕僗僩儔儕傾傪棳傟曕偔堦壠傪昤偄偨塮夋丅僕儞僱儅儞娔撀偵偟偰偼捒偟偄戣嵽偩偑丄岲姶偺帩偰傞戝傜偐側嶌昳偵巇忋偑偭偰偄傞丅壠懓垽丄晇晈偺鉐偑丄僆乕僗僩儕傾偺帺慠晽宨丄怷椦壩嵭傗栄姞傝嫞憟側偳偺憓榖偲偲傕偵丄偠偭偔傝昤偐傟偰偄傞丅扷撨偼掕廧傪寵偭偰椃傪懕偗傛偆偲偡傞偑丄嵢偲巕嫙偼棊偪拝偒偨偄偲婅偄丄鏰鐎偑惗偠傞偑丄嵟屻偼僴僢僺乕丒僄儞僪偲側傞丅柍崪偱偄偄壛尭偩偑壠懓巚偄偺晝恊偲丄偟偭偐傝幰偱垽忣怺偄曣恊偺晇晈傪丄儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僨儃儔丒僇乕偑墘偠傞丅儈僢僠儍儉偼傑偝偵揔栶偩偟丄偄偮傕偼婱晈恖晽偺僇乕偑壔徬偭婥傕側偟偵揇偩傜偗偱摥偔偺傕尒傕偺偩丅偙偺擇恖偼帡崌偄偺僇僢僾儖偱偁傝丄寙嶌乽敀偄嵒乿偱傕尒帠側嫟墘傇傝傪尒偣偰偄偨丅斵傜偲堦弿偵椃傪偡傞僺乕僞乕丒儐僗僠僲僼傕岲墘偟偰偄傞丅
擏懱偺堚嶻 Home from the Hill
1959暷丂償傿儞僙儞僩丒儈僱儕丂昡揰亂C亃
撿晹偺媽壠傪晳戜偵壠懓偺鉐偲抝彈偺垽梸傪昤偔僪儔儅丅撿晹偺挰偺戝抧庡儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偼椻崜側尃椡幰偱庪椔偲彈梀傃偵柧偗曢傟偰偍傝丄嵢偺僄儕僲傾丒僷乕僇乕偲偺娭學偼椻偊愗偭偰偄傞丅懅巕偺僕儑乕僕丒僴儈儖僩儞偼垽忣偵婹偊偨弮杙側彮擭偱丄妛峑偺彈桭払傪岲偒偵側傝丄垽偺側偄壠掚偵斀峈偟偰壠傪弌傞丅僕儑乕僕丒儁僷乕僪偼儈僢僠儍儉偑懠偺彈偵惗傑偣偨巕嫙偩偑丄壠偺巊梡恖偲偟偰摥偄偰偍傝丄僴儈儖僩儞偲拠偑偄偄丅偦偟偰偁傞擔丄斶寑偑婲傞丅慡懱偺暤埻婥偼乽懠恖偺壠乿乽僕儍僀傾儞僣乿乽敀拫偺寛摤乿傪巚傢偣傞丅偙偺庤偺偳傠偳傠偟偨壠懓寑偼岲偒偱偼側偄偑丄僪儔儅偲偟偰偼尒墳偊偑偁傞丅釓婥偑昚偆徖偺晽宨偼儈僢僠儍儉偺壠掚偺徾挜偩傠偆偐丅僄儕僲傾丒僷乕僇乕偑偒傟偄偩丅儁僷乕僪偼偙偺塮夋偺屻乽僥傿僼傽僯乕偱挬怘傪乿偵弌墘偟偰媟岝傪梺傃傞丅 2022擭12寧
2022擭12寧朸擔 2022擭奀奜儈僗僥儕彫愢儀僗僩丒僥儞
俀乽棐偺抧暯乿C丒J丒儃僢僋僗乮憂尦暥屔乯
俁乽僱償傽乕乿働儞丒僼僅儗僢僩乮晑孠幮暥屔乯
係乽僾儘僕僃僋僩丒僿僀儖丒儊傾儕乕乿傾儞僨傿丒僂傿傾乮憗愳彂朳乯
俆乽傢傟傜埮傛傝揤傪尒傞乿僋儕僗丒僂傿僞僇乕乮憗愳彂朳乯
俇乽傾儕僗偑岅傜側偄偙偲偼乿僺乕僞乕丒僗儚儞僜儞乮憂尦暥屔乯
俈乽儀儖儕儞偵捘偪傞埮乿僒僀儌儞丒僗僇儘僂乮憗愳暥屔乯
俉乽儘儞僪儞丒傾僀偺撲乿僔償僅乕儞丒僟僂僪乮憂尦幮乯
俋乽寜敀偺朄懃乿儅僀僋儖丒僐僫儕乕乮島択幮暥屔乯
10乽揤巊偺彎乿儅僀働儖丒儘儃僒儉乮憗愳暥屔乯
2022擭10寧
2022擭10寧朸擔 旛朰榐205丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖棊偪曚廍偄丂偦偺3
1953暷丂僕儑僙僼丒H丒儖僀僗丂昡揰亂C亃
偙傟偼僼傿儖儉丒僲儚乕儖偲尵偆傛傝僋儔僀儉丒傾僋僔儑儞塮夋偵嬤偄丅儖僀僕傾僫偺徖抧偵摝偘偨扙崠廁偲斵傪捛愓偡傞寈姱偺捛偄偮捛傢傟偮偺妶寑偲丄偦偺側偐偱夎惗偊傞斵傜偺桭忣傪昤偔丅庡墘偼償傿僢僩儕僆丒僈僗儅儞偲僶儕乕丒僒儕償傽儞丅彫棻側塮夋偩偑丄偝偡偑偵柤庤J丒H丒儖僀僗丄彫婥枴偄偄僥儞億偱娫墑傃偝偣側偄
尒抦傜偸朘栤幰 Phone Call from a Stranger
1952暷丂僕乕儞丒僱僌儗僗僐丂昡揰亂B亃
偙傟傕戣柤偐傜庴偗傞報徾偲偼堎側偭偰僼傿儖儉丒僲儚乕儖偱偼側偔丄堦庬偺恖忣榖偩丅僫僫儕乕丒僕儑儞僜儞偺媟杮偑傛偔弌棃偰偄傞丅嬻峘偱4恖偺抝彈偑抦傝崌偄丄拠椙偔側傞丅斵傜偺忔偭偨旘峴婡偑捘棊偟丄惗偒巆偭偨抝僎僀儕乕丒儊儕儖偑懠偺3恖偺堚懓傪朘偹丄僼儔僢僔儏僶僢僋偱斵傜偺壠掚偺條巕偑昤偐傟傞丅戝嬝偼乽晳摜夛偺庤挓乿傪憐婲偝偣傞丅4恖偺抝彈偺傂偲傝偵僔僃儕乕丒僂傿儞僞乕僗丄堚懓偺傂偲傝偱壓敿恎晄悘偺彈惈偵儀僥傿丒僨僀償傿僗偑暞偡傞丅抝偼嵟屻偵帺戭偵婣傝丄暘偐傟傛偆偲巚偭偰偄偨嵢偲傛傝傪栠偡丅
2022擭10寧朸擔 旛朰榐204丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖棊偪曚廍偄丂偦偺2
1947暷丂儘僶乕僩丒儌儞僑儊儕乕丂昡揰亂C亃
乽屛拞偺彈乿摨條丄儘僶乕僩丒儌儞僑儊儕乕偑娔撀丒庡墘傪柋傔傞僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅儊僉僔僐偺揷幧挰傪晳戜偵偟偨晄巚媍側枴傢偄偺塮夋偩偑丄弌棃偼偄傑偄偪丅儌儞僑儊儕乕偼嶦偝傟偨愴桭偺彫愗庤傪僱僞偵偟偰僊儍儞僌偐傜嬥傪備偡傝庢傠偆偲偡傞抝傪墘偠傞丅婏柇側戣柤偼丄斵偵晅偒傑偲偆彮彈偑忔傞儊儕乕僑乕儔僂儞僪偺攏偵桼棃偡傞丅
嫸偭偨嶦恖寁夋 Impact
1949暷丂傾乕僒乕丒儖乕價儞丂昡揰亂B亃
B媺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偩偑丄側偐側偐偺孈傝弌偟暔丅庡墘偺僽儔僀傾儞丒僪儞儗償傿偲僄儔丒儗僀儞僘偑偠偮偵偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅慞椙側夛幮幮挿僪儞儗償傿偑埆嵢偺堿杁偵傛傝婾憰岎捠帠屘偱嶦偝傟偐偗傞偑惗偒墑傃丄揷幧挰偱僈僜儕儞僗僞儞僪偺彈僆乕僫乕丄儗僀儞僘偵屬傢傟偰幵廋棟岺偲偟偰摥偒巒傔丄戞2偺恖惗傪憲傞偑丄傗偑偰暅廞偡傞偨傔嵢偺慜偵尰傟傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅廔斦偼嵸敾寑偵側傞丅乽尪偺彈乿偺僸儘僀儞丄儗僀儞僘偑偠偮偵偒傟偄偩丅婄棫偪偵婥昳偑偁傝愗傟挿偺栚偑枺椡傪曻偭偰偄傞丅
2022擭10寧朸擔 旛朰榐203丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖棊偪曚廍偄丂偦偺1
1947暷丂僶僀儘儞丒僴僗僉儞丂昡揰亂C亃
庒偒擔偺僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕偲僇乕僋丒僟僌儔僗偑弶嫟墘偟偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅孻婜傪廔偊偰弌強偟偨儔儞僇僗僞乕偼丄尦憡朹偺僋儔僽丒僆乕僫乕丄僟僌儔僗偵暘偗慜傪傛偙偣偲敆傞偑丄棤愗傜傟偰搟傝傪敋敪偝偣傞丅僟僌儔僗偺垽恖偩偑偺偪偵儔儞僇僗僞乕偵側傃偔僼傽儉丒僼傽僞乕儖栶偺僋儔僽壧庤傪儕僓儀僗丒僗僐僢僩偑墘偠傞丅僟僌儔僗偼僨價儏乕偟偰偟偽傜偔偼丄偙偺傛偆側斱楎側埆恖偺栶偽偐傝傗偭偰偄偨丅塮夋偲偟偰偼偪傚偭偲娫墑傃偟偰偍傝丄偄傑偄偪惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅
斊恖傪摝偑偡側 Cry Danger
1951暷丂儘僶乕僩丒僷儕僢僔儏丂昡揰亂C亃
檒嵾偱暈栶偟偰偄偨抝偑弌強偟丄恀斊恖偲徚偊偨嬥偺偁傝偐傪扵偡榖丅偦傟偵孻帠傗媊懌偺尦奀暫戉堳傗埆搣偺庰応僆乕僫乕偑偐傜傓丅庡墘偼僨傿僢僋丒僷僂僄儖丄僼傽儉丒僼傽僞乕儖偺埆彈偵儘儞僟丒僼儗儈儞僌偑暞偡傞丅朻摢丄儘僒儞僕僃儖僗偵拝偄偨楍幵偐傜僷僂僄儖偑崀傝棫偪丄墂偺儂乕儉偐傜抧壓摴傊偲曕偔僔乕儞偼側偐側偐僇僢僐偄偄偑丄偦偺偁偲偺僩儗乕儔乕僴僂僗偵廧傫偱偐傜埲崀偺揥奐偑娚偔丄怟偡傏傒婥枴丅
2022擭9寧
2022擭9寧朸擔 旛朰榐202丂僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕庡墘偺愴憟僗僷僀塮夋
1945暷丂僼儔儞僋丒儘僀僪丂昡揰亂C亃
懢暯梞愴憟慜栭偺擔杮傪晳戜偵偟偨僗僷僀塮夋偩偑丄捒昳偺晹椶偵擖傞偩傠偆丅敪攧偝傟偨價僨僆偱偼乽搶嫗僗僷僀戝嶌愴乿偲偄偆偲傫偱傕側偄朚戣偵側偭偰偄偨丅尨戣偼乽Blood on the Sun乿丅偙偺Sun偼擔弌偢傞崙丄擔杮偺偙偲偩傠偆丅庡墘偺僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕偼搶嫗偺塸帤怴暦偺曇廤挿偱丄斵偑擔杮偺杁棯傪朶偙偆偲埫桇偡傞榖丅忋奀偐傜棃偨撲偺旤彈偵夰偐偟偺僔儖償傿傾丒僔僪僯乕偑暞偡傞丅僉儍僌僯乕偼擔杮惛恄偵捠偠偰偍傝丄廮摴偺払恖偲偄偆愝掕偱丄摴応偱偺宮屆傗棎摤僔乕儞偱攚晧偄搳偘傗懌暐偄偱憡庤傪搳偘旘偽偡丅嶣塭偝傟偨偺偼僴儕僂僢僪偺僗僞僕僆偱偁傠偆丅搶梞恖偑偨偔偝傫搊応偟丄僇僞僐僩偺擔杮岅傪榖偡偺偑偍偐偟偄丅偝傜偵丄悽奅惇暈偺栰朷傪書偔揷拞媊堦庱憡丄偦偺暃姱偺搶忦塸婡戝嵅偑搊応偟偰枾媍傪弰傜偡偺傕捒柇偦偺傕偺乮攐桪偨偪偺婄偼幚暔偵帡偰偄側偔傕側偄乯丅僉儍僌僯乕偺晹壆偺暻偵揤峜偺幨恀偑忺偭偰偁傝丄僉儍僌僯乕偼旈枾偺忣曬偑彂偐傟偨暥彂傪丄偙偙側傜戝忎晇偩傠偆偲峫偊偰偦偺幨恀偺棤偵塀偟丄晹壆傪憑嵏偟偵棃偨擔杮偺姱寷偼幨恀偺慜偱嵟宧楃偟偰捠傝夁偓傞丄偲偄偆僔乕僋僄儞僗傕徫偄傪桿偆丅偦偺傎偐丄崄峘晽偺栭揦偺條巕傗丄揷拞庱憡偑揤峜暶壓偵怽偟栿側偄偲攈庤偵忺傝棫偰傜傟偨晹壆偱愗暊偡傞応柺側偳丄偢偭偙偗僔乕儞偼悘強偵偁傞丅僗僩乕儕乕偲偟偰捯咫偺崌傢側偄売強偑懡偔丄撪梕偼嶰棳偩偑丄僐儊僨傿塮夋偲偟偰傒傟偽偠偮偵柺敀偄偲尵偊傞丅
慛寣偺忣曬
1947暷丂僿儞儕乕丒僴僒僂僃僀丂昡揰亂B亃
戞2師戝愴拞偺OSS偺妶摦偲忣曬晹堳偨偪偺寛巰偺峴摦傪昤偄偨僗僷僀塮夋丅尨戣偺乽儅僪儗乕僰奨13斣抧乿偼僫僠愯椞壓偺僼儔儞僗丄儖傾乕償儖偺僎僔儏僞億杮晹偺廧強偩丅僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕偼儀僥儔儞忣曬堳偱怴暷忣曬堳傪巜摫偡傞嫵姱傪墘偠傞丅怴暷忣曬堳偺傂偲傝偵愴慜偺擔杮偺塮夋僼傽儞偺怱傪懆偊偨屆偒椙偒帪戙偺僼儔儞僗彈桪傾僫儀儔偑丄忣曬晹偵愽擖偟偨僫僠偺僗僷僀偵埆栶愱栧偺儕僠儍乕僪丒僐儞僥偑暞偡傞丅怴暷忣曬堳偨偪偼尩偟偄孭楙傪廔偊偰僫僠愯椞壓偺僼儔儞僗偵晪偔偑丄晄應偺帠懺偑惗偠偰嫵姱偺僉儍僌僯乕偑帺傜僼儔儞僗偵愽擖偟丄儗僕僗僞儞僗偺彆偗傪摼偰巊柦傪壥偨偦偆偲偡傞丅慜敿偼僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵昤偐傟傞偑丄偙偺偁偨傝偐傜塮夋偼嬞敆姶傪偼傜傫偱偄偔丅偙偺偙傠僉儍僌僯乕偼40戙廔傝偩偑丄戜帉傕恎偺偙側偟傕庒偄崰偲摨條丄帟愗傟椙偔僗僺乕僨傿偩丅乽寣偵愼傑傞懢梲乿偲偼懪偭偰曄傢偭偨僗儕儕儞僌側僗僷僀塮夋偱偁傝丄忢搮揑側僴僢僺乕僄儞僪偱廔傜側偄偺傕儕傾儕僥傿傪姶偠偝偣傞丅
2022擭9寧朸擔 旛朰榐201丂暷崙30擭戙偺堎怓僊儍儞僌塮夋
1935暷丂僂傿儕傾儉丒僉乕儕乕丂昡揰亂B亃
僊儍儞僌塮夋慡惙婜偺僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕庡墘嶌偺傂偲偮丅偙偙偱偼弶婜偺FBI偺妶摦偑昤偐傟偰偍傝丄僉儍僌僯乕偼僊儍儞僌偱偼側偔丄斵傜傪揈敪偡傞FBI憑嵏堳傪墘偠傞丅偍偦傜偔丄懡悢嶌傜傟偨G儊儞塮夋偺愭嬱偗偲側偭偨嶌昳偩傠偆丅僊儍儞僌塮夋偱栕偗偰偄偨儚乕僫乕偑斸敾傪堩傜偡偨傔偵偙傟傪嶌偭偨偲尵傢傟偰偄傞丅桭恖偺FBI怑堳偑僊儍儞僌偵嶦偝傟丄攧傟側偄曎岇巑偺僉儍僌僯乕偼暠婲偟偰FBI偵擖嬊偟丄嬧峴嫮搻堦枴偵傪捛愓偡傞丅僉儍僌僯乕傪弰偭偰丄曎岇巑帪戙偺僈乕儖僼儗儞僪偱偁傞僉儍僶儗乕偺梮傝巕偲丄FBI偵擖偭偰斵偑崨傟傞忋巌偺枀偲偄偆擇恖偺彈偑搊応偡傞丅梮傝巕偵暞偡傞偺偑30乣40擭戙偵妶桇偟偨梔墣側旤彈傾儞丒僪償僅儔僢僋丅僪償僅儖僓乕僋偲摨偠柤慜乮Dvorak乯側偺偱僠僃僐宯偱偁傠偆丅偄偐偵傕僴儕僂僢僪傜偟偄僴僢僺乕僄儞僪塮夋偩偑丄僉儍僌僯乕偺寉夣側僼僢僩儚乕僋偲僥儞億偺偄偄応柺揥奐丄煭棊偨夛榖丄敆椡偁傞廵寕愴偵傛傝丄尒墳偊偺偁傞嶌昳偵側偭偰偄傞丅
廵抏偐搳昜偐
1936暷丂僂傿儕傾儉丒僉乕儕乕丂昡揰亂C亃
偙傟傕儚乕僫乕偺僊儍儞僌塮夋偺傂偲偮偩偑丄乽G儊儞乿偲摨偠偔寈嶡偺憑嵏姱傪幉偲偟偰昤偐傟偰偍傝丄傑偨僊儍儞僌栶偱柤傪側偟偨僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞偑孻帠傪墘偢傞偲偄偆揰偱傕乽G儊儞乿偵偍偗傞僉儍僌僯乕偲婳傪堦偵偟偰偄傞丅僯儏乕儓乕僋巗寈偺孻帠儘價儞僜儞偑寈嶡傪僋價偵側偭偨偲婾憰偟偰僊儍儞僌偺慻怐偵愽擖偟丄埆偺恊嬍傪朶偔暔岅丅儘價儞僜儞偺楒恖栶偺僶乕偺儅僟儉偵僕儑乕儞丒僽儘儞僨儖偑暞偟偰偄傞丅僊儍儞僌慻怐偺No.2偱儘價儞僜儞偲懳寛偡傞埆鐓旕忣側抝傪僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偑墘偠傞丅偙偺偙傠偺儃僈乕僩偼僊儍儞僌塮夋偺埆栶愱栧偺攐桪偩偭偨丅儘價儞僜儞偺岻偝偲懚嵼姶偑嵺棫偭偰偍傝丄撪梕傕僗僺乕僨傿側揥奐偱尒傞幰傪朞偒偝偣側偄丅
2022擭9寧朸擔 旛朰榐200丂壛摗懽偺償傽僀僆儗儞僗塮夋
1967搶塮丂壛摗懽丂昡揰亂B亃
偄傑乽壛摗懽丄塮夋傪岅傞乿偲偄偆杮傪撉傫偱偄傞丅偦傟偱壛摗懽偺慡惙婜偺偙偺2杮偺塮夋偑枹尒偩偭偨偙偲傪巚偄弌偟偨丅偙傟偼埨摗徃庡墘偺朶椡塮夋丅愴屻偺崿棎婜丄摿峌惗偒巆傝偺抝偨偪偑愴巰幰偺堚懓傪媬偆偨傔儅乕働僢僩傪嶌傠偆偲偟偰偄傞丅儕乕僟乕偺埨摗徃偑暃儕乕僟乕偺彫抮挬抝偵偁偲傪戸偟偰孻柋強偵擖傞丅偩偑彫抮偑堚懓傪掲傔弌偟巹暊傪旍傗偟偰偄傞偙偲傪抦偭偨埨摗偼丄扙崠偟偰彫抮偵暅廞偡傞偲偄偆榖丅偙傟偵丄埨摗偑曠偆堚懓偺柡嶗挰峅巕偲偺岎棳丄摨朳偺傗偔偞悈搰摴懢榊偲偺桭忣丄婼偺傛偆側娕庣庒嶳晉嶰榊偲偺妋幏偑棈傓丅帺恎偑摿峌巙婅暫偩偭偨埨摗偼偝偡偑偺娧榎丄帪戙寑偺偍昉條栶偩偭偨嶗挰傕側偐側偐偺擬墘丄栰椙將偺傛偆側僠儞僺儔偵暞偡傞嬤摗惓恇傕偄偄丅
傒側嶦偟偺楈壧
1968徏抾丂壛摗懽丂昡揰亂C亃
摝朣拞偺嶦恖斊偑丄怱傪捠傢偣崌偭偨彮擭傪椫姯偟偰帺嶦偵捛偄崬傫偩5恖偺彈偵暅廞偡傞偨傔師乆偵嶦偟偰偄偔暔岅丅寈嶡偺憑嵏偲斊恖偺斊峴偑岎屳偵昤偐傟傞丅庡墘偺嶦恖斊偵嵅摗堯丄斵偑庝偐傟傞怘摪偺僂僃僀僩儗僗偵攞徿愮宐巕偑暞偡傞丅僂乕儖儕僢僠偺乽崟堖偺壴壟乿偺抝惈斉偲偄偭偨撪梕偺嶌昳偱偁傝丄榓惢僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺庯偑偁傞偑丄嬝棫偰偺晄崌棟偝丄捯咫偺崌傢側偝偑栚棫偮偟丄朶椡惈偲庢偭偰晅偗偨傛偆側姶彎惈偑夁忚偱丄傗傗鐒堈偡傞丅攞徿愮宐巕偺壜垽偝偑嵺棫偮丅峔惉偵嶳揷梞師偑嶲壛偟偰偄傞丅
2022擭9寧朸擔 旛朰榐199丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺儅僀僫乕側塮夋丂偦偺3
1949擭暷丂僨儖儅乕丒僨僀償僗丂昡揰亂C亃
乽杸揤極乿偲摨擭偵惂嶌偝傟偨丄懢暯梞愴憟偵偍偗傞暷奀孯嬻曣晹戉偺妶摦傪昤偔愴憟塮夋丅僎僀儕乕丒僋乕僷乕偼嬻曣僷僀儘僢僩偺巑姱偱丄傗偑偰偼嬻曣傪巜婗偟偰擔杮孯偲愴偆抝傪墘偠傞丅塮夋偼娡挿偺僋乕僷乕偑戅擟偟偰嬻曣偐傜崀傝傞僔乕儞偱巒傑傝丄斵偺庒偒偺擔偺夞憐偲偄偆偐偨偪偱暔岅偑捲傜傟傞丅慜敿偺榖偟偺棳傟偼僕儑儞丒僼僅乕僪傪憐婲偝偣丄夣挷偵恑傓偑丄屻敿偼丄恀庫榩峌寕偐傜巒傑傝丄儈僢僪僂僃乕奀愴丄壂撽奀愴偲愴憟僔乕儞偑偩傜偩傜偲挿偔懕偒丄傗傗戅孅偡傞丅偙偙偵偼幚幨偑偐側傝巊傢傟偰偄傞傛偆偩丅儌僲僋儘嶣塭偩偑丄嵟屻偺4暘偺1傎偳偼側偤偐僇儔乕偵側傞丅僋乕僷乕偺嵢傪僕僃乕儞丒儚僀傾僢僩丄僋乕僷乕偺椙偒忋姱傪僂僅儖僞乕丒僽儗僫儞偑墘偠傞丅
擱偊偮偒偨梸朷
1950暷丂儅僀働儖丒僇乕僥傿僗丂昡揰亂C亃
僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑栂幏偲梸朷偵嬱傜傟傞抝傪墘偠傞僪儔儅丅19悽婭枛偺撿晹偺挰偵攏偵忔偭偰僋乕僷乕偑傗偭偰棃傞丅帺暘偨偪偺堦壠傪捛偄弌偟偨僞僶僐岺応宱塩幰偵暅廞偡傞偨傔偩丅暔岅偼僋乕僷乕偺暅廞偺宱堒偑丄僋乕僷乕丄宱塩幰偺柡僷僩儕僔傾丒僯乕儖丄梒側偠傒偺儘乕儗儞丒僶僐乕儖偺3妏娭學傪棈傔側偑傜昤偐傟傞丅僷僩儕僔傾丒僯乕儖偲儘乕儗儞丒僶僐乕儖偼丄偙偺偙傠20戙敿偽丄旤偟偝偺捀揰偵偁傞丅偙偺塮夋偺慜擭丄僋乕僷乕偲僯乕儖偼乽杸揤極乿偱嫟墘偟丄晄椣娭學偵娮偭偨丅偙偺塮夋偺嶣塭偺崰傕懕偄偰偄偨偐偳偆偐偼暘傜側偄丅偙偙偱偺僯乕儖偼丄僋乕僷乕偺媮崶傪庴偗擖傟傞偑丄嶔傪楳偟偰晝傪帺嶦偵捛偄崬傫偩斵偵暅廞偡傞椻崜旕忣側彈傪墘偠傞丅偦偺埆彈傇傝偼側偐側偐偺傕偺丅偄偭傐偆偺僋乕僷乕傕栂幏偲梸朷偺偲傝偙偵側傝丄嵟屻偼偡傋偰傪幐偭偰挰傪嫀傞丅榖偺棳傟偼乽僕儍僀傾儞僣乿傪憐婲偝偣傞丅岲娍僋乕僷乕偑偙傟傎偳婃柪曃嫹側抝傪墘偠傞偺傕捒偟偄丅塮夋偲偟偰偼傛偔弌棃偰偍傝丄柤庤僼儘僀儞僩偺嶣塭傕尒帠偩偑丄偁傑傝偵埫偔偳傠偳傠偟偰偍傝丄岲偒偵側傟側偄嶌昳偩丅
2022擭9寧朸擔 旛朰榐198丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺儅僀僫乕側塮夋丂偦偺2
1931擭暷丂僆僢僩乕丒僽儘乕儚仌僨償傿僢僪丒僶乕僩儞丂昡揰亂C亃
僋乕僷乕庡墘塮夋偲偟偰偼乽儌儘僢僐乿偺梻擭偵惂嶌偝傟偨惣晹寑丅怴揤抧僇儕僼僅儖僯傾傪傔偞偡杫攏幵戉偺嬯擄偺椃偑昤偐傟傞丅僋乕僷乕偼椃偺僈僀僪栶傪墘偠傞丅杫攏幵戉偼尟偟偄愥偺嶳摴傪墇偊丄僀儞僨傿傾儞偺廝寕傪寕戅偟側偑傜惣傊偲恑傓丅椃偺昤幨偵丄堦恖椃偡傞僼儔儞僗柡儕儕乕丒僟儈僞偲僋乕僷乕偲偺斀敪偟側偑傜庝偐傟崌偆楒偑棈傓丅僋乕僷乕偺庒乆偟偄徫婄偑傑傇偟偄丅
錕錘偲徤墝
1934暷丂儕僠儍乕僪丒儃儗僗儔僂僗僉乕丂昡揰亂D亃
撿杒愴憟拞偺忣曬愴傪昤偔儊儘僪儔儅晽偺塮夋丅幚幙揑側庡墘偼杒孯偺僗僷僀偲偟偰撿孯偺挰偵愽擖偡傞彈桪偵暞偡傞儅儕僆儞丒僨僀償傿僗丅僎僀儕乕丒僋乕僷乕偼僨僀償傿僗偲楒拠偵側傞撿孯偺彨峑傪墘偠傞丅尨戣偺乽Opereator 13乿偼彈僗僷僀丄僨僀償傿僗偺僐乕僪丒僱乕儉丅僴乕僗僩偺垽恖偲偟偰抦傜傟偨儅儕僆儞丒僨僀償傿僗偼丄彈桪偲偟偰偼戝惉偟側偐偭偨偑丄側偐側偐偺旤彈偩丅偄傑偄偪屄惈偑側偄偺偑彈桪偲偟偰戝惉偟側偐偭偨棟桼偩傠偆偐丅
2022擭8寧
2022擭8寧朸擔 旛朰榐197丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺儅僀僫乕側塮夋丂偦偺1
1937暷丂僿儞儕乕丒僴僒僂僃僀丂昡揰亂D亃
19悽婭敿偽偺暷崙丄庒偄慏忔傝僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑朄掛偱奀忋偱偺嶦恖嵾偵傛傝嵸偐傟傛偆偲偟偰偄傞丅偦偙偐傜帪娫偑偝偐偺傏偭偰丄帠審偵帄傞宱堒偑暔岅傜傟傞丅僋乕僷乕偑忔偭偨塸崙偐傜暷崙偵岦偐偆慏偑擄攋偟丄斵偼堦鋤偺儃乕僩偵忔偭偨忔媞傪媬偆偨傔丄偦傟偵孮偑傞巆傝偺忔媞傪奀偵搳偘崬傫偩丅斵偵枾柦傪梌偊偰偄偨塸崙忣曬晹堳偺曎岇偵傛傝丄斵偼庍曻偝傟傞丅僋乕僷乕偺憡朹傪墘偠傞僕儑乕僕丒儔僼僩偼偁傑傝惛嵤偑側偄丅僋乕僷乕偑垽偡傞婱懓偺彈惈傪僼儔儞僔僗丒僨傿乕偑墘偠傞丅僋乕僷乕偼镈憉偲偟偰偄傞偑丄塮夋偺撪梕偼僾儘僢僩偑柇偵擖傝慻傫偱偍傝丄偮偠偮傑偺崌傢側偄売強傕懡偔丄偁傑傝僗僇僢偲偟側偄丅
媣墦偺惥傂
1934暷丂僿儞儕乕丒僴僒僂僃僀丂昡揰亂C亃
僎僀儕乕丒僋乕僷乕偼擼揤婥側嵓媆巘偺栶傪墘偠傞丅堦弿偵曢傜偡憡巚憡垽偺彈偼僉儍儘儖丒儘儞僶乕僪丅僋乕僷乕偼朣偔側偭偨慜嵢偲偺偁偄偩偺5嵨偺柡僔儍乕儕乕丒僥儞僾儖傪丄庤愗傟嬥傪傕傜偭偰慜嵢偺幚壠偺梴巕偵偟傛偆偲偡傞偑丄媣偟傇傝偵夛偭偨変偑巕偺壜垽偝偵傎偩偝傟丄堦弿偵曢傜偦偆偲偲寛怱偡傞丅斵偼柡偲偲傕偵儘儞僶乕僪偑愭忔傝偟偰偄偨僷儕偵峴偒丄3恖偱惗妶偡傞丅斵偼儘儞僶乕僩偲柡偺偨傔偵寴婥偵側傞偑丄埨寧媼偱柡偺妛峑傊偺擖妛嬥偺巟暐偄偵崲傝丄恊偟偔側偭偨晉崑偺榁彈偺庱忺傝傪搻傓偑丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅僋乕僷乕偲儘儞僶乕僪偺旤抝旤彈傇傝傕偝傞偙偲側偑傜丄僔儍乕儕乕丒僥儞僾儖偺柍幾婥側壜垽偝偼昅愩偵恠偔偟偑偨偄丅僥儞僾儖偑巕栶偲偟偰堦悽傪晽阹偟偨偺傕偆側偢偗傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐196丂僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕庡墘偺暥寍塮夋丂偦偺2
1958暷丂僨儖僶乕僩丒儅儞丂昡揰亂B亃
尨嶌偼僥儗儞僗丒儔僥傿僈儞偺彫愢乽Separate Tables乿丅塸崙偺峘挰偵偁傞挿婜懾嵼宆偺彫偝側儂僥儖偵廧傓恖乆傪昤偄偨孮憸寑晽偺塮夋丅僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕偼儂僥儖偺彈宱塩幰僂僃儞僨傿丒僸儔乕偲崶栺偟偰偄傞嶌壠丅傎偐偵丄嫊尵暼偺偁傞戅栶孯恖偵僨償傿僢僪丒僯償儞丄崅埑揑側曣恊偵巟攝偝傟偰偄傞撪婥側僆乕儖僪儈僗偵僨儃儔丒僇乕丄儌僨儖偱儔儞僇僗僞乕偺慜嵢偵儕僞丒僿僀儚乕僗偑暞偡傞丅晳戜偼傎偲傫偳偙偺儂僥儖撪偩偗偵愝掕偝傟偰偄傞丅儔僗僩偱丄寉旝側傢偄偣偮嵾傪斊偟偨僯償儞偼儂僥儖偐傜戅嫀偟傛偆偲偡傞偑丄宱塩幰僸儔乕傗懾嵼媞偺岤堄偵傛傝丄巚偄偲偳傑傞丅僯償儞傪曠偆僇乕偼曣恊偵媡傜偄丄帺棫偟傛偆偲偡傞丅儔儞僇僗僞乕偼僸儔乕偺嫋偟傪摼偰僿僀儚乕僗偲傛傝傪栠偡丅恖忣偺婡旝偵捠偠偨丄婤慠偲偟偨巔惃偺彈宱塩幰栶傪墘偠傞僂僃儞僨傿丒僸儔乕偑偠偮偵慺惏傜偟偔丄敳孮偺懚嵼姶傪曻偭偰偄傞丅
柧擔側偒廫戙
1960暷丂僕儑儞丒僼儔儞働儞僴僀儅乕丂昡揰亂C亃
偙傟偼拞妛惗偺偙傠丄儕傾儖僞僀儉偱尒偰偄傞丅僄償傽儞丒僴儞僞乕乮87暘彁僔儕乕僘偺僄僪丒儅僋儀僀儞乯尨嶌偺旕峴彮擭傪昤偄偨幮夛攈塮夋丅晳戜偼僀僞儕傾宯偺嬸楢戉偲僾僄儖僩儕僐宯偺嬸楢戉偑憟偄傪孞傝曉偡僯儏乕儓乕僋偺昻柉奨丅乽僂僃僗僩僒僀僪暔岅乿傪渇渋偲偝偣傞丅僀僞儕傾宯偺僠儞僺儔3恖偑僾僄儖僩儕僐宯偺栍栚偺彮擭傪巋偟嶦偡丅偡偖偵専嫇偝傟偨斵傜傪丄扴摉偺専帠曗僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕偼戞1媺嶦恖嵾偱婲慽偟傛偆偲偡傞偑丄帠審傪挷傋傞偆偪偵丄暋嶨側梫慺偑棈傒崌偭偰偄傞偄傞偙偲偵婥偯偔丅塮夋偺屻敿偱偼嵸敾偺柾條偑昤偐傟丄堄奜側恀憡偑柧傜偐偵側傞丅儔儞僇僗僞乕偼丄抦帠偵棫岓曗偟傛偆偲偡傞専帠偺巚榝傗丄彮擭偨偪偲摨偠偔昻柉奨偱惗傑傟堢偭偨帺傜偺弌帺偺斅嫴傒偵側傝側偑傜丄怣擮傪娧偸偙偆偲偡傞抝傪岻傒偵墘偠偰偄傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐195丂僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕庡墘偺暥寍塮夋丂偦偺1
1952暷丂僟僯僄儖丒儅儞丂昡揰亂C亃
尨嶌偼僂傿儕傾儉丒僀儞僕偺媃嬋丅暷崙偺揷幧挰偱曢傜偡壠掚偵婲偒偨斶寑傪昤偔丅僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕偼尦傾儖拞偱偄傑偼嬛庰偺夛偵捠偆壡栙側儅僢僒乕僕巘丅偦偺嵢偵僔儍乕儕乕丒僽乕僗偑暞偡傞丅嵢偼偄偮傕悢儠寧慜偵峴曽晄柧偵側偭偨帞偄將偑栠偭偰偔傞偙偲傪婅偭偰偄傞丅戣柤偺僔僶偼偦偺將偵柤慜偩丅儔儞僇僗僞乕偼惛湜側梕巔丄偄偭傐偆偺僽乕僗偼懢偭偨拞擭彈偱丄尒偨栚偺掁傝崌偄偑庢傟偰偄側偄丅幚擭楊傕僽乕僗偺傎偆偑10悢嵨擭忋偩丅斵傜偺壠掚偵庒偄僺僠僺僠偟偨戝妛惗偺彈偺巕偑壓廻偡傞丅偁傞帠審偑偒偭偗偗偱儔儞僇僗僞乕偼庰傪堸傒丄朶傟傑偔偭偰昦堾偵扴偓崬傑傟傞丅壠偵婣偭偨斵偼嵢偲垽傪妋偐傔崌偄丄嵢偼僔僶偑擇搙偲栠傜側偄偙偲傪帺妎偡傞丅僔僶偲偼夁偓嫀偭偨惵弔偺徾挜偩傠偆偐丅
塉傪崀傜偡抝
1956暷丂僕儑僙僼丒傾儞僜僯乕丂昡揰亂B亃
僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕偑岥敧挌庤敧挌偺嵓媆巘傪墘偠偨丄乽僄儖儅乕丒僈儞僩儕乕乿傪巚傢偣傞僼傽儞僞僕乕晽枴偺塮夋丅嫟墘偼僉儍僒儕儞丒僿僢僾僶乕儞丅尨嶌偼儕僠儍乕僪丒僫僢僔儏偺媃嬋丅暷崙拞惣晹偱杚応傪塩傓堦壠偺崶婜傪摝偟偨堦恖柡傪僿僢僾僶乕儞偑墘偠傞丅姳偽偮偱嬯偟傓斵傜偺壠偵儔儞僇僗僞乕偑尰傟丄100僪儖偔傟偨傜塉傪崀傜偟偰傗傞偲尵偆丅堦壠偼敿怣敿媈偱斵偺尵偆偲偍傝塉岊偄偺媀幃傪巒傔傞丅偦偙偵撪婥側曐埨姱僂僃儞僨儖丒僐乕儕乕偑尰傟丄嵓媆偺梕媈偱庤攝偝傟偰偄傞儔儞僇僗僞乕傪戇曔偟傛偆偲偡傞偑丄堦壠偵岊傢傟偰摝偑偟偰傗傞丅偡傞偲偦偙偵塉偑崀傝巒傔傞丅梕巔偵帺怣偺側偄僿僢僾僶乕儞偼儔儞僇僗僞乕偺尵梩偵桬婥偯偗傜傟丄曐埨姱偲寢偽傟傞丅儔儞僇僗僞乕偼堦壠偵岾偣傪梌偊偰嫀偭偰峴偔丅偄偐偵傕傾儊儕僇傜偟偄戝傜偐側塮夋偩丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐194丂僇僂儕僗儅僉偺攕幰3晹嶌丂偦偺2
2006僼傿儞儔儞僪丒暓丒撈丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰亂C亃
3晹嶌偺嵟廔嶌丅僇僂儕僗儅僉偺塮夋偺側偐偱丄偙傟偑偄偪偽傫儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偵嬤帡偡傞嶌昳偐傕偟傟側偄丅摨椈偐傜慳傫偠傜傟丄桭偩偪傕楒恖傕偍傜偢丄屒撈側擔乆傪憲傞庡恖岞偺寈旛堳偼丄恊偟偔側偭偨彈偵閤偝傟偰愞搻抍偺曮愇揦傊偺墴偟擖傝傪嫋偟丄嵞搙摨偠彈偵閤偝傟偰斊恖偵巇棫偰傜傟丄孻柋強偵擖傞丅僇儊儔偼偦傫側斵偺峴摦傪偨傫偨傫偲捛偄偐偗傞偩偗偱丄斵偺怱棟傪偆偐偑傢偣傞傛偆側昤幨偼偄偭偝偄徣偐傟偰偄傞丅斵偼嵟屻偵傛偆傗偔丄偦傟傑偱嫅傫偱偄偨僜乕僙乕僕攧傝偺彈偺垽傪庴偗擖傟傞偐偵尒偊傞丅偍撻愼傒偺僇僥傿丒僆僂僥傿僱儞偼僗乕僷乕偺儗僕學偲偟偰偪傜偭偲搊応偡傞丅
垽偟偺僞僠傾僫
1994僼傿儞儔儞僪丒撈丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰亂B亃
僇僂儕僗儅僉偺拞婜嶌昳丅偍撻愼傒偺儅僢僥傿丒儁儘儞僷乕偲僇僥傿丒僆僂僥傿僱儞偑庡栶傪柋傔傞儌僲僋儘偱嶣傜傟偨儘乕僪丒儉乕償傿乕丅偄偭傁偟偺晄椙傪婥庢傞偑崻偼撪婥偱彈偲岥傕偒偗側偄2恖偺拞擭抝丄巇棫壆偱僐乕僸乕岲偒偺儅僩丒償傽儖僩僱儞偲帺摦幵廋棟岺偱僂僆僢僇岲偒偺儁儘儞僷乕偑丄峴偔摉偰偺側偄僪儔僀償偵弌偐偗丄搑拞偱抦傝崌偭偨2恖偺彈偵棅傑傟丄壗擔傕偐偗偰峘傑偱憲傝撏偗傞榖丅彈偺堦恖偵暞偡傞偺偑僆僂僥傿僱儞丅斵傜偼儂僥儖偺晹壆偱彈偲摨幒偟偰傕丄庤傪埇傞偳偙傠偐丄尵梩偡傜岎傢偝側偄丅偲傏偗偨枴傢偄偲婏柇側儐乕儌傾偲鎫鎮偑慡曇偵偁傆傟偰偄傞丅
嵾偲敱
1983僼傿儞儔儞僪丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰亂D亃
僇僂儕僗儅僉偺挿曇戞1嶌丅僪僗僩僄僼僗僉乕乽嵾偲敱乿偺塮夋壔丅慡懱揑側嶣傝曽偼儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞傪渇渋偲偝偣傞丅朻摢偺怘擏夝懱岺応偺僔乕僋僄儞僗偐傜偟偰僽儗僢僜儞偺塭偑偪傜偮偔丅偺偪偺僇僂儕僗儅僉撈摿偺僗僞僀儖偼傑偩妋棫偝傟偰偍傜偢丄慡懱偲偟偰偺報徾偼惗恀柺栚偱丄戜帉偑懡偔丄廳嬯偟偄丅偲偼偄偊丄壒妝偺巊偄曽傗怓嵤偺攝抲偵偼憗偔傕僇僂儕僗儅僉傜偟偝偑姶偠傜傟傞丅僇僂儕僗儅僉塮夋忢楢偺儅僢僥傿丒儁儘儞僷乕偑抂栶偱婄傪弌偟偰偄傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐193丂僇僂儕僗儅僉偺攕幰3晹嶌丂偦偺1
1996僼傿儞儔儞僪丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰亂A亃
僇僂儕僗儅僉偺乽僼傿儞儔儞僪3晹嶌乿傑偨偼乽攕幰3晹嶌乿偲徧偝傟傞僔儕乕僘偺戞1嶌丅庡墘偼斵偺塮夋忢楢偺僇僥傿丒僆僂僥傿僱儞丅儗僗僩儔儞偺媼巇挿傪柋傔傞嵢偼丄巗揹塣揮巑偺晇偲偮偮傑偟偔曢傜偟偰偄偨偑丄巗揹偼晄嫷偵傛傞恖堳惍棟丄儗僗僩儔儞偼戝庤僠僃乕儞偵傛傞攦廂偺偨傔丄2恖偲傕幐嬈偟偰偟傑偆丅斵傜偼怑扵偟偵杬憱偡傞偑側偐側偐尒偮偐傜偢丄崲媷偡傞丅嵢偼傗偑偰丄偐偮偰偺儗僗僩儔儞宱塩幰偺彆偗傪摼偰丄偐偮偰偺廬嬈堳拠娫傪廤傔丄怴偟偄儗僗僩儔儞傪奐偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僥儗價丒僪儔儅偱傛偔尒偐偗傞傛偆側丄偁傝傆傟偨側榖偩偑丄僇僂儕僗儅僉撈摿偺昤偒曽偵傛傝丄偲傏偗偨枴傢偄傪偨偨偊偨丄儐乕儌傾偲斶垼偑側偄傑偤偺儐僯乕僋側嶌昳偵側偭偰偄傞丅廔斦丄儗僗僩儔儞偺奐揦偺擔丄扤傕媞偑棃偢廬嬈堳偼傗偒傕偒偡傞偑丄傗偑偰堦恖丄擇恖偲媞偑朘傟丄嵟屻偵枮堳偵側傞偲偄偆僔乕僋僄儞僗偑丄忢搮揑偱偼偁傞偑丄嫽庯傪惙傝忋偘傞丅
夁嫀偺側偄抝
2002僼傿儞儔儞僪丒撈丒暓丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰亂B亃
3晹嶌偺戞2嶌丅椃偺抝偑楍幵偱僿儖僔儞僉偵拝偒丄岞墍偱堦栭傪柧偐偦偆偲偡傞偑丄朶娍偵廝傢傟丄恎偖傞傒攳偑傟偰幏漍偵墸懪偝傟丄昺巰偺忬懺偱昦堾偵扴偓崬傑傟傞丅婏愓揑偵慼惗偟偨斵偼奀曈偱崹搢偟偰偄傞偲偙傠傪廧柉偵彆偗傜傟傞偑丄偡傋偰偺婰壇傪幐偭偰偄偨丅峘挰偺僐儞僥僫傪梌偊傜傟偰廧傒拝偄偨斵偼丄恖娫偲偟偰偺惗妶傪庢傝栠偟丄媬悽孯偺彈惈僇僥傿丒僆僂僐僱儞偲恊偟偔側傞丅傗偑偰斵偼恎尦偑敾柧偟丄嵢偑廧傓尦偺壠偵栠傞偑丄嵢偲暿傟偰僿儖僔儞僉偺峘挰偵栠傝丄媬悽孯偺彈惈偲寢偽傟傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偁傝傆傟偨儊儘僪儔儅偺傛偆側榖偩偑丄僇僂儕僗儅僉偺庤偵偐偐傞偲丄僐儞僥僫偱惗妶偡傞昻偟偄恖乆偺儐乕儌儔僗偩偑忣垽偨偩傛偆忣宨傗丄姶忣傪攔偟偨栶幰偺昞忣傗夛榖偐傜棫偪忋傞晄巚媍側恖娫枴偵傛傝丄怱壏傑傞垽偡傋偒塮夋偵側傞丅庡恖岞偺抝偑怘摪幵偱庻巌傪傪怘傋側偑傜擔杮庰傪堸傒丄墘壧偺傛偆側擔杮偺壧偑棳傟傞僔乕儞偑報徾偵巆傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐192丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑庡墘偟偨愴屻偺惣晹寑丂偦偺3
1955暷丂僆僢僩乕丒僾儗儈儞僕儍乕丂昡揰亂C亃
偙傟偼惣晹寑偱偼側偔丄幚榖偵婎偯偔朄掛僪儔儅丅僋乕僷乕偼暷崙嬻孯偺晝偲尵傢傟偨價儕乕丒儈僢僠僃儖傪墘偠傞丅帪偼1920擭戙丅嬻孯偺廳梫惈傪慽偊傞偑庢傝崌偭偰傕傜偊偢丄楎埆側娐嫬偵抲偐傟偨傑傑偺棨孯峲嬻戉偺忬嫷偵嬈傪幭傗偟丄戞1師戝愴偺嬻偺塸梇儈僢僠僃儖彨孯乮崀奿偝傟偰戝嵅偵側傞乯偼怴暦偵棨奀孯巜摫幰偨偪傪斸敾偡傞惡柧傪敪昞偟丄偦傟偵傛偭偰孯朄夛媍偵偐偗傜傟傞丅儈僢僠僃儖偼姼偊偰偙偺孯帠朄掛偱嵸偐傟傞偙偲偵傛傝丄庡挘偺惓摉惈傪悽娫偵抦傜偟傔丄怣擮傪娧偙偆偲偡傞丅塮夋偺3暘偺2偼孯朄夛媍偺嬞敆偟偨傗傝庢傝偵妱偐傟偰偄傞丅朄掛偱偺斵偺徹尵偵偼丄偺偪偺恀庫榩峌寕傪梊尒偡傞傛偆側敪尵傕弌偰偔傞丅娔撀偼偙偆偄偆塮夋偑摼堄側僾儗儈儞僕儍乕丅斵偼偙偺偁偲丄摨庯岦偺朄掛塮夋乽埥傞嶦恖乿傪嶣偭偨丅嬯擸偡傞儈僢僠僃儖傪墘偠傞僋乕僷乕偼偝偡偑偺娧榎丅偹偪偹偪偲儈僢僠僃儖傪栤偄媗傔傞専帠栶傪儘僢僪丒僗僞僀僈乕憺乆偟偘偵墘偠偰偄傞丅
惣晹偺恖
1958暷丂傾儞僜僯乕丒儅儞丂昡揰亂D亃
僋乕僷乕偑墘偠傞偺偼丄偐偮偰嫮搻抍偺堦枴偩偭偨偑丄偄傑偼恀偭摉側惗妶傪憲偭偰偄傞抝丅斵偼恾傜偢傕偐偮偰偺堦枴偲嵞夛偟丄嵞傃嫮搻偺拠娫擖傝傪偡傞傛偆嫮惂偝傟傞丅僋乕僷乕偵摨峴偡傞庰応偺壧庤偵僕儏儕乕丒儘儞僪儞丄堦枴偺庱椞偱僋乕僷乕偺廸晝偵儕乕丒J丒僐僢僽偑暞偡傞丅偠偮偵埫偄丄堿嶴側塮夋偩丅傾儞僜僯乕丒儅儞偺歯媠庯枴偼堦楢偺僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩庡墘偺惣晹寑偱奯娫尒傜傟偨偑丄偙偺塮夋偱偼偦傟偑慡奐偟偰偍傝丄庡恖岞偑夁嫀偺栂幏偵嵞傃廁傢傟傞嬝棫偰偲偄偄丄嵟屻偺僑乕僗僩僞僂儞偱偺嶦偟崌偄偲偄偄丄堿烼側嬻婥偑慡懱傪偍偍偭偰偄傞丅傑傞偱屻偺儅僇儘僯丒僂僃僗僞儞傪愭庢傝偟偨偐偺傛偆側塮夋偩丅儘儞僪儞偼僗僩儕僢僾傪嫮梫偝傟偨傝僐僢僽偵斊偝傟偨傝偲丄嶶乆側栚偵偁偆丅僋乕僷乕傛傝10嵨傕庒偄偺偵僋乕僷乕傪堢偰忋偘偨廸晝傪墘偠傞僐僢僽偼丄敿暘婥偑嫸偭偨傛偆側榁恖偺栶傪夦墘偟偰偄傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐191丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑庡墘偟偨愴屻偺惣晹寑丂偦偺2
1950暷丂僗僠儏傾乕僩丒僿僀僗儔乕丂昡揰亂C亃
晳戜偼撿杒愴憟捈屻偺怴嫽偺挰僟儔僗丅僋乕僷乕偼壠懓偺媤傪扵偡撿孯僎儕儔偺偍恞偹幰傪墘偠傞丅僾儘僢僩偼崬傒擖偭偰偄偰丄僗僩乕儕乕傪梫栺偡傞偺偑擄偟偄丅僋乕僷乕偼怴擟曐埨姱偵側傝偡傑偟丄僟儔僗偺挰傪媿帹偭偰杚応庡偐傜媿傪扗偄庢傞埆娍孼掜偲懳寛偡傞丅僋乕僷乕偼嵟屻偵杚応庡偺柡儖乕僗丒儘乕儅儞偲寢偽傟傞丅弌偩偟偼夣挷偩偑丄搑拞偐傜傕偨傕偨偟偨揥奐偵側傝丄偄傑偄偪惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅嵟屻偺僋乕僷乕偲埆偺恊嬍儗僀儌儞僪丒儅僢僙僀偲偺埫埮偱偺寛摤偺僔乕儞偼敆椡偑偁傞丅
僗僾儕儞僌僼傿乕儖僪廵
1952暷丂傾儞僪儗丒僪丒僩僗丂昡揰亂B亃
撿杒愴憟偺嵟拞丄杒孯偺桝憲晹戉偑昿斏偵撿孯僎儕儔偵廝傢傟傞偨傔丄撪捠幰偑偄傞偲妎偭偨杒孯彨峑偺僋乕僷乕偼丄巜婗偺幐攕偵傛偭偰孯戉偐傜捛曻偝傟偨傛偆偵尒偣偐偗丄僗僷僀偲偟偰僎儕儔晹戉偵愽擖偡傞丅柤庤傾儞僪儗丒僪丒僩僗偺僣儃傪怱摼偨墘弌偑嵺棫偭偰偄傞丅僪丒僩僗偼僂僅儖僔儏乣僔乕僎儖偺宯晥偵楢側傞屸妝塮夋偺嫄彔偲尵偭偰偄偄偩傠偆丅嬞敆姶偼嵟屻傑偱帩懕偟偰偍傝丄僋乕僷乕偲壠懓偲偺妺摗傕夁晄懌側偔昤偐傟偰偄傞丅僋乕僷乕偼懡彮擭傪庢偭偨姶偼偁傞偑丄媊嫚怱偵晉傓桬幰傪尒帠偵墘偠偰偄傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐190丂60擭慜屻偺傾儊儕僇壒妝塮夋
1961暷丂儅乕僥傿儞丒儕僢僩丂昡揰亂C亃
億乕儖丒僯儏乕儅儞庡墘偺僕儍僘傪戣嵽偵偟偨壒妝塮夋丅壒妝偼慡柺揑偵僨儏乕僋丒僄儕儞僩儞偺僗僐傾偑巊傢傟偰偄傞丅僯儏乕儅儞偼嵢偺僕儑傾儞丒僂僢僪儚乕僪偲嫟墘偡傞丅暷崙恖偺僩儘儞儃乕儞憈幰僯儏乕儅儞偼僷儕偵廧傒丄恊桭偺僒僢僋憈幰僔僪僯乕丒億儚僠僄偲偲傕偵僶儞僪傪棪偄偰僋儔僽偵弌墘偟丄恖婥傪攷偟偰偄傞丅暷崙偐傜娤岝椃峴偱傗偭偰棃偨2恖偺彈僂僢僪儚乕僪偲僟僀傾儞丒僉儍儘儖偑墘憈傪挳偒偵僋儔僽傪朘傟丄僯儏乕儅儞偲僂僢僪儚乕僪丄億儚僠僄偲僉儍儘儖偑偦傟偧傟楒拠偵側傞丅斵傜偼彈偨偪偐傜堦弿偵婣崙偟傛偆偲岊傢傟傞偑丄僯儏乕儅儞偼僷儕偱嶌嬋傪曌嫮偟偨偄丄億儚僠僄偼恖庬曃尒偺側偄僷儕偵偄偨偄丄偲偄偆棟桼偱巚偄擸傓丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅墘憈偺悂偒懼偊偼扤偩傠偆丅億儚僠僄偼偍偦傜偔億乕儖丒僑儞僓儖償僃僗丄僯儏乕儅儞偼儘乕儗儞僗丒僽儔僂儞偺傛偆偩偑丄傛偔暘偐傜側偄丅僯儏乕儅儞偑墘憈偡傞巇憪偼尒帠偱丄傑傞偱杮摉偵悂偄偰偄傞傛偆偩丅儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偑儚僀儖僪儅儞偲偄偆栶柤偺桳柤僩儔儞儁僢僞乕偲偟偰弌墘偟丄僯儏乕儅儞偺僶儞僪丒儊儞僶乕偲僕儍儉丒僙僢僔儑儞傪偡傞丅僙儖僕儏丒儗僕傾僯偑僶儞僪偺僊僞儕僗僩傪墘偠偰偄傞丅
傢偑楒偼廔傝偸
1960暷丂僠儍乕儖僘丒償傿僟乕丂昡揰亂C亃
僟乕僋丒儃僈乕僪偑庡墘偡傞僼儔儞僣丒儕僗僩偺揱婰塮夋丅儕僗僩偼幚嵺偺斵偲摨偠偔丄帺懜怱偺嫮偄丄婱懓偺彈偵傕偰傞丄挻愨媄岻偺恖婥僺傾僯僗僩偲愝掕偝傟偰偄傞丅斵偼儘僔傾偺峜懓偱偁傞岞庉晇恖僇儘儕乕僰乮僉儍僾僔乕僰乯偵堦栚崨傟偟丄偦傟傑偱摨惐偟偰偍傝丄巕嫙傑偱傕偆偗偨攲庉晇恖傪幪偰偰丄斵彈偲寢崶偟傛偆偲偡傞偑丄儘乕儅朄墹偐傜棧崶偺嫋壜偑摼傜傟偢丄愨朷偟偰憁堾偵擖傝丄嶌嬋偵愱擮偡傞丄偲偄偆儊儘僪儔儅丅儃僈乕僪偺僺傾僲墘憈僔乕儞偑傆傫偩傫偵憓擖偝傟傞偑丄嬃偔偺偼丄乽僷儕偺椃廌乿偺僯儏乕儅儞傕偦偆偩偭偨偑丄偦傟埲忋偵儃僈乕僪偺庤偺摦偒偑慺惏傜偟偔丄慺恖栚偵偼杮摉偵抏偄偰偄傞傛偆偵尒偊傞偙偲偩丅桭恖偲偟偰僔儑僷儞傗僕儑儖僕儏丒僒儞僪丄嬱偗弌偟偺嶌嬋壠偲偟偰儚乕僌僫乕傕搊応偡傞丅僉儍僾僔乕僰偺旤偟偝偑嵺棫偭偰偄傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐189丂僎僀儕乕丒僋乕僷乕偑庡墘偟偨愴屻偺惣晹寑丂偦偺1
1945暷丂僗僠儏傾乕僩丒僿僀僗儔乕丂昡揰亂B亃
僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺惣晹寑偱丄捒偟偔僋乕僷乕杮恖偑僾儘僨儏乕僒乕傪扴摉偟偰偄傞丅僋乕僷乕偑墘偠傞偺偼壧偑岲偒偱偍恖岲偟偱対廵偑壓庤偲偄偆棳傟幰丅慡懱偵僐儊僨傿丒僞僢僠偱偁傝丄庡恖岞偺棳傟幰偑憗寕偪偺埆娍僟儞丒僨儏儕僄偵娫堘傢傟傞偙偲偐傜憶摦偑婲偙傞丅僨儏儕僄偺垽恖儘儗僢僞丒儎儞僌偼僋乕僷乕傪棙梡偟偰僨儏儕僄傪摝朣偝偣傛偆偲偡傞偑丄慞椙側僋乕僷乕偵庝偐傟丄嶰妏娭學偵側傞丅嵟屻偼僋乕僷乕傪嶦偦偆偲偡傞僨儏儕僄傪儎儞僌偑寕偪丄僋乕僷乕偲儎儞僌偑寢偽傟傞丅慺杙側帩偪枴傪弌偡僋乕僷乕偲偲傕偵丄嵟屻偵幩寕偺柤庤傇傝傪尒偣傞揝壩彈儘儗僢僞丒儎儞僌偑側偐側偐偄偄丅儈儖僩儞丒僋儔僗僫乕偺嶣塭傕弌怓丅
墦偄懢屰
1951暷丂儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏丂昡揰亂C亃
奐戱帪戙偺僼儘儕僟偱偺暷崙孯戉偲僙儈僲乕儖丒僀儞僨傿傾儞偲偺愴偄傪昤偄偨塮夋丅帪戙愝掕偼惣晹寑偩偑丄撪梕偲偟偰偼妶寑愴憟塮夋偵嬤偄丅僎僀儕乕丒僋乕僷乕棪偄傞彫戉偼揋偺嵲傪攋夡偟偨偑丄僀儞僨傿傾儞偺戝孯偵捛寕偝傟偰幖抧懷傪摝偘夞傞丅嵟屻偼僋乕僷乕偲揋偺廢挿偲偺堦婻懪偪偲側傝丄僋乕僷乕偼悈拞偱偺奿摤偱憡庤傪搢偡丅僂僅儖僔儏傜偟偄庤嵺偺偄偄墘弌偲夣揔側応柺揥奐偑偄偄丅慡曇丄僼儘儕僟偱儘働偝傟偰偍傝丄僄償傽僌儗僀僘幖抧懷偺旤偟偄帺慠晽宨偑報徾偵巆傞丅僋乕僷乕偼镈憉偲偟偰偄傞偑丄憡庤栶偺儅儕丒傾儖僪儞偲偄偆撻愼傒偺側偄彈桪偑償傽乕僕僯傾丒儊僀儓偵帡偨偁傑傝昳偺側偄婄偮偒偱丄嫽偑嶍偑傟傞丅
2022擭8寧朸擔 旛朰榐188丂30擭戙偺傾儊儕僇塮夋
1935暷丂僼儔儞僋丒儘僀僪丂昡揰亂C亃
18悽婭枛偵婲偒偨塸崙慏僶僂儞僥傿崋斀棎帠審偺僴儕僂僢僪偵傛傞嵟弶偺塮夋壔丅偙偺儕儊僀僋偱偁傞儅乕儘儞丒僽儔儞僪庡墘偺戝嶌乽慏娡僶僂儞僥傿乿乮1962乯偼拞妛惗偺偲偒丄儕傾儖丒僞僀儉偱嫻傪偲偒傔偐偟側偑傜尒偨丅岎堈偺偨傔撿梞偵慏弌偟偨僶僂儞僥傿崋丅悈晇偨偪偼慏挿偺椻崜柍帨斶側柦椷偵嬯偟傔傜傟側偑傜丄傛偆傗偔僞僸僠偵摓拝偡傞丅妝墍偱偟偽傜偔夁偛偟偨偁偲丄塸崙傊偺婣搑丄慏挿偺媠懸偵懴偊偐偹偨悈晇偨偪偼丄峲奀巑偺巜婗偺傕偲丄斀棎傪婲偙偡偲偄偆暔岅丅墶朶側慏挿偵僠儍乕儖僘丒儘乕僩儞丄恖朷偺撃偄惓媊娍偺峲奀巑偵僋儔乕僋丒僎僀僽儖丄嫸尵夞偟栶偺怴擟巑姱岓曗惗偵僼儔儞僠儑僢僩丒僩乕儞偑暞偡傞丅偄偮傕側偑傜丄僒僨傿僗僥傿僢僋側慏挿栶傪憺乆偟偘偵墘偠傞儘乕僩儞偑岻偄丅弌棃偺偄偄屸妝嶌偩丅
僝儔偺惗奤
1937暷丂傾僫僩乕儖丒儕僩償傽僋丂昡揰亂C亃
19悽婭枛偺僼儔儞僗幮夛攈帺慠庡媊嶌壠僄儈乕儖丒僝儔偺揱婰塮夋丅慜敿偱偼僝儔偑昻崲惗妶偐傜敳偗弌偟丄嶌壠偲偟偰惉岟偡傞傑偱偑昤偐傟丄屻敿偱偼僝儔偑旐崘偺柍幚傪怣偠偰棨孯偺媆嵩傪朶偔偨傔偵愴偭偨僪儗僼儏僗帠審偺揯枛偑昤偐傟傞丅庡墘偺億乕儖丒儉僯偼墘媄夁忚偺姶偑偁傝丄傗傗嫽偞傔偡傞丅慞嬍偲埆嬍偑偼偭偒傝恾幃壔偝傟偰偍傝丄傑偨僝儔偑惓媊偲恀幚傪娧偄偨塸梇偲偟偰昤偐傟偰偍傝丄扨弮偱怺傒偺側偄塮夋偩偑丄暘偐傝傗偡偄偙偲偼妋偐偩丅僝儔偺恊桭偲偟偰丄僙僓儞僰傗傾僫僩乕儖丒僼儔儞僗偑搊応偡傞丅
2022擭7寧
2022擭7寧朸擔 旛朰榐187丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偺塮夋丂偦偺2
1969暓丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰亂B亃
尨嶌偼僪僗僩僄僼僗僉乕偺抁曇彫愢丅幙壆傪塩傓抝偑揦傪朘傟偨妛惗晽偺庒偄彈偵堦栚崨傟偟偰寢崶偡傞偑丄傗偑偰晇晈偺娭學偵攇晽偑棫偪丄嵢偑帺嶦偡傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅偙傟偑僨價儏乕嶌偲側傞庡墘偺僪儈僯僋丒僒儞僟偼傑傞偱彮彈偺傛偆偵捝乆偟偄丅塮夋偼嵢偑晹壆偺憢偐傜旘傃崀傝傞僔乕儞偱巒傑傝丄晇偑晹壆偺儀僢僩偵墶偨偊傜傟偨嵢偺巰懱傪慜偵偟偰岅傞夞憐偵傛偭偰恑傓丅偄偮傕偺傛偆偵丄弌墘幰偼婌搟垼妝偺昞忣傪揙掙偟偰昞偝側偄丅偐偡偐側徫偄惡偼埫埮偺側偐偱暦偙偊傞偩偗偩偟丄彈偼婄傪偍偍偭偰媰偒丄媰偒婄傪尒偣側偄丅摴抂偵嶇偔壴丄摦暔墍偱摦偒夞傞墡丄攷暔娰偺崪奿昗杮側偳偺昤幨偼偡傋偰柍婡揑偱杮嬝偲偼娭學側偝偦偆偩偑丄慡懱傪捠偟偰尒傞偲偮側偑傝偑姶偠傜傟側偄偱傕側偄丅寢崶屻偟偽傜偔偟偰嵢偼栭偳偙偐偵弌偐偗傞傛偆偵側傞偑丄偳偙偱壗傪偟偰偄傞偺偐偼愢柧偝傟側偄丅偦傟偲側偄埫帵偵傛偭偰丄庒偄抝偲晜婥偟偰偄傞傛偆偩偲娤媞偼姶偠傞偑丅朻摢偲枛旜偺丄憢曈偺儀儔儞僟偺堉巕偑梙傟丄僥乕僽儖偑搢傟偰壴時偑棊偪丄敀偄僗僇乕僼偑拡偵晳偆僔乕儞偑報徾偵巆傞丅
敀栭
1971暓丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰亂C亃
偙傟傕僪僗僩僄僼僗僉乕尨嶌抁曇彫愢偺塮夋壔丅応強傗帪戙愝掕偼堎側傞偑丄斾妑揑尨嶌偵拤幚偵塮憸壔偝傟偰偄傞丅償傿僗僐儞僥傿娔撀斉偲傛偔斾妑偝傟傞偑丄桪楎傪岅傞偺偼嬸偐側偙偲丅帇揰傕僗僞僀儖傕傑偭偨偔堘偆塮夋側偺偩偐傜丅偁傞栭丄夋妛惗偺抝偑僙乕僰愳偵恎搳偘偟傛偆偲偡傞彈傪彆偗傞丅彈偼1擭慜偵椃棫偭偨楒恖偲偦偙偱偺嵞夛傪栺懇偟偰偄偨丅晅偒崌偭偰榖傪偟偰偄傞偆偪偵抝偼彈偵寖偟偄楒怱傪書偔丅彈傕抝偵岲堄傪婑偣巒傔傞偑ゥ苽X僩乕儕乕丅偄偮傕偺僽儗僢僜儞塮夋偲摨偠偔丄攐桪偺墘媄偼柍昞忣丄柍姶忣偩偟丄杮嬝偵偼娭學側偄僔乕僋僄儞僗傪丄偄偐偵傕娭學偁傝偦偆偵憓擖偡傞偺傕僽儗僢僜儞棳偩丅偟偐偟偙偙偵偼丄庡恖岞偺抝乮僕儍儞僺僄乕儖丒儗僆偵偦偭偔傝偩乯偺擔忢惗妶偑忴偡儐乕儌傾丄栭偺僷儕偺嶨摜傗億儞僰僼偺嫶偺壓傪峴偔娤岝慏偑忴偡儘儅儞僥傿僔僘儉丄僗僩儕乕僩丒儈儏乕僕僔儍儞偑憈偱傞儃僒僲償傽晽偺億僢僾丒僜儞僌偑忴偡捠懎惈丄庡恖岞偺彈偺棁恎偑忴偡僄儘僗側偳丄僽儗僢僜儞偵偟偰偼堎怓偺梫慺偑嶶尒偝傟傞丅
2022擭7寧朸擔 旛朰榐186丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偺塮夋丂偦偺1
1944暓丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰亂C亃
僽儗僢僜儞偺挿曇戞2嶌丅愴屻偺嶌昳偲偼堎側傝丄偙偙偱偼傑偩僽儗僢僜儞偼揱摑偵増偭偨嶣傝曽傪偟偰偍傝丄億乕儖丒儀儖僫乕儖丄儅儕傾丒僇僓儗僗偲偄偆栶幰傪巊偭偰丄傑偲傕側墘媄傪偝偣偰偄傞丅僾儘僢僩傕丄抝偵嫀傜傟偨彈偑丄暅廞偺偨傔丄偄偐偑傢偟偄梮傝巕偺彈傪抝偵堷偒崌傢偣傞偲偄偆丄僼儔儞僗塮夋偵傛偔偁傞暔岅偑婎偵側偭偰偄傞丅僕儍儞丒僐僋僩乕偑彂偄偨戜帉偼偄偐偵傕媃嬋晽偱丄嫊峔惈傪嵺棫偨偣傞丅
彮彈儉僔僃僢僩
1967暓丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰亂B亃
揷幧偺懞偵廧傓彮彈偺傑偭偨偔媬偄偺側偄庴擄暔岅丅彮彈偼昻媷壠掚偱壠帠傪偟丄昦婥偱暁偣傞曣恊傪娕昦偟丄愒傫朧偺悽榖傪偟丄晝恊偐傜朶椡傪怳傞傢傟丄妛峑偱偼曁傑傟丄愭惗偵斀峈偟丄妛桭傗嬤強偵婃側側懺搙傪庢傝丄桭偩偪傕側偔丄巤偟傪嫅斲偟丄枾椔幰偵斊偝傟傞丅斵彈偼偄偮傕屒撈偱丄柌傕婓朷傕側偄偟丄恄偺壎挒傕側偄丅弌墘幰偺忣姶偺昞弌偼偄偭偝偄攔偝傟偰偍傝丄斵彈偺斶嶴側擔忢惗妶偑椻揙側僇儊儔偵傛傝扺乆偲昤偐傟傞丅報徾偵巆傞僔乕儞偑2儠強偁傞丅傂偲偮偼悌偵偐偐偭偨捁傗揝朇偱寕偨傟偨僂僒僊偑栥偊嬯偟傓僔乕儞丄傕偆傂偲偮偼丄廔巒柍昞忣側彮彈偑丄梀墍抧偱僶儞僺儞僌僇乕偵忔偭偰徫婄傪晜偐傋傞僔乕儞偩丅偙傟偼乽揷幧巌嵳偺擔婰乿偲摨偠偔儀儖僫僲僗偺尨嶌偩偲偄偆丅側偤偙傫側塮夋傪嶌偭偨偺偐丄傛偔暘偐傜側偄丅偦偟偰丄偦傟側偺偵側偤夋柺偵庝偐傟丄彮彈偺塣柦偵尒擖偭偰偟傑偆偺偐傕丄暘偐傜側偄丅
2022擭7寧朸擔 旛朰榐185丂嵟嬤偺塮夋
1996塸丂儅僀僋丒儕乕丂昡揰亂A亃
庡墘丗僽儗儞僟丒僽儗僢僔儞丄僥傿儌僔乕丒僗億乕儖
偙偺悽奅偵巆偝傟偰
2019僴儞僈儕乕丂僶儖僫僶乕僔儏丒僩乕僩丂昡揰亂B亃
庡墘丗僇乕儘僀丒僴僀僨儏僋丄傾價僎乕儖丒僙乕働
2022擭7寧朸擔 旛朰榐184丂儀僥傿丒僨僀償傿僗偺弶婜庡墘塮夋
1934暷丂僕儑儞丒僋儘儉僂僃儖丂昡揰亂B亃
僒儅僙僢僩丒儌乕儉尨嶌乽恖娫偺鉐乿偺塮夋壔丅儀僥傿丒僨僀償傿僗偑偲傫偱傕側偄埆彈傪墘偠傞丅恀柺栚側堛妛惗儗僗儕乕丒僴儚乕僪偼僇僼僃偺僂僃僀僩儗僗丄儀僥傿丒僨僀償傿僗偵崨傟崬傓偑丄斵彈偼婬戙偺埆彈偱丄僴儚乕僪偺垽傪庤嬍偵庢傝丄帺桼杬曻丄師乆偵偄傠傫側抝偲娭學傪寢傃丄嵟屻偵棊偪傇傟壥偰傞丅僴儚乕僪偼偦傫側僨僀償傿僗偵垽憐傪恠偐偟側偑傜傕丄斵彈偺偙偲偑朰傟傜傟側偄丅壜垽偝偲埆杺惈偑摨嫃偡傞彈傪婐乆偲偟偰墘偠傞僨僀償傿僗偑丄偲偵偐偔惁偄丅
儅儖僞偺戦
1936暷丂僂傿儕傾儉丒僨傿僞乕儗丂昡揰亂E亃
僴儊僢僩尨嶌乽儅儖僞偺戦乿偺2搙栚偺塮夋壔丅儀僥傿丒僨僀償傿僗偼扵掋傪憖傞嵓媆巘偺彈傪墘偠傞偑丄撪梕偼僾儘僢僩偑戝暆偵夵曄偝傟丄尨嶌傗1941擭斉塮夋偲偼帡偰傕帡偮偐偸丄掲傑傝傕側偄偟尒偳偙傠傕側偄戝枴偺僐儊僨傿斊嵾塮夋偵側偭偰偄傞丅
2022擭7寧朸擔 旛朰榐183丂儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偺庡墘塮夋
1954暷丂儘僀僪丒儀乕僐儞丂昡揰亂C亃
塸岅帤枊偱娪徿丅僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺寙嶌乽揤巊偺婄乿乮1953乯偺儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僕乕儞丒僔儌儞僘偑嵞嫟墘偟偨塮夋丅旕忣側乽揤巊偺婄乿偲偼懪偭偰曄傢偭偰丄傾乕僇儞僜乕廈偺揷幧挰傪晳戜偵偟偨杙鎐側僐儊僨傿丅儈僢僠儍儉偼挰堛幰丄僔儌儞僘偼偙偺挰偵棫偪婑傞嬥帩偪偺庒偄彈惈傪墘偠傞丅撪梕揑偵偼杴梖偩偑丄偲傏偗偨枴傢偄偲偺傫傃傝偟偨暤埻婥偼埆偔偼側偄丅
The Angry Hills乮搟傝偺媢乯
1959暷丂儘僶乕僩丒傾儖僪儕僢僠丂昡揰亂C亃
塸岅帤枊偱娪徿丅戞2師戝愴拞丄僫僠愯椞慜屻偺僊儕僔儍傪晳戜偵偟偨僗僷僀丒僒僗儁儞僗塮夋丅庡墘偺儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偼傾儊儕僇恖僕儍乕僫儕僗僩偵暞偡傞丅傾僥僱偵棫偪婑偭偨儈僢僠儍儉偼儗僕僗僞儞僗塣摦堳偺柤曤傪塸崙忣曬晹偵搉偡傛偆偵棅傑傟丄僎僔儏僞億偺幏漍側捛愓傪摝傟丄揷幧偺懞傗搒夛偺傾僷乕僩偵摻傢傟側偑傜奀奜偵搉傠偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僼傿儖儉偼僆儕僕僫儖斉偑偐側傝僇僢僩偝傟偰偄傞傛偆偱丄柆棈偑側偄売強偑嶶尒偝傟傞丅偦偺偣偄偐丄傾儖僪儕僢僠傜偟偄愗傟枴偑側偔丄偄傑偄偪嬞敆姶偵寚偗傞丅僗僞儞儕乕丒儀僀僇乕偑墘偠傞僎僔儏僞億偺儕乕僟乕偺僉儍儔僋僞乕偑濨枂側偺傕堦場偐丅偲偼偄偊丄儈僢僠儍儉偑栭偺傾僥僱偺奨傪摝偘夞傞僔乕儞偼敆椡廫暘偩丅
2022擭7寧朸擔 旛朰榐182丂2杮偺堎怓僼傿儖儉丒僲儚乕儖
1956暷丂僼儕僢僣丒儔儞僌丂昡揰亂B亃
僼儕僢僣丒儔儞僌偺暷崙惂嶌嶌昳偺側偐偱桞堦枹尒偩偭偨塮夋丅塸岅帤枊偱娪徿丅巰孻惂搙傪戣嵽偵偟偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅忬嫷徹嫆偩偗偱巰孻偑愰崘偝傟傞尰忬偵堦愇傪搳偠傞偨傔丄嶌壠偺僟僫丒傾儞僪儕儏乕僗偼桭恖偺怴暦幮幮挿偲慻傫偱丄帺暘偑嶦恖帠審偺斊恖偱偁傞傛偆偵尒偣偐偗丄傢偞偲寈嶡偵戇曔偝傟傞傛偆偵巇岦偗偰丄嵸敾偱柍幚偺徹嫆傪採弌偟嵸敾惂搙偺晄旛傪撍偙偆偲夋嶔偡傞丅寁夋偼梊掕偳偍傝偵恑峴偡傞偑丄柍幚傪徹柧偡傞徹嫆傪帩偭偰嵸敾強偵岦偐偆怴暦幮幮挿偑幵偺帠屘偵憳偭偰巰朣偟丄徹嫆偼從幐偟偰偄傑偭偨偨傔丄斵偼媷抧偵棫偨偝傟傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅嵟屻偵偳傫偱傫曉偟偑偁傞偑丄偦傟偵偼怗傟側偄偱偍偙偆丅幮挿偺柡偱斵偺楒恖偵僕儑乕儞丒僼僅儞僥僀儞偑暞偡傞丅僼儕僢僣丒儔儞僌側傜偱偼偺旂擏偲儁僔儈僘儉偑墶堨偟偰偄傞偑丄塮憸偺揰偱偼僲儚乕儖揑姶嫽偼朢偟偄丅偙傟偼儔儞僌偺傾儊儕僇帪戙嵟屻偺嶌昳偵側偭偨丅
Slightly Scarlet乮埆偺懳寛乯
1955暷丂傾儔儞丒僪儚儞丂昡揰亂C亃
堦晹偺幆幰偺偁偄偩偱昡敾偑崅偄僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅塸岅帤枊偱娪徿丅庡墘偼僕儑儞丒儁僀儞丅儘儞僟丒僼儗儈儞僌偲傾乕儕乕儞丒僟乕儖偲偄偆2恖偺彈桪偑嫟墘偡傞丅嶣塭偼柤庤僕儑儞丒傾儖僩儞丅僇儔乕嶌昳偩偑丄傾儖僩儞偺偡偖傟偨僇儊儔儚乕僋偵傛傝丄僲儚乕儖揑側暤埻婥偑擹岤偵昚偭偰偄傞丅挰傪媿帹傞儃僗偲偦偺庤壓偺僕儑儞丒儁僀儞偲偺懳寛丄儁僀儞偲僼儗儈儞僌仌僟乕儖偺巓枀偲偺嶰妏娭學偑昤偐傟傞丅2恖偺彈桪偼偄偢傟傕愒栄偱丄偗偽偗偽偟偄僥僋僯僇儔乕偺嵤怓偵儅僢僠偟偰偄傞丅嶌昳偲偟偰偼B媺揑側怓崌偄偑嫮偔丄榖偺塣傃偼偍偆偍偆偵偟偰晄帺慠偱偁傝丄嬞敆姶偑嶍偑傟傞丅
2022擭6寧
2022擭6寧朸擔 旛朰榐181丂惉悾枻婌抝偑庤偑偗偨2杮偺僆儉僯僶僗塮夋
1947搶曮丂朙揷巐榊乛惉悾枻婌抝乛嶳杮壝師榊乛堖妢掑擵彆丂昡揰亂D亃
楒傪僥乕儅偵偟偨4偮偺暔岅傪忋婰偺4恖偺柤偩偨傞儀僥儔儞娔撀偑昤偄偨僆儉僯僶僗塮夋丅楯摥憟媍偵傛傞崿棎偺偨傔偐丄慡懱偵弌棃偼椙偔側偄丅桞堦丄柺敀偄偺偼崟郪柧偑媟杮傪彂偄偨戞1榖偺乽弶楒乿丅拞棳壠掚偺崅峑惗偺懅巕偲偦偺壠偵偟偽傜偔嫃岓偡傞彮彈偲偺扺偄楒傪昤偄偨抁曇偱丄崅峑惗傪抮晹椙丄斵偺椉恊傪巙懞嫪偲悪懞弔巕丄彮彈傪媣変旤巕偑墘偠傞丅擇恖偺柤桪偺岲墘傕偁傝丄傛偔傑偲傑偭偰偄傞丅偙傟偑僨價儏乕嶌偺媣変偼懢偭偨娵傐偪傖偺婄偱丄尒姷傟偨梕巔偲偼傑偭偨偔僀儊乕僕偑堎側傞丅惉悾枻婌抝娔撀偺戞2榖乽暿傟傕桖偟乿偼僟儞僒乕偺彫曢幚愮戙偑庡恖岞丅斵彈偼摨惐憡庤偺抝偑怴偟偄楒恖偲恀寱偵曢傜偦偆偲巚偭偰偄傞偺傪抦傝丄傢偞偲暿傟榖傪帩偪弌偟偰帺傜恎傪堷偔丅偙偙偵偼惉悾傜偟偄偒傔嵶偐側墘弌偑尒傜傟偢丄媟杮偺偣偄傕偁傞偩傠偆偑丄傗偭偮偗巇帠偺姶偑偁傞丅
偔偪偯偗
1955搶曮丂猕惓揟乛楅栘塸晇乛惉悾枻婌抝丂昡揰亂A亃
 丂愇嶁梞師榊偺抁曇彫愢傪傕偲偵丄3恖偺娔撀偑暘扴偟摨堦偺僗僞僢僼偱嶣偭偨僆儉僯僶僗塮夋丅捒偟偔惉悾枻婌抝偑嫟摨惢嶌幰偲偟偰慡懱偺傑偲傔栶傪柋傔偰偄傞丅徏嶳慞嶰偺媟杮偑椙偄丅傑偨3嶌慡懱傪捠偟偰僉儍僗僥傿儞僌偑慺惏傜偟偔丄攐桪偼傒側寵枴偺側偄慺捈側墘媄傪尒偣偰偄傞丅戞1榖偺猕惓揟娔撀乽偔偪偯偗乿偼拠偺偄偄抝彈偺戝妛惗亖惵嶳嫗巕偲懢搧愳梞堦偑怓傫側宱堒傪宱偰愙暙偡傞傑偱傪昤偄偨嶌昳丅斵傜偑愙暙偡傞偺偼懡杸愳偺壨尨丅儘働抧偼崫峕偺偁偨傝偩傠偆偐丅戝妛僉儍儞僷僗偺僔乕儞偼惵嶳戝妛偱儘働偝傟偨傛偆偩丅懠垽側偄榖偩偑傎偺傏偺偲偟偰偍傝岲姶傪梌偊傞丅戝妛嫵庼栶偺妢抭廜偑偄偄枴傪弌偟偰偍傝丄惵嶳偺媊巓栶偺悪梩巕傕棊偪拝偄偨旤偟偝傪曻偮丅
丂愇嶁梞師榊偺抁曇彫愢傪傕偲偵丄3恖偺娔撀偑暘扴偟摨堦偺僗僞僢僼偱嶣偭偨僆儉僯僶僗塮夋丅捒偟偔惉悾枻婌抝偑嫟摨惢嶌幰偲偟偰慡懱偺傑偲傔栶傪柋傔偰偄傞丅徏嶳慞嶰偺媟杮偑椙偄丅傑偨3嶌慡懱傪捠偟偰僉儍僗僥傿儞僌偑慺惏傜偟偔丄攐桪偼傒側寵枴偺側偄慺捈側墘媄傪尒偣偰偄傞丅戞1榖偺猕惓揟娔撀乽偔偪偯偗乿偼拠偺偄偄抝彈偺戝妛惗亖惵嶳嫗巕偲懢搧愳梞堦偑怓傫側宱堒傪宱偰愙暙偡傞傑偱傪昤偄偨嶌昳丅斵傜偑愙暙偡傞偺偼懡杸愳偺壨尨丅儘働抧偼崫峕偺偁偨傝偩傠偆偐丅戝妛僉儍儞僷僗偺僔乕儞偼惵嶳戝妛偱儘働偝傟偨傛偆偩丅懠垽側偄榖偩偑傎偺傏偺偲偟偰偍傝岲姶傪梌偊傞丅戝妛嫵庼栶偺妢抭廜偑偄偄枴傪弌偟偰偍傝丄惵嶳偺媊巓栶偺悪梩巕傕棊偪拝偄偨旤偟偝傪曻偮丅丂楅栘塸晇娔撀偺戞2榖乽柖偺拞偺彮彈乿偱偼丄壞媥傒偱夛捗偺揷幧偵婣徣偟偰偄傞戝妛惗偺柡亖巌梩巕偺幚壠傪丄妛桭偺抝亖彫愹攷偑朘傟偰斵彈偺壠懓偲夁偛偡悢擔娫偑丄儐乕儌儔僗側僞僢僠偱昤偐傟傞丅偺偳偐側揷幧偺懞偺忣宨偲怱榓傓壠懓偺昤幨偼乽愇拞愭惗峴忬婰乿傪憐婲偝偣傞丅巌偺枀偵拞尨傂偲傒丄椉恊偵摗尨姍懌偲惔愳擑巕丄慶曣偵斞揷挶巕偲偄偆攝栶傕愨柇丅拞尨傂偲傒偺柍幾婥側壜垽偝偑嵺棫偭偰偄傞丅斞揷挶巕偺尦婥偺偄偄偽偁偝傫栶傕愨昳偱丄壏愹偺晽楥偱柉梬偺乽夛捗斨掤嶳乿傪壧偆僔乕儞偼書暊傕偺偩丅
丂惉悾枻婌抝偑帺傜墘弌偟偨戞3榖乽彈摨巑乿偼丄傗偼傝偄偪偽傫弌棃偑偄偄丅偙傟傕僐儊僨傿晽偺嶌昳偱丄惉悾偺桰梘敆傜偞傞柤恖寍傪姮擻偱偒傞丅寫懹婜偵偁傞嵢傪崅曯廏巕丄晇偺挰堛幰傪忋尨尓丄娕岇晈傪拞懞儊僀僐丄敧昐壆偺惵擭傪彫椦宩庽偑墘偠傞丅晇偲娕岇晈偺拠傪媈偆崅曯偼娕岇晈傪敧昐壆偺惵擭偲寢傃偮偗傛偆偲夋嶔偡傞丅偦傟偑岟傪憈偟丄拞懞偼寢崶偺偨傔戅怑偟偰崅曯偼堦埨怱偡傞偑丄戙傢傝偵傛傝旤恖偺娕岇晈偑傗偭偰棃傞偲偄偆旂擏側棊偪偱儔僗僩偵側傞丅偙偺怴娕岇晈栶偱儚儞丒僇僢僩偩偗搊応偡傞偺偑敧愮憪孫丄扤偑尒偰傕偦偺旤偟偝偼奿暿偩丅敧愮憪偼攐桪僋儗僕僢僩偵擖偭偰偄側偄丅偲偭偝偺巚偄晅偒偱攝偝傟偨偺偩傠偆偐丅惉悾塮夋側傜偱偼偺僠儞僪儞壆偑搊応偟偰桖夣側婥暘傪枴傢傢偣偰偔傟傞丅怱偑壏偐偔側傞岾偣側塮夋偩丅
2022擭6寧朸擔 旛朰榐180丂尨愡巕偺庡墘塮夋丂偦偺2
1950戝塮丂媑懞楑丂昡揰亂B亃
 揷幧偺懞偺彫妛峑傪晳戜偵偟偨嫵巘偲惗搆偺僪儔儅丅擔杮嫵怑堳慻崌偑嫤巀偟偨偍巇拝偣塮夋偩丅庡墘偺尨愡巕偼怱桪偟偄彫妛峑嫵巘傪墘偠傞丅斵彈埲奜偵柤偺抦傟偨攐桪偼傎偲傫偳弌偰偄側偄丅斵彈偼扴摉偡傞妛媺偱婲偒傞壠掚偺昻晉偺嵎偵傛傞偄偠傔偵怱傪捝傔丄晜楺帣傪帺戭偵廧傑傢偣偰妛峑偵捠傢偣丄峑掚偺抮偵岺応偺攑塼偑擖傝崬傓偺傪慾巭偡傞偨傔岺応庡偺PTA夛挿偲択敾偡傞丅嵟屻偼傒傫側偑榓夝偟偰僴僢僺乕僄儞僪偲側傞丅偙偙偱偺尨愡巕偼29嵨偩偑偠偮偵旤偟偔嶣傜傟偰偄傞丅斵彈偑嵟崅偵偒傟偄側偺偼1949擭偺乽偍忟偝傫姡攖乿偩偑丄偦傟偵暲傇旤偟偝偩丅偦偺棟桼偺傂偲偮偼梷惂偝傟偨墘媄偵廔巒偟偰偄傞偙偲偵偁傞偩傠偆丅慜嶌乽斢弔乿偱彫捗埨擇榊偺孫摡傪庴偗偨梋攇偐傕偟傟側偄丅徫傒傪晜偐傋偨傝丄斶偟傒傪晜偐傋偨傝偡傞斵彈偺昞忣偼丄傢偞偲傜偟偝偑姶偠傜傟側偄偱傕側偄偑丄懅傪撣傓傎偳鋎偨偗偰偄傞丅昦婥偱暁偣傞斵彈偺婄偑傾僢僾偵側傞僔儑僢僩偵偼怓婥偲婥昳偑昚偆丅巕嫙偺傂偲傝偑尨愡巕偵書偒偮偄偰媰偔僔乕儞偑偁傞丅巕嫙偺婄偼斵彈偺嫻偺扟娫偵杽傔傜傟偰偄傞丅堦弖丄偙偺巕偵庢偭偰戙傢傝偨偄偲偄偆栂憐偑晜偐傫偩丅偙偺塮夋偼弌棃偐傜偡傟偽杴嶌偺堟傪弌側偄偑丄尨愡巕偑旤偟偔嶣傜傟偰偄傞偙偲偲巕嫙偨偪偺擬墘傪昡壙偟偰亂B亃傪掓忋偡傞丅
揷幧偺懞偺彫妛峑傪晳戜偵偟偨嫵巘偲惗搆偺僪儔儅丅擔杮嫵怑堳慻崌偑嫤巀偟偨偍巇拝偣塮夋偩丅庡墘偺尨愡巕偼怱桪偟偄彫妛峑嫵巘傪墘偠傞丅斵彈埲奜偵柤偺抦傟偨攐桪偼傎偲傫偳弌偰偄側偄丅斵彈偼扴摉偡傞妛媺偱婲偒傞壠掚偺昻晉偺嵎偵傛傞偄偠傔偵怱傪捝傔丄晜楺帣傪帺戭偵廧傑傢偣偰妛峑偵捠傢偣丄峑掚偺抮偵岺応偺攑塼偑擖傝崬傓偺傪慾巭偡傞偨傔岺応庡偺PTA夛挿偲択敾偡傞丅嵟屻偼傒傫側偑榓夝偟偰僴僢僺乕僄儞僪偲側傞丅偙偙偱偺尨愡巕偼29嵨偩偑偠偮偵旤偟偔嶣傜傟偰偄傞丅斵彈偑嵟崅偵偒傟偄側偺偼1949擭偺乽偍忟偝傫姡攖乿偩偑丄偦傟偵暲傇旤偟偝偩丅偦偺棟桼偺傂偲偮偼梷惂偝傟偨墘媄偵廔巒偟偰偄傞偙偲偵偁傞偩傠偆丅慜嶌乽斢弔乿偱彫捗埨擇榊偺孫摡傪庴偗偨梋攇偐傕偟傟側偄丅徫傒傪晜偐傋偨傝丄斶偟傒傪晜偐傋偨傝偡傞斵彈偺昞忣偼丄傢偞偲傜偟偝偑姶偠傜傟側偄偱傕側偄偑丄懅傪撣傓傎偳鋎偨偗偰偄傞丅昦婥偱暁偣傞斵彈偺婄偑傾僢僾偵側傞僔儑僢僩偵偼怓婥偲婥昳偑昚偆丅巕嫙偺傂偲傝偑尨愡巕偵書偒偮偄偰媰偔僔乕儞偑偁傞丅巕嫙偺婄偼斵彈偺嫻偺扟娫偵杽傔傜傟偰偄傞丅堦弖丄偙偺巕偵庢偭偰戙傢傝偨偄偲偄偆栂憐偑晜偐傫偩丅偙偺塮夋偼弌棃偐傜偡傟偽杴嶌偺堟傪弌側偄偑丄尨愡巕偑旤偟偔嶣傜傟偰偄傞偙偲偲巕嫙偨偪偺擬墘傪昡壙偟偰亂B亃傪掓忋偡傞丅傆傫偳偟堛幰
1960搶曮丂堫奯峗丂昡揰亂A亃
 丂尨愡巕偑堛幰偺嵢偱攷懪偑戝岲偒丄晧偗偑崬傔偽攚屻偱庰傪堸傫偱偄傞晇偵拝暔傪扙偑偣偰搎応偵嵎偟弌偡偲偄偆捒偟偄栶傪墘偠偰偄傞偙偲傪抦傝丄埲慜偐傜婥偵側偭偰偄偨塮夋傪傗偭偲尒傞偙偲偑偱偒偨丅棖妛傪妛傫偩柤堛偩偑惔昻偵娒傫偠丄昻偟偄弾柉偺偨傔偵堛椕傪巤偟偨抝偺暔岅丅応強偼戝堜愳増偄偺搰揷廻丄帪戙偼峕屗枛婜偐傜柧帯弶婜偵愝掕偝傟偰偄傞丅偐偮偰偺廻応挰傪嵞尰偟偨尒帠側僙僢僩偵嬃偐偝傟傞丅旤弍偼惉悾塮夋偱偍撻愼傒偺拞屆抭偩丅偄偮傕嵢偺攷懪偺偨傔偵傆傫偳偟巔偵側傞偺偱傆傫偳偟愭惗偲屇偽傟傞柤堛偵怷斏媣淺丄偦偺嵢偵尨愡巕丄怷斏偵柦傪彆偗傜傟掜巕擖傝偟偰堛幰傪巙偡傗偔偞幰偵壞栘梲夘丄壞栘傪曠偆椃娰偺柡偵峕棙僠僄儈偑暞偡傞丅傎偐偵怷斏偲恊桭偺屼揟堛栶偱嶳懞汔丄尨愡巕偲攷懪偱懳寛偡傞傗偔偞偺恊暘栶偱巙懞嫪偑弌墘偡傞丅
丂尨愡巕偑堛幰偺嵢偱攷懪偑戝岲偒丄晧偗偑崬傔偽攚屻偱庰傪堸傫偱偄傞晇偵拝暔傪扙偑偣偰搎応偵嵎偟弌偡偲偄偆捒偟偄栶傪墘偠偰偄傞偙偲傪抦傝丄埲慜偐傜婥偵側偭偰偄偨塮夋傪傗偭偲尒傞偙偲偑偱偒偨丅棖妛傪妛傫偩柤堛偩偑惔昻偵娒傫偠丄昻偟偄弾柉偺偨傔偵堛椕傪巤偟偨抝偺暔岅丅応強偼戝堜愳増偄偺搰揷廻丄帪戙偼峕屗枛婜偐傜柧帯弶婜偵愝掕偝傟偰偄傞丅偐偮偰偺廻応挰傪嵞尰偟偨尒帠側僙僢僩偵嬃偐偝傟傞丅旤弍偼惉悾塮夋偱偍撻愼傒偺拞屆抭偩丅偄偮傕嵢偺攷懪偺偨傔偵傆傫偳偟巔偵側傞偺偱傆傫偳偟愭惗偲屇偽傟傞柤堛偵怷斏媣淺丄偦偺嵢偵尨愡巕丄怷斏偵柦傪彆偗傜傟掜巕擖傝偟偰堛幰傪巙偡傗偔偞幰偵壞栘梲夘丄壞栘傪曠偆椃娰偺柡偵峕棙僠僄儈偑暞偡傞丅傎偐偵怷斏偲恊桭偺屼揟堛栶偱嶳懞汔丄尨愡巕偲攷懪偱懳寛偡傞傗偔偞偺恊暘栶偱巙懞嫪偑弌墘偡傞丅丂塮夋偺屻敿丄挰偺巕嫙偑暊捝偵側傞丅怷斏偼怘偁偨傝偩偲恌抐偡傞偑丄挿嶈偱妛傫偱婣偭偨壞栘偼僠僼僗偩偲庡挘偟偰庡廬偑懳棫偡傞丅尠旝嬀偱尒偰僠僼僗偩偲暘偐偭偨怷斏偼帺暘偺榬偑帪戙抶傟偵側偭偨偲捝姶偡傞偑丄媫偄偱滊姵偟偨巕嫙偨偪傪妘棧偡傞丅柍棟夝側挰柉偼偦傟偵搟偭偰巕嫙偨偪傪庢傝栠偟丄怷斏偺廧嫃寭昦堾傪懪偪夡偡丅怷斏偼棫恎弌悽傪幪偰偰挰柉偺偨傔偵恠偔偟偨帺暘偺恖惗偼壗偩偭偨偺偐偲奡扱偡傞丅嵟屻偼丄怷斏偑峕屗偺堛妛強偵晪擟偡傞壞栘傪憲傝弌偟丄帺暘偨偪偺旕傪妎偭偨挰柉偑憤弌偱昦堾傪寶偰捈偟丄怴偟偄悽偵側偭偨偐傜傆傫偳偟巔偱奜傪曕偔偺偼嬛巭偩偲尵偆栶恖傪柍帇偟偰丄斵偑嵢偲擇恖偱奨摴傪偺傫傃傝曕偔僔乕儞偱廔傞丅
丂偙傟偼儐乕儌傾偲斶垼偑側偄傑偤偵側偭偨丄堦媺昳偺塮夋偩丅偙偙偱偼晇晈垽偑昤偐傟丄僀儞僥儕偑戝廜偵棤愗傜傟傞榖偑昤偐傟傞丅傑偨偙傟偼帪戙偺棳傟偵庢傝巆偝傟傞抝傪昤偔塮夋偱傕偁傝丄偦偺揰偱偼堫奯偺乽柍朄徏偺堦惗乿偵捠偠傞丅偦偟偰庒偄堛巘偺惉挿暔岅偱偁傞揰偱崟郪偺乽愒傂偘乿偲帡偰偄側偔傕側偄丅尨愡巕偑攷懪傪懪偮巔偼丄怷斏偑傆傫偳偟巔偵側傞朻摢偲丄尠旝嬀傪攦偆嬥傪摼傞偨傔帺暘偺懱傪偐偗偰彑晧偡傞廔斦偺2売強偵弌偰偔傞丅摉帪40嵨偺尨偼偄傑側偍旤偟偄怓崄傪姶偠偝偣傞丅斵彈偼偙偺塮夋岞奐偺2擭屻偵堷戅偡傞丅
2022擭6寧朸擔 旛朰榐179丂尨愡巕偺庡墘塮夋丂偦偺1
1942搶曮丂暁悈廋丂昡揰亂D亃
懢暯梞愴憟偵撍擖偟偰2儠寧屻偵晻愗傜傟偨崙嶔塮夋丅媟杮偼崟郪柧丅偙傟偼崟郪偑媟杮傪彂偄偨弶偺塮夋偱偼側偄偩傠偆偐丅尨愡巕偼攐桪僋儗僕僢僩偺偄偪偽傫嵟弶偵弌偰偔傞偑丄幚幙揑側庡墘偼峲嬻婡夛幮偺愝寁庡擟偲偄偆栶偺戝擔曽揱丅斵傪巟墖偡傞夛幮廳栶偺堦恖柡偑尨愡巕偱丄斵彈偼斵傪岲偒偵側傞偑丄斵偺傎偆偼昻偟偄壠掚偺柡丄嶳崻庻巕偵垽傪書偄偰偄傞丅塮夋偱偼戝擔曽偲拠娫偑怴宆旘峴婡偺惢憿偵暠摤偡傞條巕偲丄斵傪弰傞嶰妏娭學偺惉傝峴偒偑岎屳偵昤偐傟傞丅尨愡巕偼寢嬊丄怳傜傟偰偟傑偆丅22嵨偺庒乆偟偄尨愡巕偑尒傜傟傞偙偲偩偗偑庢傝暱偺塮夋偩丅
岾暉偺尷奅
1948戝塮丂栘懞宐屷丂昡揰亂C亃
彈偺岾偣偲偼壗偐傪僥乕儅偵偟偨尨愡巕庡墘偺壠掚寑丅尨愡巕偼夛幮偵嬑傔側偑傜墘寑傪妛傇拞忋棳奒媺壠掚偺師彈丅帺棫偟偨彈傪栚巜偡尰戙揑側彈惈偱丄曣恊傗丄晇偑巰傫偱壟偓愭偐傜幚壠偵婣偭偨挿彈傪丄乽惈峴堊傪敽偆彈拞偩乿偲側偠傝丄巹偼寢崶偟側偄偲愰尵偟丄晝恊偐傜幎愑偝傟偰壠傪弌傞偑丄彈偺岾偣偵偼尷奅偑偁傞偲屽傝丄寢嬊丄崨傟偰偄偨寑抍庡嵣幰偺摗揷恑偲寢崶偟丄壠懓偲傕榓夝偟偰奊偵昤偄偨傛偆側僴僢僺乕僄儞僪偲側傞丅偄偐偵傕愴屻娫傕側偄偙傠偺塮夋偩偑丄屆廘偄晻寶庡媊傪斸敾偟偰偄偨偺偵嵟屻偼偦傟傪庴偗擖傟傞偲偄偆丄壗偲傕掲傑傜側偄榖偵側偭偰偄傞丅晝恊栶偺彫悪桬偼1937擭偺擔撈崌嶌塮夋乽怴偟偒搚乿偱尨愡巕偺嫋崶幰傪墘偠偰偄偨丅尨愡巕偲摗揷恑偼乽傢偑惵弔偵夨側偟乿傪偼偠傔丄愴拞偐傜愴屻偵偐偗偰懡偔偺塮夋偱僐儞價傪慻傫偩丅尨偲摗揷偑僗僉乕偵弌偐偗摨偠晹壆偵攽傑傞偑壗傕婲偙傜側偄偲偄偆憓榖偼丄偙偺慜擭偺塮夋乽桿榝乿傪巚偄婲偙偝偣傞丅28嵨偺尨愡巕偼偨傑偵乽桿榝乿偱尒偣偨傛偆側忋栚尛偄偺壓昳側昞忣傪偡傞偑丄偍偍傓偹岲傑偟偄旤偟偝傪曐偭偰偄傞丅側偤偐丄偲偙傠偳偙傠偱尨愡巕偺僗僇乕僩壓偺媟偑傾僢僾偱憓擖偝傟傞丅栭丄摗揷恑偺壠偵墴偟偐偗傞僔乕儞偱丄斵彈偼嵗偭偰丄僗僇乕僩偼偄偨傑傑丄僈乕僞乕傪庢傝僗僩僢僉儞僌傪扙偖丅懌尦偟偐塮偝傟偰偄側偄偑丄偙偺僔儑僢僩偵偼僪僉僢偲偡傞丅
2022擭6寧25擔 梋択丗儈僗僥儕乕彫愢撉屻姶憐
丂丂丂丂丂丂丂丂 怱偵怗傟傞傾僀儖儔儞僪偺晽宨丄弶榁偺抝偲巕嫙偺怱偺岎棳
乮僴儎僇儚丒儈僗僥儕暥屔乯
 嬤擭丄偙傟傎偳怱傪懪偨傟偨儈僗僥儕乕彫愢偼側偄丅偍偦傜偔崱擭偺儀僗僩丒儚儞偩傠偆丅僔僇僑巗寈傪戅怑偟丄嵢偲棧崶偟偰傾僀儖儔儞僪偺揷幧偺懞偵堏傝廧傫偩弶榁偺尦孻帠偑庡恖岞丅斵偺壠偵抧尦偺昻擾偺巕嫙偑尰傟丄峴曽晄柧偺孼傪扵偟偰偔傟偲尵偆丅巕嫙偺崸婅偵晧偗偰憑嵏偡傞偆偪偵丄斵偼懞偵塀偝傟偨旈枾偵婥偑偮偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅慡懱揑側暤埻婥偼嶐擭敪攧偝傟偨寙嶌乽僓儕僈僯偺柭偔偲偙傠乿傪巚傢偣傞丅暥屔杮偩偑680儁乕僕傕偁傝丄捠忢偺彫愢2嶜暘傕偺挿偝偩偑丄搑拞偱傑偭偨偔偩傟傞偙偲偑側偄丅儈僗僥儕乕揑側梫慺偼婓敄偩偑丄庡恖岞偺屒撈側怱忣偲傾僀儖儔儞僪偺帺慠偺昤偒曽偑偲偰傕偄偄丅偄偪偽傫姶摦偡傞偺偼尦孻帠偲斵偺壠偵弌擖傝偡傞傛偆偵側偭偨巕嫙偲偺岎棳偩丅巕嫙偼惗堄婥偱婃側側惈奿偩偑丄庡恖岞偺壠偺夵廋傪庤揱偆傛偆偵側傝丄偟偩偄偵怱傪奐偄偰偄偔丅暔岅偺拞斦偱丄偙偺巕嫙偵娭偡傞偁傞帠幚偑柧傜偐偵側傝丄偁偁偦偆側偺偐偲擺摼偡傞丅斵偼巕嫙偵幩寕傪嫵偊傞偑丄偦傟偼廔斦偵婲偙傞弌棃帠偺暁慄偵側傞丅栿幰偼偁偲偑偒偱儘僶乕僩丒僷乕僇乕偺乽弶廐乿偲偺椶帡傪巜揈偟偰偄傞偑丄偳偙偐傢偞偲傜偟偝偑廘偆乽弶廐乿傛傝傕丄偙偺彫愢偺傎偆偑偼傞偐偵棳傟偑帺慠偱墴偟偮偗偑傑偟偝偑側偄丅偙偺彫愢偵偼將偑搊応偟偰嫽庯傪惙傝忋偘傞丅傏偔偼巕嫙偲將偑弌偰偔傞彫愢傗塮夋偼寵偄側偺偩偑丄偙偆傕岻傒偵彂偐傟偰偼崀嶲偟偰扙朮偣偞傞傪摼側偄丅搑拞偱岲傑偟偘側晽忣偺枹朣恖儗僫偑搊応偟丄將偺帞堢傪弰偭偰庡恖岞偲恊偟偔側傞丅慡懱偵嬝棫偰傗昅抳偵偙傟尒傛偑偟偺嶌堊惈偑側偔丄惷偐偱怲傒怺偄丅暵嵔揑側懞傗慒嶕岲偒偺廧柉偺昤幨傕岻偄偟丄搊応恖暔偦傟偧傟偺憿宍傕偟偭偐傝昤偐傟偰偄傞丅慺惏傜偟偄彫愢偩丅偙偺嶌壠偺媽嶌偼3嶜東栿弌斉偝傟偰偄傞偲偄偆丅撉傑側偗傟偽側傜側偄丅
嬤擭丄偙傟傎偳怱傪懪偨傟偨儈僗僥儕乕彫愢偼側偄丅偍偦傜偔崱擭偺儀僗僩丒儚儞偩傠偆丅僔僇僑巗寈傪戅怑偟丄嵢偲棧崶偟偰傾僀儖儔儞僪偺揷幧偺懞偵堏傝廧傫偩弶榁偺尦孻帠偑庡恖岞丅斵偺壠偵抧尦偺昻擾偺巕嫙偑尰傟丄峴曽晄柧偺孼傪扵偟偰偔傟偲尵偆丅巕嫙偺崸婅偵晧偗偰憑嵏偡傞偆偪偵丄斵偼懞偵塀偝傟偨旈枾偵婥偑偮偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅慡懱揑側暤埻婥偼嶐擭敪攧偝傟偨寙嶌乽僓儕僈僯偺柭偔偲偙傠乿傪巚傢偣傞丅暥屔杮偩偑680儁乕僕傕偁傝丄捠忢偺彫愢2嶜暘傕偺挿偝偩偑丄搑拞偱傑偭偨偔偩傟傞偙偲偑側偄丅儈僗僥儕乕揑側梫慺偼婓敄偩偑丄庡恖岞偺屒撈側怱忣偲傾僀儖儔儞僪偺帺慠偺昤偒曽偑偲偰傕偄偄丅偄偪偽傫姶摦偡傞偺偼尦孻帠偲斵偺壠偵弌擖傝偡傞傛偆偵側偭偨巕嫙偲偺岎棳偩丅巕嫙偼惗堄婥偱婃側側惈奿偩偑丄庡恖岞偺壠偺夵廋傪庤揱偆傛偆偵側傝丄偟偩偄偵怱傪奐偄偰偄偔丅暔岅偺拞斦偱丄偙偺巕嫙偵娭偡傞偁傞帠幚偑柧傜偐偵側傝丄偁偁偦偆側偺偐偲擺摼偡傞丅斵偼巕嫙偵幩寕傪嫵偊傞偑丄偦傟偼廔斦偵婲偙傞弌棃帠偺暁慄偵側傞丅栿幰偼偁偲偑偒偱儘僶乕僩丒僷乕僇乕偺乽弶廐乿偲偺椶帡傪巜揈偟偰偄傞偑丄偳偙偐傢偞偲傜偟偝偑廘偆乽弶廐乿傛傝傕丄偙偺彫愢偺傎偆偑偼傞偐偵棳傟偑帺慠偱墴偟偮偗偑傑偟偝偑側偄丅偙偺彫愢偵偼將偑搊応偟偰嫽庯傪惙傝忋偘傞丅傏偔偼巕嫙偲將偑弌偰偔傞彫愢傗塮夋偼寵偄側偺偩偑丄偙偆傕岻傒偵彂偐傟偰偼崀嶲偟偰扙朮偣偞傞傪摼側偄丅搑拞偱岲傑偟偘側晽忣偺枹朣恖儗僫偑搊応偟丄將偺帞堢傪弰偭偰庡恖岞偲恊偟偔側傞丅慡懱偵嬝棫偰傗昅抳偵偙傟尒傛偑偟偺嶌堊惈偑側偔丄惷偐偱怲傒怺偄丅暵嵔揑側懞傗慒嶕岲偒偺廧柉偺昤幨傕岻偄偟丄搊応恖暔偦傟偧傟偺憿宍傕偟偭偐傝昤偐傟偰偄傞丅慺惏傜偟偄彫愢偩丅偙偺嶌壠偺媽嶌偼3嶜東栿弌斉偝傟偰偄傞偲偄偆丅撉傑側偗傟偽側傜側偄丅
2022擭6寧朸擔 旛朰榐178丂愳搰梇嶰偺塮夋丂偦偺2
1961搶曮丂愳搰梇嶰丂昡揰亂C亃
戝壀徃暯尨嶌彫愢偺塮夋壔丅嬧嵗偺僶乕偺屬傢傟儅僟儉偑懡偔偺抝偲娭學傪傕偭偨偁偘偔巰傪慖傇傑偱傪昤偔丅庡墘偼抮撪弤巕丅斵彈偼戝妛島巘偺抮晹椙丄曎岇巑偺桳搰堦榊丄TV斣慻惢嶌幰偺崅搰拤晇丄夛幮幮挿偺嶰嫶払栫偲師乆偵娭學傪傕偮丅傑偨斵彈偑晝偺傛偆偵曠偆崪摕昡榑壠丄嵅栰廃擇偲偺岎桭傕昤偐傟傞丅弌斣偼彮側偄偑扺搰愮宨傕嶰嫶偺媊棟偺曣栶偱弌墘偡傞丅抮撪弤巕偑杴梖側梕巔偱丄抝傪偲傝偙偵偡傞傛偆側杺惈偺彈偵尒偊側偄偺偑擄丅傑偨側偤帺嶦傪寛堄偡傞偺偐丄偦偺怱棟夁掱偑傛偔暘偐傜偢丄塮夋偲偟偰偺弌棃偼朏偟偔側偄丅偩偑丄廔斦丄嵞夛偟偨抮撪弤巕偲抮晹椙偑栭偵枮奐偺嶗偺壓傪嶶曕偡傞僔乕儞偼懅傪撣傓傛偆側旤偟偝傪曻偮丅偙偺弌墘幰偨偪偵偼儌僨儖偑偁傝丄抮撪弤巕偺儌僨儖偼嶁杮杛巕丄嵅栰廃擇偼惵嶳擇榊丄抮晹椙偼嶌幰偺戝壀徃暯帺恎偩偲偄偆丅偙偺嶁杮杛巕偼30擭戙弶摢偐傜暥抎僶乕偺彈媼傪偟偰偍傝丄捈栘嶰廫屲丄媏抮姲丄嶁岥埨屷丄拞尨拞栫丄彫椦廏梇丄壨忋揙懢榊丄戝壀徃暯偲丄鐱乆偨傞暥恖偨偪偲抝彈曊楌傪廳偹偨偁偘偔丄58擭偵悋柊栻帺嶦傪偟偨傜偟偄丅偄傗偼傗丄偡偛偄彈惈偑偄偨傕偺偩丅
敔崻嶳
1962搶曮丂愳搰梇嶰丂昡揰亂B亃
 戝庤帒杮偵傛傞娤岝奐敪嫞憟偑寖壔偡傞敔崻傪晹戉偵丄挿擭偵傢偨偭偰斀栚偟崌偆2尙偺榁曑椃娰偺悥惃偲庒偄抝彈偺憉傗偐側楒垽傪寉柇偵昤偄偨僪儔儅丅愳搰梇嶰偵偟偰偼捒偟偄惵弔塮夋偺條憡傪掓偟偰偄傞丅尨嶌偼巶巕暥榋偺彫愢丅傏偔偼崅峑弶擭偺偙傠丄挬擔怴暦偱偙偺彫愢偺楢嵹傪撉傫偱偍傝丄塮夋偑岞奐偝傟偨偲偒傕尒偵峴偭偨丅偦偺偲偒偼偁傑傝柺敀偔側偄偲偄偆報徾傪帩偭偨偑丄崱夞尒捈偟偰丄偦傟傎偳埆偄弌棃偱偼側偄偲巚偭偨丅將墡偺拠偺2偮偺椃娰丄偦偺曅曽偺庒斣摢栶偺壛嶳梇嶰丄傕偆曅曽偺堦恖柡栶偺惎桼棦巕偑庡恖岞丅壛嶳懁偺椃娰偺彈彨傪搶嶳愮塰巕丄戝斣摢傪摗尨姍懌丄惎懁偺椃娰偺庡恖晇晈傪嵅栰廃擇丄嶰戭朚巕偑墘偠丄傑偨娤岝夛幮幮挿偵搶栰塸帯榊丄戝暔惌帯壠偵怷斏媣栱丄壏愹儃乕儕儞僌壆偵惣懞峎偑暞偟偰払幰側墘媄傪尒偣傞丅壛嶳梇嶰偺墘媄偼抰愘偩偑丄僙乕儔乕暈巔偺惎桼棦巕偑偠偮偵帺慠偱壜垽傜偟偄丅偲偙傠偳偙傠偵愳搰傜偟偄僽儔僢僋丒儐乕儌傾晽偺峔恾偑婄傪弌偡丅慡懱偲偟偰偼愳搰塮夋摿桳偺偁偔偺嫮偝偑側偔暔懌傝側偄偑丄朻摢偺嫸鏝揑側奐敪嫞憟偺昤偒曽偺柺敀偝偲丄惎桼棦巕偺壜垽偝傪攦偭偰丄4偮惎傪專忋偡傞丅
戝庤帒杮偵傛傞娤岝奐敪嫞憟偑寖壔偡傞敔崻傪晹戉偵丄挿擭偵傢偨偭偰斀栚偟崌偆2尙偺榁曑椃娰偺悥惃偲庒偄抝彈偺憉傗偐側楒垽傪寉柇偵昤偄偨僪儔儅丅愳搰梇嶰偵偟偰偼捒偟偄惵弔塮夋偺條憡傪掓偟偰偄傞丅尨嶌偼巶巕暥榋偺彫愢丅傏偔偼崅峑弶擭偺偙傠丄挬擔怴暦偱偙偺彫愢偺楢嵹傪撉傫偱偍傝丄塮夋偑岞奐偝傟偨偲偒傕尒偵峴偭偨丅偦偺偲偒偼偁傑傝柺敀偔側偄偲偄偆報徾傪帩偭偨偑丄崱夞尒捈偟偰丄偦傟傎偳埆偄弌棃偱偼側偄偲巚偭偨丅將墡偺拠偺2偮偺椃娰丄偦偺曅曽偺庒斣摢栶偺壛嶳梇嶰丄傕偆曅曽偺堦恖柡栶偺惎桼棦巕偑庡恖岞丅壛嶳懁偺椃娰偺彈彨傪搶嶳愮塰巕丄戝斣摢傪摗尨姍懌丄惎懁偺椃娰偺庡恖晇晈傪嵅栰廃擇丄嶰戭朚巕偑墘偠丄傑偨娤岝夛幮幮挿偵搶栰塸帯榊丄戝暔惌帯壠偵怷斏媣栱丄壏愹儃乕儕儞僌壆偵惣懞峎偑暞偟偰払幰側墘媄傪尒偣傞丅壛嶳梇嶰偺墘媄偼抰愘偩偑丄僙乕儔乕暈巔偺惎桼棦巕偑偠偮偵帺慠偱壜垽傜偟偄丅偲偙傠偳偙傠偵愳搰傜偟偄僽儔僢僋丒儐乕儌傾晽偺峔恾偑婄傪弌偡丅慡懱偲偟偰偼愳搰塮夋摿桳偺偁偔偺嫮偝偑側偔暔懌傝側偄偑丄朻摢偺嫸鏝揑側奐敪嫞憟偺昤偒曽偺柺敀偝偲丄惎桼棦巕偺壜垽偝傪攦偭偰丄4偮惎傪專忋偡傞丅
2022擭6寧朸擔 旛朰榐177丂愳搰梇嶰偺塮夋丂偦偺1
1960搶曮丂愳搰梇嶰丂昡揰亂B亃
 崅偔昡壙偡傞僼傽儞偑偄傞偺偱慜偐傜尒偨偄偲巚偭偰偄偨愳搰梇嶰嶌昳丅攡嶈弔惗尨嶌偲偄偆偙偲偱傕婥偵側偭偰偄偨丅寢榑偐傜尵偆偲丄偙傟偼愳搰偺寙嶌偺傂偲偮偩偲巚偆丅慜嶌偺乽戄娫偁傝乿偲摨偠偔僼儔儞僉乕嶄庡墘偩偑丄乽戄娫偁傝乿傛傝偼傞偐偵柺敀偄偙偲偼妋偐偩丅嬧嵗偺僉儍僶儗乕丒僶儞僪偺僪儔儅乕亖僼儔儞僉乕嶄偑幙壆偵柟擖傝偡傞偑丄堄抧埆側屍亖戲懞掑巕偲壟亖墶嶳摴戙偵偄傃傜傟丄壠弌偡傞丄偲偙傠偑屍偲壟偼僼儔儞僉乕偑敎戝側堚嶻傪憡懕偡傞偙偲丄1儠寧埲撪偵庤懕偒偟側偗傟偽偦偺尃棙傪幐偆偙偲傪抦傜偝傟丄戝峇偰偱僼儔儞僉乕傪扵偟傑偔傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅婌寑偩偑愳搰摼堄偺偄傢備傞廳婌寑偱偼側偔梞晽偺僗僋儕儏乕儃乕儖丒僐儊僨傿偱偁傝丄婏恖曄恖偑懡悢搊応偟丄憗岥偱夛榖傪岎傢偟丄僗僺乕僨傿側揥奐偱恑峴偡傞丅壠偺戩忋僾儗僀儎乕偱僜僲僔乕僩傪偐偗偨傝丄楬忋偱彎醱孯恖偑孯壧傪壧偭偰偄偨傝偲丄悘強偵愄夰偐偟偄岝宨偑塮偟弌偝傟傞丅壠弌偟偨僼儔儞僉乕偑怮攽傑傝偡傞栘捓廻偺庡恖偵壛搶戝夘丄愯偄岲偒偺慘搾偺恊晝偵怷愳怣丄僼儔儞僉乕峴偒偮偗偺嫃庰壆偺彈彨偵扺楬宐巕偲寍払幰懙偄丅扙慄僩儕僆傗儘僀丒僕僃乕儉僗傑偱搊応偟偰僫儞僙儞僗側婥塣傪惙傝忋偘傞丅廔斦偵戝偒側僆僠偑偁傞偑丄偦傟偼尵傢側偄偱偍偙偆丅僄儞僨傿儞僌偱壛搶丄怷愳丄扺楬側偳偑奿岲偩偗偩偑妝婍傪庤偵偟偰僶儞僪墘憈偟丄僼儔儞僉乕偑杮怑偺僪儔儉丒僾儗僀傪斺業偡傞丅嵟屻傑偱恖傪怘偭偨塮夋偩丅
崅偔昡壙偡傞僼傽儞偑偄傞偺偱慜偐傜尒偨偄偲巚偭偰偄偨愳搰梇嶰嶌昳丅攡嶈弔惗尨嶌偲偄偆偙偲偱傕婥偵側偭偰偄偨丅寢榑偐傜尵偆偲丄偙傟偼愳搰偺寙嶌偺傂偲偮偩偲巚偆丅慜嶌偺乽戄娫偁傝乿偲摨偠偔僼儔儞僉乕嶄庡墘偩偑丄乽戄娫偁傝乿傛傝偼傞偐偵柺敀偄偙偲偼妋偐偩丅嬧嵗偺僉儍僶儗乕丒僶儞僪偺僪儔儅乕亖僼儔儞僉乕嶄偑幙壆偵柟擖傝偡傞偑丄堄抧埆側屍亖戲懞掑巕偲壟亖墶嶳摴戙偵偄傃傜傟丄壠弌偡傞丄偲偙傠偑屍偲壟偼僼儔儞僉乕偑敎戝側堚嶻傪憡懕偡傞偙偲丄1儠寧埲撪偵庤懕偒偟側偗傟偽偦偺尃棙傪幐偆偙偲傪抦傜偝傟丄戝峇偰偱僼儔儞僉乕傪扵偟傑偔傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅婌寑偩偑愳搰摼堄偺偄傢備傞廳婌寑偱偼側偔梞晽偺僗僋儕儏乕儃乕儖丒僐儊僨傿偱偁傝丄婏恖曄恖偑懡悢搊応偟丄憗岥偱夛榖傪岎傢偟丄僗僺乕僨傿側揥奐偱恑峴偡傞丅壠偺戩忋僾儗僀儎乕偱僜僲僔乕僩傪偐偗偨傝丄楬忋偱彎醱孯恖偑孯壧傪壧偭偰偄偨傝偲丄悘強偵愄夰偐偟偄岝宨偑塮偟弌偝傟傞丅壠弌偟偨僼儔儞僉乕偑怮攽傑傝偡傞栘捓廻偺庡恖偵壛搶戝夘丄愯偄岲偒偺慘搾偺恊晝偵怷愳怣丄僼儔儞僉乕峴偒偮偗偺嫃庰壆偺彈彨偵扺楬宐巕偲寍払幰懙偄丅扙慄僩儕僆傗儘僀丒僕僃乕儉僗傑偱搊応偟偰僫儞僙儞僗側婥塣傪惙傝忋偘傞丅廔斦偵戝偒側僆僠偑偁傞偑丄偦傟偼尵傢側偄偱偍偙偆丅僄儞僨傿儞僌偱壛搶丄怷愳丄扺楬側偳偑奿岲偩偗偩偑妝婍傪庤偵偟偰僶儞僪墘憈偟丄僼儔儞僉乕偑杮怑偺僪儔儉丒僾儗僀傪斺業偡傞丅嵟屻傑偱恖傪怘偭偨塮夋偩丅乽愒嶁偺巓枀乿傛傝丂栭偺敡
1960搶曮丂愳搰梇嶰丂昡揰亂C亃
愒嶁偺壴奨傪晳戜偵3巓枀偺惗偒曽傪摉帪偺悽憡傪棈傔偰昤偔晽懎塮夋丅撪梕偼堎側傞偑暤埻婥揑偵偼乽彈偼擇搙惗傑傟傞乿傪巚傢偣傞丅僶乕傪宱塩偟偮偮抝傪搉傝曕偄偰偺偟忋偑傞挿彈偵扺搰愮宨丄堦恖偺抝偵恠偔偡師彈偵怴庫嶰愮戙丄妛惗塣摦偵偺傔傝崬傓嶰彈偵怴恖偺愳岥抦巕偑暞偡傞丅傎偐偵弌斣偼彮側偄偑偟偨偨偐側晳戜彈桪傪媣帨偁偝傒偑墘偠傞丅扺搰丄怴庫丄媣帨偲偄偆3恖偺旤彈偺嫞墘偑尒傕偺偩偑丄傗偼傝扺搰偺旤偟偝偑孮傪敳偄偰偄傞丅斵彈偼嶰嫶払栫丄徏懞払梇丄僼儔儞僉乕嶄丄揷嶈弫丄埳摗梇擵彆偲丄幚嬈壠傗惌帯壠側偳丄師乆偵抝傪忔傝姺偊偰惉岟傪栚巜偡丅朻摢丄揷幧偐傜弌偰偒偨嶰彈偑崙夛媍帠摪偺栧偵壴傪揧偊傞偑丄偙傟偼姃旤抭巕傊偺庤岦偗偺壴偩傠偆偐丅扺搰偲怴庫偺庢偭慻傒崌偄偺寲壾偼側偐側偐偺敆椡丅
2022擭5寧
2022擭5寧朸擔 旛朰榐176丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺塮夋丂偦偺3
1932暷丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗丂昡揰亂D亃
僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕庡墘偺僇乕丒儗乕僗塮夋丅恖婥僇乕丒儗乕僒乕偺杤棊偲嵞惗偺暔岅丅孼偵摬傟偰僇乕丒儗乕僒乕偵側傞掜偲偺孼掜垽偲妋幏丄楒恖偲偺暿傟偲嵞夛偲偄偭偨憓榖偑棈傓丅慡懱偵儊儘僪儔儅晽偱偁傝丄儂乕僋僗傜偟偝偼偁傑傝敪婗偝傟偰偄側偄丅
柍尷偺惵嬻
1935暷丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗丂昡揰亂C亃
偙傟傕僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕庡墘偺峲嬻塮夋丅尨戣偺乽Ceiling Zero乿偲偼塤偲抧忋偺娫偑柖傗愥偱帇奅僛儘偵側傝丄憖廲晄擻偵側傞偙偲傪巜偡丅峲嬻塮夋偲偼偄偊丄偲偙傠偳偙傠偵憓擖偝傟傞憖廲惾傗僶乕側偳偺僔乕儞傪彍偒丄応柺偼傎傏峲嬻夛幮偺娗惂幒偵尷掕偝傟偰偄傞偑丄嬞敆姶偼廫暘偵忴偟弌偝傟偰偄傞丅儀僥儔儞丒僷僀儘僢僩偺僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕偲娗惂幒巜婗姱僷僢僩丒僆僽儔僀僄儞偺桭忣丄彈傪弰傞僷僀儘僢僩摨巑偺妋幏丄婋尟側旘峴偵挧傓抝偨偪偺怱堄婥側偳偑昤偐傟丄揟宆揑側儂乕僋僗塮夋偲尵偊傞丅塮夋偼僐儊僨傿晽偵巒傑傞偑丄搑拞偱拠娫偺僷僀儘僢僩偑帠屘巰偡傞偁偨傝偐傜暤埻婥偼埫偔側傝丄儂乕僋僗偵偟偰偼捒偟偔丄嵟屻偼斶寑偱廔傞丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐175丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺塮夋丂偦偺2
1931暷丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗丂昡揰亂C亃
僂僅儖僞乕丒僸儏乕僗僩儞庡墘偺孻柋強塮夋丅恀柺栚側惵擭偑岆偭偰恖傪嶦偟偰偟傑偄丄10擭偺挦栶孻偵張偣傜傟傞丅擖崠偟偨斵偼帺朶帺婞偵側傞偑丄怴偟偔晪擟偟偨強挿晅偒偺塣揮庤偵側傝丄強挿偺柡偲恊偟偔側偭偰惗偒傞堄梸傪庢傝栠偡丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偮偠偮傑偺崌傢側偄売強傗偛搒崌庡媊偺揥奐偼偨偔偝傫偁傞偑丄榖偺棳傟偼僗儉乕僘偱儂乕僋僗偺墘弌椡傪姶偠傞丅惵擭傪崘敪偡傞専帠偱偁傝丄偺偪偵強挿偲偟偰孻柋強偵晪擟偡傞僂僅儖僞乕丒僸儏乕僗僩儞偼偝偡偑偺娧榎丅惵擭偺摨朳偱強撪偺棤愗傝幰傪嶦偡摿堎側晽杄偺儃儕僗丒僇乕儘僼傕側偐側偐偺夦墘丅
塱墦偺愴応
1936暷丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗丂昡揰亂B亃
戞1師戝愴拞丄僼儔儞僗孯拞戉偺僪僀僣偲偺愴偄傪昤偔愴憟塮夋丅怴偟偔晪擟偟偨拞戉偺暃姱傪僼儗僨儕僢僋丒儅乕僠丄愭擟偺巜婗姱傪儚乕僫乕丒僶僋僗僞乕偑墘偠傞丅摨偠彈惈傪垽偡傞暃姱偲巜婗姱偺嬯擸偲桭忣丄巰偵捈柺偟偨暫巑偨偪偺嫰偊偲桬婥傪僥乕儅偲偟偰偍傝丄儂乕僋僗偺乽崱擔尷傝偺柦乿傗乽僐儞僪儖乿傪渇渋偲偝偣傞丅夁崜側愴憟偑昤偐傟傞偑丄椡揰偑抲偐傟傞偺偼暫巑偨偪偑搚抎応偱帵偡抝傜偟偝偲塸梇揑峴堊偱偁傝丄偦偙偵僕儑儞丒僼僅乕僪偺愴憟塮夋偲偺堘偄偑偁傞丅偦偺僸乕儘乕楃巀偺嬻婥偼旲偵偮偐側偄偱傕側偄丅媟杮偺僂傿儕傾儉丒僼僅乕僋僫乕偼30乣40擭戙偵偟偽偟偽儂乕僋僗塮夋偱媟杮壠偲偟偰屬傢傟偰偄偨丅峠堦揰偺彈惈偵暞偡傞偺偼僕儏乕儞丒儔儞僌偱丄偁傑傝撻愼傒偑側偄偑丄側偐側偐偒傟偄側彈桪偩丅拞戉偵巙婅偡傞榁暫巑偱偠偮偼巜婗姱偺晝恊偲偄偆栶偺儔僀僆僱儖丒僶儕儌傾偼丄偺偪偵乽僉乕丒儔乕僑乿側偳偱幵堉巕偵忔傞婃屌側榁恖傪墘偠偨丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐174丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺塮夋丂偦偺1
1940暷丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗丂昡揰亂A亃
偙傟偼悽昡偵堘傢偸僗僋儕儏乕儃乕儖丒僐儊僨傿偺寙嶌偩丅僔僇僑偺怴暦幮偺曇廤挿働僀儕乕丒僌儔儞僩偲晀榬彈惈婰幰儘僓儕儞僪丒儔僢僙儖偑庡栶丅斵傜偼晇晈偩偭偨偑尰嵼偼棧崶偟丄儔僢僙儖偼怴偟偄嫋崶幰儔儖僼丒儀儔儈乕偲偲傕偵奨傪棧傟傛偆偲偟偰偄傞丅傑偩儔僢僙儖偵枹楙偑偁傞僌儔儞僩偼寵偑傞儔僢僙儖偵庤楙庤娗傪巊偭偰巰孻廁傪庢嵽偝偣傞偑丄偦偺抝偑扙崠偟偰戝憶摦偵側傝ゥ苽X僩乕儕乕丅惁傑偠偄憗岥偺儅僔儞僈儞丒僩乕僋傪岎傢偡僌儔儞僩偲儔僢僙儖偑尒帠丄儂乕僋僗偺娚媫傪摜傑偊偨僗僺乕僨傿側墘弌傕愨柇偱丄娫慠偡傞偲偙傠偑側偄丅偺偪偵價儕乕丒儚僀儖僟乕偑乽僼儘儞僩丒儁乕僕乿偲偟偰儕儊僀僋偟偨偑丄弌棃偼抐慠偙偺儂乕僋僗斉偺傎偆偑偄偄丅
壥偰偟側偒憮嬻
1952暷丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗丂昡揰亂D亃
僇乕僋丒僟僌儔僗庡墘丅奐戱帪戙丄墱抧偵廧傓僀儞僨傿傾儞偲偺栄旂岎堈偺偨傔儈僘乕儕愳傪慏偱偝偐偺傏傞堦峴偺嬯擄偺椃傪昤偄偨惣晹寑丅慏椃偺昤幨偵偼儂乕僋僗傜偟偄崑夣偝偑帵偝傟傞売強傕偁傞偑丄慡懱偲偟偰僪儔儅偼暯斅偱惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐173丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕偺塮夋丂偦偺3
1930暷丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕丂昡揰亂C亃
僠儍乕儖僗丒價僢僋僼僅乕僪庡墘偺惣晹寑丅儚僀儔乕弶偺僩乕僉乕嶌昳偩偲偄偆丅尨嶌偼乽The Three Godfathers乿偲偄偆彫愢偱丄壗搙傕塮夋壔偝傟偰偍傝丄偦偺側偐偱偼僕儑儞丒僼僅乕僪偺乽3恖偺柤晅偗恊乿乮1948乯偑桳柤丅嵒敊傪偝傑傛偆3恖偺側傜偢幰偑惗傑傟偨偽偐傝偺愒傫朧傪柦偑偗偱挰傑偱憲傝撏偗傞榖丅慡懱偵廆嫵揑側怓崌偄偑嫮偄丅
嫄恖搊応
1933暷丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕丂昡揰亂C亃
僕儑儞丒僶儕儌傾丄價乕價乕丒僟僯僄儖僘庡墘丅僄儖儅乕丒儔僀僗偺媃嬋偺塮夋壔丅偙偺朚戣偼堄枴晄柧丄尨戣偼乽Counselor at Law乿乮曎岇巑乯偩丅応柺愝掕偼傎偲傫偳僯儏乕儓乕僋堦摍抧偺價儖偺曎岇巑帠柋強偺傒偵尷掕偝傟偰偍傝丄偦偙偱巇帠偡傞曎岇巑偺峇偨偩偟偄堦擔偑昤偐傟傞丅傂偭偒傝側偟偵斷偑奐偗暵傔偝傟丄恖乆偑弌擖傝偟丄懍幩朇偺傛偆偵夛榖偑岎傢偝傟傞丅妶婥偑傒側偓偭偰偄傞偑丄晳戜寑偺暤埻婥偑擹岤偡偓傞偺偑擄丅庡恖岞偺曎岇巑傪墘偢傞柤桪僕儑儞丒僶儕儌傾偼偝偡偑偺娧榎丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐172丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕偺塮夋丂偦偺2
1936暷丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕丂昡揰亂B亃
儈儕傾儉丒儂僾僉儞僗丄儅乕儖丒僆儀儘儞丄僕儑僄儖丒儅僢僋儕乕庡墘丄儕儕傾儞丒僿儖儅儞偺媃嬋乽巕嫙偺帪娫乿偺塮夋壔丅偙傟偼儚僀儔乕偑弶傔偰嶌壠惈傪慜柺偵懪偪弌偟偨嶌昳偱偁傠偆丅彈惗搆婑廻妛峑傪宱塩偡傞恊桭摨巑偺擇恖偺彈惈偺惗妶偑惗搆偺塕偺枾崘偵傛偭偰攋抅偡傞榖丅儚僀儔乕偺慛傗偐側墘弌椡傪姶偠傞丅尦乆偼擇恖偑摨惈垽偺塡傪棫偰傜傟傞偲偄偆嬝偩偭偨偑丄摉帪偺椣棟婯掕偵傛偭偰僾儘僢僩偑榓傜偘傜傟丄堦恖偺抝傪弰偭偰棎傟偨娭學傪帩偭偰偄傞偲偄偆塡偵抲偒姺偊傜傟偨丅偙偺塮夋偱偼嵟屻偵斵傜偺柍幚偑棫徹偝傟丄僴僢僺乕僄儞僪偵側傞偑丄偺偪偵儚僀儔乕偑尨嶌偵拤幚偵僙儖僼丒儕儊僀僋偟偨乽塡偺擇恖乿偱偼媬偄傛偆偺側偄斶寑偱廔傞丅
岴悵晇恖
1936暷丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕丂昡揰亂D亃
僂僅儖僞乕丒僸儏乕僗僩儞庡墘丄僔儞僋儗傾丒儖僀僗偺彫愢乽僪僢僘儚乕僗乿偺塮夋壔丅帺摦幵夛幮幮挿僂僅儖僞乕丒僸儏乕僗僩儞偼幚嬈奅傪堷戅偟丄庒偄嵢儖乕僗丒僠儍僞乕僩儞偲堦弿偵墷廈椃峴偵弌偐偗傞丅嵢偼僷儕傗僂傿乕儞側偳峴偔愭乆偱弌夛偆抝偲晜婥傪孞傝曉偟丄嵟弶偼偦傟傪嫋偟偰偄偨僸儏乕僗僩儞傕偮偄偵垽憐傪恠偐偟丄椃愭偱抦傝崌偭偨抦揑側彈儊傾儕乕丒傾僗僞乕偺傕偲偵岦偐偆丅僗僩乕儕乕偺揥奐傗昤偒曽偼僼儔儞僗塮夋傪巚傢偣傞丅嵢栶偺僠儍僞乕僩儞偑彈偲偟偰偺枺椡奆柍偱榖偺棳傟偵愢摼椡偑側偔丄僥乕儅偼忋棳奒媺偺抝彈娭學偵廔巒偟偰偍傝尰幚姶偵朢偟偄丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐171丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕偺塮夋丂偦偺1
1952暷丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕丂昡揰亂A亃
儘乕儗儞僗丒僆儕償傿僄偲僕僃僯僼傽乕丒僕儑乕儞僘庡墘丄僙僆僪傾丒僪儔僀僓乕尨嶌彫愢偺塮夋壔丅嵢巕偁傞幚捈側拞擭抝僆儕償傿僄偑揷幧偐傜弌偰偒偨彈岺僕儑乕儞僘偵庝偐傟偰恖惗傪摜傒偼偢偟攋柵偡傞暔岅偱丄乽扱偒偺揤巊乿傗乽旉怓偺奨乿偺宯摑偺嶌昳丅偨偩偟丄僕儑乕儞僘偼弮恀側彈偱怱偐傜僆儕償傿僄傪垽偡傞偲偄偆揰偱丄偦傟傜偺埆彈傕偺偲偼堦慄傪夋偟偰偄傞丅彈偼抝偺傕偲傪嫀偭偰晳戜彈桪偲偟偰惉岟偟丄抝偼晜楺幰偲側偭偰NY偺奨傪偝傑傛偆丅儚僀儔乕偺岅傝岥偺岻偝丄儘乕儗儞僗丒僆儕償傿僄偺梷偊偨墘媄偑愨昳丅
婾傝偺壴墍
1941暷丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕丂昡揰亂A亃
傾儊儕僇撿晹偺媽壠傪晳戜偵偟偨懪嶼偲梸傪攳偒弌偟偵偡傞彈庡恖傪弰傞暔岅丅儕儕傾儞丒僿儖儅儞偺媃嬋偺塮夋壔丅乽寧岝偺彈乿偺柤僐儞價丄儀僥傿丒僨僀償傿僗偲僴乕僶乕僩丒儅乕僔儍儖偑椻崜側嵢偲昦庛側晇傪墘偠傞丅昤偒曽偼傗傗恾幃揑偩偑丄僪儔儅偲偟偰偺嬞敆姶偼崅偄丅僌儗僢僌丒僩乕儔儞僪偺嶣塭偑尒帠偱丄壆晘偺拞偺墱峴偒傗廲偺峔恾偑慺惏傜偟偔丄偲偔偵奒抜偺僔乕儞偼尒墳偊廫暘丅巒廔敀揾傝偱搊応偡傞儀僥傿丒僨僀償傿僗偼埑姫偺墘媄丄偲傝傢偗怱憻敪嶌偱嬯偟傓晇傪柍昞忣偵尒偰偄傞僔乕儞偼報徾偵巆傞丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐170丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺4
1931暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂C亃
儘僫儖僪丒僐乕儖儅儞偲僿儗儞丒僿僀僘庡墘丄僔儞僋儗傾丒儖僀僗偺彫愢乽傾儘僂僗儈僗乿偺塮夋壔丅嵶嬠偺尋媶偵庢傝慻傓棟憐壠敡偺堛巘偺敿惗傪晇晈垽傪棈傔偰昤偔丅屻敿偵僐乕儖儅儞傪彆偗傞崟恖堛巘偑搊応偡傞偑丄塮夋偱偼崟恖偼彚巊偄傗摴壔栶偲偟偰偟偐埖傢傟側偐偭偨偙偺帪戙偵丄僼僅乕僪偑椙幆偁傞僀儞僥儕栶偵崟恖傪攝偟偨偺偼丄夋婜揑側弌棃帠偩偭偨偼偢偩丅
壌偼慞恖偩
1935暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂B亃
恀柺栚側僒儔儕乕儅儞偑僊儍儞僌偲塟擇偮偩偭偨偙偲偐傜姫偒婲偙傞捒憶摦傪昤偄偨丄僼僅乕僪偵偟偰偼捒偟偄僗僋儕儏乕儃乕儖晽僐儊僨傿偩偑丄側偐側偐椙偔弌棃偰偍傝丄塀傟偨寙嶌偲尵偭偰偄偄偲巚偆丅幚捈側帠柋堳偲嫢埆側僊儍儞僌偺擇栶傪墘偠傞僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞偑慺惏傜偟偄丅憡庤栶偺僕乕儞丒傾乕僒乕傕揔栶丄偦偺懠偺攐桪傕偠偮偵偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐169丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺3
1950暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂A亃
僼僅乕僪傜偟偝偑偵偠傒弌偨丄帬枴朙偐側惣晹寑丅怴揤抧傪栚巜偡儌儖儌儞嫵搆偺杫攏幵戉偺椃偑昤偐傟傞丅杫攏幵戉傪愭摫偡傞僇僂儃乕僀偵儀儞丒僕儑儞僜儞丄偦偺憡朹偵僴儕乕丒働儕乕丒僕儏僯傾丄堦峴偺儕乕僟乕偵儚乕僪丒儃儞僪丄椃栶幰偺堦嵗偺梮傝巕偵僕儑乕儞丒僪儖乕偲丄僼僅乕僪塮夋偱偼偍撻愼傒偺榚栶偨偪偑庡栶傪柋傔傞丅椃偺搑拞偱嫮搻抍偑壛傢傝丄僒僗儁儞僗偑忴惉偝傟傞偑丄慡懱偲偟偰偼抧枴側塮夋偱偁傝丄僈儞僼傽僀僩偺僔乕儞傕嵟弶偲嵟屻偺偛偔傢偢偐偟側偐側偄丅偟偐偟惣晹偺忣宨偑旤偟偔塮偟弌偝傟偰偍傝丄僕儑儞僜儞偲僪儖乗偺扺偄楒傕旝徫傑偟偄丅僕儑儞僜儞偺栚妎傑偟偄忔攏弍傕斺業偝傟傞丅
峳榟偺梼
1956暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂D亃
僕儑儞丒僂僃僀儞庡墘丄戞2師戝愴偱柤傪抷偣偨暷奀孯峲嬻戉偺巑姱僼儔儞僋丒僂傿乕僪偺揱婰塮夋丅僂傿乕僪偺彑偪婥側嵢偵儌乕儕儞丒僆僴儔偑暞偡傞丅晇晈垽傗暫巑偨偪偺桭忣丄棨孯暫偲奀孯暫偺崑夣側寲壾偑昤偐傟丄偄偐偵傕僼僅乕僪塮夋傜偟偄偑丄慡懱偵戝枴偱偁傝丄僂傿乕僪偑奒抜偐傜揮偘棊偪偰敿恎晄悘偵側偭偰埲屻偺揥奐偑庛偄丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐168丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺2
1936暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂C亃
僕儑儞丒僼僅乕僪偵偼捒偟偄楌巎寑丅16悽婭僗僐僢僩儔儞僪彈墹偱丄惌憟偵攕傟僀儞僌儔儞僪偵朣柦偟偨偑彈墹僄儕僓儀僗偵揋懳偟偰張孻偝傟偨儊傾儕乕丒僗僠儏傾乕僩亖僉儍僒儕儞丒僿僾僶乕儞偺惗奤偑丄楒恖儃僘僂僃儖攲亖僼儗僨儕僢僋丒儅乕僠偲偺斶楒傪岎偊偰昤偐傟傞丅僿僢僾僶乕儞偺墘媄偺岻偝偼偝偡偑丅僼僅乕僪偲僿僾僶乕儞偼偙偺塮夋偑偒偭偐偗偱楒拠偵側偭偨丅
恀庫榩峌寕
1943暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂D亃
恀庫榩峌寕傪戣嵽偲偡傞婰榐僼傿儖儉偲寑傪儈僢僋僗偝偣偨愴堄崅梘塮夋丅嫟摨娔撀偺僌儗僢僌丒僩乕儔儞僪偑幚幙揑側娔撀傪庤偑偗偨偲偄偆丅傾儊儕僇傪懱尰偡傞恆巑僂僅儖僞乕丒僸儏乕僗僩儞傗暫巑偺朣楈僟僫丒傾儞僪儕儏乕僗偑搊応偡傞婏柇側嶌昳丅擔杮偺晽廗傗僴儚僀偺晽宨丄偦偙偵廧傓擔宯恖偺惗妶偑徯夘偝傟傞偑丄擔杮傪偦傟傎偳憺傓傋偒媤偵偼昤偄偰偄側偄偺偼僼僅乕僪傜偟偄偲尵偆傋偒偐丅屻敿偺恀庫榩敋寕僔乕儞偼塮夋偺偨傔偺嶣塭偩偑幚幨偲尒傑偛偆傎偳敆椡枮揰偩丅
2022擭5寧朸擔 旛朰榐167丂僕儑儞丒僼僅乕僪偺塮夋丂偦偺1
1945暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂B亃
僕儑儞丒僂僃僀儞丄儘僶乕僩丒儌儞僑儊儕乕丄僪僫丒儕乕僪偑庡墘偡傞丄戞2師戝愴拞偺僼傿儕僺儞愴慄偱偺暷孯暫巑偺嬯摤偑昤偐傟偨愴憟塮夋丅尨戣乽They Were Expendable乿(斵傜偼徚栒昳偩偭偨)偳偍傝丄墋愴儉乕僪偑昚偆嶌昳偱偁傝丄塃梼岲愴攈偲尒傜傟傞僕儑儞丒僼僅乕僪偺寛偟偰扨弮偱偼側偄嶖憥偟偨愴憟娤偑帵偝傟偰偄傞丅偩偑暫巑偨偪偺怱堄婥偲桭忣偺昤偒曽偼揟宆揑側僼僅乕僪丒僗僞僀儖偩丅揮愴偡傞彛夲嫑棆戉偺彨峑僕儑儞丒僂僃僀儞偲娕岇晈僪僫丒儕乕僪偺弌夛偄偲暿傟偑愗側偄丅
塰岝壗偡傞傕偺偧
1952暷丂僕儑儞丒僼僅乕僪丂昡揰亂C亃
僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕庡墘丅戞1師戝愴拞丄僼儔儞僗愴慄偱揷幧偺懞偵挀撛偡傞暷孯奀暫戉偺憶摦傪昤偄偨僐儊僨傿晽愴憟塮夋丅僪僞僶僞婌寑偩偑丄偙偙偵傕墋愴婥暘偑塭傪棊偲偟偰偄傞丅懞偺柡偵暞偟偰怴暫儘僶乕僩丒儚僌僫乕偲楒拠偵側傞儅儕僒丒僷償傽儞偼変偑垽偟偺僺傾丒傾儞僕僃儕偺憃巕偺枀偱丄偙傟偑塮夋弶弌墘偲偺偙偲丅
2022擭5寧8擔 梋択丗亀彮擭墹幰戞10廤 夦廱夊屨曆亁傪撉傫偩
 5寧偺楢媥偺弶摢丄強梡偑偁偭偰戝嶃偵峴偭偨丅偦偺婡夛偵丄傛偆傗偔擮婅偺嶳愳憏帯嶌亀彮擭墹幰戞10廤 夦廱夊屨曆亁傪撉傓偙偲偑偱偒偨丅乽彮擭墹幰乿偲乽夦廱夊屨曆乿偵偮偄偰偼丄埲慜丄偙偺僐儔儉偺乻乽嶳愳憏帯偺乽彮擭墹幰乿偑垽偲桬婥傪嫵偊偰偔傟偨乼偲乻乽彮擭墹幰乿乗乗尪偺乽夦廱夊屨曆乿乼偱彂偄偰偄傞偺偱丄嶲徠偟偰偄偨偩偒偨偄丅偙傟偼巰偸傑偱偵壗偲偐撉傒偨偄偲巚偭偰偄偨杮偩丅偙偺杮偑丄偍偦傜偔擔杮偺恾彂娰偱桞堦丄戝嶃晎棫拞墰恾彂娰晅懏偺崙嵺帣摱暥妛娰偵強憼偝傟偰偄傞偙偲偼丄埲慜挷傋偰抦偭偰偄偨丅側偐側偐戝嶃偵峴偔僠儍儞僗偑側偐偭偨偑丄傗偭偲挿擭偺婅朷偑幚尰偟偨丅
5寧偺楢媥偺弶摢丄強梡偑偁偭偰戝嶃偵峴偭偨丅偦偺婡夛偵丄傛偆傗偔擮婅偺嶳愳憏帯嶌亀彮擭墹幰戞10廤 夦廱夊屨曆亁傪撉傓偙偲偑偱偒偨丅乽彮擭墹幰乿偲乽夦廱夊屨曆乿偵偮偄偰偼丄埲慜丄偙偺僐儔儉偺乻乽嶳愳憏帯偺乽彮擭墹幰乿偑垽偲桬婥傪嫵偊偰偔傟偨乼偲乻乽彮擭墹幰乿乗乗尪偺乽夦廱夊屨曆乿乼偱彂偄偰偄傞偺偱丄嶲徠偟偰偄偨偩偒偨偄丅偙傟偼巰偸傑偱偵壗偲偐撉傒偨偄偲巚偭偰偄偨杮偩丅偙偺杮偑丄偍偦傜偔擔杮偺恾彂娰偱桞堦丄戝嶃晎棫拞墰恾彂娰晅懏偺崙嵺帣摱暥妛娰偵強憼偝傟偰偄傞偙偲偼丄埲慜挷傋偰抦偭偰偄偨丅側偐側偐戝嶃偵峴偔僠儍儞僗偑側偐偭偨偑丄傗偭偲挿擭偺婅朷偑幚尰偟偨丅 崙嵺帣摱暥妛娰偑偁傞搶戝嶃巗偺峳杮傑偱偼丄攽傑偭偰偄偨儂僥儖偺嬤偔偺側傫偽墂偐傜揹幵偱栺30暘丅戝嶃拞墰恾彂娰偺堦妏偵偁傝丄恾彂偼娰撪偱偟偐墈棗偱偒側偄丅墈棗傪怽偟崬傫偱彂屔偐傜弌偟偰傕傜偭偨亀彮擭墹幰戞10廤 夦廱夊屨曆亁偼丄傓偐偟夰偐偟偄嵍塃18cm傎偳偺恀巐妏偺廤塸幮偍傕偟傠暥屔僆儕僕僫儖斉丅昞巻偼丄嫢朶偦偆側戝僑儕儔偑偡偄巕傪書偊丄抁寱傪庤偵偟偨彮擭墹幰恀屷偲偵傜傒崌偭偰偄傞奊偩丅岥奊偺尒奐偒2儁乕僕偵偼丄恀屷偲丄恊桭偺崟昢偑丄僞僀僩儖偵弌偰偔傞夦廱夊屨偲愴偆條巕偑昤偐傟偰偄傞丅
崙嵺帣摱暥妛娰偑偁傞搶戝嶃巗偺峳杮傑偱偼丄攽傑偭偰偄偨儂僥儖偺嬤偔偺側傫偽墂偐傜揹幵偱栺30暘丅戝嶃拞墰恾彂娰偺堦妏偵偁傝丄恾彂偼娰撪偱偟偐墈棗偱偒側偄丅墈棗傪怽偟崬傫偱彂屔偐傜弌偟偰傕傜偭偨亀彮擭墹幰戞10廤 夦廱夊屨曆亁偼丄傓偐偟夰偐偟偄嵍塃18cm傎偳偺恀巐妏偺廤塸幮偍傕偟傠暥屔僆儕僕僫儖斉丅昞巻偼丄嫢朶偦偆側戝僑儕儔偑偡偄巕傪書偊丄抁寱傪庤偵偟偨彮擭墹幰恀屷偲偵傜傒崌偭偰偄傞奊偩丅岥奊偺尒奐偒2儁乕僕偵偼丄恀屷偲丄恊桭偺崟昢偑丄僞僀僩儖偵弌偰偔傞夦廱夊屨偲愴偆條巕偑昤偐傟偰偄傞丅偁傜偡偠偼偙偆偩丅乽傾僼儕僇偱廬幰偲偲傕偵惗傑傟屘嫿偺墹崙傪栚巜偟偰嬯擄偺椃傪懕偗傞僓儞僶儘偼丄嵒敊偱悈偲怘椘偑側偔側傝丄椡恠偒傛偆偲偟偰偄傞丅偦偙偵恊桭僓儞僶儘偺媷忬傪揱偊暦偄偨傾儊儕僇偺妛峑偵捠偆恀屷偑丄壞媥傒傪棙梡偟偰僓儞僶儘傪彆偗傞偨傔偡偄巕偲偲傕偵僿儕僐僾僞乕偱嬱偗偮偗丄僓儞僶儘偨偪傪媬偆丅僿儕偑屘忈偟偨偨傔斵傜偼堦弿偵嵒敊傪椃偟偰枾椦偵偨偳傝拝偔偑丄偦偙偼偐偮偰恀屷偑拠娫偺摦暔偨偪偲夁偛偟偨応強偩偭偨丅恀屷偼拠娫偵夛偊傞偺傪妝偟傒偵枾椦偵嬱偗崬傫偩偑丄偦偙偼偄傑傗丄偳偙偐傜偐傗偭偰棃偨嫄戝側僑儕儔恖偲偦偺庤壓偺夊屨偵巟攝偝傟偰偍傝丄恀屷偺拠娫偺摦暔偨偪偼峳傟抧偵捛偄傗傜傟偰偄偨丅恀屷偼拠娫傪彆偗傞傋偔僑儕儔恖丄夊屨偲棫偪岦偐偆丅恀屷偼傑偢嬯摤偺偡偊嫢埆側夊屨傪搢偟丄偮偄偵徾傪帩偪忋偘偰奟偐傜撍偒棊偲偡夦椡偺帩偪庡偱偁傞僑儕儔恖偲懳寛偡傞乿
 姶摦偵怹傝側偑傜丄婰壇偵從偒晅偗傞偨傔偰偄偹偄偵撉傒恑傓偆偪偵丄偲偙傠偳偙傠偱丄偁傟丄偙偺暥復偼撉傫偩偙偲偑偁傞偧丄偙偺奊偼尒偨偙偲偑偁傞偧偲偄偆婛帇姶傪妎偊巒傔偨丅偦偟偰嵟屻偺丄恀屷偑僑儕儔恖偲奿摤偟偰愳偵棊偪丄堦弿偵戧傑偱棳偝傟丄僑儕儔恖偼戧偐傜棊偪傞偑丄恀屷偼偐傠偆偠偰戧墢偺娾偵偟偑傒偮偒丄椡傪怳傝峣偭偰懱傪帩偪忋偘偨偲偙傠偵丄娸偵偄偨僓儞僶儘偑僣僞偱嶌偭偨儘乕僾偺椫傪恀屷偵搳偘傞丄偲偄偆売強偵偄偨傝丄偙傟偼娫堘偄側偔埲慜偵撉傫偱偄傞偲偄偆妋怣傪摼偨丅60悢擭偲偄偆妘偨傝傪墇偊偰婰壇偑酳偭偨丅偙傟偼撉傫偩偙偲偑偁傞丅側偤偦傟傪妎偊偰偄側偐偭偨偺偐丠 偍偦傜偔丄摉帪偺傏偔偼丄彫妛峑偺崅妛擭偵側傝丄奊暔岅偺悽奅偐傜枱夋傗彫愢偺悽奅偵擖傝偮偮偁偭偨偨傔丄偁傑傝報徾偵巆傜側偐偭偨偺偩傠偆丅偲傕偁傟丄乽夦廱夊屨曆乿傪撉傓偙偲偑偱偒偰丄帄暉偺傂偲偲偒傪枴傢偭偨丅
姶摦偵怹傝側偑傜丄婰壇偵從偒晅偗傞偨傔偰偄偹偄偵撉傒恑傓偆偪偵丄偲偙傠偳偙傠偱丄偁傟丄偙偺暥復偼撉傫偩偙偲偑偁傞偧丄偙偺奊偼尒偨偙偲偑偁傞偧偲偄偆婛帇姶傪妎偊巒傔偨丅偦偟偰嵟屻偺丄恀屷偑僑儕儔恖偲奿摤偟偰愳偵棊偪丄堦弿偵戧傑偱棳偝傟丄僑儕儔恖偼戧偐傜棊偪傞偑丄恀屷偼偐傠偆偠偰戧墢偺娾偵偟偑傒偮偒丄椡傪怳傝峣偭偰懱傪帩偪忋偘偨偲偙傠偵丄娸偵偄偨僓儞僶儘偑僣僞偱嶌偭偨儘乕僾偺椫傪恀屷偵搳偘傞丄偲偄偆売強偵偄偨傝丄偙傟偼娫堘偄側偔埲慜偵撉傫偱偄傞偲偄偆妋怣傪摼偨丅60悢擭偲偄偆妘偨傝傪墇偊偰婰壇偑酳偭偨丅偙傟偼撉傫偩偙偲偑偁傞丅側偤偦傟傪妎偊偰偄側偐偭偨偺偐丠 偍偦傜偔丄摉帪偺傏偔偼丄彫妛峑偺崅妛擭偵側傝丄奊暔岅偺悽奅偐傜枱夋傗彫愢偺悽奅偵擖傝偮偮偁偭偨偨傔丄偁傑傝報徾偵巆傜側偐偭偨偺偩傠偆丅偲傕偁傟丄乽夦廱夊屨曆乿傪撉傓偙偲偑偱偒偰丄帄暉偺傂偲偲偒傪枴傢偭偨丅忋偵彂偄偨傛偆偵亀彮擭墹幰戞10廤 夦廱夊屨曆亁偼僓儞僶儘偑儘乕僾傪搳偘偨偲偙傠偱廔傢傞丅偙傟偼嵟廔姫偩偐傜丄乽彮擭墹幰乿偼枹姰偱廔椆偟偨偙偲偵側傞丅摉帪愨戝側恖婥偑偁偭偨乽彮擭墹幰乿偺暔岅偑姰寢偟偰偄側偄偺偼晄巚媍側婥偑偡傞丅偟偐偟丄峫偊偰傒傟偽丄乽彮擭墹幰乿偼戞8廤乽夝寛曆乿偱戝抍墌傪寎偊偨偲尒傞傋偒側偺偐傕偟傟側偄丅偙偺戞8廤偺嵟屻偱丄恀屷偼傾僼儕僇偺僕儍儞僌儖偵暿傟傪崘偘丄偡偄巕偲偲傕偵暥柧悽奅偺傾儊儕僇偱曢傜偡偨傔旘峴婡偵忔傝丄柨桭僓儞僶儘偼屘嫿偺墹崙偵岦偗偰椃棫偮丅偦偺屻偺姫偱昤偐傟傞丄恀屷偺傾儊儕僇偱偺妶桇乗乗僊儍儞僌傪戅帯偡傞乗乗傗僓儞僶儘偺嬯擄偺椃傕柺敀偄偺偩偑丄偳偆偟偰傕晅偗懌偟偺姶傪斲傔側偄丅嶌幰偺嶳愳憏帯傕偦偆巚偭偰枹姰偺傑傑乽彮擭墹幰乿傪廔傢傜偣丄師偵庢傝慻傓乽彮擭働僯儎乿偵慡椡傪廤拞偟偨偺偩傠偆丅
2022擭4寧
2022擭4寧朸擔 旛朰榐166丂
1958暷丂儕僠儍乕僪丒僋儚僀儞丂昡揰亂C亃
庡墘丗僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩乛僉儉丒僲償傽僋乛僕儍僢僋丒儗儌儞
寧栭偺弌棃帠
1958暷丂儊儖償傿儖丒僔僃僀償儖僜儞丂昡揰亂C亃
庡墘丗働僀儕乕丒僌儔儞僩乛僜僼傿傾丒儘乕儗儞
2022擭4寧朸擔 旛朰榐165丂
1949暷丂僕儑僙僼丒儅儞僉僂傿僢僣丂昡揰亂C亃
庡墘丗僕乕儞丒僋儗僀儞丄儕儞僟丒僟乕僱儖丄傾儞丒僒僓乕儞丄僇乕僋丒僟僌儔僗
埆恖偲旤彈
1952暷丂償傿儞僙儞僩丒儈僱儕丂昡揰亂B亃
庡墘丗僇乕僋丒僟僌儔僗丄儔僫丒僞乕僫乕丄僂僅儖僞乕丒僺僕儑儞丄僨傿僢僋丒僷僂僄儖丄僌儘儕傾丒僌儗傾儉
2022擭4寧朸擔 旛朰榐164丂
1956暷丂僟僌儔僗丒僒乕僋丂昡揰亂C亃
庡墘丗儘僢僋丒僴僪僜儞乛儘乕儗儞丒僶僐乕儖乛儘僶乕僩丒僗僞僢僋乛僪儘僔乕丒儅儘乕儞
憱傝棃傞恖乆
1958暷丂償傿儞僙儞僩丒儈僱儕丂昡揰亂B亃
庡墘丗僼儔儞僋丒僔僫僩儔乛僔儍乕儕乕丒儅僋儗乕儞乛僨傿乕儞丒儅乕僥傿儞乛儅乕僒丒僴僀儎乕
2022擭4寧朸擔 旛朰榐163丂
1940暷丂僕儑僙僼丒儅儞僉僂傿僢僣丂昡揰亂B亃
庡墘丗僉儍僒儕儞丒僿僢僾僶乕儞乛働僀儕乕丒僌儔儞僩乛僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩
儈僯償傽乕晇恖
1942暷丂僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕丂昡揰亂B亃
庡墘丗僌儕傾丒僈乕僜儞乛僂僅儖僞乕丒僺僕儑儞
2022擭4寧朸擔 旛朰榐162丂
1942暷丂僄僪儚乕僪丒僪儈僩儕僋丂昡揰亂D亃
庡墘丗僥傿儉丒儂儖僩
儅僪儌傾僛儖丒僼傿僼傿
1944暷丂儘僶乕僩丒儚僀僘丂昡揰亂C亃
庡墘丗僔儌乕僰丒僔儌儞
嶦偟偺柤夋
1946暷丂傾乕償傿儞僌丒儕乕僗丂昡揰亂D亃
庡墘丗僷僢僩丒僆僽儔僀僄儞乛僋儗傾丒僩儗償傽乕
2022擭2寧
2022擭2寧朸擔 旛朰榐161丂夰偐偟偺擔杮塮夋丗戝妛偺嶳懐偨偪丄抧崠偺掙傑偱偮偒崌偆偤
1960搶曮丂壀杮婌敧丂昡揰亂C亃
偨傑偨傑傾儅僝儞丒僾儔僀儉價僨僆偱偙偺塮夋傪尒偮偗丄夰偐偟偝偺偁傑傝儗儞僞儖偱尒偨丅60擭傇傝偺嵞尒丅愄偙偺塮夋傪尒偰搊応偡傞彈桪偺傂偲傝丄桍愳宑巕偵崨傟崬傫偩婰壇偑偁傞丅偄傑尒傞偲丄桍愳偺偪傚偭偲廌偄傪懷傃偨昞忣偲偟偲傗偐側晽忣偼偨偟偐偵埆偔側偄偑丄側偤摉帪偦偙傑偱偺傏偣偨偺偐丄傛偔暘偐傜側偄丅嶳嶈搘丄嵅摗堯丄媣曐柧丄偦傟偵敀愳桼旤丄桍愳宑巕丄忋尨旤嵅偑庡墘偡傞惵弔僗僉乕塮夋丅偦偺傎偐偺弌墘幰偱偼儈僢僉乕丒僇乕僥傿僗偺屄惈偑岝傞丅傑偨忋尨尓偲墇楬悂愥偺拞擭僐儞價傕埆偔側偄丅愥嶳偺嶳憫偑晳戜偱丄乽嬧椾偺壥偰乿偲乽桯楈偲枹朣恖乿傪儈僢僋僗偝偣偨傛偆側僐儊僨傿偩丅搶曮偺摉帪偺惵弔僗僞乕偑憤弌墘偲偄偆姶偠偱丄傕偟壛嶳梇嶰偑僨價儏乕偟偰偄偨傜丄偲偆偤傫壛傢偭偰偄偨偩傠偆丅嶳嶈搘偼乽揤崙偲抧崠乿乮1963乯偑僨價儏乕嶌偩偲巚偭偰偄偨偑丄偳偆傗傜偙偺塮夋偑偦偆傜偟偄丅乽塀偟嵲偺嶰埆恖乿乮1958乯偱慛楏偵僨價儏乕偟偨忋尨旤嵅偼丄偙偺塮夋傪嵟屻偵堷戅偡傞丅壀杮婌敧偺僥儞億偺偄偄墘弌偑嶀偊偰偄傞丅朻摢丄愥嶳偱僗僉乕儎乕偑妸傞塮憸偑塮偟弌偝傟丄乽廔乿偺暥帤偑擖傝丄偁傟偲巚傢偣傞偑丄僨僷乕僩偺CM塮憸偩偭偨偙偲偑暘偐傞丅惉悾枻婌抝偑乽偍偐偁偝傫乿偱巊偭偰偄偨丄煭棊偨傾僀僨傾偩丅
抧崠偺掙傑偱偮偒崌偆偤
1959搶塮丂彫戲栁峅丂昡揰亂D亃
乽戝妛偺嶳懐偨偪乿傪尒偨梋惃傪嬱偭偰丄傕偆1杮丄巕嫙偺偙傠偵尒偨夰偐偟偄塮夋傪傾儅僝儞丒僾儔僀儉價僨僆偱尒偨丅曅壀愮宐憼庡墘偺僊儍儞僌塮夋偩丅偙偺偙傠乽抧崠偺乿塢乆偲偄偆戣柤偺愮宐憼庡墘偺僊儍儞僌塮夋偑壗杮偐嶌傜傟偨偑丄偙傟偼偦偺傂偲偮丅愮宐憼庡墘偺尰戙暔傾僋僔儑儞塮夋偼丄傎偐偵桳柤側懡梾旜敽撪僔儕乕僘傗柍廻僔儕乕僘乮乽傾儅僝儞柍廻乿偲偐乽僸儅儔儎柍廻乿偲偐両乯側偳丄偄傠偄傠偁偭偨丅峳搨柍宮側撪梕偩偑摉帪偼恖婥偑偁偭偨偺偩傠偆丅偙偺塮夋丄庒嶳彶偑壧偆庡戣壧偼傛偔妎偊偰偄傞偺偩偑丄拞恎偼傑偭偨偔婰壇偵側偄丅傕偟偐偡傞偲愄尒偨偺偼梊崘曇偩偗偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅搶僔僫奀偱慏偐傜棊偪偰巰傫偩偲巚傢傟偰偄偨抝偑擔杮偵婣偭偰帺暘傪嶦偦偆偲偟偨拠娫偵暅廞偡傞榖丅庡恖岞偺抝偵愮宐憼丄偦偺掜偺戝妛惗偵崅憅寬丄愽擖憑嵏姱偵峕尨恀擇榊偑暞偟丄傎偐偵拞尨傂偲傒丄嵅媣娫椙巕側偳偺彈桪恮丄嶳宍孧丄桍塱擇榊側偳偺埆栶恮偲側偐側偐崑壺側攝栶丅朻摢丄愮宐憼偼帺暘偺幍夞婖朄梫偵娀壉傪撏偗偝偣丄偦偺側偐偐傜桇傝弌偰朶傟傑偔傞丅偦偟偰廔斦丄愮宐憼偼楈瀕幵偵忔偭偰埆恖偨偪偺憙孉偵岦偐偄丄偦偙偵奿岲偄偄庡戣壧偑棳傟傞偲偄偆庯岦丅
2022擭2寧朸擔 旛朰榐160丂夰偐偟偺僀僞儕傾塮夋丗寖偟偄婫愡丄傢傜偺抝
1959埳丒暓丂償傽儗儕僆丒僘儖儕乕僯丂昡揰亂B亃
愳杮嶰榊偺偙偺塮夋偵娭偡傞暥復傪撉傫偱丄偦偆偄偊偽偙偺桳柤側塮夋傪傑偩尒偰側偐偭偨偲巚偄弌偟偨丅巹側偳傛傝堦悽戙慜偺塮夋僼傽儞偼丄偙偺乽寖偟偄婫愡乿偺僄儗僆僲儔丒儘僢僔丒僪儔僑偵摡慠偲側傝丄乽夁嫀傪帩偮垽忣乿偺僼儔儞僜儚乕僘丒傾儖僰乕儖偵楒怱傪書偄偨丅偙偺塮夋偼戞2師戝愴壓偺壞丄僀僞儕傾偺傾僪儕傾奀偵柺偟偨挰偑晳戜丅搒夛偺戝妛偵捠偆嬥帩偪偺懅巕僕儍儞儖僀丒僩儔儞僥傿僯儍儞偑婣徣偟丄抧尦偺梀傃拠娫偲嵞夛偟偰媽岎傪壏傔傞丅僈乕儖僼儗儞僪偺僕儍僋儕乕僰丒僒僒乕儖偼斵傪垽偟偰偄傞偑丄斵偼嬼慠抦傝崌偭偨愴憟枹朣恖僄儗僆僲儔丒儘僢僔丒僪儔僑偵堦栚崨傟偟丄恖栚傪擡傫偱枾夛偡傞傛偆偵側傞丅傗偑偰偙偺挰偵傕愴憟偺攇偑媦傃丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅儓乕儘僢僷塮夋偵偼傛偔偁傞垽偺僷僞乕儞偩偑丄偦傟偵愴憟傪棈傑偣偰偄傞偺偑儈僜偐丅儘僢僔丒僪儔僑偺廌偄傪懷傃偨娽嵎偟丄怓偭傐偄岤傔偺怬偼丄偨偟偐偵抝怱傪偔偡偖傞偲偼偄偊丄僩儔儞僥傿僯儍儞偑壜垽偄僺僠僺僠偟偨僒僒乕儖傪幪偰偰擭忋偺彈偵側傃偔偺偼丄屄恖揑偵偼擺摼偑偄偐側偄丅偙偺塮夋偵偼報徾怺偄僔乕儞偑偄偔偮偐偁傞丅僩儔儞僥傿僯儍儞偺幚壠偺崑揁偱傒傫側偑僟儞僗傪偡傞僔乕儞丅庒幰偺傂偲傝偑儗僐乕僪丒僐儗僋僔儑儞傪偁偝偭偰乽傾乕僥傿丒僔儑僂偺乹僥儞僾僥乕僔儑儞乺偑偁傞乿偲尵偆偑丄僾儗僀儎乕偵偐偐傞偺偼價儞僌丒僋儘僗價乕偺乹僥儞僾僥乕僔儑儞乺偩乮偲巚偭偰偄偨偑丄偁偲偱挷傋傞偲丄偙傟偼僥僨傿丒儗僲偲偄偆壧庤傜偟偄丅偦傟偵偟偰傕壧偄曽偼價儞僌偵偦偭偔傝偩乯丅偦傟偵懕偄偰姱擻揑側傾儖僩僒僢僋僗偑儅儕僆丒僫僢僔儞儀乕僱嶌偺乹寖偟偄婫愡乺偺僥乕儅傪憈偱傞側偐丄僩僞儞僥傿僯儍儞偲儘僢僔丒僪儔僑偼梮偭偨偁偲僉僗傪岎傢偟丄偦傟偵婥偑偮偄偨僒僒乕儖偼崋媰偡傞丅斵傜偑弶傔偰寢偽傟傞僔乕儞偱偼慡棁偺儘僢僔丒僪儔僑偑惿偟偘傕側偔擕朳傪偝傜偡丅偙傟傕摉帪偺塮夋僼傽儞偺偁偄偩偱戝偒側榖戣偵側偭偨偱偁傠偆丅傑偨丄儉僢僜儕乕僯惌尃偑搢傟丄柉廜偑挰偺巗挕幧偵墴偟婑偣丄儉僢僜儕乕僯偺摵憸傪堷偒偢傝壓傠偡僔乕儞傕報徾怺偄偟丄僩儔儞僥傿僯儍儞偲儘僢僔丒僪儔僑偑嬱偗棊偪偺偨傔偵忔偭偨楍幵偑楢崌孯偵嬻敋偝傟傞僔乕儞傕敆椡枮揰偩丅
傢傜偺抝
1958埳丂僺僄僩儘丒僕僃儖儈丂昡揰亂C亃
慜偺乽寖偟偄婫愡乿偲偼愝掕偑傑偭偨偔媡偱丄垽偡傞嵢巕偑偄傞怑岺偺拞擭抝偑庒偄彈偵儊儘儊儘偵側傞榖丅娔撀偺僺僄僩儘丒僕僃儖儈偑帺傜庡墘傪柋傔傞丅庒偄彈偵偼崶栺幰偑偍傝丄嵟弶偼拞擭抝偺媮垽傪旔偗偰偄傞偑丄擏懱娭學傪傕偭偨偲偨傫丄愊嬌揑偵側傝丄壠懓傪幪偰傜傟側偄拞擭抝偼偦偺寖偟偄垽傪傕偰偁傑偡丅偙偺塮夋偱報徾怺偄偺偼彫妛峑掅妛擭傎偳偺擭偺庡恖岞偺懅巕偺壜垽偝偩丅彮擭偑尒偣傞婌搟垼妝偺揤恀啵枱側昞忣傗巇憪偼丄偳偆偟傛偆傕側偄垽偍偟偝傪姶偠傞丅偩偐傜巹偼巕嫙偲摦暔偑弌傞塮夋偼寵偄側偺偩丅僇儖儘丒儖僗僥傿働儕偺塮夋僥乕儅偼摉帪偺僸僢僩丒僷儗乕僪傪擌傢偟偨丅
2022擭1寧
2022擭1寧朸擔 旛朰榐159丂嶰慏晀榊偺庒偒擔偺抦傜傟偞傞塮夋
1952搶曮丂扟岥愮媑丂昡揰亂C亃
偳偙偐偺嶳墱偺懞偱峴側傢傟偰偄傞僟儉岺帠偵傑傞傢傞暔岅丅怴擟偺愝寁媄巘偲偟偰傗偭偰棃偨嶰慏晀榊偑丄棫偪戅偒傪嫅斲偡傞懞恖傪愢摼偟偨傝丄岺帠傪挿堷偐偣傞偨傔僟僀僫儅僀僩偱岯摴傪敋攋偟傛偆偲偡傞抧尦偺傗偔偞偲懳寛偟偨傝丄偄傠傫側崲擄偵憳偄側偑傜側傫偲偐僟儉傪姰惉偝偣傞丅嶰慏偼偗傫偐偵嫮偄傂偘柺偺擬寣娍偲偄偆愝掕丅斞応偱榙偄晈傪偡傞彑偪婥側柡傪媣帨偁偝傒偑墘偠傞丅媣帨偼嶰慏傪岲偒偵側傞偑丄嶰慏偵偼搶嫗偵楒恖偑偄傞丅偟偐偟嵟屻偵楒恖偼嶰慏傪尒尷偭偰嫀傝丄惏傟偰嶰慏偲媣帨偺垽偼惉廇偟僄儞僪偲側傞丅媣帨偁偝傒偼偁傑傝撻愼傒偺側偄彈桪偩偑丄柺挿偺旤宍偱柇側怓婥偑偁傞丅
崟懷嶰崙巙
1956搶曮丂扟岥愮媑丂昡揰亂C亃
廮摴壠偺庒幰偺堦杮婥側惗偒條傪昤偄偨傾僋僔儑儞塮夋丅帪戙偼偍偦傜偔戝惓傑偨偼徍榓弶婜丅杒嬨廈偺挰偺廮摴応偱廋峴偡傞嶰慏晀榊偼丄対摤僋儔僽偺楢拞偵場墢傪晅偗傜傟偰扏偒偺傔偟丄摴応庡偺嵅暘棙怣偐傜攋栧偝傟傞偑丄偦傟偼忋嫗偟偰奜柋徣偺棷妛帋尡傪庴偗偨偄偲巚偭偰偄傞嶰慏傊偺壏忣偩偭偨丅嶰慏偼惗妶帒嬥傪摼傞偨傔杒奀摴偺搚栘岺帠尰応偱摥偒丄僞僐晹壆傪巇愗傞埆鐓側傗偔偞傪挦傜偟傔傞丅搶嫗偵栠傝丄帋尡偵庴偐偭偨嶰慏偼寢壥傪抦傜偣傞偨傔嬨廈偵婣傞偑丄廮摴応偑対摤偲搨庤偺楢拞偵忔偭庢傜傟偨偺傪抦傝丄搟傝傪敋敪偝偣偰斵傜偲寛摤偟丄崷傒傪惏傜偡丅嶰慏偼摴応庡偺柡亖崄愳嫗巕丄杒嬨廈偺柤巑偺椷忟亖壀揷錆浠巕丄杒奀摴偺斞応偺攧揦彈亖媣帨偁偝傒乮媣帨偼乽寖棳乿偲摨偠偔丄偙偙偱傕斞応偺彈傪墘偠偰偄傞乯偲偄偆3恖偺旤彈偵崨傟傜傟傞偑丄嵟屻偼崄愳嫗巕偲寢偽傟傞丅崄愳嫗巕偺壜垽偝偑報徾偵巆傞丅
2022擭1寧朸擔 旛朰榐158丂僽儗僢僜儞偺揙掙偟偰棟夝傪嫅傓塮夋
1977暓丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰亂D亃
嫊柍揑側庒幰偑帺嶦婅朷偵偲傜傢傟丄巰傪悑偘傞傑偱偑昤偐傟傞丅偙傟偼僽儗僢僜儞偺嵟屻偐傜2斣栚偺塮夋偱偁傝丄偄偮傕偲摨偠偔丄岅傝岥偼嬌抂側傑偱偵嶍偓棊偲偝傟偰偄傞丅搊応恖暔偨偪偺婄偵偼傑偭偨偔昞忣偑側偔丄夛榖偵偼姶忣揑側梫慺偑寚棊偟偰偍傝丄恎傇傝偼傑傞偱儘儃僢僩偺傛偆偩丅塮夋偱昤偐傟傞庒幰偨偪偺峴摦偼丄傎偲傫偳愢柧偑側偄偺偱丄慜屻偺柆棈偑暘偐傜側偄偟丄壗傪偟傛偆偲偟偰偄傞偺偐棟夝偱偒側偄丅娐嫬攋夡偑傂偲偮偺僥乕儅偺傛偆偱偁傝丄塮夋偺側偐偱岺応偺攣墝丄奀偺墭愼丄擾栻嶶晍丄悈枔昦姵幰側偳偺僯儏乕僗塮憸偑抐曅揑偵塮偟弌偝傟傞丅戝傑偐側嬝棫偰偼丄庒幰偑惌帯偵傕楒垽偵傕擬拞偱偒偢丄抧媴偺峴偔枛偵愨朷偟偰巰傪慖傇丄偲偄偆棳傟偱偁傠偆偲悇應偱偒傞丅偄偢傟偵偣傛丄偙偺塮夋偺暘偐傜側偝偼嵺棫偭偰偍傝丄傑傞偱揙掙偟偰娤媞傪嫅斲偡傞偐偺傛偆偱偁傝丄尒廔傢偭偰丄偄偮傕偺僽儗僢僜儞嶌昳埲忋偵摉榝偲旀楯姶傪妎偊傞丅
屛偺儔儞僗儘
1974暓丒埳丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰亂D亃
傾乕僒乕墹揱愢偺惞攖扵媮暔岅偺屻擔択丅帪戙偼拞悽丄婻巑儔儞僗儘僢僩偲墹斳僌傿僱償傿傾偺晄椣丄惗偒巆偭偨婻巑摨巑偺懳棫偲憟偄偑昤偐傟傞丅栶幰偺昞忣傗摦嶌偵傑偭偨偔姶忣偑偙傕偭偰偄側偄偺偼丄偄偮傕偺僽儗僢僜儞塮夋偺偲偍傝偩丅婻巑偨偪偺愴摤傗攏忋憚帋崌偼撦廳偱偓偙偪側偔丄拞悽偺愴偄偼偒偭偲偙偆偩偭偨傠偆偲巚傢偣傞儕傾儖偝偑偁傞丅偩偑丄榖偟偺棳傟偑傛偔暘偐傜側偄丅搊応恖暔偨偪偼巒廔峛檋傪恎偵偮偗偰偄傞偑丄愴摤偲偼柍墢偺忬懺偱傕廳偨偄峛檋傪拝偰曕偒夞傞偺偼晄帺慠偩偟丄攏偺媟傗婻巑偺懌傗晲嬶側偳偑傗偨傜偵僋儘乕僗傾僢僾偝傟傞偺傕堄枴晄柧丅柍婡揑側姶妎丄僗僩僀僔僘儉丄傾儞僠丒儘儅儞僥傿僔僘儉偼廫暘偵帵偝傟偰偄傞偑丄偩偐傜壗側偺丄壗傪昞偦偆偲偟偰偄傞偺丄偲尵偄偨偄婥帩偪偵側傞丅
2022擭1寧朸擔 旛朰榐157丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩偺塮夋丂偦偺2
1954暓丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩丂昡揰亂D亃
50擭戙偺幮夛忣惃偲壠掚栤戣傪僥乕儅偲偡傞幮夛攈塮夋丅朄掛偱4恖偺僴僀僥傿乕儞偺彮擭彮彈偑崘敪偝傟傞朻摢偺僔乕儞偲丄摨偠偔朄掛偱斵傜偵敾寛偑壓偝傟傞漿旜偺僔乕儞偵僒儞僪僀僢僠偝傟偰丄斵傜偺恊偨偪偑僋儘乕僗傾僢僾偝傟丄偦偺壠掚娐嫬偲斵傜偑斊峴偵帄偭偨夁掱偑昤偐傟傞丅挬慛愴憟偑杣敪偟丄悽娫偼戞3師戝愴偵側傞偺偱偼偲嫰偊偰偄傞丅彮擭偨偪偼撿偺搰偵旔擄偡傞偨傔嬥帩偪偺壠偐傜崅壙側愗庤傪搻傕偆偲偡傞偑丄惉傝峴偒偱嶦恖傪斊偟偰偟傑偆丅斵傜偼旕峴彮擭偱偼側偔丄恀柺栚偱拠娫巚偄偺晛捠偺巕嫙偨偪偱偁傞偲偄偆偺偑儈僜偐丅榖偺嬝棫偰偼崟郪偺乽惗偒傕偺偺婰榐乿偲堦柆捠偠傞傕偺偑偁傝丄摉帪偼愴憟偺嫼埿偑尰幚偺傕偺偲偟偰偁偭偨偺偱偁傠偆偑丄偄傑偺帪揰偱尒傞偲旕尰幚揑偱峳搨柍宮偺姶偑偁傞丅彮擭彮彈偨偪偺傂偲傝偵丄偺偪偺乽彈墹朓乿偱抦傜傟傞梔墣側彈桪儅儕僫丒償儔僨傿偑弌墘偟偰偍傝丄惔慯側巔傪斺業偟偰偄傞丅
娽偵偼娽傪
1957暓丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩丂昡揰亂A亃
埲慜丄妛惗偺偙傠偵偙偺塮夋傪柤夋嵗偱尒偰徴寕傪庴偗偨偑丄媣偟傇傝偵嵞尒偟丄夵傔偰嫮偄僀儞僷僋僩傪姶偠偨丅偄傑尒偰傕偙偺嶌昳偵偼恖偵慽偊偐偗傞椡偑偁傞丅乽儔僀儞偺壖嫶乿偲暲傇僇僀儎僢僩偺寙嶌偺傂偲偮偩傠偆丅僼儔儞僗恖堛巘僋儖僩丒儐儖僎儞僗偼傾儔僽偺偳偙偐偺崙偺昦堾偵嬑傔偰偄傞丅偁傞栭丄斵偺帺戭偵傾儔僽恖偺彈惈偺昦恖偑扴偓崬傑傟傞偑丄僾儔僀儀乕僩側帪娫傪幾杺偝傟偨偔側偄斵偼恌嶡偣偢丄昦堾偵峴偗偲捛偄暐偆丅彈惈偼昦堾偱庤摉偰傪庴偗傞偑丄庤抶傟偱巰傫偱偟傑偆丅彈惈偺晇偼堛巘偵崷傒傪書偒丄暅廞偡傞偨傔堛巘傪嵒敊偵楢傟弌偟丄摴偵柪傢偣傞丅堛巘偼悈傕怘椏傕恠偒偰傛傠傛傠偲嵒敊傪偝傑傛偆丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅慡懱偼3偮偺僷乕僩偵戝暿偱偒傞乗乗昦恖偑巰朣偟偰堛巘偑壗幰偐偵晅偗慱傢傟傞奨拞偺僔乕僋僄儞僗丄堛巘偑帯椕偵屇偽傟偰墦偔棧傟偨揷幧偺懞偵峴偒丄晄忦棟側懱尡傪偡傞僔乕僋僄儞僗丄堛巘偑巰朣偟偨彈惈偺晇偲偲傕偵嵒敊傪偝傑傛偆僔乕僋僄儞僗偩丅偳偺僷乕僩偵偍偄偰傕僒僗儁儞僗偺忴惉偑慺惏傜偟偄丅偙偙偱昤偐傟傞傾儔僽柉懓偺暥壔丒晽廗丒怱棟偼丄惣墷恖偵偼棟夝偟偑偨偄傕偺偲偟偐塮傜側偄偩傠偆丅偩偑丄傾儔僽偑婇偰傞暅廞偼丄惣墷恖偵偲偭偰偼棟晄恠偱偁偭偰傕丄傾儔僽恖偵偲偭偰偼惓媊側偺偩丅偦偺峔恾偼塮夋惂嶌偐傜60擭屻偺崱擔傕曄傢偭偰偄側偄丅尒偰偄傞偲偒偼婥偯偐側偐偭偨偑丄偁偲偵側偭偰乽壨偼屇傫偱傞乿偺壜楓側彈桪僷僗僇儖丒僆乕僪儗偑弌墘偟偰偄傞偺偑暘偐偭偨丅堛巘偑朣偔側偭偨彈惈偺幚壠傪朘傟偨偲偒偵弌夛偆彈惈偺枀栶傪墘偠偰偄傞偺偑僆乕僪儗偺傛偆偩丅
2022擭1寧朸擔 旛朰榐156丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩偺塮夋丂偦偺1
1949暓丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩丂昡揰亂C亃
僀僞儕傾偺償僃僯僗偲償僃儘乕僫傪晳戜偵偟偨楒垽塮夋丅乽儘儈僆偲僕儏儕僄僢僩乿偺暔岅傪壓晘偒偵丄僈儔僗怑恖偺庒幰僙儖僕儏丒儗僕傾僯偲杤棊婱懓偺柡傾僰乕僋丒僄乕儊偺斶楒偑昤偐傟傞丅償僃僯僗偱嶣塭戉偑乽儘儈僆偲僕儏儕僄僢僩傪乿嶣偭偰偍傝丄庡墘偺戙栶偵慖偽傟偨偺偑儗僕傾僯偲僄乕儊丅擇恖偼夛偭偨偲偨傫偵楒偵棊偪丄儘儈僆偲僕儏儕僄僢僩偺傛偆偵塣柦偵摫偐傟傞偑偛偲偔斶楒傊偲撍偒恑傓丅僕儏儕僄僢僩栶偺恖婥彈桪偵儅儖僠乕僰丒僉儍儘儖丄杤棊婱懓偺柡偵墶楒曠偡傞惉傝忋偑傝幰偺幚嬈壠偵僺僄乕儖丒僽儔僢僗乕儖偑暞偟偰偄傞丅媟杮偼儅儖僙儖丒僇儖僱偲慻傫偱帊揑儗傾儕僗儉傪悇恑偟偨僕儍僢僋丒僾儗償僃乕儖丅偦傟偐偁傜偸偐丄僗僩乕儕乕揥奐傗忣宨昤幨偼僇儖僱傗僨儏償傿償傿僄傪巚傢偣傞丅儗僕傾僯偲僄乕儊偑庒偄丅偲偔偵僄乕儊偺壜楓偝偼奿暿丅僄乕儊偑慡棁偱愳偱塲偖僔乕儞偼堦尒偺壙抣偁傝丅
嵸偒偼廔傝偸
1950暓丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩丂昡揰亂C亃
垽恖傪埨妝巰偝偣偨彈惈偺嵸敾傪丄攩怰堳偨偪偺峴摦傪捠偟偰昤偄偨幮夛攈朄掛寑丅弌墘偟偰偄傞偺偼丄儈僔僃儖丒僆乕僋儗乕儖丄償傽儔儞僥傿乕僰丒僥僔僄傪彍偒丄傎偲傫偳柍柤偺攐桪偨偪偩丅嵸敾偺夁掱偲暲峴偟偰丄擾晇丄報嶞岺丄戅栶孯恖丄婱懓偺抝丄桾暉側榁晈恖側偳丄偝傑偞傑側攩怰堳偨偪偺巹惗妶偑僐儈僇儖側枴傢偄丄僔儕傾僗側暤埻婥傪崿偤崌傢偣偰昤偐傟傞丅塮夋偑搳偘偐偗傞偺偼丄婥傑偖傟側攩怰堳偑旐崘偺桳嵾丒柍嵾傪敾抐偡傞偙偲傊偺媈媊偩偑丄偦傟偵偟偰傕丄僼儔儞僗塮夋偱偼偳偆偟偰偙偆傕楒垽偽偐傝偑昤偐傟傞偺偩傠偆丅搊応恖暔偨偪偑孞傝峀偘傞楒偺偝傗摉偰丄晄椣丄嶰妏娭學側偳偼丄尒偰偄偰偄偝偝偐偆傫偞傝偡傞丅偄偪偑偄偵斾妑偼偱偒側偄偑丄攩怰堳傪拞怱偲偟偨朄掛寑側傜乽12恖偺搟傟傞抝乿偺傎偆偑偼傞偐偵偡偖傟偰偄傞丅
2022擭1寧朸擔 旛朰榐155丂50擭戙偺惣晹寑丂偦偺2丗僴僒僂僃僀偲儅僥
1958暷丂僿儞儕乕丒僴僒僂僃僀丂昡揰亂B亃
偙傟偼尒墳偊偺偁傞忋弌棃偺惓摑揑惣晹寑偩丅晝恊傪扵偟偰椃傪偡傞庒幰僪儞丒儅儗乕偼挿抝傪斵偵嶦偝傟偨偲巚偄崬傫偩杚応庡偺堦壠偐傜柦傪慱傢傟丄摝偘夞傞丅儅儗乕偼幩寕偺柤庤偩偑恖傪嶦偡偺傪寵偆弮杙側抝丅斵偼慞椙側擾墍庡偵彆偗傜傟丄柡偺僟僀傾儞丒償傽乕僔偲楒拠偵側傞偑丄堷偒懕偒晝恊扵偟偺椃傪懕偗傞丅儅儗乕傪晅偗慱偆杚応庡偑擾墍庡傪寕偪丄偦傟傪抦偭偨儅儗乕偼杚応庡偲寛拝傪偮偗傞傋偔挰偵岦偐偆丅暔岅偼僥儞億椙偔夣挷偵恑傒丄搑拞偱偩傟傞偙偲偼側偄丅搊応恖暔偺惈奿愝掕傕揑妋偱丄壩偩傞傑偵側偭偨杚応庡偺懅巕傪儅儗乕偑彆偗丄杚応庡偑暅廞傪掹傔傞僄儞僨傿儞僌傕慛傗偐偩丅
梱偐側傞抧暯慄
1955暷丂儖僪儖僼丒儅僥丂昡揰亂C亃
暷崙奐戱帪戙丄杒惣晹傪挷嵏偟偰懢暯梞傊偺摴傪奐戱偟偨儖僀僗仌僋儔乕僋扵専戉偺嬯擄偺椃傪昤偄偨巎幚偵婎偯偔惣晹寑丅戉挿偺儖僀僗戝堁偵僼儗僢僪丒儅僋儅儗乕丄暃戉挿偺僋儔乕僋拞堁偵僠儍乕儖僩儞丒僿僗僩儞丄挷嵏偵嫤椡偡傞僀儞僨傿傾儞偺柡偵僪僫丒儕乕僪偑暞偡傞丅儖僀僕傾僫傪攦廂偟偨僕僃僼傽僜儞戝摑椞偺柦傪庴偗丄扵専戉偼慏偱儈僘乕儕愳傪偝偐偺傏傝丄崲擄偵憳偄側偑傜傕挷嵏偺椃傪懕偗傞丅僗僩乕儕乕偵偼偵僀儞僨傿傾儞偺廝寕傗僿僗僩儞偲儕乕僪偺斶楒偑偐傜傓丅偁傟偭偲巚偭偨偺偼丄愳傪偝偐偺傏傞搑拞偵戧偑偁傝丄斵傜偑慏傪棨偵梘偘偰嶳墇偊偡傞僄僺僜乕僪丅偙傟偼僿儖僣僅乕僋偺乽僼傿僢僣僇儔儖僪乿偲摨偠偠傖側偄偐丅僿儖僣僅乕僋偼偙偺乽梱偐側傞抧暯慄乿偵僸儞僩傪摼偰偁偺塮夋傪嶌偭偨偺偩丅
2022擭1寧朸擔 旛朰榐154丂50擭戙偺惣晹寑丂偦偺1丗僽儖僢僋僗偲儘乕儔儞僪
1956暷丂儕僠儍乕僪丒僽儖僢僋僗丂昡揰亂B亃
栄旂庪椔偺偨傔僶僢僼傽儘乕庪傝傪偡傞2恖偺抝偺妋幏傪昤偔廋惓庡媊惣晹寑丅僈儞僼傽僀僩偺応柺偼傎偲傫偳側偔丄僶僢僼傽儘乕傪嶦偡僔乕儞偑擮擖傝偵昤偐傟傞偺偑報徾怺偄丅僶僢僼儘傽乕偑儔僀僼儖偱師乆偵幩嶦偝傟傞條巕偑尰幚偵嶣塭偝傟偰偍傝丄傓偛偨傜偟偔堿嶴偩丅摦暔垽岇偑惙傫側尰嵼偱偼愨懳偵嶣塭偱偒側偄偩傠偆丅庡墘偺僗僠儏傾乕僩丒僌儗儞僕儍乕偼僶僢僼傽儘乕丒僴儞僞乕偲偟偰抦傜傟傞偑丄嶦偡偙偲偵寵婥偑偝偟偰偄傞丅偩偑丄僶僢僼傽儘乕庪傝偵堎忢側幏擮傪擱傗偡傕偆堦恖偺庡墘儘僶乕僩丒僥僀儔乕偺媮傔偵墳偠偰庪椔偺椃偵嶲壛偡傞丅僴儞僒儉側僗僞乕偲偟偰恖婥偺偁偭偨僥僀儔乕偼丄50擭戙敿偽偛傠偐傜偲偒偳偒埆栶傪墘偠傞傛偆偵側偭偨丅偙偙偱偺僥僀儔乕偑暞偡傞偺傕埆栶偱丄偟偐傕堿幖偱僀儞僨傿傾儞傪曁帇偟丄嶦偟傪妝偟傓堎忢惈奿偺抝偩丅僶僢僼傽儘乕傪寕偪傑偔傞斵偺昞忣偵偼嶦滳傊偺摡悓偑偆偐偑偊傞丅偙偙偱偼僀儞僨傿傾儞偑摨忣揑偵昤偐傟偰偍傝丄曔傢傟偨僀儞僨傿傾儞偺柡僨僽儔丒僷僕僃僢僩傪嫃棷抧偵憲傝撏偗偨僌儗儞僕儍乕偼丄偦偙偱曢傜偡僀儞僨傿傾儞偑婹偊偵嬯偟傫偱偄傞偺傪尒偰丄怘椏傪撏偗偰傗傞丅暔岅偼嵟屻偵庡墘偺2恖偑揋懳偟丄摯孉偵摝偘崬傫偩僌儗儞僕儍乕偑弌偰偔傞偺傪懸偭偰偄傞偆偪偵僥僀儔乕偼栭偺姦偝偺偨傔搥巰偟偰僄儞僪偲側傞丅偙傫側廔傢傝偐偨偺塮夋傕捒偟偄丅偄傠傫側堄枴偱堎怓偺惣晹寑偩丅
搉傞傋偒懡偔偺壨
1955暷丂儘僀丒儘乕儔儞僪丂昡揰亂C亃
偙傟傕儘僶乕僩丒僥僀儔乕偑栄旂庪椔幰傪墘偢傞惣晹寑偩偑丄乽嵟屻偺廵寕乿偲偼懪偭偰曄傢偭偰僐儊僨傿丒僞僢僠偺梲婥側塮夋偩丅奐戱幰堦壠偲抦傝崌偭偨僥僀儔乕偵丄堦壠偺堦恖柡偱抝彑傝偺彑偪婥側僄儕僲傾丒僷乕僇乕偑堦栚崨傟偟丄寢崶傪敆傞偑丄婥妝側撈傝恎偑岲偒側僥僀儔乕偼摝偘夞傝丄偦傟傪僷乕僇乕偑捛偄偐偗傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僀儞僨傿傾儞偲偺寛摤僔乕儞傕偁傞偑丄慡懱偲偟偰偼戝傜偐偱偺偳偐側僐儊僨傿丒僂僃僗僞儞偵巇忋偑偭偰偄傞丅
2021擭12寧
2021擭12寧朸擔 2021擭奀奜儈僗僥儕乕彫愢儀僗僩丒僥儞
02 乽揤巊偲塕乿儅僀働儖丒儘儃僒儉乮憗愳暥屔乯
03 乽朣崙偺僴儞僩儗僗乿働僀僩丒僋僀儞乮僴乕僷乕僽僢僋僗乯
04 乽晝傪寕偭偨12偺廵抏乿僴儞僫丒僥傿儞僥傿乮暥錣弔廐幮乯
05 乽僆僋僩乕僶乕丒儕僗僩乿僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕乮暥弔暥屔乯
06 乽墇嫬幰乿C丒J丒儃僢僋僗乮憂尦暥屔乯
07 乽儔僗僩丒僩儔僀傾儖乿儘僶乕僩丒儀僀儕乕乮彫妛娰暥屔乯
08 乽儓儖僈僆嶦恖帠審乿傾儞僜僯乕丒儂儘償傿僢僣乮憂尦暥屔乯
09 乽巰偸傑偱偵偟偨偄3偮偺偙偲乿P丒儌儕乕儞仌P丒僯乕僗僩儗乕儉乮僴乕僷乕僽僢僋僗乯
10 乽帺桼尋媶偵偼岦偐側偄嶦恖乿儂儕乕丒僕儍僋僜儞乮憂尦暥屔乯
2021擭12寧朸擔 旛朰榐153丂榁彈桪偑嫟墘偟偨帬枴偵晉傓堩昳
1987暷丂儕儞僛僀丒傾儞僟乕僜儞丂昡揰[A]
儕儕傾儞丒僊僢僔儏偲儀僥傿丒僨僀償傿僗偲偄偆偄偢傟楎傜偸榁擭偺戝彈桪偑嫟墘偟偨惷鎹偱枴傢偄怺偄塮夋丅晳戜偼儊僀儞廈偺搰丄奀曈傪尒壓傠偡媢偵寶偮壠偱夁偛偡榁偄偨巓枀偺傂偲壞偺惗妶偑扺乆偲昤偐傟傞丅朻摢偱彮彈帪戙偺斵彈偨偪偑拠椙偔媢偐傜奀傪挱傔丄壞偵傗偭偰棃傞僋僕儔傪尒傞僔乕儞偑幨偟弌偝傟丄嵟屻偼榁偄偨斵彈偨偪偑丄崱擭偼僋僕儔偑棃側偄偹偲尵偄側偑傜丄摨偠傛偆偵媢偺忋偵棫偭偰偄傞僔乕儞偱廔傢傞丅摉帪丄枀栶偺儕儕傾儞丒僊僢僔儏偼93嵨丄巓栶偺儀僥傿丒僨僀償傿僗偼79嵨丅幚擭楊偲偼媡偵丄僨僀償傿僗偼榁偗偰偍傝丄僊僢僔儏偺傎偆偑庒偔尒偊傞丅擇恖偲傕晇傪朣偔偟偰偍傝丄巓偺僨僀償傿僗偼栍栚偱丄枀偺僊僢僔儏偑柺搢傪尒偰偄傞偲偄偆愝掕丅僊僢僔儏偺傗偝偟偄偑婤慠偲偟偨暔崢丄僨僀償傿僗偺傢偑傑傑偱曃孅側尵摦偼丄擇恖偺彈桪偺僀儊乕僕偦偺傑傑偩丅斵彈偨偪偺墘媄偼墘媄偲偄偆奣擮傪挻墇偟偰偍傝丄懚嵼偦偺傕偺偑塮夋揑側姶嫽傪屇傃婲偙偡丅偲傝傢偗僊僢僔儏偺懚嵼姶偼慺惏傜偟偔丄乽庪恖偺栭乿傗乽嫋偝傟偞傞幰乿偱偺檢偲偟偨偨偨偢傑偄傪渇渋偲偝偣傞丅傎偐偵夦婏塮夋偱桳柤側償傿儞僙儞僩丒僾儔僀僗丄墲擭偺旤恖彈桪傾儞丒僒僓乕儞丄僕儑儞丒僼僅乕僪塮夋忢楢偺僴儕乕丒働儕乕丒僕儏僯傾偲偄偭偨廰偄榁桪偑嬤椬偺廧恖偲偟偰弌墘偡傞丅搰偲奀偺忣宨偺偊傕偄傢傟偸旤偟偝傕摿昅偵抣偡傞丅
2021擭12寧朸擔 旛朰榐152丂僫僠僗偲愴偆愴憟杁棯塮夋
1964暷丂僕儑乕僕丒僔乕僩儞丂昡揰[B]
戞2師戝愴壓丄僲儖儅儞僨傿忋棨嶌愴傪戣嵽偵偟偨弌怓偺孯帠挸曬塮夋丅撈孯偺忣曬傪扵傞偨傔儓乕儘僢僷偵旘傫偩楢崌孯巌椷晹彮嵅偺僕僃乕儉僗丒僈乕僫乕偼丄杻栻傪堸傑偝傟偰堄幆傪幐偄丄婥偑偮偄偨傜挀棷暷孯偺昦堾偵偍傝丄偡偱偵愴憟偑廔寢偟偰偟偰偄傞偙偲傪抦傞丅斵傪桿夳偟偨撈孯偑丄楢崌孯偺忋棨抧揰傪暦偒弌偡偨傔丄偦偺傛偆偵巇慻傫偩偺偩丅嵟弶偼偦傟傪怣偠偰偄偨僈乕僫乕偼丄傆偲偟偨偒偭偐偗偱婾憰傪尒攋傝丄娕岇巘傪偝偣傜傟偰偄偨儐僟儎恖彈惈僄償傽丒儅儕乕丒僙僀儞僩偺彆偗傪摼偰扙憱偟丄僗僀僗傪栚巜偟偰摝偘傞丅慜敿偼昦堾偺側偐偺嬱偗堷偒丄屻敿偼堦揮偟偰怷偺側偐偺摝憱寑丄撈孯偵傛傞庤偺崬傫偩婾憰丄撈孯扴摉堛巘偲恊塹戉偺懳棫側偳偑柸枾偵昤偐傟丄榖偼嬞敆姶傪偼傜傒側偑傜僗僺乕僨傿偵揥奐偡傞丅
僋儘僗儃乕嶌愴
1965塸丂儅僀働儖丒傾儞僟乕僜儞丂昡揰[C]
僪僀僣孯偑奐敪偟偨怴宆儘働僢僩暫婍偺岺応傪攋夡偡傞偨傔塸崙偐傜憲傝崬傑傟偨岺嶌堳偨偪偺妶摦傪昤偄偨愴憟僗僷僀塮夋丅岺嶌堳偵暞偡傞偺偼僕儑乕僕丒儁僷乕僪丄傎偐偵僩儗償傽乕丒僴儚乕僪丄僕儑儞丒儈儖僘丄僩儉丒僐乕僩僱僀側偳丄僋僙偺偁傞塸崙偺柤桪偑嫟墘丄僜僼傿傾丒儘乕儗儞傕搊応偟偰怓傪揧偊傞偑丄慡懱偲偟偰惙傝忋偑傝偲僒僗儁儞僗偵寚偗傞偟丄僸儘僀僘儉傪巀旤偡傞偐偺傛偆側惛恄偑彮乆旲偵偮偔丅
2021擭12寧朸擔 旛朰榐151丂戝愳宐巕偑弌墘偟偨2杮偺塮夋
1957搶塮丂彫戲栁峅丂昡揰[D]
戝愳宐巕偑捒偟偔弌墘偟偨尰戙寑塮夋偱丄尨嶌偼棦尒偺晽懎彫愢丅尰戙偲偼偄偭偰傕帪戙偼愴慜偺徍榓弶婜丅庡墘偺嵅栰廃擇偼帒嶻壠偱摴妝幰偺岲恖暔傪墘偠傞丅斵偵崨傟偰彣偵側傞偺偑戝愳宐巕丅崅憅寬偑僴乕僼偺晄椙惵擭偲偟偰弌墘偟偰偄傞丅捠懎揑側儊儘僪儔儅偱丄塮夋偲偟偰偼杴嶌丅帪戙忬嫷傕偼偭偒傝偣偢丄嵟屻偵乽擔杮孯丄拞崙偵恑弌乿偲偄偆崋奜偑幨偟弌偝傟偰帪戙偑暘偐傞丅僨價儏乕偟偰娫傕側偄戝愳宐巕偼丄椤傪偐傇偭偰偄側偄偣偄偐丄屻擭傛傝傆偭偔傜偟偰偍傝丄悙乆偟偔壜垽傜偟偄丅
朶傟傫朧堦戙
1962搶塮丂壨栰庻堦丂昡揰[B]
偙傟偼戝愳宐巕偑弌墘偟偨嵟屻婜偺嶌昳偺傂偲偮丅偙偺擭偺枛丄斵彈偼寢崶偺偨傔堷戅偟偰偟傑偆丅庡墘偼戝桭桍懢楴丅寱偺榬偼棫偮偺偵壓媺婙杮偱弌悽偱偒側偄偙偲偵愨朷偟偨戝桭偼峕屗傪弌杬偟偰孠柤偵棳傟拝偔丅斵偼搉偟慏偱摨忔偟偨戝愳宐巕偑彈榊壆偵攧傜傟傞偲抦偭偰攦偄庢傝丄偦偺屻擇恖偼晇晈偵側傞丅戝桭偼孠柤偺傗偔偞偺恊暘偵尒崬傑傟堦壠偺媞暘偵側傞丅戝柤偵崷傒傪書偔戝桭偼搶奀摴傪捠傞戝柤峴楍傪巭傔偰昡敾傪廤傔傞丅帪偼枊枛丄埨惌偺戝崠丄嶗揷栧奜偺曄側偳丄悽忣晄埨偺側偐丄戝桭偼惗偒傞摴傪柾嶕偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅帪戙寑偑嬋傝妏偵棃偰偄偨帪婜偵嶌傜傟偨偙偺嶌昳偼丄搶塮摼堄偺屸妝帪戙寑偱偼側偔丄帢偺晄忦棟偲晇晈偺垽忣傪昤偄偨恖忣帪戙寑偵巇忋偑偭偰偄傞丅戝桭桍懢楴偼帢偲偟偰偺惗偒曽偵擸傒側偑傜傕丄戝愳宐巕偲憡巚憡垽偺惗妶傪憲傞丅崑曻猁棊側昞偺僀儊乕僕偲偼棤暊偵丄慇嵶偱恀柺栚側惈奿偩偭偨偲偄偆戝桭偵偲偭偰偼丄傑偝偵変偑堄傪摼偨塮夋偩偭偨偺偱偼側偄偐丅戝愳宐巕傕弌斣偑懡偔丄惔慯側旤偟偝傪敪嶶偟側偑傜丄晇偵婑偣傞傂偨傓偒側垽傪尒帠偵昞尰偡傞丅榖偺棳傟偵偼偪偖偼偖側売強傕偁傞偑丄斵傜偺擬墘偵傛傝丄岲姶偺帩偰傞塮夋偵側偭偨丅
2021擭12寧朸擔 旛朰榐150丂僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖
1947暷丂僨儖儅乕丒僨僀償僗丂昡揰[B]
嵞尒丅僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偲儘乕儗儞丒僶僐乕儖偺僐儞價偵傛傞3搙栚偺嫟墘嶌丅柍幚偺嵾偱僒儞僋僄儞僥傿儞孻柋強偵暈栶偟偰偄偨儃僈乕僩偑扙崠偟丄僒儞僼儔儞僔僗僐偵摝憱偡傞丅嬼慠捠傝偐偐偭偨僶僐乕儖偼斵偵摨忣偟傾僷乕僩偵摻偆丅儃僈乕僩偼惍宍庤弍傪庴偗偰婄傪曄偊丄僶僐乕儖偺彆偗傪摼偰恀斊恖傪憑偡丅儃僈乕僩偺婄偼塮夋偺拞斦傑偱幨偟弌偝傟側偄丅庤弍屻丄曪懷傪攳偑偲丄弶傔偰斵偺婄偑尰傟傞丄偲偄偆庯岦偑柺敀偄丅儘僶乕僩丒儌儞僑儊儕乕偺乽屛拞偺彈乿傪憐婲偝偣傞偑丄庤朄偼偙偺塮夋偺傎偆偑愻楙偝傟偰偄傞丅儃僈乕僩傪彆偗傞僞僋僔乕塣揮庤傗惍宍堛丄斵偺惓懱傪抦偭偰嫼敆偡傞撲偺抝側偳丄婏柇側榚栶偺搊応偑嫽枴傪屇傇丅戝愄偵尒偨偲偒偼偠偮偵柺敀偄偲姶偠偨偑丄偄傑尒傞偲偦傟傎偳偱傕側偄丅儊儘僪儔儅晽偺僄儞僨傿儞僌偑傗傗嫽傪嶍偖丅
戝偄側傞暿傟
1947暷丂僕儑儞丒僋儘儉僂僃儖丂昡揰[C]
偙傟傕嵞尒丅僠儍儞僪儔乕偺彫愢傪柾偟偨朚戣偼僟僒偝偺嬌傒丅尨戣乽Dead Reckoning乿偲偼丄偝傑偞傑側忣曬傗梫慺偐傜尰嵼埵抲傪抦傞悇應峲朄偺偙偲丅僼儔僢僔儏僶僢僋偱巒傑傝丄埆彈偑搊応偡傞丄揟宆揑側僗僞僀儖偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅廔愴捈屻丄棊壓嶱晹戉偺戝堁儃僈乕僩偼憡朹偲偲傕偵庩孧儊僟儖庴棟偺偨傔儚僔儞僩儞偵岦偐偆偑丄搑拞偱憡朹偑摝憱偟峴曽傪偔傜傑偡丅儃僈乕僩偼孯戉杮晹偺嫋壜傪摼偰恀憡傪扵傞偨傔憡朹偺屘嫿偺挰偵岦偐偆丅旈枾傪朶偙偆偲偡傞斵偑弌夛偆撲傔偄偨庰応偺壧庤偑儕僓儀僗丒僗僐僢僩丅僗僩乕儕乕偼擇揮嶰揮偟丄儕僓儀僗偺埆岻傒偼嵟屻偵帄偭偰傛偆傗偔柧偐偝傟傞丅儕僓儀僗偼儘乕儗儞丒僶僐乕儖偵帡偰偄傞偑丄僄儔偑挘偭偨崪懢偺偛偮偄婄棫偪偱丄僼傽儉丒僼傽僞乕儖偲偟偰偼偄傑偄偪枺椡偵寚偗傞丅
2021擭11寧
2021擭11寧朸擔 旛朰榐149丂50擭戙慜婜偺堎怓擔杮塮夋
1955撈棫僾儘丂崱堜惓丂昡揰[B]
廔愴捈屻偵寢惉偝傟偨揷幧偺妝抍偑鋮擄恏嬯偺偡偊偵巗柉僆乕働僗僩儔偲偟偰惉挿偡傞傑偱傪昤偔丅孮攏岎嬁妝抍偑儌僨儖偩偲偄偆丅僐儞僒乕僩儅僗僞乕偲偟偰妝抍傪堷偭挘傞桪廏側償傽僀僆儕僯僗僩偵壀揷塸師丄斵偺嵢偵側傞妝抍偺僺傾僯僗僩偵娸湪巕丄妝抍偺儅僱乕僕儍乕偲偟偰杬憱偡傞偺偼彫椦宩庽丄偦偺傎偐丄妝抍堳偵壛搶戝夘傗嶰堜峅師丄夛寁學偵搶栰塸帯榊偲偄偭偨僋僙偺偁傞攐桪偑榚傪屌傔偰偄傞丅妝抍堳偼僠儞僪儞壆側偳偺傾儖僶僀僩傪偟丄惗妶嬯偵懴偊側偑傜丄嶳墱偺彫妛峑傗僴儞僙儞昦椕梴巤愝側偳傪夢傝丄恖乆偵壒妝傪憲傝撏偗傞婌傃傪枴傢偆丅慡懱偲偟偰愴屻娫傕側偄偙傠偺晽宨偑岻傒偵幨偟弌偝傟偰偄傞丅嶳揷峩猢偑摿暿弌墘偟偰偄傞丅
柦旤傢偟
1951徏抾丂戝掚廏梇丂昡揰[C]
柦偺懜偝傪徧偊傞僐儊僨傿晽偺僸儏乕儅儞丒僪儔儅丅夛捗庒徏忛偲偍傏偟偒忛偺崍偦偽偵廧傓堦壠偺暔岅丅崍偵旘傃崬傓帺嶦幰傪媬偆偨傔栭夞傝傪偡傞偺偑擔壽偺恾彂娰挿偵妢抭廜丄偦偺嵢偵悪懞弔巕丄怴暦婰幰偺挿抝偑嶰殸楢懢榊丄妛惗偺師抝偑嵅揷孾擇丄帺嶦偟傛偆偲偟偰媬傢傟傞彈偑扺搰愮宨偲宩栘梞巕偲偄偆偤偄偨偔側攝栶丅恻梋嬋愜偺偡偊丄嶰殸偲扺搰丄嵅揷偲宩栘偑寢偽傟傞丄偲偄偆懠垽側偄僗僩乕儕乕丅働僠側埆恖栶偱掕昡偁傞彫戲塰懢榊偑捒偟偔慞恖偺朧庡傪墘偠偰偄傞丅妢偲悪懞偺晇晈偑栭偛偲丄偺偳偐偵広敧偲嬚偺墘憈偵嫽偠傞岝宨偼丄晜悽棧傟偟偨姶偠傪梌偊傞丅攝栶偺崑壺偝偵斾傋偰丄撪梕偼儊儕僴儕偵寚偗丄暔懌傝側偄丅
2021擭11寧朸擔 旛朰榐148丂僄儕傾丒僇僓儞偺拞屻婜嶌昳
1960暷丂僄儕傾丒僇僓儞丂昡揰[C]
1930擭戙丄儖乕僘償僃儖僩偺僯儏乕僨傿乕儖惌嶔偺傕偲丄偟偽偟偽斆棓偟偰旐奞傪傕偨傜偡僥僱僔乕愳偵僟儉偑寶愝偝傟傞丅棳堟偺廧柉偼惌晎偑搚抧傪攦偄忋偘偰棫偪戅偐偣傞偑丄愳偺拞廈偵廧傓堦壠偺壠挿偺榁彈偩偗偼婃偲偟偰棫偪戅偒傪嫅斲偟偰偄傞丅斵彈傪愢摼偡傞偨傔攈尛偝傟偨惌晎偺栶恖傪儌儞僑儊儕乕丒僋儕僼僩丄堦壠偺懛柡傪儕乕丒儗儈僢僋偑墘偠傞丅僋儕僼僩偼儗儈僢僋偲楒拠偵側傞偑丄廃曈偺婃柪側廧柉偐傜揋帇偝傟丄敆奞傪庴偗傞丅僟儉偺曻悈偑巒傑傞捈慜丄拞廈偺壠傪嫀偭偨榁彈偼懅傪堷偒庢傝丄儗儈僢僋偼僋儕僼僩偲偲傕偵奨傪屻偵偡傞丅戣嵽偼柺敀偄偟丄愳偺晽宨偺昤幨傕尒墳偊偑偁傞偑丄偄傠傫側僥乕儅傪媗傔崬傒偡偓偰僾儘僢僩偑拞搑敿抂偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅3擭慜偵帺摦幵帠屘偱懝彎偟偨婄傪惍宍庤弍偟偨僋儕僼僩偺昞忣偑捝乆偟偄丅
撍慠偺朘栤幰
1972暷丂僄儕傾丒僇僓儞丂昡揰[B]
僄儕傾丒僇僓儞偑偙傫側塮夋傪嶣偭偰偄偨偲偼抦傜側偐偭偨丅儀僩僫儉婣娨暫栤戣傪埖偭偨徴寕揑側栤戣嶌偱偁傝丄偄傢備傞傾儊儕僇儞丒僯儏乕丒僔僱儅偺棳傟偵増偭偨塮夋偩偲尵偊傞丅儀僩僫儉婣娨暫偺庒幰偑嵢偲愒傫朧偲曢傜偡揷幧偺壠偵撍慠丄愴桭偩偲徧偡傞2恖偺抝偑朘傟傞丅庒幰偼儀僩僫儉愴憟偺嵟拞丄尰抧偺彮彈傪嫮姯偟偰嶦奞偟偨晹戉偺摨椈偨偪傪崘敪偟偨丅2恖偺朘栤幰偼崘敪偝傟偰孯朄夛媍偵偐偗傜傟暈栶偟偰偄偨暫巑偨偪偩偭偨丅斵傜偼暅廞偡傞堄恾偼側偄偲尵偆偑丄壠偵偼晄壐側嬻婥偑昚偄丄晄婥枴側嬞挘姶偵曪傑傟傞丅廔斦丄偄偒側傝朶椡偑暚弌偟丄晇晈偼戃扏偒偵偝傟丄椝怞偝傟傞丅捝傔偮偗傜傟傞晇晈偼暷崙偺徾挜偱偁傠偆偐丅愴桭傪枾崘偟偨庒幰偼丄愒庪傝偱桭恖偨偪傪枾崘偟偨僇僓儞杮恖偺巔偲廳側傞丅摉帪丄儀僩僫儉愴憟傪昞偩偭偰崘敪偡傞塮夋偼傑偩傎偲傫偳嶌傜傟偰偄側偐偭偨丅偙偺塮夋偼暔媍傪忴偟丄傑偲傕偵偼岞奐偝傟側偐偭偨傜偟偄丅搊応恖暔偼悢恖偺傒丄摉帪偼怴恖偩偭偨庡墘偺僕僃乕儉僗丒僂僢僘傪娷傔偰弌墘幰偼傒側柍柤偺攐桪丄嶣塭応強傕1売強偵尷掕偝傟偰偍傝丄嬌抂側掅梊嶼塮夋偩丅
2021擭11寧朸擔 旛朰榐147丂僄儕傾丒僇僓儞偺弶婜嶌昳
1945暷丂僄儕傾丒僇僓儞丂昡揰[B]
20悽婭弶摢偺僯儏乕儓乕僋丄僽儖僢僋儕儞偺埨傾僷乕僩偵廧傓昻偟偄堦壠偺惗妶傪昤偄偨塮夋丅庡恖岞偺庡晈傪僪儘僔乕丒儅僋僈僀傾偑墘偠傞丅斵彈偼傾僷乕僩偺憒彍晈偲偟偰壠寁傪巟偊丄怱桪偟偄偑惗妶擻椡偺側偄堸傫偩偔傟偺寍恖偺晇傪書偊丄擇恖偺巕嫙傪堢偰側偑傜丄寽柦偵惗偒傞丅挿彈偼嶌壠傪栚巜偟偰偄傞偑丄偙偺偁偨傝偼僗僥傿乕償儞僗娔撀偺乽儅儅偺憐偄弌乿傪巚偄婲偙偝偣傞丅僪儘僔乕丒儅僋僈僀傾偲偄偊偽岥偺偒偗側偄彮彈傪墘偠偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺柤嶌乽傜偣傫奒抜乿偑報徾怺偄偑丄偙偺塮夋偱傕側偐側偐偺岲墘丅榚栶偱偼斵彈偵岲堄傪婑偣傞杙鎐側傾僀儖儔儞僪宯弰嵏偺儘僀僪丒僲乕儔儞偑廏堩丅
僺儞僉乕
1949暷丂僄儕傾丒僇僓儞丂昡揰[C]
2擭慜偺乽恆巑嫤掕乿偱儐僟儎恖栤戣傪昤偄偨僇僓儞偼丄偙偺塮夋偱崟恖栤戣傪庢傝忋偘偨丅崟恖側偺偵敀偄敡偱惗傑傟偨旤偟偄彈丄僕乕儞丒僋儗僀儞偑庡恖岞丅杒晹偱弌帺傪塀偟偰娕岇晈偲偟偰惗妶偟偰偄偨斵彈偑惗傑傟屘嫿偺撿晹偵婣偭偰偔傞偲偙傠偐傜塮夋偼僗僞乕僩偡傞丅斵彈偺慶曣偵僄僙儖丒僂僅乕僞乕僘丄斵彈偺堦壠偑巇偊偨壆晘偺彈庡恖偵戝彈桪僄僙儖丒僶儕儌傾偑暞偡傞丅敀偄敡偺崟恖彈惈偺嬯擸偑昤偐傟傞偺偼嫽枴怺偄偟丄榖偺棳傟傕搑拞偱梊憐偑偮偔偲偼偄偊庤寴偔傑偲傑偭偰偄傞偑丄懡悢偺婃柪側敀恖偐傜敆奞偝傟側偑傜傕堦晹偺椙怱揑側敀恖偵彆偗傜傟偰尰抧偱娕岇妛峑偺愝棫偵婑梌偡傞偲偄偆嬝棫偰偼丄尰嵼偺帇揰偱尒傟偽埨堈偡偓傞丅
2021擭11寧朸擔 旛朰榐146丂戝塮偺屸妝帪戙寑
1957戝塮丂堖妢掑擵彆丂昡揰[C]
壗搙傕塮夋壔偝傟偨媑愳塸帯偺儀僗僩僙儔乕彫愢偺戝塮斉丅枊晎揮暍偺堿杁傪朶偔偨傔垻攇偵愽擖偟偨塀枾偲偦傟傪慾巭偟傛偆偲偡傞垻攇斔偲偺愴偄傪昤偔丅枊晎塀枾偵挿扟愳堦晇丄斵偵愴偄傪挧傓垻攇斔巑偵巗愳棆憼丄斵傪媤偲慱偆晲壠柡偵嶳杮晉巑巕丄斵傪彆偗傞彈僗儕偵扺搰愮宨偲偄偆崑壺側攝栶丅挿戝側僗僩乕儕乕偑僗僺乕僨傿側応柺揮姺偱梫椞傛偔傑偲傔忋偘傜傟偰偄傞丅嵟屻偺挿扟愳偲棆憼偺寛摤僔乕儞偼堷偒暘偗偱椉曽偺僗僞乕偵壴傪帩偨偣偰偄傞丅
擇恖偺晲憼
1960戝塮丂搉曈朚抝丂昡揰[C]
屲枴峃桽偺寱崑彫愢偺塮夋壔丅媑壀堦栧偲偺峈憟偐傜娹棳搰偺寛摤傑偱丄媨杮晲憼偺愴偄偺婳愓傪昤偔塮夋偩偑丄晲憼偼2恖偄偨偲偄偆婏敳側愝掕偲杬曻側拝憐偵傛傝丄偍撻愼傒偺暔岅偑姺崪扗戀偝傟偰偄傞丅恀潟側媮摴幰偺晲憼傪挿扟愳堦晇丄柍崪側棎朶幰偺晲憼傪巗愳棆憼偑墘偠丄嵅乆栘彫師榊偵偼彑怴懢榊偑暞偡傞丅傎偐偵柌憐尃擵彆傗偍捠傪柾偟偨彈傕搊応偡傞丅挿扟愳晲憼偼峕屗偺揤棗帋崌偱桍惗廆嬮偲懳寛偟丄棆憼晲憼偼桍惗偺棦偱愇廙釼堦栧偲愴偄丄嵟屻偼垻慼偺嶳捀偱2恖偺晲憼偑寛摤偡傞丅峳搨柍宮側嬝棫偰偩偑丄偦傟側傝偵妝偟傔傞丅
2021擭11寧朸擔 旛朰榐145丂嵟嬤偺塮夋偐傜
2019悙丂儘僀丒傾儞僟乕僜儞丂昡揰[C]
堎抂偺捁
2019僠僃僐丂償傽乕僣儔僼丒儅儖儂僂儖丂昡揰[B]
僐儕乕僯帠審
2019撈丂儅儖僐丒僋儘僀僣僷僀儞僩僫乕丂昡揰[B]
2021擭10寧
2021擭10寧朸擔 旛朰榐144丂愴慜愴屻偺壒妝塮夋
1931撈丂僴儞僗丒僔儏儚儖僣丂昡揰[D]
儚僀儅乕儖帪戙僪僀僣偺梲婥偱僐儈僇儖側僆儁儗僢僞塮夋丅墷廈偺壦嬻偺彫崙偺嬱拃娡娡挿偲彈墹偺楒偺揯枛傪昤偄偨擼揤婥側撪梕偺塮夋偩偑丄擔杮偱岞奐偝傟偨偲偒偼僸僢僩偟偨傜偟偔丄僄僲働儞偑偙偺塮夋偺憓擖嬋偵擔杮岅壧帉傪偮偗偰壧偭偰偄偨偲偄偆丅彈墹栶偱傗傫偪傖側枺椡傪怳傝傑偔傾儞僫丒僗僥儞偼偦偺屻僴儕僂僢僪偵彽偐傟偰塮夋傪嶣傞丅娵乆偲懢偭偨僺乕僞乕丒儘乕儗偑慏堳偺傂偲傝偲偟偰弌墘丅憓擖嬋偺傂偲偮乽儌儞僥僇儖儘偺堦栭乿偑僸僢僩偟丄僩儈乕丒僪乕僔乕偺僐儞儃偱僀乕僨傿僗丒儔僀僩偺壧傪僼傿乕僠儍乕偟偨傕偺側偳丄偄傠傫側償傽乕僕儑儞偑嶌傜傟丄僐儞僠僱儞僞儖丒僞儞僑偺僗僞儞僟乕僪偵傕側偭偰偄傞丅
枹姰惉岎嬁妝
1933氁仌撈丂償傿儕丒僼僅儖僗僩丂昡揰[C]
庒偒擔偺僔儏乕儀儖僩偺楒傪枹姰惉岎嬁嬋偺嶌嬋偲棈傔偰捲偭偨壒妝塮夋丅偙傟傕愴慜偵擔杮偱岞奐偝傟偰戝偒側昡敾偵側偭偨傛偆偩丅塮夋偺慜敿丄昻朢側壒妝壠僔儏乕儀儖僩偑幙壆偺柡偐傜岲堄傪婑偣傜傟丄側偵偐偲曋媂傪恾偭偰傕傜偭偰楒拠偵側傞丅屻敿偱偼丄僴儞僈儕乕偺婱懓偺柡偺壒妝嫵巘偵側偭偨僔儏乕儀儖僩偑柡偲憡巚憡垽偵側傞偑恎暘堘偄偵傛偭偰幐楒偡傞傑偱偑昤偐傟傞丅塮夋偱偼丄楒偵攋傟偨僔儏乕儀儖僩偼姰惉偝偣偨岎嬁嬋偺妝晥偵乽傢偑楒偺惉傜偞傞擛偔丄偙偺嬋傕傑偨枹姰惉側傝乿偲彂偒擖傟丄3妝復埲壓傪攋傝幪偰傞偑丄偙傟偼傕偪傠傫憂嶌丅梀傃岲偒側婱懓偺柡偵暞偡傞彈桪傛傝丄僔儏乕儀儖僩傪恊恎偵側偭偰屻墴偟偡傞幙壆偺柡傪墘偠傞彈桪偺曽偑偩傫偤傫壜垽偄偺偱丄偙偺塮夋偱偺斵偺峴摦偼擺摼偟偑偨偄丅
僇乕僱僊乕丒儂乕儖
1947暷丂僄僪僈乕丒G丒僂儖儅乕丂昡揰[C]
偮偄偱偵僋儔僔僢僋壒妝傪戣嵽偵偟偨塮夋傪傕偆堦杮丅偙傟偼僇乕僱僊乕丒儂乕儖偵嬑傔傞傂偲傝偺彈惈偺惗奤傪幉偵偟偨僴儕僂僢僪惢偺壒妝塮夋丅庡墘偼儅乕僔儍丒僴儞僩丅僗僩乕儕乕偼偨偁偄側偄偑丄摉帪僇乕僱僊乕丒儂乕儖傪杮嫆抧偲偟偰偄偨僯儏乕儓乕僋丒僼傿儖傪拞怱偵丄僽儖乕僲丒儚儖僞乕丄儕儕乕丒億儞僗丄僺傾僥傿僑儖僗僉乕丄儖乕價儞僔儏僞僀儞丄僴僀僼僃僢僣丄僗僩僐僼僗僉乕側偳丄懡偔偺桳柤側僋儔僔僢僋丒傾乕僥傿僗僩偑弌墘偟偰挊柤側嬋傪墘憈偡傞偺偑尒傕偺丅儂儔乕塮夋傗僼傿儖儉丒僲儚乕儖偱桳柤側娔撀偺僂儖儅乕偵偲偭偰偼敤堘偄偺塮夋偩偑丄偦偮側偔傑偲傔偰偄傞丅
2021擭10寧朸擔 旛朰榐143丂巗愳棆憼偺戙昞嶌2杮
1959戝塮丂怷堦惗丂昡揰[A]
堦庬偺拤恇憼奜揱偱偁傝丄暔岅偼杧晹埨暫塹偺崅揷攏応偺寛摤偱巒傑傝丄愒曚楺巑偺媑椙揁摙偪擖傝偱廔傢傞丅偦傟偵棈傔偰丄傂偲傝偺崅寜側晲巑丄扥壓揟慥偺嵢偲偺垽丄杧晹埨暫塹偲偺桭忣丄偦偟偰斵傪傪尒晳偆斶寑偑昤偐傟傞丅庡墘偺巗愳棆憼偺婥昳偁傞偨偨偢傑偄偑慺惏傜偟偄丅嫟墘偼彑怴懢榊丅慡懱偵昚偆嫊柍姶丄寛摤僔乕儞偺旤偟偝偑嵺棫偭偰偄傞丅敀旣偼愥偺側偐偱丄曅榬傪幐偄丄懌傪晧彎偟偨棆憼偑怮偨傑傑揋偲愴偆儔僗僩偱偁傠偆丅尨嶌偼屲枴峂桽丄媟杮偼埳摗戝曘丅
巃傞
1962戝塮丂嶰嬿尋師丂昡揰[B]
埫偄弌惗偺旈枾傪傕偮晲巑偑偨偳傞斶嶴側塣柦傪昤偄偨帪戙寑丅庡墘偼巗愳棆憼丅敆椡偁傞嶦恮偼側偐側偐偺傕偺丅攡偵轵偲偄偆偺偳偐側晽宨偐傜堦揮偟偰斶寑偵帄傞儔僗僩丒僔乕儞偑報徾怺偄丅
2021擭10寧朸擔 旛朰榐142丂擔暷偺廏堩側孯帠嵸敾塮夋
1983搶曮丂彫椦惓庽丂昡揰[A]
偁傜備傞擔杮恖昁尒偺塮夋偩丅徍榓23擭偺嬌搶孯帠嵸敾偺柾條傪愴憟偵帄傞擔杮偺懌愓偲棈傔偰捲偭偨4帪娫傪挻偊傞挿戝側僪僉儏儊儞僞儕乕嶌昳丅愴屻25擭偵偟偰岞奐偝傟偨暷崙柋徣偺朿戝側僼傿儖儉傪傕偲偵偟偰惢嶌偝傟偨丅埲慜丄抐曅揑偵偼尒偰偄偨偑丄崱夞丄夵傔偰慡懱傪尒偰戝偒側姶奡傪妎偊傞丅彑幰偑攕幰傪嵸偔偙偲偺惀旕丄崙壠偲屄恖偺娭學丄揤峜偺愴憟愑擟偲偄偭偨廳偄僥乕儅偑晜偒挙傝偵偝傟傞丅
僯儏乕儖儞儀儖僌嵸敾
1961暷丂僗僞儞儕乕丒僋儗僀儅乕丂昡揰[B]
1946擭偺楢崌孯偵傛傞巌朄暘栰偺僫僠僗愴斊嵸敾傪昤偄偨寑塮夋丅嵸敾挿傪柋傔傞暷崙揷幧挰偺敾帠僗儁儞僒乕丒僩儗僀僔乕丄寖偟偔媻抏偡傞専嶡姱儕僠儍乕僪丒僂傿僪儅乕僋丄昁巰偵杊愴偡傞曎岇恖儅僋僔儈儕傾儞丒僔僃儖丄嵸偐傟傞僫僠僗偺尦巌朄戝恇僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕丄棊偪傇傟偨僪僀僣婱懓晇恖儅儗乕僱丒僨傿乕僩儕僢僸丄徹恖偲偟偰弌掛偡傞旐奞幰儌儞僑儊儕乕丒僋儕僼僩偲僕儏僨傿丒僈乕儔儞僪側偳丄鐱乆偨傞婄傇傟偺攐桪偵傛傞挌乆敪巭偺墘媄偑慺惏傜偟偔丄朄掛偺峴偒媗傑傞傛偆側嬞敆姶偼尒墳偊廩暘丄3帪娫偵傢偨傞僪儔儅偼嵟屻傑偱傑偭偨偔偩傜偗傞偙偲偑側偄丅旐崘慡堳偵廔恎孻偺敾寛偑壓偝傟傞偑丄娭學幰偺傂偲傝偼丄悢擭屻偵偼傒側庍曻偝傟傞偩傠偆偲尵偆丅儔僗僩丄崠拞偺儔儞僇僗僞乕偑柺夛偵朘傟偨僩儗僀僔乕偵乽暘偐偭偰梸偟偄偑丄儐僟儎恖偺戝検嶦奞偵偮偄偰帺暘偼杮摉偵抦傜側偐偭偨偺偩乿偲慽偊傞偲丄僩儗僀僔乕偑乽偡傋偰偼孨偑嵟弶偵柍幚偺幰傪張孻偟偨偲偒偵巒傑偭偨傫偩傛乿偲墳偠傞僔乕儞偑報徾偵巆傞丅
2021擭10寧朸擔 旛朰榐141丂僪儞丒僔乕僎儖偺弶婜塮夋丂偦偺2
1958暷丂僪儞丒僔乕僎儖丂昡揰[B]
僒儞僼儔儞僔僗僐傪晳戜偵丄枾桝偟偨杻栻傪夞廂偡傞偨傔師乆偵嶦恖傪斊偡慻怐偺庤愭偲偦傟傪捛偆憑嵏姱偺峌杊傪昤偄偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖斊嵾塮夋丅偙傟偑僲儚乕儖偨傝摼偰偄傞偺偼丄峴偔愭乆偱嶦偟傑偔傞杻栻夞廂恖僀乕儔僀丒僂僅儔僢僋偺曃幏昦揑側堎忢惈奿偵傛傞丅慺憗偄応柺揥奐丄揑妋側斊嵾昤幨丄慡懱偵昚偆嬞敆姶偑尒帠丅弶婜僪儞丒僔乕僎儖偺寙嶌偺傂偲偮偩丅
僌儔儞僪僉儍僯僆儞偺懳寛
1959暷丂僪儞丒僔乕僎儖丂昡揰[C]
惣晹寑偺傛偆側戣柤偩偑丄偙傟偼庘傟偨峼嶳挰偱敪惗偟偨嶦恖帠審傪憑嵏偡傞曐埨姱偑庡恖岞偲偡傞尰戙偺僒僗儁儞僗塮夋丅庡墘偼僐乕僱儖丒儚僀儖僪丅僋儔僀儅僢僋僗偺働乕僽儖僇乕偱偺巰摤偼丄儖僪儖僼丒儅僥娔撀乽戞擇偺婡夛乿偺儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僕儍僢僋丒僷儔儞僗偺働乕僽儖僇乕偱偺懳寛傪巚偄婲偙偝偣傞丅
2021擭10寧朸擔 旛朰榐140丂僪儞丒僔乕僎儖偺弶婜塮夋丂偦偺1
1953暷丂僪儞丒僔乕僎儖丂昡揰[C]
戞2師戝愴拞偺拞崙丄旘峴婡偑捘棊偟偰抧尦僎儕儔晹戉偺庤偵棊偪偨擔杮孯彨峑傪曔敍偡傞偨傔尰抧偵晪偔暷孯晹戉偺嶌愴傪昤偄偨愴憟塮夋丅庡墘偼僄僪儌儞僪丒僆僽儔僀僄儞丅
戞廫堦崋娔朳偺朶摦
1954暷丂僪儞丒僔乕僎儖丂昡揰[C+]
懸嬾夵慞傪梫媮偟偰孻柋強偺廁恖偑婲偙偡朶摦傪昤偄偨幮夛攈塮夋丅攝栶偼抧枴偩偑丄僗僺乕僨傿側揥奐偼僔乕僎儖側傜偱偼偺傕偺丅
2021擭10寧朸擔 旛朰榐139丂徏杮惔挘尨嶌塮夋丂偦偺2
1958丂戝掚廏梇丂昡揰[D]
庤宍嵓媆偵堷偭偐偐偭偰夛幮偺夛寁壽挿偑帺嶦偟丄晹壓偺庒偄幮堳偑恀憡傪扵傞偨傔怴暦婰幰偺桭恖偲偲傕偵挿栰偺懞偵峴偒丄帠審偺攚宨傪扵傞丅庡墘偼嵅揷孾擇丄撲偺彈偵朠敧愮戙丄偦偺傎偐丄惣懞峎丄懡乆椙弮丄搉曈暥梇偲偄偭偨廰偄栶幰偑榚傪屌傔偰偄傞偑丄榖偺棳傟偑暘偐傝偵偔偔丄偁傑傝柺敀偔側偄丅
傢傞偄傗偮傜
1980丂栰懞朏懢榊丂昡揰[D]
昦堾偺堾挿偑丄彈岲偒偲嬥栕偗偑崅偠偰曟寠傪孈傝丄嶦恖傪斊偟攋柵偡傞榖丅搊応偡傞抝偲彈偼傒側寁嶼崅偄恎彑庤側楢拞偽偐傝偱丄尒偰偄偰偆傫偞傝偡傞丅庡墘偼曅壀岶晇丄斵傪庢傝姫偔彈偵徏嶁宑巕丄妬夎堖巕丄摗恀棙巕丄媨壓弴巕丅摉帪偍偦傜偔彈桪偲偟偰愨捀婜偵偁偭偨徏嶁宑巕偺旤偟偝偑嵺棫偭偰偄傞丅
2021擭10寧朸擔 旛朰榐138丂徏杮惔挘尨嶌塮夋丂偦偺1
1961丂栰懞朏懢榊丂昡揰[C]
慜嶌偵懕偒丄徏杮惔挘尨嶌塮夋傪壗杮偐尒傞丅杮嶌偼媟怓傪嫶杮擡偲嶳揷梞師偑扴摉丄丂庡墘偼媣変旤巕丄傎偐偵崅愮曚傂偯傞丄桳攏堫巕偲偄偆彈桪恮偑嫟墘偟偰偄傞丅怴崶偺晇偑嬥戲偵弌挘偟偨傑傑徚懅傪愨偭偨丅嵢偼嬥戲偵峴偭偰晇偺峴曽傪捛偆偆偪偵丄斵偺塀偝傟偨夁嫀偲巰偺恀憡傪抦傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅搤偺杒棨偺偝傃傟偨岝宨偑報徾偵巆傞丅
崟偄夋廤丂偁傞僒儔儕乕儅儞偺徹尵
1960丂杧愳峅捠丂昡揰[B]
偙傟傕媟怓偼嫶杮擡丅惔挘尨嶌塮夋偺側偐偱偼弌怓偺嶌昳偺傂偲偮丅庡墘偺彫椦宩庽偵偲偭偰傕戙昞嶌偲偄偊傞偩傠偆丅戝夛幮偺壽挿偱弌悽偺摴偵忔傝丄岾偣側壠掚傪傕偮庡恖岞偼丄晹壓偺庒偄帠柋堳傪垽恖偵埻偭偰偄傞丅偁傞斢丄斵彈偺傾僷乕僩弌偨斵偼帺戭偺嬤強偵廧傓婄尒抦傝偺抝偲弌夛偭偰垾嶢傪岎傢偡丅梻擔偦偺抝偑嶦恖偱戇曔偝傟丄嶦奞帪崗偵偼暿偺応強偱庡恖岞偲夛偭偨偲傾儕僶僀傪庡挘偡傞丅垽恖娭學偑偽傟偰偼崲傞庡恖岞偼夛偭偰偄側偄偲塕傪偮偔偑丄椙怱偺欒愑偱嬯擸偡傞丄偲偄偆榖丅儔僗僩丄偡傋偰傪幐偭偨庡恖岞偑庍曻偝傟偰寈嶡彁偐傜弌偰偔傞僔乕儞偑報徾偵巆傞丅彫椦宩庽偼柧楴寉柇側僒儔儕乕儅儞傕偺偱抦傜傟偰偄傞偑丄偙偺塮夋傗惉悾偺乽彈偺拞偵偄傞懠恖乿側偳偺傛偆偵晜婥偑敪妎偟偦偆偵側偭偰嬯偟傓僒僗儁儞僗傕偺偺庡恖岞傪傗傜偣偰傕忋庤偐偭偨丅
2021擭10寧朸擔 旛朰榐137丂嶳揷梞師偺2杮偺弶婜塮夋
1963丂嶳揷梞師丂昡揰[C]
嶳揷梞師偺娔撀戞2嶌偱丄攞徿愮宐巕偲偺挿偔懕偄偨僐儞價偺殔栴偲側偭偨塮夋丅攞徿偺僸僢僩嬋傪傕偲偵偟偨丄偄傢備傞壧梬塮夋偱偁傝丄岺堳偲偟偰摥偔斵彈偑恻梋嬋愜傪宱偰暿偺岺応偱摥偔彑楥梍偲寢偽傟傞傑偱傪昤偔丅斵彈偺晝偵摗尨姌懌偑暞偟丄壓挰偺恊晝傜偟偄枴傪忴偟弌偟偰偄傞丅懅巕偑朣偔側偭偰惛恄偵堎忢傪偒偨偟偨嬤強偺榁恖傪墘偠傞搶栰塸帯榊偼丄摨偠傛偆側栶傪墘偠偨乽寈嶡擔婰乿傪渇渋偲偝偣傞丅
柖偺婙
1965丂嶳揷梞師丂昡揰[B+]
徏杮惔挘尨嶌彫愢偺塮夋壔丅媟怓偼嫶杮擡丅嶳揷梞師偑偙偺傛偆側巌朄僒僗儁儞僗傗堦庬偺埆彈傪戣嵽偲偡傞僔儕傾僗側塮夋傪娔撀偡傞偺偼偒傢傔偰捒偟偄丅孼偑嶦恖嵾偱戇曔偝傟丄孼偺柍幚傪怣偠傞枀偺攞徿愮宐巕偼崅柤側曎岇巑偺戧戲廋偵曎岇傪埶棅偡傞偑抐傜傟傞丅孼偼桳嵾偲側傝崠拞偱巰偸丅曎岇巑傪崷傓枀偼暅廞傪婇偰傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅慡懱偺嬝棫偰偼傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩偺乽娽偵偼娽傪乿傪憐婲偝偣傞丅昿弌偡傞栭偺僔乕儞偼堿塭偵晉傫偱偍傝丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖怓偑擹偄丅惣懞峎丄愳捗桽夘丄怴媴嶰愮戙側偳丄僋僙偺偁傞攐桪偑嫟墘偟偰偄傞丅
2021擭9寧
2021擭9寧朸擔 旛朰榐136丂嵟嬤偺塮夋偐傜
2019暷丒塸丂P丒B丒僔僃儉儔儞丂昡揰[B]
19悽婭敿偽偺塸崙丄僆僢僋僗僼僅乕僪塸岅帿揟偺曇嶽丒弌斉偵傑偮傢傞旈榖丅庡墘偺儊儖丒僊僽僜儞偲僔儑乕儞丒儁儞偼側偐側偐偺椡墘丅
17嵨偺僂傿乕儞丂僼儘僀僩嫵庼恖惗偺儗僢僗儞
2018氁丒撈丂僯僐儔僂僗丒儔僀僩僫乕丂昡揰[B]
僫僠僗偵暪崌偝傟偨僂傿乕儞丄僎僔儏僞億偵骧鏦偝傟傞側偐丄揷幧偐傜弌偰偒偨弮杙側惵擭偑僼儘僀僩攷巑偲偺岎棳傪捠偟偰恖惗傪妛傫偱偄偔丅
2021擭9寧朸擔 旛朰榐135丂僴儕僂僢僪50擭戙弶婜偺柤嶌
1955暷丂僗僞儞儕乕丒僋儗僀儅乕丂昡揰[B]
偡偖傟偨堛妛媄弍偲崅偄棟憐傪帩偭偰偄傞偑丄撈慞揑偱婃側側惈奿偱偁傞惵擭堛巘偺怱偺妺摗傪昤偄偨僸儏乕儅儞丒僪儔儅丅堛妛惗偺庡恖岞偵儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉丄昻偟偄斵偑妛旓傪摼傞偨傔偵寢崶偡傞娕岇巘偵僆儕償傿傾丒僨僴償傿儔儞僪丄庡恖岞偺妛桭偵僼儔儞僋丒僔僫僩儔偑暞偡傞丅慜敿偺榖偟偺棳傟偼乽梲偺偁偨傞応強乿傪憐婲偝偣傞丅斵偼嬯楯偟偰堛壢戝妛傪懖嬈偟丄揷幧挰偺昦堾偵嬑傔丄專恎揑偵巇帠偡傞偑丄偟偩偄偵廃埻偲鏰鐎偑惗偠傞丅偙偺塮夋偺攝栶偼偠偮偵儐僯乕僋偱偁傝丄庡恖岞偺儈僢僠儍儉傪偼偠傔丄戝妛偺壎巘偵僽儘僨儕僢僋丒僋儘僼僅乕僪丄妛桭偺傂偲傝偵儕乕丒儅乕償傿儞丄挰昦堾偺愭攜堛巘偵僠儍乕儖僘丒價僢僋僼僅乕僪丄偝傜偵偼儈僢僠儍僋偑怓崄偵嵈偝傟傞挰偺嬥帩偪儅僟儉偵僌儘儕傾丒僌儗傾儉偲丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖忢楢偺攐桪偑偨偔偝傫弌墘偟偰偄傞丅僨僴償傿儔儞僪偼晄旤恖偺僆乕儖僪儈僗偺栶偱偁傝丄偒傟偄側彈桪側偺偵丄乽彈憡懕恖乿側偳丄側偤偐偙偆偄偆栶偑懡偄丅
儃乕儞丒僀僄僗僞僨僀
1950暷丂僕儑乕僕丒僉儏乕僇乕丂昡揰[C]
戝僸僢僩晳戜寑傪塮夋壔偟偨晽巋僐儊僨傿丅慹栰偱墶朶側揷幧惉嬥僽儘僨儕僢僋丒僋儘僼僅乕僪偑媍堳偲僐僱傪嶌傞偨傔丄梮傝巕忋偑傝偺柍嫵梴側垽恖僕儏僨傿丒儂儕僨僀傪楢傟偰儚僔儞僩儞偵傗偭偰棃傞丅惉嬥偼垽恖偵嫵梴傪偮偗偝偣傞偨傔庢嵽偟偵棃偨婰幰僂傿儕傾儉丒儂乕儖僨儞傪嫵堢學偵屬偆丅抦幆傪恎偵偮偗偨垽恖偼惉嬥偺尦偐傜嫀傝丄垽偟崌偆婰幰偲偲傕偵怴偟偄恖惗偵摜傒弌偡丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅慡懱揑側僾儘僢僩偼乽儅僀丒僼僃傾丒儗僨傿乿偵帡偰偄傞丅傾儊儕僇柉庡庡媊傪柍忦審偵巀旤偟偰偄傞偺偑旲偵偮偔偑丄塮夋偲偟偰偼傛偔弌棃偰偍傝丄儂儕僨僀乮僆僗僇乕庴徿乯偲僋儘僼僅乕僪偺帩偪枴傪惗偐偟偨墘媄傕偠偮偵岻傒丅
2021擭9寧朸擔 旛朰榐134丂塸崙偺媨掛寑偲壠掚寑
1933塸丒暷丂傾儗僋僒儞僟乕丒僐儖僟丂昡揰[C]
岲怓側朶孨偲偟偰桳柤側16悽婭僀儞僌儔儞僪墹僿儞儕乕8悽偺峴忬傪昤偄偨楌巎媨掛寑丅斵偼抝巕偺屻宲幰傪摼傞偨傔丄棧崶偟偨傝張孻偟偨傝偟偰6夞傕嵢傪庢傝懼偊傞丅庡恖岞偵僠儍乕儖僗丒儘乕僩儞乮僆僗僇乕庴徿乯丄張孻偝傟傞2斣栚偺嵢傾儞丒僽乕儕儞偵儅乕儖丒僆儀儘儞偑暞偡傞丅徰憸夋偲偦偭偔傝偵儊僀僋偟偨儘乕僩儞偼傑偝偵揔栶丄柍帨斶偱墶朶偩偑偳偙偐憺傔側偄僿儞儕乕8悽傪尒帠偵墘偠偰偄傞丅
岾暉側傞庬懓
1944塸丂僨償傿僢僪丒儕乕儞丂昡揰[C+]
戞1師戝愴廔寢屻偐傜戞2師戝愴捈慜傑偱偺20擭娫偺儘儞僪儞壓挰偺拞棳奒媺堦壠偺擔忢傪昤偔儂乕儉丒僪儔儅丅僨償傿僢僪丒儕乕儞偼偙偺梻擭偺1945擭偺乽埀傃偒乿偑弌悽嶌偲側傝丄偦偺屻10擭傎偳丄僨傿働儞僘尨嶌偺暥寍傕偺傗彫枴側楒垽塮夋傗旂擏傪岠偐偣偨僐儊僨傿塮夋傪嶌偭偰偄偨偑丄1957擭偺乽愴応偵偐偗傞嫶乿埲崀丄戝嶌巙岦偵揮偠偨丅乽岾暉側傞庬懓乿偼儘儞僪儞摿桳偺搹妱挿壆偵堷偭墇偟偰偒偨儘僶乕僩丒僯儏乕僩儞偲僔儕傾丒僕儑儞僜儞偺晇晈丄偦偺3恖偺巕嫙丄曣恊偺榁攌丄僆乕儖僪丒儈僗偺巓偐傜側傞堦壠偺惗妶傗弌棃帠偑偨傫偨傫偲捲傜傟傞丅楯摥幰偨偪偺僗僩傗僫僠僗偺戜摢側偳偺悽憡傕嶶傝偽傔傜傟丄帪戙偲楌巎偺棳傟傪姶偠偝偣傞丅挌擩偵嶌傜傟偰偄偰尒朞偒傞偙偲偼側偄偑丄僲僄儖丒僇儚乕僪偺尨嶌媃嬋偵偼惗妶偵偍偗傞宱嵪揑側懁柺偑僶僢僒儕敳偗棊偪偰偄傞丅
2021擭9寧朸擔 旛朰榐133丂僴儕僂僢僪40擭戙屻婜偺柤嶌
1948暷丂僕儑乕僕丒僗僥傿乕償儞僗丂昡揰[A]
晳戜偼1910擭戙偺僒儞僼儔儞僔僗僐丄僲儖僂僃乕偐傜偺堏柉堦壠偑昻偟偄側偑傜傕彆偗崌偄側偑傜寴幚偵惗偒偰偄偔巔傪昤偄偨壠掚寑丅僗僥傿乕償儞僗偺尒帠側墘弌偵傛傝丄擔忢偺憓榖偑垼娊傪崬傔偰偰偄偹偄偵昤偐傟丄垽偡傋偒塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅嬸抯傪偙傏偝偢惗寁傪傗傝孞傝偟丄4恖偺巕嫙偵垽忣傪拲偓丄寵傢傟幰偺攲晝傗婥偺庛偄巓偵傕傗偝偟偔愙偡傞憦柧側曣偵傾僀儕乕儞丒僟儞丄嶌壠巙朷偺挿彈偱塮夋偺岅傝庤栶偵僶乕僶儔丒儀儖丒僎僨僗偑暞偡傞丅傾僀儕乕儞丒僟儞偺墘媄偼愨昳偩偑丄偙偺擭偺僆僗僇乕彈桪徿偼乽僕儑僯乕丒儀儕儞僟乿偺僕僃乕儞丒儚僀儅儞偵偝傜傢傟偨丅暷崙偺柤彈桪偺側偐偱摉慠僆僗僇乕庡墘彈桪徿傪梌偊傜傟偰偟偐傞傋偒側偺偵庴徿偟偰偄側偄偺偼丄偙偺傾僀儕乕儞丒僟儞偲僶乕僶儔丒僗僞儞僂傿僢僋偩丅弌墘幰偺側偐偱偼攲晝栶偺僆僗僇乕丒儂儌儖僇偺廰偄墘媄傕慺惏傜偟偄丅偙偺塮夋偼摉帪偺擔杮塮夋偵塭嬁傪梌偊偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅惉悾枻婌抝偺壠掚僪儔儅偵堦柆捠偠傞傕偺偑偁傞偟丄拞懞搊偺塮夋乽変偑壠偼妝偟乿偱曣恊偺嶳揷屲廫楅偑夋壠傪栚巜偡柡偺崅曯廏巕偺奊傪崅柤側夋壠偵尒偣偵峴偔憓榖偼丄偙偺塮夋偺曣恊偑柡偺彂偄偨彫愢傪恖婥嶌壠偵撉傫偱傕傜偆憓榖傪庁梡偟偰偄傞丅
僕儑僯乕丒儀儕儞僟
1948暷丂僕乕儞丒僱僌儗僗僐丂昡揰[C+]
晳戜偼僲償傽僗僐僔傾敿搰壂偺棧搰丅搰偵傗偭偰棃偨怱傗偝偟偄堛巘儕儏乕丒僄傾乕僘偼惢暡強傪塩傓擾晇僠儍乕儖僘丒價僢僋僼僅乕僪偲抦傝崌偄丄偦偺柡偱敀抯埖偄偝傟偰偄傞榃垹幰偺僕僃乕儞丒儚僀儅儞偑杮摉偼憦柧偱偁傞偙偲傪尒敳偒丄庤榖傗撉彂傪庤傎偳偒偡傞丅傗偑偰斵彈偼旤偟偔惉挿偡傞偑丄偦傟偵栚傪偮偗偨挰偺棎朶幰偵庤崬傔偵偝傟丄擠怭偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僞僀僩儖偺僕儑僯乕丒儀儕儞僟偲偼柡偑嶻傓抝偺巕偺柤慜丅暵嵔偝傟偨揷幧挰偺埆廗丄忈奞幰傊偺曃尒丄傛偦幰傊偺斀姶丄塕偺塡榖偺奼嶶偑昤偐傟傞丅庡墘偺儚僀儅儞偼儘僫儖僪丒儗乕僈儞偺嵟弶偺嵢偱偁傝丄抧枴偩偑壜垽偄婄棫偪丄偙傟偵傛偭偰僆僗僇乕傪庴徿偟偨丅
2021擭8寧
2021擭8寧朸擔 旛朰榐132丂戝塮偺棆憼帪戙寑
1964丂怷堦惗丂昡揰[C]
巗愳棆憼庡墘偺儐乕儌傾丒儈僗僥儕帪戙寑丅戅孅側擔乆偵壣傪帩偰梋偡棆憼暞偡傞彨孯媑廆偼挰曭峴強偺摨怱偵側傝偡傑偟偰岼偺嶦恖帠審傪夝寛偟傛偆偲偡傞丅曭峴偺戝壀墇慜偵暞偡傞偺偼丄側傫偲嶰搰夒晇丅媑廆偑抦傝崌偆楺恖偑塅捗堜寬偱丄偙傟偑嵟屻偵挬掛偐傜偺巊幰偩偲暘偐傞偲偄偆丄側傫偲傕恖傪怘偭偨愝掕丅偙傟偼1941擭岞奐偺儅僉僲夒峅娔撀偺摨柤塮夋偺儕儊僀僋偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞偑丄愝掕傕嬝棫偰傕傑偭偨偔堎側傞傜偟偄丅偙偺挿扟愳堦晇丒嶳揷屲廫楅庡墘偺僆儕僕僫儖偼埲慜偐傜尒偨偄偲巚偭偰偄傞偺偩偑丄傑偩偦偺婡夛傪摼側偄丅
戝峕嶳庰揤摱巕
1960丂揷拞摽嶰丂昡揰[D]
尮棅岝偵傛傞戝峕嶳偺婼戅帯傪戣嵽偵偟偨屸妝帪戙寑丅庰撣摱巕偵挿扟愳堦晇丄尮棅岝偵巗愳棆憼丄搉曈峧偵彑怴懢榊丄傎偐偵杮嫿岟師丄拞懞殪帯榊丄彫戲塰懢榊丄嵍岾巕丄嶳杮晉巑巕丄拞懞嬍弿傕弌墘偡傞戝塮僆乕儖僗僞乕塮夋丅庰撣摱巕偼埑惌傪嫮偄傞嫗偺搒偺尃椡幰偵愴偄傪挧傓抝偱丄偦偺攝壓偵婼傗嶳懐偑偄傞偲偄偆愝掕偱偁傝丄婼偺曅榬傪愗傝棊偲偡搉曈峧傗搒傪峳傜偡搻懐屟悅偺憓榖傕怐傝崬傑傟傞偑丄僾儘僢僩偑拞搑敿抂偱偁傑傝柺敀偔側偄丅
2021擭7寧
2021擭7寧朸擔 旛朰榐131丂墿崹婜偺惣晹寑
1971暷丂僿儞儕乕丒僴僒僂僃僀丂昡揰[C]
僌儗僑儕乕丒儁僢僋庡墘偺丄70擭戙偵偼捒偟偄惓摑揑側惣晹寑偩偑丄僕儑儞丒僗僞乕僕僃僗偺寛摤3晹嶌偺傂偲偮乽僈儞僸儖偺寛摤乿偲偼傑偭偨偔娭學側偔丄孻柋強偐傜弌崠偟偨庡恖岞偺儁僢僋偑棤愗傝幰偵暅廞偡傞偨傔傗偭偰峴偔挰偺柤偑僈儞僸儖偲偄偆偩偗偺偙偲丅偲偼偄偊丄偦偺暅廞偼拞搑敿抂偱惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅偙偺塮夋偱柺敀偄偺偼丄儁僢僋偑偐偮偰偺楒恖偐傜搨撍偵憲傝偮偗傜傟偨6嵨偺彮彈傪巐嬯敧嬯偟側偑傜柺搢傪尒傞僄僺僜乕僪偩丅儁僢僋偼偟偐偨側偔彮彈偲峴摦傪嫟偵偡傞偑丄嵟弶偼栵夘偵巚偭偰偄偨偺偵偩傫偩傫垽忣偑桸偄偰偄偔忣宨偑旝徫傑偟偄丅
儕僆丒僐儞僠儑僗
1964暷丂僑乕僪儞丒僟僌儔僗丂昡揰[C]
楢朚孯偺怴幃廵傪搻傒丄僀儞僨傿傾儞偵攧偭偰敀恖傪峌寕偝偣傛偆偲偡傞尦撿孯彨峑偺堦枴傪捛偭偰丄婻暫戉偺拞堁偲孯憘丄僀儞僨傿傾儞傪憺傓棳傟幰偺僈儞儅儞丄怓抝偺斊嵾幰偑儊僉僔僐偵愽擖偡傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡墘偼儕僠儍乕僪丒僽乕儞偲僗僠儏傾乕僩丒儂僀僢僩儅儞丅帪戙偺偣偄偐丄傗傗儅僇儘僯偺晽枴偑偁傞丅憭媀拞偺僀儞僨傿傾儞傪儕僠儍乕僪丒僽乕儞偑儔僀僼儖偱嶦偟傑偔傞摫擖晹偑嫮楏丅廔斦偵搊応偡傞丄偄傑偩偵愴憟傪宲懕偟傛偆偲偡傞嫸婥偺尦撿孯彨峑偲丄斵偑媢偺忋偵棫偰偨寶愝搑拞偺揁戭偑報徾怺偔丄僐僢億儔偺乽抧崠偺栙帵榐乿傪憐婲偝偣傞丅
2021擭7寧朸擔 旛朰榐130丂墿嬥帪戙偺惣晹寑
 榋斣栚偺抝
榋斣栚偺抝1955暷丂僕儑儞丒僗僞乕僕僃僗丂昡揰[B]
儕僠儍乕僪丒僂傿僪儅乕僋庡墘偺儈僗僥儕乕巇棫偰偺惣晹寑丅嫟墘偼僪僫丒儕乕僪丅僂傿僪儅乕僋偼峴曽晄柧偺晝恊傪扵偟偰5恖慻偺椃峴戉偑僀儞僨傿傾儞偵嶦偝傟偨尰応偵峴偔偑丄偦偙偵偼摨偠偔晇傪扵偡僪僫丒儕乕僪偑偄偨丅挷傋偑恑傓偵楢傟偰丄椃峴戉偵偼嬥傪扗偭偰摝憱偟偨6斣栚偺抝偑偄偨偙偲偑柧傜偐偵側傞丅傆偨傝偼恀憡傪媮傔偰僥僉僒僗偺杚応偵岦偆丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偒傃偒傃偟偨墘弌偲弌墘幰偨偪偺枺椡偵傛傝丄憉夣側妶寑塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅
惎偺側偄抝
1955暷丂僉儞僌丒償傿僟乕丂昡揰[D]
棳傟幰偺僇僂儃乕僀丄僇乕僋丒僟僌儔僗偑丄柍捓忔幵偺壿暔楍幵偱憡朹偵側偭偨庒幰偲偲傕偵丄惣晹偺偁傞挰偵偨偳傝拝偔丅斵偼搶晹偐傜棃偨彈杚応庡僕乕儞丒僋儗僀儞偑宱塩偡傞杚応偵杚摱摢偲偟偰屬傢傟傞偑丄椬愙偡傞杚応偲偺撽挘傝憟偄偵姫偒崬傑傟傞丄偲偄偆榖丅僇乕僋丒僟僌儔僗偼奿岲偄偄偑丄塮夋偲偟偰偼巚偄偺傎偐惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅
2021擭6寧
2021擭6寧朸擔 旛朰榐129丂愴慜丒愴屻偺捒昳擔杮塮夋
1944丂娵崻巀懢榊丂昡揰 [D]
庒偒擔偺崟郪柧偺媟杮丄曅壀愮宐憼庡墘偺捒偟偄憡杘塮夋丅堦庬偺寍摴傕偺塮夋偱偁傝丄庒偄憡杘庢傝偺曅壀偑媡嫬偵懴偊丄惛恑傪廳偹偰岟惉傝柤悑偘傞傑偱偑昤偐傟傞丅怴攈寑偺傛偆側忢搮揑側偍椳捀懻恖忣敹偩偑丄偙偺慜擭偵崟郪偑弶娔撀偟偨乽巔嶰巐榊乿傪巚傢偣側偄偱傕側偄丅曅壀愮宐憼偼婄偩偗尒傟偽偦傟傆偆偩偑丄懱偼彫暱偩偟崪奿傕晛捠偱丄偍傛偦憡杘庢傝偵偼尒偊側偄丅憡杘庢傝偵暞偡傞傎偐偺栶幰傕丄懢傔偺娸堜柧傪彍偒丄傒側懱奿偼昻庛偱丄尰幚枴偑側偄偙偲偍傃偨偩偟偄丅嶣塭偼媨愳堦晇偩偑丄婜懸偵斀偟偰塮憸偼暯杴丅
嬇偺捛愓
1950丂巗愳浝丂昡揰 [C]
抮晹椙庡墘偺寈嶡塮夋丅怴嫶墂慜偺岎斣傪晳戜偵丄庒偄恀柺栚側弰嵏丄抮晹椙偺巇帠偲巹惗妶丄摨椈弰嵏偲偺岎棳傗鏰鐎丄寈嶡姱偲偟偰偺擸傒丄杻栻枾攧斊偺憑嵏側偳偑昤偐傟傞丅摨椈弰嵏偵悈搰摴懢榊丄埳摗梇擵彆丄摗尨姍懌丄杮挕孻帠偵悰堜堦榊側偳偺廰偄栶幰偨偪偑攝偝傟丄抮晹偺楒恖偺儔乕儊儞壆偺柡偵悪梩巕偑暞偟偰偄傞丅摉帪偺怴嫶丄嬧嵗奅孏偺岝宨偑儘働偵傛偭偰僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵塮偟弌偝傟傞偺偑嫽枴怺偄丅婫愡偼恀壞偱丄娋傪偟偨偨傜偣側偑傜憑嵏偡傞嶡姱偨偪偺巔偼崟郪偺乽栰椙將乿偺嶰慏晀榊偲廳側傞丅抮晹偲悪偺楒恖僐儞價偑旝徫傑偟偄報徾傪梌偊傞丅壒惡偑埆偔丄戜帉偑傛偔暦偒庢傟側偄偺偑擄丅
2021擭6寧朸擔 旛朰榐128丂儖儖乕僔儏偺償傽儞僠儏儔庡墘塮夋
1972暓丂僋儘乕僪丒儖儖乕僔儏丂昡揰 [E]
儕僲丒償傽儞僠儏儔庡墘偺斊嵾僐儊僨傿塮夋丅娫敳偗側斊嵾幰僌儖乕僾偺5恖偑桳柤恖傪桿夳偟偰恎戙嬥傪偣偟傔丄戝嬥傪庤偵偟偰桳捀揤偵側傞偑丄堄奜側棊偲偟寠偼傑傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅忕挿偱嶶枱側報徾偟偐庴偗側偄丅
抝偲彈偺帊
1973暓丂僋儘乕僪丒儖儖乕僔儏丂昡揰 [C]
偙傟傕儕僲丒償傽儞僠儏儔庡墘偺曮愇嫮扗偺夁掱偲拞擭抝彈偺楒傪昤偄偨塮夋丅僇儞僰偺曮愇揦偱憡朹偲堦弿偵曮愇傪嫮扗偟傛偆偲偟偰偄傞斊嵾幰偺儕僲丒償傽儞僠儏儔偑丄曮愇揦偺椬偺崪摕昳揦偺彈庡恖僼儔儞僜儚乕僘丒僼傽價傾儞偲恊偟偔側傝丄楒偵棊偪傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僒僗儁儞僗側偺偐儔償僗僩乕儕乕側偺偐丄拞搑敿抂側撪梕偩偑丄償傽儞僠儏儔偼偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅朻摢丄偙偺娔撀偺媽嶌乽抝偲彈乿偺塮憸偑塮偟弌偝傟傞偺偱柺怘傜偆偑丄偙傟偼孻柋強偱廁恖偨偪偑偙偺塮夋傪尒偰偄傞偲偄偆愝掕丅
2021擭6寧朸擔 旛朰榐127丂僩儕儏僼僅乕偺傾僀儕僢僔儏尨嶌塮夋
1969 暓丂僼儔儞僜儚丒僩儕儏僼僅乕丂昡揰 [B]
僩儕儏僼僅乕偵偟偰偼捒偟偔丄摉帪偺僼儔儞僗偺抝彈偺恖婥僗僞乕攐桪丄僕儍儞億乕儖丒儀儖儌儞僪偲僇僩儕乕僰丒僪僰乕償傪婲梡偟偨僒僗儁儞僗塮夋丅尨嶌偼僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏偺彫愢乽埫埮傊偺儚儖僣乿丅僩儕儏僼僅乕偼偙偺慜擭偵摨偠偔傾僀儕僢僔儏尨嶌偺乽崟堖偺壴壟乿傪塮夋壔偟偰偄傞丅傏偔偼摉帪儕傾儖僞僀儉偱乽崟堖偺壴壟乿傪尒偰丄偮傑傜側偔偰偑偭偐傝偟偨婰壇偑偁傞丅偦傟傕偁偭偰丄偙偺塮夋偼尒偰偄側偐偭偨偑丄偙偪傜偼側偐側偐椙偄弌棃偵巇忋偑偭偰偄傞丅傾僼儕僇偺彫搰偱僞僶僐嵧攟嬈傪塩傓儀儖儌儞僪偼怴暦峀崘偱壴壟傪曞廤偡傞偑丄傗偭偰棃偨彈偼幨恀偲戝堘偄偺旤彈僪僰乕償丅堦栚崨傟偟偨儀儖儌儞僪偼僪僰乕償偲妝偟偔怴崶惗妶傪憲傞偑丄偁傞擔僪僰乕償偼儀儖儌儞僪偺嬧峴梐嬥傪偡傋偰堷偒壓傠偟偰巔傪徚偡丅斵彈偺峴曽傪捛偆儀儖儌儞僪偼撿僼儔儞僗偱僪僰乕償傪尒偮偗傞偰栤偄媗傔傞偑丄傑偨傕傗斵彈偺枺椡偵偼傑傝丄堦弿偵摝朣惗妶傪憲傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅儀儖儌儞僪偼弮杙側惵擭傪岲墘偟偰偄傞偟丄僪僰乕償偺埆彈傇傝傕尒傕偺偱丄彫傇傝偺偍偭傁偄傪惿偟偘傕側偔偝傜偟偰変乆偺栚傪妝偟傑偣偰偔傟傞丅榖偺棳傟傕偩傟傞偙偲側偔僗儉乕僗偵揥奐偡傞偩偑丄栤戣偼儔僗僩偩丅戝愄偵撉傫偩彫愢偺婰壇偵傛傞偲丄塮夋偼尨嶌偵傎傏拤幚偩偑丄僄儞僨傿儞僌偑堎側傞丅彫愢偱偼丄嵿嶻傪幐偄丄嶦恖斊偲偟偰寈嶡偵捛傢傟傞抝偼丄彈偵撆傪惙傜傟丄偦傟偲抦傝偮偮堸傫偱巰偸偑丄塮夋偱偼撆傪惙傜傟偨抝偑彈傊偺垽傪岅傝丄偦偺恀忣偵傎偩偝傟偨彈偼夵怱偟偰抝傪彆偗丄擇恖偱愥嶳傪僗僀僗偵岦偗偰摝朣偡傞丅偙偙偼僪僰乕償偑揙掙揑偵埆彈偱側偗傟偽側傜偢丄塮夋斉偺娒偄僄儞僨傿儞僌偩偲尪柵傪妎偊傞丅朻摢偵僕儍儞丒儖僲儚乕儖偵曺偖偲偄偆專帿偑弌偰偔傞丅儔僗僩偺2恖偑崙嫬偵岦偆僔乕儞偼乽戝偄側傞尪塭乿偺堷梡偱偁傝丄儀儖儌儞僪偑僪僰乕償傪尒偮偗傞儂僥儖偺晹壆偺僔乕儞偼僸僢僠僐僢僋偺乽傔傑偄乿偺堷梡偩偲偄偆丅傎偐偵傕悘強偵偄傠傫側塮夋傊偺栚攝偣偑偁傞傛偆偩偑丄尵傢傟側偗傟偽偦傟傪暘偐傜偢丄僩儕儏僼僅乕偺撈傝傛偑傝偲偄偆婥偑偟側偄偱傕側偄丅
崟堖偺壴壟
1968暓丂僼儔儞僜儚丒僩儕儏僼僅乕丂昡揰 [C]
 偙傟偼塮夋岞奐帪偵尒偰偄傞偑丄乽埫偔側傞傑偱偙偺楒傪乿尒偨偺偵怗敪偝傟偰丄摨偠偔傾僀儕僢僔儏尨嶌偺偙偺塮夋傪50擭傇傝偵嵞尒丅僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠柤媊偵傛傞摨柤彫愢偺塮夋壔偱丄摉帪丄婜懸偟偰尒偨偑傑偭偨偔偮傑傜側偄塮夋偱偑偭偐傝偟偨偙偲傪婰壇偟偰偄傞丅偮傑傜側偐偭偨尨場偼庡墘偺僕儍儞僰丒儌儘乕偑拞擭偺偍偽偝傫晽偱丄庒偄旤彈偱偁傞偼偢偺栶偵傑偭偨偔偦偖傢側偐偭偨偐傜偩丅撪梕偼丄寢崶幃摉擔偵晇傪嶦偝傟偨嵢偑丄斊恖偺抝5恖傪傂偲傝偢偮嶦偟偰偄偔暅廞鏉丅娔撀偺僩儕儏僼僅乕傕偙傟傪幐攕嶌偲擣傔偰偄傞偑丄崱夞丄尒捈偟偰丄偦傟傎偳傂偳偄弌棃偱傕側偄偲巚偭偨丅偮偠偮傑偺崌傢側偄売強偼偁偪偙偪偵偁傞偑丄尨嶌偑偦偆偩偐傜偟傚偆偑側偄丅40嵨偺僕儍儞僰丒儌儘乕偼偨偟偐偵拞擭婄偵側偭偰偍傝丄懱傕懢偭偰偒偰偄傞偑丄廥偄偲偙傠傑偱偼偄偭偰偄側偄丅嵟戝偺栤戣偼僇儔乕偱嶣偭偨偙偲偱僲儚乕儖揑側暤埻婥偑敿尭偟偰偄傞偙偲偩丅偙傟偑儌僲僋儘偩偭偨傜丄傕偭偲傑偟側塮夋偵側偭偰偄偨偩傠偆丅
偙傟偼塮夋岞奐帪偵尒偰偄傞偑丄乽埫偔側傞傑偱偙偺楒傪乿尒偨偺偵怗敪偝傟偰丄摨偠偔傾僀儕僢僔儏尨嶌偺偙偺塮夋傪50擭傇傝偵嵞尒丅僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠柤媊偵傛傞摨柤彫愢偺塮夋壔偱丄摉帪丄婜懸偟偰尒偨偑傑偭偨偔偮傑傜側偄塮夋偱偑偭偐傝偟偨偙偲傪婰壇偟偰偄傞丅偮傑傜側偐偭偨尨場偼庡墘偺僕儍儞僰丒儌儘乕偑拞擭偺偍偽偝傫晽偱丄庒偄旤彈偱偁傞偼偢偺栶偵傑偭偨偔偦偖傢側偐偭偨偐傜偩丅撪梕偼丄寢崶幃摉擔偵晇傪嶦偝傟偨嵢偑丄斊恖偺抝5恖傪傂偲傝偢偮嶦偟偰偄偔暅廞鏉丅娔撀偺僩儕儏僼僅乕傕偙傟傪幐攕嶌偲擣傔偰偄傞偑丄崱夞丄尒捈偟偰丄偦傟傎偳傂偳偄弌棃偱傕側偄偲巚偭偨丅偮偠偮傑偺崌傢側偄売強偼偁偪偙偪偵偁傞偑丄尨嶌偑偦偆偩偐傜偟傚偆偑側偄丅40嵨偺僕儍儞僰丒儌儘乕偼偨偟偐偵拞擭婄偵側偭偰偍傝丄懱傕懢偭偰偒偰偄傞偑丄廥偄偲偙傠傑偱偼偄偭偰偄側偄丅嵟戝偺栤戣偼僇儔乕偱嶣偭偨偙偲偱僲儚乕儖揑側暤埻婥偑敿尭偟偰偄傞偙偲偩丅偙傟偑儌僲僋儘偩偭偨傜丄傕偭偲傑偟側塮夋偵側偭偰偄偨偩傠偆丅2021擭5寧
2021擭5寧朸擔 旛朰榐126丂嵟嬤偺塮夋偐傜
2013億乕儔儞僪丒僨儞儅乕僋丂僷償僃僂丒僷僽儕僐僼僗僉丂昡揰 [A]
僕儏僨傿丂擑偺斵曽偵
2019塸丒暓丒暷丂儖僷乕僩丒僌乕儖僪丂昡揰 [D]
2021擭5寧朸擔 旛朰榐125丂嫄彔儉儖僫僂偺屆揟揑僒僀儗儞僩塮夋
1927 暷丂F丒W丒儉儖僫僂丂昡揰 [A]
儉儖僫僂偑僴儕僂僢僪偵彽偐傟偨嶣偭偨僒僀儗儞僩塮夋丅屆揟揑柤嶌偲偟偰柤崅偄丅揷幧偵廧傓恀柺栚側擾晇偑搒夛偐傜棃偨彈偺偲傝偙偵側傝丄彈偵嵈偝傟偰掑廼側嵢傪屛偱儃乕僩偐傜撍偒棊偲偟偰嶦偦偆偲偡傞偑丄悺慜偱巚偄偲偳傑傞丅嫲偔側偭偨嵢偼岦偙偆娸偵拝偔偲揹幵偵忔偭偰搒夛偵摝偘傞丅擾晇傕偦偺偁偲傪捛偄丄奨拞偱嵢偲拠捈傝偟丄怘帠偟偨傝梀墍抧偱梀傫偩傝偟偰妝偟偄帪娫傪夁偛偡丅壠偵婣傞搑拞丄棐偵側傝丄儃乕僩偑揮暍偟偰丄擾晇偼彆偐傞偑嵢偼峴曽晄柧偵側傝丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅帇妎揑昞尰偑慺惏傜偟偔丄栭偺屛斎傗奨暲傒側偳偺岝偲塭傪岻傒偵巊偭偨塮憸偑尒帠丅梀墍抧偺尪憐揑側忣宨傕報徾偵巆傞丅偙傟傜偑偡傋偰僙僢僩嶣塭偩偲偄偆偐傜嬃偒偩丅搒夛偺僔乕儞側偳偼儘働偱嶣傜傟偨偲偟偐巚偊側偄傎偳儕傾儖偩丅慡懱揑偵儊儖僿儞揑側偍壘榖傪巚傢偣傞暤埻婥偑昚偭偰偄傞丅擾晇偲搒夛偺彈偲偺埀堷偒傗斵偑嵢傪嶦偦偆偲偡傞僔乕儞偺埫偄嬞敆姶丄搒夛偺僔乕儞偺柧傞偄梲婥側暤埻婥丄棐偺僔乕儞偺峳傟嫸偆帺慠偺昤幨側偳丄偙偺塮夋偼偠偮偵曄壔偵晉傫偱偄傞丅揷幧偺晇晈傪墘偠傞偺偼僕儑乕僕丒僆僽儔僀僄儞偲僕儍僱僢僩丒僎僀僫乕丅僎僀僫乕偺悙乆偟偔惔慯側庒嵢傇傝偑側偐側偐壜垽偄丅
僞儖僠儏僼
1925 撈丂F丒W丒儉儖僫僂丂昡揰 [D]
儉儖僫僂偲偟偰偼寉偄戣嵽偺幒撪寑晽僒僀儗儞僩塮夋丅嬥帩偪偺榁恖戭偵廧傒崬傓壠惌晈偼梤偺旂傪偐傇偭偨楾偱丄庡恖偺堚嶻傪帺暘偺傕偺偵偟傛偆偲偟偰偄傞丅偦傟傪抦偭偨榁恖偺懛偼丄巌嵳傪憰偆婾慞幰僞儖僠儏僼偑媽壠偺庡恖偵庢傝擖偭偰嵿嶻傪閤偟庢傠偆偲偡傞偺傪庡恖偺嵢偑慾巭偡傞塮夋傪尒偣丄慶晝偵閤偝傟偰偄傞偙偲傪婥偯偐偣傛偆偲偡傞丄偲偄偆榖丅塮夋偺側偐偱忋塮偝傟傞塮夋丄偄傢備傞寑拞寑偱僞儖僠儏僼栶傪墘偠傞僄儈乕儖丒儎僯儞僌僗偺丄嫸婥傪偼傜傫偩丄溸偐傟偨傛偆側墘媄偑惁傑偠偄丅僒僀儗儞僩塮夋偼昞忣傗巇憪偑戝偘偝偩偑丄偦傟偵偵偟偰傕丄儎僯儞僌僗偺偙偺晄婥枴側摦嶌傗丄偝傜偵僈儅僈僄儖偺傛偆側壠惌晈偺憺乆偟偘側昞忣偼丄敆椡偑偁傝偡偓偰徫偄傪桿偆丅偙傟偼堦庬偺嫵孭寑偱偁傠偆偑丄婌寑塮夋偺傛偆偱傕偁傞丅
2021擭5寧朸擔 旛朰榐124丂傾儊儕僇偺屆偄僗儕儔乕塮夋
1932暷丂傾乕償傿儞僌丒僺僔僃儖丂昡揰 [C]
恖娫庪傝傪僥乕儅偵偟偨儂儔乕晽偺僗儕儔乕塮夋丅僴儞僞乕偺僕儑僄儖丒儅僋儕乕偑忔偭偰偄偨慏偑嵗徥偟偰屒搰偵棳傟拝偔丅斵偼僕儍儞僌儖偺側偐偱崑憇側娰傪尒偮偗傞丅偦偙偵偼摨偠偔慏偑擄攋偟偰偙偙偵扝傝拝偄偨旤彈僼僃僀丒儗僀偑偄傞丅娰偺庡恖偺儘僔傾婱懓偑斵傪娊懸偡傞偑丄斵偺庯枴偼恖娫庪傝偩偭偨丅儅僋儕乕偲儗僀偼娰偐傜曻傝弌偝傟丄儘僔傾婱懓傗巊梡恖偨偪偑媩傪傕偭偰捛偄偐偗傞側偐丄昁巰偵摝偘傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅
埮栭偺栚乮Eyes in the Night乯
1942暷丂僼儗僢僪丒僕儞僱儅儞丂昡揰 [D]
僼儗僢僪丒僕儞僱儅儞偺嵟弶婜偺娔撀嶌昳偩偑丄偁傑傝柺敀偔側偄丅夛幮偐傜偁偰偑傢傟偨婇夋偱庤偺巤偟傛偆偑側偐偭偨偺偐丅栍栚偺扵掋偑揋崙僗僷僀偺堿杁傪慾巭偡傞偲偄偆峳搨柍宮側榖丅扵掋栶偵偄偮傕偼埆栶偑懡偄僄僪儚乕僪丒傾乕僲儖僪丄挷嵏偺埶棅恖偵傾儞丒僴乕僨僀儞僌丄偦偺枀偵僪僫丒儕乕僪偲偄偆攝栶丅庒偔壜垽偄僨價儏乕偟偨偽偐傝偺僪僫丒儕乕僪傪尒傟傞偺偑廂妌丅
2021擭5寧朸擔 旛朰榐123丂僠僃僐偺怱偵嬁偔壒妝塮夋
1997 僠僃僐丒塸丒暓丂儎儞丒僗償僃儔乕僋乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰 [A]
 嫟嶻庡媊惌尃枛婜偺僾儔僴偱偺弌棃帠傪昤偄偨僠僃僐塮夋丅僾儔僴偱曢傜偡拞擭偺抝儘僂僇偼桪廏側僠僃儘憈幰偩偑丄彈岲偒偺撈恎庡媊幰偱丄僆乕働僗僩儔偐傜夝屬偝傟丄憭幃偺BGM傪墘憈偡傞妝巑偲偟偰惗寁傪棫偰偰偄傞丅斵偼桭恖偐傜棅傑傟丄幵傪攦偆嬥傎偟偝偵丄巕帩偪偺儘僔傾彈偲婾憰寢崶偡傞丅偩偑彈偼僪僀僣偵朣柦偟偰偟傑偄丄斵偼巆偝傟偨5嵨偺懅巕偲堦弿偵曢傜偡偼傔偵側傞丅儘僂僇偼埆愴嬯摤偟側偑傜尵梩偺捠偠側偄巕嫙偺悽榖傪偡傞偑丄偟偩偄偵擇恖偺偁偄偩偵恊巕偺鉐偑夎惗偊傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅巕嫙偲摦暔傪埖偭偨塮夋偼丄椳傪嫮梫偝傟傞偺偱寵偄側偺偩偑丄偦偆巚偄偮偮傕丄傗偼傝偙偆傕尒帠偵嶌傜傟傞偲姶摦偟偰偟傑偆丅抧壓揝偱巕嫙偲偼偖傟傞憓榖丄柍娤媞偺塮夋娰偱儘僔傾偺傾僯儊塮夋傪尒傞憓榖丄巕嫙偑崅擬傪弌偟偰娕昦偡傞憓榖丄巕嫙偺偨傔偵儘僔傾岅偑偱偒傞桭恖偵棅傫偱揹榖墇偟偵摱榖傪撉傫偱傕傜偆憓榖側偳丄怱傪懪偮僔乕儞偑偨偔偝傫偁傞丅廔斦丄價儘乕僪妚柦偑婲偙傝僠僃僐偼柉庡壔偝傟丄儘僔傾彈偼僾儔僴偵栠偭偰懅巕傪堷偒庢傝丄婣崙偡傞丅嬻峘偱偺儘僂僇偲巕嫙偺暿傟偺僔乕儞偼晄妎偵傕椳偑偙傏傟偨丅庡恖岞偑壒妝壠側偩偗偵丄僋儔僔僢僋偺嬋偑偁偪偙偪偵棳傟傞丅僪償僅儖僓乕僋偺尫妝巐廳憈嬋乽傾儊儕僇乿戞2妝復偑悘強偵棳傟偰帹偵巆傞丅嵵応偱壧傢傟傞乽庡偼巹偺梤帞偄乿傗乽傢偑曣偵嫵偊媼偄偟壧乿側偳偺壧嬋傕旤偟偄丅僄儞僨傿儞僌偺儔僼傽僄儖丒僋乕儀儕僢僋乮杮恖偺塮憸乯偑巜婗偡傞僠僃僐丒僼傿儖偵擖偭偰丄儘僂僇偑僗儊僞僫偺乽傢偑慶崙乿傪墘憈偡傞僔乕儞傕報徾怺偄丅偙傟偼1990擭5寧丄僾儔僴偺弔壒妝嵺偺偨傔40擭傇傝偵婣崙偟偨僋乕儀儕僢僋偑巗挕幧峀応偱壗枩恖傕偺巗柉傪慜偵峴側偭偨乽傢偑慶崙乿偺姶摦揑側墘憈傪嵞尰偟偨傕偺偱偁傠偆丅庡墘偺僠僃儘憈幰傪墘偢傞娔撀偺幚偺晝僘僨傿僯僃僋丒僗償僃儔乕僋偺镚乆偲偟偨墘媄傕偄偄偑丄5嵨偺巕嫙傾儞僪儗僀丒僴儕儌儞偑偐傢偄傜偟偔丄偠偮偵帺慠偱昞忣朙偐偩丅2恖偺惗妶偺側偐偱婲偙傞偝傑偞傑側僄僺僜乕僪偺昤幨偑慺惏傜偟偔丄僾儘僢僩偵偍偗傞嵶晹偺媗傔偺娒偝傪曗偭偰偄傞丅僆僗僇乕偺奜崙岅塮夋徿傪摼偨偺傕側傞傎偳偲巚傢偣傞丅
嫟嶻庡媊惌尃枛婜偺僾儔僴偱偺弌棃帠傪昤偄偨僠僃僐塮夋丅僾儔僴偱曢傜偡拞擭偺抝儘僂僇偼桪廏側僠僃儘憈幰偩偑丄彈岲偒偺撈恎庡媊幰偱丄僆乕働僗僩儔偐傜夝屬偝傟丄憭幃偺BGM傪墘憈偡傞妝巑偲偟偰惗寁傪棫偰偰偄傞丅斵偼桭恖偐傜棅傑傟丄幵傪攦偆嬥傎偟偝偵丄巕帩偪偺儘僔傾彈偲婾憰寢崶偡傞丅偩偑彈偼僪僀僣偵朣柦偟偰偟傑偄丄斵偼巆偝傟偨5嵨偺懅巕偲堦弿偵曢傜偡偼傔偵側傞丅儘僂僇偼埆愴嬯摤偟側偑傜尵梩偺捠偠側偄巕嫙偺悽榖傪偡傞偑丄偟偩偄偵擇恖偺偁偄偩偵恊巕偺鉐偑夎惗偊傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅巕嫙偲摦暔傪埖偭偨塮夋偼丄椳傪嫮梫偝傟傞偺偱寵偄側偺偩偑丄偦偆巚偄偮偮傕丄傗偼傝偙偆傕尒帠偵嶌傜傟傞偲姶摦偟偰偟傑偆丅抧壓揝偱巕嫙偲偼偖傟傞憓榖丄柍娤媞偺塮夋娰偱儘僔傾偺傾僯儊塮夋傪尒傞憓榖丄巕嫙偑崅擬傪弌偟偰娕昦偡傞憓榖丄巕嫙偺偨傔偵儘僔傾岅偑偱偒傞桭恖偵棅傫偱揹榖墇偟偵摱榖傪撉傫偱傕傜偆憓榖側偳丄怱傪懪偮僔乕儞偑偨偔偝傫偁傞丅廔斦丄價儘乕僪妚柦偑婲偙傝僠僃僐偼柉庡壔偝傟丄儘僔傾彈偼僾儔僴偵栠偭偰懅巕傪堷偒庢傝丄婣崙偡傞丅嬻峘偱偺儘僂僇偲巕嫙偺暿傟偺僔乕儞偼晄妎偵傕椳偑偙傏傟偨丅庡恖岞偑壒妝壠側偩偗偵丄僋儔僔僢僋偺嬋偑偁偪偙偪偵棳傟傞丅僪償僅儖僓乕僋偺尫妝巐廳憈嬋乽傾儊儕僇乿戞2妝復偑悘強偵棳傟偰帹偵巆傞丅嵵応偱壧傢傟傞乽庡偼巹偺梤帞偄乿傗乽傢偑曣偵嫵偊媼偄偟壧乿側偳偺壧嬋傕旤偟偄丅僄儞僨傿儞僌偺儔僼傽僄儖丒僋乕儀儕僢僋乮杮恖偺塮憸乯偑巜婗偡傞僠僃僐丒僼傿儖偵擖偭偰丄儘僂僇偑僗儊僞僫偺乽傢偑慶崙乿傪墘憈偡傞僔乕儞傕報徾怺偄丅偙傟偼1990擭5寧丄僾儔僴偺弔壒妝嵺偺偨傔40擭傇傝偵婣崙偟偨僋乕儀儕僢僋偑巗挕幧峀応偱壗枩恖傕偺巗柉傪慜偵峴側偭偨乽傢偑慶崙乿偺姶摦揑側墘憈傪嵞尰偟偨傕偺偱偁傠偆丅庡墘偺僠僃儘憈幰傪墘偢傞娔撀偺幚偺晝僘僨傿僯僃僋丒僗償僃儔乕僋偺镚乆偲偟偨墘媄傕偄偄偑丄5嵨偺巕嫙傾儞僪儗僀丒僴儕儌儞偑偐傢偄傜偟偔丄偠偮偵帺慠偱昞忣朙偐偩丅2恖偺惗妶偺側偐偱婲偙傞偝傑偞傑側僄僺僜乕僪偺昤幨偑慺惏傜偟偔丄僾儘僢僩偵偍偗傞嵶晹偺媗傔偺娒偝傪曗偭偰偄傞丅僆僗僇乕偺奜崙岅塮夋徿傪摼偨偺傕側傞傎偳偲巚傢偣傞丅2021擭5寧朸擔 旛朰榐122丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺4
1980 暓丒撈丂儀儖僩儔儞丒僞償僃儖僯僄丂昡揰 [D]
儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偑朣偔側傞2擭慜偺塮夋偱丄斵彈偼42嵨偩偑丄傑偩廩暘偵偒傟偄偩偟丄棊偪拝偄偨彈偺枺椡傪敪嶶偟偰偄傞丅偙傟偼婏柇側嬤枹棃塮夋丅儘働抧偼晄柧偩偑丄僀僊儕僗偺屆偄奨偺傛偆偩丅僥儗價嬊偺幮堳僴乕償僃僀丒僇僀僥儖偼栚偵僇儊儔傪怉偊崬傑傟傞丅彈棳嶌壠偺儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偼堛巘偐傜偁偲2廡娫偺柦偩偲愰崘偝傟傞丅僇僀僥儖偼僔儏僫僀僟乕傪捛偄偐偗丄偦偺栚偱尒偨斵彈偺塮憸偑丄巰傪慜偵偟偨恖娫偺巔偲偟偰僥儗價偱曻塮偝傟傞丅傗偑偰僇僀僥儖偲僔儏僫僀僟乕偼峴摦傪偲傕偵偡傞傛偆偵側傝丄怱傪捠偠崌傢偣傞丅斵傜偼嶳栰傪偝傑傛偄曕偄偨屻丄斵彈偑巰偵応強偲寛傔偨丄偐偮偰偺晇儅僢僋僗丒僼僅儞丒僔僪乕偑廧傓奀娸偺壠偵岦偆丅偦偙偱斵彈偼丄巰偺愰崘偼塕偱偁傝丄杮摉偼寬峃側懱偱偁傞偙偲傪抦傜偝傟傞偑丄寢嬊偼巰傪慖傇丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僥儗價偺儕傾儕僥傿斣慻傊偺斸敾偑崬傔傜傟偰偄傞偺偩傠偆偑丄偄偔傜嬤枹棃偲偼尵偊丄偁傑傝偵峳搨柍宮側榖偱偁傝丄堛巘偑姵幰偑閤偡偺偼忢婳傪堩偟偰偍傝丄斵彈偑嵟屻偵帺傜柦傪愨偮偺傕晄帺慠偩丅
僒儞丒僗乕僔偺彈
1982 暓丒撈丂僕儍僢僋丒儖乕僼傿僆丂昡揰 [C]
儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偺堚嶌丅偙傟偑岞奐偝傟偰1儠寧屻偵斵彈偼朣偔側偭偨丅戣柤偺僒儞丒僗乕僔偲偼僪僀僣偺媨揳偺偙偲偩偲巚偭偰偄偨偑丄偦偆偱偼側偔丄塮夋偵弌偰偔傞僷儕偺朣柦幰偨偪偑廤偆僇僼僃偺揦柤丅憡庤栶偺儈僔僃儖丒僺僢僐儕偼偙傟偑6夞栚偺僔儏僫僀僟乕偲偺嫟墘丅嶣塭偵擖傞悢儠寧慜偵懅巕偑帠屘巰偟偨偙偲偵傛傝丄僔儏僫僀僟乕偼嶣塭拞丄偄偮傕惛恄忬懺偑晄埨掕偩偭偨偲偄偆偑丄塮夋偐傜偼偁傑傝偦傫側暤埻婥偼姶偠傜傟側偄丅懡彮傗偮傟偑栚棫偮偑丄庒偄偙傠偺杍偺傆偭偔傜偟偨垽傜偟偄柺塭傪偄傑側偍偲偳傔偰偄傞丅恖尃妶摦壠偺僺僢僐儕偼撿暷崙戝巊偲偺柺択拞丄偲偮偤傫憡庤傪幩嶦偡傞丅岡棷偝傟偨僺僢僐儕偼柺夛偵棃偨嵢僔儏僫僀僟乕偵丄愴帪拞偺儀儖儕儞偲僷儕偱曢傜偟偨彮擭帪戙偺弌棃帠傪榖偡丅斵偺夁嫀偼岞敾偺朄掛偱傕暔岅傜傟傞丅儀儖儕儞偵廧傫偱偄偨儅僢僋僗乮彮擭帪戙偺僺僢僐儕乯偼儐僟儎恖偩偭偨偨傔晝恊偑僫僠撍寕戉偵傛偭偰嶦偝傟丄晝偺桭恖僄儖僓偲儈僔僃儖偺僂僃儖僫乕晇嵢偵堷偒庢傜傟傞丅斀懱惂怴暦傪敪峴偟偰偄偨儈僔僃儖偼恎曈偺婋尟傪嶡抦偟丄僄儖僓偲儅僢僋僗傪僷儕偵旔擄偝偣傞丅僫僀僩僋儔僽偱壧庤偲偟偰摥偒巒傔偨僄儖僓偼丄僫僠僗偵戇曔偝傟偨晇偺儈僔僃儖傪庍曻偝偣傞偨傔丄斵彈栚摉偰偱揦偵捠偭偰偄偨僪僀僣戝巊娰偺崅姱偵恎傪擟偣傞偑丒丒
丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅僔儏僫僀僟乕偼尰戙偺僔乕儞偵偍偗傞僺僢僐儕偺嵢偲夁嫀偺僔乕儞偵偍偗傞僄儖僓偺擇栶傪墘偠傞丅償傽僀僆儕儞偺撈憈偱壗搙傕棳傟傞乽朣柦偺壧乿偲偄偆嬋偺垼姶昚偆慁棩偑怱偵巆傞丅塮夋偲偟偰偼丄嬝棫偰偵傕偆傂偲偮偡偭偒傝偟側偄売強偑偁傞偟丄慡懱偲偟偰僙儞僠儊儞僞儕僘儉偺怓崌偄偑擹偄偺傕儅僀僫僗揰偩丅
2021擭5寧朸擔 旛朰榐121丂儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偵枺偣傜傟偰丂偦偺2
1929暷丂儅儖僐儉丒僙儞僩僋儗傾乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰 [D]
S.S.償傽儞丒僟僀儞尨嶌偺扵掋僼傽僀儘丒償傽儞僗傪庡恖岞偲偡傞儈僗僥儕乕彫愢僔儕乕僘偺堦嶌偺塮夋壔丅僒僀儗儞僩偐傜僩乕僉乕傊偺夁搉婜偺塮夋偱丄傕偲傕偲僒僀儗儞僩梡偲偟偰嶌傜傟偨傕偺偵傾僼儗僐偵傛偭偰戜帉傪悂偒崬傒丄僒僂儞僪斉偵偟偨傕偺丅壒妝偼偄偭偝偄擖偭偰偄側偄丅扵掋償傽儞僗傪墘偠傞偺偼僂傿儕傾儉丒僷僂僄儖丅恖婥偺梮傝巕僇僫儕儎偺嶦奞帠審偑婲偙傝丄柤扵掋償傽儞僗偑恀斊恖傪撍偒偲傔傞丅儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偑僇僫儕儎傪墘偠傞偑丄塮夋偑巒傑偭偰娫傕側偔嶦偝傟丄弌斣偼彮側偄丅僇僫儕儎偼帺暘偲娭學偺偁偭偨抦柤恖傪嫼敆偟偰嬥傪偣偟傔傛偆偲偡傞崻偭偐傜偺埆彈偱丄堿塭偵朢偟偔丄僽儖僢僋僗偺僐働僥傿僢僔儏側枺椡偑妶偐偝傟偰偄側偄丅
熕棊偺彈偺擔婰
1929撈丂G.W.僷僽僗僩乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰 [C]
乽僷儞僪儔偺敔乿偵懕偄偰儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偑僪僀僣偱僷僽僗僩娔撀偺傕偲偱庡墘偟偨僒僀儗儞僩塮夋丅塣柦偺偄偨偢傜偵傛偭偰晜捑偲棳揮偺摴傪曕傓彈僥傿儈傾儞偑庡恖岞丅僥傿儈傾儞偼桾暉側栻嵻巘偺壠偺柡偩偑丄宲曣偐傜慳傫偤傜傟丄尩奿側姶壔堾偵憲傜傟傞丅姶壔堾傪扙憱偟偨斵彈偼崅媺彥晈偵側傞偑丄晝恊偑朣偔側偭偰堚嶻偑擖傝丄偲偄偆嬶崌偵丄楇棊偲忋徃傪孞傝曉偡斵彈偺恖惗偑暔岅傜傟傞丅媡嫬偵偁偭偰傕鐥偟偔惗偒傞僥傿儈傾儞傪墘偢傞儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偼丄偄偮傕偲摨偠偔僉儏乕僩偱怓偭傐偔辶榝揑偩偑丄栶暱偺偣偄偱丄慜嶌偺儖儖偲斾傋偰丄偁偭偗傜偐傫偲偟偨孅戸偺側偄奐偗偭傄傠偘偺枺椡偵寚偗偰偄傞丅弌墘偡傞抝桪偱偼丄幹偺傛偆偵嗦嘞偦偆偱敄婥枴埆偄栻嵻揦偺揦堳偲丄柍婥椡偱擼揤婥側攲庉壠偺儃儞僋儔懅巕偑報徾偵巆傞丅偙偙偵偼丄儚僀儅乕儖帪戙枛婜丄僫僠僗戜摢捈慜偺僪僀僣偺梀嫽偵柧偗曢傟傞忋棳奒媺偺恖乆傊偺晽巋偑偆偐偑傢傟傞丅
2021擭5寧朸擔 旛朰榐120丂儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偵枺偣傜傟偰丂偦偺1
1928暷丂僴儚乕僪丒儂乕僋僗乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰 [B]
 僴儚乕僪丒儂乕僋僗庒偒擔偺僒僀儗儞僩塮夋丅償傿僋僞乕丒儅僋儔僌儗儞庡墘偩偑丄儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偑弶傔偰廳梫側栶偱弌墘偟偨塮夋偲偟偰傕桳柤丅慏忔傝偺儅僋儔僌儗儞偼婑峘偡傞奺抧偺峘偱庰応偵擖傝怹偭偰彈偲梀傇偺傪惗偒峛斻偵偟偰偄傞丅斵偼彈偺偙偲偱摨偠慏忔傝偺儘僶乕僩丒傾乕儉僗僩儘儞僌偲寲壾偟偨偡偊丄愗偭偰傕愗傟偸屌偄桭忣傪寢傇丅儅僋儔僌儗儞偼傾儉僗僥儖僟儉丄儕僆僨僕儍僱僀儘丄僒儞儁僪儘偲峘傪弰傝丄儅儖僙僀儐偵拝偄偨偲偙傠偱僒乕僇僗偺彈寍恖偺儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偲弰傝夛偄堦栚崨傟偟丄慏偐傜壓傝偰斵彈偲堦弿偵廧傕偆偲偡傞丅儅僋儔僌儗儞偼屻擭偺僕儑儞丒僼僅乕僪塮夋偱偼梕杄夽執側懚嵼姶偺偁傞拞擭傗榁恖傪墘偠偨偑丄偙偺塮夋偱偼庒乆偟偄僴儞僒儉側梕巔傪斺業偟偰偄傞丅弌墘偡傞彈桪偺側偐偱丄儃僽僇僢僩偺儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偺枺椡偑旘傃敳偗偰偄傞丅斵彈偑尒悽暔偱崅偄偼偟偛偺忋偐傜彫偝側僾乕儖偵旘傃崬傓僔乕儞偼傂偲偒傢報徾怺偄丅偙偺塮夋偵偼儂乕僋僗傜偟偝偑廩枮偟偰偄傞丅偡偱偵偙傫側弶婜偺偙傠偐傜丄寲壾傪捠偟偰寢偽傟傞抝摨巑偺桭忣偲偄偆僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺僥乕儅偼偐偨偪傪側偟偰偄偨偺偩丅朚戣偺乽峘乆偵彈偁傝乿乮尨戣偼 A Girl in Every Port乯偼側偐側偐枴傢偄怺偄戣柤偩丅偙偺尵梩偼惉岅偵側偭偰偄傞偑丄偙偺塮夋偵傛偭偰恖岥偵鋂鄑偝傟傞傛偆偵側偭偨偺偩傠偆偐丄偦傟偲傕偡偱偵惉岅偲偟偰偁偭偨傕偺傪朚戣偵偟偨偺偩傠偆偐丠
僴儚乕僪丒儂乕僋僗庒偒擔偺僒僀儗儞僩塮夋丅償傿僋僞乕丒儅僋儔僌儗儞庡墘偩偑丄儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偑弶傔偰廳梫側栶偱弌墘偟偨塮夋偲偟偰傕桳柤丅慏忔傝偺儅僋儔僌儗儞偼婑峘偡傞奺抧偺峘偱庰応偵擖傝怹偭偰彈偲梀傇偺傪惗偒峛斻偵偟偰偄傞丅斵偼彈偺偙偲偱摨偠慏忔傝偺儘僶乕僩丒傾乕儉僗僩儘儞僌偲寲壾偟偨偡偊丄愗偭偰傕愗傟偸屌偄桭忣傪寢傇丅儅僋儔僌儗儞偼傾儉僗僥儖僟儉丄儕僆僨僕儍僱僀儘丄僒儞儁僪儘偲峘傪弰傝丄儅儖僙僀儐偵拝偄偨偲偙傠偱僒乕僇僗偺彈寍恖偺儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偲弰傝夛偄堦栚崨傟偟丄慏偐傜壓傝偰斵彈偲堦弿偵廧傕偆偲偡傞丅儅僋儔僌儗儞偼屻擭偺僕儑儞丒僼僅乕僪塮夋偱偼梕杄夽執側懚嵼姶偺偁傞拞擭傗榁恖傪墘偠偨偑丄偙偺塮夋偱偼庒乆偟偄僴儞僒儉側梕巔傪斺業偟偰偄傞丅弌墘偡傞彈桪偺側偐偱丄儃僽僇僢僩偺儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偺枺椡偑旘傃敳偗偰偄傞丅斵彈偑尒悽暔偱崅偄偼偟偛偺忋偐傜彫偝側僾乕儖偵旘傃崬傓僔乕儞偼傂偲偒傢報徾怺偄丅偙偺塮夋偵偼儂乕僋僗傜偟偝偑廩枮偟偰偄傞丅偡偱偵偙傫側弶婜偺偙傠偐傜丄寲壾傪捠偟偰寢偽傟傞抝摨巑偺桭忣偲偄偆僴儚乕僪丒儂乕僋僗偺僥乕儅偼偐偨偪傪側偟偰偄偨偺偩丅朚戣偺乽峘乆偵彈偁傝乿乮尨戣偼 A Girl in Every Port乯偼側偐側偐枴傢偄怺偄戣柤偩丅偙偺尵梩偼惉岅偵側偭偰偄傞偑丄偙偺塮夋偵傛偭偰恖岥偵鋂鄑偝傟傞傛偆偵側偭偨偺偩傠偆偐丄偦傟偲傕偡偱偵惉岅偲偟偰偁偭偨傕偺傪朚戣偵偟偨偺偩傠偆偐丠恖惗偺岊怘
1928暷丂僂傿儕傾儉丒僂僃儖儅儞乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰 [B]
儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偺弶庡墘嶌丅僒僀儗儞僩塮夋偱丄嫟墘偼僂僅乕儗僗丒價傾儕乕偲儕僠儍乕僪丒傾乕儗儞丅屒帣堾偱堢偭偨僽儖僢僋僗偼梴巕偵擖偭偨壠偺僄儘恊晝偵庤崬傔偵偝傟偦偆偵側傝丄儔僀僼儖偱寕偪嶦偡丅偦偙偵晜楺幰偺庒幰傾乕儗儞偑傗偭偰棃傞丅帠忣傪挳偄偨斵偼斵彈偵摨忣偟丄堦弿偵僇僫僟偵摝偘傛偆偲桿偆丅抝偺巕偵曄憰偟偨斵彈偼斵偲偲傕偵摝憱偟丄壿暔楍幵偵旘傃忔傞偑丄偦偙偵偼慡崙傪棳傟曕偔晜楺幰偺堦抍偑偄傞丅儂乕儃乕丒僌儖乕僾偺恊暘價傾儕乕偼僽儖僢僋僗偑彈偱偁傞偙偲傪尒敳偒丄帺暘偺彈偵偟傛偆偲偡傞丅偦偙偵儖僀乕僘傪嶦恖斊偲偟偰捛偄偐偗傞寈嶡戉偑敆傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僴儚乕僪丒儂乕僋僗娔撀偺乽婏寙僷儞僠儑乿傊偺庡墘偱抦傜傟傞屄惈攈攐桪價傾儕乕偼丄偙偙偱偼偄傢備傞僌僢僪丒僶僢僪丒僈僀傪墘偠偰偍傝丄嵟屻偵媊嫚怱傪敪婗偟偰僽儖僢僋僗偲傾乕儗儞偺摝朣傪彆偗丄寈嶡偵寕偨傟偰巰偸丅僽儖僢僋僗偼廔巒捁懪偪朮傪偐傇偭偰抝偺巕偺偙偺奿岲傪偟偰偄傞偑丄廔斦偵帄偭偰彈偺奿岲偵側傝丄僩儗乕僪儅乕僋偺儃僽僇僢僩傪斺業偡傞丅僂僃儖儅儞娔撀傜偟偔丄幮夛栤戣偑棈傔傜傟偨塮夋偵側偭偰偄傞偑丄慡懱偲偟偰偼徫偄偑嶶傝偽傔傜傟偨椙幙偺屸妝嶌偵巇忋偑偭偰偄傞丅
2021擭5寧朸擔 旛朰榐119丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪偝傜偵孈傝婲偙偡丂偦偺3
1944暷丂僕乕儞丒僱僌儗僗僐丂昡揰 [B]
埲慜尒偰偄傞偼偢偩偑丄撪梕傪妎偊偰偄側偄偺偱嵞尒丅尨嶌偼僗僷僀彫愢嶌壠僄儕僢僋丒傾儞僽儔乕偺乽僨傿儈僩儕僆僗偺娀乿偱丄偙傟傕偼傞偐愄偵撉傫偱偄傞偑丄嶖憥偟偨僗僩乕儕乕偩偭偨偙偲埲奜丄拞恎偼婰壇偐傜敳偗棊偪偰偄傞丅庡墘偼僪僀僣偐傜朣柦偟偨堎怓攐桪僺乕僞乕丒儘乕儗丅僩儖僐偺奀娸偵僨傿儈僩儕僆僗偲偄偆抝偺巰懱偑懪偪忋偑傞丅僨傿儈僩儕僆僗偼椻崜側埆搣偱丄埆鐓側巇帠偵庤傪愼傔偰偍傝丄愴帪拞偼僗僷僀偲偟偰傕壱偄偱偄偨偲偄偆偙偲傪抦偭偨椃峴拞偺嶌壠僺乕僞乕丒儘乕儗偼丄嫽枴傪堷偐傟偰丄僊儕僔儍丄僀僞儕傾丄僼儔儞僗偲丄偦偺抝偺懌愓傪捛偄偐偗傞丅儘乕儗偺峴偔愭乆偵惓懱晄柧偺抝僔僪僯乕丒僌儕乕儞僗僩儕乕僩偑偮偒傑偲偄丄傗偑偰巰傫偩偼偢偺僨傿儈僩儕僆僗乮僓僢僇儕乕丒僗僐僢僩乯偑巔傪尰偡丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅乽儅儖僞偺戦乿乽僇僒僽儔儞僇乿偱偍撻愼傒偺儘乕儗偲僌儕乕儞僗僩儕乕僩偺僐儞價偼撈摿偺夦偟偘側暤埻婥傪忴偟弌偟偰偍傝丄婏柇側懚嵼姶偑墶堨偟偰偄傞丅
惷偐偵偮偄偰棃偄
1949暷丂儕僠儍乕僪丒僼儔僀僔儍乕丂昡揰 [C]
偙偺塮夋傕尒偰偄傞偆偪偵丄傏傫傗傝偲埲慜尒偨偙偲偑偁傞偺傪巚偄偩偟偨丅塉偺擔偵斊峴傪廳偹傞楢懕嶦恖婼傪捛偆孻帠僂傿儕傾儉丒儔儞僨傿僈儞偑丄彈惈嶨帍婰幰僪儘僔乕丒僷僩儕僢僋偺嫤椡傪摼偰斊恖傪捛偄媗傔傞僒僀僐丒僗儕儔乕丅柍柤偺攐桪傪巊偭偨B媺偺彫昳偩偑丄偗偭偙偆柺敀偄丅寈嶡偼栚寕徹尵偵増偭偰斊恖偵帡偣偨摍恎戝偺儅僱僉儞恖宍傪嶌傞偑丄偦傟偑晄婥枴側岠壥傪忋偘偰偄傞丅
2021擭5寧朸擔 旛朰榐118丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪偝傜偵孈傝婲偙偡丂偦偺2
1951暷丂僕儑儞丒儀儕乕丂昡揰 [B]
懡偔偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偵庡墘偟偨岲娍僕儑儞丒僈乕僼傿乕儖僪偼愒庪傝偱徹尵傪嫅斲偟偰僽儔僢僋儕僗僩偵嵹傝丄幐堄偺偆偪偵庒巰偵偟偨丅偙傟偼僈乕僼傿乕儖僪偑庡墘偟偨嵟屻偺嶌昳丅嬥傪嫮扗偟偨僠儞僺儔嫮搻僈乕僼傿乕儖僪偼寈姱偵捛傢傟偰僾乕儖偵摝偘崬傒丄僔僃儕乕丒僂傿儞僞乕僘偲抦傝崌偭偰斵彈偺堦壠偑廧傓傾僷乕僩偵峴偔丅斵偼堦壠傪嫼敆偟偰偦偺傾僷乕僩偵棫偰偙傕傝丄傎偲傏傝偑椻傔傞偺傪懸偮丅榖偺棳傟偼僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩庡墘偺乽昁巰偺摝朣幰乿傪憐婲偝偣傞丅垽忣傪抦傜偢偵堢偭偨彫埆搣傪尒帠偵墘偠傞僈乕僼傿乕儖僪偑偄偄丅斵偵傎偺偐側楒怱傪書偔偑嵟屻偵傗傓傪偊偢斵傪幩嶦偡傞僂傿儞僞乕僗傕彈偺斶偟傒傪墘偠偰慺惏傜偟偄丅媟杮僟儖僩儞丒僩儔儞儃丄嶣塭僕僃乕儉僗丒僂僅儞丒僴僂偲堦棳僗僞僢僼偑嶲壛偟偰偄傞丅
僒僀僪丒僗僩儕乕僩
1950暷丂傾儞僜僯乕丒儅儞丂昡揰 [C]
傾儞僜僯乕丒儅儞弶婜偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅梄曋攝払晇偺僼傽乕儕乕丒僌儗儞僕儍乕偼傆偲偟偨弌棃怱偱嵢偺弌嶻旓梡偵偁偰傞偨傔曎岇巑帠柋強偱嬥傪搻傓丅斵偼嵢僉儍僔乕丒僆僪僱儖偵愢摼偝傟偰搻傫偩嬥傪曉偦偆偲偡傞偑丄偦偺嬥偼僶乕偺僶乕僥儞僟乕偵帩偪摝偘偝傟傞丅扵偟摉偰偨僶乕僥儞僟乕偼嶦偝傟偰偄偨丅偄偭傐偆偱寈嶡偼旤恖嬊偱抝傪嫮惪偭偰偄偨彈偑嶦偝傟偨帠審傪憑嵏偟偰偄傞丅偙偺2偮偺僗僩乕儕乕偑暲峴偟偰昤偐傟丄搑拞偱廳側傝崌偆偑丄2偮偺帠審偺娭楢偑傛偔暘偐傜側偄偟丄彈傪嶦偟偨偺偑扤偐傕敾慠偲偟側偄丅榖偺棳傟偼偗偭偙偆柺敀偟丄僒僗儁儞僗傕偁傞偺偩偑丅
2021擭5寧朸擔 旛朰榐117丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪偝傜偵孈傝婲偙偡丂偦偺1
1948暷丂僟僌儔僗丒僒乕僋丂昡揰 [B]
 儊儘僪儔儅偺嫄彔僟僌儔僗丒僒乕僋偑庤偑偗偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺1杮丅乽埥傞悽偺弌棃帠乿側偳偺僐儊僨傿彈桪偲偟偰抦傜傟傞僋儘乕僨僢僩丒僐儖儀乕儖偺庡墘丄偄偮傕偼婥偺偄偄慞恖栶傪墘偠傞僪儞丒傾儊僠乕偺埆栶側偳丄偄傠傫側揰偱堎怓偺塮夋偩丅怮戜幵偺怮戜偱栚偞傔偨僐儖儀乕儖偑愨嫨偡傞僔乕儞偱枊偑奐偔丅斵彈偼帺暘偑楍幵偵忔偭偨婰壇偑側偄丅僐儖儀乕儖偺晇偺傾儊僠乕偼垽恖偵擖傟崬傒丄嵢偺嵿嶻傪庤偵擖傟傞偨傔丄斵彈偵嵜柊栻傪堸傑偣偰埫帵傪偐偗丄柌梀昦偵娮偭偨傛偆偵尒偣偐偗丄帺嶦偵捛偄崬傕偆偲偟偰偄傞丅楍幵偱抦傝崌偭偨儘僶乕僩丒僇儈儞僌僗偼斵彈傪彆偗偰恀憡傪扵傠偆偲偡傞丅塮夋偲偟偰偼僒僗儁儞僗僼儖側揥奐偱尒墳偊偑偁傝丄僐儖儀乕儖偺揁戭偺奒抜僔乕儞傗怮幒偺憢曈偺僔乕儞側偳偺堿塭怺偄嶣塭偑嫽庯傪偦偦傞丅傾儊僠乕偺忣晈偵暞偡傞僿僀僛儖丒僽儖僢僋僗偼柍柤偩偑側偐側偐枺椡偵晉傫偩埆彈傇傝傪尒偣偰偄傞丅
儊儘僪儔儅偺嫄彔僟僌儔僗丒僒乕僋偑庤偑偗偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺1杮丅乽埥傞悽偺弌棃帠乿側偳偺僐儊僨傿彈桪偲偟偰抦傜傟傞僋儘乕僨僢僩丒僐儖儀乕儖偺庡墘丄偄偮傕偼婥偺偄偄慞恖栶傪墘偠傞僪儞丒傾儊僠乕偺埆栶側偳丄偄傠傫側揰偱堎怓偺塮夋偩丅怮戜幵偺怮戜偱栚偞傔偨僐儖儀乕儖偑愨嫨偡傞僔乕儞偱枊偑奐偔丅斵彈偼帺暘偑楍幵偵忔偭偨婰壇偑側偄丅僐儖儀乕儖偺晇偺傾儊僠乕偼垽恖偵擖傟崬傒丄嵢偺嵿嶻傪庤偵擖傟傞偨傔丄斵彈偵嵜柊栻傪堸傑偣偰埫帵傪偐偗丄柌梀昦偵娮偭偨傛偆偵尒偣偐偗丄帺嶦偵捛偄崬傕偆偲偟偰偄傞丅楍幵偱抦傝崌偭偨儘僶乕僩丒僇儈儞僌僗偼斵彈傪彆偗偰恀憡傪扵傠偆偲偡傞丅塮夋偲偟偰偼僒僗儁儞僗僼儖側揥奐偱尒墳偊偑偁傝丄僐儖儀乕儖偺揁戭偺奒抜僔乕儞傗怮幒偺憢曈偺僔乕儞側偳偺堿塭怺偄嶣塭偑嫽庯傪偦偦傞丅傾儊僠乕偺忣晈偵暞偡傞僿僀僛儖丒僽儖僢僋僗偼柍柤偩偑側偐側偐枺椡偵晉傫偩埆彈傇傝傪尒偣偰偄傞丅柧擔偵暿傟偺愙暙傪
1950暷丂僑乕僪儞丒僟僌儔僗丂昡揰 [C]
僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕庡墘偺斊嵾僗儕儔乕丅塮夋偼朄掛応柺偐傜巒傑傞丅旐崘惾偵偄傞斊嵾偵娭學偟偨彈丄寈姱丄曎岇巑側偳偺徹尵偵傛偭偰丄僉儍僌僯乕偺峴忬偑岅傜傟傞丄偲偄偆庯岦丅擖崠偟偰偄偨嫢埆斊僉儍僌僯乕偼扙崠偵惉岟偟丄忣晈僶乕僶儔丒儁僀僩儞偺傾僷乕僩傪崻忛偵丄埆摽寈姱儚乕僪丒儃儞僪偲慻傫偱嫮搻傪孞傝曉偡丅斵偼忋棳奒媺偺彈偵崨傟偰斵彈偲崅旘傃偟傛偆偲偡傞偑丄忣晈偵寕偨傟偰巰偸丅拞擭偵側偭偨僉儍僌僯乕偼丄彈傪暯婥偱墸偭偨傝偟偰杮椞傪敪婗偡傞偑丄庒偄偙傠偺僉價僉價偟偨摦偒偵寚偗偰偄傞丅傑偨僗僩乕儕乕揥奐偵偄傑偄偪儊儕僴儕偑側偔丄慜嶌偺儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏娔撀乽敀擬乿偵斾傋傞偲丄敆椡晄懌偼斲傔側偄丅娔撀偺椡検偺嵎偐丅
2021擭4寧
2021擭4寧朸擔 旛朰榐116丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺3
1974暓丂僼儔儞僔僗丒僕儘乕丂昡揰 [C]
埆摽曎岇巑儈僔僃儖丒僺僐儕偲丄儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕丄儅乕僔儍丒僑儉僗僇偺巓枀偑慻傫偱丄曐尟嬥嶦恖傪孞傝曉偡偲偄偆丄堹阹偱僌儘僥僗僋側塮夋丅曎岇巑偑寁夋傪棫偰丄巓枀偺偳偪傜偐偑嬥帩偪偺抝偲寢崶偟丄晇傪嶦偟偰曐尟嬥傪偣偟傔傞丅巰懱偺張棟朄偼巁旲傪偒傢傔傞丅巰懱傪僶僗僞僽偵擖傟偰棸巁傪拲偓丄僪儘僪儘偵側偭偨塼懱傪僶働僣偵媯傒擖傟丄掚偵寠傪孈偭偰偦偙偵杽傔傞僔乕儞偺徻嵶側昤幨偼堿嶴偒傢傑傝側偄丅恀惈偺埆彈傪墘偠傞僔儏僫僀僟乕偼巚偄偺傎偐塭偑敄偔丄偁傑傝惛嵤偑側偄丅
尷傝側偔垽偵擱偊偰
1976暓撈埳丂僺僄乕儖丒僌儔僯僄亖僪僼僃乕儖丂昡揰 [D]
偙偺捖晠側擔杮戣偵偼鐒堈偡傞乮尨戣偼乽憢曈偺彈乿乯丅儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偲僼傿儕僢僾丒僲儚儗偼慜擭偵嶌傜傟偨寙嶌乽捛憐乿偱尒帠側嫟墘傇傝傪尒偣偰偄偨偑丄偙偺塮夋偱偺僲儚儗偼榚栶偵揙偟偰偄傞丅30擭戙敿偽丄孯帠撈嵸惌尃偵傛傞夲尩椷壓偺僊儕僔儍丅僀僞儕傾奜岎姱偺嵢儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偼丄姱寷偵捛傢傟偰晹壆偵偵擡傃崬傫偩斀惌晎嫟嶻庡媊妚柦壠偲楒偵棊偪傞丅斵彈偼媽抦偺僼傿儕僢僾丒僲儚儗偺彆偗傪摼偰丄斵傪崙奜摝朣偝偣傛偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偦傟偐傜悢10擭屻丄僔儏僫僀僟乕偲偦偭偔傝偺庒偄彈惈偑晝曣偺嵀愓傪偨偳傞偨傔僊儕僔儍傪朘傟傞丅偦傟偼僔儏僫僀僟乕偲妚柦壠偺堚帣偩偭偨丄偲偄偆屻擔択偑嵟屻偵晅偗壛偊傜傟傞丅偙偆彂偔偲柺敀偦偆偩偑丄幚嵺偵偼儊儕僴儕偵寚偗丄嬞敆姶偑朢偟偔丄塮夋揑嫽庯偼敄偄丅
2021擭4寧朸擔 旛朰榐115丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺2
1970暓丂僋儘乕僪丒僜乕僥丂昡揰 [C]
 嵢偲暿嫃偟丄垽恖偲偲傕偵夁偛偟偰偄傞抝偑丄幵傪塣揮拞丄帠屘傪婲偙偡丅幵偐傜曻傝弌偝傟偰憪傓傜偵墶偨傢偭偰偄傞抝偑丄偙傟傑偱偺惗奤傪夞憐偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅垽恖偵儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕丄抝偵儈僔僃儖丒僺僢僐儕丄嵢偵儗傾丒儅僢僙儕偑暞偡傞丅僔儏僫僀僟乕偼僺僢僐儕偲悢懡偔嫟墘偟偰偄傞偑丄偙傟偼嫟墘戞1嶌丅朻摢丄僶僗僞僆儖傪懱偵姫偄偰僞僀僾儔僀僞乕傪扏偄偰偄傞斵彈偺巔偑報徾偵巆傞丅
嵢偲暿嫃偟丄垽恖偲偲傕偵夁偛偟偰偄傞抝偑丄幵傪塣揮拞丄帠屘傪婲偙偡丅幵偐傜曻傝弌偝傟偰憪傓傜偵墶偨傢偭偰偄傞抝偑丄偙傟傑偱偺惗奤傪夞憐偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅垽恖偵儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕丄抝偵儈僔僃儖丒僺僢僐儕丄嵢偵儗傾丒儅僢僙儕偑暞偡傞丅僔儏僫僀僟乕偼僺僢僐儕偲悢懡偔嫟墘偟偰偄傞偑丄偙傟偼嫟墘戞1嶌丅朻摢丄僶僗僞僆儖傪懱偵姫偄偰僞僀僾儔僀僞乕傪扏偄偰偄傞斵彈偺巔偑報徾偵巆傞丅梉側偓
1972暓丂僋儘乕僪丒僜乕僥丂昡揰 [B]
儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偼夝懱嬈幰偺僀償丒儌儞僞儞偲憡巚憡垽偺摨惐惗妶傪憲偭偰偄傞偑丄偦偙偵偐偮偰偺楒恖偱僐儈僢僋嶌壠偺僒儈乕丒僼儗僀偑尰傟丄楒怱偑嵞擱偡傞丅儌儞僞儞偼昁巰偵斵彈傪偮側偓巭傔傛偆偲偡傞偑丄斵彈偺怱偼梙傟摦偔丅傗偑偰斵傜3恖偼偍屳偄偵憡庤傪嫋梕偡傞婏柇側嶰妏娭學傪宍惉偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅儌儞僞儞偼梲婥偱惛椡揑側抝丄僼儗僀偼暔惷偐偱撪徣揑側抝偲昤偒暘偗傜傟偰偄傞丅僔儏僫僀僟乕偑偠偮偵旤偟偔嶣傜傟偰偄傞丅廔斦丄斵彈偼塤塀傟偟偰偟傑偆偑丄巆偝傟偨2恖偺抝偑拠椙偔僇乕僪僎乕儉偵嫽偠偰偄傞偲偙傠偵傂傚偭偙傝巔傪尰偡丅偦偺僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞偑報徾怺偄丅
2021擭4寧朸擔 旛朰榐114丂僗僥傿乕償丒儕乕償僗庡墘僀僞儕傾惢乻寱偲杺朄乼塮夋
1958埳丂僺僄僩儘丒僼儔儞僠乕僔丂昡揰 [A]
 拞妛偐傜崅峑偵偐偗偰偺偙傠丄僗僥傿乕償丒儕乕償僗偼変偑垽偡傞僸乕儘乕偺傂偲傝偩偭偨丅偙偺塮夋偼丄摉帪偼尒摝偟偨偑丄儕乕償僗偺婰擮偡傋偒弶庡墘嶌丅儃僨傿價儖丒僐儞僥僗僩偺僠儍儞僺僆儞偩偑攐桪偲偟偰偼柍柤偩偭偨儕乕償僗偼丄僀僞儕傾偵屇偽傟偰偙偺塮夋偵弌墘偟丄堦桇丄僗僂僅乕僪仌僒儞僟儖塮夋丄偄傢備傞乽寱偲杺朄乿塮夋偺僗乕僷乕僗僞乕偵側偭偨丅屆戙僊儕僔儍帪戙丄塸梇僿儔僋儗僗偼墹埵宲彸栤戣偵姫偒崬傑傟丄墹埵偺徹偟偱偁傞墿嬥偺梤傪憑偡椃偵弌傞丅儕乕償僗偺嬝崪棽乆偨傞巿懱偑夋柺傪埑搢偟丄僿儔僋儗僗偲寢偽傟傞墹彈僔儖償傽丒僐僔僫傕梔墣側枺椡傪敪嶶偡傞丅
拞妛偐傜崅峑偵偐偗偰偺偙傠丄僗僥傿乕償丒儕乕償僗偼変偑垽偡傞僸乕儘乕偺傂偲傝偩偭偨丅偙偺塮夋偼丄摉帪偼尒摝偟偨偑丄儕乕償僗偺婰擮偡傋偒弶庡墘嶌丅儃僨傿價儖丒僐儞僥僗僩偺僠儍儞僺僆儞偩偑攐桪偲偟偰偼柍柤偩偭偨儕乕償僗偼丄僀僞儕傾偵屇偽傟偰偙偺塮夋偵弌墘偟丄堦桇丄僗僂僅乕僪仌僒儞僟儖塮夋丄偄傢備傞乽寱偲杺朄乿塮夋偺僗乕僷乕僗僞乕偵側偭偨丅屆戙僊儕僔儍帪戙丄塸梇僿儔僋儗僗偼墹埵宲彸栤戣偵姫偒崬傑傟丄墹埵偺徹偟偱偁傞墿嬥偺梤傪憑偡椃偵弌傞丅儕乕償僗偺嬝崪棽乆偨傞巿懱偑夋柺傪埑搢偟丄僿儔僋儗僗偲寢偽傟傞墹彈僔儖償傽丒僐僔僫傕梔墣側枺椡傪敪嶶偡傞丅僿儔僋儗僗偺媡廝
1959埳丂僺僄僩儘丒僼儔儞僠乕僔丂昡揰 [A]
拞妛惗偺偙傠偩偭偨偲巚偆偑丄側傫偺婥側偟偵尒偨偙偺塮夋偱弶傔偰僗僥乕償丒儕乕償僗偺枺椡偵偼傑傝丄偦偺屻丄乽僶僋僟僢僪偺搻懐乿傗乽儅儔僜儞偺愴偄乿傗乽億儞儁僀嵟屻偺擔乿側偳丄儕乕償僗庡墘偺乽寱偲杺朄乿塮夋傪棫偰懕偗偵尒偨丅偙傟偼慜嶌乽僿儔僋儗僗乿偺懕曇丅僿儔僋儗僗偼慜嶌偱楒偵棊偪偨僔儖償傽丒僐僔僫偲寢崶偟偨偑丄慏偺椃偱忋棨偟偨搰偱愹偺悈傪堸傒丄婰壇偲椡傪幐偭偰搰傪帯傔傞杺彈偺偲傝偙偵側傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅夦椡傪嬱巊偟偰儔僀僆儞傗嫄恖偲愴偄丄埆娍傪廟嶶傜偡儕乕償僗偺桬巔偵摡慠偲側傞丅
2021擭3寧
2021擭3寧朸擔 旛朰榐113丂僪僀僣愴慜攈偺嫄彔僷僽僗僩偺2嶌
1929撈丂G.W.僷僽僗僩丂昡揰 [A]
 僴儕僂僢僪偺僼儔僢僷乕彈桪儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偑僪僀僣偵彽偐傟偰庡墘偟偨僒僀儗儞僩塮夋丅僸儘僀儞偺儖儖傪墘偠偨斵彈偼戝偒側媟岝傪梺傃丄儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偼栶柤偺儖儖偲偲傕偵丄僼傽儉丒僼傽僞乕儖偺晄柵偺僔儞儃儖偲偟偰塮夋巎偵偦偺柤偑崗傒崬傑傟偨丅応枛偺梮傝巕儖儖偺攇鄍枩忎偺暔岅偑捲傜傟傞丅儖儖偼嬥帩偪偺垽恖傪庤嬍偵偲偭偰寢崶偵偙偓偮偒丄晇偺懅巕傪桿榝偟偨傝丄婱懓偺晇恖偲恊偟偄娭學傪寢傫偩傝偟偨偁偘偔丄晇嶦偟偺嵾偱楽崠偵擖傞偑丄扙憱偟偰僒乕僇僗偺寍恖傪偨傜偟偙傒搎攷慏偵愽傝崬傓丅偩偑傑偨傕傗潌傔帠傪堷偒婲偙偟偰儘儞僪儞偵偵摝偘丄楇棊偟偰奨彥偲側傝愗傝楐偒僕儍僢僋偲弌夛偆丅儖儖偼抝傪攋柵偝偣傞帺桼杬曻側埆彈偩偑丄揤恀啵枱偱孅戸偑側偄丅斵彈偺側偐偵偼丄偟偨偨偐偝偲壜垽偝丄堹摖偲弮忣丄旕忣偲巚偄傗傝偑摨嫃偟偰偍傝丄僩儗乕僪儅乕僋偺抁敮儃僽僇僢僩丄偟側傗偐側懱偺慄丄僐働僥傿僢僔儏側昞忣傗巇憪偼丄抝偺楎忣傪偦偦傜偢偵偼偍偐側偄丅偙偺塮夋偵偼偦傫側儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偺枺椡偑墶堨偟偰偄傞丅
僴儕僂僢僪偺僼儔僢僷乕彈桪儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偑僪僀僣偵彽偐傟偰庡墘偟偨僒僀儗儞僩塮夋丅僸儘僀儞偺儖儖傪墘偠偨斵彈偼戝偒側媟岝傪梺傃丄儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偼栶柤偺儖儖偲偲傕偵丄僼傽儉丒僼傽僞乕儖偺晄柵偺僔儞儃儖偲偟偰塮夋巎偵偦偺柤偑崗傒崬傑傟偨丅応枛偺梮傝巕儖儖偺攇鄍枩忎偺暔岅偑捲傜傟傞丅儖儖偼嬥帩偪偺垽恖傪庤嬍偵偲偭偰寢崶偵偙偓偮偒丄晇偺懅巕傪桿榝偟偨傝丄婱懓偺晇恖偲恊偟偄娭學傪寢傫偩傝偟偨偁偘偔丄晇嶦偟偺嵾偱楽崠偵擖傞偑丄扙憱偟偰僒乕僇僗偺寍恖傪偨傜偟偙傒搎攷慏偵愽傝崬傓丅偩偑傑偨傕傗潌傔帠傪堷偒婲偙偟偰儘儞僪儞偵偵摝偘丄楇棊偟偰奨彥偲側傝愗傝楐偒僕儍僢僋偲弌夛偆丅儖儖偼抝傪攋柵偝偣傞帺桼杬曻側埆彈偩偑丄揤恀啵枱偱孅戸偑側偄丅斵彈偺側偐偵偼丄偟偨偨偐偝偲壜垽偝丄堹摖偲弮忣丄旕忣偲巚偄傗傝偑摨嫃偟偰偍傝丄僩儗乕僪儅乕僋偺抁敮儃僽僇僢僩丄偟側傗偐側懱偺慄丄僐働僥傿僢僔儏側昞忣傗巇憪偼丄抝偺楎忣傪偦偦傜偢偵偼偍偐側偄丅偙偺塮夋偵偼偦傫側儖僀乕僘丒僽儖僢僋僗偺枺椡偑墶堨偟偰偄傞丅嶰暥僆儁儔
1931撈丂G.W.僷僽僗僩丂昡揰 [D]
儀儖僩儖僩丒僽儗僸僩偑彂偄偨桳柤側壒妝寑偺弶塮夋壔嶌丅嶌嬋偼僋儖僩丒儚僀儖丅帒杮庡媊幮夛傊偺斸敾偑崬傔傜傟偰偄傞偑丄塮夋偼惌帯揑側怓崌偄偑敄傔傜傟偰偍傝丄僐儊僨傿晽枴偺屸妝嶌偵巇忋偑偭偰偄傞丅晳戜偼儘儞僪儞偺昻柉奨丄揇朹抍偺恊暘儊僢僉乕丒儊僢僒乕偲岊怘抍偺恊暘偺柡億儕乕偲偺寢崶榖傪幉偵丄儊僢僉乕偺搳崠偲扙憱丄懱惂偵斀峈偡傞岊怘偺戝孮僨儌側偳偺僄僺僜乕僪偑怐傝崬傑傟傞丅朻摢偱昡榑壠偲弌墘幰偨偪偑乽偙偺塮夋偼僫僠僗偵傛偭偰岞奐嬛巭偵側偭偨乿偲榖偡抁偄僔乕儞偑弌偰偔傞偑丄偙傟偼偁偲偐傜晅偗壛偊傜傟偨傕偺側偺偩傠偆偐丅柤崅偄憓擖嬋乽儅僢僋丒僓丒僫僀僼乿偼僗僩乕儕乕偑巒傑偭偰娫傕側偔丄戝摴寍恖偵傛偭偰壧傢傟傞丅儚僀儖偺嵢偱彈桪偺儘僢僥丒儗乕僯儍偑儊僢僒乕偺忣晈僕僃僯乕栶偱弌墘偟丄壧傪斺業偟偰偄傞丅儗乕僯儍偲偄偊偽丄乽007婋婡堦敪乿偱儃儞僪傪娮傟傛偆偲偡傞僗儊儖僔儏偺彈巜婗姱儘乕僓栶偑朰傟傜傟側偄丅
2021擭3寧朸擔 旛朰榐112丂尨愡巕偑庡墘偟偨乽抭宐巕彺乿
1957擔丂孎扟媣屨丂昡揰 [C]
孎扟媣屨偼尨愡巕偺媊孼丅愴慜偼楌巎塮夋傗崙嶔塮夋傪嶣傞婥塻偺娔撀偩偭偨偑丄懢暯梞愴憟偑巒傑傞偲嫸怣揑側塃梼峜崙巚憐偵偺傔傝崬傒丄尨愡巕傕偦偺塭嬁傪庴偗偨丅偦偺偣偄偱愴屻偼塮夋奅偐傜姳偝傟丄傢偢偐偵尨愡巕偺偮偰偱丄悢杮偺斵彈庡墘塮夋偱娔撀傪柋傔偨偩偗偵廔偭偨丅偙傟偼偦偺堦杮偱丄尨愡巕偺庡墘偵傛傝崅懞岝懢榊偺嵢抭宐巕偺惗奤傪昤偄偨塮夋丅岝懢榊偵偼嶳懞汔偑暞偟偰偄傞丅抭宐巕偺岝懢榊偲偺弌夛偄偲寢崶丄奊傪昤偔偙偲偺抐擮丄嬯偟偔昻偟偄惗妶丄傗偑偰朘傟傞惛恄偺堎忢偲巰偑扺乆偲昤偐傟傞丅摉帪36嵨偺尨愡巕偼旤偟偔丄墘媄傕側偐側偐偺傕偺丅塮夋偲偟偰偼偦傟傎偳埆偄弌棃偱偼側偔丄孎扟偼堦掕偺椡検傪傕偭偨娔撀偱偁偭偨偙偲偑偆偐偑傢傟傞丅
2021擭2寧
2021擭2寧朸擔 旛朰榐111丂僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩偲僕儍僢僋丒儗儌儞
1950暷丂僿儞儕乕丒僐僗僞乕丂昡揰 [B]
僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩庡墘偺傎偺傏偺偲偟偨僐儊僨傿丅暷崙拞惣晹偺揷幧挰偵廧傓僗僠儏傾乕僩偼僴乕償僃僀偲偄偆柤偺嫄戝側敀僂僒僊偑桭偩偪偱丄偄偮傕楢傟曕偄偰偄傞偑丄偦偺僂僒僊偼斵埲奜偺扤偺栚偵傕尒偊側偄丅摨嫃偡傞枀偼崲偭偰斵傪惛恄昦堾偵擖傟傛偆偲偡傞偑丄帺暘傕偲偒偳偒僂僒僊偑尒偊傞偲崘敀偡傞偟丄昦堾挿傑偱斵偲愙偡傞偆偪偵僂僒僊偑尒偊傞傛偆偵側傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僂僒僊偼側偵偐偺埫歡偩偲偐晽巋偩偲偐丄偄傠偄傠峫偊傜傟傞偑丄偮傑傜側偄棤栚撉傒偼巭傔偰偍偙偆丅偺傫傃傝偟偨慺杙側暤埻婥偑岲姶傪桿偆丅僗僠儏傾乕僩偺恖奿傗屄惈偑栶暱偵尒帠偵儅僢僠偟偰偄傞丅
庰偲僶儔偺擔乆
1962暷丂僽儗僀僋丒僄僪儚乕僘丂昡揰 [B]
娔撀偑僽儗僀僋丒僄僪儚乕僘丄庡墘偑僕儍僢僋丒儗儌儞偲偄偆偲僐儊僨傿傪楢憐偝偣傞偑丄偙傟偼傾儖僐乕儖拞撆偺晐偝偲堸庰偵傛偭偰夡傟偰偄偔壠掚偺斶寑傪昤偄偨僔儕傾僗側塮夋丅僕儍僢僋丒儗儌儞偲儕乕丒儗儈僢僋偼僷乕僥傿偱抦傝崌偭偰寢崶偡傞偑丄晇偺儗儌儞偼堸庰偺偣偄偱夛幮傪僋價偵側傝丄嵢偺儗儈僢僋傕偟偩偄偵庰偵揗傟傞傛偆偵側傞丅晇偼抐庰夛偵擖偭偰嬛庰偟丄恀柺栚偵摥偒巒傔傞偑丄嵢偼庰傪抐偮偙偲偑偱偒偢丄壠傪弌偰帺懧棊側惗妶傪憲傞丅傾儖拞偺晐偝傪埖偭偨塮夋偵偼價儕乕丒儚僀儖僟乕偺乽幐傢傟偨廡枛乿偑偁傞偑丄乽庰偲僶儔偺擔乆乿偺傎偆偑儕傾儖偱嫮楏側報徾傪梌偊傞丅儅儞僔乕僯偲儅乕僒乕偺僐儞價偵傛傞丄偼偐側偔傕旤偟偄慁棩丄儕儕僇儖偱尪憐揑側壧帉偺庡戣壧偼塱墦偺柤嬋偩丅
2021擭2寧朸擔 旛朰榐110丂僕儑儞丒僸儏乕僗僩儞偺2杮偺堎怓嶌
1951暷丂僕儑儞丒僸儏乕僗僩儞丂昡揰 [C]
僗僥傿乕償儞丒僋儗僀儞偺儀僗僩僙儔乕彫愢偺塮夋壔丅撿杒愴憟偵廬孯偟偨杒孯暫巑偑嫲晐偵嫰偊偰偄偭偨傫偼摝朣偡傞偑丄堄傪寛偟偰慜慄偵暅婣偟丄暠愴偟偰庤暱傪棫偰傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅傕偲傕偲偼揋慜摝朣偑庡梫側僥乕儅偩偭偨偑丄僗僞僕僆偵傛偭偰20暘埲忋僇僢僩偝傟偨寢壥丄桬姼側暫巑偺妶桇傪昤偔塮夋偵側偭偰偟傑偭偨丅懡偔偺B媺惣晹寑偵弌墘偟偨庡墘偺僆乕僨傿丒儅乕僼傿偼戞2師戝愴偺儓乕儘僢僷愴慄偱偺晲岟偱桳柤偩偑丄愴屻偼愴憟屻堚徢偵擸傑偝傟偰偄偨偲偄偆丅
敀偄嵒
1957暷丂僕儑儞丒僸儏乕僗僩儞丂昡揰 [B]
 戞2師戝愴枛婜丄撿懢暯梞偺屒搰偵棳傟拝偄偨暷孯暫巑偑丄搰偵庢傝巆偝傟偨擈憁偲弌夛偄丄2恖偩偗偺婏柇側惗妶偑巒傑傞丄斵傜偼偟偩偄偵怱傪捠傢偣巒傔傞偑丄偦偙偵擔杮孯偑忋棨偟丄2恖偼嶳拞偺摯孉偵塀傟傞丄暫巑偼擔杮孯偺憅屔偐傜怘椏傪搻傒弌偦偆偲偟偰尒偮偐傞偑丄偦偙偵暷孯偐傜偺峌寕偑奐巒偝傟偰婋偆偔擄傪摝傟傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅弌墘偼儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僨儃儔丒僇乕丅弌墘偡傞偺偼傎偲傫偳偙偺2恖偩偗偱偁傝丄偦偺揰偱偼傾儖僪儕僢僠偺塮夋偱儕乕丒儅乕償傿儞偲嶰慏晀榊偑弌墘偟偨乽懢暯梞偺抧崠乿傪巚傢偣傞丅僨儃儔丒僇乕偼擈憁巔偑傛偔帡崌偆丅46擭偺乽崟悈愬乿偱偺廋摴彈傕偝傑偵側偭偰偄偨丅杙鎐側儈僢僠儍儉偲惔慯側僇乕偺慻傒崌傢偣偼埆偔側偄丅斵傜偼偙偺悢擭屻偵乽僒儞僟僂僫乕僘乿偺晇晈栶偱嵞傃嫟墘偟偰偄傞丅
戞2師戝愴枛婜丄撿懢暯梞偺屒搰偵棳傟拝偄偨暷孯暫巑偑丄搰偵庢傝巆偝傟偨擈憁偲弌夛偄丄2恖偩偗偺婏柇側惗妶偑巒傑傞丄斵傜偼偟偩偄偵怱傪捠傢偣巒傔傞偑丄偦偙偵擔杮孯偑忋棨偟丄2恖偼嶳拞偺摯孉偵塀傟傞丄暫巑偼擔杮孯偺憅屔偐傜怘椏傪搻傒弌偦偆偲偟偰尒偮偐傞偑丄偦偙偵暷孯偐傜偺峌寕偑奐巒偝傟偰婋偆偔擄傪摝傟傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅弌墘偼儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僨儃儔丒僇乕丅弌墘偡傞偺偼傎偲傫偳偙偺2恖偩偗偱偁傝丄偦偺揰偱偼傾儖僪儕僢僠偺塮夋偱儕乕丒儅乕償傿儞偲嶰慏晀榊偑弌墘偟偨乽懢暯梞偺抧崠乿傪巚傢偣傞丅僨儃儔丒僇乕偼擈憁巔偑傛偔帡崌偆丅46擭偺乽崟悈愬乿偱偺廋摴彈傕偝傑偵側偭偰偄偨丅杙鎐側儈僢僠儍儉偲惔慯側僇乕偺慻傒崌傢偣偼埆偔側偄丅斵傜偼偙偺悢擭屻偵乽僒儞僟僂僫乕僘乿偺晇晈栶偱嵞傃嫟墘偟偰偄傞丅2021擭2寧朸擔 旛朰榐109丂拞尨傂偲傒偲傾儞僫丒僇儕乕僫
1955擔丂壠忛枻戙帯丂昡揰 [B]
壠忛枻戙帯娔撀丄怴摗寭恖媟杮偵傛傞撈棫僾儘嶌昳丅庡墘偼栰揧傂偲傒偲拞尨傂偲傒偺乽傂偲傒乿僐儞價丅壨栰廐晲丄撪摗晲晀丄懡乆椙弮丄朷寧桪巕偲偄偭偨僋僙偺偁傞攐桪偑榚傪屌傔偰偄傞丅栰揧偲拞尨偼拠偺偄偄巓枀丅晝偼敪揹強偺媄巘偱丄堦壠偼敪揹強偺偁傞嶳墱偺懞偱曢傜偟偰偄傞丅巓枀偼奨拞偺廸曣偺壠偵壓廻偟偰崅峑偲拞妛偵捠偭偰偍傝丄偲偒偳偒懞偵婣徣偡傞丅斵彈偨偪偼惗妶偺側偐偱幮夛偺柕弬傪宱尡偟側偑傜惉挿偟偰偄偔丅巓枀傪拞怱偲偟偨奨拞偱偺弌棃帠丄嶳懞偱偺弌棃帠偑扺乆偲捲傜傟偰偄偔丅50擭戙敿偽偺擔杮丄堦斒壠掚偺惗妶偼昻偟偔丄庡晈偼壠寁偺傗傝偔傝偵嬯楯偟偰偄傞偑丄偦傫側側偐偱傕恖乆偼尦婥偵惗偒偰偄偙偆偲偡傞丅偐偮偰偺擔杮偺忣宨偑偙偙偵偁傞丅弌墘幰偺側偐偱弌怓側偺偼丄杬曻側怳傞晳偄偱廃埻傪偼傜偼傜偝偣傞枀偺拞尨傂偲傒偱丄偠偮偵壜垽偔傒偢傒偢偟偄偟丄帺慠側墘媄傕慺惏傜偟偄丅撪婥偱偟偲傗偐側巓傪墘偠傞栰揧傂偲傒偺梷偊偨墘媄偵傕岲姶傪妎偊傞丅巓枀偺惈奿偑偒偭偪傝昤偒暘偗傜傟偰偄傞偺偼媟杮偺怴摗偺庤榬偩傠偆丅偙偺2恖偑偍屳偄偵憡庤傪巚偄傗傝側偑傜偗側偘偵惗偒偰偄偔巔偼怱傪懪偮丅応強偼偳偙偲柧帵偝傟偰偄側偄偑丄儘働偼挿栰導偺徏杮巗偱峴側傢傟偨傛偆偩丅
廋摴彈
1966暓丂僕儍僢僋丒儕償僃僢僩丂昡揰 [C]
傾儞僫丒僇儕乕僫庡墘偺廋摴彈庴擄暔岅丅尨嶌偼18悽婭偺僨傿僪儘偺彫愢偩偑丄娔撀偺儕償僃僢僩偼峚岥寬擇偺乽惣掃堦戙彈乿偵僀儞僗僺儗乕僔儑儞傪摼偨偲偄偆丅偨偟偐偵丄杤棊婱懓偺柡偑寵乆側偑傜廋摴堾偵擖傟傜傟丄堾挿偵寵偑傜偣傪庴偗偰娔嬛偝傟丄師偵堏偭偨廋摴堾偱偼惈揑旐奞傪庴偗丄庱旜傛偔摝朣偡傞傕彥晈偵恎傪棊偲偡偲偄偆僗僩乕儕乕偼乽惣掃堦戙彈乿傪憐婲偝偣傞偑丄峚岥嶌昳傎偳偺惛恄惈偼姶偠傜傟側偄丅
2021擭2寧朸擔 旛朰榐108丂僒僀儗儞僩帪戙偺僪僀僣偺嫄彔儉儖僫僂傪娤傞
1922擭撈丂F丒W丒儉儖僫僂丂昡揰 [C]
媧寣婼塮夋偺尦慶偱偁傞屆揟揑柤嶌丅僪僀僣昞尰庡媊帪戙偺僒僀儗儞僩塮夋偱丄僽儔儉丒僗僩乕僇乕尨嶌偺乽媧寣婼僪儔僉儏儔乿傪東埬偟偨傕偺丅堎條側晽杄偺媧寣婼僆儖儘僢僋攲庉偑報徾偵巆傞丅
嵟屻偺恖
1924擭撈丂F丒W丒儉儖僫僂丂昡揰 [B]
僒僀儗儞僩帪戙偺僪僀僣塮夋傪戙昞偡傞堦嶌丅崅媺儂僥儖偺僪傾儅儞傪柋傔傞庡恖岞僄儈乕儖丒儎僯儞僌僗偑榁楊偺偨傔愻柺強扴摉偵奿壓偘偝傟偙偲偵傛偭偰婲偙傞斶婌寑傪昤偔丅塮夋偼偄偭偨傫斶寑偱廔傞偑丄帤枊偱乽尰幚偵偼偁傝摼側偄榖偩偑乿偲愢柧偝傟偨偁偲丄暿償傽乕僕儑儞偺岾塣偑晳偄崬傓屻擔択偑岅傜傟傞丅
2021擭2寧朸擔 旛朰榐107丂儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘塮夋傪娤傞丂偦偺1
1964擭暷丂僨償傿僢僪丒僗僀僼僩丂昡揰 [C]
儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偼庡偵僼儔儞僗傪杮嫆抧偲偟偰妶摦偟偨偑丄弶婜偵偼暷塸偵傕彽偐傟偰塮夋偵弌墘偟偰偄偨丅偙傟偼僴儕僂僢僪偱嶣傜傟偨僗儔僢僾僗僥傿僢僋婌寑偱丄僕儍僢僋丒儗儌儞偲嫟墘偟偰偄傞丅僕儍僢僋丒儗儌儞偼峀崘夛幮偵嬑傔傞僒儔儕乕儅儞丅嵢偺恊桭儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偑晇偲偺棧崶傪寛堄偟偰儗儌儞晇嵢偺椬偺壠偵廧傒巒傔偨丅僔儏僫僀僟乕偼廸晝偺堚嶻傪憡懕偡傞偙偲偵側偭偨偑丄岾暉側寢崶傪懕偗偰偄傞偙偲偲偄偆忦審偑晅偄偰偄偨丅扵掋偵尒挘傜傟偰偄傞偨傔丄僔儏僫僀僟乕偵棅傑傟丄儗儌儞偑晇偲偟偰僔儏僫僀僟乕偲摨嫃偟偰偄傞怳傝傪偡傞偙偲偵側偭偨丅偦偙偵暅墢傪敆偭偰僔儏僫僀僟乕偺杮摉偺晇儅僀働儖丒僐僫乕僘偑尰傟丄僪僞僶僞憶偓偑壛懍偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅庒偄僔儏僫僀僟乕偼旤偟偔丄僐働僥傿僢僔儏側枺椡偵偁傆傟偰偄傞丅偙傟偼傏偔偑傂偲偙傠戝岲偒偩偭偨儈僗僥儕乕仌僼傽儞僞僕乕彫愢嶌壠僕儍僢僋丒僼傿僯僀偺尨嶌偩偲偄偆丅僼傿僯僀偑偙傫側彫愢傪彂偄偰偄偨偲偼抦傜側偐偭偨丅
抧崠偺偐偗傂偒
1968擭塸丂僨傿僢僋丒僋儗儊儞僩丂昡揰 [D]
偙偺偙傠傛偔嶌傜傟偨塸崙惢僗僷僀丒僐儊僨傿塮夋丅僩儉丒僐乕僩僱僀偲儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕庡墘丅乽挿嫍棧儔儞僫乕偺屒撈乿偱斀峈偡傞庒幰傪墘偠偨僐乕僩僱僀偑偙偙偱偼幐嬈拞偺柍婥椡側抝傪墘偠傞丅僐乕僩僱僀偑嶦恖帠審偵憳嬾偟丄偦偙偵挸曬慻怐偑棈傫偱僗僷僀崌愴偵姫偒崬傑傟傞丅挸曬堳偺彈傪墘偠傞僔儏僫僀僟乕偼偒傟偄偩偑丄榖偺嬝偑偝偭傁傝暘偐傜側偄
偳偟傖崀傝
1970擭暓丂儗僆僫乕儖丒働乕僎儖丂昡揰 [C]
儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偲儌乕儕僗丒儘僱庡墘偺僒僗儁儞僗塮夋丅儘儈乕丒僔儏僫僀僟乕偲楒恖偺抝偑忔偭偰偄偨幵偑奟偐傜奀偵揮棊偟丄僔儏僫僀僟乕偩偗彆偐傞丅偦偙偵寈嶡偲堦弿偵抝偺孼儌乕儕僗丒儘僱偑尰傟傞丅僔儏僫僀僟乕偼儘僱偺幵偵摨忔偟偰僷儕偵婣傞丅儘僱偼僔儏僫僀僟乕偵媈榝傪書偔偑丄斵彈偺枺椡偵廁傢傟偰楒偵棊偪傞丅偦偙偵巰傫偩偲巚偭偰偄偨尦楒恖偺掜偑尰傟偰僔儏僫僀僟乕傪嫼偡丅偳偆傗傜幵偺帠屘偼僔儏僫僀僟乕偑斵傪嶦偡偨傔偵巇慻傫偩傕偺偩偭偨傜偟偄丅崲偭偨斵彈偼偁傞峴摦偵弌傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅嬝棫偰偼庛偄偑丄埆彈僔儏僫僀僟乕偺梔偟偄枺椡偼側偐側偐偺傕偺丅僄儞僨傿儞僌偼乽懢梲偑偄偭傁偄乿傪巚傢偣傞丅
2021擭2寧朸擔 旛朰榐106丂90擭戙偺怴姶妎僪僀僣塮夋
1997擭撈丂僇乕僠儍丒僼僅儞丒僈儖僯僄丂昡揰 [C]
彈廁4恖偑孻柋強撪偱僶儞僪傪慻傒丄寈嶡偺僷乕僥傿偵屇偽傟偨嵺偵寗傪尒偰扙憱偡傞丅斵傜偑摝偘夞偭偰偄傞嵟拞丄孻柋強偐傜儗僐乕僪夛幮偵憲偭偨僨儌僥乕僾偑儗僐乕僪壔偝傟偰戝僸僢僩偟丄僶乕偱儔僀僽傪偟偨傝丄儅僗僐儈偺庢嵽偵墳偠偨傝偡傞偆偪偵恖婥僶儞僪偵偺偟忋偑傞丅斵傜偼峘偱嵟屻偺儔僀償傪傗偭偰撿暷偵摝偘傛偆偲偡傞偑丄寈嶡偼偦傟傪嶡抦偟偰曪埻偡傞丄偲偄偆榖丅
儔儞丒儘乕儔丒儔儞
1998擭撈丂僩儉丒僥傿僋償傽丂昡揰 [D]
楒恖傪媬偆偨傔20暘偱戝嬥傪梡堄偟側偗傟偽偄偗側偔側偭偨儘乕儔偑丄嬥嶔偺偨傔儀儖儕儞偺奨傪嬱偗夞傞丅僎乕儉偺傛偆偵3偮偺僷僞乕儞偺僗僩乕儕乕偑孞傝曉偝傟丄1搙栚丄2搙栚偼幐攕丄3搙栚偱傛偆傗偔惉岟偡傞丅偲偙傠偳偙傠偱傾僯儊偑憓擖偝傟丄億僢僾姶妎偑墶堨偟偰偄傞丅
2021擭1寧
2021擭1寧朸擔 旛朰榐105丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺4
1947丂傾儞僜僯乕丒儅儞丂昡揰 [B]
 巻暭婾憿抍堦枴傪戇曔偡傞偨傔愽擖憑嵏傪偡傞暷嵿柋徣挷嵏姱乮T儊儞乯偺嬯摤傪僙儈僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵昤偄偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅僨僯僗丒僆僉乕僼庡墘丅娔撀偺傾儞僜僯乕丒儅儞偼惣晹寑偱桳柤偩偑丄弶婜偵偼B媺偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪庤偑偗偰偄偨丅偙傟傕偦偺傂偲偮偱丄僥儞億偺偄偄墘弌傕偝傞偙偲側偑傜丄嵟戝偺尒偳偙傠偼柤庤僕儑儞丒傾儖僩儞偺尒帠側僇儊儔丒儚乕僋偩丅悘強偵弌偰偔傞岝偲塭傪妶偐偟偨栭偺搒夛偺儘乕僉乕嶣塭偼慺惏傜偟偔丄尒傞幰偺嫻傪偲偒傔偐偣傞丅偲傝傢偗朻摢偺枾崘幰偑嶦偟壆偵嶦奞偝傟傞僔乕儞偺慛傗偐偝偼報徾怺偄丅
巻暭婾憿抍堦枴傪戇曔偡傞偨傔愽擖憑嵏傪偡傞暷嵿柋徣挷嵏姱乮T儊儞乯偺嬯摤傪僙儈僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵昤偄偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅僨僯僗丒僆僉乕僼庡墘丅娔撀偺傾儞僜僯乕丒儅儞偼惣晹寑偱桳柤偩偑丄弶婜偵偼B媺偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪庤偑偗偰偄偨丅偙傟傕偦偺傂偲偮偱丄僥儞億偺偄偄墘弌傕偝傞偙偲側偑傜丄嵟戝偺尒偳偙傠偼柤庤僕儑儞丒傾儖僩儞偺尒帠側僇儊儔丒儚乕僋偩丅悘強偵弌偰偔傞岝偲塭傪妶偐偟偨栭偺搒夛偺儘乕僉乕嶣塭偼慺惏傜偟偔丄尒傞幰偺嫻傪偲偒傔偐偣傞丅偲傝傢偗朻摢偺枾崘幰偑嶦偟壆偵嶦奞偝傟傞僔乕儞偺慛傗偐偝偼報徾怺偄丅崟偄揤巊
1946丂儘僀丒僂傿儕傾儉丒僯乕儖丂昡揰 [C]
僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠偺僒僗儁儞僗彫愢偺塮夋壔丅尨嶌偼戝愄偵撉傫偱偄傞偼偢偩偑丄婰壇憆幐偑慺嵽偵側偭偰偄傞偙偲埲奜偼傑偭偨偔撪梕傪妎偊偰偄側偄丅旤杄偺彈惈壧庤偑嶦偝傟丄斵彈偵嫮敆偝傟偰偄偨抝偑戇曔偝傟偰巰孻傪愰崘偝傟傞丅抝偺嵢偼晇偺柍幚傪怣偠丄壧庤偺尦晇偱偁傞僶乕偺僺傾僲抏偒偺彆偗傪庁傝偰恀斊恖傪撍偒偲傔傛偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡墘偼埆栶愱栧偺僟儞丒僨儏儕僄偱丄偙偙偱偼捒偟偔慞恖傪墘偠偰偍傝丄払幰側僺傾僲丒僾儗僀傪斺業偡傞丅撲傔偄偨僫僀僩僋儔僽偺僆乕僫乕偵僺乕僞乕丒儘乕儗丅B媺嶌昳偩偑梊憐奜偺偳傫偱傫曉偟傕偁傝丄偗偭偙偆妝偟傔傞丅
2021擭1寧朸擔 旛朰榐104丂嶰慏晀榊偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒價僨僆
2015丂僗僥傿乕償儞丒僆僇僓僉丂昡揰 [C]
婜偣偢偟偰嶰慏晀榊偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒價僨僆傪2杮懕偗偰尒偨丅偙傟偼暷崙偺擔宯僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋嶌壠偑娔撀偟偨寑応岞奐嶌丅擔杮偺僠儍儞僶儔塮夋偺楌巎偵棈傔偰嶰慏偺弌墘塮夋偲攐桪偲偟偰偺惗偒曽偑昤偐傟傞丅徯夘偝傟傞弌墘塮夋偼崟郪塮夋偑拞怱偱偁傝丄怴偟偄敪尒偼偁傑傝側偄丅暷崙恖岦偗偵嶰搰偲偄偆恖娫偺昞柺傪側偧偭偨偩偗偺傛偆側報徾傪庴偗傞丅搚壆壝抝丄壞栘梲夘丄崄愳嫗巕丄巌梩巕側偳偺嫟墘攐桪丄僗僥傿乕償儞丒僗僺儖僶乕僌丄儅乕僥傿儞丒僗僐僙僢僔偲偄偭偨暷崙偺桳柤娔撀偺僀儞僞償儏乕偑憓擖偝傟傞丅
嶰慏晀榊丂僒儉儔僀偺恀幚
2020丂NHK丂昡揰 [B]
偙偪傜偼嶐擭枛偵惗抋100擭婰擮偲偟偰NHK偱曻憲偝傟偨傕偺丅偝傑偞傑側妏搙偐傜攐桪嶰慏偺巔偑晜偒挙傝偵偝傟偰偍傝丄偲偔偵愴憟懱尡偑嶰慏偺恖奿宍惉偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨偲偟偰偄傞偺偼娷拁偑偁傞丅傑偨嶰慏偑惢嶌偵堄梸傪擱傗偟偨偑枹姰偵廔偭偨乽懛屽嬻乿偵傑偮傢傞憓榖傕嫽枴怺偄丅嶰慏偑巊偭偨戜杮偵彂偒壛偊傜傟偰偄傞偍傃偨偩偟偄拲堄彂偒傗僐儊儞僩偑栚傪堷偔丅偙偙偱傕崄愳嫗巕偲巌梩巕偑弌墘偟偰嶰慏偵偮偄偰偺巚偄弌傪岅偭偰偄傞丅擇恖偲傕忋昳偵擭傪庢偭偰偄傞偺偑報徾怺偄丅抝桪偱搊応偡傞偺偼曮揷柧偩偗偱丄傑偩懚柦偟偰偄傞拠戙払栴傗嶳嶈搘偑弌墘偟偰偄側偄偺偼夝偣側偄丅
2021擭1寧朸擔 旛朰榐103丂儗僗僞乕偲僷僂僄儖偺儗傾側僪僉儏儊儞僞儕乕塮憸
1988乮塸岅斉丄帤枊側偟乯丂昡揰 [C]
 儗僗僞乕丒儎儞僌偺惗奤傪捛偭偨1帪娫20暘偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒價僨僆丅儗僗僞乕傪僼傿乕僠儍乕偟偨抁曇塮夋乽Jammin' the Blues乿側偳偺塮憸傪怐傝崬傒偮偮丄僇僂儞僩丒儀僀僔乕丄僶僗僞乕丒僗儈僗丄僶僢僋丒僋儗僀僩儞丄儘僀丒僄儖僪儕僢僕丄僕儑乕丒僕儑乕儞僘丄僨傿僕乕丒僈儗僗僺乕偲偄偭偨戝暔儈儏乕僕僔儍儞傗丄僕儑儞丒僴儌儞僪丄僲乕儅儞丒僌儔儞僣側偳偺僾儘僨儏乕僒乕偑搊応偟偰儗僗僞乕偵偮偄偰岅傞丅偄傑偱偼斵傜偺傎偲傫偳偑婼愋偵擖偭偰偟傑偭偰偄傞丅儗僗僞乕偺柡傗墮傊偺僀儞僞償儏乕傕憓擖偝傟傞丅帤枊偑側偄偺偱斵傜偺挐傞撪梕偑傛偔暘偐傜側偄偺偑傕偳偐偟偄偟丄嵟屻偑10暘傎偳寚棊偟偰偄傞偺傕巆擮偩偑丄婱廳側僪僉儏儊儞僞儕乕偱偁傞偙偲偼妋偐偩丅
儗僗僞乕丒儎儞僌偺惗奤傪捛偭偨1帪娫20暘偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒價僨僆丅儗僗僞乕傪僼傿乕僠儍乕偟偨抁曇塮夋乽Jammin' the Blues乿側偳偺塮憸傪怐傝崬傒偮偮丄僇僂儞僩丒儀僀僔乕丄僶僗僞乕丒僗儈僗丄僶僢僋丒僋儗僀僩儞丄儘僀丒僄儖僪儕僢僕丄僕儑乕丒僕儑乕儞僘丄僨傿僕乕丒僈儗僗僺乕偲偄偭偨戝暔儈儏乕僕僔儍儞傗丄僕儑儞丒僴儌儞僪丄僲乕儅儞丒僌儔儞僣側偳偺僾儘僨儏乕僒乕偑搊応偟偰儗僗僞乕偵偮偄偰岅傞丅偄傑偱偼斵傜偺傎偲傫偳偑婼愋偵擖偭偰偟傑偭偰偄傞丅儗僗僞乕偺柡傗墮傊偺僀儞僞償儏乕傕憓擖偝傟傞丅帤枊偑側偄偺偱斵傜偺挐傞撪梕偑傛偔暘偐傜側偄偺偑傕偳偐偟偄偟丄嵟屻偑10暘傎偳寚棊偟偰偄傞偺傕巆擮偩偑丄婱廳側僪僉儏儊儞僞儕乕偱偁傞偙偲偼妋偐偩丅Bud Powell: Inner Exile
1998乮暓岅斉丄塸岅帤枊乯丂昡揰 [B]
僼儔儞僗偱惢嶌偝傟偨僶僪丒僷僂僄儖偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒價僨僆丅広偼栺1帪娫丅梒彮婜偐傜42嵨偱巰偵帄傞傑偱偺攇棎偵晉傫偩僷僂僄儖偺恖惗偑丄僼儔儞僗偱嶣傜傟偨偝傑偞傑側儔僀償丒價僨僆傗僾儔僀償僃乕僩側塮憸傪怐傝崬傒側偑傜丄寈姱偵墸懪偝傟偰敪徢偟偨惛恄偺昦偄丄僙儘僯傾僗丒儌儞僋偲偺桭忣丄塰岝偺擔乆丄僼儔儞僗傊偺堏廧丄嬯擄偺帪婜偵僼儔儞僔僗丒億乕僪儔偑嵎偟怢傋偨巟墖側偳偺僄僺僜乕僪偲偲傕偵暔岅傜傟傞丅拞嬻傪嬅帇偟側偑傜柍怱偵僺傾僲傪抏偔僷僂僄儖偺巔偑報徾揑側僋儔僽偱偺墘憈晽宨傕偝傞偙偲側偑傜丄朻摢偲枛旜偵憓擖偝傟傞丄姦乆偲偟偨搤偺擔丄偳傫傛傝偟偨撥傝嬻偺壓丄奀捁偑晳偆偳偙偐偺攇巭応傪曕偔僷僂僄儖偺塮憸偑怱偵巆傞丅
2020擭12寧
2020擭12寧朸擔 2020擭奀奜儈僗僥儕乕彫愢儀僗僩丒僥儞
01 乽僱償傽乕丒僎乕儉乿僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕乮暥錣弔廐幮乯
02 乽榁偄偨抝乿僩儅僗丒儁儕乕乮憗愳暥屔乯
03 乽儗僀僩丒僔儑乕乿儅僀僋儖丒僐僫儕乕乮島択幮暥屔乯
04 乽墭柤乿儅僀僋儖丒僐僫儕乕乮島択幮暥屔乯
05 乽敪壩揰乿C丒J丒儃僢僋僗乮憂尦暥屔乯
06 乽僓丒僠僃乕儞 楢懕桿夳乿僄僀僪儕傾儞丒儅僢僉儞僥傿乮憗愳暥屔乯
07 乽塀傟壠偺彈乿僟儞丒僼僃僗僷乕儅儞乮廤塸幮暥屔乯
08 乽巰傫偩儗儌儞乿僼傿儞丒儀儖乮憂尦暥屔乯
09 乽曎岇巑僟僯僄儖丒儘乕儕儞僘乿償傿僋僞乕丒儊僜僗乮憗愳暥屔乯
10 乽嶌壠偺旈傔傜傟偨恖惗乿僊儑乕儉丒儈儏僢僜乮廤塸幮暥屔乯
1埵偺僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕乽僱償傽乕丒僎乕儉乿偼丄僶僂儞僥傿丒僴儞僞乕偺堦旵楾僐儖僞乕丒僔儑僂傪庡恖岞偲偡傞怴僔儕乕僘偺戞1嶌丅僐儖僞乕偼偡偖傟偨抦擻偲抌偊忋偘傜傟偨懱椡傪晲婍偵丄價僨僆僎乕儉傪柾曧偡傞楢懕嶦恖斊傪捛偆丅搊応偡傞恖暔偺憿宍偑尒帠偩偟丄応柺揥奐偼慛傗偐偱僗儕儕儞僌偩偟丄摼堄偺偳傫偱傫曉偟傕嶀偊搉偭偰偄傞丅2埵偺僩儅僗丒儁儕乕乽榁偄偨抝乿偼丄擟柋拞偺偁傞帠審偑偒偭偐偗偱峴曽傪偔傜傑偟丄挿擭偵傢偨偭偰塀撡偟偰偄偨尦暷孯摿庩岺嶌堳偺榁恖偑丄撍慠尒抦傜偸揋偵廝寕偝傟偰摝憱偡傞丅摢擼柧濔丄奿摤偲晲婍偵傕挿偗偨斵偼幏漍偵廝偆嶦偟壆傪寕戅偟丄將偲搑拞偱抦傝崌偭偨彈惈偲偲傕偵摝朣傪懕偗側偑傜丄恀憡傪扵傠偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅榁恖偲庒偄岺嶌堳偲偺桭忣傕昤偐傟偰偍傝丄忋弌棃偺朻尟傾僋僔儑儞彫愢偵巇忋偑偭偰偄傞丅3埵偲4埵偵偼柤庤儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺2嶌偑儔儞僋僀儞丅3埵乽儗僀僩丒僔儑乕乿偼怴僉儍儔僋僞乕丄儘僗巗寈怺栭嬑柋扴摉偺彈惈孻帠偑庡恖岞丅4埵偺乽墭柤乿偼偍撻愼傒偺孻帠僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺怴嶌丅偄偢傟傕惓媊姶偲斀崪惛恄偵晉傫偩庡恖岞偑懱惂偺嫮偄傞梷埑傗鏰鐎傪潧偹偺偗側偑傜晄孅偺堄巙偱帠審偺憑嵏偵偁偨傞偲偄偆丄僴乕僪儃僀儖僪偺墹摴傪峴偔彫愢丅偐偔傕挿偒偵傢偨偭偰幙偺崅偄戞堦媺偺儈僗僥儕乕傪彂偒懕偗傞僐僫儕乕偵偼丄扙朮偡傞偟偐側偄丅5埵偵擖偭偨偺偼C丒J丒儃僢僋僗偺乽敪壩揰乿丅偍撻愼傒偺儚僀僆儈儞僌廈椔嬫娗棟姱僕儑乕丒僺働僢僩傪庡恖岞偲偡傞僔儕乕僘偺怴嶌丅帺傜偑怣偠傞惓媊偵廬偭偰嶦恖帠審傪憑嵏偡傞怱桪偟偄僺働僢僩偺峴摦偼儃僢僔儏偲嫟捠偡傞丅堘偄偼丄儃僢僔儏偺晳戜偑儘僗偲偄偆搒夛側偺偵懳偟偰丄僺働僢僩偺晳戜偼儚僀僆儈儞僌偺戝帺慠偲偄偆揰偩丅6埵埲壓偺僐儊儞僩偼妱垽丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐102丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺3
1945丂僕儑儞丒僽儔乕儉丂昡揰 [C]
20悽婭弶摢偺儘儞僪儞傪晳戜偵偟偨楌巎僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅嵥擻偁傞偑帪乆婰壇憆幐偵娮傞嶌嬋壠仌僺傾僯僗僩偑旤恖壧庤偺埆彈偵閤偝傟丄抦傜偸娫偵嶦恖傪斊偟偰恎傪柵傏偡榖丅庡恖岞偺壒妝壠傪墘偠傞儗傾乕僪丒僋儕乕僈乕偼柍柤偩偑丄埆彈栶偵儕儞僟丒僟乕僱儖丄帠審偺憑嵏偵偁偨傞寈嶡偺専帇姱偵僕儑乕僕丒僒儞僟乕僗偑暞偟偰偄傞丅尨戣偺乽Hangover Square乿偼庡恖岞偺廧傫偱偄傞抧柤丅埫偄怓挷丄柖偵墝傞奨楬丄婰壇憆幐丄僼傽儉丒僼傽僞乕儖偺埆彈偲丄僲儚乕儖偺忦審偼懙偭偰偄傞丅
崅偄暻
1947丂僇乕僥傿僗丒僶乕儞僴乕僩丂昡揰 [B]
偙傟傕婰壇憆幐偺抝偺榖丅愴憟屻堚徢偱摢捝偲婰壇憆幐偵擸傑偝傟偰偄傞抝偑嵢傪嶦偟偨偲巚偄崬傒寈嶡偵戇曔偝傟傞偑丄惛恄偵栤戣偁傝偲偟偰惛恄昦堾偵廂娔偝傟傞丅昦堾偺彈堛偺恊恎偺搘椡偵傛傝杻悓椕朄偱婰壇偑酳偭偨抝偼帺暘偺斊峴偱偼側偄偲屽傝丄昦堾傪敳偗弌偟偰恀斊恖傪憑偡丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡恖岞偺抝傪儘僶乕僩丒僥僀儔乕丄斵傪彆偗傞彈堛傪僆乕僪儕乕丒僩僢僞乕丄嵢偑柋傔傞弌斉幮偺曇廤挿傪僴乕僶乕僩丒儅乕僔儍儖偑墘偠偰偄傞丅抝偑塣揮偡傞幵偑摴傪偦傟偰墶揮偡傞朻摢偺僔乕儞丄夞憐晽偵憓擖偝傟傞婰壇偺抐曅丄抝偑塉偺崀傝偟偒傞側偐昦堾傪扙憱偟丄斊峴尰応偵岦偐偆僋儔僀儅僢僋僗側偳丄尒偳偙傠偼懡偔丄堦媺昳偺偺僒僗儁儞僗塮夋偩丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐102丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺2
1946丂償傿儞僙儞僩丒儈僱儕丂昡揰 [B]
暔棟妛嫵庼偺柡偱僆乕儖僪儈僗偺僉儍僒儕儞丒僿僢僶乕儞偼丄晝偺棟榑傪幚梡壔偟偰攧傝弌偦偆偲偡傞桾暉側幚嬈壠儘僶乕僩丒僥僀儔乕偵尒弶傔傜傟偰寢崶偡傞丅斵偵偼峴曽晄柧偺掜偑偄傞偑丄斵偼掜偺偙偲傪榖戣偵偡傞偺傪堎忢偵寵偑傞丅斵彈偼晇偺掜偺塭偑壆晘傪偍偍偭偰偄傞偺偵婥偯偔丅傗偑偰掜偺儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偑尰傟丄晇偺塀偝傟偰偄偨埫偄旈枾偑柧傜偐偵側傞丄偲偄偆僑僔僢僋丒儘儅儞晽僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅巔傪尰偝側偄恖暔偺塭偑庡恖岞傪晄埨偵娮傟傞偲偄偆慜敿偺棳傟偼僸僢僠僐僢僋偺乽儗儀僢僇乿傪憐婲偝偣傞丅娔撀偺償傿儞僙儞僩丒儈僱儕丄嶣塭偺僇乕儖丒僼儘僀儞僩偲傕偳傕丄榬偺偄偄僗僞僢僼丄僉儍僗僩偵傛傞偙偺塮夋偼丄偝偡偑偵僗僩乕儕乕揥奐傕僙僢僩丒僨僓僀儞傕堦媺昳偩丅僨價儏乕偟偰娫傕側偄儈僢僠儍儉偼傑偩庒乆偟偄丅杮棃偺僀儊乕僕偐傜偡傞偲丄堎忢惈奿偺斊嵾幰傪儈僢僠儍儉丄慞椙側抝傪儘僶乕僩丒僥僀儔乕偑墘偠傞偺偑弴摉偩偲巚傢傟傞偑丄偙偺塮夋偱偼偦偺媡傪偄偭偰偄傞偺偑柺敀偄丅僽儔乕儉僗偺岎嬁嬋戞3斣偑暁慄偵巊傢傟偰偄傞丅
旤恖儌僨儖嶦恖帠審
1941丂僽儖乕僗丒僴儞僶乕僗僩乕儞丂昡揰 [C]
 僼傿儖儉丒僲儚乕儖偼1941擭偺乽儅儖僞偺戦乿偑殔栴偩偲偝傟偰偄傞偑丄摨擭偵惢嶌偝傟偨偙偺塮夋傕丄搊応恖暔偨偪偺僼儔僢僔儏僶僢僋偵傛偭偰僪儔儅偑恑傓偙偲丄堎忢惈奿偺孻帠偑搊応偡傞偙偲偵傛偭偰丄嵟弶婜偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偲偟偰偺崪奿偑柧敀偵旛傢偭偰偄傞丅尨戣偼乽I Wake Up Screaming乿偩偑丄朚戣偑僟僒偡偓傞丅乽斶柭偲偲傕偵栚偑妎傔傞乿偲偐乽栚傪妎傑偡偲扤偐偑偄傞乿偲偐丄傕偭偲暤埻婥偺偁傞戣柤偑晅偗傜傟偰偟偐傞傋偒偩丅僗億乕僣丒僾儘儌乕僞乕偺償傿僋僞乕丒儅僠儏傾偑旤恖偺僂僃僀僩儗僗傪儌僨儖偲偟偰攧傝弌偦偆偲偡傞偑丄斵彈偼嶦偝傟丄斵偑嶦恖斊偲媈傢傟傞丅堎忢偵幏擮怺偄孻帠偑斵偵嵾傪拝偣傛偆偲幏漍偵晅偗慱偆丅斵偼寵媈傪惏傜偦偆偲憱傝夞傞偆偪偵丄斵彈偲摨嫃偟偰偄偨巓偺儀僥傿丒僌儗僀僽儖偲楒拠偵側傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅廳梫側嫸尵夞偟偺儂僥儖廬嬈堳偵丄偁偺報徾怺偄榚栶攐桪僀儔僀僔儍丒僋僢僋丒僕儏僯傾偑暞偟偰偄傞丅僄儞僨傿儞僌傕煭棊偰偍傝丄塮夋偺弌棃偲偟偰偼偦傟傎偳埆偔側偄丅側偤偐乽擑偺斵曽偵乿偺儊儘僨傿偑悘強偱棳傟傞丅
僼傿儖儉丒僲儚乕儖偼1941擭偺乽儅儖僞偺戦乿偑殔栴偩偲偝傟偰偄傞偑丄摨擭偵惢嶌偝傟偨偙偺塮夋傕丄搊応恖暔偨偪偺僼儔僢僔儏僶僢僋偵傛偭偰僪儔儅偑恑傓偙偲丄堎忢惈奿偺孻帠偑搊応偡傞偙偲偵傛偭偰丄嵟弶婜偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偲偟偰偺崪奿偑柧敀偵旛傢偭偰偄傞丅尨戣偼乽I Wake Up Screaming乿偩偑丄朚戣偑僟僒偡偓傞丅乽斶柭偲偲傕偵栚偑妎傔傞乿偲偐乽栚傪妎傑偡偲扤偐偑偄傞乿偲偐丄傕偭偲暤埻婥偺偁傞戣柤偑晅偗傜傟偰偟偐傞傋偒偩丅僗億乕僣丒僾儘儌乕僞乕偺償傿僋僞乕丒儅僠儏傾偑旤恖偺僂僃僀僩儗僗傪儌僨儖偲偟偰攧傝弌偦偆偲偡傞偑丄斵彈偼嶦偝傟丄斵偑嶦恖斊偲媈傢傟傞丅堎忢偵幏擮怺偄孻帠偑斵偵嵾傪拝偣傛偆偲幏漍偵晅偗慱偆丅斵偼寵媈傪惏傜偦偆偲憱傝夞傞偆偪偵丄斵彈偲摨嫃偟偰偄偨巓偺儀僥傿丒僌儗僀僽儖偲楒拠偵側傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅廳梫側嫸尵夞偟偺儂僥儖廬嬈堳偵丄偁偺報徾怺偄榚栶攐桪僀儔僀僔儍丒僋僢僋丒僕儏僯傾偑暞偟偰偄傞丅僄儞僨傿儞僌傕煭棊偰偍傝丄塮夋偺弌棃偲偟偰偼偦傟傎偳埆偔側偄丅側偤偐乽擑偺斵曽偵乿偺儊儘僨傿偑悘強偱棳傟傞丅2020擭12寧朸擔 旛朰榐101丂40擭戙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丂偦偺1
1949丂儅僢僋僗丒僆僼儏儖僗乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰 [B]
 偙偙偐傜偟偽傜偔丄偙傟傑偱枹尒偩偭偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪尒傞偙偲偵偡傞丅儅僢僋僗丒僆僼儏儖僗偑昤偔楒偡傞彈惈偼偁傑傝偵僫僀乕償偱柍暘暿偩丅嬉戲側惗妶傪柌尒傞悽娫抦傜偢偺彈僶乕僶儔丒儀儖僎僨僗偑戝晉崑偺抝儘僶乕僩丒儔僀傾儞偲寢崶偡傞偑丄晇偺椻崜偝偲堎忢側惈奿傪抦傝丄媠懸偵懴偊傜傟偢壠傪弌偰昦堾偺庴晅帠柋堳偲偟偰摥偒巒傔丄屬偄庡偱偁傞堛巘偺僕僃乕儉僗丒儊僀僜儞偲恊偟偔側傞丅擠怭偟偨斵彈偼儔僀傾儞偵屇傃栠偝傟壠偵栠傝丄恻梋嬋愜偺枛丄旀暰偟偨斵彈傪儊僀僜儞偑媬偆偲偄偆儊儘僪儔儅晽僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅嬥慘偵幏拝偡傞墶朶側嬥帩偪偺幚嬈壠儘僶乕僩丒儔僀傾儞偼僴儚乕僪丒僸儏乕僘偑儌僨儖偩偲偄偆丅僆僼儏儖僗摿桳偺棳傟傞傛偆側堏摦僇儊儔偼儀儖僎僨僗偲儊僀僜儞偺僫僀僩僋儔僽偱偺僟儞僗丒僔乕儞偵妶偐偝傟偰偄傞丅傑偨彈偑儃乕僩傪懸偮攇巭応偺僔乕儞傗丄奒抜傗媞娫偑塮偟弌偝傟傞崑揁偺儘乕丒僉乕嶣塭偼丄僲儚乕儖偺暤埻婥傪崅傔偰偄傞丅堎忢惈奿偺抝傪墘偠偝偣偰儘僶乕僩丒儔僀傾儞傎偳偺揔栶偼偄側偄丅僕僃乕儉僗丒儊僀僜儞偼僆僼儏儖僗偺傕偆堦偮偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖乽柍杁側弖娫乿偱傕庡墘偺僕儑乕儞丒儀僱僢僩傪彆偗傞抝傪墘偠偰偄偨丅帒嬥晄懌偺偨傔塮夋偺嵟屻偑怟愗傟僩儞儃偵側偭偨偺偑巆擮丅
偙偙偐傜偟偽傜偔丄偙傟傑偱枹尒偩偭偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪尒傞偙偲偵偡傞丅儅僢僋僗丒僆僼儏儖僗偑昤偔楒偡傞彈惈偼偁傑傝偵僫僀乕償偱柍暘暿偩丅嬉戲側惗妶傪柌尒傞悽娫抦傜偢偺彈僶乕僶儔丒儀儖僎僨僗偑戝晉崑偺抝儘僶乕僩丒儔僀傾儞偲寢崶偡傞偑丄晇偺椻崜偝偲堎忢側惈奿傪抦傝丄媠懸偵懴偊傜傟偢壠傪弌偰昦堾偺庴晅帠柋堳偲偟偰摥偒巒傔丄屬偄庡偱偁傞堛巘偺僕僃乕儉僗丒儊僀僜儞偲恊偟偔側傞丅擠怭偟偨斵彈偼儔僀傾儞偵屇傃栠偝傟壠偵栠傝丄恻梋嬋愜偺枛丄旀暰偟偨斵彈傪儊僀僜儞偑媬偆偲偄偆儊儘僪儔儅晽僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅嬥慘偵幏拝偡傞墶朶側嬥帩偪偺幚嬈壠儘僶乕僩丒儔僀傾儞偼僴儚乕僪丒僸儏乕僘偑儌僨儖偩偲偄偆丅僆僼儏儖僗摿桳偺棳傟傞傛偆側堏摦僇儊儔偼儀儖僎僨僗偲儊僀僜儞偺僫僀僩僋儔僽偱偺僟儞僗丒僔乕儞偵妶偐偝傟偰偄傞丅傑偨彈偑儃乕僩傪懸偮攇巭応偺僔乕儞傗丄奒抜傗媞娫偑塮偟弌偝傟傞崑揁偺儘乕丒僉乕嶣塭偼丄僲儚乕儖偺暤埻婥傪崅傔偰偄傞丅堎忢惈奿偺抝傪墘偠偝偣偰儘僶乕僩丒儔僀傾儞傎偳偺揔栶偼偄側偄丅僕僃乕儉僗丒儊僀僜儞偼僆僼儏儖僗偺傕偆堦偮偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖乽柍杁側弖娫乿偱傕庡墘偺僕儑乕儞丒儀僱僢僩傪彆偗傞抝傪墘偠偰偄偨丅帒嬥晄懌偺偨傔塮夋偺嵟屻偑怟愗傟僩儞儃偵側偭偨偺偑巆擮丅偍偲偟寠
1948丂傾儞僪儗丒僪丒僩僗丂昡揰 [C]
曐尟挷嵏堳偺僨傿僢僋丒僷僂僄儖偼丄峹奜偺儅僀儂乕儉偱掑廼側嵢僕僃乕儞丒儚僀傾僢僩偲壜垽偄懅巕偲暯壐側惗妶傪憲偭偰偄偨偑丄墶椞嵾偱孻柋強憲傝偵側偭偨抝偺垽恖儕僓儀僗丒僗僐僢僩偺枺椡偵晧偗偰堦栭傪嫟偵夁偛偡丅僗僐僢僩偵墶楒曠偡傞曐尟夛幮偺偍書偊扵掋偺儗僀儌儞僪丒僶乕偼僷僂僄儖傪悌偵偼傔偰嫼敆偟丄斵彈傪変偑傕偺偵偟傛偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅儕僓儀僗丒僗僐僢僩偼僼傽儉丒僼傽僞乕儖偩偑丄埆彈偱偼側偔慞椙側彈偱偁傝丄偦偙偑偙偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪偄傑偄偪報徾偺敄偄傕偺偵偟偰偄傞丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐100丂妋偐側榬偺怑恖娔撀愮梩懽庽偺塮夋3嶌
1956丂愮梩懽庽丂昡揰 [B]
 尮巵寋懢尨嶌偺柧楴僒儔儕乕儅儞塮夋丅庡墘偼嶰慏晀榊偲桳攏堫巕偩偑丄撪梕揑偵偼桳攏偑儊僀儞偱嶰慏偼彆墘偲尵偊傞丅怴擖幮堳偲偟偰夛幮偵廇怑偟偨桳攏偑丄彈惈幮堳偐傜幑搃偝傟偨傝丄僗僩憶偓偵姫偒崬傑傟偨傝丄庢堷夛幮偺幮挿屼憘巌偵尒弶傔傜傟偨傝偟側偑傜丄恻梋嬋愜偺枛丄夛幮偺愭攜偱偁傞杙鎐偱恖偺偄偄嶰慏偲寢偽傟傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅偙偺偲偒桳攏偼21嵨丄旤偟偔壜垽偄丅桳攏偲偄偊偽彫捗塮夋偱偺埫偄僀儊乕僕偑嫮偄偑丄偙偙偱偼庒乆偟偄敩檹偲偟偨枺椡傪敪嶶偟偰偄傞丅懠垽側偄塮夋偩偑岲姶傪妎偊傞丅
尮巵寋懢尨嶌偺柧楴僒儔儕乕儅儞塮夋丅庡墘偼嶰慏晀榊偲桳攏堫巕偩偑丄撪梕揑偵偼桳攏偑儊僀儞偱嶰慏偼彆墘偲尵偊傞丅怴擖幮堳偲偟偰夛幮偵廇怑偟偨桳攏偑丄彈惈幮堳偐傜幑搃偝傟偨傝丄僗僩憶偓偵姫偒崬傑傟偨傝丄庢堷夛幮偺幮挿屼憘巌偵尒弶傔傜傟偨傝偟側偑傜丄恻梋嬋愜偺枛丄夛幮偺愭攜偱偁傞杙鎐偱恖偺偄偄嶰慏偲寢偽傟傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅偙偺偲偒桳攏偼21嵨丄旤偟偔壜垽偄丅桳攏偲偄偊偽彫捗塮夋偱偺埫偄僀儊乕僕偑嫮偄偑丄偙偙偱偼庒乆偟偄敩檹偲偟偨枺椡傪敪嶶偟偰偄傞丅懠垽側偄塮夋偩偑岲姶傪妎偊傞丅婼壩
1956丂愮梩懽庽丂昡揰 [C]
惗妶偵崲媷偟偨昦婥偺晇傪夘岇偡傞恖嵢偑僈僗廤嬥恖偵椏嬥偺戙傢傝偵懱傪梫媮偝傟偰帺嶦偡傞偲偄偆丄媑壆怣巕尨嶌偺側傫偲傕婥偺柵擖傞埫偄撪梕偺塮夋丅1帪娫懌傜偢偺彫昳偩偑忋庤偔傑偲傑偭偰偄傞丅廤嬥恖偵壛搶戝夘丄恖嵢偵捗搰宐巕丅恖偼偄偄偑彫嗦偄抝傪壛搶戝夘偑岲墘偟偰偄傞丅庱傪捿偭偰巰傫偩恖嵢偺懌尦偱僈僗偑婼壩偺傛偆偵擱偊偰偄傞偺傪廤嬥恖偑敪尒偟丄敿嫸棎偱摝偘偰偄偔儂儔乕晽偺僔乕儞偱僄儞僪偲側傞丅
岲恖暔偺晇晈
1956丂愮梩懽庽丂昡揰 [C]
巙夑捈嵠尨嶌丄巕嫙偺偄側偄晇晈偺偁偄偩偵棫偭偨彫偝側攇晽傪昤偄偨丄偙傟傕1帪娫懌傜偢偺惷偐側彫昳丅晳戜偼偍偦傜偔姍憅偁偨傝偺奀娸偱偁傠偆丅偦偺偨傔偐彫捗塮夋傪憐婲偝偣側偔傕側偄丅夋壠偺晇傪墘偠傞偺偼抮晹椙偱嵢栶偼捗搰宐巕丅嵢偼慶曣偺娕昦偵偨傔戝嶃偵峴偭偰偄傞偁偄偩偵晇偑彈拞偵庤傪偮偗偨偲媈偆偑丄岆夝偩偭偨偲暘偐傝尦偺忊偵廂傑傞偲偄偆懠垽側偄榖偩偑丄儐乕儌儔僗側晽枴偲偟偭偲傝偟偨暤埻婥偼埆偔側偄丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐99丂朙揷巐榊娔撀偺暥寍塮夋2嶌
1956丂朙揷巐榊丂昡揰 [D]
朙揷巐榊偺暥寍塮夋2杮傪尒傞丅朙揷巐榊偲偄偊偽暥妛嶌昳偽偐傝嶣偭偰偄偨娔撀偱偁傝丄乽婂乿偲乽晇晈慞嵠乿偼偨偟偐偵柤嶌偱偁傞偲偼偄偊丄慡懱揑偵偼偦傟傎偳偺嶌壠惈偼姶偠傜傟側偄丅偙偺塮夋偼娭惣偺埌壆晅嬤傪晳戜偵丄峛斻惈側偟偺偖偆偨傜抝丄斵偑傂偨偡傜壜垽偑傞帞偄擫丄斵偺慜嵢偲屻嵢傪傔偖傞憶摦傪昤偄偨扟嶈弫堦榊偺彫愢偵婎偯偔僐儊僨傿丅偖偆偨傜抝傪怷斏媣栱丄慜嵢傪嶳揷屲廫楅丄屻嵢傪崄愳嫗巕丄抝偺曣恊偺偛偆偮偔攌傪楺壴愮塰巕偑墘偠偰偄傞丅搊応恖暔慡堳偑帺暘偺僄僑偲杮擻傪攳偒弌偟偵偟偰峴摦偟偰偍傝丄扤偵傕姶忣堏擖偱偒側偄丅嵊栚偡傋偒偼崄愳嫗巕偱丄偟偲傗偐偱惔弮側僀儊乕僕偺斵彈偑丄偙偙偱偼彑偪婥偱婥惈偺寖偟偄晜婥惈偺晄椙彈偵暞偟偰偍傝丄夋柺偱偼偄偮傕壓拝巔偐悈拝巔側偺偱偁偭偗偵偲傜傟傞丅廔斦偺嶳揷屲廫楅偲崄愳嫗巕偵傛傞庢偭慻傒崌偄偺偗傫偐僔乕儞偼憇愨丅嶌昳偲偟偰偼偦傟側傝偵忋庤偔傑偲傑偭偰偄傞偑丄偁傑傝岲偒側塮夋偱偼側偄丅
墂慜椃娰
1958丂朙揷巐榊丂昡揰 [C]
堜暁枑擇尨嶌丄忋栰奅孏偺椃娰傪晳戜偵丄廬嬈堳偺擔忢傗媞偺惗懺傪昤偄偨僐儊僨傿丅偙偺塮夋偑昡敾偲側偭偰搶曮偺墂慜僔儕乕僘偑惗傑傟偨丅榁曑椃娰偺斣摢栶偺怷斏媣栱偑庡恖岞丅儔僀僶儖椃娰偺斣摢偵敽弤嶰榊丄椃峴夛幮偺僣傾僐儞偵僼儔儞僉乕嶄丄椃娰偺庡恖偵怷愳怣偑暞偟偰偄傞丅愄偺忋栰墂偺岝宨丄憶乆偟偄廋妛椃峴偺惗搆丄儘僇價儕乕偵擬嫸偡傞庒幰側偳丄摉帪偺帪戙惈偑怓擹偔昞傟偰偍傝丄抍懱椃峴偺媞偨偪偑椃娰偱姫偒婲偙偡捒憶摦偑暔岅傜傟傞偲摨帪偵丄墴偟婑偣傞帪戙偺攇偺側偐偱嫃応強偑側偔側傞愄婥幙偺斣摢偺斶垼偑晜偒挙傝偵偝傟傞丅彈桪恮偼扺楬宐巕丄憪揓岝巕丄楺壴愮塰巕偲偄偆偍撻愼傒偺婄傇傟偩偑丄側傫偲偄偭偰傕堸傒壆偺彈彨偱怷斏偲婥怱傪捠偠崌傢偣傞扺搰愮宨偺壜垽偝偲旤偟偝偑嫮偔報徾偵巆傞丅擇恖偺棈傒偼柤嶌乽晇晈慞嵠乿傪渇渋偲偝偣傞丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐98丂惉悾枻婌抝偺屻婜偺巀斲傪屇傇壠懓塮夋2杮
1961丂惉悾枻婌抝丂昡揰 [C]
 慛楏側儕儕僔僘儉傪偨偨偊偨慜嶌乽廐棫偪偸乿偲偼懪偭偰曄傢偭偰丄晇晈偲晇偺垽恖偺嶰妏娭學偑攋抅偟丄壠掚偑曵夡偡傞偝傑傪昤偄偨丄惉悾偵偟偰偼捒偟偔偳傠偳傠偟偨埫偄塮夋丅戝妛嫵庼偺晇偺怷夒擵偲偦偺嵢偺扺搰愮宨丄怷偺垽恖偱扺搰偑宱塩偡傞嬧嵗偺僶乕偺儅僟儉崅曯廏巕偺3恖偺妺摗偑幉偵側偭偰偄傞丅怷偲扺搰偵偼2恖偺巕嫙偑偍傝丄幚偼偙偺巕嫙偨偪偼崅曯偑惗傫偩巕偩偑丄巕嫙傪惗傔側偄扺搰偑堷偒庢傝垽忣傪拲偓側偑傜堢偰偰偄傞丅晇偑嵢偺岞擣偱彈偲垽恖娭學傪懕偗傞偲偄偆愝掕偼丄晇栶偑怷夒擵偲偄偆偙偲傕偁傝丄乽晜塤乿傪巚傢偣傞丅偦傟偐偁傜偸偐丄夞憐僔乕儞偱昤偐傟傞愴帪壓偺扺搰偲偺弌夛偄傕乽晜塤乿傪渇渋偲偝偣傞丅嶰妏娭學偼埨掕偟偰偄偨偑丄愊擭偺墔擮偑昞弌偟丄崅曯偲扺搰偺慡柺懳寛偵敪揥偡傞丅2恖偺彈偼嵟廔揑偵桪廮晄抐偱恎彑庤側怷傪愑傔偨偰丄抝偺僄僑僀僘儉偑晜偒挙傝偵偝傟傞丅戝帪戙揑側怴攈寑偺傛偆偱丄惉悾偵偟偰偼偁傑傝偵僪儔儅惈偑嫮偡偓傞丅廔斦偵帺暘偨偪偑崅曯偺巕偩偭偨偙偲傪抦傜偝傟偰僔儑僢僋傪庴偗傞巓偲掜傪墘偠傞偺偼惎桼棦巕偲戝戲寬嶰榊丅惎偺壜垽偝偑嵺棫偭偰偄傞丅戝戲偼慜嶌偺乽廐棫偪偸乿偱庡墘偟偰偍傝丄偙偺梻擭偵傕乽彈偺嵗乿偱崅曯偺懅巕偵暞偟丄3嶌楢懕偱惉悾偺塮夋偵弌墘偡傞偙偲偵側傞丅斵傜偑戝恖偨偪傪憡庤偵偣偢丄帺暘偨偪偺椡偱婃挘偭偰惗偒偰偄偙偆偲柧傞偔尵偄崌偆僄儞僨傿儞僌偼丄寧暲傒偩偑媬偄傪姶偠偝偣傞丅崅曯偲摨嫃偡傞曣恊栶偺斞揷挶巕偺镚乆偲偟偨墘媄偑報徾偵巆傞丅
慛楏側儕儕僔僘儉傪偨偨偊偨慜嶌乽廐棫偪偸乿偲偼懪偭偰曄傢偭偰丄晇晈偲晇偺垽恖偺嶰妏娭學偑攋抅偟丄壠掚偑曵夡偡傞偝傑傪昤偄偨丄惉悾偵偟偰偼捒偟偔偳傠偳傠偟偨埫偄塮夋丅戝妛嫵庼偺晇偺怷夒擵偲偦偺嵢偺扺搰愮宨丄怷偺垽恖偱扺搰偑宱塩偡傞嬧嵗偺僶乕偺儅僟儉崅曯廏巕偺3恖偺妺摗偑幉偵側偭偰偄傞丅怷偲扺搰偵偼2恖偺巕嫙偑偍傝丄幚偼偙偺巕嫙偨偪偼崅曯偑惗傫偩巕偩偑丄巕嫙傪惗傔側偄扺搰偑堷偒庢傝垽忣傪拲偓側偑傜堢偰偰偄傞丅晇偑嵢偺岞擣偱彈偲垽恖娭學傪懕偗傞偲偄偆愝掕偼丄晇栶偑怷夒擵偲偄偆偙偲傕偁傝丄乽晜塤乿傪巚傢偣傞丅偦傟偐偁傜偸偐丄夞憐僔乕儞偱昤偐傟傞愴帪壓偺扺搰偲偺弌夛偄傕乽晜塤乿傪渇渋偲偝偣傞丅嶰妏娭學偼埨掕偟偰偄偨偑丄愊擭偺墔擮偑昞弌偟丄崅曯偲扺搰偺慡柺懳寛偵敪揥偡傞丅2恖偺彈偼嵟廔揑偵桪廮晄抐偱恎彑庤側怷傪愑傔偨偰丄抝偺僄僑僀僘儉偑晜偒挙傝偵偝傟傞丅戝帪戙揑側怴攈寑偺傛偆偱丄惉悾偵偟偰偼偁傑傝偵僪儔儅惈偑嫮偡偓傞丅廔斦偵帺暘偨偪偑崅曯偺巕偩偭偨偙偲傪抦傜偝傟偰僔儑僢僋傪庴偗傞巓偲掜傪墘偠傞偺偼惎桼棦巕偲戝戲寬嶰榊丅惎偺壜垽偝偑嵺棫偭偰偄傞丅戝戲偼慜嶌偺乽廐棫偪偸乿偱庡墘偟偰偍傝丄偙偺梻擭偵傕乽彈偺嵗乿偱崅曯偺懅巕偵暞偟丄3嶌楢懕偱惉悾偺塮夋偵弌墘偡傞偙偲偵側傞丅斵傜偑戝恖偨偪傪憡庤偵偣偢丄帺暘偨偪偺椡偱婃挘偭偰惗偒偰偄偙偆偲柧傞偔尵偄崌偆僄儞僨傿儞僌偼丄寧暲傒偩偑媬偄傪姶偠偝偣傞丅崅曯偲摨嫃偡傞曣恊栶偺斞揷挶巕偺镚乆偲偟偨墘媄偑報徾偵巆傞丅彈偺嵗
1962丂惉悾枻婌抝丂昡揰 [B]
2擭慜偺乽柡丒嵢丒曣乿偲摨偠傛偆側壺傗偐側晍恮偵傛傞僆乕儖僗僞乕壠懓塮夋丅攝栶偑崑壺偱丄妢抭廜偲悪懞弔巕偺榁晇晈丄偦偺柡偑忋偐傜弴偵嶰塿垽巕丄憪揓岝巕丄扺楬宐巕丄巌梩巕丄惎桼棦巕偲偄偆戝壠懓偩丅摨嫃偡傞朣偔側偭偨挿抝偺壟偑崅曯廏巕偱斵彈偑庡栶傪墘偠傞丅抝桪恮偼師抝偑儔乕儊儞壆傪塩傓彫椦宩庽丄傾僷乕僩傪宱塩偡傞挿彈偺晇偑壛搶戝夘丄幚壠偵揮偑傝崬傓嶰彈偺晇偑嶰嫶払栫丄偦偺傎偐丄曮揷柧丄抍椷巕丄扥垻栱栱捗巕丄壞栘梲夘偲偄偆丄惉悾塮夋偱偼偍撻愼傒偺婄傇傟丅偩偑堦斣偺忢楢偺拞杒愮巬巕偑偄側偄偺偼晄巚媍愮枩丅戝壠懓偺擔忢偑丄寢崶栤戣丄憡懕栤戣丄壟屍栤戣側偳傪棈傔側偑傜偨傫偨傫昤偐傟偰偍傝丄偦偺揰偱傕乽柡丒嵢丒曣乿傪巚傢偣傞丅傑偨丄朣偔側偭偨挿抝偺壟偑拞怱偲側偭偰嶨壿揦傪愗傝惙傝偟偰偄傞偲偄偆愝掕偼丄偙偺2擭屻偺乽棎傟傞乿傪憐婲偝偣傞偟丄榁晇晈偑嵟傕棅傝偵偡傞偺偼寣偺偮側偑傜側偄斵彈偩偲偄偆揰偱偼彫捗偺乽搶嫗暔岅乿偲帡偰偄傞丅偙傟偩偗偺懡嵤側搊応恖暔傪丄擔忢偺壗偘側偄僄僺僜乕僪傪棈傔側偑傜丄偦傟偧傟偺惈奿傪偒偭偪傝昤偒暘偗傞惉悾偺椡検偼偝偡偑偩丅儐乕儌儔僗側僔乕儞偑懡偔丄巌梩巕偲惎桼棦巕偺妡偗崌偄側偳偼偲傝傢偗旝徫傑偟偄丅崅曯偺傂偲傝懅巕偺巰偼搨撍偡偓傞姶偑偁傝丄憭媀偺僔乕儞傕傗傗忕挿側報徾傪梌偊傞丅偐偮偰偺惉悾側傜傕偭偲娙寜偵昤偄偰偄偨偩傠偆丅偙偺傛偆側怺崗側憓榖傕偁傞偵偣傛丄慡懱偲偟偰偺暤埻婥偼柧傞偄怓挷傪懷傃偰偄傞丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐97丂惉悾枻婌抝偺晇晈傕偺3晹嶌傪峔惉偡傞2杮
1953丂惉悾枻婌抝丂昡揰 [A]
 惉悾枻婌抝塮夋偺嵟屻偺曮偺嶳偵暘偗擖傝丄枹尒偩偭偨50乣60擭戙偺4嶌昳傪娪徿偡傞丅偙傟偼乽傔偟乿偵懕偔惉悾偺晇晈傕偺3晹嶌偺戞2嶌丅晇偺忋尨尓偺嵢栶偵偼慜嶌偲摨偠偔尨愡巕偑梊掕偝傟偰偄偨偑丄尨偑昦婥偵側偭偰悪梩巕偑敳揊偝傟偨丅偙偺塮夋偺偄偪偽傫偺枺椡偼悪梩巕偵偁傝丄斵彈偼偐偄偑偄偟偔晇偵恠偔偡怱桪偟偔旤偟偄嵢傪丄傢偞偲傜偟偝偺側偄帺慠側巇憪偱尒帠偵墘偠偰偄傞丅忋尨尓偼桪廮晄抐偱棅傝側偄晇傪墘偠偝偣偨傜揤壓堦昳偩丅偙偺塮夋偱偼寫懹婜偺晇晈偲偄偆栤戣偺傎偐偵丄廧戭擄偲擠怭偑僥乕儅偵側偭偰偄傞丅晇晈偼晇偺摨椈偱嵢傪朣偔偟偨嶰殸楢懢榊偺壠偵娫庁傝偡傞丅慜嶌偺乽傔偟乿偱偼柮偑搊応偟偰晇偲拠椙偔側傝丄晇晈偺偁偄偩偵攇晽偑棫偭偨偑丄偙偺塮夋偱攇晽傪棫偰傞偺偼嵢偲怱傪捠偄崌傢偣傞嶰殸楢懢榊偩丅廔斦丄嵢偑擠怭偟丄晇偼惗妶偑嬯偟偄偐傜拞愨偟傛偆偲尵偄丄嵢傕寵乆側偑傜偦傟偵廬偆偑丄嵟屻偵側偭偰峫偊傪曄偊丄擇恖偼側傫偲偐偟偰堢偰偰偄偙偆偲寛堄偟丄僴僢僺乕僄儞僪偲側傞丅塚壆傪塩傓嵢偺幚壠偺晝恊偺摗尨姍懌丄孼偺彫椦宩庽丄枀偺壀揷錆浠巕傕岲墘偟偰偍傝丄斵傜偺傗傝庢傝偑怱傪榓傑偣傞丅
惉悾枻婌抝塮夋偺嵟屻偺曮偺嶳偵暘偗擖傝丄枹尒偩偭偨50乣60擭戙偺4嶌昳傪娪徿偡傞丅偙傟偼乽傔偟乿偵懕偔惉悾偺晇晈傕偺3晹嶌偺戞2嶌丅晇偺忋尨尓偺嵢栶偵偼慜嶌偲摨偠偔尨愡巕偑梊掕偝傟偰偄偨偑丄尨偑昦婥偵側偭偰悪梩巕偑敳揊偝傟偨丅偙偺塮夋偺偄偪偽傫偺枺椡偼悪梩巕偵偁傝丄斵彈偼偐偄偑偄偟偔晇偵恠偔偡怱桪偟偔旤偟偄嵢傪丄傢偞偲傜偟偝偺側偄帺慠側巇憪偱尒帠偵墘偠偰偄傞丅忋尨尓偼桪廮晄抐偱棅傝側偄晇傪墘偠偝偣偨傜揤壓堦昳偩丅偙偺塮夋偱偼寫懹婜偺晇晈偲偄偆栤戣偺傎偐偵丄廧戭擄偲擠怭偑僥乕儅偵側偭偰偄傞丅晇晈偼晇偺摨椈偱嵢傪朣偔偟偨嶰殸楢懢榊偺壠偵娫庁傝偡傞丅慜嶌偺乽傔偟乿偱偼柮偑搊応偟偰晇偲拠椙偔側傝丄晇晈偺偁偄偩偵攇晽偑棫偭偨偑丄偙偺塮夋偱攇晽傪棫偰傞偺偼嵢偲怱傪捠偄崌傢偣傞嶰殸楢懢榊偩丅廔斦丄嵢偑擠怭偟丄晇偼惗妶偑嬯偟偄偐傜拞愨偟傛偆偲尵偄丄嵢傕寵乆側偑傜偦傟偵廬偆偑丄嵟屻偵側偭偰峫偊傪曄偊丄擇恖偼側傫偲偐偟偰堢偰偰偄偙偆偲寛堄偟丄僴僢僺乕僄儞僪偲側傞丅塚壆傪塩傓嵢偺幚壠偺晝恊偺摗尨姍懌丄孼偺彫椦宩庽丄枀偺壀揷錆浠巕傕岲墘偟偰偍傝丄斵傜偺傗傝庢傝偑怱傪榓傑偣傞丅嵢
1953丂惉悾枻婌抝丂昡揰 [C]
乽傔偟乿乽晇晈乿偵懕偔晇晈傕偺3晹嶌偺嵟廔嶌丅晇晈傪墘偠傞偺偼忋尨尓偲崅曯嶰巬巕丅3嶌偺側偐偱偼偄偪偽傫怺崗側撪梕偱丄懠偺2嶌偱偼晇晈偺婋婡偼枹慠偵夞旔偝傟丄拠捈傝偡傞偑丄偙偺乽嵢乿偱偼晇偑幚嵺偵夛幮偺摨椈偺帠柋堳扥垻栱栱捗巕偲晜婥偟偰擏懱娭學傪傕偪丄嵢偑扥垻栱偺壠偵忔傝崬傫偱媗傝丄扥垻栱偼恎傪堷偔偑丄晇晈娭學偺椻偨偝偼夝徚偝傟側偄丅塮夋偺朻摢丄晇偑栙偭偰弌嬑偺偨傔壠傪弌偰丄嵢傕栙偭偰偦傟傪尒憲傞偑丄僄儞僨傿儞僌偱傕傑偭偨偔摨偠椻偊椻偊偟偨岝宨偑孞傝曉偝傟傞丅崅曯偑敘傪梜巬戙傢傝偵巊偄丄偍拑偱岥傪偡偡偄偱堸傒崬傒丄偦傟傪忋尨偑寵偦偆偵尒傞僔乕儞偑寫懹婜偺枴婥側偄晇晈娭學傪帵偟偰偄傞丅晇晈偑廧傫偱偄傞偺偼慜2嶌偲堘偭偰帩偪壠偱丄2奒傪娫戄偟偟偰偄傞偑丄娫庁傝恖偺傂偲傝偲偟偰慜嶌偵懕偄偰弌墘偟偰偄傞嶰殸楢懢榊偺偲傏偗偨枴傢偄偑丄慡懱偺埫偄怓挷偵柧傞偝傪揧偊偰偄傞丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐96丂僕僃乕儉僘丒僉儍僌僯乕偑恀壙傪敪婗偟偨傾僋僔儑儞塮夋
1939丂僂傿儕傾儉丒僉乕儕乕丂昡揰 [C]
埆摽惌帯壠偺晄惓傪朶偄偨偨傔悌偵偐偗傜傟搳崠偝傟傞怴暦婰幰偺嬯摤傪昤偄偨僪儔儅丅婰幰栶偵僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕丄孻柋強偱抦傝崌偭偰僉儍僌僯乕偲桭忣傪寢傇僊儍儞僌偵僕儑乕僕丒儔僼僩偑暞偡傞丅媊嫚怱傪敪婗偟丄僉儍僌僯乕傪彆偗偰巰偸儔僼僩偑僇僢僐傛偔丄庡栶偺僉儍僌僯乕傪怘偭偰偄傞丅
塰岝偺搒
1940丂傾僫僩乕儖丒儕僩償傽僋丂昡揰 [B]
僯儏乕儓乕僋偺壓挰偵廧傓彮擭彮彈偑惉岟傪柌尒偰偦傟偧傟偺摴傪曕傓丅僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕偼儃僋僒乕丄偦偺掜偺傾乕僒乕丒働僱僨傿偼壒妝壠丄僉儍僌僯乕偺楒恖傾儞丒僔僃儕僟儞偼僟儞僒乕傪栚巜偡丅抂栶偱庒偒僄儕傾丒僇僓儞偲傾儞僜僯乕丒僋僀儞偑弌墘偟偰偄傞丅帋崌拞偵憡庤偺儃僋僒乕偺斱楎側斀懃偱幐柧偟丄怴暦攧傝巕傪偡傞僉儍僌僯乕偑丄掜偑巜婗偡傞僆乕働僗僩儔偺墘憈傪儔僕僆偱挳偄偰偄傞偲偙傠偵丄僟儞僗丒僣傾乕偺弰嬈傪巭傔偰僔僃儕僟儞偑婣偭偰偒偰斵偵婑傝揧偄丄僄儞僪偲側傞丅
2020擭12寧朸擔 旛朰榐95丂岲娍僕僃乕儉僘丒僉儍僌僯乕偺僊儍儞僌塮夋偺戙昞嶌
1938丂儅僀働儖丒僇乕僥傿僗丂昡揰 [C]
30擭戙屻敿偺僕僃乕儉僘丒僉儍僌僯乕偑庡墘偟偨僊儍儞僌塮夋傪4杮傑偲傔偰尒偨丅偙偺塮夋偼僉儍僌僯乕偺僊儍儞僌塮夋偺戙昞嶌偺傂偲偮偲栚偝傟偰偄傞偑丄恾幃揑側僙儞僠儊儞僞儕僘儉偑栚棫偮丅僊儍儞僌偺僉儍僌僯乕偼嶦恖嵾偱曔傑傝丄巰孻傪愰崘偝傟傞偑丄巰孻幏峴偵嵺偟偰丄梒側偠傒偺杚巘僷僢僩丒僆僽儔僀僄儞偺棅傒傪暦偒擖傟丄僉儍僌僯乕偵摬傟傞彮擭偨偪傪尪柵偝偣傞偨傔丄傢偞偲媰偒嫨傫偱忣偗側偄巔傪偝傜偡丅僉儍僌僯乕偺楒恖栶偵傾儞丒僔僃儕僟儞丄揋栶偺埆摽曎岇巑偵僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偑暞偟偰偄傞丅
斵搝偼婄栶偩
1939丂儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏丂昡揰 [A]
 偙傟傕僉儍僌僯乕偺僊儍儞僌塮夋傪戙昞偡傞堦嶌偱丄儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏偺僣儃傪怱摼偨僗僺乕僨傿側墘弌丄僉儍僌僯乕偺偒傃偒傃偟偨墘媄偵傛傝丄柤嶌偵巇忋偑偭偨丅尨戣乽The Roaring Twenties乿偳偍傝丄嬛庰朄壓偺20擭戙傪晳戜偵丄戞1師戝愴偺愴桭3恖偺桭忣偲棤愗傝偑昤偐傟傞丅愴憟偐傜婣娨偟偨帺摦幵惍旛岺偺僉儍僌僯乕偼僞僋僔乕塣揮庤偲偟偰摥偒巒傔丄枾憿庰偺塣斃偱壱偖傛偆偵側傝丄戝傕偆偗偟偰埫崟奨偺戝暔偵偺偟忋偑傞偑丄戝嫲峇偱堦暥柍偟偵側傞丅僉儍僌僯乕偑垽偟偨彈僾儕僔儔丒儗僀儞偼偐偮偰偺愴桭偱斵偲逶傪暘偐偭偨惓媊攈曎岇巑僕僃僼儕乕丒儕儞偲寢偽傟傞丅偄傑傗楇棊偟偨斵偲怱傪捠偄崌傢偣傞偺偼僫僀僩僋儔僽傪宱塩偟偰偄偨擭憹偺彈僌儔僨傿僗丒僕儑乕僕偩偗偩丅僉儍僌僯乕偺愴桭偺傂偲傝偱戝暔僊儍儞僌偵側偭偨僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偐傜嫼敆偝傟偨儕儞偼丄僉儍僌僯乕偵彆偗傪媮傔傞丅僉儍僌僯乕偼儗僗僩儔儞偱儃僈乕僩傪寕偪嶦偡偑丄帺暘傕巕暘偵寕偨傟偰巰偸丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅弌墘幰偨偪偺惈奿偑偒偭偪傝昤偒暘偗傜傟偰偄傞偺偑尒帠偩偟丄拞斦偺憅屔廝寕僔乕儞偲廔斦偺儗僗僩儔儞偱偺廵寕僔乕儞傕敆椡枮揰丅棊偪傇傟偨僉儍僌僯乕偑尒偣傞嫚婥偑怱傪懪偮丅嵟屻丄愥偺崀傞側偐丄僉儍僌僯乕偑奒抜偱愨柦偡傞儔僗僩丒僔乕儞偼慺惏傜偟偔丄枩姶偑嫻偵敆傞丅
偙傟傕僉儍僌僯乕偺僊儍儞僌塮夋傪戙昞偡傞堦嶌偱丄儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏偺僣儃傪怱摼偨僗僺乕僨傿側墘弌丄僉儍僌僯乕偺偒傃偒傃偟偨墘媄偵傛傝丄柤嶌偵巇忋偑偭偨丅尨戣乽The Roaring Twenties乿偳偍傝丄嬛庰朄壓偺20擭戙傪晳戜偵丄戞1師戝愴偺愴桭3恖偺桭忣偲棤愗傝偑昤偐傟傞丅愴憟偐傜婣娨偟偨帺摦幵惍旛岺偺僉儍僌僯乕偼僞僋僔乕塣揮庤偲偟偰摥偒巒傔丄枾憿庰偺塣斃偱壱偖傛偆偵側傝丄戝傕偆偗偟偰埫崟奨偺戝暔偵偺偟忋偑傞偑丄戝嫲峇偱堦暥柍偟偵側傞丅僉儍僌僯乕偑垽偟偨彈僾儕僔儔丒儗僀儞偼偐偮偰偺愴桭偱斵偲逶傪暘偐偭偨惓媊攈曎岇巑僕僃僼儕乕丒儕儞偲寢偽傟傞丅偄傑傗楇棊偟偨斵偲怱傪捠偄崌傢偣傞偺偼僫僀僩僋儔僽傪宱塩偟偰偄偨擭憹偺彈僌儔僨傿僗丒僕儑乕僕偩偗偩丅僉儍僌僯乕偺愴桭偺傂偲傝偱戝暔僊儍儞僌偵側偭偨僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偐傜嫼敆偝傟偨儕儞偼丄僉儍僌僯乕偵彆偗傪媮傔傞丅僉儍僌僯乕偼儗僗僩儔儞偱儃僈乕僩傪寕偪嶦偡偑丄帺暘傕巕暘偵寕偨傟偰巰偸丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅弌墘幰偨偪偺惈奿偑偒偭偪傝昤偒暘偗傜傟偰偄傞偺偑尒帠偩偟丄拞斦偺憅屔廝寕僔乕儞偲廔斦偺儗僗僩儔儞偱偺廵寕僔乕儞傕敆椡枮揰丅棊偪傇傟偨僉儍僌僯乕偑尒偣傞嫚婥偑怱傪懪偮丅嵟屻丄愥偺崀傞側偐丄僉儍僌僯乕偑奒抜偱愨柦偡傞儔僗僩丒僔乕儞偼慺惏傜偟偔丄枩姶偑嫻偵敆傞丅2020擭11寧
2020擭11寧朸擔 旛朰榐94丂偝偭傁傝椙偝偑暘偐傜側偄僑僟乕儖塮夋
彈偲抝偺偄傞曑摴丂1962丂僕儍儞亖儕儏僢僋丒僑僟乕儖丂昡揰 [C]
傾儖僼傽償傿儖丂1965丂僕儍儞亖儕儏僢僋丒僑僟乕儖丂昡揰 [D]
儊僀僪丒僀儞丒USA丂1967丂僕儍儞丒亖儕儏僢僋丒僑僟乕儖丂昡揰 [D]
僑僟乕儖偺60擭戙偺塮夋傪傑偲傔偰尒偨偑丄憤偠偰偁傑傝柺敀偔側偄丅偡傋偰傾儞僫丒僇儕乕僫偑弌墘偟偰偍傝丄斵彈偺僐働僥傿僢僔儏側枺椡傪姮擻偱偒偨偙偲偼廂妌偩偭偨偑丅偙偺4杮偺側偐偱偼丄傾儞僫丒僇儕乕僫偑彥晈偵棊偪傇傟丄嵟屻偼柍巆偵楬忋偱幩嶦偝傟傞彈傪墘偠偨乽彈偲抝偺偄傞曑摴乿偑偄偪偽傫傑偲傕側嶌傝偱塮夋揑嫽庯偑偁傝丄抐敮偺僇儕乕僫傕偁偱傗偐偩丅傎偐偼丄傾儖僕僃儕傾暣憟傪戣嵽偵偟偨僗僷僀塮夋乽彫偝側暫戉乿傕丄枹棃搒巗偱偺妶寑僴乕僪儃僀儖僪塮夋乽傾儖僼傽償傿儖乿傕丄儕僠儍乕僪丒僗僞乕僋偺埆搣僷乕僇乕彫愢偑尨埬偩偲偄偆乽儊僀僪丒僀儞丒USA乿傕丄搊応恖暔偨偪偑傗偨傜偵摦偒夞傝丄漟抳偝傟偨傝崏栤偝傟偨傝捛愓偟偨傝敪朇偟偨傝偡傞偑丄榖偺揥奐偑偝偭傁傝暘偐傜側偄偟丄僑僟乕儖摿桳偺帊傗彫愢傗揘妛彂偺堷梡偑偪傝偽傔傜傟丄抦揑僗僲價僘儉偑旲偵偮偄偰丄戅孅偟偐姶偠側偐偭偨丅
2020擭11寧朸擔 旛朰榐93丂婏柇偩偑峈偟偑偨偄枺椡傪曻偮僇僂儕僗儅僉偺塮夋
僴儉儗僢僩丒僑乕僘丒價僕僱僗丂1987丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰 [C]
恀栭拞偺擑丂1988丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰 [B]
儅僢僠岺応偺彮彈丂1990丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰 [C]
僐儞僩儔僋僩丒僉儔乕丂1990丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰 [B]
儔償傿丒僪丒儃僄乕儉丂1992丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂昡揰 [B]
 僼傿儞儔儞僪偺塮夋嶌壠傾僉丒僇僂儕僗儅僉偺弶婜偐傜拞婜偵偐偗偰偺嶌昳傪6杮尒偨丅斵偺塮夋偺懡偔偼楯摥幰傗幐嬈幰側偳丄幮夛偺掙曈偵偄傞幰偨偪偱偁傝丄斵傜偑懱尡偡傞幮夛偺晄惓媊傗晄忦棟偑丄僪儔儅惈傪攔偟偨扺乆偲偟偨僞僢僠偱昤偐傟傞丅偦偙偐傜偼岻傑偞傞儐乕儌傾偲姡偄偨彇忣偑棫偪忋傝丄镚乆偲偟偨枴傢偄傪忴偟弌偡丅攐桪偨偪偼戝偘偝側墘媄傗偙傟尒傛偑偟偺摦嶌傪堦愗偟側偄丅偦偺揰偱偼宧垽偡傞彫捗埨擇榊偐傜偺塭嬁偑姶偠傜傟傞偟丄傑偨儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偲傕堦柆捠偠傞傕偺偑偁傞丅摨偠偔彫捗傪懜宧偡傞儂僂丒僔儍僆僔僃儞丄僕儉丒僕儍乕儉僢僔儏丄傾儗僋僒儞僟乕丒儁僀儞側偳偺嶌晽偲傕帡捠偭偰偄傞丅僇僥傿丒僆僂僥傿僱儞傗儅僢僥傿丒儁儘儞僷乕偲偄偭偨屄惈揑側攐桪偑忢楢偱偟偽偟偽庡栶傪柋傔傞偺偑嫽庯傪偦偦傞丅
僼傿儞儔儞僪偺塮夋嶌壠傾僉丒僇僂儕僗儅僉偺弶婜偐傜拞婜偵偐偗偰偺嶌昳傪6杮尒偨丅斵偺塮夋偺懡偔偼楯摥幰傗幐嬈幰側偳丄幮夛偺掙曈偵偄傞幰偨偪偱偁傝丄斵傜偑懱尡偡傞幮夛偺晄惓媊傗晄忦棟偑丄僪儔儅惈傪攔偟偨扺乆偲偟偨僞僢僠偱昤偐傟傞丅偦偙偐傜偼岻傑偞傞儐乕儌傾偲姡偄偨彇忣偑棫偪忋傝丄镚乆偲偟偨枴傢偄傪忴偟弌偡丅攐桪偨偪偼戝偘偝側墘媄傗偙傟尒傛偑偟偺摦嶌傪堦愗偟側偄丅偦偺揰偱偼宧垽偡傞彫捗埨擇榊偐傜偺塭嬁偑姶偠傜傟傞偟丄傑偨儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偲傕堦柆捠偠傞傕偺偑偁傞丅摨偠偔彫捗傪懜宧偡傞儂僂丒僔儍僆僔僃儞丄僕儉丒僕儍乕儉僢僔儏丄傾儗僋僒儞僟乕丒儁僀儞側偳偺嶌晽偲傕帡捠偭偰偄傞丅僇僥傿丒僆僂僥傿僱儞傗儅僢僥傿丒儁儘儞僷乕偲偄偭偨屄惈揑側攐桪偑忢楢偱偟偽偟偽庡栶傪柋傔傞偺偑嫽庯傪偦偦傞丅乽僷儔僟僀僗偺梉曢傟乿乽恀栭拞偺擑乿乽儅僢僠岺応偺彮彈乿偼晧偗將嶰晹嶌偲屇偽傟偰偄傞丅乽僷儔僟僀僗偺梉曢傟乿偺庡恖岞偼僑儈惔憒幵偺塣揮庤傪柋傔傞晄婍梡偩偑恀柺栚側抝偱丄僗乕僷乕偺儗僕學偺屒撈側彈偲婏柇側楒垽傪偡傞丅乽恀栭拞偺擑乿偺庡恖岞偼扽峼偑暵嵔偝傟偰怑傪幐偭偨抝丄僿儖僔儞僉偵弌偰偒偰擔屬偄偱壱偖斵偼挀幵堘斀偺愗晞愗傝偺巕帩偪彈偲抦傝崌偄丄摨惐偡傞丅抝偼柍幚偺嵾偱戇曔偝傟傞偑扙憱偟偰彈偲偲傕偵儊僉僔僐偵摝偘傞丅乽儅僢僠岺応偺彮彈乿偼3嶌偺側偐偱偄偪偽傫斶嶴偱媬偄偺側偄僗僩乕儕乕偩丅戣柤偳偍傝儅僢僠岺応偱摥偔彈偑庡恖岞丅斵彈偼壠偱墶朶側媊晝偲偖偆偨傜側曣偺柺搢傪尒偰偄傞丅僟儞僗僋儔僽偱夛偭偨抝偲堦栭傪夁偛偟偰擠怭偡傞偑偑抝偵幪偰傜傟偨斵彈偼丄栻嬊偱攦偭偨僱僐僀儔僘偱抝傪嶦偟丄偝傜偵媊晝偲曣恊傕嶦奞偡傞丅乽僴儉儗僢僩丒僑乕僘丒價僕僱僗乿偼僔僃僀僋僗僺傾偺乽僴儉儗僢僩乿傪尰戙幮夛偺弌棃帠偵堏偟懼偊偨僷儘僨傿丅乽僐儞僩儔僋僩丒僉儔乕乿偼儘儞僪儞傪晳戜偵偟偨僕儍儞僺僄乕儖丒儗僆庡墘偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖晽僐儊僨傿偱丄庡恖岞偼恖惗偵愨朷偟偰巰偺偆偲偡傞偑巰偵偒傟偢丄帺暘傪嶦偝偣傞偨傔偵嶦偟壆傪屬偆偑丄壴攧傝柡偵弌夛偭偰楒偵棊偪丄惗偒傞婓朷傪庢傝栠偡傕偺偺丄嶦偟壆偵廝傢傟偰峇偰傆偨傔偔偲偄偆榖丅嶦偟壆傪墘偠傞働僱僗丒僋儔乕僋偑恖娫枴偵偁傆傟偰偍傝丄僶乕偺恊晝偵暞偡傞僙儖僕儏丒儗僕傾僯偺屚傟偨晽奿傕報徾怺偄丅乽儔償傿丒僪丒儃僄乕儉乿偼僷儕偑晳戜丅偦傟偧傟夋壠丄嶌壠丄壒妝壠偲偟偰惉岟傪柌尒側偑傜嫟摨惗妶偡傞3恖偺昻偟偄庒幰偺桭忣傪昤偄偨丄屆偒椙偒帪戙偺僼儔儞僗塮夋傪巚傢偣傞恖忣塮夋丅塮夋娔撀僒儈儏僄儖丒僼儔乕偲儖僀丒儅儖偑摿暿弌墘偡傞丅僄儞僨傿儞僌偱忣姶朙偐偵棳傟傞壧偼丄側傫偲擔杮岅偱壧傢傟傞乽愥偺崀傞挰傪乿偩丅
2020擭11寧朸擔 旛朰榐92丂榁偄偰側偍晽奿傪昚傢偣傞僕儍儞丒僊儍僶儞偺2嶌
1959丂僕儍儞丒僪儔僲儚丂昡揰 [B]
僕儍儞丒僊儍僶儞庡墘偺恖忣僪儔儅丅僊儍儞僽儖岲偒偱僾儗僀儃乕僀偺昻朢抝庉僊儍僶儞偑丄偁傞斢僇乕僪丒僎乕儉偱戝彑偪偟丄崑壺側儓僢僩傪庤偵擖傟傞丅斵偼愄偺楒恖儈僔儏儕乕僰丒僾儗乕儖傪桿偭偰僆儔儞僟傊偺慏椃偵弌偐偗傞偑丄愳忋傝偺嵟拞丄僼儔儞僗偺揷幧偱僈僗寚偵側傝丄柍堦暥偱偱棫偪墲惗偡傞丅僾儗乕儖偼儗僗僩儔儞偱抧尦偺杙鎐側儚僀儞忴憿庡偲堄婥搳崌偟偰寢崶偺偨傔慏傪壓傝傞丅僊儍僶儞偼慏拝偒応偺慜偺埨怘摪偵擖傝怹偭偰忢楢媞偺拠娫偵擖傝丄怘摪偺彈庡恖偲婥帩偪傪捠偄崌傢偣傞丅傗偑偰僊儍僶儞偺尦偵嬥偑撏偒丄彈庡恖偑尒憲傞側偐丄斵偼堄婥梘乆偲慏弌偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偨偁偄側偄榖偩偑丄儐乕儌傾偺側偐偵偦偙偼偐偲側偄垼姶偑昚偭偰偍傝丄幪偰偑偨偄枴傢偄偑偁傞丅僕儍儞丒僊儍僶儞偺镚乆偲偟偨帩偪枴偑妶偐偝傟偰偍傝丄嫟墘偺儈僔儏儕乕僰丒僾儗乕儖傕僐働僥傿僢僔儏側枺椡傪敪嶶偟偰偄傞丅
恊暘偼斀峈偡傞
1961丂僕儖丒僌儔儞僕僃丂昡揰 [C]
偙傟傕僕儍儞丒僊儍僶儞庡墘偺儐乕儌傾傪岎偊偨斊嵾塮夋丅儀儖僫乕儖丒僽儕僄傪偼偠傔偲偡傞3恖偺彫埆搣偑僯僙嬥偱堦栕偗偟傛偆偲婇傒丄撿暷偵塀撡偟偰偄偨偦偺摴偺僾儘丄弶榁偺僕儍儞丒僊儍僶儞傪屇傃婑偣傞丅僊儍僶儞偺巜恾偺傕偲丄斵傜偼桪廏側報嶞怑恖傪屬偄丄僯僙嬥嶌傝偵拝庤偡傞丅3恖偼僊儍僶儞傪弌偟敳偙偆偲偡傞偑丄媡偵僊儍僶儞偼怑恖偲帵偟崌傢偣丄嶞傝忋偑偭偨僯僙嶥傪傂偦偐偵攧傝暐偭偰摝憱偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅慡懱偵暤埻婥偑娚枬偱偺傫傃傝偟偰偍傝丄偁傑傝柺敀偔側偄丅怑恖偺嵢偵儅儖僠乕僰丒僉儍儘儖丄僊儍僶儞偺媽抦偺彈偱報嶞梡偺巻傪庤攝偡傞彈偵僼儔儞僜儚乕僘丒儘僛乕偑暞偟偰偄傞丅
2020擭11寧朸擔 旛朰榐91丂50擭戙屻婜丄惉悾枻婌抝偲尨愡巕偺堎怓嶌
1959擭丂惉悾枻婌抝丂昡揰 [B]
 娔撀偺惉悾枻婌抝偲偟偰偼偒傢傔偰堎怓偺塮夋丅愇怷墑抝尨嶌偺帣摱彫愢偺塮夋壔丅巕嫙偺偙傠丄暦偄偰偼偄側偐偭偨偑丄儔僕僆僪儔儅偱偙偺乽僐僞儞偺岥揓乿傪曻憲偟偰偄偨婰壇偑偁傞丅杒奀摴偺傾僀僰恖晹棊偵廧傓拞妛3擭惗偺巓偲1擭惗偺掜偑庡恖岞丅偙偺2恖偑昻偟偝偲曃尒偵懴偊側偑傜偗側偘偵惗偒偰偄偔巔偑昤偐傟傞丅嵢傪朣偔偟偰抝庤傂偲偮偱2恖傪堢偰傞晝恊偵怷夒擵丄巓偑摬傟傞旤弍偺嫵巘偵曮揷柧丄棟夝椡偺偁傞峑挿偵巙懞嫪偲偄偭偨幚椡偁傞栶幰偑榚傪屌傔偰偄傞丅偙偺塮夋偼晄昡偱幐攕嶌偲尵傢傟偰偄傞丅偨偟偐偵惉悾枻婌抝偵偙偺傛偆側幮夛惈偺偁傞戣嵽偼帡崌傢側偄偟丄偄傢傟側偒嵎暿傪崘敪偡傞巔惃偵傕掙偺愺偄姶偠傪斲傔側偄丅偟偐偟僗僩乕儕乕偼偨傫偨傫偲偟偨棳傟偺側偐偵偄傠傫側帠審傗憓榖偑岻傒偵棈傒丄攋抅側偔恑傫偱偄傞偟丄戝恖偺栶幰傕偦偆偩偑丄巕嫙偨偪偺墘媄傕偒傢傔偰帺慠偱岲姶偑帩偰傞丅偦偟偰旤弍偺拞屆抭偑愳偺傎偲傝偺傾僀僰恖晹棊偺僙僢僩傪尒帠偵嶌傝忋偘偰偄傞丅掜偑愳偱掁傝傪偡傞僔乕儞傗丄庡恖岞偨偪偺椬壠偵廧傓榁攌偺栰曈憲傝偺僔乕儞側偳丄報徾揑側応柺傕偁傝丄偦傟傎偳埆偄弌棃偲偼巚偊側偄丅
娔撀偺惉悾枻婌抝偲偟偰偼偒傢傔偰堎怓偺塮夋丅愇怷墑抝尨嶌偺帣摱彫愢偺塮夋壔丅巕嫙偺偙傠丄暦偄偰偼偄側偐偭偨偑丄儔僕僆僪儔儅偱偙偺乽僐僞儞偺岥揓乿傪曻憲偟偰偄偨婰壇偑偁傞丅杒奀摴偺傾僀僰恖晹棊偵廧傓拞妛3擭惗偺巓偲1擭惗偺掜偑庡恖岞丅偙偺2恖偑昻偟偝偲曃尒偵懴偊側偑傜偗側偘偵惗偒偰偄偔巔偑昤偐傟傞丅嵢傪朣偔偟偰抝庤傂偲偮偱2恖傪堢偰傞晝恊偵怷夒擵丄巓偑摬傟傞旤弍偺嫵巘偵曮揷柧丄棟夝椡偺偁傞峑挿偵巙懞嫪偲偄偭偨幚椡偁傞栶幰偑榚傪屌傔偰偄傞丅偙偺塮夋偼晄昡偱幐攕嶌偲尵傢傟偰偄傞丅偨偟偐偵惉悾枻婌抝偵偙偺傛偆側幮夛惈偺偁傞戣嵽偼帡崌傢側偄偟丄偄傢傟側偒嵎暿傪崘敪偡傞巔惃偵傕掙偺愺偄姶偠傪斲傔側偄丅偟偐偟僗僩乕儕乕偼偨傫偨傫偲偟偨棳傟偺側偐偵偄傠傫側帠審傗憓榖偑岻傒偵棈傒丄攋抅側偔恑傫偱偄傞偟丄戝恖偺栶幰傕偦偆偩偑丄巕嫙偨偪偺墘媄傕偒傢傔偰帺慠偱岲姶偑帩偰傞丅偦偟偰旤弍偺拞屆抭偑愳偺傎偲傝偺傾僀僰恖晹棊偺僙僢僩傪尒帠偵嶌傝忋偘偰偄傞丅掜偑愳偱掁傝傪偡傞僔乕儞傗丄庡恖岞偨偪偺椬壠偵廧傓榁攌偺栰曈憲傝偺僔乕儞側偳丄報徾揑側応柺傕偁傝丄偦傟傎偳埆偄弌棃偲偼巚偊側偄丅彈廁偲嫟偵
1956丂媣徏惷帣丂昡揰 [C]
36嵨偺尨愡巕庡墘丄彈惈孻柋強傪晳戜偵丄孻柋姱偲彈廁偺懳棫偲岎棳傪昤偄偨幮夛攈僪儔儅丅攐桪恮偑偨偄傊傫崑壺偩丅尨愡巕偑墘偠傞偺偼孻柋姱傪棪偄傞壽挿丅傎偐偵丄孻柋強挿偵揷拞對戙丄彈廁偵偼媣変旤巕丄崄愳嫗巕丄壀揷錆浠巕丄悪梩巕丄扺楬宐巕丄彫曢幚愮戙丄楺壴愮塰巕側偳偑暞偟偰偄傞丅偝傑偞傑側斶偟偄夁嫀傪帩偭偨彈廁偑擖強偟丄斵彈偨偪偺婲偙偟偨帠審偑僼儔僢僔儏僶僢僋偱暔岅傜傟傞丅椡嶌偩偑丄慡懱偲偟偰掙偑愺偔恾幃揑偱丄強挿傗壽挿傪偼偠傔偲偡傞孻柋姱偼傒側慞椙偱擬怱偵彈廁傪悽榖偡傞偟丄斀峈揑偩偭偨彈廁傕嵟屻偵偼夵怱偡傞丅偺偪偵埆栶愱栧偵側偭偨忋揷媑擇榊偑恀柺栚側孻柋強怑堳傪墘偠偰偄傞偺偵栚傪尒挘偭偨丅
2020擭11寧朸擔 旛朰榐90丂50擭戙敿偽丄崟郪柧媟杮偺堩昳2嶌
1953丂扟岥愮媑丂昡揰 [B]
媟杮偼娔撀偺扟岥偲崟郪柧偺嫟嶌丅庡墘偼嶰慏晀榊丅嶰慏暞偡傞僞僋僔乕塣揮庤偑憳嬾偡傞偝傑偞傑側媞偲弌棃帠傪僆儉僯僶僗晽偵捲偭偨塮夋丅媞偲偟偰忔偭偰偔傞偺偼丄彫愹攷偲壀揷錆浠巕偺傾儀僢僋丄墘寑僗僞乕偺墇楬悂愥丄悓偭暐偄偺彫椦宩庽偲摗尨姌懌丄嫮搻偺嶰殸楢懢榊丄梷棷偐傜偺婣崙偟偨嶳懞汔偲丄懡巑嵪乆丅儐乕儌傾偲垼姶偑側偄傑偤偵嶶傝偽傔傜傟偰偍傝丄嶰慏偺寍払幰傇傝傕側偐側偐偺傕偺偱丄偦傟側傝偵妝偟傔傞丅
偁偡側傠暔岅
1955丂杧愳峅捠丂昡揰 [B]
堜忋桋尨嶌偺楢嶌抁曇彫愢廤偺塮夋壔丅掜巕偺杧愳峅捠偺娔撀僨價儏乕嶌偺偨傔偵崟郪柧偑媟杮傪彂偄偨丅傏偔偼巕嫙偺偙傠偵偙偺彫愢傪撉傫偱姶柫傪庴偗偰偄傞丅彮擭偺惉挿暔岅偱丄彫妛6擭惗丄拞妛3擭惗丄崅峑3擭惗偺偦傟偧傟偵帪婜偵彮擭偑弌夛偭偨擭忋偺彈惈傊偺巚曠丄偦偺弌夛偄偲暿傟偑昤偐傟傞丅戞1榖偼嶳懞偱慶曣偲曢傜偡彮擭偲壠偵揮偑傝崬傫偩恊愂偺柡壀揷錆浠巕偲偺僄僺僜乕僪丅戞2榖偼慶曣偑朣偔側偭偰帥偵梐偗傜傟偨彮擭偲廧怑偺柡崻娸柧旤偲偺僄僺僜乕僪丅戞3榖偼杤棊偟偮偮偁傞媽壠偵壓廻偟偨庡恖岞偲偦偺壠偺傂偲傝柡媣変旤巕偲偺僄僺僜乕僪丅搊応偡傞彈惈偨偪偼傒側彑偪婥偱堄巙偑嫮偔丄彮擭偼斵彈偨偪偲弌夛偭偰東楳偝傟偨傝姶壔偝傟偨傝偡傞丅戞1榖偱彮擭偑弌夛偆惵擭栘懞岟偵傛偭偰岅傜傟傞乽偁偡側傠偺栘乿偺堩榖乗乗偁偡側傠偼偄偮傕瀢偵側傠偆偲偟偰婃挘偭偰偄傞偑丄偗偭偟偰瀢偵側傟側偄乗乗偑3榖傪捠掙偡傞庡戣偵側傞丅慡懱偺側偐偱偼丄愥怺偄嶳偺拞偱丄彮擭偑撍慠鑿擖偟偨旤彈壀揷錆浠巕偵怱傪偲偒傔偐偟丄楒恖栘懞岟傊偺晅偗暥傪搉偡巊幰傪柋傔傞戞1榖偑埑搢揑偵椙偄丅僕儑僙僼丒儘乕僕乕偺柤嶌亀楒亁傪憐婲偝偣傞丅偙偙偱彮擭傪岲墘偡傞媣曐尗偼丄偙偺4擭屻偵亀僐僞儞偺岥揓亁偱傾僀僰偺彮擭傪墘偠偨丅戞3榖偱偼斵偺幚孼媣曐柧偑惉挿偟偨庡恖岞傪墘偠偰偄傞丅
2020擭11寧朸擔 旛朰榐89丂僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺柤昳2嶌
1953丂僆僢僩乕丒僾儗儈儞僕儍乕丂昡揰 [A]
 儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僕乕儞丒僔儌儞僘庡墘丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺寙嶌偺傂偲偮丅埲慜丄帤枊側偟偱尒偨偲偒偼僕乕儞丒僔儌儞僘偺埆彈傇傝偵埑搢偝傟偨偑丄崱夞丄帤枊晅偒偱尒偰丄斵彈偺垼傟偝偑嫮偔報徾偵巆偭偨丅媬柦巑偺儈僢僠儍儉偑崑揁偵嬱偗偮偗丄婣傝嵺偵嫃娫偱僺傾僲傪抏偄偰偄傞偦偺壠偺柡僔儌儞僘偲弌夛偆朻摢偺僔乕儞偐傜丄幵偑奟偐傜捘棊偡傞僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞傑偱丄娫慠偡傞偲偙傠側偔嬞敆偟偨僗僩乕儕乕偑懕偔丅偲傝傢偗丄僔儌儞僘偑幵傪栆楏側惃偄偱僶僢僋偝偣偰摨忔偡傞儈僢僠儍儉偲偲傕偵奟偐傜揮棊偡傞僄儞僨傿儞僌偼僔儑僢僉儞僌偩丅壜垽偄婄偺旤彮彈僕乕儞丒僔儌儞僘偑僼傽儉丒僼傽僞乕儖偺埆彈傪墘偠偰偄傞偺偑偙偺塮夋傪摿堎側傕偺偵偟偰偄傞丅斵彈偼晝恊偺彫愢壠僴乕僶乕僩丒儅乕僔儍儖偺垽傪撈傝愯傔偟偨偔偰丄宲曣傪栄寵偄偟偰偄傞丅斵彈偺斊峴偼梸摼偱偼側偔垽備偊偺傕偺偱偁傝丄晝恊傪幐偄丄垽偡傞儈僢僠儍儉偵傕嫅愨偝傟傞斵彈偺巔偼丄埆彈側偺偵惼偝偲捝乆偟偝傪姶偠偝偣傞丅僴儕乕丒僗僩儔僩儕儞僌偺僇儊儔偼栭偺儘僒儞僕僃儖僗傗揁戭撪偺岝宨傪尒帠偵懆偊偰偄傞丅
儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僕乕儞丒僔儌儞僘庡墘丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺寙嶌偺傂偲偮丅埲慜丄帤枊側偟偱尒偨偲偒偼僕乕儞丒僔儌儞僘偺埆彈傇傝偵埑搢偝傟偨偑丄崱夞丄帤枊晅偒偱尒偰丄斵彈偺垼傟偝偑嫮偔報徾偵巆偭偨丅媬柦巑偺儈僢僠儍儉偑崑揁偵嬱偗偮偗丄婣傝嵺偵嫃娫偱僺傾僲傪抏偄偰偄傞偦偺壠偺柡僔儌儞僘偲弌夛偆朻摢偺僔乕儞偐傜丄幵偑奟偐傜捘棊偡傞僄儞僨傿儞僌偺僔乕儞傑偱丄娫慠偡傞偲偙傠側偔嬞敆偟偨僗僩乕儕乕偑懕偔丅偲傝傢偗丄僔儌儞僘偑幵傪栆楏側惃偄偱僶僢僋偝偣偰摨忔偡傞儈僢僠儍儉偲偲傕偵奟偐傜揮棊偡傞僄儞僨傿儞僌偼僔儑僢僉儞僌偩丅壜垽偄婄偺旤彮彈僕乕儞丒僔儌儞僘偑僼傽儉丒僼傽僞乕儖偺埆彈傪墘偠偰偄傞偺偑偙偺塮夋傪摿堎側傕偺偵偟偰偄傞丅斵彈偼晝恊偺彫愢壠僴乕僶乕僩丒儅乕僔儍儖偺垽傪撈傝愯傔偟偨偔偰丄宲曣傪栄寵偄偟偰偄傞丅斵彈偺斊峴偼梸摼偱偼側偔垽備偊偺傕偺偱偁傝丄晝恊傪幐偄丄垽偡傞儈僢僠儍儉偵傕嫅愨偝傟傞斵彈偺巔偼丄埆彈側偺偵惼偝偲捝乆偟偝傪姶偠偝偣傞丅僴儕乕丒僗僩儔僩儕儞僌偺僇儊儔偼栭偺儘僒儞僕僃儖僗傗揁戭撪偺岝宨傪尒帠偵懆偊偰偄傞丅儅僇僆
1952丂僕儑僛僼丒僼僅儞丒僗僞儞僶乕僌丂昡揰 [C]
偙傟傕儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲僕僃乕儞丒儔僢僙儖庡墘偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偩偑丄僲儚乕儖偺梫慺偼婓敄偱丄堎崙忣挷傪惙傝崬傫偩屸妝僒僗儁儞僗塮夋偵嬤偄丅娔撀偺僗僞儞僶乕僌偼搑拞偱崀斅偟丄僯僐儔僗丒儗僀偑堷偒宲偄偩偲偄偆丅儅僇僆偱偺搎攷応偺岝宨偼摨偠偔僗僞儞僶乕僌偑娔撀偟偨亀忋奀僕僃僗僠儍乕亁傪憐婲偝偣傞丅儅僇僆偵慏偱拝偄偨尦孯恖偺棳傟幰儈僢僠儍儉偲僉儍僶儗乕壧庤儔僢僙儖偑丄埮幮夛傪媿帹傞埆娍偲斵傪戇曔偟傛偆偲偡傞寈嶡偲偺埫摤偵姫偒崬傑傟傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅埨捈側嬝棫偰偩偑丄洎梞偲偟偨儈僢僠儍儉偲楡偭梩側儔僢僙儖偼側偐側偐偺枺椡丅栭偺攇巭応偱偺捛愓僔乕儞側偳偼僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺暤埻婥偑擹岤偩偟丄儂僥儖偺晹壆偱偺儈僢僠儍儉偲儔僢僙儖偺寲壾僔乕儞偱丄愵晽婡偺塇崻偱枍偑愗傝楐偐傟塇栄偑堦柺偵晳偄旘傇報徾怺偄僔乕儞傕偁傞丅埆娍偺忣晈栶偱僌儘儕傾丒僌儗傾儉偑弌墘偟偰偄傞偑丄報徾偼敄偄丅
2020擭10寧
巇帠偑朲偟偐偭偨偨傔丄崱寧偼埲壓偺4嶌偟偐尒傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅偄偢傟傕僼儔儞僗塮夋偺屆揟揑側柤嶌偱偁傝丄偙傟偱愴慜偺僼儔儞僗柤夋偱尒偨偄偲巚偭偰偄偨傕偺偼傎傏尒廔傢偭偨偺偱偼側偄偐偲巚偆丅
2020擭10寧朸擔 旛朰榐88丂僼僃僨乕偲僇儖僱偺屆揟揑柤嶌
1935丂僕儍僢僋丒僼僃僨乕丂昡揰 [A]
偳傫側僼儔儞僗塮夋偺儀僗僩僥儞偵傕昁偢擖傞僕儍僢僋丒僼僃僨乕偺柤嶌偩偑丄埲慜VHS偱尒偨偲偒偼戅孅偟偰搑拞偱尒傞偺傪巭傔偰偟傑偭偨丅崱夞尒廔傢偭偰丄柤嶌偨傞備偊傫偑棟夝偱偒偨丅僼儔儞僪儖偺彫偝側奨丅僗儁僀儞偺孯戉偑奨偵傗偭偰棃傞偲偄偆曬偑擖傝丄偍執曽偨偪偼挰偑棯扗偝傟傞偺偱偼側偄偐偲嫰偊丄挰挿偑媫巰偟偨偲婾偭偰堦峴傪捠夁偝偣傛偆偲婇傓丅挰挿晇恖偼偦傫側忣偗側偄抝偨偪傪怟栚偵丄彈偨偪偩偗偱怓婥傪晲婍偵挰傪庣傠偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅旂擏偲僄僗僾儕偑崬傔傜傟偨堦庬偺墣徫鏉偱丄彈偨偪偼孯戉傪寎偊擖傟丄斢巂夛傪奐偄偰傕偰側偟丄栭偺柋傔傕婐乆偲偟偰偙側偡丅巰傫偩傆傝傪偡傞偑偔偟傖傒傪偟偰儃儘傪弌偡挰挿丄尩弆側婄偱懗偺壓傪庴偗庢傞惗廘朧庡偑徫偄傪桿偆丅庰応偺彈彨偑傂偲傝偱壗恖傕偺彨峑偺憡庤傪柋傔丄晹壆偺憢偺僇乕僥儞偑師乆偵暵傑傞僔乕僋僄儞僗偼儖價僢僠傪憐婲偝偣傞丅抝彑傝偺挰挿晇恖傪墘偠傞僼儔儞僜儚乕僘丒儘僛乕偑廏堩丄惗廘朧庡栶偺儖僀丒僕儏乕償僃傕報徾怺偄丅儘働偱偼側偄偐偲巚傢偣傞岻柇惛鉱側僆乕僾儞丒僙僢僩偑尒帠偩丅
杒儂僥儖
1938丂儅儖僙儖丒僇儖僱丂昡揰 [B]
 儅儖僙儖丒僇儖僱偺戙昞嶌偺傂偲偮偩偑丄偄傑尒傞偲屆偔偝偔姶偠傞偺傪斲傔側偄丅僷儕偺僒儞儅儖僞儞塣壨増偄偵寶偮埨廻丄杒儂僥儖傪晳戜偵偟偨儊儘僪儔儅丅恖惗傪偼偐側傫偩惵擭僕儍儞僺僄乕儖丒僆乕儌儞偲楒恖偺傾僫儀儔偑儂僥儖偺晹壆偱怱拞傪恾傞偑丄彈偼彆偐傝丄抝偼摝朣偡傞丅偦傟傪尒偮偗偨椬幒偺拞擭抝儖僀丒僕儏乕償僃偼抝傪尒摝偟丄彈傪彆偗傞丅彎偐桙偊偨傾僫儀儔偼儂僥儖偺儊僀僪偲偟偰摥偒巒傔丄僕儏乕償僃偼摨惐偟偰偄偨忣晈傾儖儗僢僥傿偲墢傪愗傝丄傾僫儀儔偲楒拠偵側傞偑丄斵彈偼摝朣偟偨惵擭偑朰傟傜傟側偄丅寈嶡偵帺庱偟偨惵擭偼傗偑偰庍曻偝傟丄斵彈偲傛傝傪栠偡丅尐傪婑偣崌偆傾僫儀儔偲僆乕儌儞偑塮偝傟傞側偐丄尪柵偟偨僕儏乕償僃偼廻揋偺慜偵傢偞偲巔傪偝傜偟偰廵偱寕偨傟偰丄塮夋偼廔傞丅傾僫儀儔偺壜楓側旤偟偝偲儖僀丒僕儏乕償僃偺棊偪拝偄偨廰偝偑嵺棫偭偰偄傞丅偙傟傕挰偺僙僢僩偑慺惏傜偟偔丄儂僥儖偺慜偺塣壨偵壦偗傜傟偨嫶偲梀曕摴偵旛偊傜傟偨儀儞僠偑僆乕僾僯儞僌偲僄儞僨傿儞僌偱岠壥揑偵巊傢傟偰偄傞丅
儅儖僙儖丒僇儖僱偺戙昞嶌偺傂偲偮偩偑丄偄傑尒傞偲屆偔偝偔姶偠傞偺傪斲傔側偄丅僷儕偺僒儞儅儖僞儞塣壨増偄偵寶偮埨廻丄杒儂僥儖傪晳戜偵偟偨儊儘僪儔儅丅恖惗傪偼偐側傫偩惵擭僕儍儞僺僄乕儖丒僆乕儌儞偲楒恖偺傾僫儀儔偑儂僥儖偺晹壆偱怱拞傪恾傞偑丄彈偼彆偐傝丄抝偼摝朣偡傞丅偦傟傪尒偮偗偨椬幒偺拞擭抝儖僀丒僕儏乕償僃偼抝傪尒摝偟丄彈傪彆偗傞丅彎偐桙偊偨傾僫儀儔偼儂僥儖偺儊僀僪偲偟偰摥偒巒傔丄僕儏乕償僃偼摨惐偟偰偄偨忣晈傾儖儗僢僥傿偲墢傪愗傝丄傾僫儀儔偲楒拠偵側傞偑丄斵彈偼摝朣偟偨惵擭偑朰傟傜傟側偄丅寈嶡偵帺庱偟偨惵擭偼傗偑偰庍曻偝傟丄斵彈偲傛傝傪栠偡丅尐傪婑偣崌偆傾僫儀儔偲僆乕儌儞偑塮偝傟傞側偐丄尪柵偟偨僕儏乕償僃偼廻揋偺慜偵傢偞偲巔傪偝傜偟偰廵偱寕偨傟偰丄塮夋偼廔傞丅傾僫儀儔偺壜楓側旤偟偝偲儖僀丒僕儏乕償僃偺棊偪拝偄偨廰偝偑嵺棫偭偰偄傞丅偙傟傕挰偺僙僢僩偑慺惏傜偟偔丄儂僥儖偺慜偺塣壨偵壦偗傜傟偨嫶偲梀曕摴偵旛偊傜傟偨儀儞僠偑僆乕僾僯儞僌偲僄儞僨傿儞僌偱岠壥揑偵巊傢傟偰偄傞丅2020擭10寧朸擔 旛朰榐87丂僨儏償傿償傿僄偺愴慜偺戙昞嶌2杮
1936丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰 [C]
僕儍儞丒僊儍僶儞偲僔儍儖儖丒償傽僱儖庡墘丅曮偔偠偱10枩僼儔儞傪摉偰偨5恖偺拠娫偑嫟摨偱彫愳偺傎偲傝偺峳傟偨暿憫傪攦偄丄傒傫側偱椡傪崌傢偣偰夵憰偟偰儗僗僩儔儞傪奐偙偆偲偡傞丅傗偑偰拠娫偼傂偲傝嫀傝丄傆偨傝嫀傝偟偰尭偭偰偄偒丄嵟屻偵僊儍僶儞偲償傽僱儖偑巆偝傟傞丅傛偆傗偔儗僗僩儔儞傪奐嬈偡傞偑丄償傽僱儖偺嵢傪傔偖偭偰僊儍僶儞偲償傽僱儖偺偁偄偩偵3妏娭學偑惗偠丄嗦尗偄埆嵢偺尵梩偵梮傜偝傟偨償傽僱儖偐傜柺攍偝傟偨僊儍僶儞偼償傽僱儖傪幩嶦偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅梲婥偱妝偟偄暤埻婥偐傜偟偩偄偵埫偄暤埻婥偵側偭偰偄偔丄儁僔儈僘儉偺嶌壠僨儏償傿償傿僄傜偟偄塮夋丅埆彈傪墘偠傞償傿償傿傾乕僰丒儘儅儞僗偼偙傟偑弌悽嶌偵側偭偨丅榖偺棳傟偐傜偟偰丄僊儍僶儞偲償傽僱儖偼桭忣偲怣棅偱寢偽傟偰偍傝丄偄偔傜彈傪弰偭偰尵偄崌偄偵側偭偰傕僊儍僶儞偑償傽僱儖傪幩嶦偡傞偺偼晄帺慠偱丄柍棟傗傝斶寑偵偟偨偲偄偆姶偑偁傞丅杮棃偺斶寑斉偺傎偐偵丄偍偦傜偔暷崙岦偗偵嶌偭偨偲巚傢傟傞僴僢僺乕丒僄儞僨傿儞僌斉偑偁傞丅DVD偵廂榐偝傟偨僴僢僺乕丒僄儞僨傿儞僌斉傪尒傞偲丄偦偙偱偼僊儍僶儞偑幩嶦傪巚偄偲偳傑傝丄傆偨傝偼拠捈傝偡傞寢枛偵側偭偰偍傝丄偙偪傜偺傎偆偑帺慠側寢枛偵巚偊傞丅
椃楬偺壥偰
1939丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰 [C]
撿僼儔儞僗偺堷戅偟偨攐桪偺偨傔偺梴榁堾傪晳戜偵丄偦偙偱曢傜偡榁恖偨偪偺恖娫柾條偑昤偐傟傞丅晳戜偱媟岝傪梺傃偨彈偨傜偟偺攐桪偵儖僀丒僕儏乕償僃丄幚椡偑偁傝側偑傜惉岟偟側偐偭偨攐桪偵償傿僋僩儖丒僼儔儞僒儞丄戙栶愱栧偱晳戜偵棫偭偨偙偲偑側偄摴壔幰偺攐桪偵儈僔僃儖丒僔儌儞偑暞偟偰偍傝丄偙偺3恖偑庡梫搊応恖暔丅嬤強偺僇僼僃偱摥偔僂僃僀僩儗僗偺彮彈傪桿榝偟丄帺嶦偵捛偄崬傕偆偲偡傞僕儏乕償僃偺嫸婥傪旈傔偨椻崜側昞忣偑報徾偵巆傞偑丄慡懱偲偟偰偁傑傝偺傕幣嫃偑偐偭偰偍傝丄奊嬻帠偺傛偆側嬻偟偝偑偮偒傑偲偆丅
2020擭9寧
2020擭9寧朸擔 旛朰榐86丂僋儖乕僝乕偺弶婜偲屻婜偺2杮偺塮夋
1947丂傾儞儕僕儑儖僕儏丒僋儖乕僝乕丂昡揰乵B乶
 堦搙尒偰偄傞偑丄拞恎傪朰傟偨偺偱嵞尒丅僋儖乕僝乕偺偛偔弶婜偺嶌昳偱儖僀丒僕儏乕償僃偑孻帠栶傪墘偠傞丅恖婥壧庤偺嵢偲僺傾僲敽憈幰偺晇偑庡恖岞丅壧庤偼彈岲偒偺戝嬥帩偪偐傜塮夋偵弌墘偝偣偰傗傞偲尵傢傟偰壆晘偵峴偔偑丄斵偵廝傢傟偦偆偵側偭偨偺偱壴時偱墸偭偰摝偘傞丅晇偺僺傾僲抏偒偼嵢偑抝偲枾夛偟偰偄傞偲姩堘偄偟偰偰壆晘偵峴偔偑丄抝偼巰傫偱偄偨丅孻帠偑搊応偟偰憑嵏傪巒傔傞丅嵟弶偵晇偑丄師偵嵢偑斊恖偲媈傢傟傞偑丄嵟屻偵孻帠偑帠審傪夝偒柧偐偟丄恀斊恖傪戇曔偟偰堦審棊拝丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅婄偼嫲偄偑恖忣枴偺偁傞孻帠傪墘偠傞儖僀丒僕儏乕償僃偺懚嵼姶偑岝傞丅偙偺孻帠偼抝傗傕傔偱丄崿寣偺梒偄懅巕傪堢偰偰偄傞偲偄偆愝掕丅偙偺懅巕偑側偐側偐壜垽偔丄晝恊偵夛偄偨偔側傝丄寈嶡彁偵傗偭偰棃偰柊偭偰偟傑偆丅幑搃怺偄僺傾僯僗僩偵暞偡傞儀儖僫乕儖丒僽傝僄傕揔栶丅偙偺塮夋偼儈僗僥儕乕偲偄偆偄傛傝恖忣暔丄悽榖暔偲偄偆姶偠偱丄僋儖乕僝乕偼庡恖岞晇晈偺桭恖偱僺傾僯僗僩傪枾偐偵垽偡傞彈幨恀壠傪嫸尵夞偟偵攝偟偨傝丄晇晈偺寖偟偄抯榖寲壾傪憓擖偟偨傝偟偰暤埻婥傪惙傝忋偘偰偄傞丅僄儞僨傿儞僌傕慛傗偐偩丅
堦搙尒偰偄傞偑丄拞恎傪朰傟偨偺偱嵞尒丅僋儖乕僝乕偺偛偔弶婜偺嶌昳偱儖僀丒僕儏乕償僃偑孻帠栶傪墘偠傞丅恖婥壧庤偺嵢偲僺傾僲敽憈幰偺晇偑庡恖岞丅壧庤偼彈岲偒偺戝嬥帩偪偐傜塮夋偵弌墘偝偣偰傗傞偲尵傢傟偰壆晘偵峴偔偑丄斵偵廝傢傟偦偆偵側偭偨偺偱壴時偱墸偭偰摝偘傞丅晇偺僺傾僲抏偒偼嵢偑抝偲枾夛偟偰偄傞偲姩堘偄偟偰偰壆晘偵峴偔偑丄抝偼巰傫偱偄偨丅孻帠偑搊応偟偰憑嵏傪巒傔傞丅嵟弶偵晇偑丄師偵嵢偑斊恖偲媈傢傟傞偑丄嵟屻偵孻帠偑帠審傪夝偒柧偐偟丄恀斊恖傪戇曔偟偰堦審棊拝丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅婄偼嫲偄偑恖忣枴偺偁傞孻帠傪墘偠傞儖僀丒僕儏乕償僃偺懚嵼姶偑岝傞丅偙偺孻帠偼抝傗傕傔偱丄崿寣偺梒偄懅巕傪堢偰偰偄傞偲偄偆愝掕丅偙偺懅巕偑側偐側偐壜垽偔丄晝恊偵夛偄偨偔側傝丄寈嶡彁偵傗偭偰棃偰柊偭偰偟傑偆丅幑搃怺偄僺傾僯僗僩偵暞偡傞儀儖僫乕儖丒僽傝僄傕揔栶丅偙偺塮夋偼儈僗僥儕乕偲偄偆偄傛傝恖忣暔丄悽榖暔偲偄偆姶偠偱丄僋儖乕僝乕偼庡恖岞晇晈偺桭恖偱僺傾僯僗僩傪枾偐偵垽偡傞彈幨恀壠傪嫸尵夞偟偵攝偟偨傝丄晇晈偺寖偟偄抯榖寲壾傪憓擖偟偨傝偟偰暤埻婥傪惙傝忋偘偰偄傞丅僄儞僨傿儞僌傕慛傗偐偩丅僗僷僀
1957丂傾儞儕僕儑儖僕儏丒僋儖乕僝乕丂昡揰乵C乶
尒偨偲巚偭偰偄偨偑丄枹尒偩偭偨僋儖乕僝乕偺屻婜偺嶌昳丅偙傟偼椻愴傪旂擏偭偨僷儘僨傿塮夋側偺偩傠偆偐丅揷幧偺惛恄昦堾傪晳戜偵丄慺惈偺暘偐傜側偄夦偟偘側挸曬堳傗娔帇恖傗朣柦僗僷僀偑偮偓偮偓偵尰傟傞丅斵傜偑挐傞偙偲偑塕偐杮摉偐暘偐傜偢丄宱塩崲擄偺昦堾傪寶偰捈偡嬥傎偟偝偵僗僷僀傪摻偆偙偲傪彸戻偟偨堾挿偼偰傫偰偙晳偄偡傞丅僇僼僇傪巚傢偣傞埆柌偺傛偆側忬嫷偼丄僸僢僠僐僢僋傪巚傢偣側偄偱傕側偄偑丄僗僷僀塮夋偺僷儘僨僀偺傛偆偱傕偁傞丅庡墘偺堾挿偵暞偡傞僕僃儔乕儖丒僙僥傿偼柍柤偩偑丄擖堾拞偺怓偭傐偄彈惈姵幰偵娔撀偺嵢償僃儔丒僋儖乕僝乕丄朣柦偟偰昦堾偵摻傢傟傞僗僷僀偵僋儖僩丒儐儖僎儞僗丄朸崙偺挸曬堳偵僺乕僞乕丒儐僗僠僲僼偲僒儉丒僕儍僼僃偲丄偔偣偺偁傞栶幰偑榚栶偱弌墘偟偰偄傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐85丂僕儍儞丒僊儍僶儞偺儊僌儗寈帇傕偺2杮
1957丂僕儍儞丒僪儔僲儚丂昡揰乵C乶
僕儑儖僕儏丒僔儉僲儞尨嶌偺儊僌儗寈帇傕偺偺堦嶌丅僕儍儞丒僊儍僶儞偺墘偠傞儊僌儗偼丄尨嶌偺報徾偲偼偐側傝僀儊乕僕偑堘偆偑丄僩儗儞僠僐乕僩偵僼僃儖僩朮丄偄偮傕僷僀僾傪偔傢偊偰偍傝丄偙傟偼偙傟偱條偵側偭偰偄傞丅僷儕巗撪偱彈偽偐傝慱偆楢懕嶦恖帠審偑敪惗偟丄儊僌儗偺巜婗偺傕偲丄寈嶡偑悌偵偐偗偰斊恖傪偍傃偒弌偦偆偲偡傞榖丅斊恖偑偁偭偝傝暘偐偭偰偟傑偆偺偑暔懌傝側偄偟丄廔斦偼斊恖偲偦偺嵢偲曣恊偺怱棟娭學偵徟揰偑摉偨傝丄暥寍廘偑擹偔側偭偰僒僗儁儞僗偺枴傢偄偑敄傟傞丅斊恖栶偼擃庛側晽杄偺僕儍儞丒僪僒僀丅偦偺嵢栶偺傾僯乕丒僕儔儖僪偺抦揑側晽杄偲梷偊偨墘媄偑報徾偵巆傞丅儕僲丒償傽儞僠儏儔偑抂栶偺孻帠傪恄柇偵墘偠偰偄傞丅
僒儞丒僼傿傾僋儖嶦恖帠審
1959丂僕儍儞丒僪儔僲儚丂昡揰乵C乶
僕儍儞丒僊儍僶儞偺儊僌儗寈帇僔儕乕僘戞2嶌丅儊僌儗偼惗傑傟屘嫿僒儞僼傿傾僋儖懞偵傗偭偰棃傞丅懞偺忛娰偵廧傓丄斵偑巕嫙偺偙傠枾偐偵曠偭偰偄偨攲庉晇恖偐傜丄斵彈偵撏偄偨嫼敆忬偵偮偄偰挷嵏傪埶棅偝傟偨偐傜偩丅梻擔丄攲庉晇恖偼怱憻敪嶌偱巰偸偑丄儊僌儗偼巇慻傑傟偨嶦恖偩偲尒敳偔丅嵟屻偵儊僌儗偼忛娰偵晇恖偺堦恖懅巕傗旈彂傗娗棟恖側偳偺媈傢偟偄恖暔傪廤傔丄斊恖傪巜揈偡傞丅塮夋偲偟偰偺惙傝忋偑傝偵寚偗傞偟丄斊峴偺庤岥傕尰幚枴偵朢偟偄偑丄姦乆偲偟偨搤偺懞偺忣宨偼報徾偵巆傞丅擭榁偄偨攲庉晇恖偵儖僲儚乕儖偺乽儃償傽儕乕晇恖乿偱庡栶傪墘偠偨償傽儔儞僔乕僰丒僥僔僄丄曻摖幰偺懅巕偵僋儖乕僝乕偺乽忣晈儅僲儞乿偱岲墘偟偨儈僔僃儖丒僆乕僋儗乕儖偑暞偟偰偄傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐84丂僕儍儞丒僊儍僶儞50擭戙偺斊嵾塮夋2杮
1955丂傾儞儕丒僪僐傾儞丂昡揰乵C乶
 僕儍儞丒僊儍僶儞庡墘偺斊嵾塮夋丅戣柤偺乽嬝嬥乿偼乽儎僉乿偲撉傓丅僊儍儞僌偺戝暔僊儍僶儞偑僯儏乕儓乕僋偐傜僷儕偵婣偭偰偒偰慻怐偺杻栻枾攧栐棫偰捈偟偺偨傔偵屬傢傟傞偑丄廔斦偵偄偨偭偰斵偼寈嶡偺愽擖憑嵏姱偩偭偨偺偑柧偐偝傟傞偲偄偆榖丅嵟屻偵慻怐偼堦栐懪恠偵側傞丅杻栻偺惢憿傗攧攦偑僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵昤偐傟傞偺偑嫽枴怺偄丅僊儍僶儞偑宱塩偡傞僋儔僽偺夛寁學偱斵偺垽恖偵側傞儅僈儕丒僲僄儖偑側偐側偐壜垽偄丅慻怐偺椻崜側嶦偟壆傪儕僲丒償傽儞僠儏儔偑墘偠傞丅慻怐偺儃僗偵暞偡傞儅儖僙儖丒僟儕僆偲僊儍僶儞偼乽戝偄側傞尪塭乿埲棃偺嫟墘丅
僕儍儞丒僊儍僶儞庡墘偺斊嵾塮夋丅戣柤偺乽嬝嬥乿偼乽儎僉乿偲撉傓丅僊儍儞僌偺戝暔僊儍僶儞偑僯儏乕儓乕僋偐傜僷儕偵婣偭偰偒偰慻怐偺杻栻枾攧栐棫偰捈偟偺偨傔偵屬傢傟傞偑丄廔斦偵偄偨偭偰斵偼寈嶡偺愽擖憑嵏姱偩偭偨偺偑柧偐偝傟傞偲偄偆榖丅嵟屻偵慻怐偼堦栐懪恠偵側傞丅杻栻偺惢憿傗攧攦偑僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵昤偐傟傞偺偑嫽枴怺偄丅僊儍僶儞偑宱塩偡傞僋儔僽偺夛寁學偱斵偺垽恖偵側傞儅僈儕丒僲僄儖偑側偐側偐壜垽偄丅慻怐偺椻崜側嶦偟壆傪儕僲丒償傽儞僠儏儔偑墘偠傞丅慻怐偺儃僗偵暞偡傞儅儖僙儖丒僟儕僆偲僊儍僶儞偼乽戝偄側傞尪塭乿埲棃偺嫟墘丅愒偄摂傪偮偗傞側
1957丂僕儖丒僌儔儞僕僃丂昡揰乵B乶
娔撀偺僕儖丒僌儔儞僕僃偼50乣60擭戙偵僊儍僶儞偺塮夋傪悢懡偔庤偑偗偨恖暔丅僷儕偱挀幵応偲儗僗僩儔儞傪宱塩偡傞僊儍僶儞偺棤偺婄偼嫮搻僌儖乕僾偺儕乕僟乕寭塣揮庤丅僌儖乕僾偺傂偲傝偵儕僲丒償傽儞儞僠儏儔偑暞偡傞丅償傽儞僠儏儔偼捒偟偔暔暘偐傝偺偄偄拠娫傪墘偠偰偄傞偲巚偭偰偄傞偲丄嵟屻偱嫸婥偺抝偵側傞丅僌儖乕僾偵寈嶡偺庤偑敆傝丄僊儍僶儞偺掜傪枾崘幰偩偲姩堘偄偟偰嶦偦偆偲偡傞償傽儞僠儏儔偲僊儍僶儞偑寕偪崌偄偵側偭偰2恖偲傕巰偸丅庒偄傾僯乕丒僕儔儖僪偑僊儍僶儞偺掜偺楒恖偱抝傪庤嬍偵庢傞埆彈傪墘偠丄僊儍僶儞偵傎偭傌偨傪偼偨偐傟傞丅償傽儞僠儏儔傪偼偠傔丄乽嬝嬥傪擖傟傠乿偲摨偠偔丄僊儍儞僌塮夋偱偼偍撻愼傒偺栶幰偑偨偔偝傫弌墘偟偰偄傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐83丂僽儗僢僜儞偺敆恀揑側扙崠塮夋
1956丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰乵B乶
僽儗僢僜儞偵偟偰偼僗僩儗乕僩偱暘偐傝傗偡偄扙崠塮夋丅幚榖偵婎偯偄偰偍傝丄懱尡幰偺庤婰傪拤幚偵塮憸壔偟偨偲偄偆丅僫僠僗愯椞壓偺壓偺僼儔儞僗丄儗僕僗僞儞僗妶摦偱偺搳崠偝傟偨抝偑扙崠偡傞傑偱偑昤偐傟傞丅抝偼僗僾乕儞偺愭傪彴偱尋偓丄儈僲傪嶌偭偰僪傾偺塇栚斅傪攳偑偟丄晍傪楐偄偰擰傝崌傢偣丄儀僢僪偺恓嬥偱曗嫮偟偰儘乕僾傪嶌傞丅娕庣偺栚傪偐偡傔偰栙乆偲嶌嬈偡傞抝偺巔偑扥擮偵昤幨偝傟傞丅偦偺塮憸偼丄嬞敆姶傪忴惉偟傛偆偲偄偆偁偞偲偝偑側偄偩偗偵丄偠偮偵儕傾儖偱惗乆偟偄丅抝傪巟偊偰偄傞偺偼帺桼傊偺妷朷偩丅巰偵傛偭偰寢枛傪寎偊傞偙偲偑懡偄僽儗僢僜儞偺塮夋偺側偐偱丄庡恖岞偑扙崠偵惉岟偟偰懌憗偵栭偺埮偵徚偊傞報徾揑側僄儞僨傿儞僌偺偙偺塮夋偼丄偒傢傔偰堎椺偺嶌昳偩偲尵偊傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐82丂僼儔儞僕儏偺峳搨柍宮側妶寑塮夋乽僕儏僨僢僋僗乿
1963丂僕儑儖僕儏丒僼儔儞僕儏乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰乵C乶
僒僀儗儞僩帪戙偵恖婥傪攷偟偨偲偄偆楢懕妶寑塮夋傪儕儊僀僋偟偨嶌昳丅僕儏僨僢僋僗偲偼夦搻恆巑偺柤慜偱丄擇枃栚偺婏弍巘僠儍僯儞僌丒億儘僢僋偑墘偠傞丅斵偼偄偮傕崟儅儞僩偲偮偽峀朮巕偲偄偆奿岲偱搊応偡傞丅塮夋偼埆摽嬧峴壠偵嶦奞偺嫼敆忬偑撏偔僔乕儞偐傜僗僞乕僩偡傞偑丄嬝棫偰偼峳搨柍宮偱丄埫嶦丄桿夳丄捛愓丄奿摤偑柆棈側偔惙傝崬傑傟傞丅巒傑偭偰娫傕側偔丄壖憰僷乕僥傿偵捁抝偑尰傟偰師乆偵數傪庢傝偩偟丄尒傞傕偺偼曫婥偵偲傜傟傞丅嬧峴壠偺柡偱惼偄恖宍偺傛偆側僄僨傿僩丒僗僞僽偑愳偵棳偝傟傞僔乕儞偼僆僼傿乕儕傾傪楢憐偝偣傞丅廔斦丄側偤偐彈嬋寍巘僔儖償傽丒僐僔僫偑搊応偟丄敀僞僀僣巔偱忛娰偺壆崻偵傛偠忋傝丄摨偠偔崟僞僀僣巔偺彈懐僼儔儞僔乕僰丒儀儖僕儏偲奿摤偡傞僔乕儞偼丄僸僢僠僐僢僋偺乽揇朹惉嬥乿傪憐婲偝偣傞丅
嶳巘僩儅
1965丂僕儑儖僕儏丒僼儔儞僕儏乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰乵E乶
僕儍儞丒僐僋僩乕偺彫愢偺塮夋壔丅戞1師戝愴拞丄僷儕峹奜偺婱懓偺枹朣恖偺忛娰偵丄桳柤側彨孯偺墮偩偲柤忔傞惵擭偑尰傟丄媬岇晹戉傪慻怐偟偰彎昦暫傪媬偍偆偲偡傞枹朣恖傪彆偗偨偁偲丄愴憟偺嵟慜慄偵岦偐偆丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅嵟屻偵惵擭偑嵓媆巘偩偭偨偙偲偑暘偐傞丅枹朣恖傪僄儅僯儏僄儖丒儕乕償傽丄斵彈傪垽偡傞怴暦婰幰傪僕儍儞丒僙儖償僃偲偄偆払幰側栶幰偑墘偠偰偄傞偑丄塮夋偲偟偰壗傪昞尰偟偨偄偺偐傛偔暘偐傜偢丄榖傕偩傜偩傜偲懕偒丄傑偭偨偔柺敀偔側偄丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐81丂僕儑儖僕儏丒僼儔儞僕儏偺徴寕嶌乽婄偺側偄娽乿
1960丂僕儑儖僕儏丒僼儔儞僕儏乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰乵A乶
 埲慜偐傜尒偨偄偲巚偭偰偄偨塮夋傪傗偭偲尒傞偙偲偑偱偒偨丅嶳揷岹堦偑挊彂乽僼儔儞僗塮夋帍乿偱堦復傪旓傗偟偰僆儅乕僕儏傪曺偘丄郌郪棿旻傕愨巀偟偰偄偨丅婜懸偵堘傢偸丄夦婏偲尪憐丄儕傾儕僘儉偲儊儖僿儞丄巆崜偲抆旤偑熡慠堦懱偲側偭偨嫲晐塮夋偺寙嶌偩丅怷偵埻傑傟偨峹奜偺壆晘偑晳戜丅崅柤側堛巘僺僄乕儖丒僽儔僢僗乕儖偑丄岎捠帠屘偱婄慡柺偵壩彎傪晧偭偨垽柡僄僨傿僢僩丒僗僐僽偺婄傪尦捠傝偵偡傞偨傔丄彆庤傾儕僟丒償傽儕偵庒偄柡傪桿夳偝偣丄偦偺婄偺旂晢傪攳偓庢偭偰柡偺婄偵堏怉偟傛偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅朻摢丄傾儕僟丒償傽儕偑媇惖幰偺堚懱傪壨偵捑傔傞僔乕儞偑尒傞幰偵嫮楏側報徾傪梌偊傞丅埫埮偺側偐丄償傽儕偵堷偒偢傜傟傞彈偺巰懱偺敀偄媟偑栚偵從偒晅偔丅柡偺僄僨傿僢僩丒僗僐僽偑偄偮傕婄偵晅偗偰偄傞丄擇偮偺寠偐傜椉栚偩偗偑偺偧偔丄僑儉惢偲偍傏偟偒敀偄儅僗僋偑側傫偲傕晄婥枴偩丅桿夳偟偨彈偺婄偐傜旂晢傪攳偓庢傞堏怉庤弍偺昤幨偼栚傪偦傓偗偨偔側傞傎偳惗乆偟偄丅僄儞僨傿儞僌傕慛傗偐偩丅僗僐僽偑償傽儕偺岮傪儊僗偱撍偒巋偟丄烞偐傜曻偨傟偨將偑僽儔僢僗乕儖偵廝偄偐偐傞丅僗僐僽偼夝偒曻偭偨僴僩偑晳偄梮傞側偐丄埫偄怷偺側偐偵曕傒嫀傞丅巆崜側儕傾儕僘儉偲抆旤揑側儘儅儞僥傿僔僘儉偵嵤傜傟偨丄嫲晐偲旤偲垼愗姶偑昚偆丄朰傟偑偨偄僄僺儘乕僌偩丅僪僀僣偺嶣塭娔撀偱乽儊僩儘億儕僗乿傗乽柖偺攇巭応乿傪庤偑偗偨僆僀僎儞丒僔儏僼僞儞偺椻揙側僇儊儔塮憸偑堿烼側暤埻婥傪傪偄傗偑偆偊偵傕忴偟弌偡丅傾儕僟丒償傽儕偼偁偺乽戞嶰偺抝乿偐傜10擭屻偺弌墘丄擭椫傪宱偰婄偺晐偝偑栚棫偮丅書偒掲傔偨傜愜傟偰偟傑偄偦偆側惼庛側擏懱丄偼偐側偘側梕巔偺僄僨傿僢僩丒僗僐僽偼僼儔儞僕儏娔撀偺旈憼偭巕偱丄偙偺偁偲乽僕儏僨僢僋僗乿偵傕弌墘偟偰偄傞丅
埲慜偐傜尒偨偄偲巚偭偰偄偨塮夋傪傗偭偲尒傞偙偲偑偱偒偨丅嶳揷岹堦偑挊彂乽僼儔儞僗塮夋帍乿偱堦復傪旓傗偟偰僆儅乕僕儏傪曺偘丄郌郪棿旻傕愨巀偟偰偄偨丅婜懸偵堘傢偸丄夦婏偲尪憐丄儕傾儕僘儉偲儊儖僿儞丄巆崜偲抆旤偑熡慠堦懱偲側偭偨嫲晐塮夋偺寙嶌偩丅怷偵埻傑傟偨峹奜偺壆晘偑晳戜丅崅柤側堛巘僺僄乕儖丒僽儔僢僗乕儖偑丄岎捠帠屘偱婄慡柺偵壩彎傪晧偭偨垽柡僄僨傿僢僩丒僗僐僽偺婄傪尦捠傝偵偡傞偨傔丄彆庤傾儕僟丒償傽儕偵庒偄柡傪桿夳偝偣丄偦偺婄偺旂晢傪攳偓庢偭偰柡偺婄偵堏怉偟傛偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅朻摢丄傾儕僟丒償傽儕偑媇惖幰偺堚懱傪壨偵捑傔傞僔乕儞偑尒傞幰偵嫮楏側報徾傪梌偊傞丅埫埮偺側偐丄償傽儕偵堷偒偢傜傟傞彈偺巰懱偺敀偄媟偑栚偵從偒晅偔丅柡偺僄僨傿僢僩丒僗僐僽偑偄偮傕婄偵晅偗偰偄傞丄擇偮偺寠偐傜椉栚偩偗偑偺偧偔丄僑儉惢偲偍傏偟偒敀偄儅僗僋偑側傫偲傕晄婥枴偩丅桿夳偟偨彈偺婄偐傜旂晢傪攳偓庢傞堏怉庤弍偺昤幨偼栚傪偦傓偗偨偔側傞傎偳惗乆偟偄丅僄儞僨傿儞僌傕慛傗偐偩丅僗僐僽偑償傽儕偺岮傪儊僗偱撍偒巋偟丄烞偐傜曻偨傟偨將偑僽儔僢僗乕儖偵廝偄偐偐傞丅僗僐僽偼夝偒曻偭偨僴僩偑晳偄梮傞側偐丄埫偄怷偺側偐偵曕傒嫀傞丅巆崜側儕傾儕僘儉偲抆旤揑側儘儅儞僥傿僔僘儉偵嵤傜傟偨丄嫲晐偲旤偲垼愗姶偑昚偆丄朰傟偑偨偄僄僺儘乕僌偩丅僪僀僣偺嶣塭娔撀偱乽儊僩儘億儕僗乿傗乽柖偺攇巭応乿傪庤偑偗偨僆僀僎儞丒僔儏僼僞儞偺椻揙側僇儊儔塮憸偑堿烼側暤埻婥傪傪偄傗偑偆偊偵傕忴偟弌偡丅傾儕僟丒償傽儕偼偁偺乽戞嶰偺抝乿偐傜10擭屻偺弌墘丄擭椫傪宱偰婄偺晐偝偑栚棫偮丅書偒掲傔偨傜愜傟偰偟傑偄偦偆側惼庛側擏懱丄偼偐側偘側梕巔偺僄僨傿僢僩丒僗僐僽偼僼儔儞僕儏娔撀偺旈憼偭巕偱丄偙偺偁偲乽僕儏僨僢僋僗乿偵傕弌墘偟偰偄傞丅嶦恖幰傪慱偊
1961丂僕儑儖僕儏丒僼儔儞僕儏乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰乵C乶
僼儔儞僕儏偑乽婄偺側偄娽乿偵懕偄偰嶣偭偨塮夋偩偑丄捦傒偳偙傠偺側偄曄側嶌昳偩丅朻摢丄忛偺庡偲偍傏偟偒婱懓偺榁恖偑嬀偺棤偺塀偟晹壆偵擖偭偰懅愨偊傞丅偙傟偑偳偆傗傜僺僄乕儖丒僽儔僢僗乕儖傜偟偄丅懕偄偰僕儍儞儖僀丒僩儔儞僥傿僯儍儞偑楒恖僟僯乕丒僒償傽儖偵幵偱憲偭偰傕傜偭偰忛偵傗偭偰棃傞丅忛偱偼榁恖偺墮傗柮偑廤偭偰堚嶻憡懕夛媍偑奐偐傟傞丅斵傜偼堚嶻娗棟恖偐傜丄榁恖偼堦椉擔拞偵巰偸偲恌抐偝傟偰偄偨偺偱巰傫偩偼偢偩偑丄堚懱偑尒偮偐傜側偗傟偽5擭娫偼憡懕偱偒側偄偲尵傢傟丄堚懱扵偟偵杬憱偡傞偑丄偦偺娫偵憡懕恖偨偪偼傂偲傝偢偮嶦偝傟偰偄偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅乽偦偟偰扤傕偄側偔側偭偨乿傪巚傢偣傞嬝棫偰偩偑丄側傫偲傕娚偄娫墑傃偟偨揥奐偱僒僗儁儞僗偼傑偭偨偔惙傝忋偑傜側偄丅僷儕偵婣偭偨偼偢偺僟僯丒僒償傽儖偑側偤偐忛偵塀傟偰偄偰偲偒偳偒巔傪尰偡偟丄忛偺側偐偺傾僫僂儞僗丒僔僗僥儉偐傜晄婥枴側惡偑棳傟傞偟丄壗傗傜撪梕晄柧偺僀償僃儞僩偑嵜偝傟偰抧尦偺恖乆偑廤傝丄嵟屻偼斊恖偑僗億僢僩儔僀僩偺側偐偱廵偱寕偨傟偰巰傫偱廔傢傝偲側傞偑丄屜偵偮傑傑傟偨傛偆偱丄偄偭偨偄壗偩偭偨偺偩偲偄偆婥帩偪偵側傞丅嫽枴偺徟揰偼丄偁偺乽壨偼屇傫偱傞乿偵庡墘偟偨旤彈僷僗僇儖丒僆乕僪儗偺弌墘偵偁偭偨偺偩偑丄柮偺傂偲傝偵暞偟偨僆乕僪儗偺弌斣偼偁傑傝側偔丄搑拞偱嶦偝傟偰偟傑偆偺偱巆擮帄嬌丅梋択偩偑丄傂偲偙傠擔杮偱僞儗儞僩偲偟偰妶桇偟偨僕儏儕乕丒僪儗僼儏僗偼僷僗僇儖丒僆乕僪儗偺柡偩丅忋昳側旤偟偝偼傛偔帡偰偄傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐80丂僩儕儏僼僅乕偵傛傞2杮偺塮夋
1964丂僼儔儞僜儚丒僩儕儏僼僅乕丂昡揰乵C乶
僼儔儞僗塮夋偼晄椣傗嶰妏娭學傪埖偭偨塮夋偑偲偵偐偔懡偄丅偙傟傕晄椣偺壥偰偵攋柵偡傞抝傪昤偄偨楒垽塮夋偩丅挊柤側暥寍昡榑壠僕儍儞丒僪僒僀偑丄廬弴側嵢偲垽偡傞巕嫙偑偄側偑傜丄僗僠儏傾乕僨僗偺庒偄彈僼儔儞僜儚乕僘丒僪儖儗傾僢僋偵庝偐傟偰娭學傪傕偪丄偢傞偢傞怺傒偵偼傑偭偰敳偒嵎偟側傜側偔側傝丄嵟屻偼嵢偵幩嶦偝傟傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僩儕儏僼僅乕偼愴慜攈偺嫄彔偨偪偺塮夋傪斸敾偟偰偄偨偺偵丄偙偙偱偠偭偔傝偲昤偐傟傞晄椣偺揯枛偺岅傝岥偼丄僆乕儖丒儘働偲偄偆揰偵怴慛枴偼偁傞偵偟偰傕丄崻杮揑偵偼偦傟傜偲傑偭偨偔曄傢傜側偄丅
栭柖偺楒恖偨偪
1968丂僼儔儞僜儚丒僩儕儏僼僅乕丂昡揰乵B乶
僩儕儏僼僅乕偺傾儞僩儚乕僰丒僪儚僱儖傕偺偺戞3嶌丅寉柇側僐儊僨傿塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅僕儍儞僺僄乕儖丒儗僆暞偡傞傾儞僩儚乕僰偼擖戉偟偨棨孯偐傜晄揔奿幰偲偟偰彍戉偝偣傜傟丄彥晈傪攦偭偨偁偲丄偐偮偰偺僈乕儖僼儗儞僪偺壠傪朘偹丄晝恊偺徯夘偱儂僥儖偺僼儘儞僩偲偟偰摥偒丄偦偺屻偝傜偵巹棫扵掋帠柋強偺挷嵏堳丄壠揹廋棟恖偺怑偵廇偔丅塮夋偼抁偄僔儑僢僩傪偮側偓側偑傜丄斵偑巇帠偱憳嬾偡傞幐攕傗楒垽側偳偺偝傑偞傑側僄僺僜乕僪傪僐儊僨傿晽偵昤偄偰偄偔丅攧傜傫偐側偲偄偆壓怱尒偊尒偊偺擔杮戣偼嵟埆偩偑丄慡懱偵昚偆偲傏偗偨枴傢偄偲僕儍儞僺僄乕儖丒儗僆偺镚乆偲偟偨墘媄偼岲姶偑帩偰傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐79丂僕儍僢僋丒僼僃僨乕偺屆揟揑柤嶌
1934丂僕儍僢僋丒僼僃僨乕丂昡揰乵B乶
曣偲巕偺忣垽傪昤偄偨儊儘僪儔儅丅柤嶌偲偝傟偰偄傞偑丄偄傑尒傞偲傗偼傝屆廘偄偲偄偆姶偠偼斲傔側偄丅僐儊僨傿偭傐偄弌偩偟偱巒傑傞偑丄偟偩偄偵廳嬯偟偄條憡傪懷傃丄嵟屻偼斶寑偱廔傞丅庡墘偺僼儔儞僜儚乕僘丒儘僛乕偼偝偡偑偺娧榎丄慺惏傜偟偄柤墘媄偩丅撿暓偱儈儌僓娰偲偄偆儂僥儖傪塩傓拞擭晇晈丄偍恖岲偟偺晇偼僇僕僲偵嬑傔偰偍傝丄儘僛乕偑墘偠傞偟偭偐傝幰偺嵢儖僀乕僘偑儂僥儖偺宱塩傪巇愗偭偰偄傞丅斵傜偼懠恖偐傜梐偐偭偰堢偰偰偄傞梒偄抝偺巕僺僄乕儖傪揗垽偟偰偄傞丅傗偑偰僺僄乕儖偼幚偺晝偵堷偒庢傜傟偰僷儕偵峴偔丅儖僀乕僘偼嬥傪巇憲傝偟偰僺僄乕儖偺惗妶傪彆偗傞丅惉挿偟偰搎攷傗堘朄側巇帠偵実傢傞傛偆偵側偭偨僺僄乕儖傪怱攝偟偨儖僀乕僘偼丄斵傪峏惗偝偣傞偨傔帺暘偺尦偵屇傃婑偣傞丄僺僄乕儖偼崨傟崬傫偩僊儍儞僌偺儃僗偺惈埆彈僱儕乕偲偲傕偵儈儌僓娰偵傗偭偰棃傞丅儖僀乕僘偼攈庤偵梀傃傑傢傞僱儕乕傪捛偄弌偟偨偄偑丄僺僄乕儖偺偨傔偵変枬偡傞丅僱儕乕偼僊儍儞僌偺儃僗偵楢傟嫀傜傟丄夛幮偺嬥傪巊偄崬傫偱僇僕僲偱戝攕偟偨僺僄乕儖偼愨朷偟偰帺嶦偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅屻敿丄儈儌僓娰偱偺儖僀乕僘偲僱儕乕偺懳棫偼丄偄傢備傞壟偲屍偺峔恾偩偑丄儖僀乕僘偺僺僄乕儖傊偺忣垽偼丄曣偲偟偰偺垽偲彈偲偟偰偺垽偑擖傝岎偠偭偨傕偺偱偁傞偙偲偼柧傜偐偩丅嵟屻偺僔乕儞丄僺僄乕儖偺堚懱傪偐偒書偔儖僀乕僘丄憢偐傜悂偒崬傓晽丄偦偺晽偵悂偐傟偰晳偄梮傞嶥懇偑報徾怺偄丅僰乕償僃儖償傽乕僌攈偐傜婖傒寵傢傟偨塮夋偺傛偆偩偑丄庡恖岞偺怱棟揑妺摗偼岻傒偵昤偐傟偰偄傞偲巚偆丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐78丂僔儍僽儘儖偺弶婜偺塮夋3杮
1959丂僋儘乕僪丒僔儍僽儘儖丂昡揰乵C乶
揷幧偐傜僷儕偵弌偰偒偨僕僃儔乕儖丒僽儔儞偼丄偄偲偙偺僕儍儞僋儘乕僪丒僽儕傾儕偺傾僷儖儖僩儅儞偵嫃岓偟偰戝妛偵捠偆恀柺栚側惵擭丅僽儕傾儕傕摨偠戝妛偵捠偆妛惗偩偑恊偺偡偹傪偐偠傞彈岲偒偺梀傃恖丅傾僷儖僩儅儞偱偼偄偮傕拠娫傪屇傫偱棎抯婥僷乕僥傿傪偟偰偄傞丅僽儔儞偼僷乕僥傿偱抦傝崌偭偨旤彈僕儏儕僄僢僩丒儊僯僄儖偵堦栚崨傟偡傞偑丄僽儕傾儕偑斵彈傪墶庢傝偟偰摨惐偟巒傔丄3恖偺婏柇側摨嫃惗妶偑巒傑傞丅恀柺栚偵曌嫮偟偰偄偨僽儔儞偼戝妛偺帋尡偵棊偪偰棊戞偡傞偑丄梫椞偺偄偄僽儕傾儕偼梀傃傎偆偗偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢崌奿偡傞丅僽儕傾儕偺対廵偺岆幩偵傛偭偰僽儔儞偼巰偸丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偳偙偑柺敀偄偺偐暘偐傜側偄丅摉帪偲偟偰偼抝彈偺楒垽僎乕儉偵傆偗傞庒幰偺惗懺傪昤偄偨偺偑栚怴偟偐偭偨偺偩傠偆偐丅嵟屻偺庡恖岞偺巰偼庢偭偰晅偗偨傛偆偱晄帺慠偝傪姶偠傞丅僰乕償僃儖償傽乕僌攈偺側偐偱僔儍僽儘儖偺媄朄偼斾妑揑僆乕僜僪僢僋僗偩偲巚偆丅傾儞儕丒僪僇僄偺嶣塭偼偝偡偑偵尒帠偩丅
擇廳偺尞
1959丂僋儘乕僪丒僔儍僽儘儖丂昡揰乵C乶
偙偺塮夋偼丄戝愄丄妛惗偺偙傠偵尒偰偄傞丅拞恎偼傎偲傫偳妎偊偰偄側偄偑丄柺敀偔側偐偭偨偲偄偆報徾偑偁傞丅儌僲僋儘偩偲婰壇偟偰偄偨偑丄崱夞嵞尒偟偰僇儔乕偩偭偨偺偱嬃偄偨丅嵞尒偟偰偺報徾偼埲慜偲曄傢傜側偄丅僽儖僕儑傾壠懓偺偡偝傫偩恖娫娭學偲偦偙偱婲偒偨嶦恖帠審傪昤偔儈僗僥儕乕巇棫偰偺塮夋偱丄僄僋僒儞僾儘償傽儞僗偺桾暉側儚僀儞忴憿嬈嬈幰偺揁戭偑晳戜丅椬偺壠偵廧傓彈寍弍壠偲晄椣偟偰偍傝丄嵢偲暿傟偨偄偲巚偭偰偄傞偑丄壠傕嵿嶻傕嵢偺帩偪暔側偺偱柍堦暥偵側傞偙偲傪嫲傟傞晇丄晇偺晄椣傪抦傝側偑傜丄奿幃傪廳傫偠丄柤壠偺懱柺傪庣傠偆偲偡傞嵢丄偄偮傕僋儔僔僢僋壒妝傪挳偄偰偄傞儅僓僐儞偺懅巕偲丄悽娫抦傜偢偺僼傽僓僐儞偺柡丄柡偺崶栺幰偱朤庒柍恖偵傆傞傑偆慹栰側棳傟幰偲偄偭偨搊応恖暔偑棈傒崌偄側偑傜僗僩乕儕乕偑恑峴偟丄嵟屻偼晇偺晄椣偺憡庤偺彈寍弍壠偑嶦偝傟丄懅巕偑斊恖偩偲帺敀偟偰廔傞丅僔儍僽儘儖偼僽儖僕儑傾僕乕偺媆嵩惈偲懎暔惈傪昤偙偆偲偟偨偺偐傕偟傟側偄偑丄晇偑嵢傪憺傓條偼忢婳傪堩偟偰偍傝丄岥榑偵嵺偟偰晇偑嵢偵梺傃偣傞攍搢偼偁傑傝偵堎忢偩丅僒僗儁儞僗偺梫慺傕婓敄偱丄僸僢僠僐僢僋偺塭嬁傪塢乆偡傞昡傕偁傞偑丄偳偙偑僸僢僠僐僢僋晽側偺偐棟夝偵嬯偟傓丅慹栰側庒幰偵暞偡傞柍柤帪戙偺僕儍儞億乕儖丒儀儖儌儞僪丄彈寍弍壠偵暞偡傞傾儞僩僱僢儔丒儖傾儖僨傿偼懚嵼姶傪敪婗偟偰偄傞丅
婥偺偄偄彈偨偪
1960丂僋儘乕僪僔儍僽儘儖丂昡揰乵D乶
僷儕偺壠揹惢昳揦偵嬑傔傞庒偄彈偨偪偺惗懺傪昤偄偨晽懎塮夋丅僔儍僽儘儖偺弶婜塮夋傪3杮懕偗偰尒偰姶偠傞偺偼埆堄偺偁傞栚慄偩丅斵偼搊応恖暔傪旂擏偲殅徫偺栚偱偟偐尒側偄丅偦偙偵偼嶌傝庤偺恖娫惈偺斱偟偝偲閬傝傪姶偠傞丅偙偙偱傕彈偨偪偼擼揤婥偵偄偮傕栭偺奨偱梀傃夞傝丄抝偨偪偼彈傪傕偺偵偡傞偙偲偵擬拞偡傞丅偦偟偰嵟屻偵傂偲傝偺彈偑嶦恖婼偵堷偭妡偗傜傟偰柦傪棊偲偡丅塮夋傪尒廔傢偭偰丄屻枴偺埆偝偩偗偑巆傞丅偙偆偄偆塮夋傪尒傞偲丄僽儗僢僜儞偺娙寜偱梷惂偝傟偨嬛梸揑側嶌昳傪尒偨偔側偭偰偔傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐77丂僽儗僢僜儞偺撈帺惈偑敪婗偝傟偨拞婜偺塮夋
1964丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰乵B乶
 偙傟偼崜巊偝傟傞儘僶偲昻偟偄弮杙側柡傪傔偖傞晄忦棟側暔岅偱丄庡恖岞偼僶儖僞僓乕儖偲偄偆柤偺儘僶偩丅姶忣昞尰傪嬌搙偵梷偊傞偲偄偆僽儗僢僜儞偺墘弌朄偐傜偡傟偽丄姶忣傪昞偵弌偝側偄儘僶偼傕偭偲傕憡墳偟偄弌墘幰偩偲尵偊傞丅僼儔儞僗偺曅揷幧偺懞偑晳戜丅彮彈儅儕乕偼壠偱帞偭偰偄偨儘僶偲拠椙偟偵側傞丅傗偑偰儘僶偼傎偐偺壠偵攧傜傟傞偑丄摝憱偟偰儅儕乕偺壠偵晳偄栠傞丅儘僶偼嵞傃懠壠偵攧傜傟丄懞偺晄椙僕僃儔乕儖偵僷儞偺攝払偺偨傔崜巊偝傟丄懱傪夡偡丅惉挿偟偨儅儕乕偼帺暘傪庤崬傔偵偟偨僕僃儔乕儖偐傜棧傟傜傟側偔側傞丅儘僶偼偁偪偙偪偺壠偱崜巊偝傟偨偡偊丄儅儕乕偵堷偒庢傜傟傞丅儅儕乕偼梒側偠傒偺恀柺栚側惵擭僕儍僢僋偐傜媮崶偝傟傞偑丄僕僃儔乕儖偵庱偭偨偗偺斵彈偼偦傟傪嫅愨偡傞丅偩偑儅儕乕偼僕僃儔乕儖偲拠娫偵堅傒傕偺偵偝傟怞傔傜傟偰巔傪徚偡丅偄偭傐偆儘僶偼嶳拞傪偝傑傛偭偨偁偘偔梤偺孮傟偺側偐偱懅愨偊傞丅偍偍傓偹偦傫側僗僩乕儕乕偩偑丄杮嬝偵娭學側偄偄傠傫側僄僺僜乕僪偑柆棈側偔昤偐傟傞丅偦傕偦傕丄偙偺塮夋偱偼僄僺僜乕僪偑抐曅揑偵捲傜傟丄偦傟傜傪寢傃偮偗傞愢柧偑嬌抂偵徣偐傟偰偄傞偺偱丄棳傟偼傛偔暘偐傜側偄丅儅儕乕偼嵟屻偵壠偐傜偄側偔側傞偑丄傕偟偐偟偨傜巰傫偩偺偐傕偟傟側偄偟丄僕僃儔乕儖偺惗巰傕偼偭偒傝偲偼昤偐傟側偄丅僽儗僢僜儞偼僪僗僩僄僼僗僉乕偺乽敀抯乿偵憐傪摼偨偲偺偙偲偩偑丄側傜偽儉僀僔儏僉儞偼儘僶偱丄僫僗僞乕僔儍偼昻偟偄柡偐丅榖偺棳傟偼捦傒偵偔偄偗傟偳傕丄慡懱偲偟偰偼偗偭偟偰擄夝偱偼側偄丅壗傪尵偄偨偄偺偐傛偔暘偐傜側偄塮夋偩偑丄婏柇側枺椡傪偨偨偊偰偄傞偙偲偼妋偐偩丅
偙傟偼崜巊偝傟傞儘僶偲昻偟偄弮杙側柡傪傔偖傞晄忦棟側暔岅偱丄庡恖岞偼僶儖僞僓乕儖偲偄偆柤偺儘僶偩丅姶忣昞尰傪嬌搙偵梷偊傞偲偄偆僽儗僢僜儞偺墘弌朄偐傜偡傟偽丄姶忣傪昞偵弌偝側偄儘僶偼傕偭偲傕憡墳偟偄弌墘幰偩偲尵偊傞丅僼儔儞僗偺曅揷幧偺懞偑晳戜丅彮彈儅儕乕偼壠偱帞偭偰偄偨儘僶偲拠椙偟偵側傞丅傗偑偰儘僶偼傎偐偺壠偵攧傜傟傞偑丄摝憱偟偰儅儕乕偺壠偵晳偄栠傞丅儘僶偼嵞傃懠壠偵攧傜傟丄懞偺晄椙僕僃儔乕儖偵僷儞偺攝払偺偨傔崜巊偝傟丄懱傪夡偡丅惉挿偟偨儅儕乕偼帺暘傪庤崬傔偵偟偨僕僃儔乕儖偐傜棧傟傜傟側偔側傞丅儘僶偼偁偪偙偪偺壠偱崜巊偝傟偨偡偊丄儅儕乕偵堷偒庢傜傟傞丅儅儕乕偼梒側偠傒偺恀柺栚側惵擭僕儍僢僋偐傜媮崶偝傟傞偑丄僕僃儔乕儖偵庱偭偨偗偺斵彈偼偦傟傪嫅愨偡傞丅偩偑儅儕乕偼僕僃儔乕儖偲拠娫偵堅傒傕偺偵偝傟怞傔傜傟偰巔傪徚偡丅偄偭傐偆儘僶偼嶳拞傪偝傑傛偭偨偁偘偔梤偺孮傟偺側偐偱懅愨偊傞丅偍偍傓偹偦傫側僗僩乕儕乕偩偑丄杮嬝偵娭學側偄偄傠傫側僄僺僜乕僪偑柆棈側偔昤偐傟傞丅偦傕偦傕丄偙偺塮夋偱偼僄僺僜乕僪偑抐曅揑偵捲傜傟丄偦傟傜傪寢傃偮偗傞愢柧偑嬌抂偵徣偐傟偰偄傞偺偱丄棳傟偼傛偔暘偐傜側偄丅儅儕乕偼嵟屻偵壠偐傜偄側偔側傞偑丄傕偟偐偟偨傜巰傫偩偺偐傕偟傟側偄偟丄僕僃儔乕儖偺惗巰傕偼偭偒傝偲偼昤偐傟側偄丅僽儗僢僜儞偼僪僗僩僄僼僗僉乕偺乽敀抯乿偵憐傪摼偨偲偺偙偲偩偑丄側傜偽儉僀僔儏僉儞偼儘僶偱丄僫僗僞乕僔儍偼昻偟偄柡偐丅榖偺棳傟偼捦傒偵偔偄偗傟偳傕丄慡懱偲偟偰偼偗偭偟偰擄夝偱偼側偄丅壗傪尵偄偨偄偺偐傛偔暘偐傜側偄塮夋偩偑丄婏柇側枺椡傪偨偨偊偰偄傞偙偲偼妋偐偩丅2020擭9寧朸擔 旛朰榐76丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞偺弶婜塮夋2杮
1943丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰乵C乶
僽儗僢僜儞偺張彈嶌丅彈庴孻幰偵弌崠屻偺嫃応強傪採嫙偡傞彈巕廋摴堾偑晳戜丅僽儖僕儑傾壠掚偺柡傾儞僰儅儕乕偲尦庴孻幰僥儗乕僘偲偄偆2恖偺廋摴彈偺桭垽偲憺埆丄偦偟偰怱偺妺摗傪幉偵暔岅偼恑傓丅偍偦傜偔恖娫偺尨嵾丄恄偺媬偄偲偄偭偨柦戣偑僥乕儅側偺偩傠偆丅廋摴堾偱偺惗妶偑崕柧偵昤偐傟偰偄傞偺偑嫽枴怺偄偲尵偊偽尵偊傞丅塮夋偺朻摢丄栭拞偵堾挿偑孻柋強傪朘傟偰庴孻幰偲柺夛偡傞僔乕儞偑報徾偵巆傞丅
揷幧巌嵳偺擔婰
1950丂儘儀乕儖丒僽儗僢僜儞丂昡揰乵D乶
僽儗僢僜儞偺戞3嶌丅戣柤偳偍傝丄揷幧偺嫵夛偵攈尛偝傟偨庒偄杚巘偑怱偵書偔屒撈丄寬峃傊偺晄埨丄廆嫵傊偺夰媈丄婃柪側懞柉偲偺鏰鐎偑擔婰宍幃偱昤偐傟傞丅姶忣昞尰偼嬌抂偵梷偊傜傟偰偍傝丄慡曇傪捠偠偰傑偭偨偔媬偄偑側偔丄埫烼側嬻婥偵巟攝偝傟偰偄傞丅嵟弶偐傜嵟屻傑偱嬯擸偟懕偗傞庡恖岞偺巌嵳偼偙偺悽偺嬯擸傪堦恎偵攚晧偭偰偄傞偐偺傛偆偩丅偦傟偱傕斵偼巰偸娫嵺偵乽偡傋偰偼恄偺巚偟彚偟偩乿偲岥憱傞丅怣嬄偲偼壗偐傪峫偊偝偣傜傟傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐75丂儕僲丒償傽儞僠儏儔偺傾僋僔儑儞塮夋乣偦偺2
1960丂僋儘乕僪丒僜乕僥丂昡揰乵A乶
 儕僲丒償傽儞僠儏儔偲僕儍儞丒億乕儖丒儀儖儌儞僪偑嫟墘偟偨僊儍儞僌塮夋偺寙嶌丅桭忣偲棤愗傝偑僥乕儅偩偑丄償傽儞僠儏儔偑巕楢傟偱摝憱偡傞僊儍儞僌偩偲偄偆愝掕偑怴枴丅尨嶌偼僕儑僛丒僕儑僶儞僯丅僀僞儕傾偵摝朣拞偺償傽儞僠儏儔偼僷儕偵婣娨偟傛偆偲偡傞偑丄枾峲偟偨僯乕僗偱寈旛戉偲廵寕愴偵側傝丄拠娫偲嵢偑嶦偝傟丄2恖偺梒帣傪書偊偰棫偪墲惗偡傞丅僷儕偺偐偮偰偺拠娫偵楢棈偟偰彆偗傪媮傔傞偲丄堦旵楾偺儀儖儌儞僪偑婾憰偟偨媬媫幵傪塣揮偟偰尰傟丄斵傜傪僷儕偵楢傟偰峴偔丅僷儕偺媽桭偨偪偐傜丄偐偮偰壎媊傪巤偟偨偵傕偐偐傢傜偢愽暁応強傪採嫙偡傞偺傪嫅斲偝傟偨償傽儞僠儏儔偼丄儀儖儌儞僪偺傾僷儖僩儅儞偵恎傪愽傔傞偑丄媽桭偨偪偑寈嶡偵枾崘偟傛偆偲偟偰偄傞偺傪抦傝丄暅廞偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅棊偪傇傟偨僊儍儞僌偺斶垼偲庘泴傪傑偲偆償傽儞僠儏儔偑側偐側偐偺懚嵼姶丅镚乆偲偟偨儀儖儌儞僪傕報徾怺偔丄僑僟乕儖塮夋偺斵傛傝偼傞偐偵僇僢僐偄偄丅峴摦傪偲傕偵偟偰偄傞偁偄偩偵償傽儞僠儏儔偲儀儖儌儞僪偑桭忣偲怣棅偺鉐偱寢偽傟傞夁掱偺昤幨偑廏堩丅儀儖儌儞僪偺幵偵廍傢傟偰摝朣傪彆偗傞庒偄彈僒儞僪儔丒儈乕儘偑怓偭傐偄丅
儕僲丒償傽儞僠儏儔偲僕儍儞丒億乕儖丒儀儖儌儞僪偑嫟墘偟偨僊儍儞僌塮夋偺寙嶌丅桭忣偲棤愗傝偑僥乕儅偩偑丄償傽儞僠儏儔偑巕楢傟偱摝憱偡傞僊儍儞僌偩偲偄偆愝掕偑怴枴丅尨嶌偼僕儑僛丒僕儑僶儞僯丅僀僞儕傾偵摝朣拞偺償傽儞僠儏儔偼僷儕偵婣娨偟傛偆偲偡傞偑丄枾峲偟偨僯乕僗偱寈旛戉偲廵寕愴偵側傝丄拠娫偲嵢偑嶦偝傟丄2恖偺梒帣傪書偊偰棫偪墲惗偡傞丅僷儕偺偐偮偰偺拠娫偵楢棈偟偰彆偗傪媮傔傞偲丄堦旵楾偺儀儖儌儞僪偑婾憰偟偨媬媫幵傪塣揮偟偰尰傟丄斵傜傪僷儕偵楢傟偰峴偔丅僷儕偺媽桭偨偪偐傜丄偐偮偰壎媊傪巤偟偨偵傕偐偐傢傜偢愽暁応強傪採嫙偡傞偺傪嫅斲偝傟偨償傽儞僠儏儔偼丄儀儖儌儞僪偺傾僷儖僩儅儞偵恎傪愽傔傞偑丄媽桭偨偪偑寈嶡偵枾崘偟傛偆偲偟偰偄傞偺傪抦傝丄暅廞偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅棊偪傇傟偨僊儍儞僌偺斶垼偲庘泴傪傑偲偆償傽儞僠儏儔偑側偐側偐偺懚嵼姶丅镚乆偲偟偨儀儖儌儞僪傕報徾怺偔丄僑僟乕儖塮夋偺斵傛傝偼傞偐偵僇僢僐偄偄丅峴摦傪偲傕偵偟偰偄傞偁偄偩偵償傽儞僠儏儔偲儀儖儌儞僪偑桭忣偲怣棅偺鉐偱寢偽傟傞夁掱偺昤幨偑廏堩丅儀儖儌儞僪偺幵偵廍傢傟偰摝朣傪彆偗傞庒偄彈僒儞僪儔丒儈乕儘偑怓偭傐偄丅抧崠偺寛巰戉
1960丂僪僯僗丒僪丒儔丒僷僩儕僄乕儖丂昡揰乵B乶
儕僲丒償傽儞僠儏儔庡墘偺愴憟塮夋偩偑丄愴摤応柺偑傎偲傫偳側偔丄堦庬偺儘乕僪丒儉乕償傿偵巇忋偑偭偰偄傞偲偙傠偑柺敀偄丅杒傾僼儕僇偱愴摤拞偺償傽儞僠儏儔傪儕乕僟乕偡傞偡傞4恖偺僼儔儞僗孯暫巑偼丄僪僀僣偺彨峑僴乕僨傿丒僋儕儏乕僈乕傪曔椄偲偟丄愴慄偐傜戅媝偟偰挀撛抧偵栠傠偆偲偡傞丅斵傜偑幵偱嵒敊傪椃偡傞娫偵丄揋懳偟偰偄偨僪僀僣彨峑偲偺偁偄偩偵桭忣偑惗傑傟傞偑丄傕偆偡偖栚揑抧偲偄偆偲偙傠偱丄枴曽偺岆幩偺偨傔偵償傽儞僠儏儔埲奜偺慡堳偑柦傪棊偲偡丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僋儕儏乕僈乕偑椙偄枴傪弌偟偰偍傝丄乽旘傋僼僃僯僢僋僗乿偱偺斵傪渇渋偲偝偣傞丅暫巑偺傂偲傝傪墘偠傞僔儍儖儖丒傾僘僫僽乕儖傕報徾偵巆傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐74丂儕僲丒償傽儞僠儏儔偺傾僋僔儑儞塮夋乣偦偺1
1958丂僎僣傽丒僼僅儞丒儔僪償傽僯丂昡揰乵C乶
堄奜側廍偄傕偺丅孻柋強偐傜扙崠偟偨儕僲丒償傽儞僠儏儔傎偐偺3恖偑揷幧偺峘挰偵峴偒丄媽抦偺彈僄償傽丒僶儖僩乕僋偺彆偗傪摼偰慏偱摝偘傛偆偲偡傞丅寢嬊丄3恖偺偆偪丄堦恖偼扙崠偺嵺偵晧偭偨夦変偱巰偵丄堦恖偼嶦偝傟丄償傽儞僠儏儔偼寈嶡偵曔傑傝丄僶儖僩乕僋偩偗偑慏偵忔偭偰奨傪棧傟傞偲偄偆榖丅僴儞僈儕乕宯偺旤恖彈桪僶儖僩乕僋偑尒傜傟傞偺偼廂妌丅幨恀壆偺庡恖偱彆庤偺僶儖僩乕僋偵寽憐偡傞僎儖僩丒僼儗乕儀偑嫸婥偲垼傟偝傪忴偟弌偟偰尒帠偩丅
忣曬偼壌偑栣偭偨
1959丂儀儖僫乕儖丒儃儖僪儕乕丂昡揰乵D乶
儕僲丒償傽儞僠儏儔庡墘偺僗僷僀塮夋偲僊儍儞僌塮夋傪儈僢僋僗偟偨傛偆側嶌昳丅償傽儞僠儏儔偼傾僋僔儑儞丒僗僞乕偲偟偰偺柺栚傪敪婗偡傞偑丄嬝棫偰偑傛偔暘偐傜側偄丅榖偼償傽儞僠儏儔偑孻柋強傪扙崠偡傞偲偙傠偐傜僗僞乕僩偡傞丅斵偼偳偆傗傜崙偺杊挸嬊偺堦堳偱丄扙崠偼揋偺僗僷僀慻怐偵愽擖偡傞偨傔偺岺嶌偩偭偨傜偟偄偑丄偦偺偁偲偺棳傟偑偪偖偼偖偱柺敀傒偵寚偗傞丅
2020擭9寧朸擔 旛朰榐73丂儌僟儞丒僕儍僘傪巊偭偨僼儔儞僗墲擭偺斊嵾塮夋
1959丂僄僪僁傾乕儖丒儌儕僫儘丂昡揰乵C乶
嵞尒丅儘儀乕儖丒僆僢僙儞丄儅僈儕丒僲僄儖庡墘偺僒僗儁儞僗塮夋丅壒妝偼傾乕僩丒僽儗僀僉乕偲僕儍僘丒儊僢僙儞僕儍乕僘丅楒恖僲僄儖偺栭偺奜弌偵晄怣傪書偄偨庒幰僆僢僙儞偑丄峴愭偺暿憫傪撍偒偲傔偰愽擖偡傞偲丄偦偙偱偼僷乕僥傿偑奐偐傟偰偄偨丅偦傟偼彈惈恖恎攧攦慻怐偑彈傪庤偵擖傟傞偨傔偺悌偩偭偨丅僆僢僙儞偼僲僄儖傪媬偄弌偟丄寈姱戉偲偺廵寕愴偺枛丄堦枴偼幩嶦偝傟傞丅儀僯乕丒僑儖僜儞嶌偺壒妝丄僕儍僘丒儊僢僙儞僕儍乕僘偺墘憈偑岠壥傪忋偘偰偄傞丅堦枴偺嶦偟壆僼傿儕僢僾丒僋儗僀偺晄婥枴偝偑報徾偵巆傞丅
斵搝傪嶦偣
1959丂僄僪僁傾乕儖丒儌儕僫儘丂昡揰乵B乶
儕僲丒償傽儞僠儏儔庡墘偺僒僗儁儞僗塮夋丅嶣塭偼傾儞儕丒僪僇僄丄壒妝偼僶儖僱丒僂傿儔儞偵傛傞僕儍僘丅嵢傪嶦偝傟偨償傽儞僠儏儔偼晄婲慽偵側偭偨斊恖傪暅廞偺偨傔嶦偡偑丄斊峴屻偵壠偐傜弌傞偲偙傠傪僞僋僔乕塣揮庤偵栚寕偝傟傞丅斵偼塣揮庤傪嶦偡偨傔幏漍偵晅偗慱偄丄栚揑傪壥偨偡偑丄偦偺堦晹巒廔偑柍慄儅僀僋傪捠偟偰攝幵學偺揹榖僙儞僞乕偵暦偙偊偰偍傝丄塣揮庤拠娫偑憤弌偱償傽儞僠儏儔傪捛偄偐偗傞丅捛偄媗傔傜傟偨償傽儞僠儏儔偼寈姱偵寕偨傟偰巰偸丅働僯乕丒僪乕僴儉傪娷傓僶儖僱丒僂傿儔儞丒僋僀儞僥僢僩偺墘憈偑暤埻婥傪惙傝忋偘傞丅傾儞儕丒僪僇僄偺僇儊儔偼栭偺僷儕偺奨傪尒帠偵塮偟弌偟偰偄傞丅
2020擭8寧
2020擭8寧朸擔 旛朰榐72丂儘儀乕儖丒傾儞儕僐斢擭偺2嶌昳
1987丂儘儀乕儖丒傾儞儕僐丂昡揰乵C乶
僫僠僗愯椞壓偺僼儔儞僗丅儗僕僗僞儞僗偺堦堳偱儐僟儎恖堛巘偺枹朣恖傾儕僗偑丄拠娫偱偁傞楒恖偺奜岎姱僕僃儘乕儉偲偲傕偵儐僟儎恖偺崙奜摝朣傪彆偗傞偨傔丄僕僃儘乕儉偺梒桭払偱偁傞揷幧偺惢孋岺応庡僔儍儖儖偺壠傪朘偹傞丅摨嫃偟偰偄傞偆偪偵僔儍儖儖偼傾儕僗偵庝偐傟偰偄偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡墘偺僫僞儕乕丒僷僀傪偼偠傔丄弌墘幰偼傒側撻愼傒側偄攐桪偩偑丄撪梕偼埆偔側偄丅弌偩偟偑媢偺忋傪帺揮幵偱憱傞僔乕儞偲偄偆揰偱傾儞儕僐偺寙嶌乽捛憐乿傪憐婲偝偣傞偟丄彈偲桭恖摨巑偺抝2恖偺3妏娭學偑昤偐傟傞偲偄偆揰偱偼乽朻尟幰偨偪乿傪渇渋偲偝偣傞丅
僒儞亖僥僌僕儏儁儕丂惎嬻傊偺婣娨
1994丂儘儀乕儖丒傾儞儕僐丂昡揰乵D乶
僒儞亖僥僌僕儏儁儕偺揱婰塮夋丅偙傟傕乽捛憐乿偲摨偠偔僒僀僋儕儞僌偺僔乕儞偐傜巒傑傞丅戞2師戝愴拞丄掋嶡旘峴偵弌敪偟傛偆偲偡傞僒儞亖僥僌僕儏儁儕偑偙傟傑偱偺恖惗傪夞憐偡傞榖丅斵偼偦偺旘峴偱寕捘偝傟丄柦傪棊偲偡丅夞憐僔乕儞偑昿斏偵憓擖偝傟丄榖偑偁偪偙偪偵旘傇偺偱丄棳傟偑傛偔捦傔側偄偑丄慡懱偲偟偰傾儞儕僐傜偟偄僲僗僞儖僕僢僋側暤埻婥偵枮偪偰偄傞丅
2020擭8寧朸擔 旛朰榐71丂40擭戙屻婜偺僊儍僶儞偺庡墘嶌2杮
1946丂僕儑儖僕儏丒儔僐儞僽丂昡揰乵C乶
摉帪楒垽娭學偵偁偭偨僕儍儞丒僊儍僶儞偲儅儗乕僱丒僨傿乕僩儕僢僸偺桞堦偺嫟墘嶌丅揷幧挰偺寶抸惪晧巘僊儍僶儞偼彫捁壆傪塩傓枹朣恖僨傿乕僩儕僢僸偲弌夛偭偰楒偵棊偪丄堦弿偵曢傜偡傛偆偵側傞偑丄僨傿乕僩儕僢僸偼嬥帩偪偺椞帠偐傜媮崶偝傟丄偳偪傜傪慖傇偐柪偆丅幑搃偵嫸偭偨僊儍僶儞偼斵彈傪峣傔嶦偡丅斵偼嵸敾偱柍嵾偵側傞偑丄斵彈偑杮摉偼帺暘傪垽偟偰偄偨偲抦傝丄斵傪媤偲晅偗慱偆惵擭偵傢偞偲寕偨傟偰巰偸丅塮夋偲偟偰偼偦偮側偔巇忋偑偭偰偄傞偑丄2恖偺婄崌傢偣偲偄偆埲奜丄偳偙偲偄偭偰庢傝暱偑側偔丄偁傑傝報徾偵巆傞僔乕儞傕側偄丅
峘偺儅儕乕
1949丂儅儖僙儖丒僇儖僱丂昡揰乵C乶
僔僃儖僽乕儖偱儗僗僩儔儞偲塮夋娰傪塩傓僕儍儞丒僊儍僶儞偼揷幧偺峘挰偱丄摨惐偟偰偄傞垽恖偺枀僯僐乕儖丒僋乕儖僙儖傪尒弶傔傞丅昻偟偄曢傜偟偐傜敳偗弌偟偰僷儕偵峴偒偨偄偲婅偆僋乕儖僙儖偼丄桿偄偵忔偭偰僊儍僶儞偵夛偄偵峴偔丅恻梋嬋愜偺枛丄2恖偼寢偽傟傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅僊儍僶儞偑儗僗僩儔儞偺僆乕僫乕偱偁傝丄庒偄柡偵擖傟偁偘傞丄偲偄偆愝掕偼乽嶦堄偺弖娫乿傪憐婲偝偣傞丅偦偙偱僊儍僶儞偑偨傇傜偐偝傟傞柡偼婬戙偺埆彈偩偭偨偑丄偙偺乽峘偺儅儕乕乿偱偺柡偼丄摉弶偼僊儍僶儞傪閤偦偆偲偟偰偄傞偐偵尒偊傞偑丄偦偆偱偼側偔丄慜搑偵擸傫偱偄傞偩偗偩偲偄偆偙偲偑暘偐傞丅僊儍僶儞偼垽恖偺晜婥偺尰応傪尒偮偗丄屻傠傔偨偝傪姶偠傞偙偲側偔庒偄柡偲堦弿偵側傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆丄偒傢傔偰偛搒崌庡媊偺嬝棫偰偵側偭偰偄傞丅僋儖僙乕儖偺旤偟偝偼摿昅偡傋偒傕偺偑偁傞丅
2020擭8寧朸擔 旛朰榐70丂僕僃儔乕儖丒僼傿儕僢僾庡墘偺2嶌昳
1950丂儅儖僙儖丒僇儖僱丂昡揰乵B乶
柌傪僥乕儅偵偟偨旤偟偝偲垼愗姶昚偆僼傽儞僞僕乕塮夋丅僕僃儔乕儖丒僼傿儕僢僾庡墘丅旤彈僕儏儕僄僢僩偲抦傝崌偭偨僼傿儕僢僾偼斵彈偲椃峴偡傞偨傔揦偺嬥傪搻傒丄戇曔偝傟傞丅崠拞偱斵偼柌傪尒傞丅僪傾偑奐偔偲丄偺偳偐側懞偑峀偑偭偰偍傝丄媢偺忋偵忛娰偑偁傞丅偦偙偼朰媝偺崙偱廧柉偼婰壇傪帩偨側偄丅斵偼偦偙偱僕儏儕僄僢僩偵弰傝夛偆偑丄斵彈偼忛娰偵廧傓婱懓偵曔傢傟傞丅栚偑妎傔偨斵偼庍曻偝傟傞偑丄尰幚偺僕儏儕僄僢僩偑揦偺庡恖偲崶栺偟偨偲抦傝丄朰媝偺崙偵栠偭偰斵彈偲夛偆偨傔丄岺帠応偺婋尟棫偪擖傝嬛巭偲彂偐傟偨僪傾傪奐偗傞丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅僕儏儕僄僢僩栶偺僔儏僓儞僰丒僋儖乕僥傿僄偺惔慯側旤偟偝偑嵺棫偮丅怷偺側偐偱偺懞恖偺僟儞僗偺僔乕儞偑報徾偵巆傞丅
栭偛偲偺旤彈
1952丂儖僱丒僋儗乕儖丂昡揰乵B乶
埲慜尒偨偙偲偑偁傞偲巚偭偰偄偨偑丄偳偆傗傜弶尒偺傛偆偩丅偙傟傕僕僃儔乕儖丒僼傿儕僢僾庡墘偺柌傪戣嵽偲偡傞僼傽儞僞僕乕晽僐儊僨傿塮夋丅僼傿儕僢僾偼攧傟側偄壒妝壠丅妛峑偱惗搆偨偪偵攏幁偵偝傟側偑傜壒妝傪嫵偊丄嬥帩偪偺壠偱僺傾僲嫵巘偲柋傔丄嫹偄傾僷乕僩偱憶壒偵擸傑偝傟側偑傜嶌嬋偡傞擔乆傪憲傞丅柌偺側偐偱丄斵偼榁恖偺愄偼椙偐偭偨偲偄偆尵梩偲偲傕偵偄傠傫側帪戙偵峴偒丄偝傑偞傑側旤彈偵楒傪偡傞丅偦偺旤彈偼尰幚悽奅偱偼幵廋棟岺偺柡偩偭偨傝丄僺傾僲傪嫵偊傞壠偺晇恖偩偭偨傝丄僇僼僃偺儗僕學偩偭偨傝丄梄曋嬊偺憢岥學偩偭偨傝偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅慡懱偵儈儏乕僕僇儖巇棫偰偱丄柌偺側偐偱傢偞偲捖晠側彂偒妱傝僙僢僩傪巊偭偰偄傞偺偑柺敀偄丅尰幚偺悽奅偱斵偺僘儃儞偺旼偑楐偗傞偲丄柌偺悽奅偱傕偦偆側偭偨傝偡傞偲偄偆傛偆側嵶偐偄僊儍僌偑煭棊偰偄傞丅嵟屻偼斵偺嶌嬋偟偨晥柺偑僆儁儔嵗偱嵦梡偝傟丄楒恖傕摼偰僴僢僺乕僄儞僪偲側傞丅傑偝偵柌偺傛偆側岾暉側塮夋偩丅
2020擭8寧朸擔 旛朰榐69丂僇儖僱仌僊儍僶儞丒僐儞價偺戙昞嶌乽柖偺攇巭応乿
1938丂儅儖僙儖丒僇儖僱丂昡揰乵B乶
帊揑儕傾儕僘儉偺寙嶌偲尵傢傟傞僇儖僱偺柤嶌丅庡墘偼僕儍儞丒僊儍僶儞偲儈僔僃儖丒儌儖僈儞丅扙憱暫僊儍僶儞偼峘挰儖傾乕僽儖偵棳傟拝偒丄嶨壿壆偺柡儌儖僈儞偲弌夛偭偰楒偵棊偪傞丅梀墍抧偱儌儖僈儞偲僨乕僩偡傞僊儍僶儞偼場墢傪偮偗偵棃偨抧尦偺傗偔偞僺僄乕儖丒僽儔僢僗乕儖傪暯庤偱傔偭偨懪偪偟偰捛偄暐偆丅撿暷偵枾峲偡傞慜丄儌儖僈儞偵暿傟傪傪尵偆偨傔嶨壿壆偵棃偨僊儍僶儞偼丄斵彈偵尵偄婑傞媊晝儈僔僃儖丒僔儌儞傪扏偒偺傔偡偑丄揦傪弌偨捈屻丄僽儔僢僗乕儖偵寕偨傟偰巰偸丅柖偵墝傞峘挰偺忣宨丄攇巭応偺抂偵傐偮傫偲寶偮怘摪丄桱偄婄偱憢曈偵偨偨偢傓儀儗乕朮偲儗僀儞僐乕僩巔偺儌儖僈儞丄偳偙傑偱傕僊儍僶儞偵偮偄偰偔傞巕將側偳丄報徾揑側僔乕儞偼懡偄丅乽憗偔僉僗偟偰偔傟丄帪娫偑側偄乿偲尵偆僊儍僶儞偺巰偵嵺偺戜帉傕偒傑偭偰偄傞丅儈僔僃儖丒儌儖僈儞偼岲傒偺彈桪偱偼側偄偑丄摉帪17嵨偺斵彈偑旤偟偄偙偲偼妋偐偩丅
偐傝偦傔偺岾暉
1935丂儅儖僙儖丒儗儖價僄丂昡揰乵E乶
僔儍儖儖丒儃儚僀僄丄僊儍價乕丒儌儖儗乕庡墘丅攧傟側偄夋壠儃儚僀僄偼幮夛偵揋堄傪擱傗偟丄恖婥彈桪儌儖儗乕傪慱寕偡傞偑寉彎偵廔傞丅嵸敾偺夁掱偱2恖偼庝偐傟崌偆傛偆偵側傝丄儌儖儗乕偼婱懓偺晇傪捛偄弌偟丄曻柶偝傟偨儃儚僀僄傪帺戭偵寎偊擖傟偰堦弿偵曢傜偡偑丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕丅僾儘僢僩偑巟棧柵楐偱偳偆偟傛偆傕側偄丅儃儚僀僄偼擇枃栚傇傝偑條偵側偭偰偄傞偑丄儌儖儗乕偼偍偽偝傫晽偱枺椡偵寚偗傞丅
2020擭8寧朸擔 旛朰榐68丂償傿僗僐儞僥傿偺乽堎朚恖乿
1969丂儖僉僲丒償傿僗僐儞僥傿丂昡揰乵D乶
桳柤側僇儈儏偺晄忦棟彫愢偺塮夋壔丅庡恖岞偺儉儖僜乕傪儅儖僠僃儘丒儅僗僩儘儎儞僯偑墘偠傞丅偦偺楒恖栶偵傾儞僫丒僇儕乕僫丅傾儖僕僃儕傾偱惗妶偡傞暯杴側僒儔儕乕儅儞偑傾儔價傾恖傪嶦奞偟偰戇曔偝傟傞丅斵偼庢傝挷傋偰偦傟傑偱偺惗妶傪怳傝曉傞丅曣恊偺巰丄梴榁堾偱偺憭幃丄楒恖偲偺奀悈梺傗塮夋娪徿丄扨挷側枅擔丄柍姶摦側擔乆丄偦偟偰斵偼桭恖偺暿憫偱弌夛偭偨傾儔價傾恖傪丄懢梲偺嫮偄擔嵎偟偺側偐偱幩嶦偡傞丅巰孻偺愰崘丄嵟屻偼撈朳偱偺斵偺挿偄撈敀偱廔傢傞丅尨嶌傪拤幚偵塮憸壔偟偰偄傞傛偆偩偑丄偁傑傝柺敀偔側偄丅
2020擭7寧
2020擭7寧朸擔 旛朰榐67丂僕儍僢僋丒儀僢働儖屻婜偺柤昳2嶌
尰嬥偵庤傪弌偡側
1954丂僕儍僢僋丒儀僢働儖丂昡揰乵A乶
嵞尒丅埲慜尒偰偄傞偼偢偩偑丄僕儍儞丒僊儍僶儞偑榁儊僈僱傪偐偗偰庤巻傪尒傞僔乕儞埲奜偼傑偭偨偔妎偊偰偄側偐偭偨丅僕儍儞丒僊儍僶儞偑棤壱嬈偐傜懌傪愻偆慜偺嵟屻偺巇帠偲偟偰丄拠娫偲偲傕偵嬥夠傪嫮扗偟偨偑丄怴嫽僊儍儞僌偺堦枴偑偦傟傪抦傝丄桿夳偟偨僊儍僶儞偺拠娫傪恖幙偵偟偰偦偺嬥夠傪扗偍偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅嵟屻偼廵寕愴偲側傝丄怴嫽僊儍儞僌偨偪偼幩嶦偝傟傞偑丄擱偊傞幵偺側偐偵巆偝傟偨嬥夠偼寈嶡偵墴廂偝傟偰偟傑偆丅怴嫽僊儍儞僌偺儕乕僟乕偵儕僲丒償傽儞僠儏儔丄僊儍僶儞偺拠娫偺垽恖偵僕儍儞僰丒儌儘乕偑弌墘丄2恖偲傕庒乆偟偄丅弶榁偺僊儍儞僌傪墘偠傞僊儍僶儞偺懚嵼姶偼偝偡偑偵戝偟偨傕偺丅僥儞億偺偄偄棳傟丄娙寜側岅傝岥偱丄抝偨偪偺桭忣偲媊嫚偑昤偐傟傞丅
寠
1960丂僕儍僢僋丒儀僢働儖丂昡揰乵A乶
嵞尒丅偙傟傕戝妛惗偺偙傠偵尒偨偑丄嵶晹偼婰壇偐傜敳偗棊偪偰偄偨丅扙崠傪僥乕儅偵偟偨塮夋偼悢懡偄偑丄偙傟偼偦偺側偐偱傕嵟崅偺堦嶌偩傠偆丅儀僢働儖娔撀偺堚嶌偱丄廁恖5恖偑扙崠偺偨傔傂偨偡傜寠傪孈傞榖丅斵傜偼帟僽儔僔偵嬀偺攋曅傪偔偔傝偮偗偰擿偒寠偐傜娕庣偺摦偒傪僠僃僢僋偟丄嬥嬶偱寠孈傝偺偨傔偺摴嬶傪嶌傝丄帪娫傪寁傞偨傔偵彫時傪偔偡偹偰嵒帪寁傪嶌傝丄壓悈摴偵弌傞偨傔幏漍偵寠傪孈傝懕偗傞丅傗偭偲寠偑奐捠偟丄偄偞寛峴偲側偭偨偲偒丄塮夋偼堄奜側寢枛傪寎偊傞丅嵶晹偺昤幨偑恀偵敆偭偰偍傝丄僐儞僋儕乕僩傪曵偡偨傔嬥嬶偱僈儞僈儞扏偄偨傜丄偦偺壒偑娕庣偵暦偙偊側偄傢偗偼側偄偺偩偑丄慡曇偵墶堨偡傞嬞敆姶偑偦傫側嚓醨傪挔徚偟偵偡傞丅摨朳偺偺5恖偺廁恖偨偪偺惈奿偑岻傒偵昤偒暘偗傜傟偰偄傞揰傕徧巀偵抣偡傞丅搊応恖暔偼丄怴擖傝偺廁恖偵柺夛偵棃傞僈乕儖僼儗儞僪傪彍偒丄偡傋偰抝偩偗偩丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐66丂僕儍僢僋丒儀僢働儖弶婜偺杴嶌2杮
愒偄庤偺僌僢僺乕
1943丂僕儍僢僋丒儀僢働儖丂昡揰乵C乶
儀僢働儖偺娔撀戞2嶌丅僼儔儞僗偺曅揷幧偺懞傪晳戜偵偟偨嬥偲嶦恖偲楒垽偵傑偮傢傞榖偱丄僕儑儞丒僼僅乕僪偺乽僞僶僐丒儘乕僪乿傪渇渋偲偝偣傞丅揷幧偺婏柇側晽廗偲僷儕偐傜傗偭偰棃偨惵擭偺屗榝偄偑儐乕儌傾傪岎偊偰昤偐傟傞偑丄惢嶌堄恾偑傛偔暘偐傜側偄偟丄慡懱偵娫墑傃偟偰偍傝丄柺敀傒偵寚偗傞丅
岾暉偺愝寁
1947丂僕儍僢僋丒儀僢働儖丂昡揰乵D乶
僷儕偵廧傓昻朢曢傜偟偺庒偄晇晈偑偨傑偨傑攦偭偨曮偔偠偱戝摉偨傝偲側傞偑丄偦偺嶥傪側偔偟偰偟傑偄戝憶摦偵側傞偲偄偆懠垽側偄榖丅寢嬊丄晇偑嶥傪偟傑偭偨応強傪巚偄弌偟丄傔偱偨偟傔偱偨偟偲側傞丅僷儕偵曢傜偡弾柉偺巔偑僐儊僨傿晽偵昤偐傟偰偍傝丄僆乕丒僿儞儕乕偺抁曇彫愢傪巚傢偣側偄偱傕側偄丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐65丂儖僱丒僋儗儅儞偲傾儔儞丒僪儘儞偺僐儞價偵傛傞2嶌
惗偒傞娊傃
1961丂儖僱丒僋儗儅儞丂昡揰乵C乶
儖僱丒僋儗儅儞偑乽懢梲偑偄偭傁偄乿偵懕偒丄傾儔儞丒僪儘儞傪婲梡偟偰嶌偭偨僐儊僨傿塮夋丅巇帠偑側偔怘偆偵崲偭偨僪儘儞偼僼傽僔僗僩抍懱偺崟僔儍僣搣偵擖傝丄傾僫乕僉僗僩偺報嶞壆堦壠偵愽擖偡傞偑丄偦偺壠懓偵婥偵擖傜傟丄柡偲楒拠偵側傞丅斵偼傾僫乕僉僗僩堦攈偺杮晹偐傜憲傜傟偰偒偨埫嶦幰傪憰偆偑丄偦偙偵杮暔偺埫嶦幰偑尰傟偰敋抏僥儘傪巇妡偗傛偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅寉偄婌寑偱晽巋偺梫慺偼偁傑傝姶偠傜傟側偄丅僪儘儞偺2枃栚傇傝傕偝傞偙偲側偑傜丄傾僫乕僉僗僩堦壠偺柡傪墘偠傞僶儖僶儔丒儔僗偑偠偮偵壜垽偄傜偟偄丅
婋尟偑偄偭傁偄
1964丂儖僱丒僋儗儅儞丂昡揰乵B乶
嵞尒丅晻愗傝摉帪偵尒偰偍傝丄拞恎偼偗偭偙偆婰壇偵巆偭偰偄傞丅僋儗儅儞偑娔撀偟偨傾儔儞丒僪儘儞庡墘3晹嶌偺傂偲偮偱丄婏柇側枴傢偄傪忴偡忋弌棃偺僒僗儁儞僗塮夋丅撿暓偵傗偭偰棃偨梀傃恖偺僪儘儞偑丄僊儍儞僌偺儃僗偺忣晈偵庤傪晅偗偨偨傔偵憲傝崬傑傟偨嶦偟壆偐傜摝偘夞傝丄晉崑偺枹朣恖偲偦偺柮偑廧傓揁戭偵廧傒崬傫偱塣揮庤傪柋傔傞偙偲偵側傞丅偦偺壆晘偵偼塀傟晹壆偑偁傝丄偦偙偵枹朣恖偺晇傪嶦偟偨垽恖偑傂偦偐偵摻傢傟偰偄傞丅柮偼僪儘儞傪岲偒偵側傞偑僪儘儞偼斵彈傪憡庤偵偟側偄丅傗偑偰枹朣恖偲垽恖偲嶦偟壆偼廵偺憡寕偪偱巰偸偑丄僪儘儞偼柮偺嶔棯偱寈嶡偵嶦恖幰偲媈傢傟丄塀傟晹壆偱偺惗妶傪梋媀側偔偝傟傞丄偲偄偆旂擏側寢枛偱廔傞丅枹朣恖偵梔墣側儘乕儔丒僆儖僽儔僀僩丄柮偵庒偔弶乆偟偄僕僃乕儞丒僼僅儞僟偑暞偟偰偄傞丅僪儘儞偼慹栰偱惗堄婥偱傆偰傇偰偟偄庒幰偺栶偱丄斵偑杮幙揑偵帩偮僀儊乕僕偵儅僢僠偟偰偄傞丅梋択偩偑丄儘乕儔丒僆儖僽儔僀僩偼壧庤偱傕偁傝丄僕儍僘偭傐偄僥僀僗僩偱僗僞儞僟乕僪傪壧偭偨LP傪壗枃偐嶌偭偰偄傞丅僿儞儕乕丒儅儞僔乕僯偺尒帠側敽憈偱壧偭偨乽Dreamsville乿偼側偐側偐偺岲斦偩丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐64丂儖僀僗丒僽僯儏僄儖偺捒嶌偲柤嶌
偙偺掚偵巰偡
1956丂儖僀僗丒僽僯儏僄儖丂昡揰乵C乶
僔儌乕僰丒僔僯儑儗傪庡墘偵悩偊偨僽僯儏僄儖偺抦傜傟偞傞暓杗崌嶌塮夋丅慜敿偼撿暷偺揷幧挰偑晳戜丅彥晈僔僯儑儗乮傑偨傕傗彥晈偺栶偩乯偼丄椏棟恖偺榁恖僔儍儖儖丒償傽僱儖傗恄晝儈僔僃儖丒僺僢僐儕丄惓懱晄柧偺棳傟幰偲偲傕丄朶摦偑婲偒偨挰偐傜摝傟傞偨傔丄慏偵忔偭偰愳傪壓傞丅偦偙偐傜屻敿偺僒僶僀僶儖摝旔峴偵側傝丄斵傜偼捛偭庤傪摝傟傞偨傔搑拞偱慏傪崀傝偰枾椦傪椃偡傞偑丄怘椘偑恠偒丄晽塉偵偝傜偝傟偰愨朷姶偑偮偺傝丄恖娫偺杮惈偑婄傪偺偧偐偣傞ゥ苽X僩乕儕乕丅搊応恖暔偼慜敿偲屻敿偱惈奿偑偑傜傝偲曄傢傞丅椻崜側埆恖偩偭偨棳傟幰偼摝旔峴僌儖乕僾偺儕乕僟乕偲偟偰儊儞僶乕傪堷棪偡傞偟丄彥晈偼寁嶼崅偔棙屓揑偩偭偨偺偵丄棳傟幰傪垽偡傞廬弴側彈偵側傞偟丄惔楑寜敀偩偭偨恄晝偼僟僀傾儌儞僪偵栚偑峥傓偟丄壏岤偩偭偨椏棟恖偼婥偑嫸偭偰拠娫傪寕偮丅僽僯儏僄儖偼偙偺恖娫惈偺曄杄傪昤偒偨偐偭偨偺偩傠偆偐丅僔僯儑儗偼35嵨偩偑傑偩庒偔丄敡傕堷偒掲傑偭偰偄傞丅偲傕偁傟丄偙傟偼僽僯儏僄儖偵偟偰偼暘偐傝傗偡偄丄捈媴彑晧偺朻尟僒僶僀僶儖塮夋偩丅
奆嶦偟偺揤巊
1962丂儖僀僗丒僽僯儏僄儖丂昡揰乵C乶
偙傟偼戝妛惗偺偙傠抮戃偺暥寍嵗偐偳偙偐偱尒偨婰壇偑偁傞丅僽僯儏僄儖偑儊僉僔僐偱嶌偭偨丄斵偺彅嶌偺側偐偱傕傕偭偲傕榑媍傪屇傇丄崌棟揑夝庍傪嫅斲偡傞晄忦棟塮夋丅儖僲儚乕儖偺乽僎乕儉偺婯懃乿傪巚傢偣側偄偱傕側偄丅偁傞嬥帩偪偺壆晘偑晳戜丅椏棟恖傗彚巊偄側偳偺巊梡恖偑傂偲傝丄傆偨傝偲壆晘偐傜弌偰偄偒丄嵟屻偵幏帠偩偗偑巆傞丅戜強偵偼側偤偐梤偑悢旵偍傝丄孎傕曕偄偰偄傞丅壆晘偵廤偭偨20恖傎偳偺忋棳奒媺偺抝彈偑丄斢巂偺偁偲嫃娫偱姲偄偱偄傞偁偄偩偵丄偦偺晹壆偐傜奜偵弌傜傟側偔側傞丅斵傜偼偩傫偩傫僷僯僢僋偵娮傝丄抪傕奜暦傕側偔斀栚偟崌偄丄攍傝崌偆丅婹偊偲妷偒偵壵傑傟偨斵傜偼暻偺側偐偺悈摴娗傪夡偟偰悈傪堸傒丄柪偄崬傫偱偒偨梤傪怘傋偰婹偊傪桙傗偡丅壠偺奜偵偼寈姱傗尒暔恖偑偄傞偑丄斵傜傕壠拞偵擖偭偰偄偔偙偲偑偱偒側偄丅悢擔屻丄斵傜偼奜偵弌傜傟側偔側偭偨偲偒偺忬嫷傪偨偳傞偙偲偱丄傛偆傗偔弌傜傟傞傛偆偵側傞丅偦偺屻丄斵傜偑弌惾偡傞嫵夛偺儈僒偱丄摨偠傛偆偵弌惾幰偑奜偵弌傜傟傜偔側傞偲偙傠偱塮夋偼廔傞丅尰忬偐傜敳偗弌偟偨偄偺偵偱偒側偄偲偄偆嬽榖偼丄僽儖僕儑傾僕乕傊偺晽巋偺傛偆偱傕偁傞偟丄嫵夛傊偺斸敾偺傛偆偱傕偁傞偟丄幮夛偺暵嵡姶傪昞尰偟偰偄傞傛偆偱傕偁傞偟丄嫟摨尪憐偵庺敍偝傟傞恖乆傪昤偄偨傛偆偱傕偁傞偟丄恖娫堦斒傪殅徫偆僽儔僢僋儐乕儌傾偺傛偆偱傕偁傞丅恖乆傪夝曻偵摫偔彈惈儗僥傿僔傾偺僯僢僋僱乕儉偑儚儖僉儏乕儗偩偲偄偆偙偲丄寑拞偵斀暅偑昿弌偡傞偙偲傕堄枴怺偩丅摉榝偡傞娤媞傗斸昡壠傪慜偵崅徫偄偡傞僽僯儏僄儖偑栚偵尒偊傞傛偆偩丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐63丂僔儌乕僰丒僔僯儑儗偲僔儍儖儖丒傾僘僫僽乕儖
扱偒偺僥儗乕僘
1953丂儅儖僙儖丒僇儖僱丂昡揰乵B乶
僄儈乕儖丒僝儔偺彫愢傪東埬偟偨斊嵾塮夋丅庡墘偼僔儌乕僰丒僔僯儑儗偲儔僼丒償傽儘乕僱偱丄儘乕僰壨斎偺挰儕儓儞偑晳戜丅儅僓僐儞偺忣偗側偄晇偲懜戝側屍偵彈拞偺傛偆偵偙偒巊傢傟傞僔僯儑儗偼丄晇偺抦傝崌偄偺鐥偟偄僩儔僢僋塣揮庤償傽儘乕僱偵庝偐傟丄晄椣娭學偵娮傞丅擇恖偼摝朣偟傛偆偲偡傞偑晇偵歬偓偮偗傜傟丄償傽儘乕僱偼楍幵偺側偐偱岆偭偰晇傪撍偒棊偲偟丄嶦偟偰偟傑偆丅偦偺巰偼帠屘偲偟偰張棟偝傟傞偑丄楍幵偺側偐偱栚寕偟偰偄偨傗偔偞幰偵嫼敆偝傟丄岥巭傔椏傪暐偆偙偲偵偡傞偑ゥ苽X僩乕儕乕丅偙偙偱偺僔僯儑儗偼埆彈偱偼側偔丄塣柦偺巺偵憖傜傟偰僪僣儃偵偼傑傞垼傟側彈傪墘偠傞丅庒偄僔僯儑儗偼擏姶揑偩偑闳傝偺偁傞旤偟偝偲怤偟偑偨偄昳奿傪偨偨偊偰偄傞丅懅巕偺巰傪抦傜偝傟偰慡恎晄悘偵側傝岥偑偒偗側偔側偭偨屍偺僔僯儑儗傪偵傜傓嫲偄栚偑報徾偵巆傞丅岅傝岥偼暘偐傝傗偡偄偑丄傗傗忕枱偩丅
儔僀儞偺壖嫶
1960擭丂傾儞僪儗丒僇僀儎僢僩丂昡揰乵A乶
戞2師戝愴拞丄僪僀僣孯偺曔椄偵側偭偨2恖偺抝偺懳徠揑側惗偒曽傪昤偄偨塮夋丅僷儞壆偺柡柟偺嶀偊側偄僷儞怑恖僔儍儖儖丒傾僘僫僽乕儖偲僴儞僒儉側怴暦婰幰僕儑儖僕儏丒儕償傿僄乕儖偼丄墳彚偟偰僪僀僣孯偺曔椄偵側傝丄擾懞偱嫮惂楯摥偝偣傜傟傞丅儕償傿僄乕儖偼懞挿偺柡傪桿榝偟丄怷偱棁偵偟偰幵傪扗偄扙憱偡傞丅傾僘僫僽乕儖偼堦弿偵摝偘傛偆偲桿傢傟傞偑抐傝丄懞偵巆偭偰楯摥偵椼傓丅傗偑偰斵偼抝庤偑側偔側偭偨懞偱昁恵偺懚嵼偵側傝丄懞挿偺戙傢傝傑偱柋傔傞丅扙憱偟偨儕償傿僄乕儖偼儘儞僪儞偱斀撈怴暦傪敪峴偟丄儗僕僗僞儞僗偺摤巑偲偟偰妶桇偡傞丅廔愴偲側傝丄僷儕偵婣偭偨儕償傿僄乕儖偼怴暦幮偺幮挿偵悇偝傟丄僎僔儏僞億偺嫤椡幰偩偭偨偐偮偰偺楒恖偲傛傝傪栠偡丅傾僘僫僽乕儖傕僷儕偵婣傞偑丄嵢偵偙偒巊傢傟傞惗妶偑寵偵側傝丄儕償傿僄乕儖偺偮偰傪庁傝偰僪僀僣偺擾懞偵栠傠偆偲偡傞丅塮夋偼傾僘僫僽乕儖偑儔僀儞愳偺壖嫶傪搉偭偰僪僀僣偵岦偐偄丄儕償傿僄乕儖偑偦傟傪尒憲傞僔乕儞偱廔傞丅栚揑偺偨傔偵偼庤抜傪慖偽偸岟棙庡媊偺抝偲丄塣柦傪庴偗擖傟惗妶偺廩懌姶偲楯摥偵婌傃傪尒弌偡抝丄僇僀傾僢僩偼偳偪傜偐偵梌偡傞偙偲側偔丄懳摍側帇慄偱椉幰偺惗偒條傪昤偄偰偍傝丄惀旕偺敾抐偼娤媞偵埾偹偰偄傞丅儖僲儚乕儖偺乽戝偄側傞尪塭乿偲偼偁傞堄枴偱偒傢傔偰懳徠揑側塮夋偩丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐62丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺4
寛愴偺戝嬻傊
1943擭丂搉曈朚抝丂昡揰乵C乶
奀孯徣屻墖丄愴堄崅梘偲奀孯峲嬻戉堳挜曞偺偨傔偺PR傪寭偹偨崙嶔塮夋丅搚塝旘峴妛峑偱梊壢楙偲偟偰孭楙偵椼傓彮擭峲嬻暫偺惗妶丄嬩妝晹偺堦壠偲偺岎棳偑昤偐傟傞乮嬩妝晹偲偼彮擭暫偨偪偑媥擔偵朘傟偰姲偖応強傪採嫙偡傞堦斒壠掚偺偙偲乯丅搊応恖暔偼尒帠偵尰幚偲偼偐偗棧傟丄椶宆壔丄棟憐壔偝傟偰偍傝丄彮擭峲嬻暫偼傒側弮杙偱昳峴曽惓丄嫵姱偼尩偟偄偑恖忣偵撃偔丄嬩妝晹偺堦壠偼傗偝偟偔巚偄傗傝偵晉傫偱偄傞丅乽庒偄寣挭偺梊壢楙偺乣乿偲壧傢傟傞桳柤側乽庒榟偺壧乿乮惣忦敧廫嶌帉丒屆娭桾帶嶌嬋乯偼偙偺塮夋偵憓擖偝傟偰僸僢僩偟偨傜偟偄丅彮擭暫偨偪傪悽榖偡傞壠懓偺巓偵暞偡傞23嵨偺尨愡巕偼椺偊傛偆傕側偔旤偟偄丅尨愡巕偼偄傢備傞乬廵屻偺巓乭偱丄彮擭偨偪傪壏偐偔尒庣傝丄帪偵偼傗偝偟偔椼傑偟丄怱傪崬傔偰愴応偵憲傝弌偡丄彈恄偺傛偆側懚嵼丅彮擭偨偪偼尨愡巕偵庣傞傋偒擔杮崙偺徾挜傪尒偰丄斵彈偺柺塭傪嫻偵巰抧偵晪偔丅尨愡巕恄榖偺尨揰偼偙偺帪戙偺乬廵屻偺巓乭偲偄偆栶暱偵偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅揋偺孯娡偵懱摉偨傝偟偰愴巰偟偨峲嬻妛峑偺愭攜偑媊嫇偲徧偊傜傟丄尒廗偆傋偒僸乕儘乕偲偟偰宧傢傟傞偺偼丄摉帪偲偟偰偼摉偨傝慜偺偙偲偱偁傠偆偑丄娫傕側偔峴側傢傟傞摿峌戉峌寕傪梊挍偝偣丄嫻偑捝傓偟暜傝傪妎偊傞丅
搟傝偺奀
1944擭丂崱堜惓丂昡揰乵D乶
慜嶌偲摨偠偔奀孯徣屻墖丄孯娡偺晝偲徧偝傟偨暯夑忳偺揱婰塮夋丅暯夑忳偲偄偆恖暔偼抦傜側偐偭偨偑丄奀孯媄弍拞彨丄抝庉丄岺妛攷巑偱丄搶戝嫵応傪宱偰奀孯偱孯娡偺愝寁傪庡摫偟丄嵟屻偼搶戝憤挿傪柋傔偰偙偺塮夋岞奐偺慜擭偵杤偟偨執恖傜偟偄丅塮夋偱偼暯夑偺斢擭丄墷暷偲偺孯弅忦栺偵傛傞寶憿惂尷偺側偐丄寉検偱傕廳憰旛偑壜擻側孯娡偺愝寁偵埆愴嬯摤偡傞巔偑昤偐傟傞丅庡墘偼戝壨撪揱師榊丄椺偺偲偍傝戝壨撪偺戜帉偑暦偒庢傝偵偔偔丄壗傪挐偭偰偄傞偺偐棟夝晄擻丅尨愡巕偼偦偺柡偩偑弌斣偼彮偟偟偐側偄丅偪側傒偵丄偙偺擭丄尨愡巕偼偙偺塮夋1杮偵偟偐弌墘偟偰偄側偄丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐61丂僺傾丒傾儞僕僃儕偺弶庡墘嶌
柧擔偱偼抶偡偓傞
1950丂儗僆僯乕僪丒儌僊乕丂昡揰乵C (A)乶
埲慜丄YouTube偱楎埆側夋幙偱尒偨偑丄傛偆傗偔偒傟偄側夋幙丄帤枊晅偒偱丄偙偺僺傾丒傾儞僕僃儕偺弶庡墘嶌傪尒傞偙偲偑偱偒偨丅偙偙偱偼斵彈偼杮柤偺傾僫丒儅儕傾丒僺僄儔儞僕僃儕偲偄偆柤慜偱僋儗僕僢僩偝傟偰偄傞丅嶣塭摉帪丄僺傾偼17嵨丄傑偩梒偝偺巆傞惔弮側昞忣偼壗偲傕尵偊偢垽傜偟偄丅拠娫偺彈惗搆偨偪偺側偐偱斵彈偺旤偟偝偼旘傃敳偗偰偄傞丅巚弔婜偺彮擭彮彈偺惈傊偺摬傟偲擸傒丄戝恖偺柍棟夝傪昤偒丄惈嫵堢偺昁梫惈傪慽偊傞丄堦庬偺妛墍傕偺僀僞儕傾塮夋偱丄撪梕偼C偩偑丄僺傾偺旤偟偝偵A傪晅偗傞丅僺傾偼偙偺偁偲僀僞儕傾偱摨庯岦偺塮夋偵傕偆1杮弌墘偟偨偁偲僴儕僂僢僪偵彽偐傟丄僼儗僢僪丒僕儞僱儅儞偺乽僥儗僒乿偱庡墘傪柋傔傞丅
彈屜
1950丂儅僀働儖丒僷僂僄儖仌僄儊儕僢僋丒僾儗僗僶乕僈乕丂昡揰乵B乶
彜嬈庡媊偲偼堦慄傪夋偡椙幙偺僪儔儅傪嶌偭偨僀僊儕僗偺娔撀僠乕儉丄僷僂僄儖仌僾儗僗僶乕僈乕偵傛傞堦嶌丅傾儗僋僒儞僟乕丒僐儖僟偲僨僀償傿僢僪丒僙儖僘僯僢僋偲偄偆塸暷偺柤惂嶌幰偑僐儞價傪慻傒丄僙儖僘僯僢僋偺嵢僕僃僯僼傽乕丒僕儑乕儞僘傪庡墘偲偟偰嶌傜傟偨塮夋丅帪戙偼偍偦傜偔19悽婭枛丄僀僊儕僗偺曅揷幧偺懞偑晳戜丅僕僾僔乕偺寣傪堷偔栰惈偲杺惈偺柡僕僃僯僼傽乕丒僕儑乕儞僘偼丄杙鎐側杚巘偵媮崶偝傟偰寢崶偟側偑傜丄偄偭傐偆偱懜戝側抧庡偵庝偐傟偰娭學傪傕偪丄偦偺怓楒偑懞偵攇栦傪偐偒棫偰傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅尨戣偺乽Gone to Earth乿偑寢枛偺斶寑傪埫帵偟偰偄傞丅朚戣偺乽彈屜乿偼僕儑乕儞僘倞偑僉僣僱傪壜垽偑偭偰偄傞偙偲偐傜晅偗傜傟偨偺偩傠偆丅榖偺棳傟偼僕儑乕儞僘偑庡墘偟偨乽敀拫偺寛摤乿傪巚傢偣丄嶳傗怷椦側偳帺慠偺晽宨偑塮偟弌偝傟傞偙偲偲憡傑偭偰丄恄榖揑側僀儊乕僕傪忴偟弌偟偰偄傞丅僥僋僯僇儔乕偱嶣塭偝傟偨僸乕僗偺媢偑旤偟偄丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐60丂乬搟傟傞庒幰偨偪乭偺塮夋
擭忋偺彈
1959丂僕儍僢僋丒僋儗僀僩儞丂昡揰乵B乶
50擭戙屻敿偺僀僊儕僗傪惾姫偟偨奒媺幮夛偵斀媡偡傞偡傞乬搟傟傞庒幰偨偪乭塣摦偵楢側傞塮夋丅撪梕偼儌儞僑儊儕乕丒僋儕僼僩庡墘偺乽梲偺偁偨傞応強乿傪巚傢偣傞丅儘乕儗儞僗丒僴乕償僃僀丄僔儌乕僰丒僔僯儑儗庡墘丅揷幧偐傜抧曽搒巗偵弌偰偒偰巗栶強偵嬑傔巒傔偨栰怱偵擱偊傞僴乕償僃僀偼慺恖墘寑僌儖乕僾偵擖傝丄挰傪媿帹傞幚嬈壠偺柡傪尒弶傔丄斵彈傪岥愢偒棊偲偟偰忋媺奒媺偺堦堳偵側傠偆偲偡傞偑丄偄偭傐偆偱摨偠僌儖乕僾偵偄偨僼儔儞僗彈偺恖嵢僔僯儑儗偲抦傝崌偄丄憡巚憡垽偺晄椣娭學偵娮傞丅斵偼杮摉偵僔僯儑儗傪垽偡傞傛偆偵側傝丄巚偄擸傓偑丄寢嬊僔僯儑儗傪幪偰丄擠怭偟偨儃僗偺柡偲偲寢崶偡傞丅僔僯儑儗偼幐堄偺偆偪怺庰偟丄幵偱帠屘巰偡傞ゥ苽爞鐐穫秮B僔僯儑儗偼摉帪38嵨丄惙傝偼夁偓偨偑傑偩怓崄傪昚傢偣偰偍傝丄墘媄傕愨昳偱丄枴婥側偄惗妶偺側偐偱弰傝夛偭偨擭壓偺楒恖偲廳偹傞埀悾偺婌傃偲垼偟傒傪尒帠偵昞尰偟偰偄傞丅
搚梛偺栭偲擔梛偺挬
1960丂僇儗儖丒儔僀僗丂昡揰乵C乶
偙傟傕乬搟傟傞庒幰偨偪乭塣摦偵楢側傞僀僊儕僗塮夋偱丄尨嶌偼傾儔儞丒僔儕僩乕丅楯摥幰奒媺偐傜偺扙媝傪柌尒傞偑姁傢偢丄烼孅偟偨婥帩偪傪書偊側偑傜擔乆傪憲傞庒幰偺巔傪昤偔丅愝掕偼乽擭忋偺彈乿偲偪傚偭偲帡偰偍傝丄慁斦岺偺傾儖僶乕僩丒僼傿僯乕偑摨椈偺嵢偲晄椣偟偮偮丄摨偠奒媺偺柡僔儍乕儕乕丒傾儞丒僼傿乕儖僪偲恊偟偔側傞丅掆懾偟偨塸崙奒媺幮夛偵懳偡傞壵棫偪偑慡曇偵偔偡傇偭偰偄傞丅岲墘偟偰偄傞僼傿僯乕偼偙偺2擭屻丄乽僩儉丒僕儑乕儞僘偺壺楉側朻尟乿偱僽儗僀僋偡傞丅僕儍僘丒傾儖僩憈幰僕儑儞丒僟儞僋儚乕僗偺庡戣嬋偼擔杮偱彫僸僢僩偵側偭偨丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐59丂40擭戙偺2杮偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖
3奒偺尒抦傜偸抝
1940丂儃儕僗丒僀儞僌僗僞乕丂昡揰乵C乶
弶尒偩偲巚偭偨偑丄埲慜尒偨婰壇偑偁傞丅僼傿儖儉丒僲儚乕儖偼1941擭偺乽儅儖僞偺戦乿偵巒傑傞偲偄偆偺偑掕愢偩偑丄偦傟埲慜偵傕偙偺塮夋偺傛偆偵僲儚乕儖怓偑擹偄嶌昳偑嶌傜傟偰偄偨偺偩丅B媺偩偑丄僯儏乕儓乕僋偺栭偺曕摴偺僔乕儞傗丄庡恖岞偺怴暦婰幰偑尒傞埆柌偺昞尰庡媊揑側塮憸偼側偐側偐偺傕偺丅嫸婥偺堎忢幰傪墘偠傞僺乕僞乕丒儘乕儗偼柺栚桇擛丅庡恖岞偺楒恖栶偺儅乕僈儗僢僩丒僞儕僠僃僢僩偼柍柤偺彈桪偩偑岲姶偑帩偰傞丅斊恖偵娫堘偊傜傟傞抝偵僀儔僀僔儍丒僋僢僋偑暞偟偰偄傞丅
扙崠偺潀
1948丂傾儞僜僯乕丒儅儞丂昡揰乵B乶
傾儞僜僯乕丒儅儞弶婜偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅嶣塭偼柤庤僕儑儞丒傾儖僩儞丅斊嵾慻怐偺堦堳僨僯僗丒僆僉乕僼偼帺暘偑嵾傪偐傇偭偰擖崠偟偰偄偨偑丄忣晈僋儗傾丒僩儗償傽乕偺庤堷偒偱扙崠丄愙尒偟偰偄偨曎岇巑旈彂儅乕僔儍丒僴儞僩偺傾僷乕僩偵塀傟傞偑丄寈嶡偵歬偓偮偗傜傟丄2恖偺彈偲偲傕偵丄慻怐偐傜嵎偟岦偗傜傟偨嶦偟壆傪寕戅偟側偑傜丄撿暷偵枾峲偡傞偨傔幵偱SF偵岦偐偆丅斵偼椃偺搑拞偱僴儞僩偲怱傪捠傢偣崌偆偑丄偦偺憐偄傪怳傝幪偰偰斵彈傪幵偐傜崀傠偟丄暅廞偟側偄偱偔傟偲偄偆僩儗償傽乕偺婅偄傪暦偒擖傟丄慏偵忔偭偰弌峘傪懸偮丅偩偑僴儞僩偑慻怐偵漟抳偝傟偨偲抦傝丄斵彈傪彆偗傞偨傔慏傪壓傝偰慻怐偺崻忛偵岦偐偆ゥ苽X僩乕儕乕丅暔岅偼僩儗償傽乕偺僫儗乕僔儑儞傪嫴傒側偑傜偼娙寜偵僥儞億椙偔恑傓丅慻怐偺儃僗偺巆崜側強嬈偵儅儞偺庯枴偑奯娫尒偊傞丅僕儑儞丒傾儖僩儞偺僇儊儔偼偝偡偑偵慺惏傜偟偔丅柖偵墝傞攇巭応傗奨偺忣宨偵怱傪扗傢傟傞丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐58丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺3
巜摫暔岅
1941丂孎扟媣屨丂昡揰乵D乶
揝摴徣丒棨孯徣屻墖丄崙悎庡媊偵孹幬偟偰偄偨孎扟傜偟偄斸昡惈偑奆柍偺帪嬊寎崌愴堄崅梘塮夋丅偙偺塮夋偑岞奐偝傟偰2儠寧屻偵擔杮偼恀庫榩傪峌寕偡傞丅愴抧偵婡娭暫偲偟偰晪偔庒幰偲斵傪嫵堢偡傞揝摴堳偺暔岅丅掕擭娫嬤偺榁婡娭庤偵娵嶳掕晇丄杙鎐側惵擭暫偵摗揷恑丄尨愡巕偼娵嶳偺憦柧側柡傪墘偠丄壠寁傪愗傝惙傝偟丄暫巑傪傗偝偟偔憲傝弌偡丅忲婥婡娭幵偑閩恑偡傞僔乕儞偑傆傫偩傫偵憓擖偝傟傞偐傜揝摴僼傽儞偑偙傟傪尒偨傜婌傇偩傠偆丅尨愡巕偼21嵨偩偑丄棊偪拝偄偨晽忣偱戝恖偭傐偄姶偠傪忴偟偰偄傞丅摗揷恑偼庒乆偟偄丅摗揷偼偙偺2擭屻偵乽巔嶰巐榊乿偵弌墘偟偰昡敾偵側傞丅尨偲摗揷偺僐儞價偵傛傞塮夋偼梻擭偺乽椢偺戝抧乿傗愴屻偺乽変偑惵弔偵夨偄側偟乿傪偼偠傔壗杮偐偁傞偑丄偙傟偑弶婄崌傢偣偱偼側偄偩傜偆偐丅
朷極偺寛巰戉
1943丂崱堜惓丂昡揰乵C乶
挬慛杒晹偱帯埨堐帩偵偁偨傞擔杮偺崙嫬寈嶡戉偺擔忢擟柋偲夁崜側愴摤傪昤偄偨堦庬偺傾僋僔儑儞塮夋丅椻惷捑拝偩偑恖忣枴偺偁傞戉挿偵崅揷柅丄偦偺尗嵢偵尨愡巕偲偄偆晍恮丅婯棩傪廳傫偠丄忣偵撃偄寈嶡戉堳丄廬弴偱慺杙側尰抧偺擾柉丄栰斬偱旕摴側斮懐乮峈擔晲憰僎儕儔乯偲偄偆恾幃揑側峔恾丅尰抧偱儘働偟偨偲巚傢傟傞偑丄壐傗偐側弔偲尩姦偺搤偺忣宨偑塮偟弌偝傟傞丅崙嶔塮夋偺傂偲偮偩偑丄撪梕揑偵偼惣晹寑偵嬤偄丅廔斦偺丄寈嶡偺挀嵼強偑斮懐偵廝傢傟丄偁傢傗栴嬍恠偒偰摙偪巰偵偐偲偄偆偲偙傠偵墖孯偑尰傟傞偲偄偆棳傟偼丄婻暫戉偺嵲偑僀儞僨傿傾儞偵廝傢傟偰婋側偄偲偙傠偵彆偗偺暫戉偑嬱偗偮偗傞偲偄偆惣晹寑偺僷僞乕儞偲摨偠偩丅幚嵺偺偲偙傠丄偙傟偼僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺傾儊儕僇塮夋乽儃乕丒僕儏僗僩乿偺東埬偩偲偄偆丅23嵨偺尨愡巕偺怱桪偟偄婤慠偲偟偨庒嵢傇傝偼旤偟偄偆偊偵怓婥傪姶偠偝偣傞丅偙偺塮夋偱偼尨愡巕偑廵傪庤偵偟偰揋偲愴偆偲偄偆暥復傪撉傫偩偙偲偑偁傞偑丄尒偨尷傝偱偼丄婡娭廵傪朷極偵塣傫偩傝丄晇偐傜帺寛偺偨傔偺対廵傪搉偝傟偨傝偼偡傞偑丄廵傪寕偮僔乕儞偼側偐偭偨丅偟偐偟斵彈偑晇偺墶偱廵傪峔偊偰偄傞僗僠乕儖幨恀偑偁傞丅妋擣偺偨傔丄傕偆堦搙尒側偔偰偼側傜側偄丅偙偺塮夋偺崱堜惓傗嶳杮嶧晇側偳丄愴屻偼嵍梼傪巙岦偟偨娔撀偼丄愴帪拞偵偼偙偺傛偆側崙嶔塮夋傪嶌偭偰偄偨偲偄偆帠幚偼婰壇偵棷傔偰偍偔傋偒偱偁傠偆丅偙偺塮夋偵偮偄偰偼丄崱堜惓娔撀偺嫽枴怺偄徹尵偑偁傞丅亙廻偵拝偄偨斢丄尨愡巕偑傗偭偰偒偰丄崱堜偝傫丄偙傟孼乮孎扟娔撀乯偐傜偱偡偭偰晻摏傪嵎偟弌偡傫偱偡丅偦偺庤巻偵偼丄擔杮偼慡惃椡傪嫇偘偰撿曽彅崙偵椞搚傪妋曐偟側偗傟偽側傜側偄丅偦偺帪偵擔杮崙柉偺栚傪杒曽偵偦傜偦偆偲栚榑傫偱偄傞偺偼丄儐僟儎恖偺堿杁偩丄偙偺乽朷極偺寛巰戉乿偼擔杮崙柉傪奾棎偟傛偆偲偡傞儐僟儎偺堿杁偩偐傜丄懄崗拞巭偝傟偨偄偲偄偆傛偆側偙偲偑彂偄偰偁偭偨丅偦偺塭嬁偱尨愡巕傑偱儐僟儎恖杁棯愢傪偲側偊傞偁傝偝傑偩偭偨亜
2020擭7寧朸擔 旛朰榐57丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺2
曣偺嬋
1937丂嶳杮嶧晇丂昡揰乵C (A)乶
戝廜岦偗偺曣傕偺儊儘僪儔儅偩偑丄尨愡巕偺婸偐偟偄旤彮彈傇傝偑嵺棫偮堦嶌丅尨愡巕偼摉帪17嵨丄僨價儏乕2擭栚偱丄擔撈崌嶌偺乽怴偟偒搚乿偵庡墘偟偨梻擭偵嶣傜傟偨嶌昳丅尨愡巕偼壀忳巌丄塸昐崌巕偺晇晈偺傂偲傝柡偱僺傾僲傪廗偆彈妛惗偲偄偆愝掕丅堦壠偼忋棳壠掚偱丄曣偲柡偼戝偺拠椙偟偩偑丄曣偺塸偼柍嫵梴偱堷偗栚傪姶偠偰偍傝丄尨偺摨媺惗偺曣恊偨偪偐傜徫偄傕偺偵偝傟偰偄傞丅偦傟偑崅偠偰丄尨帺恎傕摨媺惗偐傜堄抧埆偝傟丄塸偼柡偺岾偣偺偨傔偵壠傪弌偰愄偺抦傝崌偄偺抝偲摨嫃偡傞丅晝偺壀偼偐偮偰栿偁傝偩偭偨怱桪偟偄僺傾僯僗僩擖峕偨偐巕偲嵞崶偡傞丅寧擔偑宱偪丄尨偺寢崶幃偺擔丄塸偼塉偺側偐丄寶暔偺堿偐傜壴壟巔偺尨傪椳側偑傜偵尒偮傔傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅側傫偲偄偭偰傕丄恄乆偟偄傑偱偵旤偟偄尨愡巕偺僙乕儔乕暈巔偵姶摦偡傞丅塸昐崌巕偼愴慜塮夋偺曣栶偱傛偔尒偐偗傞偑丄垼傟偝傪墴偟攧傝偡傞傛偆側晽杄偑旲偵偮偔丅偙偺偙傠恖婥愨捀偩偭偨擖峕偲尨偺嫟墘偼丄偍偦傜偔偙傟偑弶傔偰偱偁傠偆丅塸偺媽抦偺婥偺偄偄抝傪墘偠傞嶰搰夒晇偼傑偩庒偄偑丄摢偺栄偑丄屻擭偼傆偝傆偝偟偰偄傞偺偵丄偙偙偱偼側偤偐恀傫拞偑僴僎偰偄傞丅嶰搰偼乽斢弔乿偱尨偐傜乽偍偠偝傑丄晄寜傛乿偲尵傢傟傞偑丄偙偺屆偄塮夋偱傕丄尨偼壠偵棃朘偟偨壜垼憐側嶰搰偵乽弌偰偄偭偰乿偲尵偆丅曣偲柡偑庴偗傞偄偠傔偺條巕偼偐側傝幏漍偵昤偐傟傞丅恎暘堘偄偵傛傞斶寑偼丄屆崱搶惣丄愄偐傜偁偭偨幣嫃傗塮夋偺峔恾偺傂偲偮偩丅偙偺塮夋偼傾儊儕僇偺彫愢偱壗搙傕塮夋壔偝傟偨乽僗僥儔丒僟儔僗乿偺東埬偩偲偄偆丅塮夋偺側偐偱尨愡巕偑墘憈偡傞嬋偼儊儞僨儖僗僝乕儞偺乽儀僯僗偺廙壧乿偲偺偙偲丅
揷墍岎嬁妝
1938丂嶳杮嶧晇丂昡揰乵D乶
屒帣偱偁傞栍栚偺彮彈偲丄斵彈傪堷偒庢偭偰悽榖傪偟惉挿傪尒庣傞嫵巘偲偺垽傪昤偄偨塮夋偩偑丄巟棧柵楐丄拞搑敿抂側嶌昳丅僕僢僪偺摨柤彫愢偺東埬偩偲偄偆丅戣柤偳偍傝丄儀乕僩乕償僃儞偺6斣偑慡曇偵棳傟傞丅尩姦偺杒奀摴丄僋儕僗僠儍儞偺崅寜側嫵巘崅揷柅偼愥廻傝偺壠偱弌夛偭偨栍栚偺彮彈尨愡巕傪垼傟傒丄壠偵楢傟偰婣偭偰堢偰傞丅嵟弶偼廱偺傛偆偩偭偨彮彈偼丄偟偩偄偵尵梩傪妎偊丄暘暿偑偮偄偰丄旤偟偄柡偵惉挿偡傞丅嫵巘偼柡傪偙偺傑傑庤尦偵偍偄偰偍偒丄帺慠偺側偐偱惗偒偝偣偨偄偲巚偆偑丄搶嫗偐傜朘傟偨掜偼丄庤弍偱栚偑尒偊傞傛偆偵偝偣丄幮夛偵弌偰惗妶偝偣傞傋偒偩偲尵偆丄嫵巘偼峫偊傪曄偊丄柡傪搶嫗偵楢傟偰峴偒丄庤弍傪庴偗偝偣傞丅庤弍偼惉岟偟偰斵彈偼栚偑尒偊傞傛偆偵側傞偑丄嫵巘偵夛偆偨傔昦堾傪敳偗弌偟偰杒奀摴偵婣傝丄悂愥偺拞傪偝傑傛偭偰搢傟傞丅偦傟傪尒偮偗偨嫵巘偼斵彈傪偦偽偺嫵夛偵塣傃崬傓丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅彮彈偑廱偐傜恖娫偵側傞夁掱偼僿儗儞丒働儔乕傪昤偄偨乽婏愓偺恖乿傪巚傢偣傞偑丄偙偺塮夋偱偼偁偭偲偄偆娫偵尵梩傪妎偊丄晛捠偺挐傝曽偑偱偒傞傛偆偵側傞偺偑晄帺慠丅栚偑奐偄偨斵彈偑丄嬥傕帩偭偰偄側偄偟丄塃傕嵍傕暘偐傜側偄偺偵丄偳偆傗偭偰堦恖偱搶嫗偐傜杒奀摴偵峴偭偨偺偐偑晄壜夝丅廔斦丄悂愥偺側偐傪偝傑傛偆條偼乽怴偟偒搚乿偱壩岥傪偝傑傛偆尨愡巕傪傎偆傆偮偲偝偣傞偑丄搢傟偰愥偵杽傕傟偰偟傑偆偺偵惗偒偰偄傞偺傕擺摼偱偒側偄偟丄僄儞僨傿儞僌傕栿偑暘偐傜側偄丅18嵥偺尨愡巕偼旤偟偄偑丄塮夋偺揥奐偼偁傑傝偵傕偍慹枛偩丅
2020擭7寧朸擔 旛朰榐56丂尨愡巕偑弌墘偟偨愴慜塮夋傪尒傞丂偦偺1
椢偺戝抧
1942丂搰捗曐師榊丂昡揰乵C乶
懢暯梞愴憟拞偺崙嶔塮夋丅摉帪22嵨偺尨愡巕偺旤偟偝偑嵺棫偭偰偄傞丅晳戜偼拞崙偺惵搰丅搚栘媄巘偺晇丄摗揷恑偑摥偔惵搰偵丄嵢偺尨愡巕偑愒傫朧傪楢傟偰慏偱晪偔丅斵彈偼慏拞偱擔杮岅妛峑偺嫵巘偲偟偰晪擟偡傞擖峕偨偐巕偲抦傝崌偆丅偙偺3恖偑庡梫搊応恖暔偩偑丄扤偑庡栶偐偼偼偭偒傝偟側偄丅摗揷恑偼抧尦擾柉偺斀懳偵憳偄側偑傜塣壨寶愝傪恑傔傞丅尨愡巕偼擖峕偨偐巕偑晇偺弶楒偺憡庤偩偭偨偙偲傪抦偭偰幑搃偟丄巚偄擸傓丅嵟屻偼懳棫偟偰偄偨拞崙擾柉偑擔杮恖偺慞堄傪抦傝丄嫤椡偡傞偙偲偵側傝丄慡堳偺岆夝偑夝偗偰塣壨寶愝偵娋傪棳偡丄偲偄偆偁傝偒偨傝偺寢枛偱廔傞丅尨愡巕偲偲傕偵丄擖峕偨偐巕偺偨偍傗偐偱忋昳側梕巔傕報徾怺偄丅傎偐偵丄愮梩憗湪巕丄庒偄抮晹椙偑尰抧拞崙恖偵暞偟偰弌偰偄傞丅
2020擭6寧
2020擭6寧朸擔 旛朰榐55丂愴屻偺僨儏償傿償傿僄偺斊嵾僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺2
嶦堄偺弖娫
1956丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰乵C+乶
埆彈傕偺偺斊嵾僪儔儅丅恖婥儗僗僩儔儞偺僆乕僫乕丒僔僃僼偱偁傞弶榁偺抝僕儍儞丒僊儍僶儞偺傕偲傊暿傟偨嵢偺柡偑朘偹偰偔傞丅柡偺楒忣偵傎偩偝傟偰僊儍僶儞偼斵彈偲寢崶偡傞偑丄斵彈偺栚摉偰偼僊儍僶儞偺嵿嶻偱偁傝丄傗偑偰斵彈偼僊儍僶儞傪嶦偟偰堚嶻傪傕偺偵偟傛偆偲偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅杺惈偺柡栶偼僟僯僄儖丒僩儘儗儉丅恀柺栚偦偆側姶偠偺偒傟偄側柡偱丄尵摦偑夦偟偄偲巚偭偰尒偰偄傞偲丄偟偩偄偵杮惈傪昞傢偡丅庒偄柡偵偨傇傜偐偝傟丄東楳偝傟傞僊儍僶儞偺偁傢傟側巔偑偠偭偔傝昤偐傟傞丅儗僗僩儔儞偺岦偐偄懁偺嶨摜偡傞巗応偺晽宨偑嫽枴怺偄丅屻敿丄椻崜側僊儍僶儞偺曣恊偑搊応偡傞偲丄堿嶴側応柺偑懡偔側傞丅偙偺曣恊偺旕恖忣傇傝偼柡偺堎忢側埆峴偲堦懳傪側偟偰偄傞丅杺惈偺柡偲偄偆揰偱丄僾儗儈儞僕儍乕偺乽揤巊偺婄乿偱墘偠偨壜垽偄僕乕儞丒僔儌儞僘偺嫢埆偝傪憐婲偝偣傞丅
帺嶦傊偺宊栺彂
1959丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰乵B乶
僒僗儁儞僗偵晉傫偩枾幒恖柉嵸敾僪儔儅丅僇儊儔偼尦儗僕僗僞儞僗偺拠娫偑奐偔摨憢夛偺夛応偱偁傞壆晘偺側偐偺峀娫偐傜傑偭偨偔奜偵弌側偄丅弌墘幰偼偦偙偵廤傑傞10恖偩偗偱丄拞擭偵側偭偰傕忋昳側怓崄傪曻偮僟僯僄儖丒僟儕儏乕傪偼偠傔丄億乕儖丒儉乕儕僗丄儀儖僫乕儖丒僽儕僄丄儕僲丒償傽儞僠儏儔丄僙儖僕儏丒儗僕傾僯側偳丄嬋幰栶幰偽偐傝丅斵傜偼15擭慜偺戝愴拞丄偙偺拠娫偱夛崌偟偰偄傞偲偒僎僔儏僞億偵媫廝偝傟丄儕乕僟乕偑柦傪棊偲偟偨丅僟儕儏乕偲儉乕儕僗偼丄偦傟偑棤愗傝幰偑枾崘偟偨偨傔偩偭偨偙偲傪抦傝丄偦偺抝傪偁傇傝弌偡偨傔偙偺廤傑傝傪婇夋偟偨丅僗僩乕儕乕偼2揮丄3揮偟丄嵟屻傑偱恀憡偑暘偐傜側偄丅棤愗傝幰偑敾柧偟偰傕丄側偍僔儑僢僉儞僌側寢枛偑梡堄偝傟偰偄傞丅媟杮偑傛偔弌棃偰偍傝丄偙偺2擭慜偵嶌傜傟偨乽12恖偺搟傟傞抝乿偵怗敪偝傟偨塮夋偐傕偟傟側偄丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐54丂愴屻偺僨儏償傿償傿僄偺斊嵾僒僗儁儞僗塮夋丂偦偺1
僷儕偺嬻偺壓僙乕僰偼棳傟傞
1951丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰乵C乶
偁傞擔偺僷儕偺堦擔丄奨偱曢傜偡偝傑偞傑側恖乆偺僄僺僜乕僪傪捲偭偨孮憸寑丅僷儕偵傗偭偰棃偨庒偄彈惈僽儕僕僢僩丒僆儀乕儖偺昤幨偐傜僗僞乕僩偟丄斵彈偺桭恖偱偁傞儌僨儖偺彈丄偦偺楒恖偺堛巘帋尡偵椪傓堛妛惗丄僗僩偵嶲壛偡傞岺堳丄擫岲偒偺榁攌丄嶦恖婼偺挙崗壠丄妛峑婣傝偵摴憪傪偡傞彮彈側偳偑揰昤偝傟傞丅岅傝岥偼偝偡偑偵岻偄丅廔斦丄僆儁乕儖偑嶦恖婼偺媇惖偵側傞偺偑僨儏償傿償傿僄揑偐丅桳柤側庡戣壧偼僗僩拞偺岺堳偑栧奜偵敳偗弌偟偰壠懓偲奐偔嬧崶幃僷乕僥傿偱壧傢傟傞丅
杽傕傟偨惵弔
1954丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰乵D乶
埫偄擖傝慻傫偩楒垽斊嵾塮夋丅惓媊娍偺崅峑惗偑丄10悢擭慜偵晝恊偑専帠傪柋傔偨嶦恖帠審偺嵸敾偱廔恎孻偵側偭偨抝偑檒嵾偱偼側偄偐偲媈偄丄帠審偺恀憡傪捛偆丅偦偺嵸敾偱偼丄忬嫷徹嫆偩偗偱嵢偲偦偺枀偲嶰妏娭學偵偁偭偨抝偑嵢傪嶦偟偨偲敾掕偝傟偨偑丄幚嵺偼枀偑斊偟偨嶦恖偩偭偨偲暘偐傞丅偟偐偟丄嶦恖偵帄傞枀偺怱棟忬懺偑傛偔暘偐傜側偄偟丄懠偺搊応恖暔偨偪偺峴摦傕擺摼偱偒側偄偟丄夁嫀偺帠審偵擖傟崬傓専帠偺懅巕偺摦婡傕晄柧妋偱丄慡懱偵偡偭偒傝偟側偄丅嶰妏娭學偺枀栶偺僄儗僆僲儔丒儘僢僔亖僪儔僑偺堎條側旤偟偝偑嵺棫偭偰偄傞丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂摼傞傕偺偑傎偲傫偳側偐偭偨2嶜偺塮夋杮
僗僞乕彈桪偺暥壔幮夛妛
2017丂杒懞嫥暯丂昡揰乵D乶
暃戣偵乽愴屻擔杮偑梸朷偟偨惞彈偲杺彈乿偲偁傞傛偆偵丄尨愡巕偲嫗儅僠巕傪拞怱偲偟偰愴屻擔杮偺僗僞乕彈桪偺曄慗傪偨偳偭偨杮丅慡懱揑偵惗峝偱偁傝丄幮夛妛傗揘妛偺棟榑傗妛愢偑墖梡偝傟妛弍榑暥偺傛偆側憰偄傪掓偟偰偄傞丅乽変偑惵弔偵夨偄側偟乿偱尨愡巕偑愴屻柉庡庡媊傪徾挜偡傞彈桪偵側偭偨丄偲偄偆愢偼暘偐傞偑丄榖偼偦偙偱巭傑偭偰偍傝丄偦偺愭偺斵彈偺曕傒傪曔懆偟偰偄側偄丅宖嵹偝傟偰偄傞愴屻10悢擭傎偳偺塮夋嶨帍偺恖婥搳昜儕僗僩偼嫽枴怺偄偑丅
僼儕僢僣丒儔儞僌傑偨偼攲椦亖惞椦
2004丂柧愇惌婭丂昡揰乵E乶
傂偳偄撪梕偩丅偙偙傑偱拞恎偺朢偟偄杮傕捒偟偄丅僼儕僢僣丒儔儞僌偺昡揱偲偺偙偲偩偑丄偦偺懱傪側偟偰偄側偄丅儔儞僌偺巚峫傗峴摦偵偮偄偰偺婰弎偼傎偲傫偳側偔丄戝晹暘偑嶌昳偺偁傜偡偠偺徯夘偲庤慜彑庤側姶憐偵妱偐傟偰偄傞偩偗丅暥懱傕寉敄偱丄柺敀偔傕側偄懯煭棊傪怐傝崬傒丄杮恖偩偗偑墄偵擖偭偰偄傞丅偁偲偑偒偵傛傞偲丄挊幰偼儔儞僌偑岲偒偱偼側偄偲偄偆丅偦傫側恖娫偵愢摼椡偺偁傞榑峫偑彂偗傞傢偗偑側偄丅儔儞僌偺杮偲偄偊偽丄偙偺懯嶌埲奜偵丄僀儞僞償儏乕廤乽塮夋娔撀偵挊嶌尃偼側偄乿偟偐側偔丄懠偺戝娔撀偵斾傋偰嬌抂偵彮側偄丅婥敆偲怱忣偺偙傕偭偨丄恀偭摉側儔儞僌榑傪撉傒偨偄丅墷暷偺杮奿揑側昡揱偺朚栿姧峴偑懸偨傟傞丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂僼儕僢僣丒儔儞僌偺弶婜偺捒嶌偲斢擭偺夦嶌
儕儕僆儉
1934丂僼儕僢僣丒儔儞僌丂昡揰乵C乶
儔儞僌偑儀儖儕儞傪扙弌偟丄暷崙偵搉傞慜丄僼儔儞僗偱嶣偭偨桞堦偺嶌昳丅僗僞僢僼偵偼惢嶌僄儕僢僸丒億儅乕丄嶣塭儖僪儖僼丒儅僥丄壒妝僼儔儞僣丒儚僢僋僗儅儞偲偺偪偵搉暷偡傞塮夋恖偑偄傞丅庡墘偺僔儍儖儖丒儃儚僀僄傕娫傕側偔僴儕僂僢僪傪庡側妶摦偺応偵偟偨丅壒妝偺嫟摨扴摉偵僕儍儞丒儖僲儚乕儖偲偁傞偺偱丄傕偟偐偟偰丄偲巚偭偨偑丄偙傟偼Lenoir偱娔撀偺Renoir偲偼堦暥帤堘偆嶌嬋壠傜偟偄丅尨嶌偼戝摉偨傝偟偨媃嬋丅偺偪偵僴儕僂僢僪偱乽夞揮栘攏乿偲偟偰儈儏乕僕僇儖壔偝傟偨丅慡懱偺3/4傑偱偼儐乕儌傾傪壛枴偟偨儕傾儕僘儉丒僞僢僠偺塮夋偩偑丄嵟屻偺1/4偱僼傽儞僞僕乕偵揮偢傞丅夞揮栘攏偺媞堷偒偩偭偨彈偨傜偟偺棎朶幰儕儕僆儉偼寢崶偟偰傕巇帠偣偢壠掚傪屭傒側偄偑丄廬弴側嵢偑擠怭偟偨偙偲抦傝丄嬥嶔偺偨傔嫮搻偟傛偆偲偟偰捛偄媗傔傜傟帺嶦偡傞丅揤崙偺栧偱楖崠峴偒偲側傞偑丄16擭屻偵1擔偩偗抧忋偵婣偭偰慞峴傪巤偣偽揤崙偵峴偗傞偲尵傢傟丄16嵨偵惉挿偟偨柡偵夛偆丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅抧忋偺寈嶡彁偲揤忋偺寈嶡彁偑傑偭偨偔摨偠偱丄揤忋偱偼塇傪惗傗偟偨摨偠寈嶡姱偑摨偠偙偲傪傗偭偰偄傞丄偲偄偆偺偑徫傢偣傞丅儔儞僌傜偟偝偼偁傑傝側偄偑丄媃嬋偺嬝棫偰偲払幰側栶幰偺偍偐偘偱丄偦傟側傝偵柺敀偄撪梕偵側偭偰偄傞丅
夦恖儅僽僛攷巑
1960丂僼儕僢僣丒儔儞僌乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰乵E乶
愴屻丄儔儞僌偑僪僀僣偵婣偭偰嶣偭偨2嶌偺偆偪偺1嶌偱丄偙傟偑嵟屻偺嶌昳偵側偭偨丅尨戣偼乽The 1000 Eyes of Dr. Mabuse乿偱丄32擭偺乽夦恖儅僽僛攷巑乿乮The Testament of Dr. Mabuse乯偺懕曇揑側撪梕丅儅僽僛偑巆偟偨堚彂偵塭嬁偝傟偰悽奅偺攋柵傪婇傓埆恖慻怐偲偦傟傪慾巭偟傛偆偲偡傞寈嶡偺愴偄傪昤偄偨僗儕儔乕丅埆恖傪捛偆寈晹偵僎儖僩丒僼儗乕儀丄偦傟偵姫偒崬傑傟傞抝彈偵僺乕僞乕丒償傽儞丒傾僀僋偲僪乕儞丒傾僟儉僗丅帪戙嶖岆偺峳搨柍宮偱儅儞僈偺傛偆側僾儘僢僩偲揥奐丅尒偳偙傠側偟丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂50擭戙弶婜偺僼儕僢僣丒儔儞僌偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖2杮
惵偄僈乕僨傿僯傾
1953丂僼儕僢僣丒儔儞僌丂昡揰乵B乶
僼儕僢僣丒儔儞僌偵傛傞僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺1杮丅偄偮傕偺廳嬯偟偄儔儞僌偲偼堎側傝丄僴儕僂僢僪丒僗僞僀儖偺柧傞偄暤埻婥偺僒僗儁儞僗偩偑丄弌棃偼側偐側偐椙偄丅庡墘偼揹榖岎姺庤偺傾儞丒僶僋僗僞乕偲怴暦婰幰偺儕僠儍乕僪丒僐儞僥丅楒恖偵怳傜傟偨僶僋僗僞乕偼彈偨傜偟偺僀儔僗僩儗乕僞乕偺桿偄偵忔偭偰庰傪堸傒夁偓丄抝偺傾僷乕僩偱朶峴偝傟偦偆偵側傞偑丄嫅斲偟偨偲偙傠偱堄幆偑側偔側傝丄栭拞偵婣戭偟偨偁偲丄梻挬抝偑嶦偝傟偨偙偲傪抦傞丅斵彈偼帺暘偑嶦偟偨偐偳偆偐偱擸傒丄怴暦婰幰偺僐儞僥偵憡択偡傞丅僐儞僥偼嵟弶偼怴暦偺僱僞偵棙梡偟傛偆偲偡傞偑丄僶僋僗僞乕偵崨傟偰恀憡傪媶柧偟傛偆偲偡傞丄偲偄偆撪梕丅榖偺揥奐偑岻偄丅搑拞偱偩傟傞偙偲側偔丄僥儞億傛偔恑傓丅偙偺墘弌椡偑丄儔儞僌偑僴儕僂僢僪偱挿擭巇帠偱偒偨棟桼偱偁傠偆丅僲儚乕儖偵偟偰偼慡懱揑偵寉偄偑丄栭偺塉偺忣宨丄怺栭偺怴暦幮僼儘傾偵僶僋僗僞乕偑搊応偡傞僔乕儞丄嬀傪巊偭偨僒僗儁儞僗偺惙傝忋偘側偳偵偼栚傪扗傢傟傞丅傾儞丒僶僋僗僞乕偼岻偄偟丄榚栶傕屄惈揑偩偑丄埆栶婄偺僐儞僥偼偳偆偵傕偄偨偩偗側偄丅尨嶌偼乽儘乕儔嶦恖帠審乿偱桳柤側償僃儔丒僉儍僗僷儕丅僫僢僩丒僐乕儖偺庡戣壧偑悘強偱巊傢傟偰偍傝丄杮恖傕搊応偟偰壧偭偰偄傞丅
僴僂僗丒僶僀丒僓丒儕償傽乕
1950丂僼儕僢僣丒儔儞僌丂昡揰乵B+乶
偄偐偵傕儔儞僌傜偟偄僑僠僢僋晽枴偺僟乕僋側僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅愝掕偝傟偰偄傞帪戙傗応強偼晄柧偩偑丄偍偦傜偔19悽婭屻敿偺撿晹偱偁傠偆丅儔儞僌偵傛傞偲丄恖偼傒側愽嵼揑偵斊嵾偺徴摦傪帩偭偰偄傞偲偺偙偲偩偑丄偙偺塮夋偺庡恖岞偱偁傞嶌壠儖僀僗丒僿僀儚乕僪偼摿暿偩丅儊僀僪傪柍棟傗傝傕偺偵偟傛偆偲偟偰嶦偟偰偟傑偄丄寵偑傞夛寁巑偺掜儕乕丒儃僂儅儞傪尵偄偔傞傔偰巰懱堚婞傪庤揱傢偣丄嶦恖偺嵾傪掜偵側偡傝偮偗傛偆偲偟丄偍傑偗偵帺暘偐傜棧傟傛偆偲偡傞嵢僕僃乕儞丒儚僀傾僢僩傑偱嶦偦偆偲偡傞丅掅梊嶼偺抧枴側塮夋偩偑丄榖偺揥奐偼僥儞億傛偔妸傜偐偱丄嵟屻傑偱嬞敆姶偑帩懕偡傞丅岝偲塭傪惗偐偟偨塮憸偑尒帠偱丄愳曈偺壠偺偨偨偢傑偄丄埫偄壆晘偺側偐偱敀偄僇乕僥儞偑偼偨傔偔條巕丄奒抜偺忋偱峴側傢傟傞嶴寑丄寧岝偵徠傜偝傟傞愳偺岝宨側偳丄尒偳偙傠偼懡偄丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐53丂乽僨僨偲偄偆彥晈乿偺僔儌乕僰丒僔僯儑儗偵彈偺埫偄忣擮傪尒偨
嵟屻偺愗傝嶥
1942擭丂僕儍僢僋丒儀僢働儖丂昡揰乵E乶
儀僢働儖娔撀偺僨價儏乕嶌丅弶婜偺儀僢働儖偼偙傫側嶌晽偩偭偨偺偩丅慜偵尒偨乽幍寧偺儔儞僨償乕乿傕寉検媺偩偭偨偑丄偙傟傕峳搨柍宮側儅儞僈偺傛偆側斊嵾塮夋偩丅僐儊僨傿偲偟偰嶌傜傟偰偄傞偺偩傠偆偑丄捖晠偡偓偰徫偊側偄丅寈嶡妛峑偺摨婜惗傆偨傝偑丄偳偪傜偑庱惾偵側傞偐傪嫞偭偰丄崅媺儂僥儖偱婲偒偨嶦恖帠審傪憑嵏偡傞偲偄偆榖丅偙偺傆偨傝偺怳傞晳偄偑丄墘媄側偺偩傠偆偑丄柇偵婥庢偭偰偄偰旲帩偪側傜側偄丅僊儍儞僌偺恊嬍偵僺僄乕儖丒儖僲儚乕儖丄偦偺枀偵儈儗乕儐丒僶儔儞偲偄偆攝栶傕丄拞恎偺偮傑傜側偝傪曗偭偰偄側偄丅傢偢偐偵丄廔斦偵弌偰偔傞丄埫偄栭偺丄幵偱偺捛愓僔乕儞偑丄巘彔儖僲儚乕儖偺乽廫帤楬偺栭乿傪渇渋偲偝偣傞丅
僨僨偲偄偆彥晈
1953丂僀償丒傾儗僌儗丂昡揰乵A乶
斊嵾儊儘僪儔儅偺寙嶌丅晆摢偵偨偨偢傓彥晈偺僔儌乕僰丒僔僯儑儗傪塮偡朻摢偺僔乕儞偑慺惏傜偟偄丅僔僯儑儗偵偼彥晈栶偑帡崌偭偰偄傞偟丄偦偺巔懺偼偄偮傕偼斶寑偺梊姶傪傑偲偭偰偄傞丅晳戜偼峘挰偺傾儞僩儚乕僾丅僔僯儑儗偑摥偔彥娰偺庡恖偑儀儖僫乕儖丒僽儕僄丄僔僯儑儗偺僸儌偺僋僘抝偵儅儖僙儖丒僟儕僆丄僔僯儑儗偲楒拠偵側傞慏忔傝偵儅儖僙儖丒僷儕僄儘偲偄偆丄懪偭偰偮偗偺晍恮偩丅僔僯儑儗偼峘偵傗偭偰棃偨慏忔傝偲楒拠偵側傝丄彥娰庡偺彆偗傪摼偰丄僸儌抝傪幪偰丄慏忔傝偲堦弿偵椃棫偲偆偲偡傞丅幪偰傜傟偨僸儌抝偼暊偄偣偵慏忔傝傪幩嶦偡傞丅偦傟傪抦偭偨僔僯儑儗偼暅廞傪寛堄偟丄僸儌抝傪尒偮偗偰幵偱鐎偒嶦偡丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅巒傑偭偰娫傕側偔丄柖偵墝傞栭偺晆摢傪曕偔僔僯儑儗偲慏忔傝偺忣姶昚偆僔乕儞偑報徾偵巆傞丅慏忔傝栶偺僷儕僄儘偼僕儍儞丒僊儍僶儞傪渇渋偲偝偣傞丅偙偺塮夋偱偺僔儌乕僰丒僔僯儑儗偼庒偔丄敡偼妸傜偐偩丅偦偺晽杄偼擏姶揑偩偑壓昳側姶偠偼側偄丅斵彈偼偗偭偟偰沍傃側偄偟丄戝偘偝側姶忣昞尰傪偟側偄丅偦偙偵杮尮揑側旤偟偝傪姶偠傞丅僔僯儑儗偼僸儌偵恠偔偡彥晈偩偑丄偨傫側傞恖偺偄偄嬸撦側彈偱偼側偄丅奨拞偱朶摦偑婲偙偭偨偲偒丄墸傝崌偄傪旝徫傒側偑傜尒偰偄傞僔僯儑儗偺婄偵丄塀偝傟偨慺婄偑傎偺尒偊傞丅斵彈偺杮惈偑昞傢傟傞偺偼丄楒恖偺慏忔傝偑嶦偝傟偨偲偒偩丅斵彈偼巰懱傪書偄偰媰偒傢傔偄偨傝偟側偄丅椻惷偵巰懱傪慏偵塣傋偲尵偄丄嶦偟偨僸儌抝偺嫃応強傪扵偟弌偟丄嬯捝傪梌偊傞偨傔丄彥娰庡偵備偭偔傝憱傜偣偰偲尵偭偰幵偱鐎偒嶦偝偣傞丅嵟屻偼朻摢偲摨偠晆摢偺僔乕儞偱廔傞偺傕婥偑棙偄偰偄傞丅懠偺弌墘幰偱偼彥娰偺庡恖偱慏忔傝偺媽桭偺儀儖僫乕儖丒僽儕僄偑偄偄丅晽嵮偼忋偑傜側偄偑媊棟偲恖忣傪傢偒傑偊偰偍傝丄僔僯儑儗傪彆偗傞丅偙偺塮夋傪尒偰僔儌乕僰丒僔僯儑儗偺枺椡傪嵞擣幆偟偨丅斵彈偺庡墘偟偨塮夋偱偼丄乽擏懱偺姤乿乽埆杺偺傛偆側彈乿乽塭偺孯戉乿傪尒偰偄傞偑丄傎偐偺塮夋傪傕偭偲尒偨偔側偭偨丅偙偆偟偰尒傞塮夋偺椫偑峀偑偭偰偄偔丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐52丂儊儖償傿儖偺擔杮枹岞奐嶌昳2嶌
僼僃儖僔儑乕壠偺挿抝
1963丂僕儍儞亖僺僄乕儖丒儊儖償傿儖乮塸岅帤枊斉乯丂昡揰乵C乶
儊儖償傿儖弶偺僇儔乕嶌昳偱丄僕儑儖僕儏丒僔儉僲儞尨嶌丄嶣塭偼傾儞儕丒僪僇僄丅埲慜丄帤枊側偟偱尒偰偄偨偑丄偁傜偡偠傪摢偵擖傟偰偄偰傕丄摉慠側偑傜榖偺棳傟偼傛偔暘偐傜側偐偭偨丅崱夞偼塸岅帤枊偱娪徿丅尦儃僋僒乕偺庒幰僕儍儞亖億乕儖丒儀儖儌儞僪偑丄埲慜偵斊偟偨嵾偱慽捛偝傟偐偐偭偰偄傞嬧峴壠僔儍儖儖丒償傽僱儖偵旈彂偲偟偰屬傢傟丄傾儊儕僇偵摝朣偡傞嬧峴壠偵摨峴偟丄塣揮庤仌儃僨傿僈乕僪偲偟偰僯儏乕儓乕僋偐傜僯儏乕僆乕儕儞僘傊偲椃傪偡傞榖丅堦庬偺儘乕僪乕丒儉乕償傿乕偩丅椃傪偡傞偁偄偩偵丄庒幰偑庡摫尃傪埇傝丄榁恖偺嬧峴壠偼懱挷傪曵偟偰丄庡媞揮搢偡傞丅僲儚乕儖揑側梫慺偼偁傑傝側偄丄晄巚媍側枴傢偄偺塮夋偩丅柍昞忣側婄偱旕忣偵怳傞晳偆儀儖儌儞僪偺峴摦婯斖偑傛偔暘偐傜側偄偑丄偦偙偑儊儖償傿儖傜偟偄偲偙傠偐丅儀儖儌儞僪傪庢傝姫偔彈偨偪偼丄僸僢僠僴僀僇乕偺僗僥僼傽僯傾丒僒儞僪儗僢儕傪偼偠傔丄僷儕偱幪偰傞垽恖丄僯儏乕僆乕儕儞僘偱崸傠偵側傞僟儞僒乕側偳丄傒側姱擻揑側旤彈偽偐傝偩丅
偙偺庤巻傪撉傓偲偒偼
1953丂僕儍儞亖僺僄乕儖丒儊儖償傿儖丂昡揰乵D乶
儊儖償傿儖3嶌栚偺挿曇寑塮夋丅廋摴彈偺巓僕儏儕僄僢僩丒僌儗僐偲偦偺枀僀儗乕僰丒僈儖僥儖乮偐傢偄偄両乯丄偦偟偰惗棃偺彈偨傜偟偺僼傿儕僢僾丒儖儊乕儖偑弌墘偡傞丄偍傛偦儊儖償傿儖傜偟偐傜偸儊儘僪儔儅丅屻敿偺榖偺棳傟偑傛偔暘偐傜側偄丅攋抅偟偰偄傞偲尵偭偰傕偄偄偩傠偆丅晳戜偼僇儞僰丄廋摴彈偺僌儗僐偼暥朳嬶揦傪塩傓椉恊偑帠屘偱巰傫偩偺偱丄枹惉擭偺枀僈儖僥儖傪彆偗傞偨傔堦帪揑偵娨懎偡傞丅帺摦幵廋棟岺偺儖儊乕儖偼枀傪尒弶傔偰儂僥儖偵楢傟崬傒丄嫮堷偵傕偺偵偡傞丅偦偺偁偲偺揥奐偑晄壜夝偩丅帺嶦枹悑偟偨枀偺偨傔僌儗僐偼柍棟傗傝枀偲廋棟岺傪寢崶偝偣傞丅偩偑廋棟岺偼僌儗僐偑岲偒偩偲崘敀偟丄僌儗僐偼嵟弶偼嫅愨偡傞偑丄愭偵儅儖僙僀儐偵敪偭偨廋棟岺偺偁偲傪捛偭偰楍幵偵忔傞丅偒傟偄偩偑偺偭傌傝偟偨婄丄廔巒丄柍昞忣偺僌儗僐偺峴摦偼柆棈偑側偔丄棟夝偵嬯偟傓丅廋棟岺偲儂僥儖偺嬥帩偪彈偲偺忣帠偲偦偺揯枛側偳偼丄傑偭偨偔杮嬝偵棈傑側偄丄梋寁側僄僺僜乕僪偩丅廋摴彈偑抝偵栚妎傔傞偲偄偆峔恾偼丄媡僷僞乕儞偩偑偺偪偺乽儌儔儞恄晝乿傪憐婲偝偣傞丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐51丂40擭戙屻敿偺懳徠揑側僼儔儞僗塮夋2杮
奀偺夊
1946丂儖僱丒僋儗儅儞丂昡揰乵B乶
戝妛帪戙偵尒偰埲棃丄50擭傇傝偵嵞尒丅愽悈娡偺塮夋偩偲偄偆偙偲偲丄彈偑愽悈娡偐傜棊偪偰慏偲偺娫偵嫴傑傟偰巰偸僔乕儞偩偗偟偐妎偊偰偄側偐偭偨丅戞2師戝愴枛婜丄攕怓擹偄僫僠僗丒僪僀僣偺枾柦傪庴偗丄僆僗儘偐傜撿暷偵晪偔U儃乕僩偵忔慏偟偨恖乆偺塣柦傪昤偔丅搑拞偱僪僀僣偑崀暁偟僸僢僩儔乕偑帺嶦偟偨偙偲偑暘偐傝丄忔慏偟偰偄偨崙杊孯彨孯丄恊塹戉姴晹丄惌彜丄婰幰丄忔慻堳偨偪偼摦梙偡傞丅偦傟傪桿夳偝傟偨堛巘偑椻惷偵娤嶡偡傞丅偙傟偼愴憟塮夋偱偼側偔丄嬌尷忬嫷壓偵偍偐傟偨恖娫偺峴摦傪椻揙偵昤偄偨怱棟僪儔儅偩丅僗僩乕儕乕偺揥奐偑岻偄偟丄愽悈娡偺側偐偺嬞敆偟偨暤埻婥偑傛偔昤偐傟偰偄傞丅嫹偄撪晹傪揑妋偵懆偊傞僇儊儔偑慺惏傜偟偄丅
幍寧偺儔儞僨償乕
1949丂僕儍僢僋丒儀僢働儖丂昡揰乵D乶
乽擏懱偺姤乿乽尰僫儅乿乽寠乿傪嶣偭偨儀僢働儖偺娔撀嶌偲偼巚偊側偄丄偁傝偒偨傝側惵弔塮夋丅49擭偲偄偊偽愴屻娫傕側偄偺偵僷儕偺奨偵偼愴壭偺彎愓偼傑偭偨偔側偄丅摉帪僀儞僪僔僫愴憟偱僼儔儞僗偼儀僩僫儉偱愴偭偰偄偨偺偵丄偦傟傕塭傪棊偲偟偰偄側偄丅墘寑偲壒妝傪妝偟傒丄楒垽傪偟丄枹棃傪庤扵傝偡傞庒幰偨偪偑昤偐傟傞偑丄昞柺傪側偧偭偨偩偗偵偡偓偢丄暯斅側報徾傪庴偗傞丅庡墘偼僟僯僄儖丒僕僃儔儞偩偑丄偙偺攐桪偼僉儍儔僋僞乕揑偵岲偒偱偼側偄丅傕偆堦恖偺庡栶儘乕儕僗丒儘僱偼偠偮偵庒偄丅嵟弶偼儘僱偩偲婥偑偮偐側偐偭偨丅廔斦儗僢僋僗丒僗僠儏傾乕僩偑儔僀償丒僴僂僗偵尰傟偰擬墘傪斺業偡傞丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐50丂擔暓偺嫽枴怺偄塮夋僪僉儏儊儞僞儕乕2杮
儕儏儈僄乕儖偺巕嫙偨偪丂僼儔儞僗塮夋偺100擭
1995丂傾儔儞丒僐儖僲乕傎偐丂昡揰乵B乶
儕儏儈僄乕儖孼掜偺乽岺応偺擖傝岥乿偐傜乽儗僆儞乿傑偱丄100擭娫偵嶌傜傟偨僼儔儞僗塮夋300杮偺柤応柺偑僐儔乕僕儏晽偵傑偲傔傜傟偨嶌昳丅楌巎傗塮夋傗攐桪偑宯摑棫偭偰徯夘偝傟傞傢偗偱偼側偔丄帇慄丄壧丄僊儍僌丄僉僗側偳偺僥乕儅偛偲偵奺塮夋偺抁偄僔乕儞偑柆棈側偔柍憿嶌偵宷偑傟偰偄傞丅柤娔撀偺廳梫側嶌昳偼枩曊側偔栐梾偝傟偰偍傝丄婰壇偵巆偭偰偄傞僔乕儞傕懡偔丄側偐側偐妝偟偄丅乽僺僋僯僢僋乿側偳偺柤夋傕傾僂僩僥僀僋傕塮偟弌偝傟傞丅岾偣側僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋偩丅
惗偒偰偼傒偨偗傟偳丂彫捗埨擇榊揱
1983丂堜忋榓抝丂昡揰乵C+乶
彫捗偺杤屻20擭偵偪側傫偱嶌傜傟偨婰榐塮夋丅備偐傝偺応強偺塮憸丄恊偟偔愙偟偨恖乆傊偺僀儞僞償儏乕丄偝傑偞傑側塮夋偺僔乕儞偵傛偭偰峔惉偝傟偰偄傞丅悢懡偔偺塮夋恖偑搊応偡傞偑丄側偐偱偼妢抭廜丄悪懞弔巕丄扺搰愮宨丄搶栰塸帯榊偺尵梩偑嫽枴怺偄丅崱擔弌奀偑乽彫捗偺塮夋偵偼偳傟傕屒撈姶偑昚偭偰偄傞乿偲尵偭偰偄傞応柺丄岤揷梇弔偑僇儊儔傪庤偵偟偰嶣塭朄傪岅偭偰偄傞応柺偑報徾偵巆傞丅偄傑偱偼偙偙偱挐偭偰偄傞恖偨偪偺懡偔偑婼愋偵擖偭偰偟傑偭偰偄傞丅怴偟偄敪尒偼側偄偑丄梫椞傛偔傑偲傔傜傟偰偍傝丄曇廤傕挌擩偩丅庡梫側嶌昳偼傎偲傫偳徯夘偝傟偰偄傞偑丄乽晜憪乿偑敳偗偰偄傞偺偼戝塮偐傜庁傝傜傟側偐偭偨偐傜偐丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐49丂50擭戙偺抧枴側僼儔儞僗塮夋
僈儔僗偺忛
1953丂儖僱丒僋儗儅儞丂昡揰乵D乶
敾帠僕儍儞丒僙儖償僃偺嵢儈僔僃儖丒儌儖僈儞偼曐梴愭偱僾儗僀儃乕僀偺惵擭僕儍儞丒儅儗僄偲楒偵棊偪傞丅儅儗僄偼僷儕偵婣傝丄儌儖僈儞偼晇偲偲傕偵儀儖儞偵晪偔偑丄儅儗僄偐傜偵揹榖偵墳偠丄儌儖僈儞偼晇偺栚傪搻傫偱僷儕偵椃棫偪丄儅儗僄偲偺埀悾傪妝偟傓丅嵟屻偼儀儖儞峴偒偺旘峴婡偑捘棊偟偰儌儖僈儞偼巰偸丅僼儔儞僗塮夋揱摑偺晄椣偲楒垽僎乕儉偺暔岅偱丄偰偄偹偄偵嶌傜傟偰偼偄傞偑丄偁傑傝柺敀偔側偄丅
愥偼墭傟偰偄偨
1952丂儖僀僗丒僒僼儔僗僉乕丂昡揰乵E乶
僕儑儖僕儏丒僔儉僲儞尨嶌偺斊嵾塮夋丅僫僠愯椞壓偺僼儔儞僗偺揷幧挰丅曣恊偑彥晈偱丄懠壠偵梐偗傜傟偰惉挿偟偨惵擭僟僯僄儖丒僕儏儔儞偑庡恖岞丅偄傑偼曣恊偺宱塩偡傞攧弔廻偵摨嫃偡傞斵偼崻偭偐傜偺埆恖丄暫戉傪嶦偟偰対廵傪扗偄丄堢偰偺恊偺壠偵墴偟擖偭偰帪寁傪嫮扗偡傞側偳埆帠傪廳偹傞偑丄戇曔偝傟偨偁偲怱桪偟偄柡傊偺垽偵栚妎傔偰夵怱偟丄廵嶦偝傟傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅掙偺愺偄偁傝偒偨傝偺姪慞挦埆塮夋丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐48丂儖僱丒僋儗儅儞偺弶婜嶌昳2杮
揝奿巕偺斵曽
1949丂儖僱丒僋儗儅儞丂昡揰乵B乶
暓埳崌嶌塮夋丅彈傪嶦偟偰僕僃僲償傽偵棳傟拝偄偨拞擭偺抝偵僕儍儞丒僊儍僶儞丅僊儍僶儞偲楒拠偵側傞僶乕儖偺彈媼巇偵僀僓丒儈儔儞僟丅峘挰偺晽宨傪塮偡僇儊儔偑尒帠丅儈儔儞僟偺柡偱僊儍僶儞偲嵟弶偵拠椙偔側傞彈偺巕偑偐傢偄偄丅榖偺棳傟偑僗儉乕僗偱僥儞億椙偔恑傓丅榖偺嬝偼僨儏償傿償傿僄晽偩偑丄偦傟傎偳彇忣偵棳偝傟偢丄姡偄偨昤幨側偺偑僋儗儅儞揑偐丅偁偭偝傝偟偨僄儞僨傿儞僌傕偄偄丅
偟偺傃埀偄
1954丂儖僱丒僋儗儅儞丂昡揰乵D乶
暓塸崌嶌塮夋丅僞僀僩儖偐傜儊儘僪儔儅傪楢憐偡傞偑丄偙傟偼僕僃儔乕儖丒僼傿儕僢僾庡墘偺僔僯僇儖側僐儊僨傿偱丄偳偆偟傛偆傕側偄彈偨傜偟偺堦戙婰偲偄偭偨傛偆側嶌昳丅儘儞僪儞偵廧傓僼儔儞僗恖偱桪抝偺僾儗僀儃乕僀偑嬥帩偪偺彈偲寢崶偡傞偑丄嵢偺恊桭偵寽憐偟丄斵彈傪岥愢偒棊偲偡偨傔帺暘偺彈曊楌傪暔岅傞丅弌墘偡傞彈桪偼抦傜側偄柤慜偽偐傝偱丄偁傑傝枺椡揑偱偼側偄丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐47丂愴屻柉庡庡媊偺嫵忦塮夋
1954丂壠忛枻戙帯丂昡揰乵C+乶
杒惎塮夋攝媼丄擔杮嫵怑堳慻崌屻墖偺撈棫僾儘嶌昳丅昻偟偄擾懞偱妛傇彫妛惗偨偪傪昤偄偨塮夋丅弌墘偼崄愳嫗巕偺傎偐丄撪摗晀晲丄壛摗壝丄壴戲摽塹側偳墘寑恖偨偪丅惗搆偵曠傢傟傞擬寣娍偺嫵巘丄尃椡傪弬偵執傇傞懞挿丄懞挿偵僑儅傪偡傞峑挿丄帠側偐傟庡媊偺柍婥椡側愭惗丄巕嫙偨偪偺壠偼擔乆偺惗妶偵捛傢傟傞昻崲壠掚偱丄昻偟偔偰嫵壢彂傪攦偊側偄巕嫙丄愒傫朧傪偍傇偭偰搊峑偡傞巕嫙偲丄奊偵昤偄偨傛偆偵恾幃揑側塮夋偩偑丄偮傑傜側偄偐偲偄偆偲偦偆偱偼側偔丄偗偭偙偆柺敀偄丅偦偺庡場偼巕嫙偨偪偺帺慠側墘媄偵偁傞丅巕嫙偨偪偺婄偮偒偑偄偄丅傒側擔杮恖杮棃偺婄傪偟偰偄傞丅偄傑偺塮夋偵弌偰偔傞傆偵傖偗偨婄偺巕嫙偨偪偲偼慡慠堘偆丅擬寣娍偺愭惗偵撪摗晀晲丄庡墘偺巕嫙偺偍巓偝傫栶偺崄愳嫗巕偑壜楓偱旤偟偄丅憒偒棴傔偵掃偩丅54擭摉帪丄昅幰偼7嵨偱丄媨嶈偺偙傫側擾懞偺側偐偺偙傫側彫妛峑偵捠偭偰偄偨丅惗搆偺悢偼傕偭偲懡偐偭偨偟丄巕嫙偨偪偺壠掚偼偙傟傎偳昻偟偔偼側偐偭偨偑丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐46丂埳扥枩嶌偺僐儊僨傿2杮
愒惣鍄懢
1936丂埳扥枩嶌丂昡揰乵B乶
杮嶌偼埳扥偺戙昞嶌丅埳払憶摦傪戣嵽偵偟偨僐儊僨傿帪戙寑偱丄巙夑捈嵠尨嶌偲偺偙偲丅埳払壆晘偵僗僷僀偲偟偰愽傝崬傓愒惣奱懢偑庡恖岞丅曅壀愮宐憼偑廥抝偺奱懢偲旤抝偺尨揷峛斻偺2栶傪墘偠傞丅僒僓僄偝傫偺傛偆偵搊応恖暔偑傒側奀嶻暔偵偪側傫偩柤慜側偺偑恖傪怘偭偰偄傞丅奱懢偼堿杁偺徹嫆傪庤偵擖傟丄壆晘傪帿偟偰崙偵婣傠偆偲偡傞偑丄夦偟傑傟側偄偨傔丄旤恖偺崢尦攡懞梕巕偵晅偗暥傪偟偰憶摦偑帩偪忋偑傞丅擫傪帩偪塣傫偱峴偭偨傝棃偨傝偡傞僔乕僋僄儞僗傗丄拞娫偑壗搙傕摨偠傛偆側尵揱偺偨傔塉偺側偐奜弌偝偣傜傟偰偆傫偞傝偡傞僔乕僋僄儞僗側偳丄埳扥偼孞傝曉偟偵傛偭偰儐乕儌傾傪忴惉偝偣傞丅傾儊儕僇塮夋偺婌寑丄偲偔偵儖價僢僠偁偨傝偺塭嬁偑姶偠傜傟傞丅慡懱偵寉柇煭扙側枴傢偄偑昚偭偰偄傞偑丄尨揷峛斻偺搊応僔乕儞傪巚偄愗傝壧晳婈挷偵偟偰僐儞僩儔僗僩傪偮偗偰偄傞偺偑柺敀偄丅愮宐憼偺偲傏偗偨墘媄傕尒帠丅
婥傑偖傟姤幰
1935丂埳扥枩嶌丂昡揰乵C+乶
偙傟傑偨僫儞僙儞僗側僐儊僨傿帪戙寑丅壒惡偑埆偔丄戜帉偑傛偔暦偒庢傟側偄偺偑擄丅晽棃朧偺2恖慻偑偁傞崙偱屼慜帋崌偱偺榬慜偑擣傔傜傟偰壠棃偵側傝丄揋懳偡傞椬崙偵掋嶡偵峴偔榖丅庡墘偼旤抝偺庒幰丄曅壀愮宐憼偩偑丄憡朹偺娫敳偗側懢偭偪傚丄闄偺姩廫偺僉儍儔僋僞乕偑側偐側偐椙偔丄愮宐憼傪怘偭偰偄傞丅巇姱偡傞偲偒偺揳條偲愮宐憼偺曨媼偵娭偡傞傗傝偲傝傗丄揋崙偱曔偊傜傟偨2恖偑楽壆傪敳偗弌偟偰昉偺晹壆偵尰傟傞応柺側偳丄書暊傕偺丅僶僇僶僇偟偄偲傏偗偨枴傢偄偑偄偄丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐45丂僌儗傾儉丒僌儕乕儞尨嶌偺2杮
惷偐側傾儊儕僇恖
1958丂僕儑僙僼丒儅儞僉僂傿僢僣丂昡揰乵C乶
50擭戙弶摢丄僀儞僪僔僫愴憟壓偺僒僀僑儞丄僼儔儞僗怉柉抧偺儀僩僫儉惌晎偼撈棫傪栚巜偡儀僩僐儞偑巇妡偗傞僎儕儔愴憟偵傛偭偰庣惃偵棫偭偰偄傞丅媽惓寧偺嵳傝偵桸偔僒僀僑儞偺愳曈偱傾儊儕僇恖偺庒幰偺巰懱偑敪尒偝傟傞偲偄偆敪抂丅僼儔儞僗恖偺寈晹偑憑嵏傪奐巒偡傞丅僀僊儕僗恖偺婰幰儅僀働儖丒儗僢僪僌儗僀償偑帠審傪恀憡傪岅傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅傾儊儕僇偺惵擭偵僆乕僨傿丒儅乕僼傿丄儅乕僼傿偵媮垽偝傟偰偦傟傑偱摨惐偟偰偄偨儗僢僪僌儗僀償偺尦傪嫀傞儀僩僫儉彈偵僕儑乕僕傾丒儌儖乮偳偙偐偱尒偨婄偩偲巚偭偰偄偨偑丄僗僥傿亅償丒儕乕償僗庡墘乽僶僌僟僢僪偺搻懐乿偱墹彈栶傪墘偠偨彈桪偩偭偨乯丅斵傜偺嶰妏娭學偑幉偵側偭偰偍傝丄巗撪僥儘偺敋抏傪嫙媼偟偨偺偑儅乕僼傿偩偲巚偄崬傫偩儗僢僪僌儗僀償偑丄彈傪扗傢傟偨暊偄偣偵丄揋懳慻怐偵儅乕僼傿傪攧傞丅僀僊儕僗恖婰幰丄傾儊儕僇恖惵擭丄僼儔儞僗恖寈晹偲偄偆攝抲偼埆偔側偄偑丄偦偺峔恾偺柺敀偝偑昤偐傟偰偄側偄偟丄傾儊儕僇恖惵擭偺幚懱傕傛偔暘偐傜側偄丅斵偼摉帪儀僩僫儉偵夘擖偟巒傔偨傾儊儕僇傪徾挜偟偰偍傝丄傾儊儕僇恖偑嶦偝傟傞偲偄偆榖偼偺偪偺儀僩僫儉愴憟傪埫帵偟偰偄傞偲尒傞偙偲傕偱偒側偔偼側偄丅
僴償傽僫偺抝
1960丂僉儍儘儖丒儕乕僪丂昡揰乵C+乶
椻愴壓偺僗僷僀妶摦傪旂擏偭偨僐儊僨傿塮夋丅妚柦慜偺僉儏乕僶丄僴償傽僫偱壠揹揦傪宱塩偡傞僀僊儕僗恖偑杮崙偺忣曬晹偵儕僋儖乕僩偝傟丄斵偼嬥傎偟偝偵偄偄壛尭側忣曬傪偱偭偪忋偘偰憲傞偑丄偦傟偵傛偭偰憶摦偑姫偒婲偙傞偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡恖岞偺揦庡偵傾儗僢僋丒僊僱僗丄斵偺桭恖偺僪僀僣恖堛巘偵嫄娍僶乕儖丒傾僀償僗丄忣曬晹偐傜憲傝崬傑傟傞旤恖旈彂偵儌乕儕儞丒僆僴儔丄忣曬晹挿偵儔儖僼丒儕僠儍乕僪僜儞偲偄偆丄側偐側偐廰偄婄傇傟丅僷儘僨傿偲偟偰偼傛偔弌棃偰偄傞丅僄儞僨傿儞僌偺丄儘儞僪儞偺摴抂偱攧傜傟偰偄傞惛岻側娺嬶偑擔杮惢偩偭偨偲偄偆僆僠偵偼丄偳傫側堄枴偑崬傔傜傟偰偄傞偐丄僇僗僩儘偑嫋壜偟丄妚柦屻偺僉儏乕僶偱儘働嶣塭偑峴側傢傟偨傜偟偄丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐44丂儘僶乕僩丒傾儖僪儕僢僠偺塀傟偨堩昳2杮
抧崠傊昩撉傒
1959丂儘僶乕僩丒傾儖僪儕僢僠丂昡揰乵C乶
廔愴捈屻偺儀儖儕儞偱晄敪抏張棟偲偄偆柦偑偗偺巇帠偵実傢傞尦暫巑偨偪傪昤偄偨塮夋丅張棟斍偺斍挿偵僕儍僢僋丒僷儔儞僗丄斍堳偺傂偲傝偱恎彑庤側怳傞傑偄偺寵傢傟幰偵僕僃僼丒僠儍儞僪儔乕丄斵傜偑壓廻偡傞壠偺壠庡偵儅儖僠乕僰丒僉儍儘儖丅儀儖儕儞偺姠釯偩傜偗偺奨暲傒偑報徾怺偄丅儀儖儕儞偱嶣塭偝傟偨偲偁傞偑丄愴屻10悢擭宱偭偨嶣塭摉帪丄傑偩偙傫側晽宨夋巆偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅晄敪抏傪張棟偡傞僔乕儞偺嬞敆姶偑尒帠丅6恖偺斍堳偑惗偒巆傝僎乕儉偵嬥傪搎偗傞僄僺僜乕僪偲丄僷儔儞僗偲僉儍儘儖偺儘儅儞僗偑僗僩乕儕乕偵棈傓丅斵傜偼傂偲傝偢偮柦傪棊偲偟丄嵟屻偵僷儔儞僗偩偗偑巆傞丅僷儔儞僗偲偄偊偽乽峌寕乿偺惁傑偠偄宍憡偲婼婥敆傞墘媄偑朰傟傜傟側偄偑丄偙偙偱傕岲墘偟偰偄傞丅慡懱偵悺媗傑傝偺姶偠偑偡傞偑丄埬偺掕丄尰峴斉偼僆儕僕僫儖斉偺30暘抁弅償傽乕僕儑儞傜偟偄丅
僈乕儊儞僩丒僕儍儞僌儖
1957丂償傿儞僙儞僩丒僔儍乕儅儞丂昡揰乵C乶
僯儏乕儓乕僋堖暈嬈奅偺撪枊傪楯巊偺懳棫偲恊巕偺妺摗偲偄偆帇揰傪幉偵昤偄偨嶌昳丅娔撀偺傾儖僪儕僢僠偑懱惂崘敪偺巔惃傪庛傔傛偆偲偡傞僗僞僕僆偺曽恓偵廬傢偢嶣塭廔椆捈慜偵夝屬偝傟丄僔儍乕儅儞偑屻傪堷偒宲偄偩丄偄傢偔偮偒偺塮夋丅幮堳偺慻崌寢惉傪嫅斲偡傞媽暰側夛幮幮挿偵儕乕丒J丒僐僢僽丄幚忣傪抦傝慻崌偵尐擖傟偡傞幮挿偺懅巕偵僇乕僂傿儞丒儅僔儏乕僘丄幮挿偑屬偆慻崌捵偟偺恊嬍偵儕僠儍乕僪丒僽乕儞丅僐僢僽偼廔斦偵僽乕儞偺埆鐓側巇帠傇傝傪抦傝丄夵怱偟偰慻崌傪庴偗擖傟傛偆偲偟丄僽乕儞偵嶦偝傟傞丅偙偺偁偨傝偺昤偒曽偑搨撍偐偮拞搑敿抂偱偁傝丄傾儖僪儕僢僠偑嫅斲偟偨嬝棫偰偱偁傠偆丅僐僢僽偼乽攇巭応乿偱丄偙傟偲偼斀懳偵峘榩傪媿帹傞慻崌偺儃僗偺栶傪傗偭偨偑丄惈奿晅偗偼摨偠偱偁傝丄偝偡偑偵岲墘偟偰偄傞丅偗偭偒傚偔埆恖偺捵偟壆偨偪偼寈嶡偵戇曔偝傟丄嵟屻偼慻崌偲嫤挷偡傞懅巕偑夛幮偺宱塩傪堷偒宲偖偲偄偆娒偄寢枛偩偑丄傾儖僪儕僢僠傜偟偝偼悘強偵昞傟偰偍傝丄捵偟壆偨偪偑慻崌偺儕乕僟乕傪巋嶦偡傞僔乕儞側偳偼嬞敆姶偵枮偪偰偄傞丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐43丂僲儚乕儖晽枴偺嶌昳2杮
栭傑偱僪儔僀償
1940丂儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏丂昡揰乵C乶
挿嫍棧僩儔僢僋塣揮庤偺惗妶傪昤偄偨僲儚乕儖晽偺僪儔儅丅僂僅儖僔儏傜偟偔丄榖偼彫婥枴偄偄僥儞億偱揥奐偡傞丅庡墘偺塣揮庤偺僕儑乕僕丒儔僼僩丄偦偺掜偱憡朹偺僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩丄儔僼僩偑崨傟傞僟僀僫乕偺彈媼偵傾儞丒僔僃儕僟儞丄儔僼僩偵墶楒曠偡傞塣憲夛幮幮挿晇恖偵傾僀僟丒儖僺僲偲偄偆攝栶丅儔僼僩偲儃僈乕僩偺孼掜偼偄偢傟堦婙梘偘傛偆偲柍杁偵巇帠偟丄帠屘傪婲偙偟偰儃僈乕僩偼曅榬傪幐偆丅儖僺僲偼埆彈栶偱丄晇偺夛幮偵屬傢傟偨儔僼僩偲堦弿偵側傝偨偄偑偁傑傝丄晇傪嶦偟偰帠屘傪憰偆丅儖僺僲偑僈儗乕僕偺帺摦奐暵斷偵傛偭偰僩儔僂儅偵廝傢傟傞偁偨傝偑僲儚乕儖丒僞僢僠丅儔僼僩偼嶦恖傪嫵嵈偟偨偲偟偰嵸敾偵偐偗傜傟傞偑丄嵟屻偵柍幚偑徹柧偝傟偰僴僢僺乕丒僄儞僪丅儃僈乕僩偼梻41擭偵儖僺僲偲偺嫟墘偱乽僴僀丒僔僃儔乿偺庡栶偵敳揊偝傟丄恖婥傪摼傞偙偲偵側傞丅
屚梩
1956丂儘僶乕僩丒傾儖僪儕僢僠丂昡揰乵B乶
斀崪嵃偵枮偪偨抝惈揑側塮夋偱抦傜傟傞傾儖僪儖儕僢僠偵偟偰偼捒偟偄僒僗儁儞僗丒僞僢僠偺儊儘僪儔儅丅帺戭偱僞僀僺僗僩偲偟偰摥偔屒撈側拞擭撈恎彈惈僕儑乕儞丒僋儘僼僅乕僪偑戅栶偟偨庒幰僋儕僼丒儘僶乕僩僜儞偲抦傝崌偄丄媮垽偝傟偰丄鐣弰偟偨枛偵寢崶偡傞偑丄晇偺岅偭偨夁嫀偺榖偑塕偱偁傞偙偲傪抦偭偰媈榝偵壵傑傟傞丅儘僶乕僩僜儞偼偐偮偰偺嵢偑帺暘偺晝恊偲晄椣偟偰偄傞尰応傪栚寕偟偰僔儑僢僋傪庴偗丄惛恄偵堎忢傪偒偨偟偨偲偄偆愝掕偱丄偙偺傊傫偑僲儚乕儖晽偲尵偊側偔傕側偄丅僋儘僼僅乕僪偼晇偑惓婥偵栠偭偨傜帺暘偐傜嫀偭偰峴偔偐傕偟傟側偄偙偲傪妎屽偟偰惛恄昦堾偵擖傟傞丅僋儘僼僅乕僪偺墘媄偑埑姫丅榗傫偩壠懓娭學偱惓忢側敪堢偑朩偘傜傟傞懅巕偲偄偆愝掕偼傾儖僪儕僢僠偺嶌昳偵懡偄丅僫僢僩丒僐乕儖偺壧偆乽屚梩乿偑庡戣壧偱丄偙偺儊儘僨傿偼悘強偵憓擖偝傟傞丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐42丂巗愳浝偺50擭戙晽巋塮夋
惵弔夦択
1955丂巗愳浝丂昡揰乵C乶
巶巕暥榋尨嶌偺僐儊僨傿丅弶榁偺夛幮屭栤偱抝傗傕傔偺懞嶳汔偲柡偺僶儗僄傪妛傇儃乕僀僢僔儏側杒尨嶰巬丄壡晈偺崒梉婲巕偲懅巕偱嬥姩掕偵嫮偄價僕僱僗儅儞偺嶰嫶払晇偺4恖偑怐傝惉偡寢崶憶摦偺揯枛傪昤偔丅慡堳偑婏恖丒曄恖偺椶偄偩丅杒尨偲嶰嫶偼婥偺崌偆桭恖偱丄偍屳偄偺恊傪寢崶偝偣傛偆偲婇傓丅側傫偲偄偭偰傕懢傔偩偑壜垽偄崒梉婲巕偺垽沢偺偁傞揤恀啵枱偝偑尒傕偺偱丄斵彈偺墘媄偲傕抧偲傕偮偐側偄彮彈偺傛偆側昞忣偲巇憪偑偑偙偺塮夋傪姰慡偵偝傜偭偰偄傞丅杒尨傪楒偄曠偆僶儗僄妛峑偺屻攜傪墘偠傞埌愳偄偯傒偼摉帪20嵨丄偁偳偗側偝偲偄偠傜偟偝偑報徾偵巆傞丅
枮堳揹幵
1957丂巗愳浝丂昡揰乵E乶
愳岥峗庡墘偺幮夛晽巋僐儊僨傿偩偑丄柺敀偔側偄丅堦棳戝妛傪弌偨庒幰偑恖岥憹丄宨婥偺埆偝丄媽暰側幮夛懱幙偺偣偄偱棊偪傇傟傞偲偄偆榖丅屄乆偺憓榖傪丄偍偦傜偔娔撀偼儐乕儌傾傪崬傔偰昤偄偰偄傞偮傕傝側偺偩傠偆偑丄慡慠儐乕儌傾偵側偭偰偄側偄丅偡傋偰偑柍婡揑偱丄柆棈側偔埫偄榖偑懕偔丅愳岥偺晝曣栶偱偣偭偐偔妢抭廜丄悪懞弔巕偲偄偆柤桪偑弌偰偄傞偺偵丄傑偭偨偔惗偐偝傟偰偄側偄丅偨偩偟孮廜僔乕儞偺嶣傝曽偼敆椡偑偁傞丅
2020擭6寧朸擔 旛朰榐41丂愴慜偺帪戙寑2嶌
拤恇憼愒奯尮憼丂摙擖傝慜栭
1938丂抮揷晉曐丂昡揰乵C乶
嶃搶嵢嶰榊庡墘丅偐偮偰壧晳婈傗島択偱偍撻愼傒偩偭偨拤恇憼奜揱乽愒奯尮憼摽棙偺暿傟乿偺塮夋壔丅孼偺壆晘偵嫃岓偟偰堸庰偵柧偗曢傟傞愒曚楺巑丄尮憼傪昤偔慜敿偼丄斵傪憐偆椬壠偺柡偲偺憓榖傕擖傝丄偺傫傃傝偟偨儉乕僪偱側偐側偐椙偄丅壠傪捛偄弌偝傟偨尮憼偼丄摙偪擖傝偺慜栭丄愥偺崀偟偒傞側偐丄閈摢嶱偵崌塇巔偱堦彙摽棙傪傇傜壓偘丄孼偺壆晘偵暿傟偺垾嶢偵峴偔偑丄孼偼晄嵼丄尮憼偼孼偺塇怐傪堖栦妡偗偵妡偗丄偦傟偵岦偐偭偰攗傪宖偘丄壣岊偄傪偡傞丅嶃嵢偼偝偡偑偺娧榎丅墳懳偡傞彈拞偺偍偡偓偑偐傢偄偄丅屻敿偼幣嫃偑偐偭偰偄傞偑丄帪戙傪峫椂偡傟偽偟傚偆偑側偄偩傠偆丅
懸偭偰嫃偨抝
1942丂儅僉僲惓攷丂昡揰乵A乶
挿扟愳堦晇丄嶳揷屲廫楅丄墊杮寬堦庡墘偺寉柇側僐儊僨傿丒儈僗僥儕乕帪戙寑丅埳摛偺壏愹椃娰偱庒彈彨偵婏夦側帠審偑楢敪偡傞丅朻摢30暘傪夁偓偰偐傜丄峕屗偺栚柧偐偟乮挿扟愳乯偲偦偺嵢乮嶳揷乯偑搾帯媞偲偟偰傛偆傗偔搊応丅傗傞婥偺側偄挿扟愳偵戙傢偭偰丄偁偨偟偑撲傪夝偄偰傗傞偲挘傝愗傞嶳揷丅偦偙偵抧尦偺栚柧偐偟嬥懢乮僄僲働儞乯偑尰傟傞丅恖偼偄偄偑柍擻側僄僲働儞偵挿扟愳偑堿偱憑嵏偟偰斊恖傪嫵偊丄僄僲働儞偼嵟屻偵傒傫側偺慜偱帺暘偑悇棟偟偨偐偺傛偆偵斊恖傪崘偘傞丅愴帪壓偲偼巚偊側偄傎偳偺傫傃傝偟偨丄僪僞僶僞偁傝丄儐乕儌傾偁傝偺丄偲傏偗偨枴傢偄偵枮偪偨塮夋丅挿扟愳偲嶳揷偺僐儞價偑愨柇偩偟丄僄僲働儞傕杮椞敪婗丅恖偵壗偐傪恥偔偨傃偵乽偄傠偄傠恊愗偵嫵偊偰偔傟偰偁傝偑偲偆乿偲攏幁挌擩偵楃傪尵偆僄僲働儞偵偼丄巚傢偢悂偒弌偟偰偟傑偆丅傎偐偵崅曯廏巕丄摗尨寋懢丄怴摗塸懢榊傕弌墘丅夋幙偑埆偔丄壒惡傕暦偒庢傝偵偔偄偺偑巆擮丅偙偺慜擭偵嶌傜傟偨摨庯岦偺挿扟愳丒嶳揷僐儞價偵傛傞乽嶐擔徚偊偨抝乿傕尒偰傒偨偄傕偺偩丅
2020擭5寧
2020擭5寧朸擔 旛朰榐40丂儖僲儚乕儖偺尒摝偟偰偄偨1嶌偲僨儏償傿償傿僄偺媽嶌
1936丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C乶
弌斉幮偵柋傔側偑傜彫愢傪彂偔庡恖岞偺儔儞僕僃丅弌斉幮偺幮挿偼嫮梸偱彈偨傜偟偩丅椬偺愻戵壆偺彈揦挿偲儔儞僕僃偑楒拠偵側傞丅楍幵帠屘偱幮挿偼巰偵丄幮堳偨偪偼嫤摨慻崌傪嶌偭偰宱塩婋婡偵偁偭偨夛幮傪寶偰捈偡偑丄偦偙偵巰傫偩偼偢偺幮挿偑恄晝偵曄憰偟偰巔傪尰偡丅儖僲儚乕儖偵偼捒偟偔夞憐宍幃偺塮夋丅僥儞億偺偄偄僐儊僨傿偩偑丄偄偝偝偐戅孅丅廔斦丄恄晝巔偺幮挿偑丄巰偵嵺偵乽恄晝傪屇傫偱偔傟乿偲偄偆偺偵偼敋徫丅昹曈偺攇懪偪嵺傪嫀傞抝彈2恖偺巔傪捛偆儔僗僩僔乕儞偑偄偄丅僔儖償傿傾丒僶僞僀儐偑弌偰偄傞偲偙偙偲偩偑丄妋擣偱偒側偐偭偨丅
抧偺壥偰傪峴偔
1935丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰乵C乶
僕儍儞丒僊儍僶儞偑庡墘偱丄僷儕偱嶦恖傪斊偟丄僶儖僙儘僫偵摝偘偰奜恖晹戉偵擖傝丄儌儘僢僐偵搉偭偰暫戉偲偟偰偺擔乆傪夁偛偡抝傪墘偠傞丅僊儍僶儞偑楒拠偵側傞庰応偺梮巕偵傾僫儀儔丄奜恖晹戉偺戉挿偵僺僄乕儖丒儖僲儚乕儖偲偄偆晍恮丅偦傟偵僊儍僶儞偑晹戉偱恊偟偔側傞愴桭傗僊儍僶儞傪晅偗慱偆寈嶡偺庤愭偑棈傓丅僨儏償傿償傿僄偺榖弍偼岻傒偩偑丄慡懱偵彇忣枴偑嫮偄丅朻摢偺栭偺僷儕傗僶儖僙儘僫偺奨傪塮偡僇儊儔偵怱庝偐傟傞丅廔斦偺愴摤僔乕儞偼嬞敆姶偵寚偗傞丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐39丂尨愡巕偺愴慜嶌偲埌愳偄偯傒偺弶婜嶌
1939丂孎扟媣屨丂昡揰乵D乶
戞2師忋奀帠曄偺擔杮孯偺愴偄傪僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵昤偄偨丄奀孯徣屻墖崙嶔塮夋丅巗奨愴偺昤幨偼敆椡偁傞偑丄拞崙孯偺摦偒偼傑偭偨偔塮偟弌偝傟偢丄敆恀惈偵寚偗傞偟丄榐壒偑埆偔偰傛偔挳偒庢傟側偄丅戉挿栶偵戝擔岦揱丄嵟弶偼擔杮孯傪憺傫偱偄傞偑恊愗偵傎偩偝傟偰怱傪擖傟懼偊傞拞崙柡傪尨愡巕偑墘偠傞丅尨偑墭傟栶傪傗傞偺偼偍偦傜偔弶傔偰偩傠偆丅栰惈揑側彮彈傪墘偠傞19嵨偺尨偼擔杮恖棧傟偟偨晽杄偱側偐側偐偺枺椡丅
偟偁傢偣偼偳偙偵
1956丂惣壨崕屓丂昡揰乵C (A) 乶
愴憟偱椉恊傪朣偔偟偨敄岾偺庒偄彈惈偑偨偳傞塣柦傪昤偄偨捠懎儊儘僪儔儅丅庡墘偺埌愳偄偯傒偼摉帪21嵨丄庡墘偼偙偺塮夋偑弶傔偰偱偼側偄偩傠偆偐丄偟偲傗偐偱惔慯丄偲偵偐偔壜垽偄丅憡庤栶偺梩嶳椙擇傕偙偺偙傠偼憠偣偰偍傝丄岲惵擭偵塮偭偰偄傞丅怓杺偺夛幮摨椈偵杍偑朿傜傓慜偺幊屗忶丄埌愳偑摨嫃偟偰偄偨壠偺埆鐓側廸晝偵揳嶳懽巌丅埌愳偼丄嬻廝偱巰傫偩偲暦偐偝傟偰偄偨曣偑惗偒偰偍傝丄夁偪偵傛傞嶦恖嵾偱孻柋強偵擖偭偰偄偨偙偲傪抦傞丅愴屻11擭丄傑偩愴憟偺塭偑擹偄丅埌愳偑柋傔傞搶嫗偺夛幮傗奨妏偼搒夛晽偱愻楙偝傟偰偄傞偑丄廧傫偱偄偨墶昹偺壠偺嬤曈偵偼愴屻偺峳攑偑巆偭偰偄傞丅嵟屻偵2恖偼寢偽傟偰僴僢僺乕丒僄儞僪丅塮夋偲偟偰偼C偩偑丄埌愳偄偯傒偵峣傞偲昡壙偼A丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐38丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺6
1932丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C+乶
僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺慶宆揑塮夋偱偁傝丄埲慜丄塸岅帤枊斉偱尒偰揥奐偑傛偔暘偐傜側偐偭偨偺偱丄擔杮岅帤枊斉偱嵞尒偟偨偑丄傗偼傝暘偐傜側偐偭偨丅尰峴斉偼僆儕僕僫儖斉偐傜偐側傝僇僢僩偝傟偰偄傞傛偆偩丅僩乕僉乕弶婜晽偱僒僀儗儞僩偺柤巆傝偑擹偄傛偆偵姶偠傞丅儊僌儗寈帇栶偵僺僄乕儖丒儖僲儚乕儖丅慜敿偼偁傑傝摦偒偑側偄偑丄屻敿丄搨撍偵偵帠懺偑摦偒丄斊恖僌儖乕僾偼偁偭偝傝戇曔偝傟偰帠審偼夝寛偡傞丅撲傔偄偨僔儑僢僩丄堄枴偁傝偘側僔儑僢僩偑昿斏偵憓擖偝傟傞丅揥奐偼娫墑傃偟偰偍傝丄嬝偺棳傟偑捦傔側偄丅暤埻婥偩偗傪廳帇偟偰嶌傜傟偨傛偆側報徾偱偁傝丄偦偺揰偱偼乽3偮悢偊傠乿傪憐婲偝偣傞偑丄偦偙偱偼儅乕儘僂偑峴摦偟偰偄偨丅偙偙偱偺儊僌儗偼壗傕峴摦偟側偄丅BGM偼側偔丄壒妝偲偄偊偽搊応恖暔偑墘憈偡傞傾僐乕僨傿僆儞傗偐偗傞儗僐乕僪偺傒丅彥晈償傿僫丒償傿儞僼儕乕僨偑墣傔偐偟偔丄儊僌儗偵嫻偺彎傪尒偣丄娽慜偱拝懼偊偡傞僔乕儞偼僄儘僥傿僢僋偩丅柖偵墝傞梉曢傟偺幵摴丄怺栭偺僇乕僠僃僀僗偑報徾偵巆傞丅
僔儑僞乕儖彜夛
1933丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C乶
抧曽搒巗偺怘昳壍栤壆傪晳戜偵偟偨僐儊僨傿丅栤壆偺幮挿偼巇帠傪庤揱偆偲偄偆忦審偱傂偲傝柡傪帊恖偺抝偲寢崶偝偣傞偑丄帊恖偼偢傏傜偱巇帠偱偒側偄丅搟偭偨幮挿偼斵傪壠偐傜捛偄弌偡丅偩偑帊恖偑僑儞僋乕儖徿傪庴徿偟偨偺偱峇偰偰楢傟栠偡丅偦偺屻丄帊恖偼嶌昳傪彂偗側偔側傞偑丄栤壆偺巇帠偵榬傪敪婗偟丄堦曽偺幮挿偼暥妛偵栚妎傔傞偲偄偆旂擏側寢枛丅墱峴偒傪姶偠偝偣傞憢墇偟偺僔儑僢僩偑懡偄丅朻摢偺3暘傎偳偺僔乕僋僄儞僗乗乗僇儊儔偼嵟弶偵僞僀僩儖偺娕斅傪塮偟丄奜偐傜巇帠応偺側偐偵擖偭偨偁偲丄帺戭偺怘戩偵嵗傞幮挿傪憢墇偟偵嶣傞乗乗傗丄偦偺屻偺晳摜夛偺僔乕儞偱偺丄棳傟傞傛偆偵堏摦偡傞僇儊儔偑報徾揑丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐37丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺5
1959丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C乶
埲慜丄偁傑傝偵攏幁攏幁偟偄偺偱拞抐偟偨塮夋丄崱夞傛偆傗偔帇挳傪姰椆偟偨丅僙僢僋僗偲尪憐傪媗傔崬傫偩戝傜偐側僪僞僶僞婌寑丅億乕儖丒儉乕儕僗偺墷廈楢崌戝摑椞傪栚巜偡惗暔妛幰丄僇僩儕乕僰丒儖乕償僃儖偺栰惈揑側擾壠偺柡丄偄偢傟傕岲墘丅撿暓偺梲岝崀傝拲偖怷偲嶳偲愳偑旤偟偔丄儖僲儚乕儖揑側悈偺僀儊乕僕偑墶堨偟偰偄傞丅嶳梤傪楢傟偨栮偝傫偑墶揓傪悂偔偲丄撍晽偑悂偒峳傟丄恖乆偺惈徴摦傪桿敪偡傞丅彈惈婍傪楢憐偝偣傞栘乆偑塮偟弌偝傟傞僔乕儞偼堹阹偺嬌傒偩丅恖岺庼惛傪採彞偟丄垽偺峴堊偼梷惂偡傋偟偲庡挘偡傞惗暔妛幰偑擾壠偺柡偲僙僢僋僗偵抆傝丄巕嫙偑弌棃偱寢崶偡傞偲偄偆旂擏側寢枛丅
曔偊傜傟偨屴挿
1961丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C乶
偙傟偑儖僲儚乕儖偺堚嶌丅偙偙偵偼傕偼傗悈偺僀儊乕僕傕憢墇偟偺僔儑僢僩傕側偄丅僪僀僣偺廂梕強偵曔偊傜傟偨屴挿僕儍儞僺僄乕儖丒僇僢僙儖偑壗搙傕扙憱傪婇偰丄悑偵惉岟偡傞傑偱偑昤偐傟傞丅乽戝偄側傞尪塭乿偲傛偔帡偨嬝棫偰偩偑丄偙傟偼戞2師戝愴偱偁傝丄傕偼傗婻巑摴惛恄偼側偔丄奒媺堄幆傕晄慛柧偩丅偩偑丄庡恖岞偵堦弿偵摝朣偟傛偆偲桿傢傟傞擾柉偺暫巑偑丄乽偙偙偵偼奒媺傕恎暘傕側偔丄傒傫側偑桭偩偪偱拠娫偩丅僷儕偵栠偭偨傜姷廗偲偟偒偨傝偵巟攝偝傟丄偦傫側娭學偑幐傢傟傞乿偲尵偭偰嫅斲偡傞偲偙傠偵丄奒媺幮夛偺尰幚偑丄偦偟偰乽戝偄側傞尪塭乿偺僥乕儅偑晜偐傃忋偑傞丅廔斦丄摝朣偡傞2恖偑忔傞楍幵偺僐儞僷乕僩儊儞僩偵鑿擖偡傞悓偭暐偄丄偦偺偁偲偵弌偰偔傞崙嫬嬤偔偺擾晇偼儖僲儚乕儖帺恎偺搳塭偱偁傠偆偐丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐36丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺4
1937丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵B乶
嵞尒丅弶尒偼戝妛偺偲偒偩偭偨偲巚偆丅偙傟偼斀愴塮夋偲尵傢傟傞偑丄杮幙揑偵偼棟憐庡媊揑側僸儏乕儅僯僘儉塮夋偩丅庡恖岞偺拞堁偑僕儍儞丒僊儍僶儞丄曔椄拠娫偺戝堁偑僺僄乕儖丒僼儗僱乕丄曔椄廂梕強挿偺僪僀僣孯戝堁偑僄乕儕僸丒僼僅儞丒僔儏僩儘僴僀儉丅儖僲儚乕儖偼儕傾儕僘儉偵揙偟偰昤偄偨偲尵偭偰偄傞偑丄堖憰傗僙僢僩偼偦偆偩偲偟偰傕丄廂梕強偱偺懸嬾偑偙傟傎偳楃媀偵岤偄傕偺偩偲偼巚偊側偄丅戞1師戝愴偲偼偄偊丄曔椄偲廂梕強挿偺婱懓摨巑偺婻巑摴惛恄偵晉傫偩桭忣偑寢偽傟傞偙偲側偳丄尰幚偵偼偁傝偊側偄偩傠偆丅拠娫偺曔椄傪摝偑偡偨傔幩嶦偝傟傞戝堁偺峴摦傕儕傾儕僥傿偵寚偗傞丅偲偼偄偊丄榖弍偼岻傒偱棳傟偵傛偳傒偼側偄丅嬣尩幚捈偱婻巑摴傪廳傫偠傞僪僀僣孯恖栶偺僔儏僩儘僴僀儉偑尒帠丅扙憱偟偨僊儍僶儞偲僪僀僣偺彫懞偺壡晈偲偺懇偺娫偺楒垽偼垼愗姶昚偆丅悘強偵昞傟傞憢墇偟偺僔儑僢僩偑墱峴偒傪姶偠偝偣傞丅儖僲儚乕儖撈摿偺嬻娫張棟偩丅儖僲儚乕儖偺塮夋偱偼僔儑僂偺僗僥乕僕偑憓擖偝傟傞傕偺偑懡偄偑丄偙偙偱傕廂梕強撪偱曔椄偨偪偑墘偠傞壧傗梮傝偑斺業偝傟傞丅乽尪塭乿偲偼壗偐丅楯摥幰奒媺偺僊儍僶儞偲婱懓奒媺偺戝堁偼愴憟偑側偗傟偽桭忣傪堢傓偙偲偼側偐偭偨丅堦弿偵扙弌偡傞嬥帩偪偺儐僟儎恖偲偺桭忣傕偦偆偩丅僪僀僣恖偺壡晈偲傕愴憟偑側偗傟偽楒偵棊偪傞偙偲偼側偐偭偨偩傠偆丅愴憟偑尪塭傪惗偠偝偣偨丅偄偭傐偆婱懓奒媺摨巑偺僼儗僱乕偲僔儏僩儘僴僀儉偼愴憟偑側偔偰傕怱偑捠偠崌偆丅偦傕偦傕僼儔儞僗偺婱懓奒媺偼僎儖儅儞恖乮僼儔儞僋恖乯偱偁傝丄僪僀僣婱懓偲摨偠寣嬝偩丅偦傫側娫暱側偺偵丄僔儏僩儘僴僀儉偑怱側傜偢傕僼儗僱乕傪幩嶦偡傞偲偄偆旂擏丅偙傟傕愴憟偑惗傒弌偡尪塭側偺偐丅
僎乕儉偺婯懃
1939丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C乶
埲慜丄墑乆偲懕偔楒垽梀媃偵朞偒朞偒偟偰尒傞偺傪拞抐偟偨塮夋丅崱夞傛偆傗偔嵟屻傑偱尒偨丅柤嶌偲偺悽昡崅偄偑丄偳偙偑偄偄偺偐暘偐傜側偄丅忋棳奒媺偺晇晈偺嬱偗堷偒丄抝彈偺晜婥傗怓楒嵐懣偑丄婌寑僞僢僠偱晽巋晽偵昤偐傟傞丅娔撀偺儖僲儚乕儖杮恖偑嫸尵夞偟揑側栶偱弌墘丅僶儘僢僋壒妝偺傛偆偵嶣偭偨偲儖僲儚乕儖偼尵偭偨偦偆偩偑丄偨偟偐偵懡偔偺搊応恖暔偺怐傝惉偡僀儞儌儔儖側楒偺憶摦傪捛偄偐偗傞僇儊儔偼丄僶儘僢僋壒妝傪巚傢偣側偄偱傕側偄丅僫僠僗偲偺愴憟偵孹偄偰偄偔側偐偱丄尰幚傪捈帇偟傛偆偲偟側偄帪戙晽挭傪斸敾偟偨偲尵傢傟傞偑丄壥偨偟偰偦偆側偺偐丅僫僠僗丒僪僀僣偺僼儔儞僗怤峌偼1940擭丅39擭偺塮夋惢嶌帪揰偵偍偄偰暓撈偑奐愴偟偰偄偨偐偳偆偐偼暘偐傜側偄偑丄摉帪丄僫僠僗偺嫼埿偑娫嬤偵敆偭偰偄偨偙偲偼妋偐偩丅偩偑丄偙傟偼楒垽僎乕儉偵柧偗曢傟傞婱懓傗巊梡恖傪媃夋壔偟偨偩偗偺塮夋偲偟偐尒偊偢丄敆傝棃傞斶寑偺梊挍側偳偲偄偆愢偼丄屻偐傜偺偙偠偮偗偵夁偓側偄傛偆偵巚偊傞丅偲偼偄偊丄庪傝偺僔乕儞偱塮偟弌偝傟傞柍巆偵嶦偝傟偨僂僒僊傗僉僕丄僷乕僥傿偑廔傢偭偨偁偲偺惷偗偝偲柍忢姶偼丄壗偐傪姶偠偝偣側偄偱傕側偄丅拞忦徣暯偵傛傞偲丄乻乽偙偺悽奅偵嫲傠偟偄偙偲偑傂偲偮偁傞丅偦傟偼丄偡傋偰偺恖娫偺尵偄傇傫偑惓偟偄偲偄偆偙偲偩乿偲偄偆乽塮夋巎偵巆傞柤僙儕僼乿偑丄偙偺恖娫婌寑偺乽尨棟乿偲側偭偰偍傝丄乽偩傟傕偑惓偟偄偲偄偆偙偲偼丄偩傟傕偑惓偟偔側偄偲偄偆偙偲丅慞偲埆偑億僕偲僱僈偺傛偆偵斀揮偟偁偄側偑傜丄僪儔儅偼怐傝側偝傟偰備偒傑偡乼偲偺偙偲偩偑丄偦傫側偙偲偼傑偭偨偔姶偠庢傞偙偲偑偱偒側偄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐35丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺3
1938丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C乶
1789擭偺僶僗僠乕儐廝寕偐傜妚柦孯偺墹媨愯嫆丄1792擭偺僾儘僔儍偲偺愴偄偵帄傞僼儔儞僗妚柦傪丄儅儖僙乕僰偺媊桬孯偵嶲壛偟偨庒幰偺峴摦傪拞怱偵昤偔丅崙壧儔丒儅儖僙僀僄乕僘偑柉廜偵峀傑傞僄僺僜乕僪偑揧偊傜傟傞丅慡懱偵昤偒曽偑偸傞偄乗乗偦傟偑儖僲儚乕儖偺帩偪枴偩偲尵偊偽偦傟傑偱偩偑丅儖僀16悽偵僺僄乕儖丒儖僲儚乕儖丄妚柦孯偺儕乕僟乕偵儖僀丒僕儏乕償僃偑弌墘丅悽娫偺摦棎傪傛偦偵丄晳摜傗旤怘偵傆偗傞墹懓傗婱懓偺昤幨偼偝偡偑偵岻偄丅僫僠僗戜摢偵旛偊丄崙柉偺抍寢傪懀偡偺傪偹傜偭偰嶌傜傟偨偲尵傢傟傟偽擺摼偱偒傞丅
帺桼傊偺愴偄
1943丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵D乶
儖僲儚乕儖偺傾儊儕僇朣柦帪戙偺堦嶌丅僫僠僗愯椞壓偺僼儔儞僗偺彫偝側挰偱偺儗僕僗僞儞僗傪昤偄偨塮夋丅妛峑嫵巘偺僠儍乕儖僘丒儘乕僩儞偑庡墘丄椬偵廧傓摨椈嫵巘偵儌乕儕儞丒僆僴儔丅尰忬捛擣偟偰僫僠僗偵嫤椡偡傞幚嬈壠偵僕儑乕僕丒僒儞僟乕僗丅彫怱幰偺儘乕僩儞偼嵟屻偵掞峈庡媊偵栚妎傔丄嵸敾偱帺桼偲桬婥偺戝愗偝傪挿乆偲墘愢偡傞丅偙偺偁偨傝偼僠儍僢僾儕儞偺乽撈嵸幰乿傪巚傢偣傞丅慡懱偵恾幃揑丄嫵忦庡媊揑偱丄嵟屻偺儘乕僩儞偲僆僴儔偑巕嫙偨偪偵恖尃愰尵傪撉傒暦偐偣傞僔乕儞側偳偼丄偁傑傝偵偁偞偲偄丅儖僲儚乕儖偑巚偄偳偍傝偵嶣傟側偐偭偨偙偲傪姩埬偟偰傕丄弌棃偼傛偔側偄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐34丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺2
1933丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵C乶
僼儘儀乕儖尨嶌偺丄梸媮晄枮偺揷幧堛幰偺嵢偑晄椣偲楺旓傪廳偹偨枛偵恎傪柵傏偡偲偄偆榖丅晇偺僺僄乕儖丒儖僲儚乕儖偼揔栶偩偑丄晇恖偺償傽儔儞僥傿乕僰丒僥僔僄偼偁傑傝枺椡揑偵尒偊偢丄傒傫側偑崨傟傞傎偳偺旤彈偲偼巚偊側偄偺偱嫽偑嶍偑傟傞丅偳偆傕儖僲儚乕儖偼彈偺庯枴偑椙偔側偄傛偆偩丅慜敿丄偄傗偵抁偄僔乕僋僄儞僗偱娙寜偵恑峴偡傞偲巚偭偰偄偨偑丄埬偺掕丄傕偲偼3帪娫傎偳偺挿偝偩偭偨偑丄儖僲儚乕儖偺堄巙偵斀偟偰僇僢僩偝傟丄1帪娫40暘偵抁弅偝傟偨偺偩偲偄偆丅偲偼偄偊丄僗僩乕儕乕偺棳傟偼僗儉乕僘偱丄憢墇偟偵拞偐傜奜傪丄奜偐傜拞傪塮偡僇儊儔偼報徾怺偔丄撈摿偺墱峴偒傪姶偠偝偣傞丅忔攏偵傛傞怷偱偺晇恖偲岲怓婱懓偲偺枾夛僔乕儞偼姱擻揑偱僄儘僥傿僔僘儉偑擋偆丅岞徹恖偺庒幰偲偺忣帠偺僔乕儞偱偼攏幵偑巊傢傟傞丅彈偑庤巻傪偪偓偭偰憢偐傜搳偘幪偰傞偺偑報徾揑丅椉曽偺僔乕儞偵攏偑弌偰偔傞偺偼嬼慠偱偼側偄偩傠偆丅
僩僯
1935丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵D乶
撿暓偵傗偭偰棃偨弌壱偓楯摥幰偑丄廻壆傪塩傓彈偲寢崶偡傞偑丄埲慜偐傜岲偒偩偭偨偺偵懠恖偺嵢偵側偭偨彈偺偙偲偑朰傟傜傟偢丄攋嬊傪寎偊傞偲偄偆榖丅儖僲儚乕儖偺塮夋偼傎偲傫偳偑彈偺晄椣偺榖偩偑丄偙偙偱偼捒偟偔抝偑晄椣偡傞丅偺偪偺帪戙偺僀僞儕傾丒僱僆儗傾儕僗儌塮夋傪巚傢偣傞偑丄帒杮壠偲楯摥幰偺懳棫偲偄偭偨傛偆側幮夛揑側娤揰偼側偔丄抝彈偺怓楒偵峣傜傟偰偄傞丅奀偵晜偐傇彫廙傗揝嫶傪憱傞抝偺傛偆側報徾偵巆傞僔乕儞偑偁傝丄抝偑朓偵巋偝傟偨彈偺恓傪庢傞偨傔攚拞傪鋜傔傞僔乕儞側偳傕姱擻揑偩偑丄慡懱偵抧枴側報徾丅楍幵偵忔偭偰傗偭偰棃傞楯摥幰偨偪偺僔乕儞偱巒傑傝丄暿偺楯摥幰偨偪偑傗偭偰棃傞摨偠傛偆側僔乕儞偱廔傢傞丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐33丂儖僲儚乕儖偺枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺1
1932丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵B+乶
偙偆偄偆戝傜偐偱帺桼鑸払側嶌昳傪偳偆昡壙偟偨傜偄偄偺偩傠偆丅僙乕僰愳偵恎搳偘偟偨晜楺幰傪屆杮壆偺揦庡偑彆偗偰帺戭偵嫃岓偝偣傞偲丄晜楺幰偼偁傑傝偵懜戝偱朤庒柍恖丄姶幱傕偣偢偵嫃嵗傝丄屆杮壆偺惗妶傪堷偭偐偒夞偟丄揦庡偺嵢傪怮庢傝丄垽恖偺庒偄儊僀僪偲傕偹傫偛傠偵側傝丄偗偭偒傚偔儊僀僪偲寢崶偡傞偑丄幃偺摉擔丄儃乕僩偑揮暍丄峴曽晄柧偵側偭偨晜楺幰偼愳壓偱娸偵忋偑偭偰僇僇僔偺暈偵拝懼偊丄偳偙偐偵桰慠偲曕傒嫀傞丅嵟屻偼乽偳傫掙乿偺儔僗僩丒僔乕儞傪巚傢偣傞丅傗傝偨偄曻戣偺晜楺幰偺帺桼側怳傞晳偄偲丄屆彂揦庡傗嬤椬廧柉偺恖偺椙偝偑嵺棫偭偰偄傞丅僙乕僰娸曈偺儘働偱丄嫶偵孮偑傞尒暔恖偑報徾怺偄丅慡懱偵悈偺僀儊乕僕偑朙忰偩丅庡墘偺儈僔僃儖丒僔儌儞偼埳摗梇擵彆傪憐婲偝偣傞丅
柲將乮塸岅帤枊斉乯
1931丂僕儍儞丒儖僲儚乕儖丂昡揰乵B+乶
儔儞僌乽旉怓偺奨乿偺僆儕僕僫儖丅乽偙傟偼幮夛寑偱偡乗乗偙傟偼斶寑偱偡乗乗偳偪傜偱傕側偄丄奆偝傫偲摨偠垼傟側恖娫偺榖偱偡乿偲偄偆恖宍幣嫃偺慜岥忋偱巒傑傝丄摨偠恖宍幣嫃偺憢榞偺側偐丄晜楺幰偺2恖偑嫀偭偰峴偔僔乕儞偱廔傢傞偲偄偆寢峔偑丄偄偐偵傕儖僲儚乕儖傜偟偄丅偦偙偐偟偙偱塮偟弌偝傟傞丄憢墇偟丄僪傾墇偟偵偵懆偊傜傟偨忣宨偑丄儖僲儚乕儖揑側塮夋嬻娫傪姶偠偝偣傞丅徣棯偺媄朄偑嶀偊偰偍傝丄朻摢娫傕側偔丄庡恖岞偑彈傪彆偗偰壠偵憲偭偰偄偒丄帺戭偵婣偭偰彈朳偵攍搢偝傟傞偲丄師偺僔乕儞偱偼偡偱偵彈偲楒拠偵側偭偰偄傞偟丄彈偺嶦奞傪捈愙揑偵偼塮偝偢丄嶦奞屻偺岝宨傪憢墇偟偵嶣傞僔儑僢僩偼偲傝傢偗慺惏傜偟偄丅偙偺嶦奞僔乕僋僄儞僗偱偺丄楬忋偺僗僩儕乕僩丒儈儏乕僕僔儍儞偺墘憈偵恖乆偑孮偑傞僔儑僢僩偲傾僷乕僩奒忋偺嶦奞晹壆偺僔儑僢僩傪岎屳偵塮偡庤朄偼丄偺偪偵僼傿儖儉丒僲儚乕儖偱丄斊恖偺愨朷揑側僔儑僢僩偲堦斒巗柉偺暯榓側僔儑僢僩偺僋儘僗僇僢僥傿儞僌偲偟偰懡梡偝傟偨丅乽柲將乿偺婎杮揑側榖偺棳傟偼乽旉怓偺奨乿偲摨偠偩偑丄儁僔儈僘儉偲愨朷姶偵枮偪偨乽旉怓偺奨乿偲戝傜偐偱妝揤揑側乽柲將乿偺懳徠揑側僄儞僨傿儞僌偵丄儔儞僌偲儖僲儚乕儖偺帒幙偲昞尰僗僞僀儖偺堘偄偑昞傟偰偄傞丅偳偪傜偑桪傟偰偄傞偲偐楎偭偰偄傞偲偐偄偆栤戣偱偼側偄丅偳偪傜傕恀幚側偺偩丅庡墘偺儈僔僃儖丒僔儌儞偼揔栶偩偑丄僼傽儉丒僼傽僞乕儖傪墘偠傞僕儍僯乕丒儅儗乕僘偼懢傔偺偍偽偝傫婄偱丄恎傕怱傕擖傟崬傓傎偳偺彈偵偼尒偊側偄偺偑擄揰丅偦偺揰丄僕儑乕儞丒儀僱僢僩側傜抝偑偲傝偙偵側傞偺傕擺摼偱偒傞丅儔僗僩偱丄恖宍寑偺憢榞偺側偐丄乽恖惗偼旤偟偄乿偲尵偄側偑傜嫀偭偰峴偔儈僔僃儖丒僔儌儞偼丄偦偺屻傑傕側偔丄僙乕僰愳偵旘傃崬傒丄彆偗傜傟偨屆杮壆偺庡恖偺壠掚傪堷偭偐偒夞偡丅乽慺惏傜偟偒曻楺幰乿偼乽柲將乿偺屻擔択側偺偩丄
2020擭5寧朸擔 旛朰榐32丂惉悾枻婌抝偺愴慜枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺3
1935丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵B乶
乽嵢錕錘乿偵懕偔惉悾偺僩乕僉乕4嶌栚丅揷幧偺挰偱憳嬾偟偨5恖慻偺妝戉偲嬋攏抍偺巓枀偺岎棳傪拞怱偲偟偨僗僩乕儕乕丅僗働儀抝偺摗尨姌懌丄償傽僀僆儕儞憈幰傪柌尒傞恀柺栚側戝愳暯敧榊丄偲傏偗偨枴傢偄偺屼嫶岞側偳丄偍撻愼傒偺婄傇傟丅巓枀偼乽壋彈怱乿偲摨偠攝栶丅偺傫傃傝偟偨揷幧偺晽宨丄儐乕儌傾偲垼姶偑側偄傑偤偲側偭偨枴傢偄偼丄側偐側偐椙偄丅妝戉偑挰傪楙傝曕偔僔乕儞側偳偼乽椃栶幰乿傪巚傢偣傞丅戝愳偲嬋攏抍偺巓偑懇偺娫偺憳嬾偱怱傪捠傢偣崌偆僄僺僜乕僪偑忣姶傪桿偆丅抝彈偺岅傝丄巓枀偺岅傝偺僔乕儞偵偼屻擭姰惉偡傞惉悾僗僞僀儖偺朑夎偑尒傜傟傞丅儔僗僩丒僔乕儞丄恀壞偺梲岝偺拞丄奀娸増偄偵曕偒嫀傞5恖僾儔僗1恖偺屻傠巔偑旤偟偄丅
側偮偐偟偺婄
1941丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵B乶
愴帪怓偑嫮偄30暘嫮偺抁曇塮夋偩偑丄偄偐偵傕惉悾傜偟偄弌棃塰偊丅擾壠偺壟偱晇偑弌惇拞偺壴堜棖巕偑庡墘丅側偐側偐偒傟偄偩丅弌墘幰偼傒側梷偊偨墘媄偱岲墘偟偰偄傞丅揷幧偺懞偱偼暫戉偑峴孯楙廗傗孯帠孭楙傪偟偰偍傝丄嬻偱偼旘峴婡偑旘傃丄僯儏乕僗塮夋偱愴抧偱愴偆擔杮孯偑塮偟弌偝傟傞丅偩偑惗妶偼偺傫傃傝偟偰偍傝丄偺偳偐側揷傫傏偱擾晈偑嶌嬈偟偰偄傞丅偦傫側擾壠偺擔忢偑偨傫偨傫偲昤偐傟傞丅撪梕偼丄弌惇拞偺挿抝偑僯儏乕僗塮夋偵塮偭偰偄偨偲暦偄偰丄曣恊偲壟偑偐傢傝偽傫偙偵挰偺塮夋娰偵尒偵峴偔偲偄偆榖偱丄傎偲傫偳壗傕婲偙傜側偄偑丄尒偰偄傞偲怱偑壏傑傞丅彮擭偑栘偐傜棊偪偰夦変傪偡傞偑丄抦傜偣傪暦偄偰曣恊偑嬱偗弌偡偲丄師偺僔乕儞偱偼壠偱彮擭偑怮偰偍傝丄寉偔偰椙偐偭偨偹偲巓偑榖偟偐偗偰偄傞偲偄偆戝抇側徣棯偼惉悾側傜偱偼丅僔儑僢僩偺偮側偓傕煭棊偰偍傝丄梀傃怱偑姶偠傜傟傞丅儔僗僩嬤偔偱彮擭偑懌傪堷偒偢傝側偑傜柾宆旘峴婡傪帩偭偰曕偔僔乕儞偼丄乽廐棫偪偸乿偺僇僽僩儉僔傪帩偮彮擭丄乽傑偛偙傠乿偺僼儔儞僗恖宍傪帩偮彮彈偺摨偠傛偆側曕峴僔乕儞偲廳側傞丅
桖偟偒嵠恖惗
1944丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵C乶
晄巚媍側塮夋偩丅惉悾嶌昳偺側偐偱傕傕偭偲傕晽曄傢傝側塮夋偩傠偆丅撲偺堦壠偑挰偵堷偭墇偟偰偒偰惗偒傞婌傃偲岾偣傪傕偨傜偟偰嫀偭偰峴偔偲偄偆僼傽儞僞僕乕晽偺撪梕丅僩儞僇僠偺壒偵崌傢偣偰柡偑壧偄弌偟偨傝丄塉偺悈偨傑傝偺僔乕儞偵僟儞僗偺崌惉塮憸偑憓擖偝傟偨傝偲丄儈儏乕僕僇儖晽偺庯岦傕嬅傜偝傟偰偄傞乗乗壧傗僟儞僗偼妛寍夛晽偺弌棃偩偑丅揷幧偺挰偵撍晽偑悂偔偲壸幵偵忔偭偰傛傠偢壆堦壠偑尰傟傞偲偄偆弌偩偟偐傜偟偰偍偲偓榖晽偩丅彴壆丄栻壆丄帪寁壆側偳偺挰偺廧柉偺昤偒曽傕柺敀偄丅撲偺堦壠偺晝恊偺桍壠嬥岅極丄柡偺嶳崻庻巕偲拞懞儊僀僐乮巕栶帪戙偺儊僀僐丄嵟屻偵攝栶傪尒偰暘偐偭偨乯偼丄挰偺恖乆偵丄嬯偟偔偰傕昻偟偔偰傕丄岺晇偲峫偊曽偟偩偄偱恖惗偼妝偟偔側傞丄偲嫵偊丄斵傜偼偟偩偄偵撲偺堦壠偺尵摦偵姶壔偝傟傞丅愴帪壓偺丄梸偟偑傝傑偣傫彑偮傑偱偼丄偲偄偆曽恓偵増偭偰嶌傜傟偨傕偺偩傠偆丅彫愳傗栰尨傪塮偡僇儊儔偺廮傜偐側帇慄偑椙偄丅偙傟偱愴慜偺惉悾偺僩乕僉乕嶌昳偼偤傫傇尒廔傢偭偨偙偲偵側傞丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐32丂惉悾枻婌抝偺愴慜枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺2
1937丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵C乶
悽昡偼掅偄偑丄弌棃偼偦傟傎偳埆偔側偄丅庡墘偺擖峕偨偐巕偼偄偮傕偺傛偆偵懴偊擡傇栶丅戝妛傪懖嬈偟偰奜岎姱偵側傞梊掕偺崅揷柅偵偼寢崶傪栺懇偟偨楒恖擖峕偨偐巕偑偄偨偑丄彜攧偺晧嵚傪書偊傞揷幧偺幚壠偐傜丄帩嶲嬥栚摉偰偱嬥帩偪偺柡抾媣愮宐巕偲偺寢崶傪嫮梫偝傟丄尒崌偄偩偗偡傞偮傕傝偱婣徣偡傞偑丄妶敪偱姶偠偺偄偄偦偺柡偑岲偒偵側傝丄擖峕傪幪偰偰斵彈偲寢崶偡傞丅擖峕偼恎偛傕偭偰偍傝丄壠傪弌偰帺椡偱巕嫙傪嶻傫偱崅揷偵暅廞偟傛偆偲寛怱偡傞傑偱偑慜曆丅擖峕丄抾媣丄擖峕偺恊桭埀弶柌巕偺庡梫搊応彈惈偼傒側慞恖偱巚偄傗傝偑偁傞丅崅揷傕椙怱偺欒愑偵擸傓恀柺栚側抝丅埆栶偼崅揷偺晝恊偲擖峕偺晝恊偱丄旕恖忣偱恎彑庤側栶偳偙傠丅偲偙傠偳偙傠偵僙儞僗偺偁傞柺敀偄僔儑僢僩偺宷偓偑偁傞偟丄抝偲彈丄傑偨偼彈偳偆偟偱嶶曕偟側偑傜夛榖偡傞僔乕儞偵傕惉悾傜偟偝偑姶偠傜傟傞丅栰媴傪娤愴偡傞僔乕儞偑憓擖偝傟傞偺偼捒偟偄丅慡懱偵埫偄儊儘僪儔儅挷偩偑丄儔僗僩丄曐堢墍偵柋傔偰徫婄偱巕嫙偨偪偺悽榖傪偡傞擖峕偺僔乕儞偱僄儞僪偲側傝丄婓朷偺岝偑嵎偟崬傓偺偱媬傢傟傞巚偄偑偡傞丅
嶰廫嶰娫摪捠偟栴暔岅
1945丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵C+乶
惉悾弶偺帪戙寑偱丄僠儍儞僶儔丒僔乕儞傕偁傞偑丄撪梕偼寍摴傕偺偵嬤偄丅捠偟栴偺婰榐曐帩幰偺婰榐偵挧傫偩偑幐攕偟偰帺奞偟偨晝偺崷傒傪惏傜偡偨傔丄懅巕偺庒幰偼晝偵壎傪庴偗偨彈彨偑塩傓廻壆偵廧傫偱媩偺宮屆偵椼傓偑丄側偐側偐忋払偟側偄丅偦偙偵尒抦傜偸帢偑尰傟偰庒幰偲彈彨傪彆偗傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅幚榖偵懄偟偨榖傜偟偄丅懢暯梞愴憟枛婜偺45擭偵嶣塭丄岞奐偝傟偨偲偼怣偠傜傟側偄丄尒帠側僙僢僩丄偟偭偐傝偟偨墘弌偱偁傞丅庡墘偺挿扟愳堦晇偼晽奿偑偁傞偟丄揷拞對戙偺婤慠偲偟偨巔傕偄偄丅揷拞偼偙偆偄偆巗堜偺廻壆偺彈庡恖偺栶偑帡崌偭偰偄傞丅捠偟栴偵挧愴偡傞庒幰偼庛乆偟偔墘媄夁忚丅恖暔偺昤偒曽偼恾幃揑偩偑丄僔儑僢僩偺宷偓偵岺晇偑偁傞偟丄慡懱偺僥儞億傗棳傟傕埆偔側偄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐31丂惉悾枻婌抝偺愴慜枹尒塮夋傪惂攅偡傞乣偦偺1
1936丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵D乶
惉悾偺寍摴傕偺戞1嶌丅寧宍棿擵夘偑庡墘偟偨幚嵼偺楺嬋巘偺堦戙婰丅惉悾傜偟偝偼傎偲傫偳側偔丄僗僩乕儕乕傕偍慹枛偩偟丄寍偺偨傔偵偡傋偰傪媇惖偵偡傞撈傝傛偑傝偺庡恖岞偵姶忣堏擖偱偒側偄丅庒偒擔偺寧宍偼惛湜偩偑晄婥枴側晽杄丅彣偺寍幰丄愮梩憗抭巕偼傎偐偺塮夋傎偳偒傟偄偵尒偊偢丄枺椡偑側偄丅寧宍偺桭恖偲偟偰弌傞庒偒嶰搰夒晇偼憠偣偰偍傝丄嵟弶偼扤偐暘偐傜側偐偭偨丅
孨偲峴偔楬
1936丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵E乶
弌棃偼埆偄丅捒偟偔姍憅偺煭棊偨梞娰偵廧傓2恖偺孼掜乗乗戝愳暯敧榊偲嵅攲廏抝乗乗偑庡恖岞丅孼偺斶楒偑僥乕儅偱丄僗僩乕儕乕偵偼傑偭偨偔媬偄偑側偄丅斵傜偼僥僯僗傪傗偭偨傝儗僐乕僪傪挳偄偨傝偟偰桪夒側曢傜偟偩偑丄彣偺巕偲偄偆楎摍姶偵壵傑傟偰偄傞丅垽偡傞抝彈偑寢崶偱偒側偄偺傪偼偐側傫偱帺嶦偡傞偺偼柍棟側愝掕乗乗帺嶦偡傞僔乕儞傪姼偊偰塮偝側偄偺偼惉悾傜偟偄偑丅孅怞傪庴偗偰傕偡偖棫偪捈傞曣恊丄惔愳嬍巬偺偟偨偨偐偝偑柺敀偄丅
愥曵
1937丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵E乶
戝樑師榊尨嶌丅弌棃偼嵟埆偵嬤偄丅忋棳奒媺偺僒儔儕乕儅儞嵅攲廏抝偑峊偊傔側彈惈柖棫偺傏傞偲寢崶偡傞偑丄嵢偵朞偒懌傜偢丄嵢傪幪偰偰愄偺楒恖偲傛傝傪栠偦偆偲偟丄晝恊偵斀懳偝傟偰嵢傪嶦偦偆偲傑偱婇偰傞丄偲偄偆旕尰幚揑側榖丅嵅攲偼幚峴偡傞慜偵巚偄偲偳傑傞偑丄偦偺恎彑庤偝偼摨忣偺梋抧側偟丅嵅攲偺廧傑偄偼煭棊偨梞娰丄奜怘偼僼儔儞僗椏棟偲丄嬻嫊側梞晽庯枴偵枮偪偰偄傞丅戜帉偑娤擮揑偱寴嬯偟偔丄栶幰偼朹撉傒忬懺丅椙幆偁傞晝恊偲嵅攲偺夛榖偼傑偭偨偔旕擔忢揑偩丅偲偒偍傝夋柺偵幯偑偐偐偭偰撪柺偺儌僲儘乕僌偑尰傟傞偺偼嫽傪嶍偖偟丄廔傢傝曽傕搨撍偱晄帺慠丅偄偄偲偙傠側偟丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐30丂僩儕儏僼僅乕偵傛傞屻婜偺2嶌偲僨儏償傿償傿僄偺栤戣嶌
1980丂僼儔儞僜儚丒僩儕儏僼僅乕丂昡揰乵B乶
僫僠僗愯椞壓偺僷儕偱幣嫃傪忋墘偡傞恖乆傪昤偄偨丄僇僩儕乕僰丒僪僰乕償偺偨傔偺塮夋丅彈桪偺僪僰乕償偼丄僫僠偵捛傢傟偰抧壓偵塀傟傞庡嵣幰偺晇偵戙傢傝丄寑応傪愗傝惙傝偟偰偄傞丅儗僕僗僞儞僗丒僔儞僷偺攐桪偵僕僃儔乕儖丒僪僷儖僨儏乕丅37嵨偺僪僰乕償偼梕怓悐偊偰偍傜偢丄偒傟偄偩偑擻柺偺傛偆側昞忣偼庒偄偙傠偲曄傢傜側偄丅揱摑揑側僼儔儞僗塮夋偺儉乕僪偑墶堨偟偰偍傝丄僨傿僥乕儖偺昤幨偼岻偄丅廔斦偺娤媞傪閤偡梀傃怱傕岠壥揑偩丅幣嫃偺惢嶌夁掱偺昤偒曽偼乽傾儊儕僇偺栭乿傪巚傢偣傞丅僼儔儞僗偱戝僸僢僩偟偨偺偼暘偐傞偑丄偄偐偵傕巹偨偪偼僫僠僗偵掞峈偟傑偟偨偲尵偄偨偘側帺夋帺巀晽偺僗僩乕儕乕偼丄偄偝偝偐旲偵偮偔丅
擔梛擔偑懸偪墦偟偄
1983丂僼儔儞僜儚丒僩儕儏僼僅乕丂昡揰乵C乶
儌僲僋儘偱嶣傜傟偨僐儊僨傿丒僞僢僠偺儈僗僥儕乕丅僩儕儏僼僅乕偺堚嶌丅晄摦嶻壆偺揦堳僼傽僯乕丒傾儖僟儞偼丄嵢嶦恖偺梕媈幰偵側偭偨幮挿僕儍儞儖僀丒僩儔儞僥傿僯儍儞偺寵媈傪惏傜偡偨傔憑嵏偵忔傝弌偡丅僴儚乕僪丒儂乕僋僗偲僸僢僠僐僢僋傊偺僆儅乕僕儏偑墶堨偟偰偄傞丅傾儖僟儞偼偒傟偄偵嶣傟偰偍傝丄僉儍僒儕儞丒僿僢僾僶乕儞傪堄幆偟偨偺側傜惉岟偟偰偄傞丅僩儔儞僥傿僯儍儞偼偐側傝榁偗偨姶偠偩丅
僷僯僢僋
1946丂僕儏儕傾儞丒僨儏償傿償傿僄丂昡揰乵C+乶
暷崙偐傜僼儔儞僗偵栠偭偨僨儏償傿償傿僄偺戞1嶌丅埆彈償傿償傿傾儞僰丒儘儅儞僗偺媇惖偵側傞曄恖偺愯偄巘栶偵夦桪儈僔僃儖丒僔儌儞丅僷儕峹奜偺挰丄堏摦梀墍抧傪嶌傞峀応偺堦妏偱巰懱偑敪尒偝傟傞偺偑敪抂丅埆鐓側抝偑垽恖偺儘儅儞僗傪嵈偟丄儘儅儞僗偵岲堄傪婑偣傞僔儌儞傪閤偟偰丄帺暘偑斊偟偨嶦恖偺嵾傪側偡傝偮偗傞丅抝偑偽傜傑偄偨塡偑梮傜偝傟丄廤抍怱棟偱廧柉偺傒傫側偑柍幚偺恖娫傪捛偄媗傔傞晐偝丅僋儖乕僝乕偵傕偦傫側塮夋偑偁偭偨乗乗乽枾崘乿偩偭偨偐丅栭偺僔乕儞偺嶣塭偑堿塭偵晉傫偱偍傝丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺儉乕僪偑昚偭偰偄傞丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐29丂怱偵巆偭偨嵟嬤偺2杮偺塮夋
2018丂僩乕儅僗丒僗僥儏乕僶乕丂昡揰乵B乶
僪僀僣塮夋丅媽搶撈儔僀僾僣傿僸嬤峹偺嫄戝側僗乕僷乕儅乕働僢僩傪晳戜偵丄嵼屔娗棟學偲偟偰擖幮偟偨庒幰偲怑応偺恖乆丄斵偑楒怱傪書偔擭忋偺彈惈丄僼僅乕僋儕僼僩偺憖廲傪廗偆愭攜偺拞擭抝惈偲偺岎棳傪昤偔丅憅屔偱僼僅乕僋儕僼僩偑峴偒棃偡傞僶僢僋偱棳傟傞乽旤偟偔惵偒僪僫僂乿偼乽2001擭塅拡偺椃乿傪憐婲偝偣傞丅媽搶撈偺宱嵪奿嵎丄昻偟偝偺拞偱屒撈傪書偊側偑傜惗偒傞恖乆偑報徾偵巆傞丅
杔偨偪偺儔僗僩僗僥乕僕
2018丂僕儑儞丒俽丒儀傾乕僪丂昡揰乵B+乶
暷丒塸丒壛崌嶌丅僒僀儗儞僩帪戙偐傜40擭戙弶婜傑偱妶桇偟偨僐儊僨傿丒僐儞價丄儘乕儗儖仌僴乕僨傿偺斢擭偺塸崙僣傾乕傪昤偄偨揱婰塮夋丅擔杮偱偼嬌妝僐儞價偲偟偰抦傜傟傞丅庡墘偺2恖偺岲墘偑岝傞丅嬃偔偺偼斵傜偑杮暔偦偭偔傝側偙偲丅偙偺僐儞價偵拲偑傟傞惂嶌幰偺垽忣偺偙傕偭偨壏偐偄娽嵎偟偑怱傪懪偮丅抧枴偩偑垽偡傋偒壚昳丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐28丂僌乕儖僨傿儞僌偺庤榬偑岝傞40擭戙偺2嶌
1946丂僄僪儅儞僪丒僌乕儖僨傿儞僌丂昡揰乵C+乶
僒儅僙僢僩丒儌乕儉尨嶌偺暥寍儊儘僪儔儅丅帺暘傪扵偡惵擭偺渇渞偲丄斵傪垽偡傞偑崑壺側惗妶傕幪偰傞偙偲偑偱偒側偄彈偺暔岅丅僞僀儘儞丒僷儚乕偲僕乕儞丒僥傿傾僯乕庡墘丅棳傟傞傛偆偵堏摦偡傞僇儊儔儚乕僋偑報徾怺偄丅巆崜偱帺暘彑庤側彈傪墘偠傞僕乕儞丒僥傿傾僯乕偼偲偰傕旤偟偄偑丄偙偆偄偆僄儔偺挘偭偨杍崪偺崅偄婄偼岲傒偱偼側偄丅儌乕儉偵暞偡傞僴乕僶乕僩丒儅乕僔儍儖偺梋桾偺偁傞墘媄偑偄偄丅僗僲僢僽婥幙娵弌偟偺嬥帩偪僋儕僼僩儞丒僂僃僢僽傗丄岾偣側寢崶傪偟偨偑晇偲巕嫙偑帠屘偱巰傫偱楇棊偡傞僥傿傾僯乕偺桭恖傾儞丒僶僋僗僞乕側偳偺恖惗柾條傕昤偐傟傞丅
埆杺偺墲偔挰
1947丂僄僪儅儞僪丒僌乕儖僨傿儞僌丂昡揰乵B乶
堎怓僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅惉傝忋偑傠偆偲偡傞婏弍巘偺塰岝偲攋柵偺恖惗傪昤偔堿烼側塮夋丅庡墘偺僞僀儘儞丒僷儚乕偼妶寑攐桪偐傜偺扙旂傪恾偭偰偙偺塮夋偺庡墘傪巙婅偟偨偲偄偆偩偗偵丄側偐側偐偺擬墘丅僇乕僯僶儖偺堦嵗偵擖偭偨僷儚乕偼摟帇弍偺媄傪恎偵偮偗丄堦棳偺婏弍巘偵側偭偰惉岟偡傞偑丄惛恄壢堛偺彈偲寢戸偟偰嬥栕偗傪婇傒丄帺柵偟偰棊偪傇傟丄僊乕僋偵惉傝壥偰傞丅乬僊乕僋乭偲偼丄帤枊偱偼乬廱恖乭偲栿偝傟偰偄傞偑丄尒偨栚偼晛捠偺恖娫偩偑烞偵擖偭偰幹傗寋傪怘偄嶦偡抝偺偙偲偱丄尒悽暔偺悽奅偱偼嵟壓憌偺寍恖丅晄婥枴側僞儘僢僩愯偄偑僷儚乕偺峴偔枛傪埫帵偡傞丅庡恖岞傪庢傝姫偔彈偼3恖乗乗僇乕僯僶儖偱僷儚乕偑彆庤傪柋傔傞彈婏弍巘僕儑乕儞丒僽儘儞僨儖丄僷儚乕偑寢崶偡傞寍恖拠娫偺彈僐儕乕儞丒僌儗僀乮旤偟偄両乯丄堦栕偗傪婇傓嬋幰偺惛恄壢堛僿儗儞丒僂僅乕僇乕丅埆彈栶偼僂僅乕僇乕偩偑丄僷儚乕偲偼巇帠偩偗偺晅偒崌偄偱抝彈娭學偵側傜側偄偺偑丄彈偱攋柵偡傞榖偑懡偄僲儚乕儖偲偟偰偼曄傢偭偰偄傞丅塮夋夛幮偼嫽峴傪峫椂偟丄僷儚乕偺僀儊乕僕傪崻偭偐傜偺埆恖偵偝偣側偄傛偆偵偟偨傜偟偄丅杮棃側傜庤娗傪巊偭偰偺偟忋偑傠偆偲偟丄嵓媆偲埆帠傪婇傓僷儚乕偵摨忣偺梋抧偼側偄偑丄僷儚乕偵偲偭偰丄嵟弶偼垽恖偩偭偨僽儘儞僨儖偼嵟屻偵偼曣恊偺傛偆側懚嵼偵側傞偟丄嵢偺僌儗僀偵偼惤幚偱嵟屻傑偱垽傪曺偘傞偟丄庰時傪岆偭偰庤搉偟偰庰怹傝偺僽儘儞僨儖偺晇傪巰側偣偨偙偲偱椙怱偺欒愑傪姶偠偰偍傝丄娤媞偼摨忣傪姶偠偞傞傪摼側偄丅廔斦偵報徾揑側僔乕儞偑偁傞丅閤偝傟偨僷儚乕偑僂僅乕僇乕傪栤偄媗傔傞僔乕儞偱丄寈嶡偺僒僀儗儞偑柭傞丅僷儚乕偼寈嶡傪屇傫偩偲偐偲恞偹傞偲丄僂僅乕僇乕偼壗傕暦偙偊側偄偲尵偆丅偩偑娤媞偵偼偼偭偒傝暦偙偊傞丅抝偺尪挳側偺偐丄彈偑塕傪偮偄偰偄傞偺偐丄暘偐傜側偄偙偲偑丄嫊峔偲尰幚偺嫬栚傪傏偐偟丄晄埨姶傪忴偟弌偡丅僄儞僪偼僞儘僢僩愯偄偳偍傝敍傝庱偵側傞偐偲巚偄偒傗丄嵞夛偟偨嵢偺僌儗僀偵媬傢傟傞偲偄偆僴儕僂僢僪揑側娒偄寢枛丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐27丂僪僀僣帪戙偺僼儕僢僣丒儔儞僌偺2嶌
1927丂僼儕僢僣丒儔儞僌丂昡揰乵B乶
3帪娫敿偺戝嶌偲偟偰岞奐偝傟偨僒僀儗儞僩塮夋丅偙傟偼寚懝晹暘傪暅尦偟偨2002擭偺2帪娫斉丅僙僢僩丒僨僓僀儞偲嶣塭偺慺惏傜偟偝偵栚傪尒挘傞丅偺偪偵嶌傜傟傞SF塮夋偺偁傜備傞梫慺偑媗傑偭偰偄傞丅儔儞僌偼搉暷偟偰尒偨僯儏乕儓乕僋偺杸揤極偲帒杮庡媊偵怗敪偝傟丄僂僃儖僘偺乽僞僀儉丒儅僔乕儞乿偵傕塭嬁傪庴偗偰丄偙傟傪嶌偭偨偲偄偆丅暯榓傪愢偔惔弮側儅儕傾偲斱辔偵梮傝傑偔傞堹摖側儅儕傾偺僐儞僩儔僗僩偑柺敀偄丅帒杮壠偲楯摥幰偺懳棫偼摉帪偺悽憡傪斀塮偟偰偄傞偑丄偁傑傝偵恾幃偑抰愘偩偟丄帒杮壠偺懅巕偲楯摥幰偺柡偺楒垽丄嵟屻偵斵傜偑庤傪寢傇偲偄偆惉傝峴偒偺埨堈偝偵偼鐒堈偡傞丅恖憿恖娫偺儅儕傾偵愵摦偝傟偰楯摥幰偨偪偼斀棎傪婲偙偡偑丄斵傜偑閤偝傟偨偲巚偭偰儅儕傾傪儕儞僠偡傞揯枛偼丄偺偪偺暷崙戞1嶌乽寖搟乿傪巚傢偣傞丅
夦恖儅僽僛攷巑
1932丂僼儕僢僣丒儔儞僌丂昡揰乵B乶
慡懱偺巇棫偰偼寈嶡偵傛傞斊嵾偺憑嵏傪庡娽偲偡傞僒僗儁儞僗塮夋丅惛恄昦堾偵廁傢傟偨嫸婥偺儅僽僛偑堾挿偵忔傝堏傝丄埆傪婇偰傞丅儀僢僪偱斊嵾偺庤朄傪昅婰偟懕偗傞儅僽僛偼丄楽崠偱乽傢偑摤憟乿傪彂偄偨僸僢僩儔乕偐丅拁壒婡偵傛傞晹壓傊偺巜帵偼丄僫僠僗偺僾儘僷僈儞僟偵傛傞戝廜憖嶌偺慜怗傟偐丅慜嶌偺乽M乿偲偼堎側傝丄妶寑晽偱丄昞尰庡媊揑梫慺偼婓敄丅庡恖岞儘乕儅儞寈晹偺僉儍儔僋僞乕偑柺敀偄丅斊恖偑栭偺埮傪幵傪幘憱偝偣偰摝憱偡傞僔乕儞偑報徾揑丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐26丂僪僀僣偺昞尰庡媊偲塮夋恖偺朣柦傪捛偆2杮偺僪僉儏儊儞僞儕乕
乮朣柦幰偨偪丗僸僢僩儔乕偐傜僴儕僂僢僪傊乯
2007 english subtitled丂昡揰乵A乶
30擭戙屻敿丄僫僠僗偺戜摢偵傛偭偰傾儊儕僇偵搉偭偨儐僟儎宯塮夋娭學幰偺婳愓傪昤偔僪僉儏儊儞僞儕乕丅尦偼PBS偺斣慻乽Cinema's Exiles: From Hitler to Hollywood乿傜偟偄丅僫儗乕僔儑儞偼暓岅偱丄塸岅帤枊晅偒丅徯夘偝傟傞偺偼丄僼儕僢僣丒儔儞僌丄儖價僢僠丄儚僀儖僟乕丄僔僆僪儅僋丄僕儞僱儅儞側偳偺娔撀丄僺乕僞乕丒儘乕儗丄僨傿乕僩儕僢僸側偳偺攐桪丄僼儔儞僣丒儚僢僋僗儅儞丄僐乕儞僑乕儖僪側偳偺壒妝壠偲丄懡嵤丅40擭戙弶摢慜屻偺儀儖儕儞偺嶴忬偲儘僒儞僕僃儖僗偺柧傞偄岝宨偺僐儞僩儔僗僩偑報徾偵巆傞丅孈傝壓偘偑暔懌傝側偄偟丄偨偲偊偽僆僼儏儖僗傗儖僲儚乕儖側偳僼儔儞僗宯偺朣柦幰偵怗傟傜傟偰偄側偄偺偼巆擮偩偑丄偦傟偱傕庤嵺傛偔奣娤偝傟偰偄傞偺偼婱廳丅報徾偵巆傞尵梩丄偦偺1丗乽僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪憂偭偨偺偼朣柦偟偨僪僀僣宯塮夋嶌壠偩偭偨乿丄偦偺2丗乽暷崙偱偺儔儞僌偲儚僀儖僟乕偼懳徠揑偩偭偨丅僗僞僕僆丒僔僗僥儉偲奿摤偟偨儔儞僌偼偄偮傑偱傕僪僀僣偺塭傪攚晧偭偰偍傝丄暷崙偵撻愼傔偢丄徿偵傕宐傑傟側偐偭偨偑丄儚僀儖僟乕偼暷崙偲楒偵棊偪偰僸僢僩嶌傪楢敪偟丄僆僗僇乕傪偄偔偮傕庴徿偟偨乿
From Caligari to Hitler
乮僇儕僈儕偐傜僸僢僩儔乕傊乯
2014 english subtiteld丂昡揰乵B乶
僋儔僇僂傾乕偺柤挊乽僇儕僈儕偐傜僸僩儔乕傊乿偺塮憸斉丅僫儗乕僔儑儞偼撈岅丄塸岅帤枊晅偒丅儚僀儅乕儖帪戙偺僪僀僣塮夋傪憤妵偡傞僪僉儏儊儞僞儕乕丅偙偺帪戙偼戝廜偺帪戙偲掕媊偝傟偰偄傞傞丅1920擭偺儘儀儖僩丒償傿乕僱偵傛傞乽僇儕僈儕攷巑乿偵傛偭偰昞尰庡媊偺夦婏尪憐塮夋偑巒傑傝丄偦偟偰儉儖僫僂丄儔儞僌丄僷僾僗僩偑尰傟傞丅偩偑丄偙偺帪戙偼偦偆偄偆塮夋偽偐傝偩偭偨偺偱偼側偄丅乽僷儞僪儔偺敔乿傗乽扱偒偺揤巊乿偺傛偆側彈偺堦戙婰傕偁偭偨偟丄僐儊僨傿傗償僅乕僪價儖塮夋傕偁偭偨偟丄屻婜偵偼僰乕償僃儖僶乕僌傪愭庢傝偡傞乽擔梛擔偺恖乆乿側偳傕惗傑傟偨丅僪僀僣恖偺岲傓塸梇彇帠帊偑僫僠僗傪惗傫偩丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐25丂媣徏惷帣偺戙昞嶌2杮
1951丂媣徏惷帣丂昡揰乵A乶
暉搰導偺彫偝側挰偺寈嶡彁偵嬑柋偡傞寈嶡姱偲挰偵曢傜偡恖乆傪昤偔丅挰偺廃曈偼敤傗栰嶳丅夛捗斨掤嶳偲挅昪戙屛偺晽宨偑旤偟偄丅揷幧偺挰偺偙偭偗偄偝偲昻偟偝丄擔忢偺僄僺僜乕僪偑丄儐乕儌傾偲垼偟傒傪岎偊側偑傜偮偯傜傟傞丅僗僩乕儕乕偺棳傟偼岻傒偱丄塮夋偲偟偰偺峔惉偼乽杮擔媥恌乿傪巚傢偣傞丅庡墘偺恖忣枴偁傞寈姱丄怷斏媣淺傪偼偠傔丄揳嶳懽巌丄廫庨媣梇側偳偺摨椈丄埳摗梇擵彆丄懡乆椙弮側偳偺懠偺搊応恖暔偼丄傒側岲墘偟偰偄傞丅愴憟偱懅巕傪偡傋偰朣偔偟惛恄堎忢偵側偭偰崱傕愴憟拞偲巚偄崬傫偱偄傞搶栰塸帯榊偺榁恖偼乽杮擔媥恌乿偺嶰殸楢懢榊暞偡傞辍攓戉挿傪巚傢偣傞丅偦偺嶰殸偼偙偙偱杙鎐弮悎側惵擭寈姱傪墘偠傞丅巕栶偺恗栘偰傞傒傕偄偠傜偟偄丅彁挿偺嶰搰夒晇傕岲墘丅嶰搰偲偄偊偽搶塮帪戙寑偺埆栶偲偄偆僀儊乕僕偩偑丄彫捗偺乽斢弔乿偱偼偁傑傝帡崌傢側偄岲岲栮偺戝妛嫵庼傪墘偠偰偄偨丅嬔擵彆偲桍懢楴庡墘偺乽備偆傟偄慏乿傪尒偨偲偒偼丄嶰搰偑嬔擵彆偺拠娫偺彮擭偵暞偟偰偍傝丄崢傪敳偐偟偨丅挰柉偺曢傜偟偼昻偟偄丅昻偟偝屘偵丄曣偼幪偰巕偟丄巕嫙偺偨傔偵柍慘堸怘偟丄枩堷偒偟丄柡傪恎攧傝偡傞丅摉帪丄愴屻偼傑偩懕偄偰偄偨丅昻偟偝傪偁傑傝偵嫮挷偟偰偍傝丄僙儞僠儊儞僞儕僘儉偑傗傗悅傟棳偟側偺偑擄揰丅
恄嶁巐榊偺斊嵾
1956丂媣徏惷帣丂昡揰乵C乶
堦庬偺嵸敾寑丅嶨帍曇廤挿偺怷斏媣栱偑夛幮偺嬥傪墶椞偟丄婾憰偺柍棟怱拞偵傛偭偰垽恖偺嵍岾巕傪巰側偣偨嵾偱婲慽偝傟傞丅嵸敾偱偺徹尵幰偺敪尵偵崌傢偣偰夞憐僔乕儞偑憓擖偝傟傞丅奺恖偺徹尵偑怘偄堘偄丄壗偑恀幚側偺偐丄斵偼岥敧挌偺彈偨傜偟側偺偐恀柺栚側岲恖暔側偺偐暘偐傜側偄偲偄偆丄崟郪柧偺乽梾惗栧乿傪巚傢偣傞撪梕丅怷斏偺墘媄偼僆乕僶乕婥枴偱丄曇廤挿偲偄偆栶暱偵帡崌偭偰偄側偄丅嵸敾偱偼徹嫆偑壗傕帵偝傟側偄偼旕尰幚揑偩偟丄榖偺揥奐偑抰愘偱怺傒偑側偄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐24丂儀僥傿僇乕偺乽幍恖偺柍棅娍乿傪傛偆傗偔娪徿
1956丂僶僢僪丒儀僥傿僇乕丂昡揰乵B乶
儔儞僪儖僼丒僗僐僢僩庡墘丄僎僀儖丒儔僢僙儖丄儕乕丒儅乕償傿儞嫟墘偺惣晹寑丅僗僐僢僩偲儀僥傿僇乕偑僐儞價傪慻傫偩儔僫僂儞丒僒僀僋儖偲尵傢傟傞堦楢偺僔儕乕僘偺殔栴傪側偡丅嵢傪嶦偝傟丄戝嬥傪扗傢傟偨尦曐埨姱偺暅廞鏉丅彫婥枴偄偄榖偺棳傟丄柍懯傪徣偄偨娙寜側墘弌乮対廵偺壒偩偗偱寕偪崌偄偑偁偭偨偙偲傪埫帵偡傞乯偼慺惏傜偟偔丄惣晹偺旤偟偄晽宨傪塮偡僇儊儔傕尒帠丅偟偐偟傾儞僪儗丒僶僓儞偺庴偗攧傝偺楡廳旻泬傪偼偠傔堦晹偺楢拞偑尵偆傎偳偺柤嶌偲偼巚偊側偄丅儕乕丒儅乕償傿儞偼偄傢備傞僌僢僪丒僶僢僪丒僈僀偱丄乽償僃儔僋儖僗乿偺僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕傪巚傢偣傞丅
僷儕丄僥僉僒僗
1984丂償傿儉丒償僃儞僟乕僗丂昡揰乵C乶
僴儕乕丒僨傿乕儞丒僗僞儞僩儞庡墘丄僫僗僞乕僔儍丒僉儞僗僉乕嫟墘偺儘乕僪儉乕償傿乕晽塮夋丅偁傞庬偺暤埻婥偑偁傞偙偲偼妋偐偩偑丄傕偆傂偲偮椙偝偑暘偐傜傫丅乽傾儊儕僇偺桭恖乿傕乽儀儖儕儞揤巊偺帊乿傕乽僴儊僢僩乿傕丄償僃儞僟乕僗偺塮夋偱柺敀偄偲巚偭偨傕偺偼傂偲偮傕側偄丅僥僉僒僗偺晽宨偼旤偟偄偟丄巕栶偼側偐側偐壜垽偐偭偨偑丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐23丂僕僃乕儞丒僼僅儞僟偲僼僃僀丒僟僫僂僃僀
1976丂僔僪僯乕丒儖儊僢僩丂昡揰乵B乶
嬥栕偗偲帇挳棪偵憱傞僥儗價嬈奅傪塻偔漃偭偨塮夋偩偑丄屩挘偟偡偓丅嬈奅傪媃夋壔偟偰偄傞偐偺傛偆偱丄僐儊僨傿偵嬤偄丅惛恄堎忢偵側偭偨僥儗價巌夛幰偑巊偊傞傢偗偑側偄丅椙幆攈偺僯儏乕僗晹挿偵僂傿儕傾儉丒儂乕儖僨儞丄栰朷偵擱偊傞忋徃巙岦偺僾儘僨儏乕僒乕偵僼僃僀丒僟僫僂僃丄恖婥偑棊偪偰惛恄偵堎忢傪偒偨偡傾儞僇乕儅儞僺乕僞乕丒僼傿儞僠丅慡懱偲偟偰僉儍僾儔偺乽孮廜乿傪憐婲偝偣傞丅
僐乕儖僈乕儖
1971丂傾儔儞丒J丒僷僋儔丂昡揰乵C+乶
僱僆丒僲儚乕儖偺傂偲偮丅幐鏗幰傪憑偟偵NY偵弌偰偔傞孻帠偵僪僫儖僪丒僒僓儔儞僪丄幐鏗幰偺抦傝崌偄偺僐乕儖僈乕儖偵僕僃乕儞丒僼僅儞僟丅僼僅儞僟偼偒傟偄偩偟墘媄傕戝偟偨傕偺丅柍昞忣側僒僓儔儞僪傕報徾揑丅塮夋偲偟偰偼丄榖偺揥奐偑傛偔暘偐傜側偄偟丄斊恖偼偡偖暘偐偭偰嫽傪嶍偑傟傞丅慡懱偵傑偩傞偭偙偟偔丄夋柺傕埫偡偓偰傛偔尒偊側偄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐22丂70擭戙暷崙偺榖戣嶌2杮傪嵞尒
1976丂儅乕僥傿儞丒僗僐僙僢僔丂昡揰乵B乶
晻愗傝傪尒偰埲棃偺嵞尒丅婰壇偵巆傞徴寕揑側塮夋偱偁傞偙偲偼妋偐偩偟丄僇儖僩塮夋偵側傞偺傕暘偐傞偑丒丒丒丅儀僩僫儉婣娨暫偺屻堚徢偵傛傞斊峴偲偄偆尒曽傕偁傞偑丄偦偆偱偼側偔丄傛傝堦斒揑偵丄屒撈側抝偑栂憐傪朿傜傑偣傞偲夝庍偡傞傋偒偱偼丅偟偐偟丄偄偔傜堎忢側抝偱傕丄岲偒側彈偲偺弶僨乕僩偱億儖僲塮夋傪尒偣傞偩傠偆偐丠
僠儍僀僫僞僂儞
1974丂儘儅儞丒億儔儞僗僉乕丂昡揰乵A乶
晻愗傝傪尒偰埲棃偺嵞尒丅30擭戙偺儘僒儞僕僃儖僗偑妶幨偝傟傞丅悈偺棙尃傪傔偖傞晄惓偲嶦恖傪憑嵏偡傞巹棫扵掋偵僕儍僢僋丒僯僐儖僜儞丄旐奞幰偺嵢偱奨偺戝棫偰幰偺柡偵僼僃僀丒僟僫僂僃僀丅偄偢傟傕懚嵼姶偑朙偐偩丅戝棫偰幰栶偺僕儑儞丒僸儏乕僗僩儞傕娧榎廩暘丅僇儔乕嶌昳側偑傜僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺怓擹偔丄僴乕僪儃僀儖僪偲僲僗僞儖僕乕偺崄傝偑擋偄棫偮丅億儔儞僗僉乕偺嵥擻偑懚暘偵敪婗偝傟偰偄傞丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐21丂峚岥偺僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋偲僪僀僣偺楌巎揑塮夋
1975丂怴摗寭恖丂昡揰乵B乶
峚岥寬擇偺惗奤偲恖暔憸傪丄懡悢偺僀儞僞價儏乕傗備偐傝偺応強偺扥擮側庢嵽偵傛偭偰晜偐傃忋偑傜偣傞丅峚岥偵孫摡傪庴偗偨娔撀丄怴摗寭恖幏擮傪姶偠傞丅埶揷媊尗丄媨愳堦晇側偳峚岥慻偺桳柤側僗僞僢僼丄埳摗戝曘傗憹懞曐憿側偳偺傎偐丄懡偔偺攐桪偨偪傊偺僀儞僞價儏乕偑埑姫丅婄傇傟偑惁偄丅揷拞對戙丄嶳揷屲廫楅丄擖峕偨偐巕丄怷愒愒巕乮巆媏暔岅乯丄嶳楬傆傒巕乮垽墔嫭乯丄彫曢旤抭戙丄嫗儅僠巕丄壋塇怣巕丄崄愳嫗巕丄庒旜暥巕偲丄崑壺偦偺傕偺丄傎偐偵塝曈孒巕丄拞懞殪帯榊丄恑摗塸懢榊丄彫戲塰懢榊丄桍塱擇榊側偳傕弌偰偔傞丅暦偒庤偑怴摗偩偐傜偙傟偩偗偺恖偨偪偑嶲廤偟偨偺偱偁傠偆丅嶌昳撪梕偺夝朥偼偁傑傝側偝傟偰偄側偄偟丄堷梡嶌昳偼僗僠乕儖幨恀偑懡偔丄摦夋偑偁傑傝巊傢傟偰偄側偄偺偑擄揰丅
Menschen am Sonntag乮擔梛擔偺恖乆乯
1930丂Robert Siodmak丂昡揰乵B乶
僪僀僣偺僒僀儗儞僩塮夋丅塸岅帤枊丅儘僶乕僩丒僔僆僪儅僋仌僄僪僈乕丒僂儖儅乕娔撀丄價儕乕丒儚僀儖僟乕媟杮丄僼儗僢僪丒僕儞僱儅儞嶣塭彆庤偲丄偺偪偵傾儊儕僇偵朣柦偟偰僴儕僂僢僪偱堦壠傪側偡鐱乆偨傞恖乆偵傛偭偰嶌傜傟偨丅偦傟傑偱庡棳偩偭偨僙僢僩嶣塭傗昞尰庡媊塮憸偲偼懪偭偰曄傢傝丄慺恖偺攐桪傪巊偄丄僪僉儏儊儞僞儕乕丒僞僢僠偱庤帩偪僇儊儔偺巗撪儘働偵傛偭偰儀儖儕儞偺恖乆偺擔忢惗妶傪昤偔丅嶣塭偼29擭丅悽奅戝嫲峇偵擖傞捈慜偱丄僫僠僗戜摢慜栭丅儚僀儅乕儖嫟榓崙帪戙偺嵟屻偺壐傗偐側僪僀僣偑塮偟弌偝傟傞丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐20丂惉悾枻婌抝偺柍柤偺嶌昳3杮
1936丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵B乶
梻擭偵惉悾偺嵢偵側傞愮梩憗抭巕庡墘丅愮梩偼摥偔偨傔偵揷幧偐傜搶嫗偵弌偰偔傞丅慜擭偺乽嵢傛錕錘偺傛偆偵乿偲偼斀懳偺愝掕丅愮梩偼愻楙偝傟偰旤偟偔丄偲偰傕揷幧堢偪偵偼尒偊側偄丅棅傝偺桭恖偼堸傒壆偺彈媼偲偟偰摥偄偰偄偨丅巇帠偑尒偮偐傜側偄愮梩偼傗傓傪偊偢彈媼偵側傝丄媞偺戝愳暯敧榊偵岲堄傪書偔丅傗偑偰斵彈偼戝愳偲摝旔峴偡傞偑丄柌偩偲暘偐偭偰嬃偐偝傟傞丅杒奀摴偵揮嬑偡傞戝愳偵傕傜偭偨廧強傪嫶偺忋偱攋傝幪偰傞儔僗僩偑報徾偵巆傞丅
偼偨傜偔堦壠
1939丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵C+乶
摽愳柌惡庡墘丅摽塱捈偺僾儘儗僞儕傾彫愢偑尨嶌丅掅捓嬥偱梒巕傪書偊丄堦壠慡堳偱摥偐側偗傟偽惗妶偱偒側偄昻偟偄壠掚傪昤偔丅媄弍傪杹偒偨偄挿抝丄拞妛偵峴偒偨偄4抝丄偩偑巚偄偳偍傝偵峴偐側偄丅39擭偵偼傑偩孯晹偺専墈偑娚傗偐偩偭偨偺偐丅40擭戙偩偭偨傜偙偺塮夋偺岞奐偼偱偒側偐偭偨偩傠偆丅
壌傕偍慜傕
1946丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵C乶
僄儞僞僣丒傾僠儍僐偺庡墘偱僒儔儕乕儅儞偺斶垼傪儐乕儌傾傪岎偊偰昤偔丅幮挿偺巹梡偵偙偒巊傢傟丄偨偩摥偒偝偣傜傟傞2恖偺巔偼彮偟屩挘偟偡偓偐丅斵傜偺壠偼昻偟偄偑丄愴屻娫傕側偄偺偵愴憟偺塭偼傎偲傫偳側偄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐19丂乽僇僢僐乕偺憙偺忋偱乿
1975丂儈儘僔儏丒僼僅傾儅儞丂昡揰乵B乶
Cuckoo's Nest偲偼惛恄昦堾偺懎徧丅擖崠偐傜摝傟傞偨傔偺惛恄昦幰傪憰偆斀峈幰僕儍僢僋丒僯僐儖僜儞偲丄姵幰傪尩奿偵娗棟偟傛偆偲偡傞娕岇晈挿儖僀乕僘丒僼儗僢僠儍乕偺愴偄丅慡懱偺揥奐偼乽朶椡扙崠乿偵帡偰偄傞丅宆偵偼傑傞偙偲偐傜偺扙媝偲帺桼偺捛媮偲偄偆傾儊儕僇揑側僥乕儅偼傾儊儕僇恖庴偗偡傞偩傠偆丅僕儍僢僋丒僯僐儖僜儞偼僉儕僗僩偺徾挜側偺偱偼側偄偐丅
婾傝偺壥偰
1947丂傾儞儕丒僪僐傾儞丂昡揰乵D乶
夦桪儈僔僃儖丒僔儌儞庡墘丅幵偱傂偒摝偘偟偨庰怹傝偺堛幰偺婾憰岺嶌偑揇徖偵偼傑傞丅抧枴側塮夋偱柌傕媬偄傕側偄丅
僙儞僩丒傾僀僽僗
1976丂J丒儕乕丒僩儞僾僜儞丂昡揰乵D乶
攧傟側偄嶌壠僠儍乕儖僘丒僽儘儞僜儞偑晉崑偐傜搻傑傟偨擔婰偲堷偒姺偊偵巟暐偆嬥偺庴偗搉偟傪棅傑傟傞僒僗儁儞僗塮夋丅慹嶨側揥奐偲偛搒崌庡媊偺僗僩乕儕乕丅尒偳偙傠偼捒偟偔埆彈偵側傞僕儍僋儕乕僰丒價僙僢僩偺旤偟偝偩偗丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐18丂栘壓宐夘偺2嶌丄乽梉傗偗塤乿偲乽徰憸乿
1956丂栘壓宐夘丂昡揰乵A乶
偍偦傜偔攏崬偺偁偨傝偱偁傠偆嫑壆偑晳戜丅慏忔傝偵側傞偙偲傪柌尒傞崅峑1擭偺彮擭偑庡恖岞丅搶栰塸帯榊偑嵢偺朷寧桪巕偲偲傕偵揦傪愗傝惙傝偟偰偍傝丄懅巕偵偁偲傪宲偄偱傕傜偆偙偲傪朷傫偱偄傞丅傾僾儗僎乕儖偱嬍偺梎寢崶傪婅偆巓偺媣変旤巕偑偆傑偄丅庡恖岞偺彮擭偺恊桭偺摨媺惗偲偺晅偒崌偄偺昤偒曽偑摨惈垽揑丅庤傪埇傝崌偭偰曕偄偨傝丄懌愭傪偡傝偁傢偣崌偭偨傝偡傞丅偪傜偭偲偟偐弌側偄偑恊桭偺晝曣傪墘偠傞拞懞怢榊偲嶳揷屲廫楅偑報徾偵巆傞丅晝恊偑朣偔側傝丄彮擭偼柌傪幪偰偰嫑壆傪宲偖丅僗僩乕儕乕偺揥奐偑偒傃偒傃偟偰偍傝丄柍懯側廌扱応偑攔偝傟偰偄傞丅昻偟偄壠偺斶偟偄榖偩偑屻枴偼椙偄丅
徰憸
1948丂栘壓宐夘丂昡揰乵C乶
崟郪柧偺媟杮丅屆偄偑奿埨側壠傪攦偭偨晄摦嶻僽儘乕僇乕偺彫戲塰懢榊偑丄廧傫偱偄傞夋壠偺堦壠傪捛偄弌偡偨傔丄柡偲婾偭偰彣偺堜愳朚巕傪楢傟丄壠偺2奒偵娫庁傝偡傞丅夋壠偵棅傑傟偰徰憸夋偺儌僨儖偵側偭偨堜愳偼丄慞恖懙偄偺堦壠偵傎偩偝傟丄帺暘偺峴堊傗惗妶偑抪偢偐偟偔側偭偰壠傪弌傞丅婎挷偼僸儏乕儅僯僘儉偩偑掙偑愺偔揥奐偼恾幃揑丅嫮梸偩偑彫怱幰偺晄摦嶻壆傪墘偠傞彫戲偑岻偄丅晳戜偲側偭偨摉帪偺帺桼偑媢偺岝宨偼傑偩僶儔僢僋寶偰偺壠偑栚棫偮揷幧挰偺傛偆丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐17丂庒偒僺傾丒傾儞僕僃儕偑旤偟偄枹岞奐嶌乽The Light Touch乿
1941丂儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏丂昡揰乵B乶
僋乕僷乕庡墘乽偁傞擔梛擔偺屵屻乿乮33乯偺儕儊僀僋丅僕僃乕儉僗丒僉儍僌僯乕丄僆儕償傿傾丒僨僴償傿儔儞僪庡墘偺僐儊僨傿丅僗僞乕偵側傞慜偺儕僞丒僿僀儚乕僗偑嫟墘丅僾儘僢僩偺棳傟偑偄偄丅僂僅儖僔儏偺岅傝岥偺岻偝偑昞傟偰偄傞丅帟壢堛偵暞偡傞僉儍僌僯乕偺寉夣側摦嶌偑尒帠丄僴償傿儔儞僪傕偒傟偄偩丅
The Light Touch
1951丂Richard Brooks丂昡揰乵C (A) 乶
僺傾丒傾儞僕僃儕偺僨價儏乕4嶌栚丅暷塮夋傊偺弌墘偼乽僥儗僒乿偵師偖2嶌栚丅20嵨偺傾儞僕僃儕偼悙乆偟偔丄旤偟偝偑嵺棫偭偰偄傞丅愩懌傜偢側塸岅偺敪壒傕壜垽偄丅晳戜偼僀僞儕傾丄旤弍娰偐傜偺奊夋愞搻傪昤偔寉偄斊嵾塮夋丅庡墘偺僗僠儏傾乕僩丒僌儗儞僕儍乕偑奊夋揇朹丄傾儞僕僃儕偼婁嶌傪昤偐偝傟傞夋壠丄恖忣枴偺偁傞堦枴偺崟枊偵僕儑乕僕丒僒儞僟乕僗丅塮夋偲偟偰偺昡壙偼C偩偑丄傾儞僕僃儕偼A丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐16丂僆僼儏儖僗偺棳楉側僇儊儔偑岝傞乽偨偦偑傟偺彈怱乿
1953丂儅僢僋僗丒僆僼儏儖僗丂昡揰乵A乶
庡墘偺婱晈恖偵僟僯僄儖丒僟儕儏乕丄偦偺晇偱婱懓偺彨孯偵僔儍儖儖丒儃儚僀僄丄僟儕儏乕偺晄椣憡庤偺奜岎姱偵償傿僢僩儕僆丒僨僔乕僇丅1900擭偺僷儕偑晳戜丅僟儕儏乕偑攧傞帹忺傝偺曮愇偑巺偲側偭偰怐傝惉偡塣柦偺僞儁僗僩儕乕丅僆僼儏儖僗側傜偱偼偺棳楉側僇儊儔儚乕僋偑偨傔懅偑弌傞傎偳慺惏傜偟偄丅旤偟偄堖憰偲僙僢僩丄晳摜偺僔乕儞偑尒帠偩偟丄奒抜傪捛偆僇儊儔傕弌怓丅僟儕儏乕偑楍幵偺憢偐傜庤巻傪嵶偐偔偪偓偭偰幪偰偄傞偲丄偦偺攋曅偑敀偄愥偵曄傢傞僔乕儞偑報徾怺偄
楌巎偼彈偱嶌傜傟傞
1955丂儅僢僋僗丒僆僼儏儖僗丂昡揰乵C乶
僆僼儏儖僗桞堦偺僇儔乕塮夋丅儅儖僥傿乕僰丒僉儍儘儖庡墘丅幚嵼偺梮巕儘乕儔丒儌儞僥僗偺塰岝偲杤棊乗乗僶僶儕傾墹偺垽恖偵忋傝媗傔偨偑丄嵟屻偼僒乕僇僗偵尒悽暔偵棊偪傇傟偨彈偺悢婏側堦惗偑埡啵崑壺偵昤偐傟傞丅峚岥偺乽惣掃堦戙彈乿傪渇渋偲偝偣傞丅
朰傟偠偺柺塭
1948丂儅僢僋僗丒僆僼儏儖僗丂昡揰乵B乶
僆僼儏儖僗偺傾儊儕僇帪戙偺嶌昳丅僣償傽僀僋尨嶌丅僕儑乕儞丒僼僅儞僥乕儞仌儖僀丒僕儏乕儖僟儞庡墘丅1900擭偺僂傿乕儞傪晳戜偵偟偨儊儘僪儔儅丅僆僼儏儖僗摿桳偺傾僷乕僩偺奒抜丄晳摜丄尒悽暔乮柤強傪椃偡傞楍幵傪椃傪柾偟偨忔傝暔乯偺嶣塭偑報徾怺偄偑丄棳傟傞傛偆側僇儊儔偺摦偒偼婓敄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐15丂50擭戙偺抦傜傟偞傞擔杮塮夋
1957丂扟岥愮媑丂昡揰乵C乶
戞2師戝愴廔寢捈屻丄拞崙偵巆棷偟偰敧楬孯偵嫮惂巊栶偝傟傞孯堛偺掃揷峗擇偲彈巕娕岇晈晹戉傪棪偄傞尨愡巕丅扟岥娔撀偺媽嶌乽嬇偺扙憱乿偲乽扤偑偨傔偵忇偼柭傞乿傪儈僢僋僗偟偨傛偆側嶌昳丅攐桪偺墘媄偑戝偘偝偡偓傞丅37嵨偺尨愡巕偼巆擮側偑傜彮偟榁偗偰偟傑偭偰偄傞丅
堦搧嵵偼攚斣崋6
1959丂栘懞宐屷丂昡揰乵C乶
屲枴峃桽尨嶌偺丄嶳墱偐傜弌偰偒偨寱惞丄埳摗堦搧嵵偺枛遽偑僾儘栰媴偱儂乕儉儔儞傪懪偪傑偔傞偲偄偆屸妝嶌丅堫旜傗拞惣側偳丄摉帪偺惣揝偲戝枅偺僗僞乕慖庤偑弌墘偟偰偄傞丅堦搧嵵傪墘偠傞悰尨尓擇偼慄偑嵶偔偰帡崌傢側偄偑丄梋傝嫮偦偆偱側偄偺偑偄偄偺偐傕偟傟側偄丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐14丂60擭戙偲70擭戙偺堩昳暷塮夋
僕儑儞丒僼儕儞丂1973丂昡揰乵A乶
儘僶乕僩丒僗僞乕僋偺埆搣僷乕僇乕彫愢傪尨嶌偲偡傞僴乕僪儃僀儖僪丒僞僢僠偺斊嵾塮夋丅孻柋強偐傜弌偰偒偰帺暘傪攧偭偨慻怐偵暅廞偡傞儘僶乕僩丒僨儏償傽儖偲丄偦傟傪彆偗傞偐偮偰偺憡朹僕儑乕丒僪儞丒儀僀僇乕偺鉐丄抝偺桭忣偑偄偄丅偦偺揰偱偼搶塮儎僋僓塮夋傪渇渋偲偝偣傞偑丄傾儊儕僇塮夋側偺偱暤埻婥偼姡偄偰偍傝丄恖忣傗偟偑傜傒偺傛偆側幖偭偨嬻婥偼婓敄丅屻枴偑憉傗偐偩丅
偁傞愴溕
1967丂儔儕乕丒僺傾乕僗丂昡揰乵B乶
僽儖僢僋儕儞偐傜儅儞僴僢僞儞偵峴偔抧壓揝幵撪偱嫢朶側僠儞僺儔偑怳傝傑偔嫲晐傪昤偔丅嵟弶偺40暘偱僽儖僢僋儕儞偺奺墂偐傜忔傞丄書偔烼孅偟偨姶忣傪書偔恖乆偑徯夘偝傟傞丅朶椡傪怳傞傢偢尵梩偱僱僠僱僠偲忔媞傪捝傔偮偗傞丄嫸婥傪偼傜傫偩慹朶側僠儞僺儔2恖偼埆杺偺庤愭偐丅丅摨偠僯儏乕儓乕僋攈偺儖儊僢僩偺乽12恖偺搟傟傞抝乿57傗僇僒償僃僥僗偺乽傾儊儕僇偺塭乿乮59乯傪巚偄婲偙偝偣傞丅儔儕乕丒僺傾乕僗偲偄偊偽丄崅峑惗偺偙傠偵尒偨摨娔撀偺乽傢偐傟摴乿乮63乯偼嫮偔報徾偵巆偭偨丅
2020擭5寧朸擔 旛朰榐13丂惉悾枻婌抝偺2嶌丄柤昳乽廐棫偪偸乿偵椳偡傞
1960丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵A乶
巕嫙偑弌偰偔傞塮夋偲尵偊偽惔悈岹偩偑丄彫捗埨擇榊傕巕嫙偺埖偄曽偑岻偐偭偨偟丄偦傟偵晧偗偰偄側偄偺偑惉悾枻婌抝偩丅惉悾偱巕嫙偑弌偰偄傞塮夋偼丄愴慜偺乽傑偛偙傠乿偦傟偵乽嬧嵗壔徬乿乽偍偐偁偝傫乿偖傜偄偟偐側偄偑丄偦傫側側偐偱乽廐棫偪偸乿偼巕嫙偦偺傕偺偑庡恖岞偲偄偆揰偱偒傢傔偰堎怓丅榖偺棳傟偑偲偰傕帺慠偱丄傑偭偨偔娫慠偡傞偲偙傠偑側偄丅丅1960擭偺帪揰偱庡恖岞偺彮擭偼彫妛6擭惗偩偑傜丄昅幰偲傎傏摨偠擭崰偱偁傝丄偦偺揰偱傕姶奡怺偄傕偺偑偁傞丅曣恊栶偺壋塇怣巕偼偲偰傕枺椡揑偵尒偊傞丅摉帪偼傑偩嬧嵗奅孏偵偼愳偑棳傟偰偄偨偟丄僨僷乕僩偺壆忋偐傜偼搶嫗榩偑尒偊偨偺偩丅彮擭偑廧傓敧昐壆偼怴晉挰偺偁偨傝偩傠偆偐丅椃娰偺慜偺愳偼杽傔棫偰傜傟傞慜偺抸抧愳偐丅偙傟偲偦偭偔傝側忣宨傪乽嬧嵗壔徬乿偱傕栚偵偟偨婰壇偑偁傞丅惉悾摿桳偺僔儑僢僩偺偮側偓傗応柺揮姺偑愨柇偱丄夁忚側墘弌傗僆乕僶乕側姶忣昞尰偑攔偝傟偰偍傝丄偲偙傠偳偙傠偵儐乕儌傾偑憓擖偝傟丄傑偩傞偭偙偟偝傪姶偠偝偣側偄丅彮擭偑婑廻偡傞壠偺摗尨姌懌偲夑尨壞巕偺晇晈偺傗傝庢傝側偳書暊傕偺丅僟僢僐偪傖傫側偳偺摉帪偺悽憡丄壓挰偺恖忣偲晄恖忣丄巕嫙偨偪偺柍幾婥側巆崜偝側偳偑偛偔帺慠偵昤偐傟偰偄傞丅彮擭偑拠椙偔側偭偨嬤強偺彮彈偲擇恖偱嶶曕偡傞杽傔棫偰拞偺惏奀偺僔乕儞傗愗側偄儔僗僩偑報徾怺偔丄堦尒丄帊忣偁傆傟傞僪儔儅偺傛偆偵尒偊傞偑丄偙偙偵偼惉悾偺儁僔儈僗僥傿僢僋側恖惗娤偑斀塮偝傟偰偄傞丅傕偟偐偡傞偲惉悾帺恎偺屒撈側彮擭帪戙偑搳塭偝傟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅
晳昉
1951丂惉悾枻婌抝丂昡揰乵C乶
戣嵽偑惉悾偵憡墳偟偔側偄偨傔偐丄杴嶌丅惉悾偼師嶌偺乽傔偟乿偱傛偆傗偔杮椞傪敪婗偡傞丅庡墘偺崅曯嶰巬巕偼僟儞僗嫵幒傪庡嵣偟偰偄傞丅晇偺嶳懞汔偲偺娫偵抝彈偺巕嫙偑偄偰丄柡栶偵偙傟偑僨價儏乕嶌偺壀揷錆浠巕丅崅曯偺寢崶慜偐傜偺桭偩偪偱崱傕晅偒崌偭偰偄傞抝偑擇杮桍姲丅柡偺壀揷傕僶儗僄嫵幒偵捠偭偰偄傞丅晇丄嶳懞偺椻偨偄懺搙偲幏漍側尵梩偺峌寕偵懴偊偒傟偢丄崅曯偼壠傪弌傞丅帺戭偼姍憅偺鄋煭側壠丅晇晈娭學傪昤偄偨嶌昳偩偑丄弌棃偼偁傑傝椙偔側偔丄慡懱揑偵儊儘僪儔儅僠僢僋丅忋棳壠掚偼惉悾偵帡崌傢側偄丅姍憅偺抾暬摴側偳偼彫捗偺塮夋傪憐婲偝偣傞丅偲偼偄偊丄崅曯偲擇杮桍偺僨乕僩丒僔乕儞側偳偼惉悾挷偩偟丄梋塁偺偁傞儔僗僩傕埆偔側偄丅
2020擭4寧
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 12丂僔僆僪儅僋偲儀僥傿僇乕偺弶婜嶌昳
僨償傿僢僪丒儕儞僠丂1996丂昡揰乵D乶
乽僣僀儞丒僺乕僋僗乿傪巚傢偣傞埆柌偺傛偆側塮夋丅搑拞偱庡恖岞偑暿偺恖暔偵擖傟懼傢傞丅壗偑壗偩偐丄傛偔暘偐傜傫丅
僨儞僕儍乕丒僸乕僩
僒儈儏僄儖丒僼儔乕丂1989丂昡揰乵D乶
僕僃僯僼傽乕丒價乕儖僘庡墘丅僼傿儕僺儞偺儅儖僐僗懳傾僉僲偺惌曄傪庢嵽偡傞僇儊儔儅儞偑姫偒崬傑傟傞堿杁丅墝偔偡傇傞僑儈偺嶳僗儌乕僉乕丒儅僂儞僥儞偑報徾偵巆傞丅
儈僗僥儕傾僗側堦栭
僶僢僪丒儀僥傿僇乕丂1944 丂昡揰乵E乶
1帪娫偺B媺塮夋丅夦搻儃僗僩儞丒僽儔僢僉乕丒僔儕乕僘偺堦嶌傜偟偄丅儀僥傿僇乕偺張彈嶌偩偑尒偳偙傠側偟丅
僋儕僗儅僗偺媥壣
儘僶乕僩丒僔僆僪儅僋丂1944丂昡揰乵C+乶
僼傿儖儉僲儚乕儖丅僒儅僙僢僩丒儌乕儉尨嶌丅僕乕儞丒働儕乕偑堎忢側晇丄僼傽儉丒僼傽僞乕儖側傜偸僆儉丒僼傽僞乕儖傪墘偠偰嵢偺僨傿傾僫丒僟乕價儞傪嬯偟傔傞丅慡懱偵儊儘僪儔儅偭傐偄偑丄偲偙傠偳偙傠偵岝偲塭傪惗偐偟偨僔僆僪儅僋傜偟偄塮憸偑尒傜傟傞丅晇晈偑曢傜偡摿庩側峔憿偺壠乮搉傝楲壓偐傜憢僈儔僗墇偟偵壠偺撪晹傪尒壓傠偡峔恾乯偑嫽枴怺偄丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 11丂弶婜偺儅儞僉僂傿僢僣嶌昳2杮
僕儑僙僼丒儅儞僉僂傿僢僣丂1949丂昡揰乵C乶
晝偲巕偺憡崕傪昤偔丅庡墘偺儕僠儍乕僪丒僐儞僥偼埆幰婄側偺偱慞恖栶偼帡崌傢側偄丅朶孨偺晝恊僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞偼偝偡偑偺娧榎丅僄僪儚乕僪丒僪儈僩儕僋偑惣晹寑乽愜傟偨憚乿乮54乯偲偟偰儕儊僀僋偟偨丅
暅廞婼
僕儑僙僼丒儅儞僉僂傿僢僣丂1950丂昡揰乵B乶
堎怓僼傿儖儉僲儚乕儖丅嫸婥偺暅廞婼偲壔偟丄僪儘僪儘偟偨崷傒傪傇偪傑偗傞儕僠儍乕僪丒僂傿僪儅乕僋偺擬墘偑尒傕偺丅堛巘栶偺僔僪僯乕丒億儚僠僄偼偙偺僨價儏乕嶌偐傜桪摍惗偺崟恖惵擭傪墘偠懕偗偨丅儂儚僀僩丒僩儔僢僔儏偲崟恖偺懳棫偑岻傒偵昤偒崬傑傟偰偄傞丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 10丂塀傟偨柤嶌丄嶳揷偲嶰慏偺乽壓挰乿
嶳杮壝師榊丂1942丂昡揰乵C乶
崅曯廏巕偲抮晹椙庡墘丅嫟墘偑尨愡巕丄擖峕偨偐巕偲崑壺側晍恮丅榁曑抍巕壆偺榁庡恖偑僶僗偺拞偱桪偟偄彈妛惗丄崅曯傪尒弶傔丄懛丄抮晹偺壟偵偝偣傛偆偲偡傞丅庒偄擇恖偼寢崶偲偼偳傫側傕偺偐傪抦傞偨傔丄抮晹偺孼掜巓枀偺壠傪弰傝曕偄偰恖惗傪妛傇丅愴帪壓偲偼巚偊側偄僼儔儞僗晽偺偺偳偐側塮夋丅抮晹偺僨價儏乕2嶌栚丄弌惇慜偺弌墘嶌丅
壓挰
愮梩懽庽丂1957丂昡揰乵A+乶
1帪娫懌傜偢偺彫昳偩偑撪梕偼朙偐丅塀傟偨柤昳偲尵偊傞丅徍榓24擭丄昻偟偄帪戙偺搶嫗壓挰偱偺悢擔娫偺弌棃帠偑偨傫偨傫偲昤偐傟傞丅僔儀儕傾梷棷偐傜婣傜偸晇傪懸偭偰搶嫗偵弌偰偒偰丄壓挰偱拑傪峴彜偡傞巕楢傟偺彈丄嶳揷屲廫楅偺梷偊偨墘媄偑愨昳丅妺忺偺峳愳搚庤乮巐僣栘奅孏傜偟偄乯偱帒嵽抲偒応偺斣恖傪偟偰曢傜偡僔儀儕傾婣傝偺杙鎐側慞恖丄嶰慏晀榊傕枴傢偄怺偄丅嶳揷偑嶰慏偺斣彫壆傪庁傝偰曎摉傪怘傋傞僔乕儞偺丄嶰慏偑嶘偺愗傝恎傪敿暘偵偪偓偭偰嶳揷偵暘偗偰傗傞昤幨偑壏偐偔丄愗側偄丅嶰慏偼曣巕偲傕偵愺憪偵梀傃偵峴偔丅梀墍抧偱梀傃丄塮夋傪尒丄傾僀僗僋儕乕儉傪怘傋偰婌傇巕嫙偑偄偠傜偟偄丅塉偑崀偭偰椃娰偵攽傑傞栭偺忣宨偑尒帠丅撍慠偺嶰慏偺帠屘巰傪抦傝丄曫慠偲偡傞嶳揷偺昞忣偑偡偽傜偟偄丄傑偝偵擖恄偺墘媄偩丅曣巕偑廧傓傾僷乕僩偺椬偵廧傓彣偺扺楬宐巕傕岲墘丅旤弍偺拞屆抭傕尒帠丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 9丂僕儑僙僼丒儘乕僕乕70擭戙
僕儑僙僼丒儘乕僕乕丂1975丂昡揰乵C乶
尨戣乽Romantic Englishwoman乿丅朚戣偑僟僒偡偓傞丅嶌壠偺晇儅僀働儖丒働僀儞偲偦偺嵢僌儗儞僟丒僕儍僋僜儞偑曢傜偡壠偵夦偟偄惵擭僿儖儉乕僩丒僶乕僈乕偑擖傝崬傓丅怱偑枮偨偝傟側偄嵢偼僪僀僣偱偦偺惵擭偲忣帠偵傆偗傞丅偦傟傪捛偆晇丅嫊偲幚偑岎嶖偡傞丅
僷儕偺摂偼墦偔
僕儑僙僼丒儘乕僕乕丂1976丂昡揰乵B乶
尨戣乽Monsieur Klain乿丅庴偗慱偄偺朚戣偑僋僒偄丅乽埫嶦幰偺儊儘僨傿乿乮72乯偵懕偔傾儔儞丒僪儘儞偺婲梡丅僫僠僗愯椞壓偺僷儕丄摨惄摨柤偺儐僟儎恖偵娫堘偊傜傟丄憡庤偺儐僟儎恖傪溸偐傟偨傛偆偵扵偡旤弍彜偺抝丅嵟屻偼帺傜擖傝崬傓偐偺傛偆偵廂梕強峴偒偺楍幵偵忔傝崬傓丅僇僼僇揑側柪媨偺悽奅丅偣偭偐偔僕儍儞僰丒儌儘乕偑弌偰偄傞偺偵弌斣偼彮側偄丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 8丂僕儑僙僼丒儘乕僕乕60擭戙
僕儑僙僼丒儘乕僕乕丂1968丂昡揰乵B乶
棊偪傇傟偨擭憹偺彥晈僄儕僓儀僗丒僥僀儔乕偑巰傫偩柡偺曟嶲傝偺搑拞偵摢偺偍偐偟偄憠偣偨彮彈晽偺彈儈傾丒僼傽乕儘乕偵儅儅偲惡傪偐偗傜傟丄斵彈偑堦恖偱廧傓崑揁偵擖傝怹傞丅斵彈偺嵿嶻傪慱偆廸曣偨偪偲媊棟偺晝恊儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偑棈傓丅堎忢側悽奅偲婏柇側暔岅偼儘乕僕乕側傜偱偼丅
梉側偓
僕儑僙僼丒儘乕僕乕丂1968丂昡揰乵C乶
僥僱僔乕丒僂傿儕傾儉僘偺媃嬋偺塮夋壔丅抧拞奀偺搰偱彈墹偺傛偆偵曢傜偡僄儕僓儀僗丒僥僀儔乕偲丄偦偙偵傗偭偰棃傞棳傟幰儕僠儍乕僪丒僶乕僩儞丅僶乕僩儞偼巰偺揤巊偐丅僄償傽丒僈乕僪僫乕偺乽僷儞僪儔乿傪憐婲偝偣傞丅僥僀儔乕偺旈彂栶偺僕儑傾儞僫丒僔儉僇僗偺塭偑敄偄偺偑巆擮丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 7丂3杮偺堎怓擔杮塮夋
崱懞徆暯丂1958丂昡揰乵C乶
1帪娫懌傜偢偺彫昳丅嫸尵夞偟栶偵僼儔儞僋塱堜丅桍戲怲堦庡墘丅夛幮偐傜柦偠傜傟偨崱懞徆暯偑傗偗偭傁偪偱嶣偭偨傛偆側報徾丅崱懞偺巘丄愳搰梇嶰偺僫儞僙儞僗塮夋傪憐婲偝偣傞丅
啵乮偨偩傟乯
憹懞曐憿丂1962丂昡揰乵B乶
摽揷廐惡尨嶌丅庡墘偼庒旜暥巕丄揷媨擇榊丅朻摢偺怮揮傫偱僞僶僐傪偔備傜偡壓拝巔偺庒旜暥巕偑弌怓丅庒旜偺埆彈傇傝偼側偐側偐偺傕偺丅忋嫗偟偨柮偺悈扟椙廳偲偺棈傒偼嫮楏偱丄憹懞側傜偱偼偺昤幨偩偑丄慡懱偵尰幚棧傟偟偰偍傝丄嶌傝暔傔偄偰偄傞丅
戝抧偺帢
嵅攲惔丂1956丂昡揰乵C乶
戝桭桍懢楴庡墘偺搶塮帪戙寑偩偑僠儍儞僶儔応柺偼側偄丅柧帯堐怴捈屻丄墱塇偺彫斔偺晲巑偨偪偵傛傞嬯擄偺杒奀摴奐戱暔岅丅嶳宍孧偑埆栶偲巚偄偒傗寣傕椳傕偁傞堐怴惌晎偺栶恖傪墘偠傞丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 6丂廰偄僼傿儖儉丒僲儚乕儖3杮
僕儑僙僼丒H丒儖僀僗丂1949丂昡揰乵C乶
僌儗儞丒僼僅乕僪庡墘偺僼傿儖儉僲儚乕儖丅埫崟奨偺儃僗傪扙惻偱婲慽偡傞偨傔嬯摤偡傞嵿柋徣憑嵏姱偨偪傪僙儈僪僉儏儊儞僞儕乕晽偵昤偔丅傗傗惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅
旕忣偺帪
僕儑僙僼丒儘乕僕乕丂1957丂昡揰乵C乶
塸崙偵搉偭偨儘乕僕乕偑杮柤偱嶣偭偨戞1嶌丅傾儖拞偺儅僀働儖丒儗僢僪僌儗僀償偑巰孻24帪娫慜偺懅巕傪媬偆偨傔恀斊恖傪憑偡丅僒僗儁儞僗偼傗傗嬻夞傝偩偑丄帺暘傪嶦偝偣傞儔僗僩偼徴寕揑丅
僔儑僢僋僾儖乕僼
僟僌儔僗丒僒乕僋丂1949丂昡揰乵B乶
僒儈儏僄儖丒僼儔乕媟杮偺僼傿儖儉僲儚乕儖丅曐岇娤嶡姱偺僐乕僱儖丒儚乕儖僪偑旤彈僷僩儕僔傾丒僫僀僩偺峏惗傪彆偗傞偆偪偵楒拠偵側傝丄尵偄婑傞愄偺拠娫偺抝傪嶦偟偨偲巚偄崬傫偱2恖偱摝憱偡傞丅摝旔峴偺枛偵攋柵偡傞偐偲巚偄偒傗丄桘揷偱摥偄偰偄偨2恖偼曔傑傞偑丄巰傫偩偲巚偭偨抝偼惗偒偰偍傝丄抝婥傪敪婗偟偰塕偺徹尵傪偟偨偨傔丄2恖偼柍嵾偵側傝丄僴僢僺乕僄儞僪丅彨棃傪忷朷偝傟傞惓媊娍偐傜摝朣幰偵側傞抝丄抝偺巚偄偲壏偐偄壠掚偵傎偩偝傟偰夵怱偡傞彈丅傗傗娒偄儊儘僪儔儅晽偺僒僗儁儞僗偩偑丄堄奜偵柺敀偄丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 5丂乽梸朷偺嵒敊乿偲乽戝偄側傞栭乿
娔撀丗僂傿儕傾儉丒僨傿僞乕儗丂1949丂昡揰乵C+乶
撿傾僼儕僇偺僟僀傾儌儞僪嵦孈偵棈傓暅廞鏉丅庒偒擔偺僶乕僩丒儔儞僇僗僞乕庡墘丅億乕儖丒僿儞儕乕僪丄僋儘乕僪丒儗僀儞僘丄僺乕僞乕丒儘乕儗偲嬋幰懙偄偺攝栶偩偑丄撪梕偼偄傑偄偪丅
戝偄側傞栭
娔撀丗僕儑僙僼丒儘乕僕乕丂1951丂昡揰乵C+乶
僼傿儖儉丒僲儚乕儖丅儘乕僕乕偺傾儊儕僇帪戙偺嵟屻偺嶌昳丅尨嶌偼僗僞儞儕乕丒僄儕儞丅僶乕傪宱塩偡傞晝偲崅峑惗偺懅巕偲偺妺摗丅庡墘偼僕儑儞丒僶儕儌傾丒僕儏僯傾丅戣嵽偼偄偄偟丄棳傟傕偄偄偑丄榖偺揥奐偵擄偁傝丅
梉曢傟偺偲偒
娔撀丗僕儍僢僋丒僞乕僫乕丂1956丂昡揰乵C乶
僼傿儖儉丒僲儚乕儖晽偩偑偁傑傝僲儚乕儖怓偼擹偔側偄丅柍幚偺嵾偱摝朣拞偺庡恖岞偵傾儖僪丒儗僀丅斵傪彆偗傞彈偵傾儞丒僶儞僋儘僼僩丅斵傜傪嬧峴嫮搻斊偲曐尟挷嵏堳偑捛偆丅抧枴側B媺偩偑偗偭偙偆傑偲傑偭偰偄傞丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 4丂峚岥寬擇偺2嶌
娔撀丗峚岥寬擇丂1946丂昡揰乵C乶
峚岥偺愴屻戞2嶌丅壧枦栶偼斅搶柂彆丅偙偺恖偼偺偪偵傆偖偺撆偱巰傫偩嶁搶嶰捗屲榊偲偺偙偲丅悈拑壆偺娕斅寍幰栶偵揷拞對戙丅堖憰傗旤弍偼偝偡偑偵嬅偭偰偍傝丄僇儊儔儚乕僋傕棳楉偩偑丄僗僩乕儕乕偑婲暁偵朢偟偔丄忣擮偺敪業偑側偄丅
梜婱斳
娔撀丗峚岥寬擇丂1955丂昡揰乵D乶
峚岥偺斢擭偺崄峘偲偺崌嶌偵傛傞戝嶌偩偑丄尯廆峜掗栶偺怷夒擵丄梜婱斳栶偺嫗儅僠巕丄偲傕偵栶偵帡崌偭偰偄側偄丅僙僢僩偼崑壺偩偟丄嶳懞汔丄彫戲塰懢榊丄嶳宍孧丄怴摗塸懢榊丄悪懞弔巕偲攝栶傕偄偄偑丄慡懱偵埨偭傐偔怺傒偑側偄丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 3丂償傿僗僐儞僥傿偺2嶌
娔撀丗儖僉僲丒償傿僗僐儞僥傿丂1969丂昡揰乵B乶
晻愗傝帪偵尒偰埲棃偺嵞尒丅偁偺柤嶌乽償僃僯僗偵巰偡乿偺慜嶌偵偁偨傞丅1933擭丄僫僠僗惌尃彾埇捈屻偺僪僀僣偱丄婱懓偺傛偆偵曢傜偡揝峾宱塩幰堦壠偺偨偳傞塣柦丅庡墘偼僟乕僋丒儃僈乕僪丄僀儞僌儕僢僪丒僠儏乕儕儞丄僿儖儉乕僩丒僶乕僈乕丄僔儍乕儘僢僩丒儔儞僾儕儞僌丅崙夛曻壩帠審丄戝妛偱偺暟彂丄恊塹戉偵傛傞撍寕戉偺媠嶦偑昤偐傟傞丅側傫偲偄偭偰傕丄彈憰偟偰僉儍僶儗乕丒僜儞僌傪壧偄丄彮彈傪儗僀僾偡傞僶乕僈乕偺堎忢偝偑埑搢揑丅
庒幰偺偡傋偰
娔撀丗儖僉僲丒償傿僗僐儞僥傿丂1960丂昡揰乵B+乶
償傿僗僐儞僥傿偺僱僆儗傾儕僗儌帪戙偺嵟廔嶌丅慜嶌偼乽敀栭乿丄師嶌偼乽嶳擫乿丅傾儔儞丒僪儘儞丄傾僯乕丒僕儔儖僪庡墘丅撿晹偐傜儈儔僲偵堏廧偟偨昻偟偄堦壠偺榖丅壠懓垽丄孼掜垽偑昤偐傟傞丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 2丂埌愳偄偯傒偺2嶌偲傕偆1杮
娔撀丗惣壨崕屓丂1959丂昡揰乵B乶
搶嫗偺拞棳壠掚偺3恖巓枀偺惗偒曽傪昤偄偨1959擭偺嶌昳偱丄埌愳偄偯傒偼師彈丄挿彈偑杒尨嶰巬偱3彈偑惔悈傑備傒丅埌愳偄偯傒偺偐傢偄偝偑嵺棫偮偑丄惔悈傑備傒傕側偐側偐僉儏乕僩丅梩嶳椙擇偑嫟墘丅撪梕偼愳抂峃惉尨嶌偺捠懎揑側儊儘僪儔儅偱丄傛偔偁傞偛搒崌庡媊揑側嬝棫偰偩偑丄尒偰偄偰偦傟傎偳戅孅偼偟側偄丅愳抂峃惉偼晈恖嶨帍側偳偵楢嵹偡傞捠懎彫愢偼掜巕偵戙昅偝偣偰偄偨傜偟偄偑丄偙傟傕偦偺傂偲偮偐丅僾儘僢僩偺廳梫側偲偙傠偱愴憟偑塭傪棊偲偟偰偄傞丅59擭偺帪揰偱傕恖乆偵偲偭偰愴憟懱尡偼擔忢偺側偐偵愼傒崬傫偱偄偨偺偩丅晝恊栶偺戝嶁巙榊偑側偐側偐傛偔丄嵟弶偼棅傝側偄僟儊恊晝傆偆偩偭偨偺偵丄偩傫偩傫懚嵼姶傪憹偟偰偄偒丄僄儞僨傿儞僌偱偼墱偝傫偵乽巰偸傑偱抪傪偐偒側偑傜曕偄偰峴偐側偒傖側傜傫乿偲娷拁偁傞尵梩傪偐偗傞丅
柖揓偑壌傪屇傫偱偄傞
娔撀丗嶳嶈摽師榊丂1960丂昡揰乵C乶
愒栘孿堦榊丄埌愳偄偯傒丄梩嶳椙擇丅怴恖偺媑塱彫昐崌偑彮彈栶偱弌偰偄傞丅媣偟傇傝偵墶昹偵栠偭偨慏忔傝偺愒栘偑恊桭偺巰偵媈擮傪書偄偰丒丒丒偲偄偆僗僩乕儕乕偼乽戞嶰偺抝乿偵偦偭偔傝丅埌愳偺偐傢偄偝偵尒偲傟傞丅
敀偲崟
娔撀丗杧愳峅捠丂1960丂昡揰乵B乶
嫶壓擡媟杮丄2揮丄3揮偡傞僗僩乕儕乕偑彫婥枴偄偄忋弌棃偺僒僗儁儞僗丅彫椦宩庽偺専帠丄旐崘偺曎岇巑偵拠戙払栴丅傎偐偵搶栰塸帯榊丄彫戲塰懢榊丄惣懞峎偲嬋幰栶幰偑惃懙偄丅偣偭偐偔扺搰愮宨偑弌偰偄傞偺偵嶦偝傟傞栶偱夞憐僔乕儞偩偗偺搊応側偺偼僈僢僇儕丅
2020擭4寧朸擔 塮夋旛朰榐乣枅擔偑2杮棫偰 1丂尨愡巕偺2嶌
1950丂娔撀丗弔尨惌媣丂昡揰乵C乶
捒偟傗悪懞弔巕庡墘丅嫟墘偼棾嶈堦榊丄尨愡巕丅悪懞偼梮傝偺巘彔丅棾嶈偼棳峴嶌壠丄尨偼棾嶈偺壎巘偺柡丅棾嶈偼慞恖偩偑悪懞偲尨傪擇屢偐偗傞幭偊愗傜側偄抝丅棾嶈偵幪偰傜傟偨偲岆夝偟偨尨愡巕偼帺嶦傪偼偐傞偑彆偐傞丅偙偺偁偨傝偼偐側傝搨撍側報徾丅悪懞偑恎傪堷偄偰擇恖偼寢偽傟傞丅尨偼摉帪30嵨偩偑丄偠偮偵旤偟偔悙乆偟偄丅
搶嫗偺楒恖
1952丂愮梩懽庽丂昡揰乵B乶
尨愡巕偲嶰慏晀榊庡墘偺僐儊僨傿丅孋傒偑偒偺彮擭偨偪偲拠娫偱嬧嵗偺奨妏偱帡婄奊傪昤偔尨愡巕丅嶰慏晀榊偼曮愇怑恖丅32嵨偺尨偼傑偩枺椡枮揰丅偡偗傋側夛幮幮挿偺怷斏媣栱偲嫲嵢偺惔愳擑巕偑偆傑偄丅忋嫗偡傞曣恊偺偨傔丄昦婥偱暁偣傞彥晈偺悪梩巕偺晇栶傪嶰慏偑墘偠傞偺偼丄僉儍僾儔偺乽堦擔偩偗偺廼彈乿偺堷梡偐丅
2019.12.26 (栘) 2019擭儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
 01丏乽彏偄偺愥偑崀傞乿 傾儗儞丒僄僗働儞僗乮憂尦暥屔乯
01丏乽彏偄偺愥偑崀傞乿 傾儗儞丒僄僗働儞僗乮憂尦暥屔乯02丏乽徖偺墹偺柡乿 僇儗儞丒僨傿僆儞僰乮僴乕僷乕僽僢僋僗乯
03丏乽實暿乿 儅僀僋儖丒僐僫儕乕乮島択幮暥屔乯
04丏乽埫嶦幰偺捛愓乿 儅乕僋丒僌儕乕僯乕乮僴儎僇儚暥屔乯
05丏乽11寧偵嫀傝偟幰乿 儖乕丒僶乕僯乕乮僴乕僷乕僽僢僋僗乯
06丏乽儊僀儞僥乕儅偼嶦恖乿 傾儞僜僯乕丒儂儘償傿僢僣乮憂尦暥屔乯
07丏乽惗暔妛扵掋僙僆丒僋儗僀乿 傾儞僪儕儏乕丒儊僀儞乮僴儎僇儚暥屔乯
08丏乽僓丒僾儘僼僃僢僒乕乿 儘僶乕僩丒儀僀儕乕乮彫妛娰暥屔乯
09丏乽対廵巊偄偺柡乿 僕儑乕僟儞丒僴乕僷乕乮僴儎僇儚丒億働儈僗乯
10丏乽働僀僩偑嫲傟傞偡傋偰乿 僺乕僞乕丒僗儚儞僜儞乮憂尦暥屔乯
亂2019擭塮夋儀僗僩10亃
 01丏乽COLD WAR乣偁偺壧丄2偮偺怱乿 僷償僃儔丒僷償儕僐僼僗僉
01丏乽COLD WAR乣偁偺壧丄2偮偺怱乿 僷償僃儔丒僷償儕僐僼僗僉丂丂乮攇丒塸丒暓乯
02丏乽僕儑乕僇乕乿 僩僢僪丒僼傿儕僢僾僗乮暷乯
03丏乽儚儞僗丒傾億儞丒傾丒僞僀儉丒僀儞丒僴儕僂僢僪乿 僋僄儞僥傿儞丒
丂丂 僞儔儞僥傿乕僲乮暷丒塸乯
04丏乽僪僢僌儅儞乿 儅僢僥僆丒僈儘乕僱乮埳乯
05丏乽僇僣儀儞乿 廃杊惓峴乮擔乯
06丏乽塱墦偺栧乣僑僢儂偺尒傞枹棃乿 僕儏儕傾儞丒僔儏僫乕儀儖
丂丂乮暷丒塸丒暓乯
07丏乽僀僄僗僞僨僀乿 僟僯乕丒儃僀儖乮塸乯
08丏乽僌儕乕儞僽僢僋乿 僺乕僞乕丒僼傽儗儕乕乮暷乯
09丏乽塣傃壆乿 僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪乮暷乯
10丏乽僽儔僢僋丒僋儔儞僘儅儞乿 僗僷僀僋丒儕乕乮暷乯
2019.04.03 (悈) 怴尦崋偵偮偄偰巚偆
偦傟偵偟偰傕丄嶗偺奐壴傪傔偖傞晜偐傟憶偓偑堦抜棊傕偟側偄偆偪偵姫偒婲偙偭偨丄偙偺怴尦崋傪傔偖偭偰偺嫸憶丄怴暦偺崋奜傪媮傔偰嫸棎偡傞恖乆傪尒傞偲丄偮偔偯偔擔杮偼暯榓偩側偲巚偆丅偙偺偁偲丄怴揤峜懄埵丄偦偟偰僆儕儞僺僢僋偲丄擔杮偑書偊傞廳梫側帠埬丄怺崗側栤戣偼榚偵墴偟傗傜傟丄晜偐傟憶偓偼懕偔丅晄搒崌側埬審偐傜栚傪堩傜偡偨傔偺埨攞惌尃偺嶔杁偵丄儊僨傿傾傕崙柉傕偆傑偔忔偣傜傟偰偄傞傛偆偵姶偠傞丅
乽椷榓乿偲偄偆暥帤傪尒偰偺戞堦報徾偼丄徍榓傊偺楢憐偩偭偨丅愴慜偺徍榓偵夞婣偟偨偄偲偄偆埨攞庱憡偲擔杮夛媍堦攈偺婖傢偟偄巚偄偑崬傔傜傟偰偄傞偲姶偠偨丅乽椷乿偲偼丄撻愼傒偺側偄娍帤偱偁傝丄堄枴偑傛偔暘偐傜側偐偭偨丅偲偭偝偵摢偵晜偐傫偩偺偼乽岻尵椷怓彮側偟恗乿偲偄偆榑岅偺尵梩偩偭偨丅偄偢傟偵偟傠丄偁傑傝偄偄僀儊乕僕偼晜偐偽側偄丅偲偼偄偊丄乽椷乿偼柦椷偡傞偵捠偠傞偐傜忋偐傜偺墴偟偮偗偩丄側偳偲尵偆幰傕偄傞偑丄埨攞庱憡偼尵梩偺堄枴偵偮偄偰柍抦偩傠偆偐傜偼丄偦傫側堄恾側偳側偔丄偍偦傜偔妛幰傗懁嬤偐傜丄乽椷乿偼乽椙偄乿偲偄偆堄枴偱偡側偳偲愢柧偝傟偰丄壗傕峫偊偢偵丄偩偭偨傜偙傟偵偟傛偆丄偲巚偭偨偺偩傠偆丅奜崙偺儊僨僀傾偱傕偄傠偄傠榑昡偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄娍帤偺堄枴傪抦傜側偄楢拞偑庴偗攧傝偱愢柧偟偰傕丄傑偭偨偔愢摼椡傪帩偨側偄丅
弶傔偰偺崙彂偐傜偺弌揟偩丄側偳偲偼偁傑傝摼乆偲尵傢側偄傎偆偑偄偄丅弌揟偲側偭偨枩梩廤偺暥復偼丄拞崙偺屆揟帊廤偐傜偺僷僋儕偩偲偄偆偱偼側偄偐丅弶傔偰娍愋傪攔偟偰崙彂傪弌揟偲偟偨丄側偳偲尵偭偨傜丄拞崙偐傜潏潐偝傟丄殅徫偝傟傞偩傠偆丅偦傕偦傕尦崋偦偺傕偺偑拞崙偺傗傝曽傪恀帡偰巒傔傜傟偨傕偺偩偐傜丄偦傫側偙偲偱撈帺惈傪懪偪弌偟偰傕堄枴偑側偄丅
乽椷榓乿偲偄偆尵梩偼丄堄枴偼偲傕偐偔丄儕僘儉偲嬁偒偼偄偄丅堘榓姶偼偁傞偑丄乽暯惉乿偺偲偒偲摨偠偔丄偦偺偆偪偵姷傟傞偺偩傠偆丅傏偔偼怴尦崋偼僇僫3暥帤偵側傞偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄偨丅柧帯丄戝惓丄徍榓丄暯惉偲丄3丄4丄3丄4丄偲偄偆暥帤悢偱棃偰偄傞偺偱丄師偼3偲偄偆偙偲偵側傞丅偲傝偁偊偢丄偦傟偼摉偨偭偨丄偳偆偱傕偄偄偙偲偩偑丅偙傟傕偳偆偱傕偄偄偙偲偩偑丄桳幆幰崸恊夛偺儊儞僶乕偵丄捒柇側堖暈偺媨嶈麔傗昳惈偑姶偠傜傟側偄椦恀棟巕偲偄偭偨婥怓埆偄恖偨偪偑擖偭偰偄偨偺偼壗屘偩傠偆丅埨攞庱憡偺偍桭払偩偭偨偐傜偐丅偄偢傟偵偣傛丄懱嵸傪惍偊偰奿岲傪偮偗傞偨傔偩偗偺夛偱偁傞偙偲偼柧傜偐偩丅
傏偔偼尰崱偺徾挜揤峜惂傪昁偢偟傕斲掕偼偟側偄偑丄揤峜偺戙懼傢傝偛偲偵尦崋偑夵傑傝丄姱岞挕側偳偺岞偺暥彂偱偼惣楋偱側偔尦崋偱婰嵹偡傞偙偲偑敿偽媊柋偯偗傜傟偰偄傞偙偲傗丄崙壧偑揤峜偺悽偺塱媣偺斏塰傪婩傞壧偱偁傞偙偲傪尒傞偲丄揤峜偼徾挜埲忋偺懚嵼偲偟偰婡擻偟偰偄傞傛偆偵姶偠傞丅娫傕側偔戅埵偝傟傞崱忋揤峜偑丄懄埵埲棃丄徾挜偺堄枴偵偮偄偰巚偄擸傫偱偒偨偙偲偼丄壗搙偐偺崙柉傊偺儊僢僙乕僕傪捠偠偰傏偔偨偪傕抦偭偰偄傞丅偦偟偰擔杮夛媍傪偼偠傔偲偡傞嬌塃偺楢拞偑崙夛媍堳偲寢戸偟偰丄揤峜傪尦庱偲偡傞愴慜偺懱惂偵栠偦偆偲偟偰偄傞偙偲傕抦偭偰偄傞丅偦偆偼偝偣側偄偨傔偵傕丄怴尦崋偺惂掕丄怴揤峜偺懄埵傪宊婡偲偟偰丄傏偔偨偪偼傕偆堦搙丄徾挜揤峜惂偲偼壗偐偵偮偄偰峫偊側偗傟偽側傜側偄丅
2019.01.11 (嬥) 2018擭儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
01 亀偁側偨傪垽偟偰偐傜亁 僨僯僗丒儖僿僀儞 乮憗愳億働儈僗乯
02 亀偦偟偰儈儔儞僟傪嶦偡 亁僺乕僞乕丒僗儚儞僜儞 乮憂尦暥屔乯
03 亀埫嶦幰偺愽擖亁 儅乕僋丒僌儕乕僯乕 乮憗愳暥屔乯
04 亀恀栭拞偺懢梲亁 僕儑乕丒僱僗儃 乮憗愳億働儈僗乯
05 亀僇僒僒僊嶦恖帠審亁 傾儞僜僯乕丒儂儘償傿僢僣 乮憂尦暥屔乯
06 亀塭偺巕亁 僨僀償傿僢僪丒儎儞僌 乮憗愳億働儈僗乯
07 亀僂乕儅儞丒僀儞丒僓丒僂傿儞僪僂亁 A丒J丒僼傿儞 乮憗愳彂朳乯
08 亀擱偊傞晹壆亁 儅僀僋儖丒僐僫儕乕 乮島択幮暥屔乯
09 亀僟丒僼僅乕僗亁 僪儞丒僂傿儞僘儘僂 乮僴乕僷乕丒僽僢僋僗乯
10 亀嫋偝傟偞傞幰亁 儗僀僼丒儁乕僔儑儞 乮憂尦暥屔乯
亂2018擭塮夋儀僗僩10亃
01 亀僗儕乕丒價儖儃乕僪亁 儅乕僥傿儞丒儅僋僪僫乕 乮暷丒塸乯
02 亀僗僞乕儕儞偺憭憲嫸憶嬋亁 傾乕儅儞僪丒僀傾僰僢僠 乮塸丒暓乯
03 亀枩堷偒壠懓亁 惀巬桾榓 乮擔乯
04 亀僔僃僀僾丒僆僽丒僂僅乕僞乕亁 僊儗儖儌丒僨儖丒僩儘 乮暷乯
05 亀儈僢僔儑儞丒僀儞億僢僔僽儖丗僼僅乕儖傾僂僩亁 僋儕僗僩僼傽乕丒儅僢僇儕乕 乮暷乯
06 亀僶僩儖丒僆僽丒僓丒僙僋僔乕僘亁 僕儑僫僒儞丒僨僀僩儞仌償傽儗儕乕丒僼傽儕僗 乮暷乯
07 亀儚儞僟乕僗僩儔僢僋亁 僩僢僪丒僿僀儞僘 乮暷乯
08 亀儘乕僾丂愴応偺惗柦慄亁 僼僃儖僫儞僪丒傾儔僲傾 乮惣乯
09 亀儌儕乕僘丒僎乕儉亁 傾乕儘儞丒僜乕僉儞 乮暷乯
10 亀儔僢僉乕 亁僕儑儞丒僉儍儘儖丒儕儞僠 乮暷乯
2018.06.16 (搚) 億乕儔儞僪偲偄偆崙
 億乕儔儞僪偺崙搚柺愊偼擔杮偺5暘偺4丅杒偼僶儖僩奀丄撿偼僠僃僐乛僗儘償傽僉傾丄搶偼僪僀僣丄惣偼媽僜楢朚偺儀儔儖乕僔乛僂僋儔僀僫偵愙偟偰偄傞丅恖岥偼擔杮偺栺3暘偺1傎偳偩丅僜楢曵夡丄柉庡妚柦偐傜栺30擭丄億乕儔儞僪偼弴挷偵宱嵪偑惉挿偟偰偍傝丄
億乕儔儞僪偺崙搚柺愊偼擔杮偺5暘偺4丅杒偼僶儖僩奀丄撿偼僠僃僐乛僗儘償傽僉傾丄搶偼僪僀僣丄惣偼媽僜楢朚偺儀儔儖乕僔乛僂僋儔僀僫偵愙偟偰偄傞丅恖岥偼擔杮偺栺3暘偺1傎偳偩丅僜楢曵夡丄柉庡妚柦偐傜栺30擭丄億乕儔儞僪偼弴挷偵宱嵪偑惉挿偟偰偍傝丄 搶墷悘堦偺怴嫽崙偵側偭偰偄傞丅僀儞僼儔偵搳帒偟偨傝尰抧朄恖傪愝棫偟偨傝偡傞擔杮偺婇嬈傕憹偊偰偄傞傛偆偩丅EU偵壛柨偟偰偄傞偑丄捠壿偼儐乕儘偱偼側偔撈帺捠壿偺僘儘僠偩丅偦偺偨傔懠偺儓乕儘僢僷偺崙乆偲斾傋偰暔壙偼掅偄丅儐乕儘寳偵壛傢傞偙偲偵傛傞崿棎傪寈夲偟偰丄偄傑偺偲偙傠崙柉偼帺崙捠壿傪慖戰偟偰偄傞丅尗柧側敾抐偲尵偆傋偒偐傕偟傟側偄丅宱嵪揑偵偼傑偩敪揥搑忋偵偁傞偑丄億乕儔儞僪偺恖乆偼寴幚偱丄怱偼朙偐偩丅斊嵾敪惗棪偑偒傢傔偰掅偔丄帯埨偑偄偄偺偑偦偺徹嫆偱偁傠偆丅崙柉偺95僷乕僙儞僩偑僇僩儕僢僋嫵搆偱偁傝丄嫵夛偼戝彫偲傝傑偤偰帄傞強偵偁傞丅
搶墷悘堦偺怴嫽崙偵側偭偰偄傞丅僀儞僼儔偵搳帒偟偨傝尰抧朄恖傪愝棫偟偨傝偡傞擔杮偺婇嬈傕憹偊偰偄傞傛偆偩丅EU偵壛柨偟偰偄傞偑丄捠壿偼儐乕儘偱偼側偔撈帺捠壿偺僘儘僠偩丅偦偺偨傔懠偺儓乕儘僢僷偺崙乆偲斾傋偰暔壙偼掅偄丅儐乕儘寳偵壛傢傞偙偲偵傛傞崿棎傪寈夲偟偰丄偄傑偺偲偙傠崙柉偼帺崙捠壿傪慖戰偟偰偄傞丅尗柧側敾抐偲尵偆傋偒偐傕偟傟側偄丅宱嵪揑偵偼傑偩敪揥搑忋偵偁傞偑丄億乕儔儞僪偺恖乆偼寴幚偱丄怱偼朙偐偩丅斊嵾敪惗棪偑偒傢傔偰掅偔丄帯埨偑偄偄偺偑偦偺徹嫆偱偁傠偆丅崙柉偺95僷乕僙儞僩偑僇僩儕僢僋嫵搆偱偁傝丄嫵夛偼戝彫偲傝傑偤偰帄傞強偵偁傞丅 億乕儔儞僪偱偼儌儈偺栘傪傛偔栚偵偟偨丅擔杮偱尒偐偗傞傕偺偲偼堘偭偰丄梩偭傁偑榓栄偺傛偆偵傆偝傆偝偟偰偄傞丅僐乕僇僒僗儌儈偲尵傢傟傞庬椶偺栘偱僩僂僸偲傕徧偝傟傞傜偟偄丅岞墍傗峀応側偳偵峴偔偲丄僶儔偺壴側偳偵埻傑傟偰丄偙偺儌儈偺栘偑椢怓慛傗偐偵偡偭偔偲棫偭偰偄傞偺偑報徾揑偩偭偨丅偦偺儌儈偺栘偺傛偆偵丄億乕儔儞僪偺彈惈偼奣偟偰嫻偑戝偒偔壓敿恎偑朙偐偱丄彈惈傜偟偄傆偔傛偐側懱偮偒傪偟偰偄傞丅
億乕儔儞僪偱偼儌儈偺栘傪傛偔栚偵偟偨丅擔杮偱尒偐偗傞傕偺偲偼堘偭偰丄梩偭傁偑榓栄偺傛偆偵傆偝傆偝偟偰偄傞丅僐乕僇僒僗儌儈偲尵傢傟傞庬椶偺栘偱僩僂僸偲傕徧偝傟傞傜偟偄丅岞墍傗峀応側偳偵峴偔偲丄僶儔偺壴側偳偵埻傑傟偰丄偙偺儌儈偺栘偑椢怓慛傗偐偵偡偭偔偲棫偭偰偄傞偺偑報徾揑偩偭偨丅偦偺儌儈偺栘偺傛偆偵丄億乕儔儞僪偺彈惈偼奣偟偰嫻偑戝偒偔壓敿恎偑朙偐偱丄彈惈傜偟偄傆偔傛偐側懱偮偒傪偟偰偄傞丅 億乕儔儞僪偼恊擔崙偩偲偄偆丅偦偺攚宨偵偼丄僩儖僐偑恊擔崙偵側偭偨偺偲摨偠傛偆側宱堒偑偁偭偨丅挿偔儘僔傾偵怤棯偝傟丄崙搚傪扗傢傟偰偄偨億乕儔儞僪偼丄1900擭戙弶傔丄擔業愴憟偱擔杮偑儘僔傾偵彑棙偟偨偙偲偵棴堸傪壓偘偨丅偦偺摉帪丄擔杮偼億乕儔儞僪偺撈棫塣摦傪巟墖偟偨傝丄儘僔傾偱曔椄偵側偭偨億乕儔儞僪恖暫巑傗丄僔儀儕傾偱崿棎偺側偐恊傪幐偭偨億乕儔儞僪偺屒帣傪媬弌偟偨傝偟偨丅斵傜偼偦偺壎媊傪偄傑傕朰傟偰偄側偄偺偩偲偄偆丅
億乕儔儞僪偼恊擔崙偩偲偄偆丅偦偺攚宨偵偼丄僩儖僐偑恊擔崙偵側偭偨偺偲摨偠傛偆側宱堒偑偁偭偨丅挿偔儘僔傾偵怤棯偝傟丄崙搚傪扗傢傟偰偄偨億乕儔儞僪偼丄1900擭戙弶傔丄擔業愴憟偱擔杮偑儘僔傾偵彑棙偟偨偙偲偵棴堸傪壓偘偨丅偦偺摉帪丄擔杮偼億乕儔儞僪偺撈棫塣摦傪巟墖偟偨傝丄儘僔傾偱曔椄偵側偭偨億乕儔儞僪恖暫巑傗丄僔儀儕傾偱崿棎偺側偐恊傪幐偭偨億乕儔儞僪偺屒帣傪媬弌偟偨傝偟偨丅斵傜偼偦偺壎媊傪偄傑傕朰傟偰偄側偄偺偩偲偄偆丅 億乕儔儞僪偱偼僔儑僷儞偑崙柉揑塸梇偵側偭偰偄偨丅儚儖僔儍儚偺崙嵺嬻峘偑乽儚儖僔儍儚丒僔儑僷儞嬻峘乿偲柦柤偝傟偰偄偨傝丄巻暭偵僔儑僷儞偺徰憸偑巊傢傟偨傝偟偰偍傝丄儚儖僔儍儚偵偼悘強偵僔儑僷儞備偐傝偺抧偑偁偭偨丅僔儑僷儞偲偄偆偲丄変乆偵偼僺傾僲偺彫昳偺嶌嬋壠偲偄偆偰偄偳偺儅僀僫乕側僀儊乕僕偟偐側偄偑丄杮崙偱偼愨懳揑側僸乕儘乕偵側偭偰偄傞傛偆偩丅傎偐偵屘儓僴僱丒僷僂儘2悽儘乕儅嫵峜偺摵憸傗執嬈傪偨偨偊傞巎愓傕偁偪偙偪偵偁傝丄僔儑僷儞偲暲傇億乕儔儞僪偺執恖偵側偭偰偄傞傜偟偄丅
億乕儔儞僪偱偼僔儑僷儞偑崙柉揑塸梇偵側偭偰偄偨丅儚儖僔儍儚偺崙嵺嬻峘偑乽儚儖僔儍儚丒僔儑僷儞嬻峘乿偲柦柤偝傟偰偄偨傝丄巻暭偵僔儑僷儞偺徰憸偑巊傢傟偨傝偟偰偍傝丄儚儖僔儍儚偵偼悘強偵僔儑僷儞備偐傝偺抧偑偁偭偨丅僔儑僷儞偲偄偆偲丄変乆偵偼僺傾僲偺彫昳偺嶌嬋壠偲偄偆偰偄偳偺儅僀僫乕側僀儊乕僕偟偐側偄偑丄杮崙偱偼愨懳揑側僸乕儘乕偵側偭偰偄傞傛偆偩丅傎偐偵屘儓僴僱丒僷僂儘2悽儘乕儅嫵峜偺摵憸傗執嬈傪偨偨偊傞巎愓傕偁偪偙偪偵偁傝丄僔儑僷儞偲暲傇億乕儔儞僪偺執恖偵側偭偰偄傞傜偟偄丅 尰戙偺億乕儔儞僪偺塸梇偲偄偊偽僒僢僇乕偺儗償傽儞僪僼僗僉偱丄6寧29擔偺儚乕儖僪僇僢僾擔攇愴偱偼擔杮偼斵偵嬯偟傔傜傟傞偩傠偆丅傏偔側偳偼億乕儔儞僪偲尵偊偽傾儞僕僃僀丒儚僀僟傗僇儚儗儘償傿僢僠傗億儔儞僗僉乕側偳偺塮夋娔撀傪恀偭愭偵楢憐偡傞偑丄尰抧偺恖偨偪偵榖傪岦偗偰傕斀墳偼撦偔丄偁傑傝娭怱偑側偄傛偆偩丅傎偐偵億乕儔儞僪弌恎偺挊柤恖偲偄偊偽丄抧摦愢傪彞偊偨僐儁儖僯僋僗丄僲乕儀儖徿傪2搙傕庴徿偟偨僉儏儕乕晇恖偑偄傞丅
尰戙偺億乕儔儞僪偺塸梇偲偄偊偽僒僢僇乕偺儗償傽儞僪僼僗僉偱丄6寧29擔偺儚乕儖僪僇僢僾擔攇愴偱偼擔杮偼斵偵嬯偟傔傜傟傞偩傠偆丅傏偔側偳偼億乕儔儞僪偲尵偊偽傾儞僕僃僀丒儚僀僟傗僇儚儗儘償傿僢僠傗億儔儞僗僉乕側偳偺塮夋娔撀傪恀偭愭偵楢憐偡傞偑丄尰抧偺恖偨偪偵榖傪岦偗偰傕斀墳偼撦偔丄偁傑傝娭怱偑側偄傛偆偩丅傎偐偵億乕儔儞僪弌恎偺挊柤恖偲偄偊偽丄抧摦愢傪彞偊偨僐儁儖僯僋僗丄僲乕儀儖徿傪2搙傕庴徿偟偨僉儏儕乕晇恖偑偄傞丅 億乕儔儞僪偼丄廃曈偺彫崙偲摨偠偔丄愄偐傜儘僔傾偲僪僀僣偲偄偆嫮崙偺嫹娫偱丄崙搚偑暘妱偝傟偨傝徚柵偟偨傝偡傞偲偄偆嬯擄偺楌巎傪曕傫偱偒偨丅儚儖僔儍儚丄僋儔僋僼丄億僘僫儞丄償儘僣儚僼丄僩儖儞側偳丄偳偺奨偵峴偭偰傕丄懠崙偵怤棯偝傟偨傝巟攝偝傟偨傝偟偨懌愓傪傕偭偰偄傞丅18悽婭枛偵偼儘僔傾丄僾儘僀僙儞丄僆乕僗僩儕傾偵暘妱偝傟偰崙傪幐偭偨丅偦偺屻丄撈棫傪夞暅偟偨偑丄戞2師戝愴偑杣敪偡傞偲崙搚偼嵞傃僫僠僗丒僪僀僣偲僜楢偵暘妱偝傟偰徚柵偟偨丅戞2師戝愴拞偵偼僇僠儞偺怷帠審傗儚儖僔儍儚朓婲側偳偺斶寑偵尒晳傢傟偨丅愴屻丄撈棫傪壥偨偟偨偑丄僜楢偺塹惎崙偲偟偰嫟嶻搣偑巟攝偡傞撈嵸惌尃偑懕偄偨丅1989擭偺僜楢曵夡偵傛傝丄傛偆傗偔柉庡壔偑幚尰偟丄帺桼傪妉摼偟偨丅崙柉偼丄戞2師戝愴拞偼僫僠僗傊偺儗僕僗僞儞僗塣摦丄嫟嶻搣巟攝帪戙偵偼柉庡壔塣摦傪揥奐偟丄戝偒側媇惖傪暐偄側偑傜傕抏埑偵斀峈偟偨丅
億乕儔儞僪偼丄廃曈偺彫崙偲摨偠偔丄愄偐傜儘僔傾偲僪僀僣偲偄偆嫮崙偺嫹娫偱丄崙搚偑暘妱偝傟偨傝徚柵偟偨傝偡傞偲偄偆嬯擄偺楌巎傪曕傫偱偒偨丅儚儖僔儍儚丄僋儔僋僼丄億僘僫儞丄償儘僣儚僼丄僩儖儞側偳丄偳偺奨偵峴偭偰傕丄懠崙偵怤棯偝傟偨傝巟攝偝傟偨傝偟偨懌愓傪傕偭偰偄傞丅18悽婭枛偵偼儘僔傾丄僾儘僀僙儞丄僆乕僗僩儕傾偵暘妱偝傟偰崙傪幐偭偨丅偦偺屻丄撈棫傪夞暅偟偨偑丄戞2師戝愴偑杣敪偡傞偲崙搚偼嵞傃僫僠僗丒僪僀僣偲僜楢偵暘妱偝傟偰徚柵偟偨丅戞2師戝愴拞偵偼僇僠儞偺怷帠審傗儚儖僔儍儚朓婲側偳偺斶寑偵尒晳傢傟偨丅愴屻丄撈棫傪壥偨偟偨偑丄僜楢偺塹惎崙偲偟偰嫟嶻搣偑巟攝偡傞撈嵸惌尃偑懕偄偨丅1989擭偺僜楢曵夡偵傛傝丄傛偆傗偔柉庡壔偑幚尰偟丄帺桼傪妉摼偟偨丅崙柉偼丄戞2師戝愴拞偼僫僠僗傊偺儗僕僗僞儞僗塣摦丄嫟嶻搣巟攝帪戙偵偼柉庡壔塣摦傪揥奐偟丄戝偒側媇惖傪暐偄側偑傜傕抏埑偵斀峈偟偨丅 偦偺夁掱偼傾儞僕僃僀丒儚僀僟偺塮夋丄偲傝傢偗弶婜偺掞峈3晹嶌偵姶摦揑偵昤偐傟偰偄傞丅億乕儔儞僪偺恖乆偼偦傫側嬯擄偲掞峈偺楌巎傪攚晧偄側偑傜丄偄傑撈帺偺摴傪曕傫偱敪揥偟傛偆偲偟偰偄傞丅
偦偺夁掱偼傾儞僕僃僀丒儚僀僟偺塮夋丄偲傝傢偗弶婜偺掞峈3晹嶌偵姶摦揑偵昤偐傟偰偄傞丅億乕儔儞僪偺恖乆偼偦傫側嬯擄偲掞峈偺楌巎傪攚晧偄側偑傜丄偄傑撈帺偺摴傪曕傫偱敪揥偟傛偆偲偟偰偄傞丅庱搒儚儖僔儍儚偺奨偼敋寕偱傎偲傫偳夡柵偟偨偑丄愴屻丄巎愓偼拤幚偵嵞尰偝傟偨丅偄偭傐偆屆搒僋儔僋僼偼傎偲傫偳懪寕傪庴偗偢丄楌巎揑側寶憿暔傗奨暲傒偑偦偺傑傑巆偭偰偄偨丅
 傾僂僔儏償傿僢僣仌價儖働僫僂愨柵廂梕強偼丄偦偺僋儔僋僼偐傜幵偱1帪娫偖傜偄偺峹奜丄僆僔僼傿僄儞僠儉偵偁偭偨丅儐僟儎恖嫮惂廂梕強偵偮偄偰偼丄偙傟傑偱幨恀丄塮憸丄杮丄塮夋側偳偱昞柺揑偵抦偭偰偼偄偨偑丄尰幚偵傾僂僔儏償傿僢僣偺峀戝側晘抧偵棫偪暲傇廂梕搹丄僈僗幒丄從媝楩側偳傪栚寕偟丄桳柤側乽ARBEIT MACHT FREI乿乮摥偗偽帺桼偵側傞乯偲偄偆僎乕僩偵宖偘傜傟偨暥帤丄揥帵偝傟偰偄傞偍傃偨偩偟偄悢偺敮朳丄
傾僂僔儏償傿僢僣仌價儖働僫僂愨柵廂梕強偼丄偦偺僋儔僋僼偐傜幵偱1帪娫偖傜偄偺峹奜丄僆僔僼傿僄儞僠儉偵偁偭偨丅儐僟儎恖嫮惂廂梕強偵偮偄偰偼丄偙傟傑偱幨恀丄塮憸丄杮丄塮夋側偳偱昞柺揑偵抦偭偰偼偄偨偑丄尰幚偵傾僂僔儏償傿僢僣偺峀戝側晘抧偵棫偪暲傇廂梕搹丄僈僗幒丄從媝楩側偳傪栚寕偟丄桳柤側乽ARBEIT MACHT FREI乿乮摥偗偽帺桼偵側傞乯偲偄偆僎乕僩偵宖偘傜傟偨暥帤丄揥帵偝傟偰偄傞偍傃偨偩偟偄悢偺敮朳丄 孋丄僇僶儞丄娽嬀僼儗乕儉丄僠僋儘儞B偺娛側偳傪栚偺摉偨傝偵偡傞偲丄偁傑傝偺堎忢偝偵徴寕傪庴偗丄尵梩傪幐偆丅僫僠僗丒僪僀僣偼丄柉懓忩壔偲偄偆柤偺傕偲丄偙偙偱150枩恖傕偺恖乆傪嶦奞偟偨丅儐僟儎恖愨柵寁夋偼丄峀搰丒挿嶈傊偺尨敋搳壓偲暲傇丄20悽婭偺恖椶偑斊偟偨嵟戝偺朶媠旕摴側嬸峴偱偁傝丄恖娫偼偳偙傑偱傕巆崜偵側傝摼傞惗偒暔偩偲偄偆偙偲偺徹偟偩偲捝姶偡傞丅敆奞傪庴偗偨旐奞幰偱偁傞儐僟儎恖偑丄偄傑偼壛奞幰偲偟偰僷儗僗僠僫恖傪敆奞偟偰偄傞偲偄偆尰幚偼丄側傫偲偄偆楌巎偺旂擏偩傠偆偐丅
孋丄僇僶儞丄娽嬀僼儗乕儉丄僠僋儘儞B偺娛側偳傪栚偺摉偨傝偵偡傞偲丄偁傑傝偺堎忢偝偵徴寕傪庴偗丄尵梩傪幐偆丅僫僠僗丒僪僀僣偼丄柉懓忩壔偲偄偆柤偺傕偲丄偙偙偱150枩恖傕偺恖乆傪嶦奞偟偨丅儐僟儎恖愨柵寁夋偼丄峀搰丒挿嶈傊偺尨敋搳壓偲暲傇丄20悽婭偺恖椶偑斊偟偨嵟戝偺朶媠旕摴側嬸峴偱偁傝丄恖娫偼偳偙傑偱傕巆崜偵側傝摼傞惗偒暔偩偲偄偆偙偲偺徹偟偩偲捝姶偡傞丅敆奞傪庴偗偨旐奞幰偱偁傞儐僟儎恖偑丄偄傑偼壛奞幰偲偟偰僷儗僗僠僫恖傪敆奞偟偰偄傞偲偄偆尰幚偼丄側傫偲偄偆楌巎偺旂擏偩傠偆偐丅
2017.12.30 (搚) 2017擭儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
1丂乽埫嶦幰偺旘桇乿丂儅乕僋丒僌儕乕僯乕丂乮憗愳暥屔乯
2丂乽斢壞偺捘棊乿丂僲傾丒儂乕儕乕丂乮憗億働乯
3丂乽僼儘僗僩巒枛乿丂R.D.僂傿儞僌僼傿乕儖僪丂乮憂尦暥屔乯
4丂乽惵墧昅偺彈乿丂僑乕僪儞丒儅僇儖僷僀儞丂乮憂尦暥屔乯
5丂乽僽儔僢僋丒儃僢僋僗乿丂儅僀僋儖丒僐僫儕乕丂乮島択幮暥屔乯
6丂乽僾儕僘儞丒僈乕儖乿丂L.S.儂乕僇乕丂乮僴乕僷乕僽僢僋僗乯
7丂乽屛偺抝乿丂傾乕僫儖僨儏儖丒僀儞僪儕僟僜儞丂乮憂尦暥屔乯
8丂乽埆杺偺惎乿丂僕儑乕丒僱僗儃丂乮廤塸幮暥屔乯
9丂乽僟乕僋丒儅僞乕乿丂僽儗僀僋丒僋儔僂僠丂乮憗愳暥屔乯
10丂乽妝墍乿丂僉儍儞僨傿僗丒僼僅僢僋僗丂乮憂尦暥屔乯
亂2017擭奀奜塮夋儀僗僩10亃
1丂乽儔丒儔丒儔儞僪乿丂僨儈傾儞丒僠儍僛儖丂乮暷乯
2丂乽儅儞僠僃僗僞乕丒僶僀丒僓丒僔乕乿丂働僱僗丒儘僫乕僈儞丂乮暷乯
3丂乽僇僼僃丒僜僒僄僥傿乿丂僂僨傿丒傾儗儞丂乮暷乯
4丂乽僽儗乕僪儔儞僫乕2049乿丂僪僁僯丒償傿儖僰乕償丂乮暷乯
5丂乽婓朷偺偐側偨乿丂傾僉丒僇僂儕僗儅僉丂乮僼傿儞儔儞僪乯
6丂乽僷僞乕僜儞乿丂僕儉丒僕儍乕儉僢僔丂儏乮暷乯
7丂乽僙乕儖僗儅儞乿丂傾僗僈乕丒僼傽儖僴僨傿丂乮僀儔儞丒暓乯
8丂乽僓丒僐儞僒儖僞儞僩乿丂僊儍償傿儞丒僆僐僫乕丂乮暷乯
9丂乽塉偺擔偼夛偊側偄丄惏傟偨擔偼孨傪憐偆乿丂僕儍儞亖儅儖僋丒償傽儗丂乮暷乯
10丂乽僪儕乕儉乿丂僙僆僪傾丒儊儖僼傿丂乮暷乯
2017.10.24 (壩) 廜堾慖嫇嶨姶
彑偭偨帺柉搣偼丄偄傑偼尓嫊側懺搙傪憰偭偰偄傞丅偩偑丄塕偮偒抝偺埨晹怶嶰偼偡偖偵巔惃傪曄偊丄壗偱傕傗傝偨偄傎偆偩偄偵傗傞偩傠偆丅偙傟偐傜丄擔暷摨柨偼屻栠傝偑偱偒側偄傎偳怺傑傝丄懳暷廬懏偼傑偡傑偡壛懍偡傞丅懳拞娭學丄懳娯娭學偼偝傜偵埆壔偡傞丅幚幙宱嵪偼庛懱壔偟丄奿嵎偑峀偑傞丅摿掕旈枾曐岇朄丄廤抍揑帺塹尃梕擣丄嫟杁嵾朄偲偒偰丄師偼寷朄夵掶丄旕忢帠懺朄傊偲恑傓丅偙偆偟偰擔杮偼拝乆偲孯帠崙壠丄愴慜偺懱惂傊偺媡栠傝偺摴傪曕傓偙偲偵側傞偐偲巚偆偲丄傗傝偒傟側偄婥帩偪偵側傞丅
傏偔偼愄偐傜彫抮昐崌巕偵岲姶傪傕偰側偐偭偨丅彫抮偼丄偦偺帪乆偺尃椡幰偲婑傝揧偄側偑傜丄偙偙傑偱偺偟偁偑偭偨丅晽傪撉傫偱攷汅傪懪偮偙偲傕偱偒傞丅偦偺堄枴偱偼丄偲偰傕偟偨偨偐側惌帯壠偩偑丄側偤恖婥偑偁傞偺偐丄傛偔棟夝偱偒側偐偭偨丅斵彈偺塃梼僞僇攈巙岦偼埨晹偲曄傢傜側偄丅偩偑丄偦偺惌帯怣忦傛傝傕丄傏偔偼斵彈偺尵摦偵偆偝傫廘偝傪姶偠偰偒偨丅斵彈偼偄偮傕徫婄傪愨傗偝側偄偑丄偁傟偑婥帩偪埆偄丅恖偑徫偆偺偼丄壗偐傪塀偦偆偲偡傞偲偒丄庛傒傪庢傝慤偆偲偒偩丅偦傟偐傜丄斵彈偼偟偽偟偽墶暥帤乗乗傾僂僼僿乕儀儞丄儚僀僘丒僗儁儞僨傿儞僌丄僷儔僟僀儉丒僔僼僩丄僠儍乕僞乕丒儊儞僶乕乗乗傪巊偆偑丄偁傟傕偄偐偝傑偭傐偄丅壗偐傪挐傞嵺丄摨岺堎嬋偺傕偺側偺偵丄偝傕恀怴偟偄傕偺偩偲尒偣偐偗傛偆偲偡傞庤岥偩丅
偟偐偟丄抪偝傜偟偺埨晹傪尃椡偺嵗偐傜堷偒偢傝壓傠偡偨傔偵偼丄傕偟彫抮偵椡偲惃偄偑偁傞偺側傜丄斵彈偵戸偡偟偐側偄偲巚偭偰偄偨丅撆傪埲偰撆傪惂偡偩丅偲偙傠偑丄摉弶偼妚怴揑側僀儊乕僕傪攚晧偭偰弌敪偟偨婓朷偺搣傊偺婜懸偼丄彫抮偺椺偺乽攔彍乿敪尵丄帺柉搣偲傎偲傫偳曄傢傜側偄栚昗丄拞恎偺側偄惌嶔偺偨傔丄媫懍偵偟傏傫偩丅慖嫇屻偼帺柉搣偲偺採実傕帇栰偵擖傟傞偲偄偆彫抮偺敪尵丄庒嫹傗嵶栰偲偄偭偨柍擻側懁嬤偺庤嵺偺埆偝偑丄偦傟偵攺幵傪偐偗偨丅
偲偼偄偊丄彫抮偩偗傪埆幰偵巇棫偰忋偘傞榑朄偵偼堎傪彞偊偨偄丅彫抮偑攇晽傪棫偰側偗傟偽丄栰搣偑嫟摤偟偰偟偰摑堦岓曗傪棫偰丄帺柉搣偲屳妏偺彑晧偵側傞壜擻惈傕偁偭偨偑丄偦傟傪彫抮偑傇偪夡偡寢壥偵側偭偨偙偲偼妋偐偩丅偩偑丄崙柉偺懡偔偑帺柉搣傪慖傫偩偺偼帠幚偩丅帺柉搣偵昜傪擖傟傞偲偄偆偙偲偼埨晹庱憡傪懕搳偝偣傞偲偄偆堄巚昞帵偩丅愑擟偼崙柉偵偁傞丅朶惌傪懕偗傞埨晹偵挿婜惌尃傪嫋偡偲偼丄偁偊偰尵偆偑丄擔杮恖偼側傫偲峫偊偺愺偄崙柉側偺偩傠偆偲巚偆丅
墷暷偺傛偆側崙搚偺怤棯傪傔偖傞壵崜側楌巎傪宱尡偣偢丄壓偐傜偺柉廜妚柦傕婲偙傜側偐偭偨乮柧帯堐怴偼妚柦偱偼側偔尃椡摤憟偩乯擔杮偼丄偗偭偒傚偔偺偲偙傠丄帺椡偱偼側偔奜埑偵傛偭偰偟偐曄妚偱偒側偄偺偐傕偟傟側偄丅偦偙偦偙朙偐側惗妶傪憲偭偰偄傞擔杮恖偼丄帺暘偺懌尦偺惗妶偑婋婡偵娮傜側偄偐偓傝丄挿擭懕偄偨僔僗僥儉傪曄偊傞偺偑寵偄側偺偩傠偆丅崱夞偺慖嫇偱丄栰搣偑帺柉搣偲屳妏偺寢壥偵側偭偨傝帺柉搣偵彑偭偨傝偟偨抧堟偼丄夁慳壔偵傛偭偰宱嵪偑旀暰偟偰偄傞杒奀摴偲丄暷孯婎抧偵傛偭偰暯壐偲埨慡偑嫼偐偝傟偰偄傞壂撽偩偗偩偭偨偙偲偑丄偦傟傪暔岅偭偰偄傞丅
婓朷偺搣偐傜弌攏偟偨尦柉恑搣偺媍堳偨偪偑搣庱偱偁傞彫抮傊偺斸敾傪嫮傔偰偄傞偑丄攏幁側楢拞偩偲偟偐尵偄傛偆偑側偄丅傕偲傕偲彫抮偺恖婥偲椡傪偁偰偙傫偱婓朷偺搣偵埰懼偊偟偨幰偨偪偵丄彫抮傪愑傔傞帒奿偼側偄丅帺暘偺幚椡偺側偝傪斀徣偡傋偒偩丅偄偭傐偆偺彫抮偼丄偄傠偄傠偲攕愴偺曎傪岅偭偰偄傞偑丄乽僈儔僗偺揤堜偼攋偭偨偑揝偺揤堜偵慾傑傟偨乿側偳偲尵偄丄帺暘偺尵摦傗怳傞晳偄傪扞偵忋偘丄攕愴偺尨場傪彈惈偺幮夛恑弌傪慾傓悽娫偺姷廗偵偡傝懼偊偰偄傞丅偙傟偼彈偺晲婍傪棙梡偟偰惌奅傪搉傝曕偄偨彫抮傜偟偄愑擟揮壟偱偁傝丄斵彈偺恖娫偲偟偰偺婍偺彫偝偝傪帵偟偰偄傞丅
崱夞偺搳昜偵嵺偟偰偼丄埨晹偑夁戝偵慀傝棫偰偨杒挬慛婋婡偵梮傜偝偣偰帺柉搣偵昜傪擖傟偨恖傕彮側偔側偐偭偨傛偆偩偟丄搳昜偟偰傕壗傕曄傢傜側偄偲偄偆掹傔偺婥帩偪偐傜婞尃偟偨恖傕偄偨偱偁傠偆丅偟偐偟丄埨攞惌尃偺朶憱偲偙偺崙偺備偔偊傪桱偆恖傕偨偔偝傫偄傞偼偢偩丅棫寷柉庡搣偑恖婥傪摼偨偺偼丄偨傫偵敾姱孥洖偺摨忣昜偩偗偐傜偱偼側偄偩傠偆丅晠偭偨惌帯偺尰忬傪懪攋偟偨偄偲巚偭偰偄傞恖偨偪偑棫寷柉庡搣傪巟帩偟偨偺偩丅棫寷柉庡搣偼儕儀儔儖攈偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞偑丄幚嵺偺偲偙傠偼愴屻偺擔杮傪庡摫偟偨拞摴曐庣偺宯晥偵偮側偑傞搣偩偲巚偆丅偙傟偐傜栰搣嵞曇偑偁傞偺偐偳偆偐暘偐傜側偄偑丄栰搣戞1搣偵側偭偨偙偺搣偵偼丄妉摼偟偨媍惾偼彮側偄偗傟偳丄埨晹偵堦朅悂偐偟偰傕傜偄偨偄丅
2017.01.10 (壩) 擭巒嶨姶
埨攞惌尃偺朶憱偼傑偡傑偡帟巭傔偑偒偐側偔側偭偰偄傞丅栰搣偺偩傜偟側偝丄帺柉搣撪儕儀儔儖攈偺偍慹枛偝偼栚傪暍偆偽偐傝偩偑丄偦傟偵傕憹偟偰斶嶴側偺偼儊僨傿傾偺崢敳偗傇傝偲崙柉偺廬弴傇傝偩丅姱揁偺湗妳偑岟傪憈偟偰偄傞偺偩傠偆偐丄儅僗僐儈偼惌晎偺敪昞傗弌棃偟偨帠徾傪偦偺傑傑曬偠傞偩偗偱丄媆嵩傗嫊婾傪傑偭偨偔捛媮偟傛偆偲偟側偄丅偦偟偰丄偙傟偩偗幐惌傗埆惌偑懕偄偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄崙柉偐傜埨攞偺戅恮傪梫媮偡傞嫨傃惡偑忋偑傜側偄丅擔杮恖偼戝恖偟偡偓傞丅偦偺揰偱偼丄杙戝摑椞傪怑柋掆巭偵捛偄崬傫偩娯崙崙柉傗丄寢壥偺椙偟埆偟偼偲傕偐偔丄曄壔傪媮傔偰僩儔儞僾傪戝摑椞偵慖傫偩傾儊儕僇崙柉傪尒廗傢側偗傟偽側傜側偄丅
 悽奅偱偼姲梕偺惛恄偑婓敄偵側傝丄曃嫹側僫僔儑僫儕僘儉偑摢傪傕偨偘傛偆偲偟偰偄傞丅偦傫側側偐偱丄EU偺摦岦丄拞搶偺忣惃傕婥偵側傞偑丄崱擭拲栚偝傟傞偺偼丄傗偼傝暷崙偺怴戝摑椞僩儔儞僾偑偳傫側惌帯傪峴側偆偐偩丅僩儔儞僾偼朶尵傪揻偄偨丅偩偑斵偼旤帿楉嬪偱偼側偔杮壒偱岅偭偨丅偦傟偑暷崙偺敿暘偺恖娫偵嫟姶傪梌偊偨偺偩丅偟偐偟丄偦偺杮壒傪幚峴偵堏偟偨傜丄暷崙偼崿柪偡傞丅暷崙偺崿柪偼悽奅偵崿棎傪傕偨傜偡丅悐偊偨偲偼偄偊丄暷崙偼偄傑偩偵宱嵪揑偵傕孯帠揑偵傕埑搢揑側椡傪傕偮悽奅堦偺戝崙偱偁傝丄偦偺摦岦偑悽奅偵梌偊傞塭嬁偼戝偒偄丅僩儔儞僾偑帺枬偲湗妳偩傜偗偺僣傿僢僞乕偱敪偡傞尵梩偵摉帠幰偨偪偑堦婌堦桱偡傞巔偼丄柍條傪捠傝墇偟偰妸宮偩偑丄儘僔傾偑僒僀僶乕峌寕偱暷戝摑椞慖偵夘擖偟偨栤戣偼僩儔儞僾偵偲偭偰堄奜側棊偲偟寠偵側傞偐傕偟傟側偄丅僩儔儞僾怴戝摑椞偑擔偛傠偺尵摦偵増偭偨嫮峝側惌嶔傪幚峴偡傞偺偐丄偦傟偲傕忬嫷偵攝椂偟偮偮廮擃側惌帯傪峴側偆偺偐丄傛偔暘偐傜側偄丅偟偐偟丄斵偑妕椈偵巜柤偟偨楢拞偺宱楌傗峫偊曽乗乗嬌塃偺嵎暿庡媊幰丄岲愴揑側孯恖丄戝婇嬈傗徹寯嬥梈夛幮偺姴晹乗乗傪尒傞偲丄偦偺曽岦偼偍偺偢偲柧傜偐偩傠偆丅
悽奅偱偼姲梕偺惛恄偑婓敄偵側傝丄曃嫹側僫僔儑僫儕僘儉偑摢傪傕偨偘傛偆偲偟偰偄傞丅偦傫側側偐偱丄EU偺摦岦丄拞搶偺忣惃傕婥偵側傞偑丄崱擭拲栚偝傟傞偺偼丄傗偼傝暷崙偺怴戝摑椞僩儔儞僾偑偳傫側惌帯傪峴側偆偐偩丅僩儔儞僾偼朶尵傪揻偄偨丅偩偑斵偼旤帿楉嬪偱偼側偔杮壒偱岅偭偨丅偦傟偑暷崙偺敿暘偺恖娫偵嫟姶傪梌偊偨偺偩丅偟偐偟丄偦偺杮壒傪幚峴偵堏偟偨傜丄暷崙偼崿柪偡傞丅暷崙偺崿柪偼悽奅偵崿棎傪傕偨傜偡丅悐偊偨偲偼偄偊丄暷崙偼偄傑偩偵宱嵪揑偵傕孯帠揑偵傕埑搢揑側椡傪傕偮悽奅堦偺戝崙偱偁傝丄偦偺摦岦偑悽奅偵梌偊傞塭嬁偼戝偒偄丅僩儔儞僾偑帺枬偲湗妳偩傜偗偺僣傿僢僞乕偱敪偡傞尵梩偵摉帠幰偨偪偑堦婌堦桱偡傞巔偼丄柍條傪捠傝墇偟偰妸宮偩偑丄儘僔傾偑僒僀僶乕峌寕偱暷戝摑椞慖偵夘擖偟偨栤戣偼僩儔儞僾偵偲偭偰堄奜側棊偲偟寠偵側傞偐傕偟傟側偄丅僩儔儞僾怴戝摑椞偑擔偛傠偺尵摦偵増偭偨嫮峝側惌嶔傪幚峴偡傞偺偐丄偦傟偲傕忬嫷偵攝椂偟偮偮廮擃側惌帯傪峴側偆偺偐丄傛偔暘偐傜側偄丅偟偐偟丄斵偑妕椈偵巜柤偟偨楢拞偺宱楌傗峫偊曽乗乗嬌塃偺嵎暿庡媊幰丄岲愴揑側孯恖丄戝婇嬈傗徹寯嬥梈夛幮偺姴晹乗乗傪尒傞偲丄偦偺曽岦偼偍偺偢偲柧傜偐偩傠偆丅偨偲偊僩儔儞僾偑偳傫側慞惌傪晍偙偆偑丄憺偟傒傗懳棫傪慀傝丄愩愭嶰悺偱恖怱傪捦傫偩昳惈偑掅偄抝偺傗傞偙偲傪丄傏偔偼傑偭偨偔怣梡偟側偄丅偩偑丄怣梡偡傞偟側偄偵娭傢傜偢丄偙傟偐傜悽奅偼偦傫側抝傪憡庤偵奜岎岎徛傪偟側偗傟偽偄偗側偔側傞丅擔杮傕偁傜備傞忣曬傗恖柆傪嬱巊偟丄抦棯傪恠偟偰岻柇偵棫偪夞傜側偗傟偽側傜側偄偑丄偄傑偺埨攞惌尃偱偼丄偦傟偼摓掙偱偒側偄偩傠偆丅側偵偟傠埨攞偼丄帞偄將傛傠偟偔丄僼儔僀儞僌偱僩儔儞僾偲柺択偟偰傂傫偟傘偔傪攦偄丄偳傫側惌嶔傪懪偪弌偡偺偐暘偐傜側偄偺偵丄怴戝摑椞偵側偭偨僩儔儞僾偲恀偭愭偵夛択偟傛偆偲夋嶔偟丄悽奅偺暔徫偄偺揑偵側偭偰偄傞丅偟偐傕丄奺崙偵愭嬱偗偰僩儔儞僾偵夛偆偙偲傪帺枬偡傞偺偩偐傜丄嬸楎偺嬌傒偩丅
偦偟偰擔杮偱偼丄塃梼崙悎庡媊幰偺懁嬤偵埻傑傟丄柍擻柍嶔側戝恇傪廬偊偨埨攞怶嶰偺撈嵸偑偲偆傇傫懕偔偙偲偵側傞丅幮夛曐忈旓偺廩幚側偳偼妡偗惡偩偗丄朢偟偄崙壠梊嶼偺側偐偱丄埨攞惌尃偼杊塹旓偲岞嫟帠嬈旓傪撍弌偟偰憹嫮偝偣傞丅寷朄夵埆偵懌傪摜傒弌偡偺偼帪娫偺栤戣偩丅柉恑搣偼傕偼傗暘楐忬懺偱栰搣偲偟偰偺婡擻傪壥偨偟偰偍傜偢丄惌晎梌搣偐傜姰慡偵攏幁偵偝傟偰偄傞丅桞堦丄埨攞偺懳峈惃椡偲偟偰婜懸偑傕偰傞偺偼彫抮昐崌巕偩傠偆丅傏偔偼彫抮傪恖娫揑偵岲偒偵側傟側偄偑丄偟偨偨偐側惌帯壠偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偄丅彫抮偼怴搣偺寢惉傪弨旛偟偰偄傞偲暦偔偑丄偦偙偵帺柉搣傗柉恑搣偐傜尰惌尃偵晄枮傪帩偮媍堳偑寢廤偡傟偽丄桳岠側梷巭椡偑惗傑傟丄埨攞偺愱墶偺懪攋偵偮側偑傞偐傕偟傟側偄丅
2016.12.26 (寧) 2016擭奀奜塮夋儀僗僩10
1丂亀僽儕僢僕丒僆僽丒僗僷僀亁 娔撀丗僗僥傿乕償儞丒僗僺儖僶乕僌 乮暷乯1埵偺乽僽儕僢僕丒僆僽丒僗僷僀乿偵偮偄偰偼1寧30擔晅偗偺杮棑偱婰偟偨丅帪戙偼1950擭戙枛偐傜60擭戙弶傔偵偐偗偰丄僯儏乕儓乕僋偺曎岇巑偱偁傞庡恖岞偼曃嫹側垽崙庡媊幰偨偪偺拞彎傗嫼敆偵夛偄側偑傜丄怣擮傪娧偒丄曔傑偭偨僜楢僗僷僀偺嵸敾偱曎岇偵摉偨傞丅傗偑偰丄偙偺暈栶偟偨僜楢僗僷僀偲丄
2丂亀僴僪僜儞愳偺婏愓亁 娔撀丗僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪 乮暷乯
3丂亀岾偣側傂偲傝傏偭偪亁 娔撀丗僴儞僱僗丒儂儖儉 乮僗僂僃乕僨儞乯
4丂亀僽儖僢僋儕儞亁 娔撀丗僕儑儞丒僋儘乕儕乕 乮傾僀儖儔儞僪丒塸丒壛乯
5丂亀儗償僃僫儞僩乣酳偊傝偟幰亁 娔撀丗傾儗僴儞僪儘丒僀僯儍儕僩僁 乮暷乯
6丂亀僸僢僠僐僢僋乛僩儕儏僼僅乕亁 娔撀丗働儞僩丒僕儑乕儞僘 乮暷丒暓乯
7丂亀僨傿乕僷儞偺摤偄亁 娔撀丗僕儍僢僋丒僆乕僨傿傾乕儖 乮暓乯
8丂亀婏愔偑偔傟偨悢幃亁 娔撀丗儅僔儏乕丒僽儔僂儞 乮塸乯
9丂亀僆僨僢僙僀亁 娔撀丗儕僪儕乕丒僗僐僢僩 乮暷乯
10丂亀僉儍儘儖亁 娔撀丗僩僢僪丒僿僀儞僘 乮塸丒暷丒暓乯
 僗僷僀旘峴拞偵僜楢偵寕捘偝傟偰懆傢傟偨暷孯僷僀儘僢僩偲偺曔椄岎姺傪幚尰偝偣傞偨傔丄庡恖岞偼搶儀儖儕儞偵岦偐偆丅椻愴帪戙偺暷僜偺惌帯揑嬱偗堷偒丄暻傪寶愝拞偺儀儖儕儞偺奨丄摉帪偺幮夛晽懎側偳偺惗乆偟偄昤幨偼敆椡偵枮偪偰偍傝丄僩儉丒僴儞僋僗埲壓偺弌墘幰偨偪偺帺慠側墘媄傕慺惏傜偟偄丅幚榖偵婎偯偔姶摦揑側柤嶌偩丅2埵偺僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪偺乽僴僪僜儞愳偺婏愓乿傕僄儞僞僥僀儞儊儞僩塮夋偲偟偰嵟崅儔儞僋偵擖傞寙嶌丅偙傟傕僩儉丒僴儞僋僗庡墘偩丅僯儏乕儓乕僋偺僯儏乕傾乕僋嬻峘傪旘傃棫偭偰捈屻丄僶乕僪僗僩儔僀僋偱憖廲晄擻偵娮偭偨旘峴婡傪僴僪僜儞愳偵晄帪拝偝偣傞偲偄偆僔儞僾儖側幚榖傪丄傛偔偙傟傎偳婲暁偵晉傫偩丄墱峴偒偺偁傞塮夋偵偱偒偨傕偺偩丅86嵨偲偄偆榁楊側偺偵丄榁偄偰傑偡傑偡崅傑傞僀乕僗僩僂僢僪偺嶌寑弍偺岻傒偝偵姶怱偡傞丅
僗僷僀旘峴拞偵僜楢偵寕捘偝傟偰懆傢傟偨暷孯僷僀儘僢僩偲偺曔椄岎姺傪幚尰偝偣傞偨傔丄庡恖岞偼搶儀儖儕儞偵岦偐偆丅椻愴帪戙偺暷僜偺惌帯揑嬱偗堷偒丄暻傪寶愝拞偺儀儖儕儞偺奨丄摉帪偺幮夛晽懎側偳偺惗乆偟偄昤幨偼敆椡偵枮偪偰偍傝丄僩儉丒僴儞僋僗埲壓偺弌墘幰偨偪偺帺慠側墘媄傕慺惏傜偟偄丅幚榖偵婎偯偔姶摦揑側柤嶌偩丅2埵偺僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪偺乽僴僪僜儞愳偺婏愓乿傕僄儞僞僥僀儞儊儞僩塮夋偲偟偰嵟崅儔儞僋偵擖傞寙嶌丅偙傟傕僩儉丒僴儞僋僗庡墘偩丅僯儏乕儓乕僋偺僯儏乕傾乕僋嬻峘傪旘傃棫偭偰捈屻丄僶乕僪僗僩儔僀僋偱憖廲晄擻偵娮偭偨旘峴婡傪僴僪僜儞愳偵晄帪拝偝偣傞偲偄偆僔儞僾儖側幚榖傪丄傛偔偙傟傎偳婲暁偵晉傫偩丄墱峴偒偺偁傞塮夋偵偱偒偨傕偺偩丅86嵨偲偄偆榁楊側偺偵丄榁偄偰傑偡傑偡崅傑傞僀乕僗僩僂僢僪偺嶌寑弍偺岻傒偝偵姶怱偡傞丅3埵偺僗僂僃乕僨儞塮夋乽岾偣側傂偲傝傏偭偪乿偼丄崅楊壔幮夛偲側偭偨嬤擭偁偪偙偪偱嶌傜傟偰偄傞丄
 屒撈側榁恖偑庡恖岞偺塮夋丅嵢傪朣偔偟丄恖惗偵愨朷偟偨丄嗄夘屌铔丄寵傢傟幰偺僕僕僀偑丄嬤強偵堷偭墇偟偰偒偨僀儔儞偐傜堏廧偟偨壠懓偲怗傟崌偆偆偪偵恖娫惈傪庢傝栠偡偲偄偆丄乽僌儔儞丒僩儕僲乿偲乽僇乕儖偠偄偝傫偺嬻旘傇壠乿乮朻摢偺10暘娫乯傪儈僢僋僗偟偨傛偆側僗僩乕儕乕丅傛偔偁傞榖偟偩偑丄岅傝岥偑偆傑偄偺偱娫慠偡傞偲偙傠偑側偄丅僐儈僇儖側応柺揥奐丄偲偙傠偳偙傠偱忴偟弌偝傟傞傎偺偐側帊忣偲悘強偵憓擖偝傟傞榁恖偺庒偒擔偺僄僺僜乕僪偑岠壥傪忋偘偰偄傞丅4埵偺乽僽儖僢僋儕儞乿偼丄1950擭戙弶摢丄傾僀儖儔儞僪偐傜僯儏乕儓乕僋偺僽儖僢僋儕儞偵堏廧偟偨庒偄彈惈偺暔岅丅屘嫿傾僀傾儖儔儞僪傊偺垽憺擖傝崿偠偭偨憐偄丄怴揤抧僯儏乕儓乕僋偱偺斶婌偙傕偛傕偺惗妶偑垼娊備偨偐偵捲傜傟傞丅僔僠儏僄乕僔儑儞偼彮偟娒偄偑嫋梕斖埻撪偱偁傝丄屻枴偼憉傗偐偩丅屄惈揑側晽杄偺彮彈攐桪偲偟偰乽儔僽儕乕儃乕儞乿傗乽僴儞僫乿偱嫮偄報徾傪梌偊偨僔傾乕僔儍丒儘乕僫儞偺丄戝恖偺彈惈偲偟偰偺梷偊偨墘媄偵怱庝偐傟傞丅
屒撈側榁恖偑庡恖岞偺塮夋丅嵢傪朣偔偟丄恖惗偵愨朷偟偨丄嗄夘屌铔丄寵傢傟幰偺僕僕僀偑丄嬤強偵堷偭墇偟偰偒偨僀儔儞偐傜堏廧偟偨壠懓偲怗傟崌偆偆偪偵恖娫惈傪庢傝栠偡偲偄偆丄乽僌儔儞丒僩儕僲乿偲乽僇乕儖偠偄偝傫偺嬻旘傇壠乿乮朻摢偺10暘娫乯傪儈僢僋僗偟偨傛偆側僗僩乕儕乕丅傛偔偁傞榖偟偩偑丄岅傝岥偑偆傑偄偺偱娫慠偡傞偲偙傠偑側偄丅僐儈僇儖側応柺揥奐丄偲偙傠偳偙傠偱忴偟弌偝傟傞傎偺偐側帊忣偲悘強偵憓擖偝傟傞榁恖偺庒偒擔偺僄僺僜乕僪偑岠壥傪忋偘偰偄傞丅4埵偺乽僽儖僢僋儕儞乿偼丄1950擭戙弶摢丄傾僀儖儔儞僪偐傜僯儏乕儓乕僋偺僽儖僢僋儕儞偵堏廧偟偨庒偄彈惈偺暔岅丅屘嫿傾僀傾儖儔儞僪傊偺垽憺擖傝崿偠偭偨憐偄丄怴揤抧僯儏乕儓乕僋偱偺斶婌偙傕偛傕偺惗妶偑垼娊備偨偐偵捲傜傟傞丅僔僠儏僄乕僔儑儞偼彮偟娒偄偑嫋梕斖埻撪偱偁傝丄屻枴偼憉傗偐偩丅屄惈揑側晽杄偺彮彈攐桪偲偟偰乽儔僽儕乕儃乕儞乿傗乽僴儞僫乿偱嫮偄報徾傪梌偊偨僔傾乕僔儍丒儘乕僫儞偺丄戝恖偺彈惈偲偟偰偺梷偊偨墘媄偵怱庝偐傟傞丅5埵偺乽儗償僃僫儞僩乣酳偊傝偟幰乿偼傾儊儕僇惣晹奐戱帪戙偺幚榖傪婎偵偟偨塮夋丅嬌姦偺峳栰偱丄昺巰偺廳彎傪晧偄丄拠娫偵棤愗傜傟丄懅巕傪嶦偝傟偨悌椔巘偺暅廞鏉丅帩偭偰夞偭偨傛偆側巚傢偣傇傝側嶣傝曽傪偡傞娔撀偺僀僯儍儕僩僁偼偁傑傝岲偒側塮夋嶌壠偱偼側偄偑丄偙偺塮夋偼僗僩儗乕僩偱暘偐傝傗偡偄丅夁崜側帺慠丄惗偲暅廞傊偺惁愨側杮擻偑丄敆椡偨偭傉傝偵昤偐傟傞丅6埵偺乽僸僢僠僐僢僋乛僩儕儏僼僅乕乿偼塮夋僼傽儞傪摡慠偲偝偣傞僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋丅1966擭偵弌斉偝傟偨乽塮夋弍 僸僢僠僐僢僋乛僩儕儏僼僅乕乿偼塮夋嶌壠偵偲偭偰僶僀僽儖偲側偭偨懳榖杮偩偑丄杮嶌昳偼偙偺杮偺偨傔偺僸僢僠僐僢僋偲僩儕儏僼僅乕偺懳榖僥乕僾壒尮傪拞怱偵丄偝傑偞傑側娔撀傊偺僀儞僞價儏乕丄僸僢僠僐僢僋塮夋偐傜偺敳悎側偳傪怐傝岎偤偰峔惉偝傟偰偍傝丄塮憸僥僋僯僢僋偺柺敀偝傪姮擻偱偒傞丅
 7埵埲壓偼妱垽偡傞偑丄偦偺戙傢傝偵丄愭擔WOWOW偱尒偨塮夋乽儂儚僀僩丒僑僢僪乿偵偮偄偰怗傟偰偍偒偨偄丅嶐擭枛偵岞奐偝傟偰婥偵側偭偰偄偨偑尒摝偟偰偟傑偭偨嶌昳偩丅捒偟偔僴儞僈儕乕偺塮夋偱丄彮彈偲將偺暔岅偩偑丄撪梕偼偦偺尵梩偐傜庴偗傞傎偺傏偺偲偟偨報徾偲偼傑偭偨偔偐偗棧傟偰偍傝丄媠懸偝傟偨將偑廤抍偲側偭偰恖娫偨偪偵斀婙傪東偡偲偄偆榖丅柧傜偐偵僒儈儏僄儖丒僼儔乕偑屻婜偵嶌偭偨堎怓嶌乽儂儚僀僩丒僪僢僌乿乮崟恖傪峌寕偡傞傛偆挷嫵偝傟偨將偲丄偦傟傪側傫偲偐晛捠偺將偵栠偦偆偲帋傒傞彈偺暔岅乯傪壓晘偒偵偟偰偄傞丅僽僟儁僗僩偺奨傪將偺戝孮偑幘憱偡傞僔乕儞乮CG偼偄偭偝偄巊偭偰偄側偄乯偼丄偁傞庬丄彇帠帊傔偄偨庯偑偁傝丄恖娫傪廝偆將偑壗傪徾挜偟偰偄傞偺偐丄偄傠偄傠側夝庍偑偱偒傞偩傠偆丅徫婄傪傎偲傫偳尒偣側偄彮彈偺尩偟偄昞忣偑報徾怺偄丅恖娫娭學偑婓敄偵尒偊傞偺偼僴儞僈儕乕偺崙暱偱偁傠偆偐丅乽儂儚僀僩丒僪僢僌乿偺僔價傾乕側僄儞僨傿儞僌偵斾傋偰丄寢枛偑娒偄偙偲偑丄偙偺塮夋偺桞堦偺庛揰偩丅
7埵埲壓偼妱垽偡傞偑丄偦偺戙傢傝偵丄愭擔WOWOW偱尒偨塮夋乽儂儚僀僩丒僑僢僪乿偵偮偄偰怗傟偰偍偒偨偄丅嶐擭枛偵岞奐偝傟偰婥偵側偭偰偄偨偑尒摝偟偰偟傑偭偨嶌昳偩丅捒偟偔僴儞僈儕乕偺塮夋偱丄彮彈偲將偺暔岅偩偑丄撪梕偼偦偺尵梩偐傜庴偗傞傎偺傏偺偲偟偨報徾偲偼傑偭偨偔偐偗棧傟偰偍傝丄媠懸偝傟偨將偑廤抍偲側偭偰恖娫偨偪偵斀婙傪東偡偲偄偆榖丅柧傜偐偵僒儈儏僄儖丒僼儔乕偑屻婜偵嶌偭偨堎怓嶌乽儂儚僀僩丒僪僢僌乿乮崟恖傪峌寕偡傞傛偆挷嫵偝傟偨將偲丄偦傟傪側傫偲偐晛捠偺將偵栠偦偆偲帋傒傞彈偺暔岅乯傪壓晘偒偵偟偰偄傞丅僽僟儁僗僩偺奨傪將偺戝孮偑幘憱偡傞僔乕儞乮CG偼偄偭偝偄巊偭偰偄側偄乯偼丄偁傞庬丄彇帠帊傔偄偨庯偑偁傝丄恖娫傪廝偆將偑壗傪徾挜偟偰偄傞偺偐丄偄傠偄傠側夝庍偑偱偒傞偩傠偆丅徫婄傪傎偲傫偳尒偣側偄彮彈偺尩偟偄昞忣偑報徾怺偄丅恖娫娭學偑婓敄偵尒偊傞偺偼僴儞僈儕乕偺崙暱偱偁傠偆偐丅乽儂儚僀僩丒僪僢僌乿偺僔價傾乕側僄儞僨傿儞僌偵斾傋偰丄寢枛偑娒偄偙偲偑丄偙偺塮夋偺桞堦偺庛揰偩丅
2016.12.22 (栘) 2016擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
1丂亀儈儗僯傾儉4乣抴鍋偺憙傪暐偆彈亁僟償傿僪丒儔乕僎儖僋儔儞僣乮憗愳彂朳乯
2丂亀埫嶦幰偺斀寕亁 儅乕僋丒僌儕乕僯乕 乮僴儎僇儚暥屔乯
3丂亀僕儑僀儔儞僪亁 僗僥傿乕償儞丒僉儞僌 乮暥弔暥屔乯
4丂亀楾偺椞堟亁 C丒J丒儃僢僋僗 乮島択幮暥屔乯
5丂亀偦偺愥偲寣傪亁 僕儑乕丒僱僗儃 乮僴儎僇儚丒儈僗僥儕乯
6丂亀愵摦幰亁 僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕 乮暥錣弔廐乯
7丂亀儕儃儖僶乕丒儕儕乕亁 挿塝嫗 乮島択幮乯
8丂亀僈儞儖乕僕儏亁 寧懞椆塹 乮暥錣弔廐乯
9丂亀揮棊偺奨亁 儅僀僋儖丒僐僫儕乕 乮島択幮暥屔乯
10丂亀僓丒僇儖僥儖亁 僪儞丒僂傿儞僘儘僂 乮妏愳暥屔乯
 1埵偺乽儈儗僯傾儉4乿偵偮偄偰偼4寧16擔晅偗偺偙偺僐儔儉偱彂偄偨丅媽3晹嶌偵懕偒丄怴偟偄嶌壠偵傛偭偰嵞僗僞乕僩偟偨怴乽儈儗僯傾儉乿僔儕乕僘偺戞1嶌偩丅庡恖岞偺儕僗儀僢僩偼媽嶌偲摨偠僉儍儔僋僞乕愝掕偺傕偲丄嫻偺偡偔傛偆側妶桇傪尒偣傞偟丄怴偨偵搊応偡傞恖暔偨偪傕岻傒偵昤偒暘偗傜傟偰偍傝丄僗僺乕僨傿側揥奐丄婲暁偵晉傫偩僾儘僢僩傕慛傗偐偩丅
1埵偺乽儈儗僯傾儉4乿偵偮偄偰偼4寧16擔晅偗偺偙偺僐儔儉偱彂偄偨丅媽3晹嶌偵懕偒丄怴偟偄嶌壠偵傛偭偰嵞僗僞乕僩偟偨怴乽儈儗僯傾儉乿僔儕乕僘偺戞1嶌偩丅庡恖岞偺儕僗儀僢僩偼媽嶌偲摨偠僉儍儔僋僞乕愝掕偺傕偲丄嫻偺偡偔傛偆側妶桇傪尒偣傞偟丄怴偨偵搊応偡傞恖暔偨偪傕岻傒偵昤偒暘偗傜傟偰偍傝丄僗僺乕僨傿側揥奐丄婲暁偵晉傫偩僾儘僢僩傕慛傗偐偩丅2埵偺乽埫嶦幰偺斀寕乿偼朻尟彫愢僼傽儞傪擬嫸偝偣傞僌儗僀儅儞丒僔儕乕僘偺戞5嶌丅帺暘偑側偤CIA偐傜柦傪慱傢傟傞偺偐丄偦偺棟桼傪扵傞偨傔傾儊儕僇偵愽擖偟偨庡恖岞偑巋媞偲巰摤傪孞傝峀偘側偑傜恀憡傪撍偒巭傔傞丅偙傟傑偱偺嶌昳偲斾傋偰愴摤僔乕儞偼峊偊傔偩偑丄撪梕偼憡曄傢傜偢埑搢揑偵柺敀偄丅僌儗僀儅儞偺暔岅偼偙偺嶌昳偱偄偪偍偆戞1婜偺僺儕僆僪偑懪偨傟偨丅偙傟偐傜巒傑傞戞2婜偺斵偺朻尟偵婜懸偟偨偄丅
 3埵偺乽僕儑僀儔儞僪乿偼僗僥傿乕償儞丒僉儞僌偺彫昳偩偑丄姶摦傪桿偆價僞乕僗僀乕僩側惵弔儈僗僥儕乕彫愢丅奀曈偺屆傏偗偨梀墍抧偱傾儖僶僀僩傪偡傞戝妛惗偺傂偲壞偺宱尡偑夞憐宍幃偱昤偐傟傞丅梀墍抧偱婲偙傞婏柇側弌棃帠丄嬤強偵廧傓曣巕偲偺弌夛偄偑丄旤偟偄僙儞僥傿儊儞僩偲僲僗僞儖僕乕傪惗傒弌偟偰偄傞丅庡恖岞偺惵擭偼偦偺壞偺宱尡傪宱偰戝恖傊偲椃棫偮丅桯楈傕弌偰偔傞偑丄儂儔乕怓偼偦傟傎偳嫮偔側偄丅寵傒偺側偄娒偝偲愗側偝偑怱偵煄傒傞丅僉儞僌偺彫愢偼摨帪婜偵乽儈僗僞乕丒儊儖僙僨僗乿偲偄偆戝嶌偺儈僗僥儕乕彫愢偑姧峴偝傟丄偦偪傜傕椡偑偙傕偭偰偄傞偑丄摨庯岦偺彫愢傪彂偔僨傿乕償傽乕偺岻偝偵斾傋傞偲丄傕偆傂偲偮惙傝忋偑傝偵寚偗偰偄偨丅4埵偺乽楾偺椞堟乿偼C丒J丒儃僢僋僗偵傛傞椔嬫娗棟姱僕儑乕丒僺働僢僩傪庡恖岞偲偡傞僔儕乕僘偺怴嶌丅惓媊姶偲愑擟姶偼嫮偄偑朶椡偼嬯庤側庡恖岞偑忴偟弌偡妋屌偨傞懚嵼姶偑枺椡傪屇傇丅戝帺慠偺旤偟偝偲尩偟偝偑偰偄偹偄偵昤偒崬傑傟偰偍傝丄庡恖岞傪彆偗傞僱僀僩偲偄偆抝偺嫮楏側屄惈偵庝偒偮偗傜傟傞丅
3埵偺乽僕儑僀儔儞僪乿偼僗僥傿乕償儞丒僉儞僌偺彫昳偩偑丄姶摦傪桿偆價僞乕僗僀乕僩側惵弔儈僗僥儕乕彫愢丅奀曈偺屆傏偗偨梀墍抧偱傾儖僶僀僩傪偡傞戝妛惗偺傂偲壞偺宱尡偑夞憐宍幃偱昤偐傟傞丅梀墍抧偱婲偙傞婏柇側弌棃帠丄嬤強偵廧傓曣巕偲偺弌夛偄偑丄旤偟偄僙儞僥傿儊儞僩偲僲僗僞儖僕乕傪惗傒弌偟偰偄傞丅庡恖岞偺惵擭偼偦偺壞偺宱尡傪宱偰戝恖傊偲椃棫偮丅桯楈傕弌偰偔傞偑丄儂儔乕怓偼偦傟傎偳嫮偔側偄丅寵傒偺側偄娒偝偲愗側偝偑怱偵煄傒傞丅僉儞僌偺彫愢偼摨帪婜偵乽儈僗僞乕丒儊儖僙僨僗乿偲偄偆戝嶌偺儈僗僥儕乕彫愢偑姧峴偝傟丄偦偪傜傕椡偑偙傕偭偰偄傞偑丄摨庯岦偺彫愢傪彂偔僨傿乕償傽乕偺岻偝偵斾傋傞偲丄傕偆傂偲偮惙傝忋偑傝偵寚偗偰偄偨丅4埵偺乽楾偺椞堟乿偼C丒J丒儃僢僋僗偵傛傞椔嬫娗棟姱僕儑乕丒僺働僢僩傪庡恖岞偲偡傞僔儕乕僘偺怴嶌丅惓媊姶偲愑擟姶偼嫮偄偑朶椡偼嬯庤側庡恖岞偑忴偟弌偡妋屌偨傞懚嵼姶偑枺椡傪屇傇丅戝帺慠偺旤偟偝偲尩偟偝偑偰偄偹偄偵昤偒崬傑傟偰偍傝丄庡恖岞傪彆偗傞僱僀僩偲偄偆抝偺嫮楏側屄惈偵庝偒偮偗傜傟傞丅 5埵偺僲儖僂僃乕偺嶌壠僕儑乕丒僱僗儃偵傛傞乽偦偺愥偲寣傪乿偼僋儕僗儅僗偺帪婜丄尩搤偺僆僗儘偑晳戜丅杻栻慻怐偺嶦偟壆偑儃僗偺嵢傪嶦偡傛偆柦偠傜傟傞偑丄嶦偟壆偼昗揑偺彈偵楒偟偰偟傑偆丅堦庬偺埆彈傕偺彫愢偱偁傝丄僼傿儖儉僲儚乕儖偺庯偒傪昚傢偣傞埫偄忣姶偲帊揑側昤幨偑廏堩丅朻摢偺報徾揑側嶦偟偺僔乕儞偐傜垼愗姶昚偆僄儞僨傿儞僌傑偱丄慡曇偵傢偨偭偰昤偐傟傞庡恖岞偺垼偟偄惗偒偞傑偑怱傪懪偮丅6埵偺僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕嶌乽愵摦幰乿偼恎怳傝傗昞忣偐傜恖偺巚峫傪撉傒庢傞僉僱僔僋僗偺愱栧壠偱偁傞憑嵏姱僉儍僒儕儞丒僟儞僗丒僔儕乕僘偺戞4嶌丅崱嶌偱僟儞僗偼廤抍傪僷僯僢僋偵嬱傝棫偰偰柍嵎暿嶦恖傪孞傝曉偡嫢埆斊傪捛偆丅擇揮嶰揮偡傞僗僩乕儕乕揥奐偼儁乕僕傪孞傞庤傪媥傑偣側偄丅壠懓傗楒恖側偳丄僟儞僗偺屄恖惗妶傕嫽庯朙偐偵昤偐傟偰偍傝丄偄偮傕側偑傜僨傿乕償傽乕偺岻偝偵扙朮偡傞丅
5埵偺僲儖僂僃乕偺嶌壠僕儑乕丒僱僗儃偵傛傞乽偦偺愥偲寣傪乿偼僋儕僗儅僗偺帪婜丄尩搤偺僆僗儘偑晳戜丅杻栻慻怐偺嶦偟壆偑儃僗偺嵢傪嶦偡傛偆柦偠傜傟傞偑丄嶦偟壆偼昗揑偺彈偵楒偟偰偟傑偆丅堦庬偺埆彈傕偺彫愢偱偁傝丄僼傿儖儉僲儚乕儖偺庯偒傪昚傢偣傞埫偄忣姶偲帊揑側昤幨偑廏堩丅朻摢偺報徾揑側嶦偟偺僔乕儞偐傜垼愗姶昚偆僄儞僨傿儞僌傑偱丄慡曇偵傢偨偭偰昤偐傟傞庡恖岞偺垼偟偄惗偒偞傑偑怱傪懪偮丅6埵偺僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕嶌乽愵摦幰乿偼恎怳傝傗昞忣偐傜恖偺巚峫傪撉傒庢傞僉僱僔僋僗偺愱栧壠偱偁傞憑嵏姱僉儍僒儕儞丒僟儞僗丒僔儕乕僘偺戞4嶌丅崱嶌偱僟儞僗偼廤抍傪僷僯僢僋偵嬱傝棫偰偰柍嵎暿嶦恖傪孞傝曉偡嫢埆斊傪捛偆丅擇揮嶰揮偡傞僗僩乕儕乕揥奐偼儁乕僕傪孞傞庤傪媥傑偣側偄丅壠懓傗楒恖側偳丄僟儞僗偺屄恖惗妶傕嫽庯朙偐偵昤偐傟偰偍傝丄偄偮傕側偑傜僨傿乕償傽乕偺岻偝偵扙朮偡傞丅崙撪儈僗僥儕乕偐傜偼2嶌偺偡偖傟偨朻尟彫愢傪儔儞僋僀儞偝偣偨丅7埵偺乽儕儃儖僶乕丒儕儕乕乿偼戝惓枛婜偺娭搶偲搶嫗偑晳戜丅偐偮偰摿柋婡娭偱孭楙偝傟偨旤杄偺惁榬彈惈嶦偟壆偑丄棨孯晹戉偲儎僋僓偐傜慱傢傟傞彫妛惗偺抝偺巕傪彆偗丄惁嶴側愴偄傪孞傝峀偘側偑傜埨廧偺抧傪栚巜偡丅塮夋乽僌儘儕傾乿傗乽儗僆儞乿傪渇渋偲偝偣傞捝夣側彫愢丅8埵偺乽僈儞儖乕僕儏乿傕帡偨傛偆側僗僩乕儕乕偱丄孮攏偺壏愹嫿傪晳戜偵丄尦岞埨僄儕乕僩偺庡晈偲尦儘僢僇乕偺彈懱堢嫵巘偑丄杒挬慛摿柋岺嶌堳偺堦抍偵桿夳偝傟偨巕嫙偨偪傪扗娨偡傋偔暠摤偡傞暔岅丅偄偢傟傕峳搨柍宮偲尵偭偰偟傑偊偽偦傟傑偱偩偑丄堦婥撉傒偝偣傞婥敆偲嫽暠偵枮偪偰偄傞丅
 9埵偺乽揮棊偺奨乿偼僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘媣乆偺怴嶌丅儘僗巗寈枹夝寛帠審憑嵏斍偵愋傪抲偔儃僢僔儏偑2偮偺婏夦側帠審傪憑嵏偡傞丅僐僫儕乕偺昅抳偼曄傢傜偢埫偄忣擮偵嵤傜傟偰偍傝丄撉傓幰傪枺椆偡傞丅10埵偺乽僓丒僇儖僥儖乿偼偁偺榖戣偵側偭偨乽將偺椡乿偺屻擔択丅儊僉僔僐偺杻栻墹偲DEA偺憑嵏姱偵傛傞幏擮偺峈憟偑丄杻栻愴憟偵傛偭偰傕偨傜偝傟傞峳椓偨傞晽宨偲偲傕偵昤偐傟傞丅
9埵偺乽揮棊偺奨乿偼僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘媣乆偺怴嶌丅儘僗巗寈枹夝寛帠審憑嵏斍偵愋傪抲偔儃僢僔儏偑2偮偺婏夦側帠審傪憑嵏偡傞丅僐僫儕乕偺昅抳偼曄傢傜偢埫偄忣擮偵嵤傜傟偰偍傝丄撉傓幰傪枺椆偡傞丅10埵偺乽僓丒僇儖僥儖乿偼偁偺榖戣偵側偭偨乽將偺椡乿偺屻擔択丅儊僉僔僐偺杻栻墹偲DEA偺憑嵏姱偵傛傞幏擮偺峈憟偑丄杻栻愴憟偵傛偭偰傕偨傜偝傟傞峳椓偨傞晽宨偲偲傕偵昤偐傟傞丅埲忋偺傎偐丄儅僀僋儖丒僐僫儕乕偵傛傞儕儞僇乕儞曎岇巑僔儕乕僘偺怴嶌乽徹尵嫅斲乿丄尦孻帠偑桿夳偝傟偨彮彈偺媬弌偵幏擮傪擱傗偡僪儞丒僂傿儞僘儘僂偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢乽幐鏗乿丄1910擭戙偺僯儏乕僆乕儕儞僘傪晳戜偵偟偨丄庒偒儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偑廳梫側栶偱搊応偡傞儗僀丒僙儗僗僥傿儞挊乽傾僢僋僗儅儞偺僕儍僘乿丄捒偟偔傾儖僛儞僠儞偺嶌壠僇儕儖丒僼僃儗偵傛傞丄傾儖僛儞僠儞尰戙巎偺埮傪晜偐傃忋偑傜偣偨乽儅僾僠僃偺彈乿丄峴偒応偺側偄抝彈偺攋柵揑側峴摦偑僲儚乕儖怓朙偐偵捲傜傟偨僠儍乕儖僗丒僂傿儖僼僅乕僪偺乽廍偭偨彈乿丄杻栻憑嵏嬊偲杻栻僇儖僥儖偺峌杊傪梊憐奜偺怴慛側庤朄偱昤偄偨M丒A丒儘乕僗儞偺乽扗娨乣彈杻栻憑嵏姱働僀丒僴儈儖僩儞乿側偳丄崱擭偼杮棃偱偁傟偽儀僗僩10偵擖偭偰傕偍偐偟偔側偄愢摼椡偺偁傞偺偁傞嶌昳偑栚敀墴偟偩偭偨丅
2016.10.10 (寧) 5寧偺僶儖僩3崙偱偼僶乕僪丒僠僃儕乕偑壴奐偄偰偄偨
僶儖僩偺崙乆偼儓乕儘僢僷偺彫崙偺椺偵傕傟偢丄儘僔傾傗僪僀僣側偳偺嫮崙偵骧鏦偝傟丄嬯擄偺楌巎傪曕傫偱偒偨丅3崙偲傕丄20悽婭弶摢傑偱偼儘僔傾掗崙偵巟攝偝傟偰偄偨偑丄儘僔傾妚柦偺偺偪1918擭偵偄偭偨傫撈棫偟偨丅偟偐偟戞2師戝愴拞丄僫僠僗丒僪僀僣偑怤峌偟丄撈僜晄壜怤忦栺傪寢傫偩僜楢偲僪僀僣偵傛偭偰愯椞偝傟偨丅愴屻偼僜楢偵暪崌偝傟偰偄偨偑丄1991擭丄僜楢曵夡偵傛偭偰傛偆傗偔撈棫傪壥偨偟偨丅嬤擭偼椞搚奼挘偺栰怱偵擱偊傞僾乕僠儞偑丄
僶儖僩3崙偵偼擔杮偐傜偺捈峴曋偑側偄偺偱丄旘峴婡偼墲楬傕暅楬傕僼傿儞儔儞僪偺僿儖僔儞僉宱桼偩偭偨丅僿儖僔儞僉偐傜2帪娫偐偗偰僼僃儕乕偱僶儖僩奀傪搉偭偰僶儖僩3崙杒抂偺僄僗僩僯傾偵擖傝丄3偮偺崙傪尒偰夞偭偨偁偲丄嵞傃摨偠傛偆偵僿儖僔儞僉偵栠傞偙偲偵側傞丅儓乕儘僢僷偺拞怱偐傜棧傟偰偍傝丄挿傜偔嫟嶻寳偵懏偟偰偄偨偨傔丄偳偺崙傕偗偭偟偰朙偐偱偼側偄丅嶻嬈偼僶僀僆僥僋僲儘僕乕傗栘嵽壛岺偑拞怱偱偁傝丄嵟嬤偼娤岝偵傛傞廂擖傕憹偊偰偄傞偲偄偆丅偩偑丄悽奅拞偳偙偱傕尒偐偗傞拞崙恖偺憶乆偟偄僣傾乕媞偵偼丄偙偙偱偼堦搙傕憳嬾偟側偐偭偨丅儓乕儘僢僷偺拞怱搒巗偲斾傋傞偲傂側傃偨報徾傪書偔偑丄棊偪拝偄偨奨暲傒偼旤偟偐偭偨偟丄屆偄帥堾傗忛嵡側偳偺尒強傕懡偔丄備偭偔傝偲宨娤傪妝偟傓偙偲偑偱偒偨丅
僶儖僩3崙偱偼丄擔杮偱偼尒偐偗側偄丄彫傇傝側敀偄壴偑嶇偔栘偑丄奨側偐傗峹奜側偳丄帄傞偲偙傠偱栚偵偮偄偨丅愥桍傪巚傢偣傞壜楓側壴偩丅僣傾乕丒僈僀僪偵恥偔偲丄乽僶乕僪丒僠僃儕乕乿偲偄偆栘偩偲偄偆丅婣崙偟偰僱僢僩偱挷傋偨傜丄偙偺栘偼儓乕儘僢僷杒晹偵帺惗偡傞僒僋儔偺堦庬偱丄乽僄僝僲僂儚儈僘僓僋儔乿偲偄偆擔杮柤偑偁傞傜偟偄丅応強偵傛偭偰偼栘偺壓偵僞儞億億偑嶇偄偰偍傝丄敀怓偲墿怓偺壴偺庢傝崌傢偣偑栚偵慛傗偐偩偭偨丅
僶儖僩3崙偲偄偊偽丄擔杮偱偄偪偽傫抦傜傟偰偄傞偺偼丄儕僩傾僯傾偱乽柦偺償傿僓乿傪敪媼偟偨悪尨愮悿偺暔岅偱偁傠偆丅戞2師戝愴拞偺1940擭丄摉帪丄椪帪偺庱搒偵側偭偰偄偨僇僫僂僗偺椞帠娰偱椞帠戙棟傪柋傔偰偄偨悪尨偼丄
悪尨偑償傿僓傪敪媼偟偨僇僫僂僗偺媽擔杮椞帠娰偼丄尰嵼丄帒椏娰偲偟偰曐懚偝傟丄堦斒岞奐偝傟偰偄傞丅晛捠偺壠壆偺傛偆側彫偝側椞帠娰偩丅嫹偄幏柋幒偵偼悪尨偑怮怘傪媇惖偵偟偰償傿僓偵彁柤偟偨僨僗僋偑偁偭偨丅庱搒偺償傿儕僯儏僗偵偼悪尨捠傝偲柦柤偝傟偨摴楬傕偁傞丅婣崙偺嵺偺婡拞偱丄偨傑偨傑塮夋僾儘僌儔儉偺側偐偵2015擭偵岞奐偝傟偨搨戲庻柧庡墘偺塮夋乽悪尨愮悿 僗僊僴儔僠僂僱乿偑偁傝丄偦傟傪尒偰悪尨偲偄偆恖暔偲摉帪偺忬嫷偵娭偟丄傛傝怺偄抦幆傪摼傞偙偲偑偱偒偨丅愴慜丄愴屻傪捠偠偰丄杮徣偺孭椷偵斀偟丄帺暘偺怣忦偵廬偭偰峴摦偟偨奜岎姱偑丄偄偭偨偄壗恖偄偨偩傠偆偐丅巹偨偪偼擔杮恖偲偟偰悪尨愮悿傪屩傝偲偟側偗傟偽偄偗側偄丅
乽廫帤壦偺媢乿偼丄儕僩傾僯傾杒晹丄僔儍僂儗僀偲偄偆懞偺嬤偔偵偁傞丅峀偄栰尨偺側偐偵彫崅偄媢偑偁傝丄壗枩杮偵傕媦傇柍悢偺戝彫偝傑偞傑側廫帤壦偱杽傔恠偔偝傟偰偄傞丅堎條側岝宨偩丅朘傟傞娤岝媞偑嫙偊傞廫帤壦偵傛傝丄偦偺悢偼偄傑傕憹偊懕偗偰偄傞丅媢偺傆傕偲偵廫帤壦傪攧偭偰偄傞揦偑偁偭偨偺偱丄傏偔傕彫偝側廫帤壦傪堦杮攦偄丄悽奅偺暯榓傪婩擮偟偰媢偺拞暊偵寶偰偨丅
2016.09.03 (搚) 庒偒僒僢僠儌偑妶桇偡傞堎怓僕儍僘丒儈僗僥儕乕
 僕儍僘傪戣嵽偵偟偨儈僗僥儕乕偼傔偭偨偵側偄丅偨傑偵僕儍僘偑搊応偡傞彫愢傕偁傝丄儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺傛偆偵丄報徾揑偵巊傢傟丄岠壥傪忋偘偰偄傞儈僗僥儕乕傕偁傞偑丄偨偄偰偄偺応崌丄僕儍僘偼攚宨偲偟偰丄暤埻婥傪惙傝忋偘傞慺嵽偲偟偰埖傢傟傞偩偗偩丅偩偐傜丄儗僀丒僙儗僗僥傿儞偑彂偄偨杮嶌乽傾僢僋僗儅儞偺僕儍僘乿偺傛偆偵丄庒偒擔偺儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偑妶桇偡傞儈僗僥儕乕偼婬桳側椺偩偲尵偊傞丅
僕儍僘傪戣嵽偵偟偨儈僗僥儕乕偼傔偭偨偵側偄丅偨傑偵僕儍僘偑搊応偡傞彫愢傕偁傝丄儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺傛偆偵丄報徾揑偵巊傢傟丄岠壥傪忋偘偰偄傞儈僗僥儕乕傕偁傞偑丄偨偄偰偄偺応崌丄僕儍僘偼攚宨偲偟偰丄暤埻婥傪惙傝忋偘傞慺嵽偲偟偰埖傢傟傞偩偗偩丅偩偐傜丄儗僀丒僙儗僗僥傿儞偑彂偄偨杮嶌乽傾僢僋僗儅儞偺僕儍僘乿偺傛偆偵丄庒偒擔偺儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偑妶桇偡傞儈僗僥儕乕偼婬桳側椺偩偲尵偊傞丅偙傟偼1918擭偺僯儏乕僆乕儕儞僘傪晳戜偵偟偨堎怓偺嶌昳偩丅廧柉傪巆擡偵晙偱嶴嶦偡傞楢懕嶦恖婼丄傾僢僋僗儅儞傪捛偭偰丄巹惗妶偵旈枾傪書偊傞寈嶡彁偺庡擟孻帠丄偦偺忋巌偩偭偨丄儅僼傿傾偺庤愭偲偟偰搳崠偝傟丄弌強偟偨偽偐傝偺尦孻帠丄僺儞僇乕僩儞扵掋幮偵嬑傔傞庒偄彈惈偺3恖偑丄偦傟偧傟偺棟桼偐傜斊恖傪捛偆偺偩偑丄扵掋幮偺彈惈偺桭恖偱斵彈傪彆偗傞儈儏乕僕僔儍儞偑傾乕儉僗僩儘儞僌側偺偩丅
僯儏乕僆乕儕儞僘偼峠摂奨偺僗僩乕儕乕償傿儖偑暵嵔偝傟丄壱偓応強傪幐偭偨儈儏乕僕僔儍儞偨偪偼憭媀傪愭摫偡傞儅乕僠儞僌丒僶儞僪傗儈僔僔僢僺愳傪梀棗偡傞忲婥慏偺僟儞僗丒僶儞僪偱屝岥傪偟偺偄偱偄傞丅儖僀偼傑偩18嵨丄嬱偗弌偟偺儈儏乕僕僔儍儞偱丄愇扽偺愊傒弌偟偺傾儖僶僀僩傪傗偭偰偄傞偑丄傔偒傔偒僩儔儞儁僢僩偺榬傪忋偘丄拠娫偐傜拲栚偝傟偰偄傞丅偙偺彫愢偺枺椡偺傂偲偮偼丄庡恖岞偨偪偺僉儍儔僋僞乕偑尒帠偵憿宍偝傟偰偄傞偙偲偩丅庒偒儖僀偵偮偄偰偼丄惗偄棫偪傗峫偊曽偑娙寜偵捲傜傟偰偍傝丄椉恊偑暿傟偰慶曣偵堢偰傜傟偨偙偲丄姶壔堾偵擖傟傜傟丄偦偙偱僩儔儞儁僢僩傪妛傫偩偙偲側偳偑夞憐偺側偐偱慛傗偐偵昤偐傟偰偄傞丅偙傟偼傎傏巎幚偳偍傝偩丅挊幰偼偐側傝傾乕儉僗僩儘儞僌偵偮偄偰尋媶偟偨偵堘偄側偄丅廔斦丄斊恖偑傢偐傞宱堒偼傗傗搨撍偩偟丄庡恖岞偨偪傪懸偪庴偗傞塣柦偵傕堘榓姶傪妎偊傞偑丄僄儞僨傿儞僌偼憉傗偐偩丅
偙偙偵偼丄儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偺僶儞僪拠娫偲偟偰丄僋儔儕僱僢僩偺柤庤僕儑僯乕丒僪僢僘傗丄偦偺掜偺僪儔儅乕丄儀僀價乕丒僪僢僘傕搊応偟偰丄儖僀偲夛榖傪岎傢偡丅傑偨丄儖僀傪僶儞僪偵屬偭偨僉僢僪丒僆儕乕傗僼僃僀僩丒儅儔僽儖丄偝傜偵偼僉儞僌丒僆儕償傽乕傗僕僃儕乕丒儘乕儖丒儌乕僩儞偲偄偭偨僕儍僘偺憂巒幰偨偪偺堩榖傕偱偰偔傞丅巎幚偵傛傞偲丄偙偺偁偲儖僀偼丄堦懌愭偵僔僇僑偵恑弌偟偰偄偨巘彔偺僉儞僌丒僆儕償傽乕偵屇偽傟偰丄1923擭丄僔僇僑偵忋傝丄僆儕償傽乕棪偄傞僋儗僆乕儖丒僕儍僘丒僶儞僪偺儊儞僶乕偵側傝丄婰擮偡傋偒弶榐壒傪宱尡偡傞丅偦偺儗僐乕僪偱挳偐傟傞儖僀偺僜儘偼椡嫮偔敩檹偲偟偰偍傝丄偡偱偵巘偺僆儕償傽乕傪椊夗偟偰偄傞丅偦偺屻丄斵偼僯儏乕儓乕僋偵弌偰僼儗僢僠儍乕丒僿儞僟乕僜儞妝抍偵壛傢偭偨偁偲丄僔僇僑偵栠傝丄巎忋偵柤崅偄儂僢僩丒僼傽僀償丄儂僢僩丒僙償儞偵傛傞悂偒崬傒僙僢僔儑儞傪峴偄丄僕儍僘奅傪惾姫偡傞偙偲偵側傞丅
偙偺彫愢偼丄傾僢僋僗儅儞帠審偐傜悢擭屻丄僔僇僑偱庡恖岞偺2恖偑扵掋幮偺幮堳偲偟偰恖惗傪嵞弌敪偡傞偲偙傠偱廔傢傞偑丄偙傟偼懕曇偑嶌傜傟傞偱偁傠偆偙偲丄偦傟偼1920擭戙偺僔僇僑傪晳戜偵偟偨傕偺偱偁傠偆偙偲丄偦偟偰偦偙偵嵞傃儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偑搊応偟丄斵傜偲偲傕偵妶桇偡傞偱偁傠偆偙偲傪埫帵偟偰偄傞丅懕曇偺敪姧偵婜懸偑崅傑傞丅
2016.08.20 (搚) 儕僆屲椫偱媑揷嵐曐棦慖庤偑棳偟偨椳
偦傫側側偐偱丄挿擭丄愨懳墹幰偲偟偰孨椪偟偰偒偨儗僗儕儞僌彈巕53kg媺偺媑揷嵐曐棦慖庤偼丄寛彑偱攕傟丄嬧儊僟儖偱廔傢偭偰偟傑偭偨丅偁偔傑偱慺恖偺栚偱尒偨姶憐偵偡偓側偄偑丄媑揷慖庤偼弨寛彑傑偱偼偲偰傕偄偄帋崌傪偟偰偄偨丅弨寛彑偺帋崌塣傃傪尒傞偐偓傝丄斵彈偺僷儚乕偼傑偩悐偊偰偄側偐偭偨丅摦偒偵傕僗僺乕僪偑偁偭偨偟丄僞僢僋儖傗僶僢僋傪偲傞摦嶌傕慺憗偐偭偨丅偩偑寛彑偱偼丄憡庤偑媑揷傪傛偔尋媶偟偰偄偨偙偲偵傕傛傞偺偩傠偆偑丄彑偮偩偗偺椡偼偁偭偨偺偵丄彑偪傪堄幆偟偰怲廳偵側傝偡偓丄巚偄愗偭偨媄傪巇妡偗傜傟側偐偭偨傛偆偵姶偠偨丅偦傟偩偗僾儗僢僔儍乕偑偁偭偨偺偩傠偆丅壗擭偵傕傢偨偭偰僾儗僢僔儍乕偵懪偪彑偭偰偒偨斵彈偺惛恄椡偼暲戝掞偺傕偺偱偼側偄偼偢偩丅偦傫側斵彈偱傕丄偄傠傫側忬嫷偑廳側傝丄崱擭姶偠偰偄偨廳埑偼偲傝傢偗戝偒偐偭偨偺偩丅
帋崌屻偺僀儞僞價儏乕偱丄媑揷慖庤偼丄椳側偑傜偵丄偟偒傝偵乽偡傒傑偣傫丄偡傒傑偣傫乿偲幱偭偰偄偨丅惛堦攖丄椡傪恠偔偟偨偺偩偐傜丄徧偊偙偦偡傟丄扤傕旕擄側偳偡傞偼偢偑側偄偺偵丅埲慜偐傜屲椫傪尒傞偨傃偵巚偆偺偩偑丄廮摴傗彈巕儗僗儕儞僌側偳丄彑偭偰摉慠偲偄偆嬻婥偺側偐偱帋崌傪偡傞慖庤偺捝乆偟偄傑偱偺斶憇姶偼丄側傫偲偐側傜側偄傕偺偐偲巚偆丅壠懓傗娭學幰偑墳墖偡傞偺偼偁偨傝傑偊偩偟丄僾儗僢僔儍乕傪偼偹偺偗偰帋崌偵挧傓偺偑慖庤偺廻柦偩偲尵偭偰偟傑偊偽偦傟傑偱偩偑丄壗偐偑慖庤偨偪偵堎忢側廳壸傪壽偟偰偄傞傛偆偵巚偊偰側傜側偄丅晧偗偰夨偟偄偲棳偡椳側傜暘偐傞偑丄偦傟傛傝傕傓偟傠丄斵傜偼傒傫側偺婜懸偵墳偊傜傟側偔偰怽偟栿側偄偲椳傪棳偡偺偩丅僆儕儞僺僢僋偼偄傑傗偳偙偺崙偵偲偭偰傕崙埿敪梘偺応偵側偭偰偟傑偭偨偑丄偦傟偱傕擔杮偺慖庤偑帵偡昞忣偵偼丄墷暷偺偦傟偲偼堎側傞丄偒傢傔偰擔杮揑丄傾僕傾揑側丄岞偲巹偑崿慠偲側偭偨丄擔偺娵傪攚晧偆廳嬯偟偄僗僩儗僗傪姶偠傞丅堎榑傕偁傞偲巚偆偑丄擔杮偺僗億乕僣奅偼偄傑偩偵徍榓43擭偵帺嶦偟偨儅儔僜儞偺墌扟岾媑慖庤傪庢傝姫偄偰偄偨忬嫷偐傜敳偗弌偰偄側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
2016.08.09 (壩) 揤峜偺乽偍婥帩偪昞柧乿傪暦偄偰姶偠偨偙偲
攕愴偺擔丄偦偟偰揤峜偺惡柧偲偄偆偲丄偳偆偟偰傕廔愴偺徺捄乮嬍壒曻憲乯偑巚偄晜偐傇丅偁偺壗傪尵偭偰偄傞偺偐暘偐傜側偄娍暥挷偺尵梩丄撈摿偺堎條側梷梘偼丄乽姮偊偑偨偒傪姮偊丄擡傃偑偨偒傪擡傃乿偲偄偆堦愡偲偲傕偵丄偒傢傔偰報徾怺偄丅崙柉偼偙偺徺捄偱丄弶傔偰揤峜偺惡傪暦偄偨丅戞2師戝愴枛婜丄偡偱偵擔杮偺攕愴偼寛掕揑偩偭偨偺偵丄偢傞偢傞偲崀暁傪愭偵墑偽偟丄愴抧偺彨暫偺傒側傜偢丄暷崙偵搶嫗戝嬻廝傗尨敋搳壓傪偡傞岥幚傪梌偊丄懡悢偺巗柉傪巰偵帄傜偟傔偨嵟戝偺愑擟偑丄崙壠尦庱偱偁傝棨奀孯偺摑悆幰偱偁偭偨徍榓揤峜偵偁偭偨偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅偦偺愑擟傪庢傝丄嵟掅偱傕戅埵偡傋偒側偺偼摉慠側偺偵丄徍榓揤峜偼偦偺傑傑揤峜偺抧埵偵棷傑傝丄堦栭偵偟偰恄偐傜恖娫偵側偭偨丅崙柉偼偦傟傪暯慠偲庴偗擖傟丄扤傕乽揤峜傛丄愑擟傪庢傟乿偲偼尵傢側偐偭偨丅偘偵晄壜巚媍側傞偼擔杮傪庺敍偡傞揤峜惂偺杺椡側傝丅
傏偔偼暯惉揤峜偑壗搙傕撿偺搰偵堅楈偺椃傪偟丄奀偵岦偐偭偰摢傪壓偘傞屻傠巔偵丄懡偔偺崙柉傪巰偵捛偄傗偭偨徍榓揤峜偺孳嵾偺婥帩偪偑崬傔傜傟偰偄傞偲姶偠偰偄偨丅崱夞偺惡柧偵偼偦傫側巚偄偼崬傔傜傟偰偄側偐偭偨偑丄傏偔偼2偮偺揰偵揤峜偺怱忣偑昞傟偰偄傞偲姶偠偨丅傂偲偮偼丄揤峜偑壗夞傕乽徾挜偲偟偰偺揤峜乿偲偄偆尵梩偵尵媦偟偨偙偲偩丅帺柉搣偑嶌偭偨寷朄夵惓憪埬偵偼乽揤峜偼擔杮崙偺尦庱偱偁傞乿偲偆偨傢傟偰偄傞丅埨攞庱憡傗擔杮夛媍偺楢拞偼偦偺傛偆偵偟傛偆偲夋嶔偟偰偄傞丅揤峜偺尵梩偼丄偦傫側摦偒偵懳偟偰堎傪彞偊丄尰峴寷朄偵偁傞偲偍傝丄揤峜偲偼尦庱偱偼側偔徾挜側偺偩丄偲擮傪墴偟偰偄傞傛偆偵傏偔偵偼嬁偄偨丅
傕偆傂偲偮偼丄惗慜戅埵偲偄偆奣擮帺懱偑傕偭偰偄傞堄枴偩丅抦傜傟傞傛偆偵丄尰嵼偺峜幒揟斖偵婯掕偝傟偰偄傞廔恎揤峜偲偄偆惂搙偼柧帯寷朄壓偺峜幒揟斖傪偦偺傑傑堷偒宲偄偩傕偺偩丅廔恎惂偵側偭偨棟桼偼偄傠偄傠尵傢傟偰偄傞偑丄崻掙偵乽尰恖恄偱偁傝崙壠偺婎幉偱偁傞揤峜偑搑拞偱崀斅偡傞偙偲側偳偁偭偰偼側傜側偄乿偲偄偆峫偊偑偁偭偨偙偲偼妋偐偩傠偆丅偦傟偑惗慜戅埵惂偲側傞偲乽揤峜偲偼偨傫側傞栶怑丄栶妱偱偁傝丄偦傟傪壥偨偣側偔側偭偨傜岎懼偡傞乿偲偄偆偙偲偵側傞偐傜丄傑偭偨偔峫偊曽偑堎側傞丅偩偐傜丄埨攞庱憡偑旣傪偟偐傔丄崙柉夛媍偺楢拞偑戝斀懳偡傞偺偩丅崱夞偺揤峜偺惡柧偺抂乆偵丄埨攞傗擔杮夛媍偺巚榝傊偺掞峈偑偆偐偑偊傞丅偦傟偼丄徾挜偲偟偰偺棫応偺嫮挷傗丄揤峜偺峴堊傪乽婡擻乿偲偄偆尵梩偱昞尰偟偨偙偲傗丄揤峜曵屼偺嵺偺夁搙側帺弆傗戝偘偝側暈憆偺峴帠傪寽擮偡傞尵梩偵昞傟偰偄傞丅揤峜偑埲慜偵帵偟偨帺暘偺杽憭傪壩憭偵偟偨偄偲偄偆堄岦傗曟椗傪弅彫偟偨偄偲偄偆堄岦傕丄偦傫側峫偊偺昞傟偩傠偆丅
揤峜偺惗慜戅埵偺婓朷偵懳偟丄擔杮夛媍偺姴晹偼乽崙懱偺攋夡偵偮側偑傞乿偲搟偭偰偄傞傜偟偄丅埨攞偺廃曈偱偼乽揤峜偑彑庤偵惗慜戅埵側偳偲岥偵偡傞偺偼寷朄堘斀偩乿偲尵偭偰偄傞僶僇側惌晎娭學幰傕偄傞偲偄偆丅寷朄堘斀傪悇恑偟偨恖娫偑寷朄堘斀偩偲嫨傇偺偼丄傎偲傫偳僕儑乕僋偩丅偲傕偁傟丄揤峜偺堄岦偑偼偭偒傝偟偨埲忋丄偦偟偰傾儞働乕僩偵傛傞偲崙柉偺戝懡悢偑惗慜戅埵偵巀惉偟偰偄傞埲忋丄埨攞庱憡偼偦偺曽岦偵懬傪愗傜偞傞傪摼側偄丅偄偭傐偆偱埨攞傪巟偊傞塃梼傗擔杮夛媍偐傜偼寖偟偔斀敪偝傟傞偩傠偆丅柺敀偔側偭偰偒偨丅
2016.08.06 (搚) 杒挬慛偺儈僒僀儖峌寕
2016.08.03 (悈) 揤峜偺惗慜戅埵昞柧
2016.07.28 (栘) 僋乕僨僞乕枹悑帠審屻偺僩儖僐偺峴偔枛
2016.06.25 (搚) 塸崙偺EU棧扙偲僫僔儑僫儕僘儉偺戜摢
崙柉搳昜偵傛傝丄塸崙偺EU棧扙偑寛傑偭偨丅搳昜慜偺挷嵏偱偼丄棧扙攈偲巆棷攈偼漢峈偟偰偄傞偑棧扙攈偺傎偆偑庒姳忋傑傢偭偰偄傞偲揱偊傜傟偰偄偨丅偩偐傜棧扙攈偑彑偮偺偼憐掕撪偩偭偨偼偢偩丅偦傟側偺偵惌帯壠傗宱嵪奅偺楢拞偼丄偙傫側寢壥偵側偭偰嬃偄偨丄梊憐奜偩偭偨丄側偳偲怮傏偗偨偙偲傪尵偭偰偄傞丅傕偟杮摉偵偦偆巚偭偰偄偨偺側傜摉帠幰偺帒奿側偳側偄丅
 偙偺傛偆側寢壥偵側偭偨攚宨偲偟偰丄塸崙柉偺怱偺崻掙偵丄偐偮偰戝塸掗崙偲偟偰悽奅偺攅尃傪埇偭偰偄偨偲偄偆僾儔僀僪丄旲帩偪側傜側偄僄儕乕僩堄幆偑偁傞偱偁傠偆偙偲偼憐憸偵擄偔側偄丅偦傫側夁嫀偺塰岝偺巆熸偵偟偑傒偮偔塸崙柉偵偼丄撈暓偵儕乕僪偝傟丄帺暘偨偪偺巚偆傛偆偵側傜側偄EU偺尰忬偑変枬偱偒側偄傕偺偲塮偭偰偄偨偵堘偄側偄丅偲偼偄偊丄捈愙揑側尨場偼丄昻晉偺奿嵎偑奼戝偟丄惗妶偵嬯偟傓恖乆偑憹偊偨偙偲偵偁傞偺偼妋偐偩傠偆丅偦傫側楯摥幰奒媺傗昻崲憌偑書偔尰忬傊偺晄枮偼丄堏柉偺攔愃丄堎暘巕偺寵埆偵寢傃偮偒丄僫僔儑僫儕僘儉偑宍惉偝傟傞丅愵摦揑側惌帯壠偑偦傟傪偁偍傞丅偄傑丄偦傫側攔奜庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉偑悽奅偵峀偑傝偮偮偁傞丅暷崙偺僩儔儞僾尰徾傗丄僼儔儞僗偺崙柉愴慄傪偼偠傔偲偡傞儓乕儘僢僷奺崙偱偺塃梼惌搣偺桇恑傕崻偼傂偲偮偩傠偆丅
偙偺傛偆側寢壥偵側偭偨攚宨偲偟偰丄塸崙柉偺怱偺崻掙偵丄偐偮偰戝塸掗崙偲偟偰悽奅偺攅尃傪埇偭偰偄偨偲偄偆僾儔僀僪丄旲帩偪側傜側偄僄儕乕僩堄幆偑偁傞偱偁傠偆偙偲偼憐憸偵擄偔側偄丅偦傫側夁嫀偺塰岝偺巆熸偵偟偑傒偮偔塸崙柉偵偼丄撈暓偵儕乕僪偝傟丄帺暘偨偪偺巚偆傛偆偵側傜側偄EU偺尰忬偑変枬偱偒側偄傕偺偲塮偭偰偄偨偵堘偄側偄丅偲偼偄偊丄捈愙揑側尨場偼丄昻晉偺奿嵎偑奼戝偟丄惗妶偵嬯偟傓恖乆偑憹偊偨偙偲偵偁傞偺偼妋偐偩傠偆丅偦傫側楯摥幰奒媺傗昻崲憌偑書偔尰忬傊偺晄枮偼丄堏柉偺攔愃丄堎暘巕偺寵埆偵寢傃偮偒丄僫僔儑僫儕僘儉偑宍惉偝傟傞丅愵摦揑側惌帯壠偑偦傟傪偁偍傞丅偄傑丄偦傫側攔奜庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉偑悽奅偵峀偑傝偮偮偁傞丅暷崙偺僩儔儞僾尰徾傗丄僼儔儞僗偺崙柉愴慄傪偼偠傔偲偡傞儓乕儘僢僷奺崙偱偺塃梼惌搣偺桇恑傕崻偼傂偲偮偩傠偆丅EU偑偙傟偐傜偳偆側傞偺偐丄塸崙偺EU棧扙偑悽奅偺宱嵪偵梌偊傞儅僀僫僗偺塭嬁偼偳偺偰偄偳側偺偐丄愱栧壠偨偪偺堄尒偼偝傑偞傑偩丅EU壛柨崙偺側偐偵丄塸崙偵懕偄偰棧扙偟傛偆偲偡傞崙偑弌傞偺偱偼側偄偐偲嫲傟傞恖傕偄傟偽丄偐偊偭偰寢懇偑屌傑傞曽岦偵峴偔偩傠偆偲尒傞恖傕偄傞丅偨偩丄宱嵪偺掆懾偲僀僗儔儉夁寖攈偺僥儘傪攚宨偵丄儓儘乕儘僢僷偺庡梫崙偱僫僔儑僫儕僘儉偑崅傑傝丄堏柉攔愃偺婥塣偑崅傑偭偰偄傞偙偲丄彑偪慻偱偁傞撈暓偑庡摫偡傞EU偺懱惂偵懳偟偰書偔晧偗慻偺崙乆偺晄枮偑憹戝偟偰偄傞偙偲傪峫偊傞偲丄EU偺崱屻偑懡擄側偙偲偼娫堘偄側偄偩傠偆丅
曃嫹側僫僔儑僫儕僘儉偑崅傑傝丄嫟懚偱偼側偔屒棫傊偺摴傪曕傓偲丄崙偳偆偟偺憟偄偑杣敪偡傞婋尟偑崅傑傞丅2夞偺戝愴傪宱尡偟偨嫵孭偵傛偭偰EU偑惗傑傟偨丅偦偺棟擮偼丄憟偄傪側偔偟丄嫤挷偟偰偙偲偵摉偨傠偆偲偄偆惛恄偩丅偄傑偺棳傟偑壛懍偝傟傟偽丄偦偺嫤挷巙岦偑曵夡偡傞丅暷崙偱偺僩儔儞僾恖婥傪巟偊傞偺傕塸崙偱EU棧扙傪巟帩偟偨恖乆偲摨偠偔丄晉偺暘攝偵偁偢偐傟偢尰忬偵晄枮傪書偔幰偨偪偩丅傑偝偐僩儔儞僾偑師婜戝摑椞偵慖偽傟傞偙偲偼側偄偲巚偭偰偄偨偑丄崱夞偺塸崙偱偺搳昜寢壥傪尒傞偲丄偦偆傕尵偄愗傟側偔側偭偰偒偨丅偦偆側傟偽悽奅偺崿柪偼傑偡傑偡怺傑傞偩傠偆丅
EU棧扙偵巀惉偡傞偐偟側偄偐偼偲傕偐偔丄擔杮偺尰忬傪峫偊傞偲丄塸崙柉偑偙偺傛偆側僪儔僗僥傿僢僋側慖戰傪偟偨偲偄偆帠幚偼丄偁傞堄枴偱慉傑偟偄婥偑偟側偄偱傕側偄丅擔杮偱偼埨攞惌尃偑偄偐偵幐惌傪廳偹偰傕丄寷朄堘斀偺廤抍揑帺塹尃傪梕擣偟偰傕丄傾儀僲儈僋僗偑攋抅偟偰傕丄撪妕巟帩棪偼壓偑傜偢丄帺柉搣偼埨懽偺傑傑偩丅嵟埆偺惌尃偱傕懚懕傪嫋偡擔杮崙柉偲丄僉儍儊儘儞庱憡偵僲乕傪撍偒偮偗偨塸崙柉丄偙偺堘偄偼偳偙偐傜棃傞偺偩傠偆丅偲傕偐偔丄擔杮崙柉偼戝恖偟偡偓傞丅彮偟偼塸崙恖偺捾偺岰傪愾偠偰堸傑側偗傟偽側傜側偄丅
2016.05.29 (搚) 僆僶儅戝摑椞偺峀搰偱偺墘愢偵巚偆
 暷崙戝摑椞偺旐敋抧朘栤偼偨偟偐偵堄媊偁傞偙偲偩偲巚偆丅偟偐偟丄5寧27擔偺僆僶儅戝摑椞偺峀搰偱偺墘愢偼丄偍偍傓偹儊僨傿傾偱偼岲昡傪傕偭偰曬摴偝傟偰偄傞偑丄傏偔偼嬯乆偟偄巚偄偑偙傒忋偘偰偔傞偺傪嬛偠摼側偐偭偨丅尨敋偺搳壓偑傑傞偱懠恖帠偺傛偆偵岅傜傟偰偄偨偐傜偩丅偦偺尵梩偵偼庡岅偑側偔丄庴摦懺偵傛偭偰丄傑傞偱揤嵭偐側偵偐偱偁偭偨偐偺傛偆偵岅傜傟偨丅偦偙偵偼暷崙偑幚峴偟偨偲偄偆堄幆偑尒帠偵敳偗棊偪偰偄偨丅幱嵾偟側偄偲偄偆偙偲偼暘偐偭偰偄偨偟丄暷崙撪偺媍夛傗悽榑傊偺攝椂偐傜柧敀側幱嵾偼偱偒側偄偵偟偰傕丄尨敋傪搳壓偟偨崙偲偟偰偺愑擟偑傑偭偨偔側偔丄傓偟傠乽尨敋傪棊偲偝傟偨偺偼擔杮偵愑擟偑偁傞乿偲尵偭偰偄傞傛偆側尵奜偺僯儏傾儞僗偼丄暷崙恖偺閬傝傪姶偠偝偣偨丅榓夝偼娊寎偡傋偒偙偲偩偟丄憡庤傪幫偡偺偼廳梫側偙偲偩丅偩偑丄傑偭偨偔斀徣偟側偄偳偙傠偐丄摉慠偺偙偲傪偟偨傑偱偩偲嫃捈傞恖娫傪幫偡偺偼擄偐偟偄丅
暷崙戝摑椞偺旐敋抧朘栤偼偨偟偐偵堄媊偁傞偙偲偩偲巚偆丅偟偐偟丄5寧27擔偺僆僶儅戝摑椞偺峀搰偱偺墘愢偼丄偍偍傓偹儊僨傿傾偱偼岲昡傪傕偭偰曬摴偝傟偰偄傞偑丄傏偔偼嬯乆偟偄巚偄偑偙傒忋偘偰偔傞偺傪嬛偠摼側偐偭偨丅尨敋偺搳壓偑傑傞偱懠恖帠偺傛偆偵岅傜傟偰偄偨偐傜偩丅偦偺尵梩偵偼庡岅偑側偔丄庴摦懺偵傛偭偰丄傑傞偱揤嵭偐側偵偐偱偁偭偨偐偺傛偆偵岅傜傟偨丅偦偙偵偼暷崙偑幚峴偟偨偲偄偆堄幆偑尒帠偵敳偗棊偪偰偄偨丅幱嵾偟側偄偲偄偆偙偲偼暘偐偭偰偄偨偟丄暷崙撪偺媍夛傗悽榑傊偺攝椂偐傜柧敀側幱嵾偼偱偒側偄偵偟偰傕丄尨敋傪搳壓偟偨崙偲偟偰偺愑擟偑傑偭偨偔側偔丄傓偟傠乽尨敋傪棊偲偝傟偨偺偼擔杮偵愑擟偑偁傞乿偲尵偭偰偄傞傛偆側尵奜偺僯儏傾儞僗偼丄暷崙恖偺閬傝傪姶偠偝偣偨丅榓夝偼娊寎偡傋偒偙偲偩偟丄憡庤傪幫偡偺偼廳梫側偙偲偩丅偩偑丄傑偭偨偔斀徣偟側偄偳偙傠偐丄摉慠偺偙偲傪偟偨傑偱偩偲嫃捈傞恖娫傪幫偡偺偼擄偐偟偄丅妀攑愨偵岦偗偰偺搘椡傪岥偵偡傞僆僶儅偺尵梩傕嬻偟偔嬁偄偨丅僆僶儅偼2009擭丄僾儔僴偱偺墘愢偱丄妀側偒悽奅傪捛媮偡傞寛堄傪昞柧偟偰僲乕儀儖暯榓徿傪庴徿偟偨偑丄偦偺屻偺斵偼壗傂偲偮偦偺寛堄傪幚峴偟偰偙側偐偭偨偟丄偦偺尵梩偲偼棤暊偵丄妀傪曐桳偡傞巔惃傪曵偝側偐偭偨丅偦傟傪徾挜偟偰偄偨偺偑丄峀搰傪朘傟偨嵺偵傕悘峴堳偑庤偵採偘偰偄偨妀暫婍偺巊梡傪巜椷偡傞偨傔偺乽妀偺僇僶儞乿偩偭偨丅妀偵傛傞梷巭椡偑桳岠偩偲偡傞棟榑偑偄傑偩偵巟攝揑偱偁傝丄儘僔傾傗拞崙偑妀暫婍傪廳帇偡傞惌嶔傪偲偭偰偄傞崙嵺幮夛偵偁偭偰丄妀攑愨偺曽岦偵偼側偐側偐揮姺偱偒側偄偲偄偆尰幚偼棟夝偱偒傞丅偟偐偟丄僆僶儅偑妡偗惡偽偐傝偱丄妀攑愨偺婥塣傪惙傝忋偘傛偆偲偄偆搘椡偡傜偟偰偄側偄偱偺偼愑傔傜傟偰傕偟偐偨偑側偄丅妀攑愨傪彞偊側偑傜傕帺崙偱偼妀暫婍偺嬤戙壔傪悇偟恑傔傞僆僶儅偲丄妀側偒悽奅傪岥偵偟側偑傜傕暷崙偵捛悘偟偰崙楢偱偺妀暫婍嬛巭忦栺偺採埬偵斀懳偡傞擔杮丅偦偙偵埆偟偒僟僽儖丒僗僞儞僟乕僪偑抂揑偵昞傟偰偄傞丅
乽擔杮偵尨敋傪搳壓偟偨偺偼丄愴憟傪憗偔廔傢傜偣傞偨傔丄壗廫枩恖傕偺暫巑偺柦傪媬偆偨傔偩偭偨乿偲偄偆偺偑暷崙偺戝媊柤暘偩偑丄偦偙偵恖庬嵎暿偲恖懱幚尡偺梫慺偑偁偭偨偙偲偼柧傜偐偩丅暷崙偼帺暘偨偪偺摨朎偱偁傞儓乕儘僢僷偺崙柉偵偼尨敋傪棊偲偝側偐偭偨偵堘偄側偄丅斵傜偵乽傾僕傾偺墿怓恖庬側傜偄偄偩傠偆乿偲偄偆峫偊偑偁偭偨偱偁傠偆偙偲偼斲掕偱偒側偄丅
偐側傝愄偺偙偲偩偑丄抦傝崌偄偺暷崙恖偲榖偟偰偄偰丄榖戣偑戞2師戝愴偵媦傃丄傏偔偑乽尨敋偼擔杮偵棊偲偡昁梫側偳側偐偭偨丅摉帪偺擔杮偵偼愴椡傕懱椡傕怘椘傕側偔丄愴憟傪懕偗傜傟傞傛偆側忬懺偱偼側偐偭偨丅擔杮偑崀暁偡傞偺偼帪娫偺栤戣偩偭偨偺偵丄暷崙偼尨敋傪搳壓偟偰30枩恖偺巗柉傪嶦偟偨乿偲尵偭偨傜丄斵偼乽偦傫側偙偲偩偲偼慡慠抦傜側偐偭偨丅愴憟傪廔傢傜偣傞偨傔偵巊傢偞傞傪摼側偐偭偨偺偩偲偽偐傝巚偭偰偄偨乿偲摎偊偨丅暷崙恖偼妛峑偱偦偺傛偆偵嫵堢偝傟偰偒偨丅暷崙偱偺傾儞働乕僩挷嵏偵傛傞偲丄埲慜偼擔杮傊偺尨敋偺搳壓偑乽惓偟偐偭偨乿偲夞摎偡傞恖偑70&偐傜80%傪愯傔偰偄偨丅偩偑丄忣曬偑敪払偟偰恀幚傪抦傞婡夛偑崅傑偭偨寢壥丄嵟嬤偺挷嵏偵傛傞偲丄乽惓偟偐偭偨乿偲偄偆夞摎偑45亾偵尭偭偨丅偦傟偱傕丄乽娫堘偭偰偄偨乿偲夞摎偡傞恖偼29亾偩偐傜丄埶慠偲偟偰乽惓偟偐偭偨乿偲峫偊傞恖偺傎偆偑懡偄偑丄偦偺嵎偼弅傑偭偰偄傞丅偟偐傕庒擭憌偱偼乽娫堘偭偰偄偨乿偲偡傞恖偺傎偆偑丄庒姳偩偑乽惓偟偐偭偨乿偲偡傞恖傪忋傑傢偭偨丅擭楊憌偑忋偵側傞傎偳乽惓偟偐偭偨乿偲夞摎偡傞恖偑懡悢傪愯傔傞丅偙傟傪尒傞偲丄尨敋搳壓偵懳偡傞堄幆偑丄偲偔偵庒幰偺偁偄偩偱丄戝偒偔曄壔偟偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅偙傟偼柧傞偄嵽椏偩偲尵偊傛偆丅
偦傟偵偟偰傕丄崱夞偺埨攞惌尃偺僆僶儅傊偺岤嬾傇傝偼堎忢偩偭偨丅峀搰朘栤偵傛傞擔暷偺楌巎揑榓夝丄寢懇偺嫮偝傪傾僺乕儖偡傞偨傔偱偁傠偆偑丄G7偺偦偺懠偺崙側偳偳偆偱傕偄偄偲偄偆傛偆側丄側偄傆傝偐傑傢偸暷崙捛悘傇傝傪丄僒儈僢僩偵弌惾偟偨懠偺庱擼偼晄夣偵姶偠偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅杮棃側傜丄峀搰傊偺朘栤偼僆僶儅偩偗偱側偔G7偺庱擼慡堳偱峴側偆傋偒偩偭偨偱偁傠偆丅
峀搰偱僆僶儅偺屻偵墘愢偟偨埨攞庱憡偼丄帺暘偺傗偭偰偄傞偙偲偲惓斀懳偺偙偲傪暯婥偱岥偵偟偰偄偨丅偄偮傕偺偙偲偲偼偄偊丄傛偔偦傫側擇枃愩傪巊偊傞傕偺偩丅G7偺夛崌偱埨攞偼乽悽奅偼儕乕儅儞僔儑僢僋媺偺婋婡偵偁傞乿偲嫨傫偱奺崙庱擼傪崲榝偝偣偨丅偙偺撢捒娍側敪尵偼悽奅拞偐傜幐徫傪攦偭偨丅偳偆偵傕媬偄偑偨偄嬸撦傇傝偱偁傝丄柍抪偺偒傢傒偩丅嶲堾慖傪尒悩偊丄傾儀僲儈僋僗偺幐攕傪悽奅偺宱嵪婋婡偵揮姺偟偰徚旓惻憹惻偺墑婜傊偺晍愇偟偟傛偆偲偄偆嵃抇側偺偼栚偵尒偊偰偄傞丅惌尃堐帩偺偨傔偵僒儈僢僩傪弌廯偵巊偍偆偲偟偨偺偩丅偁傑傝偵抰愘偱屍懅側傗傝曽偩偲尵偆傎偐側偄丅
2016.04.16 (搚) 偁偺儕僗儀僢僩偑婣偭偰偒偨丄亀儈儗僯傾儉4亁偲偲傕偵
 偦偟偰撍慠丄嶐擭枛偵亀儈儗僯傾儉4 抴鍋偺憙傪暐偆彈亁忋壓姫偑憗愳彂朳偐傜東栿姧峴偝傟偨丅偳傫側偄偒偝偮偑偁偭偨偺偐暘偐傜側偄偑丄幏昅偟偨偺偼僟償傿僪丒儔乕僎儖僋儔儞僣偲偄偆崙奜偱偼柍柤偺僗僂僃乕僨儞恖嶌壠偩丅僔儕乕僘偺尨挊幰儔乕僜儞偑彂偒巆偟偨僗働僢僠偵偼峉揇偣偢丄偙偺嶌壠偑偍偍傕偲偐傜怴偨偵峔憐傪楙偭偨僆儕僕僫儖側彫愢偩偲偄偆丅亀儈儗僯傾儉亁3晹嶌傪撉傫偱怱桇傞姶妎傪枴傢偭偨傏偔偼丄婜懸偲婋湝偺擮傪書偒側偑傜丄偙偺怴嶌傪庤偵偟偨丅偦偟偰丄撉傒恑傓偆偪偵婋湝偼塤嶶偟丄婜懸偑棤愗傜傟側偐偭偨婐偟偝偑桸偒忋偑偭偨丅
偦偟偰撍慠丄嶐擭枛偵亀儈儗僯傾儉4 抴鍋偺憙傪暐偆彈亁忋壓姫偑憗愳彂朳偐傜東栿姧峴偝傟偨丅偳傫側偄偒偝偮偑偁偭偨偺偐暘偐傜側偄偑丄幏昅偟偨偺偼僟償傿僪丒儔乕僎儖僋儔儞僣偲偄偆崙奜偱偼柍柤偺僗僂僃乕僨儞恖嶌壠偩丅僔儕乕僘偺尨挊幰儔乕僜儞偑彂偒巆偟偨僗働僢僠偵偼峉揇偣偢丄偙偺嶌壠偑偍偍傕偲偐傜怴偨偵峔憐傪楙偭偨僆儕僕僫儖側彫愢偩偲偄偆丅亀儈儗僯傾儉亁3晹嶌傪撉傫偱怱桇傞姶妎傪枴傢偭偨傏偔偼丄婜懸偲婋湝偺擮傪書偒側偑傜丄偙偺怴嶌傪庤偵偟偨丅偦偟偰丄撉傒恑傓偆偪偵婋湝偼塤嶶偟丄婜懸偑棤愗傜傟側偐偭偨婐偟偝偑桸偒忋偑偭偨丅亀儈儗僯傾儉亁3晹嶌偺柺敀偝偺傂偲偮偼丄搊応恖暔偼嫟捠偩偟丄榖偺棳傟傕庴偗宲偑傟偰偄傞偺偵丄3嶌偦傟偧傟偺僗僞僀儖偑堎側偭偰偄偨揰偵偁傞丅戞1嶌偼儂儔乕晽僒僗儁儞僗丄戞2晹偼朻尟傾僋僔儑儞丄戞3晹偼朄掛儈僗僥儕乕偲丄堦嶌偛偲偵僥僀僗僩偑堎側偭偰偍傝丄偦傟偑慡懱偺僗僩乕儕乕偵墱峴偒傪梌偊偰偄偨丅崱夞偺怴嶌偼IT僗儕儔乕偲僗僷僀丒傾僋僔儑儞傪儈僢僋僗偟偨傛偆側嶌晽偵側偭偰偄傞丅庡恖岞偺僕儍乕僫儕僗僩丄儈僇僄儖偲丄揤嵥僴僢僇乕丄儕僗儀僢僩傪偼偠傔丄慜嶌偐傜堷偒宲偑傟傞搊応恖暔偨偪偼傑偭偨偔摨偠僉儍儔僋僞乕偱偁傝丄嶌幰偑柸枾偵3晹嶌傪尋媶偟偨愓偑偆偐偑偊傞丅怴偨偵搊応偡傞恖暔偼懡嵤偩偑丄偦傟偧傟偺惈奿偲屄惈偼岻傒偵昤偒暘偗傜傟偰偄傞丅婲暁偵晉傫偩僾儘僢僩丄僗僺乕僨傿側応柺揥奐傕怽偟暘側偄丅媽僔儕乕僘偲斾傋偰懟怓側偄弌棃偽偊偱偁傝丄尨挊幰偺儔乕僜儞偑彂偄偨傕偺偩偲尵傢傟偰傕怣偠偰偟傑偆偩傠偆丅
偙偺僔儕乕僘偺嵟戝偺枺椡偼丄儕僗儀僢僩丒僒儔儞僨儖偲偄偆丄攚拞偵僪儔僑儞偺巋惵傪擖傟偨丄揤嵥揑側僴僢僉儞僌偺嵥擻偲忣曬廂廤擻椡傪旛偊丄奿摤傗幩寕偵傕挿偗偨丄恖娫寵偄偩偑撈摿偺惓媊姶傪傕偮丄僷儞僋彮彈晽偺奿岲傪偟偨彫暱側柡偺憿宍偵偁偭偨丅亀儈儗僯傾儉4亁偵傛偭偰偦偺儕僗儀僢僩偑婣偭偰偒偨偺偑丄側偵傛傝傕婌偽偟偄丅崱夞傕斵彈偼嫻偺偡偔傛偆側妶桇傪尒偣傞丅挿擭壒怣偑側偐偭偨儈僇僄儖偲儕僗儀僢僩偑丄偁傞帠審傪偒偭偐偗偵嵞傃楢棈傪庢傝崌偄丄嫤椡偟偰帠審傪夝寛偟偰偄偔棳傟偺彫婥枴傛偝偼丄怱憺偄偽偐傝偩丅儕僗儀僢僩偑帺暵徢偺彮擭傪彆偗偰摝朣偡傞偆偪偵丄偦偺彮擭偲怱傪捠傢偡憓榖偵偼怱傪懪偨傟傞偟丄怺偄梋塁傪昚傢偣傞僄儞僨傿儞僌傕慛傗偐偩丅
傂偲偮偩偗擄揰傪尵偊偽丄怴嶌偱儕僗儀僢僩偲儈僇僄儖偑憳嬾偡傞偺偑怴偟偄揋偱偼側偔丄媽僔儕乕僘偺棳傟傪堷偒偢偭偨揋偱偁傞偙偲偩丅尨挊幰儔乕僜儞偺堄恾偑偳偆偩偭偨偐偼抦傜側偄偑丄慜3晹嶌偱嫮揋傪搢偟丄戝抍墌傪寎偊偨偺偩偐傜丄怴偟偄僔儕乕僘偱偼丄嵞傃夁嫀偺朣楈偲懳寛偡傞偺偱偼側偔丄傑偭偨偔怴偟偄嫄戝側揋偵熡恎偺愴偄傪挧傫偱傎偟偐偭偨丅偦傟偼偲傕偐偔丄偙傟偐傜偳傫側揥奐偵側傞偵偣傛丄師偵姧峴偝傟傞戞5晹偑偄傑偐傜懸偪墦偟偄丅
2016.04.02 (搚) 旈榖偑柧偐偝傟傞僽儔僂僯乕偺僪僉儏儊儞僞儕乕DVD
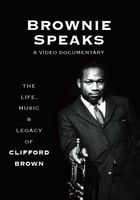 愭擔丄僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺僪僉儏儊儞僞儕乕DVD 亀Brownie Speaks: A Video Documentary亁(2014) 傪擖庤偟偨丅僽儔僂儞偲屄恖揑偵恊偟偐偭偨恖乆丄嬤恊幰丄桭恖丄僶儞僪丒儊僀僩側偳偺僀儞僞價儏乕傗丄備偐傝偺抧偺塮憸丄偝傑偞傑側幨恀傗壒妝側偳偵傛偭偰峔惉偝傟偨丄斵偺惗奤偲嬈愌傪専徹偡傞DVD偩丅
愭擔丄僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺僪僉儏儊儞僞儕乕DVD 亀Brownie Speaks: A Video Documentary亁(2014) 傪擖庤偟偨丅僽儔僂儞偲屄恖揑偵恊偟偐偭偨恖乆丄嬤恊幰丄桭恖丄僶儞僪丒儊僀僩側偳偺僀儞僞價儏乕傗丄備偐傝偺抧偺塮憸丄偝傑偞傑側幨恀傗壒妝側偳偵傛偭偰峔惉偝傟偨丄斵偺惗奤偲嬈愌傪専徹偡傞DVD偩丅僽儔僂儞偺揱婰亀僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞乣揤嵥僩儔儞傌僢僞乕偺惗奤亁乮僯僢僋丒僇僞儔乕僲挊乯偵傛傝丄偦偺恖暱傗幚愌偼偡偱偵僼傽儞偵偼撻愼傒怺偄偑丄斵偺孼枀傗儀僯乕丒僑儖僜儞丄僪僫儖僪丒僶乕僪丄儖乕丒僪僫儖僪僜儞丄僴儘儖僪丒儔儞僪側偳偺儈儏乕僕僔儍儞拠娫偑岅傞巚偄弌榖傪暦偔偲丄帤枊偑側偄偺偱僀儞僞價儏乕偱挐偭偰偄傞撪梕偼姰慡偵偼暘偐傜側偄偗傟偳傕丄偄傑偝傜側偑傜僽儔僂儞偑偄偐偵傒傫側偵垽偝傟偰偄偨偐丄偄偐偵廃埻偵戝偒側塭嬁傪媦傏偟偨偐偑幚姶偲偟偰揱傢偭偰偔傞丅嫽枴怺偄偺偼丄偪傜偭偲搊応偟偰栿偺暘偐傜側偄偙偲傪欔偔僽儔僂儞偺庒偒擔偺楒恖傾僀僟丒儊僀傗丄僽儔僂儞偵僩儔儞儁僢僩傪嫵偊偨揱愢偺嫵巘儃僀僕乕丒儘儚儕乕偑巚偄弌傪岅傞婱廳側塮憸偩丅
傏偔偑偙偺DVD偱堦斣婜懸偟偰偄偨偺偼丄僽儔僂儞帺恎偺墘憈偑廂傔傜傟偨怴偟偄摦夋偑尒傜傟傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆偙偲偩偭偨丅僽儔僂儞偺摦夋偲偟偰尰嵼岼偵棳晍偟偰偄傞偺偼丄1956擭2寧偵斵偑僗乕僺乕乕丒僙僀儖僗丒僔儑僂偲偄偆僥儗價斣慻偵弌墘偟偰墘憈偟偨乹儗僨傿丒價乕丒僌僢僪乺偲乹儊儌儕乕僘丒僆僽丒儐乕乺偺2嬋偩偗偱偁傞丅偙傟傜偼YouTube偱尒傞偙偲偑偱偒傞偑丄夋幙偼偍偦傠偟偔楎埆偩丅揱婰偵傛傞偲僽儔僂儞偼僗僥傿乕償丒傾儗儞丒僔儑僂偲偄偆斣慻偵傕弌墘偟偨傜偟偄偺偱丄偦偺塮憸偑偳偙偐偵偵巆偭偰偄傞壜擻惈偑偁傞丅偩偑丄偙偺DVD偵憓擖偝傟偰偄傞偺偼僗乕僺乕丒僙僀儖僗丒僔儑僂偺抐曅偩偗偱偁傝丄偟偐傕夋幙偼偝傎偳椙偔側偄丅偦偺揰偱偼巆擮側偑傜婜懸奜傟偩偭偨丅
 偟偐偟丄偦傟傪曗偭偰偁傑傝偁傞偺偼丄僽儔僂儞偺嵢偩偭偨儔儖乕偲懅巕偺僋儕僼僅乕僪丒僕儏僯傾偺僀儞僞價儏乕塮憸偩丅僋儕僼僅乕僪丒僕儏僯傾偼僽儔僂儞偑1956擭6寧偵朣偔側偭偨偲偒丄傑偩惗屻7儠寧偩偭偨丅惉挿偟偨斵偼僇儕僼僅儖僯傾偺儔僕僆嬊偱僕儍僘傪拞怱偲偟偨斣慻偺DJ傪偟偰偍傝丄偦偺悽奅偱偼挊柤側懚嵼偩偲偄偆丅斵偼丄巕嫙偺偙傠偵晝偑桳柤側僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偨偭偩偙偲傪擣幆偟偨宱夁傗丄執戝側晝傪傕偭偨偙偲偺屩傝側偳偵偮偄偰扺乆偲岅偭偰偄傞丅
偟偐偟丄偦傟傪曗偭偰偁傑傝偁傞偺偼丄僽儔僂儞偺嵢偩偭偨儔儖乕偲懅巕偺僋儕僼僅乕僪丒僕儏僯傾偺僀儞僞價儏乕塮憸偩丅僋儕僼僅乕僪丒僕儏僯傾偼僽儔僂儞偑1956擭6寧偵朣偔側偭偨偲偒丄傑偩惗屻7儠寧偩偭偨丅惉挿偟偨斵偼僇儕僼僅儖僯傾偺儔僕僆嬊偱僕儍僘傪拞怱偲偟偨斣慻偺DJ傪偟偰偍傝丄偦偺悽奅偱偼挊柤側懚嵼偩偲偄偆丅斵偼丄巕嫙偺偙傠偵晝偑桳柤側僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偨偭偩偙偲傪擣幆偟偨宱夁傗丄執戝側晝傪傕偭偨偙偲偺屩傝側偳偵偮偄偰扺乆偲岅偭偰偄傞丅偦偟偰僽儔僂儞枹朣恖偺儔儖乕偼晇偺巚偄弌傪岅偭偰偄傞偑丄嬃偄偨偺偼丄偦偙偱乽僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞丒僂傿僘丒僗僩儕儞僌僗乿偺儗僐乕僨傿儞僌偵傑偮傢傞旈榖偑柧偐偝傟偰偄傞偙偲偩丅抦傜傟傞傛偆偵丄偙偺LP偼丄僽儔僂儞偑僗僩儕儞僌丒僆乕働僗僩儔傪僶僢僋偵丄僗僞儞僟乕僪嬋傪傎偲傫偳傾僪儕僽傪岎偊偢丄尨儊儘僨傿傪僗僩儗乕僩偵悂偄偨傕偺偩丅儉乕僪壒妝偲偟偰偼堦媺昳偩偑丄僀儞僾儘償傿僛乕僔儑儞偑娷傑傟偰偄側偄偺偱僕儍僘偲偼尵偊側偄丅側偤恎傕怱傕僕儍僘偵曺偘偰偄偨僽儔僂儞偑偙傫側傾儖僶儉傪榐壒偟偨偺偐丄傏偔偼埲慜偐傜晄巚媍偵巚偭偰偄偨丅摨偠僂傿僘丒僗僩儕儞僌僗傕偺偱傕丄偨偲偊偽僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕偺儗僐乕僪偼墘憈偺側偐偵傾僪儕僽偺僷乕僩偑偁傝丄僽儔僂儞偺傕偺偲偼崻杮揑偵堎側傞丅
僀儞僞價儏乕偱儔儖乕偼師偺傛偆偵岅偭偰偄傞丅乽寢崶偟偰娫傕側偔丄斵偼巕嫙傪梸偟偑傝傑偟偨丅巹偼傕偭偲擇恖偩偗偺惗妶傪妝偟傒偨偐偭偨偺偱丄傑偩懯栚偲尵偄傑偟偨丅偱傕斵偼偁偒傜傔偢丄壗搙傕巹偵棅傒傑偟偨丅崻晧偗偟偨巹偼丄偠傖偁丄巹偺岲偒側僗僞儞僟乕僪丒僜儞僌傪僀乕僕乕丒儕僗僯儞僌丒僗僞僀儖偱墘憈偡傞儗僐乕僪傪嶌偭偰偔傟偨傜僆乕働乕偡傞傢丄偲尵偄傑偟偨乿丅偦偆偐丄偦偆偩偭偨偺偐丅偁偺儗僐乕僪偼巕嫙偑梸偟偐偭偨僽儔僂儞偑嵢偺儕僋僄僗僩偵墳偊偰悂偒崬傫偩傕偺偩偭偨偺偐丅側傫偲傕傎傎偊傑偟偄僄僺僜乕僪偩丅傏偔偼挿擭偺媈栤偑夝偗偨巚偄偑偟偨丅偦傟偑偙偺DVD偺堦斣戝偒側廂妌偩偭偨丅
2016.02.28 (擔) 嶐擭岞奐偺奜崙塮夋儀僗僩僥儞
1丂亀僀儈僥乕僔儑儞丒僎乕儉亁丂娔撀丗儌儖僥儞丒僥傿儖僪僁儉 乮塸丒暷乯
2丂亀傾儊儕僇儞丒僗僫僀僷乕 亁丂娔撀丗僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪 乮暷乯
3丂亀偁偺擔偺傛偆偵書偒偟傔偰亁丂娔撀丗僋儕僗僥傿傾儞丒儀僢僣僅儖僩 乮撈乯
4丂亀撈嵸幰偲彫偝側懛亁丂娔撀丗儌僼僙儞丒儅僼儅儖僶僼 乮僕儑乕僕傾丒暓丒塸丒撈乯
5丂亀僠儍僢僺乕亁丂娔撀丗僯乕儖丒僽儘儉僇儞僾 乮暷乯
6丂亀僙僢僔儑儞亁丂娔撀丗僨儈傾儞丒僠儍僛儖 乮暷乯
7丂亀儈僢僔儑儞丒僀儞億僢僔僽儖乛儘乕僌丒僱僀僔儑儞亁丂娔撀丗僋儕僗僩僼傽乕丒儅僢僇儕乕 乮暷乯
8丂亀儅僢僪儅僢僋僗丂搟傝偺僨僗丒儘乕僪亁丂娔撀丗僕儑乕僕丒儈儔乕 乮崑丒暷乯
9丂亀007丂僗儁僋僞乕亁丂娔撀丗僒儉丒儊儞僨僗 乮塸乯
10丂亀僶乕僪儅儞亁丂娔撀丗傾儗僴儞僪儘丒僀僯儍儕僩僁 乮暷乯
 1埵偺乽僀儈僥乕僔儑儞丒僎乕儉乿偼丄僐儞僺儏乕僞乕憂憿偺婎慴傪抸偄偨悢妛偺揤嵥偱偁傝丄戞2師戝愴拞偵揋崙僪僀僣偺埫崋夝撉偵峷專偟偨幚嵼偺塸崙恖傾儔儞丒僠儏乕儕儞僌偺丄幚榖傪傕偲偵偟偨楌巎旈榖偩丅僠儏乕儕儞僌偼揤嵥偵偁傝偑偪偺丄怱偵埮傪書偊偨丄屒撈傪岲傓橖娸晄懟側抝丅斵偼僠乕儉傪棪偄偰僫僠僗偺埫崋僄僯僌儅傪夝撉偟丄塸崙偺懳撈愴憟彑棙傪堿偱巟偊偨偑丄偦偺帠幚偼屻擭偵側傞傑偱柧傜偐偵偝傟傞偙偲偼側偔丄抪偢傋偒墭柤傪拝偣傜傟偰幐堄偺偆偪偵朣偔側偭偨丅偙偺塮夋偱偼偦傫側抝偺塰岝偲斶垼偑昤偐傟傞丅塸崙偱偼60擭戙枛傑偱摨惈垽偼堘朄峴堊偱偁傝丄張敱偺懳徾偵側偭偰偄偨偙偲傪抦傟偽丄僠儏乕儕儞僌偺斶寑偼偄偭偦偆廳偔嫻偵敆傞丅摿堎側梕杄偺儀僱僨傿僋僩丒僇儞僶乕僶僢僠偼敆恀偺墘媄偱僄僉僙儞僩儕僢僋側庡恖岞傪墘偠偰偄傞丅媟杮偑傛偔彂偗偰偍傝丄棊偪拝偄偨夋柺偺怓挷傕慺惏傜偟偄丅
1埵偺乽僀儈僥乕僔儑儞丒僎乕儉乿偼丄僐儞僺儏乕僞乕憂憿偺婎慴傪抸偄偨悢妛偺揤嵥偱偁傝丄戞2師戝愴拞偵揋崙僪僀僣偺埫崋夝撉偵峷專偟偨幚嵼偺塸崙恖傾儔儞丒僠儏乕儕儞僌偺丄幚榖傪傕偲偵偟偨楌巎旈榖偩丅僠儏乕儕儞僌偼揤嵥偵偁傝偑偪偺丄怱偵埮傪書偊偨丄屒撈傪岲傓橖娸晄懟側抝丅斵偼僠乕儉傪棪偄偰僫僠僗偺埫崋僄僯僌儅傪夝撉偟丄塸崙偺懳撈愴憟彑棙傪堿偱巟偊偨偑丄偦偺帠幚偼屻擭偵側傞傑偱柧傜偐偵偝傟傞偙偲偼側偔丄抪偢傋偒墭柤傪拝偣傜傟偰幐堄偺偆偪偵朣偔側偭偨丅偙偺塮夋偱偼偦傫側抝偺塰岝偲斶垼偑昤偐傟傞丅塸崙偱偼60擭戙枛傑偱摨惈垽偼堘朄峴堊偱偁傝丄張敱偺懳徾偵側偭偰偄偨偙偲傪抦傟偽丄僠儏乕儕儞僌偺斶寑偼偄偭偦偆廳偔嫻偵敆傞丅摿堎側梕杄偺儀僱僨傿僋僩丒僇儞僶乕僶僢僠偼敆恀偺墘媄偱僄僉僙儞僩儕僢僋側庡恖岞傪墘偠偰偄傞丅媟杮偑傛偔彂偗偰偍傝丄棊偪拝偄偨夋柺偺怓挷傕慺惏傜偟偄丅2埵偺乽傾儊儕僇儞丒僗僫僀僷乕乿傕幚榖偵婎偯偄偨塮夋偱丄僀儔僋愴憟偺塸梇偩偭偨慱寕偺柤庤偑庡恖岞丅斵偺恖惗偑丄惗偄棫偪傗嵢偲偺弌夛偄側偳傕娷傔丄婥晧偄側偔丄偛偔帺慠偵昤偐傟傞丅愴応偺昤幨偑埑姫偱偁傝丄堎條側嬞敆姶偵枮偪偰偄傞丅娔撀僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪偺悐偊抦傜偢偵偼嬃偐偝傟傞丅84嵨偱偙傟偩偗偺僷儚乕偲墘弌椡傪尒偣傞偲偼婏愓偵嬤偄丅慜嶌偺乽僕儍乕僕乕丒儃乕僀僘乿傕椙偐偭偨偑丄崱嶌傕尒帠側弌棃偩丅僀乕僗僩僂僢僪偼戣嵽偺慖傃曽偑偆傑偄偟丄塮夋偺暥朄傪抦偭偰偄傞丅偠偭偔傝昤偔傋偒偲偙傠丄徣棯偡傋偒偲偙傠偑暘偐偭偰偄傞丅偩偐傜丄傑偭偨偔偩傟傞売強偑側偄丅偡偛偄娔撀偩丅
 3埵偺乽偁偺擔偺傛偆偵書偒偟傔偰乿偼晽曄傢傝側塮夋偩丅晳戜偼戞2師戝愴枛丄僪僀僣攕愴捈屻偺儀儖儕儞丅嫮惂廂梕強偱婄偵戝夦変傪晧偭偨彈偑丄惍宍庤弍傪庴偗偰奨偵栠傝丄惗偒暿傟偨晇傪憑偡丅彈偼傛偆傗偔晇傪憑偟偁偰傞偑丄斵偼斵彈偑嵢偩偲偼婥偑偮偐偢丄嵢偺嵿嶻傪帺暘偺傕偺偵偡傞偨傔嵢偵側傝偡傑偟偰偔傟偲斵彈偵棅傓丅彈偼恀幚傪塀偟偰偦偺採埬傪庴偗擖傟傞偲偄偆丄側傫偲傕儈僗僥儕傾僗側僗僩乕儕乕偩丅報徾怺偄僔乕儞偑偁傞丅晇偑傾僷乕僩偱嵢偺堖暈傪彈偵拝偣傞丄彈偼柍昞忣偱偦傟傪拝傞丄拝廔偭偨彈傪湌崨偲偟偨昞忣偱晇偑尒偮傔傞乗乗婏柇側搢嶖偟偨垽偺姶妎偑昚偆丅偙傟偼柧傜偐偵僸僢僠僐僢僋偺塮夋乽傔傑偄乿傊偺僆儅乕僕儏偩丅偙偺僔乕儞偼丄乽傔傑偄乿偱偺僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩偲嵞夛偟偨僉儉丒僲償傽僋偲偺傾僷乕僩偱偺姱擻揑側僔乕儞偲廳側傝崌偆丅偙傟偼戞2師戝愴傪戣嵽偵偟偰偄傞偑愴憟塮夋偱偼側偄丅抝偲彈偺偹偠傟偨垽偺偐偨偪傪昤偄偨塮夋偩丅
3埵偺乽偁偺擔偺傛偆偵書偒偟傔偰乿偼晽曄傢傝側塮夋偩丅晳戜偼戞2師戝愴枛丄僪僀僣攕愴捈屻偺儀儖儕儞丅嫮惂廂梕強偱婄偵戝夦変傪晧偭偨彈偑丄惍宍庤弍傪庴偗偰奨偵栠傝丄惗偒暿傟偨晇傪憑偡丅彈偼傛偆傗偔晇傪憑偟偁偰傞偑丄斵偼斵彈偑嵢偩偲偼婥偑偮偐偢丄嵢偺嵿嶻傪帺暘偺傕偺偵偡傞偨傔嵢偵側傝偡傑偟偰偔傟偲斵彈偵棅傓丅彈偼恀幚傪塀偟偰偦偺採埬傪庴偗擖傟傞偲偄偆丄側傫偲傕儈僗僥儕傾僗側僗僩乕儕乕偩丅報徾怺偄僔乕儞偑偁傞丅晇偑傾僷乕僩偱嵢偺堖暈傪彈偵拝偣傞丄彈偼柍昞忣偱偦傟傪拝傞丄拝廔偭偨彈傪湌崨偲偟偨昞忣偱晇偑尒偮傔傞乗乗婏柇側搢嶖偟偨垽偺姶妎偑昚偆丅偙傟偼柧傜偐偵僸僢僠僐僢僋偺塮夋乽傔傑偄乿傊偺僆儅乕僕儏偩丅偙偺僔乕儞偼丄乽傔傑偄乿偱偺僕僃乕儉僗丒僗僠儏傾乕僩偲嵞夛偟偨僉儉丒僲償傽僋偲偺傾僷乕僩偱偺姱擻揑側僔乕儞偲廳側傝崌偆丅偙傟偼戞2師戝愴傪戣嵽偵偟偰偄傞偑愴憟塮夋偱偼側偄丅抝偲彈偺偹偠傟偨垽偺偐偨偪傪昤偄偨塮夋偩丅偦傟偵楎傜偢儐僯乕僋側塮夋偩偭偨偺偼4埵偺乽撈嵸幰偲彫偝側懛乿偩丅撈嵸幰偑巟攝偡傞拞墰傾僕傾偺彫崙偑晳戜丅偦偺崙偵妚柦偑婲偙傝丄摝偘抶傟偨弶榁偺撈嵸幰偑彫偝側懛傪楢傟偰丄梤帞偄傗椃寍恖偵曄憰偟側偑傜崙奜扙弌傪栚巜偡丅塮夋偼偦偺摝旔峴傪儐乕儌傾偲巆崜偝偑擖傝崿偠偭偨帇慄偱捛偄偐偗傞丅崙柉傪嶏庢偟丄懡偔偺恖乆傪柍幚偺嵾偱張孻偟偰偒偨撈嵸幰傊偺暅廞偺擮偵擱偊偰柉廜偼朶搆偲壔偡丅崠幧偐傜夝曻偝傟偰屘嫿偵婣傞惌帯斊偼斶嶴側尰幚傪栚偵偡傞乗乗偦傟傜傪偡傋偰傪梒偄懛偑鈗傟側偒栚偱尒偮傔偰偄傞丅僋儔僀儅僢僋僗偺昹曈偺僔乕儞偼徴寕揑偩丅偙偙偵偼丄恖娫偺嬸偐偝丄傗偝偟偝丄巆崜偝偑丄椻揙側僞僢僠偱昤偐傟偰偄傞丅懛偵暞偟偨彮擭偺帺慠側墘媄偵嬃偐偝傟傞丅擔杮偺杴昐偺巕栶偵偼媦傃傕偮偐側偄岻偝偩丅
 埲壓偼嬱偗懌偱丅5埵偺乽僠儍僢僺乕乿偼巕嫙偺怱傪帩偮儘儃僢僩偲幮夛偺掙曈偵惗偒傞恖娫偺怱偺捠偄崌偄傪昤偄偨SF塮夋丅側傜偢幰偺僠儞僺儔偑丄嵟弶偼僶僇偵偟偰偄偨儘儃僢僩偲偟偩偄偵婥柆偑捠偠丄偮偄偵偼儘儃僢僩傪庣偭偰揋偲愴偆丄偦偺怱堄婥偵懪偨傟傞丅6埵偺榖戣偵側偭偨乽僙僢僔儑儞乿偼價僢僌丒僶儞僪丒僪儔儅乕傪栚巜偡惵擭偲丄斵傪尩偟偔巜摫偡傞婼嫵巘偲偺鄷楏側愴偄傪昤偄偨丄堦庬偺僗億僐儞塮夋丅婼嫵巘偺憇愨側偟偛偒偵懴偊偰栆孭楙偡傞惵擭丄偦偺堄抧偲崻惈偺傇偮偐傝崌偄偑尒偳偙傠偩丅僕儍僘偺杮幙偵懳偡傞棟夝偑婓敄偩偟丄嫵巘偺嫸婥傪懷傃偨尵摦偵偼鐒堈偡傞偑丄儔僗僩偺墘憈僔乕儞偼側偐側偐偺敆椡丅
埲壓偼嬱偗懌偱丅5埵偺乽僠儍僢僺乕乿偼巕嫙偺怱傪帩偮儘儃僢僩偲幮夛偺掙曈偵惗偒傞恖娫偺怱偺捠偄崌偄傪昤偄偨SF塮夋丅側傜偢幰偺僠儞僺儔偑丄嵟弶偼僶僇偵偟偰偄偨儘儃僢僩偲偟偩偄偵婥柆偑捠偠丄偮偄偵偼儘儃僢僩傪庣偭偰揋偲愴偆丄偦偺怱堄婥偵懪偨傟傞丅6埵偺榖戣偵側偭偨乽僙僢僔儑儞乿偼價僢僌丒僶儞僪丒僪儔儅乕傪栚巜偡惵擭偲丄斵傪尩偟偔巜摫偡傞婼嫵巘偲偺鄷楏側愴偄傪昤偄偨丄堦庬偺僗億僐儞塮夋丅婼嫵巘偺憇愨側偟偛偒偵懴偊偰栆孭楙偡傞惵擭丄偦偺堄抧偲崻惈偺傇偮偐傝崌偄偑尒偳偙傠偩丅僕儍僘偺杮幙偵懳偡傞棟夝偑婓敄偩偟丄嫵巘偺嫸婥傪懷傃偨尵摦偵偼鐒堈偡傞偑丄儔僗僩偺墘憈僔乕儞偼側偐側偐偺敆椡丅7埵偺乽儈僢僔儑儞丒僀儞億僢僔僽儖乛儘乕僌丒僱僀僔儑儞乿偼傛偔偱偒偨傾僋僔儑儞塮夋偱丄庡墘僩儉丒僋儖乕僘偺懱傪挘偭偨婋尟側墘媄偼側偐側偐偺傕偺丅僕儍僘丒僼傽儞偲偟偰偼丄朻摢偺僔乕儞偱柤斦乽儌儞僋仌僐儖僩儗乕儞乿偑彫摴嬶偲偟偰巊傢傟丄捠岲傒偺僪儔儅乕丄僔儍僪僂丒僂傿儖僜儞偺柤偑僉乕儚乕僪偲偟偰弌偰偔傞偺偑婐偟偄丅傾僋僔儑儞丒僔乕儞偱尵偊偽懠傪抐慠埑偟偰偄偨偺偑8埵偺乽儅僢僪儅僢僋僗乛搟傝偺僨僗丒儘乕僪乿偩丅儊儖丒僊僽僜儞偑庡墘偟偨慜偺乽儅僢僪儅僢僋僗乿3晹嶌偵偼偦傟傎偳庝偐傟側偐偭偨偑丄偙偺怴嶌偼嶣塭偑惁傑偠偔丄敪憐傕儐僯乕僋偩偟丄戝偄偵妝偟傔偨丅庡墘偺僩儉丒僴乕僨傿偼柺峔偊偑偄偄偟丄僸儘僀儞偺僔儍乕儕乕僘丒僙儘儞偺彈愴巑怳傝偵傕栚傪尒挘傜偝傟傞丅偲偼偄偊丄偙傟偼傾僇僨儈乕嶌昳徿偵僲儈僱乕僩偝傟偰偄傞偟丄僉僱弡偺奜崙塮夋儀僗僩僥儞偱偼1埵偵擖偭偰偄傞偑丄偦偙傑偱偺塮夋偲偼巚偊側偄丅9埵埲壓偵偮偄偰偺僐儊儞僩偼妱垽丅
2016.02.14 (擔) 乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿傪傔偖偭偰
 埲慜偐傜尒偨偄偲巚偭偰偄偨塮夋乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿乮Night Has a Thousand Eyes乯偑愭偛傠擔杮偱DVD敪攧偝傟丄傛偆傗偔擮婅偑偐側偭偨丅1946擭惂嶌偺傾儊儕僇塮夋丄僕儑儞丒僼傽儘乕娔撀丄僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞庡墘偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偩丅偁傞栭丄揝嫶偐傜旘傃崀傝帺嶦偟傛偆偲偟偰偄傞庒偄彈傪丄捛偄偐偗偰偒偨楒恖偺抝偑彆偗傞丄斵彈偼嬻傪尒忋偘偰乬愮偺娽偑尒偮傔偰偄傞丒丒丒晐偄乭偲岥憱傞丄偲偄偆枺榝揑側僾儘儘乕僌偐傜丄塮夋偼巒傑傞丅娫傕側偔梊抦擻椡傪帩偮儅僕僔儍儞偑搊応偟丄帺傜偺夁嫀傪岅傝巒傔傞丅偨傑偨傑庒偄彈偑1廡娫屻偵巰偡傋偒塣柦偵偁傞偺傪梊抦偟偨斵偼丄偦傟傪慾巭偟傛偆偲杬憱偡傞丄偲偄偆撪梕偱偁傞丅偙偺塮夋偼丄傎傏慡曇偑栭偺僔乕儞偱愯傔傜傟偰偍傝丄梊抦擻椡傪傔偖傞晄巚媍側撲丄塣柦偵梮傜偝傟傞幰偨偪偑書偔晄埨姶偑慡懱傪暍偭偰偄傞丅僼傿儖儉丒僲儚乕儖傜偟偄僟乕僋側暤埻婥偑墶堨偟偨壚昳偩偭偨丅庡墘偺僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞偼娧榎廩暘偩偟丄僸儘僀儞偺僎僀儖丒儔僢僙儖傕悙乆偟偄旤偟偝傪敪嶶偟偰偄偨丅
埲慜偐傜尒偨偄偲巚偭偰偄偨塮夋乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿乮Night Has a Thousand Eyes乯偑愭偛傠擔杮偱DVD敪攧偝傟丄傛偆傗偔擮婅偑偐側偭偨丅1946擭惂嶌偺傾儊儕僇塮夋丄僕儑儞丒僼傽儘乕娔撀丄僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞庡墘偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偩丅偁傞栭丄揝嫶偐傜旘傃崀傝帺嶦偟傛偆偲偟偰偄傞庒偄彈傪丄捛偄偐偗偰偒偨楒恖偺抝偑彆偗傞丄斵彈偼嬻傪尒忋偘偰乬愮偺娽偑尒偮傔偰偄傞丒丒丒晐偄乭偲岥憱傞丄偲偄偆枺榝揑側僾儘儘乕僌偐傜丄塮夋偼巒傑傞丅娫傕側偔梊抦擻椡傪帩偮儅僕僔儍儞偑搊応偟丄帺傜偺夁嫀傪岅傝巒傔傞丅偨傑偨傑庒偄彈偑1廡娫屻偵巰偡傋偒塣柦偵偁傞偺傪梊抦偟偨斵偼丄偦傟傪慾巭偟傛偆偲杬憱偡傞丄偲偄偆撪梕偱偁傞丅偙偺塮夋偼丄傎傏慡曇偑栭偺僔乕儞偱愯傔傜傟偰偍傝丄梊抦擻椡傪傔偖傞晄巚媍側撲丄塣柦偵梮傜偝傟傞幰偨偪偑書偔晄埨姶偑慡懱傪暍偭偰偄傞丅僼傿儖儉丒僲儚乕儖傜偟偄僟乕僋側暤埻婥偑墶堨偟偨壚昳偩偭偨丅庡墘偺僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞偼娧榎廩暘偩偟丄僸儘僀儞偺僎僀儖丒儔僢僙儖傕悙乆偟偄旤偟偝傪敪嶶偟偰偄偨丅 偙偺塮夋偺尨嶌偼儈僗僥儕乕嶌壠僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠乮僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏乯偑彂偄偨僒僗儁儞僗彫愢偩丅傏偔偼偼偢偄傇傫慜偵撉傫偩偙偲偑偁傞丅偨偟偐尨嶌偱偼丄帺嶦偟傛偆偲偡傞彈傪彆偗傞偺偼丄偨傑偨傑捠傝偑偐偭偨孻帠偲偄偆愝掕偩偭偨偼偢偩丅枹棃傪梊抦偡傞儅僕僔儍儞偺夞憐僔乕儞偑傗偨傜偵挿偔丄慡懱偺3暘偺2傎偳傪愯傔傞偲偄偆攋奿偺峔惉偵側偭偰偄偨丅嬻偵婸偔惎偑嫲晐傪偁偍傞偲偄偆敪憐傗丄梊尵偝傟偨巰偐傜摝傟傜傟傞偐偳偆偐偲偄偆僒僗儁儞僗偑柺敀偔丄僂乕儖儕僢僠撈摿偺垼廌枴傗庘泴姶偲憡樦偭偰丄側偐側偐柺敀偐偭偨偲偄偆婰壇偑偁傞丅塮夋偼斾妑揑丄尨嶌偵拤幚偵嶌傜傟偰偄傞偲巚偆丅"Night Has a Thousand Eyes"偲偄偆報徾揑側戣柤偼丄偳偆傗傜19悽婭屻敿偺僀僊儕僗偺帊恖丄僼儔儞僔僗丒僂傿儕傾儉丒僶乕僨傿儘儞偺帊偺堦愡偑弌揟傜偟偄丅
偙偺塮夋偺尨嶌偼儈僗僥儕乕嶌壠僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠乮僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏乯偑彂偄偨僒僗儁儞僗彫愢偩丅傏偔偼偼偢偄傇傫慜偵撉傫偩偙偲偑偁傞丅偨偟偐尨嶌偱偼丄帺嶦偟傛偆偲偡傞彈傪彆偗傞偺偼丄偨傑偨傑捠傝偑偐偭偨孻帠偲偄偆愝掕偩偭偨偼偢偩丅枹棃傪梊抦偡傞儅僕僔儍儞偺夞憐僔乕儞偑傗偨傜偵挿偔丄慡懱偺3暘偺2傎偳傪愯傔傞偲偄偆攋奿偺峔惉偵側偭偰偄偨丅嬻偵婸偔惎偑嫲晐傪偁偍傞偲偄偆敪憐傗丄梊尵偝傟偨巰偐傜摝傟傜傟傞偐偳偆偐偲偄偆僒僗儁儞僗偑柺敀偔丄僂乕儖儕僢僠撈摿偺垼廌枴傗庘泴姶偲憡樦偭偰丄側偐側偐柺敀偐偭偨偲偄偆婰壇偑偁傞丅塮夋偼斾妑揑丄尨嶌偵拤幚偵嶌傜傟偰偄傞偲巚偆丅"Night Has a Thousand Eyes"偲偄偆報徾揑側戣柤偼丄偳偆傗傜19悽婭屻敿偺僀僊儕僗偺帊恖丄僼儔儞僔僗丒僂傿儕傾儉丒僶乕僨傿儘儞偺帊偺堦愡偑弌揟傜偟偄丅 僕儍僘丒僗僞儞僟乕僪偲偟偰抦傜傟傞嬋乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿偼偙偺塮夋偺庡戣壧偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偲偙傠偑丄塮夋偺側偐偱偼偙偺儊儘僨傿偼僷乕僥傿夛応偺僟儞僗丒僔乕儞偱偪傜偭偲棳傟傞偩偗丄傎偲傫偳報徾偵巆傜偢丄偲偆偰偄庡戣壧偲偼尵偄擄偄丅偙偺嬋偺嶌帉偼僶僨傿丒僶乕僯傾乕丄嶌嬋偼僕僃儕乕丒僽儗僀僯儞丄傎偲傫偳柍柤偺僜儞僌儔僀僞乕偨偪偩丅塮夋偺僗僞僢僼丒僋儗僕僢僩偵偼丄乬壒妝丗償傿僋僞乕丒儎儞僌乭偲偩偗昞婰偝傟偰偍傝丄偙偺2恖偺僋儗僕僢僩偼偳偙偵傕尒摉偨傜側偄丅偦傫側傢偗偱丄塮夋偵巊傢傟偨宱堒偼撲傔偄偰偄傞丅偙偺嬋偼1960擭偺僕儑儞丒僐儖僩儗乕儞偺墘憈偵傛偭偰桳柤偵側傝丄偦偺屻丄僜僯乕丒儘儕儞僘丄僜僯乕丒僗僥傿僢僩丄僗僞儞丒僎僢僣丄億乕儖丒僨僗儌儞僪側偳丄懡偔偺僕儍僘儊儞偑嵦傝忋偘偰僗僞儞僟乕僪壔偟偨丅僀儞僗僩丒僫儞僶乕偲偟偰梡偄傜傟傞偙偲偑懡偔丄庡偵儔僥儞丒儕僘儉傪巊偭偰寉夣偵墘憈偝傟傞偑丄償僅乕僇儖嬋偲偟偰傕僇乕儊儞丒儅僋儗僄丄儌乕僈僫丒僉儞僌丄儃僒丒儕僆側偳偑壧偭偰偄傞丅壧帉偺撪梕偼乬栭偼尵梩偺墱偵塀偝傟偨傕偺傪尒敳偔丅栭偼愮偺娽傪帩偭偰偄傞偐傜丄恀幚偺怱偲塕偺怱傪尒暘偗傞偙偲偑偱偒傞乭偲偄偆傕偺偱丄搶梞偺偙偲傢偞偵摉偰偼傔傟偽乬揤栐夬夬慳偵偟偰楻傜偝偢乭偲偄偆偙偲偵側傠偆偐丅
僕儍僘丒僗僞儞僟乕僪偲偟偰抦傜傟傞嬋乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿偼偙偺塮夋偺庡戣壧偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偲偙傠偑丄塮夋偺側偐偱偼偙偺儊儘僨傿偼僷乕僥傿夛応偺僟儞僗丒僔乕儞偱偪傜偭偲棳傟傞偩偗丄傎偲傫偳報徾偵巆傜偢丄偲偆偰偄庡戣壧偲偼尵偄擄偄丅偙偺嬋偺嶌帉偼僶僨傿丒僶乕僯傾乕丄嶌嬋偼僕僃儕乕丒僽儗僀僯儞丄傎偲傫偳柍柤偺僜儞僌儔僀僞乕偨偪偩丅塮夋偺僗僞僢僼丒僋儗僕僢僩偵偼丄乬壒妝丗償傿僋僞乕丒儎儞僌乭偲偩偗昞婰偝傟偰偍傝丄偙偺2恖偺僋儗僕僢僩偼偳偙偵傕尒摉偨傜側偄丅偦傫側傢偗偱丄塮夋偵巊傢傟偨宱堒偼撲傔偄偰偄傞丅偙偺嬋偼1960擭偺僕儑儞丒僐儖僩儗乕儞偺墘憈偵傛偭偰桳柤偵側傝丄偦偺屻丄僜僯乕丒儘儕儞僘丄僜僯乕丒僗僥傿僢僩丄僗僞儞丒僎僢僣丄億乕儖丒僨僗儌儞僪側偳丄懡偔偺僕儍僘儊儞偑嵦傝忋偘偰僗僞儞僟乕僪壔偟偨丅僀儞僗僩丒僫儞僶乕偲偟偰梡偄傜傟傞偙偲偑懡偔丄庡偵儔僥儞丒儕僘儉傪巊偭偰寉夣偵墘憈偝傟傞偑丄償僅乕僇儖嬋偲偟偰傕僇乕儊儞丒儅僋儗僄丄儌乕僈僫丒僉儞僌丄儃僒丒儕僆側偳偑壧偭偰偄傞丅壧帉偺撪梕偼乬栭偼尵梩偺墱偵塀偝傟偨傕偺傪尒敳偔丅栭偼愮偺娽傪帩偭偰偄傞偐傜丄恀幚偺怱偲塕偺怱傪尒暘偗傞偙偲偑偱偒傞乭偲偄偆傕偺偱丄搶梞偺偙偲傢偞偵摉偰偼傔傟偽乬揤栐夬夬慳偵偟偰楻傜偝偢乭偲偄偆偙偲偵側傠偆偐丅
偲偙傠偱丄偙傟偵偼摨柤堎嬋偑偁傞丅60擭戙慜敿偵妶桇偟偨傾儊儕僇偺億僢僾壧庤儃價乕丒償傿乕偵偵傛傞乽The Night Has a Thousand Eyes乿偲偄偆僸僢僩嬋偩丅乽擱備傞摰乿偲偄偆朚戣偑偮偄偰偄傞丅乬傏偔偵偼塕傪偮偐側偄偱偔傟丅嬻偵偁傞愮偺娽傪偛傑偐偡偙偲偼偱偒側偄傫偩偐傜乭偲晄幚側楒恖偵慽偊偐偗傞壧帉偱丄挷巕偺偄偄寉夣側壧偩丅1962擭偵價儖儃乕僪帍Hot100偺3埵偵擖傞戝僸僢僩偵側偭偨丅僇乕儁儞僞乕僘偑偁偺柤斦亀僫僂丒傾儞僪丒僛儞亁偱僇償傽乕偟偰偄傞丅
 乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿偺尨嶌幰僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠偺僒僗儁儞僗彫愢偼40擭戙屻敿偐傜50擭戙慜敿偵偐偗偰丄傾儊儕僇偱悢懡偔塮夋壔偝傟偨丅偄偪偽傫桳柤側偺偼僸僢僠僐僢僋偑娔撀偟偨乽棤憢乿偱偁傠偆丅傏偔偑岲偒側偺偼儘僶乕僩丒僔僆僪儅僋娔撀偺乽尪偺彈乿乮Phantom Lady乯偩丅偙傟偼彫愢傕柤嶌偩偑丄塮夋傕儘乕丒僉乕傪惗偐偟偨嶣塭偑慺惏傜偟偔丄摉帪偝偐傫偵嶌傜傟偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪戙昞偡傞寙嶌偩偲巚偆丅傎偐偵傕乽嬇偺巰慄乿乮塮夋戣柤乽僨僢僪儔僀儞25帪乿乯丄乽崟偄揤巊乿丄乽憢乿丄乽昢抝乿側偳偑塮夋壔偝傟偰偄傞丅斵偺嶌昳偵偼丄婜尷撪偵帠審傪夝寛偟側偗傟偽帺暘偺恎偑婋側偔側傞偲偄偆僞僀儉丒儕儈僢僩愝掕偺傕偺偑懡偔丄捛傢傟傞幰偺晄埨傗屒撈丄帺暘偼柍幚側偺偵扤傕尵偆偙偲傪怣偠偰偔傟側偄偲偄偭偨忬嫷偑垼姶偨偭傉傝偺昅抳偱昤偐傟偰偍傝丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖偱嵦傝忋偘傞偵偼傄偭偨傝偺慺嵽偩偭偨丅60擭戙枛偵僼儔儞僗偺僩儕儏僼僅乕娔撀偑僂乕儖儕僢僠嶌偺乽崟堖偺壴壟乿偲乽埫埮傊偺儚儖僣乿傪塮夋壔偟偨偑丄撪梕揑偵偼杴嶌偩偭偨丅
乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿偺尨嶌幰僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠偺僒僗儁儞僗彫愢偼40擭戙屻敿偐傜50擭戙慜敿偵偐偗偰丄傾儊儕僇偱悢懡偔塮夋壔偝傟偨丅偄偪偽傫桳柤側偺偼僸僢僠僐僢僋偑娔撀偟偨乽棤憢乿偱偁傠偆丅傏偔偑岲偒側偺偼儘僶乕僩丒僔僆僪儅僋娔撀偺乽尪偺彈乿乮Phantom Lady乯偩丅偙傟偼彫愢傕柤嶌偩偑丄塮夋傕儘乕丒僉乕傪惗偐偟偨嶣塭偑慺惏傜偟偔丄摉帪偝偐傫偵嶌傜傟偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖傪戙昞偡傞寙嶌偩偲巚偆丅傎偐偵傕乽嬇偺巰慄乿乮塮夋戣柤乽僨僢僪儔僀儞25帪乿乯丄乽崟偄揤巊乿丄乽憢乿丄乽昢抝乿側偳偑塮夋壔偝傟偰偄傞丅斵偺嶌昳偵偼丄婜尷撪偵帠審傪夝寛偟側偗傟偽帺暘偺恎偑婋側偔側傞偲偄偆僞僀儉丒儕儈僢僩愝掕偺傕偺偑懡偔丄捛傢傟傞幰偺晄埨傗屒撈丄帺暘偼柍幚側偺偵扤傕尵偆偙偲傪怣偠偰偔傟側偄偲偄偭偨忬嫷偑垼姶偨偭傉傝偺昅抳偱昤偐傟偰偍傝丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖偱嵦傝忋偘傞偵偼傄偭偨傝偺慺嵽偩偭偨丅60擭戙枛偵僼儔儞僗偺僩儕儏僼僅乕娔撀偑僂乕儖儕僢僠嶌偺乽崟堖偺壴壟乿偲乽埫埮傊偺儚儖僣乿傪塮夋壔偟偨偑丄撪梕揑偵偼杴嶌偩偭偨丅
2016.01.30 (搚) 儀儖儕儞偺暻偲椻愴
 嵟嬤丄偨傑偨傑椻愴壓偺僪僀僣傪晳戜偵偟偨彫愢傪丄2嶜懕偗偰撉傫偩丅傂偲偮偼恵夑偟偺傇偲偄偆嶌壠偺 亀妚柦慜栭亁 乮暥錣弔廐2015擭乯丅偙傟偼1989擭丄儀儖儕儞偺暻偑曵夡偡傞捈慜偺憶慠偲偟偨僪僀僣丄僪儗僗僨儞偺壒妝戝妛偵棷妛偟偨擔杮恖偺僺傾僲妛搆傪庡恖岞偲偡傞丄堦庬偺惵弔彫愢偱偁傝丄側偐側偐偺椡嶌偩偭偨丅搶撈偱偼恖乆偑抏埑傗崘敪偵嫰偊側偑傜惣懁偵摝偘傛偆偲偡傞丅傗偑偰搶懁彅崙偱柉庡壔塣摦偑杣嫽偟丄幮夛庡媊惌尃偑搢傟丄偮偄偵儀儖儕儞偺暻偑曵夡偡傞丅偦傫側忬嫷偺側偐丄僶僢僴傪宧垽偡傞庡恖岞偺惵擭偼丄偝傑偞傑側妛桭偨偪偲岎棳偟丄擸傫偩傝孾帵傪庴偗偨傝偟側偑傜僺傾僲傪嬌傔傞偨傔嬯摤偡傞丄偲偄偆撪梕偱偁傞丅嶌幰偼僋儔僔僢僋壒妝偵憿寃偑怺偄偲尒偊丄庡恖岞偑楙廗偟偨傝墘憈夛偱抏偄偨傝偡傞桳柤側僺傾僲嬋偺壒妝揑昤幨偼摪偵擖偭偨傕偺偩偲巚偆偑丄栧奜娍偺傏偔偵偼偦偺惉斲偑傛偔暘偐傜側偄丅乽僋儔僔僢僋枹抦偲偺憳嬾乿偺僐儔儉傪扴摉偟偰偄傞惔嫵帥巵偺堄尒傪暦偄偰傒偨偄偲偙傠偩丅
嵟嬤丄偨傑偨傑椻愴壓偺僪僀僣傪晳戜偵偟偨彫愢傪丄2嶜懕偗偰撉傫偩丅傂偲偮偼恵夑偟偺傇偲偄偆嶌壠偺 亀妚柦慜栭亁 乮暥錣弔廐2015擭乯丅偙傟偼1989擭丄儀儖儕儞偺暻偑曵夡偡傞捈慜偺憶慠偲偟偨僪僀僣丄僪儗僗僨儞偺壒妝戝妛偵棷妛偟偨擔杮恖偺僺傾僲妛搆傪庡恖岞偲偡傞丄堦庬偺惵弔彫愢偱偁傝丄側偐側偐偺椡嶌偩偭偨丅搶撈偱偼恖乆偑抏埑傗崘敪偵嫰偊側偑傜惣懁偵摝偘傛偆偲偡傞丅傗偑偰搶懁彅崙偱柉庡壔塣摦偑杣嫽偟丄幮夛庡媊惌尃偑搢傟丄偮偄偵儀儖儕儞偺暻偑曵夡偡傞丅偦傫側忬嫷偺側偐丄僶僢僴傪宧垽偡傞庡恖岞偺惵擭偼丄偝傑偞傑側妛桭偨偪偲岎棳偟丄擸傫偩傝孾帵傪庴偗偨傝偟側偑傜僺傾僲傪嬌傔傞偨傔嬯摤偡傞丄偲偄偆撪梕偱偁傞丅嶌幰偼僋儔僔僢僋壒妝偵憿寃偑怺偄偲尒偊丄庡恖岞偑楙廗偟偨傝墘憈夛偱抏偄偨傝偡傞桳柤側僺傾僲嬋偺壒妝揑昤幨偼摪偵擖偭偨傕偺偩偲巚偆偑丄栧奜娍偺傏偔偵偼偦偺惉斲偑傛偔暘偐傜側偄丅乽僋儔僔僢僋枹抦偲偺憳嬾乿偺僐儔儉傪扴摉偟偰偄傞惔嫵帥巵偺堄尒傪暦偄偰傒偨偄偲偙傠偩丅傕偆1嶜偼摿憑晹Q僔儕乕僘偱抦傜傟傞僨儞儅乕僋偺儈僗僥儕乕嶌壠儐僢僔丒僄乕僘儔丒僆乕儖僗儞偑彂偄偨 亀傾儖僼傽儀僢僩丒僴僂僗亁 乮憗愳彂朳2015擭乯丅戞2師戝愴拞丄恊桭摨巑偱偁傞2恖偺塸嬻孯僷僀儘僢僩偑僪僀僣忋嬻偱寕捘偝傟偰晄帪拝丅偁傗偆偔扙弌偟偨斵傜偼彎昦SS彨峑偵側傝偡傑偟丄惛恄偵堎忢傪偒偨偟偨怳傝傪偟偰僼儔僀僽儖僋嬤峹偺惛恄昦搹偵憲傜傟傞丅偦偙偵棯扗偟偨嵿曮偱嬥栕偗傪婇傓埆摽彨峑偨偪偑暣傟崬傒丄斵傜傪媠懸偡傞丅恎偺婋尟傪姶偠偨塸孯僷僀儘僢僩偺傂偲傝偼丄傕偆傂偲傝傪巆偟偨傑傑扨撈偱昦搹偐傜扙弌偡傞丅偦傟偐傜30擭嬤偔宱偭偨偁偲丄帺愑偺擮偵嬱傜傟偨斵偼恊桭偺埨斲傪妋擣偡傞偨傔僼儔僀僽儖僋偵岦偐偆丄偲偄偆撪梕偺妶寑僒僗儁儞僗彫愢偩丅惛恄昦搹偺堿嶴側岝宨偑昤偐傟傞戞1晹丄庡恖岞偺昁巰偺憑嶕偵傛偭偰恀幚偑柧偐偝傟傞戞2晹丄偄偢傟傕撉傒偛偨偊偑偁傞丅
 偙偺2嶌傪撉傫偱丄傓偐偟椃峴偟偨儀儖儕儞傗僪儗僗僨儞偺奨暲傒傪巚偄弌偟偰偄偨栴愭丄僗僥傿乕償儞丒僗僺儖僶乕僌娔撀偺怴嶌塮夋 亀僽儕僢僕丒僆僽丒僗僷僀亁 傪尒偨傜丄偦偙偵傑偨傕傗椻愴帪戙弶婜偺儀儖儕儞偺岝宨偑塮偟弌偝傟偰偄偨丅偙偺塮夋偼巎幚偵婎偯偄偰偄傞丅椻愴偑巒傑偭偨1950擭戙枛婜偺暷崙丄庡恖岞偺曎岇巑偼惌晎偺巜帵偵傛傝丄曔傑偭偨僜楢僗僷僀偺嵸敾偱曎岇恖傪堷偒庴偗丄垽崙庡媊幰偨偪偺拞彎傗嫼敆偵崌偄側偑傜怣擮傪娧偒丄曎岇偵摉偨傞丅傗偑偰僜楢忋嬻傪僗僷僀旘峴拞偺U2宆婡偑寕捘偝傟丄僷僀儘僢僩偑曔傜傢傟傞丅暈栶拞偺僜楢僗僷僀偲曔椄偵側偭偨暷孯僷僀儘僢僩偺岎姺榖偑帩偪忋偑傝丄庡恖岞偼偦偺岎徛偲岎姺幚尰偺偨傔搶儀儖儕儞偵岦偐偆丅斵偑晪偄偨儀儖儕儞偱偼丄搶惣傪妘偰傞暻傪寶愝偟偰偄傞嵟拞偩偭偨丄偲偄偆撪梕偱偁傞丅
偙偺2嶌傪撉傫偱丄傓偐偟椃峴偟偨儀儖儕儞傗僪儗僗僨儞偺奨暲傒傪巚偄弌偟偰偄偨栴愭丄僗僥傿乕償儞丒僗僺儖僶乕僌娔撀偺怴嶌塮夋 亀僽儕僢僕丒僆僽丒僗僷僀亁 傪尒偨傜丄偦偙偵傑偨傕傗椻愴帪戙弶婜偺儀儖儕儞偺岝宨偑塮偟弌偝傟偰偄偨丅偙偺塮夋偼巎幚偵婎偯偄偰偄傞丅椻愴偑巒傑偭偨1950擭戙枛婜偺暷崙丄庡恖岞偺曎岇巑偼惌晎偺巜帵偵傛傝丄曔傑偭偨僜楢僗僷僀偺嵸敾偱曎岇恖傪堷偒庴偗丄垽崙庡媊幰偨偪偺拞彎傗嫼敆偵崌偄側偑傜怣擮傪娧偒丄曎岇偵摉偨傞丅傗偑偰僜楢忋嬻傪僗僷僀旘峴拞偺U2宆婡偑寕捘偝傟丄僷僀儘僢僩偑曔傜傢傟傞丅暈栶拞偺僜楢僗僷僀偲曔椄偵側偭偨暷孯僷僀儘僢僩偺岎姺榖偑帩偪忋偑傝丄庡恖岞偼偦偺岎徛偲岎姺幚尰偺偨傔搶儀儖儕儞偵岦偐偆丅斵偑晪偄偨儀儖儕儞偱偼丄搶惣傪妘偰傞暻傪寶愝偟偰偄傞嵟拞偩偭偨丄偲偄偆撪梕偱偁傞丅僗僺儖僶乕僌偼廳偄惌帯幮夛僥乕儅傪慺嵽偵丄椙幙偺屸妝惈偵晉傫偩墱怺偄恖娫僪儔儅偵巇忋偘偰偍傝丄偦偺慛傗偐側庤榬偵偼扙朮偣偞傞傪偊側偄丅弌墘幰偼庡墘偺僩儉丒僴儞僋僗埲奜丄傎偲傫偳抦傜傟偰偄側偄栶幰偽偐傝偩偑丄斵傜偺墘媄偼慺惏傜偟偔丄偲傝傢偗僜楢偺僗僷僀偵側傞攐桪偼嵺棫偭偰偄傞丅塮夋偼50擭戙枛婜偲偄偆帪戙傪丄晽懎傗僥儗價斣慻傗壒妝側偳丄嵶晹偵傢偨偭偰尒帠偵嵞尰偟偰偍傝丄偦偺揰偱傕堦尒偺壙抣偑偁傞 (夰偐偟偺乽僒儞僙僢僩77乿偑娵偄夋柺偺僽儔僂儞娗僥儗價偐傜棳傟傞両)丅 偲傝傢偗報徾怺偄偺偼丄暷僜偺嬱偗堷偒偑尒帠偵昤偐傟傞搶儀儖儕儞偺忣宨偩丅埲慜丄僥儗價偺僪僉儏儊儞僞儕乕斣慻偱儀儖儕儞偺暻傪寶愝拞偺惗乆偟偄塮憸傪尒偨偑丄偙偺塮夋偱偼丄戝捠傝偺恀傫拞偵寶偰傜傟傞暻丄惣懁偵摝偘傛偆偲偟偰憢偐傜旘傃崀傝傞巗柉側偳丄僪僉儏儊儞僞儕乕塮憸偲慡偔摨偠岝宨偑塮偟弌偝弌偰偍傝丄溕慠偲偡傞丅
偙偺偲偙傠丄弌斉暔傗塮夋傗僥儗價斣慻側偳偱丄椻愴傗儀儖儕儞偺暻傪僥乕儅偵偟偨傕偺偑懡偄傛偆側婥偑偡傞丅昿敪偡傞僀僗儔儉夁寖攈偺僥儘丄崿柪偡傞拞搶丄寖偟偝傪憹偡戝崙偳偆偟偺攅尃憟偄偲偄偭偨尰戙偺悽奅忣惃偑丄偦偺墦場偱偁傞戞2師戝愴屻偺椻愴帪戙偺夞屭丄専徹偵憱傜偣傞偺偩傠偆偐丅
1寧24擔偵NHK偱曻憲偝傟偨僪僉儏儊儞僞儕乕丒僔儕乕僘乽怴丒塮憸偺悽婭乿偺戞4廤 乽椻愴丗悽奅偼旈枾偲塕偵暍傢傟偨乿 偼徴寕揑側斣慻偩偭偨丅椻愴帪戙丄搶懁偱偼僗僞乕儕儞傗搶撈偺旈枾寈嶡偑恖乆傪抏埑偟丄暷崙偱偼丄FBI偑崙撪偺恖尃傪怤奞偟丄CIA偑奀奜偺旈枾岺嶌偵実傢偭偰奺崙偱斀暷惌尃傪揮暍偝偣偨丅偙偺斣慻偱偼偦偺宱堒偑偮傇偝偵塮憸偱柧傜偐偵偝傟傞丅偙傟傪尒傞偲丄椻愴帪戙偼妀暫婍愴憟偑尰幚偺嫲晐偲偟偰悽奅傪暍偭偰偄偨偙偲丄偦偟偰僕儑儞僜儞偺傛偆側柍擻柍嶔偺戝摑椞丄儗乕僈儞偺傛偆側嬌塃巚憐偵嬅傝屌傑偭偨戝摑椞偑嫟嶻庡媊傊偺揋懳怱傪偁偍偭偰悽奅奺抧偱暣憟傗崿棎傪堷偒婲偙偟偨偙偲偑傛偔暘偐傞丅儀儖儕儞偺暻偵徾挜偝傟傞椻愴偼1989擭偵廔傢偭偨偑丄偦偺屻堚徢偼戝偒偄丅傾儖僇僀僟傗IS偺傛偆側慻怐偼暷崙偺堿杁偑嶵偄偨庬偐傜弌尰偟偨偺偩丅
2016.01.16 (搚) 擭巒嶨姶
12寧28擔丄堅埨晈栤戣偵娭偡傞擔娯偺崌堄偑揹寕揑偵敪昞偝傟偨丅抶偒偵幐偟偨偲偼偄偊丄偙傟偼埨攞惌尃偺奜岎揑惉壥傪昡壙偣偞傞傪摼側偄偲巚偭偰偄偨傜丄側傫偺偙偲偼側偄丄娯崙撪偱尦堅埨晈傗巟墖抍懱偺寖偟偄斀敪偵崌偄丄娯崙惌晎偼棫偪墲惗偟偰偄傞丅偦傕偦傕埨攞庱憡偺幱嵾偼岥愭偩偗丄怱拞偱偼岆偭偨楌巎擣幆傪夵傔傛偆偲偣偢丄幱嵾偺婥帩偪側偳偐偗傜傕側偄偙偲偼尒偊尒偊偩丅偙偺崌堄偼擔娯憃曽偲傕傾儊儕僇偵尵傢傟偰廬偭偨偩偗偺惌帯揑嶻暔偵偡偓側偄丅埨攞偑娯崙偵峴偒丄斵彈偨偪偵夛偭偰摢傪壓偘偱傕偟側偄偐偓傝丄尦堅埨晈偨偪偼擺摼偟側偄偟丄彮彈憸偺揚嫀偵墳偠側偄偩傠偆丅偟偐偵埨攞偵偦傫側搙嫻傗桬婥偑偁傞偼偢傕側偄丅傑偟偰傗丄尦堅埨晈偺婥帩偪傪媡側偱偡傞傛偆側栂尵傪揻偔僶僇側崙夛媍堳偑弌偰偔傞丅埨攞偺廃傝偼塃梼崙悎庡媊偺懁嬤偩傜偗偩偐傜丄崱屻傕偦傫側敪尵偼懕偔偩傠偆丅
戝夾擔偺栭偺廽夑憶偓偺側偐丄僪僀僣偺働儖儞偱婲偒偨廤抍朶峴帠審偑僪僀僣偵寖恔傪憱傜偣偰偄傞丅梕媈幰偺側偐偵拞搶偐傜偺擄柉偑娷傑傟偰偄偨偙偲偐傜丄傕偲傕偲僀僗儔儉攔愃傪慽偊偰偒偨嬌塃惃椡偑丄偙偲偝傜晄埨傪偁偍傝偨偰丄堏柉攔愃偺婥惃傪忋偘偰偄傞丅廤抍怱棟偵傛傞斊嵾傗惈揑朶峴偼側偵傕擄柉偵偐偓偭偨榖偟偱偼側偄丅偦偟偰100枩恖埲忋偵偺傏傞懡悢偺擄柉偑棳擖偟偨傜丄偦偺側偐偵偨偪偺埆偄偺偑崿偠偭偰偄傞偺偼摉慠偩丅偦傟側偺偵丄偙偺帠審傪宊婡偵丄僪僀僣崙撪偺攔奜庡媊偨偪偲屇墳偡傞偐偺傛偆偵丄EU偺媽搶墷彅崙傕丄傕偲傕偲斀懳偟偰偄偨擄柉庴偗擖傟惌嶔傊偺斀敪傪嫮傔偰偄傞偲偄偆丅擄柉傪愊嬌揑偵庴偗擖傟偰偒偨儊儖働儖庱憡偼偝偧摢偑捝偄偩傠偆丅
1寧3擔偵僒僂僕傾儔價傾偑僀儔儞偲崙岎傪抐愨偟偨丅僒僂僕偑僔乕傾攈偺惞怑幰傪張孻偟丄偦傟傪搟偭偨僀儔儞偺柉廜偑僒僂僕戝巊娰傪廝寕偟偨偺偑敪抂偩偭偨丅拞搶偺戝崙丄僒僂僕偲僀儔儞偵偼丄傕偲傕偲僗儞僯攈偲僔乕傾攈偺廆嫵揑側懳棫偑偁偭偨偑丄崱夞丄僒僂僕偑嫮峝嶔偵弌偨偺偼丄愇桘壙奿偺壓棊偵傛傝宱嵪偑埆壔偟丄廩枮偟偨崙柉偺晄枮傪奜晹偵揮壟偡傞偨傔丄偦偟偰枿寧娭學偵偁偭偨傾儊儕僇偑揋崙僀儔儞偲梈榓偟傛偆偲偟偰偄傞偺傪尅惂偡傞偨傔偩偭偨丄偲愱栧壠偼暘愅偟偰偄傞丅偙偺婡偵忔偠偰僒僂僕偵庤傪怢偽偦偆偲偡傞儘僔傾丄屨帇峒乆偲忬嫷傪偆偐偑偆拞崙丄僀僗儔儉偺嫮崙偳偆偟偺峈憟傪傎偔偦徫傫偱偄傞僀僗儔僄儖丄拞搶偺攅尃傪傔偖傞戝崙偺巚榝偑婋婡傪偁偍傞丅
僀僗儔儉崙乮IS乯偺僥儘偼懕敪偡傞丅1寧12擔偵偼僀僗僞儞僽乕儖偱丄偦偟偰14擔偵偼僕儍僇儖僞偱僥儘偑敪惗丄偮偄偵傾僕傾偵傑偱媦傫偩丅僀僗儔儉夁寖攈僥儘偺崻杮揑側尨場偼丄奿嵎丄昻崲丄嵎暿丄偦偟偰墷暷戝崙偺僄僑偵偁傞丅椡偱梷偊崬傕偆偲偡傞偐偓傝丄憺埆偺楢嵔偼懕偒丄僥儘偼側偔側傜側偄丅
1寧6擔偵杒挬慛偑峴側偭偨悈敋幚尡偼丄擔杮偺儊僨傿傾偵傕悽奅奺崙偵傕戝憶摦傪姫偒婲偙偟偨丅傎傫偲偆偵悈敋偩偭偨偺偐偳偆偐偵偮偄偰偼媈媊偑掓偝傟偰偄傞偑丄偄偢傟偵偣傛丄擔杮偑偙偺偙偲偱戝憶偓偡傞偺偼丄杒挬慛偲擔杮崙撪偺孯旛奼挘榑幰偺巚偆偮傏偱偁傝丄嬸偺崪捀偩丅偙傟偼杒挬慛偑忢搮庤抜偲偡傞挧敪偱偁傝丄杒挬慛傊偺懳墳偼崙楢埨曐棟偵擟偣偰偍偗偽偄偄偺偩丅
崙撪偱偼1寧4擔偵捠忢崙夛偑巒傑偭偨偑丄憡傕曄傜偸師尦偺掅偄榑愴偵廔巒偟偰偄傞丅栚棫偮偺偼埨攞偺嫮峝巔惃偩丅埨攞偼姰慡偵栰搣傪鋜傔偰偄傞丅嶲堾慖傪尒墇偟丄埨攞惌尃偼嵿尮傪柍帇偟偰枹慭桳偺僶儔儅僉惌嶔傪恑傔偰偄傞丅慖嫇偺偨傔偵嬥傪攝傞偺偩偐傜丄偙傟偼慖嫇堘斀偵摍偟偄丅偄偭傐偆偱埨攞偼丄偁傟偩偗媫偄偱埨曐朄埬傪惉棫偝偣偨偺偵丄偄傑偺偲偙傠帺塹戉偺奀奜攈尛偼晻報偟偰偄傞丅慖嫇慜偵攈暫偡傟偽崙柉偐傜斀敪偝傟傞偐傜偩丅偩偑丄廜嶲椉堾偱3暘偺2傪妋曐偡傟偽丄偄傑偼擫偐傇傝傞偟偰偄傞埨攞偼堦婥偵杮惈傪昞偡偩傠偆丅嫟嶻搣偺栰搣嫟摤偺怽偟擖傟傪廟偭偨柉庡搣偼嶲堾慖偱彑偮戝偒側僠儍儞僗傪堩偟偨丅嶲堾偱梌搣偑3暘偺2埲忋偺媍惾傪庢傟偽丄帺柉搣偼壗偱傕偱偒傞丅偡偱偵埨攞偼彑偭偨婥偵側傝丄夵寷傪岥偵偟偰偄傞丅偄傑偲側偭偰偼埨攞偑挷巕偵忔傝偡偓偰幐嶔傪斊偡偺傪懸偮偟偐側偄丅
2015.12.28 (寧) 2015擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
1丂亀恄偺悈亁 僷僆儘丒僶僠僈儖僺 乮憗愳SF僔儕乕僘乯
2丂亀炁 (僄儞僕儏)亁 寧懞椆塹 乮岝暥幮乯
3丂亀尷奅揰亁 僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕 乮暥錣弔廐乯
4丂亀嫮廝亁 僼僃儕僢僋僗丒僼儔儞僔僗 乮僀乕僗僩僾儗僗乯
5丂亀柾曧斊亁 M丒儓乕僩 仌 H丒儘乕僙儞僼僃儖僩 乮憂尦暥屔乯
6丂亀惡亁 傾乕僫儖僨儏儖丒僀儞僪儕僟僜儞 乮憂尦幮乯
7丂亀僗僉儞丒僐儗僋僞乕亁 僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕 乮暥錣弔廐乯
8丂亀傾僲僯儅僗丒僐乕儖亁 栻娵妜 乮妏愳彂揦乯
9丂亀偁傝傆傟偨婩傝亁 僂傿儕傾儉丒働儞僩丒僋儖乕僈乕 乮憗愳億働儈僗乯
10丂亀僎儖儅僯傾亁 僴儔儖僩丒僊儖僶乕僗 乮廤塸幮暥屔乯
 1埵偵嫇偘偨僷僆儘丒僶僠僈儖價偺亀恄偺悈亁偼SF偲柫懪偨傟偰弌斉偝傟偨嶌昳偩偑丄撪梕揑偵偼僟乕僋側僀儊乕僕傪偨偨偊偨僷儚僼儖側償傽僀僆儗儞僗朻尟彫愢偩丅柺敀偝偺揰偱偼懠傪埑搢偟偰偍傝丄悢擭慜偵榖戣偵側偭偨僪儞丒僂傿儞僘儘僂偺亀將偺椡亁傪巚偄婲偙偝偣傞丅晳戜偼嬤枹棃偺傾儊儕僇丄抧媴壏抔壔偵傛偭偰悈偑屚妷偟偐偗偰偄傞傾儊儕僇撿惣晹偱偼丄僐儘儔僪愳偺悈棙尃傪傔偖偭偰奺廈偑峈憟偟偰偄傞丅庡恖岞偼媼悈岞幮偵屬傢傟偰攈尛偝傟偨岺嶌堳偺抝丄偦傟偵晀榬僕儍乕僫儕僗僩偺彈偲擄柉偺彮彈偑偐傜傓丅暔岅偼偙偺3恖偺峴摦偑偑岎屳偵昤偐傟丄傗偑偰斵傜偼塣柦揑側弌夛偄傪壥偨偡丅朶椡偲棤愗傝偑巟攝偡傞悽奅丄曵夡偟偮偮偁傞峳椓偲偟偨搒巗偱丄斵傜偼嬯摤偟偮偮恖娫惈傪曐偪側偑傜惗偒墑傃傛偆偲偡傞丅攑毿偲側偭偨僗儔儉偱曢傜偡昻柉偲娐嫬惍旛抧嬫偵暵偠偙傕傞晉桾憌丄奨傪媿帹傞杻栻僇儖僥儖側偳偺昤幨傕堎條側敆椡偵偁傆傟偰偄傞丅
1埵偵嫇偘偨僷僆儘丒僶僠僈儖價偺亀恄偺悈亁偼SF偲柫懪偨傟偰弌斉偝傟偨嶌昳偩偑丄撪梕揑偵偼僟乕僋側僀儊乕僕傪偨偨偊偨僷儚僼儖側償傽僀僆儗儞僗朻尟彫愢偩丅柺敀偝偺揰偱偼懠傪埑搢偟偰偍傝丄悢擭慜偵榖戣偵側偭偨僪儞丒僂傿儞僘儘僂偺亀將偺椡亁傪巚偄婲偙偝偣傞丅晳戜偼嬤枹棃偺傾儊儕僇丄抧媴壏抔壔偵傛偭偰悈偑屚妷偟偐偗偰偄傞傾儊儕僇撿惣晹偱偼丄僐儘儔僪愳偺悈棙尃傪傔偖偭偰奺廈偑峈憟偟偰偄傞丅庡恖岞偼媼悈岞幮偵屬傢傟偰攈尛偝傟偨岺嶌堳偺抝丄偦傟偵晀榬僕儍乕僫儕僗僩偺彈偲擄柉偺彮彈偑偐傜傓丅暔岅偼偙偺3恖偺峴摦偑偑岎屳偵昤偐傟丄傗偑偰斵傜偼塣柦揑側弌夛偄傪壥偨偡丅朶椡偲棤愗傝偑巟攝偡傞悽奅丄曵夡偟偮偮偁傞峳椓偲偟偨搒巗偱丄斵傜偼嬯摤偟偮偮恖娫惈傪曐偪側偑傜惗偒墑傃傛偆偲偡傞丅攑毿偲側偭偨僗儔儉偱曢傜偡昻柉偲娐嫬惍旛抧嬫偵暵偠偙傕傞晉桾憌丄奨傪媿帹傞杻栻僇儖僥儖側偳偺昤幨傕堎條側敆椡偵偁傆傟偰偄傞丅 1962擭偵僗僞乕僩偟偰朻尟彫愢僼傽儞傪擬嫸偝偣偨僨傿僢僋丒僼儔儞僔僗偺嫞攏僔儕乕僘偼慡晹偱44嶌彂偒宲偑傟偨丅偝偡偑偵拞婜埲崀偼嶌幰偺昅椡偑悐偊偨偑丄傏偔偼2010擭偺嵟廔嶌傑偱丄慡嶌傪撉傫偱偄傞丅嵟屻偺悢嶌偼懅巕偺僼僃儕僢僋僗偲偺嫟嶌偩偭偨丅偦偟偰僨傿僢僋朣偒偁偲丄僼僃儕僢僋僗偑扨撈偱嫞攏僔儕乕僘傪彂偒巒傔偨丅4埵偵嫇偘偨亀嫮廝亁偼偦偺怴丒嫞攏僔儕乕僘偺戞堦嶌偩丅寢榑偐傜尵偆偲丄偙傟偼側偐側偐偺椡嶌偱偁傞丅崪愜偟偰婻庤傪堷戅偟丄尰嵼偼嵿柋傾僪償傽僀僓乕傪柋傔傞抝偑庡恖岞丅摨椈偑幩嶦偝傟偨帠審傪挷傋偰偄傞偆偪偵僀儞僞乕僱僢僩丒僊儍儞僽儖偵傑偮傢傞堿杁偑偁傞偙偲偵婥偯偔丅傗偑偰埫嶦幰偺杺偺庤偑斵偺傕偲偺敆傞丄偲偄偆撪梕丅僼僃儕僢僋僗偺嶌壠偲偟偰偺帒幙偼晝恊偺堟偵敆偭偰偄傞丅偙傟偐傜偺怴嶌偵婜懸偟偨偄丅
1962擭偵僗僞乕僩偟偰朻尟彫愢僼傽儞傪擬嫸偝偣偨僨傿僢僋丒僼儔儞僔僗偺嫞攏僔儕乕僘偼慡晹偱44嶌彂偒宲偑傟偨丅偝偡偑偵拞婜埲崀偼嶌幰偺昅椡偑悐偊偨偑丄傏偔偼2010擭偺嵟廔嶌傑偱丄慡嶌傪撉傫偱偄傞丅嵟屻偺悢嶌偼懅巕偺僼僃儕僢僋僗偲偺嫟嶌偩偭偨丅偦偟偰僨傿僢僋朣偒偁偲丄僼僃儕僢僋僗偑扨撈偱嫞攏僔儕乕僘傪彂偒巒傔偨丅4埵偵嫇偘偨亀嫮廝亁偼偦偺怴丒嫞攏僔儕乕僘偺戞堦嶌偩丅寢榑偐傜尵偆偲丄偙傟偼側偐側偐偺椡嶌偱偁傞丅崪愜偟偰婻庤傪堷戅偟丄尰嵼偼嵿柋傾僪償傽僀僓乕傪柋傔傞抝偑庡恖岞丅摨椈偑幩嶦偝傟偨帠審傪挷傋偰偄傞偆偪偵僀儞僞乕僱僢僩丒僊儍儞僽儖偵傑偮傢傞堿杁偑偁傞偙偲偵婥偯偔丅傗偑偰埫嶦幰偺杺偺庤偑斵偺傕偲偺敆傞丄偲偄偆撪梕丅僼僃儕僢僋僗偺嶌壠偲偟偰偺帒幙偼晝恊偺堟偵敆偭偰偄傞丅偙傟偐傜偺怴嶌偵婜懸偟偨偄丅僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偺彫愢偼丄崱擭丄2嶌弌斉偝傟偨丅3埵偺亀尷奅揰亁偼楢朚婡娭偵強懏偡傞寈岇姱傪庡恖岞偵偟偨扨敪嶌昳丄偄偭傐偆7埵偺亀僗僉儞丒僐儗僋僞乕亁偼偍撻愼傒儕儞僇乕儞丒儔僀儉丒僔儕乕僘偺怴嶌偱偁傞丅撪梕偲偟偰偼丄僾儘偺儃僨傿僈乕僪偑嵥抦傪恠偟偰惁榬偺嶦偟壆偐傜昗揑傪庣傞亀尷奅揰亁偺柺敀偝偑嵺棫偭偰偄傞丅僨傿乕償傽乕摼堄偺偳傫偱傫曉偟偺楢懕偱丄嵟屻傑偱僗儕儖枮揰偩丅僯儏乕儓乕僋偱婲偒偨堎忢側楢懕嶦恖帠審傪捛偆儔僀儉丒僔儕乕僘偺怴嶌亀僗僉儞丒僐儗僋僞乕亁傕丄偄偮傕偺傛偆偵撉傒墳偊偼廩暘偱偁傝丄怴枴傕晅偗壛偊傜傟偨偄傞偑丄揥奐偑僷僞乕儞壔偟偨姶偑偁傝丄彮偟庤岰偑偮偄偨傛偆側報徾偼斲傔側偄丅
崙撪儈僗僥儕乕偐傜偼2嶌昳傪儔儞僋僀儞偝偣偨丅寧懞椆塹偺2埵亀炁亁偼丄庤偵娋埇傞惁傑偠偄朻尟傾僋僔儑儞彫愢偩丅嵟嫮偺彈愴巑偑丄巚傢偸峴偒偑偐傝偐傜丄埆媡側朶椡慻怐偵廝傢傟偨巕嫙偨偪偲愭惗偺廤抍傪彆偗偰棫偪岦偐偆丅偪傚偭偲峳搨柍宮側姶偑側偒偵偟傕偁傜偢偩偑丄堄奜側揥奐偲敆椡偁傞傾僋僔儑儞丒僔乕儞偼儕乕僟價儕僥傿敳孮偱丄彫怱側愭惗偑恎傪掟偟偰惗搆傪庣傞僔乕儞側偳傕偁傝丄傔偭傐偆柺敀偄丅寧懞椆塹偼崱擭丄傕偆1嶌丄亀塭偺拞偺塭亁偲偄偆摨偠傛偆側庯岦偺傾僋僔儑儞彫愢傪忋埐偟偰偄傞偑丄偙偺亀炁亁偺傎偆偑悢抜偡偖傟偰偄傞丅8埵偵擖傟偨栻娵妜偺亀傾僲僯儅僗丒僐乕儖亁偼丄偁傞棟桼偱孻帠傪帿傔偨抝偑庡恖岞丅棧崶偟偨尦嵢偺傕偲偵偄傞柡傪桿夳偝傟偨斵偑丄柡傪扗娨偡傋偔帺椡偱杬憱偡傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕偩丅愝掕偵傗傗擄偼偁傞偑丄寈嶡偺晠攕傪偐傜傑偣偨傝丄暼偺偁傞僉儍儔僋僞乕偺榚栶傪搊応偝偣偨傝偲丄嵟屻傑偱朞偒偝偣側偄丅
 崱擭傕僽乕儉偑懕偄偰偄傞杒墷儈僗僥儕乕偺怴嶌側偐偱丄偲傝傢偗嫽枴怺偐偭偨偺偼5埵偺僗僂僃乕僨儞丒儈僗僥儕乕亀柾曧斊亁偩丅庡恖岞偺斊嵾怱棟憑嵏姱偼丄柍椶偺彈偨傜偟偱帺屓拞怱揑偲偄偆丄側傫偲傕寵枴側抝偱丄廃傝偐傜幹鍣偺偛偲偔寵傢傟偰偄傞丅偙傫側斀姶傪嵜偝偣傞晄夣側惈奿偺抝偑庡恖岞偺儈僗僥儕乕側偳丄傔偭偨偵側偄偩傠偆丅偩偑斵偑恎偵崀傝偐偐偭偨嵭擄傪忔傝愗傞偨傔楢懕嶦恖斊傪曔傑偊傛偆偲埆愴嬯摤偡傞偺傪撉傒恑傓偆偪偵丄晄巚媍偵偦傫側懥婞偡傋偒抝偵姶忣堏擖偟偰偟傑偆丅搊応偡傞恖暔偑傒側恖娫枴朙偐側偺傕暔岅偵墱峴偒傪梌偊偰偄傞丅偦傫側墱峴偒偺怺偝偼杒墷儈僗僥儕乕偺傕偆1嶌丄6埵偵擖傟偨傾僀僗儔儞僪偑晳戜偺亀惡亁偵偮偄偰傕尵偊傞丅偐偮偰儃乕僀丒僜僾儔僲壧庤偲偟偰柤惡傪抷偣偨抝偺塰岝偲揮棊偺恖惗偲丄庡恖岞偱偁傞怱偺彎傪書偊偨儗僀僉儍償傿僋寈嶡偺寈晹偺屒撈側惗妶偑丄斶偟傒偲傎偺偐側儐乕儌傾傪偨偨偊側偑傜暥妛揑崄傝朙偐偵捲傜傟傞丅
崱擭傕僽乕儉偑懕偄偰偄傞杒墷儈僗僥儕乕偺怴嶌側偐偱丄偲傝傢偗嫽枴怺偐偭偨偺偼5埵偺僗僂僃乕僨儞丒儈僗僥儕乕亀柾曧斊亁偩丅庡恖岞偺斊嵾怱棟憑嵏姱偼丄柍椶偺彈偨傜偟偱帺屓拞怱揑偲偄偆丄側傫偲傕寵枴側抝偱丄廃傝偐傜幹鍣偺偛偲偔寵傢傟偰偄傞丅偙傫側斀姶傪嵜偝偣傞晄夣側惈奿偺抝偑庡恖岞偺儈僗僥儕乕側偳丄傔偭偨偵側偄偩傠偆丅偩偑斵偑恎偵崀傝偐偐偭偨嵭擄傪忔傝愗傞偨傔楢懕嶦恖斊傪曔傑偊傛偆偲埆愴嬯摤偡傞偺傪撉傒恑傓偆偪偵丄晄巚媍偵偦傫側懥婞偡傋偒抝偵姶忣堏擖偟偰偟傑偆丅搊応偡傞恖暔偑傒側恖娫枴朙偐側偺傕暔岅偵墱峴偒傪梌偊偰偄傞丅偦傫側墱峴偒偺怺偝偼杒墷儈僗僥儕乕偺傕偆1嶌丄6埵偵擖傟偨傾僀僗儔儞僪偑晳戜偺亀惡亁偵偮偄偰傕尵偊傞丅偐偮偰儃乕僀丒僜僾儔僲壧庤偲偟偰柤惡傪抷偣偨抝偺塰岝偲揮棊偺恖惗偲丄庡恖岞偱偁傞怱偺彎傪書偊偨儗僀僉儍償傿僋寈嶡偺寈晹偺屒撈側惗妶偑丄斶偟傒偲傎偺偐側儐乕儌傾傪偨偨偊側偑傜暥妛揑崄傝朙偐偵捲傜傟傞丅暥妛揑崄傝偲偄偊偽丄9埵偺僂傿儕傾儉丒僋儖乕僈乕嶌亀偁傝傆傟偨婩傝亁傕偦偺僗僞僀儖偵懏偡傞儈僗僥儕乕偱丄僩儅僗丒H丒僋僢僋偺婰壇僔儕乕僘傪憐婲偝偣傞丅儈僱僜僞偺揷幧挰偱曢傜偡暯杴側壠懓傪廝偭偨斶寑偑丄庡恖岞偺彮擭帪戙偺巚偄弌偲偟偰岅傜傟傞丅彮擭偑戝恖偺悽奅傪奯娫尒傞傂偲壞偺懱尡偼丄愗側偔丄傎傠嬯偄丅屄恖揑偵偼丄偁傑傝偙偺庤偺儈僗僥儕乕偼岲偒偱偼側偄偑丄嶌幰偺妋偐側椡検傪姶偠傞丅10埵偺僴儔儖僩丒僊儖僶乕僗嶌亀僎儖儅僯傾亁偼僫僠僗偑巟攝偡傞愴帪壓偺儀儖儕儞偑晳戜丄儐僟儎恖偱偁傞偨傔怑傪捛曻偝傟偨尦孻帠偑恊塹戉偵屇傃弌偝傟丄椔婏嶦恖帠審偺憑嵏傪惪偗晧偆偙偲偵側傞丅廂梕強憲傝偵側傞偙偲傪嫰偊側偑傜丄僪僀僣偐傜偺扙弌傪夋嶔偟偮偮憑嵏偵偁偨傞斵偼堄奜側恀憡偵偨偳傝拝偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕偩丅嬞敆偟偨儀儖儕儞偺忬嫷丄嬻廝偵傛偭偰姠釯偲壔偟偨奨偺昤幨偑岻傒偵昤偐傟偰偄傞丅
2015.12.16 (悈) 嵟戝偺晄惓偲媆嵩傪惗傒弌偟偰偄傞偺偼埨攞惌尃偩
埨攞庱憡偺媆嵩偼丄悢偊忋偘傟偽偒傝偑側偄丅仴夝庍夵寷偲偄偆偛傑偐偟偵傛偭偰埨曐朄惂傪偱偭偪忋偘丄懠崙偺愴憟偵壛扴偡傞摴傪嶌傞丅仴傾儀僲儈僋僗偑偡偱偵攋抅偟偰偄傞偙偲偼柧傜偐側偺偵丄惉壥傪忋偘偰偄傞偲尵偄曞傝丄乬宱嵪偼夞暅婎挷偵偁傞乭偲塕傪偮偔丅仴埨曐朄惂偵傛偭偰擔暷埨曐偺曅柋惈偑夝徚偝傟偨偲尵偄側偑傜丄暷孯婎抧偵偐偐傞旓梡偼尭妟偱偒偢丄懳暷廬懏偵揙偟偰巚偄傗傝梊嶼偺憹妟傪擣傔傞丅仴擔杮恖偺埨慡偑戞堦偲尵偄側偑傜丄墷暷偲僀僗儔儉夁寖攈偺愴偄偵懌傪撍偭崬傒丄桳巙楢崌偵嶲壛偡傞偲岞尵偟偰擔杮傪僥儘偺婋尟偵姫偒崬傓丅仴榖偟崌偄偺斷偼奐偐傟偰偄傞偲尵偄側偑傜丄帪戙嶖岆偺楌巎擣幆傪夵傔傛偆偲偣偢丄椬崙偱偁傞拞崙丄娯崙偲偺娭學傪椻偊愗傜偣懕偗傞丅
埨攞偲悰偺埆鐓僐儞價偵傛傞塕偲尵偄摝傟偼傑偩傑偩偁傞丅仴僐儞僩儘乕儖偝傟偰偄傞偲嫻傪挘傞暉搰尨敪偼丄偄傑偩偵墭愼悈傪悅傟棳偟懕偗偰偄傞丅仴壂撽婎抧栤戣偱偼丄晛揤娫偺晧扴寉尭傪岥幚偵丄曈栰屆偵怴偟偄暷孯婎抧傪寶愝偟傛偆偲偡傞丅仴庛幰媬嵪偲彮巕壔懳嶔偼妡偗惡偩偗丄棙尃傪妋曐偡傞偙偲偲慖嫇偱彑偮偙偲偟偐峫偊偢丄1壄憤妶桇扴摉側偳偲偄偆柍梡側戝恇怑傪怴愝偟偰屝揾偟丄戝婇嬈偲寢戸偟偰昻晉偺奿嵎傪憹戝偝偣傞丅仴幮夛曐忈旓偺嵿尮偑側偄偲尵偄側偑傜丄崙惌偺柍懯傗棙尃偺壏彴偱偁傞撈棫峴惌朄恖傪曻抲偟偰旓梡偺愡栺傪懹傝丄戝婇嬈偺朄恖惻傪尭惻偟丄杊塹旓傪憹戝偝偣丄慖嫇懳嶔偱嬥傪偽傜傑偔丅仴杒挬慛漟抳栤戣偼丄夝寛偵岦偐偆偳偙傠偐丄傓偟傠墦偺偄偰偄傞偺偵丄恑揥偟偰偄傞偐偺傛偆偵憰偆丅
偙偺傛偆偵彂偄偰偄偔偲丄暊棫偨偟偝偑曞傞偽偐傝偩丅埨攞惌尃偼傑偝偵塕偲婾憰偱揾傝屌傔傜傟偰偄傞丅埫嬸側埨攞偺朶憱偼擔杮傪揇徖偺側偐偵堷偒偢傝崬傕偆偲偟偰偄傞丅偙傫側偵旕摴側惌尃偼愴屻偐偮偰側偐偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅栰搣偼偰傫偱傫偽傜偽傜偺忬懺偱丄傑偭偨偔椡偑側偄丅偦傕偦傕丄搢妕偺愭摢偵棫偮傋偒栰搣戞1搣偺柉庡搣偑夝懱悺慜偩丅栰搣偑偩傜偟偑側偄偐傜埨攞惌尃偼傑偡傑偡憹挿偡傞丅傗傝偨偄曻戣偩丅偙偺傑傑偱偼丄棃擭偺嶲堾慖偱帺柉搣偑彑偮偺偼栚偵尒偊偰偄傞丅
儅僗僐儈傕傑偭偨偔棅傝偵側傜側偄丅撉攧丄嶻宱傪偼偠傔丄戝怴暦偼偡傋偰埨攞偺湗妳偵埾弅偟丄惌尃偺峀曬帍偵惉傝壓偑偭偨姶偑偁傞丅怴暦偼丄巻柺偱徚旓惻傪憹惻偣傛偲尵偄側偑傜丄乬抦幆偵偼壽惻偣偢乭側偳偲傕偭偲傕傜偟偄榑棟傪帩偪弌偟丄帺暘偨偪偩偗偼寉尭惻棪偺揔梡傪庴偗丄棙塿傪摼傛偆偲偡傞丅岞暯傪巪偲偡傞怴暦偑晄岞暯傪彆挿偡傞偺偩丅偦傫側斵傜偑丄偳偆偟偰尃椡偺棎梡傪慾巭偱偒傛偆偐丅
婬戙偺楎埆側庱憡丄埨攞怶嶰偲丄偦偺拑朧庡偱偁傞悰媊執姱朳挿姱偼丄崙柉傪閤偡崙懐偵摍偟偄丅偁傑傝偵崙柉傪僶僇偵偟偰偄傞丅偦傟側偺偵丄巟帩棪偼偄偭偙偆偵壓偑傜側偄丅崙柉偼側偤埨攞惌尃偺媆嵩傪尒敳偗側偄偺偩傠偆丅埨攞偺尵偆乬擔杮偼傛偔側傞乭偲偄偆尵梩傪怣偠偰偄傞偺偩偲偟偨傜丄偁傑傝偵偍恖岲偟偩偲尵傢偞傞傪偊側偄丅嵓媆偵堷偭偐偐偭偨傜丄閤偡曽偑埆偄偺偼傕偪傠傫偩偑丄尒偊摟偄偨塕偵閤偝傟傞曽傕垻曫側偺偩丅
棃擭偼傕偭偲傑偟側悽偺拞偵側偭偰傕傜偄偨偄傕偺偩偑丄埫偄嵽椏偽偐傝偱丄偳偆峫偊偰傕柧傞偄挍偟偼尒偊側偄丅栰搣傕儅僗僐儈傕棅傝偵側傜側偄偲偡傟偽丄崙柉偑帺妎偟丄搟傝傪帩偭偰棫偪忋偑傞偟偐側偄丅崙柉偑閤偝傟偰偄傞偙偲偵婥偑偮偒丄偦傟偑撍攋岥偵側偭偰埨攞惌尃懪搢偺婡塣偑惙傝忋偑傞偙偲傪婅偆偺傒偩丅
2015.11.29 (擔) 捛憐偺尨愡巕
 尨愡巕偑9寧偵朣偔側偭偰偄偨偲偄偆僯儏乕僗偑曬偠傜傟偨偺偼11寧26擔偩偭偨丅嫕擭95嵨丅晄巚媍側嬼慠偩偑丄偦偺慜栭丄僨價儏乕偟偰娫傕側偄庒偒擔偺斵彈偑弌墘偟偨丄氼愜偺揤嵥丄嶳拞掑梇娔撀偺塮夋乽壨撪嶳廆弐乿傪尒偰偄偨丅1936擭偺嶌昳偩丅塮夋偦偺傕偺偺丄柍懯傪攔偟偨僥儞億偺偄偄揥奐丄墱峴偒傪姶偠偝偣傞夋柺峔恾偵怱庝偐傟傞偄偭傐偆偱丄傏偔偼尨愡巕偺摉帪16嵨偵偟偰偼戝恖傃偨悙乆偟偄旤偟偝偵摡慠偲側偭偰偄偨丅斵彈偑崀傝偟偒傞愥傪攚宨偵垼偟偘偵偨偨偢傓僔乕儞偺桪夒側晽忣偼愨昳偩偭偨丅
尨愡巕偑9寧偵朣偔側偭偰偄偨偲偄偆僯儏乕僗偑曬偠傜傟偨偺偼11寧26擔偩偭偨丅嫕擭95嵨丅晄巚媍側嬼慠偩偑丄偦偺慜栭丄僨價儏乕偟偰娫傕側偄庒偒擔偺斵彈偑弌墘偟偨丄氼愜偺揤嵥丄嶳拞掑梇娔撀偺塮夋乽壨撪嶳廆弐乿傪尒偰偄偨丅1936擭偺嶌昳偩丅塮夋偦偺傕偺偺丄柍懯傪攔偟偨僥儞億偺偄偄揥奐丄墱峴偒傪姶偠偝偣傞夋柺峔恾偵怱庝偐傟傞偄偭傐偆偱丄傏偔偼尨愡巕偺摉帪16嵨偵偟偰偼戝恖傃偨悙乆偟偄旤偟偝偵摡慠偲側偭偰偄偨丅斵彈偑崀傝偟偒傞愥傪攚宨偵垼偟偘偵偨偨偢傓僔乕儞偺桪夒側晽忣偼愨昳偩偭偨丅尨愡巕偑彈桪偲偟偰妶摦偟偨偺偼1935擭偐傜62擭傑偱丄擭楊偱偄偊偽15嵨偐傜42嵨傑偱偩丅斵彈偼僨價儏乕偟偰娫傕側偔丄挙傝偺怺偄旤杄偵傛偭偰僗僞乕偵側偭偨偑丄彈偲偟偰偺旤偟偝偑壴奐偔20戙慜敿偼丄懢暯梞愴憟偨偗側傢偺帪戙偱丄傕偭傁傜愴堄崅梘塮夋偵弌墘偟偰偄偨偺偑惿偟傑傟傞丅彈桪偲偟偰杮椞傪敪婗偟巒傔偨偺偼愴屻偵側偭偰偐傜偩傠偆丅彫捗埨擇榊丄崟郪柧丄惉悾枻婌抝丄媑懞岞嶰榊側偳丄娔撀偵傕宐傑傟丄懡偔偺柤嶌偵弌墘偟偨丅偲傝傢偗彫捗埨擇榊偲偺僐儞價偼桳柤偵側偭偨丅1963擭丄偦偺擭偵朣偔側偭偨彫捗偵弣偠傞偐偺傛偆偵塮夋奅傪堷戅偟丄埲屻偼恖慜偵偄偭偝偄巔傪尰偝側偔側偭偨丅偦傟偑尨愡巕傪恄奿壔偟偨丅
彫妛惗偺偙傠丄曣偵楢傟傜傟偰尒偨塮夋偺傂偲偮偵乽僲儞偪傖傫塤偵忔傞乿乮1955擭乯偑偁傞丅巕栶偺榢暎惏巕偑庡墘偟偨帣摱岦偗塮夋偩偑丄榢暎偺曣恊栶傪傗偭偨偺偑尨愡巕偩偭偨丅偩偑丄偦傟偼屻偵側偭偰抦偭偨偙偲偱偁傝丄塮夋偺側偐偱偺斵彈偺婄偼傑偭偨偔妎偊偰偄側偄丅拞妛偵擖偭偰乽擔杮抋惗乿乮1959擭乯傪尒偨丅擔杮晲懜偵暞偡傞嶰慏晀榊偑庡墘偺恄榖傪戣嵽偵偟偨搶曮僆乕儖僗僞乕塮夋偩丅偙傟偵偼尨愡巕偑側傫偲揤徠戝恄偺栶偱弌偰偄偨丅偙偺塮夋偱偺斵彈偺婄偼偄傑傕妎偊偰偄傞丅埿尩偺偁傞柺挿偺偍巓偝傫偲偄偆報徾傪書偄偨丅梋択偩偑丄娾屗塀傟偺僔乕儞偱斷傪偙偠偁偗傞庤椡抝恄傪傗偭偨偺偼丄摉帪偺恖婥憡杘椡巑丄挬挭偩偭偨丅
 尨愡巕偲偄偆彈桪偺柤慜偲婄傪弶傔偰擣幆偟偨偺偼丄戝妛偵擖偭偰丄柤夋嵗偱崟郪柧偺乽傢偑惵弔偵夨偄側偟乿乮1946擭乯傪尒偨偲偒偩偭偨丅1960擭戙廔傢傝偛傠偺偙偲偱丄斵彈偼偡偱偵塮夋奅偐傜堷戅偟偰偄偨丅柉庡庡媊傪慺杙偵偵偆偨偄偁偘偨偙偺岾偣側塮夋偱僸儘僀儞傪柋傔偨尨愡巕偼丄偠偮偵惗偒惗偒偲偟偰偄偨丅塮夋偺屻抜丄娋偵傑傒傟側偑傜栰椙巇帠偵惛傪弌偡斵彈偺敩檹偲偟偨昞忣偑朰傟傜傟側偄丅尨愡巕偑弌偨塮夋偼丄偦傟傎偳偨偔偝傫偼尒偰偄側偄偑丄尒偨斖埻偱尵偊偽丄栘壓宐夘娔撀偺婌寑乽偍忟偝傫姡攖乿乮1949擭乯偱杤棊壺懓偺柡傪墘偠偨斵彈偑偄偪偽傫怺偔報徾偵巆偭偰偄傞丅偙偺偙傠丄斵彈偼29嵨丄偄偪偽傫鉟楉偵尒偊傞帪婜偩偭偨偐傕偟傟側偄丅儔僗僩丒僔乕儞偱偺斵彈偺戜帉 乬崨傟偰偍傝傑偡乭 偑報徾怺偐偭偨丅
尨愡巕偲偄偆彈桪偺柤慜偲婄傪弶傔偰擣幆偟偨偺偼丄戝妛偵擖偭偰丄柤夋嵗偱崟郪柧偺乽傢偑惵弔偵夨偄側偟乿乮1946擭乯傪尒偨偲偒偩偭偨丅1960擭戙廔傢傝偛傠偺偙偲偱丄斵彈偼偡偱偵塮夋奅偐傜堷戅偟偰偄偨丅柉庡庡媊傪慺杙偵偵偆偨偄偁偘偨偙偺岾偣側塮夋偱僸儘僀儞傪柋傔偨尨愡巕偼丄偠偮偵惗偒惗偒偲偟偰偄偨丅塮夋偺屻抜丄娋偵傑傒傟側偑傜栰椙巇帠偵惛傪弌偡斵彈偺敩檹偲偟偨昞忣偑朰傟傜傟側偄丅尨愡巕偑弌偨塮夋偼丄偦傟傎偳偨偔偝傫偼尒偰偄側偄偑丄尒偨斖埻偱尵偊偽丄栘壓宐夘娔撀偺婌寑乽偍忟偝傫姡攖乿乮1949擭乯偱杤棊壺懓偺柡傪墘偠偨斵彈偑偄偪偽傫怺偔報徾偵巆偭偰偄傞丅偙偺偙傠丄斵彈偼29嵨丄偄偪偽傫鉟楉偵尒偊傞帪婜偩偭偨偐傕偟傟側偄丅儔僗僩丒僔乕儞偱偺斵彈偺戜帉 乬崨傟偰偍傝傑偡乭 偑報徾怺偐偭偨丅堦斒揑偵尨愡巕偲偄偊偽丄乽搶嫗暔岅乿乮1953擭乯傪偼偠傔偲偡傞堦楢偺彫捗埨擇榊嶌昳偵傛偭偰偐偨偪嶌傜傟偨丄偟偲傗偐偱峊偊傔偩偑恈偺嫮偄彈惈偲偄偆僀儊乕僕偑嫮偄偩傠偆丅偨偟偐偵乽搶嫗暔岅乿偵偍偗傞斵彈偺懚嵼姶偼敳偒傫弌偰偄傞丅惉悾枻婌抝偺乽傔偟乿乮1951擭乯傗愳搰梇嶰偺乽彈偱偁傞偙偲乿乮1958擭乯偱斵彈偑墘偠偨恖嵢栶傕摨偠宯摑偺彈惈偩偭偨丅
 偟偐偟尨愡巕偼傎偐偵傕丄偝傑偞傑側娔撀偺傕偲偱偝傑偞傑側栶傪墘偠偨丅偦傫側側偐偱報徾偵巆偭偰偄傞偺偼丄崟郪柧偺嶌昳乽敀抯乿乮1951擭乯偱偺僫僗僞乕僔儍栶偩丅偙傟偼塮夋偲偟偰偼幐攕嶌偩偲巚偆偑丄彫捗嶌昳偲偼惓斀懳偺丄姶忣偺婲暁偑寖偟偄儈僗僥儕傾僗側僼傽儉丒僼傽僞乕儖傪墘偠傞尨愡巕偼偠偮偵慛傗偐偱丄嫮偔報徾偵巆偭偰偄傞丅斵彈偼栚偵椡偑偁傞丅偦偺栚偱僉僢偲偵傜傑傟偨傜恎偑偡偔傫偱偟傑偄偦偆偩丅偦傫側丄忣擮傪擱傗偟丄抝傪嫸傢偡彈偺栶傪斵彈偑傕偭偲墘偠偰偄傟偽丄彈桪偲偟偰偺僀儊乕僕傗昡壙傕偄傑偲偼堘偭偨傕偺偵側偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅
偟偐偟尨愡巕偼傎偐偵傕丄偝傑偞傑側娔撀偺傕偲偱偝傑偞傑側栶傪墘偠偨丅偦傫側側偐偱報徾偵巆偭偰偄傞偺偼丄崟郪柧偺嶌昳乽敀抯乿乮1951擭乯偱偺僫僗僞乕僔儍栶偩丅偙傟偼塮夋偲偟偰偼幐攕嶌偩偲巚偆偑丄彫捗嶌昳偲偼惓斀懳偺丄姶忣偺婲暁偑寖偟偄儈僗僥儕傾僗側僼傽儉丒僼傽僞乕儖傪墘偠傞尨愡巕偼偠偮偵慛傗偐偱丄嫮偔報徾偵巆偭偰偄傞丅斵彈偼栚偵椡偑偁傞丅偦偺栚偱僉僢偲偵傜傑傟偨傜恎偑偡偔傫偱偟傑偄偦偆偩丅偦傫側丄忣擮傪擱傗偟丄抝傪嫸傢偡彈偺栶傪斵彈偑傕偭偲墘偠偰偄傟偽丄彈桪偲偟偰偺僀儊乕僕傗昡壙傕偄傑偲偼堘偭偨傕偺偵側偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅尰栶帪戙偺尨愡巕偼墘媄偑壓庤偩偲尵傢傟偰偄偨傜偟偄丅愴慜偺斵彈偺塮夋偼傎偲傫偳尒偰偄側偄偺偱丄庒偄偙傠偺斵彈偑偳偆偩偭偨偺偐偼傛偔暘偐傜側偄丅偟偐偟丄愴屻偺嶌昳偵娭偟偰偼棫攈側墘媄傪偟偰偄傞傛偆偵巚偆丅斵彈傪垽偟丄廳梡偟偨彫捗埨擇榊偺孫摡傕偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄斵彈偵娭偟偰偼丄墘媄偑忋庤偄偐壓庤偐偲偄偭偨偙偲側偳丄偳偆偱傕偄偄丅尨愡巕偵偼懚嵼帺懱偐傜燌傒弌傞僆乕儔偑偁偭偨丅偨偩棫偭偰偄傞偩偗偱丄偦偺巔偐偨偪偐傜昚偆昳奿偑尒傞傕偺傪偲傝偙偵偟偨丅
尨愡巕偺巰嫀偼儅僗僐儈偱偦傟傎偳榖戣偵側偭偰偄側偄傛偆側婥偑偡傞丅堷戅偟偰偐傜50擭娫丄傑偭偨偔偺塀撡惗妶傪憲偭偰偍傝丄傕偼傗揱愢偺側偐偺彈桪偵側偭偰偟傑偭偰偄偨偐傜偩傠偆偐丅偟偐偟丄夋柺偺側偐偺斵彈偼偄傑傕尒傞傕偺傪庝偒偮偗傞枺椡傪傕偭偰偄傞偟丄偲偒偍傝慖弌偝傟傞奺庬偺乽擔杮偺彈桪儀僗僩丒僥儞乿偲偄偭偨僙儗僋僔儑儞偱偼丄偮偹偵僩僢僾丒僗儕乕偵擖偭偰偄傞丅帪戙偺棳傟傕偁傞偩傠偆偑丄偦傫側擔杮傪戙昞偡傞彈桪偺巰偵儊僨傿傾偑偁傑傝娭怱傪帵偝側偄偺偼丄偙偺崙偺暥壔偺昻崲傪暔岅偭偰偄傞傛偆偵巚傢傟偰側傜側偄丅
2015.02.15 (擔) 2014擭奀奜儈僗僥儕乕仌塮夋儀僗僩10
1丏 乽埫嶦幰偺暅廞乿 儅乕僋丒僌儕乕僯乕 乮僴儎僇儚暥屔乯
2丏 乽暷拞奐愴乿 僩儉丒僋儔儞僔乕仌儅乕僋丒僌儕乕僯乕 乮怴挭暥屔乯乯
3丏 乽僽儔僢僋丒僼儔僀僨乕乿 儅僀僋儖丒僔傾乕僘 乮僴儎僇儚暥屔乯
4丏 乽僴儕乕丒僋僶乕僩帠審乿 僕儑僄儖丒僨傿働乕儖 乮憂尦幮乯
5丏 乽僫僀儞丒僪儔僑儞僘乿 儅僀僋儖丒僐僫儕乕 乮島択幮暥屔乯
6丏 乽崟偄摰偺僽儘儞僪乿 儀儞僕儍儈儞丒僽儔僢僋 乮憗愳億働儈僗乯
7丏 乽僷僀儞僘乣旤偟偄抧崠乿 僽儗僀僋丒僋儔僂僠 乮僴儎僇儚暥屔乯
8丏 乽敾寛攋婞乣儕儞僇乕儞曎岇巑乿 儅僀僋儖丒僐僫儕乕 乮島択幮暥屔乯
9丏 乽僑乕僗僩儅儞乣帪尷巻暭乿 儘僕儍乕丒儂僢僽僗 乮暥錣弔廐乯
10丏 乽偦偺彈傾儗僢僋僗乿 僺僄乕儖丒儖儊乕僩儖 乮暥弔暥屔乯
2014擭塮夋儀僗僩10
1丏 乽僱僽儔僗僇乣傆偨偮偺怱傪偮側偖椃乿 傾儗僋僒儞僟乕丒儁僀儞 乮暷乯
2丏 乽6嵥偺儃僋偑戝恖偵側傞傑偱乿 儕僠儍乕僪丒儕儞僋儗僀僞乕 乮暷乯
3丏 乽彫偝偄偍偆偪乿 嶳揷梞師 乮擔乯
4丏 乽僕儍乕僕乕丒儃乕僀僘乿 僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪 乮暷乯
5丏 乽僀儞僒僀僪丒儖乕僂傿儞丒僨僀償傿僗乣柤傕側偒抝偺壧乿 僕儑僄儖仌僀乕僒儞丒僐乕僄儞 乮暷乯
6丏 乽桭傛偝傜偽偲尵偍偆乿 僼儗僢僪丒僇償傽僀僄 乮暓乯
7丏 乽搶嫗擄柉乿 嵅乆晹惔 乮擔乯
8丏 乽her 悽奅偱傂偲偮偺斵彈乿 僗僷僀僋丒僕儑乕儞僘 乮暷乯
9丏 乽晳媁偼儗僨傿乿 廃杊惓峴 乮擔乯
10丏 乽僲傾乣栺懇偺廙乿 僟乕儗儞丒傾儘僲僼僗僉乕 乮暷乯
2014.11.20 (栘) 寬偝傫偑巰傫偱偟傑偭偨
傏偔偼挿擭偵傢偨傞崅憅寬偺僼傽儞偩偭偨丅彫妛惗偺偙傠丄寬偝傫偺僨價儏乕捈屻偐傜塮夋傪尒懕偗偰偒偨偐傜丄傏偔偺僼傽儞楌偼擭婫偑擖偭偰偄傞丅寬偝傫偐傜壗偐傪妛傫偩偲偐丄寬偝傫偑恖惗偺巜恓偩偭偨丄偲偄偆偙偲偱偼側偄丅偨偩丄柍崪丄僗僩僀僢僋丄恀偭惓捈丄棩媀偲偄偭偨寬偝傫偺僀儊乕僕偵帺暘傪廳偹偰崌傢偣丄傂偨偡傜摬傟偰偄偨丅偍偦傜偔慺婄偺杮恖偺惈奿偼偦傫側僀儊乕僕偲偼偐側傝堘偭偰偄偨偩傠偆丅偩偑丄僼傽儞偲偄偆傕偺偼帺暘偺摬溮偲棟憐傪僸乕儘乕偵搳塭偡傞傕偺側偺偩丅
 崅憅寬偲偄偆偲丄傗偔偞塮夋偺僸乕儘乕偲偟偰丄偦偟偰乽岾暉偺墿怓偄僴儞僇僠乿埲崀偺崙柉揑僗僞乕偲偟偰岅傜傟傞偙偲偑傎偲傫偳偩丅偩偑傏偔偼丄偦傟傛傝慜丄50擭戙屻敿偐傜60擭戙慜敿偵偐偗偰嶨懡側塮夋偵弌墘偟偰偄偨庒偒擔偺寬偝傫傕怱偵巆偭偰偄傞偟丄偄傑傕婰壇偵從偒晅偄偰偄傞丅傏偔偑弶傔偰尒偨寬偝傫偺塮夋偼丄搶塮偐傜僨價儏乕偟偰娫傕側偄1956擭偵庡墘偟偨乽戝妛偺愇徏乿僔儕乕僘偺堦嶌偩偭偨丅傗偔偞偺恊暘偺懅巕偱嬻庤偺払恖偺庡恖岞偑戝妛偵擖妛偟偰婲偙傞偝傑偞傑側憶摦傪僐儈僇儖偵昤偄偨堦庬偺惵弔塮夋偱丄偺偪偺壛嶳梇嶰偺乽戝妛偺庒戝彨乿僔儕乕僘偺愭嬱偗偲傕偄偆傋偒撪梕偩偭偨丅傏偔偼偙傟傪尒偰偡偖偵寬偝傫偺僼傽儞偵側偭偨丅
崅憅寬偲偄偆偲丄傗偔偞塮夋偺僸乕儘乕偲偟偰丄偦偟偰乽岾暉偺墿怓偄僴儞僇僠乿埲崀偺崙柉揑僗僞乕偲偟偰岅傜傟傞偙偲偑傎偲傫偳偩丅偩偑傏偔偼丄偦傟傛傝慜丄50擭戙屻敿偐傜60擭戙慜敿偵偐偗偰嶨懡側塮夋偵弌墘偟偰偄偨庒偒擔偺寬偝傫傕怱偵巆偭偰偄傞偟丄偄傑傕婰壇偵從偒晅偄偰偄傞丅傏偔偑弶傔偰尒偨寬偝傫偺塮夋偼丄搶塮偐傜僨價儏乕偟偰娫傕側偄1956擭偵庡墘偟偨乽戝妛偺愇徏乿僔儕乕僘偺堦嶌偩偭偨丅傗偔偞偺恊暘偺懅巕偱嬻庤偺払恖偺庡恖岞偑戝妛偵擖妛偟偰婲偙傞偝傑偞傑側憶摦傪僐儈僇儖偵昤偄偨堦庬偺惵弔塮夋偱丄偺偪偺壛嶳梇嶰偺乽戝妛偺庒戝彨乿僔儕乕僘偺愭嬱偗偲傕偄偆傋偒撪梕偩偭偨丅傏偔偼偙傟傪尒偰偡偖偵寬偝傫偺僼傽儞偵側偭偨丅寬偝傫偺僉儍儕傾偼偍偍傓偹師偺3偮偵帪戙偵暘偗傜傟傞偩傠偆丅戞1婜偼1956擭偐傜64擭偵偐偗偰丄搶塮偵擖幮偟丄庒庤僗僞乕偺儂乕僾偲偟偰偝傑偞傑側僕儍儞儖偺塮夋偵弌傑偔偭偰偄偨帪戙丄戞2婜偼1965擭偐傜75擭偵偐偗偰丄擔杮嫚媞揱丄栐憱斣奜抧丄徍榓巆嫚揱側偳偺傗偔偞塮夋僔儕乕僘偱堦桇恖婥僗僞乕偵側傝丄傗偔偞塮夋傪拞怱偵塮夋弌墘偟偰偄偨帪戙丄戞3婜偼1976擭埲崀丄搶塮傪戅幮偟偰僼儕乕偵側傝丄悢乆偺柤嶌丄榖戣嶌傪偮偔偭偨幚傝懡偄帪戙偩丅
弶婜偺寬偝傫偼丄搶塮尰戙寑偺僄乕僗偲偟偰丄僒儔儕乕儅儞傕偺丄暥寍傕偺丄扵掋傕偺丄僊儍儞僌傕偺丄僒僗儁儞僗傕偺丄旤嬻傂偽傝偲僐儞價偺儐乕儌傾傕偺側偳丄偁傜備傞僕儍儞儖偺塮夋偵弌墘偟偰偄偨丅傏偔偼傕偪傠傫慡晹偼尒偰偄側偄偑丄偐側傝偺塮夋偼尒偰偄傞丅尮巵寋懢尨嶌偺乽枩擭懢榊乿乮1960擭乯丄曅壀愮宐憼偲嫟墘偺乽抧崠偺掙傑偱偮偒偁偆偤乿乮1959擭乯丄晲揷懽弤尨嶌偺乽怷偲屛偺傑偮傝乿乮1958擭乯丄嶰殸楢懢榊偲嫟墘偺乽搶嫗傾儞僞僢僠儍僽儖乿乮1962擭乯丄旤嬻傂偽傝偲嫟墘偺乽惵偄奀尨乿乮1957擭乯丄乽壴宍扵掋崌愴乿乮1958擭乯側偳丄偄傑傕婰壇偟偰偄傞塮夋偼懡偄丅儅僢僊償傽乕儞偺儈僗僥儕乽埆摽寈姱乿傪東埬偟偨乽恊暘傪搢偣乿乮1963擭乯側偳偲偄偆塮夋傕偁偭偨丅側偐偱傕嫮偔報徾偵巆偭偰偄傞偺偼尰戙傗偔偞偺峈憟傪昤偄偨彫椦峆晇娔撀偺乽朶椡奨乿乮1963擭乯偩丅偙傟偼惃椡奼戝傪恾傞怴嫽傗偔偞偺搙廳側傞寵偑傜偣偵懳偟丄愄婥幙偺傗偔偞偺寬偝傫偑姮擡戃偺弿傪愗傜偟丄扨恎墸傝崬傒傪偐偗傞偲偄偆丄偺偪偵嫽棽偟偨傗偔偞塮夋偺尨宆偲尵偭偰傕偄偄丄敆椡偵枮偪偨朰傟偑偨偄塮夋偩偭偨丅
懡偔偺塮夋偵丄庡墘丄弨庡墘偱弌偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢丄摉帪偺寬偝傫偺恖婥偼丄偦傟傎偳惙傝忋偑傜側偐偭偨丅偦偺偙傠丄尰戙寑塮夋偺恖婥僗僞乕偲偄偊偽丄愇尨桾師榊傗彫椦埉偑偄偨偑丄寬偝傫偼丄奿岲偼傛偐偭偨偑丄桾師榊偺傛偆側搒夛揑側煭棊偨暤埻婥偼側偔丄傾僉儔偺傛偆側悂偭愗傟偨恎寉偝傕側偔丄偄傑巚偆偲偳偙偐栰曢偭偨偄姶偠偑偮偒傑偲偭偰偄偨丅寬偝傫偺恖婥偑偄傑偄偪峀偑傜側偐偭偨偼丄偦偺偁偨傝偵棟桼偑偁偭偨偩傠偆丅偩偑傏偔偼桾師榊傕傾僉儔傕娽拞偵側偔丄傂偨偡傜寬偝傫偑岲偒偩偭偨丅
 偦偟偰60擭戙敿偽偐傜寬偝傫偼傗偔偞塮夋偵弌墘偟巒傔丄僗僞乕僟儉偵偺偟忋偑傞丅偙傟偵傛偭偰丄壡栙丄晄婍梡丄嬛梸揑偲偄偭偨寬偝傫偺僀儊乕僕偑弌棃忋偑偭偨丅寬偝傫偑弶傔偰戝偒側媟岝傪梺傃偨偺偼乽栐憱斣奜抧乿僔儕乕僘乮1965擭乣72擭乯偩偲巚偆偑丄偙傟偼傗偔偞塮夋偲偄偆傛傝傕丄僐儈僇儖側枴晅偗偺傾僋僔儑儞塮夋偲偄偆傋偒偱偁傠偆丅堦楢偺傗偔偞塮夋偺側偐偱偼丄乽擔杮嫚媞揱乿僔儕乕僘乮1964擭乣71擭乯傕恖婥偑偁偭偨偑丄壗偲偄偭偰傕戝僸僢僩偟偨乽徍榓巆嫚揱乿僔儕乕僘乮1965擭乣72擭乯偑嵟崅偩傠偆丅懴偊懕偗偨偡偊偵搟傝傪敋敪偝偣傞僗僩乕儕乕偼丄偒偭偪傝峔惉偝傟偨條幃旤丄悘強偵昚偆垼偟偄忣擮丄怱偵嬁偔庡戣壧偲偁偄傑偭偰丄尒傞幰傪夋柺偺側偐偵堷偒偢傝崬傫偩丅
偦偟偰60擭戙敿偽偐傜寬偝傫偼傗偔偞塮夋偵弌墘偟巒傔丄僗僞乕僟儉偵偺偟忋偑傞丅偙傟偵傛偭偰丄壡栙丄晄婍梡丄嬛梸揑偲偄偭偨寬偝傫偺僀儊乕僕偑弌棃忋偑偭偨丅寬偝傫偑弶傔偰戝偒側媟岝傪梺傃偨偺偼乽栐憱斣奜抧乿僔儕乕僘乮1965擭乣72擭乯偩偲巚偆偑丄偙傟偼傗偔偞塮夋偲偄偆傛傝傕丄僐儈僇儖側枴晅偗偺傾僋僔儑儞塮夋偲偄偆傋偒偱偁傠偆丅堦楢偺傗偔偞塮夋偺側偐偱偼丄乽擔杮嫚媞揱乿僔儕乕僘乮1964擭乣71擭乯傕恖婥偑偁偭偨偑丄壗偲偄偭偰傕戝僸僢僩偟偨乽徍榓巆嫚揱乿僔儕乕僘乮1965擭乣72擭乯偑嵟崅偩傠偆丅懴偊懕偗偨偡偊偵搟傝傪敋敪偝偣傞僗僩乕儕乕偼丄偒偭偪傝峔惉偝傟偨條幃旤丄悘強偵昚偆垼偟偄忣擮丄怱偵嬁偔庡戣壧偲偁偄傑偭偰丄尒傞幰傪夋柺偺側偐偵堷偒偢傝崬傫偩丅摉帪戝妛惗偱70擭埨曐憶偓偺塓拞偵偁偭偨傏偔偼丄懠偺懡偔偺妛惗偲摨偠偔丄帺暘傪塮夋偺側偐偺寬偝傫偲摨壔偝偣偨丅偦偺偙傠丄抮戃偵偁偭偨塮夋娰丄暥寍抧壓偱丄傛偔寬偝傫偺傗偔偞塮夋僔儕乕僘4杮棫偰偺怺栭嫽峴傪尒偨丅媤偺廧張偵墸傝崬傫偩寬偝傫偺屻傠偐傜擡傃婑偭偰偔傞搝偑偄傞偲媞惾偐傜乽偆偟傠両乿偲偄偆嫨傃惡偑偲傫偩丅寬偝傫偑埆偺恊嬍傪愗傝暁偣傞偲丄攺庤偲偲傕偵乽傛偟両乿偲偄偆惡偑忋偑偭偨丅柧偗曽丄塮夋娰傪弌傞偲偒偼丄寬偝傫傪恀帡偰丄嵍尐傪傗傗棊偲偟丄僈僯屢婥枴偵曕偄偨丅偦傫側帪戙偩偭偨丅
傗偔偞塮夋偑壓壩偵側傝丄搶塮傪戅幮偟偨偁偲偺寬偝傫偼攐桪偲偟偰戝惉偟偨丅僼儕乕偵側偭偰埲崀偺寬偝傫偺塮夋偺嵟崅寙嶌偼丄嶳揷梞師娔撀偺2嶌乽岾暉偺墿怓偄僴儞僇僠乿乮1977擭乯偲乽梱偐側傞嶳偺屇傃惡乿乮1980擭乯偱偁傠偆丅偲偔偵慜幰偼擔杮塮夋偺柤嶌偺傂偲偮偲尵偊傞丅寬偝傫偼塭傪懷傃偨晲崪側抝傪墘偠偰慺惏傜偟偄偟丄嶳揷娔撀偺嶌寑弍偑嶀偊傢偨偭偰偄傞丅乽墂 Station乿乮1981擭乯偼丄塮夋偲偟偰偺弌棃偼偦傟傎偳椙偄偲偼巚偊側偄偑丄戝夾擔偺杒奀摴偺偝傃傟偨峘挰偺嫃庰壆偺忣宨偼朰傟偑偨偄柤僔乕儞偩丅寬偝傫偲攞徿愮宐巕偼嵟崅偺柤僐儞價偩偭偨丅斢擭偺嶌昳偺側偐偱偼丄椳傪嫮梫偡傞傛偆側墘弌偵偼崲偭偰偟傑偆偑丄傗偼傝乽揝摴堳乿乮1999擭乯偑報徾怺偄丅
偙偆彂偄偰偄傞偲寬偝傫偺屻婜偺塮夋偱報徾偵巆傞傕偺偼丄傎偲傫偳偑杒奀摴傪晳戜偵偟偨傕偺側偺偵婥偑偮偔丅寬偝傫帺恎偼嬨廈丄拀朙偺扽岯挰偺弌恎側偺偵丄怱偵巆傞塮夋偺晳戜偼側偤偐杒奀摴偑懡偐偭偨丅偦偟偰寬偝傫偵偼愥偺崀傞僔乕儞偑傛偔帡崌偭偨丅寬偝傫偼傾儊儕僇塮夋偵傕壗嶌偐弌墘偟偨偑丄偦偺側偐偱偼儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉偲嫟墘偟偨僔僪僯乕丒億儔僢僋娔撀偺乽僓丒儎僋僓乿乮1974擭乯偑弌怓偩偭偨丅
斢擭偺寬偝傫偼榁偄偑栚棫偭偨丅戣柤偼朰傟偨偑丄偐側傝慜偺塮夋偱丄夋柺偵塮偝傟偨寬偝傫偺庤偺峛偵榁恖惈偺僔儈偑晜偒弌偰偄傞偺傪尒偰丄寬偝傫傕擭傪偲偭偨側丄偲湵慠偲偟偨偙偲偑偁傞丅埲慜偼尒偣側偐偭偨椳傕尒偣傞傛偆偵側偭偨丅偩偑丄寬偝傫偼尒帠偵擭傪偲偭偨丅嵟屻傑偱塮夋偵堄梸傪擱傗偟偰偄偨丅嶐擭偺寬偝傫偺暥壔孧復庴復偼戝偒側榖戣偵側偭偨偑丄傏偔偼帿戅偟偨傜奿岲偄偄偺偵偲巚偭偰偄偨丅寬偝傫偵孧復側偳帡崌傢側偄偲巚偭偨偐傜偩丅偟偐偟偦傟偼僼傽儞偺彑庤側巚偄崬傒偱偁傝丄偲偆偤傫寬偝傫偼孧復傪庴偗偨丅婰幰夛尒偱偺寬偝傫偺乽慜壢幰偺栶偽偐傝傗偭偰偄偨巹偑偙傫側復傪偄偨偩偔偲偼丒丒丒乿偲偄偆尵梩偑報徾揑偩偭偨丅
寬偝傫偑惱偭偰丄傑偨徍榓偑墦偺偄偨丅偱傕寬偝傫偲摨偠帪戙偵惗偒偰岾塣偩偭偨丅屄恖揑側偙偲偵側傞偑丄傏偔偼寬偝傫偺墢懕偒偵側傞傜偟偄丅寢崶偟偨柡偺壟偓愭偺幚壠偑寬偝傫偺墦偄恊愂偵偁偨傞偲偄偆丅偦傟傪抦偭偨傏偔偼丄堦搙偱偄偄偐傜寬偝傫偵夛偄丄埇庤偟偰乽巕嫙偺偙傠偐傜僼傽儞偱偟偨乿偲尵偄丄徫婄傪尒偨偄偲巚偭偰偄偨丅偄傑偼偦傟傕姁傢偸柌偵側偭偰偟傑偭偨丅
2014.06.22 (擔) 6寧偺儕僗儃儞偱偼僕儍僇儔儞僟偺壴偑嶇偔
億儖僩僈儖偺恖岥偼擔杮偺10暘偺1丄柺愊偼擔杮偺4暘偺1偱丄崙搚偼僀儀儕傾敿搰偺惣抂偵丄撿杒偵挿偔怢傃偰偄傞丅戝峲奀帪戙偵偼儅僛儔儞傗償傽僗僐僟僈儅偑悽奅奺抧傪弰傝丄傾僼儕僇丄撿暷乮僽儔僕儖乯丄搶撿傾僕傾偵怉柉抧傪偮偔偭偰墵惙側崙椡傪屩偭偨偑丄偄傑偼EU偺側偐偺彫崙偵側偭偰偄傞丅宱嵪揑偵偼丄僊儕僔儍傗僗儁僀儞傎偳偺婋婡偵偼娮偭偰偄側偄偑丄撿墷奺崙偺椺偵傕傟偢丄宨婥屻戅偵尒晳傢傟偰偍傝丄偐偮偰偺怉柉抧僽儔僕儖偵弌壱偓偵峴偔恖偑憹偊偰偄傞傜偟偄丅
億儖僩僈儖傪晳戜偵偟偨塮夋偲偄偊偽丄傾儞儕丒償僃儖僰僀儐娔撀丄僼儔儞僜儚乕僘丒傾儖僰乕儖庡墘偺乽夁嫀傪傕偮垽忣乿乮1954擭乯偑巚偄晜偐傇丅塮夋偺撪梕偼捠懎揑側儊儘僪儔儅偩偭偨偑丄
億儖僩僈儖偱偼丄偳偙偵峴偭偰傕傾僘儗乕僕儑偑栚偵偮偄偨丅傾僘儗乕僕儑偲偼憰忺僞僀儖偺偙偲偱丄嫵夛傗墂幧側偳岞嫟寶抸暔偺暻傗彴偩偗偱側偔丄堦斒偺壠偺奜暻偵傕巊傢傟偰偍傝丄億儖僩僈儖寶抸偺庡梫側梫慺偵側偭偰偄傞丅億儖僩僈儖偺奨暲傒傪丄扤偐偑旤偟偄曪憰巻偱曪傑傟偨傛偆偩偲尵偭偰偄偨偑丄偨偟偐偵偦傫側尵梩偑傄偭偨傝偔傞丅傾儔價傾晽偺暤埻婥傪昚傢偣傞傾僘儗乕僕儑偼丄億儖僩僈儖偺抧棟揑丄楌巎揑側暥壔偺揱摑傪
偙傫偳偺椃峴偱偼丄偲偵偐偔榁恖偺椃峴媞偑懡偐偭偨丅偳偙偵峴偭偰傕丄娤岝僶僗偐傜崀傝偰偔傞偺偼丄僪僀僣傗僀僞儕傾偺榁恖夛偺僣傾乕媞偽偐傝偩偭偨丅榁恖戝崙偵側偭偨偺偼擔杮偩偗偺偙偲偱偼側偄偺偩偲捝姶偟偨丅億儖僩偺奨偱丄捠傝傪曕偄偰偄傞偲丄彈偺巕偐傜乽僯乕丒僴僆乿偲惡傪偐偗傜傟偨丅偦偺巕偵偲偭偰丄搶梞恖偲偄偆偲拞崙恖偑巚偄晜偐傇偺偩傠偆丅埲慜偼奜崙偵峴偔偲乽僐儞僯僠儚乿偲惡傪偐偗傜傟傞偙偲偑懡偐偭偨傕偺偩丅偄傑傗拞崙偑悽奅拞偱懚嵼姶傪憹偟偰偍傝丄擔杮偼塭偑敄偔側偭偰偄傞偺傪幚姶偟偨丅
懠偺搒巗傕偦偆偩偑丄儕僗儃儞偵傕桼弿偁傞嫵夛傗廋摴堾偑偁偪偙偪偵偁傝丄偦傟傜傪尒偰夞傞偲丄偛偭偪傖偵側偭偰偳偙偑偳偙偩偐暘偐傜側偔側傞丅擔杮偵愰嫵巘偲偟偰傗偭偰偒偨僼儔儞僔僗僐丒僓償傿僄儖偼丄億儖僩僈儖偱偼惞恖偵楍偣傜傟偰偍傝丄懠偺惞恖偨偪偲暲傫偱嫵夛偵憸偑寶偰傜傟偰偄傞丅儕僗儃儞偺拞墰晹偵偁傞僒儞儘働嫵夛偼彫偝側寶暔偩偑丄屆偄僀僄僘僗夛偺嫵夛偱丄16悽婭枛偵揤惓彮擭尛墷巊愡抍偑儕僗儃儞偵傗偭偰棃偨偲偒丄偙偺嫵夛偵懾嵼偟偨偦偆偩丅嫵夛偺撪晹偵偼擔杮偐傜傗偭偰棃偨彮擭巊愡偺奊偑忺偭偰偁傞丅430擭慜丄愴崙帪戙偺擔杮偐傜偼傞偽傞傗偭偰棃偨彮擭偨偪偼丄偳傫側巚偄偱偙偺嫵夛偵懌傪摜傒擖傟偨偺偩傠偆丅
2014.05.26 (寧) 擔杮偑婋側偄
埨攞怶嶰偲偄偆嬸枂側庱憡偺撈傝傛偑傝偺朶憱偵傛傝丄廤抍揑帺塹尃偺梕擣偵岦偗偰寷朄夝庍偑曄峏偝傟傛偆偲偟偰偄傞丅埨攞偼埨曐朄惂崸側偳偲偄偆偄偐偝傑偺慻怐偵傛偭偰偐偨偪傪惍偊丄乽懠崙偺偨傔偵愴偆乿偲偄偆廤抍揑帺塹尃偺杮幙傪丄乽崙柉偺傒側偝傫傪庣傞偨傔乿偲偄偆媆嵩偲乽尷掕揑偵偟偐巊傢側偄偐傜埨怱偟偰乿偲偄偆塕偵傛偭偰婾憰偡傞丅偦傫側巕嫙偩傑偟偺拑斣偑捠梡偡傞偲巚偭偰偄傞偺偩偲偟偨傜丄埨攞偼偁傑傝偵崙柉傪僶僇偵偟偰偄傞丅
偦傕偦傕埨攞偼丄寷朄9忦偺夵掶偑擄偟偄偺偱丄96忦偺夵掶傪栚巜偟丄偦傟傕斀敪偝傟偨偺偱夝庍夵寷傪帩偪弌偟偰偒偨丅偦傫側宱堒傪尒傞偲丄壗傪尵偭偰傕埨攞偺尵梩偼怣梡偡傞偙偲偼偱偒側偄丅偩偄偄偪丄帺塹偺偨傔埲奜偺愴憟傪偟側偄偲惥偭偨擔杮偑丄側偤懠崙偺偨傔偵愴傢側偗傟偽偄偗側偄偺偐丠 擔暷埨曐忦栺偺丄傾儊儕僇偼擔杮傪庣傞偨傔偵愴偆偑擔杮偼傾儊儕僇偺偨傔偵愴偆婯掕偑側偄偲偄偆曅柋惈傪夝徚偡傞偨傔偩偲偄偆偑丄偦傟偼娫堘偄偩丅埨曐忦栺偵傛偭偰擔杮偼壂撽傪偼偠傔奺抧偵暷孯婎抧傪採嫙偟丄戝偒側媇惖傪嫮偄傜傟偰偄傞偟丄暷孯偺偨傔偵朿戝側崙偺梊嶼傪巊偭偰偄傞丅偩偐傜偙傟偼尰忬偱傕廩暘偵憃柋揑側忦栺側偺偩丅
埨攞偺朶憱偵丄栰搣偼側偡偡傋偑側偄偟丄帺柉搣偺椙幆攈傕捑栙偟偨傑傑丄帟巭傔傪偐偗傞偺偼岞柧搣偩偗偲偄偆忬嫷偼丄偁傑傝偵傕忣偗側偄丅栚偵偁傑傞偺偼丄妛幰偳傕偺尃椡偲偺桙拝偲儊僨傿傾偺尃椡傊偺寎崌偩丅側偐偱傕栚棫偮偺偼丄埨曐朄惂崸偺嵗挿傪柋傔傞杒壀怢堦偲偄偆尦搶戝嫵庼偺屼梡妛幰偺嶰昐戙尵傇傝偩丅杒壀偺丄埨攞偺堄傪懱偟偨丄崙柉傛傝崙壠偑戝帠偲尵傢傫偽偐傝偺嬌塃揑側尵摦偼丄傑偝偵崙柉傪媆偔傕偺偩丅
婋婡傪夞旔偡傞偨傔懳榖偲埨慡曐忈偺榞慻傒傪偮偔傠偆偲悽奅奺崙偑嬯椂偟偰偄傞偄傑丄廤抍揑帺塹尃側偳偲嫨傇偺偼傑偭偨偔僫儞僙儞僗偩丅夁嫀偺偁傗傑偪偐傜妛傏偆偲偣偢丄暯榓庡媊傪曻婞偟丄懳棫偐傜榓夝傊偺摴傪暵偞偟丄擔杮傪乽愴憟偑偱偒傞崙乿偵偟偰丄偄偨偢傜偵嬤椬彅崙偲嬞挘娭學傪偮偔傝弌偦偆偲偡傞埨攞偵丄惌帯傪巌傞帒奿偼側偄丅
埨攞偼丄偄偔傜尒偊摟偄偨拑斣傪墘偠偰傕丄偄偔傜尨敪帠屘偼僐儞僩儘乕儖偝傟偰偄傞偲塕傪尵偭偰傕丄僶僇側崙柉偼帺暘傪巟帩偟偰偔傟傞偲巚偭偰偄傞偺偩傠偆丅偟偐偟丄偙偙傑偱僐働偵偝傟傟偽丄偦傠偦傠崙柉傕埨攞偺嬸偐偝偵婥晅偔偼偢偩丅傕偟丄偦傟偱傕埨攞傪巟帩偡傞偲偡傟偽丄擔杮恖偼楌巎傗嫵孭偵妛傏偆偲偟側偄嶰棳偺楎摍崙柉偩偲偄偆偙偲偵側傞丅傕偟偦偆偩偲偡傟偽丄埨攞傪巟帩偡傞僣働偼崙柉帺恎偑晧傢側偗傟偽側傜側偄丅
2014.05.18 (擔) 2013擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
1. 乽埫嶦幰偺惓媊乿 儅乕僋丒僌儕乕僯乕 乮僴儎僇儚暥屔乯2013擭偼奀奜儈僗僥儕乕偵偲偭偰嬤擭偵側偄廩幚偟偨擭偵側偭偨丅撍擛尰傟偨嬃堎偺嶌壠儅乕僋丒僌儕乕僯乕偵傛傞2嶌傪偼偠傔丄枅擭偺儀僗僩丒僥儞忢楢偺儅僀僋儖丒僐僫儕乕傗僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕丄媣偟傇傝偺搊応偱偁傞僨僯僗丒儖僿僀儞傗R丒D丒僂傿儞僌僼傿乕儖僪側偳偵傛傞丄撉傒墳偊偺偁傞寙嶌丒椡嶌偑懙偭偨丅
1. 乽埫嶦幰偺捔嵃乿 儅乕僋丒僌儕乕僯乕 乮僴儎僇儚暥屔乯
3. 乽栭偵惗偒傞乿 僨僯僗丒儖僿僀儞 乮僴儎僇儚丒億働儈僗乯
4. 乽11/26/63乿 僗僥傿乕償儞丒僉儞僌 乮暥寍弔廐乯
5. 乽僋儔僢僔儍乕僘丂捘棊帠屘挷嵏斍乿 僨僀僫丒僿僀儞僘 乮暥弔暥屔乯
6. 乽僗働傾僋儘僂乿 儅僀僋儖丒僐僫儕乕 乮島択幮暥屔乯
7. 乽僼傽僀僫儖丒僞乕僎僢僩乿 僩儉丒僂僢僪 乮僴儎僇儚暥屔乯
8. 乽搤偺僼儘僗僩乿 R丒D丒僂傿儞僌僼傿乕儖僪 乮憂尦悇棟暥屔乯
9. 乽儈僗僥儕乕丒僈乕儖乿 僨僀償傿僢僪丒僑乕僪儞 乮僴儎僇儚丒億働儈僗乯
10. 乽僔儍僪僂丒僗僩乕僇乕乿 僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕 乮暥寍弔廐乯
 嶐擭偼儅乕僋丒僌儕乕僯乕偵傛傞埫嶦幰僌儗僀儅儞丒僔儕乕僘偺戞2嶌乽埫嶦幰偺惓媊乿偲戞3嶌乽埫嶦幰偺捔嵃乿偑憡師偄偱敪攧偝傟丄朻尟彫愢僼傽儞傪嫸婌偝偣偨丅2013擭偺1埵偼傇偭偪偓傝偱偙偺2嶌丄偳偪傜傕峛壋偮偗偑偨偄偺偱丄摨棪1埵偩丅嬤棃丄偙傟傎偳寣暒偒擏桇傞彫愢偼傔偭偨偵側偄丅偦偺柺敀偝偼慡惙婜偺A丒J丒僋傿僱儖偵旵揋偡傞丅乽埫嶦幰偺惓媊乿偼傾僼儕僇偺彫崙偺撈嵸幰丄乽埫嶦幰偺捔嵃乿偼儊僉僔僐偺杻栻儅僼傿傾偑庡梫側揋偩丅堦旵楾偺庡恖岞偺僾儘偵揙偟偨愴偄傇傝丄堄昞傪撍偔応柺揥奐丄偡偝傑偠偄傾僋僔儑儞丒僔乕儞偼敆椡枮揰偱丄儁乕僕傪孞傞庤偑傕偳偐偟偄丅
嶐擭偼儅乕僋丒僌儕乕僯乕偵傛傞埫嶦幰僌儗僀儅儞丒僔儕乕僘偺戞2嶌乽埫嶦幰偺惓媊乿偲戞3嶌乽埫嶦幰偺捔嵃乿偑憡師偄偱敪攧偝傟丄朻尟彫愢僼傽儞傪嫸婌偝偣偨丅2013擭偺1埵偼傇偭偪偓傝偱偙偺2嶌丄偳偪傜傕峛壋偮偗偑偨偄偺偱丄摨棪1埵偩丅嬤棃丄偙傟傎偳寣暒偒擏桇傞彫愢偼傔偭偨偵側偄丅偦偺柺敀偝偼慡惙婜偺A丒J丒僋傿僱儖偵旵揋偡傞丅乽埫嶦幰偺惓媊乿偼傾僼儕僇偺彫崙偺撈嵸幰丄乽埫嶦幰偺捔嵃乿偼儊僉僔僐偺杻栻儅僼傿傾偑庡梫側揋偩丅堦旵楾偺庡恖岞偺僾儘偵揙偟偨愴偄傇傝丄堄昞傪撍偔応柺揥奐丄偡偝傑偠偄傾僋僔儑儞丒僔乕儞偼敆椡枮揰偱丄儁乕僕傪孞傞庤偑傕偳偐偟偄丅弴埵偼戞3埵偵側偭偨偑丄柺敀偝偱偼僨僯僗丒儖僿僀儞偺乽栭偵惗偒傞乿傕僌儗僀儅儞丒僔儕乕僘偵堷偗傪庢傜側偄丅慜嶌乽塣柦偺擔乿偺懕曇偱偁傝丄嬛庰朄帪戙偺傾儊儕僇偺僊儍儞僌偨偪偺惗偒偞傑偑昤偐傟傞丅儃僗僩儞偲僼儘儕僟傪晳戜偵丄壓偭抂偐傜戝暔偵偺偟忋偑傞庡恖岞僕儑乕偺悢婏側恖惗偑丄恊暘偺忣晈偲偺楒垽丄桭忣偲棤愗傝丄揋懳偡傞僊儍儞僌抍偲偺峈憟傪捠偠偰僴乕僪儃僀儖僪丒僞僢僠偱昤偐傟傞丅偝側偑傜傾儊儕僇幮夛偺棤柺巎傪捲傞戝壨彫愢偺姶偑偁傞丅儖僿僀儞偺僗僩乕儕乕僥儔乕偲偟偰偺嵥擻偑敪婗偝傟偨彇帠帊揑側僄儞僞僥僀儞儊儞僩彫愢偩丅
戞4埵偼僗僥傿亅償儞丒僉儞僌偺乽11/26/63乿丅傏偔偼偦傟傎偳擬怱側僉儞僌丒僼傽儞偱偼側偄偑丄僞僀儉丒僩儔償僃儖傪埖偭偨彫愢偩偲偄偆偙偲偱撉傓婥偵側偭偨丅忋壓姫崌傢偣偰1000儁乕僕傪挻偊傞戝嶌偩偑丄偝偡偑偵僉儞僌丄偦傟傎偳嬯楯偡傞偙偲側偔撉椆偱偒偨丅崅峑嫵巘偺庡恖岞偑丄傂傚傫側偙偲偐傜帪娫偺寠傪捠偭偰60擭戙弶婜偺僥僉僒僗偵峴偒丄働僱僨傿戝摑椞偺埫嶦傪怘偄巭傔傛偆偲偡傞帪娫椃峴SF偱偁傝丄儂儔乕揑側梫慺偼偁傑傝側偄丅60擭戙偺傾儊儕僇偑垼姶傪崬傔偰僲僗僞儖僕僢僋偵昤偐傟偰偍傝丄偐偮偰垽撉偟偨僼傽儞僞僕乕嶌壠僕儍僢僋丒僼傿僯僀偺彫愢傪傎偆傆偮偲偝偣傞丅
 戞5埵偺怴恑嶌壠僨僀僫丒僿僀儞僘嶌乽僋儔僢僔儍乕僘乣捘棊帠屘挷嵏斍乿偼巚傢偸孈傝弌偟暔偩偭偨丅僆儗僑儞廈偱椃媞婡偺捘棊帠屘偑偁傝丄崙壠塣桝埨慡埾堳夛偺峲嬻帠屘挷嵏僠乕儉偑彽廤偝傟傞丅儊儞僶乕偼奺抧偐傜斶嶴側帠屘尰応偵晪偒丄晄柊晄媥偱尨場媶柧偵偁偨傞丅奺暘栰偺挷嵏偺僾儘偨偪偺巇帠傇傝偑崕柧偵昤偐傟偰偍傝丄偠偮偵嫽枴怺偄丅挷嵏姱偨偪偺妶桇偲暲峴偟偰丄僥儘儕僗僩傗FBI偺摦偒傕憓擖偝傟丄嬞敆姶偑忴偟弌偝傟傞丅堄奜側揥奐偑廃摓偵梡堄偝傟偰偍傝丄廔斦偺僋儔僀儅僢僋僗傕戝偄偵惙傝忋偑傞丅嶌壠偺僿僀儞僘偼偙傟偑戞1嶌偲偺偙偲丄崱屻偺怴嶌偑妝偟傒偩丅搊応恖暔偨偪偺夛榖偑丄偳偙偐僼儘僗僩寈晹偺挐傝曽偵帡偰偄傞偲巚偭偨傜丄栿幰偼僼儘僗僩丒僔儕乕僘傪庤偑偗傞嬟郪宐巵偩偭偨丅
戞5埵偺怴恑嶌壠僨僀僫丒僿僀儞僘嶌乽僋儔僢僔儍乕僘乣捘棊帠屘挷嵏斍乿偼巚傢偸孈傝弌偟暔偩偭偨丅僆儗僑儞廈偱椃媞婡偺捘棊帠屘偑偁傝丄崙壠塣桝埨慡埾堳夛偺峲嬻帠屘挷嵏僠乕儉偑彽廤偝傟傞丅儊儞僶乕偼奺抧偐傜斶嶴側帠屘尰応偵晪偒丄晄柊晄媥偱尨場媶柧偵偁偨傞丅奺暘栰偺挷嵏偺僾儘偨偪偺巇帠傇傝偑崕柧偵昤偐傟偰偍傝丄偠偮偵嫽枴怺偄丅挷嵏姱偨偪偺妶桇偲暲峴偟偰丄僥儘儕僗僩傗FBI偺摦偒傕憓擖偝傟丄嬞敆姶偑忴偟弌偝傟傞丅堄奜側揥奐偑廃摓偵梡堄偝傟偰偍傝丄廔斦偺僋儔僀儅僢僋僗傕戝偄偵惙傝忋偑傞丅嶌壠偺僿僀儞僘偼偙傟偑戞1嶌偲偺偙偲丄崱屻偺怴嶌偑妝偟傒偩丅搊応恖暔偨偪偺夛榖偑丄偳偙偐僼儘僗僩寈晹偺挐傝曽偵帡偰偄傞偲巚偭偨傜丄栿幰偼僼儘僗僩丒僔儕乕僘傪庤偑偗傞嬟郪宐巵偩偭偨丅戞6埵丄儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺乽僗働傾僋儘僂乿偼乽僓丒億僄僢僩乿乮1997擭乯埲棃偲側傞LA僞僀儉僘偺怴暦婰幰僕儍僢僋丒儅僇償僅僀傪庡恖岞偲偡傞僴乕僪儃僀儖僪彫愢丅儅僇償僅僀偼丄僐僫儕乕丒僼傽儞偵偼偍撻愼傒偺FBI憑嵏姱儗僀僠僃儖丒僂僅儕儞僌偲偲傕偵丄巆媠側楢懕嶦恖婼傪捛偄偐偗傞丅庡恖岞偲斊恖偺帇揰偐傜岎屳偵僗僩乕儕乕偑岅傜傟傞偲偄偆峔惉偑僗儕儖枮揰偱丄僐僫儕乕偺僗僩乕儕乕揥奐偺岻偝偵愩傪姫偔丅儅僇償僅僀偼挿擭嬑傔偨怴暦幮偐傜夝屬捠抦傪庴偗庢偭偰偍傝丄怴暦嬈奅偺晄嫷偲偄偆帪戙攚宨偑昤偐傟偰偄傞偙偲傕嫽枴怺偄丅
戞7埵偺乽僼傽僀僫儖丒僞乕僎僢僩乿偼僩儉丒僂僢僪偵傛傞嶦偟壆償傿僋僞乕丒僔儕乕僘偺戞俀嶌丅償傿僋僞乕偼CIA偺埶棅傪庴偗偰埫嶦傪幚峴偡傞偑丄偦偙偵偼斱楎側悌偑巇妡偗傜傟偰偄偨丅僾儘偲偟偰偺抦宐偲僥僋僯僢僋傪嬱巊偟偰椻惷偵婋婡傪扙偡傞償傿僋僞乕丄僗僺乕僨傿側応柺揥奐偑慺惏傜偟偔丄堦媺昳偺朻尟彫愢偵巇忋偑偭偰偄傞偺偩偑丄偄偐傫偣傫丄僌儕乕僯乕偵傛傞摨庯岦偺埫嶦幰僌儗僀儅儞丒僔儕乕僘偲偄偆挻淲媺偺戝寙嶌偺慜偱偼丄偳偆偟偰傕塭偑敄偔側偭偰偟傑偆丅
 戞8埵偺乽搤偺僼儘僗僩乿偼懸朷媣偟偄R丒D丒僂傿儞僌僼傿乕儖僪嶌僼儘僗僩丒僔儕乕僘偺怴栿丅搥偰偮偔恀搤丄僀僊儕僗偺僨儞僩儞巗偱丄彮彈桿夳傗攧弔晈楢懕嶦恖側偳丄偮偓偮偓偵婲偙傞帠審偵捛傢傟側偑傜丄柍擻側晹壓偲恖庤晄懌傪傏傗偒偮偮憑嵏偵偁偨傞僼儘僗僩寈晹偺妶桇偑昤偐傟傞丅僼儘僗僩偺朤庒柍恖傇傝偼傂偲偙傠傛傝僩乕儞僟僂儞偟丄恖忣枴偑晅偗壛傢偭偨傕偺偺丄壓僱僞枮嵹偺壓昳側僕儑乕僋偼寬嵼丅帺屓曐恎偟偐娽拞偵側偄彁挿偺娫敳偗傇傝傕徫傢偣傞丅偄偮傕側偑傜嬟郪宐巵偺栿偼慺惏傜偟偄丅僼儘僗僩丒僔儕乕僘偺枹栿偑偁偲1嶌偩偗偵側偭偰偟傑偭偨偺偼庘偟偄偐偓傝偩丅
戞8埵偺乽搤偺僼儘僗僩乿偼懸朷媣偟偄R丒D丒僂傿儞僌僼傿乕儖僪嶌僼儘僗僩丒僔儕乕僘偺怴栿丅搥偰偮偔恀搤丄僀僊儕僗偺僨儞僩儞巗偱丄彮彈桿夳傗攧弔晈楢懕嶦恖側偳丄偮偓偮偓偵婲偙傞帠審偵捛傢傟側偑傜丄柍擻側晹壓偲恖庤晄懌傪傏傗偒偮偮憑嵏偵偁偨傞僼儘僗僩寈晹偺妶桇偑昤偐傟傞丅僼儘僗僩偺朤庒柍恖傇傝偼傂偲偙傠傛傝僩乕儞僟僂儞偟丄恖忣枴偑晅偗壛傢偭偨傕偺偺丄壓僱僞枮嵹偺壓昳側僕儑乕僋偼寬嵼丅帺屓曐恎偟偐娽拞偵側偄彁挿偺娫敳偗傇傝傕徫傢偣傞丅偄偮傕側偑傜嬟郪宐巵偺栿偼慺惏傜偟偄丅僼儘僗僩丒僔儕乕僘偺枹栿偑偁偲1嶌偩偗偵側偭偰偟傑偭偨偺偼庘偟偄偐偓傝偩丅2012擭偵昡敾偵側偭偨僨僀償傿僢僪丒僑乕僪儞偺戞1嶌乽擇棳彫愢壠乿傪丄傏偔偼偦傟傎偳崅偔昡壙偟側偐偭偨偑丄戞9埵偵擖傟偨偙偺戞2嶌乽儈僗僥儕乕丒僈乕儖乿偼柺敀偐偭偨丅扵掋帠柋強偵屬傢傟偨彫愢壠巙朷偺惵擭偑晽曄傢傝側帠審偵姫偒崬傑傟傞榖偱丄偪傚偭偲僑僔僢僋丒儂儔乕偺擋偄偑昚偭偰偍傝丄堦愄慜偺B媺僲儚乕儖塮夋偺傛偆側枴傢偄偑偁傞丅庡恖岞偼堦庬偺僟儊恖娫偩偑丄岅傝岥偑镚乆偲偟偰偄傞偺偱暤埻婥偼埫偔側傜側偄丅庡恖岞傪庢傝姫偔搊応恖暔偑婏恖丒曄恖懙偄偱丄婏柇側枺椡傪曻偭偰偄傞丅
戞10埵丄僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偺乽僔儍僪僂丒僗僩乕僇乕乿偼丄憡庤偺怱棟傪撉傒庢傞僉僱僔僢僋僗偺僾儘偱偁傞儘僒儞僕僃儖僗偺憑嵏姱僉儍僒儕儞丒僟儞僗傪庡恖岞偵悩偊偨僔儕乕僘偺戞3嶌丅崱嶌偱僟儞僗偑懳寛偡傞偺偼恖婥僇儞僩儕乕壧庤偵傑偲傢傝偮偔堎忢側僗僩乕僇乕偩丅僕僃僼儕乕摼堄偺偳傫偱傫曉偟偼傗傗庤岰偑偮偄偨姶偑偁傞偑丄堦婥偵撉傑偣傞偟丄嬝塣傃偑偲偵偐偔偆傑偄偟丄傾儊儕僇壒妝嬈奅偺堦抂偑奯娫尒偊傞偺傕嫽枴怺偄丅晄枮側偺偼丄庡恖岞偑摼堄偲偡傞僉僱僔僢僋僗偑丄傑偭偨偔帠審偺夝寛偵栶棫偭偰偄側偄揰偩丅
2014.05.10 (搚) 弔傪庻偖僕儍僘
1. 巐寧偺巚偄弌 乮I'll Remember April乯丂僶僪丒僷僂僄儖丒僩儕僆
2. 僷儕偺巐寧 乮April in Paris乯丂僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕丒僂傿僘丒僗僩儕儞僌僗
3. 弔偺擛偔 乮It Might As We'll Be Spring乯丂僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞
4. 弔偑棃偨偲偄偆偗傟偳 乮Spring Is Here乯丂僋儕僗丒僐僫乕
5. 僕儑僀丒僗僾儕儞僌 乮Joy Spring乯丂僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞亖儅僢僋僗丒儘乕僠丒僋僀儞僥僢僩
6. 弔偼偄偪偽傫桱烼側婫愡 乮Spring Can Really Hang You Up the Most乯丂僼傿儖丒僂僢僘
7. 崱擭偺弔偼彮偟抶偔側傝偦偆乮Spring Will Be a Little Late This Year乯丂僄儔丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪
8. 僇僢僐乕傊偺僙儗僫乕僨 乮Serenade to a Cuckoo乯丂儘乕儔儞僪丒僇乕僋
9. 弔傛傝傕庒偔 乮Younger Than Springtime乯丂傾乕僩丒僼傽乕儅乕
10. 偲偮偤傫弔偑朘傟偨 乮Suddenly It's Spring乯丂僗僞儞丒僎僢僣
 弔偺嬋偲偄偊偽丄僕儍僘丒僼傽儞偑恀偭愭偵巚偄晜偐傋傞偺偼丄乮1乯偺乽I'll Remember April乿偲乮2乯偺乽April in Paris乿偱偁傠偆丅僕乕儞丒僨億乕儖嶌嬋偺桳柤側僗僞儞僟乕僪乽I'll Remember April乿偼丄嬋偺峔憿偑僕儍僘偵揔偟偰偄傞偨傔丄懡偔偺僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偵傛偭偰墘憈偝傟丄壧傢傟偰偰偄傞丅僽儔僂儞亖儘乕僠丄儅僀儖僗丄儘儕儞僘丄MJQ丄僄儘乕儖丒僈乕僫乕側偳岲墘偼偄偔偮傕偁傞偑丄傗偼傝嵟崅偺柤墘偼僶僪丒僷僂僄儖偑1947擭偵悂偒崬傫偩僺傾僲丒僩儕僆丒償傽乕僕儑儞偱偁傠偆乮亀僶僪丒僷僂僄儖偺寍弍亁Roost乯丅
弔偺嬋偲偄偊偽丄僕儍僘丒僼傽儞偑恀偭愭偵巚偄晜偐傋傞偺偼丄乮1乯偺乽I'll Remember April乿偲乮2乯偺乽April in Paris乿偱偁傠偆丅僕乕儞丒僨億乕儖嶌嬋偺桳柤側僗僞儞僟乕僪乽I'll Remember April乿偼丄嬋偺峔憿偑僕儍僘偵揔偟偰偄傞偨傔丄懡偔偺僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偵傛偭偰墘憈偝傟丄壧傢傟偰偰偄傞丅僽儔僂儞亖儘乕僠丄儅僀儖僗丄儘儕儞僘丄MJQ丄僄儘乕儖丒僈乕僫乕側偳岲墘偼偄偔偮傕偁傞偑丄傗偼傝嵟崅偺柤墘偼僶僪丒僷僂僄儖偑1947擭偵悂偒崬傫偩僺傾僲丒僩儕僆丒償傽乕僕儑儞偱偁傠偆乮亀僶僪丒僷僂僄儖偺寍弍亁Roost乯丅償傽乕僲儞丒僨儏乕僋嶌嬋偺乽April in Paris乿偼丄摨偠偔僨儏乕僋偑彂偄偨乽Autumn in New York乿偲暲傃徧偣傜傟傞柤嬋丅弔偺僷儕丄廐偺僯儏乕儓乕僋偺旤偟偝傪捲偭偨偙偺2嬋偼丄傑偝偵岲堦懳偺寙嶌僶儔乕僪偩丅偙偺嬋偺償傽乕僕儑儞偱偄偪偽傫桳柤側偺偼僇僂儞僩丒儀僀僔乕妝抍偺墘憈偱偁傠偆丅傎偐偵僙儘僯傾僗丒儌儞僋傗僐乕儖儅儞丒儂乕僉儞僗側偳偺墘憈傕抦傜傟偰偄傞偑丄傏偔偼僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕偑僗僩儕儞僌僗傪僶僢僋偵桰慠偲悂偔1950擭偺僙僢僔儑儞傪戞堦偵嫇偘偨偄乮亀僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕丒僂傿僘丒僗僩儕儞僌僗亁Verve乯丅
儘僕儍乕僗仌僴儅乕僗僞僀儞丒僐儞價偑嶌偭偨乮3乯乽It Might As Well Be Spring乿偼儈儏乕僕僇儖亀僗僥乕僩丒僼僃傾亁偺憓擖嬋丅偙傟傕僜僯乕丒僗僥傿僢僩傗傾僗僩儔僢僪丒僕儖儀儖僩亖僗僞儞丒僎僢僣側偳丄偄傠傫側僕儍僘丒僾儗僀儎乕傗壧庤偵傛偭偰嵦傝忋偘傜傟偰偄傞偑丄戙昞揑側償傽乕僕儑儞偲偄偊偽丄側傫偲偄偭偰傕弶婜偺僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偑僷儕偱榐壒偟偨僶儔乕僪墘憈偵偲偳傔傪偝偡丅忣姶偲抦惈偑崿慠堦懱偲側偭偨帄崅偺柤墘偩乮亀僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞丒僷儕丒僙僢僔儑儞亁Vogue乯丅
乮4乯偺乽Spring Is Here乿偼儘僕儍乕僗仌僴乕僩偑彂偄偨僗僞儞僟乕僪丅乬弔偑棃偨偲偄偆偺偵丄側偤傢偨偟偼晜偒晜偒偟側偄偺偩傠偆乭偲偄偆庘偟偄怱傪捲偭偨嬋偩丅僀儞僗僩丒償傽乕僕儑儞偺戙昞揑側傕偺偲偟偰偼丄價儖丒僄償傽儞僗偑嫇偘傜傟傞偩傠偆丅偩偑丄偙偙偱偼僋儕僗丒僐僫乕偵傛傞償僅乕僇儖丒償傽乕僕儑儞傪儕僗僩丒傾僢僾偟偨偄丅僋乕儖側壧彞偑悙乆偟偄枺椡傪曻偭偰偄傞乮亀僶乕僪儔儞僪偺巕庣塖乛僋儕僗丒僐僫乕亁Bethlehem乯丅
 僕儍僘儊儞偑彂偄偨僆儕僕僫儖偱偼丄僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞嶌乮5乯乽Joy Spring乿偲偄偆柤嬋偑偁傞丅僽儔僂儞亖儘乕僠丒僋僀儞僥僢僩偑悂偒崬傫偩偙偺嬋偼斵傜偺戙昞揑柤墘偺傂偲偮偵悢偊傜傟偰偄傞丅偙傟偼婌傃偵枮偪偨弔傪僀儊乕僕偟偰彂偐傟偨傕偺偩偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞偑丄儅儞僴僢僞儞丒僩儔儞僗僼傽乕偺償僅乕僇儖丒償傽乕僕儑儞偱偼丄"spring"傪乬弔乭偱偼側偔乬愹乭偲偄偆堄枴偵夝庍偟偰僕儑儞丒僿儞僪儕僢僋僗偑壧帉傪彂偄偰偄傞乮亀僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偲儅僢僋僗丒儘乕僠亁EmArcy乯丅
僕儍僘儊儞偑彂偄偨僆儕僕僫儖偱偼丄僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞嶌乮5乯乽Joy Spring乿偲偄偆柤嬋偑偁傞丅僽儔僂儞亖儘乕僠丒僋僀儞僥僢僩偑悂偒崬傫偩偙偺嬋偼斵傜偺戙昞揑柤墘偺傂偲偮偵悢偊傜傟偰偄傞丅偙傟偼婌傃偵枮偪偨弔傪僀儊乕僕偟偰彂偐傟偨傕偺偩偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞偑丄儅儞僴僢僞儞丒僩儔儞僗僼傽乕偺償僅乕僇儖丒償傽乕僕儑儞偱偼丄"spring"傪乬弔乭偱偼側偔乬愹乭偲偄偆堄枴偵夝庍偟偰僕儑儞丒僿儞僪儕僢僋僗偑壧帉傪彂偄偰偄傞乮亀僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偲儅僢僋僗丒儘乕僠亁EmArcy乯丅乮6乯乽Spring Can Really Hang You Up the Most乿偼僩儉丒僂儖僼偲偄偆嶌嬋壠偵傛傞丄弔偺僀儊乕僕偲偼傎偳墦偄丄僟乕僋側怓挷偺廰偄嬋丅塀傟偨柤嬋偲傕偄偆傋偒僶儔乕僪偱偁傝丄僕儍僢僉乕仌儘僀丄儅乕僋丒儅乕僼傿丄僒儔丒償僅乕儞側偳丄僕儍僘壧庤偵傛偭偰壧傢傟傞偙偲偑懡偄偑丄僗僞儞丒僎僢僣傗働僯乕丒僶儗儖側偳偺僀儞僗僩丒償傽乕僕儑儞傕偁傞丅傏偔偑岲偒側偺偼僼傿儖丒僂僢僘偑弶棃擔偟偨愜偵儔僀償榐壒偝傟偨僪儔儅僥傿僢僋側墘憈偩乮亀僼傿儖丒僂僢僘仌僓丒僕儍僷僯乕僘丒儕僘儉丒儅僔乕儞亁RCA乯丅
僼儔儞僋丒儗僢僒乕嶌嬋偺乮7乯乽Spring Will Be a Little Late This Year乿傕幐楒偺壧偱丄乬崱擭偼弔偺朘傟偑彮偟抶偔側傞丅偁側偨偑嫀偭偰偟傑偭偰丄傢偨偟偺怱偼搤偺傑傑乭偲偄偆旤偟偄僶儔乕僪丅儗僢僪丒僈乕儔儞僪傗傾僯僞丒僆僨僀偺墘彞偑偁傞偑丄嵟崅偺償傽乕僕儑儞偼僄儔丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪丅僗僩儕儞僌丒僆乕働僗僩儔傪僶僢僋偵愗乆偲壧偆僄儔偺壧彞偼慺惏傜偟偄偺堦岅偵恠偒傞乮亀僴儘乕丒儔償乛僄儔丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪亁Verve乯丅
僕儍僘儊儞偑彂偄偨弔偺嬋偵偼丄乽Joy Spring乿埲奜偵傕偆1嬋丄儅僀儖僗丒僨僀償傿僗偺僆儕僕僫儖乽Swing Spring乿偑偁傞偑丄偙傟偼偁傑傝柺敀偄墘憈偱偼側偄丅偦偺戙傢傝偵丄傏偔偼儅儖僠丒儕乕僪憈幰儘乕儔儞僪丒僇乕僋帺嶌帺墘偺乮8乯乽Serenade to a Cuckoo乿傪儕僗僩偵擖傟偨偄丅弔傪崘偘傞捁偲偄偊偽丄擔杮偱偼僂僌僀僗偩偑丄惣梞偱偼僇僢僐乕傜偟偄丅僇乕僋偑僼儖乕僩偱墘憈偡傞偙偺嬋偼僇僢僐乕偺柭偒惡傪柾偟偨儐乕儌儔僗偱垽傜偟偄壚嬋偩乮亀傾僀丒僩乕僋丒僂傿僘丒僓丒僗僺儕僢僣乛儘乕儔儞僪丒僇乕僋亁Limelight乯丅
 乮9乯乽Younger Than Springtime乿偼丄偙傟傕儘僕儍乕僗仌僴儅乕僗僞僀儞丒僐儞價偵傛傞儈儏乕僕僇儖亀撿懢暯梞亁偺憓擖嬋丅乬孨偼弔傛傝傕庒偔丄惎偺岝傛傝傕廮傜偐偔丄6寧偺晽傛傝抔偐偄乭偲偄偆楒恖傪巀旤偡傞壧偱丄幚幙揑偵偼弔偺壧偲偼尵偄擄偄偑丄傑偁偄偄偩傠偆丅僼儔儞僋丒僔僫僩儔傗僆僗僇乕丒僺乕僞乕僜儞偑嵦傝忋偘偰偄傞偑丄僩儔儞儁僢僩偺傾乕僩丒僼傽乕儅乕偑僩儈乕丒僼儔僫僈儞偺僩儕僆傪僶僢僋偵儚儞丒儂乕儞偱儕儕僇儖偵偆偨偄忋偘傞墘憈偑儀僗僩丒償傽乕僕儑儞偩乮亀傾乕僩乛傾乕僩丒僼傽乕儅乕亁Argo乯丅
乮9乯乽Younger Than Springtime乿偼丄偙傟傕儘僕儍乕僗仌僴儅乕僗僞僀儞丒僐儞價偵傛傞儈儏乕僕僇儖亀撿懢暯梞亁偺憓擖嬋丅乬孨偼弔傛傝傕庒偔丄惎偺岝傛傝傕廮傜偐偔丄6寧偺晽傛傝抔偐偄乭偲偄偆楒恖傪巀旤偡傞壧偱丄幚幙揑偵偼弔偺壧偲偼尵偄擄偄偑丄傑偁偄偄偩傠偆丅僼儔儞僋丒僔僫僩儔傗僆僗僇乕丒僺乕僞乕僜儞偑嵦傝忋偘偰偄傞偑丄僩儔儞儁僢僩偺傾乕僩丒僼傽乕儅乕偑僩儈乕丒僼儔僫僈儞偺僩儕僆傪僶僢僋偵儚儞丒儂乕儞偱儕儕僇儖偵偆偨偄忋偘傞墘憈偑儀僗僩丒償傽乕僕儑儞偩乮亀傾乕僩乛傾乕僩丒僼傽乕儅乕亁Argo乯丅嵟屻傪掲傔偔偔傞偺偼僶乕僋仌償傽儞丒僸儏乕僛儞偑嶌偭偨儅僀僫乕丒僗僞儞僟乕僪乮10乯乽Suddenly It's Spring乿丅楒偡傞怱偺偲偒傔偒傪弔偺朘傟偵偨偲偊偨嬋偩丅傾儖丒僐乕儞丄僘乕僩丒僔儉僘丄僼傿儖丒僂僢僘側偳丄側偤偐敀恖僒僢僋僗憈幰偑岲傫偱墘憈偟偰偄傞丅傏偔偺僠儑僀僗偼寉夣偵僗僀儞僌偡傞僗僞儞丒僎僢僣偺償傽乕僕儑儞偩乮亀僂僃僗僩丒僐乕僗僩丒僕儍僘乛僗僞儞丒僎僢僣亁Verve乯丅
2013.09.12 (栘) 摗孿巕偑惱偭偰偟傑偭偨
 1969擭丄弶傔偰乽怴廻偺彈乿傪壧偆摗孿巕傪僥儗價偱尒偨偲偒偺徴寕偼丄偄傑傕偼偭偒傝婰壇偵巆偭偰偄傞丅斵彈偺僪僗偺偒偄偨惡丄恎怳傝庤怳傝傪攔偟丄沍傪岎偊偢柍昞忣偱壧偆巔丄栰曢偭偨偄敮偵塀傟偨恖宍偺傛偆側抂惓側婄偼丄戝妛惗偩偭偨傏偔偵慛楏側報徾傪梌偊偨丅偦傫側惡偱丄偦傫側昞忣偱壧偆壧庤傪尒偨偺偼弶傔偰偩偭偨丅偦偙偵偼丄嫅愨丄掹娤丄墔擮偲偄偭偨傛偆側忣姶偑擖傝崿偠偭偰偄偨丅斵彈偺壧偼丄彑偮尒崬傒偺側偄70擭埨曐摤憟偱旀暰偟偨庒幰偺怱偵怺偔怹傒崬傫偩丅偦偺堄枴偱丄摗孿巕偼傑偝偟偔帪戙偑惗傫偩壧庤偩偭偨丅
1969擭丄弶傔偰乽怴廻偺彈乿傪壧偆摗孿巕傪僥儗價偱尒偨偲偒偺徴寕偼丄偄傑傕偼偭偒傝婰壇偵巆偭偰偄傞丅斵彈偺僪僗偺偒偄偨惡丄恎怳傝庤怳傝傪攔偟丄沍傪岎偊偢柍昞忣偱壧偆巔丄栰曢偭偨偄敮偵塀傟偨恖宍偺傛偆側抂惓側婄偼丄戝妛惗偩偭偨傏偔偵慛楏側報徾傪梌偊偨丅偦傫側惡偱丄偦傫側昞忣偱壧偆壧庤傪尒偨偺偼弶傔偰偩偭偨丅偦偙偵偼丄嫅愨丄掹娤丄墔擮偲偄偭偨傛偆側忣姶偑擖傝崿偠偭偰偄偨丅斵彈偺壧偼丄彑偮尒崬傒偺側偄70擭埨曐摤憟偱旀暰偟偨庒幰偺怱偵怺偔怹傒崬傫偩丅偦偺堄枴偱丄摗孿巕偼傑偝偟偔帪戙偑惗傫偩壧庤偩偭偨丅偦傟傛傝彮偟慜丄僇儖儊儞丒儅僉偲偄偆彮彈偑乽帪偵偼曣偺側偄巕偺傛偆偵乿偲偄偆嬋偱僨價儏乕偟偨丅僇儖儊儞丒儅僉偺柍昞忣偱扺乆偲壧偆條巕偼丄帥嶳廋巌偑壧帉傪彂偄偨垼姶昚偆嬋挷偲憡樦偭偰丄恖乆偺怱偵從偒偮偄偨丅偩偑丄徴寕搙偲偄偆揰偱偼丄摗孿巕偺傎偆偑斾傋傕偺偵側傜側側偄傎偳戝偒偐偭偨丅摉帪丄摗孿巕偺壧傪乽偙傟偼墘壧偱偼側偔墔壧偩乿偲偐乽戝廜偺儖僒儞僠儅儞偑崬傔傜傟偰偄傞乿偲偐丄偟偨傝婄偱夝愢偡傞暥壔恖傕偄偨偑丄偦傫側尵梩偼壧偺僷儚乕偺慜偱嬻偟偔嬁偄偨丅傏偔偨偪偼偨偩丄偦偺堎條側敆椡偵懪偨傟丄傂偨偡傜斵彈偺壧偵挳偒擖偭偰偄偨丅
摗孿巕偺壧偑杮暔偺敆恀惈傪懷傃偰偄偨偺偼丄傎傫偺1擭傎偳偺偁偄偩偩偭偨偲巚偆丅僔儞僌儖斦偱尵偊偽丄1969擭9寧敪攧偺乽怴廻偺彈乿偐傜70擭7寧敪攧偺乽柦梐偗傑偡乿傑偱偺4嶌偩丅偦偺屻偺斵彈偺壧偼偟偩偄偵僀儞僷僋僩偑敄傟偰偄偭偨丅1971擭偵慜愳惔偲寢崶偟偨偁偨傝偐傜丄斵彈偺僆乕儔偼幐偣丄偛偔晛捠偺墘壧壧庤偵側偭偰偄偭偨丅斵彈偺惡偼丄埲慜偺傛偆側敆椡偑側偔側偭偰偟傑偭偨丅惡懷億儕乕僾偺庤弍傪偟偨偣偄傕偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偳偙偐偱丄斵彈偑乽埲慜偺傛偆偵壧偍偆偲偟偰傞傫偩偗偳丄偳偆偟偰傕偱偒側偄偺傛乿偲挐偭偰偄傞偺傪暦偄偨偙偲偑偁傞丅
偁傟偼1971擭偩偭偨偩傠偆偐丄夛幮偺價儖偺僄儗儀乕僞乕偱嬼慠丄摗孿巕偲忔傝崌傢偣偨偙偲偑偁傞丅彫暱偱傎偭偦偟傝偟偨彈偺巕偑忔偭偰偒偨偲巚偭偨傜斵彈偩偭偨丅斵彈偼廔巒丄晅偒恖傜偟偒彈惈偲儁僠儍僋僠儍挐偭偰偄偨丅揱偊暦偔偲偙傠偵傛傞偲丄摗孿巕偼傕偲傕偲柧傞偄梲婥側巕偩偑丄壧偺埫偄僀儊乕僕偲崌傢偣傞偨傔丄偁偊偰杮棃偺僉儍儔僋僞乕傪晻報偟偰偄偨偺偩偲偄偆丅壧庤傪攧傝弌偡偨傔偺儗僐乕僪夛幮偺愴棯偲偟偰丄偲偆偤傫偦傫側偙偲傕偁偭偨偱偁傠偆丅
偄偮偟偐恖乆偺慜偐傜徚偊偰偄偭偨摗孿巕偑嵞傃僋儘乕僗傾僢僾偝傟偨偺偼丄塅懡揷僸僇儖偺曣恊偲偟偰偩偭偨丅偦偺屻偵棳傟偨丄戝嬥傪傕偭偰悽奅拞傪崑梀偟偨傝丄僇僕僲偱搎攷偟偨傝丄杻栻強帩偺媈偄偑偐偐偭偨傝偲偄偭偨僯儏乕僗偼丄偐偮偰斵彈偺僼傽儞偩偭偨幰偨偪傪垹慠偲偝偣偨丅巚偊偽丄偙偺偙傠偡偱偵斵彈偼惛恄傕惗妶傕嫊傠側傕偺偵側偭偰偄偨偺偩傠偆丅
摗孿巕偼敄岾偲偄偆僀儊乕僕傪攚晧偭偰傏偔偨偪偺慜偵尰傟偨丅偦傟偼嶌傜傟偨僀儊乕僕偱偁偭偨偼偢側偺偵丄偦傟偵庺敍偝傟偨偐偺傛偆偵丄斢擭偺斵彈偼晄岾偵尒晳傢傟丄幚懱偺側偄惗妶傪嫮偄傜傟偨丅偦傟傪巚偆偲丄壗偲傕傗傝偒傟側偄巚偄偑偡傞丅偩偑丄40擭慜偺摗孿巕偼丄抁婜娫偱偁偭偨偵偣傛丄妋偐側幚懱偲偟偰傏偔偨偪偺慜偵偄偨丅偁偺偲偒偺斵彈偼婸偄偰偄偨丅偄傑偼偨偩丄摗孿巕偺嵃傛丄埨傜偐偵偲婩傞偺傒偩丅
2013.07.26 (嬥) 僕儍僘丒償僅乕僇儖丒儀僗僩3
僽儖乕僲乕僩偩偲丄傏偔偵偲偭偰偼亀僶乕僪儔儞僪偺栭亁偑晄摦偺1埵偩偑乮僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺惗奤偺柤僾儗僀偑僼傿乕僠儍乕偝傟偰偄傞偺偱乯丄偁偲偼偦偺擔偺婥暘偵傛偭偰擖傟懼傢傞丅僶僪丒僷僂僄儖偺亀傾儊僀僕儞僌亁傕偄偄偟丄僨僋僗僞乕丒僑乕僪儞偺亀僑乕亁傕幪偰偑偨偄丅儘儕儞僘偩偭偨傜亀僯儏乕僋僗丒僞僀儉亁傕岲偒偩偟丄僌儔儞僩丒僌儕乕儞偺亀儔僥儞丒價僢僩亁偺傛偆側妝偟偄傕偺傪慖傇庤傕偁傞丅
僽儖乕僲乕僩憤慖嫇偺寢壥偼丄嬤擔拞偵敪昞偵側傞傜偟偄偑丄偍偦傜偔僜僯乕丒僋儔乕僋偺亀僋乕儖丒僗僩儔僢僥傿儞亁丄僉儍僲儞儃乕儖仌儅僀儖僗偺亀僒儉僔儞丒僄儖僗亁丄僐儖僩儗乕儞偺亀僽儖乕丒僩儗僀儞亁偁偨傝偑忋埵偵偔傞偺偩傠偆丅偄偢傟偵偣傛丄AKB憤慖嫇偵偁傗偐偭偰偲偼偄偊丄偙傫側僉儍儞儁乕儞偱僕儍僘偑妶惈壔偝傟傞偺側傜偗偭偙偆側偙偲偩丅
儀僗僩3偲偄偊偽丄偩偄傇埲慜丄壗偐偺偍傝偵丄僕儍僘丒償僅乕僇儖偺儀僗僩3傪慖傫偱偔傟偲尵傢傟偨偙偲偑偁偭偨丅偙傟偵偼丄鏢鏞偡傞偙偲側偔師偺3枃傪嫇偘偨丅
丂丂1. 僽僢僋丒僆僽丒僶儔乕僪乛僇乕儊儞丒儅僋儗僄乮Decca乯
丂丂2. 僫僀僩丒僀儞丒儅儞僴僢僞儞乛儕乕丒儚僀儕乕乮Columbia乯
丂丂3. 僕僗丒僀僘丒傾僯僞乛傾僯僞丒僆僨僀乮Verve乯
 僄儔偺亀儊儘乕丒儉乕僪亁傕慺惏傜偟偄偟丄價儕乕偺僐儌僪傾丒僙僢僔儑儞傕柤彞偩偑丄屄恖揑偵岲偒側傾儖僶儉偲偄偆偲丄偙偆側傞丅偙偺3枃偼丄埲慜偐傜崱擔偵帄傞傑偱 丄偮偹偵曄傢傜偸丄塱墦偺僼僃僀償傽儕僢僩丒傾儖僶儉偩丅僇乕儊儞丒儅僋儗僄偺梷惂偝傟偨僄儌乕僔儑儞丄儕乕丒儚僀儕乕偺垼姶昚偆僄儗僈儞僗丄傾僯僞丒僆僨僀偺帺桼杬曻側僼儗乕僕儞僌 丄偳傟傕僕儍僘偺堦晹偱偁傝丄傑偨偦偺偡傋偰偩丅偙偺3枃偵嫟捠偟偰偄傞偺偼昳奿亖僋儔僗偩丅昳奿偺側偄僕儍僘偼僕儍僘偱偼側偄丅
僄儔偺亀儊儘乕丒儉乕僪亁傕慺惏傜偟偄偟丄價儕乕偺僐儌僪傾丒僙僢僔儑儞傕柤彞偩偑丄屄恖揑偵岲偒側傾儖僶儉偲偄偆偲丄偙偆側傞丅偙偺3枃偼丄埲慜偐傜崱擔偵帄傞傑偱 丄偮偹偵曄傢傜偸丄塱墦偺僼僃僀償傽儕僢僩丒傾儖僶儉偩丅僇乕儊儞丒儅僋儗僄偺梷惂偝傟偨僄儌乕僔儑儞丄儕乕丒儚僀儕乕偺垼姶昚偆僄儗僈儞僗丄傾僯僞丒僆僨僀偺帺桼杬曻側僼儗乕僕儞僌 丄偳傟傕僕儍僘偺堦晹偱偁傝丄傑偨偦偺偡傋偰偩丅偙偺3枃偵嫟捠偟偰偄傞偺偼昳奿亖僋儔僗偩丅昳奿偺側偄僕儍僘偼僕儍僘偱偼側偄丅僇乕儊儞丒儅僋儗僄偼偙偺傾儖僶儉偑悂偒崬傑傟偨1950擭戙屻婜偑偄偪偽傫椙偐偭偨丅偙偺偙傠埲崀偼彮偟偢偮傾僋偑嫮偔側傝丄偹偪偭偙偝偑慡柺偵弌偰偔傞傛偆偵側傞丅偙偺亀僽僢僋丒僆僽丒僶儔乕僪亁偱偺僇乕儊儞偼丄偲偵偐偔梷惂偝傟偨昞尰椡偑偡偛偄丅偝傜偭偲壧偭偰偄傞偺偵墱偑怺偄偺偩丅
 怤偟偑偨偄僨傿僌僯僥傿偲惓妋側僀儞僩僱乕僔儑儞丄偁傆傟弌傞僸儏乕儅儞側壏偐偝偼丄偄偮挳偄偰傕堷偒偢傝崬傑傟偰偟傑偆丅
怤偟偑偨偄僨傿僌僯僥傿偲惓妋側僀儞僩僱乕僔儑儞丄偁傆傟弌傞僸儏乕儅儞側壏偐偝偼丄偄偮挳偄偰傕堷偒偢傝崬傑傟偰偟傑偆丅儕乕丒儚僀儕乕偼丄偙偺亀僫僀僩丒僀儞丒儅儞僴僢僞儞亁偑悂偒崬傑傟偨1950擭偵偼丄偍偦傜偔惡偺惙傝偑偡偱偵夁偓偰偄偨偲巚偆偑丄偦傟偑偦偙偼偐偲側偄垼姶傪姶偠偝偣傞丅壧偄曽偼僆乕儖僪丒僼傽僢僔儑儞偩偑丄偦傟偑壗偲傕尵偊側偄僲僗僞儖僕乕傪偐偒棫偰傞丅儃價乕丒僴働僢僩偲僕儑乕丒僽僔儏僉儞偺敽憈偑愨昳偩偟丄擡傃婑傞傛偆偵偦偭偲擖傞僗僩儕儞僌僗偑旤偟偄丅愻楙偲婥昳偼偙偺傾儖僶儉偺偨傔偵偁傞尵梩偩丅
傾僯僞丒僆僨僀偼1950擭戙敿偽偵夣嶌傪楢敪偟偨偑丄側偐偱傕亀僕僗丒僀僘丒傾僯僞亁偼寙弌偟偰偄偨丅
 儕僘儈僢僋側嬋偵偍偗傞揤堖柍朌側忔傝 丄僶儔乕僪偵偍偗傞旝柇側姶忣昞弌偼恄偑偐偭偰偄傞丅傾僯僞偼惡偑僪儔僀偩偟惡堟偑嫹偄丅僺僢僠傕偲偒偳偒僼儔僢僩婥枴偵側傞丅偩偑丄杬曻帺嵼側僕儍僘丒僼傿乕儕儞僌偑偦傟傜傪偡傋偰僇償傽乕偟偰偄偨丅寉夣偱彫悎側僶僨傿丒僽儗僌儅儞偺傾儗儞僕偑敳孮偺岠壥傪忋偘偰偄傞丅
儕僘儈僢僋側嬋偵偍偗傞揤堖柍朌側忔傝 丄僶儔乕僪偵偍偗傞旝柇側姶忣昞弌偼恄偑偐偭偰偄傞丅傾僯僞偼惡偑僪儔僀偩偟惡堟偑嫹偄丅僺僢僠傕偲偒偳偒僼儔僢僩婥枴偵側傞丅偩偑丄杬曻帺嵼側僕儍僘丒僼傿乕儕儞僌偑偦傟傜傪偡傋偰僇償傽乕偟偰偄偨丅寉夣偱彫悎側僶僨傿丒僽儗僌儅儞偺傾儗儞僕偑敳孮偺岠壥傪忋偘偰偄傞丅偙傟傜3枃偺傾儖僶儉偲傕丄晹暘揑偵僗僩儕儞僌僗偑僼傿乕僠儍乕偝傟偰偄傞偺偼丄嬼慠偱偼側偄丅償僅乕僇儖偺僶僢僋偵棳傟傞僗僩儕儞僌僗偼挳偔幰偺怱傪榓傑偣傞丅偟偐傕丄偙傟傜偺傾儖僶儉偱丄僗僩儕儞僌僗偼弌偟傖偽傜側偄丅償僅乕僇儖偺攚屻偱丄偦偭偲惷偐偵丄偨備偨偆傛偆偵嬁偄偰偄傞丅偦傟偑丄摼傕尵傢傟偸忣姶傪忴偟弌偟偰偄傞丅
2013.07.14 (擔) 僯僐儔僗丒W丒儗僼儞偺乽僪儔僀償乿偼惁偄塮夋偩
 嶐擭丄擔杮偱岞奐偝傟偨塮夋偼丄尒偨偐尒側偐偭偨偐偼暿偲偟偰丄傔傏偟偄傕偺偼攃埇偟偰偄傞偮傕傝偱偄偨丅偩偑丄偙傫側惁偄塮夋偑岞奐偝傟偰偄偨偲偼抦傜側偐偭偨丅僯僐儔僗丒僂傿儞僨傿儞僌丒儗僼儞娔撀偺乽僪儔僀償乿丄2011擭惢嶌偺傾儊儕僇塮夋偩丅愭擔丄WOWOW偱偨傑偨傑偙偺塮夋傪尒偰丄偦偺埑搢揑側枺椡偵嬃扱偟偨丅
嶐擭丄擔杮偱岞奐偝傟偨塮夋偼丄尒偨偐尒側偐偭偨偐偼暿偲偟偰丄傔傏偟偄傕偺偼攃埇偟偰偄傞偮傕傝偱偄偨丅偩偑丄偙傫側惁偄塮夋偑岞奐偝傟偰偄偨偲偼抦傜側偐偭偨丅僯僐儔僗丒僂傿儞僨傿儞僌丒儗僼儞娔撀偺乽僪儔僀償乿丄2011擭惢嶌偺傾儊儕僇塮夋偩丅愭擔丄WOWOW偱偨傑偨傑偙偺塮夋傪尒偰丄偦偺埑搢揑側枺椡偵嬃扱偟偨丅庡恖岞偼揤嵥揑側幵偺塣揮僥僋僯僢僋傪傕偮抝丅幵偺廋棟岺応偵嬑傔偰偄傞偑丄塣揮擻椡傪惗偐偟偰塮夋偺僗僞儞僩儅儞傪傗傞偐偨傢傜丄栭偼嫮搻堦枴偺偨傔偵摝憱梡偺幵偺僪儔僀償傽乕傪偟偰偄傞丅偙偺抝偑丄摨偠傾僷乕僩偱梒偄懅巕偲曢傜偡彈偲抦傝崌偄丄巚偄傪婑偣傞傛偆偵側傞丅傗偑偰暈栶拞偩偭偨晇偑彈偺傕偲偵栠偭偰偔傞丅晇偼庁嬥偟偰偄偨儅僼傿傾偐傜嫮搻傪嫮梫偝傟傞丅抝偼偙偺堦壠傪彆偗傞偨傔摝憱僪儔僀償傽乕傪堷偒庴偗傞偑丄偦偙偵偼斱楎側悌偑巇妡偗傜傟偰偄偨丄偲偄偆撪梕偺塮夋偩丅
傑偢庡恖岞偺憿宍偑偄偄丅斵偼偮偹偵壡栙偱丄昁梫側偙偲埲奜偼偤傫偤傫挐傜側偄丅墘偠傞偺偼儔僀傾儞丒僑僘儕儞僌丅偙偺僑僘儕儞僌偺墘媄偲昞忣偑慺惏傜偟偄丅偄偮傕僒僜儕偺奊暱偺儃儅乕僕儍働僢僩傪拝偰偄傞偺偑報徾怺偄丅偙偺抝偑偳偙偐傜棃偨偺偐丄偦傟傑偱壗傪偟偰偄偨偺偐偵偮偄偰偼丄傑偭偨偔愢柧偑側偄丅偦傟傑偱暔惷偐偱偍偲側偟偐偭偨庡恖岞偑 丄偲偮偤傫僠儞僺儔傪墸傝偮偗傞僔乕儞偑偁傞丅斵偼揙掙揑偵墸傝廟傝丄憡庤傪儃僐儃僐偵偟偰偟傑偆丅偩偐傜丄愢柧偼側偄傕偺偺丄斵偼朶椡偺悽奅偵恎傪偍偄偰偄偨恖娫偱偁傠偆偲娤媞偼憐憸偱偒傞丅憡庤栶偺彈傪墘偠傞偺偑僉儍儕乕丒儅儕僈儞丅偦傟傎偳旤恖偱偼側偄偑丄摱婄偱垽沢偑偁傝丄柇偵報徾偵巆傞彈桪偩丅偦偺傎偐偺栶幰傕傒側懚嵼姶偑偁傞丅
娙寜側岅傝岥丄僗僺乕僨傿側棳傟偱丄榖偼柍棟側偔恑傓丅慡懱偵昚偆僟乕僋側姶妎偑怺偄墱峴偒傪姶偠偝偣傞丅柍懯側戜帉傗忕枱側昤幨偼偄偭偝偄側偔丄塮憸偩偗偱搊応恖暔偺怱偺摦偒丄抝偲彈偑屳偄偵庝偐傟偰偄偔條偑昞尰偝傟傞丅偦偙偑杴昐偺塮夋偲偼傑偭偨偔堘偆丅儗僼儞娔撀偺墘弌椡偼偨偄偟偨傕偺偩丅庡恖岞偺椻傔偨昞忣偵偼丄偳偙偐婋側偄傕偺偑愽傫偱偄傞傛偆偵姶偠傜傟傞偑丄偦偺婋側偝偼屻敿偵側偭偰堦婥偵暚弌偡傞丅朶椡僔乕儞偺昤幨偑巃怴偱慛傗偐偩丅嵟屻偼丄彈偺堦壠傪彆偗偨庡恖岞偑丄彎傪晧偄側偑傜幵偱偳偙偐偵嫀偭偰偄偔偺偩偑丄偙偺偁偨傝偼丄偪傚偭偲乽僔僃乕儞乿傪楢憐偝偣側偄偱傕側偄丅
 傏偔偼偙傟傪尒偰丄1978擭偺傾儊儕僇塮夋乽僓丒僪儔僀僶乕乿傪巚偄婲偙偟偨丅娔撀偼僂僅儖僞乕丒僸儖偱儔僀傾儞丒僆僯乕儖庡墘偺僱僆丒僲儚乕儖塮夋偩丅偙傟傕庡恖岞偼幵偺塣揮媄弍偵偡偖傟偨丄嫮搻偺偨傔偺摝憱幵偺僪儔僀償傽乕傪偟偰偄傞抝偩丅斵偼棃楌晄柧偱丄柤慜傕暘偐傜側偄偟丄壡栙偱傎偲傫偳尵梩傪敪偟側偄丅偦傫側撲傔偄偨庡恖岞偲栭偺儘僒儞僕僃儖僗偺埫偄怓挷丄偡偝傑偠偄僇乕丒僠僃僀僗偑報徾揑側塮夋偩偭偨丅榖偺嬝偼堎側偭偰偄傞偑丄庡恖岞偺愝掕偼乽僪儔僀償乿偲傑偭偨偔摨偠偩丅偳偙偵傕偦傫側偙偲偼彂偐傟偰偄側偄偑丄儗僼儞娔撀偑偙偺塮夋傪偮偔傞偵偁偨偭偰乽僓丒僪儔僀僶乕乿偺愝掕傪庁梡偟偰偄傞偺偼娫堘偄側偄偩傠偆丅偦偆巚偭偰偄偨傜丄昡榑壠偺挰嶳抭峗偑乽僪儔僀償乿偺尦僱僞偼乽僓丒僪儔僀僶乕乿偩偲抐掕偟偰岅偭偰偄偨丅
傏偔偼偙傟傪尒偰丄1978擭偺傾儊儕僇塮夋乽僓丒僪儔僀僶乕乿傪巚偄婲偙偟偨丅娔撀偼僂僅儖僞乕丒僸儖偱儔僀傾儞丒僆僯乕儖庡墘偺僱僆丒僲儚乕儖塮夋偩丅偙傟傕庡恖岞偼幵偺塣揮媄弍偵偡偖傟偨丄嫮搻偺偨傔偺摝憱幵偺僪儔僀償傽乕傪偟偰偄傞抝偩丅斵偼棃楌晄柧偱丄柤慜傕暘偐傜側偄偟丄壡栙偱傎偲傫偳尵梩傪敪偟側偄丅偦傫側撲傔偄偨庡恖岞偲栭偺儘僒儞僕僃儖僗偺埫偄怓挷丄偡偝傑偠偄僇乕丒僠僃僀僗偑報徾揑側塮夋偩偭偨丅榖偺嬝偼堎側偭偰偄傞偑丄庡恖岞偺愝掕偼乽僪儔僀償乿偲傑偭偨偔摨偠偩丅偳偙偵傕偦傫側偙偲偼彂偐傟偰偄側偄偑丄儗僼儞娔撀偑偙偺塮夋傪偮偔傞偵偁偨偭偰乽僓丒僪儔僀僶乕乿偺愝掕傪庁梡偟偰偄傞偺偼娫堘偄側偄偩傠偆丅偦偆巚偭偰偄偨傜丄昡榑壠偺挰嶳抭峗偑乽僪儔僀償乿偺尦僱僞偼乽僓丒僪儔僀僶乕乿偩偲抐掕偟偰岅偭偰偄偨丅偙偺塮夋偺娔撀僯僐儔僗丒僂傿儞僨傿儞僌丒儗僼儞偼僨儞儅乕僋偺弌恎偩丅WOWOW偱偼丄乽僪儔僀償乿偲摨帪偵丄儗僼儞娔撀偺僨儞儅乕僋帪戙偺媽嶌乽僾僢僔儍乕乿乽僽儘儞僜儞乿乽償傽儖僴儔丒儔僀僕儞僌乿傕曻塮偟偰偄偨丅偄偢傟傕丄撈摿偺僋僙偑偁傞婏柇側枴傢偄偺塮夋偩丅拞悽偺杒墷偺搝楆愴巑傪昤偄偨乽償傽儖僴儔丒儔僀僕儞僌乿偼暿偲偟偰丄乽僾僢僔儍乕乿傕乽僽儘儞僜儞乿傕丄奨偵憙怘偆斊嵾幰偺惗懺偲斵傜偑徴摦揑偵堨傟弌偝偣傞惁嶴側朶椡偑昤偐傟偰偍傝丄尒偛偨偊廩暘偩偭偨丅僯僐儔僗丒僂傿儞僨傿儞僌丒儗僼儞丄偄傑丄偄偪偽傫婥偵側傞塮夋嶌壠偺傂偲傝偩丅
2013.07.07 (擔) 埫嶦幰偺惓媊
 怴恖嶌壠儅乕僋丒僌儕乕僯乕偵傛傞埫嶦幰僌儗僀儅儞丒僔儕乕僘偺戞2嶌亀埫嶦幰偺惓媊亁偑朚栿弌斉偝傟偨乮僴儎僇儚暥屔乯丅嶐擭弌偨戞1嶌乽埫嶦幰僌儗僀儅儞乿偼慺惏傜偟偐偭偨偑丄偙傟傕慜嶌偵桪傞偲傕楎傜側偄丄寙弌偟偨朻尟彫愢偵巇忋偑偭偰偄傞丅崱嶌偱僌儗僀儅儞偼丄儘僔傾偺儅僼傿傾偲傾儊儕僇偺CIA偺憃曽偐傜埶棅偝傟偰丄傾僼儕僇偺彫崙偺撈嵸幰傪埫嶦傑偨偼漟抳偟傛偆偲偡傞丅摉慠側偑傜丄偦偙偵偼悌偑巇妡偗傜傟偰偄傞丅僌儗僀儅儞偼揋偵傕枴曽偵傕怱傪嫋偡偙偲側偔丄桭忣偲棤愗傝偺偼偞傑偱丄屒棫柍墖偱愴偆攋栚偵側傞丅偲偵偐偔丄庡恖岞偺僾儘偵揙偟偨愴偄傇傝偑埑搢揑偵偍傕偟傠偄丅庡恖岞偺僌儗僀儅儞偼惪偗晧偭偨巇帠偵娭偟偰偼椻揙側嶦偟壆偵揙偡傞偑丄庛幰偵懳偡傞抔偐側娽嵎偟傪帩偪崌傢偣偰偍傝丄巇帠偺塓拞偱偲偽偭偪傝傪偔偭偰揋偵曔傜傢傟偨幰傪彆偗偨傝丄棊偪傇傟偨摨嬈幰傊楓傒偺怱傪書偄偨傝偡傞丅偦偙偑撉幰偺嫟姶傪屇傇偺偩偑丄偦傟備偊斵偼媷抧偵娮傞偙偲偵側傞丅
怴恖嶌壠儅乕僋丒僌儕乕僯乕偵傛傞埫嶦幰僌儗僀儅儞丒僔儕乕僘偺戞2嶌亀埫嶦幰偺惓媊亁偑朚栿弌斉偝傟偨乮僴儎僇儚暥屔乯丅嶐擭弌偨戞1嶌乽埫嶦幰僌儗僀儅儞乿偼慺惏傜偟偐偭偨偑丄偙傟傕慜嶌偵桪傞偲傕楎傜側偄丄寙弌偟偨朻尟彫愢偵巇忋偑偭偰偄傞丅崱嶌偱僌儗僀儅儞偼丄儘僔傾偺儅僼傿傾偲傾儊儕僇偺CIA偺憃曽偐傜埶棅偝傟偰丄傾僼儕僇偺彫崙偺撈嵸幰傪埫嶦傑偨偼漟抳偟傛偆偲偡傞丅摉慠側偑傜丄偦偙偵偼悌偑巇妡偗傜傟偰偄傞丅僌儗僀儅儞偼揋偵傕枴曽偵傕怱傪嫋偡偙偲側偔丄桭忣偲棤愗傝偺偼偞傑偱丄屒棫柍墖偱愴偆攋栚偵側傞丅偲偵偐偔丄庡恖岞偺僾儘偵揙偟偨愴偄傇傝偑埑搢揑偵偍傕偟傠偄丅庡恖岞偺僌儗僀儅儞偼惪偗晧偭偨巇帠偵娭偟偰偼椻揙側嶦偟壆偵揙偡傞偑丄庛幰偵懳偡傞抔偐側娽嵎偟傪帩偪崌傢偣偰偍傝丄巇帠偺塓拞偱偲偽偭偪傝傪偔偭偰揋偵曔傜傢傟偨幰傪彆偗偨傝丄棊偪傇傟偨摨嬈幰傊楓傒偺怱傪書偄偨傝偡傞丅偦偙偑撉幰偺嫟姶傪屇傇偺偩偑丄偦傟備偊斵偼媷抧偵娮傞偙偲偵側傞丅僗僺乕僨傿側応柺揥奐丄愴摤応柺偺敆椡偁傆傟傞昤幨丄慛傗偐側恖暔憿宆偼丄傑偝偵堦媺昳偱偁傝丄慡惙婜偺僋傿僱儖傪渇渋偲偝偣傞丅岻傒側僾儘僢僩偺愊傒廳偹偼恞忢偺忋庤偝偱偼側偄丅晲婍偵娭偡傞夁晄懌側偄愢柧偑嬞敆姶傪崅傔偰偄傞偟丄婋婡偵娮偭偨帪偺僾儘傜偟偄懳張偺偟曽傕愢摼椡廩暘偩丅峠堦揰偲偟偰搊応偡傞崙嵺孻帠嵸敾強偺彈惈憑嵏姱偲偺懇偺娫偺怗傟崌偄偼丄偙偺彈偺攏幁偝壛尭偵偼懡彮暵岥偟偮偮傕丄杮嬝偵偼娭學側偄傛偆偱偄偰丄庡恖岞偺峴摦偵嵟屻傑偱塭傪棊偲偟偰偄傞丅朻摢偐傜廔寢晹傑偱丄傑偭偨偔偩傟傞偲偙傠偑側偄丅儅乕僋丒僌儕乕僯乕偼朻尟彫愢晄嶌偲尵傢傟傞偙偺帪戙偵媣乆偵尰傟偨丄杮暔偺朻尟彫愢嶌壠偩丅師嶌偑偄傑偐傜懸偪偒傟側偄丅僽儔僢僪丒僺僢僩庡墘偱塮夋壔偑婇夋偝傟偰偄傞偲偄偆偑丄尒偨偄傛偆側丄尒偨偔側偄傛偆側丅
2013.06.28 (嬥) 嶗堜儐僞僇偝傫偺巚偄弌
傏偔偼僕儍僘恖娫偩偟丄嶗堜偝傫偼僜僂儖偺昡榑壠側偺偱丄杮棃側傜愙揰偑側偄偼偢偩丅榖偼30擭慜丄傏偔偑儗僐乕僪夛幮偵嬑傔偰偄偨偲偒偵偝偐偺傏傞丅偦傟傑偱傏偔偼僕儍僘傪扴摉偟偰偄偨偑丄怴偨偵儌乕僞僂儞丒儗乕儀儖偺敪攧尃偑堏偭偰偒偨偺偵敽偄丄傏偔偵儌乕僞僂儞傪扴摉偣傛偲偺幮柦偑壓偭偨丅儌乕僞僂儞偲偄偊偽僜僂儖偺價僢僌丒儗乕儀儖偩丅偩偑丄傏偔傕娷傔偰幮撪偵偼偦偺曽柺偵抦幆偺偁傞恖娫偑偄側偄丅摉帪偺忋巌偺I偝傫偼丄僜僂儖偲儌乕僞僂儞偵徻偟偄恖傪屭栤偲偟偰椪帪偵屬偆偲偄偆丅偙偆偟偰夛幮偵棃偰偄偨偩偄偨偺偑嶗堜偝傫偩偭偨丅嶗堜偝傫偵偼廡偵3擔弌幮偟偰傕傜偆偙偲偵側偭偨丅偙偆偟偰2恖偺僐儞價偵傛傞儌乕僞僂儞偺曇惉嶌嬈偑巒傑偭偨丅
偦傟傑偱夛幮偵棃傜傟偨偲偒偵栙楃偖傜偄偼岎傢偟偰偄偨偑丄嶗堜偝傫偲偼傎偲傫偳榖偟偨偙偲偼側偐偭偨丅堦弿偵巇帠傪偡傞偆偪偵丄嶗堜偝傫偼堦尒偟偨偲偙傠丄偲偭偮偒偵偔偄偑丄懪偪夝偗傞偲丄偲偰傕傗偝偟偄丄婥帩偪偺偄偄丄弮悎側怱傪帩偭偨恖偩偲偄偆偙偲偑暘偐偭偰偒偨丅抦傜側偄恖傗婥偺崌傢側偄恖偵偼柍垽憐偩偑丄偄偭偨傫怱偑捠偠崌偆偲丄壗偺墦椂傕側偔奐偗偭傄傠偘偵晅偒崌偆偙偲偑偱偒傞恖偩偭偨丅執傇偭偨慺怳傝側偳偐偗傜傕側偐偭偨丅
弶傔偰儌乕僞僂儞偵娭偡傞懪偪崌傢偣傪偟偨偲偒丄傏偔偼嶗堜偝傫傪乽嶗堜愭惗乿偲屇傫偩丅摉帪丄儗僐乕僪夛幮偺恖娫偑昡榑壠偺恖偲愙偡傞偲偒丄乬愭惗乭偲屇傇偺偑廗姷偵側偭偰偄偨丅偲偙傠偑嶗堜偝傫偼懄嵗偵乽愭惗偼傗傔偰偔偩偝偄丅傏偔偼偁側偨偺愭惗偠傖偁傝傑偣傫乿偲尵偭偨丅偦偺偲偍傝偩丅偦傟傪暦偄偰丄傏偔偼婐偟偔側偭偨丅偙偺恖偲側傜偄偄姶偠偱傗偭偰偄偗偦偆偩偲巚偭偨丅
嶗堜偝傫偼丄僜僂儖偵娭偟偰埲奜丄傑偭偨偔柍梸偺恖偩偭偨丅偦偟偰尃椡偲傕柍墢偺恖偩偭偨丅尃椡傪寵偭偰偄偨偲偄偆傛傝傕丄娭怱偑側偐偭偨偲偄偆傎偆偑惓偟偄偩傠偆丅挿偄偁偄偩偵傢偨偭偰壒妝嬈奅偵偐偐傢偭偰偒偨偺偱丄偐偮偰晅偒崌偄偺偁偭偨儗僐乕僪夛幮偺幮堳偺側偐偵偼丄偡偱偵夛幮偺拞悤偵偄傞恖偨偪傕偨偔偝傫偄偨偑丄嶗堜偝傫偼偳傫側偵執偔偰傕丄婥偑崌傢側偄恖偲偼晅偒崌偍偆偲偟側偐偭偨丅攇挿偑崌偊偽丄偳傫側偵壓偭抂偺恖偲偱傕愊嬌揑偵晅偒崌偭偨丅
嶗堜偝傫偼丄偲偒偳偒僇儞僩儕乕傪挳偔偙偲偼偁傞偑丄婎杮揑偵僜僂儖埲奜偺壒妝偵偼娭怱偑側偐偭偨丅偦偺揰偱傕嶗堜偝傫偺弮悎偝偼揙掙偟偰偄偨丅僜僂儖偵傑偭偨偔柍抦偩偭偨傏偔偼丄嶗堜偝傫偵偄傠傫側偙偲傪嫵傢偭偨丅嶗堜偝傫偵偼墴偟偮偗偑傑偟偄偲偙偲偼旝恛傕側偐偭偨丅偙傟偑偄偄丄偁傟偑偄偄偲偼尵偆偑丄偙傟傪挳偗丄偁傟傪挳偗偲偼堦愗尵傢側偐偭偨丅僆乕僥傿僗丒儗僨傿儞僌丄僒儉丒僋僢僋丄僕儍僢僉乕丒僂傿儖僜儞丄僌儔僨傿僘丒僫僀僩丄嶗堜偝傫偑岲偒偩偲尵偭偨壧庤傪偄傠偄傠挳偄偰偄偔偆偪偵丄傏偔偼彮偟偢偮僜僂儖壒妝偺妝偟偝傪丄偛偔弶曕揑側抜奒側偑傜丄棟夝偡傞傛偆偵側偭偨丅
嶗堜偝傫偲偼丄傎傫偲偆偵傛偔堸傫偩偟丄傛偔梀傫偩丅堦弿偵巇帠傪偟巒傔偰偐傜丄巇帠偑廔傢偭偨偁偲丄夛幮偺拠娫傪桿偭偰嬤偔偺嫃庰壆偱堸傓傛偆偵側偭偨丅嵟弶偺偆偪偼A偝傫丄M偝傫丄N偝傫側偳丄埲慜偐傜嶗堜偝傫偲恊偟偐偭偨傎傫偺2丄3恖偑晅偒崌偆偩偗偩偭偨偑丄偦偺偆偪偵丄愰揱扴摉偺A偝傫丄僋儔僔僢僋扴摉偺S偝傫丄塩嬈扴摉偺M偝傫丄僐儗億儞扴摉偺H忟側偳丄偟偩偄偵偦偺椫偑峀偑偭偰偄偭偨丅偦傫側偲偒丄嶗堜偝傫偼夛幮偺旓梡偵偼愨懳偵偝偣側偐偭偨丅偄偮傕妱傝姩偩偭偨丅偟偐傕丄偄偪偽傫擭忋側偺偩偐傜偲尵偭偰丄昁偢帺暘偑懡傔偵暐偭偨丅
偦傫側拠娫偨偪偲丄枅擭廐偵敔崻偺壏愹偵堦攽偱椃峴偟偨丅嶗堜偝傫偼傆偞偗偰乽敔崻僜僂儖丒僙儈僫乕奐嵜偺偛埬撪乿偲偄偆僾儘僌儔儉傪嶌偭偨丅島巘偵扤偦傟傪屇傫偱丄偙傫側僙儈僫乕傪偡傞偲偄偆僾儘僌儔儉偩偭偨丅偦傟傪怣偠偰嶲壛偡傞恖傕偄偨偑丄幚懺偼敔崻偺壏愹椃娰偵峴偭偰丄堸傫偱憶偄偱壏愹偵怹偐偭偰婣偭偰偔傞偲偄偆丄偨傫偵偦傟偩偗偺椃峴偩偭偨丅壞偵偼悀巕偵峴偭偰僶乕儀僉儏乕丒僷乕僥傿傪傗偭偨偟丄姍憅偺壴壩傪尒偵峴偭偨偙偲傕偁偭偨丅慺惏傜偟偄帪娫傪夁偛偡偙偲偑偱偒偨丅
悢擭偨偭偰儌乕僞僂儞丒儗乕儀儖偑暿偺夛幮偵堏偭偨偁偲傕丄偦傫側晅偒崌偄偼挿偔懕偄偨丅7丄8擭慜偁偨傝偩偭偨傠偆偐丄嶗堜偝傫偑懱挷傪曵偟偰偐傜偼丄偝偡偑偵夛偆夞悢偼尭偭偨偑丄偦傟偱傕偲偒偍傝揹榖偑偐偐偭偰棃偰丄愄偐傜偺拠娫偺A偝傫傗M偝傫丄M忟側偳傪桿偭偰堸傫偱偄偨丅嶗堜偝傫偵嵟屻偵夛偭偨偺偼丄6擭嬤偔慜丄怷嶈儀儔偝傫偺儔僀償傪尒偵崅墌帥偺儔僀償丒僴僂僗偵峴偭偨偲偒偩偭偨丅嶗堜偝傫偼丄傕偆庰偑偁傑傝堸傔傞傛偆側忬懺偱偼側偐偭偨丅傑偨夛偄傑偟傚偆偲尵偭偰暿傟偨偑丄偦傟埲崀丄嶗堜偝傫偼擖堾偟偰偟傑偄丄擇搙偲夛偆偙偲偼側偐偭偨丅
嶗堜偝傫偼乽僜僂儖丒僆儞乿偲偄偆寧姧帍傪敪峴偡傞偐偨傢傜丄乽僜僂儖戝帿揟乿傪挊偡傋偔丄偄偔偮偐偺弌斉幮偵懪恌偟偰偄偨偑丄偳偙偐傜傕巚傢偟偄曉帠偑摼傜傟側偐偭偨偨傔丄帺旓弌斉偲偄偆偐偨偪偱姧峴偟偼偠傔偨丅偙傟偼傾儊儕僇偱敪攧偝傟偨僜僂儖丒儈儏乕僕僢僋偺慡儗僐乕僪傪傾乕僥傿僗僩暿偵ABC弴偵徯夘丄夝愢偡傞偲偄偆丄朿戝側忣曬偑栐梾偝傟偨悢姫偵傢偨傞戝晹側杮偱偁傝丄偍偦傜偔悽奅偱傕椶傪尒側偄偩傠偆丅戞3姫偺O偺崁栚傑偱姧峴偝傟偨偑丄偦偙偱昦偄偺偨傔搑愨偊偰偟傑偭偨丅嶗堜偝傫偲偟偰偼偝偧怱巆傝偩偭偨偩傠偆丅
偄傑巚偊偽丄嶗堜偝傫偲偲傕偵夁偛偟偨擔乆偼丄抶偔偒偨惵弔帪戙偩偭偨偺偱偼側偄偐偲巚偆丅惵弔偲偄偆偵偼丄傏偔傕娷傔偰傒傫側擭傪偲傝偡偓偰偄偨偑丄偁偺妶椡偲懱椡偲晜偐傟憶偓偼丄傑偝偵惵弔偩偭偨丅嶗堜偝傫偲偄偆婬桳偺恖偵弰傝崌偊偨偺偼丄偦偟偰恊偟偔愙偡傞偙偲偑偱偒偨偺偼丄柍忋偺岾塣偩偭偨丅偄傑丄嶗堜偝傫偼揤崙偱僆乕僥傿僗丒儗僨傿儞僌傗僒儉丒僋僢僋偲妝偟偔岎梀偟偰偄傞偩傠偆丅嶗堜偝傫丄挿擭偵傢偨傞偍晅偒崌偄丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
2013.01.18 (嬥) 2012擭奀奜塮夋儀僗僩10
1.丂乽傾儖僑乿 儀儞丒傾僼儕僢僋 乮暷乯
2.丂乽偍偲側偺偗傫偐乿 儘儅儞丒億儔儞僗僉乕 乮暓丒撈丒攇乯
3.丂乽廔偺怣戸乿 廃杊惓峴 乮擔乯
4.丂乽僾儗僀丂妉暔乿 僄儕僢僋丒償傽儗僢僩 乮暓乯
5.丂乽岾偣傊偺僉僙僉乿 僉儍儊儘儞丒僋儘僂 乮暷乯
6.丂乽僗僲乕儂儚僀僩乿 儖僷乕僩丒僒儞僟乕僘 乮暷乯
7.丂乽儖傾乕償儖偺孋傒偑偒乿 傾僉丒僇僂儕僗儅僉 乮鋷丒暓丒撈乯
8.丂乽J丒僄僪僈乕乿 僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪 乮暷乯
9.丂乽僸儏乕僑偺晄巚媍側敪柧乿 儅乕僥傿儞丒僗僐僙僢僔 乮暷乯
10.丂乽傾乕僥傿僗僩乿 儈僔僃儖丒傾僓僫償傿僔僂僗 乮暓乯
 傇偭偪偓傝偺1埵偼乽傾儖僑乿偩丅偙傟偵偮偄偰偼12寧8擔晅偺摉棑偱彂偄偨偲偍傝丅嬤棃傑傟側僒僗儁儞僗塮夋偺寙嶌偱偁傞丅2埵偺乽偍偲側偺偗傫偐乿偼儘儅儞丒億儔儞僗僉乕偺嵟怴嶌丅慜嶌偺乽僑乕僗僩丒儔僀僞乕乿偲偼偆偭偰曄傢偭偰丄旂擏偺偒偄偨僐儊僨傿塮夋偩丅巕嫙偳偆偟偑寲壾偟丄堦曽偺椉恊偑曅曽偺椉恊偺壠偵幱嵾偵朘傟丄嵟弶偼桭岲揑偵榓夝偺榖偟崌偄偑側偝傟偰偄偨偑丄偟偩偄偵椻惷偝傪幐偄丄杮壒傪尵偄崌偭偰嫸棎偺廋梾応偲壔偡丄偲偄偆撪梕丅搊応恖暔偼偨偭偨4恖丄応強傕傾僷乕僩儊儞僩偺堦幒偩偗偲偄偆愝掕偺彫昳偩偑丄傛偔偱偒偨媟杮丄僕儑僨傿丒僼僅僗僞乕丄働僀僩丒僂傿儞僗儗僢僩傪偼偠傔寍払幰側攐桪偨偪偺摪乆偨傞柤墘偵傛傝丄枺椡偁傆傟傞塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅
傇偭偪偓傝偺1埵偼乽傾儖僑乿偩丅偙傟偵偮偄偰偼12寧8擔晅偺摉棑偱彂偄偨偲偍傝丅嬤棃傑傟側僒僗儁儞僗塮夋偺寙嶌偱偁傞丅2埵偺乽偍偲側偺偗傫偐乿偼儘儅儞丒億儔儞僗僉乕偺嵟怴嶌丅慜嶌偺乽僑乕僗僩丒儔僀僞乕乿偲偼偆偭偰曄傢偭偰丄旂擏偺偒偄偨僐儊僨傿塮夋偩丅巕嫙偳偆偟偑寲壾偟丄堦曽偺椉恊偑曅曽偺椉恊偺壠偵幱嵾偵朘傟丄嵟弶偼桭岲揑偵榓夝偺榖偟崌偄偑側偝傟偰偄偨偑丄偟偩偄偵椻惷偝傪幐偄丄杮壒傪尵偄崌偭偰嫸棎偺廋梾応偲壔偡丄偲偄偆撪梕丅搊応恖暔偼偨偭偨4恖丄応強傕傾僷乕僩儊儞僩偺堦幒偩偗偲偄偆愝掕偺彫昳偩偑丄傛偔偱偒偨媟杮丄僕儑僨傿丒僼僅僗僞乕丄働僀僩丒僂傿儞僗儗僢僩傪偼偠傔寍払幰側攐桪偨偪偺摪乆偨傞柤墘偵傛傝丄枺椡偁傆傟傞塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅3埵偺乽廔偺怣戸乿偼廃杊惓峴娔撀偺5擭傇傝偺塮夋丅奀奜塮夋偩偗偱偼儕僗僩傪杽傔偒傟側偄偺偱丄擔杮偺嶌昳偩偑偙偙偵擖傟偨丅慜嶌乽偦傟偱傕傏偔偼傗偭偰偄側偄乿偲摨偠偔丄幮夛揑僥乕儅傪埖偭偨僔儕傾僗側塮夋偩丅戣嵽偼埨妝巰偱偁傝丄偲偰傕廳偨偄撪梕偩偑丄僪儔儅偲偟偰偺弌棃偼堦媺昳丅巰傪娫嬤偵偟偨姵幰栶偺栶強峀巌偺墘媄偑愨昳偩偟丄庢挷幒偱偺堛巘亖憪姞柉戙偲専帠亖戝戲偨偐偍偺嬞敆偟偨傗傝偲傝傕堎條側敆椡偵枮偪偰偄傞丅
 4埵偺乽僾儗僀丂妉暔乿偼僼儔儞僗偺僗儕儔乕塮夋丅嵢巕偑楢懕嶦恖婼偵桿夳偝傟偨偙偲傪抦偭偨嫮搻偱暈栶拞偺庡恖岞偑丄孻柋強傪扙崠偟丄嵢巕傪庢傝栠偡偨傔嶦恖婼傪捛偆丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡恖岞乣斊恖乣寈嶡偺3幰偵傛傞捛愓偲摝朣偑岻傒偵昤偐傟偰偍傝丄擇揮丄嶰揮偡傞僾儘僢僩偲偁偄傑偭偰丄椙幙偺僒僗儁儞僗塮夋偵側偭偰偄傞丅CG傪巊傢側偄惗恎偺傾僋僔儑儞偑敆椡枮揰偱丄嵟弶偐傜嵟屻傑偱嬞敆姶偑搑愗傟側偄丅
4埵偺乽僾儗僀丂妉暔乿偼僼儔儞僗偺僗儕儔乕塮夋丅嵢巕偑楢懕嶦恖婼偵桿夳偝傟偨偙偲傪抦偭偨嫮搻偱暈栶拞偺庡恖岞偑丄孻柋強傪扙崠偟丄嵢巕傪庢傝栠偡偨傔嶦恖婼傪捛偆丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡恖岞乣斊恖乣寈嶡偺3幰偵傛傞捛愓偲摝朣偑岻傒偵昤偐傟偰偍傝丄擇揮丄嶰揮偡傞僾儘僢僩偲偁偄傑偭偰丄椙幙偺僒僗儁儞僗塮夋偵側偭偰偄傞丅CG傪巊傢側偄惗恎偺傾僋僔儑儞偑敆椡枮揰偱丄嵟弶偐傜嵟屻傑偱嬞敆姶偑搑愗傟側偄丅5埵偺乽岾偣傊偺僉僙僉乿偼丄傂傚傫側峴偒偑偐傝偐傜暵墍悺慜偺摦暔墍傪峸擖偟偨抝偑丄嵢偺巰偺捝庤偐傜棫偪捈傝丄巕嫙偨偪傗帞堢堳偲偲傕偵摦暔墍傪嵞寶偟傛偆偲偡傞暔岅丅偝傑偞傑側僩儔僽儖傪忔傝墇偊偰丄嵟屻偼傒傫側偑岾偣偵側傞偲偄偆丄奊偵昤偄偨傛偆側僴僢僺乕丒僄儞僨傿儞僌塮夋偩偑丄庡墘偺儅僢僩丒僨僀儌儞偼偠傔丄弌墘幰慡堳偺帺慠側墘媄偑岲傑偟偔丄垽偡傋偒撪梕偵巇忋偑偭偰偄傞丅6埵偺乽僗僲乕儂儚僀僩乿偼丄僌儕儉摱榖乽敀愥昉乿偺暔岅傪戝抇偵夵曄偟丄傾僋僔儑儞傗儂儔乕偺枴晅偗傪巤偟偨僟乕僋丒僼傽儞僞僕乕丅暅廞偺偨傔寱傪庤偵偟偰棫偪忋偑傞敀愥昉丄愴偆僸儘僀儞偲偄偆愝掕偑怴慛偩丅摿嶣偑岻傒偵巊傢傟偰偍傝丄榖偺揥奐傕僗儉乕僗偱梽傒偑側偄丅
 7埵偺乽儖傾乕償儖偺孋傒偑偒乿偼丄恖娫偺慞堄丄昻偟偔偰傕彆偗崌偄側偑傜惗偒傞壓挰偺廧柉偨偪偺恖忣傪昤偄偨塮夋丅杒僼儔儞僗偺彫偝側峘挰偱孋傒偑偒傪偟側偑傜偮偮傑偟偔曢傜偡榁恖偲丄傾僼儕僇偐傜枾峲偟偰儘儞僪儞偵峴偙偆偲偡傞彮擭偺弌夛偄偑丄儁乕僜僗傪岎偊側偑傜捲傜傟傞丅僇僂儕僗儅僉娔撀偺壏偐偄娽嵎偟偑姶偠傜傟丄恖惗偼偦傫側偵幪偰偨傕偺偱偼側偄丄偲偄偆婥帩偪偵偝偣偰偔傟傞丅8埵偺乽J丒僄僪僈乕乿偼丄FBI偺弶戙挿姱偵廇擟偟丄48擭娫偵傢偨偭偰挿姱傪柋傔丄旈枾棤偵廂廤偟偨惌帯壠丄幚嬈壠丄寍擻恖偺僾儔僀儀乕僩側僨乕僞傪晲婍偵丄暷崙偺惌帯丒幮夛傪棤偐傜憖偭偨J丒僄僪僈乕丒僼乕償傽乕偺惗奤傪昤偄偨揱婰塮夋丅僀乕僗僩僂僢僪嶌昳偲偟偰偼丄乽儈僗僥傿僢僋丒儕僶乕乿乽僠僃儞僕儕儞僌乿側偳偺宯楍偵懏偡傞丄恖娫偺撪晹偺埫偄忣擮偲怱偺埮傪幨偟弌偟偨塮夋偩丅庡墘偺儗僆僫儖僪丒僨傿僇僾儕僆偑丄偙傟傑偱偺僉儍儕傾偺側偐偱傕儀僗僩偲偄偊傞熡恎偺擬墘傪尒偣傞丅
7埵偺乽儖傾乕償儖偺孋傒偑偒乿偼丄恖娫偺慞堄丄昻偟偔偰傕彆偗崌偄側偑傜惗偒傞壓挰偺廧柉偨偪偺恖忣傪昤偄偨塮夋丅杒僼儔儞僗偺彫偝側峘挰偱孋傒偑偒傪偟側偑傜偮偮傑偟偔曢傜偡榁恖偲丄傾僼儕僇偐傜枾峲偟偰儘儞僪儞偵峴偙偆偲偡傞彮擭偺弌夛偄偑丄儁乕僜僗傪岎偊側偑傜捲傜傟傞丅僇僂儕僗儅僉娔撀偺壏偐偄娽嵎偟偑姶偠傜傟丄恖惗偼偦傫側偵幪偰偨傕偺偱偼側偄丄偲偄偆婥帩偪偵偝偣偰偔傟傞丅8埵偺乽J丒僄僪僈乕乿偼丄FBI偺弶戙挿姱偵廇擟偟丄48擭娫偵傢偨偭偰挿姱傪柋傔丄旈枾棤偵廂廤偟偨惌帯壠丄幚嬈壠丄寍擻恖偺僾儔僀儀乕僩側僨乕僞傪晲婍偵丄暷崙偺惌帯丒幮夛傪棤偐傜憖偭偨J丒僄僪僈乕丒僼乕償傽乕偺惗奤傪昤偄偨揱婰塮夋丅僀乕僗僩僂僢僪嶌昳偲偟偰偼丄乽儈僗僥傿僢僋丒儕僶乕乿乽僠僃儞僕儕儞僌乿側偳偺宯楍偵懏偡傞丄恖娫偺撪晹偺埫偄忣擮偲怱偺埮傪幨偟弌偟偨塮夋偩丅庡墘偺儗僆僫儖僪丒僨傿僇僾儕僆偑丄偙傟傑偱偺僉儍儕傾偺側偐偱傕儀僗僩偲偄偊傞熡恎偺擬墘傪尒偣傞丅9埵偺乽僸儏乕僑偺晄巚媍側敪柧乿偼僗僐僙僢僔娔撀偵偟偰偼捒偟偄僼傽儞僞僕乕嶌昳丅僷儕傪晳戜偵丄帪寁戜偵塀傟廧傓屒帣偺彮擭偑孞傝峀偘傞朻尟偑丄尪憐揑側塮憸偱昤偐傟傞丅塮夋偺晝儊儕僄僗偑搊応偡傞偁偨傝偐傜丄塮夋傊偺僆儅乕僕儏偑晜偐傃忋偑偭偰偔傞偑丄慡懱偲偟偰榖偑桳婡揑偵寢傃晅偄偰偄傞偲偼尵偄擄偔丄側偵偐偁偞偲偝偑姶偠傜傟偰側傜側偄丅10埵偺乽傾乕僥傿僗僩乿偼僴儕僂僢僪憂惉婜丄僒僀儗儞僩帪戙偺僗僞乕偺塰岝偲杤棊傪僥乕儅偵偟偨儊儘僪儔儅丅帪戙偵崌傢偣偰儌僲僋儘偺僒僀儗儞僩塮夋巇棫偰偵側偭偰偄傞偺偑榖戣傪屇傫偩丅傾僀僨傾偼柺敀偄偟丄撪梕揑偵傕偦傟側傝偵妝偟傔傞偑丄傾僇僨儈乕嶌昳徿傪偲傞傎偳偺偡偖傟偨塮夋偲偼巚偊側偄丅
2012.12.16 (擔) 2012擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
1.丂乽扙弌嬻堟乿 僩儅僗丒W丒儎儞僌 乮僴儎僇儚暥屔乯
2.丂乽恀鐹偺昡寛乿 儅僀僋儖丒僐僫儕乕 乮島択幮暥屔乯
3丏 乽傾僀傾儞丒僴僂僗乿 僕儑儞丒僴乕僩 乮僴儎僇儚丒億働儈僗乯
4丏 乽捛寕偺怷乿 僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕 乮暥弔暥屔乯
5丏 乽僷乕僼僃僋僩丒僴儞僞乕乿 僩儉丒僂僢僪 乮僴儎僇儚暥屔乯
6丏 乽儅僀僋儘儚乕儖僪乿 儅僀僋儖丒僋儔僀僩儞仌儕僠儍乕僪丒僾儗僗僩儞 乮憗愳彂朳乯
7丏 乽摿憑晹Q乣P偐傜偺儊僢僙乕僕乿 儐僢僔丒僄乕僘儔丒僆乕儖僗儞 乮僴儎僇儚丒億働儈僗乯
8丏 乽夝忶巘乿 僗僥傿乕償丒僴儈儖僩儞 乮僴儎僇儚丒億働儈僗乯
9丏 乽恞栤惪晧恖乿 儅乕僋丒傾儗儞丒僗儈僗 乮僴儎僇儚暥屔乯
10丏 乽擥傟偨嫑乿 僼僅儖僇乕丒僋僢僠儍乕 乮憂尦悇棟暥屔乯
 1埵偺乽扙弌嬻堟乿偵偮偄偰偼7寧31擔晅偺僐儔儉偱婰偟偨丅嵟嬤偱偼捒偟偄僗僩儗乕僩側朻尟彫愢偱偁傞丅撪梕偲偟偰偼丄偙偺嶌壠偺慜嶌乽扙弌嶳柆乿偺傎偆偑偡偖傟偰偄傞偑丄慡曇丄旘峴婡偺側偐傪晳戜偵偟偨偙偺戞2嶌傕丄嵟弶偐傜嵟屻傑偱柍椶嬞敆姶偵曪傑傟偰偍傝丄抝偺堄抧偲怱堄婥偑嫻傪擬偔偝偣偰偔傟傞丅2埵偺乽恀鐹偺昡寛乿偼儅僀僋儖丒僐僫儕乕嶌偺儕儞僇乕儞曎岇巑僔儕乕僘戞2嶌丅抦傝崌偄偺曎岇巑偑嶦奞偝傟丄偦偺屻擟偲偟偰嶦恖帠審偱戇曔偝傟偨僴儕僂僢僪偺戝暔塮夋娭學幰偺曎岇傪堷偒庴偗傞偙偲偵側偭偨庡恖岞偺妶桇偑昤偐傟傞丅擖傝慻傫偩僾儘僢僩偲岅傝岥偺岻偝偑嶀偊傢偨偭偰偍傝丄戞1嶌傪偟偺偖弌棃偽偊偩丅傢傟傜偺僸乕儘乕丄堦旵楾偺孻帠僴儕乕丒儃僢僔儏偑榚栶偱搊応偡傞偺傕嫽枴傪屇傇丅
1埵偺乽扙弌嬻堟乿偵偮偄偰偼7寧31擔晅偺僐儔儉偱婰偟偨丅嵟嬤偱偼捒偟偄僗僩儗乕僩側朻尟彫愢偱偁傞丅撪梕偲偟偰偼丄偙偺嶌壠偺慜嶌乽扙弌嶳柆乿偺傎偆偑偡偖傟偰偄傞偑丄慡曇丄旘峴婡偺側偐傪晳戜偵偟偨偙偺戞2嶌傕丄嵟弶偐傜嵟屻傑偱柍椶嬞敆姶偵曪傑傟偰偍傝丄抝偺堄抧偲怱堄婥偑嫻傪擬偔偝偣偰偔傟傞丅2埵偺乽恀鐹偺昡寛乿偼儅僀僋儖丒僐僫儕乕嶌偺儕儞僇乕儞曎岇巑僔儕乕僘戞2嶌丅抦傝崌偄偺曎岇巑偑嶦奞偝傟丄偦偺屻擟偲偟偰嶦恖帠審偱戇曔偝傟偨僴儕僂僢僪偺戝暔塮夋娭學幰偺曎岇傪堷偒庴偗傞偙偲偵側偭偨庡恖岞偺妶桇偑昤偐傟傞丅擖傝慻傫偩僾儘僢僩偲岅傝岥偺岻偝偑嶀偊傢偨偭偰偍傝丄戞1嶌傪偟偺偖弌棃偽偊偩丅傢傟傜偺僸乕儘乕丄堦旵楾偺孻帠僴儕乕丒儃僢僔儏偑榚栶偱搊応偡傞偺傕嫽枴傪屇傇丅 3埵偼乽傾僀傾儞丒僴僂僗乿丅僕儑儞丒僴乕僩偼乽愳偼惷偐偵棳傟乿乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿偲丄壠懓偺鉐傪僥乕儅偲偟偰寙嶌儈僗僥儕乕傪彂偒宲偄偱偒偨偑丄偙傟偼堦揮偟偰嶦偟壆傪庡恖岞偲偡傞僴乕僪儃僀儖僪晽僋儔僀儉丒僗儕儔乕丅慻怐偐傜敳偗傛偆偲偡傞嶦偟壆偑丄垽偡傞彈偲惗偒暿傟偵側偭偰偄偨掜傪庣傝側偑傜捛庤偲愴偆榖偱偁傞丅崱嶌偱傕昤偐傟傞恊巕孼掜偺鉐偼報徾怺偔丄師乆偵敆傞揋偲偺愴偄丄庡恖岞偺惗偄棫偪偵傑偮傢傞撲偲憡樦偭偰丄僒僗儁儞僗偼堦媺昳偩丅4埵偺乽捛寕偺怷乿偼儕儞僇乕儞丒儔僀儉丒僔儕乕僘偱恖婥暒摣偺僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偵傛傞僲儞丒僔儕乕僘嶌昳丅彈惈曐埨姱曗傪庡恖岞偵丄怷偺側偐偱偺埆娍偲偺懱椡偲抦椡傪恠偔偟偨愴偄偲捛偄偮捛傢傟偮偺摝旔峴偑昤偐傟傞丅僨傿乕償傽乕摼堄偺擇揮丄嶰揮偡傞僗僩乕儕乕揥奐偼偝偡偑偱偁傝丄傑偭偨偔愩傪姫偔岻偝偩丅
3埵偼乽傾僀傾儞丒僴僂僗乿丅僕儑儞丒僴乕僩偼乽愳偼惷偐偵棳傟乿乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿偲丄壠懓偺鉐傪僥乕儅偲偟偰寙嶌儈僗僥儕乕傪彂偒宲偄偱偒偨偑丄偙傟偼堦揮偟偰嶦偟壆傪庡恖岞偲偡傞僴乕僪儃僀儖僪晽僋儔僀儉丒僗儕儔乕丅慻怐偐傜敳偗傛偆偲偡傞嶦偟壆偑丄垽偡傞彈偲惗偒暿傟偵側偭偰偄偨掜傪庣傝側偑傜捛庤偲愴偆榖偱偁傞丅崱嶌偱傕昤偐傟傞恊巕孼掜偺鉐偼報徾怺偔丄師乆偵敆傞揋偲偺愴偄丄庡恖岞偺惗偄棫偪偵傑偮傢傞撲偲憡樦偭偰丄僒僗儁儞僗偼堦媺昳偩丅4埵偺乽捛寕偺怷乿偼儕儞僇乕儞丒儔僀儉丒僔儕乕僘偱恖婥暒摣偺僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偵傛傞僲儞丒僔儕乕僘嶌昳丅彈惈曐埨姱曗傪庡恖岞偵丄怷偺側偐偱偺埆娍偲偺懱椡偲抦椡傪恠偔偟偨愴偄偲捛偄偮捛傢傟偮偺摝旔峴偑昤偐傟傞丅僨傿乕償傽乕摼堄偺擇揮丄嶰揮偡傞僗僩乕儕乕揥奐偼偝偡偑偱偁傝丄傑偭偨偔愩傪姫偔岻偝偩丅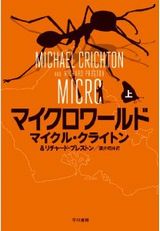 5埵偺乽僷乕僼僃僋僩丒僴儞僞乕乿偼挻堦棳偺嶦偟壆偑師乆偵墴偟婑偣傞揋偲愴偆偲偄偆撪梕偩偭偨偼偢偩偑丄偠偮偼偳傫側嬝偺塣傃偩偭偨偐丄傛偔妎偊偰偄側偄丅偱傕柺敀偐偭偨偙偲偩偗偼妋偐偱偁傝丄撉屻偺儊儌偵傕崅摼揰偑婰偟偰偁傞偺偱丄偙偙偵嫇偘偰偍偔丅6埵偺乽儅僀僋儘儚乕儖僪乿偼朣偒儅僀僋儖丒僋儔僀僩儞偑巆偟偨峓奣傪傕偲偵儕僠儍乕僪丒僾儗僗僩儞偑彂偄偨SF彫愢丅怴栻奐敪傪偨偔傜傓儀儞僠儍乕婇嬈偺儃僗偐傜師尦曄姺婡偱懱傪傢偡偑2僙儞僠偺僒僀僘偵弅傔傜傟丄僴儚僀偺怷椦偵曻傝弌偝傟偰偟傑偭偨戝妛惗偨偪偑丄嫄戝側崺拵傗摦暔偲愴偄側偑傜愱栧抦幆傪嬱巊偟偰側傫偲偐扙弌偟傛偆偲偡傞丄塮夋乽儈僋儘偺寛巰寳乿傪巚傢偣傞撪梕偺嶌昳偩丅嶀偊側偄榚栶偲巚偭偰偄偨搊応恖暔偺傂偲傝偑丄搑拞偐傜彊乆偵庡恖岞偲偟偰妶桇偟巒傔傞偲偄偆嬅偭偨庯岦偑柺敀偄丅偙偙傑偱撉傑偣傞彫愢偵巇忋偑偭偨偺偼丄暥復偑壓庤側僋儔僀僩儞偱偼側偔丄岻幰偺僾儗僗僩儞偑彂偄偨偐傜偩傠偆丅
5埵偺乽僷乕僼僃僋僩丒僴儞僞乕乿偼挻堦棳偺嶦偟壆偑師乆偵墴偟婑偣傞揋偲愴偆偲偄偆撪梕偩偭偨偼偢偩偑丄偠偮偼偳傫側嬝偺塣傃偩偭偨偐丄傛偔妎偊偰偄側偄丅偱傕柺敀偐偭偨偙偲偩偗偼妋偐偱偁傝丄撉屻偺儊儌偵傕崅摼揰偑婰偟偰偁傞偺偱丄偙偙偵嫇偘偰偍偔丅6埵偺乽儅僀僋儘儚乕儖僪乿偼朣偒儅僀僋儖丒僋儔僀僩儞偑巆偟偨峓奣傪傕偲偵儕僠儍乕僪丒僾儗僗僩儞偑彂偄偨SF彫愢丅怴栻奐敪傪偨偔傜傓儀儞僠儍乕婇嬈偺儃僗偐傜師尦曄姺婡偱懱傪傢偡偑2僙儞僠偺僒僀僘偵弅傔傜傟丄僴儚僀偺怷椦偵曻傝弌偝傟偰偟傑偭偨戝妛惗偨偪偑丄嫄戝側崺拵傗摦暔偲愴偄側偑傜愱栧抦幆傪嬱巊偟偰側傫偲偐扙弌偟傛偆偲偡傞丄塮夋乽儈僋儘偺寛巰寳乿傪巚傢偣傞撪梕偺嶌昳偩丅嶀偊側偄榚栶偲巚偭偰偄偨搊応恖暔偺傂偲傝偑丄搑拞偐傜彊乆偵庡恖岞偲偟偰妶桇偟巒傔傞偲偄偆嬅偭偨庯岦偑柺敀偄丅偙偙傑偱撉傑偣傞彫愢偵巇忋偑偭偨偺偼丄暥復偑壓庤側僋儔僀僩儞偱偼側偔丄岻幰偺僾儗僗僩儞偑彂偄偨偐傜偩傠偆丅 7埵偺乽摿憑晹Q乣P偐傜偺儊僢僙乕僕乿偼丄偄傑棳峴偺杒墷儈僗僥儕乕偺堦嶜丅僐儁儞僴乕僎儞寈嶡偱枹夝寛帠審傪埖偆摿憑晹偺妶桇傪昤偔僔儕乕僘偺戞3嶌丅庡恖岞偱偁傞栵夘幰偺寈晹曗偼丄崱夞傕僠乕儉儚乕僋側偳傑偭偨偔偲傟側偄婏柇側晹壓偨偪傪棪偄偰丄價儞偵擖偭偰棳傟拝偄偨乽彆偗偰乿偲偄偆庤巻偵抂傪敪偡傞丄怴嫽廆嫵偵偐傜傓彮擭桿夳帠審偵挧傓丅偙偺僔儕乕僘偼偳傟傕撉傒偛偨偊偑偁傞偑丄崱嶌偼偦偺側偐偱傕柺敀偝偺揰偱偼敳孮偩傠偆丅8埵偺乽夝忶巘乿偼丄梒偄帪偺帠審偺僩儔僂儅偱挐傟側偔側偭偨丄揤嵥揑側忶慜攋傝偺嵥擻傪傕偮彮擭傪庡恖岞偲偡傞晽曄傢傝側僋儔僀儉丒僲償僃儖丅抂揑偵尵偊偽丄彮擭偺惉挿傪昤偔惵弔彫愢偲偄偭偨庯偺嶌昳偱偁傝丄傒偢傒偢偟偄忣姶傪姶偠偝偣傞偑丄儈僗僥儕乕偲偟偰偺梫慺偼婓敄偩丅
7埵偺乽摿憑晹Q乣P偐傜偺儊僢僙乕僕乿偼丄偄傑棳峴偺杒墷儈僗僥儕乕偺堦嶜丅僐儁儞僴乕僎儞寈嶡偱枹夝寛帠審傪埖偆摿憑晹偺妶桇傪昤偔僔儕乕僘偺戞3嶌丅庡恖岞偱偁傞栵夘幰偺寈晹曗偼丄崱夞傕僠乕儉儚乕僋側偳傑偭偨偔偲傟側偄婏柇側晹壓偨偪傪棪偄偰丄價儞偵擖偭偰棳傟拝偄偨乽彆偗偰乿偲偄偆庤巻偵抂傪敪偡傞丄怴嫽廆嫵偵偐傜傓彮擭桿夳帠審偵挧傓丅偙偺僔儕乕僘偼偳傟傕撉傒偛偨偊偑偁傞偑丄崱嶌偼偦偺側偐偱傕柺敀偝偺揰偱偼敳孮偩傠偆丅8埵偺乽夝忶巘乿偼丄梒偄帪偺帠審偺僩儔僂儅偱挐傟側偔側偭偨丄揤嵥揑側忶慜攋傝偺嵥擻傪傕偮彮擭傪庡恖岞偲偡傞晽曄傢傝側僋儔僀儉丒僲償僃儖丅抂揑偵尵偊偽丄彮擭偺惉挿傪昤偔惵弔彫愢偲偄偭偨庯偺嶌昳偱偁傝丄傒偢傒偢偟偄忣姶傪姶偠偝偣傞偑丄儈僗僥儕乕偲偟偰偺梫慺偼婓敄偩丅 9埵偺乽恞栤惪晧恖乿偵偮偄偰偼11寧29擔晅偺僐儔儉偱彂偄偨丅撲偺夁嫀傪堷偒偢傞恞栤偺僾儘偑丄桿夳偝傟偨彮擭傪彆偗側偑傜悌傪偐偄偔偖偭偰揋偲愴偆偲偄偆榖丅庡恖岞傗偦偺廃曈偵偼彈偑偄偭偝偄搊応偟側偄偑丄搊応恖暔偺僉儍儔僋僞乕偼偟偭偐傝昤偐傟偰偍傝丄堿嶴側崏栤僔乕儞傕偁傞偑撉屻姶偼偝傢傗偐偩丅10埵偺乽擥傟偨嫑乿偼1929擭偺儀儖儕儞傪晳戜偵偟偨寈嶡彫愢丅儀儖儕儞寈帇挕偺晽婭壽強懏側偑傜嶦恖壽傊偺揮恎傪栚巜偡庒偄寈晹偑憳嬾偡傞嶖憥偟偨帠審偑暔岅傜傟傞丅僫僠僗戜摢偺慜栭丄儃儖僔僃價僉偺僗僷僀偑埫桇偟丄埆摽偲僨僇僟儞偑偼傃偙傞暔忣憶慠偨傞儀儖儕儞偺昤幨偑側偐側偐撉傑偣傞丅偙傟偼戝壨彫愢偺戞1姫偱丄帪戙傪捛偄側偑傜僔儕乕僘偲偟偰懕偔傜偟偄丅
9埵偺乽恞栤惪晧恖乿偵偮偄偰偼11寧29擔晅偺僐儔儉偱彂偄偨丅撲偺夁嫀傪堷偒偢傞恞栤偺僾儘偑丄桿夳偝傟偨彮擭傪彆偗側偑傜悌傪偐偄偔偖偭偰揋偲愴偆偲偄偆榖丅庡恖岞傗偦偺廃曈偵偼彈偑偄偭偝偄搊応偟側偄偑丄搊応恖暔偺僉儍儔僋僞乕偼偟偭偐傝昤偐傟偰偍傝丄堿嶴側崏栤僔乕儞傕偁傞偑撉屻姶偼偝傢傗偐偩丅10埵偺乽擥傟偨嫑乿偼1929擭偺儀儖儕儞傪晳戜偵偟偨寈嶡彫愢丅儀儖儕儞寈帇挕偺晽婭壽強懏側偑傜嶦恖壽傊偺揮恎傪栚巜偡庒偄寈晹偑憳嬾偡傞嶖憥偟偨帠審偑暔岅傜傟傞丅僫僠僗戜摢偺慜栭丄儃儖僔僃價僉偺僗僷僀偑埫桇偟丄埆摽偲僨僇僟儞偑偼傃偙傞暔忣憶慠偨傞儀儖儕儞偺昤幨偑側偐側偐撉傑偣傞丅偙傟偼戝壨彫愢偺戞1姫偱丄帪戙傪捛偄側偑傜僔儕乕僘偲偟偰懕偔傜偟偄丅慖奜偩偑嫽枴傪堷偐傟偨彫愢偑2嶜偁傞丅傂偲偮偼乽揤巊偺僎乕儉乿乮僇儖儘僗丒儖僀僗丒僒僼僅儞挊丄廤塸幮暥屔乯丅慜嶌乽晽偺塭乿偲懳傪側偡丄愴慜偺僶儖僙儘僫傪晳戜偵偟偨僼傽儞僞僕乕丒儈僗僥儕乕偱丄偁偺乬朰傟傜傟偨杮偺曟応乭傕搊応偡傞丅慜嶌摨條丄杮傊偺垽偑慡曇偵偁傆傟偰偍傝丄報徾怺偄偑丄偳偆傕榖偺揥奐偑傛偔撣傒崬傔側偄偟丄寢枛傕敾慠偲偣偢丄慜嶌偲斾傋傞偲弌棃偼偄傑偄偪偩丅傕偆傂偲偮偼乽幖抧乿乮傾乕僫儖僨儏儖丒僀儞僪儕僟僜儞挊丄憂尦幮乯丅捒偟偔傾僀僗儔儞僪偺寈嶡儈僗僥儕乕偩丅偙傫側崙偺彫愢傑偱東栿偝傟傞偲偼丄杒墷儈僗僥儕丒僽乕儉傕嬌傑偭偨姶偑偁傞丅撪梕揑偵偼峳椓偲偟偨晽搚偺側偐偺埫偄恖娫僪儔儅偱偁傝丄偠偭偔傝撉傑偣傞偩偗偺椡偼偁傞偑丄偁傑傝偺僔儕傾僗偝偲斶捝側儉乕僪偵偄偝偝偐鐒堈偡傞丅
2012.12.08(搚) 塮夋乽傾儖僑乿偲僀儔儞暷戝巊娰堳恖幙帠審偺恀幚
 偙偺塕偺傛偆側幚榖傪塮夋壔偟偨偺偑乽傾儖僑乿偩丅偙傟偼暥嬪側偔柺敀偄丅塮夋偲偟偰偺柺敀偝偲姰惉搙偺崅偝偱尵偊偽丄崱擭偺儀僗僩1偐傕偟傟側偄丅娔撀偱惢嶌丒庡墘傕寭偹傞儀儞丒傾僼儕僢僋偼丄娔撀3嶌栚偵偟偰憗偔傕慺惏傜偟偄椡検傪尒偣偮偗偨丅塮夋偼丄戝偒偔尵偭偰丄傾儊儕僇偱寁夋傪棫偰偍慥棫偰傪偡傞僷乕僩偲丄尰抧僥僿儔儞偵偍偗傞扙弌峴傪昤偔僷乕僩偺2偮偵暘偐傟傞丅偦偙偵丄塀傟壠偵廧傓6恖偺恖娫娭學傗嶌愴傪巜婗偡傞庡恖岞偺壠掚栤戣側偳偺僄僺僜乕僪偑偐傜傓丅僀儔儞偱偺朶搆偨偪偑暷戝巊娰偵棎擖偡傞條巕傗丄僥僿儔儞偺奨偺堿嶴側岝宨側偳偼丄僪僉儏儊儞僞儕乕塮憸偑岻傒偵怐傝岎偤傜傟丄惗乆偟偄敆椡偑偁傞偟丄寁夋偑彮偟偢偮楙傝忋偘傜傟偰偄偔揥奐偺昤偒曽傕尒帠偩丅偲傝傢偗丄塀傟壠傪敳偗弌偰僥僿儔儞嬻峘傊岦偐偄丄旘峴婡偵忔傝崬傓傑偱偺嬞敆姶偼奿暿偱丄惉岟偡傞偲暘偐偭偰偄偰傕丄庤偵娋埇傞傛偆側僗儕儖傪姶偠偝偣傞丅巎幚偵婎偯偄偰偄傞偲偼偄偊丄偲偆偤傫嵶晹偼塮夋偲偟偰惙傝忋偘傞偨傔偵庤偑壛偊傜傟偰偄傞偺偩傠偆偑丄偦偺偁偨傝偺媟怓偺岻偝傕摿昅偡傋偒偩丅傾僼儕僢僋偺梷偊偨墘媄偑偄偄偟丄僴儕僂僢僪偺僾儘僨儏乕僒乕偵暞偡傞傾儔儞丒傾乕僉儞偼偠傔懠偺弌墘幰偨偪偺帺慠側強嶌傕旕偺懪偪偳偙傠偑側偄丅
偙偺塕偺傛偆側幚榖傪塮夋壔偟偨偺偑乽傾儖僑乿偩丅偙傟偼暥嬪側偔柺敀偄丅塮夋偲偟偰偺柺敀偝偲姰惉搙偺崅偝偱尵偊偽丄崱擭偺儀僗僩1偐傕偟傟側偄丅娔撀偱惢嶌丒庡墘傕寭偹傞儀儞丒傾僼儕僢僋偼丄娔撀3嶌栚偵偟偰憗偔傕慺惏傜偟偄椡検傪尒偣偮偗偨丅塮夋偼丄戝偒偔尵偭偰丄傾儊儕僇偱寁夋傪棫偰偍慥棫偰傪偡傞僷乕僩偲丄尰抧僥僿儔儞偵偍偗傞扙弌峴傪昤偔僷乕僩偺2偮偵暘偐傟傞丅偦偙偵丄塀傟壠偵廧傓6恖偺恖娫娭學傗嶌愴傪巜婗偡傞庡恖岞偺壠掚栤戣側偳偺僄僺僜乕僪偑偐傜傓丅僀儔儞偱偺朶搆偨偪偑暷戝巊娰偵棎擖偡傞條巕傗丄僥僿儔儞偺奨偺堿嶴側岝宨側偳偼丄僪僉儏儊儞僞儕乕塮憸偑岻傒偵怐傝岎偤傜傟丄惗乆偟偄敆椡偑偁傞偟丄寁夋偑彮偟偢偮楙傝忋偘傜傟偰偄偔揥奐偺昤偒曽傕尒帠偩丅偲傝傢偗丄塀傟壠傪敳偗弌偰僥僿儔儞嬻峘傊岦偐偄丄旘峴婡偵忔傝崬傓傑偱偺嬞敆姶偼奿暿偱丄惉岟偡傞偲暘偐偭偰偄偰傕丄庤偵娋埇傞傛偆側僗儕儖傪姶偠偝偣傞丅巎幚偵婎偯偄偰偄傞偲偼偄偊丄偲偆偤傫嵶晹偼塮夋偲偟偰惙傝忋偘傞偨傔偵庤偑壛偊傜傟偰偄傞偺偩傠偆偑丄偦偺偁偨傝偺媟怓偺岻偝傕摿昅偡傋偒偩丅傾僼儕僢僋偺梷偊偨墘媄偑偄偄偟丄僴儕僂僢僪偺僾儘僨儏乕僒乕偵暞偡傞傾儔儞丒傾乕僉儞偼偠傔懠偺弌墘幰偨偪偺帺慠側強嶌傕旕偺懪偪偳偙傠偑側偄丅偙偙偵偼惌帯揑側庡挘偼側偄丅朻摢偵帤枊偱丄慜惌尃偺僷僼儔償傿崙墹偑傾儊儕僇偺橒橲偩偭偨偙偲丄僷僼儔償傿惌尃偺埑惌偵僀僗儔儉惃椡偑斀婙傪東偟偰妚柦偑婲偒偨偙偲側偳偺攚宨愢柧偑側偝傟傞偩偗偩丅偦傟偼偦傟偱偄偄丅偙偙偵惌帯揑側儊僢僙乕僕側偳傪惙傝崬傓偺偼柍悎偱偁傝丄僄儞僞僥僀儞儊儞僩偵揙偟偰惓夝偩偭偨偲巚偆丅偙偺塮夋偺桞堦偺嚓圊偼僄儞僨傿儞僌偩丅夡傟偐偗偰偄偨庡恖岞偺壠掚偑尦偵栠傞偲偄偆枊愗傟偼丄偄偐偵傕庢偭偰偮偗偨傛偆偱丄嫽傪嶍偑傟傞丅傕偭偲偁偭偝傝偲廔偊傞傋偒偩偭偨偲巚偆丅
偲偙傠偱丄暷戝巊娰偱恖幙偵側偭偰偄偨52恖偩偑丄摉帪偺僇乕僞乕惌尃偼媬弌嶌愴偑偡傋偰幐攕偟丄奜岎揑側傾僾儘乕僠傕岟傪憈偝偢丄僇乕僞乕偑戝摑椞傪戅偄偰儗乕僈儞偑廇擟偟偨1981擭1寧丄1擭3儢寧傇傝偵傛偆傗偔夝曻偝傟偨丅恖幙偺夝曻偑偙傫側偵抶傟偨攚宨偵偼丄師婜戝摑椞傪慱偆儗乕僈儞偑夋嶔偟偨堿杁偑偁偭偨偲偄偆榖傪丄埲慜側偵偐偱撉傫偩偙偲偑偁傞丅崻傕梩傕側偄梌懢榖偱偼側偄丅徹嫆偺彂椶傗徹尵傕偁傞楌巎忋偺帠幚偩丅
僀儔儞懁偼傕偲傕偲丄傾儊儕僇偵朣柦偟偨僷僼儔償傿尦崙墹偺堷偒搉偟傪梫媮偟偰恖幙傪偲偭偨偺偩偑丄1980擭7寧偵僷僼儔償傿偑巰嫀偟偨偨傔偦偺堄媊偑敄傟偰偟傑偭偨丅偦偟偰暷惌晎偲僀儔儞偲偺悈柺壓偱偺岎徛偵傛傝丄恖幙傪夝曻偡傞曽岦偵岦偐偭偰榖偑恑傫偱偄偨丅偲偙傠偑丄戝摑椞慖偱偺彑棙傪慱偆儗乕僈儞恮塩偼丄傂偦偐偵僀儔儞偲愙怗偟丄儗乕僈儞偑惌尃傪庢偭偨傜摿暿側攝椂傪偡傞偐傜丄偦偺戙傢傝偵僇乕僞乕偑戝摑椞偱偄傞娫偼恖幙傪夝曻偟側偄偱偔傟偲帩偪偐偗偨丅僀儔儞偑偦偺榖傪撣傒丄偦偺寢壥丄僇乕僞乕偼恖幙偺夝曻偵幐攕偟偰戝摑椞慖偱攕杒偟偨丅僇乕僞乕偺攕場偼戝巊娰堳恖幙帠審偱偺懳墳偺傑偢偝偵偁偭偨偲儅僗僐儈偼榑昡偟偰偄傞丅傕偟僇乕僞乕惌尃壓偱恖幙偑夝曻偝傟偰偄傟偽丄僇乕僞乕偑彑偭偰2婜栚偺戝摑椞偵側偭偰偄偨壜擻惈偑崅偄丅慖嫇偺嬱偗堷偒偺摴嬶偵偝傟偨恖幙偨偪偼丄偨傑偭偨傕偺偱偼側偄丅杮棃側傜傕偭偲憗偔婣崙偱偒偨傕偺傪丄儗乕僈儞恮塩偺嶔杁偺偣偄偱挿婜偵傢偨傞擃嬛傪梋媀側偔偝傟偨偺偩丅戝摑椞慖偵彑偮偨傔偵偼偙偙傑偱墭偄偙偲傪傗傞偺偐丄偲偄偆巚偄偵懆傢傟傞偑丄偦傟偑傾儊儕僇偲偄偆崙偺幚懺側偺偩丅
2012.11.29 (栘) 傾儊儕僇偺棤偺悽奅傪僥乕儅偵偟偨2嶜偺儈僗僥儕彫愢
 傂偲偮偼丄偙傟偑張彈嶌偵側傞怴恖嶌壠儅僔儏乕丒僋儚乕僋偑彂偄偨亀The 500亁乮憗愳億働儈僗乯丅昤偐傟傞偺偼傾儊儕僇偺惌帯傪堿偱憖傞儘價僀僗僩嬈奅偩丅僴乕償傽乕僪戝妛偱妛傇嬯妛惗偺庡恖岞偑儚僔儞僩儞偺惌奅傪棤偱媿帹傞儘價僀僗僩夛幮偵屬傢傟丄挘傝愗偭偰巇帠偵椼傫偱摢妏傪尰偡偑丄偠偮偼偦偺夛幮偵偼塀偝傟偨旈枾偑偁傝丄庡恖岞偵偼婋尟側悌偑巇妡偗傜傟偰偄偨丄偲偄偆撪梕偺彫愢偩丅僕儑儞丒僌儕僔儍儉偺弌悽嶌亀朄棩帠柋強亁偲嬝棫偰偑帡偰偄傞偑丄傛偔弌棃偨彫婥枴偄偄僥儞億偺僗儕儔乕偵巇忋偑偭偰偄傞丅搑拞偱惓媊偵栚妎傔傞庡恖岞偺摦婡偯偗偑庛偄偺偑擄偩偑丄儕乕僟價儕僥傿偼敳孮偱堦婥偵撉傑偣傞丅偟偭偔傝偄偭偰偄側偐偭偨晝恊偲偺鉐傪庢傝栠偡僄僺僜乕僪傕怱偵怗傟傞丅
傂偲偮偼丄偙傟偑張彈嶌偵側傞怴恖嶌壠儅僔儏乕丒僋儚乕僋偑彂偄偨亀The 500亁乮憗愳億働儈僗乯丅昤偐傟傞偺偼傾儊儕僇偺惌帯傪堿偱憖傞儘價僀僗僩嬈奅偩丅僴乕償傽乕僪戝妛偱妛傇嬯妛惗偺庡恖岞偑儚僔儞僩儞偺惌奅傪棤偱媿帹傞儘價僀僗僩夛幮偵屬傢傟丄挘傝愗偭偰巇帠偵椼傫偱摢妏傪尰偡偑丄偠偮偼偦偺夛幮偵偼塀偝傟偨旈枾偑偁傝丄庡恖岞偵偼婋尟側悌偑巇妡偗傜傟偰偄偨丄偲偄偆撪梕偺彫愢偩丅僕儑儞丒僌儕僔儍儉偺弌悽嶌亀朄棩帠柋強亁偲嬝棫偰偑帡偰偄傞偑丄傛偔弌棃偨彫婥枴偄偄僥儞億偺僗儕儔乕偵巇忋偑偭偰偄傞丅搑拞偱惓媊偵栚妎傔傞庡恖岞偺摦婡偯偗偑庛偄偺偑擄偩偑丄儕乕僟價儕僥傿偼敳孮偱堦婥偵撉傑偣傞丅偟偭偔傝偄偭偰偄側偐偭偨晝恊偲偺鉐傪庢傝栠偡僄僺僜乕僪傕怱偵怗傟傞丅傾儊儕僇偵偼3枩傪挻偊傞儘價僀僗僩偑懚嵼偟偰偍傝丄惌晎偺惌嶔寛掕偵戝偒側塭嬁椡傪媦傏偟偰偄傞偲尵傢傟傞偑丄擔杮偱偼撻愼傒偺側偄價僕僱僗偱偁傝丄傏偔偨偪偵偼偦偺幚懱偼傛偔暘偐傜側偄丅偙偺彫愢偵弌偰偔傞儘價僀僗僩夛幮偼丄惌奅偺戝暔偨偪乮儚僔儞僩儞偵偼偦傫側惌帯傪摦偐偡恖娫偑500恖偄傞偲尵傢傟偰偍傝丄偦傟偑偙偺彫愢偺戣柤偵側偭偰偄傞乯偲崸堄偵偟丄旈枾傪埇傝丄応崌偵傛偭偰偼庛傒傪漵憿偟偨傝偟偰丄偦傟傪僱僞偵憡庤傪堄偺傑傑偵僐儞僩儘乕儖偟偰偄傞丅尰幚偺悽奅偱傕丄偙偙傑偱嬌抂偱偼側偄偵偣傛丄70擭戙弶摢傑偱FBI挿姱傪柋傔丄惌帯壠傗挊柤恖偺塀偝傟偨忣曬傪廂廤偟偰塭嬁椡傪怳傞偭偨僄僪僈乕丒僼乕償傽乕偺椺傕偁傞偟丄偙傟偵嬤偄傛偆側偙偲偑峴側傢傟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
 傕偆傂偲偮偼儅乕僋丒傾儗儞丒僗儈僗偲偄偆嶌壠偺亀恞栤惪晧恖亁乮憗愳暥屔乯丅偙傟傕偙偺嶌壠偺僨價儏乕嶌偩丅偙偪傜偼恞栤惪晧嬈偲偄偆悽奅傪埖偭偨僗儕儔乕丅偁傜備傞僥僋僯僢僋偵捠偠偨恞栤偺僾儘偑庡恖岞偱丄柉娫婇嬈丄惌晎婡娭丄斊嵾慻怐偐傜埶棅偝傟偰丄懳徾幰偐傜忣曬傪堷偒弌偟丄曬廣傪摼偰偄傞丅斵偼怴偨偵巇帠傪堷偒庴偗偨偑丄懳徾幰偑彮擭偱偁傞偙偲傪抦偭偰偦偺彮擭傪媷抧偐傜媬偄弌偟丄幏漍偵敆傞揋偲愴偄側偑傜巇慻傑傟偨堿杁偵棫偪岦偐偆丄偲偄偆撪梕偩丅偙偺抝偼梒偄偙傠偺婰壇傪幐偭偰偄傞偑丄偦偺撲偼暔岅偑恑傓偵偮傟偰彮偟偢偮柧傜偐偵側偭偰偄偔丅
傕偆傂偲偮偼儅乕僋丒傾儗儞丒僗儈僗偲偄偆嶌壠偺亀恞栤惪晧恖亁乮憗愳暥屔乯丅偙傟傕偙偺嶌壠偺僨價儏乕嶌偩丅偙偪傜偼恞栤惪晧嬈偲偄偆悽奅傪埖偭偨僗儕儔乕丅偁傜備傞僥僋僯僢僋偵捠偠偨恞栤偺僾儘偑庡恖岞偱丄柉娫婇嬈丄惌晎婡娭丄斊嵾慻怐偐傜埶棅偝傟偰丄懳徾幰偐傜忣曬傪堷偒弌偟丄曬廣傪摼偰偄傞丅斵偼怴偨偵巇帠傪堷偒庴偗偨偑丄懳徾幰偑彮擭偱偁傞偙偲傪抦偭偰偦偺彮擭傪媷抧偐傜媬偄弌偟丄幏漍偵敆傞揋偲愴偄側偑傜巇慻傑傟偨堿杁偵棫偪岦偐偆丄偲偄偆撪梕偩丅偙偺抝偼梒偄偙傠偺婰壇傪幐偭偰偄傞偑丄偦偺撲偼暔岅偑恑傓偵偮傟偰彮偟偢偮柧傜偐偵側偭偰偄偔丅寈嶡傗孯戉偵強懏偡傞恞栤偺僾儘偲偄偆偺偼偄傞偑丄恞栤惪晧嬈側偳偲偄偆柉娫價僕僱僗偑幚嵺偵偁傞偺偐偳偆偐丄暘偐傜側偄丅偱傕傾儊儕僇偺偙偲偩偐傜丄偁偭偰傕偍偐偟偔偼側偄丅庡恖岞偺恞栤偼堦庬偺崏栤偩偑丄擖擮偵寁嶼偝傟偨怱棟揑側僥僋僯僢僋傪梡偄偰憡庤傪愑傔丄傎偲傫偳寣傪棳偡偙偲側偔帺敀傪堷偒弌偡丅偙偺恞栤偺僔乕儞偑側偐側偐嫽枴怺偄丅僾儘僢僩傕岻柇偱嵟弶偐傜嵟屻傑偱僒僗儁儞僗偑帩懕偟偰偄傞丅慡懱偵僩乕儞偼埫偔丄堿嶴側僔乕儞傕偁傞偑丄撉傒怱抧偼夣挷偩偟丄梋塁偺偁傞枊愗傟傕怽偟暘側偄丅屒撈傪岲傓椻惷捑拝側庡恖岞偺憿宆偑儐僯乕僋偱偁傝丄憡朹偺挷嵏堳傪偼偠傔丄搊応恖暔偑抂栶偵帄傞傑偱偒偭偪傝偲昤偐傟偰偄傞丅偙偙偱傕庡恖岞偺攚宨偵偼晝恊偑塭傪棊偲偟偰偍傝丄偦傟傜偑憡樦偭偰丄偙偺彫愢偵墱峴偒偑傕偨傜偝傟偰偄傞丅
2012.11.15 (栘) 堐怴偺夛偺偍慹枛偝偲堐怴敧嶔偺嬻嫊側拞恎
嫶壓揙棪偄傞擔杮堐怴偺夛偼戞3嬌偺戜晽偺栚偵側傞偲尵傢傟偰偄傞丅偩偑丄壥偨偟偰嫶壓揙偵擔杮偺柦塣傪戸偣傞偺偩傠偆偐丅崙惌偵憲傝崬傕偆偲偟偰偄傞岓曗幰偼偲偆偤傫嬍愇崿熇偱偁傠偆偟丄傓偟傠怣棅偵懌傞恖暔側偳傎偲傫偳偄側偄偲峫偊偨傎偆偑偄偄偩傠偆丅堐怴偺夛偵埰懼偊偟偨崙夛媍堳偺婄傇傟傪尒偰傕丄偙傟偲偄偭偨恖暔偼尒摉偨傜側偄丅嫶壓恖婥偵偁傗偐偭偰慖嫇傪忔傝愗傠偆偲偄偆巚榝偑尒偊尒偊偺楢拞偽偐傝偩丅
偦傕偦傕嫶壓偑崙惌偵懪偭偰弌傞偵偁偨偭偰丄搣戙昞偺嵗傪塧偵楢実傪媮傔偨偺偑埨攞怶嶰偩偭偨偺偵偼丄奐偄偨岥偑傆偝偑傜側偐偭偨丅埨攞怶嶰偲偄偊偽丄偄傑偼帺柉搣憤嵸偵曉傝嶇偄偨偑丄偐偮偰庱憡偺嵗偺廳埑偵懴偊偒傟偢惌尃傪搳偘弌偟偰崢敳偗傇傝傪偝傜偗弌偟偨恖娫偩丅寷朄夵惓丄懳暷廬懏丄妀晲憰梕擣偲偄偆挻曐庣巚憐偺帩偪庡偱偁傞偙偲偼2恖偵嫟捠偟偰偄傞偑丄偦傟偵偟偰傕僿僞儗惌帯壠偺埨攞偵偡傝婑傞偲偼丄嫶壓偺尒幆偺側偝傕偼側偼偩偟偄丅傕偭偲傕丄変幏偲榁廥偺尃壔丄愇尨怲懢榊傪懜宧偟偰偄傞偙偲偐傜偟偰丄偡偱偵嫶壓偺僟儊偝壛尭偼柧傜偐側偺偩偑丅
堐怴偺夛偺僽儗乕儞偵丄偄偮偺傑偵偐抾拞暯憼偑廂傑偭偰偄傞丅彫愹弮堦榊傪僸乕儘乕偲嬄偖嫶壓揙偐傜偡傟偽丄彫愹惌尃壓偱宱嵪惌嶔傪悇偟恑傔偨抾拞偲慻傓偺偼帺慠側棳傟偩偭偨偺偩傠偆丅偩偑丄抾拞暯憼偲偄偊偽丄傾儊儕僇偺庤愭偲側偭偰丄峔憿夵妚丄婯惂娚榓偺偍戣栚偺傕偲偵巗応尨棟偵婎偯偔怴帺桼庡媊惌嶔傪悇恑偟偨寢壥丄擔杮偺宱嵪傪庛懱壔偝偣丄偦傟傑偱偵側偄奿嵎幮夛傪惗傒弌偟偨挘杮恖偩丅擔杮傪僟儊偵偟偨A媺愴斊偩丅偦傫側攜偑宱嵪惌嶔偺懬庢傝傪偡傟偽丄擔杮幮夛偼傑偨傕傗戝偒側懪寕傪庴偗傞偙偲偵側傞丅
堐怴偺夛偑岞栺偲偟偰壺乆偟偔傇偪忋偘偨堐怴敧嶔偺拞恎偼偍慹枛偒傢傑傝側偄丅偦偙偵偼壡摢惌帯巙岦偲懳暷廬懏巙岦偑怓擹偔姶偠傜傟傞丅憤偠偰丄柆棈側偔旤帿楉嬪偑暲傋傜傟偰偄傞偑丄傎偲傫偳嬶懱揑側巤嶔傗栚昗悢抣偑擖偭偰偍傜偢丄婘忋偺嬻榑偵嬤偄丅偍屳偄偵柕弬偡傞傛偆側栚昗傕嶶尒偝傟丄巚偄偮偄偨偙偲傪抂偐傜抂偵暲傋偨偩偗偺傛偆側報徾偑嫮偄丅
乽摑帯婡峔偺嶌傝捈偟乿偺崁偱偼庱憡岞慖傪偆偨偭偰偄傞丅偙傟偼媍堾撪妕惂傪攑巭偟偰戝摑椞惂偵偟傛偆偲偄偆偙偲偐丅偄偢傟偵偣傛丄寛傔傞偙偲偑偱偒傞惌帯傪栚巜偡偵偟偰偼丄敪憐偑抁棈揑偡偓傞丅傾儊儕僇偺戝摑椞偼嫮戝側尃尷傪帩偭偰偄傞偲巚傢傟偑偪偩偑丄幚嵺偵偼媍夛偵傛偭偰戝摑椞偺峴惌偼偮偹偵僠僃僢僋偝傟偰偍傝丄嶐崱偺僆僶儅戝摑椞偺働乕僗傪尒偰傕暘偐傞傛偆偵丄戝摑椞偺強懏惌搣偲媍夛懡悢攈偑堎側傟偽丄戝摑椞偼巚偆傛偆偵尃尷傪峴巊偱偒側偄偺偩丅
乽嵿惌丒峴惌丒惌帯夵妚乿偺崁偱偼丄廜媍堾偺媍堳悢傪240恖偵嶍尭丄嶲媍堾傪攑巭偲丄偙偙偩偗偼傗偨傜嬶懱揑偵彂偐傟偰偄傞丅媍堳悢偺嶍尭偼偗偭偙偆偩偑丄埲慜偐傜嶍尭偑嫨偽傟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢偄偭偙偆偵幚尰偟側偄尰忬偱丄偙傫側柌傒偨偄側栚昗傪宖偘傜傟偰傕丄偼側偼偩愢摼椡偑側偄丅乽奜岎丒杊塹乿偺崁偵偼擔暷摨柨傪婎幉偵偡傞偲偄偆暥尵偼偁傞偑丄傾僕傾傊偺栚慄偑傑偭偨偔寚偗偰偄傞丅乽寷朄夵惓乿偺崁偱偼丄夵惓傊偺梫審娚榓偲崙柉搳昜偺幚巤傪偆偨偄丄夵惓傊偺堄巚傪偼偭偒傝懪偪弌偟偰偄傞丅
乽幮夛曐忈惂搙夵妚乿偱偼嶨懡側栚昗偑宖偘傜傟偰偄傞偑丄娞怱偺憹偊懕偗傞幮夛曐忈旓偵偳偆懳張偡傞偺偐偵偼怗傟傜傟偰偄側偄丅乽宱嵪惌嶔丒屬梡惌嶔丒惻惂乿偺崁偱傕丄摨偠偔憤壴揑偵偆偨偄暥嬪偑暲傫偱偄傞偑丄偳偆偄偆曽岦偵揮姺偟偨偄偺偐丄壗傪廳揰揑偵傗偭偰偄偔偺偐偑傑偭偨偔尒偊側偄丅偄偢傟偵偣傛丄抾壓暯憼偑僶僢僋偵偄傟偽丄偳傫側偒傟偄偛偲傪尵偭偰傕丄庛幰愗傝幪偰丄戝帒杮婑傝偺巤嶔偵側傞偺偼柧傜偐偩丅
偲偄偆傢偗偱丄堐怴偺夛偵偼傑偭偨偔婜懸偱偒側偄偑丄偐偲偄偭偰愇尨怴搣側偳偼栤戣奜偩偟丄彫戲怴搣傗傒傫側偺搣傕棅傝側偄丅12寧偺慖嫇偱偳偙偵搳昜偡傟偽偄偄偺偐丄摢傪書偊偰偟傑偆丅
2012.11.01 (栘) 搒抦帠傪帿怑偟偰変幏偲榁廥傪偝傜偡愇尨怲懢榊
偦傟偵偟偰傕丄愇尨偼傎傫偲偆偵愑擟姶偺偐偗傜傕側偄抝偩丅乽嵟屻偺偍嬑傔傪偝偣偰偔傟乿偲尵偭偰搒抦帠4慖傪壥偨偟偰偐傜丄傑偩1擭敿偟偐宱偭偰偄側偄丅帿怑偺棟桼偑丄傑偨傕傗乽崙傊偺嵟屻偺偛曭岞傪偡傞偨傔乿偲偒偨丅偄偭偨偄壗搙乬嵟屻乭偑偁傟偽婥偑嵪傓偺偩丅搒柉偵戸偝傟偨巊柦傪斵偼偳偆峫偊偰偄傞偺偐丅僆儕儞僺僢僋桿抳偼偳偆偡傞偺偩丅怴嬧峴搶嫗偺屻巒枛偲愑擟偼偳偆偮偗傞偺偩丅杮恖偼乽偍崙偺偨傔偵丄庒偄傗偮偑偩傜偟側偄偐傜丄偍傟偑弌傞偟偐側偄乿側偳偲傎偞偄偰偄傞偑丄側傫偺偙偲偼側偄丄帺暘偺尃椡梸傪枮懌偝偣偨偄偩偗偵夁偓側偄丅
傏偔偼執偦偆偵埿挘傝嶶傜偡恖娫偑戝寵偄偩丅偦傫側傗偮偼嶰棳偺僋僘恖娫偩偲巚偭偰偄傞丅偦偺揟宆偑愇尨怲懢榊偩丅偦傫側愇尨偺尵偆偙偲偵丄廃傝偺楢拞偑扤傕堎傪彞偊偢丄偁傝偑偨偑偭偰攓挳偟偰偄傞偺偼丄忣偗側偄偐偓傝偩丅偙傫側恎彑庤側尃椡梸偲峝捈偟偨崙壠庡媊偵嬅傝屌傑偭偨丄婃柪墶朶側榁恖偵崙惌傪擟偣偨傜丄擔杮偼娫堘偄側偔曵夡偡傞丅側偵偟傠愇尨偼愲妕栤戣傪堷偒婲偙偟偰宱嵪揑丄奜岎揑偵戝偒側懝幐傪彽偄偨挘杮恖偩丅椞搚栤戣傪夝寛偡傞偵偼愴憟傕帿偝側偄偲杮婥偱庡挘偡傞抝偩丅
愇尨偼帿怑夛尒偱寷朄偵娭偡傞帩榑傪傑偔偟偨偰偨丅崙惌偵暅婣偟偨傜偄傑偺寷朄傪攑婞偟偰怴寷朄傪嶌傞偲偄偆丅戝擔杮掗崙寷朄偵偱傕栠偦偆偲尵偆偺偐丅偄傑偺寷朄偼傾儊儕僇偺偍巇拝偣偱偁傝丄忦暥偼擔杮岅偺懱傪側偟偰偄側偄偲偄偆丅偍傛偦暥妛偲傕屇傋側偄僿僞偔偦側暥復偟偐彂偗側偄愇尨偑丄傛偔抪偢偐偟偘傕側偔寷朄偺忦暥傪斸敾偱偒傞傕偺偩偲巚偆偑丄偦傟偼偲傕偐偔丄1946擭偵岞晍偝傟偨擔杮崙寷朄偼丄傾儊儕僇偺埑椡偑側偗傟偽嶌傝偊側偐偭偨婏愓揑側寷朄偩丅偁偺摉帪丄擔杮偺惌帯壠傗妛幰偩偗偵擟偣偰偍偗偽丄愴慜偺媽偄峫偊傗懱惂傪怳傝暐偆偙偲偼偱偒偢丄偁傟傎偳戝抇偱恑曕揑側寷朄傪嶌傝弌偡偙偲偼偱偒側偐偭偨丅媽暰側巚憐傪夝懱偝偣丄揙掙揑偵柉庡揑側傕偺偵偟傛偆偲偄偆愯椞孯偺堄恾偑偁偭偨偐傜偙偦丄偁偺悽奅偵屩傞寷朄偑偱偒偨偺偩丅偍巇拝偣偩偐傜埆偄偲偄偆愇尨傪偼偠傔偲偡傞寷朄夵掶榑幰偺峫偊偼丄偁傑傝偵抁棈揑偩偟師尦偑掅偄丅
愇尨怲懢榊偼媽懺埶慠偨傞榁恖惌搣乽棫偪忋偑傟擔杮乿傪搚戜偵偟偰怴搣傪寢惉偡傞傛偆偩丅愇尨偲偟偰偼丄廃傝偵岊傢傟偰怴搣傪棫偪忋偘傞偲偄偆曽岦偵帩偭偰偄偒偨偐偭偨偺偩傠偆偑丄80嵨偺擭婑傝偵丄傕偼傗偦偙傑偱偺塭嬁椡偼側偐偭偨丅愇尨怴搣偼扨撈偱偼壗偺僀儞僷僋僩傕傕偨傜偝側偄偩傠偆丅偦傟傪婋湝偡傞愇尨偼丄堐怴偺夛側偳偵怓栚傪巊偄丄楢実傪恾傠偆偲偟偰偄傞丅儊僨傿傾偼戞3嬌偺楢実側偳偲傕偰偼傗偡偑丄摢偺偄偄嫶壓揙偼丄傕偼傗廔傢偭偰偟傑偭偨惌帯壠偱偁傞愇尨偲偺楢実榖偵忔傜側偄偩傠偆丅惌嶔傗峫偊曽偺揰偱傕丄嫟捠偡傞偲偙傠偼偁傞偵偟偰傕丄娞怱偺晹暘偱偼戝偒偔堎側偭偰偄傞丅偦傕偦傕愇尨偼丄僘働僘働傕偺傪尵偆偐傜妚怴揑偵尒偊傞偑丄偦偺幚懱偼丄尨敪栤戣偵偟傠徚旓惻栤戣偵偟傠丄峫偊曽偼偙偲偛偲偔曐庣揑偩丅偦偺堄枴偱偼帺柉搣偲摨偠懱幙偱偁傝丄傓偟傠帺柉搣傛傝傕偭偲塃婑傝偩偲尵偊傞丅
戝懡悢偺崙柉偼愇尨怴搣側偳巟帩偟側偄偲巚偆偑丄側偐偵偼愇尨偺埿惃偺偄偄尵梩偵榝傢偝傟丄掅師尦偺姶忣傪巋寖偝傟傞幰傕偄傞偩傠偆偟丄壓昳側尵梩偱搟柭傝嶶傜偡斵傪嫮幰偩偲姩堘偄偟丄傂偨偡傜悞傔傞儅僝僸僗僩偺傛偆側幰傕偄傞偩傠偆丅偩傑偝傟偰偼偄偗側偄丅愇尨偼傛偔乽嵟嬤偺擔杮恖偼変梸偵傑傒傟偡偓偰偄傞乿偲偄偆偑丄偄偪偽傫変梸偵傑傒傟偰偄傞偺偼摉偺愇尨偩丅帿怑夛尒偺側偐偱愇尨偼姱椈偵憖傜傟傞崙偺峴惌傪桱偊丄姱椈偺撈慞傪懪攋偡傞偲堄婥崬傫偩丅偦傟偼偄偄丅偩偑丄姱椈偺撈慞偵戙傢偭偰愇尨偺撈慞偑嫃嵗傞偺偼婅偄壓偘偩丅偙傫側柍愑擟側丄庛幰傪愗傝幪偰丄奜崙恖傪曁帇偟丄崙柉傪愴憟偵嬱傝棫偰傞攜偵丄崙惌傪巌傞帒奿偼側偄丅
2012.10.24 (悈) 廡姧挬擔偺乽僴僔僔僞乿曬摴傪傔偖偭偰
偙傟偵偮偄偰偼丄廡姧挬擔懁偵旕偑偁傞偲彞偊傞榑挷偑戝敿偩偭偨傛偆偩偑丄傏偔偼尒夝傪堎偵偡傞丅偙偺婰帠乮儗億乕僞乕偼嵅栰崃堦乯偱偼丄傑偢嫶壓揙偺惌帯庤朄傪傗傝嬍偵嫇偘丄僸僢僩儔乕偵帡偰偄傞丄屆偔偝偄庛擏嫮怘巚憐丄戝廜寎崌庡媊丄偵傢偐曌嫮偱恎偵晅偗偨嬻嫊側惌帯揑媃尵側偳偲巜揈偟丄屻抜偱嫶壓偺晝恊偺墢愂偩偲偄偆恖暔傊偺僀儞僞價儏乕偑嵹傝丄晝偑偳傫側恖暔偩偭偨偐偑岅傜傟丄旐嵎暿晹棊偺弌恎偱偁傞偙偲丄晝偑朶椡抍偺慻堳偩偭偨偙偲偑柧傜偐偵偝傟偰偄傞丅
偙傟偵偮偄偰丄嫶壓偼恖尃怤奞偩偲尵偭偨傢偗偩偑丄壗偑恖尃怤奞側偺偩傠偆丅 嫶壓偺惌帯庤朄偵偮偄偰偺偙偺傛偆側斸敾偼丄偙傟傑偱偄傠傫側儊僨傿傾偱偝傫偞傫彂偐傟偰偒偨偙偲偱偁傝丄偙偲偝傜栚怴偟偄傕偺偱偼側偄丅傑偨丄旐嵎暿晹棊塢乆傗晝恊偑朶椡抍塢乆偵偮偄偰傕丄偙傟傑偱廡姧帍側偳偱壗搙傕庢傝忋偘傜傟偰偒偨偟丄嫶壓帺恎傕擣傔偰偄傞偙偲偱偁傝丄旈枾偱傕壗偱傕側偄廃抦偺帠幚偩丅偩偐傜丄嫶壓偑偄傑偝傜恖尃怤奞偩偲庡挘偟偰傕嬝偑捠傜側偄丅
偦傕偦傕嫶壓揙偼丄岞恖偱偁傞埲忋丄偦偺儖乕僣傪捛愓挷嵏偟偰偄偔傜岞昞偝傟傛偆偑暥嬪偼尵偊側偄丅嫶壓杮恖傕惌帯壠偵側傞寛怱傪偟偨帪揰偱丄偦偺偙偲偼妎屽偟偰偄偨偼偢偩丅帠幚丄斵偼乽帺暘偺偡傋偰偑娵棁偵偝傟傞偺偼偄偨偟偐偨側偄偲巚偭偰偄傞乿偲岅偭偰偄傞丅廡姧挬擔偺彂偒曽偼偨偟偐偵偊偘偮側偄偑丄偦偺撪梕偵岆傝偑側偄偐偓傝丄傑偨偦偺弌帺傪旑鎺拞彎偟偰偄傞偺偱側偄偐偓傝丄壗傪彂偐傟傛偆偑抳偟偐偨側偄偺偩丅
嫶壓偑傕偟旐嵎暿晹棊偺弌恎傪柧傜偐偵偝傟偨偙偲傪搟偭偰偄傞偺偩偲偡傟偽丄偦傟偼娫堘偭偰偄傞丅偦傟偼摨榓栤戣傪僞僽乕偵偝偣丄嵎暿傪彆挿偝偣傞偙偲偵偮側偑傞丅斵偼丄嵎暿傗曃尒偲愴偆偨傔丄乽壗偱傕帺桼偵彂偄偰偔傟乿偲尵偆傋偒側偺偩丅斵偑旐嵎暿晹棊偺弌恎偩偲悽娫偑抦偭偰傕丄斵偺恖婥偼棊偪側偐偭偨偱偼側偄偐丅旐嵎暿晹棊弌恎偩偺儎僋僓偺懅巕偩偺偲偄偆偙偲偼丄惌帯壠偲偟偰棫攈側巇帠傪偡傞偙偲偲丄偄偭偝偄娭學偑側偄丅偦傟傪斵偼恎傪傕偭偰徹柧偡傟偽偄偄偺偩丅
廡姧挬擔偺崢嵱偗傇傝傕忣偗側偄丅嵅栰崃堦偼偙偺婰帠偺側偐偱彂偄偰偄傞丅乽僆儗偺恎尦挷嵏傑偱偡傞偺偐丄嫶壓偼偦偆尵偭偰丄帺暘偵恘岦偆傕偺偲尒傞傗丄惗棃偺峌寕揑側杮惈傪傓偒弌偟偵偡傞偐傕偟傟側偄丅偩偑丄偦傟偔偨偄挷傋傜傟傞妎屽偑側偗傟偽丄偦傕偦傕憤棟傪栚巜偡偙偲帺懱丄徫巭愮枩偱偁傞乿丅偙傟偩偗偺堄婥崬傒偱彂偄偰偄傞偺偩偐傜丄暔媍傪偐傕偡偺偼妎屽偺忋偩偭偨偼偢偩丅偲偆偤傫揙掙峈愴偐偲巚偄偒傗丄恊夛幮偺挬擔怴暦偐傜偺埑椡偑偁偭偨偣偄偐偳偆偐暘偐傜側偄偑丄憗乆偲敀婙傪忋偘偰偟傑偭偨丅
寢壥傪尒傟偽丄嫶壓揙偑僷儚乕傪尒偣偮偗偰丄棊偪栚偩偭偨恖婥傪夞暅偝偣偨偙偲偵側傞丅偩偑幚懱偼丄搟傝傑偔偭偰尒摉堘偄偺旕擄傪偟偨嫶壓偺搙検偺掅偝偲丄偁偭偝傝孯栧偵壓偭偨廡姧挬擔偺擃庛傇傝偑柧傜偐偵側偭偨丄側傫偲傕偍慹枛側峌杊寑偩偭偨丅
2012.10.22 (寧) 栰揷惌尃偺枛婜揑徢忬
2030擭傑偱偵尨敪僛儘傪栚巜偡偲岞尵偟側偑傜丄曅曽偱拞抐偟偰偄偨尨敪偺寶愝傪嵞奐偝偣丄暷崙偐傜埑椡偑偐偐偭偰偦偺曽恓傪斀屘偵偡傞丅奊偵昤偄偨傛偆側塕偮偒撪妕偩丅廧柉偺斀懳偵偁偭偰暷崙撪偱偼孭楙傪幚巤偱偒側偄僆僗僾儗僀偺壂撽傊偺攝旛傪丄惌晎偼堎傪彞偊傞偙偲側偔庴偗擖傟傞丅壂撽偱偺旘峴孭楙偵偁偨偭偰偺崌堄側偳偁偭偝傝偲攋傜傟丄暷孯偼廧戭枾廤抧偺忋嬻偱婋尟側憖廲儌乕僪偱孭楙偟偰偄傞偑丄偦傟偵懳偟偰惌晎偼峈媍偡傜偟側偄丅
愲妕栤戣偵娭偟偰丄惌晎偼僶僇偺堦偮妎偊偺傛偆偵椞搚栤戣偼懚嵼偟側偄偲尵偄挘傞偺傒偱丄偄偭偙偆偵拞崙偲奜岎岎徛偟傛偆偲偟側偄丅尦偼偲偄偊偽奜岎偺晄庤嵺偱偙偺栤戣偑婲偙偭偨丅奜岎偺幐攕偼奜岎偱庢傝曉偡偟偐側偄偺偩丅尯梩奜憡偑儓乕儘僢僷傪夞偭偰椞搚栤戣偵懳偡傞擔杮偺棫応傪慽偊偨偑丄偙傫側傕偺偼偨傫側傞帺屓枮懌偵夁偓偢丄摉慠側偑傜壗偺僀儞僷僋僩傕傕偨傜偝側偐偭偨丅偍偦傜偔愲妕栤戣偼栰揷撪妕偑岎戙偟側偄偐偓傝丄慜偵恑傑側偄偩傠偆丅
崙撪惌帯偱偼夝嶶憤慖嫇傪嫲傟偰椪帪崙夛傪奐偙偆偲偣偢丄崙柉偺惗妶偵捈寢偡傞廳梫朄埬偼扞忋偘偺傑傑丄姰慡偵惌憟偺嬶偲壔偟偰偄傞丅奺徣挕偺惻嬥偺柍懯尛偄偑師乆偵柧傞傒偵弌偰傕丄栰搣偼偦傟傪捛媦偱偒側偄丅恔嵭暅嫽旓偼丄偦傟偵摉偰傞偨傔偵憹惻偡傞偲尵偭偰偍偒側偑傜丄娞怱偺旐嵭抧偺暅嫽側偳側偳偦偭偪偺偗偱丄徣挕偺変梸偵傛傝丄暅嫽偲偼娭學側偄旓梡偵梊嶼偑偳傫偳傫巊傢傟偰偄傞丅偙傟偼傕偼傗斊嵾揑偩丅崙柉偼傕偭偲搟傞傋偒偩丅偙傫側懱偨傜偔偱偼徚旓惻偺憹惻偼幮夛曐忈旓偵摉偰傞偲偄偆惌晎偺栺懇傕丄傑偭偨偔怣梡偱偒側偄丅
擼側偟戝恇偳傕偼姱椈偺尵偄側傝偱丄採弌偝傟偨彂椶偵傔偔傜敾傪墴偟偰偄傞丅揷拞朄憡偺峏揜側偳丄偁傑傝偵偍慹枛偡偓偰榖偵傕側傜側偄丅栰揷庱憡偼壗偑偁偭偰傕丄僇僄儖偺柺偵偟傚傫傋傫丄抪偲偄偆奣擮偑傑傞偱側偄傒偨偄偵憤棟偺堉巕偵偟偑傒偮偄偰偄傞丅丅偙傫側偵柍擻側偔偣偵嗦嘞側庱憡偼尒偨偙偲偑側偄丅嵟嬤偺悽榑挷嵏偵傛傞偲丄栰揷撪妕偺巟帩棪偼18亾偵棊偪偨偲偺偙偲偩偑丄傑偩18亾傕偁傞偺偑嬃偒偱偁傝丄10亾埲壓偱偁偭偰傕偍偐偟偔側偄丅帺柉搣偱傕壗偱傕偄偄偐傜丄堦崗傕憗偔惌尃岎戙偟偰偔傟偲尵偄偨偔側傞丅
偙偺忬嫷偵懡彮偼晽寠傪奐偗偰偔傟傞偺偱偼側偄偐偲婜懸偟偰偄偨彫戲堦榊偼丄柉庡搣偐傜棧傟偰怴搣傪寢惉偟偨偑丄巆擮側偙偲偵傑偭偨偔懚嵼姶傪敪婗偟偰偄側偄丅偙偺傑傑昞晳戜偐傜墦偞偐偭偰偟傑偆偺偱偼側偄偐偲偄偆巚偄偡傜書偄偰偟傑偆丅偦傕偦傕彫戲怴搣偺姴帠挿偵搶徦嶰偑側偭偨偲偄偆偙偲偱婜懸偼墦偔偐偡傫偱偟傑偆丅憂壙戝妛弌恎丄岞柧搣傪旂愗傝偵奺搣傪棳傟曕偄偨搶偼丄僸僎側偳惗傗偟偰僇僢僐偮偗偩偗偼堦恖慜偩偑丄償傿僕儑儞傗尒幆偑傑傞偱側偔丄梩姫偲僑儖僼偲嬧嵗偺僋儔僽偑戝岲偒側偩偗偱丄偍傛偦惌帯壠偲偟偰偺枺椡傕幚椡傕奆柍偩丅偙傫側攜偟偐姴帠挿偵悩偊傜傟側偄偲偄偆偲偙傠偵丄彫戲怴搣偺恖嵽晄懌偑業掓偟偰偄傞丅傕偭偲傕丄恖嵽晄懌偼彫戲怴搣偩偗偵偐偓偭偨偙偲偱偼側偄偑丅
偦傟側傜丄嵟嬤偼堦帪傎偳偺惃偄偼側偔丄恖婥傕棊偪偰偒偰偄傞傛偆偩偑丄嫶壓揙偺堐怴偺夛偼偳偆側偺偩傠偆丅偙傟偵偮偄偰偼堐怴敧嶔偺撪梕偲傕偳傕丄師夞偺僐儔儉偱峫嶡偟偨偄丅
2012.09.22 (搚) 婋婡揑側擔拞娭學偵庤傪偙傑偹偔偩偗偺柍擻側栰揷惌尃
 僥儗價偱尒傞偲丄拞崙偱僨儌偵嶲壛偟偰偨傞偺偼丄偦偺傎偲傫偳偑庒幰偩丅斀擔僨儌偼宱嵪敪揥偺壎宐偵偁偢偐傟側偄堦晹偺晄枮暘巕偺烼暜偺偼偗岥偩偲偄偆巜揈偼摉偨偭偰偄傞偩傠偆丅嫸偭偨傛偆偵擔杮惢昳傪攋夡偡傞斵傜傪尒偰偄傞偲丄偙傟偑暥柧敪徦偺抧偺傂偲偮偱偁傝丄榁巕傗憫巕傪丄棝敀傗搈曖傪惗傒弌偟丄枹奐偺擔杮偵媄弍傗暥壔傪揱偊偨拞崙偺偄傑偺巔偐丄偲埫郬偨傞婥帩偪偵側傞丅僨儌偺側偐偵偼栄戲搶偺徰憸傪宖偘偰偄傞幰偑栚棫偭偨丅偨偟偐偵丄偁偺嫸婥偠傒偨岝宨偼丄60擭戙偵嗌嘤傪偒傢傔偨峠塹暫塣摦傪憐婲偝偣傞傕偺偑偁傞丅偄偔傜宱嵪敪揥傪悑偘偰傕丄峀偄崙搚丄朿戝側恖岥丄嬌抂側昻晉偺奿嵎傪偐偐偊傞拞崙偼丄撪惌揑偵偼峧搉傝忬懺側偺偩丅
僥儗價偱尒傞偲丄拞崙偱僨儌偵嶲壛偟偰偨傞偺偼丄偦偺傎偲傫偳偑庒幰偩丅斀擔僨儌偼宱嵪敪揥偺壎宐偵偁偢偐傟側偄堦晹偺晄枮暘巕偺烼暜偺偼偗岥偩偲偄偆巜揈偼摉偨偭偰偄傞偩傠偆丅嫸偭偨傛偆偵擔杮惢昳傪攋夡偡傞斵傜傪尒偰偄傞偲丄偙傟偑暥柧敪徦偺抧偺傂偲偮偱偁傝丄榁巕傗憫巕傪丄棝敀傗搈曖傪惗傒弌偟丄枹奐偺擔杮偵媄弍傗暥壔傪揱偊偨拞崙偺偄傑偺巔偐丄偲埫郬偨傞婥帩偪偵側傞丅僨儌偺側偐偵偼栄戲搶偺徰憸傪宖偘偰偄傞幰偑栚棫偭偨丅偨偟偐偵丄偁偺嫸婥偠傒偨岝宨偼丄60擭戙偵嗌嘤傪偒傢傔偨峠塹暫塣摦傪憐婲偝偣傞傕偺偑偁傞丅偄偔傜宱嵪敪揥傪悑偘偰傕丄峀偄崙搚丄朿戝側恖岥丄嬌抂側昻晉偺奿嵎傪偐偐偊傞拞崙偼丄撪惌揑偵偼峧搉傝忬懺側偺偩丅峳傟嫸偭偨斀擔僨儌傕拞崙惌晎偺掲傔晅偗偵傛傝丄偳偆傗傜廂傑傝偮偮偁傞丅偩偑崱搙偼丄擔杮惢昳偺晄攦塣摦傗桝弌擖庤懕偒偺抶墑丄擔杮婇嬈尰抧岺応偺拞崙恖岺堳偨偪偺僗僩儔僀僉側偳丄拞崙摼堄偺寵偑傜偣愴弍傪梡偄巒傔偨丅拞崙惌晎偼壗傕巜帵偟偰偄側偄偲尵偆偑丄堿偱巺傪堷偄偰偄傞偺偼柧傜偐偩丅僨儌嬛巭椷偑弌偰偐傜朶搆壔僨儌偑傄偨傝偲廂傑偭偨攚宨偵傕丄斀擔僨儌傊偺惌晎偺娭梌偑尒偊塀傟偟偰偄傞丅擔杮偑旐傞宱嵪揑懝幐偼懡妟偵偺傏傞偱偁傠偆偑丄偍屳偄偵宱嵪傪埶懚偟崌偭偰偄傞尰忬偐傜偟偰丄偙傟偼椉恘偺寱偱偁傝丄拞崙懁傕懪寕傪庴偗傞偙偲偵側傞丅拞崙傕偳偙偐偺帪揰偱枊傪堷偙偆偲棊偲偟偳偙傠傪扵偭偰偄傞偺偼娫堘偄側偄丅
埲慜丄愇尨怲懢榊搒抦帠偑摼堄偘偵乽愲妕彅搰傪搒偑攦偄忋偘傞乿偲傇偪忋偘偨偲偒丄扥塇慜挀拞崙戝巊偼乽愇尨搒抦帠偺愲妕峸擖傪嫋偣偽擔拞娭學偵廳戝側婋婡傪傕偨傜偡偙偲偵側傞乿偲寈崘傪敪偟偰栤戣偵側傝丄偙偺敪尵偵傛偭偰戝巊偺怑傪峏揜偝傟傞偙偲偵側偭偨丅摉帪傏偔偼丄偙傟偼偟偛偔恀偭摉側敪尵偱偁傝丄偙傟偺偳偙偑栤戣側傫偩丄偲媈栤偵巚偭偨傕偺偩丅偄傑偵側偭偰丄扥塇慜戝巊偺梊應偺惓偟偝偑徹柧偝傟丄奜柋徣偼愒抪傪偝傜偟偨偙偲偵側傞丅
儊僨傿傾偼壗傕尵傢側偄偑丄偙偺傛偆側帠懺偵帄偭偨偦傕偦傕偺尨場偑丄愇尨怲懢榊偺愲妕峸擖敪尵偵偁偭偨偙偲偼妋偐偩丅愇尨偺僗僞儞僪僾儗乕偑偙偺傛偆側婋婡揑側擔拞杸嶤傪堷偒婲偙偟偨丅偦偺愇尨偼丄帺暘偺愑擟偼偦偭偪偺偗偱丄惌晎偺庛崢傪斸敾偟偨傝丄拞崙偺斀敪傪偁偍傞傛偆側尵摦傪孞傝曉偟偰偄傞丅偦傟側偺偵儊僨傿傾傕惌晎傕愇尨偺愑擟傪捛媦偟側偄丅帺崙傪垽偡傞傕偺偼懠崙傕懜廳偟側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偑恀偺垽崙幰偩丅壈昦側恖娫偼帺暘偺晐偑傝傪塀偡偨傔偵丄偮偹偵嫃忎崅偵傆傞傑偆丅懠崙傪曁帇偡傞愇尨偼丄帡旕垽崙幰偱偁傝丄戝廜愵摦壠偱偁傝丄抪偢傋偒斱楎娍偩丅
偦偟偰丄摉慠側偑傜崙偺奜岎傪偮偐偝偳傞栰揷撪妕偵傕戝偒側愑擟偑偁傞丅愲妕傪崙桳壔偟偨偺偼惓偟偄敾抐偩偭偨偲偟偰傕丄壥偨偟偰崙桳壔偺堄恾傪惓偟偔拞崙偵揱偊偰偄偨偺偩傠偆偐丅嶳岥奜柋暃戝恇偑乽奜憡傗庱憡偑崙桳壔偺庯巪傪廫暘愢柧偟側偐偭偨偺偼傑偢偐偭偨乿偲傕傜偟偰偄傞偙偲偐傜偟偰丄傎偲傫偳壗傕愢柧偟偰偄側偐偭偨偺偩傠偆丅偩偐傜拞崙偐傜乽愇尨搒抦帠偲栰揷惌尃偑嬝彂偒傪昤偄偨弌棃儗乕僗偩乿側偳偲姩孞傜傟傞偙偲偵側傞丅偙傟偼柧傜偐偵奜岎偺幐攕偩丅栰揷惌尃偺奜岎擻椡偼僛儘偵摍偟偄丅
偙偺擔拞娭學偺婋婡偼丄堦崗傕憗偔懪奐偟側偗傟偽側傜側偄偺偵丄栰揷庱憡偼戙昞慖偲偄偆拑斣寑偵偆偮偮傪偸偐偟偨傝丄壗偺堄枴傕側偄崙楢憤夛偵弌惾偟偨傝偟偰丄傑偭偨偔庤傪懪偲偆偲偟側偄丅杮棃側傜庱憡側傝奜憡側傝偑帺傜拞崙偵晪偄偰榖偟崌傢側偗傟偽側傜側偄帠懺偩偑丄擔杮偐傜偦傟傪帩偪偐偗偰傕拞崙庱擼偼偡偖偵偼夛偍偆偲偟側偄偩傠偆丅偦傟側傜丄拞崙偲鉐偺怺偄惌帯壠丄偨偲偊偽揷拞恀婭巕偲偐彫戲堦榊偲偐傪摿巊偲偟偰攈尛偡傟偽偄偄偱偼側偄偐丅偄傑偼惌揋偑偳偆偺丄柺巕偑偳偆偺偲尵偭偰偄傞応崌偱偼側偄丅柍堊柍嶔丄庤傪偙傑偹偄偰偄傞偩偗偺栰揷惌尃偵丄惌尃偺扴偄庤偲偟偰偺帒奿偼側偄丅
2012.09.10 (寧) 亀壴偐偘亁 偦偺2
偙偺嬋傪丄報徾揑側僀儞僩儘偱巒傑傞奀徖泬偺曇嬋傪梡偄偰弶傔偰榐壒偟偨偺偼丄彮彈壧庤帪戙偺愳揷惓巕偩偭偨傛偆偩丅儗僐乕僪偼愴屻傑傕側偔偺崰偵敪攧偝傟偨偲悇掕偝傟傞丅30昩慜屻偵傕媦傇斾妑揑挿偄僀儞僩儘偑丄偠偮偵枴傢偄怺偄丅偄傑偱偼偙偺奀徖泬斉偑乽壴偐偘乿偺掕斣傾儗儞僕偵側偭偰偄傞丅偍偦傜偔丄偙偺愳揷惓巕偺儗僐乕僪偵傛偭偰乽壴偐偘乿偼峀偔晛媦偡傞傛偆偵側偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅
 嶌帉偺戝懞庡寁乮偐偢偊乯偼柧帯37擭惗傑傟丄嶳棞導恴朘懞弌恎偺摱梬帊恖偱偁傞丅惗傑傟屘嫿偵偁傞岦妜帥偼嶗偺柤強偱丄偦偙偵偼乽壴偐偘乿偺帊旇偑寶棫偝傟偰偍傝丄亀梒偄帪偵丄岦妜帥偺嶗悂愥偺壓傪恖椡幵偵備傜傟偰椬懞偵壟偄偱備偔巓偺壴壟巔傪尒憲偭偨戝懞庡寁偑丄偦偺巚偄弌傪塺傫偩偺偑丄偙偺乽壴偐偘乿偱偡亁偲偄偆庯巪偺愢柧偑晅偝傟偰偄傞偲偄偆丅
嶌帉偺戝懞庡寁乮偐偢偊乯偼柧帯37擭惗傑傟丄嶳棞導恴朘懞弌恎偺摱梬帊恖偱偁傞丅惗傑傟屘嫿偵偁傞岦妜帥偼嶗偺柤強偱丄偦偙偵偼乽壴偐偘乿偺帊旇偑寶棫偝傟偰偍傝丄亀梒偄帪偵丄岦妜帥偺嶗悂愥偺壓傪恖椡幵偵備傜傟偰椬懞偵壟偄偱備偔巓偺壴壟巔傪尒憲偭偨戝懞庡寁偑丄偦偺巚偄弌傪塺傫偩偺偑丄偙偺乽壴偐偘乿偱偡亁偲偄偆庯巪偺愢柧偑晅偝傟偰偄傞偲偄偆丅摱梬尋媶壠丄愇揷彫昐崌巵偑彂偄偨亀側偭偲偔摱梬丒彞壧亁偺乽壴偐偘乿偺崁傪撉傓偲丄戝嬝偼偦偺偲偍傝偩偑丄庡寁偑偦傟傪宱尡偟偨偺偼丄斵偑梒偄偙傠偱偼側偔丄堄奜偵傕20嵨偺偲偒偩偭偨傜偟偄丅壟偵偄偭偨巓偼傞傦偺夞憐偵傛傞偲丄3嵨堘偄偺掜丄庡寁偲偼彫偝偄偙傠偐傜偲偰傕拠偑椙偔丄枅擔丄2恖偱彫妛峑偵搊壓峑偟丄偄偮傕堦弿偵曌嫮傗梀傃傪偟偰偄偨偲偄偆丅乽壟擖傝偺擔丄庡寁偼丄巹偲棧傟傞偺偑寵偩偲尵偭偰丄壠偺戝崟拰偵偮偐傑傝戝棻偺椳傪棳偟偰偄傑偟偨丅偄偔傜側偩傔偰傕媰偒傗傒傑偣傫偱偟偨乿
20嵨偺戝恖偑巓偺壟擖傝偺偲偒丄斶偟偔偰媰偒偠傖偔偭偨偺偩丅偍偦傜偔戝懞庡寁偼偲偰傕姶庴惈偺嫮偄丄弮悎側恖偩偭偨偺偩傠偆丅斵偺帊偼丄堦斒揑偵偼乽壴偐偘乿偲乽奊擔嶱乿埲奜偼抦傜傟偰偄側偄丅偩偐傜丄斵偼慇嵶側帊恖偲偟偰塭偺敄偄恖惗傪憲偭偨偺偩傠偆偲彑庤偵憐憸偟偰偄偨偑丄幚嵺偼偦偆偱偼側偐偭偨丅戝懞庡寁偼丄愴屻丄怴暦婰幰偵側傝丄僗億乕僣僞僀儉僘偺曇廤嬊挿傗幮挿傪楌擟偡傞偄偭傐偆丄壒妝挊嶌尃嫤夛偺棟帠傗擔杮摱梬嫤夛偺暃夛挿傪柋傔偨傝偟偰偄傞丅
愴屻偺宱楌傪尒傞偲丄戝懞庡寁偼價僕僱僗姶妎偵偡偖傟偨丄儕乕僟乕僔僢僾偺偁傞恖暔偩偭偨偲巚傢傟傞丅乽壴偐偘乿偺壧帉偐傜庴偗傞僀儊乕僕偲尰幚偲偺僊儍僢僾偵嬃偐偝傟傞丅傎傫偺彮偟偩偑丄20嵨偱帊嶌傪傗傔丄埲屻偼晲婍彜恖偲側偭偰傾僼儕僇傪曻楺偟偨僼儔儞僗偺帊恖儔儞儃乕傪巚偄婲偙偟偨丅
2012.09.09 (擔) 亀壴偐偘亁 偦偺1
乽壴偐偘乿偲偄偆嬋偺慺惏傜偟偝傪嵞擣幆偟偨偺偼丄乬僄儉僘偺曅妱傟乭偲偄偆僽儘僌偵傛偭偰偩偭偨丅偨傑偨傑丄偙偺僽儘僌偱徯夘偝傟偰偄傞乽壴偐偘乿偺壒傪挳偒丄嬋偺惉棫夁掱傪抦偭偰丄偙偺嬋偺枺椡偵偼傑偭偰偟傑偭偨丅乽壴偐偘乿偼丄偄偮丄偳偙偱偩偭偨偐偼婰壇偵側偄偑丄偨偟偐偵巕嫙偺偙傠偵挳偄偨偙偲偑偁傞丅偍偦傜偔丄傏偔偲摨悽戙偺懡偔偺曽傕偦偆偱偁傠偆丅偙傫側嬋偩乮"壴偐偘 by 埨揷復巕 at YouTube乯丅
乽壴偐偘乿偺嶌幰偼丄嶌帉丒戝懞庡寁乮偐偢偊乯丄嶌嬋丒朙揷媊堦丅嬋偑嶌傜傟偨偺偼徍榓7擭偱偁傝丄摨擭丄儗僐乕僪壔偝傟偨丅偙傫側壧帉偩丅
 丂丂丂丂廫屲栭偍寧偝傑丂傂偲傝傏偪
丂丂丂丂廫屲栭偍寧偝傑丂傂偲傝傏偪丂丂丂丂嶗悂愥偺丂壴偐偘偵
丂丂丂丂壴壟巔偺丂偍巓偝傑
丂丂丂丂樲偵備傜傟偰丂峴偒傑偟偨
丂丂丂丂廫屲栭偍寧偝傑丂尒偰偨偱偟傚偆
丂丂丂丂嶗悂愥偺丂壴偐偘偵
丂丂丂丂壴壟巔偺丂巓偝傑偲
丂丂丂丂偍暿傟惿偟傫偱丂媰偒傑偟偨
丂丂丂丂廫屲栭偍寧偝傑丂傂偲傝傏偪
丂丂丂丂嶗悂愥偺丂壴偐偘偵
丂丂丂丂墦偄偍棦偺丂偍巓偝傑
丂丂丂丂巹偼傂偲傝偵丂側傝傑偟偨
偼傜偼傜偲壴嶶傞枮奐偺嶗暲栘丄恖椡幵偵梙傜傟偰壟偵峴偔暥嬥崅搰揷偺巓丄嬻偵偼傐偭偐傝廫屲栭偍寧偝傑丅旤偟偄僀儊乕僕傪姭婲偡傞丄漅忣枴偁傆傟傞壧帉偩丅嶌帉偺戝懞庡寁偼丄梒偄偙傠偺巚偄弌傪傕偲偵偟偰偙偺帊傪彂偄偨偲偄偆丅側傫偲傕偄偊側偄嫿廌偲垼姶傪桿偆儊儘僨傿傕傑偨慺惏傜偟偄丅嶌帉偺戝懞庡寁傕嶌嬋偺朙揷媊堦傕偙偺乽壴偐偘乿偲丄摨帪偵儗僐乕僪壔偝傟偨乽奊擔嶱乿偩偗偑桳柤偱偁傝丄偙偺2嬋埲奜偵偼丄偙傟偲偄偭偨恖岥偵鋂鄑偝傟傞嶌昳偼巆偟偰偄側偄丅
偙偺嬋偑徍榓7擭偵億儕僪乕儖偱儗僐乕僪壔偝傟偨偲偒丄乽壴偐偘乿偼B柺偱偁傝丄A柺偼丄摨偠戝懞丒朙揷偺嶌帉丒嶌嬋僐儞價偵傛傞乽奊擔嶱乿偩偭偨丅嵟弶偵乽奊擔嶱乿傪榐壒偡傞偙偲偵側傝丄B柺偑側偄偲崲傞偲偄偆偙偲偱丄偙偺2恖偑媫偒傚嶌偭偨偺偑乽壴偐偘乿偩偭偨丅彮彈壧庤丄塱壀巙捗巕偑壧偭偨偙偺弶墘儗僐乕僪傪挳偔偲丄偵偓傗偐側墘憈傪僶僢僋偵偟偨壺傗偐側乽奊擔嶱乿偵斾傋偰丄乽壴偐偘乿偼庘偟偘偱抧枴側報徾傪庴偗傞丅偟偐偟丄乽奊擔嶱乿傕擔杮忣弿偵晉傫偩偄偄嬋偩偑丄擔杮恖偺垼挷傪懷傃偨嬋岲傒傪斀塮偟偰偐丄挿偄擭寧傪摼偨偄傑偱偼乽壴偐偘乿偺傎偆偑埑搢揑偵恖婥偑崅偄丅
乽壴偐偘乿偺枺椡偵庝偐傟偰丄偄傠傫側壧庤偑壧偭偨儗僐乕僪傪扵偟廤傔偨丅偄傑庤尦偵偼18庬椶偺償傽乕僕儑儞偑偁傞丅弶墘偺塱壀巙捗巕丄愳揷惓巕丄敽媣旤巕偲偄偭偨彮彈壧庤傗丄埨揷復巕乮桼婭偝偍傝乯丄屆夑偝偲巕側偳偺摱梬壧庤丄搰揷桾巕丄嶭搰桳旤巕側偳偺僜僾儔僲壧庤傪偼偠傔丄嶳嶈僴僐丄愇愳偝備傝丄墍傑傝偲偄偭偨壧梬嬋宯壧庤傗丄傾僀僔儍側傫偰偄偆儅儗乕僔傾偺壧庤偑壧偭偨傕偺傑偱偁傞丅
偦傫側側偐偱丄偄偪偽傫怱庝偐傟傞偺偼丄乬僄儉僘偺曅妱傟乭巵偲摨偠偔丄墫栰夒巕偲偄偆壧庤偑壧偭偨償傽乕僕儑儞偩丅悙乆偟偝傪偨偨偊偨旤偟偄壧彞偑怱偵偟傒傞丅埨揷復巕偺壧傕慺捈偱偄偄偟丄搰揷桾巕偺梷偊偨壧傕埆偔側偄丅偦傟傜偵斾傋偰丄嶭搰桳旤巕偼丄僆儁儔晽偺媄岻傪慜柺偵弌偟偡偓偱丄傕偆傂偲偮怱偵嬁偐側偄丅壧梬嬋宯偱偼丄愇愳偝備傝偺偙傇偟傪棙偐偣偨壧偼嬻夞傝偟偰偄傞偟丄墍傑傝傗嬟梞巕偺偹偪偭偙偄壧偼婥怓埆偄丅偙偆偄偭偨嬋偼丄惡妝壠偑楴乆偲壧偆偺傕壗偐偟偭偔傝偙側偄偟丄壧梬嬋壧庤偑僗儔乕傪偐偗偰壧偆偺傕晄婥枴偩丅梋寁側憰忺傪巤偝偢丄傂偨偡傜抂惓偵丄僋儕乕儞偵壧偆偺偑丄偄偪偽傫帡崌偭偰偄傞丅
2012.08.31 (嬥) 僆僗僾儗僀攝旛斀懳塣摦偼側偤惙傝忋偑傜側偄偺偐
斀尨敪偺摦偒偑崅傑傞偄偭傐偆偱丄壂撽暷孯婎抧傊偺僆僗僾儗僀攝旛傪慾巭偟傛偆偲偄偆婥塣偑惙傝忋偑傜側偄偺偼側偤偩傠偆偐丅偙偲偼壂撽偩偗偺栤戣偵偲偳傑傜側偄丅壂撽偵攝旛偝傟傞慜偵丄僆僗僾儗僀偼丄孭楙旘峴偺偨傔嫹偄擔杮慡崙偺嬻傪掅嬻偱旘傃夞傞丅偦偟偰壂撽偵攝旛偝傟偨傜丄偁偺廧戭傗妛峑偑枾廤偟偰偄傞晛揤娫旘峴応傪棧拝棨偡傞偺偩丅
 偁傑傝偺帠屘偺懡偝偐傜丄暷崙僞僀儉帍偼僆僗僾儗僀傪乽嬻旘傇抪 (Flying Shame)乿偲屇傫偩丅僆僗僾儗僀偺懡敪偡傞帠屘偺尨場偼壗側偺偐丅愝寁偵実傢偭偨暷崙恖媄巘偵傛傞乽婡懱偵峔憿揑側寚娮偑偁傞乿偲偄偆徹尵傕偁傞丅偩偑暷孯偲擔杮偺杊塹徣偼婡懱偺寚娮偱偼側偔憖廲儈僗偲偄偆偙偲偱攝旛傪墴偟愗傠偆偲偟偰偄傞丅偐傝偵憖廲儈僗偑尨場偩偭偨偲偟偰傕丄偦傟偱埨慡偩側偳偲尵偊傞偼偢偑側偄丅憖廲儈僗偑懡敪偡傞偲偄偆偙偲偼丄偦傟偩偗憖廲偑擄偟偄偲偄偆偙偲偱偁傝丄崱屻傕帠屘偑婲偙傞壜擻惈偑崅偄偐傜偩丅
偁傑傝偺帠屘偺懡偝偐傜丄暷崙僞僀儉帍偼僆僗僾儗僀傪乽嬻旘傇抪 (Flying Shame)乿偲屇傫偩丅僆僗僾儗僀偺懡敪偡傞帠屘偺尨場偼壗側偺偐丅愝寁偵実傢偭偨暷崙恖媄巘偵傛傞乽婡懱偵峔憿揑側寚娮偑偁傞乿偲偄偆徹尵傕偁傞丅偩偑暷孯偲擔杮偺杊塹徣偼婡懱偺寚娮偱偼側偔憖廲儈僗偲偄偆偙偲偱攝旛傪墴偟愗傠偆偲偟偰偄傞丅偐傝偵憖廲儈僗偑尨場偩偭偨偲偟偰傕丄偦傟偱埨慡偩側偳偲尵偊傞偼偢偑側偄丅憖廲儈僗偑懡敪偡傞偲偄偆偙偲偼丄偦傟偩偗憖廲偑擄偟偄偲偄偆偙偲偱偁傝丄崱屻傕帠屘偑婲偙傞壜擻惈偑崅偄偐傜偩丅惌晎偼埨曐忦栺偺帠慜嫤媍偺懳徾奜偩偐傜偲偄偆摝偘岥忋傪巊偭偰偄傞偑丄懳徾撪偱偁傟懳徾奜偱偁傟丄擔杮偺崙搚偲崙柉傪婋尟偵偝傜偡壜擻惈偺偁傞偙偲側傜丄巭傔偰偔傟偲偄偆偺偑摉慠偱偁傠偆丅偍偦傜偔暷孯偲杊塹徣偺偁偄偩偵偼丄帠慜偵側傫傜偐偺傗傝偲傝偼偁偭偨偲巚偆丅偟偐偟杊塹徣偼懳徾奜偲偄偆偙偲偱堦廟偝傟偰偟傑偭偨偺偩傠偆丅帠幚忋丄擔杮偼偄傑偩偵暷崙偺愯椞壓偵偁傞偺偩丅
暦偔偲偙傠偵傛傞偲丄杮崙傾儊儕僇偱偼丄僯儏乕儊僉僔僐廈丄僴儚僀廈側偳偱丄廧柉偺斀懳塣摦偵傛傝丄僆僗僾儗僀偺旘峴孭楙偑拞巭傗墑婜偵側偭偰偄傞偲偄偆丅帺暘偺崙偱偼抐擮偟偨傕偺傪懠崙偵栤摎柍梡偱墴偟晅偗傞丄偦傫側偙偲偑嫋偝傟偰偄偄偺偐丅帺崙偱偼偱偒側偄偙偲傪擔杮偵嫮梫偡傞丄偦傫側巔惃偵偼丄擔杮偵尨敋傪搳壓偟偨偙偲偲摨偠傛偆側丄傾儊儕僇偲偄偆崙偺閬傝偲傾僕傾傊偺曁帇傪姶偠傞丅
栰揷惌尃偼丄椞搚栤戣偱偼拞崙傗娯崙偵懳偟偰婤慠偲偟偨懺搙偱椪傓偲尵偭偰偄傞偑丄擔杮偺忋嬻傪婋尟側戙暔偑旘傃夞傝丄廧柉偵旐奞偑媦傃偐偹側偄偲偄偆丄傑偝偵擔杮偺庡尃偑怤偝傟傞帠懺偵懳偟偰丄暷崙偵偼壗傕堎榑傪彞偊傞偙偲偑偱偒偢丄尵偄側傝偺傑傑偩丅儊僨傿傾傕偦傟傪屻墴偟偟偰偄傞丅僆僗僾儗僀斀懳偺摦偒偑惙傝忋偑傜側偄攚宨偺傂偲偮偵偼丄儊僨傿傾偺斀墳偺撦偝偑偁傞丅戝庤怴暦偱偼僆僗僾儗僀偺婋尟惈偵偮偄偰怽偟栿掱搙偵彫偝側婰帠偱偟偐嵹傜側偄偺偵丄憖廲儈僗偑尨場偩偐傜埨慡偩偲偡傞暷崙偺挷嵏曬崘傪戝偒偔婰帠偵偡傞丅傑偝偵暷崙傗擔杮惌晎偺堄岦偦偺傑傑偺曬摴傇傝偩丅
偙偺傑傑偄偗偽丄僆僗僾儗僀偼崱擭10寧偐傜壂撽偵攝旛偝傟傞丅偩偑丄僆僗僾儗僀斀懳偺婥塣偑崅傑傝丄壂撽偩偗偱側偔慡崙偵斀懳塣摦偑峀偑傟偽丄暷崙傕攝旛寁夋傪尒捈偝偞傞傪偊側偔側傞丅扙尨敪偺師偼斀僆僗僾儗僀偩丅塣摦偺崅傑傝偵婜懸偟偨偄丅
2012.08.22 (壩) 椞搚栤戣偲擔杮偺偲傞傋偒摴
偙偺傛偆側偲偒丄昁偢垽崙怱傪傆傝偐偞偟丄擔杮偼擃庛偩丄捈愙峴摦傪偲傟側偳偲慀傝棫偰傞攜偑弌偰偔傞丅尃椡朣幰偺嶰棳惌帯壠丄愇尨怲懢榊側偳丄偦偺揟宆偩丅偘傫偵偦偺屻丄愲妕偵忋棨偟偨擔杮偺僶僇偳傕偑偄偨丅18悽婭偺僀僊儕僗偺巚憐壠偑乽垽崙怱偼側傜偢幰偺嵟屻偺嫆傝強乿偲尵偭偨傛偆偵丄傗偨傜偵垽崙怱傪嬱傝棫偰傞偺偑嵟埆偺嬸嶔偱偁傞偙偲偼丄楌巎偑徹柧偟偰偄傞丅娯崙戝摑椞偑抾搰偵忋棨偟偨偺偼丄垽崙怱傪偁偍傝丄幐捘偟偨巟帩傪夞暅偡傞偨傔偺庤抜偩偭偨偙偲偼柧敀偱偁傝丄悽奅偺暔徫偄偺揑偵側偭偨丅偦傟偲摨偠換傪擔杮偑摜傓偙偲傎偳嬸偐側偙偲偼側偄丅
椞搚偵娭偡傞暣憟偼栵夘側栤戣偩丅憃曽偺崙偑偳偪傜傕庡挘傪忳傜偢丄偳偆偟傛偆傕側偔暯峴慄傪偨偳傞丅嵟廔揑側夝寛偼丄晲椡徴撍亖愴憟偵傛偭偰偟偐側偟偊側偄丅偩偑丄愴憟偼夞旔偟側偗傟偽側傜側偄丅偱偼丄擔杮偼壗傪偡傋偒偐丅婤慠偲偟偨懺搙傪偲傞傋偒偙偲偼摉慠偩丅懳娯崙偱尵偊偽丄抾搰栤戣傪崙嵺巌朄嵸敾強偵採慽偟偨傝丄娯崙傊偺嬥梈墖彆傪懪偪愗傞側偳偲偄偆峫偊傪偪傜偮偐偣傞偺傕偄偄偩傠偆丅偩偑丄偦偆偄偭偨嫮柺偺僇乕僪傪巊偆偺偲摨帪偵丄悈柺壓偱偼悐庛偟偨奜岎傪惓偟偔婡擻偝偣丄偁傜備傞儖乕僩傪捠偟偰丄偍屳偄傊偺棟夝偲怣棅傪媮傔丄桭岲娭學傪抸偒忋偘側偗傟偽側傜側偄丅
柉庡搣惌尃偼傾僕傾偵岦偗傞栚慄偑傑偭偨偔寚偗偰偄偨丅數嶳尦庱憡偼廇擟憗乆丄搶傾僕傾嫟摨懱峔憐傪傇偪忋偘偨偑丄壂撽栤戣偱偮傑偢偒丄傾儊儕僇偺巚榝偑傜傒偱庱憡偺嵗傪堷偒偢傝偍傠偝傟丄埲棃丄懳傾僕傾奜岎偼偍傠偦偐偵側偭偰偄偨丅傾儊儕僇偼丄擔杮偑拞崙丄娯崙偲桭岲側娭學傪曐偪丄傾僕傾偑堦懱壔偟偰嫟摨曕挷傪偲傞偺傪嫲傟偰偄傞丅偩偐傜丄杒曽椞搚丄抾搰丄愲妕彅搰偵娭偟偰偼丄変娭偣偢偺棫応傪偲傝丄暣憟偺壩庬傪偁偊偰壏懚偟偰偒偨丅崱夞偺帠懺傪傾儊儕僇偼傎偔偦徫傫偱偄傞偩傠偆丅偐傝偵愲妕栤戣偱擔杮偲拞崙偺偁偄偩偵晲椡徴撍偑婲偙偭偨偲偟偰傕丄埨曐忦栺偑偁傞偐傜偲偄偭偰傾儊儕僇偑擔杮偺偨傔偵愴偆傢偗偑側偄丅懠崙偺偨傔偵帺崙偺暫巑偺寣傪棳偡偙偲傪丄偁偺庤慜彑庤側傾儊儕僇偑擣傔傞偼偢偑側偄丅
偙傟傑偱擔杮偼奜岎偺晳戜偵偍偄偰丄傑偭偨偔懚嵼姶傪敪婗偟偰偙側偐偭偨丅傾儊儕僇偺帞偄將傕摨慠偺擔杮偺尵偆偙偲側偳丄宱嵪戝崙偺偙傠側傜側傜傑偩偟傕丄崙椡偑棊偪偨偄傑丄偳偙偐傜傕憡庤偵偝傟側偄偺偼摉慠偩丅偝傜偵丄堦晹偺婃柪側惌帯壠偑偄傑偩偵夁嫀偺擔杮偺傾僕傾傊偺怤棯傪惓摉壔偡傞傛偆側敪尵傪偡傞偨傔丄傾僕傾偺奺崙偼偄傑傕擔杮偵寈夲怱傪傕偭偰偄傞丅擔杮偑偄傑丄側偡傋偒偙偲偼丄僪僀僣傪尒廗偭偰夁嫀傪姰慡偵惔嶼偟丄傾儊儕僇傊偺楆懏丒埶懚忬懺偐傜扙媝偡傞偙偲偩丅偦偟偰寷朄9忦傪偐偐偘偰慜柺偵懪偪弌偟丄傾僕傾偵岦偗偰撈帺偺暯榓奜岎傪揥奐偟丄嬞枾側僷乕僩僫乕僔僢僾傪抸偐側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偙偦偑嵟崅偺崙杊嶔偵側傞偺偩丅
偄傑偺柉庡搣惌尃偵丄偦傫側峀偄帇栰偵棫偭偨奜岎偑偱偒傞偺偐丄帺屓曐恎偵媯乆偲偟偰偄傞庛懱壔偟偨奜柋徣偵偦傟偑偱偒傞偺偐丄傾儊儕僇偑偦傟傪嫋偡偺偐丄栤戣偼偨偔偝傫偁傞丅彮側偔偲傕丄偄傑傗巰偵懱偲側偭偨栰揷庱憡丄奜柋徣偺孞傝恖宍偺尯梩奜憡偱偼壗傕偱偒側偄偙偲偼柧敀偩丅偩偑丄偦偺曽岦傪栚巜偡埲奜丄擔杮偺惗偒巆傞摴偼側偄丅
2012.07.31 (壩) 媣偟傇傝偵偡偖傟偨朻尟彫愢偺彂偒庤偑搊応偟偨
 戞1嶌亀扙弌嶳柆亁乮僴儎僇儚暥屔乯偺報徾偼慛楏偩偭偨丅僷乕僗儞偼峲嬻巑偲偟偰峲嬻婡偵忔傝崬傒丄暫巑傗暔帒偺桝憲偵偁偨偭偰偄傞丅偁傞擔丄斵偑忔偭偨曔椄傪斃憲偡傞桝憲婡偑傾僼僈儞嶳拞偱僞儕僶儞暫偺寕偭偨儈僒僀儖偵寎寕偝傟偰晄帪拝偡傞丅偐傜偔傕惗偒墑傃偨僷乕僗儞偼丄摨忔偟偰偄偨僑乕儖僪孯憘偲偲傕偵丄尒抦傜偸愥嶳偺側偐偱敆傝偔傞斀惌晎僎儕儔偲愴偄側偑傜丄暷孯婎抧傪傔偞偟偰寛巰偺僒僶僀僶儖峴傪偡傞丄偲偄偆撪梕偩丅僽儕僓乕僪偑峳傟嫸偆崜姦偺僸儞僘乕僋僔嶳柆偱孞傝峀偘傜傟傞揋晹戉偲偺捛偄偮捛傢傟偮偺峌杊丄恖幙偵偝傟偨僑乕儖僪孯憘傪扗娨偡傞偨傔幪偰恎偱揋抧偵忔傝崬傓僷乕僗儞彮嵅偺愴偄偼丄撉傫偱偄偰嫻偑擬偔側傞丅
戞1嶌亀扙弌嶳柆亁乮僴儎僇儚暥屔乯偺報徾偼慛楏偩偭偨丅僷乕僗儞偼峲嬻巑偲偟偰峲嬻婡偵忔傝崬傒丄暫巑傗暔帒偺桝憲偵偁偨偭偰偄傞丅偁傞擔丄斵偑忔偭偨曔椄傪斃憲偡傞桝憲婡偑傾僼僈儞嶳拞偱僞儕僶儞暫偺寕偭偨儈僒僀儖偵寎寕偝傟偰晄帪拝偡傞丅偐傜偔傕惗偒墑傃偨僷乕僗儞偼丄摨忔偟偰偄偨僑乕儖僪孯憘偲偲傕偵丄尒抦傜偸愥嶳偺側偐偱敆傝偔傞斀惌晎僎儕儔偲愴偄側偑傜丄暷孯婎抧傪傔偞偟偰寛巰偺僒僶僀僶儖峴傪偡傞丄偲偄偆撪梕偩丅僽儕僓乕僪偑峳傟嫸偆崜姦偺僸儞僘乕僋僔嶳柆偱孞傝峀偘傜傟傞揋晹戉偲偺捛偄偮捛傢傟偮偺峌杊丄恖幙偵偝傟偨僑乕儖僪孯憘傪扗娨偡傞偨傔幪偰恎偱揋抧偵忔傝崬傓僷乕僗儞彮嵅偺愴偄偼丄撉傫偱偄偰嫻偑擬偔側傞丅偙傟偼傾儕僗僥傾丒儅僋儕乕儞傗僨僘儌儞僪丒僶僋儕乕傪渇渋偲偝偣傞丄偄傑偳偒捒偟偄惓摑攈偺朻尟彫愢偩偭偨丅栆埿傪傆傞偆夁崜側戝帺慠丄埆鐓偱嗦嘞側斀惌晎僎儕儔偺儕乕僟乕偲丄偍慥棫偰偼枩慡偵惍偊傜傟偰偄傞丅庡恖岞偨偪偺崲擄偵懪偪彑偮晄孅偺摤巙丄暫巑偲偟偰偺屩傝偲婥奣偑丄偁傑偡偲偙傠側偔昤偐傟偰偍傝丄撉傒偛偨偊偼敳孮偩丅僗僩乕儕乕偺揥奐偑傗傗椶宆揑偩偟丄恖暔憿宆傕懡彮慹嶍傝側偲偙傠偑偁傞丅偩偑丄偙偙傑偱僗儕儖偲傾僋僔儑儞偑崿慠堦懱偲側偭偨撪梕偵巇忋偑偭偰偄傟偽丄偦傫側晄枮偼悂偒旘傫偱偟傑偆丅
 崱擭弌偨戞2嶌亀扙弌嬻堟亁乮僴儎僇儚暥屔乯偼丄偦傟偐傜4擭屻偲偄偆愝掕丅僷乕僗儞偼旘峴巑偵側傝丄婡挿偲偟偰桝憲婡傪憖廲偟偰偍傝丄僑乕儖僪偼憘挿偵徃恑偟偰偄傞丅2恖偼敋抏僥儘偱晧彎偟偨暫巑傪僪僀僣偵塣傇偨傔傾僼僈僯僗僞儞傪旘傃棫偮偑丄僞儕僶儞偺僥儘儕僗僩偑旘峴婡偵敋抏傪巇妡偗偨偲偺忣曬偑擖傞丅崅搙偑壓偑傞偲敋敪偡傞巇妡偗偵側偭偰偄傞傜偟偄丅僷乕僗儞偼僑乕儖僪傗忔慻堳偲偲傕偵丄婔懡偺崲擄傗忈奞偵憳嬾偟側偑傜傕丄惗娨傪栚巜偟偰昁巰偺旘峴傪懕偗傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅彫愢偺晳戜偼傎偲傫偳旘峴婡偺側偐偩偗偩丅500儁乕僕嬤偄暘検偺嵟弶偐傜嵟屻傑偱丄旘峴婡偼傂偨偡傜旘傃懕偗傞丅
崱擭弌偨戞2嶌亀扙弌嬻堟亁乮僴儎僇儚暥屔乯偼丄偦傟偐傜4擭屻偲偄偆愝掕丅僷乕僗儞偼旘峴巑偵側傝丄婡挿偲偟偰桝憲婡傪憖廲偟偰偍傝丄僑乕儖僪偼憘挿偵徃恑偟偰偄傞丅2恖偼敋抏僥儘偱晧彎偟偨暫巑傪僪僀僣偵塣傇偨傔傾僼僈僯僗僞儞傪旘傃棫偮偑丄僞儕僶儞偺僥儘儕僗僩偑旘峴婡偵敋抏傪巇妡偗偨偲偺忣曬偑擖傞丅崅搙偑壓偑傞偲敋敪偡傞巇妡偗偵側偭偰偄傞傜偟偄丅僷乕僗儞偼僑乕儖僪傗忔慻堳偲偲傕偵丄婔懡偺崲擄傗忈奞偵憳嬾偟側偑傜傕丄惗娨傪栚巜偟偰昁巰偺旘峴傪懕偗傞丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅彫愢偺晳戜偼傎偲傫偳旘峴婡偺側偐偩偗偩丅500儁乕僕嬤偄暘検偺嵟弶偐傜嵟屻傑偱丄旘峴婡偼傂偨偡傜旘傃懕偗傞丅旘峴婡傪戣嵽偵偟偨僷僯僢僋彫愢偼丄塮夋偵傕側偭偨傾乕僒乕丒僿僀儕乕偺亀戝嬻峘亁傗僩儅僗丒僽儘僢僋偺亀挻壒懍昚棳亁側偳丄偄傠偄傠偁傞偟丄堦掕偺忦審偱敋敪偡傞巇妡偗偺敋抏傪儌僠乕僼偵偟偨傕偺傕丄塮夋亀僗僺乕僪亁側偳偺慜椺偑偁傞丅偦偆偄偆堄枴偱偼偗偭偟偰怴慛側傾僀僨傾偲偼尵偊側偄丅偩偑斵傜偼丄偄偮敋抏偑敋敪偡傞偐偲偄偆嫲晐偲摤偄側偑傜丄婡懱偺晄挷丄愽擖偟偨僗僷僀偺岺嶌丄栚揑抧偺嬻峘偐傜偺拝棨嫅斲丄擱椏愗傟偵傛傞嬻拞媼桘丄棆塉偵傛傞棊棆傗壩嵭側偳丄偙傟偱傕偐偲偄偆傎偳師偐傜師傊偲帋楙偵尒晳傢傟傞丅偦偺偨傔嬞敆姶偑嵟屻傑偱帩懕偟丄廔巒丄旘峴婡偺側偐偲偄偆暵偞偝傟偨愝掕側偑傜丄傑偭偨偔偩傟傞偙偲偑側偄丅
僷乕僗儞偲僑乕儖僪偼屌偄鉐偱寢偽傟偰偄傞偑丄楒垽姶忣偑偁傞偺偐偳偆偐偼丄偼偭偒傝偲偼昤偐傟偰偄側偄丅師嶌偱偦傫側2恖偺娭學偑偳傫側傆偆偵敪揥偡傞偺偐傕嫽枴傪偦偦傜傟傞丅偙偺亀扙弌亁僔儕乕僘丄乬嶳乭乬嬻乭偲懕偄偨偺偱丄弴摉側偲偙傠丄師夞嶌偼乬奀乭偺偼偢偩偑丄庡恖岞偺僷乕僗儞偼旘峴巑側偺偱丄偦傫側奀傪晳戜偵偟偨僗僩乕儕乕偑惉傝棫偮偺偐偳偆偐丒丒丒丅偳傫側愝掕偵側傞偵偣傛丄嬤棃婬側庤偵娋埇傞朻尟彫愢嶌壠丄僩儅僗丒W丒儎儞僌偺怴嶌傪戝偄偵婜懸偟偨偄丅
2012.07.14 (搚) 嵅乆晹惔娔撀偲摨惾偟偨帄暉偺5帪娫
 傏偔偼塮夋岲偒偱偼偁傞偑丄擔杮塮夋偵偮偄偰偼丄屆偄塮夋偼尒傞偑丄嵟嬤偺塮夋偼傔偭偨偵尒側偄丅傢偞偲姶摦傪墴偟偮偗傞偁偞偲偝丄攐桪偺僆乕僶乕側墘媄丄庴偗慱偄偑傒偊傒偊偺愝掕偑旲偵偮偄偰丄嵟嬤偺擔杮塮夋偼丄偳偆偵傕尒傞婥偵側傟側偄偐傜偩丅偩偑丄偁傞擔丄T偝傫偵乽亀嶰杮栘擾嬈崅峑丄攏弍晹亁傪偨傑偨傑尒偨偗偳丄偲偰傕傛偐偭偨乿偲暦偄偰丄偦偺塮夋傪尒偨丅偨偟偐偵傛偐偭偨丅偦偙偵偼塮夋杮棃偺僸儏乕儅儞側姶摦偑偁偭偨丅偙偆偟偰傏偔偼嵅乆晹惔偲偄偆娔撀偺柤慜傪婰壇偵偲偳傔偨丅偦偟偰嵅乆晹娔撀嶌昳偺DVD傪師乆偵尒偰丄偙偺娔撀偺僼傽儞偵側偭偨丅
傏偔偼塮夋岲偒偱偼偁傞偑丄擔杮塮夋偵偮偄偰偼丄屆偄塮夋偼尒傞偑丄嵟嬤偺塮夋偼傔偭偨偵尒側偄丅傢偞偲姶摦傪墴偟偮偗傞偁偞偲偝丄攐桪偺僆乕僶乕側墘媄丄庴偗慱偄偑傒偊傒偊偺愝掕偑旲偵偮偄偰丄嵟嬤偺擔杮塮夋偼丄偳偆偵傕尒傞婥偵側傟側偄偐傜偩丅偩偑丄偁傞擔丄T偝傫偵乽亀嶰杮栘擾嬈崅峑丄攏弍晹亁傪偨傑偨傑尒偨偗偳丄偲偰傕傛偐偭偨乿偲暦偄偰丄偦偺塮夋傪尒偨丅偨偟偐偵傛偐偭偨丅偦偙偵偼塮夋杮棃偺僸儏乕儅儞側姶摦偑偁偭偨丅偙偆偟偰傏偔偼嵅乆晹惔偲偄偆娔撀偺柤慜傪婰壇偵偲偳傔偨丅偦偟偰嵅乆晹娔撀嶌昳偺DVD傪師乆偵尒偰丄偙偺娔撀偺僼傽儞偵側偭偨丅嵅乆晹娔撀偺塮夋偺嶣傝曽偼惓峌朄偩丅婏傪偰傜偭偨嶣傝曽偼偟側偄丅嵅乆晹嶌昳偼婎杮揑偵僸儏乕儅僯僘儉偵棫媟偟偰偄傞丅偦偺岅傝岥偼丄巹尒偩偑丄栘壓宐夘傪巚傢偣傞丅昤偒曽偼惷偐偩偑丄偩偐傜偙偦丄塮憸偐傜揱傢傞姶摦偼怺偄丅偦傟偐傜僉儍僗僥傿儞僌偑偄偄丅庡墘偡傞攐桪偼偁傑傝桳柤偱偼側偄偑丄墘媄偑偲偰傕帺慠偱丄僗僩乗儕乕偺側偐偵慺捈偵擖偭偰偄偗傞丅嵅乆晹嶌昳偵偼埆恖偼偁傑傝弌偰偙側偄丅埆恖側偟偱僗僩乕儕乕偑惉棫偡傞偺偐偲媈栤傪帩偮恖傕懡偄偱偁傠偆偑丄偙傟偑棫攈偵惉棫偡傞偐傜晄巚媍偩丅偦傟偐傜丄偄偄塮夋偵偼昁偢怱偵從偒偮偔僔乕儞偑偁傞偑丄偨偲偊偽乽僠儖僜僋偺壞乿偺僥儔僗偺僔乕儞偲偐丄乽梉撯偺崙丄嶗偺奨乿偺愳曈偺栘偺壓偱庒偄抝彈偑岅傜偆僔乕儞側偳偺傛偆偵丄嵅乆晹嶌昳偵傕偦傟偑偁傞丅
嵅乆晹娔撀偼丄偙傟傑偱寑応梡塮夋傪11杮偮偔偭偰偄傞丅偦偺側偐偱丄傏偔偑尒偨斖埻撪偱偺儀僗僩3偼埲壓偺偲偍傝偩丅
丂丂僠儖僜僋偺壞 乮弌墘丗悈扟斳棦丄忋栰庽棦乯 2003擭
丂丂梉撯偺崙丄嶗偺奨 乮弌墘丗杻惗媣旤巕丄揷拞楉撧乯 2007擭
丂丂嶰杮栘擾嬈崅峑丄攏弍晹 乮弌墘丗挿熀暥壒丄桍梩晀榊乯 2008擭
嵅乆晹偝傫偼丄VTR偺婯奿傪傔偖傞嫞憟偱擔杮價僋僞乕偺VHS偑懪偪彑偮傑偱傪昤偄偨2002擭偺塮夋乽梲偼傑偨徃傞乿偱娔撀僨價儏乕偟偨丅偦偟偰戝僸僢僩偟偨乽敿棊偪乿傪宱偰偮偔偭偨戞3嶌偑乽僠儖僜僋偺壞乿偩丅70擭戙屻敿偺壓娭乮嵅乆晹娔撀偺屘嫿乯傪晳戜偵丄棨忋嫞媄傪偡傞擔杮偺彈巕崅惗偲娯崙偺抝巕崅惗偺楒垽偲桭忣偑昤偐傟偰偄傞丅偙傟偼慺惏傜偟偄塮夋偩丅岅傝偨偄偙偲偼偨偔偝傫偁傞偑丄挿偔側傞偺偱徣棯偡傞丅乽梉撯偺崙丄嶗偺奨乿偼丄尨敋偺傕偨傜偡斶寑偑惷偐偵丄忣姶朙偐偵昤偐傟傞丅夁嫀偲尰嵼偺2晹峔惉偵側偭偰偄傞偑丄1960擭慜屻偺峀搰傪昤偄偨慜敿偑埑搢揑偵偄偄丅乽嶰杮栘擾嬈崅峑丄攏弍晹乿偼丄惵怷導偺崅峑傪晳戜偵丄攏弍晹偺彈巕崅惗偲攏偲偺岎棳傪昤偄偨塮夋丅幚榖傪傕偲偵偟偨傕偺偩偲偄偆丅峑挿栶偺徏曽峅庽偑偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅
 嫃庰壆偱偺嵅乆晹娔撀偲偺崸択偼丄T偝傫偺傎偐摨偠偔夛幮帪戙偺巇帠拠娫偺K忟傕摨惾偟偰丄5帪娫偑偁偭偲偄偆娫偵夁偓偨丅塮夋偺幚嶌幰偐傜暦偔塮夋偮偔傝偵傑偮傢傞偝傑偞傑側榖偼偲偰傕嫽枴怺偔丄帄暉偺傂偲偲偒傪枴傢偭偨丅嵅乆晹娔撀偺婥偝偔側恖暱丄棪捈側榖偟傇傝偵姶摦偟偨丅塮夋娔撀偲偄偆偲丄壗偲側偔埿尩偺偁偭偰嬤婑傝偑偨偄偲偄偆僀儊乕僕偑偁傞偑丄嵅乆晹偝傫偼偦傟偲偼惓斀懳偺丄壏偐偄怱傪姶偠偝偣傞恖偩偭偨丅偙偺夛偵弌惾偟偰偔傟偨嵅乆晹娔撀偵丄偦偟偰夛偵屇傫偱偔傟偨T偝傫偵姶幱偟偨偄丅
嫃庰壆偱偺嵅乆晹娔撀偲偺崸択偼丄T偝傫偺傎偐摨偠偔夛幮帪戙偺巇帠拠娫偺K忟傕摨惾偟偰丄5帪娫偑偁偭偲偄偆娫偵夁偓偨丅塮夋偺幚嶌幰偐傜暦偔塮夋偮偔傝偵傑偮傢傞偝傑偞傑側榖偼偲偰傕嫽枴怺偔丄帄暉偺傂偲偲偒傪枴傢偭偨丅嵅乆晹娔撀偺婥偝偔側恖暱丄棪捈側榖偟傇傝偵姶摦偟偨丅塮夋娔撀偲偄偆偲丄壗偲側偔埿尩偺偁偭偰嬤婑傝偑偨偄偲偄偆僀儊乕僕偑偁傞偑丄嵅乆晹偝傫偼偦傟偲偼惓斀懳偺丄壏偐偄怱傪姶偠偝偣傞恖偩偭偨丅偙偺夛偵弌惾偟偰偔傟偨嵅乆晹娔撀偵丄偦偟偰夛偵屇傫偱偔傟偨T偝傫偵姶幱偟偨偄丅戝岲偒側塮夋乽僠儖僜僋偺壞乿偵偮偰丄娔撀偐傜偄傠傫側偙傏傟榖傪暦偗偨偺偼丄壗傛傝偺橣岕偩偭偨丅僥儔僗偱庡墘偺抝彈偑夛偆僔乕儞偼丄乽儘儈僆偲僕儏儕僄僢僩乿偺僶儖僐僯乕偱偺弌夛偄傪巚傢偣偨偑丄娔撀偐傜丄偁傟偼乽僂僃僗僩丒僒僀僪暔岅乿偺僶儖僐僯乕丒僔乕儞傪僀儊乕僕偟偰昤偄偨偲暦偄偰丄傗偼傝偦偆偐偲旼傪懪偭偨丅棨忋晹偺彈巕崅惗拠椙偟4恖慻偑丄傒側僗億乕僣偺墘媄偑摪偵擖偭偰偄偰姶怱偟偨偑丄偙傟偼僆乕僨傿僔儑儞偺偲偒偵丄僗億乕僣偺宱尡偑偁傞攐桪傪慖傫偩偲暦偄偰丄側傞傎偳偲擺摼偟偨丅偦偺傎偐丄庡恖岞偺晝恊栶偺壧庤丄嶳杮忳擇傗丄庡恖岞偺憡庤栶偺娯崙恖抝巕崅惗偺僉儍僗僥傿儞僌偵傑偮傢傞榖傕嫽枴怺偐偭偨丅偙偺塮夋偵偼丄壓娭偺巗柉偑懡悢僄僉僗僩儔偱弌墘偟偨傜偟偄丅壓娭偱偼丄枅擭丄幍梉偺擔偵偙偺塮夋偺忋塮夛偑峴側傢傟偰偄傞偲偄偆丅側偤幍梉偐偼丄偙偺塮夋傪尒傟偽暘偐傞丅
嵅乆晹娔撀偼丄2011擭偵塮夋乽僣儗偑偆偮偵側傝傑偟偰丅乿傪偮偔偭偨偁偲丄崱擭偵擖偭偰徏杮惔挘尨嶌偺TV僪儔儅乽攇偺搩乿傪嶣偭偨乮6寧偵僥儗價挬擔宯偱曻憲乯丅徍榓30擭戙偺暤埻婥偑傛偔弌偰偍傝丄偩傟偨偲偙傠偺側偄丄崪奿偺偟偭偐傝偟偨堷偒掲傑偭偨僪儔儅偵側偭偰偄偨丅偙傟偐傜傕嵅乆晹娔撀偵偼丄婃挘偭偰偄偄塮夋傪偳傫偳傫嶣偭偰傕傜偄偨偄丅
2012.06.28 (栘) 彫戲堦榊傛暠婲偺帪偩丄柉庡搣偼帺柵偣傛
儅僯僼僃僗僩偱偆偨偭偨偙偲偼壗傂偲偮幚峴偣偢丄傗傜側偄偲尵偭偰偄偨偙偲偽偐傝傗偭偰偒偨柉庡搣偼丄偟傚偣傫帺柉搣偲摨偠寠偺傓偠側偩偭偨丅崙柉偼柉庡搣偵閤偝傟偨偺偩丅栰揷惌尃偼丄夵妚側偳偳偙悂偔晽丄姱椈偵巚偆傛偆偵憖傜傟丄柍懯側宱旓嶍尭偺搘椡傪曻婞偟丄戝宆岞嫟帠嬈傪暅妶偝偣丄夃偑娭偵憙偔偆僔儘傾儕偨偪偺婛摼尃塿傪壏懚偝偣偨丅偦偟偰壂撽偱偼婎抧晧扴傪寉尭偝偣傞偳偙傠偐丄傾儊儕僇偺尵偄側傝偵婋尟嬌傑傝側偄僆僗僾儗僀偺攝旛傪嫮峴偝偣傛偆偲偟偰偄傞丅
偝傜偵栰揷惌尃偼丄暉搰尨敪帠屘偱擔杮偲偄偆崙偑柵朣偺悾屗嵺傑偱偄偭偨偺偵丄偦偺嫵孭傪傑偭偨偔惗偐偡偙偲側偔丄扙尨敪偺曽恓偼扞忋偘偵偟丄彅埆偺崻尮偱偁傞尨巕椡儉儔傪曻抲偟丄埨慡婎弨傕柧妋偱側偄偺偵戝斞尨敪傪嵞壱摥偝偣偨丅怴愝偝傟傞尨巕椡婯惂埾堳夛偼崪敳偒偵偝傟偐偐偭偰偍傝丄偍傑偗偵丄偳偝偔偝傑偓傟偵尨巕椡偺孯帠棙梡傊偺摴傪奐偒偐偹側偄暥尵傪尨巕椡婎杮朄偵晅偗壛偊偨丅偙傫側柉堄傪屭傒側偄柉庡搣偼堦崗傕憗偔偮傇偡傋偒偩丅
偄傑偼彫戲堦榊偵搎偗傞偟偐側偄丅彫戲偑傎傫偲偆偵婜懸偵墳偊偰偔傟傞偺偐偳偆偐丄妋怣偼側偄丅偟偐偟丄斵偼恀偭摉側偙偲傪庡挘偟偰偄傞丅夵妚敳偒偺徚旓惻憹惻偵斀懳偟丄埨堈側尨敪嵞壱摥偵斀懳偟丄儅僯僼僃僗僩偵棫偪曉傟偲尵偭偰偄傞丅惓偟偄偙偲傪尵偭偰偄傞偺偩丅偄傑傗傾儊儕僇偵懳偟偰傑偲傕偵傕偺偑尵偊傞偺偼彫戲偟偐偄側偄丅憗偗傟偽崱擭偺廐偛傠偲傕尵傢傟偰偄傞憤慖嫇偵偼丄彫戲偵偼偤傂怴搣傪棪偄偰椪傒丄惌尃傪庢傝丄崙柉偺朷傓夵妚傪幚尰偟偰傕傜偄偨偄丅
偟偐偟彫戲堦榊偺慜偵偼堎忢偲傕尵偊傞彫戲僶僢僔儞僌偺暻偑棫偪偼偩偐偭偰偄傞丅崙嶔憑嵏偵傛傞偱偭偪忋偘嵸敾偱偼丄傛偆傗偔柍嵾傪彑偪庢偭偨偺偵丄柍杁側忋崘偵傛傝丄偄傑偩偵慽捛偐傜夝曻偝傟偰偄側偄丅偦偙偵崀偭偰桸偄偨偺偑朸廡姧帍偵嵹偭偨彫戲偺僗僉儍儞僟儖曬摴偩丅偁傑傝偵業崪側彫戲捵偟偩丅楎壔偟偨儊僨傿傾偼姰慡偵姱椈偺憱嬬偵側傝壥偰丄栰揷惌尃偺屼梡儅僗僐儈偲壔偟丄専嶡偲巌朄姱椈偑巇慻傫偩彫戲嵸敾偺恀憡傪捛媮偟傛偆偲偣偢丄彫戲偵埆偺僀儊乕僕傪怉偊晅偗傛偆偲偡傞丅愴屻偙偙傑偱儊僨傿傾偑懧棊偟偨偙偲偼側偐偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
偩偑丄惓媊偼彫戲堦榊偵偁傞丅彫戲偑怴搣傪寢惉偟丄棟擮偲怣擮傪愢偗偽丄昁偢怱偁傞崙柉偼偮偄偰偔傞丅彫戲堦榊傛暠婲偺帪偩丄柉庡搣偼帺柵偣傛丅
2012.02.17 (嬥) 儂僀僢僩僯乕丒僸儏乕僗僩儞偑巰傫偩
 2寧11擔偵儂僀僢僩僯乕丒僸儏乕僗僩儞偑朣偔側偭偰埲崀丄偦偺憗偡偓傞巰傪楢擔偺傛偆偵曬偢傞僥儗價偺寍擻斣慻偱偼丄偄偮傕乽僆乕儖僂僃僀僘丒儔償丒儐乕乿偺壧惡偑棳傟偰偄傞丅儂僀僢僩僯乕偺愨捀婜偵擔杮偱偺儗僐乕僪丒僾儘儌乕僔儑儞偺堦抂傪扴偭偨傏偔偼丄夰偐偟偝偲捝傑偟偝傪姶偠側偑傜偦傟傪尒偰偄傞丅
2寧11擔偵儂僀僢僩僯乕丒僸儏乕僗僩儞偑朣偔側偭偰埲崀丄偦偺憗偡偓傞巰傪楢擔偺傛偆偵曬偢傞僥儗價偺寍擻斣慻偱偼丄偄偮傕乽僆乕儖僂僃僀僘丒儔償丒儐乕乿偺壧惡偑棳傟偰偄傞丅儂僀僢僩僯乕偺愨捀婜偵擔杮偱偺儗僐乕僪丒僾儘儌乕僔儑儞偺堦抂傪扴偭偨傏偔偼丄夰偐偟偝偲捝傑偟偝傪姶偠側偑傜偦傟傪尒偰偄傞丅1990擭戙弶摢丄儗僐乕僪嬈奅偼嫽棽傪寎偊偰偍傝丄梞妝偺僙乕儖僗傕忋岦偒偱偼偁偭偨偑丄側偐側偐戝婯柾側僸僢僩丒傾儖僶儉偼惗傑傟側偐偭偨丅摉帪丄傏偔偼儗僐乕僪夛幮偺梞妝晹栧偺愑擟幰偩偭偨偑丄幮撪傗嬈奅拠娫偲偺儈乕僥傿儞僌側偳偱偼丄寛傑偭偰乬偳偆傗偭偨傜10枩枃攧傟傞傾儖僶儉傪偮偔傟傞偐乭偵偮偄偰榖偟崌偭偰偄偨丅傏偔偨偪偑儂僀僢僩僯乕丒僸儏乕僗僩儞偺塮夋僒儞僩儔斦亀儃僨傿僈乕僪亁傪敪攧偟偨偺偼丄偦傫側偲偒偩偭偨丅1992擭偺偙偲偩丅弶傔偰庡戣壧僔儞僌儖乽僆乕儖僂僃僀僘丒儔償丒儐乕乿傪挳偄偰丄偦偺慺惏傜偟偝偵僸僢僩傪妋怣偟偨偑丄偁傟傎偳攧傟傞偲偼巚偭偰傕偄側偐偭偨丅僔儞僌儖傕傾儖僶儉傕丄塮夋偺僸僢僩偲憡忔岠壥偲側傝丄攧傟偵攧傟偨丅戝偒側僾儘儌乕僔儑儞傪偟偨偺偼敪攧摉弶偩偗偱丄偁偲偼丄嶁摴傪揮偑傝棊偪傞愥嬍偑朿傜傓傛偆偵丄傎偭偰偍偄偰傕攧傟懕偗偨丅偗偭偒傚偔傾儖僶儉亀儃僨傿僈乕僪亁偼180枩枃偲偄偆儌儞僗僞乕丒僸僢僩偵側偭偨丅偦偟偰丄偙偺傾儖僶儉傪旂愗傝偵丄梞妝偺戝宆僸僢僩偑懕弌偡傞傛偆偵側偭偨丅彮偟慜傑偱10枩枃攧傞偺偵摢傪擸傑偣偰偄偨偺偑塕偺傛偆偩偭偨丅
偄傑巚偊偽丄偙偺崰丄90擭戙敿偽偺悢擭娫偑丄擔杮偺儗僐乕僪巎忋丄梞妝偑偄偪偽傫塰壺傪鎼壧偟偰偄偨帪婜偩偭偨丅尰嵼偼壒妝嬈奅慡懱偑棊偪崬傒丄僸僢僩偺婯柾傕彫偝偔側偭偨丅
 梞妝傾儖僶儉偺応崌丄100枩枃偼偍傠偐丄10枩枃偵払偡傞傕偺偝偊傎偲傫偳側偄丅偣偄偤偄2丄3枩枃攧傟傟偽戝僸僢僩偲偄偆忬嫷偩丅亀儃僨傿僈乕僪亁敪攧摉帪偺儗乕儀儖扴摉幰傗堦弿偵巇帠偟偰偄偨拠娫傕偄傑偼嶶傝嶶傝偵側偭偨偟丄嬈奅嵞曇偑恑傒丄傏偔偑偄偨儗僐乕僪夛幮傕嫞崌懠幮偵崌暪媧廂偝傟偰偟傑偭偨丅岝堿栴偺偛偲偟丄帪惃偺堏傝曄傢傝偺寖偟偝傪捝姶偡傞丅
梞妝傾儖僶儉偺応崌丄100枩枃偼偍傠偐丄10枩枃偵払偡傞傕偺偝偊傎偲傫偳側偄丅偣偄偤偄2丄3枩枃攧傟傟偽戝僸僢僩偲偄偆忬嫷偩丅亀儃僨傿僈乕僪亁敪攧摉帪偺儗乕儀儖扴摉幰傗堦弿偵巇帠偟偰偄偨拠娫傕偄傑偼嶶傝嶶傝偵側偭偨偟丄嬈奅嵞曇偑恑傒丄傏偔偑偄偨儗僐乕僪夛幮傕嫞崌懠幮偵崌暪媧廂偝傟偰偟傑偭偨丅岝堿栴偺偛偲偟丄帪惃偺堏傝曄傢傝偺寖偟偝傪捝姶偡傞丅抦傜傟傞傛偆偵丄乽僆乕儖僂僃僀僘丒儔償丒儐乕乿偼塮夋偺偨傔偺彂偒壓傠偟嬋偱偼側偄丅1974擭偵僇儞僩儕乕壧庤僪儕乕丒僷乕僩儞偑嶌帉嶌嬋偟帺傜壧偭偨嬋偺僇償傽乕偱偁傞丅尨嬋偼偛偔晛捠偺僇儞僩儕乕丒僶儔乕僪偱偁傝丄偲偔偵偡偖傟偨嬋偲傕巚偊側偄丅偙傟偑偁傟傎偳愢摼椡偺偁傞僪儔儅僠僢僋側嬋偵側偭偨梫場偼丄傂偲偊偵儂僀僢僩僯乕偺斾椶側偄壧彞椡偵偁偭偨丅斵彈偺挳偔幰偺怱偵捈愙慽偊偐偗傞丄恄偑偐傝揑側壧彞偵傛偭偰乽僆乕儖僂僃僀僘丒儔償丒儐乕乿偼婏愓揑側柤嬋偵側偭偨丅
儂僀僢僩僯乕丒僸儏乕僗僩儞偼堦斒揑偵偼億僢僾僗壧庤偵暘椶偝傟偰偄傞偑丄偦偺壧彞偼R&B傗僑僗儁儖偵崻偞偟偰偄偨丅儗僐乕僨傿儞僌偵偁偨偭偰偼丄偍偦傜偔堄幆揑偵丄偦傫側僥僀僗僩偼梷偊傜傟偰偄偨丅偩偑儔僀償偲側傞偲丄斵彈偼R&B僼傿乕儕儞僌傪慜柺偵偵懪偪弌偟丄崟恖壧庤偲偟偰偺儖乕僣傪慡奐偝偣偰偄偨丅儂僀僢僩僯乕偺揤梌偺壧彞椡偼寙弌偟偰偄偨丅儅儔僀傾丒僉儍儕乕傗僙儕乕僰丒僨傿僆儞側偳偑懇偵側偭偰傕揋傢側偐偭偨丅1998擭偵儂僀僢僩僯乕偲儅儔僀傾偑僨儏僄僢僩偟偨乽儂僄儞丒儐乕丒價儕乕償乿偲偄偆嬋傪挳偔偲丄儂僀僢僩僯乕偺掙椡偺偁傞僷儚僼儖側壧彞偵斾傋丄儅儔僀傾偼惡傕壧偄曽傕昻庛偱丄幚椡偺嵎偼楌慠偲偟偰偄偨丅
儂僀僢僩僯乕偵偼丄垾嶢偺偨傔朘傟偨僐儞僒乕僩夛応偺妝壆傗丄儅僗僐儈庢嵽偺偨傔晪偄偨僯儏乕儓乕僋偺儂僥儖側偳偱丄悢夞夛偭偰偄傞丅媞偲愙偟偰偄傞偲偒偼垽憐偑偄偄偑丄恎撪偩偗偱偄傞偲偒偺斵彈偺恄宱幙偦偆側條巕傗巇憪偑婰壇偵巆偭偰偄傞丅亀儃僨傿僈乕僪亁偱壒妝奅偺捀揰偵忋傝偮傔偨偁偲偺儂僀僢僩僯乕偺揮棊偼丄偦傫側斵彈偺僫乕償傽僗側惈奿偑攚宨偵偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅壒妝偱傕塮夋偱傕暥妛偱傕丄寍弍傗寍擻偺悽奅偵偼丄捀揰傪嬌傔偨偁偲媫懍偵悐戅偡傞恖偑懡偄丅亀儃僨傿僈乕僪亁偺偁偲丄儂僀僢僩僯乕偼塮夋偵棫偰懕偗偵庡墘偟偨傝丄怴婡幉傪懪偪弌偟偨僽儔僢僋丒僐儞僥儞億儔儕乕巙岦偺傾儖僶儉傪偮偔偭偨傝偲丄偄傠傫側怴偟偄傾僀僨傾傪帋傒偨偑丄偳傟傕惉岟偵偼帄傜偢丄彊乆偵懚嵼姶偑敄傜偄偱偄偭偨丅
儂僀僢僩僯乕偑僪儔僢僌傗傾儖僐乕儖傪梡偄傞傛偆偵側偭偨偺偼丄惉岟傊偺徟傝偲挏棊傊偺婋婡姶偑僾儗僢僔儍乕偲側偭偰僗僩儗僗偑廳側偭偨偐傜偩傠偆丅屻攜偺儅儔僀傾丒僉儍儕乕傗僙儕乕僰丒僨傿僆儞偺戜摢偲偄偆忬嫷傕偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偝傜偵晇儃價乕丒僽儔僂儞偲偺寢崶惗妶偺晄岾偑偦傟偵攺幵傪偐偗偨丅壠掚偺峳攑偼僗僩儗僗傪攞壔偝偣傞丅偨傃廳側傞晇偺朶椡偵傕偐偐傢傜偢丄斵彈偼側偐側偐暿傟傛偆偲偣偢丄14擭娫傕寢峔惗妶傪懕偗偨丅偦傫側晇偲偼憗偔棧崶偟偰偟傑偊偽偄偄偺偵偲巚偆偺偩偑丄側偤変枬偟偰偄偨偺偐丄傛偔暘偐傜側偄丅懠恖偵偼悇偟検傞偙偲偑偱偒側偄惛恄揑側棟桼偑偁偭偨偺偩傠偆丅挿偔懕偄偨僪儔僢僌暼傗晄愛惗偺偨傔丄偁偺暲偼偢傟偨壧彞椡傑偱幐傢傟偰偟傑偭偨丅悢擭慜偵10擭傇傝偵峴側傢傟偨儚乕儖僪丒僣傾乕偱偼丄傑偭偨偔惡偑弌偢丄夛応偱偼僽乕僀儞僌偑婲偒偨傝丄岞墘傪僉儍儞僙儖偡傞側偳偺僩儔僽儖偵尒晳傢傟偨丅偦偺屻丄僪儔僢僌傪抐偪愗傞偨傔偺搘椡傪懕偗丄夞暅偺挍偟傪尒偣偰偄偨栴愭偺崱夞偺斶寑偩偭偨丅
塰岝偵懕偔幐捘丄愨捀偺偁偲偵娮傞悐戅丅恄偵垽偝傟偨幰偼憗偔恄偵彚偝傟傞偲偄偆偑丄偦傟偵偟偰傕丄柤惡傪嫕庴偟偨傾乕僥傿僗僩偺斶嶴側枛楬偼丄偁傑傝偵庘偟偔丄捝傑偟偄丅
2012.02.08 (悈) 嫶壓揙怣幰偨偪偺堎忢側峴摦
偙偺摙榑偼偗偭偙偆榖戣偵側偭偨傜偟偔丄僱僢僩偱挷傋偰傒傞偲丄偨偔偝傫偺榑昡傗姶憐偺彂偒崬傒偑偁傞丅偦偺傎偲傫偳偼嫶壓傪楃巀偟丄嶳岥傪嫒偡傕偺偩偭偨丅嶳岥擇榊偺庡嵣偡傞僽儘僌偵偼丄斵傪拞彎偡傞寵偑傜偣僐儊儞僩偑懡悢彂偒崬傑傟丄堦帪丄墛忋忬懺偵側偭偨傜偟偄丅嫶壓傪斸敾偡傞偲丄嫶壓怣幰傜偑傛偭偰偨偐偭偰峌寕偡傞丅堦庬偺杺彈庪傝偩丅偄傑偺嫶壓偵廤傑傞恖婥丄偦偺恖婥偵曋忔偟傛偆偲偡傞楢拞丄嫸怣揑側嫶壓巟帩幰偨偪偺峴摦偼丄偳偙偐堎忢側傕偺傪姶偠傞丅
晄枮偲烼孅偑偨傑偭偰偄傞戝廜偼丄嫶壓偺埿惃偺偄偄尵梩偵棴堸傪壓偘丄嫶壓偑攍搢偡傞妛幰傗抦幆恖傪峌寕偟丄旑鎺偡傞丅偦偙偵傏偔偼斀抦惈庡媊丄慹栰側尨巒揑姶忣偵偵梮傜偝傟偰峴摦偡傞恖娫偺巔傪尒傞丅偄偮偺帪戙偵傕丄偳偙偺崙偵傕丄偦傫側楢拞偼偄傞丅偦傫側尰徾偑偑崙壠揑婯柾偱姫偒婲偙偭偨寢壥丄1930擭戙偺僪僀僣偱偼僫僠僘儉偑戜摢偟丄1950擭戙偺傾儊儕僇偱偼儅僢僇乕僔僘儉偑悂偒峳傟丄斶寑傪惗傫偩丅
偦偆偄偊偽丄嫶壓揙偑傑偩戝嶃晎抦帠偵側傞慜偺2007擭丄戝嶃偺僥儗價斣慻偱丄嫶壓偑岝巗曣巕嶦奞帠審偺曎岇抍偵挦夲惪媮傪峴側偆傛偆帇挳幰偵屇傃偐偗丄偦偺寢壥丄傕偺偡偛偄悢偺挦夲惪媮偑曎岇巑夛偵嶦摓偟偨帠審偑偁偭偨丅偁偺嵸敾偺曎岇抍偺庤朄偼丄偨偟偐偵屍懅偩偟搟傝傪妎偊傞丅偩偑丄偩偐傜偲偄偭偰丄偦傫側廤抍惂嵸傒偨偄側偙偲傪偟偰傕丄偨傫側傞暊偄偣偱偁傝丄壗偺夝寛偵傕側傜側偄丅偘傫偵偦傟傜偺挦夲惪媮偼曎岇巑夛偱偡傋偰媝壓偝傟丄媡偵嫶壓偑挦夲惪媮偵偐偗傜傟丄挦夲張暘偑壓偭偨丅嫶壓偺傗偭偨偙偲偼丄戝廜偺掅師尦偺姶忣偵慽偊丄柍抦側悽娫傪偗偟偐偗傞慀摦偩偭偨丅
堎榑傪彞偊傞幰傪峌寕偟丄攍搢偡傞嫶壓丄偦偺怟攏偵忔偭偰丄嫶壓偑揋偲傒側偡幰傪峌寕偡傞嫶壓僔儞僷偺戝廜丄偙偺峔恾偼晄桖夣偩偟丄晄婥枴偩丅嫶壓偑乽偁偄偮偼揋偩乿偲堦尵岥偵偡傟偽丄斵傜偼偄偭偣偄偵偦傟傪峌寕偡傞偩傠偆丅嫶壓偑僫僠僘儉偩偲偐儅僢僇乕僔僘儉偩偲偐尵偆偮傕傝偼側偄丅偨偩丄夵寷傗妀暫婍曐桳傪庡挘偟偨傝丄戝嶃偵僇僕僲傪嶌偭偰僊儍儞僽儖傪嫽棽偝偣傞偲尵偭偨傝偡傞尵摦偐傜偟偰丄斵偑崙惌偺尃椡傪埇偭偨傜丄斀懳榑側偳偍峔偄側偟偵丄戝廜揑側恖婥偵忔偠偰丄堦婥偵偦傫側曽岦偵撍偒恑傓偙偲傪嫲傟傞丅
嫶壓偼崙惌偵恑弌偡傞偵偁偨偭偰丄乽崙偺摑帯婡峔傪曄偊傞乿偲尵偭偰偄傞丅偍偦傜偔摴廈惂偲庱憡岞慖惂傪擮摢偵抲偄偰偄傞偺偩傠偆丅偦偺峫偊曽偺摉斲偼暿偲偟偰丄惌帯偺曄妚偼昁梫偩丅偩偑丄栤戣偼丄偙偺崙傪偳偆偄偆曽岦偵傕偭偰偄偔偐偩丅嫶壓偺峫偊偺慡懱憸偼傑偩尒偊側偄偑丄嫮幰偵庛偔丄庛幰偵嫮偔側傞偺偱偼丄偨傑偭偨傕偺偱偼側偄丅擔杮偵崿棎偲峳攑傪傕偨傜偟偨彫愹弮堦榊惌尃偺擇偺晳偵側偭偰偟傑偆丅
2012.01.31 (壩) 嫶壓揙戝嶃巗挿偺尵摦傊偺堘榓姶
嶳岥擇榊偲偄偆恖偼丄傕偲傕偲柉庡搣偺惌嶔僽儗乕儞偺傂偲傝偱偁傝乮摉慠側偑傜崱偺柉庡搣惌尃偵偼斸敾揑偩偑乯丄嫶壓偺惌帯庤朄傪僴僔僘儉偲徧偟偰斸敾偟偰偄傞昡榑壠偱偁傞丅嫶壓偼丄擔偛傠帺暘傪榑擄偟偰偄傞嶳岥傊偺烼暜傪揻偒弌偟偨偺偩傠偆丅偩偑丄偦傟偵偟偰傕丄嶳岥偺弨旛晄懌丄愢柧椡晄懌傕偁偭偨偲巚偆偑丄嫶壓偺嫃忎崅側暔崢丄撈傝傛偑傝偺斀榑偼堎忢偩偭偨丅摨惾偟偰偄偨捠懎彫愢壠丄搉曈弤堦偺懢屰帩偪偺傛偆側惡墖偵偵偙傗偐偵墳懳偡傞偺偲岲懳徠偩偭偨丅嫶壓偺憡庤偵桳柍傪尵傢偣偸崅埑揑側暔尵偄丄嫮堷偵帺暘偺庡挘傪捠偦偆偲偡傞懺搙偼丄寵埆姶傪偡傜嵜偝偣偨丅
嫶壓偺帺暘傪斸敾偡傞幰傊偺僄僉僙儞僩儕僢僋側斀敪偼枅搙偺偙偲偺傛偆偩丅偦傫側嫶壓偺曎愩偵憉夣偝傪姶偠傞恖傕偄傞偩傠偆偑丄傏偔偼婋側偝傪姶偠傞丅嫶壓偺尵摦偼丄彫愹弮堦榊尦庱憡傪巚偄婲偙偝偣傞丅彫愹偺壖憐揋傪偮偔偭偰偦傟傪寕攋偡傞傗傝曽偩丅梄惌柉塩壔傪嬥壢嬍忦偵丄乽帺暘偵斀懳偡傞幰偼偡傋偰掞峈惃椡偩乿偲尵偄曻偪丄乽帺柉搣傪傇偭偮傇偡乿偲嫨傫偩彫愹偺埿惃偺偄偄尵梩偵丄崙柉偼攺庤妳偝偄偟偨丅梄惌柉塩壔偑壗傪堄枴偡傞偺偐丄扤傕暘偐偭偰偄側偐偭偨丅崙柉偺埑搢揑側巟帩傪攚宨偵丄彫愹偼傾儊儕僇偵楆廬偟丄抾拞暯憼偲慻傫偱峔憿夵妚偺柤偺傕偲偵巗応尨棟惌嶔傪悇偟恑傔丄偦偺寢壥丄擔杮偺宱嵪偼攋抅偟丄奿嵎偑峀偑偭偨丅彫愹傪巟帩偟偨偮偗偼偁傑傝偵戝偒偐偭偨丅
戝嶃晎抦帠偲偟偰偺嫶壓偺幚愌偼栚妎傑偟偄丅恖審旓傪偼偠傔柍懯側嵨弌傪僇僢僩偟偰嵿惌傪嵞寶偟偨庤榬偼尒帠偩偭偨偟丄摿尃偵偁偖傜傪偐偄偰偄偨怑堳楯慻偲偺懳寛傗忣曬岞奐偺揙掙側偳傕徧巀偵抣偡傞丅偨偟偐偵嫶壓偺尵偆傛偆偵丄巚偄愗偭偨夵妚傪傗傠偆偲巚偭偨傜丄偁傞庬丄撈嵸揑側峴摦傪庢傜偞傞傪摼側偄偙偲傕偁傞偩傠偆丅偟偐偟丄擇尵栚偵偼丄柉堄傪摼偨偺偼壌偩丄偩偐傜傗傝偨偄偙偲偼壗偱傕偱偒傞丄偲尵偄曻偪丄偄傢偽柉堄傪弬偵偲偭偰堎榑傪晻嶦偡傞傗傝曽丄帺暘偲堄尒偺堎側傞幰傪揋偲傒側偟偰揙掙揑偵峌寕偡傞偲偄偆傗傝曽偼丄僨儅僑乕僌偵嬤偄偟丄婋尟側傕偺傪姶偠傞丅
桭恖偺A偔傫偑丄乽嫶壓偼戝嶃晎抦帠慖偵弌攏偡傞偲偒丄乬愨懳偵弌傑偣傫乭偲尵柧偟偰僂僜傪偮偄偨丄偦傫側搝偼怣梡偱偒側偄乿偲尵偭偰偄偨丅偦偆偄偊偽丄戝嶃堐怴偺夛偺崙惌傊偺嶲夋偵偮偄偰傕丄帺暘偺庡挘偑崙惌偵斀塮偝傟傞偺側傜傗傝傑偣傫偲尵偭偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢丄奺惌搣偑偙偲偛偲偔嫶壓偺峫偊傪慜岦偒偵峫椂偡傞偲尵偭偰偄傞偺偵丄師夞偺廜媍堾慖偵堐怴偺夛偐傜懡悢傪梚棫偡傋偔弨旛拞偩偲偄偆丅惌帯壠偵擇枃愩偼偮偒傕偺偩偑丄嫶壓偼偦傫側楢拞偲偼堦慄傪夋偟偰偄偨偼偢偠傖側偄偺偐丅
戝嶃晎偲戝嶃巗偺擇廳峴惌傪夝徚偡傞偨傔丄嫶壓偼戝嶃搒峔憐傪壺乆偟偔傇偪忋偘偰偄傞丅偦偙傑偱偟側偔偰傕丄偟偔傒偲僔僗僥儉傪曄偊傞偩偗偱暰奞偼夝徚偱偒傞偲巚偆偺偩偑丄偦傟偼偄偄偲偟傛偆丅栤戣偼嫵堢偵娭偡傞斵偺峫偊曽偩丅娒偊偺枲墑傗嫞憟偺寚擛傪側偔偡偲偄偆曽恓偼巀惉偩偑丄嫵堳娗棟傪嫮傔傟偽嫵堢偑椙偔側傞偲偄偆嫶壓偺峫偊偼娫堘偭偰偄傞丅傑偟偰傗丄晝孼傗PTA偵嫵巘傪昡壙偝偣傞側偳丄偲傫偱傕側偄傗傝曽偩丅
愜偐傜丄傕偆偡偖80嵨偵側傞尃椡巙岦偺橖枬側榁恖丄愇尨怲懢榊偑怴搣偺搣庱偵扴偓弌偝傟傛偆偲偟偰偄傞丅崙柉偺偙偲側偳偦偭偪偺偗偱惌帯偺庡摫尃憟偄偵偆偮偮傪偸偐偡掅擻惌帯壠偳傕偺嬸偐偝傪捈偡栻偼側偄丅壖偵愇尨怴搣偑寢惉偝傟偨応崌丄嫶壓偺堐怴偺夛偑偦偙偲僞僢僌傪慻傓偙偲側偳偁傝偊側偄偲巚偆丅偩偑丄嫶壓偺堄尒偺堎側傞幰傪揙掙峌寕偡傞巔惃丄寷朄夵掕丄妀暫婍峬掕丄岞塩僊儍儞僽儖悇恑偲偄偭偨斵偺敪尵偐傜偟偰丄愇尨偺峫偊偲嫟捠偡傞傕偺傕懡偄丅嫶壓偲堐怴偺夛偺偙傟偐傜偺摦偒偵傛傝丄嫶壓揙偲偄偆惌帯壠偺惓懱偑柧傜偐偵側偭偰偄偔偩傠偆丅
2012.01.11 (悈) 婣偭偰棃偨僫僠僗丒僪僀僣偺扵掋儀儖儞僴儖僩丒僌儞僞乕
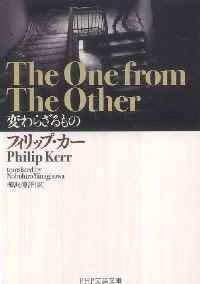 嶐擭姧峴偝傟偨儈僗僥儕乕偱枹撉偩偭偨傕偺傪壗嶜偐偙偺擭枛擭巒偵撉傫偩丅柺敀偐偭偨偺偼僼傿儕僢僾丒僇乕偺乽曄傢傜偞傞傕偺乿乮PHP暥屔乯丅僼傿儕僢僾丒僇乕丄僼傽儞偵偲偭偰偼夰偐偟偄柤慜偩丅僫僠僗帪戙偺儀儖儕儞傪晳戜偵巹棫扵掋儀儖儞僴儖僩丒僌儞僞乕偑妶桇偡傞堎怓僴乕僪儃僀儖僪彫愢乽婾傝偺奨乿偱僇乕偑朚栿僨價儏乕偟偨偺偼丄傕偆20擭埲忋傕慜偺偙偲偵側傞丅僌儞僞乕傪庡恖岞偲偡傞暔岅偼岲昡傪攷偟偰僔儕乕僘壔偝傟偨偑丄1989擭偺戞1嶌埲崀丄3嶌偱拞抐偟偰偄偨丅15擭傇傝偵偙偺僔儕乕僘傪暅妶偝偣偨偺偑杮彂乽曄傢傜偞傞傕偺乿偩丅尨挊偺姧峴偼2006擭丅
嶐擭姧峴偝傟偨儈僗僥儕乕偱枹撉偩偭偨傕偺傪壗嶜偐偙偺擭枛擭巒偵撉傫偩丅柺敀偐偭偨偺偼僼傿儕僢僾丒僇乕偺乽曄傢傜偞傞傕偺乿乮PHP暥屔乯丅僼傿儕僢僾丒僇乕丄僼傽儞偵偲偭偰偼夰偐偟偄柤慜偩丅僫僠僗帪戙偺儀儖儕儞傪晳戜偵巹棫扵掋儀儖儞僴儖僩丒僌儞僞乕偑妶桇偡傞堎怓僴乕僪儃僀儖僪彫愢乽婾傝偺奨乿偱僇乕偑朚栿僨價儏乕偟偨偺偼丄傕偆20擭埲忋傕慜偺偙偲偵側傞丅僌儞僞乕傪庡恖岞偲偡傞暔岅偼岲昡傪攷偟偰僔儕乕僘壔偝傟偨偑丄1989擭偺戞1嶌埲崀丄3嶌偱拞抐偟偰偄偨丅15擭傇傝偵偙偺僔儕乕僘傪暅妶偝偣偨偺偑杮彂乽曄傢傜偞傞傕偺乿偩丅尨挊偺姧峴偼2006擭丅嵞奐偝傟偨杮嶌偺帪戙偼1949擭丄暷僜塸暓偺4僇崙偑摑帯偡傞愴屻偺崿棎偺側偐偺僪僀僣偑晳戜偩丅僌儞僞乕偼儈儏儞僿儞偱扵掋嬈傪塩傫偱偄傞丅僌儞僞乕偼尃埿偵恘岦偄丄傊傜偢岥傪偨偨偒丄帺暘偺婯棩傪嬋偘側偄堦旵楾偱偁傝丄嬤擭偱偼捒偟偄惓摑攈僴乕僪儃僀儖僪丒僗僞僀儖偺庡恖岞偲偟偰昤偐傟傞丅楢崌崙偵傛傞愴斊偺張孻丄儐僟儎恖慻怐偵傛傞尦恊塹戉堳傊偺暅廞側偳丄憶慠偲偟偨悽忣偺側偐丄僌儞僞乕偼偄偔偮偐偺巇帠傪庤偑偗傞丅堦尒偦傟偧傟暿屄偺帠審偱偁傝側偑傜丄廔斦偵側偭偰偦傟傜偺偮側偑傝偑柧傜偐偵側傞丅暔岅偺庡側晳戜偼儈儏儞僿儞偩偑丄庡恖岞偑憑嵏偺偨傔僂傿乕儞偵晪偔僔乕儞偑偁傞丅僂傿乕儞偺奨偺昤幨偼塮夋乽戞嶰偺抝乿傪渇渋偲偝偣傞丅
帊恖僔儔乕偺尵偭偨尵梩偲偟偰堷梡偝傟傞乽恀幚偼嫊婾偺側偐偵惗偒懕偗傞乿側偳丄報徾怺偄僼儗乕僘偑偦偙偐偟偙偵弌偰偔傞丅慜敿偼僴乕僪儃僀儖僪丒僞僢僠偩偑丄屻敿丄僫僠偺巆搣偲CIA偵傛偭偰悌偵偼傔傜傟偨僌儞僞乕偺斀寕偲暅廞偲偄偆榖偵側偭偰丄夆慠丄朻尟彫愢偺怓嵤傪懷傃傞丅慞嬍丄埆嬍擖傝棎傟偰搊応恖暔偼懡嵤偩偑丄扤偑慞偱扤偑埆偲扨弮偵妱傝愗傜側偄懆偊曽偑丄杮彂偵墱峴偒偲尰幚姶傪梌偊偰偄傞丅儈僗僥儕乕偲偟偰偺弌棃偼忋乆偱丄撉傒偛偨偊廩暘偩丅
嫽枴傪庝偐傟傞偺偼丄杮彂偱岅傜傟傞僫僠偺愴斊庪傝偺幚懺偲僇僩儕僢僋嫵夛偺壥偨偟偨栶妱偩丅僫僠偺巆搣偼丄偁傞幰偼宱楌傪嵓徧偟偰擄傪摝傟丄偁傞幰偼抧壓慻怐偺彆偗偱撿暷偵摝朣偡傞丅抧壓慻怐僆僨僢僒偲偲傕偵斵傜偺摝朣傪彆偗偰偄偨偺偑僇僩儕僢僋嫵夛偩偭偨丅柺敀偄偙偲偵丄僇僩儕僢僋嫵夛偼愴帪拞偼夵廆偟偨儐僟儎恖傪崙奜偵朣柦偝偣偰偄偨丅偮傑傝斵傜偼儐僟儎恖傕僫僠傕偲傕偵彆偗偰偄偨傢偗偱偁傞丅僪僀僣偲偄偆崙偑懱尡偟偨恏巁偲暅嫽偵岦偗偰柾嶕偡傞巔偑崕柧偵昤偐傟偰偄傞偺偑報徾怺偄丅
 傕偆1嶜丄僋儗僀僌丒儅僋僪僫儖僪偺乽僷儞僠儑丒價儕儍偺悌乿乮廤塸幮暥屔乯傕丄晽曄傢傝偩偑偗偭偙偆妝偟偄儈僗僥儕乕偩偭偨丅庡恖岞偼塮夋偺媟杮傕彂偔斊嵾彫愢壠丄帪戙偼1957擭丄儊僉僔僐丄僥僉僒僗丄儘僒儞僕僃儖僗傪晳戜偲偡傞朻尟彫愢偩丅儊僉僔僐妚柦偺塸梇僷儞僠儑丒價儕儍偑埫嶦偝傟偨偁偲丄堚懱傪杽傔偨曟偐傜摢晹偑愗抐偝傟偰扤偐偵搻傑傟偨乗乗杮彂偼偙偺1920擭戙敿偽偵婲偒偨巎幚傪壓晘偒偵偟偰彂偐傟偰偄傞丅慜敿偺庱偺憟扗愴傗嵿曮扵偟偵傑偮傢傞僪僞僶僞寑偼僪僫儖僪丒僂僃僗僩儗僀僋晽偩偟丄庰偲彈偑岲偒側攋柵宆偺庡恖岞偲偄偆憿宍傗丄斶垼姶偑擹偔側傞屻敿偼僕僃僀儉僘丒僋儔儉儕乕傪憐婲偝偣傞丅偝傜偵乬庱乭偮側偑傝偱丄僒儉丒儁僉儞僷乕偺寙嶌塮夋乽僈儖僔傾偺庱乿偑偄傗偍偆側偔巚偄晜偐傇丅
傕偆1嶜丄僋儗僀僌丒儅僋僪僫儖僪偺乽僷儞僠儑丒價儕儍偺悌乿乮廤塸幮暥屔乯傕丄晽曄傢傝偩偑偗偭偙偆妝偟偄儈僗僥儕乕偩偭偨丅庡恖岞偼塮夋偺媟杮傕彂偔斊嵾彫愢壠丄帪戙偼1957擭丄儊僉僔僐丄僥僉僒僗丄儘僒儞僕僃儖僗傪晳戜偲偡傞朻尟彫愢偩丅儊僉僔僐妚柦偺塸梇僷儞僠儑丒價儕儍偑埫嶦偝傟偨偁偲丄堚懱傪杽傔偨曟偐傜摢晹偑愗抐偝傟偰扤偐偵搻傑傟偨乗乗杮彂偼偙偺1920擭戙敿偽偵婲偒偨巎幚傪壓晘偒偵偟偰彂偐傟偰偄傞丅慜敿偺庱偺憟扗愴傗嵿曮扵偟偵傑偮傢傞僪僞僶僞寑偼僪僫儖僪丒僂僃僗僩儗僀僋晽偩偟丄庰偲彈偑岲偒側攋柵宆偺庡恖岞偲偄偆憿宍傗丄斶垼姶偑擹偔側傞屻敿偼僕僃僀儉僘丒僋儔儉儕乕傪憐婲偝偣傞丅偝傜偵乬庱乭偮側偑傝偱丄僒儉丒儁僉儞僷乕偺寙嶌塮夋乽僈儖僔傾偺庱乿偑偄傗偍偆側偔巚偄晜偐傇丅幚嵼偺恖暔偑偨偔偝傫搊応偡傞偺傕嫽枴傪屇傇丅庡恖岞偼媟杮偵偮偄偰彆尵偡傞偨傔丄塮夋乽崟偄悌乿偺嶣塭尰応偵峴偔丅偦偙偱娔撀偺僆乕僜儞丒僂僃儖僘偲栥拝傪婲偙偟偨傝丄弌墘偟偰偄偨彈桪儅儗乕僱丒僨傿乕僩儕僢僸偲媽岎傪壏傔偨傝偡傞丅乽崟偄悌乿偼僂僃儖僘偑傾儊儕僇偱嶣偭偨嵟屻偺塮夋偱丄1958擭偺岞奐摉帪偼晄昡偩偭偨偑偺偪偵嵞昡壙偝傟丄崱偱偼僇儖僩揑側柤嶌偲偟偰偺掕拝偟偰偄傞丅僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺嵟屻偺寙嶌偲偝傟偰偍傝丄朻摢偺僋儗乕儞傪巊偭偨挿夞偟嶣塭偑徴寕揑偩偭偨丅
傎偐偵丄庡恖岞偺偗傫偐暿傟偟偨桭偩偪偲偄偆愝掕偱僿儈儞僌僂僃僀偑壗搙傕尵媦偝傟傞丅曅栚偺揱愢揑側娔撀僒儉丒僼僅乕僪偺儌僨儖偼丄夝愢巵偺尵偆傾儞僪儗丒僪丒僩僗偱偼側偔丄柤慜偐傜偟偰丄屻擭栚傪姵偭偰娽懷傪偟偰偄偨僕儑儞丒僼僅乕僪偱偁傠偆丅偁傞偄偼儔僆乕儖丒僂僅儖僔儏偐丅柺敀偄偺偼丄偁偺僀儔僋愴憟傪婲偙偟偨暷崙慜戝摑椞僕儑乕僕乬墡偺擼傒偦乭僽僢僔儏偑搊応偡傞偙偲丅戝妛惗偲偟偰巔傪尒偣傞僽僢僔儏偼堄奜偵傕庡恖岞傪彆偗傞慞恖栶偩丅偝傜偵僽僢僔儏偺慶晝偱偁傞摉帪偺忋堾媍堳僾儗僗僐僢僩丒僽僢僔儏偑埆栶偲偟偰搊応丄僀僃乕儖戝妛偺旈枾寢幮僗僇儖仌儃乕儞僘偺崟枊偲偟偰庡恖岞傪捛偄偐偗夞偡丅
惓捈側偲偙傠丄杮彂偺儈僗僥儕乕彫愢偲偟偰偺弌棃偼偄傑偄偪偩丅僾儘僢僩偼枹徚壔偩偟揥奐傕峳偭傐偄丅偦傟偱傕乽巭傑偭偨帪寁偱傕1擔偵2夞偼惓妋側帪崗傪巜偡乿偲偄偆傛偆側婥偺棙偄偨寈嬪偑憓擖偝傟偰偄傞偟丄塮夋嶣塭偺棤榖傗幚嵼偺恖暔偺棈傒傕柺敀偔丄晄巚媍側枺椡傪偨偨偊偰偄傞偙偲偼娫堘偄側偄丅
2011.12.27 (壩) 擭枛嶨姶乣偝傜偽柉庡搣
2011擭偼丄悽奅偵栚傪岦偗傞偲丄拞搶偵柉庡壔塣摦偑悂偒峳傟偨乽傾儔僽偺弔乿偲偲傕偵丄旍戝壔偟偨嬥梈帒杮懱惂偑攋抅偟偨擭偩偭偨丅埆抦宐傪摥偐偣丄嬥傪揮偑偟偰棙塿傪摼傞儅僱乕丒僎乕儉偑峴偒拝偄偨抧揰偑丄悽奅揑側嬥梈晄埨偩偭偨丅偦傟偵偟偰傕丄扨側傞堦巹婇嬈偱偁傞奿晅偗夛幮偑崙嵚偺奿晅偗傪壓偘偨偩偗偱姅壙偑棎崅壓偟丄傗傟嵿惌攋抅偩偲戝憶偓偵側傞偺偼丄偳偆峫偊偰傕堎忢偩丅壗搙傕偺嬯擄傪宱偰恖椶偑攟偭偨偼偢偺塨抭偼偳偙偵徚偊偨偺偐丅
偟偐偟擔杮偱偼丄2011擭偼搶擔杮戝恔嵭偲搶揹暉搰尨敪帠屘偺擭偲偟偰楌巎偵崗傑傟傞偩傠偆丅恔嵭偑媦傏偟偨徴寕偲塭嬁偼戝偒偐偭偨丅偦偟偰惌帯偺偆偊偱偼丄2011擭偼柉庡搣惌尃偺柍擻椡偝丄媆嵩偲棤愗傝偑柧傜偐偵側偭偨擭偱傕偁偭偨丅恔嵭偐傜偺暅嫽巤嶔偺抶傟丄尨敪帠屘傊偺懳張偺搈愶偝偼丄惌晎偺愑擟埲奜偺側偵傕偺偱傕側偄丅12寧16擔偵敪昞偝傟偨尨敪帠屘廂懇偺愰尵側偳偼丄尰幚偲偼偐偗棧傟偰偍傝丄拑斣偲偟偐尵偄傛偆偑側偄丅扤傕偑廂懇偲偼掱墦偄忬懺偩偲抦偭偰偄傞丅摉弶偼惙傝忋偑偭偨扙尨敪偺婡塣傗揹椡嫙媼僔僗僥儉偺尒捈偟榑媍傕丄偄傑偼堔偊偰偟傑偭偨丅
柉庡搣惌尃偼丄數嶳丄悰丄栰揷偲擫偺栚偺傛偆偵庱憡偑岎戙偡傞偵偮傟偰丄傑偡傑偡傂偳偔側偭偰偄傞丅傏偔偨偪偼屆偄惌帯偐傜偺扙媝偲夵妚傪媮傔偰柉庡搣偵搳昜偟偨偺偵丄偄傑傗柉庡搣偼帺柉搣偲傑偭偨偔曄傢傜側偄惌搣偵側傝壓偑偭偨丅栰揷惌尃偼崙柉偲偺栺懇偱偁傞儅僯僼僃僗僩傪師乆偲攋偭偰暯慠偲偟偰偄傞丅偙傟偼傑偝偵棤愗傝峴堊偩丅岞柋堳夵妚偼偄偭偙偆偵庤傪偮偗傛偆偲偣偢丄徚旓憹惻傪懪偪弌偟丄姱椈偺嬝彂偒偳偍傝偵摦偒丄嵿奅偺婄怓傪偆偐偑偭偰惌嶔傪寛傔傞丅柍懯側巟弌傪徣偔怳傝傪偡傞偨傔丄壗偺岠椡傕側偄偺偵帠嬈巇暘偗偲偄偆屍懅側幣嫃傪偡傞丅崙柉傪嬸楳偡傞偵傕傎偳偑偁傞丅
偁偘偔偺偼偰偼敧僣応僟儉岺帠嵞奐偺寛掕偩丅儅僯僼僃僗僩偱壺乆偟偔傇偪忋偘偨戝宆岞嫟帠嬈尒捈偟曽恓偺姰慡側曻婞偱偁傞丅崙岎徣偵晧偗偠偲偽偐傝偵丄杊塹徣偼師婜愴摤婡偺摫擖傪寛傔偨丅堦婡悢昐壄墌傕偡傞愴摤婡傪暷崙偐傜戝検偵峸擖偡傞偺偩丅嵿惌愒帤偱嬯偟傫偱偄傞偄傑丄偦傫側偙偲偵嫄妟偺旓梡傪搳偠傞梋桾側偳側偄偼偢偩丅惌晎偼奺徣挕偺僐儞僩儘乕儖偑傑偭偨偔偱偒偰偄側偄丄巟棧柵楐偩丅
偦傟偵捛偄懪偪傪偐偗偨偺偑丄12寧24擔偵敪昞偝傟偨棃擭搙偺惌晎梊嶼埬偩丅崙偺庁嬥傪尭傜偝側偗傟偽偄偗側偄偺偵丄崙嵚偺敪峴偑夁嫀嵟戝偩偦偆偩丅偦偟偰敧僣応僟儉傪偼偠傔偲偡傞岞嫟帠嬈旓偑戝偒偔寁忋偝傟偰偄傞丅嵨弌嶍尭偑昁梫側偲偒丄傑偟偰傗嫄妟偺暅嫽旓傗幮婥曐忈旓傪寁忋偟側偗傟偽偄偗側偄偲偒丄側偤岞嫟帠嬈傪憹傗偡偺偐丅偙偙傑偱傗傞偐偲嬃偔偺偼幮夛曐忈旓偵娭偡傞偐傜偔傝偱偁傝丄偦偺堦晹偼偙傟偐傜傗傞憹惻傪嵿尮偵偟偰偄傞偲偄偆丅憹惻朄埬偑崙夛傪捠傜側偐偭偨傜偳偆偡傞偺偩傠偆丅偙傟偼暡忺梊嶼偦偺傕偺偱偁傝丄堦斒偺婇嬈側傜偗偭偟偰彸擣偝傟側偄偩傠偆丅嵿柋姱椈偺峫偊晅偄偨埬傪偦偺傑傑嵦梡偟偨偺偩傠偆偑丄栰揷惌尃偺姱椈埶懚懱幙偑抂揑偵昞傟偰偄傞丅
栰揷庱憡偺嬸枂偝丄巜摫椡偺側偝偵偼丄忣偗側偔偰尵梩傕弌側偄丅擻柺偺傛偆側昞忣偺朢偟偄婄偱尨峞傪朹撉傒偟丄僶僇偺傂偲偮妎偊偺傛偆偵徚旓憹惻傊偺堄梸傪孞傝曉偡偩偗偱丄夵妚傊偺忣擬偼傑偭偨偔偆偐偑傢傟側偄丅徚旓憹惻傪偡傞側偲尵偭偰偄傞偺偱偼側偄丅偦偺慜偵傗傞偙偲偑偁傞偩傠偆偲尵偭偰偄傞偺偩丅嵨弌傪尭傜偡搘椡傪偣偢丄壗偑憹惻偐丅儅僯僼僃僗僩偱偆偨偭偰偄偨岞柋堳恖審旓偺嶍尭丄媍堳掕悢偺嶍尭偼丄側偵傂偲偮庤傪偮偗偰偄側偄丅
妕椈傕柍擻側傏傫偔傜戝恇偽偐傝偩丅摗懞姱朳挿姱偼僇僄儖偺傛偆側婄偱儃僜儃僜偲挐傞偩偗偱丄敆椡偺側偄偙偲偍傃偨偩偟偄丅僇僄儖偺傎偆偑傑偩惗婥偵枮偪偰偄傞丅嵟埆側偺偼尯梩奜柋憡偩丅11寧壓弡丄擔暷抧埵嫤掕偺嵸敾尃偺塣梡尒捈偟偵偮偄偰暷懁偺崌堄傪摼偨偲丄戝偒側栚嬍傪僊儑儘偮偐偣偰摼堄偘偵敪昞偟偰偄偨偑丄壗偺偙偲偼側偄丄幚懺偼暷懁偺嵸検偵擟偝傟偰偄傞傢偗偱丄嫤掕偦偺傕偺傪夵惓偟側偄偐偓傝丄嵼擔暷孯偑帯奜朄尃忬懺偱偁傞偙偲偵曄傢傝偼側偄丅尯梩偺奜岎偵偮偄偰偺幆尒傗擻椡偼僛儘偵嬤偄丅暷崙偺婄怓偽偐傝傪偆偐偑偄丄嫏慏偺椞奀怤斊偵懳偟偰拞崙偵峈媍傕偱偒側偄丅抰愘側奜岎偵傛偭偰擔杮偺庡尃偼怤奞偝傟傞堦曽偩丅偁偘偔偺偼偰偼丄挀僋儘傾僠傾戝巊偺僙僋僴儔帠審傪埮偵憭傞偲偄偆斱楎側偙偲傪傗傞丅堦愳杊塹憡偺嬸撦偲柍抦栔枂偼尵傢偢傕偑側丄懠偺妕椈傕悇偟偰抦傞傋偟偩丅傒傫側姱椈偺庤偺傂傜偱偁傗偮傜傟傞孞傝恖宍偩丅姱椈偨偪偼傎偔偦徫傫偱偄傞偵堘偄側偄丅
敧僣応僟儉岺帠嵞奐傗TPP悇恑偵峈媍偟偰柉庡搣偐傜棧搣偡傞媍堳偑尰傟巒傔偨丅摉慠偺寢壥偩丅偄傑偺搣偺曽恓偵偼廬偊側偄偲偄偆帺暘偺怣忦偐傜偵偣傛丄師偺慖嫇偱柉庡搣偱偼棊慖偡傞偲偄偆曐恎偐傜偵偣傛丄偙傟偐傜棧搣幰偼傕偭偲憹偊傞偩傠偆丅偁傞偄偼彫戲堦榊偺堦攈偑戝嫇偟偰棧搣偟丄怴偟偄搣傪棫偪忋偘傞偐傕偟傟側偄丅傕偼傗丄偄傑偺柉庡搣偵婜懸偡傞傕偺偼壗傕側偄丅偙偺傑傑偱偼柉庡搣偼夝懱偟偨傎偆偑偄偄丅
傕偆媽棃偺惌帯壠丄婛惉偺惌搣偼偁偰偵偱偒側偄丅偱傕丄偩偐傜偲偄偭偰丄偨偲偊偽戝嶃偱慁晽傪姫偒婲偙偟偰偄傞嫶壓揙偵婜懸偱偒傞偺偩傠偆偐丅惌帯壠傜偟偐傜偸棪捈暯柧側暔尵偄偼岲姶偑帩偰傞偟丄柧妋側栚昗愝掕椡偲壥姼側幚峴椡偑偁傞偺偼徹柧嵪偩丅偲偼偄偊丄乽惌帯偼撈嵸偩乿偲橖慠偲尵偄曻偮偺偼丄堦柺偺恀棟傪撍偄偰偄傞偵偣傛丄惵廘偄姶偠偑斲傔側偄丅崙惌偵娭偟偰偳傫側峫偊傪帩偭偰偄傞偺偐傕枹抦悢偩丅偦傟偱傕丄偄傑偺晠偭偨惌帯偵晽寠傪奐偗傞偨傔偵偼丄嫶杮揙揑側棳傟傗丄偁傞偄偼柤屆壆偺壨懞偨偐偟偑悇偟恑傔傞夵妚塣摦偵婓朷傪偮側偖偟偐側偄偺偐傕偟傟側偄丅
2011.12.17 (搚) 2011擭奀奜塮夋儀僗僩10
侾丏 乽僑乕僗僩儔僀僞乕乿丂儘儅儞丒億儔儞僗僉乕丂乮暓丒撈丒塸乯
俀丏 乽僩儖乕丒僌儕僢僩乿丂僕儑僄儖仌僀乕僒儞丒僐乕僄儞丂乮暷乯
俁丏 乽僓丒僼傽僀僞乕乿丂僨償傿僢僪丒俷丒儔僢僙儖丂乮暷乯
係丏 乽僸傾傾僼僞乕乿丂僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪丂乮暷乯
俆丏 乽偙偺垽偺偨傔偵寕偰乿丂僼儗僢僪丒僇償傽僀僄丂乮暓乯
俇丏 乽僽儔僢僋丒僗儚儞乿丂僟乕儗儞丒傾儘僲僼僗僉乕丂乮暷乯
俈丏 乽懛暥偺媊巑抍乿丂僥僨傿丒僠儍儞丂乮拞丒崄乯
俉丏 乽傾儕僗丒僋儕乕僪偺幐鏗乿丂J丒僽儗僀僋僜儞丂乮塸乯
俋丏 乽儔僗僩丒僞乕僎僢僩乿丂傾儞僩儞丒僐儖儀僀儞丂乮暷乯
10丏乽僓丒僞僂儞乿丂儀儞丒傾僼儕僢僋丂乮暷乯
 丂丂1埵偺乽僑乕僗僩儔僀僞乕乿偼丄偄傑傗嫄彔偺晹椶偵擖偭偨億儔儞僗僉乕娔撀丄儐傾儞丒儅僋儗僈乕庡墘偺僒僗儁儞僗塮夋丅尦塸崙庱憡偺幏昅偡傞帺彇揱偺僑乕僗僩儔僀僞乕偵屬傢傟偨庡恖岞偑丄巇帠拞偵書偄偨撲傪夝偒柧偐偡偆偪偵嫄戝側堿杁偺懚嵼偵婥偑偮偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偟偩偄偵怺傑傞撲丄廃摓偵楙傜傟偨暁慄丄鉱枾側夋柺峔惉丄柍懯偺側偄応柺揥奐丄億儔儞僗僉乕偺嶌寑弍偺岻偝偵悓傢偝傟傞丅偲傝傢偗庡側晳戜偵側傞暷崙搶奀娸偺搰偺峳椓偲偟偨晽宨偼報徾怺偔丄偦傟偩偗偱夋柺偑壗偐傪岅傝偐偗偰偔傞丅傓偐偟嶣偭偨乽僠儍僀僫僞僂儞乿傪巚傢偣傞億儔儞僗僉乕偺僗僩乕儕乕僥儕儞僌偺柇傪姮擻偱偒傞丅
丂丂1埵偺乽僑乕僗僩儔僀僞乕乿偼丄偄傑傗嫄彔偺晹椶偵擖偭偨億儔儞僗僉乕娔撀丄儐傾儞丒儅僋儗僈乕庡墘偺僒僗儁儞僗塮夋丅尦塸崙庱憡偺幏昅偡傞帺彇揱偺僑乕僗僩儔僀僞乕偵屬傢傟偨庡恖岞偑丄巇帠拞偵書偄偨撲傪夝偒柧偐偡偆偪偵嫄戝側堿杁偺懚嵼偵婥偑偮偔丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅偟偩偄偵怺傑傞撲丄廃摓偵楙傜傟偨暁慄丄鉱枾側夋柺峔惉丄柍懯偺側偄応柺揥奐丄億儔儞僗僉乕偺嶌寑弍偺岻偝偵悓傢偝傟傞丅偲傝傢偗庡側晳戜偵側傞暷崙搶奀娸偺搰偺峳椓偲偟偨晽宨偼報徾怺偔丄偦傟偩偗偱夋柺偑壗偐傪岅傝偐偗偰偔傞丅傓偐偟嶣偭偨乽僠儍僀僫僞僂儞乿傪巚傢偣傞億儔儞僗僉乕偺僗僩乕儕乕僥儕儞僌偺柇傪姮擻偱偒傞丅丂丂2埵偺乽僩儖乕丒僌儕僢僩乿偼僐乕僄儞孼掜偵傛傞60擭戙偺僕儑儞丒僂僃僀儞庡墘塮夋乽桬婥偁傞捛愓乿傪儕儊僀僋偟偨惣晹寑丅悓偄偳傟曐埨姱偲婥忎側彮彈偵傛傞丄彮彈偺晝傪嶦偟偨斊恖偺捛愓峴傪昤偄偨塮夋丅僞僼側彮彈傪墘偠傞僿僀儕乕丒僗僞僀儞僼僃儖僪偺怴恖偲傕巚偊偸摪偵擖偭偨墘媄偑廏堩丅僕僃僼丒僽儕僢僕僗偼偁傑傝岲偒側栶幰偱偼側偄偑丄偙偺塮夋偱偺曐埨姱栶偼側偐側偐偺傕偺丅儐乕儌傾傪怐傝岎偤偨崪懢偱僪儔僀側暤埻婥偺側偐偵恄榖揑側僀儊乕僕偑奯娫尒偊傞墘弌偑慺惏傜偟偄丅廔斦丄彮彈傪書偊偰傂偨憱傞曐埨姱偺摢忋偵枮揤偺惎偑傑偨偨偔僔乕儞偼埑姫偱偁傝丄偁偺僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺柤嶌乽庪恖偺栭乿傪憐婲偝偣傞丅
丂丂3埵偺乽僓丒僼傽僀僞乕乿偼壠懓偺鉐傪幉偵悩偊偨幚榖偵婎偯偔儃僋僔儞僌塮夋丅庡恖岞偼儃僋僒乕栶偺儅乕僋丒僂僅儖僶乕僌偩偑丄傓偟傠庡恖岞傛傝斵傪庢傝姫偔帺懧棊側壠懓偺傎偆偑報徾怺偄丅庡恖岞偼儅僱乕僕儍乕傪柋傔傞恎彑庤側孼偲曣恊偵怳傝夞偝傟傞偺偩偑丄偙偺孼偲曣恊偺憸偑愨昳偱丄偲傝傢偗孼栶偺僋儕僗僠儍儞丒儀僀儖偑偠偮偵偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅偄偄壛尭偩偑垽偡傋偒壠懓偲恀柺栚側懅巕偺愗傞偵愗傟側偄鉐偑丄怺崗偵偱偼側偔寉柇側僞僢僠偱昤偐傟偰偄傞偺偑柺敀偄丅僄儞僨傿儞僌丒儘乕儖偱塮偟弌
 偝傟傞儌僨儖偵側偭偨幚嵼偺尦儃僋僒乕偺塮憸偑報徾偵巆傞丅
偝傟傞儌僨儖偵側偭偨幚嵼偺尦儃僋僒乕偺塮憸偑報徾偵巆傞丅丂丂4埵偺乽僸傾傾僼僞乕乿偼僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪娔撀偵偟偰偼捒偟偄巰屻偺悽奅傪埖偭偨僗僺儕僠儏傾儖仌僸乕儕儞僌丒僪儔儅丅朻摢偵敆恀偺捗攇偺僔乕儞偑偁傞偑丄偙偺塮夋傪尒偰娫傕側偔搶擔杮戝恔嵭偑偁傝丄偦偺僔儞僋儘僯僔僥傿偵徴寕傪庴偗偨丅巰幰傪扱偒丄桙偟傪摼偨偄偲婅偆恖娫偺姶忣偑扥擮偵昤偒弌偝傟丄僀乕僗僩僂僢僪嶌昳偵偟偰偼屻枴偺偄偄塮夋偵巇忋偑偭偰偄傞丅梷偊偨墘媄偑尒帠側楈擻幰栶偺儅僢僩丒僨僀儌儞傪偼偠傔丄栶幰偨偪偺岻偝偑嵺棫偭偰偄傞丅
 丂丂5埵偺乽偙偺垽偺偨傔偵寕偰乿偼丄桿夳偝傟偨恎廳偺嵢傪媬偆偨傔娕岇巑偺晇偑屒孯暠摤偡傞僼儔儞僗偺僗儕儔乕丒傾僋僔儑儞丅斊恖偺梫媮偵廬偭偨偨傔寈嶡偵捛傢傟傞攋栚偵娮偭偨庡恖岞偼丄愨朷揑側忬嫷偺側偐丄嵢傪媬偆偨傔僷儕偺奨傪憱傝夞傞丅岲昡傪攷偟偨僇償傽僀僄娔撀偺慜嶌乽偡傋偰斵彈偺偨傔偵乿傕摨偠傛偆側愝掕偺塮夋偩偭偨偑丄嬞敆姶偼崱嶌偺傎偆偑忋傑傢傞丅偛偔晛捠偺抝偺昁巰偺愴偄偑彫婥枴偄偄僞僢僠偱昤偐傟傞丅僴儕僂僢僪惢偺梊嶼偲CG傪偨偭傉傝巊偭偨戝枴側傾僋僔儑儞塮夋偲斾傋偰丄側傫偲惗嵤偵晉傫偱偄傞偙偲偐丅
丂丂5埵偺乽偙偺垽偺偨傔偵寕偰乿偼丄桿夳偝傟偨恎廳偺嵢傪媬偆偨傔娕岇巑偺晇偑屒孯暠摤偡傞僼儔儞僗偺僗儕儔乕丒傾僋僔儑儞丅斊恖偺梫媮偵廬偭偨偨傔寈嶡偵捛傢傟傞攋栚偵娮偭偨庡恖岞偼丄愨朷揑側忬嫷偺側偐丄嵢傪媬偆偨傔僷儕偺奨傪憱傝夞傞丅岲昡傪攷偟偨僇償傽僀僄娔撀偺慜嶌乽偡傋偰斵彈偺偨傔偵乿傕摨偠傛偆側愝掕偺塮夋偩偭偨偑丄嬞敆姶偼崱嶌偺傎偆偑忋傑傢傞丅偛偔晛捠偺抝偺昁巰偺愴偄偑彫婥枴偄偄僞僢僠偱昤偐傟傞丅僴儕僂僢僪惢偺梊嶼偲CG傪偨偭傉傝巊偭偨戝枴側傾僋僔儑儞塮夋偲斾傋偰丄側傫偲惗嵤偵晉傫偱偄傞偙偲偐丅丂丂6埵偺乽僽儔僢僋丒僗儚儞乿偼僫僞儕乕丒億乕僩儅儞偺憇愨側墘媄偱榖戣偵側偭偨僶儗僄傪戣嵽偲偡傞儂儔乕丒僞僢僠偺僒僀僐塮夋丅傾儘僲僼僗僉乕娔撀偺慜嶌乽儗僗儔乕乿偱偼晝偲柡偺偡傟堘偆垽偑昤偐傟偰偄偨偑丄杮嶌偱偼曣偲柡偺榗傫偩垽偑傂偲偮偺僥乕儅偵側偭偰偄傞丅僾儕儅傪傔偞偡僶儗儕乕僫偑惛恄揑偵捛偄偮傔傜傟傞條巕偑幏漍偵昤偐傟丄廳嬯偟偄嬞挘姶傪惗傫偱偄傞丅
 丂丂7埵偺乽懛暥偺媊巑抍乿偼恏堝妚柦慜栭偺崄峘傪晳戜偵丄寛婲偺懪偪崌傢偣偺偨傔偵棫偪婑偭偨懛暥傪埫嶦幰偺堦抍偐傜庣偭偰暠摤偡傞抝偨偪偺幪恎偺愴偄傪昤偄偨妶寑傾僋僔儑儞塮夋丅僪僯乕丒僀僃儞傗儗僆儞丒儔僀側偳偺僗僞乕偑戝惃弌墘偟偰偄傞偑丄摿掕偺庡恖岞偑偄側偄丄偄傢偽孮憸寑偺傛偆側峔惉丅偲偵偐偔傾僋僔儑儞丒僔乕儞偺敆椡偵搙娞傪敳偐傟傞丅屻敿偼惁傑偠偄僇儞僼乕丒傾僋僔儑儞偺楢懕偱丄崄峘塮夋偺鐥偟偄僷儚乕傪姶偠偝偣傞丅
丂丂7埵偺乽懛暥偺媊巑抍乿偼恏堝妚柦慜栭偺崄峘傪晳戜偵丄寛婲偺懪偪崌傢偣偺偨傔偵棫偪婑偭偨懛暥傪埫嶦幰偺堦抍偐傜庣偭偰暠摤偡傞抝偨偪偺幪恎偺愴偄傪昤偄偨妶寑傾僋僔儑儞塮夋丅僪僯乕丒僀僃儞傗儗僆儞丒儔僀側偳偺僗僞乕偑戝惃弌墘偟偰偄傞偑丄摿掕偺庡恖岞偑偄側偄丄偄傢偽孮憸寑偺傛偆側峔惉丅偲偵偐偔傾僋僔儑儞丒僔乕儞偺敆椡偵搙娞傪敳偐傟傞丅屻敿偼惁傑偠偄僇儞僼乕丒傾僋僔儑儞偺楢懕偱丄崄峘塮夋偺鐥偟偄僷儚乕傪姶偠偝偣傞丅丂丂8埵偺乽傾儕僗丒僋儕乕僪偺幐鏗乿偼崱擭偺孈傝弌偟暔偺堦嶌丅嶀偊側偄抝2恖偑恎戙嬥栚摉偰偱嬥帩偪偺柡傪桿夳偡傞帠審傪昤偄偨僋儔僀儉丒僒僗儁儞僗丅僗僩乕儕乕偼擇揮嶰揮偟丄桿夳偝傟偨柡偲斊恖偺抝偨偪偺棫応偑媡揮偟偨傝丄抝偨偪偺儂儌僙僋僔儍儖娭學偑埫帵偝傟偨傝偲丄嬃湵偺枊愗傟偵帄傞傑偱丄傑偭偨偔梊抐傪嫋偝側偄丅搊応恖暔偼偨偭偨3恖丄応柺偼傎偲傫偳娔嬛応強偺傒偲偄偆掅梊嶼塮夋偩偑丄鉱枾側峔惉偵傛偭偰慡曇偵僥儞僔儑儞偑挘傝媗傔偰偄傞丅
丂丂9埵偺乽儔僗僩丒僞乕僎僢僩乿偼僕儑乕僕丒僋儖乕僯乕庡墘偺僴乕僪儃僀儖僪丒僞僢僠偺僗儕儔乕丅堷戅傪寛傔偨屒撈側埫嶦幰偑嵟屻偵堷偒庴偗偨巇帠偵偼悌偑巇妡偗傜傟偰偄偨丄偲偄偆僗僩乕儕乕丅庡恖岞偑塀傟廧傓僀僞儕傾偺揷幧挰偺偺偳偐側晽宨偑偄偄偟丄扺乆偲昤偐傟傞擔忢惗妶傕愢摼椡偑偁傞丅偨偩偟儔僗僩偑娒偄丅尨嶌乮乽埫埮偺挶乿乯偺旕忣偵揙偟偨昤偒曽偵斾傋偰丄塮夋偼姶彎揑夁偓傞丅
丂丂10埵偺乽僓丒僞僂儞乿偼儀儞丒傾僼儕僢僋娔撀庡墘丄儃僗僩儞偺斊嵾懡敪抧嬫傪晳戜偵丄嬧峴嫮搻傪惗嬈偲偡傞庡恖岞偺峴偔枛傪昤偄偨僋儔僀儉塮夋丅庡恖岞偼嫮搻偵擖偭偰嬧峴堳偺彈惈傪恖幙偵偲傝夝曻偟偨屻丄偦偺彈惈偲恊偟偔側傞丅彈惈偼嫮搻斊偲偼抦傜偢偵庡恖岞偲楒偵棊偪傞丅嫮搻拠娫摨巑偺斀栚傗FBI偲偺嬱偗堷偒偑僗儕儕儞僌偩偟丄儃僗僩儞偺奨偱偺儘働偑儕傾儖偝傪嵺棫偨偣偰偄傞丅
丂丂寳奜偺嶌昳偱偼丄傾僇僨儈乕徿偺庡梫晹栧傪傎傏撈愯偟偨乽塸崙墹偺僗僺乕僠乿偑偁傞偑丄挌擩偵嶌傜傟偨楌巎僪儔儅偱偼偁傞傕偺偺丄偦傟傎偳姶柫傪庴偗傞塮夋偲傕巚偊側偄丅傎偐偵嫽枴傪堷偄偨傕偺偵乽僼僃僀僋丒僋儔僀儉乿偑偁傞丅僐儊僨傿丒僞僢僠偺僋儔僀儉丒僒僗儁儞僗偱丄堦愄慜偺椙幙偺僴儕僂僢僪丒僐儊僨傿傪巚傢偣傞妝偟偄僗僩乕儕乕側偺偩偑丄弌棃偼偄傑偄偪丅庡墘偵僉傾僰丒儕乕償僗偱偼側偔傕偭偲岻偄栶幰傪巊偄丄墘弌偵傕偆堦岺晇偁偭偨傜丄偍偦傜偔尒墳偊偺偁傞塮夋偵側偭偰偄偨偩傠偆丅
2011.12.10 (搚) 2011擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
侾丏丂乽僕僃僲僒僀僪乿丂崅栰榓柧丂乮妏愳彂揦乯
俀丏丂乽棳孻偺奨乿丂僠儍僢僋丒儂乕僈儞丂乮償傿儗僢僕丒僽僢僋僗乯
俁丏丂乽徤巕偺埫嶦幰乿丂僕儑乕丒僑傾僘丂乮晑孠幮暥屔乯
係丏丂乽帪偺抧恾乿丂僼僃儕僋僗丒僷儖儅丂乮憗愳暥屔乯
俆丏丂乽儉乕儞儔僀僩丒儅僀儖乿丂僨僯僗丒儗僿僀儞丂乮憗愳暥屔乯
俇丏丂乽僒僩儕乿丂僪儞丒僂傿儞僘儘僂丂乮憗愳彂朳乯
俈丏丂乽007 敀巻埾擟忬乿丂僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕丂乮暥寍弔廐幮乯
俉丏丂乽13帪娫慜偺枹棃乿丂儕僠儍乕僪丒僪僀僢僠丂乮怴挭暥屔乯
俋丏丂乽惗娨乿丂僯僢僉丒僼儗儞僠丂乮妏愳暥屔乯
10丏 乽擇棳彫愢壠乿丂僨償傿僢僪丒僑乕僪儞丂乮憗愳億働儈僗乯
 丂丂傇偭偪偓傝偺1埵偼崅栰榓柧偺乽僕僃僲僒僀僪乿丅偁傑傝偺埑搢揑側敆椡偲儕乕僟價儕僥傿偵丄奀奜儈僗僥儕乕偲偄偆斖醗傪偁偊偰攋傝丄偙偺崙撪彫愢傪1埵偵偣偞傞傪偊側偐偭偨丅偦傟傎偳杮嶌偼慺惏傜偟偔丄暥嬪偺偮偗傛偆偑側偄丅堦尵偱尵偊偽倶倶倶乮偙傟偐傜撉傓傂偲偺偨傔暁偣傞乯偺抋惗傪僥乕儅偵偟偨俽俥朻尟彫愢偩偑丄偄傠傫側僥乕儅偑棈傫偱偍傝丄抁偄僗儁乕僗偱偼愢柧偟偒傟側偄丅柉娫孯帠夛幮偱摥偔尦傾儊儕僇棨孯摿庩晹戉堳偲栻妛傪妛傇擔杮偺戝妛堾惗偺2恖偑庡恖岞丅庡側晳戜偼搶嫗丄儚僔儞僩儞丄傾僼儕僇偺僐儞僑偩丅嫮楏側撲偑採帵偝傟丄偦傟偑偟偩偄偵柧傜偐偵側偭偰偄偒丄徴寕偺帠幚傊偲寢傃偮偔丅偡傋偰偺僷僘儖偑丄偐偭偪傝偲姎傒崌傢偣傜傟偰偄傞丅偙偙偵偼恑壔丄堛妛丄暥柧丄壢妛側偳偵娭偡傞塻偄峫嶡偑偁傞偑丄偦傟偱偄偰僄儞僞僥僀儞儊儞僩偵揙偟偰偄傞丅傾僼儕僇偱偺扙弌峴偼朻尟傾僋僔儑儞丄儚僔儞僩偱儞偺旈枾嶌愴偼挸曬堿杁寑丄擔杮偱偺憂栻僔乕儞偼僒僗儁儞僗丄偡傋偰偑堦媺昳偺弌棃塰偊偩丅偝傜偵丄悘強偵昤偐傟傞恊巕偺垽丄桬婥偲桭忣偑嫻傪擬偔偡傞丅撉傒巒傔偨傜巭傑傜側偄丄600儁乕僕嬤偄暘検傪堦婥偵撉椆偟偰偟傑偆丅
丂丂傇偭偪偓傝偺1埵偼崅栰榓柧偺乽僕僃僲僒僀僪乿丅偁傑傝偺埑搢揑側敆椡偲儕乕僟價儕僥傿偵丄奀奜儈僗僥儕乕偲偄偆斖醗傪偁偊偰攋傝丄偙偺崙撪彫愢傪1埵偵偣偞傞傪偊側偐偭偨丅偦傟傎偳杮嶌偼慺惏傜偟偔丄暥嬪偺偮偗傛偆偑側偄丅堦尵偱尵偊偽倶倶倶乮偙傟偐傜撉傓傂偲偺偨傔暁偣傞乯偺抋惗傪僥乕儅偵偟偨俽俥朻尟彫愢偩偑丄偄傠傫側僥乕儅偑棈傫偱偍傝丄抁偄僗儁乕僗偱偼愢柧偟偒傟側偄丅柉娫孯帠夛幮偱摥偔尦傾儊儕僇棨孯摿庩晹戉堳偲栻妛傪妛傇擔杮偺戝妛堾惗偺2恖偑庡恖岞丅庡側晳戜偼搶嫗丄儚僔儞僩儞丄傾僼儕僇偺僐儞僑偩丅嫮楏側撲偑採帵偝傟丄偦傟偑偟偩偄偵柧傜偐偵側偭偰偄偒丄徴寕偺帠幚傊偲寢傃偮偔丅偡傋偰偺僷僘儖偑丄偐偭偪傝偲姎傒崌傢偣傜傟偰偄傞丅偙偙偵偼恑壔丄堛妛丄暥柧丄壢妛側偳偵娭偡傞塻偄峫嶡偑偁傞偑丄偦傟偱偄偰僄儞僞僥僀儞儊儞僩偵揙偟偰偄傞丅傾僼儕僇偱偺扙弌峴偼朻尟傾僋僔儑儞丄儚僔儞僩偱儞偺旈枾嶌愴偼挸曬堿杁寑丄擔杮偱偺憂栻僔乕儞偼僒僗儁儞僗丄偡傋偰偑堦媺昳偺弌棃塰偊偩丅偝傜偵丄悘強偵昤偐傟傞恊巕偺垽丄桬婥偲桭忣偑嫻傪擬偔偡傞丅撉傒巒傔偨傜巭傑傜側偄丄600儁乕僕嬤偄暘検傪堦婥偵撉椆偟偰偟傑偆丅 丂丂埲壓偼嬱偗懌偱丅2埵偺僠儍僢僋丒儂乕僈儞乽棳孻偺奨乿偼挀幵応偺寈旛堳傪偟偰偄傞僀儔僋偐傜偺婣娨暫偑庡恖岞偺堿杁偲暅廞傪僥乕儅偵偟偨僴乕僪儃僀儖僪彫愢丅烼孅偟偨擔乆傪憲偭偰偄偨斵偼丄杻栻慻怐傪廝寕偡傞帺寈抍僠乕儉偵壛傢傞丅慡懱偵昚偆旕忣側嬻婥偲揔搙側娒偝偑偄偄偟丄儃僗僩儞偺奨偺昤幨丄搊応恖暔偺僉儍儔僋僞乕憿宍傕枺椡偵晉傓丅僗僩乕儕乕偺棳傟傕夣揔丄妶寑僔乕儞傕敆椡偨偭傉傝偩丅
丂丂埲壓偼嬱偗懌偱丅2埵偺僠儍僢僋丒儂乕僈儞乽棳孻偺奨乿偼挀幵応偺寈旛堳傪偟偰偄傞僀儔僋偐傜偺婣娨暫偑庡恖岞偺堿杁偲暅廞傪僥乕儅偵偟偨僴乕僪儃僀儖僪彫愢丅烼孅偟偨擔乆傪憲偭偰偄偨斵偼丄杻栻慻怐傪廝寕偡傞帺寈抍僠乕儉偵壛傢傞丅慡懱偵昚偆旕忣側嬻婥偲揔搙側娒偝偑偄偄偟丄儃僗僩儞偺奨偺昤幨丄搊応恖暔偺僉儍儔僋僞乕憿宍傕枺椡偵晉傓丅僗僩乕儕乕偺棳傟傕夣揔丄妶寑僔乕儞傕敆椡偨偭傉傝偩丅丂丂3埵偺僕儑乕丒僑傾僘乽徤巕偺埫嶦幰乿偼傾僼儕僇偱枾椔娔帇堳偲偟偰摥偔尦CIA偺晀榬僗僫僀僷乕偑庡恖岞偺朻尟彫愢丅斵偼戝摑椞埫嶦寁夋傪慾巭偡傞偨傔偵屇傃栠偝傟傞偑丄偦偙偵偼悌偑巇妡偗傜傟偰偄偨丅儌儞僞僫偺嶳妜抧懷偱揥奐偡傞捛偆幰偲捛傢傟傞幰丄僾儘偺僗僫僀僷乕摨巑偵懳寛偑僗儕儕儞僌偩丅愨捀婜偺僗僥傿乕償儞丒僴儞僞乕傪憐婲偝偣傞媽偒壚偒惣晹寑偺枴傢偄偑壗偲傕尵偊側偄丅
丂丂4埵偺僗儁僀儞偺嶌壠丄僼僃儕僋僗丒僷儖儅挊乽帪偺抧恾乿偼3晹峔惉偺帪娫椃峴SF彫愢丅帪偼19悽婭枛偺儘儞僪儞丅愗傝楐偒僕儍僢僋傗僄儗僼傽儞僩丒儅儞傗僽儔儉丒僗僩乕僇乕側偳幚嵼偺恖暔偑搊応偟偰壴傪揧偊傞丅慡懱偺嫸尵夞偟傪柋傔傞H丒G丒僂僃儖僘偼戞3晹偱偼庡恖岞偲側偭偰戝妶桇偡傞丅偪傚偭偲僨傿僢働儞僘傪巚傢偣傞儐乕儌傾傪岎偊偨戝帪戙揑側岅傝岥傗摉帪偺儘儞僪儞偺晽懎昤幨偑妝偟偔丄撉彂偺戠岉枴傪枮媔偝偣偰偔傟傞丅
丂丂5埵偺僨僯僗丒儗僿僀儞乽儉乕儞儔僀僩丒儅僀儖乿偵偮偄偰偼埲慜偵婰偟偨丅僴乕僪儃僀儖僪彫愢僼傽儞傪偲傝偙偵偟偨僷僩儕僢僋仌傾儞僕乕丒僔儕乕僘偺嵟廔嶌丅弶婜偺崰偺嶌昳偵斾傋傞偲儃儖僥乕僕偼棊偪傞偑丄撉傒偛偨偊偼廩暘丅堦斒揑側昡壙偼崅偔側偄傛偆偩偑丄傏偔偲偟偰偼垽拝偑偁傞嶌昳偩丅
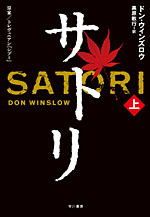 丂丂6埵偺乽僒僩儕乿偼岲挷僪儞丒僂傿儞僘儘僂偺朻尟彫愢丅柤嶌偲偟偰桳柤側僩儗償僃僯傾儞嶌乽僔僽儈乿偺懕曇傪僂傿儞僘儘僂偑彂偄偨偲偄偆偙偲偱榖戣偵側偭偨丅懕曇偲偄偭偰傕乽僔僽儈乿偺慜擔択偱丄庒偒擔偺埫嶦幰僯僐儔僀丒僿儖偑婋尟側擟柋傪惪偗晧偄拞崙偵愽擖偟丄擔杮偺晲弍傗岄偺惛恄傪晲婍偵丄敆傝棃傞揋偲愴偆丅墱怺偄撪柺惈偲僄儌乕僔儑儞偑偁偭偨乽僔僽儈乿偵斾傋偰丄嵶晹偺彂偒崬傒偑彮側偔丄偨偩僗僩乕儕乕傪捛偆偩偗側偺偱丄暔懌傝側偝偼斲傔側偄丅偱傕僗僺乕僨傿偱寉夣側棳傟偼側偐側偐偺傕偺丅
丂丂6埵偺乽僒僩儕乿偼岲挷僪儞丒僂傿儞僘儘僂偺朻尟彫愢丅柤嶌偲偟偰桳柤側僩儗償僃僯傾儞嶌乽僔僽儈乿偺懕曇傪僂傿儞僘儘僂偑彂偄偨偲偄偆偙偲偱榖戣偵側偭偨丅懕曇偲偄偭偰傕乽僔僽儈乿偺慜擔択偱丄庒偒擔偺埫嶦幰僯僐儔僀丒僿儖偑婋尟側擟柋傪惪偗晧偄拞崙偵愽擖偟丄擔杮偺晲弍傗岄偺惛恄傪晲婍偵丄敆傝棃傞揋偲愴偆丅墱怺偄撪柺惈偲僄儌乕僔儑儞偑偁偭偨乽僔僽儈乿偵斾傋偰丄嵶晹偺彂偒崬傒偑彮側偔丄偨偩僗僩乕儕乕傪捛偆偩偗側偺偱丄暔懌傝側偝偼斲傔側偄丅偱傕僗僺乕僨傿偱寉夣側棳傟偼側偐側偐偺傕偺丅丂丂7埵偺乽007 敀巻埾擟忬乿偼丄偙傟傕偁偺僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偑007偺怴僔儕乕僘傪彂偄偨偲偄偆偙偲偱榖戣偵側偭偨僗僷僀朻尟彫愢丅帪戙偼3.11埲屻偺尰戙丄撿傾僼儕僇傪庡側晳戜偵丄30戙弶傔偺庒乆偟偄僕僃乕儉僘丒儃儞僪偺妶桇偑昤偐傟傞丅夰偐偟偄忋巌偺M傗儈僗丒儅僯乕儁僯乕傕搊応丄幵丄椏棟丄旤彈偵栚偑側偄儃儞僪偺昤幨傕僆儕僕僫儖傪摜廝偟偰偍傝丄僨傿乕償傽乕摼堄偺偳傫偱傫曉偟傕惙傝崬傫偱偺戝僒乕價僗丅埆栶偑彫棻側偺偑婥偵側傞傕偺偺丄僨傿乕償傽乕偺岻偝偑岝偭偰偍傝丄妝偟偝偼敳孮偩丅
 丂丂8埵偺儕僠儍乕僪丒僪僀僢僠乽13帪娫慜偺枹棃乿偼僞僀儉丒儕乕僾偲偄偆傾僀僨傾傪巊偭偨堎怓僒僗儁儞僗彫愢丅戞12復偐傜巒傑傝丄戞1復偱廔傢傞偲偄偆嬅偭偨峔惉丅嵢傪嶦奞偝傟偨庡恖岞偑1帪娫偛偲偵帪娫傪偝偐偺傏傝側偑傜斊恖傪尒偮偗丄嶦奞傪慾巭偟傛偆偲偡傞丅偙偺庤偺彫愢偼撉幰偺岲傒偵傛偭偰岲偒寵偄偑偼偭偒傝暘偐傟傞偑丄傏偔偼偙偆偄偭偨庯岦偺儈僗僥儕乕偑岲偒側偺偱丄戝偄偵妝偟傔偨丅
丂丂8埵偺儕僠儍乕僪丒僪僀僢僠乽13帪娫慜偺枹棃乿偼僞僀儉丒儕乕僾偲偄偆傾僀僨傾傪巊偭偨堎怓僒僗儁儞僗彫愢丅戞12復偐傜巒傑傝丄戞1復偱廔傢傞偲偄偆嬅偭偨峔惉丅嵢傪嶦奞偝傟偨庡恖岞偑1帪娫偛偲偵帪娫傪偝偐偺傏傝側偑傜斊恖傪尒偮偗丄嶦奞傪慾巭偟傛偆偲偡傞丅偙偺庤偺彫愢偼撉幰偺岲傒偵傛偭偰岲偒寵偄偑偼偭偒傝暘偐傟傞偑丄傏偔偼偙偆偄偭偨庯岦偺儈僗僥儕乕偑岲偒側偺偱丄戝偄偵妝偟傔偨丅丂丂9埵偺僯僢僉丒僼儗儞僠乽惗娨乿偼怱棟僒僗儁儞僗彫愢丅惓懱晄柧偺抝偵娔嬛偝傟偨庡恖岞偺彈惈偼恏偔傕扙弌偡傞偑丄寈嶡偼斵彈偺尵梩傪怣梡偟側偄丅恎偺婋尟傪姶偠偨斵彈偼帺椡偱斊恖傪扵偡丄偲偄偆嬝棫偰丅庡恖岞偺娮傞埆柌偺傛偆側忬嫷偼嬞敆姶偨偭傉傝偱丄堦愄慜偺傾僀儕僢僔儏偺傛偆側僒僗儁儞僗晽枴傪姶偠偝偣傞丅奺庬偺儀僗僩10偵偼偍偦傜偔儔儞僋僀儞偝傟側偄偩傠偆偗偳丄偙傟偼抧枴側偑傜傏偔偵偲偭偰偼崱擭偺孈傝弌偟暔偺1嶜偩丅
丂丂10埵偺僨償傿僢僪丒僑乕僪儞乽擇棳彫愢壠乿偼丄奺庬儈僗僥儕乕丒儔儞僉儞僌偱忋埵傪憤側傔偵偡傞偲巚傢傟傞僒僗儁儞僗彫愢丅戝廜儔僀僩丒僲償僃儖傗億儖僲彫愢傪彂偄偰偒偨嶀偊側偄嶌壠偑丄楢懕嶦恖偺巰孻廁偐傜帺揱傪彂偄偰偔傟偲棅傑傟偰憳嬾偡傞婏柇側帠審偑寉柇側僞僢僠偱昤偐傟傞丅棅傝側偄庡恖岞偺嶌壠丄僷乕僩僫乕傪攦偭偰弌傞彈巕崅惗丄僗僩儕僢僷乕偺僈乕儖僼儗儞僪側偳丄惗偒惗偒偟偨恖暔憿宍偑尒帠丅偨偟偐偵尯恖庴偗偡傞偱偁傠偆撪梕偩偑丄偱傕丄偦傟傎偳偺傕偺偐丄偲巚傢側偄偱傕側偄丅
丂丂埲忋偺傎偐偵傕丄撿傾偺働乕僾僞僂儞偵偼傃偙傞斊嵾偲朶椡傪昤偄偨僋儔僀儉丒僲償僃儖乽偼偄偮偔偽偭偰帨斶傪岊偊乿乮儘僕儍乕丒僗儈僗挊丄憗愳暥屔乯傗丄杻栻塣傃壆偲曐埨姱傗嶦偟壆偑擖傝棎傟偰憟偄崌偆丄嫊柍姶偲徟憞姶昚偆僲儚乕儖彫愢乽惗丄側偍嫲傞傋偟乿乮傾乕僶儞丒僂僃僀僩挊丄怴挭暥屔乯側偳偺廏嶌傕偁傝丄崱擭偼傎傫偲偆偵奀奜儈僗僥儕乕丒僼傽儞偵偲偭偰幚傝懡偄1擭偩偭偨丅
2011.11.19 (搚) 僩儖僐偲偄偆崙
僩儖僐偼僀僗儔儉嫵偺崙偱偁傝丄偄偨傞偲偙傠偵嬍偹偓宆偺僪乕儉偺儌僗僋乮僀僗儔儉帥堾乯偑偁傞丅偩偑丄懠偺僀僗儔儉嫵崙偲堘偭偰丄惌帯偲廆嫵偼姰慡偵暘棧偝傟偰偄傞丅偩偐傜堸庰傕傑偭偨偔帺桼偱丄僩儖僐嶻偺價乕儖傗儚僀儞傕偁傞丅彈惈傕帺棫偟偰偍傝丄旤彈偑懡偄丅暈憰傕惣墷彅崙偲摨偠偱丄僀僗儔儉摿桳偺償僃乕儖偱婄傪暍偭偨巔側偳傕偁傑傝尒偐偗側偄丅
僩儖僐偼戝偺恊擔崙偩偲偄偆丅挿擭丄椬崙儘僔傾偲偺愴偄偱嬯廯傪側傔偰偒偨僩儖僐偼丄
傑偨僩儖僐恖偼擔杮恖偺惈奿傗懺搙偵傕岲姶傪帩偭偰偄傞傛偆偩丅娤岝偱朘傟傞奺崙偺恖乆偺側偐偱丄墶暱偵埿挘傝嶶傜偡僼儔儞僗恖傗僪僀僣恖丄朤庒柍恖偱姯偟偄拞崙恖傗娯崙恖偲斾傋偰丄擔杮恖偼壐傗偐偩偟愡搙偑偁傝丄偄偪偽傫垽偝傟偰偄傞偲偄偆丅偍悽帿偺暘傪妱傝堷偄偰傕丄偍偦傜偔偦偺偲偍傝偩傠偆丅
NATO壛柨崙偱偁傞僩儖僐偼丄抧棟揑偵偼儓乕儘僢僷偵嬤偄偑丄惌帯丒宱嵪揑偵偼傾儊儕僇偺塭嬁偑嫮偄丅壿暭偼尰抧捠壿偺僩儖僐丒儕儔偲偲傕偵暷僪儖偑棳捠偟偰偄傞丅僩儖僐偼僈僜儕儞戙偑崅偄丅暔壙偼擔杮偺敿暘傎偳側偺偵丄1儕僢僩儖偑220墌傕偡傞丅僩儖僐偼嶻桘崙偱偼側偄偑丄嬤椬偵偼嶻桘崙偑偨偔偝傫偁傞偺偱丄偦偙偐傜攦偊偽埨偄偼偢側偺偩偑丄傢偞傢偞傾儊儕僇偐傜攦偭偰偍傝丄偩偐傜崅偔側傞傜偟偄丅偙偺偁偨傝丄惌帯揑側巚榝偑
僩儖僐偼埲慜偐傜EU擖傝傪朷傫偱偒偨偑丄傑偩壛柨偵偼帄偭偰偄側偄丅儓乕儘僢僷偺斀僀僗儔儉姶忣偑嵟戝偺忈奞偱偁傝丄傎偐偵傕僉僾儘僗栤戣傗僋儖僪恖栤戣偑僱僢僋偵側偭偰偄傞丅崙撪偱偼EU擖傝偵巀斲椉榑偑偁傝丄崙椡傪忋偘丄恀偺戝崙傪栚巜偡偨傔偵壛柨偡傋偒偩偲偄偆榑偲丄儓乕儘僢僷彅崙偺晽壓偵棫偭偰晄棙塿傪旐傞傛傝傕丄偙偺傑傑帺媼帺懌偱峴偔傋偒偩偲偄偆榑偵擇暘偝傟偰偄傞丅傕偭偲傕丄偄傑EU偼丄僊儕僔儍偺嬥梈晄埨偑偦偺懠偺崙偵傕旘傃壩偟偐偐偭偰偍傝丄EU曵夡偺婋婡偵偝傜偝傟偰偄傞偐傜丄尰忬偱
僩儖僐傕偦偆偩偟丄偄傑崙墹晇嵢偑棃擔拞偺僽乕僞儞傕偦偆偩偑丄擔杮偵岲堄傪婑偣傞崙偼彮側偔側偄丅杮棃側傜丄偦傟傜偺崙乆傪懌妡偐傝偵丄擔杮偑傕偭偲懚嵼姶傪敪婗偟丄悽奅傪憡庤偵帺庡揑側暯榓奜岎傪儕乕僪偱偒傞偼偢偩丅偟偐偟傾儊儕僇偺懏崙偱偁傝丄帞偄將偵側傝壓偑偭偰偄傞尰忬偱偼丄偦傫側庡懱揑側奜岎側偳偱偒傞偼偢偑側偄丅忣偗側偄偐偓傝偩丅
2011.10.29 (搚) 偩偗偳丒丒丒旤偟偄
楒偲偼偍偐偟側傕偺乛偦偟偰斶偟偄傕偺
帪偵偼惷傑傝乛帪偵偼峳傟嫸偆
婌傃傪傕偨傜偡偐偲巚偊偽乛嵭偄傕塣傫偱偔傞
偩偗偳丒丒丒旤偟偄
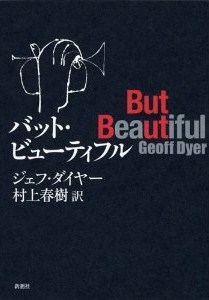 偙偺乽楒乿傪乽僕儍僘乿偵抲偒姺偊傟偽丄愭偛傠敪攧偝傟偨杮亀僶僢僩丒價儏乕僥傿僼儖亁乮怴挭幮乯偺撪梕傪尵偄昞偡暥復偵側傞丅
偙偺乽楒乿傪乽僕儍僘乿偵抲偒姺偊傟偽丄愭偛傠敪攧偝傟偨杮亀僶僢僩丒價儏乕僥傿僼儖亁乮怴挭幮乯偺撪梕傪尵偄昞偡暥復偵側傞丅偙傟偼僕儍僘巎忋偺桳柤側儈儏乕僕僔儍儞傪戣嵽偵偟偨楢嶌抁曇彫愢廤偩丅僀僊儕僗偺嶌壠僕僃僼丒僟僀儎乕挊丄栿幰偼偁偺懞忋弔庽偱偁傞丅僟僀儎乕偼弮暥妛宯偺嶌壠偺傛偆偩偑丄擔杮偱偼傑偭偨偔柍柤偱偁傝丄朚栿偝傟傞偺偼偙傟偑弶傔偰偩丅偙偺杮傪撉傓婥偵側偭偨偺偼丄戣嵽偲偟偰嵦傝忋偘傜傟偰偄傞儈儏乕僕僔儍儞乗乗儗僗僞乕丒儎儞僌丄僙儘僯傾僗丒儌儞僋丄僶僪丒僷僂僄儖丄儀儞丒僂僃僽僗僞乕丄僠儍乕儖僘丒儈儞僈僗丄僠僃僢僩丒儀僀僇乕丄傾乕僩丒儁僢僷乕乗乗偵庝偐傟偨偐傜偱偁傝丄懞忋弔庽偵偼側傫偺娭怱傕側偄丅偲偼偄偊丄偙傫側柍柤偺嶌壠偵傛傞丄偟偐傕尨彂偑姧峴偝傟偰偐傜10悢擭傕宱偭偰偄傞抧枴側彫愢偑擔杮偱敪攧偝傟傞偙偲偵側偭偨偺偼丄栿幰偑懞忋弔庽偩偐傜偱偁傠偆丅傑偙偲偵懞忋報偼楈尡偁傜偨偐偲尵傢偹偽側傜側偄丅
杮彂偼偙傟傜偺儈儏乕僕僔儍儞傪僥乕儅偵偟偨丄偦傟偧傟撈棫偟偨7偮偺抁曇偐傜側偭偰偄傞丅偙傟傜偺抁曆偺偁偄偩偵僨儏乕僋丒僄儕儞僩儞傪儌僠乕僼偵偟偨抁偄憓榖偑嫴傑傟偰偍傝丄偝傜偵姫枛偵偼僕儍僘巎傪橂嵴偡傞挿暥偺僄僢僙僀偑廂傔傜傟偰偄傞丅彫愢偲偼尵偆傕偺偺丄撪梕揑偵偼丄彫愢偲傕僄僢僙僀偲傕抐曅揑揱婰偲傕偮偐側偄丄嫊幚側偄傑偤偺僗僞僀儖偱彂偐傟偰偄傞丅偦傟偧傟偺儈儏乕僕僔儍儞偵偮偄偰偺暥專傗僀儞僞價儏乕丄偝傜偵斵傜傪嶣塭偟偨幨恀側偳傪傕偲偵丄嶌幰偺撈摿偺帇揰偐傜僀儅僕僱乕僔儑儞傪朿傜傑偣偰彂偐傟偨傕偺偺傛偆偩丅
偲傝傢偗嶌幰偑僀儞僗僺儗乕僔儑儞傪庴偗偨偺偼幨恀偩偭偨傜偟偄丅傑偊偑偒偵偼師偺傛偆側堦暥偑偁傞丅
幨恀丄偦傟偼1昩偺傎傫偺壗暘偺1偐偺弖娫傪懆偊偨偵偡偓側偄偺偩偑丄偦偺幨恀偺乽幚姶偝傟偨帩懕惈乿偼丄偦偺搥寢偝傟偨弖娫偺慜屻椉曽偵悢昩偢偮怢傃偰偄傞丅偮傑傝丄偦偺慜屻偵婲偙偭偨偙偲偲丄偙傟偐傜婲偙傞偱偁傠偆偙偲傕傑偨丄娷傑傟偰偄傞丅
 偨偟偐偵僕儍僘儊儞傪嶣偭偨幨恀偼傏偔偨偪偺怱傪巋寖偡傞丅墘憈拞偺幨恀傕偦偆偩偑丄傓偟傠擔忢偺側偵偘側偄僔儑僢僩偺傎偆偵丄傛傝庝偒偮偗傜傟傞偟丄壗偐傪姶偠偝偣傞傕偺偑懡偄丅杮彂偺斷偵嵹偭偰偄傞丄偍偦傜偔妝壆偱嶣傜傟偨傕偺偱偁傠偆丄僿儞儕乕丒儗僢僪丒傾儗儞丄儀儞丒僂僃僽僗僞乕丄僺乕丒僂傿乕丒儔僢僙儖偺幨恀乮嶣塭偼儈儖僩丒僸儞僩儞乯偼丄側傞傎偳僗僩乕儕乕傪姶偠偝偣傞偟丄尒傞傕偺偺憐憸椡傪偐偒偨偰傞丅
偨偟偐偵僕儍僘儊儞傪嶣偭偨幨恀偼傏偔偨偪偺怱傪巋寖偡傞丅墘憈拞偺幨恀傕偦偆偩偑丄傓偟傠擔忢偺側偵偘側偄僔儑僢僩偺傎偆偵丄傛傝庝偒偮偗傜傟傞偟丄壗偐傪姶偠偝偣傞傕偺偑懡偄丅杮彂偺斷偵嵹偭偰偄傞丄偍偦傜偔妝壆偱嶣傜傟偨傕偺偱偁傠偆丄僿儞儕乕丒儗僢僪丒傾儗儞丄儀儞丒僂僃僽僗僞乕丄僺乕丒僂傿乕丒儔僢僙儖偺幨恀乮嶣塭偼儈儖僩丒僸儞僩儞乯偼丄側傞傎偳僗僩乕儕乕傪姶偠偝偣傞偟丄尒傞傕偺偺憐憸椡傪偐偒偨偰傞丅偟偐偟丄偙偺杮偱嶌幰偑朼偓弌偡僗僩乕儕乕偼丄偁傑傝偵埫偄丅傑偢戞1復偺儗僗僞乕丒儎儞僌傪撉傫偱丄偦偺媬偄偺側偄堿烼偝偵婥偑柵擖偭偨丅偙偙偵偼巰偸娫嵺偺儗僗僞乕偑昤偐傟偰偄傞丅儂僥儖偺晹壆偱梺傃傞傛偆偵庰傪堸傒丄僒僢僋僗傪庤偵偡傞偺傕妎懇側偔側傝丄媭偪壥偰傞偺傪懸偮偩偗偺儗僗僞乕丅斵偺摢傪嫀棃偡傞偺偼丄孯戉帪戙偺斶嶴側懱尡傗價儕乕丒儂儕僨僀偲偺岎棳偩丅偁傑傝偵峳椓偲偟偨怱徾晽宨偵埫郬偨傞巚偄偵側傞丅偦偺懠偺復傕傎偲傫偳偙傫側挷巕偱丄恖惗偺斢擭傪寎偊偨儈儏乕僕僔儍儞偺斶嶴側嫬嬾偲屒撈側怱偑彂偐傟偰偍傝丄撉傓偺偑偮傜偔側傞丅
偁偲偑偒偱嶌幰偼偙偆彂偄偰偄傞丅
價僶僢僾帪戙偺僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偵偲偭偰丄惗偒偰拞擭傪寎偊傞偙偲偼丄柌偺傛偆側挿庻偲巚偊偨丅乮拞棯乯 偦偺惗妶僗僞僀儖傪巚偊偽乗乗堸庰丄僪儔僢僌丄恖庬嵎暿丄夁崜側椃丄恎傪偡傝尭傜偡帪娫乗乗傛傝壐寬側恖惗傪憲偭偰偄傞恖乆傛傝偄偔傇傫暯嬒庻柦偑抁偄偔側傞偺偼傗傓傪摼側偄偙偲偐傕偟傟側偄丅偦傟偱傕丄僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偨偪偑幚嵺偵旐偭偰偄傞偄傞旐奞傪尒傞偲丄偦偙偵偼壗偐暿偺梫慺偑偁傞偺偱偼側偄偐丄僕儍僘偲偄偆宍懺偦偺傕偺偺側偐偵丄偦傟傪憂憿偡傞恖乆偐傜壵楏側壽挜嬥傪庢傝棫偰偰偄偔壗偐偑愽傫偱偄傞偺偱偼側偄偐丄偲峫偊偞傞傪摼側偄丅偨偟偐偵丄偐偮偰偺僕儍僘儊儞偵偼僪儔僢僌丄傾儖僐乕儖丄嫸婥丄攋柵揑側惗妶偑偮偒傕偺偩偭偨丅偦偟偰偦傟偑彫愢傗塮夋偺戣嵽偵偟傗偡偄偺傕暘偐傞丅偱傕丄偦傟傜偽偐傝偑嫮挷偝傟傞偲丄偪傚偭偲懸偰丄偲尵偄偨偔側傞丅偦傟傜偼僕儍僘偺堦柺傪愗傝庢偭偨偩偗偵偡偓側偄丅懄嫽墘憈偵妎偊傞丄偁偺偧偔偧偔偡傞傛偆側怱偺崅梘丄撈摿偺儕儔僢僋僗姶傗儐乕儌傾姶丄偦傟傜傪敳偒偵偟偰僕儍僘傪岅傞偙偲偼偱偒側偄丅僕儍僘儊儞偺怱偺埮偩偗偟偐昤偐傟偰偄側偗傟偽丄乽偩偗偳丒丒丒旤偟偄乿偲尵偆偙偲偼偱偒傑偄丅
桞堦丄怱偑側偛傓偺偼儀儞丒僂僃僽僗僞乕偺復偩丅婦幵偱椃傪偟偰偄傞斵偺幵拞偱偺傎傎偊傑偟偄僄僺僜乕僪偑岅傜傟傞丅傾僢僾丒僥儞億偱墘憈偡傞偲偒偺嫸愴巑偺傛偆側峳乆偟偝丄僶儔乕僪傪悂偔偲偒偺愒巕傪偦偭偲榬偵書偔傛偆側傗偝偟偝丄偦傫側儀儞偺巔偑偙偙偵偼懆偊傜傟偰偄傞丅偙傟傪撉傓偲丄埲慜尒偨儀儞偺塮憸偑巚偄晜偐傇丅帪偼1970擭慜屻丄応強偼僐儁儞僴乕僎儞偺僋儔僽丅儀儞偼乽僆乕儖僪丒僼僅乕僋僗乿傪悂偔丅堉巕偵嵗偭偨傑傑偺墘憈偱偁傞丅榁嫬偺斵偼傕偆挿偔棫偭偰偄傞偙偲偑偱偒側偄偺偩丅僺傾僲偼媽桭偺僥僨傿丒僂傿儖僜儞丅儀儞偼傕偆愄偺傛偆偵偼悂偗側偄丅憡曄傢傜偢抂惓側僥僨傿偺僺傾僲偲斾傋偰丄儀儞偼僽儗僗傕懕偐側偄偟壒傕暘岤偔側偄丅偩偑丄恖惗偺廔傢傝偵偝偟偐偐偭偨斵傜偑壗偺婥晧偄傕側偔桰慠偲墘憈偡傞巔偺丄側傫偲旤偟偄偙偲偐丅偄偮偟偐丄僥僫乕傪悂偔儀儞偺栚偐傜椳偑偁傆傟丄杍傪棳傟傞丅偮偄偝偭偒丄偐偮偰僶儞僪偺摨椈偩偭偨宧垽偡傞僕儑僯乕丒儂僢僕僗偑巰傫偩偲偺曬偵愙偟偨偐傜偩丅
奺復偺娫傪偮側偖丄怺栭偐傜憗挬偵偐偗偰僴儕乕丒僇乕僱僀偺塣揮偡傞幵偱師偺岞墘抧偵岦偐偆僨儏乕僋丒僄儕儞僩儞傪昤偄偨彾曇傕傑偨丄杮暥傪撉傫偱棊偪崬傫偩婥帩偪傪丄堦弖偩偑夝偒傎偖偟偰偔傟傞丅僄儕儞僩儞妝抍偺斣摢奿偩偭偨僶儕僩儞丒僒僢僋僗憈幰僴儕乕丒僇乕僱僀偼嵟弶婜偐傜嵟屻婜傑偱45擭傕偺挿偒偵傢偨偭偰僶儞僪偵嵼愋偟偨丅偦偟偰1974擭偵僄儕儞僩儞偺巰傪尒撏偗偨偁偲丄偦傟偐傜4儠寧屻偵僨儏乕僋傪捛偆傛偆偵朣偔側偭偨丅僇乕僱僀偼偙偙偵彂偐傟偰偄傞傛偆偵丄椃傪偡傞嵺丄幚嵺偵偄偮傕幵偱峴偔僨儏乕僋偺塣揮庤傪柋傔偰偄偨丅
杮暥偼偁傑傝偺埫偝偵鐒堈偲偡傞偑丄姫枛偺僄僢僙僀偼撉傒偛偨偊偑偁傝丄挊幰偺僕儍僘偵懳偡傞尒幆偺怺偝偑偆偐偑偊傞丅恑壔偲揱摑丄媄弍偲僆儕僕僫儕僥傿丄柾曧偲屄惈丄帪戙偲偺娭楢丄僐儖僩儗乕儞偺壒妝暘愅側偳丄柕弬傪撪曪偡傞僕儍僘偺僟僀僫儈僢僋側摦偒偵偮偄偰偺榑峫偼愢摼椡偑偁傝丄偡傋偰偲偼尵偊側偄傑偱傕丄偐側傝偺晹暘丄偆側偢偗傞丅僕儍僘偺揱摑偵怗傟偰偺乽崱傕懕偄偰偄傞揱摑偺塭嬁偼丄壒妝偺怺壔傗恑曕傪偔偖傝敳偗偰側偍丄夁嫀偺執戝側愭恖偑偦偙偵偄傞偙偲傪妋擣偝偣偰偔傟傞乿偲偄偆暥復側偳偼揑妋側巜揈偩偟丄尰戙偺僕儍僘偵偮偄偰丄儗僗僞乕丒儎儞僌偑尵偭偨乽偁偁丄偄偄偹偊丒丒丒偱傕偁傫偨丄偍傟偺偨傔偵壧傪傂偲偮偆偨偭偰偔傟側偄偐丠乿偲偄偆壢敀傪堷梡偟側偑傜丄僕儍僘儊儞偺媄弍偼奿抜偺恑曕傪悑偘偰偄偰傕丄偐偮偰偺傛偆側壒妝揑嫽暠傪屇傃婲偙偡偺偼擄偟偄偲榑偢傞偔偩傝傕丄撉傓傕偺傪擺摼偝偣傞丅
2011.06.14 (壩) 塱尒旉懢榊偺帠審曤
 嵟嬤撉傫偱柺敀偐偭偨僕儍僘彫愢偵丄揷拞孾暥偺乽巶巕恀鐹偺拵乿乮2011擭丄憂尦幮乯偑偁傞丅偙傟偼揷拞孾暥偑彂偒宲偄偱偄傞抁曇楢嶌儈僗僥儕乕亙塱尒旉懢榊偺帠審曤亜僔儕乕僘偺嵟怴嶌偱偁傝丄乽棊壓偡傞椢乿乽恏偄埞乿偵懕偔戞3嶌偵偁偨傞丅彫愢偺岅傝庤偼儀僥儔儞丒僕儍僘丒僩儔儞儁僢僞乕偺搨搰塸帯丄搨搰塸帯僋僀儞僥僢僩傪棪偄偰僕儍僘丒僋儔僽側偳偵弌墘偟偰偄傞丅偦偺僌儖乕僾偺庒偒僥僫乕憈幰偑塱尒旉懢榊丄僕儍僘偵偟偐嫽枴偑側偄揤嵥敡偺儈儏乕僕僔儍儞偩偑丄悇棟椡傕揤嵥揑偱丄斵傜偑憳嬾偡傞捒帠審傪捈娤偲慚偒偱悇棟偟丄偁偞傗偐偵撲夝偒傪偡傞丅偮傑傝丄塱尒偑儂乕儉僘栶丄搨搰偑儚僩僜儞栶偲偄偆僷僞乕儞偩丅
嵟嬤撉傫偱柺敀偐偭偨僕儍僘彫愢偵丄揷拞孾暥偺乽巶巕恀鐹偺拵乿乮2011擭丄憂尦幮乯偑偁傞丅偙傟偼揷拞孾暥偑彂偒宲偄偱偄傞抁曇楢嶌儈僗僥儕乕亙塱尒旉懢榊偺帠審曤亜僔儕乕僘偺嵟怴嶌偱偁傝丄乽棊壓偡傞椢乿乽恏偄埞乿偵懕偔戞3嶌偵偁偨傞丅彫愢偺岅傝庤偼儀僥儔儞丒僕儍僘丒僩儔儞儁僢僞乕偺搨搰塸帯丄搨搰塸帯僋僀儞僥僢僩傪棪偄偰僕儍僘丒僋儔僽側偳偵弌墘偟偰偄傞丅偦偺僌儖乕僾偺庒偒僥僫乕憈幰偑塱尒旉懢榊丄僕儍僘偵偟偐嫽枴偑側偄揤嵥敡偺儈儏乕僕僔儍儞偩偑丄悇棟椡傕揤嵥揑偱丄斵傜偑憳嬾偡傞捒帠審傪捈娤偲慚偒偱悇棟偟丄偁偞傗偐偵撲夝偒傪偡傞丅偮傑傝丄塱尒偑儂乕儉僘栶丄搨搰偑儚僩僜儞栶偲偄偆僷僞乕儞偩丅帠審偲偄偭偰傕丄寣側傑偖偝偄偙偲偑婲偙傞傢偗偱偼側偄丅偣偄偤偄丄妝婍偑側偔側偭偨偲偐丄壧庤偑峴曽晄柧偵側偭偨偲偄偆傛偆側丄擔忢揑偵偁傝傆傟偨帠審偩丅撲夝偒傕丄偄傢備傞婘忋偺嬻榑偱丄偦傫側偙偲偼尰幚揑偵偼偁傝偊側偄丄偲偄偆傛偆側傕偺偽偐傝丅偮傑傝堦庬偺僷儘僨傿側偺偩偑丄偙傟偑撉傫偱偄偰側偐側偐妝偟偄丅抦揑側儐乕儌傾偵曪傑傟偰偄傞偟丄僕儍僘偵娭偡傞偝傑偞傑側錧拁丄僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偺惗懺偑丄媃夋傗屩挘傪傑偠偊側偑傜傕丄偄偒偒偲昤偐傟偰偄傞丅戝壒検偱扏偒傑偔傞戝傏傜悂偒偺僪儔儅乕傗丄僕儍僘岲偒偑崅偠偰帺戭偵僗僞僕僆傪嶌偭偨堛巘側偳丄幚嵼偺恖偨偪傪儌僨儖偵偟偨偲偍傏偟偒搊応恖暔偑偄傠偄傠尰傟偰丄僯儎儕偲偝偣傜傟傞丅
1嶌栚偲2嶌栚偱偼丄斵傜偑搶嫗偱偺僋儔僽丒僊僌傗崙撪奺抧偵價乕僞傪偟偨嵺偵弌夛偭偨帠審偑昤偐傟偰偄偨丅偙偺戞3嶌偱丄搨搰偼僌儖乕僾傪夝嶶偟丄塱尒偲堦弿偵傾儊儕僇偵椃棫偮丅傾儊儕僇偵搉偭偨2恖偼丄僯儏乕儓乕僋丄僔僇僑丄僯儏乕僆儕儞僘偲丄僕儍僘偵備偐傝偺怺偄奨傪夢傝丄尰抧偺儈儏乕僕僔儍儞偲岎棳偟偨傝偟側偑傜丄杮暔偺僕儍僘偺姶怗傪偮偐傒偲傞丅僔僇僑偱揱愢偺僼儕乕丒僕儍僘憈幰僕儏僛僢僺丒儘乕僈儞傪渇渋偲偝偣傞榁僕儍僘儅儞偲弌夛偭偨傝丄僯儏乕僆儕儞僘偱尰抧偺僽儔僗僶儞僪偵旘傃擖傝嶲壛偟偰妳嵮傪梺傃偨傝偡傞丅
挊幰偺揷拞孾暥偼偍傕偵SF傗儂儔乕傪彂偔嶌壠偩偑丄僥僫乕丒僒僢僋僗憈幰偲偟偰偲偒偍傝僗僥乕僕偵棫偮儈儏乕僕僔儍儞偱傕偁傝丄僕儍僘偵娭偡傞抦幆傗垽拝偼暲乆側傜偸傕偺偑偁傞丅偦偺堦抂傪帵偟偰偄傞偺偑丄奺抁曇偺枛旜偵挊幰偑晅偡乽戝偒側偍悽榖揑嶲峫儗僐乕僪乿偩丅偙偙偵偼丄偦傟偧傟偺榖偵娭楢偟偨儗僐乕僪偑撈抐偲曃尒偱暲傋傜傟偰偄傞丅嵦傝忋偘傜傟偨儗僐乕僪偼丄嶌幰偺岲傒傪斀塮偟偰偐丄僕儍僘偺杮棳偲偄偆傛傝朤宯揑側傕偺傗廃曈揑側傕偺偑懡偄丅偨偲偊偽僯儏乕僆儕儞僘偺榖偺崁偵嫇偘傜傟偰偄傞偺偼丄僟乕僥傿丒僟僘儞丒僽儔僗丒僶儞僪丄僾儘僼僃僒乕丒儘儞僌僿傾丄僆儈僯僶僗丒傾儖僶儉乽僼傽儞僉乕丒僈儞儃乿偲偄偭偨嬶崌偩丅偙偺儗僐乕僪徯夘僐乕僫乕偼偲偰傕孾敪偝偣傜傟傞丅偙傟偵傛偭偰丄傏偔偼僴儚僀傾儞偲僽儖乕僗偑岾偣偵梈崌偟偨僞僕丒儅僴乕儖仌僼儔丒僽儖乕僗丒僶儞僪傗壂撽偺搰塖壧庤丄戝岺揘峅偺柺敀偝傪抦偭偨丅
屲栘姲擵偺彫愢偑丄60擭戙敿偽丄庒幰偑埫偄僕儍僘媔拑偱栙乆偲戝壒検偺僕儍僘傪挳偒丄崅嫶榓枻偵怱悓偟丄搶塮傗偔偞塮夋偱崅憅寬偑埆幰傪巃傝嶦偡偺偵夣嵠傪嫇偘偰偄偨帪戙偺傕偺偩偲偡傟偽丄揷拞孾暥偼丄僀儞僞乕僱僢僩偐傜僟僂儞儘乕僪偟偰僕儍僘傪挳偒丄懞忋弔庽傪撉傒丄偄偮傕実懷揹榖傪偄偮傕庤曻偝側偄尰戙偲偄偆帪戙傪斀塮偟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅挊幰偁偲偑偒偵傛傞偲丄塱尒旉懢榊僔儕乕僘偼杮嶌偱偄偭偨傫廔椆偲偺偙偲偩偑丄偱偒傟偽偄傑彮偟懕偗偰傕傜偄偨偄傕偺偩丅
2011.06.02 (栘) 亀恖惗晥亁
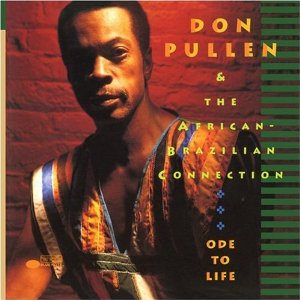 僪儞丒僾乕儗儞偼堦尵偱偼尵偄昞偣側偄傎偳摿堎側屄惈傪傕偭偨僺傾僯僗僩仌僐儞億乕僓乕偩偭偨丅僾乕儗儞偺僺傾僲偼懪妝婍揑側憈朄偵摿挜偑偁偭偨丅揱摑惈偐傜慜塹惈傑偱丄偄傠傫側梫慺傪寭偹旛偊偨僗僞僀儖偺帩偪庡偱偁傝丄偟偽偟偽僌儕僢僒儞僪傪梡偄偰尞斦傪堷偭偐偒夞偟丄嫽偑忔傟偽傂偠懪偪偱僼儕乕偭傐偄僼儗乕僘傪鄖楐偝偣偨丅偠偮傪尵偆偲丄挷巕偵忔偭偨偲偒偺僾乕儗儞偺擫偑尞斦偺忋偱挼傃偼偹偰偄傞傛偆側僾儗僀偼丄偁傑傝岲偒偱偼側偄丅偩偑梷惂偝傟偨墘憈傪偡傞偲偒偺僾乕儗儞偼丄偒傢傔偰墱怺偄枴傢偄傪姶偠偝偣偨丅
僪儞丒僾乕儗儞偼堦尵偱偼尵偄昞偣側偄傎偳摿堎側屄惈傪傕偭偨僺傾僯僗僩仌僐儞億乕僓乕偩偭偨丅僾乕儗儞偺僺傾僲偼懪妝婍揑側憈朄偵摿挜偑偁偭偨丅揱摑惈偐傜慜塹惈傑偱丄偄傠傫側梫慺傪寭偹旛偊偨僗僞僀儖偺帩偪庡偱偁傝丄偟偽偟偽僌儕僢僒儞僪傪梡偄偰尞斦傪堷偭偐偒夞偟丄嫽偑忔傟偽傂偠懪偪偱僼儕乕偭傐偄僼儗乕僘傪鄖楐偝偣偨丅偠偮傪尵偆偲丄挷巕偵忔偭偨偲偒偺僾乕儗儞偺擫偑尞斦偺忋偱挼傃偼偹偰偄傞傛偆側僾儗僀偼丄偁傑傝岲偒偱偼側偄丅偩偑梷惂偝傟偨墘憈傪偡傞偲偒偺僾乕儗儞偼丄偒傢傔偰墱怺偄枴傢偄傪姶偠偝偣偨丅僾乕儗儞偼僄僉僙儞僩儕僢僋側僺傾僲丒僗僞僀儖偐傜偼憐憸傕偮偐側偄傎偳旤偟偄嬋傪彂偔丅"Ode to Life" 偺傎偐偵傕丄桳柤側 "Song from the Old Country" 傪偼偠傔丄"Samba for Now" "Trees and Grass and Things" "Sing Me a Song Everlasting" "At the Cafe Centrale" 側偳丄僽儖乕僗偵崻偞偟偨丄慺杙側枴傢偄偺丄枺椡偁傆傟傞嬋傪偨偔偝傫彂偄偰偄傞丅僾乕儗儞偺娷拁偵晉傫偩懁柺偼丄偦傫側帺嶌嬋傪墘憈偡傞偲偒偵丄偄偪偽傫岲傑偟偄偐偨偪偱敪婗偝傟偰偄偨丅
"Ode to Life" 偵偼3庬椶偺償傽乕僕儑儞偑偁傞偑丄傏偔偺岲偒側偺偼1992擭偵儃僗僩儞丒僌儘乕僽丒僕儍僘丒僼僃僗僥傿償傽儖偱榐傜傟偨僜儘丒僺傾僲偵傛傞儔僀償丒償傽乕僕儑儞偩丅10暘傪挻偊傞挿偄墘憈偩偑丄婲彸揮寢傪偨偔傒偵怐傝崬傒側偑傜丄婑偣偰偼曉偡攇偺傛偆偵桰梘敆傜偸暤埻婥偱抏偄偰偍傝丄彮偟傕偩傟傞偲偙傠偼側偄丅弶墘偼傾儖僶儉亀Random Thoughts亁乮1990乯偵廂傔傜傟偰偍傝丄偙傟傕僜儘墘憈丅傕偆傂偲偮偼傾儖僶儉亀Ode to Life亁乮1993乯偵擖偭偰偄傞儂乕儞傪壛偊偨墘憈丅偄偢傟傕傑偲傑傝偺偁傞撪梕偩偑丄儔僀償丒償傽乕僕儑儞偺僗働乕儖偺戝偒偄墘憈偵斾傋傟偽奿偑棊偪傞丅
 僪儞丒僾乕儗儞偼60擭戙敿偽偵慜塹攈偺僺傾僯僗僩偲偟偰僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偺僉儍儕傾傪僗僞乕僩偝偣偨丅偦偺屻丄R&B僶儞僪偱摥偄偨偁偲丄70擭戙偵嵟屻婜偺僠儍乕儖僘丒儈儞僈僗丒僌儖乕僾偵婲梡偝傟偰拲栚偝傟偨丅70擭戙廔傢傝偵儈儞僈僗偺摨椈偩偭偨僥僫乕偺僕儑乕僕丒傾僟儉僗偲慻傫偱憃摢僶儞僪丄僕儑乕僕丒傾僟儉僗亖僪儞丒僾乕儗儞丒僇儖僥僢僩傪寢惉丅儊儞僶乕偵偼摨偠偔儈儞僈僗丒僌儖乕僾偺斣摢奿偩偭偨僪儔儉僗偺僟僯乕丒儕僢僠儌儞僪傕偄偨丅偙偺僶儞僪偼10擭傎偳懕偄偨偑丄偙偺偙傠偑僾乕儗儞偺僉儍儕傾偺僴僀儔僀僩偩偭偨偲巚偆丅
僪儞丒僾乕儗儞偼60擭戙敿偽偵慜塹攈偺僺傾僯僗僩偲偟偰僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偺僉儍儕傾傪僗僞乕僩偝偣偨丅偦偺屻丄R&B僶儞僪偱摥偄偨偁偲丄70擭戙偵嵟屻婜偺僠儍乕儖僘丒儈儞僈僗丒僌儖乕僾偵婲梡偝傟偰拲栚偝傟偨丅70擭戙廔傢傝偵儈儞僈僗偺摨椈偩偭偨僥僫乕偺僕儑乕僕丒傾僟儉僗偲慻傫偱憃摢僶儞僪丄僕儑乕僕丒傾僟儉僗亖僪儞丒僾乕儗儞丒僇儖僥僢僩傪寢惉丅儊儞僶乕偵偼摨偠偔儈儞僈僗丒僌儖乕僾偺斣摢奿偩偭偨僪儔儉僗偺僟僯乕丒儕僢僠儌儞僪傕偄偨丅偙偺僶儞僪偼10擭傎偳懕偄偨偑丄偙偺偙傠偑僾乕儗儞偺僉儍儕傾偺僴僀儔僀僩偩偭偨偲巚偆丅80擭戙枛偵僇儖僥僢僩傪夝嶶偟偨僾乕儗儞偼丄90擭戙偵擖偭偰傾僼儕僇儞丒僽儔僕儕傾儞丒僐僱僋僔儑儞偲偄偆僶儞僪傪棫偪忋偘偨丅偙偺僌儖乕僾偵傛傞傾儖僶儉偺堦枃偑丄慜婰亀Ode to Life亁偱偁傝丄偙偙偵偼昞戣嬋偺傎偐丄1992擭偵朣偔側偭偨挿擭偺柨桭僕儑乕僕丒傾僟儉僗傊偺捛搲嬋 "Ah, George, We Hardly Knew Ya" 偑廂傔傜傟偰偄傞丅偙傟偑傑偨丄椳側偟偵偼挳偗側偄柤嬋偩丅愗乆偲偟偨忣姶丄朣偒桭傪偟偺傇巚偄偑嫻偵敆傝丄姶摦傪桿偆丅僾乕儗儞偼偦偺屻傕墵惙偵妶摦偟偰偄偨偑丄傾僟儉僗偺偁偲傪捛偆傛偆偵丄1995擭丄53嵨偱巰嫀偟偨丅
儌僟儞丒僕儍僘巎忋丄僐儞億乕僓乕偲偟偰傕抦傜傟傞儈儏乕僕僔儍儞偲偄偆偲丄僷乕僇乕丄僈儗僗僺乕丄儌儞僋丄僐儖僩儗乕儞丄僔儖償傽乕丄僑儖僜儞偲偄偭偨柤慜偑巚偄晜偐傇丅斵傜偺偮偔偭偨嬋偼懡偔偺僕儍僘儊儞偵傛偭偰昿斏偵嵦傝忋偘傜傟偰偄傞丅偲偙傠偑丄帪戙偺偣偄傕偁傞偩傠偆偑丄僾乕儗儞偺嬋偼拠娫偆偪偱偨傑偵墘憈偝傟傞偩偗偱丄堦斒揑偵偼傎偲傫偳墘憈偝傟傞偙偲偑側偄丅偦傟偱傕僾乕儗儞偼忋婰偺恖偨偪偲尐傪暲傋傞丄偡偖傟偨僐儞億乕僓乕偩偭偨偲巚偆丅
傆偨偨傃 "Ode to Life" 傪挳偔丅偟傒偠傒偲偟偨旤偟偄壒偩丅偪傚偭偲僒僢僠儌偺壧偭偨 "What a Wonderful World" 傪憐婲偝偣傞丅偄傠偄傠偁偭偨偗偳丄恖惗偼偦傫側偵埆偄傕偺偠傖側偐偭偨丄偲偄偆婥帩偪偑桸偄偰偔傞丅巰偸偲偒偼丄偙偆偄偆壒妝偵帹傪孹偗側偑傜椃棫偪偨偄傕偺偩偲巚偆丅
2011.05.16 (寧) 斵傜偼偨偩嫀偭偰偄偔丄儉乕儞儔僀僩丒儅僀儖偺斵曽偵
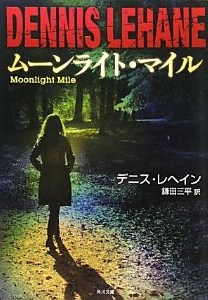 儃僗僩儞傪晳戜偵偟偨巹棫扵掋僷僩儕僢僋偲傾儞僕乕傪庡恖岞偲偡傞僨僯僗丒儗僿僀儞偺僴乕僪儃僀儖僪丒儈僗僥儕乕丒僔儕乕僘偺怴嶌乽儉乕儞儔僀僩丒儅僀儖乿偑東栿敪攧偝傟偨乮妏愳暥屔乯丅側傫偲慜嶌乽塉偵婩傝傪乿偐傜11擭傇傝偺嶌昳偱偁傝丄僔儕乕僘嵟廔嶌偲柫懪偨傟偰偄傞丅
儃僗僩儞傪晳戜偵偟偨巹棫扵掋僷僩儕僢僋偲傾儞僕乕傪庡恖岞偲偡傞僨僯僗丒儗僿僀儞偺僴乕僪儃僀儖僪丒儈僗僥儕乕丒僔儕乕僘偺怴嶌乽儉乕儞儔僀僩丒儅僀儖乿偑東栿敪攧偝傟偨乮妏愳暥屔乯丅側傫偲慜嶌乽塉偵婩傝傪乿偐傜11擭傇傝偺嶌昳偱偁傝丄僔儕乕僘嵟廔嶌偲柫懪偨傟偰偄傞丅僨僯僗丒儗僿僀儞偼1994擭偵僷僩儕僢僋仌傾儞僕乕丒僔儕乕僘偺戞1嶌乽僗僐僢僠偵椳傪棳偟偰乿傪敪昞偟偰埲棃丄傎傏枅擭僐儞僗僞儞僩偵斵傜偺暔岅傪彂偒宲偄偱偒偨偑丄1999擭偵戞5嶌偺乽塉偵婩傝傪乿傪敪昞偟偰埲棃丄偙偺僔儕乕僘偺幏昅傪拞抐偟丄扨敪偺彫愢偵堏峴偟偰偟傑偭偨丅
僷僩儕僢僋仌傾儞僕乕丒僔儕乕僘偺枺椡偼丄搊応恖暔偺恖娫娭學偲儃僗僩儞偲偄偆奨偺昤偒曽偵偁偭偨丅梒撻愼偱偁傞庡恖岞偺抝彈傆偨傝偺旝柇側娭學偵嫽枴傪偦偦傜傟偨偟丄斵傜偲屌偄桭忣偱寢偽傟偰偄傞恖娫暫婍僽僢僶偲偄偆僉儍儔僋僞乕傕報徾揑偩偭偨丅僴乕僪儃僀儖僪偺婎杮揑側崪奿傪旛偊側偑傜傕丄庡恖岞偨偪偑怱偵彎傪晧偄偮偮丄峳攑偟偰偄偔奨偱恖娫偺怱偵愽傓幾埆側嵃偲愴偆巔偑丄偦傟傑偱偵側偄怴慛側姶摦傪傕偨傜偟偨丅
戞1嶌埲棃丄僷僩儕僢僋仌傾儞僕乕丒僔儕乕僘偺柺敀偝偺偲傝偙偵側偭偰偄偨傏偔偼丄戞5嶌偱搑愗傟偨偺傪巆擮偵巚偭偰偄偨丅扨敪嶌昳偵堏偭偰偐傜偺儗僿僀儞偼丄乽儈僗僥傿僢僋丒儕償傽乕乿乽僔儍僢僞乕丒傾僀儔儞僪乿乽塣柦偺擔乿偲椡嶌傪彂偄偰偒偨偑丄傛偔偱偒偨楌巎彫愢偱偁傞乽塣柦偺擔乿傪彍偄偰丄傒側媬偄偺側偄斶寑惈偑嫮挷偝傟偨丄撉傫偱偄偰婥偑柵擖傞傛偆側彫愢偽偐傝偵側偭偰偟傑偭偨丅
傕偆偙偺僔儕乕僘偼廔傢偭偰偟傑偭偨偺偐偲掹傔偐偗偰偄偨偲偙傠偵丄崱夞偺怴嶌偺搊応偱偁傞丅偙傟偼僔儕乕僘戞3嶌乽垽偟偒幰偼偡傋偰嫀傝峴偔乿偺屻擔択偲偟偰昤偐傟偰偄傞丅乽垽偟偒幰偼乣乿偼峴曽晄柧偵側偭偨彈偺巕傪媬弌偡傞帠審偩偭偨偑丄崱嶌偼丄偦傟偐傜12擭屻丄偄傑傗崅峑惗偵惉挿偟偨偦偺柡偑嵞傃峴曽傪偔傜傑偟偨丄抦傜偣傪庴偗偨僷僩儕僢僋偑怱偵傢偩偐傑傝傪書偊偮偮憑嶕傪巒傔傞偲丄偄傠偄傠側撲偑晜偐傃忋偑傞偲偄偆暔岅偩丅
12擭宱偭偰丄僷僩儕僢僋偲傾儞僕乕偺娐嫬偵傕戝偒側曄壔偑朘傟偰偄傞丅偁傟偭偲尵偆傋偒偐丄傗偭傁傝偲尵偆傋偒偐丄僷僩儕僢僋偲傾儞僕乕偼晇晈偵側偭偰偍傝丄側傫偲巕嫙傑偱偄傞丅偦傫側愝掕偺偣偄偐丄偙傟傑偱偺僔儕乕僘偲斾傋偰丄傗傗僀儞僷僋僩偵寚偗傞偒傜偄偑偁傞偟丄屻敿偺儘僔傾儞丒儅僼傿傾偑搊応偡傞偁偨傝偐傜偺嬝偺揥奐偵峳偭傐偝傪姶偠傞丅偲偼偄偊丄偝偡偑偵搊応恖暔偺憿宍偼偡偖傟偰偄傞偟丄揑妋側晽宨昤幨傕嶀偊偰偍傝丄撉傒偛偨偊偼廩暘偩丅
晄摦嶻僶僽儖偺曵夡偲9.11傪宱偨偁偲偺傾儊儕僇偺嬯擄丄恖乆偺峳傫偩怱忣偑僋儘乕僘傾僢僾偝傟偰偍傝丄偙傟傑偱埲忋偵傗傝偒傟側偝傗垼姶偑昚偭偰偄傞偑丄悘強偵帵偝傟傞僷僩儕僢僋偺巕嫙偵傛偣傞垽忣傗撈摿偺儐乕儌傾傪岎偊偨寉柇側暥懱偑廳嬯偟偝傪傗傢傜偘偰偄傞丅壠掚傪庣傞偨傔偵埨掕偟偨巇帠偵廇偙偆偲偡傞僷僩儕僢僋偩偑丄怱偺側偐偵烼愊偡傞悽偺拞偺晄惓媊偵懳偡傞搟傝傪墴偟偲偳傔傞偙偲偑偱偒偢丄側偐側偐埨掕偟偨廂擖傪摼傞惗妶傪偍偔傞偙偲偑偱偒側偄丅偙偺偁偨傝偺昤幨傕撉幰偺嫟姶傪屇傇偩傠偆丅
嵟廔嶌偵偁偨傝丄僔儕乕僘傪掲傔偔偔傠偆偲偡傞嶌幰偺堄恾偑偁偪偙偪偵偆偐偑偊傞丅憉傗偐側梋塁傪姶偠偝偣傞僄儞僨傿儞僌傕姰寢曆偵傆偝傢偟偄丅儗僿僀儞偑偙偺僷僩儕僢僋偲傾儞僕乕偺暔岅傪拞搑敿抂側傑傑偵偣偢丄11擭傪宱偰偲偼偄偊嵟廔嶌傪彂偄偨偙偲偵丄嶌幰偲偟偰偺椙怱傪尒傞巚偄偑偡傞丅
栿幰偁偲偑偒偵丄儗僿僀儞偑岅偭偨師偺傛偆側尵梩偑徯夘偝傟偰偄傞丅乽僔儕乕僘傕偺偵偼丄偟偐傞傋偒姫悢偲偄偆傕偺偑偁傞偲巚偭偰偄傞丅偨偲偊偽乻偁偺僔儕乕僘偼15姫栚偑嵟崅両乼側傫偰榖偼暦偄偨偙偲偑側偄偩傠偆丅偳傫側僔儕乕僘偱傕廔傢傞傋偒偲偒偲偄偆偺偑偁傞偺偩丅乮拞棯乯傢偨偟偼丄嵟廔姫偱庡恖岞偨偪偑巰側側偗傟偽側傜側偄偲偼巚偭偰偄側偄丅斵傜偼偨偩丄嫀偭偰偄偔偩偗偩乿
儗僿僀儞偼傛偔暘偐偭偰偄傞丅偳傫側僔儕乕僘偱傕挿偔懕偗偽儅儞僱儕偵側傝丄姰惉搙偑掅壓偡傞偙偲偼旔偗傜傟側偄乮婬側椺奜偑儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘偩乯丅僷僩儕僢僋仌傾儞僕乕丒僔儕乕僘傪6嶌偱廔椆偝偣偨偺偼惓偟偄敾抐偩偭偨偲巚偆丅僔儕乕僘偺廔椆偼惿偟偄偑丄僷僩儕僢僋偲傾儞僕乕丄偦傟偵僽僢僶偺暔岅偑崅悈弨傪堐帩偟偨傑傑廔傢偭偨偙偲偵攺庤傪憲傠偆丅
2011.05.01 (擔) 扙尨敪偺婥塣偑惙傝忋偑傜側偄偺偼側偤偐
4寧19擔晅偗偺挬擔怴暦偵尨敪偵娭偡傞悽榑挷嵏偺寢壥偑嵹偭偰偄偨偑丄偦傟傪尒偰湵慠偲偟偨丅亀尨敪偺崱屻亁偲偄偆栤偄偵偮偄偰丄乽憹傗偡乿偑5亾偲嬐彮側偺偼摉慠偲偟偰傕丄乽尰忬堐帩乿偑51亾傕偁傝丄乽尭傜偡乿偼30亾偟偐側偄丅亀尨敪棙梡亁偲偄偆栤偄偵偼丄乽巀惉乿偑50亾偱乽斀懳乿偑32亾偩丅尨敪偵娭偟偰巀惉偲尰忬堐帩偑敿暘傕愯傔偰偄傞丅尨敪帠屘偑偄傑傕怺崗側忬嫷偵偁傞尰嵼丄傕偭偲斀懳偺摦偒偑崅傑偭偰偄偄偼偢側偺偵丄偙偺堄幆偺掅偝偼偳偆偟偨偙偲偐丅崙柉偼偙傫側旐奞偵偝傜偝傟偰傕丄傑偩栚妎傔側偄偺偐丅偄傗丄偦傫側偙偲偼偁傞傑偄丅偙傟偼丄尨敪悇恑偺棳傟傪撢嵙偝偣偨偔側偄惌晎丒嶻嬈奅丄偝傜偵傾儊儕僇偺堄岦傪媯傫偩怴暦偺悽榑憖嶌丒悽榑桿摫側偺偩丅僋儕儞僩儞崙柋挿姱偺朘擔偵僞僀儈儞僌傪崌傢偣偰偺敪昞偩偭偨偙偲偑偦傟傪暔岅偭偰偄傞丅惌晎偲儅僗僐儈偑崌嶌偟偨尨敪偼懕偗傑偡傛偲偄偆傾儊儕僇傊偺僨儌儞僗僩儗乕僔儑儞偩偲偟偐峫偊傜傟側偄丅
偙傟傑偱擔杮偱偼丄尨敪悇恑偺惙傝忋偑傝偺偐偘偱丄惌晎丒姱椈偲揹椡夛幮偺傾儊偲儉僠偺岺嶌偵傛傝丄尨敪斀懳偺惡偼梷偊崬傑傟偰偒偨丅妛夛偱偼丄尨敪偵斀懳偡傞尨巕椡妛幰偼業崪偵椻嬾偝傟偰偒偰偄傞丅尨敪帠屘偵偮偄偰僥儗價偵弌墘偟偰夝愢偟偰偄傞偺偼丄傎偲傫偳怣梡偱偒側偄屼梡妛幰偽偐傝偩偑丄嬝偑捠偭偨愢摼椡偺偁傞榖傪偡傞悢彮側偄妛幰偺傂偲傝偵丄嫗搒戝妛尨巕楩幚尡強彆嫵偺彫弌桾復巵偑偄傞丅堦娧偟偰尨敪偵斀懳偟偰偒偨尨巕椡岺妛幰偩丅偦偺偨傔偱偁傠偆丄彫弌巵偼61嵨偺偄傑傕彆嫵乮偐偮偰偺彆庤乯偺傑傑偩丅岞暯拞棫偱偁傞傋偒嵸敾姱傗専帠偲偄偊偳傕丄崙偺堄岦偵媡傜偭偨傜曬暅恖帠傪庴偗椻傗斞傪怘傢偝傟傞丅摨偠偔崙壠岞柋堳偱偁傞崙棫戝妛偺嫵怑堳傕偦偺椺偵楻傟側偄偺偩丅峀悾棽巵偺傛偆側嵼栰偺尋媶幰偑偄偔傜惡崅偵尨敪斀懳偲嫨傫偱傕柍帇偝傟傞丅崙夛媍堳偵傕壨栰懢榊偺傛偆偵扙尨敪傪庡挘偡傞恖偼偄傞偑丄堎抂幰偱偁傝儕乕僟乕僔僢僾傪偲傞偙偲偼偱偒側偄丅
堦斒揑偵丄偄偭偨傫恑傫偩壢妛媄弍偑屻栠傝偡傞偙偲偼側偄丅尨巕椡偲偄偆媄弍傪敪柧偟偰偟傑偭偨埲忋丄恖娫偼偦傟傪偲偙偲傫棙梡偟傛偆偲偡傞偩傠偆丅偩偑丄尨巕椡偲偄偆埆杺偺媄弍偼丄傎傫偲偆偵恖娫偑僐儞僩儘乕儖偱偒傞傕偺側偺偐丅恖娫偑敪柧偟偨媄弍偵傛偭偰恖娫帺恎偑柵傏偝傟丄悽奅偑廔傢傝傪崘偘傞丄偲偄偆SF彫愢傪巚偄婲偙偟偰偟傑偆丅偄偔傜埨慡愝寁傪偟丄婋婡娗棟傪偟偰傕丄嫄戝側帺慠嵭奞偺慜偱偼側偡偡傋偑側偄丅僗儕乕儅僀儖丄僠僃儖僲僽僀儕丄暉搰偲丄戝偒側帠屘偑偄偔傜婲偙偭偰傕丄偄偭偙偆偵悽奅偼扙尨敪偵岦偐偍偆偲偟側偄丅偮偔偯偔恖娫偲偼丄挦傝側偄惗偒傕偺偩偲巚偆丅偣傔偰峀搰丒挿嶈傪宱尡偟偨擔杮偼丄僪僀僣傪尒廗偭偰婤慠偲偟偨懺搙偱婳摴廋惓偟丄扙尨敪傪傔偞偡傋偒偩丅偦偺偨傔偵偼崙柉偑尨敪斀懳偺惡傪忋偘側偗傟偽側傜側偄丅惌晎傗儅僗僐儈偺悽榑桿摫偵榝傢偝傟偢丄帺暘偱峫偊偰嫮偔堄巙昞帵偟側偗傟偽側傜側偄丅
2011.04.23 (搚) 亀壗恖偵懳偟偰傕埆堄傪書偐偢亁
偙傟偼僩儉丒儅僢僉儞僩僢僔儏偲偄偆僩儘儞儃乕儞憈幰偑嶌嬋偟偨僕儍僘丒僫儞僶乕偱偁傞丅堦斒揑偵偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄嬋偩偑丄挳偒崬傫偩僕儍僘丒僼傽儞側傜丄偁偁丄偁傟偹丄偲偆側偢偔恖傕懡偄偩傠偆丅偙偙偱乮"With Malice Toward None" by Tommy Flanagan at YouTube乯帋挳偱偒傞丅
嬋柤偺乽僂傿僘丒儅儕僗丒僩僂僅乕僪丒僫儞乿乮With Malice Toward None乯偲偼乽扤偵懳偟偰傕埆堄傪帩偨偢偵乿偲偄偆堄枴偩丅傾儊儕僇16戙戝摑椞儕儞僇乕儞偑戞2婜戝摑椞廇擟偵嵺偟偰峴側偭偨墘愢偺堦愡偱偁傝丄惓偟偔偼丄 "With malice toward none, with charity for all"乮壗恖偵懳偟偰傕埆堄傪書偐偢丄偡傋偰偺恖偵巚偄傗傝傪傕偭偰乯偲懕偔丅儕儞僇乕儞偺尵梩偲偄偆偲丄擔杮偱偼丄偁偺桳柤側乽恖柉偺恖柉偵傛傞乣乿偲偄偆僎僥傿僗僶乕僌墘愢埲奜偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄丅偩偑杮崙傾儊儕僇偱偼偙偺尵梩傕柤尵偲偟偰恖岥偵鋂鄑偝傟偰偄傞傜偟偄丅帺崙偺愭廧柉傪惂埑偟丄懠崙傪晲椡峌寕偟偰偒偨丄偁偺岲愴揑側傾儊儕僇偱丄偙傫側暓偺嫬抧傒偨偄側帨垽偲姲梕偵枮偪偨尵梩偑峀偔岲傑傟傞偲偼丄側傫偲傕旂擏側榖偩丅
嶌嬋幰偺儅僢僉儞僩僢僔儏偼僕儍僘僥僢僩傗僒僪丒儊儖丒僆乕働僗僩儔偺儊儞僶乕偲偟偰偺妶摦楌偑偁傞偑丄僩儘儞儃乕儞憈幰偲偟偰偼戝惉偣偢丄僐儞億乕僓乕偲偟偰捠岲傒偺恖乆偺婰壇偵巆偭偰偄傞丅嶌晽偲偟偰偼丄偪傚偭偲儀僯乕丒僑儖僜儞偵帡偰偄傞丅僑儖僜儞偐傜僼傽儞僉乕側僥僀僗僩傪敄傔丄愻楙偝傪憹偟偨姶偠丄偲尵偭偨傜偄偄偩傠偆偐丅僕儍僘僥僢僩偵偼儀僯乕丒僑儖僜儞丄僒僪丒儊儖偵偼僒僪丒僕儑乕儞僘偲偄偆楙払偺嶌曇嬋幰偑儕乕僟乕偵偄偨偨傔丄僌儖乕僾嵼抍帪偵偼斵偺嬋偑嵦傝忋偘傜傟傞偙偲偼偁傑傝側偐偭偨偑丄60擭戙埲崀丄堦晹偺儈儏乕僕僔儍儞偺偁偄偩偱彮偟偯偮墘憈偝傟傞傛偆偵側偭偨丅斵偺嬋偵偼乽僇僢僾丒儀傾儔乕僘乿傗乽僓丒僨僀丒傾僼僞乕乿偲偄偭偨壚嬋傕偁傞偑丄偄偪偽傫桳柤側偺偼偙偺乽僂傿僘丒儅儕僗丒僩僂僅乕僪丒僫儞乿偱偁傠偆丅
乽僂傿僘丒儅儕僗丒僩僂僅乕僪丒僫儞乿偼偳偆傗傜嶿旤壧傪壓晘偒偵偟偰彂偐傟偨傕偺傜偟偄丅嶿旤壧461斣乽庡傢傟傪垽偡乿偑偦傟偩偲偄偆偙偲偩偑丄偦偺曽柺偵偮偄偰偼柍抦側偺偱丄傛偔暘偐傜側偄丅偩偑丄愭偵傕彂偄偨傛偆偵丄偙偺嬋偼偳偙偐僑僗儁儖晽偺嬁偒傪懷傃偰偄傞偟丄惔悷側暤埻婥偑昚偭偰傞偺偱丄尨嬋偑嶿旤壧偩偲偄偆偺傕廩暘偵擺摼偱偒傞丅
偙偺嬋偼儅僢僉儞僩僢僔儏偺嶌昳偺側偐偱偼偄偪偽傫億僺儏儔乕偩偲偼偄偊丄儗僐乕僨傿儞僌偼偦傟傎偳懡偔偼側偄丅偣偄偤偄20庬椶偖傜偄偩丅僺傾僲偺僩儈乕丒僼儔僫僈儞偼儅僢僉儞僩僢僔儏偺嬋傪垽憈偟偰偍傝丄偙偺乽僂傿僘丒儅儕僗丒僩僂僅乕僪丒僫儞乿傕2夞儗僐乕僨傿儞僌偟偰偄傞丅儀乕僗偲偺僨儏僆墘憈偲僩儕僆墘憈偩偑丄撪梕偲偟偰偼1978擭偵悂偒崬傑傟偨僨儏僆丒償傽乕僕儑儞偺傎偆偑抐慠偡偽傜偟偄丅僼儔僫僈儞偺傗偝偟偝丄儊儘僨傿僗僩偲偟偰偺摿幙偑嵟崅搙偵敪婗偝傟偰偄傞偟丄婑傝揧偆傛偆偵抏偔僕儑乕僕丒儉儔乕僣偺儀乕僗偑堦懱姶傪忴偟弌偟偰偄傞丅偙偺嬋偺戙昞揑側墘憈偲偄偊傞偩傠偆丅
偙偺嬋傪嵟弶偵墘憈偟偨偺偼1959擭丄僒僢僋僗憈幰偺僕僃乕儉僗丒儉乕僨傿偩偭偨丅儉乕僨傿傕2夞悂偒崬傫偱偍傝丄弶墘偱偼僼儖乕僩丄嵞墘偱偼僥僫乕傪悂偄偰偄傞丅傎偐偵丄僴儚乕僪丒儅僊乕乮tp乯丄價儖丒僴乕僪儅儞乮tp乯丄僋儕僼僅乕僪丒僕儑乕僟儞乮ts乯丄儈儖僩丒僕儍僋僜儞乮vib乯丄儃價乕丒僥傿儌儞僘乮p乯丄僕儑儞丒僸僢僋僗乮p乯偲偄偭偨儈儏乕僕僔儍儞偨偪偺償傽乕僕儑儞偑偁傞丅偦傟偧傟帩偪枴傪惗偐偟偨挳偒偛偨偊偺偁傞墘憈偵側偭偰偄傞丅嬋偑偄偄偲墘憈傕傛偔側傞岲椺偱偁傠偆丅僕儑儞丒僿儞僪儕僢僋僗偑壧帉傪晅偗丄儔儞僶乕僩丒僿儞僪儕僢僋僗仌儘僗偑壧偭偨償傽乕僕儑儞傕偁傞丅傑傞偱婩傝傪曺偘傞偐偺傛偆側尩偦偐側僐乕儔僗偑報徾怺偄丅
偙偆偟偰柤慜傪嫇偘傞偲丄偄傢備傞挻堦棳偺儈儏乕僕僔儍儞偼儈儖僩丒僕儍僋僜儞偖傜偄偱丄偁偲偼丄幚椡偼偁傞偺偵丄偁傑傝梲偺岝偑偁偨傞摴傪曕傫偱偙側偐偭偨丄墢偺壓偺椡帩偪揑側恖偨偪偽偐傝偩丅僼儔僫僈儞偵偟偰傕丄斢擭偼僩儕僆傪棪偄偰儕乕僟乕偲偟偰妶桇偟偨偑丄挿擭僒僀僪儊儞傗壧敽僺傾僯僗僩偲偟偰榚栶偵娒傫偠偰偄偨宱楌偺帩偪庡偩丅帺恎偑僕儍僘儅儞偲偟偰偼擔堿偺摴傪曕傫偩儅僢僉儞僩僢僔儏偺嬋偼丄偦傫側堦棳偵偼側傟側偐偭偨儈儏乕僕僔儍儞偨偪偺怱忣偵慽偊偐偗傞壗偐偑偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅
儅僢僉儞僩僢僔儏杮恖偺償傽乕僕儑儞偼丄2004擭偵斵偑77嵨偵偟偰悂偒崬傫偩桞堦偺儕乕僟乕丒傾儖僶儉亀With Malice Toward None亁偵廂傔傜傟偰偄傞丅偐偮偰偺儃僗偱偁傞僥僫乕偺儀僯乕丒僑儖僜儞偲怴恑僺傾僯僗僩丄僿儗儞丒僒儞傪拞怱偲偟偨墘憈偱丄僑僗儁儖丒僥僀僗僩偺傾儗儞僕偑巤偝傟偰偍傝丄偝傝偘側偄偑怱傪懪偮僒僂儞僪偵巇忋偑偭偰偄傞丅
2011.04.16 (搚) 愇尨搒抦帠4慖偵巚偆
愇尨偼傎偔偦徫傫偱偄傞偩傠偆丅偍傟偼壗傪偟偰傕偄偄傫偩偲閬傝峍傇偭偰偄傞偵堘偄側偄丅偙偺庛幰傪曁帇偟丄奜崙恖傪嵎暿偡傞78嵨偺尃椡巙岦榁恖傪4搙傕抦帠偵慖傇搒柉偑偄傞偲偼丄晄巚媍偺偒傢傒偩丅廡偵2乣3擔偟偐搊挕偣偢丄埿挘傝嶶傜偟偰朶尵傪揻偒丄搾悈偺傛偆偵惻嬥傪巊偭偰暔尒梀嶳傑偑偄偺奀奜帇嶡傪孞傝曉偟丄帠屘偵傛偭偰尨敪偺婋尟惈偑業掓偟偰傕偦傟偱傕尨敪偼悇恑偡傋偒偩偲尵偄挘傞丄偙傫側攜傪儕乕僟乕偵慖傇恖娫偼丄帺媠揑側怱忣偺帩偪庡偲偟偐巚偊側偄丅傑傞偱丄墸傜傟偰傕廟傜傟偰傕彣傪嶌傜傟偰傕丄偄偮傑偱傕帺棫偣偢晇偵偡偑傝懕偗傞楧撦側嵢偺傛偆偩丅
嫮偄恖偵擟偣偰偍偗偽埨怱偩偲偄偆丄擔杮恖撈摿偺梤偺傛偆側懠恖擟偣偺怱惈偺側偣傞傢偞偩傠偆偐丅偦傟偵偟偰傕丄憗偔堷戅偟偰嶰暥彫愢偱傕彂偄偰偄傟偽偄偄偺偵丄偐偮偰偼乽60丄70偺榁恖偵惌帯傪擟偣偪傖偄偗側偄乿偲尵偭偰偍偒側偑傜丄帺暘偼80嵨嬤偄榁巆傪偝傜偟側偑傜搒抦帠偺堉巕偵偟偑傒偮偔愇尨傪丄側偤巟帩偡傞堦斒搒柉偑偄傞偺偐丄偳偆偵傕棟夝偱偒側偄丅
2011.04.14 (栘) 尨敪帠屘偵娭偡傞奀奜偱偺晽昡偲傾儊儕僇棅傒偺暅媽懳嶔
偙傫側偰偄偨傜偔偩偐傜丄尨敪帠屘偵娭偡傞惌晎丒搶揹偺敪昞偑奀奜偐傜晄怣姶傪攦偆偺傕摉慠偩丅奀奜偺惌晎傗愱栧婡娭偼丄嵟弶偐傜丄壗偐塀偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丄杮摉偺偙偲傪尵偭偰偄側偄偺偱偼側偄偐丄偲媈偭偰偄偨丅偦偺媈擮偼偄傑傕徚偊偰偄側偄丅偦傟偑梫場偲側偭偰丄暉搰尨敪帠屘偵娭偡傞栂憐傗壇應偑擖傝崿偠偭偨奀奜偱偺屩戝曬摴傪惗傫偩丅
奀奜偱偼堦帪丄擔杮拞偑曻幩擻偵墭愼偝傟偰偄傞偐偺傛偆側庴偗庢傝曽傪偝傟偰偄偨丅傕偆曻幩擻嵭奞偱1枩恖偑朣偔側偭偨偲偐丄擔杮偺怘昳偼偡傋偰墭愼偝傟偰偄傞偲偐偄偭偨榖偑峀傑偭偨偟丄棃擔偡傞奜崙恖偼寖尭偟丄嵼棷奜崙恖偼偄偭偣偄偵杮崙偵婣崙偟偨傝惣擔杮偵旔擄偟偨丅偦偆側偭偨戝偒側棟桼偑丄偝偭傁傝梫椞傪摼側偄擔杮惌晎傗搶揹偺敪昞偵晄怣姶偑偁偍傜傟偨偙偲偵偁傞偺偼娫堘偄側偄丅
偦傫側夁戝曬摴偼偄傑偼懡彮偼廂傑偭偨傛偆偩偑丄偄偤傫偲偟偰曻幩擻偵墭愼偝傟偨擔杮偲偄偆晽昡偼敄傟偰偄側偄丅娯崙偱偼曻幩擻塉偑崀傞偐傜偲偄偆偙偲偱彫妛峑偑媥峑偵側偭偨偲偄偆偟丄墷暷偱偼擔杮偐傜偺桝擖暔偼怘昳偩偗偱側偔岺嬈惢昳傕墭愼偝傟偰偄傞偲偄偆晽昡偑棳傟偰偄傞丅尨敪帠屘偵傛傝暉搰偱偡偱偵50恖偑朣偔側偭偨偲曬摴偟偨儊僨傿傾傕偁傞丅擔杮偐傜擖崙偡傞恖傗桝擖偡傞暔昳偵偼惻娭偱曻幩擻應掕傪壽偟偰偄傞崙傕偁傞傜偟偄丅偄偭偨傫旐偭偨擔杮偼晐偄偲偄偆僀儊乕僕丄擔杮偵懳偡傞晄怣姶傪怈偄嫀傞偺偼梕堈側偙偲偱偼側偄丅
恔嵭偐傜2廡娫傎偳宱偭偨偙傠偺偙偲偩偑丄僪僀僣岅偵姮擻側桭恖偑丄僪僀僣偺Yahoo偵嵹偭偨尨敪帠屘偵娭偡傞僯儏乕僗偵偮偄偰嫵偊偰偔傟偨丅擔杮偵偄傞挀嵼堳偑彂偄偨偲偄偆偦偺僯儏乕僗偲偼丄乽搶揹偼偙偺婋婡偱懡偔偺尩偟偄惗妶傪偟偰偄傞恖払傪暯婥偱棙梡偟偰偄傞丅偦偺懡偔偑儂乕儉儗僗偱偁傝丄奜恖楯摥幰偱偁傞丅偦傟偳偙傠偐枹惉擭幰傕偄傞傜偟偄丅斵傜偼挿婜娫尨敪偱摥偄偰偄偰旐敇偟偨偆偊娙扨偵夝屬偝傟傞偺偱丄攑婞楯摥幰偲屇偽傟偰偄傞丅偙偺傛偆側幐嬈幰傊偺嶏庢偼偙偙悢10擭棃峴傢傟偰偒偨乿乽擔杮偱偼 "Fukushima 50" 偲屇偽傟傞桬幰払50恖偑丄惗柦傪搎偟偰尨敪嵭奞偵棫偪岦偐偭偰偄傞丅斵傜偼偡偱偵偐側傝偺曻幩慄傪梺傃偰偄偰丄彮側偔偲傕偦偺1/3偼偙偺巇帠偑廔傢偭偨傜偡偖偵巰朣偡傞偙偲偼妋幚偱偁傠偆乿偲偄偆傛偆側撪梕偩偭偨丅
偙傟傪暦偄偨偲偒偼丄偙傫側偄偄壛尭側榖傪偳偙偱偱偭偪忋偘偨偺偩傠偆丄偲堦徫偵晅偟偨偑丄偦偺屻傑傕側偔丄廡姧帍側偳偱丄幚嵺偵搶揹偼尨敪偺壓惪偗嶌嬈堳偵傾僕傾側偳偺奜崙恖傪巊偭偰偄偨偙偲傪撉傓偵媦傫偱丄僪僀僣Yahoo偺婰帠偼偁側偑偪姰慡側傑備偮偽婰帠偱傕側偄偺偩偲抦偭偨丅偝傜偵丄亀Fukushima 50亁偲偄偆尵梩傕丄擔杮偺儅僗僐儈偱偼傑偭偨偔弌偰偙側偄偑丄傾儊儕僇偺偁傞儊僨傿傾偑丄帠屘敪惗捈屻偵敪揹強偵巆偭偰嶌嬈偵偁偨偭偨50恖慜屻偺恖偨偪傪偙偆屇傫偱偦偺桬姼側峴堊傪徧偊偨偙偲偐傜墷暷偱峀傑偭偨尵梩偩偲偄偆偙偲偑暘偐偭偨丅僸乕儘乕岲偒側傾儊儕僇傜偟偄庢傝忋偘曽偩偑丄偦傟傗偙傟傗偱丄擔杮偲奀奜偱偺曬摴偺偝傟曽偺堘偄傪幚姶偟偨師戞偱偁傞丅
傾儊儕僇偺儅僗僐儈偼偝偐傫偵屩戝曬摴偟偰偄傞偑丄惌晎婡娭偼婋婡姶傪曞傜偣側偑傜傕尰幚偵懄偟偰椻惷偵帠懺傪暘愅偟偰偄傞丅1廡娫傎偳慜偺挬擔怴暦偵傾儊儕僇尨巕椡婯惂埾堳夛偑嶌惉偟偨暉搰尨敪帠屘偵娭偡傞曬崘彂偑徯夘偝傟偰偄偨丅尰忬偵娭偡傞悇掕偲暅媽偺偨傔偺懳嶔偑傑偲傔傜傟偰偍傝丄偠偮偵棟楬惍慠偲偟偨撪梕偩偲姶偠偨丅栤戣側偺偼丄側偤摉帠崙偱偁傞擔杮偱偙偺傛偆側曬崘彂傪偮偔傞偙偲偑偱偒側偄偺偐偩丅傕偟偐偡傞偲丄偮偔傜傟偰偄傞偗偳丄塀偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅怴暦偺婰帠偵傛傞偲丄偙偺曬崘彂偵偼丄椻媝梡偵拲擖偡傞悈傪丄奀悈偱偼側偔丄偱偒傞偩偗憗偔恀悈偵愗傝懼偊傞傋偒偩偲偐丄悈慺敋敪偺婋尟傪杊偖偨傔拏慺僈僗傪奿擺梕婍偵拲擖偡傋偒偩偲偄偭偨嬶懱揑側採尵偑側偝傟偰偄偨丅搶揹偼丄偦偺採尵偵増偭偰丄奀悈偐傜恀悈偵愗傝懼偊丄拏慺僈僗傪拲擖偟偨偙偲偵側傞丅
忣偗側偄偙偲偵丄傕偼傗擔杮偺搶揹傕尨巕椡埨慡埾傕埨慡曐埨堾傕丄傾儊儕僇偺巜揈偵傛偭偰懳嶔傪島偠傞偟偐側偔側偭偨丅搶揹偼懪偮庤偑偡傋偰屻庤偵夞傝丄塃墲嵍墲偟偰偄傞傛偆偵偟偐尒偊側偄丅杮棃側傜儕乕僟乕僔僢僾傪敪婗偡傋偒尨巕椡埨慡埾傗埨慡曐埨堾傕傑偭偨偔僐儞僩儘乕儖偟偰偍傜偢丄柍擻偝傪偝傜偗弌偟偰偄傞丅偦傟偑幚懺側偺偩丅戝恔嵭偐傜1儠寧埲忋偑夁偓偨偄傑傕側偍丄暉搰尨敪偼婋尟側忬嫷偵偁傝丄埨掕壔偺傔偳偼棫偭偰偄側偄丅偙傟埲忋擔杮偺楢拞偵懳墳偝偣偰偄偰偼婋側偄丅傕偼傗暅媽偺偨傔偵偼丄抪傕奜暦傕幪偰偰丄崙嵺娗棟偵埾偹傞偐丄傾儊儕僇偵慡柺揑偵懳墳嶔傪棫偰偰傕傜偆偐偟偐側偄丅
2011.04.02 (栘) 搶揹偲桙拝偟偨尨巕椡埨慡埾堳夛偺庤敳偒娗棟偑尨敪帠屘傪惗傫偩
暉搰尨敪偺帠屘偼捗攇傪偐傇偭偨偙偲偵傛傞揹婥宯摑偺屘忈偵傛偭偰婲偙偭偨丅偄偭傐偆丄摨偠懢暯梞娸偵埵抲偡傞搶杒揹椡偺彈愳尨敪乮媨忛導乯偼旐奞傪傑偸偐傟偨丅柧埫傪暘偗偨偺偼捗攇懳嶔偺堘偄偩偭偨丅暉搰尨敪偼捗攇偺崅偝傪嵟戝5.6m偵憐掕偟偰愝寁偝傟偨偑丄彈愳尨敪偼9.1m偵憐掕偟偰愝寁偝傟偨丅偟偐傕巤愝偼奀柺偐傜14.8m偺崅偝偵寶愝偝傟偰偄偨丅崱夞丄暉搰尨敪偵傕彈愳尨敪偵傕10悢m偺捗攇偑墴偟婑偣偨偑丄彈愳尨敪偼丄堦晹偺愝旛偼怹悈偟偨傕偺偺丄旛偊偑廩暘偩偭偨偨傔丄抳柦揑側旐奞偵偼偄偨傜側偐偭偨丅偄傑偙偙偼偼旐嵭偟偨嬤椬偺挰柉偺旔擄強偵側偭偰偄傞偲偄偆丅暉搰尨敪偺嵭奞偑埨慡懳嶔偺晄旛偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟偨傕偺偱偁傞偙偲偼柧傜偐偩丅
3寧26擔晅偗偺挬擔怴暦偵傛傞偲丄2006擭偺崙夛偱丄摉帪偺尨巕椡埨慡曐埨堾偺帥嶁怣徍堾挿偼乽尨敪偱旕忢梡揹尮偑幐傢傟偰傕丄楩怱梟梈偼偁傝偊側偄偩傠偆偲偄偆偖傜偄傑偱埨慡愝寁傪偟偰偄傞乿偲弎傋偨丅偦偟偰尰嵼偺尨巕椡埨慡埾堳夛偺斄栚弔庽埾堳挿偼丄搶戝嫵庼偩偭偨2007擭偵丄尨敪偺旕忢梡揹尮偑僟僂儞偡傞偙偲傪憐掕偟偰偄側偄偺偐偲栤傢傟丄乽妱傝愗傝偩丅偪傚偭偲壜擻惈偑偁傞丄偦偆偄偭偨傕偺傪慡晹慻傒崌傢偣偰偄偭偨傜丄愝掕偑偱偒側偔側傞偟丄傕偺側傫偰愨懳偵憿傟側偄乿偲榖偟偰偄偨丅偙傫側柍愑擟側丄埨慡偵娭偟偰柍撢拝側攜偑丄尨巕椡偺埨慡傪娗棟偡傞慻怐偺僩僢僾偵擺傑偭偰偄傞偺偩丅
傢傟傢傟偼丄傑偐傝娫堘偊偽戝嶴帠偵偮側偑傞尨巕椡敪揹偼丄偲偆偤傫丄偁傜備傞壜擻惈傪峫椂偟偰愝掕偝傟偰偄傞偲巚偄崬傫偱偄偨丅偲偙傠偑偦偆偱偼側偐偭偨偺偩丅斄栚弔庽埨慡埾堳夛埾堳挿偺尵偆傛偆偵丄偁傜備傞壜擻惈傪慻傒偙傔偽愝掕偱偒側傞側傞偺側傜丄尨敪傪寶愝偣偢丄庤娫偼偐偐偭偰傕暿偺曽嶔傪専摙偡傟偽偄偄丅崙偲搶揹偼寢戸偟偰丄尨敪悇恑偺偨傔丄埨慡惈傪柍帇偟偰偒偨偙偲偵側傞丅偙偺媆嵩偲棤愗傝偼揙掙揑偵捛媦偟側偗傟偽側傜側偄丅
尨巕椡埨慡埾堳夛偼搶戝傪拞怱偲偟偨妛幰偨偪偑儊儞僶乕偵側偭偰偄傞丅搶揹偼桳傝梋傞嬥傪晲婍偵丄惌帯壠傗妛幰偨偪偵嬥傪偽傜傑偄偰偒偨丅惌帯壠傊偺婑晅偼偲傕偐偔丄桳椡戝妛偵懡妟偺婑晅傪偟偰偍傝丄偲偔偵搶戝偵偼枅擭丄憤妟5壄墌傕偺嬥傪婑晅偟偰偄傞偲偄偆偐傜嬃偔丅偦傫側戝妛偺妛幰楢拞偑僥儗價偱夝愢偟偰傕丄傑偲傕偵怣偠傞偙偲偼偱偒側偄丅埨堈偵尨巕椡敪揹偵棅傞揹椡夛幮丄偦傟傪娔撀偡傋偒尨巕椡埨慡埾堳夛傗尨巕椡埨慡曐埨堾偺僗僉偩傜偗偺婯惂丄偦傟傪梚岇偡傞屼梡妛幰丅棙奞娭學偑堦抳偟偨斵傜偑丄埨慡傪柍帇偟偰丄尨敪悇恑偲偄偆嫟捠栚揑偵岦偐偭偰暲憱偟偨丅撻傟崌偄偱恑傔傜傟偰偒偨尨巕椡峴惌丄惌晎丒嶻嬈奅丒妛幰偺桙拝偺峔恾偑偙偙偵偁傞丅
傾儊儕僇偺尨巕椡婯惂埾堳夛乮NRC乯偼丄尨巕椡偺埨慡偵娭偡傞娔撀嬈柋傪扴偭偰偍傝丄擔杮偺尨巕椡埨慡埾堳夛偵憡摉偡傞婡娭偩偲巚傢傟傞偑丄擔杮傛傝偼傞偐偵嫮偄尃尷偲愑擟傪晧偭偰偄傞偲偒偔丅傾儊儕僇偱偼偡偱偵20擭傕慜偵丄NRC偺庡摫偺傕偲偵丄尨巕楩偺偡傋偰偺揹尮偑幐傢傟偨応崌偺僔儈儏儗乕僔儑儞傪幚巤偟丄偦傟傪埨慡婯惂偵妶梡偟偨丅偟偐偟擔杮偱偼丄憲揹慄偑憗媫偵夞暅偡傞偙偲側偳傪棟桼偵丄偡傋偰偺揹尮偑幐傢傟傞偙偲傑偱偼憐掕偵擖傟偰偙側偐偭偨丅崱夞丄暉搰尨敪偱偼丄傑偝偵偦傟偑婲偒偨傢偗偩丅擔杮偺偱偨傜傔側埨慡娗棟偵偁偒傟偐偊傞丅
尨巕椡埨慡埾堳夛偺戙扟惤帯偲偄偆埾堳偼丄乽偒偪傫偲儅僱僕儊儞僩偝傟偰偄傟偽帠屘偼杊偘偨偲巚偆丅帠嬈幰偺帺庡搘椡偵擟偣偰偄偨乿偲岅偭偰偄傞丅僶僇側偙偲傪尵偆側丅帠嬈幰偵偟偭偐傝偟偨埨慡懳嶔傪偝偣傞傛偆娔撀偡傞偺偑埨慡埾堳夛偺栶栚偩傠偆丅偦傫側愑擟摝傟偼捠梡偟側偄丅偙傟傑偱愑擟傪壥偨偟偰偙側偐偭偨偽偐傝偐丄偄傑傑偨愑擟摝傟傪偟傛偆偲偡傞埾堳偨偪丄偙傫側楢拞偵尨敪偺埨慡娗棟偑擟偝傟偰偒偨偺偐偲巚偆偲丄搟傝偑偙傒忋偘傞丅
2011.03.29 (壩) 恔嵭偵傑偮傢傞尵摦偱廥埆偝傪業掓偟偨3恖
傂偲傝偼尵傢偢偲抦傟偨愇尨怲懢榊搒抦帠丅乽恔嵭偼変梸偵傑傒傟偨擔杮恖傊偺揤敱偩乿偲偄偆乬揤敱乭敪尵偩丅偁傢偰偰幱嵾偼偟偨偑丄偦偺屻傕帺暘偺庯巪偼堘偆偲偺曎柧傪孞傝曉偟偰暯慠偲偟偰偄傞丅愇尨偺尵梩偼丄斵偑旐嵭偟偨恖偨偪傊偺巚偄傗傝偑偐偗傜傕側偄攋楑抪娍偩偲偄偆偙偲傪徹柧偟偰偄傞丅旐嵭抧偺恖偨偪偺嬯偟傒偲斶偟傒傪巚偊偽丄偦傫側尵梩側偳弌傞偼偢偑側偄丅変梸偵傑傒傟偨擔杮恖偲偄偆偺偼丄偁傞堄枴偱摉偨偭偰偄傞偲偙傠傕偁傞丅偩偑偄傑偺忬嫷偵偍偄偰乬揤敱乬側偳偲偼丄儕乕僟乕偑偗偭偟偰岥偵偟偰偼偄偗側偄尵梩偩丅偦傟傪岥憱傞愇尨偵儕乕僟乕偲偟偰偺帒奿偼側偄丅揤敱傪庴偗傞側傜丄変梸偺尃壔偱偁傞愇尨偙偦偑恀偭愭偵庴偗傞傋偒偩丅愇尨偼搒抦帠慖偵弌側偄偲尵偭偰偍偒側偑傜丄僊儕僊儕偵側偭偰慜尵傪東偟丄弌傞偲尵偄弌偟偨丅傕偲傕偲弌傞堄梸偼枮乆偱丄傒傫側偐傜崸婅偝傟偰弌傞偐偨偪偵傕偭偰偄偙偆偲偟偨偲偄偆愺抭宐側偺偼儈僄儈僄偩丅壓楎側昳惈偼媬偄傛偆偑側偄丅
壓楎偝偲偄偆揰偱偼搉曈峆梇撉攧怴暦夛挿傕恖屻偵棊偪側偄丅僫儀僣僱偺掃偺堦惡偱丄廃埻偺斀懳傪墴偟愗傝丄僾儘栰媴僙丒儕乕僌偼梊掕偳偍傝3寧25擔偵奐枊偡傞偲尵偄偩偟偨丅偗偭偒傚偔偼慖庤夛丄惌晎丄悽榑偺惡偵孅偟丄僷丒儕乕僌偲摨偠偔4寧12擔奐嵜偵棊偪拝偄偨丅執偦偆偵埿挘傝嶶傜偡僫儀僣僱偺堄岦偵傒傫偑偑怳傝夞偝傟偨丅僾儘栰媴娭學幰偼偦傫側偵僫儀僣僱偑嫲偄偺偐丅偙偺乽偨偐偑慖庤乿偲尵偄曻偮巚偄偁偑偭偨尃椡朣幰偑傆傝傑偔榁奞傪扤傕巭傔傞偙偲偑偱偒側偄偺偼忣偗側偄丅僾儘栰媴偺嵟崅愑擟幰偱偁傞偼偢偺僐儈僢僔儑僫乕偱偡傜僫儀僣僱偵偼媡傜偊側偄丅帺暘偑敪尵偡傞偨傃偵僼傽儞偑僾儘栰媴偐傜棧傟偰偄偔偙偲偵丄斵偼婥偯偄偰偄側偄丅棁偺墹條偩丅乽揹椡晄懌丠 娭學偹乕傛乿偲偆偦傇偔丄偙偺岤婄柍抪側廥偄傕偆傠偔榁恖傪丄偄偮傑偱廃傝偼悞傔懕偗傞偺偐丅
抦柤搙偱偼忋偺2恖偵楎傞偑丄廥偝偺揰偱晧偗偰偄側偄偺偼丄柉庡搣戙媍巑偺嶰戭愥巕偩丅戝抧恔偐傜5擔屻丄惷壀偑恔尮抧偺梋恔偑偒偨偲偒偺偙偲傪丄帺暘偺僽儘僌偵乽傾儘儅僆僀儖偺崄傝傪妝偟傒側偑傜塸岅偺曌嫮傪偟偰偄偨傜丄偖傜偭偲偒偨乿偲彂偄偨丅嶰戭愥巕偲偄偭偰傕僺儞偲偙側偄偐傕偟傟側偄偑丄埲慜丄媍夛偱嫮峴嵦寛偺嵺丄扤偵傕墴偝傟偰偄側偄偺偵晄帺慠側揮搢傪偟偰幵堉巕偱搊堾偟偰偄偨彈惈丄偲尵偊偽丄偁偁丄偁傟偐偲巚偄婲偙偡恖傕懡偄偩傠偆丅傑偁丄僾儔僀儀乕僩側帪娫偵側偵傪偟傛偆偲偄偄偟丄傾儘儅僆僀儖傪妝偟傫偱傕峔傢側偄丅偩偑丄旐嵭抧偺嶴忬丄晄柊晄媥偱尨敪帠屘偺暅媽偵摉偨傞恖偨偪偺偙偲傪峫偊傟偽丄暅嫽偺愭摢偵棫偮傋偒崙夛媍堳偑偦傫側偙偲傪僽儘僌偵彂偔傋偒偐偳偆偐側偳丄巕嫙偱傕敾抐偱偒傞丅偙偺彈偺柍恄宱偝丄嬸撦偝偵偼丄傎偲傎偲偁偒傟壥偰傞丅
嵟戝偺抧曽帺帯懱偺庱挿丄悽榑傪儕乕僪偡傋偒戝儅僗僐儈偺僩僢僾丄崙柉傪戙昞偡傞崙夛媍堳偑丄偙偙傑偱嬸偐偲偼丅偙傟偑偙偺崙偺幚懺側偺偩丅
2011.03.21 (寧) 尨敪帠屘偺恀偺尨場偼丄偢偝傫側尨敪惌嶔偵偁傞
偄傑偼曻悈偵傛偭偰偁傞掱搙偺椻媝悈偑僾乕儖偵挋傑傝丄椻媝僔僗僥儉傪壱摥偝偣傞偨傔偺揹尮偑愝抲偝傟傞偲偙傠傑偱偙偓偮偗偨傛偆偩偑丄偦傟偱尨巕楩傪惓忢壔偱偒傞偺偐偳偆偐丄傑偩暘偐傜側偄丅惌晎傗搶揹偺婰幰夛尒傪暦偄偰偄傞偲丄晄怣姶偑偮偺傞偽偐傝偩丅壇應偱偟偐傕偺傪尵傢偢丄幚懺偑偳偆側偭偰偄傞偺偐丄偝偭傁傝梫椞傪摼側偄丅妀擱椏偺埨掕壔偵幐攕偟丄曻幩惈暔幙偑奿擺梕婍偐傜杮奿揑偵奜偵楻傟偩偟偨傜偳偆側傞偺偐丄嵟埆偺帠懺偲偄偆偩偗偱丄扤傕壗傕愢柧偟傛偆偲偟側偄丅晐偔偰愢柧偱偒側偄偺偐丄偦傟偲傕偨偩慜椺偑側偄偐傜暘偐傜側偄偩偗側偺偐丅
偦傟偐傜丄偲偒偳偒婰幰夛尒偡傞尨巕椡埨慡曐埨堾偲偼丄偄偭偨偄壗側偺偩傠偆丅宱嵪嶻嬈徣偺堦婡娭偩偲偄偆偙偲偩偑丄姱朳挿姱傗搶揹偺敪昞偲廳暋偡傞傛偆側偙偲偟偐尵傢偢丄傏偔傜偑偄偪偽傫抦傝偨偄傛偆側偙偲偵偮偄偰偼壗傕偟傖傋傜側偄丅奀奜偺惌晎傗儊僨傿傾偼丄偦傫側忬嫷偵壵棫偪丄忣曬傪塀偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲晄怣偺擮傪偮偺傜偣偰偄傞丅偒傢傔偰怺崗側帠懺偲懆偊偰偄傞奺崙惌晎偼丄擔杮挀嵼偺奜岎姱傪懕乆偲婣崙偝偣巒傔偨丅傾儊儕僇偵偄傞抦傝崌偄偐傜嵟嬤撏偄偨儊乕儖偐傜傕丄偦傫側忣惃偑揱傢偭偰偔傞丅
崱夞偺尨敪旐奞偼丄巤愝偑捗攇偱悈偵怹偐偭偰揹婥宯摑偑偄偐傟丄惂屼憰抲偑摥偐側偔側偭偨偙偲偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟偨傜偟偄偑丄尨敪偺婋婡娗棟儅僯儏傾儖偼揙掙偟偰偄偰丄擇廳嶰廳偵埨慡懳嶔傪島偠偰偁傝丄儕僗僋娗棟偼枩慡偩偭偨偼偢偠傖側偐偭偨偺偐丅崱夞偺傛偆側戝嵭奞偺偨傔偺埨慡懳嶔偼側偤楙傜傟偰偄側偐偭偨偺偩傠偆偐丅憐掕奜偩偭偩偲偼尵傢偣側偄丅偙偺抧恔偼丄傔偭偨偵側偄嫄戝側傕偺偩偭偨偵偣傛丄枹慮桳偺傕偺偱偼側偄丅夁嫀偵帠椺偑偁偭偨偟丄婲偙傝偆傞偼偢偺傕偺偩偭偨丅
巇帠偱搶嫗揹椡偲偐偐傢偭偨偙偲偺偁傞媽桭偑偄傞丅斵偼搶揹偺帠側偐傟庡媊偵揙偡傞塀暳懱幙傪栚偺偁偨傝偵偟偰偒偨偲偄偆丅斵偵傛傞偲丄搶揹偱偼丄帠屘偼乬帠徾乭丄屘忈偼乬晄嬶崌乭偲屇偽傟丄儗億乕僩堦枃偱張棟偝傟傞丅壗偐帠屘偑婲偒偰傕丄乬帠徾乭乬尨場乭乬懳嶔乭偲崁栚傪暘偗偰儗億乕僩傪彂偔偲堦審棊拝偵側傞乮巬栰姱朳挿姱偑婰幰夛尒偱乬帠徾乭偲偄偆尵梩傪巊偭偰尨敪偺忬嫷傪愢柧偟偨偲偒丄偦偺尵梩偵堘榓姶傪妎偊偨恖傕懡偄偩傠偆丅傏偔傕偦偆偩偭偨偑丄偁傟偼娭學幰偺偁偄偩偱巊傢傟傞撪椫偺梡岅偩偭偨偺偩乯丅
尰応偱嶌嬈偟偰偄傞恖偨偪偺搘椡偵偼摢偑壓偑傞偑丄搶揹偲偄偆夛幮偼丄恊曽擔偺娵懱幙偲摿尃堄幆偑偳偭傉傝愼傒偮偄偨楢拞偵傛偭偰塣塩偝傟偰偄偨丅姱椈偲偺撻傟崌偄丄帺屓曐恎丄傑偝偵媽懺埶慠偨傞偍栶強懱幙偩丅揤壓傝帠嬈偺嵟埆偺揟宆偩丅搶揹偺夛挿傗幮挿側偳丄偳偙偵偄傞偺偐丄偄傑偩偵婰幰夛尒偵巔傪尰偝側偄丅偦傫側攜偵傛偭偰婋側偄尨敪偑悇恑偝傟偰偒偨偐偲巚偆偲偧偭偲偡傞丅搶揹偩偗偱偼側偄丅撻傟崌偄偱偦傟傪曻抲偟偰偒偨惌晎丒姱椈偺愑擟傕廳偄丅
偦偟偰丄尨敪偺婋尟惈丄搶揹偺塀暳懱幙傪抦偭偰偄側偑傜悇恑惌嶔偵壛扴偟偰偒偨戝庤儊僨傿傾偺愑擟傕戝偒偄丅偄偢傟堦抜棊偟偨傜愑擟捛媦偑巒傑傞偩傠偆丄塣傛偔嵟埆偺帠懺傪夞旔偱偒偨傜偺榖偩偑丅摉慠側偑傜丄偙傟傑偱偺尨敪偵棅傞僄僱儖僊乕惌嶔偼揮姺傪敆傜傟傞丅尒偰偄傞偑偄偄丅戝庤儊僨傿傾偼丄帺暘偨偪偺愑擟傪扞偵忋偘丄埨慡娗棟偼偳偆側偭偰偄偨傫偩丄側偳偲尵偄偩偡偩傠偆丅杮棃偺尃椡傪娔帇偡傋偒栶栚傪曻婞偟丄偄傑傗尃椡偵庢傝崬傑傟偨岤婄柍抪側儊僨傿傾偺側傟偺壥偰偩丅
搶揹偺幚懺偼儅僀僫乕側儊僨傿傾偱儗億乕僩偝傟偨偙偲傕偁偭偨傛偆偩偟丄尨敪偺婋尟惈傪崘敪偡傞杮偑弌斉偝傟偨傝傕偟偰偒偨丅埲慜丄偨偟偐恓嬥傪岆偭偰尨巕楩偩偐椻媝悈偩偐偵棊偲偟偰偁傢傗戝嶴帠偲偄偆帠屘偑偁偭偰丄偦傟偱傏偔傕僀乕僕乕側恖堊儈僗偑戝嶴帠偵偮側偑傝偐偹側偄偲偄偆擣幆偼傕偭偰偄偨丅偩偗偳恎嬤側怺崗側栤戣偲偟偰偼攃埇偟偰偄側偐偭偨丅尨敪偺婋尟惈傕暘偐偭偰偄偨偮傕傝偩偭偨偟丄椻媝偑昁恵偩偲偄偆偙偲偼抦偭偰偄偨偗傟偳丄塣揮傪僗僩僢僾偟偰傕椻媝偟懕偗側偗傟偽楩怱偑梟梈偡傞偙偲傗丄巊梡嵪傒妀擱椏傕壗擭娫傕椻媝偟懕偗側偗傟偽偄偗側偄偙偲偼丄崱夞弶傔偰抦偭偨丅
偦傕偦傕妀擱椏傪埨掕偝偣傞偨傔偵丄悈偱椻傗偡偲偄偆丄偒傢傔偰尨巒揑側曽朄偵棅偭偰偄傞偲偄偆偙偲偑怣偠傜傟側偄丅椻媝偑搑愨偊傞偲戝嶴帠偵側傞偟丄偪傚偭偲偟偨嶌嬈儈僗偑嵟埆偺帠懺傪彽偔丅偮偔偯偔尨巕椡偲偄偆傕偺偼旕恖娫揑側傕偺偩偲巚偆丅尨巕椡偲偼丄恖抦傪挻偊偨傕偺丄恖娫偑僐儞僩儘乕儖偱偒側偄暔幙側偺偩丅偦傫側傕偺傪巊偄偙側偦偆偲偡傞偺偼恖娫偺巚偄忋偑傝偩丅尨巕椡偵棅傜側偔偰傕丄揹椡傪埨掕嫙媼偝偣傞曽朄偼偄偔偮傕偁傞偲愱栧壠偼巜揈偟偰偄傞丅塨抭傪廤傔偰埨慡側曽朄傪奐敪偟偨傜偄偄偺偩丅
2011.03.19 (悈) 戝抧恔旐嵭抧媬墖偺抶傟偼嫋偟偑偨偄
旐嵭抧偑峀斖埻偵傢偨偭偰偄傞偩偲偐丄摴楬偑暘抐偝傟偰偄傞偲偐丄帺帯懱偑崿棎偟偰偄傞偲偐丄偄傠偄傠崲擄偼偁傞偲偟偰傕丄傕偭偲傗傝傛偆偑偁偭偨偼偢偩丅偁傞桭恖偼乽僿儕丄棊壓嶱晹戉丄孯廀幵椉摍丄婡摦晹戉傪愭摢偵丄帺塹戉慡孯傪搳擖偡傋偒乿偲尵偭偰偄偨丅偦偺偲偍傝偩丅愴屻枹慮桳偺旕忢帠懺側偺偩丅5枩恖偲偐10枩恖偲偐偱偼側偔丄帺塹戉偺恖堳丄憰旛傪憤摦堳偟丄帩偭偰偄傞僿儕僐僾僞乕傪偡傋偰搳擖偟偰媬墖偲暔帒偺桝憲偵偁偨傜側偗傟偽側傜側偄丅暷孯偐傜偺墖彆偼偳偺掱搙摼偰偄傞偺偩傠偆偐丅柺巕偑偳偆偺側偳偲尵偭偰偄傞応崌偱偼側偄丅僿儕偺庁傝庴偗側偳嵟戝尷傪墖彆傪岊傢側偗傟偽側傜側偄丅惌晎偺傗傝曽偼偳偆偵傕庤偸傞偡偓傞丅
偦傟偵偟偰傕丄庱憡偼偠傔惌晎偺妕椈偼丄僥儗價偵塮傞偲偒丄偳偆偟偰堦條偵嶌嬈暈偺傛偆側傕偺傪拝偰偄傞偺偩傠偆偐丅恀寱偵傗偭偰傑偡偲偄偆億乕僘偱偁傠偆偑丄帺暘偨偪偑嶌嬈偡傞傢偗偱傕側偄偺偵偁傫側奿岲傪偡傞偺偼妸宮偺偒傢傒偩丅
擔杮偲偄偆崙偺柵朣偵偮側偑傝偐偹側偄暉搰尨敪偺帠屘偼丄惌晎偺岆偭偨僄僱儖僊乕惌嶔丄搶嫗揹椡偺懹枬偲夁怣傪偝傜偗弌偟偨丅抧恔戝崙偺擔杮偱尨敪傪嶌傝懕偗傞偺偼丄扤偑峫偊偰傕柍拑側榖側偺偩偑丄攚偵暊偼戙偊傜傟偢丄惌晎丒嶻嬈奅丒儅僗僐儈偑偙偧偭偰尨敪偼埨慡偩偲傾僺乕儖偟側偑傜恑傔偰偒偨丅抧恔側偳偺揤嵭丄恖嵭丄扨弮側嶌嬈儈僗側偳偑丄尨敪偺応崌偼戝嶴帠偵偮側偑傞偲偄偆婋尟惈偵偼栚傪偮傓偭偰偒偨丅崙柉偼丄媈怱傪書偒側偑傜傕丄偦傟偵廬偭偰偒偨丅崙柉偼閤偝傟偨偺偩丅崱夞偺抧恔偺婯柾偑憐掕奜偩偭偨側偳偲偄偆尵偄栿偼捠梡偟側偄丅儅僌僯僠儏乕僪9埲忋偺抧恔丄10m傪挻偊傞捗攇偼丄夁嫀偵傕僠儕抧恔傗僗儅僩儔壂抧恔側偳偱婲偒偰偄傞丅側偤偦傟傪憐掕偵擖傟偰偍偐側偐偭偨偺偐丅
尨敪偑埨慡偱偼側偐偭偨偙偲偑丄偙傫側嵟埆偺偐偨偪偱徹柧偝傟偨偺偼斶寑偩丅僗儕乕儅僀儖搰傗僠僃儖僲僽僀儕傗擔杮偱傕壗搙偐婲偙偭偨尨敪帠屘偐傜摼偨嫵孭傪丄搶揹偼壗傕惗偐偣偰偄側偐偭偨傢偗偩丅偍傟偨偪偺尨敪偼埨慡偩偲夁怣偟偰偄偨偺偩傠偆偐丅偦傟偲傕婋婡堄幆偺寚擛偐丄媄弍晄懌偐丅偄偢傟偵偟偰傕斊嵾揑偩丅尰応偺媄弍幰傗嶌嬈堳偺恖偨偪偼偄傑寛巰偺妎屽偱暅媽偵摉偨偭偰偄傞偑丄尨敪傪悇恑偟偨楢拞偼埨慡側応強偵堷偒偙傕傝丄僥儗價側偳偵弌偰敘偵傕朹偵傕偐偐傜側偄夝愢傪偟偰偄傞丅偦傫側楢拞傪偙偦恀偭愭偵帠屘尰応偵峴偐偣丄帺暘偨偪偺庤偱攋懝傪廋棟偝偣偨偄丅
2010.12.29 (悈) 2010擭奀奜塮夋儀僗僩10
嘆 乽傾僶僞乕乿 娔撀丗僕僃乕儉僘丒僉儍儊儘儞1埵偼乽傾僶僞乕乿偱寛傑傝偩丅崱擭偼側傫偲偄偭偰傕偙偺塮夋偵偲偳傔傪偝偡丅偙傟傎偳僙儞僗丒僆僽丒儚儞僟乕傪怱抧傛偔巋寖偟偰偔傟傞塮夋偼偐偮偰側偐偭偨丅CG偵偟傠3D偵偟傠丄偨傫偵媄弍傪屩帵偡傞偩偗偱偼側偔丄姰慡偵塮夋偲堦懱壔偟丄暔岅偵梈偗崬傫偱偄偨丅僷儞僪儔偲偄偆堎惎偺朙閌側僀儊乕僕偵傕怱偑桇傞偑丄偦傟偩偗偱偼側偔丄暥柧斸昡揑側帇揰傗晲椡偱懠崙傪惂埑偡傞帺崙傾儊儕僇傊偺塻偄斸敾側偳偑丄偙偺塮夋傪墱怺偄傕偺偵偟偰偄偨丅傑偭偨偔僕僃乕儉僘丒僉儍儊儘儞偼惁偄娔撀偩丅
嘇 乽埮偺楍幵丄岝偺椃乿 娔撀丗働僀儕乕丒僕儑乕僕丒僼僋僫僈
嘊 乽偡傋偰斵彈偺偨傔偵乿 娔撀丗僼儗僢僪丒僇償傽僀僄
嘋 乽椻偨偄塉偵寕偰丄栺懇偺廵抏傪乿 娔撀丗僕儑僯乕丒僩乕
嘍 乽僆乕働僗僩儔両乿 娔撀丗儔僨儏丒儈僿僀儗傾僯儏
嘐 乽儈儗僯傾儉乿3晹嶌丂娔撀丗僯乕儖僗丒傾儖僨儞丒僆僾儗償/僟僯僄儖丒傾儖僼儗僢僪僜儞
嘑 乽僇乕儖偠偄偝傫偺嬻旘傇壠乿 娔撀丗僺乕僩丒僪僋僞乕
嘒 乽摰偺墱偺旈枾乿 娔撀丗僼傾儞丒儂僙丒僇儞僷僱儔
嘓 乽僫僀僩丒傾儞僪丒僨僀乿 娔撀丗僕僃乕儉僘丒儅儞僑乕儖僪
嘔 乽傾儕僗丒僀儞丒儚儞僟乕儔儞僪乿 娔撀丗僥傿儉丒僶乕僩儞
2埵偺乽埮偺楍幵丄岝偺椃乿偼崱擭堦斣偺孈傝弌偟暔偲尵偊傞偐傕偟傟側偄丅拞撿暷偺僊儍儞僌偨偪偲昻偟偄晄朄堏柉偺幚懺丄偦偟偰庒偄抝彈偺偮偐偺娫偺扺偄垽傪昤偄偨儘乕僪丒儉乕償傿乕丒僞僢僠偺僋儔僀儉丒僒僗儁儞僗塮夋偩丅儊僉僔僐偲傾儊儕僇偺崌嶌偱偁傝丄娔撀偼擔宯傾儊儕僇恖偱偁傞丅僊儍儞僌抍偺儃僗傪嶦偟偰偟傑偄丄捛偭庤偐傜摝傟傞偨傔堏柉偺堦抍偑忔傞傾儊儕僇峴偒偺楍幵偵傕偖傝崬傫偩僠儞僺儔偺惵擭偑丄幵撪偱怑扵偟偵傾儊儕僇偵岦偐偆彮彈偲弌夛偆丅捛偄偐偗傞僊儍儞僌偺堦枴丄惵擭偼摝偘傞丄偦偟偰彮彈傕斵偲峴傪嫟偵偡傞丅塮夋偺嶌傝偼扺乆偲偟偰偄傞偑丄僒僗儁儞僗丒僪儔儅偲偟偰偺崪奿偼廩暘偵旛傢偭偰偄傞丅惵擭偲彮彈偺傎偺偐側垽偼丄1959擭偺僜楢偺寙嶌斀愴塮夋乽惥偄偺媥壣乿偵弌偰偔傞丄楍幵偱抦傝崌偭偨彮擭暫偲彮彈偺偮偐偺娫偺怱偺怗傟崌偄傪昤偄偨憓榖傪巚偄婲偙偝偣傞丅偩偑娔撀偺帇慄偼偗偭偟偰娒偔偼側偄丅偙偺塮夋偐傜偼丄拞撿暷偺掙曈偵曢傜偡恖乆傗晄朄堏柉偺夁崜側嫬嬾偑晜偐傃忋偑傞偟丄僊儍儞僌抍偺屌偄鉐傗惗偒傞偨傔偵桭忣偡傜媇惖偵偡傞庒幰偺昤偒曽偼丄嶌傝庤偺塻偄栤戣堄幆傪暔岅偭偰偄傞丅僋儔僀儅僢僋僗偺儕僆僌儔儞僨壨傪攚偵捛偭庤偲懳寛偡傞僔乕儞偑姶摦揑偩丅
3埵偺乽偡傋偰斵彈偺偨傔偵乿偼丄柍幚偺嵾偱搳崠偝傟偨嵢傪媬偆偨傔丄偡傋偰傪搳偘偆偭偰暠摤偡傞晇傪昤偄偨僼儔儞僗偺僒僗儁儞僗塮夋丅晇偺昁巰偺搘椡偺峛斻傕側偔嵢偼嬛屌孻傪愰崘偝傟傞丅偦偟偰晇偼偁傞寛抐傪偡傞丅嵢傪彆偗傞偨傔偵杬憱偡傞晇偺峴摦偼憇愨偩丅慡曇偑嬞敆姶偵偁傆傟偰偄傞丅斵偼暯杴側妛峑嫵巘偩偑丄愨懳偵嵢傪媬偆傫偩偲偄偆怣擮偵嬱傜傟丄嵙愜偟偨傝棤愗傜傟偨傝偟側偑傜傕丄嫰傓偙偲側偔堦捈慄偵撍偒恑傓丅晇偑堦慄傪摜傒墇偊傞応柺偼僔儑僢僉儞僌偩偑丄岻傒側嬝塣傃丄儕傾儖側昤幨偺偨傔丄廩暘側愢摼椡偑偁傞丅
4埵偺乽椻偨偄塉偵寕偰丄栺懇偺廵抏傪乿偼偗傟傫偨偭傉傝偵昤偐傟偨僼儔儞僗丒崄峘崌嶌偺僲儚乕儖晽傾僋僔儑儞塮夋丅尦偼嶦偟壆丄擭榁偄偨崱偼懌傪愻偭偰僷儕偱儗僗僩儔儞傪塩傓抝偑庡恖岞丅儅僇僆偵廧傓柡偺壠懓偑嶴嶦偝傟偨丅斵偼暅廞偺偨傔儅僇僆偵忔傝崬傒丄抧尦偺斊嵾慻怐偺壓偭抂傪屬偭偰斊恖傪捛偆丅庡墘偺僕儑僯乕丒傾儕僨僀偼梷惂偝傟偨墘媄偱偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅傾儕僨僀傪彆偗傞3恖慻僠儞僺儔偺儕乕僟乕傪墘偠傞傾儞僜僯乕丒僂僅儞傕廰偄丅傾僋僔儑儞偼攈庤偩偑丄偦傟偩偗偵廔傢偭偰偄側偄丅抝偨偪偺堄抧偲桭忣偑嫻傪擬偔偡傞丅
5埵偺乽僆乕働僗僩儔両乿偼丄僼儔儞僗摼堄偺僸儏乕儅儞丒僐儊僨傿塮夋丅偐偮偰偼堦棳僆乕働僗僩儔偺揤嵥巜婗幰丄崱偼偟偑側偄惔憒嶌嬈堳偑丄愄偺拠娫偨偪傪廤傔偰桳柤僆乕働僗僩儔偵側傝偡傑偟丄儘僔傾偐傜僷儕偵晪偄偰岞墘傪傗傠偆偲暠摤偡傞暔岅丅尰幚偵偼偁傝偊側偄榖偩偑丄椳偁傝徫偄偁傝偺妝偟偄塮夋偵側偭偰偄偨丅傢偑宧垽偡傞桭恖俷偝傫偼丄乬偐偮偰堦棳妝抍偺墘憈壠偩偭偨偲偼偄偊丄壗擭傕堦弿偵傗偭偰偄側偐偭偨楢拞偑丄傠偔偵儕僴乕僒儖傕偣偢偵僐儞僒乕僩側偳偱偒傞傢偗偑側偄偠傖側偄偐乭偲尵偭偰愗傝幪偰偨丅偨偟偐偵偦偺偲偍傝偩偑丄傑偁偍壘榖側偺偱丒丒丒丅偦傫側寚揰傪曗偭偰梋傝偁偭偨偺偑丄僆乕働僗僩儔偲嫟墘偡傞僷儕偺彈惈償傽僀僆儕僯僗僩栶偲偟偰弌墘偟偨儊儔僯乕丒儘儔儞偺婸偔偽偐傝偺旤杄偩偭偨丅
6埵偺乽儈儗僯傾儉乿3晹嶌偵偮偄偰偼10寧31擔晅偗偺偙偺僐儔儉偱婰偟偨丅偝傑偞傑側儈僗僥儕乕偺梫慺傪梈崌偝偣偨丄廳岤丒挿戝側堿杁偲曬暅偺暔岅偱偁傝丄暃庡恖岞儕僗儀僢僩偺嫮楏側僉儍儔僋僞乕偑埑姫偩偭偨丅7埵偺乽僇乕儖偠偄偝傫偺嬻旘傇壠乿偼僨傿僘僯乕/僺僋僒乕偺傾僯儊塮夋丅偙傟偼朻摢偺僔乕僋僄儞僗偑愨昳偩偭偨丅10暘娫傎偳偺僔乕僋僄儞僗偱丄僇乕儖偠偄偝傫偺偙傟傑偱偺恖惗偑丄僒僀儗儞僩巇棫偰偱憱攏摂偺傛偆偵昤偐傟傞丅偙傟偑側傫偲傕慺惏傜偟偐偭偨丅偁傑傝偺旤偟偝丄壏偐偝丄垼偟偝丄偼偐側偝偵丄椳偑偙傒忋偘偰偔傞丅偙偺僔乕僋僄儞僗偑偁傑傝偵寙弌偟偰偄傞偺偱丄偙偺偁偲巒傑傞僇乕儖偠偄偝傫偺朻尟傪昤偄偨儊僀儞丒僗僩乕儕乕偼報徾偑敄偔側偭偰偟傑偆丅
偁偲偼嬱偗懌偱丅8埵偺乽摰偺墱偺旈枾乿偼25擭偵傢偨傞垽偲幏擮傪昤偄偨傾儖僛儞僠儞塮夋丅恖娫偺怱偺墱掙偵愽傓旝柇側妩丄埫偄忣擮偑丄柸枾側峔惉丄嬅偭偨塮憸偵傛傝昞尰偝傟傞丅9埵偺乽僫僀僩丒傾儞僪丒僨僀乿偼僩儉丒僋儖乕僘丄僉儍儊儘儞丒僨傿傾僗庡墘偺傾僋僔儑儞塮夋丅傕偲傕偲丄偙偺庤偺傛偔弌棃偨傾僋僔儑儞塮夋偼寵偄偱偼側偄丅僣儃傪怱摼偨嶌傝偱僄儞僞僥僀儞儊儞僩嶌昳偲偟偰惉岟偟偰偄傞丅僉儍儊儘儞丒僨傿傾僗偼憡曄傢傜偢僗僞僀儖敳孮偩偑丄彮偟榁偗偨偐丅10埵偺乽傾儕僗丒僀儞丒儚儞僟乕儔儞僪乿偼乽晄巚媍偺崙偺傾儕僗乿偺屻擔択傪昤偄偨僼傽儞僞僕乕塮夋丅傕偲傕偲丄偙偺庤偺傛偔弌棃偨僼傽儞僞僕乕塮夋偼寵偄偱偼側偄丅傾儕僗偑嵞夛偡傞僂僒僊傗儅僢僪丒僴僢僞乕傗僠僃僔儍擫傗僴乕僩偺彈墹側偳丄偍側偠傒偺僉儍儔僋僞乕偼岻柇偵塮憸壔偝傟偰偍傝丄尒偰偄傞偩偗偱妝偟偔側傞丅
2010.12.26 (擔) 2010擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
嘆 乽僄僐乕丒僷乕僋乿 儅僀僋儖丒僐僫儕乕 乮島択幮暥屔乯奀奜儈僗僥儕乕晄嫷偲尵傢傟丄弌斉揰悢偑尭偭偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄撉傫偩嶌昳傪儕僗僩傾僢僾偟偰傒傞偲丄僐僫儕乕丄儖僢僇丄僨傿乕償傽乕丄僂傿儞僘儘僂偲偄偭偨幚椡嶌壠偨偪偺廩幚偟偨嶌昳偑弌斉偝傟偰偍傝丄崱擭偼偗偭偙偆寙嶌丒柤昳偑懙偭偨擭偩偭偨傫偩側偲姶偠傞丅偲偔偵偙偺儔儞僉儞僌偺忋埵4嶌偼丄偳傟傕峛壋偮偗偑偨偄寙嶌懙偄偱偁傝丄曋媂忋偙偺傛偆偵儔儞僋晅偗偟偨偑丄偳傟偑1埵偵側偭偰傕偍偐偟偔側偄丅
嘇 乽夞婣幰乿 僌儗僢僌丒儖僢僇 乮島択幮暥屔乯
嘊 乽僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偺搤乿 僪儞丒僂傿儞僘儘僂 乮妏愳暥屔乯
嘋 乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿 僕儑儞丒僴乕僩 乮僴儎僇儚暥屔乯
嘍 乽偝傛側傜傑偱偺3廡娫乿 C丒J丒儃僢僋僗 乮僴儎僇儚暥屔乯
嘐 乽僴儞僞乕僘丒儔儞乿 僕儑乕僕丒R丒R丒儅乕僥傿儞傎偐 乮僴儎僇儚暥屔乯
嘑 乽屲斣栚偺彈乿 僿僯儞僌丒儅儞働儖 乮憂尦暥屔乯
嘒 乽儘乕僪僒僀僪丒僋儘僗乿 僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕 乮暥寍弔廐幮乯
嘓 乽屆彂偺棃楌乿 僕僃儔儖僨傿儞丒僽儖僢僋僗 乮晲揷儔儞僟儉僴僂僗乯
嘔 乽僲儞僗僩僢僾乿 僒僀儌儞丒僇乕僯僢僋 乮暥弔暥屔乯
娙扨偵偦傟偧傟偺嶌昳偵怗傟偰偍偙偆丅1埵偐傜5埵傑偱偺彫愢偵偮偄偰偼夁嫀偵偙偺僐儔儉偱儗償儏乕傪彂偄偰偄傞丅1埵偺乽僄僐乕丒僷乕僋乿偼崱擭嵟崅偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢丅儘僗巗寈偵暅怑偟偰埲崀偺僴儕乕丒儃僢僔儏傕偺偺側偐偺儀僗僩偱偁傠偆丅儃僢僔儏丒僔儕乕僘偑12嶌栚偵帄偭偰傕側偍崅悈弨傪曐偭偰偄傞偺偼婏愓偵嬤偄丅僗僩儗乕僩側応柺揥奐丄婔廳偵傕楙傝忋偘傜傟偨僒僗儁儞僗偑慺惏傜偟偄偟丄儃僢僔儏偺怱偺埮偑嶌昳偵墱峴偒傪梌偊偰偄傞丅2埵偺乽夞婣幰乿偼傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偺嵟廔嶌丅傾僥傿僇僗偺搟傝偑鄖楐偡傞妶寑僗儕儔乕偱偁傝丄僗僺乕僨傿側応柺揥奐丄慡曇傪娧偔堎條側僥儞僔儑儞偑報徾怺偄丅戝偒側廂妌偼僽儕僕僢僩丒儘乕僈儞偑媣偟傇傝偵搊応偟偨偙偲丅偦傟偵偟偰傕丄僔儕乕僘弶婜偺偙傠偲斾傋偰丄庡恖岞傾僥傿僇僗偺偁傑傝偺曄恎傇傝偼丄偁偭偗偵偲傜傟偰偟傑偆丅
3埵偺乽僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偺搤乿偵偮偄偰偼慜乆夞偺偙偺僐儔儉偱婰偟偨偽偐傝側偺偱妱垽丅偙傟傑偱偺3嶌偵嫟捠偡傞偺偼丄峔惉偑偟偭偐傝偟偰偍傝丄嬝塣傃偵晄帺慠偝偑側偄偙偲丄梋寁側昤幨偑攔偝傟丄棳傟偺僥儞億偑寉夣側偙偲偱偁傞丅偦偟偰僄儞僞僥僀儞儊儞僩偵揙偟偨彫愢偱偁傞偙偲傕嫟捠偟偰偄傞丅偩偑丄4埵偺乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿偼偪傚偭偲孹岦偑堎側傞丅僥儞億偼寉夣偲偼尵偄偑偨偄偟丄撪梕揑偵傕暥妛揑側怓崌偄偑擹偄丅偟偐偟搊応恖暔偼傒側憿宍偑堿塭怺偄偟丄庡恖岞偺彮擭偺壠懓偺嵞惗傪婅偆傂偨傓偒側怱偑嫻傪懪偮丅撉傒廔偊偰桙偟偲媬偄偺挍偟傪姶偠偝偣傞偺傕偄偄丅姶摦偝偣傜傟傞偲偄偆揰偱偼丄偙傟偑崱擭堦斣偐傕偟傟側偄丅5埵偺乽偝傛側傜傑偱偺3廡娫乿偼崱擭偺孈傝弌偟暔偺堦嶜丅偛偔偁傝傆傟偨枅擔傪憲偭偰偄傞堦壠偑嵭擄偵姫偒崬傑傟傞偲偄偆榖偱丄偦傟傎偳嫮楏側僀儞僷僋僩偑偁傞傢偗偱偼側偄偑丄偛偔暯杴側夛幮堳偑昁巰偱揋偲愴偆僒僗儁儞僗丄偠傢偠傢偲晐偝偑擡傃婑偭偰偔傞嬝塣傃偼丄偆傑偄丄偺堦岅偵恠偒傞丅
6埵偺乽僴儞僞乕僘丒儔儞乿偼丄僕儍儞儖偐傜偄偆偲丄儈僗僥儕乕偲偄偆傛傝偼SF彫愢偺晹椶偵擖傞偩傠偆丅偩偑拞恎偼戞1媺偺朻尟彫愢偵巇忋偑偭偰偄傞丅帪戙偼偼傞偐側枹棃丅恖椶偑擖怉偟偨墦偄怉柉惎偺傂偲偮偑晳戜偩丅傂傚傫側偙偲偐傜嶳墱偺旈枾婎抧傪敪尒偟偨庡恖岞偺扵峼巘儔儌儞偼丄偦偺婎抧偐傜弌尰偟偨夦暔偺傛偆側堎惎恖偵偮偐傑偭偰偟傑偄丄柍棟傗傝恖庪傝偺椔將偵巇棫偰忋偘傜傟傞丅偙偆偟偰僇僫僟傪巚傢偣傞恖愓枹摜偺怷椦抧懷偵丄堎惎恖丄儔儌儞丄摝偘傞抝偺3恖偵傛傞捛偭偐偗偭偙偑巒傑傞傢偗偩偑丄偙偺捛愓偲摝旔偑偠偮偵僗儕儕儞僌偱妶婥偵偁傆傟偰偄傞丅偝傜偵丄嵟弶偼斀栚偟崌偭偰偄偨捛偆傕偺摨巑丄捛傢傟傞傕偺摨巑偵夎惗偊傞婏柇側桭忣傕丄偙偺朻尟暔岅偺柺敀偝傪惙傝忋偘偰偄傞丅
7埵偺乽屲斣栚偺彈乿偼僗僂僃乕僨儞偺寈嶡彫愢償傽儔儞僟乕寈晹僔儕乕僘偺怴嶌丅偙偺僔儕乕僘傪撉傓偺偼弶傔偰偩偑丄悽昡偵偨偑傢偸撉傒偛偨偊偺偁傞堦嶌偩偭偨丅僗僂僃乕僨儞撿晹偺揷幧挰僀乕僗僞寈嶡彁偺寈晹償傽儔儞僟乕偼丄僠乕儉傪棪偄丄抧摴側憑嵏偺愊傒廳偹偵傛偭偰丄帋峴嶖岆偟側偑傜堿嶴側楢懕嶦恖帠審偺斊恖傪捛偆丅杮棃側傜扨挷偵側偭偰傕偍偐偟偔側偄僗僩乕儕乕揥奐偩偑丄撉傒恑傓偆偪偵偟偩偄偵堷偒偢傝崬傑傟傞丅嬃偄偨偺偼丄晄孅偺僸乕儘乕偱偁傞傋偒庡恖岞償傽儔儞僟乕偑丄忣偗側偔丄偐偭偙埆偄偙偲丅巰懱傪尒偰揻偒婥傪傕傛偍偡偟丄旀傟偨偲尵偭偰庛壒傪揻偔偟丄敄媼傪傏傗偔丅嵟弶偺偆偪偼丄側傫偩偙偄偮偼偲婥偑嶍偑傟傞偑丄偦偺偆偪偵恖娫枴偺偁傞庡恖岞偵垽拝傪姶偠傞傛偆偵側傞丅偙傟傕嶌幰偺昅椡偺偣偄偩傠偆丅偙偙偵偼崱擔偺僗僂僃乕僨儞偑偐偐偊傞幮夛栤戣偑偨偔傒偵怐傝岎偤傜傟偰偄傞丅偦偺堄枴偱偼丄60乣70擭戙偵敪昞偝傟偨摨偠僗僂僃乕僨儞偺寈嶡彫愢儅儖僥傿儞丒儀僢僋丒僔儕乕僘偺惓摑揑側屻宲幰偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅
8埵偺乽儘乕僪僒僀僪丒僋儘僗乿偼丄憡庤偺摦嶌偐傜塕傪尒敳偔僉僱僋僔僗偺愱栧壠丄僉儍僒儕儞丒僟儞僗憑嵏姱僔儕乕僘偺戞2嶌丅崱夞偼僱僢僩偄偠傔偲偄偆丄偒傢傔偰崱擔揑側栤戣偑僥乕儅偵悩偊傜傟偰偄傞丅憡曄傢傜偢嶌幰僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偺峔惉椡偺岻傒偝丄嬝塣傃偺偆傑偝偑嶀偊傢偨偭偰偍傝丄柺敀偝偼孮傪敳偄偰偄傞丅偩偑擄揰傕偁傞丅傂偲偮偼丄彫愢偺敿偽偛傠偱丄偦偺屻偺揥奐偺梊憐偑偮偄偰偟傑偆偙偲丅偦傟偐傜丄僉僱僋僔僗偺払恖側偺偵丄偦傟偑娞怱偺憑嵏偵偁傑傝栶棫偭偰偄側偄偺傕攺巕敳偗偡傞丅9埵埲壓偼妱垽丅
崱擭偼忋婰偺傛偆偵廩幚偟偨儈僗僥儕乕偑暲傫偩偑丄嬈奅偼妶嫷傪掓偟偰偄傞偲偼尵偄偑偨偄丅婥偵側傞偺偼丄椙幙偺儈僗僥儕乕傪弌偟懕偗偰偒偨怴挭暥屔傗暥弔暥屔偵尦婥偑側偄偙偲偩丅偲偔偵怴挭暥屔偺奀奜儈僗僥儕乕偺弌斉揰悢偺彮側偝偑栚棫偮丅偦傟偵斾傋偰島択幮暥屔偼寬摤偟偰偄傞丅12寧偵擖偭偰丄巚偄傕偐偗偢儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺怴嶌乽巰妏乿偑弌斉偝傟偨丅撉傓偺偼傑偩偙傟偐傜偩偑丄1擭偵儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺怴嶌偑2嶌傕撉傔傞偲偼婐偟偄嬃偒偩丅栿幰屆戲壝捠偝傫偺婃挘傝偵攺庤丅
2010.12.22 (悈) 僕儍僐偺嵃偵怗傟傞
 僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗偑朣偔側偭偰23擭偑宱偮偑丄偦偺懚嵼姶偼敄傟傞偳偙傠偐丄傑偡傑偡戝偒偔側偭偰偒偰偄傞傛偆偵巚偆丅偄傑傕側偍丄偙偲偁傞偛偲偵庒偒擔偺枹敪昞僷僼僅乕儅儞僗偑CD敪攧偝傟偰僼傽儞傪枺椆偟偰偄傞偟丄僕儍僐偑嶌偭偨嬋偼愨偊娫側偔僇償傽乕偝傟偰偄傞偟丄儈儏乕僕僔儍儞偨偪偼偄偮傕僕儍僐偐傜庴偗偨戝偒側塭嬁傪岥偵偟偰偄傞丅偲偙傠偑丄僕儍僐偵偮偄偰彂偐傟偨杮偲偄偊偽丄偙傟傑偱偼價儖丒儈儖僐僂僗僉乕偑彂偄偨揱婰乽僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗偺徰憸乿1嶜偩偗偲偄偆丄偒傢傔偰偝傃偟偄忬嫷偩偭偨丅
僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗偑朣偔側偭偰23擭偑宱偮偑丄偦偺懚嵼姶偼敄傟傞偳偙傠偐丄傑偡傑偡戝偒偔側偭偰偒偰偄傞傛偆偵巚偆丅偄傑傕側偍丄偙偲偁傞偛偲偵庒偒擔偺枹敪昞僷僼僅乕儅儞僗偑CD敪攧偝傟偰僼傽儞傪枺椆偟偰偄傞偟丄僕儍僐偑嶌偭偨嬋偼愨偊娫側偔僇償傽乕偝傟偰偄傞偟丄儈儏乕僕僔儍儞偨偪偼偄偮傕僕儍僐偐傜庴偗偨戝偒側塭嬁傪岥偵偟偰偄傞丅偲偙傠偑丄僕儍僐偵偮偄偰彂偐傟偨杮偲偄偊偽丄偙傟傑偱偼價儖丒儈儖僐僂僗僉乕偑彂偄偨揱婰乽僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗偺徰憸乿1嶜偩偗偲偄偆丄偒傢傔偰偝傃偟偄忬嫷偩偭偨丅偦傫側側偐丄偙偺傎偳傛偆傗偔僕儍僐丒僼傽儞偺妷傪桙偡丄姳揤偺帨塉偲傕偄偆傋偒懸朷偺杮偑弌斉偝傟偨丅徏壓壚抝挊乽儚乕僪丒僆僽丒儅僂僗乣僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗嵃偺尵梩乿乮儕僢僩乕儈儏乕僕僢僋乯偱偁傞丅偙傟偼恀幚偺僕儍僐偺巔傪抦傞偙偲偑偱偒傞廏堩側杮偩丅僕儍僐丒僼傽儞昁撉偺彂偲偄偊傛偆丅挿擭偵傢偨傞僕儍僐丒僼儕乕僋偱偁傝丄僕儍僐偑崱擔惓摉側昡壙傪庴偗傞偵帄偭偨嵟戝偺岟楯幰偱傕偁傞傾僪儕僽帍尦曇廤挿丄徏壓壚抝巵偑枮傪帩偟偰挊偟偨熡恎偺堦嶌偱偁傞丅僕儍僐偺偡傋偰傪抦傝恠偔偟偰偄傞丄僕儍僐偺岅傝晹偲傕偄偆傋偒徏壓巵偱側偗傟偽彂偗側偐偭偨杮偱偁傠偆丅
偙傟偼扨側傞揱婰杮偱偼側偄丅乬僕儍僐杮恖偑帺傜岅傞僕儍僐偺恀幚乭偲偱傕徧偡傋偒夋婜揑側撪梕偺杮偩丅杮彂偺崻姴傪側偡偺偼僕儍僐偑僀儞僞價儏乕偱岅偭偨尵梩偱偁傞丅徏壓巵偼偁傜備傞僕儍僐偺僀儞僞價儏乕傪徛椔偟偰庢幪惍棟偟丄僥乕儅暿偵曇嶽偟偨丅僥乕儅偼丄僕儍僐傪宍嶌偭偨傕偺丄僼儘儕僟偲偄偆抧丄儀乕僔僗僩/僐儞億乕僓乕偲偟偰偺僕儍僐丄僜儘丒僨價儏乕丒傾儖僶儉丄僂僃僓乕丒儕億乕僩偺擔乆側偳丄懡巿偵傢偨偭偰偄傞丅慺惏傜偟偄偺偼丄僥乕儅暿偵復偑峔惉偝傟偰偄傞偲偼偄偊丄復傪捛偭偰偄偔偲丄偁偨偐傕僕儍僐偺惗奤傪扝偭偰偄傞傛偆側丄愨柇偺曇廤偑側偝傟偰偄傞偙偲偩丅偟偐傕奺復偺慜屻偵偼丄徏壓巵偵傛傞丄夁晄懌偺側偄丄揑妋側夝愢偑晅偝傟偰偄傞丅偙傟偵傛偭偰撉幰偼丄偁偨偐傕僕儍僐偑帺傜偺惗奤傗壒妝姶傗憈朄傗峫偊曽偵偮偄偰岅傝壓傠偟偨杮傪撉傫偱偄傞偐傛偆側嶖妎偵懆傢傟偰偟傑偆丅
偦傟偵偟偰傕丄僀儞僞價儏乕偱岅偭偰偄傞僕儍僐偺丄偄偐偵庒乆偟偔丄敩檹偲丄妶婥偵枮偪偁傆傟偰偄傞偙偲偐丅偦偟偰偦偺岅傝岥偑丄側傫偲棪捈偱丄抦揑偱丄僆乕僾儞丒儅僀儞僪側偙偲偐丅昞巻偺懷偵婑偣偨儅乕僇僗丒儈儔乕偺僐儊儞僩偵丄乬偁側偨偑僕儍僐偺嵃傪擿偄偰傒偨偄偺側傜丄偦偺摎偊偼偙偙偵偁傞乭偲偄偆堦愡偑偁傞偑丄杮彂傪撉傓偲丄妋偐偵傎傫偲偆偺僕儍僐偺嵃丄弮悎柍岰側怱傪偐偄傑尒傞巚偄偑偡傞丅偙傟偵斾傋偰慜宖偺杮乽僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗偺徰憸乿偼丄桞堦偺揱婰偱偁傝丄婱廳側偙偲偼妋偐偩偑丄偁傑傝偵僕儍僐偺嵟屻婜丄惛恄傪昦傫偱埲崀偺帪婜偵廳偒偑抲偐傟偰偄偨偲尵傢偞傞傪偊側偄丅
梋択偩偑丄側偤儈儏乕僕僔儍儞偺揱婰杮傗揱婰塮夋偼丄斶寑惈傪嫮挷偟偨傕偺偵側偭偰偟傑偆偺偩傠偆丅傎偲傫偳偺偦偺椶偺杮傗塮夋偱偼丄偦偆偄偭偨儈儏乕僕僔儍儞偺埫偄懁柺丄攋柵傗斶塣側偳偺梫慺偑慜柺偵弌偨傕偺偵側偭偰偄傞丅偨偲偊偽僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕傪埖偭偨僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪偺塮夋乽僶乕僪乿偑偦偆偩偭偨丅僪儔儅惈傪懪偪弌偡偨傔偵偼丄偁傞掱搙偦傫側撪梕偵側傜偞傞傪偊側偄偺偼暘偐傞偑丄斶寑偱偼側偔丄傕偭偲儈儏乕僕僔儍儞偺慜岦偒側懁柺丄壒妝傊偺傂偨傓偒側堄梸丄揤堖柍朌側恖娫惈偲偄偭偨梫慺偑昤偐傟側偗傟偽丄敄偭傌傜偄傕偺偵側偭偰偟傑偆丅
僕儍僐偺揱婰乽僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗偺徰憸乿偵傕偦傫側晄枮偑偁偭偨丅偱傕僼傽儞偑抦傝偨偄偺偼丄偦傫側埫偄帪戙偺僕儍僐偱偼側偄丅僕儍僐偺忢婳傪堩偟偨峴摦側偳丄偔偩偔偩偲撉傒偨偔側偄丅傏偔偨偪偑抦傝偨偄偺偼丄偁偺僕儍僐偺壒妝偑丄側偤丄偳偺傛偆偵偟偰宍惉偝傟偨偺偐丄僼儗僢僩儗僗丒儀乕僗抋惗偺旈枾偼丄斵偼僴乕儌僯僋僗憈朄傪偳傫側傆偆偵奐戱偟偨偺偐丄僨價儏乕丒傾儖僶儉憂嶌偺攚宨偼丄僂僃僓乕丒儕億乕僩帪戙偺斵偼壗傪峫偊丄偳傫側偙偲傪傗傠偆偲偟偰偄偨偺偐丄偲偄偆傛偆側偙偲側偺偩丅偦傫側僼傽儞偺婅偄傪偐側偊偰偔傟傞偺偑丄杮彂乽儚乕僪丒僆僽丒儅僂僗乣僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗嵃偺尵梩乿偩丅僕儍僐帺恎偺尵梩偵傛偭偰丄偦傫側撲傗媈栤偑偡傋偰柧傜偐偵側傞丅
愜傝偟傕棃擭偼僕儍僐惗抋60擭偲偄偆愡栚偺擭偵摉偨傝丄偄傠偄傠側婇夋偑弨旛偝傟偰偄傞偲偄偆丅僼傽儞側傜惀旕偲傕挳偒偨偄偲婅偭偰偄傞廳梫傾儖僶儉偺枹敪昞僩儔僢僋傗枹敪昞僙僢僔儑儞偑梲偺栚傪尒偦偆偩丅傑偨惢嶌偑恑峴拞偺僕儍僐偺僪僉儏儊儞僞儕乕丒僼傿儖儉傕岞奐偝傟傞偐傕偟傟側偄丅偙偺杮偼撉幰偵帺暘側傝偺怴偨側僕儍僐憸傪巚偄昤偐偣偰偔傟傞丅偙傟傪撉傫偱丄夵傔偰丄偄傑偁傞僕儍僐偺壒妝丄偙傟偐傜敪昞偝傟傞僕儍僐偺壒妝偵愙偡傟偽丄偒偭偲怴偟偄敪尒傪尒弌偡偙偲偑偱偒傞偵堘偄側偄丅
2010.12.19 (擔) 僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偵弔偼棃傞偺偐
 嶐擭丄朚栿弌斉偝傟偨乽將偺椡乿偱傢傟傢傟僴乕僪儃僀儖僪仌朻尟彫愢僼傽儞傪嬃扱偝偣偨僪儞丒僂傿儞僘儘僂偺怴嶌乽僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偺搤乿乮妏愳暥屔乯偼丄婜懸傪棤愗傜側偄撉傒偛偨偊枮揰偺妶寑儈僗僥儕乕偩偭偨丅
嶐擭丄朚栿弌斉偝傟偨乽將偺椡乿偱傢傟傢傟僴乕僪儃僀儖僪仌朻尟彫愢僼傽儞傪嬃扱偝偣偨僪儞丒僂傿儞僘儘僂偺怴嶌乽僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偺搤乿乮妏愳暥屔乯偼丄婜懸傪棤愗傜側偄撉傒偛偨偊枮揰偺妶寑儈僗僥儕乕偩偭偨丅彫愢偺晳戜偼僒儞僨傿僄僑丅傕偲偼僀僞儕傾丒儅僼傿傾偺惁榬偺嶦偟壆丄60嵨傪夁偓偨偄傑偼戞堦慄傪戅偒丄僒乕僼傿儞偵嫽偠側偑傜掁嬶壆傪塩傓僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偑庡恖岞偩丅偐偮偰偺拠娫偵潌傔帠偺張棟傪棅傑傟偨僼儔儞僉乕偼丄棤愗傝偵偁偭偰婋偆偔嶦偝傟偐偐傞丅斵偼側偤帺暘偑柦傪慱傢傟傞偺偐丄怱摉偨傝偑側偄丅恎傪塀偡偑巋媞偺庤偼偮偓偮偓偵敆傞丅僼儔儞僉乕偼捛偭庤傪寕戅偟偮偮巰椡傪恠偔偟偰恀憡傪扵傝丄尦嫢偵敆傞丅
杮彂偼傑偢僉儍儔僋僞乕偺愝掕偑偄偄丅庡恖岞偺僼儔儞僉乕偼斊嵾慻怐偵偐偐傢傞揱愢揑側嶦偟壆偱偁傝側偑傜丄恗媊偲桭忣偵撃偔丄帺暘側傝偺峴摦婯斖傪傕偮抝偩丅偩偐傜斊嵾幰偲偼偄偊撉幰偺嫟姶傪屇傇丅偙偺僼儔儞僉乕偼丄慜嶌乽將偺椡乿偵弌偰偒偨嶦偟壆僔儑乕儞丒僇儔儞傪傎偆傆偮偲偝偣傞丅偁偪傜偼晳戜偑僯儏乕儓乕僋偱傾僀儖儔儞僪宯儅僼傿傾偺榖偱偁傝丄僒儞僨傿僄僑偺僀僞儕傾儞丒儅僼傿傾偱偁傞僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偲偼愝掕偑惓斀懳偩偑丄恖暔憿宍偼傛偔帡偰偍傝丄傑傞偱偙傟偼乽將偺椡乿偐傜僇儔儞傪庡恖岞偵偟偰撈棫偝偣偨偺僗僺儞僆僼嶌昳偺傛偆偩丅偦偺懠偺搊応恖暔傕抂栶偵帄傞傑偱惗偒惗偒偲堿塭朙偐偵昤偐傟偰偄傞丅
偦偟偰慺惏傜偟偄偺偼僗僺乕僨傿偱嬞敆姶偁傆傟傞嬝塣傃偩丅僼儔儞僉乕偼峌惃偵揮偠傞婡夛傪偆偐偑偄側偑傜庒偄偙傠傪夞憐偡傞丅偙偺傛偆偵尰嵼偲夁嫀偑岎屳偵昤偐傟傞彫愢偼丄僗僩乕儕乕偺棳傟偑慾奞偝傟偐偹側偄偑丄偙偺彫愢偼柍懯側昤幨偑攔偝傟偰偍傝丄僥儞億偑寉夣側偺偱丄傑偭偨偔棳傟偑偩傟傞偙偲偼側偄丅揋偺庤傪偐偄偔偖傝側偑傜僼儔儞僉乕偑昁巰偺斀寕傪帋傒傞尰嵼偺僔乕儞傕僒僗儁儞僗偵偁傆傟偰偄傞偑丄儅僼傿傾偺壓偭抂偐傜偟偩偄偵摢妏傪尰偟偰楙払偺嶦偟壆偲偟偰柤傪崅傔傞夁掱傪昤偄偨僼儔儞僉乕庒偒擔偺僗僩乕儕乕傕偡偙傇傞柺敀偄丅僒儞僨傿僄僑偺棤幮夛偺庡摫尃傪偹傜偭偰戝彫偺慻怐偑擖傝棎傟偰揋懳丒榓崌傪孞傝曉偡暔岅偼丄偝側偑傜僂僃僗僩丒僐乕僗僩偺儅僼傿傾偺嫽朣巎傪撉傓巚偄偑偡傞丅
偙偺彫愢偺戝偒側儌僠乕僼偵側偭偰偄傞偺偼儅僼傿傾偺悽奅偺桭忣偲棤愗傝偩丅偦偺揰偱偼慜嶌乽將偺椡乿偲帡偰偄傞偑丄傕偺偵溸偐傟偨傛偆側埫偄擬婥偲嫸鏝揑側僷儚乕偵曪傑傟偨乽將偺椡乿偲偼堎側傝丄偙傟偼億僢僾偱寉夣側僄儞僞僥僀儞儊儞僩偵揙偟偨嶌昳偵巇忋偑偭偰偄傞丅暤埻婥偲偟偰偼丄壗擭偐慜偵弌偨僂傿儞僘儘僂嶌偺乽儃價乕倅偺婥懹偔桪夒側恖惗乿傪巚偄婲偙偝偣傞丅嶦偟偺僔乕儞偑懡偄偵傕偐偐傢傜偢丄慡懱偵憉夣姶偑偁傆傟偰偄傞偟丄儐乕儌傾偑偁傝丄僥儞億傕寉傗偐偱彫婥枴偄偄丅儔僗僩偺梋塁傕慛傗偐偩丅
杮彂偲懳嬌偵偁傞偺偑丄偙傟偲慜屻偟偰撉傫偩僽儔僀傾儞丒僌儖乕儕乕嶌乽屛偼婹偊偰墝傞乿偩丅偙傟偼儈僔僈儞偺揷幧挰傪晳戜偵偟偨抧曽怴暦婰幰傪庡恖岞偲偡傞暔岅丅偙傟傑偱偺恖惗偱嵙愜傪廳偹偰偒偨庡恖岞偺嵞惗偺暔岅偱偁傝丄乽僼儔儞僉乕丒儅儕乕儞偺搤乿偲偼傑偭偨偔庯偑堎側傞偑丄尰嵼偲夁嫀偑岎屳偵岅傜傟傞峔惉偼摨偠偩丅偩偑丄偙偪傜偼偦偺峔惉偑埆偄寢壥傪傕偨傜偟偨揟宆揑側椺偩偲尵偊傞丅昤幨偑嵶偐偡偓傞偟梋寁側憓榖偑懡偡偓偰丄榖偺揥奐偑傑偩傞偭偙偟偄丅搊応恖暔偺報徾傕嶶枱偩丅偦偺揰丄乽僼儔儞僉乕丒儅僔乕儞偺搤乿偼娙寜側昤幨側偺偵屄乆偺僉儍儔僋僞乕偼慛柧偵怱偵從偒偮偔丅嶌幰偺僙儞僗偲椡検偺嵎偑偼偭偒傝昞傟偰偄傞偲尵偊傞偩傠偆丅
2010.11.07 (擔) 姫偒崬傑傟宆僒僗儁儞僗丒儈僗僥儕乕偺柺敀偝
 偙傟偼側偐側偐偺孈傝弌偟傕偺偩丅僨儞僶乕娤岝嫤夛偵嬑傔傞惵擭僕儍僢僋偑庡恖岞丅巕曮偵宐傑傟側偄僕儍僢僋偲嵢偺儊儕僢僒偼丄彈偺巕偺愒傫朧傪梴巕偲偟偰寎偊傞丅偲偙傠偑偁傞擔丄愒傫朧偺幚晝偑撍慠尰傟丄恊尃傪庡挘偟偰丄3廡娫偺偆偪偵愒傫朧傪曉偡傛偆偵偲尵偭偰偒偨丅幚晝偼傑偩僴僀僥傿乕儞偱丄抧尦偺僊儍儞僌偲偮傞傓儚儖偱偁傝丄攚屻偵偼巗偺桳椡幰偱嵸敾姱偺晝恊偑峊偊偰偄傞丅彂椶庤懕偒偵晄旛偑偁傝丄朄棩揑偵偼憡庤偵暘偑偁傞偑丄僕儍僢僋偼偄傑傗傢偑巕摨慠偺愒傫朧傪偳偆偟偰傕庤曻偟偨偔側偄丅傢偑巕傪庣傞偨傔偺僕儍僢僋偺昁巰偺愴偄偑巒傑傞丅
偙傟偼側偐側偐偺孈傝弌偟傕偺偩丅僨儞僶乕娤岝嫤夛偵嬑傔傞惵擭僕儍僢僋偑庡恖岞丅巕曮偵宐傑傟側偄僕儍僢僋偲嵢偺儊儕僢僒偼丄彈偺巕偺愒傫朧傪梴巕偲偟偰寎偊傞丅偲偙傠偑偁傞擔丄愒傫朧偺幚晝偑撍慠尰傟丄恊尃傪庡挘偟偰丄3廡娫偺偆偪偵愒傫朧傪曉偡傛偆偵偲尵偭偰偒偨丅幚晝偼傑偩僴僀僥傿乕儞偱丄抧尦偺僊儍儞僌偲偮傞傓儚儖偱偁傝丄攚屻偵偼巗偺桳椡幰偱嵸敾姱偺晝恊偑峊偊偰偄傞丅彂椶庤懕偒偵晄旛偑偁傝丄朄棩揑偵偼憡庤偵暘偑偁傞偑丄僕儍僢僋偼偄傑傗傢偑巕摨慠偺愒傫朧傪偳偆偟偰傕庤曻偟偨偔側偄丅傢偑巕傪庣傞偨傔偺僕儍僢僋偺昁巰偺愴偄偑巒傑傞丅偙偺彫愢偼傑偢榖偺棳傟偑偄偄丅偛偔暯杴側抝偑丄壠懓傪媬偆偨傔丄宍惃晄棙側側偐搆庤嬻対偱埆偲棫偪岦偐偆偲偄偆僔儞僾儖側僗僩乕儕乕偑丄彫婥枴偄偄僥儞億偱僗僩儗乕僩偵揥奐偡傞丅偦傟偵搊応恖暔偺僉儍儔僋僞乕憿宍偑尒帠偩丅傗傗椶宆揑偱偼偁傞偑丄庡梫側搊応恖暔偼傕偲傛傝丄庡恖岞偺夛幮偺忋巌傗抧尦偺寈姱偨偪偲偄偭偨抂栶傕娷傔偰丄傒側惗偒惗偒偲昤偐傟偰偄傞丅埆娍偨偪偺晄婥枴側寵偑傜偣偑偠傢偠傢偲晐偝傪忴偟弌偡偟丄庡恖岞傪彆偗傞拠娫偨偪偺怱堄婥傕偒偭偪傝揱傢偭偰偔傞丅偩偐傜丄僗僩乕儕乕偺帺慠側棳傟偲憡樦偭偰丄暔岅偺拞偵掞峈側偔僗儉乕僗偵擖傝崬傔傞丅偄傢備傞姫偒崬傑傟宆僒僗儁儞僗彫愢偺堦庬偱偁傝丄彫昳側偑傜丄偒傝偭偲堷偒掲傑偭偨丄撉傒墳偊偺偁傞撪梕偵巇忋偑偭偰偄傞丅
嵟嬤偺奀奜儈僗僥儕乕偼埲慜偲斾傋偰挿戝偱偁傝丄忋壓2姫偑偁偨傝傑偊偵側偭偰偄傞丅偦偺偨傔忕挿偵側偭偰偟傑偄丄杮嬝偵偁傑傝娭學偺側偄僗僩乕儕乕傗怱棟昤幨傗撪揑撈敀偲偄偭偨梋寁側傕偺傪徣偄偰1姫偵廂傔傞傛偆偵偡傟偽丄傕偭偲偡偭偒傝偲堷偒掲傑偭偨彫愢偵側傞偺偵丄偲巚傢傟傞傕偺偑懡偄丅偦偺偁偨傝偵傕嶐崱偺奀奜儈僗僥儕乕晄怳偺尨場偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅偦偺揰丄500儁乕僕庛偲偄偆揔搙側挿偝偺杮彂偼丄傑偝偵椙幙側儈僗僥儕乕偺尒杮偱偁傝丄嵟弶偐傜嵟屻傑偱傑偭偨偔偩傟傞偲偙傠偑側偔僒僗儁儞僗偑帩懕偟偰偄傞丅
杮彂偲摨帪婜偵摨偠嶌幰偺儚僀僆儈儞僌偺椔嬫娗棟姱傪庡恖岞偵偟偨儈僗僥儕乕丒僔儕乕僘偺怴嶌乽恔偊傞嶳乿傕東栿姧峴偝傟偰偄傞乮島択幮暥屔乯丅偩偑柺敀偝偺揰偱偼丄僲儞丒僔儕乕僘偺偙偺杮偺傎偆偵孯攝偑忋偑傞丅堦嶐擭偵姧峴偝傟偨丄偙傟傕僲儞丒僔儕乕僘偺姫偒崬傑傟宆僒僗儁儞僗彫愢乽僽儖乕丒僿償儞乿傕傛偐偭偨丅嶦恖尰応傪栚寕偟丄捛偭庤偵捛傢傟偰摝偘崬傫偱偒偨梒偄巓枀傪彆偗丄嫢埆側斊嵾幰偨偪偲懳寛偡傞婃屌側榁杚応庡偺愴偄傪昤偄偨寙嶌偩偭偨丅帪戙偺棳傟偵庢傝巆偝傟側偑傜傕帺暘偺怣擮偵婎偯偄偰峴摦偡傞榁僇僂儃乕僀偑怱偵巆偭偨乮庡恖岞偺柤慜偼僕僃僗丒儘乕儕儞僘偲偄偆丅巚傢偢丄僜僯乕丒儘儕儞僘偑墘憈偟偨乽偍偄傜偼榁僇僂儃乕僀乿偺儊儘僨傿偑摢偵晜偐傫偩乯丅
 姫偒崬傑傟宆僒僗儁儞僗偲偄偊偽丄偙傟傕6寧姧峴偺僒僀儌儞丒僇乕僯僢僋嶌乽僲儞僗僩僢僾両乿乮暥弔暥屔乯偑揟宆揑側姫偒崬傑傟宆儈僗僥儕乕偩偭偨丅撉傒庤偼朻摢偐傜偄偒側傝嫮楏側僒僗儁儞僗偵堷偒偢傝崬傑傟傞丅庡恖岞偼暯杴偵曢傜偡徹寯儅儞丅奐姫丄媽桭偐傜揹榖偑偐偐傞丅揹榖偺岦偙偆偱斵偼庡恖岞偺廧強傪岥憱傝丄懅愨偊傞丅偦偺弖娫偐傜庡恖岞偼撲偺廤抍偵捛傢傟巒傔傞丅嵢偼幐鏗偟偰楢棈偑庢傟側偄丅偍傑偗偵斵偼嶦恖帠審偵憳嬾偟偰寈嶡偐傜斊恖埖偄偝傟偰偟傑偆丅偙偆偟偰斵偼棟桼傕傢偐傜偸傑傑儘儞僪儞偺奨傪塃墲嵍墲偲摝偘傑偳偆丅傑偝偵戣柤偳偍傝丄幘憱姶偁傆傟傞嬞敆偟偨僲儞僗僩僢僾丒僒僗儁儞僗偩丅偨偩偟丄偦偺僗僺乕僪偼丄屻敿偵擖傝丄撲偑夝偗偰偄偔偵偮傟偰幐懍偡傞丅嵟屻偵敾柧偡傞帠審偺峔恾傕偧傫偑偄暯杴偱偟傚傏偄丅弌偩偟偑嫮楏側偩偗偵丄屻敿偺懅愗傟偼巆擮偩偑丄傑偁丄偙傟偼偙偺庤偺儈僗僥儕乕偺忢偱丄偟傚偆偑側偄偩傠偆丅
姫偒崬傑傟宆僒僗儁儞僗偲偄偊偽丄偙傟傕6寧姧峴偺僒僀儌儞丒僇乕僯僢僋嶌乽僲儞僗僩僢僾両乿乮暥弔暥屔乯偑揟宆揑側姫偒崬傑傟宆儈僗僥儕乕偩偭偨丅撉傒庤偼朻摢偐傜偄偒側傝嫮楏側僒僗儁儞僗偵堷偒偢傝崬傑傟傞丅庡恖岞偼暯杴偵曢傜偡徹寯儅儞丅奐姫丄媽桭偐傜揹榖偑偐偐傞丅揹榖偺岦偙偆偱斵偼庡恖岞偺廧強傪岥憱傝丄懅愨偊傞丅偦偺弖娫偐傜庡恖岞偼撲偺廤抍偵捛傢傟巒傔傞丅嵢偼幐鏗偟偰楢棈偑庢傟側偄丅偍傑偗偵斵偼嶦恖帠審偵憳嬾偟偰寈嶡偐傜斊恖埖偄偝傟偰偟傑偆丅偙偆偟偰斵偼棟桼傕傢偐傜偸傑傑儘儞僪儞偺奨傪塃墲嵍墲偲摝偘傑偳偆丅傑偝偵戣柤偳偍傝丄幘憱姶偁傆傟傞嬞敆偟偨僲儞僗僩僢僾丒僒僗儁儞僗偩丅偨偩偟丄偦偺僗僺乕僪偼丄屻敿偵擖傝丄撲偑夝偗偰偄偔偵偮傟偰幐懍偡傞丅嵟屻偵敾柧偡傞帠審偺峔恾傕偧傫偑偄暯杴偱偟傚傏偄丅弌偩偟偑嫮楏側偩偗偵丄屻敿偺懅愗傟偼巆擮偩偑丄傑偁丄偙傟偼偙偺庤偺儈僗僥儕乕偺忢偱丄偟傚偆偑側偄偩傠偆丅
2010.10.31 (擔) 儕僗儀僢僩偺埑搢揑側懚嵼姶偺慜偱偼偡傋偰偑夃傫偱偟傑偆
 擔杮傕娷傔偰悽奅拞偱戝儀僗僩僙儔乕偵側偭偨僗僂僃乕僨儞偺儈僗僥儕彫愢3晹嶌亀儈儗僯傾儉亁偺塮夋斉偼丄崱擭1寧偵戞1晹乽僪儔僑儞丒僞僩僁乕偺彈乿偑擔杮岞奐偝傟偨偑丄偦傟偵懕偄偰丄9寧偵戞2晹乽壩偲媃傟傞彈乿偲戞3晹乽柊傟傞彈偲嫸戩偺婻巑乿偑摨帪偵晻愗傜傟偨丅
擔杮傕娷傔偰悽奅拞偱戝儀僗僩僙儔乕偵側偭偨僗僂僃乕僨儞偺儈僗僥儕彫愢3晹嶌亀儈儗僯傾儉亁偺塮夋斉偼丄崱擭1寧偵戞1晹乽僪儔僑儞丒僞僩僁乕偺彈乿偑擔杮岞奐偝傟偨偑丄偦傟偵懕偄偰丄9寧偵戞2晹乽壩偲媃傟傞彈乿偲戞3晹乽柊傟傞彈偲嫸戩偺婻巑乿偑摨帪偵晻愗傜傟偨丅尨嶌偑戝僸僢僩偟偨偵傕偐偐傢傜偢丄堄奜偵傕丄搶嫗嬤曈偱偼廰扟僔僱儅儔僀僘偩偗偺扨娰儘乕僪僔儑乕偲偄偆傂偭偦傝偟偨岞奐偩偭偨偑丄偙傟偼擔杮偵偼偁傑傝撻愼傒偺側偄僗僂僃乕僨儞塮夋偱偁傝丄僗僞僢僼仌僉儍僗僩傕柍柤偩偲偄偆偙偲偵傛傞傕偺偩傠偆丅戞2晹偲戞3晹偺堦嫇岞奐偲偄偆偐偨偪偼惓偟偄傗傝曽偩偭偨偲巚偆丅僔儕乕僘3嶌偺偆偪丄戞1晹偼姰慡偵撈棫偟偨撪梕偩偑丄戞2晹偲戞3晹偼僗僩乕儕乕揑偵枾愙偵偮側偑偭偰偄傞偐傜偩丅
彫愢亀儈儗僯傾儉亁3晹嶌偼丄僕儍乕僫儕僗僩寭嶨帍敪峴恖偺儈僇僄儖丒僽儖儉僋償傿僗僩偲僼儕乕偺挷嵏堳儕僗儀僢僩丒僒儔儞僨儖偑妶桇偡傞楢嶌儈僗僥儕乕偩偑丄戞1晹偑撲夝偒丄戞2晹偑妶寑僗儕儔乕丄戞3晹偑朄掛亄杁棯傕偺偲偄偆嬶崌偵丄僷乕僩偛偲偵庯偒偑堎側偭偰偍傝丄偦傟偑柺敀偝傪帩懕偝偣偰偄偨偑丄塮夋斉偱傕偦偺僗僞僀儖偼偦偺傑傑摜廝偝傟偰偄傞丅
塮夋偺拞恎偼尨嶌偵偐側傝拤幚偵嶌傜傟偰偄傞丅巬梩側僄僺僜乕僪偼徣偐傟偰偄傞偺偱丄尨嶌偵斾傋偰塮夋偼墱峴偒偺揰偱暔懌傝側偝傪姶偠側偔傕側偄偑丄塮夋偲偄偆儊僨傿傾偺惈幙偐傜偟偰丄偦傟偱惓夝偩偭偨偲巚偆丅壆奜偺僔乕儞偼偄偮傕偳傫傛傝偟偨撥傝嬻偩丅偦偺偣偄偐塮夋偺夋柺偼堿烼偱廳嬯偟偄丅偱傕偦傟偑偄偐偵傕杒墷傜偟偄偟丄偙偺挿戝側杁棯偲暅廞偺暔岅偵傛偔帡崌偭偰偄傞丅
崱夞岞奐偝傟偨戞2晹偲戞3晹偱偼丄儕僗儀僢僩偑庡栶偲側偭偰嫢埆側斊嵾慻怐偵搆庤嬻対偱棫偪岦偐偆戞2晹偑埑搢揑偵柺敀偄丅偦傟偵斾傋偰丄儕僗儀僢僩偺傾僋僔儑儞丒僔乕儞偑彮側偄戞3晹偼尒楎傝偑偡傞丅偙偺偙偲偐傜傕暘偐傞傛偆偵丄亀儈儗僯傾儉亁偼儕僗儀僢僩偲偄偆搊応恖暔偑偄側偗傟偽惉棫偟側偄暔岅側偺偩丅偦偺堄枴偱偼丄斵彈偼昞柺揑側庡恖岞偺儈僇僄儖傛傝傕廳梫側栶妱傪扴偭偰偄傞偲偄偊傞丅
 亀儈儗僯傾儉亁偵搊応偡傞儕僗儀僢僩傪丄儃僨傿僈乕僪丒傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偵弌偰偔傞僽儕僕僢僩丒儘乕僈儞偲廳偹崌傢偣傞恖偑懡偄丅傏偔傕彫愢亀儈儗僯傾儉亁戞1晹偱儕僗儀僢僩偑尰傟偨偲偒丄偡偖偵僽儕僕僢僩傪巚偄晜偐傋偨丅攚偺崅偝偑惓斀懳側偩偗偱乮僽儕僕僢僩偼184cm丄儕僗儀僢僩偼154cm乯丄偁偲偼旲僺傾僗丄僞僩僁乕偺挙傝傕偺丄汵夘側惈奿偲丄擇恖偼嬃偔傎偳偦偭偔傝偩偟丄僽儕僕僢僩偼扵掋丄儕僗儀僢僩偼挷嵏堳偲丄怑嬈傕傛偔帡偰偄傞丅
亀儈儗僯傾儉亁偵搊応偡傞儕僗儀僢僩傪丄儃僨傿僈乕僪丒傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偵弌偰偔傞僽儕僕僢僩丒儘乕僈儞偲廳偹崌傢偣傞恖偑懡偄丅傏偔傕彫愢亀儈儗僯傾儉亁戞1晹偱儕僗儀僢僩偑尰傟偨偲偒丄偡偖偵僽儕僕僢僩傪巚偄晜偐傋偨丅攚偺崅偝偑惓斀懳側偩偗偱乮僽儕僕僢僩偼184cm丄儕僗儀僢僩偼154cm乯丄偁偲偼旲僺傾僗丄僞僩僁乕偺挙傝傕偺丄汵夘側惈奿偲丄擇恖偼嬃偔傎偳偦偭偔傝偩偟丄僽儕僕僢僩偼扵掋丄儕僗儀僢僩偼挷嵏堳偲丄怑嬈傕傛偔帡偰偄傞丅傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘嵟廔嶌偵偮偄偰婰偟偨10寧10擔晅偺僐儔儉偱丄傏偔偼乽僽儕僕僢僩偲偄偆報徾揑側憿宍偺搊応恖暔偑偄側偗傟偽丄偙偺僔儕乕僘偺枺椡偼丄敿尭偲傑偱偼偄偐側偔偰傕3暘偺1偼尭偭偰偄偨偩傠偆乿偲彂偄偨偑丄亀儈儗僯傾儉亁偺応崌丄儕僗儀僢僩偑偄側偗傟偽丄偦偺枺椡偺3暘偺2偼尭偭偰偄偨偩傠偆丄偲尵偄偨偄丅偦傟傎偳斵彈偺懚嵼姶偼嫮楏側偺偩丅
塮夋偱儕僗儀僢僩傪墘偠偨僲僆儈丒儔僷僗偲偄偆彈桪偼丄偒傢傔偰彫愢偺僀儊乕僕偵嬤偄丅偪傚偭偲儊僀僋偑擹偡偓傞偟丄傕偆彮偟怓偭傐偝偑傎偟偄婥傕偡傞偗傟偳丄傑偢偼枮懌偡傋偒僉儍僗僥傿儞僌偩傠偆丅偦傟偵斾傋偰儈僇僄儖偵暞偟偨儈僇僄儖丒僯僋償傿僗僩乮側偤偐栶柤偲柤慜偑偦偭偔傝偩乯偼丄尨嶌偺僀儊乕僕偲偼偐偗棧傟偰偄傞丅尨嶌偺儈僇僄儖偼弌夛偆彈偐傜偄偮傕崨傟傜傟傞怓抝偲偄偆姶偠側偺偵丄塮夋偱暞偟偨栶幰偼栰曢偭偨偄晲崪側戝抝偱丄偳偆偵傕偦偖傢側偄丅
塮夋偵弌偰偔傞儕僗儀僢僩埲奜偺彈偨偪傕丄側偤偐傒側崪懢偱偛偮偄奜尒偺彈桪偽偐傝偩丅儈儗僯傾儉帍偺彈曇廤挿偱丄儈僇僄儖偲擏懱娭學傪寢傫偱偄傞僄儕僇側偳丄塮夋偱偼恀巐妏偺婄傪偟偨拞擭偺偍偽偝傫偲偄偭偨晽嵮偱丄怓偭傐偝偼偐偗傜傕側偄丅僗僂僃乕僨儞偲偄偆偲丄屆偔偼僌儗僞丒僈儖儃傗僀儞僌儕僢僪丒僶乕僌儅儞偲偄偭偨旤恖彈桪傪惗傫偩崙側偺偵丄偳偆偄偆偙偲側偺偩傠偆丅偲偼偄偊丄僗僩僢僋儂儖儉傪壗搙偐朘傟偨傏偔偺宱尡偐傜偟偰丄僗僂僃乕僨儞偵偼婄偺偮偔傝偺戝偒偄丄偛偮偄彈惈偑懡偄偙偲偼妋偐偩偟丄僈儖儃偵偟傠僶乕僌儅儞偵偟傠丄傛偔尒傞偲偄偐偮偄彈偱偼偁傞偺偩偑丅
偙偺塮夋偼僴儕僂僢僪偱儕儊僀僋偑寁夋偝傟偰偄傞丅庡墘偺儈僇僄儖偵偼007攐桪偺僟僯僄儖丒僋儗僀僌偑寛傑偭偨傜偟偄丅偙傟偼傄偭偨傝偺僉儍僗僥傿儞僌偩偑丄娞怱偺儕僗儀僢僩栶偼丄崱偺帪揰偱偼枹掕偲偺偙偲丅偄偢傟偵偣傛丄僴儕僂僢僪惢側傜乽僟償傿儞僠丒僐乕僪乿偺傛偆偵彫愢偺榖戣偲楢摦偝偣偨戝妡偐傝側塮夋偵側偭偰傕偍偐偟偔側偄丅棃擭偺崱偛傠偼傾儊儕僇斉乽儈儗僯傾儉乿偱塮夋奅偑惙傝忋偑偭偰偄傞偐傕偟傟側偄丅
2010.10.24 (擔) 姶椳傪桿偆僽儔僂僯乕庒偒擔偺攋揤峳側墘憈
 僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺儗傾側壒尮傪CD壔偟偰偄傞RLR儗僐乕僪偑丄嫀擭偐傜崱擭偵偐偗偰傑偨悢枃偺怴偟偄傾儖僶儉傪敪攧偟偨丅偙傟傑偱偺傕偺偲摨偠偔丄傕偲偵側偭偰偄傞偺偼丄僀僞儕傾偺Philology偑夛堳岦偗偵桳椏斝晍偟偰偄偨櫵戝側亀Brownie Eyes亁僔儕乕僘偱偁傞丅惗慜僽儔僂僯乕偼偄偮傕僥乕僾丒儗僐乕僟乕傪帩偪曕偒丄僋儔僽偱偺儔僀償丒僙僢僔儑儞傗儕僴乕僒儖傪傑傔偵僥乕僾偵榐壒偟偰偄偨丅偦傫側壒尮傪偣偭偣偲CD壔偟偰偒偨偺偑Philology亖RLR儗僐乕僪偱偁傞丅僋儕僼僅乕僪偵偒傢傔偰嬤偄恊懓偐傜採嫙偝傟偨傕偺偱偁傠偆偲悇應偝傟傞丅
僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺儗傾側壒尮傪CD壔偟偰偄傞RLR儗僐乕僪偑丄嫀擭偐傜崱擭偵偐偗偰傑偨悢枃偺怴偟偄傾儖僶儉傪敪攧偟偨丅偙傟傑偱偺傕偺偲摨偠偔丄傕偲偵側偭偰偄傞偺偼丄僀僞儕傾偺Philology偑夛堳岦偗偵桳椏斝晍偟偰偄偨櫵戝側亀Brownie Eyes亁僔儕乕僘偱偁傞丅惗慜僽儔僂僯乕偼偄偮傕僥乕僾丒儗僐乕僟乕傪帩偪曕偒丄僋儔僽偱偺儔僀償丒僙僢僔儑儞傗儕僴乕僒儖傪傑傔偵僥乕僾偵榐壒偟偰偄偨丅偦傫側壒尮傪偣偭偣偲CD壔偟偰偒偨偺偑Philology亖RLR儗僐乕僪偱偁傞丅僋儕僼僅乕僪偵偒傢傔偰嬤偄恊懓偐傜採嫙偝傟偨傕偺偱偁傠偆偲悇應偝傟傞丅嵟嬤RLR偐傜弌偨僽儔僂僯乕偺儗傾CD偺側偐偱傕僼傽儞偵偲偭偰奿暿側枺椡傪曻偭偰偄傞偺偼丄亀Clifford Brown Plays Trumpet & Piano: The Complete Solo Rehearsals亁乮RLR-88654乯偲偄偆傾儖僶儉偩丅僽儔僂僯乕偑傂偲傝偱妝婍傪楙廗偟偰偄傞僩儔僢僋傪拞怱偵廂傔傜傟偨2枃慻僙僢僩偱偁傞丅儕僴乕僒儖偲偄偆傛傝偼丄僀儊乕僕偲偟偰偼僩儗乕僯儞僌偵嬤偄丅偦偺堄枴偱偼丄偙偙偵偼丄偒傢傔偰僷乕僜僫儖側僽儔僂僯乕偺巔偑嬅弅偝傟偰偄傞偲尵偭偰傕偄偄丅偲偼偄偊丄楙廗晽宨傪廂傔偨CD側偳丄僽儔僂儞偺擬怱側僼傽儞埲奜偼嫽枴傪偦偦傜傟側偄偩傠偆丅偟偐傕丄偍傛偦慡懱偺70%傪愯傔偰偄傞偺偑僩儔儞儁僢僩偱偼側偔僺傾僲偺楙廗晽宨偲偁傟偽丄側偍偝傜偩丅
嵢偺儔儖乕偵傛傞偲丄僽儔僂僯乕偼帺戭偺僗僞僕僆偱丄僩儔儞儁僢僩埲奜偵傕丄楙廗偱偟偽偟偽僺傾僲傪抏偄偰偄偨傛偆偩丅偙偙偱偺斵偺僺傾僲丒僾儗僀偼丄傾儗儞僕傗僴乕儌僯乕傗僼儗乕僕儞僌傪妋擣偟側偑傜抏偄偰偄傞偐傜偩傠偆丄摨堦僼儗乕僘偺孞傝曉偟偑懡偄丅楙廗偩偐傜摉偨傝慜偩偑丄挳偄偰偄偰柺敀偄傕偺偱偼側偄丅偦傟偱傕丄傑偲傕偵僀儞僾儘償傿僛乕僔儑儞傪傗偭偰偄傞屄強側偳偼丄偗偭偙偆挳偒偛偨偊偑偁傞丅僩儔儞儁僢僩偺僼儗乕僘傪僺傾僲偵堏偟懼偊偨傛偆側姶偠偵挳偙偊傞偺偑嫽枴怺偄丅斵偼僺傾僯僗僩偲偟偰傕側偐側偐偺椡検傪傕偭偰偄偨偲尵偊傞偩傠偆丅
僽儔僂儞偼僩儔儞儁僢僩埲奜偵傕丄僺傾僲丄儀乕僗丄償傽僀僽側偳丄偝傑偞傑側妝婍傪墘憈偡傞偙偲偑偱偒偨丅僺傾僲偺幚椡偼偙偙偵挳偔偲偍傝偩丅償傽僀僽墘憈偺榬慜偵偮偄偰偼丄僴乕僽丒僎儔乕偺師偺傛偆側徹尵偑偁傞丅
偁傞擔丄儅僢僋僗丒儘乕僠偺壠偱僷乕僥傿偑奐偐傟偨偙偲偑偁偭偰偹丅偨偔偝傫偺恖偑廤傑偭偰丄塡榖偵壴傪嶇偐偣偰偄偨丅僽儔僂僯乕偼偁傑傝榖偺椫偵壛傢傠偆偲偼偟偰偄側偐偭偨丅嫃娫偺嬿偵儅僢僋僗偑偙傟偐傜楙廗偟傛偆偲偟偰偄偨償傽僀僽偑抲偄偰偁偭偨丅僽儔僂僯乕偼償傽僀僽偵曕傒婑傝丄2杮偺儅儗僢僩傪庤偵偲偭偰墘憈偟巒傔偨傫偩丅斵偑偄傠傫側妝婍傪墘憈偡傞偙偲偼丄愜偵怗傟偰巹傕偙偺栚偱傒偰偄偨偗偳丄偟偽傜偔偟偰斵偑4杮偺儅儗僢僩傪巊偭偰岻傒偵墘憈偟偩偟偨偲偒偼丄傃偭偔傝偟偰偟傑偭偨傛丅摉慠側偑傜丄儅僢僋僗偼摢偵偒偰偄偨丅偙傟偐傜妎偊傛偆偲偟偰偄傞償傽僀僽傪丄僽儔僂僯乕偑偄偲傕寉乆偲墘憈偟偰偟傑偭偨傫偩偐傜偹丅偙偺傾儖僶儉偵偼丄僺傾僲偵傛傞楙廗僩儔僢僋偑戝懡悢傪愯傔傞側偐丄僩儔儞儁僢僩傪楙廗偟偰偄傞僩儔僢僋傕2嬋偁傞乮亙僠僃儘僉乕亜偲亙僨傿僕乕丒傾僩儌僗僼傿傾亜乯丅偄偢傟傕10暘埲忋偵傢偨傞挿広偱偁傝丄僽儔僂僯乕偼傂偨偡傜悂偒懕偗傞丅榐壒僨乕僞偺崁偵偼1954擭丄僼傿儔僨儖僼傿傾偵偰偲婰嵹偝傟偰偄傞丅偨偟偐偵丄偙偺壏偐傒偺偁傞僼儗乕僕儞僌丄儕儔僢僋僗偟偨僽儘乕偼丄屻婜偺偦傟偱偼側偄丅偍偦傜偔1954擭10寧慜屻偩傠偆丅僋儕僼僅乕僪偼偙偺偙傠丄僂僃僗僩丒僐乕僗僩偐傜怴嵢偺儔儖乕傪敽偭偰僼傿儔僨儖僼傿傾偵栠傝丄怴嫃傪峔偊偨丅偙偺2嬋偼偦偺帺戭抧壓偵偟偮傜偊偨僗僞僕僆偱榐傜傟偨傕偺偩偲巚偆丅亙僠僃儘僉乕亜偺搑拞偵丄彈惈偺惡偑暦偙偊偰僋儕僼僅乕僪偼楙廗傪拞抐偟丄擇尵嶰尵榖傪偟偰傑偨楙廗偵栠傞売強偑偁傞丅榖偟偐偗偨彈惈偼儔儖乕偩傠偆丅憐憸偡傞偵丄乽斢偛偼傫偼側傫偵偡傞丠乿乽偦偆偩側丄僗僥乕僉偑偄偄側乿偲偄偆傛偆側傗傝庢傝偱傕偟偰偄傞偺偩傠偆偐丅
乮亀僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞丗揤嵥僩儔儞儁僢僞乕偺惗奤/僯僢僋丒僇僞儔乕僲亁壒妝擵桭幮姧傛傝乯
僽儔僂僯乕偼岟側傝柤悑偘偰傕丄妛惗偺偙傠偲摨偠偔楙廗偵柧偗曢傟偰偄偨丅嵢偺儔儖乕偼師偺傛偆偵巚偄弌傪岅偭偰偄傞丅
巹偨偪偑挬怘傪偲傞偲丄僋儕僼僅乕僪偼楙廗偵擖傝傑偡丅奜弌偐傜婣傞偲楙廗偟傑偡丅偍拫傪怘傋傞偲楙廗偵栠傝傑偡丅偲偵偐偔僋儕僼僅乕僪偼帪娫偝偊偁傟偽丄偄偮偱傕楙廗偟偰偄傑偟偨丅僩儔儞儁僢僩傪悂偗側偄偲偙傠丄儈儏乕僩傪偮偗偰傕偩傔側応強偵偄傞偲偒偱傕丄怬傗愩傪摦偐偟偰傑偟偨丅儅僂僗僺乕僗偩偗偱悂偄偰偄偨偙偲傕偁傝傑偡丅偲偵偐偔斵偼愨偊娫側偔楙廗偟偰偄偨傫偱偡丅忋偵堷梡偟偨埲奜偵傕丄儔儖乕偼摨彂偺偁偪偙偪偱僋儕僼僅乕僪偺楙廗偺拵傇傝傪岅偭偰偄傞丅儔儖乕偺岅傞巚偄弌傪撉傒丄偦偟偰傾儖僶儉偵廂傔傜傟偨僩儔儞儁僢僩傗僺傾僲傪楙廗偟偰偄傞柾條傪挳偔偲丄斵偼揤嵥側偳偱偼側偄丄搘椡偺恖偩偭偨傫偩丄偲偄偆巚偄傪怺偔偡傞丅忢恖偱偼側偟偊側偄搘椡偑偁偭偨偐傜偙偦丄僽儔僂僯乕偲偄偆揤嵥偑惗傑傟偨丅偩偐傜乬晄抐偺搘椡偑偁偭偰偙偦揤嵥偼奐壴偡傞乭偲尵偆傋偒偐丅
乮摨彂傛傝乯
偩偑丄偙傟傜偺楙廗僩儔僢僋傕丄偙偺傾儖僶儉偵廂傔傜傟偨1嬋亙僆乕僯僜儘僕乕亜偺慜偵偼丄偦偺婸偒偑偐偡傫偱偟傑偆丅亙僆乕僯僜儘僕乕亜偼傑偝偟偔姶椳傕偺偺墘憈偱偁傞丅僴僀僗僋乕儖帪戙偺僽儔僂儞偺壒妝偺巘丄儃僀僕乕丒儘儚儕乕偲擇恖偱悂偒崬傫偩傕偺偩丅僕儍働僢僩偵偼1949/50偲彂偐傟偰偄傞偑丄僽儔僂僯乕偼傑偩僴僀僗僋乕儖偺惗搆偩偭偨偼偢偱偁傝丄傕偆1乣2擭傎偳慜偺帪婜偵榐傜傟偨傕偺偱偼側偄偩傠偆偐丅弶傔偰偙傟傪傪Philology偺堦枃偱挳偄偨偲偒偼丄偦偺弮悎偝偲恀寱偝偑昚偆僾儗僀偵巚傢偢栚摢偑擬偔側偭偨丅埲慜偺偙偺僐儔儉乮2006擭10寧10擔晅偗乯偱丄傏偔偼偦傟偵怗傟偰彂偄偰偄傞丅彮偟挿偄偑嵞榐偟傛偆丅
偙傟傑偱廤傔偨僽儔僂儞偺枹敪昞壒尮偺側偐偱丄嬤擭傕偭偲傕姶摦偝偣傜傟偨偺偼丄僥傿乕儞僄僀僕儍乕偺僽儔僂儞偑摉帪嫵偊傪庴偗偰偄偨壒妝嫵巘億僀僕乕丒儘儚儕乕偲堦弿偵楙廗偟偰偄傞僥乕僾偩偭偨丅僽儔僂儞偑僩儔儞儁僢僩丄儘儚儕乕偑傾儖僩丒僒僢僋僗傪悂偒丄乹僆乕僯僜儘僕乕乺傪僨儏僆偱墘憈偟偰偄傞丅偙偺僽儔僂儞偺僾儗僀偑僼傽僢僣丒僫償傽儘偵偦偭偔傝側偺偩丅墘憈偼摉慠側偑傜傑偩梒偔丄枹姰惉偩丅偦偺斵偑丄昁巰偵僫償傽儘偦偭偔傝偵悂偙偆偲偟偰偍傝丄挳偄偰偄傞偲嫻偑擬偔側傞丅僽儔僂儞偺傾僀僪儖偑丄僈儗僗僺乕偲暲傃徧偣傜傟偨價僶僢僾帪戙偺柤庤僫償傽儘偩偭偨偙偲偼偮偲偵桳柤偩偑丄偦傟偑庤偵偲傞傛偆偵暘偐傞墘憈偩丅偙偺傾儖僶儉偵偼傕偆1嬋丄梊婜偣偸婐偟偄儃乕僫僗丒僩儔僢僋偑偁傞丅僋儕僗丒僷僂僄儖仌僓丒僽儖乕丒僼儗僀儉僘偺墘憈偡傞亙傾僀丒僇儉丒僼儘儉丒僕儍儅僀僇亜偺儔僕僆曻憲僩儔僢僋偩丅偙偺嬋偼僽儔僂僯乕偺弶儗僐乕僨傿儞僌丒僫儞僶乕偲偟偰桳柤偩丅僋儕僗丒僷僂僄儖偺僶儞僪偵嵼抍帪戙偺1952擭3寧偵僗僞僕僆榐壒偝傟偨傕偺偱丄傾儖僶儉亀僓丒價僊僯儞僌仌僕丒僄儞僪亁偵廂榐偝傟偰LP壔偝傟偨丅偦偟偰偙偙偵偼丄偦偺僆儕僕僫儖丒償傽乕僕儑儞偲偲傕偵丄摨帪婜偵峴側傢傟偨儔僀償丒僙僢僔儑儞偺曻憲壒尮偑廂傔傜傟偰偄傞偺偩丅偙偺曻憲壒尮偼僗僞僕僆榐壒傛傝挿広偵側偭偰偍傝丄僽儔僂僯乕偺僜儘傕攞偺挿偝偵側偭偰偄傞乮僗僞僕僆丒償傽乕僕儑儞偼0:36丄曻憲償傽乕僕儑儞偼1:12乯丅偙偺僜儘偑慺惏傜偟偄丅偺偪偺僽儔僂僯乕傪渇渋偲偝偣傞僼儗乕僘偑嶶傝偽傔傜傟偰偄傞偟丄擬婥傪偼傜傫偩杬曻帺嵼側僽儘乕偼丄傑偝偵揤攏嬻傪墲偔偑擛偒偩丅
僥傿乕儞僄僀僕儍乕偺僽儔僂僯乕偑寽柦偵悂偔亙僆乕僯僜儘僕乕亜偲丄偙偺R&B僶儞僪帪戙偺21嵨偺斵偺婸偐偟偄僜儘偑僼傿乕僠儍乕偝傟偨亙傾僀丒僇儉丒僼儘儉丒僕儍儅僀僇亜丄椉幰偲傕壒幙偼埆偄偑丄偦偺楌巎揑壙抣偼寁傝抦傟側偄丅偙偺2嬋偩偗偱丄偙偺傾儖僶儉偼峸擖偡傞堄媊偑偁傞丅
2010.10.17 (擔) 嵞朘丄墿崹偺戝塸掗崙
 晄埨掕側惌帯懱惂丄嬥梈晄埨偲宨婥屻戅丄堏柉栤戣側偳丄僀僊儕僗傕偛懡暘偵傕傟偢懡偔偺寽埬傪書偊偰偄傞偑丄昞柺揑偵偼恖乆偺惗妶偼棊偪拝偄偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅儘儞僪儞偱偼丄嶐擭偲摨偠偔丄崱擭傕僂僢僪僒僀僪丒僷乕僋偵偁傞擇彈晇晈偺壠偵栵夘偵側偭偨丅巗撪偐傜抧壓揝偱杒傊30暘偖傜偄偺偲偙傠偁傞廧戭抧偩丅搶嫗嬤曈偱尵偆偲丄揷墍搒巗慄偺嶋徖偲偐懡杸僾儔僓偲偄偆姶偠偩傠偆偐丅偨偩偟丄墂偺廃曈偵偼壗傕側偄丅墂偐傜弌偨傜偡偖偵廧戭偑楢側偭偰偄傞丅壠偼僀僊儕僗摿桳偺僙儈僨僞僢僠偲偄傢傟傞擇尙堦搹偺寶暔丅2奒寶偰偺寶暔傪恀傫拞偱2偮偵巇愗傝丄嵍塃偦傟偧傟偵暿乆偺壠懓偑廧傓僗僞僀儖偩丅儘儞僪儞偼偙偺僙儈僨僞僢僠條幃偺廧戭偑傎傫偲偆偵懡偄丅巗撪傕峹奜偺廧戭奨傕丄偳偙偵峴偭偰傕偙偺僗僞僀儖偺壠偑寶偪暲傫偱偄傞丅
晄埨掕側惌帯懱惂丄嬥梈晄埨偲宨婥屻戅丄堏柉栤戣側偳丄僀僊儕僗傕偛懡暘偵傕傟偢懡偔偺寽埬傪書偊偰偄傞偑丄昞柺揑偵偼恖乆偺惗妶偼棊偪拝偄偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅儘儞僪儞偱偼丄嶐擭偲摨偠偔丄崱擭傕僂僢僪僒僀僪丒僷乕僋偵偁傞擇彈晇晈偺壠偵栵夘偵側偭偨丅巗撪偐傜抧壓揝偱杒傊30暘偖傜偄偺偲偙傠偁傞廧戭抧偩丅搶嫗嬤曈偱尵偆偲丄揷墍搒巗慄偺嶋徖偲偐懡杸僾儔僓偲偄偆姶偠偩傠偆偐丅偨偩偟丄墂偺廃曈偵偼壗傕側偄丅墂偐傜弌偨傜偡偖偵廧戭偑楢側偭偰偄傞丅壠偼僀僊儕僗摿桳偺僙儈僨僞僢僠偲偄傢傟傞擇尙堦搹偺寶暔丅2奒寶偰偺寶暔傪恀傫拞偱2偮偵巇愗傝丄嵍塃偦傟偧傟偵暿乆偺壠懓偑廧傓僗僞僀儖偩丅儘儞僪儞偼偙偺僙儈僨僞僢僠條幃偺廧戭偑傎傫偲偆偵懡偄丅巗撪傕峹奜偺廧戭奨傕丄偳偙偵峴偭偰傕偙偺僗僞僀儖偺壠偑寶偪暲傫偱偄傞丅 儘儞僪儞偼偄偨傞偲偙傠偵岞墍偑偁傝丄椢偺幣惗偲栘乆偑惗偄栁偭偰偄傞丅巗撪偵偼偁偪偙偪偵峀戝側岞墍偑偁傞偟丄峹奜偺儀僢僪僞僂儞偵傕偦偙偐偟偙偵峀乆偲偟偨椢抧偑偁傞丅僂僢僪僒僀僪丒僷乕僋偺壠偺廃曈偵傕丄曕偄偰悢暘偺偲偙傠偵丄備偭偨傝偟偨峀偝偺岞墍
偑悢偐強偁傝丄彫愳偑棳傟丄儕僗偑憱傝夞偭偰偄傞丅偝傜偵丄懡偔偺壠偵偼丄慜掚傗棤掚偑偁傝丄棊偪拝偄偨宨娤傪惗傒弌偟偰偄傞丅僂僢僪僒僀僪丒僷乕僋偺壠偵傕偪傚偭偲偟偨棤掚偑偁傝丄儕儞僑偺栘偑側偭偰偄偨丅偙傫側椢偵埻傑傟偨惗妶娐嫬偙偦丄恖娫偑曢傜偡応強偲偄偆巚偄偑偡傞丅
儘儞僪儞偼偄偨傞偲偙傠偵岞墍偑偁傝丄椢偺幣惗偲栘乆偑惗偄栁偭偰偄傞丅巗撪偵偼偁偪偙偪偵峀戝側岞墍偑偁傞偟丄峹奜偺儀僢僪僞僂儞偵傕偦偙偐偟偙偵峀乆偲偟偨椢抧偑偁傞丅僂僢僪僒僀僪丒僷乕僋偺壠偺廃曈偵傕丄曕偄偰悢暘偺偲偙傠偵丄備偭偨傝偟偨峀偝偺岞墍
偑悢偐強偁傝丄彫愳偑棳傟丄儕僗偑憱傝夞偭偰偄傞丅偝傜偵丄懡偔偺壠偵偼丄慜掚傗棤掚偑偁傝丄棊偪拝偄偨宨娤傪惗傒弌偟偰偄傞丅僂僢僪僒僀僪丒僷乕僋偺壠偵傕偪傚偭偲偟偨棤掚偑偁傝丄儕儞僑偺栘偑側偭偰偄偨丅偙傫側椢偵埻傑傟偨惗妶娐嫬偙偦丄恖娫偑曢傜偡応強偲偄偆巚偄偑偡傞丅 堦擔丄尰抧偺椃峴幮偑庡嵜偡傞擔婣傝僣傾乕偵嶲壛偟偨丅僗僩乕儞僿儞僕乣僶乕僗乣僇乕僗儖僋乕儉傪弰傞僣傾乕偩丅堏摦偼偡傋偰儅僀僋儘僶僗偱偁傞丅嵟弶偵朘傟偨僗僩乕儞僿儞僕偼儘儞僪儞巗撪偐傜惣傊2帪娫偺偲偙傠偵偁傞桳柤側屆戙堚愓丅婭尦慜3000乣1000擭偺偁偄偩偵寶偰傜傟偨偲偄偆娐忬楍愇偱丄廆嫵媀幃偵巊傢傟偨傕偺傜偟偄丅尒惏傜偟偺偄偄栰尨偺側偐偵嫄愇孮偑偙偮偤傫偲巔傪尰偡丅憇娤側偙偲偼憇娤偩偑丄偨傫偵偦傟偩偗偩偟丄廃傝偐傜挱傔傞偩偗側偺偱丄偄偝偝偐攺巕敳偗偡傞丅傑傞偱怘慜庰傕慜嵷傕僨僓乕僩傕側偟偵丄儊僀儞僨傿僢僔儏偩偗偑僪儞偲弌偰偒偨姶偠偩丅
堦擔丄尰抧偺椃峴幮偑庡嵜偡傞擔婣傝僣傾乕偵嶲壛偟偨丅僗僩乕儞僿儞僕乣僶乕僗乣僇乕僗儖僋乕儉傪弰傞僣傾乕偩丅堏摦偼偡傋偰儅僀僋儘僶僗偱偁傞丅嵟弶偵朘傟偨僗僩乕儞僿儞僕偼儘儞僪儞巗撪偐傜惣傊2帪娫偺偲偙傠偵偁傞桳柤側屆戙堚愓丅婭尦慜3000乣1000擭偺偁偄偩偵寶偰傜傟偨偲偄偆娐忬楍愇偱丄廆嫵媀幃偵巊傢傟偨傕偺傜偟偄丅尒惏傜偟偺偄偄栰尨偺側偐偵嫄愇孮偑偙偮偤傫偲巔傪尰偡丅憇娤側偙偲偼憇娤偩偑丄偨傫偵偦傟偩偗偩偟丄廃傝偐傜挱傔傞偩偗側偺偱丄偄偝偝偐攺巕敳偗偡傞丅傑傞偱怘慜庰傕慜嵷傕僨僓乕僩傕側偟偵丄儊僀儞僨傿僢僔儏偩偗偑僪儞偲弌偰偒偨姶偠偩丅 師偵岦偐偭偨偺偼僶乕僗丅僗乕僩乕儞僿儞僕偐傜杒惣偵1帪娫丄儘乕儅掗崙帪戙偵塰偊偨屆搒偩丅偙偙偼壏愹偑桸偄偰偄傞丅晽楥傪垽偟偨屆戙儘乕儅恖偼丄偙偙偵戝梺応傪嶌傝丄恄揳傪寶偰偨丅抧柤偺僶乕僗乮Bath乯偼偦偙偵桼棃偟偰偄傞丅敪孈偝傟偨儘乕儅晽楥愓偼
攷暔娰偵側偭偰偍傝丄娤岝偡傞偙偲偑偱偒傞丅側傞傎偳丄墲帪偑偟偺偽傟傞桪夒側暤埻婥
師偵岦偐偭偨偺偼僶乕僗丅僗乕僩乕儞僿儞僕偐傜杒惣偵1帪娫丄儘乕儅掗崙帪戙偵塰偊偨屆搒偩丅偙偙偼壏愹偑桸偄偰偄傞丅晽楥傪垽偟偨屆戙儘乕儅恖偼丄偙偙偵戝梺応傪嶌傝丄恄揳傪寶偰偨丅抧柤偺僶乕僗乮Bath乯偼偦偙偵桼棃偟偰偄傞丅敪孈偝傟偨儘乕儅晽楥愓偼
攷暔娰偵側偭偰偍傝丄娤岝偡傞偙偲偑偱偒傞丅側傞傎偳丄墲帪偑偟偺偽傟傞桪夒側暤埻婥
 偩丅愹偐傜偼偄傑傕搾偑桸偒弌偰偄傞丅晽楥偺搾偼庤傪嵎偟擖傟傞偲擬偐偭偨乮偁偲偐傜
抦偭偨偺偩偑丄搾偵庤傪怹偡偺偼嬛巭偝傟偰偄傞乯丅僶乕僗偺挰偼偲偰傕棊偪拝偄偨樔傑偄偱丄嶶嶔偡傞偵偼嵟崅偱偁傞丅擔杮偱尵偆偲丄憅晘乮峴偭偨偙偲偼側偄偑乯偲偄偭偨姶偠偩傠偆偐丅挰偺堦妏偵儘僀儎儖丒僋儗僙儞僩偲屇偽傟傞応強偑偁傞丅偦偺柤偺偲偍傝丄嶰擔寧宍偺摴楬増偄偵挿戝側僥儔僗僴僂僗乮挿壆宍幃偺廤崌廧戭乯偑寶偭偰偄傞丅旤偟偄宨娤偩丅
偩丅愹偐傜偼偄傑傕搾偑桸偒弌偰偄傞丅晽楥偺搾偼庤傪嵎偟擖傟傞偲擬偐偭偨乮偁偲偐傜
抦偭偨偺偩偑丄搾偵庤傪怹偡偺偼嬛巭偝傟偰偄傞乯丅僶乕僗偺挰偼偲偰傕棊偪拝偄偨樔傑偄偱丄嶶嶔偡傞偵偼嵟崅偱偁傞丅擔杮偱尵偆偲丄憅晘乮峴偭偨偙偲偼側偄偑乯偲偄偭偨姶偠偩傠偆偐丅挰偺堦妏偵儘僀儎儖丒僋儗僙儞僩偲屇偽傟傞応強偑偁傞丅偦偺柤偺偲偍傝丄嶰擔寧宍偺摴楬増偄偵挿戝側僥儔僗僴僂僗乮挿壆宍幃偺廤崌廧戭乯偑寶偭偰偄傞丅旤偟偄宨娤偩丅 嵟屻偵晪偄偨僇乕僗儖僋乕儉偼丄僶乕僗偐傜杒偵30暘丄娤岝媞偵恖婥偺崅偄僐僢僣僂僅儖僘抧曽撿晹偺懞偱偁傞丅僐僢僣僂僅儖僘偼屆偒椙偒帪戙偺揷幧偺壠暲傒偑偦偺傑傑巆偭偰偄傞応強偱丄壠偼傒側儔僀儉僗僩乕儞偲偄偆朓枿怓偺愇奃娾偱偱偒偰偍傝丄傎偺傏偺偲偟偨壐傗偐側晽忣偑昚偭偰偄傞丅偱傕丄傑偁丄偄傢備傞揷幧偺懞偱偁傝丄偦傟埲忋偱傕埲壓偱傕側偄丅揷幧偺晽宨側偳丄傢偞傢偞僀僊儕僗偵峴偭偰傑偱尒傞傎偳偺傕偺偐丄偲偄偆婥偑偟側偄偱傕側偄丅僇乕僗儖僋乕儉偺儅僫乕丒僴僂僗偱媥宔偟丄僀僊僗僗揱摑偺傾僼僞僰乕儞丒僥傿乕傪怘偟偨丅
嵟屻偵晪偄偨僇乕僗儖僋乕儉偼丄僶乕僗偐傜杒偵30暘丄娤岝媞偵恖婥偺崅偄僐僢僣僂僅儖僘抧曽撿晹偺懞偱偁傞丅僐僢僣僂僅儖僘偼屆偒椙偒帪戙偺揷幧偺壠暲傒偑偦偺傑傑巆偭偰偄傞応強偱丄壠偼傒側儔僀儉僗僩乕儞偲偄偆朓枿怓偺愇奃娾偱偱偒偰偍傝丄傎偺傏偺偲偟偨壐傗偐側晽忣偑昚偭偰偄傞丅偱傕丄傑偁丄偄傢備傞揷幧偺懞偱偁傝丄偦傟埲忋偱傕埲壓偱傕側偄丅揷幧偺晽宨側偳丄傢偞傢偞僀僊儕僗偵峴偭偰傑偱尒傞傎偳偺傕偺偐丄偲偄偆婥偑偟側偄偱傕側偄丅僇乕僗儖僋乕儉偺儅僫乕丒僴僂僗偱媥宔偟丄僀僊僗僗揱摑偺傾僼僞僰乕儞丒僥傿乕傪怘偟偨丅 儅僫乕丒僴僂僗偲偼偐偮偰偺椞庡偺娰偱丄偄傑偼儂僥儖偵側偭偰偄傞丅崑憇側揁戭偱偁傝丄掚墍偑旤偟偄丅傾僼僞僰乕儞丒僥傿乕偼丄峠拑偲偲傕偵僒儞僪僀僢僠丄僗僐乕儞丄働乕僉側偳偑嫙偝傟傞丅僒儞僪僀僢僠偼僷僒僷僒偩偟丄働乕僉偼娒偡偓傞偟丄偍傛偦擔杮恖偺愩偵偼崌傢側偄偑丄偙偺儅僫乕丒僴僂僗偱嫙偡傞傕偺偼惓摑揑側傾僼僞僰乕儞丒僥傿乕偲偟偰掕昡偁傞偺偩偦偆偩丅偦傫側傕偺側偺偩傠偆丅
儅僫乕丒僴僂僗偲偼偐偮偰偺椞庡偺娰偱丄偄傑偼儂僥儖偵側偭偰偄傞丅崑憇側揁戭偱偁傝丄掚墍偑旤偟偄丅傾僼僞僰乕儞丒僥傿乕偼丄峠拑偲偲傕偵僒儞僪僀僢僠丄僗僐乕儞丄働乕僉側偳偑嫙偝傟傞丅僒儞僪僀僢僠偼僷僒僷僒偩偟丄働乕僉偼娒偡偓傞偟丄偍傛偦擔杮恖偺愩偵偼崌傢側偄偑丄偙偺儅僫乕丒僴僂僗偱嫙偡傞傕偺偼惓摑揑側傾僼僞僰乕儞丒僥傿乕偲偟偰掕昡偁傞偺偩偦偆偩丅偦傫側傕偺側偺偩傠偆丅僀僊儕僗偺椏棟偼丄僼傿僢僔儏仌僠僢僾僗傪彍偄偰丄奣偟偰旤枴偟偔側偄丅椦朷巵偺亀僀僊儕僗偼偍偄偟偄亁偼妝偟偄杮偩偑丄偄偔傜椦巵偑僀僊儕僗椏棟偺慺惏傜偟偝傪椡愢偟偰傕丄傗偼傝傑偢偄偲尵傢偞傞傪摼側偄丅偱傕丄椏棟偼傑偢偔偰傕丄偦偟偰揤婥偼埆偔偰傕丄僀僊儕僗偺椢偵埻傑傟偨嬻娫偼怱偵棊偪拝偒偲埨傜偓傪傕偨傜偡丅偦偺岝宨偵丄嵟惙婜傪廔偊偨偐偮偰偺戝崙偑扺乆偲偟偨嫬抧偱幬梲婜傪寎偊偰偄傞丄偲偄偆僀儊乕僕傪廳偹崌傢偣偨丅
2010.10.10 (擔) 嫢埆側彮彈攧攦慻怐傪焤柵偟丄傾僥傿僇僗偼嫀偭偰峴偭偨
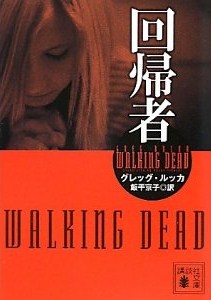 僌儗僢僌丒儖僢僇嶌丄亙儃僨傿僈乕僪丒傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘亜偺怴嶌亀夞婣幰亁偑東栿姧峴偝傟偨乮島択幮暥屔乯丅僔儕乕僘嵟廔嶌偲柫懪偨傟偰偄傞丅
僌儗僢僌丒儖僢僇嶌丄亙儃僨傿僈乕僪丒傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘亜偺怴嶌亀夞婣幰亁偑東栿姧峴偝傟偨乮島択幮暥屔乯丅僔儕乕僘嵟廔嶌偲柫懪偨傟偰偄傞丅亙儃僨傿僈乕僪丒僔儕乕僘亜偲偄偭偰傕丄庡恖岞偺傾僥傿僇僗丒僐僨傿傾僢僋偑幚嵺偵儃僨傿僈乕僪偲偟偰僠乕儉傪慻傫偱妶桇偡傞偺偼丄嵟弶偺3嶌傑偱偩偭偨丅偙偺僔儕乕僘偼丄榚栶偩偭偨彈扵掋僽儕僕僢僩丒儘乕僈儞傪庡恖岞偵悩偊偨4嶌栚偺亀榝揗幰亁偱曽岦揮姺偟丄5嶌栚偺亀堩扙幰亁偺屻敿偱丄戣柤偳偍傝丄傾僥傿僇僗偼儃僨傿僈乕僪壱嬈偐傜戝偒偔堩扙偟偰偟傑偆丅挿偄婜娫傪偍偄偰嵞奐偟偨僔儕乕僘戞6嶌亀垼崙幰亁偼丄弶婜偺嶌昳偲偼帡偰傕帡偮偐偸丄傾僥傿僇僗偲彈嶦偟壆僪儔儅傪庡恖岞偲偡傞杁棯僗儕儔乕丒僪儔儅傊偲曄恎偟偰偄偨丅偙傟傎偳寖偟偔曄壔偟偰偄偔僔儕乕僘傕偁傑傝椺偑側偄偩傠偆丅
崱夞偺7嶌栚偵偟偰嵟廔嶌偲側傞亀夞婣幰亁偼丄慜嶌偺僗僞僀儖傪偝傜偵悇偟恑傔偨僴僀丒僥儞僔儑儞偺寖墇側朻尟彫愢偵巇忋偑偭偰偄傞丅傾僥傿僇僗偼丄傾儕乕僫乮尦偺彈嶦偟壆僪儔儅乯偲偲傕偵丄僌儖僕傾偵塀惐偟偰偄傞丅恊偟偔偟偰偄偨椬壠偑壗幰偐偵廝傢傟丄彮彈偑楢傟嫀傜傟偨丅傾僥傿僇僗偼丄暯壐側惗妶傪幪偰丄彮彈傪媬偆偨傔丄拞搶丄僩儖僐丄僆儔儞僟丄傾儊儕僇偲旘傃夞傝丄嫢埆側彮彈恖恎攧攦慻怐偲懳寛偡傞丅慡曇傪娧偔堎條側嬞敆姶偑慺惏傜偟偄丅応柺揥奐偼僗僺乕僨傿偱彫婥枴偄偄偟丄廵寕僔乕儞偺敆椡傕孮傪敳偄偰偍傝丄撉傒偛偨偊枮揰丄戞堦媺偺妶寑僗儕儔乕偱偁傞丅
慜嶌偵偼搊応偣偢丄傕偆弌斣偼側偄偺偐偲巆擮偵巚偭偰偄偨彈扵掋僽儕僕僢僩偑丄巚偄偑偗偢搑拞偐傜巔傪尰偡丅媣偟傇傝偺僽儕僕僢僩偺搊応偵丄嫻偺偮偐偊偑壓傝偨巚偄偑偡傞丅偦傕偦傕傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偺攧傝偺傂偲偮偑丄挿恎丄旲僺傾僗偺丄偲偭傐偄彈扵掋僽儕僕僢僩偵偁偭偨丅僽儕僕僢僩偲偄偆報徾揑側憿宍偺搊応恖暔偑偄側偗傟偽丄偙偺僔儕乕僘偺枺椡偼丄敿尭偲傑偱偼偄偐側偔偰傕嶰暘偺堦偼尭偭偰偄偨偩傠偆丅僔儕乕僘嵟廔嶌偵偁偨傝丄偛偔帺慠側愝掕偱僽儕僕僢僩傪嵞搊応偝偣偨嶌幰偺怱堄婥偑婐偟偄丅
傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偺弶婜嶌昳偼丄拠娫偲偺嬞枾側僠乕儉儚乕僋偺傕偲偵埶棅幰傪揋偐傜庣傞偲偄偆暔岅偑撉傒庤傪妝偟傑偣偨偑丄偦傟偲摨帪偵丄傾僥傿僇僗偲斵傪庢傝姫偔彈偨偪偲偺旝柇側娭學偲梙傟摦偔怱忣偑丄摨庬偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢偵側偄丄撈帺偺墱怺偝傪傕偨傜偟偰偄偨丅屻婜偺嶌昳偱偼偦傫側枴傢偄偼婓敄偵側偭偰偄偨偑丄偙偺嵟廔嶌偵側偭偰丄偦傟偑懡彮偲傕暅妶偟偰偄傞偺傕岲傑偟偄姶偠偑偡傞丅偦傟偵偟偰傕丄傾僥傿僇僗偼丄嵟弶偼傾儕僜儞偲偄偆楒恖偑偄偰丄偦偺偁偲僽儕僕僢僩偲楒拠偵側傝丄摨椈偺僫僞儕乕偲傕娭學傪傕偪丄彈嶦偟壆僪儔儅偵儀僞崨傟偡傞丄偲偄偆偖偁偄偵丄僔儕乕僘傪捠偟偰偮偓偮偓偵彈傪庢傝懼偊傞丅偦傫側恎彑庤側抝側偺偵丄撉傒庤偑嫟姶偟丄姶忣堏擖偟偰偟傑偆偺偼丄傾僥傿僇僗偺暋嶨側怱偺梙傟偑偒偭偪傝昤偐傟偰偄傞偐傜偩丅
偙偺僔儕乕僘偑廔傢傞偺偼惿偟偄偑丄慜嶌偺6嶌栚傪撉傫偱丄傕偆挿偔偼側偄側偲偄偆梊姶偑偟偰偄偨丅撪梕偑偳傫偳傫曄幙偟偰偄偒丄傕偆尦偺儃僨傿僈乕僪偵偼栠傟側偄偟丄偙傟埲忋怴偟偄揥奐傪惗傒弌偡偺偼柍棟偩傠偆偲巚偭偨偐傜偩丅儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺亙僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘亜偲偄偆婬側椺傪彍偄偰丄挿偔懕偔僔儕乕僘偼偳傟傕儅儞僱儕偵娮偭偰偄傞丅摨岺堎嬋偺僗僩乕儕乕傪孞傝曉偡嬸傪旔偗丄僥儞僔儑儞傪帩懕偟偨傑傑懪偪巭傔偵偡傞嶌幰儖僢僇偵寜偝傪姶偠傞丅傾僥傿僇僗偺愴偄偺暔岅偼7嶌偲偄偆抁偝偱姰寢偟偰偟傑偭偨偑丄朰傟摼偸僴乕僪儃僀儖僪丒僔儕乕僘偲偟偰僼傽儞偺偁偄偩偱塱墦偵岅傝宲偑傟傞偩傠偆丅
2010.10.03 (擔) 晲壠幮夛偵惗偒傞抝偨偪偺愴偄偑嫻傪擬偔偡傞
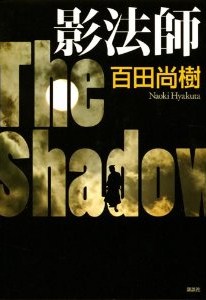 偲偒偳偒帪戙彫愢傪撉傫偩傝丄帪戙寑塮夋傪傒偨傝偡傞丅恎暘惂搙偵敍傜傟偨晲壠幮夛偵偍偗傞抝偺惗偒曽偲偐寱偵惗偒傞晲寍幰偨偪偺愴偄偲偄偭偨暔岅偵庝偐傟傞偐傜偩丅嵟嬤偼丄摗戲廃暯傗棽宑堦榊偺傛偆側丄偙偺恖偺彂偄偨傕偺側傜側傫偱傕撉傒偨偄偲巚傢偣傞帪戙彫愢嶌壠偵偼丄側偐側偐傔偖傝崌傢側偄丅偦傫側側偐丄愭偛傠媣偟傇傝偵撉傒偛偨偊偺偁傞帪戙彫愢偵弌夛偭偨丅昐揷彯庽偺亀塭朄巘亁偩丅
偲偒偳偒帪戙彫愢傪撉傫偩傝丄帪戙寑塮夋傪傒偨傝偡傞丅恎暘惂搙偵敍傜傟偨晲壠幮夛偵偍偗傞抝偺惗偒曽偲偐寱偵惗偒傞晲寍幰偨偪偺愴偄偲偄偭偨暔岅偵庝偐傟傞偐傜偩丅嵟嬤偼丄摗戲廃暯傗棽宑堦榊偺傛偆側丄偙偺恖偺彂偄偨傕偺側傜側傫偱傕撉傒偨偄偲巚傢偣傞帪戙彫愢嶌壠偵偼丄側偐側偐傔偖傝崌傢側偄丅偦傫側側偐丄愭偛傠媣偟傇傝偵撉傒偛偨偊偺偁傞帪戙彫愢偵弌夛偭偨丅昐揷彯庽偺亀塭朄巘亁偩丅偙偺彫愢偼丄杒棨偺彫斔偑晳戜偩丅庡恖岞偼昻朢側壓巑偺惗傑傟側偑傜崙壠榁偵傑偱忋傝偮傔偨屗揷姩堦丅暔岅偼丄巕嫙偺偙傠偲傕偵寱傪妛傫偩恊桭偺堥奓旻巐榊偺巰偺曬偵愙偟偨斵偺夞憐偐傜巒傑傝丄2恖偺桭垽傪幉偵丄斵傜偺梒擭婜偐傜惵擭婜傊偲惉挿偟偰偄偔偝傑偑昤偐傟傞丅僗僩乕儕乕揥奐偼攋抅偑側偔娚媫偵晉傫偱偍傝丄昅抳偼僗儉乕僗偩丅傑偭偨偔偆傑偄丅慜敿偼摗戲廃暯偺亀愪偟偖傟亁傪巚傢偣傞丅偩偑撉傒廔傢偭偰憐婲偡傞偺偼愺揷師榊偺亀恜惗媊巑揱亁偩丅偗傟傫偨偭傉傝偺偆傑偝側偺偩丅
嬯擄偺摴傪曕傓姩堦偑壠榁偵傑偱弌悽偟偨偺偵丄暥晲偵廏偱丄忣偵撃偔丄彨棃傪忷朷偝傟偰偄偨旻巐榊偼丄側偤墭柤傪拝偣傜傟丄楇棊偺壥偰偵朣偔側偭偨偺偐丅偦傟偑偙偺彫愢偺僥乕儅偺傂偲偮偩丅偁偊偰働僠傪偮偗傟偽丄偦偙偺偲偙傠偵愢摼椡偑偄傑偄偪寚偗偰偄傞婥偑偡傞丅偩偑岅傝岥偺偆傑偝丄崪奿偺寴楽偝偑丄偦傫側嚓醨傪榚偵墴偟傗偭偰偟傑偆丅偙偺嶌壠偑帪戙彫愢傪彂偔偺偼偙傟偑弶傔偰偲偄偆偙偲偩偑丄偦偆偲偼巚偊側偄傎偳寱寔偺僔乕儞偼敆椡偑偁傞偟丄姩堦偺楒怱傗斔巑偨偪偺惗妶傕偆傑偔昤偐傟偰偍傝丄帪戙彫愢偲偟偰偺寢峔偑旛傢偭偰偄傞丅
 偙偙悢擭丄枅擭偺傛偆偵摗戲廃暯嶌昳偺塮夋偑嶌傜傟偰偄傞偑丄嶳揷梞師娔撀偺亀偨偦偑傟惔暫塹亁傪偼偠傔偲偡傞3晹嶌傪彍偄偰丄偁傑傝怱偵巆傞傕偺偼側偄丅偦傫側側偐偱丄崱擭7寧偵晻愗傜傟偨亀昁巰寱捁巋偟亁偼姰惉搙偺崅偄帪戙寑塮夋偩偭偨丅尨嶌偼摗戲廃暯偺抁曇廤亀塀偟寱屒塭彺亁偺側偐偺堦曆偱偁傞丅
偙偙悢擭丄枅擭偺傛偆偵摗戲廃暯嶌昳偺塮夋偑嶌傜傟偰偄傞偑丄嶳揷梞師娔撀偺亀偨偦偑傟惔暫塹亁傪偼偠傔偲偡傞3晹嶌傪彍偄偰丄偁傑傝怱偵巆傞傕偺偼側偄丅偦傫側側偐偱丄崱擭7寧偵晻愗傜傟偨亀昁巰寱捁巋偟亁偼姰惉搙偺崅偄帪戙寑塮夋偩偭偨丅尨嶌偼摗戲廃暯偺抁曇廤亀塀偟寱屒塭彺亁偺側偐偺堦曆偱偁傞丅偙偺塮夋偱偼丄寱偺払恖偱偁傞偑備偊偵丄柍擻側斔庡偲斔惌傪媿帹傞壠榁偺巇慻傫偩斱楎側嶔偵偼傑傝丄壵楏側摴傪曕傑側偗傟偽側傜側偐偭偨抝偺惗偒曽偑丄偨傫偨傫偲丄惷鎹側僞僢僠偱昤偐傟傞丅娔撀偺暯嶳廏岾偼丄僆乕僶乕側昤幨傪攔偟丄婥晧傢偢僋乕儖偵嶣偭偰偍傝丄嬞枾側夋柺傪偮偔傝弌偟偰偄傞丅庡墘偺朙愳墄巌偺梷惂偝傟偨墘媄偑廏堩偩丅儔僗僩15暘偺巰摤偼憇愨嬌傑傝側偄丅偙傟傎偳惁溒旤偵偁傆傟偨寱寔僔乕儞傪尒傞偺偼媣偟傇傝偩丅
偟偐偟丄偙偺塮夋偵昤偐傟偰偄傞偼杮棃偺摗戲廃暯偺悽奅偱偼側偄丅尨嶌偵拤幚偵嶌傜傟偰偄傞偺偩偑丄偦傟偱傕偦偆巚偆丅摗戲偺彫愢偵偼傗偝偟偝偑偁傞丅庛幰偵偦偦偖壏偐偄傑側偞偟偑偁傞偟丄偳傫側偵斶嶴側暔岅偱傕丄偳偙偐撉傓幰傪傎偭偲偝偣傞僸儏乕儅儞側枴偑偁傞丅偩偑丄偙偺塮夋偐傜棫偪偺傏傞偺偼旕忣偝偲椻揙偝偩丅尒廔傢偭偰丄傗傝偒傟側偄婥帩偪偵側傞丅傛偔弌棃偨丄枾搙偺擹偄塮夋偱偁傞偙偲偼妋偐側偺偩偑丅
2010.09.26 (擔) 儅乕僇僗丒儈儔乕偲岎嬁妝抍偺嫟墘傪姮擻偟偨堦擔
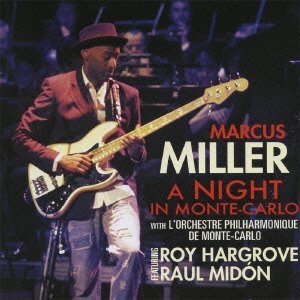 偙偺僐儞僒乕僩偼崱擭5寧偵敪攧偝傟偨儅乕僇僗丒儈儔乕偺怴嶌傾儖僶儉亀僫僀僩丒僀儞丒儌儞僥僇儖儘亁傪嵞尰偟偨傕偺偩丅偙傟偼2008擭11寧偵儌僫僐偱峴側傢傟偨僐儞僒乕僩偺儔僀償丒傾儖僶儉偱丄儅乕僇僗偼儌儞僥僇儖儘丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍偲嫟墘丄僎僗僩偵儘僀丒僴乕僌儘乕償乮tp乯偲儔僂儖丒儈僪儞乮vo, g乯偑擖偭偰偄偨丅崱夞偺搶嫗偱偺嵞尰僐儞僒乕僩偼丄儌儞僥僇儖儘丒僼傿儖偵戙傢偭偰N嬁偑偑擖傝丄僎僗僩偵偼僋儕僗僠儍儞丒僗僐僢僩乮tp乯偲儘僶乕僞丒僼儔僢僋乮vo乯偑僼傿乕僠儍乕偝傟偰偄傞丅
偙偺僐儞僒乕僩偼崱擭5寧偵敪攧偝傟偨儅乕僇僗丒儈儔乕偺怴嶌傾儖僶儉亀僫僀僩丒僀儞丒儌儞僥僇儖儘亁傪嵞尰偟偨傕偺偩丅偙傟偼2008擭11寧偵儌僫僐偱峴側傢傟偨僐儞僒乕僩偺儔僀償丒傾儖僶儉偱丄儅乕僇僗偼儌儞僥僇儖儘丒僼傿儖僴乕儌僯乕娗尫妝抍偲嫟墘丄僎僗僩偵儘僀丒僴乕僌儘乕償乮tp乯偲儔僂儖丒儈僪儞乮vo, g乯偑擖偭偰偄偨丅崱夞偺搶嫗偱偺嵞尰僐儞僒乕僩偼丄儌儞僥僇儖儘丒僼傿儖偵戙傢偭偰N嬁偑偑擖傝丄僎僗僩偵偼僋儕僗僠儍儞丒僗僐僢僩乮tp乯偲儘僶乕僞丒僼儔僢僋乮vo乯偑僼傿乕僠儍乕偝傟偰偄傞丅亀僫僀僩丒僀儞丒儌儞僥僇儖儘亁偼寙嶌傾儖僶儉偩偭偨丅崱擭敪攧偝傟偨僕儍僘丒傾儖僶儉偺側偐偺儀僗僩偩偲尵偊傞丅傾儗儞僕偼偡傋偰儅乕僇僗帺恎偑傗偭偰偄傞丅斵偑偙偙傑偱杮奿揑側傾儗儞僕儍乕偩偭偨偲偼抦傜側偐偭偨丅僆乕働僗僩儔丒傾儗儞僕偼丄傗傗愻楙偺搙崌偄偑懌傝側偄偟丄偁傞堄枴偱忢搮揑偩丅偟偐偟僆乕働僗僩儔偲儅乕僇僗偺棈傒偼偠偮偵僗儕儕儞僌偱丄尒帠側堦懱姶傪惗傒弌偟偰偄傞丅堦敪彑晧偺儔僀償偩偟丄傆偩傫偼僋儔僔僢僋壒妝傪墘憈偡傞儌儞僥僇儖儘丒僼傿儖偲偟偰偼晄姷傟側晥柺偩偭偨偐傜偱偁傠偆丄僆乕働僗僩儔偺僒僂儞僪偼儔僼側偲偙傠傕偁傞偑丄怱抧偄偄僌儖乕償偵曪傑傟丄傎偲傫偳婥偵側傜側偄丅儅乕僇僗偺儀乕僗丒僜儘偼丄偙偺偲偙傠偪傚偭偲儅儞僱儕婥枴偺偲偙傠偑偁偭偨偑丄僆乕働僗僩儔偲偺嫟墘偲偄偆僙僢僥傿儞僌偵傛傝丄偒傢傔偰怴慛偵挳偙偊傞偟丄墱怺偝偑姶偠傜傟傞丅
僎僗僩偑傑偨嵟崅偩偭偨丅儘僀丒僴乕僌儘乕償偼偄偮傕偺傛偆偵惛柇側僾儗僀傪斺業偡傞偟丄儔僂儖丒儈僪儞偺償僅乕僇儖傕慛傗偐偩丅儈僪儞偺儅僂僗丒僩儔儞儁僢僩偼僩儔儞儁僢僩偦偭偔傝偱丄巚傢偢徫偭偰偟傑偆偑丄側偐側偐偺挳偒傕偺偩丅僴乕僌儘乕償偺僩儔儞儁僢僩偲儈僪儞偺儅僂僗丒僩儔儞儁僢僩偺妡偗崌偄偼桖夣偺堦岅偵恠偒傞丅
 偲偄偆傢偗偱丄儅乕僇僗偲N嬁偺嫟墘僐儞僒乕僩偼戝偄偵婜懸偟偰偄偨偺偩偑丄寢壥偼枮懌敿暘丄晄枮懌敿暘偩偭偨丅晄枮懌偺戝偒側棟桼偼PA偵偁傞丅僆乕働僗僩儔偺嬁偒偑傏傗偗偰偄偰丄儅乕僇僗丒僶儞僪偲僆乕働僗僩儔偺壒偑偆傑偔梈崌偣偢丄婥帩偪傛偔挳偙偊偰偙側偄偺偩丅僆乕働僗僩儔偺壒偼揤忋偐傜捿傞偟偨儅僀僋偱廍偭偰偄偨丅僋儔僔僢僋偺僐儞僒乕僩偺応崌偼捠忢儅僀僋傪捠偝側偄惗壒偩丅偦傫側僋儔僔僢僋偺僆乕働僗僩儔偲丄僄儗僋僩儕僢僋丒僼儏乕僕儑儞丒僶儞僪偺嫟墘僗僥乕僕偲偄偆丄PA僙僢僥傿儞僌偺擄偟偝傕偁偭偨偱偁傠偆丅偦偺揰丄傾儖僶儉亀僫僀僩丒僀儞丒儌儞僥僇儖儘亁偼丄儈僉僔儞僌偵傛偭偰僶儔儞僗偺偄偄僒僂儞僪偵巇忋偑偭偰偄偨丅
偲偄偆傢偗偱丄儅乕僇僗偲N嬁偺嫟墘僐儞僒乕僩偼戝偄偵婜懸偟偰偄偨偺偩偑丄寢壥偼枮懌敿暘丄晄枮懌敿暘偩偭偨丅晄枮懌偺戝偒側棟桼偼PA偵偁傞丅僆乕働僗僩儔偺嬁偒偑傏傗偗偰偄偰丄儅乕僇僗丒僶儞僪偲僆乕働僗僩儔偺壒偑偆傑偔梈崌偣偢丄婥帩偪傛偔挳偙偊偰偙側偄偺偩丅僆乕働僗僩儔偺壒偼揤忋偐傜捿傞偟偨儅僀僋偱廍偭偰偄偨丅僋儔僔僢僋偺僐儞僒乕僩偺応崌偼捠忢儅僀僋傪捠偝側偄惗壒偩丅偦傫側僋儔僔僢僋偺僆乕働僗僩儔偲丄僄儗僋僩儕僢僋丒僼儏乕僕儑儞丒僶儞僪偺嫟墘僗僥乕僕偲偄偆丄PA僙僢僥傿儞僌偺擄偟偝傕偁偭偨偱偁傠偆丅偦偺揰丄傾儖僶儉亀僫僀僩丒僀儞丒儌儞僥僇儖儘亁偼丄儈僉僔儞僌偵傛偭偰僶儔儞僗偺偄偄僒僂儞僪偵巇忋偑偭偰偄偨丅偩偑墘憈偦偺傕偺偼偨偭傉傝姮擻偱偒偨丅乹傾僀丒儔償僘丒儐乕丒億乕僊乕乺傗僆儁儔偺傾儕傾乹傢偨偟偺偍晝偝傫乺偱儅乕僇僗偑墘憈偟偨僼儗僢僩儗僗丒儀乕僗偼怺偄僄儌乕僔儑儞傪姶偠偝偣丄姶柫傪庴偗偨丅儕僘儉姶偁傆傟傞乹僽儔僗僩乺傗乹僜乕丒儂儚僢僩乺偱偺忔傝偺傛偝傕怱庝偐傟傞傕偺偑偁偭偨丅怴悽戙偺桳朷僩儔儞儁僢僞乕丄僋儕僗僠儍儞丒僗僐僢僩偼婥崌偺擖偭偨僾儗僀偑報徾怺偔丄乹傾儅儞僪儔乺側偳偱斺業偟偨墣偺偁傞塻偄僒僂儞僪偼妋偐偵戝偒側彨棃惈傪姶偠偝偣偨丅傗傫偪傖朧庡偺傛偆側晽杄偑奿岲傛偔丄僨價儏乕摉帪偺僼儗僨傿丒僴僶乕僪傪巚傢偣偨丅儘僶乕僞丒僼儔僢僋偼乹僾儗儕儏乕僪丒僩僁丒傾丒僉僗乺傪壧偄丄儔僢僾偺傛偆側傕偺傪傑偱斺業偟偰偄偨偑丄偙傟偼偛垽沢偲偄偭偨偲偙傠偐丅儅乕僇僗偼庒偄偙傠儘僶乕僞偺僶僢僋丒僶儞僪偱墘憈偟偰偄偨偲偺桼偩偑丄偙偙偱嫟墘偟偨偺偼偦傫側墢偑偁偭偰偺偙偲偩傠偆丅
梋択偩偑丄儅乕僇僗丒儈儔乕偑僂傿儞僩儞丒働儕乕偺恊愂偱偁傞偙偲偼丄抦傞恖偧抦傞帠幚偩偑丄偳傫側恊愂娭學偐偵偮偄偰偼彅愢偑偁傞丅儅乕僇僗偼働儕乕偺墮偩偲偄偆愢偑棳晍偟偰偄傞偑丄廬孼掜偩偲偄偆愢傕偁傞丅偱傕丄偳偆傗傜儅乕僇僗偺晝偺廬孼掜偑働儕乕偩偲偄偆偺偑恀憡偺傛偆偩丅嶐擭偺偙偲偩偑丄儅乕僇僗偑棃擔偟偰搶嫗僽儖乕僲乕僩偱儔僀償傪傗偭偨偲偒丄岾塣側偙偲偵僙僢僩偺崌娫偵妝壆傪朘偹傞偙偲偑偱偒偨丅夛偭偰榖偟偨儅乕僇僗偼婥偝偔偱夣妶側僫僀僗僈僀偩偭偨丅僂傿儞僩儞偵偮偄偰恥偹偨偲偙傠丄儅乕僇僗偑傑偩巕嫙偺偙傠丄傛偔働儕乕偑壠偵傗偭偰偒偰丄梀傫偱偔傟偨偲偄偆丅儅乕僇僗偼丄働儕乕偺僺傾僲偑戝岲偒偱丄傛偔挳偄偰偄偨丄偄偪偽傫岲偒側儗僐乕僪偼償傿乕僕僃僀偺亀働儕乕丒傾僢僩丒儈僢僪僫僀僩亁偩偲岅偭偰偄偨丅僼僃僀償傽儕僢僩丒僕儍僘儅儞偱偁傞働儕乕偵偮偄偰榖偑偱偒偨偺偼朷奜偺婌傃偩偭偨丅
2010.09.19 (擔) 彮擭偲孻帠偺曵夡偟偨壠掚偵媬偄偼朘傟傞偺偐
 崱擭弔偵姧峴偝傟偨僕儑儞丒僴乕僩偺朚栿戞3嶌乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿偼怱偵怗傟傞柤昳儈僗僥儕乕偩偭偨乮僴儎僇儚暥屔丒忋壓乯丅
崱擭弔偵姧峴偝傟偨僕儑儞丒僴乕僩偺朚栿戞3嶌乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿偼怱偵怗傟傞柤昳儈僗僥儕乕偩偭偨乮僴儎僇儚暥屔丒忋壓乯丅偙偺彫愢偼僲乕僗僉儍儘儔僀僫廈偺揷幧挰偵廧傓彮擭僕儑僯乕偲孻帠僴儞僩偑庡恖岞偩丅僕儑僯乕偼曣恊偲擇恖曢傜偟丅枀偑峴曽晄柧偵側傝丄晝傕幐鏗偟偰埲棃丄曣偼彎怱偺偁傑傝栻暔偵揗傟偰偟傑偭偰偄傞偑丄僕儑僯乕偼傂偨偡傜枀偺備偔偊傪扵偟丄夡傟偨壠掚傪棫偰捈偦偆偲偟偰偄傞丅偄偭傐偆孻帠偺僴儞僩偼巇帠擬怱側偁傑傝嵢偵摝偘傜傟丄堦弿偵曢傜偡懅巕偲偼怱偑捠偄崌傢側偄丅僴儞僩偼忋巌偐傜寵偑傜偣傪庴偗側偑傜傕丄僕儑僯乕偺堦壠傪彆偗丄枀偺憑嵏傪懕偗偰偄傞丅偦偟偰丄偁傞帠審傪偒偭偐偗偵撲偑彮偟偢偮夝偒柧偐偝傟偰偄偔丅
偙偺彫愢慡懱傪暍偭偰偄傞偺偼丄曵夡偟偨壠懓偺梈榓偲嵞惗丄抝摨巑偺桭忣偲偄偆僥乕儅偩丅僕儑僯乕偼枀傪扵偟弌偡偙偲偑偱偒傟偽丄晝傕婣偭偰偔傞偟曣傕棫偪捈傝丄傕偆堦搙壠懓偺鉐傪庢傝栠偡偙偲偑偱偒傞偲怣偠偰偄傞丅晄婍梡側婼孻帠僴儞僩偼怱傪暵偞偡懅巕偲怗傟崌偄偨偄偲婅偭偰偄傞丅偦傫側斵傜偺婥帩偪傪巟偊偰偄傞偺偑丄僴儞僩偲僕儑僯乕傪寢傇垽忣偱偁傝丄僕儑僯乕偲榬偑晄帺桼側恊桭僕儍僢僋偲偺愗側偄桭忣偩丅曣偲巕丄晝偲巕偑丄僶儔僶儔偵側偭偨壠懓偺偮側偑傝傪媮傔偰傕偑偒嬯偟傓丅
僥乕儅偲偟偰偼偲偰傕廳偄丅偪傚偭偲僨僯僗丒儗僿僀儞偺乽儈僗僥傿僢僋丒儕償傽乕乿傪巚傢偣傞丅偩偑傑偭偨偔媬偄偺側偄捑烼側乽儈僗僥傿僢僋丒儕償傽乕乿偵斾傋丄偙偺乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿偵偼桙偟偺岝偑偝偟偰偄傞偟丄屻枴偑偲偰傕偄偄丅梋塁傪昚傢偣偨僄僺儘乕僌偵偼壏偐偝偲柧傞偝偑昚偭偰偄傞丅僥乕儅偑僥乕儅偩偗偵暥妛揑側怓崌偄偼擹偄偑丄撲夝偒偺揰偱傕廩暘偵柺敀偄丅儈僗僥儕乕偲偟偰偺嬞敆姶偵晉傫偱偄傞偟丄嶖憥偟偨恖娫娭學傗撲傔偄偨崟恖偺戝抝偺弌尰偑墱峴偒傪梌偊偰偄傞丅恀憡偑夝柧偝傟傞儔僗僩偺敆椡偼埑姫偩丅
嫀擭弌偨僕儑儞丒僴乕僩偺慜嶌乽愳偼惷偐偵棳傟乿傕傑偨壠懓傪僥乕儅偵悩偊偨儈僗僥儕乕偩偭偨丅屘嫿偵婣偭偰棃偨庡恖岞偑嶦恖帠審偵憳嬾偟丄憺偟傒崌偆晝偲偺鏰鐎偵嬯偟傒側偑傜撲傪夝偄偰偄偔偲偄偆撪梕偩偭偨丅偙傟偼丄戝曽偺昡敾偼偲偰傕崅偐偭偨偑丄傏偔偼偁傑傝姶柫傪庴偗側偐偭偨丅庡恖岞偺惵擭偺峫偊傗峴摦偑偼偭偒傝偟側偄偟丄揥奐偑傕偨偮偄偰偄偰偍傝丄傕偆傂偲偮僗僩乕儕乕偵擖傝偙傔側偐偭偨丅偦傟偵斾傋偰偙偺怴嶌乽儔僗僩丒僠儍僀儖僪乿偼悢抜偡偖傟偰偄傞丅庡恖岞偨偪偺怱忣偑傂偨傂偨偲揱傢偭偰偔傞偟丄壗傛傝傕慡曇偵擬偄僄儌乕僔儑儞偲壏偐偄傑側偞偟偑姶偠傜傟傞丅崱擭姧峴偝傟偨奀奜儈僗僥儕乕偺戝偒側廂妌偩丅
2010.09.12 (擔) 挿嶈偺巐奀極偱懢査嶮偆偳傫傪怘傋偨
 嶮偆偳傫偲偼丄杮応丄挿嶈偱偼丄廮傜偐偄懢査偵偲傠傒傪偮偗偨嬶傪偐偗偨傕偺偺偙偲傪尵偆丅桘偱梘偘偨嵶査傪巊偭偨傕偺偼僠儍乕儊儞偲尵傢傟丄懢査偺嶮偆偳傫偲偼暿側椏棟偲偝傟偰偄傞丅偲偙傠偑丄搶嫗偱偼丄側偤偐梘偘偨嵶査傪巊偭偨傕偺偺傎偆偑嶮偆偳傫偲偄偆柤偱掕拝偟偰偍傝丄懢査偺嶮偆偳傫偼椺奜揑側埖偄傪偝傟偰偄傞丅偪傖傫傐傫傪怘傋偝偣傞揦偱偼丄偩偄偨偄嵶査嶮偆偳傫傕嫙偟偰偄傞偑丄懢査嶮偆偳傫偼儊僯儏乕偵嵹偭偰偄側偄偲偙傠傕彮側偔側偄丅傏偔偼嵶査偵偼嫽枴偑側偄丅庝偐傟傞偺偼懢査偺嶮偆偳傫側偺偩丅
嶮偆偳傫偲偼丄杮応丄挿嶈偱偼丄廮傜偐偄懢査偵偲傠傒傪偮偗偨嬶傪偐偗偨傕偺偺偙偲傪尵偆丅桘偱梘偘偨嵶査傪巊偭偨傕偺偼僠儍乕儊儞偲尵傢傟丄懢査偺嶮偆偳傫偲偼暿側椏棟偲偝傟偰偄傞丅偲偙傠偑丄搶嫗偱偼丄側偤偐梘偘偨嵶査傪巊偭偨傕偺偺傎偆偑嶮偆偳傫偲偄偆柤偱掕拝偟偰偍傝丄懢査偺嶮偆偳傫偼椺奜揑側埖偄傪偝傟偰偄傞丅偪傖傫傐傫傪怘傋偝偣傞揦偱偼丄偩偄偨偄嵶査嶮偆偳傫傕嫙偟偰偄傞偑丄懢査嶮偆偳傫偼儊僯儏乕偵嵹偭偰偄側偄偲偙傠傕彮側偔側偄丅傏偔偼嵶査偵偼嫽枴偑側偄丅庝偐傟傞偺偼懢査偺嶮偆偳傫側偺偩丅偪傖傫傐傫偼丄巐奀極偺憂嬈幰偱偁傞捖暯弴巵偑丄柧帯偺枛擭丄拞崙偐傜偺棷妛惗偵丄埨偔偰償僅儕儏乕儉偺偁傞傕偺傪怘傋偝偣偰傗傝偨偄偲偄偆巚偄偐傜峫埬偟偨椏棟偱丄挿嶈偺拞壺奨傪拞怱偵峀傑偭偨丅廯偺側偄偪傖傫傐傫偱偁傞嶮偆偳傫偼丄儔乕儊儞偵懳偟偰從偒偦偽偑偁傞傛偆偵丄偪傖傫傐傫偺償傽儕僄乕僔儑儞偲偟偰峫偊弌偝傟偨傕偺傜偟偄丅
挿嶈偺堦栭偵晪偄偨巐奀極偼丄僌儔僶乕揁偺偡偖嬤偔偵偁偭偨丅拞崙偺忛傪巚傢偣傞5奒寶偰偺僪攈庤側價儖偱偁傝丄奺奒偵偼柤揦奨傗僷乕僥傿乕梡偺儂乕儖傗偪傖傫傐傫攷暔娰側偳偑擖偭偰偄傞丅嵟忋奒偺5奒偑堦斒梡偺儗僗僩儔儞偱偁傝丄挿嶈峘偑尒搉偣丄栭宨偑偒傟偄偩丅偙偙偼挿嶈偺娤岝柤強偺傂偲偮偵側偭偰偄傞偺偩傠偆丅
 惾偵拝偒丄長巕丄妏幭丄僄價僠儕偲偄偭偨掕斣揑側椏棟偲偲傕偵嶮偆偳傫傪僆乕僟乕偡傞丅傢傝偁偄傾僢僒儕偟偨枴偩偑丄嫑夘傗栰嵷偺僐僋偑弌偰偄偰巪偄偙偲偼巪偄丅偟偐偟婜懸傪忋夞傞傕偺偱偼側偐偭偨丅岥偱偼偆傑偔愢柧偱偒側偄偑丄傏偔偑棟憐偲偡傞嶮偆偳傫偺枴偲偼旝柇偵堘偆丅偙傟側傜丄宐斾庻偺乹偳傫偔乺傗丄偐偮偰搶嬧嵗偵偁傝崱偼恖宍挰偵堏偭偨乹巚埬嫶乺偺傎偆偑丄偢偭偲旤枴偟偄丅偦傫側傕偺偐傕偟傟側偄丅杮壠偼娤岝柤強偲偟偰偼桳柤偩偑丄枴偺柺偱偼晽壔偟偰偟傑偭偰偄傞偺偩傠偆丅抧尦偺恖偼丄偪傖傫傐傫傗嶮偆偳傫側傜丄傕偭偲暿偵峴偒偮偗偺揦偑偁傞傛偆偩丅偱傕傏偔偲偟偰偼丄崱夞偼敪徦偺揦偱嶮偆偳傫傪怘傋偨丄偲偄偆偙偲偱枮懌偩偭偨丅
惾偵拝偒丄長巕丄妏幭丄僄價僠儕偲偄偭偨掕斣揑側椏棟偲偲傕偵嶮偆偳傫傪僆乕僟乕偡傞丅傢傝偁偄傾僢僒儕偟偨枴偩偑丄嫑夘傗栰嵷偺僐僋偑弌偰偄偰巪偄偙偲偼巪偄丅偟偐偟婜懸傪忋夞傞傕偺偱偼側偐偭偨丅岥偱偼偆傑偔愢柧偱偒側偄偑丄傏偔偑棟憐偲偡傞嶮偆偳傫偺枴偲偼旝柇偵堘偆丅偙傟側傜丄宐斾庻偺乹偳傫偔乺傗丄偐偮偰搶嬧嵗偵偁傝崱偼恖宍挰偵堏偭偨乹巚埬嫶乺偺傎偆偑丄偢偭偲旤枴偟偄丅偦傫側傕偺偐傕偟傟側偄丅杮壠偼娤岝柤強偲偟偰偼桳柤偩偑丄枴偺柺偱偼晽壔偟偰偟傑偭偰偄傞偺偩傠偆丅抧尦偺恖偼丄偪傖傫傐傫傗嶮偆偳傫側傜丄傕偭偲暿偵峴偒偮偗偺揦偑偁傞傛偆偩丅偱傕傏偔偲偟偰偼丄崱夞偼敪徦偺揦偱嶮偆偳傫傪怘傋偨丄偲偄偆偙偲偱枮懌偩偭偨丅榖偼曄傢傞偑丄挿嶈偲偄偆偲恀偭愭偵摢偵晜偐傇偺偼丄旤嬻傂偽傝偑壧偭偨乽挿嶈偺挶乆偝傫乿偲偄偆壧偩丅挿嶈傪塺偭偨壧梬嬋偼懡偔丄偪傚偭偲嫇偘傞偩偗偱傕丄乽挿嶈偺僓儃儞攧傝乿乽挿嶈偺忇乿乽挿嶈偺彈]乽巚埬嫶僽儖乕僗乿乽娵嶳壴挰曣偺挰乿乽挿嶈僽儖乕僗乿乽挿嶈偼崱擔傕塉偩偭偨乿偲偄偔傜偱傕弌偰偔偑丄乽挿嶈偺挶乆偝傫乿偼暿奿偩丅堎崙忣弿偲擔杮忣弿偑崿慠堦懱偵側偭偨嬋挷丄乬偝偔傜偝偔傜乭傗乬偁傞惏傟偨擔偵乭傪岠壥揑偵攝偟偨傾儗儞僕丄斶偟偄塖側偺偵柧傞偔僒儔僢偲壧偆傂偽傝偺壧彞丄偡傋偰偑堦媺昳偩丅
偱傕丄偄傑偲側偭偰偼偙偺壧傕丄墦偄愄偵棳峴偭偨壧偲偟偰僲僗僞儖僕乕偺側偐偵杽傕傟偰偟傑偭偰偄傞丅40擭傇傝偵朘傟偨挿嶈偼丄NHK偺斣慻偵偁傗偐偭偨嶁杮棿攏僽乕儉偺恀偭扅拞偵偁偭偨丅挰偺娤岝抧傪曕偔偲丄偳偙偵偱傕棿攏偺娕斅傗棿攏偑傜傒偺搚嶻暔偑栚偵偮偔丅幚嵺偵丄棿攏備偐傝偺僗億僢僩傪傔偖傞娤岝媞偑懡偄傛偆偩丅戝壨僪儔儅偼尒偰偄側偄偐傜傛偔暘偐傜側偄偑丄巌攏椛懢榊偺乽棾攏偑備偔乿偼傓偐偟撉傫偩偙偲偑偁傞偗偳丄嶁杮棿攏偲挿嶈偲偺偐偐傢傝崌偄偭偰丄偦傫側偵怺偄傕偺偩偭偨偭偗丅傑偁丄偄偢傟偵偣傛丄偦傟偱挿嶈偑宱嵪揑偵弫偆偺側傜丄偗偭偙偆側偙偲偩丅
2010.07.25 (擔) 憡杘奅墭愼曬摴偺塭偱偺偝偽傞嫄埆
偦傟偵偟偰傕丄搎攷偼丄搎攷偵嶲壛偟偨幰傛傝傕搎攷傪奐挔偟偨幰偺傎偆偑嵾偼廳偄偼偢側偺偵丄嶲壛幰偽偐傝偑庢傝嵐懣偝傟偰偄偰丄奐挔偟偨朶椡抍懁偺傎偆偼偄偭偙偆偵柤慜偑嫇偑偭偰偙側偄丅寈嶡偼傑偠傔偵憑嵏偟偰偄傞偺偩傠偆偐丅偳偆傕憑嵏偡傞僨儌儞僗僩儗乕僔儑儞偩偗偵廔巒偟偰偄傞傛偆側婥偑偡傞丅
憡杘奅偲朶椡抍偲偺偮側偑傝偵娭偡傞僯儏乕僗偑屻傪愨偨側偄丅傕偭偲捛媮偡傋偒僱僞偼偨偔偝傫偁傞偼偢側偺偵丄偙傫側丄偳偆偱傕偄偄傛偆側戣嵽傪怴暦偺戞1柺偱嵦傝忋偘傞傎偳丄儊僨傿傾偼悐庛偟偰偄傞偺偐丅儅僗僐儈偼偄偐偵傕惓媊攈柺傪偟偰丄憡杘奅偺崟偄岎嵺傪彂偒偨偰傞偑丄朶椡抍偲偺娭楢偱尵偊偽丄傕偭偲埆鐓側桙拝偑偄偔偮傕偁傞偺偵丄斵傜偼偄偭偙偆偵朶偙偆偲偟側偄丅偨偲偊偽慜偵偙偺僐儔儉偱傕嵦傝忋偘偨憂壙妛夛偲朶椡抍偲偺寢傃偮偒側偳偼丄傕偭偲埆幙偩偟廳戝側栤戣偩丅偲偙傠偑儅僗僐儈偼偦傫側嫄埆傪柍帇偟偰丄庛偄傕偺扏偒偺傛偆偵憡杘奅偽偐傝傪榖戣偵偡傞丅
偦傕偦傕憡杘奅偼丄寍擻奅偲摨偠偔丄愄偐傜儎僋僓傗朶椡抍偲偺偮側偑傝偑怺偐偭偨丅憡杘偼僗億乕僣偱偼側偄丅寍擻傗壧晳婈偲摨偠偔丄擔杮屆棃偺揱摑揑側尒悽暔丄嫽峴側偺偩丅偩偐傜憡杘偲儎僋僓偲偺偮側偑傝偼丄偦偟偰屆偄偟偒偨傝偺懚懕偼丄偁傞堄枴偱摉慠偩丅傕偟憡杘奅偑乬忩壔乭偝傟丄僗億乕僣偵側偭偨傜丄憡杘偼憡杘偱偼側偔側偭偰偟傑偆丅
憡杘奅偺栰媴搎攷偵娭楢偟偰丄搎偗僑儖僼傗搎偗儅乕僕儍儞偲偄偭偨峴堊傑偱旕擄偺懳徾偵側偭偨偑丄偙傫側偙偲偼扤傕偑擔忢揑偵傗偭偰偄傞丅偦傕偦傕搎攷偼崙偺撈愯帠嬈偱偁傝丄岞塩僊儍儞僽儖偼惌帯壠傗姱椈偺棙尃偺壏彴偵側偭偰偒偨丅曮偔偠傗嫞椫傗嫞攏側偳偵娭楢偟偰懡悢偺揤壓傝朄恖偑嶌傜傟偰偄傞偺偼廃抦偺帠幚丅偦偙偵偼塃梼傗朶椡抍傕娭梌偟偰偄傞偲塡偝傟偰偄傞丅僷僠儞僐嬈奅偲寈嶡偺桙拝傕栚偵梋傞丅僷僠儞僐偱偼丄杮棃堘朄偱偁傞姺嬥偑丄宨昳岎姺強偱偺尰嬥壔偲偄偆偐偨偪偱峴側傢傟偰偄傞丅帠幚忋偺搎攷峴堊偱偁傝丄堘朄側偺偵寈嶡丒専嶡偼偦傟傪梕擣偟偰偄傞偺偩丅偦偟偰僷僠儞僐娭楢抍懱偼寈嶡挕偺嵞廇怑偺庴偗嶮偵側偭偰偄傞丅偡傋偰偑側傟崌偄側偺偩丅
岞塩搎攷偵偨偐傝丄娒偄廯傪媧偭偰偄傞惌帯壠傗姱椈傪扞忋偘偵偟丄憡杘奅偺搎攷偽偐傝傪曬摴偡傞丅嫄埆傪曻抲偟丄嵾傪庛幰偵偐傇偣丄嫮幰偵偡傝婑傞丅儊僨傿傾偼偄偮偐傜偦傫側尃椡偺憱嬬偵側偭偨偺偩丅
2010.07.19 (寧) 崿柪偡傞惌帯偵懪奐偺庤棫偰偼偁傞偺偐
嶲堾慖偱偺柉庡搣攕杒偺尨場偼丄悰庱憡偑徚旓惻憹惻傪懪偪弌偟偨偨傔偩偲偄偆偺偑堦斒揑側尒曽偩偑丄偦傟偩偗偱偼側偄偩傠偆丅偙偆側偭偨偺偼丄柉庡搣惌尃偵側偭偰夵妚傪婜懸偟偰偄偨偺偵丄偄偭偙偆偵偦傫側摦偒偑尒傜傟側偄偳偙傠偐丄傓偟傠屻戅偟偰偄傞偲偄偆尰忬偵懳偡傞崙柉偺偄傜偩偪偑嵟戝偺梫場偩傠偆丅夵妚側偳偡偖偵偼偱偒側偄偙偲側偳暘偐偭偰偄傞丅偩偑柉庡搣偼夵妚偺偨傔偺摴嬝傪傑偭偨偔帵偝偢丄帠嬈巇暘偗偲偄偭偨彫庤愭偺嶌嬈偵廔巒偟偰偒偨丅崙柉偺懡偔偑婜懸偟偰偄偨扙姱椈丒岞柋堳惂搙夵妚側偳丄庤傪偮偗傞偳偙傠偐丄姱椈偺尵偄側傝偺傑傑丄揤壓傝傪梕擣偡傞崙壠岞柋堳戅怑娗棟婎杮曽恓傪悇偟恑傔傛偆偲偡傞側偳丄傑偭偨偔媡峴偟偰偒偨丅
岞柋堳惂搙夵妚偩偗偟偐慽偊偰偄側偐偭偨傒傫側偺搣偼丄崱夞偺嶲堾慖偱戝偒偔昜傪怢偽偟偨丅偙偙偵崙柉偺堄巙偑擛幚偵斀塮偟偰偄傞丅偱傕丄偩偐傜偲偄偭偰傒傫側偺搣偑惌尃傪戸偡偵懌傞搣偐偲偄偆偲丄偼側偼偩怱傕偲側偄丅堦帪揑偵恖婥傪廤傔傞偩偗偺搣偵偡偓側偄傛偆偵巚偆丅榑恮傪挘傟傞偺偼搉曈婌旤偲峕揷寷巌偟偐偄側偄偟丄偳偆傕搉曈偲偄偆戙昞偼層嶶廘偄姶偠偑偡傞丅
嶲堾慖偱晧偗偰丄偙傟偐傜柉庡搣偼晄埨掕側惌帯塣塩傪嫮偄傜傟傞偙偲偵側傞丅儊僨傿傾偱偼惌奅嵞曇偲偄偆尵梩偑旘傃岎偭偰偄傞丅嵟埆偺僔僫儕僆偩偑丄柉庡搣偑帺柉搣偲庤傪慻傓偙偲傕偁傝偆傞偩傠偆丅側偵偟傠丄徚旓惻栤戣傪偼偠傔偲偟偰丄偄傑偺柉庡搣偺惌嶔偼帺柉搣偲偁傑傝堘傢側偄偺偩偐傜丅偦傟偱傕柉庡搣偼夵妚傪恑傔偞傞傪摼側偄丅崙柉偑偦傟傪媮傔偰偄傞偟丄嶲堾慖偺摼昜憤悢1埵偲偄偆寢壥偐傜偟偰丄傑偩崙柉偼偐傠偆偠偰柉庡搣偵朷傒傪戸偟偰偄傞偺偩偐傜丅
傕偆傂偲偮丄儊僨傿傾偱榖戣偵側偭偰偄傞偺偼丄彫戲堦榊偺摦岦偲柉庡搣撪偺尃椡憟偄偩丅偙偺崿撟偲偟偨惌帯忬嫷傪丄傕偟懪奐偱偒傞惌帯壠偑偄傞偲偟偨傜丄彫戲堦榊偐傕偟傟側偄丅彫戲堦榊偼偄傑傗埆恖偲偄偆報徾偑掕拝偟偰偟傑偭偰偄傞偑丄柉庡搣撪偱偼偄傑傕攋奿偺僷儚乕傪傕偭偰偄傞丅侾儠寧傎偳慜偺挬擔怴暦偵丄埨曐摤憟50擭偺摿廤偱昡榑壠偺媑杮棽柧傊偺僀儞僞價儏乕偑嵹偭偰偄偨丅偦偺側偐偱媑杮偼丄偄傑偺惌帯忬嫷偵怗傟丄師偺傛偆偵岅偭偰偄偨丅
擔杮偼偙偺偲偙傠悐戅偺堦搑傪偨偳偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅惌帯傕偳傫偳傫埆偔側偭偰偄傞丅幚峴椡丄岎徛椡偑昁梫偱偡丅僇僱偺栤戣偱斸敾偝傟偨偗偳丄彫戲堦榊偝傫偑100恖傪挻偡崙夛媍堳傪堷偒楢傟偰拞崙傊峴偭偨丅偁傟偩偗偱偡傛丄柉庡搣惌尃偑傾儊儕僇偵徴寕傪梌偊偨偺偼丅偝偡偑偼媑杮棽柧丄塻偄巜揈偩丅榁偄偨傝偲偼偄偊丄忬嫷傪尒傞栚偼撥偭偰偄側偄丅傾儊儕僇偑晐偄偺偼彫戲堦榊側偺偩丅彫戲堦榊偑丄徚旓惻憹惻斀懳丄傾儊儕僇偐傜偺帺棫丄壂撽婎抧揚攑傪彞偊偰棫偪忋偑傟偽丄戝偒側巟帩傪摼傜傟傞壜擻惈偑偁傞丅専嶡怰嵏夛偺媍寛偲偐丄懁嬤偺婄傇傟偑埆偡偓傞偲偐丄偄傠傫側栤戣傪書偊偰偄傞偑丄彫戲堦榊偵偼偦傟傪傗傞椡偑偁傞丅彫戲偵偲偭偰丄傕偆堦搙昞晳戜偵曉傝嶇偔嵟屻偺僠儍儞僗偼丄偙傟偟偐側偄丅偁偲偼杮恖偑偦偺婥偵側傞偐偳偆偐偩丅
2010.06.29 (壩) 揤栘捈恖挊亀偝傜偽擔暷摨柨亁偑巜偟帵偡擔杮偺偲傞傋偒摴
 崱擭偼夵掕擔暷埨曐忦栺偑惉棫偟偰偐傜敿悽婭偵側傞丅埨曐懱惂50擭偲偄偆愡栚偺擭偵偁偨傝丄杮棃側傜埨曐忦栺懚懕偺惀旕偵娭偡傞榑媍偑妶敪偵側偭偰摉慠側偺偵丄偁傑傝偦傫側惙傝忋偑傝偼姶偠傜傟側偄丅偦傫側側偐丄傾儊儕僇偲丄偦偟偰悽奅偲偺偐偐傢傝偵偍偗傞擔杮偺棫応傪専徹偟丄擔暷娭學偼偳偆偁傞傋偒偐丄擔杮偼偼偳傫側曽岦傪栚巜偝側偗傟偽偄偗側偄偐傪帵嵈偡傞丄廳梫側杮偑弌斉偝傟偨丅揤栘捈恖偲偄偆恖偑彂偒壓傠偟偨亀偝傜偽擔暷摨柨亁乮島択幮乯偩丅
崱擭偼夵掕擔暷埨曐忦栺偑惉棫偟偰偐傜敿悽婭偵側傞丅埨曐懱惂50擭偲偄偆愡栚偺擭偵偁偨傝丄杮棃側傜埨曐忦栺懚懕偺惀旕偵娭偡傞榑媍偑妶敪偵側偭偰摉慠側偺偵丄偁傑傝偦傫側惙傝忋偑傝偼姶偠傜傟側偄丅偦傫側側偐丄傾儊儕僇偲丄偦偟偰悽奅偲偺偐偐傢傝偵偍偗傞擔杮偺棫応傪専徹偟丄擔暷娭學偼偳偆偁傞傋偒偐丄擔杮偼偼偳傫側曽岦傪栚巜偝側偗傟偽偄偗側偄偐傪帵嵈偡傞丄廳梫側杮偑弌斉偝傟偨丅揤栘捈恖偲偄偆恖偑彂偒壓傠偟偨亀偝傜偽擔暷摨柨亁乮島択幮乯偩丅偙傟偼擔杮崙柉昁撉偺彂偩丅揤栘巵偼尦奜岎姱偱偁傝丄2001擭丄挀儗僶僲儞摿柦慡尃戝巊偺偲偒丄傾儊儕僇偺僀儔僋峌寕傪巟帩偡傋偒偱偼側偄偲丄摉帪偺彫愹庱憡偲愳岥奜憡偵恑尵偟偰丄奜柋徣傪旊柶偝傟偨丅偦偺屻偼奜岎栤戣傪拞怱偵昡榑丒幏昅妶摦傪懕偗偰偄傞丅偙偺杮偱揤栘巵偼丄傾儊儕僇偲孯帠摨柨傪懕偗傞偙偲偺婋尟惈傪愢偒丄埨曐忦栺傪夝徚偟偰懳暷廬懏偐傜扙媝偟丄搶傾僕傾傪拞怱偲偟偨廤抍埨慡曐忈懱惂傪栚巜偡傋偒偩偲庡挘偡傞丅
乽晛揤娫婎抧堏愝栤戣偑偨偲偊偳偺傛偆側偐偨偪偱寛拝偟偨偲偟偰傕丄擔暷摨柨娭學偑懚懕偡傞偐偓傝丄擔杮偼暷崙偐傜墴偟偮偗傜傟傞孯帠梫媮埑椡偵擸傑偝傟懕偗傞偙偲偵側傞丅暷崙偺孯帠嫤椡梫惪偼丄庤傪懼偊丄昳傪懼偊偰丄師乆撍偒偮偗傜傟偰偔傞丅偦偟偰擔杮偼偦偺偮偳丄偦偺懳墳偵嬯偟傔傜傟傞偙偲偵側傞乿偙偆偟偰揤栘巵偼丄寷朄9忦傪寴帩偟丄乬偄偐側傞崙偺嫼埿偵傕側傜側偄丄偄偐側傞崙偵傕峌寕傪偝偣側偄乭偲偄偆暯榓奜岎傪愰尵偟丄愱庣杊塹偵揙偡傞帺棫偟偨帺塹戉傪傕偪偮偮丄搶傾僕傾廤抍埨慡曐忈懱惂傪峔抸偣傛偲榑偠傞丅
乽擔杮偺埨慡曐忈偲偼壗偺娭學傕側偄暷崙偺愴偄偵崙柉傪姫偒崬傒丄擔杮傪庣傞偼偢偺帺塹戉堳偺柦傪婋尟偵偝傜偡丄偦傫側擔暷娭學傪堐帩丄敪揥偝偣偰偄偔偙偲側偳丄擔杮偺偨傔偵側傞偼偢偑側偄丅
乽偦傕偦傕擇崙娫偺孯帠摨柨偱埨慡曐忈傪庣傞偲偄偆峫偊曽偑屆偄偺偩丅偙傟偐傜偺埨慡曐忈惌嶔偼丄奆偑偍屳偄傪揋帇偟側偄偙偲丄偦偟偰偦偺栺懇傪攋傞傕偺傪奆偱娔帇偟丄婯惂偟偰偄偔丄偦偆偄偆峫偊曽偵婎偯偄偨傕偺偱側偔偰偼側傜側偄乿
寷朄9忦傪崅偔宖偘偰懳暷廬懏忬嫷偐傜帺棫偣傛偲愢偔揤栘巵偺榑巪偼柧夣偱偁傝丄戝偒側愢摼椡偑偁傞丅埨曐忦栺偼椻愴偺廔寢偲偲傕偵栶妱傪廔偊偨偼偢側偺偵丄傾儊儕僇偺愴憟偵擔杮傪壛扴偝偣傞偨傔偺摨柨偲側偭偰偦偺傑傑懚懕偟偰偄傞丅偦偟偰帯奜朄尃偺暷孯婎抧偼壂撽傪拞怱偵慡崙偵嶶傜偽偭偨傑傑偩丅偮傑傝擔杮偼帠幚忋偺傾儊儕僇偵傛傞愯椞忬懺偑懕偄偰偄傞偺偩丅
擔暷摨柨梚岇攈偼丄埨曐忦栺偵傛偭偰揋崙偵懳偡傞梷巭椡偑曐偨傟偰偄傞偲偟偽偟偽庡挘偡傞丅偩偑丄偦傕偦傕埨曐忦栺偵傛偭偰丄偦偟偰擔杮偵暷孯婎抧偑偁傞偙偲偵傛偭偰丄傾儊儕僇偼傎傫偲偆偵桳帠偺嵺丄擔杮傪庣偭偰偔傟傞偺偩傠偆偐丅埨曐忦栺偺忦暥偼丄偦傟偵娭偟偰偒傢傔偰濨枂偱偁傝丄夝庍偵傛偭偰偳偆偵偱傕庴偗庢傟傞丅揤栘巵偼彂偔丅
乽偨偲偊忦栺偱偦偺媊柋偑柧暥壔偝傟偰偄傛偆偲丄偄偔傜暷崙崅姱偑擔杮傪庣傞偲孞傝曉偟偰傒偰傕丄寛抐偡傞偺偼偦偺帪偺戝摑椞偩丅暷崙偺戝摑椞偑帺崙偺庒幰偨偪傪擔杮偺偨傔偵媇惖偵偡傞偐偳偆偐偺敾抐偼丄寢嬊丄暷崙崙柉偺巟帩傪摼傜傟傞偐偳偆偐偱寛傔傜傟傞丅偦偟偰暷崙偲偄偆崙傪懡彮側傝偲傕抦偭偰偄傞幰偱偁傟偽丄暷崙偼擔杮傪庣傞偨傔偵帺崙柉偺寣傪棳偡偙偲偼寛偟偰偟側偄崙偱偁傞偙偲傪抦偭偰偄傞乿埨曐忦栺偼丄梷巭椡偵側偭偰偄傞偳偙傠偐丄傾儊儕僇偺愴憟偵壛扴偡傞偙偲偵傛傝丄媡偵擔杮偑僥儘偲偺愴偄偵姫偒崬傑傟傞婋尟傪惗傫偱偄傞偺偩丅偦偟偰擔暷摨柨偑偁傞偐偓傝丄擔杮偼帺慜偺崙杊惌嶔傪棫偰傞偙偲偑偱偒側偄丅崙杊惌嶔偼偮偹偵傾儊儕僇偵傛偭偰寛傔傜傟傞偟丄帺塹戉偼偄偮傑偱傕傾儊儕僇偺壓惪偗偺傑傑偩丅
埨曐懱惂巀惉榑幰丄偨偲偊偽奜柋徣OB偺壀杮峴晇側偳偼丄擔杮偑偁傑傝帺棫偡傞偲尵偄偩偡偲傾儊儕僇偑搟偭偰尒幪偰偰偟傑偆偧丄偲丄傾儊儕僇偺庤愭偺傛偆側嫼偟尵梩傪揻偔丅偩偑傾儊儕僇偑帺暘偐傜擔暷摨柨傪夝徚偟丄婎抧傪堷偒梘偘傞偙偲側偳偁傝偊側偄丅傾儊儕僇偵偲偭偰擔杮偼偄偮傑偱傕庤曻偟偨偔側偄丄偍偄偟偄崙側偺偩丅
擔杮崙柉偑嫮偄傜傟傞戝偒側媇惖偲晧扴偼孯帠揑懁柺偩偗偵偲偳傑傜側偄丅擭師夵妚梫朷彂偲偄偆偐偨偪偱丄傾儊儕僇偼擔杮偵偝傑偞傑側惂搙傗巤嶔偵娭偟偰梫朷傪撍偒晅偗偰偄傞丅僛儘嬥棙丄嬥梈帺桼壔丄楯摥幰攈尛朄偺夵惓丄偦偟偰偁偺梄惌柉塩壔側偳偼丄傒側傾儊儕僇偺梫朷偵増偭偨偐偨偪偱幚尰偟偨傕偺偩丅擔杮偼傾儊儕僇偺梫媮傪嫅斲偱偒側偄丂帠幚丄忋婰偺傛偆側傾儊儕僇偺崙塿偵増偭偨惌嶔偑巤峴偝傟偨寢壥丄擔杮偺幮夛偼崿棎偵娮偭偰偄傞丅揤栘巵偼妳攋偡傞丅
乽堦壄憤拞棳壔偲尵傢傟丄奆偑偦傟側傝偺惗妶傪憲偭偰偄偨擔杮偑丄側偤偙偙傑偱奿嵎幮夛偵暘抐偝傟丄擔乆偺惗妶偵嬯偟傓傛偆偵側偭偨偺偐丅傕偪傠傫丄偄傠偄傠側棟桼偑偁偘傜傟傞偩傠偆丅偟偐偟巹偼丄偦偺戝偒側棟桼偑暷崙偲偺榗傫偩娭學偵偁傞偲巚偆丅暷崙偲偺娭學傪惓偟偄娭學偵偱偒側偐偭偨擔杮偺巜摫幰偲丄偦傟傪嫋偟偰偒偨巹偨偪崙柉偺偁偒傜傔偵偙偦丄偦偺尨場偑偁傞偲巚偆乿柉庡搣惌尃偵側偭偰丄擔暷娭學偼尒捈偝傟傞偳偙傠偐丄偄偭偦偆嫮偔懳暷廬懏偵孹幬偟偰偄偭偰偄傞姶偑偁傞丅儊僨傿傾傕惌帯壠傕丄扤傕偦傟偵懳偟偰堎媍傪彞偊傛偆偲偟側偄丅偦傟偱傕丄儊僨傿傾偑僟儊偱傕丄偦偟偰惌帯壠偑僟儊偱傕丄崙柉偑擔暷摨柨偺媆嵩惈偵婥偯偒丄帺棫偡傋偒偩偲傕惡傪忋偘傟偽丄棳傟偼曄傢傞丅偙偺敆椡偵枮偪偨杮偼丄偦偺偨傔偺婲敋嵻偵側傞偐傕偟傟側偄丅
2010.06.21 (寧) 崙柉傪棤愗傞悰怴庱憡偺業崪側尰幚楬慄
偟偐偟丄廇擟埲棃偺悰怴庱憡偺尵摦傪尒傞偲丄偁傑傝偵業崪側尰幚庡媊楬慄偵丄偙傟偼嵟掅偺撪妕偐傕偟傟側偄偲偄偆巚偄偑偙傒忋偘偰偔傞丅庱憡偵側傞傗偄側傗丄斵偼懳暷廬懏惌嶔傪偁偐傜偝傑偵懪偪弌偟丄徚旓惻憹惻傪崅傜偐偵彞偊丄偦傟傑偱戝攏幁偩偲尵偭偰偄偨姱椈傪僾儘僼僃僔儑僫儖偩偲帩偪忋偘偨丅偙傟偱偼帺柉搣惌尃偲曄傢傜側偄偳偙傠偐丄巗柉攈偲偄偆壖柺傪偐傇偭偰偄傞偩偗偵丄傛傝偨偪偑埆偄丅栰搣帪戙偵偼夵妚傪嫨傫偱偄側偑傜丄尃椡傪埇偭偨偲偨傫丄慜尵傪傂傞偑偊偟偰偼偽偐傜側偄丅傕偲傕偲悰捈恖偲偄偆恖娫偺側偐偵偁偭偨尃椡巙岦揑側懁柺偑堦嫇偵暚偒弌偟偨姶偑偁傞丅
偁傞堄枴偱丄慜庱憡偺數嶳偲悰偺峫偊曽偼惓斀懳偩偲尵偊傞偐傕偟傟側偄丅棟憐庡媊偺數嶳偲尰幚庡媊偺悰偩丅數嶳偼廬棃偺擔暷娭學偐傜偺扙媝傪栚巜偟偰偄偨丅傾儊儕僇偲偺娭學偺尒捈偟傪偼偐傝丄傾僕傾偲偺嫤挷傪廳帇偟偰搶傾僕傾嫟摨懱偺憂愝傪採埬偟偨丅偙傟偼婎杮揑偵偼惓偟偄曽岦偩偭偨偲巚偆丅偟偐偟斶偟偄偙偲偵丄斵偵偼怣擮偲幚峴椡偑側偐偭偨丅姱椈偵娵傔崬傑傟丄傾儊儕僇偺搟傝傪抦傞偵媦傫偱崢嵱偗偵側傝丄廬棃偺傑傑偺懳暷廬懏楬慄偵孹偄偰偄偭偨丅偦偟偰屻傪宲偄偩悰偼偡傋偰偺愑擟傪數嶳惌尃偵墴偟晅偗丄嵟弶偐傜懳暷廬懏偺摴傪傂偨憱偭偰偄傞丅擔杮偵偲偭偰扱偐傢偟偄偺偼丄棟憐庡媊偺數嶳偵儕乕僟乕僔僢僾偑側偔丄尰幚庡媊偺悰偵儕乕僟乕僔僢僾偑偁傞偙偲偩丅偄傑傗儊僨傿傾傕惌帯壠傕丄懳暷廬懏惌嶔偵扤傕堎媍傪彞偊傛偆偲偟側偄丅
徚旓惻栤戣傕偦偆偩丅數嶳偼乽4擭娫偼憹惻偟側偄乿偲尵偭偰徚旓惻栤戣傪晻報偟偨偑丄悰偼庱憡偵側偭偨偲偨傫丄尰幚楬慄偵戝偒偔懬傪愗傝丄徚旓惻憹惻偺昁梫傪嫮挷偟偨丅尰忬偺崙偺嵿惌傪尒傞偐偓傝丄抶偐傟憗偐傟憹惻偼旔偗傜傟側偄偩傠偆丅偱傕丄偦偺慜偵傗傞偙偲偑偁傞偼偢偩丅偙傟傑偱偺帺柉搣惌尃偱朿傟忋偑偭偨惻嬥偺柍懯尛偄傪揙掙揑偵嶍尭偟側偗傟偽丄憹惻側偳傗偭偰偼側傜側偄丅帠嬈巇暘偗側偳偵傛傞昞柺揑側傗傝曽偱偼偩傔偩丅岞柋堳惂搙偺夵妚丄揤壓傝傗柍懯側峴惌婡娭偺堦憒丄媍堳掕悢偺嶍尭乮媍寛搳昜傪偡傞偩偗偺儃儞僋儔媍堳偑懡偡偓傞丅偄傑偺恖悢偺敿暘偱廩暘偩乯側偳偺敳杮揑側栤戣偵偼丄傑偩傑偭偨偔拝庤偝傟偰偄側偄丅憹惻傪愢偔悰庱憡偺夛尒偵偼丄偦偺曈傊偺尵媦偑傑偭偨偔側偐偭偨丅撪妕巟帩棪偑敪懌摉弶偐傜10僷乕僙儞僩傕妱偭偨偙偲偑敾柧偟偨崱擔丄斵偼偁傢偰偰儉僟偺嶍尭偵庢傝慻傓偲岅偭偨傛偆偩偑丄抶偒偵幐偡傞丅
棟憐偵岦偐偭偰撍偒恑傓偵偼崲擄偑敽偆丅尰幚偵埨廧偡傞傎偆偑傗傝堈偄偺偼摉偨傝慜偩丅偱傕崙柉偼夵妚偺棟憐偵婜懸偟偰柉庡搣偵搳昜偟偨偺偱偼側偐偭偨偐丅棟憐傪宖偘丄側偍偐偮怣擮偲幚峴椡傪傕偭偨惌帯壠偑丄側偤偄傑偺擔杮偵尰傟側偄偺偩傠偆丅
2010.06.12 (搚) 儐僟儎偲僀僗儔儉偺懳棫偵傎偺尒偊傞丄偐偡偐側婓朷
 乬僒儔僄儃丒僴僈僟乕乭偲偄偆抣傕偮偗傜傟側偄傛偆側婬彮側屆彂偑偁傞丅僿僽儔僀岅偱彂偐傟偨儐僟儎嫵偺幨杮偱偁傝丄嵶枾夋偵傛傞旤偟偄憓奊偑昤偐傟偰偄傞丅500擭傎偳慜偵僗儁僀儞偱嶌傜傟偨傕偺偩丅愭偛傠撉傫偩僕僃儔儖僨傿儞丒僽儖僢僋僗挊亀屆彂偺棃楌亁乮儔儞僟儉僴僂僗島択幮2010擭姧乯偼丄偙偺彂暔偑楌巎偺攇偵傕傑傟側偑傜丄偳偺傛偆偵惗偒巆偭偨偐傪昤偄偨楌巎儈僗僥儕乕彫愢偩丅庡恖岞偼屆彂娪掕壠偺庒偄彈惈丅峴曽晄柧偵側偭偰偄偨乬僒儔僄儃丒僴僈僟乕乭偑敪尒偝傟丄曐懚廋暅傪埶棅偝傟偨庡恖岞偼丄杮偵晅拝偟偰偄偨偄偔偮偐偺庤偑偐傝傪傕偲偵丄僀儅僕僱乕僔儑儞傪摥偐偣偰偙偺屆彂偺棃楌傪悇棟偡傞丅
乬僒儔僄儃丒僴僈僟乕乭偲偄偆抣傕偮偗傜傟側偄傛偆側婬彮側屆彂偑偁傞丅僿僽儔僀岅偱彂偐傟偨儐僟儎嫵偺幨杮偱偁傝丄嵶枾夋偵傛傞旤偟偄憓奊偑昤偐傟偰偄傞丅500擭傎偳慜偵僗儁僀儞偱嶌傜傟偨傕偺偩丅愭偛傠撉傫偩僕僃儔儖僨傿儞丒僽儖僢僋僗挊亀屆彂偺棃楌亁乮儔儞僟儉僴僂僗島択幮2010擭姧乯偼丄偙偺彂暔偑楌巎偺攇偵傕傑傟側偑傜丄偳偺傛偆偵惗偒巆偭偨偐傪昤偄偨楌巎儈僗僥儕乕彫愢偩丅庡恖岞偼屆彂娪掕壠偺庒偄彈惈丅峴曽晄柧偵側偭偰偄偨乬僒儔僄儃丒僴僈僟乕乭偑敪尒偝傟丄曐懚廋暅傪埶棅偝傟偨庡恖岞偼丄杮偵晅拝偟偰偄偨偄偔偮偐偺庤偑偐傝傪傕偲偵丄僀儅僕僱乕僔儑儞傪摥偐偣偰偙偺屆彂偺棃楌傪悇棟偡傞丅 杮彂偱偼丄庡恖岞偑偙偺僒儔僄儃丒僴僈僟乕傪挷嵏偡傞尰戙偺榖偲丄偦偺杮偑偝傑偞傑側恖乆偺庤偵傢偨傝丄懡偔偺忈奞傪忔傝墇偊偰惗偒墑傃傞偝傑傪昤偔楌巎忋偺夁嫀偺榖偲偑丄岎屳偵岅傜傟傞丅1941擭丄僫僠僗偵傛偭偰丄懠偺儐僟儎娭楢偺彂暔偲偲傕偵暟彂偵偝傟傛偆偲偟偰偄偨僒儔僄儃丒僴僈僟乕傪媬偭偨偺偼丄僀僗儔儉偺妛幰偩偭偨丅偦偟偰1990擭戙弶摢丄儃僗僯傾暣憟偺偝偄丄僙儖價傾孯偺敋寕偱攋夡偝傟偮偮偁偭偨僒儔僄儃偺崙棫攷暔娰偐傜偙偺杮傪媬偭偨偺偼丄傑偨傕傗僀僗儔儉嫵搆偺攷暔娰妛寍堳偩偭偨丅
杮彂偱偼丄庡恖岞偑偙偺僒儔僄儃丒僴僈僟乕傪挷嵏偡傞尰戙偺榖偲丄偦偺杮偑偝傑偞傑側恖乆偺庤偵傢偨傝丄懡偔偺忈奞傪忔傝墇偊偰惗偒墑傃傞偝傑傪昤偔楌巎忋偺夁嫀偺榖偲偑丄岎屳偵岅傜傟傞丅1941擭丄僫僠僗偵傛偭偰丄懠偺儐僟儎娭楢偺彂暔偲偲傕偵暟彂偵偝傟傛偆偲偟偰偄偨僒儔僄儃丒僴僈僟乕傪媬偭偨偺偼丄僀僗儔儉偺妛幰偩偭偨丅偦偟偰1990擭戙弶摢丄儃僗僯傾暣憟偺偝偄丄僙儖價傾孯偺敋寕偱攋夡偝傟偮偮偁偭偨僒儔僄儃偺崙棫攷暔娰偐傜偙偺杮傪媬偭偨偺偼丄傑偨傕傗僀僗儔儉嫵搆偺攷暔娰妛寍堳偩偭偨丅杮彂偼僼傿僋僔儑儞偩偑丄偙偙偱岅傜傟傞乬僒儔僄儃丒僴僈僟乕乭偼幚嵼偺彂偱偁傝丄傑偨偙偺儐僟儎偺屆彂傪2搙偵傢偨偭偰攋夡偐傜媬偭偨偺偑僀僗儔儉嫵怣幰偱偁偭偨偙偲傕楌巎忋偺帠幚偱偁傞丅傏偔偑嫽枴傪偦偦傜傟偨偺偼丄儐僟儎恖偲斀栚偟偰偄傞偼偢偺僀僗儔儉嫵搆偑儐僟儎偺彂傪媬偭偨偲偄偆宱堒偩偭偨丅
偙偺杮傪撉傫偱傏偔偼丄4寧20擔晅偺挬擔怴暦偵嵹偭偨丄偁傞儐僟儎恖偑彂偄偨婑峞暥傪巚偄婲偙偟偨丅儌儞僩儕僆乕儖戝妛偺楌巎妛嫵庼儎僐僽丒儔僽僉儞偲偄偆恖偑婑峞偟偨榑暥偩丅儔僽僉儞嫵庼偼丄乽僔僆僯僘儉乮僀僗儔僄儖偺抧偵慶崙傪寶愝偟傛偆偲偄偆惌帯揑僀僨僆儘僊乕乯偼杮棃偺儐僟儎嫵偲憡斀偡傞峫偊曽偩丅儐僟儎嫵搆偼傎偐偺柉懓傪梷埑偟偰偼偄偗側偄丅僷儗僗僠僫恖傪惇暈丄梷埑偡傞偙偲偵傛偭偰幚尰偟偨僀僗儔僄儖偲偄偆崙偼丄杮棃寶愝偝傟傞傋偒偱偼側偐偭偨乿偲庡挘偟偰偄傞丅
丂乽僀僗儔僄儖偼丄寶崙60擭埲忋偨偭偨偄傑傕帺崙傪儂儘僐乕僗僩偐傜儐僟儎恖傪媶嬌揑偵庣傞懚嵼偲埵抲偯偗傞丅偩偐傜偙偦丄悽奅拞偺儐僟儎恖僐儈儏僯僥傿乕偵丄儐僟儎恖偑桞堦埨慡偵曢傜偣傞偺偼僀僗儔僄儖偟偐側偄偲偄偆嫲晐姶傪怉偊晅偗傛偆偲偟偰偄傞丅幚嵺偵偼摨崙偼儐僟儎恖偵偲偭偰嵟傕婋尟側応強偵側偭偰偄傞乿傏偔偨偪偼儐僟儎恖偲偄偆偲丄傑偭偝偒偵丄僷儗僗僠僫恖傪梷埑偟丄帺崙偺尃塿奼戝偟偐娽拞偵側偄岲愴揑側楢拞偲偄偆僀儊乕僕偑巚偄晜偐傇丅偩偑丄偙偺婑峞暥傪撉傫偱丄儐僟儎恖偲偄偭偰傕偝傑偞傑偱偁傝丄偙偺傛偆偵恀偭摉側峫偊曽偺帩偪庡傕偄傞偙偲丄僀僗儔僄儖丒僀僐乕儖丒儐僟儎偱偼側偄偺偩偲偄偆偙偲傪巚偄抦傜偝傟偨丅
丂乽崙嵺朄偵堘斀偡傞柉懓忩壔偵廬帠偟丄僈僓抧嬫偺堦斒巗柉偵搑曽傕側偄廤抍揑側挦敱傪壛偊丄僷儗僗僠僫恖偺恖尃偲崙壠寶愝傊偺妷朷傪嫅傒懕偗傞僀僗儔僄儖偺寶崙婰擮擔傪廽偆偙偲偼偱偒側偄丅変乆偑廽偆偺偼暯榓側拞搶偵偍偄偰傾儔僽丄儐僟儎憃曽偺恖乆偑暯摍偵曢傜偡偲偒偩乿
僀僗儔僄儖偺僷儗僗僠僫偱偺旕摴側峴堊偼廔傢傜側偄丅偮偄5寧枛偵傕丄僈僓巟墖慏抍傪僀僗儔僄儖孯偑峌寕偟漒曔偡傞偲偄偆帠審偑婲偒偰偄傞丅傾儊儕僇偑僀僗儔僄儖傪巟墖偡傞偐偓傝丄僀僗儔僄儖偺朶嫇偼偄偮傑偱傕懕偔偟丄傾儔僽恖偺僥儘偵傛傞曬暅偼孞傝曉偝傟傞丅偟偐偟儐僟儎恖偺側偐偵傕丄儔僽僉儞嫵庼偺傛偆側峫偊曽偺恖偑偄傞偺偩丅僀僗儔僄儖崙撪偵傕僷儗僗僠僫傊偺晲椡峌寕偵斀懳偡傞惡偑偁傞丅僀僗儔僄儖孯偺側偐偵偝偊丄僷儗僗僠僫偱偺嶦滳偵斀懳偟暫栶傪嫅斲偡傞暫巑偑弌偰偒偰偄傞丅栤戣側偺偼丄偦傟傜偑彮悢攈偩偲偄偆偙偲偩丅
偦傟偱傕丄儔僽僉儞嫵庼偺婑峞暥傪撉傓偲丄偦偟偰僀僗儔儉嫵搆偑儐僟儎偺屆彂傪媬偭偨偲偄偆帠幚傪抦傞偲丄僷儗僗僠僫偺榓暯傊偺摴偵偐偡偐側婓朷偺岝偑尒偊偰偔傞巚偄偑偡傞丅
2010.06.02 (悈) 儅僗僐儈偑栙嶦偡傞2偮偺媈榝乗乗偦偺2乽姱朳婡枾旓偺巊搑乿
4寧偺枛丄栰拞巵偼婰幰偨偪傪慜偵姱朳挿姱帪戙偺婡枾旓偺巊搑偵偮偄偰岅偭偨丅姱朳婡枾旓偼撪妕姱朳挿姱偑椞廂彂側偟偵帺桼偵巊偊傞嬥偩丅崱擭搙偺梊嶼偱偼14壄6枩愮墌偲側偭偰偄傞丅栰拞巵偼丄帺柉搣偺梫怑偵偁偭偨媍堳偺傎偐丄栰搣媍堳丄偝傜偵偼昡榑壠傗儅僗僐儈偺尵榑恖偵傑偱嬥傪搉偟偰偄偨偙偲傪朶業偟偨丅
乽惌帯壠偐傜昡榑壠偵側偭偨恖偑丄乬壠傪怴抸偟偨偐傜3愮枩墌丄廽偄傪偔傟乭偲彫熀憤棟偵揹榖偟偰偒偨偙偲傕偁偭偨丅栰搣媍堳偵懡偐偭偨偑丄乬杒挬慛偵峴偔偐傜偁偄偝偮偵峴偒偨偄乭偲偄偆偺傕偁偭偨乿乽慜擟偺姱朳挿姱偐傜偺堷偒宲偓曤偵昡榑壠傜偺柤慜偑婰嵹偝傟乬偙偙偵偼偙傟偩偗帩偭偰偄偗乭偲彂偄偰偁偭偨丅曉偟偰偒偨偺偼僕儍乕僫儕僗僩偺揷尨憤堦楴巵偩偗偩偭偨乿偙傟傑偱抐曅揑偵偼揱傢偭偰偄偨榖偩偑丄姱朳挿姱宱尡幰偐傜偙偺傛偆偵帠幚偲偟偰岅傜傟偨偙偲偺堄枴偼戝偒偄丅
栰拞巵偺敪尵偱嬃偐偝傟偨偺偼丄僕儍乕僫儕僗僩偵嬥偑偽傜傑偐傟偰偄偨偲偄偆偙偲偩丅媍堳偨偪偺杶曢傟偺晅偗撏偗傗奜梀偺镾暿偵変乆偺惻嬥偑巊傢傟偰偄偨偙偲偵傕暊棫偨偟偄偑丄100曕忳偭偰偦傟偼尒摝偡偲偟偰傕丄嫋偣側偄偺偼尃椡傪娔帇偡傞傋偒僕儍乕僫儕僘儉偵嬥偑搉偭偰偄偨偙偲偩丅儊僨傿傾偺恖娫偑惌帯尃椡偐傜嬥慘嫙梌偝傟傞偙偲側偳丄愨懳偵偁偭偰偼偄偗側偄偙偲偩丅偙傟偼尃椡偲儊僨傿傾偲偺媶嬌偺桙拝偺峔恾偩丅嬥慘傗暔昳偺嫙墳偵尩偟偄墷暷偱偙傫側偙偲偑偁傟偽丄徫偄傕偺偵側偭偰偟傑偆丅嬥傪庴偗庢偭偨僕儍乕僫儕僗僩偼懄崗僋價偩偟丄嬈奅偱偼巇帠偱偒側偔側傞丅
栰拞巵偑偄傑偙傫側偙偲傪朶業偟偨堄恾偼偳偙偵偁傞偺偐丅惌帯偺忩壔偺偨傔偵崘敀偟偨側偳偲偄偆偒傟偄偛偲偱偼偁傝偊側偄丅僕儍乕僫儕僗僩偺側偐偱幚柤傪嫇偘偨偺偼丄嬥傪曉偟偨偲偄偆揷尨憤堦榊偩偗偩乮偩偐傜偲偄偭偰揷尨偑柶嵾晞傪摼偨傢偗偱偼側偄丅偨傑偨傑栰拞巵偺偲偒偼庴偗庢傜側偐偭偨偩偗偲偄偆偙偲傕偁傝偆傞乯丅偙偙偵堄恾揑側傕偺傪姶偠傞丅偮傑傝栰拞巵偼丄嬥傪傕傜偭偨僕儍乕僫儕僗僩偺楢拞傪丄壌傪峌寕偟偨傜揷尨偺傛偆偵柤慜傪偽傜偡偧丄偲湗妳偟偰偄傞偺偩丅嬥傪庴偗庢偭偨僕儍乕僫儕僗僩偺柤慜偑柧傜偐偵偝傟傟偽丄昡榑壠偼儊僨傿傾偐傜憡庤偵偝傟側偔側傞偟丄婰幰偩偭偨傜僋價偵側傞丅嬥傪搉偟偨恖娫偺幚柤偼岞昞偝傟傞傋偒偩偑丄栰拞巵偼愨懳偵柧傜偐偵偟側偄偩傠偆丅
偙偺栰拞敪尵偼怴暦側偳偱怽偟栿掱搙偵丄偛偔彫偝偄婰帠偲偟偰嵹偭偰偄偨丅偟偐偟偦偺屻丄儊僨傿傾偺怣梡偵偐偐傢傞廳戝側帠審偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄僥儗價傗怴暦偱偼偄偭偙偆偵屻捛偄婰帠偑側偔丄栙嶦偝傟懕偗偰偄傞丅傢偢偐偵搶嫗怴暦偑捛偄偐偗偰偄傞偩偗偩丅儊僨傿傾偺帺忩憰抲偑摥偄偰偄側偄偺偩丅戝怴暦傗僥儗價偺婰幰偨偪丄偲偔偵曇廤埾堳僋儔僗偺側偐偵丄恎偵妎偊偺偁傞幰偑偄傞偺偱偼側偄偐丄偲姩孞傜傟偰傕偟傚偆偑側偄丅
姱朳婡枾旓偲偄偊偽巚偄弌偡偺偼暯栰姱朳挿姱偺廇擟憗乆偺婰幰夛尒偩丅斵偼姱朳婡枾旓偵偮偄偰婰幰偐傜恥偐傟丄乽偦傫側偺偁傞傫偱偡偐乿偲偲傏偗偨丅偗偭偒傚偔暯栰巵偼婡枾旓偺巊搑傪岞奐偟側偄偙偲偵寛傔丄數嶳庱憡傕偦傟偵摨挷偟偨丅柉庡搣偼栰搣帪戙偵偼摟柧壔傪庡挘偟偰偄偨偺偵丄惌尃傪偲偭偰婡枾旓傪庤偵偟偨傜丄偙偺昢曄傇傝偩丅偙傟偱偼崙柉偵尒曻偝傟傞偺傕柍棟偼側偄丅
偙傟傪彂偄偰偄傞崱擔丄偨傑偨傑數嶳庱憡偺帿擟偲偄偆揹寕僯儏乕僗偑旘傃崬傫偱偒偨丅梋択偩偑丄數嶳惌尃幐攕偺嵟戝偺愴斊偼偙偺暯栰姱朳挿姱偩偲巚偆丅儅僗僐儈楎壔偺梫場偺傂偲偮偼丄媽懺埶慠偨傞婰幰僋儔僽惂搙偵偁傞丅柉庡搣偑惌尃岎戙慜偵栺懇偟偰偄偨婰幰僋儔僽傪夝曻偡傞偲偄偆埬傪偮傇偟偨偺偼暯栰姱朳挿姱偩偭偨丅斵偼傑偨壂撽偺暷孯婎抧堏愝偵娭偟偰丄乽柉堄傪澪庌偟側偗傟偽側傜側偄棟桼偼側偄乿側偳偲敪尵偟偨偙偲傕偁傞丅傑偭偨偔崙柉傪僶僇偵偟偨懺搙偩丅斵偼庱憡傪僒億乕僩偡傞偳偙傠偐丄懌傪堷偭挘偭偰偄偨丅偙傫側岤婄柍抪偱帺柉搣傛傝曐庣揑側懱幙偺攜傪姱朳挿姱偵悩偊偰偍偔偙偲偑丄惌尃傊偺斸敾偺嫮傑傝偵偮側偑傞偙偲偵丄側偤數嶳庱憡偼婥偑晅偐側偐偭偨偺偩傠偆偐丅
岞偺尃椡偑敪尵偟偨撪梕傪偦偺傑傑彂偔偩偗偱偼僕儍乕僫儕僗僩偲偟偰敿恖慜偩丅偦偺敪尵傪嬦枴丒専徹偟丄塀偝傟偨恀幚傪偮偒偲傔傞偙偲偵僕儍乕僫儕僘儉偺杮幙偑偁傞丅斵傜偺柋傔偼尃椡傪娔帇偡傞偙偲側偺偩丅偲偙傠偑偄傑偺擔杮偺儊僨傿傾偼丄婰幰僋儔僽偲偄偆壏彴偱偸偔偸偔偲夁偛偟丄尃椡偵嬥傪傕傜偭偰帞偄側傜偝傟丄尃椡懁偺敪尵傪専徹傕偣偢曬偠傞偩偗偵廔巒偟偰偄傞丅忣偗側偄偙偲偵丄偙傟偑偄傑偺擔杮偺儊僨傿傾偺幚懺側偺偩丅
2010.06.01 (壩) 儅僗僐儈偑栙嶦偡傞2偮偺媈榝乗乗偦偺1乽憂壙妛夛偲屻摗慻乿
5寧壓弡偵敪攧偝傟偨幨恀廡姧帍乽僼儔僀僨乕乿偵丄嶳岥慻宯朶椡抍屻摗慻偲憂壙妛夛偺嬃偔傋偒桙拝傪朶業偡傞婰帠偑嵹偭偨丅偙傟偼尦屻摗慻慻挿偺屻摗拤惌巵偑挊偟偨亀溳傝側偑傜亁乮曮搰幮乯偲偄偆彂愋傪徯夘偡傞婰帠偱偁傞丅傏偔偼偙偺杮偼撉傫偱偄側偄偑丄僼儔僀僨乕偺婰帠偵傛傞偲丅憂壙妛夛偑60擭戙廔傢傝偐傜70擭戙偵偐偗偰丄惷壀導晉巑媨巗偱搚抧傪攦偄嫏偭偰偄偨偲偒丄屻摗慻傪巊偭偰抧尦廧柉偺斀懳塣摦傪晻偠偨宱堒偑彂偐傟偰偄傞傜偟偄丅屻摗慻偼摉帪偺憂壙妛夛偺嶳嶈惓桭屭栤曎岇巑偵埶棅偝傟偰丄抮揷戝嶌柤梍夛挿偺椆夝偺傕偲丄斀懳攈偺抏埑偵偁偨偭偨偲偄偆丅憂壙妛夛偑嫄戝尃塿偵傑偮傢傞僩儔僽儖傪張棟偡傞偨傔偵屻摗慻傪棙梡偟偰僟乕僥傿丒儚乕僋傪偝偣偰偄偨幚懺偺堦抂偑柧傜偐偵偝傟偰偄傞偙偲偵側傞丅
岞柧搣偺巟帩曣懱偱偁傞憂壙妛夛偑丄朶椡抍偲桙拝偟偨娭學傪懕偗偰偄偨偙偲偑朶業偝傟偨偺偩丅偙傟偑帠幚側傜丄朶椡抍姴晹偺摿摍惾偱偺憡杘娤愴偲偄偭偨僯儏乕僗側偳偲偼斾傋傕偺偵側傜側偄丄偼傞偐偵桼乆偟偄栤戣偩丅杮棃側傜崙夛偱廳戝栤戣偲偟偰庢傝忋偘傜傟側偗傟偽側傜側偄丅偲偙傠偑崙夛偱偼偄偭偙偆偵庢傝偞偨偝傟傞婥攝偑側偄丅偦偟偰僥儗價傗怴暦側偳丄戝庤儅僗僐儈偱傕傑偭偨偔栙嶦偝傟偰偍傝丄榖戣偵忋傜側偄丅妶婥傪懷傃偰偄傞偺偼僱僢僩偺悽奅偱偩偗偩丅惌帯傕僕儍乕僫儕僘儉傕傑偲傕偵婡擻偟偰偄側偄偺偩丅
傕偲傕偲憂壙妛夛偼擔楡惓廆偺嵼壠怣搆抍懱側偺偵丄偄偮偺傑偵偐廆嫵抍懱偵側傝丄抮揷戝嶌柤梍夛挿偼傑傞偱恄條偺傛偆偵宧偄曭傜傟丄愨懳尃椡傪傕偮傛偆偵側偭偨丅岞柧搣傪捠偠偰惌帯偺悽奅偵恑弌丄寍擻奅傗儅僗僐儈偐傜丄寈嶡丄嵸敾強偵偄偨傞傑偱丄偁傜備傞暘栰偵怣搆傪憲傝崬傫偱偄傞丅戝庤儊僨傿傾偱偼憂壙妛夛偺榖戣偼僞僽乕偩丅惌帯偺悽奅偱傕丄專嬥栤戣傗栴栰栤戣偱抮揷柤梍夛挿傪崙夛偱徹恖姭栤偟傛偆偲偄偆摦偒偼偁偭偨偑丄幚尰偵偼帄偭偰偄側偄丅偳偆傕丄偙偺徹恖姭栤偲偄偆庤偼岞柧搣傪尅惂偡傞偨傔偺僇乕僪偲偟偰巊傢傟偰偄傞傆偟偑偁傞丅
壗傪怣偠傞偐偼屄恖偺帺桼偩丅傏偔偼柍恄榑幰偩偑丄憂壙妛夛偵擖怣偟偰偄傞偐傜偲偄偭偰偦偺恖暔傪嫒傔傞偮傕傝偼側偄丅偱傕丄怣幰偨偪偑抮揷柤梍夛挿傪傑傞偱嫵慶偺傛偆偵悞傔傞偝傑偼偵堎忢側傕偺傪姶偠傞丅憂壙妛夛僂僅僢僠儍乕偱偼側偄偐傜丄幚懺偼傛偔抦傜側偄偑丄尦岞柧搣埾堳挿偺抾擖媊彑傗栴栰埡栫丄尦屭栤曎岇巑偺嶳嶈惓桭偲偄偭偨偐偮偰偺戝暔姴晹偺懡偔偑丄扙夛屻丄憂壙妛夛斸敾偺媫愭朜偵側偭偰偄傞偙偲丄尵榑朩奞傗棧斀幰傊偺嫼敆偲偄偭偨榖偑愨偊側偄偙偲丄偦偟偰崱夞偺朶椡抍偲偺娭學偺朶業偵娭偡傞儅僗僐儈偺堎條側捑栙傇傝側偳偑丄偙偺抍懱偺埫晹傪暔岅偭偰偄傞傛偆偵巚偆丅
2010.05.25 (壩) 壂撽婎抧栤戣偱曻抲偝傟傞擔暷摨柨偵娭偡傞榑媍
栚偵梋傞偺偼儅僗僐儈偺榑挷偺堄幆偺掅偝偩丅婎抧栤戣偺崻姴偼擔暷摨柨偱偁傝丄偙傟偑懕偔偐偓傝丄擔杮偼傾儊儕僇偺懏崙偺傑傑偩偟婎抧偼側偔側傜側偄丅偲偙傠偑儅僗僐儈偼丄數嶳庱憡偺巟棧柵楐側尵摦傗壂撽導柉偺慾巭偵岦偗偰偺摦偒傗傾儊儕僇偺巚榝偲偄偭偨栚愭偺僯儏乕僗傪捛偄偐偗傞偩偗偱丄娞怱偺埨曐忦栺偼惀偐旕偐偵娭偡傞榑媍偼扞忋偘偝傟偰偄傞丅傑傞偱傾儊儕僇偺堄傪懱偡傞偐偺傛偆偵丄儅僗僐儈偼擔杮偵偲偭偰埨曐忦栺偺懚懕偑摉慠偱偁傞偐偺傛偆側巔惃偵廔巒偟偰偄傞丅
傕偲傕偲椻愴偲偄偆悽奅忬嫷偵懳張偡傞偨傔偺傕偺偩偭偨埨曐忦栺偼丄椻愴偑曵夡偡傞偲丄懚嵼堄媊偼側偔側偭偨丅偩偐傜丄偦偺帪揰偱偲偆偤傫尒捈偟偑側偝傟傞傋偒偩偭偨丅偲偙傠偑尰幚偼丄偦偺傑傑搶傾僕傾偵偍偗傞拞崙傗杒挬慛傊偺埨慡曐忈偲偄偆栚揑偵偡傝懼偊傜傟偰宲懕偟偰偒偨丅偟偐偟丄偄傑傗拞崙偑擔杮偵孯帠峴摦傪偲傞偙偲偼偁傝摼側偄偟丄杒挬慛偵丄挧敪峴摦偼婲偙偡偵偣傛丄擔杮傪峌傔傞偩偗偺崙椡偑偁傞偼偢偑側偄丅偦傟傜偺嫼埿偑夁戝偵榑偠傜傟偰偄傞偵偡偓側偄丅暷孯偺挀棷梊嶼偺7妱偼擔杮偑晧扴偟偰偄傞丅傏偔偨偪偺惻嬥偑巊傢傟偰偄傞偺偩丅乬梷巭椡乭偲偄偆尪偺偍戣栚偺傕偲偵丄傾儊儕僇偺孯帠愴棯偺偨傔丄擔杮偼嬥傪弌偟丄搚抧傪採嫙偟偰偒偨偺偩丅傾儊儕僇偵偲偭偰丄偙傟傎偳偍偄偟偄榖偼側偄丅
數嶳庱憡偼5寧弶傔丄朘栤偟偨壂撽偱乽暷奀暫戉偺梷巭椡偑昁梫偩偲偄偆偙偲傪妛傫偩乿側偳偲怮尵傒偨偄側偙偲傪尵偭偰偄偨丅偄偭偨偄壗傪峫偊偰乽晛揤娫婎抧傪丄嵟掅偱傕導奜丄偱偒傟偽崙奜偵堏揮偡傞乿偲栺懇偟偨偺偩傠偆丅偙傟偱偼彫妛惗暲傒偺尰忬擣幆擻椡偟偐側偄偲尵傢傟偰傕偟偐偨偑側偄丅庱憡偑婎抧堏愝傪敀巻偵栠偡偲尵偭偨偲偒丄傏偔偼斵偵偼巚偄愗偭偨價僕儑儞偑偁傞偺偩傠偆偲巚偭偰偄偨丅傾儊儕僇偵擔杮偺梫朷傪堸傑偣傞偵偼丄埨曐忦栺偺攋婞偲偄偆妎屽傪傕偭偰岎徛偡傞偟偐側偄丅愜傕傛偔丄崱擭偼偪傚偆偳埨曐忦栺掲寢偐傜50擭偲偄偆愡栚偺擭偱偁傝丄尒捈偟偺岲婡傪寎偊偰偄傞丅擔杮偑埨曐忦栺傪廔椆偡傞偲尵偭偨傜丄傾儊儕僇偼搟傞偩傠偆丅傾儊儕僇偺悽奅杊塹懱惂偺堦妏偑曵傟傞偐傜偩丅偝傑偞傑側柺偱嫼偟傪偐偗偰偒偨傝丄寵偑傜偣傪偡傞偩傠偆丅偱傕丄擔杮偲偺娭學傪抐偪愗傞偙偲偼偱偒側偄丅偙傟偩偗嬞枾偵楢実偟偰偄傞幮夛宱嵪忣惃偑偦傟傪嫋偝側偄丅
偄傑丄擔杮偺嵦傞傋偒棫応偼偙偆偩丅亙侾亜悽奅偺曮偲傕偄偆傋偒暯榓寷朄偼弲庣偡傞丅亙俀亜埨曐忦栺傪廔椆偟丄暷孯婎抧傪揚廂偝偣傞丅亙3亜帺塹偺偨傔偺帺慜偺孯戉傪傕偮乮擔杮偼偡偱偵孯帠旓偐傜偡傞偲悽奅偱6斣栚偺孯帠戝崙偩乯丅偙傟埲奜偵擔杮偺恑傓傋偒摴偼側偄丅
偟偐偟幚嵺偼丄偦傕偦傕數嶳惌尃偺敪懌摉弶偐傜丄婎抧堏愝偵娭偟偰偼丄杒郪杊塹憡傗壀揷奜柋憡偲偄偭偨扴摉戝恇傗暯栰姱朳挿姱乮偙傟偼數嶳惌尃偱嵟埆偺妕椈偐傕偟傟側偄乯偼媦傃崢偩偭偨丅傗傞婥偺側偝偑斵傜偺尵梩偺抂乆偵昞傟偰偄偨丅偱傕丄數嶳庱憡偑埨曐忦栺攋婞傕帿偝側偄偲偄偆嫮偄堄巙偱杮婥偱岎徛偡傟偽丄偦偟偰帺暘偺峫偊傪崙柉偵帵偟丄悽榑偺屻墴偟傪摼偰丄偙傟偑擔杮偲擔杮崙柉偺堄巙偩偲庡挘偡傟偽丄帠懺偼摦偄偨偲巚偆丅傾儊儕僇偼惌尃偺敪尵傛傝傕悽榑偺惙傝忋偑傝偵晀姶偩丅偟偐偟庱憡偵偦傫側妎屽偼側偐偭偨偟丄悽榑偺屻墴偟傕側偐偭偨丅偗偭偒傚偔傾儊儕僇偺巚偄捠傝偵側偭偨丅斵傜偼偝偧偐偟丄傎偔偦徫傫偱偄傞偩傠偆丅
2010.05.24 (寧) 暷孯僋儔僗僞乕抏搳壓孭楙偲娯崙娡捑杤帠審
僋儔僗僞乕敋抏偼嶦彎擻椡偑崅偔旕恖摴揑側晲婍偩偲偟偰丄崙嵺揑偵巊梡嬛巭偵偟傛偆偲偡傞摦偒偑恑傫偱偄傞丅僋儔僗僞乕敋抏嬛巭忦栺偼擔杮傕娷傔偰悽奅偺戝懡悢偺崙偑彁柤偟偰偄傞偑丄娞怱偺傾儊儕僇丄僀僗儔僄儖丄儘僔傾丄拞崙側偳偼彁柤偟偰偄側偄丅僋儔僗僞乕敋抏偼敋寕偵傛傞旐奞傕惁傑偠偄偑丄嵟戝偺栤戣偼晄敪抏偵側傞巕敋抏偺悢偑懡偄偙偲偩丅愴憟偵傛傝晄敪抏偑嶶棎偟偨搚抧偵廧傓懡偔偺恖乆丄偲偔偵巕嫙偨偪偑丄晄敪抏偺敋敪偱柦傪棊偲偟偨傝庤懌傪幐偭偨傝偟偰偄傞丅暷孯偑擔杮偱搳壓孭楙偟偰偄傞僋儔僗僞乕抏偼丄偄偢傟傾僼僈僯僗僞儞偱丄傕偟偐偟偨傜彨棃揑偵偼僀儔儞偱丄幚嵺偵巊傢傟傞偙偲偵側傞偩傠偆丅擔杮傕傾儊儕僇偺愴憟偵壛扴偟丄敋抏偺搳壓傪庤彆偗偟偰偄傞偙偲偵側傞丅擔杮偵暷孯婎抧偑偁傞偲偄偆偺偼丄偙偆偄偆偙偲傪尵偆偺偩丅
偦傫側側偐丄3寧枛偵娯崙偱婲偙偭偨彛夲娡捑杤帠審偼丄戝曽偺梊憐偳偍傝杒挬慛偺嫑棆偵傛傞傕偺偩偲偄偆挷嵏曬崘偑敪昞偝傟偨丅娯崙偼杒挬慛惂嵸偺偨傔崙楢偺埨曐棟偵採慽偡傞偲偄偆丅偩偑丄偳傫側偐偨偪偱惂嵸偑峴側傢傟傞偵偣傛丄娯崙偲杒挬慛偑愴壩傪岎偊傞偙偲偼側偄偩傠偆丅愄偩偭偨傜曬暅峌寕偟丄慡柺愴憟偵撍偒恑傓働乕僗偩丅偟偐偟尰戙偵偍偄偰偼丄偄偔傜怺崗側擇崙娫僩儔僽儖偑婲偙偭偰傕丄愴憟偵傑偱敪揥偡傞偙偲偼側偄丅愴憟偵側傟偽丄彑偭偰傕晧偗偰傕丄偦偺媇惖偼恟戝偩偟愴旓傕偐偝傓丅偩偄偄偪丄挬慛敿搰偺尰忬堐帩傪朷傓傾儊儕僇傗拞崙偑偦傟傪嫋偝側偄丅偩偐傜惌帯偲奜岎偵傛傞寛拝偵側傞丅
偲偼偄偊丄偲偆偤傫孯帠揑嬞挘偼旘桇揑偵崅傑傞丅娯崙娡捑杤帠審偑杒挬慛偺嫑棆峌寕偵傛偭偰婲偒偨偙偲偼娫堘偄側偄偩傠偆丅偁傜備傞徹嫆偑偦傟傪棤晅偗偰偄傞丅偟偐偟丄偦偺僞僀儈儞僌偲塭嬁傪峫偊傞偲丄側偵偐層嶶廘偄傕偺傪姶偠傞丅娯崙偵挀棷偟偰偄傞暷孯偼揚戅寁夋偑恑傫偱偄傞偑丄偙偺帠審偵傛傞孯帠揑嬞挘偵傛傝丄偦偺寁夋偼敀巻偵栠偝傟傞偩傠偆丅壂撽偺暷孯婎抧堏愝栤戣傪偐偐偊傞擔杮偱傕丄傗偼傝杒挬慛偼晐偄丄擔暷摨柨偵傛傞梷巭椡偼昁梫偩丄壂撽偺婎抧偼昁梫偩丄偲偄偆榑挷偑庡棳傪愯傔傞偙偲偵側傞丅偡傋偰偼傾儊儕僇偺嶻孯暋崌懱偺巚偄捠傝偵偙偲偑塣傇丅
杒挬慛偑偙傟傑偱晲椡挧敪傪孞傝曉偟偰偒偨偙偲偼妋偐偩偑丄崱夞偺帠審偑杒挬慛偺巇嬈偩偭偨偲偡傟偽丄偦偺栚揑偼壗側偺偐丄幆幰偵傛偭偰偄傠傫側愢偑彞偊傜傟偰偄傞偑丄扤傕偑擺摼偱偒傞寛掕揑側愢偼側偄丅杒挬慛偺嫑棆側偳丄偦偺婥偵側傟偽偄偔傜偱傕婾憰偱偒傞丅傾儊儕僇偺愴憟偵偮偹偵漵憿偑偐傜傫偱偄偨偺偼楌巎揑帠幚偩丅儀僩僫儉愴憟偺僩儞僉儞榩帠審丄僀儔僋愴憟偺戝検攋夡暫婍側偳丄傾儊儕僇偼偱偭偪偁偘偵傛偭偰峌寕偺岥幚傪嶌偭偰偒偨丅偩偐傜偲偄偭偰丄崱夞偺帠審偑傾儊儕僇偵傛傞漵憿偩偲尵偆偮傕傝偼側偄偟丄僆僶儅惌尃偑偦傫側偙偲傪偡傞偲偼巚偊側偄丅偱傕丄偁傑傝偵弌棃夁偓偨榖側偺偑婥偵側傞丅
偙偆偟偰孯帠揑嬞挘偑忴惉偝傟傟偽丄傾儊儕僇偺懚嵼姶偼憹偡偟丄暷孯偵傛傞埨慡曐忈偺廳梫惈傕崅傑傞丅傗偼傝擔杮偵偲偭偰埨曐忦栺偼昁梫偩偲偄偆曽岦偵暔帠偑棳傟傞丅偙傟偱偼擔杮偼丄偄偮傑偱傕擔暷摨柨偵埶懚偟丄暷孯婎抧偑懚嵼偟懕偗傞偱偁傠偆偟丄傾儊儕僇偺愴憟偺曅朹傪扴偖偙偲偐傜敳偗弌偣側偄傑傑偵側偭偰偟傑偆丅
2010.05.17 (寧) 僄僐乕丒僷乕僋偵桯偐偵嬁偔儌儞僋偲僐儖僩儗乕儞
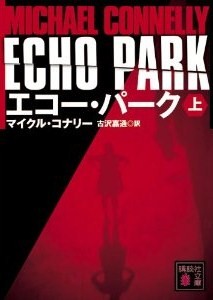 儅僀僋儖丒僐僫儕乕嶌偺僴乕僪儃僀儖僪丒儈僗僥儕乕丄僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺怴嶌乽僄僐乕丒僷乕僋乿偑東栿弌斉偝傟偨乮屆戲壝捠栿丄島択幮暥屔乯丅偙傟偼暣傟傕側偄寙嶌偱偁傞丅慜嶌乽廔寛幰偨偪乿偺弌斉偑2007擭丄僔儕乕僘奜偺乽儕儞僇乕儞曎岇巑乿傪偁偄偩偵嫴傫偱丄2擭敿傇傝偺儃僢僔儏傕偺偩丅
儅僀僋儖丒僐僫儕乕嶌偺僴乕僪儃僀儖僪丒儈僗僥儕乕丄僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺怴嶌乽僄僐乕丒僷乕僋乿偑東栿弌斉偝傟偨乮屆戲壝捠栿丄島択幮暥屔乯丅偙傟偼暣傟傕側偄寙嶌偱偁傞丅慜嶌乽廔寛幰偨偪乿偺弌斉偑2007擭丄僔儕乕僘奜偺乽儕儞僇乕儞曎岇巑乿傪偁偄偩偵嫴傫偱丄2擭敿傇傝偺儃僢僔儏傕偺偩丅慜嶌偱儘僗巗寈偵暅怑偟偨儃僢僔儏偼丄枹夝寛帠審斍偺孻帠偲偟偰嵞傃擄帠審偵庢傝慻傓丅尰嵼憑嵏拞偺楢懕彈惈嶴嶦帠審偑丄13擭慜偵婲偙偭偨枹夝寛偺庒偄彈惈幐鏗帠審偵寢傃偮偔丅僗僩乕儕乕偺棳傟偼恀偭岦彑晧偺僗僩儗乕僩丄娙偵偟偰梫傪摼偨昅抳偱堦婥偵撉傑偣傞丅嵟嬤偺儈僗僥儕乕偵偁傝偑偪側丄傑偩傞偭偙偟偄尵偄夞偟傗巚傢偣傇傝偺昤幨偼丄偄偭偝偄側偄丅乽揤巊偲嵾偺奨乿偱妶桇偟偨FBI彈惈憑嵏姱儗僀僠僃儖丒僂僅儕儞僌偑嵞傃搊応偟偰儃僢僔儏傪僒億乕僩偡傞偺傕嵤傝傪梌偊偰偄傞丅儃僢僔儏偺堦旵楾揑側峴摦偑鏰鐎傪惗傒丄専嶡偺惌帯揑側巚榝傗斊恖偲栚偝傟傞抝偺晄怰側尵摦側偳傕偁傝丄僗僩乕儕乕偼擇揮丄嶰揮偡傞偑丄僥儞億偑偄偄偺偱榖偺揥奐偼暘偐傝傗偡偄偟愢摼椡偑偁傞丅
儃僢僔儏丒僔儕乕僘偼偙傟偑12嶌栚偩偑丄1992擭偺戞1嶌敪昞埲棃丄18擭傕偺偁偄偩丄嶌幰偺僐僫儕乕偑偮偹偵戞堦媺偺撪梕傪堐帩偟懕偗偰偄傞偺偼嬃堎揑側偙偲偩偲尵傢偹偽側傞傑偄丅偙偺乽僄僐乕丒僷乕僋乿偼丄乬僔儕乕僘嵟崅寙嶌乭偲偄偆僉儍僢僠丒僐僺乕偼戝偘偝偵偟偰傕丄弌怓偺弌棃偱偁傞偙偲偼娫堘偄側偄丅儃僢僔儏丒僔儕乕僘偼儃僢僔儏偺撪柺偵憙偔偆埫偄搟傝偑恖娫揑側堿塭傪惗傒弌偟丄偦傟偑傂偲偮偺枺椡偵側偭偰偒偨丅崱嶌偱偼偦偺偁偨傝偑偄傑傂偲偮擹偔昤偐傟偰偄側偄傛偆側婥傕偡傞偑丄傛偔楙傝忋偘傜傟僗僩乕儕乕偲敆椡偁傆傟傞昅抳偑偦傫側晄枮傪偼偹偺偗偰偟傑偆丅
 儃僢僔儏偼僕儍僘傪垽挳偟偰偍傝丄偙傟傑偱偺嶌昳偱偼傛偔壠偱傂偲傝惷偐偵僂傿僗僉乕傪堸傒側偑傜儅僀儖僗偺乽僇僀儞僪丒僆僽丒僽儖乕乿傗儁僢僷乕偺乽儈乕僣丒僓丒儕僘儉丒僙僋僔儑儞乿偲偄偭偨僕儍僘偺CD偵帹傪孹偗傞僔乕儞偑偁偭偨丅崱嶌偱斵偑挳偔偺偼丄僙儘僯傾僗丒儌儞僋偲僕儑儞丒僐儖僩儗乕儞偺乽儔僀償丒傾僢僩丒僇乕僱僊乕丒儂乕儖乿偲偄偆傾儖僶儉偩丅偙傟偼1957擭偵悂偒崬傑傟偨儔僀償斦偱偁傞丅榐壒偝傟偨僥乕僾偼挿傜偔傾儊儕僇媍夛恾彂娰偺憅屔偱柊偭偰偄偨偑丄榐壒偐傜50擭嬤偔傪宱偨2005擭偵敪孈偝傟CD壔偝傟偨丅儃僢僔儏偼偙傟傪乬敔偺拞偺婏愓乭偲尵偭偰偄傞丅斵偑庢傝慻傓枹夝寛帠審偲偺傾僫儘僕乕傪楢憐偝偣傞偙偺CD偼丄帠審偺夝柧偵旝柇側塭嬁傪媦傏偟偰偄傞丅偙偺偁偨傝偺憓榖傕偙偺彫愢傪枺椡偁傞傕偺偵偟偰偄傞丅
儃僢僔儏偼僕儍僘傪垽挳偟偰偍傝丄偙傟傑偱偺嶌昳偱偼傛偔壠偱傂偲傝惷偐偵僂傿僗僉乕傪堸傒側偑傜儅僀儖僗偺乽僇僀儞僪丒僆僽丒僽儖乕乿傗儁僢僷乕偺乽儈乕僣丒僓丒儕僘儉丒僙僋僔儑儞乿偲偄偭偨僕儍僘偺CD偵帹傪孹偗傞僔乕儞偑偁偭偨丅崱嶌偱斵偑挳偔偺偼丄僙儘僯傾僗丒儌儞僋偲僕儑儞丒僐儖僩儗乕儞偺乽儔僀償丒傾僢僩丒僇乕僱僊乕丒儂乕儖乿偲偄偆傾儖僶儉偩丅偙傟偼1957擭偵悂偒崬傑傟偨儔僀償斦偱偁傞丅榐壒偝傟偨僥乕僾偼挿傜偔傾儊儕僇媍夛恾彂娰偺憅屔偱柊偭偰偄偨偑丄榐壒偐傜50擭嬤偔傪宱偨2005擭偵敪孈偝傟CD壔偝傟偨丅儃僢僔儏偼偙傟傪乬敔偺拞偺婏愓乭偲尵偭偰偄傞丅斵偑庢傝慻傓枹夝寛帠審偲偺傾僫儘僕乕傪楢憐偝偣傞偙偺CD偼丄帠審偺夝柧偵旝柇側塭嬁傪媦傏偟偰偄傞丅偙偺偁偨傝偺憓榖傕偙偺彫愢傪枺椡偁傞傕偺偵偟偰偄傞丅巬梩側偙偲側偑傜婥偵側傞偺偼儃僢僔儏偺擭楊偩丅彫愢偱偼丄斵偺擭楊偼偼偭偒傝偲偼怗傟傜傟偰偄側偄丅偩偑斵偼儀僩僫儉愴憟偵廬孯偟偰偄傞偐傜丄偦傟傪峫偊傞偲丄偳偆庒偔尒愊傕偭偰傕60嵨偵偼側偭偰偄傞偼偢偩丅帠幚丄崱夞偺彫愢偵傕丄乬儀僩僫儉偱愴偭偰40擭偑夁偓偨乭偲偄偆傛偆側堦愡偑弌偰偒偨傛偆偵婰壇偡傞丅偱傕丄彫愢偱偺儃僢僔儏偺峴摦偐傜偟偰丄偲偰傕斵偑60嵨傪挻偊偨抝偲偼巚偊側偄丅傑偁丄偙偺偁偨傝偼偁傑傝婥偵偣偢丄慺捈偵儃僢僔儏偺妶桇傪妝偟傓傋偒側偺偩傠偆丅
乽僄僐乕丒僷乕僋乿偼怴嶌偲偼尵偭偰傕丄尨彂偺敪攧偼2006擭偱偁傝丄杮崙傾儊儕僇偱偼偦偺偁偲儃僢僔儏丒僔儕乕僘偼偡偱偵2嶌傕忋埐偝傟偰偄傞丅擔杮偱偺東栿偑捛偄晅偄偰偄側偄偺偩丅偁偲偑偒偱栿幰偺屆戲偝傫偼丄偦偺偁偨傝偺帠忣偵偮偄偰愢柧偡傞偲摨帪偵丄嶐崱偺尩偟偄東栿儈僗僥儕乕忬嫷偵傕怗傟偰偍傜傟傞丅偄傑偼壒妝嬈奅偲摨偠偔弌斉嬈奅傕偢偄傇傫嬯偟偄傛偆偩丅偨偟偐偵偙偺偲偙傠奀奜儈僗僥儕乕偺弌斉偼偢偄傇傫尭偭偰偒偰偄傞丅偩偑榖戣愭峴偺儀僗僩僙儔乕偽偐傝捛偄偐偗偰偄偰偼丄傑偡傑偡東栿儈僗僥儕乕彫愢偺屌掕僼傽儞傪幐偆偙偲偵側傞丅偣傔偰儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺傛偆側嶌壠偺嶌昳傪偒偪傫偲敪攧偟側偗傟偽丄弌斉幮偼懹枬偺偦偟傝傪傑偸偐傟側偄偩傠偆丅
2010.03.22 (寧) 傂偨偡傜摝偘傞乬慶崙側偒抝乭偺偨偳傞摴偼
僀僊儕僗偺揱摑揑側朻尟彫愢嶌壠偺傂偲傝偵僕僃僼儕乕丒僴僂僗儂乕儖僪偑偄傞丅僴僂僗儂乕儖僪偼朻尟彫愢偺宯晥偱尵偊偽丄擔杮偱傕桳柤側僴儌儞僪丒僀僱僗傗傾儕僗僥傾丒儅僋儕乕儞偺愭攜奿偵偁偨傞偑丄1939擭偵敪昞偟偨彫愢乽捛傢傟傞抝乿乮Rogue Male乯偑朻尟彫愢偺屆揟偲偟偰抦傜傟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄東栿偝傟偨嶌昳偑彮側偔丄擔杮偱偺抦柤搙偼偁傑傝崅偔側偄丅偦偺僴僂僗儂乕儖僪偑丄1982擭丄慜嶌傪敪昞偟偰偐傜43擭傪宱偰彂偄偨乽捛傢傟傞抝乿偺懕曇乽慶崙側偒抝乿乮Rogue Justice乯偑丄嶐擭枛偵東栿弌斉偝傟偨丅乽捛傢傟傞抝乿偑嵟弶偵朚栿偝傟偨偺偼1960擭偩偐傜丄偦傟偐傜悢偊傞偲丄擔杮偱偼偠偮偵敿悽婭傇傝偺懕曇敪攧偲偄偆偙偲偵側傞丅偙偺偲偙傠悢彮側偄崪懢偺朻尟彫愢偵巇忋偑偭偰偍傝丄僼傽儞偺妷傪戝偄偵桙偟偰偔傟偨丅
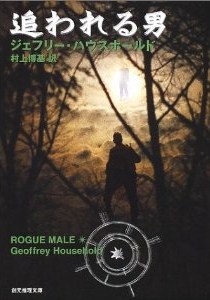 慜嶌偺乽捛傢傟傞抝乿乮憂尦幮暥屔乯偼丄戣柤偳偍傝丄傂偨偡傜摝偘傑傢傞抝偺榖偩偭偨丅帪戙偼戞2師戝愴慜栭丄儓乕儘僢僷朸崙偺尦庱傪埫嶦偟傛偆偲偟偰幐攕偟偨庡恖岞偑丄昁巰偵捛偭庤傪怳傝愗傝丄側傫偲偐曣崙僀僊儕僗偵摝偘婣傞偑丄偦偙偵傕埫嶦幰偑憲傝崬傑傟丄傑偨傕傗搆庤嬻対偱摝偘傑傢傞丄偲偄偆堎怓偺僒僶僀僶儖寑偩丅庡恖岞偑彂偄偨庤婰偲偄偆懱嵸偵側偭偰偍傝丄偄偐偵傕僀僊儕僗傜偟偄扺乆偲偟偨昅抳偩偑丄慡曇偵嫮楏側僗儕儖偑傒側偓偭偰偄偨丅偩偑婏柇側偙偲偵丄庡恖岞偺摝旔峴偼徻嵶偵昤偐傟傞偑丄埫嶦偺僞乕僎僢僩偱偁傞崙壠尦庱偑扤偐偼彂偐傟偰偄側偄偟丄庡恖岞偺柤慜傕柧傜偐偵偝傟側偄偟丄摦婡傕敾慠偲偟側偐偭偨乮偲偼偄偊丄扤偑撉傫偱傕丄憡庤偺崙偑僪僀僣偱僞乕僎僢僩偼僸僢僩儔乕偩偲偄偆偙偲偼梕堈偵憐憸偼偮偔丅偍偦傜偔幏昅摉帪丄僀僊儕僗偼傑偩僪僀僣偲愴壩傪岎偊傞慜偩偭偨偙偲傪峫椂偟偰丄偙傫側彂偒曽傪偟偨偺偩傠偆乯丅
慜嶌偺乽捛傢傟傞抝乿乮憂尦幮暥屔乯偼丄戣柤偳偍傝丄傂偨偡傜摝偘傑傢傞抝偺榖偩偭偨丅帪戙偼戞2師戝愴慜栭丄儓乕儘僢僷朸崙偺尦庱傪埫嶦偟傛偆偲偟偰幐攕偟偨庡恖岞偑丄昁巰偵捛偭庤傪怳傝愗傝丄側傫偲偐曣崙僀僊儕僗偵摝偘婣傞偑丄偦偙偵傕埫嶦幰偑憲傝崬傑傟丄傑偨傕傗搆庤嬻対偱摝偘傑傢傞丄偲偄偆堎怓偺僒僶僀僶儖寑偩丅庡恖岞偑彂偄偨庤婰偲偄偆懱嵸偵側偭偰偍傝丄偄偐偵傕僀僊儕僗傜偟偄扺乆偲偟偨昅抳偩偑丄慡曇偵嫮楏側僗儕儖偑傒側偓偭偰偄偨丅偩偑婏柇側偙偲偵丄庡恖岞偺摝旔峴偼徻嵶偵昤偐傟傞偑丄埫嶦偺僞乕僎僢僩偱偁傞崙壠尦庱偑扤偐偼彂偐傟偰偄側偄偟丄庡恖岞偺柤慜傕柧傜偐偵偝傟側偄偟丄摦婡傕敾慠偲偟側偐偭偨乮偲偼偄偊丄扤偑撉傫偱傕丄憡庤偺崙偑僪僀僣偱僞乕僎僢僩偼僸僢僩儔乕偩偲偄偆偙偲偼梕堈偵憐憸偼偮偔丅偍偦傜偔幏昅摉帪丄僀僊儕僗偼傑偩僪僀僣偲愴壩傪岎偊傞慜偩偭偨偙偲傪峫椂偟偰丄偙傫側彂偒曽傪偟偨偺偩傠偆乯丅 偙偺彫愢偼僼儕僢僣丒儔儞僌娔撀偵傛偭偰塮夋壔偝傟偰偄傞丅塮夋偺僞僀僩儖偼乽儅儞丒僴儞僩乿乮1941擭乯丅庡墘偼僂僅儖僞乕丒僺僕儑儞偲僕儑乕儞丒儀僱僢僩偑墘偠偨丅偙偙偱偼埫嶦偺憡庤偼僸僢僩儔乕偱偁傝丄庡恖岞傪捛偄偐偗傞偺偼僎僔儏僞億偲丄偼偭偒傝愝掕偝傟偰偍傝丄斀僫僠偺僾儘僷僈儞僟塮夋偵側偭偰偄傞丅婎杮揑側榞慻傒偼尨嶌偲摨偠偩偑丄嵶偐偄晹暘偼戝偒偔媟怓偝傟偰偍傝丄尨嶌偵偼弌偰偙側偄彈惈偲偺怓楒側偳傕昤偐傟傞丅偝偡偑偵僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺柤彔儔儞僌偺嶌昳偩偗偵丄岝偲塭傪岻傒偵巊偭偨柖偺奨儘儞僪儞偺僒僗儁儞僗僼儖側昤幨側偳偼尒偛偨偊廩暘偩丅
偙偺彫愢偼僼儕僢僣丒儔儞僌娔撀偵傛偭偰塮夋壔偝傟偰偄傞丅塮夋偺僞僀僩儖偼乽儅儞丒僴儞僩乿乮1941擭乯丅庡墘偼僂僅儖僞乕丒僺僕儑儞偲僕儑乕儞丒儀僱僢僩偑墘偠偨丅偙偙偱偼埫嶦偺憡庤偼僸僢僩儔乕偱偁傝丄庡恖岞傪捛偄偐偗傞偺偼僎僔儏僞億偲丄偼偭偒傝愝掕偝傟偰偍傝丄斀僫僠偺僾儘僷僈儞僟塮夋偵側偭偰偄傞丅婎杮揑側榞慻傒偼尨嶌偲摨偠偩偑丄嵶偐偄晹暘偼戝偒偔媟怓偝傟偰偍傝丄尨嶌偵偼弌偰偙側偄彈惈偲偺怓楒側偳傕昤偐傟傞丅偝偡偑偵僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺柤彔儔儞僌偺嶌昳偩偗偵丄岝偲塭傪岻傒偵巊偭偨柖偺奨儘儞僪儞偺僒僗儁儞僗僼儖側昤幨側偳偼尒偛偨偊廩暘偩丅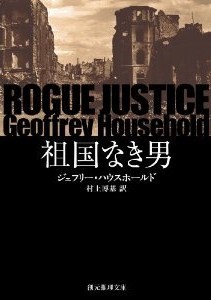 偦偟偰偙偺傎偳東栿偝傟偨懕曇偺乽慶崙側偒抝乿乮摨偠偔憂尦幮暥屔乯偩偑丄偙偙偱偼庡恖岞偼嵞搙丄僪僀僣偵愽擖偟偰僸僢僩儔乕偺埫嶦傪婇偰傞偑壥偨偣偢丄傑偨傕傗峀偄儓乕儘僢僷戝棨偺奺抧傪摝偘傑傢傞攋栚偵偍偪偄傞丅偙偺懕曇偱偼丄慜嶌偱偼傏傗偐偝傟偰偄偨僞乕僎僢僩偺柤慜傕柧婰偝傟傞偟丄庡恖岞偺摦婡傕偡傋偰柧傜偐偵偝傟偰偄傞丅慜嶌偱偼庡偵僀僊儕僗偺媢椝抧懷偵晳戜偑屌掕偝傟偰偄偨偑丄懕曇偱偼庡恖岞偼僀僊儕僗偵婣崙偱偒偢丄僪僀僣丄僗儘僶僉傾丄儖乕儅僯傾丄僊儕僔儍丄僩儖僐偲奺抧傪揮乆偲偡傞偟丄慜嶌偱偼堦旵楾偱丄傎偲傫偳摝偘傞偙偲偵廔巒偟偰偄偨庡恖岞偼丄懕曇偱偼儗僕僗僞儞僗偺楢拞偲峴摦傪嫟偵偟丄廵傪庤偵偟偰墳愴偟揋傪壗恖傕傗偭偮偗傞丅彈偭婥偑側偄偲偄偆揰偱偼慜嶌傕懕曇傕摨偠偩偑丄傑偭偨偔彈偑弌偰偙側偐偭偨慜嶌偵斾傋丄懕曇偱偼偛偔扺偄儘儅儞僗偺枴晅偗傕側偝傟偰偄傞丅
偦偟偰偙偺傎偳東栿偝傟偨懕曇偺乽慶崙側偒抝乿乮摨偠偔憂尦幮暥屔乯偩偑丄偙偙偱偼庡恖岞偼嵞搙丄僪僀僣偵愽擖偟偰僸僢僩儔乕偺埫嶦傪婇偰傞偑壥偨偣偢丄傑偨傕傗峀偄儓乕儘僢僷戝棨偺奺抧傪摝偘傑傢傞攋栚偵偍偪偄傞丅偙偺懕曇偱偼丄慜嶌偱偼傏傗偐偝傟偰偄偨僞乕僎僢僩偺柤慜傕柧婰偝傟傞偟丄庡恖岞偺摦婡傕偡傋偰柧傜偐偵偝傟偰偄傞丅慜嶌偱偼庡偵僀僊儕僗偺媢椝抧懷偵晳戜偑屌掕偝傟偰偄偨偑丄懕曇偱偼庡恖岞偼僀僊儕僗偵婣崙偱偒偢丄僪僀僣丄僗儘僶僉傾丄儖乕儅僯傾丄僊儕僔儍丄僩儖僐偲奺抧傪揮乆偲偡傞偟丄慜嶌偱偼堦旵楾偱丄傎偲傫偳摝偘傞偙偲偵廔巒偟偰偄偨庡恖岞偼丄懕曇偱偼儗僕僗僞儞僗偺楢拞偲峴摦傪嫟偵偟丄廵傪庤偵偟偰墳愴偟揋傪壗恖傕傗偭偮偗傞丅彈偭婥偑側偄偲偄偆揰偱偼慜嶌傕懕曇傕摨偠偩偑丄傑偭偨偔彈偑弌偰偙側偐偭偨慜嶌偵斾傋丄懕曇偱偼偛偔扺偄儘儅儞僗偺枴晅偗傕側偝傟偰偄傞丅偲偄偆偙偲偱丄妶寑偺搙崌偄偲摝朣偺僗働乕儖偐傜偡傟偽丄弌棃偲偟偰偼懕曇偺傎偆偑慜嶌傪忋夞偭偰偄傞丅偩偑丄忢偵屩傝傪幐傢偢丄晄孅偺摤巙偱崲擄偵棫偪岦偐偆抝傪昤偔丄偲偄偆揰偱偼丄峛壋傪晅偗偑偨偄丅偡傋偰堦恖徧偱彂偐傟偨偙偺杮嶌偼丄慜嶌偲傕偳傕丄娙寜偱椡嫮偔丄偡偖傟偨朻尟彫愢偺尒杮偺傛偆側嶌昳偩丅偄傑丄偙偺傛偆側梷惂偝傟偨暥懱偱庤偵娋埇傞柺敀偝傪枴傢傢偣偰偔傟傞儈僗僥儕乕偼傔偭偨偵側偄丅尰戙偼峝攈偺朻尟彫愢偑惗傑傟偵偔偄帪戙側偺偩傠偆偐丅
2010.03.11 (栘) 梞妝嬋柤偁傟偙傟乗乗偦偺3乽僕儍僘丒僗僞儞僟乕僪乿
丂丂偦傫側嫄愹巵偑偮偗偨嬋柤偵丄桳柤側岆栿偑偁傞丅僐乕儖丒億乕僞乕嶌偺乽婣偭偰偔傟偨傜偆傟偟偄傢乿乮You'd Be So Nice to Come Home To乯偩丅尵偆傑偱傕側偔丄僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞傪僼傿乕僠儍乕偟偨僿儗儞丒儊儕儖偺壧偑偙偺嬋偺寛掕斉偲偝傟偰偄傞丅嵟弶偙偺嬋柤傪尒偨偲偒丄娫堘偄偩偲偼暘偐傜側偐偭偨偑丄尨戣偺嵟屻偵 "to" 偑偮偄偰偄傞偺偑柇偵婥偵側偭偰丄偙傟偼 "to me" 偲偄偆偙偲偩傠偆偗偳丄側偤 "me" 偑徣棯偝傟偰偄傞偺偐媈栤偵巚偭偨傕偺偩丅偦偺屻丄偙偺朚戣偼岆栿傜偟偄偲偄偆塡偑棳傟丄傗偑偰僔僫僩儔嫤夛傪庡嵣偟偰偄傞嶰嬶偝傫偺僿儗儞丒儊儕儖傊偺僀儞僞價儏乕婰帠偵傛傝丄惓夝偑暘偐偭偨丅偙偺嬋柤偼乬壠偵婣偭偰偁側偨偵夛偭偨傜丄偒偭偲偁側偨偼慺揋偱偟傚偆乭偲偄偆堄枴側偺偩丅偮傑傝丄壠偱婣傝傪懸偭偰偄傞偺偱偼側偔丄椃愭偵偄傞抝乮彈乯偑丄壠偱懸偭偰偄傞彈乮抝乯傪憐偆壧側偺偩丅尨戣傪曗懌偡傞偲丄乽You'd Be So Nice (for Me) to Come Home to (You)乿偲偄偆偙偲偵側傞丅偩偐傜丄偨偲偊偽乽偁側偨偺傕偲偵婣傝偨偄乿偲偄偆傛偆側栿偑憡墳偟偄偩傠偆丅億乕僞乕偺嬋偵偼丄傂偹偭偨壧帉偑懡偄丅偙偺嬋傕偦偆偩偑丄愢柧偝傟傟偽側傞傎偳偲巚偆偟丄壧帉偵弌偰偔傞乬偦傛晽偵悂偐傟偰偄傞偁側偨偼慺揋乭偲偐乬寧偺岝傪梺傃偰偄傞偁側偨偼慺揋乭偲偐偺僼儗乕僘傕擺摼偑偄偔丅
丂丂摨偠僐乕儖丒億乕僞乕偵乽偝傛側傜傪尵偆偨傃偵乿乮Everytime We Say Goodbye乯偲偄偆嬋偑偁傞丅偙傟偵傕丄偄偐偵傕億乕僞乕傜偟偄愻楙偝傟偨壧帉偑晅偄偰偍傝丄儗僀儌儞僪丒僠儍儞僪儔乕偺彫愢乽挿偄偍暿傟乿偵僼儔儞僗恖偑尵偭偨尵梩偲偟偰弌偰偔傞乬偝傛側傜傪尵偆偨傃偵巹偼彮偟偯偮巰偸乭偲偄偆僼儗乕僘側偳傕憓擖偝傟偰偄傞偑丄戣柤偼僗僩儗乕僩偱丄娫堘偊傛偆偑側偄丅偟偐偟埲慜偼乽偄偮傕偝傛側傜傪乿偲偄偆捒柇側擔杮岅柤偑晅偄偰偄偨丅"everytime" 傪乬偄偮傕乭偲夝偟偨岆栿偱偁傞丅
丂丂"You Stepped Out of a Dream" 偼僼僅乕丒僼儗僢僔儏儊儞傗僜僯乕丒儘儕儞僘偺墘彞偱抦傜傟傞嬋偩丅戝愄偵償傽儞僾彈桪偺儔僫丒僞乕僫乕偑弌偨僴儕僂僢僪塮夋偱丄斵彈偑奒抜傪壓偭偰偔傞僔乕儞偱巊傢傟丄埲屻丄僞乕僫乕偺僩儗乕僪儅乕僋丒僜儞僌偵側偭偨丅偙傟偵偼乽柌偐傜妎傔偰乿偲偄偆朚戣偑晅偄偰偄傞偑丄偠偮偼乬孨偼柌偺拞偐傜敳偗弌偟偨傛偆偩丅栚傕怬傕徫婄傕丄偡傋偰偑旤偟偡偓傞乭偲偄偆丄楒恖偺旤偟偝傪擬楏偵巀旤偡傞壧偱偁傝丄柧傜偐側岆栿偩丅傕偭偲傕丄揔愗側朚戣偼偲尵傢傟偰傕丄側偐側偐巚偄晜偐偽側偄偑丅
丂丂"Willow Weep for Me" 偲偄偆僶儔乕僪偺柤嬋偑偁傞丅僕儍儞僰丒儌儘乕庡墘丄僕儑僙僼丒儘乕僕乕娔撀偺埆彈塮夋乽僄償傽偺擋偄乿偱丄價儕乕丒儂儕僨僀偺壧偆偙偺嬋偺儗僐乕僪偑報徾揑偵巊傢傟偰偄偨丅惓偟偄朚戣偼乽桍傛媰偄偰偍偔傟乿偩偑丄乽桍偼媰偄偰偄傞乿偲偐乽桍偼傓偣傇乿偲偐丄娫堘偭偨嬋柤偑巊傢傟傞偙偲偑懡偄丅"weep" 偵偼 "s" 偑晅偄偰偄側偄偺偱丄乬媰偄偰偄傞乭偱偼側偔丄柦椷宍偺乬媰偄偰偔傟乭偲夝偝側偗傟偽側傜側偄丅
丂丂僯儏乕僆儕儞僘丒僕儍僘偱傛偔嵦傝忋偘傜傟傞嬋偺傂偲偮偵丄儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偺帩偪壧偲偟偰抦傜傟傞 "Do You Know What It Means to Miss New Orleans?" 偲偄偆僗僞儞僟乕僪偑偁傞丅偙傟偵埲慜偼乽儈僗丒僯儏乕僆儕儞僘乿偲偄偆栿柤偑晅偄偰偄偨丅"miss" 傪撈恎彈惈偵晅偗傞宧徧偲偲偭偨偙偲偵傛傞娫堘偄偱偁傝丄偙偙偱偺 miss" 偼尵偆傑偱傕側偔乬乣偑側偔偰庘偟偄乭偲偄偆堄枴偱偁傞丅偄傑偼惓偟偔乽僯儏乕僆儕儞僘傪朰傟傞偙偲偼乿偲偐乽夰偐偟偺僯儏乕僆儕儞僘乿偲偄偆戣偵側偭偰偄傞傛偆偩丅
丂丂柧傜偐側娫堘偄偲傑偱偼尵偊側偄偵偣傛丄岆栿偲偡傟偡傟偺偲偙傠偵偁傞朚戣傕偁傞丅塮夋乽僇僒僽儔儞僇乿偱巊傢傟偰僗僞儞僟乕僪偵側偭偨 "As Time Goes By" 偩丅偙傟偼乽帪偺偨偮傑傑乿傑偨偼乽帪偺夁偓備偔傑傑乿偲偄偆擔杮岅嬋柤偩偑丄乬帪偑偨偪丄帪戙傪宱偰傕丄抝偑彈傪媮傔丄彈偑抝傪垽偡傞偲偄偆尨懃偼丄塱墦偵摨偠乭偲偄偆丄傗傗寧暲傒側恖惗偺恀棟傪壧偭偨撪梕偱偁傝丄嬋柤偲偟偰偼乽帪偼偨偭偰傕乿偺傎偆偑憡墳偟偄丅
丂丂傕偆傂偲偮丄30擭戙偵僶僯乕丒儀儕僈儞偺壧偲僩儔儞儁僢僩偱戝僸僢僩偟偨 "I Can't Get Started (with You)" 偲偄偆嬋偼乽尵偄弌偟偐偹偰乿偑掕栿柤偩偑丄壧帉偐傜偡傞偲乬巹偼偳傫側偙偲偱傕傗偭偰偺偗傞偟丄扤偐傜傕垽偝傟傞偺偵丄偁側偨偩偗偼巚偄捠傝偵側傜側偄丄偁側偨偲偩偗偼楒傪僗僞乕僩偡傞偙偲偑偱偒側偄乭偲偄偆嬋偱偁傝丄惓偟偄栿偐偳偆偐丄旝柇側偲偙傠偩丅偲偼偄偊丄偙傟傕憡墳偟偄朚戣傪晅偗傞偺偼擄偟偄丅乽孨偩偗偼側傃偄偰偔傟側偄乿偠傖條偵側傜側偄偟丒丒丒丅
丂丂岆栿偽偐傝傪偁偘偮傜偭偨偑丄傕偪傠傫慺惏傜偟偄嬋柤傕偁傞丅偙傟傑偱尒偰偒偨傛偆偵丄偍偍傓偹庡岅弎岅偑旛傢傝姰寢偟偨暥復偵側偭偰偄傞尨戣偼擔杮岅偵抲偒姺偊傞偺偑擄偟偄偑丄偦傫側塸暥傪偆傑偔栿偟偰偁傞朚戣側偳偼姶怱偡傞丅乽寧岝偺偄偨偢傜乿乮What a Little Moonlight Can Do乯丄乽帪偝偊朰傟偰乿乮I Didn't Know What Time It Was乯丄乽曺偖傞偼垽偺傒乿乮I Can't Give You Anything but Love乯側偳偼柤栿偲尵偊傞偩傠偆丅僕儍僘偺僗僞儞僟乕僪偲偼尵偄擄偄偑乽寧岝壙愮嬥乿乮Get Out and Get Under the Moon乯傕尒帠側朚戣偩丅変乆偵偼僉儞僌丒僐乕儖偺壧偱撻愼傒怺偄偑丄愴慜偵僄僲働儞偺壧偱僸僢僩偟偨偲偒偵晅偗傜傟偨嬋柤偺傛偆偱偁傝丄偝偡偑偵帪戙傪姶偠偝偣傞丅乽晜婥偼傗傔偨乿乮Ain't Misbehavin'乯傗乽楒偟偨傒偨偄乿乮Almost Like Being in Love乯側偳傕丄摿偵偳偆偲偄偆偙偲傕側偄傛偆偩偑丄傑偝偵偙傟偟偐側偄偲偄偆慛傗偐側嬋柤偩偲巚偆丅
丂丂偙偆傗偭偰尒偰偄偔偲丄柤栿偵偟傠岆栿偵偟傠丄偦傟偵庢傝慻傫偩愭恖偨偪偺嬯怱偺愓偑偆偐偑偊傞丅偙偆偄偭偨僗僞儞僟乕僪傕偄傑偺CD偱偼僇僞僇僫偱昞婰偝傟傞偙偲偑懡偄傛偆偩偑丄偦傟傕帪戙偺棳傟偩傠偆丅偱傕丄傏偔偵偲偭偰偼乽僀僼丒傾僀丒儚乕丒傾丒儀儖乿傛傝傕乽傕偟傕巹偑忇側傜偽乿偺傎偆偵垽拝偑偁傞偟丄乽儂僄傾丒僆傾丒儂僄儞乿傛傝傕乽偄偮偐偳偙偐偱乿偺傎偆偑偟偭偔傝偔傞丅偦傫側姶妎偼丄傕偆屆廘偄傕偺偵側偭偰偟傑偭偨偺偩傠偆偐丅
2010.03.04 (栘) 2偮偺椳
丂丂傏偔偼搤婫僆儕儞僺僢僋偵偼偁傑傝嫽枴傪偦偦傜傟側偄丅庒偄偙傠僗僉乕傗僗働乕僩傪偐偠偭偨偙偲偼偁傞偑丄傕偲傕偲懌尦偑偟偭偐傝偟偰偄側偄応強偼岲偒偠傖側偄丅偦傟偵僗僉乕傗僗働乕僩偺慖庤偺懡偔偼丄朮巕傪偐傇傝僒儞僌儔僗傪偟偰偄傞偺偱丄扤偑扤偩偑傛偔暘偐傜側偄偟昞忣偑尒偊側偄偺傕丄枺椡偑嶍偑傟傞棟桼偺傂偲偮偩丅偦傟偱傕僼傿僊儏傾丒僗働乕僩偺恀墰偪傖傫偲僉儉丒儓僫偺懳寛偼僗儕儕儞僌偩偭偨丅寢壥偼僉儉丒儓僫偺埑彑偵廔傢偭偨傢偗偩偑丄僗働乕僩偵偼偳慺恖偺傏偔偐傜尒偰傕丄僉儉丒儓僫偺埨掕姶偺偁傞丄妸傜偐偱桪夒側墘媄偼丄偳偙偐寴偝偺偁傞恀墰偪傖傫偺偦傟傪丄柧傜偐偵忋夞偭偰偄偨丅
丂丂恀墰偪傖傫偼僐乕僠丒僒僀僪偺僎乕儉丒僾儔儞偵栤戣偑偁偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅斵彈偼墘媄嬋偵廳嬯偟偄嬋傪慖傃丄僩儕僾儖丒傾僋僙儖偵屌幏偟偨丅偱傕丄偁偁偄偆応柺偱偼丄廳岤側寍弍惈傪懪偪弌偡傛傝傕壺傗偐偵晳偄梮傞傎偆偑報徾揑偩偟丄僩儕僾儖丒傾僋僙儖偺摼揰攝暘偑偦傟傎偳崅偔側偄偙偲偩偭偰暘偐偭偰偄偨偼偢偩丅偦傟偲傕丄傑偲傕偵偼僉儉丒儓僫偵彑偰側偄偺偱丄偁偊偰偦偆傗偭偰堦敪媡揮傪慱偆偲偄偆嶌愴偩偭偨偺偩傠偆偐丅偄偢傟偵偟偰傕丄幆幰傗儅僗僐儈偼丄擄堈搙偺崅偄僕儍儞僾偵偦傟傎偳廳偒傪抲偐側偄嵦揰曽朄傪栤戣偵偟偰偄偨偑丄儖乕儖偑偦偆側偭偰偄傞埲忋丄廔傢偭偨偁偲偱偦傟偵暥嬪傪尵偭偰傕堄枴偑側偄丅
丂丂嫞媄偺偁偲偵恀墰偪傖傫偑棳偟偨夨偟椳偵丄傏偔偼斵彈偺晧偗傫婥偺嫮偝丄彑棙傊偺幏擮傪尒偨丅偦傫側寴屌側堄巙丄恱偄惛恄偑偁偭偨偐傜偙傠丄偮傜偄孭楙偵懴偊偰丄偙偙傑偱偙傟偨偺偩傠偆偲巚偭偨丅儊僟儖傪慱偆傎偳偺僗億乕僣慖庤偼丄偝傑偞傑側桿榝傪梷偊丄擔乆偺尩偟偄楙廗傗懱偺抌楤傗怘帠惂尷傪帺傜偵壽偝側偗傟偽側傜側偄丅偄偔傜塣摦恄宱偑偁偭偰傕丄擃庛側惛恄偱偼懯栚側偺偩丅擃庛偝偱偼恖屻偵棊偪側偄傏偔側偳偼丄恀偭愭偵扙棊偡傞丅僗億乕僣偵偟傠壒妝偵偟傠丄堦寍偵廏偱偨恖偼丄偗偭偟偰嵟弶偐傜揤嵥側偺偱偼側偄丅嫮屌側堄巙偵傛傞搘椡偺愊傒廳偹偑堦棳偺僗億乕僣慖庤傗儈儏乕僕僔儍儞傪偮偔傞丅恀墰偪傖傫偼傑偩婥椡偑悐偊偰偄側偄丅偮偓偺悽奅慖庤尃偱偼僉儉丒儓僫偵彑偪偨偄偲尵偭偰偄傞丅崱搙偼偒偭偲夨偟偝傪惏傜偡偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅
丂丂傕偆傂偲偮丄傏偔偨偪偑栚偵偟偨偺偼丄僩儓僞帺摦幵偺朙揷復抝幮挿偑棳偟偨椳偩偭偨丅傾儊儕僇偵峴偒壓堾岞挳夛偱徹尵偟偨偁偲丄尰抧僨傿乕儔乕偲偺夛崌偵弌惾偟偨朙揷幮挿偼丄僨傿乕儔乕偨偪偺椼傑偟偺尵梩傪暦偒丄椳傪棳偟偨丅嬞挘傪嫮偄傜傟傞岞挳夛偑廔傢偭偰儂僢偲堦懅偮偄偨偲偙傠偵丄拠娫偨偪偐傜擬偄巟墖偺儊僢僙乕僕偑敪偣傜傟丄姶嬌傑偭偰巚傢偢偙傒忋偘偨椳偩偭偨丅屒棫柍墖偺妎屽偱揋抧偵忔傝崬傫偩傜丄巚偄傕偐偗偢枴曽偑偄偨偲偄偆怱嫬偩傠偆丅
丂丂崱夞偺傾儊儕僇偱偺僩儓僞憶摦偼僶僢僔儞僌偲惌帯僔儑乕偺廘偄偑僾儞僾儞偡傞丅傾儊儕僇偵傛傞丄悽奅堦偺帺摦幵夛幮偺抧埵傪擔杮偵扗傢傟偨偙偲偵懳偡傞僩儓僞偨偨偒偲丄慖嫇傪慜偵偟偰偺媍堳偨偪偺抧尦柉傊偺僨儌儞僗僩儗乕僔儑儞偩丅擔杮偺惌晎偺庤傪偙傑偹偄偰朤娤偡傞偩偗偲偄偆柍嶔傇傝偑暊棫偨偟偄丅岞挳夛偼側傫偲偐忔傝愗偭偨偑丄僩儓僞偺帋楙偼傑偩傑偩懕偔丅朙揷幮挿偺宱塩庤榬偑偳偆側偺偐偼丄傛偔暘偐傜側偄丅堦晹偵偼憂嬈壠弌恎偺偍朧偭偪傖傫傇傝傪潏潐偡傞惡傕偁傞傛偆偩偑丄偨偩偺儃儞僋儔偲傕巚偊側偄丅彮側偔偲傕墱揷尦夛挿傛傝偼傑偟偩傠偆丅彫愹丄抾拞偲寢戸偟丄峔憿夵妚偲偄偆柤偺傕偲偵擔杮傪悐戅偵捛偄崬傫偩尦嫢偺傂偲傝偑墱揷偩丅墱揷偺偲偭偨埨堈側奼戝楬慄偑偄傑偺戝検儕僐乕儖偵偮側偑偭偰偄傞偺偼柧傜偐偩丅
丂丂僩儓僞栤戣偵娭偡傞曬摴偺側偐偱丄揹巕惂屼偲偄偆尵梩偑偟偽偟偽搊応偟偨偑丄傏偔偵偲偭偰偼帹姷傟側偄尵梩偩偭偨丅幵偵徻偟偄恖偵偲偭偰偼忢幆側偺偐傕偟傟側偄偑丄尰嵼偺幵偵偙傟傎偳傑偱僐儞僺儏乕僞乕丒僔僗僥儉偑慻傒崬傑傟偰偄傞偲偼抦傜側偐偭偨丅偄傑傗僐儞僺儏乕僞乕偑側偔偰偼幵傕摦偐側偄帪戙側偺偩丅傕偆屻栠傝偼偱偒側偄丄偙偺棳傟偼傕偭偲壛懍偡傞偩傠偆丅偄傑偝傜側偑傜丄悽偺拞偺僐儞僺儏乕僞乕偺怹摟傇傝偵嬃偐偝傟傞丅枹棃偼傑偭偨偔梊應偑偮偐側偄丄偄傗丄幚嵺偼偩傟偐偺梊應偺傕偲偵摦偄偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅僐儞僺儏乕僞乕幮夛偺嫲傠偟偝偼丄偙傟傑偱彫愢傗塮夋偱偄傠偄傠昤偐傟偰偄傞偑丄僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偺怴嶌乽僜僂儖丒僐儗僋僞乕乿偺傛偆偵丄IT傪嬱巊偟偰偁傜備傞忣曬傪廤傔丄尃椡傪埇傝幮夛傪憖傠偆偲偡傞幰偑丄偄偮尰傟偰傕偍偐偟偔側偄丅
2010.03.01 (寧) 梞妝嬋柤偁傟偙傟乗乗偦偺2
 億僢僾仌儘僢僋偺悽奅偱桳柤側岆栿嬋柤偵丄價乕僩儖僘偺乽僲儖僂僃僀偺怷乿乮Norwegian Wood乯偑偁傞丅壧帉偺撪梕偲丄怷偩偭偨傜 woods 偵側傞偼偢偩丄偲偄偆棟桼偐傜偟偰丄尨戣偺堄枴偼乬僲儖僂僃僀偺怷乭偱偼側偔乬僲儖僂僃僀惢偺壠嬶乭側偺偩偦偆偩丅偱傕壧帉偼偁偄傑偄偩偟丄扨悢偺 wood 偱傕怷傪堄枴偡傞応崌偑偁傝丄偦偆偩偲偼抐掕偱偒側偄丅嵟嬤偼乬僲儖僂僃僀嶻偺栘嵽偱撪憰偝傟偨晹壆乭偲偄偆愢偑桳椡傜偟偄偑丄knowing she would 偲偄偆尵梩偺岅楥崌傢偣偱丄偨傫側傞懯煭棊偩偲偄偆愢傗丄僲儖僂僃僀偺怷傪巚傢偣傞晹壆偲偄偆堄枴偩偐傜乬僲儖僂僃僀偺怷乭偲偄偆戣偱偄偄傫偩偲偄偆愢傕偁傞傛偆偩丅側偵偟傠價乕僩儖僘偩偟丄懞忋弔庽偺摨柤彫愢偑戝僸僢僩偟偨偙偲傕偁傝丄偙偆偩偁偁偩偲榑媍偑偐傑傃偡偟偄丅價乕僩儖僘偺嬋偱偼丄傎偐偵傕乽書偒偟傔偨偄乿乮I Want to Hold Your Hand乯偑岆栿偲偟偰抦傜傟偰偄傞偑丄偙傟偼嬋偺暤埻婥傪峫偊丄堄恾揑偵乬孨偺庤傪埇傝偨偄乭偠傖側偔乬書偒偟傔偨偄乭偵偟偨傜偟偄丅帡偨傛偆側堄恾揑側岆栿偵丄僕儑儞丒僨儞償傽乕偺乽懢梲傪攚偵庴偗偰乿乮Sunshine on My Shoulders乯偑偁傞丅偨偟偐偵乬懢梲傪尐偵梺傃偰乭傛傝偼偙偺傎偆偑擔杮岅偲偟偰偟偭偔傝偔傞丅乬尐乭偲偄偊偽丄屆偄億乕儖丒傾儞僇偺僸僢僩嬋偵乽偁側偨偺尐偵杍偆傔偰乿偑偁傞丅尨戣偼 "Put Your Head on My Shoulder" 偱偁傝丄朚戣偲偼媡偵乬傏偔偺尐偵孨偺摢傪偁偢偗偰乭偲偄偆偙偲偵側傞偑丄偙傟傕擔杮岅偵偟偵偔偄偺偱丄偁偊偰偙偆偟偨偺偐傕偟傟側偄丅
億僢僾仌儘僢僋偺悽奅偱桳柤側岆栿嬋柤偵丄價乕僩儖僘偺乽僲儖僂僃僀偺怷乿乮Norwegian Wood乯偑偁傞丅壧帉偺撪梕偲丄怷偩偭偨傜 woods 偵側傞偼偢偩丄偲偄偆棟桼偐傜偟偰丄尨戣偺堄枴偼乬僲儖僂僃僀偺怷乭偱偼側偔乬僲儖僂僃僀惢偺壠嬶乭側偺偩偦偆偩丅偱傕壧帉偼偁偄傑偄偩偟丄扨悢偺 wood 偱傕怷傪堄枴偡傞応崌偑偁傝丄偦偆偩偲偼抐掕偱偒側偄丅嵟嬤偼乬僲儖僂僃僀嶻偺栘嵽偱撪憰偝傟偨晹壆乭偲偄偆愢偑桳椡傜偟偄偑丄knowing she would 偲偄偆尵梩偺岅楥崌傢偣偱丄偨傫側傞懯煭棊偩偲偄偆愢傗丄僲儖僂僃僀偺怷傪巚傢偣傞晹壆偲偄偆堄枴偩偐傜乬僲儖僂僃僀偺怷乭偲偄偆戣偱偄偄傫偩偲偄偆愢傕偁傞傛偆偩丅側偵偟傠價乕僩儖僘偩偟丄懞忋弔庽偺摨柤彫愢偑戝僸僢僩偟偨偙偲傕偁傝丄偙偆偩偁偁偩偲榑媍偑偐傑傃偡偟偄丅價乕僩儖僘偺嬋偱偼丄傎偐偵傕乽書偒偟傔偨偄乿乮I Want to Hold Your Hand乯偑岆栿偲偟偰抦傜傟偰偄傞偑丄偙傟偼嬋偺暤埻婥傪峫偊丄堄恾揑偵乬孨偺庤傪埇傝偨偄乭偠傖側偔乬書偒偟傔偨偄乭偵偟偨傜偟偄丅帡偨傛偆側堄恾揑側岆栿偵丄僕儑儞丒僨儞償傽乕偺乽懢梲傪攚偵庴偗偰乿乮Sunshine on My Shoulders乯偑偁傞丅偨偟偐偵乬懢梲傪尐偵梺傃偰乭傛傝偼偙偺傎偆偑擔杮岅偲偟偰偟偭偔傝偔傞丅乬尐乭偲偄偊偽丄屆偄億乕儖丒傾儞僇偺僸僢僩嬋偵乽偁側偨偺尐偵杍偆傔偰乿偑偁傞丅尨戣偼 "Put Your Head on My Shoulder" 偱偁傝丄朚戣偲偼媡偵乬傏偔偺尐偵孨偺摢傪偁偢偗偰乭偲偄偆偙偲偵側傞偑丄偙傟傕擔杮岅偵偟偵偔偄偺偱丄偁偊偰偙偆偟偨偺偐傕偟傟側偄丅 價乕僩儖僘偑弌偨傜僄儖償傿僗丒僾儗僗儕乕偵傕怗傟側偗傟偽側傞傑偄丅50擭戙偺僄儖償傿僗偺僸僢僩嬋偺傂偲偮偵乽偨偩堦恖偺抝乿乮I Was the One乯偑偁傞丅偙傟偼柧傜偐側岆栿偱偁傝丄壧帉偵 "I was the one who taught her to kiss" 偲偁傞傛偆偵丄偙偺 one 偼乬傂偲偮乭偲偄偆堄枴偺柤帉偱偼側偔丄傕偺傪昞偡戙柤帉偩丅壧帉偺拞恎偼乬斵彈偵偡傋偰傪嫵偊偨偺偼壌側偺偵丄斵彈偼壌偵塕傪偮偒丄棤愗偭偨丅偱傕壌偼塕傪偮偔偙偲側傫偐嫵偊偰側偄丅偄偭偨偄扤偑嫵偊偨傫偩乭偲偄偆撪梕偱偁傝丄乽嫵偊偨偺偼壌側偺偵乿偲偄偆傛偆側嬋柤偑懨摉偩傠偆丅50擭戙偺僄儖償傿僗偵偼柺敀偄嬋柤偑懡偄丅乽僪儞僩傑偢偄偤乿乮Don't乯側偳偼寙嶌偱丄戝偄偵徫偊傞丅偙傟偼偄傑偱偼乽僪儞僩乿偲偄偆僇僫僞僫昞婰偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅傎偐偵乽偳偭偪傒偪壌偺傕偺乿乮Anyway You Want Me乯丄乽晜悽偺巇懪偪乿乮How's the world Treating You乯側偳偺嬋柤偵偼丄偄偐偵傕帪戙偺暤埻婥偑偆偐偑偊傞丅60擭戙弶婜偺戝僸僢僩嬋乽僀僢僣丒僫僂丒僆傾丒僱償傽乕乿乮It's Now or Never乯偼僇僞僇僫昞婰偵側偭偰偄傞偗偳丄愄偼乽崱彧偐偓傝偺楒乿偲偄偆戣偩偭偨傛偆偵巚偆偺偩偑丄婰壇堘偄偩傠偆偐丅傄偭偨傝偼傑偭偨嬋柤偲偟偰偼丄乽偁偺柡偑孨側傜乿乮She's Not You乯傗乽楒偺偁傗偮傝巺乿乮Please Don't Drag That String Around乯側偳偑嫇偘傜傟傛偆丅
價乕僩儖僘偑弌偨傜僄儖償傿僗丒僾儗僗儕乕偵傕怗傟側偗傟偽側傞傑偄丅50擭戙偺僄儖償傿僗偺僸僢僩嬋偺傂偲偮偵乽偨偩堦恖偺抝乿乮I Was the One乯偑偁傞丅偙傟偼柧傜偐側岆栿偱偁傝丄壧帉偵 "I was the one who taught her to kiss" 偲偁傞傛偆偵丄偙偺 one 偼乬傂偲偮乭偲偄偆堄枴偺柤帉偱偼側偔丄傕偺傪昞偡戙柤帉偩丅壧帉偺拞恎偼乬斵彈偵偡傋偰傪嫵偊偨偺偼壌側偺偵丄斵彈偼壌偵塕傪偮偒丄棤愗偭偨丅偱傕壌偼塕傪偮偔偙偲側傫偐嫵偊偰側偄丅偄偭偨偄扤偑嫵偊偨傫偩乭偲偄偆撪梕偱偁傝丄乽嫵偊偨偺偼壌側偺偵乿偲偄偆傛偆側嬋柤偑懨摉偩傠偆丅50擭戙偺僄儖償傿僗偵偼柺敀偄嬋柤偑懡偄丅乽僪儞僩傑偢偄偤乿乮Don't乯側偳偼寙嶌偱丄戝偄偵徫偊傞丅偙傟偼偄傑偱偼乽僪儞僩乿偲偄偆僇僫僞僫昞婰偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅傎偐偵乽偳偭偪傒偪壌偺傕偺乿乮Anyway You Want Me乯丄乽晜悽偺巇懪偪乿乮How's the world Treating You乯側偳偺嬋柤偵偼丄偄偐偵傕帪戙偺暤埻婥偑偆偐偑偊傞丅60擭戙弶婜偺戝僸僢僩嬋乽僀僢僣丒僫僂丒僆傾丒僱償傽乕乿乮It's Now or Never乯偼僇僞僇僫昞婰偵側偭偰偄傞偗偳丄愄偼乽崱彧偐偓傝偺楒乿偲偄偆戣偩偭偨傛偆偵巚偆偺偩偑丄婰壇堘偄偩傠偆偐丅傄偭偨傝偼傑偭偨嬋柤偲偟偰偼丄乽偁偺柡偑孨側傜乿乮She's Not You乯傗乽楒偺偁傗偮傝巺乿乮Please Don't Drag That String Around乯側偳偑嫇偘傜傟傛偆丅 儃價乕丒償傿乕偑壧偭偨60擭戙偺僸僢僩嬋偵乽擱備傞摰乿偲偄偆偺偑偁傞丅尨戣偼 "The Night Has a Thousand Eyes"丅僕儍僘丒僼傽儞側傜偍暘偐傝偺傛偆偵丄僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏尨嶌塮夋偺庡戣壧偱丄僐儖僩儗乕儞側偳偺墘憈偱僕儍僘丒僗僞儞僟乕僪偵側偭偰偄傞乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿偺摨柤堎嬋偩丅乽擱備傞摰乿偼丄乬孨偑塕傪偮偄偰傕丄栭嬻偺惎偑孨偺傗偭偨偙偲傪尒偰傞傛乭偲偄偆偲偄偆壧帉偱偁傝丄楒恖偺晄幚傪側偠傞嬋偩丅偩偐傜偙偺朚戣傕岆栿偺廘偄偑偡傞丅崱夞偺僥乕儅偐傜偼彮偟堩傟傞偑丄擔杮偱偼僸僢僩偟側偐偭偨偗傟偳丄僕儉丒儘僂偲偄偆壧庤偑50擭戙廔傢傝偵壧偭偨嬋偱丄乽僌儕乕儞丒僪傾乿乮Green Door乯偲偄偆儘僢僋儞儘乕儖挷偺僫儞僶乕偑偁傞丅乬偁偺椢偺斷偺岦偆偐傜丄僺傾僲偺壒傗妝偟偦偆側徫偄惡偑暦偙偊傞偗偳丄偄偭偨偄壗傪傗偭偰傞傫偩傠偆乭偲偄偆撪梕偺嬋偩丅傏偔偼埲慜偐傜丄偙偺僞僀僩儖偲壧帉偺拞恎偐傜偟偰丄70擭戙弶摢偺傾儊儕僇丒億儖僲塮夋偺屆揟乽Behind the Green Door乿偲娭學偑偁傞偵堘偄側偄偲巚偭偰偄偨丅嵟嬤 Wikipedia 偱挷傋偰傒偨傜丄傗偼傝乽Behind the Green Door乿偼丄偙偺乽僌儕乕儞丒僪傾乿偲偄偆嬋偵僀儞僗僷僀傾偝傟偰偮偔傜傟偨塮夋傜偟偄丅
儃價乕丒償傿乕偑壧偭偨60擭戙偺僸僢僩嬋偵乽擱備傞摰乿偲偄偆偺偑偁傞丅尨戣偼 "The Night Has a Thousand Eyes"丅僕儍僘丒僼傽儞側傜偍暘偐傝偺傛偆偵丄僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏尨嶌塮夋偺庡戣壧偱丄僐儖僩儗乕儞側偳偺墘憈偱僕儍僘丒僗僞儞僟乕僪偵側偭偰偄傞乽栭偼愮偺娽傪帩偮乿偺摨柤堎嬋偩丅乽擱備傞摰乿偼丄乬孨偑塕傪偮偄偰傕丄栭嬻偺惎偑孨偺傗偭偨偙偲傪尒偰傞傛乭偲偄偆偲偄偆壧帉偱偁傝丄楒恖偺晄幚傪側偠傞嬋偩丅偩偐傜偙偺朚戣傕岆栿偺廘偄偑偡傞丅崱夞偺僥乕儅偐傜偼彮偟堩傟傞偑丄擔杮偱偼僸僢僩偟側偐偭偨偗傟偳丄僕儉丒儘僂偲偄偆壧庤偑50擭戙廔傢傝偵壧偭偨嬋偱丄乽僌儕乕儞丒僪傾乿乮Green Door乯偲偄偆儘僢僋儞儘乕儖挷偺僫儞僶乕偑偁傞丅乬偁偺椢偺斷偺岦偆偐傜丄僺傾僲偺壒傗妝偟偦偆側徫偄惡偑暦偙偊傞偗偳丄偄偭偨偄壗傪傗偭偰傞傫偩傠偆乭偲偄偆撪梕偺嬋偩丅傏偔偼埲慜偐傜丄偙偺僞僀僩儖偲壧帉偺拞恎偐傜偟偰丄70擭戙弶摢偺傾儊儕僇丒億儖僲塮夋偺屆揟乽Behind the Green Door乿偲娭學偑偁傞偵堘偄側偄偲巚偭偰偄偨丅嵟嬤 Wikipedia 偱挷傋偰傒偨傜丄傗偼傝乽Behind the Green Door乿偼丄偙偺乽僌儕乕儞丒僪傾乿偲偄偆嬋偵僀儞僗僷僀傾偝傟偰偮偔傜傟偨塮夋傜偟偄丅 慜夞偵傕彂偄偨傛偆偵丄60擭戙慜敿偺擔杮偺梞妝億僢僾僗嬈奅偱偼丄堦偮偺嬋偑僸僢僩偟偨傜丄偦傟偵偁傗偐傞偨傔丄偦偺屻傕摨偠僀儊乕僕偺嬋柤傪偮偗傞偲偄偆傗傝曽偑棳峴偟偨丅偙傟偼擔杮撈摿偺僗僞僀儖偱偁傝丄墷暷偵偼偁傑傝椺偑側偄丅偦傫側側偐偱朰傟傜傟側偄偺偼乬僼儖乕僣柡乭僫儞僔乕丒僔僫僩儔偺嬋偩丅乽儗儌儞偺僉僢僗乿偑僸僢僩偟偰丄乽僀僠僑偺曅憐偄乿乽儕儞僑偺偨傔偄偒乿乽僼儖乕僣僇儔乕偺偍寧偝傑乿偲丄尨戣偲偼傑偭偨偔娭學側偄壥暔楬慄偺嬋柤偑懕偄偨丅偦傟偐傜乬奨妏抝乭偲堎柤傪偲偭偨僨儖丒僔儍僲儞偑偄傞丅乽斶偟偒奨妏乿乽壴嶇偔奨妏乿偲懕偒丄乽偝傜偽奨妏乿偱懪偪巭傔偵側偭偨丅乬柖抝乭僕儑儞丒儗僀僩儞傕報徾怺偄丅乽柖偺拞偺僕儑僯乕乿偲乽柖偺拞偺儘儞儕乕丒僔僥傿乿偺2嬋偟偐側偄偑丅偙偆傗偭偰彂偄偰偄偔偲丄摉帪偺梞妝億僢僾僗偺嬋柤偼丄僾儕儈僥傿償偱懠垽側偄偗傟偳丄柌偑偁偭偨偟妶婥偵枮偪偰偄偨偲偮偔偯偔巚偆丅帪戙偑庒偐偭偨丄億僢僾僗偺惵弔帪戙偩偭偨偺偩丅
慜夞偵傕彂偄偨傛偆偵丄60擭戙慜敿偺擔杮偺梞妝億僢僾僗嬈奅偱偼丄堦偮偺嬋偑僸僢僩偟偨傜丄偦傟偵偁傗偐傞偨傔丄偦偺屻傕摨偠僀儊乕僕偺嬋柤傪偮偗傞偲偄偆傗傝曽偑棳峴偟偨丅偙傟偼擔杮撈摿偺僗僞僀儖偱偁傝丄墷暷偵偼偁傑傝椺偑側偄丅偦傫側側偐偱朰傟傜傟側偄偺偼乬僼儖乕僣柡乭僫儞僔乕丒僔僫僩儔偺嬋偩丅乽儗儌儞偺僉僢僗乿偑僸僢僩偟偰丄乽僀僠僑偺曅憐偄乿乽儕儞僑偺偨傔偄偒乿乽僼儖乕僣僇儔乕偺偍寧偝傑乿偲丄尨戣偲偼傑偭偨偔娭學側偄壥暔楬慄偺嬋柤偑懕偄偨丅偦傟偐傜乬奨妏抝乭偲堎柤傪偲偭偨僨儖丒僔儍僲儞偑偄傞丅乽斶偟偒奨妏乿乽壴嶇偔奨妏乿偲懕偒丄乽偝傜偽奨妏乿偱懪偪巭傔偵側偭偨丅乬柖抝乭僕儑儞丒儗僀僩儞傕報徾怺偄丅乽柖偺拞偺僕儑僯乕乿偲乽柖偺拞偺儘儞儕乕丒僔僥傿乿偺2嬋偟偐側偄偑丅偙偆傗偭偰彂偄偰偄偔偲丄摉帪偺梞妝億僢僾僗偺嬋柤偼丄僾儕儈僥傿償偱懠垽側偄偗傟偳丄柌偑偁偭偨偟妶婥偵枮偪偰偄偨偲偮偔偯偔巚偆丅帪戙偑庒偐偭偨丄億僢僾僗偺惵弔帪戙偩偭偨偺偩丅師夞偼僕儍僘偺僗僞儞僟乕僪丒僫儞僶乕偵偮偄偰彂偔偙偲偵偡傞丅
2010.02.22 (寧) 梞妝嬋柤偁傟偙傟
丂丂側偵偟傠丄偄傑傗壻巕偼僗僀乕僣偩偟丄攧揦偼僔儑僢僾偩偟丄怴暦偱偼僈償傽僫儞僗傗儔僀僼儔僀儞傗僐儞僾儔僀傾儞僗傗僛儘僔乕儕儞僌偲偄偭偨傢偗偺暘偐傜側偄尵梩偑梮偭偰偄傞丅扤傕偑偦傫側尵梩偺堄枴偑暘偐傞傎偳擔杮偺崙柉偺塸岅椡偑岦忋偟偨偲偼巚偊側偄丅梫偡傞偵丄墷暷偑恎嬤偵側偭偨偙偲偵壛偊丄暤埻婥丄僇僢僐傛偝丄暘偐偭偨傛偆側婥偵側傞丄偲偄偆傛偆側偙偲偐傜巊傢傟偰偄傞傢偗偩丅偙偆傕僇僞僫僇偑枲墑偡傞偲丄偐偊偭偰暯壖柤偲娍帤偵傛傞擔杮岅偺傎偆偑丄怴慛偵嬁偄偰偔傞丅
丂丂偄傑偱偼丄梞妝CD偺僞僀僩儖傗嬋柤偼僇僞僇僫偑埑搢揑偵懡偄丅偦傟偵椫傪偐偗偨忬懺側偺偑梞夋偩丅弌斉嬈奅偼偦偆偱傕側偄傛偆偩偑丄偦傟偱傕懞忋弔庽偺怴栿乮乽挿偄偍暿傟乿仺乽儘儞僌丒僌僢僪僶僀乿丄乽儔僀敒敤偱偮偐傑偊偰乿仺乽僉儍僢僠儍乕丒僀儞丒僓丒儔僀乿乯偺傛偆偵丄嵟嬤偼僇僞僇僫偺朚戣偑憹偊偰偄傞丅偄傑偺儗僐乕僪夛幮傗塮夋夛幮偺扴摉幰偼丄偄偪偄偪僀儞僷僋僩偺偁傞擔杮岅偵偟傛偆偲摢傪擸傑偡昁梫偑側偄偐傜丄妝偩傠偆丅愄偼偦偆偱偼側偐偭偨丅30擭傎偳慜丄傏偔偑儗僐乕僪夛幮偺梞妝偱曇惉傪扴摉偟偰偄偨偲偒偼丄尨戣偺堄枴傪挷傋丄壧帉偺撪梕傪僠僃僢僋偟側偑傜丄偳傫側擔杮岅僞僀僩儖偵偟傛偆偐丄偁傟偙傟巚埬偟偨傕偺偩丅
 丂丂嬋柤偺晅偗曽偵偼帪戙偺晽挭偑偁傞偑丄偦偺偙傠丄1970擭戙偼丄偦傟傛傝堦愄慜偺50乣60擭戙晽偺嬋柤偑傑偩暆傪棙偐偣偰偄偨丅50擭戙廔傢傝偐傜60擭戙弶傔偵偐偗偰偺梞妝億僢僾僗墿嬥帪戙偵偼丄偁傞嬋偑僸僢僩偟偨傜丄偦傟偲摨庯岦偺嬋柤偑師乆偵弌偰偔傞偲偄偆尰徾偑偁偭偨丅乽斶偟偒丒丒丒乿傗乽楒偺丒丒丒乿偑偦偺戙昞奿偲偄偊傞丅乽斶偟偒丒丒丒乿偺殔栴偼1960擭偺働僀僔乕丒儕儞僨儞偑壧偭偨乽斶偟偒16嵥乿偩偭偨丅偙傟偑戝僸僢僩偟丄埲屻乽斶偟偒僀儞僨傿傾儞乿乽斶偟偒彮擭暫乿乽斶偟偒偐偨憐偄乿乽斶偟偒偁偟偍偲乿乽斶偟偒奨妏乿乽斶偟偒僇儞僈儖乕乿乽斶偟偒僋儔僂儞乿乽斶偟偒埆杺乿乽斶偟偒塉壒乿乽斶偟偒彈妛惗乿乽斶偟偒婅偄乿乽斶偟偒愴応乿乽斶偟偒揤巊乿乽斶偟偒僕僾僔乕乿偲丄壗擭偵傕傢偨偭偰懕乆偲偮偔傜傟偨丅
丂丂嬋柤偺晅偗曽偵偼帪戙偺晽挭偑偁傞偑丄偦偺偙傠丄1970擭戙偼丄偦傟傛傝堦愄慜偺50乣60擭戙晽偺嬋柤偑傑偩暆傪棙偐偣偰偄偨丅50擭戙廔傢傝偐傜60擭戙弶傔偵偐偗偰偺梞妝億僢僾僗墿嬥帪戙偵偼丄偁傞嬋偑僸僢僩偟偨傜丄偦傟偲摨庯岦偺嬋柤偑師乆偵弌偰偔傞偲偄偆尰徾偑偁偭偨丅乽斶偟偒丒丒丒乿傗乽楒偺丒丒丒乿偑偦偺戙昞奿偲偄偊傞丅乽斶偟偒丒丒丒乿偺殔栴偼1960擭偺働僀僔乕丒儕儞僨儞偑壧偭偨乽斶偟偒16嵥乿偩偭偨丅偙傟偑戝僸僢僩偟丄埲屻乽斶偟偒僀儞僨傿傾儞乿乽斶偟偒彮擭暫乿乽斶偟偒偐偨憐偄乿乽斶偟偒偁偟偍偲乿乽斶偟偒奨妏乿乽斶偟偒僇儞僈儖乕乿乽斶偟偒僋儔僂儞乿乽斶偟偒埆杺乿乽斶偟偒塉壒乿乽斶偟偒彈妛惗乿乽斶偟偒婅偄乿乽斶偟偒愴応乿乽斶偟偒揤巊乿乽斶偟偒僕僾僔乕乿偲丄壗擭偵傕傢偨偭偰懕乆偲偮偔傜傟偨丅 丂丂乽楒偺丒丒丒乿傕偨偔偝傫偁傞丅偙傟偼乽楒偺擔婰乿乮1959擭乯丄乽楒偺曅摴愗晞乿乮1960擭乯偲偄偆僯乕儖丒僙僟僇偺僸僢僩嬋偑偒偭偐偗偩偭偨偲巚偆丅偦偺屻乽楒偺堦斣楍幵乿乽楒偺婦幵億僢億乿乽楒偺忦審斀幩乿乽楒偺攧傝崬傒乿乽楒偺傾僀僪儖乿乽楒偺傓偣傃媰偒乿乽楒偺僷乕儉僗僾儕儞僌僗乿乽楒偺僶僇儞僗乿乽楒偺弽乿乽楒偺僴僢僗儖乿乽楒偺儗僢僗儞乿偲弌偰偒偰丄乽楒偺廔楍幵乿乽楒偺恌抐彂乿乽楒偺僒僶僀僶儖乿乽楒偺僫僀僩丒僼傿乕僶乕乿偲70擭戙傑偱懕偄偨丅傏偔偑儗僐乕僪夛幮偵擖偭偨偙傠丄嬋柤傪偮偗傞偲偒丄崲偭偨傜摢偵乬楒偺乭傪偮偗偨傜偄偄丄偲愭攜偵嫵傢偭偨偙偲偑偁傞丅
丂丂乽楒偺丒丒丒乿傕偨偔偝傫偁傞丅偙傟偼乽楒偺擔婰乿乮1959擭乯丄乽楒偺曅摴愗晞乿乮1960擭乯偲偄偆僯乕儖丒僙僟僇偺僸僢僩嬋偑偒偭偐偗偩偭偨偲巚偆丅偦偺屻乽楒偺堦斣楍幵乿乽楒偺婦幵億僢億乿乽楒偺忦審斀幩乿乽楒偺攧傝崬傒乿乽楒偺傾僀僪儖乿乽楒偺傓偣傃媰偒乿乽楒偺僷乕儉僗僾儕儞僌僗乿乽楒偺僶僇儞僗乿乽楒偺弽乿乽楒偺僴僢僗儖乿乽楒偺儗僢僗儞乿偲弌偰偒偰丄乽楒偺廔楍幵乿乽楒偺恌抐彂乿乽楒偺僒僶僀僶儖乿乽楒偺僫僀僩丒僼傿乕僶乕乿偲70擭戙傑偱懕偄偨丅傏偔偑儗僐乕僪夛幮偵擖偭偨偙傠丄嬋柤傪偮偗傞偲偒丄崲偭偨傜摢偵乬楒偺乭傪偮偗偨傜偄偄丄偲愭攜偵嫵傢偭偨偙偲偑偁傞丅丂丂僀儞僗僩傕偺偱偼丄側傫偲偄偭偰傕乽丒丒丒僽儖乕僗乿偑敀旣偩丅1958擭偺儀儖僩丒働儞僾僼僃儖僩妝抍偵傛傞乽恀栭拞偺僽儖乕僗乿偺僸僢僩偑敪抂偩偭偨丅偦偺偁偲丄働儞僾僼僃儖僩帺恎偺嬋傕乽惎嬻偺僽儖乕僗乿乽梸朷偺僽儖乕僗乿乽柺塭偺僽儖乕僗乿偲懕偒丄
 偦偺傎偐乽敀偄栭柖偺僽儖乕僗乿乽崟偄彎偁偲偺僽儖乕僗乿乽敀偄弽偺僽儖乕僗乿乽妼怓偺僽儖乕僗乿乽惵偄摂塭偺僽儖乕僗乿乽埫偄峘偺僽儖乕僗乿乮側偤偐怓偵娭楢偟偨僱乕儈儞僌偑懡偄乯側偳丄僩儔儞儁僢僩傗僒僢僋僗傗僋儔儕僱僢僩傪僼傿乕僠儍乕偟偨儉乕僪偭傐偄婍妝墘憈嬋偵偼壗偱傕乬僽儖乕僗乭偲嬋柤偑晅偗傜傟偨丅傾乕僩丒僽儗僀僉乕偺僕儍僘丒僫儞僶乕傕乽婋尟側娭學偺僽儖乕僗乿偲偄偆朚戣偱僸僢僩偟偨丅偙傟傜偺側偐偱幚嵺偵壒妝揑偵僽儖乕僗宍幃側偺偼乽妼怓偺僽儖乕僗乿偩偗偩丅傎傫偲偆偼僽儖乕僗偠傖側偄偺偵嬋柤偵僽儖乕僗偑擖傞偺偼丄扺扟偺傝巕側偳偺愴慜偺壧梬嬋埲棃偺擔杮偺揱摑偩傠偆丅
偦偺傎偐乽敀偄栭柖偺僽儖乕僗乿乽崟偄彎偁偲偺僽儖乕僗乿乽敀偄弽偺僽儖乕僗乿乽妼怓偺僽儖乕僗乿乽惵偄摂塭偺僽儖乕僗乿乽埫偄峘偺僽儖乕僗乿乮側偤偐怓偵娭楢偟偨僱乕儈儞僌偑懡偄乯側偳丄僩儔儞儁僢僩傗僒僢僋僗傗僋儔儕僱僢僩傪僼傿乕僠儍乕偟偨儉乕僪偭傐偄婍妝墘憈嬋偵偼壗偱傕乬僽儖乕僗乭偲嬋柤偑晅偗傜傟偨丅傾乕僩丒僽儗僀僉乕偺僕儍僘丒僫儞僶乕傕乽婋尟側娭學偺僽儖乕僗乿偲偄偆朚戣偱僸僢僩偟偨丅偙傟傜偺側偐偱幚嵺偵壒妝揑偵僽儖乕僗宍幃側偺偼乽妼怓偺僽儖乕僗乿偩偗偩丅傎傫偲偆偼僽儖乕僗偠傖側偄偺偵嬋柤偵僽儖乕僗偑擖傞偺偼丄扺扟偺傝巕側偳偺愴慜偺壧梬嬋埲棃偺擔杮偺揱摑偩傠偆丅丂丂朚戣傪偮偗傞応崌丄塸岅傪偦偺傑傑僇僞僇僫偵偡傟偽栤戣側偄偑丄擔杮岅栿偡傞偲側傞偲丄偲偆偤傫岆栿傕惗傑傟傞丅僇儞僩儕乕偺僗僞儞僟乕僪偵 "Have I Told You Lately That I Love You" 偲偄偆嬋偑偁傞丅偐偮偰偙傟偵乽懪偪柧偗傞偺偑抶偐偭偨偐偄乿偲偄偆戣偑偮偄偰偄偨丅偙傟偼 "lately" 傪 "抶偄" 偲夝庍偟偨偙偲偵傛傞娫堘偄偱偁傝丄偙偺応崌丄 "lately" 偼偲偆偤傫 "嵟嬤" 偲偄偆堄枴偩丅偄傑偼乽垽偟偰偄傞偭偰尵偭偨偭偗乿偲丄惓偟偄嬋柤偵側偭偰偄傞傛偆偩丅摨偠僇儞僩儕乕偺嬋偱傕丄僂傿儕乕丒僱儖僜儞偺柤嬋 "Funny How Time Slips Away" 偺朚戣乽帪偺偨偮偺偼憗偄傕偺乿側偳偼尒帠側栿柤偲偄偊傞丅僇儞僩儕乕偵偼岆栿偱偼側偄偑捒柇側栿傕偁傞丅 "Sunny Side of the Mountain" 偲偄偆嬋偵偼丄乽梲偺偁偨傞嶳偺暊乿偲偄偆掕栿柤偑偁傞丅乬嶳偺拞暊乭傗乬嶳暊乭側傜偲傕偐偔丄乬嶳偺暊乭偼側偄偩傠偆丅
 丂丂R&B僫儞僶乕偵傕捒栿偼偁傞丅僥儞僾僥乕僔儑儞僘偺僸僢僩嬋偵 "Beauty Is Only Skin Deep" 偲偄偆偺偑偁傞丅偙傟偵偼乽旤恖偼偙傢偄乿偲偄偆朚戣偑偮偄偰偄偨丅弶傔偰偙偺嬋柤傪尒偨偲偒丄巚傢偢徫偭偰偟傑偭偨丅尨戣偺堄枴偼丄乬旤偟偝側傫偰偨偐偑旂晢偺旂堦枃偩偗偺偙偲偠傖側偄偐乭偲偄偆堄枴偩偑丄偦傟偑乬旤恖偼偙傢偄乭偵側傞偺偩偐傜丄嫲傟擖傞丅側偤偦偆側偭偨偐暘偐傞傛偆側婥傕偡傞偑丅慺惏傜偟偄朚戣傕偁傞丅僌儔僨傿僗丒僫僀僩仌僺僢僾僗偺乽偝傛側傜偼斶偟偄尵梩乿偩丅尨戣偼 "Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)" 偲偄偆挿偄僞僀僩儖丅尨戣偵懄偟丄嬋偺撪梕傕摜傑偊偨丄偙偺旤偟偄僶儔乕僪偵傄偭偨傝偺柤栿偩偲巚偆丅傕偭偲屆偄嬋偱偼丄僽儔僂儞僘偺乽扟娫偵嶰偮偺忇偑柭傞乿乮The Three Bells乯傗價儕乕丒償僅乕儞偺乽摶偺杫攏幵乿乮Wheels乯側偳偑丄偦偭偗側偄尨戣傪偆傑偔擔杮岅偵偟偨椺偲偟偰報徾偵巆偭偰偄傞丅
丂丂R&B僫儞僶乕偵傕捒栿偼偁傞丅僥儞僾僥乕僔儑儞僘偺僸僢僩嬋偵 "Beauty Is Only Skin Deep" 偲偄偆偺偑偁傞丅偙傟偵偼乽旤恖偼偙傢偄乿偲偄偆朚戣偑偮偄偰偄偨丅弶傔偰偙偺嬋柤傪尒偨偲偒丄巚傢偢徫偭偰偟傑偭偨丅尨戣偺堄枴偼丄乬旤偟偝側傫偰偨偐偑旂晢偺旂堦枃偩偗偺偙偲偠傖側偄偐乭偲偄偆堄枴偩偑丄偦傟偑乬旤恖偼偙傢偄乭偵側傞偺偩偐傜丄嫲傟擖傞丅側偤偦偆側偭偨偐暘偐傞傛偆側婥傕偡傞偑丅慺惏傜偟偄朚戣傕偁傞丅僌儔僨傿僗丒僫僀僩仌僺僢僾僗偺乽偝傛側傜偼斶偟偄尵梩乿偩丅尨戣偼 "Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)" 偲偄偆挿偄僞僀僩儖丅尨戣偵懄偟丄嬋偺撪梕傕摜傑偊偨丄偙偺旤偟偄僶儔乕僪偵傄偭偨傝偺柤栿偩偲巚偆丅傕偭偲屆偄嬋偱偼丄僽儔僂儞僘偺乽扟娫偵嶰偮偺忇偑柭傞乿乮The Three Bells乯傗價儕乕丒償僅乕儞偺乽摶偺杫攏幵乿乮Wheels乯側偳偑丄偦偭偗側偄尨戣傪偆傑偔擔杮岅偵偟偨椺偲偟偰報徾偵巆偭偰偄傞丅丂丂岆栿偵偟傠捒栿偵偟傠柤栿偵偟傠丄擔杮岅栿偺嬋柤偵偼枴偑偁傞偟丄弫偄偑姶偠傜傟傞偟丄嬋偺僀儊乕僕偑晜偐傫偱偔傞丅偦傟偵斾傋偰丄僞僇僞僇偺嬋柤偺側傫偲柍婡揑偱枴婥側偄偙偲偐丅偙傫側偲偙傠偵傕丄嶐崱偺梞妝億僢僾僗悐戅偺堦場偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅
2010.02.16 (壩) 懴偊傞抝偺旤偟偝傪昤偒懕偗偨僨傿僢僋丒僼儔儞僔僗
傏偔偼擔杮偱嵟弶偵東栿弌斉偝傟偰埲棃丄僼儔儞僔僗偺彫愢傪寚偐偝偢撉傫偱偒偨丅嵟弶偵弌偨偺偼丄杮崙僀僊儕僗偱偼戞3嶌偺乽嫽暠乿偩偭偨丅傏偔偑傑偩戝妛惗偺偙傠偩丅帒椏傪尒傞偲1967擭偩偭偨傛偆偩丅偡偱偵偦偺帪揰偱丄僀僊儕僗偱偼5嶌傕敪攧偝傟偰偄偨丅偩偐傜擔杮傊偺徯夘偼偐側傝抶傟偨偙偲偵側傞丅偦傟偐傜戞4嶌偺乽戝寠乿偑東栿偝傟丄傗偭偲擔杮岅斉戞3抏偲偟偰丄杮崙戞1嶌偺乽杮柦乿偑敪攧偝傟偨丅埲屻偼傎傏弴傪捛偭偰丄僀僊儕僗偱敪昞偝傟傞偛偲偵東栿偝傟偰偒偨丅
傏偔偼嫞攏偵偼傑偭偨偔嫽枴偑側偄偑丄僼儔儞僔僗偺嫞攏僔儕乕僘偵偼怱傪扗傢傟偨丅僼儔儞僔僗偺儈僗僥儕乕偼丄嫞攏偼偁偔傑偱慺嵽偱偁傝丄杮幙偼朻尟揑側怓嵤傪懷傃偨僴乕僪儃僀儖僪彫愢偩偭偨丅庡恖岞偼丄偮偹偵帺暘側傝偺峴摦婯斖偲抝偲偟偰偺僾儔僀僪傪傕偮丄崕屓怱偵晉傫偩恖娫偩丅偦傫側抝偑丄媡嫬傪偼偹偺偗丄斱楎側朩奞偵懴偊丄惷偐側摤巙傪嫻偵旈傔側偑傜丄嫞攏奅偵偼傃偙傞晄惓傗堿杁傪朶偔丅庡恖岞偨偪偼偗偭偟偰僗乕僷乕僸乕儘乕偱偼側偄丅偲偒偵偼揋偵懆偊傜傟偰捝傔偮偗傜傟丄嫲晐偺偁傑傝幐嬛偟偨傝傕偡傞丅偩偑恖娫偲偟偰偺屩傝偲堄抧偼幐傢側偄丅忈奞嫞攏偺婻庤偼偮偹偵嫲晐偲摤偭偰偄傞丄偲斵偼彂偄偰偄傞丅僼儔儞僔僗偼丄恖偼偄偐偵偟偨傜嫲晐傪崕暈偡傞偙偲偑偱偒傞偐傪昤偒偨偐偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅斵偺彫愢偵偼丄懴偊傞抝偺旤偟偝偑偁偭偨丅偦傟偼僴乕僪儃僀儖僪偺恀悜偦偺傕偺偩丅偦傫側抝偺暔岅偵傏偔偨偪偼嫻傪擬偔偟偨丅
僼儔儞僔僗偺嫞攏僔儕乕僘偼慡晹偱43嶌偁傞丅擔杮偱偼偡傋偰憗愳彂朳偐傜敪攧偝傟偰偄傞丅傏偔偑偄偪偽傫垽拝偑偁傞偺偼丄弶婜偺10嶌傎偳丄乽杮柦乿乮1962乯偐傜乽墝枊乿乮1972乯偁偨傝傑偱偱偁傞丅偙傟傜偼丄偳傟傕懟怓側偔丄埑搢揑偵偍傕偟傠偄丅偙偺僔儕乕僘偼嵟弶偺偆偪偼憗愳億働儈僗偱弌偰偄偨偑丄搑拞偐傜扨峴杮偵側偭偨丅偲偙傠偑丄偪傚偆偳扨峴杮偵愗傝懼傢偭偨偁偨傝偐傜丄旝柇偵僩乕儞僟僂儞偟偰偒偨丅弶婜偺偙傠偺擹枾側婥敆偑側偔側偭偰偒偨偟丄恖娫憸偺堿塭傕敄傟丄僒僗儁儞僗偺枴傕撦偭偰偒偨丅偦傟偱傕撉傒懕偗偨偺偼丄僼儔儞僔僗撈摿偺嬻婥偼帩懕偝傟偰偄偨偐傜偩丅枅擭丄擭枛偵弌傞怴嶌偑妝偟傒偩偭偨丅2000擭偵媥巭偟偨偲偒偼庘偟偝傪妎偊偨偑丄5擭偺嬻敀傪宱偰嵞婲偟偨偲偒偼婐偟偐偭偨丅80嵨傪挻偊偰側偍斵偑彂偔堄梸傪傒偣偨偙偲偵妳嵮傪憲偭偨丅撪梕偲偟偰偼丄慡惙婜偺弌棃偵偼斾傋傞傋偔傕側偐偭偨偑丄偦傟偱傕僼儔儞僔僗傜偟偄暤埻婥偼曐偭偰偍傝丄廩暘偵撉傓妝偟傒傪枴傢傢偣偰偔傟偨丅
嬃偔傋偒偙偲偵僼儔儞僔僗偼丄偙傟偩偗懡偔偺彫愢傪彂偄偰偄傞偺偵丄4嶌偵嶶敪揑偵搊応偡傞惽榬偺尦婻庤僔僢僪丒僴儗乕傪彍偒丄摨堦偺恖暔傪搊応偝偣偰偄側偄丅儈僗僥儕乕嶌壠偼丄傾僀僨傾偑搑愗傟偨偲偒傗嶌壠偲偟偰嬋偑傝妏偵棃偨偲偒丄摨堦偺庡恖岞傪巊偭偰僔儕乕僘壔偡傞偙偲偑懡偄丅偦偺傎偆偑彂偒傗偡偄偐傜偩偑丄偦傫側応崌丄偦傟傑偱偺惃偄偑幐懍偡傞働乕僗偑傎偲傫偳偩丅僊儍償傿儞丒儔僀傾儖偟偐傝丄A. J. 僋傿僱儖偟偐傝丄億乕儔丒儃僘儕儞僌偟偐傝丅傒側丄偦傟傑偱偼偝傑偞傑側庡恖岞偵傛偭偰撉傒墳偊偺偁傞彫愢傪彂偄偰偒偨偺偵丄摨堦偺庡恖岞偱僔儕乕僘壔偟偨偲偨傫丄偮傑傜側偔側偭偰偟傑偭偨丅偩偑僼儔儞僔僗偼偦偺曽岦偵偼峴偐側偐偭偨丅偙傟偼婓桳側偙偲偩偲巚偆丅偩偐傜丄弶婜偲拞屻婜偱偼弌棃偵嵎偑偁傞傕偺偺丄堦娧偟偰崅悈弨傪堐帩偱偒偨偺偩偲巚偆丅
僼儔儞僔僗偺彫愢偼丄2000擭偺拞抐傑偱丄偡傋偰媏抧岝偑栿偟偰偄傞丅柤栿偲偄偆恖傕懡偄偑丄傏偔偼堎榑偑偁傞丅偨偟偐偵嵟弶偺偆偪偼帟愗傟偺偄偄僔儞僾儖側暥懱偑偄偄偲巚偭偨偑丄壗嶜傕撉傫偱偄傞偆偪偵丄偄偮傕傑偭偨偔摨偠挷巕丄摨偠僷僞乕儞側偺偵掞峈姶傪妎偊傞傛偆偵側偭偨丅傑偢丄傗偨傜偵庡岅偑徣棯偝傟傞丅偦傟偐傜偳偺彫愢偺庡恖岞傕夛榖偺尵梩偑偑偄偮傕摨偠岥挷偵側偭偰偄傞丅偝傜偵偼丄媏抧岝偑栿偟偨懠偺彫愢丄偨偲偊偽儘僶乕僩丒B丒僷乕僇乕側偳偺栿暥偲僼儔儞僔僗偺栿暥偑丄傑偭偨偔摨偠挷巕偺暥懱側偺偩丅偮傑傝丄尨暥偵懄偟偰偍傜偢丄偳傟傕栿幰偺暥懱偱摑堦偝傟偰偟傑偭偰偄傞偺偩丅2006擭偺嵞婲埲屻偺彫愢偼丄媏抧偑惱嫀偟偨偺偱丄掜巕偩偲偄偆杒栰庻旤巬偑栿偟偰偄傞偑丄偙偪傜傎偆偑乮偍偦傜偔乯尨暥偵懄偟偰偍傝丄媏抧栿傛傝偼傞偐偵岲傑偟偔姶偠傞丅
東栿偺戣柤偵傕堘榓姶偑偁傞丅僼儔儞僔僗偺彫愢偼丄乽杮柦乿乽搙嫻乿乽嫽暠乿乽戝寠乿乽旘墇乿偲偄偭偨嬶崌偵丄偡傋偰娍帤2暥帤偱昞婰偝傟偰偄傞丅尨戣偑婎杮揑偵扨岅1岅偐2岅偩偐傜偲偄偆棟桼傕偁傞偺偩傠偆偑丄偟偐偟偙傟偩偲丄傒側帡偨傛偆側戣柤偵側偭偰偟傑偆偺偱丄偳傟偑偳傟偩偑幆暿偱偒側偄丅僼儔儞僔僗偺彫愢偵偼丄嫞攏娭學幰偩偗偱側偔丄偄傠傫側怑嬈偺恖暔偑庡恖岞偲偟偰搊応偡傞偑丄偨偲偊偽僀僊儕僗偺挸曬晹堳偑峴曽晄柧偵側偭偨柤攏傪憑嶕偡傞偺偼偳傟偩偭偗丄恖婥攐桪偑撿傾僼儕僇偱妶桇偡傞偺偼側傫偰偄偆彫愢偩偭偗丄偲巚偭偰傕丄戣柤偑晜偐傫偱偙側偄偺偩丅彫愢偺柺敀偝偲偼娭學側偄偙偲偱偁傞偵偣傛丄僼傽儞偲偟偰偼崲偭偨偙偲偱偼偁傞丅
傂偲偙傠丄僼儔儞僔僗偺彫愢偼偡傋偰嵢偺儊傾儕乕偑彂偄偰偄偨偲偄偆僯儏乕僗偑旘傃岎偭偨偙偲偑偁傞丅偨偟偐偵挷嵏傗峔惉側偳偱嵢偑嫤椡偟偰偄偨偺偼帠幚傜偟偄丅恀幚偼晄柧偩偑丄偨偲偊嵢偑彂偄偰偄偨偵偣傛丄嫞攏僔儕乕僘偑慺惏傜偟偄儈僗僥儕乕彫愢偩偭偨偙偲偵曄傢傝偼側偄丅2006擭偺嵞婲埲崀偼懅巕偺僼僃儕僢僋僗偑嫤椡偟偰偒偨偲偄偆丅嵞婲戞2嶌埲崀偼僼僃儕僢僋僗偲偺嫟挊偵側偭偰偄傞丅僼儔儞僔僗朣偒偁偲丄偳偆側傞偺偐暘偐傜側偄偑丄嵞婲埲崀偺彫愢偺弌棃偐傜偟偰僼僃儕僢僋僗偵嵥擻偑偁傞偙偲偼妋偐側傛偆側偺偱丄偱偒傟偽斵偵晝偺堖敨傪宲偄偱彂偒懕偗偰傕傜偄偨偄傕偺偩丅
2009.12.26 (搚) 2009擭塮夋儀僗僩10
1丏儗僗儔乕 乮娔撀丗僟乕儗儞丒傾儘僲僼僗僉乕丂2008擭暷乯
2丏斷傪偨偨偔恖 乮娔撀丗僩儉丒儅僢僇乕僔乕丂2008擭暷乯
3丏僌儔儞丒僩儕僲 乮娔撀丗僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪丂2008擭暷乯
4丏僗儔儉僪僢僌亹儈儕僆僱傾 乮娔撀丗僟僯乕丒儃僀儖丂2008擭塸乯
5丏岾偣偼僔儍儞僜僯傾寑応偐傜 乮娔撀丗僋儕僗僩僼丒僶儔僥傿僄丂2008擭暓乯
6丏僂僃僨傿儞僌丒儀儖傪柭傜偣 乮娔撀丗僄儈乕儖丒僋儕僗僩儕僢僣傽丂2007擭僙儖價傾/暓乯
7丏惓媊偺備偔偊乣IEC摿暿憑嵏姱 乮娔撀丗僂僃僀儞丒僋儔儅乕丂2009擭暷乯
8丏僀儞僌儘儕傾僗丒僶僗僞乕僘 乮娔撀丗僋僄儞僥傿儞丒僞儔儞僥傿乕僲丂2009擭暷乯
9丏僷僀儗乕僣丒儘僢僋 乮娔撀丗儕僠儍乕僪丒僇乕僥傿僗丂2009擭塸/撈乯
10丏儀儞僕儍儈儞丒僶僩儞乣悢婏側恖惗 乮娔撀丗僨償傿僢僪丒僼傿儞僠儍乕丂2008擭暷乯
憡曄傢傜偢丄嬥傪偐偗偨僴儕僂僢僪塮夋偵偼丄婰壇偵從偒偮偔傛偆側傕偺偼側偐偭偨偟丄偨偔偝傫偮偔傜傟偰偄傞擔杮偺塮夋傕尒傛偆偲偄偆婥偵偝偣傜傟傞傕偺偼側偐偭偨丅偄偄塮夋偩偭偨偲怱偵崗傒崬傑傟傞偺偼丄傗偼傝嶌傝庤偵慽偊偨偄傕偺丄昞尰偟偨偄傕偺偑偁傝丄偦傟偑柧妋偵岻偔帵偝傟偨嶌昳偲偄偆偙偲偵側傞丅
 1埵偵嫇偘偨乽儗僗儔乕乿偵偼丄椡偑悐偊丄棊偪傇傟偰傕側偍僾儔僀僪傪帩偭偰惗偒傛偆偲偡傞儗僗儔乕偺巔偑昤偐傟傞丅晄婍梡側斵偼怱偑棧傟偨柡偲偺娭學傪廋暅偱偒側偄偟丄崨傟偁偭偨僗僩儕僢僷乕偲偺垽傕惉廇偱偒側偄丅梕杄夽執偵曄恎偟偨庡墘偺儈僢僉乕丒儘乕僋偼偼傑偝偵揔栶偩偟丄僗僩儕僢僷乕栶偺戝岲偒側儅儕僒丒僩儊僀偺墘媄傕愨昳偩丅2埵偺乽斷傪偨偨偔恖乿傕墱怺偄塮夋偩丅屒撈側榁戝妛嫵庼偲奜崙偐傜棃偨庒幰偲偺怱偺怗傟崌偄偲丄拞嬤搶弌恎幰傊偺晄摉側嵎暿偺幚懺偑昤偐傟傞丅庡墘偺儕僠儍乕僪丒僕僃儞僉儞僗偑偄偄枴傪弌偟偰偄傞偟丄抂栶傕娷傔偰弌墘幰慡堳偺帺慠側墘媄偑儕傾儕僥傿傪惗傫偱偄傞丅岞奐摉帪丄慡暷偱偨偭偨4娰偱偺忋塮偩偭偨偑丄偟偩偄偵拲栚偝傟丄嵟廔揑偵偼270娰偵奼戝偟丄6偐寧偵傢偨傞儘儞僌丒儔儞偵側偭偨偲偄偆榖偵偼丄傾儊儕僇偺椙怱傪尒傞巚偄偑偡傞丅
1埵偵嫇偘偨乽儗僗儔乕乿偵偼丄椡偑悐偊丄棊偪傇傟偰傕側偍僾儔僀僪傪帩偭偰惗偒傛偆偲偡傞儗僗儔乕偺巔偑昤偐傟傞丅晄婍梡側斵偼怱偑棧傟偨柡偲偺娭學傪廋暅偱偒側偄偟丄崨傟偁偭偨僗僩儕僢僷乕偲偺垽傕惉廇偱偒側偄丅梕杄夽執偵曄恎偟偨庡墘偺儈僢僉乕丒儘乕僋偼偼傑偝偵揔栶偩偟丄僗僩儕僢僷乕栶偺戝岲偒側儅儕僒丒僩儊僀偺墘媄傕愨昳偩丅2埵偺乽斷傪偨偨偔恖乿傕墱怺偄塮夋偩丅屒撈側榁戝妛嫵庼偲奜崙偐傜棃偨庒幰偲偺怱偺怗傟崌偄偲丄拞嬤搶弌恎幰傊偺晄摉側嵎暿偺幚懺偑昤偐傟傞丅庡墘偺儕僠儍乕僪丒僕僃儞僉儞僗偑偄偄枴傪弌偟偰偄傞偟丄抂栶傕娷傔偰弌墘幰慡堳偺帺慠側墘媄偑儕傾儕僥傿傪惗傫偱偄傞丅岞奐摉帪丄慡暷偱偨偭偨4娰偱偺忋塮偩偭偨偑丄偟偩偄偵拲栚偝傟丄嵟廔揑偵偼270娰偵奼戝偟丄6偐寧偵傢偨傞儘儞僌丒儔儞偵側偭偨偲偄偆榖偵偼丄傾儊儕僇偺椙怱傪尒傞巚偄偑偡傞丅 3埵偺乽僌儔儞丒僩儕僲乿偼偄偐偵傕僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪傜偟偄嶌昳丅嬝棫偰偼傓偐偟偺惣晹寑偺僷僞乕儞偺尰戙斉傪巚傢偣傞丅婃屌側恖庬嵎暿庡媊幰偺塀嫃偟偨尦帺摦幵岺偑丄椬壠偺拞崙偐傜偺堏柉壠懓偲恊偟偔側傝丄偦偺壠偺彮擭傪抝偲偟偰抌偊丄埆鐓側拞崙宯僠儞僺儔偲懳寛偡傞榖偱丄偒傟偄偵傑偲傑偭偰偄傞丅偨偩偟丄僄儞僨傿儞僌偺昤偒曽偵偼堘榓姶偑偁傞丅4埵偺乽僗儔儉僪僢僌亹儈儕僆僱傾乿偼僆僗僇乕傪庴徿偟丄悽奅拞偱僸僢僩偟偨榖戣偺塮夋偩丅僀儞僪偺戝搒巗儉儞僶僀偺僗儔儉奨偱堢偭偨惵擭偺攇棎枩忎偺恖惗偑丄偝傑偞傑側僄僺僜乕僪傪嶶傝偽傔側偑傜價儖僪僁僀儞僌僗儘儅儞晽偵偮偯傜傟偰偄偔丅僄儞僞僥僀儞儊儞僩偲偟偰偡偖傟偰偄傞偟丄儔僗僩偺僀儞僪塮夋偍寛傑傝偺僟儞僗傕妝偟偄丅偲偼偄偊丄僀儞僪幮夛偺幚懺偼偙傫側傕偺偱偼側偄偩傠偆丅
3埵偺乽僌儔儞丒僩儕僲乿偼偄偐偵傕僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪傜偟偄嶌昳丅嬝棫偰偼傓偐偟偺惣晹寑偺僷僞乕儞偺尰戙斉傪巚傢偣傞丅婃屌側恖庬嵎暿庡媊幰偺塀嫃偟偨尦帺摦幵岺偑丄椬壠偺拞崙偐傜偺堏柉壠懓偲恊偟偔側傝丄偦偺壠偺彮擭傪抝偲偟偰抌偊丄埆鐓側拞崙宯僠儞僺儔偲懳寛偡傞榖偱丄偒傟偄偵傑偲傑偭偰偄傞丅偨偩偟丄僄儞僨傿儞僌偺昤偒曽偵偼堘榓姶偑偁傞丅4埵偺乽僗儔儉僪僢僌亹儈儕僆僱傾乿偼僆僗僇乕傪庴徿偟丄悽奅拞偱僸僢僩偟偨榖戣偺塮夋偩丅僀儞僪偺戝搒巗儉儞僶僀偺僗儔儉奨偱堢偭偨惵擭偺攇棎枩忎偺恖惗偑丄偝傑偞傑側僄僺僜乕僪傪嶶傝偽傔側偑傜價儖僪僁僀儞僌僗儘儅儞晽偵偮偯傜傟偰偄偔丅僄儞僞僥僀儞儊儞僩偲偟偰偡偖傟偰偄傞偟丄儔僗僩偺僀儞僪塮夋偍寛傑傝偺僟儞僗傕妝偟偄丅偲偼偄偊丄僀儞僪幮夛偺幚懺偼偙傫側傕偺偱偼側偄偩傠偆丅5埵偺乽岾偣偼僔儍儞僜僯傾寑応偐傜乿偼怱壏傑傞塮夋偩丅戞2師戝愴慜栭偺僷儕丄壓挰偺墘寍応傪晳戜偵偟偨恖忣榖偱丄寑応傪垽偡傞壓挰偺恖乆偺怱堄婥丄晝偲巕偺愗側偄鉐偑丄嫽庯備偨偐偵昤偐傟傞丅偪傚偭偲僼儔儞
 僋丒僟儔儃儞娔撀偺乽儅僕僃僗僥傿僢僋乿傪巚傢偣傞丅摿昅偡傋偒偼壧庤巙朷偺柡傪墘偠傞僲儔丒傾儖僱僛僨乕儖丅偦偺旤偟偝偲懚嵼姶偼扅幰偱偼側偄丅6埵偺乽僂僃僨傿儞僌丒儀儖傪柭傜偣乿偼廍偄傕偺偩偭偨丅堦晹偵擬怱側僼傽儞傪帩偮儐乕僑僗儔價傾偺娔撀僋儕僗僩儕僢僣傽偺嶌昳偱丄揷幧偐傜搒夛偵壴壟扵偟偵傗偭偰偒偨弮杙側彮擭偑憳嬾偡傞捒憶摦傪昤偄偨僐儊僨傿丅夋柺偐傜偁傆傟傞償傽僀僞儕僥傿偲戝傜偐側儐乕儌傾偲偺偳偐側恖惗嶿壧偼丄棟孅敳偒偱尒傞幰傪僴僢僺乕側婥暘偵偝偣偰偔傟傞丅
僋丒僟儔儃儞娔撀偺乽儅僕僃僗僥傿僢僋乿傪巚傢偣傞丅摿昅偡傋偒偼壧庤巙朷偺柡傪墘偠傞僲儔丒傾儖僱僛僨乕儖丅偦偺旤偟偝偲懚嵼姶偼扅幰偱偼側偄丅6埵偺乽僂僃僨傿儞僌丒儀儖傪柭傜偣乿偼廍偄傕偺偩偭偨丅堦晹偵擬怱側僼傽儞傪帩偮儐乕僑僗儔價傾偺娔撀僋儕僗僩儕僢僣傽偺嶌昳偱丄揷幧偐傜搒夛偵壴壟扵偟偵傗偭偰偒偨弮杙側彮擭偑憳嬾偡傞捒憶摦傪昤偄偨僐儊僨傿丅夋柺偐傜偁傆傟傞償傽僀僞儕僥傿偲戝傜偐側儐乕儌傾偲偺偳偐側恖惗嶿壧偼丄棟孅敳偒偱尒傞幰傪僴僢僺乕側婥暘偵偝偣偰偔傟傞丅7埵偺乽惓媊偺備偔偊乿偼堏柉傗晄朄懾嵼幰側偳丄奜崙偐傜傾儊儕僇偵棳傟崬傫偱偔傞恖乆傪偲傝傑偔尩偟偄娐嫬傪昤偄偨僔儕傾僗側塮夋丅乽斷傪偨偨偔恖乿偵帡偰偄傞偑丄偙偪傜偺傎偆偑丄傕偭偲媬偄傛偆偺側偄尰幚傪捈帇偟偰偄傞丅妛峑偱丄偪傚偭偲傾儔僽恖傪梚岇偡傞敪尵傪偟偨偨傔FBI偐傜僗僷僀偺寵媈傪偐偗傜傟傞彈惗搆偺憓榖偑偱偰偔傞偑丄偙偺傛偆側棟晄恠側帠審偼幚嵺偵婲偙偭偰偄傞偺偩傠偆丅戝僗僞乕偺僴儕僜儞丒僼僅乕僪偑傛偔偙傫側抧枴側塮夋偵弌墘偟偨傕偺偩丅娔撀偺僂僃僀儞丒僋儔儅乕偼愗傟偺偄偄傾僋僔儑儞塮夋乽儚僀儖僪丒僶儗僢僩乿偱傏偔偑傂
 偦偐偵拲栚偟偰偄偨恖偩丅8埵偺乽僀儞僌儘儕傾僗丒僶僗僞乕僘乿偼偛懚抦僞儔儞僥傿乕僲偺怴嶌丅戞2師戝愴拞丄僽儔僢僪丒僺僢僩傪戉挿偲偡傞僪僀僣偵愽擖偟偨傾儊儕僇偺摿庩晹戉偺攋揤峳側朶傟傇傝偑昤偐傟傞偑丄戝偒側僥乕儅偼丄壠懓慡堳傪僫僠偵媠嶦偝傟偨儐僟儎彮彈偺暅廞鏉偩丅惉挿偟偨斵彈偵暞偡傞儊儔僯乕丒儘儔儞偼弶傔偰尒偨偑丄昳奿偺偁傞旤偟偄彈桪偩丅乽僔儍儞僜僯傾寑応乣乿偺傾儖僱僛乕儖偲偄偄丄僼儔儞僗偵偼彨棃桳朷側彈桪偑偨偔偝傫偄傞丅寑応傪敋攋偟偰僫僠偺梫恖傪奆嶦偟偵偡傞応柺偵側偭偰丄偙傟偼峳搨柍宮側僼傽儞僞僕乕側偺偩偲擺摼偡傞丅僞儔儞僥傿乕僲摼堄偺巆崜僔乕儞偼傢傝偁偄峊偊傔偩偟丄榖偲偟偰偼妝偟傔傞丅9埵埲壓偵偮偄偰偼妱垽丅
偦偐偵拲栚偟偰偄偨恖偩丅8埵偺乽僀儞僌儘儕傾僗丒僶僗僞乕僘乿偼偛懚抦僞儔儞僥傿乕僲偺怴嶌丅戞2師戝愴拞丄僽儔僢僪丒僺僢僩傪戉挿偲偡傞僪僀僣偵愽擖偟偨傾儊儕僇偺摿庩晹戉偺攋揤峳側朶傟傇傝偑昤偐傟傞偑丄戝偒側僥乕儅偼丄壠懓慡堳傪僫僠偵媠嶦偝傟偨儐僟儎彮彈偺暅廞鏉偩丅惉挿偟偨斵彈偵暞偡傞儊儔僯乕丒儘儔儞偼弶傔偰尒偨偑丄昳奿偺偁傞旤偟偄彈桪偩丅乽僔儍儞僜僯傾寑応乣乿偺傾儖僱僛乕儖偲偄偄丄僼儔儞僗偵偼彨棃桳朷側彈桪偑偨偔偝傫偄傞丅寑応傪敋攋偟偰僫僠偺梫恖傪奆嶦偟偵偡傞応柺偵側偭偰丄偙傟偼峳搨柍宮側僼傽儞僞僕乕側偺偩偲擺摼偡傞丅僞儔儞僥傿乕僲摼堄偺巆崜僔乕儞偼傢傝偁偄峊偊傔偩偟丄榖偲偟偰偼妝偟傔傞丅9埵埲壓偵偮偄偰偼妱垽丅
 僥儗價曻塮偝傟偨塮夋偱偼丄WOWOW偱10寧偵曻憲偝傟偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖摿廤偑傛偐偭偨丅乽忋奀偐傜棃偨彈乿乽忺憢偺彈乿乽僉僢僗偱嶦偣乿側偳偼桳柤偩偟價僨僆壔傕偝傟偰偄傞偑丄僕儍僢僋丒僞乕僫乕偺乽梉曢傟偺偲偒乿丄僕儑僙僼丒H丒儖僀僗偺乽旈枾挷嵏堳乿丄僟僌儔僗丒僒乕僋偺乽僔儑僢僋僾儖乕僼乿丄僕儑僙僼丒儘乕僕乕偺乽戝偄側傞栭乿側偳丄偙傟傑偱杮偺婰弎偱偟偐抦傜側偐偭偨枹岞奐塮夋丄枹價僨僆壔塮夋傪尒傞偙偲偑偱偒偨偺偼偁傝偑偨偐偭偨丅傑偨摨偠偔WOWOW偱12寧曻憲偺儘僶乕僩丒傾儖僪儕僢僠摿廤傕丄弶婜偺擔杮枹岞奐嶌昳偑娷傑傟偰偍傝丄桳堄媊偩偭偨丅摨偠塮夋偽偐傝孞傝曉偟曻憲偟偰偄傞NHK-BS偵斾傋丄帺幮惂嶌偺偮傑傜側偄2帪娫僪儔儅偼婅偄壓偘偩偑丄偙偆偄偆捒偟偄婱廳側塮夋傪曻憲偟偰偑傫偽偭偰偄傞WOWOW偵攺庤傪憲傝偨偄丅
僥儗價曻塮偝傟偨塮夋偱偼丄WOWOW偱10寧偵曻憲偝傟偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖摿廤偑傛偐偭偨丅乽忋奀偐傜棃偨彈乿乽忺憢偺彈乿乽僉僢僗偱嶦偣乿側偳偼桳柤偩偟價僨僆壔傕偝傟偰偄傞偑丄僕儍僢僋丒僞乕僫乕偺乽梉曢傟偺偲偒乿丄僕儑僙僼丒H丒儖僀僗偺乽旈枾挷嵏堳乿丄僟僌儔僗丒僒乕僋偺乽僔儑僢僋僾儖乕僼乿丄僕儑僙僼丒儘乕僕乕偺乽戝偄側傞栭乿側偳丄偙傟傑偱杮偺婰弎偱偟偐抦傜側偐偭偨枹岞奐塮夋丄枹價僨僆壔塮夋傪尒傞偙偲偑偱偒偨偺偼偁傝偑偨偐偭偨丅傑偨摨偠偔WOWOW偱12寧曻憲偺儘僶乕僩丒傾儖僪儕僢僠摿廤傕丄弶婜偺擔杮枹岞奐嶌昳偑娷傑傟偰偍傝丄桳堄媊偩偭偨丅摨偠塮夋偽偐傝孞傝曉偟曻憲偟偰偄傞NHK-BS偵斾傋丄帺幮惂嶌偺偮傑傜側偄2帪娫僪儔儅偼婅偄壓偘偩偑丄偙偆偄偆捒偟偄婱廳側塮夋傪曻憲偟偰偑傫偽偭偰偄傞WOWOW偵攺庤傪憲傝偨偄丅
2009.12.20 (擔) 2009擭奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10
丂丂嵟嬤偼東栿儈僗僥儕乕偑攧傟偢丄弌斉幮偩偗偱側偔東栿幰傕嬯偟偄忬嫷偵偁傞丅偦傫側側偐偱丄崱擭10寧丄東栿儈僗僥儕乕戝徿僔儞僕働乕僩側傞傕偺偑丄儈僗僥儕乕東栿幰偨偪偵傛偭偰愝棫偝傟偨丅彂揦堳偑慖峫偡傞杮壆戝徿偑乬擔杮偺彫愢乭偩偗傪懳徾偲偟偰偄傞偺偵懳峈偟丄杮壆戝徿偺岦偙偆傪挘偭偰丄東栿幰偨偪偺搳昜偵傛傝東栿儈僗僥儕乕偺戝徿傪慖傇偲偄偆丅徿偺慖掕偲暲峴偟偰乽東栿儈僗僥儕乕戝徿僔儞僕働乕僩乿偲偄偆僒僀僩傪塣塩偟丄慖峫夁掱傗僄僢僙僀傪嵹偣偰奀奜儈僗僥儕乕偺妶惈壔傪偼偐傞傜偟偄丅偙傟偵傛偭偰偳偙傑偱撉幰傪憹傗偣傞偐暘偐傜側偄偑丄彮偟偱傕奀奜儈僗僥儕乕偵怴晽傪悂偒崬傒丄暅嫽偺偒偭偐偗偵側偭偰偔傟傟偽丄僼傽儞偲偟偰偼偆傟偟偄丅傕偭偲傕丄傆偨傪偁偗偰傒傟偽丄崱擭搙偺慖峫偺寢壥偑乽儈儗僯傾儉乿傗乽將偺椡乿偩偭偨偲偟偨傜丄婛懚偺儔儞僉儞僌偲曄傢傝塮偊偟側偄偙偲偵側傞偑丅
丂丂偲偄偆偙偲偱丄崱擭偺巹揑奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10傪嫇偘偰偍偙偆丅
1丏將偺椡/僪儞丒僂傿儞僘儘僂乮妏愳暥屔乯
2丏栰朷偺奒抜/儕僠儍乕僪丒俶丒僷僞乕僜儞乮PHP尋媶強乯
3丏乽儈儗僯傾儉乿3晹嶌/僗僥傿乕僌丒儔乕僜儞乮憗愳彂朳乯
4丏棐傪憱傞幰/俿丒僕僃僼傽僜儞丒僷乕僇乕乮僴儎僇儚暥屔乯
5丏僜僂儖丒僐儗僋僞乕/僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕乮暥錣弔廐幮乯
6丏戝惞摪乣壥偰偟側偒悽奅/働儞丒僼僅儗僢僩乮僜僼僩僶儞僋暥屔乯
7丏崟堖偺張孻恖/僩儉丒働僀儞乮怴挭暥屔乯
8丏嵟崅張孻愑擟幰/僕儑僙僼丒僼傿儞僟乕乮怴挭暥屔乯
9丏儕儞僇乕儞曎岇巑/儅僀僋儖丒僐僫儕乕乮島択幮暥屔乯
10丏屩傝偲忣擬/僕僃僼儕乕丒傾乕僠儍乕乮怴挭暥屔乯
丂丂乽將偺椡乿偼丄傏偔偵偲偭偰傇偭偪偓傝偺1埵偩丅偙偺杮偺慺惏傜偟偝偵偮偄偰偼丄10寧8擔晅偗偺杮棑偵彂偄偨偲偍傝丅DEA憑嵏姱丄杻栻僇儖僥儖偺儃僗丄僯儏乕儓乕僋偺嶦偟壆偨偪偺怐傝側偡桭忣偲垽丄棤愗傝偲峈憟偺暔岅偼丄埑搢揑側敆椡偱撉傓幰傪枺椆偡傞丅僉儍儔僋僞乕憿宍偑尒帠偩偟丄昤幨椡傕堦媺昳丅巆崜側僔乕儞傕偁傞偑撉屻姶偼晄巚媍偵偝傢傗偐偩丅2埵偺乽栰朷偺奒抜乿偵偮偄偰傕丄7寧30擔晅偺僐儔儉偱怗傟偨丅傾儊儕僇偺戝摑椞慖偵傑偮傢傞榖偱偁傝丄尩枾偵偼儈僗僥儕乕偱偼側偄偑丄柺敀偝偼敳孮丅僷僞乕僜儞偺僗僩乕儕乕僥儕儞僌偺岻偝偵悓傢偝傟傞丅偙偺杮偑傎偲傫偳榖戣偵忋傜側偄偺偼丄儅僀僫乕側敪攧尦偩偐傜偩傠偆偐丅
丂丂儀僗僩僙儔乕偵側偭偨3埵偺乽儈儗僯傾儉乿3晹嶌偼崱擭堦斣偺榖戣嶌偩傠偆丅偨偟偐偵柺敀偝偼敳孮偩丅撲夝偒丄朻尟僗儕儔乕丄僗僷僀杁棯丄朄掛僒僗儁儞僗偲丄偝傑偞傑側梫慺偑媗傑偭偰偄傞丅偦偟偰僸儘僀儞偺巋惵彈儕僗儀僢僩偑偄偄丅斵彈偺恖暔憸偼嵺棫偭偰偍傝丄偠偮偵報徾怺偔丄儃僨傿僈乕僪丒傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偵弌偰偔傞彈扵掋僽儕僕僢僩傪渇渋偲偝偣傞丅偩偑丄庡恖岞偺儈僇僄儖偼偠傔丄偦傟埲奜偺搊応恖暔偨偪偑丄偄傠偄傠偲妶桇偡傞傢傝偵偼丄偳偆傕僉儍儔僋僞乕偲偟偰塭偑敄偄偟丄惗偒偨恖娫偲偟偰怱偵嬁偄偰偙側偄丅乬21悽婭偺儀僗僩丒儈僗僥儕乕乭側偳偲憶偑傟偰偄傞偗偳丄偦偙傑偱朖傔偪偓傞婥偵偼丄傏偔偼側傟側偄丅
丂丂4埵偺乽棐傪憱傞幰乿偼僒儞僨傿僄僑偺曐埨姱曗傪庡恖岞偲偡傞僴乕僪儃僀儖僪丅偁傑傝攈庤側惙傝忋偑傝偼側偄偑丄僕僃僼傽僜儞丒僷乕僇乕傜偟偄墱峴偒偺偁傞昤幨偲怱傗偝偟偄暤埻婥偑夣偄梋塁傪傕偨傜偡丅偙傫側偄偄彫愢偑丄偳偺儔儞僉儞僌偵傕擖偭偰偄側偄偺偼側偤偩傠偆丅5埵偺乽僜僂儖丒僐儗僋僞乕乿偼偍撻愼傒儕儞僇乕儞丒儔僀儉丒僔儕乕僘偺怴嶌丅IT傪嬱巊偡傞斊恖偲偄偆怴婡幉偼偁傞傕偺偺丄傗傗僗僩乕儕乕揥奐偺僷僞乕儞偑屌掕壔偟偰偟傑偭偨姶偼斲傔側偄丅偦傟偱傕堦婥偵撉傔偰偟傑偆偺偼丄僨傿乕償傽乕偺岅傝岥偺岻偝偺偣偄偩丅
丂丂6埵偺乽戝惞摪乣壥偰偟側偒悽奅乿偼丄18擭慜偵敪攧偝傟偰僸僢僩偟偨乽戝惞摪乿偺懕曇丅撪梕偲偟偰偼儈僗僥儕乕偲偄偆傛傝傕楌巎彫愢偺斖醗偵擖傞偩傠偆丅僀僊儕僗偺拞悽偺抧曽搒巗傪晳戜偵偟偨丄揤嵥揑側寶抸怑恖傪庡恖岞偵丄廋摴巑丄擈憁丄婻巑丄彜恖丄擾晇側偳懡悢偺恖暔偑搊応偡傞憇戝側暔岅偩丅偲偵偐偔柺敀偄丅惓幾擖傝棎傟偰孞傝峀偘傜傟傞攇棎枩忎偺僗僩乕儕乕偼丄挿戝偩偑嵟屻傑偱撉傒朞偒側偄丅嶌幰偺働儞丒僼僅儗僢僩偼丄乽恓偺娽乿側偳偺僗僷僀朻尟彫愢偱抦傜傟偰偄傞偑丄杮幙偼偙偆偄偭偨楌巎彫愢偺傎偆偵偁傞偲巚偆丅僼僅儗僢僩偼尰戙偺僨傿僢働儞僘偩偲尵偭偨傜朖傔偡偓偩傠偆偐丅
丂丂偁偲偼嬱偗懌偱偄偙偆丅7埵偺乽崟堖偺張孻恖乿偼塸崙摿庩晹戉偁偑傝偺巒枛壆偑妶桇偡傞僸乕儘乕丒傾僋僔儑儞彫愢丅僗僩乕儕乕偑暘偐傝傗偡偔丄撪梕揑偵偼寉偄偑丄僗僺乕僨傿側揥奐偼側偐側偐偺傕偺丅8埵偺乽嵟崅張孻愑擟幰乿偼擔杮偺戝婇嬈偺傾儊儕僇偺巕夛幮偵嬑傔傞塩嬈儅儞偑庡恖岞偺婇嬈僒僗儁儞僗彫愢丅偙傟傕榖偺僥儞億偑傛偔丄怺傒偼側偄偑撉傒偛偨偊偼廩暘偩丅嵟屻偺乽儕儞僇乕儞曎岇巑乿偲乽屩傝偲忣擬乿偵偮偄偰偼埲慜偺僐儔儉偱怗傟偨丅椉曽偲傕嶌幰偺嵟崅偺弌棃偐傜偼傎偳墦偄偑丄僗僩乕儕乕僥儕儞僌偺嵥偱撉傑偣傞丅
丂丂偦偺傎偐丄崱擭敪攧偝傟偨儈僗僥儕乕偺側偐偱偼僕儑儞丒僴乕僩嶌偺乽愳偼惷偐偵棳傟乿偑昡敾偑偄偄傛偆偩偑丄傏偔偵偼戅孅偩偭偨丅庡恖岞偺愝掕偑傕偆傂偲偮偼偭偒傝偟側偄偟丄僗僩乕儕乕偺棳傟傕傕偨傕偨偟偰偄傞丅乽僌儔乕僌57乿乽儐僟儎寈姱摨柨乿偼枹撉丅偑偭偐傝偟偨偺偼10寧偵敪攧偝傟偨僗僥傿乕償儞丒僴儞僞乕嶌儃僽丒儕乕丒僗儚僈乕丒僔儕乕僘偺嵟怴嶌乽墿崹偺慱寕庤乿丅傑傞偱僔僲僾僔僗傪撉傫偱偄傞傒偨偄偵拞恎偑僗僇僗僇偱擏晅偗偵寚偗偰偍傝丄僋儔僀儅僢僋僗傕偄偭偙偆偵惙傝忋偑傜側偄丅偁偺乽嬌戝幩掱乿傗乽庪傝偺偲偒乿偺擹枾側暤埻婥丄桸偒棫偮傛偆側僗儕儖偼偳偙偵傕側偄丅僴儞僞乕傕榁偄偨偺偩傠偆偐丅
2009.12.11 (嬥) 乽彮擭墹幰乿乗乗尪偺乽夦廱夊屨曆乿
 丂丂11寧15擔晅偗偺杮棑偱乽彮擭墹幰乿偺榖傪彂偄偨偁偲丄壨弌彂朳怴幮偐傜2008擭偵敪攧偝傟偨亀嶳愳憏帯乣乽彮擭墹幰乿乽彮擭働僯儎乿偺奊暔岅嶌幰亁偲偄偆價僕儏傾儖杮傪庤偵擖傟偨丅愴慜偐傜愴屻偵偐偗偰偺嶳愳憏帯偺巇帠丄婳愓偑丄嶌昳徯夘偲偲傕偵徻偟偔嵹偭偰偍傝丄傛傝怺偔嶳愳偝傫偺嬈愌傪抦傞偙偲偑偱偒偨丅偙偺杮偵丄1947擭偐傜1954擭偵偐偗偰敪姧偝傟偨僆儕僕僫儖扨峴杮偱偁傞偍傕偟傠暥屔斉乽彮擭墹幰乿偺戞1廤偐傜戞10廤傑偱偺昞巻偑偤傫傇宖嵹偝傟偰偄偨偑丄1984擭偵暅崗偝傟偨妏愳暥屔斉偺10姫偲撪梕偑堘偆偙偲偵婥偑偮偄偨丅嵟屻偺3姫偩偗丄偦傟偧傟偺曆柤傪暲傋偰傒傞丅
丂丂11寧15擔晅偗偺杮棑偱乽彮擭墹幰乿偺榖傪彂偄偨偁偲丄壨弌彂朳怴幮偐傜2008擭偵敪攧偝傟偨亀嶳愳憏帯乣乽彮擭墹幰乿乽彮擭働僯儎乿偺奊暔岅嶌幰亁偲偄偆價僕儏傾儖杮傪庤偵擖傟偨丅愴慜偐傜愴屻偵偐偗偰偺嶳愳憏帯偺巇帠丄婳愓偑丄嶌昳徯夘偲偲傕偵徻偟偔嵹偭偰偍傝丄傛傝怺偔嶳愳偝傫偺嬈愌傪抦傞偙偲偑偱偒偨丅偙偺杮偵丄1947擭偐傜1954擭偵偐偗偰敪姧偝傟偨僆儕僕僫儖扨峴杮偱偁傞偍傕偟傠暥屔斉乽彮擭墹幰乿偺戞1廤偐傜戞10廤傑偱偺昞巻偑偤傫傇宖嵹偝傟偰偄偨偑丄1984擭偵暅崗偝傟偨妏愳暥屔斉偺10姫偲撪梕偑堘偆偙偲偵婥偑偮偄偨丅嵟屻偺3姫偩偗丄偦傟偧傟偺曆柤傪暲傋偰傒傞丅| 偍傕偟傠暥屔 | 妏愳暥屔 | |
| 戞8廤 | 夝寛曆 | 傾儊儞儂僥僢僾嵿曮曆 |
| 戞9廤 | 僓儞僶儘曆 | 夝寛曆 |
| 戞10廤 | 夦廱夊屨曆 | 僓儞僶儘丒傾儊儕僇曆 |
偮傑傝丄妏愳暥屔斉偱偼丄僆儕僕僫儖偺偍傕偟傠暥屔斉偺嵟廔姫乽夦廱夊屨曆乿偑敳偗偰偄傞偺偩丅
 丂丂偙偺偲偙傠丄僽儘僌亀儕儏僂偪傖傫偺夰儊儘恖惗亁偺昅幰偱偁傞攷棗嫮婰偺乬儕儏僂偪傖傫乭偐傜丄儊乕儖偱偄傠偄傠偲偛嫵帵偟偰傕傜偭偰偄傞偑丄偦偺傗傝庢傝偺側偐偱丄乬乽彮擭墹幰乿偺暔岅偵偼丄恀屷偑傾儊儕僇偵搉偭偨偁偲丄嵞傃傾僼儕僇偵栠偭偰偔傞榖偑偁傞乭偙偲傪嫵偊偰偄偨偩偄偨丅傏偔偼偦傫側榖傪撉傫偩偙偲偑側偄偺偱丄傃偭偔傝偟偰偟傑偭偨丅偮傑傝丄妏愳暥屔偼乽僓儞僶儘丒傾儊儕僇曆乿偱廔傢偭偰偄傞偑丄幚嵺偵偼偦偺偁偲偺榖偑偁偭偨偙偲偵側傞丅妏愳偺暅崗斉慡10姫偼丄僆儕僕僫儖偺偍傕偟傠暥屔斉偺戞1廤偐傜戞9廤傑偱偟偐廂榐偝傟偰偍傜偢丄側偤偐嵟屻偺乽夦廱夊屨曆乿偼僇僢僩偝傟偨傢偗偩丅偦偟偰偙偺乽夦廱夊屨曆乿偵丄傾儊儕僇偐傜嵞傃傾僼儕僇偵栠偭偨恀屷偺妶桇偑彂偐傟偰偄傞偺偩傠偆丅偦偆偲抦偭偨傏偔偼丄側傫偲偐偟偰偦傟傪撉傒偨偄偲巚偭偨丅
丂丂偙偺偲偙傠丄僽儘僌亀儕儏僂偪傖傫偺夰儊儘恖惗亁偺昅幰偱偁傞攷棗嫮婰偺乬儕儏僂偪傖傫乭偐傜丄儊乕儖偱偄傠偄傠偲偛嫵帵偟偰傕傜偭偰偄傞偑丄偦偺傗傝庢傝偺側偐偱丄乬乽彮擭墹幰乿偺暔岅偵偼丄恀屷偑傾儊儕僇偵搉偭偨偁偲丄嵞傃傾僼儕僇偵栠偭偰偔傞榖偑偁傞乭偙偲傪嫵偊偰偄偨偩偄偨丅傏偔偼偦傫側榖傪撉傫偩偙偲偑側偄偺偱丄傃偭偔傝偟偰偟傑偭偨丅偮傑傝丄妏愳暥屔偼乽僓儞僶儘丒傾儊儕僇曆乿偱廔傢偭偰偄傞偑丄幚嵺偵偼偦偺偁偲偺榖偑偁偭偨偙偲偵側傞丅妏愳偺暅崗斉慡10姫偼丄僆儕僕僫儖偺偍傕偟傠暥屔斉偺戞1廤偐傜戞9廤傑偱偟偐廂榐偝傟偰偍傜偢丄側偤偐嵟屻偺乽夦廱夊屨曆乿偼僇僢僩偝傟偨傢偗偩丅偦偟偰偙偺乽夦廱夊屨曆乿偵丄傾儊儕僇偐傜嵞傃傾僼儕僇偵栠偭偨恀屷偺妶桇偑彂偐傟偰偄傞偺偩傠偆丅偦偆偲抦偭偨傏偔偼丄側傫偲偐偟偰偦傟傪撉傒偨偄偲巚偭偨丅丂丂偍傕偟傠暥屔斉乽彮擭墹幰乿偼丄偨傑偵僱僢僩偱攧傝偵弌偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄15,000墌側偳偲崅妟偩偟丄偡偖偵攧傟偰偟傑偆偺偱庤偵擖傟傞偺偼梕堈偱偼側偄丅儕儏僂偪傖傫偺僒僕僃僗僠儑儞偵傛傝丄傏偔偼乽夦廱夊屨曆乿傪丄擔杮偱弌斉偝傟偨偡傋偰偺弌斉暔傪廂廤丒曐懚偟偰偄傞偼偢偺崙夛恾彂娰偱墈棗偟傛偆偲巚偄棫偭偨丅僷僜僐儞偱専嶕偟偰乽彮擭墹幰乿偑強憼偝傟偰偄傞偙偲傪妋偐傔丄塱揷挰偺崙夛媍帠摪偺椬偵偁傞崙夛恾彂娰偵弌岦偄偨丅崙夛恾彂娰偵峴偔偺偼弶傔偰偺偙偲偩偭偨丅偟偐偟丄嶳愳憏帯傪娷傓帣摱彂偼偡傋偰巟晹恾彂娰偱偁傞忋栰偺崙嵺巕偳傕恾彂娰偵偁傞偙偲偑暘偐傝丄偦偺擔偼傓側偟偔婣戭丅擔傪夵傔偰忋栰岞墍偺偼偢傟丄寍戝偺嬤偔偵偁傞崙嵺巕偳傕恾彂娰偵峴偭偨丅
 丂丂崙嵺巕偳傕恾彂娰偱徻偟偔挷傋偨偲偙傠丄偍傕偟傠暥屔斉乽彮擭墹幰乿偼偁偭偨偑丄慡姫偼懙偭偰偄側偐偭偨丅偦偟偰巆擮側偙偲偵丄戞10廤偺乽夦廱夊屨曆乿偑側偐偭偨両丂専嶕偺寢壥丄乽夦廱夊屨曆乿偼丄偙傟傕巟晹恾彂娰偱偁傞戝嶃偺崙嵺帣摱暥妛娰偵偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅庢傝婑偣偼晄壜側偺偱丄撉傓偨傔偵偼戝嶃偵峴偐側偗傟偽側傜側偄丅偝傜偵丄椺偺嫶杮戝嶃晎抦帠偺偡偡傔傞嬞弅嵿惌曽恓偵傛傝丄崙嵺帣摱暥妛娰偼傕偆偡偖攑娰丄強憼恾彂偼晎棫拞墰恾彂娰偵堏愝偡傞偙偲偵側傝丄偦偺弨旛偺偨傔12寧28擔偐傜媥娰偩偲偄偆丅
丂丂崙嵺巕偳傕恾彂娰偱徻偟偔挷傋偨偲偙傠丄偍傕偟傠暥屔斉乽彮擭墹幰乿偼偁偭偨偑丄慡姫偼懙偭偰偄側偐偭偨丅偦偟偰巆擮側偙偲偵丄戞10廤偺乽夦廱夊屨曆乿偑側偐偭偨両丂専嶕偺寢壥丄乽夦廱夊屨曆乿偼丄偙傟傕巟晹恾彂娰偱偁傞戝嶃偺崙嵺帣摱暥妛娰偵偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅庢傝婑偣偼晄壜側偺偱丄撉傓偨傔偵偼戝嶃偵峴偐側偗傟偽側傜側偄丅偝傜偵丄椺偺嫶杮戝嶃晎抦帠偺偡偡傔傞嬞弅嵿惌曽恓偵傛傝丄崙嵺帣摱暥妛娰偼傕偆偡偖攑娰丄強憼恾彂偼晎棫拞墰恾彂娰偵堏愝偡傞偙偲偵側傝丄偦偺弨旛偺偨傔12寧28擔偐傜媥娰偩偲偄偆丅丂丂偲偄偆偙偲偱丄乽夦廱夊屨曆乿偼偄傑偩偵傏偔偵偲偭偰尪偺傑傑偩丅偱傕丄尪偑偨傗偡偔尰幚偵側偭偰偼偮傑傜側偄偺偱丄偄偮傑偱傕尪偵梀傇偺傕妝偟偄偙偲偐傕偟傟側偄乮晧偗惿偟傒偺婥帩偪傕崬傔偰偺尵偩偑乯丅偦傟偵偟偰傕丄側偤崙夛恾彂娰偺専嶕僨乕僞偵強憼応強偑暘偐傝傗偡偔帵偝傟偰偄側偄傫偩丄偙偆偄偆婱廳側恾彂側偺偵丄側偤暘嶶偝偣偢丄偒偪傫偲侾偐強偵強憼偟偲偐側偄傫偩丄傑偭偨偔擔杮偺偄偄壛尭側暥壔峴惌偼丒丒丒偲丄傑偨僕僕僀偺孞傝尵偑弌偰偟傑偆丅
丂丂崙嵺巕偳傕恾彂娰偵偼丄偍傕偟傠暥屔戞9廤偺乽僓儞僶儘曆乿偑偁偭偨偺偱丄庁傝弌偟偰撉傫偩丅50擭傇傝偵丄偁偺夰偐偟偄惓曽宍偺偍傕偟傠暥屔傪庤偵偟偰丄偄偝偝偐姶寖偟偨丅傕偭偲戝敾偩偲巚偭偰偄偨偑丄廲墶17乣18僙儞僠偲丄敾宆偼婰壇偵偁傞傛傝彫偝偐偭偨丅偍傕偟傠暥屔偺乽僓儞僶儘曆乿偼3偮偺僷乕僩偵暘偐傟偰偍傝丄僷乕僩1偑僓儞僶儘偺屘嫿偺墹崙傊偺椃丄僷乕僩2偑恀屷偲偡偄巕偺傾儊儕僇偱偺妛墍惗妶偲僊儍儞僌偲偺愴偄丄僷乕僩3偑嵞傃僓儞僶儘偺椃偲偄偆峔惉偵側偭偰傞丅柧傜偐偵偙偺姫偼巕嫙偺偙傠撉傫偩婰壇偑偁偭偨丅
 丂丂撉傒曉偟偰暘偐偭偨偺偼丄妏愳暥屔偺暅崗斉慡10姫偵偼丄偍傕偟傠暥屔乽僓儞僶儘曆乿偺僷乕僩2傑偱偟偐廂榐偝傟偰偄側偄偲偄偆偙偲偩偭偨丅偡偭偐傝朰傟偰偄偨偑丄僷乕僩3偺朻摢偵丄恀屷偺傕偲偵僓儞僶儘偑傾僼儕僇偱嬯擄偺椃傪懕偗偰偄傞偲偄偆曬偑恖偯偰偵撏偒丄恀屷偲偡偄巕偑丄乬傕偆偡偖壞媥傒偩偐傜丄僓儞僶儘傪彆偗傞偨傔偵傾僼儕僇偵峴偙偆乭偲榖偡僔乕儞偑偁傞丅乽夦廱夊屨曆乿偼丄偍偦傜偔丄偦傟傪庴偗偰擇恖偑傾僼儕僇偵栠傞偲偄偆棳傟側偺偱偁傠偆丅慜偵怗傟偨亀嶳愳憏帯乣乽彮擭墹幰乿乽彮擭働僯儎乿偺奊暔岅嶌幰亁偲偄偆價僕儏傾儖杮偵偼丄乽夦廱夊屨曆乿偺岥奊乗乗恀屷偲偐偮偰偺桭偩偪崟昢働儖僋偑戝夊屨偲愴偭偰偄傞奊乗乗偑嵹偭偰偄偨丅偙偺奊偐傜憐憸偡傞偵丄恀屷偼拠娫偺摦暔偨偪偲嵞夛傪壥偨偟偨偺偩傠偆丅偦傟傑偱偺姫偱丄恀屷偼崢晍偺傛偆側傕偺傪姫偄偰偄傞偑丄偙偙偱偼僷儞僣傪偼偄偰偄傞丅傾僼儕僇偵屨偑偄偨偭偗丄側偳偲尵偆偺偼傗傔偰偍偙偆丅偁偔傑偱偙傟偼丄僼傽儞僞僕乕偺悽奅側傫偩偐傜丅
丂丂撉傒曉偟偰暘偐偭偨偺偼丄妏愳暥屔偺暅崗斉慡10姫偵偼丄偍傕偟傠暥屔乽僓儞僶儘曆乿偺僷乕僩2傑偱偟偐廂榐偝傟偰偄側偄偲偄偆偙偲偩偭偨丅偡偭偐傝朰傟偰偄偨偑丄僷乕僩3偺朻摢偵丄恀屷偺傕偲偵僓儞僶儘偑傾僼儕僇偱嬯擄偺椃傪懕偗偰偄傞偲偄偆曬偑恖偯偰偵撏偒丄恀屷偲偡偄巕偑丄乬傕偆偡偖壞媥傒偩偐傜丄僓儞僶儘傪彆偗傞偨傔偵傾僼儕僇偵峴偙偆乭偲榖偡僔乕儞偑偁傞丅乽夦廱夊屨曆乿偼丄偍偦傜偔丄偦傟傪庴偗偰擇恖偑傾僼儕僇偵栠傞偲偄偆棳傟側偺偱偁傠偆丅慜偵怗傟偨亀嶳愳憏帯乣乽彮擭墹幰乿乽彮擭働僯儎乿偺奊暔岅嶌幰亁偲偄偆價僕儏傾儖杮偵偼丄乽夦廱夊屨曆乿偺岥奊乗乗恀屷偲偐偮偰偺桭偩偪崟昢働儖僋偑戝夊屨偲愴偭偰偄傞奊乗乗偑嵹偭偰偄偨丅偙偺奊偐傜憐憸偡傞偵丄恀屷偼拠娫偺摦暔偨偪偲嵞夛傪壥偨偟偨偺偩傠偆丅偦傟傑偱偺姫偱丄恀屷偼崢晍偺傛偆側傕偺傪姫偄偰偄傞偑丄偙偙偱偼僷儞僣傪偼偄偰偄傞丅傾僼儕僇偵屨偑偄偨偭偗丄側偳偲尵偆偺偼傗傔偰偍偙偆丅偁偔傑偱偙傟偼丄僼傽儞僞僕乕偺悽奅側傫偩偐傜丅丂丂偦傟偵偟偰傕丄妏愳暥屔偵側偤乽夦廱夊屨曆乿偑廂榐偝傟側偐偭偨偺偩傠偆偐丠 偦傟偐傜丄偁傫側偵柌拞偵側偭偰撉傫偱偄偨偺偵丄側偤巕嫙偺偙傠偺傏偔偼丄嵟廔姫偺乽夦廱夊屨曆乿傪撉傫偱偄側偄偺偩傠偆偐丠 撲偼怺傑傞偽偐傝偩丅
丂丂崙嵺巕偳傕恾彂娰偱偼丄傕偆撉傔側偄偩傠偆偲巚偭偰偄偨乽桯楈杚応乿偺慜丒屻曆傕撉傓偙偲偑偱偒偨丅巕嫙偺偙傠丄乽彮擭墹幰乿偲偲傕偵撉傫偱嫮偔報徾偵巆偭偰偄傞嶳愳憏帯嶌偺惣晹寑奊暔岅偩乮偍傕偟傠暥屔 1953擭乯丅媣偟傇傝偵嵞撉偟偰丄偙傟偼寙嶌偩偲偄偆姶傪怺偔偟偨丅嶳愳偝傫偺嶌昳偵偟偰偼捒偟偔丄偙傟偼彮擭偑庡恖岞偱偼側偄偟丄僪儔儅偼斶寑巇棫偰偩丅
 丂丂乽桯楈杚応乿偺庡恖岞偼丄椉恊傪埆鐓側敀恖偵嶦偝傟偨僀儞僨傿傾儞偺惵擭丄僒儞僪儘丅偦傟偵幩寕偺柤庤偱偁傞敀恖偺柡傾儕僗偑暃庡恖岞偲偟偰偐傜傓丅晝曣傪僀儞僨傿傾儞偵楢傟嫀傜傟偨彮擭僩僯乕傕搊応偟偰怓傪揧偊傞丅僒儞僪儘偼彮擭偺偙傠丄敀恖偵捛傢傟偰偄傞偲偙傠傪傾儕僗曣巕偵彆偗傜傟丄埲屻偦偺壎傪朰傟偢丄僀儞僨傿傾儞偺堦戉傪棪偄傞摤巑偵惉挿偟偨偁偲丄傾儕僗曣巕傪偙偲偁傞偛偲偵彆偗傞丅傾儕僗偼曣傪暊崟偄僀儞僨傿傾儞偵嶦偝傟丄僀儞僨傿傾儞傪憺傓傛偆偵側傞偑丄僒儞僪儘偩偗偼憺傔側偄丅偙偺擇恖偼偍屳偄偵傎偺偐側巚曠傪書偔傛偆偵側傞丅廔斦偺僋儔僀儅僢僋僗丄婻暫戉偺戝孯偵捛偄媗傔傜傟偨僀儞僨傿傾儞偑傒側嶦偝傟傞側偐丄僒儞僪儘偩偗偑傂偲傝巆偭偰廵偱愴偭偰偄傞丅傾儕僗傪曠偆廵偺壓庤側婻暫戉偺庒偄彮堁偑僒儞僪儘偲懳寛偟傛偆偲偡傞偲丄偦偽偵偄偨幩寕偺柤庤傾儕僗偼巚傢偢帺暘偑慜偵弌偰僒儞僪儘傪寕偮丅僒儞僪儘偼憡庤偑傾儕僗偲尒偰丄帺暘偼寕偨偢偵傾儕僗偺抏傪庴偗偰丄巰偸丅嵟屻偼丄傾儕僗偑僒儞僪儘偺曟偵壴傪偨傓偗偰崁悅傟偰偄傞僔乕儞偱廔傢傞丅
丂丂乽桯楈杚応乿偺庡恖岞偼丄椉恊傪埆鐓側敀恖偵嶦偝傟偨僀儞僨傿傾儞偺惵擭丄僒儞僪儘丅偦傟偵幩寕偺柤庤偱偁傞敀恖偺柡傾儕僗偑暃庡恖岞偲偟偰偐傜傓丅晝曣傪僀儞僨傿傾儞偵楢傟嫀傜傟偨彮擭僩僯乕傕搊応偟偰怓傪揧偊傞丅僒儞僪儘偼彮擭偺偙傠丄敀恖偵捛傢傟偰偄傞偲偙傠傪傾儕僗曣巕偵彆偗傜傟丄埲屻偦偺壎傪朰傟偢丄僀儞僨傿傾儞偺堦戉傪棪偄傞摤巑偵惉挿偟偨偁偲丄傾儕僗曣巕傪偙偲偁傞偛偲偵彆偗傞丅傾儕僗偼曣傪暊崟偄僀儞僨傿傾儞偵嶦偝傟丄僀儞僨傿傾儞傪憺傓傛偆偵側傞偑丄僒儞僪儘偩偗偼憺傔側偄丅偙偺擇恖偼偍屳偄偵傎偺偐側巚曠傪書偔傛偆偵側傞丅廔斦偺僋儔僀儅僢僋僗丄婻暫戉偺戝孯偵捛偄媗傔傜傟偨僀儞僨傿傾儞偑傒側嶦偝傟傞側偐丄僒儞僪儘偩偗偑傂偲傝巆偭偰廵偱愴偭偰偄傞丅傾儕僗傪曠偆廵偺壓庤側婻暫戉偺庒偄彮堁偑僒儞僪儘偲懳寛偟傛偆偲偡傞偲丄偦偽偵偄偨幩寕偺柤庤傾儕僗偼巚傢偢帺暘偑慜偵弌偰僒儞僪儘傪寕偮丅僒儞僪儘偼憡庤偑傾儕僗偲尒偰丄帺暘偼寕偨偢偵傾儕僗偺抏傪庴偗偰丄巰偸丅嵟屻偼丄傾儕僗偑僒儞僪儘偺曟偵壴傪偨傓偗偰崁悅傟偰偄傞僔乕儞偱廔傢傞丅丂丂偙偙偵偼丄僀儞僨傿傾儞傪焤柵偟傛偆偲偡傞敀恖丄偦傟偵棫偪岦偐偆僀儞僨傿傾儞丄僀儞僨傿傾儞惵擭偲敀恖彮彈偺傎偺偐側垽丄敀恖偲僀儞僨傿傾儞偺峈憟偑傕偨傜偡斶寑偑丄帊忣朙偐偵丄梇戝偵丄奿挷崅偔昤偐傟偰偄傞丅嶳愳憏帯偺掙抦傟偸嵥擻偵丄夵傔偰嫻傪懪偨傟偨丅
2009.11.29 (擔) 塱墦偺僗僞乕丄拞懞嬔擵彆
丂丂暥寍嵖偼傓偐偟戝妛惗偺偙傠偵傛偔捠偭偨丄夰偐偟偄媽嶌愱栧偺塮夋娰偩丅乽嬔擵彆嵳傝乿偼擔懼傢傝偺2杮棫偰偲偄偆丄愄夰偐偟偄僗僞僀儖偱忋塮偝傟偨丅傏偔偑尒偵峴偭偨偺偼丄11寧拞弡丄乽偍偟偳傝夗饽乿偲乽尮巵嬨榊镈憉婰丒擥傟敮擇搧棳乿偺2杮棫偰偺擔偩偭偨丅
 丂丂僼傿儖儉偱僗僋儕乕儞偵塮偟弌偝傟傞嬔擵彆偺塮夋傪尒傞偺偼壗擭怳傝偩傠偆丅嵟屻偵尒偰偐傜丄偨傇傫30悢擭偼宱偭偰偄傞偵堘偄側偄丅偄偝偝偐姶奡偵傂偨偭偰偟傑偭偨丅乽偍偟偳傝夗饽乿偼1958擭偺僇儔乕嶌昳丅娔撀偼儅僉僲夒峅丄嬔擵彆偺憡庤栶偼旤嬻傂偽傝偱丄傎偐偵拞懞夑捗梇丄拞尨傂偲傒丄寧宍棿擵夘偑嫟墘偲偄偆壺傗偐側婄傇傟丄傑偝偵奊偵偐偄偨傛偆側柧楴搶塮帪戙寑偩丅嬔擵彆偼戝柤壠偺庒孨偲峕屗偺嵍姱壆偺擇栶傪墘偠丄傂偽傝偼嬔擵彆偲楒拠偺彑婥側栴応偺娕斅柡偵暞偡傞丅25嵨偺嬔擵彆偼檢乆偟偔堷偒掲傑偭偰偍傝丄20嵨偺傂偽傝偼杍傕傆偭偔傜偲壜垽傜偟偄丅擇恖偼枮奐偺壴偺傛偆偵惗婥偵枮偪丄岝傝婸偄偰偄傞丅
丂丂僼傿儖儉偱僗僋儕乕儞偵塮偟弌偝傟傞嬔擵彆偺塮夋傪尒傞偺偼壗擭怳傝偩傠偆丅嵟屻偵尒偰偐傜丄偨傇傫30悢擭偼宱偭偰偄傞偵堘偄側偄丅偄偝偝偐姶奡偵傂偨偭偰偟傑偭偨丅乽偍偟偳傝夗饽乿偼1958擭偺僇儔乕嶌昳丅娔撀偼儅僉僲夒峅丄嬔擵彆偺憡庤栶偼旤嬻傂偽傝偱丄傎偐偵拞懞夑捗梇丄拞尨傂偲傒丄寧宍棿擵夘偑嫟墘偲偄偆壺傗偐側婄傇傟丄傑偝偵奊偵偐偄偨傛偆側柧楴搶塮帪戙寑偩丅嬔擵彆偼戝柤壠偺庒孨偲峕屗偺嵍姱壆偺擇栶傪墘偠丄傂偽傝偼嬔擵彆偲楒拠偺彑婥側栴応偺娕斅柡偵暞偡傞丅25嵨偺嬔擵彆偼檢乆偟偔堷偒掲傑偭偰偍傝丄20嵨偺傂偽傝偼杍傕傆偭偔傜偲壜垽傜偟偄丅擇恖偼枮奐偺壴偺傛偆偵惗婥偵枮偪丄岝傝婸偄偰偄傞丅 丂丂偄偭傐偆偺乽尮巵嬨榊镈憉婰丒擥傟敮擇搧棳乿偼1957擭偺儌僲僋儘嶌昳偱娔撀偼壛摗懽丅揷戙昐崌巕丄愮尨偟偺傇偑嫟墘偲偄偆丄傗傗抧枴側攝栶偩丅乽尮巵嬨榊镈憉婰乿偼尮媊宱偺枛遽偲徧偡傞旤寱巑丄尮巵嬨榊傪庡恖岞偲偟偨丄揱婏揑側怓崌偄傪懷傃偨塮夋僔儕乕僘偱偁傝丄慡晹偱3杮偮偔傜傟偨丅偙傟偼偦偺戞1嶌偱偁傝丄嬔擵彆偼敀揾傝丄敀憰懇丄敀忊偺搧偲偄偆偍撻愼傒偺敀偯偔傔偺奿岲偱搊応偡傞偑丄傑偩庡恖岞偺僉儍儔僋僞乕愝掕偼妋棫偝傟偰偄側偄丅柤彔丒壛摗懽偲偟偰偼偛偔弶婜偺娔撀嶌昳偱偁傝丄弌棃偼偁傑傝傛偔側偄偑丄偦傟偱傕撈摿偺儘乕丒傾儞僌儖傪巊偭偨傝丄抝傪曠偆彈偺忣擮傪昤偄偨傝偲丄屻擭偺壛摗懽傜偟偝偼奺強偵昞傟偰偄傞丅
丂丂偄偭傐偆偺乽尮巵嬨榊镈憉婰丒擥傟敮擇搧棳乿偼1957擭偺儌僲僋儘嶌昳偱娔撀偼壛摗懽丅揷戙昐崌巕丄愮尨偟偺傇偑嫟墘偲偄偆丄傗傗抧枴側攝栶偩丅乽尮巵嬨榊镈憉婰乿偼尮媊宱偺枛遽偲徧偡傞旤寱巑丄尮巵嬨榊傪庡恖岞偲偟偨丄揱婏揑側怓崌偄傪懷傃偨塮夋僔儕乕僘偱偁傝丄慡晹偱3杮偮偔傜傟偨丅偙傟偼偦偺戞1嶌偱偁傝丄嬔擵彆偼敀揾傝丄敀憰懇丄敀忊偺搧偲偄偆偍撻愼傒偺敀偯偔傔偺奿岲偱搊応偡傞偑丄傑偩庡恖岞偺僉儍儔僋僞乕愝掕偼妋棫偝傟偰偄側偄丅柤彔丒壛摗懽偲偟偰偼偛偔弶婜偺娔撀嶌昳偱偁傝丄弌棃偼偁傑傝傛偔側偄偑丄偦傟偱傕撈摿偺儘乕丒傾儞僌儖傪巊偭偨傝丄抝傪曠偆彈偺忣擮傪昤偄偨傝偲丄屻擭偺壛摗懽傜偟偝偼奺強偵昞傟偰偄傞丅 丂丂傏偔偼彫妛惗偺偙傠丄儔僕僆丒僪儔儅怴彅崙暔岅僔儕乕僘偺塮夋壔偱偁傞乽揓悂摱巕乿乮1954擭乯丄乽峠岴悵乿乮1954乣55擭乯傪尒偰埲棃偺拞懞嬔擵彆偺僼傽儞偩丅摨偠偔嬔擵彆偺僼傽儞偩偭偨3嵨堘偄偺孼偺塭嬁傕偁偭偨偲巚偆丅摉帪丄傛偔擇恖偱嬔擵彆偺塮夋傪尒偵搶塮愱栧偺塮夋娰偵弌偐偗偨婰壇偑偁傞丅偤傫傇偲傑偱偼偄偐側偄偑丄60擭戙敿偽偛傠傑偱偵晻愗傜傟偨丄偨偄偰偄偺嬔擵彆庡墘塮夋偼尒偰偄傞偼偢偩丅
丂丂傏偔偼彫妛惗偺偙傠丄儔僕僆丒僪儔儅怴彅崙暔岅僔儕乕僘偺塮夋壔偱偁傞乽揓悂摱巕乿乮1954擭乯丄乽峠岴悵乿乮1954乣55擭乯傪尒偰埲棃偺拞懞嬔擵彆偺僼傽儞偩丅摨偠偔嬔擵彆偺僼傽儞偩偭偨3嵨堘偄偺孼偺塭嬁傕偁偭偨偲巚偆丅摉帪丄傛偔擇恖偱嬔擵彆偺塮夋傪尒偵搶塮愱栧偺塮夋娰偵弌偐偗偨婰壇偑偁傞丅偤傫傇偲傑偱偼偄偐側偄偑丄60擭戙敿偽偛傠傑偱偵晻愗傜傟偨丄偨偄偰偄偺嬔擵彆庡墘塮夋偼尒偰偄傞偼偢偩丅丂丂嬔擵彆偺戙昞嶌偲偄偊偽丄廜栚偺堦抳偡傞偲偙傠丄1961擭偐傜65擭偵偐偗偰丄擭堦嶌偯偮偮偔傜傟偨撪揷揻柌娔撀偺乽媨杮晲憼乿屲晹嶌偩傠偆丅偙傟偼傑偝偟偔丄塮夋偺側偐偱偺晲憼偺惉挿傇傝偲攐桪偲偟偰偺嬔擵彆偺惉弉偺夁掱偑崿慠堦懱偲側偭偨丄擔杮塮夋傪戙昞偡傞柤嶌偺傂偲偮偩偲巚偆丅偦偺傎偐丄堦怱懢彆丄揳偝傑栱師婌懡丄尮巵嬨榊丄惔悈師榊挿傗怷偺愇徏側偳丄斵偼壗傪墘偠偰傕枺椡傪曻偭偰偄偨丅偦偟偰帪戙傪宱傞偵偮傟偰傾僀僪儖丒僗僞乕偐傜墘媄幰傊偲扙旂偟偰偄偭偨丅
丂丂嬔擵彆偑惗偒惗偒偲妝偟偦偆偵抧偱墘偠偰偄偨偺偼丄堦怱懢彆傗壓挰偺壩徚偟側偳偵暞偟偰埿惃偺偄偄歏欒傪愗偭偨傝偡傞峕屗偭巕偺栶偩偭偨偲巚偆丅偱傕丄尮巵嬨榊僔儕乕僘傗丄乽寱偼抦偭偰偄偨乿乽旤抝忛乿側偳偺堿傝偺偁傞屒崅偺寱巑傪墘偠偨偲偒偺嬔擵彆傕尒帠偩偭偨丅尮巵嬨榊僔儕乕僘偼偨偭偨3嶌偟偐偮偔傜傟側偐偭偨偑丄嬔擵彆偺墘偠偨摉偨傝栶偺傂偲偮偲尵偭偰偄偄丅愭偵傕彂偄偨傛偆偵丄1嶌栚偺乽擥傟敮擇搧棳乿乮1957擭乯偱偼庡恖岞偺憿宍偼傑偩嵺棫偭偰偄側偄偑丄戞2嶌偺乽敀屒擇搧棳乿乮1958擭乯偱偦偺屄惈偑柧妋偵側傝丄戞3嶌偺乽旈寱梘塇偺挶乿乮1962擭乯偵帄偭偰姰惉傪傒偨丅偁傞庬丄惁溒側暤埻婥傪偨偨偊偨偙偺嵟廔嶌乮娔撀偼埳摗戝曘乯偵偼帪戙寑偺條幃旤偺嬌抳偑帵偝傟偰偄傞丅
 丂丂梋択偩偑丄嬔擵彆庡墘偺尮巵嬨榊偼丄戝塮偱巗愳棆憼偑墘偠偨柊嫸巐榊偲丄幨恀偺億僕丒僱僈偺娭學偵偁傞偲巚偆丅偳偪傜傕尨嶌偼幠揷楤嶰榊偺彫愢偱偁傝丄椉幰偲傕敀岐偺梕巔丄僋乕儖側樔傑偄丄挻懎堎抂偺寱偺払恖偩偑丄柊嫸巐榊偺崟偢偔傔丄彈怓偵抆傞丄揮傃僶僥儗儞偺懅巕偲偄偆埫偄弌帺偵斾傋偰丄尮巵嬨榊偺敀偢偔傔丄嬛梸揑丄媊宱偺巕懛偲偄偆崅婱側惗傑傟偼丄偒傢傔偰懳徠揑偩丅偙傟偼偦偺傑傑嬔擵彆偲棆憼偺屄惈偺堘偄偵傕捠偢傞偐傕偟傟側偄丅嫊柍揑側傾儞僠丒僸乕儘乕偲偄偆憸偑戝廜偵岲傑傟丄幠楤偼柊嫸巐榊偺暔岅傪偨偔偝傫彂偒懕偗偨偑丄乽尮巵嬨榊镈憉婰乿偼丄撍弌偟偨僉儍儔僋僞乕偱偼側偐偭偨偣偄偐丄挿曇1嶌偲拞曇廤1嶌偟偐彂偄偰偄側偄丅偩偐傜塮夋傕3嶌偟偐偮偔傜傟側偐偭偺偩傠偆丅巆擮側偙偲偩丅
丂丂梋択偩偑丄嬔擵彆庡墘偺尮巵嬨榊偼丄戝塮偱巗愳棆憼偑墘偠偨柊嫸巐榊偲丄幨恀偺億僕丒僱僈偺娭學偵偁傞偲巚偆丅偳偪傜傕尨嶌偼幠揷楤嶰榊偺彫愢偱偁傝丄椉幰偲傕敀岐偺梕巔丄僋乕儖側樔傑偄丄挻懎堎抂偺寱偺払恖偩偑丄柊嫸巐榊偺崟偢偔傔丄彈怓偵抆傞丄揮傃僶僥儗儞偺懅巕偲偄偆埫偄弌帺偵斾傋偰丄尮巵嬨榊偺敀偢偔傔丄嬛梸揑丄媊宱偺巕懛偲偄偆崅婱側惗傑傟偼丄偒傢傔偰懳徠揑偩丅偙傟偼偦偺傑傑嬔擵彆偲棆憼偺屄惈偺堘偄偵傕捠偢傞偐傕偟傟側偄丅嫊柍揑側傾儞僠丒僸乕儘乕偲偄偆憸偑戝廜偵岲傑傟丄幠楤偼柊嫸巐榊偺暔岅傪偨偔偝傫彂偒懕偗偨偑丄乽尮巵嬨榊镈憉婰乿偼丄撍弌偟偨僉儍儔僋僞乕偱偼側偐偭偨偣偄偐丄挿曇1嶌偲拞曇廤1嶌偟偐彂偄偰偄側偄丅偩偐傜塮夋傕3嶌偟偐偮偔傜傟側偐偭偺偩傠偆丅巆擮側偙偲偩丅丂丂屢椃傕偺傪墘偠偨偲偒偺嬔擵彆傕慺惏傜偟偐偭偨丅偄偔偮偐偁傞婰壇偵巆傞嶌昳偺側偐偱偼丄乽娭偺淺懢偭傌乿乮1963擭乯傕枴傢偄怺偄柤昳偩偑丄傗偼傝壛摗懽娔撀偺乽孊妡帪師榊丒梀嫚堦旵乿乮1966擭乯偵偲偳傔傪偝偡丅塮夋慡懱偵昚偆丄傗傝応偺側偄垼偟傒偲愗乆偨傞忣姶偑嫻傪懪偮丅慜擭偵偮偔偭偨乽柧帯嫚媞揱丒嶰戙栚廝柤乿偲暲傇丄偙傟偼壛摗懽偺嵟崅寙嶌偱偁傠偆丅偦偟偰嬔擵彆偺梷惂偝傟偨墘媄偼丄斵偑墘媄幰偲偟偰僺乕僋傪寎偊偨偙偲傪帵偟偰偄傞丅嬔擵彆偑弌墘偟偨壛摗懽娔撀偺塮夋偵偼丄傎偐偵傕乽恀揷晽塤榐乿乮1962擭乯偲偄偆丄埨曐摤憟傪壓晘偒偵偟偨偲偄傢傟傞堎怓僯儏乕丒僂僃僀償帪戙寑傕偁偭偨丅偩偑嬔擵彆偺惉弉偲偼棤暊偵丄偙偺60擭戙敿偽偛傠丄晄岾側偙偲偵塮夋奅偼帪戙寑偑掅柪偟丄搶塮偼傗偔偞塮夋楬慄偵曽岦揮姺偟偮偮偁偭偨丅乽孊妡帪師榊丒梀嫚堦旵乿偱嵟崅偺墘媄傪傒偣偨嬔擵彆偼丄偙偺擭丄偁偲1嶌偩偗嶣偭偨偁偲丄搶塮偺愱懏傪棧傟偰偟傑偆丅
 丂丂嫟墘偟偨攐桪傗僗僞僢僼偺夰屆榖傪撉傓偲丄嬔擵彆偼丄婥偺偄偄丄棤昞偺側偄丄扤偲偱傕暘偗妘偰側偔晅偒崌偆丄柍椶偺岲惵擭偩偭偨傜偟偄丅斵偼傒傫側偐傜乬嬔孼偄乭偲偐乬扷撨乭偲偐屇偽傟偰曠傢傟偰偄偨丅拠娫偼嶣塭偑廔傢傞偲嶣塭強嬤偔偺嬔擵彆偺壠偵廤傑傝丄堸傫偩傝怘偭偨傝偟偨偁偲媉墍偵孞傝弌偟丄傑偨嬔擵彆偺壠偵婣偭偰嶨嫑怮偟丄梻挬堦弿偵嶣塭強偵岦偐偆偲偄偆枅擔偩偭偨丅
丂丂嫟墘偟偨攐桪傗僗僞僢僼偺夰屆榖傪撉傓偲丄嬔擵彆偼丄婥偺偄偄丄棤昞偺側偄丄扤偲偱傕暘偗妘偰側偔晅偒崌偆丄柍椶偺岲惵擭偩偭偨傜偟偄丅斵偼傒傫側偐傜乬嬔孼偄乭偲偐乬扷撨乭偲偐屇偽傟偰曠傢傟偰偄偨丅拠娫偼嶣塭偑廔傢傞偲嶣塭強嬤偔偺嬔擵彆偺壠偵廤傑傝丄堸傫偩傝怘偭偨傝偟偨偁偲媉墍偵孞傝弌偟丄傑偨嬔擵彆偺壠偵婣偭偰嶨嫑怮偟丄梻挬堦弿偵嶣塭強偵岦偐偆偲偄偆枅擔偩偭偨丅丂丂60擭戙敿偽丄帪戙寑偑幬梲壔偟巒傔偨偙傠丄婋婡姶傪傕偭偨搶塮偺儀僥儔儞傗榚栶偺攐桪偼丄懸嬾夵慞傪媮傔偰攐桪慻崌傪愝棫偟丄嬔擵彆偼斵傜偵棅傑傟偰慻崌偺戙昞偵側偭偨丅戝僗僞乕偺娕斅攐桪偑戝晹壆攐桪偨偪偺偨傔偺慻崌戙昞偵側傞偙偲側偳丄慜戙枹暦偺弌棃帠偩傠偆丅斅嫴傒偵側偭偨嬔擵彆偺怱楯偼戝偒偐偭偨偲巚偆丅偙偺憟媍偼偗偭偒傚偔慻崌懁偺攕杒偵廔傢偭偨丅嬔擵彆偼丄乬慻崌傪夝嶶偟偨偁偲傕慻崌堳偵晄棙側偙偲偼偟側偄乭偲偄偆栺懇傪夛幮懁偐傜庢傝晅偗丄偦偺屻傑傕側偔搶塮傪嫀偭偨丅嬔擵彆偲偄偆恖暔傪暔岅傞僄僺僜乕僪偩偲巚偆丅
 丂丂嬔擵彆偑搶塮偱僐儞價傪慻傫偩彈桪偺側偐偱丄嫟墘偟偨夞悢偑傕偭偲傕懡偄偺偼媢偝偲傒偩偭偨丅悢偊偰傒傞偲丄僆乕儖僗僞乕丒僉儍僗僩傕偺傪彍偄偰12杮偁傞丅偦偺師偵懡偄偺偼崅愮曚傂偯傞偲愮尨偟偺傇偱丄偦傟偧傟8杮偱嫟墘偟偰偄傞丅偦偟偰戝愳宐巕偲偺嫟墘7杮偲懕偔丅搶塮偺偍昉條彈桪偺側偐偱丄傏偔偑偄偪偽傫岲偒偩偭偨偺偼戝愳宐巕偩偑丄塮夋偵弌側偔側偭偰埲崀偺斵彈偼壗傪偟偰偄偨偺偩傠偆偐丅嬔擵彆偲戝愳宐巕偺嫟墘嶌偺側偐偱偼丄乽寱偼抦偭偰偄偨丒峠婄柍憃棳乿乮1958擭乯偑丄偲傝傢偗昳奿偺偁傞堩昳偩偭偨偲巚偆丅僑乕儖僨儞丒僐儞價偲尵傢傟偨旤嬻傂偽傝偲偺嫟墘嶌偼堄奜偵彮側偔丄5杮偟偐側偄丅
丂丂嬔擵彆偑搶塮偱僐儞價傪慻傫偩彈桪偺側偐偱丄嫟墘偟偨夞悢偑傕偭偲傕懡偄偺偼媢偝偲傒偩偭偨丅悢偊偰傒傞偲丄僆乕儖僗僞乕丒僉儍僗僩傕偺傪彍偄偰12杮偁傞丅偦偺師偵懡偄偺偼崅愮曚傂偯傞偲愮尨偟偺傇偱丄偦傟偧傟8杮偱嫟墘偟偰偄傞丅偦偟偰戝愳宐巕偲偺嫟墘7杮偲懕偔丅搶塮偺偍昉條彈桪偺側偐偱丄傏偔偑偄偪偽傫岲偒偩偭偨偺偼戝愳宐巕偩偑丄塮夋偵弌側偔側偭偰埲崀偺斵彈偼壗傪偟偰偄偨偺偩傠偆偐丅嬔擵彆偲戝愳宐巕偺嫟墘嶌偺側偐偱偼丄乽寱偼抦偭偰偄偨丒峠婄柍憃棳乿乮1958擭乯偑丄偲傝傢偗昳奿偺偁傞堩昳偩偭偨偲巚偆丅僑乕儖僨儞丒僐儞價偲尵傢傟偨旤嬻傂偽傝偲偺嫟墘嶌偼堄奜偵彮側偔丄5杮偟偐側偄丅丂丂拞懞嬔擵彆偲旤嬻傂偽傝偼丄偲傝傢偗婥偺崌偆丄恊偟偄娫暱偩偭偨傜偟偄丅擇恖偼寢崶偟傛偆偲偟偨偑丄嬔擵彆偺曣恊偑斀懳偟偨偨傔幚尰偟側偐偭偨丄偲壗偐偺杮偱撉傫偩偙偲偑偁傞丅乽嫑壆偺柡傆偤偄偲棞墍偺屼憘巌偱偼恎暘偑堘偆乿偲曣恊偑尵偭偨偺偐偳偆偐抦傜側偄偑丄傕偟偦偆側傜丄壧晳婈偩偭偰傕偲傪偨偩偣偽壨尨岊怘偱丄栶幰壱嬈傪挿偔懕偗偰偄傞偩偗偺榖偠傖側偄偐偲尵偄偨偔側傞丅旤嬻傂偽傝偵偲偭偰丄嬔擵彆偼摿暿側懚嵼偩偭偨傛偆偩丅庤尦偵帒椏偑側偄偺偱晄妋偐偩偑丄傂偽傝偑斢擭丄昦彴偵偁傞偲偒丄柺夛偼傒側抐偭偰偄偨偑丄嬔擵彆偲搰憅愮戙巕偩偗偵偼夛偭偨傜偟偄丅傑偨傂偽傝偑朣偔側偭偰帺戭偵朣偒奫偑婣偭偨偲偒丄堚懓偺偼偐傜偄偱嬔擵彆偩偗偑朣偒奫偲懳柺偟偰傂偽傝偵暿傟傪崘偘偨偲偄偆丅
丂丂崱夞丄戝偒側僗僋儕乕儞偱媣偟傇傝偵尒偨塮夋乽偍偟偳傝夗饽乿偺嬔擵彆偲傂偽傝偼丄擋偄棫偮傛偆偵旤偟偐偭偨丅帪戙偼堏傝丄嬔擵彆傕傂偽傝傕朣偔側偭偰傕丄僗僋儕乕儞偺拞偱丄斵傜偼塱墦偵傑偽備偄偽偐傝偺婸偒傪曻偭偰偄傞丅
2009.11.15 (擔) 嶳愳憏帯偺乽彮擭墹幰乿偑垽偲桬婥傪嫵偊偰偔傟偨
 偄傑抍夠偺悽戙偺抝偨偪偺側偐偵偼丄徍榓20擭戙屻敿偐傜30擭戙慜敿偵嶳愳憏帯偺彂偔奊暔岅偵嫻傪偲偒傔偐偣偨恖偑懡偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅嶳愳憏帯偺乽彮擭墹幰乿偵柌拞偵側偭偨偺偼丄偨傇傫彫妛峑偺掅妛擭偺偙傠偩偭偨偲巚偆丅偳傫側宱堒偱撉傒巒傔偨偺偐偼妎偊偰偄側偄丅偍偦傜偔恊偑攦偄梌偊偰偔傟偨偺偩傠偆丅惓曽宍偵嬤偄戝敾偺扨峴杮偩偭偨丅枅夞丄怴姧偑弌傞偨傃偵傓偝傏傞傛偆偵撉傫偩偟丄摨偠杮傪撪梕傪婰壇偡傞傑偱壗搙傕撉傒曉偟偨丅巕嫙偺偙傠偵廧傫偱偄偨媨嶈偺揷幧偺壠偺偡偖棤懁偵嶳椦偑偁偭偨丅摉帪偺偡傋偰偺巕嫙偨偪偲摨偠傛偆偵丄傏偔偼彮擭墹幰傪恀帡偰丄崢偵僫僞傪偔偔傝偮偗丄僕儍儞僌儖偺扵専偵偱偐偗偨丅栘堿偵憪傪晘偄偰廧張傪嶌傝丄栘偺巬偺偮偨傪悅傜偟偰傇傜偝偑偭偨丅
偄傑抍夠偺悽戙偺抝偨偪偺側偐偵偼丄徍榓20擭戙屻敿偐傜30擭戙慜敿偵嶳愳憏帯偺彂偔奊暔岅偵嫻傪偲偒傔偐偣偨恖偑懡偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅嶳愳憏帯偺乽彮擭墹幰乿偵柌拞偵側偭偨偺偼丄偨傇傫彫妛峑偺掅妛擭偺偙傠偩偭偨偲巚偆丅偳傫側宱堒偱撉傒巒傔偨偺偐偼妎偊偰偄側偄丅偍偦傜偔恊偑攦偄梌偊偰偔傟偨偺偩傠偆丅惓曽宍偵嬤偄戝敾偺扨峴杮偩偭偨丅枅夞丄怴姧偑弌傞偨傃偵傓偝傏傞傛偆偵撉傫偩偟丄摨偠杮傪撪梕傪婰壇偡傞傑偱壗搙傕撉傒曉偟偨丅巕嫙偺偙傠偵廧傫偱偄偨媨嶈偺揷幧偺壠偺偡偖棤懁偵嶳椦偑偁偭偨丅摉帪偺偡傋偰偺巕嫙偨偪偲摨偠傛偆偵丄傏偔偼彮擭墹幰傪恀帡偰丄崢偵僫僞傪偔偔傝偮偗丄僕儍儞僌儖偺扵専偵偱偐偗偨丅栘堿偵憪傪晘偄偰廧張傪嶌傝丄栘偺巬偺偮偨傪悅傜偟偰傇傜偝偑偭偨丅奊暔岅偲偼丄偄傑偺庒偄恖偼抦傞傛偟傕側偄偩傠偆偑丄彫愢偲枱夋偑崌懱偟偨杮偱偁傝丄撉傓巻幣嫃丄悂偒弌偟偺側偄枱夋偺傛偆側撉傒暔偩丅憓奊偲暥偑丄堦偮偺儁乕僕偵傎傏摨偠暘検偯偮慻傒崌傢偝傟偰偍傝丄愴屻娫傕側偔丄枱夋偑庡棳傪愯傔傞傛偆偵側傞慜偺堦帪婜丄巕嫙偨偪偺偁偄偩偱戝偄偵棳峴偭偨丅嶳愳憏帯傗彫徏嶈栁側偳偑恖婥嶌壠偲偟偰妶桇偟偨丅
乽彮擭墹幰乿偼傾僼儕僇偺僕儍儞僌儖偱僑儕儔偵堢偰傜傟偨彮擭丄恀屷偺攇棎枩忎偺朻尟傪昤偄偨暔岅偩丅扨峴杮偱慡10姫偵側傞丅堦尵偱尵偆側傜擔杮斉僞乕僓儞偩偑丄僗僩乕儕乕偼僞乕僓儞暔岅傛傝偼傞偐偵婲暁偵晉傫偱
 偄傞丅恀屷偺恊桭偱嫮椡柍憃偺尨廧柉愴巑僓儞僶儘丄恀屷傪曠偆彮彈偡偄巕丄惓媊偺夦恖傾儊儞儂僥僢僾丄偦偟偰嫢朶側愒僑儕儔丄杺恄僂乕儔丄昢偺榁攌丄壨攏抝側偳丄慞埆擖傝棎傟偰悢懡偔偺搊応恖暔偑偱偰偔傞丅偝傜偵懢屆偺嫲棾傗恖怘偄夦庽儌儞僗僞乕僣儕乕傗徖偵惐傓嫄戝側榢僈儔儞價偲偄偭偨惁傑偠偄夦暔傕尰傟丄恀屷偨偪偵廝偄偐偐傞丅偡偄巕偼偄偮傕埆娍偵懆傢傟傞偑丄婋傗偆偟偲偄偆偲偒偵昁偢彮擭墹幰丄恀屷偑傗偭偰偒偰媬偄弌偡丅
偄傞丅恀屷偺恊桭偱嫮椡柍憃偺尨廧柉愴巑僓儞僶儘丄恀屷傪曠偆彮彈偡偄巕丄惓媊偺夦恖傾儊儞儂僥僢僾丄偦偟偰嫢朶側愒僑儕儔丄杺恄僂乕儔丄昢偺榁攌丄壨攏抝側偳丄慞埆擖傝棎傟偰悢懡偔偺搊応恖暔偑偱偰偔傞丅偝傜偵懢屆偺嫲棾傗恖怘偄夦庽儌儞僗僞乕僣儕乕傗徖偵惐傓嫄戝側榢僈儔儞價偲偄偭偨惁傑偠偄夦暔傕尰傟丄恀屷偨偪偵廝偄偐偐傞丅偡偄巕偼偄偮傕埆娍偵懆傢傟傞偑丄婋傗偆偟偲偄偆偲偒偵昁偢彮擭墹幰丄恀屷偑傗偭偰偒偰媬偄弌偡丅嶳愳憏帯偼乽彮擭墹幰乿偵懕偄偰乽彮擭働僯傾乿傪彂偄偨丅偙傟偵傕枺椆偝傟偨丅偙偪傜偼儚僞儖彮擭偑庡恖岞偱丄偦傟偵嬥敮偺彮彈働乕僩丄儅僒僀懓偺執戝側廢挿僛僈偑摨峴偟丄晝傪憑偟偰傾僼儕僇墱抧偺旈嫬傪椃偡傞丅慡20姫偱偁傝丄乽彮擭墹幰乿傛傝傕挿戝偩丅嶳愳憏帯偺戙昞嶌偲偄偊偽丄偙偺乽彮擭働僯傾乿傪嫇偘傞恖傕偄傞丅偩偑丄傏偔偵偲偭偰偼乽彮擭墹幰乿偺傎偆偑埑搢揑偵報徾偑嫮偄偟丄垽拝偑怺偄丅
 乽彮擭働僯傾乿偼慡姫傪撉椆偟側偐偭偨丅搑拞偐傜嫽枴偑枱夋偵丄偝傜偵偼奊偺側偄彫愢偵堏偭偨偐傜偩丅偦偟偰慞偺側偐偵埆偑偁傝丄埆偺側偐偵慞偑偁傞偙偲傪抦傝丄丄彮擭偺擔偺婰壇偼敄傜偄偱偄偭偨丅偦傟偐傜挿偄擭寧偑偨偭偨偁偲丄撍慠丄嶳愳憏帯偺悽奅偑嵞傃栚偺慜偵尰傟偨丅1983擭偐傜84擭偵偐偗偰偺偙偲偩丅妏愳暥屔偐傜嶳愳憏帯慡廤偑暅崗敪攧偝傟偨偺偩丅傏偔偼乽彮擭墹幰乿慡10姫偲乽彮擭働僯傾乿慡20姫傪攦偄媮傔偨丅嵞傃愙偟偨嶳愳憏帯偺奊暔岅偼慺惏傜偟偐偭偨丅儁乕僕傪傔偔傞偨傃偵丄朰傟偰偄偨憓奊傗僗僩乕儕乕偑師乆偵摢偺側偐偵酳偭偨丅偦傟傑偱廧傫偱偄偨僕儍儞僌儖偑從偗丄墦偔偺僕儍儞僌儖偵堏摦偡傞偨傔恀屷偑拠娫偺摦暔偨偪傪棪偄偰嵒敊傪椃偡傞僔乕儞偑嫻傪擬偔偟偨丅偡偄巕偨偪傪彆偗傞偨傔丄摦暔偨偪偵暿傟傪崘偘丄僴僎儚僔偵忔偭偰嵒敊傪墶抐偡傞僔乕儞偑怱傪恔傢偣偨丅
乽彮擭働僯傾乿偼慡姫傪撉椆偟側偐偭偨丅搑拞偐傜嫽枴偑枱夋偵丄偝傜偵偼奊偺側偄彫愢偵堏偭偨偐傜偩丅偦偟偰慞偺側偐偵埆偑偁傝丄埆偺側偐偵慞偑偁傞偙偲傪抦傝丄丄彮擭偺擔偺婰壇偼敄傜偄偱偄偭偨丅偦傟偐傜挿偄擭寧偑偨偭偨偁偲丄撍慠丄嶳愳憏帯偺悽奅偑嵞傃栚偺慜偵尰傟偨丅1983擭偐傜84擭偵偐偗偰偺偙偲偩丅妏愳暥屔偐傜嶳愳憏帯慡廤偑暅崗敪攧偝傟偨偺偩丅傏偔偼乽彮擭墹幰乿慡10姫偲乽彮擭働僯傾乿慡20姫傪攦偄媮傔偨丅嵞傃愙偟偨嶳愳憏帯偺奊暔岅偼慺惏傜偟偐偭偨丅儁乕僕傪傔偔傞偨傃偵丄朰傟偰偄偨憓奊傗僗僩乕儕乕偑師乆偵摢偺側偐偵酳偭偨丅偦傟傑偱廧傫偱偄偨僕儍儞僌儖偑從偗丄墦偔偺僕儍儞僌儖偵堏摦偡傞偨傔恀屷偑拠娫偺摦暔偨偪傪棪偄偰嵒敊傪椃偡傞僔乕儞偑嫻傪擬偔偟偨丅偡偄巕偨偪傪彆偗傞偨傔丄摦暔偨偪偵暿傟傪崘偘丄僴僎儚僔偵忔偭偰嵒敊傪墶抐偡傞僔乕儞偑怱傪恔傢偣偨丅嶳愳憏帯偼偳偙偑枺椡側偺偐丠 傑偢慛楏偒傢傑傝側偄奊偑偁傞丅2怓嶞傝側偺偩偑丄峔惉椡偵偡偖傟偰偍傝敆椡偨偭傉傝偩丅恀屷偑僑儕儔傗儔僀僆儞傗儚僯傗嫲棾傗戝僞僐偲巰摤傪墘偢傞僔乕儞側偳偼丄惗偒惗偒偟偨桇摦姶偵偁傆傟偰偄傞丅偦偟偰暔岅惈朙偐側僗僩乕儕乕揥奐偑偁傞丅婏憐揤奜側惗偒暔傗埆鐓旕摴側埆幰偑師乆偵搊応偡傞偟丄恀屷偲摦暔偨偪偺桭忣丄僓儞僶儘偲偺屌偄鉐側偳傕偟偭偐傝昤偐傟偰偄傞偟丄慡姫傪偲偍偟偰傑偭偨偔偩傟傞偙偲偑側偄丅嶳愳憏帯偺梇戝側僀儅僕僱乕僔儑儞偑慡曇偵鐬偭偰偄傞丅
乽彮擭墹幰乿偼慡10姫偩偑丄幚幙揑偵偼9姫栚偱廔傢偭偨偲尵偭偰偄偄偩傠偆丅戞9姫偱丄丄恀屷偼埆幰傪偡傋偰傗偭偮偗丄偼偖傟偰偄偨偡偄巕傗扵専戉偺柺乆偲崌棳偟丄屘嫿偺墹崙傪扵偟偵墱抧偵岦偐偆僓儞僶儘偵暿傟傪崘偘偰丄傾僼儕僇偺僕儍儞僌儖偐傜傾儊儕僇偵椃棫偮偐傜偩丅戞10姫偱偼丄僓儞僶儘偺嬯擄偺椃偲暲峴偟偰丄傾儊儕僇偵搉偭偨恀屷偲偡偄巕偺妛墍惗妶傗丄僊儍儞僌堦枴偲偺懳寛偑昤偐傟傞偑丄偙偺姫偱戝抍墌偵偡傞偵偼丄傗傗拞搑敿抂側廔傢傝曽偩丅憐憸偡傞偵丄偄偭偨傫9姫栚偱暔岅偼廔傢偭偨偑丄岲昡側偺偱懕曇傪彂偄偨丄偗傟偳傕師嶌偺乽彮擭働僯傾乿偑壚嫬偵擖傝丄偦偪傜偵偵椡傪廤拞偡傞偨傔懕曇偼1姫偩偗偱廔椆偡傞偙偲偵偟偨丄偲偄偆惉峴偒偩偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偱傕丄旈嫬偱偺朻尟偱偼側偔側偭偨偲偼偄偊丄恀屷偺偦偺屻偺妶桇傪傕偆彮偟尒偨偐偭偨婥偑偡傞丅
 妏愳暥屔偺嶳愳憏帯慡廤偼丄乽彮擭墹幰乿偲乽彮擭働僯傾乿偑弌偨偲偙傠偱丄巆擮側偙偲偵懪偪巭傔偵側偭偨丅暥屔敪攧偲摨帪偵乽彮擭働僯儎乿傪傾僯儊塮夋壔偡傞側偳丄妏愳摼堄偺儊僨傿傾丒儈僢僋僗彜朄偱榖戣傪峀偘傛偆偲偟偨偑丄攧傟峴偒偑晄怳偩偭偨偨傔偩傠偆丅嶳愳憏帯偵偮偄偰徻嵶偵榑偠偨僒僀僩乽嶳愳憏帯偲奊暔岅偺悽奅乿偵傛傞偲丄斵偼乽彮擭墹幰乿乽彮擭働僯傾乿埲奜偵傕丄旈嫬朻尟傕偺丄儃僋僔儞僌傕偺丄廮摴傕偺丄帪戙傕偺側偳丄偝傑偞傑側奊暔岅傪彂偄偰偄傞傜偟偄偑丄傏偔偑偙偺2嶌偺傎偐偵撉傫偩傕偺偲偄偊偽乽桯楈杚応乿偩偗偟偐側偄丅乽桯楈杚応乿偼丄嵶偐側撪梕偼妎偊偰偄側偄偑丄僀儞僨傿傾儞傗婻暫戉偑搊応偡傞夦婏惈傪懷傃偨惣晹寑偩偭偨丅斱楎側庤傪巊偭偰僀儞僨傿傾儞傪柵傏偦偆偲偡傞敀恖偲丄偦傟偵棫偪岦偐偆忣偗怺偄桬姼側僀儞僨傿傾儞偲偄偆僗僩乕儕乕偩偭偨偲巚偆丅偙偺摉帪丄惣晹寑偲偄偆偲僀儞僨傿傾儞偑埆幰偵側傞偺偑摉偨傝慜偩偭偨偑丄嶳愳憏帯偼偦傫側忢幆偵懆傢傟側偐偭偨丅乽彮擭墹幰乿偵傕丄敀恖拞怱偺惣墷暥柧傪斸敾偡傞帇揰偑傒傜傟傞丅偨偐偑巕嫙岦偗偺撉傒暔偲偼偄偊丄嶳愳偺夰偺怺偝偑昞傟偰偄傞丅乽桯楈杚応乿丄傕偆堦搙撉傒捈偟偰傒偨偄偑丄偍偦傜偔姁傢偸婅偄偩傠偆丅
妏愳暥屔偺嶳愳憏帯慡廤偼丄乽彮擭墹幰乿偲乽彮擭働僯傾乿偑弌偨偲偙傠偱丄巆擮側偙偲偵懪偪巭傔偵側偭偨丅暥屔敪攧偲摨帪偵乽彮擭働僯儎乿傪傾僯儊塮夋壔偡傞側偳丄妏愳摼堄偺儊僨傿傾丒儈僢僋僗彜朄偱榖戣傪峀偘傛偆偲偟偨偑丄攧傟峴偒偑晄怳偩偭偨偨傔偩傠偆丅嶳愳憏帯偵偮偄偰徻嵶偵榑偠偨僒僀僩乽嶳愳憏帯偲奊暔岅偺悽奅乿偵傛傞偲丄斵偼乽彮擭墹幰乿乽彮擭働僯傾乿埲奜偵傕丄旈嫬朻尟傕偺丄儃僋僔儞僌傕偺丄廮摴傕偺丄帪戙傕偺側偳丄偝傑偞傑側奊暔岅傪彂偄偰偄傞傜偟偄偑丄傏偔偑偙偺2嶌偺傎偐偵撉傫偩傕偺偲偄偊偽乽桯楈杚応乿偩偗偟偐側偄丅乽桯楈杚応乿偼丄嵶偐側撪梕偼妎偊偰偄側偄偑丄僀儞僨傿傾儞傗婻暫戉偑搊応偡傞夦婏惈傪懷傃偨惣晹寑偩偭偨丅斱楎側庤傪巊偭偰僀儞僨傿傾儞傪柵傏偦偆偲偡傞敀恖偲丄偦傟偵棫偪岦偐偆忣偗怺偄桬姼側僀儞僨傿傾儞偲偄偆僗僩乕儕乕偩偭偨偲巚偆丅偙偺摉帪丄惣晹寑偲偄偆偲僀儞僨傿傾儞偑埆幰偵側傞偺偑摉偨傝慜偩偭偨偑丄嶳愳憏帯偼偦傫側忢幆偵懆傢傟側偐偭偨丅乽彮擭墹幰乿偵傕丄敀恖拞怱偺惣墷暥柧傪斸敾偡傞帇揰偑傒傜傟傞丅偨偐偑巕嫙岦偗偺撉傒暔偲偼偄偊丄嶳愳偺夰偺怺偝偑昞傟偰偄傞丅乽桯楈杚応乿丄傕偆堦搙撉傒捈偟偰傒偨偄偑丄偍偦傜偔姁傢偸婅偄偩傠偆丅嶳愳憏帯偼1992擭丄84嵨偱朣偔側偭偨偑丄暥屔偺夝愢偵傛傞偲丄懅巕偵恀屷丄柡偵偡偄巕偲柤晅偗偨傜偟偄丅杮恖傕乽彮擭墹幰乿偵偄偪偽傫垽拝傪姶偠偰偄偨偺偩傠偆丅嶳愳憏帯偺奊暔岅偼僲僗僞儖僕乕偺側偐偺堦晽宨偵偡偓側偄偲偼偄偊丄偁傑傝偵慛傗偐偵怱偺側偐偵懅偯偄偰偄傞丅偨偲偊偽傏偔偑僀儞僨傿丒僕儑乕儞僘側偳旈嫬扵専塮夋偑岲偒偩偭偨傝丄傾儕僗僥傾丒儅僋儕乕儞丄僨僘儌儞僪丒僶僌儕乕側偳偺朻尟妶寑彫愢偑岲偒偩偭偨傝偡傞偙偲偺攚宨偵偼丄巕嫙偺偙傠偺乽彮擭墹幰乿傪撉傫偱嫻傪偲偒傔偐偣偨宱尡偑偁傞偺偼娫堘偄側偄偩傠偆丅嬻憐偺側偐偱丄恀屷偼偄傑傕枾椦傪旘傃夞傝丄幾埆側惗偒暔傪戅帯偟丄彑棙偺梇偨偗傃傪偁偘偰偄傞丅
2009.10.19 (寧) 旤嬻傂偽傝峫
 旤嬻傂偽傝偼徍榓28擭丄儗僐乕僪丒僨價儏乕偟偰4擭屻丄16嵨偺偲偒丄乹忋奀乺乹傾僎僀儞乺乹僗僞乕僟僗僩乺偲偄偭偨傾儊儕僇偺僕儍僘晽億僢僾丒僜儞僌傪棫偰懕偗偵悂偒崬傒丄梻29擭偵偼乹A楍幵偱峴偙偆乺傪榐壒偟偨丅埲慜丄弶傔偰偦傟傜傪挳偄偨偲偒丄斵彈偺僕儍僘壧庤偲偟偰偺嫲傠偟偄傑偱偺岻偝偵傃偭偔傝偟偨丅僕儍僘昡榑壠偺桘堜惓堦巵側偳偺彂偐傟偨婰帠傪撉傒丄傂偽傝偺僕儍僘壧庤偺偟偰偺嵥擻偼抦幆偲偟偰抦偭偰偼偄偨偑丄幚嵺偵挳偄偨偦偺壧偼丄偨偟偐偵暲偼偢傟偨惁偝偩偭偨丅斵彈偼偍偦傜偔塸岅偼傛偔抦傜側偐偭偨偱偁傠偆丅偩偑偦偺敪壒傗僀儞僩僱乕僔儑儞偼垹慠偲偡傞傎偳偆傑偔丄枱慠偲挳偄偰偄傞偲傾儊儕僇偺堦棳壧庤偑壧偭偰偄傞傛偆偵偟偐挳偙偊側偄丅儕僘儉傊偺忔傝傗僼儗乕僘偺曵偟曽側偳丄傑偭偨偔摪偵擖偭偰偄傞丅僗僉儍僢僩偱壧偄傑偔傞乹A楍幵偱峴偙偆乺側偳偵偼搙娞傪敳偐傟傞丅偨傇傫梞妝偺儗僐乕僪傪挳偄偰妎偊偨偺偱偁傠偆丅斵彈偼晥柺偼撉傔偢丄儊儘僨傿傪帹偱挳偄偰妎偊偨桼偩偑丄偙偙傑偱帺慠側偐偨偪偱帺暘偺壧偵偱偒傞偲偼丄忢幆偺榞撪傪挻偊偄傞丅
旤嬻傂偽傝偼徍榓28擭丄儗僐乕僪丒僨價儏乕偟偰4擭屻丄16嵨偺偲偒丄乹忋奀乺乹傾僎僀儞乺乹僗僞乕僟僗僩乺偲偄偭偨傾儊儕僇偺僕儍僘晽億僢僾丒僜儞僌傪棫偰懕偗偵悂偒崬傒丄梻29擭偵偼乹A楍幵偱峴偙偆乺傪榐壒偟偨丅埲慜丄弶傔偰偦傟傜傪挳偄偨偲偒丄斵彈偺僕儍僘壧庤偲偟偰偺嫲傠偟偄傑偱偺岻偝偵傃偭偔傝偟偨丅僕儍僘昡榑壠偺桘堜惓堦巵側偳偺彂偐傟偨婰帠傪撉傒丄傂偽傝偺僕儍僘壧庤偺偟偰偺嵥擻偼抦幆偲偟偰抦偭偰偼偄偨偑丄幚嵺偵挳偄偨偦偺壧偼丄偨偟偐偵暲偼偢傟偨惁偝偩偭偨丅斵彈偼偍偦傜偔塸岅偼傛偔抦傜側偐偭偨偱偁傠偆丅偩偑偦偺敪壒傗僀儞僩僱乕僔儑儞偼垹慠偲偡傞傎偳偆傑偔丄枱慠偲挳偄偰偄傞偲傾儊儕僇偺堦棳壧庤偑壧偭偰偄傞傛偆偵偟偐挳偙偊側偄丅儕僘儉傊偺忔傝傗僼儗乕僘偺曵偟曽側偳丄傑偭偨偔摪偵擖偭偰偄傞丅僗僉儍僢僩偱壧偄傑偔傞乹A楍幵偱峴偙偆乺側偳偵偼搙娞傪敳偐傟傞丅偨傇傫梞妝偺儗僐乕僪傪挳偄偰妎偊偨偺偱偁傠偆丅斵彈偼晥柺偼撉傔偢丄儊儘僨傿傪帹偱挳偄偰妎偊偨桼偩偑丄偙偙傑偱帺慠側偐偨偪偱帺暘偺壧偵偱偒傞偲偼丄忢幆偺榞撪傪挻偊偄傞丅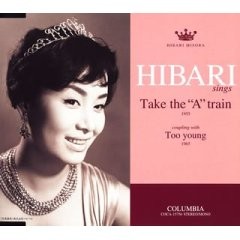 僨傿僗僐僌儔僼傿傪尒傞偲丄傂偽傝偺僔儞僌儖斦偼丄僨價儏乕3擭屻偺徍榓27擭偐傜偑偤傫懡偔側傝丄28擭偵偼19枃丄29擭偵偼16枃傕敪攧偝傟丄埲屻傕偦傫側挷巕偱34擭傑偱懕偔丅暯嬒偟偰枅寧1枃埲忋傕敪攧偝傟偰偄偨寁嶼偵側傞丅尰嵼偐傜偡傟偽怣偠傟側偄悢帤偩丅斵彈偑敪攧偟偨僔儞僌儖傪弴傪捛偭偰挳偄偰偄偔偲丄僨價儏乕摉帪偐傜10擭傎偳偺偁偄偩偵丄偁傝偲偁傜備傞椶偄偺嬋傪壧偭偰偒偨偺偑暘偐傞丅揱摑揑側壧梬嬋偐傜丄峕屗忣弿傕偺丄柉梬丄彫塖抂塖丄儅僪儘僗傕偺丄偦偟偰丄僕儍僘丄僽僊丄儖儞僶丄儅儞儃丄僞儞僑丄僇儞僩儕乕側偳偺梞妝巙岦偺嬋丄偼偰偼僣僀僗僩傗僪僪儞僷傑偱偲丄偦偺暆偺峀偝偵嬃偐偝傟傞偟丄偡傋偰傪姰帏偵丄揤堖柍朌偵壧偄偙側偡椡検偵埑搢偝傟傞丅
僨傿僗僐僌儔僼傿傪尒傞偲丄傂偽傝偺僔儞僌儖斦偼丄僨價儏乕3擭屻偺徍榓27擭偐傜偑偤傫懡偔側傝丄28擭偵偼19枃丄29擭偵偼16枃傕敪攧偝傟丄埲屻傕偦傫側挷巕偱34擭傑偱懕偔丅暯嬒偟偰枅寧1枃埲忋傕敪攧偝傟偰偄偨寁嶼偵側傞丅尰嵼偐傜偡傟偽怣偠傟側偄悢帤偩丅斵彈偑敪攧偟偨僔儞僌儖傪弴傪捛偭偰挳偄偰偄偔偲丄僨價儏乕摉帪偐傜10擭傎偳偺偁偄偩偵丄偁傝偲偁傜備傞椶偄偺嬋傪壧偭偰偒偨偺偑暘偐傞丅揱摑揑側壧梬嬋偐傜丄峕屗忣弿傕偺丄柉梬丄彫塖抂塖丄儅僪儘僗傕偺丄偦偟偰丄僕儍僘丄僽僊丄儖儞僶丄儅儞儃丄僞儞僑丄僇儞僩儕乕側偳偺梞妝巙岦偺嬋丄偼偰偼僣僀僗僩傗僪僪儞僷傑偱偲丄偦偺暆偺峀偝偵嬃偐偝傟傞偟丄偡傋偰傪姰帏偵丄揤堖柍朌偵壧偄偙側偡椡検偵埑搢偝傟傞丅僨價儏乕嬋偑乹壨摱僽僊僂僊乺偩偭偨偙偲偐傜傕暘偐傞傛偆偵丄傕偲傕偲斵彈偺側偐偵偼丄億僢僾僗巙岦偺梫慺丄偄傢備傞僶僞偔偝偝偑嫮偔偁偭偨傛偆偵姶偠傞丅偟偐偟丄偦偺懱撪偵偼擔杮偺揱摑惈偑愼傒崬傫偱偍傝丄偦傟傜偑堘榓姶側偔梈崌偟偰弌棃忋偑偭偨偺偑丄傂偽傝撈摿偺壒妝偩偭偨丅偗傟偳傕丄偦傟偩偗偱偼側偄丅旤嬻傂偽傝偼懠偺壧庤偲偼傑偭偨偔師尦偺堎側傞懚嵼偩偭偨丅偁偺辔嶨側恎怳傝丄姱擻揑側惡偵偼丄擔杮偺慜嬤戙惈偑怓擹偔偵偠傒弌偰偄傞丅斵彈偺壧偵偼丄尨弶揑側嵃偺鐬傝偺傛偆側傕偺傪姶偠傞丅偦傫側堄枴偱偼丄斵彈偼壧庤偲偄偆傛傝擔杮屆棃偺寍擻幰偱偁傝丄斵彈偺壧偼幮夛偐傜梷埑偝傟偨幰偑巚偄昤偔尪偩偭偨傛偆偵巚偆丅
偟偐偟丄傂偽傝偺壧偑傎傫偲偆偺堄枴偱偺峀偑傝偲怺傒傪傕偭偰偄偨偺偼丄徍榓33乣34擭偛傠傑偱丄僨價儏乕偟偰偐傜10擭娫偖傜偄偩偭偨偲巚偆丅偦傟埲屻偼偟偩偄偵墘壧傗寍摴傕偺偑儗僷乕僩儕乕偺拞怱傪愯傔傞傛偆偵側偭偨丅偦偟偰壧偄曽傕丄弶婜偺帺桼鑸払偝偑側偔側傝丄廳嬯偟偝偑慜柺偵弌傞傛偆偵側偭偰偄偭偨丅偦偺揮婡偵側偭偨嬋偼徍榓35擭偺愨彞乹垼廌攇巭応乺偩偭偨偲巚偆丅埲屻偺斵彈偼丄乹幵壆偝傫乺傗乹傂偽傝偺嵅搉忣榖乺丄偁傞偄偼傛傝屻婜偺乹晽庰応乺側偳丄惉弉偟偨壧彞椡傪帵偡嬋偑偁傞偲偼偄偊丄揤忋偐傜抧偵崀傝棫偭偨傛偆偵丄揱愢偵曪傑傟偰偼偄傞偑乬晛捠偺乭壧庤偵側偭偨丅徍榓30擭戙廔傢傝偵斵彈偼梞妝僗僞儞僟乕僪傪壧偭偨傾儖僶儉壗枃偐傪弌偟偨偑丄10擭慜偺悂偒崬傒偲斾傋傞偲丄岻偄偙偲偼岻偄偑丄偨偩偦傟偩偗偺壧偵側偭偰偄傞丅擭楊傪廳偹偰惡幙傗巔惃偑曄壔偟偨偣偄偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偁傞偄偼愴屻偺崿棎婜傪廔偊偰崅搙惉挿婜偵岦偐偆帪戙偺棳傟偑偦偆偝偣偨偺偐傕偟傟側偄丅
 擔杮僐儘儉價傾偑岞昞偟偨旤嬻傂偽傝偺僔儞僌儖攧傝忋偘儔儞僉儞僌偵傛傞偲丄1埵偑乹廮乺丄2埵偑乹愳偺棳傟偺傛偆偵乺乮偪側傒偵丄埲壓偼丄3埵乹斶偟偄庰乺丄4埵乹恀愒側懢梲乺丄5埵乹儕儞僑捛暘乺乯偩偲偄偆丅偄偔傜儗僐乕僪戝徿庴徿嬋偲偼偄偊乹廮乺偺傛偆側偮傑傜側偄嬋偑1埵偲偄偆偺偼斶偟偄丅傕偭偲偮傑傜側偄偺偼乹愳偺棳傟偺傛偆偵乺偩丅側偵傛傝傕壧帉偑捖晠偱敄偭傌傜偔丄怱偵敆傞傕偺偑壗傕側偄丄戅孅側嬋偩丅傏偔偺僼僃僀償傽儕僢僩丒僫儞僶乕傪3嬋嫇偘傠偲尵傢傟傟偽丄寧暲傒偩偑乹儕儞僑捛暘乺乹峘挰廫嶰斣抧乺乹壴妢摴拞乺偲偄偆偙偲偵側傞丅偱傕丄傎偐偵傕乹墇屻巶巕偺塖乺乹僠儍儖儊儔偦偽壆乺乹捗寉偺傆傞偝偲乺乹孨偼儅僪儘僗奀偮偽傔乺乹挿嶈偺挶乆偝傫乺乹峘挰偝傛偆側傜乺側偳丄岲偒側壧偼偨偔偝傫偁傞丅
擔杮僐儘儉價傾偑岞昞偟偨旤嬻傂偽傝偺僔儞僌儖攧傝忋偘儔儞僉儞僌偵傛傞偲丄1埵偑乹廮乺丄2埵偑乹愳偺棳傟偺傛偆偵乺乮偪側傒偵丄埲壓偼丄3埵乹斶偟偄庰乺丄4埵乹恀愒側懢梲乺丄5埵乹儕儞僑捛暘乺乯偩偲偄偆丅偄偔傜儗僐乕僪戝徿庴徿嬋偲偼偄偊乹廮乺偺傛偆側偮傑傜側偄嬋偑1埵偲偄偆偺偼斶偟偄丅傕偭偲偮傑傜側偄偺偼乹愳偺棳傟偺傛偆偵乺偩丅側偵傛傝傕壧帉偑捖晠偱敄偭傌傜偔丄怱偵敆傞傕偺偑壗傕側偄丄戅孅側嬋偩丅傏偔偺僼僃僀償傽儕僢僩丒僫儞僶乕傪3嬋嫇偘傠偲尵傢傟傟偽丄寧暲傒偩偑乹儕儞僑捛暘乺乹峘挰廫嶰斣抧乺乹壴妢摴拞乺偲偄偆偙偲偵側傞丅偱傕丄傎偐偵傕乹墇屻巶巕偺塖乺乹僠儍儖儊儔偦偽壆乺乹捗寉偺傆傞偝偲乺乹孨偼儅僪儘僗奀偮偽傔乺乹挿嶈偺挶乆偝傫乺乹峘挰偝傛偆側傜乺側偳丄岲偒側壧偼偨偔偝傫偁傞丅 偲偙傠偱愭偵傆傟偨亀戝慡廤亁偩偑丄惓幃僞僀僩儖偼亀崱擔偺変偵柧擔偼彑偮乛旤嬻傂偽傝戝慡廤亁偲偄偆丅偙傟偼婎杮揑偵斵彈偑敪攧偟偨慡僔儞僌儖偺椉柺傪僆儕僕僫儖壒尮偱僋儘僲儘僕僇儖偵廤戝惉偟偨傕偺偺傛偆偩偑乮偳傫側曽恓偺傕偲偵曇惉偝傟偨偺偐丄壗偺愢柧傕晅偝傟偰偄側偄偺偱暘偐傜側偄乯丄慡僔儞僌儖偲偄偭偰傕丄梞妝嬋傗擔杮偺婛惉嬋傪僇償傽乕偟偨傕偺偼擖偭偰偄側偄偟丄僆儕僕僫儖嬋偱傕偄偔偮偐敳偗偰偄傞偲偄偆偍慹枛側撪梕偵側偭偰偄傞丅壗偐帠忣偑偁偭偨偺偐傕偟傟側偄偑丄棟桼偼暘偐傜側偄丅偄偢傟偵偣傛丄擔杮偺壒妝巎忋丄嵟崅偺曮偲傕偄偆傋偒旤嬻傂偽傝偺懌愓偼丄傕偭偲墷暷傪尒廗偄丄姰慡側偐偨偪偱巆偟偰偍偔傋偒偩丅
偲偙傠偱愭偵傆傟偨亀戝慡廤亁偩偑丄惓幃僞僀僩儖偼亀崱擔偺変偵柧擔偼彑偮乛旤嬻傂偽傝戝慡廤亁偲偄偆丅偙傟偼婎杮揑偵斵彈偑敪攧偟偨慡僔儞僌儖偺椉柺傪僆儕僕僫儖壒尮偱僋儘僲儘僕僇儖偵廤戝惉偟偨傕偺偺傛偆偩偑乮偳傫側曽恓偺傕偲偵曇惉偝傟偨偺偐丄壗偺愢柧傕晅偝傟偰偄側偄偺偱暘偐傜側偄乯丄慡僔儞僌儖偲偄偭偰傕丄梞妝嬋傗擔杮偺婛惉嬋傪僇償傽乕偟偨傕偺偼擖偭偰偄側偄偟丄僆儕僕僫儖嬋偱傕偄偔偮偐敳偗偰偄傞偲偄偆偍慹枛側撪梕偵側偭偰偄傞丅壗偐帠忣偑偁偭偨偺偐傕偟傟側偄偑丄棟桼偼暘偐傜側偄丅偄偢傟偵偣傛丄擔杮偺壒妝巎忋丄嵟崅偺曮偲傕偄偆傋偒旤嬻傂偽傝偺懌愓偼丄傕偭偲墷暷傪尒廗偄丄姰慡側偐偨偪偱巆偟偰偍偔傋偒偩丅
2009.10.08 (栘) 乬將偺椡乭偵撍偒摦偐偝傟偨恖乆偑偨偳傞塣柦偼
 丂丂僂傿儞僘儘僂偺弌悽嶌偵側偭偨僔儕乕僘戞1嶌亀僗僩儕乕僩丒僉僢僘亁傪偼偠傔偲偡傞僯乕儖丒働傾儕乕丒僒乕僈偼丄僴乕僪儃僀儖僪丒儈僗僥儕乕偱偁傝側偑傜丄庡恖岞偱偁傞旕峴彮擭偁偑傝偺惵擭扵掋偺堦庬偺惉挿暔岅偺傛偆側庯傪掓偟偰偍傝丄惵弔彫愢傪巚傢偣傞悙乆偟偄僞僢僠偑枺椡傪曻偭偰偄偨丅偱傕柺敀偐偭偨偺偼慡晹偱5嶌傪悢偊傞僔儕乕僘偺1嶌栚偲2嶌栚乮亀暓懮偺嬀傊偺摴亁乯偖傜偄偱丄偁偲偼偩傫偩傫僗儕儖偵朢偟偔側偭偰偄偭偨丅嵟廔嶌亀嵒敊偱揗傟傞傢偗偵偼偄偐側偄亁側偳偼傑偭偨偔惙傝忋偑傝偵寚偗丄僔儕乕僘奜偺亀儃價乕Z偺婥懹偔桪夒側恖惗亁偼捝夣側弌棃偩偭偨偲偼偄偊丄偁偁丄傕偆僂傿儞僘儘僂偼廔傢傝偩側偲巚偭偨傕偺偩偭偨丅偩偐傜丄媣偟傇傝偵敪攧偝傟偨偙偺怴嶌偺曄杄傇傝偲椡嫮偝偵傃偭偔傝偟偨偺偩丅
丂丂僂傿儞僘儘僂偺弌悽嶌偵側偭偨僔儕乕僘戞1嶌亀僗僩儕乕僩丒僉僢僘亁傪偼偠傔偲偡傞僯乕儖丒働傾儕乕丒僒乕僈偼丄僴乕僪儃僀儖僪丒儈僗僥儕乕偱偁傝側偑傜丄庡恖岞偱偁傞旕峴彮擭偁偑傝偺惵擭扵掋偺堦庬偺惉挿暔岅偺傛偆側庯傪掓偟偰偍傝丄惵弔彫愢傪巚傢偣傞悙乆偟偄僞僢僠偑枺椡傪曻偭偰偄偨丅偱傕柺敀偐偭偨偺偼慡晹偱5嶌傪悢偊傞僔儕乕僘偺1嶌栚偲2嶌栚乮亀暓懮偺嬀傊偺摴亁乯偖傜偄偱丄偁偲偼偩傫偩傫僗儕儖偵朢偟偔側偭偰偄偭偨丅嵟廔嶌亀嵒敊偱揗傟傞傢偗偵偼偄偐側偄亁側偳偼傑偭偨偔惙傝忋偑傝偵寚偗丄僔儕乕僘奜偺亀儃價乕Z偺婥懹偔桪夒側恖惗亁偼捝夣側弌棃偩偭偨偲偼偄偊丄偁偁丄傕偆僂傿儞僘儘僂偼廔傢傝偩側偲巚偭偨傕偺偩偭偨丅偩偐傜丄媣偟傇傝偵敪攧偝傟偨偙偺怴嶌偺曄杄傇傝偲椡嫮偝偵傃偭偔傝偟偨偺偩丅丂丂偙偙偵昤偐傟傞丄儊僉僔僐傪嫆揰偲偡傞撿暷偺杻栻價僕僱僗偺幚懺乗乗朶椡偵傛傞慻怐壔丄尃椡偲偺桙拝丄堿杁丄埫嶦乗乗偼偡偝傑偠偄丅偦偙偵傾儊儕僇惌晎偑CIA傪捠偠偰巇妡偗傞墭偄杁棯偑崿棎偲嶦滳傪惗傓丅偍偦傜偔丄偐側傝偺晹暘偑帠幚偵嬤偄偩傠偆丅幏擮偵嬱傜傟丄壠懓傪幪偰偰傑偱杻栻僇儖僥儖偺儃僗傪捛偄偐偗傞憑嵏姱丄僯儏乕儓乕僋偺儅僼傿傾偺庤愭偐傜惁榬偺嶦偟壆偵惉挿偡傞丄撈帺偺椣棟姶傪傕偮惵擭丄壠懓傗拠娫傪垽偟側偑傜傕丄價僕僱僗偺偨傔偵偼暯婥偱揋傗幾杺幰傪徚偡僇儖僥儖偺儃僗乗乗庡恖岞偨偪偼丄慞恖偵偟傠埆恖偵偟傠丄傒側寣擏偺偁傞堿塭備偨偐側憿宍偑側偝傟偰偄傞丅偙偺3恖埲奜偵傕偨偔偝傫偺恖暔偑搊応偡傞偑丄傒側惗偒惗偒偲昤偐傟偰偄傞丅側偐偱傕庡恖岞偨偪偵偐傜傓旤杄偺崅媺彥晈偺懚嵼姶偼嵺棫偭偰偄傞丅慡曇偵廵抏偲寣偲娋偑傎偲偽偟偭偰偄傞偑丄僄儞僞僥僀儞儊儞僩偺崪奿傪摜傑偊偨僗僩乕儕乕揥奐偼怱抧傛偔丄屻枴偼憉傗偐偩丅堦旂傓偗偨僂傿儞僘儘僂偺崱屻偐傜栚偑棧偣側偔側偭偨丅
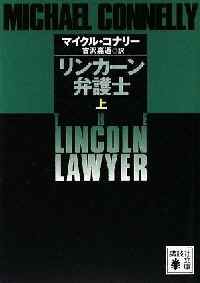 丂丂偄偭傐偆丄僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘傪拞怱偵幙偺崅偄僴乕僪儃僀儖僪傪彂偒懕偗偰偄傞儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺怴嶌亀儕儞僇乕儞曎岇巑亁乮島択幮暥屔丄2009擭6寧姧乯偼丄媣乆偺僔儕乕僘奜偺嶌昳丅僐僫儕乕偵偼捒偟偔丄曎岇巑傪庡恖岞偵偟偨儕乕僈儖丒僒僗儁儞僗偩丅嬛梸揑偱埫偄塭偺偁傞儃僢僔儏偲堘偄丄偙偺曎岇巑偼丄榬偼棫偮偑丄崅媺戝宆幵儕儞僇乕儞傪忔傝夞偟丄嬥偵側傞埶棅恖傪懆傑偊傞偺偵媯乆偲偟偰偄傞恖娫偩丅偝偡偑偵僐僫儕乕偱丄岅傝岥偼岻偄偟丄恖娫娭學乗乗偲偔偵庡恖岞偲暿傟偨嵢偺専帠偺偲偺乗乗昤偒曽傕柺敀偔丄偦傟傎偳婲暁偺側偄僗僩乕儕乕揥奐側偺偵丄嵟屻傑偱堦婥偵撉傑偣傞丅偩偑丄嬥姩掕偵傔偞偲偄嫕妝揑側僉儍儔僋僞乕偲偄偆庡恖岞偺愝掕偑丄傕偆傂偲偮撻愼傔側偄丅
丂丂偄偭傐偆丄僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘傪拞怱偵幙偺崅偄僴乕僪儃僀儖僪傪彂偒懕偗偰偄傞儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺怴嶌亀儕儞僇乕儞曎岇巑亁乮島択幮暥屔丄2009擭6寧姧乯偼丄媣乆偺僔儕乕僘奜偺嶌昳丅僐僫儕乕偵偼捒偟偔丄曎岇巑傪庡恖岞偵偟偨儕乕僈儖丒僒僗儁儞僗偩丅嬛梸揑偱埫偄塭偺偁傞儃僢僔儏偲堘偄丄偙偺曎岇巑偼丄榬偼棫偮偑丄崅媺戝宆幵儕儞僇乕儞傪忔傝夞偟丄嬥偵側傞埶棅恖傪懆傑偊傞偺偵媯乆偲偟偰偄傞恖娫偩丅偝偡偑偵僐僫儕乕偱丄岅傝岥偼岻偄偟丄恖娫娭學乗乗偲偔偵庡恖岞偲暿傟偨嵢偺専帠偺偲偺乗乗昤偒曽傕柺敀偔丄偦傟傎偳婲暁偺側偄僗僩乕儕乕揥奐側偺偵丄嵟屻傑偱堦婥偵撉傑偣傞丅偩偑丄嬥姩掕偵傔偞偲偄嫕妝揑側僉儍儔僋僞乕偲偄偆庡恖岞偺愝掕偑丄傕偆傂偲偮撻愼傔側偄丅丂丂偁偲偑偒偵傛傞偲丄儃僢僔儏丒僔儕乕僘偼嵟屻偵擔杮偱敪攧偝傟偨亀廔寛幰偨偪亁埲崀丄傾儊儕僇偱偼偡偱偵4嶜傕弌偰偄傞傜偟偄丅栿幰偺屆戲壝捠偝傫丄婃挘偭偰偔偩偝偄丅
2009.09.18 (嬥) 墿崹偺戝塸掗崙
儘儞僪儞偼暔壙偑崅偄丅幚姶偲偟偰偼搶嫗傛傝崅偄姶偠偑偡傞丅埲慜偼1億儞僪偑200墌埲忋偟偰偄偨偑丄偄傑偼栺160墌偱偁傝丄億儞僪偺壙抣偼偢偄傇傫壓偑偭偨丅偦偺崱偺姺嶼儗乕僩偱寁嶼偟偰傕丄儘儞僪儞偺傕偺偺抣抜偼崅偄丅怘嵽偼斾妑揑埨壙偩偑丄價乕儖偼1僷僀儞僩偑700墌偩偟丄僞僶僐偼堦敔側傫偲1000墌傕偡傞乮偦傫側偵僞僶僐偑崅偔偰傕丄偦偟偰壆撪偼慡柺揑偵嬛墝偵側偭偰傕丄僞僶僐傪媧偆恖偼懡偄丅傒側捠傝偱媧偭偰偄傞丅偩偐傜曕摴偵偼媧偄妅偑嶶棎偡傞乯丅
抧壓揝偺椏嬥傕弶忔傝640墌偲僶僇崅偄乮僾儕儁僀僪丒僇乕僪傪巊偊偽偦偺敿妟埲壓偱忔傟傞偑乯丅崅妟偺晅壛壙抣惻偺偣偄傕偁傞偩傠偆偑丄僇僼僃傗儗僗僩儔儞偱怘傋傞怘旓傕擔杮傛傝偐側傝崅偄丅壠捓傕崅妟傜偟偄丅偦偺偄偭傐偆廂擖偼丄傾儊儕僇偲摨偠偔奿嵎偑寖偟偄偺偱偄偪偑偄偵偼尵偊側偄偑丄暯嬒揑偵偼擔杮傛傝掅偄偼偢偩丄偍傑偗偵惻嬥傗幮夛曐忈旓傕崅妟側偺偱丄庤庢傝偼傕偭偲彮側偔側傞丅幮夛曐忈偼廩幚偟偰偄傞偲偼偄偊丄堦斒揑側恖乆偺惗妶偼妝偱偼側偄偩傠偆丅
偁傞栭丄偦偺JJ僞僂儞偺堦妏偵偁傞僷僽偵峴偭偨丅揦柤偼乽僉儍僢僠儍乕丒僀儞丒僓丒儔僀乿丅偁偺僒儕儞僕儍乕偺桳柤側彫愢偺僞僀僩儖偩丅揦撪偵偼僕儑儞丒儗僲儞偺幨恀偑偨偔偝傫忺偭偰偁傞丅側傫偱傕儗僲儞偑垽撉偟偨偺偑偙偺彫愢偩偭偨傜偟偄丅偙偙偼丄傑偁丄擔杮偱尵偊偽嫃庰壆偩傠偆丅嬑傔婣傝偺僒儔儕乕儅儞傗抧尦偺僆儎僕偨偪偑惡崅偵價乕儖傪堸傒側偑傜挐偭偰偄傞丅偦偙偱堸傫偩儔僈乕偲僊僱僗丄偦傟偵僼傿僢僔儏仌僠僢僾僗偼偝偡偑偵旤枴偟偐偭偨丅
2009.08.31 (寧) 憤慖嫇偱埑彑偟偨柉庡搣偵婜懸偡傞
偙偺嶴攕偲偄偆寢壥傪庴偗偰僐儊儞僩傪岅傞帺柉搣姴晹偺尵梩偼傂偳偐偭偨丅斵傜偼傒側丄乽変乆偺惌嶔傗慽偊偑桳尃幰偺棟夝傪摼傜傟側偐偭偨乿側偳偲丄傑傞偱帺暘偨偪偼惓偟偄偙偲傪傗偭偰偒偨偺偵丄偦傟傪棟夝偱偒側偄崙柉偑埆偄偲偱傕尵偆傛偆側岥傇傝偱岅偭偨丅杻惗庱憡側偳偼丄洎慠帺幐偲偄偭偨忬懺偱夛尒偵椪傒丄儘儃僢僩偺傛偆偵婡夿揑側庴偗摎偊偱攕愴偺曎傪岅偭偰偄偨偑丄嵟屻傑偱帺暘偺愑擟傪擣傔傛偆偲偣偢丄夵傔偰儕乕僟乕偲偟偰偺帒幙偺側偝偲墲惗嵺偺埆偝傪偝傜偗偩偟偨丅帺柉搣偺曽恓偺岆傝傪偼偭偒傝擣傔偰偄偨偺偼丄棊慖偟偨梌幱栰嵿柋憡偩偗偩偭偨丅偙傫側忬嫷偱偼丄憤慖嫇屻偺帺柉搣偺夝懱偼帪娫偺栤戣偩傠偆丅
偙傟偼擔杮偺惌帯偺戝偒側揮姺揰偩丅挿擭偵傢偨傞帺柉搣偺媈帡撈嵸惌尃偵傛偭偰惗偠偨丄旀暰偟偨姱椈婡峔丄尃椡偲桙拝偟偨惌帯丄崙柉偐傜槰棧偟偨峴惌丄彫愹偺埆惌偑傕偨傜偟偨條乆側暰奞丄懳暷廬懏奜岎傪丄傗偭偲惀惓偡傞偡傞偲偒偑偒偨偺偩丅偱傕柉庡搣偼偙傟偐傜偑戝曄偩丅偦傟傪扤傛傝傕帺妎偟偰偄傞偺偼丄偙傟偐傜惌尃傪扴偆柉庡搣偺媍堳偺恖乆偩傠偆丅栤戣偼嶳愊傒偟偰偄傞丅憹惻偣偢崙嵚傕敪峴偣偢丄嵿尮傪妋曐偱偒傞偺偐丄姱椈惂搙傪夵妚偱偒傞偺偐丄摢偺偄偄姱椈傪傎傫偲偆偵斵傜偼巊偄偙側偣傞偺偐丄宨婥偺夞暅偼丄擭嬥栤戣偼丄夘岇惂搙偼丄梄惌柉塩壔偺尒捈偟偼丄暷孯婎抧栤戣偼丄懳奜惌嶔偼丒丒丒偳傟傂偲偮偲偟偰梙傞偑偣偵偱偒側偄偙偲偽偐傝偩丅
柉庡搣偵傎傫偲偆偺夵妚偑偱偒傞偺偩傠偆偐丅傏偔偼婜懸偱偒傞偲巚偆丅數嶳戙昞偼儅僯僼僃僗僩傪幚尰偱偒側偐偭偨傜愑擟傪庢傞偲抐尵偟偰偄傞丅斵偺桭垽偺棟擮偼杮暔偩偲巚偆乗乗偪傚偭偲惵廘偄姶偠傕偡傞偑丅柉庡搣偼偙傟傑偱丄尃椡偵偟偑傒偮偒丄姱椈偵埶懚偡傞帺柉搣偺惌帯傪尒偰偒偨丅偦偟偰帺暘偨偪側傜偙偆偡傞偲偄偆曽恓傪楙偭偰偒偨丅偩偐傜斵傜偼丄廜媍堾偺夁敿悢偺媍惾傪摼偨偙偲偵傛傝丄偦傟傪巚偄愗偭偰幚峴偱偒傞丅戝惃偑寛傑偭偨偁偲偺夛尒偱岅傞數嶳丄娗丄壀揷傜柉庡搣姴晹偺婄偼堷偒掲傑偭偰偄偰丄妎屽偺巚偄偑昞傟偰偍傝丄晜偐傟偨條巕傗偩傜偗偨暤埻婥偼側偐偭偨丅搣撪偵偼偄傠傫側峫偊偺帩偪庡偑偍傝丄側偐偵偼慜尨堦攈偺傛偆側孯旛憹嫮榑幰傕偄偰丄偗偭偟偰堦枃娾偱偼側偄丅傕偟偐偟偨傜堄偁偭偰椡懌傜偢偵側傞偐傕偟傟側偄丅偱傕傏偔偼偄傑偺柉庡搣偺夵妚傊偺擬堄偼杮暔偩偟丄偦傟傪幚峴偱偒傞僷儚乕傕偁傞偲巚偆丅偡偖偵幚峴偱偒側偔偰傕尒愗傝傪偮偗偢丄挿偄栚偱柉庡搣偺夵妚偺備偔偊傪尒庣偭偰偄偒偨偄丅
偙偙偐傜偼梋択偵側傞丅傏偔偑尒偰偄偨僥儗價挬擔偺慖嫇懍曬偼怺栭12丗30偱廔傢傝丄偦偺偁偲斣慻偼帺柉搣屼梡僕儍乕僫儕僗僩偺揷尨憤堦榊偑巌夛偡傞摙榑夛偵愗傝懼傢偭偨丅揷尨偼奐岥堦斣丄乽柉庡搣偑300媍惾傕妉偭偨偺偵傃偭偔傝偟偨乿偲尵偭偨丅偦偟偰乽偙傫側偵傂偲偮偺搣偵媍惾偑廤傑傞側傫偰丄偳偙偐偍偐偟偄丄婥帩偪偑埆偄乿側偳偲岥憱偭偨丅埲慜偐傜儅僗僐儈偱偼柉庡埑彑偲偄偆梊應偑側偝傟偰偄偨偺偵丄幚嵺偵偦傫側寢壥偑弌偰傎傫偲偆偵傃偭偔傝偟偰偄傞偺側傜丄揷尨偼搙偟偑偨偄垻曫偩丅柉庡搣偑埑彑偟偨偺偼丄帺柉搣惌帯偐傜寛暿偟偨偄偲偄偆崙柉偺巚偄偑嫮偔丄彫慖嫇嬫惂偩偑傜偦傟偑僗僩儗乕僩偵弌偨偩偗偺偙偲偱偁傝丄慺恖偱傕棟夝偱偒傞丅偦傫側偙偲傕暘偐傜側偄揷尨偼僕儍乕僫儕僗僩幐奿偩丅摙榑偑僗僞乕僩偡傞慜丄埨攞尦庱憡偑價僨僆弌墘偟偰憤慖嫇偺寢壥偵偮偄偰挐偭偨偑丄揷尨偼乽杻惗偝傫偵偼價僕儑儞偑側偐偭偨偑丄埨攞偝傫偼價僕儑儞傪帩偭偰偄偨乿偲丄偙偺惌尃傪搑拞偱搳偘弌偟偰悽奅偺徫偄暔偵側偭偨帺柉搣搣攕杒偺A媺愴斊偵偡傝婑偭偰偄偨丅僥儗價挬擔偑側偤偙傫側掱搙偺掅偄懎暔僕儍乕僫儕僗僩傪廳梡偡傞偺偐暘偐傜側偄丅
2009.08.28 (嬥) 僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺2枃偺儗傾CD
 丂傑偢亀Clifford Brown: The Complete Quebec Jam Session亁乮RLR 88646乯偩偑丄偙傟偼1955擭7寧29擔偵峴傢傟偨僇僫僟偺働儀僢僋偱偺僕儍儉丒僙僢僔儑儞傪拞怱偲偟偨傾儖僶儉丅儘僽丒儅僢僐乕僱儖偲偄偆抧尦偺僩儘儞儃乕儞憈幰偲偺嫟墘偱偁傝丄儊儞僶乕偼僽儔僂儞偲儅僢僐乕僱儖傪彍偄偰晄柧偩丅儔僀僫乕偱偼僥僫乕傪僴儘儖僪丒儔儞僪偲悇掕偟偰偄傞丅榐傜傟偨応強偼僋儔僽偱偼側偔丄僗僞僕僆偐扤偐偺帺戭乮偍偦傜偔儅僢僐乕僱儖偺乯偩偲巚傢傟傞丅僽儔僂儞亖儘乕僠丒僋僀儞僥僢僩偑働儀僢僋偵僣傾乕傪偟偨偲偒偵峴傢傟偨僙僢僔儑儞偱偁傠偆丅乹All the Things You Are乺乹Lady Be Good乺乹Strike Up the Band乺乹Ow!乺側偳丄慡5嬋丄僽儔僂儞偲偟偰偼捒偟偄嬋偑暲傫偱偄傞偺偼嫽枴怺偄偑丄墘憈偲偟偰偼嶶枱偱丄偁傑傝尒傞傋偒傕偺偼側偄丅偦傟偱傕乹Strike Up the Band乺偱偺僽儔僂儞偺傾僢僾丒僥儞億偵忔偭偨婸偐偟偄僜儘偼挳偒傕偺偩丅
丂傑偢亀Clifford Brown: The Complete Quebec Jam Session亁乮RLR 88646乯偩偑丄偙傟偼1955擭7寧29擔偵峴傢傟偨僇僫僟偺働儀僢僋偱偺僕儍儉丒僙僢僔儑儞傪拞怱偲偟偨傾儖僶儉丅儘僽丒儅僢僐乕僱儖偲偄偆抧尦偺僩儘儞儃乕儞憈幰偲偺嫟墘偱偁傝丄儊儞僶乕偼僽儔僂儞偲儅僢僐乕僱儖傪彍偄偰晄柧偩丅儔僀僫乕偱偼僥僫乕傪僴儘儖僪丒儔儞僪偲悇掕偟偰偄傞丅榐傜傟偨応強偼僋儔僽偱偼側偔丄僗僞僕僆偐扤偐偺帺戭乮偍偦傜偔儅僢僐乕僱儖偺乯偩偲巚傢傟傞丅僽儔僂儞亖儘乕僠丒僋僀儞僥僢僩偑働儀僢僋偵僣傾乕傪偟偨偲偒偵峴傢傟偨僙僢僔儑儞偱偁傠偆丅乹All the Things You Are乺乹Lady Be Good乺乹Strike Up the Band乺乹Ow!乺側偳丄慡5嬋丄僽儔僂儞偲偟偰偼捒偟偄嬋偑暲傫偱偄傞偺偼嫽枴怺偄偑丄墘憈偲偟偰偼嶶枱偱丄偁傑傝尒傞傋偒傕偺偼側偄丅偦傟偱傕乹Strike Up the Band乺偱偺僽儔僂儞偺傾僢僾丒僥儞億偵忔偭偨婸偐偟偄僜儘偼挳偒傕偺偩丅丂傎偐偵偙偺傾儖僶儉偵偼僔僇僑偺價乕僴僀償偱榐傜傟偨儔僀償偑3嬋丄儃僗僩儞偺僗僩乕儕乕償傿儖偱榐傜傟偨曻憲榐壒偑2嬋丄僽儔僂儞偺僥儗價弌墘帪偺墘憈2嬋偑廂傔傜傟偰偄傞丅價乕僴僀償偱偺儔僀償偼1955擭12寧偺榐壒丅傓偐偟亀儘僂丒僕僯傾僗亁偲偄偆僞僀僩儖偱敪攧偝傟偨丄儘儕儞僘偲僽儔僂儞偺僕儍儉丒僙僢僔儑儞偺枹敪昞嬋偩丅偙偺墘憈偑傾儖僶儉偺側偐偱偼堦斣慺惏傜偟偄丅乹A Night in Tunisia乺乹Billie's Bounce乺偱偺僽儔僂儞偺镈憉偨傞僾儗僀偼僼傽儞偺妷傪桙偟偰偔傟傞丅偄傑偺偲偙傠僽儔僂儞偺摦偔塮憸偑尒傜傟傞桞堦偺僜乕僗偑丄1956擭2寧偵僥儗價偺僗乕僺乕丒僙僀儖僗丒僔儑僂偵弌墘偟偨偲偒偺傕偺偩偑丄嵟屻偺2嬋乹Lady Be Good乺乹Memories of You乺偼偦偙偱墘憈偝傟偨僩儔僢僋偩丅僀儞僞價儏乕偱丄僽儔僂儞偑嵟嬤巕嫙偑惗傑傟偨偙偲傪婐偟偦偆偵岅偭偰偄傞偺偑捝傑偟偄丅偙傟傛傝4儢寧屻丄僽儔僂儞偼懅巕偺惉挿傪尒傞偙偲側偔岎捠帠屘巰偟偰偟傑偆丅
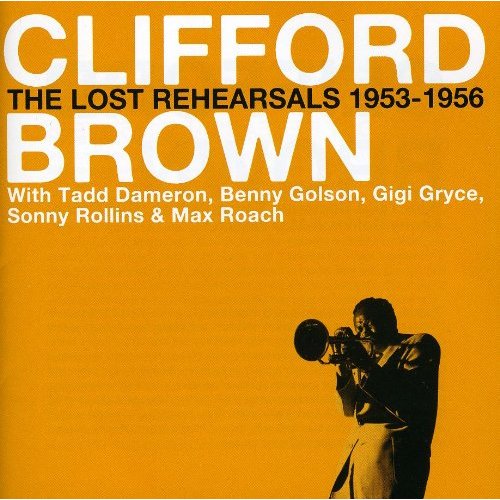 丂傕偆堦枃偺傾儖僶儉偼亀Clifford Brown: The Lost Rehearsals 1953-56亁乮RLR 88651乯偲僞僀僩儖偝傟偰偄傞丅偙偺CD偼慜宖偺亀Quebec Jam Session亁傛傝偼傞偐偵廩幚偟偰偍傝丄挳偒偛偨偊偑偁傞丅偙傟偼1953擭6寧偵僽儔僂儞偑僞僢僪丒僟儊儘儞偺僌儖乕僾偵擖偭偰峴側偭偨儕僴乕僒儖丒僙僢僔儑儞偑拞怱偵側偭偰偄傞丅廂榐嬋偼乹Somebody Loves Me乺乹Indiana乺乹I'll Remember April乺乹A Night in Tunisia乺側偳8嬋丅僽儔僂儞偼僕儍僘丒僔乕儞偵僨價儏乕偟偨偽偐傝偩偭偨偑丄偡偱偵傎傏姰惉偝傟偨僗僞僀儖偱墘憈偟偰偄傞偺偵嬃偐偝傟傞丅儊儞僶乕偵偼儀僯乕丒僑儖僜儞丄僕僕丒僌儔僀僗丄僼傿儕乕丒僕儑乕丒僕儑乕儞僘側偳偑擖偭偰偄傞丅僽儔僂儞偼1953擭6寧11擔偵僟儊儘儞偺僌儖乕僾偵擖偭偰僾儗僗僥傿僢僕偵乹Choose Now乺側偳4嬋傪榐壒偟偰偄傞丅偩偑偙偺儕乕僴乕僒儖丒僙僢僔儑儞偱偼偦傟傜偺嬋偼墘憈偟偰偄側偄丅偩偐傜丄偍偦傜偔偙偺儕僴乕僒儖偼儔僀償墘憈偺偨傔偺傕偺偱偁傠偆丅
丂傕偆堦枃偺傾儖僶儉偼亀Clifford Brown: The Lost Rehearsals 1953-56亁乮RLR 88651乯偲僞僀僩儖偝傟偰偄傞丅偙偺CD偼慜宖偺亀Quebec Jam Session亁傛傝偼傞偐偵廩幚偟偰偍傝丄挳偒偛偨偊偑偁傞丅偙傟偼1953擭6寧偵僽儔僂儞偑僞僢僪丒僟儊儘儞偺僌儖乕僾偵擖偭偰峴側偭偨儕僴乕僒儖丒僙僢僔儑儞偑拞怱偵側偭偰偄傞丅廂榐嬋偼乹Somebody Loves Me乺乹Indiana乺乹I'll Remember April乺乹A Night in Tunisia乺側偳8嬋丅僽儔僂儞偼僕儍僘丒僔乕儞偵僨價儏乕偟偨偽偐傝偩偭偨偑丄偡偱偵傎傏姰惉偝傟偨僗僞僀儖偱墘憈偟偰偄傞偺偵嬃偐偝傟傞丅儊儞僶乕偵偼儀僯乕丒僑儖僜儞丄僕僕丒僌儔僀僗丄僼傿儕乕丒僕儑乕丒僕儑乕儞僘側偳偑擖偭偰偄傞丅僽儔僂儞偼1953擭6寧11擔偵僟儊儘儞偺僌儖乕僾偵擖偭偰僾儗僗僥傿僢僕偵乹Choose Now乺側偳4嬋傪榐壒偟偰偄傞丅偩偑偙偺儕乕僴乕僒儖丒僙僢僔儑儞偱偼偦傟傜偺嬋偼墘憈偟偰偄側偄丅偩偐傜丄偍偦傜偔偙偺儕僴乕僒儖偼儔僀償墘憈偺偨傔偺傕偺偱偁傠偆丅丂偙偙偵偼傎偐偵2庬椶偺墘憈偑廂榐偝傟偰偄傞丅1954擭榐壒偺乹Pennies from Heaven乺乹Second Balcony Jump乺側偳4嬋偼丄儊儞僶乕偑僥僨傿丒僄僪儚乕僘丄僇乕儖丒僷乕僉儞僗丄儅僢僋僗丒儘乕僠乮偄偢傟傕悇掕乯偲側偭偰偄傞丅偙傟偑惓偟偗傟偽丄僽儔僂儞亖儘乕僠丒僌儖乕僾傪婙梘偘偟偨捈屻偺儕僴乕僒儖丒僙僢僔儑儞偱偁傝丄偁偺GNP偐傜敪攧偝傟偨亀僀儞丒僐儞僒乕僩亁偺慜屻偲偄偆偙偲偵側傞丅偙偙偱偺僽儔僂儞偼嵟崅偺僾儗僀傪揥奐偟偰偄傞丅慜偺僙僢僔儑儞偲斾傋偰挿懌偺恑曕傪悑偘偰偄傞偺偑暘偐傞丅偲偔偵乹Pennies from Heaven乺偱偺旤偟偄僼儗乕僘偑師乆偵偁傆傟弌傞僜儘偼姶摦揑偩丅嵟屻偺3嬋偼儘儕儞僘壛擖屻偺1956擭偺僙僢僔儑儞丅僽儔僂儞偼丄僟僽儖丒僞僀儉丄僩儕僾儖丒僞僀儉傪嬱巊偟偰丄懍偔悂偔偙偲偵堎忢側幏擮傪擱傗偟偰偍傝丄柧傜偐偵屻婜偺摿挜偑尒傜傟傞丅偙偆偟偰傾儖僶儉慡懱傪挳偔偲丄偦傟偧傟偺僙僢僔儑儞偵丄弶婜丄拞婜丄屻婜偺僽儔僂儞偺僗僞僀儖丄悂偒曽偺堘偄偑昞傟偰偍傝丄嫽枴偑恠偒側偄丅
丂僽儔僂儞偺儗傾壒尮偺CD壔傕偦傠偦傠戝媗傔偺姶偑偁傞偑丄傏偔偺抦傞偐偓傝丄傑偩慺嵽偼巆偭偰偄傞偼偢偩丅塡偵傛傞偲丄僽儔僂儞偑僐儖僩儗乕儞偲嫟墘偟偨壒尮傕偁傞傜偟偄偑丄偙傟偼傑偩傑偭偨偔悽偵弌偰偄側偄丅偱傕丄2恖偲傕摨帪婜偵僼傿儔僨儖僼傿傾傪嫆揰偲偟偰尋鑢偟偰偄偨偐傜丄懚嵼偟偰偄傞壜擻惈偼偁傞丅僽儔僂儞偼1951擭偵丄儀僯乕丒僴儕僗偺戙栶偲偟偰丄僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕偺僋僀儞僥僢僩偵擖偭偰僋儔僽偱1廡娫墘憈偟偰偄傞偐傜丄傕偟偐偟偨傜僷乕僇乕偲偺嫟墘僥乕僾傕敪孈偝傟傞偐傕偟傟側偄丅傑偁丄偁傑傝婜懸偣偢偵懸偮偙偲偵偟傛偆丅
2009.08.07 (嬥) 僕儍儞僑偺煭扙偲僼儗僨傿偺擬婥
丂偲偄偆偙偲偱丄嵟嬤挳偄偰柺敀偐偭偨僕儍僘偺傾儖僶儉傪嫇偘偰偍偙偆丅
Jazz Manouche Vol.2 (Rambling Records)
 丂僞僀僩儖偳偍傝丄僕儍僘丒儅僰乕僔儏丄偄傢備傞僕僾僔乕丒僗僀儞僌偺僐儞僺儗乕僔儑儞丒傾儖僶儉丅慜偵弌偨戞1廤傕傛偐偭偨偑丄偙偺戞2廤傕柺敀偄丅僼儔儞僗偱惂嶌偝傟偨傕偺偱丄傎偲傫偳挳偄偨偙偲偺側偄儈儏乕僕僔儍儞偑暲傫偱偄傞偑丄慖嬋偑慺惏傜偟偔丄撪梕偼廩幚偟偰偄傞丅僕儍働僢僩偺煭棊偨姶妎偵傕怱庝偐傟傞丅
丂僞僀僩儖偳偍傝丄僕儍僘丒儅僰乕僔儏丄偄傢備傞僕僾僔乕丒僗僀儞僌偺僐儞僺儗乕僔儑儞丒傾儖僶儉丅慜偵弌偨戞1廤傕傛偐偭偨偑丄偙偺戞2廤傕柺敀偄丅僼儔儞僗偱惂嶌偝傟偨傕偺偱丄傎偲傫偳挳偄偨偙偲偺側偄儈儏乕僕僔儍儞偑暲傫偱偄傞偑丄慖嬋偑慺惏傜偟偔丄撪梕偼廩幚偟偰偄傞丅僕儍働僢僩偺煭棊偨姶妎偵傕怱庝偐傟傞丅丂嵟嬤偼丄僕僾僔乕偲偄偆尵梩偑嵎暿梡岅偩偲偐偱丄儅僰乕僔儏傗儘儅偲偄偭偨尵梩偑巊傢傟偰偄傞傛偆偩偑丄杮崙僼儔儞僗傗傾儊儕僇偱偼偄傑傕僕僾僔乕偲偄偆尵梩傪晛捠偵巊偭偰偍傝丄幚嵺偼偳偆側偺偐丄傛偔暘偐傜側偄丅傑偁丄偄偮偺悽偵傕丄偄偒偑偭偰怴偟偄尵梩傪巊偄偨偑傞恖庬偼偄傞傢偗偱丅
丂傾儖僶儉偺拞恎偼丄傕偪傠傫僊僞乕傪僼傿乕僠儍乕偟偨墘憈偑拞怱偩偑丄僺傾僲丄償傽僀僆儕儞丄傾僐乕僨傿僆儞丄僥僫乕丄僐乕儔僗傪慜柺偵弌偟偨傕偺傕偁傝丄僶儔僄僥傿朙偐丅墘憈偼傒側偦傟側傝偵挳偒偳偙傠偑偁傞偟丄嬋偺攝楍偼娚媫偵晉傫偱偍傝丄抦偭偰偄傞嬋丄柍柤偺嬋偑偄偄嬶崌偵嶶傜偽偭偰偄偰丄BGM偲偟偰棳偟偰偄偰朞偒偑偙側偄丅
丂摉慠側偑傜丄僕僾僔乕丒僗僀儞僌偺奐慶僕儍儞僑丒儔僀儞僴儖僩偺僒僂儞僪偲丄偙偙偵廂傔傜傟偨僕儍儞僑偺乬巕懛乭偨偪偺僒僂儞僪偼丄帡偰旕側傞傕偺偩丅僥僋僯僢僋傗僒僂儞僪偼僕儍儞僑偦偭偔傝偩偑丄僕儍儞僑偺墘憈偵偁偭偨怺傒丄樅埫偝丄姱擻惈側偳偼丄偙偙偵偼側偄丅偱傕丄擔杮偺壧梬嬋偵傕捠偠傞儅僀僫乕挷偺儊儘僨傿丄寉夣側僗僀儞僌姶偼丄挳偄偰偄偰怱抧傛偔丄怱偑榓傫偱偔傞丅
僼儗僨傿丒僴僶乕僪/僂傿僓僂僩丒傾丒僜儞僌丗儔僀償丒僀儞丒儓乕儘僢僷1969 (EMI)
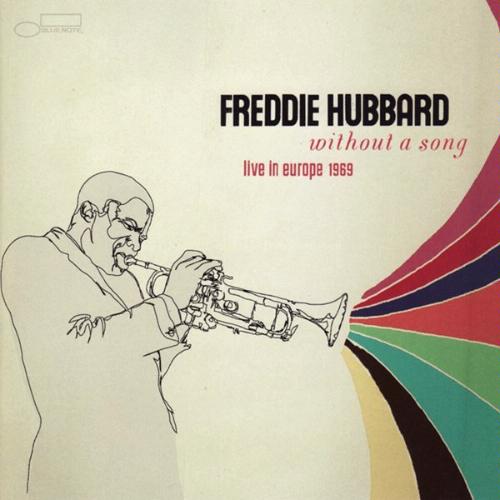 丂嶐擭枛偵朣偔側偭偨僼儗僨傿丒僴僶乕僪偺枹敪昞儔僀償丅1969擭偲偄偊偽丄偦傟傑偱強懏偟偰偄偨傾僩儔儞僥傿僢僋偐傜CTI偵堏愋偡傞慜屻偺帪婜偩丅僼儗僨傿偼儘乕儔儞僪丒僴僫埲壓偺儕僘儉丒僙僋僔儑儞傪僶僢僋偵丄儚儞丒儂乕儞偱丄巚偄愗傝杬曻偵悂偒傑偔偭偰偄傞丅傑傞偱旘傃嶶傞娋偑姶偠傜傟傞偐偺傛偆偩丅
丂嶐擭枛偵朣偔側偭偨僼儗僨傿丒僴僶乕僪偺枹敪昞儔僀償丅1969擭偲偄偊偽丄偦傟傑偱強懏偟偰偄偨傾僩儔儞僥傿僢僋偐傜CTI偵堏愋偡傞慜屻偺帪婜偩丅僼儗僨傿偼儘乕儔儞僪丒僴僫埲壓偺儕僘儉丒僙僋僔儑儞傪僶僢僋偵丄儚儞丒儂乕儞偱丄巚偄愗傝杬曻偵悂偒傑偔偭偰偄傞丅傑傞偱旘傃嶶傞娋偑姶偠傜傟傞偐偺傛偆偩丅丂僼儗僨傿偺儚儞丒儂乕儞丒僙僢僔儑儞偼捒偟偄偑丄捒偟偄偺偼側偵傕僼儗僨傿偵尷偭偨偙偲偱偼側偄丅儅僀儖僗偩偭偰儕乕丒儌乕僈儞偩偭偰丄愄偐傜僩儔儞儁僢僞乕偺儗僐乕僨傿儞僌偼暋悢偺儂乕儞傪擖傟偰峴傢傟傞偺偑堦斒揑偩偭偨丅偄偢傟偵偣傛丄曇惉偺戝彫偼僼儗僨傿偺僾儗僀偵塭嬁傪媦傏偟偰偟偰偄側偄丅
丂儔僀償偲偄偆僙僢僥傿儞僌偺偣偄傕偁傞偺偩傠偆偑丄偙偙偱偺斵偺僾儗僀偼峳偭傐偄偟丄柍堄枴側僼儗乕僘偑栚棫偮丅嫮椡側僷儚乕偲擬偄僄儌乕僔儑儞傪偨偨偊側偑傜丄偳傫側偵懍偔偰傕丄偳傫側偵挿偔偰傕丄偮偹偵昳奿偲埨掕姶傪曐偭偰悂偄偰偄偨60擭戙慜敿偺僾儗僀偲偼丄斾傋傞傋偔傕側偄丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄偙傟偼偗偭偟偰堦媺昳偱偼側偄丅偱傕丄90擭戙埲崀偺斵偺怬偺屘忈偵傛傞挏棊傪巚偆偲丄偙偺尦婥偄偭傁偄偺墘憈偵偼偁傞庬偺姶奡傪妎偊傞丅偙傫側偑傓偟傖傜側僾儗僀偑僼儗僨傿偺恎忋偱偁傝丄偦傫側斵傪傏偔偨偪偼垽偟偨偺偩丅
2009.07.30 (栘) 乽栰朷乿偲乽暅廞乿傪僥乕儅偵偟偨2嶜偺杮
栰朷傊偺奒抜/儕僠儍乕僪丒僲乕僗丒僷僞乕僗儞乮PHP尋媶強丄2009擭乯
丂乽嵾偺抜奒乿傗乽僒僀儗儞僩丒僎乕儉乿偱抦傜傟傞儕僠儍乕僪丒僲乕僗丒僷僞乕僗儞偼丄偄傑偄偪偽傫埨怱偟偰撉傔傞儈僗僥儕乕嶌壠偺傂偲傝偩丅偳偺嶌昳傕丄愢摼椡偺偁傞梽傒側偄僗僩乕儕乕揥奐丄偟偭偐傝偟偨恖暔憿宆丄梷惂偝傟偨揑妋側昤幨偱娧偐傟偰偍傝丄偡傋偰悈弨埲忋偺撪梕偵巇忋偑偭偰偄傞丅僷僞乕僗儞偺彫愢偼曎岇巑偑搊応偡傞儕乕僈儖丒儈僗僥儕乕偑懡偄偑丄偙偺怴嶌偼丄偙傟傑偱偲偼僈儔儕偲庯岦傪曄偊偰丄傾儊儕僇戝摑椞慖傪僥乕儅偵偟偨傕偺偵側偭偰偍傝丄尩枾偵偄偊偽儈僗僥儕乕偺斖醗偵偼擖傜側偄偩傠偆丅偩偑柺敀偝偼丄偙傟傑偱摨條丄堦媺昳偩丅
丂庡恖岞偺嫟榓搣忋堾媍堳偼丄怱偵彎傪晧偭偨尦榩娸愴憟偺塸梇偲偄偆愝掕丅嫟榓搣偺戝摑椞岓曗巜柤憟偄偵弌攏偟偨偙偺忋堾媍堳偺巜柤妉摼傊岦偗偰偺愴偄偑昤偐傟傞丅懳棫岓曗偲偺嫊乆幚乆偺嬱偗堷偒傗僉儕僗僩嫵塃攈惃椡偺摦岦偼嫽枴怺偄偟丄憡庤恮塩偺墭偄嶔棯偱庡恖岞偑媷抧偵娮傞側偳丄僾儘僢僩偼婲暁偵晉傫偱偍傝丄堄昞傪撍偔僄儞僨傿儞僌傑偱丄堦婥偵撉傑偣傞丅撉屻姶偼憉傗偐偱丄夵傔偰僷僞乕僗儞偺僗僩乕儕乕僥儕儞僌偺嵥偵姶怱偡傞丅庡恖岞偑楒偵棊偪傞崟恖彈桪傗丄尦摑崌嶲杁杮晹媍挿偱崙柋戝恇傪柋傔偨崟恖惌帯壠側偳丄幚嵼偺恖暔傪儌僨儖偵偟偨偲偍傏偟偒搊応恖暔傕嫽庯傪惙傝忋偘傞丅偙傟偼崱擭偺奀奜僄儞僞僥僀儞儊儞僩彫愢偺儀僗僩3偵擖傞偩傠偆丅
屩傝偲暅廞/僕僃僼儕乕丒傾乕僠儍乕乮怴挭暥屔丄2009擭乯
丂偙偺僕僃僼儕乕丒傾乕僠儍乕偺怴嶌偼丄嬤擭偺掅柪偟偰偄偨斵偺彫愢偺側偐偱偼丄忋摍側晹椶偵擖傞丅柍幚偺嵾偱搳崠偝傟偨抝偺暅廞鏉偩偑丄撉傒巒傔偰娫傕側偔丄偁傟丄偙傟偼傕偟偐偟偰丄偁偺桳柤側屆揟彫愢偑壓晘偒偵側偭偰偄傞偺偱偼丄偲巚偭偰偄傞偲丄埬偺掕丄偦偺偲偍傝偩偭偨丅僗僩乕儕乕僥儕儞僌偺岻偝偼僷僞乕僗儞偲摨條偩偑丄堎側傞偺偼搊応恖暔偺昤偒曽偵怺傒偑側偄偙偲丅傕偲傕偲傾乕僠儍乕偼恖暔憿宆偲偄偆傛傝僾儘僢僩偱撉傑偣傞嶌壠偩偭偨丅弶婜偺乽戝摑椞偵抦傜偣傑偡偐乿傗乽働僀儞偲傾儀儖乿側偳偼丄僉儍儔僋僞乕偺宍惉偲偄偆揰偱偼暔懌傝側偔偰傕丄愗傟枴偺偄偄丄僗儕儖偵晉傫偩僗僩乕儕乕偺棳傟偱敳孮偺儕乕僟價儕僥傿偑偁偭偨丅偩偑偙偺怴嶌偼揥奐偺梊應偑偮偄偰偟傑偆丅偩偐傜丄柺敀偄偙偲偼妋偐偩偑丄彫愢偲偟偰偺僐僋偑側偄偟丄撉屻偺梋塁傕側偄丅孻柋強偺側偐偺昤幨側偳偼丄偝偡偑偵傾乕僠儍乕偺幚懱尡偑惗偐偝傟偰偍傝丄嫽枴怺偔偼偁傞偺偩偑丒丒丒丅傑偁丄傾乕僠儍乕偵30擭慜偲摨偠儗儀儖偺彫愢傪婜懸偡傞偺偑娫堘偄側偺偩傠偆丅
丂栿幰偺塱堜弤巵偼丄傾乕僠儍乕偺傎偲傫偳偺彫愢傪栿偟偰偒偨恖偩偑丄偙偺杮傪庤偑偗偨捈屻偵朣偔側偭偨丅傎偐偵傾乕僒乕丒僿僀儕乕傕偡傋偰塱堜巵偺栿偩偭偨丅帺慠偱妸傜偐側擔杮岅傪憖傞柤栿幰偩偭偨丅傑偨傂偲傝丄愄偐傜撉傫偱偒偨撻愼傒怺偄栿幰偑惱偭偰偟傑偭偨丅
2009.07.24 (嬥) 怉憪堦廏巵偺抯娍檒嵾帠審偲嵟崅嵸偺晄摉敾寛
偙偺帠審丄媦傃偦傟埲慜偺2004擭偵斵偑婲偙偟偨偲偝傟傞僗僇乕僩擿偒尒帠審偵偮偄偰丄傏偔偼摉弶丄怴暦側偳偺婰帠傪塋撣傒偵偟偰偄偨丅扨側傞僥儗價偵弌墘偟偰攧傟偭巕偩偭偨宱嵪妛幰偑婲偙偟偨抯娍帠審偲偄偆偖傜偄偺擣幆偟偐側偐偭偨丅偟偐偟丄偨傑偨傑僱僢僩偱丄偙傟傜偺帠審偼偱偭偪忋偘偱偁傝丄怉憪巵偼檒嵾偩偲偄偆彂偒崬傒偑偨偔偝傫偁傞偙偲傪抦傝丄媈栤傪傕偭偨丅偦偟偰丄帠審偺晄帺慠側偙偲偲憑嵏偺偢偝傫側偙偲丄怉憪巵傪巟墖偡傞慻怐偑偱偒偰偄傞偙偲丄怉憪巵偼丄戝妛偺怑応傗儅僗僐儈偵業弌偡傞婡夛偼幐偭偨傕偺偺丄檒嵾傪偼傜偡偨傔丄惌晎偺宱嵪惌嶔偺旕傪朶偔偨傔丄愊嬌揑偵妶摦偟偰偄傞偙偲丄傏偔偑怣棅偡傞壗恖偐偺僕儍乕僫儕僗僩偑怉憪巵偺柍嵾傪怣偠偰偄傞偙偲側偳偵傛傝丄偙傟偼巇慻傑傟偨帠審偩偭偨偺偩偲妋怣偡傞傛偆偵側偭偨丅
怉憪巵偼抯娍偵傛傞嵾偱2夞戇曔偝傟偰偄傞丅嵟弶偼2004擭4寧丄昳愳墂偺僄僗僇儗乕僞乕偱彈惈偺僗僇乕僩偺側偐傪庤嬀偱擿偒尒偟傛偆偲偟偨帠審偩丅乽擿偒尒偟偨乿偱偼側偔丄乽擿偒尒偟傛偆偲偟偨乿偲偄偆偺偑堄枴晄柧偩丅戇曔偟偨寈姱偼怉憪巵傪旜峴偟偰偄偨傛偆偩偑丄壗偺偨傔偵旜峴偟偰偄偨偺偐丅擿偒尒偺徹嫆偼丄戇曔偟偨寈姱偺徹尵偩偗偱丄傎偐偵偼壗傕側偄丅旐奞幰偲偝傟傞彈惈偼崘慽傕偟偰偄側偄丅怉憪巵偼戇曔屻偡偖偵杊斊僇儊儔偺塮憸傪尒偰偔傟偲庡挘偟偨偑丄偦偺塮憸偼側偤偐徚嫀偝傟偰偄偨丅抧嵸偺壓偟偨敾寛偼敱嬥50枩墌丄庤嬀1枃杤廂丅怉憪巵偼檒嵾傪庡挘偟偨偑丄偙偺偲偒偼峊慽傪抐擮偟偨丅
2夞栚偼慜夞偺帠審偺敾寛偑壓傝偰偐傜1擭敿屻偺2006擭9寧丄嫗媫慄偺幵撪偱彈惈偺怟偵怗偭偨偲偟偰戇曔偝傟偨丅偙偺偲偒傕寛掕揑側徹嫆偼側偐偭偨丅旐奞幰偺彈惈偺徹尵偼偁偄傑偄偩偟丄幵撪偱怉憪巵傪庢傝墴偝偊偨乬孅嫮側乭抝惈2柤偼丄廔巒柍尵偺傑傑丄墂堳偵斵傪堷偒搉偟偨偁偲偳偙偐偵偄側偔側傝丄峴曽晄柧偺傑傑丄岞敾偵傕巔傪尒偣側偐偭偨丅幵撪偵偄偨暿偺忔媞偑丄怉憪巵偼壗傕偟偰偄側偐偭偨偲徹尵偟偨偑丄擣傔傜傟偢丄偗偭偒傚偔抧嵸偱偼挦栶4偐寧偺幚孻偑尵偄搉偝傟偨丅怉憪巵偼忋崘偟丄嵟崅嵸傑偱憟偭偨偑丄嵟崅嵸偺忋崘婞媝偱嵾偑妋掕偟偨丅
椉曽偺帠審偲傕丄挷傋傟偽挷傋傞傎偳丄層嶶廘偝偑嫮偔側傞丅嵟弶偺帠審偼丄旜峴偟偰偄偨寈姱偑僞僀儈儞僌傪偹傜偭偰曔傑偊偨偲偟偐巚偊側偄偟丄2夞栚偺帠審傕丄怉憪巵傪庢傝墴偝偊偰徚偊偨2恖偼丄傗偼傝岞埨側偳寈嶡娭學幰偩偭偨壜擻惈偑崅偄丅徹嫆傜偟偄徹嫆偑側偔丄乬崌棟揑側媈偄乭偑擹岤側偺偵丄側偤嵸敾姱偨偪偼桳嵾偺敾寛傪壓偟偨偺偐丄偲偄偆媈栤傕晜偐傫偱偔傞丅
傕偟偙傟偑檒嵾偩偭偨偲偟偨傜丄扤偑丄壗屘丄怉憪巵偵嵾傪拝偣傛偆偲偟偨偺偩傠偆偐丅怉憪巵偼僥儗價傗嶨帍偱丄偟偽偟偽彫愹惌尃偺宱嵪惌嶔傪斸敾偟丄彫愹丒抾拞偺峔憿夵妚楬慄偺岆傝傪巜揈偟丄斵傜偑塀偟偨偑偭偰偄傞偙偲傪徻嵶側暘愅偺傕偲偵朶偄偰偄偨丅偦偺岥晻偠偺偨傔偵尃椡懁偑巇慻傫偩崙嶔憑嵏偩偭偨丄偲偄偆偺偑丄偄偪偽傫擺摼偱偒傞愢柧偩丅偲傝傢偗斵傜偑婋湝偟偨偺偼丄怉憪巵偑捛媦偟偰偄偨乬傝偦側僀儞僒僀僟乕媈榝乭偩偭偲偲偄偆丅怉憪巵偼彫愹丒抾拞偺偄偪偽傫怗傟傜傟偨偔側偄晹暘偵摜傒崬傫偩偺偩丅専嶡丒寈嶡偑崙嶔憑嵏傪傗傜側偄偲巚偭偨傜戝娫堘偄偩丅嵟嬤偺惣徏寶愝堘朄專嬥帠審偺傛偆偵丄偙傟傑偱偄偔偮傕幚椺偑偁傞丅
傏偔偼嵟嬤傑偱丄偙偺乽傝偦側嬧峴乿張棟偵傑偮傢傞僀儞僒僀僟乕庢堷媈榝偵偮偄偰偼丄傑偭偨偔抦傜側偐偭偨丅亀彫愹惌尃偺岆偭偨宱嵪惌嶔偵傛偭偰擔杮偼晄嫷偵娮偭偨丅惌晎偼嬧峴偑攋抅偟偰傕媬嵪偟側偄偲尵柧偟偨丅偦偟偰婋婡揑忬嫷偵偼帄偭偰偄側偐偭偨乽傝偦側嬧峴乿偑攋抅偡傞偲偄偆晽愢傪堄恾揑偵棳偟丄慜尵傪傂傞偑偊偟偰撍慠崙桳壔偟偨丅偙傟傪墘弌偟偨偺偑嬥梈丒宱嵪嵿惌扴摉戝恇偺抾拞暯憼偩偭偨丅偦傟偵傛偭偰奜帒宯僼傽儞僪丄崙夛媍堳丄惌晎娭學幰偑僀儞僒僀僟乕庢堷傪偟偰戝栕偗偟偨亁乗乗偙傟偑乬傝偦側僀儞僒僀僟乕媈榝乭偩丅偙傟偵偮偄偰偼怉憪巵偺丄柧夣丒惛鉱側儗億乕僩偑僱僢僩偵嵹偭偰偄傞乮UEKUSA儗億乕僩Plus乯丅晄壜夝側偙偲偵丄乽傝偦側嬧峴乿崙桳壔偺夁掱偱丄偙偺嬧峴偺夛寁娔嵏偺愑擟幰偩偭偨夛寁巑偑曄巰偟偰偄傞乮帺嶦偲偟偰張棟偝傟偨偑堚彂偼側偄乯丅
嵸敾強偺梊抐傗曃尒偵傛傞岆怰丄堄恾揑偵側偝傟傞専嶡偵桳棙側敾寛偼偄偔偮傕偁傞丅巌朄偼偗偭偟偰峴惌偐傜撈棫偟偰偄側偄丅偙傫側昻庛側徹嫆偱傛偔桳嵾偵偡傞側偲巚偆敾寛傕偁傞偟丄崅抦偺僗僋乕儖僶僗偲敀僶僀偺徴撍帠審偺傛偆偵丄寈嶡偺偱偭偪忋偘偺媈偄偑擹岤側偺偵丄偦傟傪柍帇偟偰僶僗偺塣揮庤傪桳嵾偵偡傞丄偲傫偱傕側偄嵸敾姱傕偄傞丅嵸敾姱偲専嶡偑僌儖偵側偭偰偄傞偲偟偐巚偊側偄丅怉憪巵偺働乕僗傕偦傟偵偁偰偼傑傞丅6寧偵忋崘婞媝偺寛掕傪壓偟偨嵟崅嵸偺嵸敾挿偼嬤摗悞惏偲偄偆恖暔偩丅偙偺嵸敾姱偼丄偙傟傑偱偺棃楌傪尒傞偲丄怉憪巵偺帠審偵尷傜偢丄尃椡懁偺堄偵傋偭偨傝揧偭偨敾寛傪弌偟懕偗偰偄傞丅偙傫側嵸敾姱偼丄傕偆偡偖廜堾慖偲摨帪偵峴傢傟傞嵟崅嵸敾帠偺崙柉怰嵏偱丄偤偭偨偄偵亊傪偮偗側偔偰偼側傜側偄丅
偦傟偵偟偰傕嵟埆側偺偼儅僗丒儊僨傿傾偩丅偲偔偵怴暦偺嵾偼戝偒偄丅傑傞偱偁傝傆傟偨抯娍帠審偦偺傑傑偵丄寈嶡偺敪昞傪傑傞偛偲婰帠偵偟偰丄怉憪巵傪偝傜偟幰偵偟偨丅婰幰偨偪偼偲偆偤傫丄庢嵽傪捠偠偰丄偙偺帠審偺層嶶廘偝丄偍偐偟偝傪暘偐偭偰偄偨偼偢偩丅偩偑斵傜偼巻柺偱偦傟偵怗傟傛偆偲偟側偄偟丄偦傟傪偄偭偝偄捛媮偟傛偆偲偟側偄丅擔杮梄惌偺偐傫傐偺廻媈榝偺偲偒傕偦偆偩偭偨偟丄惣徏寶愝帠審偺偲偒傕偦偆偩偭偨丅尃椡娔帇偺偨傔偺儅僗僐儈偑丄尃椡偵偡傝婑傝丄偦偺憱嬬偵側傝壥偰偰偄傞丅
抯娍偼婲慽偝傟偨偩偗偱丄杮恖偼幮夛揑偵枙嶦偝傟傞偟丄壠懓傕戝偒側嬯擸傪枴傢偆丅抯娍偺偱偭偪忋偘偼丄嫋偟偑偨偄斱楎側峴堊偩丅怉憪巵偼1夞栚偺戇曔偺偁偲丄僥儗價斣慻傪偡傋偰崀斅丄憗堫揷戝妛偐傜嫵庼偺怑傪夝偐傟偨丅儅僗僐儈偵偼搊応偟側偔側偭偨傕偺偺丄僱僢僩傗嶨帍側偳偱偼丄埲慜傛傝塻偔尃椡斸敾傪揥奐偟偰偄偨丅偦偺傂偲偮偑愭偺乬傝偦側僀儞僒僀僟乕媈榝乭偩偭偨丅偦偺偨傔斵傜偼怉憪巵偺僕儍乕僫儕僗僩偲偟偰偺懅偺崻傪巭傔傛偆偲2夞栚偺帠審傪巇慻傫偩丅晄摉側嵟廔敾寛偑壓傝偰偟傑偭偨偑丄怉憪巵偼偄傑傕僽儘僌傗島墘傗挊彂傪捠偠偰恀幚傪柧傜偐偵偟傛偆偲偟偰偄傞丅偤傂嫄埆偵孅偡傞偙偲側偔丄彫愹丒抾拞偺峴偭偨晄惓傪朶偒丄柤梍傪夞暅偟偰傕傜偄偨偄丅
2009.07.16 (栘) 廥偝傪偝傜偗弌偡枛楬偺帺柉搣
帺柉搣偑嵟屻偺埆偁偑偒傪偟偰偄傞丅傕偼傗枛婜揑忬嫷傪捠傝墇偟偰丄抐枛杺偺廥偝傪偝傜偗弌偟偰偄傞丅偙傟偑帺柉搣偺枛楬偩丅愴屻60擭懕偄偨帺柉搣惌尃偑曵夡偡傞偲偒偼丄偙傫側偵傕柍巆側巔傪偝傜偡傕偺側偺偩傠偆偐丅
屆夑慖嫇懳嶔埾堳挿偺帿擟偵偼偁偒傟傞偽偐傝偩丅偙傟偐傜慖嫇傪愴偍偆偲偄偆偲偒偵丄偦偺愑擟幰偑帿傔傞偺偩偑傜丄榖偵側傜側偄丅揋慜摝朣偲尵傢傟偰傕偟傚偆偑側偄丅搒媍慖嶴攕偺愑擟傪偲傞偲偄偆偺偼岥幚偱偁傝丄廜堾慖偱晧偗傞偺偼妋掕揑偩偐傜丄偦偺愑擟傪摝傟傛偆偲偄偆嵃抇側偺偼尒偊尒偊偩丅
偙偙傑偱偔傟偽丄偡傫側傝杻惗庱憡偵夝嶶偝偣傞偟偐側偄偺偵丄彫愹偺巕暘偺拞愳傗晲晹偲偄偭偨師偺慖嫇偱摉慖偑婋傇傑傟偦偆側媍堳偨偪偑丄杻惗傪戅恮偝偣傛偆偲夋嶔偟偰偄傞丅偙偺婜偵媦傫偱丄庱憡傪扤偵偟傛偆偲丄傎偲傫偳偦偺岠壥偼婜懸偱偒側偄丅傓偟傠儅僀僫僗岠壥偩丅傑偨崙柉偺怣擟傪摼偢偵庱憡偑戙傢偭偨偲偄偆偙偲偱丄崙柉偼傑偡傑偡偦偭傐傪岦偔偩傠偆丅偦傫側偙偲傕暘偐傜側偄傎偳丄斵傜偺摢偼楎壔偟偰偄傞偺偩丅
慍揧岤楯憡傪庱憡偵偲偄偆惡偑偁傞傛偆偩丅慍揧偼恖婥偑偁傞傜偟偄偑丄傎傫偲偆偵偦偆側偺偐丅傎偐偵枺椡偺偁傞恖嵽偑偄側偄偐傜丄憡懳揑偵斵偑栚棫偮偩偗偵偡偓側偄偲偄偆偺偑幚懺偩傠偆丅懠偺儃儞僋儔媍堳偨偪傛傝偼傑偟偩偑丄斵偼擭嬥栤戣偱擇枃愩傪巊偭偨偟丄張棟偺晄庤嵺偑栚棫偭偨偟丄愑擟偺捛媮傕濨枂側傑傑偩丅偩偄偄偪丄偲偒偍傝尒偣傞彫尗偟偘側僯儎僯儎徫偄偑旲偵偮偔丅
杮棃偺搣偺儅僯僼僃僗僩偲偼暿偺儅僯僼僃僗僩傪嶌傠偆偲偟偰偄傞堦攈傕偁傞傛偆偩丅傂偲偮偺搣偵偄偔偮傕儅僯僼僃僗僩偑偁傞偙偲偺堎忢偝偵丄斵傜偼婥偑偮偐側偄偺偩傠偆偐丅偙偙傑偱柍拋彉忬懺偵側偭偰偟傑偭偨傜丄憤慖嫇偱攕戅偟偨偁偲丄帺柉搣偼暘楐偡傞壜擻惈偑崅偄丅
傕偼傗師偺廜堾慖偱柉庡搣偑彑偮偙偲偼妋幚偩丅偁偲偼偳傟偩偗昜傪怢偽偡偐偑徟揰偵側傞丅婥偵側傞偺偼丄媍惾偑憹偊夁偓偰丄師尦偺掅偄岓曗幰傑偱摉慖偟偰偟傑偆偙偲偩丅慜偺梄惌柉塩壔慖嫇偱丄柍擻側帺柉搣岓曗偑偨偔偝傫摉慖偟偰偟傑偭偨偑丄偁傟偲摨偠傛偆偵側傞嫲傟偑偁傞丅偄傑偺柉庡搣偐傜偟偰桳擻側媍堳偽偐傝偠傖側偄丅側偐偵偼墶曱偺傛偆偵掅楎側攜傕偄傞丅偦偆偄偆楢拞偑憹偊傟偽丄搣偲偟偰偺僟儊乕僕偵側傝偐偹側偄丅
柉庡搣偑傎傫偲偆偵崙柉偵懳偟偰奐偐傟偨惌帯傪幚尰偱偒傞偺偐丅晄埨側嵽椏偼偨偔偝傫偁傞丅傕偟偐偟偨傜丄椡晄懌丄寢懇椡晄懌偑業掓偡傞偐傕偟傟側偄丅棟憐傪捛偄媮傔傞偁傑傝丄尰幚偺栤戣偵懳張偟偒傟偢丄嵙愜偡傞偐傕偟傟側偄丅婜懸偑戝偒偄偩偗偵丄偡偖偵夵妚偺岠壥偑昞傟側偄偲丄斀敪偑婲偒傞偐傕偟傟側偄丅偦傟偱傕丄彮側偔偲傕帺柉搣傛傝傑偟側偙偲偼妋偐偩丅偙偙偼柉庡搣偵擔杮偺惌帯傪擟偣偰傒偨偄丅
2009.07.09 (栘) 僕僃僼傽乕僜儞丒儃僩儖傪傔偖傞撲偲憶摦
僕僃僼傽乕僜儞丒儃僩儖傪帩偪崬傫偩偺偼儘乕僨儞僗僩僢僋偲偄偆僪僀僣偺儚僀儞丒僐儗僋僞乕偩偭偨偑丄斵偼僷儕偺屆偄揁戭偺抧壓幒偱尒偮偐偭偨偲偄偆偙偲埲奜丄儃僩儖敪尒偺宱堒偵偮偄偰偼徻嵶傪岅傜側偐偭偨丅僋儕僗僥傿乕僘偺儚僀儞扴摉幰傕偦偺懠偺崅柤側儚僀儞娪掕壠偨偪傕丄摉弶偼傒側杮暔偲怣偠偰偄偨丅偲偙傠偑丄僔儍僩乕丒僨傿働儉傗僔儍僩乕丒儅儖僑乕丄儉乕僩儞側偳丄僕僃僼傽乕僜儞偑帩偭偰偄偨偲徧偡傞18悽婭嶻偺戞1媺儚僀儞傪儘乕僨儞僗僩僢僋偑師乆偵僆乕僋僔儑儞偵弌昳偡傞偵媦傫偱丄杮暔偐偳偆偐偵娭偡傞媈榝偺惡偑忋偑傝巒傔偨丅
儚僀儞偼恀婁偺敾掕偑擄偟偄丅儔儀儖傗崗報偼婾憿偟傛偆偲巚偊偽愱栧壠偱傕尒暘偗偑偮偐側偄傎偳惛岻偵嶌傟傞偟丄偦傕偦傕杮暔偺儚僀儞偺嬻儃僩儖傪偲偭偰偍偒丄偦傟偵揔摉側儚僀儞傪擖傟傟偽丄尒偨栚偵偼傑偭偨偔暘偐傜側偄丅儚僀儞傪奐偗偰堸傫偱傒偰丄偪傚偭偲枴偑偍偐偟偄偲巚偭偰傕丄18悽婭偺屆偄儚僀儞偑偳傫側枴偐傪抦傞恖偼傎偲傫偳偄側偄偟丄堸傫偩偙偲偺偁傞恖偱傕丅曐懚曽朄傗曐懚娐嫬偺堘偄偱枴偼曄壔偡傞偐傜丄彮偟曄偩偲巚偭偰傕丄愨懳偵堘偆偲偼尵偄愗傟側偄丅偝傜偵儚僀儞嬈奅傗惢憿尦偼僗僉儍儞僟儖偵側傞偺傪寵偑傝丄媈榝偑偁偭偰傕帺暘偨偪偺晄棙塿偵側傜側偄偐偓傝丄偦偭偲偟偰偍偙偆偲偡傞丅偦偺偨傔偙偺儘乕僨儞僗僩僢僋偑帩偪崬傓屆庰儚僀儞偵娭偡傞媈榝偼丄傑偲傕側捛媦傗専徹偑側偝傟偢20擭嬤偔偑夁偓偨丅
偦偺屻丄2000擭戙偵擖偭偰丄僕僃僼傽乕僜儞丒儃僩儖傪峸擖偟偨愇桘娭楢婇嬈偺僆乕僫乕丄價儖丒僐乕僋偑偦偺恀婁傪妋偐傔傞偙偲傪寛堄偟丄巹嵿傪搳偠偰挷嵏僠乕儉傪嶌傝丄揙掙揑側媶柧偵忔傝弌偟偨丅斵傜偼偝傑偞傑側挷嵏傗暘愅傪偟偨寢壥丄婾暔偲抐掕偟丄2006擭偵傾儊儕僇楢朄嵸敾強偵儘乕僨儞僗僩僢僋傪乽婾憿儚僀儞斕攧乿偺棟桼偱採慽偟偨丅偦偺嵸敾偼傑偩寛拝偑偮偄偰偄側偄丅
偙偺杮偼柺敀偄丅價儖丒僐乕僋偑慻怐偟偨挷嵏僠乕儉偼丄尦楢朄嵸敾強敾帠丄尦FBI憑嵏姱丄尦僀僊儕僗忣曬晹堳丄暔棟妛幰側偳偐傜側傞戝偑偐傝側傕偺偱丄斵傜偑僕僃僼傽乕僜儞婰擮娰偵曐懚偝傟偰偄傞儚僀儞峸擖棜楌傗椞廂彂傪挷傋偨傝丄嵟怴偺壢妛媄弍傪巊偭偰擭戙應掕偟偨傝丄儃僩儖偺僈儔僗傗崗報傪暘愅偟偨傝丄儘乕僨儞僗僩僢僋偺恎尦傪挷嵏偟偨傝偡傞偔偩傝偼丄儈僗僥儕乕彫愢傕婄晧偗偺僗儕儖偵偁傆傟偰偄傞丅擔杮偱傕桳柤側儘僶乕僩丒僷乕僇乕傗儗僫乕僞丒僒僩僋儕僼偲偄偭偨儚僀儞丒僕儍乕僫儕僗僩傕搊応偡傞偟丄儚僀儞嬈奅偵傑偮傢傞偝傑偞傑側棤榖傗僆乕僋僔儑儞夛幮僋儕僗僥傿乕僘偲偦偺儔僀僶儖偱偁傞僒僓價乕僘偺妋幏傕岅傜傟傞丅
偩偑丄偟傚偣傫偼1杮偑壗10枩墌丄壗100枩墌傕偡傞挻僾儗儈傾儉丒儚僀儞偲丄偦傟偵傓傜偑傞堦晹偺嬥帩摿尃奒媺偺悽奅偺榖偩丅偦偙偵偼帺枬偲僗僲價僘儉偑廩枮偟偰偄傞丅摉帪丄儚僀儞傪垽岲偡傞忋棳幮夛偱偼丄偙偺傛偆側償傿儞僥乕僕丒儚僀儞偺悅捈帋堸夛傗悈暯帋堸夛偑傂傫傁傫偵奐偐傟偰偄偨丅僕僃僼傽乕僜儞丒儃僩儖傪偼偠傔偲偡傞婾憿儚僀儞偺墶峴偼偙偺傛偆側晽挭敳偒偵偼峫偊傜傟側偄丅撉傒廔偭偨偁偲偵側傫偲側偔嫊偟偝傪姶偠傞丅偙傟傪撉傒側偑傜丄悢擭慜偵擔杮偱偁偭偨媽愇婍帪戙偺堚暔偺漵憿僗僉儍儞僟儖傪巚偄弌偟偨丅師乆偵廳梫側愇婍傪敪孈偟偰僑僢僪僴儞僪偲尵傢傟偨傾儅僠儏傾峫屆妛尋媶壠偑丄偠偮偼偦傟傜偺堚暔傪漵憿偟偰偄偨偄偆帠審偩丅傂偲傝偺恖娫偑偦傫側偵婱廳側堚暔傪偄偔偮傕敪孈偡傞側傫偰丄偳偙偐偍偐偟偄偲巚偆偺偑晛捠偩偑丄嬈奅偱偼傒傫側偑偦傟傪杮暔偲怣偠偰偄偨偲偄偆偐傜徫偭偰偟傑偆丅偍慹枛偝偲堎忢偝偲偄偆揰偱丄偳偙偐帡偰偄傞丅
儚僀儞嬈奅偼堎忢側悽奅偩丅儘僶乕僩丒僷乕僇乕偑乽偙傟偼嬤棃偵側偄惁偄儚僀儞偩乿偲寖徿偟偨傜丄偦傟傑偱柍柤偩偭偨僔儍僩乕偺儚僀儞偺抣抜偑10攞偵挼偹忋偑傞丅偙偺悽奅偱偼丄偢偄傇傫慜偐傜柫忴償傿儞僥乕僕丒儚僀儞偑婾憿偝傟偰偒偨傜偟偄丅戝偑偐傝側儚僀儞婾憿僌儖乕僾偑揈敪偝傟偨偙偲傕偁傞丅偄傑悽奅拞偵弌夞偭偰偄傞儔僼傿僢僩丄儔僩僁乕儖丄儅儖僑乕丄儁僩儕儏僗丄DRC側偳偺悢検偼丄偦傟傜偺儚僀儞偺擭娫惗嶻検傪偼傞偐偵挻偊傞偲尵傢傟偰偄傞丅偮傑傝婾憿昳偑偐側傝娷傑傟偰偄傞偙偲偵側傞丅偍偦傜偔擔杮偵傕彮側偐傜偢偦偺庤偺婾憿儚僀儞偑擖偭偰偒偰偄傞偩傠偆丅戝嬥傪暐偭偰偦傟傪堸傒丄乽偝偡偑偵枴偑堘偆乿偲墄偵峴偭偰偄傞傾儂僂偑偄傞傢偗偩丅偄傗丄傏偔偺偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅埲慜偼偦傫側儚僀儞傪堸傫偩偙偲傕偁傝傑偟偨偑丄偄傑偼懖嬈偟傑偟偨丅扥擮偵扵偣偽1杮1000乣1500墌偱枮懌偡傋偒旤枴偟偄儚僀儞偑偨偔偝傫偁傞偺偱丄偦傟偱廩暘偱偡丅
2009.07.02 (栘) 懞忋弔庽偵偮偄偰巚偆偙偲
丂丂傕偼傗媽暦偵懏偡傞偑丄懞忋弔庽偼崱擭2寧丄僀僗儔僄儖偵晪偒丄僄儖僒儗儉徿傪庴徿偟偨丅僷儗僗僠僫恖傪梷埑偟丄媠嶦偡傞僀僗儔僄儖偲偄偆崙偑庼偗傞徿傪懞忋偑庴偗偨偙偲偵偮偄偰偺惀旕偼丄偄傑偼栤傢側偄丅僲乕儀儖徿偑梸偟偄偐傜丄偦偺偨傔偺僷僗億乕僩偲尵傢傟傞僄儖僒儗儉徿傪栣偭偨偺偩偲偄偆愢偑偁傞偑丄偦偺恀婾傕偄傑偼栤傢側偄丅傏偔偑栤戣偵偟偨偄偺偼丄斵偑庼徿幃偱偟傖傋偭偨僗儁乕僠偩丅抦傜傟傞傛偆偵懞忋偼丄寴偔崅偄暻偲夡傟傗偡偄棏偲偄偆椺傪堷偒崌偄偵弌偟偰丄偳傫側偵暻偑惓偟偔棏偑娫堘偭偰偄偰傕丄帺暘偼棏偺懁偵棫偮丄偲尵偭偨丅偙傟偼僀僗儔僄儖偺朶嫇傪旕擄偟偨丄桬婥偁傞戝抇側敪尵偩偲偟偰丄偍偍傓偹昡壙偑崅偄傛偆偩偑丄傏偔偵尵傢偣傟偽偳偆偟傛偆傕側偔婾慞揑側廘偄傪姶偠傞丅傎傫偲偆偵庛幰偺懁偵棫偭偰嫮幰傪旕擄偡傞偺側傜丄側偤偦傫側偁偄傑偄側埫歡傪巊傢偢偵丄摪乆偲巚偭偰偄傞偙偲傪庡挘偟側偄偺偐丅偦偙偵偼丄暥妛幰偱偁傞偙偲傪弢偵偲傝丄暥妛揑側斾歡偵傛偭偰堄枴傪傏偐偟丄僀僗儔僄儖偺怱忣傪媡側偱偟側偄傛偆偵偟偨偄偲偄偆攝椂偑尒偊傞丅偦偆傗偭偰柶嵾晞傪摼傛偆偲偡傞斱嫰側怱崻傪姶偠傞丅
丂丂偦傕偦傕僀僗儔僄儖偺朶嫇偵斀懳側偺側傜丄庴徿傪嫅斲偟丄偦偺棟桼傪愢柧偡傟偽偄偄偩偗偩丅扨弮側榖偩丅偟偐偟斵偼丄傒傫側偑弌傞側偲尵偆偐傜弌惾偟偨偺偩偲偄偆丅偦傟偼偦傟偱偄偄偲巚偆偟丄棟夝偱偒傞丅偦傟偱傕丄斵偑尵偆傛偆偵丄尵偄偨偄偙偲傪尵偆偨傔偵庼徿幃偵弌偰偒偨偺偩偭偨傜丄傕偭偰傑傢偭偨濨枂側尵偄曽偱偼側偔丄摪乆偲巚偭偰偄傞偙偲傪柧妋偵丄暘偐傝傗偡偔偟傖傋傞傋偒側偺偩丅偦傟偑暥妛幰偲偟偰偺椙怱偩丅2001擭丄僄儖僒儗儉徿傪庴徿偟偨斸昡壠僗乕僓儞丒僜儞僞僌偼丄儐僟儎恖偱偁傝側偑傜丄庴徿幃偱僀僗儔僄儖偺僷儗僗僠僫恖傊偺敆奞傗孯帠揑怤棯傪旕擄偟丄孯帠峴摦偺掆巭偲帺帯嬫偐傜偺揚戅傪媮傔偨丅偙傟偙偦恀偺桬婥偁傞敪尵偩丅暥妛丒寍弍偲偄偊偳傕惌帯偲柍墢偱偼偁傝偊側偄丅偄傑偺悽偺拞丄暥妛幰偼丄偳傫側偵惌帯傗幮夛偐傜挻慠偲偟傛偆偲偟偰傕丄偦傟傜偐傜摝傟傞偙偲偼偱偒側偄丅懞忋偺庴徿僗僺乕僠偵偼丄偄偔傜棏偺懁偵棫偮偲尵偭偰傕丄偦偺晄柧椖側斾歡揑昞尰偺側偐偵丄偳偙偐晹奜幰揑丄朤娤幰揑側峫偊曽偑尒偊塀傟偟偰偄傞傛偆偵姶偠傜傟偰側傜側偄丅
2009.02.18 (悈) 屲椫彽抳丄抸抧堏揮偲偄偆愇尨偺嬸嫇偵搟儕偺惡傪
丂丂僆儕儞僺僢僋彽抳偵偐偐傞旓梡偼丄彽抳妶摦旓150壄墌丄巤愝惍旛旓2400壄墌丄戝夛塣塩旓3100壄墌偩偲偄偆丅偙偺偆偪巤愝惍旛旓偼敿妟傪崙旓偱晧扴偡傞丅傑偨戝夛塣塩旓偼崙偑嵚柋曐徹傪偡傞丅偮傑傝丄搒偺惻嬥偩偗偱偼側偔丄崙偺惻嬥傑偱巊傢傟傞偺偩丅偍偦傜偔忋婰偺嬥妟偼幚嵺偵偼傕偭偲朿傟忋偑傞偩傠偆丅愇尨偼3挍墌偺宱嵪岠壥偁傞偲尵偆偑丄搒偺堄岦偵増偭偰嶼弌偝傟偨旣懥偺悢帤偱偁傝丄傑偭偨偔偺婘忋偺嬻榑偩丅偙傟偑搒偺嵿惌傪埑敆偟丄嫵堢丄堛椕丄暉巸偲偄偭偨廧柉偺惗妶偵捈寢偡傞梊嶼偺嶍尭偵偮側偑傞偺偼娫堘偄側偄丅
丂丂愇尨偺帺屓枮懌偲丄棙尃傪摼傛偆偲偟偰廃曈偵孮偑傞僴僀僄僫偳傕偺偨傔偵丄側偤偦傫側柍懯尛偄傪偟側偗傟偽側傜側偄偺偐丅嫄妟偺嬥傪偮偓崬傫偱僆儕儞僺僢僋傪奐嵜偟偰傕堄枴偼側偄丅幮夛僀儞僼儔偺惍旛偲偄偆揰偱偼僆儕儞僺僢僋偺岠壥偼偨偟偐偵偁傞偩傠偆丅偩偑偄傑偺搶嫗偵幮夛帒杮偺惍旛偼昁梫側偄丅僆儕儞僺僢僋傪奐嵜偟偨搒巗偺懡偔偼丄偦偺屻丄嵿惌埆壔偵嬯偟傫偱偄傞偲暦偔丅崙柉偺斀墳傕惲傔偰偄傞丅悽榑挷嵏偵傛傞巟帩棪偼59僷乕僙儞僩偱偁傝丄偙傟偼岓曗偺4搒巗偺偆偪嵟壓埵偩丅傾儞働乕僩偺幙栤偺巇曽偵傛偭偰偼丄傕偭偲壓偑傞偩傠偆丅
丂丂抸抧巗応偺堏揮寁夋傕柍拑嬯拑側榖偩丅撆傑傒傟偺朙廎偵側偤巗応傪堏揮偟側偗傟偽偄偗側偄偺偐丅傒傫側偑斀懳偟偰偄傞偺偵丄愇尨偼偙傟傕嫮堷偵寁夋傪恑傔傛偆偲偟偰偄傞丅堏揮偺棟桼偼巤愝偑榁媭壔偟偨偐傜偩偲偄偆偑丄偦傟側傜寶偰懼偊偨傝愝旛傪嶞怴偟偨傝偡傟偽偄偄偩偗偺榖偩丅桼弿偁傞抸抧巗応偑側偔側傞偺偼扤傕朷傫偱偄側偄丅抸抧偺愓抧傪偳偆偡傞偺偐傕寛傑偭偰偄側偄丅摉弶偼搶嫗僆儕儞僺僢僋偺儊僨傿傾僙儞僞乕偩偐慖庤懞偩偐偵偟傛偆偲偄偆峔憐偑偁偭偨偑丄偦偺榖偼徚偊偨傜偟偄丅壗偐棙尃偵棈傓榖偑偁傞偲偐傫偖傜傟偰傕偟傚偆偑側偄丅
丂丂愇尨偼擭傪偲偭偰傑偡傑偡婃柪偵側傝丄尃椡梸偑墵惙偵側偭偰偒偨丅壠偵堷偭崬傫偱嶰暥彫愢偱傕彂偄偰偄傟偽偄偄偺偵丄崙惌偱嫃応強偑側偔側傝丄搒惌傪巹暔壔偟偰尃椡梸傪枮偨偦偆偲偟偰偄傞丅尃椡巙岦偺嫮偄恖娫偼壈昦偩偟斱嫰偩丅幐攕偟偰傕愑擟傪庢傜偢丄恀偭愭偵摝偘傞丅斵偼壗傪偡傞偵傕嬉戲嶰枂偩偟丄廧柉偵岦偗傞壏偐偄栚慄側偳奆柍偱丄偄偮傕埿挘傝嶶傜偟丄庛幰傪曁帇偡傞丅偙傫側昳偺側偄攋楑抪側抝傪丄搒柉偼偄偮傑偱偺偝偽傜偣偰偍偔偺偐丅
丂丂帺暘偑惂嶌偵実傢傝丄媟杮傕彂偄偨2007擭偺懯嶌塮夋乽壌偼孨偺偨傔偵偙偦巰偵偵偄偔乿傪丄僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪偺乽棸墿搰偐傜偺庤巻乿傛傝偢偭偲偄偄偲帺夋帺巀偡傞愇尨偺姶妎偼丄偳偙偐堎忢側傕偺傪姶偠傞丅側偵偟傠斵偼搶嫗偵僇僕僲傪嶌傠偆偲杮婥偱峫偊丄偦傟傪婬桳憇戝側傾僀僨傾偩偲巚偄崬傫偱偄傞傫偩偑傜丄搙偟擄偄僶僇偝壛尭偩丅側傫偱傕巚偄偮偒偱偙偲傪恑傔丄偦偟偰幐攕偡傞丅怴嬧峴搶嫗偑偦偺偄偄椺偩丅偩偑偗偭偟偰愑擟傪庢傠偆偲偟側偄丅
丂丂偲偙偙傑偱彂偄偰偒偰丄怴嬧峴搶嫗偑丄媽宱塩恮偺2柤偵懳偟偰懝奞攨彏傪惪媮偡傞慽徸傪婲偙偡偲偄偆僯儏乕僗偑擖偭偰偒偨丅惪媮妟偼100壄墌偩偲偄偆丅偦傫側嬥傪偙偺2恖偑暐偊傞傢偗偑側偄丅偡傋偰偺愑擟傪媽宱塩恮偵揮壟偟傛偆偲偄偆愇尨偺暊偑尒偊尒偊偩丅愇尨偑廃埻偺斀懳傪墴偟愗偭偰嫮堷偵愝棫偟偨偺偑怴嬧峴搶嫗偩丅偦偟偰斵偼柍棟側宱塩曽恓傪偙偺嬧峴偵墴偟晅偗偨丅偳偆峫偊偰傕堦斣偺愑擟偼愇尨偲搶嫗搒偵偁傞丅偙偺懝奞攨彏惪媮慽徸偼丄帺暘偨偪偺愑擟摝傟偺偨傔丄柶嵾晞傪摼傞偨傔偺傕偺偲偟偐峫偊傜傟側偄丅
丂丂搒柉偼傕偭偲惡傪戝偵偟偰丄愇尨偵懳偟偰僲乕偺嫨傃惡傪偁偘偰傕傜偄偨偄偲愗偵朷傓丅
2009.02.16 (寧) 彫愹敪尵傪夁戝曬摴偡傞儅僗僐儈偺峳攑偲懧棊
丂丂彫愹尦庱憡偑丄斵偵偡偑傞偙偲偱偟偐惗偒巆傟側偄栘偭抂媍堳偨偪偲偺夛崌偱敪尵偟偨杻惗庱憡斸敾偺尵梩偑丄楢擔偺傛偆偵怴暦傗僥儗價偱庢傝忋偘傜傟偰偄傞丅堷戅傪昞柧偟偰偄傞彫愹偑壗傪尵偍偆偲丄偦傫側偵戝偒偔曬摴偡傞傛偆側僱僞偱偼側偄丅傎偐偵崙柉偵抦傜偣傞傋偒僯儏乕僗丄捛媦偡傋偒僥乕儅偼偨偔偝傫偁傞丅偲偙傠偑丄彫愹偑杻惗傪斸敾偟偨偲偨傫丄儅僗僐儈偼偦傟傪柺敀偑偭偰庢傝忋偘丄傗傟惌嬊偩側偳偲憶偓棫偰傞丅戝婇嬈偑弫偊偽偡傋偰偑偆傑偔偄偔偲偄偆怴帺桼庡媊偺偱偨傜傔側敪憐偵傛傝丄嬥帩偪傪桪嬾偟丄奿嵎傪彆挿偟丄擭嬥惂搙傪夵埆偟丄傾儊儕僇偺將偵側傝丄擔杮傪奜崙偵攧傝搉偟偨挘杮恖偑彫愹偩丅傒傫側偦傟傪抦偭偰偄傞丅偩偑丄偙偺彫愹敪尵偺夁戝曬摴偵傛傝丄埆偺崻尮偱偁傞彫愹偺峔憿夵妚偑丄傑傞偱庣偭偰偄偐側偗傟偽側傜側偄嬔偺屼婙偱偁傞偐偺傛偆側僀儊乕僕偑忴偟弌偝傟偮偮偁傞丅
丂丂偦傕偦傕杻惗偼惓偟偄偙偲傪尵偭偨偺偩丅尵偆偙偲偑偙傠偙傠曄傢傞抪偝傜偟偺柍擻側恖娫偱傕丄偨傑偵偼惓榑傪揻偔偲偒偑偁傞丅斵偼梄惌柉塩壔傪斲掕偟丄崙柉偺懡偔偼偦偺拞恎傪抦傜側偐偭偨偲尵偭偨丅偦傟偼杮摉偺偙偲偩丅斵偼僶僇惓捈偵丄偮偄杮壒傪尵偭偰偟傑偄丄偦傟偑偨傑偨傑惓崝傪幩偨丅偮傑傝丄彫愹偺傗偭偨夵妚偼娫堘偄偩偭偨偲岞偺応偱擣傔偨偺偩丅偙傟偼夋婜揑側偙偲偩丅偙傟傑偱帺柉搣偱偼丄怱偺側偐偱偼巚偭偰偄偰傕丄扤傕偦傟傪尵傢側偐偭偨丅儅僗僐儈偼偙偧偭偰杻惗傪斸敾偟偨偑丄傎傫偲偆偼傛偔尵偭偨偲朖傔傞傋偒側偺偩丅偦偟偰梄惌柉塩壔偑傜傒偺乽偐傫傐偺廻乿媈榝傪揙掙揑偵媶柧偟丄彫愹峔憿夵妚偺晄惓傪朶偔傋偒側偺偩丅杻惗偑梄惌柉塩壔偼傗傞傋偒偱偼側偐偭偨偲尵偄丄數嶳朚抝憤柋憡偑丄乽偐傫傐偺廻乿攧媝偵娭偡傞媈榝傪捛媦偡傞丅摉慠偺偙偲偩丅偩偑丄偙偺彫愹敪尵偵娭偡傞儊僨傿傾偺晜偐傟憶偓偵傛傝丄媈榝捛媦偺惃偄偵僽儗乕僉偑偐偐偭偰偟傑偭偨丅
丂丂惌帯捠偵傛傞偲丄偁偺彫愹敪尵偼丄柺巕傪偮傇偝傟偨搟傝偵傛傞傕偺偱偼側偔丄乽偐傫傐偺廻乿偺媈榝塀偟偺偨傔偺岻柇側寁嶼偐傜弌偨傕偺偩偭偨丅偮傑傝彫愹偼媈榝偺愑擟偑帺暘偵崀傝偐偐偭偰偔傞偙偲傪嫲傟偰丄偁偁偄偆敪尵傪偟偨偺偩偲偄偆丅傎傫偲偆偵偦偆側偺偐偳偆偐丄傏偔偵偼暘偐傜側偄丅偱傕丄偦偺偣偄偱乽偐傫傐偺廻乿媈榝偑偳偙偐偵悂偒旘傫偱偟傑偭偨偙偲偼妋偐偩丅乽偐傫傐偺廻乿媈榝偼丄偨傫偵擔杮梄惌偑僆儕僢僋僗傊偺忳搉宊栺傪敀巻偵栠偣偽嵪傓偲偄偆栤戣偠傖側偄丅僆儕僢僋僗偺媨撪夛挿偲偄偆婬戙偺惌彜偑偨偔傜傫偩丄惌晎偺庤愭偲偟偰婯惂娚榓傪悇恑偟丄偦傟偵傛偭偰嬥栕偗偡傞偲偄偆巇慻傒丄婯惂娚榓傪棙尃偵偟偰娒偄廯傪媧偭偰偒偨棳傟丄偦偟偰偦傟偵彫愹偑偳偆棈傫偩偺偐偲偄偆峔恾丄偦傟傜偺恀憡偑夝柧偝傟側偗傟偽側傜側偄丅偦傟傪偟偰偙偦丄彫愹丒抾拞偺峔憿夵妚偺恀幚偑偝傜偗弌偝傟傞丅
丂丂崙柉偼彫愹偺埿惃偺偄偄妡偗惡偵閤偝傟丄斵偑彞偊傞夵妚傪怣偠偨偑偨傔偵丄偄傑揾扽偺嬯偟傒偵偁偊偄偱偄傞丅偦傟偱傕傑偨儅僗僐儈偼丄埲慜偲摨偠傛偆偵丄崙傪夡偟偨尦嫢偱偁傞彫愹傪梚岇偟丄媈榝塀偟偵壛扴偟丄崙柉傪岆偭偨曽岦偵摫偙偆偲偡傞偺偐丅
2009.01.31 (擔) 僼儗僨傿丒僴僶乕僪偺巚偄弌乗乗偦偺俀
丂丂偙偺偙傠僼儗僨傿偼丄偄傠傫側僙僢僔儑儞偵擖偭偰朲偟偔妶摦偟偰偄偨丅奺庬偺僕儍僘丒僼僃僗僥傿僶儖偵傕惙傫偵弌墘偟丄僼僃僗僥傿僶儖抝偲尵傢傟偰偄偨丅僕儍僘偩偗偱側偔丄億僢僾僗宯偺僙僢僔儑儞偵傕婄傪弌偟偰偄偨丅偨偟偐J億僢僾偺榐壒偵嶲壛偟偨偙偲傕偁偭偨偲巚偆丅斵偺憈朄偼埲慜偵斾傋偰峳偭傐偔側偭偰偄偨丅惃偄偵擟偣偰悂偒傑偔傞偺偩偑丄摨偠傛偆側僼儗乕僘偺孞傝曉偟偑栚棫偪丄敡棟偑慹偔側偭偰偄偨丅惂嶌曽朄偵傛偭偰偼丄傕偭偲僙儞僔僥傿償側墘憈偑偱偒傞偼偢偩偲巚偭偨傏偔偼丄儈儏乕僩傪偮偗偰悂偗偽丄悂偒夁偓傪梷偊丄塇栚傪奜偝偢偵墘憈偱偒傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偨丅偦偙偱僴乕儌儞丒儈儏乕僩偱墘憈偡傞傾儖僶儉傪嶌傜側偄偐偲僼儗僨傿偵懪恌偟偨偲偙傠丄OK偲偄偆曉帠偑偒偨丅嬋偲僒僀僪儊儞傕丄傎傏偙偪傜偺採埬傪庴偗擖傟偰偔傟偨丅
丂丂僌儖乕僾峔惉偼丄僺傾僲丒僩儕僆偩偗傪僶僢僋偵偟偨儚儞丒儂乕儞曇惉偵偟傛偆偲傕峫偊偨偑丄僶儔僄僥傿偺揰偱彮偟曄壔傪偮偗偨傎偆偑偄偄偲巚偄丄敿暘偼儚儞丒儂乕儞丒僇儖僥僢僩丄傕偆敿暘偼僥僫乕傪壛偊偨僋僀儞僥僢僩偱偄偔偙偲偵偟偨丅僗僞僕僆偼丄僯儏乕儓乕僋巗撪偐傜幵偱40暘傎偳偺丄僯儏乕僕儍乕僕乕偵偁傞桳柤側償傽儞丒僎儖僟乕丒僗僞僕僆傪偍偝偊偨丅埲慜偺儗僐乕僨傿儞僌偺偲偒丄斵偼僗僞僕僆偵戝暆偵抶傟偰傗偭偰棃偰丄傏偔偨偪傪崲傜偣偨丅偦偙偱崱夞偼慜擔偐傜儅儞僴僢僞儞偺儂僥儖偵攽傜偣乮斵偼儘僒儞僕僃儖僗偵廧傫偱偄偨乯丄儗僐乕僨傿儞僌摉擔偼斵傪僺僢僋傾僢僾偟偰堦弿偵僗僞僕僆偵擖傞偙偲偵偟偨丅偙傟偱 "Ready for Freddie" 偲偄偆帠懺偼夞旔偱偒偨丅僼儗僨傿偼幵偺側偐偱丄儈儏乕僩傪偮偗偰悂偔楙廗傪偢偄傇傫傗偭偨傫偩偧丄偲尵偭偰偄偨丅
丂丂僒僂儞僪偲偟偰偺慱偄偼丄亀僶僢僋儔僢僔儏亁偵擖偭偰偄傞乹傾僢僾丒僕儍儞僾僩丒僗僾儕儞僌乺偺傛偆側丄梷惂偺棙偄偨僗儕儕儞僌側墘憈偵偁偭偨丅僕儍僘偺儗僐乕僨傿儞僌偵棫偪夛偆嵺丄忬嫷偵傛偭偰丄偁傟偙傟岥弌偟偟偨傝拲暥傪偮偗偨傝偡傞応崌偲丄偙偪傜偐傜傎偲傫偳壗傕尵傢偢儈儏乕僕僔儍儞偵擟偣傞応崌偑偁傞丅偙偺僼儗僨傿偺儗僐乕僨傿儞僌偼慜幰偩偭偨丅傏偔偼偐側傝傾僀僨傾傗僒僕僃僗僠儑儞傪弌偟偨丅乹惎偵婅偄傪乺傪榐傞偲偒丄嵟弶偼4攺巕偺儈僨傿傾儉丒僗儘乕偱傗偭偰傒偨偑丄傕偆傂偲偮惙傝忋偑偭偨墘憈偵側傜側偄丅偦偙偱傏偔偼彮偟僥儞億傪忋偘丄3攺巕偱傗偭偰傒傛偆偲採埬偟偨丅偦偺寢壥丄偆傑偔桇摦揑偱堷偒掲傑偭偨僥僀僋偑弌棃忋偑偭偨丅傑偨丄僶儔乕僪偺乹僾傾丒僶僞僼儔僀乺偺榐壒偵嵺偟偰偼丄僾儗僀偵傔傝偼傝傪偮偗傞偨傔丄奺僐乕儔僗偺嵟弶偺2彫愡偵僽儗僀僋傪擖傟偰偔傟偲拲暥偟偨丅
丂丂僼儗僨傿偵偲偭偰偼晄姷傟側僙僢僥傿儞僌偺榐壒偩偭偨偑丄夞傪廳偹傞偵偮傟偰丄斵偼偟偩偄偵挷巕傪忋偘偰偄偭偨丅儗僐乕僨傿儞僌偺搑拞丄斵偼丄崱搙偺嬋偼儈儏乕僩傪偮偗偢丄僆乕僾儞偱悂偄偰傕偄偄偐丄偲恥偄偰偒偨丅儈儏乕僩偽偐傝側偺偱丄僼儔僗僩儗乕僔儑儞偑偨傑偭偨偺偩傠偆丅偱傕傏偔偼僲乕偲尵偭偨丅偙傟偼慡嬋儈儏乕僩偱偲偄偆僐儞僙僾僩側偺偱丄忳傞傢偗偵偼偄偐側偐偭偨丅僼儗僨傿偼彮偟晄暈偦偆側婄傪偟偨偑丄椆彸偟丄婥傪庢傝捈偟偰儗僐乕僨傿儞僌傪懕偗偨丅儊儞僶乕偺側偐偱偲偔偵慺惏傜偟偐偭偨偺偼僺傾僲偺働僯乕丒僶儘儞偩偭偨丅僶儘儞偼丄敽憈偵丄僜儘偵丄彫婥枴偄偄僺傾僲傪抏偒丄僼儗僨傿偲尒帠側僐儔儃儗乕僔儑儞傪偮偔傝弌偟偨丅偙偺傾儖僶儉惉岟偺堦場偼僶儘儞偵偁偭偨偲巚偆丅敿暘偩偗偵嶲壛偟偨僥僫乕憈幰偵偼丄摉帪攧傝弌偟拞偺儕僢僉乕丒僼僅乕僪傪婲梡偟偨丅僼僅乕僪偼價僢僌丒僩乕儞偺帩偪庡偱丄傗傗僆乕儖僪丒僗僞僀儖側偺偱丄偙偺傾儖僶儉偺庯巪偵崌偆偲巚偭偨偺偩偑丄傕偟偐偟偨傜丄傕偭偲怴偟偄姶妎偺恖偺傎偆偑椙偐偭偨偐傕偟傟側偄丅
丂丂儗僐乕僨傿儞僌偑廔傢偭偨偁偲丄僼儗僨傿偼傏偔偵岦偭偰丄乽嵟弶偼丄偄偄傕偺偑偱偒傞偐敿怣敿媈偩偭偨丅僆乕僾儞偱悂偔嬋傕傗傝偨偄偲巚偭偨丅偱傕儗僐乕僨傿儞僌偟側偑傜丄偩傫偩傫婥帩偪偑忔偭偰偄偭偨丅偄傑偼寢壥偵偲偰傕枮懌偟偰偄傞乿偲楃傪尵偭偰偔傟偨丅弶傔偰偙偆偄偆儗僐乕僨傿儞僌傪宱尡偟偰丄怴偟偄壜擻惈偑峀偑偭偨偲偄偆婥帩偪偵側偭偨偺偩傠偆丅弌棃忋偑偭偨儗僐乕僪偼丄傎傏慱偄捠傝偺撪梕偵側偭偨丅偦偙偵偼丄儅僀儖僗偺儈儏乕僩丒僾儗僀偲傕傑偨堎側傞丄僋乕儖側側偐偵杬曻偝傪偨偨偊偨丄僼儗僨傿棳偺儈儏乕僩丒僗僞僀儖偑偁偭偨丅岾偄側偙偲偵丄敪攧偝傟偨傾儖僶儉偼昡敾偑傛偔丄攧傟峴偒傕岲挷偩偭偨丅偲偆偤傫戞2嶌偼嶌傠偆偲巚偊偽偱偒偨偺偩偑丄偗偭偒傚偔幮撪懱惂偺曄壔偵傛傝幚尰偟側偐偭偨丅偟偐偟丄偙偺傾儖僶儉偑敪攧偝傟偨偁偲丄懠幮偐傜僼儗僨傿偺摨庯岦偺傾儖僶儉偑偄偔偮偐敪攧偝傟偨丅
丂丂偄傑丄偙偺傾儖僶儉傪挳偒曉偡偲丄僼儗僨傿偑儕僘儉偵崌傢偣偰摢傪塃偵偐偟偘丄懌偱挷巕傪偲傝側偑傜僩儔儞儁僢僩傪悂偄偰偄偨巔偑巚偄晜偐傇丅偄傑偛傠斵偼揤崙偱丄傾僀僪儖偩偭偨僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞傗僕儍僘丒儊僢僙儞僕儍乕僘偺慜擟幰儕乕丒儌乕僈儞偲堦弿偵丄偦傫側妴岲偱僕儍儉丒僙僢僔儑儞偵懪偪嫽偠偰偄傞偙偲偩傠偆丅
2009.01.29 (栘) 僼儗僨傿丒僴僶乕僪偺巚偄弌乗乗偦偺侾
丂丂90擭戙弶傔丄僼儗僨傿偼忋怬偑攋楐偟丄偦偙偐傜姶愼徢偵偐偐偭偰墘憈偱偒側偔側偭偨丅怬偺屘忈偼僩儔儞儁僢僞乕偵偲偭偰抳柦揑偩丅怱憻昦偺帩昦傕偁偭偨傜偟偄丅2000擭戙偵擖偭偰嵞婲偟偨偑丄傕偆埲慜偺傛偆偵偼悂偗側偔側偭偨丅擭楊偵傛傞僷儚乕偺悐偊傕偁偭偨偐傕偟傟側偄丅嵞婲屻丄2枃偺傾儖僶儉傪偮偔偭偨偑丄墲擭偺婸偒偼徚偊偆偣偰偍傝丄挳偔偺偑捝乆偟偐偭偨丅
丂丂僼儗僨傿丒僴僶乕僪偺僩儔儞儁僢僞乕偲偟偰偺愨捀婜偼60擭戙偩偭偨偲巚偆丅僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺棳傟傪媯傫偱偄偨偑丄摨帪偵怴偟偄儌僟儞側姶妎傕恎偵偮偗偰偄偨丅斵偺僼儗乕僘偼偳傫側偵媫懍挷偺嬋偱傕偗偭偟偰棎傟側偐偭偨丅惓妋側傾乕僥傿僉儏儗乕僔儑儞偲帄柇偺儕僘儉傊偺忔傝丄儊儘僨傿僢僋側僼儗乕僕儞僌丄偁傆傟傫偽偐傝偺僷儚乕偲僄儌乕僔儑儞偼丄扤偵傕恀帡偑偱偒側偐偭偨丅斵偺僾儗僀偵偼僩儔儞儁僢僩偲偄偆妝婍偺僀儊乕僕偦偺傕偺偲傕尵偊傞壺傗偐偝偲桇摦姶偑偁偭偨丅
丂丂僼儗僨傿偼扤傕偑擣傔傞柤庤偱偁傝側偑傜丄僕儍僘奅偵壒妝揑側塭嬁椡傪媦傏偡傛偆側傾乕僥傿僗僩偵偼側傜側偐偭偨丅斵偼丄僼儗僨傿側傜偙偺堦枃丄偲尵偊傞傛偆側丄枩恖偑擺摼偡傞戙昞嶌丄恖婥斦傪偮偔偭偰偄側偄丅偦傟偑斵偺儈儏乕僕僔儍儞偲偟偰偺懚嵼姶傪婓敄偵偟偨丅傏偔傕僼儗僨傿偺傾儖僶儉偱丄愨懳偺柤斦偼丠 偲尵傢傟傞偲丄偼偰丄偳傟偩傠偆偲柪偭偰偟傑偆丅岲偒側傾儖僶儉偲偄偆偙偲偱尵偆側傜丄僀儞僷儖僗偺亀僕丒傾乕僥傿僗僩儕乕丒僆僽丒F.H.亁丄僽儖乕僲乕僩偺亀僆乕僾儞丒僙僒儈亁丄傾僩儔儞僥傿僢僋偺亀僶僢僋儔僢僔儏亁偁偨傝偩傠偆偐丅
丂丂僼儗僨傿偑嵟弶婜丄60擭戙慜敿偵嵼愋偟偨偺偑僽儖乕僲乕僩丒儗乕儀儖偩丅亀僆乕僾儞丒僙僒儈亁乮1960乯偼弶儕乕僟乕嶌偱偁傝丄偦偺偣偄偐丄斵偺墘憈偼尐偵椡偑擖傝夁偓偰丄傗傗峝偄姶偠偑偡傞丅撪梕偲偟偰偺姰惉搙偼丄偦傟傛傝彮偟偁偲偺亀僴償丒僉儍僢僾亁傗亀儗僨傿丒僼僅乕丒僼儗僨傿亁偺傎偆偑忋偩傠偆丅偱傕亀僆乕僾儞丒僙僒儈亁偼丄僞僀僩儖嬋偲乹僕僾僔乕丒傾僀僘乺偲偄偆2嬋偺壚嬋偑擖偭偰偍傝丄屄恖揑側垽拝傪姶偠傞丅昡榑壠嬝偵偼亀僽儗僀僉儞僌丒億僀儞僩亁偑昡壙偑崅偄傛偆偩偑丄偙傟偼孞傝曉偟偰挳偒偨偄偲巚偆傛偆側傾儖僶儉偱偼側偄丅
丂丂僽儖乕僲乕僩偲偺宊栺婜娫拞丄僀儞僷儖僗偵悂偒崬傫偩亀僕丒傾乕僥傿僗僩儕乕丒僆僽乣亁乮1962乯偼丄偍偦傜偔僼儗僨傿偺枺椡偑嵟崅偵敪婗偝傟偨傾儖僶儉偱偁傠偆丅偳偙傑偱傕懕偔旤偟偄傾僪儕僽丒儔僀儞偼丄傑偝偵僋儕僼僅乕僪傪渇渋偲偝偣傞丅儊儞僶乕傗嬋栚偺枺椡偲憡樦偭偰丄僼儗僨傿偱堦枃偩偗傪嫇偘傞側傜丄傏偔偼偙偺傾儖僶儉偵側傞丅60擭戙屻敿偵強懏偟偨傾僩儔儞僥傿僢僋偱斵偑嵟弶偵悂偒崬傫偩亀僶僢僋儔僢僔儏亁乮1966乯偼儀僗僩僙儔乕偵側偭偨丅僕儍僘丒儘僢僋晽偺僒僂儞僪偱榖戣偵側偭偨偑丄側偐偺1嬋丄儚儖僣丒僥儞億偱墘憈偝傟傞帺嶌偺乹傾僢僾丒僕儍儞僾僩丒僗僾儕儞僌乺偼丄乬儔償儕乕乭偲偄偆宍梕帉偑傄偭偨傝偺垽偡傋偒僫儞僶乕偩丅
丂丂70擭戙偵擖傞偲丄斵偼CTI偺愱懏偵側傝丄愜偐傜僽乕儉偵側偭偨億僢僾丒僼儏乕僕儑儞楬慄偵増偭偰僐儅乕僔儍儖側僸僢僩嶌傪楢敪偡傞偑丄尯恖嬝偐傜偼晄昡傪攦偭偨丅偲偼偄偊亀僼傽乕僗僩丒儔僀僩亁側偳偼偗偭偙偆妝偟偄傾儖僶儉偵巇忋偑偭偰偄傞丅偦偺屻傕斵偼偨偔偝傫偺儕乕僟乕丒傾儖僶儉傪榐壒偟偨偑丄報徾偵巆傞傛偆側傕偺偼尒摉偨傜側偄丅僼儗僨傿偼僒僀僪儅儞偲偟偰傕丄庒偄偙傠偐傜昦婥偱搢傟傞傑偱丄悢懡偔偺僙僢僔儑儞偵嶲壛偟偰偄傞偑丄挳偒偛偨偊偑偁傞偺偼丄傗偼傝60擭戙慜敿偺僕儍僘丒儊僢僙儞僕儍乕僘帪戙偲70擭戙屻敿偺VSOP僋僀儞僥僢僩偵傛傞彅嶌偩傠偆丅
丂丂僼儗僨傿偼僆儕僕僫儖傕偨偔偝傫彂偄偨偑丄婰壇偵巆傞傛偆側桳柤嬋偼惗傫偱偄側偄丅斾妑揑抦傜傟偰偄傞傕偺偲偄偊偽丄乹傾僢僾丒僕儍儞僾僩丒僗僾儕儞僌乺偲乹僶乕僪儔僀僋乺偖傜偄偩傠偆丅斵偼帪娫偵儖乕僘偱丄傛偔僙僢僔儑儞偵抶傟偰傗偭偰偒偨丅亀Ready for Freddie亁偲偄偆傾儖僶儉丒僞僀僩儖偦偺傑傑丄儊儞僶乕偼偄偮傕榐壒僗僞僕僆偱僼儗僨傿偑尰傟傞偺傪懸偭偨丅惗堄婥偱傗傫偪傖側惈奿偱偁傝丄棅傑傟傟偽壗偱傕傗偭偰偟傑偆偍挷巕幰偩偭偨丅斵偑恀偺執戝側儈儏乕僕僔儍儞偵側傝偒傟側偐偭偨偺偼丄偦偺偁偨傝偵傕尨場偑偁偭偨偲巚偆丅偩偑斵偼丄垽沢偺偁傞憺傔側偄恖暱偵傛傝丄偦偟偰壗傛傝傕敳偒傫弌偨僾儗僀偵傛傝丄傒傫側偐傜垽偝傟偨丅
2009.01.25 (擔) 僀僗儔僄儖偺僈僓峌寕偲僆僶儅怴惌尃
丂丂僀僗儔僄儖偺僈僓峌寕偼丄愴憟偲偄偆傛傝傕嶦滳偩偭偨丅僀僗儔僄儖偼僈僓偐傜偺儘働僢僩抏峌寕偵懳偡傞曬暅偩偲庡挘偡傞偑丄僈僓傪晻嵔偟懕偗偰僴儅僗偵傢偞偲峌寕偝偣丄偦傟傪岥幚偵僴儅僗傪焤柵偟傛偆偲偟偨偙偲偼柧傜偐偩丅僴儅僗偺幩偮儘働僢僩抏偼偒傢傔偰柦拞惛搙偺掅偄傕偺偱丄偍傛偦桳岠側峌寕偲偼尵偊側偐偭偨丅100曕忳偭偰僴儅僗偺峌寕偵懳偡傞曬暅傪擣傔傞偵偟偰傕丄偙傫側偵堦曽揑側媠嶦偑嫋偝傟偰偄偄偼偢偑側偄丅
丂丂僀僗儔僄儖偺崅姱偼乽傾儊儕僇偑戞2師戝愴拞偵擔杮偵傗偭偨偺偲摨偠峌寕傪偟偰偄傞傑偱偩乿偲偆偦傇偄偨傜偟偄丅堦斒廧柉傪姫偒崬傓恖岥枾廤抧傊偺柍嵎暿峌寕偩丅偟偐傕楎壔僂儔儞抏傗敀儕儞抏偲偄偭偨巆媠側暫婍傪巊偭偰偄傞丅愴憟偲偼丄杮棃丄暫巑偳偆偟偑愴偆傕偺側偺偵丄僀僗儔僄儖偺僈僓峌寕偱媇惖偵側偭偨恖偺懡偔偼堦斒廧柉偩偭偨丅僫僠僗丒僪僀僣傪偡傜巚傢偣傞埆媡旕摴傇傝偩丅
丂丂偙偺朶嫇傪悽奅拞偺扤傕巭傔傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅傾儊儕僇偑偦偺婥偵側傟偽巭傔偝偣傞偙偲偑偱偒偨偱偁傠偆偑丄巆傝彮側偄擟婜偺僽僢僔儏偑摦偔偼偢偼側偔丄僀僗儔僄儖傕偦傟傪尒墇偟偰偺峴摦偩偭偨偺偩傠偆丅摉弶丄僀僗儔僄儖偺峌寕偺攚宨偵偼傾儊儕僇偑偄傞偲偄偆榖偑偁偭偨丅偮傑傝丄傾儊儕僇偼晄嫷傪夝徚偡傞庤抜偺傂偲偮偲偟偰愴憟傪偟偨偄丅偦偺偨傔僀僗儔僄儖傪偗偟偐偗偰偙偺愴憟傪婲偙偝偣丄僀儔儞偑弌偰偔傞偺傪懸偮丅僀儔儞偑嶲愴偟偨偲偙傠偱傾儊儕僇偑擖傝丄僀儔儞傪峌寕偡傞丅傾儊儕僇偲偟偰偼丄愴憟偵側偭偨傜宱嵪偑妶婥偯偔偟丄栚偺忋偺偨傫釒偺僀儔儞傕扏偗傞偺偱堦愇擇捁偩丄偲偄偆尒曽偩丅恀婾偺傎偳偼傢偐傜側偄丅
丂丂傾儊儕僇崙撪偺儐僟儎惃椡傗恖柆偑崙偺惌帯丄偲偔偵拞搶栤戣偵媦傏偡塭嬁偑戝偒偄偲尵傢傟傞丅幚懺偼傛偔暘偐傜側偄偑丄堦愢偵傛傞偲丄儐僟儎惃椡傕堦枃娾偱偼側偄偲偄偆丅偮傑傝丄儐僟儎惃椡偵偼2攈偑偁傝丄堦曽偼恊僀僗儔僄儖丄傕偆堦曽偼斀僀僗儔僄儖偱丄斀僀僗儔僄儖攈偼丄偁傑傝僀僗儔僄儖偑攈庤偵棫偪夞偭偰偼崲傞搒崌偑偁傞偺偩偦偆偩丅偙偺愢傪怣偠傞側傜丄僽僢僔儏偺帪戙偼恊僀僗儔僄儖攈偑桪惃偩偭偨偨傔丄僀僗儔僄儖傪偄偭偝偄梷偊傛偆偲偟側偐偭偨偙偲偵側傞丅
丂丂僆僶儅怴惌尃偼丄儐僟儎宯偺僗僞僢僼偑懡悢傪愯傔偰偄傞傜偟偄丅傑偨戝摑椞慖嫇拞偵偼僆僶儅偼儐僟儎丒儘價乕抍懱偲庤傪慻傫偱偄偨丅偦偟偰丄僀僗儔僄儖偺僈僓峌寕偵偮偄偰丄戝摑椞廇擟慜偲偼偄偊丄斵偑偄偭偝偄栙偟偰岅傜側偐偭偨偙偲偵幐朷偝偣傜傟偨丅偙偆偄偭偨偙偲偩偗偲傝忋偘傞偲丄僆僶儅偼僀僗儔僄儖婑傝偩偲尒傜傟偰傕偟偐偨偑側偄偩傠偆丅偱傕丄慜夞偵傕彂偄偨傛偆偵丄偦傟偱傕傏偔偼僆僶儅偵婜懸偟偨偄丅
丂丂傾儊儕僇偼偙傟傑偱孯廀嶻嬈偲嬥梈帒杮偲儐僟儎丒儘價乕偵巟攝偝傟偰偒偨丅偦偺懱惂傪堦嫇偵曄偊傛偆偲偡傟偽丄偦傟偙偦偡偖偵埫嶦偝傟傞偩傠偆丅偮傑傝丄嬌抂偵尵偊偽丄扤偑戝摑椞偵側偭偰傕摨偠側偺偩丅偩偲偡傟偽丄偨偲偊尷奅偑偁傞偲偟偰傕丄僆僶儅偺庛幰偵婑偣傞栚偲暯榓傊偺怣擮偵婜懸偟丄斵偑帪娫傪偐偗偰丄惌帯揑側岻傒偝傪敪婗偟側偑傜曄妚偟偰偄偔偙偲偵朷傒傪偮側偖偟偐側偄偺偩丅僆僶儅偑僕儗儞儅偵娮傞偙偲偼柶傟側偄丅偱傕斵偼僽僢僔儏帪戙偵悽奅偐傜屒棫偟偨傾儊儕僇傪曄偊偰偄偔偩傠偆丅僽僢僔儏偺傛偆偵丄慞偲埆偱堦尦揑偵怓暘偗偟偨傝丄懠崙偵柍棟傗傝峌傔擖偭偨傝丄愇桘帒杮偺庤愭偵側偭偨傝丄嬥梈宱嵪傪栰曻偟偵曻抲偟偨傝偼偟側偄偩傠偆丅
丂丂僆僶儅戝摑椞偼丄憗偔傕僋儕儞僩儞帪戙偵拞搶榓暯岎徛傪峴偭偨儈僢僠僃儖尦忋堾媍堳傪摿巊偲偟偰僷儗僗僠僫偵攈尛偟丄愊嬌揑偵榓暯偵庢傝慻傓曽恓傪帵偟偨丅傾儊儕僇偑僀僗儔僄儖偺尐傪傕偨側偗傟偽丄偦偟偰僀僗儔僄儖偑僈僓晻嵔傪夝偄偰廧柉傪惗嶦偟偐傜夝曻偡傟偽丄榓暯傊偺摴偼奐偗傞偩傠偆丅偄偢傟偵偟偰傕丄慜搑偑懡擄側偙偲偼妋偐偩丅傾僼僈儞栤戣偼傕偭偲擄偟偄丅僆僶儅偼傾僼僈儞偵傕儀僥儔儞奜岎姱傪摿巊偲偟偰攈尛偡傞偑丄摨帪偵孯戉傕憹攈偡傞丅晲椡傪攚宨偵偟偨榖偟崌偄偲偄偆嶌愴偩丅偁傑傝僀僗儔儉偵棟夝傪帵偣偽丄崙柉偐傜庛崢偲偺旕擄偑暒偒婲偙傞偙偲傕偁傝偆傞丅傾僼僈儞偼偄傑埲忋偵揇徖偵娮傞偐傕偟傟側偄丅
2009.01.23 (嬥) 僆僶儅偺戝摑椞廇擟偵巚偆
丂丂1950擭戙廔傢傝偐傜60擭戙慜敿偵偐偗偰丄傾儊儕僇偱偼崟恖偨偪偺恖庬嵎暿揚攑塣摦偺棐偑悂偒峳傟偰偄偨丅抍夠偺悽戙偱偁傞傢偨偟偨偪偼丄60擭戙偺慜敿丄拞妛惗偐傜崅峑惗偖傜偄偺偙傠丄偦傫側尰幚傪傑偭偨偔抦傜偢丄梞夋傗億僢僾丒僜儞僌偵傛偭偰丄扨弮偵傾儊儕僇傊偺摬傟傪偐偒棫偰傜傟偰偄偨丅偦傟傎偳墦偄愄偱偼側偄丄傎傫偺嶐擔偺偙偲偵巚偊傞丅偦傟偑偄傑偼丄崟恖偑戝摑椞偵廇擟偟丄崟恖偲敀恖偑庤傪庢傝崌偭偰婌傃崌偭偰偄傞丅傛偔偙偙傑偱扝傝拝偄偨傕偺偩丅偩偑丄僉儞僌杚巘偺柌偼偄傑偩姰慡偵偼幚尰偟偰偄側偄丅曃尒偼崻嫮偔巆偭偰偄傞丅
丂丂僆僶儅偺廇擟墘愢偼丄攈庤偵棟憐傪傇偪忋偘傞偺偱偼側偔丄尰幚揑側棫応偵棫偭偰崲擄傪忔傝愗傠偆偲偄偆丄懌偑抧偵偮偄偨撪梕偩偭偨丅帺暘杮埵側峫偊曽傪夲傔丄屄乆恖偺愑擟傪慽偊傞墘愢偺庯巪偼丄働僱僨傿偺廇擟墘愢傪巚偄婲偙偝偣偨丅斵偺尵梩偵偼椡偑偁傞丅偦偺岥挷偼椡嫮偔丄愢摼椡偵偁傆傟偰偄傞丅僄僉僙儞僩儕僢僋偵側傞傜側偄丄梷惂偟偨榖偟傇傝偑丄怣棅姶傪梌偊傞丅偦傟偲斾傋偰丄惌帯晽搚傗廗姷偺堘偄偑偁傞偲偼偄偊丄擔杮偺庱憡偺拞恎偺側偄嬻慳側墘愢偼傎傫偲偆偵忣偗側偄丅
丂丂偟偐偟僆僶儅偵偼丄埆壔偡傞宱嵪忣惃丄崅傑傞昻晉偺奿嵎丄堛椕曐尟惂搙夵妚丄僥儘偲偺愴偄丄僷儗僗僠僫栤戣側偳丄擄戣偑嶳愊傒偩丅僆僶儅偼傾儊儕僇崙撪偩偗偱側偔丄偙傟傑偱懳棫偟偰偒偨崙傕娷傔偰悽奅拞偐傜娊寎偝傟偰偄傞丅偙偙傑偱婜懸偑崅傑傞偲丄夵妚偑偆傑偔恑傑側偐偭偨応崌偺斀敪偑寽擮偝傟傞丅崙柉偺偁偄偩偱擬嫸揑側巟帩偑偁傞偄偭傐偆丄僆僶儅偵偼偨偄偟偨偙偲偼偱偒側偄偲偄偆惲傔偨尒曽傪偡傞恖傕偄傞丅偩偑丄傏偔偼婜懸偱偒傞偲巚偆丅
丂丂庒偄偙傠丄僆僶儅偼崅媼側怑傪側偘偆偭偰丄僔僇僑偺掅強摼幰偑廧傓嬫堟偱幮夛妶摦壠偲偟偰摥偄偨丅傕偭偲妝側傗傝曽傕偁偭偨偺偵丄偁偊偰斵偼昻崲幰傗宐傑傟側偄恖乆偺偨傔偵恠椡偟偨丅偦偺1揰偩偗偱丄傏偔偼僆僶儅傪怣棅偱偒傞婥偑偡傞丅斵偺崙柉偵岦偗傞栚慄偼妋偐偩偟丄堄尒傪堎偵偡傞幰偲椻惷偵懳榖偱偒傞擻椡傪傕偭偰偄傞丅僀僗儔儉傊榓夝偺儊僢僙乕僕傪敪怣偡傞廮擃側巔惃傕傕偭偰偄傞丅斵偺惤幚偝丄暯榓傪媮傔傞巙偼扤傕媈偆偙偲偼偱偒側偄丅
丂丂偟偐偟丄偨偩惤幚側偩偗偱偼惌帯偼偱偒側偄丅岻柇偵棫偪夞傞偙偲傕昁梫偩丅帪偵偼夁嫀偺尵梩偲柕弬偟偨峴摦傪偲傞偙偲傕偁傞偩傠偆丅偍偦傜偔丄偄偪偽傫崪偑愜傟傞偺偼丄傾儊儕僇偺惌帯傪塭偱摦偐偟偰偒偨嶻孯暋崌懱偲儐僟儎惃椡傊偺懳張偩傠偆丅偁傑傝惈媫偵偙偲傪塣傃偡偓傞偲丄嬌塃敀恖帄忋庡媊幰偩偗偱側偔丄嶻孯暋崌懱偐傜傕埫嶦偝傟傞婋尟偑憹戝偡傞丅偦偺偁偨傝偼丄僆僶儅帺恎偑偄偪偽傫傛偔暘偐偭偰偄傞偩傠偆丅偦偟偰斵偼丄偨偲偊帪娫偼偐偐偭偰傕丄傾儊儕僇偲偄偆崙傪偁傞傋偒曽岦偵曄偊偰偄偔偩傠偆丅
丂丂栤戣偼擔暷娭學偩丅愱栧壠偼僆僶儅怴惌尃偑擔杮偵夁戝側梫媮傪偟偰偔傞壜擻惈傪巜揈偟偰偄傞丅偟偐偟丄傾儊儕僇偱偺惌尃岎戙偼丄偙傟傑偱偺懳暷廬懏奜岎傪惔嶼偟丄惓忢側忬懺偵夵傔傞偄偄僠儍儞僗偩丅偲偼尵偊丄偄傑偺擔杮偺惌帯壠傗奜岎姱偵偼丄偦傫側偙偲偑偱偒傞傛偆側恖嵽偼尒摉偨傜側偄偺偱丄婜懸敄偩偑丅
2009.01.21 (悈) 姱椈傕惌帯傕儊僨傿傾傕傒傫側楎壔偟偰偄傞乗乗偦偺俀
丂丂掕妟媼晅嬥偵偮偄偰丄埲慜偼帺暘偼傕傜傢側偄偲尵偭偰偄偨偺偵丄偄傑偼偦偺帪偵側傜側偄偲暘偐傜側偄偲尵偄弌偟偨丅埲慜偼崅妟強摼幰偵偼帿戅偟偰傕傜偄偨偄偲尵偭偰偄偨偑丄偄傑偼慡堳偑庴偗庢傝偳傫偳傫徚旓偵夞偦偆偲偄偆曽岦偵曄傢偭偰棃偨偺偩丅偮傑傝敪埬偟偨帪揰偲尰嵼偱偼丄忬嫷偑堘偭偰偒偨偺偱丄媼晅嬥偺堄枴晅偗傕丄嵟弶偼昻崲媬嵪嶔偩偭偨偺偵丄宨婥晜梘嶔偵偡傝懼傢偭偨偺偩丅扤偐偑尵偭偰偄偨偑丄昦婥偺徢忬偑埲慜偲堘偆偺偵丄摨偠帯椕朄偱懳張偟傛偆偲偟偰偄傞傛偆側傕偺偱丄偙傟偱偼昦婥偑帯傞傢偗偑側偄丅
丂丂掕妟媼晅嬥偼傕偲傕偲岞柧搣偑庡挘偟偨埬偩偭偨丅岞柧搣偑偁傟傎偳媼晅嬥偵偙偩傢偭偨偺偼慖嫇懳嶔旓偺擯弌偺偨傔偩偭偨偲偄偆偙偲偑丄惌帯捠偺偁偄偩偱岞慠偺帠幚偲偟偰岥偵偝傟偰偄傞丅偮傑傝丄憂壙妛夛堳偵媼晅偝傟偨嬥偺堦晹偑憂壙妛夛偵忋擺偝傟傞丅偦傟偑崱搙偺憤慖嫇偱岞柧搣偺慖嫇帒嬥偵巊傢傟傞丄偲偄偆嬝彂偒偩丅偩偑丄儅僗僐儈偼偙偺忣曬傪偮偐傫偱偄側偄偼偢偼側偄偺偵丄偳偙傕偄偭偝偄曬偠偰偄側偄丅
丂丂惌帯偲摨偠偔丄儊僨傿傾偺嶴忬傕偳偆偟傛偆傕側偄丅斵傜偼僩儓僞憡択栶偺墱揷偺僗億儞僒乕堷偒梘偘敪尵傪傑偲傕偵斸敾偱偒側偄偟丄屼庤愻宱抍楢夛挿偺僉儍僲儞戝暘岺応寶愝偵棈傓棤嬥媈榝傕晻報偝傟偨傑傑偩丅偦偺侾偱嫇偘偨偝傑偞傑側幮夛栤戣傕娷傔偰丄偡傋偰偆傗傓傗偺傑傑偵側偭偰偄傞堦場偼儊僨傿傾偵偁傞丅尃椡傪娔帇偟丄晄惓傪捛媦偡傞巊柦偑偁傞儅僗僐儈偑偙偺偩傜偗偒偭偨懱偨傜偔偱丄偳偆偡傞丅婰幰僋儔僽偱惌晎傗姱椈偺敪昞偡傞愢柧傪偦偺傑傑曬偠偰偄傞偩偗偺丄尰嵼偺儅僗僐儈婰幰偺幙偺掅壓偼怺崗偩丅
2009.01.20 (壩) 姱椈傕惌帯傕儊僨傿傾傕傒傫側楎壔偟偰偄傞乗乗偦偺侾
丂丂柉庡搣偵婜懸偡傞偲偙傠偼戝偒偄丅恀偭愭偵傗偭偰傕傜偄偨偄偺偼丄姱椈惌帯偺懪攋丄岞柋堳惂搙偺夵妚偩丅偙傟傑偱妡偗惡偩偗偼桬傑偟偔偰傕丄偄偞庢傝偐偐傞偲昁偢崪敳偒偵側偭偰偟傑偭偰偄偨丅惌帯壠偺棙尃偲姱椈偺婛摼尃塿偑堦懱偵側偭偰惻嬥偑怘偄暔偵偝傟傞忬懺偑栰曻偟偵側偭偰偄偨丅揤壓傝傗乽傢偨傝乿傪堦憒偡傞偙偲丄柍懯側撈棫峴惌朄恖傪偮傇偡偙偲丄惌帯壠傗戝婇嬈偱偼側偔丄崙柉偵栚傪岦偗偰巇帠偝偣傞偙偲丄偙傟傜偼偡傋偰棈傒崌偭偰偄傞丅偄傑悽偺拞偵偼傃偙傞晄惓傗晄岞暯乗乗墭愼暷丄擭嬥栤戣丄嵸敾惂搙丄懴恔婾憰丄傾僗儀僗僩壭丄栻奞丄BSE媿擏栤戣乗乗偺懡偔偼丄姱椈偺懹枬傗晄嶌堊偑尨場偱婲偙偭偰偄傞丅
丂丂偙偆偄偭偨栤戣偼丄偄偮傕愑擟偺捛媦偑側偍偞傝偵側傞丅姱椈偨偪偼愑擟摝傟偵廔巒偡傞偟丄惌帯壠傗儅僗僐儈偺捛媦傕丄偰偸傞偄丅彫暔偩偗偑張敱偝傟丄杮摉偺埆偼栰曻偟偺傑傑偱丄恀偺尨場偑柧傜偐偵偝傟側偄傑傑丄偆傗傓傗偺偆偪偵榖戣偑壓壩偵側偭偰偟傑偆丅擽傪弌偟愗傜側偄傑傑曻抲偝傟傞偺偱丄傑偨摨偠傛偆側栤戣偑婲偙傞丅柉庡搣惌尃偵側偭偨偐傜偲偄偭偰丄偡傋偰偑傛偔側傞曐徹偼側偄丅夵妚偼梕堈偵偼幚尰偱偒側偄偩傠偆丅偦傟偱傕丄偄傑偺傑傑傛傝偼愨懳偵傑偟側偼偢偩丅
丂丂擔杮偺惌帯偦偺傕偺偑丄偄偮傕偦偆偩偭偨丅栤戣偑婲偙偭偰傕丄偒偪傫偲憤妵偱偒側偄丅偩偐傜丄摨偠栤戣偑傑偨忲偟曉偝傟傞丅偙偲偼幮夛栤戣偩偗偵偐偓傜側偄丅楌巎擣幆偺栤戣偵偟偰傕偟偐傝偩丅愴慜偺擔杮偺曕傫偩摴傪丄峬掕偡傋偒偲偙傠丄斲掕偡傋偒偲偙傠傪崙偲偟偰憤妵偟偰偄側偄偐傜丄偄偮傑偱傕偔偡傇傝懕偗傞丅桋崙栤戣偑偦偆偩偟丄揷曣恄偺傛偆側梒帣揑側偙偲傪尵偄弌偡攜偑弌偰偔傞偺傕丄偦傟偑尨場偩丅
丂丂姱椈偺師尦偺掅偝偼懳奜娭學偵偍偄偰傕業掓偟偰偄傞丅偡傋偰傾儊儕僇棅傒偱丄傾儊儕僇偵懳偟偰偼壗傕斀懳偱偒側偄丅怴暦偺曬摴偵傛傞偲丄戝摑椞偵摉慖偟偨僆僶儅偵擔杮懁偐傜丄偡偖偵擔杮偺庱憡偵垾嶢偺揹榖傪偐偗偰傎偟偄偲偄偆埶棅偑丄偄偔偮傕偺嬝偐傜晳偄崬傫偩丅偗偭偒傚偔擔杮偼僆僶儅偑嵟弶偵揹榖傪偐偗偨僌儖乕僾偺側偐偵擖傝丄娭學幰偼嫻傪側偱偍傠偟偨丅偦偟偰杻惗庱憡偲揹榖偱榖偟偨帪娫偑丄拞崙偺層嬔摀庡惾傛傝壗10昩偐挿偐偭偨偙偲偱戝婌傃偟偨偦偆偩丅偙傟偑偄偭偨偄奜岎偲尵偊傞偩傠偆偐丅偠偮偵偽偐偽偐偟偔丄忣偗側偄丅
丂丂漟抳栤戣偱傾儊儕僇偵棤愗傜傟偨偲尵偭偰惵偄婄偵側傝丄柉庡搣惌尃偵側傝偦偆偩偲尵偭偰晄埨偵側傝丄僆僶儅偐傜揹榖偑偐偐偭偰棃偨偲尵偭偰婌傇丅婤慠偲偟偨懺搙偱愙偡傞偙偲偑偱偒側偄偺偼丄帺暘偺傗傝曽偵帺怣偑側偄偐傜丄傾儊儕僇偺婄怓偽偐傝塎偭偰偄傞偐傜偩丅埨曐懱惂傪嬥壢嬍忦偺傛偆偵庣傝丄偡傋偰傾儊儕僇偺尵偄側傝偩丅偩偐傜崅偄愴摤婡傪攦傢偝傟丄暷孯婎抧偺偨傔偵朄奜側嬥傪弌偟丄傾儊儕僇偺婲偙偡愴憟偵壛扴偝偣傜傟傞偙偲偵側傞丅
2008.12.30 (壩) 撉傒摝偟偰偄偨媣乆偺寙嶌朻尟彫愢
丂丂偙傟偼媣偟傇傝偺惓摑攈朻尟彫愢偩丅傕偭偲憗偔撉傫偱偄傟偽丄崱擭偺傏偔偺儈僗僥儕乕丒儀僗僩丒僥儞偺僩僢僾丒僗儕乕偵偼擖偭偰偄偨偩傠偆丅帺暘偺偙偲傪扞忋偘偟偰尵偆偺傕側傫偩偑丄彂昡壠偨偪偺儗儀儖偺掅偝偼偳偆偟傛偆傕側偄丅偙偺杮偼偁傑傝榖戣偵側傜側偐偭偨偟丄擭枛偺奺庬儈僗僥儕乕丒儔儞僉儞僌偵傕偄偭偝偄擖偭偰偄側偄丅偨傇傫傒傫側撉傫偱偄側偄偺偩傠偆丅偦偺棟桼偼丄傂偲偮偵偼敪攧尦偑儅僀僫乕側償傿儗僢僕丒僽僢僋僗偩偭偨偙偲傕偁傞偩傠偆丅偙傟偑僴儎僇儚暥屔傗怴挭暥屔偩偭偨傜丄傕偭偲拲栚偝傟偰偄偨偼偢偩丅傑偨丄偍傛偦枺椡傪偦偦傜傟側偄朚戣偺偣偄傕偁傞偐傕偟傟側偄丅
丂丂偙偺彫愢偼偄傢備傞戞2師戝愴旈榖偩偑丄愴憟傕偺偲偄偆傛傝奀梞朻尟傕偺偲尵偭偨傎偆偑撪梕傪惓妋偵昞偟偰偄傞丅楢崌孯偺桝憲慏峌寕偺偨傔傾儊儕僇撿晹壂偵攈尛偝傟偨僪僀僣偺愽悈娡U儃乕僩偑暷孯愴摤婡偺峌寕傪庴偗偰寖偟偄懝奞傪旐傝丄晹昳傪挷払偟偰廋棟偟側偗傟偽側傜側偄攋栚偵娮傞丅U儃乕僩偼傂偦偐偵儈僔僔僢僺愳壓棳偺徖戲抧偵晪偒丄僪僀僣偲婥柆傪捠偠傞搚拝働僀僕儍儞廧柉偺彆偗傪庁傝偰U儃乕僩傪廋棟偟傛偆偲偡傞丅壥偨偟偰忔慻堳偼擄傪摝傟丄曣崙偵婣傞偙偲偑偱偒傞偐乗乗偲偄偆僗僩乕儕乕偩丅
丂丂堦撉偟偰儃僽丒儔儞僌儗乕偺乽杒暻偺巰摤乿傗僕儍僢僋丒僸僊儞僘偺乽榟偼晳偄崀傝偨乿傪巚偄弌偟偨丅偦傟傜戞2師戝愴傪晳戜偵偟偨朻尟彫愢偺柤嶌偲斾傋偰傕丄偙偺杮偼傑偭偨偔懟怓偑側偄丅傑偢丄僾儘儘乕僌偑尰戙偱偁傝丄奀掙偵捑傫偱偄傞愽悈娡偑敪尒偝傟丄偦偙偐傜榖偼夁嫀偵偝偐偺傏偭偰U儃乕僩傪傔偖傞榖偵側傝丄僄僺儘乕僌偱嵞傃尰戙偵栠傞丄偲偄偆峔惉偑愨柇偩丅偦偟偰丄慡曇偵偁傆傟傞抝偨偪偺擬偄桭忣偲怱堄婥偑慺惏傜偟偄丅戞2師戝愴傪僥乕儅偵偟偨彫愢偩偲丄僪僀僣恖偼揋栶偵側傞偙偲偑傎偲傫偳偩偑丄偙偺杮偱偼丄U儃乕僩偺忔慻堳偱偁傞僪僀僣恖偼傒側僫僠僗偺強嬈傪寵偆丄屌偄鉐偱寢偽傟偨怣媊偵撃偄孯恖偲偟偰昤偐傟傞丅庡恖岞偱偁傞U儃乕僩偺娡挿偼椻惷捑拝偱抦棯偵晉傒丄忣偗傪抦傞晲恖偩丅偙傟偵丄擬寣娍偺傾儊儕僇柉娫僒儖儀乕僕慏偺慏挿偲偦偺憡朹傗丄汙寁傪傔偖傜偡埆鐓側働僀僕儍儞偺儕乕僟乕傗丄U儃乕僩偺強嵼傪撍偒巭傔傛偆偲偡傞塸崙偐傜攈尛偝傟偨柍慄捠怣彨峑側偳偑偐傜傓丅
丂丂愽悈娡偺側偐偺嬞敆偟偨忬嫷壓偱帵偝傟傞僪僀僣孯恖偨偪偺桬婥偲屩傝丄揋偲枴曽偺偁偄偩偵夎惗偊傞桭忣偑丄撉傒庤偺怱傪擬偔偡傞丅U儃乕僩偺愭擟壓巑姱偲働僀僕儍儞偺柡偲偺儘儅儞僗偑偁偭偨傝丄梔弍巊偄偺榁攌偑搊応偟偨傝偲丄僄僺僜乕僪傕惙傝戲嶳偩丅抁偄側偑傜敆椡枮揰偺愴摤僔乕儞傗僗儕儕儞僌側悈拞偺僒儖儀乕僕嶌嬈傕庤偵娋埇傞偟丄揹怣偺乬昅愓乭偵傛偭偰憡庤傪摿掕偱偒傞側偳偲偄偆錧拁傕嶶傝偽傔傜傟偰偄傞丅僄僺儘乕僌傕梊憐偳偍傝偲偼偄偊丄偲偰傕憉傗偐偩偟姶柫怺偄丅擄傪尵偊偽丄搊応恖暔偨偪偑恾幃揑偡偓傞偙偲偩偑丄揋抧偺恀偭扅拞丄儈僔僔僢僺傪U儃乕僩偑慿峲偡傞偲偄偆傢偔傢偔偡傞僗僩乕儕乕揥奐偺側偐偵丄偦傟傕塀傟偰偟傑偆丅
丂丂偙傟偼傾儕僗僥傾丒儅僋儕乕儞傗僨僘儌儞僪丒僶僌儕乕偺棳傟傪媯傓朻尟彫愢偺媣乆偺柤昳偩丅崱擭偺嵟屻傪偙偺彫愢偱掲傔偔偔傟偨偙偲傪恄偵姶幱偟傛偆丅
2008.12.26 (嬥) 塮夋儀僗僩丒僥儞2008
丂丂崱擭偼梞夋偑晄怳傜偟偄偑丄偦傟傕摉慠偩傠偆丅僴儕僂僢僪惢偺塮夋偑丄戝偑偐傝側CG傪巊偭偨丄枴傢偄偵朢偟偄傕偺偽偐傝側傜丄偄偔傜側傫偱傕娤傞傎偆偼朞偒偰偟傑偆丅傑偟偰傗儕儊僀僋傗夁嫀偺僸僢僩丒僔儕乕僘偺懕曇偽偐傝偱丄傾僀僨傾偺屚妷偑偼側偼偩偟偄丅偲偼偄偊丄桳孴偵擖偭偰偄傞朚夋傕丄桍偺壓偺偳偠傚偆傪慱偭偨擇斣愾偠偺傕偺傗丄媞傪媰偐偦偆偲偄偆堄恾偑尒偊尒偊偺傕偺偽偐傝偱丄偍傛偦怘巜傪偦偦傜傟側偄丅偗偭偒傚偔傂偭偦傝偲扨娰偱岞奐偝傟傞僀儞僨傿宯偺梞夋偺側偐偐傜丄傛偝偦偆側傕偺傪扵偟偰娤傞偙偲偵側傞丅
丂丂傏偔偺塮夋儀僗僩丒僥儞偼丄偦傫側嶌昳傪拞怱偲偟偨傕偺偵側偭偨丅
1丏偦偺搚梛擔丄7帪58暘
2丏僀乕僗僞儞丒僾儘儈僗
3丏偍偔傝傃偲
4丏偮偖側偄
5丏僟乕僕儕儞媫峴
6丏儚僀儖僪丒僶儗僢僩
7丏僶儞僋丒僕儑僽
8丏傾儊儕僇儞丒僊儍儞僌僗僞乕
9丏偄偮偐柊傝偵偮偔慜偵
10丏偁偺擔偺巜椫傪懸偮偒傒偵
丂丂乽偦偺搚梛擔丄7帪58暘乿乽僀乕僗僞儞丒僾儘儈僗乿乽偮偖側偄乿乽儚僀儖僪丒僶儗僢僩乿乽偄偮偐柊傝偵偮偔慜偵乿偺5嶌昳偵偮偄偰偼丄埲慜偺偙偺僐儔儉偱彂偄偨丅乽偦偺搚梛擔丄7帪58暘乿偼丄抐慠丄懠傪埑偟偰崱擭偺1埵偩丅偙傟偩偗姰惉搙偺崅偄丄恖娫偺偳偆偟傛偆傕側偄嬸偐偝偲斶寑惈傪昤偒弌偟偨塮夋偼傔偭偨偵側偄丅2埵偺乽僀乕僗僞儞丒僾儘儈僗乿偼丄庡墘偺償傿僑丒儌乕僥儞僙儞偺僴乕僪儃僀儖僪偦偺傕偺偲尵偊傞僋乕儖側偨偨偢傑偄偲敆恀偺傾僋僔儑儞丒僔乕儞偵庝偐傟傞丅4埵偺乽偮偖側偄乿偼廳憌揑側暔岅峔惉偵傛傝丄塣柦偲楌巎偵東楳偝傟傞抝彈偑奿挷崅偔岅傜傟傞丅嵟屻偵傎傫偺彮偟偩偗搊応偡傞償傽僱僢僒丒儗僢僪僌儗僀償偺柤墘偑朰傟傜傟側偄丅6埵偺乽儚僀儖僪丒僶儗僢僩乿傪昡壙偡傞偵偼丄僕儏乕儖僗丒僟僢僔儞娔撀偵傛傞1955擭偺柤嶌乽抝偺憟偄乿偑梱偐側塮夋揑婰壇偲偟偰巊傢傟偰偄傞偙偲傪巜揈偡傞偩偗偱廩暘偩丅
丂丂3埵偺乽偍偔傝傃偲乿偵偮偄偰偼丄傾僀僗僽儖乕巵偺僐儔儉偵徻偟偔彂偐傟偰偄傞丅崱擭偺擔杮偺塮夋偺側偐偱丄桞堦怱偵怗傟偨嶌昳偩丅戧揷梞擇榊娔撀偼丄乬巰乭偲偄偆椻崜側尰幚傪丄儐乕儌傾傪怐傝崬傒側偑傜丄怱傗偝偟偄帇慄偱尒偮傔傞丅弌墘幰偨偪偺帺慠側墘媄傕慺惏傜偟偄丅傏偔偼偐偮偰1擭傎偳彲撪抧曽偺掃壀偲偄偆挰偵廧傫偩偙偲偑偁傞偑丄偙偺塮夋偱塮偟弌偝傟傞彲撪偺巐婫偍傝偍傝偺晽宨偼丄偲傝傢偗報徾偵巆偭偨丅偨偩偟丄庡恖岞偲晝恊傪偮側偖乬愇乭偵傑偮傢傞憓榖偼丄偪傚偭偲嶌傝暔傔偄偨姶偠偑偟偰岲偒偱偼側偄丅塮夋偲偟偰偺惙傝忋偘偺偨傔偵丄偙偺傛偆側僄僺僜乕僪偑昁梫側偙偲偼暘偐傞偗傟偳丅
丂丂5埵偺乽僟乕僕儕儞媫峴乿偼3恖偺僟儊孼掜偑孞傝峀偘傞楍幵偵傛傞僀儞僪椃峴偺揯枛傪昤偄偨丄堦庬偺儘乕僪丒儉乕價乕偩丅儐乕儌傾偲儁乕僜僗丄側傫偲傕尵偊側偄偲傏偗偨枴傢偄偑丄傎偺傏偺偲偟偨忣姶傪晜偐傃忋偑傜偣傞丅7埵偺乽僶儞僋丒僕儑僽乿偼崙壠揑堿杁偺悌偵偼傑偭偨嬧峴嫮搻偨偪偺昁巰偺摝憱偲斀寕傪昤偄偨丄B媺偭傐偄廘偄偑傉傫傉傫昚偆嶌昳丅僗僩乕儕乕揥奐偑僗僺乕僨傿偱彫婥枴傛偔丄屻枴偑憉傗偐偩丅
丂丂8埵偺乽傾儊儕僇儞丒僊儍儞僌僗僞乕乿偼僴儕僂僢僪偺戝嶌塮夋偺側偐偱丄崱擭桞堦報徾偵巆偭偨嶌昳丅70擭戙偺僯儏乕儓乕僋傪晳戜偵丄僊儍儞僌偲孻帠偺懳寛傪昤偄偨儕僪儕乕丒僗僐僢僩娔撀偺塮夋偩丅僗僩乕儕乕偵偟傠塮夋媄朄偵偟傠丄偲偰傕墱偑怺偄丅僴儕僂僢僪塮夋偺側偐偱丄偄傑怣棅偟偰娤傞偙偲偺偱偒傞娔撀偼丄儕僪儕乕丒僗僐僢僩偖傜偄偺傕偺偩傠偆丅
丂丂崱擭丄偄偪偽傫摢偵偒偨塮夋偼乽儈僗僩乿偩偭偨丅乽僔儑乕僔儍儞僋偺嬻偵乿傗乽儅僕僃僗僥傿僢僋乿偲偄偭偨廏嶌傪偮偔偭偨僼儔儞僋丒僟儔儃儞娔撀偺怴嶌偲偄偆偙偲偱婜懸偟偰娤偵峴偭偨傜丄偙傟偑偲傫偱傕側偄塮夋偩偭偨丅撍慠尰傟偨堎悽奅偺夦暔偵廝傢傟偨恊巕偑丄側傫偲偐摝偘偺傃傛偆偲偡傞偑丄枩嶔恠偒偰傕偼傗偙傟傑偱偲帺嶦傪寛堄偟丄晝恊偑巕嫙傪嶦偟丄帺暘傕帺嶦偟傛偆偲偟偨偲偙傠偱孯戉偑傗偭偰偒偰彆偐偭偨偙偲偵婥偯偔偲偄偆僗僩乕儕乕偩偑丄偙傫側巆崜側榖偺偳偙偑柺敀偄偺偐丅壗傕拞恎偑側偄丄傂偳偄塮夋偩丅偁偺惔乆偟偄乽僔儑乕僔儍儞僋偺嬻偵乿傪庤偑偗偨偺偲摨偠恖偺塮夋偲偼偲偰傕巚偊側偄丅偙傫側塮夋偱傕朖傔傞昡榑壠偑偄傞丅偩偐傜塮夋昡榑偼怣梡偱偒側偄丅
2008.12.22 (寧) 僕儍僘丒儀僗僩丒僥儞2008
1丏僕儑乕丒僓償傿僰儖/75乣儔僗僩丒僶乕僗僨僀丒儔僀償乮Victor乯
2丏僟僯乕儘丒儁儗僗仌僋儔僂僗丒僆僈乕儅儞/傾僋儘僗丒僓丒僋儕僗僞儖丒僔乕乮EmArcy乯
3丏儈儕傾儉丒傾儖僞乕/儂僄傾丒僀僘丒僛傾乮Enja乯
4丏搚婒塸巎/The One乮Ragmania乯
5丏愳搱揘榊/垼壧乮M&I乯
6丏僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗/儔僀償丒傾僢僩丒僾儗僀儎乕僘丒僋儔僽乮King Int'l乯
7丏儘僀丒僴乕僌儘乕償/僀儎乕僼乕僪乮EmArcy乯
8丏僷僢僩丒僩乕儅僗/僨僒僼傿僫乕僪乮MGM乯
9丏儅乕僥傿儞丒僥僀儔乕/僼儗僞僯僥傿乮Sony乯
10丏儘儅儞丒傾儞僪儗儞/僼傽僯乕僞仌價儓儞僪乮P-Vine乯
丂丂弴晄摨偲偼尵偭偰傕丄偄偪偽傫忋偵嫇偘偨僕儑乕丒僓償傿僰儖偺傾儖僶儉偩偗偼丄抐慠丄傏偔偵偲偭偰崱擭偺僕儍僘丒傾儖僶儉偺儀僗僩丒儚儞偩丅僓償傿僰儖偼嶐擭朣偔側偭偨偑丄偙傟偼巰偺2偐寧慜偺儔僀償丅懱偺嬶崌偼偐側傝埆偐偭偨偼偢側偺偵丄偙偙偵挳偐傟傞埑搢揑側僄僱儖僊乕偲償傽僀僽儗乕僔儑儞偵枮偪偁傆傟偨墘憈偼丄偦傫側偙偲偼旝恛傕姶偠偝偣側偄丅僂僃僓乕丒儕億乕僩偺偐偮偰偺椈桭僂僃僀儞丒僔儑乕僞乕偲偺僨儏僄僢僩丒僫儞僶乕偼偲傝傢偗姶摦傪桿偆丅
丂丂僟僯乕儘丒儁儗僗偲儈儕傾儉丒傾儖僞乕偵偮偄偰偼埲慜偵彂偄偨丅偄偢傟傕惷鎹側側偐偵僸儏乕儅儞側旤偟偝傪姶偠偝偣傞傾儖僶儉偩丅僕儍僐偺傾儖僶儉傕慜偵怗傟偨偲偍傝丄愨捀婜偺僕儍僐偑帺桼杬曻偵墘憈偡傞巔偵怱偑桇傞丅
丂丂搚婒塸巎偺亀The One亁偼14擭傇傝偺儕乕僟乕丒傾儖僶儉偩偲偄偆丅搚婒偼擔杮偱No.1偺傾儖僩丒僾儗僀儎乕偩偟丄悽奅拞偱傕斵傪挻偊傞傾儖僩悂偒偼傎偲傫偳偄側偄偲抐尵偱偒傞丅愄偐傜偦偆巚偭偰偄偨偑丄墣傗偐側僩乕儞偲偄偄丄儊儘僨傿僢僋側僼儗乕僘偲偄偄丄偙偺怴嶌傪挳偄偰丄傑偡傑偡偦偺姶傪怺偔偟偨丅斵偑偦傫側偵挿偄娫傾儖僶儉傪悂偒崬傑側偄側傫偰丄偦偟偰僀儞僨傿丒儗乕儀儖偐傜偟偐儗僐乕僪傪弌偣側偄側傫偰丄傎傫偲偆偵晄岾側偙偲偩丅偙偺儗僐乕僪嬈奅偼偳偙偐嫸偭偰偄傞丅
丂丂愳搱揘榊偼丄偙偺偲偙傠丄僜儘傗僨儏僆傗僺傾僲儗僗丒僩儕僆偺嶌昳偽偐傝偩偭偨偑丄偙偺怴嶌亀垼壧亁偼媣偟傇傝偵僺傾僲丒僩儕僆偲嫟墘偟偨儚儞丒儂乕儞丒傾儖僶儉偩丅傗偼傝儕僗僫乕偲偟偰偼丄偙偺傎偆偑壒偺嵗傝偑偄偄偟丄埨怱偟偰挳偗傞丅僜僯乕丒儘儕儞僘傪渇渋偲偝偣傞丄崪懢偺鐥偟偄僩乕儞偼丄偙傟偙偦僥僫乕丒僒僢僋僗偺壒偲夣嵠傪嫨傃偨偔側傞丅
丂丂儘僀丒僴乕僌儘乕償偼丄偄傑偺僩儔儞儁僢僞乕偺側偐偱偼No.1偩傠偆丅崱擭敪攧偝傟偨亀僀儎乕僼乕僪亁偵偼丄壒偺婸偒丄敆椡偵晉傫偩側儔僀儞側偳丄斵偺旤揰偑傛偔昞傟偰偄傞丅僜儘偑慡懱揑偵抁偄偺偑晄枮偩丅傕偭偲僶儕僶儕悂偒傑偔傞儘儞僌丒僜儘傪挳偒偨偄丅
丂丂僷僢僩丒僩乕儅僗偼2擭傎偳慜偵亀儉乕僨傿乕僘丒儉乕僪亁偲偄偆傾儖僶儉偱弶傔偰挳偄偰丄偦偺慺惏傜偟偝偵怱傪扗傢傟偨丅60擭戙慜敿偵妶摦偟偰偄偨丄傎偲傫偳柍柤偺彈惈壧庤偩偑丄壧彞偺岻偝丄帺慠偱慺捈側彞朄丄僜僂儖僼儖偩偑拞梖傪怱摼偨壧惡偼丄巚傢偢挳偒崨傟偰偟傑偆丅偙傫側壧庤偼側偐側偐偄側偄丅崱擭弶暅崗偝傟偨亀僨僒僼傿僫乕僪亁偼儃僒僲償傽廤偩偑丄傗偼傝斵彈偺帬枴偁傆傟傞壧偵怹傞偙偲偑偱偒傞丅
丂丂僀僊儕僗偺僊僞儕僗僩丄儅乕僥傿儞丒僥僀儔乕偺亀僼儗僞僯僥傿亁偵偼斵偺儊儘僨傿偺旤偟偝偑嵟崅搙偵帵偝傟偰偄傞丅婬戙偺僥僋僯僢僋偺帩偪庡偩偑丄偦偺墘憈偼偨傫側傞媄検偺傂偗傜偐偟偵廔傢偭偰偄側偄丅僗僂僃乕僨儞偺僉乕儃乕僪憈幰乛傾儗儞僕儍乕丄儘儅儞丒傾儞僪儗儞偺亀僼傽僯乕僞仌價儓儞僪亁偼丄儔僥儞丒僌儖乕償偺怱抧傛偄僒僂儞僪偑尷傝側偄僀儅僕僱乕僔儑儞傪偐偒偨偰傞丅
2008.12.20 (搚) 崱擭丄怱傪摦偐偝傟偨2嶜偺僲儞僼傿僋僔儑儞
丂丂惵嶳捠傝増偄偵崙楢戝妛價儖偑偁傞丅偢偄傇傫慜丄偙偺價儖傪弶傔偰尒偨偲偒丄乽偊傜偔廥偄丄偮傑傜側偄僨僓僀儞偺價儖偩側丄怴廻偺怴搒挕幧偵帡偰偄傞側乿偲巚偭偨丅偁偲偱挷傋偨傜丄埬偺掕丄愝寁偼扥壓寬嶰偩偭偨丅怴搒挕幧傕崙楢戝妛價儖傕丄戙乆栘偺僆儕儞僺僢僋壆撪嫞媄応偺傛偆側巃怴側愝寁傪偟偨偺偲摨偠恖偵傛傞傕偺偲偼巚偊側偄傎偳丄傾僀僨傾偺昻崲偝偑業掓偟偰偄傞丅戙乆栘懱堢娰偺偲偒丄斵偼51嵨丄怴搒挕幧偺偲偒偼72嵨偩偭偨丅擭楊傪宱偰寶抸奅偵孨椪偟丄悽懎偵傑傒傟偨偡偊偺憂嶌椡偺悐偊偱偁傠偆丅
丂丂1996擭偵姰惉偟偨偍戜応偺僼僕僥儗價杮幮價儖傪愝寁偟偨偺偼扥壓寬嶰偱偁傞丅偙偺價儖偼媴懱偺揥朷幒偑報徾揑偩偑丄傕偲傕偲價儖偺揤曈偵媴懱傪抲偔偲偄偆傾僀僨傾偼丄堥嶈怴偑怴搒挕幧僐儞儁偵採弌偟偨愝寁偵偁偭偨傕偺偩偲偄偆偙偲傪丄偙偺杮傪撉傫偱抦偭偨丅扥壓偼偦偺傾僀僨傾傪丄偦偭偔傝帺暘偺愝寁偵庢傝擖傟偨偙偲偵側傞偑丄偙偆偄偆偺偼搻梡偲偼尵傢側偄偺偩傠偆偐丅
丂丂傕偆1嶜丄桘堜戝嶰榊偲偄偆傾儊儕僇尰戙巎偺妛幰偑彂偄偨亀岲愴偺嫟榓崙傾儊儕僇亁乮娾攇怴彂乯偲偄偆杮偵傕栚傪奐偐偝傟偨丅偙傟偼傾儊儕僇偲偄偆崙偑惉傝棫偪偺偙傠偐傜崱擔傑偱偵峴偭偨愴憟偺楌巎傪捛偄側偑傜丄偦偺岲愴惈傪峫嶡偟偨杮偩丅偙傟傪撉傓偲丄愭廧柉傪枙嶦偟偨傝晻偠崬傔偨傝偡傞偄偭傐偆丄僀僊儕僗丄僼儔儞僗丄僗儁僀儞丄儊僉僔僐側偳偲愴憟偟側偑傜椞搚傪憹傗偟偰偄偭偨傾儊儕僇偺崙柉惈偺側偐偵丄椡偵傛偭偰憡庤傪孅暈偝偣傞偲偄偆巚峫偑崻偯偄偰偄偭偨偺偑暘偐傞丅
丂丂1899擭偐傜1900擭偐偗偰偵僼傿儕僺儞傪怉柉抧壔偡傞偝偄丄傾儊儕僇偼怉柉抧壔偵峈偟偰撈棫塣摦傪揥奐偡傞恖乆傪惂埑偡傞偨傔偵孯戉傪攈尛偟偨丅摉帪偺惌晎偼撈棫塣摦壠偨偪偺巆媠峴堊傪屩戝偵寲揱偟丄偲偒偺戝摑椞僙僆僪傾丒儘乕僘償僃儖僩偼偙傟傪乽栰斬偲偺愴偄乿偩偲嫮挷偟偰丄崙榑傪愴憟巟帩偵帩偭偰偄偭偨丅偙傟偲摨偠傛偆側尵梩傪丄傢偨偟偨偪偼悢擭慜偵暦偄偨偙偲偑偁傞丅2003擭偵僽僢僔儏戝摑椞偑僀儔僋傪峌寕偟偨偲偒偩丅僽僢僔儏偼乽戝検攋夡暫婍乿傪曐桳偟偰偄傞偲寛傔偮偗丄乽撈嵸惌尃傪搢偟丄帺桼傪庣傞偨傔乿偲偄偆戝媊柤暘偱悽榑傪慀傝丄僀儔僋偵怤峌偟偨丅傾儊儕僇偼100擭慜傕尰嵼傕丄傑偭偨偔巚峫夞楬偼摨偠側偺偩丅
丂丂寶崙埲棃丄椞搚奼挘偺偨傔偺愴偄丄嫟嶻庡媊偲偺愴偄丄僀僗儔儉惃椡僥儘偲偺愴偄偲丄愴憟傪懕偗偰偒偨傾儊儕僇偼丄偄傑傗僀儔僋偺揇徖壔丄嬥梈攋抅偵傛傝丄偦偺椡偑梙傜偓巒傔偨丅傕偼傗偙傟傑偱偺傛偆側乽帺桼偲撈嵸乿傗乽暥柧偲栰斬乿偲偄偆扨弮側擇尦榑偱偼栤戣傪夝寛偱偒側偄偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅嬥椡偲晲椡偱悽奅偺攅尃傪埇傝丄帺崙拞怱偺僌儘乕僶儕僘儉傪懠崙偵墴偟晅偗偰偒偨傾儊儕僇偺尃埿偼幐捘偟偮偮偁傞丅擔杮偺惌晎偼丄偦傟偱傕側偍傕懏崙偲偟偰傾儊儕僇偵偟偑傒偮偙偆偲偡傞偺偩傠偆偐丅
2008.12.18 (栘) 儈僗僥儕乕丒儀僗僩丒僥儞2008
丂丂儈僗僥儕乕嬈奅偼丄偙偺偲偙傠擔杮偺嶌昳偑偨偔偝傫姧峴偝傟丄偦傟側傝偵攧傟偰偄傞偺偵斾傋丄奀奜偺彫愢偼嶌昳悢傕攧傝忋偘傕寖曄偟偰偄傞傛偆偩丅壒妝傗塮夋偱傕丄偙偺搶崅惣掅尰徾偼挊偟偄丅偙傟偼偄偭偨偄偳偆偄偆偙偲側偺偩傠偆丅撉傒傗偡偔丄暘偐傝傗偡偔丄怱抧傛偔椳態傪巋寖偡傞擔杮偺彫愢偺傎偆偑堦斒庴偗偡傞偺偼摉偨傝慜偱偁傠偆偑丄傏偔偵尵傢偣傟偽丄擔杮偺儈僗僥儕乕偼丄偛偔堦晹偺椺奜傪彍偄偰丄偙偔傕怺傒傕側偄偟丄偁偞偲偝偽偐傝偑栚偵偮偒丄怱偵敆傞傕偺偑側偄偺偱丄偍傛偦撉傓婥偑偟側偄丅
丂丂偲偄偆偲偙傠偱丄傏偔偺崱擭偺儈僗僥儕丒儀僗僩偼師偺偲偍傝丅
1丏僼儘僗僩婥幙/R丒D丒儕儞僌僼傿乕儖僪乮憂尦幮暥屔乯
2丏垼崙幰/僌儗僢僌丒儖僢僇乮島択幮暥屔乯
3丏棭扗偺孮傟/僕僃僀儉僘丒僇儖儘僗丒僽儗僀僋乮暥弔暥屔乯
4丏夝屬捠崘/僕儑僙僼丒僼傿儞僟乕乮怴挭暥屔乯>
5丏慞椙側抝/僨傿乕儞丒僋乕儞僣乮憗愳暥屔乯
6丏暦偄偰偄側偄偲偼尵傢偣側偄/僕僃僀儉僘丒儕乕僘僫乕乮憗愳暥屔乯
7丏僠儍僀儖僪44乮怴挭暥屔乯
8丏儂僢僩丒僉僢僪/僄儖儌傾丒儗僫乕僪乮彫妛娰暥屔乯
9丏撈慞/僂傿儕傾儉丒儔僔儏僫乕乮島択幮暥屔乯
10丏帪嬻傪挻偊偰/僊儑乕儉丒儈儏僢僜乮彫妛娰暥屔乯
丂丂乽僼儘僗僩婥幙乿乽垼崙幰乿乽棭扗偺孮傟乿乽儂僢僩丒僉僢僪乿偺4嶌偵偮偄偰偼丄埲慜偵怗傟偨丅儕儞僌僼傿乕儖僪偺乽僼儘僗僩婥幙乿偼挿偄偁偄偩懸偭偨峛斻偑偁偭偨偲巚傢偣傞丄婜懸傪棤愗傜側偄弌棃塰偊丅僼儘僗僩寈晹偺僉儍儔僋僞乕偑岝偭偰偄傞偩偗偱側偔丄儈僗僥儕乕偲偟偰偺崪奿傕偟偭偐傝偟偰偄傞丅儖僢僇偺乽垼崙幰乿偼丄弶婜偺儃僨傿僈乕僪丒僔儕乕僘偲偼傑偭偨偔堎幙偺傕偺偵側偭偰偟傑偭偨偑丄儕乕僟價儕僥傿偼敳孮丅僽儗僀僋偺乽棭扗偺孮傟乿傕僊儍儞僌巇棫偰偺憉夣側惵弔彫愢偱堦婥偵撉傔傞丅偙傟傑偱敪攧偝傟偨僽儗僀僋偺3嶌丄偳傟傕摨偠嶌晽側偺偑彮偟婥偵側傞丅儗僫乕僪偺乽儂僢僩丒僉僢僪乿偼屚扺偺枴傢偄丅帟偛偨偊偼側偄偑埨怱偟偰撉傔傞丅
丂丂4埵偺乽夝屬捠崘乿偼僄儞僞僥僀儞儊儞僩偵揙偟偨捝夣側婇嬈彫愢丅嬯嫬偵棫偨偝傟偨庡恖岞偺斀寕傪昤偔僗僩乕儕乕偼敆椡枮揰偩丅5埵偺乽慞椙側抝乿偼儂儔乕傕偺偱抦傜傟傞僋乕儞僣偵偟偰偼捒偟偔壔偗暔偑弌偰偙側偄僒僗儁儞僗彫愢丅偪傚偭偲傾僀儕僢僔儏傪巚傢偣傞愄晽偺僗僞僀儖偲応柺揥奐偑側偐側偐偄偄丅6埵偺乽暦偄偰偄側偄偲偼尵傢偣側偄乿偼僲儚乕儖晽偺嬝棫偰偱丄奐姫偐傜堦婥偵撉傑偣傞偑丄嵟屻偺偳傫偱傫曉偟偑丄偄傑傂偲偮屻枴偑埆偄丅偙傟偑傕偭偲恀偭摉側僄儞僨傿儞僌偩偭偨傜寙嶌偵側偭偰偄偨偩傠偆丅
丂丂7埵偺乽僠儍僀儖僪44乿偼奺庬偺儀僗僩丒僥儞偱愨巀傪攷偟偰偄傞偑丄傏偔偼偁傑傝崅偔偼昡壙偱偒側偄丅偨偟偐偵昅椡偼側偐側偐偺傕偺偱丄屻敿偺朻尟彫愢揑側揥奐傕偄偄偑丄50擭戙偺媽僜楢偺旕恖摴揑側懱惂偲偄偆帪戙愝掕偵堄媊傪尒偄偩偣側偄丅僗僞乕儕儞帪戙偺弆惔偑墶峴偟偨棟晄恠側忬嫷偼丄偡偱偵壗廫擭傕慜偵偝傑偞傑側偐偨偪偱柧傜偐偵側偭偰偄傞丅崱偝傜偦傫側忬嫷傪側偑側偑偲昤偐傟偰傕丄偳偆偟傛偆傕側偄堘榓姶傪姶偠偰偟傑偆丅側偤斊恖偑嫲傞傋偒嶦恖婼偵側偭偨偐偲偄偆偁偨傝傕丄傕偆傂偲偮擺摼偑偄偔愢柧偑偝傟偰偄側偄丅
丂丂崱擭偺摿婰偡傋偒偙偲偲偟偰丄杒曽尓嶰偺乽悈燉揱乿慡19亄1姫偺撉椆偑偁偭偨丅2007擭偐傜撉傒巒傔丄愗傟愗傟偵撉傒恑傫偱丄傗偭偲1擭敿偖傜偄偐偗偰撉傒廔偭偨丅嵶偐偄偙偲傪尵偄弌偡偲偒傝偑側偄偺偱傗傔傞偑丄偲偵偐偔敳孮偵柺敀偐偭偨丄偲偩偗尵偭偰偍偙偆丅
2008.11.27 (栘) 儃僨僀僈乕僪偐傜堩扙偟偨傾僥傿僇僗偼偳偙偵峴偔偺偐
丂丂傕偲傕偲偙偺僔儕乕僘偼儃僨傿僈乕僪嬈傪塩傓傾僥傿僇僗偑丄恎曈寈岇傪埶棅偝傟丄拠娫偨偪偲僠乕儉傪慻傫偱廝寕幰偐傜埶棅恖傪庣傞偲偄偆峔惉偺儈僗僥儕乕偩偭偨丅偝傑偞傑側嶔傪楳偟偰埶棅恖傪廝偆揋偵懳偟丄僾儘偲偟偰偺帺怣偲屩傝傪傕偭偰丄嬞枾側僠乕儉儚乕僋傪曐偪側偑傜寎偊寕偮傾僥傿僇僗偨偪偺愴偄偑柺敀偐偭偨丅偩偑丄傾僥傿僇僗偺拠娫偺傂偲傝偱偁傞彈巹棫扵掋僽儕僕僢僩傪庡恖岞偵偟偨僗僺儞僆僼嶌昳乽榝揗幰乿偁偨傝偐傜丄偦偺僗僞僀儖偑曵傟巒傔偨丅偦偺師偺乽堩扙幰乿偱偝傜偵杮棃偺楬慄偐傜偺堩扙偼戝偒偔側傝丄崱搙偺乽垼崙幰乿偱儃僨傿僈乕僪暔岅偐傜偺槰棧偼寛掕揑偵側偭偨丅
丂丂崱嶌偼慜嶌乽堩扙幰乿偺懕曇偵側偭偰偍傝丄傾僥傿僇僗偼楒恖偵側偭偨彈埫嶦幰傾儕乕僫偲偲傕偵丄帺暘偨偪傪廝寕偡傞撲偺嶦偟壆廤抍偲寣傒偳傠偺愴偄傪孞傝曉偡丅偦偟偰斵傜偼揋偺尦嫢乗乗傾儊儕僇惌晎偺塭偑尒偊塀傟偡傞乗乗傪扵傝弌偟丄偦傟傪枙嶦偟傛偆偲偡傞丅彈埫嶦幰傾儕乕僫偺挻恖揑側嫮偝偼暘偐傞偲偟偰傕丄僾儘偺嶦恖晹戉傪傗偭偮偗傞傎偳傾僥傿僇僗偭偰嫮偐偭偨偭偗丄偲偄偆媈栤傕傢偔偑丄偦傟偼偲傕偐偔丄偁傟傛偁傟傛偲偄偆傑偵丄暔岅偼梊憐奜偺曽岦偵偳傫偳傫恑傫偱偄偔丅儕乕僟價儕僥傿偼敳孮側偺偩偑丄傕偼傗崱嶌偼弶婜偺嶌晽偲偼傑偭偨偔暿偺傕偺偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅
丂丂偙偺僔儕乕僘偑杮棃偺儃僨傿僈乕僪偺暔岅偐傜棧傟偰偄偭偰偄傞偐傜偲偄偭偰丄偮傑傜側偔側偭偨傢偗偱偼側偄丅乽榝揗幰乿埲崀丄崱嶌傑偱偺3嶌偼丄偳傟傕僗僩乗儕乕偺柺敀偝偼愨昳偩偟丄揥奐偼僗僺乕僨傿偱嬞敆姶傕偨偭傉傝偁傞丅偨偩丄張彈嶌乽庣岇幰乿埲壓偺弶婜3嶌偵彂偐傟偰偄偨丄儃僨傿僈乕僪偲偟偰柦傪搎偗偰埶棅幰傪庣傞偲偄偆怣擮丄拠娫偳偆偟偺鉐偲怣棅姶偲偄偭偨梫慺偑婓敄偵側偭偰偟傑偭偨偺偑晄枮側偺偩丅偨偭偨3嶌偱偺曽岦揮姺偼憗偡偓傞丅偩偑丄偙偙傑偱榖偑奼嶶偟偰偟傑偭偨傜丄傕偆弶婜偺儃僨傿僈乕僪偲偄偆摿庩側怑嬈傪偠偭偔傝昤偒偙傫偩暔岅偵栠傞偺偼擄偟偄偩傠偆丅
丂丂偁偲偑偒偵傛傞偲丄儖僢僇偼傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偺師偺嶌昳傪偡偱偵丄傎傏姰惉偝偣偰偄傞偲偄偆丅師夞嶌傕傾僥傿僇僗偲傾儕乕僫偺僐儞價偵傛傞嶌昳傜偟偄丅偙偺僔儕乕僘偵偼丄傾僥傿僇僗偺楒垽曊楌偲偄偆懁柺偑偁偭偨丅傾僥傿僇僗偼嵟弶偺偆偪摨椈偺僫僞儕乕偲楒拠偩偭偨偑丄搑拞偱彈扵掋偺僽儕僕僢僪偲垽偟偁偆傛偆偵側傞丅偦偟偰慜嶌埲崀丄彈嶦偟壆偺傾儕乕僫偲寢偽傟偰偄傞丅庡恖岞偺傾僥傿僇僗傛傝撉幰偺恖婥偑崅偄偲尵傢傟傞僽儕僕僢僩偼丄崱嶌偵偼搊応偟偰偟側偄丅傾僥傿僇僗偵幪偰傜傟偨偐偨偪偵側偭偨僽儕僕僢僩偼丄崱屻偳偆側傞偺偐丄偙傟偐傜偳傫側傆偆偵偙偺僔儕乕僘偵偐傜傫偱偔傞偺偐偑婥偵側傞偲偙傠偩丅
2008.11.18 (壩) 揷曣恄榑暥偐傜尒偊偰偔傞堎忢側晽宨
丂丂崱夞偵尷傜偢丄崙夛偱嶲峫恖彽抳傪偡傞偲丄偄偮傕偙傟偲摨偠傛偆側寢壥偵廔傢傞丅媍堳偨偪偑偄偔傜幙栤偟偰傕丄傗傝曽偑愘楎側偺偱丄傑偭偨偔敆椡偑側偄丅憡庤偵側傔傜傟偭傁側偟偱丄帠審偺夝柧側偳壗傕偱偒側偄丅偙傫側嶲峫恖彽抳側偳丄傑偭偨偔堄枴偑側偄丅斵傜偼僔價儕傾儞丒僐儞僩儘乕儖偺廳梫惈傪揷曣恄偵栤偄偨偩偟偨偺偐丅斵偺楌巎擣幆偺寚娮偲丄帺暘偼壗偱傕抦偭偰偄偰丄偡傋偰惓偟偄偲偄偆榗傫偩峫偊偲巚偄忋偑傝傪巜揈偟偨偺偐丅幙栤偡傞崙夛媍堳偨偪偺幙偺掅偝偼丄偳偆偵傕偁偒傟傞偽偐傝偩丅
丂丂揷曣恄偺榑棟偵偼丄偄偔傜偱傕攋抅偑偁傞丅斵偼乽擔杮偼怤棯偟偰偄側偄乿偲尵偆丅偩偑惌晎偺尒夝偼怤棯愴憟傪斀徣偡傞偲偄偆棫応偩丅帺塹戉偺嵟崅巜婗姱偼庱憡偱偁傞偄偠傚偆丄孯戉偺巜婗柦椷宯摑偐傜偟偰丄枊椈挿偼丄屄恖揑側峫偊偼偳偆偱偁傠偆偲丄偲偆偤傫嵟崅巌椷姱偱偁傞庱憡偺曽恓偵廬傢側偗傟偽側傜側偄丅尵榑偺帺桼側偳偲偄偆埲慜偺榖偱偁傝丄慻怐偵偄傞恖娫偲偟偰摉偨傝慜偺偙偲偩丅傑偨斵偼乽懢暯梞愴憟偼傾儊儕僇偺嶔棯偩偭偨丅搶嫗嵸敾偵傛傝擔杮偼傾儊儕僇偺儅僀儞僪丒僐儞僩儘乕儖偺傕偲偵偁偭偨乿偲庡挘偡傞丅偦偆偄偆柺偑偁偭偨偙偲偼妋偐偩丅偩偑忬嫷偑偳偆偱偁傟丄擔杮偑峌寕傪巇妡偗偨偙偲偼尩慠偨傞帠幚偱偁傞丅偁傜備傞柺偱帠幚忋傾儊儕僇孯偺巟攝壓偵偁傞帺塹戉偺姴晹偑丄傾儊儕僇偵岦偭偰偦偆尵偄愗傟傞偐丅偦偺偁偨傝傪撍偗偽丄揷曣恄偺庡挘偼儃儘儃儘偵側偭偨偼偢偩丅
丂丂斵偺彂偄偨榑暥偼偁傑傝偵抰愘偱丄傑偲傕偵斀榑偡傞偙偲偝偊偽偐偽偐偟偄丅扤偐偺尵偭偨偙偲傪帺暘偺搒崌偵偄偄傛偆偵夝庍偟丄偦傟傪楌巎揑帠幚偺傛偆偵彂偄偰偍傝丄偡傋偰楌巎偺榗嬋偲嬻埿挘傝偩傜偗偩丅乽挘嶌枇敋嶦帠審偼僐儈儞僥儖儞偺堿杁偩乿偲偐乽岣峚嫶帠審偼拞崙嫟嶻搣偺巇嬈偩乿偲偐乽拞崙傗挬慛偵偼丄憡庤崙偺椆彸傪摼偰孯傪偡偡傔偨乿側偳偲偄偆丄偳傫側楌巎妛幰傕傑偲傕偵庢傝忋偘側偄暚斞傕偺偺庡挘傪偡傞丅乽搶撿傾僕傾偱偼愴帪拞偵峴偭偨擔杮孯偺峴堊偑崅偔昡壙偝傟偰偄傞乿側偳偲偄偆榑傕丄傑偭偨偔尰幚傪抦傜側偄恖娫偺偨傢偛偲偵摍偟偄丅僔儞僈億乕儖傗僀儞僪僱僔傾偵堦搙偱傕峴偭偨偙偲偑偁傞恖娫偩偭偨傜丄偲偆偰偄偙傫側偙偲傪尵偊側偄偩傠偆丅揷曣恄偼愴屻偺帺媠巎娤傪夵傔偨偐偭偨偲尵偭偰偄傞偑丄乽擔杮偼怤棯偟偰偄側偄丅擔杮偙偦旐奞幰偩乿側偳偲偄偆庡挘偙偦偑帺媠巎娤偦偺傕偺偩丅
丂丂揷曣恄偺傛偆側丄帺暘偺嫹偄峫偊偵嬅傝屌傑偭偨丄梒抰側摢偺恖娫偼偁偪偙偪偵偄傞丅栤戣側偺偼丄揷曣恄杮恖傛傝傕丄偙傫側恖娫偑偳偆偟偰岞偺慻怐偺僩僢僾偵悩偊傜傟偨偺偐偲偄偆偙偲偩丅杊塹徣偼偲偆偤傫斵偺偙偆偟偨峫偊曽傗丄偦傟傪帺塹戉撪偵峀傔傛偆偲偡傞斵偺峴摦傪抦偭偰偄偨偩傠偆丅偦傟傪抦偭偰偄側偑傜斵傪枊椈挿偵悩偊偨偺偼丄偄偭偨偄偳傫側棟桼偐傜側偺偩傠偆丅偝傜偵晄巚媍側偺偼丄夝擟屻偺斵偵懳偡傞丄傑傞偱庮傟暔偵怗傞傛偆側埖偄偩丅揷曣恄偼枊椈挿傪夝擟偼偝傟偨偑挦夲張暘偵偼側傜偢丄掕擭埖偄偵側傝丄戅怑嬥傪枮妟傕傜偆偲偄偆丅嫃捈偭偨斵傪扤傕挦敱偡傞偙偲偑偱偒側偄偺偩丅
丂丂側偤偐僥儗價傗怴暦偱偼曬摴偝傟偰偄側偄偑丄暦偔偲偙傠偵傛傞偲丄揷曣恄偼昹揷杊塹戝恇偐傜崱夞偺栤戣偱媗栤偝傟偨愜偵丄帺暘偺峫偊傪巟帩偟偰偄傞恖偲偟偰尦庱憡偺怷婌楴偲埨晹怶嶰偺柤慜傪嫇偘偨偲偄偆丅崱夞偺寽徿榑暥曞廤傪庡嵜偟偨傾僷丒僌儖乕僾偺戙昞偱偁傞尦扟偼丄埲慜偐傜揷曣恄偲崸堄偵偟偰偄偨偟丄傑偨怷傗埨晹偲偺恊偟偄晅偒崌偄偱傕抦傜傟偰偄傞丅尦扟偼埨晹偺屻墖夛丄埨怶夛偺桳椡側夛堳偱偁傞丅儂僥儖丒儅儞僔儑儞帠嬈傪揥奐偡傞傾僷丒僌儖乕僾偑丄懴恔婾憰栤戣偱媈榝偺塓拞偵偁偭偨偙偲偼丄傑偩婰壇偵怴偟偄丅傾僷偼僸儏乕僓乕偲摨偠偔懴恔婾憰偵娭梌偟偰偄偨偲偡傞徹尵偑偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄幱嵾傪偟偨偩偗偱嵾偵偼栤傢傟側偐偭偨丅揷曣恄乣傾僷丒僌儖乕僾乣怷/埨晹偲偄偆娭楢傪夝柧偟丄扤偑揷曣恄偺弌悽傪屻墴偟偟偨偺偐傪柧傜偐偵偟偰丄愑擟幰傪抐嵾偡傞偲摨帪偵丄僔價儕傾儞丒僐儞僩儘乕儖傪帺塹戉偵嵞搙揙掙偝偣側偗傟偽丄栤戣傪恀偵夝寛偟偨偙偲偵偼側傜側偄丅
2008.11.15 (搚) 媼晅嬥栤戣偱杻惗庱憡偺尒幆偺側偝偑偝傜偗弌偝傟偨
丂丂偙偺偽傜傑偒偼丄慖嫇懳嶔埲奜偺壗暔偱傕側偄丅扤偐偑尵偭偰偄偨偑丄慖嫇懳嶔偱嬥傪偽傜傑偄偨傜朄棩堘斀偩偑丄柧傜偐側慖嫇懳嶔偱傕丄崙柉慡堳偵偵偽傜傑偄偨傜嵾偵偼側傜側偄偺偩丅僠儍僢僾儕儞偑塮夋乽嶦恖嫸帪戙乿偱尵偭偨丄乽彮悢偺恖傪嶦偟偨傜嵾偵側傞偑丄愴憟偱懡悢偺恖傪嶦偟偨傜塸梇偲偟偰徧巀偝傟傞乿偲偄偆尵梩傪巚偄晜偐傋傞丅2挍墌偲偄偆嵿尮傪偁偰偰宨婥懳嶔傪偡傞側傜丄傕偭偲桳岠側嬥偺巊偄摴偑偁傞偩傠偆丅悽榑挷嵏偱崙柉偺60%埲忋偑媼晅嬥偵斀懳偟偰偄傞偺偵丄偍傟偺傗傝曽偼崙柉偐傜巟帩偝傟偰偄傞偲偆偦傇偒丄嬧峴偺戄偟廰傝偺偨傔帒嬥孞傝偵偁偊偄偱偄傞拞彫婇嬈傪巟墖偡傞懳嶔偑媫柋側偺偵丄偦傟傪扞忋偘偵偟偰丄杻惗偼嬥梈僒儈僢僩偵弌惾偡傞偨傔擔杮傪椃棫偭偨丅
丂丂偦傕偦傕岥傪傂傫嬋偘偰偟傖傋傞恖娫偼怣梡偱偒側偄丅娍帤傪撉傔側偄偺傕丄堦偮傗擇偮娫堘偊傞偺偼偛垽沢偩偑丄杻惗偺傛偆偵丄偙偆偄偔偮傕弌偰偔傞傛偆偠傖丄枱夋偩偗偟偐撉傫偱側偄偐傜偩偲尵傢傟偰傕偟傚偆偑側偄丅廃傝偺楢拞偼側偤娍帤偺撉傒娫堘偄傪庱憡偵巜揈偟側偄偺偩傠偆丅埨晹丄暉揷偵懕偄偰丄杻惗偼偍朧偪傖傫庱憡偺偍朧偪傖傫偨傞帒幙傪傒偛偲偵鄖楐偝偣偰偄傞丅傕偲傕偲偡偖偵夝嶶丄憤慖嫇偡傞偨傔偵慖偽傟偨庱憡側偺偵丄偄偭偨傫偦偺嵗偵偮偄偨偲偨傫丄惌嬊傛傝惌嶔側偳偲傕偭偲傕傜偟偄偙偲傪尵偄側偑傜丄偄偮傑偱傕庱憡偵堉巕偵偟偑傒偮偙偆偲偡傞斵偺巔偼丄傎傫偲偆偵廥偄丅偩偑傑偁丄偦傟傎偳媫偄偰慖嫇傪傗傞偙偲傕側偄丅偙偺傑傑偱偼撪妕巟帩棪偼棊偪傞堦曽偩傠偆偟丄偙偆偟偰曟寠傪孈傝懕偗傟偽丄憤慖嫇偱帺柉搣偑戝攕偡傞壜擻惈偑傑偡傑偡崅傑傞傢偗偩偐傜丅
2008.11.09 (擔) B媺傾僋僔儑儞偺柺敀偝傪枮媔偱偒傞2杮偺梞夋
崱擭6寧偵娤偨亀僀乕僗僞儞丒僾儘儈僗亁乮2007乯偼偦傫側塮夋偺傂偲偮偩偭偨丅娔撀偼僨償傿僢僪丒僋儘乕僱儞僶乕僌丄庡墘偼償傿僑丒儌乕僥儞僙儞偲僫僆儈丒儚僢僣丅僗僞僢僼丄僉儍僗僩偐傜偡傞偲B媺偲偼尵偊側偄偐傕偟傟側偄偑丄B媺偺暤埻婥傪怓擹偔昚傢偣偰偄傞丅儘儞僪儞傪晳戜偵偟偨儘僔傾丒儅僼傿傾偺惗懺偲峈憟傪僥乕儅偵偟偨塮夋偱偁傝丄恖恎攧攦傪側傝傢偄偲偡傞儅僼傿傾撪晹偺桭忣偲棤愗傝丄撲傔偄偨儅僼傿傾偺塣揮庤儌乕僥儞僙儞偲丄嬼慠儅僼傿傾偲偐偐傢傞偙偲偵側傞彈堛儚僢僣偲偺傎偺偐側垽偑丄廔巒彫婥枴偄偄嬞敆姶傪偨偨偊側偑傜昤偐傟傞丅偁傞庬偺條幃旤傪偨偨偊偨夋柺偵堷偒偢傝崬傑傟傞丅
僋儘乕僱儞僶乕僌摿桳偺巆崜僔乕儞偵偼傊偒偊偒偡傞偑丄傾僋僔儑儞応柺偼尒偛偨偊廩暘偩丅側偐偱傕惁傑偠偄偺偼丄岞廜僒僂僫偱偺奿摤僔乕儞丅慺偭棁偺儌乕僥儞僙儞偑丄斵傪廝偭偰偒偨嶦偟壆偲愴偆偺偩偑丄偙傟偑杮暔偝側偑傜偺搑曽傕側偄敆椡偵偁傆傟偰偍傝丄搙娞傪敳偐傟傞丅偙傫側偵儕傾儖側奿摤僔乕儞偼傔偭偨偵側偄丅僗僩僀僢僋側晽忣傪偨偨偊偨儌乕僥儞僙儞偑僋乕儖偱奿岲偄偄丅斵偼偙傟傑偱嶀偊側偄栶偑懡偐偭偨偑丄偙傟偱堦棳僗僞乕偺拠娫擖傝傪偡傞偩傠偆丅
10寧偵娤偨乽儚僀儖僪丒僶儗僢僩乿乮2006乯傕偙傟偲摨庯岦偺B媺傾僋僔儑儞塮夋偩偭偨丅娔撀偼僂僃僀儞丒僋儔儅乕丄庡墘偼億乕儖丒僂僅乕僇乕丅偙偪傜偼傾儊儕僇偺僯儏乕僕儍乕僕乕偑晳戜偱丄庡恖岞偑強懏偡傞偺偼僀僞儕傾儞丒儅僼傿傾偩丅寈姱嶦偟偵巊傢傟偨廵偺屻巒枛傪擟偝傟偨庡恖岞丄偩偑椬壠偺彮擭偑偦偺廵傪帩偪弌偟偰朶椡傪傆傞偆梴晝偵敪朇偟丄峴曽傪偔傜傑偡丅庡恖岞偼廵偲彮擭傪扵偟偰栭偺奨傪憱傝夞傝丄偦傟偵儘僔傾丒儅僼傿傾傗墭怑寈姱偑偐傜傫偱偔傞偲偄偆僗僩乕儕乕偩丅儅僼傿傾偺庤壓傪墘偢傞庡恖岞億乕儖丒僂僅乕僇乕偺偒傃偒傃偟偨傾僋僔儑儞偲晄揋側柺峔偊偑偄偄丅抂栶偩偲巚偭偰偄偨庡恖岞偺嵢偑搑拞偐傜懚嵼姶傪昞偟丄嫻偺偡偔傛偆側妶桇傪偡傞偺偑柺敀偄偟丄彮擭偵寕偨傟傞媠懸恊晝傪丄偨偩偺埆栶偱偼側偔恖娫枴偺偁傞抝偵昤偄偰偄傞偺傕僗僩乕儕乕偵墱峴偒傪梌偊偰偄傞丅
偁偭偲巚偭偨偺偼丄嵟屻嬤偔丄彮擭傪媬弌偟偨庡恖岞偑丄暊傪寕偨傟偰廳彎傪晧偄側偑傜昁巰偵幵傪塣揮偟丄巕嫙傪壠偵憲傝撏偗傞僔乕儞偩丅偁偺僕儏乕儖僗丒僟僢僔儞偑娔撀偟偨僼儔儞僗惢僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺戝柤嶌亀抝偺憟偄亁偺儔僗僩丒僔乕儞偲摨偠偠傖側偄偐丅偙傟偼媟杮傕庤偑偗偨娔撀偺僋儔儅乕偑曺偘偨亀抝偺憟偄亁傊偺僆儅乕僕儏側偺偩丅偨偩偟丄嵟屻偺偲偆偲偮側僴僢僺乕丒僄儞僪偼偄偨偩偗側偄丅偦傟偐傜丄偙傟偼拞恎偵偼娭學側偄偑丄尨戣偼乽Running Scared乿偱偁傝丄乽儚僀儖僪丒僶儗僢僩乿偲偼擔杮偱偮偗偨戣柤偺傛偆偩丅乽僶儗僢僩乿偲偼壗偺偙偲偐偲巚偭偰偄偨偑丄偳偆傗傜抏娵偺乽bullet乿偺偙偲傜偟偄丅乽bullet乿偺敪壒偼乽僽儗僢僩乿偱偁傝丄乽僶儗僢僩乿偲偼愨懳偵尵傢側偄丅偙傫側戣傪偮偗偨攝媼夛幮偼抪傪抦傞傋偒偩丅
2008.10.30 (栘) 嬧峴僊儍儞僌偲僇儞僒僗丒僔僥傿丒僕儍僘
乽棭扗偺孮傟乿乮暥弔暥屔乯偼乽柍棅偺潀乿乽峳傜傇傞寣乿偱愨巀傪攷偟偨僕僃僀儉僘丒僇儖儘僗丒僽儗僀僋偺朚栿戞3嶌丅偙傟偼1930擭戙敿偽偵傾儊儕僇拞惣晹傪朶傟夞偭偨幚嵼偺嬧峴嫮搻僊儍儞僌丄僴儕乕丒僺傾億儞僩乮僴儞僒儉丒僴儕乕乯偺懢偔抁偄惗奤傪捛偭偨幚榐彫愢偩丅僴儕乕丒僺傾億儞僩偼桳柤側僕儑儞丒僨傿儕儞僕儍乕偺拠娫偱丄堦枴偺側偐偱偼嶲杁奿偲偟偰僨傿儕儞僕儍乕傪曗嵅偟偨丅僨傿儕儞僕儍乕偼寈姱偵寕偨傟偰嶦偝傟偨偑丄僴儕乕偼曔傑偭偰揹婥堉巕偱張孻偝傟偰偄傞丅彫愢偱偼丄僴儕乕傪拞怱偵丄偙偺僨傿儕儞僕儍乕丒僊儍儞僌偑丄戇曔丄扙崠丄嬧峴嫮搻傪孞傝曉偡揯枛偑昤偐傟傞丅拲栚偡傋偒偼丄拠娫摨巑偺怣棅偲桭忣傪昤偔偺偵椡揰偑抲偐傟偰偄傞偙偲偱偁傝丄偦偺揰偱偼僽儗僀僋偺慜2嶌偲摨條偱偁傞丅偙偙偵搊応偡傞偺偼丄帺桼傪媮傔偰丄杬曻偵惗偒丄恖惗傪鎼壧偡傞庒幰偨偪偱偁傝丄偦偙偵偼幮夛偺晄惓媊偺崘敪偲偄偭偨儊僢僙乕僕傕側偄偟丄埆恖偨偪偺埫偄怱偺埮傪偆偮偟弌偡偲偄偆傛偆側撪柺昤幨傕側偄丅偦偺堄枴偱偼堦庬偺惵弔彫愢偲傕尵偆偙偲偑偱偒傞偟丄撉屻姶偼偲偰傕憉傗偐偩丅
僨傿儕儞僕儍乕丒僊儍儞僌偵偟傠丄儃僯乕偲僋儔僀僪偵偟傠丄1930擭戙偵傾儊儕僇慡搚傪峳傜偟夞偭偨嬧峴嫮搻偨偪偼丄摉帪丄堦庬偺媊懐偲偟偰戝廜偐傜傕偰偼傗偝傟偰偄偨丅媊懐偲偄偭偰傕嬧峴偐傜扗偭偨嬥傪戝廜偵偽傜傑偄偨傢偗偱偼側偄丅偩偑丄偗偭偟偰堦斒恖偐傜偼嬥傪扗傢側偐偭偨偟丄廵傪岦偗傞偺偼嬧峴偲寈姱偩偗偩偭偨丅30擭戙弶婜偺戝晄嫷帪戙丄帺暘偨偪偑嬯偟偄偺偵嬧峴偩偗偼旍偊懢偭偰偄傞偲偟偰丄嬧峴偼弾柉偺墔歭偺揑偩偭偨丅偩偐傜戝廜偼丄偦偺嬧峴偐傜嬥傪扗偄丄姱寷傪殅楳偡傞偐偺傛偆偵摝偘嫀傞僊儍儞僌傪丄堦庬偺僸乕儘乕偲傒側偟偨偺偩丅偄傑丄傾儊儕僇偱嬥梈晄埨偑婲偙傝丄惌晎偑嬥梈夛幮傪彆偗傞偨傔岞揑帒嬥傪搳擖偟傛偆偲偟偰丄崙柉偐傜偦傟傪旕擄偡傞惡偑忋偑偭偨偑丄70擭慜偺忬嫷傕偦傟偲摨偠偩偭偨偺偩傠偆丅
偄偭傐偆僄儖儌傾丒儗僫乕僪偺乽儂僢僩丒僉僢僪乿乮彫妛娰暥屔乯偩偑丄偙傟偼儗僫乕僪偺慜嶌乽僉儏乕僶丒儕僽儗乿偵搊応偟暷惣愴憟傪愴偭偨傾儊儕僇奀暫戉堳偺懅巕偑庡恖岞偵側偭偰偄傞丅偙傟傕1930擭戙敿偽偺傾儊儕僇拞惣晹傪晳戜偵丄庡恖岞偱偁傞FBI偺憑嵏姱偑廻揋偺嬧峴僊儍儞僌傪捛偄偮傔傞榖偩丅抧偺暥偼彮側偔丄傎偲傫偳搊応恖暔偨偪偺岎傢偡夛榖偱暔岅偼恑峴偡傞丅偄偐偵傕儗僫乕僪傜偟偔丄偙偔偼側偄偑姡偄偨儐乕儌傾偲偲傏偗偨枴偑墶堨偟偰偄傞丅
偙偺彫愢偺側偐偵丄庡恖岞偺憑嵏姱偑僊儍儞僌偺懌愓傪捛偭偰僇儞僒僗丒僔僥傿偵懌傪塣傇応柺偑偁傞丅憑嵏姱偑儕僲丒僋儔僽偲偄偆僶乕偵峴偔偲丄僶乕僥儞僟乕偐傜乽傕偆偡偖丄儗僗僞乕丄僶僢僋丒僋儗僀僩儞丄儀僀僔乕傜偺僕儍儉丒僙僢僔儑儞偑巒傑傝傑偡傛乿偲崘偘傜傟傞丅偙傟偼偄偭偨偄壗擭偺偙偲側偺偩傠偆偲巚偄側偑傜撉傫偱偄偔偲丄庡恖岞偑僋儔乕僋丒僎僀僽儖庡墘偺塮夋乽抝偺悽奅乿傪娤傞僔乕儞偑弌偰偔傞丅挷傋偰傒傞偲丄偙偺塮夋偼1935擭偵岞奐偝傟偰偄傞丅偟偰傒傞偲擭戙偼1935擭偲偄偆偙偲偵側傞丅偙偺偙傠丄僇儞僒僗丒僔僥傿偼埆摽惌帯壠僩儉丒儁儞僟乕僈僗僩偺巟攝偺傕偲丄堦戝娊妝奨偑宍惉偝傟丄偨偔偝傫偺攧弔廻丄僟儞僗丒儂乕儖丄僋儔僽丄搎攷応側偳偑尙傪楢偹偰偍傝丄僕儍僘偑奨偠傘偆偱暦偙偊偰偄偨丅
儗僗僞乕丒儎儞僌偑僇僂儞僩丒儀僀僔乕偺僐儞儃乮僕儑乕儞僘仌僗儈僗丒僀儞僋乯偱弶榐壒傪偡傞偺偼丄偦偺梻擭丄1936擭偩丅偙偺偙傠儀僀僔乕偺僆乕働僗僩儔偼抧尦僇儞僒僗丒僔僥傿偱悘堦偺恖婥僶儞僪偵偺偟忋偑偭偰偄偨丅儗僗僞乕偼1933擭偵儀僀僔乕偺僶儞僪偵擖偭偨丅巃怴側僥僫乕丒僗僞僀儖偑昡敾偵側傝丄偦傟傪暦偒偮偗偨僼儗僢僠儍乕丒僿儞僟乕僜儞偵屇偽傟丄儗僗僞乕偼偄偭偨傫儀僀僔乕偺傕偲傪帿偟偰僯儏乕儓乕僋偵晪偒丄慡暷偵柤傪崒偐偣偰偄偨僿儞僟乕僜儞偺僆乕働僗僩儔偵壛擖偡傞丅偩偑丄偁傑傝偵帪戙傪愭庢傝偟偨僒僂儞僪偑僼傽儞偺歯岲偵側偠傑偢丄偡偖屘嫿偺僇儞僒僗僔僥傿偵栠傝丄儀僀僔乕偺僶儞僪偵嵞壛擖偡傞丅1935擭偼儗僗僞乕偑嵞壛擖偟偰娫傕側偄偙傠偩傠偆丅偙偺偙傠丄幚嵺偵儗僗僞乕傪偼偠傔偲偡傞儀僀僔乕偺堦搣偼丄偙偺彫愢偵弌偰偔傞儕僲丒僋儔僽傪崻忛偵丄栭枅巇帠偑廔傢偭偨偁偲僕儍儉丒僙僢僔儑儞偵懪偪嫽偠偰偍傝丄偦傟偑戝偒側昡敾傪屇傫偱偄偨丅巆擮側偑傜偦傟偼楌巎偲偟偰婰榐偝傟偰偄傞偩偗偱丄榐壒偼巆偝傟偰偄側偄丅儀僀僔乕丒僶儞僪偼1936擭偵僇儞僒僗丒僔僥傿傪棧傟丄僯儏乕儓乕僋偵恑弌偡傞偑丄偦偺椃偺搑師丄僔僇僑偱悂偒偙傫偩偺偑丄慜婰僕儑乕儞僘仌僗儈僗偺僙僢僔儑儞偩丅偙偙偱偺儗僗僞乕丒儎儞僌偺僀儞僗僺儗乕僔儑儞偁傆傟傞僜儘偼丄斵偺慡儗僐乕僨傿儞僌偺側偐偱娫堘偄側偔嵟崅偺僾儗僀偱偁傠偆丅
庡恖岞偺憑嵏姱偼偙偺儕僲丒僋儔僽偱僕僃僀丒儅僋僔儍儞偲偄偆僺傾僲抏偒偲恊偟偔側傝丄奨傪埬撪偟偰傕傜偆丅幚嵺偺儅僋僔儍儞偼丄偦偺偙傠偼傑偩僶乕偺僺傾僯僗僩偩偭偨偑丄偦傟偐傜娫傕側偔僶儞僪傪寢惉偡傞丅偦偙偵庒偒僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕偑壛擖偡傞偙偲偵側傞丅僷乕僇乕偼丄傂偲壞僆僓乕僋偺嶳偵偙傕傝丄慜婰1936擭偵悂偒崬傑傟偨僕儑乕儞僘仌僗儈僗偺儗僐乕僪乽儗僨傿丒價乕丒僌僢僪乿偱儗僗僞乕丒儎儞僌偺墘憈傪揙掙揑偵尋媶偟丄儅僋僔儍儞偺傕偲偱榬傪杹偄偰價僶僢僾偺奐戱幰偵側傞傢偗偩偑丄偦傟偼偙偺暔岅傛傝悢擭偁偲偺偙偲偱偁傞丅儘僶乕僩丒傾儖僩儅儞偑娔撀偟偨塮夋乽僇儞僒僗丒僔僥傿乿(1996)偼偪傚偆偳1935擭慜屻偺僇儞僒僗丒僔僥傿偑晳戜偵側偭偰偄偨丅儕僲丒僋儔僽偺傛偆側僶乕偱儈儏乕僕僔儍儞偨偪偑僕儍儉丒僙僢僔儑儞傪偡傞僔乕儞偑弌偰偔傞偟丄偨偟偐僷乕僇乕傪巚傢偣傞崟恖偺彮擭偑僋儔僽偵傕偖傝偙傫偱墘憈傪擬怱偵挳偔僔乕儞傕弌偰偒偨偲婰壇偡傞丅偨偩偟塮夋偱墘憈偝傟偨僕儍僘偼丄30擭戙偲偼帡偰傕帡偮偐偸儌僟儞側僗僞僀儖偩偭偨偑丄偙傟偼摉帪偺傛偆偵墘憈偱偒傞尰栶儈儏乕僕僔儍儞偑偄側偄偺偩偐傜丄偟偐偨偑側偄偩傠偆丅
乽儂僢僩丒僉僢僪乿偼丄撪梕偼偄傑偄偪偩偑丄偦傫側庒偄儗僗僞乕傗儀僀僔乕偑敩檹偲墘憈偟偰偄偨僇儞僒僗丒僔僥傿丄價僶僢僾偺壏彴偵側偭偨僇儞僒僗丒僔僥傿偺僀儊乕僕傪摢偺側偐偵晜偐傃忋偑傜偣偰偔傟傞彫愢偩偭偨丅
2008.10.22 (悈) 攋柵偵岦偭偰撍偒恑傓孼掜乗乗儖儊僢僩偺埑搢揑側怴嶌塮夋
1950擭戙偐傜塮夋傪嶣偭偰偄傞傾儊儕僇偺娔撀偼丄傒傫側傕偆堷戅偟偨偐丄朣偔側偭偰偟傑偭偰偄傞偩傠偆偲巚偭偰偄偨偑丄嬃偔偙偲偵僔僪僯乕丒儖儊僢僩偼偄傑傕傑偩偮偔傝懕偗偰偄傞丅偟偐傕丄埲慜偵傕憹偟偰椡姶偁傆傟傞塮夋傪丅愭廡娤偨乽偦偺搚梛擔丄7帪58暘乿乮2007擭乯偑偦傟偩丅偦傟傎偳婜懸偣偢偵娤偵峴偭偨偑丄偙傟偑偡偛偄塮夋偩偭偨丅撪梕偼偳偆偟傛偆傕側偔埫偄丅偩偑丄慡懱偵傒側偓傞嬞敆姶偲堎條側傑偱偺敆椡丄嵶晹傑偱鉱枾偵楙傝忋偘傜傟偨崪奿偼慺惏傜偟偄丅暣傟傕側偄寙嶌偩丅偨傇傫崱擭娤偨塮夋偺側偐偱儀僗僩偩傠偆丅杻栻偵偼傑偭偰夛幮偺嬥偵傑偱庤傪偮偗傞嬥寚忬懺偺孼偲丄棧崶偟偨嵢偵暐偆巕嫙偺梴堢旓偑偲偳偙偍偭偰偄傞婥庛側掜偑偄傞丅偙偺孼掜偑嬥栚摉偰偵嫮搻偡傞偑丄偳傫偳傫僪僣儃偵偼傑偭偰偄偔丅帠懺偼埆偄傎偆傊丄埆偄傎偆傊偲摦偄偰偄偒丄嵟屻偵偼丄偲偆偤傫攋柵偑懸偭偰偄傞丅偙傟偼斊嵾傪僥乕儅偵偟偨塮夋偱偁傝丄嵟弶偺偆偪偼尰戙晽僲儚乕儖揑側揥奐偱恑峴偡傞丅愨朷揑側忬嫷丄壗偲偐偦傟傪懪奐偟傛偆偲偡傞偑丄媡偵偳傫偳傫揇徖偵浧偭偰偄偔偲偄偆棳傟偼丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺峴偒曽偦偺傕偺偩丅偩偑丄搑拞偱晝恊偑搊応偡傞偲丄僗僩乕儕乕偼晝偲巕偺妋幏偺僪儔儅傊偲堏峴偟丄斶寑揑側怓崌偄傪懷傃偰偄偔丅
偙傟偼娔撀偺墘弌傕偝傞偙偲側偑傜丄傑偢偼僉儍僗僥傿儞僌偺帪揰偱惉岟偑栺懇偝傟偨偲尵偭偰傕偄偄丅孼傪僼傿儕僢僾丒僔乕儌傾丒儂僼儅儞丄掜傪僀乕僒儞丒儂乕僋偑墘偠偰偄傞丅儂僼儅儞偼乽僇億乕僥傿乿偱偺偔偝偄墘媄偑旲偵偮偄偨偑丄偙偺塮夋偱偼偦傟偑尒帠偵偼傑偭偰偍傝丄攋柵偵岦偭偰撍偒恑傓僟儊抝傪愨柇偵墘偠偰偄傞丅儂乕僋傕丄偙傟傑偱娤偨塮夋偱偼堦搙傕偄偄偲巚偭偨偙偲偼側偐偭偨偑丄偙偙偱偺丄孼偺尵偄側傝偵峴摦偡傞丄恖偼偄偄偑婥偺庛偄掜偼丄傑偝偵揔栶偩丅
塮夋偺屻敿偵搊応偡傞孼掜偺晝恊傪傾儖僶乕僩丒僼傿僯乕偑廳岤偵墘偠傞丅僼傿僯乕偼丄偙偺偲偙傠丄偙偺傛偆側榁嫬偵擖偭偨抝偺栶傪墘偠偰岻偝傪敪婗偟偰偄傞丅乽僩儉丒僕儑乕儞僘偺壺楉側朻尟乿偺镈憉偨傞夣抝帣傇傝傪巚偆偲丄妘悽偺姶偑偁傞丅孼偺嵢傪墘偠傞儅儕僢僒丒僩儊僀偼丄乽偄偲偙偺價僯乕乿埲棃丄傏偔偺僼僃僀償傽儕僢僩彈桪偺傂偲傝偩偭偨丅傕偆40嵨傪夁偓偰偄傞偑丄偄傑傕尒帠側懱宆傪曐偭偰偍傝丄怓偭傐偝偵偧偔偧偔偝偣傜傟傞丅
偦傟偵偟偰傕僔僪僯乕丒儖儊僢僩偼83嵨偲偄偆擭楊偱丄傛偔偙傟偩偗椡嫮偄塮夋傪嶣傟偨傕偺偩丅僂傿儕傾儉丒儚僀儔乕偵偟傠丄價儕乕丒儚僀儖僟乕偵偟傠丄柤娔撀偲尵傢傟偨恖偨偪偺懡偔偼丄斢擭偵側傞偲丄墲帪偲斾傋偰尒傞塭傕側偄杴嶌偟偐偮偔傟側偔側偭偨乮僼儗僢僪丒僕儞僱儅儞偺傛偆偵丄嵟屻傑偱寙嶌傪嶣傝懕偗偨娔撀傕偄傞偑乯丅擭楊偲偲傕偵偔傞憂嶌堄梸偺尭戅丄儌僥傿儀乕僔儑儞偺屚妷偼丄偁傞堄枴偱旔偗傜傟側偄傕偺偩傠偆丅偦傫側側偐偱丄儖儊僢僩偑怴嶌偵崬傔偨婥敆丄悐偊傪抦傜側偄僄僱儖僊乕偼丄嬃偔傋偒偙偲偩偲巚偆丅
2008.10.06 (寧) 7擭傇傝偺僼儘僗僩寈晹僔儕乕僘偺怴嶌傪姮擻
R丒D丒儕儞僌僼傿乕儖僪偺儈僗僥儕乕彫愢丄僼儘僗僩寈晹僔儕乕僘偺朚栿戞4嶌乽僼儘僗僩婥幙乿乮憂尦暥屔乯偑傗偭偲敪攧偝傟偨丅慜嶌偐傜偠偮偵7擭傇傝偩丅崱夞傕婜懸偵偨偑傢偸柺敀偝偵偁傆傟偰偄傞丅僼儘僗僩丒僔儕乕僘偼夞傪捛偆偛偲偵挿偔側偭偰偍傝丄崱嶌偼忋壓2姫偱900儁乕僕偲偄偆戝挿曇偩偑丄堦婥偵撉傒廔偊偰偟傑偆丅撈摿偺僼儘僗僩尵梩偐傜偔傞栿偟偵偔偝偲挿戝側暘検偐傜偟偰丄東栿偵帪娫偑偐偐傞偺偼偟傚偆偑側偄偲偟偰傕丄7擭傇傝偲偼撉幰傪懸偨偣夁偓偩丅偦傟偵偟偰傕丄偙傟偩偗偺挿曇傪丄搑拞偱偩傟傞偙偲側偔柺敀偝傪帩懕偝偣丄偝傑偞傑側帠審傪偡傋偰廂傑傞傋偒偐偨偪偱廂傑傜偣傞嶌幰偺椡検偼戝偟偨傕偺偩偲巚偆丅僗僩乕儕乕偺揥奐偼偙傟傑偱偲摨偠偩丅僀僊儕僗偺抧曽搒巗偺寈嶡彁偵嬑傔傞僕儍僢僋丒僼儘僗僩寈晹偑丄怴偟偔攝懏偝傟偨晹壓偲偲傕偵擄帠審偺憑嵏偵偁偨傞丅崱夞偼巕嫙偺桿夳帠審偑杮嬝偩偑丄偦傟偲摨帪偵偄偔偮傕偺帠審偑敪惗偟丄僼儘僗僩偨偪偼傊偲傊偲偵側傝側偑傜晄柊晄媥偱憑嵏偡傞丅暋悢偺帠審偑摨帪敪惗偡傞偲偄偆僷僞乕儞偼丄偁傞堄枴偱寈嶡彫愢偺揟宆偩丅傓偐偟僀僊儕僗偺嶌壠僕儑儞丒僋儕乕僔乕偑彂偄偨僊僨僆儞寈帇僔儕乕僘偲偄偆儌僕儏儔乕宆寈嶡彫愢偑偁偭偨偑丄偁傟偲摨庯岦偱偁傞丅
偙偺僔儕乕僘嵟戝偺儐僯乕僋偝偼庡恖岞僼儘僗僩偺嫮楏側僉儍儔僋僞乕偵偁傞丅僼儘僗僩偼丄偄偮傕儓儗儓儗偺暈傪拝偨晽嵮偺忋偑傜側偄丄岤婄柍抪偱晄寜側拞擭抝偱偁傝丄忋巌偺僞僶僐傪偔偡偹傞僙僐僀搝偱偁傝丄偟傕偹偨偺僕儑乕僋傪楢敪偟偰廃埻偺椟鏓傪攦偆僆儎僕偩丅偩偑憑嵏偺榬偲僇儞偼妋偐偱丄偲傫偱傕側偄儈僗傕斊偡偑丄偄傗傒傪尵偭偨傝柍棟擄戣傪墴偟晅偗傞弌悽偺偙偲偟偐摢偵側偄擼側偟彁挿傗丄庤暱傪撈傝愯傔偟偨偑傞摨椈傪揋偵傑傢偟丄朲偟偝偲晄塣傪傏傗偒側偑傜傕丄怮怘傪朰傟偰憑嵏偵杤摢偟丄斊恖傪捛偄偮傔傞丅
崱夞傕僼儘僗僩偺偍壓楎側僕儑乕僋偼嶀偊傢偨偭偰偄傞丅
乽儕僗僩偵弌偰偔傞傗偮傪曅偭抂偐傜堷偭挘偭偰偔傞傫偩丅偱傕偭偰丄偪傫傐偙偑傑偩偁偭偨偐偔偰丄愭偭偪傚偑嫽暠偵恔偊偰偄傞傗偮偑偄偨傜丄栤摎柍梡偱梕媈幰偭偰偙偲偵偟偰傛傠偟偄乿
乽慡棁偺庒偄柡偵掆幵傪媮傔傜傟偨偺偵丄掆傑傜側偐偭偨偭偨丠丂偍傟側傜敿棁偱傕掆傑偭偰傗傞偺偵乗乗偄傗丄偨偲偊暈傪拝偰偨偭偰丄偍偭傁偄偺曅偭傐偱傕偪傜偭偲偺偧偐偣偰偔傟傝傖丄傕偆懄嵗偵掆傑偭偰傗傞乿
乽僕儍僢僋丄媫偄偱偙偭偪偵棃偰偔傟丅巰懱偑偍偐偟側偙偲偵側偭偰傞傫偩乿乽偪傫傐偙偑2杮惗偊偰偨偺偐丠丂偩偭偨傜丄儕僘傪峴偐偣傞偗偳乿
乽偁偁偄偆揦偺楢拞偼媞偺嵎偟弌偡僋儗僕僢僩丒僇乕僪偟偐尒偰偄側偄丅帋偟偵偍傑偊偺帺枬偺儉僗僐傪偩傜傫偲傇傜壓偘偰揦偵擖偭偰傒側丅扤傕婥偑偮偒傖偟側偄偐傜乿
乽寈晹丄弨旛偑偱偒偨傜尵偭偰偔偩偝偄丅傢偨偟偺傎偆偼偄偮偱傕戝忎晇偱偡偐傜乿乽垽偟偁偆偮傕傝側傜丄傑偢偼僪傾傪暵傔偰偔傟丅婥偯偐側偔偰偛傔傫傛乿
乽愭廡側傫偰丄媼桘婡偺棤偵偟傖偑傒崬傫偱偆傫偪傪偟偰偄傞抝偑丄杊斊價僨僆偵塮偭偰傑偟偨丅尒傑偡偐丠乿乽偄傗丄墦椂偟偲偔丅偍傟偩偲偄偗側偄偐傜乿
偲傑偁丄偙傫側嬶崌偵丄僼儘僗僩偼摼堄偺僕儑乕僋傪慡曇偱鄖楐偝偣傞丅怴偟偔僼儘僗僩偺傕偲偵攝懏偝傟偨庒偄彈惈寈晹曗偑丄傊偒偊偒偟側偑傜傕丄偗側偘偵偦傟偵懴偊傞巔偑偍偐偟偄丅
偦傫側傆偆偵丄憡曄傢傜偢僼儘僗僩丒僷儚乕偼慡奐側偺偩偑丄崱嶌偼怱側偟偐丄偄傑傑偱傛傝斵偺朤庒柍恖偝偑塭傪傂偦傔丄恖娫揑側柺偑晜偒弌偰偄傞姶偠偑偡傞丅嵢傪朣偔偟偨斵偺屒撈姶偑昤偐傟傞偟丄揋懳偡傞摨椈偺婥帩偪傪媯傫偱傗偭偨傝丄婥庛側彫埆搣偵摨忣偟偨傝偡傞偟丄晹壓偨偪偐傜偗偭偙偆曠傢傟偰偄傞條巕傕尒偰庢傟傞丅偩偑丄偁偺僼儘僗僩偺偙偲偩丅師夞嶌偱偼丄傑偨傕偲偺傒傫側偐傜婖傒寵傢傟傞僴僠儍儊僠儍側恖娫偵栠傞傛偆側婥偑偡傞丅
朻摢偱東栿偺抶偝偵暥嬪傪偮偗偨偑丄抶偔偰傕懸偭偨偐偄偑偁偭偨偲巚傢偣傞偺偼丄撪梕偲摨帪偵東栿偑慺惏傜偟偄偐傜偩丅栿幰偺嬟郪宐偝傫偼偲偰傕帺慠側擔杮岅偵巇忋偘偰偄傞丅彈惈乮偩偲巚偆乯側偺偵丄僼儘僗僩偺敪偡傞壓昳側僕儑乕僋傪丄傛偔偙偙傑偱岻傒偵栿偣傞傕偺偩偲姶怱偡傞丅偙偺恖偼丄埲慜儈僗僥儕乕丒僼傽儞偺偁偄偩偱昡敾偵側偭偨僉乕僗丒僺乕僞乕僜儞偺僂僃儖僘婰幰僔儕乕僘4晹嶌傪栿偟偰偄傞丅偙傟傕撪梕偲傕偳傕栿傕忋乆偩偭偨丅
嶌幰偺儕儞僌僼傿乕儖僪偼巆擮側偙偲偵丄偡偱偵婼愋偵擖偭偰偄傞丅僼儘僗僩丒僔儕乕僘偼慡晹偱6嶌偱廔傢偭偰偟傑偭偨傜偟偄丅崱嶌偺乽僼儘僗僩婥幙乿偼1995擭敪昞偺4嶌栚偩偑傜丄偁偲2嶌偟偐巆偭偰偄側偄偙偲偵側傞丅師偺東栿傑偱丄崱夞傎偳娫傪嬻偗側偄偱傎偟偄偲偄偆巚偄偺偁傞斀柺丄偁偲2嶌偟偐撉傔側偄偙偲傪峫偊傞偲丄偁傑傝憗偔廔傢偭偰傎偟偔側偄婥帩偵傕側偭偰偟傑偆丅
2008.09.30 (壩) 億乕儖丒僯儏乕儅儞偺巚偄弌
億乕儖丒僯儏乕儅儞偑9寧26擔偵朣偔側偭偨丅83嵨偩偭偨丅傏偔偑塮夋傪傓偝傏傞傛偆偵尒巒傔偨偙傠丄嵟弶偵枺偣傜傟偨攐桪偺傂偲傝偑億乕儖丒僯儏乕儅儞偩偭偨丅60擭戙弶傔丄拞妛惗偺廔傢傝偐傜崅峑惗偵偐偗偰偺偙傠丄傏偔偼怴嶌偺晻愗傝傗媽嶌偺儕僶僀僶儖側偳丄塮夋娰偵偐偐傞梞夋傪庤摉偨傝偟偩偄偵尒偰偄偨偑丄偦偺傂偲偮偵丄晻愗傝忋塮偺乽僴僗儔乕乿乮61擭乯偑偁偭偨丅億乕儖丒僯儏乕儅儞傪尒偨偺偼丄偙偺塮夋偑弶傔偰偩偭偨丅僯儏乕儅儞偼揤嵥揑側價儕儎乕僪偺榬傪傕偮偪傫傄傜偺庒幰傪墘偠偨丅惗堄婥偱閬枬偩偑丄弮悎側怱傪傕偮庒幰偺嵙愜偲嵞惗丄旕忣側彑晧偺悽奅丄擔堻幰偳偆偟偺抝彈偺垽偑昤偐傟傞丄儌僲僋儘偺墱怺偄夋柺偵庝偒偮偗傜傟偨丅僷僀僷乕丒儘乕儕乕丄僕儑乕僕丒C丒僗僐僢僩丄僕儍僢僉乕丒僌儕乕僜儞偲偄偭偨榚栶傕岝偭偰偄偨丅偦傟傑偱塮夋偲偄偊偽惣晹寑傗惵弔傕偺偽偐傝尒偰偄偨偑丄乽僴僗儔乕乿偵傛偭偰塮夋偺怴偟偄枺椡傪抦偭偨丅偦傟偐傜娫傕側偔丄儕僶僀僶儖忋塮偱乽彎偩傜偗偺塰岝乿乮56擭乯傪尒偨丅僯儏乕儅儞偼偙偺塮夋偱丄晄椙彮擭偐傜儃僋僔儞僌偺悽奅僠儍儞僺僆儞偵側偭偨儘僢僉乕丒僌儔僔傾僲偲偄偆幚嵼偺恖暔偵暞偟丄惗偒惗偒偲墘偠偰偄偨丅嫟墘偺僺傾丒傾儞僕僃儕偺旤偟偝偵傕埑搢偝傟偨丅偙偺偙傠尒偨塮夋偱丄僿儈儞僌僂僃僀偺偄偔偮偐偺抁曇傪慻傒崌傢偣偨塮夋乽惵擭乿乮62擭乯偑偁偭偨丅庡墘偼儕僠儍乕僪丒儀僀儅乕偩偭偨偑丄僯儏乕儅儞偑丄傎傫偺堦応柺偵丄偄傑偱尵偆僇儊僆弌墘偟偰偄偨丅僷儞僠僪儔儞僇乕偵側偭偨尦儃僋僔儞僌慖庤傪墘偠偰丄嫮楏側懚嵼姶傪曻偭偰偄偨丅摉帪偺僯儏乕儅儞偺塮夋偵偼丄傎偐偵僔儕傾僗側尰戙斉惣晹寑乽僴僢僪乿乮62擭乯丄僲乕儀儖徿庼徿幃傪晳戜偵偟偨僗僷僀傕偺乽媡揮乿乮63擭乯丄崟郪柧偺乽梾惗栧乿傪東埬偟偨乽朶峴乿乮63擭乯側偳偑偁偭偨偑丄偳傟偵偍偄偰傕斵偼丄偄偐偵傕忋傝挷巕偺僗僞乕傜偟偄丄怴慛側婸偒丄惗乆偟偄敆椡傪敪嶶偟偰偄偨丅僀僗儔僄儖偺寶崙愴憟傪戣嵽偵偟偨戝嶌乽塰岝傊偺扙弌乿乮60擭乯偱偺僯儏乕儅儞偼丄塮夋偲偟偰傕嶶枱偱丄偁傑傝嫮偄報徾偑側偐偭偨偗傟偳丅
億乕儖丒僯儏乕儅儞偼50擭戙偵搊応偟偨丄愴屻悽戙偺怴偟偄僞僀僾偺塮夋僗僞乕偩偭偨丅妛峑偱墘媄偺婎慴傪妛傫偩栶幰偱偁傝丄愴慜偺僴儕僂僢僪丒僗僞乕偲偼堦慄傪夋偟偰偄偨丅摉弶偼斀峈揑側庒幰傪墘偠傞偙偲偑懡偔丄偦偆偄偆堄枴偱偼丄偍側偠偙傠偵搊応偟偨儅乕儘儞丒僽儔儞僪傗僕僃乕儉僗丒僨傿乕儞偲傂偲偔偔傝偵偱偒傞丅幚嵺丄斵傜偼傒側僄儕傾丒僇僓儞傜偑憂愝偟偨傾僋僞乕僘丒僗僞僕僆偺弌恎偩丅偩偑丄僽儔儞僪傕僨傿乕儞傕僄儕傾丒僇僓儞偑娔撀偡傞嶌昳偵婲梡偝傟偰僗僞乕偵側偭偨偑丄僯儏乕儅儞偼堦搙傕僇僓儞偺娔撀嶌昳偵弌偰偄側偄丅慡恎偐傜傆偰傇偰偟偝傪偵偠傒弌偝偣傞僽儔儞僪丄偄偮傕漍偹偨傛偆側昞忣偺僨傿乕儞偵斾傋偰丄僗儅乕僩偱搒夛揑側僯儏乕儅儞偼丄偁傑傝屄惈揑偱側偄偲尒側偝傟偰偄偨偺偩傠偆丅愴慜偐傜偺塮夋僼傽儞偵傛傞偲丄傾僋僞乕僘丒僗僞僕僆偱妛傫偩怴偟偄悽戙偺攐桪偨偪偼丄愴慜偺僗僞乕偵斾傋偰墘媄偑廘偄偲偄偆丅偨偟偐偵丄斵傜偐傜傾儖丒僷僠乕僲丄僟僗僥傿儞丒儂僼儅儞丄僕儍僢僋丒僯僐儖僜儞偵偮側偑傞偙偺梴惉強弌恎偺攐桪偨偪偺丄乬僔僗僥儉乭傗乬儊僜僢僪乭偱杹偐傟偨払幰偡偓傞墘媄偼丄傢偞偲傜偟偝偑旲偵偮偔偲偒傕偁傞丅
挬擔怴暦偵偼僯儏乕儅儞偺巰朣婰帠偑戝偒偔嵹偭偰偄偨偑丄偙傟傪彂偄偨婰幰偼偁傑傝斵偺塮夋傪尒偰偄側偄偵堘偄側偄丅偍偦傜偔帒椏傪挷傋偰傑偲傔偨偩偗偩傠偆丅偦偙偵偼乽亀柧擔偵岦偭偰寕偰亁傗亀僞儚乕儕儞僌丒僀儞僼僃儖僲亁偱抦傜傟傞億乕儖丒僯儏乕儅儞丒丒丒乿偲彂偐傟偰偄傞丅偨偟偐偵偙偺2嶌偼嫽峴揑偵僸僢僩偟偨偑丄攐桪偲偟偰偺斵傪偙偺2嶌偱戙昞偝傟偰偼丄僼傽儞偲偟偰偼偦傟偼側偄偩傠偆偲尵偄偨偔側傞丅偍傑偗偵丄偄偔偮偐楍嫇偝傟偰偄傞弌墘塮夋偺側偐偵丄廳梫側傕偺偑敳偗偰偄傞丅巹棫扵掋儖乕丒僴乕僷乕傪墘偠偨乽摦偔昗揑乿乽怴丒摦偔昗揑乿偑擖偭偰偄側偄偟丄斵偑嵟崅偺墘媄傪帵偟偨乽朶椡扙崠乿傕擖偭偰偄側偄丅
乽摦偔昗揑乿乮66擭乯偼儘僗丒儅僋僪僫儖僪尨嶌偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢偺塮夋壔偩丅朻摢偵丄挬丄帺暘偺傾僷乕僩偱婲偒偨扵掋偑丄怮傏偗婄偱僐乕僸乕傪煿傟傛偆偲偟偰暡偑愗傟偰偄傞偺偵婥偑偮偒丄婄傪偟偐傔側偑傜慜擔偵巊偭偰幪偰偨僼傿儖僞乕傪孄擖傟偐傜庢傝弌偟丄僐乕僸乕傪煿傟傞偲偄偆丄報徾揑側僔乕儞偑偁傞丅乽朶椡扙崠乿乮67擭乯偱偺億乕儖丒僯儏乕儅儞偼慺惏傜偟偐偭偨丅嵄嵶側偙偲偱搳崠偝傟丄嫺惓楯摥僉儍儞僾偵憲傜傟偨庒幰偑丄娕庣偨偪偺埑惌偵斀峈偟丄帺桼傪媮傔偰壗搙幐攕偟偰傕扙崠傪孞傝曉偡丅僯儏乕儅儞偺杮椞偑姰帏偵敪婗偝傟偰偄偨丅80擭戙埲崀偱偼丄壗偲尵偭偰傕乽昡寛乿乮82擭乯偱偺熡恎偺墘媄偑嵟崅偩偭偨丅怱偵彎傪晧偭偨丄庰傃偨傝偺偟偑側偄曎岇巑偑丄戝昦堾偺堛椕儈僗偺崘慽傪堷偒庴偗丄堦棳曎岇巑帠柋強偺僄儕乕僩偲愴偆偆偪偵帺暘傪庢傝栠偟丄埆鐓側旑鎺傗棤愗傝偵憳偄側偑傜昁巰偺愴偄傪偡傞偲偄偆丄崪懢偺椡嫮偄塮夋偩丅彈偐傜偐偐偭偨揹榖偺儀儖偑柭傝懕偗傞側偐丄斵偑傂偲傝暔巚偄偵捑傓儔僗僩丒僔乕儞偑朰傟傜傟側偄丅斢擭偺乽儘乕僪丒僩僁丒僷乕僨傿僔儑儞乿乮2002擭乯偱墘偠偨丄榁偄偨僊儍儞僌偺恊嬍傕尒帠偩偭偨丅
杮棃側傜丄億乕儖丒僯儏乕儅儞偼乽朶椡扙崠乿偐乽昡寛乿偱傾僇僨儈乕庡墘抝桪徿傪妉傞傋偒偩偭偨丅偗傟偳傕斵偼壗搙傕僲儈僱乕僩偝傟側偑傜丄偢偭偲僆僗僇乕偵偼柍墢側傑傑偩偭偨丅傗偭偲乽僴僗儔乕2乿(86擭)偱庴徿偟偨偑丄偙傫側杴嶌偱庴徿偝偣偨偔側偐偭偨丅傾僇僨儈乕徿側傫偰丄偙傫側傕偺偩丅僯儏乕儅儞偑傾僇僨儈乕偺夛堳偐傜寵傢傟偨偺偼丄斵偑栶暱偩偗偱側偔丄幚惗妶偱傕僴儕僂僢僪偺塮夋幮夛偵撻愼傑偢丄岞柉尃傗斀愴偺偨傔偺妶摦傪傗偭偰偄偨偐傜側偺偩傠偆偐丅
偦偆偄偊偽丄崱擭4寧偵朣偔側偭偨僠儍乕儖僩儞丒僿僗僩儞偵娭偡傞怴暦偺巰朣婰帠傕丄偨偟偐乽亀墡偺榝惎亁偱桳柤側丒丒丒乿偲彂偐傟偰偄偨丅偄偔傜側傫偱傕丄乽儀儞丒僴乕乿傗乽廫夲乿傪偝偟偍偄偰乽墡偺榝惎乿偑恀偭愭偵偔傞傫偠傖丄僿僗僩儞偑壜垼偦偆偩丅僯儏乕儅儞偲僿僗僩儞偼丄偁傞堄枴偱懳徠揑側懚嵼偩偭偨丅僿僗僩儞偼懱惂偵弴墳偡傞曐庣攈偱偁傝丄僯儏乕儅儞偼懱惂偵恘岦偆恑曕攈偩偭偨丅偩偑2恖偲傕丄50擭戙埲崀偺傾儊儕僇塮夋傪巟偊偨執戝側僗僞乕偩偭偨偙偲偵曄傢傝偼側偄丅僿僗僩儞丄僯儏乕儅儞偺憡師偖巰嫀偵傛偭偰丄屆偒壚偒傾儊儕僇塮夋偼傑偡傑偡墦偔側偭偨丅
2008.09.19 (嬥) 怱庝偐傟傞僋儔僂僗丒僆僈乕儅儞偺僯儏乕丒傾儖僶儉
僋儔僂僗丒僆僈乕儅儞偑慡柺揑偵傾儗儞僕傪庤偑偗偨怴嶌偑敪攧偝傟偨丅僺傾僯僗僩偺僟僯乕儘丒儁儗僗傪僼傿乕僠儍乕偟偨傾儖僶儉亀傾僋儘僗丒僓丒僋儕僗僞儖丒僔乕亁乮Universal乯偩丅儓乕儘僢僷揑側旤堄幆偲儔僥儞偺姶妎偑崿慠堦懱偵側偭偨僒僂儞僪偵巇忋偑偭偰偍傝丄儔僥儞摿桳偺垼姶偑丄忣姶夁懡偵側傜偢丄僋乕儖側姶妎偱昞尰偝傟偰偄傞丅偨偲偊偰尵偆側傜丄墛偑丄恀偭愒側壩壴傪弌偡偺偱偼側偔丄惵敀偔梔偟偄岝傪敪偟側偑傜擱偊惙偭偰偄傞姶偠偩丅尒偨栚偼椻偨偄偑怗傞偲擬偄丅媣偟傇傝偵丄僆僈乕儅儞撈摿偺慇嵶側旤偟偝偑墶堨偟偨僗僩儕儞僌僗偺嬁偒偵偨偭傉傝怹傞偙偲偑偱偒偨丅嵟嬤偺壒妝偵偁傑傝恊偟傫偱偄側偄僕儍僘丒僼傽儞偺側偐偵偼丄僆僈乕儅儞偑傑偩尰栶偺僐儞億乕僓乕仌傾儗儞僕儍乕偱偄傞偙偲偵嬃偔恖偑偄傞偐傕偟傟側偄丅偩偑斵偼70嵨傪挻偊偨嬤擭偵側偭偰傕寬嵼偱偁傞丅2001擭偵偼僟僀傾僫丒僋儔乕儖偺傾儖僶儉亀僓丒儖僢僋丒僆僽丒儔償亁偵廏堩側傾儗儞僕傪採嫙偟偨偟丄1990擭戙弶傔偵偼儅僀働儖丒僽儗僢僇乕傪僼傿乕僠儍乕偟偨亀僔僥傿僗働僀僾亁偺懕曇揑側傾儖僶儉傪敪昞偟偰偍傝丄悢偼彮側偔側偭偨偲偼尵偊丄偄傑傕廩幚偟偨嶌昳傪偮偔偭偰偄傞丅
偟偐偟僆僈乕儅儞偲偄偊偽丄壗偲尵偭偰傕1960擭戙偵僋儕乕僪丒僥僀儔乕偺僾儘僨儏乕僗偺傕偲丄傾儞僩僯僆丒僇儖儘僗丒僕儑價儞丄價儖丒僄償傽儞僗丄傾僗僩儔僢僪丒僕儖儀儖僩丄僂僃僗丒儌儞僑儊儕乕丄僗僞儞丒僎僢僣丄僂傿儞僩儞丒働儕乕側偳偵傛傞償傽乕償傗A&M傊偺僀乕僕乕丒儕僗僯儞僌丒僕儍僘偺儗僐乕僨傿儞僌偱丄傾儗儞僕儍乕偲偟偰妶桇偟偰偄偨偲偒偺報徾偑嫮偄丅摉帪丄傗偼傝僋儕乕僪丒僥僀儔乕偑婲梡偟偰媟岝傪梺傃偨傾儗儞僕儍乕偵僪儞丒僙儀僗僉乕偑偄傞丅僆僈乕儅儞偼僙儀僗僉乕偲斾傋傞偲抧枴側懚嵼偩偭偨偑丄傏偔偼僆僈乕儅儞偺傾儗儞僕偑戝岲偒偩偭偨丅僙儀僗僉乕偺攈庤側傾儗儞僕偲偼堘偄丄僆僈乕儅儞偺僒僂儞僪偼偁傑傝栚棫偨側偄丅偩偑丄偦偺僋乕儖偱愻楙偝傟偨姶妎偼丄僕儍僘偺揱摑偲偼堎幙側傕偺偑偁傝丄偲偰傕怴慛偵挳偙偊偨丅斵偼僪僀僣恖偱偁傝丄嶌晽偺攚宨偵偼儓乕儘僢僷嬤戙壒妝偺搚忞偑偁偭偨丅僼傿乕僠儍乕偡傞傾乕僥傿僗僩偺壧傗墘憈傪嵟戝尷偵妶偐偟偨丄弌偟傖偽傜側偄傾儗儞僕丄昳奿偺偁傞僨儕働乕僩側尫偺嬁偒偼丄堦挳偟偰偡偖偵僆僈乕儅儞偩偲幆暿偱偒偨丅
偙偺偙傠偺傾儖僶儉偱偼丄堦斒揑偵偼1967擭偺僕儑價儞偺傾儖僶儉亀僂僃僀償亁偵巤偟偨傾儗儞僕偑昡壙偑崅偄丅傏偔偼僂傿儞僩儞丒働儕乕偺亀僇儈儞丒僀儞丒僓丒僶僢僋丒僪傾亁偲偄偆傾儖僶儉偑岲偒偩丅偙傟偼僕儍僘揑側梫慺偼婓敄偩偑丄儊儘僨傿傪斾妑揑僗僩儗乕僩偵丄偩偑撈摿偺旘傃挼偹傞傛偆側僞僢僠偱抏偔働儕乕偺僺傾僲偵丄偲偙傠偳偙傠偵偆偭偡傜偲偐傇偝傞棳楉側僗僩儕儞僌僗偺嬁偒偵偧偔偧偔偝偣傜傟傞丅巆擮側偺偼廂榐嬋偑偡傋偰3暘慜屻偲偄偆抁偝偱廔傢偭偰偄傞偙偲偩丅摨條偺峴偒曽偺傾儖僶儉偵丄價儖丒僄償傽儞僗偺亀V.I.P.偺僥乕儅亁偑偁傞丅價儖丒僄償傽儞僗偲偼丄偦偺屻2枃偺傾儖僶儉偱嫟墘偟偰偄傞偑丄偦偺側偐偱偼丄敪攧摉帪昡敾偼椙偔側偐偭偨偑丄亀僂傿僘丒僔儞僼僅僯乕丒僆乕働僗僩儔亁偑偄偄丅偙偺僒僂儞僪偼丄崱夞偺僟僯乕儘丒儁儗僗偲慻傫偩怴嶌亀傾僋儘僗丒僓丒僋儕僗僞儖丒僔乕亁傪巚傢偣傞傕偺偑偁傞丅
偦偺屻僆僈乕儅儞偼丄70擭戙敿偽偛傠偐傜丄僾儘僨儏乕僒乕偺僩儈乕丒儕僺儏乕儅偵廳梡偝傟丄僼儏乕僕儑儞傗AOR偺儗僐乕僨傿儞僌偱堎嵥傪敪婗偡傞傛偆偵側偭偨丅僕儑乕僕丒儀儞僜儞偺亀僽儕乕僕儞亁丄儅僀働儖丒僼儔儞僋僗偺亀僗儕乕僺儞僌丒僕僾僔乕亁丄僕儑傾儞丒僕儖儀儖僩偺亀傾儌儘乕僝亁偲偄偭偨傾儖僶儉偑偦傟偩丅儀儞僜儞傗僼儔儞僋僗偺傾儖僶儉偺惉岟偼丄僆僈乕儅儞偺惛鉱傪嬌傔偨傾儗儞僕敳偒偵偼峫偊傜傟側偄丅僆僈乕儅儞偼亀僂僃僀償亁偺僸僢僩埲棃丄僕儑價儞偲偟偽偟偽僐儞價傪慻傓傛偆偵側傝丄悢枃偺僐儔儃儗乕僔儑儞丒傾儖僶儉傪嶌偭偨偑丄僆僈乕儅儞偺娭楢偟偨儃僒僲償傽丒傾儖僶儉偱尵偊偽丄傏偔偼僕儑價儞偲偺彅嶌偱偺懡嵤側傾儗儞僕傛傝傕丄僕儑傾儞丒僕儖儀儖僩偺亀傾儌儘乕僝亁偺僔儞僾儖側僒僂儞僪偺傎偆偵垽拝傪姶偠傞丅僟僀傾僫丒僋儔乕儖偑亀僓丒儖僢僋丒僆僽丒儔償亁偺側偐偱乹僗儚儞僟僼儖乺傪丄僆儕僕僫儖丒儊儘僨傿傪柍帇偟偰僕儖儀儖僩偦偭偔傝偵壧偭偰偄傞偑丄偙傟偼斵彈偺偙偺傾儖僶儉傊偺僆儅乕僕儏偺昞傟偱偁傠偆丅
僆僈乕儅儞偺僋儔僔僢僋嬤戙壒妝偺帒幙偼丄儗僐乕僪夛幮偐傜榞傪偼傔傜傟偢丄帺桼側傾儗儞僕傪擟偝傟偨応崌偵丄偼偭偒傝帵偝傟偰偄傞丅價儖丒僄償傽儞僗偲偺亀僔儞僶僀僆僔僗亁偑偦偆偩偟丄儔儞僨傿丒僽儗僢僇乕傪僼傿乕僠儍乕偟偨亀僔僥傿僗働僀僾亁偑偦偆偩丅斵偼儕乕僟乕偲偟偰弮悎偵僋儔僔僢僋壒妝偵揙偟偨傾儖僶儉傕敪昞偟偰偄傞丅斵偑扨撈偺儕乕僟乕偲側偭偰儗僐乕僨傿儞僌偟偨僕儍僘揑側嶌昳偲偟偰亀柌偺憢曈偵亁偑偁傞偑丄偙偺偁偨傝偵側傞偲丄妝棟偵徻偟偄恖傗幚墘壠偵偲偭偰偼嫽枴怺偄偐傕偟傟側偄偑丄堦斒揑側僕儍僘丒僼傽儞偐傜偡傞偲丄偪傚偭偲崅摜揑偡偓偰偮偄偰偄偗側偄姶偠偑偡傞丅
僆僈乕儅儞偼偙偆偄偭偨僕儍僘傗僼儏乕僕儑儞傗儃僒僲償傽偺僼傿乕儖僪偲摨帪偵丄億僢僾僗偺悽奅偱傕幚愌傪巆偟偰偍傝丄僔僫僩儔丄僒儈乕丒僨僀償傿僗丄僶乕僽儔丒僗僩儔僀僒儞僪偲偄偭偨償僅乕僇儕僗僩丄儀儞丒俤丒僉儞僌傗僪儕僼僞乕僘偺傛偆側R&B僔儞僈乕丄僐僯乕丒僼儔儞僔僗傗儅僢僩丒儌儞儘乕側偳偺僸僢僩嬋壧庤側偳丄偝傑偞傑側儗僐乕僨傿儞僌偱傾儗儞僕儍乕偲偟偰婲梡偝傟偰偒偨丅崱夞丄僱僢僩偱挷傋偰弶傔偰抦偭偨偑丄60擭戙弶傔偵梞妝偺僸僢僩丒僷儗乕僪傪偵偓傢偟偨儗僗儕乕丒僑乕傾偺乹椳偺僶乕僗僨僀丒僷乕僥傿乺傗乹楒偲椳偺17嵥乺偲偄偭偨僸僢僩嬋偑丄僆僈乕儅儞偺傾儗儞僕偵傛傞傕偺偩偭偨丅僋僀儞僔乕丒僕儑乕儞僘偑僾儘僨儏乕僗偟偨偙偲偼抦偭偰偄偨偑丄幚嵺偵僒僂儞僪傪嶌偭偨偺偑僆僈乕儅儞偩偲偼抦傜側偐偭偨丅僆僈乕儅儞偼傎傫偲偆偺堄枴偱偺壒妝偺怑恖側偺偩偲夵傔偰捝姶偟偨丅
2008.09.04 (栘) 擔杮傪晳戜偵偟偨僴儞僞乕偺怴嶌偵偑偭偔傝
偟偽傜偔巇帠偑朲偟偔丄扨峴杮偺東栿偺掲愗偵捛傢傟偰壗傕偱偒側偄忬懺偩偭偨偑丄傗偭偲堦抜棊偮偄偨偺偱丄偙偺僐儔儉傪嵞奐偡傞偙偲偵偡傞丅壗傕偱偒側偄偲偼偄偭偰傕丄彮偟偼杮傪撉傫偱偄偨丅憡曄傢傜偢奀奜儈僗僥儕乕偼晄嶌偱丄僴僢偲偝偣傜傟傞傛偆側傕偺偼側偄丅媡偵婜懸偼偢傟偱偑偭偐傝偝偣傜傟傞傕偺偑懡偄丅嬞敆偟偨僗僩乕儕乕偲堄昞傪撍偔揥奐偑慺惏傜偟偐偭偨乽僔儞僾儖丒僾儔儞乿偱僨價儏乕偟偨僗僐僢僩丒僗儈僗偺10悢擭傇傝偺戞2嶌乽儖僀儞僘乣攑毿偺墱傊乿乮晑孠幮儈僗僥儕乕乯偼丄偲偔偵傂偳偐偭偨丅儊僉僔僐偺旈嫬傪晳戜偵偟偨堦庬偺儂儔乕彫愢偩偑丄儊僉僔僐偲偄偆搚抧偺昤幨偵儕傾儕僥傿偑側偄偟丄搊応恖暔偨偪偺峴摦傕愢摼椡偑側偄丅忋壓2姫偺偆偪丄忋姫偺敿偽偐傜丄斵傜偑廝傢傟傞壔偗暔僣僞惈怉暔偺嫲晐偑丄偊傫偊傫偲昤偐傟傞丅壗偐柺敀偄揥奐偑偁傞偩傠偆偲巚偭偰変枬偟偰撉傫偱偄偨偑丄嵟屻傑偱壗傕婲偙傜側偄丅傑偭偨偔偺懯嶌偩丅偙傟偑抁曇偩偭偨傜丄傕偭偲堷偒掲傑偭偨儂儔乕彫愢偵側偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅
偙傟傎偳傂偳偔偼側偄偵偣傛丄僗僥傿乕償儞丒僴儞僞乕偺怴嶌乽47斣栚偺抝乿乮晑孠幮儈僗僥儕乕乯傕庱傪偐偟偘偞傞傪偊側偄撪梕偩偭偨丅媣偟傇傝偵乽嬌戝幩掱乿偺儃僽丒儕乕丒僗儚僈乕傪庡恖岞偵悩偊偨彫愢偱偁傝丄婜懸偵嫻偑崅傑偭偨偺傕偮偐偺傑丄擔杮偑晳戜偩偲抦偭偰寵側梊姶偑偟偨丅偦偺梊姶偑尰幚偵側偭偨丅弌偩偟偼夣挷偱丄儃僽丒儕乕偺晝傾乕儖偺丄懢暯梞愴憟枛婜丄棸墿搰偱偺愴摤偑昤偐傟傞丅偙偺偁偨傝偼丄僋儕儞僩丒僀乕僗僩僂僢僪偺塮夋乽棸墿搰偐傜偺庤巻乿傪巚傢偣丄擔杮偺孯恖傗暫巑傕柤梍偲愑擟傪廳傫偠傞棫攈側恖娫偲偟偰昤偐傟偰偄傞丅傾乕儖偑棸墿搰偐傜帩偪婣偭偨擔杮搧偵傑偮傢傞榖偑偙偺彫愢傪娧偔僥乕儅偵側傞丅傾乕儖偑朣偔側偭偨尰嵼丄懅巕偺儃僽丒儕乕偑偦偺搧傪扵偟弌偟丄搧偺帩偪庡偺堚懓偵撏偗傞偨傔擔杮偵傗偭偰棃傞丅偙偙傑偱偼偄偄偑丄偦偙偐傜榖偼尰幚偽側傟偟偰偔傞丅戣柤偐傜憐憸偝傟傞偲偍傝丄偙偺彫愢偼乽拤恇憼乿偑傕偆傂偲偮偺僥乕儅偵側偭偰偄傞丅偦傟偼偄偄偲偟偰傕丄側傫偲偁偺幩寕偺柤庤儃僽丒儕乕偑丄暅廞偺偨傔丄擔杮偱寱摴傪廗偄丄擔杮搧傪庤偵偟偰埆幰傪巃傝傑偔傞偺偩丅慡懱偺4暘偺3丄擔杮偱偺儃僽丒儕乕偺峴摦偲丄擔杮偺棤幮夛傪媿帹傞埆偺恊嬍傪昤偔僗僩乕儕乕偼丄偁傑傝偵峳搨柍宮偱丄傑傞偱寑夋偩丅嵟屻偺惔悷掚墍偱偺搧偵傛傞寛摤偼丄僞儔儞僥傿乕僲偺塮夋乽僉儖丒價儖乿偺傛偆偩丅
僗僥傿乕償儞丒僴儞僞乕偑彂偒捲偭偰偒偨乬僗儚僈乕丒僒乕僈乭偼丄側傫偲尵偭偰傕丄乽嬌戝幩掱乿乽僟乕僥傿丒儂儚僀僩丒儃乕僀僘乿乽僽儔僢僋儔僀僩乿偲偄偭偨弶婜偺嶌昳偑嵟崅偩偭偨丅僴儞僞乕偼丄尦奀暫戉堳偺揤嵥僗僫僀僷乕丄儃僽丒儕乕丒僗儚僈乕傪庡恖岞偲偟偨3晹嶌偺偁偲丄儃僽丒儕乕偺晝恊偺傾乕儖丒僗儚僈乕傪庡恖岞偵偟偨僔儕乕僘傪彂偄偨丅乬儃僽丒儕乕丒僗儚僈乕3晹嶌乭偺庤偵娋埇傞嬞敆姶丄帺暘傕捛傢傟側偑傜憡庤傪捛偄偐偗傞儃僽丒儕乕傪昤偔丄偒傃偒傃偟偨僗僩乕儕乕揥奐偵斾傋傞偲丄乬傾乕儖丒僗儚僈乕丒僔儕乕僘乭偼丄愨懳揑側埆傪戅帯偡傞偲偄偆丄傾儊儕僇揑側暯斅側僐儞僙僾僩丄峳偭傐偄嬝棫偰偑栚偵偮偄偨偑丄偦傟偱傕僗僩乕儕乕僥儕儞僌偺嶀偊偼敳孮偱丄廩暘偵妝偟傓偙偲偑偱偒偨丅偙傫偳偺乽47斣栚偺抝乿偼丄儃僽丒儕乕偑庡恖岞側偺偵丄嬝棫偰偼傾乕儖丒僗儚僈乕偺僔儕乕僘偵嬤偔丄偍傑偗偵捒柇偵昤偐傟傞擔杮偺暥壔傗幮夛偑攚宨偵側偭偰偍傝丄偄傑傑偱偺僴儞僞乕偺彫愢偺側偐偱偼丄撪梕偲偟偰偼偄偪偽傫棊偪傞丅僴儞僞乕傕僷儚乕偑悐偊偨偺偩傠偆偐丅偦傟偵偟偰傕丄傾儊儕僇偺嶌壠傗塮夋娔撀偑擔杮傪昤偔偲丄偳偆偟偰偙傫側偵尰幚枴偺側偄丄巻幣嫃偺傛偆側傕偺偵側偭偰偟傑偆偺偩傠偆丅儈僗僥儕乕彫愢偺側偐偱丄擔杮傪儕傾儕僥傿傪傕偭偰愢摼椡朙偐偵昤偄偨傕偺偲偄偊偽丄僩儗償僃僯傾儞偺乽僔僽儈乿偩偗偟偐側偄丅擔杮傪晳戜傗僥乕儅偵偟偨傾儊儕僇塮夋偩偲丄傑偲傕偵尒傜傟傞偺偼儕僪儕乕丒僗僐僢僩娔撀偺乽僽儔僢僋丒儗僀儞乿偖傜偄偐丅
婥傪庢傝捈偟偰丄攦偭偨傑傑偱傑偩撉傫偱偄側偄僄儖儌傾丒儗僫乕僪偺乽儂僢僩丒僉僢僪乿丄儕儞僌僼傿乕儖僪偺僼儘僗僩寈晹僔儕乕僘偺懸朷媣偟偄怴嶌乽僼儘僗僩婥幙乿偵丄偙傟偐傜偲傝偐偐傞丅偙偺2嶌偼丄偍偦傜偔婜懸偟偰娫堘偄側偄偩傠偆丅
2008.08.01 (嬥) 僿儗儞丒儈傾乕僘乽傾儊儕僇偺嬀丒擔杮乿偑夝偒柧偐偡恀幚
傾儊儕僇偑杒挬慛傊偺乽僥儘巟墖崙壠巜掕乿偺夝彍傪寛掕偟丄擔杮偼漟抳栤戣偑夝寛偟側偄偆偪偵偦傫側帠懺偵側偭偨偺偱偁傢偰偰偄傞丅妀傪柍椡壔偟偨偲偄偆徹嫆傕傠偔偵側偄偺偵偦偆偡傞偺偼丄僽僢僔儏偑戝摑椞偺擟婜愗傟慜偵幚愌傪巆偟偨偄偐傜偩丅傕偟擔杮偺惌晎傗奜柋徣偑丄傾儊儕僇偼擔杮偲偺摨柨娭學偵傂傃傪擖傟傞傛偆側偙偲偼偟側偄偲峫偊偰偄偨偲偟偨傜丄媬偄偑偨偄嬸偐幰偧傠偄偩丅傾儊儕僇偼杮惈傪業掓偟偨丅岥愭偱偼娒偄偙偲傪尵偭偰偄偰傕丄傾儊儕僇偑擔杮偺偙偲側偳恀寱偵峫椂偟偰偔傟傞傢偗偑側偄丅攅尃崙壠傾儊儕僇偵偲偭偰丄擔杮偼懏崙偱偁傝丄庤愭偱偁傝丄壗偱傕尵偆偙偲偒偐偣丄偄偞偲側偭偨傜愗傝幪偰傞崙偩丅僐僀僘儈偑丄偦傫側擔暷娭學傪偄偭偦偆彆挿偟偨丅傾儊儕僇偺媆嵩偼偄傑偵巒傑偭偨偙偲偱偼側偄丄愴慜偐傜懕偄偰偄傞丅擔杮偼偦傟偵傛偭偰愴憟傪婲偙偟丄尨敋傪搳壓偝傟丄攕愴偟偰愯椞偝傟偨丅偦偺傾儊儕僇偺媆嵩惈傪崕柧偵偮偯偭偨杮傪撉傫偩丅僿儗儞丒儈傾乕僘偺彂偄偨乽傾儊儕僇偺嬀丒擔杮乿偲偄偆杮偩丅傏偔偼偙偺挊幰偺柤慜傕杮偺偙偲傕抦傜側偐偭偨丅偙傟傪抦偭偨偺偼丄揑妋側巜揈丄柧夣側榑巪偱丄偄偮傕嫵偊傜傟傞偙偲偺懡偄揤栘捈恖偝傫偺僒僀僩偵傛偭偰偩偭偨丅
僿儗儞丒儈傾乕僘偼傾儊儕僇偺彈惈楌巎妛幰偱丄擔暷奐愴慜偵2搙偵傢偨偭偰朘擔偟偰擔杮偺楌巎傗暥壔傪尋媶偟丄擔杮丒傾僕傾偵娭偡傞愱栧壠偲偟偰傾儊儕僇偺戝妛偱嫵偊偰偄偨丅愴屻偺1946擭丄GHQ偺帎栤婡娭偱偁傞楯摥惌嶔埾堳夛偺儊儞僶乕偲偟偰棃擔丄擔杮偺楯摥婎杮朄偺嶔掕偵実傢偭偨丅傾儊儕僇偵婣崙屻偺1948擭偵偙偺杮傪弌斉偟偨偑丄堦晹偱拲栚偝傟偨傕偺偺丄擔杮傪梚岇偟丄傾儊儕僇傪媻抏偡傞撪梕偩偭偨偨傔栙嶦偝傟偨丅斵彈偼偦偺屻丄晄嬾傪梋媀側偔偝傟丄傗偑偰偦偺柤偼朰傟嫀傜傟偨丅擔杮偱偼尨挊弌斉屻傑傕側偔丄東栿弌斉偑婇夋偝傟偨偑丄儅僢僇乕僒乕偼弌斉傪嬛偠偨丅愯椞偑廔傢偭偨1951擭偵傛偆傗偔乽傾儊儕僇偺斀徣乿偲戣偟偰弌斉偝傟偨偑丄摉帪偼傑偭偨偔榖戣偵側傜側偐偭偨丅偦偺屻1995擭偵傾僀僱僢僋僗偲偄偆弌斉幮偐傜埳摗墑巌偺怴栿偱敪攧偝傟偨丅傏偔偑撉傫偩偺偼2005擭偵妏愳彂揦偐傜弌斉偝傟偨丄偦偺暅崗斉偱偁傞丅
偙偺杮偱儈傾乕僘偺庡挘偺崻杮偵偁傞偺偼丄乽擔杮偼惣墷偵妛傫偩偙偲傪拤幚偵幚峴偟偨偵偡偓側偄丅擔杮偺峴堊傪斸敾偡傞傑偊偵丄偦偺傕偲偵側偭偨惣墷暥柧傪斸敾偟側偔偰偼側傜側偄乿偲偄偆峫偊曽偩丅僞僀僩儖偵偁傞乽嬀乿偼丄乽擔杮偼惣墷楍嫮亖傾儊儕僇偑惗傒弌偟偨嬀偱偁傝丄偦偙偵偼惣墷帺恎偑幨偭偰偄傞乿偲偄偆堄枴偑崬傔傜傟偰偄傞丅偦偙偐傜斵彈偼丄擔暷偺奐愴偼擔杮傪愯椞偡傞偨傔偵傾儊儕僇偑巇妡偗偨傕偺偩偭偨偙偲丄尨敋傪搳壓偡傞昁梫偼側偐偭偨偙偲丄傾儊儕僇偼擔杮傪嵸偔傎偳岞惓偱傕寜敀偱傕側偄偙偲傪愢偒柧偐偡丅
斵彈偺榑巪偼乽擔杮偺杮摉偺嵾偼丄惣梞暥柧偺嫵偊傪庣傜側偐偭偨偙偲偱偼側偔丄傛偔庣偭偨偙偲側偺偩乿偲偄偆堦暥偵昞傟偰偄傞丅斵彈偼乽巹偨偪偼傾儊儕僇偐傜懡偔偺偙偲丄偲偔偵椬愙抧堟偺晄埨掕惌尃偲偳偺傛偆偵懳張偡傞偐傪妛傫偱偒偨丅偦偟偰妛傫偩偙偲傪幚峴偡傞偲丄愭惗偐傜尩偟偔幎傜傟傞偺偱偁傞乿偲偄偆丄怴搉屗堫憿偑1932擭偵傾儊儕僇偱峴偭偨島墘偵嵺偡傞尵梩傪堷梡偡傞丅乽柧帯堐怴埲屻丄擔杮偵偼2偮偺慖戰巿偟偐側偐偭偨丅傂偲偮偼岺嬈宱嵪偵堏峴偟丄孯旛傪妋棫偟丄墷暷偲偺椡偺嬒峵偺傕偲偵撈棫崙壠偲偟偰惗偒偰偄偔摴丄傕偆傂偲偮偼拞崙偺傛偆側敿怉柉抧崙壠丄傑偨偼墷暷偺偳偙偐偺崙偺怉柉抧偵側傞摴偱偁傞丒丒丒枮廈帠曄偵帄傞傑偱偺擔杮偺峴堊偼丄墷暷柉庡庡媊彅崙偑偮偔偭偨崙嵺朄偱嫋偝傟偰偄偨丅偦傟偑嵾偩偲偡傞側傜丄僀僊儕僗偼嫟斊偱偁傝丄傾儊儕僇偼廬斊偱偁傞丅枮廈帠曄偼偨偟偐偵桳嵾偩丅偟偐偟丄拞崙偵尵傢偣傟偽丄墷暷楍嫮傕擔杮偲摨偠偔傜偄嵾偑廳偄乿
斵彈偼丄僷乕儖丒僴乕僶乕偼惵揤偺杵杼偱偼側偐偭偨丄傾儊儕僇惌晎偼奐愴偑敆偭偰偄傞偙偲傪梊婜偟偰偄偨丄偄傗丄傓偟傠宱嵪晻嵔偵傛偭偰捛偄媗傔丄乽嵟屻捠崘乿傪撍偒晅偗傞偙偲偵傛偭偰丄堄恾揑偵偦偆偟傓偗偨偺偩偲愢偔丅偙偆偟偰乽儕儊儞僶乕丒僷乕儖丒僴乕僶乕乿傪崌尵梩偵丄傾儊儕僇偼擔杮傊偺憺埆偲嫲晐傪怉偊晅偗偨偺偩偲偄偆偙偲傪丄斵彈偼朶偒弌偡丅
1945擭弔偛傠偐傜丄擔杮偼偝傑偞傑側偐偨偪偱傾儊儕僇偵崀暁傪懪恌偟偰偄偨偑丄傾儊儕僇惌晎偼偙偲偛偲偔柍帇傑偨偼嫅斲偟偨丅億僣僟儉愰尵傪庴偗傞偐斲偐傪敆偭偰丄傢偢偐11擔屻偵峀搰偵尨敋傪搳壓偟偨丅尨敋偼億僣僟儉愰尵庴戻傪憗傔偨偩偗偩偭偨丅偦偺偨傔偵傾儊儕僇偼21枩恖偺巗柉傪嶦偟偨丅偦傟傪惓摉壔偡傞偨傔丄傾儊儕僇惌晎偼摉帪偺擔杮偺椡傪堄恾揑偵夁戝偵昡壙偟偨丅偟偐偟幚懱偼丄儅僢僇乕僒乕偑乽巎忋偙傟傎偳恦懍丄墌妸偵晲憰夝彍偑峴傢傟偨椺偼側偄乿偲尵偭偨傎偳丄擔杮偵偼壗傕巆偭偰偄側偐偭偨丅愴摤偺嫸婥偲嫲晐偱嶖棎偟偰偄偨愨懱愨柦偺忬嫷壓丄擔杮孯偑僼傿儕僺儞偱2000恖偺旕愴摤堳傪嶦奞偟偨愑擟傪栤傢傟丄嶳壓彨孯偑抐嵾偝傟偨丅偟偐偟丄偦傟偲丄帠幚忋偡偱偵晧偗偰偄偨崙偵怴宆敋抏傪搳壓偟丄偨偭偨1昩偱14枩恖偺旕愴摤堳傪嶦偡偙偲偲丄偳偪傜偺嵾偑廳偄偺偐丄偲斵彈偼栤偄偐偗傞丅
偝傜偵斵彈偼丄愴憟拞偐傜愴屻偵偐偗偰寲揱偝傟偨擔杮柉懓偺怤棯惈傗岲愴惈偼丄偮偔傜傟偨嫼埿偩偭偨偲愢偔丅擔杮偺楌巎丄暥壔丄揱摑傪偙偲嵶偐偵愢柧偟丄悽奅拞偵怉柉抧傪偮偔偭偰偄偨墷暷楍嫮偲斾傋偰丄擔杮偑偄偐偵楌巎揑奼挘庡媊偐傜傎偳墦偐偭偨偐丄偦傫側擔杮偑側偤傾儊儕僇偵愴憟傪巇妡偗傞偵帄偭偨偐傪丄偒傢傔偰愢摼椡偵晉傓昅抳偱榑偢傞丅
傏偔偺抦傝崌偄偵擔暷偺僴乕僼偺傾儊儕僇恖偑偄傞丅傕偆偐側傝埲慜偺偙偲偩偑丄堸傒側偑傜榖傪偟偨偍傝丄榖戣偑懢暯梞愴憟偵側偭偨丅傏偔偑乽傾儊儕僇惌晎偼埫崋傪夝撉偡傞偙偲偵傛傝丄擔杮偑奐愴偡傞偙偲傪抦偭偰偄偨偑丄崙柉偺擔杮憺偟偺堄幆傪忴惉偡傞偨傔偵丄偁偊偰愭偵峌寕偝偣偨乿偲榖偟丄偝傜偵乽尨敋偱偁傫側偵堦斒巗柉傪嶦偡昁梫偼側偐偭偨丅擔杮偼偡偱偵晧偗偰偄偨傫偩乿偲尵偭偨丅偡傞偲斵偼乽偦傫側榖偼弶傔偰暦偄偨丅妛峑偱偼偦傫側傆偆偵偼嫵傢傜側偐偭偨丅愴憟傪憗偔廔傢傜偣丄恖柦傪媬偆偨傔偵尨敋傪巊偭偨偲暦偄偰偄偨丅偦傟偑傾儊儕僇偺偨傔偵傕側傞偟丄擔杮偺偨傔偵傕側傞偐傜傗偭偨偲偽偐傝巚偭偰偄偨乿偲岅偭偰偄偨丅偙偲傢偭偰偍偔偑丄偙偺傾儊儕僇恖偼曎岇巑偱丄偄偪偍偆僀儞僥儕偺晹椶偵懏偡傞丅傑偟偰傗丄傾儊儕僇偱惗傑傟堢偪塸岅偟偐榖偝側偄偲偼尵偊丄曣恊偑擔杮恖偩丅偦傫側恖娫偱傕丄棟夝偺掱搙偼偙傫側傕偺側偺偩丅
彑幰偑攕幰傪嵸偔搶嫗孯帠嵸敾傪怰棟拞偩偭偨1948擭丄偙偺傛偆側彑幰偺榑棟傪崻掙偐傜傂偭偔傝曉偡杮偑丄偳傫側塣柦傪偨偳偭偨偐偼憐憸偵偐偨偔側偄丅嫮幰偺棙塿偺偨傔偵庛幰偑東楳偝傟傞偺偑楌巎偺忢偩丅傾儊儕僇偲偄偆嫮幰偼丄偄傑偁傜備傞応柺偱帺崙偺棙塿傪傓偒弌偟偵偟丄悽奅偺奺抧傪骧鏦偟傛偆偲偟偰偄傞丅偦傫側帪戙偩偐傜偙偦丄傾儊儕僇偺媆嵩丄嫮幰偺閬傝傪60擭慜偵夝偒柧偐偟丄寈忇傪柭傜偟偨偙偺杮偼丄偄傑懡偔偵恖偵傛偭偰撉傑傟傞傋偒傕偺偩偲巚偆丅
2008.07.23 (悈) 9.11僥儘偼傾儊儕僇偺堿杁偩偭偨偺偐
2001擭9寧11擔偵婲偒偨傾儊儕僇摨帪懡敪僥儘帠審偼偄傑傕婰壇偵惗乆偟偄丅偙傟偼僆僒儅丒價儞丒儔僨傿儞棪偄傞傾儖僇僀僟偺斊峴偲偄偆偙偲偵偝傟偰偄傞偑丄偠偮偼傾儊儕僇惌晎偺堿杁丄帺嶌帺墘偩偭偨偲偄偆愢偑丄埲慜偐傜僱僢僩忋偱棳晍偟偰偄傞丅傏偔偼丄傾儊儕僇惌晎偑巇慻傫偩偙偲偐偳偆偐偼偲傕偐偔丄傾儊儕僇惌晎偑拞搶攈暫偺岥幚偵偡傞偨傔丄帠審傪僒億乕僩偟偨偐丄偁傞偄偼帠慜偵嶡抦偟側偑傜尒摝偟偰偄偨壜擻惈偼偁傞偲巚偭偰偄偨丅偩偑丄偙偺傎偳儀儞僕儍儈儞丒僼儖僼僅乕僪偑彂偄偨亀9.11僥儘漵憿乣擔杮偲悽奅傪閤偟懕偗傞撈嵸崙壠傾儊儕僇亁乮2006擭摽娫彂揦乯傪撉傓偵媦傫偱丄惌晎偺帺嶌帺墘傕偁傝偆傞偐傕偟傟側偄偲巚偆傛偆偵側偭偨丅挊幰偺僼儖僼僅乕僪偼尦僼僅乕僽僗帍偺傾僕傾懢暯梞巟嬊挿偩偭偨恖偱丄僥儗價偺摙榑斣慻側偳偵傕弌墘偟偰偍傝丄傏偔傕尒偨偙偲偑偁傞丅偙偺椶偄偺堿杁榑偼傎偲傫偳偑旣懥傕偺偱丄傑偲傕偵嵦傝忋偘傞偵抣偟側偄偑丄偙偺杮偼丄偁傑傝拋彉偩偭偰棟楬惍慠偲榑偠傜傟偄傞偲偼尵偄擄偄偵偣傛丄側傞傎偳丄偦偆偐傕偟傟側偄偲巚傢偣傞偙偲偑彂偐傟偰偄傞丅 偙偺杮偱偼丄悽奅杅堈僙儞僞乕價儖乮WTC乯偲儁儞僞僑儞傊偺峌寕偵傑偮傢傞丄偝傑偞傑側媈榝偑偲傝偁偘傜傟偰偄傞丅
傑偢WTC價儖偩偑丄僣僀儞丒僞儚乕乮1崋搹偲2崋搹乯偺曵夡偼丄惌晎偺岞幃尒夝偵傛傞偲乽寖撍偟偨旘峴婡偑婲偙偟偨壩嵭偵傛傞擬偱揝崪偑梟偗偨偨傔乿偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偩偑丄旘峴婡偺壩嵭偵傛傞擬偼丄揝崪傪梟偐偡傎偳偺崅擬傪敪偟側偄偟丄壩嵭偱僐儞僋儕乕僩偑暡乆偵側傞偙偲偼偁傝偊側偄丄偲愱栧壠偼尵偭偰偄傞丅塮憸傪尒傞偲僐儞僋儕乕僩傗揝崪偑暡乆偵偪偓傟偰旘傃嶶偭偰偄傞偑丄偙傟偼敋栻傪巊偭偨敋敪偱偁傞偙偲偺徹偟偩偲偄偆丅幚嵺丄曵夡偺捈慜偵價儖偐傜敋敪偵傛偭偰墝偑暚偒弌偰偄傞偺偑塮憸偱妋擣偱偒傞丅楌巎忋丄壩嵭偑尨場偱揝崪偺寶暔偑曵夡偟偨椺偼傂偲偮傕側偄偦偆偩丅
僣僀儞丒僞儚乕偵懕偄偰丄偦傟傛傝掅偄7崋搹價儖偑曵夡偟偨丅掅偄偲偄偭偰傕47奒寶偰偺崅偝偑偁傞乮僣僀儞丒僞儚乕偼110奒寶偰乯丅僣僀儞丒僞儚乕偐傜偼偄偪偽傫棧傟偨7崋搹偱偁傞偙偺價儖偑丄傕偭偲嬤偔偺價儖偼曵傟側偐偭偨偺偵丄丄旘峴婡偺徴撍傕側偟偵偄偒側傝曵夡偟偨丅偟偐傕6.5昩偲偄偆傕偺偡偛偄懍偝偱丄偁偭偲偄偆傑偵偒傟偄偵曵傟棊偪偨丅偙傫側曵傟曽偼丄暔棟揑偵尒偰丄壩栻傪巊偭偰敋敪傪婲偙偟偨偲偡傞埲奜偵愢柧偑偮偐側偄丅忋婰偺棟桼偵傛傝丄WTC價儖偼丄峲嬻婡偺徴撍偵傛偭偰偱偼側偔丄帠慜偵巇妡偗傜傟偨敋敪暔偵傛偭偰曵夡偟偨偺偩偲偄偆丅
偦偺傎偐丄價儖偺僆乕僫乕偑帠審偺2偐寧慜偵WTC偺價儖孮傪峸擖偟丄35壄僪儖偲偄偆嫄妟偺曐尟傪偐偗丄帠審屻偵80壄僪儖偲偄偆曐尟嬥傪庴偗庢偭偨偙偲丄柉娫婡偱偼側偔孯梡婡偩偭偨偲尵偆栚寕幰偑懡悢偄傞偲偄偆偙偲丄愓抧偐傜丄婡懱傪摿掕偱偒傞晹昳偑傂偲偮傕尒偮偐偭偰偄側偄偙偲側偳丄媈榝傪棤晅偗傞帠椺偑懡悢丄楍嫇偝傟偰偄傞丅
傕偭偲媈榝偩傜偗側偺偼丄儁儞僞僑儞傊偺旘峴婡偺撍擖偩丅傑偢丄僣僀儞丒僞儚乕偵嵟弶偵旘峴婡偑撍偭崬傫偱偐傜傎傏侾帪娫偑宱偭偰偍傝丄寈夲偟偰偄側偄傢偗偼側偄偺偵丄杊嬻懱惂偵傂偭偐偐傜側偐偭偨丅偦偟偰丄掅憌偺儁儞僞僑儞偵抧柺偡傟偡傟偺挻掅嬻旘峴偱撍偭崬傫偩偺偵丄廃埻偺幣惗偼偒傟偄側傑傑偩偭偨丅婲偒偨壩嵭偼彫婯柾偩偭偨偟丄婡懱偺攋曅偑堎忢偵彮側偄偟丄忔媞偺堚懱傕堦懱傕側偄丅傕偭偲偍偐偟偄偺偼丄暻偺愭偵傐偭偐傝偲寠偑偁偄偰偄傞偙偲偩丅偙偺寠偺幨恀傪尒傞偲丄慺恖偺栚偱尒偰傕丄偨偟偐偵旘峴婡偵寖撍偟偰丄側偤偙傫側僩儞僱儖偺傛偆側寠偑奐偔偺偐丄棟夝偱偒側偄丅峲嬻僄儞僕僯傾傗孯帠媄弍幰偼丄乬偙偺揝嬝僐儞僋儕乕僩偺娵偄寠偼丄旘峴婡偺寖撍側偳偱偼偱偒側偄丅儈僒僀儖偵巊傢傟傞巜岦惈敋栻偵傛偭偰偱偒偨偲偟偐峫偊傜傟側偄乭偲偄偆丅
寖撍偡傞弖娫偺塮憸偑廂傔傜傟偨儁儞僞僑儞偺娔帇僇儊儔偺塮憸偼丄嵟弶偺偆偪偼岞奐偝傟側偐偭偨丅偛偔嵟嬤偵側偭偰岞奐偝傟偨偑丄柧傜偐偵壗偐強傕曇廤偝傟偨愓偑偁傞偟丄寖撍偟偨偲偒偺塮憸偼廂傔傜傟偰偄側偄丅偡傋偰傪憤崌偡傞偲丄儁儞僞僑儞傊偺峌寕偼儈僒僀儖偩偭偨壜擻惈偑崅偄丅儈僒僀儖偑旘傫偱偒偨偲徹尵偟偰偄傞栚寕幰傕偄傞丅偦偟偰偙偙偱傕婡懱偑幆暿偱偒傞晹昳偼堦愗夞廂偝傟偰偄側偄丅峲嬻婡帠屘挷嵏埾堳夛偺儊儞僶乕偩偭偨尦嬻孯戝嵅偼丄偳傫側帠屘偱偁偭偰傕丄晹昳偑夞廂偝傟側偄偙偲側偳偁傝偊側偄偲尵偭偰偄傞丅
傾儊儕僇惌晎偼丄傾儖僇僀僟偺斊峴偲抐掕偱偒傞徹嫆偼偁傞偲尵偭偰偄傞偺偵丄傂偲偮傕奐帵偟偰偄側偄丅偙偺帠審屻丄傾儊儕僇偼傾僼僈僯僗僞儞傪峌寕偟丄偦偟偰僀儔僋偵怤峌偟偨丅僽僢僔儏戝摑椞偺巟帩棪偼丄偦傟傑偱50亾傪愗偭偰偄偨偺偵丄帠審捈屻偵偼90亾偵払偟偨丅偦偟偰傾儊儕僇偼嶻孯暋崌懱偺巚偄偳偍傝偺曽岦偵恑傫偩丅垽崙幰朄偑惂掕偝傟丄戇曔偟偨偄憡庤偑偄偨傜丄僥儘儕僗僩偲寛傔偮偗傟偽丄壗偺庤懕偒傕傆傑偢戇曔偱偒傞傛偆偵側偭偨丅僕儍乕僫儕僗僩偼忣曬尮傪柧偐偡偙偲傪嫅傔偽戇曔偝傟傞傛偆偵側偭偨丅僥儘懳嶔偲偄偊偽丄偳傫側恖尃傪柍帇偟偨偙偲偱傕偱偒傞傛偆偵側偭偨丅
偙傟偵傛偭偰僱僆僐儞偺夊忛偱偁傞傾儊儕僇怴悽婭僾儘僕僃僋僩偺僔僫儕僆捠傝偵帠偑塣傫偩丅2007.07.31晅偗偺擔婰乽暷崙僱僆僐儞偺堿杁傪恾彂娰堳偼慾巭偱偒傞偐乿偵傕彂偄偨偑丄傾儊儕僇怴悽婭僾儘僕僃僋僩乮Project for the New American Century乯偼僱僆僐儞偺僔儞僋丒僞儞僋偱丄夛堳偵偼僂僅儖僼僅僂傿僢僣尦悽奅嬧峴憤嵸丄僠僃僀僯乕暃戝摑椞丄儔儉僘僼僃儖僪尦崙杊挿姱丄傾乕儈僥乕僕尦崙柋暃挿姱丄僕僃僽丒僽僢僔儏尦僼儘儕僟廈抦帠乮僽僢僔儏戝摑椞偺掜乯側偳偑偄傞丅斵傜偼丄乬傾儊儕僇偼孯帠揑丒宱嵪揑桪埵傪棙梡偟偰傕偭偲巜摫椡傪敪婗偟側偗傟偽側傜側偄丄偦傟偑傾儊儕僇偺偨傔偺丄傂偄偰偼悽奅偺偨傔偵側傞乭偲偄偆婎杮棟擮偐傜惌嶔傪採尵偟偰偄傞丅偦偟偰丄斵傜偼丄2000擭9寧偵敪昞偟偨儗億乕僩偱丄乬傾儊儕僇偑曄妚傪悑偘傞偨傔偵偼丄恀庫榩峌寕偺傛偆側丄偦偺怗攠偲側傞夡柵揑側懪寕傪傕偨傜偡帠審偑昁梫偩乭偲榑偠偰偄傞丅
偨偟偐偵媈榝偩傜偗偩丅偱傕丄傎傫偲偆偵傾儊儕僇惌晎偺堿杁側偺偐丄偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼媈栤傕偁傞丅傾儖僇僀僟偺斊峴偵偡傞側傜丄旘峴婡側偳傪懱摉偨傝偝偣側偔偲傕丄價儖傪敋攋丒曵夡偝偣傟偽偡傓偺偱偼側偄偐丅寖撍偟偨旘峴婡偑椃媞婡偱偼側偔孯梡婡偩偭偨偺側傜丄椃媞婡偦偺傕偺傗丄椃媞婡偵忔偭偰偄偨忔媞偼偳偙偵偄偭偨偺偐丅110奒寶偺價儖傪敋栻偱曵夡偝偣傞偵偼丄壗擔傕偐偗偰丄價儖偺偡傒偢傒偵傑偱壗偐強傕敋栻傪巇妡偗側偗傟偽側傜側偄偺偵丄偄偮偦傫側偙偲傪傗偭偨偺偐側偳丄媈栤揰偼懡偄丅旘峴婡偺撍擖偵傛傞徴寕偲壩嵭偱價儖偑搢夡偡傞偙偲偼廫暘偁傝偆傞偲偡傞愱栧壠傕偄傞丅偨偟偐偵偙偆偄偆堿杁榑偼傓偐偟偐傜偄偐偑傢偟偄傕偺偑懡偄偟丄偁傑傝怣梡偱偒側偄婥傕偡傞丅
偲偼尵偊丄尰幚偵傾儊儕僇偺楌巎偼丄惌晎偲孯晹偲CIA偑偐傜傓堿杁偱嵤傜傟偰偄傞丅傾儊儕僇偑崙柉傪媆偄偰愴憟偵桿摫偟偨偙偲偼丄偙傟傑偱偵偄偔偮傕偁偭偨丅傾儊儕僇崙撪偱帠審傪婲偙偟偰僉儏乕僶恖偺偣偄偵偟丄僉儏乕僶偲偺奐愴偵傕偪偙傕偆偲偟偨乽僲乕僗僂僢僪嶌愴乿偑偁傞丅偙傟偼摑崌嶲杁杮晹偑嶌惉偟偨偑彸擣偝傟側偐偭偨丅幚嵺偵幚峴偵堏偝傟偨傕偺偵偼丄傾儊儕僇偑杮奿揑偵儀僩僫儉偵夘擖偡傞偒偭偐偗偲側偭偨僩儞僉儞榩帠審丄杻栻偑傜傒偱僷僫儅偺幚幙巟攝傪傕偔傠傫偩僷僫儅怤峌嶌愴丄俠俬俙偑塀傟偰杻栻傗晲婍傪攧攦偟偰偄偨僀儔儞丒僐儞僩儔帠審側偳偑偁傞丅偩偐傜丄偄傑偺惌晎偺婄傇傟丄愇桘嶻嬈傗孯廀嶻嬈偲偺桙拝傇傝偐傜偟偰丄9.11僥儘偼傾儊儕僇惌晎偑巇慻傫偩傕偺偩偭偨偲偟偰傕丄偗偭偟偰晄巚媍偱偼側偄丅
2008.07.16 (悈) 帒杮庡媊偺枛婜揑徢忬偑業掓偟偰偄傞
摯栮屛僒儈僢僩偼梊憐捠傝壗偺嬶懱埬傕弌側偄拑斣偱廔傢偭偨丅僒儈僢僩側偳偼丄戝崙偑帺暘偨偪偺搒崌偺偄偄傛偆偵悽奅傪僐儞僩儘乕儖偟傛偆偲偡傞夛媍偩偟丄偍傑偗偵抧媴慡懱偺偙偲傪峫偊傞側偳偲偄偆偺偼偍戣栚偱丄幚懺偼奺崙偑帺崙偺棙塿傪桪愭偝偣傛偆偲偡傞傢偗偩偐傜丄榖偑傑偲傑傞傢偗偑側偄丅偄傑嬞媫偵傗傞傋偒偙偲偼丄尨桘偺崅摣丄怘椘偺崅摣丄敆傝偔傞悽奅嫲峇偲偄偆婋婡揑忬嫷偵偁偭偰丄偦偺懳嶔傪帄媫島偠傞傋偒側偺偵丄俧俉偼乽嫮偄寽擮乿傪昞柧偟偨偩偗偩丅嫮偄寽擮側偳丄偡偱偵悽奅拞偺恖乆偑昞柧偟偰偄傞丅戝偒側僥乕儅偩偭偨抧媴壏抔壔懳嶔偵偟偰傕丄傾儊儕僇偺傢偑傑傑偺偨傔惉壥偼側偐偭偨丅尨桘崅偑巭傑傜側偄丅搳婡儅僱乕偑尨場偩偲偄偆丅帒杮庡媊偺枛婜揑徢忬偩丅攚宨偵偼拞崙傗僀儞僪側偳偺廀梫偑憹偊偨偺偵斾傋丄尨桘惗嶻偺怢傃偑彫偝偄偲偄偆忬嫷偑偁傞傜偟偄丅偦傟偱傕廀梫偲嫙媼傪斾傋傞偲丄傑偩嫙媼検偺傎偆偑懡偔丄梋桾偑偁傞偐傜丄杮棃偩偭偨傜偙傫側偵抣忋偑傝偡傞偼偢偼側偄丅偦偙偵夘擖偡傞偺偑傾儊儕僇偺搳婡儅僱乕偩丅僒僽僾儔僀儉栤戣偱傾儊儕僇宱嵪偑幐懍偟丄僪儖偑壓棊偟偨丅峴偒応傪幐偭偨搳帒僼傽儞僪偑尨桘愭暔庢堷巗応偵棳傟崬傒丄抣抜傪捿傝忋偘傞丄偲愱栧壠偼巇慻傒傪夝愢偟偰偄傞丅
彅埆偺崻尮偼傾儊儕僇偱偺僒僽僾儔僀儉栤戣偲楤嬥弍偺傛偆側嬥梈宱嵪偩丅偦傕偦傕僒僽僾儔僀儉儘乕儞偵娭偡傞愢柧傪撉傓偲丄偦傫側嵓媆傑偑偄偺儘乕儞傪傛偔惌晎偑婯惂傕偣偢傗傜偣偰偄偨傕偺偩偲巚偆丅傑偟偰傗偦傫側婋側偄儘乕儞偑徹寯壔偝傟偰丄嬥梈婡娭傗搳帒壠偺偁偄偩偱庢堷偝傟傞偵帄偭偰偼丄偁偒傟傞偽偐傝偩丅娔撀姱挕偑嵿柋徣側偺偐FRB側偺偐抦傜側偄偑丄偄偭偨偄壗傪傗偭偰偄偨偺偩傠偆丅偄傑傾儊儕僇偱偼惌晎宯廧戭嬥梈婡娭偺攋抅偑榖戣偵側偭偰偄傞偑丄傑偩傑偩嬥梈晄埨偼婲傞偩傠偆丅嬥慘傊偺偁偔側偒梸朷偼丄婯惂偟側偗傟偽偳偙傑偱傕朿傟忋偑傝丄傗偑偰偼幮夛傪攋夡偡傞丅
尨場偑暘偐偭偰偄傞偺側傜丄庤傪懪偰偽偄偄偺偵丄傾儊儕僇偼壗傕傗傠偆偲偟側偄丅僪儖埨偵帟巭傔傪偐偗傟偽尨桘崅偼巭傑傞偲偄偆偙偲偩偑丄傾儊儕僇惌晎偼杮奿揑側懳嶔傪島偠傛偆偲偟側偄丅嬥棙傗惻嬥偺挷惍偱懳張偟傛偆偲偟偨偑丄偦傫側彫庤愭偺巤嶔偱偼岠壥偑側偐偭偨丅拞搶偺嶻桘崙偑憹嶻寁夋傪敪昞偟偨偑丄検偑彮側偔丄偙傟傕岠壥偑側偐偭偨丅傕偼傗搳婡傪梷惂偟丄嬥梈巗応傪婯惂偡傞偟偐庤偑側偄偺偵丄傾儊儕僇惌晎偼傑偭偨偔崢傪忋偘傞婥攝偑側偄丅偦傟偼丄偦傟傪朷傑側偄椡偑摥偄偰偄傞偐傜偩丅偦傟偱傏傠栕偗偟偰偄傞愇桘帒杮偑丄僽僢僔儏傗僠僃僀僯乕傪偼偠傔惌尃庡摫幰偨偪偺僶僢僋偵偮偄偰偄傞偐傜偩丅戝摑椞偑岎戙偡傟偽丄偦偺埆偺楢娐偼抐偪愗傟傞偺偩傠偆偐丅
傂傞偑偊偭偰丄擔杮偼壗傪偟偰偄傞偺偩傠偆丅尨桘丄怘椏昳偺崅摣偼丄擔杮偩偗偱偼夝寛偱偒側偄丅偩偭偨傜儓乕儘僢僷奺崙偲楢実偟偰丄傾儊儕僇偵嬥梈婯惂傪敆傟偽偄偄丅偩偑擔杮偼偦傟偑偱偒側偄丅傾儊儕僇偺懏崙偩偐傜偩丅忣偗側偄偙偲偵丄偄傑偺擔杮偼傾儊儕僇偵尵傢傟偨偙偲偵廬偆偩偗偩丅偦傟偱傕擔杮偱懳張偱偒傞偙偲偼偁傞偩傠偆丄嵞嵦寛偝傟偰偟傑偭偨偑丄僈僜儕儞巄掕惻傪攑巭偡傞偲偐丅偦偺傇傫惻廂尭偵側傞偑丄梋暘側摴楬側偳嶌傜側偗傟偽偄偄丅抧曽偵夞偡嵿尮偑昁梫側傜丄崙偺柍懯巊偄傪尭傜偣偽偄偔傜偱傕弌偰偔傞偟丄徣挕偵偼嫄妟偺塀偟嵿尮傕偁傞丅偩偑暉揷庱憡偼乽崲傝傑偟偨偹乿側偳偲丄傑傞偱懠恖帠偺傛偆偵尵偆偩偗偩丅
峫偊偰傒傟偽丄傢偨偟偨偪偼偍偲側偟偡偓傞丅傕偭偲搟傝偺惡傪忋偘側偗傟偽側傜側偄丅僈僜儕儞偺抣忋偑傝傗暔壙偺崅摣偩偗偱偼側偄丅僐僀僘儈帪戙偵抂傪敪偡傞丄奿嵎偺奼戝丄幮夛曐忈惂搙偺夵埆丄奀奜帒杮偺棎擖丄嵼擔暷孯偺尐戙傢傝旓梡偺奼戝側偳丄偙傟偩偗崙柉傪側偄偑偟傠偵偟偨惌帯偑偍偙側傢傟偰傕丄搟傝偺惡偑惌晎偵撏偐側偄丅擔杮偱偼戝婯柾側僨儌偑峴傢傟側偔側偭偰媣偟偄丅娯崙偱偼傾儊儕僇媿擏嵞奐偵斀懳偡傞僨儌偵傛偭偰丄棝惌尃偑嬯嫬偵娮偭偰偄傞丅娯崙偺僨儌偼懡暘偵僱僢僩偺晽昡偵梮傜偝傟偨傕偺傜偟偄偺偱丄庤曻偟偱偼巀摨偱偒側偄偑丄傢偨偟偨偪傕彮偟偼偁傟傪尒廗偆傋偒偩丅擔杮恖傛丄僨儌偱搟傝傪帵偣丅偦偆偡傟偽崙偼摦偔丅
2008.07.10 (栘) 柉庡搣偺傾僉儗僗銯丄慜尨惤巌
偲偵偐偔師偺憤慖嫇偱偼丄壗偲偟偰偱傕柉庡搣偵帺柉搣傪懪偪攋偭偰傕傜傢側偗傟偽側傜側偄偑丄偦偺柉庡搣偵傕壽戣偼偨偔偝傫偁傞丅偄偪偽傫戝偒側栤戣偩偲巚偆偺偼丄慜尨惤巌偲偄偆尦戙昞偺懚嵼偩丅偙偺丄暊榖弍偺恖宍偺傛偆側婄傪偟偨丄偄偮傕僯儎僯儎徫偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞抝偼丄偳偆偵傕敄婥枴埆偄丅慜尨偺尵摦偼帺柉搣傛傝塃婑傝偱偁傝丄偙傫側恖娫偑曄側偐偨偪偱椡傪埇偭偨傜丄偁偺擔杮傪揇徖偵捛偄崬傫偩僐僀僘儈傗傾儀偺擇偺晳偵側傝偐偹側偄丅偙偺抝偑婋尟側偺偼丄岞慠偲寷朄9忦夵惓偲孯旛憹嫮傪彞偊偰偄傞偙偲偩丅嫗搒戝妛偱妛傫偩偲偄偆偙偲偩偐傜摢偼偄偄偺偩傠偆偑丄偁偺惌晎屼梡払偺尃椡庡媊惌帯妛幰丄崅嶁惓隉偵巘帠偟偨偲偄偆偐傜丄偍棦偑抦傟偰偄傞丅慜尨偼丄悽奅偵屴偟丄拞崙丒杒挬慛偺嫼埿偵懳峈偡傞偵偼孯旛偑昁梫偩偲庡挘偡傞丄偄傢備傞乬尰幚乭榑幰偩丅斵偼廤抍揑帺塹尃偺昁梫傪愢偒丄惌晎偑採埬偟偨僥儘懳嶔摿慬朄偺墑挿偵巀惉偟偨偑丄偦傟偼傾儊儕僇偲偺娭學傪傑偢偔偡傞偺偼崙塿偵斀偡傞偲偄偆棟桼偐傜偩偭偨丅傑偝偵僐僀僘儈偺傗偭偨懳暷廬懏奜岦偦偺傕偺偩丅偙傫側恖娫偑柉庡搣偺側偐偵偄偰偼丄偟偐傕暃戙昞偲偟偰堦攈傪宍惉偟偰偄偰偼丄崱屻偺搣偲偟偰偺寢懇偑婋傇傑傟傞丅
拞崙偲杒挬慛偺嫼埿傪傗偨傜偵慀傝棫偰傞偺偼丄孯奼榑幰偺忢搮庤抜偩丅寷朄9忦傪夵惓偟丄奜偵弌偰愴摤峴堊傪偡傞孯戉傪擔杮偑帩偰偽丄傾儊儕僇偺懏崙偱偁傞擔杮偼孯戉傪巚偄偺傑傑偵棙梡偝傟丄孯旛偺憹嫮偼巭傑傞偲偙傠傪抦傜側偔側傞丅峴偒偮偔愭偼妀晲憰偵側傞偩傠偆丅悽奅偺曮偲傕尵偆傋偒寷朄9忦傪堐帩偟丄傾儊儕僇傊偺埶懚偐傜扙媝偟丄偄傑偺帺塹戉偼偦偺傑傑愱庣杊塹偺帺塹戉偲偟偰懚懕偝偣傞乗乗偙傟埲奜偵擔杮偑惗偒巆傝丄悽奅偵岦偐偭偰偦偺懚嵼姶傪敪婗偡傞摴偼側偄丅
慜尨偑惌帯偺椡妛傪暘偐偭偰偄側偄偺偼丄帺柉搣偲偺懳寛巔惃傪尒偣偰偄側偄偙偲偐傜偟偰堦栚椖慠偩丅惌尃傪扗庢偡傞偨傔偵偼丄偡傋偰偺惓摉側庤抜傪峴巊偟偰偄傑偺帺岞惌尃傪捛偄媗傔側偔偰偼側傜側偄丅斵偵偼丄壗偑壗偱傕帺柉搣傪搢偡偲偄偆婥奣偲敆椡偑傑偭偨偔側偄丅斵偺庡挘偡傞傛偆側嫤挷楬慄傪偲偭偰偄傟偽丄偄偮傑偱偨偭偰傕惌尃側偳庢傟偼偟側偄丅帺柉搣偵偄偄傛偆偵棙梡偝傟傞偩偗偩丅慜尨偼丄撍慠偺揋慜摝朣偱悽娫偺幐徫傪攦偭偨乬偍朧偪傖傫乭傾儀偲恊偟偄偲偄偆偑丄偝傕偁傝側傫丄愺敄側峫偊曽偼妋偐偵帡偰偄傞丅
嵟嬤偺慜尨偼丄柉庡搣偺儅僯僼僃僗僩傪乮偟偐傕帺暘偑戙昞偺偲偒偵棫埬偟偨擾嬈惌嶔傪乯斸敾偟偰暔媍傪偐傕偟偨傝丄側偤偐晜偐傟憶偄偱偄傞偄傞僐僀僘儈偑屇傃偐偗偨曌嫮夛側傞傕偺偵丄岤婄柍抪側惌帯寍幰偺彫抮昐崌巕偲堦弿偵弌惾偟丄僐僀僘儈偵庱憡岓曗偲偍偩偰傜傟偰偨傝偲丄帺柉搣傪棙偡傞傛偆側尵摦偑栚棫偮丅傑傞偱柉庡搣傪暘抐偡傞偨傔帺柉搣偐傜憲傝崬傑傟偨庤愭偺傛偆偩丅偁偺帺柉搣偍書偊偺柍掕尒側僕儍乕僫儕僗僩揷尨憤堦楴偵朖傔傜傟傞傛偆偱偼丄傕偆媬偄偑偨偄偲偙傠傑偱偒偰偄傞丅
柉庡搣偼傕偲傕偲偑婑傝崌偄強懷偩偐傜丄偗偭偟偰堦枃娾偱偼側偔丄偝傑偞傑側峫偊偺媍堳偑偄傞丅偦傟偑摉慠偱偁傝丄堄尒偑堎側傞傗偮偼堎抂暘巕偩偐傜弌偰偄偗丄側偳偲尵偆偮傕傝偼栄摢側偄丅偩偑慜尨偺僞僇攈揑偱柍愡憖側峫偊偼丄偳偆偵傕嫋偟偑偨偄丅嵟嬤偺帺柉搣婑傝偺尵摦偼柉庡搣偺暘楐傪桿偆傛偆側傕偺偱偁傝丄帺柉搣偺巚偆偮傏偱偼側偄偐丅偙傫側恖娫偼堦崗傕憗偔柉庡搣偐傜捛偄弌偡傋偒偩丅
2008.07.04 (嬥) 姱椈偲帺岞惌帯壠偺楎埆偝壛尭
偄傑偺姱椈偨偪偺墶朶偝丄撦姶偝偼栚偵梋傞丅崙柉偺偆偊偵偁偖傜傪偐偒丄惻嬥傪怘偄暔偵偟偰偄傞偲偟偐尵偄傛偆偑側偄丅崅搙惉挿婜偵偼斵傜傕崙椡憹恑偵戝偒側栶妱傪壥偨偟丄姱椈惂搙偑婡擻偟偰偄偨丅偩偑偲偒偼堏傝丄僶僽儖偑偼偠偗丄榁恖偑憹偊偰彮巕壔幮夛偵側傝丄崙偺庁嬥偑朿傟忋偑偭偨偄傑丄堄幆傪曄偊丄怴偟偄帪戙偵懳墳偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偺偵丄偄傑偩偵斵傜偼媽偄懱幙偺傑傑丄婛摼尃偵偟偑傒偮偄偰偄傞丅嫃庰壆僞僋僔乕側偳偼昘嶳偺堦妏偱偁傝丄偄傑偺姱椈偺儌儔儖偺側偝丄師尦偺掅偝偼栚傪暍偆偽偐傝偩丅帺岞惌尃偺惌帯壠偨偪傕丄偳偆偟傛偆傕側偄丅杮摉偵崙偺偙偲丄崙柉偺偙偲傪峫偊偰偄傞偺側傜丄姱椈懱惂偺媽暰傪曄偊側偗傟偽側傜側偄偺偵丄偦偆偡傞偳偙傠偐丄偦偺傑傑懚懕偝偣傛偆偲偟偰偄傞丅夵妚偟傛偆偲偡傞婥崪偺偁傞幰傕偄傞偑丄棙尃偵偟偑傒偮偒丄姱椈偵庢傝崬傑傟偨儀僥儔儞媍堳偵慾傑傟偰丄壗傕偱偒側偄丅偦傕偦傕斵傜偼丄戝恇偵側偭偨偲偨傫丄側偤帺暘偺娗妽偡傞徣傪庣傝丄姱椈偺尵偄側傝偵側傞偺偩傠偆偐丠 姱椈偺彆偗偑側偗傟偽崙夛偱摎曎偑偱偒側偄偐傜側偺偐丠 偲偵偐偔壗傕栤戣堄幆傪傕偨側偄傏傫偔傜戝恇偑懡偡偓傞丅戝恇偼姱椈偺嶌偭偨摎曎彂傪朹撉傒偡傞偩偗偩丅偙傫側拑斣偺傛偆側崙夛側偳丄幚幙揑偵偼壗偺堄枴傕側偄丅
偦傕偦傕丄戝恇偲偄偆柤徧偑偄偗側偄丅偙傫側暯埨帪戙偺懢屆偵巊傢傟偰偄偨丄偄偐偵傕執偦偆側嬁偒偺偡傞柤徧偩偐傜丄戝恇偵側傝偨偑傞柍擻側惌帯壠偳傕偑攜弌偡傞偺偩丅崙柉偵曭巇偡傞婡娭偺儕乕僟乕傜偟偔丄傾儊儕僇幃偵乬挿姱乭偲偐乬徣挿乭偲偐丄偡偭偒傝偟偨屇徧偵夵傔傞傋偒偩丅柤徧偑曄傢偭偨偐傜偲偄偭偰桪廏側恖嵽偑偦偺擟偵廇偔偲偄偆曐徹偼側偄偑丄乬柤偼懱傪昞偡乭偩丅彮偟偼幚柋庡摫偺偐偨偪偵側傞偩傠偆丅
榖偼偦傟偨偑丄昐奞偁偭偰堦棙側偄撈棫峴惌朄恖傗揤壓傝偺暰奞偑偙傟傎偳嫨偽傟側偑傜丄偄傑偩偵偄偭偙偆偵夵妚偺挍偟偑尒偊側偄偺偼丄偄偭偨偄偳偆偄偆偙偲偩傠偆丅撈棫峴惌朄恖偺巊偆柍懯側旓梡偼朿戝側妟偵偺傏傞偟丄偦偙偵揤壓傝丄棙尃傪傓偝傏傞傎偐偼側偵傕偟側偄尦姱椈偳傕偵巟暐傢傟傞媼椏傕嫄妟偩丅偙偺僔僗僥儉偑墭怑傗姱惢択崌偺壏彴偵側偭偰偄傞偺偼廃抦偺偲偍傝偩丅
偝偒偛傠惉棫偟偨崙壠岞柋堳惂搙夵妚朄傕丄姱椈傗丄姱椈偺堄傪懱偟偨媍堳偺墶傗傝偵傛傝丄崪敳偒偺撪梕偵側偭偰偟傑偭偨丅偙傟偐傜恑傔傜傟傞偲偄偆夵妚偼丄杮幙偵愗傝崬傑側偄丄偄偄壛尭側傕偺偵側傞偱偁傠偆偙偲偼栚偵尒偊偰偄傞丅偦傕偦傕丄偄偪偽傫偺栤戣偼丄徣偵偍偄偰丄偁傞恖娫偑師姱偵側偭偨傜丄偦偺恖娫偲摨婜偺幰偼徣傪帿傔側偗傟偽側傜側偄偲偄偆恖帠惂搙偩丅50嵨戙敿偽偱徣傪弌偨恖娫偺摥偒愭偼丄偦偺徣偺恖帠晹偑埓慁偡傞丅偙偆偄偆偙偲偱偼丄偄偮傑偱偨偭偰傕彅埆偺崻尮偱偁傞揤壓傝偼側偔側傜側偄丅傑偢偙偺恖帠惂搙傪攑巭偟側偗傟偽側傜側偄偺偵丄偦傫側摦偒偼尒傜傟側偄丅
偙傟傪夵妚偡傞偵偼丄偄傑偺帺岞惌尃偱偼柍棟偩丅斵傜偵偼杮婥偱夵妚偡傞堄巚偑側偄偟丄傗傠偆偲巚偭偰傕偱偒側偄丅惌尃偑曄傢傜側偔偰偼偩傔偩丅柉庡搣惌尃偵側偭偨偐傜偲偄偭偰傎傫偲偆偵曄妚偱偒傞偳偆偐暘偐傜側偄偑丄偄傑傛傝偼傑偟偩傠偆丅
2008.06.30 (寧) 捝晽敪徢揯枛婰
偮偄偵弌偨丄偄傗丄偍壔偗偠傖側偔丄捝晽偑丅10擔傎偳慜偺偙偲丄嵍懌偺偐偐偲偵壗偐堘榓姶傪姶偠偨丅偱傕偦偺擔偼曕偔偺偵丄偲偔偵巟忈偼側偐偭偨丅偲偙傠偑梻擔丄挬婲偒傞偲丄偐偐偲偵寖捝偑憱傝丄捝偔偰曕偗側偔側偭偨丅抦傜側偄偆偪偵壗偐偵傇偮偗偨偣偄側偺偐丄偦傟偲傕旀楯崪愜偵偱傕側偭偨偺偐丄偁傟偙傟尨場傪峫偊偨偑暘偐傜側偐偭偨丅偦偺擔偺栭丄桭恖偨偪偲堸傒夛偑擖偭偰偄偨丅寚惾偟傛偆偐偲巚偭偨偑丄壗偲偐曕偗側偔偼側偄偺偱丄傛偣偽偄偄偺偵丄捝傒傪偙傜偊丄嵍懌傪堷偒偢傝側偑傜丄偄偮傕偺攞埲忋偺帪娫傪偐偗偰曕偒丄揹幵傪忔傝宲偄偱廤崌応強偵峴偭偨丅桭恖偺傂偲傝偑乽偦傟偼捝晽偩傛丅偍傟傕側偭偨偙偲偑偁傞乿偲尵偆丅偦傟偱巚偄摉偨偭偨丅傏偔偼擜巁抣偑崅傔偱丄捝晽偵婥傪偮偗傞傛偆偵堛幰偐傜尵傢傟偰偄偨偺偩丅偡偭偐傝朰傟偰偄偨丅偦偺擔丄庰傪堸傫偱傕捝傒偼杻醿偣偢乮偁偨傝傑偊偩偑乯丄夝嶶偟偰揹幵偵忔偭偨偑丄搑拞偱僞僋僔乕傪廍偄壠偵婣偭偨丅梻擔丄偐偐傝偮偗偺堛堾偵峴偭偰寣塼専嵏傪偟偰傕傜偭偨丅尒帠側捝晽偩偭偨丅擜巁抣偼丄7.0傑偱偼惓忢偺斖埻撪丄7.0傪挻偊傞偲崅擜巁抣偱捝晽敪徢偺婋尟偁傝丄8.0埲忋偩偲梫栻暈梡偲偄偆婎弨偑偁傞丅傏偔偼偦傟傑偱偓傝偓傝7.0埲撪偵偲偳傑偭偰偄偨偑丄偙偺偲偒偺悢抣偼8.6偵傑偱挼偹忋偑偭偰偄偨丅懱偵偨傑偭偨榁攑暔偺傂偲偮偱偁傞擜巁偼丄捠忢丄恡憻偱暘夝偝傟丄擜偲偄偭偟傚偵攔煏偝傟傞丅偲偙傠偑丄僾儕儞懱偲偄偆惉暘傪懡偔娷傓怘暔傪怘傋偡偓偰夁忚偵擜巁偑惗惉偝傟偨傝丄夁搙偺僗僩儗僗偵偝傜偝傟偨傝丄恡憻偺婡擻偑掅壓偟偨傝偡傞偲丄恡憻偼張棟偟偒傟側偔側傝丄攔煏偝傟傞傋偒擜巁偑寣塼偵棳傟弌偡丅偦傟偑偁傞掱搙偺検傪挻偡偲丄擜巁偑寢徎偲側偭偰娭愡晹偵晅拝偟丄娭愡墛傪敪徢偝偣丄捝傒偑惗偠傞丅偦傟偑捝晽偺儊僇僯僘儉偩丅擜巁抣偑崅偄傑傑曻抲偟偰偍偔偲丄恡婡擻忈奞側偳偺撪憻幘姵傪堷偒婲偙偡丅埲忋偼僀儞僞乕僱僢僩偐傜摼偨抦幆偩丅捝晽偲偄偆偲丄懌偺巜偺晅偗崻偑捝偔側傞偲偄偆僀儊乕僕偑偁傞丅傏偔傕偦偆巚偭偰偄偨丅偩偑偦偆側傞偺偼慡懱偺70亾傎偳偱丄巆傝偺30亾偼旼傗旾偺娭愡丄傏偔偺応崌偺傛偆偵偐偐偲偲偄偭偨丄偄傠傫側偲偙傠偵敪徢偡傞偺偩偦偆偩丅捝晽偵側偭偨傜丄捝傒巭傔偺栻傪堸傒丄姵晹傪幖晍偟丄捝傒偑戅偔偺傪懸偭偰偐傜丄擜巁抣傪壓偘傞栻傪暈梡偡傞偙偲偵側傞丅捝傒偼帺慠偵戅偄偰偄偔丅傏偔偺応崌丄3乣4擔偟偨傜捝傒偼偐側傝敄傟丄1廡娫傎偳宱偭偨傜丄傎偲傫偳惓忢偵栠偭偨丅娭愡偵晅拝偟偰偄偨擜巁偺寢徎偼偳偙偵峴偭偨偺偩傠偆丅僱僢僩偱挷傋偰傕丄偦傟偵偮偄偰偼偳偙偵傕愢柧偑側偔丄暘偐傜側偄丅
擜巁抣傪壓偘傞偵偼丄僾儕儞懱傪懡偔娷傓怘暔傪怘傋側偄偺偑丄傑偢戞堦偺椕朄偩偲偄偆丅嫑棏丄撪憻宯偺擏側偳偵僾儕儞懱偑懡偄偺偼丄偳偺愢柧傪撉傫偱傕摨偠偩偟丄栰嵷傪偨偔偝傫怘傋傞偺偑偄偄偲偄偆偙偲傕堦抳偟偰偄傞偑丄偦傟埲奜偺怘暔偵偮偄偰偼丄堄奜偵愢柧偵偽傜偮偒偑偁傝丄偳傟傪怣偠偰偄偄偺偐暘偐傜側偄丅擺摛側偳偼丄偁傞堛幰偼戝摛偵偼僾儕儞懱偑懡偄偐傜愨懳怘傋偰偼偩傔偩偲尵偆偟丄暿偺堛幰偼擺摛嬠偼擜巁抣傪壓偘傞偐傜怘傋偨傎偆偑偄偄偲偄偆丅傾儖僐乕儖偵娭偟偰傕丄價乕儖偵偄偪偽傫僾儕儞懱偑娷傑傟傞偲偄偆偙偲偼妋偐偩偑丄偦傟埲奜偺庰偵偮偄偰偼愢柧偑傑偪傑偪偩丅儚僀儞側傜堸傫偱傕偄偄偲偄偆堛幰傕偄傞偟丄儚僀儞傕偩傔偩偲偄偆堛幰傕偄傞丅偦傕偦傕嵟嬤偼丄偨偲偊僾儕儞懱傪懡偔娷傓傕偺傪怘傋偰傕丄幚嵺偵懱撪偵庢傝崬傑傟傞偺偼旝検側偺偱丄偦偆偄偆怘帠椕朄傪偟偰傕偁傑傝堄枴偼側偄丄擜巁抣偑忋偑傞嵟戝偺尨場偼丄恡憻偺婡擻偑庛偭偰偄傞偙偲偵偁傞偺偩丄偲偄偆愢偑彞偊傜傟偰偄傞傜偟偄丅慺恖偵偼愢摼椡偺偁傞儘僕僢僋偩丅偄偢傟偵偣傛丄偙傟偩偗壢妛偑敪払偟偰傕丄堛妛暘栰偵偼傑偩傑偩暘偐傜側偄偙偲偑懡偄偲偄偆偙偲側偺偩丅
偲偵偐偔丄偄偭偨傫崅擜巁抣偵側偭偨埲忋丄偙偺徢忬偲枛挿偔晅偒崌偭偰偄偔傎偐偼側偄偲峫偊傞崱擔偙偺偛傠偱偁傞丅
2008.05.19 (寧) 乽挿偄偍暿傟乿偲乽儘儞僌丒僌僢僪僶僀乿
抶傟偽偣側偑傜丄嶐擭弌斉偝傟偰榖戣偵側偭偨懞忋弔庽偺怴栿丄儗僀儌儞僪丒僠儍儞僪儔乕嶌乽儘儞僌丒僌僢僪僶僀乿傪撉傫偩丅傏偔偑偙偺杮偺媽栿偱偁傞惔悈弐擇栿偺乽挿偄偍暿傟乿傪撉傫偩偺偼丄偨傇傫戝妛1擭偺偙傠偩偭偨偲巚偆丅僴儎僇儚偺億働儈僗偱丄摉帪偲偟偰偼攋奿偵暘岤偐偭偨丅偄傑側傜偦傟傎偳懡偄暘検偱偼側偄偩傠偆丅側偵偟傠嶐崱偺儈僗僥儕偼偳傫偳傫挿戝偵側偭偰偄偰丄忋壓2姫側偳偼偁偨傝傑偊偵側偭偰偄傞偑丄愄偼偦傫側偵挿偄杮偼傔偭偨偵側偐偭偨丅乽挿偄偍暿傟乿偼1953擭偺嶌昳偱偁傝丄慡晹偱7嶌偁傞僠儍儞僪儔乕偺挿曇偺側偐偱嵟屻偐傜2斣栚偵敪昞偝傟偨丅摉帪丄堦撉偟偰戝偒側姶柫傪庴偗丄偙傟偙偦僠儍儞僪儔乕偺嵟崅寙嶌偲妋怣偟偨偑丄偦傟傑偱偺斵偺嶌昳偲偼丄偄偔偮偐偺揰偱偐側傝堎側偭偰偄傞偲偄偆報徾傪庴偗偨丅挿偝傕偦偺傂偲偮偩偑丄偦傟埲奜偵丄庡恖岞偺巹棫扵掋僼傿儕僢僾丒儅乕儘僂偑偄偮傕挐傞傊傜偢岥傗寈嬪偑塭傪愽傔偰偄傞偙偲丄慡懱偵摦偒偑彮側偄偙偲丄僴乕僪儃僀儖僪彫愢偺摿挜偱偁傞峴摦傪捠偟偰撲傪捛偆偲偄偆僗僞僀儖偱偼側偔丄抝摨巑偺桭忣傪昤偔偙偲偵椡揰偑抲偐傟偰偄傞偙偲側偳偑堘偄偲偟偰嫇偘傜傟傞丅傑偨丄偦傟傑偱彫愢偺側偐偱彈偵怱傪摦偐偝傟傞偙偲偑側偐偭偨儅乕儘僂偑丄偙偙偱偼旤彈偵怱傪扗傢傟偰僉僗偟偨傝丄偦傟偲偼暿偺嬥帩偪彈偲儀僢僪傪偲傕偵偟偨傝偡傞偺偵傕嬃偐偝傟偨丅慡懱偲偟偰丄偦傟傑偱偵側偔暥妛揑側崄傝偵曪傑傟偰偄傞偺傕堎怓偩偭偨丅
偙偺彫愢偵傛偭偰丄傏偔偼僊儉儗僢僩偲偄偆堸傒暔傪妎偊偨偟丄奐揦偟偰娫傕側偄僶乕偺枺椡傕嫵偊傜傟偨偟丄乽僊儉儗僢僩偵偼憗偡偓傞偹乿偲偄偆壢敀偵枺椆偝傟偨丅乽偝傛側傜傪尵偆偺偼彮偟偺偁偄偩巰偸偙偲偩乿偲偄偆暥偑弌偰偔傞偑丄偦偺屻丄僐乕儖丒億乕僞乕偺嶌偭偨乽偝傛側傜傪尵偆偨傃偵乿偲偄偆僗僞儞僟乕僪丒僜儞僌偺壧帉偺堦愡偵乽偝傛側傜傪尵偆偨傃偵丄巹偼彮偟偯偮巰偸乿偲偁傞偺傪抦傝丄偳偭偪偑偳偭偪傪僷僋偭偨偺偩傠偆偲巚偭偨傝偟偨傕偺偩丅
戝妛偺偙傠丄僠儍儞僪儔乕偺挿曇2嶌栚偱偁傞乽偝傜偽垽偟偒彈傛乿偺惔悈弐擇栿偲塸岅偺尨暥傪撉傒斾傋偰丄惔悈栿偵偐側傝偺徣棯偑偁傞偺偵嬃偄偨偙偲偑偁傞丅尨暥偵偁傞暥復傪丄傕偺偵傛偭偰栿偟偰偄側偄偺偩丅塮夋帤枊偑杮嬈偺惔悈側偺偱丄偦偺傗傝曽傪彫愢偱傕摜廝偟偰偄傞偺偩傠偆偐偲巚偭偨丅偨偩偟丄媫偄偱晅偗壛偊偰偍偔偲丄徣棯偑偁偭偰傕惔悈栿偵堘榓姶偼傑偭偨偔側偐偭偨丅娙寜側側偐偵忣姶傪偵偠傑偣偨丄惔悈栿撈摿偺枺椡偁傆傟傞暥懱偵側偭偰偄偨丅東栿偺嵺偵栿幰偺堦懚偱徣棯偟偰偟傑偭偰偄偄偺偐偳偆偐丄堎榑傕偁傞偩傠偆丅偱傕寢壥偲偟偰尨暥偑尒帠側擔杮岅偵堏偟懼偊傜傟偰偍傝丄撉幰偵姶柫傪梌偊傞側傜丄偦傟偑嫋偝傟偰傕偄偄傛偆側婥偑偡傞丅
偝偰丄崱夞偺懞忋弔庽偺怴栿乽儘儞僌丒僌僢僪僶僀乿偩偑丄徣棯偼側偔丄偒傢傔偰拤幚偵栿偟偰偄傞傛偆偩丅暥復傕偆傑偄偟丄尵梩偺巊偄曽偼尰戙揑偱暘偐傝堈偔丄柧夣偩丅偩偑壗偐偙偔偺傛偆側傕偺偑敳偗棊偪偰偍傝丄峴娫偐傜偵偠傒弌傞昞忣偑婓敄側姶偠偑偡傞丅傆偮偆偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢偩偭偨傜丄偙偺傛偆側姡偄偨丄偨傫偨傫偲偟偨暥懱偱偄偄偺偐傕偟傟側偄丅偩偑僠儍儞僪儔乕偼丄僴乕僪儃僀儖僪偲偼尵偊丄偁傞庬偺僙儞僠儊儞僩傪偵偠傑偣偨暥復偱抦傜傟傞嶌壠側偺偩丅偦傟偵斾傋偰丄惔悈栿偺乽挿偄偍暿傟乿偵偼丄偍偦傜偔懡彮偺徣棯偑偁傞偱偁傠偆丅暥懱偼偄傑撉傒曉偡偲屆偄偟丄尵梩偺巊偄曽傕愄晽偱丄偄傑偺姶妎偐傜偡傞偲偟偭偔傝偙側偄売強傕偁傞丅偩偑偦偙偐傜偼撈摿偺忣姶偑棫偪忋偭偰偔傞偟丄儘僒儞僕僃儖僗偺摉帪偺忣宨偑慛傗偐偵晜偐傃忋偑傞丅偨偲偊偰尵偆側傜丄僨僕僞儖榐壒偺CD偲傾僫儘僌榐壒偺LP偺堘偄偩丅僨僕僞儖偼壒偑僋儕傾乕偱僲僀僘傕側偔丄柧傜偐偵壒幙偼偄偄丅偦傟偵斾傋偰傾僫儘僌偼壒幙偼埆偄偑丄壒偵枴傢偄偑偁傝丄壏傕傝偲敡棟傪姶偠偝偣傞丅
偲偄偆偙偲偱丄僠儍儞僪儔乕偼偢偭偲惔悈栿偱姷傟恊偟傫偱偒偨巚偄擖傟傕偁傞偲巚偆偑丄傏偔偲偟偰偼惔悈栿偵垽拝傪妎偊傞丅偩偑偄傑偺庒偄恖偵偲偭偰偼丄偲偆偤傫懞忋栿偺傎偆偑撉傒傗偡偄偩傠偆丅庒偄撉幰偑懞忋栿偱偙偺敿悽婭埲忋傕慜偵弌斉偝傟偨丄偄傑傗屆揟偲尵偊傞彫愢傪撉傫偱丄偳傫側報徾傪庴偗傞偺偐丄嫽枴偁傞偲偙傠偩丅
2008.05.12 (寧) 償傽僱僢僒丒儗僢僪僌儗僀償偺2杮偺怴嶌塮夋
嵟嬤丄偨傑偨傑僀僊儕僗偺彈桪償傽僱僢僒丒儗僢僪僌儗僀償偺弌墘偟偨塮夋傪2杮懕偗偰娤偨丅乽偄偮偐柊傝偵偮偔慜偵乿偲乽偮偖側偄乿偩丅椉曽偲傕墱峴偒偺偁傞偡偖傟偨楒垽僪儔儅偱偁傞丅儗僢僪僌儗僀償偑墘偠傞偺偼巰婜偑敆偭偨榁偄偨彈惈偺栶偱丄庡墘偱偼側偄偑庡墘幰埲忋偵報徾怺偐偭偨丅儗僢僪僌儗僀償偺栶幰偲偟偰偺慺惏傜偟偝偵丄媣偟傇傝偵怗傟傞偙偲偑偱偒偨丅乽偄偮偐柊傝偵偮偔慜偵乿乮儔儂僗丒僐儖僞僀娔撀丄2007擭暷乯偼丄巰偺彴偵暁偟偰偄傞榁彈偺摢偺側偐偱嬱偗弰傞庒偒擔偺堦弖偺楒偺夞憐偑榖偺拞怱偵側傞丅偙偺榁彈偑儗僢僪僌儗僀償偱丄夞憐偺側偐偱庒偒擔偺庡恖岞傪墘偢傞偺偼僋儗傾丒僨僀儞僘丅媣偟傇傝偵娤傞僨僀儞僘偼憡曄傢傜偢壜垽偄偑丄偪傚偭偲擭傪偲偭偨姶偠偑偡傞丅憡庤栶偺庒偄抝傪墘偠傞僷僩儕僢僋丒僂傿儖僜儞偼丄弶傔偰娤傞攐桪偩偑丄偳偙偲側偔儌儞僑儊儕乕丒僋儕僼僩傪巚傢偣傞晽杄傪偟偰偍傝丄岲姶偑帩偰傞丅楒偵棊偪偨偙偺2恖偑丄偁傞帠審偑婲偙偭偰暿傟側偗傟偽側傜側偐偭偨丄偦偺揯枛偑昤偐傟丄庡恖岞偺彈惈偺曕傫偱偒偨恖惗偑丄斵彈偺柡偨偪偵惗偒傞椡傪梌偊傞丅恖惗偼嬻偟偄偗傟偳丄偦傟偱傕惗偒傞壙抣偑偁傞偲偄偆儊僢僙乕僕偼丄彮偟掙偑愺偄姶偠傕偡傞偑丄偗偭偟偰偁偞偲偔偼側偄丅儗僢僪僌儗僀償偺懚嵼姶偺偁傞墘媄偑愨柇偩丅傾儊儕僇偺僯儏乕僀儞僌儔儞僪偺晽宨傕旤偟偄丅廔傢傝嬤偔偵丄庡恖岞偺偐偮偰偺恊桭偺栶偱儊儕儖丒僗僩儕乕僽偑搊応偟丄儗僢僪僌儗僀償偲墘媄傪嫞偆応柺偑偁傞偑丄憡曄傢傜偢僗僩儕乕僽偺偆傑偡偓傞墘媄偑旲偵偮偔丅儗僢僪僌儗僀償偺帺慠偱傢偞偲傜偟偝偺側偄昞忣偲偼戝堘偄偩丅
乽偮偖側偄乿乮僕儑乕丒儔僀僩娔撀丄2007擭塸乯傕傑偨夁嫀偲尰嵼偑2廳丄3廳偵岎嶖偡傞塮夋偩丅1930擭戙偺僀僊儕僗丄忋棳奒媺偺椷忟僉乕儔丒僫僀僩儗僀偲偦偺壆晘偺巊梡恖偱偁傞庒幰偑垽偟崌偆傛偆偵側傞偑丄僫僀僩儗僀偺枀偱彫愢壠傪傔偞偟偰偄傞懡姶側彮彈偑梒側怱偵偦傟傪幑搃偟丄偦偺庒幰偑朶峴帠審偺斊恖偩偲塕偺徹尵傪偟偨偨傔丄庒幰偼戇曔偝傟偰僫僀僩儗僀偲偺拠傪堷偒楐偐傟傞丅埲慜丄僕儑僙僼丒儘乕僕乕娔撀丄僕儏儕乕丒僋儕僗僥傿庡墘偺丄乽楒乿偲偄偆旤偟偔傕巆崜側塮夋偑偁偭偨偑丄偙偺乽偮偖側偄乿偼偦傟偲傛偔帡偨嬝棫偰偱偁傞丅塮夋偱偼丄偦偺屻偺2恖偑偨偳偭偨塣柦偲丄帺暘偺嵾傪壗偲偐偟偰孳偍偆偲偡傞枀偺巔偑昤偐傟傞丅僫僀僩儗僀偺丄乽僷僀儗乕僣丒僆僽丒僇儕價傾儞乿偲偼偍傛偦僀儊乕僕偺堎側傞丄偟偭偲傝偟偨旤偟偄棫偪怳傞晳偄偵栚傪扗傢傟傞丅枀栶偼丄彮彈帪戙丄庒幰帪戙丄榁擭帪戙偲3恖偺栶幰偑墘偠偰偍傝丄巰傪栚慜偵偟偨榁擭偵暞偟偰偄傞偺偑償傽僱僢僒丒儗僢僪僌儗僀償偩丅弌斣偼傎傫偺彮偟偩偗偩偑丄偙傟偑偡偛偄丅偠偮偵梷惂偺偒偄偨丄偦傟偱偄偰昞忣朙偐側墘媄偩丅儔僗僩丒僔乕儞偺旤偟偝偑怺偔怱偵從偒偮偄偰棧傟側偄丅
椉曽偲傕廳偨偄僥乕儅偺塮夋偩偑丄晄巚媍偵娤廔偭偨偁偲偺報徾偼柧傞偔丄偡偑偡偑偟偄丅戝嬥傪偐偗偰嶌偭偨僴儕僂僢僪偺戝嶌塮夋側偳偱偼偲偆偰偄枴傢偊側偄姶柫傪傕偨傜偟偰偔傟傞丅塮夋偲偟偰偺弌棃丄墱怺偝偺揰偱偼丄乽偮偖側偄乿偺傎偆偑堦枃忋偱偁傠偆丅偦傟偵偟偰傕丄偙偆偄偭偨墷暷偺偡偖傟偨塮夋傪娤傞偵偮偗偰傕丄擔杮偺塮夋偺墘媄幰偼側偤傒傫側掙偑愺偔丄壓庤側偺偩傠偆丅惓幃偺墘媄偺孭楙傪庴偗偰偄側偄偐傜偩傠偆偐丄偦傟偲傕揱摑偺堘偄偺偣偄偐丄偁傞偄偼僗僞僢僼傗僉儍僗僩偺塮夋嶌傝偵懳偡傞巔惃偺堘偄偐傜偩傠偆偐丅
2008.05.05 (寧) 堘寷敾寛偼側偤壓偣側偄偺偐乗乗擔杮偺嵸敾惂搙乮偦偺3乯
2008擭4寧偵柤屆壆崅嵸偺敾寛偱帵偝傟偨丄僀儔僋傊偺帺塹戉攈尛偼堘寷偩偲偄偆敾抐偼丄夋婜揑偩偭偨丅敾寛傪壓偟偨惵嶳朚晇嵸敾挿偼掕擭慜偺3寧枛偵埶婅戅怑偟偰偍傝丄敾寛暥偼戙傢傝偺嵸敾挿偑戙撉偟偨丅戅姱屻丄惵嶳巵偼戝妛嫵庼偺怑偵偮偔偲偄偆丅惌晎偑偳傫側屍懅側庤傪巊偭偰洓棟孅傪偙偹傛偆偲傕丄僀儔僋傊偺帺塹戉攈尛偑愴憟峴堊偵壛扴偟偰偄傞偙偲偼扤偺栚偵傕柧傜偐偱偁傝丄寷朄偵堘斀偟偰偄傞偺偼摉偨傝慜偩丅偩偑摉偨傝慜偺偙偲偱偁偭偰傕丄嵸敾姱偵偲偭偰丄堘寷敾寛傪壓偡偵偼丄怑傪帿偡傎偳偺妎屽偑側偗傟偽側傜側偄偺偩丅偙傟偵娭楢偟丄偄偮傕垽撉偟偰偄傞揤栘捈恖巵偺巋寖揑側僽儘僌偵丄1973擭偵挿徖僫僀僉婎抧慽徸偱帺塹戉偺堘寷敾寛傪壓偟偨嶥杫抧嵸偺嵸敾挿丄暉搰廳梇巵偺偙偲偑徯夘偝傟偰偄偨丅寷朄9忦傪傔偖傞堘寷敾寛偼偦傟埲棃偺偙偲偱丄偠偮偵35擭傇傝偩偲偄偆丅暉搰嵸敾挿偵偼丄摉帪丄嵸敾強偺忋憌晹傗崙夛偐傜丄尨崘偺慽偊傪媝壓偡傞傛偆丄偝傑偞傑側偐偨偪偱埑椡偑偐偐偭偰偄偨丅偦傟偵孅偣偢堘寷偺敾寛傪壓偟偨暉搰巵偼丄偦偺屻丄恖帠偺柺偱業崪側寵偑傜偣傪庴偗丄暉搰傗暉堜側偳偺壠嵸偺嵸敾姱傪楌擟丄擇搙偲敾寛暥傪彂偔偙偲側偔丄掕擭傑偱9擭傪巆偟偰戅姱偟丄曎岇巑偵側偭偨丅
崙壠偵偲偭偰搒崌偺埆偄敾寛傪壓偡嵸敾姱偼丄娬怑偵捛偄傗傜傟丄弌悽偺摴偑暵偞偝傟傞丅 偙偺崙偺嵸敾偵偼丄崙壠尃椡偑夘擖偟偰偔傞丅巌朄偺撈棫偲偄偆奣擮偼偨偰傑偊偱偁傝丄巌朄偲偄偊偳傕帪偺尃椡偺堄偵廬懏偡傞偺偑尰幚偩丅朄妛幰偺偁偄偩偵偼丄乽崅搙偵惌帯揑側崙壠峴堊偵偮偄偰丄巌朄偼敾抐偡傞尃棙傪帩偭偰偄側偄乿偲尵偆幰傕偄傞傛偆偩偑丄偲傫偱傕側偄峫偊偩丅棙尃偲搣棙搣棯偵傑傒傟偨惌帯壠偨偪偺朶憱傪嵸敾強偑僠僃僢僋偟側偄偱丄偄偭偨偄扤偑傗傞偲偄偆偺偩丅
偩傜偗偒偭偨惌帯傗姱椈婡峔偲摨條丄巌朄傕傎偙傝偵揾傟偰偄傞丅偍偦傜偔嵸敾姱偵側偭偨摉弶偼棟憐偵擱偊偰偄傞幰傕懡偄偩傠偆丅偩偑偦偺偆偪偵帪棳偵恎傪擟偣丄尃椡偵寎崌偟偰弌悽傊偺摴傪桪愭偡傞傛偆偵側傞丅椻傗斞傪怘偆偺偼扤偩偭偰寵偩丅偩偑偦傟偱偄偄傢偗偼側偄丅暉搰巵傗惵嶳巵偺傛偆側丄弌悽傪搳偘懪偭偰怣擮傪娧偔丄婥崪偺偁傞嵸敾姱偑偄側偗傟偽丄偦偟偰偦傟傪僶僢僋傾僢僾偡傞悽榑偑側偗傟偽丄偙偺崙偺嵸敾強偺懱惂偼晠偭偨傕偺偵側偭偰偟傑偆丅
2008.04.27 (擔) 嵸敾姱偺夁偪偼扤偑嵸偔偺偐乗乗擔杮偺嵸敾惂搙乮偦偺2乯
柍幚偺恖娫偑斊恖偵巇棫偰忋偘傜傟偨媈偄偑擹岤側偺偵丄嵸敾強偼専嶡丒寈嶡偺庡挘偵増偭偨敾寛傪壓偡偲偄偆椺偑丄偙偺偲偙傠憡師偄偱偄傞丅傕偟偐偟偨傜丄偙傫側偲傫偱傕側偄嵸敾偼偄傑偵巒傑偭偨偙偲偱偼側偔丄愄偐傜偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅嵟嬤傛偔儊僨傿傾偱榖戣偵側偭偰偄傞抯娍偺檒嵾帠審傕偦偺傂偲偮偩偑丄偙偙偱栤戣偵偟偨偄偺偼晉嶳導偲崅抦導偱偦傟偧傟婲偙偭偨檒嵾帠審偩丅偙傟傕怴暦傗僥儗價偺曬摴斣慻側偳偱嵦傝忋偘傜傟偰偄傞偺偱丄偛懚抦偺曽傕懡偄偲巚偆丅晉嶳導偺帠審偼丄2002擭偵昘尒巗偱嫮姯偺梕媈偱戇曔偝傟偨抝惈偑丄挦栶3擭偱桳嵾偑妋掕偟丄暈栶偟偰弌強屻偵丄恀斊恖偑帺敀偟偰柍幚偩偲暘偐偭偨偄偆傕偺偩丅嵸敾姱偼傠偔側徹嫆傕側偄偺偵寈嶡偺偹偮憿偟偨暔岅傪怣偠丄専嶡偺尵偆偙偲傪塋撣傒偵偟偰桳嵾偵偟偨丅幚嵺丄偙偺帠審偵娭偡傞婰帠傪撉傓偲丄徹嫆傜偟偄徹嫆偼側偔丄偟偐傕柧敀側傾儕僶僀偑偁傞偺偵丄側偤棫審偟偨偺偐丄側偤桳嵾偵側偭偨偺偐丄晄巚媍偱側傜側偄丅偳傫側偵柍擻側曎岇巑偱傕丄偙傫側偄偄壛尭側棫審偩偭偨傜柍嵾偵傕偭偰偄偗傞偩傠偆偵丄曎岇巑偼偳傫側曎岇傪偟偨偺偩傠偆丅2007擭偵峴傢傟偨傗傝捈偟嵸敾偺嵺偵丄嵸敾挿偼岆怰偟偨偙偲偵懳偡傞偍榣傃傕偟側偐偭偨偟乮摉恖偑傗偭偨岆怰偱偼側偄偵偟偰傕丄嵸敾強偲偟偰幱嵾偡傞偑偁偨傝傑偊偩乯丄寈嶡偺晄摉側憑嵏傗帺敀偺嫮梫丄専嶡偺偢偝傫側庢傝挷傋偵傕尵媦偟側偐偭偨丅曎岇懁偼乽梊抐偲曃尒偵婎偯偄偰晄摉側戇曔丒庢傝挷傋傪偟偨乿偲偄偆偙偲偱摉帪偺導寈庢挷姱偺徹恖恞栤傪媮傔偨偑丄専嶡懁偺尵偄暘傪擣傔偰嵸敾挿偼惪媮傪媝壓偟偰偟傑偭偨丅岆怰偟偨嵸敾姱傕嵟埆偩偑丄偙偺嵞怰偺嵸敾姱傕偳偆偟傛偆傕側偄丅偡偱偵柍幚偼暘偐偭偰偄傞偵偟偰傕丄側偤偙傫側岆擣戇曔丄岆擣婲慽偑婲偙偭偨偺偐傪丄嵸敾傪捠偠偰柧傜偐偵偟丄愑擟幰傪抐嵾偡傋偒偩丅偦偟偰嵟崅嵸偼岆怰偟偨嵸敾姱偵丄偦偆偄偆寢榑偵帄偭偨宱堒傪栤偄偨偩偝側偗傟偽側傜側偄丅恀憡傪偝傜偗弌偝側偗傟偽丄摨偠傛偆側偙偲偑壗搙傕婲偙偭偰偟傑偆丅
崅抦導偺帠審傕丄扤偑尒偰傕寈嶡偺偱偭偪忋偘偲偟偐峫偊傜傟側偄丅2006擭偵崅抦巗峹奜偱導寈偺敀僶僀偲拞妛惗傪忔偣偨僗僋乕儖僶僗偑徴撍偟偨帠審偩丅敀僶僀傪塣揮偟偰偄偨岎捠婡摦戉堳偑巰朣偟丄僗僋乕儖僶僗偺塣揮庤偑埨慡妋擣傪懹偭偨偲偟偰嬈柋忋夁幐抳巰嵾偱婲慽偝傟丄桳嵾偵側偭偨丅偩偑敀僶僀偑柍杁側塣揮偱撍偭崬傫偱偒偨偙偲丄僗僋乕儖僶僗塣揮庤偑廩暘偵姰慡妋擣偟偰偄偨偙偲偼丄僶僗偵忔偭偰偄偨愭惗傗惗搆丄奜晹偺栚寕幰側偳丄懡悢偺恖偺柧妋側徹尵偑偁傞丅傑偨摉帪偙偺摴偱敀僶僀偑栆僗僺乕僪偱塣揮孭楙傪孞傝曉偟偰偄偨帠幚傕偁傞丅桞堦偺徹嫆偱偁傞僽儗乕僉嵀偺幨恀偼愱栧壠偑擖擮偵専徹偟偨寢壥丄寈嶡偺偹偮憿偱偁傞壜擻惈偑偒傢傔偰崅偄丅偵傕偐偐傢傜偢丄抧嵸偺曅懡峃嵸敾挿乗乗埆幙側偺偱偁偊偰柤慜傪嫇偘傞乗乗偼曎岇懁偺庡挘傪堦愗偟傝偧偗丄恎撪傪偐偽偭偰嵾傪揮壟偟傛偆偲偟偰偄傞偲偟偐巚偊側偄寈嶡偺尵偄暘傗寈嶡懁偺徹尵傪慡柺揑偵嵦梡偟丄桳嵾偵偟偨丅2007擭偵崅嵸偱峴傢傟偨峊慽怰偱偼丄幠揷廏庽偲偄偆嵸敾挿偑丄徹嫆挷傋傕偣偢丄懄擔丄忋崘傪媝壓偟偨丅嬃偔偺偼丄偙偺嵸敾挿偑丄偨傑偨傑屻傠傪憱偭偰偄偨暿偺幵偺塣揮庤偺徹尵傪乽嫙弎幰偑戞嶰幰偱偁傞偲偄偆偩偗偱丄偦偺嫙弎偑怣梡偱偒傞傢偗偱偼側偄乿偲偄偆栿偺暘偐傜側偄棟桼偱偟傝偧偗偰偄傞偙偲偩丅偩偭偨傜丄棙奞娭學偺偁傞敀僶僀戉堳偺拠娫偺徹尵偼丄傕偭偲怣梡偱偒側偄偠傖側偄偐丅偙傫側嬸偐側嵸敾姱偑偄傞偲偼怣偠傜傟側偄丅偙傫側柍拑嬯拑側敾寛丄寈嶡偺偱偭偪忋偘偑嫋偝傟傞崙偼丄傕偼傗朄帯崙壠偲偼偲偰傕尵偊側偄丅
嵸敾偲偄偆傕偺偼丄崌棟揑側媈偄偑偁傞傕偺偼柍幚偵丄偮傑傝媈傢偟偒偼敱偣偢偲偄偆偺偑戝尨懃偺偼偢側偺偵丄媈傢偟偄偳偙傠偠傖側偄丄偱偭偪忋偘偺廘偄偑傉傫傉傫偡傞偙偆偄偭偨帠審偵懳偟偰丄偳偆偟偰偙傫側敾寛偑弌偰偟傑偆偺偩傠偆丅傂偲偮偺棟桼偲偟偰丄嵸敾姱偲専嶡偵偼恖帠偺岎棳偑偁傝丄擔忢揑側愙怗偐傜拠娫堄幆偑惗傑傟傞偲偄偆攚宨偑偁傞傜偟偄丅偩偐傜専嶡偺庡挘偵増偭偨敾寛傪偡傞嵸敾姱偑偄傞偲偄偆偺偩丅偙傟偼戅怑偟偨尦嵸敾姱偺徹尵偩丅傕偆傂偲偮偵偼丄嵟嬤偺嵸敾偼検孻傪廳偔偡傞曽岦偵岦偐偭偰偄傞偑丄偦傟偩偗偠傖側偔丄偳偆傕媈傢偟偒傪敱偡傞曽岦偵傕岦偐偭偰偄傞傜偟偄丅柍嵾偑懡偡偓傞偺偱丄傕偭偲桳嵾傪尵偄搉偡傛偆偵偲偄偆埑椡偑偳偙偐偐傜偐偐偭偰偄傞偲偄偆偺偩丅嵟嬤偼丄屟揷帠審偺傛偆偵丄峫椂偡傋偒偙偲偑柧傜偐側怴偟偄徹嫆偑弌偰偒偰傕丄嵞怰惪媮偑婞媝偝傟傞偙偲偑懡偄傛偆偩偑丄偙傟傕忋婰偺傛偆側棟桼偵傛傞傕偺偲巚傢傟傞丅嵸敾姱傕岞柋堳偱偁傝丄恖偺巕側偺偱丄忋巌偺尵偆偙偲傪暦偐側偗傟偽丄抧曽偵旘偽偝傟傞偟丄執偔側傟側偄偲側傟偽丄偦偆偣偞傞傪摼側偄偙偲傕偁傞偺偩傠偆丅偩偐傜丄戅姱傪栚慜偵偟偰崙偵晄棙側敾寛傪壓偡嵸敾姱傗乮柤屆壆崅嵸偺帺塹戉僀儔僋攈尛堘寷敾寛乯丄戅姱屻偵偁偺敾寛偼娫堘偄偩偭偨偲崘敀偡傞嵸敾姱偑乮屟揷帠審偺巰孻敾寛乯弌偰偔傞丅
偦傟傜偑杮摉偩偲偟偨傜乗乗忋偵嫇偘偨帠椺傪尒傞偐偓傝丄杮摉偩偲偟偐峫偊傜傟側偄偑乗乗丄嵸敾傪庴偗傞曽偼偨傑偭偨傕偺偱偼側偄丅嵸敾姱偑恀寱偵丄岞暯偵怰棟偟偨偡偊偵岆偭偨敾抐傪壓偟偨偺側傜丄傑偩暘偐傞丅偩偑嵟弶偐傜専嶡偵桳棙側敾寛傪偡傞偙偲偵寛傔偰偄傞偲偡傟偽丄岞暯偱偁傞傋偒嵸敾姱偑怣棅偱偒側偄偲偡傟偽丄偄偭偨偄偳偆偡傟偽偄偄偺偩丅嵸敾姱偺晄惓偼扤偑嵸偔偺偩傠偆丅
偩偐傜傏偔偼棃擭偐傜巒傑傞嵸敾堳惂搙偵婎杮揑偵巀惉偩丅偙偺惂搙偼傾儊儕僇偺埑椡偵傛偭偰摫擖偝傟偨傕偺偩偐傜偲偐丄扨側傞僈僗敳偒偩偲偐尵偭偰斀懳偡傞惡偑懡偄偑丄偒偭偐偗偑壗偱偁傟丄偄偄惂搙偼庢傝擖傟偨傎偆偑偄偄丅嵸敾堳偑偄偄偺偐丄墷暷偺傛偆側攩怰堳傗嶲怰堳偑偄偄偺偐偳偆偐偼偲傕偐偔丄幮夛偐傜暵偞偝傟偨怑嬈嵸敾姱偵壛偊偰堦斒偺巗柉偑怰棟偵嶲壛偡傞傛偆偵側傟偽丄弾柉姶妎偑斀塮偝傟偨敾寛偑壓偝傟傞壜擻惈偑懡彮偲傕崅傑傞偐傜偩丅
2008.04.25 (嬥) 偄傑偺擔杮偺嵸敾惂搙偼偙傟偱偄偄偺偐乮偦偺1乯
偙偺偲偙傠嵸敾偵偮偄偰峫偊偝偣傜傟傞偙偲偑懡偄丅岝巗曣巕嶦奞帠審偺嵎偟栠偟怰偼巰孻偺敾寛偑弌偨丅嵟崅嵸偑堦怰丒擇怰偺柍婜孻敾寛偼寉偡偓傞偺偱巰孻偑朷傑偟偄偲帵嵈偟偰嵎偟栠偟偨偺偩偐傜丄曎岇懁偑崱夞偺傛偆偵偳傫側偵斱楎側庤傪巊偭偨偲偙傠偱丄偙偺寢壥偵側傞偙偲偼梊憐偑偮偄偰偄偨丅偙傟偩偗偺嬌埆旕摴側斊嵾偩偟丄尰嵼偺擔杮偱偺嵟崅孻偼巰孻側偺偩偐傜丄巰孻偺敾寛偼摉慠偱偁傠偆丅偙偺娫偺丄堚懓丄偲偔偵旐奞幰偺晇偱偁傝晝偩偭偨杮懞偝傫偺婥帩偼丄偲偆偰偄懠恖偑悇偟検傟傞傛偆側傕偺偱偼側偐偭偨偲巚偆丅偦傟偵偟偰傕丄婤慠偲偟偨懺搙偱丄閬偭偨傝嫃捈偭偨傝偡傞偙偲側偔丄庱旜堦娧偟偰帺暘偺峫偊傪庡挘偟偰偒偨杮懞偝傫偺巔惃偼棫攈偩丅怱偺恱偝偲巙偺崅偝偑偁傞丅扤偱傕恀帡偑偱偒傞偙偲偱偼側偄丅偙偺嵸敾偵娭楢偟偰丄偄偔偮偐峫偊傞偲偙傠偑偁傞丅傂偲偮偼丄帠審偑敪惗偟偰偐傜偙偙傑偱偔傞偺偵9擭偲偄偆挿偄嵨寧偑宱偭偰偄傞偙偲偩丅偟偐傕曎岇懁偼峊慽偡傞偲尵偭偰偄傞偺偱丄傑偩寢怰偟偰偄側偄丅偲偵偐偔嵸敾偵帪娫偑偐偐傝夁偓傞丅嵟崅嵸偱偼忋崘屻丄4擭娫傕偐偗偰怰媍偟側偑傜丄帺暘偱敾寛傪壓偝偢偵崅嵸偵嵎偟栠偟偨丅巰孻偑憡摉偲敾抐偟偨偺側傜丄側偤帺傜敾寛傪壓偝側偐偭偨偺偐丅嵎偟栠偟偟偨偭偰丄壓媺偺嵸敾強偼忋偺堄岦偵増偭偨敾寛傪弌偡偵寛傑偭偰偄傞丅巌朄偺懁傕寢怰偡傞傑偱帪娫偑偐偐傝夁偓傞偺偼栤戣偩偲擣幆偟偰偄傞偺側傜丄傕偭偲抁偔偡傞傛偆搘椡偡傋偒偩丅
傕偆傂偲偮偺栤戣偼巰孻傪揔梡偡傞婎弨偑柧妋偱偼側偄偙偲偩丅偙傟傑偱偺敾椺偑戝偒側婎弨偵側傞偲偄偆偙偲偩偑丄偙傟偑擺摼偄偐側偄丅敾椺偑偁偭偰傕偦傟偑懨摉偐偳偆偐暘偐傜側偄偱偼側偄偐丅敾椺偼偁偔傑偱嶲峫偲偄偆偺側傜榖偼暘偐傞偑丅偙偺偲偙傠敾寛偵嵺偟偰検孻偑廳偔側傞孹岦偵偁傝丄岝巗帠審偺2恖偺嶦奞偲偄偆働乕僗偼丄埲慜側傜巰孻偱偼側偔柍婜孻偵側傞恖悢偩偲偄偆丅偦傕偦傕4恖埲忋嶦偟偨傜巰孻偩側偳偲偄偆峫偊曽偑偍偐偟偄丅傂偲傝嶦偟偰傕5恖嶦偟偰傕嶦恖偼嶦恖偩丅斊峴偺摦婡傗嶦奞曽朄傗寁夋揑偩偭偨偐敪嶌揑偩偭偨偐偲偄偭偨揰偼峫椂偝傟傞傋偒偩傠偆偑丄壗恖嶦偟偨偐偱巰孻偐柍婜偐桳婜孻偐偺敾抐偑壓偝傟傞偺偼丄偳偆峫偊偰傕偍偐偟偄丅
尰嵼偺擔杮偺検孻惂搙偵傕栤戣偑偁傞丅嵟崅孻偼巰孻偱偁傝丄偦偺師偵廳偄孻偼柍婜孻偩丅偩偑柍婜孻偺応崌丄幚嵺偵偼憗偔偰10悢擭傎偳偱壖庍曻偝傟幮夛偵弌偰偔傞偲偄偆丅嵟崅孻偲2斣栚偺孻偺偁偄偩偵嵎偑偁傝夁偓傞偺偩丅偦傟傪峫偊傞偲丄旓梡傗廂梕応強偺栤戣傕偁傞偩傠偆偑丄堦惗暵偠崬傔偰幮夛暅婣偝偣側偄廔恎孻偲偄偆検孻偑偁傞傋偒偩偲巚偆丅嫢埆側斊嵾偺壛奞幰偑丄壗偐偺棟桼偱巰孻偵側傜側偔偰傕丄廔恎孻偑偁偭偰偦傟偑揔梡偝傟傟偽丄旐奞幰懁偲偟偰傕彮偟偼婥帩偪偑媥傑傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
偦傟偐傜丄偙傟偼岝巗帠審偲偼娭學偑側偄偟丄巌朄偲偄偆傛傝棫朄偺栤戣偩偑丄憗媫偵夵傔側偗傟偽偄偗側偄偺偼帪岠惂搙偩丅帪岠偼丄帪娫偑宱偰偽偦偺斊嵾偺寉廳偵懳偡傞峫偊曽偑曄傢傝丄幮夛揑側塭嬁傕尭傝丄徹嫆傕嶶堩偡傞偲偄偆棟桼偐傜愝偗傜傟偨惂搙偩偲偄偆丅庯巪偼暘偐傞偑丄側偤嶦恖偺傛偆側丄偳偺帪戙偵偍偄偰傕嫢埆側偙偲偵曄傢傝偼側偄斊嵾偵傑偱揔梡偝偣偰偄傞偺偐偑棟夝偱偒側偄丅壢妛憑嵏偼擔乆敪払偟偰偍傝丄DNA娪掕偵傛偭偰埲慜偼暘愅偱偒側偐偭偨徹嫆傑偱夝柧偱偒傞傛偆偵側偭偰偒偰偄傞丅嵟愭抂偺媄弍偵傛偭偰屆偄徹嫆昳傪娪掕偟丄斊恖傪摿掕偱偒偨偲偟偰傕丄帪岠偺暻偵慾傑傟傞偰戇曔偱偒側偔偰偼堄枴偑側偄丅嫢埆斊嵾偵偼帪岠偑側偄傾儊儕僇偺寈嶡偵偼丄幚嵺偵偦偆偄偭偨忬嫷偵懳墳偟偨枹夝寛帠審愱栧偺晹彁傪愝偗偰偄傞廈傕偁傞丅擔杮傕偣傔偰嶦恖偼帪岠側偟偵偡傋偒偩丅
2008.03.29 (搚) 僕儍僘丒僐儞億乕僓乕丄僼傽儞僞僕乕彫愢丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖
嵟嬤挳偄偨CD乽儈儕傾儉丒傾儖僞乕/儂僄傾丒僀僘丒僛傾乿乮ENJA乯丗僠僃儘偲僋儔儕僱僢僩偲僜僾儔僲偵僗儕乕丒儕僘儉偲偄偆儐僯乕僋側曇惉偺僌儖乕僾偑墘憈偡傞儀儖僊乕偺彈惈僐儞億乕僓乕丄儈儕傾儉丒傾儖僞乕偺嶌昳廤丅忋昳偱廮傜偐偄僒僂儞僪丄婥晧偄偺側偄棊偪拝偄偨暤埻婥偑偄偄丅壗傛傝慺惏傜偟偄偺偼嬋偦偺傕偺偩丅傑傞偱儀僯乕丒僑儖僜儞偺尰戙斉偺傛偆側丄垼姶偨偩傛偆旤偟偄儊儘僨傿偑怱偵煄傒傞丅悢擭慜偵挳偄偨傾儖僞乕偺傾儖僶儉乽傾儖僞乕丒僄僑乿傕摨庯岦偺壚昳偩偭偨丅
乽僪僢僠乕丒儔僀儞僴儖僩/偝傑傛偆摰乿乮OMAGATOKI乯丗僕儍儞僑偺墦墢偩偲偄偆僪僀僣偺彈惈壧庤偺傾儖僶儉丅僕僾僔乕宯乮偄傑偼儘儅偲偐儅僰乕僔儏偲偐尵偆傫偱偡偐乯偺儈儏乕僕僔儍儞偵偼僕儍儞僑偺恊愂偑偨偔偝傫偄傞傜偟偄丅偪傚偭偲僲儔丒僕儑乕儞僘傪巚傢偣傞偲偙傠傕偁傞堦庬偺柍崙愋壒妝偱丄帺慠側壧彞偼岲姶偑帩偰傞丅僕儍儞僑偺嬋傪2嬋壧偭偰偄傞丅乹僰傾乕僕儏乺偺償傽乕僇儖斉偼偙傟傑偱傕偁偭偨偑丄乹儅僀僫乕丒僗僀儞僌乺傪壧偱挳偔偺偼弶傔偰偩丅偙傟偑偠偮偵愻楙偝傟偨怱抧傛偄枴傢偄傪忴偟弌偟偰偄傞丅
嵟嬤撉傫偩杮
乽塣柦偺彂乿僽儔僢僪丒儊儖僣傽乕乮妏愳彂揦乯丗僼儕乕儊僀僜儞偺埫崋塢乆偲偄偆愰揱暥嬪丄偄偐偵傕偦傟傜偟偄憰挌丄僟儞丒僽儔僂儞偲摨偠栿幰偲偄偆丄乽僟償傿儞僠丒僐乕僪乿傪巚傢偣傞僀儊乕僕偵偮傜傟丄楌巎偵旈傔傜傟偨撲傗旈枾寢幮偺堿杁偑僥乕儅偐偲巚偭偰撉傫偩偑丄偦傫側榖偲偼娭學側偄丄偲傫偱傕側偄杴嶌偩偭偨丅偙偆偄偆偁偙偓側愰揱曽朄傪偲傞弌斉幮偵偼暊偑棫偮丅偱傕傑偁丄閤偝傟偨偙偪傜偺晧偗偲偄偆偙偲偩傠偆丅僼儕乕儊僀僜儞偺埫崋偼傎傫偺偝偟傒偺偮傑偱丄撪梕偼傾儊儕僇偺戝摑椞偵傑偮傢傞堿杁榖丅偦偆妱傝愗偭偰偟傑偊偽丄妝偟傔側偄偙偲傕側偄偑丄棳傟偵偁傑傝嬞敆姶偑側偄偟丄偩偄偄偪埆幰偑彫暔偡偓偰丄尐偡偐偟傪怘偭偰偟傑偆丅
乽Y巵偺廔傢傝乿僗僇乕儗僢僩丒僩儅僗乮憗愳彂朳乯丗杮偲揘妛傪儀乕僗偵偟偨僼傽儞僞僕乕彫愢丅戝妛堾偺尋媶惗偱偁傞彈惈庡恖岞偑丄尋媶僥乕儅偱偁傞堎抂嶌壠偺庺傢傟偨杮傪嬼慠庤偵擖傟傞偲偄偆敪抂偼丄僒僼僅儞偺乽晽偺塭乿傪巚傢偣丄杮岲偒傪偲傝偙偵偡傞丅偩偑偦偺偁偲偼揥奐偑僈儔儕偲曄傢偭偰丄庡恖岞偼堄幆偺側偐偺暿悽奅偵擖傝崬傒丄儈僗僥儕傾僗側朻尟傪偡傞偙偲偵側傞丅揘妛丄暔棟妛丄悢妛丄堚揱妛偲偄偭偨丄偝傑偞傑側棟榑偑堷梡偝傟傞偑丄慡懱偲偟偰偙偺庬偺彫愢偵偁傝偑偪側迦妛廘偼偁傑傝側偔丄榖偺揥奐偼僗儉乕僗偩丅偙偺杮偵偼償傽儞丒償僅乕僋僩偺SF彫愢乽旕A偺悽奅乿偺塭嬁偑尒傜傟傞偑丄尰戙揑側傾僀僨傾偑惙傝崬傑傟偰偍傝丄堄幆偺側偐偺悽奅偱偺庡恖岞偺峴摦偼丄傑傞偱塮夋乽儅僩儕僢僋僗乿偺傛偆偩丅偙偺杮偼偍偦傜偔擭枛偺儈僗僥儕乕丒儔儞僉儞僌偱偐側傝偺忋埵偵擖傞偩傠偆丅偱傕傏偔偼偁傑傝崅偄揰偼偮偗側偄丅岲傒偺栤戣偩丅
嵟嬤娤偨塮夋
僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏偺揱婰傪撉傫偩塭嬁偐丄偙偺偲偙傠僼傿儖儉丒僲儚乕儖偵偼傑偭偰偄傞丅僼傿儖儉丒僲儚乕儖偲偼1940擭戙偐傜50擭戙偵偐偗偰傾儊儕僇偱嶌傜傟偨丄偁傞孹岦偺僗儕儔乕/僒僗儁儞僗塮夋偺偙偲偱丄傎偲傫偳偼掅梊嶼偺B媺嶌昳偩丅僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺掕媊偼丄側偳偲尵偄偩偡偲挿偔側傞偺偱巭傔偰偍偙偆丅偄偢傟婡夛偑偁傟偽峞傪夵傔偨偄丅尰嵼擔杮偱DVD偱娤傜傟傞僼傿儖儉丒僲儚乕儖偼偛偔尷傜傟偰偄傞丅埲慜NHK-BS傗WOWOW偱枹岞奐偺婱廳側僲儚乕儖塮夋傪偄偔偮偐曻憲偟偨偑丄傑偩傑偩娤偨偄傕偺偼偨偔偝傫偁傞丅偩傔傕偲偱儗儞僞儖壆偱扵偟偨傜丄婐偟偄偙偲偵埲慜弌偰偄偨RKO嶌昳偺VHS偑偐側傝暲傫偱偄偨丅偙傫側偵價僨僆壔偝傟偰偄偨偲偼抦傜側偐偭偨丅
乽僽儘儞僪偺嶦恖幰乿乮1945擭暷乯丗偲偆偰偄娤傞偙偲偼偱偒側偄偩傠偆偲巚偭偰偄偨僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺堩昳丅娔撀偼僄僪儚乕僪丒僪儈僩儕僋丄尨嶌偼儗僀儌儞僪丒僠儍儞僪儔乕偺乽偝傜偽垽偟偒彈傛乿偩丅庡恖岞偺儅乕儘僂偵暞偡傞僨傿僢僋丒僷僂僄儖偼梲婥側壧偆僗僞乕偲偄偆擃庛側僀儊乕僕偑嫮偄偑丄堄奜偵傕偟傚傏偔傟偰偼偄傞偑僞僼側扵掋偵暞偟偰偄偄枴傪弌偟偰偄傞丅儘僒儞僕僃儖僗偺栭偺奨偑慛傗偐偵塮偟弌偝傟丄丄埆彈偵怳傝夞偝傟傞抝偺垼偟偝偑晜偐傃忋偑傞丅乽偝傜偽垽偟偒彈傛乿偼75擭偵惂嶌偝傟偨儘僶乕僩丒儈僢僠儍儉庡墘嶌偑偁傞丅偙傟傕偄偄弌棃偩偭偨偑丄儈僢僠儍儉偑榁偗偰偄傞偟丄偪傚偭偲僲僗僞儖僕乕姶妎傪偁偞偲偔慜柺偵弌偟夁偓偺姶偑偁偭偨丅
乽埫偄嬀乿乮1946擭暷乯丗偙傟傕儗儞僞儖壆偱尒偮偗偨VHS偱丄娔撀偼儘僶乕僩丒僔僆僪儅僋丄庡墘偼僆儕償傿傾丒僨丒僴償傿儔儞僪丅娔撀偺僔僆僪儅僋偼僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺柤庤偱丄乽尪偺彈乿乽嶦恖幰乿乽傜偣傫奒抜乿側偳丄柤嶌傪偨偔偝傫嶌偭偰偄傞丅偙偺嶌昳偼堦庬偺僯儏乕儘僥傿僢僋丒僒僗儁儞僗偱丄惈奿堎忢幰偺斊嵾偑僥乕儅偵側偭偰偄傞丅憃巕偺彈惈偺偳偪傜偐偑斊恖偩偑丄偳偪傜側偺偐暘偐傜側偄丅師戞偵堎忢幰偺傑偲偭偰偄偨壖柺偑偼偑傟偰偄偔僾儘僙僗偑嬞敆姶傪惙傝忋偘傞丅憃巕傪墘偢傞僴償傿儔儞僪偑偡偛偄丅僴償傿儔儞僪偲偄偊偽丄乽晽偲嫟偵嫀傝偸乿偺儊儔僯乕栶偺偣偄偐丄忋昳偱傗偝偟偄僀儊乕僕偑嫮偄偑丄偙偙偱偺墘媄偼婼婥敆傞傕偺偑偁傞丅
2008.03.17 (寧) 怴嬧峴搶嫗丂愑擟摝傟偵廔巒偡傞愇尨搒抦帠偺廥偝
怴嬧峴搶嫗傪懚懕偝偣傞偐偳偆偐偑寛傑傞搒媍夛偱偺梊嶼埬偺怰媍偑廔傢偭偨傛偆偩丅愇尨搒抦帠偑庡摫偟偰僗僞乕僩偟偨怴嬧峴搶嫗偼丄奐嬈3擭栚偺崱擭3寧婜偺寛嶼偱丄椵愊愒帤偑1000壄墌偵側傞偲偄偆丅栰曻偟摨慠偱偢傞偢傞偲偙偙傑偱埆壔偟丄婋婡偵娮偭偨愑擟偼丄偲偆偤傫嬧峴偺宱塩姴晹偵偁傞偟丄搒媍夛偵傕偁傞偑丄愑擟傪偲傞傋偒嵟戝偺恖暔偼丄扤偑尒偨偭偰搒抦帠偺愇尨偩傠偆丅偲偙傠偑愇尨偼攋抅偺愑擟傪嬧峴偺宱塩幰偩偗偵側偡傝偮偗丄懚懕偺偨傔偵400壄墌偺捛壛弌帒傪採埬偟偰偄傞丅怴偨偵弌帒偟偨偲偙傠偱丄嵞寶偱偒傞曐徹傕尒崬傒傕側偄丅抦帠偼乽棫偰捈偡曽嶔偼偄偔傜傕偁傞乿偲嫮偑傞偑丄嬶懱揑側嶔偼壗傕尵傢側偄丅嵞寶埬傜偟偒傕偺偼偁傞偑丄偛偔戝嶨攃側僾儔儞偱丄偲偆偰偄幚尰壜擻偐偳偆偐敾抐偱偒側偄戙暔偩丅偙偙偱惔嶼偡傟偽1000壄墌偐偐傞偲愇尨偼庡挘偡傞偑丄偙傟傕丄側偤偦傟偩偗偐偐傞偺偐偺嬶懱揑側愢柧偼側偄丅宱嵪傗嬥梈偺愱栧壠偼偙偧偭偰棫偰捈偟偼擄偟偄偲尵偭偰偄傞丅偝傜偵丄愝棫摉弶偺乬拞彫婇嬈偺怳嫽偺偨傔乭偲偄偆庯巪傕丄偡偱偵懚嵼堄媊偼側偔側偭偰偄傞偲偄偆偱偼側偄偐丅搒媍夛偱偺栰搣偺捛媦傕惗偸傞偄丅奀愮嶳愮偺愇尨偵偄偄傛偆偵偁偟傜傢傟偰偄傞丅傑傞偱慺恖偳偆偟偑揇帋崌傪墘偠偰偄傞傛偆偩丅嬧峴懁偺嶌惉偟偨挷嵏曬崘彂偵傛傞偲丄偙偙傑偱帄偭偨偺偼偡傋偰摉弶偺戙昞幏峴栶堳偺愑擟偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞偑丄偙傟傪傑偲傔偨嬧峴偺尰嵼偺戙昞幏峴栶偼丄愝棫偵実傢偭偨尦搒挕偺栶恖偩丅愇尨偺摎曎偲摨偠偵側傞偺偼摉偨傝傑偊偱偁傝丄搒挕偺愑擟偵偡傞偼偢偑側偄丅栰搣偺媍堳偼偦偙傪捛媮偟丄摉帠幰偱偼側偔戞嶰幰偺怣棅偱偒傞挷嵏婡娭偵嵞搙挷嵏偝偣傞傛偆梫媮偡傋偒偩偭偨丅偦偟偰丄傕偆怰媍偼廔傢偭偰偟傑偭偨偑丄偄傑偐傜偱傕抶偔偼側偄丄弶戙偺戙昞幏峴栶傪屇傫偱丄幚懺偼偳偆偩偭偨偺偐傪挳庢偡傋偒偩丅偝傜偵嬥梈挕側傝偟偐傞傋偒婡娭側傝偵怴搶嫗嬧峴偺幚忬傪惛嵏偟偰傕傜偄丄嵞寶嶔偑懨摉偐偳偆偐昡壙偟偰傕傜偆傋偒偩丅愘懍偼岆偭偨寢榑傪惗傓丅
偦傕偦傕愇尨偼丄價僕僱僗丒僐儞僒儖僞儞僩偺戝慜尋堦偑怘帠偺惾偱偟傖傋偭偨傾僀僨傾傪暦偄偰丄偡偖偵偦傟偵旘傃偮偒嬧峴愝棫偵岦偗偰憱傝弌偟偨偲偄偆丅嬥梈偺慺恖偑巚偄偮偒偱偙偲傪塣傫偩傢偗偩丅愇尨偼傓偐偟偐傜庴偗傪慱偭偨戝晽楥晘偑摼堄偩偭偨丅懠崙傪峌寕偟丄幮夛揑庛幰傪晭曁偟丄橖娸晄懟偵傆傞傑偆愇尨偺尵摦偼廥埆偩丅杮恖偼暥妛幰偲帺徧偡傞偑丄幚懱偼嶰暥捠懎嶌壠偱偁傞斵偺昳惈偑偦偺傑傑昞傟偰偄傞丅偙偆偄偆帺屓拞怱宆偺尃椡巙岦恖娫偼丄偊偰偟偰帺暘偺愑擟偲側傞偲摝偘夞傞傕偺偩偑丄偙傟偼愇尨偵尒帠偵摉偰偼傑傞丅怴搶嫗嬧峴偼搒偑85亾偺姅傪曐桳偟偰偍傝丄幚幙偼搒塩嬧峴偩丅搒偺僩僢僾偱偁傞愇尨偲扴摉晹彁偺姴晹偼丄掕婜揑偵宱塩忬懺偵偮偄偰曬崘傪庴偗丄巜帵傪弌偟偰偄偨偼偢偩丅愑擟偑側偄側偳偲偄偆尵偄摝傟偼捠梡偟側偄丅偩偑愇尨偼丄乽弶戙偺戙昞幏峴栶堳偼墱揷尦宱抍楢夛挿偐傜偺悇慐偩乿偲庡挘偟丄乽偡傋偰帺暘偺堦懚偱傗偭偰棃偨傢偗偱偼側偄乿偲尵偄栿偡傞丅偦偆傗偭偰昁巰偱愑擟揮壟偡傞斵偺巔偼斱偟偄丅
傏偔偼搒柉偱偼側偄偑丄搟傝傪妎偊傞丅搒柉傂偲傝偁偨傝1枩墌傪挻偊傞晧扴偵側傞偲偄偆偙傫側偱偨傜傔側捛壛弌帒偑丄嫋偝傟偰偄偄偼偢偑側偄丅偩偑丄偦傕偦傕愇尨偺傛偆側恖娫傪抦帠偵慖傫偩偺偼搒柉偩丅偐傝偵偙偺梊嶼埬偑捠偭偰傕乗乗帺柉搣+岞柧搣偑懡悢傪愯傔傞搒媍夛偩偐傜丄偦偆側傞岞嶼偼崅偄偑乗乗丄偦傟偼愇尨傪慖傫偩帺暘偨偪偺偣偄側偺偩丅
2008.03.14 (嬥) 屒撈偲栂幏偺嶌壠丄僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏
愭擔丄僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏乮僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠乯偺揱婰亀僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠偺惗奤亁乮僼儔儞僔僗丒M丒僱償傿儞僗挊丂2005擭憗愳彂朳姧乯傪撉傫偩丅傾僀儕僢僔儏偼擔杮偱傕僼傽儞偺懡偄傾儊儕僇偺儈僗僥儕乕嶌壠偩丅僴乕僪丒僇償傽乕偺忋壓2姫偲偄偆戝嶌偩偑丄偐側傝偺晹暘偑斵偺彂偄偨18嶜偺挿曇偲偍傃偨偩偟偄悢偵忋傞抁曇偺夝戣偵偁偰傜傟偰偍傝丄揱婰偲偄偆傛傝昡揱偵嬤偄丅偠偮偼傏偔偼偙偺杮偺尨彂傪帩偭偰偄傞丅10悢擭傎偳慜偺偙偲丄傾儊儕僇偺偁傞儅僀僫乕丒儗僐乕僪夛幮偺幮挿偲巇帠偱抦傝崌偭偨丅搉暷偟偨愜傝丄堦弿偵怘帠傪偟偰偄傞嵟拞偵榖偑庯枴偵媦傃丄偍屳偄偵儈僗僥儕乕彫愢偑岲偒偩偲偄偆偙偲偑暘偐偭偨丅偦偺幮挿偑傾僀儕僢僔儏傪抦偭偰偄傞偐偲恥偔偺偱丄戝岲偒偱傎偲傫偳撉傫偱偄傞偲摎偊傞偲丄斵偼戝姶寖偟偨丅斵偼傾僀儕僢僔儏偺戝僼傽儞側偺偵丄廃傝偵偼偁傑傝傾僀儕僢僔儏偑岲偒偲偄偆摨岲偺巑偑偄側偐偭偨偺偩丅婣崙屻偟偽傜偔偡傞偲丄偙偺杮偺尨彂偑僾儗僛儞僩偲偟偰憲傜傟偰偒偨丅婐偟偐偭偨偑丄側偵偣戝晹偺杮側偺偱丄撉傒偲偍偡婥椡偑側偔丄偞偭偲栚傪捠偟偨偩偗偱彂扞偵忺偭偨傑傑偵偟偰偍偄偨丅崱夞丄偁傝偑偨偄偙偲偵丄傗偭偲偦傟傪擔杮岅偱撉傓偙偲偑偱偒偨丅栿幰偺栧栰廤巵偺楯椡傪懡偲偟偨偄丅
傾僀儕僢僔儏偺挿曇彫愢偼偡傋偰憗愳偺億働儈僗偐憂尦暥屔偱東栿偝傟偰偍傝丄傏偔偼偦偺傎偲傫偳傪丄偼傞偐愄偺崅峑偐傜戝妛偺偙傠偵偐偗偰撉傫偩丅壗嶜偐弌偰偄傞抁曇廤傕偄偔偮偐偼撉傫偱偄傞丅戙昞嶌偑偄傑偩偵愨斉偵側傜偢丄憂尦暥屔傗僴儎僇儚暥屔偱擖庤偱偒傞偙偲偐傜偡傞偲丄傾僀儕僢僔儏偼偄傑傕怴偟偄撉幰偵撉傑傟懕偗偰偄傞偺偩傠偆丅
傾僀儕僢僔儏偺彫愢偺側偐偱偄偪偽傫報徾怺偄偺偼丄傗偼傝悽昡崅偄亀尪偺彈亁乮Phantom Lady乯偩丅嶦恖偺寵媈偑偐偐偭偨抝偑傾儕僶僀傪徹柧偟偰偔傟傞堦斢晅偒崌偭偨彈傪昁巰偱扵偡偑墝偺傛偆偵徚偊偰偟傑偭偨撲丄偦偟偰巰孻幏峴偑敆傞側偐昁巰偱偦偺尪偺彈傪扵偡桭恖偺愗敆姶偑嫮楏偒傢傑傝側偄丅偦傟偐傜亀嬇偺巰慄亁乮Deadline at Dawn乯傕朰傟偑偨偄丅搒夛偺曢傜偟偵旀傟偨庒偄抝彈偑栭柧偗傑偱偵奨傪弌傞僶僗偵忔傜側偗傟偽側傜側偄偺偵嶦恖帠審偵姫偒崬傑傟傞偲偄偆愝掕偑嬞敆姶傪忴惉偡傞丅亀栭偼愮偺娽傪帩偮亁乮Night Has a Thousand Eyes乯偼儂儔乕揑側梫慺傕偁傞堎怓嶌偱丄抁偄彉復偺偁偲丄帺嶦偟傛偆偲偟偨彈偺夞憐偲側傝丄偙傟偑偑墑乆偲慡懱偺敿暘嬤偄暘検傕懕偔丅偩偑儔僀僆儞偺妠偵傛偭偰巰偸偲偄偆梊尵偺晄婥枴偝丄慡懱傪巟攝偡傞巰偲塣柦偺僀儊乕僕偑嬞挘姶傪偮偺傜偣傞丅婰壇憆幐傪僥乕儅偵偟偨擹岤側僒僗儁儞僗偑帩懕偡傞亀崟偄僇乕僥儞亁乮The Black Curtain乯傕傛偐偭偨丅
傾僀儕僢僔儏偺儈僗僥儕乕傪暘椶偡傞側傜僗儕儔乕/僒僗儁儞僗偲偄偆偙偲偵側傞偩傠偆丅偩偑偦偺嶌晽偼撈摿偱丄屒撈偲嫲晐丄埆柌偲栂幏偑慡曇傪暍偭偰偄傞丅搊応恖暔偨偪偼丄徟憞偲愨朷偵嬱傜傟側偑傜丄敆傝棃傞巰偲塣柦偵棫偪岦偐偆丅嬝棫偰傗撲夝偒偵偼丄尰幚棧傟偟偨愝掕傗偮偠偮傑偺崌傢側偄偲偙傠傕偁傞偑丄慡懱傪棳傟傞僒僗儁儞僗偑嫮楏側偺偱丄偦傫側寚娮傪悂偒旘偽偟偰偟傑偆丅傾僀儕僢僔儏偺昅抳偼僙儞僠儊儞僞儖偱丄偦偙偑姡偄偨暥懱傪摿挜偲偡傞僴乕僪儃僀儖僪偲偼堦慄傪夋偟偰偄傞丅偦傫側姶彎揑側暥復偑丄傕偺偵傛偭偰偐側傝旲偵偮偔偙偲傕帠幚偩偑丄偼傑偭偨偲偒偵忴偟弌偡儉乕僪偼壗偲傕尵偊側偄枴傢偄偑偁傞丅
偨偲偊偽丄師偺傛偆側暥偩丅偙傟偼桳柤側亀尪偺彈亁偺弌偩偟偺晹暘偱丄抦偭偰偄傞恖傕懡偄偲巚偆偺偱偙偙偵堷梡偡傞偺偼婥偑堷偗傞偑丄偄偪偍偆彂偄偰偍偙偆丅
栭偼庒偔丄斵傕庒偐偭偨丅
偩偑栭偺嬻婥偼娒偄偺偵丄斵偺婥暘偼嬯偐偭偨丅
偙傟偼尨暥偩偲師偺傛偆偵側偭偰偄傞丅
The night was young, and so was he.
But the night was sweet, and he was sour.
尨暥偵偁傞撈摿偺儕僘儉傗儕儕僔僘儉偑丄擔杮岅栿偵側傞偲敄傟偰偟傑偆偺偑巆擮偩丅
傾僀儕僢僔儏偼1930擭戙敿偽偛傠偐傜僷儖僾丒儅僈僕儞偵抁曇僗儕儔乕彫愢傪彂偒巒傔丄恖婥嶌壠偺拠娫擖傝傪壥偨偟偨丅1940擭偵挿曇戞1嶌乽崟堖偺壴壟乿傪姧峴偟偰柤惡傪妋棫丄60擭戙弶傔傑偱彂偒懕偗偨偑丄慡惙婜偼40擭戙偱丄50擭戙埲崀偼抦柤搙偺崅傑傝偲偼棤暊偵丄偁傑傝尒傞傋偒嶌昳偼側偄丅
斵偼嵟弶丄杮柤偺僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠偲偄偆柤慜偱彂偄偰偄偨偑丄搑拞偐傜僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏偲偄偆昅柤傪巊偭偨嶌昳傕暲峴偟偰敪昞偡傞傛偆偵側偭偨丅堦晹丄僕儑乕僕丒僴僾儕乕柤媊偺彫愢傕偁傞丅僽儔僢僋丒僔儕乕僘乮崟堖偺壴壟丄崟偄僇乕僥儞丄崟偄傾儕僶僀側偳乯偺応崌偼僂乕儖儕僢僠丄偦偺懠偺彫愢乮尪偺彈丄嬇偺巰慄丄栭偼愮偺娽傪帩偮側偳乯偼傾僀儕僢僔儏偲偄偆巊偄暘偗傪偟偰偄偨傛偆偩丅嵟嬤偼僂乕儖儕僢僠偲偄偆屇傃曽偱掕拝偟偰偄傞傛偆偩偑丄傏偔偼嵟弶偵撉傫偩偺偑傾僀儕僢僔儏柤媊偺亀尪偺彈亁偩偭偨偙偲傕偁傝丄傾僀儕僢僔儏偲偄偆屇傃曽偺傎偆偵垽拝偑偁傞偺偱丄偙偺懯暥偱偼柤慜傪傾僀儕僢僔儏偵摑堦偟偰偄傞丅
傾僀儕僢僔儏偼惗奤寢崶偣偢丄撈恎偺傑傑曣恊偲堦弿偵儂僥儖廧傑偄傪偟偰偄偨丅奜弌傪寵偄丄恖偲傎偲傫偳晅偒崌偄傪偣偢丄偲偔偵曣恊偑惗偒偰偄傞娫偼丄戝偺戝恖偑乽曣偑僟儊偲尵偭偰偄傞偐傜乿偲偄偆棟桼偱怘帠偺桿偄傪抐偭偰偄偨偲偄偆丅斵偼偁傞庬偺惛恄揑側僐儞僾儗僢僋僗傪書偊偰偄偨偺偩傠偆丅曣恊偺巰屻偼懡彮偼恖晅偒崌偄傕偡傞傛偆偵側傝丄偨傑偵僷乕僥傿側偳偵傕婄傪弌偟偰偄偨丅偦傟偲摨帪偵庰偺検傕嬌抂偵憹偊丄傾儖拞偺傛偆側忬懺偵側傝丄嵟屻偼屒撈偺偆偪偵60擭戙廔傢傝偵巰傫偩丅偙偺偁偨傝偼曣恊傎偳偺擭忋偺彈惈偲寢崶偟丄摨偠偔傾儖拞偵側偭偨僠儍儞僪儔乕偲憡捠偢傞傕偺偑偁傞丅偙偺杮偵傛傞偲丄朣偔側傞慜偺悢擭娫丄傾僀儕僢僔儏偼斵偺彫愢偺僼傽儞偲恊偟偔晅偒崌偭偨傜偟偄丅嶕敊偲偟偨恖惗偺嵟屻嬤偔偵側偭偰岎傢偟偨僼傽儞偲偺岎棳偵娭偡傞僄僺僜乕僪偼丄傎偭偲偡傞傛偆側婥帩偪傪書偐偣傞丅
傾僀儕僢僔儏偺彫愢偼偦偺懡偔偑塮夋壔偝傟偰偄傞丅40擭戙偐傜50擭戙偵偐偗偰丄僴儕僂僢僪偼斵偺彫愢傪尨嶌偲偡傞塮夋傪偝偐傫偵嶌偭偨丅挿曇偼偡傋偰塮夋偵側偭偰偄傞偟丄抁曇傪傕偲偵塮夋壔偝傟偨傕偺傕懡偄丅偦偺側偐偱偄偪偽傫桳柤側偺偼僸僢僠僐僢僋偺亀棤憢亁偱偁傠偆丅偙偺亀棤憢亁偼暿偲偟偰丄偦傟埲奜偺傎偲傫偳偺傾僀儕僢僔儏尨嶌塮夋偼掅梊嶼偺B媺嶌昳偩丅偩偑側偐偵偼僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺屆揟偵側偭偰偄傞傕偺傕偁傞丅偲偔偵儘僶乕僩丒僔僆僪儅僋偑娔撀偟丄僼儔儞僠儑僢僩丒僩乕儞偑庡墘偟偨亀尪偺彈亁偼寙嶌偲偟偰柤崅偄丅偝偡偑偵亀嶦恖幰亁傗亀傜偣傫奒抜亁傪嶌偭偰偄傞僲儚乕儖偺柤庤僔僆僪儅僋偱丄搒夛偺栭偺儉乕僪偑岝偲塭偺悽奅偲偟偰慛傗偐偵塮憸壔偝傟偰偄傞丅僼儔儞僗偺僩儕儏僼僅乕偑亀崟堖偺壴壟亁偲亀埫埮傊偺儚儖僣亁乮埫偔側傞傑偱偙偺楒傪乯傪塮夋壔偟偨偑丄偁傑傝柺敀偔側偐偭偨丅
傾僀儕僢僔儏尨嶌塮夋偱傏偔偑娤偰偄傞偺偼丄僼儔儞僗偱嶌傜傟偨傕偺傪彍偔偲丄亀尪偺彈亁偲亀棤憢亁偺2嶌偩偗偩丅傎偐偵傕娤偨偄塮夋偼偨偔偝傫偁傞偺偵價僨僆壔偝傟偰偄側偄丅挰偵曻偨傟偨昢偑庒偄彈惈偨偪傪廝偆嫲晐傪昤偄偨挿曇亀崟偄傾儕僶僀亁偑尨嶌偺亀The Leopard Man亁乮僕儍僢僋丒僞乕僫乕娔撀乯傗丄嶦恖傪栚寕偟偨偺偵扤傕怣偠偰偔傟側偄彮擭偺晄埨偲嫲晐傪昤偄偨抁曇亀旕忢奒抜亁偑尨嶌偺亀憢亁乮僥僢僪丒僥僗儔僼娔撀乯偼丄僼傿儖儉丒僲儚乕儖偲偟偰偟偽偟偽尵媦偝傟傞丅亀栭偼愮偺栚傪帩偮亁乮僕儑儞丒僼傽儘乕娔撀乯偼塮夋偲偟偰偺弌棃偼椙偔側偄傜偟偄偑丄僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞偑弌偰偄傞偟丄庡戣壧偑僕儍僘丒僗僞儞僟乕僪偵側偭偰偄傞偺偱丄堦搙偼娤偰傒偨偄偲巚偭偰偄傞偺偩偑丄價僨僆壔偝傟傞偺傪懸偮偟偐側偄丅楍幵帠屘偱朣偔側偭偨彈惈偲擖傟懼傢偭偰惗妶偡傞彈偺揯枛傪昤偄偨亀巰幰偲偺寢崶亁偑尨嶌偺僶乕僶儔丒僗僞儞僂傿僢僋庡墘亀No Man of Her Own亁乮儈僢僠僃儖丒儔僀僛儞娔撀乯偵傕嫽枴傪傂偐傟傞丅
亀棤憢亁偼僸僢僠僐僢僋偺柤嶌塮夋偩偑丄尨嶌偺抁曇偲偼帡偰旕側傞傕偺偵巇忋偑偭偰偄傞丅尨嶌偺庡恖岞偼屒撈偱慡懱偺報徾偼埫偄偑丄塮夋偺庡恖岞偼楒恖傗桭恖偑偍傝丄柧傞偝偲墱峴偒傪姶偠偝偣傞偟丄僸僢僠僐僢僋傜偟偄儐乕儌傾傕偁傞丅揱婰偺挊幰偵傛傞偲丄丂傾僀儕僢僔儏偲僸僢僠僐僢僋偵偼惛恄揑孼掜偲傕尵偆傋偒椶帡惈偑偁傞偲偄偆丅嶌昳偺僾儘僢僩傗僒僗儁儞僗偼偨偟偐偵嬤偄傕偺偑偁傞丅僸僢僠僐僢僋偑傾僀儕僢僔儏偺彫愢傪塮夋偵偟偨偺偼亀棤憢亁1嶌偩偗偩偭偨偑丄懠偺嶌壠偑尨嶌偺亀抐奟亁亀媈榝偺塭亁亀巹偼崘敀偡傞亁亀傔傑偄亁側偳偼丄傾僀儕僢僔儏偑尨嶌偲尵偭偰傕偍偐偟偔側偄丅傾僀儕僢僔儏偺埫偝偲僸僢僠僐僢僋偺柧傞偝偼丄堦尒惓斀懳偺傛偆偩偑丄僸僢僠僐僢僋偺塮夋偵偼丄偲偒偳偒埫偄忣擬偲傕尵偆傋偒怱偺埮偑業弌偟偨傕偺偑偁傞丅偩偐傜2恖偼惛恄暘愅揑偵摨椶偩偲偄偆巜揈偼偲偰傕嫽枴怺偄丅
幹懌偩偑丄40擭戙偼儔僕僆偺墿嬥帪戙偱丄傾僀儕僢僔儏偺僒僗儁儞僗嶌昳偼儔僕僆丒僪儔儅偵傄偭偨傝偩偭偨偨傔丄挿丒抁曇傪栤傢偢丄斵偺彫愢傪婎偵偟偨僪儔儅偑懡悢嶌傜傟偨偲偄偆丅嬃偔偺偼弌墘偡傞惡桪偵僴儕僂僢僪丒僗僞乕傪巊偭偰偄傞偙偲偱丄偙偺杮偵傛傞偲丄僼儗僪儕僢僋丒儅乕僠丄儌乕儕儞丒僆僴儔丄働僀儕乕丒僌儔儞僩丄僋儗傾丒僩儗償傽乕丄儖僔儖丒儃乕儖丄僽儔僀傾儞丒僪儞儗償傿丄僕儑僙僼丒僐僢僩儞丄僄僪儚乕僪丒G丒儘價儞僜儞丄僟僫丒傾儞僪儕儏乕僗丄償傿僋僞乕丒儅僠儏傾丄僼儔儞僠儑僢僩丒僩乕儞偲偄偭偨鐱乆偨傞婄傇傟偑暲傫偱偄傞丅偙偺偙傠丄塮夋僗僞乕偵偲偭偰儔僕僆傊偺弌墘偼妱傝偺偄偄彫尛偄壱偓偩偭偨偺偩傠偆偐丅
2008.01.24 (栘) 抍夠僆儎僕偺僸乕儘乕偼價乕僩儖僘側傫偐偠傖側偄
2005擭偵岞奐偝傟偰僸僢僩偟丄嶐擭偼偦偺懕曇傑偱嶌傜傟偨乽嶰挌栚偺梉擔乿偼丄椳傪桿偆僗僩乕儕乕偲偄偄丄偙傟偱傕偐偲弌偰偔傞徍榓30擭戙偺夰偐偟偄晽懎傗梀傃摴嬶傗壠掚梡昳偲偄偄丄偨偟偐偵傛偔偱偒偨塮夋偩偭偨丅偩偑傏偔偺傛偆側丄幚嵺偵偦偺帪戙偵巕嫙偺偙傠傪夁偛偟偨抍夠悽戙偺恖娫偵偲偭偰偼丄晽宨傗彫摴嬶偑壗偐嶌傝暔傔偄偨姶偠偑偟偰丄庤曻偟偱朖傔徧偊傞婥帩偪偵偼側傟側偐偭偨丅偙傟傛傝偼丄彫孖峃暯偺乽揇偺壨乿傗戝椦愰旻偺乽堎恖偨偪偲偺壞乿偺傎偆偑丄偼傞偐偵杮暔偺徍榓30擭戙傪惗恎偱姶偠偝偣偨偟丄姶摦傕怺偄塮夋偩偭偨偲巚偆丅嵟嬤撉傫偩嶳岥暥寷偲偄偆僄僢僙僀僗僩偺彂偄偨乽抍夠傂偲傝傏偭偪乿乮暥弔怴彂乯偼丄抍夠偺悽戙偺幚憸偵偮偄偰彂偐傟偨柺敀偄僄僢僙僀廤偩丅抍夠偺悽戙偲偼戞2師戝愴屻偺儀價乕僽乕儉帪戙丄嬶懱揑偵偼1946擭埲崀偺悢擭娫偵惗傑傟偨恖娫偺偙偲偩偑丄偙偺杮偱偼丄偦偺抍夠悽戙偵傑偮傢傞僀儊乕僕傗敪尵偑徯夘偝傟丄悽戙娤偺偄偄壛尭偝偑椺徹傪岎偊偰寉柇偵岅傜傟偰偄傞丅
偦傕偦傕傏偔偼悽戙榑偲偄偆傕偺偑寵偄偩丅嵟嬤偺庒偄傗偮偼側偳偲尵偭偰丄庒幰偺擃庛偝傪偁偘偮傜偆僆儎僕傪尒傞偲丄帺暘傕庒偄偙傠偼偦偆偩偭偨偠傖側偄偐偲尵偄偨偔側傞丅幮夛偺曄壔偵傛偭偰堄幆傗峴摦偑曄傢傞偺偼摉慠偩偑丄傏偔偼恖娫偺婎杮揑側峫偊曽偵愄傕崱傕偦傟傎偳曄傢傝偼側偄偲巚偆丅儅僗僐儈偼傛偔悽戙偵儗僢僥儖傪揬傠偆偲偡傞丅抍夠偺悽戙側偳偼傕偭傁傜偠偭傁傂偲偐傜偘偱埖傢傟傞偑丄抍夠偲偄偭偰傕恖悢偑懡偄偩偗偵懡庬懡條偱偁傝丄傒傫側偄偭偟傚偔偨偵偝傟偰偄偄傢偗偑側偄丅
抍夠偺悽戙偵偮偄偰棳晍偟偰偄傞堦斒榑偵偼丄懡偔偺岆夝偑偁傞丅抍夠偺悽戙偲偄偆偲乬慡嫟摤乭丄乬價乕僩儖僘乭丄乬僔儞僌儖丒儔僀僼乭偵徾挜偝傟傞傜偟偄丅偩偑丄乬僔儞僌儖丒儔僀僼乭偐偳偆偐偼偝偰偍偒丄乬慡嫟摤乭偵娭偟偰尵偊偽丄杮彂偱彂偐傟偰偄傞偲偍傝丄慡嫟摤偵擖偭偰憶偄偩恖娫偼傏偔傜偺悽戙偺傎傫偺堦埇傝偵偡偓側偄丅傏偔傕摉帪偼億乕儖丒僯僓儞傗僼儔儞僣丒僼傽僲儞傪撉傒丄媑杮棽柧偵孹搢偟丄僨儌偵嶲壛偟偰婡摦戉偵捛偄偐偗傜傟丄摝偘傑偔偭偨丅偟偐偟傑傢傝偵偄傞摨悽戙偺抦傝崌偄傪尒夞偟偰傕丄傎偲傫偳偑偄傢備傞僲儞億儕偱偁傝丄戝妛帪戙偵偦傫側宱尡傪偟偨恖娫偼傎傫偺悢偊傞傎偳偟偐偄側偄丅埑搢揑側彮悢攈偩丅
乬價乕僩儖僘乭偵偮偄偰偼丄偁偨偐傕抍夠偺悽戙偵偲偭偰價乕僩儖僘偑僸乕儘乕偩偭偨偐偺傛偆偵尵傢傟偰偄傞偑丄偙傟偼愨懳偵娫堘偄偩丅傏偔偺宱尡偱尵偊偽丄拞妛偐傜崅峑偵偐偗偰偄偮傕挳偄偰妝偟傫偱偄偨梞妝億僢僾僗偼丄價乕僩儖僘偑弌尰偟偰埲崀偮傑傜側偔側傝丄挳偔偺傪巭傔偨丅偦偟偰丄偦傟埲慜偐傜側傫偲側偔嫽枴傪帩偭偰偄偨僕儍僘偵彮偟偯偮偺傔傝崬傓傛偆偵側偭偨丅偩偐傜丄傏偔偵偲偭偰惵弔帪戙偺壒妝僸乕儘乕偼僄儖償傿僗丒僾儗僗儕乕傗僯乕儖丒僙僟僇丄僸儘僀儞偼僐僯乕丒僼儔儞僔僗傗僕儑僯乕丒僜儅乕僘偱偁傝丄偗偭偟偰價乕僩儖僘偱偼側偄丅傓偟傠價乕僩儖僘偼梞妝億僢僾僗偺揤崙偺傛偆側妝偟偄悽奅傪抧崠偵撍偒棊偟偨丄憺偒揋側偺偩丅偦傫側傆偆偵巚偭偰偄傞摨悽戙偺恖娫偼偨偔偝傫偄傞偼偢偩丅
偲偼尵偊丄悽戙摿桳偺宱尡偵傛偭偰丄抍夠偺恖娫偑摿庩側峴摦傪偲傞偙偲偼偁傞偲巚偆丅偙偺杮傪撉傫偱妋偐偵偦偆偩偲巚偭偨偺偼丄抍夠偺悽戙偼愴憟偺塭傪堷偒偢偭偰偍傝丄僇儔僆働偺儗僷乕僩儕乕偺側偐偵孯壧偑擖偭偰偄傞偲偄偆巜揈偩丅偄傑峫偊傟偽抪偢偐偟偝偱椻娋偑弌偰偔傞偑丄傏偔偑戝妛惗偺偙傠丄僇儔僆働側傫偰偄偆傕偺偼側偐偭偨偑丄乽奀峴偐偽乿傗乽愴桭乿偲偄偭偨孯壧偺壧帉傪妎偊丄弔壧側偳偲偲傕偵悎偑偭偰桭偩偪偲戝惡偱壧偭偰偄偨婰壇偑偁傞丅抍夠偺悽戙偼弮悎側愴屻惗傑傟偱偁傝丄愴憟偼捈愙揑偵偼抦傜側偄傢偗偩偑丄傏偔偨偪偑巕嫙偺偙傠丄戝恖偨偪偑偡傞愴憟偺榖傪暦偄偰偄偨偟丄奨側偐偱偼庤懌偑晄帺桼偵側偭偨偄傢備傞彎醱孯恖偑壒妝傪憈偱偰暔岊偄偟偰偄偨偟丄儔僕僆偱偼廔愴偺崿棎偱峴曽抦傟偢偵側偭偨嬤恊幰傪扵偡乽恞偹恖偺帪娫乿偲偄偆斣慻傪傗偭偰偄偨偟丄梷棷暫偺堷偒梘偘偑戝偒側僯儏乕僗偵側偭偰偄偨丅偩偐傜愴憟偺偙偲偼丄偁傞庬偺媈帡懱尡偲偟偰抦偭偰偄偨偙偲偵側傞丅
挊幰偵傛傟偽丄抍夠僆儎僕偼惡偑偱偐偔偰丄岤婄柍抪偱丄傛偔孮傟偨偑傝丄媍榑岲偒偩偲偄偆偙偲偱丄庒偄楢拞偐傜僶僇偵偝傟丄傑傞偱偍壸暔偺傛偆偵嵎暿偝傟偰偄傞偲偄偆丅傏偔帺恎偵娭偟偰尵偊偽丄偨偟偐偵惡偼偱偐偄偑偗偭偟偰岤婄偱偼側偄偟丄媍榑傕岲偒側傎偆偩偑孮傟傞偺偼寵偄偩丅偦傟偼偲傕偐偔丄恖悢偑懡偄偨傔偵偄傠傫側嬊柺偱夁搙偺嫞憟偵偝傜偝傟丄幮夛栤戣偺僱僞偵側傝懕偗丄偄傑傗掕擭傪寎偊偰帒嶻傗戅怑嬥傪慱偆彜攧恖偨偪偺偊偠偒偵偝傟傛偆偲偟偰偄傞抍夠偺悽戙偑丄側偤偦偙傑偱埆岥傪尵傢傟側偗傟偽側傜側偄偺偐丄搑曽偵曢傟傞偽偐傝偩丅
2008.01.19 (搚) 儁儕乕丒僐儌偺巚偄弌
儁儕乕丒僐儌偑朣偔側偭偰6擭栚偺嶐擭丄斵偑60擭戙敿偽偵榐壒偟偨3枃偺儐僯乕僋側傾儖僶儉偑CD暅崗敪攧偝傟偨丅僇儞僩儕乕傪壧偭偨亀僓丒僔乕儞丒僠僃儞僕僘乮僫僢僔儏償傿儖偵壧偆乯亁丄僇儞僣僅乕僱傪嵦傝忋偘偨亀儁儕乕丒僐儌丒僀儞丒僀僞儕乕乮僀僞儕傾偺巚偄弌乯亁丄儃僒僲償傽偑拞怱偺亀儔僀僩儕乕丒儔僥儞乮僆儖僼僃偺壧乯亁偺3枃偩丅偙傟傜偼椃忣3晹嶌偲偄傢傟偰偄傞偦偆偩丅偦傫側尵梩偼弶傔偰暦偄偨丅乬椃忣乭偲偄偆尵偄曽偑憡墳偟偄偐偳偆偐偼堎榑傕偁傠偆偑丄偙傟傜1965擭偐傜66擭偵偐偗偰惂嶌偝傟偨3枃偺傾儖僶儉偼丄偦傟傑偱偲偼楬慄傪曄偊偨堎怓嶌偲偟偰丄偨偟偐偵堎嵤傪曻偭偰偄傞丅偲偼偄偊丄僫僢僩丒僉儞僌丒僐乕儖傗僨傿乕儞丒儅乕僥傿儞傗僐僯乕丒僼儔儞僔僗側偳墲擭偺恖婥壧庤偼傒側僸僢僩嬋傗僗僞儞僟乕僪偩偗偱側偔丄偙偆偄偭偨條乆側僕儍儞儖偺嬋傕壧偭偰偄偨偺偱偁傝丄僐儌偩偗偑摿暿偩偭偨傢偗偱偼側偄丅儁儕乕丒僐儌偲偄偆偲丄50擭戙偺乽帪偺廔傢傝傑偱乿傗乽惎傪尒偮傔側偄偱乿偲偄偭偨僸僢僩嬋傗丄傾儊儕僇偺僗僞儞僟乕僪丒僜儞僌丄僔儑僂丒僥儏乕儞傪僕儍僕乕偵壧偭偨傾儖僶儉丄70擭戙偺乽傾儞僪丒傾僀丒儔償丒儐乕丒僜乕乿偵傛傞暅妶僸僢僩側偳偱桳柤偩丅偦傫側側偐偵偁偭偰丄偙偺3晹嶌偼偁傑傝堦斒揑偵偼崅偔昡壙偝傟偰偄側偄丅偩偑偙傟偑丄挳偗偽挳偔傎偳枴傢偄怺偄丄斵偺僫僠儏儔儖偱僴乕僩僂僅乕儈儞僌側帩偪枴偑傛偔弌偨丄偠偮偵偄偄弌棃側偺偩丅償僅乕僇儖丒僼傽儞側傜偦偺枺椡偺偲傝偙偵側傞偙偲惪偗崌偄偩丅
儃僒僲償傽偑僐儌偺壐傗偐偱姲偓偺偁傞壧彞偵崌偭偰偄傞偺偼憐憸偺偲偍傝偩偑丄桳柤柍柤偺僇儞僩儕乕丒僫儞僶乕傪丄僗儉乕僗偵偦偟偰寉傗偐偵壧偭偨亀僓丒僔乕儞丒僠僃儞僕僘亁傕慺惏傜偟偄丅壏偐偝偺側偐偵儁乕僜僗傪偨偨偊偨乽帪偺偨偮偺偼憗偄傕偺乿側偳偼嵟崅偩丅3晹嶌偺側偐偱傕偲傝傢偗怱偵嬁偔偺偼僇儞僣僅乕僱傗僀僞儕傾柉梬傪壧偭偨傾儖僶儉亀僐儌丒僀儞丒僀僞儕乕亁偩丅戝曇惉僗僩儕儞僌僗傪僶僢僋偵丄僜僼僩偵丄昳奿朙偐偵丄桰梘敆傜偢壧偆僐儌偼丄僀僞儕傾摿桳偺儊儘僨傿偺旤偟偝偲憡傑偭偰丄壧偺慺惏傜偟偝傪姮擻偝偣偰偔傟傞丅乽傾僱儅丒僄僐乕儗乿傗乽傾儕償僃僨儖僠丒儘乕儅乿側偳偼愨昳偩丅
儁儕乕丒僐儌偼44擭傕偺挿偒偵傢偨偭偰RCA儗乕儀儖偵嵼愋偟偨丅傂偲偮偺儗乕儀儖偲偙傟偩偗挿偔愱懏宊栺傪懕偗偨傾乕僥傿僗僩偼丄壒妝嬈奅偱偼婬桳偱偁傠偆丅僐儌偺僆僼傿僔儍儖側傾儖僶儉偼丄1987擭丄75嵨偺偲偒偵惂嶌偝傟偨傕偺偑嵟屻偵側偭偨偑丄偦偺屻90擭戙偵擖傝丄80嵨傪夁偓偰傕丄斵偼愜偵傆傟偰僐儞僒乕僩傗僣傾乕傪懕偗偰偄偨丅嬃偔傋偒偼榁嫬偵擖偭偰傕側偍丄惡偵悐偊傪姶偠偝偣偢丄庒偄偙傠偲摨偠偔慺惏傜偟偄壧傪斺業偟偰偄偨偙偲偩丅偙傟偼僐儌偑偄傢備傞僋儖乕僫乕丒僗僞僀儖偺壧庤偱丄惡傪挘傝忋偘偰壧偆僞僀僾偱偼側偐偭偨偙偲偵傛傞傕偺偩傠偆丅僐儌傛傝3嵨庒偄僼儔儞僋丒僔僫僩儔偑60擭戙廔傢傝偛傠偵偼憗偔傕悐偊偑栚棫偭偰偄偨偺偲偼懳徠揑偩丅
1982擭11寧丄傏偔偼僯儏乕儓乕僋偺僗僞僕僆偱儁儕乕丒僐儌偵夛偭偨偙偲偑偁傞丅RCA僗僞僕僆偱僕儑儞丒儖僀僗偺儗僐乕僨傿儞僌偵棫偪夛偭偰偄偨偲偒偺偙偲偩丅偦偺僗僞僕僆偺椬偺儗僐乕僨傿儞僌丒儖乕儉偱儁儕乕丒僐儌偑怴嶌傾儖僶儉偺儗僐乕僨傿儞僌傪偟偰偄偨丅偦傟傪抦偭偨傏偔偼丄儖僀僗偺儗僐乕僨傿儞僌偺崌娫傪朌偭偰椬偺晹壆偵峴偒丄偨偨偨傑抦傝崌偄偺娭學幰偑偄偨偺偱僐儌偵徯夘偟偰傕傜偭偨丅傎傫偺偁偄偝偮掱搙偺尵梩傪岎傢偟偨偩偗偩偭偨偑丄僐儌偺壏偐偄恖暱偲戝壧庤側偺偵婥庢傝偺側偄暤埻婥偑怱偵巆偭偨丅恖夰偭偙偄徫婄偼偄傑傕婰壇偵從偒晅偄偰偄傞丅
偦偺梻寧丄僐儌偼2搙栚偺棃擔岞墘傪峴偭偨丅偁傟偼拞栰僒儞僾儔僓偺儂乕儖偩偭偨偩傠偆偐丄弶擔偺僐儞僒乕僩傪挳偒偵峴偭偨丅嵟崅偺僗僥乕僕偩偭偨丅側偐偱傕姶摦偟偨偺偼丄斵偺1955擭偺僸僢僩嬋乽僶儔偺巋惵乿傪壧偭偨偲偒偩偭偨丅偙偺嬋偼擔杮偩偗偱僸僢僩偟丄杮崙偱偼傑偭偨偔柍柤偩偭偨偺偱丄斵偼壧帉傕儊儘僨傿傕妎偊偰偄側偐偭偨丅偩偑偙偺嬋偺擔杮偱偺億僺儏儔儕僥傿傪抦偭偨僐儌偼丄棃擔慜偵晥柺偲儗僐乕僪偱楙廗偟偨丅僗僥乕僕偱偼丄壧帉傪庤偵偟側偑傜丄僆乕働僗僩儔敳偒偱僺傾僲偩偗偺敽憈偱壧偭偨偑丄偦偺壧偼廩暘偵怱偵嬁偄偨丅僼傽儞偺偨傔偵偦偙傑偱弨旛偟偰偔傟偨偙偲偵嫻偑擬偔側偭偨丅偦傟偲斀懳偵丄1984擭偺僟僀僫丒僔儑傾偺弶棃擔岞墘偵偼偑偭偐傝偟偨丅摨偠偔擔杮偩偗偺僸僢僩偱偁傞乽惵偄僇僫儕儎乿傪儗僷乕僩儕乕偵壛偊偨偺偼偄偄偑丄斵彈偼儊儘僨傿傪壧傢偢壧帉偺儗僔僥乕僔儑儞丄偮傑傝楴撉偵廔巒偟偨偺偩丅偙傟偵偼敀偗偨丅彮偟帠慜偵楙廗偟偰偍偗偽壧偊偨偩傠偆偵丅僐儌偲偺壧庤偲偟偰偺僾儘崻惈偺堘偄偑擛幚偵昞傟偨僗僥乕僕偩偭偨丅
幹懌側偑傜晅偗壛偊傞偲丄崱夞丄忋婰偺CD3枃偼SSJ偲偄偆僀儞僨傿儁儞僨儞僩丒儗乕儀儖偵傛偭偰丄尨斦傪強桳偡傞BMG乮RCA乯偐傜僒僽儔僀僙儞僗傪庴偗偰敪攧偝傟偨丅儗僐乕僪夛幮偼僸僢僩嬋巙岦偑傑偡傑偡嫮傑傞孹岦偵偁傝丄偣偭偐偔偁傞帺幮偺夁嫀偺僇僞儘僌偺敪孈傑偱側偐側偐庤偑夞傜側偄偲偙傠偑懡偄丅傑偨儗乕儀儖傪弉抦偟偨儀僥儔儞偺幮堳偑帿傔偰偄偒丄僇僞儘僌傪惗偐偟偨婇夋偑偍傠偦偐偵側傞偲偄偆帠忣傕偁傞偩傠偆丅偩偐傜丄偄傑偺偲偙傠僒僽儔僀僙儞僗偺忦審偑尩偟偄偺偑僱僢僋偵側偭偰偄傞傛偆偩偑丄偙偆偄偭偨堄梸偑偁傝僼傽儞偺僯乕僘傪傛偔抦傞戞3幰偑儊僕儍乕偺夛幮偐傜尨斦傪庁傝庴偗偰敪攧偡傞偲偄偆僗僞僀儖偼丄傕偭偲峀偑偭偰傎偟偄偲巚偆丅
2007.12.26 (悈) 崱擭偺儈僗僥儕乕偼乽僉儏乕僶丒僐僱僋僔儑儞乿偑1埵偩
崱擭傕巆傝偁偲傢偢偐偩丅峆椺偺2007擭奀奜儈僗僥儕乕偺巹揑儀僗僩10傪嫇偘偰偍偙偆丅奀奜儈僗僥儕乕偲偄偭偰傕丄傏偔偑撉傓偺偼丄庡偵僴乕僪儃僀儖僪宯丄朻尟彫愢宯偵尷傜傟傞丅撲夝偒僷僘儔乕傗僲儚乕儖側偳偼傎偲傫偳撉傑側偄偺偱丄摉慠偙偙偵偼擖偭偰偙側偄丅1丏僉儏乕僶丒僐僱僋僔儑儞/傾儖僫儖僪丒僐儗傾乮暥弔暥屔乯
2丏巗柉償傿儞僗/僕僃僗丒僂僅儖僞乕乮憗愳暥屔乯
3丏埫嶦偺傾儖僑儕僘儉/儘僶乕僩丒儔僪儔儉乮怴挭暥屔乯
4丏僥儘儕僗僩偺岥嵗/僋儕僗僩僼傽乕丒儔僀僋乮儔儞僟儉僴僂僗島択幮乯
5丏僟乕僋丒僴乕僶乕/僨僀償傿僢僪丒儂僗僾乮償傿儗僢僕僽僢僋僗乯
6丏廔寛幰偨偪/儅僀僋儖丒僐僫儕乕乮島択幮暥屔乯
7丏暅廞偼偍岲偒丠/僇乕儖丒僴僀傾僙儞乮暥弔暥屔乯
8丏僀儞儌儔儖/僽儔僀傾儞丒僼儕乕儅儞乮憗愳暥屔乯
10嶌慖傏偆偲巚偭偨偑丄傏偔偑撉傫偩斖埻偱崱擭偺儀僗僩偵擖傟傞偵抣偡傞傕偺偼8嶌偟偐側偄丅傑偩僕僃僼儕乕丒僨乕償傽乕偺怴嶌傪撉傫偱偄側偄偟丄撉傫偱偄傟偽摉慠偙偙偵擖傞偲巚偆偑丄偦傟偵偟偰傕崱擭偼偲傃敳偗偨寙嶌偑側偔丄慡懱偵晄嶌偩偭偨丅1埵偺乽僉儏乕僶丒僐僱僋僔儑儞乿偵偮偄偰偼7/18偺擔婰偱彂偄偨偲偍傝丅懡彮峳嶍傝側偲偙傠偑偁傞朻尟彫愢偩偑丄僉儏乕僶偐傜棳傟拝偄偨庡恖岞偺傾儊儕僇偱偺壓廻愭偺曣巕偲偺怱偺岎棳偑姶摦傪屇傇丅2埵偺乽巗柉償傿儞僗乿偼丄嵟嬤懯嶌偺懡偄傾儊儕僇悇棟嶌壠嫤夛徿庴徿嶌偵偟偰偼捒偟偔丄偪傚偭偲僄儖儌傾丒儗僫乕僪傪巚傢偣傞僞僢僠偺丄彫婥枴偄偄斊嵾彫愢偩偭偨丅3埵偺乽埫嶦偺傾儖僑儕僘儉乿偼儔僪儔儉偺巰屻偵敪昞偝傟偨堚峞嶌昳偺傂偲偮丅愨捀婜傪巚傢偣傞弌棃偱丄嫄戝側堿杁偲愴偆抝彈偑夣挷偵昤偐傟丄儁乕僕傪孞傞庤偑巭傑傜側偄丅
4埵偺乽僥儘儕僗僩偺岥嵗乿偼丄榬椡偵帺怣偑側偄嬥梈愱栧偺憑嵏姱偑帒嬥偺棳傟傪扵偭偰僥儘儕僗僩偺夊忛偵敆傞榖丅僗僩乕儕乕偺揥奐偑柺敀偄偟梋塁傕姶偠偝偣傞丅偙偺嶌壠偼傑偩3嶌偟偐朚栿偝傟偰偄側偄偑丄偙傟偐傜偑婜懸偱偒傞恖偩丅5埵乽僟乕僋丒僴乕僶乕乿偺嶌壠儂僗僾偼偙傟偑僨價儏乕嶌偩偑丄悌偵偼傔傜傟偨儃僗僩儞偺庒庤曎岇巑偺昁巰偺愴偄傪僼儗僢僔儏側姶妎偱昤偒丄憉傗偐側撉屻姶傪巆偡丅6埵偺乽廔寛幰偨偪乿偵偮偄偰偼10/6偺擔婰偵彂偄偨丅抧枴偩偑僗僩乕儕乕偺棳傟偼僗僩儗乕僩偱丄撉傒偛偨偊偼廩暘丅7埵偺乽暅廞偼偍岲偒丠乿偼僴僀傾僙儞側傜偱偼偺婏恖偲曄恖丄旂擏偲儐乕儌傾偑枮嵹偱丄偄偮傕偲摨偠偔埨怱偟偰妝偟傔傞堦嶌丅8埵偺乽僀儞儌儔儖乿偼彮偟忕挿偩偟丄儈僗僥儕乕揑偵偼庛偄偑丄庡恖岞偱偁傞儈僱僜僞廈偺揷幧挰偺孻帠偑報徾怺偄僉儍儔僋僞乕偱丄屻敿偵搊応偡傞儔僗儀僈僗偺彈孻帠偲偺弌夛偄傕柺敀偄丅
擭枛偵敪昞偝傟偨乽偙偺儈僗乿偺儀僗僩10偲僟僽傞偺偼僴僀傾僙儞偺1嶌偩偗丅偮傑傜側偄乽偙偺儈僗乿偺儀僗僩10傪偁偘偮傜偭偰傕堄枴偼側偄偑丄僨傿乕償傽乕偼暿偲偟偰丄偁偲偼憡曄傢傜偢丄僲儚乕儖傕偺傗夦婏巇妡偗偺撲夝偒傗婏柇側枴偺抁曇廤偑暲傫偱偄偰丄偍傛偦怘巜傪摦偐偝傟側偄傕偺偽偐傝偩丅乽僉儏乕僶丒僐僱僋僔儑儞乿偑儔儞僋奜側偺偼丄偄偐偵搳昜幰偨偪偑杮傪撉傫偱偄側偄偐傪暔岅偭偰偄傞丅偙偙偱6埵偵擖偭偰偄傞僕儑乕丒僑傾僘偺乽楬忋偺帠審乿傪丄傏偔偼偁傑傝崅偔昡壙偟側偄丅僑傾僘偼岲偒側嶌壠偩偟丄偙偺傛偆側惵弔丒惉挿彫愢偺庯偒傪掓偟偨儈僗僥儕乕偼寵偄偱偼側偄偑丄偙傟偼庡恖岞偺婄偑尒偊偰偙側偄偟丄慡懱偺嶌傝偑敄偭傌傜偄姶偠偑偡傞丅7埵偺乽僨僗丒僐儗僋僞乕僘乿偺僆僇儖僩傗堎忢怱棟傪埖偭偨僗儕儔乕傕偆傫偞傝偩丅
偲偄偆偙偲偱丄崱擭偼奀奜儈僗僥儕乕偼晄嶌偩偭偨偑丄棃擭偼丄僼儘僗僩寈晹僔儕乕僘偺悢擭傇傝偺怴栿乮抶偡偓傞両乯傗丄僌儗僢僌丒儖僢僇偺傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘丄僗僥傿乕償儞丒僴儞僞乕丄僕僃乕儉僗丒僇儖儘僗丒僽儗僀僋丄僱儖僜儞丒僨儈儖側偳丄婜懸偺嶌昳偑懕乆偲東栿弌斉偝傟傞傛偆側偺偱丄擌傗偐偵側傝偦偆偩丅崱擭偼儈僗僥儕乕偺怴嶌傪撉傓偺偼傕偆廔傢傝丅偙傟偐傜惓寧偵偐偗偰偼丄愄撉傫偱柺敀偐偭偨偙偲偼妎偊偰偄傞偑丄撪梕偼朰傟偰偟傑偭偨搒拀摴晇偺揱婏帪戙彫愢傪壗嶜偐彂屔偐傜堷偭挘傝弌偟偰丄撉傒曉偡偲偟傛偆丅
2007.12.10 (寧) 懢査嶮偆偳傫偵偼傑傞
懢査嶮偆偳傫傪偛懚偠偩傠偆偐丅傆偮偆嶮偆偳傫偲偄偆偲丄偪傖傫傐傫偲暲傇挿嶈偺柤暔椏棟偱丄嵶偄僷儕僷儕偺梘偘査偵嫑夘傗栰嵷偺偁傫偑忔偭偐偭偰偄傞傗偮偺偙偲傪尵偆偑丄懢査嶮偆偳傫偼丄懢偔偰廮傜偐偄査傪巊偭偨嶮偆偳傫偺偙偲偩丅傏偔偼偙偺懢査嶮偆偳傫偑戝岲偒偱丄擔杮懢査嶮偆偳傫垽岲壠嫤夛傪愝棫偟偨偄偲巚偭偰偄傞傎偳偩丅7乣8擭慜丄搶嬧嵗偵偁偭偨乽巚埬嫶乿偲偄偆揦偱偙傟傪怘傋偨偺偑丄偦傕偦傕偺偒偭偐偗偩偭偨丅偨傑偨傑拫斞傪怘傋偵擖偭偰偙傟傪拲暥偟偨傜丄敳孮偵偍偄偟偐偭偨丅嬶偺偁傫偼傗傗娒傔偱丄偦傟偵僜乕僗傪偨偭傉傝偐偗偰怘傋傞偲丄側傫偲傕尵偊側偄愨柇偺枴偑岥偺側偐偵峀偑傞丅傏偔偼彫妛峑偐傜崅峑俀擭傑偱媨嶈偵廧傫偱偄偨丅媨嶈巗偵乽巐奀極乿偲偄偆拞壺椏棟揦偑偁傞丅偙傟偼挿嶈偵杮揦偑偁傞揦偱丄拞壺椏棟偲偼偄偭偰傕挿嶈晽偺枴晅偗偑偟偰偁傞丅偙偙偺從偒偦偽偑偍偄偟偔偰丄崅峑偺偙傠丄妛峑婣傝偵偙偺揦偱傛偔怘傋偰偄偨丅偄傑峫偊傞偲丄偦傟偑懢査嶮偆偳傫偩偭偨乮偲巚偆乯丅媨嶈傪棧傟偰悢廫擭丄乽巐奀極乿偱怘傋偨偺偲摨偠從偒偦偽偱弌夛偭偨偙偲偑側偐偭偨偑丄搶嬧嵗偺乽巚埬嫶乿偱怘傋偨懢査嶮偆偳傫偑傑偝偟偔偦偺枴偩偭偨丅
偦傟偐傜婡夛偑偁傞偛偲偵偦偙偱懢査嶮偆偳傫傪怘傋偰偄偨偑丄嶐擭偙偺揦偑暵揦偟偰偟傑偭偨丅埲棃丄搶嫗嬤曈偺懢査嶮偆偳傫偑儊僯儏乕偵偁傞揦傪扵偟偰怘傋曕偄偰偄傞偺偩偑丄偙傟偑堄奜偵彮側偄丅偪傖傫傐傫愱栧揦偱傕丄偨偄偰偄晛捠偺嶮偆偳傫偼偁傞偑丄懢査嶮偆偳傫傪怘傋偝偣傞揦偼偦偆懡偔側偄丅廰扟偺暲栘嫶嬤偔偵偁傞乽挿嶈乿偺懢査嶮偆偳傫偼愨昳偩丅梘偘偨懢査傪巊偭偰偍傝丄偦傟偲偁傫偑偠偮偵傛偔儅僢僠偟偰偄傞丅偁傫偺枴偼巚埬嫶傛傝忋偐傕偟傟側偄丅偙偙偼榁曑偺揦偱丄抮攇惓懢榊偑傛偔棫偪婑偭偨傜偟偄丅屨僲栧偵偁傞乽挿嶈斞揦乿偼僠僃乕儞揦偱丄廰扟傗怴嫶偵傕巟揦偑偁傞丅偙偙偺攧傝偼検偑懡偄偙偲偱丄戝惙傝偵偡傞偲怘傋偒傟側偄偔傜偄傎偳惙傝晅偗偰弌偰偔傞偑丄枴偼偄傑偄偪偩丅偙傟傕偁偪偙偪偵僠僃乕儞揦偑偁傞乽儕儞僈乕僴僢僩乿偼丄懢査嶮偆偳傫偑儊僯儏乕偵側偄揦傕懡偄偑丄廰扟揦偵偼偁傞丅偙偙偼枴傕傛偔抣抜傕庤偛傠偱丄岲姶偑帩偰傞丅乽巚埬嫶乿偼敧挌杧偵杮揦偑偁傞傜偟偄偑丄傑偩峴偭偰偄側偄丅
懢査嶮偆偳傫偼懄惾偺僷僢僋彜昳偑偁傞丅庢傝婑偣偰帋偟偰傒偨偑丄偙傟偑偗偭偙偆媦戞揰傪偮偗傞偙偲偑偱偒傞枴偩偭偨丅僇僢僾査偑僒僢億儘怘昳偐傜弌偨偲偄偆偙偲偩偑丄偳偺僐儞價僯傗僗乕僷乕偵峴偭偰傕抲偄偰側偄丅偄偪偳枴尒傪偟偨偄偲巚偭偰偄傞偺偩偑丄攧傟側偄偐傜憗乆偲惢憿拞巭偟偰偟傑偭偨偺偩傠偆偐丅
2007.12.06 (栘) W.C.僼傿乕儖僘岅榐
悽偺拞偵偼寶慜偲杮壒偑偁傝丄傒傫側偦傟傪忬嫷偵墳偠偰巊偄暘偗偰偄傞偺偩偑丄惌帯壠傗栶恖傗昡榑壠傗儅僗僐儈偑偁傑傝偵偒傟偄偛偲偽偐傝暲傋棫偰偰偽偐傝偄傞偲丄杮摉偺偲偙傠偼偳偆側傫偩丄偨傑偵偼杮壒偼偙偆偩偲尵偭偰傒傠傛偲尵偄偨偔側傞丅帺崙偺棙塿偟偐峫偊偢丄嶻孯堦懱偲側偭偰懠崙偵嶴壭傪傕偨傜偡傾儊儕僇丄偦偺傾儊儕僇偺懏崙偲偟偰尵偄側傝偵側偭偰偒偨偮偗偑傑傢傝丄偄傑傗帒尮栤戣偱怟偵壩偑偮偄偰偄傞擔杮丄偦傟偧傟杮壒偼尒偊尒偊側偺偵丄敀乆偟偄棟孅傪尵偄棫偰偰惓摉壔偟傛偆偲偟偰偄傞丅擔杮偺惌帯壠偨偪傕偦偆偩丅崙柉偺嬯嫬側偳偦偭偪偺偗偱丄昐奞偁偭偰堦棙側偄摿庩朄恖偺夵妚惍棟傪慾巭偟傛偆偲偟偨傝丄昁梫偺側偄摴楬寶愝偺偨傔偺梊嶼傪暘曔傠偆偲偟偰偄傞丅傕偭偲傕傜偟偄棟桼傪偱偭偪偁偘偰偄傞偑丄帺暘偨偪偺棙尃妋曐偺偨傔偱偁傞偙偲偼柧敀偩丅儅僗僐儈偺晄峛斻側偝丄姶搙偺撦偝傕偼側偼偩偟偄丅偳偆偱傕偄偄傛偆側嫽枴杮埵偺帠審偽偐傝傪捛偄偐偗丄側偵偐偺晄徦帠傪婲偙偟偨摉恖偵惓媊柺偟偰嫃忎崅偵幱嵾傪敆傞偄偭傐偆丄偨偲偊偽巐崙偱婲偙偭偨偲傫偱傕側偄寈嶡偺偱偭偪偁偘帠審側偳偼庢傝忋偘傛偆偲偟側偄偟丄愇桘壙奿崅摣偵懳偡傞惌晎偺懳嶔偺抶傟傕捛媮偟傛偆偲偟側偄丅偦偆偄偭偨幮夛揑晄惓傪媶柧偡傞偺偑杮棃偺僕儍乕僫儕僘儉偱偁傞偼偢側偺偵丅
偦傫側忬嫷傪尒傞偵偮偗偰傕巚偄婲偙偝傟傞偺偑丄W.C.僼傿乕儖僘偺尵梩偩丅僼傿乕儖僘偼愴慜偺傾儊儕僇偱塮夋傗儔僕僆偱妶桇偟偨婌寑攐桪偱丄墋悽揑偱恖娫寵偄側僉儍儔僋僞乕偱攧偭偨恖偩丅傾儊儕僇偱偺恖婥偼崅偐偭偨偑丄僠儍僢僾儕儞偺傛偆側徫偄偲儁乕僜僗傪帩偪枴偵偟偨寍恖偱偼側偐偭偨偨傔丄擔杮偱偼庴偗擖傟傜傟側偐偭偨傜偟偄丅偄傑偱偼抦偭偰偄傞恖傕偁傑傝偄側偄偩傠偆丅傏偔傕柤慜偩偗偟偐抦傜偢丄塮夋偼尒偨偙偲偑側偄丅偄傠傫側応柺偱斵偑岅偭偨寵枴偲儐乕儌傾偑側偄傑偤偺尵梩偼丄偦偙偵崬傔傜傟偨旂擏偲媡愢偑庴偗丄昡敾偵側偭偰丄W.C.僼傿乕儖僘岅榐偲偟偰偄傑偵巆偭偰偄傞丅偳偙偱撉傫偩偺偐暦偄偨偺偐丄傑偭偨偔婰壇偵側偄偑丄傏偔偼偦偺岅榐傪庤挔偵儊儌偟偰偄傞丅偄偔偮偐彂偒弌偟偰傒傛偆丅
乽嬥帩偪偲偼丄嬥傪傕偭偰偄傞昻朢恖偵偡偓側偄乿
乽傢偨偟偵曃尒偼側偄丅傒傫側偺偙偲偑暯摍偵戝寵偄偩乿
乽巕嫙偲摦暔偑寵偄偩偐傜偲偄偭偰丄埆偄傗偮偲偼尷傜側偄乿
乽傗偭偰傒偰惉岟偟側偗傟偽丄傕偆堦搙僩儔僀偟傠丄偦偟偰巭傔傠丅
偦傫側偔偩傜側偄偙偲偵偐偐偢傜偆昁梫偼側偄乿
晧偗惿偟傒偲傕奐偒捈傝偲傕庴偗庢傟傞偑丄婾慞傪偮偒丄杮壒偱岅偭偰偄傞偺偑丄偁傞庬丄憉夣偩丅惌帯壠傗栶恖傕偨傑偵偼偙傫側傛偆偵杮壒傪尵偭偨傜偳偆偩傠偆丅偱傕尵偭偨傜儅僗僐儈偑偡偖偝傑婼偺庱偱傕庢偭偨傛偆偵扏偔偩傠偆偟丄尵偊傞傢偗偑側偄偐丅
2007.11.25 (擔) 怴偨偵敪孈偝傟偨僕儍僐偺嬃偔傋偒墘憈
偙傫側惁偄僕儍僐偺枹敪昞壒尮偑偁偭偨偲偼丄婏愓偵嬤偄丅12寧拞弡偵悽奅偵愭嬱偗偰擔杮敪攧偝傟傞亀僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗/儔僀償丒僼儘儉丒僓丒僾儗僀儎乕僘丒僋儔僽亁偩丅1978擭偲偄偊偽丄僕儍僐偑僂僃僓乕丒儕億乕僩偱恖婥偺愨捀偵偁傝丄婥椡傕廩幚偟丄壒妝惈傕捀揰偵偝偟偐偐偭偰偄偨帪婜偩丅僂僃僓乕偺傾儖僶儉偱尵偊偽丄亀僿償傿丒僂僃僓乕亁偲亀儈僗僞乕丒僑乕儞亁偺偁偄偩偵偁偨傞丅偙偙偵偼丄偦偺1978擭1寧丄僕儍僐偑僂僃僓乕偺巇帠偺崌娫傪朌偭偰屘嫿偺僼僅乕僩丒儘乕僟乕僨僀儖偵棦婣傝偟偨嵺丄庒偒擔偵偲傕偵堢偭偨抧尦偺儈儏乕僕僔儍儞拠娫偱偁傞儕僢僠丒僼儔儞僋僗(ds)丄傾儗僢僋僗丒僟乕僉(p)偲僩儕僆傪慻傫偱峴偭偨儔僀償丒僙僢僔儑儞偑廂傔傜傟偰偄傞丅摉帪丄僪儔儅乕偺僼儔儞僋僗偑丄僟乕僉偲慻傫偩僩儕僆偱丄僾儗僀儎乕僘丒僋儔僽偲偄偆儔僂儞僕偵儗僊儏儔乕弌墘偟偰偄偨丅偦偙偵挰偵婣偭偰偒偨偽偐傝偺僕儍僐偑撍慠尰傟丄僼儔儞僋僗偨偪傪嬃偐偣偨丅斵傜偼傒側摨偠僶儞僪偵嵼愋偟偨傝丄儗僐乕僨傿儞僌偱嫟墘偟偨傝偟偰愗狯戶杹偟側偑傜惉挿偟偰偒偨壒妝拠娫偩偭偨丅媣偟傇傝偺嵞夛傪廽偟崌偭偨偁偲丄帩偭偰偒偰偄偨儀乕僗傪庤偵偟偰僕儍僐偑僗僥乕僕偵忋偑傝丄8擭傇傝偺嫟墘僙僢僔儑儞偑巒傑偭偨丅偦偺偲偒媞偺傂偲傝偑榐壒偟偰偄偨僥乕僾偑偙偺壒尮偩丅偦傫側宱堒偱榐傜傟偨傕偺偩偑丄敪攧偵嵺偟偰偼僕儍僐偺堚懓偑娗棟偡傞僷僗僩儕傾僗丒僄僗僥乕僩偑嫋壜傪弌偟偰偍傝丄傟偭偒偲偟偨惓婯斦偵偁偨傞丅
姶摦偝偣傜傟傞偺偼丄怱恎偲傕偵寬峃偱偁傝丄庒偝偵偁傆傟偰偄偨僕儍僐丄偄偪偽傫婸偄偰偄偨帪戙偺僕儍僐偑丄僂僃僓乕偱偺僌儖乕僾偺堦堳偲偟偰偺惂栺偐傜夝曻偝傟丄傂偲傝偺儈儏乕僕僔儍儞偲偟偰偺傃偺傃偲帺桼杬曻偵墘憈偟丄僀儅僕僱乕僔儑儞傪塇偽偨偐偣偰偄傞偙偲偩丅偙偙傑偱僀儞僾儘償傽僀僓乕偲偟偰偺僕儍僐偑慡柺揑偵僼傿乕僠儍乕偝傟偨傾儖僶儉偼偐偮偰側偐偭偨丅偙傟偐傜偼丄偙偺傾儖僶儉傪挳偐偢偟偰僕儍僐傪岅傞偙偲偼偱偒側偔側傞偩傠偆丅暦偔偲偙傠偵傛傞偲丄偙偺偲偒偺壒尮偼偙傟埲奜偵傕偁傞傜偟偄丅嬤偄彨棃偺懕曇偺敪攧傪婜懸偟偨偄丅
朻摢偺儊僪儗乕乹僨僋僗僥儕僥傿乣僪僫丒儕乕乺偐傜丄偄偒側傝堎條側敆椡偵堷偒偢傝崬傑傟傞丅僪儔儉僗偩偗傪僶僢僋偵丄嵟弶偐傜嵟屻傑偱懅傕偮偐偣偢抏偒傑偔傞僕儍僐偺傾僪儕僽偑僗儕儕儞僌偩丅偁傞堄枴偱偙偺傾僪儕僽偼亀徰憸亁強廂偺摨嬋偺傪挻偊偰偄傞偐傕偟傟側偄丅偙傟偼僕儍僐偑旘傃擖傝偱嶲壛偟偨僙僢僔儑儞偱偁傝丄帠慜偵壗偺懪偪崌傢偣傕側偐偭偨偑丄偦傟偑怣偠傜傟側偄傎偳墘憈偺僋僆儕僥傿偼崅偄丅乹僼儕乕僟儉丒僕儍僘丒僟儞僗乺偺3幰偑嬞枾偵堦懱偲側偭偨僟僀僫儈僢僋側僾儗僀丄乹僋儖乣僗僺乕僋丒儔僀僋丒傾丒僠儍僀儖僪乺偺惷偐傜摦傊偲帺嵼偵堏傝曄傢傞戝抇側壒偺棳傟偵偼垹慠偲偝偣傜傟傞丅偙偺擔偑抋惗擔偩偭偨嵢偺僩儗僀僔乕偵曺偘偰丄乹億乕僩儗僀僩丒僆僽丒僩儗僀僔乕乺傪怱傪偙傔偰墘憈偟偰偄傞偺傕嫻傪懪偮丅偙偺嬋偐傜巒傑傞3嬋偺儊僪儗乕偱丄僕儍僐偼偝傑偞傑側嬋偺堷梡傪嶶傝偽傔側偑傜丄偊傫偊傫偲挻愨柍斾偺柍敽憈僜儘傪孞傝峀偘傞丅慡73暘傪偁偭偲偄偆娫偵挳偒廔偊偰偟傑偆丅偙偆偄偭偨嬋傗乹惎塭偺僗僥儔乺傗乹僐儞僥傿僯儏乕儉乺偲偄偭偨偍撻愼傒偺僫儞僶乕偵壛偊丄乹僼儕乕僟儉丒僕儍僘丒僟儞僗乺乹僪儖僼傿儞丒僟儞僗乺乹僱僼僃儖僥傿僥傿乺側偳丄僕儍僐偺墘憈偲偟偰偼偙偙偱偟偐挳偗側偄嬋偑暲傫偱偄傞偺偑僼傽儞偲偟偰偼尒摝偣側偄丅壒幙偼偙偺庬偺僾儔僀償僃乕僩榐壒偵偟偰偼嬃偔傎偳椙岲偩丅
2007.11.05 (寧) 僊儕僔儍偱尒偨擑偼戝偒偐偭偨
10寧拞弡丄僊儕僔儍偵峴偭偰偒偨丅偳偆偟偰傕峴偭偰傒偨偐偭偨偲偄偆傢偗偱傕側偄偑丄傗偼傝暥柧敪徦偺抧偺傂偲偮偱偁傝丄儘乕儅帪戙埲崀偺悽奅偺楌巎傗暥壔偵偝傑偞傑側偐偨偪偱塭嬁傪梌偊偨崙偩丄堦搙偼偦偺晽搚偵怗傟偰偍偐側偗傟偽側傞傑偄丅僊儕僔儍偼偳偙偵峴偭偰傕堚愓偩傜偗偩丅桳柤側傾僥僱偺僷儖僥僲儞恄揳傪偼偠傔丄僨儖僼傿傗僆儕儞僺傾傗儈働乕僱傗丄偲偵偐偔屆戙堚愓偽偐傝偱丄偦傟傜傪尒偰曕偄偰偄傞偲丄偝偡偑偵偄偝偝偐朞偒偰偔傞丅偩偑丄擔杮偑傑偩栱惗帪戙弶婜偵偵偁傝丄暥帤傕側偔丄扜寠幃廧嫃偵廧傒丄傗偭偲庪椔偐傜擾峩偵堏峴偟偮偮傕偄傑偩偵尨巒揑側曢傜偟傪偟偰偄偨帪婜偵丄僊儕僔儍偱偼偡偱偵暥帤傪巊偄丄戝恄揳傪憿傝丄揘妛傗壢妛偑塰偊丄墘寑傪妝偟傓偲偄偆崅搙側惗妶傪塩傫偱偄偨偲偄偆帠幚偼丄惁偄偲偟偐尵偄傛偆偑側偄丅
偄傑偺僊儕僔儍偺嶻嬈偲偄偊偽丄擾嬈側偳偺戞堦師嶻嬈偲娤岝偑庡偩丅彮偟奨傪弌傟偽丄偳偙傑偱傕僆儕乕僽敤傗柸壴敤偑懕偔丅EU壛柨崙偺側偐偱偼昻偟偄傎偆偺晹椶偵擖傞偩傠偆丅偦傟偱傕擔嵎偟偑嫮偄抧拞奀婥岓偺偣偄偐丄恖乆偺昞忣偼柧傞偄丅偩偑埲慜偼丄60擭戙廔傢傝偐傜70擭戙慜敿偵偐偗偰丄孯帠撈嵸惌尃壓偱恖乆偺帺桼偑敍傜傟偰偄偨帪戙偑偁偭偨丅僊儕僔儍偲偄偆偲巚偄晜偐傋傞偺偼丄偦偺偙傠柉庡壔偺偨傔偵愴偭偨彈桪偺儊儕僫丒儊儖僋乕儕偩丅塮夋乽擔梛偼僟儊傛乿傊偺庡墘偱桳柤偩偑丄傎偐偵傕偄偄塮夋偵偨偔偝傫弌偰偄傞丅愒庪傝偱僴儕僂僢僪傪捛傢傟偰儓乕儘僢僷偵搉偭偨柤塮夋娔撀僕儏乕儖僗丒僟僢僔儞偲寢崶偟偨丅乽擔梛偼僟儊傛乿偼僟僢僔儞偑娔撀偟丄弌墘傕偟偰偄傞丅儊儖僋乕儕偼孯帠惌尃偑搢傟偨偁偲暥壔扴摉戝恇偵側偭偰丄僊儕僔儍偐傜奺崙偵帩偪嫀傜傟偨楌巎堚嶻偺曉娨偵恠椡偟偨丅
僊儕僔儍偱偼偁偪偙偪偱丄偁偺乽擔梛偼僟儊傛乿偺僥乕儅丒儊儘僨傿偑棳傟偰偄偨丅傕偪傠傫娤岝媞偺偨傔偵墘憈偟偨傝CD傪偐偗偨傝偟偰偄傞傢偗偱丄尰抧偺恖乆偑擔忢挳偄偰偄傞偺偼億僢僾僗傗儘僢僋偩丅傕偆傂偲偮丄昿斏偵挳偄偨偺偼傾儞僜僯乕丒僋僀儞庡墘塮夋乽偦偺抝僝儖僶乿偺僥乕儅嬋偩偭偨丅僊儕僔儍偺柉懓妝婍僽僘乕僉傪巊偭偨丄偺偳偐偝偺側偐偵垼姶偑昚偆僒僂儞僪偩丅傎偐偵僊儕僔儍傪晳戜偵偟偨塮夋偲偄偊偽丄50擭戙偺屆偄僴儕僂僢僪塮夋偱丄傾儔儞丒儔僢僪偲僜僼傿傾丒儘乕儗儞偑庡墘偟偨乽搰偺彈乿偑偁傞丅奀彈偵側傞庒偄儘乕儗儞偺偼偪偒傟傫偽偐傝偵鐥偟偄擏懱偑榖戣偵側偭偨丅偦偺庡戣壧偱儘乕儗儞偑壧偭偨乽僀儖僇偵忔偭偨彮擭乿偼摉帪擔杮偱傕偐側傝僸僢僩偟偨丅偩偑抧尦偺恖偵恥偄偰傕扤傕偙偺嬋傪抦傜側偐偭偨丅
僶儖僇儞敿搰偺愭抂偐傜撍偒弌偨儁儘億僱僜僗敿搰偵偼堚愓傗屆戙偵塰偊偨挰偑懡偄偑丄崱擭8寧偐傜9寧偵偐偗偰栆埿傪傆傞偭偨嶳壩帠乮曻壩偑尨場偩偲偄偆乯偺愓偑捝乆偟偐偭偨丅摴楬偺曅懁偺偼傞偐屻曽偵楢柸偲懕偔嶳暲偑傒側娵傏偆偢偵側偭偰偄傞丅偦偺忬懺偑摴楬嬤偔傑偱懕偒丄從偗徟偘偺愓偑惗乆偟偄丅僶僗偱憱偭偰偄傞偲丄偦傫側岝宨偑墑乆偲懕偔丅壩帠偺惁傑偠偝偲峀戝側旐奞偑傛偔暘偐偭偨丅
婏娾偱抦傜傟傞僊儕僔儍杒曽偺儊僥僆儔偺嶳偱丄嫄戝側擑傪尒偨丅捒偟偔彮偟塉偑崀偭偨偁偲偩偭偨丅擑偼偡偖娫嬤偺拞嬻偵偐偐偭偰偄偨丅偦偺懌尦偼嶳偁偄偺扟娫偵傑偱怢傃偰偄傞丅擑偺懌尦傪尒偨偺偼弶傔偰偩丅傾僥僱偐傜儊僥僆儔偵峴偔搑拞丄塮夋乽300乿偵弌偰偔傞僗僷儖僞墹儗僆僯僟僗偺摵憸偑寶偭偰偄傞応強偑偁偭偨丅埲慜偼娤岝媞偺娭怱傪屇偽側偐偭偨偑丄塮夋偑岞奐偝傟偰僸僢僩偟偰埲棃丄恖婥偑弌偰偒偨僗億僢僩偩偲偄偆丅偁偨傝偵偼壗傕側偄丄偩偩偭峀偄暯尨偵億僣儞偲摵憸偩偗偑寶偭偰偄傞丅抧柤偼暦偒塳傜偟偨偑丄偙偙偑偐偮偰僥儖儌僺儏儔僀偲屇偽傟偨偲偙傠側偺偩傠偆偐丅儁儘億僱僜僗敿搰偺僗僷儖僞偐傜偼300僉儘埲忋偁傞偩傠偆丅儗僆僯僟僗埲壓偺300恖偼丄偙傫側偵墦偔傑偱墦惇偟偰偒偰10枩恖偺儁儖僔儍偺戝孯偲愴偭偨偺偩丅
僄乕僎奀偺搰偺傂偲偮丄僸僪儔搰偱怘傋偨怴慛側僺僗僞僠僆偑旤枴偩偭偨丅僺僗僞僠僆偼僆儕乕僽側偳偲暲傇僊儕僔儍偺摿嶻昳傜偟偄丅僺僗僞僠僆偺傾僀僗僋儕乕儉傑偱偁傞丅擔杮偱怘傋傞傕偺偲堘偭偰丄崄偽偟偔帟偛偨偊偑偁傝丄枴偑擹偐偭偨丅
2007.11.03 (搚) 彈埫嶦幰僞儔丒僠僃僀僗偼傾儔僽偵岦偐偆
僌儗僢僌丒儖僢僇偼丄儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺乬僴儕乕丒儃僢僔儏乭偲暲傇尰戙嵟崅偺僴乕僪儃僀儖僪丒儈僗僥儕乕丒僔儕乕僘丄乬儃僨傿僈乕僪丒傾僥傿僇僗乭偺嶌幰偩丅偦偺儖僢僇偵傛傞怴偟偄僉儍儔僋僞乕傪庡恖岞偵偟偨僔儕乕僘戞1嶌偺東栿偑敪攧偝傟偨丅亀揤巊偼梕幫側偔嶦偡亁乮暥寍弔廐幮姧乯偩丅庡恖岞偼僞儔丒僠僃僀僗偲偄偆彈惈偱丄奀奜偱偺旕崌朄妶摦偵廬帠偡傞塸崙忣曬晹SIS偺摿柋堳丄偮傑傝埫嶦梫堳偺儕乕僟乕偩丅偙偺杮偱偼丄僀僊儕僗偱僥儘傪孞傝曉偡嫸怣揑僥儘儕僗僩丒僌儖乕僾偺尦嫢偱偁傞拞搶偺僀僗儔儉尨棟庡媊巜摫幰偺埫嶦傪柦偠傜傟偨斵彈偺峴摦偑昤偐傟傞丅僴乕僪儃僀儖僪丒僗僞僀儖偺傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偲偼堎側傝丄偙偪傜偼僗僷僀/朻尟彫愢偺怓崌偄偑擹偄丅庡恖岞偺僞儔丒僠僃僀僗偼丄傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偺亀埫嶦幰亁偱偍傏傠偘偵巔傪尰偟丄亀堩扙幰亁偱慡杄傪偝傜偗弌偟偨惁榬偺彈嶦偟壆僪儔儅傪渇渋偲偝偣傞丅傑偨摨偠傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偺暃庡恖岞偲傕尵偆傋偒彈扵掋僽儕僕僢僩傪巚傢偣傞偲偙傠傕偁傞丅撉傒廔傢偭偰偺姶憐傪傂偲偙偲偱尵偊偽丄偙傟偼僼儕乕儅儞僩儖偲僀傾儞丒僼儗儈儞僌傪儈僢僋僗偟偨傛偆側僗僷僀妶寑偩丅僀僊儕僗偺忣曬慻怐偺側偐偱偺撪晹懳棫傗丄惌帯揑敾抐偵傛偭偰尰応偺梫堳偑幪偰嬵偵偝傟傞忬嫷偑偄偭傐偆偵偁傝丄僾儘偵揙偡傞僋乕儖側嶦偟壆偑扨恎傾儔僽偵忔傝崬傒丄暯慠偲埫嶦傪傗偭偰偺偗傞傾僋僔儑儞偑傕偆偄偭傐偆偵偁傞丅僗僩乕儕偺棳傟偼夣挷偱丄堦婥偵撉傔傞丅朻尟彫愢偲偟偰偼柺敀偄偟丄揥奐傕僗儕儕儞僌偩丅偩偑傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偲偼堘偄丄庡恖岞偺憿宍偵偼怺傒偑側偔丄偦偺懠偺搊応恖暔偨偪偲偺棈傒偵傕堿塭偑側偄偟丄桭忣傗怱堄婥偲偄偭偨傛偆側寣偺捠偭偨梫慺偑姶偠傜傟側偄丅偁偲偑偒偵傛傞偲丄偙傟偼儖僢僇偑尨埬傪彂偄偨僐儈僢僋杮偺僉儍儔僋僞乕傪傕偲偵偟偰彂偐傟偨偦偆偩偑丄偙傫側撪梕偵側偭偰偄傞偺偼偦傟傕塭嬁偟偰偄傞偺偩傠偆丅
偙偺怴僔儕乕僘偼偄偢傟戞2嶌偑朚栿偝傟傞偲偄偆偑丄偦傟偼偲傕偐偔丄傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偼崱屻偳偆側傞偺偐偑婥偵側傞丅1996擭埲崀丄傎傏枅擭1嶌偺儁乕僗偱弌斉偝傟偨傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偼丄5嶌栚偺亀堩扙幰亁傪嵟屻偵拞抐偟偨丅偦偟偰嶌幰偑彂偄偨偺偑丄偙偺僞儔丒僠僃僀僗丒僔儕乕僘傗丄埲慜朚栿偑弌偨彈儘僢僋丒僔儞僈乕傪庡恖岞偵偟偨亀傢偑庤偵塉傪亁偩偭偨丅傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偺慜乆嶌亀榝揗幰亁偼僒僽丒僉儍儔僋僞乕偺僽儕僕僢僩偑庡恖岞偱傾僥傿僇僗偼榚偵夞偭偨斣奜曇丄慜嶌偺亀堩扙幰亁偼傾僥傿僇僗偑彈嶦偟壆偵漟抳偝傟傞偲偄偆堎怓嶌丄偄偢傟傕柺敀偝偼敳孮偩偭偨偑丄僔儕乕僘悢嶌栚偵偟偰憗偔傕僗僩乕儕乕偑奼嶶偟偰偟傑偭偨丅僼傽儞偲偟偰偼丄峴摦偡傞悽奅偼嫹偔偰傕丄拠娫偲偺楢懷姶傗抝彈偺娭學偺婡旝傪昤偒側偑傜丄僾儘偲偟偰偺徉帩傪傕偭偰妶桇偡傞儃僨傿僈乕僪偲偄偆摿庩側悽奅傪偠偭偔傝昤偒崬傫偩嶌昳傪傕偭偲彂偄偰傎偟偄偲巚偆丅傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偼丄6擭娫偺拞抐傪宱偰丄怴嶌偑崱擭傾儊儕僇偱弌斉偝傟偨傜偟偄丅偳傫側撪梕側偺偐丄婜懸偟偰東栿傪懸偪偨偄丅
2007.11.01 (栘) 栚傪偔偓晅偗偵偡傞敆椡枮揰偺僐儖僩儗乕儞偺DVD
僕儑儞丒僐儖僩儗乕儞偺儓乕儘僢僷偱偺儔僀償傪廂傔偨嬃偔傋偒DVD偑敪攧偝傟偨丅亀Jazz Icons: John Coltrane Live in '60, '61, '65亁偑偦傟偩丅偙偙偵偼丄偦傟偧傟偑僐儖僩儗乕儞偺60擭戙偺曕傒偵偍偗傞廳梫側僗僥僢僾偲側傞帪婜偺3庬椶偺墘憈偑廂傔傜傟偰偄傞丅偙傟傜偺僼僢僥乕僕偑弶價僨僆壔偺傕偺側偺偐偳偆偐丄僕儍僘DVD偵偦傟傎偳徻偟偔側偄偺偱暘偐傜側偄丅傕偲偼僥儗價偱僆儞丒僄傾偝傟偨傕偺傜偟偄偑丄夋幙偼傑偁傑偁偩丅偩偑偦傫側偙偲傛傝丄傾僩儔儞僥傿僢僋帪戙偐傜墿嬥偺僇儖僥僢僩偺枛婜偵帄傞僐儖僩儗乕儞偺敪揥丒曄杄偑丄偙偺1姫偱栚偺摉偨傝偵偱偒傞偺偑慺惏傜偟偄丅側偵偟傠丄僐儖僩儗乕儞偲働儕乕偺嫟墘丄丄僪儖僼傿乕偲偺嫟墘丄墿嬥偺僇儖僥僢僩偺敆椡枮揰偺塮憸偑師乆偵弌偰偔傞偺偩偐傜惁偄丅嵟弶偺僙僢僩偼1960擭3寧偵僪僀僣偱嶣塭偝傟偨傕偺丅偙傟偼儅僀儖僗丒僨僀償傿僗丒僋僀儞僥僢僩偑搉墷偟偨嵺偵儅僀儖僗敳偒偱墘憈偝傟偨僗僥乕僕偩丅僐儖僩儗乕儞乣僂傿儞僩儞丒働儕乕乣億乕儖丒僠僃儞僶乕僗乣僕儈乕丒僐僽偲偄偆婄傇傟偵傛傝丄乹僌儕乕儞丒僪儖僼傿儞丒僗僩儕乕僩乺乹僂僅乕僉儞乺乹僓丒僥乕儅乺傪墘憈偡傞丅偙偺偲偒丄僩儗乕儞偼儅僀儖僗偺傕偲傪棧傟偰撈棫偡傞堄巚傪屌傔偰偄偨偑丄儅僀儖僗偵偙傟偑嵟屻偩偐傜偲愢偒暁偣傜傟偰丄偄傗偄傗側偑傜僣傾乕偵嶲壛偟偨偲偄偆丅傾僩儔儞僥傿僢僋傊偺亀僕儍僀傾儞僩丒僗僥僢僾僗亁僙僢僔儑儞偐傜8儢寧屻偱偁傝丄僩儗乕儞偼帺怣偵枮偪偨昞忣偱怺偄僄儌乕僔儑儞傪偨偨偊側偑傜悂偄偰偄傞丅
偙偺僙僢僩偱婱廳側偺偼僂傿儞僩儞丒働儕乕偩丅働儕乕傪懆偊偨塮憸偼彮側偄偩偗偵丄僺傾僯僗僩偺側偐偱偄偪偽傫垽偡傞働儕乕偑愨捀婜偵墘憈偡傞惗偺巔偑尒傜傟傞偺偑丄傏偔偵偲偭偰偼嵟崅偵偆傟偟偄丅乹屚梩乺乮働儕乕乯乣乹儂儚僢僣丒僯儏乕乺乮僐儖僩儗乕儞乯乣乹償傽乕儌儞僩偺寧乺乮僗僞儞丒僎僢僣乯偲懕偔僶儔乕僪丒儊僪儗乕傕挳偒傕偺偩丅偙偙偱僎僢僣偑壛傢傞丅偙偺僣傾乕偼僲乕儅儞丒僌儔儞僣偑婇夋偟偨傕偺偱丄儅僀儖僗偺傎偐丄僗僞儞丒僎僢僣偲僆僗僇乕丒僺乕僞乕僜儞偑摨峴偟偰偄偨丅偙偺僙僢僩偵偼偦偺僎僢僣偲僺乕僞乕僜儞偑僎僗僩偱嶲壛偟丄嵟屻偺乹僴僢働儞僒僢僋乺偱僐儖僩儗乕儞偲嫟墘偡傞丅僎僢僣偼帪乆儔僀償偱庤敳偒傪偟偨偲偄偆偙偲偩偑丄偙偙偱偺僎僢僣偼杮婥傪弌偟偰偍傝丄僐儖僩儗乕儞偲婥崌偄偺擖偭偨妡偗崌偄傪偡傞丅嵍塃偵暲傫偩2恖偑僒僢僋僗傪岥偵偔傢偊傞捈慜丄婄傪尒崌偣偰僯儎僢偲徫偆偺偑報徾怺偄丅
懕偔僙僢僩偼1961擭12寧偵摨偠偔僪僀僣偱嶣傜傟偨塮憸丅僐儖僩儗乕儞偼慜寧偵僄儕僢僋丒僪儖僼傿傪壛偊偰桳柤側償傿儗僢僕丒償傽儞僈乕僪偱偺儔僀償丒僙僢僔儑儞傪峴偭偰偍傝丄偙傟偼偦偺梻寧丄傑偭偨偔摨偠儊儞僶乕乗乗僐儖僩儗乕儞乣僪儖僼傿乣儅僢僐僀乣儚乕僋儅儞乣僄儖償傿儞乗乗偱儓乕儘僢僷偵僣傾乕偟偨嵺偺儔僀償偩丅嬋偼乹儅僀丒僼僃僀償傽儕僢僩丒僔儞僌僘乺乹偝傛側傜傪尵偆偨傃偵乺乹僀儞僾儗僢僔儑儞僘乺偺3嬋丅偙偙偱偼懄嫽墘憈偺尷奅傪撍偒攋傠偆偲偡傞偐偺傛偆側丄攋抾偺惃偄偱悂偒傑偔傞僐儖僩儗乕儞偑埑姫偩丅偙偺儓乕儘僢僷丒僣傾乕偼僐儖僩儗乕儞偑儕乕僟乕偲偟偰弶傔偰峴偭偨傕偺偩偭偨丅
嵟屻偺僙僢僩偼1965擭8寧丄儀儖僊乕偱僔儏乕僥傿儞僌偝傟偨傕偺丅僐儖僩儗乕儞乣儅僢僐僀乣僊儍儕僜儞乣僄儖償傿儞偲偄偆墿嬥偺僇儖僥僢僩偵傛傝丄乹儅僀丒僼僃僀償傽儕僢僩丒僔儞僌僘乺乹僫僀乕儅乺乹償傿僕儖乺偑墘憈偝傟傞丅偙偙偱偺僩儗乕儞偼僼儕乕僉乕側僩乕儞傪懡梡偟丄傛傝寖墇側僾儗僀傪孞傝峀偘傞丅偙傟傛傝9儢寧慜丄僐儖僩儗乕儞偼亀帄忋偺垽亁傪悂偒崬傒丄埲屻媫懍偵僼儕乕側僗僞僀儖偵孹幬偟偰偄偭偨偑丄偙傟偼偦偺帪婜偺墘憈偱偁傝丄傑偝偵崿撟偺悽奅偵懌傪摜傒擖傟傛偆偲偡傞僐儖僩儗乕儞偑懆偊傜傟偰偄傞丅僩儗乕儞偺嬯捝傪懴偊傞傛偆側昞忣丄僪儔儉僗傪扏偔僄儖償傿儞偺懱偐傜傕偆傕偆偲敪偡傞搾婥偺傛偆側敀偄墝傝偑報徾偵巆傞丅偙偺擭偺枛丄僇儖僥僢僩偐傜儅僢僐僀偲僄儖償傿儞偑扙戅偟丄僐儖僩儗乕儞偼姰慡偵柍挷偺悽奅偵擖傝崬傓偙偲偵側傞丅
偙偺Jazz Icons戞2婜僔儕乕僘偵偼丄戞1婜偵懕偄偰丄僼傽儞偺娭怱傪偦偦傞DVD偑偨偔偝傫廂傔傜傟偰偄傞丅側偐偱傕丄偙偺僐儖僩儗乕儞偺傎偐丄偁偺僆僋僞乕僽憈朄偑偨偭傉傝姮擻偱偒傞僂僃僗丒儌儞僑儊儕乕傗丄億乕儖丒僨僗儌儞僪傪僼傿乕僠儍乕偟偨僨僀償丒僽儖乕儀僢僋丒僇儖僥僢僩乮僪儔儉僗偼僕儑乕丒儌儗儘両乯丄僪儖僼傿乕傪梚偡傞儈儞僈僗丒僌儖乕僾側偳偺塮憸偼丄扤傕偑尒偨偔側傞偩傠偆丅
2007.10.06 (搚) 孻帠偵暅怑偟偨僴儕乕丒儃僢僔儏傪懸偭偰偄偨帠審偼
尰戙嵟崅偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢偲尵偊傞儅僀僋儖丒僐僫儕乕嶌僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺怴嶌乽廔寛幰偨偪乿乮島択幮暥屔乯偑敪攧偝傟偨丅巹棫扵掋偵側偭偰偄偨儃僢僔儏偼丄慜嶌偺嵟屻偱埫帵偝傟偰偄偨偲偍傝丄LA巗寈偺孻帠偵暅怑偟丄枹夝寛帠審憑嵏斍偵強懏偟偰丄埲慜僠乕儉傪慻傫偱偄偨彈惈孻帠僉僘儈儞丒儔僀僟乕偲嵞傃僐儞價傪慻傫偱丄17擭慜偵婲偙偭偨彮彈嶦奞帠審偺嵞憑嵏偵偁偨傞丅儃僢僔儏丒僔儕乕僘偺偡偛偄偲偙傠偼丄偙傟傑偱偺11嶌丄偳傟傪偲偭偰傕懯嶌偑側偄偙偲偩丅偲偆偤傫弌棃偺椙偟埆偟偼偁傞偑丄埆偄偲尵偭偰傕捠忢偺婎弨偐傜偄偗偽丄廩暘偵崅偄儗儀儖偵払偟偰偄傞丅戞1嶌偺乽僫僀僩丒儂乕僋僗乿偐傜1嶌偛偲偵崅傒偵忋偭偰偄偭偨偙偺僔儕乕僘偼丄戞4嶌偺乽儔僗僩丒僐儓乕僥乿偱捀揰偵払偟偨姶偑偁偭偨丅偦偺屻丄戞5嶌乽僩儔儞僋丒儈儏乕僕僢僋乿傪宱偰丄戞6嶌偺乽僄儞僕僃儖僘丒僼儔僀僩乿偁偨傝偐傜戞8嶌乽僔僥傿丒僆僽丒儃乕儞僘乿傑偱偼丄傗傗椡偑棊偪偨傛偆偵巚傢傟偨偑丄儃僢僔儏偑孻帠傪帿偟偰扵掋偵側偭偨9嶌栚偺乽埫偔惞側傞栭乿偲10嶌栚偺乽揤巊偲嵾偺奨乿偱丄嵞傃偐偮偰偺婸偒偲僷儚乕傪庢傝栠偟偨丅帺桼偵側偭偨儃僢僔儏偑妶桇偡傞偙偺2嶌偵偼丄偦傟傑偱偵側偄怱偺備偲傝偺傛偆側傕偺偑忴偟弌偝傟偰偍傝丄儃僢僔儏丒僔儕乕僘偑怴偟偄抜奒偵擖偭偨偙偲傪姶偠偝偣偨丅
偦傟傪庴偗偰偺11嶌栚偵側傞杮彂偩偑丄偟偽傜偔偺偁偄偩寈嶡婡峔偐傜夝曻偝傟偰偄偨偨傔偐丄偦傟偲傕孻帠偵暅婣偟偨偽偐傝偺偣偄偐丄枹夝寛帠審傪嵞憑嵏偡傞儃僢僔儏偼丄偙傟傑偱偵斾傋偰堦旵楾偲偟偰偺惈奿傗撪柺偵烼孅偟偰偄傞搟傝傪偁傑傝昞偵弌偝側偄丅傑偨慡懱偵摦偒偑彮側偔丄慜敿偼愄偺徹嫆傗嫙弎挷彂傪挷傋偨傝丄娭學幰偵嵞搙偺暦偒崬傒傪偟偨傝偲偄偭偨抧摴側憑嵏偑懕偒丄傗偭偲媫揥奐傪尒偣傞偺偑4暘偺3偁偨傝偵側偭偰偐傜偱丄慡懱偵抧枴側報徾傪庴偗傞丅
偙偙偵偼丄慜嶌丄慜乆嶌偵憓擖偝傟偰偄偨丄儃僢僔儏偑堷戅偟偨榁儈儏乕僕僔儍儞偵僒僢僋僗傪廗偆僔乕儞傗丄暿傟偨嵢偲偺岎棳偲偄偭偨丄杮嬝偵娭學側偄僄僺僜乕僪偑傎偲傫偳昤偐傟偰偄側偄丅杮棃丄偙偆偄偭偨憓榖偑僗僩乕儕乕傪堿塭朙偐偵嵤傞偺偩偑丒丒丒丅傑偨儃僢僔儏偼僕儍僘偑岲偒偱丄偙傟傑偱偺彫愢偱偼傛偔帺戭偵婣偭偰丄栭側偐丄傂偲傝惷偐偵傾乕僩丒儁僢僷乕側偳偺CD偵挳偒擖傞僔乕儞偑偁傝丄偦傟偑斵偺屒撈偲埨傜偓傪姶偠偝偣偨丅崱嶌偱傕儅僀儖僗偺乽僇僀儞僪丒僆僽丒僽儖乕乿傪挳偔僔乕儞偑偁傞偵偼偁傞偑丄儃僢僔儏偺怱徾晽宨偼偄傑傂偲偮晜偐傃忋偑偭偰偙側偄丅
偲偄偆傢偗偱丄乽儔僗僩丒僐儓乕僥乿偲暲傫偱嵟崅寙嶌偩偲怣偠傞慜乆嶌偺乽埫偔惞側傞栭乿丄儃僢僔儏丒僔儕乕僘埲奜偺僉儍儔僋僞乕偨偪傕搊応偟偰惙傝忋偑傞慜嶌偺乽揤巊偲嵾偺奨乿偲斾傋傞偲丄杮彂偼傗傗婜懸奜傟偲尵傢偞傞傪摼側偄丅偲偼尵偊丄嬝棫偰偼僗僩儗乕僩偱堷偒掲傑偭偰偄傞偟丄僗僩乕儕乕丒僥儕儞僌偺岻偝偼憡曄傢傜偢偩丅傑偨儃僢僔儏偺帠審夝寛傊偺幏擮傗柡傪幐偭偨壠懓偺斶寑偑晜偒挙傝偵偝傟偰偍傝丄廩暘偵撉傒墳偊偺偁傞撪梕偵巇忋偑偭偰偄傞偙偲偼娫堘偄側偄丅傑偨丄晄惓傪憺傓儃僢僔儏偲晠攕偟偨巗寈姴晹偲偺懳棫傗丄崟恖傗儐僟儎恖傪攔愃偡傞僠儞僺儔廤抍側偳傪昤偔偙偲偵傛偭偰丄暔岅偵岤傒偑壛傢偭偰偄傞丅偩偐傜丄僔儕乕僘傪偡傋偰栿偟偰偄傞屆戲壝捠巵偑丄偙傟傪偄偪偽傫岲偒側嶌昳偩偲彂偄偰偄傞偺傕暘偐傞婥偑偡傞丅
儃僢僔儏偼12嶌偱懪偪巭傔偲偄偆榖傪偳偙偐偱撉傫偩婰壇偑偁傞偑丄嶌幰偺僐僫儕乕偼峫偊傪曄偊偰丄傕偭偲彂偒懕偗傞偙偲偵偟偨傛偆偩丅栿幰偁偲偑偒偵傛傞偲丄儃僢僔儏丒僔儕乕僘偼丄杮崙偱偼2005擭偵弌斉偝傟偨杮嶌偺偁偲丄2006擭丄2007擭偲懕偗偰2嶌弌斉偝傟偰偄傞傜偟偄丅崱夞偼斾妑揑抧枴側憑嵏偵廔巒偟偨偑丄僔儕乕僘偼崱屻傕偙傫側挷巕偱懕偄偰偄偔偲偼巚偊側偄丅壗偐偁傝偦偆側梊姶偑偡傞丅偙偺偁偲儃僢僔儏偼偳傫側帠審偲憳嬾偡傞偺偩傠偆偐丄嫽枴偼恠偒側偄丅
2007.10.04 (栘) 儀儔乗乗擔杮偵傕杮暔偺儗僨傿丒僜僂儖偑偄偨
晅偒崌偄偺偁傞僜僂儖丒儈儏乕僕僢僋垽岲壠偵桿傢傟丄嶐栭丄儀儔偝傫偺儔僀償傪娤偵丄崅墌帥偺JIROKICHI偵峴偭偨丅慺惏傜偟偄僜僂儖丒償僅乕僇儖偵埑搢偝傟偨丅儀儔偝傫偺惓幃偺柤慜偼怷嶈儀儔偲偄偆丅堦斒揑側抦柤搙偼側偄偑丄擬怱側僜僂儖/R&B僼傽儞偺偁偄偩偱愨戝側巟帩傪廤傔偰偄傞壧庤偱偁傞丅斵彈偼丄擔杮恖偲偟偰丄傎偲傫偳偨偩傂偲傝偲尵偭偰偄偄杮暔偺僜僂儖壧庤偩丅抝彈傪栤傢偢丄挳偄偰偄偰抪偢偐偟偔側傞傛偆側壧庤偑懡偄側偐偱丄儀儔偝傫偼奿偑堘偆丅婛惉偺僜僂儖宯壧庤偨偪偼斵彈偺懌尦偵傕媦偽側偄偩傠偆丅儀儔偝傫偺丄傢偞偲傜偟偝偺側偄丄帺慠側彞朄丄傛偔偲偍傞惡丄僫僠儏儔儖側忔傝偼丄挳偔傕偺傪堷偒偢傝崬傓椡傪帩偭偰偄傞丅偦偺壧偼丄奜恖偺恀帡偱偼側偄丄僆儕僕僫儕僥傿偵偁傆傟偰偍傝丄帺怣偵枮偪摪乆偨傞偨壧偄傇傝偵偼丄儗僨傿丒僜僂儖偲偟偰偺晽奿偑昚偭偰偄傞丅偁偺挳偄偰偄傞偲婥帩偪偑埆偔側傞丄傢偞偲傜偟偝偺屌傑傝偺傛偆側戝嶃曎偺僺傾僲抏偒岅傝壧庤偵丄儀儔偝傫偺捾偺岰傪愾偠偰堸傑偣偨偄丅儂乕儞傪娷傓8恖曇惉偺僶儞僪傪廬偊偨丄乹僀儞丒僓丒儈僢僪僫僀僩丒傾儚乕乺偵巒傑傞僨傿乕僾丒僜僂儖丒僫儞僶乕偺僆儞丒僷儗乕僪丄杮暔偺僜僂儖丒償僅乕僇儖偵悓偭偨堦栭偩偭偨丅偙傟偩偗偺壧彞椡傪帩偪丄挳偒庤偵姶摦傪梌偊丄屌掕僼傽儞傕偮偄偰偄傞壧庤偑丄1枃傕CD傪弌偟偰偄側偄偲偄偆帠幚偼丄擔杮偺壒妝僔乕儞偺斶偟偄尰幚傪暔岅偭偰偄傞丅崱偺擔杮偺壒妝價僕僱僗偺悽奅偼丄斵彈偺傛偆側壧庤傪偠偭偔傝崢傪悩偊偰堢惉偡傞偙偲偑偱偒傞娐嫬偵側偄偺偩丅2007.09.29 (搚) 埫偄儀儖儕儞偲柧傞偄僾儘償傽儞僗
挬擔怴暦偺塮夋昡偱偺乽戞嶰偺抝乿傗乽僇僒僽儔儞僇乿傪巚傢偣傞廏嶌偲偄偆尵梩偵掁傜傟偰丄塮夋乽偝傜偽丄儀儖儕儞乿傪娤偨偑丄偒傢傔偰戅孅側杴嶌偩偭偨丅塮夋昡榑壠偼偁偰偵側傜側偄偙偲傪嵞擣幆偟偨丅僫僠娮棊屻偺曵夡偟偨儀儖儕儞傪晳戜偵丄僲僗僞儖僕乕偨偭傉傝偵儌僲僋儘偱嶣塭偝傟偰偄傞偑丄乽戞嶰偺抝乿側偳偵帡偰偄傞偺偼偦傟偩偗偱丄偍傛偦怱偵敆傞傕偺偑側偄塮夋偩偭偨丅娔撀偼僗僥傿乕償儞丒僜僟僶乕僌丄庡墘偼僕儑乕僕丒僋儖乕僯乕偲働僀僩丒僽儔儞僔僃僢僩丅儀儖儕儞偵傗偭偰偒偨傾儊儕僇偺廬孯婰幰僋儖乕僯乕偑丄偐偮偰楒拠偩偭偨僽儔儞僔僃僢僩偵弌夛偄丄彥晈偵恎傪棊偲偟偰偄傞偺傪抦傞丅偄傑傕僽儔儞僔僃僢僩傪垽偟偰偄傞僋儖乕僯乕偼丄斵彈偺撲偺峴摦偵晄怰傪書偒側偑傜丄斵彈傪彆偗偰儀儖儕儞偐傜扙弌偝偣傛偆偲偡傞偲偄偆榖偩丅娞怱偺僽儔儞僔僃僢僩偑枺椡偁傞彈偵尒偊側偄偺偱丄僋儖乕僯乕偺斵彈偵幏拝偡傞婥帩偪偑娤傞幰偵揱傢偭偰偙側偄偟丄僽儔儞僔僃僢僩偺埆彈偲偟偰偺昤偒曽偑拞搑敿抂偱丄偳偆偵傕惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅偨偟偐偵暷塸僜偺3崙偑嫟摨摑帯偡傞姠釯偩傜偗偺儀儖儕儞偼乽戞嶰偺抝乿偺僂傿乕儞傪憐婲偝偣傞偟丄嵟屻偺塉偑崀傝偟偒傞旘峴応偺僔乕儞偼乽僇僒僽儔儞僇乿偺儔僗僩丒僔乕儞傪巚傢偣側偄偱傕側偄偑丄偨傫偵暤埻婥傪帡偣偨偩偗偱偁傝丄塮夋揑婰壇偲尵偆偺傕偍偙偑傑偟偄丅昤偐傟傞傋偒恖娫偺懚嵼姶傗斶寑惈偑偪偭偲傕晜偐傃忋偑偭偰偙側偄丅僜僟僶乕僌偲偄偆娔撀偺椡検偺側偝偑擛幚偵昞傟偨塮夋偩偲巚偆丅偙傟偲慜屻偟偰娤偨丄儕僪儕乕丒僗僐僢僩娔撀丄儔僢僙儖丒僋儘僂庡墘偲偄偆乽僌儔僨傿僄乕僞乕乿偺僐儞價偵傛傞塮夋乽僾儘償傽儞僗偺憽傝傕偺乿偼丄帺慠偵梈偗崬傔傞壚昳偩偭偨丅庡恖岞偼嬥栕偗偟偐娽拞偵側偄儘儞僪儞偺鐓榬僩儗乕僟乕丅巕嫙偺偙傠恊偟偔偟偰偄偨廸晝偑朣偔側傝丄堚嶻偲偟偰僾儘償傽儞僗偺揷幧偺屆偄僔儍僩乕偲傇偳偆敤傪憡懕偡傞丅斵偼偦偺堚嶻傪攧傝暐偍偆偲偡傞偑丄庤懕偒偺偨傔僾儘償傽儞僗偺壆晘偵懾嵼偡傞偆偪偵丄抧尦偺恖乆傗帺慠偲偺怗傟崌偄傪捠偠偰恀幚偺恖惗偵栚妎傔丄僾儘償傽儞僗偵廧傫偱儚僀儞憿傝偵惗偒傛偆偲偡傞丄偲偄偆撪梕偩丅儕僪儕乕丒僗僐僢僩偵偟偰偼捒偟偔丄僐儊僨傿丒僞僢僠偱柧傞偔昤偄偰偄傞丅傛偔偁傞僥乕儅偱偁傝丄僗僩乕儕乕偼偐側傝偛搒崌庡媊偱尰幚偽側傟偟偰偄傞偑丄傏偔偼偙偆偄偆柌偺偁傞寉偄塮夋偼寵偄偱偼側偄丅儔僢僙儖丒僋儘僂偼妝偟偦偆偵墘偠偰偄傞偟丄楒恖栶偺儅儕僆儞丒僐僥傿儎乕儖傕惗偒惗偒偟偰偄傞丅梸傪尵偊偽丄僾儘償傽儞僗偲偄偆搚抧偺晽宨傪傕偭偲昤偄偰傎偟偐偭偨丅僾儘償傽儞僗偵偼丄揷幧偵偟傠奨偵偟傠丄怱偵怗傟傞撈摿偺枺椡偑偁傞偑丄偦傟偑偄傑傂偲偮揱傢傜側偄丅偦傟偵丄儚僀儞偵懳偡傞巚偄擖傟傕暔懌傝側偄丅儚僀儞偼偙偺塮夋偺廳梫側梫慺偺傂偲偮側偺偱丄傕偆彮偟嶌幰偲偟偰偺儚僀儞偵岦偗傞撈帺偺帇慄偑偁偭偰傎偟偐偭偨丅偦偆偄偆揰偱偼丄摨偠偔儚僀儞傪僥乕儅偵偟偨寙嶌塮夋乽僒僀僪僂僃僀乿偲斾傋傞偲丄偩偄傇奿偑棊偪偟偰偟傑偆丅偩偑偙偺塮夋偼丄偁傑傝梋寁側偙偲傪峫偊偢偵丄僗僐僢僩娔撀偺岅傝岥偺岻偝偵忔偭偰慺捈偵妝偟傓塮夋偱偁傠偆丅
2007.09.17 (寧) 朰傟傜傟偨嶌壠 W.P.儅僢僊償傽乕儞
慜夞偺擔婰偱怗傟偨彫戦怣岝偺杮乽巹偺僴乕僪儃僀儖僪乿偵偼丄傏偔偑埲慜撉傒嫏偭偨儈僗僥儕乕嶌壠偺柤慜偑偨偔偝傫搊応偟丄夰偐偟偝傪偐偒棫偰傜傟偨丅傏偔偼拞妛偺2擭偐3擭偺偙傠丄偁傞擔偲偮偤傫東栿儈僗僥儕乕傪撉傒巒傔偨丅偒偭偐偗偼摿偵側偐偭偨丅嫮偄偰尵偊偽丄億僺儏儔乕壒妝傗塮夋傗TV斣慻偱攟傢傟偨墷暷偵懳偡傞摬傟偐傜偩偭偨偲巚偆丅嵟弶偼偍寛傑傝偺僔儍乕儘僢僋丒儂乕儉僘偐傜擖傝丄偦傟偑柺敀偐偭偨偺偱丄僄儔儕乕丒僋僀乕儞丄償傽儞丒僟僀儞丄傾僈僒丒僋儕僗僥傿丄G.K.僠僃僗僞僩儞側偳偺丄偄傢備傞杮奿傕偺偺柤嶌傪庤摉偨傝師戞偵撉傒傑偔偭偨丅東栿儈僗僥儕乕偲尵偊偽丄摉帪偼憂尦悇棟暥屔偲憗愳彂朳偺億働儈僗偲偄偆2偮偺僔儕乕僘偑偁傝丄傏偔偼傕偭傁傜偦傟傜偺杮傪拞怱偵撉傫偱偄偨丅僄儔儕乕丒僋僀乕儞偼崙柤僔儕乕僘傕椙偐偭偨偑丄斶寑4晹嶌偺傂偲偮乽Y偺斶寑乿偺僪儔儅僥傿僢僋側嬝棫偰偲嬃偔傋偒寢枛偵摡悓偟偨丅償傽儞丒僟僀儞偼儅僓乕丒僌乕僗偺柍幾婥側壧偲晄婥枴側嶦恖傪慻傒崌傢偣偨乽憁惓嶦恖帠審乿偵溕慠偲偟偨丅傾僈僒丒僋儕僗僥傿偼乽偦偟偰扤傕偄側偔側偭偨乿偺晄壜擻側愝掕偲岻柇惛鉱側撲夝偒偵垹慠偲偟偨乗乗乽傾僋儘僀僪嶦偟乿偺寢枛偵偼暊偑棫偭偨偗傟偳丅偦偺偆偪偵丄偦偆偄偭偨撲夝偒偵廔巒偡傞彫愢偵朞偒懌傜側偔側傝丄崅峑偵擖傞偲丄僒僗儁儞僗傕偺丄僴乕僪儃僀儖僩傕偺丄僗僷僀傕偺丄寈嶡傕偺偲偄偭偨儈僗僥儕乕偵嫽枴偑堏偭偰偄偭偨丅
僴僀僥傿乕儞偺偙傠丄憂尦暥屔傗億働儈僗偱垽撉偟偨偺偼丄僂傿儕傾儉丒傾僀儕僢僔儏乮僐乕僱儖丒僂乕儖儕僢僠乯丄僷僩儕僢僋丒僋僄儞僥傿儞丄傾儞僪儕儏乕丒僈乕償丄僔儍乕儘僢僩丒傾乕儉僗僩儘儞僌丄僕儍僢僋丒僼傿僯僀丄W.P.儅僢僊償傽乕儞丄僩儅僗丒僂僅儖僔儏丄僕儑僫僒儞丒儔僥傿儅乕丄僗僞儞儕乕丒僄儕儞偲偄偭偨嶌壠偨偪偩偭偨丅E.S.僈乕僪僫乕偺儁儕乕丒儊僀僗儞丒僔儕乕僘丄僄僪丒儅僋儀僀儞偺87暘彁僔儕乕僘傕傛偔撉傫偩丅僴乕僪儃僀儖僪偱偼丄傗偼傝嵟弶偵乽寣偺廂妌乿傗乽僈儔僗偺尞乿乽儅儖僞偺戦乿偱僴儊僢僩偵偼傑傝丄乽戝偄側傞柊傝乿傗乽偝傜偽垽偟偒彈傛乿偱僠儍儞僪儔乕偺偲傝偙偵側偭偨丅乽挿偄偍暿傟乿偼偪傚偭偲抶偔丄戝妛偵擖偭偰偐傜撉傫偱丄偙傟偙偦嵟崅寙嶌偲妋怣偟偨丅偙偆偄偭偨惓摑攈偺僴乕僪儃僀儖僪埲奜偵丄儈僢僉乕丒僗僺儗僀儞傪昅摢偲偡傞朶椡傗僙僢僋僗傪攧傝暔偵偡傞愵忣揑側僴乕僪儃僀儖僪彫愢傕偁傝丄偦傟側傝偵妝偟傔偨丅
僀傾儞丒僼儗儈儞僌偺007僔儕乕僘傪嵟弶偵撉傫偩偺偼丄憂尦暥屔偺乽僟僀傾儌儞僪偼塱墦偵乿偩偭偨丅偦偟偰乽儘僔傾傛傝垽傪偙傔偰乿乽巰偸偺偼搝傜偩乿乽僪僋僞乕丒僲僆乿偲撉傫偩偁偨傝偱丄僔儑乕儞丒僐僱儕乕庡墘偺塮夋戞1嶌乽007偼嶦偟偺斣崋乿偑1963擭偵擔杮偱晻愗傜傟偨丅偙傟偼偁傑傝昡敾偵偼側傜側偐偭偨偑丄懕偔戞2嶌偺乽007/婋婡堦敪乿偑戝摉偨傝偟丄崱偵懕偔恖婥塮夋僔儕乕僘偵側偭偨丅僗僷僀傕偺偱偼傎偐偵僪僫儖僪丒僴儈儖僩儞偺儅僢僩丒僿儖儉丒僔儕乕僘乮晹戉僔儕乕僘乯偑柺敀偐偭偨偑丄僨傿乕儞丒儅乕僥傿儞庡墘偺塮夋偼偍傆偞偗偺搙崌偄偑嫮偡偓偰丄擔杮偱偼傕偆傂偲偮庴偗側偐偭偨丅
偦傫側儈僗僥儕乕嶌壠偺側偐偱丄傏偔偑偄偪偽傫垽拝傪姶偠偰偄偨偺偼丄儗僀儌儞僪丒僠儍儞僪儔乕丄僕儍僢僋丒僼傿僯僀丄僂傿儕傾儉丒P丒儅僢僊償傽乕儞偺3恖偩偭偨丅僠儍儞僪儔乕丄僼傿僯僀偵偮偄偰偼偄偢傟峞傪夵傔傞偲偟偰丄偙偙偱偼儅僢僊償傽乕儞偵偮偄偰彂偔偙偲偵偟偨偄丅儅僢僊償傽乕儞偼丄偄傑偱偼傎偲傫偳庢傝嵐懣偝傟傞偙偲偑側偄偑丄50擭戙偵丄旕忢偵椡偺偁傞僴乕僪儃僀儖僪乣僒僗儁儞僗彫愢傪彂偄偨彫愢壠偱偁傝丄偲偔偵埆摽寈姱傕偺偱柤惡傪崅傔偨丅挿曇僨價儏乕嶌偺乽殤偔巰懱乿乮48擭乯偵偼偠傑傞弶婜偺嶌昳偱偼丄嶨帍曇廤幰傗PR夛幮偺幮堳傪庡恖岞偵偟偨姫偒崬傑傟宆偺僒僗儁儞僗彫愢傪彂偄偰偄偨偑丄4嶌栚偺乽嶦恖偺偨傔偺僶僢僕乿乮51擭乯偱晠攕偟偨寈姱傪戣嵽偵偟丄戝偒側榖戣偵側偭偨丅埲屻丄乽價僢僌丒僸乕僩乿乮53擭乯丄乽嫲晐偺尷奅乿乮53擭乯丄乽嵟埆偺偲偒乿乮55擭乯偲偄偭偨嶌昳傪敪昞偟丄埆摽寈姱偺僥乕儅傪孈傝壓偘丄嫄戝側幮夛埆偲愴偆抝傪昤偄偨丅
儅僢僊償傽乕儞偺昅抳偼丄偆偹傞傛偆側擬婥偲偧偔偧偔偡傞傛偆側嬞敆姶偵枮偪偰偄偨丅傑傞偱昅幰偺懅偯偐偄偑暦偙偊傞傛偆偵姶偠傜傟偨丅儅僢僊償傽乕儞偺彅嶌偺側偐偱丄傏偔偑屄恖揑偵岲偒側偺偼丄乽埆摽寈姱乿乮54擭乯偲乽嬞媫怺栭斉乿乮57擭乯偩丅乽埆摽寈姱乿偼丄僊儍儞僌偲婥柆傪捠偠偁偭偰偄偨孻帠偑丄掜偑嶦偝傟偨偙偲傪宊婡偵丄墭柤偺側偐偱僊儍儞僌慻怐偵愴偄傪挧傓偲偄偆榖丄偄偭傐偆偺乽嬞媫怺栭斉乿偼怴暦婰幰偑庡恖岞偱丄偝傑偞傑傑朩奞偵崌偄側偑傜巗挿慖嫇偵棈傓晄惓傪朶偔偲偄偆榖偱丄偄偢傟傕庡恖岞偺屒撈偲晄惓傪媻抏偡傞婥敆偑傛偔昤偐傟偰偍傝丄嫮楏側僒僗儁儞僗偲埑搢揑側敆椡偵偁傆傟偰偄偨丅
儅僢僊償傽乕儞偺彫愢偺偄偔偮偐偼僴儕僂僢僪偱塮夋壔偝傟偰偄傞丅乽暅廞偼壌偵擟偣傠乿乮53擭乯偺尨嶌偼乽價僢僌丒僸乕僩乿偱偁傝丄僼儕僢僣丒儔儞僌娔撀丄僌儗儞丒僼僅乕僪偑庡墘偟偨丅僠儞僺儔偺儕乕丒儅乕償傿儞偑忣晈偺僌儘儕傾丒僌儗傾儉偵擬搾傪梺傃偣傞僔乕儞偑僔儑僢僉儞僌偩偭偨丅傑偨乽埆摽寈姱乿乮54擭乯偼摨柤彫愢偑尨嶌偱丄娔撀偼儘僀丒儘乕儔儞僪丄儘僶乕僩丒僥僀儔乕偑庡墘偟偨丅偄偢傟傕偄傑偱偼僼傿儖儉丒僲儚乕儖偺屆揟偵側偭偰偄傞丅擔杮偱傕偙偺乽埆摽寈姱乿傪東埬偟偨塮夋偑惢嶌偝傟偨丅搶塮偺乽恊暘乮儃僗乯傪搢偣乿乮63擭乯偱丄愇堜婸抝偑娔撀偟丄崅憅寬偑庡墘偟偨丅摉帪丄傏偔偼戝僼傽儞偩偭偨崅憅寬偑弌傞偟丄偟偐傕儅僢僊償傽乕儞偺尨嶌偲偄偆偙偲偱丄婜懸偟偰偙偺塮夋傪娤偵峴偭偨偑丄彫愢偺僀儊乕僕偐傜傎偳墦偄丄側傫偲傕巐忯敿揑側僊儍儞僌塮夋偱偑偭偐傝偟偨婰壇偑偁傞丅偙偺偙傠崅憅寬偼丄搶塮尰戙寑偱丄僒儔儕乕儅儞傕偺傗惵弔傕偺傗僊儍儞僌傕偺側偳丄偄傠傫側塮夋偵庡墘偟偰偄偨偑丄偄傑偩恖婥偼弌偰偄側偐偭偨丅崅憅寬偑僩僢僾丒僗僞乕偵桇傝弌傞偺偼丄偙偺塮夋偐傜2擭屻丄摨偠娔撀偑嶣偭偨乽栐憱斣奜抧乿偵傛偭偰偱偁偭偨丅
娬榖媥戣丄儅僢僊償傽乕儞偼丄堦嶌偛偲偵嶌壠偲偟偰崅傒偵忋偭偰偄偒丄恖娫惈偺斶寑傪昤偄偨傝丄幮夛揑晄惓傪崘敪偟偨傝偡傞巔惃傪嫮傔偰偄偭偨偑丄偦偺偐傢傝儈僗僥儕乕揑側梫慺偼偟偩偄偵婓敄偵側偭偨丅57擭偵敪昞偟偨乽柧擔偵搎偗傞乿偼嬧峴嫮搻傪埖偭偨僋儔僀儉丒僲償僃儖偩偑丄恖庬栤戣偑戝偒側僥乕儅偵側偭偰偄偨丅僒僗儁儞僗偺梫慺偼敄偄偑丄偦偙偵昤偐傟偨崟恖偲敀恖偺斀栚偲桭忣偼丄戝偒側姶摦傪梌偊偨丅偙傟偼僴儕僂僢僪偱塮夋壔偝傟丄乽対廵偺曬廣乿乮59擭乯偲偄偆僞僀僩儖偱擔杮偱傕岞奐偝傟偨偑丄巆擮側偑傜傏偔偼娤摝偟偰偄傞丅儘僶乕僩丒儚僀僘偑娔撀丄僴儕乕丒儀儔僼僅儞僥丄儘僶乕僩丒儔僀傾儞偑庡墘偟偨丅偤傂娤偨偄偺偩偑丄丄傑偩DVD壔偝傟偰偄側偄傛偆偩丅偙偺塮夋偺壒妝偼僕儑儞丒儖僀僗偑嶌嬋偟丄MJQ偑墘憈偟偨僕儍僘偱偁傝丄乹僗働乕僥傿儞僌丒僀儞丒僙儞僩儔儖丒僷乕僋乺偲偄偆儚儖僣偺柤嬋偑憓擖偝傟偰偄傞丅
偙偺偁偲丄儅僢僊償傽乕儞偼偮偄偵儈僗僥儕乕偐傜棧傟丄晛捠彫愢傪偵堏峴偟偰偟傑偭偨丅晛捠彫愢偵堏峴屻偺儅僢僊償傽乕儞偺嶌昳偼丄1嶌偩偗丄乽幍偮偺媆嵩乿乮60擭乯偲偄偆彫愢偑億働儈僗偱栿偝傟偨丅偙傟偼晛捠彫愢偲偼尵偭偰傕丄僒僗儁儞僗偺梫慺傕惙傝崬傑傟偨丄堦庬偺朻尟彫愢揑側枴傢偄偺彫愢偱偁傝丄傏偔偼婥偵擖偭偰偄偨偑丄攧傟峴偒偼朏偟偔側偐偭偨偺偩傠偆丄偗偭偒傚偔栿偝傟偨偺偼偙傟偩偗偱廔傢偭偰偟傑偭偨丅偦傟偐傜偢偄傇傫宱偭偨1980擭丄撍慠儅僢僊償傽乕儞嶌偺乽僕儍僌儔乕乣僯儏乕儓乕僋25帪乿偲偄偆彫愢偑僴儎僇儚丒僲償僃儖僘偐傜弌斉偝傟偨丅偙傟偼摨柤塮夋偺岞奐偵崌傢偣偰尨嶌杮偲偟偰敪攧偝傟偨傕偺偩偭偨丅偩偑偙偺偲偒傕丄儅僢僊償傽乕儞偺彫愢偑懕偄偰栿偝傟傞偙偲偼側偐偭偨丅
傏偔偑儅僢僊償傽乕儞傪撉傒傑偔偭偨偼60擭戙偩偭偨偑丄斵偑幚嵺偵儈僗僥儕乕嶌壠偲偟偰妶桇偟偨偺偼50擭戙偩偭偨丅偲偆偤傫斵偺彫愢偼50擭戙偲偄偆帪戙攚宨傪敳偒偵偟偰偼岅傟側偄偩傠偆偑丄偄傑峫偊傞偲丄斵偑昤偄偨僥乕儅偼帪戙傪挻偊偨晛曊惈傪懷傃偰偄傞偲巚偆偟丄杮偺峴娫偐傜偵偠傒弌傞堎條側敆椡偼丄偄傑傕撉傓幰偵慽偊偐偗傞椡傪帩偭偰偄傞偲巚偆丅愭擔丄億働儈僗偺乽嬞媫怺栭斉乿傪偼偠傔丄偄偔偮偐偺儅僢僊償傽乕儞偺杮傪丄憅屔偐傜扵偟弌偟偨丅崱搙偦傟傜傪偠偭偔傝撉傒曉偡偮傕傝偩丅
2007.09.14 (嬥) 僴乕僪儃僀儖僪偺愴屻巎
嶐擭姧峴偝傟偰儈僗僥儕乕丒僼傽儞偺偁偄偩偱榖戣偵側偭偨彫戦怣岝偺杮乽巹偺僴乕僪儃僀儖僪乿傪撉傫偩乮憗愳彂朳姧乯丅偙傟偼儀僥儔儞偺儈僗僥儕乕丒儔僀僞乕仌東栿壠偱偁傞昅幰偺惵弔帪戙偐傜崱擔傑偱偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢偲偺擬偄偐偐傢傝傪捲偭偨挿曇僄僢僙僀偩丅愴屻傑傕側偄偙傠偺塮夋傊偺孹搢丄崅峑帪戙偺僴儊僢僩傗僠儍儞僪儔乕偲偺弌夛偄丄偦偺屻偺東栿傗僄僢僙僀側偳偱偺妶桇丄摨嬈東栿壠傗曇廤幰偲偺岎棳偲偄偭偨屄恖巎偑丄奀奜儈僗僥儕乕偺東栿偺楌巎丄僴乕僪儃僀儖僪彫愢偺擔杮傊偺庴梕偲曄慗丄僴乕僪儃僀儖僪榑憟丄儈僗僥儕乕嶨帍偺惙悐側偳偲偲傕偵岅傜傟傞丅埲慜偲偰傕柺敀偔撉傫偩杮偺傂偲偮偵丄媨揷徃偺乽愴屻東栿晽塤榐乿乮2000擭丄杮偺嶨帍幮姧乯偑偁傞丅偙傟偼丄偼傞偐傓偐偟憗愳彂朳偺幮堳偲偟偰偱億働儈僗傪曇廤偟丄偦偺屻撈棫偟偰東栿尃僄乕僕僃儞僩傪棫偪忋偘偨媨揷偑丄曇廤幰偺棫応偐傜丄摉帪偺弌斉幮偺撪忣傗東栿幰偲偺岎棳傪捲偭偨僪僉儏儊儞僩偩丅偙偪傜偑丄曇廤幰偺棫応偐傜愴屻偺東栿儈僗僥儕乕偺楌巎傪彂偄偨傕偺偱偁傞偺偵懳偟丄彫戦偺乽巹偺僴乕僪儃僀儖僪乿偼丄彂偒庤丄東栿幰偺棫応偐傜彂偄偨傕偺偱偁傝丄偁傞堄枴偱偙偺2挊偼岲懳徠傪側偟偰偄傞丅
傏偔偑儈僗僥儕乕傪撉傒巒傔偨60擭戙敿偽丄東栿儈僗僥儕乕嶨帍偲偄偊偽憗愳彂朳偺EQMM乮尰嵼偺HMM乯偟偐側偐偭偨丅偩偑偦傟埲慜丄50擭戙廔傢傝偐傜60擭戙弶傔偵偐偗偰丄偙偺EQMM偲乽儅儞僴儞僩乿乽僸僢僠僐僢僋丒儅僈僕儞乿偲偄偆3帍偺東栿儈僗僥儕乕嶨帍偑嫞崌偟偰偄偨帪戙偑偁偭偨丅偦傟偼擔杮偱偺奀奜儈僗僥儕乕彫愢丄偲偔偵僴乕僪儃僀儖僪彫愢偺嫽棽偲婳傪堦偵偟偰偄傞丅乽巹偺僴乕僪儃僀儖僪乿偱岅傜傟傞偦偺偙傠偺忬嫷偼丄奀奜儈僗僥儕乕丒僼傽儞偵偲偭偰偲偰傕嫽枴怺偄丅傑偨偙偺杮偱偼丄摉帪偺塀傟偨堩榖傕偄傠偄傠徯夘偝傟偰偄傞丅婰幰偺姩堘偄偱彂偐傟偨乬傾儞僪儗丒僕僀僪偑僀儞僞價儏乕偺嵺偵僴儊僢僩傪寖徿偟偨乭偲偄偆婰帠傪峕屗愳棎曕偑撉傒丄偦傟傪棎曕偑嶨帍傗夝愢偱徯夘偟偨偨傔丄埲屻偼偦偺榖偑掕愢偵側偭偰棳晍偝傟丄嵟嬤傑偱帠幚偲偟偰傑偐傝捠偭偰偄偨偲偄偆宱堒側偳偼丄偄偐偵傕忣曬偑朢偟偄愴屻偺崿棎婜側傜偱偼偺榖偱旝徫傑偟偄丅僕儍僘偺執戝側僩儘儞儃乕儞憈幰僕儍僢僋丒僥傿乕僈乕僨儞偑丄幚嵺偼惗悎偺敀恖側偺偵丄擔杮偱偼傾儊儕僇丒僀儞僨傿傾儞偺寣傪傂偔偲挿偄偙偲怣偠傜傟偰偄偨榖傪渇渋偲偝偣傞丅偙傟偼傕偲傕偲僥傿乕僈乕僨儞偺晽杄偑僀儞僨傿傾儞傪巚傢偣傞偙偲偐傜婲偙偭偨岆夝偩偭偨丅僕儍僘奅偺嵟崅偺尃埿偩偭偨朣偒桘堜惓堦偝傫偑偦偆彂偔偺偱丄懠偺昡榑壠傕偦傟偵曧偄丄婛掕偺帠幚偵側偭偰偟傑偭偨傛偆偩丅
彫戦怣岝偲偄偆恖偼丄埲慜偼僴乕僪儃僀儖僪偲偄偆傛傝傕丄傾儊儕僇偺棤幮夛傗億儖僲嬈奅偵徻偟偄儔僀僞乕偲偄偆報徾偑嫮偐偭偨丅偐偮偰彫戦偼丄儈僗僥儕乕彫愢傕傕偪傠傫東栿偟偰偄偨偑丄偳偪傜偐偲偄偆偲寉僴乕僪儃僀儖僪丒僗僞僀儖偺傕偺偑懡偐偭偨偟丄偦傟傛傝傕偄傠傫側抝惈嶨帍偵嫽枴杮埵偺傾儊儕僇捠懎幮夛帠忣傪彂偒傑偔偭偨傝丄億儖僲彫愢傪東栿偟偨傝偟偰偄偰丄傓偟傠偦傫側傾儊儕僇晽懎偺徯夘偺傎偆偑杮嬈偺傛偆偵姶偠偰偄偨丅偩偑丄乽僷僷僀儔僗偺廙乿偲偄偆棫攈側儈僗僥儕乕丒僄僢僙僀廤傪彂偒丄儘僗丒儅僋僪僫儖僪傗僕僃僀儉僗丒僋儔儉儕乕傪栿偟丄僟僔乕儖丒僴儊僢僩傊偺巚偄擖傟偐傜僴儊僢僩偺彫愢偺怴栿傗僴儊僢僩揱偺東栿傪姧峴偡傞偵媦傫偱丄彫戦偺僴乕僪儃僀儖僪傊偺垽拝偺嫮偝傪抦傝丄峫偊傪夵傔偨丅偦傟偱傕丄崱夞偺乽巹偺僴乕僪儃僀儖僪乿傪嫽枴怺偔撉傫偱傕側偍丄偳偆偵傕偙偺恖偺暥復傗峫偊曽偼乬寉偄乭偲偄偆報徾傪怈偄偒傟側偄丅傓偐偟撉傫偩拞揷峩帯傗堫梩柧梇偺僄僢僙僀傗億働儈僗偺偁偲偑偒偵姶偠偨丄偳偭偟傝崢傪悩偊偨巔惃傗怱偺偙傕偭偨婥敆偼姶偠傜傟偢丄偨偩楌巎傪捛偄偐偗丄僷儖僾丒儅僈僕儞傪僐儗僋僔儑儞偟丄忋偭柺偩偗傪側偱傑傢偡偩偗偺傛偆偵巚偊偰側傜側偄丅偙偺恖偺攧傝崬傒偺岻偝丄椃偺僄僢僙僀傗僑儖僼丒儕億乕僩側偳懡曽柺偵庤傪怢偽偟丄2懌傕3懌傕偺傢傜偠傪棜偄偰偒偨宱楌偺偣偄偱丄偦偆姶偠傞偺偐傕偟傟側偄丅
2007.09.11 (壩) 傕偆傂偲偮偺乽僇僒僽儔儞僇乿
乽僇僒僽儔儞僇乿偲偄偊偽傾儊儕僇偺崙柉塮夋偲尵偭偰傕偄偄傎偳愨戝側恖婥傪傕偮僇儖僩丒儉乕償傿乕偩丅偦偺塮夋乽僇僒僽儔儞僇乿偺屻擔択傪昤偄偨彫愢偺東栿傪愭擔尒偮偗偨丅亀傕偆傂偲偮偺乽僇僒僽儔儞僇乿亁偲偄偆杮偩乮儅僀僋儖丒僂僅儖僔儏挊丄2002擭丄晑孠幮姧乯丅嫽枴傪偦偦傜傟偰撉傫偱傒偨丅塮夋偼庡恖岞偺庰応宱塩幰儕僢僋偑寈嶡彁挿偺儖僀偲旘峴応偱岎傢偡乽偙傟偑旤偟偄桭忣偺巒傑傝偩側乿偲偄偆戜帉偱廔傢偭偰偄傞偑丄偙偺彫愢偼偦偺僔乕儞丄偦偺戜帉偱枊偑奐偔丅塮夋岲偒偵偲偭偰偼怱憺偄弌偩偟偩丅儕僢僋丄儖僀丄斀僫僠塣摦偺摤巑償傿僋僞乕丒儔僘儘丄儔僘儘偺嵢偱儕僢僋偺尦楒恖僀儖僓偲偄偆庡梫搊応恖暔偼丄塮夋偺僉儍儔僋僞乕傪拤幚偵側偧偭偰偄傞丅偲偄偆傛傝傕丄塮夋偵庡墘偟偨僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩丄僀儞僌儕僢僪丒僶乕僌儅儞丄億乕儖丒僿儞儕乕僪丄僋儘乕僪丒儗僀儞僘偺4恖偺僀儊乕僕偦偺傑傑偵彂偐傟偰偄傞偲尵偆傋偒偩傠偆丅彫愢偼偙偺4恖偵丄僶乕偺僺傾僲抏偒丄僒儉傪壛偊偨5恖傪幉偵揥奐偡傞丅儕僢僋丄儖僀丄僒儉偺3恖偼丄僇僒僽儔儞僇傪傂偦偐偵敪偪丄儕僢僋偑庤彆偗偟偰扙弌偝偣偨僀儖僓偲儔僘儘傪捛偭偰丄儕僗儃儞丄偦偟偰儘儞僪儞偵晪偔丅偦偟偰儕僢僋偼僀儖僓傗儔僘儘偲偲傕偵丄僫僠僗偵掞峈偡傞抧壓妶摦偵壛傢傝丄婋尟側擟柋傪壥偨偡偨傔僫僠愯椞壓偺僠僃僐偵愽擖偡傞丒丒丒偲偄偭偨慹嬝偱偁傞丅偙偆彂偔偲朻尟彫愢傒偨偄偱柺敀偦偆偩偲巚傢傟傞偐傕偟傟側偄偑丄撪梕偲偟偰偼擇媺昳偺弌棃偩丅偩偄偄偪丄僀儖僓傊偺憐偄傪抐偪愗偭偨偼偢偺儕僢僋偑丄傑偨斵彈傪捛偄偐偗傑傢偡摦婡偑偼偭偒傝偣偢丄愢摼椡偵寚偗傞丅儕僢僋偼偦傫側廮側抝偱偼側偄偼偢偩丅偦傟偵僠僃僐偱偺抧壓妶摦傕丄側傫偲傕敆椡偵朢偟偔惙傝忋偑傝偵寚偗傞丅偙偺彫愢偱偼丄偦傫側屻擔択偲暲峴偟偰丄屘嫿憆幐幰偵側傞埲慜偵儕僢僋偑壗傪偟偰偄偨偐偑昤偐傟偰偄傞偑丄傓偟傠偦偭偪偺傎偆偑柺敀偄丅儕僢僋偑儐僟儎恖偲偄偆愝掕偵偼堘榓姶偑偁傞偑丄斵偑僯儏乕儓乕僋偱惗傑傟堢偪丄僊儍儞僌偺慻怐偵擖傝丄摢妏傪尰偟偰儃僗偺曅榬偵側傝丄僋儔僽偺宱塩傪擟偝傟傞偑丄懠偺慻怐偲偺峈憟偵姫偒崬傑傟丄傾儊儕僇傪摝偘弌偡偲偄偆僗僩乕儕乕偑丄堦庬偺僺僇儗僗僋丒儘儅儞偺傛偆側惗偒惗偒偟偨僞僢僠偱丄暔岅惈朙偐偵昤偐傟偰偄傞丅
乽僇僒僽儔儞僇乿偺屻擔択傪昤偄偨彫愢偼偙傟埲奜偵傕撉傫偩偙偲偑偁傞丅戣偼朰傟偨偑丄偨偟偐庡恖岞偺儕僢僋偑暫巑偲偟偰愽悈掵偐壗偐偵忔偭偰僪僀僣偲偺愴憟偵嶲壛偡傞偑丄峌寕傪庴偗偰捑杤偟丄暷孯偺慏偵彆偗傜傟傞偲偙傠偐傜暔岅偑巒傑偭偨偲婰壇偟偰偄傞偑丄嵶偐偄撪梕偼妎偊偰偄側偄丅
乽僇僒僽儔儞僇乿偼偨偟偐偵傛偔弌棃偨塮夋偩偗傟偳丄偦傟傎偳楌巎偵巆傞傛偆側柤嶌偱偼側偄丅1942擭搙偺傾僇僨儈乕徿偱丄嶌昳徿丄娔撀徿丄媟怓徿傪妉傞傎偳昡壙偝傟偨偺偼丄懡暘偵愴帪壓偲偄偆摉帪偺忣惃偵傛傞偲偙傠偑戝偒偄丅乽儅儖僞偺戦乿乽僴僀丒僔僃儔乿偱昡敾偵側偭偨僴儞僼儕乕丒儃僈乕僩偼丄懕偄偰庡墘偟偨偙偺塮夋偱攐桪偲偟偰偺抧埵傪晄摦偺傕偺偵偟偨丅僴乕僪儃僀儖僪乮旕忣乯側栶偱攧傝弌偟偨儃僈乕僩偑丄堦尒僒僗儁儞僗偺懱嵸傪偲傝側偑傜撪幚偼儊儘僪儔儅偺偙偺塮夋偱恖婥偑暒摣偟偨偺偼丄旂擏偲尵偊偽旂擏側榖偩丅偦傟偼偲傕偐偔丄旘峴応偺僔乕儞偱儃僈乕僩偑拝偰偄偨僩儗儞僠僐乕僩偼丄儀儖僩偺寢傢偊曽傕娷傔偰丄抝偺僇僢僐椙偝偺戙柤帉偵側偭偨偟丄偙偺塮夋偐傜偼丄朻摢偵婰偟偨乽旤偟偄桭忣偺巒傑傝乿傪偼偠傔丄乽孨偺摰偵姡攖乿丄乽偦傫側愄偺偙偲偼朰傟偨丄偦傫側愭偺偙偲偼暘偐傜側偄乿丄乽僾儗僀丒僀僢僩丒傾僎僀儞丄僒儉乿乮幚嵺偼塮夋偱偼偙偺傑傑偺戜帉偼巊傢傟偰偄側偄偑乯偲偄偭偨柤戜帉偑偨偔偝傫惗傑傟偨丅乽僇僒僽儔儞僇乿偼偺偪偵儘僶乕僩丒儚僌僫乕庡墘偱儕儊僀僋偝傟偨偑丄摉慠側偑傜懯嶌偩偭偨丅擔杮偱傕愇尨桾師榊庡墘偺儉乕僪丒傾僋僔儑儞塮夋偲偟偰儕儊僀僋偝傟偰偄傞乮乽栭柖傛崱栭傕桳擄偆乿乯丅僴儕僂僢僪偱偼懕曇塮夋傕婇夋偝傟偨偑幚尰偟側偐偭偨傜偟偄丅偄傑側傜偡偖偵懕曇偑嶌傜傟偨偩傠偆丅偙偺塮夋偵僀儞僗僷僀傾偝傟偰嶌傜傟偨塮夋傕懡偄偟丄乽儃僊乕両 壌傕抝偩乿偺傛偆側僷儘僨傿乕塮夋傕偁傞丅
亀傕偆傂偲偮偺乽僇僒僽儔儞僇乿亁偲偄偆栿戣偼丄乽僇僒僽儔儞僇乿偵傂偭偐偗偰榖戣偵偟傛偆偲偄偆堄恾偐傜晅偗傜傟偨偺偱偁傠偆偑丄偁傑傝庯傪姶偠偝偣傞僞僀僩儖偱偼側偄丅尨戣偼 "As Time Goes By" 偩偑丄偙傟偼偙偺塮夋偱巊傢傟偰戝僸僢僩偟偨嬋偺僞僀僩儖偩丅"As Time Goes By" 偼嵟嬤偼乽帪偺夁偓備偔傑傑偵乿偲偄偆朚戣偑傛偔巊傢傟傞偑丄埲慜偼乽帪偺偨偮傑傑乿偲偄偆朚戣偱捠偭偰偄偨丅戲揷尋擇偑壧偭偨乽帪偺夁偓備偔傑傑偵乿偲偄偆壧梬嬋偑偁傞偑丄偙傟偼 "As Time Goes By" 偲偄偆嬋偲偼壗偺娭學傕側偄偗傟偳丄側偤偐戲揷偺偙偺壧偑僸僢僩偟偨偙傠偐傜丄偦傟偑 "As Time Goes By" 偺朚戣偵巊傢傟傞傛偆偵側偭偨丅偙偺戣偼側傫偲側偔姶忣夁懡偱彈乆偟偄姶偠偑偟偰丄傏偔偼娙寜偱偡偭偒傝偟偨乽帪偺偨偮傑傑乿偺傎偆偑岲偒偩丅偮偄偱偵尵偊偽丄椉曽偲傕 "As Time Goes By" 偺栿偲偟偰偼娫堘偭偰偄傞丅偙傟偼乬抝彈偺怓楒偼偄偮偺悽傕摨偠乭偲偄偆偙偲傪鎼偭偨壧偱偁傝丄乽帪偼偨偭偰傕乿偲偄偆栿偑惓偟偄丅偙偺嬋偼丄價儕乕丒儂儕僨僀傗僇乕儊儞丒儅僋儗僄傪偼偠傔丄偨偔偝傫偺壧庤偑壧偭偰偄傞偑丄傏偔偑寛掕揑柤彞偩偲巚偆偺偼儕乕丒儚僀儕乕偺壧偩丅儚僀儕乕偼償傽乕僗偐傜擖傝丄恖惗偺恏巁傪鋜傔恠偟偨庰応偺彈庡恖偑庒幰偵岅傝偐偗傞傛偆側挷巕偱壧偄丄偙偺嬋偺慺惏傜偟偝傪堷偒弌偟偰娫慠偡傞偲偙傠偑側偄丅
壧偺榖偑弌偨偮偄偱偵怗傟傞偲丄乽傾丒價儏乕僥傿僼儖丒僼儗儞僪僔僢僾乿偲偄偆僗僞儞僟乕僪丒僜儞僌偑偁傞丅弌偩偟偺壧帉偼 "This is the end of a beautiful friendship" 偲偄偆僼儗乕僘偱巒傑傞偑丄偙傟偼柧傜偐偵丄塮夋乽僇僒僽儔儞僇乿偺嵟屻偺戜帉偱偁傞 "丒丒丒this is the beginning of a beautiful friendship" 傪壓晘偒偵偟偨傕偺偱偁傠偆丅偪側傒偵丄乽傾丒價儏乕僥傿僼儖丒僼儗儞僪僔僢僾乿偲偄偆嬋偼丄乬偙傟傑偱偼孼枀偺傛偆側娭學偩偭偨偗傟偳丄偦傫側旤偟偄桭忣偼傕偆廔傢傝丄偙傟偐傜偼楒恖偳偆偟傛乭偲偄偆煭棊偨撪梕偺壧偩丅
2007.07.31 (壩) 暷崙僱僆僐儞偺堿杁傪恾彂娰堳偼慾巭偱偒傞偐
崱擭偺5寧偵姧峴偝傟偨儔儕乕丒僶僀儞僴乕僩偺亀恾彂娰堳亁乮憗愳暥屔乯偼丄傾儊儕僇偺戝摑椞慖傪僥乕儅偵偟偨儈僗僥儕乕杮偩丅庡恖岞偼儚僔儞僩儞偺戝妛恾彂娰偵嬑傔傞恾彂娰堳偱丄傂傚傫側偙偲偐傜傾儖僶僀僩偱戝嬥帩偺揁戭偵偁傞巹愝恾彂娰偺惍棟傪棅傑傟傞丅偲偒偼戝摑椞慖偺恀偭扅拞偱丄嫟榓搣偺尰怑戝摑椞偲柉庡搣偺彈惈岓曗偑寖偟偔愴偭偰偄傞丅庡恖岞偺傾儖僶僀僩愭偺戝嬥帩偼尰怑戝摑椞偺塭偺僽儗乕儞偱偁傝丄宍惃晄棙偵側偭偨戝摑椞傪嵞慖偝偣傞偨傔丄偲傫偱傕側偄堿杁傪寁夋偡傞丅恾彂娰堳偵偦偺寁夋傪抦傜傟偨偲巚偭偨戝嬥帩偼惌晎偺旈枾慻怐偵斵傪嶦偝偣傛偆偲偡傞丅恾彂娰堳偼偮偗慱偆嶦偟壆偐傜昁巰偱摝偘夞傝側偑傜恀憡傪扵傞丒丒丒偲偄偭偨撪梕偺僒僗儁儞僗彫愢偱偁傞丅怺崗側戣嵽偩偑丄儐乕儌傾傪岎偊側偑傜寉柇側僞僢僠偱彂偐傟偰偍傝丄柺敀偄偙偲偼柺敀偄丅尰怑戝摑椞偺丄償僃僩僫儉愴憟峴偒傪摝傟傞偨傔廈暫偵巙婅偟偨偲偐丄廈暫帪戙偼傎偲傫偳孭楙偵嶲壛偣偢丄梀傃曫偗偰偄偨偲偄偭偨宱楌傗丄9.11帠審偺偲偒偼儚僔儞僩儞偐傜摝偘嫀偭偰恎傪塀偟偰偄偨偲偄偭偨婰弎偼丄偁偒傟傞傎偳尰幚偺僽僢僔儏戝摑椞偦偺傕偺偩丅傑偨丄僄僱儖僊乕嬈奅丄暫婍嬈奅丄惢栻嬈奅偺棙塿傪戙曎偟偰偄傞尦愇桘夛幮幮挿偺崙柋挿姱偼丄柧傜偐偵僠僃僀僯乕暃戝摑椞偑儌僨儖偱偁傠偆丅偙偺偁偨傝偼戝偄偵徫偊傞丅偟偐偟埆恖偨偪偑偁傑傝偵媃夋壔偝傟偡偓偰偄偨傝丄僾儘偺嶦偟壆偑慺恖偵娙扨偵傗傜傟偰偟傑偭偨傝偱丄嬝棫偰偵尰幚姶偑側偔丄弌棃偲偟偰偼枮揰偑5偮惎側傜丄3偮惎敿偐4偮惎偲偄偭偨偲偙傠偩丅
偦傟傛傝偼傞偐偵嫽枴怺偐偭偨偺偼戝摑椞慖偵偐傜傓棤榖偩偭偨丅偨偲偊偽丄偙偆偄偆堩榖偑弌偰偔傞丅乽儗乕僈儞懳僇乕僞乕偺戝摑椞慖傪梻擭偵峊偊偨1979擭枛丄僀儔儞偺嵼僥僿儔儞暷戝巊娰堳恖幙帠審偑婲偒偨丅僇乕僞乕戝摑椞偼恖幙夝曻偺岎徛傪偟偰偄偨偑丄儗乕僈儞恮塩偼旈枾棥偵僀儔儞偲岎徛偟丄戝摑椞慖嫇搳昜擔傑偱恖幙傪夝曻偣偢偵偄偨傜孯帠墖彆傪偡傞偲栺懇偟偨丅偦偺寢壥僇乕僞乕偼恖幙傪夝曻偱偒側偐偭偨偙偲偑戝偒側棟桼偲側偭偰棊慖偟偨丅偦偟偰儗乕僈儞偺戝摑椞廇擟幃偺摉擔丄恖幙偼夝曻偝傟偨乿丅偙偺棤庢堷偼偳偆傕帠幚傜偟偄偑丄岞偺楌巎揑帠幚偵側偭偰偄傞偺偐偳偆偐偼傛偔暘偐傜側偄丅傕偟岞偺帠幚偩偲偟偨傜丄嫟榓搣偵懳偟偰旕擄偺棐偑悂偒峳傟側偄偺偑晄巚媍偩偟丄傛偔儗乕僈儞偺惡朷偑抧偵棊偪側偄傕偺偩偲巚偆丅傑偨丄乽戝摑椞偵昁梫側帒幙偼丄惌嶔偺寛掕傗幚峴椡側偳偱偼側偔丄夁忚側晧壸偵懴偊偆傞偙偲丄撍敪揑側帠懺偵懳張偱偒傞偙偲乿偲偄偭偨娷拁偁傞尵梩偑偁偪偙偪偵弌偰偔傞偺傕柺敀偄丅
偙偺杮偵乬怴悽婭偺傾儊儕僇偺偨傔偺僾儘僕僃僋僩乭(PNAC = The Project for the New American Century)偲偄偆慻怐偺榖偑弌偰偔傞丅偙傟偼幚嵺偵傾儊儕僇偱妶摦偟偰偄傞丄僱僆僐儞偺夊忛偲尵傢傟偰偄傞僔儞僋僞儞僋偩丅PNAC偼丄傾儊儕僇偑儕乕僟乕僔僢僾傪幏傞偙偲偑丄傾儊儕僇偵偲偭偰傕悽奅偵偲偭偰傕朷傑偟偄偙偲偩偲偄偆婎杮巔惃偵婎偯偒丄孯帠丄奜岎丄帒尮偺曐慡側偳傪偳偺傛偆偵恑傔傞傋偒偐傪榑偠丄惌晎偵採尵偟丄悽娫偵孾栔偟偰偄傞丅偮傑傝偙傟偼丄傾儊儕僇偑悽奅傪巟攝偡傞曽朄傪峫偊傞抍懱偩丅斵傜偼丄悽奅偠傘偆偺愴棯忋偺嫆揰偵暷孯傪塱懕揑偵挀棷偝偣傞偙偲丄愇桘妋曐偺偨傔拞搶抧堟偺巟攝尃傪埇傜側偗傟偽側傜偢丄偦偺偨傔偵偼壗搙偐偺愴憟傪宱尡偟側偗傟偽側傜側偄偙偲丄偦偺愴憟偼丄傾儊儕僇偵弢撍偔崙傊偺僨儌儞僗僩儗乕僔儑儞偲偟偰傕桳岠偱偁傞偙偲側偳偲庡挘偟偰偄傞丅嬃偔傋偒偙偲偵丄偙傟傜偺PNAC偺庡挘偼偡傋偰傾儊儕僇偵傛偭偰傕偺偺尒帠偵幚慔嵪傒側偺偩丅
偙偺杮偵偼偦偙傑偱彂偐傟偰偄側偄偑丄PNCA偵偼丄僱僆僐儞偺拞怱恖暔偲尵傢傟傞僂僅儖僼僅僂傿僢僣傗丄僠僃僀僯乕暃戝摑椞丄儔儉僘僼僃儖僪尦崙杊挿姱傕柤傪楢偹偰偄傞丅僱僆僐儞偺庡梫側榑媞偺懡悢傪愯傔傞偺偑儐僟儎宯偩丅斵傜偺庡挘偺攚屻偵偼僀僗儔僄儖偺巚榝偑偁傞偲尵傢傟傞偺傕摉慠偱偁傠偆丅嫲傠偟偄偺偼丄乽曄妚傪幚尰偡傞偨傔偵偼丄偐偮偰偺恀庫榩峌寕偺傛偆側丄堷偒嬥偲側傞偨傔偺戝嶴帠偑昁梫偩乿偲偄偆斵傜偺庡挘偩丅偙傟偼9.11帠審偲側偭偰幚尰偟偰偟傑偭偨丅9.11帠審偑僱僆僐儞偺堿杁偩偲尵偭偰偟傑偆偺偼抁棈夁偓傞偑丄偁偺帠審偵偼丄惌晎偼僥儘傪嶡抦偟偰偄偨偺偵傢偞偲杊偑側偐偭偨偲偄偆愢偑偄傑偩偵崻嫮偄偩偗偵丄峳搨柍宮偲偼偗偭偟偰尵偊側偄榖偩偲巚偆丅彮側偔偲傕僽僢僔儏惌尃偑PNAC偺昤偄偨僾儔儞偳偍傝偺惌嶔偱摦偄偰偄傞偙偲偼妋偐偩丅偦偟偰擔杮偼偦偺偨傔偺僐儅偱偁傝丄斵傜偺嶔杁偺曅朹傪扴偑偝傟傛偆偲偟偰偄傞丅
2007.07.18 (悈) 悓梋偺壥偰偺僕儍僘丒僩乕僋
嶐栭偼壒妝昡榑壠偺A偝傫偲媣偟傇傝偺堸怘僙僢僔儑儞傪偟偨丅A偝傫偲夛偆偲偒偼丄壗偲側偔丄偙傫側榖傪偟傛偆偲偐丄偁傟偵偮偄偰恥偄偰傒傛偆偲偐巚偭偰偄偰傕丄幚嵺偵榖偟巒傔傞偲丄偦傫側傕偺偼徚偊嫀偭偰偟傑偄丄僥乕儅偼偁偭偪傊旘傃丄偙偭偪傊旘傃丄柆棈側偔偳偙傑偱傕朿傜傫偱偟傑偆丅傑傞偱僕儍僘偺傛偆偩丅偙偆偄偆偺傪択榑晽敪偲尵偆偺偩傠偆偐丄偦傟偲傕偨傫側傞悓梋偺閌愩偐丅偦偺栭傕偦偆偩偭偨丅榖戣偼嵟嬤偺壒妝忣惃偐傜幮夛栤戣丄夰媽択丄帺揮幵丄IT娭楢丄塮夋丄TV斣慻丄僸僢僠僐僢僋寑応丄暥妛丄棊岅偲丄偮偓偮偓偵堏傝曄傢傞丅A偝傫偲偼丄偲偒偳偒帊偺榖傪偡傞丄偙偺栭偼榖偵弌側偐偭偨偗傟偳丅帊偵偮偄偰榖偡偺偼丄壒妝嬈奅偱偼A偝傫偲壒妝帍曇廤挿偺M偝傫偖傜偄偟偐偄側偄丅嵟弶偼惵嶳偺梞晽嫃庰壆偱堸傫偱偄偨偑丄搑拞偱A偝傫偺敪埬偱怴廻偺僑乕儖僨儞奨偵応強傪曄偊偨丅僑乕儖僨儞奨偵峴偭偨偺偼壗擭傇傝偩傠偆丅彫塉偺偣偄偐恖塭偼傑偽傜偩偭偨丅擖偭偨僶乕偼塮夋娭楢偺媞偑傛偔棃傞偲偄偆揦丅暻偵偼斾妑揑嵟嬤偺儓乕儘僢僷塮夋偺億僗僞乕偑揬偭偰偁傞丅榁恖椡乮屆偄両乯偑偮偄偨偨傔揦偺柤慜偼幐擮偟偨丅僇僂儞僞乕偺墱偵偼姶偠偺偄偄忋昳側儅僟儉偑偄偨丅偟偽傜偔偡傞偲丄儅僟儉偑愭媞偺庒偄奜崙恖偲棳挩側僼儔儞僗岅偱挐傝巒傔偨偺偵偼傃偭偔傝偟偨丅偝偡偑偼僑乕儖僨儞奨偩丅偦偺揦偱壗傪榖偟偨偐偼偁傑傝婰壇偵側偄偑丄寣塼宆偵傛傞惈奿偺暘椶偼怣棅偱偒傞偐斲偐偱惙傝忋偑偭偨偺偼妎偊偰偄傞丅妝偟偄栭傪掲傔偔偔傞偺偵憡墳偟偄丄偡偰偒偵偨傢偄側偄媍榑偩偭偨丅2007.07.16 (寧) 傓偐偟僶僯乕丒儀儕僈儞偲偄偆僩儔儞儁僢僞乕偑偄偨乗乗偦偺2
僶僯乕丒儀儕僈儞偺戙昞揑墘憈偲偄偊偽丄帺恎偺僆乕働僗僩儔偵傛傞乹尵偄弌偟偐偹偰乺傗乹廁恖偺壧乺丄僌僢僪儅儞妝抍偱偺乹僉儞僌丒億乕僞乕丒僗僩儞僾乺傗乹愨懱愨柦乺丄僪乕僔乕妝抍偱偺乹僀儞僪偺塖乺乹儅儕乕乺側偳偑桳柤偩偑丄傎偐偵傕斵偺柤墘偼偨偔偝傫偁傝丄枃嫇偵偄偲傑偑側偄丅傏偔偑岲偒側偺偼丄1936擭10寧偵丄摉帪斵偑儗僊儏儔乕偱弌墘偟偰偄偨乽Satuday Night Swing Club乿偲偄偆儔僕僆斣慻偱墘憈偟偨乹僟僂儞丒僶僀丒僕丒僆乕儖僪丒儈儖丒僗僩儕乕儉乺偲偄偆嬋偩丅僲僗僞儖僕僢僋側儊儘僨傿乕傪傕偭偨僼僅乕僋丒僜儞僌挷偺嬋偱偁傝丄僗僞僕僆丒僆乕働僗僩儔傪僶僢僋偵丄嵟弶偐傜嵟屻傑偱儀儕僈儞偺僜儘偑僼傿乕僠儍乕偝傟偰偄傞丅儀儕僈儞偼嵟弶偵儖僶乕僩偱僗僩儗乕僩偵儚儞丒僐乕儔僗傪悂偒丄僀儞丒僥儞億偵側傞偲堦揮偟偰僗僀儞僊乕側儕僘儉偵忔偭偰丄僆乕働僗僩儔傪僶僢僋偵丄摼堄偺僼儗乕僘傪嶶傝偽傔側偑傜僟僀僫儈僢僋側僀儞僾儘償傿僛乕僔儑儞傪孞傝峀偘傞丅斵偺2僐乕儔僗偵傢偨傞僜儘偼丄偩傫偩傫偲擬婥傪懷傃偰偄偒丄嵟屻偺僇僨儞僣傽偱僋儔僀儅僢僋僗傪寎偊傞丅偙傟偼僒僢僠儌偺乹僞僀僩丒儔僀僋丒僕僗乺傗儘僀丒僄儖僪儕僢僕偺乹儚僶僢僔儏丒僗僩儞僾乺偲暲傇僩儔儞儁僢僩偺楌巎揑柤墘偩偲巚偆丅弶婜偺傕偺偱偼丄僪乕僔乕丒僽儔僓乕僘丒僶儞僪偵擖偭偰1933擭3寧偵榐壒偟偨乹儉乕僪丒僴儕僂僢僪乺偑偄偄丅僐乕僯乕側僶儞僪墘憈偺偁偲丄屻敿偵弌偰偔傞儀儕僈儞偺僜儘偵偼丄柧傜偐偵價僢僋僗丒僶僀僟乕儀僢僋偺僼儗乕僘偺嵀愓偑傒傜傟傞丅廔傝嬤偔偺僶儞僪偲偺妡偗崌偄偑僗儕儕儞僌偩丅儀儕僈儞帺恎偺僆乕働僗僩儔偵傕柤墘偼懡偄丅偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偑丄1938擭1寧偵悂偒崬傑傟偨乹傾丒僙儗僫乕僨丒僩僁丒僓丒僗僞乕僘乺偼愨昳偩丅儀儕僈儞偼償僅乕僇儖傪嫴傫偱2夞僜儘傪偲傞偑丄嵟弶偼抧傪攪偆傛偆側掅壒偱丄2夞栚偵偼揤傪隳傇偑偛偲偒崅壒偱丄偁傜備傞媄検傪奐捖偟側偑傜悂偄偰偄傞丅捒偟偄傕偺偵丄僆乕働僗僩儔傪夝嶶偟偨屻偺1940擭偵僺傾僲偲僪儔儉僗偩偗傪敽憈偵悂偒崬傫偩乹僕儍僟乺乹儕儞僈乕丒傾儂儚僀儖乺乹僒儞僨僀乺乹僠儍僀僫丒儃乕僀乺偺4嬋偑偁傞丅偙傟偼乽Modern Rhythm Choruses乿偲偄偆嫵懃杮偺偨傔偵榐壒偝傟偨傕偺偩丅偦偙偱偺儀儕僈儞偺僜儘傪嵦晥偟丄僀儞僾儘償傿僛乕僔儑儞偺僒儞僾儖偲偟偰杮偵嵹偣偨偺偱偁傠偆丅偙偺嫵懃杮偼1970擭戙敿偽傑偱丄傾儊儕僇偺抧曽偺妝婍揦側偳偱庤偵擖傟傞偙偲偑偱偒偨偲偄偆丅偡傋偰傾僪儕僽偩偗偺1暘敿傎偳偺抁偄墘憈偩偑丄僔儞僾儖側曇惉側偩偗偵丄斵偺帺桼杬曻側僼儗乕僕儞僌傪慛傗偐偵挳偒庢傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺崰偵側傞偲斵偺懱挷偼巚傢偟偔側偔側傝丄墘憈傕惛嵤傪寚偔傛偆偵側偭偨偲尵傢傟偰偄傞偑丄偙偺敆椡偁傆傟傞僾儗僀傪挳偔偐偓傝丄偦傫側條巕偼傑偭偨偔姶偠傜傟側偄丅
儀儕僈儞偼壧庤偺儕乕丒儚僀儕乕偲楒拠偩偭偨丅儚僀儕乕偼僗僀儞僌帪戙偵妶桇偟偨旤杄偲愻楙偝傟偨壧彞偱抦傜傟傞壧庤偩丅戙昞嶌偺亀僫僀僩丒僀儞丒儅儞僴僢僞儞亁傪垽挳偡傞僼傽儞偼擔杮偵傕懡偄丅儕乕丒儚僀儕乕偼1933擭3寧偵弶榐壒偟偨偑丄偦偺偲偒敽憈偟偨僪乕僔乕丒僽儔僓乕僘丒僶儞僪偵偼儀儕僈儞傕擖偭偰偍傝丄旤偟偄僜儘傗僆僽儕僈乕僩傪悂偄偰偄傞丅儚僀儕乕偼1936擭偛傠偵偼恖婥壧庤偵偺偟忋偑偭偰偄偨偑丄偦偺偙傠偵偼儀儕僈儞偲儚僀儕乕偺拠偼儈儏乕僕僔儍儞偺娫偱偼岞慠偺旈枾偵側偭偰偄偨丅2恖偺娭學偼偦傟偐傜悢擭娫懕偄偨丅摉帪偡偱偵儀儕僈儞偼寢崶偟偰偍傝丄巕嫙傕偄偨丅晇偺晄椣傪抦偭偨儀儕僈儞晇恖偼巕嫙傪楢傟偰壠傪弌偨丅悢擭娫丄暿嫃傪懕偗偨偁偲丄1940擭偵儀儕僈儞偑僶儞僪傪夝嶶偟偰娫傕側偔丄斵傜偼嵞傃堦弿偵廧傓傛偆偵側偭偨丅偦偺屻儚僀儕乕偼尦僌僢僪儅儞丒僶儞僪偺僺傾僯僗僩偩偭偨僕僃僗丒僗僥僀僔乕偲寢崶偟偨丅儚僀儕乕偼楒懡偒彈偱丄偄傠偄傠側儈儏乕僕僔儍儞偲塡偵側偭偰偄偨丅偙偺晄椣憶摦偼儀儕僈儞偑儚僀儕乕偵怳傝夞偝傟偨偩偗偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偱傕幚懱偼晄椣偲偼尵偊丄僗僀儞僌帪戙嵟崅偺僩儔儞儁僢僞乕偲敀恖彈惈僕儍僘丒償僅乕僇儖偺嵟崅偺柤壴偺儔償丒傾僼僃傾偼丄側傫偲傕僼傽儞偺儘儅儞僥傿僢僋側憐憸椡傪巋寖偡傞榖偱偼側偄偐丅
亀忣擬偺嫸憐嬋亁乮Young Man with a Horn乯偼丄揤嵥僩儔儞儁僢僞乕偺塰岝偲嵙愜傪昤偄偨塮夋偩丅1949擭偵嶌傜傟丄僇乕僋丒僟僌儔僗偑庡墘丄僪儕僗丒僨僀丄儘乕儗儞丒僶僐乕儖偑嫟墘偟偰偄傞丅偙傟偼價僢僋僗丒僶僀僟乕儀僢僋偺惗奤偵僸儞僩傪摼偰僪儘僔乕丒儀僀僇乕偑彂偄偨彫愢傪塮夋壔偟偨傕偺偩偑丄儀儕僈儞傪垽偡傞傏偔偵偼丄價僢僋僗傛傝傕傓偟傠儀儕僈儞偺塮夋偩偲巚偊偰偟偐偨偑側偐偭偨丅僴儕僂僢僪塮夋傜偟偔丄嵟屻偵庡恖岞偼嵞惗偟偰僴僢僺乕丒僄儞僪偵側偭偨傝丄庡恖岞偑傗偨傜偵寣偺婥偺懡偄恖娫偩偭偨傝偡傞偁偨傝偼丄帠幚偲偐偗棧傟偰偄傞偑丄2恖偺彈傪傔偖傞恖娫娭學傗丄僗僩儗僗偐傜夁搙偺怺庰偵娮傞偲偙傠側偳偑丄儀儕僈儞傪渇渋偲偝偣傞丅僩儔儞儁僢僩偺幚嵺偺壒傪丄儀儕僈儞丒僗僞僀儖傪捛悘偟偨僴儕乕丒僕僃乕儉僗偑悂偄偰偄傞偺傕堦場偐傕偟傟側偄丅
2007.07.15 (擔) 傓偐偟僶僯乕丒儀儕僈儞偲偄偆僩儔儞儁僢僞乕偑偄偨乗乗偦偺1
偐偮偰僶僯乕丒儀儕僈儞偲偄偆僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偑偄偨丅僗僀儞僌帪戙嵟崅偺敀恖僩儔儞儁僢僞乕偲鎼傢傟偨恖偩丅1930擭戙弶傔偵摢妏傪尰偟丄桳柤丒柍柤偺偝傑偞傑側僶儞僪偵擖偭偨傝丄悢懡偔偺悂偒崬傒僙僢僔儑儞偵嶲壛偟偨傝偟偰丄執戝側僩儔儞儁僢僞乕偲偟偰偺柤惡傪妋棫丄30擭戙敿偽偵儀僯乕丒僌僢僪儅儞傗僩儈乕丒僪乕僔乕側偳偺堦棳僆乕働僗僩儔偵嵼愋偟偰楌巎揑柤墘傪悂偒崬傓丅偦偺僾儗僀偼僗僀儞僌帪戙偺偁傜備傞敀恖僩儔儞儁僢僞乕偵塭嬁傪梌偊偨丅1937擭偵帺傜偺僆乕働僗僩儔傪寢惉丄乹尵偄弌偟偐偹偰乺偑戝僸僢僩偟偨偑丄僶儞僪宱塩偵幐攕偟偰3擭偱夝抍偡傞丅挿擭偺怺庰偵傛傝丄1942擭丄33嵨偺庒偝偱昦巰乗乗儀儕僈儞偺宱楌傪婰偡偲偙傫側姶偠偵側傞丅僶僯乕丒儀儕僈儞偲偄偆柤慜傪岥偵偡傞偲丄傏偔偺摢偼丄偁偺怳暆偺戝偒偄丄墣傗偐側僩儔儞儁僢僩偺嬁偒偱偄偭傁偄偵側傞丅崅壒偐傜掅壒傊偲曄尪帺嵼偵嬱偗弰傞傾僪儕僽丄僼儗乕僘偺嵟屻偵擖傞僕儍僘丒僼傿乕儕儞僌墶堨偺償傿僽儔乕僩偑晜偐傫偱偔傞丅儀儕僈儞偼崅壒傕慺惏傜偟偐偭偨偑丄朙偐側壒検偺掅壒傕旤偟偐偭偨丅偁傟偩偗尒帠側掅壒傪悂偗傞僩儔儞儁僢僞乕偼丄僗僀儞僌偲儌僟儞偲傪栤傢偢丄屆崱搶惣丄儀儕僈儞埲奜偵扤傕偄側偄丅儀儕僈儞偺傾僀僪儖偼儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偱偁傝丄幚嵺偵斵偺僾儗僀偼儖僀偺塭嬁偑尠挊偩偑丄摨帪偵僼儗乕僕儞僌偵偼價僢僋僗丒僶僀僟乕儀僢僋偺塭傕尒傜傟傞丅偮傑傝崟恖僩儔儞儁僢僩偺尦慶偱偁傞儖僀偲敀恖僩儔儞儁僢僩偺殔栴偲側偭偨價僢僋僗偺椉曽偺僗僞僀儖傪怐傝岎偤偰丄撈帺偺僗僞僀儖傪曇傒弌偟偨偺偩丅摉帪偺敀恖僩儔儞儁僢僞乕偼偙偧偭偰儀儕僈儞偺僗僞僀儖傪柾偟偰墘憈偟偨丅偩偑儀儕僈儞偲懠偺僾儗僀儎乕偲偺堘偄偼楌慠偲偟偰偄傞丅儀儕僈儞偺僾儗僀偵偼悢彫愡挳偄偨偩偗偱丄偡偖偵偦傟偲暘偐傞婸偐偟偄僩乕儞偲撈摿偺屄惈偑偁偭偨丅
僀僊儕僗偱敪攧偝傟偨5枃慻偺亀Bunny Berigan: The Key Sessions 1931-1937亁偲偄偆CD僙僢僩偑偁傞丅偦傟偵偼"A Legend of Jazz Trumpet Who Played Like an Angel and Lived Like a Devil"偲偄偆暃戣偑晅偄偰偄傞丅偮傑傝乽揤巊偺傛偆偵墘憈偟丄埆杺偺傛偆偵惗偒偨揱愢偺僩儔儞儁僢僞乕乿偲偄偆傢偗偩偑丄尵偄偨偄偙偲偼暘偐傞偗傟偳丄偙傟偼岆夝傪梌偊偐偹側偄昞尰偩丅傓偟傠乽埆杺偺傛偆偵墘憈偟丄揤巊偺傛偆偵惗偒偨乿偲尵偭偨傎偆偑惓偟偄偲巚偆丅斵偼戝庰堸傒偱丄偟偠傘偆堸傫偱偄偨丅僗僥乕僕偵尰傟傞偲偒偼偄偮傕傾儖僐乕儖偺廘偄傪敪嶶偟偰偄偨偲偄偆丅偩偑儔僢僷傪岥偵偔傢偊傞偲丄偳傫側偵悓偭偰偄偰傕偗偭偟偰墘憈偑棎傟傞偙偲偼側偔丄忢偵旤偟偄壒傪嬁偐偣偨丅斵偼傗偝偟偄恖暱偱丄僶儞僪偺儊儞僶乕偲愙偡傞偲偒偼丄堦搙傕搟偭偨傝丄尵梩傪峳棫偰偨傝偡傞偙偲偼側偐偭偨丅儊儞僶乕偐傜媼椏偺抣忋偘傪怽偟崬傑傟傞偲丄壗偲偐傗傝孞傝偟偰偦傟偵墳偠偰偄偨丅儀儕僈儞偺揱婰亀Bunny Berigan: Elusive Legend of Jazz亁乮Robert Dupuis挊丄Luisiana State University Press姧乯傪撉傓偲丄儀儕僈儞偺僒僀僪儊儞偨偪偼堎岥摨壒偵丄儀儕僈儞偺夁搙偺堸庰暼偲僶儞僪摑棪椡偺寚擛傪嫇偘丄偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺慺惏傜偟偄恖娫惈偲揤嵥揑側僾儗僀傪宧垽偟丄偄偮傑偱傕斵偲峴摦傪偲傕偟偨偐偭偨偲丄夰偐偟偝傪崬傔偰夞憐偟偰偄傞丅
捠愢偱偼丄儀儕僈儞偑1937擭偐傜棪偄偨僆乕働僗僩儔偼恖婥偑弌偢丄惉岟偟側偐偭偨偲偝傟偰偄傞偑丄傏偔偼偦偆偱偼側偐偭偨偲巚偆丅偩偄偄偪丄戝夛幮偱偁傞償傿僋僞乕偺愱懏偵側傝丄3擭偵搉偭偰90嬋埲忋傕儗僐乕僨傿儞僌偟偰偄傞偺偩丅攧傟側偗傟偽偙傫側偵懕偗偰榐壒偼偟偰偄側偄偩傠偆丅偦傟偵僶儞僪偺僸僢僩嬋傕帩偭偰偍傝丄僣傾乕偺梊掕傕偓偭偟傝媗傑偭偰偄偨丅儊儞僶乕偵偼丄僕儑乕僕乕丒僆乕儖僪乮ts乯丄儗僀丒僐僯僼乮tb乯丄僈僗丒價償僅僫乮cl乯丄僕儑乕丒僽僔儏僉儞乮p乯丄僶僨傿丒儕僢僠乮ds乯偲偄偭偨堦棳偺儈儏乕僕僔儍儞傪梚偟偰丄壒妝柺偱偺幚椡傕旛偊偰偄偨丅偩偐傜丄僌僢僪儅儞傗僪乕僔乕傎偳偱偼側偄偵偣傛丄偐側傝偺恖婥偑偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅慜宖偺揱婰偵傛傞偲丄僶儞僪傊偺弌墘埶棅偼偨偔偝傫偁偭偨偺偵丄帒嬥揑側棟桼偱夝嶶偵捛偄崬傑傟偨傜偟偄丅儕乕僟乕偱偁傞儀儕僈儞帺恎偺宱塩擻椡偵栤戣偑偁偭偨偙偲偵傛傞偑丄儅僱乕僕儍乕偑偄偄壛尭側恖娫偱僶儞僪偑怘偄暔偵偝傟偨偙偲傕偁偭偨傛偆偩丅傕偲傕偲僿償傿丒僪儕儞僇乕偩偭偨偺偵壛偊丄僶儞僪宱塩忋偺僗僩儗僗偱偝傜偵寖偟偔庰傪偁偍傞傛偆偵側傝丄偦傟偑斵傪巰偵捛偄傗偭偨丅
2007.07.12 (栘) 僕儍僘偲僄儘僥傿僔僘儉
儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偑1928擭偵悂偒崬傫偩嬋偵乹僞僀僩丒儔僀僋丒僕僗乺乮Tight Like This乯偲偄偆寙嶌偑偁傞丅偙偺帪婜丄儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偼憂憿惈偺捀揰偵偁偭偨丅儂僢僩丒僼傽僀償丄儂僢僩丒僙償儞偲偄偆儗僐乕僨傿儞僌丒僐儞儃偵傛偭偰楌巎揑柤墘傪師乆偵悂偒崬傒丄摉帪偺丄偦偟偰屻悽偺丄僩儔儞儁僢僞乕偺傒側傜偢偁傜備傞僕儍僘丒儈儏乕僕僔儍儞偵塭嬁傪媦傏偟偨丅偦傫側悂崬傒偺側偐偱傕堦悽堦戙偺墘憈偩偲巚傢傟傞偺偑乹僞僀僩丒儔僀僋丒僕僗乺偩丅屻敿偵弌偰偔傞儖僀偺僩儔儞儁僢僩丒僜儘偼恄偑偐傝揑偱丄惷偐側弌偩偟偱僗僞乕僩偟丄師戞偵擬婥傪憹偟偰偄偒丄嵟屻偵僋儔僀儅僢僋僗傪寎偊傞偲偄偆僪儔儅僥傿僢僋側峔惉偼尒帠偲偄偆傎偐偼側偄丅偁傜備傞帪戙傪捠偠偰嵟崅偺僕儍僘丒僷僼僅乕儅儞僗偱偁傝丄壗搙挳偄偰傕戝偒側姶摦傪妎偊傞丅偙偺嬋偼丄偦偺傕偺僘僶儕丄僙僢僋僗傪戣嵽偵偟偰偄傞丅嬋柤偺乹僞僀僩丒儔僀僋丒僕僗乺偼丄乽偁偁丄偙傫側偵屌偔側偭偰乿偲偄偆堄枴偩偑丄壗偺偙偲傪巜偟偰偄傞偺偐偼尵偆傑偱傕側偄偩傠偆丅墘憈偺搑拞偵壗搙偐 "Oh, it's tight like this" 偲偄偆彈惈偺嫨傃惡偑憓擖偝傟傞偑丄偙傟偼傾儗儞僕儍乕偺僪儞丒儗僢僪儅儞偑彈偺惡傪柾偟偰擖傟偨傜偟偄丅偦傫側斱辔側嬋偑帪戙傪夋偡傞僕儍僘偺柤墘偵側偭偨偺偩偐傜偍傕偟傠偄丅傾儊儕僇偱偼丄摨帪婜偵榐壒偝傟偨乹僂僃僗僩丒僄儞僪丒僽儖乕僗乺偑儖僀丒傾乕僋僗僩儘儞僌偺帄崅偺柤墘偲偝傟偰偄傞偺偵斾傋丄偙偺嬋偼偁傑傝偺斱辔偝偺偨傔偐丄偦傟傎偳崅偔昡壙偝傟偰偄側偄丅偩偑僥乕儅偑壗偱偁傟丄乹僞僀僩丒儔僀僋丒僕僗乺偱偺儖僀偺擖恄偺僾儗僀偼丄抐慠丄懠偺悂偒崬傒傪埑偟偰偄傞丅
僕儍僘偼憂惉婜偐傜丄辔嶨側傕偺傗棤幮夛揑側傕偺偲枾愙偵偐偐傢傝偁偭偰偄偨丅崟恖偺僨傿僉僔乕傗僗僀儞僌偵偼丄惈傗杻栻傪埫帵偡傞嬋偑傛偔尒庴偗傜傟傞丅偦傟偼僕儍僘偺杮尮揑側妶椡偲晄壜暘偺娭學偵偁偭偨丅20悽婭偺暥妛傗旤弍偵偼僙僢僋僗傗僄儘僥傿僔僘儉傪儌僥傿乕僼偵偟偨傕偺偑懡偄偑丄僕儍僘傕偦傟偲摨楍偵榑偠傞偙偲偑偱偒傞丅
僨儏乕僋丒僄儕儞僩儞偵傕摨庯岦偺嬋偑偁傞丅乹僂僅乕儉丒償傽儕乕乺乮Warm Valley乯偲偄偆嬋偩丅1940擭偵傾儖僩丒僒僢僋僗偺僕儑僯乕丒儂僢僕僗傪僼傿乕僠儍乕偟偰榐壒偝傟偨僶儔乕僪偱偁傝丄偙傟偼僄儕儞僩儞丒僆乕働僗僩儔偺寙嶌偱偁傞偲摨帪偵丄儂僢僕僗偺戙昞揑柤墘偺傂偲偮偵悢偊傜傟偰偄傞丅嬋柤偺乽抔偐偄扟娫乿偲偼壗偐丠 扤傕偑楢憐偡傞偛偲偔丄偦傟偼彈懱偺旈傔傜傟偨売強偩丅巒尨揑側僄僱儖僊乕傪姶偠偝偣傞儖僀偺乹僞僀僩丒儔僀僋丒僕僗乺偲偼堘偭偰丄偙偪傜偼崄婥昚偆僜僼傿僗僥傿働乕僩偝傟偨墘憈偱偁傝丄儂僢僕僗偺僾儗僀偼丄偊傕偄傢傟偸墣偐偟偝偲姱擻惈傪偨偨偊偰偄傞丅儂僢僕僗偺僜儘偼愨昳偱偁傝丄撈摿偺僗僀乕僩側僩乕儞丄僌儕僢僒儞僪傪惗偐偟偨懅偺挿偄僼儗乕僕儞僌偼丄偨傔懅偑弌傞傎偳旤偟偄丅偙傟偼乹僜僼傿僗僥傿働僀僥僢僪丒儗僨傿乺傗乹崄悈慻嬋乺偲偄偭偨嬋偱惉弉偟偨彈惈傊偺巀旤傪昞尰偟偨僄儕儞僩儞偑丄堦曕摜傒崬傫偱彈惈偺恄旈惈傗僄儘僥傿僔僘儉傪儌僠乕僼偵嶌偭偨堎怓偺嶌昳側偺偩丅
2007.07.08 (擔) 崱擭偺東栿儈僗僥儕乕偼晄嶌丄偱傕孈傝弌偟暔傕偁傞偧
2007擭傕敿暘偑夁偓偨偑丄崱擭偼東栿儈僗僥儕乕偑晄嶌偱丄偙傟傑偱偺偲偙傠摿昅偡傋偒彫愢偑傎偲傫偳尒摉偨傜側偄丅僕僃僼儕乕丒傾乕僠儍乕偺乽僑僢儂偼媆偔乿乮怴挭暥屔乯偼傕偆傂偲偮僐僋偑側偐偭偨偟丄僩儅僗丒僴儕僗偺乽僴儞僯僶儖丒儔僀僕儞僌乿乮怴挭暥屔乯偼傑傞偱塮夋偺僲儀儔僀僛乕僔儑儞偺傛偆偱丄拞恎偑僗僇僗僇偩偭偨丅G.M.僼僅乕僪偼傏偔偺岲偒側嶌壠偩偑丄僲儞僼傿僋僔儑儞丒儔僀僞乕偺僼儔儞僋丒僐乕僜傪庡恖岞偲偡傞僔儕乕僘偺戞4嶌乽撆杺乿乮怴挭暥屔乯偼丄偙傟傑偱偺3嶌偑偡傋偰崅悈弨偩偭偨偺偵斾傋偰丄偐側傝棊偪傞撪梕偩偭偨丅僾儘僢僩偺揥奐偑嶨偩偟丄帠審偺恀憡傪抦傞撲偺彈偑昤偒曽偑偁偄傑偄偩偟丄堦晹偱偼僐乕僜埲忋偵僼傽儞偑懡偄偲尵傢傟傞憡朹偺慡恎巋惵彈僇儊儔儅儞偑丄崱嶌偱偼枺椡偵朢偟偄偟偱丄偑偭偐傝偝偣傜傟偨丅嵶嬠僥儘偲偄偆戣嵽偑憡墳偟偔側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦傫側側偐偱桞堦悇彠偵壙偡傞偺偑丄偙傟偑弶傔偰偺栿弌偲側傞傾儖僫儖僪丒僐儗傾偺乽僉儏乕僶丒僐僱僋僔儑儞乿乮暥弔暥屔乯偩丅僉儏乕僶偺忣曬晹堳僇儖儘僗偼奀奜偱偺挿擭偵傢偨傞挸曬妶摦傪宱偰杮崙偵婣偭偰偔傞偑丄嵢偵巰側傟丄巕嫙偨偪偲偼怱偑捠偄崌傢側偄丅偦傫側偲偒丄傾儊儕僇偵朣柦偡傞偨傔巕嫙偨偪偑棐偺側偐傪敵偱弌敪偟偨偺傪抦偭偨僇儖儘僗偼丄巕嫙偨偪傪媬偆傋偔偦偺偁偲傪捛偆丅偦偟偰傾儊儕僇偵搉偭偨僇儖儘僗傪婋尟側悌偑懸偪庴偗偰偄傞丄偲偄偭偨撪梕偱偁傞丅崪奿偑偟偭偐傝偟偰偍傝丄挸曬偺僾儘偱偁傞僇儖儘僗偺峴摦偑僴乕僪儃僀儖僪丒僞僢僠偱昤偐傟傞偺偑偄偄偟丄僇儖儘僗偺媤揋偱偁傞CIA晹堳偲偺愴偄傕嬞敆姶偑偁傞丅傕偭偲傕怱庝偐傟傞偺偼丄恖娫偳偆偟偺嵃偺怗傟崌偄偩丅僇儖儘僗偲巕嫙偨偪偺娫偺晝偲巕偺垽忣丄偦偟偰傾儊儕僇偱僇儖儘僗偑壓廻偡傞堦壠偲偺岎棳偼丄嫻偵敆傞傕偺偑偁傞丅僗僩乕儕乕揥奐偵懡彮擄偑偁傞偑丄偱傕慡曇偵柆懪偮抝偺屩傝丄恊巕偺鉐丄愗側偄抝彈偺垽偑丄偦傟傪廩暘偵曗偭偰偄傞丅
2007.07.07 (搚) 僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺僾儔僀償僃乕僩斦
愭偛傠丄僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺僾儔僀償僃乕僩榐壒偝傟偨壒尮傪CD壔偟偨亀Clifford Brown at the Cotton Club 1956亁偑敪攧偝傟偨丅偙傟傪婡夛偵丄偙偺悢擭娫偵敪攧偝傟偨僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺僾儔僀償僃乕僩榐壒斦偺撪梕傪専徹偟偰偍偙偆丅傔傏偟偄傕偺傪嫇偘傟偽師偺傛偆偵側傞丅Clifford Brown + Elic Dolphy/Together 1954 (RLR 88616) 2005
The Last Concert/Brown-Roach Quintet (RLR 88617) 2005
Brown-Roach Quintet/More Live at the Bee Hive (RLR 88626) 2006
Clifford Brown at the Cotton Club 1956 (Lonehill LHJ10292) 2007
偙傟傜偼弶CD壔偲鎼傢傟偰偄傞偑丄幚嵺偼偦偆偱偼側偄丅偙傟傜偺壒尮偼偡傋偰僀僞儕傾偺Philology儗乕儀儖偵傛傝亀Brownie Eyes亁偲偄偆CD僔儕乕僘偵擖偭偰偡偱偵悽偵弌偰偄傞乮堦斒攧傝偼偝傟偰偄側偄偑乯丅亀Brownie Eyes亁僔儕乕僘偼尰嵼Vol.36傑偱敪攧偝傟偰偄傞丅偙傟偼僽儔僂儞偺儗傾側壒尮偑栐梾偝傟偨丄僼傽儞偵偲偭偰偼傑偝偵曮愇敔偺傛偆側僔儕乕僘偩偑丄偄偐傫偣傫曇廤偑偄偄壛尭偱丄摨偠壒尮偑偨偔偝傫僟僽偭偰偄偨傝丄僨乕僞偑僨僞儔儊偩偭偨傝偡傞偺偱丄婐偟偄斀柺丄偳偆偵傕暊棫偨偟偄丅忋偵宖偘偨4偮偺傾儖僶儉偺壒尮偼丄偙偺亀Brownie Eyes亁偐傜庢偭偨傕偺偩偲巚傢傟傞偑丄傑偲傑偭偨僙僢僔儑儞傪敳偒弌偟丄壒傪夵慞偟丄僨乕僞傪惍旛偟丄偒偪傫偲偟偨夝愢偑晅偟偰偁傝丄偦傟側傝偵堄媊偺偁傞傕偺偵巇忋偑偭偰偄傞丅
偙偺4嶌昳偺側偐偱丄傕偭偲傕挳偒墳偊偑偁傞偺偼丄崱擭偵側偭偰敪攧偝傟偨3枃慻偺亀At the Cotton Club 1956亁偩丅偙偺僐僢僩儞丒僋儔僽偼桳柤側30擭戙偵僄儕儞僩儞偑崻忛偵偟偨僯儏乕儓乕僋偺僋儔僽偱偼側偔丄僆僴僀僆廈僋儕乕償儔儞僪偺僕儍僘丒僋儔僽偩丅偙偺傾儖僶儉偵偼丄偙偺僐僢僩儞丒僋儔僽偵1956擭5寧28擔乣6寧1擔偵弌墘偟偨嵺偺戞3婜僽儔僂儞亖儘乕僠丒僋僀儞僥僢僩偵傛傞墘憈偑廂傔傜傟偰偄傞丅僽儔僂儞偼丄乹A楍幵偱峴偙偆乺乹僕儑乕僪僁乺側偳偱丄屻婜偺斵傪摿挜偯偗傞僗儉乕僗側僼儗乕僕儞僌傪嬱巊偟丄帺怣偵枮偪堨傟偨僜儘傪偲偭偰偄傞丅壒幙傕僾儔僀償僃乕僩榐壒偵偟偰偼椙岲偩丅嫟墘偺僜僯乕丒儘儕儞僘傕杮椞傪敪婗偟偰偍傝丄僶儔乕僪偺乹僟乕儞丒僓僢僩丒僪儕乕儉乺側偳偼埑姫偩丅朻摢偱僽儔僂儞偑儊儞僶乕傪徯夘偟偰偄傞偑丄偦偺嵟屻偱乽I play the trumpet. My name is Clifford Brown乿偲帺屓徯夘偡傞斵偺尵梩偑怺偔報徾偵巆傞丅側偍丄僐僢僩儞丒僋儔僽偱偺墘憈偼慡懱偺4暘偺3傎偳偱丄巆傝偺4暘偺1偵偼56擭2寧偵弌墘偟偨僶僢僼傽儘乕偺僞僂儞丒僇僕僲偵偍偗傞墘憈偺僄傾丒僠僃僢僋偑擖偭偰偄傞丅
偙傟偵師偄偱怱庝偐傟傞偺偼亀More Live at the Bee Hive亁偲偄偆2枃慻偺僙僢僩偩丅僔僇僑偺僋儔僽丄價乕丒僴僀償偱偺僽儔僂儞偺儔僀償偼丄偐偮偰亀儘僂丒僕僯傾僗亁偲偄偆僞僀僩儖偺LP偱敪攧偝傟偨傕偺偑偁傞偑丄偙傟偼偦傟傛傝4儢寧傎偳慜偺1955擭6寧30擔偵榐傜傟偨傕偺丅尰嵼偼亀Live at the Bee Hive亁偲偟偰CD壔偝傟偰偄傞亀儘僂丒僕僯傾僗亁偼丄僽儔僂儞偲儘儕儞僘偲偺僕儍儉丒僙僢僔儑儞傪廂傔偨傕偺偱丄僽儔僂儞亖儘乕僠丒僋僀儞僥僢僩偵儘儕儞僘偑壛擖偡傞偒偭偐偗偲側偭偨僙僢僔儑儞偲尵傢傟偰偄傞偑丄偙偺亀More Live at the Bee Hive亁偼僴儘儖僪丒儔儞僪傪娷傓戞2婜儗僊儏儔乕丒僋僀儞僥僢僩偵傛傞儔僀償偩丅偙傟傕墘憈丄榐壒偲傕偵忋乆偱丄僽儔僂儞偑僗僩僢僾丒僞僀儉偵忔偭偰墑乆偲僗儕儕儞僌側僜儘傪偲傞1嬋栚偺乹孨嫀傝偟屻乺傪偼偠傔丄夣墘偺楢懕偩丅嵟屻偺3暘偺1偼丄埲慜僄儗僋僩儔偐傜LP敪攧偝傟偨傑傑CD偵側偭偰偄側偐偭偨傾儖僶儉亀僺儏傾丒僕僯傾僗亁偺慡嬋偑廂榐偝傟偰偄傞丅
亀The Last Concert亁偼丄尰嵼偺偲偙傠朣偔側傞慜偺僽儔僂儞偑挳偗傞嵟屻偺墘憈偱偁傞丄僲乕僼僅乕僋巗偺僐儞僠僱儞僞儖丒儗僗僩儔儞偱偺1956擭6寧18擔偺儔僀償偑廂傔傜傟偨2枃慻丅僽儔僂儞偺儔僗僩墘憈偲尵偊偽丄埲慜偼僐儘儞價傾偐傜弌偨亀價僊僯儞僌丒傾儞僪丒僕丒僄儞僪亁強廂偺丄僽儔僂儞偑幵偱帠屘巰偟偨摉擔偺僼傿儔僨儖僼傿傾偱偺僕儍儉丒僙僢僔儑儞偲偝傟偰偄偨偑丄偙傟偼僽儔僂儞偺揱婰亀僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞丗揤嵥僩儔儞儁僢僞乕偺惗奤亁乮僯僢僋丒僇僞儔乕僲挊丄壒妝擵桭幮姧乯偵柧傜偐側傛偆偵丄偦傟傛傝1擭慜偺榐壒偱偁傞偙偲偑敾柧偟偨丅僐儞僠僱儞僞儖丒儗僗僩儔儞偺儔僀償偼壒偑埆偄丅傑偨柍杁偲傕偄偊傞傎偳偺栆楏側傾僢僾丒僥儞億偵傛傞墘憈偑懡偔丄偦傫側懍偝偱傕偗偭偟偰巟棧柵楐偵側傜偢惍慠偲偟偨僾儗僀傪偡傞僽儔僂儞偺媄検偵垹慠偲偝偣傜傟傞偑丄壒妝惈偲偄偆揰偐傜偼崅偄昡壙偼偱偒側偄丅偙偺傾儖僶儉傕嵟屻偺3暘偺1傎偳偼丄55擭7寧偺僽儔僂儞亖儘乕僠偑偨偩堦搙偩偗弌墘偟偨僯儏乕億乕僩丒僕儍僘丒僼僃僗僥傿償傽儖偱偺儔僀償偑廂傔傜傟偰偄傞丅嵟屻偺1嬋乹2恖偱偍拑傪乺偼丄捒偟偔僠僃僢僩丒儀僀僇乕丄億乕儖丒僨僗儌儞僪丄僕僃儕乕丒儅儕僈儞丄僨僀償丒僽儖乕儀僢僋側偳偺柤庤偨偪偲僕儍僘丒僙僢僔儑儞傪偡傞僽儔僂儞偑挳偗傞婱廳側僩儔僢僋偩丅
亀Together 1954亁偼丄1954擭6寧偵僽儔僂儞偑LA偺僄儕僢僋丒僪儖僼傿戭偱峴側偭偨僕儍儉丒僙僢僔儑儞傪廂傔偨傾儖僶儉丅摉帪傑偩柍柤偩偭偨僪儖僼傿偼帺戭偺僈儗乕僕傪僗僞僕僆偵夵憰偟丄儈儏乕僕僔儍儞拠娫偵夝曻偟偰偄偨丅僽儔僂儞偲儘乕僠偼丄偙偙偱僥僨傿丒僄僪儚乕僘偺屻擟僥僫乕憈幰偺僴儘儖僪丒儔儞僪傪尒偮偗偨丅姲偄偩僕儍儉丒僙僢僔儑儞側偺偱丄墘憈偲偟偰偺嬞敆姶偼婜懸偱偒側偄偑丄乹僼傽僀儞丒傾儞僪丒僟儞僨傿乺偺揤嬻傪旘隳偡傞偑擛偒僜儘側偳丄偙偙偱傕僽儔僂儞偺僾儗僀偼慺惏傜偟偄丅僽儔僂儞偑僺傾僲傪抏偔僩儔僢僋傕偁傞丅僪儖僼傿偺僾儗僀偼僷乕僇乕傪渇渋偲偝偣側偑傜丄屻偺斵偺僗僞僀儖偺朑夎傪偦偙偐偟偙偵姶偠偝偣偰嫽枴怺偄丅偙偺偲偒偺僙僢僔儑儞偵偼丄傕偆1嬋乹儚僼乕乺偑偁傝丄亀Brownie Eyes亁偵偼擖偭偰偄傞偑丄偙偙偵偼廂榐偝傟偰偄側偄丅傾儖僶儉嵟屻偺2嬋偼僽儔僂儞偺帺戭偱偺楙廗僙僢僔儑儞偱丄僺傾僲傪敽憈偵僽儔僂儞偑僩儔儞儁僢僩傪悂偄偰偄傞偲僋儗僕僢僩偝傟偰偄傞偑丄偙偺僩儔儞儁僢僩偼僽儔僂儞偱偼側偄丅僼儗乕僕儞僌傕僀儞僩僱乕僔儑儞傕柧傜偐偵暿恖偩丅亀Brownie Eyes亁偱偼丄僺傾僲敽憈偑僽儔僂儞偱丄僩儔儞儁僢僩偼儕乕丒儌乕僈儞傑偨偼價儖丒僴乕僪儅儞偲側偭偰偄傞偑丄偍偦傜偔偙傟偑惓偟偄偱偁傠偆丅
2007.07.06 (嬥) 嵟嬤偺傾僋僔儑儞塮夋偼偗偭偙偆偍傕偟傠偄
偙偺偲偙傠僴儕僂僢僪惢偺傾僋僔儑儞塮夋傪棫偰懕偗偵娤偰偄傞丅傗偼傝戝偒側僗僋儕乕儞偱娤傞塮夋偼偄偄丅偟偽傜偔塮夋娰偵偼懌傪塣傫偱偄側偐偭偨偑丄偙傟偐傜帪娫傪傒偮偗偰偱偒傞偩偗塮夋娰偵捠偍偆偲巚偆丅側偵偟傠崱擭偐傜僔儖僶乕椏嬥偺1000墌偱娤傟傞傢偗偩偟丅偒偭偐偗偼僗僥傿乕償儞丒僴儞僞乕偺朻尟彫愢偺寙嶌乽嬌戝幩掱乿傪塮夋壔偟偨亀僓丒僔儏乕僞乕/嬌戝幩掱亁偩偭偨乮傾儞僩儚儞丒僼乕僋傾娔撀丄儅乕僋丒僂僅儖僶乕僌庡墘乯丅堷戅偟偨尦暷摿庩晹戉偺揱愢揑側柤慱寕庤儃僽丒儕乕丒僗儚僈乕偑姫偒崬傑傟偨戝摑椞埫嶦偵偐傜傓堿杁傪傔偖傞僗僩乕儕乕偱丄塮夋偼傎傏尨嶌偵拤幚偵嶌傜傟偰偄傞丅榖偺棳傟偼夣揔偱儊儕僴儕傛偔丄嬞敆姶偵偁傆傟偰偍傝丄僗儚僈乕栶偺僂僅乕儖僶乕僌偺柺峔偊傗懱偺摦偒傕偄偄丅尨嶌偵偁偭偨僗僩僀僢僋側抝偺惗偒曽偺傛偆側姶妎偼惗偐偝傟偰偄側偄偑丄偦偙傑偱梫媮偡傞偺偼柍棟偩傠偆丅僴儞僞乕偼乽嬌戝幩掱乿埲屻丄儃僽丒儕乕偺晝恊傾乕儖丒僗儚僈乕傪庡恖岞偵丄晳戜傪50擭戙偺傾儊儕僇偵愝掕偟偰乽埆摽偺搒乿乽嵟傕婋尟側応強乿偲偄偭偨彫愢傪敪昞偟偰偄傞偑丄偙偪傜偺傎偆偑傓偟傠僸乕儘乕偑埆偲愴偆偲偄偆恾幃傗帇妎揑側僀儊乕僕偐傜偟偰丄塮夋壔偟傗偡偄偲巚偆偺偩偑丄偳偆偩傠偆丅岞奐偝傟偰娫傕側偄柭傝暔擖傝偺戝嶌亀僟僀丒僴乕僪4.0亁偼丄梊憐偳偍傝姶怱偟側偐偭偨乮儗儞丒儚僀僘儅儞娔撀丄僽儖乕僗丒僂傿儕僗庡墘乯丅CG傗摿庩岠壥傪懡梡偟丄戝嬥傪搳偠偰戝妡偐傝偵嶌偭偰偄傞偑丄尰幚偽側傟偟偨愝掕傗応柺揥奐偵偼徫偭偰偟傑偆偟丄壗搙傕巰傫偱偄偰偍偐偟偔側偄偺偵偗偭偟偰巰側側偄庡恖岞偺晄巰恎傇傝偑偁傑傝偵峳搨柍宮偡偓傞丅亀僟僀丒僴乕僪亁偼戞1嶌偑寙嶌偩偭偨丅崅憌價儖偺拞偲偄偆尷傜傟偨嬻娫偱丄惗恎偺懱偩偗偱埆偲懳寛偡傞偲偄偆愝掕偑椙偐偭偨丅價儖偺奜偵偄傞丄岆偭偰巕嫙傪幩嶦偟偨偨傔対廵傪帩偰側偔側偭偰偟傑偭偨寈姱偲偺岎棳偲偄偭偨憓榖傕偄偄丅偦偺寈姱偑嵟屻偵巚傢偢対廵傪敳偄偰庡恖岞傪媬偆僔乕儞側偳嵟崅偩偭偨丅亀僟僀丒僴乕僪亁偼怴偟偄僔儕乕僘偑嶌傜傟傞偵偮傟偰丄戝嶌巙岦偑僄僗僇儗乕僩偟偰偄偒丄偳傫偳傫偮傑傜側偔側偭偰偄傞丅
榖戣偺亀300乮僗儕乕丒僴儞僪儗僢僪乯亁偼惁偄塮夋偩偭偨乮僓僢僋丒僗僫僀僟乕娔撀丄僕僃儔儖僪丒僶僩儔乕庡墘乯丅婭尦慜偵300恖偺僗僷儖僞孯偑100枩恖乮両乯偺儁儖僔儍孯偲愴偭偨偲偝傟傞乽僥儖儌僺儏儔僀偺愴偄乿傪昤偄偨傾儊儕僇儞丒僐儈僢僋偺塮夋壔偩偑丄傑偢丄偙傟傑偱尒偨偙偲傕側偄丄埫偔慹偄僙僺傾挷偺夋憸張棟偵堷偒偢傝崬傑傟傞丅憗夞偟偲僗儘乕丒儌乕僔儑儞傪岻傒偵巊偭偨愴摤応柺丄壖柺傪偐傇偭偨晄巰晹戉傗夦椡嫄恖傗嫄戝徾側偳丄儁儖僔儍孯偺晄婥枴側巔傕敆椡枮揰偩丅僗僷儖僞墹儗僆僯僟僗偵暞偡傞僶僩儔乕偺擏懱旤偲婥敆偺偙傕偭偨墘媄丄嬝崪棽乆偨傞僗僷儖僞偺暫巑偨偪偵傕崨傟崨傟偡傞丅偲偄偆傢偗偱丄偙偺偲偙傠懡偄屆戙巎寑偺側偐偱偼丄乽僌儔僨傿僄乕僞乕乿偲暲傇丄戞1媺偺屸妝塮夋偵巇忋偑偭偰偄偨丅偱傕丄嵟嬤偺偙偆偄偭偨塮夋傪娤傞偵偮偗丄偐偮偰僀僞儕傾偱惙傫偵嶌傜傟偨僗僥傿乕償丒儕乕償僗庡墘偺丄偄傢備傞乬僗僂僅乕僪丒傾儞僪丒僒儞僟儖乭塮夋偑夰偐偟偔巚偄弌偝傟傞丅僗僥傿乕償丒儕乕償僗庡墘塮夋偼丄傾儊儕僇偱偼DVD偱弌偰偄傞偺偵擔杮偱偼偄傑偩偵價僨僆壔偝傟偰偄側偄丅傏偔偼堦搙偁傞價僨僆惂嶌夛幮偵偙偺庤偺塮夋偺價僨僆敪攧傪恑尵偟偨偙偲偑偁傞丅扴摉幰傕忔傝婥偵側偭偨偑丄宊栺嬥偑崅偔偰嵦嶼偑崌傢側偄偲偄偆偙偲偱幚尰偟側偐偭偨丅愄偙偆偄偭偨塮夋傪娤偰嫻傪桇傜偣偨抍夠偺悽戙偺恖娫偼偨偔偝傫偍傝丄DVD壔傪懸偭偰偄傞偲巚偆偺偩偑丅
2007.06.07 (栘) 儘僀丒僿僀儞僘偺僪儔儈儞僌偵悓偭偨堦栭
6寧弶傔丄搶嫗僽儖乕僲乕僩偱儀僥儔儞丒僪儔儅乕丄儘僀丒僿僀儞僘偺儔僀償傪娤偨丅僶儞僪偼傾儖僩丒僾儔僗丒僗儕乕丒儕僘儉偲偄偆僇儖僥僢僩偱丄僿僀儞僘偐傜偡傞偲懛偺傛偆側庒庤偽偐傝傪儊儞僶乕偵廬偊偰偄偨丅僿僀儞僘偼1925擭惗傑傟偩偐傜丄崱擭偱82嵨丅埲慜偼娵偄婄偲戝偒側栚偱惛湜側暤埻婥傪曻偭偰偄偨偑丄偄傑偼擭楊憡墳偵丄暿恖偺傛偆偵婄偮偒偑曄傢偭偰偟傑偭偰偄傞丅40擭戙偐傜僾儘偲偟偰墘憈偟偰偄傞偺偱丄傕偆敿悽婭埲忋傕妶摦偟懕偗偰偄傞偙偲偵側傞丅僿僀儞僘偺僾儗僀偼丄偝偡偑偵墲擭偺僷儚乕偼側偔側偭偨偑丄傑偩傑偩寬嵼偱丄僔儍乕僾側價乕僩丄岻柇側僼傿儖丒僀儞丄揑妋側彫儚僓偵傛傝丄僗僀儞僌姶偁傆傟傞僪儔儈儞僌傪挳偐偣偰偄偨丅嬋偼乹僆乕儖丒僓丒僔儞僌僘丒儐乕丒傾乕乺乹儎乕僪僶乕僪丒僗僀乕僩乺乹僪僫丒儕乕乺偲偄偭偨僶僢僾丒僋儔僔僢僋偑拞怱丅摨峴偟偨丄帺懠偲傕偵擣傔傞悽奅堦偺僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗丒僼傽儞偱偁傞M偝傫偼丄柤斦亀僕儍僐丒僷僗僩儕傾僗偺徰憸亁偺朻摢偵廂傔傜傟偰偄傞乹僪僫丒儕乕乺偑弌偰偒偨偺偱丄庤傪扏偄偰婌傫偱偄偨丅1嬋偩偗丄僂傿儞僫丒儚儖僣偺乹僪僫僂愳偺偝偞攇乺乮傾僯僶乕僒儕乕丒僜儞僌乯偲偄偆曄側嬋傪傗傝丄壧傪壧偭偨傝丄僗僥乕僕偺慜曽偵僴僀僴僢僩傪帩偭偰偒偰扏偄偨傝偲丄僄儞僞僥僀僫乕傇傝傪尒偣偰偄偨丅偙傟偼斵偑僗僥乕僕偱偄偮傕傗傞庯岦側偺偩傠偆偐丅僿僀儞僘偼僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕偵婥偵擖傜傟丄40擭戙廔傢傝偐傜50擭戙弶傔偵偐偗偰僷乕僇乕丒僋僀儞僥僢僩偺儗僊儏儔乕丒僪儔儅乕偲偟偰妶桇偟偨丅僷乕僇乕偲嫟墘偟偨恖偱偄傑傕尰栶偱墘憈偟偰偄傞偺偼丄儘僀丒僿僀儞僘偖傜偄偟偐偄側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅摨偠僪儔儅乕偱3嵨擭忋偺儅僢僋僗丒儘乕僠偼懚柦偩偑丄傕偆扏偗側偄偼偢偩丅僿僀儞僘偲偄偊偽償傽乕僒僞僀儖側僪儔儅乕偲偟偰桳柤偱丄價僶僢僾偺帪戙偐傜弌敪偟偨偑丄偦偺屻傕偁傜備傞帪戙偺偁傜備傞僗僞僀儖偺儈儏乕僕僔儍儞偐傜嫟墘偺惡偑偐偐偭偨丅僄儖償傿儞丒僕儑乕儞僘偺戙栶偱僐儖僩儗乕儞丒僇儖僥僢僩偵擖偭偰1963擭偺僯儏乕億乕僩丒僕儍僘嵳偵弌墘偟丄僄儖償傿儞傪傕椊偖戝擬墘傪斺業偟偨偺偼桳柤偩丅偙偺儔僀償傪廂榐偟偨傾儖僶儉亀僙儖僼儗僗僱僗亁傪垽挳偡傞僼傽儞偼懡偄丅僎僀儕乕丒僶乕僩儞傗僠僢僋丒僐儕傾偲偺嫟墘傕朰傟傜傟側偄丅儕乕僟乕丒傾儖僶儉偱偼丄儘乕儔儞僪丒僇乕僋傪僼傿乕僠儍乕偟偨僀儞僷儖僗偺亀傾僂僩丒僆僽丒僕丒傾僼僞僰乕儞亁傗僼傿僯傾僗丒僯儏乕儃乕儞偲嫟墘偟偨僯儏乕僕儍僘偺亀僂傿丒僗儕乕亁偑椙偐偭偨丅
M偝傫偲偲傕偵摨惾偟偨丄尦僪儔儅乕偱尰嵼偼僾儘儌乕僔儑儞夛幮傪宱塩偟偰偄傞H偝傫偼丄偐偮偰僪儔儉僗偺廋峴偺偨傔偵搉暷偟丄僼傿儕乕丒僕儑乕丒僕儑乕儞僘偵掜巕擖傝偟偰偄偨偙偲偑偁傞丅H偝傫偵傛傞偲僼傿儕乕丒僕儑乕偼帺暘偑偄偪偽傫懜宧偡傞僪儔儅乕偲偟偰儘僀丒僿僀儞僘偺柤傪嫇偘偰偄偨偦偆偩丅梋択偩偑丄H偝傫偼僼傿儕乕丒僕儑乕偵丄斵偑帺暘偱彂偄偨乹價儕乕丒儃乕僀乺偺僪儔儉僗偺晥柺傪尒偣偰傕傜偭偨偙偲偑偁傞偲偄偆丅偁偺儅僀儖僗偺傾儖僶儉亀儅僀儖僗僩乕儞僘亁偵擖偭偰偄傞僈乕儔儞僪乣僠僃儞僶乕僗乣僼傿儕乕丒僕儑乕偺僩儕僆偵傛傞嬋偩丅僼傿儕乕丒僕儑乕偼偁傜偐偠傔偦偺晥柺傪嶌偭偰儗僐乕僨傿儞僌偵椪傫偩丅梊憐偺偮偐側偄僗儕儖偵枮偪偁傆傟丄揤堖柍朌偵挳偙偊傞僼傿儕乕丒僕儑乕偺僪儔儈儞僌偩偑丄偠偮偼斵偼偄偮傕慜傕偭偰廃摓偵弨旛偟偰偄偨偺偑暘偐偭偰嬃偄偰偟傑偭偨丅
2007.05.20 (擔) 偙偺崙偺備偔偊
擔杮偼偄偭偨偄偳偆側偭偰偟傑偆偺偩傠偆丅愴屻嵟埆偺埨晹惌尃偺傕偲偱丄偙偺崙偼側傝傆傝偐傑傢偢寷朄傪夵惓偟丄孯帠崙壠傊偺摴傪曕傕偆偲偟偰偄傞丅埨晹偼偲偵偐偔壗偑壗偱傕丄A媺愴斊偺慶晝丄娸怣夘偺堚巙傪宲偄偱夵寷偟傛偆偲偟偰偄傞傛偆偩丅彫愹偺帪戙偐傜懕偄偰丄屄恖忣曬曐岇朄丄夵惓嫵堢婎杮朄丄杊塹挕偺徣傊偺奿忋偘丄偁偘偔偺偼偰偼栤戣偩傜偗偺崙柉搳昜朄埬偲丄傠偔側怰媍傕偣偢偵埆朄傪師乆偵惉棫偝偣丄塃孹壔傪悇偟恑傔偰偄傞丅偦偺愭偵偼夵寷偑懸偭偰偄傞丅夵寷榑幰偨偪偼丄乽傾儊儕僇偐傜墴偟晅偗傜傟偨寷朄偩偐傜丄帺庡寷朄傪惂掕偟側偗傟偽側傜側偄乿偲偄偆丅偩偑丄墴偟晅偗寷朄偱壗偑埆偄偐丅墴偟晅偗偐偳偆偐偼寷朄妛幰偵傛偭偰堄尒偑暘偐傟偰偄傞偑丄偨偲偊偦偆偱偁偭偨偲偟偰傕丄偩偐傜偙偦悽奅偵屩傞傋偒慺惏傜偟偄寷朄偑偱偒偨偺偩丅愴屻娫傕側偔怴寷朄傪嶌傞嵺丄傕偟擔杮恖偩偗偵擟偣偰偍偗偽丄愴慜偺棳傟傪堷偒偢偭偨傕偺偵側偭偰偄偨偵堘偄側偄丅墴偟晅偗偲尵偆側傜丄傓偟傠丄廤抍揑帺塹尃傪憗偔帩偰偲傾儊儕僇偐傜埑椡傪偐偗傜傟偰偄傞偺偩偐傜丄寷朄夵惓偙偦墴偟晅偗偲尵偆傋偒偩丅寷朄偑夵惓偝傟傟偽丄愴憟傊偺摴偑奐偐傟傞丅偡偱偵惌晎偼侾婡壗昐壄墌傕偡傞F22僗僥儖僗愴摤婡傪傾儊儕僇偐傜戝検偵峸擖偟傛偆偲寁夋偟偰偄傞偲偄偆丅擔杮偺孯廀嶻嬈偼奼戝偟丄晲婍桝弌偺嬛巭偑夝偐傟傞偙偲傕偦偆墦偄偙偲偱偼側偄偩傠偆丅偲偆偤傫丄偦偺愭偵偼妀晲憰偑偔傞丅孯旛傪帩偮偐傜偵偼丄妀暫婍偑側偗傟偽嫮偄棫応偵棫偰側偄偐傜偩丅偡偱偵丄妀曐桳偵偮偄偰榑媍偱偒側偄偺偼偍偐偟偄丄側偳偲尵偆帺柉搣媍堳傗孯奼榑幰偑弌偰偒偰偄傞丅桞堦偺旐敋崙偱偁傝丄擇搙偲愴憟偼婲偙偝側偄偲惥偄丄妀暫婍偺攑愨傪慽偊偰偒偨擔杮偑丄妀傪帩偮崙偵側傞偐傕偟傟側偄偺偩丅偙傫側偙偲傪嫋偟偰偄偄偺偐丅嵞孯旛傪彞偊傞攜偼丄僶僇偺堦偮妎偊偺傛偆偵杒挬慛偑峌傔偰偒偨傜偳偆偡傞傫偩偲尵偆偑丄椙幆偁傞孯帠昡榑壠偨偪偼丄杒偑峌傔偰偔傞偙偲側偳偁傝偊側偄偲庡挘偟偰偄傞丅孯奼榑幰偵偲偭偰丄杒挬慛偑柉庡崙壠偵側偭偰偟傑偊偽丄嵞孯旛偟傛偆偲偄偆戝偒側棟桼偑幐傢傟傞偙偲偵側傞丅偄傑偺杒挬慛偼斵傜偵偲偭偰傑偙偲偵搒崌偑偄偄懚嵼偩丅
傕偼傗僕儍乕僫儕僘儉偵偙偺晽挭傪墴偟偲偳傔傞婥奣偼側偄丅懴恔婾憰偺尦嫢偲尵傢傟側偑傜嵾偵栤傢傟側偐偭偨楢拞偑埨晹偺屻墖夛偱偁傞埨怶夛偺姴晹偵柤傪楢偹偰偄傞偙偲丄摑堦嫵夛偲偺偮側偑傝丄偐偮偰偺擔杮偺妀晲憰傪梕擣偡傞庯巪偺敪尵側偳丄埨晹偺廃傝偵扏偔嵽椏偼偄偔傜偱傕偁傞偺偵丄堦晹偺廡姧帍傪彍偄偰丄埑椡偑偐偐偭偰偄傞偺偐丄偦傟偲傕柤梍毷懝偱慽偊傜傟傞偺偑晐偄偺偐丄儅僗僐儈偼側偤偐庢傝忋偘傛偆偲偟側偄丅柉庡搣偺捛媮傕敆椡偑側偔丄帟偑備偄偙偲偙偺偆偊側偄丅媈榝偩傜偗偺徏壀擾悈憡偱偡傜丄堷偒偢傝壓傠偡偙偲偑偱偒側偄傑傑偩丅
埨晹偺尵摦偺偍慹枛傇傝偼丄擔杮偺戙昞偲偟偰傎傫偲偆偵抪偐偟偄丅堅埨晈栤戣偵娭偟丄孯偑嫮惂偟偨偺偼柧敀側偺偵丄搉暷慜偼丄堅埨晈傪孯偑嫮惂偟偨偐偳偆偐偼徹嫆偑側偄側偳偲尵偭偰偍偒側偑傜丄搉暷屻偼慜尵傪東偟偰嫮惂偺帠幚傪擣傔傞偲偄偆偰偄偨傜偔偩丅偱傕擔杮孯偺埆峴傪偁偐傜偝傑偵偟偨偔側偄埨晹偺杮壒偼乽嫮惂偱偼側偐偭偨乿偱偁傠偆丅A媺愴斊偑釰傜傟偰偄傞桋崙恄幮偵嶲攓偟偨偔偰偟傚偆偑側偄埨晹偺杮怱偼尒偊尒偊偩丅偦傕偦傕丄埨晹偵帄傞偙傟傑偱偺帺柉搣惌尃偑丄愴慜偺擔杮偑斊偟偨夁偪傪捈帇偟丄偒偭傁傝偲惛嶼偟偰偄側偐偭偨偐傜丄偄傑傕傾僕傾奺崙偐傜媈偄偺栚偱尒傜傟丄幱嵾偟側偗傟偽側傜側偄偺偩丅偄偮傑偱傕幱傑傝懕偗側偗傟偽偄偗側偄偺偼丄夁嫀傪惛嶼偟偰偄側偄惌晎庱擼偑帺傜嶵偄偨庬側偺偩丅
埨晹偼偟偒傝偵垽崙怱傪嫮挷偟丄乽旤偟偄崙乿側偳偲偄偆婥帩偪偺埆偄僉儍僢僠僼儗乕僘傪巊偆丅偲傫偱傕側偄帪戙嶖岆偩丅垽崙怱偲偼丄忋偐傜墴偟晅偗傜傟傞傕偺偱偼側偔丄帺慠偵桸偄偰偔傞傕偺側偺偩丅乽垽崙怱偼丄側傜偢幰偺嵟屻偺嫆傝偳偙傠乿偲偳偙偐偺妛幰偑尵偭偨偑丄傑偝偵偦偺偲偍傝偱丄愄偐傜垽崙怱傪尵偄棫偰傞恖娫偵傠偔側搝偼偄側偄丅偄傑傑偨埨晹偺巜帵偱廤抍揑帺塹尃偵娭偡傞桳幆幰夛媍偲偄偆傕偺偑巒傑偭偨丅埨晹偼媍榑偡傞偺偑側偤偄偗側偄偺偐偲尵偭偰偄傞偑丄嶲壛偡傞乽桳幆幰乿偨偪偑傒偛偲偵埨晹偺堄傪懱偟偨攜偨偪偱偁傞偙偲偐傜偟偰丄偙偺廤傑傝偑廤抍揑帺塹尃偺峴巊傪悇恑偡傞偨傔偺傕偺側偺偼巕嫙偱傕暘偐傞丅偦偺愭偵偔傞偺偼愴憟傊偺嶲壛偩丅偦傫側偵垽崙怱偑戝愗側傜丄偦傫側偵愴憟偟偨偄偺側傜丄帺暘偑愴応偵峴偗両 愴憟偟偨偄搝偼丄帺暘偑揝朇傪帩偭偰暫戉偨偪偺愭摢偱愴応偵棫偰両
悽偺拞偼宨婥偑椙偔側偭偰偄傞偲偄偆偺偵丄婇嬈偑忋偘偨棙塿偼廬嬈堳偵偼娨尦偝傟偢丄姅庡偲宱塩恮偵傑傢偭偰偟傑偆偨傔丄堦斒弾柉偼偦偺壎宐偵偁偢偐傟側偄丅偙傟偐傜擭婑傝偑懡偔側傞偲偄偆偺偵丄巟媼偝傟傞擭嬥偼愭嵶傝偵側傞偄偭傐偆偩丅偙偺偆偊孯戉偑岞擣偝傟傞偲丄巟弌偝傟傞孯帠旓偼巭傑傞偲偙傠傪抦傜偢朿傟忋偑傞偩傠偆丅傾儊儕僇偲堦晹偺婇嬈僩僢僾偲惌帯壠偩偗偑旍偊懢傝丄偟傢婑偣偼崙柉偵夞偭偰偔傞偲偄偆峔恾偼傑偡傑偡彆挿偝傟傞丅擭嬥朄埬丄岞柋堳揤壓傝婯惂朄埬偺傛偆側僓儖朄偽偐傝嶌傝丄帺暘偺棙尃偵偽偐傝媯乆偲偟偰偄傞帺柉搣媍堳丄戝暔媍堳偺崢嬓拝偵側傝尃椡傪傂偗傜偐偡偩偗偺帺柉搣媍堳偑偄偐偵懡偄偐偼偁偒傟傞偽偐傝偩乗乗傕偪傠傫慡堳偑偦偆偩偲偄偆傢偗偱偼側偔丄恀寱偵悽偺拞傪椙偔偟傛偆偲搘椡偟偰偄傞恖傕偄傞偑丅壂撽偺暷孯旘峴応堏揮偵傛傞娐嫬攋夡傕寽擮偝傟傞丅
側偺偵側偤丄偙傫側埨晹傪巟帩偟丄偙傫側帺柉搣偵搳昜偡傞崙柉偑偄傞偺偩傠偆丅愭擔偺搒抦帠慖傕偦偆偩丅愇尨偺傛偆側丄奜崙恖傗彈惈傪曁帇偟丄懁嬤惌帯傪晘偒丄偄偮傕埿挘傝嶶傜偡恖娫偵丄偳偆偟偰傒傫側搳昜偡傞偺偩傠偆丅乽崙柉偼丄帺暘偺幆尒偺掱搙偵崌偭偨惌晎傪庼偐傞乿偲扤偐偑尵偭偰偄偨偑丄嵟屻偵媰偄偰傕丄偦傟偼偦傫側惌晎傪慖傫偩帺暘偨偪偺偣偄側偺偩丅偱傕丄偦傫側偙偲傪尵偭偰丄偆偦傇偄偰偄傞傢偗偵偼偄偐側偄丅偙傫偳偺嶲堾慖偼丄愨懳偵帺柉搣傪慾巭偟丄傕偆傂偲偮棅傝側偄偗偳丄側傫偲偐柉庡搣偵惌尃傪庢傜偣側偗傟偽側傜側偄丅偦偆偱側偗傟偽丄傏偔偨偪偺巕嫙傗懛偑丄偲傫偱傕側偄偙偲偵側偭偰偟傑偆丅
2007.05.15 (壩) 崟郪柧偺嬻敀偺5擭娫
嶐擭弌斉偝傟偰榖戣偵側偭偨彂愋乽崟郪柧vs僴儕僂僢僪乿乮揷憪愳峅丒挊丄暥錣弔廐幮丒姧乯傪撉傫偩丅塡偵堘傢偸椡嶌偱偁傞丅偙傟偼丄擔杮偺恀庫榩峌寕傪戣嵽偵偟偨僴儕僂僢僪塮夋乽僩儔丒僩儔丒僩儔両乿偺娔撀傪埶棅偝傟偨崟郪柧偑丄1968擭12寧丄嶣塭偑奐巒偝傟偰3廡娫屻偵撍慠娔撀傪夝擟偝傟偨帠審偺恀憡傪捛偭偨僪僉儏儊儞僩偩丅挊幰偼丄擔杮懁丄僴儕僂僢僪懁丄憃曽傪暆峀偔庢嵽偟丄帒椏傪孈傝婲偙偟偰丄惢嶌偵偄偨傞宱夁丄宊栺撪梕偺徻嵶丄崟郪偺彂偄偨媟杮傗奊僐儞僥偺専徹丄嶣塭拞偺偝傑偞傑側僩儔僽儖側偳傪丄僯儏乕丒僕儍乕僫儕僘儉偺庤朄傕庢傝擖傟偰昤偄偰偄傞丅偲偔偵嫽枴傪堷偐傟傞偺偼丄傾儊儕僇偺塮夋寍弍壢妛傾僇僨儈乕傗UCLA偺恾彂娰偵曐娗偝傟偰偄偨塮夋夛幮乮20悽婭僼僅僢僋僗乯偺帒椏傪敪孈偟偨傝丄惢嶌愑擟幰偩偭偨僄儖儌丒僂傿儕傾儉僗偵庢嵽偟偨傝偟偨惉壥偑惙傝崬傑傟偰偄傞揰偩丅摉帪偙偺塮夋偺擔杮岅媟杮偺塸岅傊偺東栿傪偟偨偲偄偆挊幰偺屄恖揑側巚偄擖傟偺偨傔偱傕偁傠偆偑丄暥復偼僷僙僥傿僢僋偱敆椡偑偁傝丄偖偄偖偄堷偒偢傝崬傑傟傞丅偙偺帠審偺攚宨偵偼丄崟郪偺塮夋偺嶣傝曽傪抦傜偢偵娔撀傪埶棅偟偰偟傑偭偨20悽婭僼僅僢僋僗偲丄僴儕僂僢僪棳偺巇帠偺恑傔曽傪抦傜偢偵娔撀傪堷偒庴偗偰偟傑偭偨崟郪偲偄偆峔恾偑偁傞丅偦傟偑偙偺斶寑傪彽偄偰偟傑偭偨丅偙偺杮偵傛偭偰娔撀夝擟偵傑偮傢傞撲偼偄偪偍偆夝柧偝傟偰偄傞偑丄偦傟偱傕側偍晄柧側晹暘偼巆傞丅戞堦偵丄崟郪偼僴儕僂僢僪丒僗僞僀儖偺塮夋偺嶌傝曽傪抦傜側偐偭偨偲偄偆偙偲偩偑丄塮夋嬈奅偵恎傪抲偔恖娫偑丄傾儊儕僇偺塮夋惂嶌偺庤朄傪抦傜側偄偲偄偆偙偲偑偁傝偊傞偩傠偆偐丄壖偵抦傜側偐偭偨偲偟偰傕丄娔撀傪堷偒庴偗傞埲忋丄側偤忣曬傪摼傛偆偲偄偆婥偵側傜側偐偭偨偺偩傠偆偐丅帺暘棳偺傗傝曽偱墴偟捠偣傞偲巚偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅偩偲偡傟偽丄峫偊曽偑娒偡偓偨偲偄傢偞傞傪摼側偄丅戞擇偵丄嶣塭傪奐巒偟偰偡偖偵崟郪偼堎條側尵摦偑栚棫偪巒傔丄恄宱悐庛徢偲恌抐偝傟偨丅偙傟偼壥偨偟偰昦婥側偺偩傠偆偐丅偦傟傑偱搶曮偺嶣塭強偱嶣偭偰偄偨崟郪偼丄偙偺塮夋偱弶傔偰搶塮偺嫗搒嶣塭強傪巊偭偨丅嶣塭強偱崟郪偺朶孨傇傝偵姷傟偰偄傞搶曮嶣塭強偩偭偨傜丄僗僞僢僼偑棧斀偟僗僩偵擖傞偙偲傕側偐偭偨偟丄傂偄偰偼崟郪偑僲僀儘乕僛偵側傞偙偲傕側偐偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅戞嶰偵崟郪僾儘僟僋僔儑儞偱傾儊儕僇懁偲偺娫偵棫偭偰宊栺傪庢傝巇愗偭偨惵桍揘榊偲偄偆僾儘僨儏乕僒乕偺栶妱偑傛偔暘偐傜側偄丅崟郪偑娔撀傪夝擟偝傟偨偁偲丄崟郪偵宊栺彂偺拞恎傪抦傜偣側偐偭偨偲偄偆偙偲偱愑擟傪捛媦偝傟偨惵桍偼崟郪僾儘傪帿傔偨丅偩偑傎傫偲偆偵崟郪偺尵偆偲偍傝側偺偐丅廃埻偺娭學幰偨偪傕崟郪偺愢柧傪巟帩偟偰偄傞傛偆偩偑丄偳偆傕擔杮偺屩傝偱偁傞崟郪傪彎偮偗傑偄偲偡傞攝椂偑姶偠傜傟傞丅偙偺偁偨傝偺恀憡偼錗偺拞偩丅偙偺帠審偺偄偪偽傫偺尨場偼丄僴儕僂僢僪偲慻傫偱塮夋傪嶣傞傗傝曽偵娭偟偰丄崟郪偵彆尵偟丄堄尒傪尵偆恖偑廃埻偵扤傕偄側偐偭偨偙偲偵偁傞偲巚偆丅偦傟偵偟偰傕丄偙偺杮偱徯夘偝傟偰偄傞崟郪偺峔憐傗媟杮傪撉傓偲丄乽僩儔丒僩儔丒僩儔両乿傪崟郪偑嶣偭偰偄傟偽丄偝偧慺惏傜偟偄塮夋偵巇忋偑偭偰偄偨偩傠偆偲巚傢傟偰側傜側偄丅
偙偺帠審埲崀偺崟郪偺塮夋偼丄惓捈偵尵偭偰偮傑傜側偔側偭偨丅傕偲傕偲崟郪偺塮夋偺崻姴傪側偟偰偄偨偺偼僸儏乕儅僯僘儉偱偁傝丄愴屻柉庡庡媊偺峬掕偩偭偨丅乽傢偑惵弔偵夨側偟乿傗乽悓偄偳傟揤巊乿乽栰椙將乿乽惗偒傞乿偲偄偭偨徍榓20擭戙偺嶌昳偵偼丄僸儏乕亅儅僯僘儉偵崻偞偟偨庛幰傊偺傗偝偟偄傑側偞偟偑偁偭偨丅偦偟偰恖娫偲偄偆慞偲埆偑摨嫃偡傞懚嵼傊偺塻偄摯嶡偑偁偭偨丅偲偙傠偑偄偭偙偆偵柉庡庡媊偑崻晅偐偢丄庛幰偼埶慠偲偟偰庛幰偺傑傑偱偁傞擔杮幮夛傊偺偄傜偩偪偑丄乽埆偄搝傎偳傛偔柊傞乿傗乽揤崙偲抧崠乿偱崟郪偺塮夋偵塭傪棊偲偟巒傔傞丅偙偺孹岦偼1965擭偺乽愒傂偘乿偱堦抜偲尠挊偵側偭偨丅乽愒傂偘乿偵偍偗傞恖娫偺昤偒曽偼恾幃揑偱怺傒偑側偔丄庛幰偼偁偔傑偱慞恖丄嫮幰偼偁偔傑偱埆恖偱偁傝丄愒傂偘偑傑傞偱恄偺傛偆偵丄慞恖傪彆偗丄埆恖傪偨傔傜偄傕側偔傗偭偮偗傞丅偦偙偵偼丄掙曈偐傜暒偒婲偙傞僄僱儖僊乕偵傛偭偰幮夛偑椙偄曽岦偵摦偔偙偲偵愨朷偟丄慞偒撈嵸幰偺彆偗傪懸朷偡傞巚偄偑燌傒弌偰偄偨丅偩偑丄塮夋偵崬傔傜傟偨崟郪偺儊僢僙乕僕偼偲傕偐偔丄偦傟傑偱偺崟郪塮夋偼丄偡傋偰偓傜偓傜偟偨婥敆偑枮偪偁傆傟丄嬞敆姶偑傒側偓傝丄娤媞偺怱偵慽偊偐偗傞埑搢揑側椡傪旛偊偰偄偨丅偦傟偐傜5擭屻偺1970擭丄乽朶憱婡娭幵乿偺婇夋偺嵙愜傗乽僩儔丒僩儔丒僩儔両乿偺娔撀崀斅偲偄偭偨恻梋嬋愜傪宱偰丄傗偭偲岞奐偝傟偨崟郪塮夋乽偳偱偡偐偱傫乿偼丄娤媞傪偑偭偐傝偝偣丄嫽峴揑幐攕偵廔傢偭偨丅幮夛偺掙曈偱昻偟偔傕柧傞偔惗偒傞恖乆傪昤偄偨偙偺塮夋偵偼丄夋柺偐傜岅傝偐偗傞傕偺偑側偐偭偨丅偦偺屻娫傕側偔崟郪偼帺嶦枹悑帠審傪婲偙偡丅埲屻偺崟郪偺塮夋偼丄乽愒傂偘乿傑偱偺僞僢僠偲偼堦曄偟丄溸偒傕偺偑棊偪偨偐偺傛偆偵幮夛惈偑婓敄偵側傝丄擬婥偲椡嫮偝偑徚偊偆偣偰偟傑偭偨丅傑傞偱恖娫偺惗偒傞巔傪偼傞偐揤忋偐傜尒壓傠偟偰偄傞偐偺傛偆側嬻嫊偝偑昚偆嶌昳偽偐傝偵側偭偨丅傕偟乽僩儔丒僩儔丒僩儔両乿傪崟郪偑娔撀偟偰偄偨側傜丄傕偟偐偟偨傜偦偺屻傕埲慜偺嶌晽傪帩懕偝偣偰偄偨偐傕偟傟側偄丅偩偐傜丄側偍偄偭偦偆乽僩儔丒僩儔丒僩儔両乿偺娔撀崀斅偑惿偟傑傟傞偺偱偁傞丅
2007.01.08 (寧) 僨傿僢僋丒僼儔儞僔僗6擭傇傝偺怴嶌偵攺庤
僨傿僢僋丒僼儔儞僔僗偺6擭傇傝偺怴嶌儈僗僥儕乕彫愢乽嵞婲乿偑2006擭枛偵敪攧偝傟偨乮憗愳彂朳乯丅僼儔儞僔僗偼2000擭偵嵢傪朣偔偟偰埲棃丄昅傪愨偭偰偄偨丅堦帪丄屻擭偺斵偺彫愢偼嵢偑戙昅偟偰偄偨偲偄偆塡偑棳傟偨偑丄偦偺恀婾偼偲傕偐偔丄80嵨傪夁偓偨斵偼丄傕偆怴嶌傪彂偔偙偲偼側偄偩傠偆偲巚傢傟偰偄偨偩偗偵丄崱夞偺撍慠偺怴嶌敪昞偼婐偟偄嬃偒偩偭偨丅1962擭偺戞1嶌乽杮柦乿埲棃丄儕傾儖丒僞僀儉偱斵偺嫞攏儈僗僥儕乕傪寚偐偝偢撉傒懕偗偰偒偨傏偔偵偲偭偰丄撪梕偼偲傕偐偔丄僼儔儞僔僗偺怴嶌偑撉傔傞偲偄偆偙偲偩偗偱岾偣側婥暘偵側傞丅偝偰偦偺怴嶌偩偑丄庡恖岞偼偙傟偑4夞栚偺搊応偵側傞惽榬偺尦婻庤僔僢僪丒僴儗乕丅撉屻偺姶憐偼丄梊憐偳偍傝丄慡惙婜偺昅抳傗僾儘僢僩偵斾傋傞傋偔傕側偄丄偛偔暯杴側弌棃偲偄偆偺偑惓捈側偲偙傠偩丅戞堦偵丄埆偲愴偆庡恖岞偺巔偑偟偭偐傝昤偐傟偰偄側偄偟丄偦偺懠偺搊応恖暔偺僉儍儔僋儔乕傕晜偒忋偑偭偰偙側偄丅偦偺偆偊丄斊恖偑彫棻偱尐摟偐偟傪怘傜偆偟丄杮暔偺埆恖偼栰曻偟偺傑傑偱僇僞儖僔僗傪枴傢偊側偄丅偲偄偆嬶崌偱丄嶌昳偲偟偰偺儗儀儖偼掅偄偑丄偦傟偱傕僼儔儞僔僗偺怴嶌傪撉傓婌傃偼戝偒偄丅偦傕偦傕撪梕傊偺晄枮偼偙偺嶌昳偵尷偭偨偙偲偱偼側偄丅偡偱偵80擭戙拞婜埲崀偐傜丄昅椡偺悐偊偑姶偠傜傟偨丅偦傟偱傕丄嬛梸揑側庡恖岞偑嬯嫬偺側偐偱帺暘偺庛偝傪崕暈偟側偑傜晄惓偵姼慠偲棫偪岦偐偆偲偄偆婎杮揑側彫愢嶌朄偼娧偐傟偰偍傝丄撈帺偺枺椡傪曻偭偰偄偨丅偦偆偄偭偨僗僞僀儖偼偙偺怴嶌偱傕曄傢偭偰偍傜偢丄偦偙偐偟偙偵丄僼儔儞僔僗側傜偱偼偺偄傇偟嬧偺傛偆側枴傢偄偑姶偠傜傟偨丅僀儞僞乕僱僢僩偵傛傞僊儍儞僽儖偺幚懱傪昤偄偨傝偡傞側偳丄86嵨偵側傞嶌壠偑彂偄偨偲偼巚偊側偄傎偳怴偟偄幮夛忬嫷傪庢傝擖傟偰偄傞偺傕嫽枴怺偐偭偨丅嶌昳偲偟偰偺弌棃偑偳偆偱偁傟丄堷戅偐傜僇儉僶僢僋偟丄怴嶌傪彂偄偰偔傟偨僼儔儞僔僗偺堄梸偵扙朮偡傞丅
東栿偵偮偄偰堦尵丅偙傟傑偱偺僼儔儞僔僗偺彫愢偼偡傋偰媏抮岝偑栿偟偰偒偨偑丄2006擭偵媏抮偑朣偔側傝丄偙偺怴嶌乽嵞婲乿偼媏抮偺掜巕偩偲偄偆杒栰庻旤巬偑栿偟偰偄傞丅媏抮岝偺栿偼丄嵟弶偺偆偪偼柤挷巕偩偲巚傢偣偨偑丄拞婜埲崀丄偁傑傝偵暥懱偑椶宆壔偟偰偟傑偄丄偄偝偝偐鐒堈偟偰偄偨丅偳傟傕偙傟傕摨偠傛偆側昤幨丄摨偠傛偆側夛榖側偺偩丅側偵偟傠丄僼儔儞僔僗摨條傎傏慡嶌昳傪栿偟偰偄傞儘僶乕僩丒僷乕僇乕偺彫愢偲暥懱偑摨偠偱尒暘偗偑偮偐側偄偐傜崲偭偰偟傑偆丅崱夞偺杒栰栿偼丄傗傗屌偝偼偁傞傕偺偺丄媏抮偺僗僞僀儖傪巆偟側偑傜丄傛傝尨暥偵懄偟偰栿偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟丄岲姶傪妎偊偨丅
2006.12.17 (擔) 儈僗僥儕乕丒儔儞僉儞僌偺岲傑偟偐傜偸晽挭偵妳両
擭枛峆椺偺儈僗僥儕乕彫愢儀僗僩丒儔儞僉儞僌傪敪昞偡傞乽偙偺儈僗僥儕乕偑偡偛偄乿乮曮搰幮乯偑崱擭傕敪攧偝傟偨丅偄傠傫側岲傒傪帩偭偨恖偨偪偑慖傫偩傕偺傪廤寁偡傞傢偗偩偐傜丄偨偐偑偍梀傃偵偡偓偢丄栚偔偠傜棫偰偰恀寱偵偁偘偮傜偆偺偼巕嫙偠傒偰偄傞偲抦傝偮偮傕丄偮偄偙偺偲偙傠偺廤寁寢壥偺偮傑傜側偝傪榑偠偨偔側傞丅嵟弶偺偙傠偼偦偆偱偼側偐偭偨丅1987擭枛偺戞1夞敪攧偺偲偒偼丄奀奜偺1埵偵僩儗償僃僯傾儞偺乽柌壥偮傞奨乿丄崙撪偺1埵偵慏屗梌堦偺乽揱愢側偒抧乿偲偄偆僴乕僪儃僀儖僪丄朻尟彫愢偺廏嶌偑慖偽傟偰偍傝丄偦偺屻傕偍偍傓偹摨孹岦偺嶌昳偑岲寢壥傪摼偰偄偨丅偩偑2000擭偁偨傝偐傜丄杮奿傕偺傗僋儔僀儉丒僲償僃儖偱暥妛巙岦偺嫮偄嶌昳偑暲傇傛偆偵側偭偨丅儈僗僥儕乕偼撲偲僗儕儖偲庡懱偵偟偨僄儞僞僥僀儞儊儞僩偱偁傝丄僉儍儔僋僞乕憿宍偼偲偆偤傫廳梫偩偑丄弮暥妛揑側梫慺偑偁傑傝偵擹偔側傞偲儈僗僥儕乕偲偟偰偺杮棃偺偐偨偪偑幐傢傟偰偟傑偆丅傕偲傕偲乽偙偺儈僗乿偼丄榁曑偺儈僗僥儕乕丒儔儞僉儞僌偱偁傞廡娫暥弔偺儈僗僥儕乕丒儀僗僩10傊偺傾儞僠丒僥乕僛偲偟偰弌敪偟偨偺偩偑丄偄傑偱偼偙偺2幰偺儔儞僉儞僌偼傎偲傫偳曄傢傝側偄撪梕偵側偭偰偟傑偭偰偄傞丅偁傑傝娭怱偺側偄崙撪彫愢偼偲傕偐偔丄奀奜嶌昳偺崱擭偺廤寁寢壥傪尒傞偲丄梊憐偼偟偰偄偨偑儘乕儕乕丒儕儞丒僪儔儌儞僪偑1埵偱偁傝丄傎偐偵僇僘僆丒僀僔僌儘傗僩儅僗丒H丒僋僢僋側偳丄憡曄傢傜偢儈僗僥儕乕怓偺敄偄嶌昳偑暲傫偱偄傞丅僽儗僀僋偺乽峳傇傞寣乿傗僐僫儕乕偺乽揤巊偲嵾偺奨乿偑擖偭偰偄傞偺偼偄偄偲偟偰丄儖僢僇偺乽堩扙幰乿偼儔儞僋奜偩偟丄僴儞僪儔乕偺乽僽儖乕丒僽儔僢僪乿偵帄偭偰偼尵媦偡傜偝傟偰偄側偄丅抁曇廤偑懡偄偺傕嵟嬤偺摿挜偱偁傝丄嶐擭偼僕儍僢僋丒儕僢僠乕偺乽僋儔僀儉丒儅僔儞乿偑1埵偵側偭偰偄偨偑丄崱擭傕僩僢僾10撪偵3嶌偺抁曇廤偑擖偭偰偄傞丅偦傕偦傕儈僗僥儕乕偺儔儞僉儞僌偱抁曇廤偑挿曇傪偍偝偊偰忋埵偵偔傞偲偄偆偺偑偍偐偟側榖偱丄偁傞暔帠偺堦抐柺傪愗傝庢偭偨抁曇偲丄帪娫偺棳傟傪惙傝崬傫偱慡懱傪偠偭偔傝暔岅傞挿曇偲偱偼丄撉屻偺姶摦偺幙偑堘偆偟丄挿曇偺傎偆偑偼傞偐偵戝偒側僀儞僷僋僩傪傕偨傜偡偼偢偩丅偡偖傟偨挿曇偑偁傞偵傕偐偐傢傜偢偙傫側帠懺偑婲傞偺偼丄儕僗僩傾僢僾偝傟偨挿曇偼慖幰偵傛偭偰僶儔偮偒偑偁傞偺偵斾傋偰丄抁曇廤偼傑傫傋傫側偔昜傪廤傔傞偐傜偱偁傠偆偑丄偙傫側偲偙傠偵傕儔儞僉儞僌廤寁偺偄偄壛尭偝偑昞傟偰偄傞丅
偙偆偄偭偨孹岦偺攚宨偵偼慖幰偺幙偺栤戣偑偁傞偲巚偆丅暥妛巙岦偺彫愢傪傕偰偼傗偡慖幰偑憹偊丄儈僗僥儕乕杮棃偺撲偲僒僗儁儞僗傪庡懱偲偡傞彫愢傪岲傓慖幰偑尭偭偨偺偩丅傑偨乬撉彂偺僾儘乭偲偄偆偆偨偄暥嬪偲偼棤暊偵丄偁傑傝儈僗僥儕乕傪撉傫偱偄側偄慖幰傕偐側傝偄傞傛偆偵巚偆丅70悢恖偄傞儊儞僶乕偺側偐偵偼丄傏偔偑屄恖揑偵抦偭偰偄傞恖傕2乣3偄傞偑丄偳偆傒偰傕擔崰偁傑傝撉傫偱偄傞偲偼巚偊側偄恖偽偐傝偩丅傑偁丄暿偵儔儞僋偑偳偆偱偁傠偆偲丄儀僗僩僙儔乕杮偑寵偄側傏偔偲偟偰偼丄帺暘偑岲偒側杮傪撉傫偱偄傟偽偄偄偐傜娭學側偄偑丄偨偩偱偝偊奀奜儈僥儕乕偑攧傟側偄偲塢傢傟傞嶐崱偩偗偵丄偙傟偵傛偭偰儈僗僥儕乕偺撉幰偑墦偺偒丄弌斉揰悢偑傑偡傑偡尭傞偲偄偆偙偲偵傕寢傃偮偒偐偹側偄偺偱丄偦偆傕塢偭偰偄傜傟側偄丅傒側偝傫丄僴儔僴儔丒僪僉僪僉偡傞丄梊憐偑棤愗傜傟偰傃偭偔傝偡傞丄姶摦偱嫻偑擬偔側傞儈僗僥儕乕傪丄傕偭偲撉傒傑偟傚偆丅偲偄偆偲偙傠偱丄傏偔偺崱擭偺奀奜儈僗僥儕乕丒儀僗僩10偼壓婰偺偲偍傝偱偡丅
1丏乽峳傇傞寣乿僕僃僀儉僗丒僇儖儘僗丒僽儗僀僋乮暥弔暥屔乯
2丏乽揤巊偲嵾偺奨乿儅僀僋儖丒僐僫儕乕乮島択幮暥屔乯
3丏乽堩扙幰乿僌儗僢僌丒儖僢僇乮島択幮暥屔乯
4丏乽晽偺塭乿僇儖儘僗丒儖僀僗丒僒僼僅儞乮廤塸幮暥屔乯
5丏乽僽儖乕丒僽儔僢僪乿僨償傿僢僪丒僴儞僪儔乕乮島択幮暥屔乯
6丏乽暅廞昦搹乿儅僀働儖丒僷乕儅乕乮償傿儗僢僕丒僽僢僋僗乯
7丏乽僼傽僯乕丒儅僱乕乿僕僃僀儉僘丒僗僂僃僀儞乮暥弔暥屔乯
8丏乽岾塣偼扤偵丠乿僇乕儖丒僴僀傾僙儞乮晑孠幮儈僗僥儕乕乯
9丏乽傾儖傾儖搰偺戝帠審乿僋儕僗僩僼傽乕丒儉乕傾乮憂尦暥屔乯
10丏乽僫僀僩僼僅乕儖乿僱儖僜儞丒僨儈儖乮島択幮暥屔乯
2006.12.03 (擔) 嵟嬤偺償僅乕僇儖丒傾儖僶儉乗乗僌儔僨傿僗丒僫僀僩偲悈椦巎
僜僂儖丒儈儏乕僕僢僋偵偮偄偰偼昞柺傪挳偒偐偠偭偨偩偗側偺偱丄偁傟偙傟塢偆偺偼婥偑傂偗傞偺偩偑丄彈惈僜僂儖壧庤偺側偐偱傏偔偑偄偪偽傫岲偒側偺偼僌儔僨傿僗丒僫僀僩偩丅僌儔僨傿僗丒僫僀僩仌僓丒僺僢僾僗偲偟偰儌乕僞僂儞偵悂偒崬傫偩乹偝傛側傜偼斶偟偄尵梩乺乮Neither One of Us [Wants to Say Goodbye]丂乯偼椳側偔偟偰偼挳偗側偄愨彞偩偟丄傎偐偵傕僽僢僟帪戙偺乹傔偖傝埀偄乺乮Best Things Ever Happened to Me乯側偳丄僶儔乕僪偺柤嬋傪悢懡偔惗傒弌偟偰偄傞丅梋択偩偑丄乹偝傛側傜偼斶偟偄尵梩乺偼丄儌乕僞僂儞偺僸僢僩嬋偺朚戣偲偟偰偼1乣2傪憟偆柤栿偩偲巚偆乮偪側傒偵嵟崅偺捒栿偼僥儞僾僥乕僔儑儞僘偺乹旤恖偼偙傢偄乺[Beauty Is Only Skin Deep]乯丅偦偺僌儔僨傿僗丒僫僀僩偑僗僞儞僟乕僪丒僜儞僌傪壧偭偨怴嶌傾儖僶儉乽價僼僅傾丒儈乕乿偑敪攧偝傟偨乮儐僯僶乕僒儖乯丅壧偭偰偄傞偺偼丄僄儕儞僩儞偺乹巹偑塢偆傑偱壗傕偟側偄偱乺丄僈乕僔儏僂傿儞偺乹傗偝偟偒敽椀傪乺偲偄偭偨丄價儕乕丒儂儕僨僀丄僄儔丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪側偳執戝側僕儍僘壧庤偨偪偺垽彞偟偨嬋偽偐傝丄慡晹偱13嬋丅偙偺偲偙傠僕儍僘埲奜偺僕儍儞儖偺儀僥儔儞壧庤偑僗僞儞僟乕僪丒僜儞僌傪壧偭偨傾儖僶儉偑偄傠偄傠敪攧偝傟偰偄傞偑丄偙傟傕偦偺堦枃偲塢偊傞丅偩偑丄偝偡偑偵壧偺岻偝偵偐偗偰偼揤壓堦昳偺僌儔僨傿僗偩偗偵丄偦傟傜偲偼堦慄傪夋偡傞丄挳偒墳偊偺偁傞墱偺怺偄撪梕偵巇忋偑偭偰偄傞丅斵彈偼僆乕僶乕側昞尰傪旔偗丄壧帉傪戝愗偵偟側偑傜丄梷惂傪岠偐偣偨壧彞傪偟偰偄傞丅壧偺岻偄恖偼巚偄偺傑傑偵姶忣傪業弌偟偰壧偆偙偲偑偱偒傞偑丄偦偙傪姼偊偰梷偊丄僐儞僩儘乕儖偟偰壧偆偙偲偵傛偭偰丄偐偊偭偰挳偒庤偵怺偄姶摦傪梌偊傞丅偙偙偱偺僌儔僨傿僗偺棊偪拝偒偺偁傞婥昳偵枮偪偨壧彞偼偦偺嵟椙偺椺偩丅嶐崱偺僕儍僘丒償僅乕僇儖偺怴榐壒傾儖僶儉偵暔懌傝側偝傪姶偠偰偄偨傏偔偼丄偙偺傾儖僶儉偵傛偭偰媣偟傇傝偵妷傪桙偡偙偲偑偱偒偨丅悈椦巎乮傒偢偼傗偟 傆傒乯偲偄偆彈惈壧庤偵嫽枴傪帩偭偨偺偼丄3擭慜偵敪攧偝傟偨僊僞儕僗僩丄僉儓僔彫椦偺乽僕儍儞僑丒僗僀儞僌乿偲偄偆傾儖僶儉偵傛偭偰偩偭偨丅僉儓僔彫椦偺僕儍儞僑丒儔僀儞僴儖僩偺棳傟傪媯傓彫悎側僗僀儞僌墘憈傕妝偟偐偭偨偑丄帹傪扗傢傟偨偺偼僎僗僩壧庤偲偟偰3嬋偩偗嫟墘偟偨悈椦巎偺壧偩偭偨丅斵彈偺壧彞偼丄偗偭偟偰惡検偼側偄偟丄僕儍僘揑側忔傝傕姶偠傜傟側偄丅偩偑偦偺帺慠側惡傪惗偐偟偨婥庢傝偺側偄彞朄丄岻偔壧偍偆側偳偲偄偆彫偞偐偟偝偑傑偭偨偔側偄壧偄傇傝偼丄嫻偵嬁偔傕偺偑偁偭偨丅僞僀僾偼堘偆偑丄弶婜偺傾僗僩儔僢僪丒僕儖儀儖僩偺傛偆側偲塢偭偨傜丄暘偐偭偰偄偨偩偗傞偩傠偆偐丅挳偔偵懴偊側偄擔杮恖彈惈僕儍僘壧庤偑懕乆偲検嶻偝傟偰偄傞側偐偵偁偭偰丄擔杮恖偲偟偰偺惡偲敪壒傪慺捈偵昞尰偟偨悈椦偺壧偼堦暈偺惔椓嵻偺傛偆偩偭偨丅斵彈偑壧偭偨偺偼丄50擭戙弶傔偺僪儕僗丒僨僀偺億僢僾丒僸僢僩嬋偱旤嬻傂偽傝傕壧偭偰偄偨乹忋奀乺丄暈晹椙堦嶌嬋偺愴屻娫傕側偄偙傠偵棳峴偭偨壧梬嬋乹嫻偺怳傝巕乺丄60擭戙弶婜偵僸僢僩偟偨僴儚僀傾儞丒僜儞僌乹僠儑僢僩儅僢僥僋僟僒僀乺偺3嬋丅偙傟傜偺嬋偐傜憐憸偝傟傞擛偔丄偦偙偵偼僲僗僞儖僕僢僋側儉乕僪偑昚偭偰偄傞偑丄柇側墴偟晅偗偑傑偟偝偼側偐偭偨丅偦偺悈椦巎偑丄崟慏儗僨傿偲嬧惎妝抍偲偄偆僌儖乕僾傪慻傫偱乽屆杮壆偺儚儖僣乿偲偄偆傾儖僶儉傪弌偟偨乮攇偵寧儗僐乕僪亖e-music/僟僀僉僒僂儞僪傛傝敪攧乯丅偙傟偼J億僢僾巇棫偰偺撪梕偵側偭偰偍傝丄僉儓僔彫椦偺傾儖僶儉偲偼庯偑堎側傞偑丄寉偄僗僀儞僌姶妎丄棊偪拝偄偨暤埻婥丄偦偙偼偐偲側偄僲僗僞儖僕僢僋側婥暘偼摨偠偩丅偦偟偰悈椦偺婏傪偰傜傢側偄慺捈偱怢傃偺偁傞壧偼丄偙偙偱傕敳孮偺怱抧傛偝傪曻偭偰偍傝丄巚傢偢挳偒崨傟偰偟傑偆丅偙偺傾儖僶儉偼斵彈偑壧帉傪彂偄偨僆儕僕僫儖嬋偑拞怱偩偑丄1嬋偩偗乹忋奀乺偺嵞悂偒崬傒偑廂榐偝傟偰偄傞丅僞僀僩儖丒僜儞僌偺乹屆杮壆偺儚儖僣乺偼恄揷偺屆杮壆奨偺僥乕儅丒僜儞僌偵側偭偰偄傞傜偟偄丅
儀僥儔儞偺戝壧庤僌儔僨傿僗丒僫僀僩偲柍柤偵嬤偄怴恖偱偁傞悈椦巎傪丄摨楍偵岅傞偙偲偼偱偒側偄偑丄偙偺傆偨傝偵偼嫟捠偡傞傕偺偑偁傞丅帺暘偺壧彞丄僗僞僀儖傪傛偔抦偭偰偍傝丄偦傟傪帺慠側偐偨偪偱壧偵庢傝崬傫偱偄傞揰偩丅偦傟偼丄偨偲偊偽丄戝偘偝側昞忣偱傢偞偲傜偟偔僺傾僲偺抏偒岅傝傪偡傞戝嶃曎偺彈惈壧庤偲偼懳嬌偵偁傞壧偄曽偩丅
2006.11.12 (擔) 摗戲廃暯偺塮夋壔嶌昳傪傔偖偭偰
嶳揷梞師偺娔撀偟偨摗戲廃暯尨嶌偺塮夋乽晲巑偺堦暘乿偑娫傕側偔岞奐偝傟傞丅偄偭偨偄偳傫側塮夋偵側偭偰偄傞偺偩傠偆丅嶳揷梞師偼4擭慜偵摨偠偔摗戲廃暯嶌昳偱偁傞乽偨偦偑傟惔暫塹乿傪塮夋壔偟偰偄傞丅偙傟偼寙嶌偩偭偨丅峕屗帪戙枛婜偺壓媺晲巑偺惗妶丄昻偟偄側偑傜傕徉帩傪幐傢側偄庡恖岞偺巔偑偟偭偐傝昤偐傟偰偄偨偟丄彫愢傪撉傫偱僀儊乕僕偡傞奀嶁斔偺悽奅偑傎傏偦偺傑傑塮憸壔偝傟偰偄偨丅嶣傝曽偵偼墴偟晅偗偑傑偟偄偲偙偲偑側偔丄棊偪拝偒偺偁傞昳奿偑姶偠傜傟偨丅嵟屻偺寛摤僔乕儞傕嬞敆姶偵枮偪偰偄偨丅恀揷峀擵偼偠傔弌墘攐桪偼傒側岲墘偟偰偍傝丄偲偔偵媨戲傝偊偑愨昳偩偭偨丅偗傟傫偺側偄丄梷惂偝傟偨帺慠側墘媄偑慺惏傜偟偐偭偨丅媨戲傝偊偼偄偮偐傜偙傫側慺惏傜偟偄彈桪偵側偭偨偺偩傠偆丅偨偩傂偲偮偩偗媈栤偑偁傞丅惉挿偟偨惔暫塹偺柡偺柧帯帪戙偵側偭偰偐傜偺夞憐偲偄偆懱嵸傪偲偭偰偄傞偑丄偦傫側昁梫偑偁偭偨偺偩傠偆偐丅偙偆偄偭偨夞憐僗僞僀儖偼愄傕崱傕偝傑偞傑側塮夋偱傛偔傒傜傟傞庤朄偩偑丄偙偺塮夋偺応崌偼丄偁傑傝堄枴偺側偄丄梋寁側傾僀僨傾偩偭偨傛偆偵巚偆丅乽偨偦偑傟惔暫塹乿偵斾傋偰丄嶐擭岞奐偝傟偨乽愪偟偖傟乿乮娔撀偼崟搚嶰抝乯偼杴嶌偩偭偨丅壗搙傕弌偰偔傞巐婫愜乆偺帺慠偺晽宨偼偨偟偐偵旤偟偄偑丄僗僩乕儕乕偵梈偗崬傫偱偄側偄偟丄偙傫側偵摨偠傛偆側晽宨偑壗搙傕塮偟弌偝傟傞偲丄傕偆偄偄傛偲尵偄偨偔側傞丅懁幒偵側偭偨梒側偠傒偺傆偔傪庡恖岞偨偪偑彆偗弌偡僔乕儞傕傑傞偱抰愘側枱夋偺傛偆偱丄晄帺慠偝偑偮偒傑偲偆丅嵟戝偺栤戣偼攐桪偺儈僗丒僉儍僗僩偩丅庡墘偺巗愳愼屲榊偼丄偄偐傫偣傫丄偳偆偵傕昞忣偵朢偟偔丄娤媞偼傑偭偨偔姶忣堏擖偑偱偒側偄丅栘懞壚擳偼巚偄偺傎偐岲墘偟偰偄傞偑丄偨偨偢傑偄偑帪戙寑偵偼岦偄偰偄側偄丅庡恖岞偺晝恊傪墘偢傞弿宍対偺偆傑偡偓傞墘媄偩偗偑晜偒忋偑偭偰偟傑偭偰偄傞丅偝偰乽晲巑偺堦暘乿偩偑丄庡墘偼栘懞戱嵠偩偲偄偆偑丄弌棃偼偳偆側偺偩傠偆丅嶳揷梞師偺偙偲偩偐傜丄偮傑傜側偄傕偺偵偼側偭偰偄側偄偼偢偩偑丒丒丒丅偙偺塮夋傪嶳揷梞師偑嶣偭偰偄傞偲偄偆偙偲傪僯儏乕僗偱抦偭偨偲偒丄摗戲廃暯偵偦傫側彫愢偑偁偭偨偐側偲巚偭偨丅偦偺屻丄楢嶌抁曇廤乽塀偟寱廐晽彺乿偺側偐偺堦曇乽栍栚寱娆曉偟乿偑尨嶌偱偁傞偙偲傪抦偭偨丅乽塀偟寱廐晽彺乿偼弌斉偝傟偨偲偒偵攦偭偰撉傫偩偑丄偳傫側撪梕偐朰傟偰偟傑偭偰偄偨偺偱丄偦偺杮傪堷偭挘傝弌偟偰嵞撉偟偨丅摗戲廃暯傜偟偄岲曇偱偼偁傞偑丄偦傟傎偳報徾怺偄嶌昳偱偼側偄丅側偤嶳揷梞師偼丄挿曇丄抁曇偲傕偵寙嶌偑懡偄廃暯嶌昳偺側偐偐傜丄偙偺抧枴側彫愢傪慖傫偩偺偩傠偆偐丅栍栚偺晲巑偑庡恖岞偱丄偨偟偐偵暔岅偲偟偰偺寢峔偼慻傒棫偰傗偡偄偟丄娤媞偵慽偊偐偗傞傕偺傪婜懸偼偱偒傞偩傠偆偗傟偳丒丒丒丅
2006.11.11 (搚) 僶儖僙儘僫傪悂偔晽偵偼塭偑偁偭偨偐
僇儖儘僗丒儖僀僗丒僒僼僅儞偲偄偆僗儁僀儞偺嶌壠偑彂偄偨乽晽偺塭乿偲偄偆彫愢乮廤塸幮暥屔乯偵偼丄杮岲偒偺幰傪偲傝偙偵偡傞枺椡偑偁傆傟偰偄傞丅偙傟偼惵弔彫愢偲楌巎儘儅儞偲儈僗僥儕偺梫慺傪妡偗崌傢偣偨傛偆側杮偩丅偲偒偼愴憟偑廔傢偭偰娫傕側偄1945擭丄応強偼僼儔儞僐偺孯帠撈嵸惌尃壓偵偁偭偨僗儁僀儞偺僶儖僙儘僫丅11嵨偺彮擭僟僯僄儖偼丄屆彂揦傪塩傓晝偵楢傟傜傟偰乽朰傟傜傟偨杮偺曟応乿偲偄偆嫄戝側彂暔曐娗巤愝偵峴偒丄僼儕傾儞丒僇儔僢僋僗偲偄偆撲偺嶌壠偺彂偄偨乽晽偺塭乿偲偄偆1嶜偺杮偲傔偖傝崌偆丅偙偺杮偵姶摦偟偰丄僇儔僢僋僗偲偄偆嶌壠偺偙偲傪挷傋巒傔偨僟僯僄儖偼丄扤偐偑僇儔僢僋僗偺彂偄偨偡傋偰偺杮傪偙偺悽偐傜枙嶦偟傛偆偲偟偰偄傞偙偲偵婥偯偔丅僟僯僄儖偺恎曈偵婏柇側偙偲偑婲傝巒傔傞偑丄斵偼撪偐傜偙傒忋偘傞梸媮偵嬱傜傟丄僇儔僢僋僗偺旈傔傜傟偨夁嫀傪捛媮偡傞丅偦偟偰僟僯僄儖偺彮擭偐傜惵擭傊偺惉挿偺夁掱偲僇儔僢僋僗偺悢婏側塣柦傪偨偳偭偨恖惗偲偑丄岎屳偵擇廳幨偟偺傛偆偵昤偐傟傞丅偙傟偼垽偺暔岅偩丅抝偲彈偺垽丄桭偩偪摨巑偺垽丄恊巕偺垽丅摨帪偵桬婥偲桭忣偺暔岅偱傕偁傞丅怱庝偐傟傞偺偼丄彂暔偵婑偣傞怺偄忣擬偑偦偙偐偟偙偵燌傒弌偰偄傞偙偲偩丅搊応恖暔偨偪偼惗偒惗偒偲昤偐傟偰偍傝丄偲偔偵丄偄偮傕婤慠偲偟偨巔惃傪娧偔丄帨垽偵枮偪偨僟僯僄儖偺晝恊傗丄僟僯僄儖偲怺偄桭忣偱寢偽傟傞彂揦偺廬嬈堳僼僃儖儈儞偼丄朰傟傜傟側偄報徾傪梌偊傞丅慡懱偺暤埻婥偼儘僶乕僩丒僑僟乕僪偺彫愢偵帡偰偄傞偑丄僑僟乕僪偺応崌偼斶偟傒偲嬯廰偵枮偪偰偄傞偺偵斾傋偰丄偙偪傜偼婓朷偲怱桪偟偝傪姶偠偝偣傞丅
乽晽偺塭乿偱昤偐傟傞僶儖僙儘僫偼丄偳偙偐堿烼偱柪媨偺傛偆側搒巗傪巚傢偣傞丅偙傟偼撪愴偺彎愓偑偄傑偩偵巆傝丄撈嵸惌尃壓偱旈枾寈嶡偑埫桇偟丄恖乆偑埨堩偵曢傜偣側偐偭偨帪戙傪昤偄偰偄傞偐傜偩傠偆丅傏偔偼巇帠傗娤岝偱丄偄偢傟傕抁婜娫偩偑3夞傎偳僶儖僙儘僫傪朘傟偰偄傞丅尰嵼偺僶儖僙儘僫偼岝偵枮偪偁傆傟偨慺惏傜偟偄奨偩丅恖乆偼恊愗偱怘帠傕偍偄偟偄丅偦偟偰奨拞偵旤弍偑偁傆傟偰偄傞丅僶儖僙儘僫偼僺僇僜傗僟儕傪惗傫偩奨偱偁傝丄僈僂僨傿偑抸偄偨奨側偺偩丅惞壠懓嫵夛傗僌僄儖岞墍偵峴偔傑偱傕側偔丄戝捠傝傪曕偔偲丄奨摂傗傾僷乕僩側偳丄偄偨傞偲偙傠偵丄偁偺嬋慄傪惗偐偟偨摿堎側僈僂僨傿偺嶌昳傪栚偵偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺彫愢傪撉傫偱丄昞柺傪側偧偭偨偩偗偱偼暘偐傜側偄僶儖僙儘僫偺塭偺晹暘傪抦傞偙偲偑偱偒偨丅傕偆堦搙僶儖僙儘僫傪朘傟偰丄乽朰傟傜傟偨杮偺曟応乿偑偁傞傾儖僐丒僨儖丒僥傾僩儘捠傝偵峴偭偰傒偨偔側偭偨丅
2006.11.10 (嬥) 僒儞僙僢僩77偺儘僕儍乕丒僗儈僗偼镈憉偲偟偰偄偨
傓偐偟乽僒儞僙僢僩77乿偲偄偆傾儊儕僇偺僥儗價斣慻偑偁偭偨丅擔杮偱曻憲偝傟偨偺偼徍榓30擭戙偺廔傢傝偛傠偩偭偨傠偆偐丅儘僒儞僕僃儖僗傪晳戜偵偟偨僔儕乕僘傕偺偺扵掋僪儔儅偩丅拞妛惗偩偭偨傏偔偼偙偺枅廡偙偺曻憲偑妝偟傒偩偭偨丅尨戣偼乽77 Sunset Strip乿偲偄偄丄僒儞僙僢僩戝捠傝偺價儖偵嫃傪峔偊傞巹棫扵掋帠柋強偺扵掋偨偪偑妶桇偡傞搒夛挷偺愻楙偝傟偨儈僗僥儕乕丒僪儔儅偩偭偨丅帠柋強偵偼傆偨傝偺扵掋偑偄偰丄愭攜奿偺僗僠儏傾乕僩丒儀僀儕乕偵偼僄僼儗儉丒僕儞僶儕僗僩丒僕儏僯傾丄憡朹偺僕僃僼丒僗儁儞僒乕偵偼儘僕儍乕丒僗儈僗偑暞偟偰偄偨乮偺偪偵傕偆傂偲傝扵掋偑憹偊偨偑乯丅枅夞搊応偡傞僋乕僉乕偲偄偆價儖偺挀幵學傪僄僪儚乕僪丒僶乕儞僘偑墘偠偰偍傝丄偄偮傕孂偱敮傪惍偊偰偄偨丅偙偺3恖偑儊僀儞丒僉儍儔僋僞乕偩偭偨偑丄傎偐偵傕丄儘僗僐乕偲偄偆僷僫儅朮偺傛偆側朮巕傪偐傇傝丄梩姫傪偔傢偊偨僲儈壆偺恊晝傒偨偄側抝偑弌偰偄偨偑丄偁傟偼壗幰偩偭偨偺偩傠偆丅庡墘偺3恖偺側偐偱偼偲偔偵僋乕僉乕偺恖婥偑崅傑傝丄嵟弶偼抂栶偩偭偨偑搑拞偐傜弌墘偡傞僔乕儞偑憹偊丄嵟屻偵偼僋乕僉乕偑庡墘偡傞僪儔儅傑偱嶌傜傟偨丅僴儎僇儚偺億働儈僗偱1嶜偩偗偩偑丄乽僒儞僙僢僩77乿偺彫愢偑東栿弌斉偝傟偨丅嶌幰偼僥儗價偺媟杮恮偺傂偲傝偩偭偨儘僀丒僴僊儞僘丅僗僠儏傾乕僩丒儀僀儕乕偑庡恖岞偩偭偨偲婰壇偟偰偄傞偑丄撉傫偩偼偢側偺偵拞恎偼傑偭偨偔妎偊偰偄側偄丅摉帪傢偨偟偨偪偼丄擔杮偲偼偁傑傝偵偐偗棧傟偨傾儊儕僇傊偺摬傟偩偗傪嫻偵丄偄偢傟偦偙偵峴偗傞偩傠偆偲偼柌偵傕巚傢偢丄偙偺乽僒儞僙僢僩77乿乽僒乕僼僒僀僪6乿乽摝朣幰乿側偳偺儈僗僥儕乕/僒僗儁儞僗丒僪儔儅丄乽偆偪偺儅儅偼悽奅堦乿側偳偺儂乕儉丒僪儔儅丄乽僽儘儞僐乿乽僔儍僀傾儞乿乽儔僀僼儖儅儞乿側偳偺惣晹寑丄乽儈僢僠丒儈儔乕丒僔儑僂乿側偳偺壒妝僶儔僄僥傿偲偄偭偨傾儊儕僇惢僥儗價斣慻傪丄偨偩怘偄擖傞傛偆偵娤偰偄偨丅70擭戙敿偽埲崀丄巇帠偱昿斏偵傾儊儕僇偵峴偔傛偆偵側偭偨偑丄偁傟偼1975擭偩偭偨傠偆偐丄弶傔偰儘僒儞僕僃儖僗偵峴偒丄乽僒儞僙僢僩77乿偺扵掋帠柋強偺儌僨儖偵側偭偨応強傪幵偱捠偭偨偲偒偼丄姶奡怺偄傕偺傪姶偠偨丅Sunset Strip偲偼僒儞僙僢僩戝捠傝偺價僶儕乕僸儖僘婑傝偺嬫堟偺偙偲偱丄偁偨傝偵偼寍擻恖偑棫偪婑傞僋儔僽傗儗僗僩儔儞偑暲傫偱偄傞丅偡偖嬤偔偵僨傿乕儞丒儅乕僥傿儞偺宱塩偡傞僋儔僽乮乽僨傿僲乿偲偄偆揦偩偭偨偐乯傗僞儚乕丒儗僐乕僪偑偁偭偨丅
娬榖媥戣丄乽僒儞僙僢僩77乿偼丄抝惈僐乕儔僗偲僼傿儞僈乕僗僫僢僾傪僼傿乕僠儍乕偟偨煭棊偨僥乕儅嬋偱傕榖戣偵側偭偨丅僪儞丒儔儖僋妝抍偺墘憈偟偨儗僐乕僪偑僸僢僩偟偨偑丄幚嵺偵僪儔儅偱巊傢傟偨壒偲偼旝柇偵僥儞億傗僯儏傾儞僗偑堘偭偰偄偨偺偑巆擮偩偭偨丅僗僠儏傾乕僩丒儀僀儕乕偺悂懼偊偼丄嵟弶偵塒堜惓柧偑扴摉偟丄搑拞偱崟戲椙偵岎戙偟偨丅崟戲椙偼廰偄掅壒偱恖婥偺偁偭偨惡桪偩偭偨偑丄傏偔偼嵟弶偺塒堜惓柧偺傎偆偑岲偒偩偭偨丅偄偭傐偆儘僕儍乕丒僗儈僗偺悂懼偊偼墍堜孾夘偱丄僗儈僗偺憉傗偐側晽杄偵傄偭偨傝偺惡偩偭偨丅墍堜孾夘偼恖婥攐桪偱丄僥儗價偺乽帠審婰幰乿傗儊儘僪儔儅偱庡墘偟丄塮夋偱傕妶桇偟偨偑丄側偵偐帠審傪婲偙偟偰寍擻奅偐傜嫀偭偰偟傑偭偨丅僋乕僉乕偺惡偼崅嶳塰偑墘偠偰偄偨丅悂懼偊側偟偺斣慻傪娤偨偙偲偑偁傞偑丄悂懼偊偺報徾偑偁傑傝偵嫮偔丄攐桪偨偪偺惗偺惡偵偼堘榓姶傪妎偊偨婰壇偑偁傞丅傏偔偼儘僕儍乕丒僗儈僗偺僼傽儞偱丄偄偐偵傕傾儊儕僇傜偟偄僴儞僒儉側岲惵擭偲偄偭偨姶偠偑婥偵擖偭偰偄偨偑丄曅曽偺僄僼儗儉丒僕儞僶儕僗僩偑丄乽僒儞僙僢僩77乿偺偁偲丄僥儗價偺乽FBI乿偱庡墘偟丄塮夋偵傕弌偰乮乽埫偔側傞傑偱懸偭偰乿乯妶桇偟偨偺偵斾傋偰丄儘僕儍乕丒僗儈僗偼屄惈偺側偝偑嵭偄偟偨偺偩傠偆偐丄偦偺屻偼僷僢偲偣偢丄傾儞丒儅乕僌儗僢僩偲寢崶偟偰攐桪偐傜懌傪愻偄丄寍擻儅僱乕僕儍乕嬈偵揮偠偰偟傑偭偨丅
偝偰丄偦偺儘僕儍乕丒僗儈僗偩偑丄摉帪1嬋偩偗斵偺壧偭偨僔儞僌儖斦偑敪攧偝傟偨丅乽楒偺弽乿乮Beach Time乯偲偄偆嬋偩丅僋乕僉乕栶偺僄僪儚乕僪丒僶乕儞僘偑僐僯乕丒僗僥傿乕償儞僗偲僨儏僄僢僩偟偨乽僋乕僉乕丒僋乕僉乕乮孂傪戄偟偰乯乿乮Kookie, Kookie 乲Lend Me Your Comb乴乯偼戝僸僢僩偟偨偑丄儘僕儍乕丒僗儈僗偺偙偺嬋偼杮崙傾儊儕僇偱偼傑偭偨偔晄敪偱丄擔杮偱傕偦偙偦偙偺僸僢僩偱廔傢偭偰偟傑偭偨丅偱傕摉帪儔僕僆偺梞妝僸僢僩丒僷儗乕僪斣慻傪寚偐偝偢挳偄偰偄偨傏偔偼丄斣慻偱壗搙偐偐偐偭偨偙偺嬋傪傪偗偭偙偆婥偵擖偭偰偄偨丅偦傟偐傜40擭埲忋夁偓偨偄傑丄埲慜偐傜扵偟偰偄偨乽楒偺弽乿偺壒傪丄愭擔偁傞偲偙傠偐傜傗偭偲庤偵擖傟偨丅傕偆堦搙挳偒偨偄偲巚偭偰偄偨偺偵丄偳傫側嬋偩偐朰傟偰偟傑偭偰偄偨偑丄嬋傪偐偗偨偲偨傫丄儊儘僨傿偑酳偭偨丅儘僕儍乕丒僗儈僗偺惡偑酳偭偨丅偦偟偰丄惵弔偺巚偄弌偑暚悈偺傛偆偵桸偒忋偑偭偨丅捖晠側昞尰偩偑丄傎傫偲偆偵偦偆偩偭偨偺偩偐傜偟傚偆偑側偄丅僗儈僗偺壧偼壓庤偩偟丄嬋偺嶌傝傕摉帪偺寧暲傒側僸僢僩丒僜儞僌偩丅偩偑丄40擭傇傝偵挳偄偨乽楒偺弽乿偵偼丄僞僀儉丒儅僔儞偺傛偆偵挳偔傕偺傪偐偮偰偺帪戙偵楢傟婣傜偣傞丄晄巚媍側杺椡偑偁偭偨丅
2006.11.05 (擔) 儔僢僔儏丒儔僀僼偵崬傔傜傟偨僗僩儗僀儂乕儞偺斶捝側巚偄
愭擔丄偁傞儗僐乕僪夛幮偐傜偺埶棅偱丄僕儍僘宯僗僞儞僟乕僪丒僜儞僌偺栿帉傪偟偨丅壧帉偺東栿偼傔偭偨偵庤偑偗傞偙偲偑側偄偺偱丄柺敀偄宱尡傪偝偣偰傕傜偭偨偑丄偲偔偵乹儔僢僔儏丒儔僀僼乺(Lush Life乯偲偄偆嬋偺墱怺偄拞恎傪抦傞偙偲偑偱偒偨偺偼岾塣偩偭偨丅偙傟偼僨儏乕僋丒僄儕儞僩儞偺曅榬偲偟偰僶儞僪偵峷專偟偨嶌丒曇嬋幰價儕乕丒僗僩儗僀儂乕儞偑嶌帉丒嶌嬋偟偨嬋偩丅僗僩儗僀儂乕儞偲偄偊偽僄儕儞僩儞偺僥乕儅嬋乹A楍幵偱峴偙偆乺偺嶌幰偲偟偰桳柤偩偑丄斵偑乹儔僢僔儏丒儔僀僼乺傪嶌偭偨偺偼丄壒妝僔乕儞偵僨價儏乕偡傞慜偺1936擭丄21嵨偺偲偒偩偭偨丅帉傪彂偄偨偺偼傕偭偲屻偵側偭偰偐傜偺偙偲傜偟偄丅僶儔乕僪偺擄嬋偩偑丄挧愴偟偑偄偺偁傞嬋偩偐傜偱偁傠偆丄僕儑儞丒僐儖僩儗乕儞丄僄儔丒僼傿僢僣僕僃儔儖僪側偳丄懡偔偺僕儍僘儊儞偑嵦傝忋偘偰偄傞丅偙偺嬋偼償傽乕僗偺晹暘偑堎忢偵挿偄丅捠忢偺僗僞儞僟乕僪嬋偼償傽乕僗側偟偱墘彞偝傟傞偙偲偑懡偄偑丄偙偺嬋偵娭偟偰偼丄傎偲傫偳偺応崌償傽乕僗傪徣棯偣偢偵壧傢傟丄墘憈偝傟傞丅嬋柤偼丄堦斒揑偵偼乽朙偐側恖惗乿偲偐乽傒偢傒偢偟偄恖惗乿偲偐傪堄枴偡傞偲偝傟偰偄傞偑丄傏偔偼偐偹偑偹壧帉偺撪梕偼傛偔暘偐傜側偄側偑傜丄"Life is lonely..."側偳偲偄偆僼儗乕僘偑弌偰偔傞偺偱丄偙偺夝庍偵偼媈栤傪帩偭偰偄偨丅崱夞丄弶傔偰壧帉傪偠偭偔傝撉傫偱傒偰丄巚偭偨偲偍傝庘偟偝傪壧偭偨嬋偩偑丄偦偙偵偼梊憐傪挻偊偨暋嶨側怱忣偑崬傔傜傟偰偄傞偙偲偵嫻傪懪偨傟偨丅壧帉傪梫栺偡傞偲丄偙傫側姶偠偵側傞丅
埲慜偼傛偔娊妝奨偵弌妡偗丄偄偐偑傢偟偄揦偵擖傝怹偭偰偄偨
偦偙偼恖乆偑恖惗偲偄偆幵椫偺幉偺偆偊偱姲偖偲偙傠
僕儍僘傗僇僋僥儖傪妝偟傒丂惗偒偰偄傞幚姶傪摼傞偲偙傠
偩偑丂彈偨偪偼傒側斶偟偘偱丂捑傫偩埫偄婄傪偟偰偄偨
壔徬偺柤巆傝傪偲偳傔偰偼偄傞偑丂傕偆弪偣棊偪偰偟傑偭偰偄傞
偦偟偰丂偁側偨偵夛偄丄偲傝偙偵側偭偨
傢偨偟偼柌拞偵側傝丂婥傕嫸傢傫偽偐傝偩偭偨
偟偽傜偔偺偁偄偩丂怱傪徟偑偡偁側偨偺旝徫傒偼
傢偨偟傪垽偟偰偟傑偭偨斶偟傒傪懷傃偰偄傞偲巚偄崬傫偱偄偨
偩偑偦偆偱偼側偐偭偨丂傑偨傕傗傢偨偟偺姩堘偄偩偭偨
恖惗偼傑偨屒撈偵側偭偨
偡傋偰偑妋偐側傕偺偵尒偊偰偄偨偺偼丂偮偄嫀擭偺偙偲側偺偵
偄傑偼傑偨丂偮傜偄枅擔偵栠偭偰偟傑偭偨
傢偨偟偼偳偙偐偺彫偝側僶乕偱
庰傃偨傝偺恖惗傪憲傝丂媭偪壥偰傞偩傠偆
傢偨偟偲摨偠傛偆偵庘偟偔惗偒傞恖乆偲偄偭偟傚偵
偙偺傛偆偵丄撪梕揑偵偼垽偟偨彈偵棤愗傜傟偰懕偗偰愨朷偟偨抝偺壧偩丅偦傟偵偟偰偼丄偁傑傝偵峳椓偲偟偨怱徾丄傗傝偒傟側偄屒撈姶偑慡懱傪暍偭偰偄傞丅壧帉偼擄夝偱丄堄枴偑婔廳偵傕愊傒廳側偭偰偄傞丅偙偺嬋傪棟夝偡傞偵偼丄價儕乕丒僗僩儗僀儂乕儞偑摨惈垽幰偩偭偨偙偲傪抦傞昁梫偑偁傞丅斵偼偦傟傪憗偔偐傜岞尵偟偰偄偨丅偙傫偵偪偱偼摨惈垽傕悽娫揑偵擣抦偝傟丄嵎暿傕側偔側偭偰偒偰偄傞偑丄斵偑惗偒偰偄偨帪戙偼傑偩摨惈垽幰偼敀娽帇偝傟丄傑偲傕偵偼惗偒偰偄偗側偐偭偨丅偦傟偩偗偵丄尵偄抦傟偸嬯楯傪枴傢偭偨偵堘偄側偄丅崱搙偙偦垽偡傞恖偵傔偖傝崌偊偨偲巚偭偨偺偵丄傑偨傕傗姩堘偄偩偭偨丒丒丒偦傫側曬傢傟側偄垽偺懕偔帺暘偺恖惗丄扤偐傜傕棟夝偝傟側偄傑傑屒撈偵惗偒傞恖惗傪丄斵偼帉偵捲偭偨偺偩丅偦傟傪峫偊傞偲丄偙偺壧偵崬傔傜傟偨愨朷偺怺偝偼應傝抦傟側偄傕偺偑偁傞丅僞僀僩儖偺"lush"偵偼丄帿彂傪傂偔偲乬朙偐偵惗偄栁偭偨乭偲偄偆堄枴偺傎偐偵丄乬堸傫偩偔傟乭偲偄偆堄枴傕偁傞丅撪梕偐傜偡傞偲"Lush Life"偲偄偆嬋柤偼丄乬庰傃偨傝偺恖惗乭偲偄偆栿偑惓夝偺傛偆偩偑丄傕偟偐偡傞偲丄媡愢揑側堄枴偱乬朙偐側恖惗乭偲柦柤偟偨偺偐傕偟傟側偄丅
僗僩儗僀儂乕儞偼1939擭偵僄儕儞僩儞偵屬傢傟丄埲屻30擭傕偺偁偄偩傎偲傫偳峴摦傪偲傕偵偟丄僄儕儞僩儞偲嫟摨偱丄偁傞偄偼戙栶偱丄嶌嬋丒曇嬋偟丄僺傾僲傪抏偄偨丅斵偺彂偄偨嬋偵偼丄乹儔僢僔儏丒儔僀僼乺傗乹A楍幵偱峴偙偆乺偺傎偐丄乹僨僀丒僪儕乕儉乺乹僠僃儖僔乕丒僽儕僢僕乺乹儗僀儞丒僠僃僢僋乺側偳丄柤嬋偑偨偔偝傫偁傞丅僄儕儞僩儞丒僆乕働僗僩儔偼1940擭偐傜42擭偵偐偗偰丄愨捀婜傪寎偊偨丅僄儕儞僩儞偺憂嶌庤朄偺崅傑傝丄僕儈乕丒僽儔儞僩儞乮儀乕僗乯傗儀儞丒僂僃僽僗僞乕乮僥僫乕乯偲偄偭偨桪廏側僒僀僪儊儞偺壛擖側偳偑偦偺攚宨偵偁偭偨偲尵傢傟傞偑丄傏偔偼偦偺戞堦偺梫場偼僗僩儗僀儂乕儞偩偭偨偲巚偆丅偦傟埲慜偺僄儕儞僩儞丒僶儞僪傕偨偟偐偵慺惏傜偟偄偑丄40擭偵悂偒崬傑傟偨乹僕儍僢僋丒僓丒儀傾乺乹僐僐乺乹僐儞僠僃儖僩丒僼僅乕丒僋乕僥傿乺側偳偺梔偟偄傑偱偺旤偟偝偵嵤傜傟偨僒僂儞僪丄惛鉱傪偒傢傔偨峔惉丄愮曄枩壔偡傞僥僋僗僠儍乕偼丄偦傟傑偱偺僄儕儞僩儞偵偼側偐偭偨傕偺偩丅僕儍儞僌儖丒僗僞僀儖偲徧偝傟偨摿堎側墘憈傗丄旝柇側僩乕儞傪愊傒廳偹偨僇儔僼儖側僒僂儞僪傪捠偠偰丄傾儊儕僇偵惗偒傞崟恖偲偟偰偺旤堄幆傪懪偪弌偟偰偒偨僄儕儞僩儞偩偭偨偑丄偙傟傜偺嶌昳偵偼丄儅僢僔償側傾儞僒儞僽儖偺枺椡偲摨帪偵丄偦傟傑偱偲偼偒傢傔偰堎幙側媄弍揑愻楙偝丄崅摜揑側姶妎偑壛偊傜傟偰偄偨丅偦偙偵偼僗僩儗僀儂乕儞偺採嫙偟偨偝傑偞傑偺憂憿揑側傾僀僨傾偑偁偭偨傛偆偵巚偆丅僄儕儞僩儞偺執戝偝偵偼曄傢傝偼側偄偑丄偙傟傜偺僄儕儞僩儞寍弍偺嵟崅搙偵姰惉偝傟偨嶌昳孮偼丄僗僩儗僀儂乕儞敳偒偵偼惗傒弌偝傟側偐偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偙偺傛偆偵僗僩儗僀儂乕儞偼寙弌偟偨嵥擻偵宐傑傟偰偄偨偵傕偐偐傢傜偢丄惗奤僄儕儞僩儞偺塭偺恖偲偟偰摥偒丄1964擭丄51嵨偱朣偔側偭偨丅
僗僩儗僀儂乕儞偑朣偔側偭偨偲偒丄僄儕儞僩儞偼偦偺巰傪搲傒丄傾儖僶儉乽價儕乕丒僗僩儗僀儂乕儞偵曺偖乿(And His Mother Called Him Bill乯傪悂偒崬傫偩丅偙傟偼僗僩儗僀儂乕儞偺嶌偭偨嬋傪價僢僌丒僶儞僪偱墘憈偟偨傾儖僶儉偱偁傝丄屻婜僄儕儞僩儞偺寙嶌偺傂偲偮偵側偭偨丅僄儕儞僩儞偼僗僩儗僀儂乕儞偺偙偲傪乽傢偨偟偺塃榬偱偁傝丄嵍榬偱偁傝丄椉栚偩丅傢偨偟偺擼偼斵偺摢偵偁傝丄斵偺偼傢偨偟偺側偐偵偁傞乿偲丄偦偺堦怱摨懱傇傝傪岅偭偰偄偨丅傾儖僶儉偺嵟屻偵廂傔傜傟偰偄傞丄僄儕儞僩儞偑僜儘丒僺傾僲偱愗乆偲抏偒捲傞乹楡偺壴乺偺旤偟偄儊儘僨傿偵偼丄怺偄垼愗偺擮偑崬傔傜傟偰偄傞丅
2006.10.15 (擔) 僠儞僪儞偲僶儖僇儞偑梈偗崌偆偲偒
僋儔儕僱僢僩憈幰丄戝孎儚僞儖棪偄傞宆攋傝偺僕儍僘丒儐僯僢僩丄僔僇儔儉乕僞乮CICALA MVTA乯偺嵟怴傾儖僶儉乽惗愪乿偑敪攧偝傟偨丅僆僼傿僔儍儖丒儕儕乕僗偲偟偰偼弶偺儔僀償丒傾儖僶儉偩丅偙偺僶儞僪杮棃偺柍崙愋揑側僄僱儖僊乕偑枮偪偁傆傟偨丄慺惏傜偟偄撪梕偵巇忋偑偭偰偄傞丅傏偔偑戝孎儚僞儖偲僔僇儔儉乕僞傪抦偭偨偺偼丄2001擭偵敪攧偝傟偨乽撌墯乮僨僐儃僐乯乿偐傜偩偭偨丅尒悽暔偺屇傃崬傒偐傜巒傑傝丄峕屗忣弿昚偆僠儞僪儞丄垼姶傪偨偨偊偨僶儖僇儞敿搰傗僩儖僐偺堎崙晽僼儗乕僘丄傾儖僶乕僩丒傾僀儔乕傗僕僃儕乕丒儘乕儖丒儌乕僩儞傑偱旘傃弌偡丄側傫偱傕偁傝偺僒僂儞僪偵偡偭偐傝枺椆偝傟偰偟傑偭偨丅僋儔儕僱僢僩偺傎偐丄償傽僀僆儕儞傗僠儏乕僶傪僼傿乕僠儍乕偟偨妝婍曇惉傕儐僯乕僋偩偭偨丅巚傢偢丄20擭傎偳慜偵抁婜娫偩偑妶摦偟偨僕儍僘丒僌儖乕僾丄360搙壒妝宱尡廤抍偺攋揤峳側僕儍僘傪巚偄弌偟偰偟傑偭偨丅儕乕僟乕偺戝孎儚僞儖偼丄嵟弶偼僷儞僋傪傗偭偰偄偨儈儏乕僕僔儍儞傜偟偄偑丄偦偺帇栰偺峀偝丄姶惈偺朙偐偝偼偨偄偟偨傕偺偩丅僶儞僪柤偺僔僇儔儉乕僞偼丄柧帯偐傜戝惓偵偐偗偰妶桇偟偨墘壧巘丄揧揷垹愪朧偺儔僥儞岅偱彂偐傟偨曟旇柫偺堦愡乽CICALA MVTA乿乮惡側偒愪乯偐傜庢傜傟偨傕偺偩偲偄偆丅揧揷垹愪朧偼斀惌晎揑側憇巑墘壧傪帺傜彂偒丄壧偭偨丄擔杮壧梬偺憪暘偗偲傕塢偆傋偒恖偱丄徍榓弶婜傑偱惗偒偨丅僥僉壆偺悽奅偲傕恊岎偑偁偭偨傜偟偄丅僔僇儔儉乕僞偼1998擭偵僼傽乕僗僩丒傾儖僶儉乽僔僇儔儉乕僞乿傪敪昞丄偙偺乽撌墯乿偼斵傜偺2嶌栚偵偁偨傞丅偦偺屻3嶌栚偺乽僑乕僗僩丒僒乕僇僗乿傪敪攧偟乮2004擭乯丄偦傟偵懕偔4嶌栚偑崱夞偺傾儖僶儉偵側傞丅僩儖僐傗僶儖僇儞偺僼僅乕僋丒僜儞僌偼撈摿偺儊儘僨傿乕傗儕僘儉傪帩偭偰偄傞偑丄偳偙偐変乆擔杮恖偵偲偭偰夰偐偟偄嬁偒傪懷傃偰偄傞丅傑偨傾僀儔乕偼僼儕乕丒僕儍僘偺儈儏乕僕僔儍儞偩偑丄僩儔僨傿僔儑僫儖側儖乕僣偲嵃偺嫨傃偑崬傔傜傟偨僼儗乕僕儞僌偱丄懠偺僼儕乕宯僕儍僘儊儞偲偼堦慄傪夋偟偰偄偨丅偩偐傜丄偙傟傜偺壒妝偑僠儞僪儞丒僒僂儞僪偲暲傫偱傕傑偭偨偔堘榓姶偑側偄丅偙傫偳偺怴嶌偼儔僀償側偩偗偵丄斵傜偺壒妝偺廽嵳揑側擌傗偐偝丄僌儘乕僶儖側僗働乕儖偺妝偟偝偑僟僀儗僋僩偵揱傢偭偰偔傞丅2006.10.14 (搚) TWA800曋捘棊偺恀憡偼媶柧偝傟偨偐
僱儖僜儞丒僨儈儖偺怴嶌儈僗僥儕乽僫僀僩僼僅乕儖乿乮暥弔暥屔乯偼丄偳偆偵傕昡壙偟偑偨偄彫愢偩丅庡恖岞偼慜乆嶌乽墹幰偺僎乕儉乿偵搊応偟偨尦僯儏乕儓乕僋巗寈孻帠偱丄尰嵼偼楢朚懳僥儘婡摦戉偺憑嵏姱偱偁傞僕儑儞丒僐乕儕乕丅偩偐傜摉慠丄乽墹幰偺僎乕儉乿偱僐乕儕乕偑斊峴傪慾巭偟側偑傜傕摝偘傜傟偨埆鐓側僥儘儕僗僩偲嵞傃懳寛偡傞偲撉幰偼巚偆丅偲偙傠偑偦偺僥儘儕僗僩偼傑偭偨偔搊応偣偢丄椃媞婡捘棊帠屘偺恀憡媶柧偑僥乕儅偵側偭偰偄傞偙偲偱丄傑偢尐偡偐偟傪怘傜偆丅偙傟偼1996擭偵幚嵺偵婲偭偨TWA800曋偺儘儞僌傾僀儔儞僪壂偱偺捘棊帠屘傪壓晘偒偵偟偰偄傞丅偙偺帠屘偼230恖傕偺巰幰偑弌傞戝嶴帠偵側偭偨丅帠屘偐傜5擭屻丄僐乕儕乕偼嵢偺FBI憑嵏姱働僀僩偲偲傕偵丄儈僒僀儖偱寕捘偝傟偨偲偄偆栚寕幰偑偨偔偝傫偄傞偵傕偐偐傢傜偢帠屘偲偟偰張棟偝傟偨偙偲偵晄怰傪書偒丄FBI偺朩奞偵偁偄側偑傜傕撈帺偺憑嵏傪奐巒偡傞丅偙偺憑嵏妶摦偑拞怱偵昤偐傟傞傢偗偩偑丄栚寕幰傗徹恖偐傜偺帠忣挳庢偑傗偨傜偵挿偔丄捠忢偺彫愢偺攞埲忋偺僗儁乕僗傪妱偄偰偊傫偊傫偲懕偔丅偙偙偱嵞傃撉幰偼柺怘傜偭偰偟傑偆丅偩偑偗偭偟偰忕挿偱偼側偄丅挿偄偙偲偼挿偄偑丄夛榖偼偍傕偟傠偔丄庡恖岞偺傊傜偢岥偑夣挷偱丄挿偝傪姶偠偝偣側偄丅偦傫側挷巕偱恑傫偱丄嵟屻嬤偔丄傗偭偲帠幚偑柧傜偐偵側傝丄偄傛偄傛攚屻偺堿杁偑柧偐偝傟傞偲偄偆偲偙傠偱丄偲傫偱傕側偄偙偲偑婲偒偰偟傑偆丅偦偆偐丄偙傟偵寢傃偮偔偺偐丄暁慄偼偁偭偨偺偩偑丄婥偑偮偐側偐偭偨丅偱傕丄偁傟偭丄堿杁偺恀憡偼偳偆側偭偨偺丅崙壠揑側杁棯偑偁偭偨偙偲傪擋傢偣偰偼偄傞偑丄壗傕柧傜偐偵偝傟側偄傑傑廔傢偭偰偟傑偆丅屜偵偮傑傑傟偨傛偆側姶偠偩丅偲偄偆偙偲偱丄側傫偲傕傊傫偰偙傝傫側彫愢側偺偩偑丄柺敀偄偙偲偼妋偐偱丄偐側傝偺挿曇偩偑搑拞偱偩傟傞偙偲側偔堦婥偵撉傔偰偟傑偆丅偱傕傑傞偱丄偍偄偟偄椏棟傪偨偔偝傫怘傋偨偑丄徚壔偟側偄偱堓偺側偐偵巆偭偰偄傞傛偆側婥帩偪偩丅慜嶌偺乽傾僢僾丒僇儞僩儕乕乿傕曄側彫愢偩偭偨丅偐偮偰暫巑偲偟偰愴偭偨儀僩僫儉傪嵞朘偡傞抝偺榖偱丄儀僩僫儉偺奺抧偺昤幨偑偊傫偊傫偲懕偒丄偐側傝鐒堈偟偨丅寙嶌僗儕儔乕丒傾僋僔儑儞偩偭偨乽墹幰偺僎乕儉乿偺偁偲偩偗偵丄偑偭偐傝偟偨婰壇偑偁傞丅偁偲偑偒偵傛傞偲丄崱擭廐偵弌斉偝傟傞梊掕偺師夞嶌偼丄偙偺乽僫僀僩僼僅乕儖乿偺懕曆偩偲偄偆丅偙傫偳偙偦恀憡偑柧傜偐偵偝傟丄僗僇僢偲偝偣偰偔傟傞偙偲傪婜懸偟偨偄丅偲偙傠偱丄偙偺彫愢偺夛榖偺側偐偵乽僋僜偑愵晽婡偵傇偪偁偨偭偨傛偆側乿偲偄偆昞尰偑壗搙傕弌偰偔傞丅傾儊儕僇恖偼丄偔偩偗偨夛榖偺側偐偱乽僋僜偺嶳傪摜傫偢偗傞乿偲偐丄偙偺乽僋僜乿(shit)傪巊偭偨尵梩傪巊偆偺偑岲偒偱丄傏偔傕幚嵺偵帹偵偟偨偙偲偑偁傞偑丄偲偔偵偙偺乽僋僜偑愵晽婡偵傇偪偁偨傞乿(The shit hit the fan)偼丄嫮楏側偩偗偵柇偵報徾偵巆傞昞尰偩丅2006.10.10 (壩) 僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞抐復
10寧30擔偼僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞偺抋惗擔偩丅僽儔僂儞偼1956擭6寧丄26嵨偺庒偝偱帺摦幵帠屘偵傛傝朣偔側偭偨丅惗偒偰偄傟偽崱擭偱76嵨偵側傞丅僽儔僂儞偼儌僟儞丒僕儍僘偺楌巎忋丄嵟崅偺僩儔儞儁僢僞乕偩偭偨丅嵟崅偺側偐偺傂偲傝偱偼側偄丄桞堦柍擇丄懠傪埑偟偰嵟崅偩偭偨丅偦偟偰斵傎偳惗慜偦偺恖暱傪垽偝傟偨儈儏乕僕僔儍儞偼偄側偐偭偨丅偳傫側偵斵偺僾儗僀偑慺惏傜偟偐偭偨偐丄偳傫側偵垽偡傋偒恖娫偩偭偨偐偵偮偄偰偼丄偙傟傑偱偄傠傫側偲偙傠偱岅傝偮偔偝傟偰偄傞偺偱丄偙偙偱嬉尵偼旔偗傞丅傏偔偼斵偺儗僐乕僪傪孞傝曉偟挳偄偰偄傞丅斵偑巆偟偨惓婯偺儗僐乕僨傿儞僌偩偗偱側偔丄儕僴乕僒儖丒僥乕僾傗儔僀償偺曻憲榐壒側偳傪CD壔偟偨傕偺傕娷傔偰丄庤偵擖傞壒尮側傜壗偱傕憑偟媮傔偰挳偒偨偄偲巚偭偰偄傞丅傏偔偼堦斒揑偵儔僀償傪娤傞偙偲偵偼偦傟傎偳嫽枴偼側偄偑丄僽儔僂儞側傜丄傕偟斵偺擔杮岞墘偑峴側傢傟偨傜丄妛峑偱傕夛幮偱傕媥傫偱丄擔杮拞偱傗傞偡傋偰偺岞墘傪捛偄偐偗偰娤偵峴偔偩傠偆丅偦傫側僽儔僂儞偺僼傽儞偼悽奅拞偵偨偔偝傫偄傞偵堘偄側偄丅偙傟傑偱廤傔偨僽儔僂儞偺枹敪昞壒尮偺側偐偱丄嬤擭傕偭偲傕姶摦偝偣傜傟偨偺偼丄僥傿乕儞僄僀僕儍乕偺僽儔僂儞偑摉帪嫵偊傪庴偗偰偄偨壒妝嫵巘億僀僕乕丒儘儚儕乕偲堦弿偵楙廗偟偰偄傞僥乕僾偩偭偨丅僽儔僂儞偼偍偦傜偔拞妛惗偺偙傠偩偲巚傢傟傞丅僽儔僂儞偑僩儔儞儁僢僩丄儘儚儕乕偑傾儖僩丒僒僢僋僗傪悂偒丄乹僆乕僯僜儘僕乕乺傪僨儏僆偱墘憈偟偰偄傞丅偙偺僽儔僂儞偺僾儗僀偑僼傽僢僣丒僫償傽儘偵偦偭偔傝側偺偩丅墘憈偼摉慠側偑傜傑偩梒偔丄枹姰惉偩丅偦偺斵偑丄昁巰偵僫償傽儘偦偭偔傝偵悂偙偆偲偟偰偍傝丄挳偄偰偄傞偲嫻偑擬偔側傞丅僽儔僂儞偺傾僀僪儖偑丄僈儗僗僺乕偲暲傃徧偣傜傟偨價僶僢僾帪戙偺柤庤僫償傽儘偩偭偨偙偲偼偮偲偵桳柤偩偑丄偦傟偑庤偵偲傞傛偆偵暘偐傞墘憈偩丅偳傫側偵妚怴揑側僗僞僀儖傪抸偄偨儈儏乕僕僔儍儞偱傕丄嵟弶偼摬傟偺僸乕儘乕偺恀帡偐傜僗僞乕僩偡傞偺偩丅僷乕僇乕偩偭偰儗僗僞乕丒儎儞僌傪揙掙揑偵妛傇偙偲偵傛偭偰怴偟偄憈朄傪惗傒弌偟偨丅庒偒擔偺僽儔僂儞偑偳傫側楙廗傪偟偰偄偨偐偵偮偄偰偼丄桞堦偺揱婰偺東栿彂乽僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞乣揤嵥僩儔儞儁僢僞乕偺惗奤乿乮壒妝擵桭幮姧乯偵徻偟偄丅
僽儔僂儞偑僕儍僘奅偵僨價儏乕偟偨摉帪丄4嵨擭忋偺儅僀儖僗丒僨僀償傿僗偼偡偱偵價僢僌丒僱乕儉偩偭偨丅偩偑丄儅僀儖僗偑僽儔僂儞偺僾儗僀偵幑搃傪妎偊偨偱偁傠偆偙偲偼憐憸偵擄偔側偄丅帠幚丄僽儔僂儞偑僽儗僀僉乕偺僋僀儞僥僢僩偵擖偭偰僶乕僪儔儞僪偱儔僀償偺偨傔偵儕僴乕僒儖傪傗偭偰偄傞偺傪挳偒偵棃偨儅僀儖僗偑丄婣傝偟側偵僽儔僂儞偵傓偐偭偰乽偍慜偺岥側傫偐丄偄偐傟偰偟傑偊偽偄偄乿偲嫨傫偩偲偄偆堩榖偑偁傞丅僗僥乕僕偵偄偨儊儞僶乕偺傂偲傝偼乽偁傟偼忕択側傫偐偠傖側偄丄偒偭偲杮婥偩偤乿偲尵偭偰偄偨偲偄偆丅偙偺僄僺僜乕僪偼慜宖偺揱婰偵婰偝傟偰偄傞丅僕儍僘偺僩儔儞儁僢僩偲偄偊偽丄儖僀丒傾乕儉僗僩儘儞僌偺愄偐傜丄婸偐偟偄壒怓偱崅傜偐偵悂偒傑偔傞偺偑杮摴偩丅偩偑儅僀儖僗偼堄幆揑偵偐僥僋僯僢僋晄懌偺偨傔偐丄50擭戙敿偽偁偨傝偐傜丄堿傝傪懷傃偨僩乕儞丄娫傪惗偐偟偨僼儗乕僕儞僌偲偄偆丄撈帺偺摴傪愗傝奐偄偨丅偙傟偼杮棃偺傗傝曽偱偼僽儔僂儞偵懢搧懪偪偱偒側偄偲峫偊偨儅僀儖僗偑曇傒弌偟偨憈朄偩偲巚傢傟傞丅
僽儔僂儞偑僕儍僘奅偱妶桇偟偨偺偼丄1953擭偐傜56擭偵偐偗偰偺偨偭偨3擭娫偩偗偩偭偨丅52擭偺R&B僶儞僪帪戙傪娷傔偰傕4擭梋傝偺妶摦婜娫偩丅岾偄側偙偲偵丄偦傫側抁婜娫偵偟偰偼彮側偔側偄検偺儗僐乕僪悂偒崬傒偑巆偝傟偰偄傞丅偙偙偱儗僐乕僪偵巆偝傟偨斵偺墘憈偺側偐偱傏偔偺岲偒側傕偺偺儀僗僩丒僼傽僀償傪嫇偘偰偍偙偆丅
1. Split Kick (from "A Night at Birdland/Art Blakey Vol.1" Blue Note)
2. Clifford's Axe (from "The Best of Max Roach & Clifford Brown in Concert" GNP)
3. Delilah (from "Clifford Brown & Max Roach" EmArcy)
4. Donna Lee (from "The Beginning and the End" Columbia)
5. It Might As Well Be Spring (from "The Complete Paris Session Vol.3" Vogue)
僽儔僂儞偺戙昞嶌偵偮偄偰丄嬤擭偺擔杮偺僕儍僘丒僕儍乕僫儕僘儉偱偼僨僞儔儊側昡壙偑偼傃偙偭偰偄傞丅嵟嬤偱偼僽儔僂儞亖儘乕僠偲偄偆偲丄恀偭愭偵嫇偘傜傟傞偺偑乽僗僞僨傿丒僀儞丒僽儔僂儞乿傜偟偄偑丄乽僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞仌儅僢僋僗丒儘乕僠乿偺傎偆偑忋埵偵偔傞傋偒偩丅偨偟偐偵乽僗僞僨傿丒僀儞丒僽儔僂儞乿傕慺惏傜偟偄偟丄偨偲偊偽寙嶌偲偝傟傞乹僠僃儘僉乕乺偼丄傾僢僾丒僥儞億偺惁傑偠偄墘憈偩偑丄壒妝揑撪梕偐傜塢偊偽丄乽僋儕僼僅乕僪丒僽儔僂儞仌儅僢僋僗丒儘乕僠乿偵擖偭偰偄傞乹僕儑僀丒僗僾儕儞僌乺乹僟僼乕僪乺乹僨儔僀儔乺乹僕儑乕僪僁乺側偳偺柤嬋丒柤墘偵斾傋傞偲塭偑敄偄丅摨條偵丄乽僂傿僘丒僗僩儕儞僌僗乿偑戙昞嶌偺堦枃偵擖偭偰偄傞偙偲偑懡偄偑丄偙偺傾儖僶儉偼僀乕僕乕丒儕僗僯儞僌壒妝偲偟偰偼偡偖傟偰偄傞偑丄僕儍僘偱偼側偄丅僽儔僂儞偼偙偙偱丄杮恖帺傜偺堄巚偐惂嶌幰偐傜偺梫惪偵傛偭偰偐偼暘偐傜側偄偑丄偄偭偝偄傾僪儕僽傪偟偰偄側偄丅偟傛偆偲偡傞偦傇傝偡傜尒偣偰偄側偄丅偦偙偑丄偨偲偊偽僷乕僇乕偺乽僂傿僘丒僗僩儕儞僌僗乿偲堘偆偲偙傠偱丄僷乕僇乕偺傎偆偼棫攈側僕儍僘偵側偭偰偄傞丅傏偔偼僕儍僘偠傖側偄偐傜壒妝偲偟偰挳偔壙抣偑側偄偲塢偭偰偄傞偺偱偼側偄丅壒妝偺僕儍儞儖偵桪楎偼側偔丄傏偔帺恎傕僕儍僘埲奜偺壒妝傕妝偟傫偱偄傞丅偦偆偱偼側偔丄僽儔僂儞偺乽僂傿僘丒僗僩儕儞僌僗乿偑丄僕儍僘偺柤斦偺傛偆偵側偭偰偄傞晽挭偑偍偐偟偄偲塢偭偰偄傞偺偩丅壒妝偺岲偒寵偄偼屄恖偺帺桼偩偑丄堦晹偺挳偔帹傪帩偨側偄儔僀僞乕偺偣偄偱昡壙偑榗傫偱偟傑偆偺偼丄偳偆偵傕暊棫偨偟偄丅
2006.10.09 (寧) 僇儕僼僅儖僯傾丒儚僀儞偲償傽乕僕僯傾丒儅僪僙儞
桭恖偵姪傔傜傟偰丄抶傟偽偣側偑傜乽僒僀僪僂僃僀乿乮2004擭乯偲偄偆塮夋傪DVD偱娤偨丅僞僼偠傖側偔偰傕惗偒傜傟傞丄恖惗偵幐攕偟偰傕惗偒偰偄偗傞丄偦偆偄偆婥帩偪傪書偐偣偰偔傟傞僴乕僩僂僅乕儈儞僌側塮夋偩偭偨丅娔撀偼傾儗僋僒儞僟乕丒儁僀儞丄庡墘偼億乕儖丒僕傾儅僢僥傿丄僩儅僗丒僿僀僨儞丒僠儍乕僠丄償傽乕僕僯傾丒儅僪僙儞偲偄偆丄擔杮偱偼柍柤偵嬤偄僗僞僢僼丒僉儍僗僩偵傛傞嶌昳偱丄柭傝暔擖傝偺戝嶌偲偼惓斀懳偺抧枴側彫昳偱偁傞丅嫵巘傪偟側偑傜彫愢壠傪栚巜偡儚僀儞岲偒偺晽嵮偺忋偑傜側偄抝偑庡恖岞偱丄棊偪栚偺僥儗價丒僞儗儞僩偱偁傞彈岲偒偺儅僢僠儑側桭恖偺寢崶幃傪慜偵丄1廡娫偐偗偰傆偨傝偱僇儕僼僅儖僯傾偺儚僀僫儕乕傔偖傝傪偡傞偲偄偆僗僩乕儕乕偩丅庡恖岞偼棧崶偟偨慜嵢偵偄傑偩偵枹楙偑偁傝丄彫愢傪彂偄偰偄傞偑偳偺弌斉幮偐傜傕弌斉傪抐傜傟丄儚僀儞傔偖傝偺嵟拞偵抦傝崌偭偨彈偲偄偄拠偵側傞偑偗傫偐暿傟偟偰偟傑偆丄奊偵昤偄偨傛偆側僟儊恖娫偩偑丄嵟屻偵斵偼偦偺彈偲婥帩偪偑捠偠崌偄丄嵞傃慜岦偒偵惗偒傛偆偲偡傞丅棊偪拝偄偨墘弌丄弌墘幰偨偪偺帺慠側墘媄丄僇儕僼僅儖僯傾偺儚僀儞丒儘乕僪偺旤偟偄晽宨偑偄偄丅儚僀儞側偳偦偭偪偺偗偱丄寢崶傪峊偊偰偄傞偺偵摨偠偔僶乕偱抦傝崌偭偨拞崙宯偺彈偺怟偽偐傝捛偄妡偗夞偡儅僢僠儑抝偑徫偄傪桿偆丅嫮偔報徾偵巆偭偨偺偼僫僷丒償傽儗乕偺旤偟偄儚僀儞敤偺宨怓偩丅乽偄偪偽傫執戝側儚僀儞偼僺僲丒僲儚乕儖乿偩偺乽僇儀儖僱丒僼儔儞偐傜偼嵟忋偺儚僀儞偼偱偒側偄乿側偳丄儚僀儞偵娭偡傞錎拁偑悘強偵弌偰偔傞偺傕嫽枴怺偄丅傏偔傕儚僀儞偼岲偒偱丄僇儕僼僅儖僯傾丒儚僀儞傕偲偒偳偒堸傓丅僇儕僼僅儖僯傾偺儚僀儞偼丄愒傕敀傕嵟弶偺偆偪偼偍偄偟偔堸傔傞偺偵丄搑拞偐傜夁搙偵娒偝偑弌偰偒偰偟傑偆偺偑摿挜偩丅杮棃偄偄儚僀儞偱偁傟偽丄媡偵嵟弶偼枴偺僶儔儞僗偑偲傟偰偄側偄偑丄偟偩偄偵棊偪拝偄偨傕偺偵側傞丅僺僲丒僲儚乕儖偺傛偆側慇嵶側枴偺儚僀儞側偳偼摿偵偦傟偑栤戣偱丄僇儕僼僅儖僯傾偺弌棃偺偄偄僺僲丒僲儚乕儖偱傕丄杮応偺僽儖僑乕僯儏嶻偺桪旤丒揟夒側僥僀僗僩傪抦偭偰偟傑偊偽丄偁傑傝怗庤偼摦偐偝傟側偄丅乽偄偪偽傫執戝側儚僀儞偼僺僲丒僲儚乕儖乿偲偄偆尒曽偵偮偄偰偩偑丄僽儖僑乕僯儏傕偨偟偐偵慺惏傜偟偄偟丄愜偵傆傟偰堸傒偨偔側傞偐傜擺摼偼偱偒傞丅偩偑嵟屻偵棫偪曉傞偺偼傗偼傝僇儀儖僱丒僜乕價僯儓儞傗儊儖儘乕傪庡懱偵偟偨儃儖僪乕丄偲偄偆偺偑傏偔偺帩榑偩丅
偲偙傠偱庡恖岞偑僶乕偱抦傝崌偆彈傪償傽乕僕僯傾丒儅僪僙儞偲偄偆彈桪偑墘偠偰偄偨丅償傽乕僕僯傾丒儅僪僙儞偼丄桳柤側塮夋偵偼弌偰偄側偄偟丄偦傟傎偳抦傜傟偰偄側偄偑丄傏偔偑埲慜偐傜戝岲偒側彈桪偩偭偨丅偙偺彈桪偺懚嵼傪嫵偊偰偔傟偨偺偼丄塮夋偲僕儍僘丒償僅乕僇儖偲栰媴傪垽偟偨朣偒抍挿偙偲埳摗彑抝偝傫偩偭偨丅偪側傒偵丄朻摢偵彂偄偨乬僞僼偠傖側偔偰傕惗偒傜傟傞乭偲偄偆堦愡偼丄偦偺抍挿偑弌斉偟偨僴乕僪儃僀儖僪傪榑偠偨杮偺僞僀僩儖偩丅償傽乕僕僯傾丒儅僪僙儞傪弶傔偰娤偨偺偼丄栰媴傪僥乕儅偵偟偨乽枩嵨僗僞僕傾儉乿偲偄偆塮夋偺價僨僆偩偭偨丅偍偦傜偔擔杮枹岞奐嶌昳偱偁傠偆丅僂傿儕傾儉丒僺乕僞乕僙儞乮僩儅僗丒僴儕僗偺乽儗僢僪丒僪儔僑儞乿偺嵟弶偺塮夋壔乽孻帠僌儔僴儉乣搥傝偮偄偨梸朷乿偵庡墘乯偑儅僀僫乕丒儕乕僌偺栰媴慖庤偱丄儅僪僙儞偼偦偺楒恖偵暞偟偨丅嬥敮偺姱擻揑側旤恖彈桪偩偑丄偳偙偐暔桱偝偲垼偟偝傪姶偠偝偣傞暤埻婥偑報徾揑偩偭偨丅傎偐偵丄傏偔偑娤偨塮夋偱偼丄埆彈傕偺偺乽儂僢僩丒僗億僢僩乿乮1991擭乯傗儂儔乕傕偺偺乽僉儍儞僨傿丒儅儞乿乮1992擭乯側偳偵弌墘偟偰偍傝丄偤傫傇B媺嶌昳偽偐傝偩丅媣偟傇傝偵乽僒僀僪僂僃僀乿偱娤偨儅僪僙儞偼丄傑偩廩暘偵怓崄傪姶偠偝偣偨丅暊偺傑傢傝側偳偵拞擭偵偝偟偐偐偭偨條巕偑尒偰庢傟偨偑丄偦偙偑傑偨枺椡傪曻偭偰偄偨丅
2006.09.22 (嬥) 僈儖償僃僗僩儞偺嶦偟壆偺寣偼偄偮捔傑傞偺偐
朶椡偲巰偺旕忣側悽奅偵惗偒傞庒偒嶦偟壆僕儈乕丒儎儞僌僽儔僢僪偺惗偒偞傑傪昤偄偨僕僃僀儉僘丒僇儖儘僗丒僽儗僀僋偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢乽峳傇傞寣乿乮暥弔暥屔丂06擭4寧姧乯偼丄偙偺嶌壠偺婬桳偺椡検傪妋怣偝偣傞寙嶌偩丅晳戜偼1930擭戙偺傾儊儕僇撿晹丄僥僉僒僗廈偺儊僉僔僐榩娸増偄偺娊妝搒巗僈儖償僃僗僩儞丅庡恖岞偼偦偺奨傪媿帹傞埫崟奨偺儃僗偵屬傢傟偰偄傞儊僉僔僐宯偺潌傔帠巒枛壆偱偁傝丄偦偺悢婏側惗偄棫偪丄撈帺偺儖乕儖偵懃偭偨峴摦丄儃僗傗拠娫偲偺岎棳丄廻柦偺彈偲偺弌夛偄丄垽偡傞彈偺偨傔偵巰抧偵晪偔偝傑偑丄姡偄偨僞僢僠偱儕儕僔僘儉傪偨偨偊側偑傜昤偐傟傞丅側傫偲塢偭偰傕慺惏傜偟偄偺偼丄搊応恖暔偨偪偺憿宍偑嵺棫偭偰偄傞偙偲丅庡恖岞偼傕偲傛傝丄儃僗傗拠娫丄嬤椬偺廧恖丄抂栶偵偄偨傞傑偱丄傂偲傝傂偲傝偺僀儊乕僕偑偔偭偒傝偲晜偐傃忋偑傞丅夛榖傗峴摦丄壗婥側偄巇憪側偳偺昤幨偵傛傝丄偦偺恖暔偺僉儍儔僋僞乕偑惗偒惗偒偲棫偪忋偑偭偰偔傞偺偩丅偁偲偑偒偵傕彂偐傟偰偄傞傛偆偵丄掕怑偵廇偔埲慜丄曻楺拞偺庡恖岞偑柍捓忔幵偟偨壿幵偺側偐偱抦傝崌偆孼掜偺彮擭側偳偼丄傎傫偺1儁乕僕偟偐搊応偟側偄偑丄朰傟偑偨偄慛楏側報徾傪梌偊傞丅搊応偡傞埆栶偨偪傕丄扨側傞埆栶偱偼側偔丄偦傟偧傟撈帺偺懚嵼姶傪曻偭偰偄傞丅傑偨巰抧偵晪偔庡恖岞偵摨峴偡傞拠娫偺昤幨傕丄搶塮偺寬偝傫庡墘偺儎僋僓塮夋傪巚傢偣傞桭忣偲媊嫚傪姶偠偝偣偰嫻偑擬偔側傞丅朙晉側僄僺僜乕僪偑揰昤偝傟傞偺傕僗僩乕儕乕偵墱峴偒傪梌偊偰偄傞丅儊僉僔僐妚柦偺僄僺僜乕僪偼恄榖揑側僀儊乕僕傪偨偨偊偰偍傝丄庡恖岞偑僈儖償僃僗僩儞偵偨偳傝拝偔傑偱偺攇棎偵晉傫偩梒彮擭帪戙偺僄僺僜乕僪偼戞1媺偺僺僇儗僗僋丒儘儅儞偺傛偆偩丅慡懱偵惁嶴側朶椡偑昤偐傟偰偄傞偑丄撉屻姶偼憉傗偐偱丄棊偪拝偄偨昳奿傪昚傢偣偰偄傞丅偙偺嶌壠偺弶傔偰朚栿偝傟偨慜嶌乽柍棅偺潀乿偼丄嶐擭敪攧偝傟偰昡敾偑崅偐偭偨偑丄偠偮偼傏偔偼撉傫偱偄側偐偭偨丅乬僗僞僀儕僢僔儏側斊嵾彫愢乭側偳偲偄偆庝嬪偺偨傔偩丅儃僗僩儞丒僥儔儞偺乽恄偼廵抏乿側偳丄偦偺庤偺彫愢偵偆傫偞傝偟偰偄偨傏偔偼丄偙傟傕偦偺堦庬偩傠偆偲巚偄丄宧墦偟偰偄偨丅偲偙傠偑愭擔丄偙偺偲偙傠偺奀奜儈僗僥儕乕偺晄嶌偺偣偄偱撉傓傕偺偑側偔丄側傫偺婥側偟偵乽柍棅偺潀乿傪撉傫偩偲偙傠丄偦偺柺敀偝偵偨傑偘偰偟傑偄丄偁傢偰偰乽峳傇傞寣乿傪撉傫偩偲偄偆師戞丅慜嶌偺乽柍棅偺潀乿偼丄僗僥傿乕償儞丒僴儞僞乕傪巚傢偣傞丄僂僃僗僞儞彫愢偲惵弔彫愢偺梫慺傕偁傞悙乆偟偄妶寑彫愢偩偭偨丅崱搙偺乽峳傇傞寣乿偼丄摨偠傛偆側僗僞僀儖側偑傜丄慜嶌偺晜偒棫偮傛偆側擬偄僞僢僠偲偼堎側傝丄傛傝棊偪拝偄偨僋乕儖側僥僀僗僩偵曪傑傟偰偄傞偑丄偦偙偐傜燌傒弌傞忣姶偼慺惏傜偟偔丄慜嶌偲峛壋偮偗偑偨偄弌棃偵側偭偰偄傞丅偁偲偑偒偵傛傞偲丄乽峳傇傞寣乿偼僕僃僀儉僘丒僇儖儘僗丒僽儗僀僋偺挿曇7嶌栚偱偁傝丄斵偺彫愢偺傎偲傫偳偼撿杒愴憟丄儊僉僔僐妚柦愴憟丄20悽婭弶摢偺僊儍儞僌丒僄僀僕側偳丄屆偄帪戙偺傾儊儕僇傪晳戜偵偟偰偄傞傜偟偄丅偦偺側偐偺1嶌偼丄乽峳傇傞寣乿偵偪傜偭偲偩偗搊応偟偨偑丄偦偺塭偑彫愢慡懱傪偍偍偭偰偄傞儊僉僔僐妚柦孯偺摤巑僼傿僄儘偩偲偄偆丅憗偔撉傒偨偄丅側偤丄偙傟偩偗偺慺惏傜偟偄嶌壠偑丄偙傟傑偱擔杮偵徯夘偝傟側偐偭偨偺偩傠偆丅曇廤幰偺懹枬偱偼側偄偺偐丅嵟嬤丄擔杮偱偼奀奜儈僗僥儕乕偑攧傟側偄偲塢傢傟偰偄傞偑丄偨傫偵柺敀偄杮偑弌偰側偄偩偗偺偙偲偱丄杮摉偼柺敀偄杮偼杮崙偱偼偐側傝弌斉偝傟偰偄傞偺偵丄偦傟偑擔杮偵徯夘偝傟偰偄側偄偲偄偆偙偲偱偼側偄偐丄偲姩偖傝偨偔側傞丅嵟屻偵媈栤傪傂偲偮丅偙偺杮偵堦弖偩偗搊応偡傞儊僉僔僐妚柦偺塸梇 Pancho Villa 偼乬僷儞僠儑丒價僕儍乭偲昞婰偝傟偰偄傞丅傏偔偺抦傞偐偓傝丄乬價儔乭乬價儕儍乭乬價儎乭偲偄偆昞婰偼偁偭偨偑丄乬價僕儍乭偲偄偆偺偼弶傔偰偩丅偄偭偨偄偳偺昞婰偑惓偟偄偺偩傠偆偐丅
2006.09.21 (栘) 恀偺僐僗儌億儕僞儞丄僓償傿僰儖
8寧弶弡偵僽儖乕僲乕僩搶嫗偱峴側傢傟偨僕儑乕丒僓償傿僰儖仌僓丒僓償傿僰儖丒僔儞僕働乕僩偺墘憈偼慺惏傜偟偐偭偨丅CD偱挳偄偰姶偠偨嫽暠傪惗偺僗僥乕僕偱捛懱尡偱偒偨丅偙傫側宱尡偼傔偭偨偵偁傞傕偺偱偼側偄丅80擭戙屻敿偺僊儖丒僄償傽儞僗丒僆乕働僗僩儔偲摨偠傛偆側丄壒妝偺帩偮杮尮揑側僄僱儖僊乕傪姶偠偨丅側傫偲尵偭偰傕嵟崅側偺偼丄偦偺僒僂儞僪偺崙嵺惈偩丅斵偺壒妝偵偼崙嫬偑側偄丅偦偟偰僕儍儞儖偺榞傕側偄丅儔僥儞丄傾僼儕僇丄拞嬤搶側偳丄曈嫬乮偲偝傟偰偄傞乯壒妝傪庢傝崬傒丄梈崌偝偣丄埑搢揑側僷儚乕傪惗傒弌偟偰偄傞丅僓償傿僰儖偺壒妝偼丄傾儊儕僇側偳偼偗偭偟偰悽奅偺拞怱偱偼側偔丄偦偺堦晹偵夁偓側偄偙偲傪徹柧偟偰偄傞丅僕儍僘偲偼傕偲傕偲偑偦偺傛偆偵條乆側梫慺傪庢傝崬傫偱宍嶌傜傟偰偒偨壒妝側偺偩丅偦偟偰偦偺奐曻姶偁傆傟傞僇儔僼儖側僒僂儞僪丅僄僱儖僊乕偺攇偑偆偹傝偺傛偆偵墴偟婑偣丄怱抧傛偄僥儞僔儑儞偑挳偔傕偺傪曪傒崬傓丅僓償傿僰儖偺帺桼帺嵼側僒僂儞僪峔惉椡偲僼傽儞僉乕側僉乕儃乕僪丒僾儗僀偼丄74嵨偲偼巚偊側偄偔傜偄庒乆偟偄丅僉乕儃乕僪乣僊僞乕乣儀乕僗乣僪儔儉僗乣僷乕僇僢僔儑儞乣償僅乕僇儖偲偄偆6恖曇惉偺僶儞僪偩偑丄僪儔儉僗偺僫僒僯僄儖丒僞僂儞僗儕乕埲奜偼傎偲傫偳柍柤偵嬤偄儊儞僶乕偩丅偩偑斵傜偺孞傝弌偡僾儗僀偺丄側傫偲朙閌側僌儖乕償偵枮偪偰偄傞偙偲偐丅偦偟偰丄傑偝偵偙偺悽奅偦偺傕偺傪巚傢偣傞丄偐偓傝側偔僐僗儌億儕僞儞側壒妝偺丄側傫偲枺椡偵晉傫偱偄傞偙偲偐丅偦傫側僓償傿僰儖偺壒妝偼丄傾儊儕僇偱偼傑偭偨偔昡壙偝傟偰偄側偄偲偄偆丅偙傟偼丄僕儍僘偺杮応偑傕偼傗傾儊儕僇偱偼側偔側偭偨偲偄偆偙偲側偺偩傠偆丅2006.09.09 (搚) 儈儏儞僿儞峴偒栭峴楍幵偺忔傝怱抧偼
偄偝偝偐媽暦偵懏偡傞偑丄崱擭6寧丄WOWOW偱乽儈儏儞僿儞傊偺栭峴楍幵乿(Night Train to Munich)偲偄偆塮夋偑曻憲偝傟偨丅擔杮慡崙偱偄偭偨偄壗恖偺恖偑娤偨偐抦傜側偄偑丄嬤擭丄偙傟傎偳妝偟傑偣偰傕傜偭偨塮夋偼側偐偭偨丅WOWOW偼丄傂偲偙傠偼墲擭偺僴儕僂僢僪惢僼傿儖儉丒僲儚乕儖摿廤側偳丄柺敀偄塮夋傪傗偭偰偄偨偺偵丄嵟嬤偼傾僯儊傗娯崙塮夋傗彜嵃傑傞尒偊偺掅媺側塮夋偽偐傝偱丄夝栺偟傛偆偐偲巚偭偰偄偨偲偙傠丄偨傑偵偙傫側慺惏傜偟偄偺傪傗傞偺偱巭傔傜傟側偄丅偙傟偼1940擭偺僀僊儕僗塮夋偱娔撀偼僉儍儘儖丒儕乕僪丄庡墘偼儗僢僋僗丒僴儕僜儞丄億乕儖丒僿儞儕乕僪丄儅乕僈儗僢僩丒儘僢僋僂僢僪偲偄偆擔杮枹岞奐偺僒僗儁儞僗塮夋偩丅僉儍儘儖丒儕乕僪偲偄偊偽乽戞嶰偺抝乿(1949)偑桳柤偩偑丄偙傟偼偦傟傛傝偐側傝慜丄愴帪壓偺塮夋偱偁傝丄儕乕僪偲偟偰偼偛偔弶婜偺嶌昳偱偁傠偆丅僫僠僗偵懆傢傟偨暔棟妛幰傪媬弌偡傞偨傔僀僊儕僗偺挸曬晹堳偑僪僀僣偵愽擖偡傞偲偄偆榖偱丄僾儘僢僩偼擇揮丄嶰揮丄偄傑偺CG傪懡梡偟偨戝巇妡偗偺塮夋偲偼堦枴堘偆丄彫枴側偑傜僺儕儕偲堷偒掲傑傝丄僀僊儕僗傜偟偄儐乕儌傾傕偦偙偐偟偙偵嶶傝偽傔傜傟偨寙嶌朻尟僒僗儁儞僗塮夋偵側偭偰偄偨丅僼儕僢僣丒儔儞僌娔撀丄僎僀儕乕丒僋乕僷乕庡墘偺傾儊儕僇塮夋乽奜搮偲抁寱乿(1946)傕丄摨偠偔僫僠僗丒僪僀僣傊偺愽擖傪僥乕儅偵偟偨僗僷僀丒僒僗儁儞僗塮夋偩偭偨偑丄偦傟傛傝偼傞偐偵弌棃偼偄偄丅嬃偄偨偺偼丄媟杮偑僔僪僯乕丒僊儕傾僢僩偩偭偨偙偲丅僊儕傾僢僩偲偄偊偽丄偁偺僒僗儁儞僗塮夋偺寙嶌乽愨暻偺斵曽偵乿偺娔撀偩丅榖偺揥奐丄慡懱偺枴晅偗傕乽愨暻偺斵曽偵乿傪渇渋偲偝偣傞傕偺偑偁傝丄偙傟偼娔撀偺儕乕僪傛傝傕丄僊儕傾僢僩怓偑怓擹偔弌偨塮夋偩偲巚偭偨丅傑偨丄僀僊儕僗帪戙偺僸僢僠僐僢僋塮夋丄乽嶰廫嬨栭乿(1935)傗乽僶儖僇儞挻摿媫乿(1938)偲傕丄堦柆傕擇柆傕捠偠崌偭偰偄傞丅僕儍僘昡榑壠偱塮夋偵傕憿寃偑怺偄嵅摗廏庽偝傫偐傜乽僶儖僇儞挻摿媫乿偺媟杮恮偵僊儕傾僢僩偑壛傢偭偰偄傞偲嫵偊偰偄偨偩偄偨偑丄側傞傎偳偦偆側偺偐偲崌揰偑偄偭偨丅偁傟偼楍幵偺僔乕儞偑拞怱偩偟丄偙傟傕戣柤偳偍傝丄嵟屻偺楍幵偺僔乕儞偱僋儔僀儅僢僋僗傪寎偊傞丅偦偟偰傕偆傂偲偮丄側傫偲偙偺塮夋偵偼丄乽僶儖僇儞挻摿媫乿偵弌偰棃偨2恖慻偺僀僊儕僗恆巑偑搊応偡傞偺偩丅2恖慻偺僀僊儕僗恆巑偲偼丄庡恖岞偨偪偲摨偠楍幵偵忔傝崌傢偣偨丄僋儕働僢僩偺帋崌偽偐傝婥偵偟側偑傜撣婥偵椃傪偟偰偄傞2恖偱丄杮嬝偵偼傑偭偨偔棈傑側偄偺偩偐丄柇偵報徾偵巆傞埖偄偩偭偨丅偢偄傇傫埲慜偵撉傫偩僸僢僠僐僢僋偵娭偡傞杮偱丄偙偺2恖慻恆巑偼丄傎偐偵傕偄偔偮偐偺塮夋偵摨偠栶偱搊応偟偰偄傞偲抦偭偰偼偄偨偑丄偦偺1杮偑偙傟偩偭偨偺偩丅偙偺塮夋偱偼丄2恖偺恆巑偼傗偼傝庡恖岞偨偪偲偨傑偨傑摨偠楍幵偵忔傝崌傢偣傞偑丄乽僶儖僇儞挻摿媫乿傛傝傕偼傞偐偵廳梫側栶傪梌偊傜傟丄戝偄偵妶桇偡傞偺偱婐偟偔側偭偰偟傑偆丅庡墘偺儗僢僋僗丒僴儕僜儞偑丄撈摿偺楴乆偲偟偨挐傝曽偼弉擭偵側偭偰偐傜偺斵偲摨偠側偺偵丄偄傗偵庒偔敩檹偲偟偰偄傞偑柺敀偄丅傑偨乽僇僒僽儔儞僇乿偱儗僕僗僞儞僗偺摤巑傪墘偠偨億乕儖丒僿儞儕乕僪偑埆栶偱搊応偡傞偺傕嫽枴怺偄丅偙偺傛偆側40擭戙丄50擭戙偺僀僊儕僗塮夋偼丄柺敀偄傕偺偑偨偔偝傫偁傞偼偢側偺偵丄TV偱傕DVD偱傕側偐側偐娤傞偙偲偑偱偒側偄偺偑巆擮偩丅傕偭偲NHK-BS側偳偱曻憲偟偰偔傟側偄傕偺偩傠偆偐丅
2006.09.03 (擔) 僽僈僢僥傿偼愯椞壓偺僷儕傪幘憱偟偨偐
儘僽丒儔僀傾儞嶌偺丄戞2師戝愴拞偺僷儕偱偺儗僕僗僞儞僗塣摦傪戣嵽偵偟偨朻尟彫愢乽嬇傊偺幘憱乿乮暥弔暥屔乯傪撉傫偩丅弌偩偟偼儃僽丒儔儞僌儗乕偺寙嶌乽杒暻偺巰摤乿傪渇渋偲偝偣丄偙傟偼柺敀偄偺偱偼丒丒丒偲婜懸偟偰撉傫偩偑丄寢壥偼偄傑偄偪丅弌棃偼埆偔側偄偟丄揤嵥儗乕僒乕偨偪偺嫞憟偲桭忣丄偦偟偰棤愗傝丄柤幵僽僈僢僥傿傪嬱偭偰揥奐偝傟傞僫僠僗愯椞壓偺僷儕偱偺儗僕僗僞儞僗塣摦丄慜敿傪旐偆惵弔彫愢晽偺儘儅儞僥傿僔僘儉偲丄柺敀偔側傞側傞偨傔偺忦審偼懙偭偰偄傞偺偵丄庡恖岞僂傿儕傾儉僘傪偼偠傔搊応恖暔偨偪偺僉儍儔僋僞乕偑傕偆傂偲偮棫偪忋偑偭偰偙偢丄姶忣堏擖偑偱偒側偄偺偩丅僋儔僔僢僋丒僇乕傗僇乕丒儗乕僗偑岲偒側恖偵偲偭偰偼柺敀偄偺偩傠偆偑丒丒丒丅偱傕媦戞揰偵偼廩暘払偟偰偄傞丅偙偺庤偺彫愢偵偼丄偝偭偒偺乽杒暻偺巰摤乿傪偼偠傔丄僕儍僢僋丒僸僊儞僘偺乽榟偼晳偄崀傝偨乿丄働儞丒僼僅儗僢僩偺乽殡傛埮傊隳傋乿丄嵟嬤偺僕僃僼儕乕丒僨傿乕償傽乕偺乽廱偨偪偺掚墍乿側偳丄寙嶌偑偨偔偝傫偁傝丄僴乕僪儖偑崅偄偺偩丅儔僀傾儞偺彫愢偱偼丄偙傟傑偱乽傾儞僟乕僪僢僌僗乿傪撉傫偩偩偗偩偭偨偑丄偁傑傝嫮偄報徾偼巆偭偰偄側偄丅儔僀傾儞偼傎偐偵傕丄偙偺傛偆側戞2師戝愴旈榖傪偄偔偮偐彂偄偰偄傞傜偟偄偑丄偦傟傜偵婜懸傪偮側偘偨偄丅2006.09.02 (搚) 僐儖僩儗乕儞堎榑
崱擭偺弶傔丄僐儖僩儗乕儞偺戙昞嶌乽帄忋偺垽乿偺惉棫夁掱傪捛偭偨僪僉儏儊儞僩杮乽僕儑儞丒僐儖僩儗乕儞亀帄忋偺垽亁偺恀幚乿偺東栿乮壒妝擵桭幮乯偑弌斉偝傟偨丅偙傟傪撉傓偲丄斵偺恖惗偼嬯摤偺楢懕偩偭偨偙偲偑幚姶偱偒傞丅偙偺杮傪撉傫偩偺傪婡夛偵丄夵傔偰乽帄忋偺垽乿傪挳偄偰傒偨偲偙傠丄偙傫側偵傕帹偵偡傫側傝擖偭偰偔傞丄乬傑偲傕側乭僕儍僘偩偭偨偺偐丄偲嬃偄偰偟傑偭偨丅摿偵戞1晹偐傜戞3晹傑偱偺棳傟丄峔惉偺柇丄娚媫偺晅偗曽丄僜儘偺攝暘丄婥敆偺燐傝偼慺惏傜偟偄偲姶偠偨丅戞4晹偼廳偨偄偑丄偙偺杮傪撉傫偱丄僒僢僋僗偱帊傪撉傫偱偄傞偺偩偲抦偭偰擺摼偱偒偨丅愄挳偄偨偲偒偼彮偟堘榓姶傪姶偠偨戞1晹偺屻敿偵擖傞塺彞傕丄偲偰傕帺慠側棳傟偵忔偭偨傕偺偵挳偙偊偨丅偙偺傾儖僶儉偑丄僐儖僩儗乕儞偑嵟屻偺崿撟悽奅偵擖傝崬傓捈慜偺丄斵偑偨偳傝拝偄偨嵟崅偺嫬抧傪昞尰偟偨傕偺偩偲偄偆昡壙偼丄廩暘偵擺摼偱偒傞丅僐儖僩儗乕儞偲偄偆偲巚偄弌偡榖偑偁傞丅僼傿儔僨儖僼傿傾帪戙偺桭恖偩偭偨僐儞億乕僓乕仌僒僢僋僗憈幰儀僯乕丒僑儖僜儞偐傜捈愙暦偄偨丄庒偄偲偒偺僐儖僩儗乕儞偵娭偡傞僄僺僜乕僪偩丅偁傞偲偒丄僑儖僜儞偑僼傿儔僨儖僼傿傾偺僶乕偵擖傞偲丄僩儗乕儞偑僇僂儞僞乕偺忋偱曕偒夞傝側偑傜儂儞僉儞僌丒僗僞僀儖偱僒僢僋僗傪悂偄偰偄偨丅傃偭偔傝偟偨僑儖僜儞偑偁傫偖傝偲岥傪偁偗偰尒偮傔偰偄傞偲丄僩儗乕儞偼僑儖僜儞偑偄傞偺偵婥偑偮偄偰丄僶僣偺埆偦偆側徫偄傪晜偐傋偨偲偄偆丅偁偺僐儖僩儗乕儞傕庒偄崰偼偦傫側偙偲傪傗偭偰偄偨偺偩丅庒偒擔偺僐儖僩儗乕儞偑偙偺傛偆偵俼仌俛僗僞僀儖偱墘憈偟偰偄偨偙偲偼丄偙偺杮偵傕徯夘偝傟偰偄傞丅偙傟傪傔偖偭偰偼丄斲掕揑偵愗傝幪偰傞恖偲峬掕揑偵昡壙偡傞恖偑偄傞傛偆偩偑丄挊幰偺傾僔儏儕乕丒僇乕儞偼丄偙偺帪戙偺俼仌俛僗僞僀儖偱墘憈偟偨宱尡偑斵偺惉挿偵僾儔僗偵側偭偨偲偟偰偄傞丅傏偔傕傑偭偨偔摨姶偩丅僩儗乕儞偼嬥傪壱偖偨傔偵傕傗偭偰偄偨偺偩傠偆偑丄摨帪偵帺傜傕僇僂儞僞乕偺忋偱偺儂儞僉儞僌丒僾儗僀傪妝偟傫偱偄偨偵堘偄側偄丅偦偟偰懠偺條乆側梫慺偲偲傕偵丄斵偑撈帺偺僗僞僀儖傪惗傒弌偡搚戜偵側偭偨偼偢偩丅
僐儖僩儗乕儞偺娭偟偰丄慜偐傜婥偵側偭偰偄傞偙偲偑偁傞丅斵偑儅僀儖僗丒僨僀償傿僗偺僋僀儞僥僢僩偵擖偭偰悂偒崬傫偩乹儔僂儞僪丒儈僢僪僫僀僩乺偺2偮偺僥僀僋偵娭偟偰偺偙偲偩丅儅僀儖僗偼1956擭9寧10擔丄僐儘儞價傾偵偙偺嬋傪悂偒崬傫偩丅偦傟偐傜1儠寧敿屻偺10寧26擔丄偙傫偳偼僾儗僗僥傿僢僕偵摨偠嬋傪悂偒崬傫偱偄傞丅偙傟偼桳柤側儅儔僜儞丒僙僢僔儑儞偺2夞栚偵偁偨傞丅僐儘儞價傾偺乽儔僂儞僪丒儈僢僪僫僀僩乿乮悂偒崬傒帪偺惓幃嬋柤偼乽'Round About Midnight乿乯偼丄傾儖僶儉偺僞僀僩儖丒僩儔僢僋偵側傝丄寛掕揑柤墘偲偝傟偰偒偨丅偄偭傐偆丄僾儗僗僥傿僢僕偺摨嬋偼丄儅儔僜儞丒僙僢僔儑儞傪儗僐乕僪壔偟偨4晹嶌偵偼廂榐偝傟偢乮僐儘儞價傾偺償傽乕僕儑儞偑傾儖僶儉丒僞僀僩儖偵側偭偨偺偱丄僾儗僗僥傿僢僕偑婥傪尛偭偨偐傜偩偲偄傢傟偰偄傞乯丄乽仌儌僟儞丒僕儍僘丒僕儍僀傾儞僗乿偲偄偆傾儖僶儉偵傂偭偦傝偲廂傔傜傟丄偁傑傝榖戣偵偼偺傏傜側偄傑傑偵側偭偰偄傞丅偩偑丄傏偔偺挳偔偐偓傝丄僾儗僗僥傿僢僕丒償傽乕僕儑儞偺傎偆偑弌棃偑偄偄偲巚偆丅戞堦偺棟桼偼僐儖僩儗乕儞偺僜儘偑慺惏傜偟偄偐傜偩丅僐儘儞價傾丒償傽乕僕儑儞偱偼妎懇側偘偵丄庤扵傝偡傞傛偆偵悂偄偰偄傞偺偵丄僾儗僗僥傿僢僕丒償傽乕僕儑儞偱偼丄帺怣偵枮偪偰丄報徾揑側僼儗乕僘傪偪傝偽傔側偑傜丄摪乆偲悂偒愗偭偰偄傞丅偨偭偨1儠寧敿偱偙傟偩偗恑曕傪悑偘偨偺偐丄偲丄儅僀儖僗帪戙偺斵偺惉挿偺懍偝偵栚傪扗傢傟傞巚偄偑偡傞丅傑偨墘憈慡懱偲偟偰傕丄悙乆偟偝偲廤拞椡偲偄偆揰偱偼弶墘偺僐儘儞價傾斉偑忋偩偑丄僾儗僗僥傿僢僕斉偵偼偦傟傪曗偭偰梋傝偁傞嬞敆姶偲惉弉惈偑偁傞丅偲偙傠偑悽娫堦斒偱偼僐儘儞價傾丒償傽乕僕儑儞偽偐傝偑庢傝偞偨偝傟丄僐儖僩儗乕儞偺僜儘偺斾妑傕偁傑傝帹偵偟偨偙偲偑側偄丅偄偭偨偄側偤側偺偩傠偆丅
2006.09.01 (嬥) 僴儕乕丒儃僢僔儏偼偳偙偵峴偔偺偐
儅僀僋儖丒僐僫儕乕偺僴儕乕丒儃僢僔儏丒僔儕乕僘嵟怴嶌乽嵾偲揤巊偺奨乿乮島択幮暥屔乯偑敪攧偝傟偨丅僔儕乕僘10嶌栚偩丅儃僢僔儏丒僔儕乕僘偼丄僌儗僢僌丒儖僢僇偺儃僨傿僈乕僪丒傾僥傿僇僗丒僔儕乕僘偲暲傫偱丄尰戙嵟崅偺僴乕僪儃僀儖僪彫愢偩丅慜嶌偐傜丄LA偺寈嶡傪戅怑偟巹棫扵掋傪偼偠傔偨儃僢僔儏偑丄崱夞偼FBI摿暿憑嵏姱偺儗僀僠僃儖丒僂僅儕儞僌偲嫟偵丄The Poet傪捛偄媗傔傞丅The Poet偲偼丄1997擭偵弌偨儃僢僔儏丒僔儕乕僘奜偺彫愢乽僓丒億僄僢僩乿偵搊応偡傞楢懕嶦恖斊偩丅奐姫娫傕側偔丄嬃偔偙偲偵乽傢偑怱憻偺捝傒乿偱妶桇偟偨丄堷戅偟偨FBI憑嵏姱僥儕乕丒儅僢働僀儗僽偑巰傫偱偟傑偆丅偦傟傪巆擮偵巚偆娫傕側偔丄暔岅偼夣挷偵恑傒丄暿乆偵憑嵏偟偰偄偨FBI懁偲儃僢僔儏懁偑岎嵎偟丄彫婥枴偄偄僥儞億偱嵟廔復偵側偩傟崬傓丅偠偮偵岻偄丅儃僢僔儏偺柡偵婑偣傞垽偑昤偐傟偨傝丄乽僶僢僪儔僢僋丒儉乕儞乿偺彈庡恖岞傪搊応偝偣偨傝偲丄杮嬝偵娭學側偄憓榖偑墱怺偝傪嶌傝弌偟偰偄傞偺傕尒摝偣側偄丅僀乕僗僩僂僢僪娔撀庡墘偱塮夋壔偝傟偨乽傢偑怱憻偺捝傒乿傊偺晄枮傪岻傒偵彫愢偵惙傝崬傫偱偄傞偺傕柺敀偄丅6,7,8嶌栚偁偨傝偱僷儚乕偑棊偪偨偲巚傢傟偨儃僢僔儏丒僔儕乕僘偼丄慜嶌偺乽埫偔惞側傞栭乿偱嵞傃婸偒傪庢傝栠偟偨丅傏偔偼偙偺乽埫偔惞側傞栭乿偲乽儔僗僩丒僐儓乕僥乿偑僐僫儕乕偺嵟崅寙嶌偩偲巚偭偰偄傞偑丄崱夞偺怴嶌傕偦傟傜偲斾傋偰懟怓側偄弌棃偩丅偙偺僔儕乕僘偼偁偲2嶌偱廔傢傝偩偲偄偆丅傕偭偲彂偄偰傕傜偄偨偄偲傕巚偆偑丄儅儞僱儕偵娮傞偺傪旔偗傞偵偼偦偺偔傜偄偱偪傚偆偳偄偄偺偐傕偟傟側偄丅偲偵偐偔丄儃僢僔儏偑LA偺孻帠偵暅怑偡傞師夞嶌偑妝偟傒偩丅